
今日の活動
| あなたは | |||
|
|
人目の訪問者です。 |
◎世界と君の闘いでは、世界に加勢せよ
(カフカ『罪、苦しみ、希望、そして真の道についての考察』より)

三年生のある生徒が、夏季休業中の旅行で撮影した写真を視ています。若い感性と豊かな感情が表現されている素敵な写真がいっぱいです。来週には実習船の見学(17日)、水泳実習(19日)、吹奏楽部定期演奏会(22日)、そして次週27日は星輝祭文化の部があり、豊かな体験から学ぶ多様な機会がまっています。
◎地域とともにある学校
実行委員会に入られている先生から、学習会の案内チラシをいただきました。日生中学校三年生も毎年「ハンセン病問題学習」に取り組んでいますが、私たち教員もしっかりと学ばなくてはなりませんね。



◎多くの人に支えられて(9/12)
使わなくなった用品を使って、家庭科では、筆箱や小物入れなどのリサイクル品の製作に取り組んでいます。この日も保護者の方から消防団で使われていた丈夫なホースの提供をしていただきました。ありがとうございました。さて、布の特徴を大事にして君なら何をつくりますか?

◎学級弁論大会 はじまりはじまりっ~(9/11)
書くことは考えること。考えることは生きること。語ることによって、「新しく知る」すべを体得します。そして、仲間の考えや思いをさらに「わかる」ことができるのが弁論大会です。
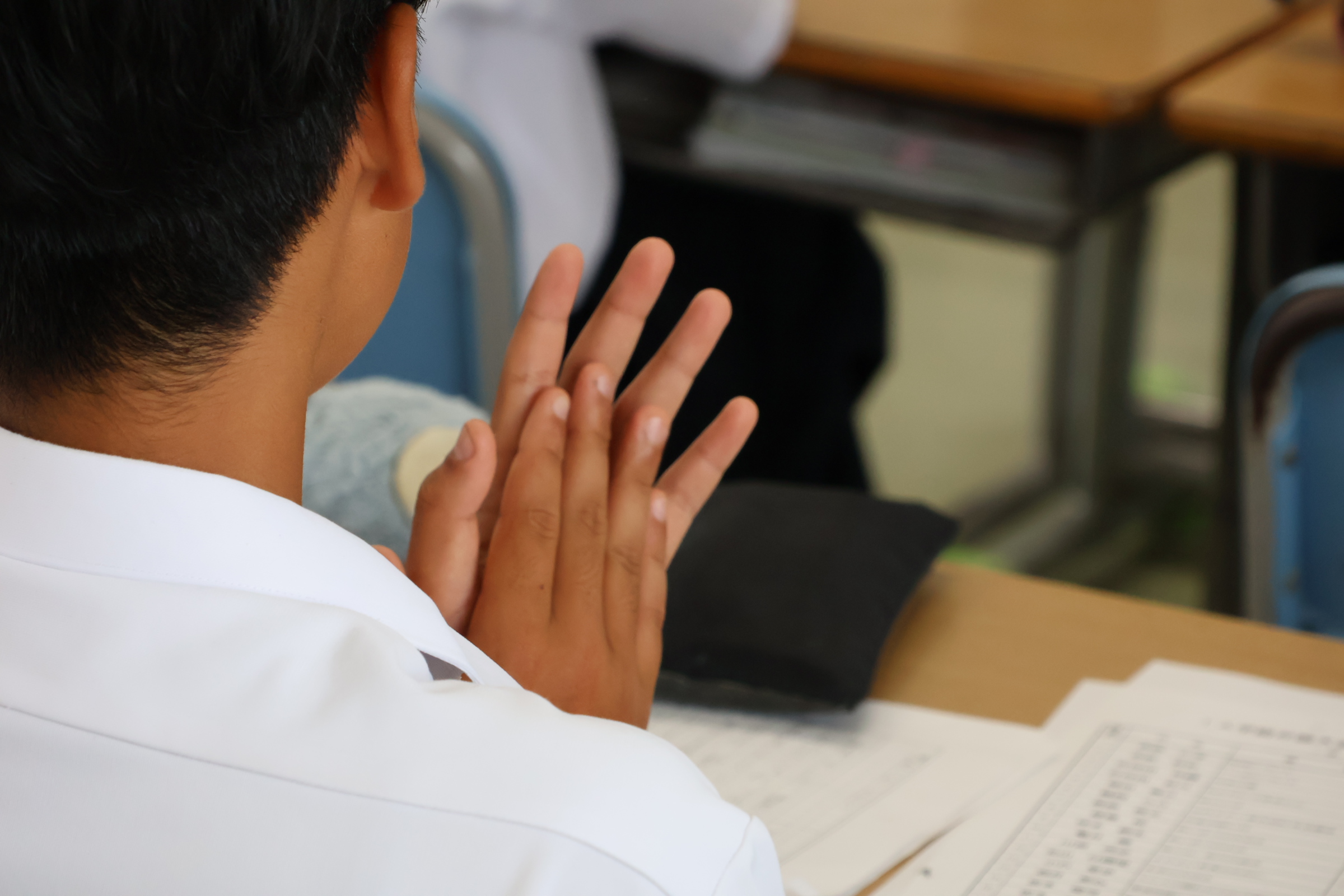


ボランティアで学んだこと 命の大切さに気づいた広島研修 スマホ依存症の怖さ 私の学校生活 一歩踏み出す勇気 フードロスについて 中学校生活で学んだこと 戦争がもたらすもの 地球温暖化 なぜ人は時に相手がいやがることをしてしまうのか AIについて 制服と私服のメリット・デメリット 努力は本当に報われるのか 部活について 食品ロスの問題点 スマホの良いところと悪いところ 友だちとのお金のやりとり 携帯は本当に便利なものか ゴミについて 双子のよさ 高齢者問題 携帯電話のよいところと悪いところ お米を守るために。食品ロスを考えよう 地球温暖化で変わったこと 人と人との関わりの中で感じたこと 生命の大切さ よりよい未来のために 「みんな違ってみんないい」って正解? 海と山、別々のよさ あいさつのよさ スマホの使用について そばにある命は 目標 うたがってみること ゴミ問題について なぜ人は物を忘れてしまうのか インターネットの怖さ デジタルタトゥーの身近な怖さ 今私にできること ボランティアに参加して お金の使い方 協力とは 中学校生活の思い出 なぜ弁論をしないといけないのか 私たちにできること あいさつの大切さ 広島・沖縄研修で学んだこと 努力の意味 スマートフォンのメリット・デメリット 少子高齢社会の今 「できない」から始まった私の挑戦 なぜ僕は静かにできないのか いじめについて 「ありがとう」を伝えたい アジアの旅から学んだこと 深刻な地球温暖化について 手伝いの大切さ 平和の代償 将来の夢 自分がたいせつにしている物 いじめについて 勉強について 公共マナーを大切にする意味 環境問題について 成功へ向けた自己研磨、失敗という研磨剤について なぜ宿題をするのか ゴミ問題について 言葉の遣い方 日本食について 私の幸せな時間 平和について ながら生活が奪う時間 人生を振り返った「座右の銘」 僕の宝物 海を守るために私たちができること 時間は大切 勉強する意味 健康のありがたさ 今の地球 あいさつはなぜするのか 家族とのふれ合い 便利さと引き換えに失ったもの 平和への願い 自由について 本と電子機器の良さ なぜ弁論をするのか あいさつの大切さ 戦争について 気持ちが大切 お手伝いをする理由 高齢者の免許返納について スマホ時間について 中学校でがんばったこと(論題の一部)
◎職員図書リニューアル✨
研修用、ちょっとひといき用の本を入れ替えました。先日の校内研修で話題になった書籍もありますよ。
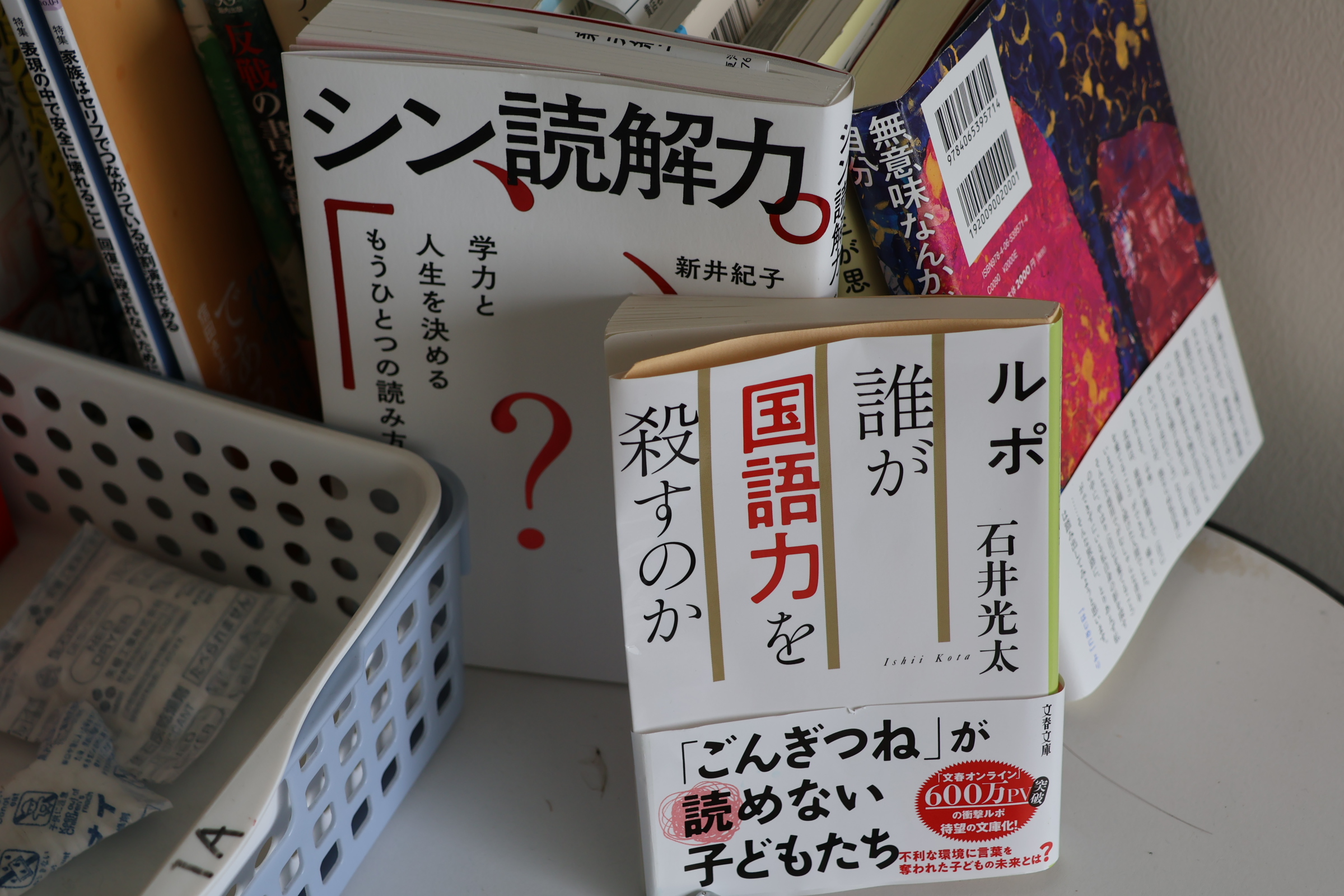
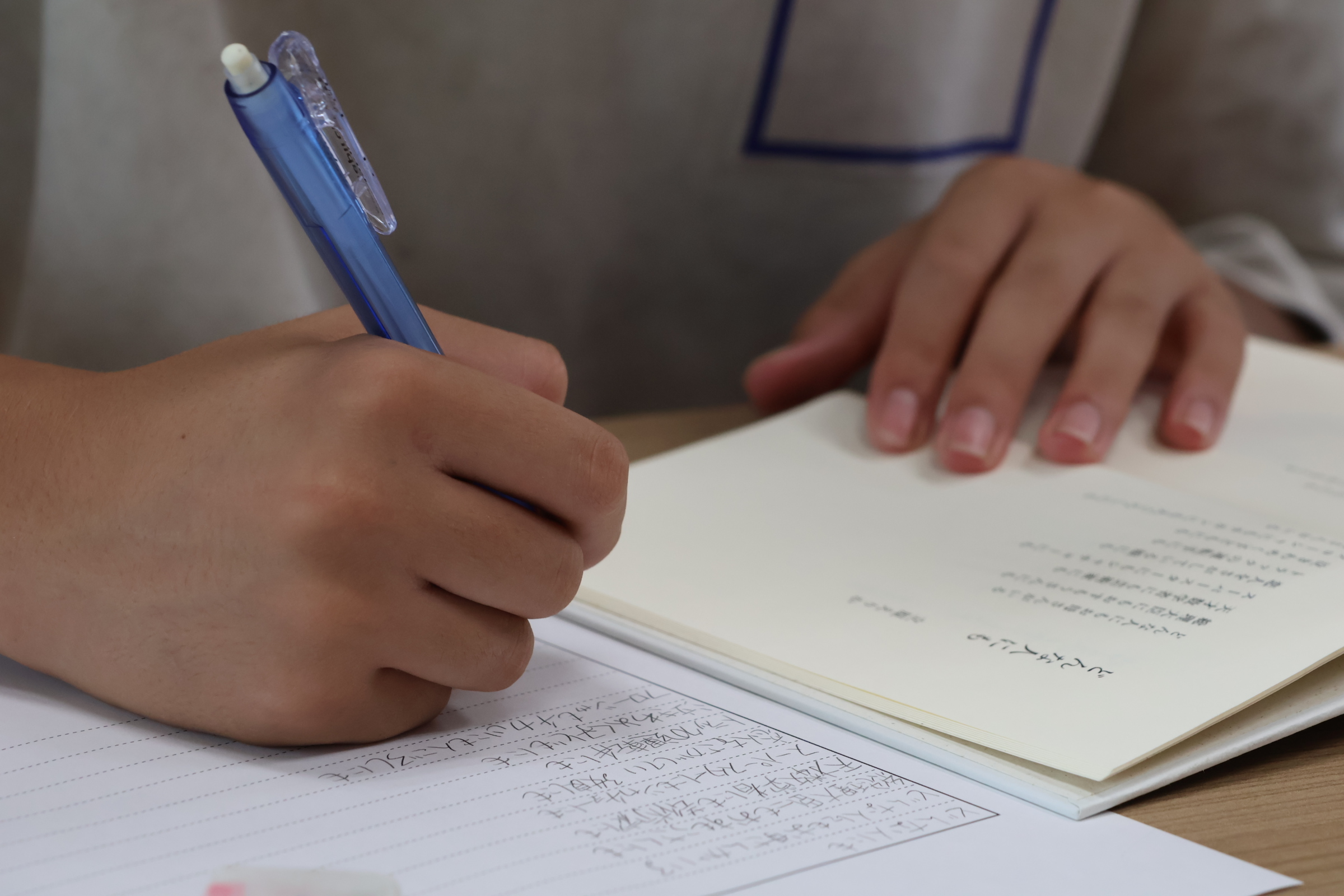

◎多くに人に支えられて(9/11)
本日、水質検査をしていただきました。ありがとうございました。また、中学校では毎月10日にすべての校内の安全点検を行っています。
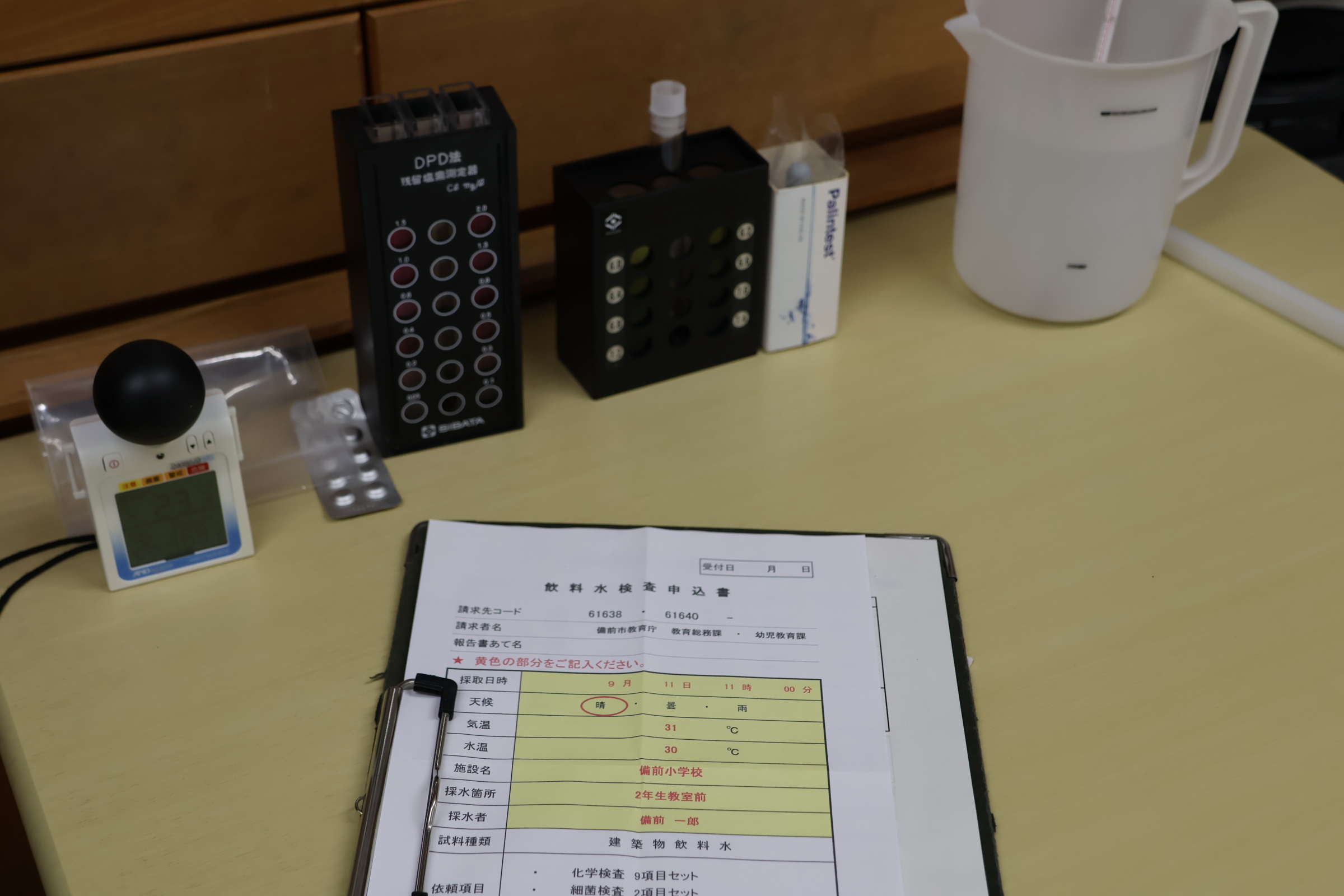
◎多くの人に支えられて(9/10)
今年度も、通学路の安全(危険箇所・修繕箇所等)について、たくさんの情報やご意見をいただき、大変お世話になりました。助かりました。集約して市教育委員会へ報告させていただきました。ご協力をありがとうございました。
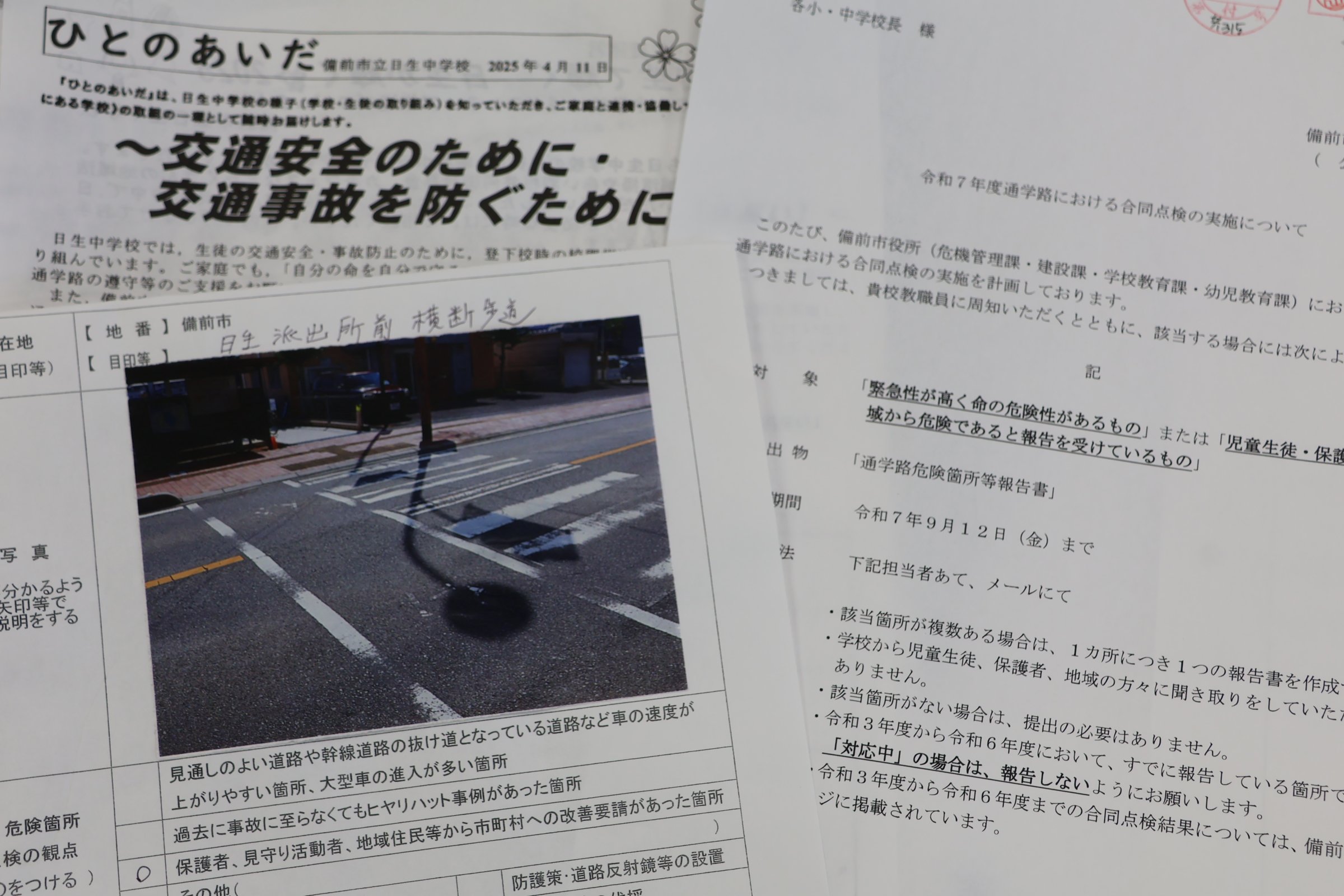
◎学習環境の整備を努めています(9/10)

◎すべての山に登れ (musical:「Sound of music」挿入歌)
備前市から若い先生方が、研修で日生中学校の授業を観に来られました。(9/9)


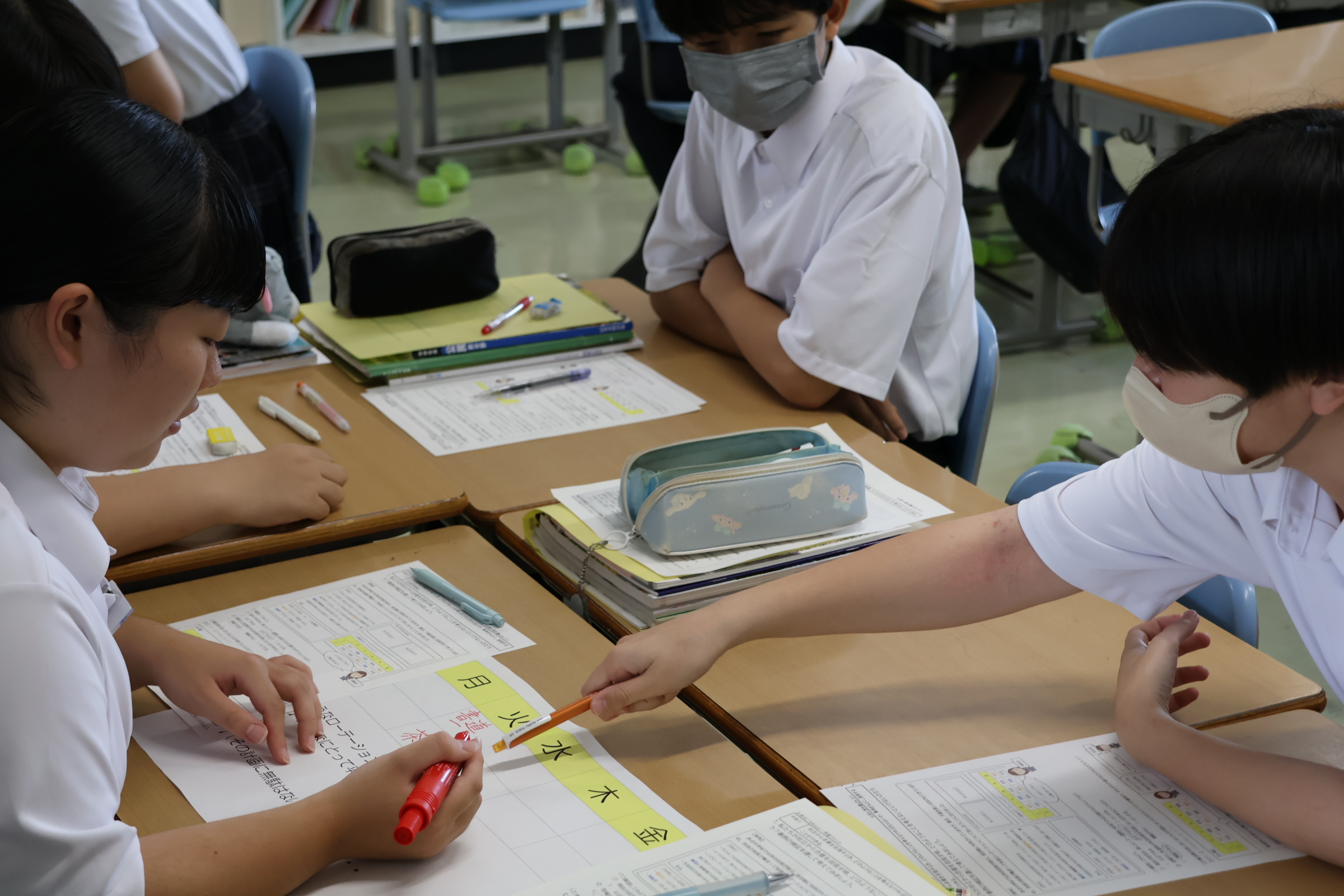


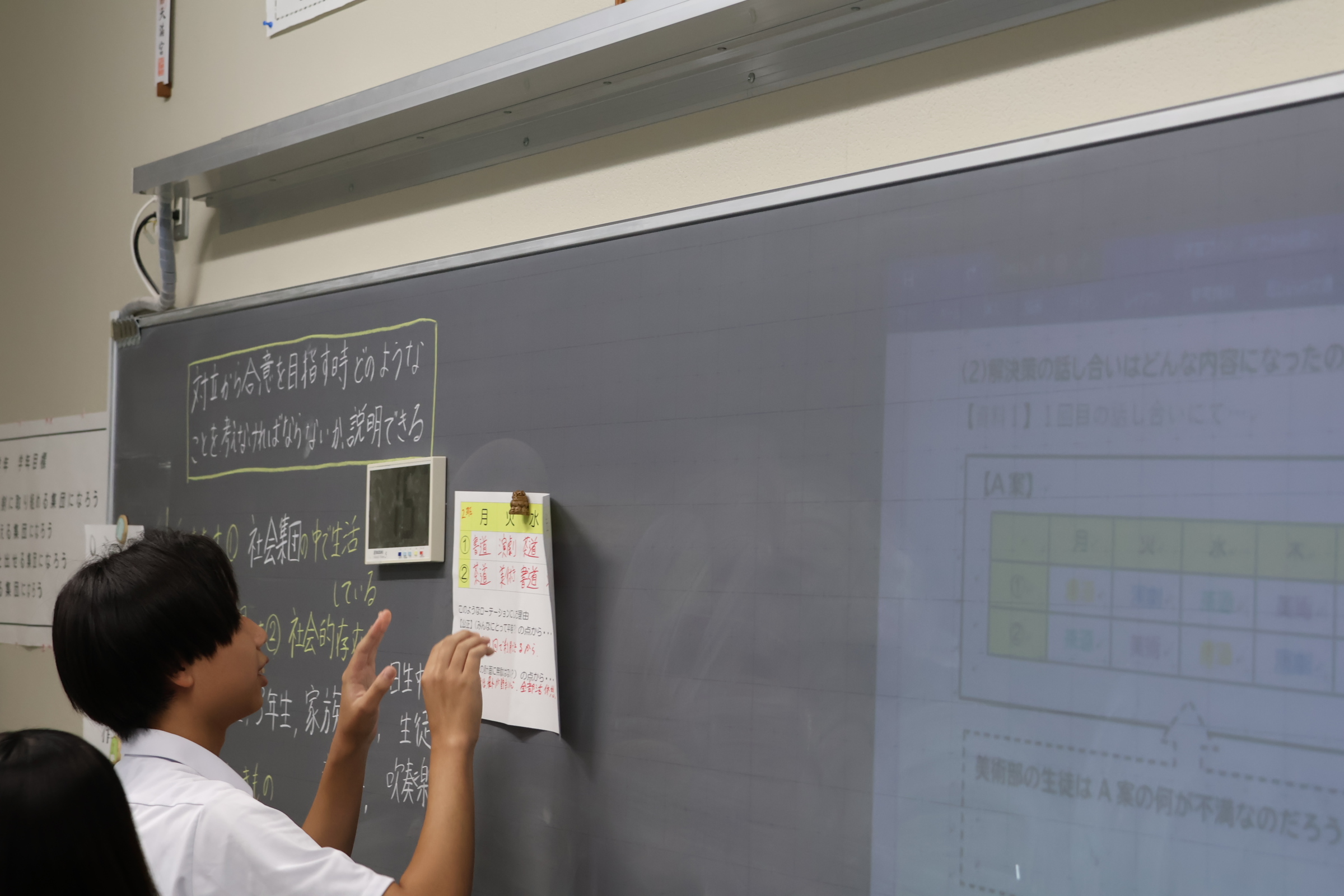
時代は流れるけど、若い先生たちに伝えたいこと・引き継いでほしいことがたくさんあります。
◎ミネルヴァの梟(ふくろう)は黄昏どきに飛び立つ ヘーゲル『法の哲学 序文』
校内研修で先生たちも勉強しています。(9/8)
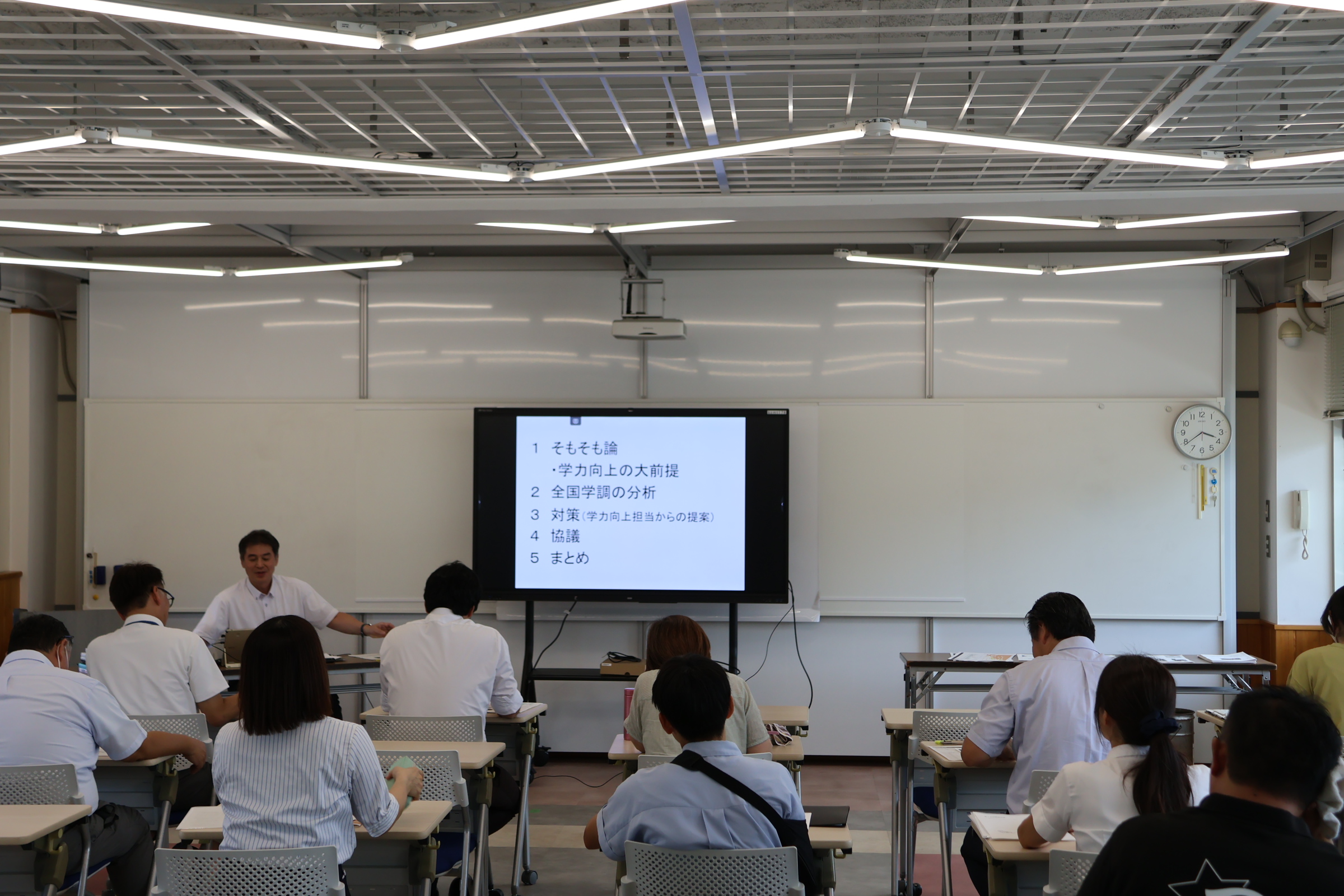
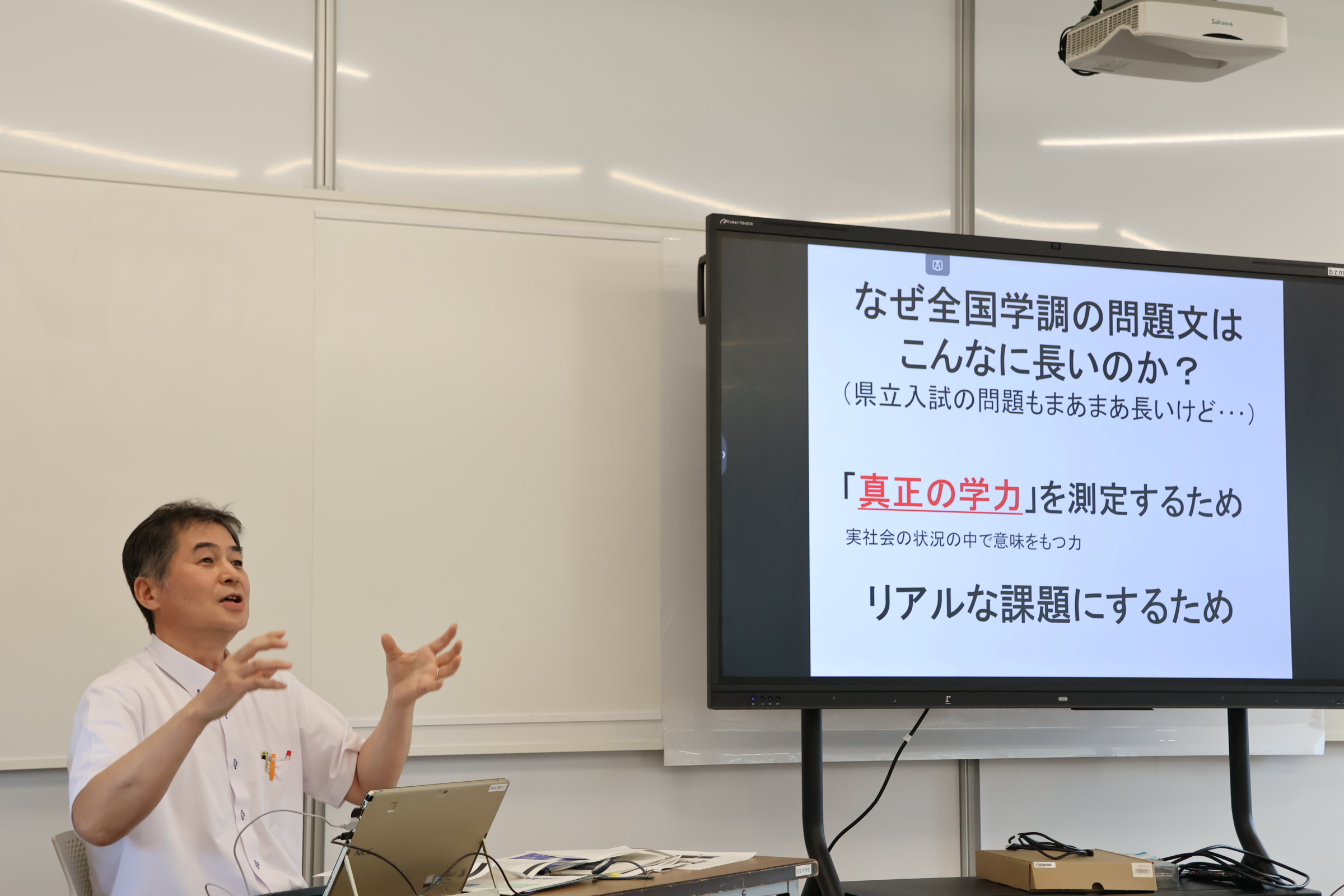
◎前へ・先へ・確かな一歩を。
日生中学校生徒会選挙公示 選挙管理委員会より(9/8)
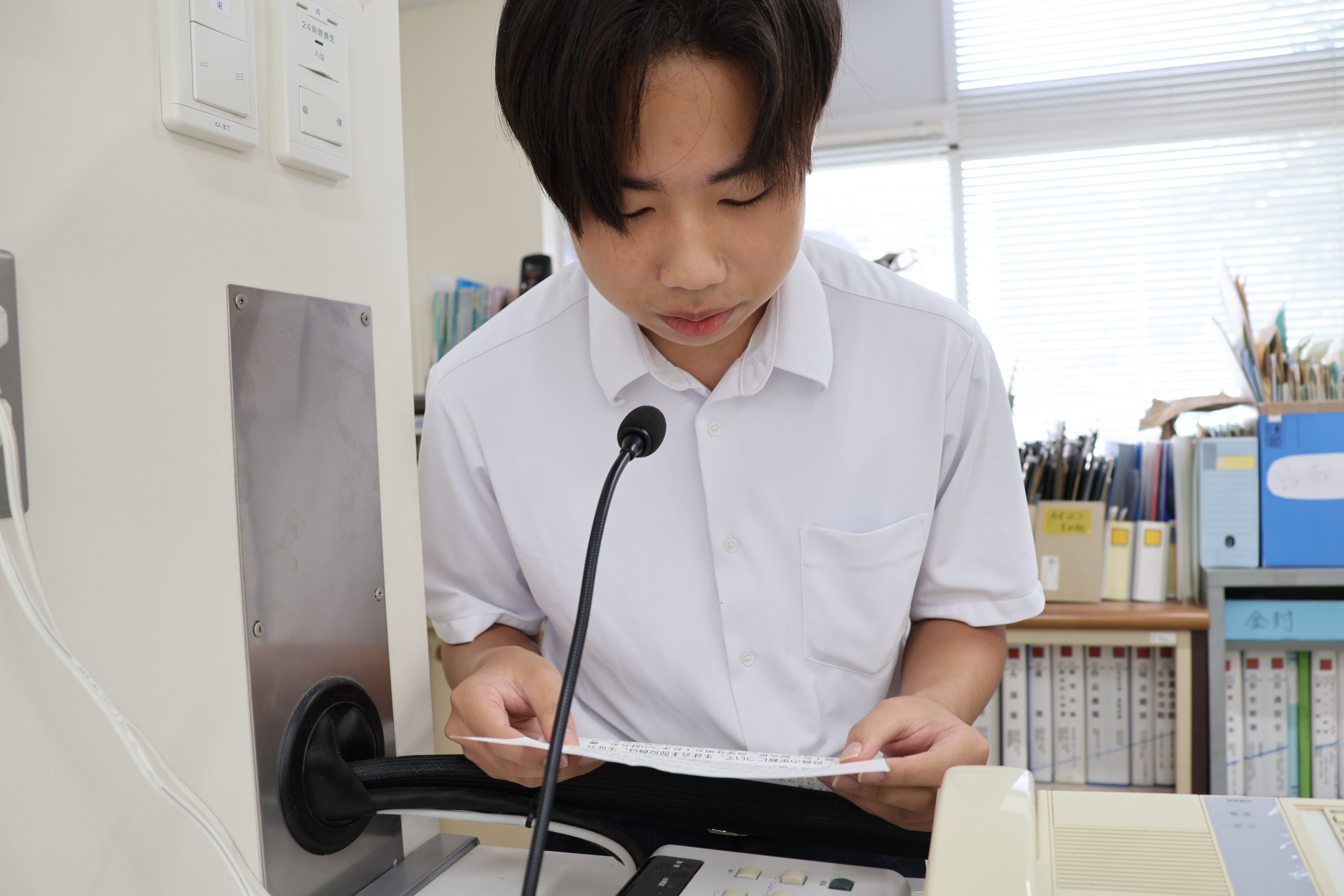
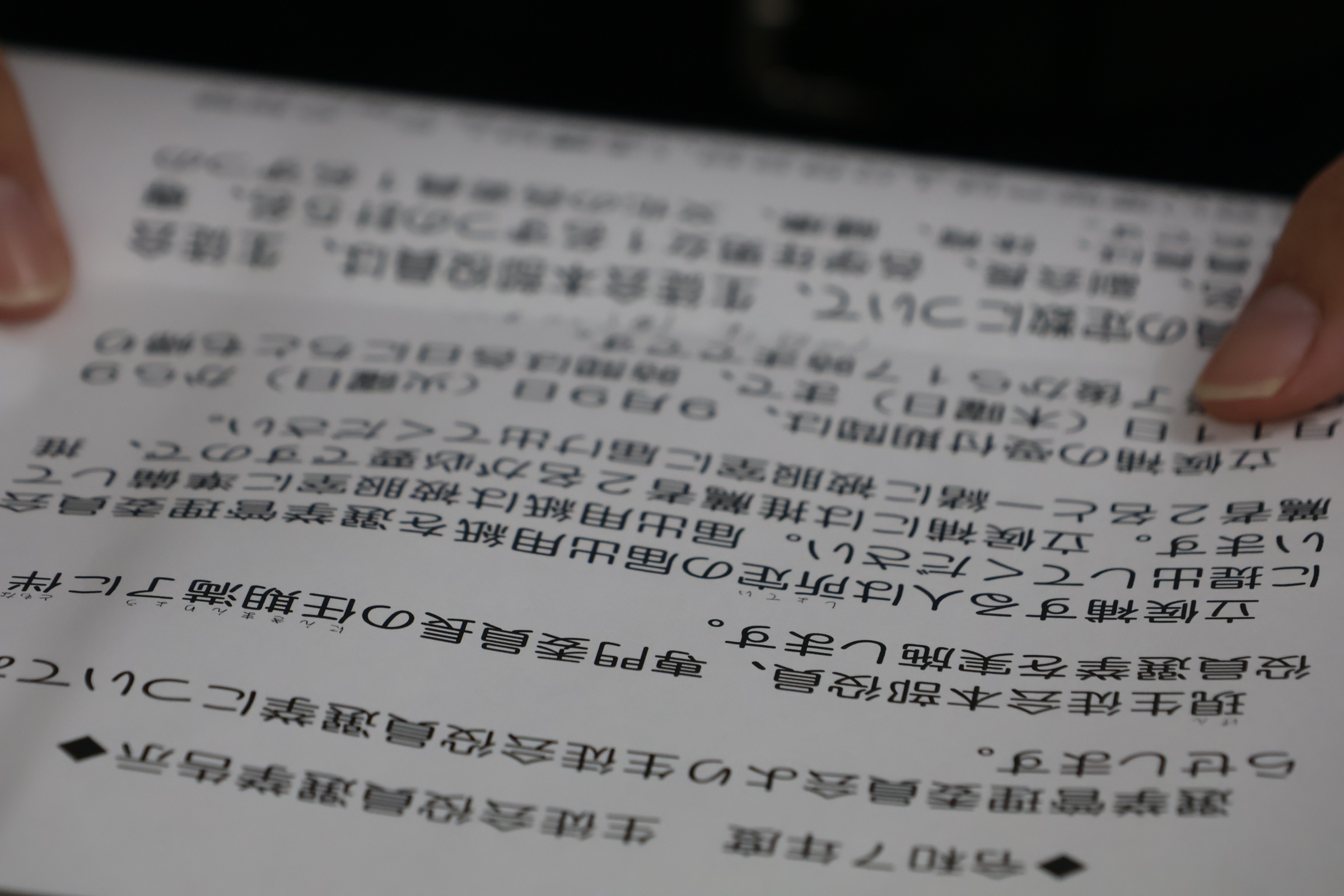
立候補者受付は11日(木)まで✨
◎聴きに来てね♬
会場は地域公民館となりました。
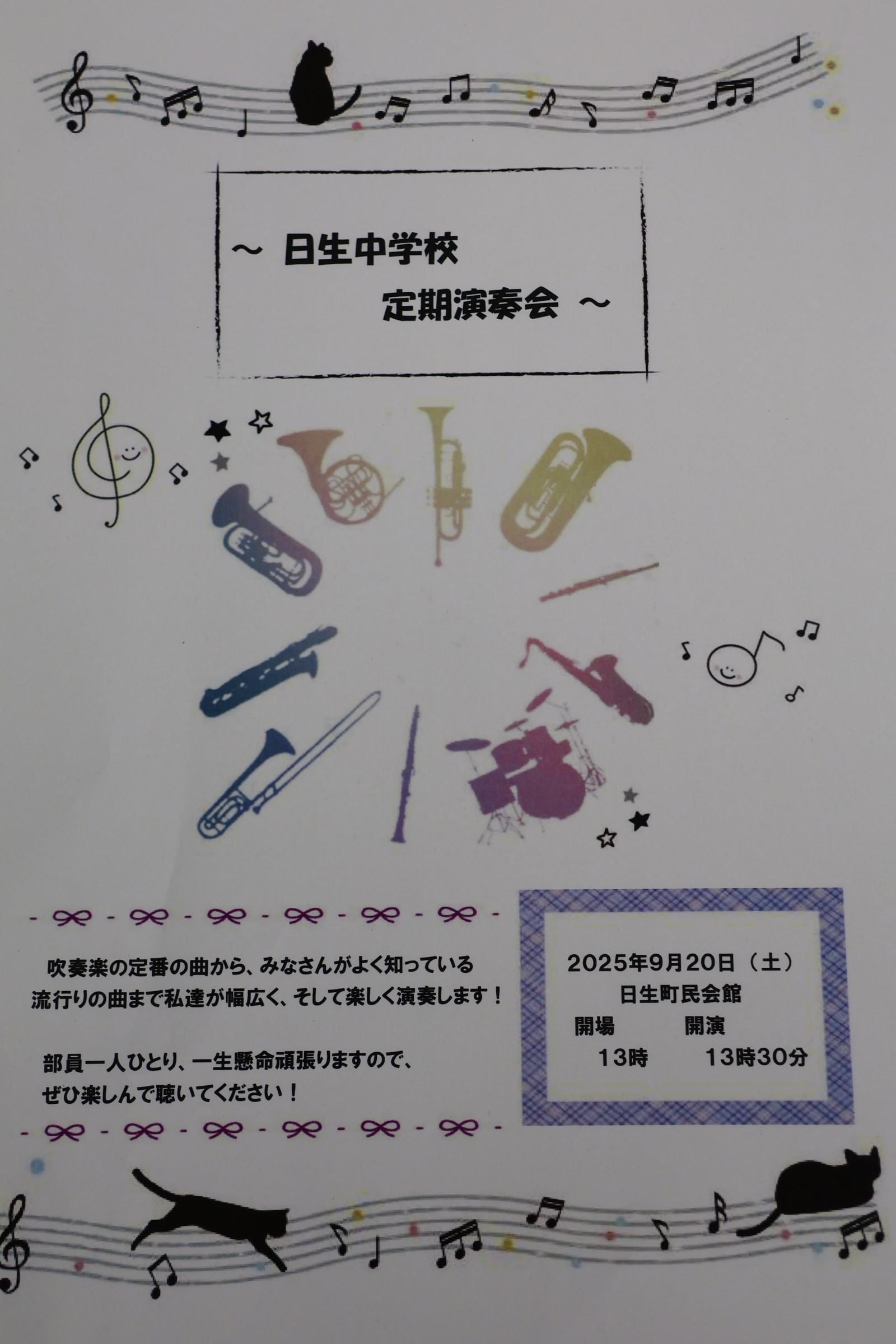
◎多くの人に支えられて
資源物回収での総重量は5740㎏、補助制度申請し28‚700円の収益となりました。ご協力をありがとうございました。PTA活動費として大切に使わせていただきます。 PTA会長

◎地域と共にある学校
先週末のあかりまつりにも多くの生徒で参加させていただきました。ありがとうございました。



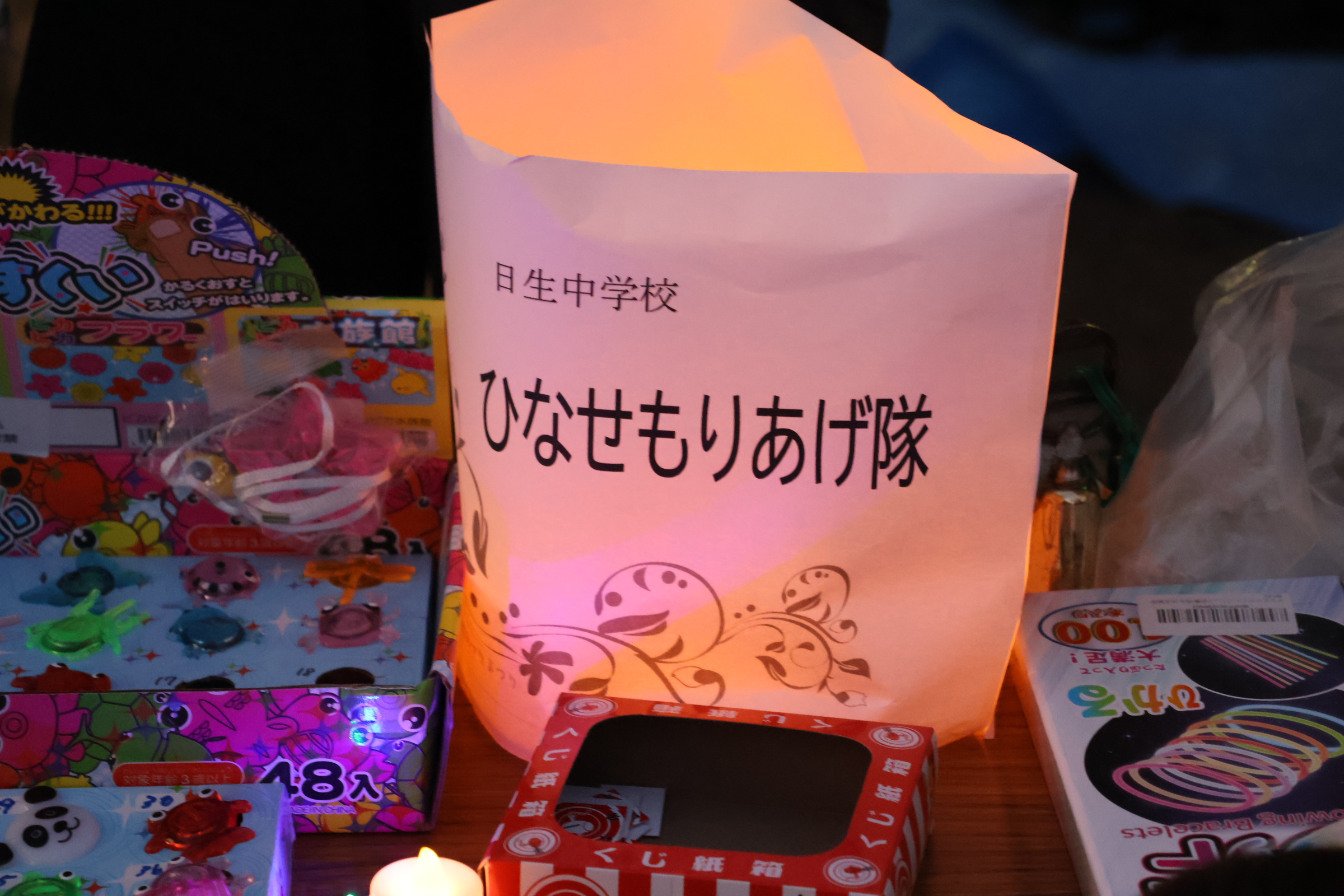





◎日生で輝く 日生が輝く(9/6)

◎どんな雲も裏は銀色に光っている(9/5:台風15号接近)
Every cloud has a silver lining.(イギリスのことわざ)


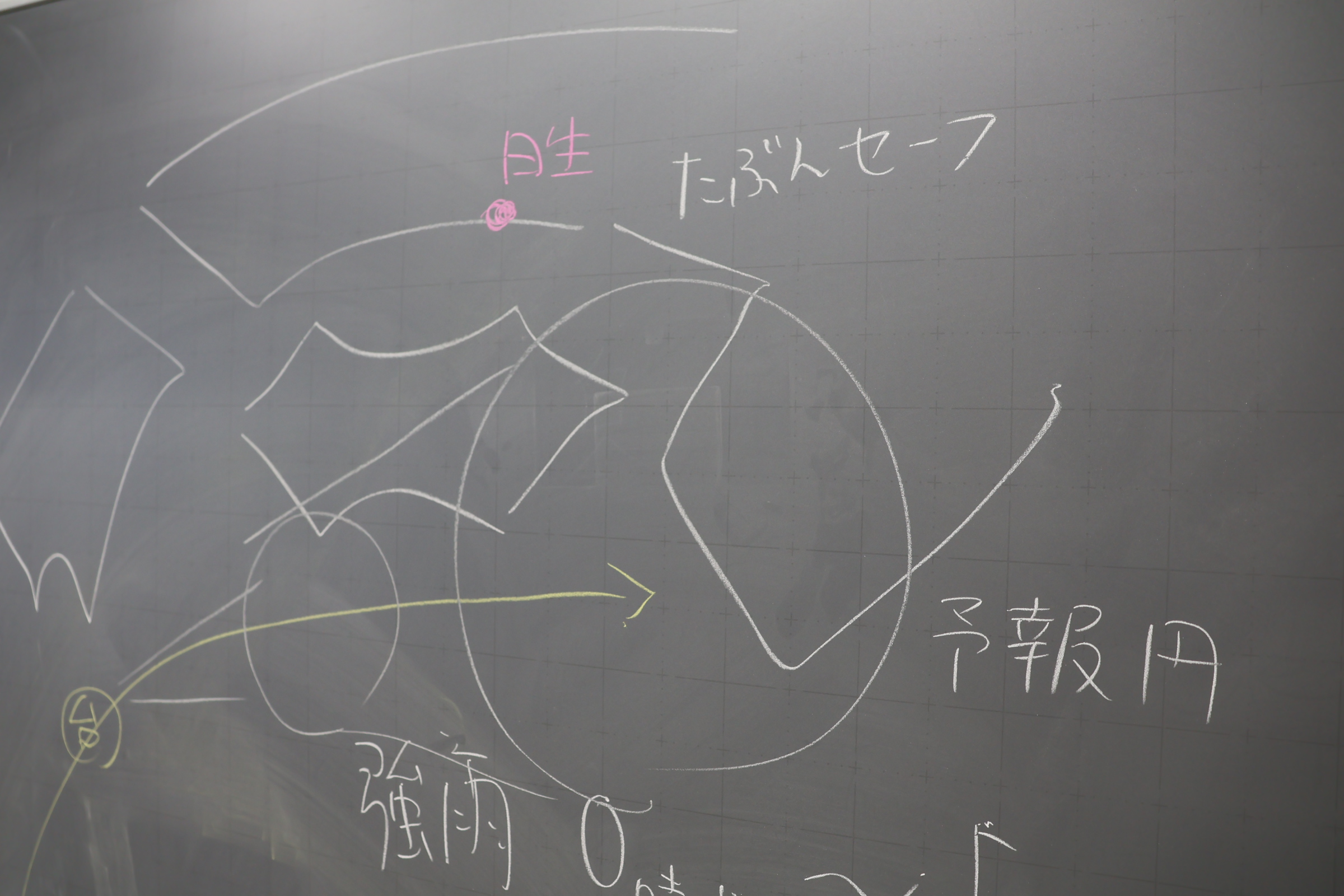



◎情報を正しく、命を大切に行動するために(9/4)
台風が接近しています。気象に関する情報をしっかりと手に入れましょう。また、警報発令時等の対応についても再確認しましょう。

◎明日のことが分からないといふことは
人の生きる愉しさをつないでゆくものだ 室生犀星 「明日になってみないと」
テニス部表彰と生徒朝礼(9/4)



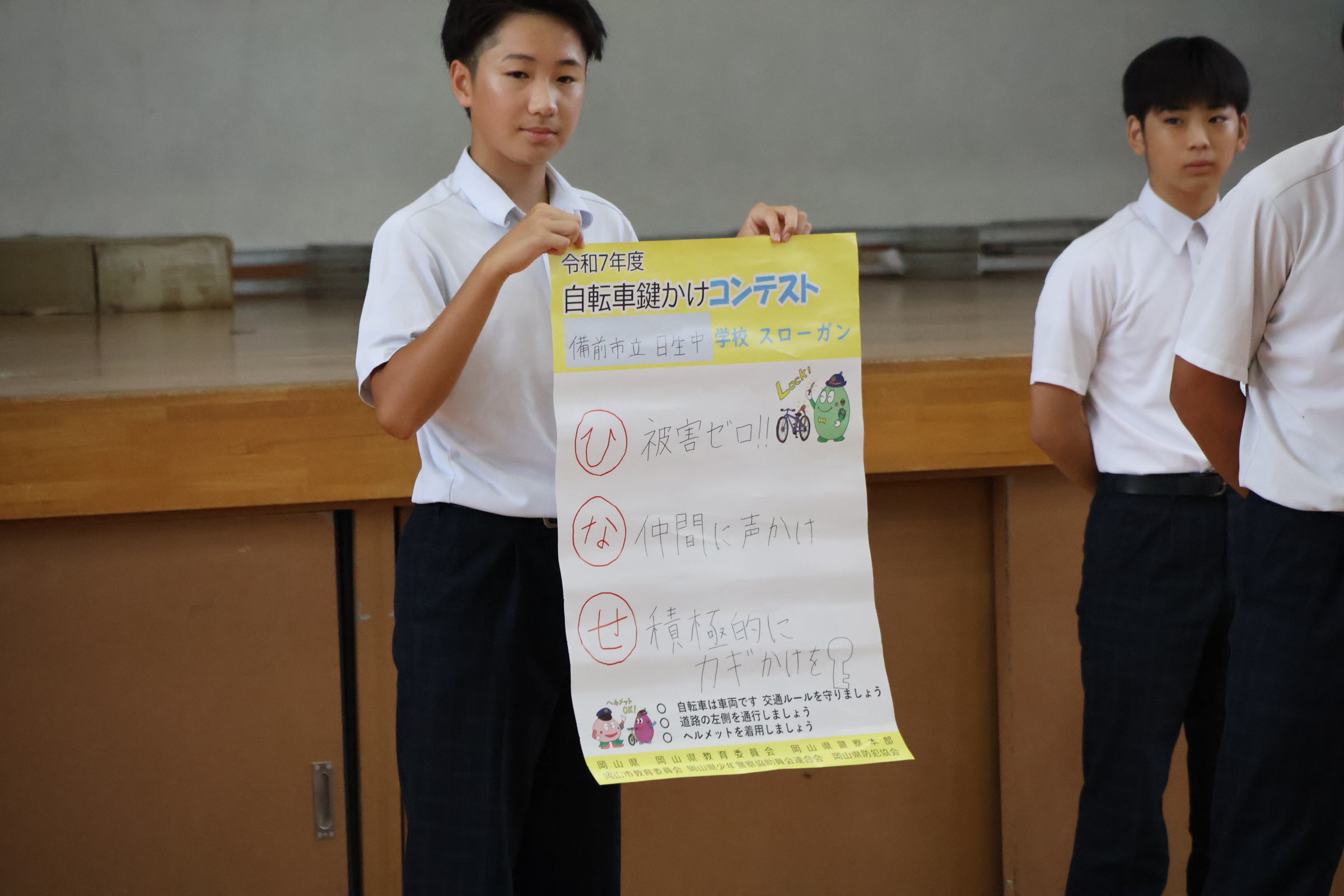


◎絆~声でつなぐ 情熱のハーモニーへ♬
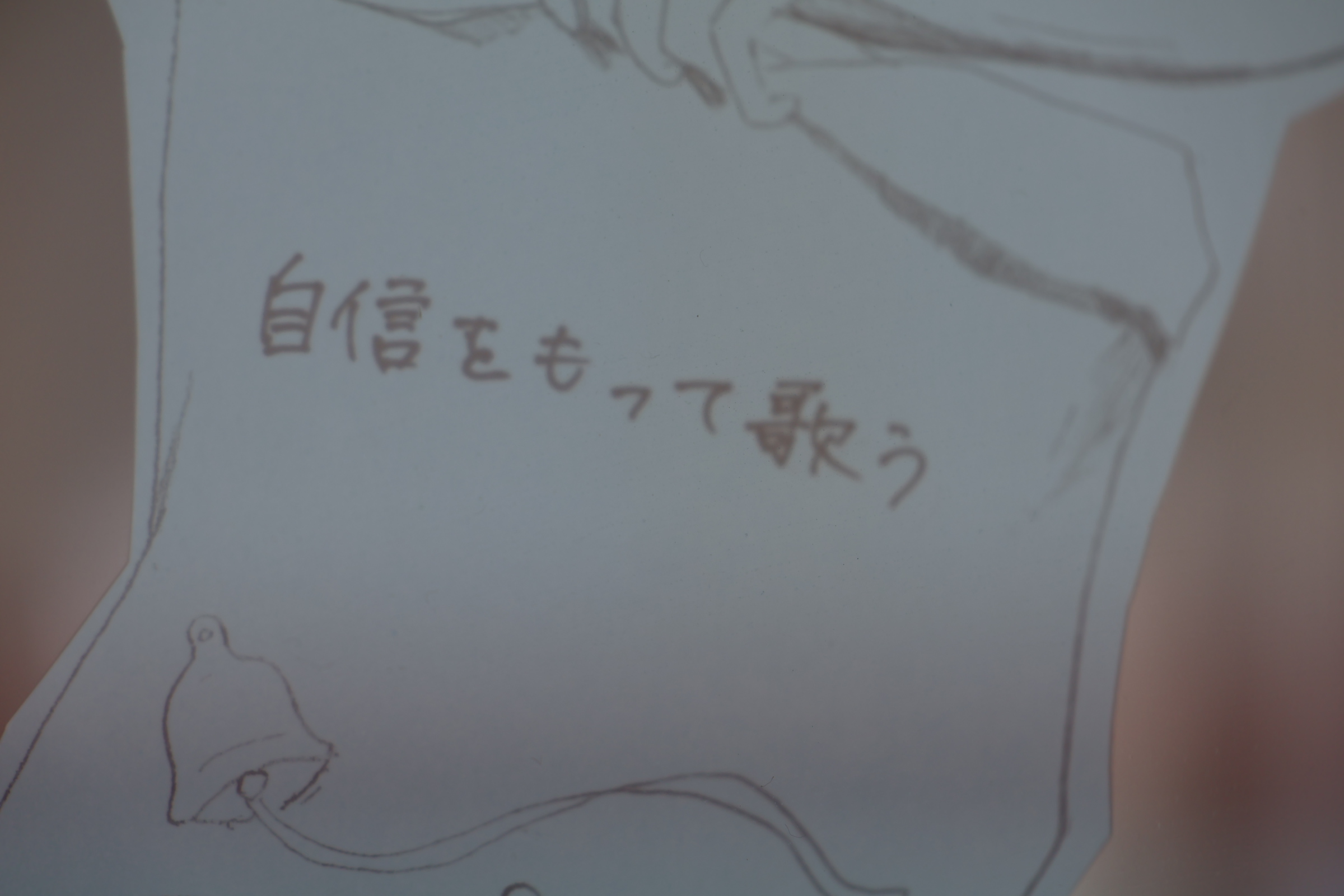
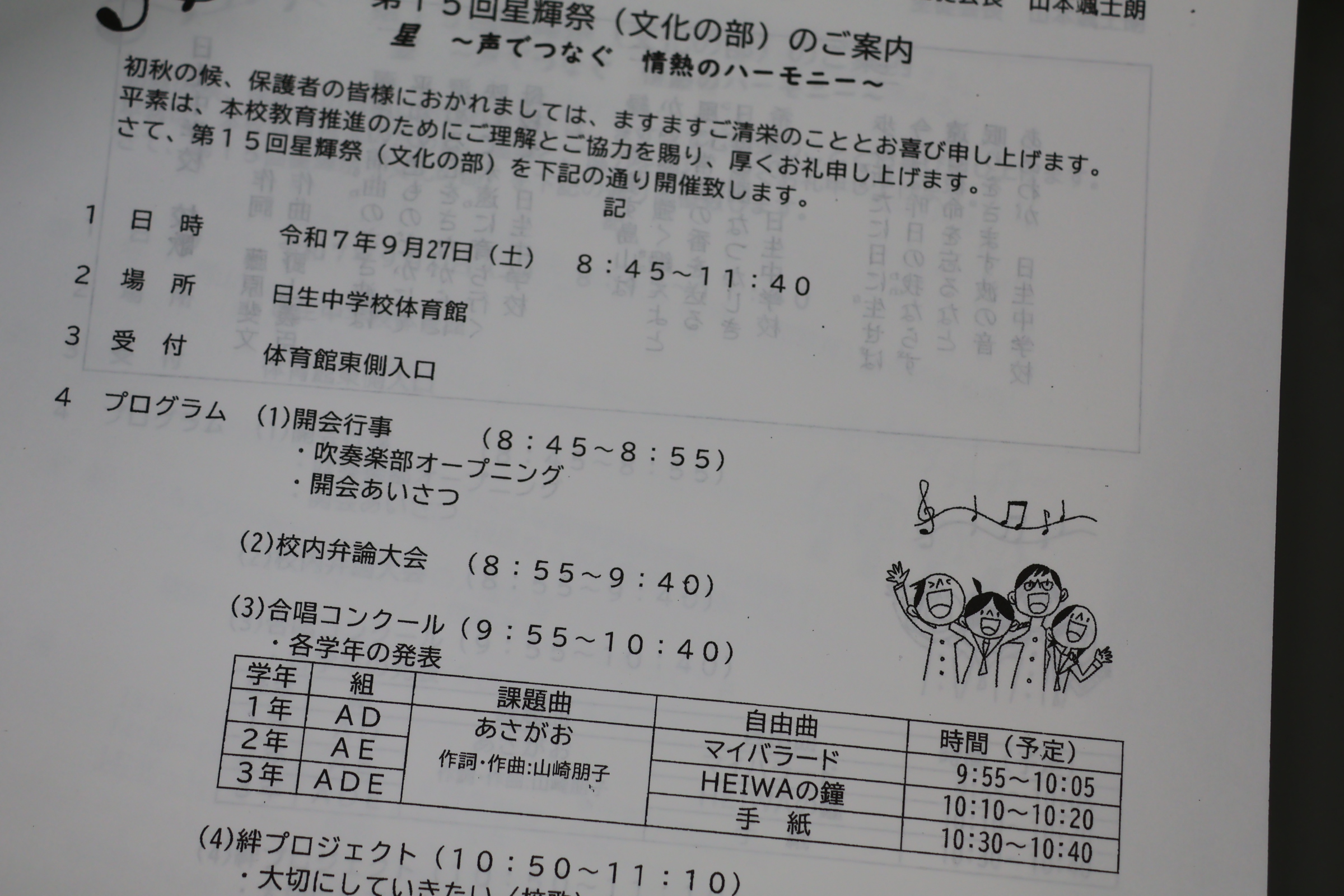
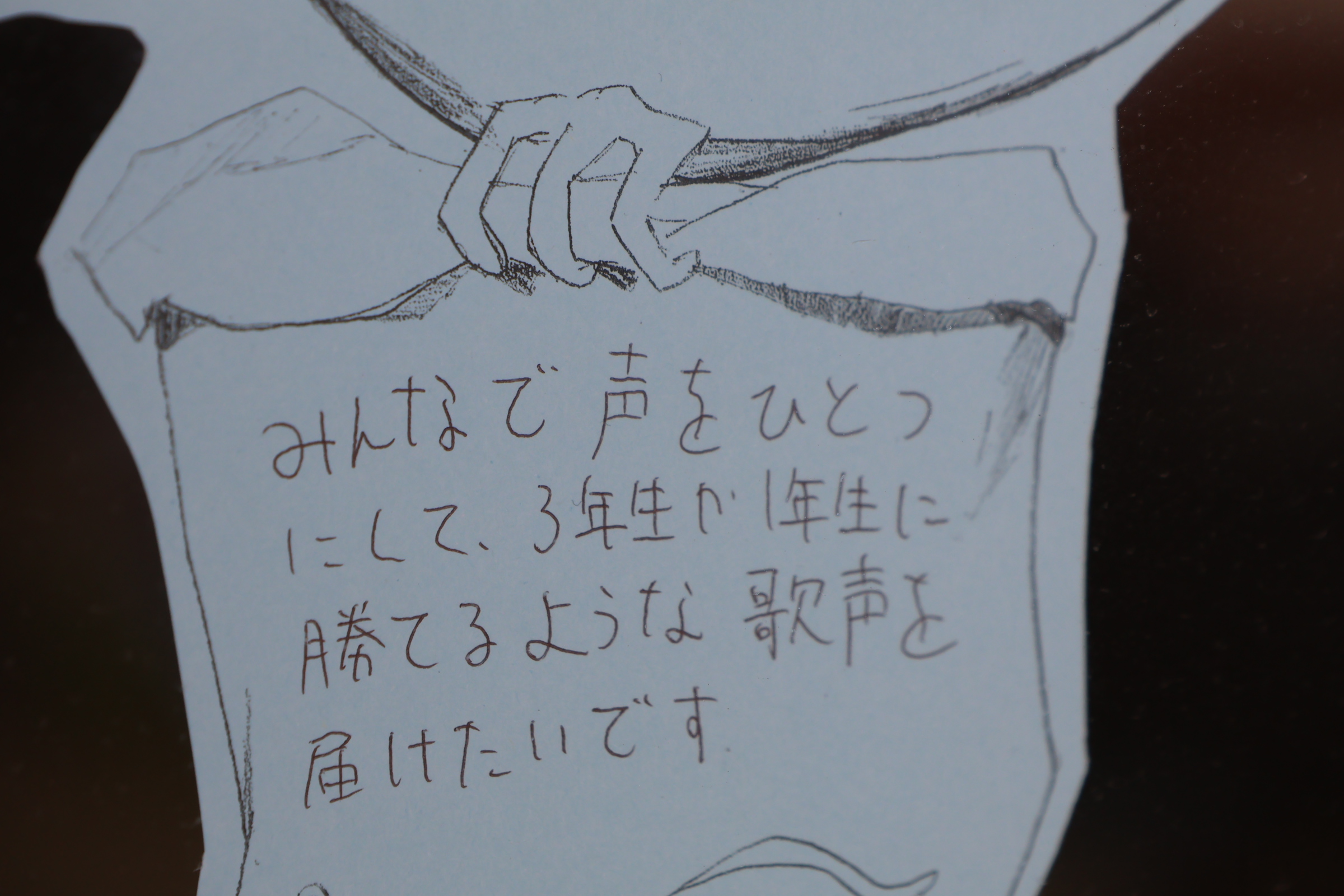
◎今日は水曜日(9/3)
ほっとスペースOPEN!、英会話教室あります(*^o^*)

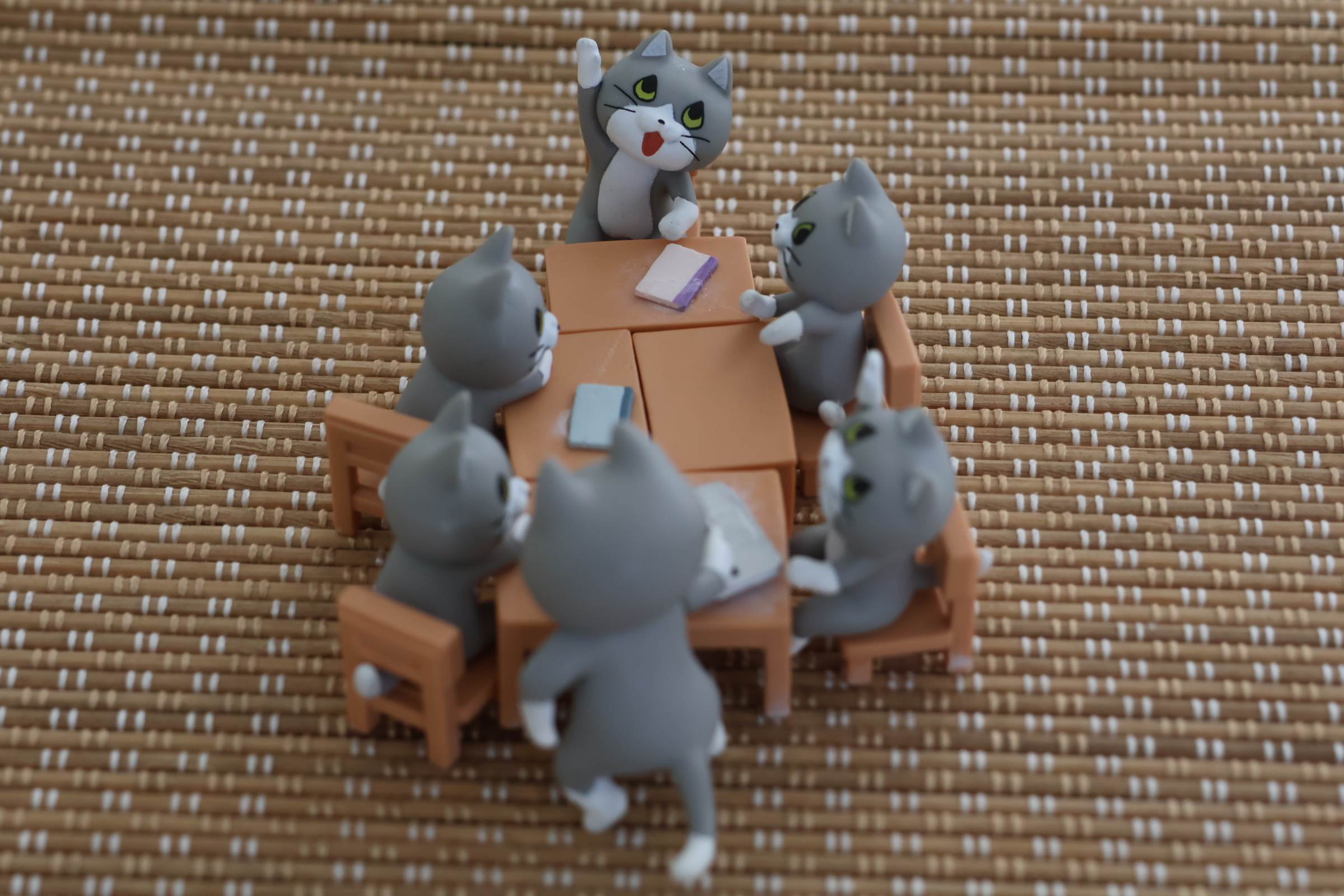
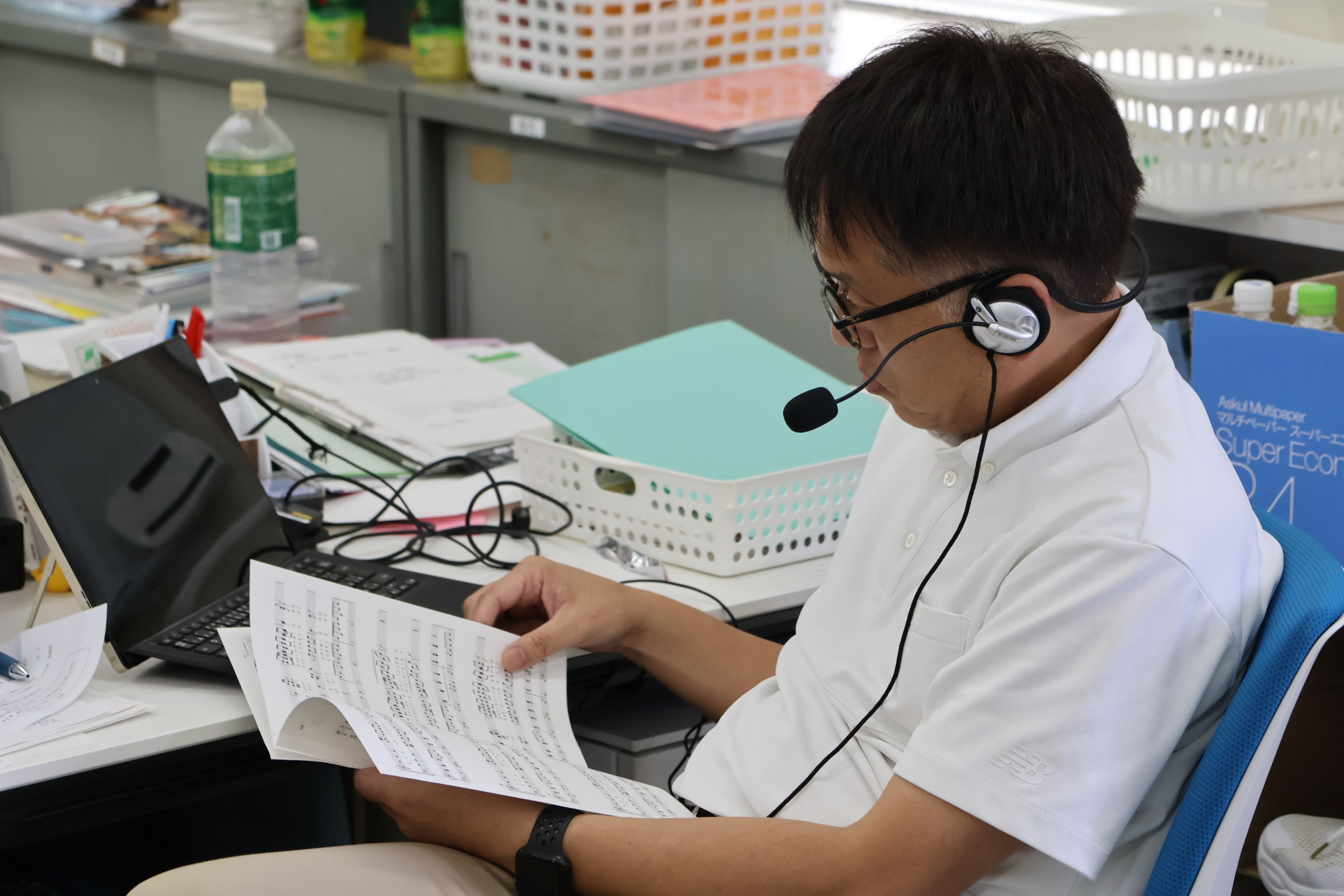
◎道を拓く 私の一所懸命(9/2:到達度テスト乗りきったよ)
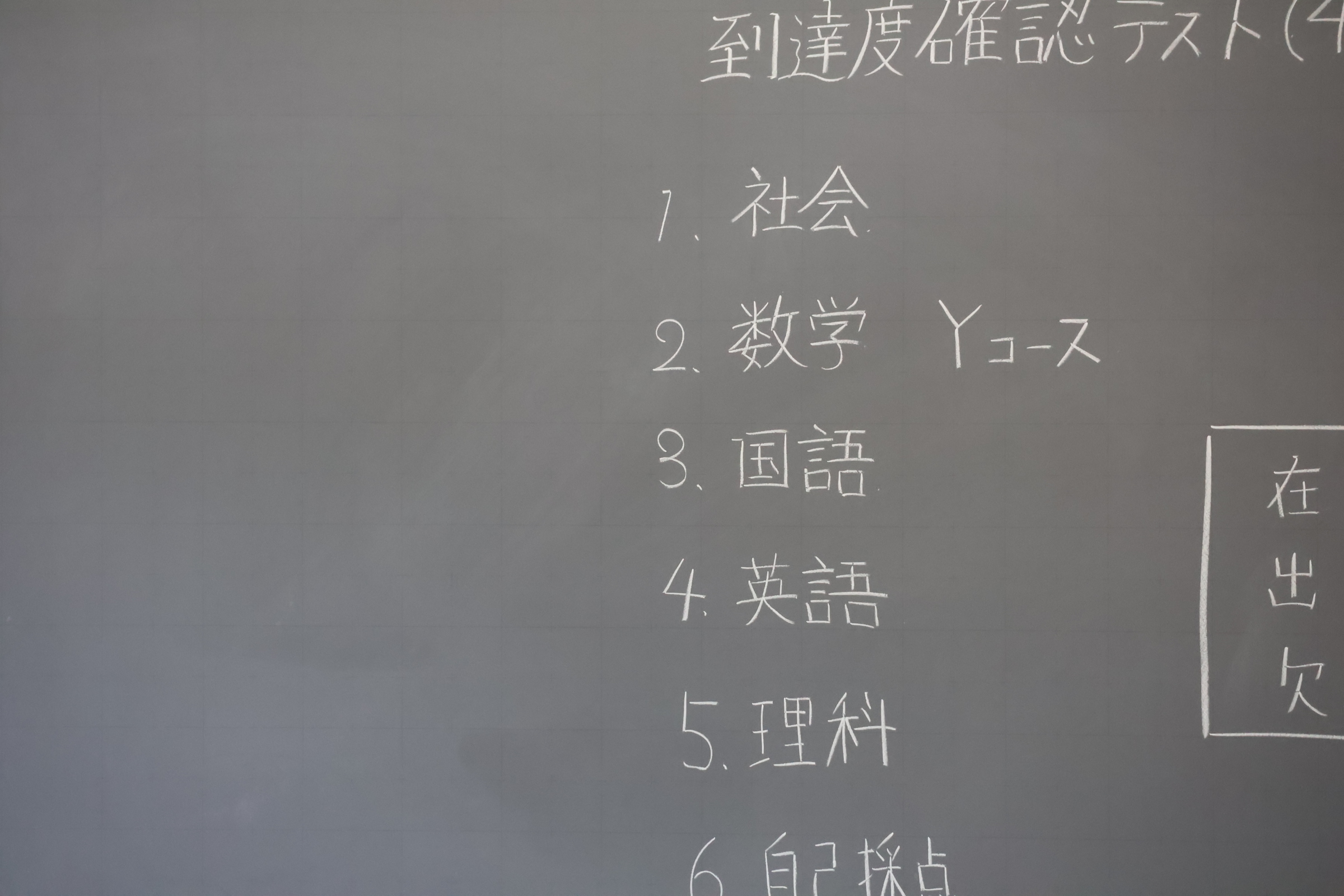
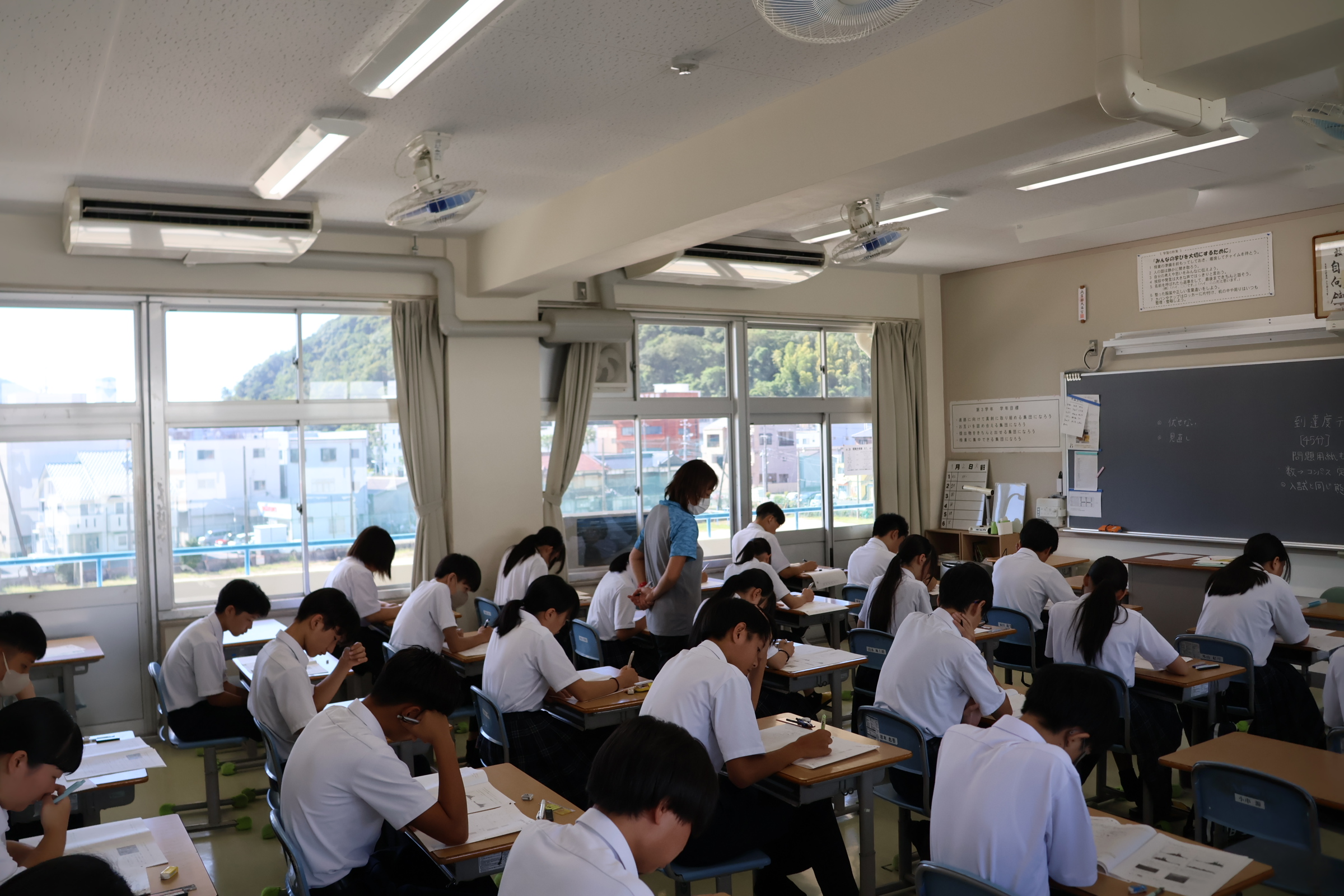
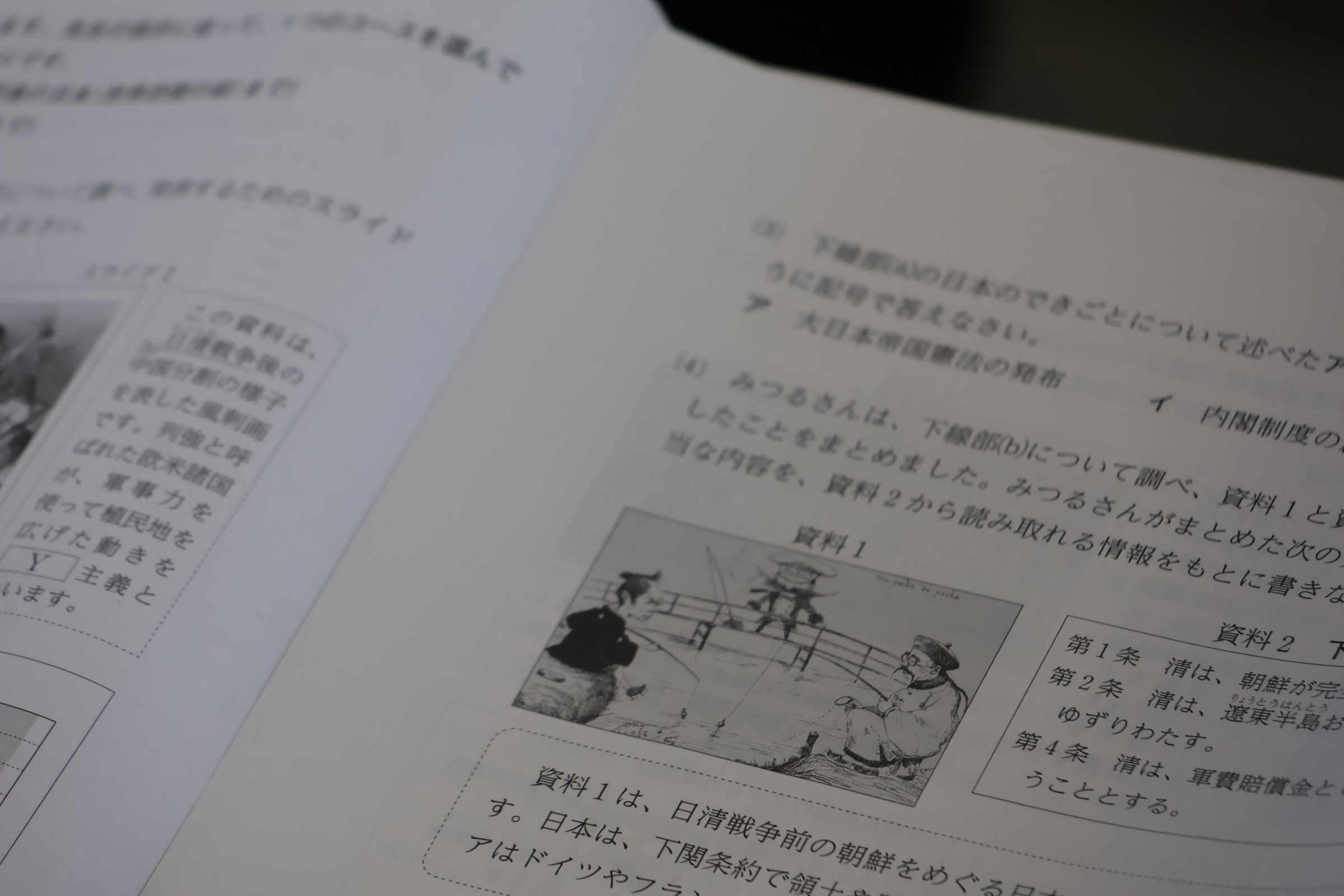
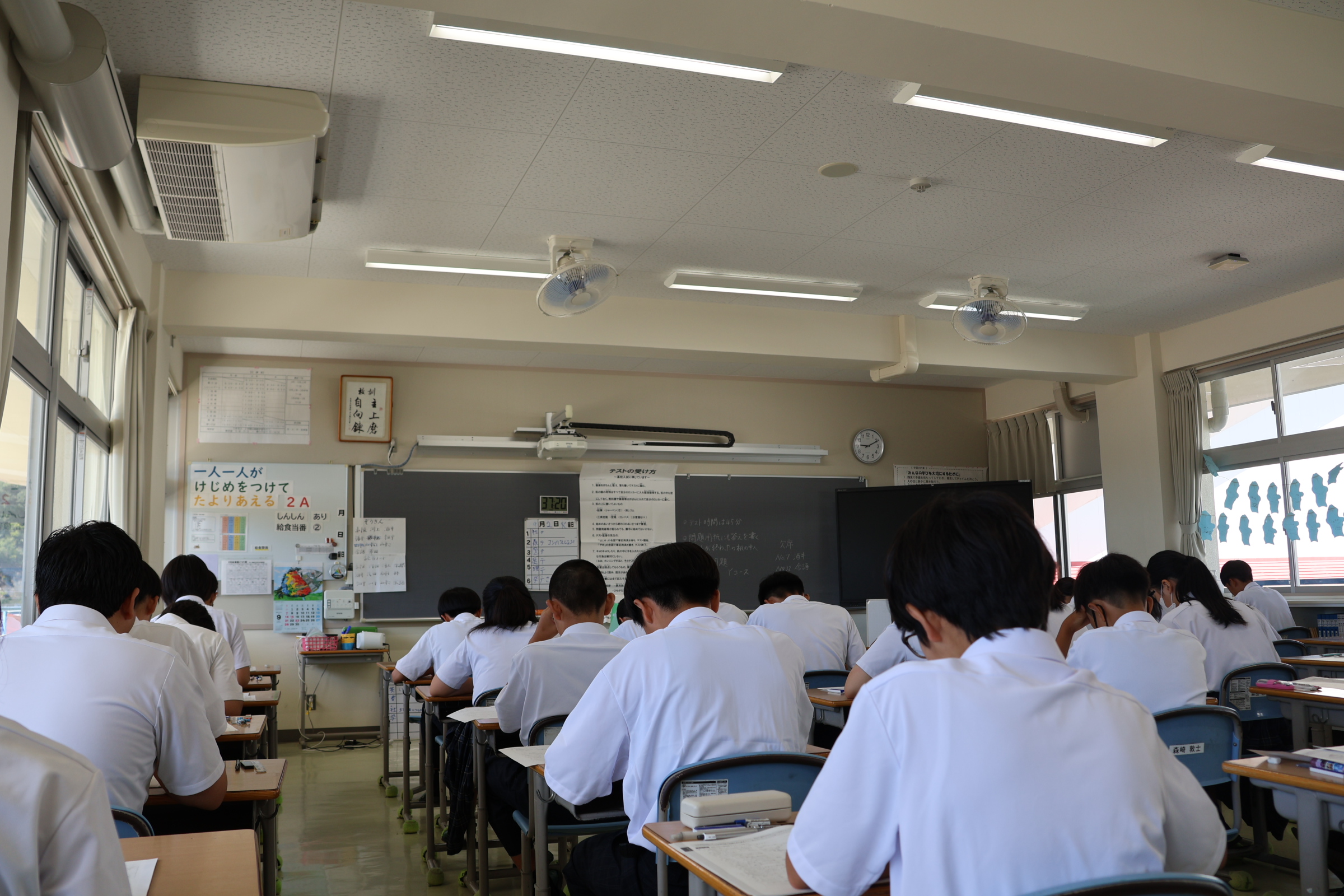

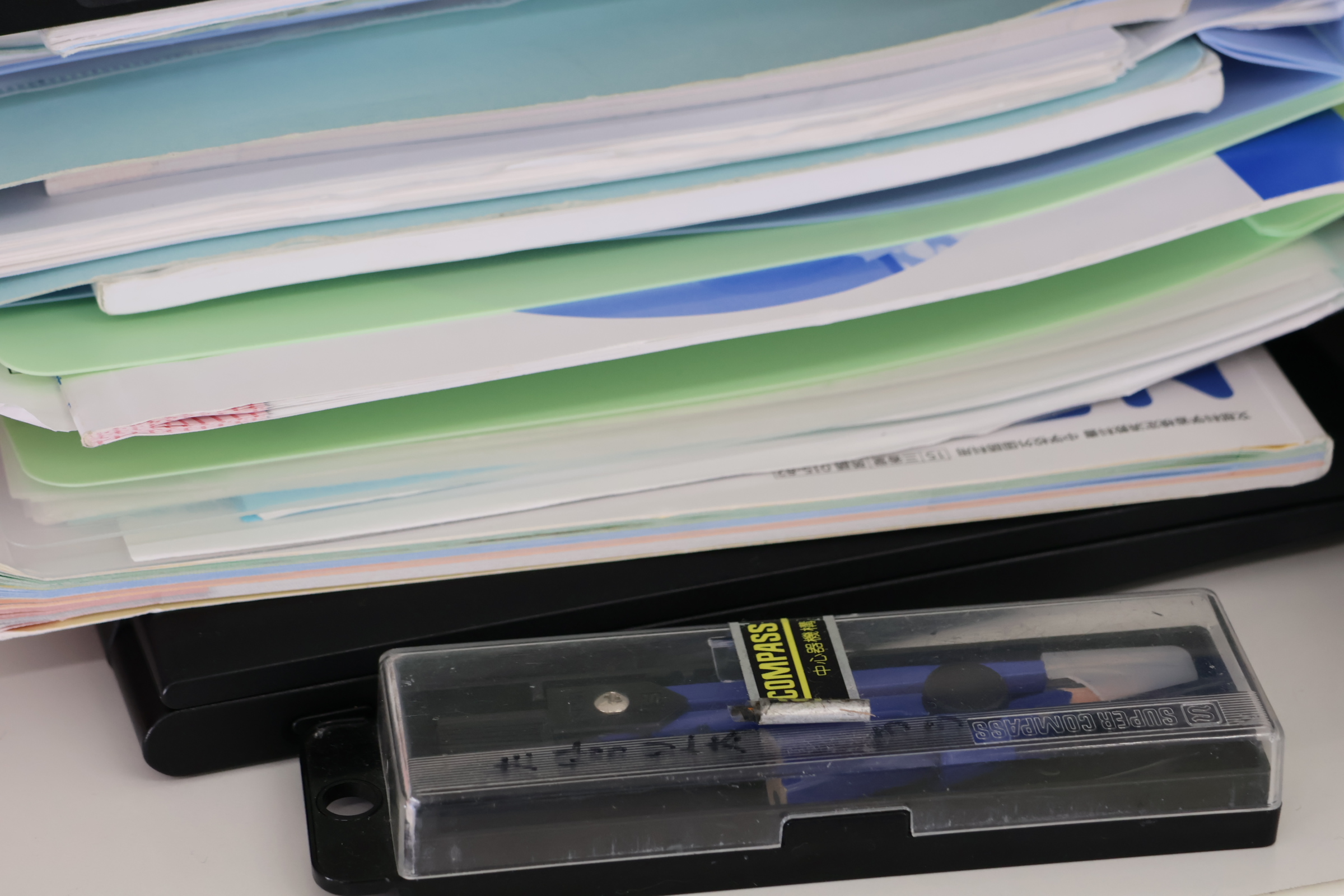
◎おはよう!勉強してきたぁ?がんばろうね(9/2:8:12)


◎日生で輝く 日生が輝く
9/6の頭島あかりまつりでの準備を進めています。小さなおともだち~、ワクワクくじを楽しみに待っていてね。

◎道を拓く 弓削丸が今年も来港!
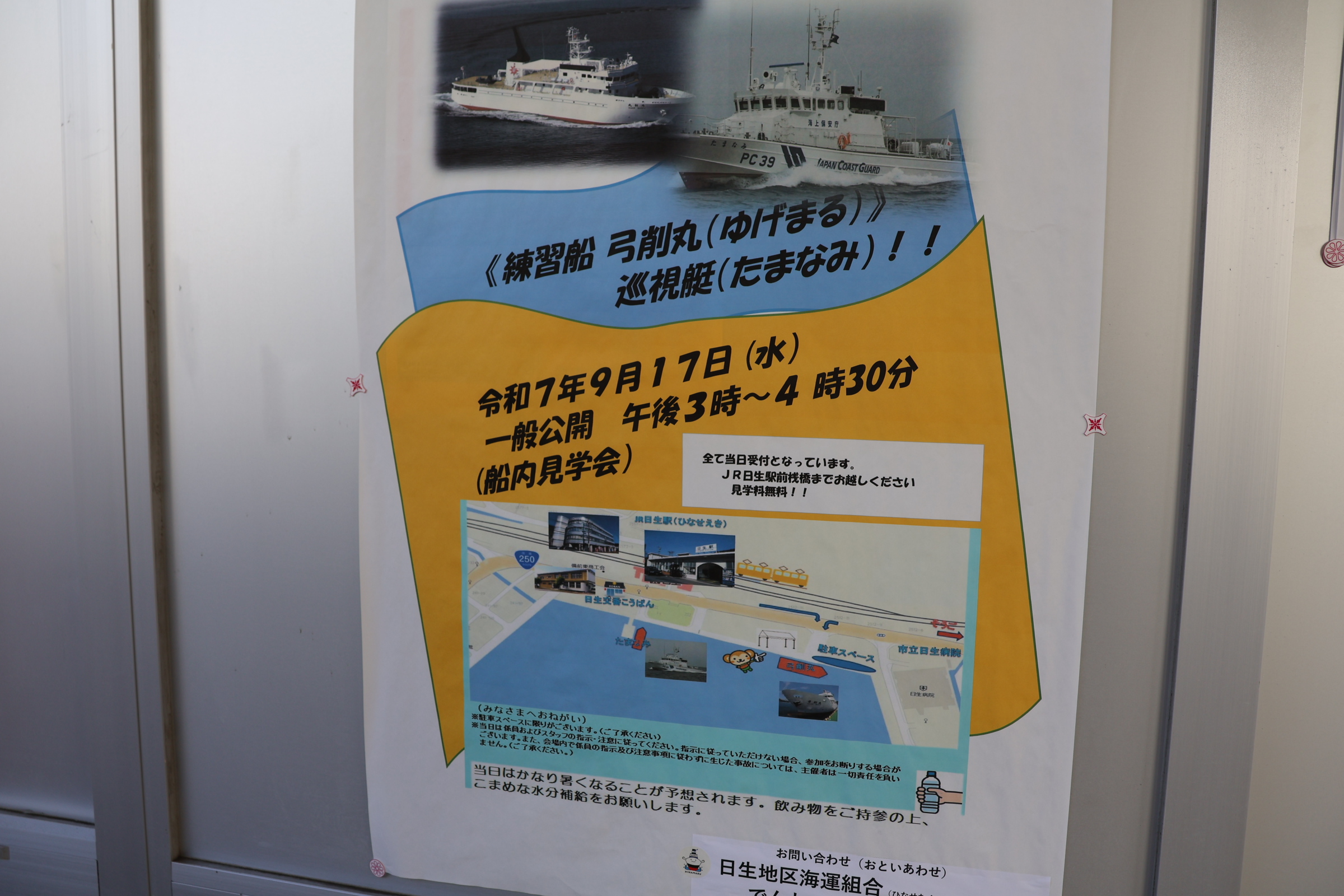
◎麒麟(きりん)闘ひて日月食し、鯨魚死して彗星出づ 『淮南子』巻三 天文訓

9月8日は皆既月食です。月食とは、太陽-地球-月が一直線に並んだ時に、地球の影の中に満月が入り込み、月の表面に太陽光が当たらなくなる現象です。9月8日(月曜日)の未明から明け方にかけて(9月7日の深夜遅く)、満月全体が地球の影の中に入る皆既月食が観測できます。今回は皆既月食の状態が1時間20分以上続く、なかなかの好条件です。月食は望遠鏡を使わなくても肉眼で十分楽しむことができ、初心者でも天体観測気分を満喫できるおすすめの天文現象です。今回の皆既月食は2022年11月以来3年ぶりに観測できるものです。月食の終盤には月が西へ低くなるため、西側の見晴らしがよい場所で見るのが良いでしょう。皆既月食中の月は、完全に真っ暗にはならず、ほんのりと赤い色(赤銅色)に色づき、たいへん美しく味わい深いながめとなります。これは、地球の影に入った月の表面を地球の大気の層を通り抜けた赤い光がほんのり照らすためです。皆既月食中は満月のまぶしい輝きが失われるため、周辺の星座の星たちも鮮やかに見ることができます。月食の観測・記録は、色えんぴつを使って月の形や色あいが時間とともに変化する様子をスケッチするのがおすすめです。月食はお子さまの初めての観測体験として最適な天文現象です。大人にサポートしてもらい楽しみましょう。次に岡山県内で観測できる月食は、半年後の2026年3月3日(火曜日)、ひな祭りの夜の皆既月食です。[倉敷科学センター 天文情報9月より]
◎星輝祭文化の部
声でつなぐ 情熱のハーモニー
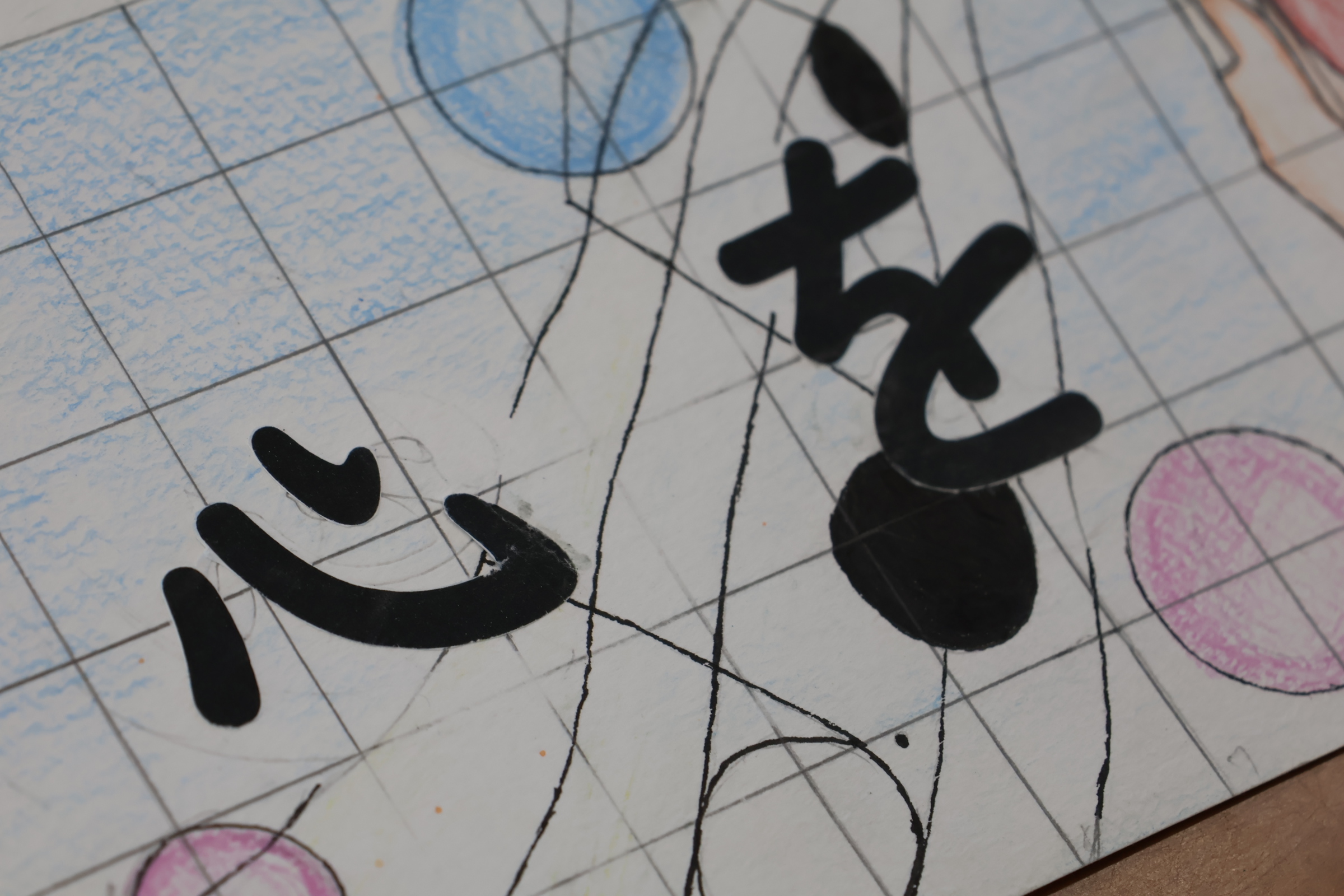
仲間と共に練習をがんばります!9/1にご案内を配布しました。
◎誇りと責任、そして絆(9/1:あいさつ運動)


◎9月 長月 September
九月、遊び過ごした天使。九月、蹠(あなうら)を焼かない砂浜。九月、もう一度ふりかへる地平線――今日は船は出てゐない。 堀口大學「九月の言葉」(『白い花束』)より




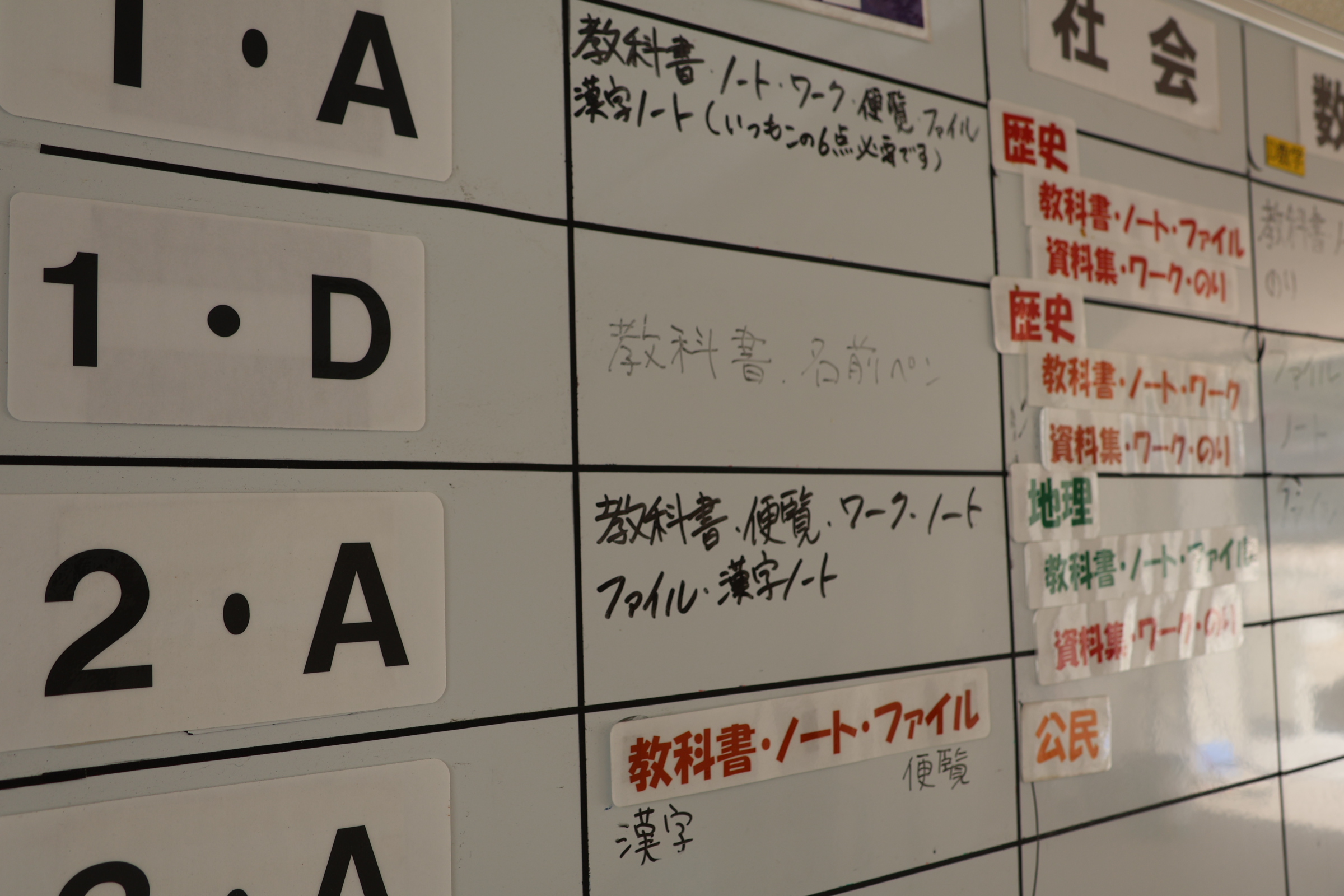

◎防災の日 防災給食に取り組みました(9/1)
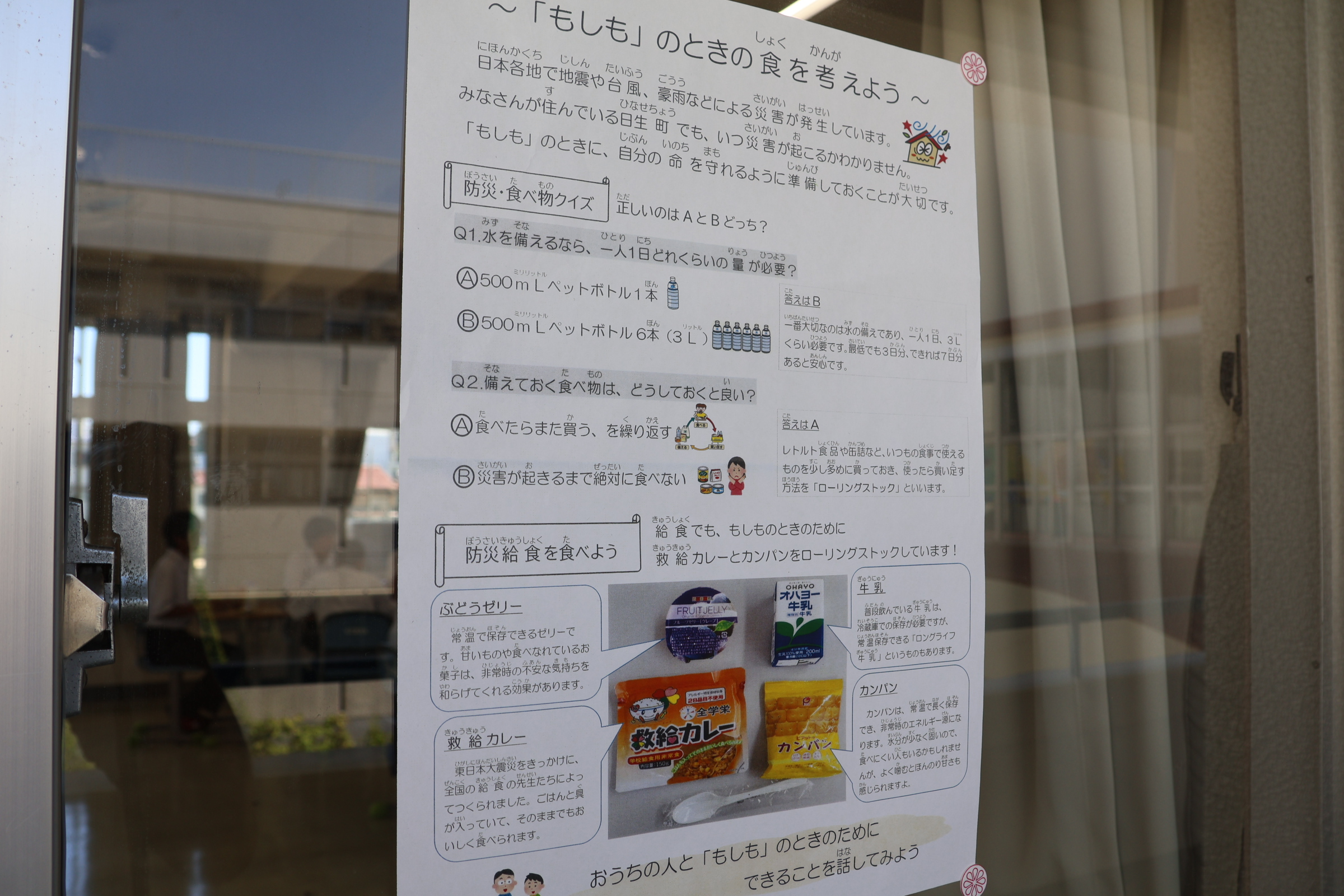








防災の日は、1923年9月1日に発生した関東大震災の犠牲者をしのび、災害からの復興を祈って1960年に内閣の閣議了解により制定されました。それ以降、「防災の日」は毎年9月1日に行われています。9月1日を中心とした8月30日から9月5日までの期間は「防災週間」とされ、9月全体は「防災月間」となっています。
関東大震災は、東京や横浜を中心に大きな被害をもたらし、多くの命が失われました。この出来事は日本にとって大きな教訓となり、防災の重要性を痛感するとともに、日本の防災の仕組みを大きく変えることにもなりました。この震災の教訓を忘れずに再び同じような被害を避けるために、日本政府は1960年9月1日を「防災の日」と定め、防災の日前後には、テレビや新聞・雑誌などを中心に多くのメディアが「防災」をテーマに取り上げて特集をします。とくに「民放NHK6局防災プロジェクト」として防災の大切さを地上波主要メディアが連携して番組やニュースを制作しています。関心をもって視聴しましょう。さらに、防災の日前後(8月・9月)は「台風シーズン」と呼ばれています。毎年、日本は多くの台風に見舞われ、そのたびに大きな被害が発生します。台風を中心にした災害の多い9月だからこそ、防災の日を通じて、台風や地震、津波などの自然災害に対する準備と対応を見直す機会としましょう。読売新聞、HHK‚ひなビジョンさんが取材に来られました。今日の「もぎたて」(NHK)で放送されます。
◎日生で輝く 日生が輝く ひと・まち・つながる











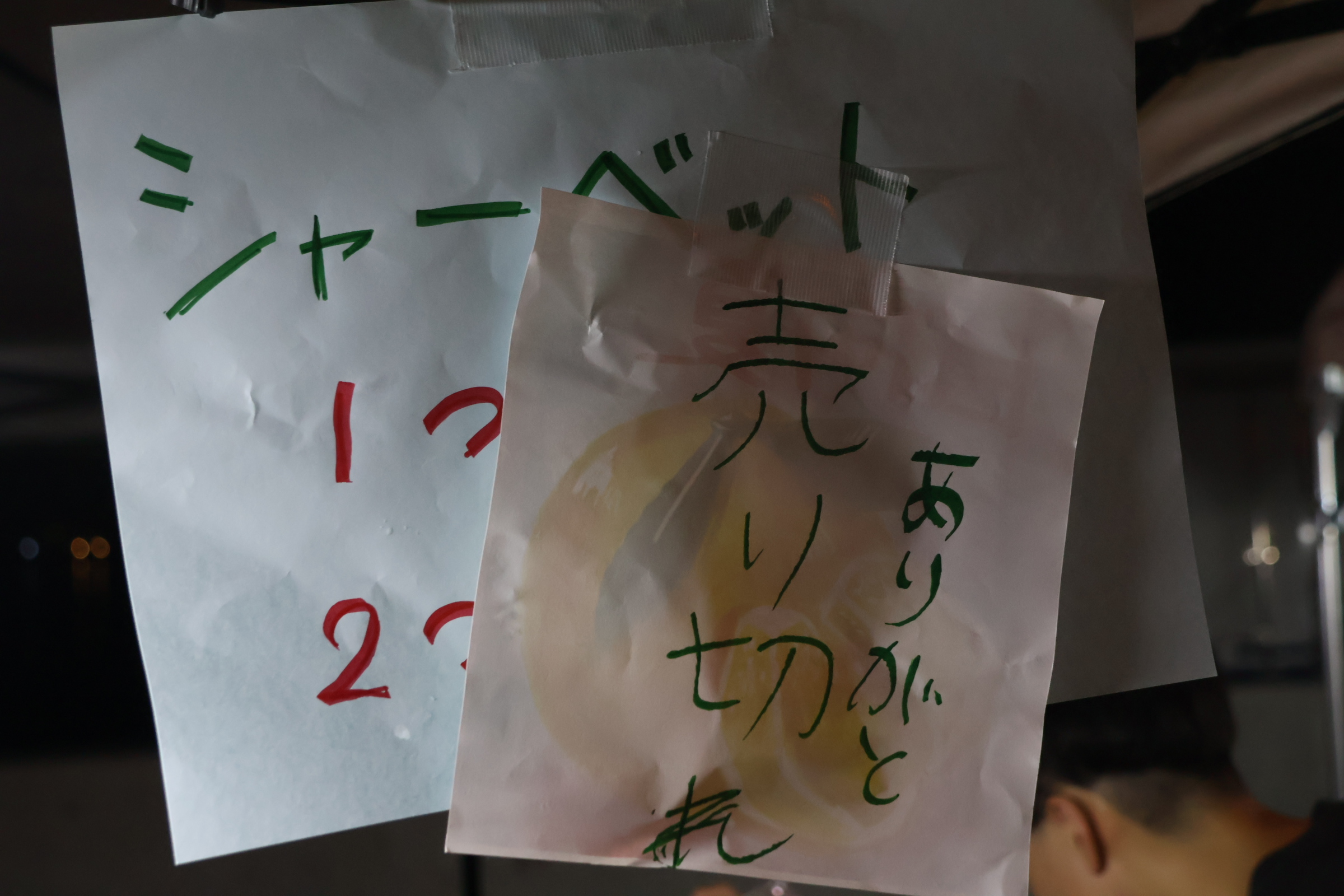
第1回ひなせランタン夜市(8/30)の開催にあたり、生徒会執行部は開会イベントへ参加、中学校地域盛りあげ隊は出店ブースでの子どもお楽しみくじと、フルーツシャーベットと飲料の提供を行いました。ご協力、ご支援をありがとうございました。また、30年ぶりとなる日生音頭による盆踊りの復活にも参加し、夜空に上がる願いをこめたランタンに思いを馳せることもできました。地域とともにある学校として、来週も頭島あかりまつり頑張ります。来場をお待ちしています!応援よろしくお願いします。
◎出会いに心をこめて(8/29:だっぴしました!)

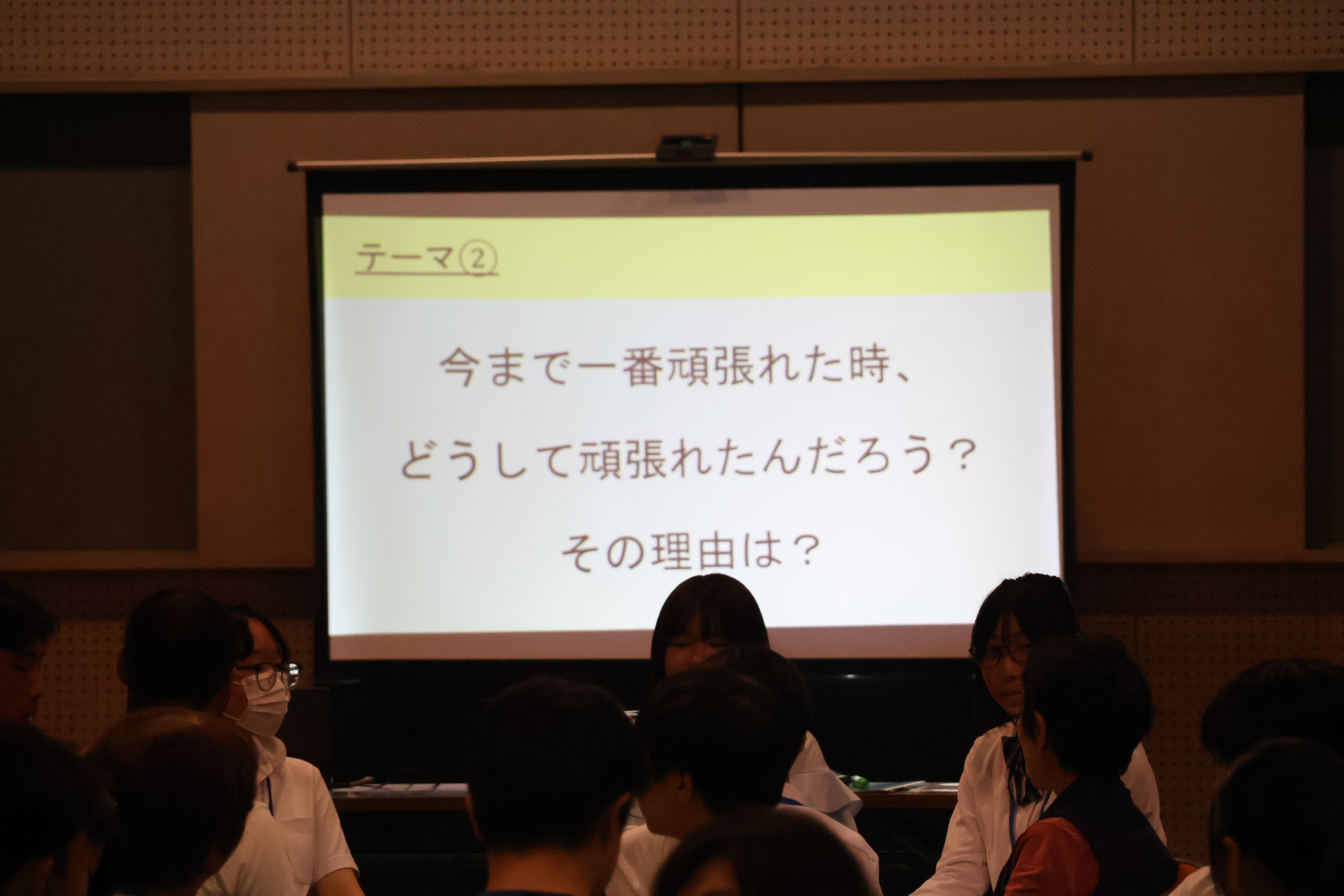

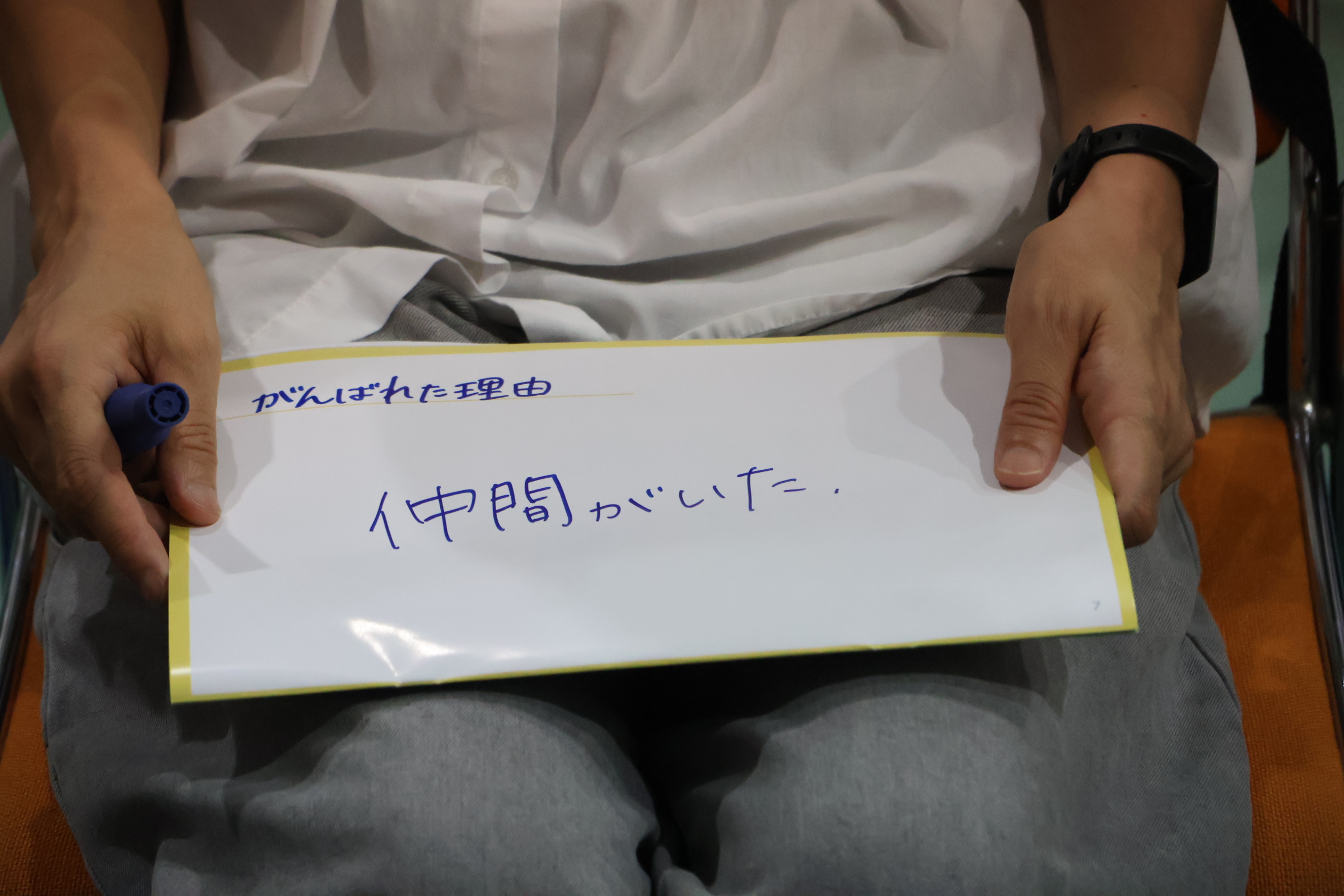





◎多くの人に支えられて(8/29)
学習環境の整備を積極的に進めています。暑い中山本スポーツさんありがとうございました。

◎一人ひとり 進路を切り拓く
春15の会について山陽新聞の記事(8/28)を紹介します。準備にかかわった実行委員会の皆さん、相談会に来てくださった高校関係の方々ありがとうございました。中学校区からもたくさんの保護者や生徒が参加させていただきました。2学期も、一人ひとりの進路実現に向けて、充実した学校生活がおくれるように支援・サポートしていきたいと思います。

◎多くの人に支えられて(8/28)
熱中症対策のために備前市が設置したウオーターサーバーの定期点検日でした。暑い中での点検作業をありがとうございました。まだまだ暑い日が続きそうですので、各自の水筒への補充を中心に2学期も大切に利用したいと思います。

◎朝には意味があり 宵には感情がある(8/27:始業のつどい)
in the morning is meaning ‚in the evening there is feeling.ガートルード・スタイン『やさしい釦(ボタン)』
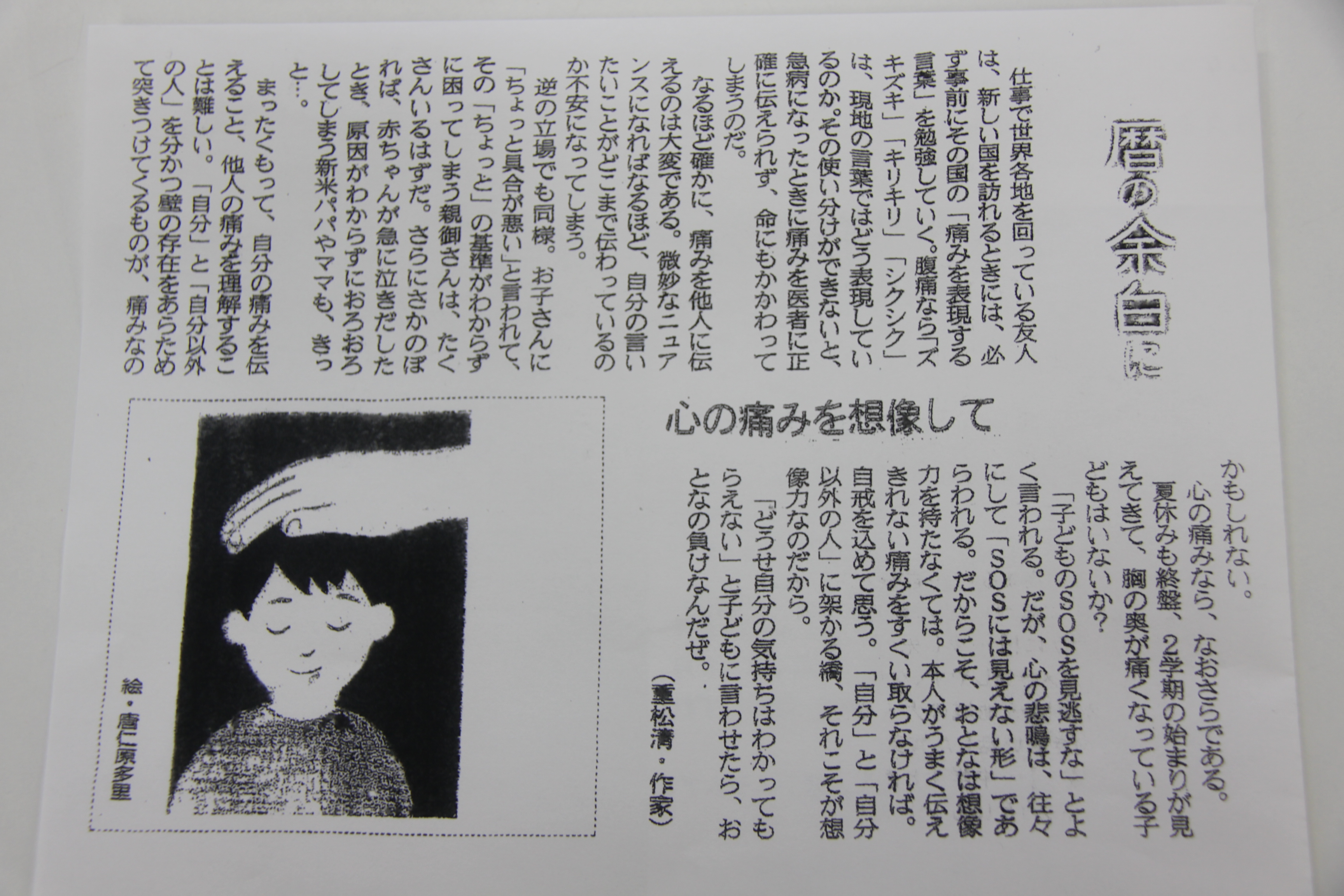
2学期最初の時期は、みんな不安や悩みをもつことがしばしばあります。何かお子さんのことで心配やご相談がありましたら、お気軽に学年団や学校へご連絡ください。〈0869ー72-1365〉(^_^)
◎人権宣言記念日(8/26)
1789年8月26日、フランス革命のさなか、憲法制定国民議会によって「人間と市民の権利の宣言(通称:人権宣言)」が採択されました。この宣言は、自由・平等・言論の自由・人民主権など、現代の人権思想の根幹をなす原則を明記した、歴史的にも画期的な文書です。 この日を記念する「人権宣言記念日」は、私たちが日々の暮らしの中で人権の大切さを再認識し、互いの尊厳を尊重する姿勢を育むための機会とされています。また、この宣言は世界中の人権保護の基準にも大きな影響を与え、ユネスコの「世界の記憶」にも登録されるなど、その普遍的な価値が国際的に高く評価されています。
◎地域と共にある学校として(8/25)
今年(9/27)も、日生地区栄養委員会・日生地区愛育委員さんが、星輝祭文化の部の当日に、保護者対象の健康相談ブースを開設してくださいます。その打ち合わせを、この日市保健課健康係さんと行いました。文化の部に来校された際には、測定コーナーがあり、血管年齢、血圧測定、骨の健康チェック、握力測定等が無料で受けられます。日生中はこれからも地域連携・協働活動を通した、〈地域・学校づくり〉を大切にしてきます。

◎脱皮します(8.29)
今年度も、たくさんの方々のご協力をいただき、2年生は〈だっぴ〉に取り組みます。今年は、吉永中学校と合同でリフレセンター備前を会場に行います。(*^o^*)

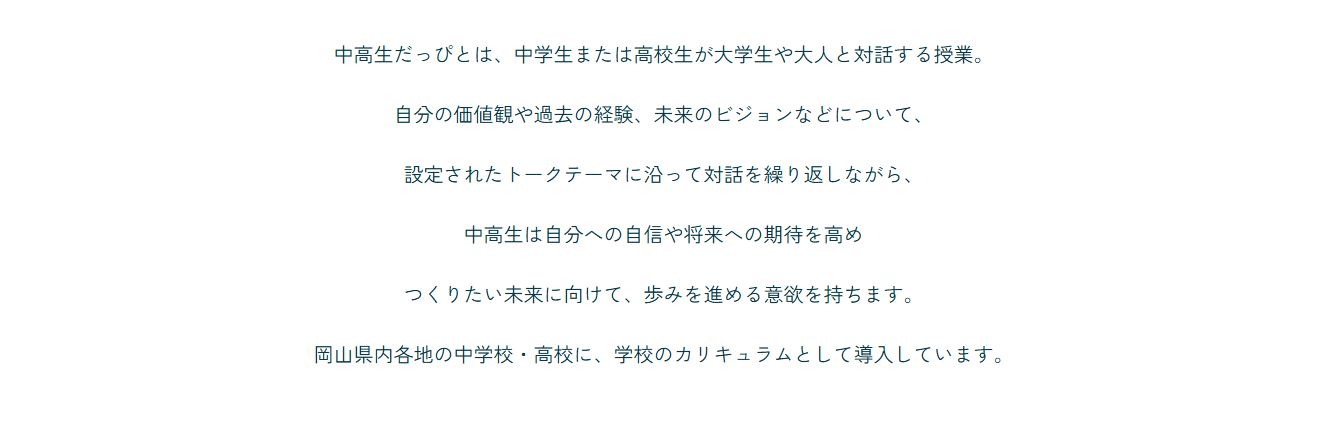
HPもごらんください。
◎自分らしい進路は必ずある(8/23:春15の会)
春15の会(特別支援教育のニーズのある子どものための進路情報交流学習会)実行委員会は、日生中学校を会場にお借りして情報交流会を開催されました。保護者・生徒、教員、支援者、福祉関係、高校、進路機関の方々を合わせて125名の参加がありました。座談会では、岡山御津高校の末廣さんからは学校生活の状況について、メンターや就労先の企業の立場から二井さんからお話しをしていただきました。継いで中学校からは今の入試制度のしくみ(進路計画)のお話しがありました。コーディネーターの朝倉さんは〈自分で決める〉ことをキーワードに、進路実現にむけて多機関連携の必要性などをまとめてくださいました。午後からは23ブースでの個別相談会と学校説明をおこないました。また、YouTube配信での進路情報は11月28日まで視聴することができます。ゆっくり、じっくりとご覧ください。






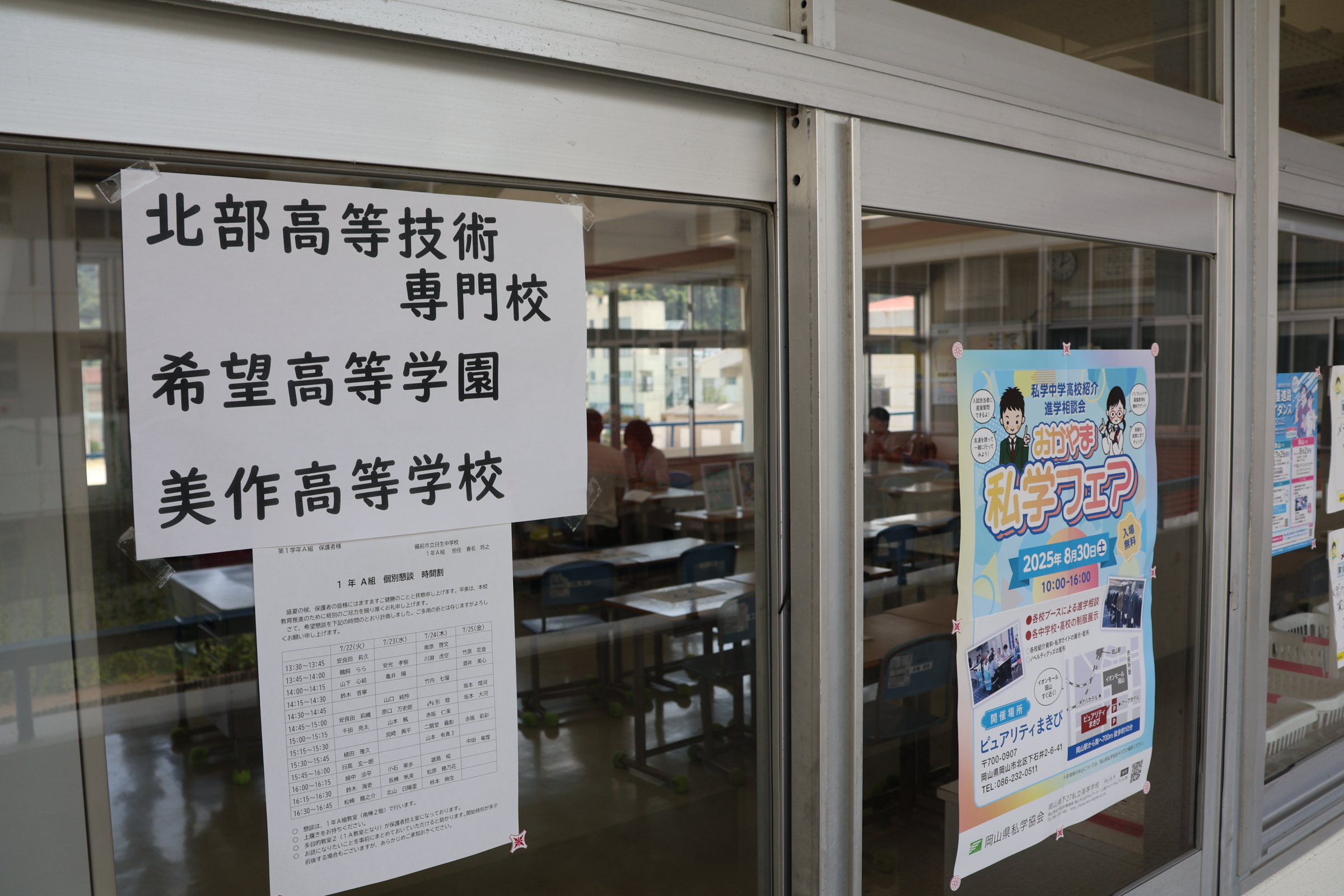


◎日生が輝く 日生で輝く
観光協会からご案内をいただきました。
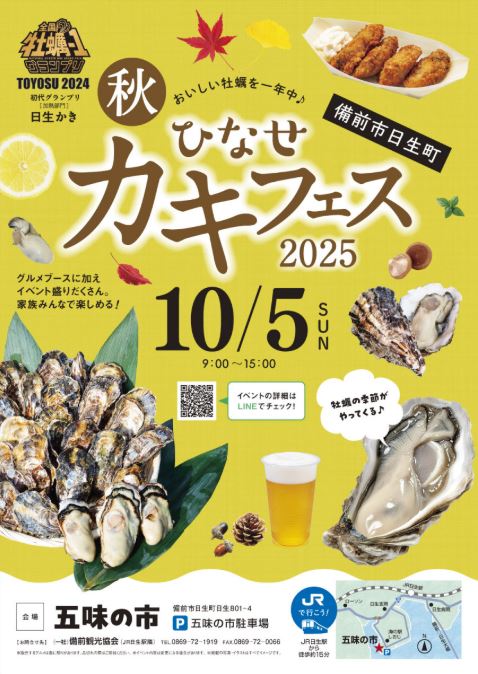
◎山陽新聞を掲示しています~NIESで社会につながる~
滄海月明らかにして珠に涙あり


月が明るい夜、蒼い海で人魚が流す涙は真になるという 李商隠「錦瑟」
◎だけど君の永遠の夏は色あせない(夏休みももう少し)
今年も、文化委員会は小学校へ中学生出前お話し会で訪問(7/31、8/1)してきました。たくさんの小学生に喜んでいもらいました。また、本校での図書館イベントも楽しい時間を過ごすことができました。




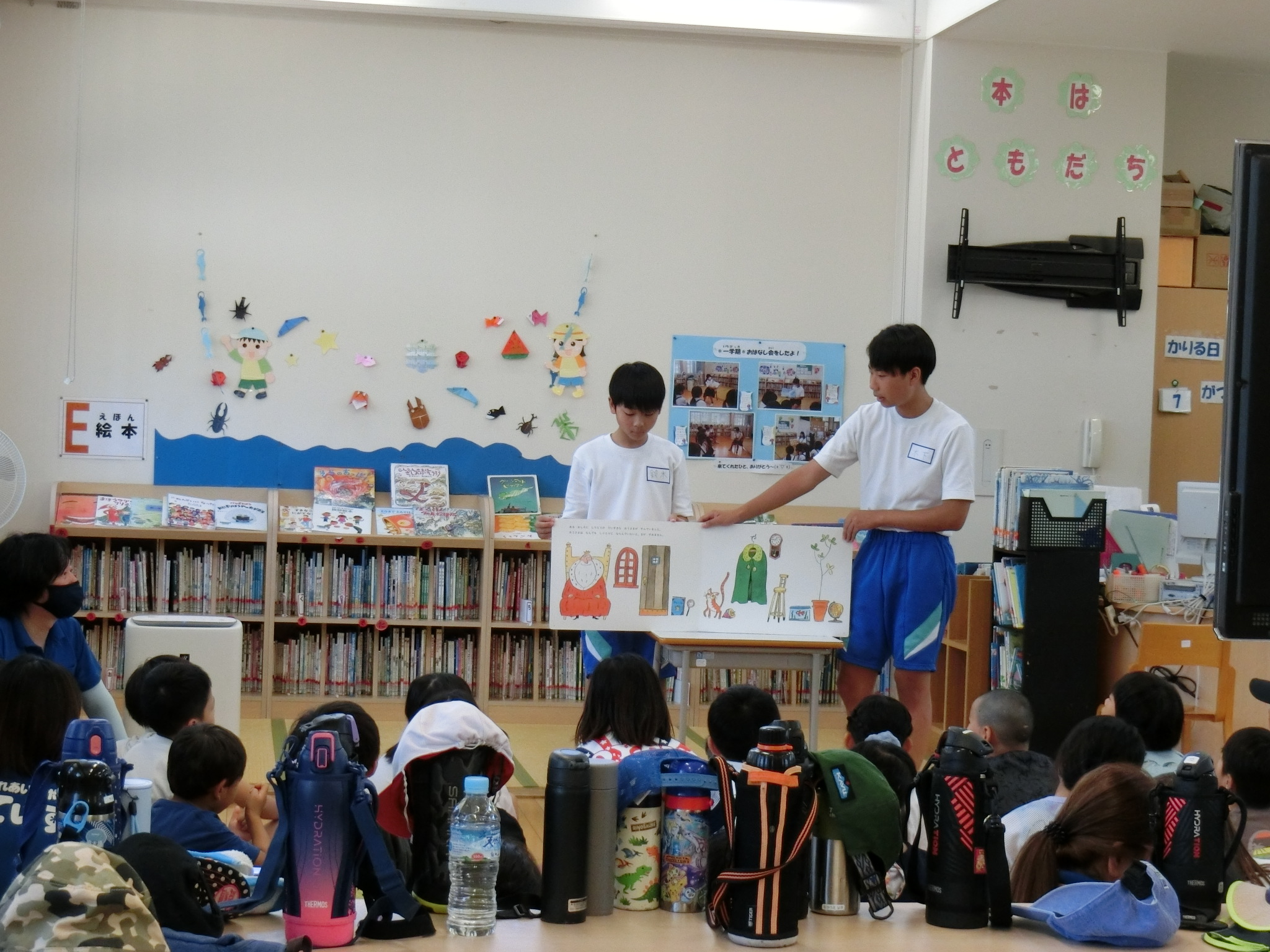



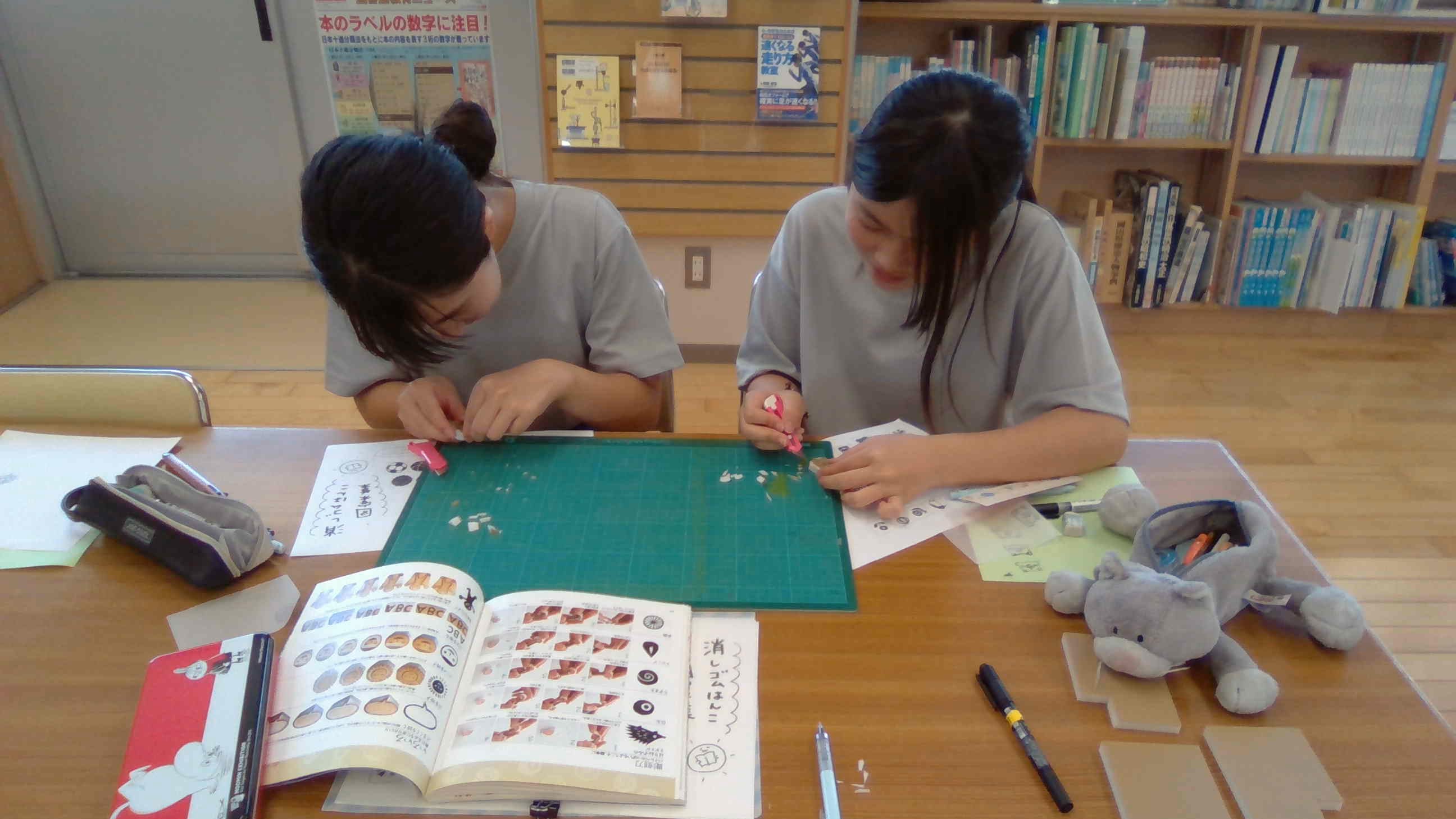
But thy eternal summer shall not fade‚(シェイクスピア『ソネット』第16番(1609))※アガサ・クリスティ『春にして君を離れ』(中村妙子訳)では「汝(な)がとこしえの夏はうつろわず」と訳される。
◎多くの人に支えられて(8/22)
1980年度3年C組卒業生有志のみなさんからご寄付をいただきました。ありがとうございました。大切に教育活動に使わせていただきます。
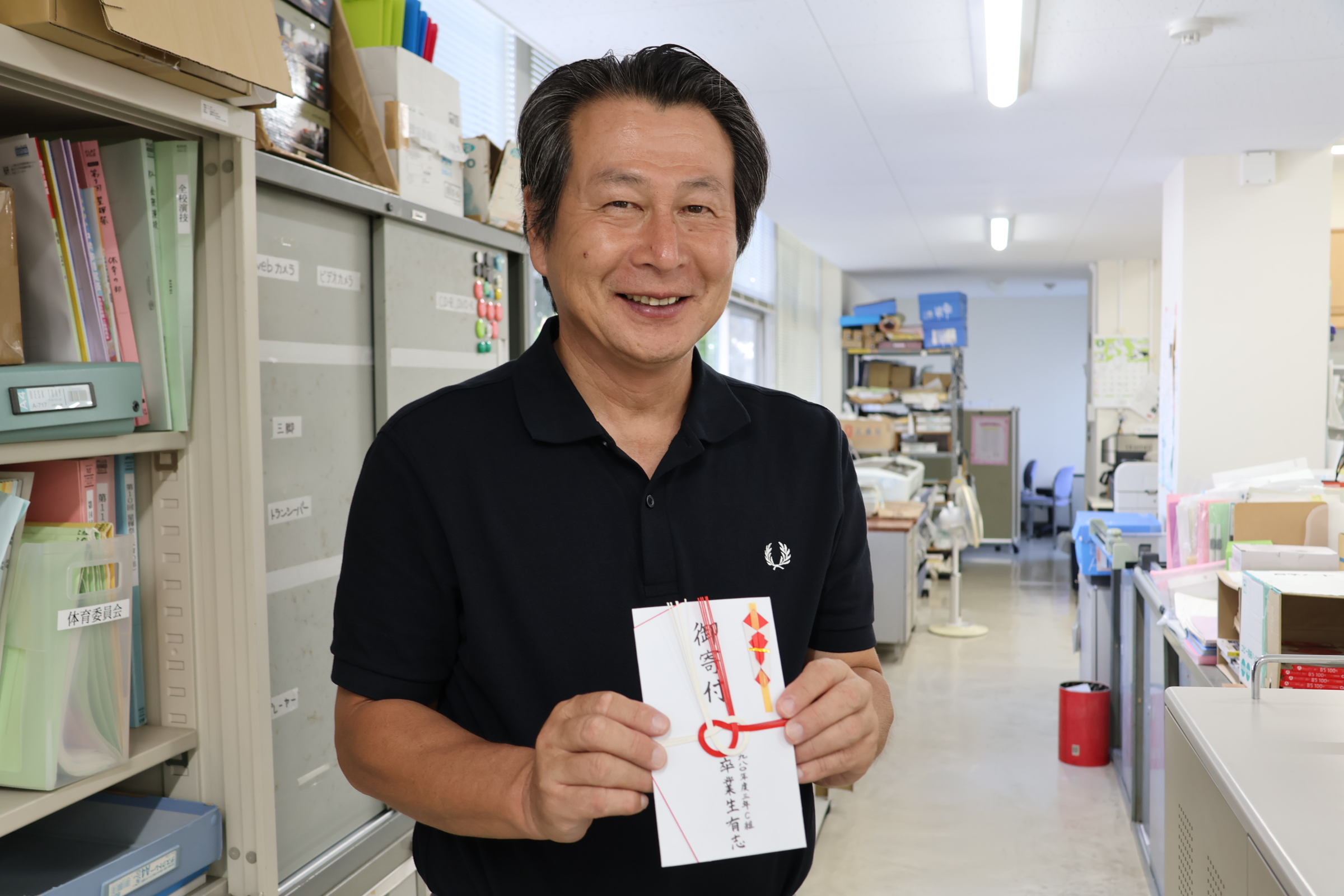
〈サイダーの泡立ちて消ゆ夏の月 山頭火〉(8/21)
今日は、教職員研修でした。
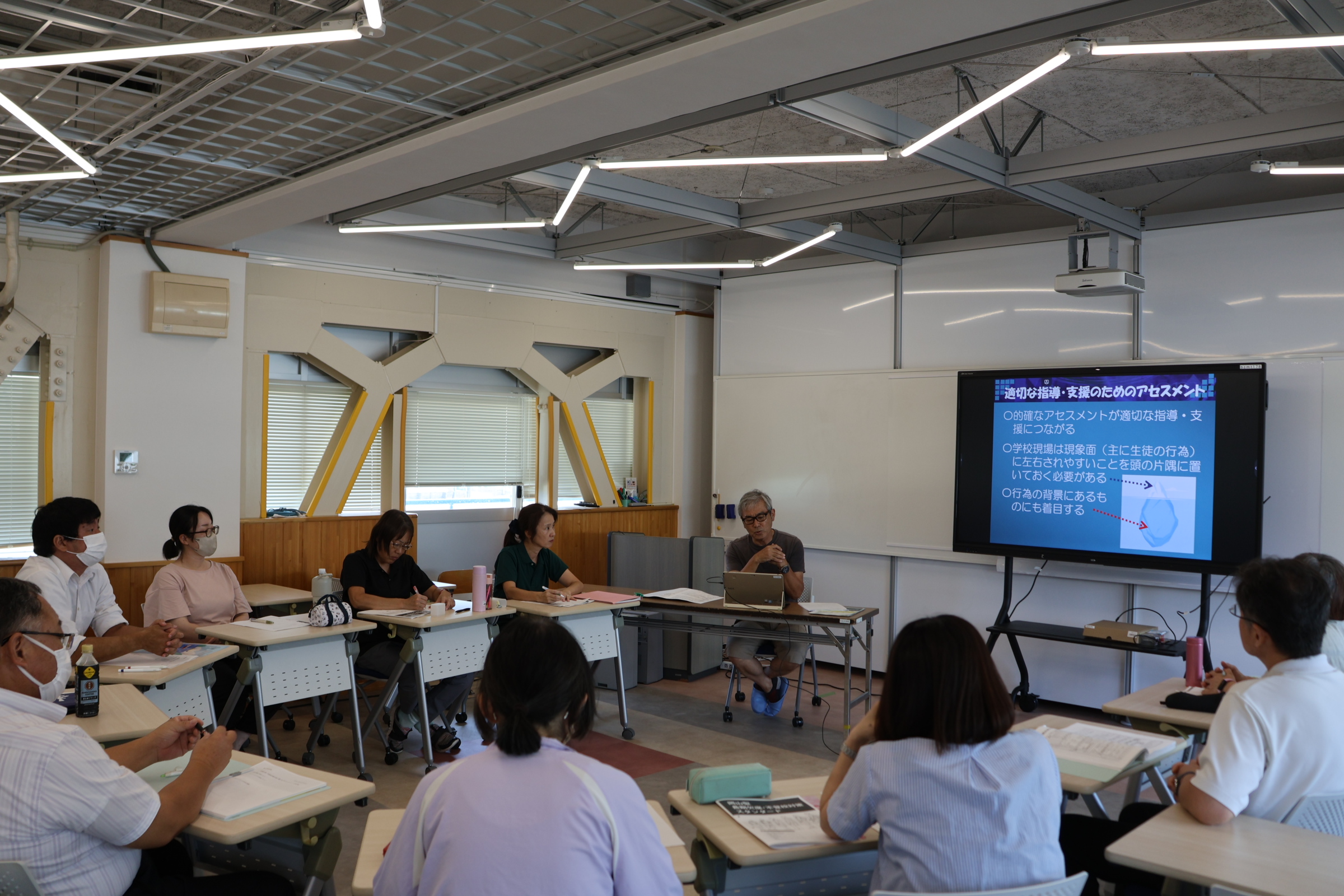
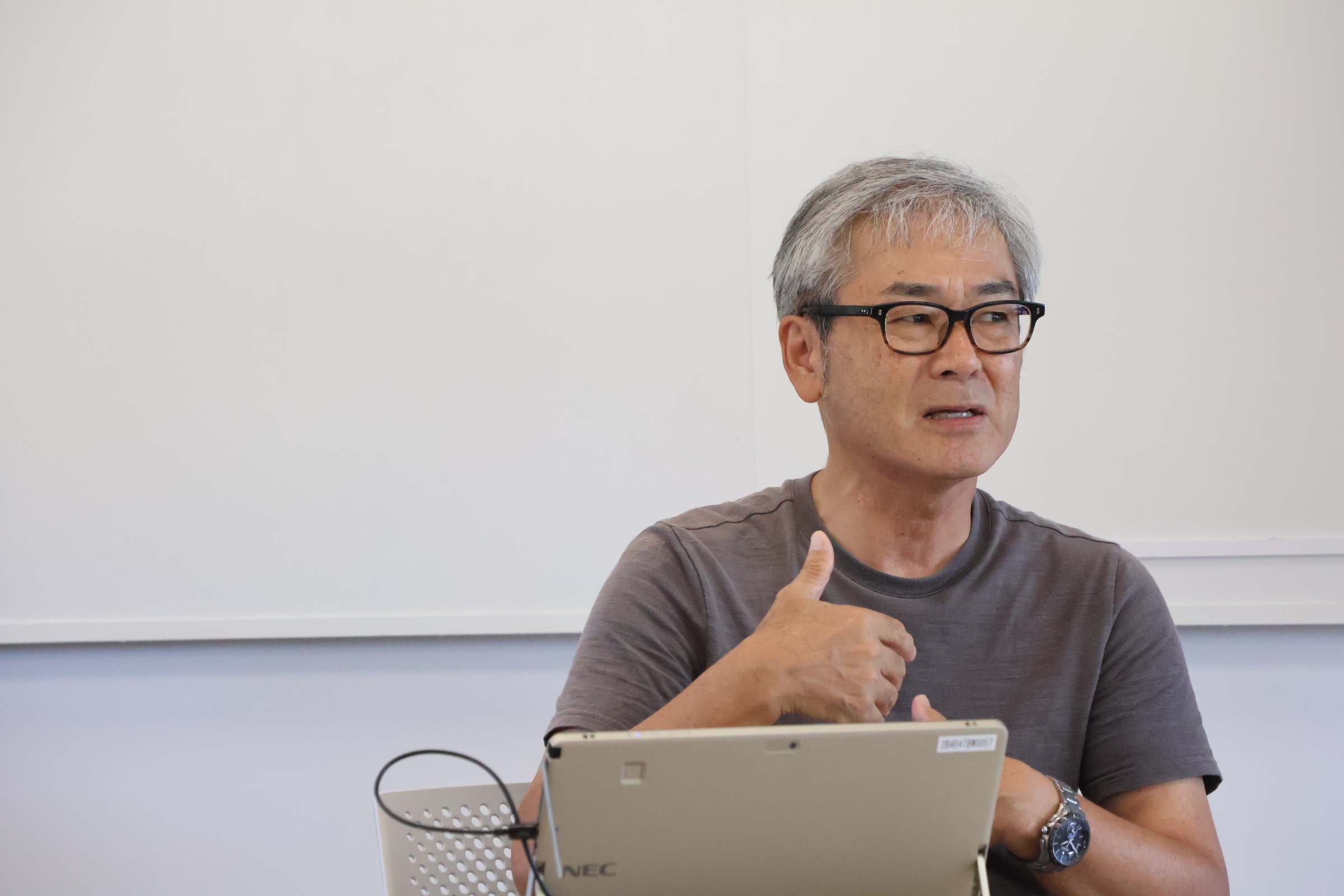

◎輪になって踊ろ!23日は練習会

着付け体験学習の時(7/4)にも、日生音頭を踊りましたが、8月30日の夜市は、やぐらを囲んで、地域の方々と共に、思いっきり踊れるチャンスです!
◎ひなせランタン夜市(8/30)を盛りあげよう
〈開催概要〉 Blue Ocean “みらいへ” の寄港に合わせて、日生の美しい海辺と駅前空間を活用したナイトイベントを開催します。 LEDスカイランタンやフォトジェニックな空間演出により、夏の最後の思い出づくりをお楽しみいただけます。また、屋台やひなせ盆踊り、太鼓の演奏、縁日など、さまざまな催しもご用意しております。大切な人とご家族と、もちろんおひとりでも。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
主催 備前市 協力 一般社団法人備前観光協会 ひなせランタン夜市実行委員会 備前東商工会 地元有志ノ会 詳しくは、https://hinaselantern.com/#ol-section-voice

 (イメージ)
(イメージ)日生音頭おどりメンバー、中学校もりあげ隊による出店、縁日ブーススタッフを大募集中です。→ひな中ボランティア推進プロジェクト事務局(日生中学校)まで至急連絡を!(^^)!。
また、9月6日(土)頭島灯りまつり、10月17日(金)備前焼祭り前夜祭出店ボランティアスタッフも併せて募集中です。
◎春15の会は今週末(8/23)です。
春15(いちご)の会(特別支援教育のニーズのある子ども・保護者のための進路情報交流学習会)は日生中学校を会場に開催します。参加申し込みができていなくても、当日参加可能です。最新の進路情報と元気と希望を手に入れましょう。24の高校・団体さんとの無料相談ブースがあります。
 *案内をどうぞ。
*案内をどうぞ。◎残暑お見舞い申し上げます。

休業中も水やりをありがとうございました。
◎日生で輝く 日生が輝く(8/13:ひなせみなとまつり)
今年も、日生中学校地域もりあげ隊で参加しました。ご支援・ご協力をありがとうございました。
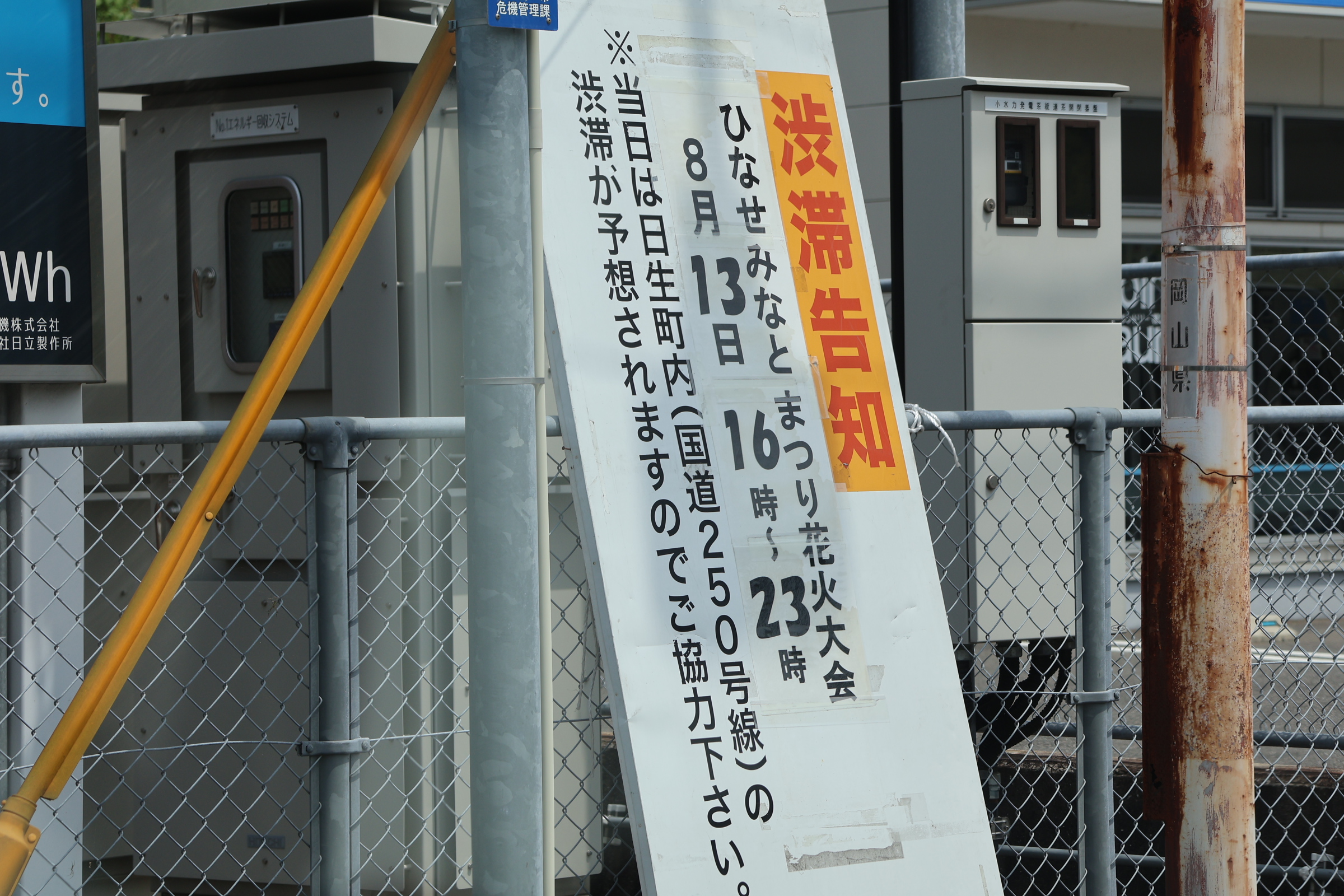








◎先生たちも学んでいます
教職員は夏季休業中は、校内外の研修や勉強会に足を運び研鑽に励んでいます。8月7日は、岡山県人権教育研究大会(マービーふれあいセンター)が開催されて、本校からも先生方が参加されました。
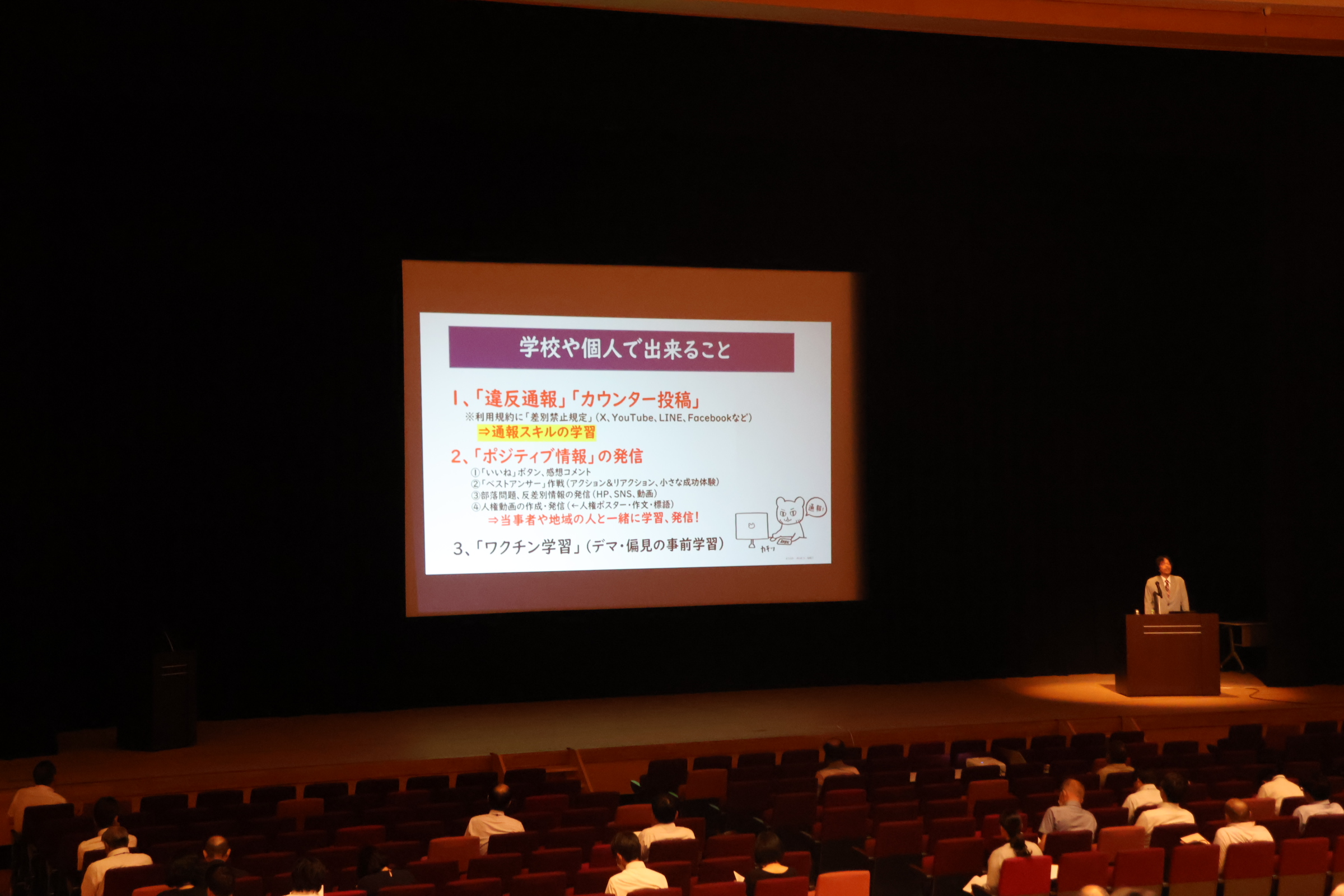

◎多くの人に支えられて
備前警察署から根木スクールサポーターが地域巡回で来校されました。また、備前保健所と引きこもりや家庭支援などについて協議しました。


◎青空に残された 私の心は夏模様♪(2025.8)



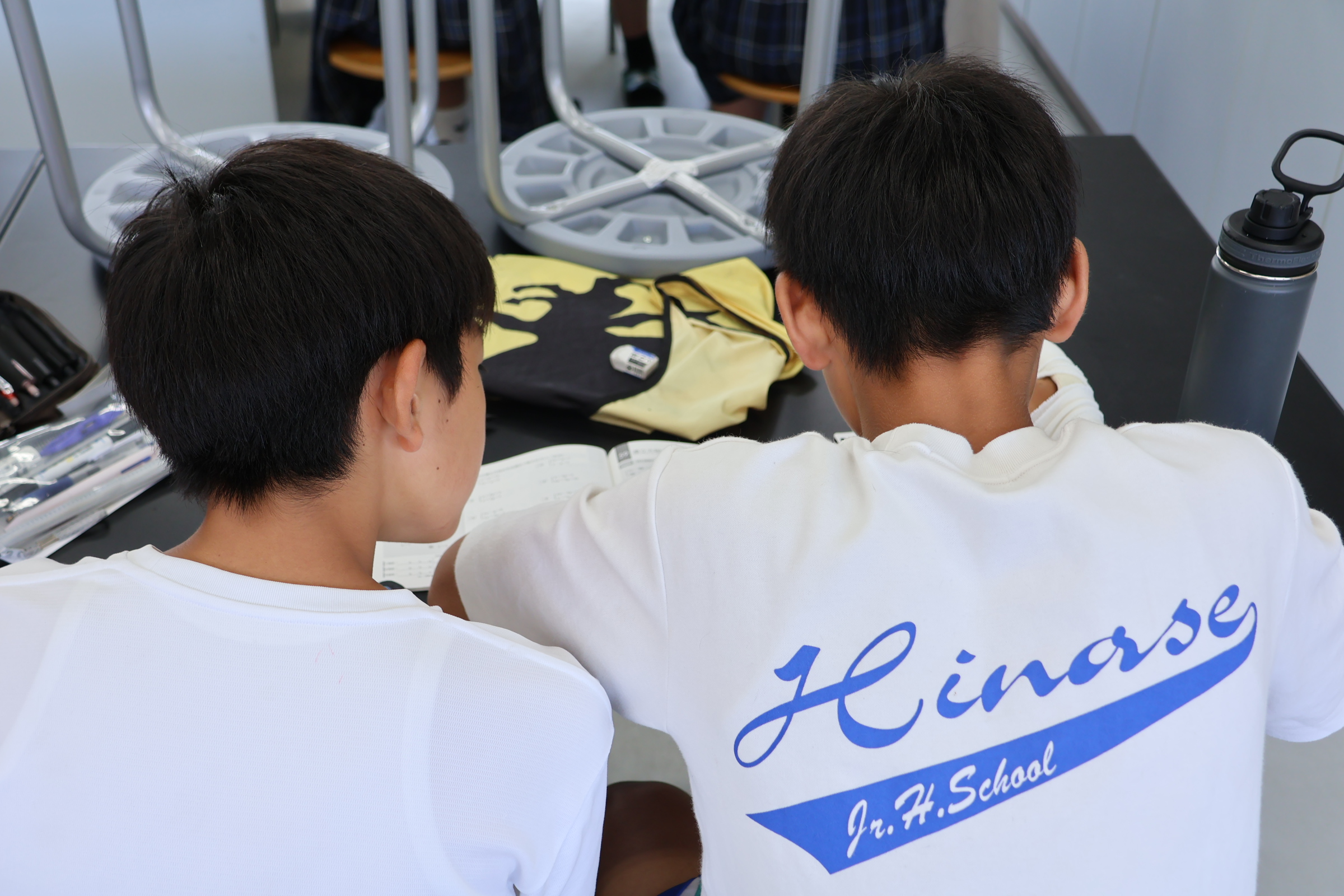

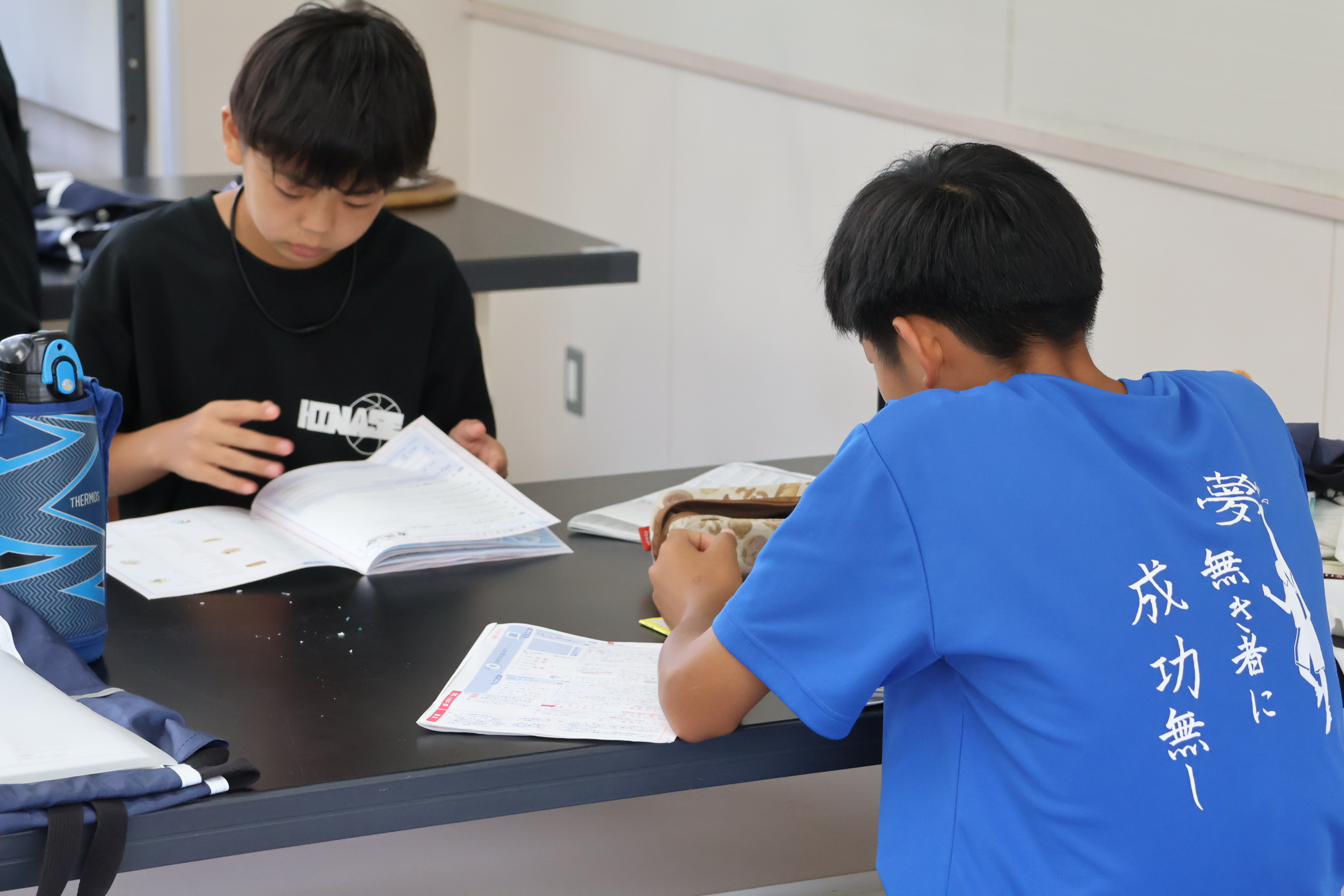


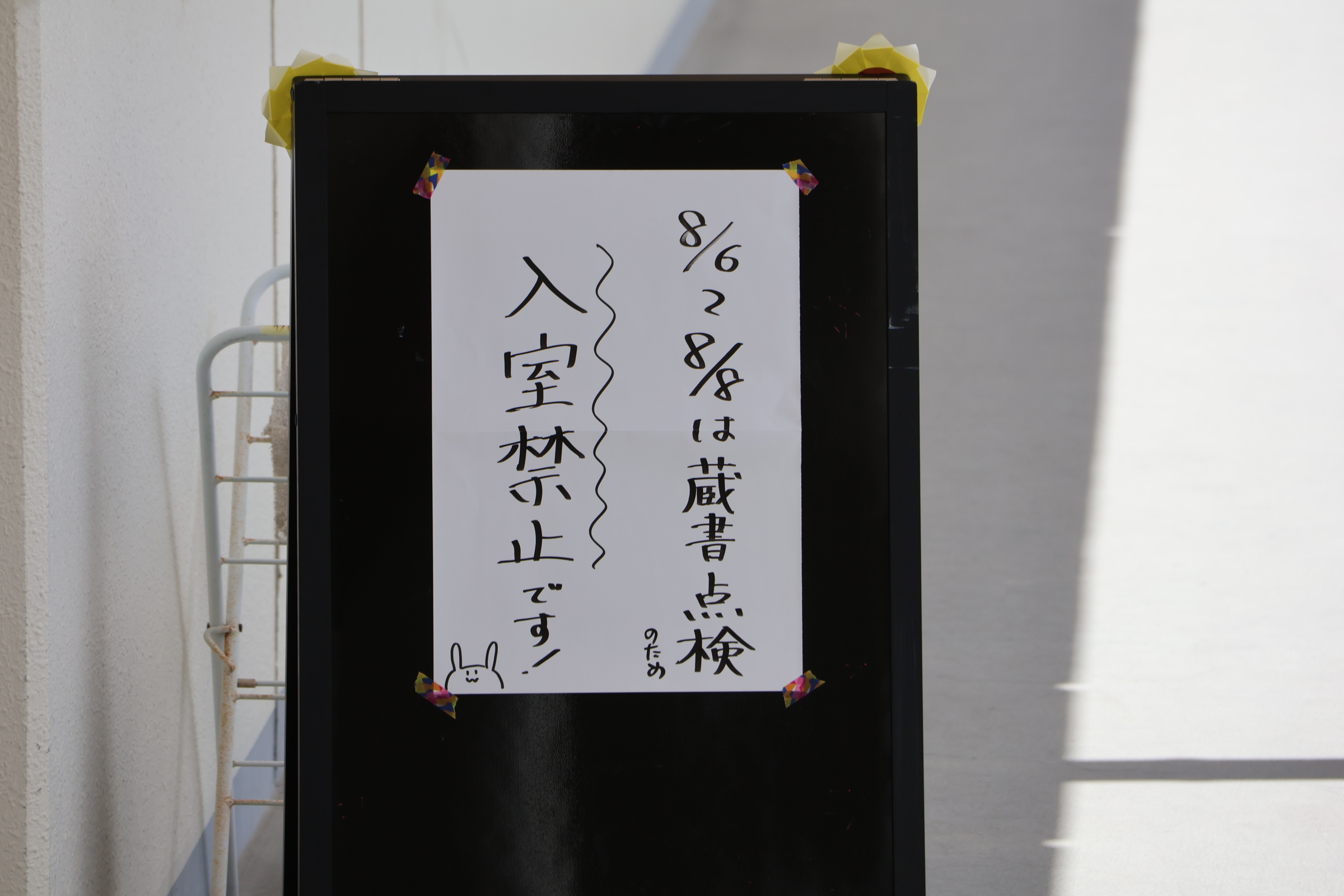
◎けふなり けふなり。きのふありて何かせむ。(8/2)

三大流星群の一つ「ペルセウス座流星群」が、8月13日(水)5時頃に活動の極大を迎える予想です。暗くなった頃には空に昇って、ペルセウス座流星群が見られるようになります。いつもより多くの流星を見られるのは11日(月)から13日(水)の3夜ほどで、一番の見頃は12日(火)深夜から13日(水)未明です。いずれの夜も、放射点が高く昇ってくる未明に向けて流星の数は多くなると予想されます。見頃の時期は明るい月が昇っているため、見える個数は例年より少なめとなります。国立天文台によると、最も多くの流星が出現するのは13日(水)の夜明け前の頃で、空の条件が良いところでは、1時間あたり30個ほどの流星を見られるチャンスがあるとのことです。流星はペルセウス座の周辺のみに出現するわけではなく、夜空のどこにでも現れるため、できるだけ空を広く眺めるようにして流星観測を楽しんでみましょう。
◎一度見た星を見失うことはない。私たちはいつでも、なりたかった自分になれる
No star is ever lost we once have seen‚ We always may be what we might have been. Ere the pilgrimage be done. Adelaide Anne Procter (1858). “Legends and Lyrics: A Book of Verses”‚
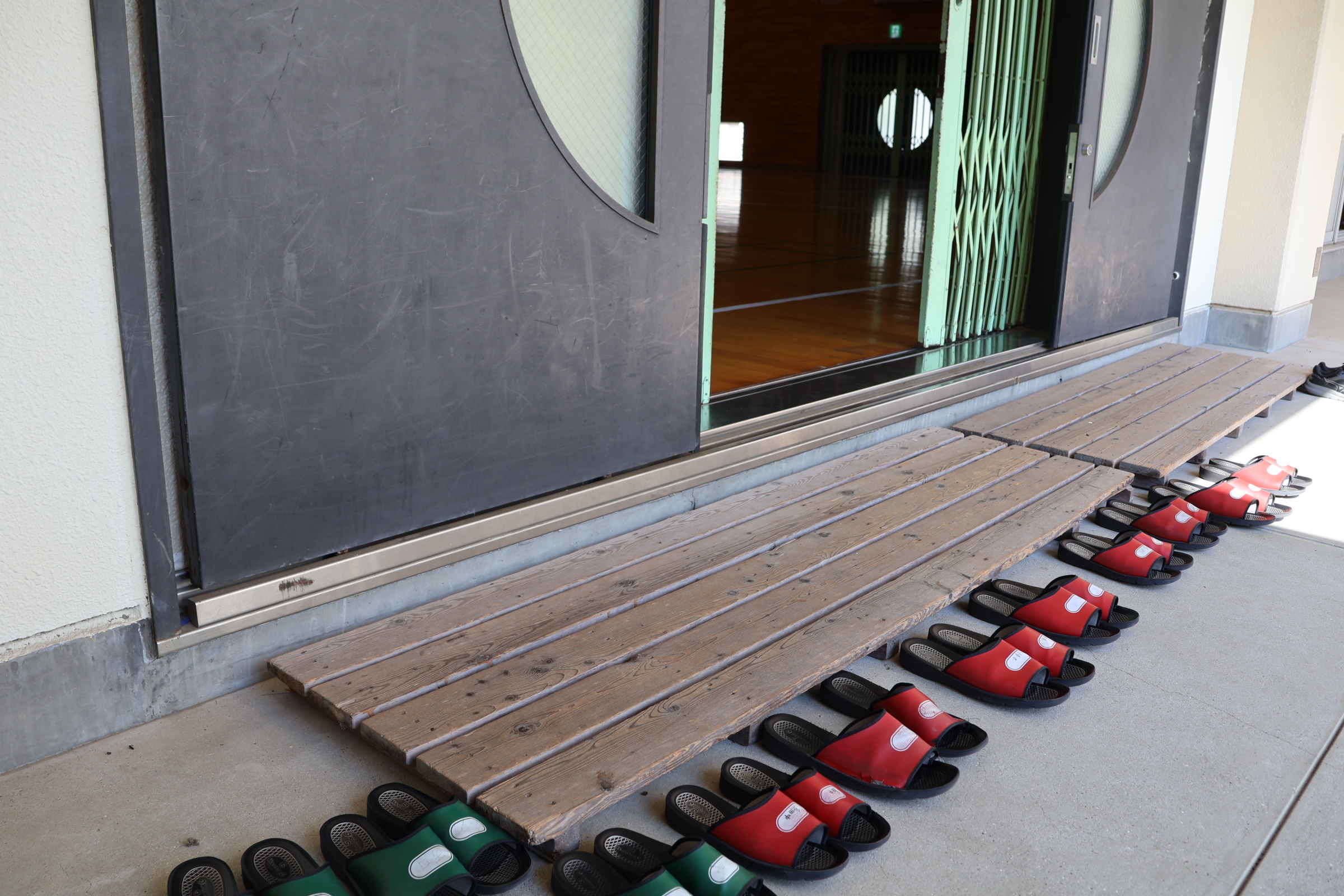





◎いのちを守る行動を(7/31)備前市津波ハザードマップをご確認ください。
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/4/4320.html

◎真の連携へ! つながる意味をあらためて!(7/29 )
地元コミニティの場「ひなせうみラボ」を会場に、日生中学校区連携協議会研修会を開催しました。朝倉さん(圏域相談支援コーディネーター 主任相談専門員)、杉原さん(備前市社会福祉協議会福祉課障がい者福祉係)に来ていただきました。朝倉さんからの提起は『十五年間を見通したこ小中、保育・教育と福祉の確かな連携へ』として、①相談支援を中心とした福祉サービスの内容、②当事者・家族からのねがいや思いを受けて。③「福祉」からみた「保育・教育」、そして連携へ を「キーワード」にした話を受けて、参加者同士の深い質疑・意見交流の時間となりました。



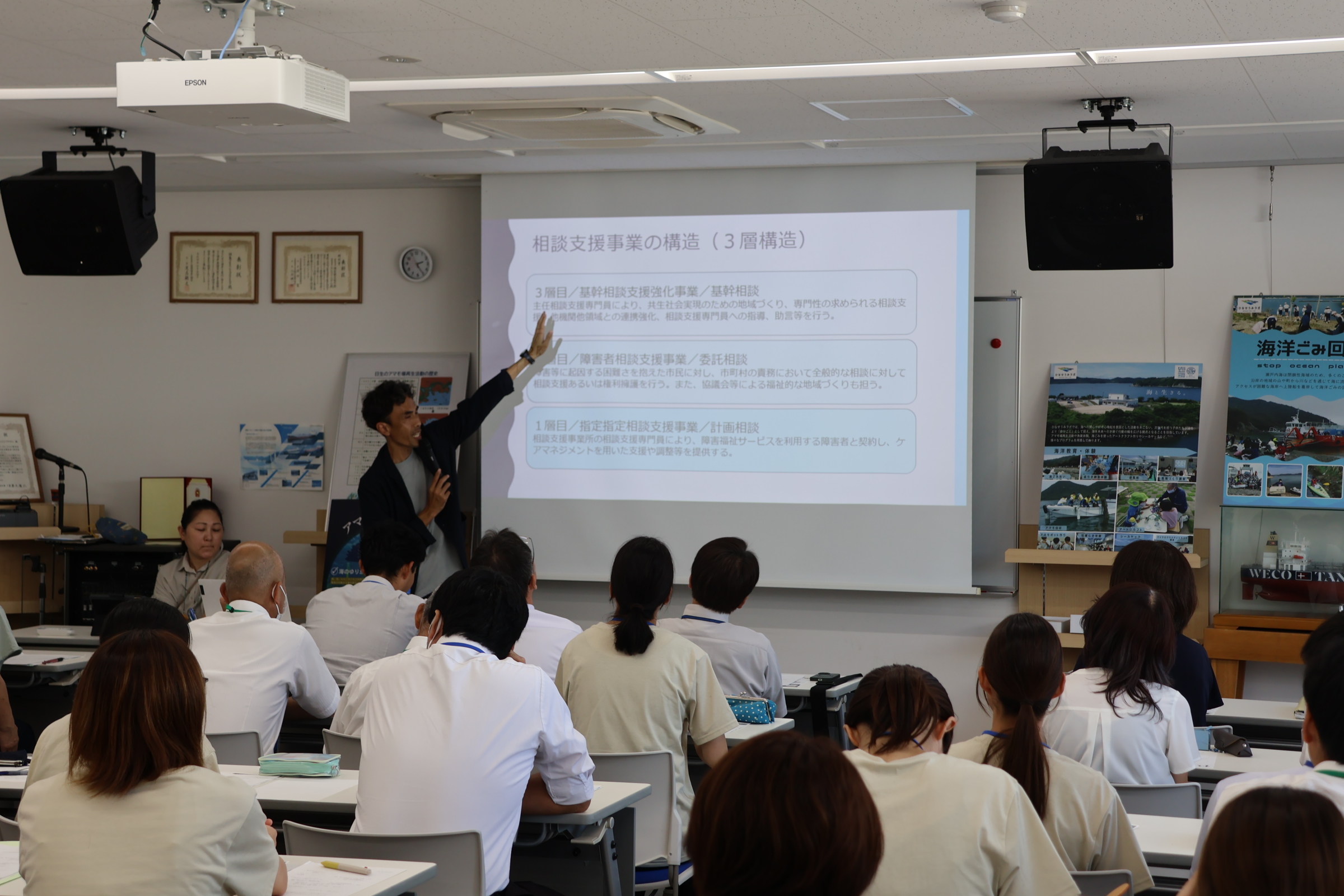
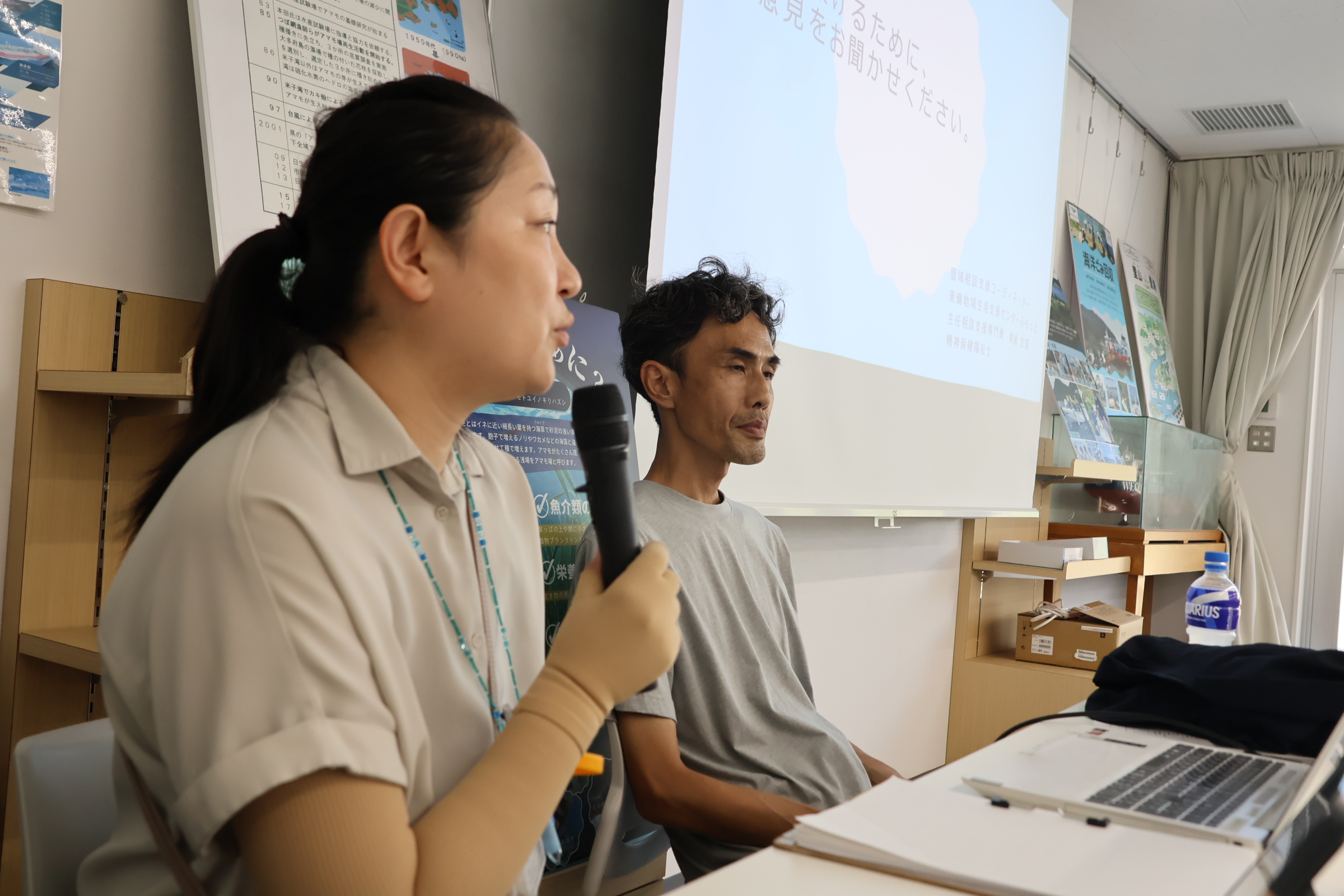

◎我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか(7/31)
(D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? ゴーギャン)

7月第4木曜日、瀬戸内市のハンセン病療養所長島愛生園で、亡くなった入所者を悼む慰霊の花火が打ち上げられました。花火には、偏見・差別のない社会の実現への誓いが込められています。亡くなった人たちの魂を慰める花火約2000発が、瀬戸内市の夜空を彩りました。国立ハンセン病療養所長島愛生園では、毎年、地域の人を招いての慰霊の花火大会が行われています。
◎同じ夏は二度とやってこないのだ シルビア・プラス (7/23)
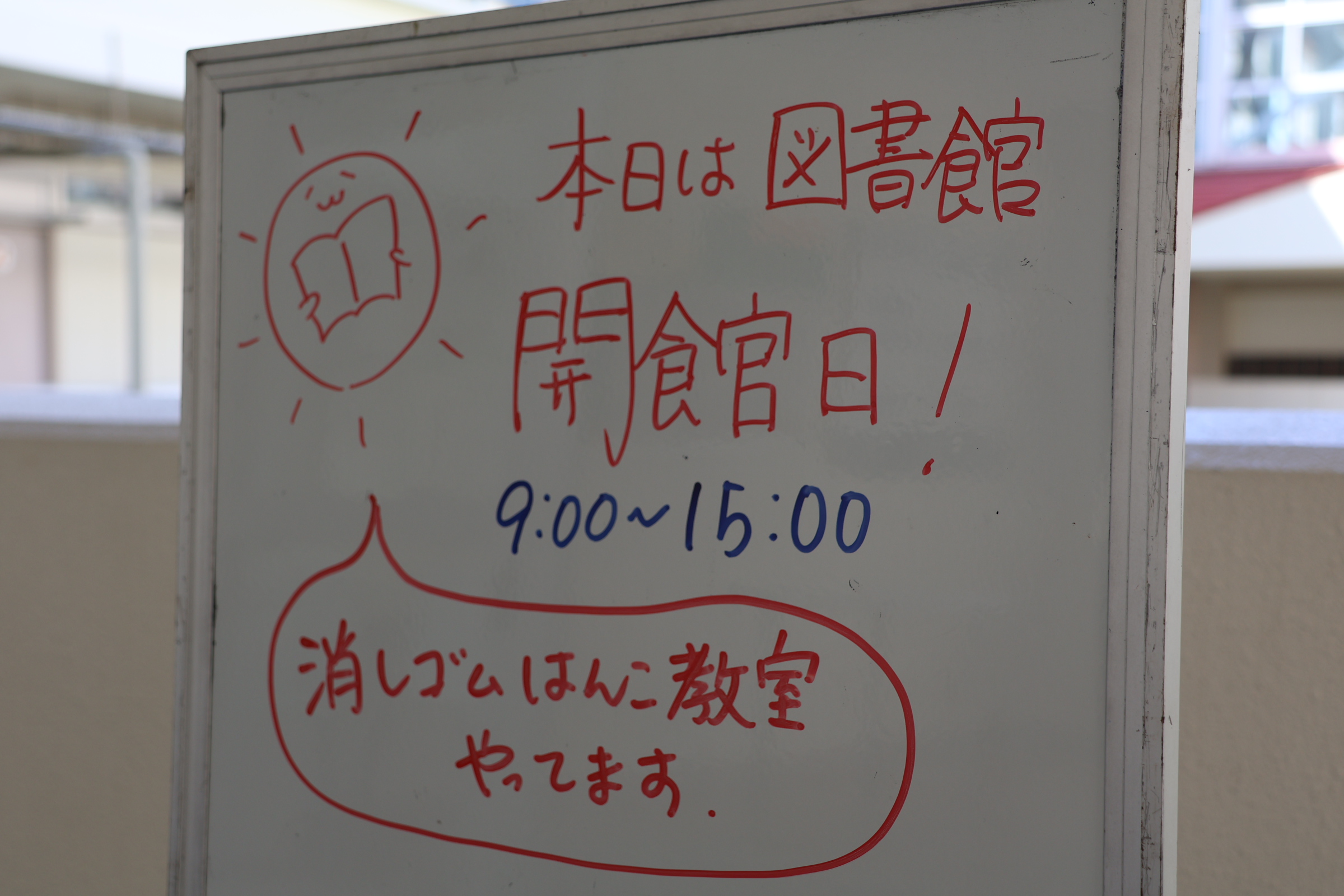

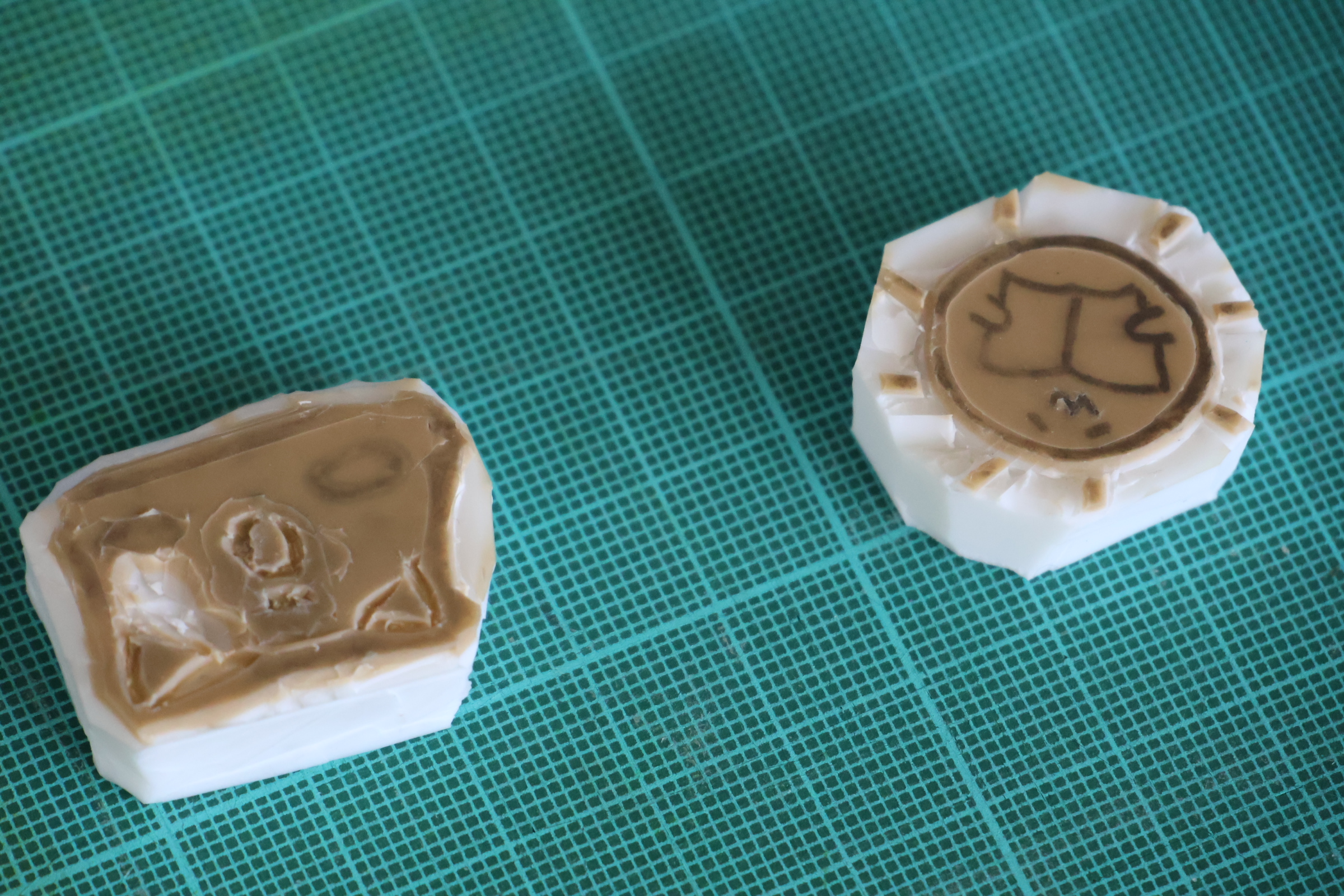

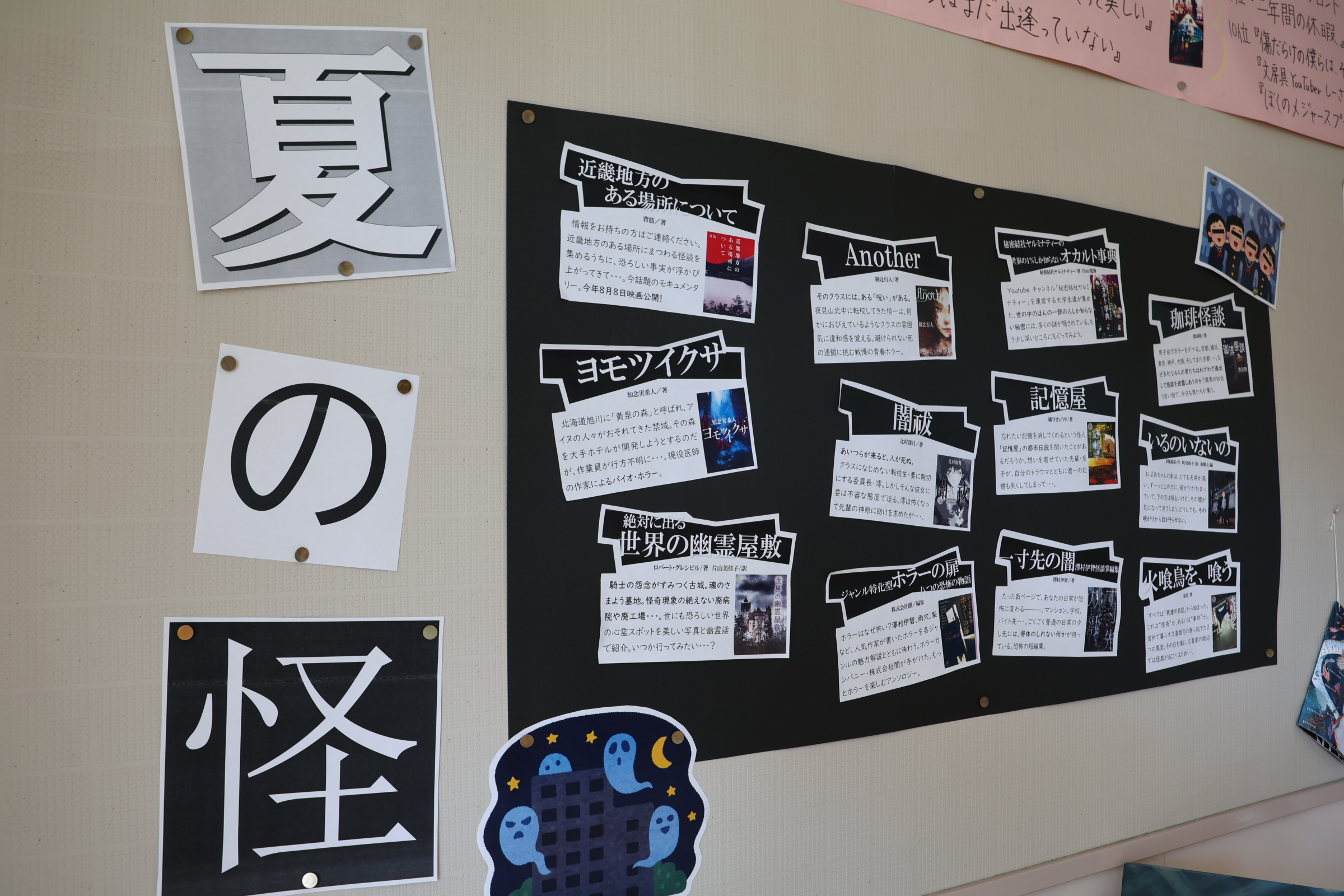

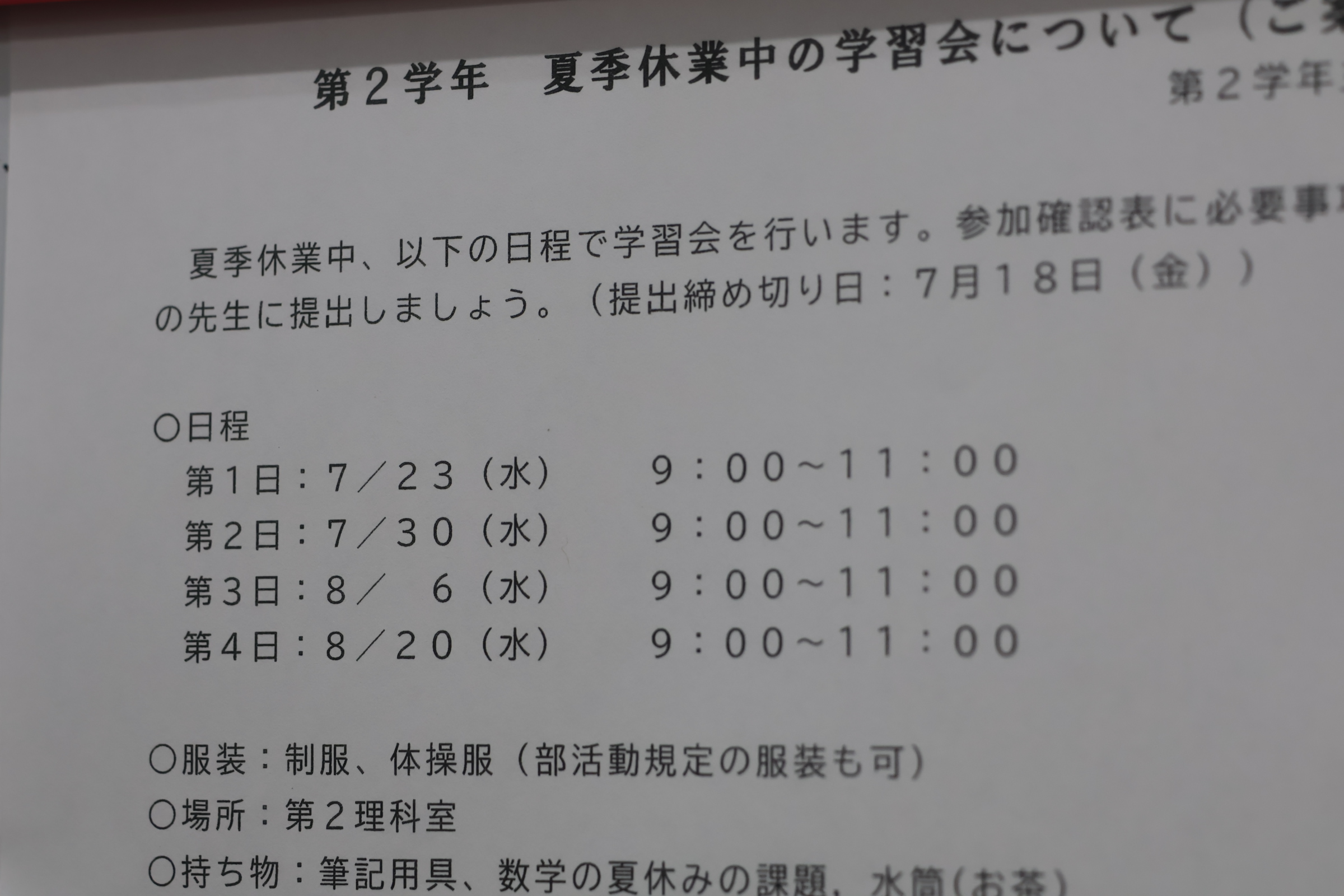


◎確かな進路保障を(7/23:山陽新聞から)
春15の会についての取材があったことを教頭先生から聞きました。今日の掲載記事を紹介します。
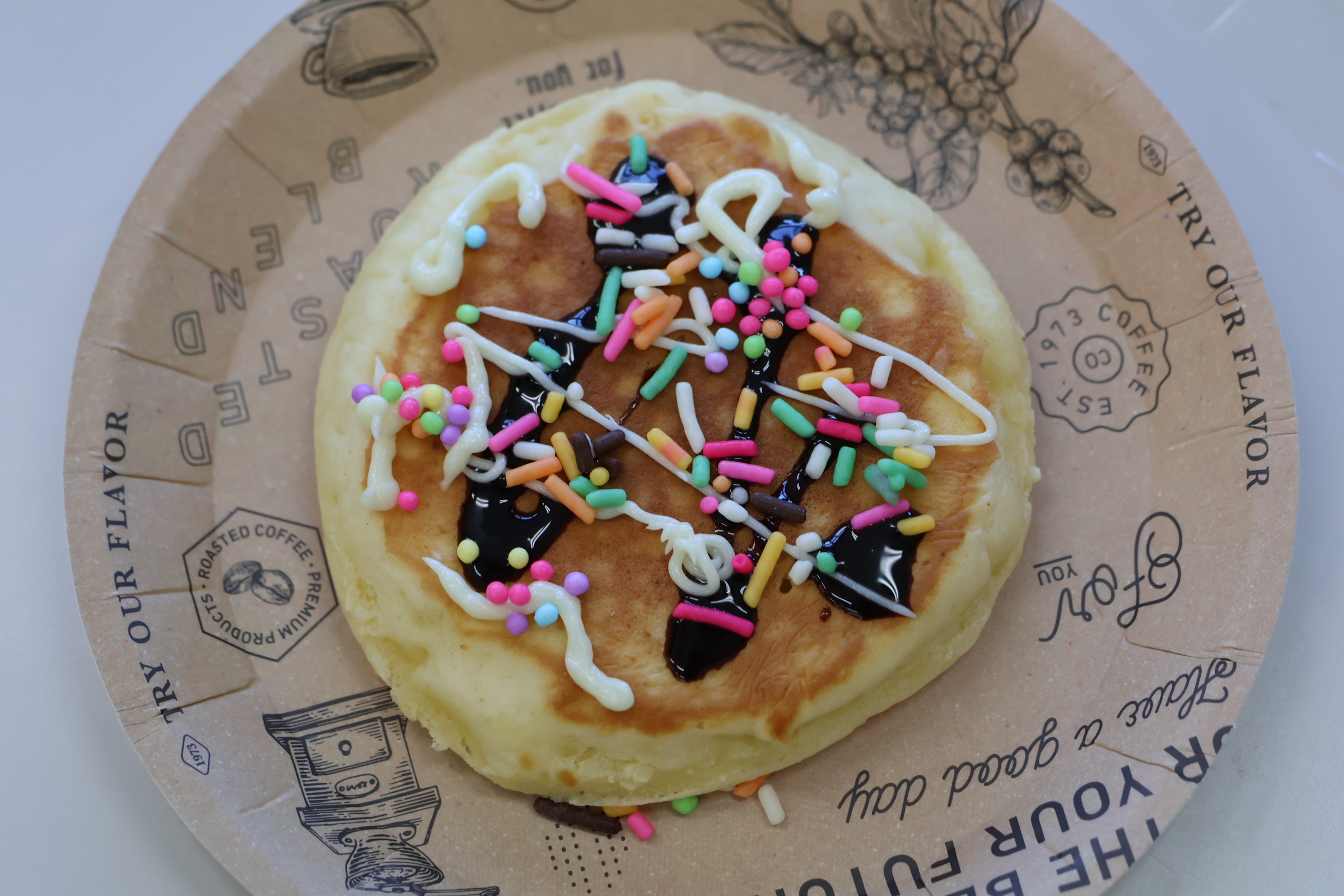
◎星輝祭(文化の部)ホリゾント作製開始!(7/22)
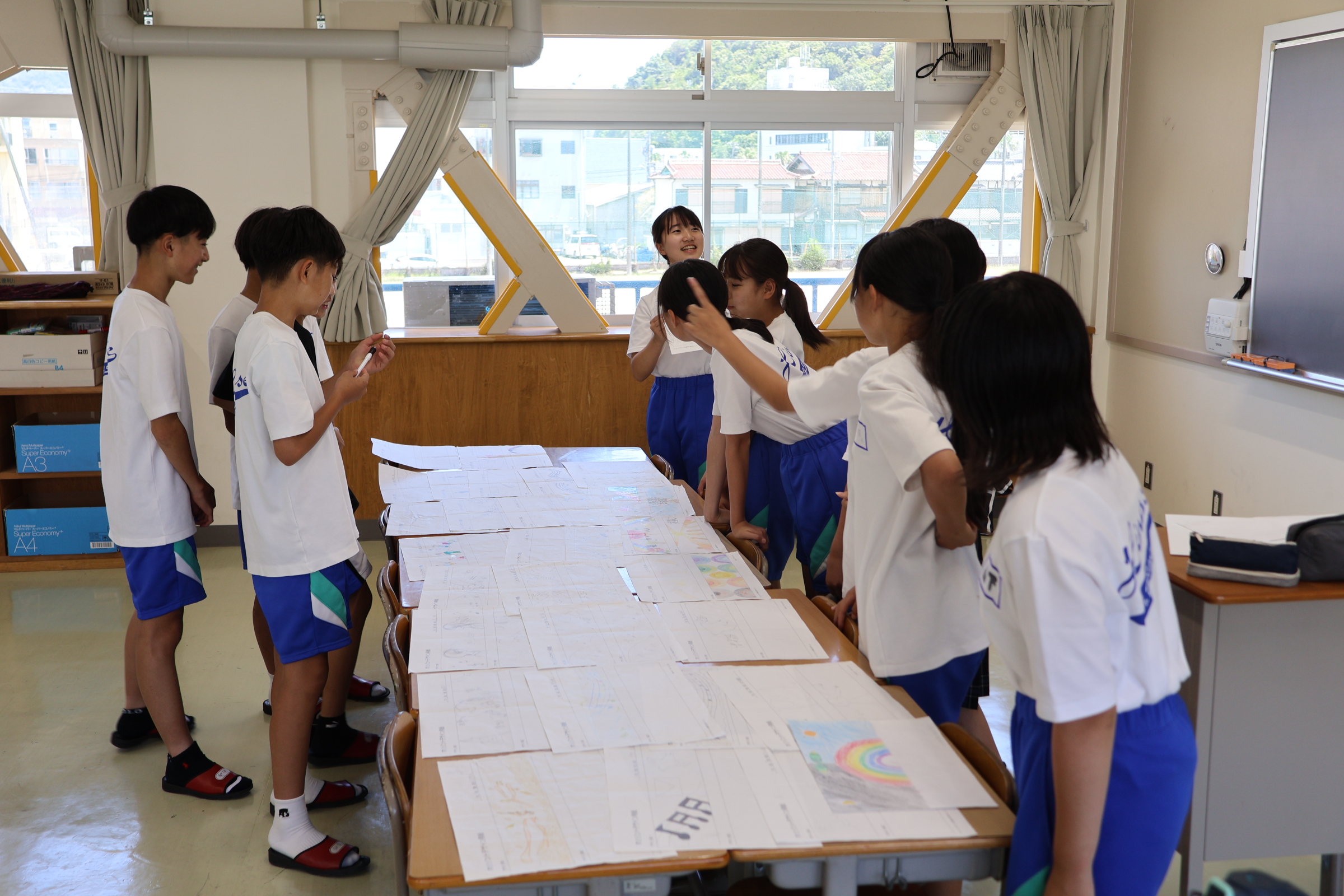
◎日生で輝く 日生が輝く
ボランティア推進プロジェクト(7/22かきだこプロジェクト試食会)





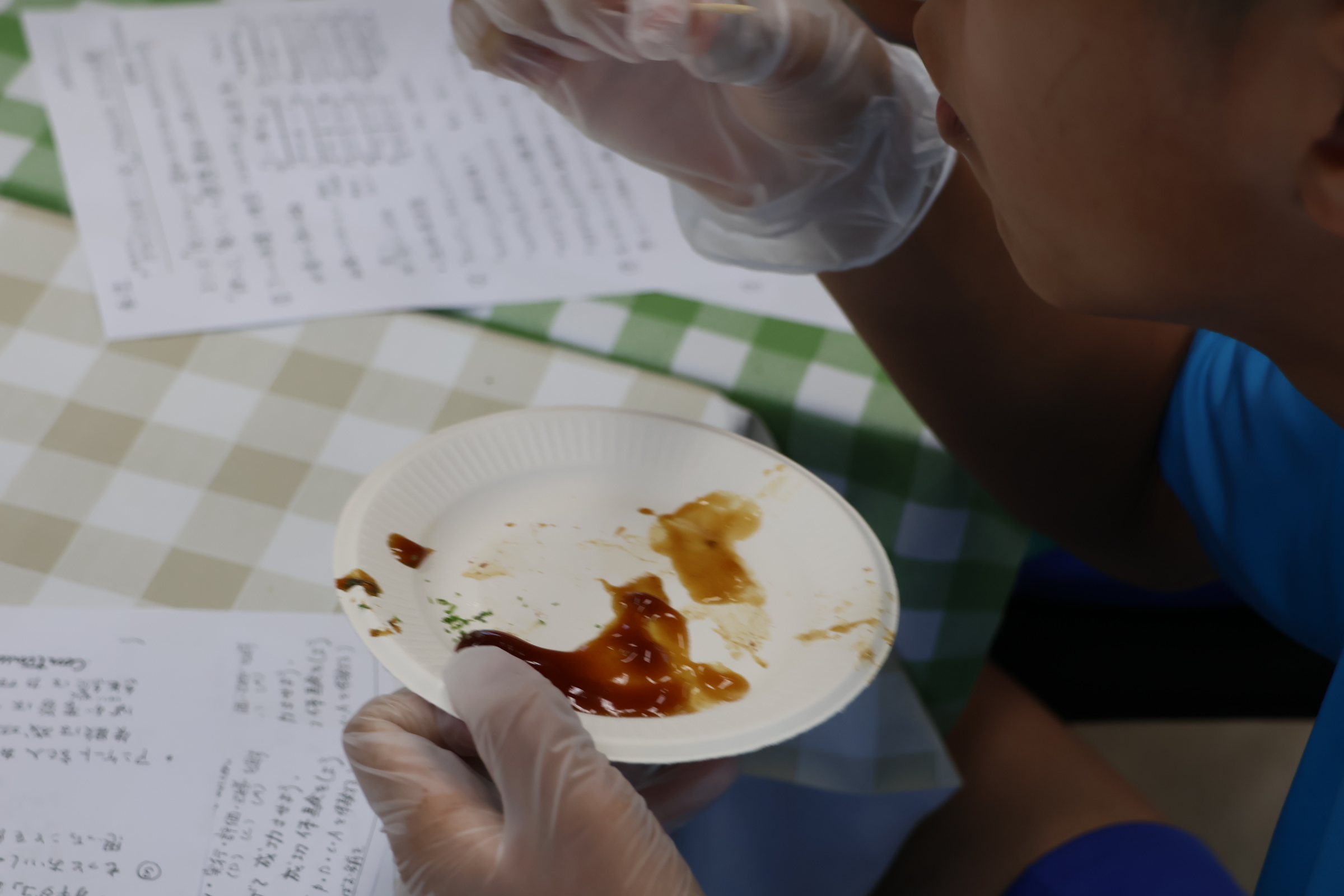



◎大暑 (7/22)

今年2025年は7月22日が二十四節気の1つ「大暑(たいしょ)」です。この7月22日から8月6日までを「大暑(たいしょ)」の期間としています。「大暑」は、名前の通り「一年で最も暑さが厳しい頃」を意味しています。「大暑」の前後の暦を見ると、前の暦は7月7日の「小暑(しょうしょ)」で、後の暦は8月7日の「立秋(りっしゅう)」です。
「小暑」は、一年で最も昼間の時間が長くなる「夏至」から15日目ごろにあたり、本格的に暑くなる頃という意味です。また、「立秋」は秋が立つと書くように、暦の上では秋が始まり、少し秋の気配が漂い始める頃を意味しています。現代では、「小暑」も「立秋」も厳しい暑さが続いているのが現実ですが、前後の暦の名前からも「大暑」が一番暑い頃というのが想像できますね。「大暑」の頃は、各地で梅雨が明けて、夏の太平洋高気圧が勢力を広げ、まさに盛夏というのがぴったりの時季です。
日本国内で観測された最高気温の記録を見ると、全国1位は静岡県浜松市と埼玉県熊谷市で観測された41.1℃です。静岡県浜松市の記録は、2020年8月17日とお盆休みの頃に出ていますが、埼玉県熊谷市の記録は2018年7月23日となっていて、上位の多くは「大暑」の頃に記録されています。データから見ても、大暑のあたりが、年間で最も暑い頃ということができます。
厳しい暑さに加えて、大雨にも気を付けたい時期です。気温が高くなると空気中には雨の元になる水蒸気を含みやすくなります。晴れていても、突然積乱雲が発達し、局地的に短時間で大雨が降る、いわゆるゲリラ豪雨の発生頻度が高まります。暑さと大雨は隣り合わせにあり、条件が重なると「災害級の猛暑」や「災害級の大雨」が発生することもあるため、どちらも注意が欠かせない時期といえるでしょう。
「大暑」は、「暑中見舞い」を出す頃です。二十四節気の「小暑」から「大暑」までが、「暑中見舞い」を出すタイミングにあたります。「大暑」の次の暦である「立秋」を過ぎると、ここからの暑さは「残暑」と言われるようになり、「残暑見舞い」を出すようになります。「暑中見舞い」は、普段なかなか会うことのできない方やお世話になった方へ健康を気遣う夏の挨拶状で、江戸時代に生まれたと言われています。今は季節の挨拶もメールやSNSが主流となってきていますが、お葉書で送るという昔ながらの風情ある文化も受け継いでいきたいですね。時候の挨拶に加えて、自分らしいエピソードや近況報告も添えてみてはいかがでしょうか。
「大暑」の時期は、夏の「土用の丑の日」と重なります。「土用の丑の日」というと夏のイメージがありますが、実際に「土用」は1年間のうち季節の変わり目ごとに4回あり、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間のことを言います。暑さがひときわ厳しい夏の「土用の丑の日」は、2025年は7月19日と31日に2回あります。昔は季節の変わり目に様々な習わしがあり、特に夏の「土用の丑の日」には、「う」のつく食べ物を食べると夏バテしないという風習がありました。土用の丑の日というと、うなぎが思い浮かびますが、もともとは暑くても食べやすく胃腸に良いうどんや梅干し、瓜(ウリ)など「う」のつく食べ物などが食べられていたそうです。滋養強壮のあり、夏バテ予防にもなるうなぎや、さっぱりと食べられるうどんなどを食べて、最も暑い時期を元気に乗り切りたいですね。
◎蜘蛛は網張る私は私を肯定する 種田山頭火(~8/27始業の集い)

◎日生で輝く 日生が輝く
ひなせのちから(7/18:生徒会主催地域清掃ボラ・川東地区社協の皆さんと)









◎地域と共にある学校(7/18)
頭島あかりまつり実行委員さんをお招きして、今年も行燈づくりに取り組みました。お祭りの夜、色とりどりの灯りが夜を彩ります。また、出店ボランティア、大学生ボラとの運営スタッフを募集します。
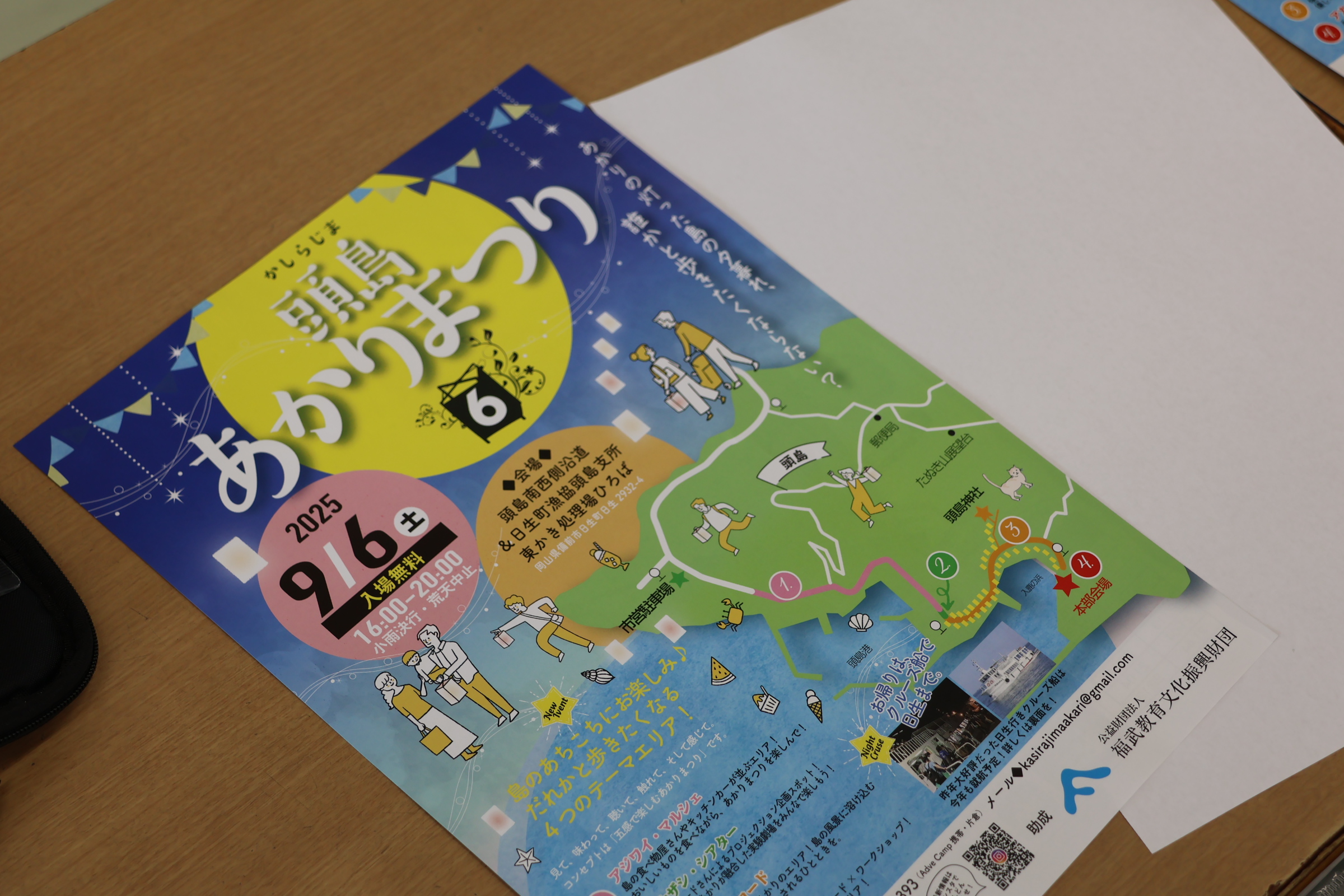
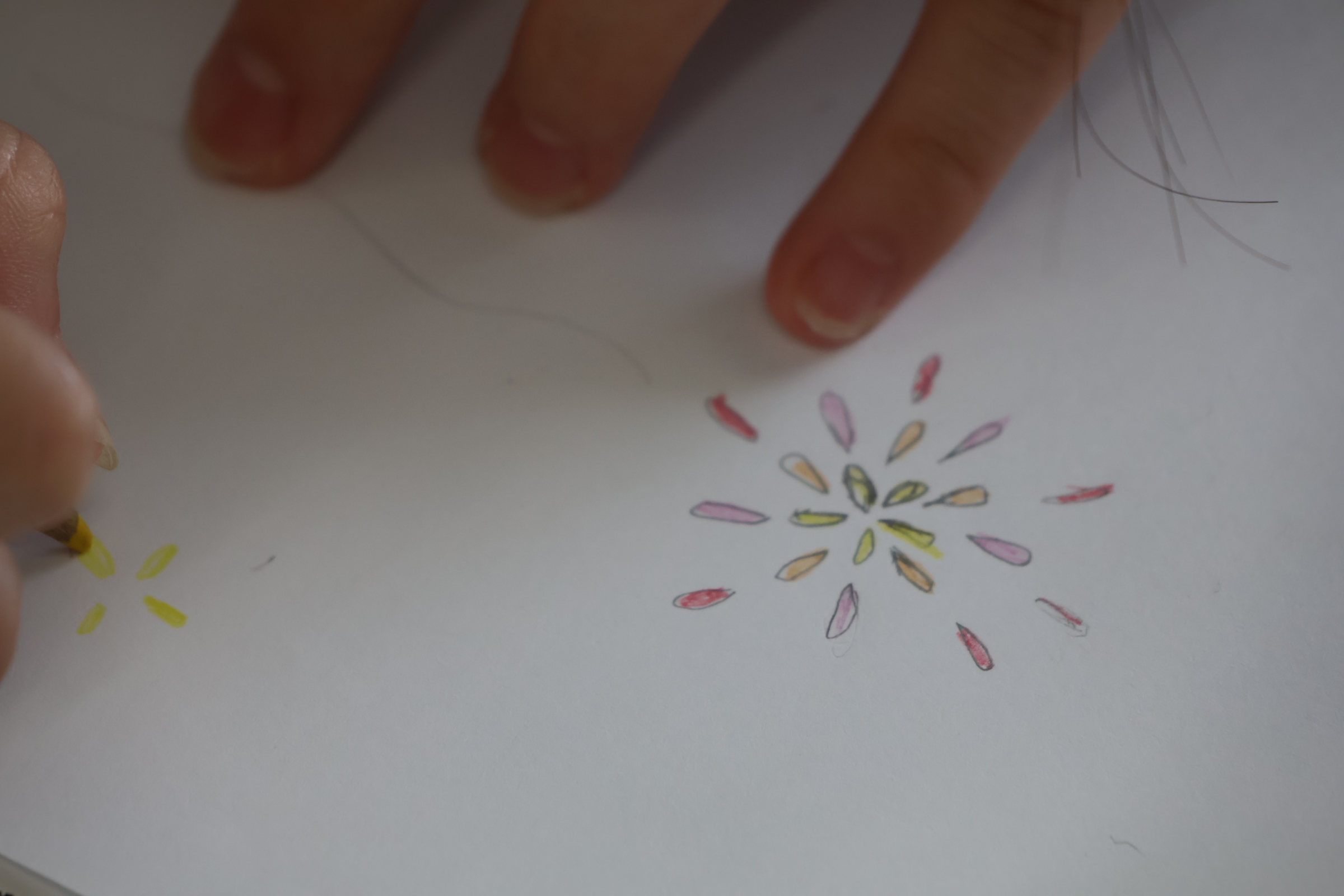
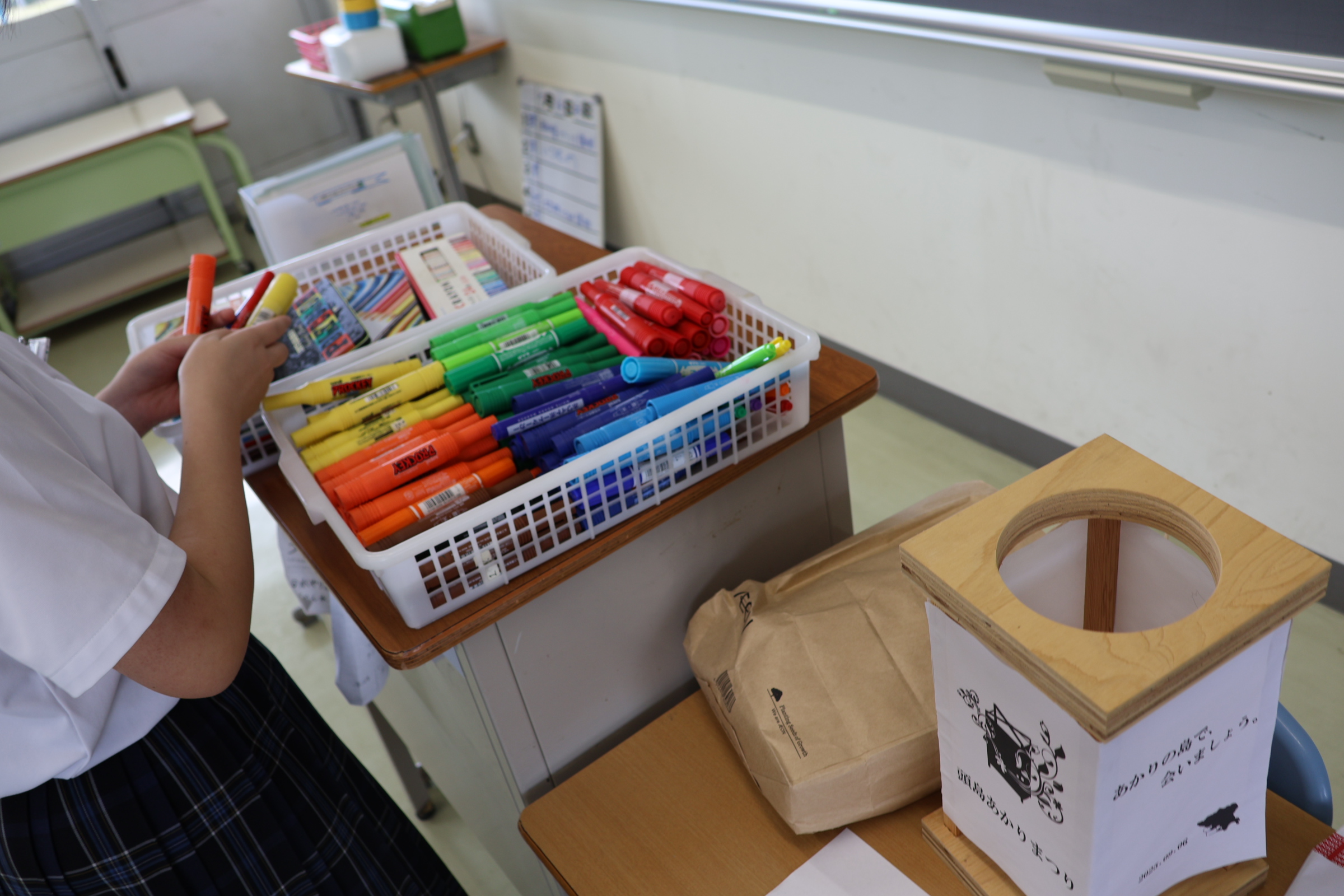
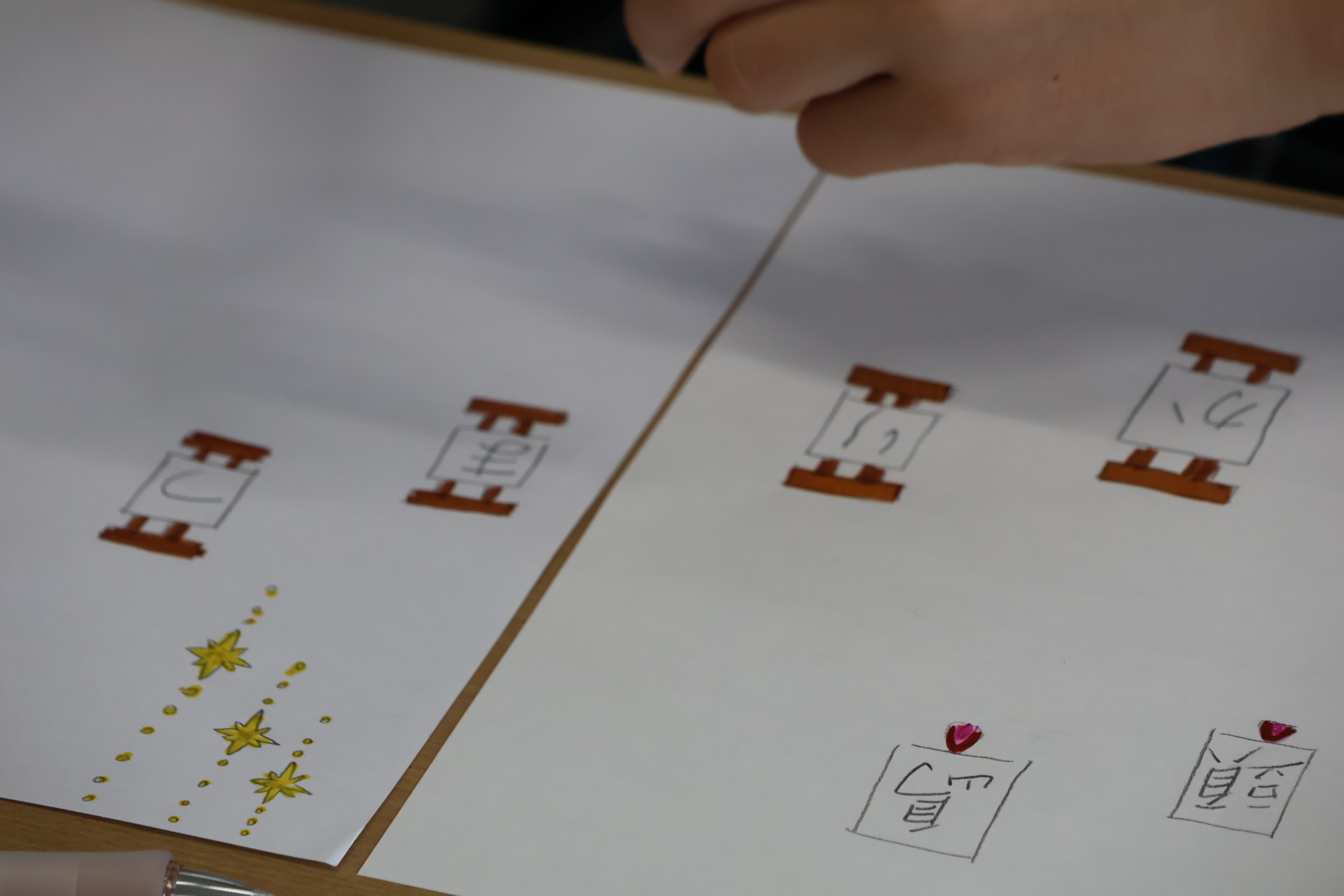

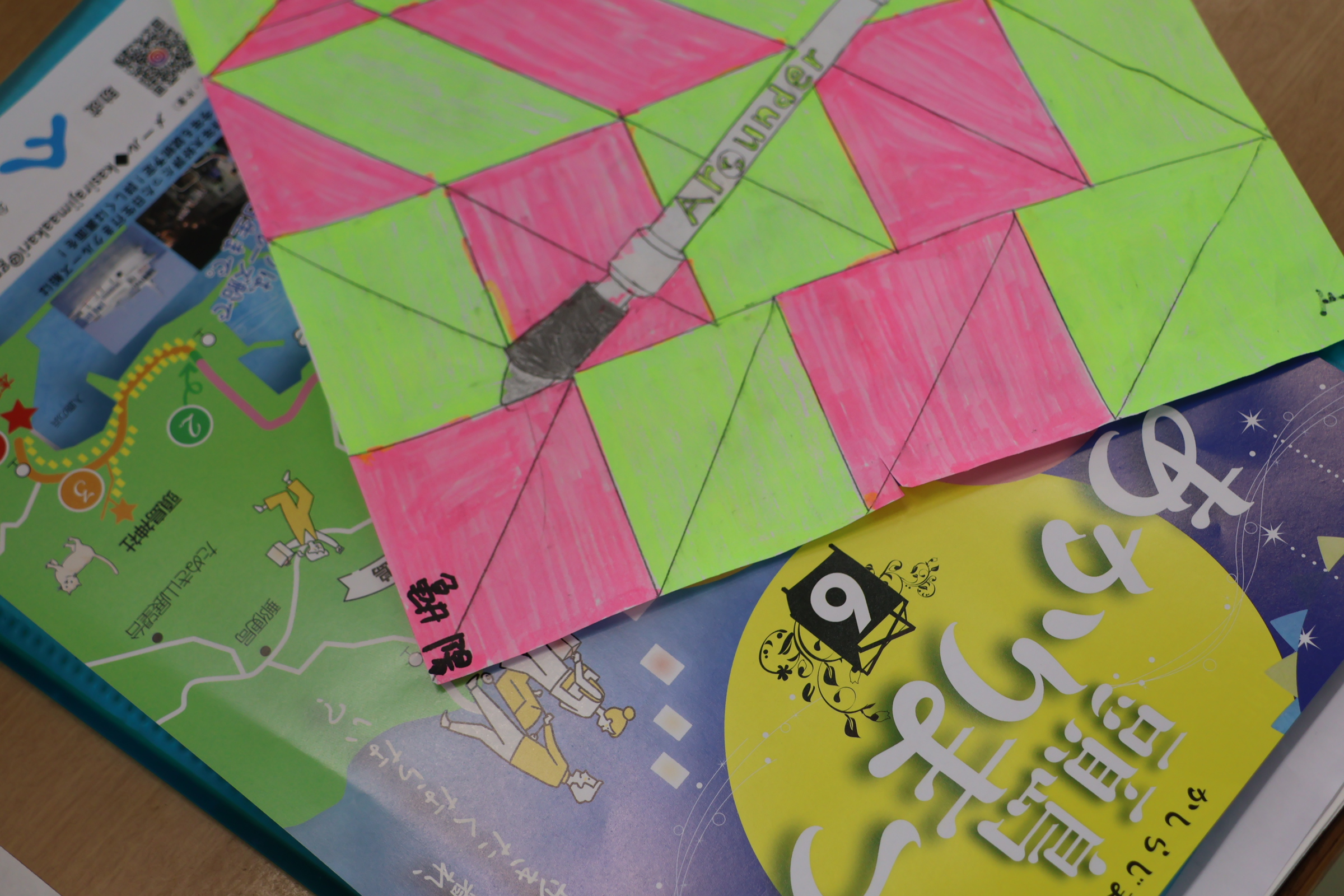

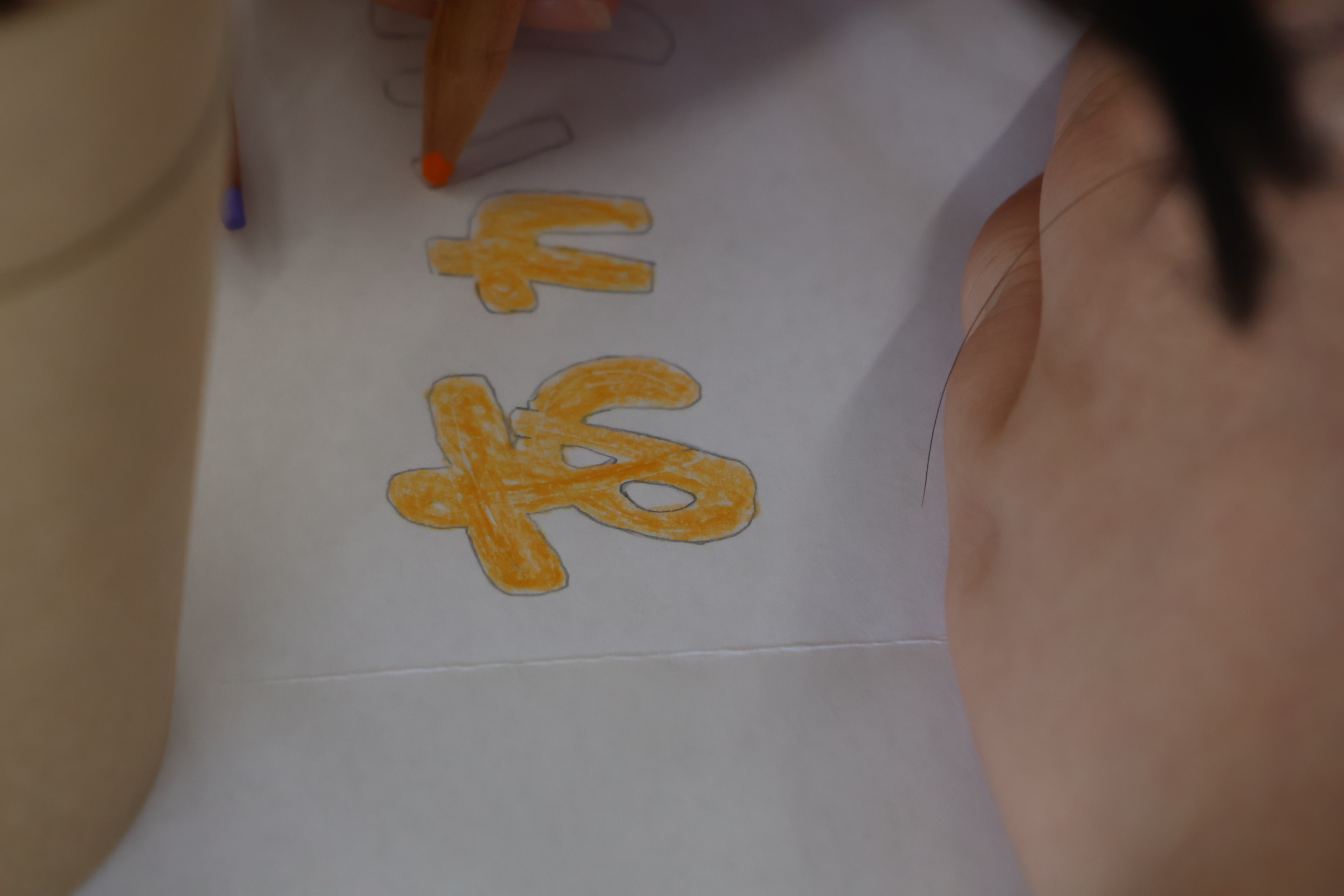

◎SUMMER TIME BLUES
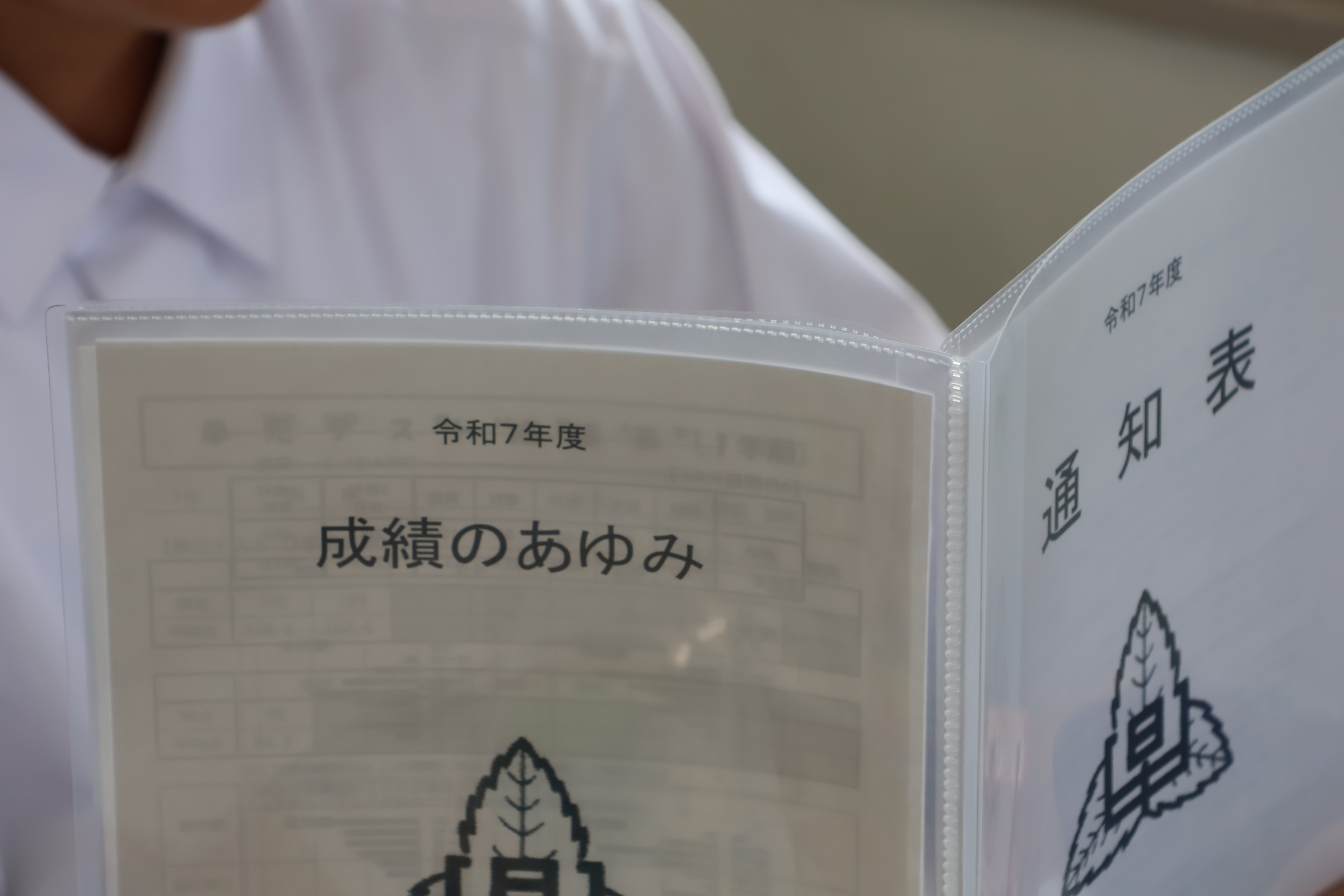
◎ここまで、そしてここから。(7/18:終業式)









じぶん 高橋新吉
じぶんがすっぽりとじぶんから抜け出したならば
このような自己に執着することはなくなる
じぶんばかりだったらなんにもないことになる
他があってはじめてじぶんがあるのだ
◎多文化共生社会で生きていく私たち(7/17)
備前市国際交流事業で来市された中国からの交流生が日生中学校に寄られました。。生徒に紹介(贈って)いただいた漢詩をもとに授業(2年生国語)をしました。
七夕今宵看碧宵 今宵(こよい)、七夕(たなばた)の夜(よ) 空(そら)は碧(あお)く澄(す)み渡(わた)り
牛郎織女渡河橋 彦星(ひこぼし)と織姫(おりひめ)が 天ノ川(あまのがわ)の橋(はし)を渡(わた)る
家家乞巧望秋月 家々(いえいえ)では 秋(あき)の月明(つきあ)かりの下(もと)で 上達(じょうたつ)を願(ねが)い
穿尽紅糸幾万条 針(はり)に幾(いく)万本(まんぼん)の赤(あか)糸(いと)を通(とお)している

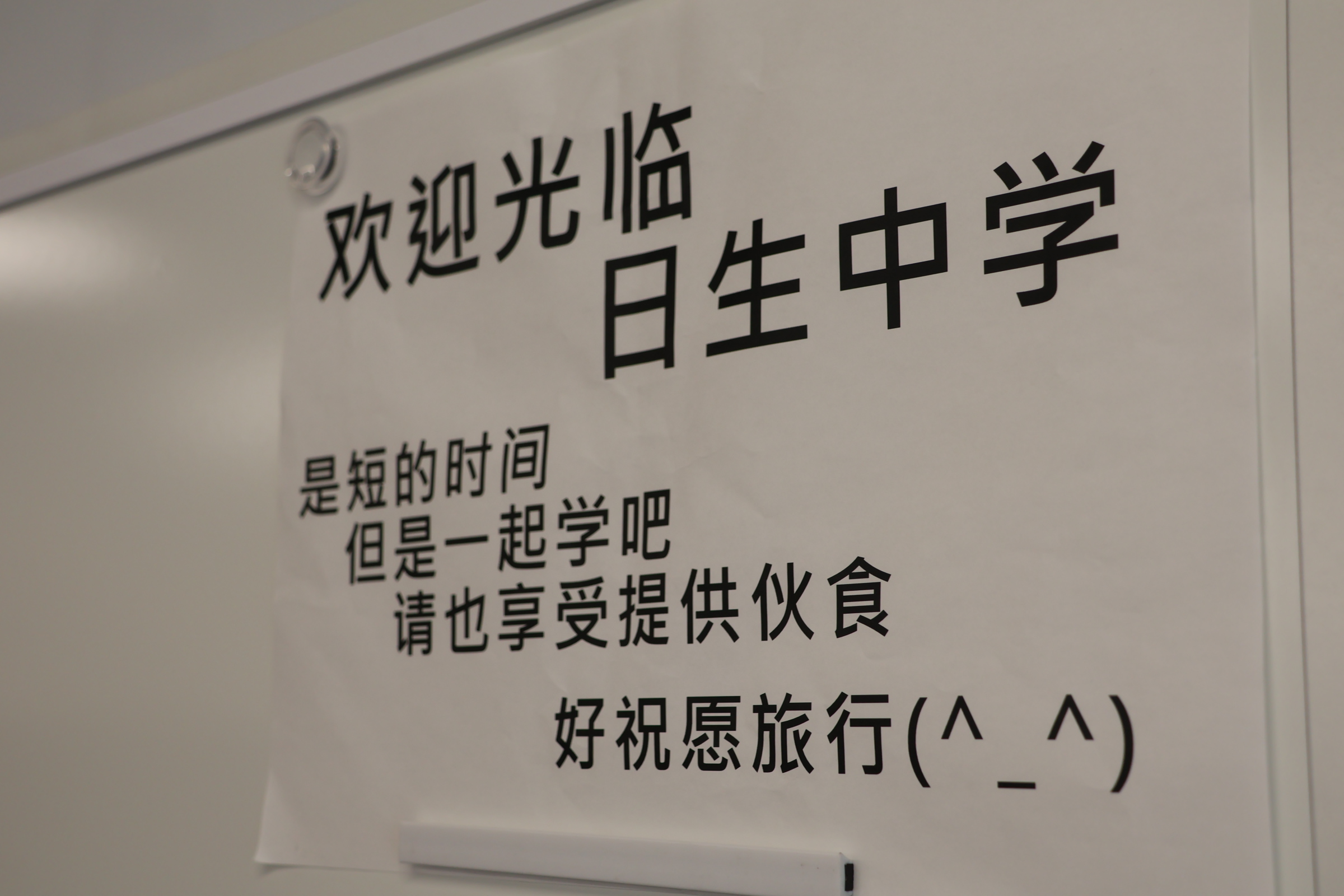

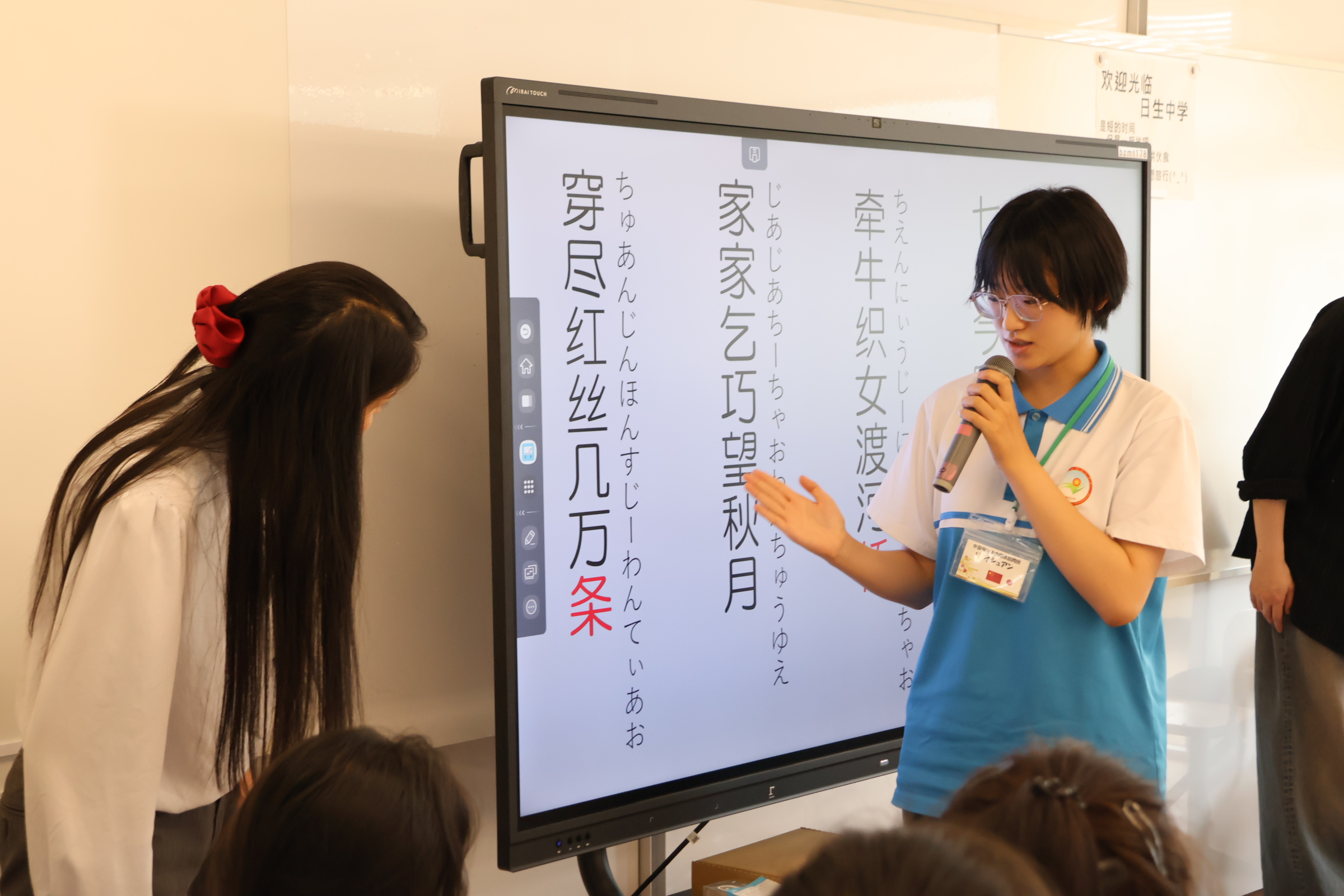





ようこそ日生中へ!!(^^)!
◎1学期もがんばったね
日々ヒビが入りハートが砕けて 勇気も自信も亡くすけど 挫けながらも強く生きて行ける 大人になるための毎日です。愛を愛し 恋に恋する 僕らはそうさ人間さ 愛を愛し 偉大に恋する 僕らもそうさ人間さ 短い春が終わってゆく 短い夏が終わってゆく 新しい時代と生きている あなたに恋をする そんな、私に気づいて欲しいのです あなたに気づいて欲しいのです。♫

大変遅くなり、すいません。広島研修・修学旅行、星輝祭(体育の部)の写真注文に関するお知らせ用紙は、18日(金)に配布します。夏季休業中に、ゆっくり御覧くださり、注文ください。(~8月末締切)
◎君看双眼色 不語似無憂(7/16:施錠チェック)


安全は自分から。夏休みも大事に!
◎多くの人に支えられて(7/16)
18日に行う生徒会主催の地域清掃ボランティアの下準備の草刈りを教頭先生がしてくださいました。ありがとうございました。18日は4つのグループに分かれて、社協川東地区協議会の方々と活動を行います。たいへんな暑さが予想されますが、ガンバロウね!みんな。

Il faux cultiver notre jardin. 〈自分の庭を耕やせ!〉ヴォルテール『カンディード』
◎大切な私、大切なあなたとして(7/15)
鳥越先生(デイジーライフ)をお招きして、性教育講演会をおこないました。


ふりかえりの一部
「自分を大切にすること、相手を大切にすることを知ったので、対等な関係についてよく考えていこうと思った。」
「自分のからだとパートナーのからだを守ることを気を付けたい」
「性に関する知識を恥ずかしいと思わずに、正しい知識をもつ」
「まずは知るということが大切だと思った。いろいろな情報がある中で正しい情報を知り、自分の中に入れようと思った。」
「自分のことばや言動が、相手を傷つけていないか、よく考えようと思った」
「自分で抱えこまずに、相談することが大事という話が心に残った」
◎みんなが、健康で元気に(7/14)



本校の立川先生が役員をされている夏祭り(7/13)へ教頭先生が行かれました。場所は、 高嶺神社御旅所(兵庫県赤穂郡上郡町山野里※山上の神社ではありません)です。古来からの伝統である『茅の輪』をくぐり、無病息災を祈る神事だそうです。また、優雅で美しい「浦安の舞」が披露され、神社の境内を厳かに彩ります。さらに自治会による模擬店やステージイベントも行われます。(日生でも8/13のひなせ夏まつりでの中学校の出店を計画しています。ボランティア推進プロジェクトのスタッフを募集していますので、早めに申し込みましょう。)さて、神社について少し調べてみました。《高嶺神社は、平安時代の天禄3年(972年)に天皇の勅命により祀られました。当時、この地域では流行病が蔓延し、多くの人々が亡くなっていました。ある夜、天から光が降り、有明山からも光が立ち上がり、その光が「神田柳田森」に到達しました。この現象を朝廷に報告し、天皇が調べた結果、「天竺摩詞陀国の牛頭天王(須佐之男命)が当地の鎮守として鎮まった」との託宣を受けました。それ以降、流行病は治まり、人々は通常の生活に戻ることができました。」「夏祭りは無病息災、家内安全、家運隆昌、諸難消除を祈る祭りです。特に、髙嶺神社の御祭神である須佐之男命(牛頭天王)が蘇民将来に『茅の輪』を与え、災難・疫病から守った伝説は有名です。このため、全国の神社で『茅の輪』を設け、皆様に『輪越し』をしていただき、各家の玄関に『茅の輪』を掛ける風習があります。輪越しの神事はどなたでも参加可能です。神前の大きな『茅の輪』をくぐり、ご家庭用の『茅の輪』をお受けください。玄関に掛けて、邪悪を追い払いましょう》今年も学校玄関に飾る「茅の輪」をありがとうございます。
◎子どもたちの豊かな育ちに向けて(7/11)
備前警察署管内学校警察連絡協議会を開催しました。コロナ禍以降、初の参集形式の会としました。顔を見合いながら連携推進に向けて協議をおこないました。また、今年度の活動として、学校別懇談会を行い、各校の課題解決にむけての相談や情報交換の充実を進めていきます。

「あのう、わたくし、ここからどの道を行けばいいか、教えていただきたいんですけど」
「それは、君がどこへ行きたいかによるわな」とネコのこたえだ。
「どこだっていいんですけどーー」
「それならどの道だってかまわんだろ」
「――どこかへ辿り着きさえすればね」アリスがいいそえると、ネコはネコで、
「そりゃあ行きつけらあ。ちゃんと歩き続けて行きさえすりゃあね」
"Would you tell me‚ please‚ which way I ought to go from here?"
"That depends a good deal on where you want to get to‚" said the Cat.
"I don't much care where--" said Alice.
"Then it doesn't matter which way you go‚" said the Cat.
"--so long as I get somewhere‚" Alice added as an explanation.
"Oh‚ you're sure to do that‚" said the Cat‚ "if you only walk long enough." 不思議の国のアリス (新潮文庫)/新潮社
◎今日もひたむきに(7/11)





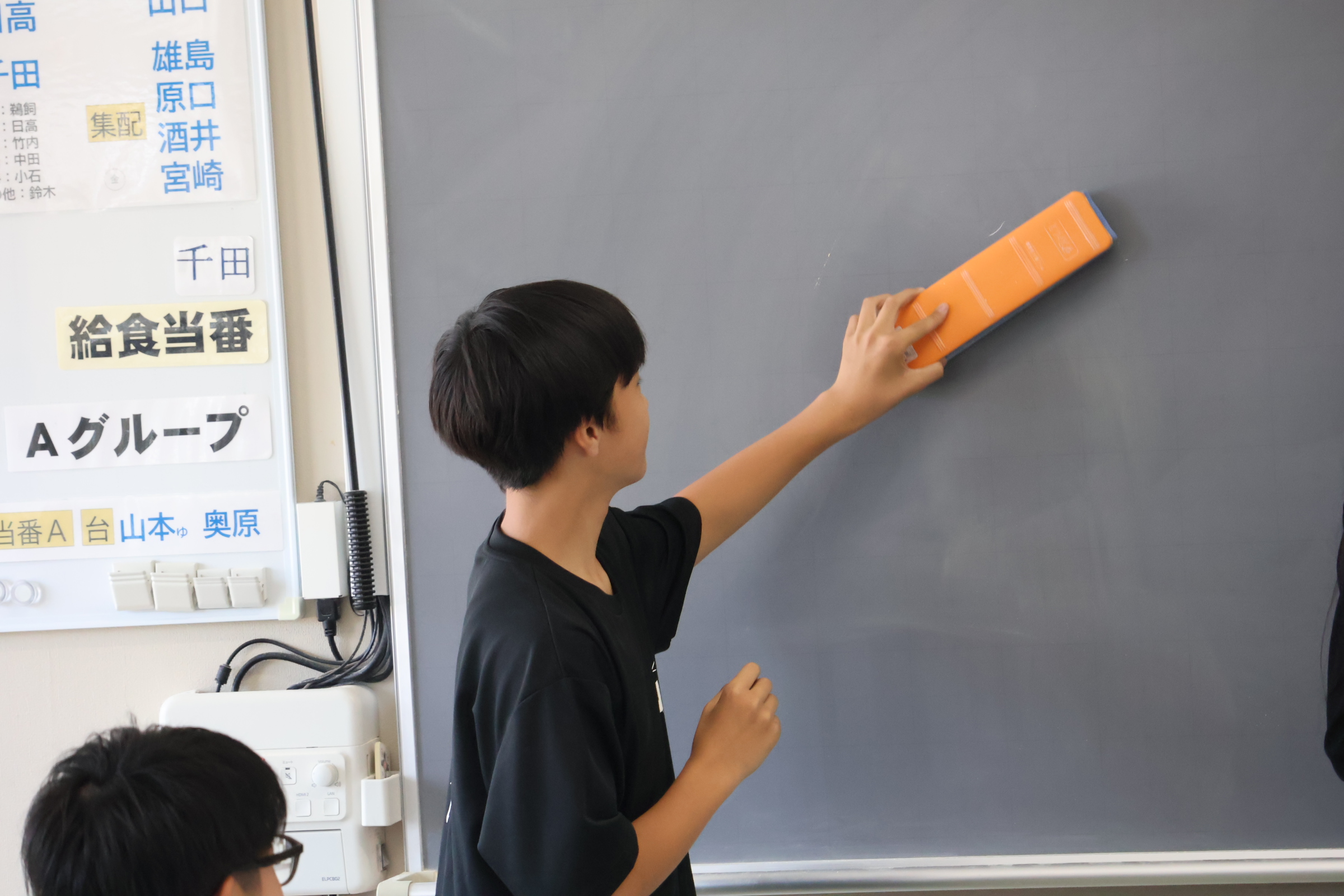

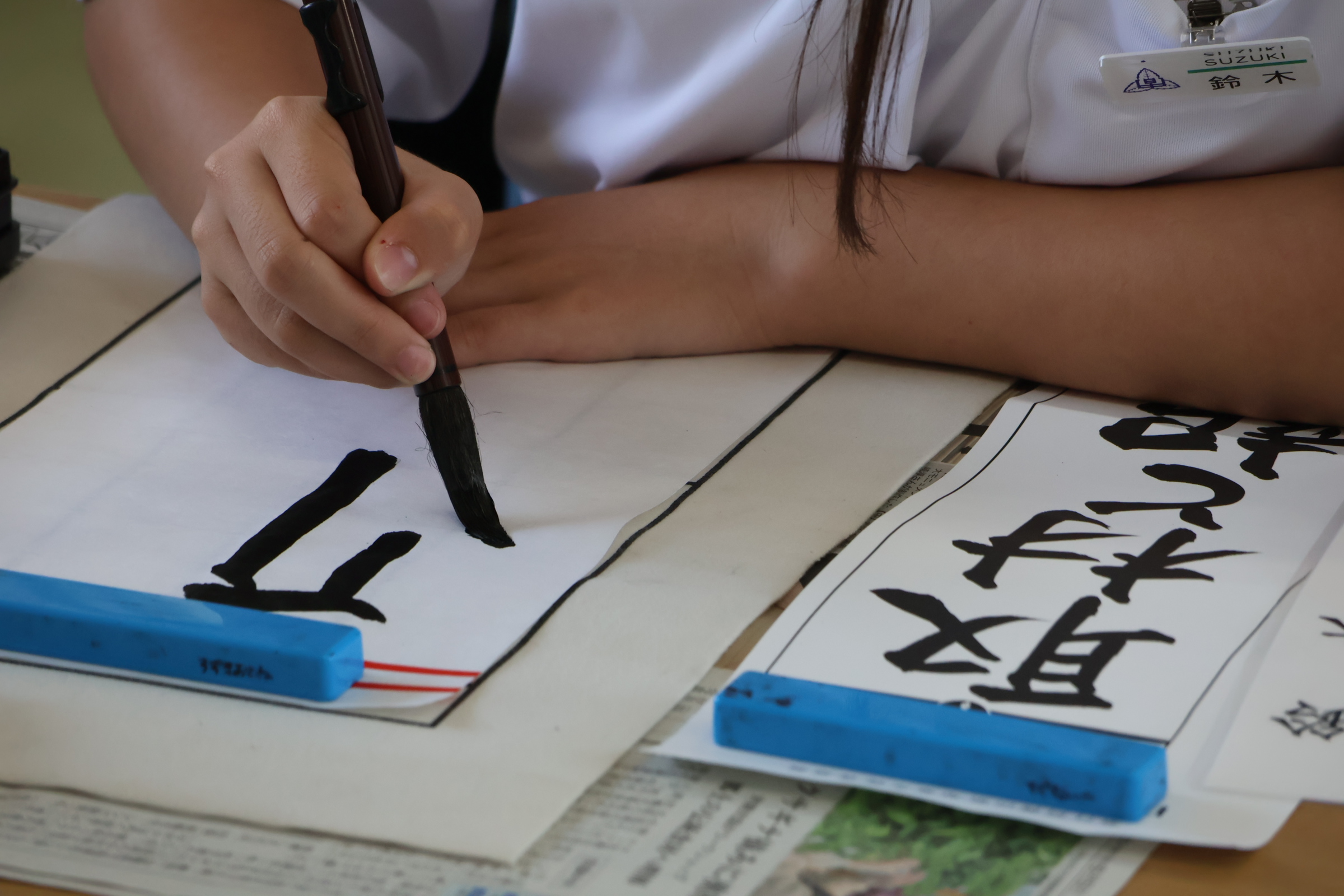

光岡先生、二日間ありがとうございました。
◎夏が来る♬


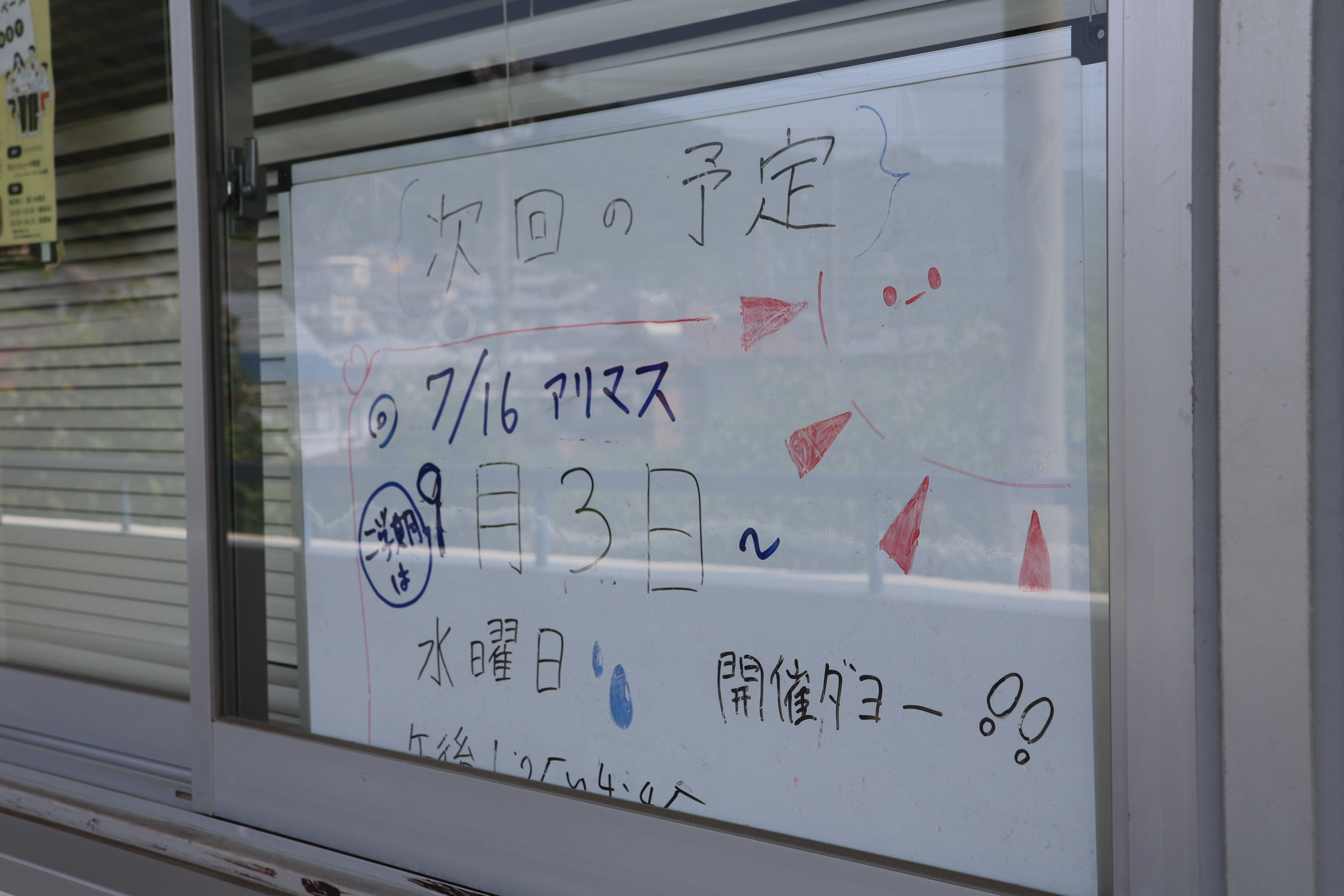
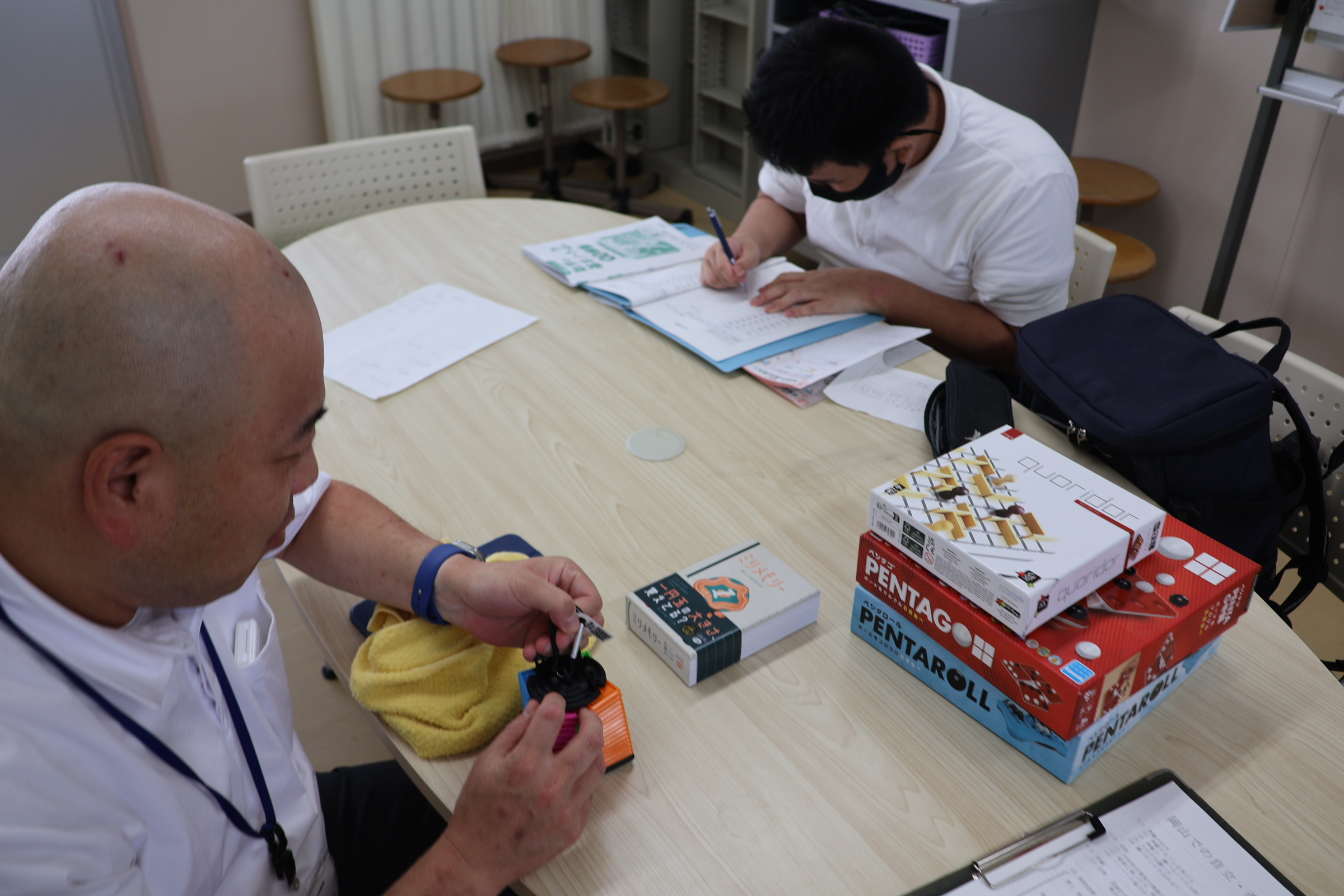





◎生き抜くちからを~多くの人に支えられて(7/1(社会科(地理的分野))
エリアティチャーとして中務さんをお招きして、ハザードマップの読み取りから防災・減災・備災について学習サポートをしていただきました。
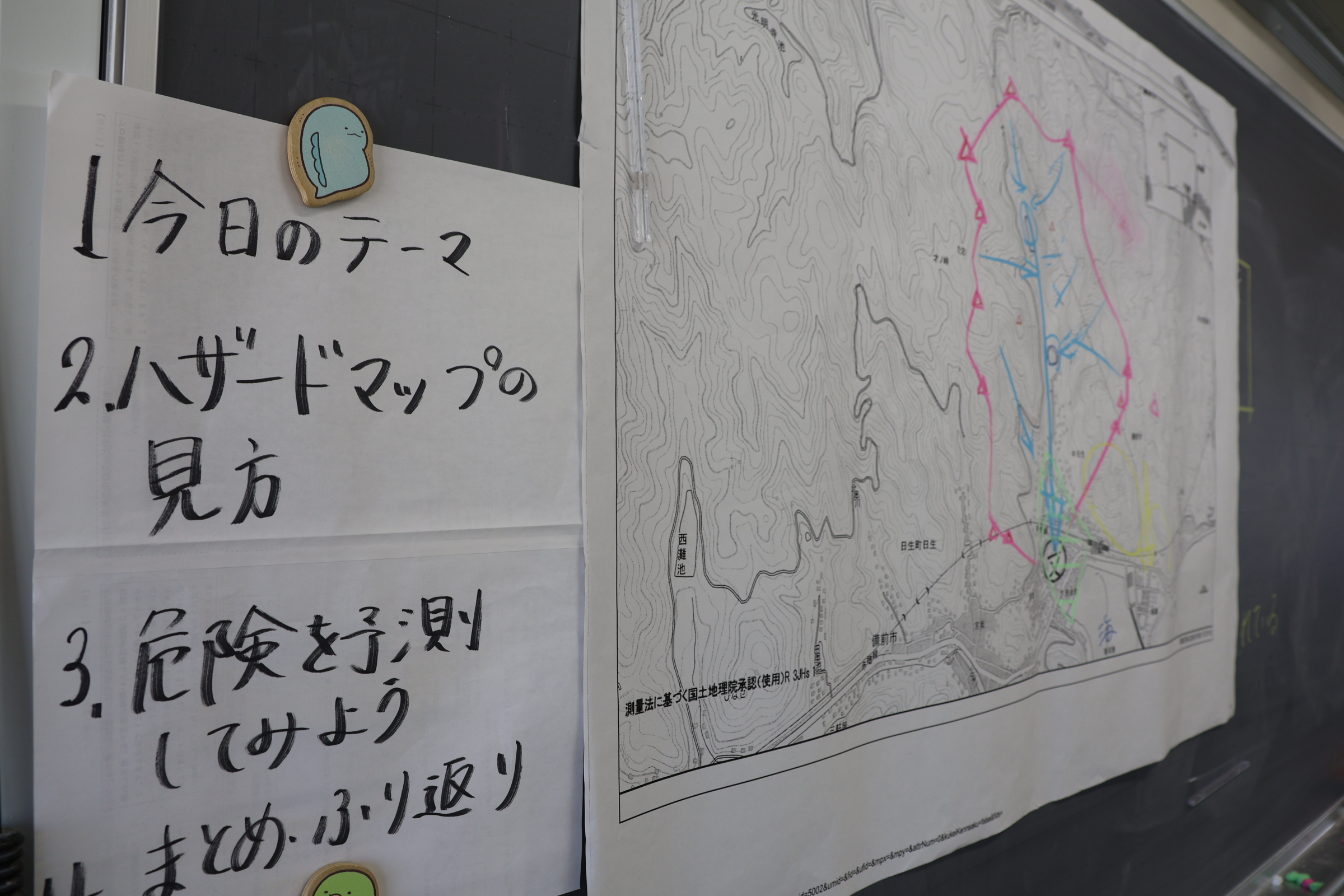

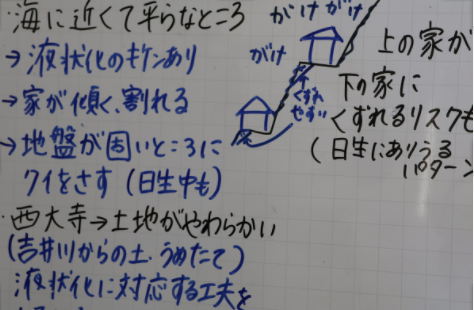



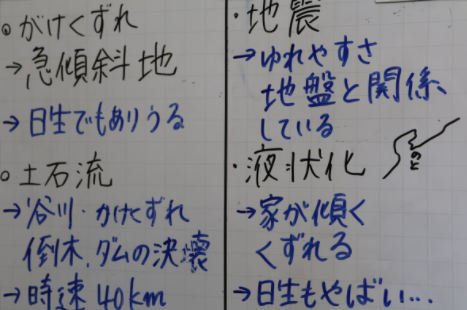


◎日本文化を学ぶ~多くの人に支えられて(7/10:国語(書写))
エリアティチャーとして光岡さんをお招きして、書道展の作品づくりのサポートをしていただいています。
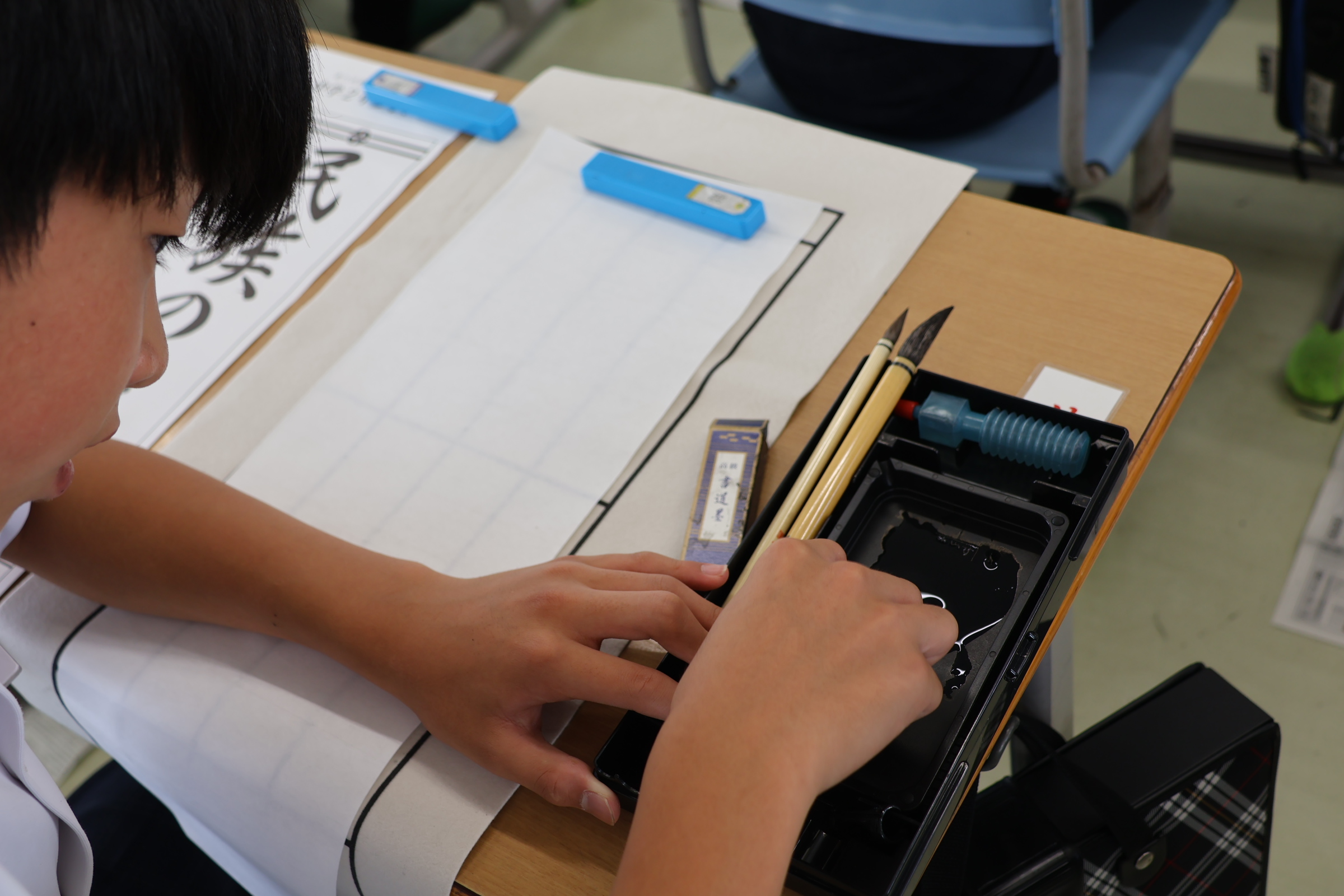

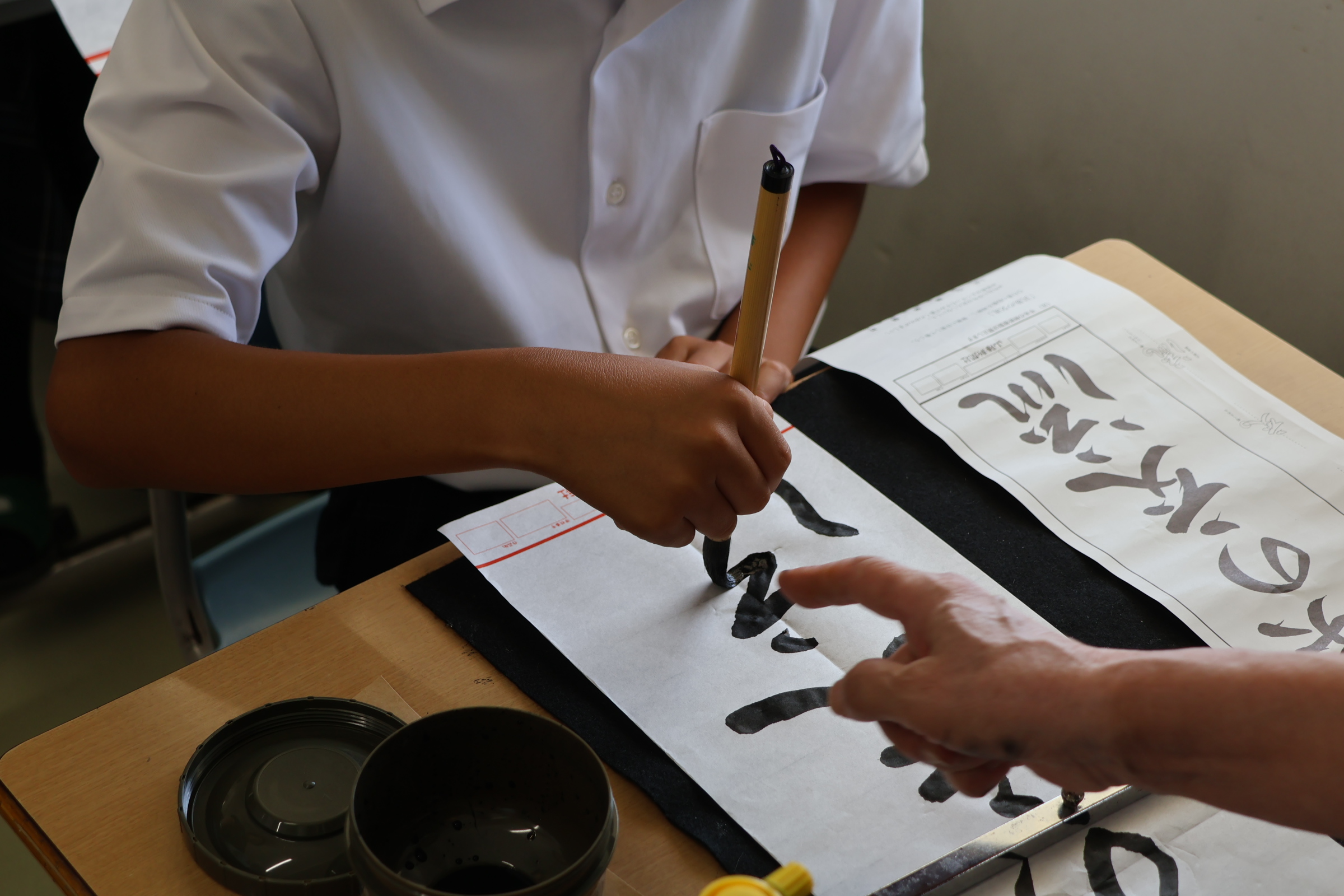


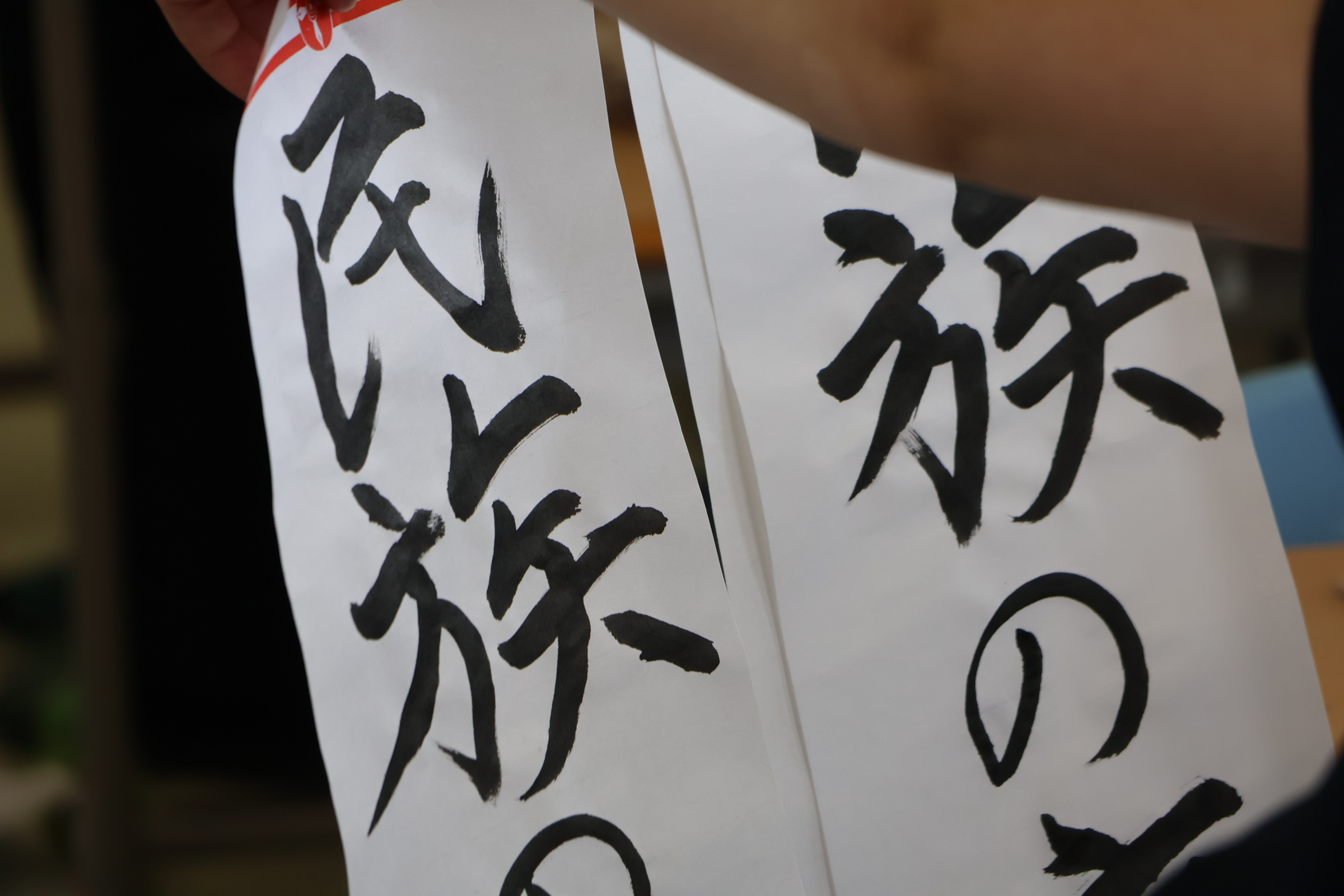
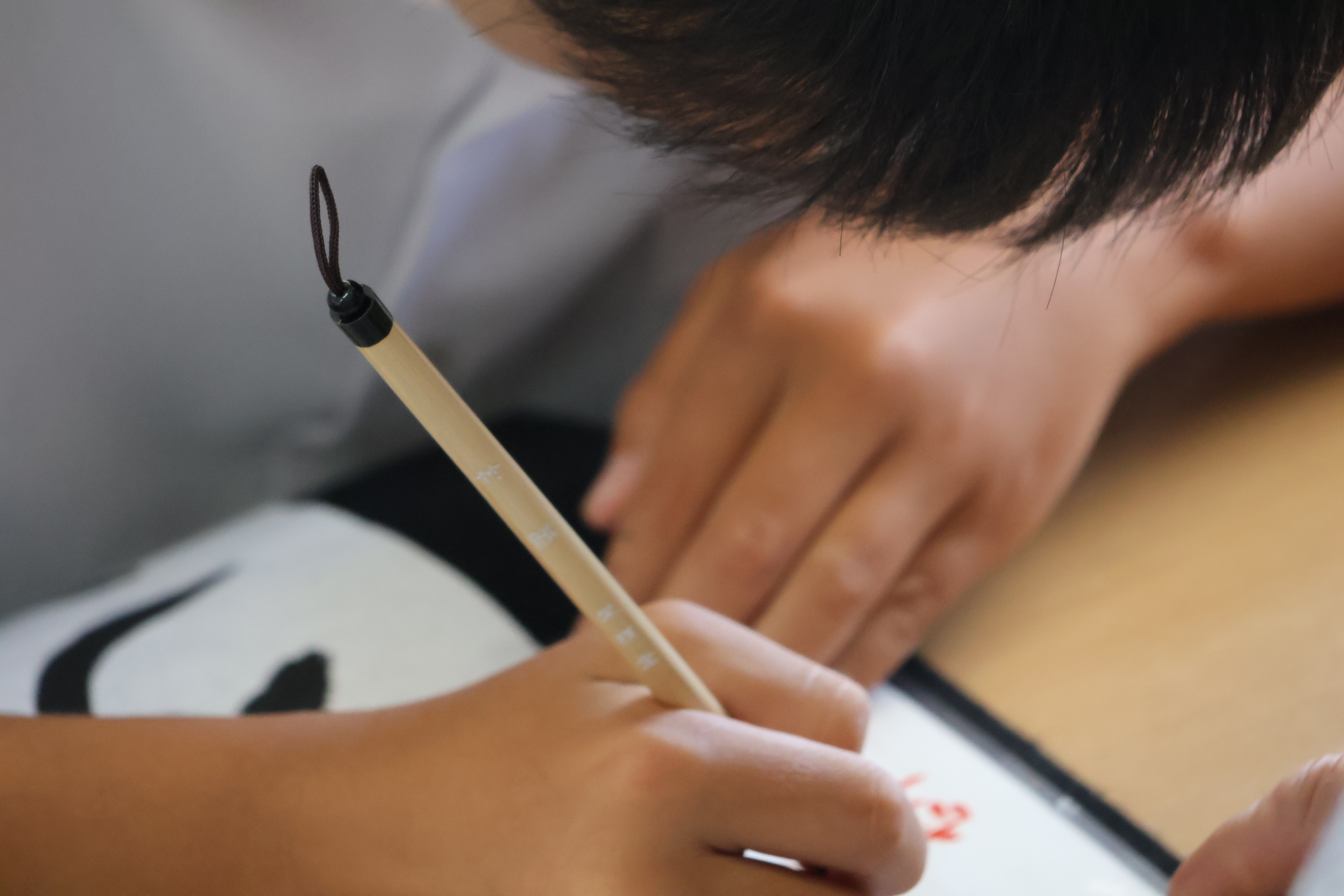
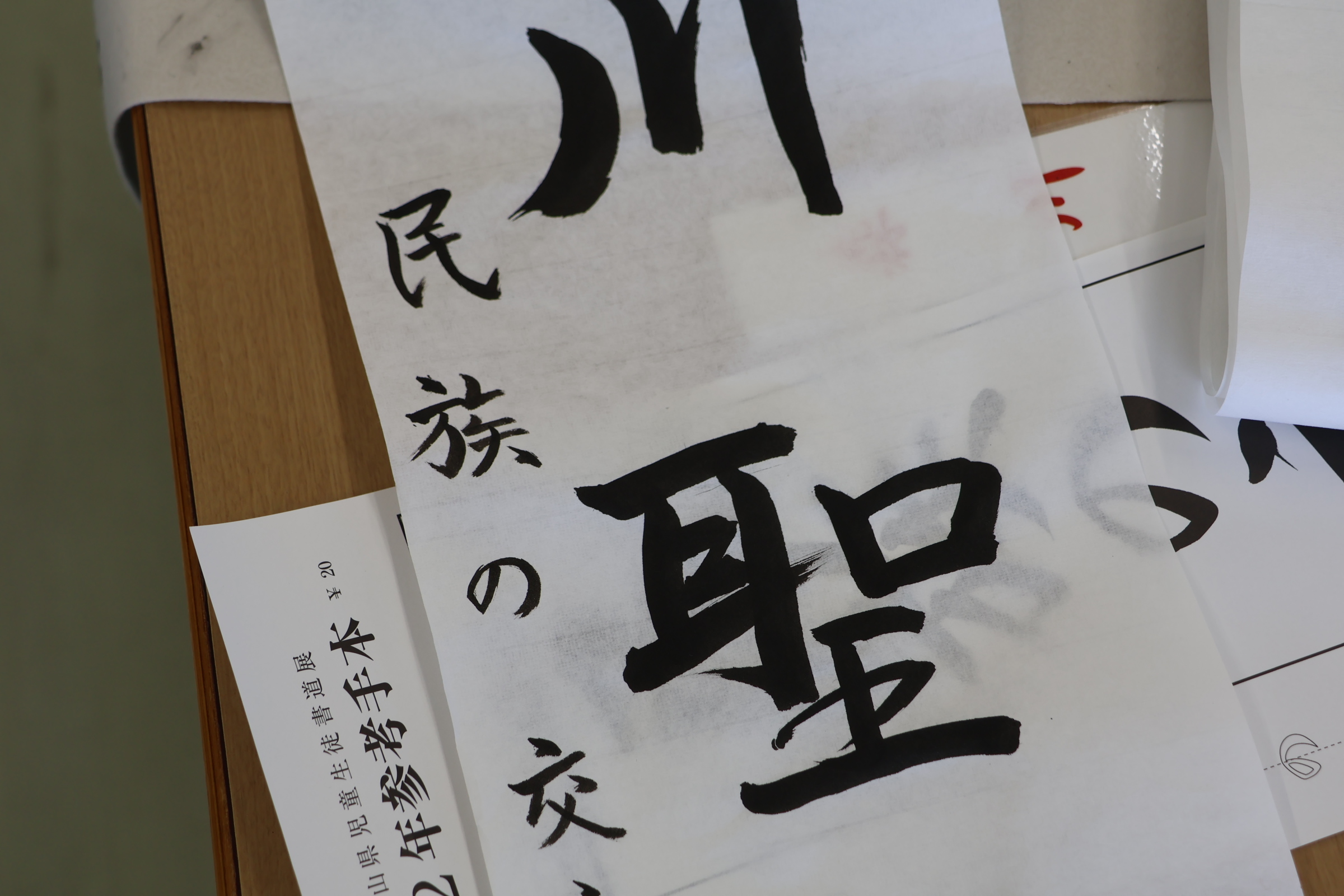

◎ひな中らしく わたし輝く 夏ボラの夏✨
事業所との打ち合わせ会(7/9)


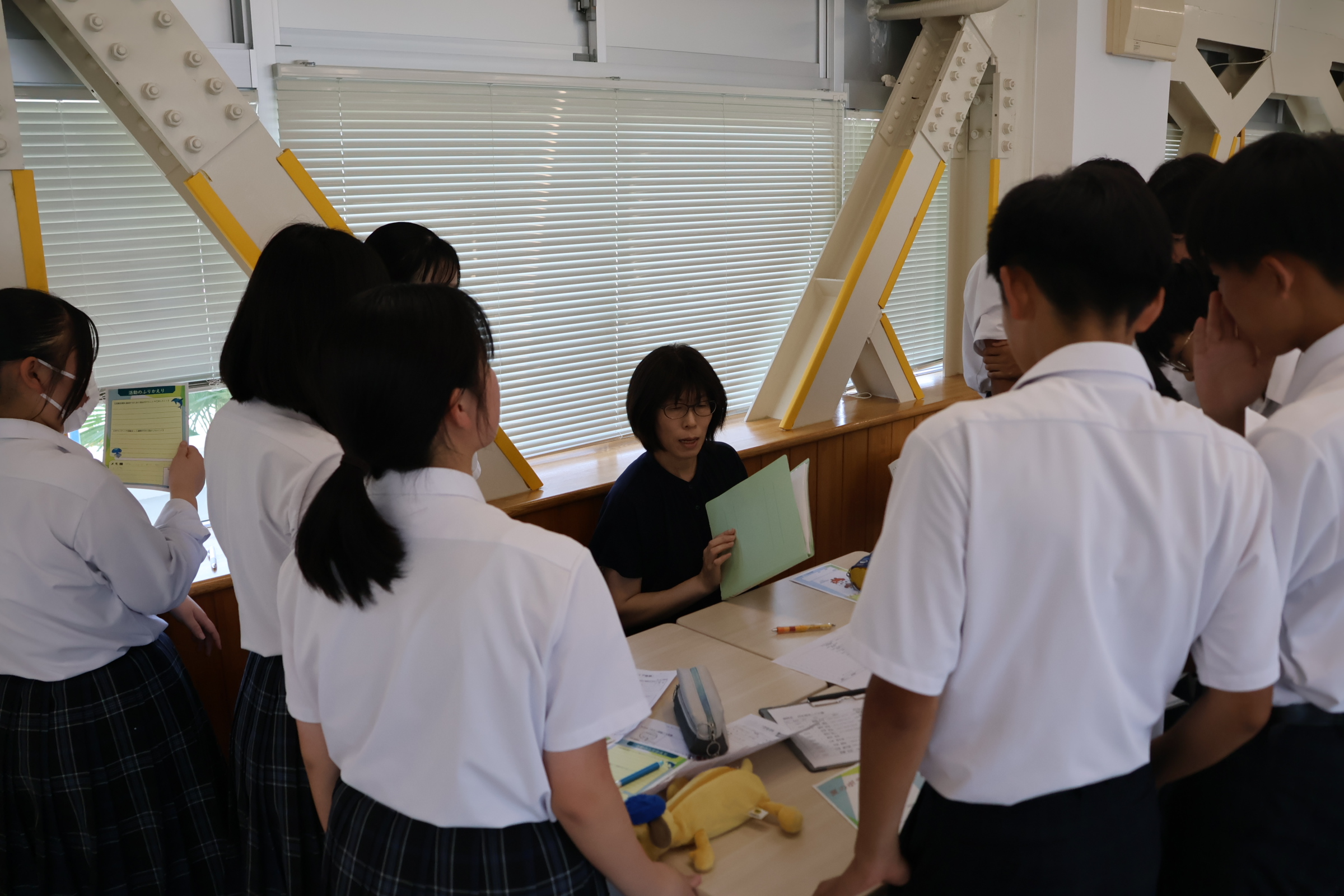
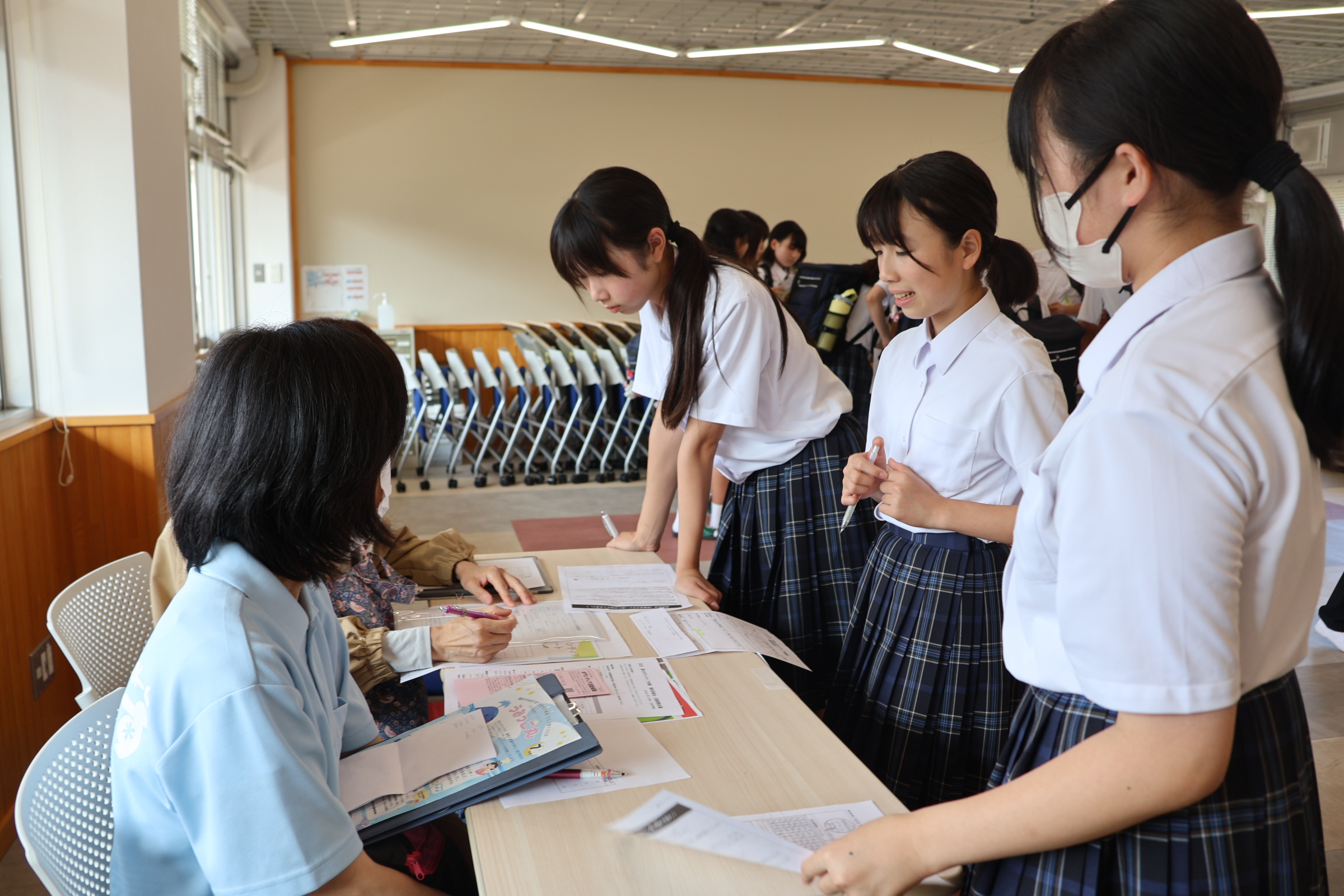

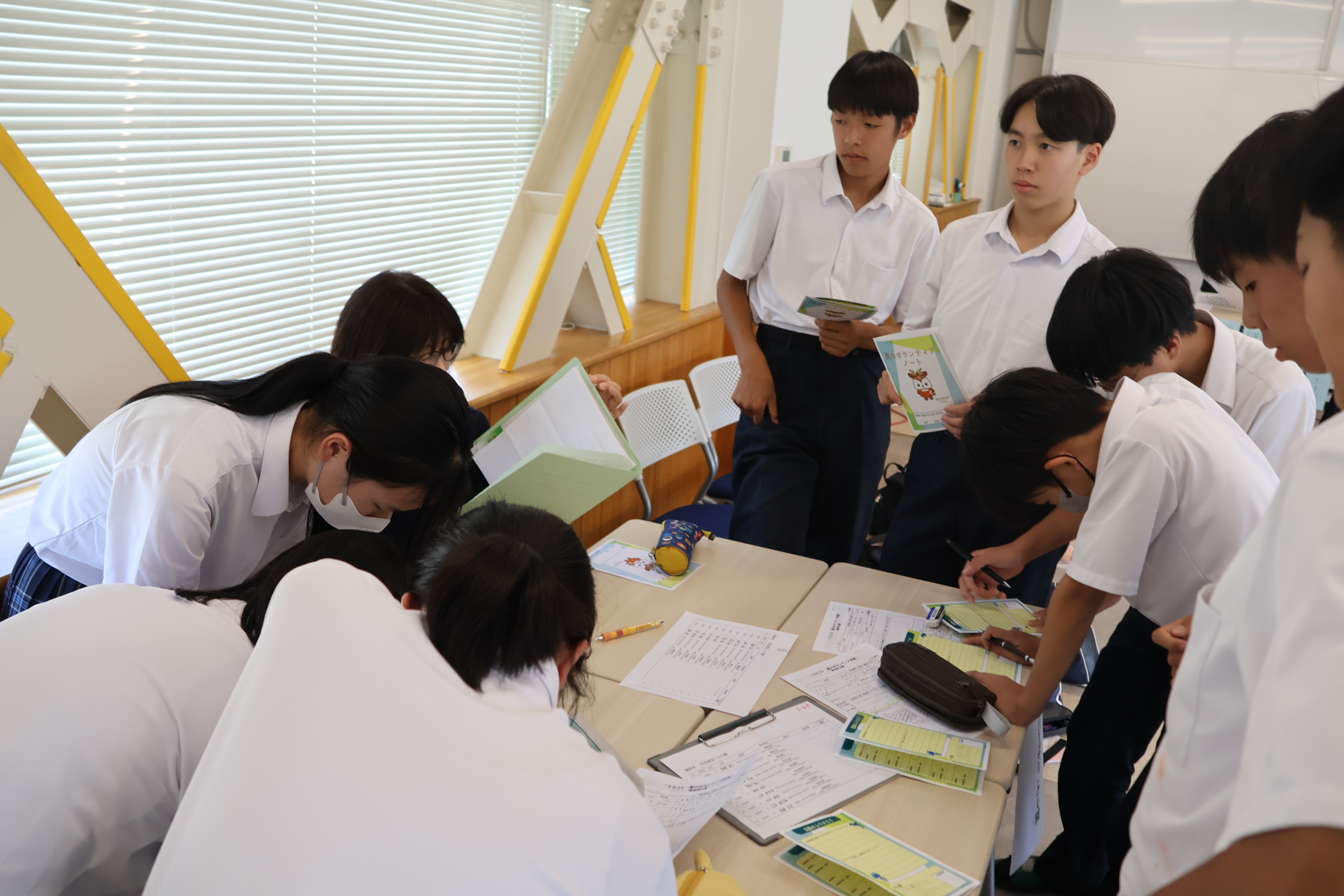
◎スマホ・携帯電話安全教室(7/9)
ソーシャルメディア研究会の大学生を講師として、今年度も、中学校連携の一環としてリテラシー学習の場を設けました。
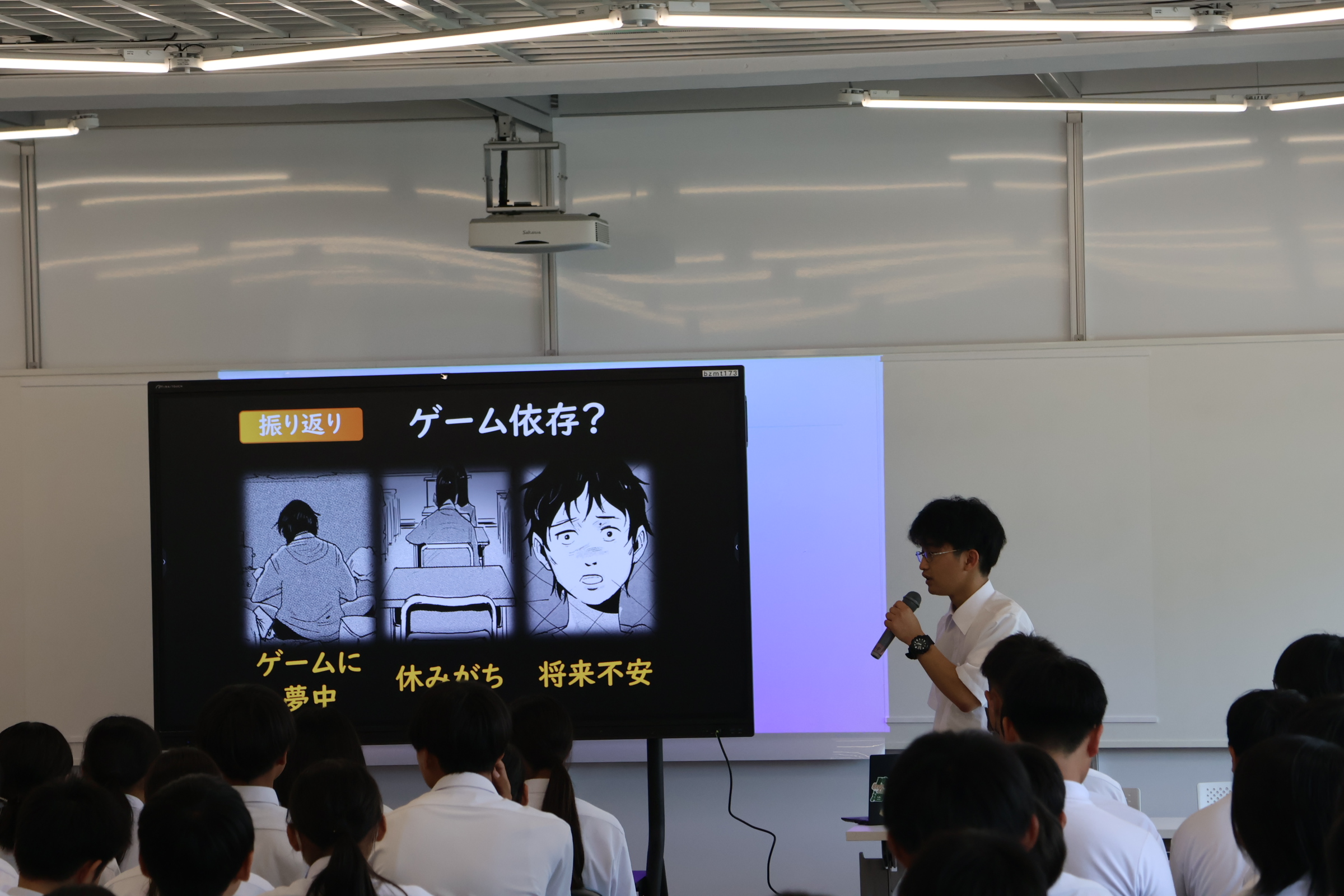

◎Hello!仲間のことを知ること、
仲間に知ってもらうことって楽しいね!大切ね!(7/9:英語授業)






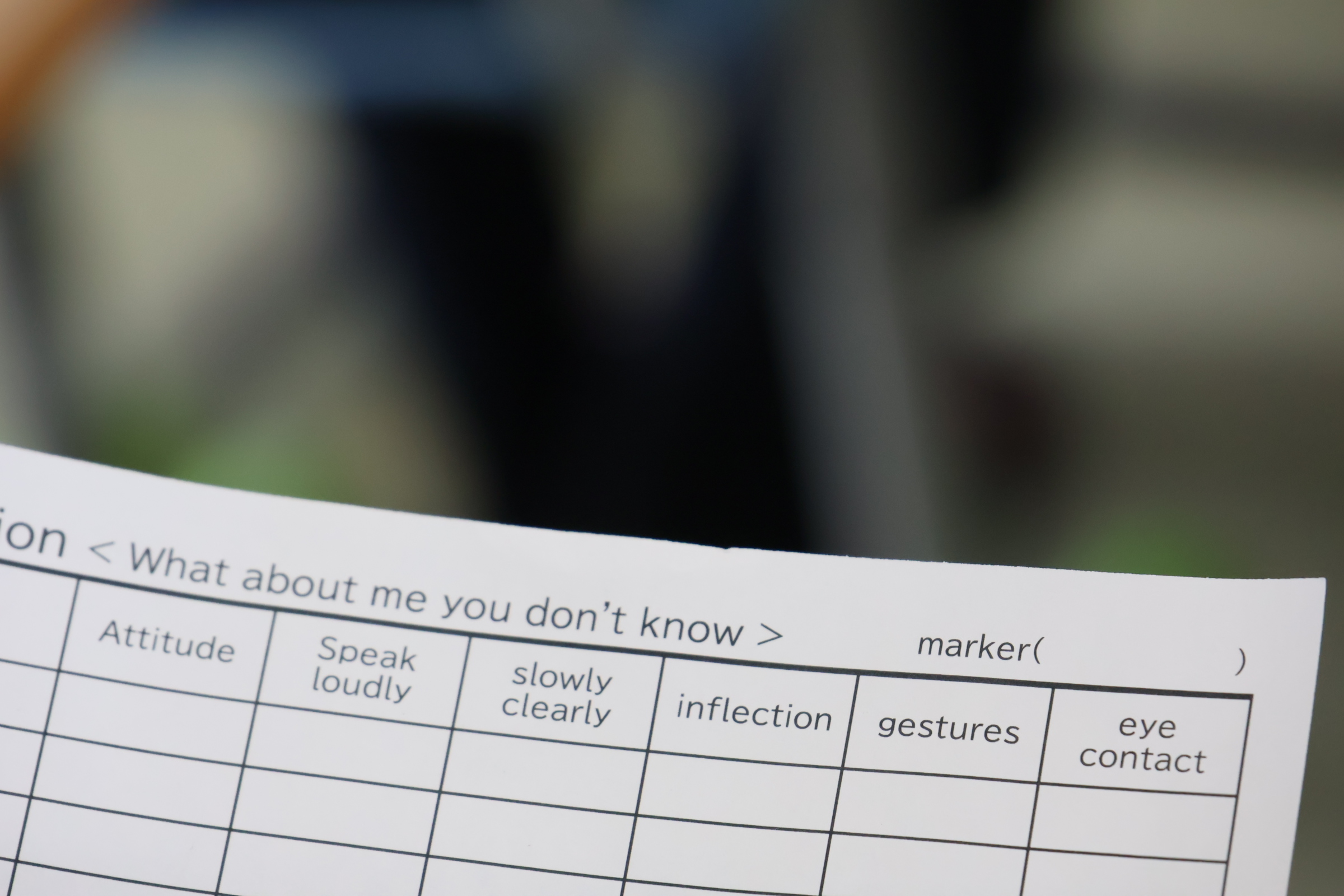


◎守るためには、考えてうごく(7/8:不審者対応避難訓練)
備前警察署から根来さんらをお招きして避難訓練を行いました。また、夏季休業中に向けて、水難事故、非行防止についてもお話をしていただきました。


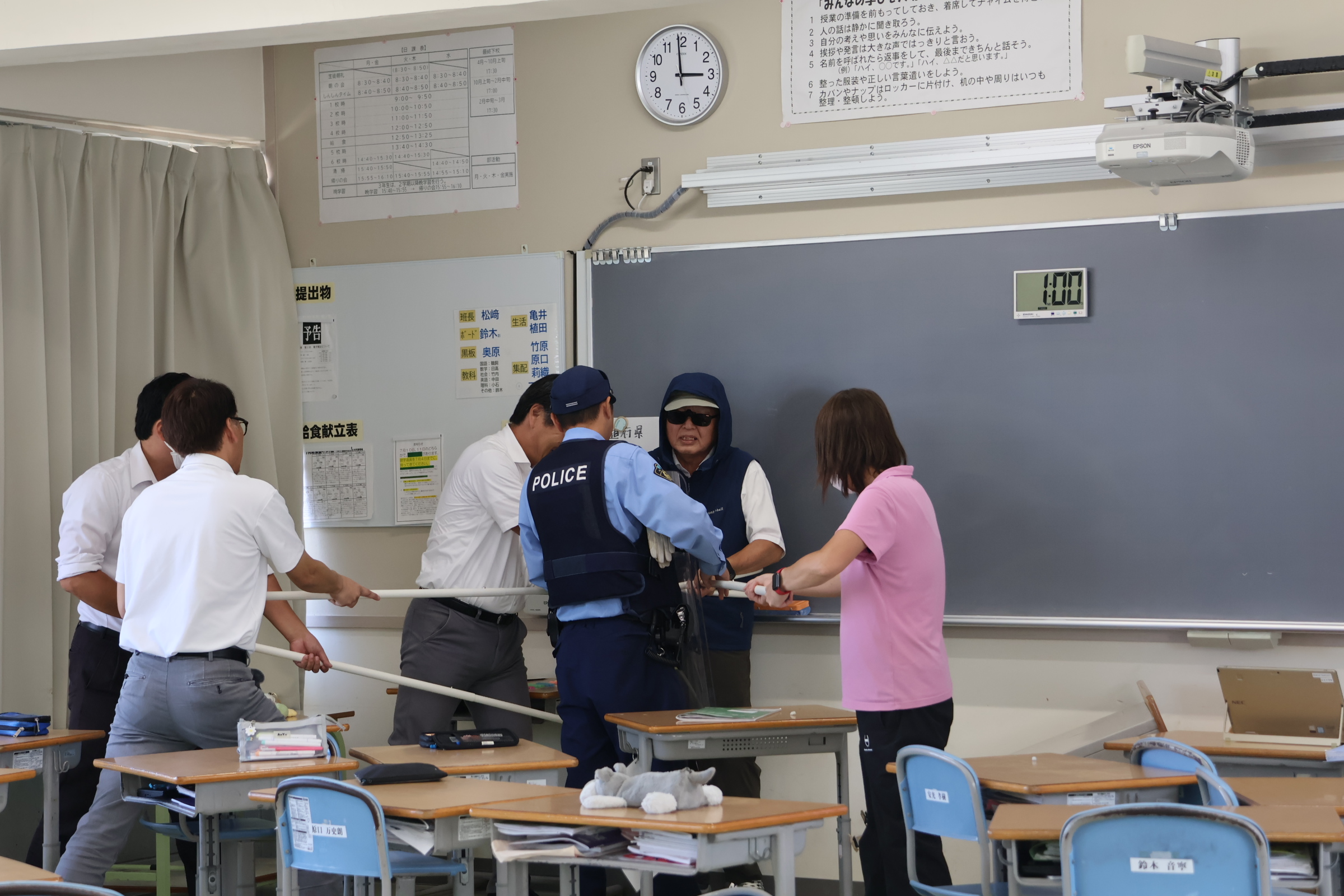
◎自分らしく せいいっぱい 進路は多様
春15(いちご)の会の案内が届きました。(7/8)

今日の日生親の会でも‚進級・進学についての話題があります。
◎7月7日 ~晴れた夜空 数を増やす星 かなえたい願いは♪

7月7日、いろんな日(記念日)となっていますね。例えば、
◇アルティメットの日:フライングディスクを使った団体競技である「アルティメット」の魅力を広めるために制定された日。アルティメットが7人対7人で試合をすることから。
◇糸魚川・七夕は笹ずしの日:糸魚川流域の郷土料理である「笹ずし」のおいしさを広めるために制定された日。7月7日が「笹の節句」と呼ばれていることから。
◇川の日:地域の良好な環境づくりを考え、河川に対する関心を取り戻すために制定された日。七夕伝説に天の川のイメージがあることから、7月7日に。
◇コンペイトウの日:金平糖の文化を後世に伝えるために制定された日。金平糖が星の形をしていることから、織姫と彦星の七夕伝説にちなんで7月7日に。
◇ソサイチ(7人制サッカー)の日:ブラジル発祥の7人制サッカー「ソサイチ」の魅力を広めるために制定された日。ソサイチが7人対7人で試合をすることから。
◇七夕:彦星と織姫が年に一度だけ会うことが許されているという伝説で、その日付が7月7日であることから。
◇手織りの日:機織り機などを使って自分の手で布を織る「手織り」の文化の発展のために制定された日。七夕に、彦星に会うために1日だけ機織りを休む織姫の代わりに手織りをしようという思いを込めて7月7日に。
◇ハスカップの日:北海道で栽培されているベリーの一種「ハスカップ」の魅力を広めるために制定された日。ハスカップの花言葉が「愛の契り」であることから、織姫と彦星の七夕伝説にちなんで7月7日に。
◇みんなで土砂災害の減災を願う日:自分が住んでいる地域のため池や崖などでの、土砂災害の危険性を知るために制定された日。2018年7月に西日本や東海地方で記録的な大雨となり、7月7日に土砂災害が多発したことから。
◇ゆかたの日:中国で昔、七夕の日に裁縫の上達を祈る風習があったことにちなんで。
さて、7月7日「七夕」にちなんだ、七夕に関するクイズをいくつか!チャレンジしてみましょう。
Q1.七夕は元々どんな行事だったでしょう?(1)正月行事(2)盆行事(3)成人行事
Q2.七夕に食べられる行事食は、次のうちどれでしょう?(1)うなぎ(2)水ようかん(3)そうめん
Q3.七夕の日に願いを書くのは、次のうちどれでしょう?(1)葉書(2)短冊(3)半紙
Q4.七夕の日に、織姫と彦星が渡ると言われている「天の川」。英語で「天の川」のことを何というでしょう?(1)スターライン(2)ナイトリバー(3)ミルキーウェイ
こたえ
Q1.七夕は元々どんな行事だった?《答》(2)盆行事→元々、日本では7月7日の夜にお盆の行事が行われていました。
Q2.七夕に食べられる行事食は?《答》(3)そうめん→七夕の日には、そうめんを食べる風習があります。元々は中国で無病息災を願って7月7日に麺を食べる習慣があることにちなんでいるという説があります。
Q3.七夕の日に願いを書くの?《答》(2)短冊→七夕の日には、紙や薄い木や竹の皮を細長く切った短冊に願いを書いて、笹の木にかざります。
Q4.七夕の日に、織姫と彦星が渡ると言われている「天の川」。英語で「天の川」のことを?《答》(3)ミルキーウェイ→天の川のことを、英語では「ミルキーウェイ(Milky Way)」と言います。「乳の川」という意味で、ギリシャ神話で女神ヘラの母乳が流れ落ちたものとされています。
◎チャレンジ✨ 扉をひらく(7/4:家庭科1年生)
今年も、多くのひとに支えられて「浴衣」着付け学習、そしてエリアティチャーさんらと「日生音頭」の練習。





















なんと!8/13のひなせ夏まつりでの、ひな中盛り上げ隊ブースでは、浴衣来店で割引だそうですよ。(出店スタッフも募集中)
◎鍵かけコンテスト中。高い意識を(7/3:体育委員会活動中)

◎ひな中の風~~~
繰り返し練習、練習。書写に取り組んでいます!(7/4~10)
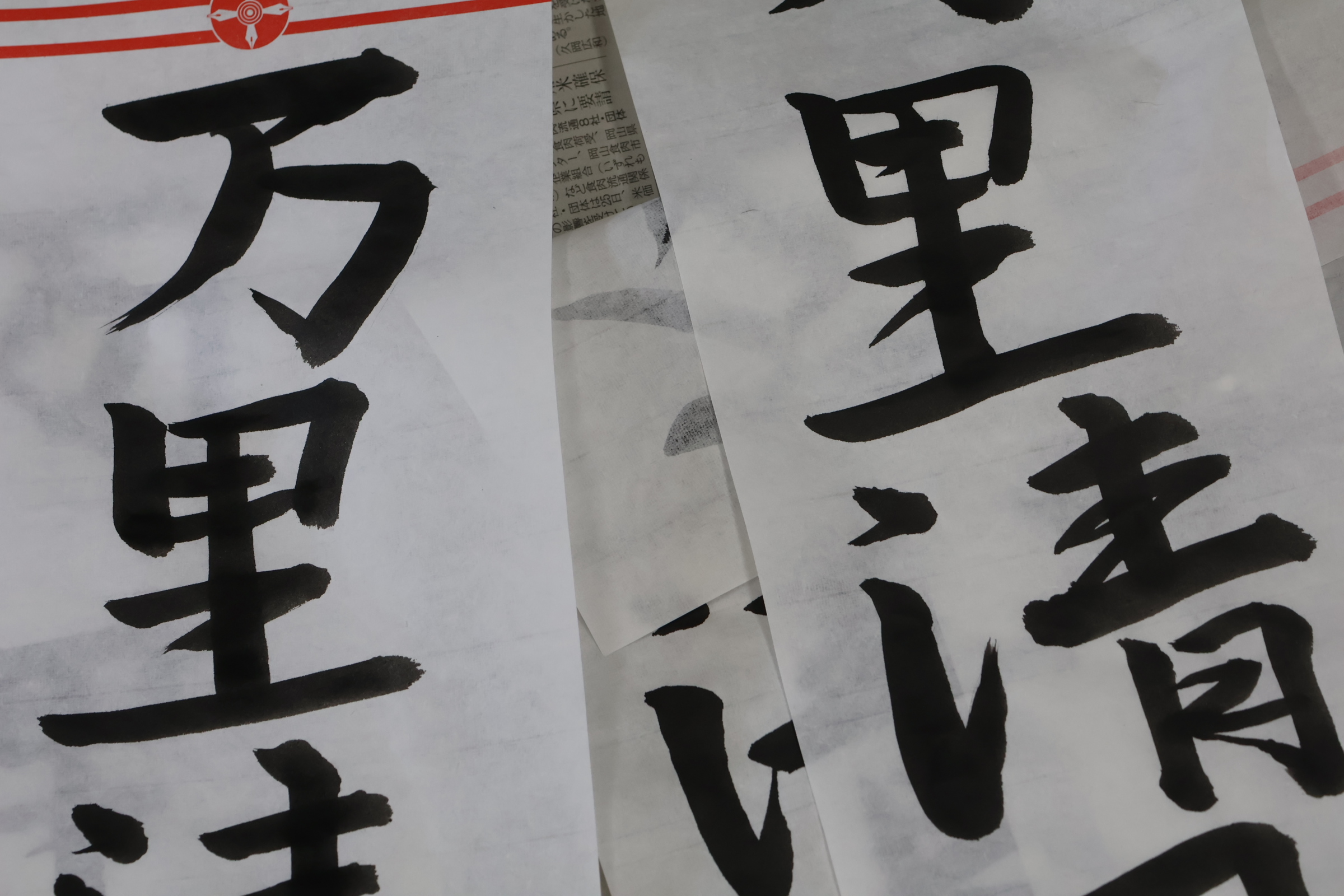
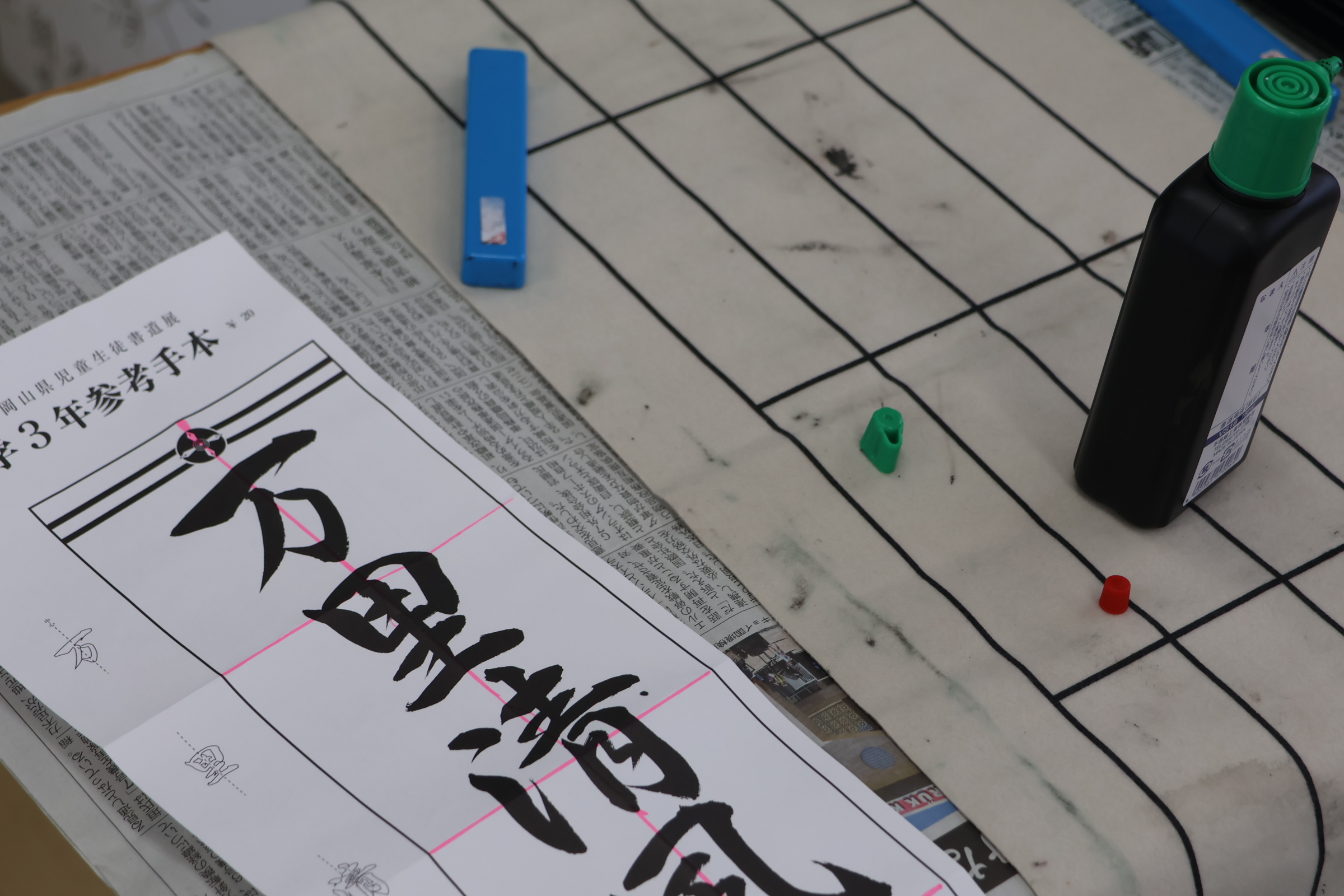

◎ひな中の風~~
伝えるちからは進路を切り拓く力(7/4:英語授業(1年・3年))
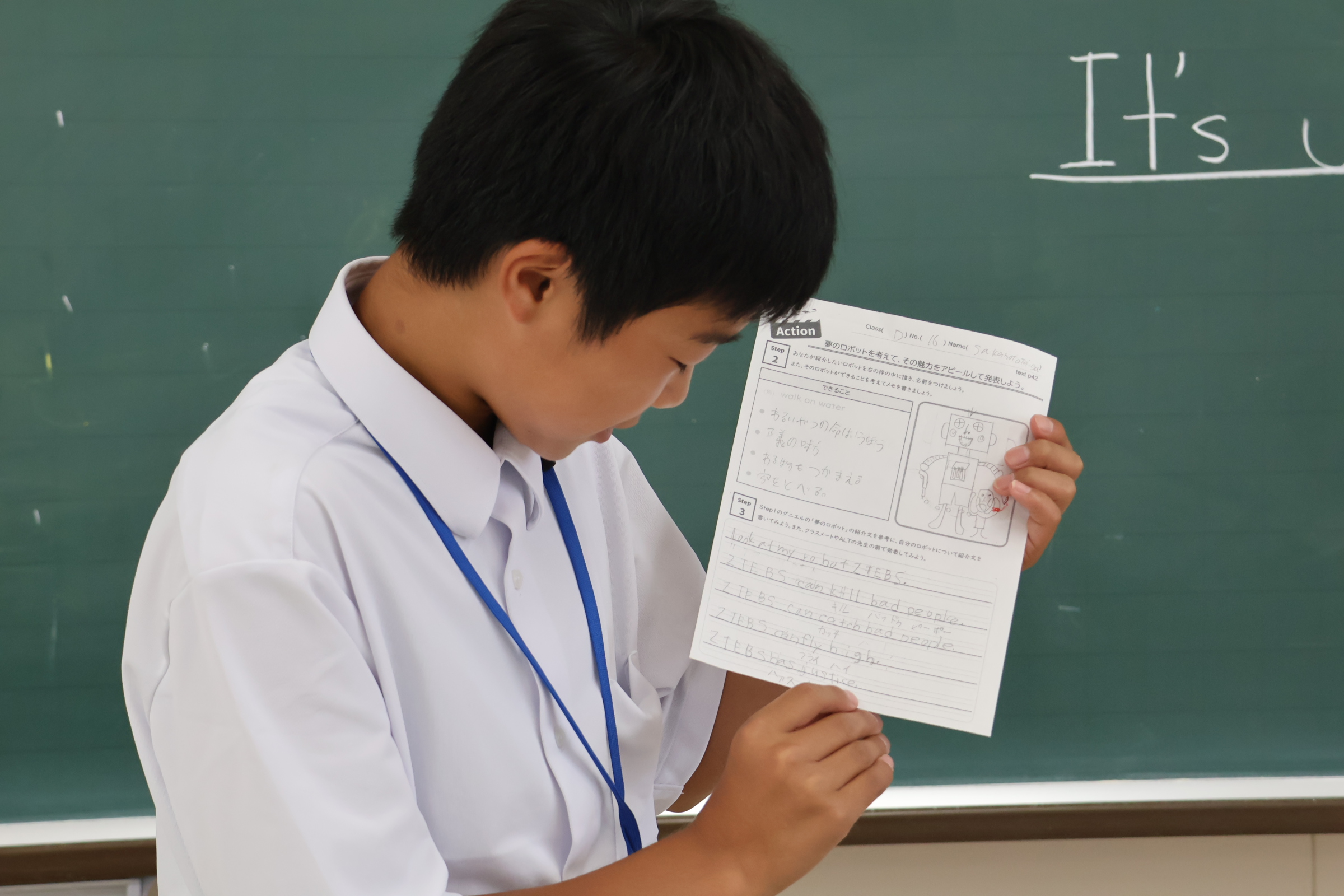



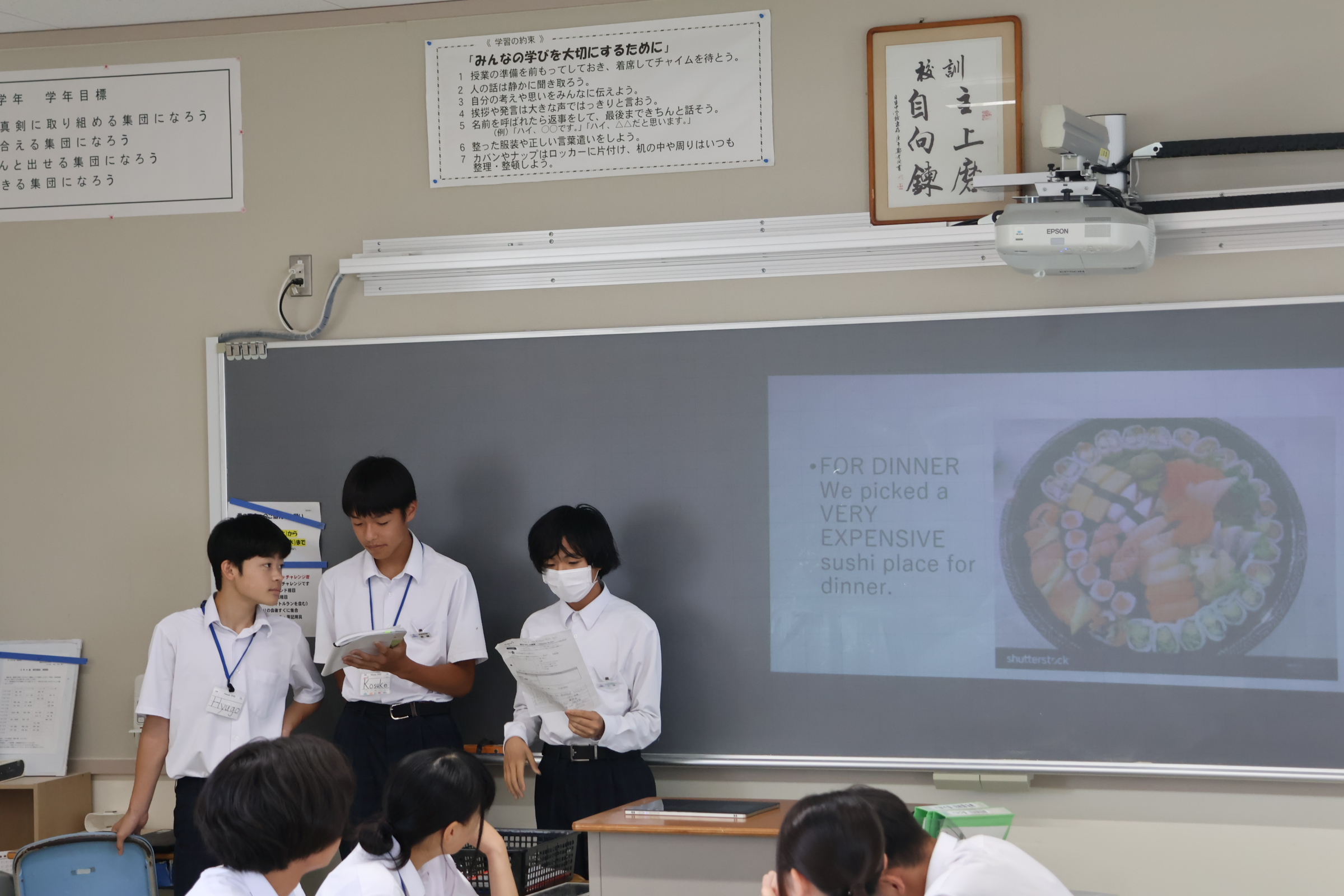
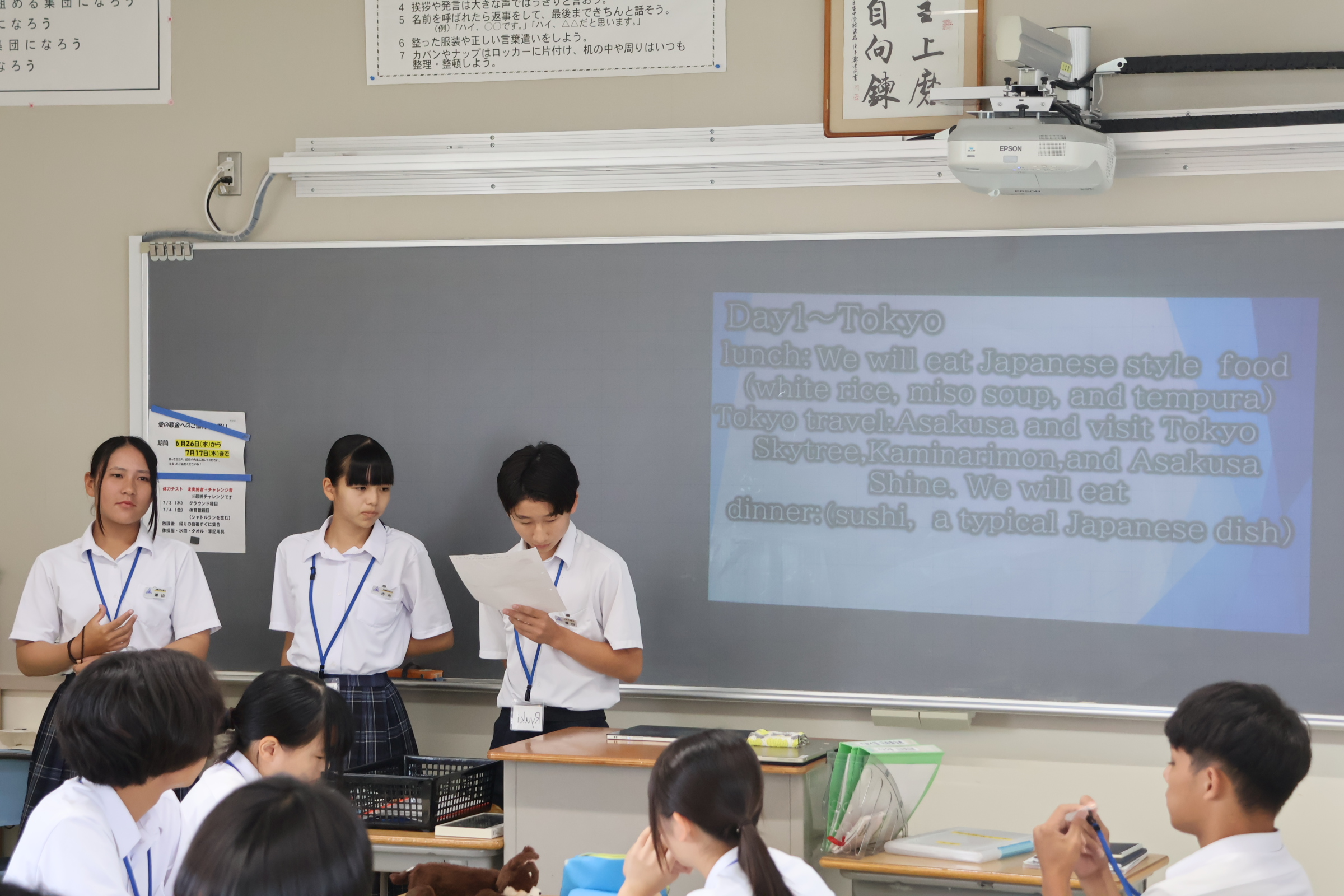

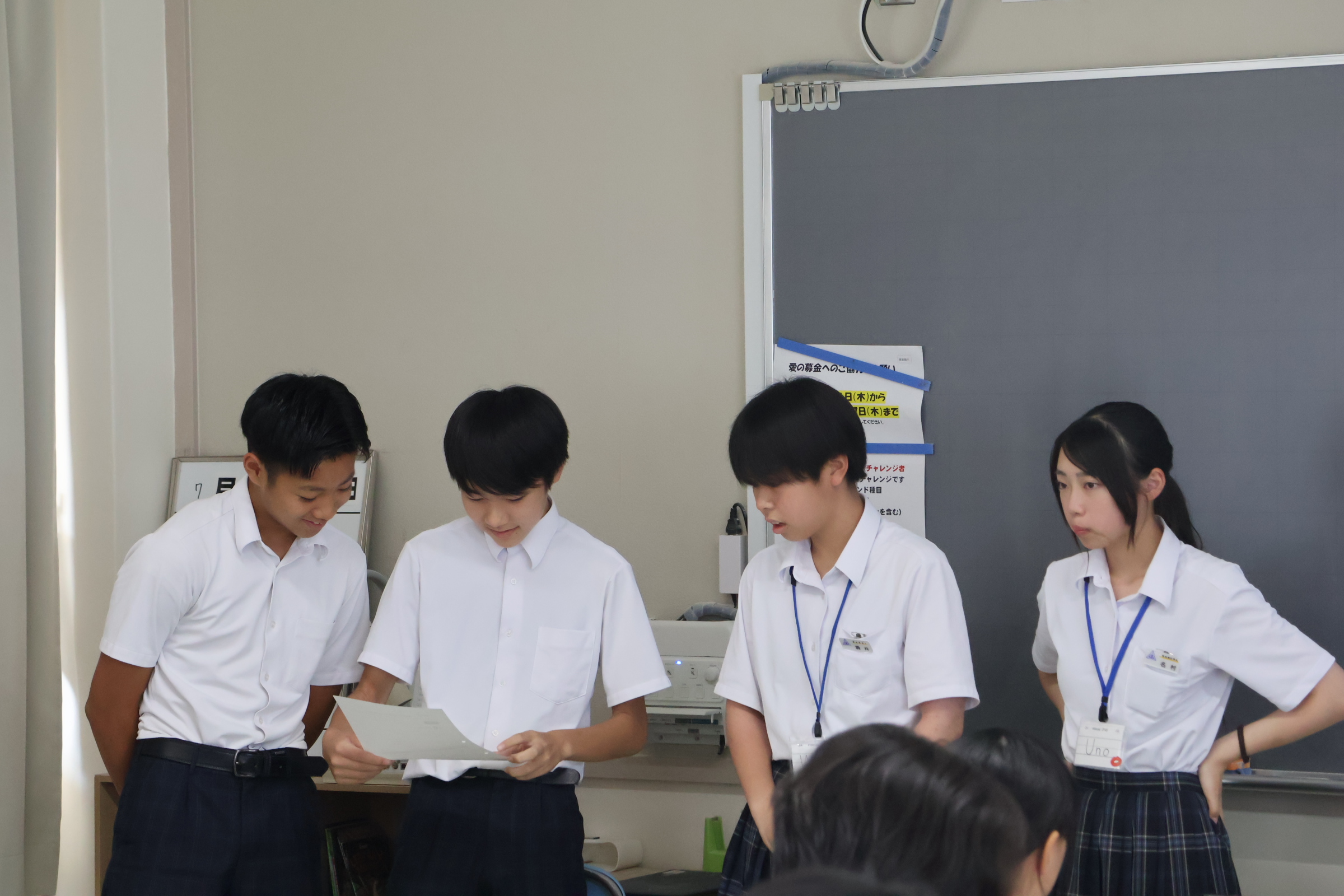

◎まだまだチャレンジ!体力テスト(7/3~4予定)
天候・気温の状況を鑑みて、実施します。

◎聞くことは、私たちの未来に効く
経験と知恵を学ぶ~海洋学習「聞き書き」活動(7 /3)
2年生が、漁協、観光協会、NPO里海づくり研究協議会、神戸税関さんらをエリアティチャーとして「聞き書き」活動に取り組みました。



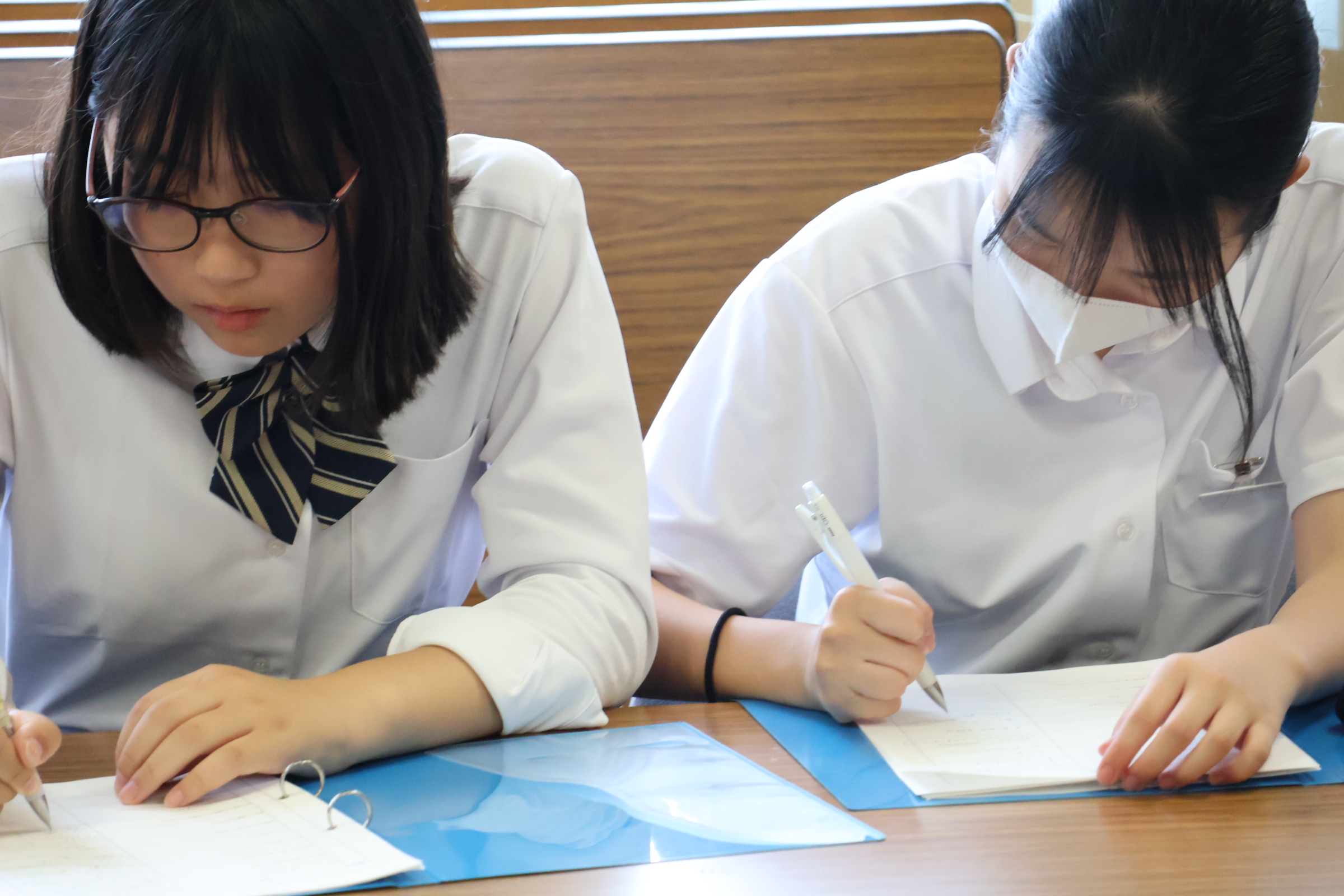





「聞き書き」:話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法です。話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法が一般的で、 この方法は、民俗学の研究や地域づくり、福祉の現場などで広く活用されています。聞き書きは、対話を通じて話し手の人生や価値観を引き出し、その人の経験や知恵を記録することを目的としています。
◎願いを叶えよ(7/3:ほっとスペース前)


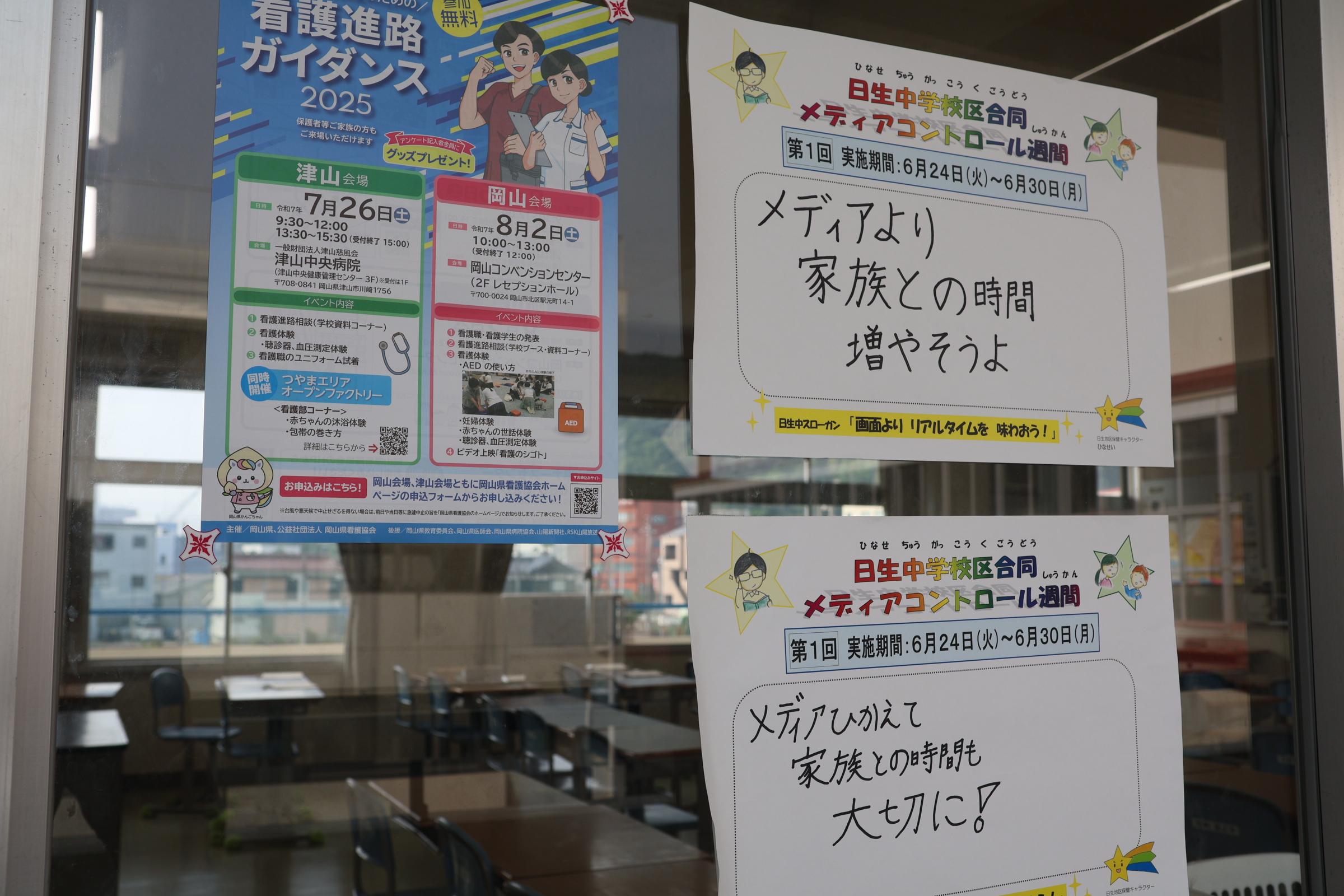



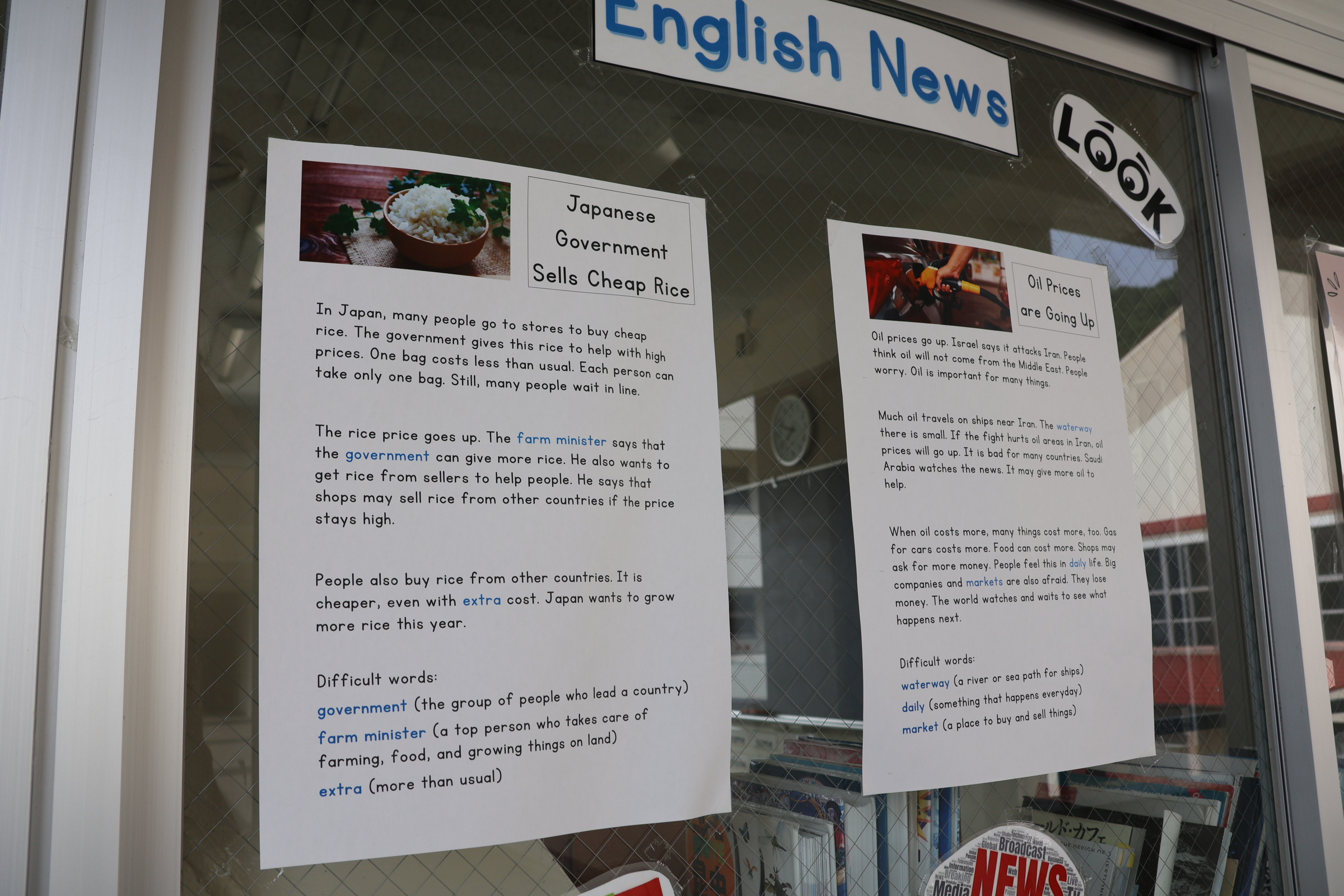
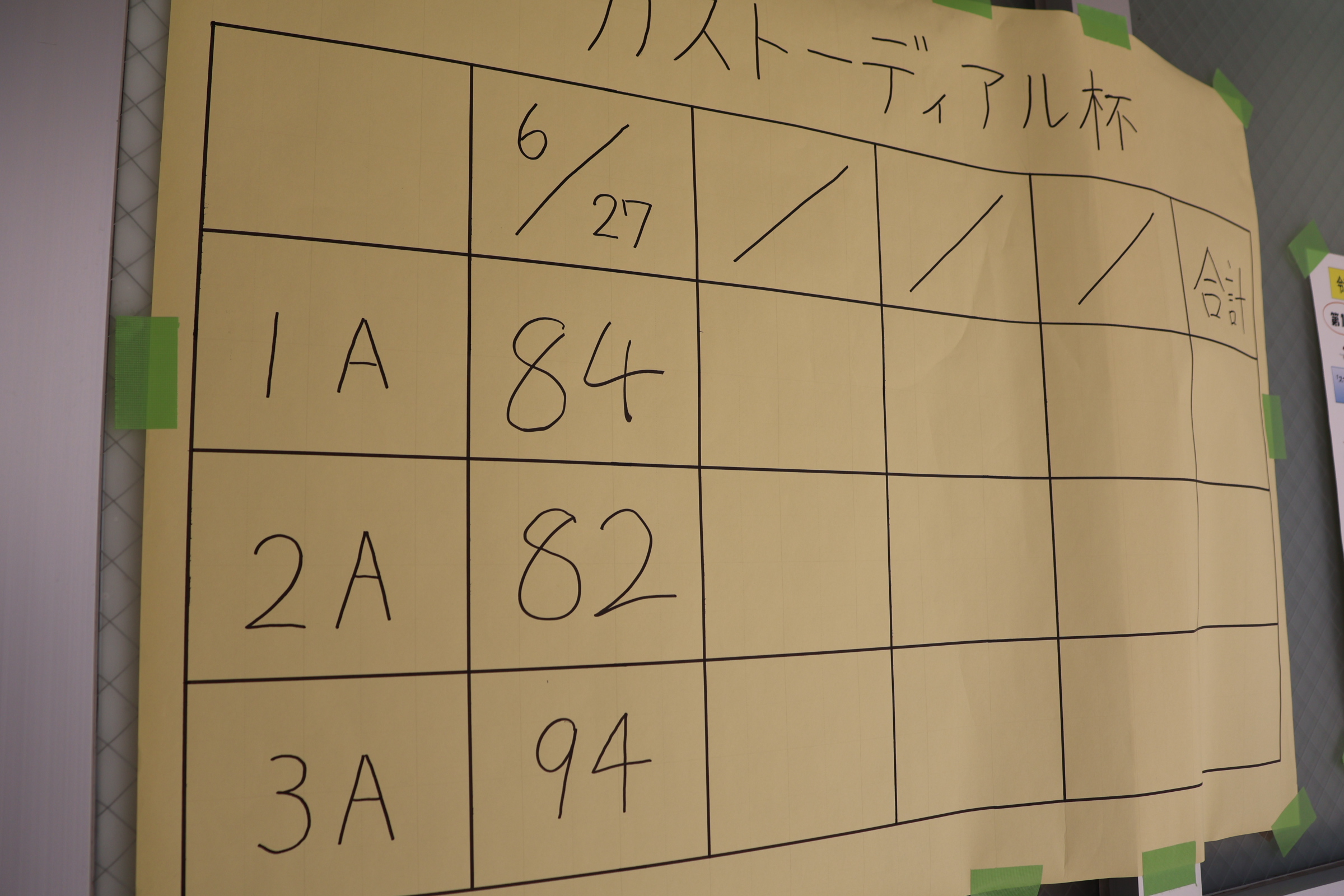
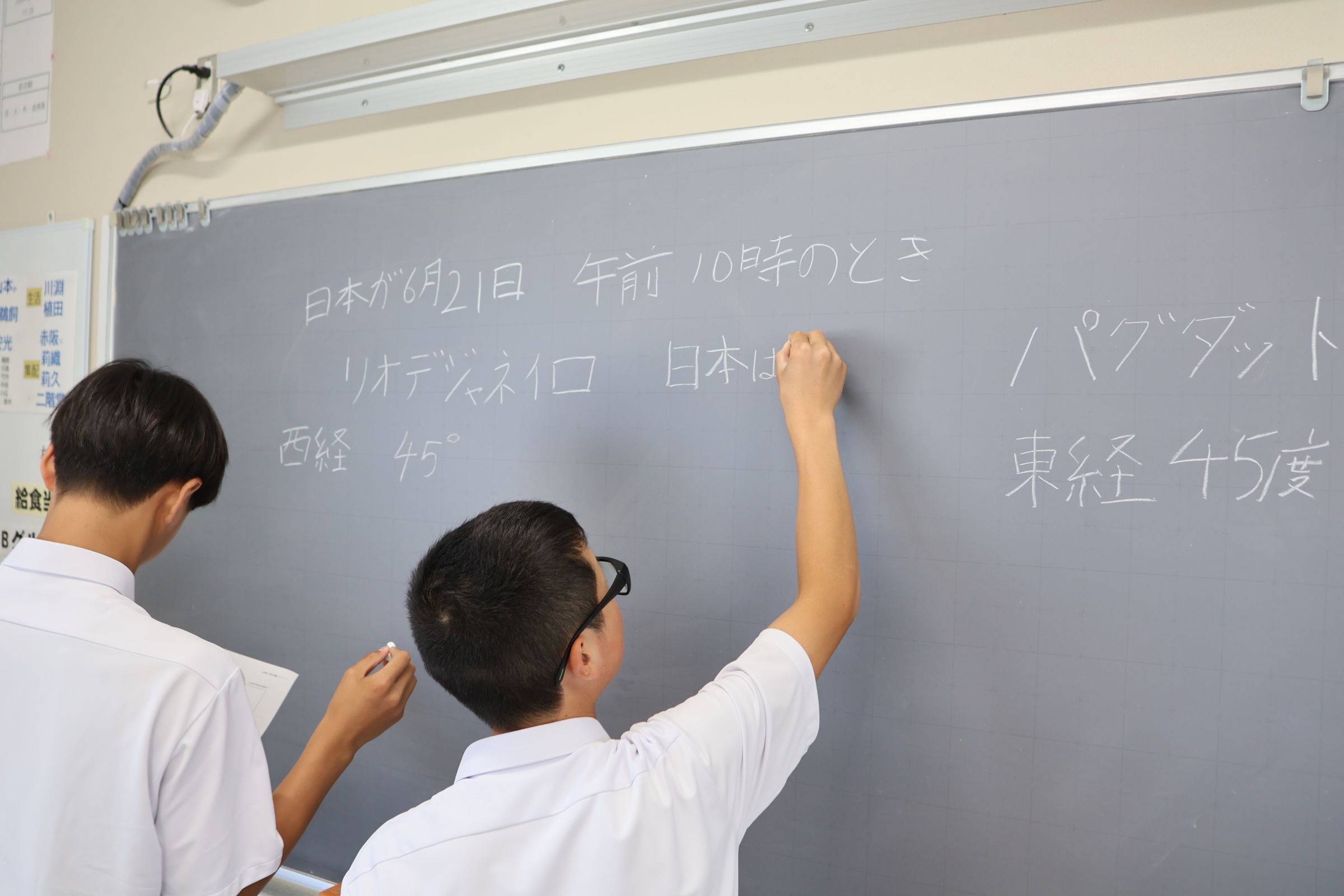
Everyone’s a star and deserves the right to twinkle. Marilyn Monroe
(誰もがスターなのよ。みんな輝く権利を持っている。)
◎確かな「子どもを見る眼」を。
先日の校内研修の講師である土田光子さんの著書を職員用図書に置いています。校長先生ありがとうございます。今日(7 /2)の校内研修では評価・評定について研修します。
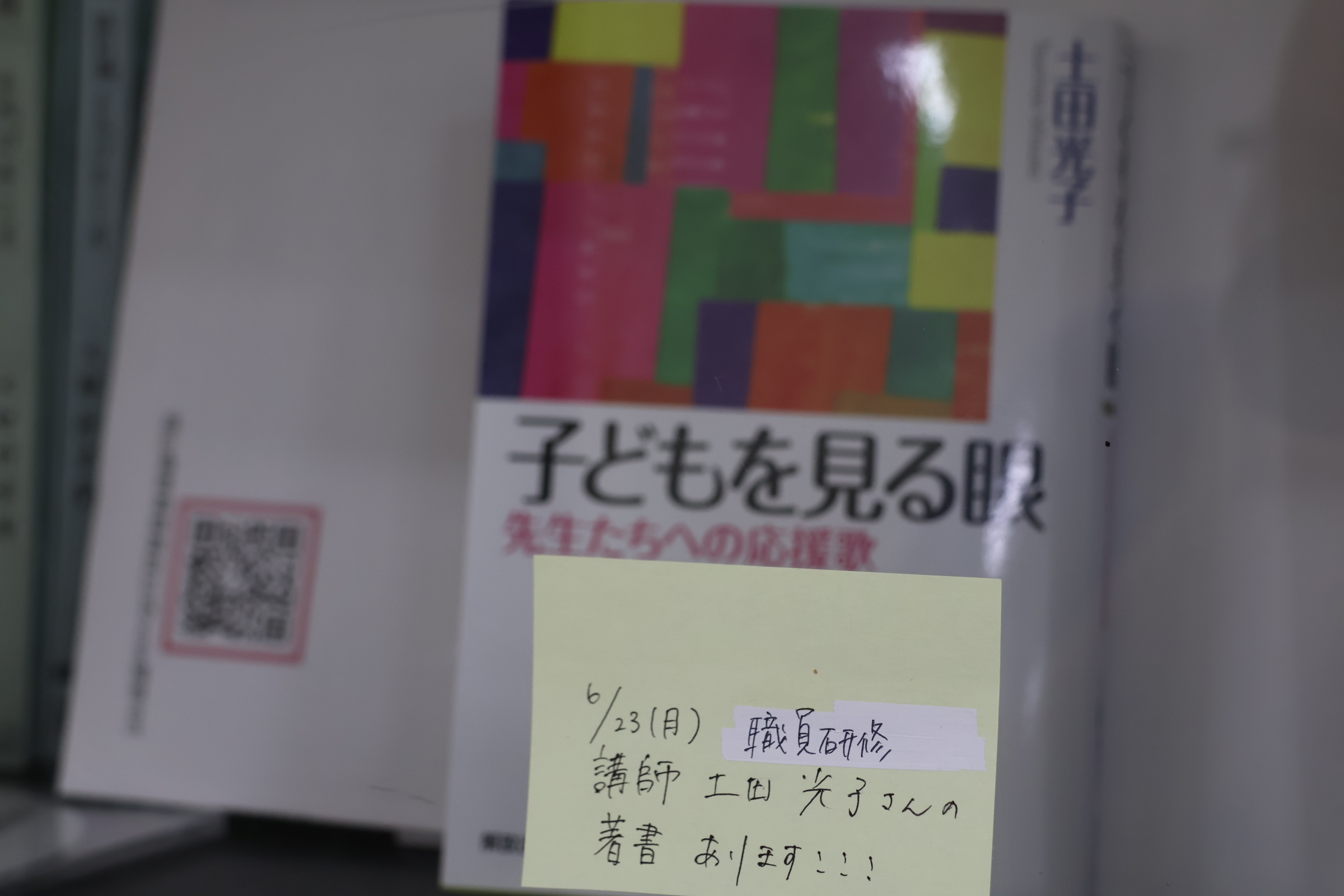
◎多くの人に支えられて(7/1:星に願いを)
立川先生、笹を今年もご準備くださり、ありがとうございました。

◎多くの人に支えられて~自分らしく生きるために(7/1)
備前市人権擁護委員(谷口さん、有吉さん、、杉本さん)が来校され、人権SOSミニレターを配ってくださいました。ありがとうございました。


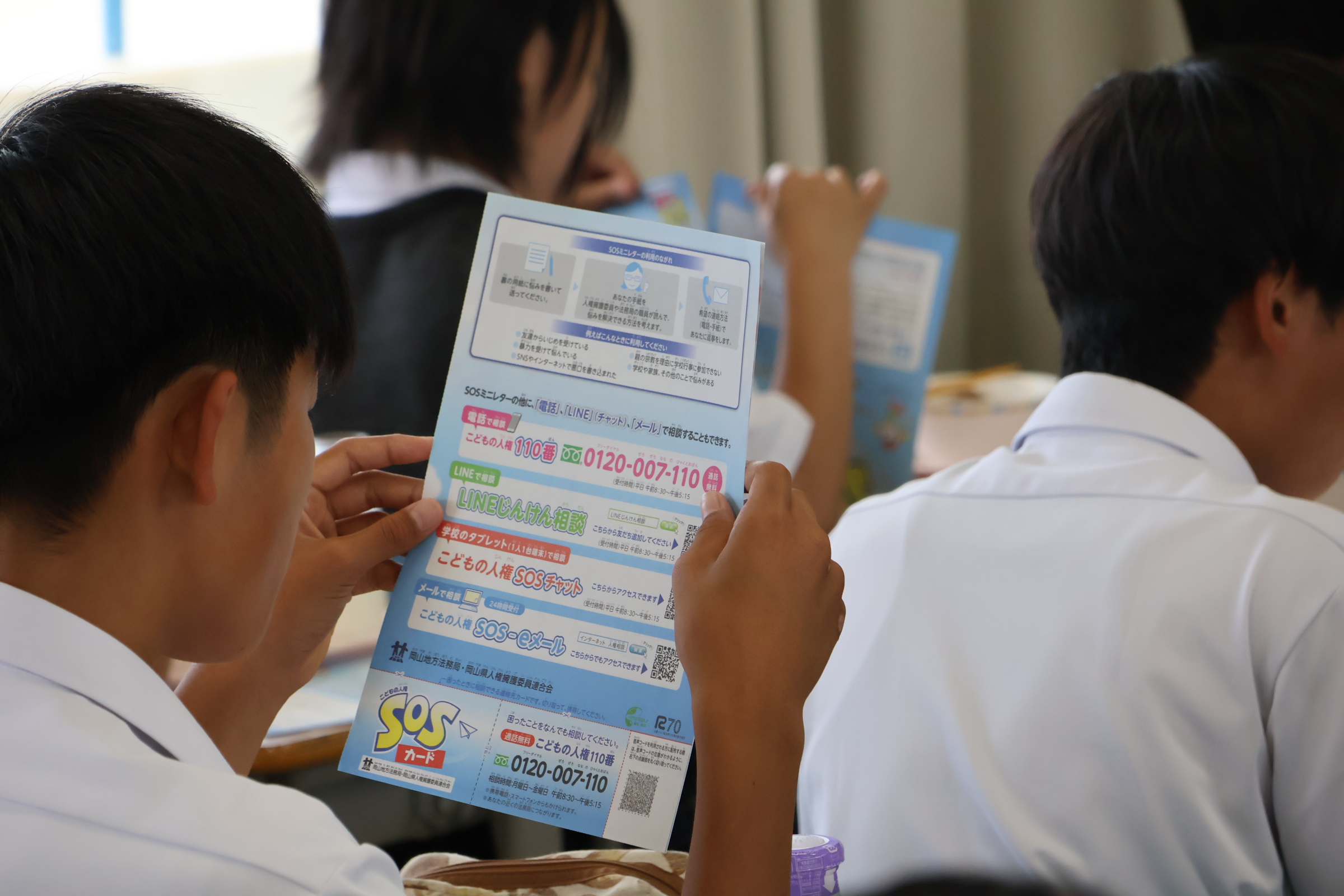
◎DRIFT AWAY Dobie Gray

◎暑いけど がんばってます!

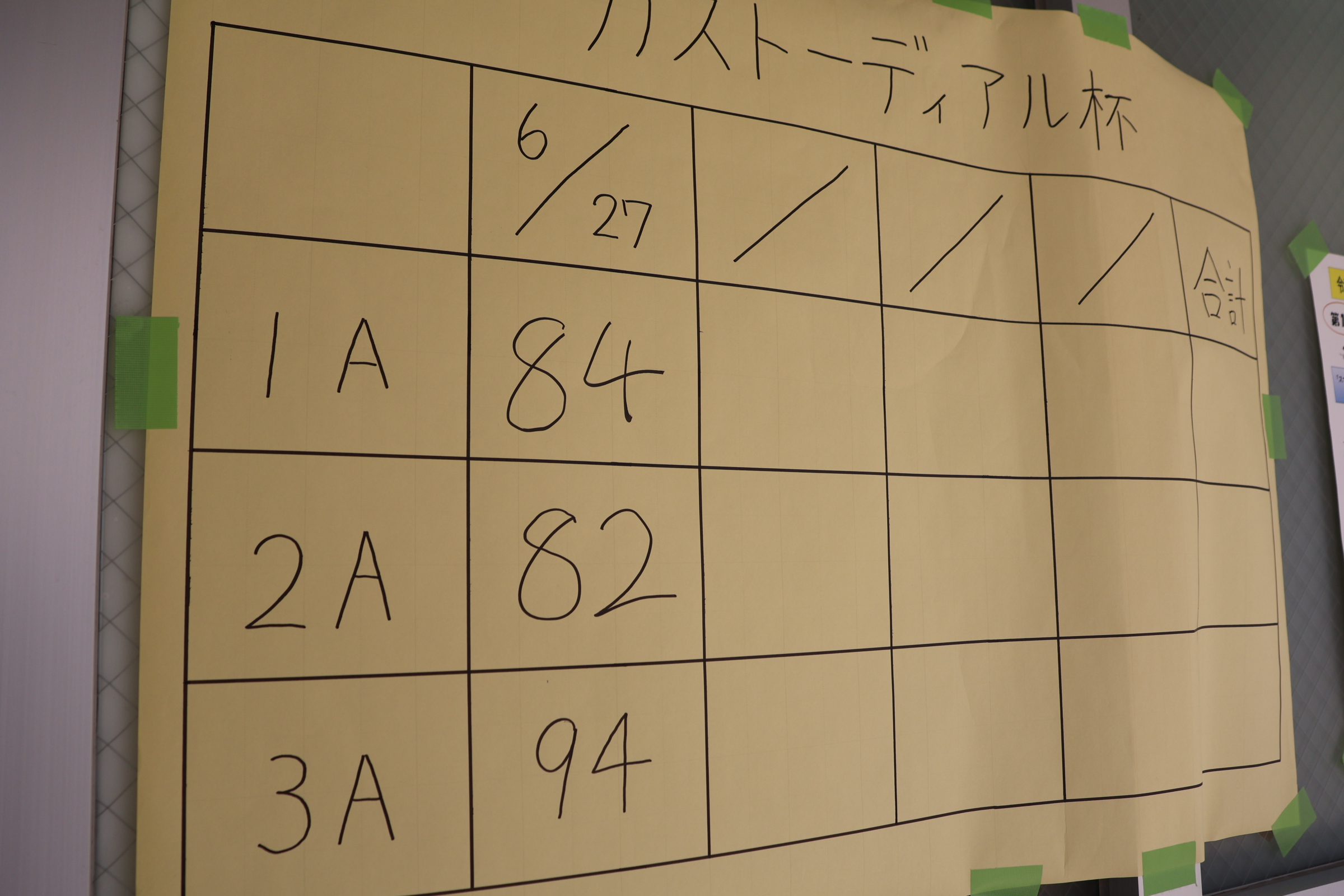


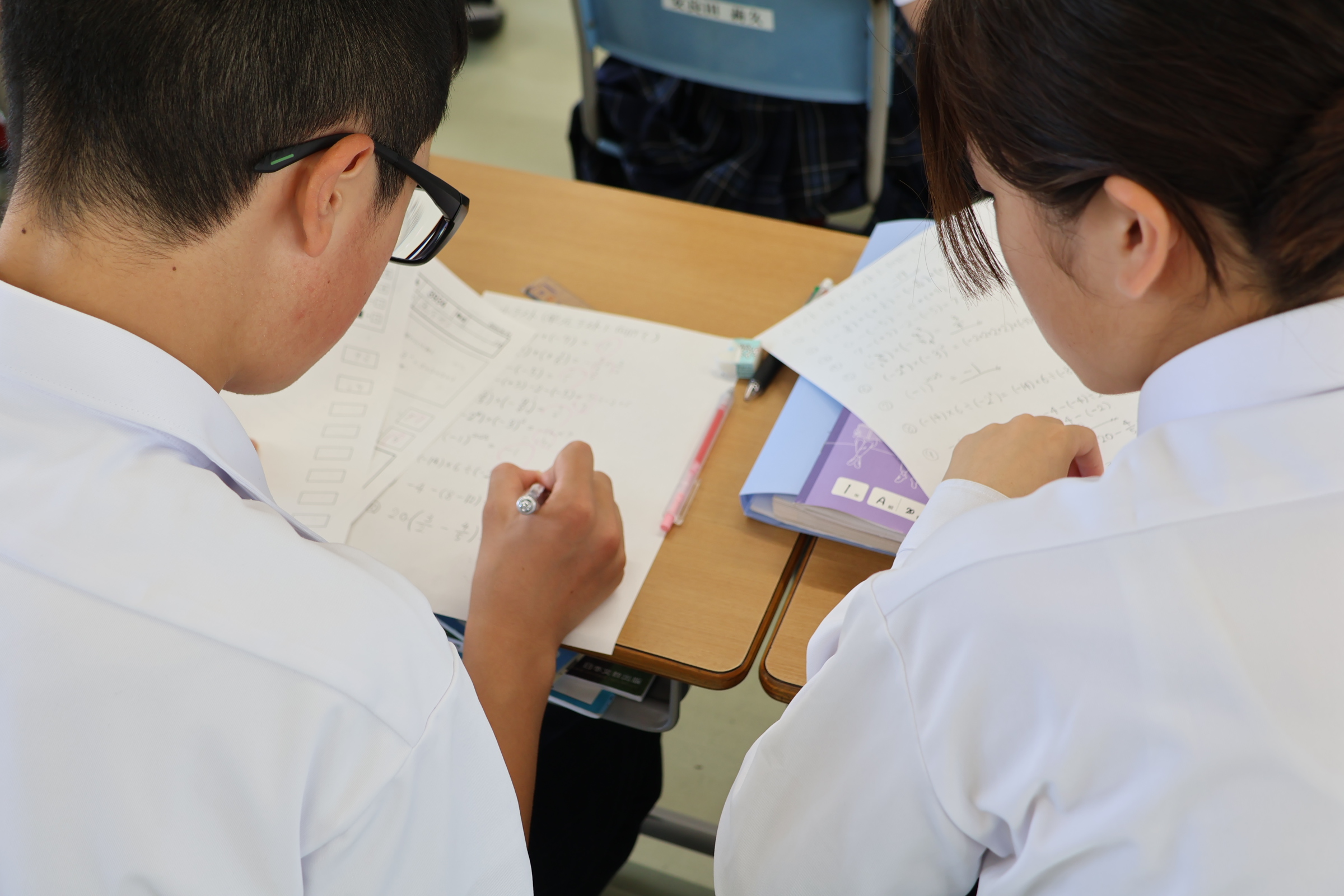

〈えっ、七時なのにこんなに明るいの? うん、と七時が答えれば夏 岡野大嗣〉(7/1)
7月「文月(ふみづき)」という呼び名の由来は、稲穂の「穂」から来ている説と、文字の「文」から来ているという、大きく2つの説が考えられています。旧暦をもとに農業を営んでいた昔の人々にとって、7月は稲穂が育つ時期です。そこで、穂がよく見えるという意味の「穂見(ほみ)」、穂が膨らむ(含む)という意味の「含み(ふみ)」から「穂見月(ほみづき)」、「穂含月(ほふみづき)」と呼ばれるようになりました。そこから、「ふみづき」という言葉に転じたと言われています。また、七夕行事にちなんで短冊に願い事を書いたことから、「文」の字を当てたという説もあります。現代でも、七夕の短冊にいろんな願いを書きますね。(今年も、ほっとスペースにも笹を置きますよ)しかし、もともとは七夕の短冊には、「文章が上手になりますように」「習字が上達しますように」といった、「文」にまつわる願いを書くものでした。そのため、「文披き月(ふみひらきづき)」から転じたというのが定説になっています。しかし一説によると、中国の風習で7月7日に古書の虫干しをしたことから、「文開く月」と呼ばれていたとも言われています。諸説ありますが、文章にまつわる「文」という説が有力のようですね。季節や気候とはあまり関係ないのが、意外でした。7月の別名には他にも、
・七夕月
・棚機月(たなばたつき)
・女郎花月(おみなえしづき)
・蘭月(らんげつ)
・涼月(りょうげつ)というものがあります。風物詩である七夕や、季節の花に関する名前が多いですね。「文月」よりも、上の異名のほうが季節感があって風雅な印象を受けます。ちなみに「涼月」とは、暑くなっていくにつれて風が吹くと涼しく感じることからこう呼ばれるそうです。古くは漢詩にも登場する表現です。今年の夏も猛暑の予想ですが、「涼月」の名にならって、風鈴の音や打ち水など、日常の中の「涼」を探してみてもいいかもしれませんね。

◎ひな中のちから〈ボランティア推進プロジェクト 依頼続々〉
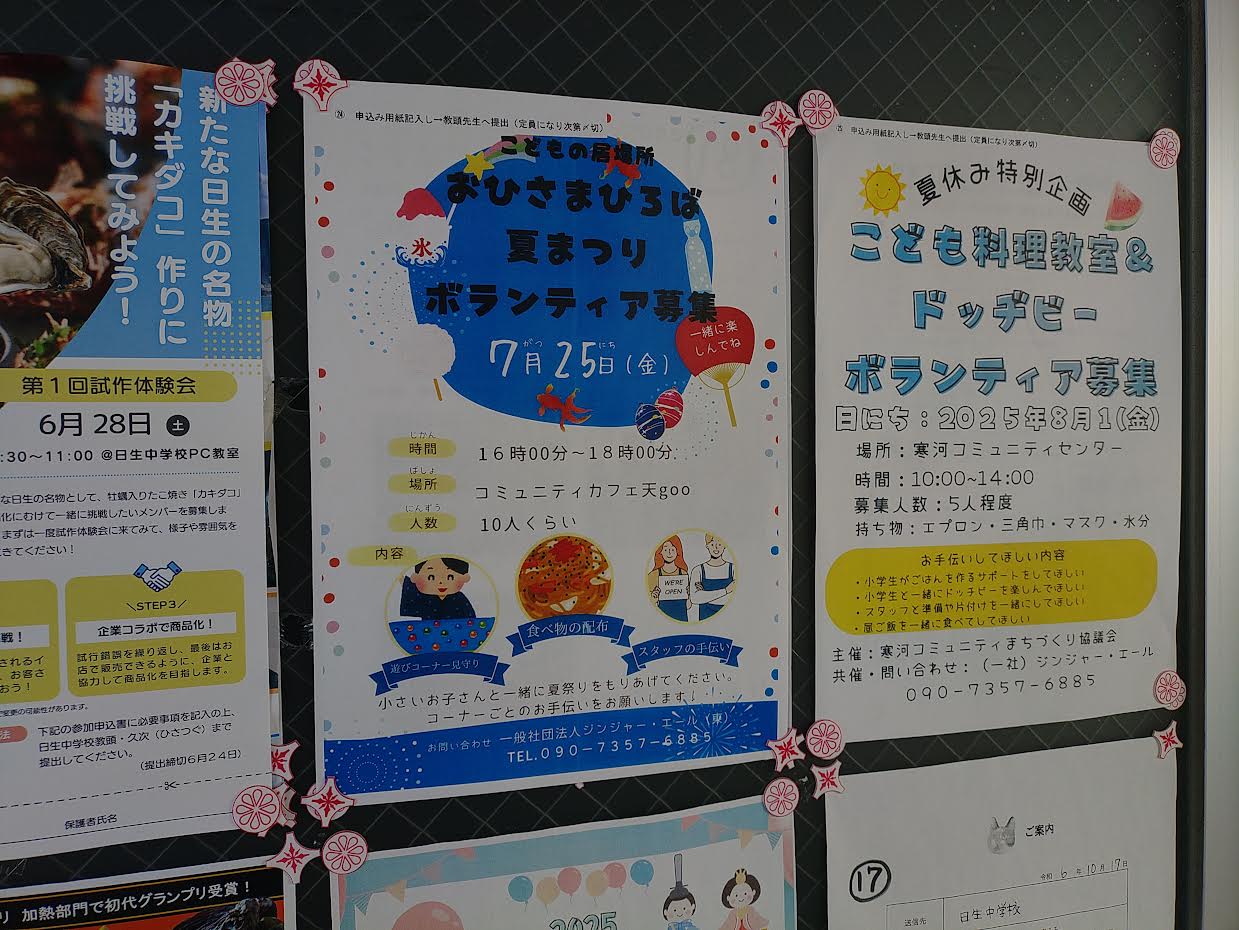
◎ひな中のちから(28日:PTA資源物回収)









多くのご支援・ご協力をありがとうございました。奥橋さん、今年も助かりました。ありがとうございました。
◎HINASE REGACY
カストーディアル杯から(27 ~)
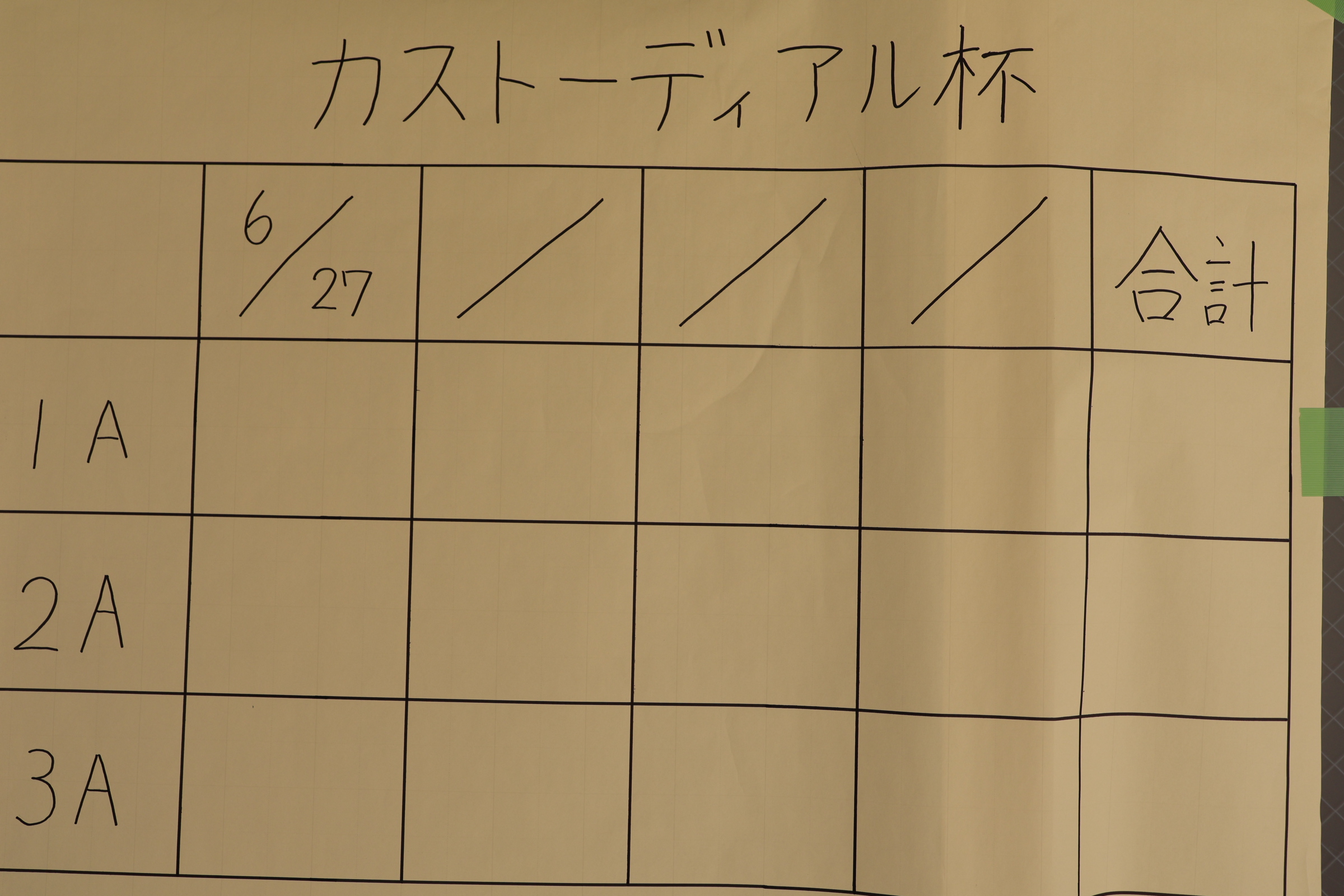


◎向き合う ~全校集会を受けて~(6/26:生徒朝礼)



ショートストーリー劇で、生徒会からみんなで。
7月の生活目標は「レインボーブリッジの3番 他のひとの良いところをみつけることができる」
◎今度は食べたらいけん、鹿さん。(6/25:環境委員会)



◎経験と知恵を学ぶために~海洋学習「聞き書き」活動へ(6/25)
2年生は7月3日に、漁協、観光協会、NPO里海づくり研究協議会、神戸税関さんら(予定)をエリアティチャーにお迎えして、「聞き書き」活動に取り組みます。
ちなみに「聞き書き」とは・・・話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法です。話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法が一般的で、 この方法は、民俗学の研究や地域づくり、福祉の現場などで広く活用されています。聞き書きは、対話を通じて話し手の人生や価値観を引き出し、その人の経験や知恵を記録することを目的としています。今日、25日(水)は、「聞き書き」甲子園を主宰されている、共存の森ネットワークの吉野さんからお話を聴き、7月3日に向けての事前学習・準備を進めました。




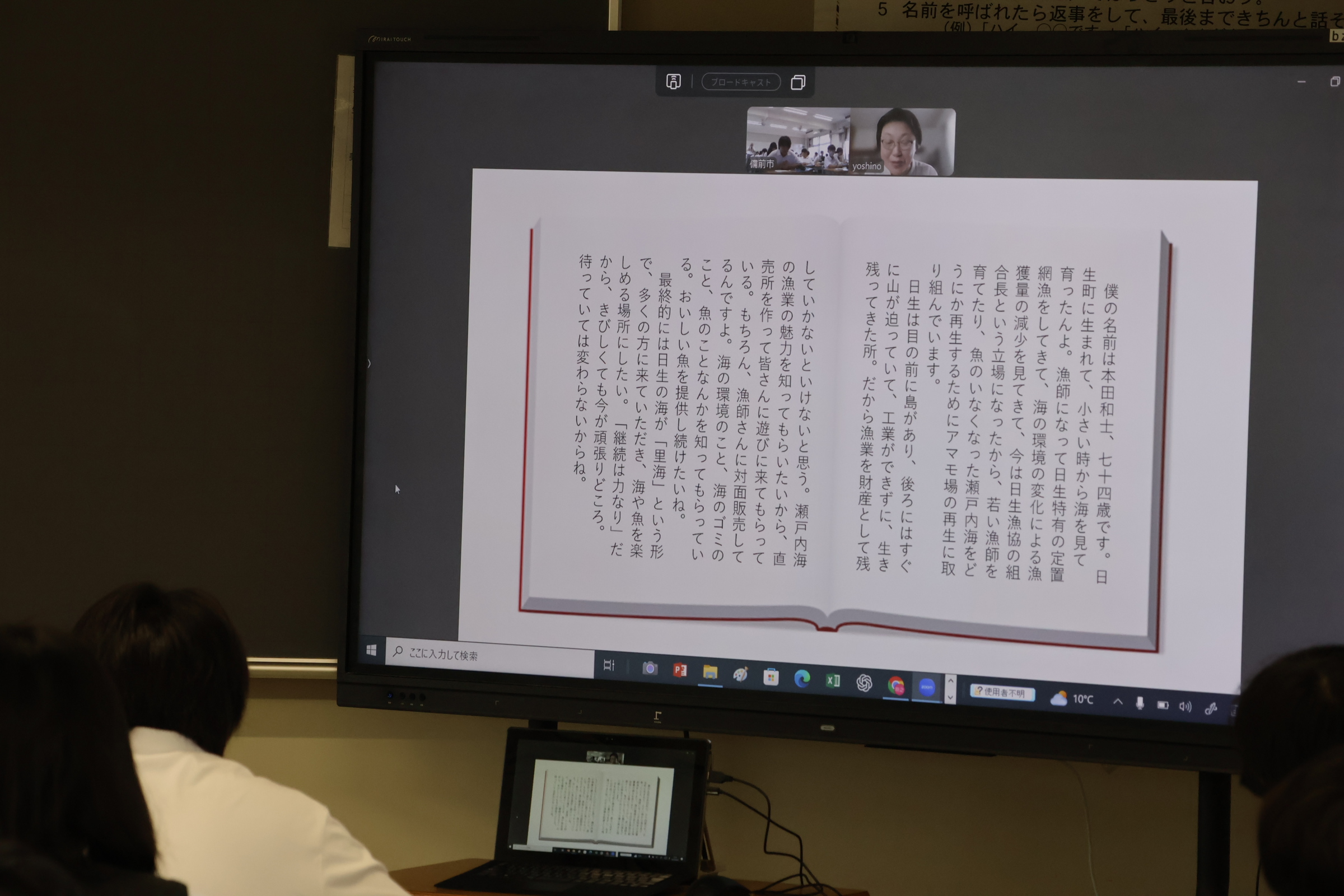
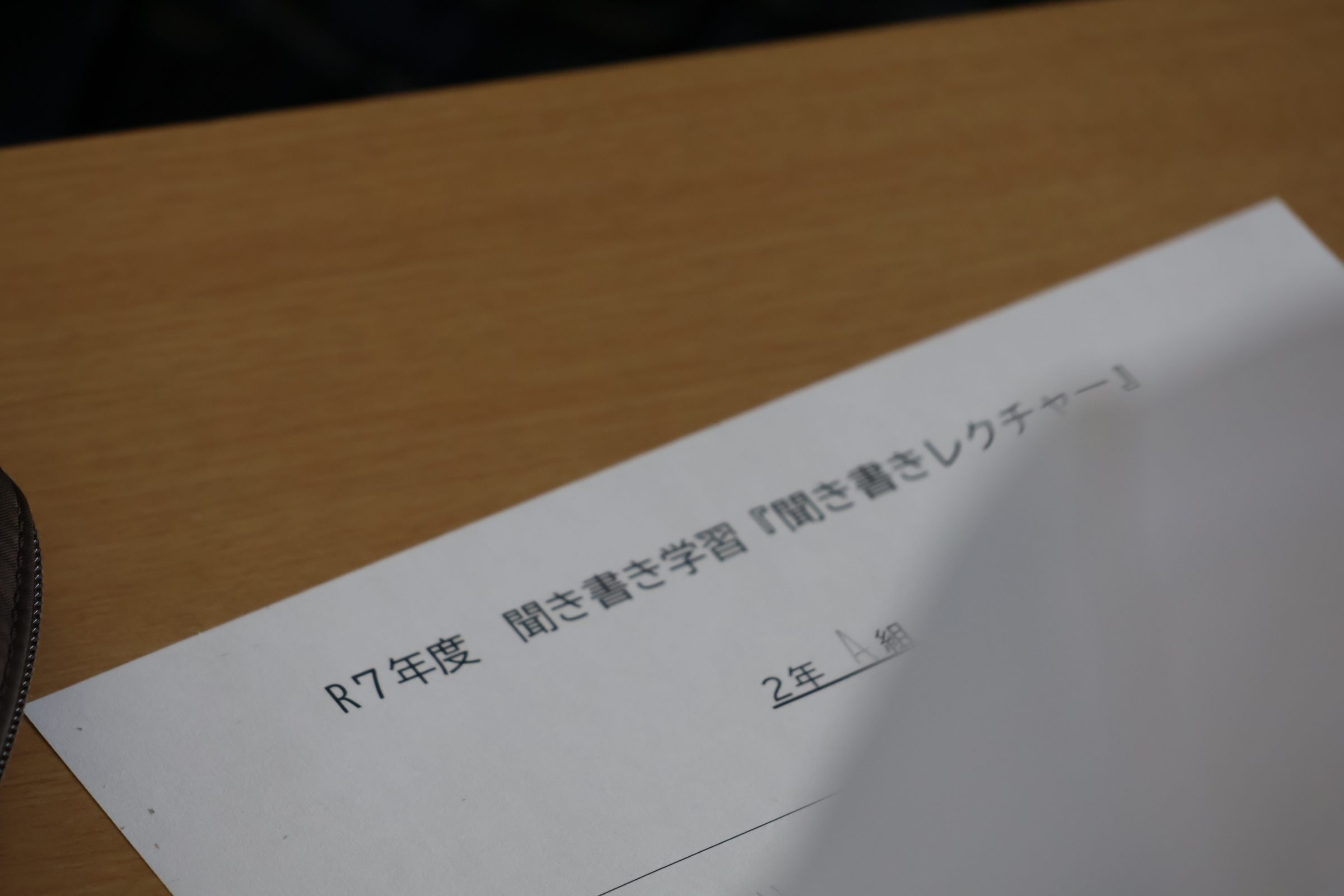
◎毎日が大切(6/25:岡山県教委AP訪問)
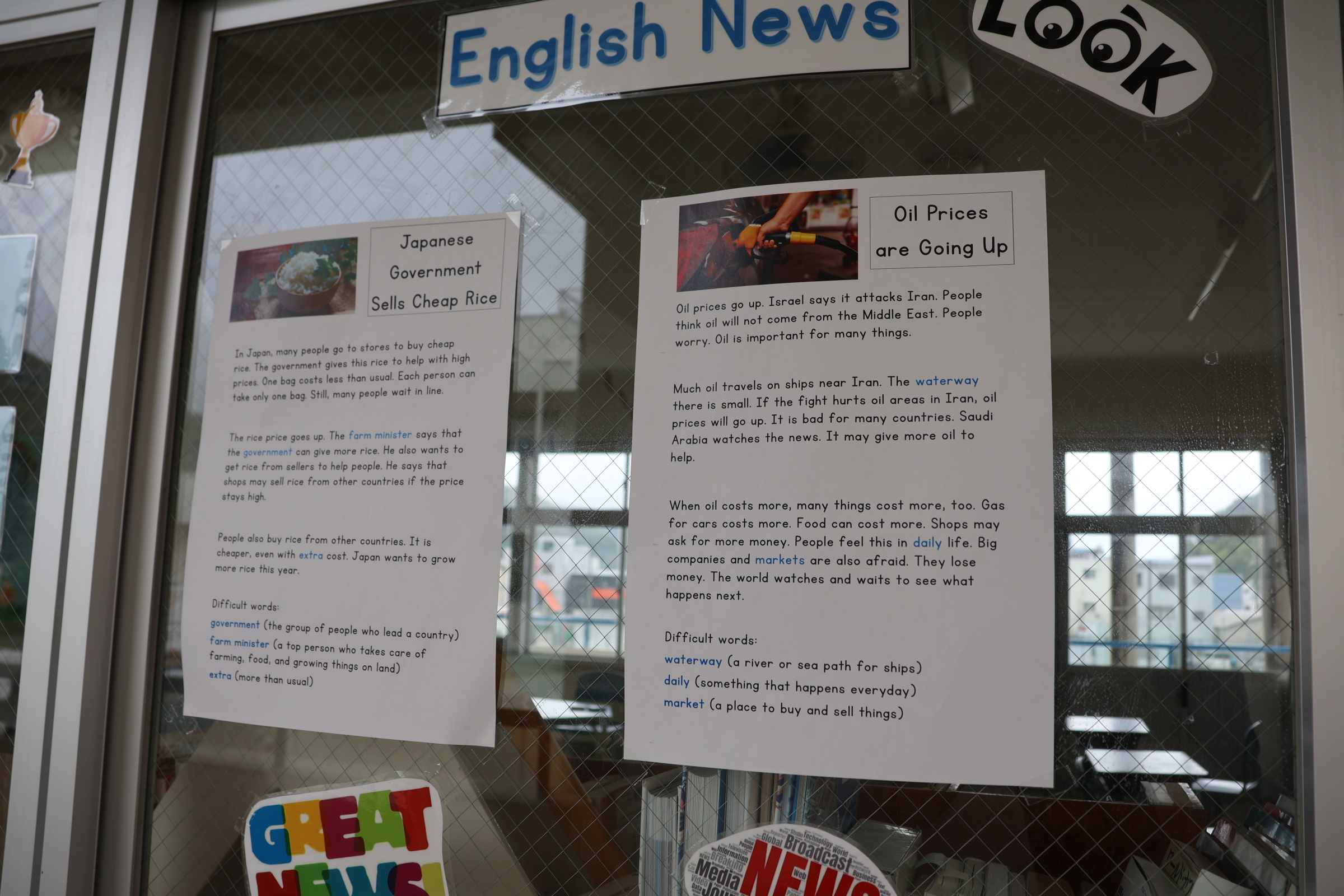

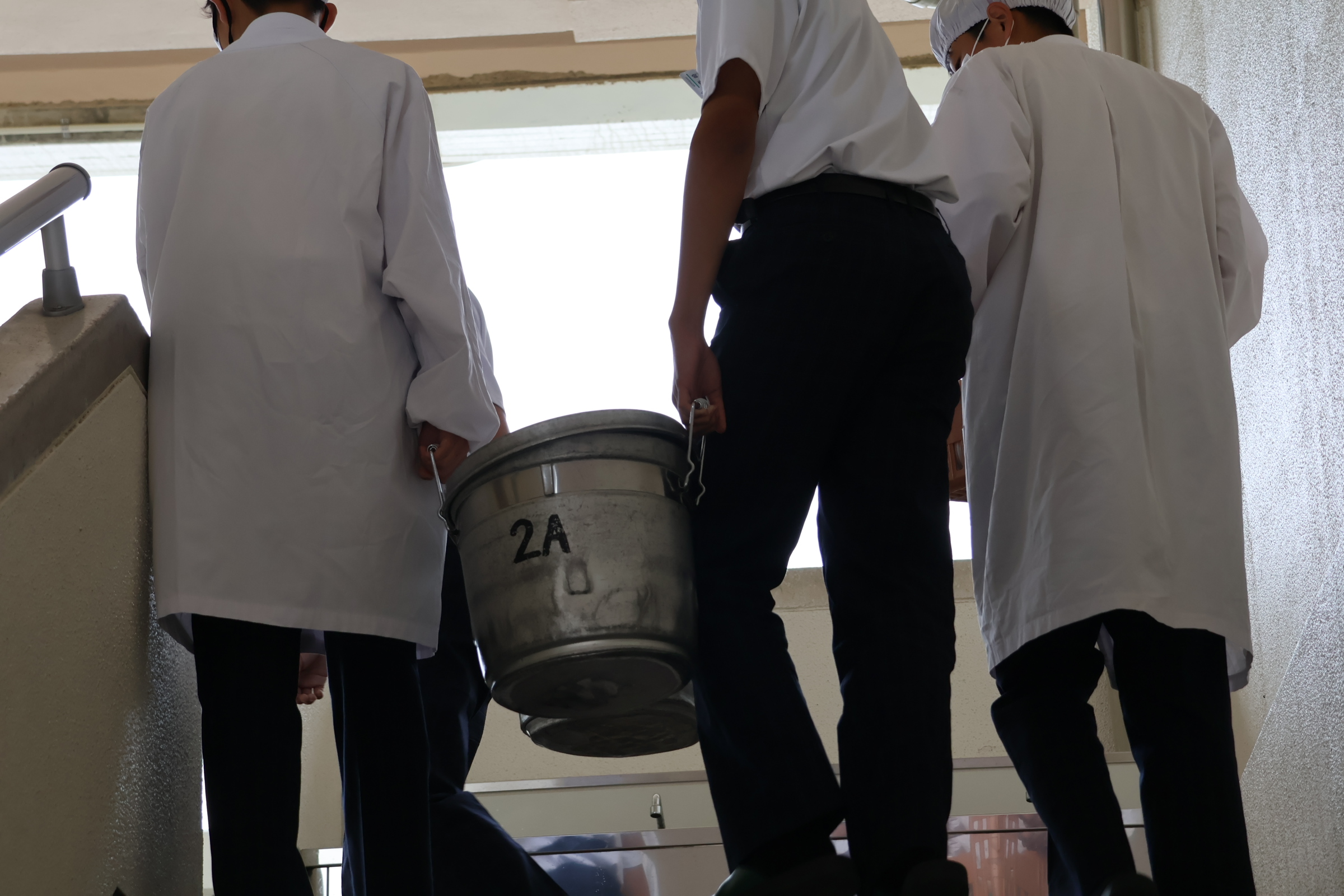

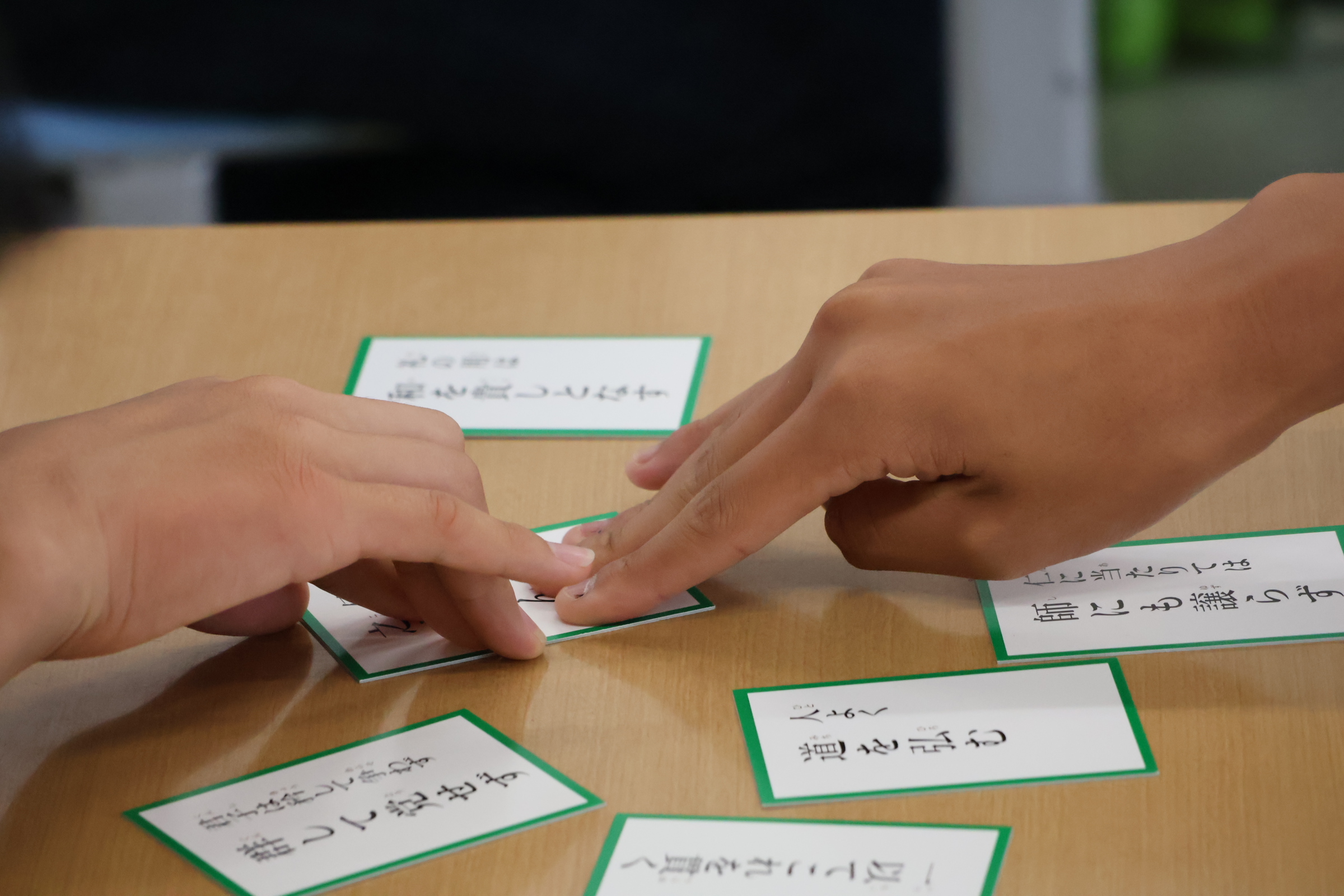
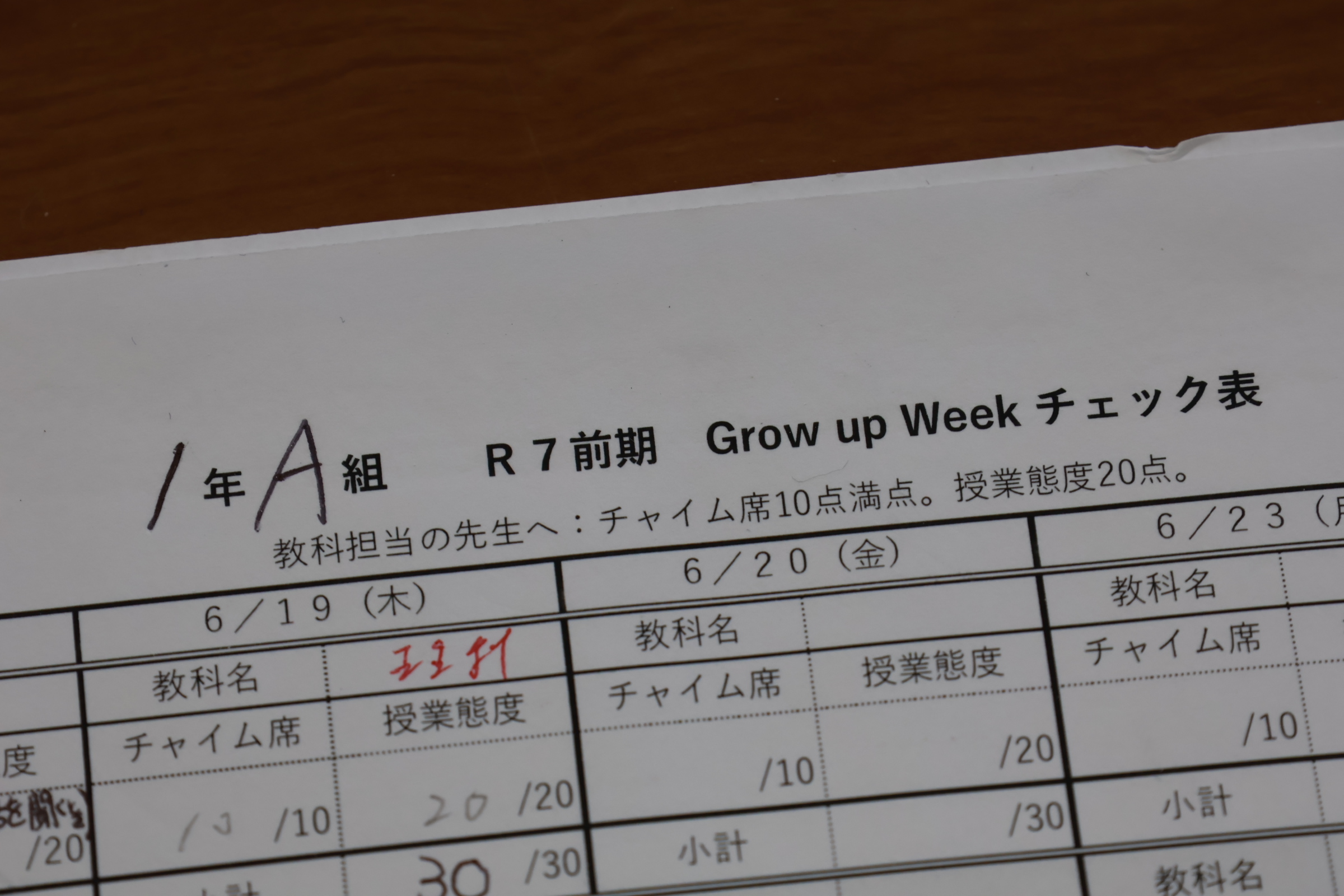
今日は、第1回AP(アクションプラン)訪問があり、岡山県教育庁・備前市教育委員会より合わせて5名の先生方が来られました。本校の重点取組についての説明、また、授業を参観していただき、課題等を共有した上で多面的な協議を行いました。共有実践事項を大事にして、1学期も後半、本日の学びを機に目指すところや修正点を確認しながら毎日の教育活動をさらに大切にしていきたいと思います。
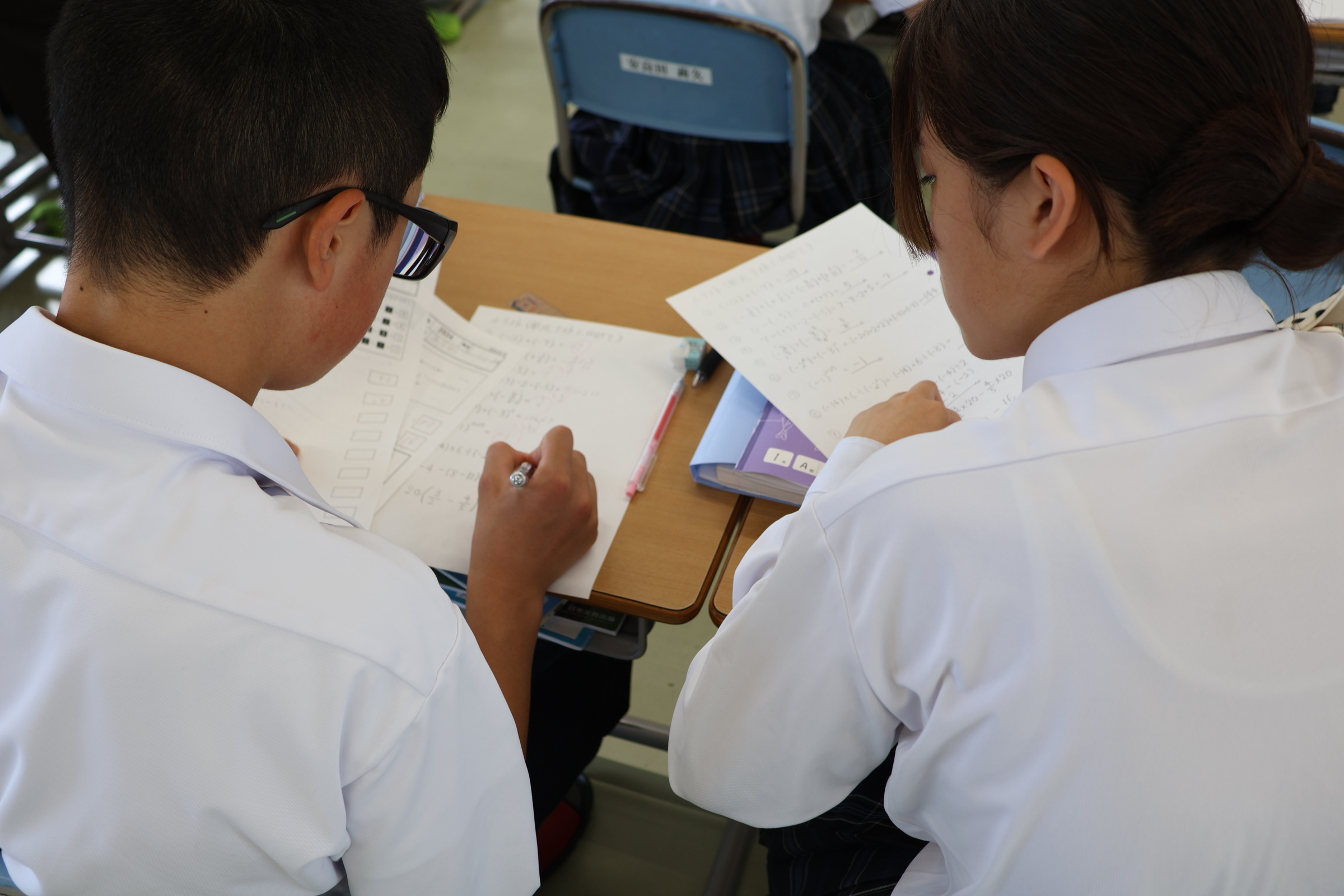


◎夏ボラ申込は今日25日(水)校内締め切り!

◎そうだよ、メディアはコントロールするのよ(6/24)
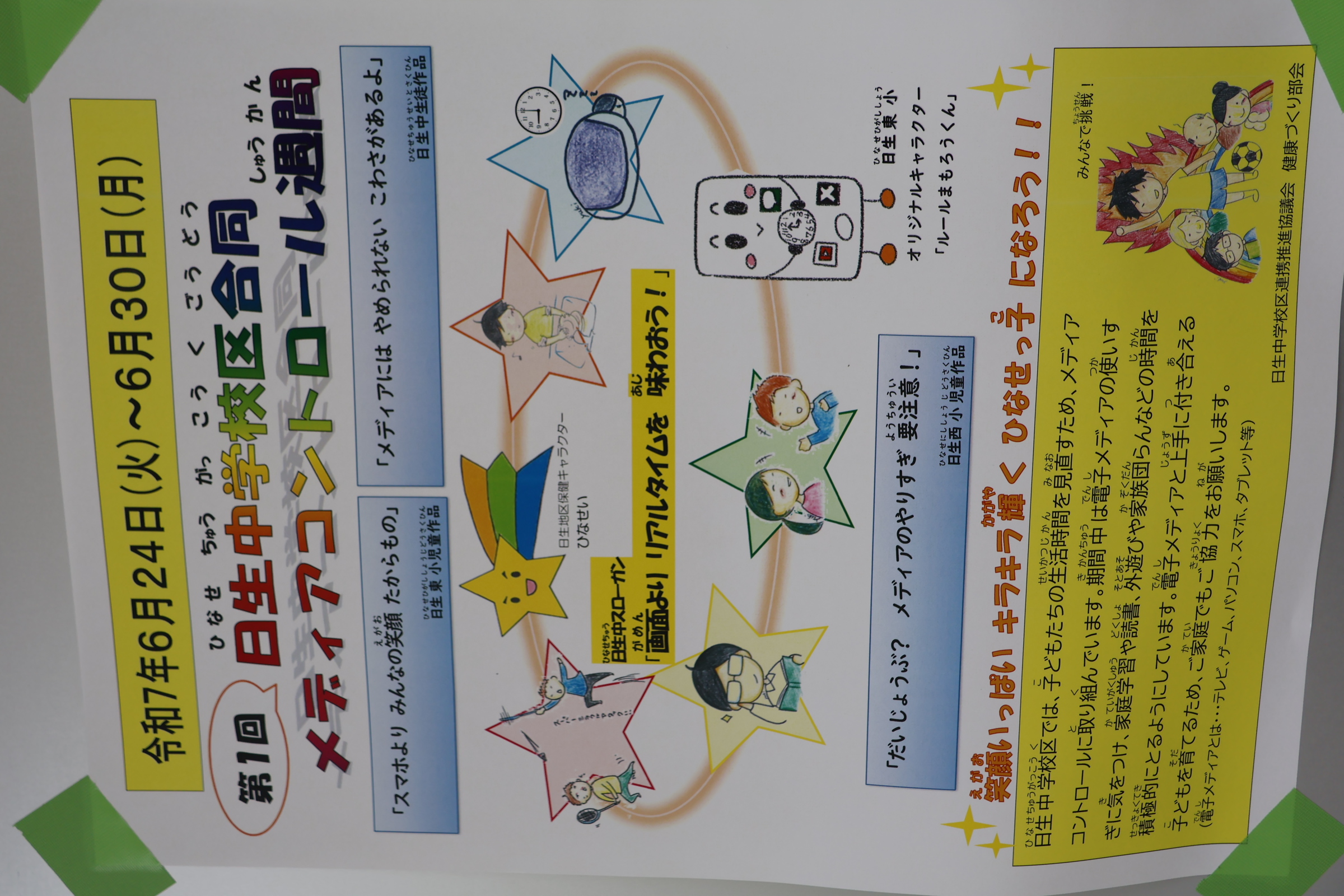
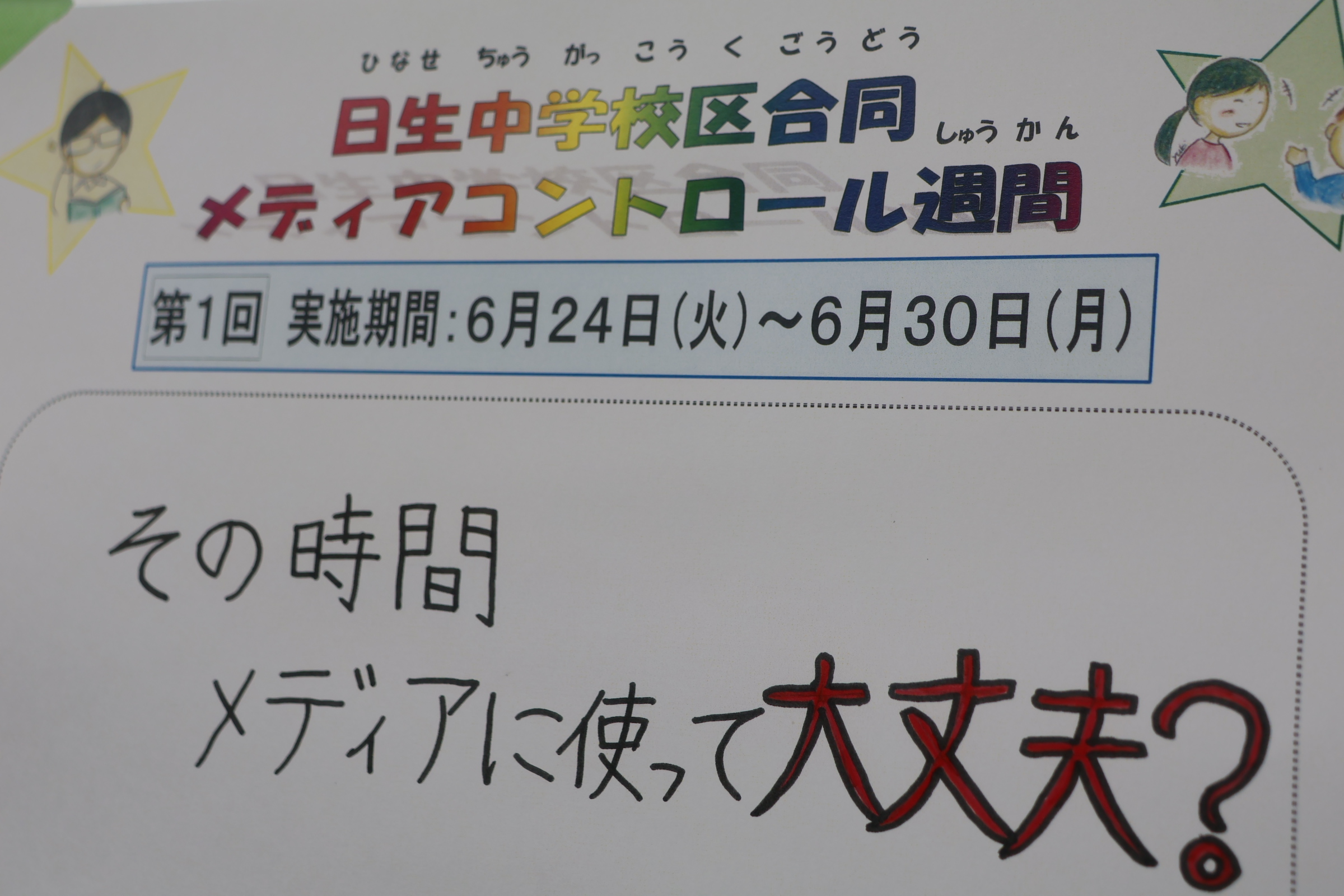
◎6.24一人ひとりが考える全校集会
生活を大切にすること。自分を大切にすること。仲間を大切にすること。



◎みんなが幸せになる人権学習 (6/23:校内研修)
土田光子さん(大阪多様性教育ネットワーク)をお招きして、研修会を開催しました。本校だけでなく、和気、瀬戸内、赤磐から来られた方々と共に、「みんなが幸せになる人権学習~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~」をテーマに、教職員としての学びを深める〈熱い90分〉でした。


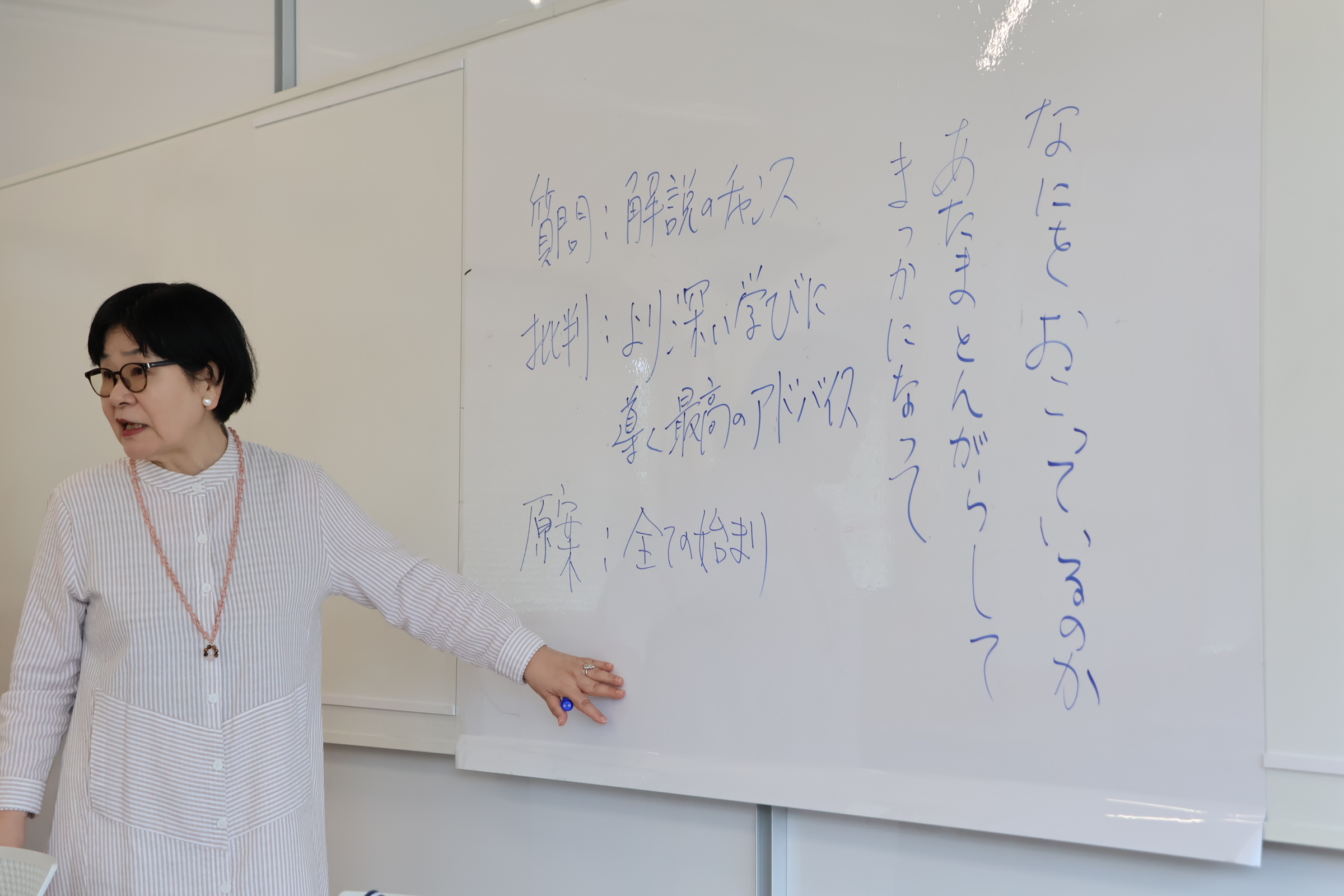
◎ヒロシマ・オキナワから、オカヤマで
2年生は広島研修、3年生は沖縄修学旅行で、反戦・平和学習に取り組んできました。今日6月23日は、沖縄では、組織的な戦闘が終わったといわれる慰霊の日です。また、6月29日は岡山大空襲があった日です。山陽新聞(6/23)の記事について「ひとのあいだ」で生徒に紹介をしています。戦後80年という節目の年です。子どもたちと共に読んでいただけると幸いです。
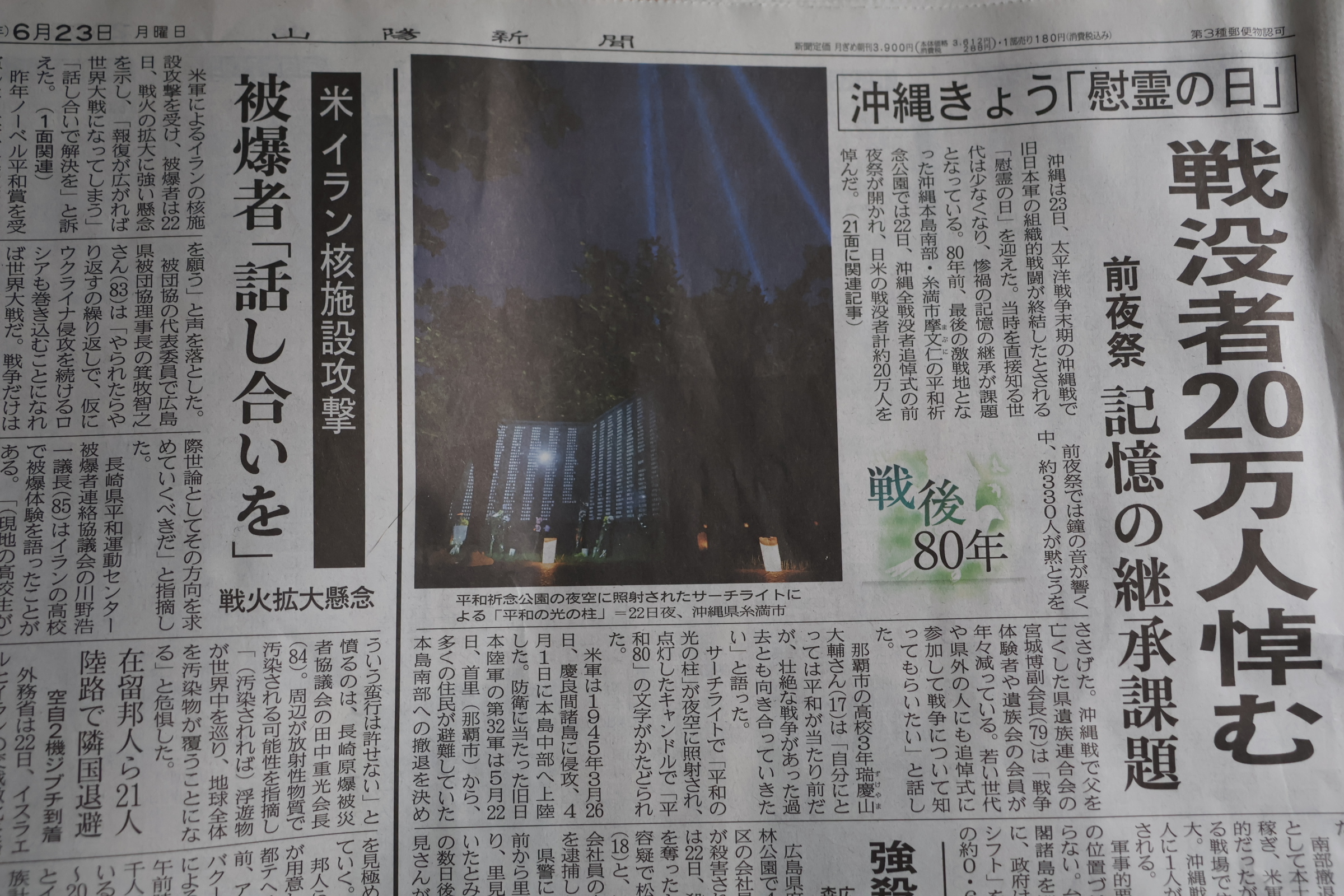
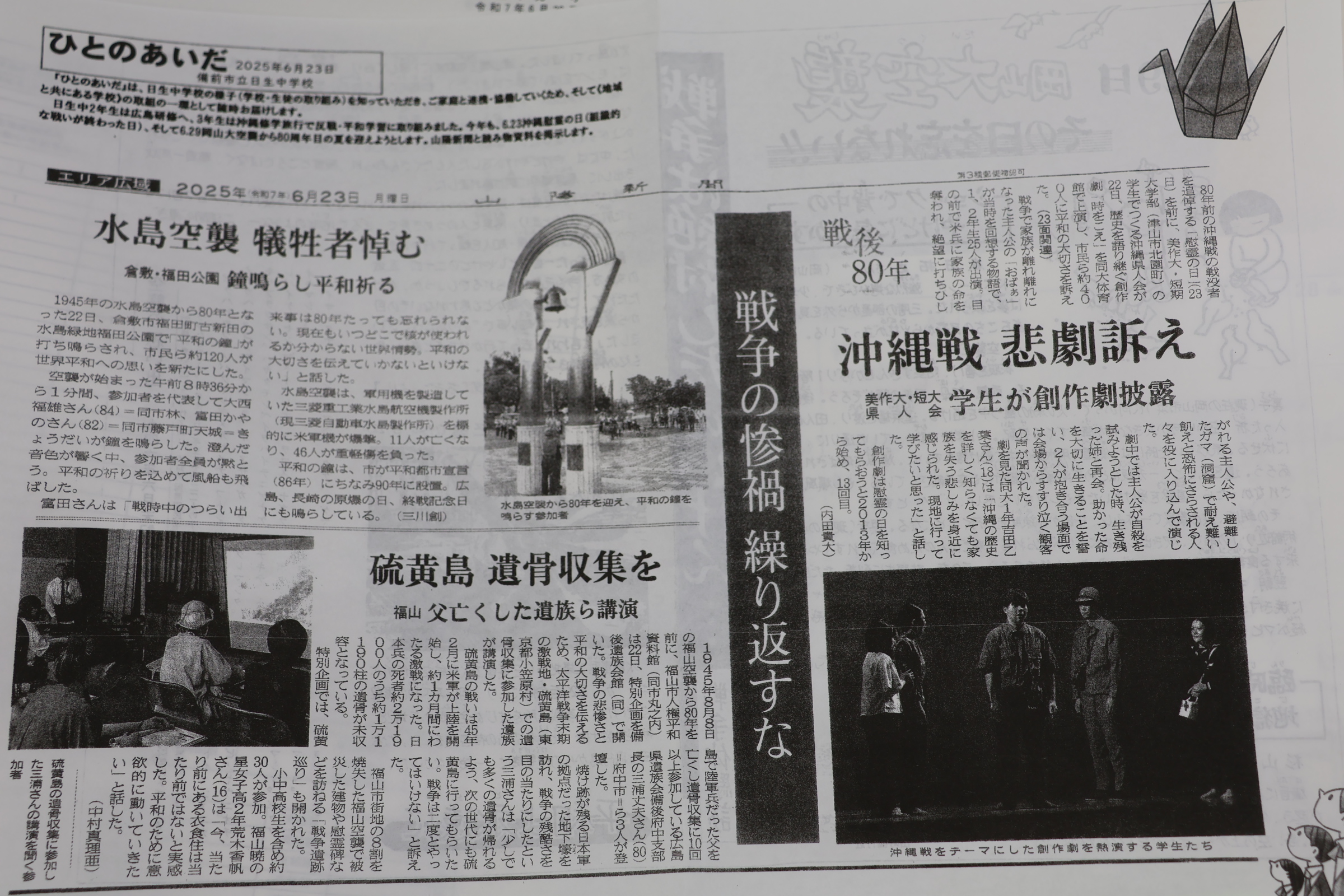
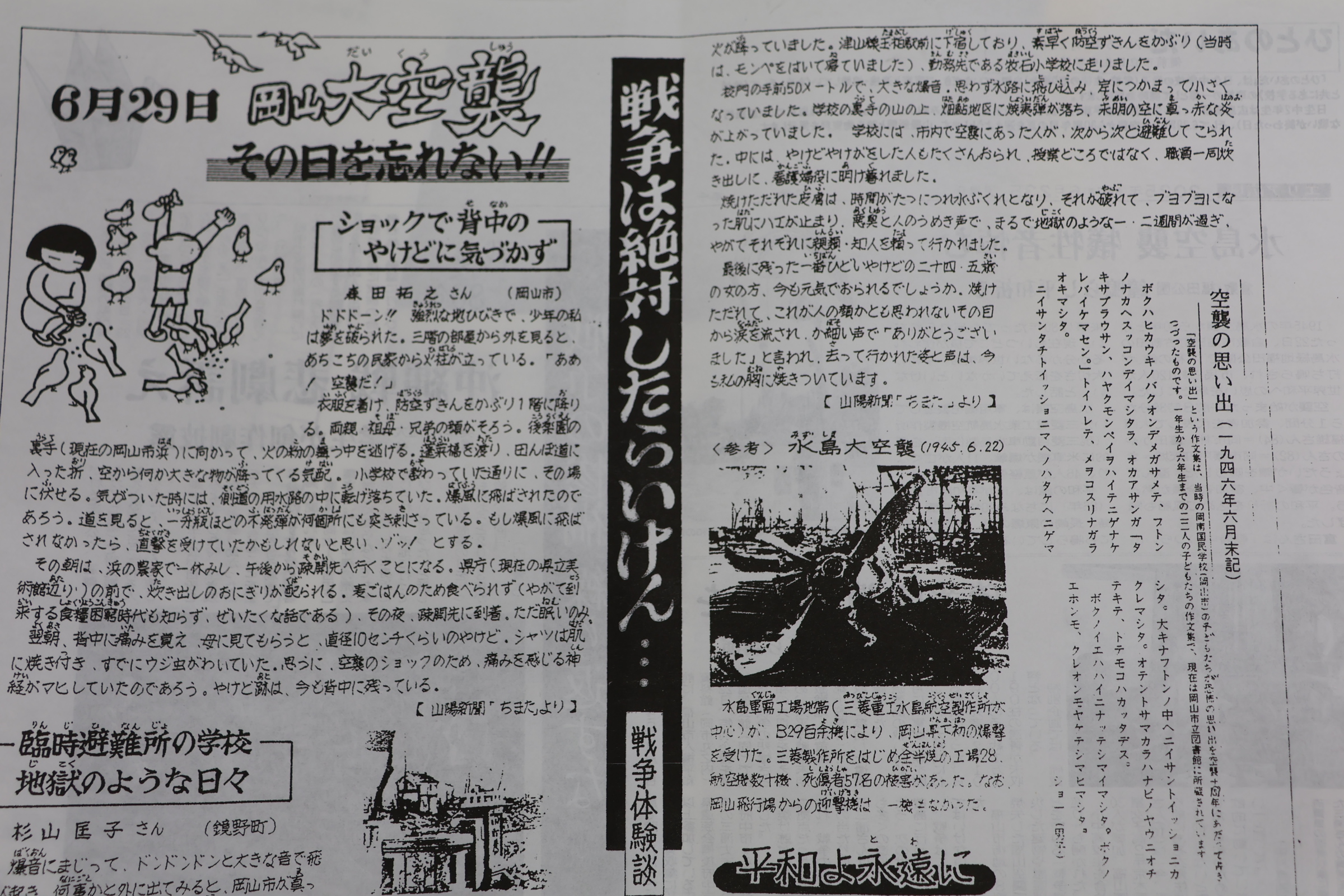
◎こ小中の確かな連携を進めています(6/20)
こども園での人権講演会に参加しました。「親子を幸せをするわらべうた~心の安全基地~」として、梶谷恵子さん(どんぐり文庫)のわらべうた遊びを楽しみました。また、ひなせ親の会(次回は7/5)の紹介をしました。
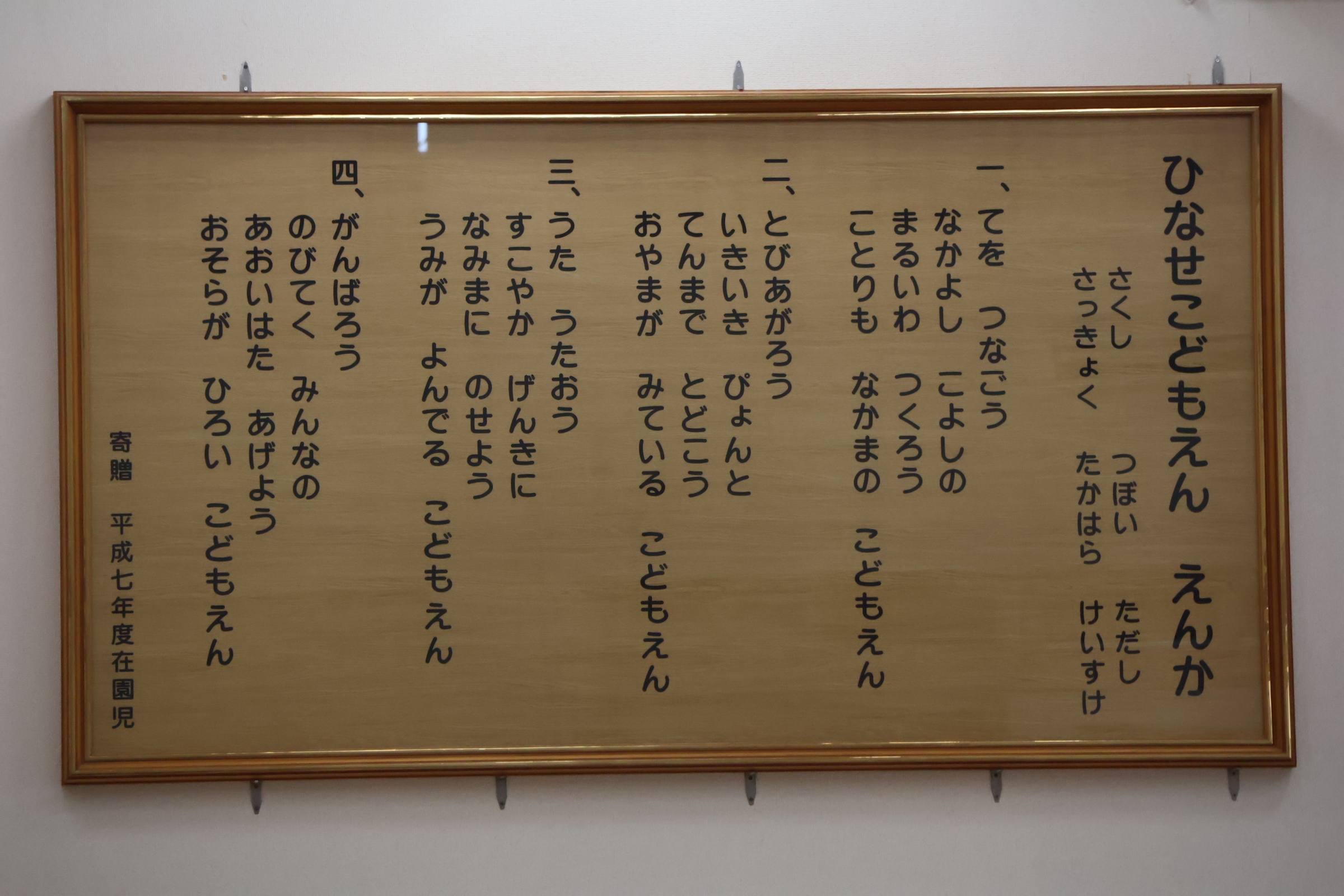





◎生活を高める取り組み✨(6/19)
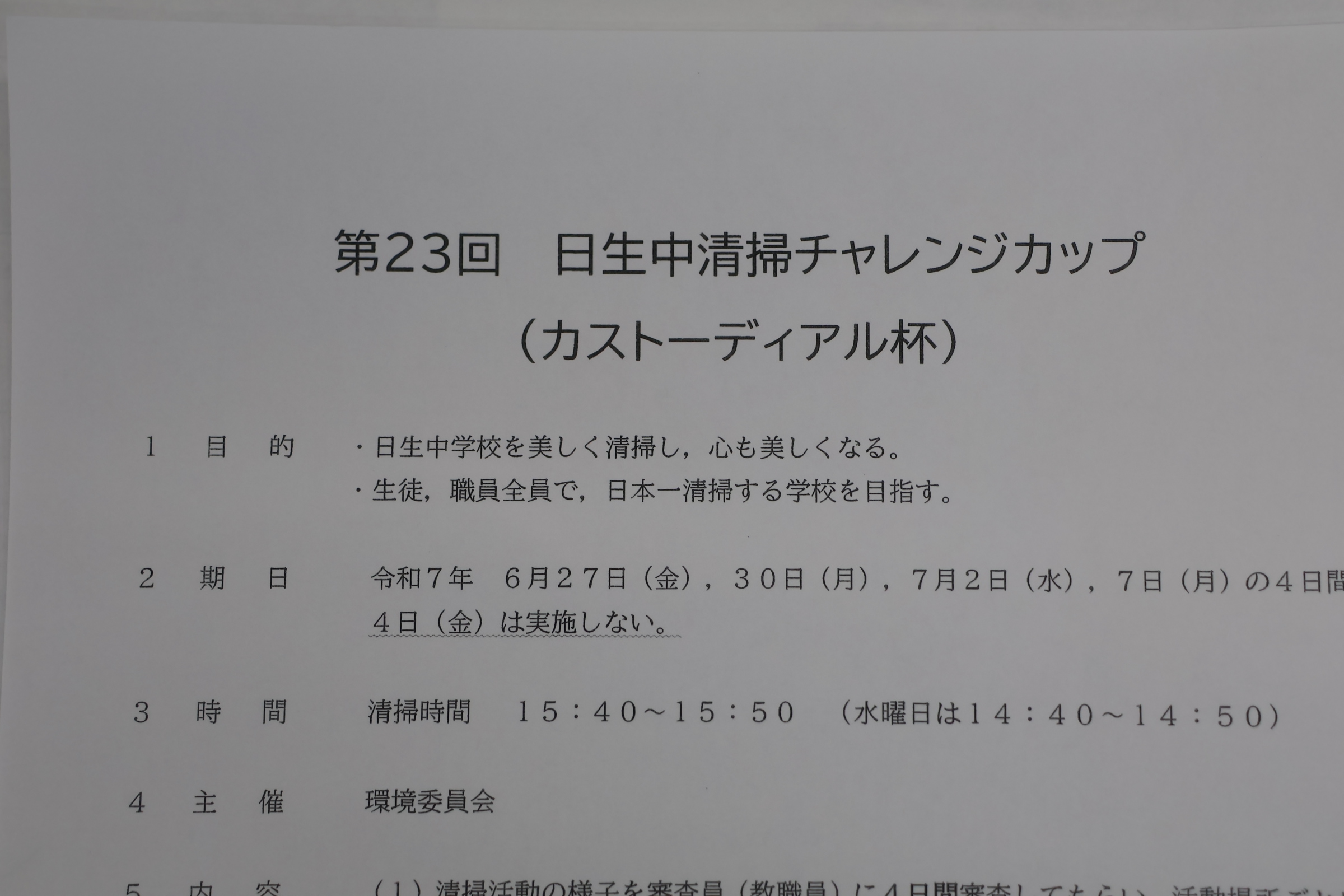
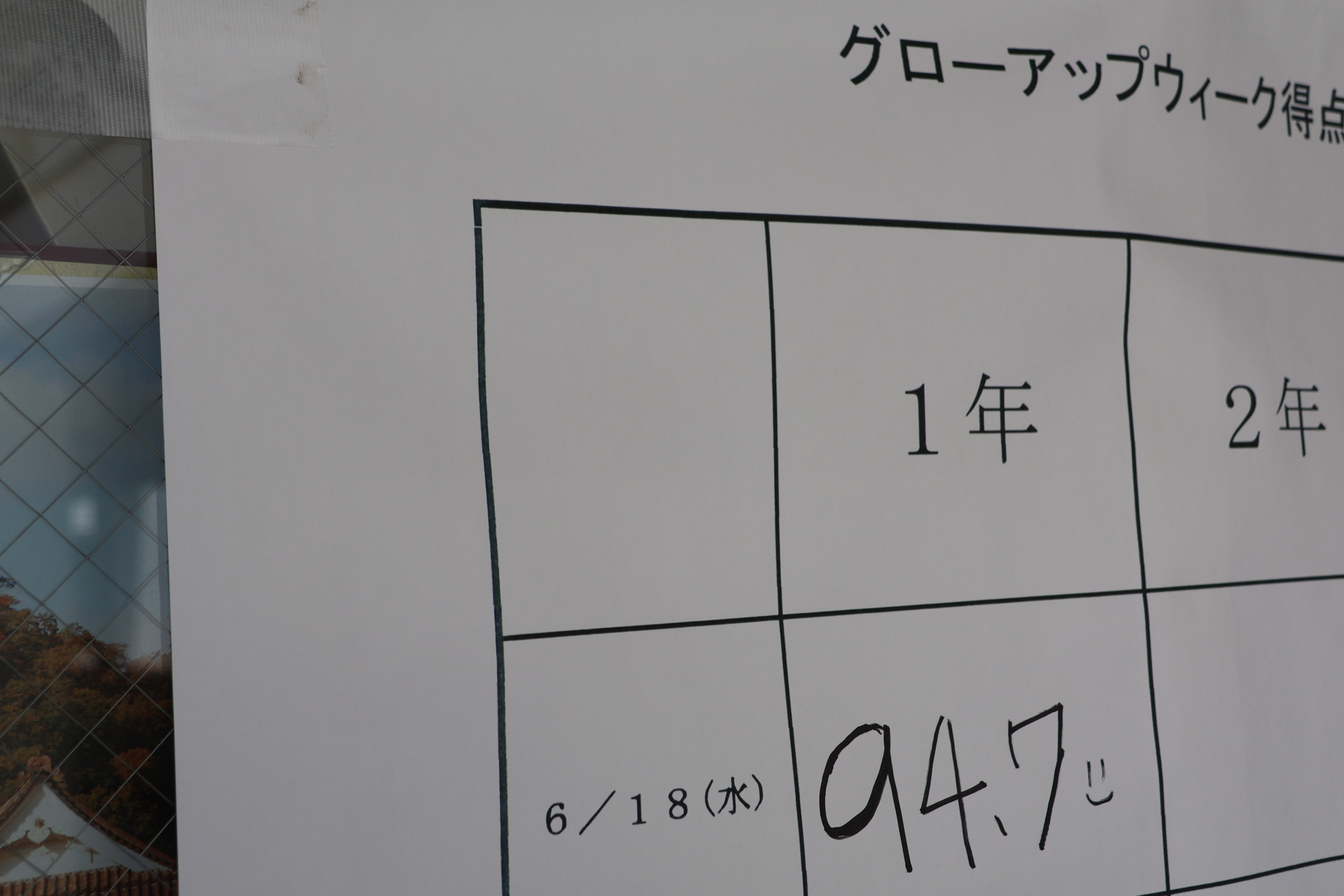
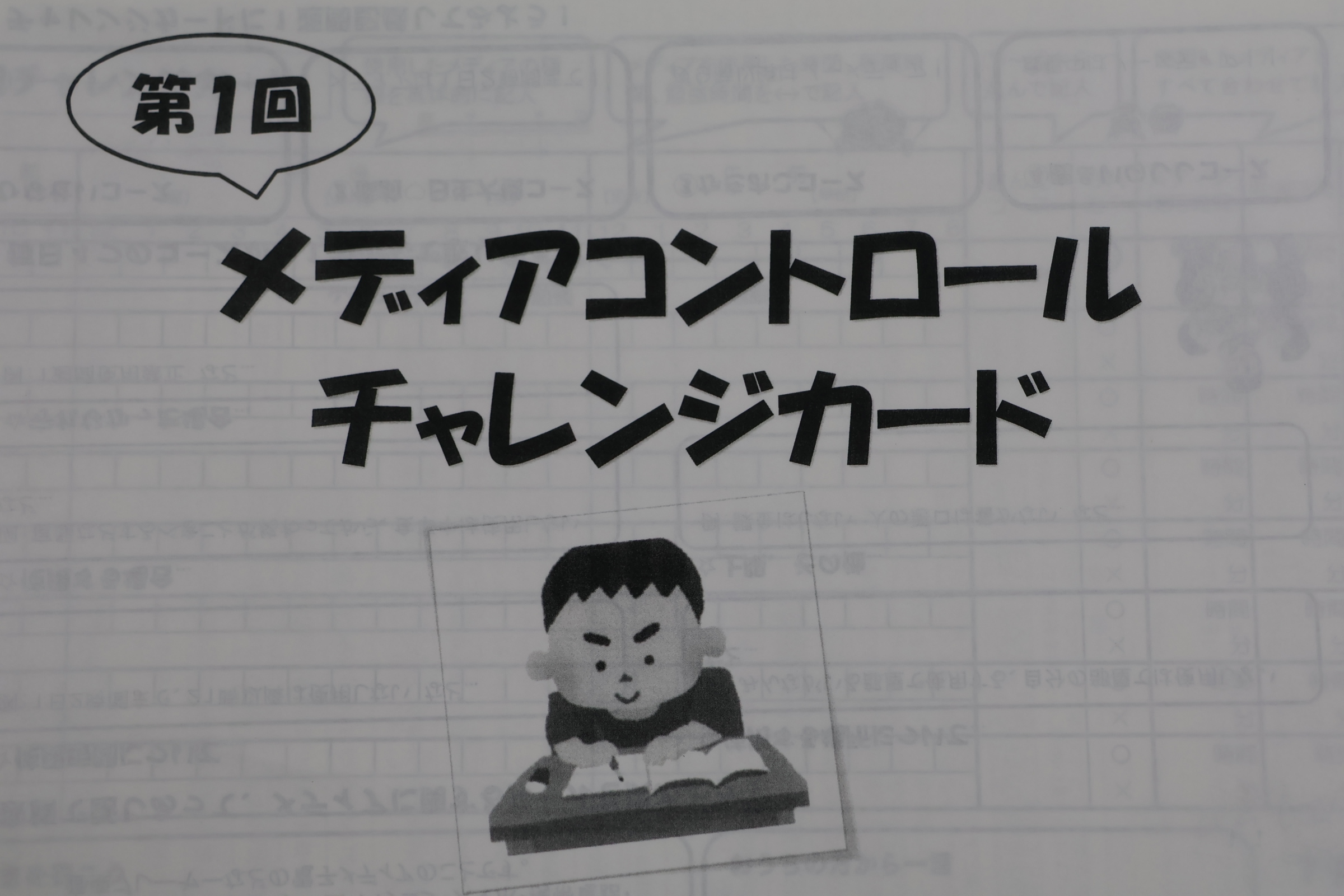
◎次のステージへ(6/19)

〈人間はしっぽがないから焼きたてのパン屋でトングをかちかち鳴らす 岡野大嗣〉


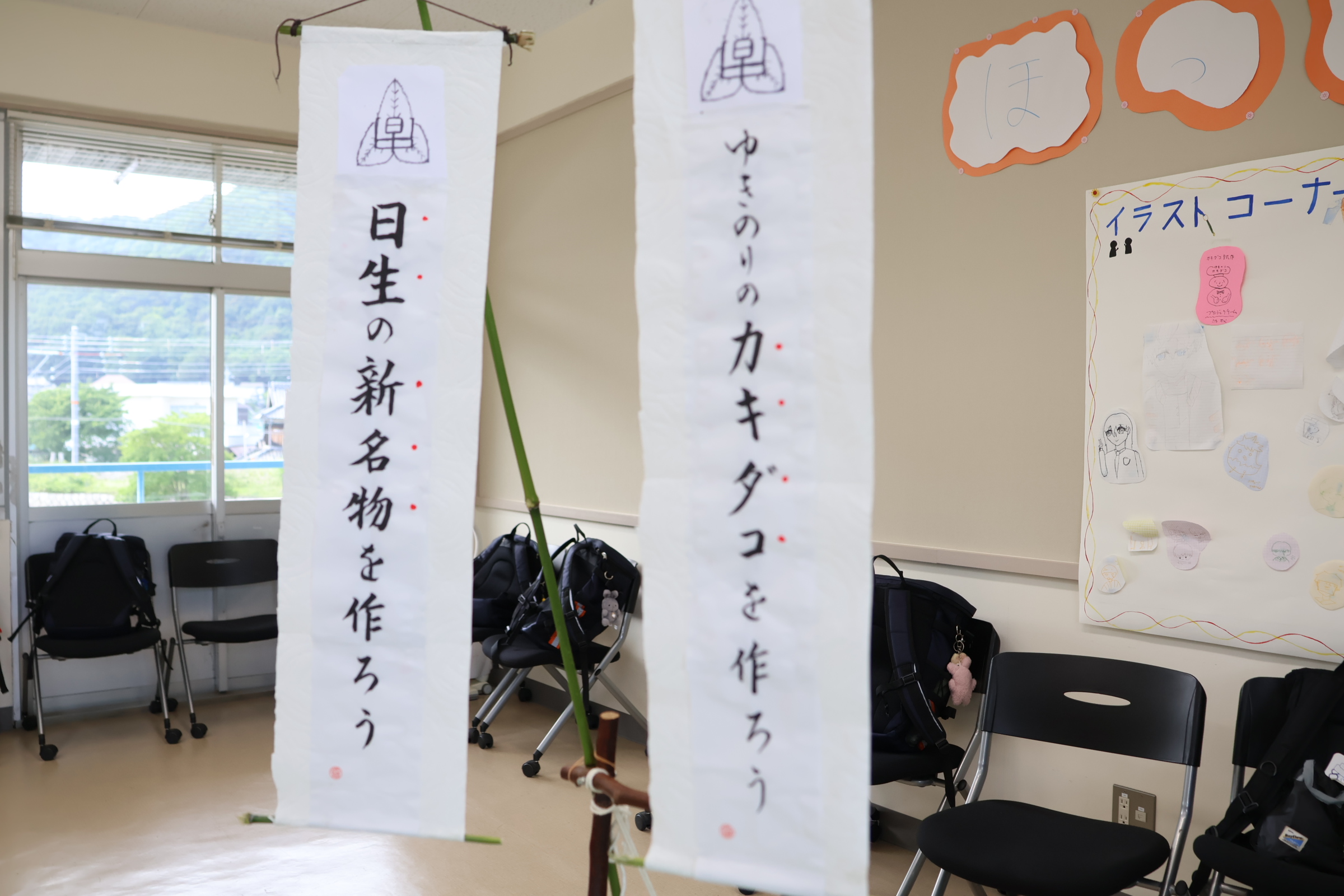
豊かな放課後の時間。私たちの大切な時間として。(6/18:英会話教室・ほっとスペース)
◎そんなひな中に惚れました(6/18)

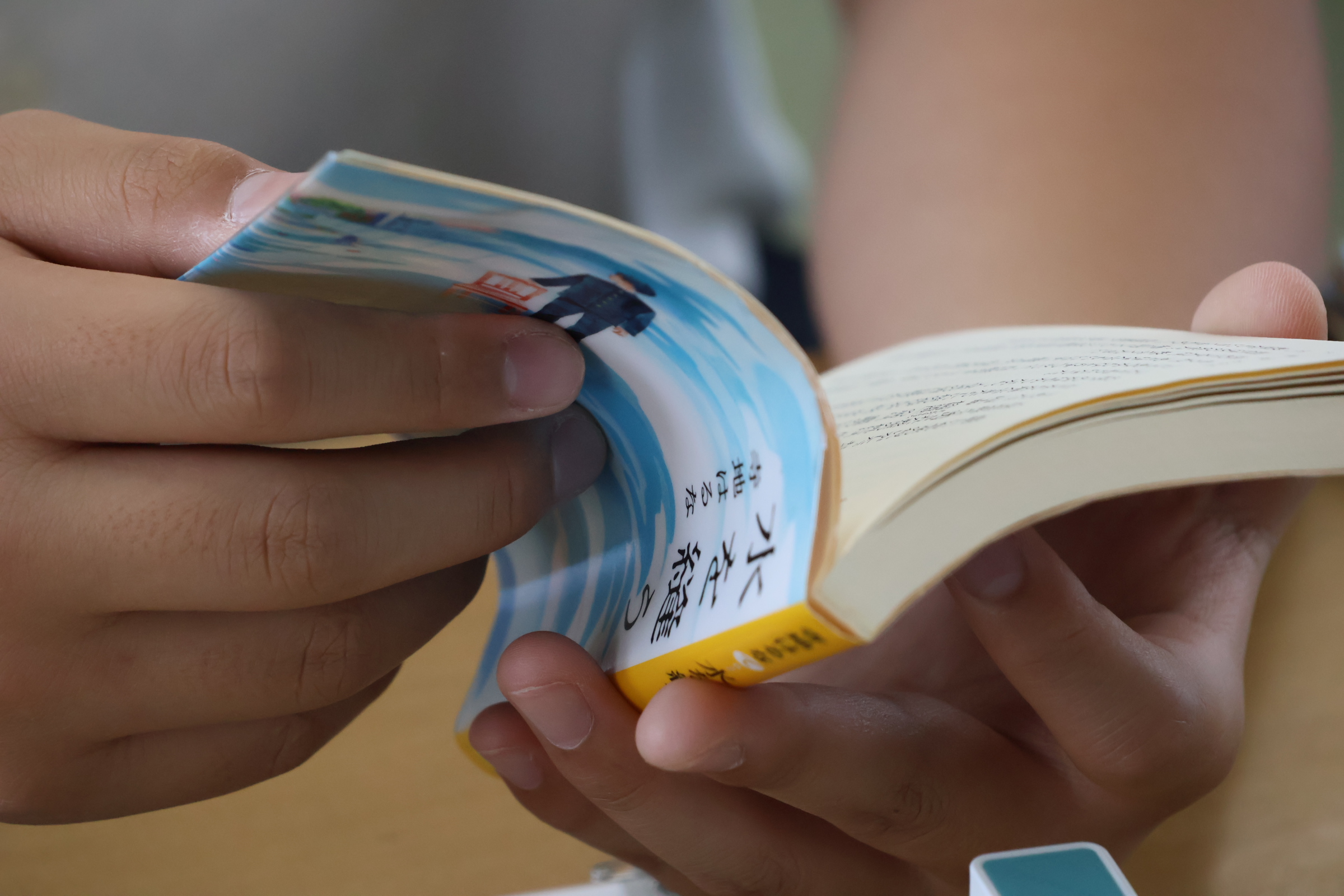
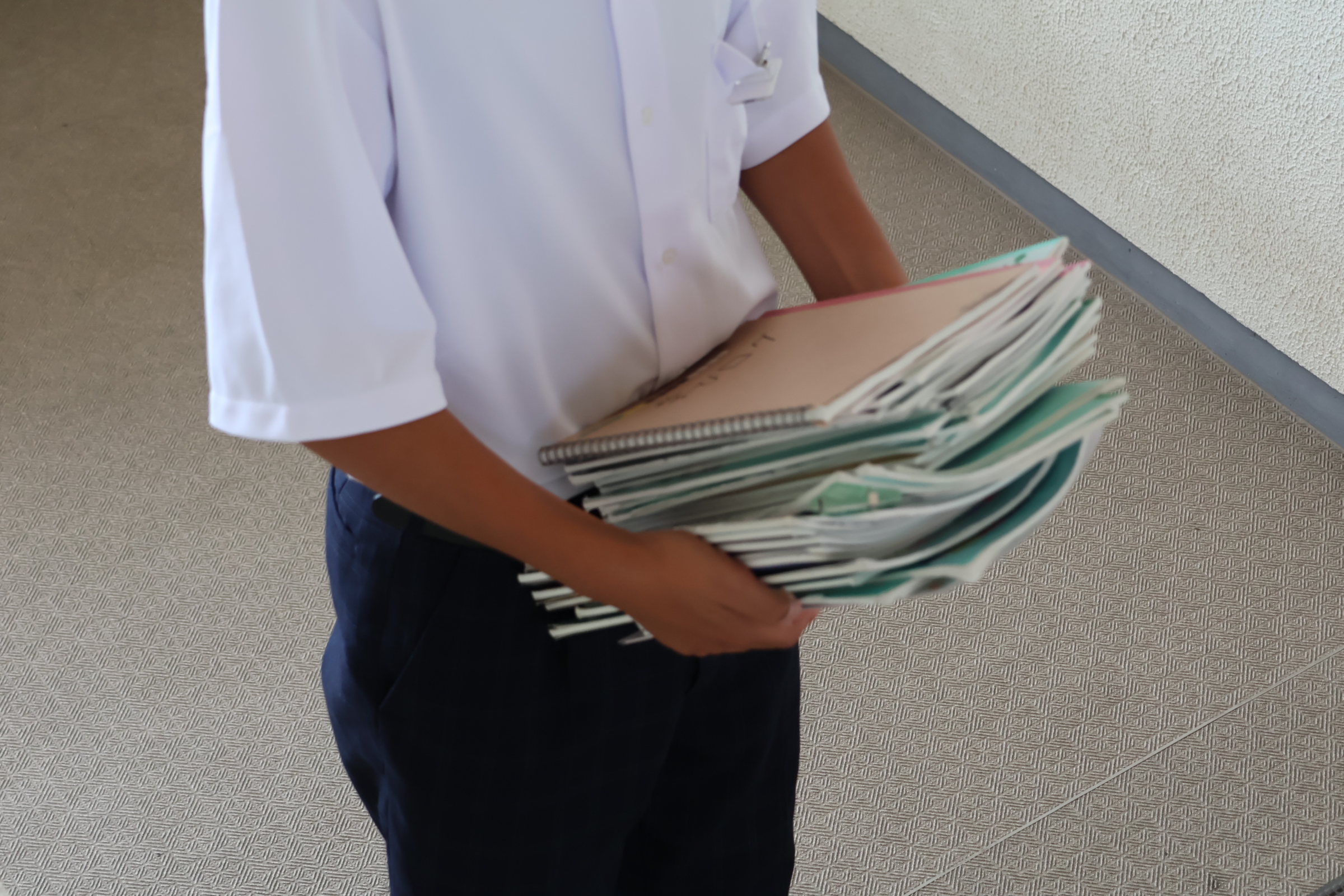
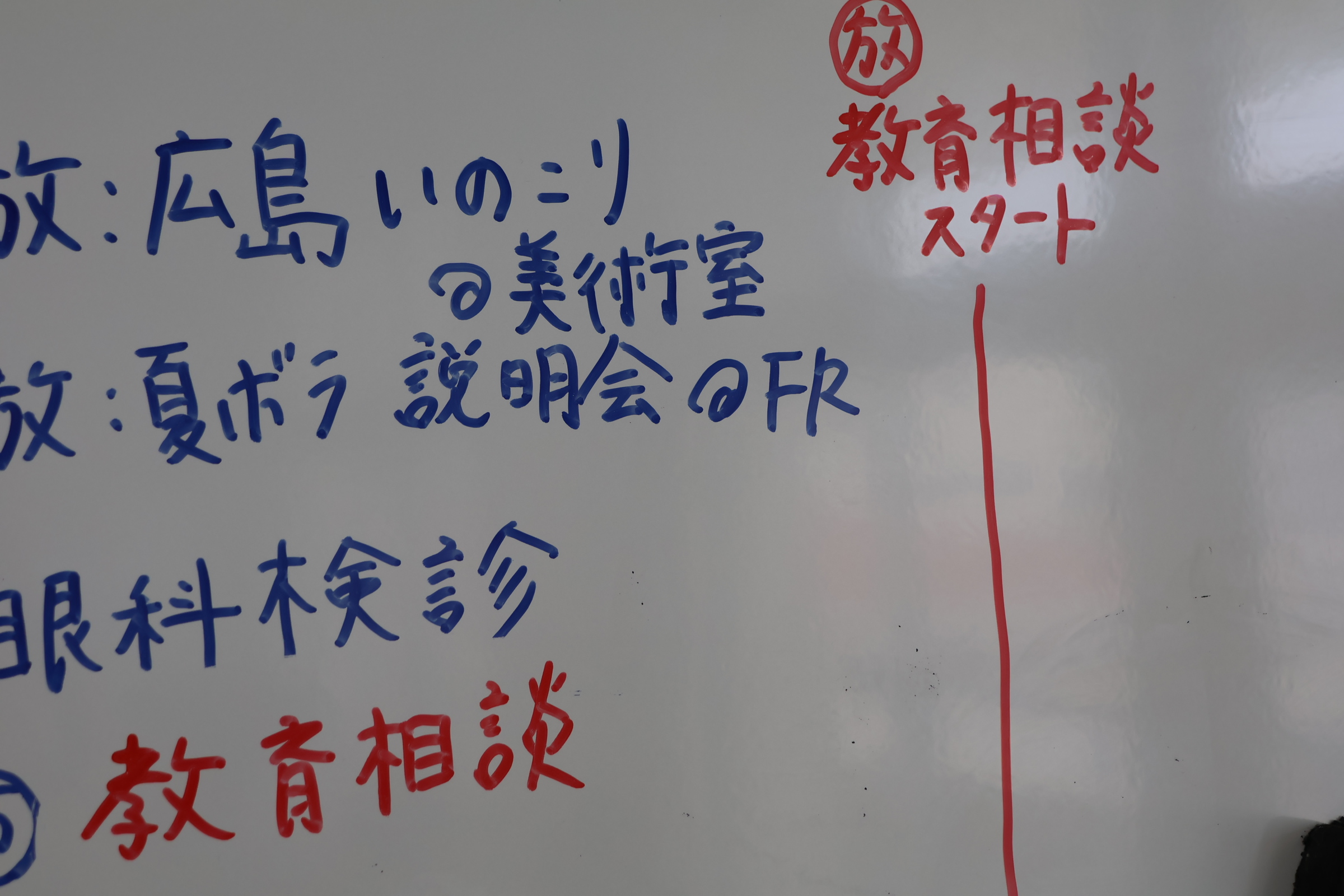


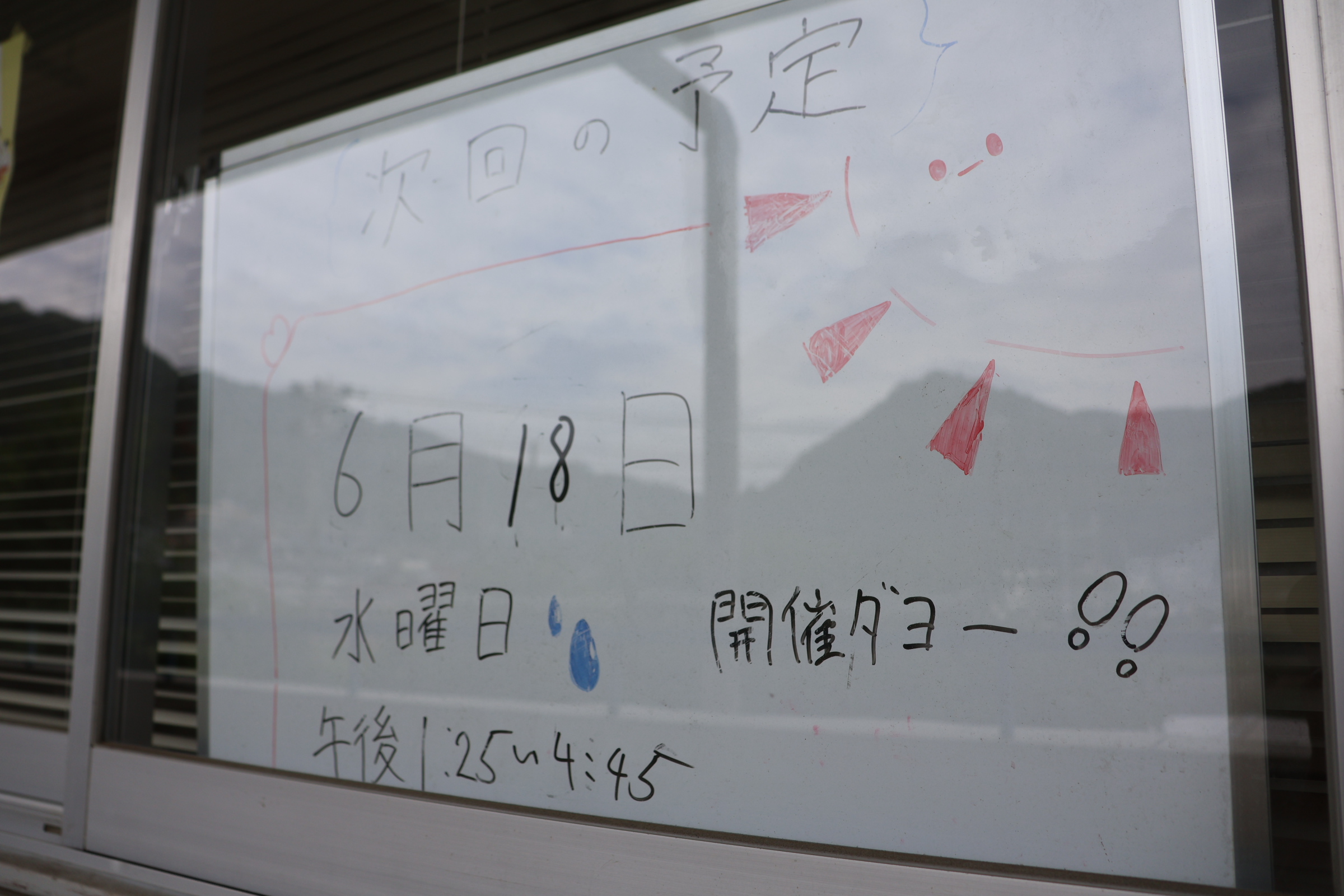
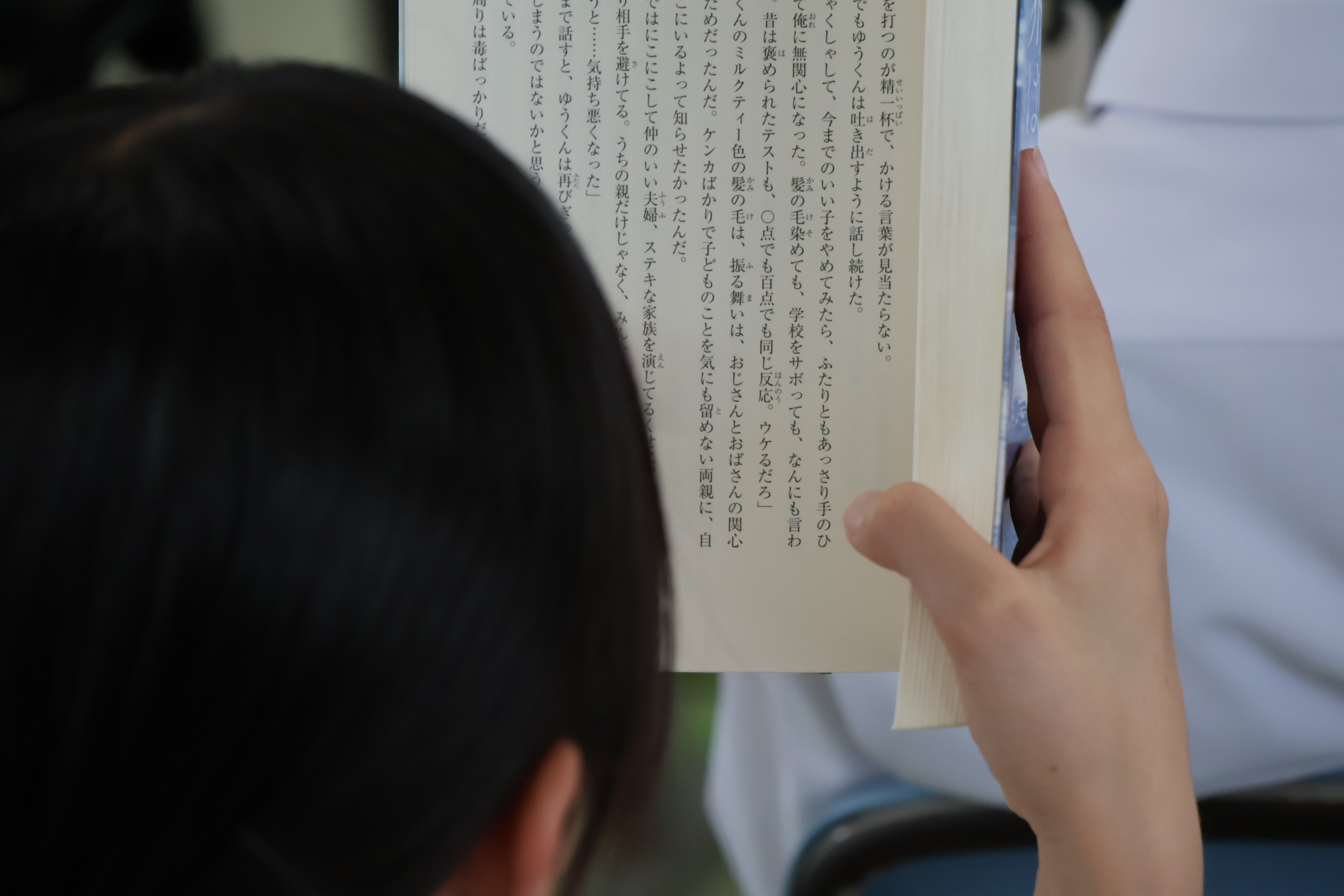
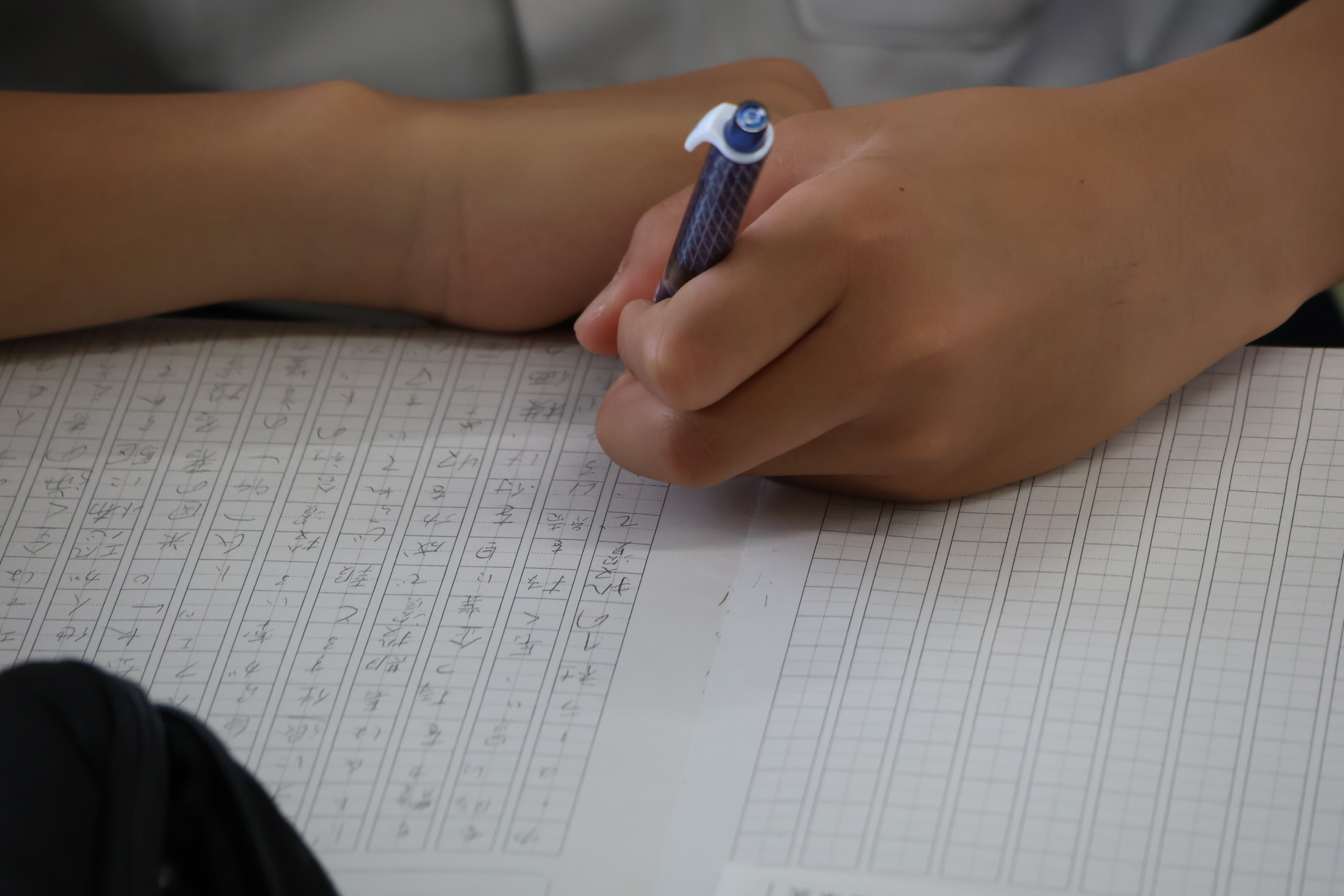
毎日を大切にしています
◎ひな中の熱
~待ってろよ!夏(6/17:夏ボラ校内説明会)

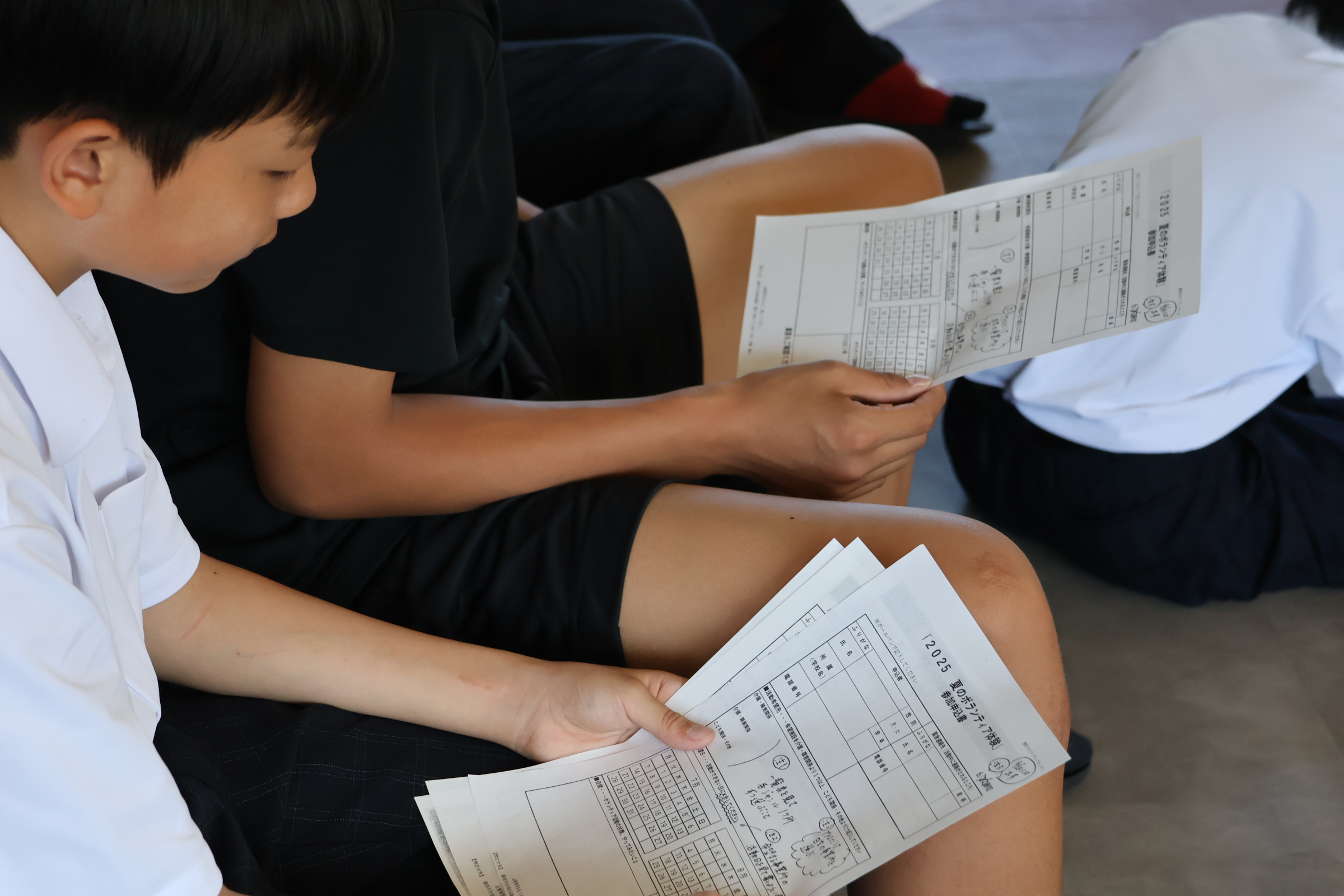
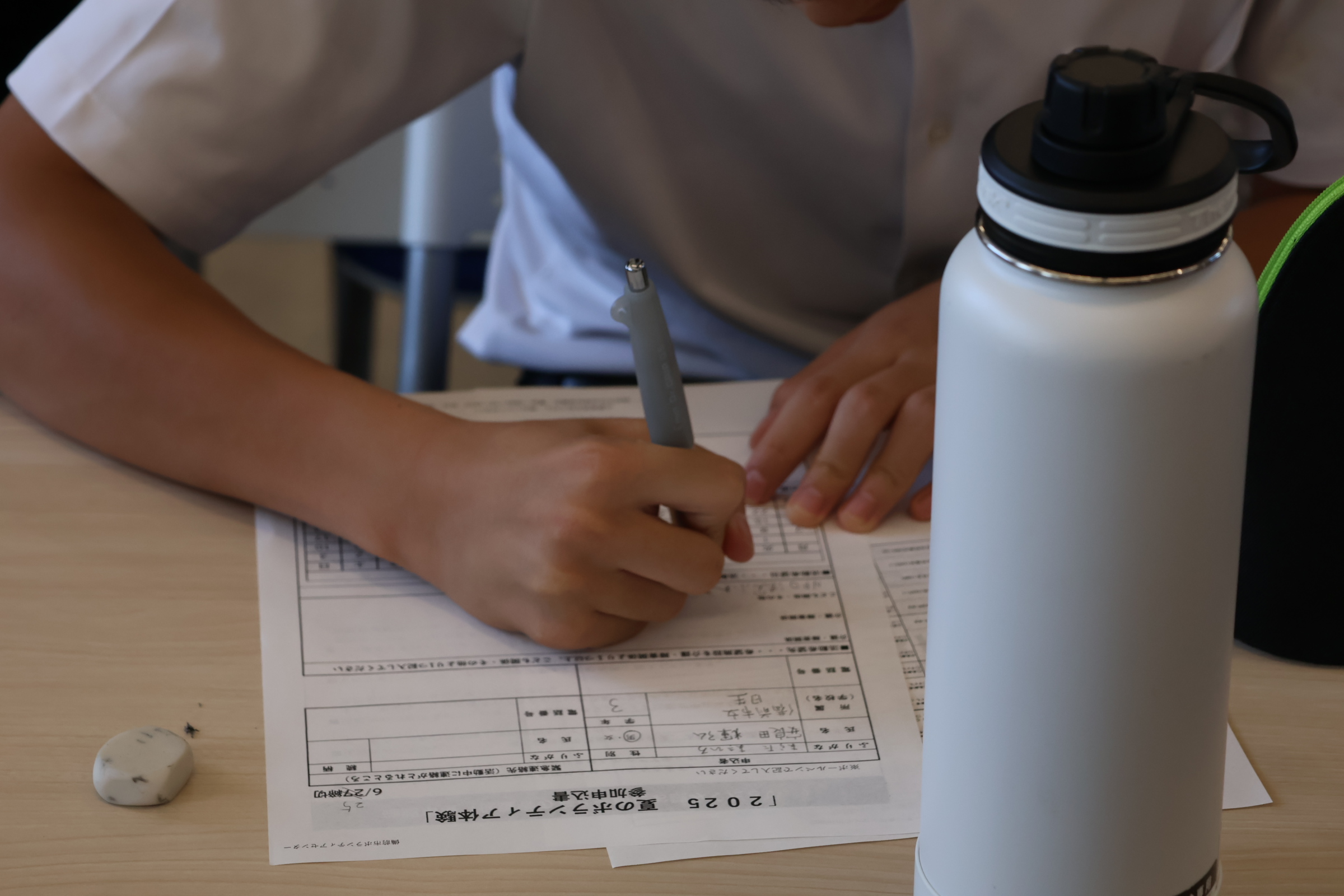
説明会場にいっぱい。
・校内締め切り(6/25(水))*保護者署名・押印、自分のスケジュールを確認。
・社会福祉協議会さん来校、受け入れ施設との調整会議(7/9(水))
〈「ありがとうございました。」と後輩の声受け最後の部活動終わる〉


◎私たちの始まりの風景18
ここはどこでしょう?(6/16校内編)






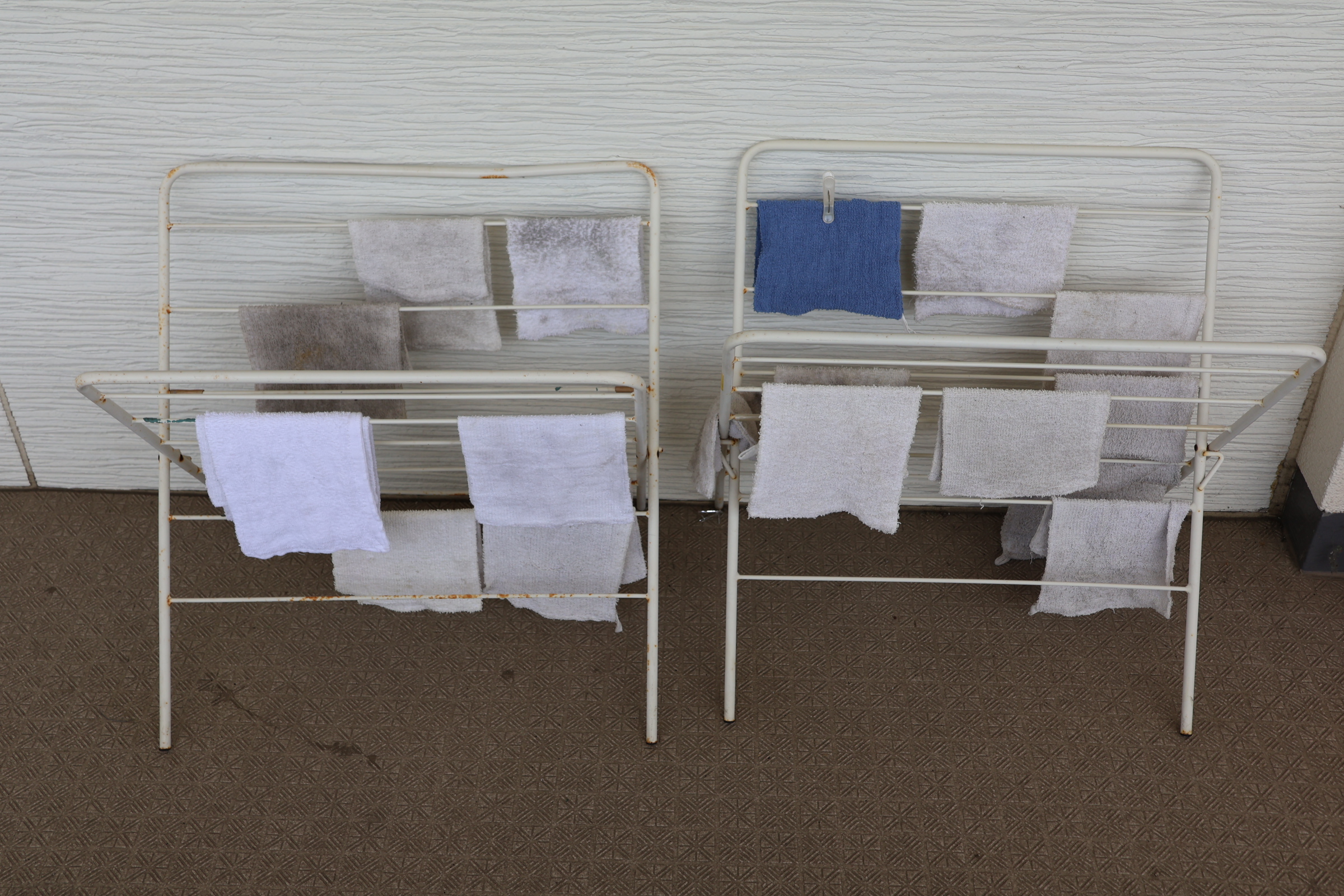

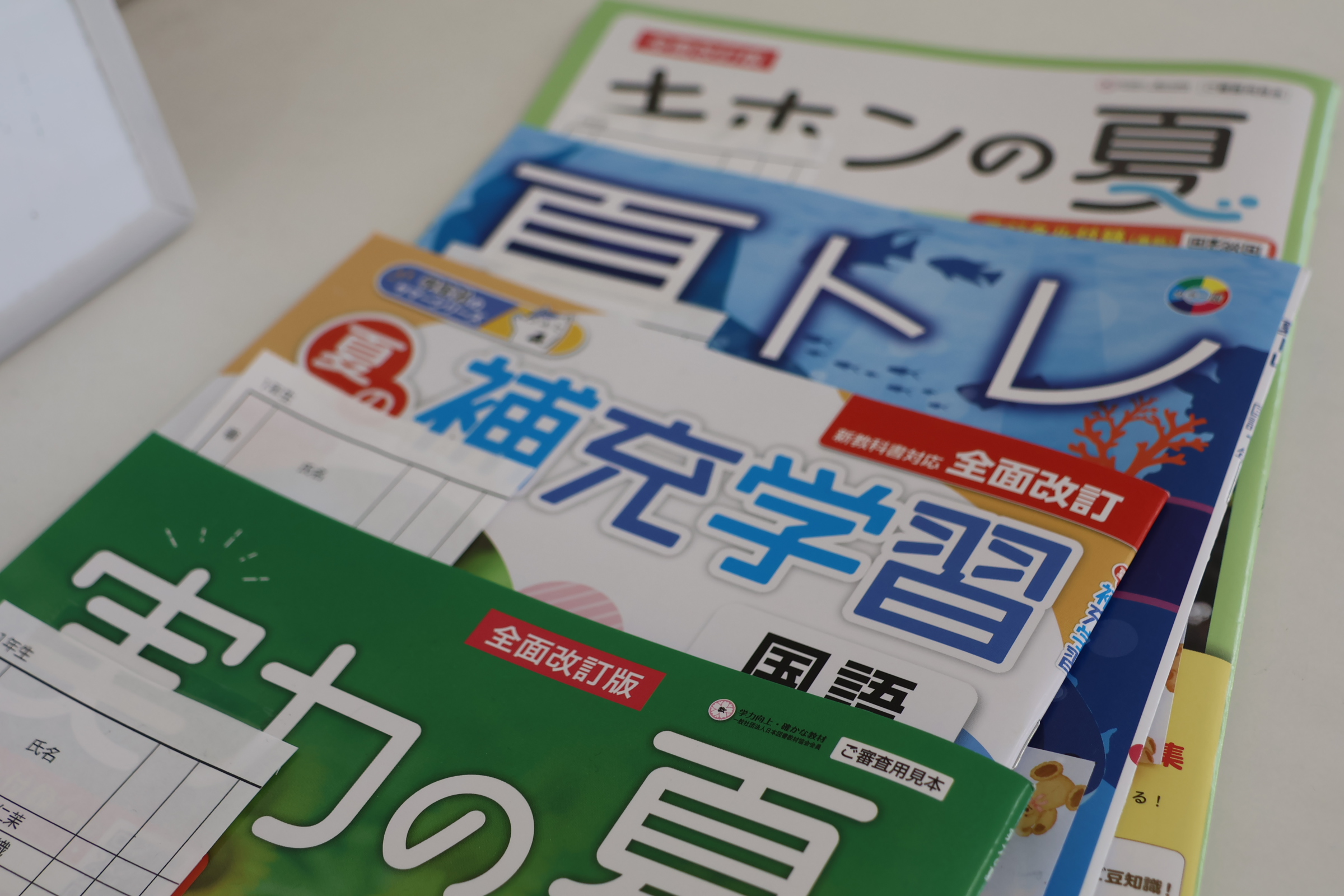
◎あめつち (6/13)









6/14~15 総体・吹奏楽祭 仲間と共に、一所懸命。


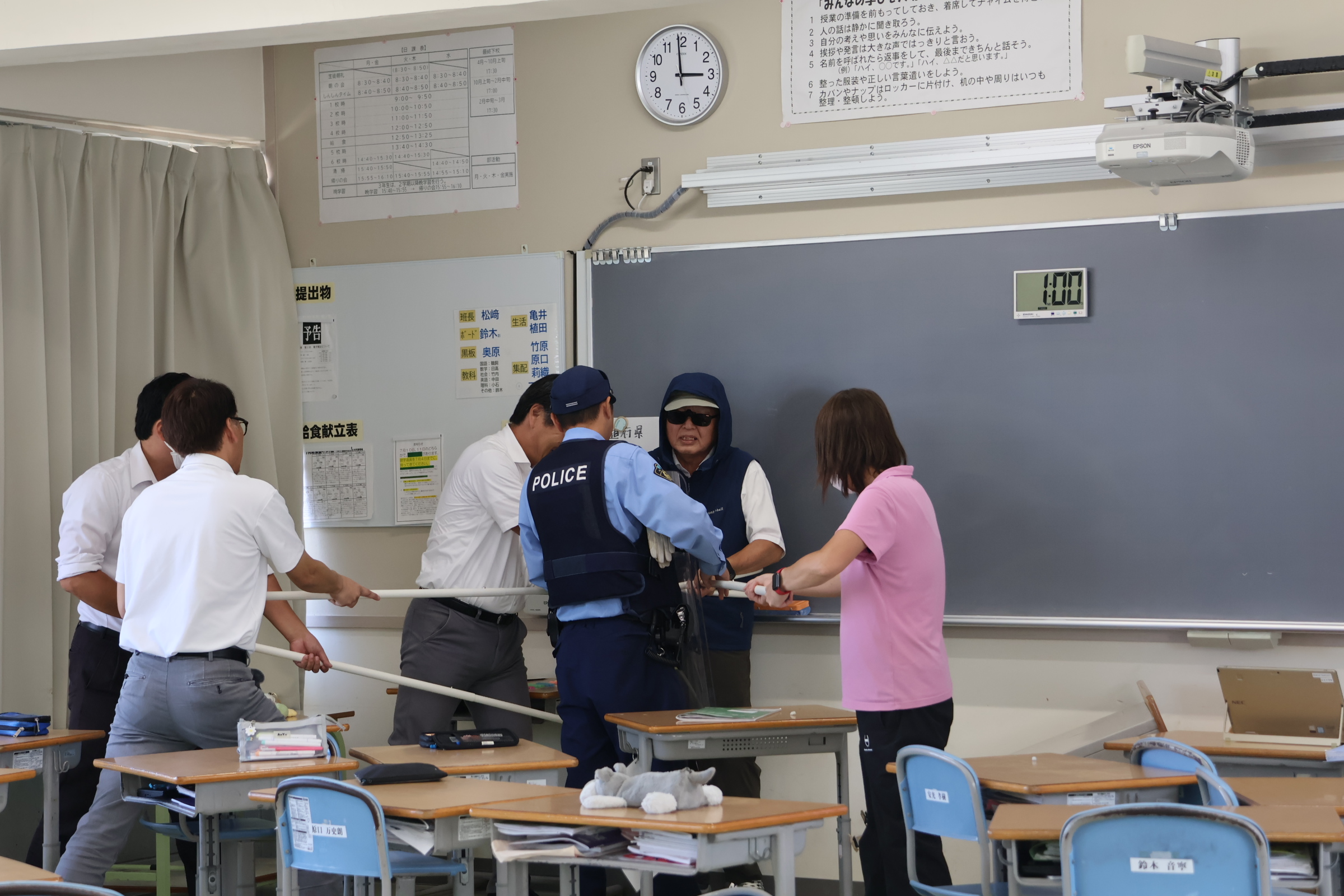
◎自分らしく せいいっぱい 進路は多様
春15(いちご)の会の案内が届きました。(7/8)

今日の日生親の会でも‚進級・進学についての話題があります。
◎7月7日 ~晴れた夜空 数を増やす星 かなえたい願いは♪

7月7日、いろんな日(記念日)となっていますね。例えば、
◇アルティメットの日:フライングディスクを使った団体競技である「アルティメット」の魅力を広めるために制定された日。アルティメットが7人対7人で試合をすることから。
◇糸魚川・七夕は笹ずしの日:糸魚川流域の郷土料理である「笹ずし」のおいしさを広めるために制定された日。7月7日が「笹の節句」と呼ばれていることから。
◇川の日:地域の良好な環境づくりを考え、河川に対する関心を取り戻すために制定された日。七夕伝説に天の川のイメージがあることから、7月7日に。
◇コンペイトウの日:金平糖の文化を後世に伝えるために制定された日。金平糖が星の形をしていることから、織姫と彦星の七夕伝説にちなんで7月7日に。
◇ソサイチ(7人制サッカー)の日:ブラジル発祥の7人制サッカー「ソサイチ」の魅力を広めるために制定された日。ソサイチが7人対7人で試合をすることから。
◇七夕:彦星と織姫が年に一度だけ会うことが許されているという伝説で、その日付が7月7日であることから。
◇手織りの日:機織り機などを使って自分の手で布を織る「手織り」の文化の発展のために制定された日。七夕に、彦星に会うために1日だけ機織りを休む織姫の代わりに手織りをしようという思いを込めて7月7日に。
◇ハスカップの日:北海道で栽培されているベリーの一種「ハスカップ」の魅力を広めるために制定された日。ハスカップの花言葉が「愛の契り」であることから、織姫と彦星の七夕伝説にちなんで7月7日に。
◇みんなで土砂災害の減災を願う日:自分が住んでいる地域のため池や崖などでの、土砂災害の危険性を知るために制定された日。2018年7月に西日本や東海地方で記録的な大雨となり、7月7日に土砂災害が多発したことから。
◇ゆかたの日:中国で昔、七夕の日に裁縫の上達を祈る風習があったことにちなんで。
さて、7月7日「七夕」にちなんだ、七夕に関するクイズをいくつか!チャレンジしてみましょう。
Q1.七夕は元々どんな行事だったでしょう?(1)正月行事(2)盆行事(3)成人行事
Q2.七夕に食べられる行事食は、次のうちどれでしょう?(1)うなぎ(2)水ようかん(3)そうめん
Q3.七夕の日に願いを書くのは、次のうちどれでしょう?(1)葉書(2)短冊(3)半紙
Q4.七夕の日に、織姫と彦星が渡ると言われている「天の川」。英語で「天の川」のことを何というでしょう?(1)スターライン(2)ナイトリバー(3)ミルキーウェイ
こたえ
Q1.七夕は元々どんな行事だった?《答》(2)盆行事→元々、日本では7月7日の夜にお盆の行事が行われていました。
Q2.七夕に食べられる行事食は?《答》(3)そうめん→七夕の日には、そうめんを食べる風習があります。元々は中国で無病息災を願って7月7日に麺を食べる習慣があることにちなんでいるという説があります。
Q3.七夕の日に願いを書くの?《答》(2)短冊→七夕の日には、紙や薄い木や竹の皮を細長く切った短冊に願いを書いて、笹の木にかざります。
Q4.七夕の日に、織姫と彦星が渡ると言われている「天の川」。英語で「天の川」のことを?《答》(3)ミルキーウェイ→天の川のことを、英語では「ミルキーウェイ(Milky Way)」と言います。「乳の川」という意味で、ギリシャ神話で女神ヘラの母乳が流れ落ちたものとされています。
◎チャレンジ✨ 扉をひらく(7/4:家庭科1年生)
今年も、多くのひとに支えられて「浴衣」着付け学習、そしてエリアティチャーさんらと「日生音頭」の練習。





















なんと!8/13のひなせ夏まつりでの、ひな中盛り上げ隊ブースでは、浴衣来店で割引だそうですよ。(出店スタッフも募集中)
◎鍵かけコンテスト中。高い意識を(7/3:体育委員会活動中)

◎ひな中の風~~~
繰り返し練習、練習。書写に取り組んでいます!(7/4~10)
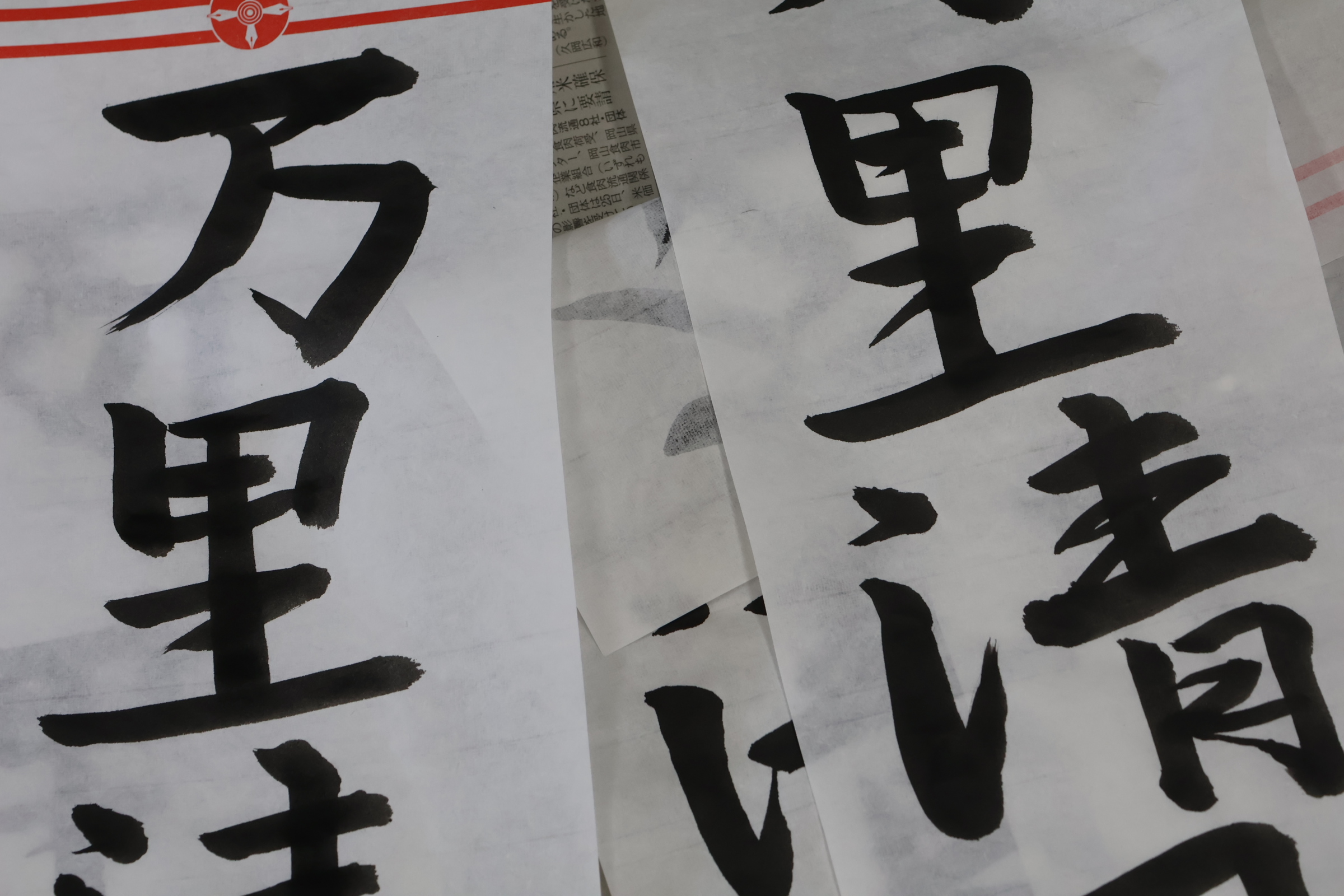
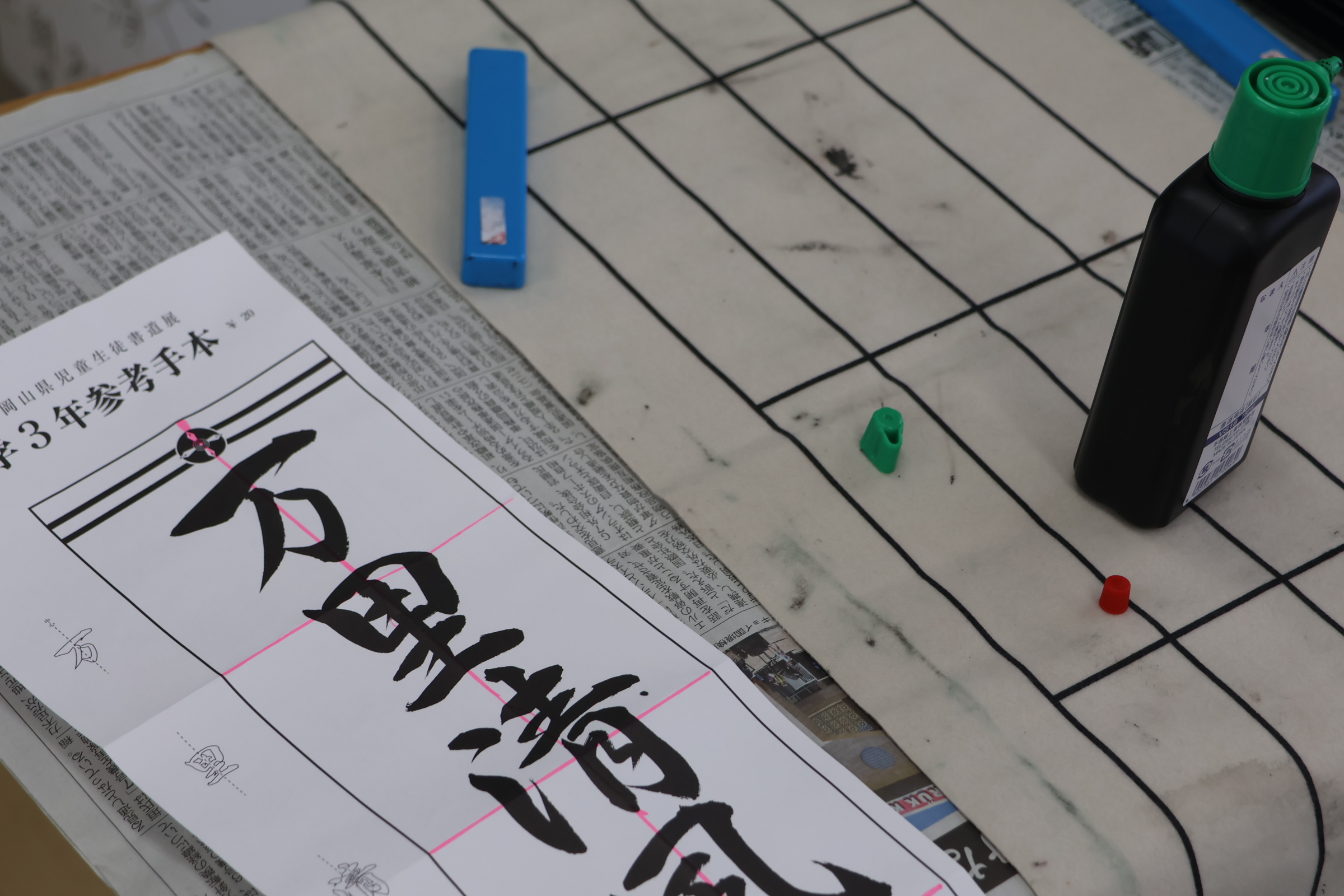

◎ひな中の風~~
伝えるちからは進路を切り拓く力(7/4:英語授業(1年・3年))
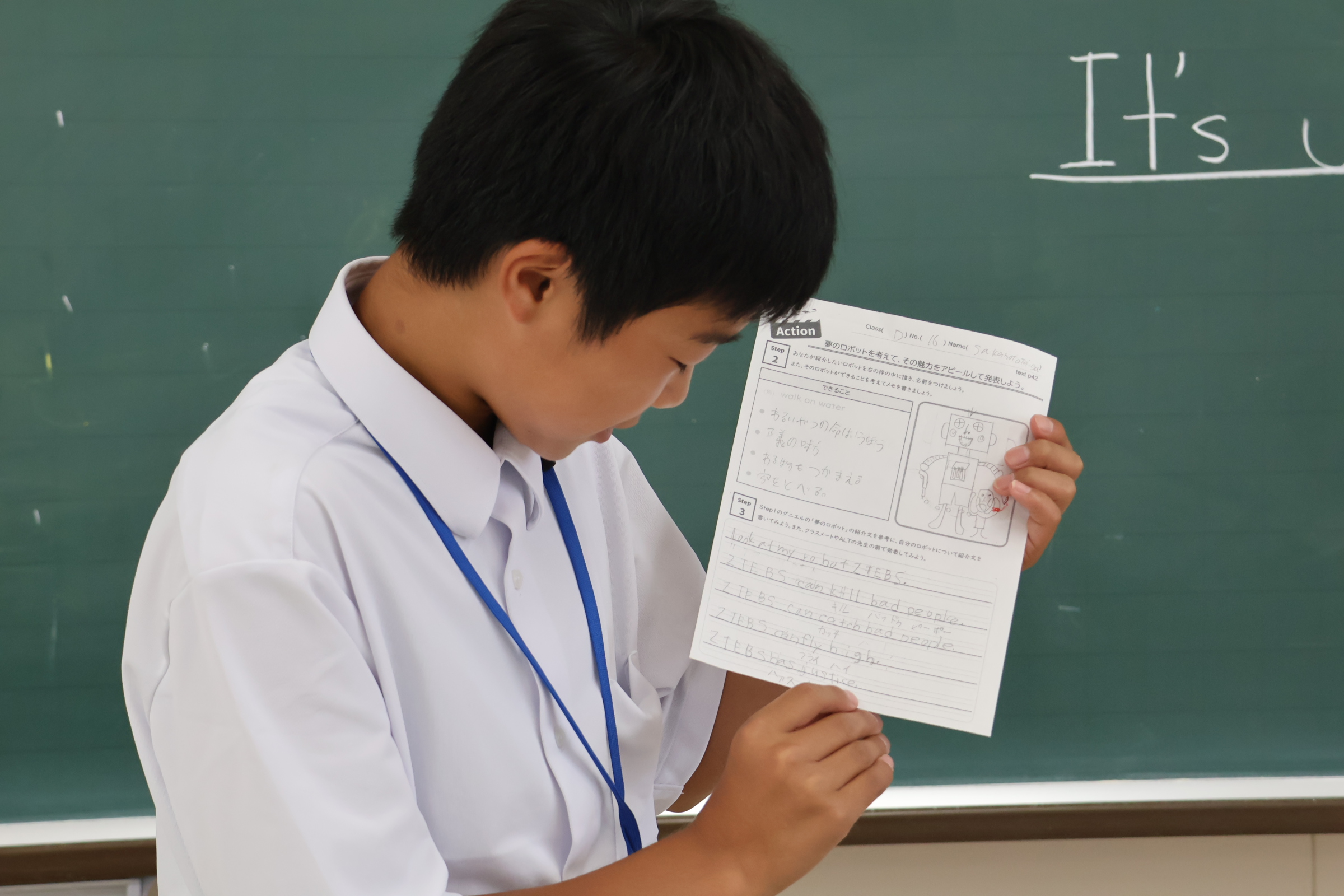



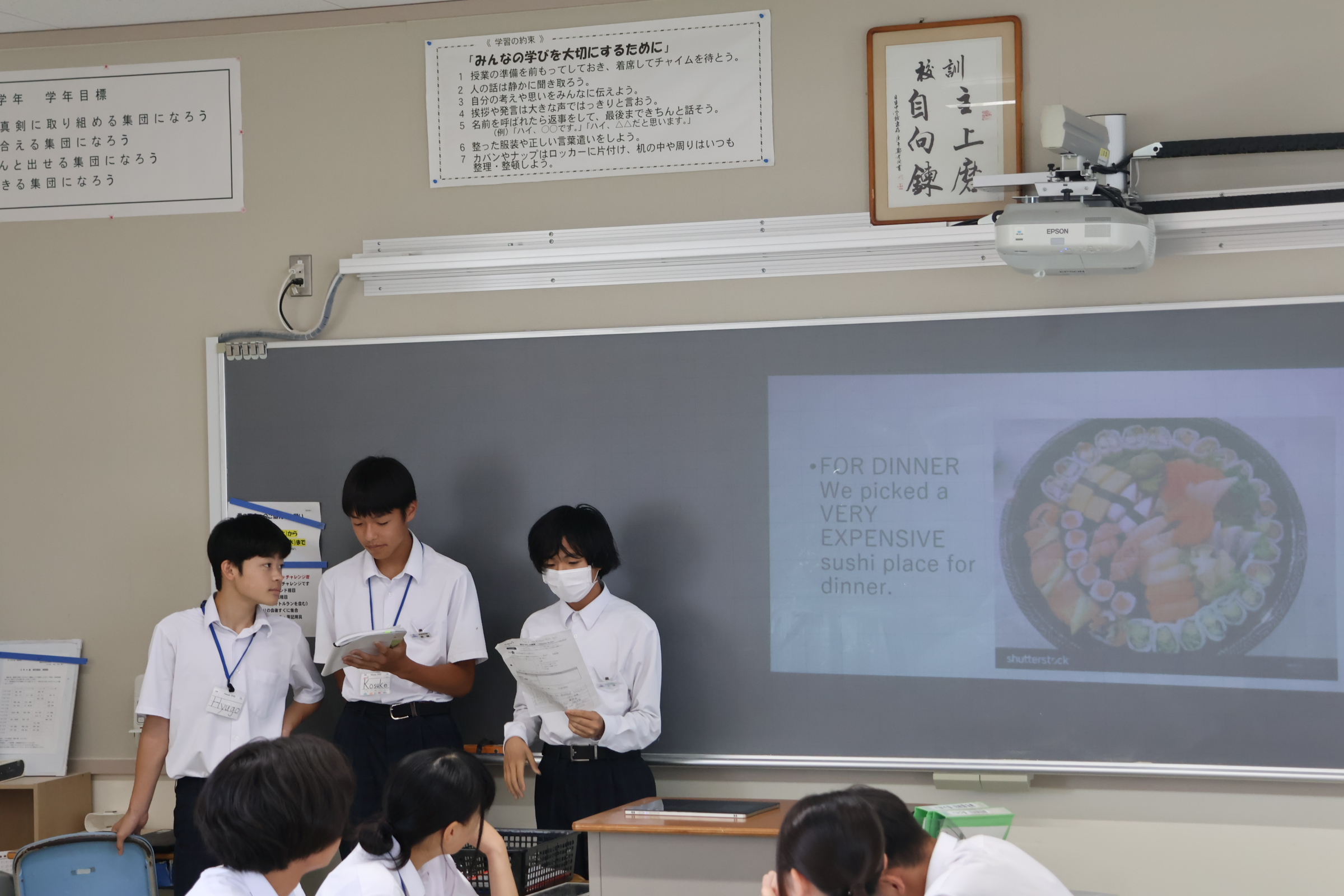
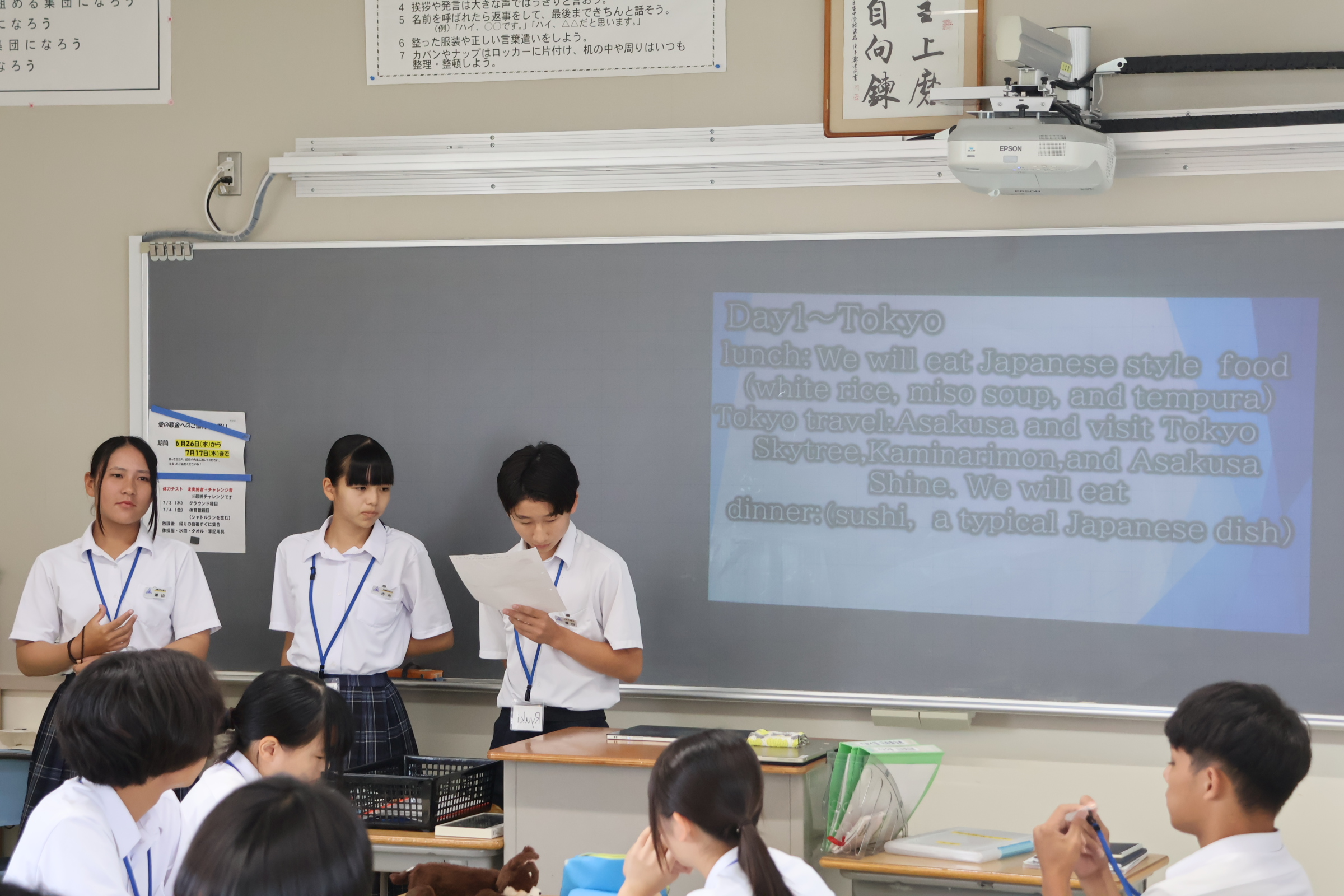

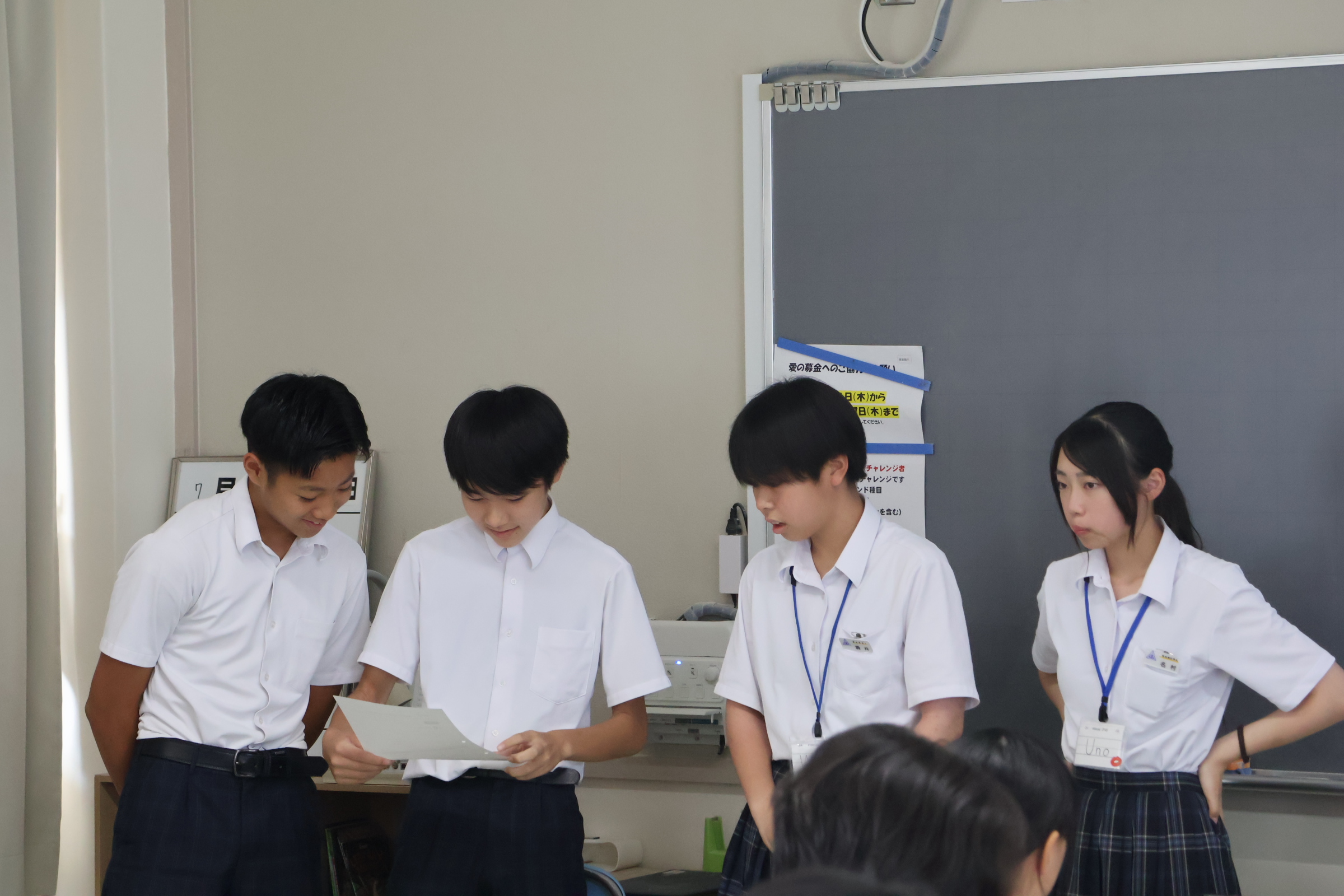

◎まだまだチャレンジ!体力テスト(7/3~4予定)
天候・気温の状況を鑑みて、実施します。

◎聞くことは、私たちの未来に効く
経験と知恵を学ぶ~海洋学習「聞き書き」活動(7 /3)
2年生が、漁協、観光協会、NPO里海づくり研究協議会、神戸税関さんらをエリアティチャーとして「聞き書き」活動に取り組みました。



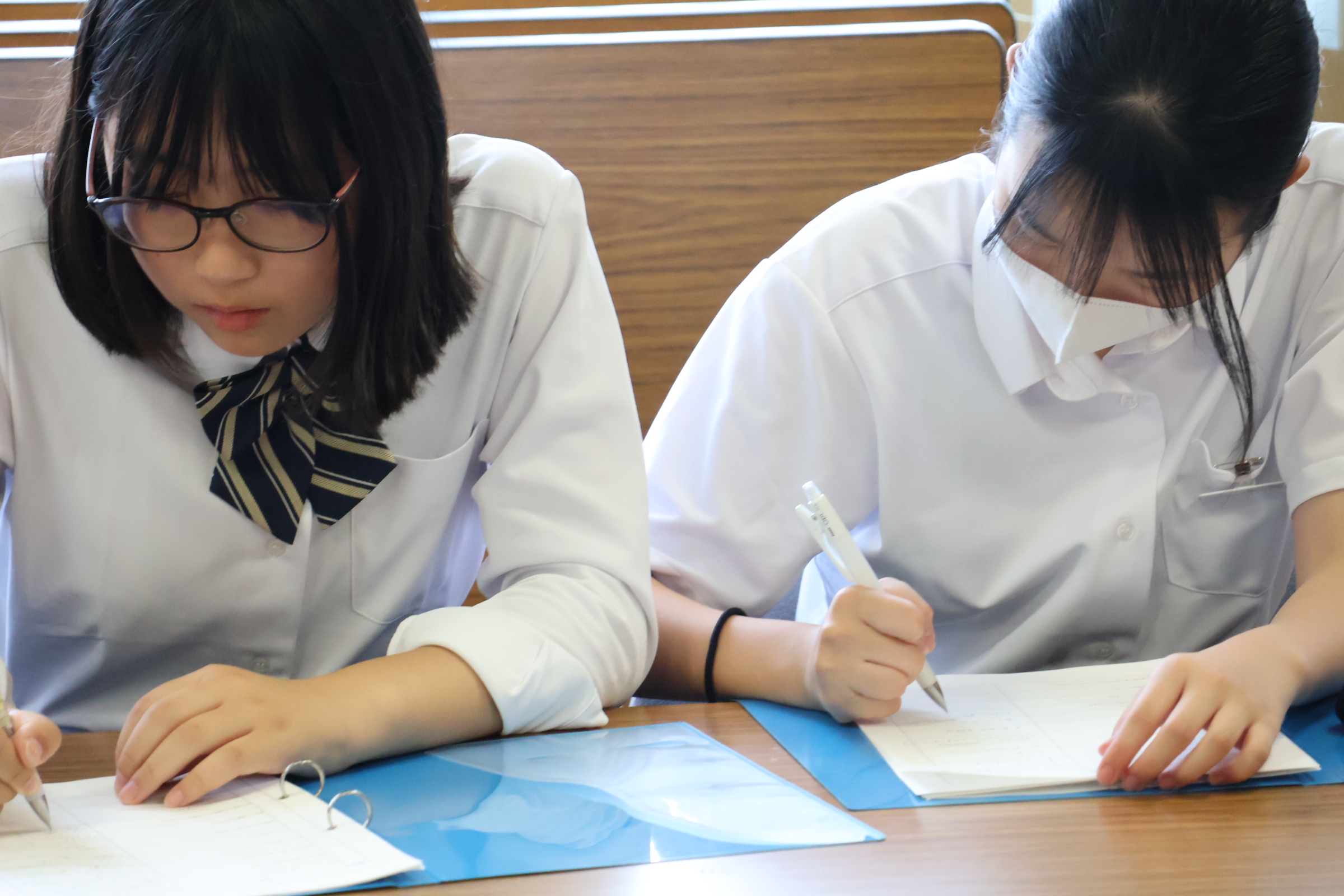





「聞き書き」:話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法です。話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法が一般的で、 この方法は、民俗学の研究や地域づくり、福祉の現場などで広く活用されています。聞き書きは、対話を通じて話し手の人生や価値観を引き出し、その人の経験や知恵を記録することを目的としています。
◎願いを叶えよ(7/3:ほっとスペース前)


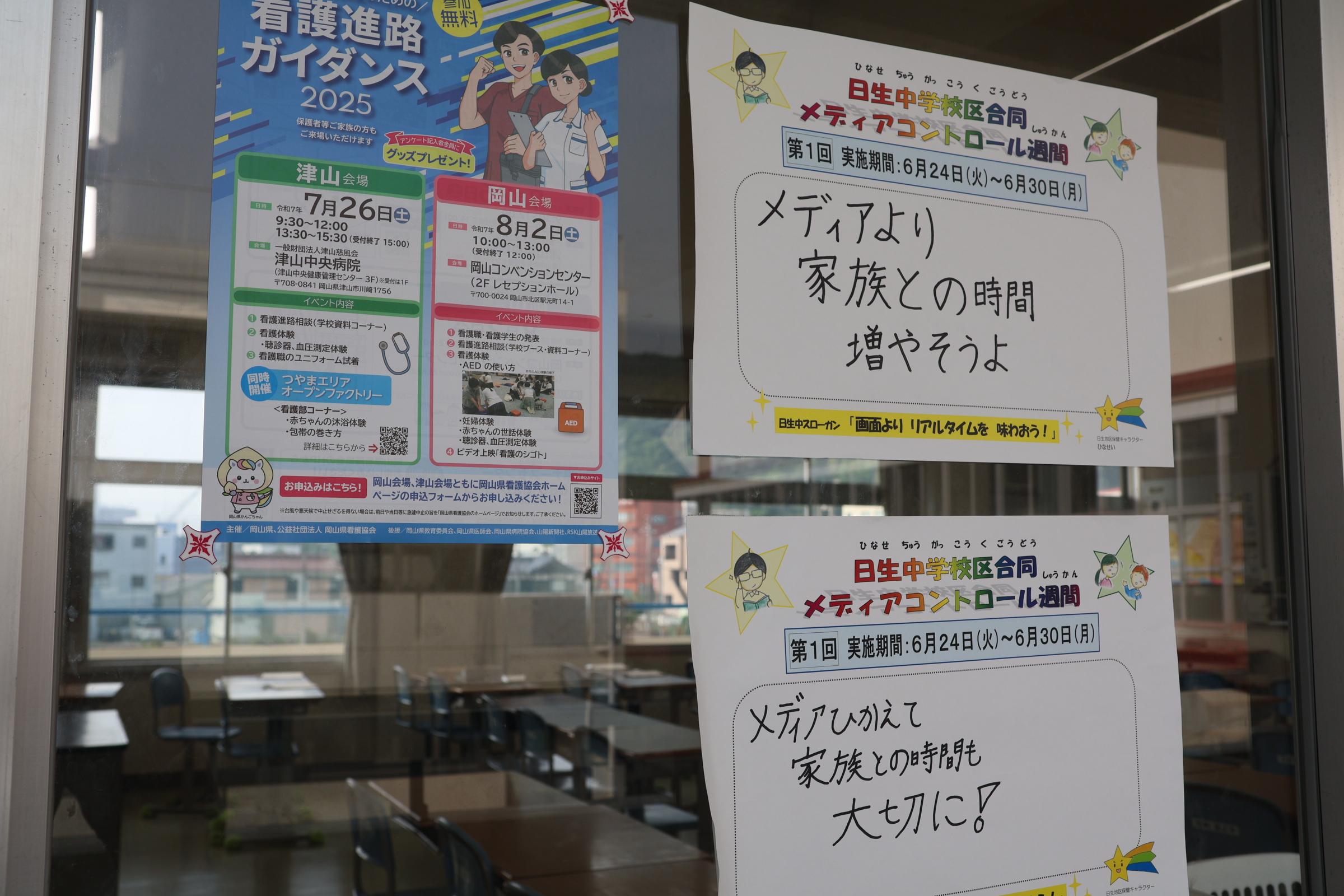



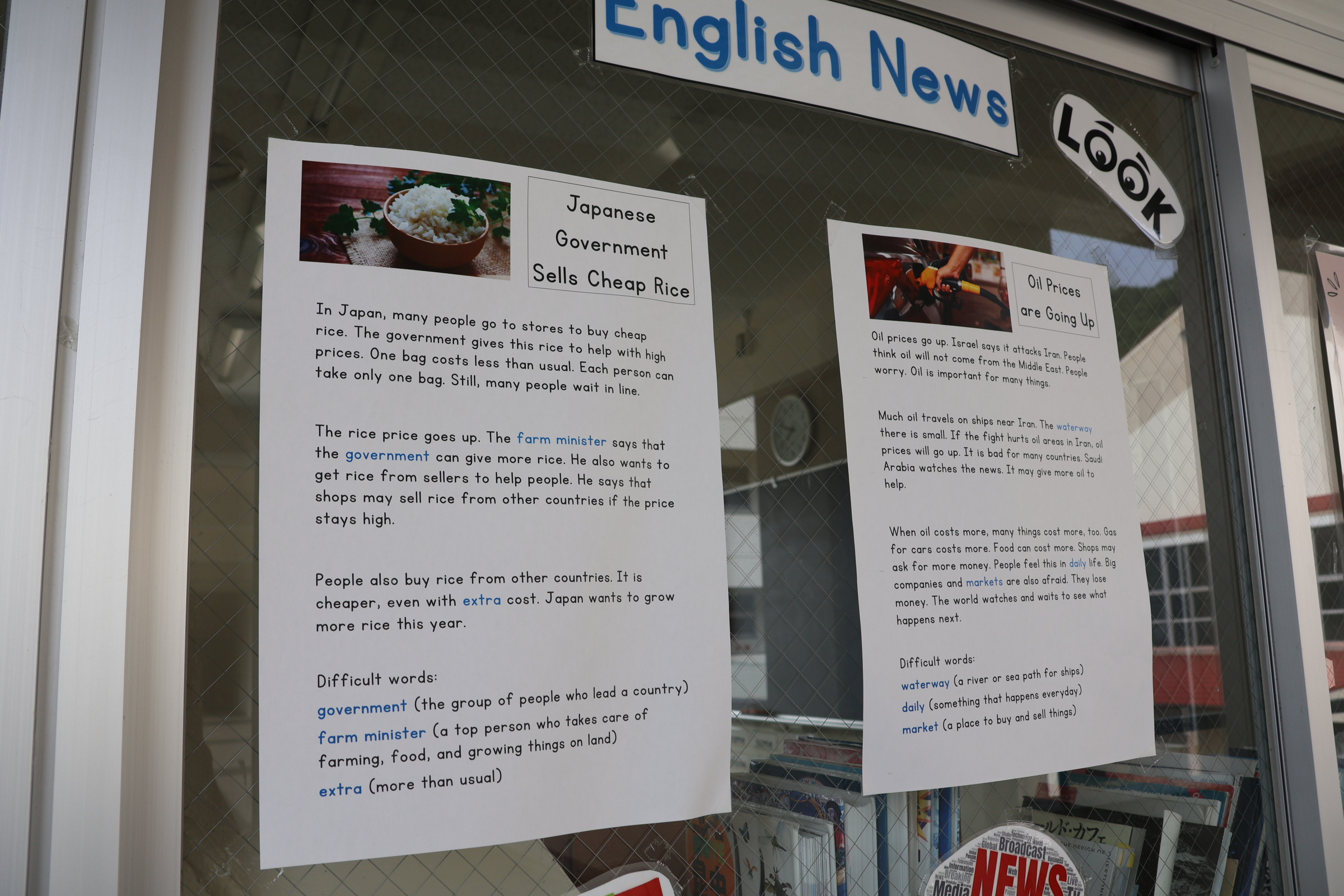
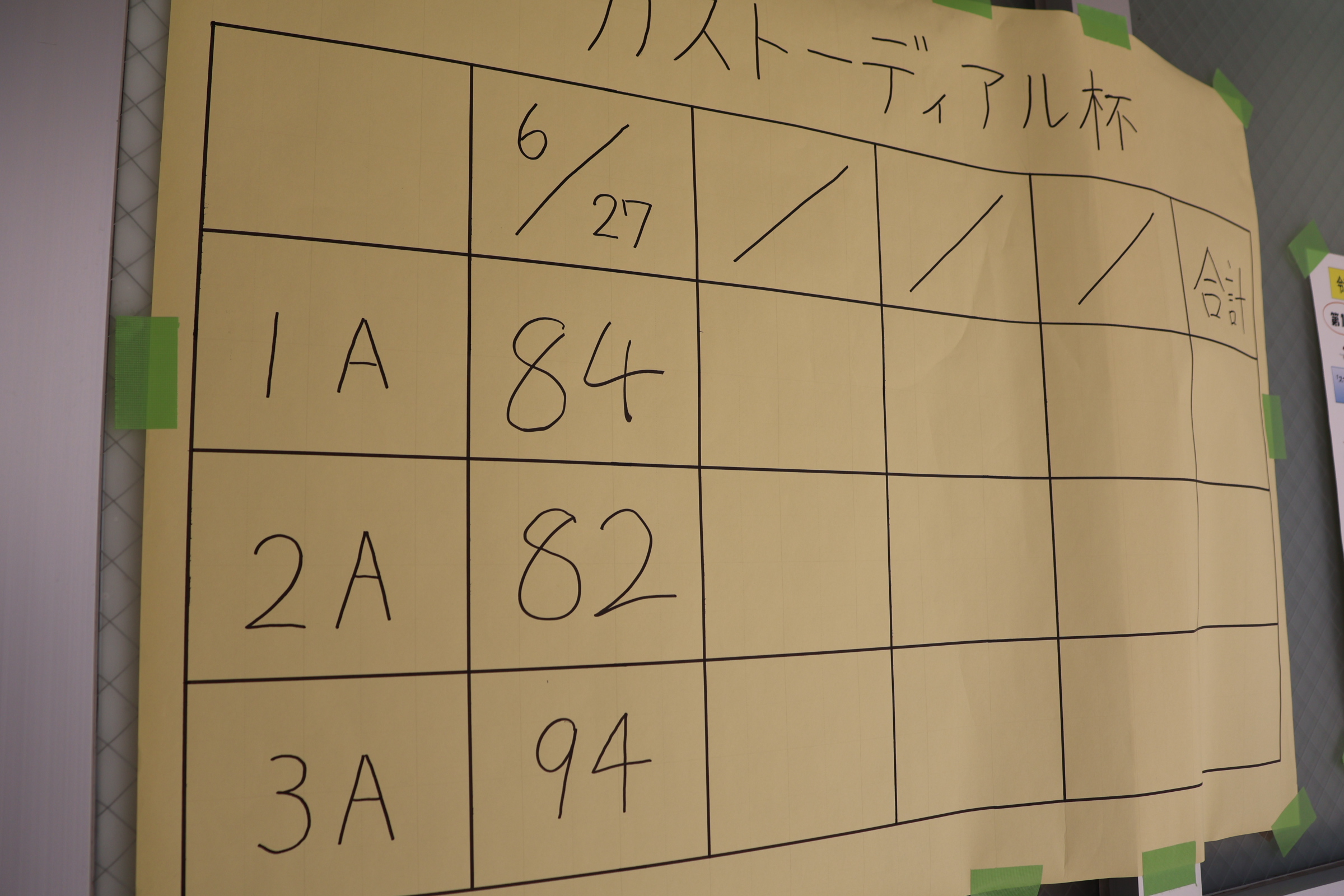
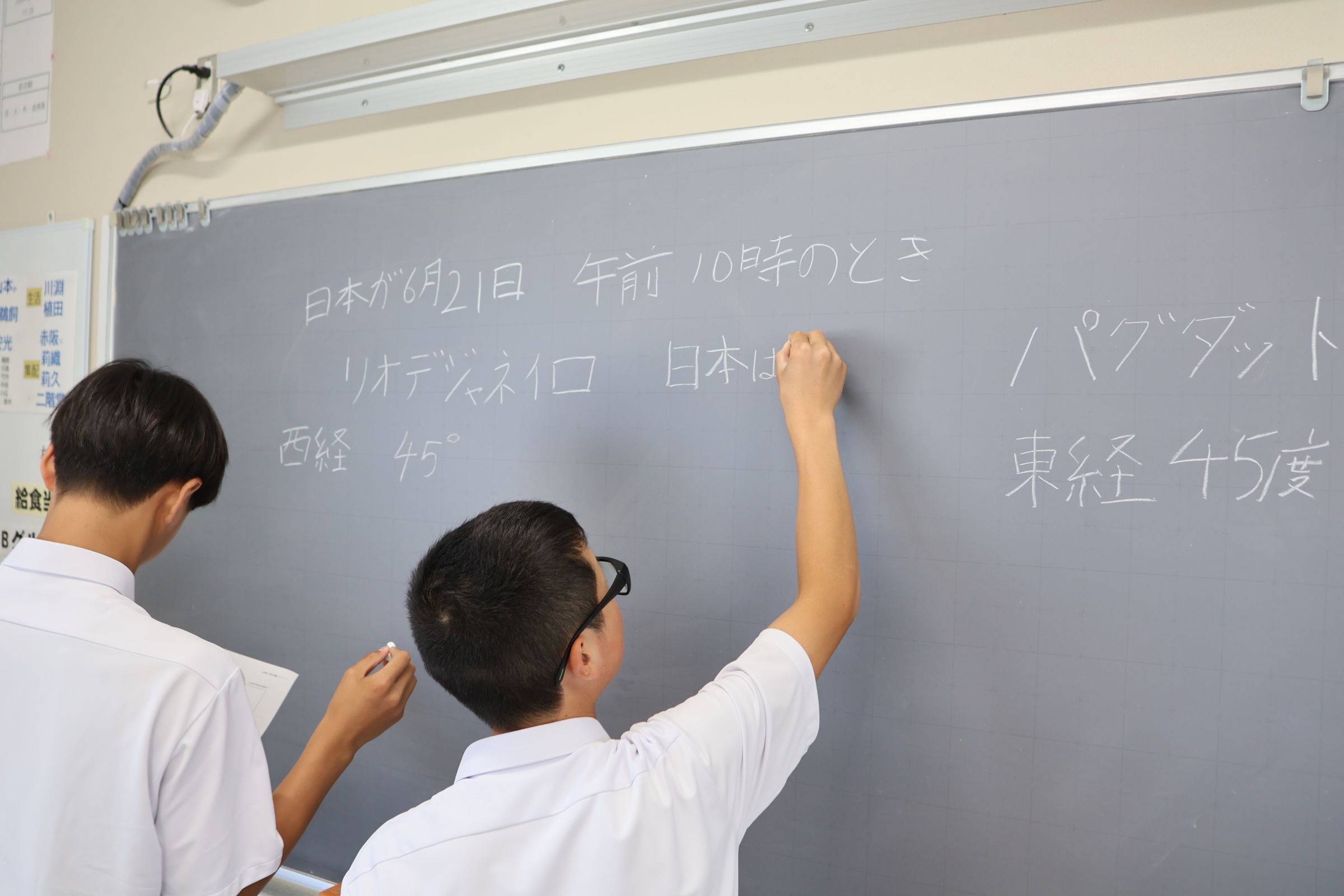
Everyone’s a star and deserves the right to twinkle. Marilyn Monroe
(誰もがスターなのよ。みんな輝く権利を持っている。)
◎確かな「子どもを見る眼」を。
先日の校内研修の講師である土田光子さんの著書を職員用図書に置いています。校長先生ありがとうございます。今日(7 /2)の校内研修では評価・評定について研修します。
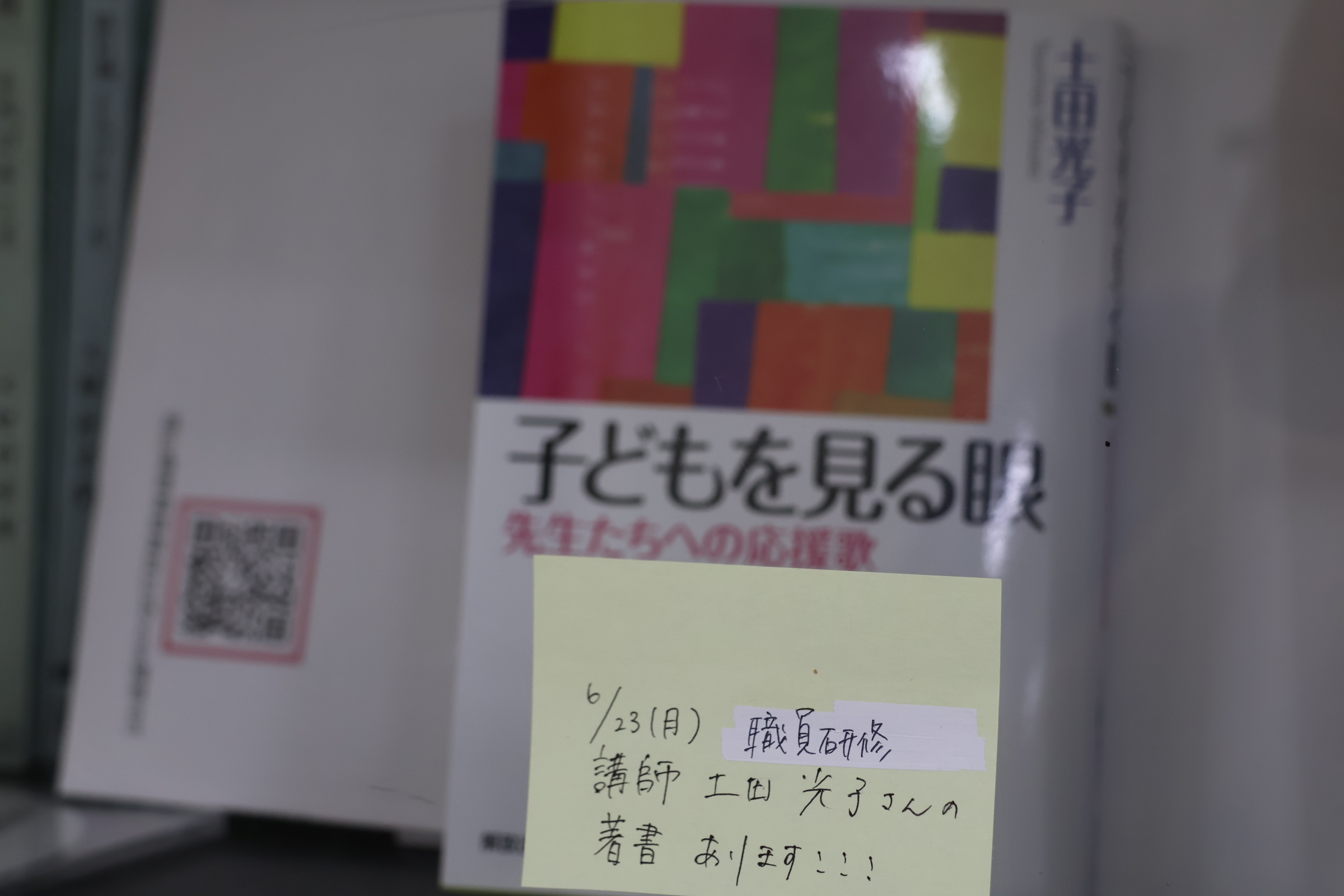
◎多くの人に支えられて(7/1:星に願いを)
立川先生、笹を今年もご準備くださり、ありがとうございました。

◎多くの人に支えられて~自分らしく生きるために(7/1)
備前市人権擁護委員(谷口さん、有吉さん、、杉本さん)が来校され、人権SOSミニレターを配ってくださいました。ありがとうございました。


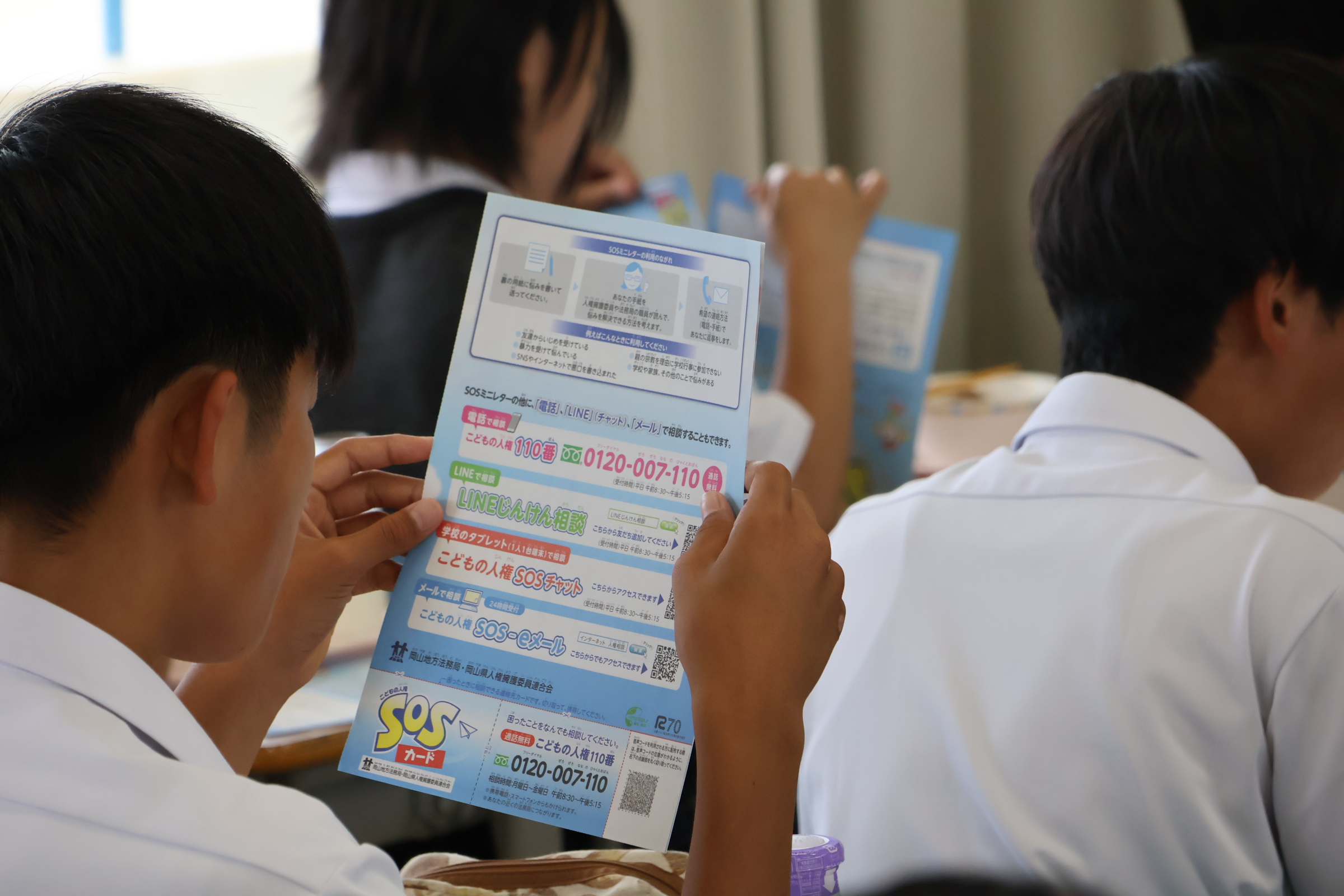
◎DRIFT AWAY Dobie Gray

◎暑いけど がんばってます!

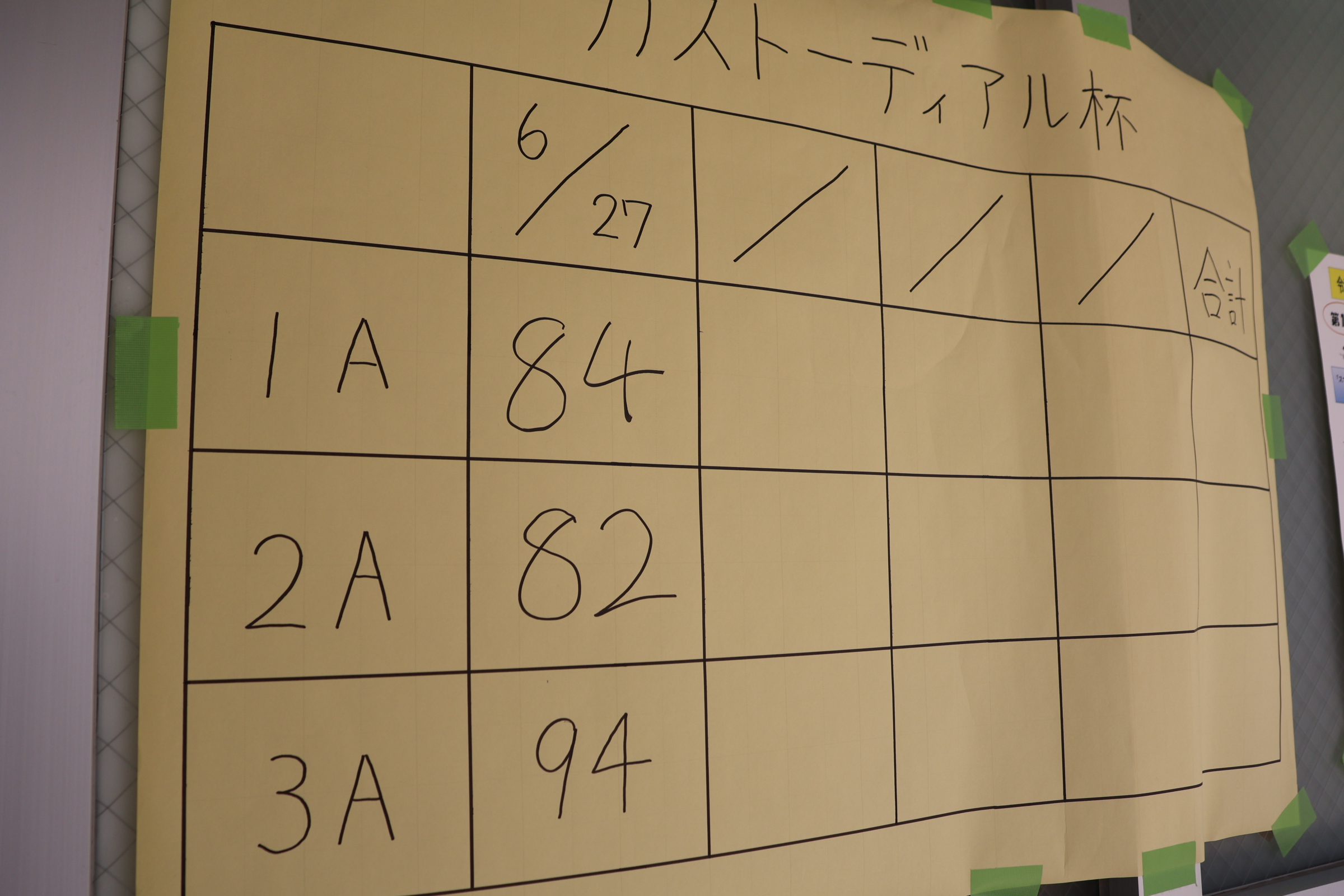


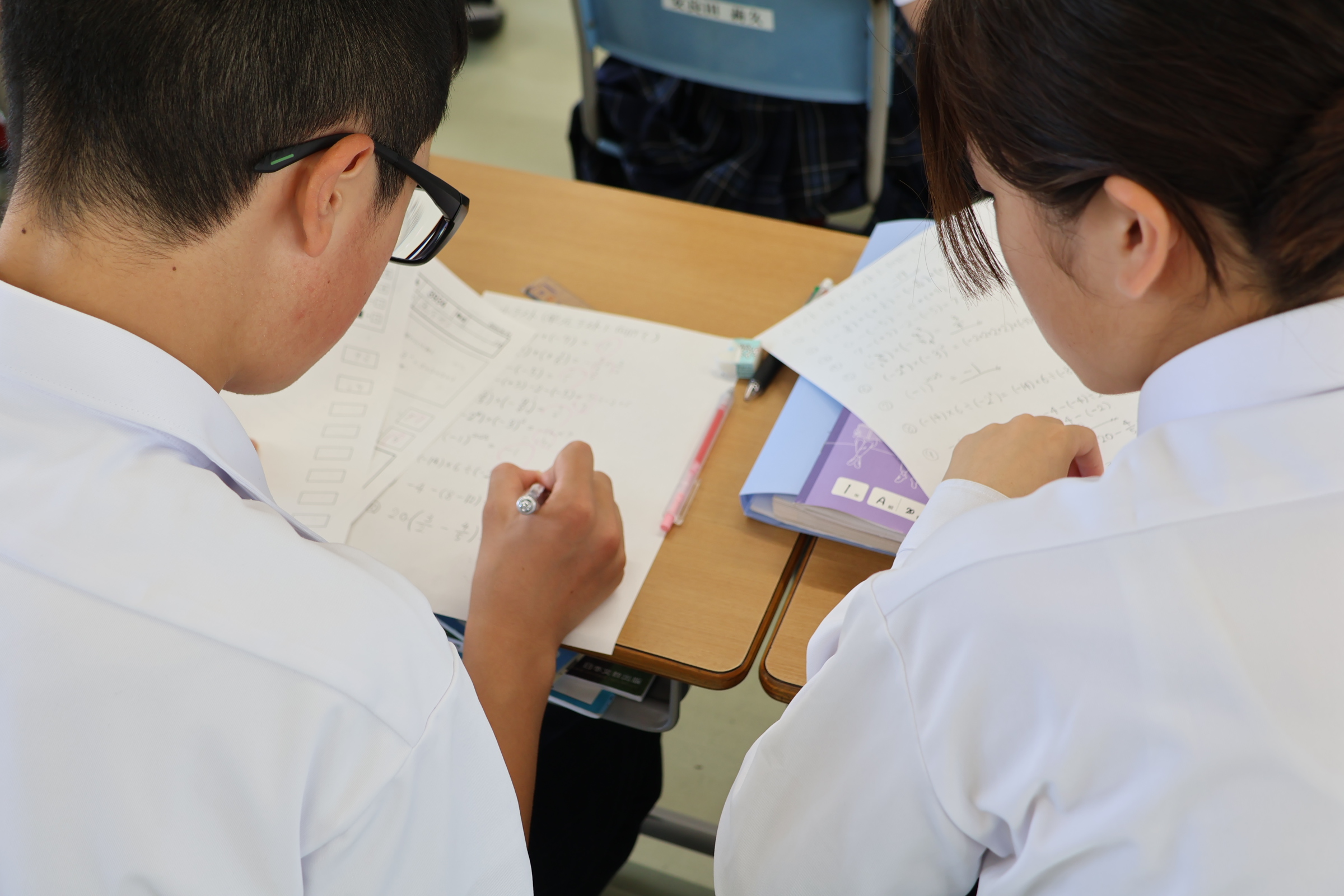

〈えっ、七時なのにこんなに明るいの? うん、と七時が答えれば夏 岡野大嗣〉(7/1)
7月「文月(ふみづき)」という呼び名の由来は、稲穂の「穂」から来ている説と、文字の「文」から来ているという、大きく2つの説が考えられています。旧暦をもとに農業を営んでいた昔の人々にとって、7月は稲穂が育つ時期です。そこで、穂がよく見えるという意味の「穂見(ほみ)」、穂が膨らむ(含む)という意味の「含み(ふみ)」から「穂見月(ほみづき)」、「穂含月(ほふみづき)」と呼ばれるようになりました。そこから、「ふみづき」という言葉に転じたと言われています。また、七夕行事にちなんで短冊に願い事を書いたことから、「文」の字を当てたという説もあります。現代でも、七夕の短冊にいろんな願いを書きますね。(今年も、ほっとスペースにも笹を置きますよ)しかし、もともとは七夕の短冊には、「文章が上手になりますように」「習字が上達しますように」といった、「文」にまつわる願いを書くものでした。そのため、「文披き月(ふみひらきづき)」から転じたというのが定説になっています。しかし一説によると、中国の風習で7月7日に古書の虫干しをしたことから、「文開く月」と呼ばれていたとも言われています。諸説ありますが、文章にまつわる「文」という説が有力のようですね。季節や気候とはあまり関係ないのが、意外でした。7月の別名には他にも、
・七夕月
・棚機月(たなばたつき)
・女郎花月(おみなえしづき)
・蘭月(らんげつ)
・涼月(りょうげつ)というものがあります。風物詩である七夕や、季節の花に関する名前が多いですね。「文月」よりも、上の異名のほうが季節感があって風雅な印象を受けます。ちなみに「涼月」とは、暑くなっていくにつれて風が吹くと涼しく感じることからこう呼ばれるそうです。古くは漢詩にも登場する表現です。今年の夏も猛暑の予想ですが、「涼月」の名にならって、風鈴の音や打ち水など、日常の中の「涼」を探してみてもいいかもしれませんね。

◎ひな中のちから〈ボランティア推進プロジェクト 依頼続々〉
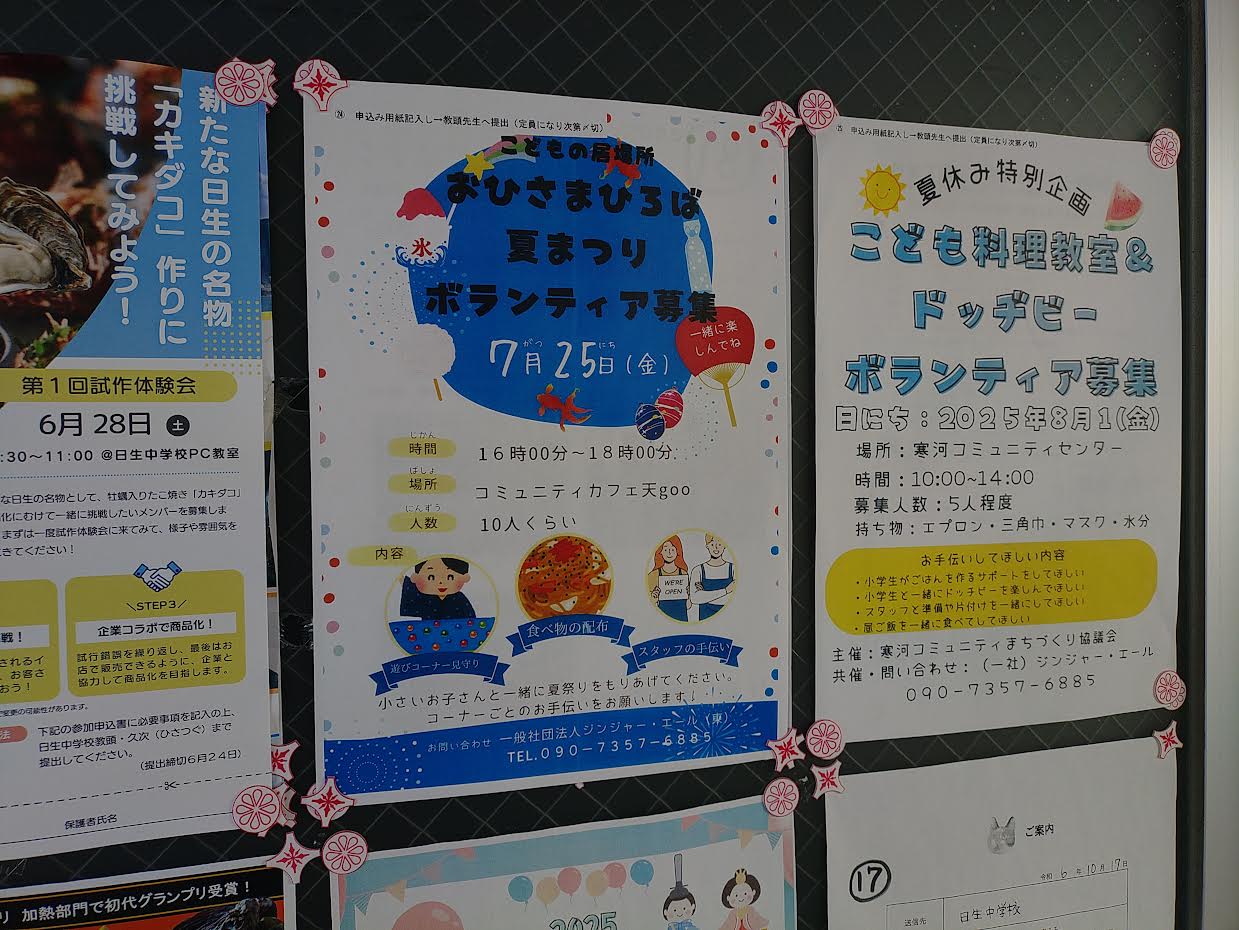
◎ひな中のちから(28日:PTA資源物回収)









多くのご支援・ご協力をありがとうございました。奥橋さん、今年も助かりました。ありがとうございました。
◎HINASE REGACY
カストーディアル杯から(27 ~)
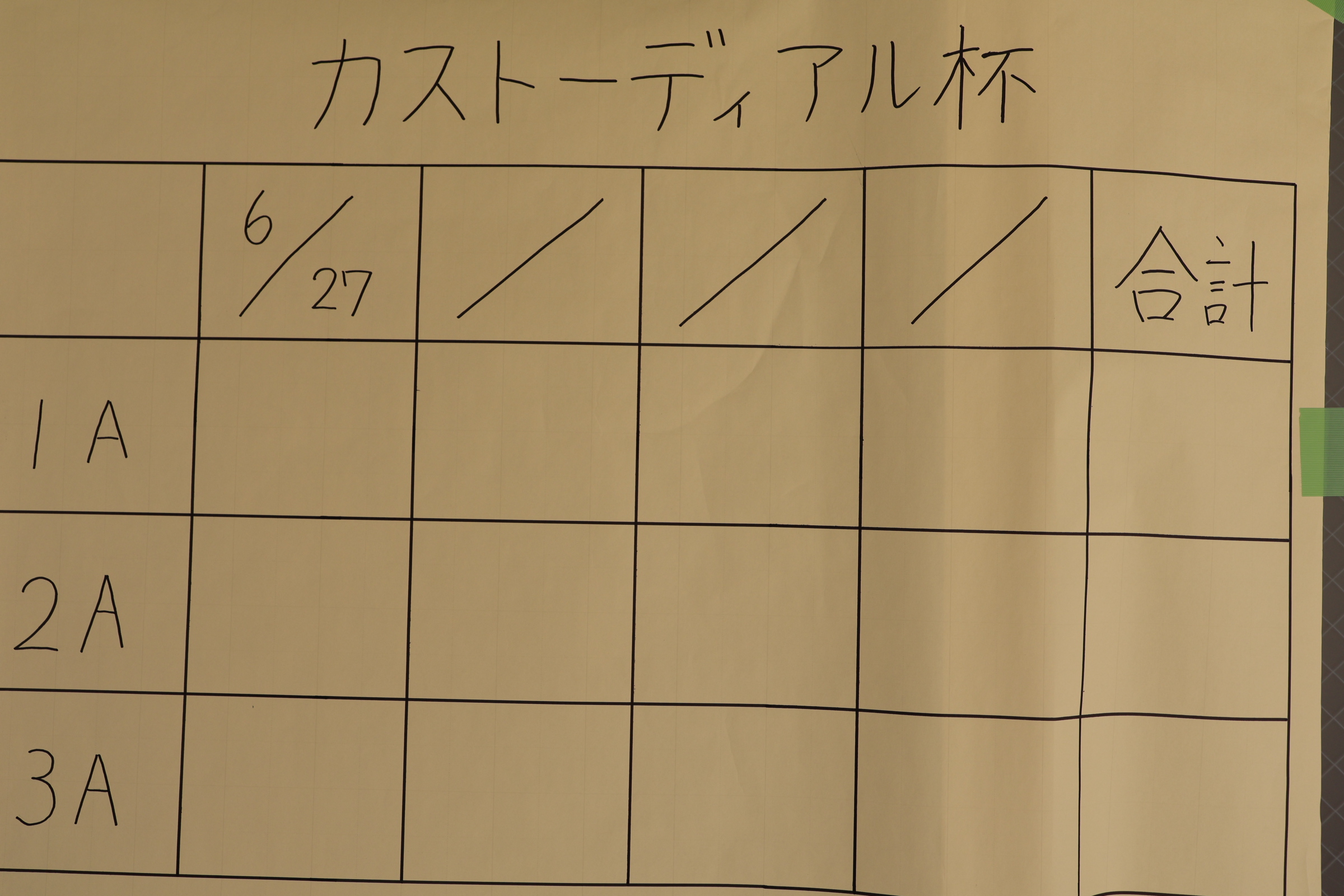


◎向き合う ~全校集会を受けて~(6/26:生徒朝礼)



ショートストーリー劇で、生徒会からみんなで。
7月の生活目標は「レインボーブリッジの3番 他のひとの良いところをみつけることができる」
◎今度は食べたらいけん、鹿さん。(6/25:環境委員会)



◎経験と知恵を学ぶために~海洋学習「聞き書き」活動へ(6/25)
2年生は7月3日に、漁協、観光協会、NPO里海づくり研究協議会、神戸税関さんら(予定)をエリアティチャーにお迎えして、「聞き書き」活動に取り組みます。
ちなみに「聞き書き」とは・・・話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法です。話し手の言葉をそのまま記録し、語り手が目の前で話しているかのように文章にまとめる手法が一般的で、 この方法は、民俗学の研究や地域づくり、福祉の現場などで広く活用されています。聞き書きは、対話を通じて話し手の人生や価値観を引き出し、その人の経験や知恵を記録することを目的としています。今日、25日(水)は、「聞き書き」甲子園を主宰されている、共存の森ネットワークの吉野さんからお話を聴き、7月3日に向けての事前学習・準備を進めました。




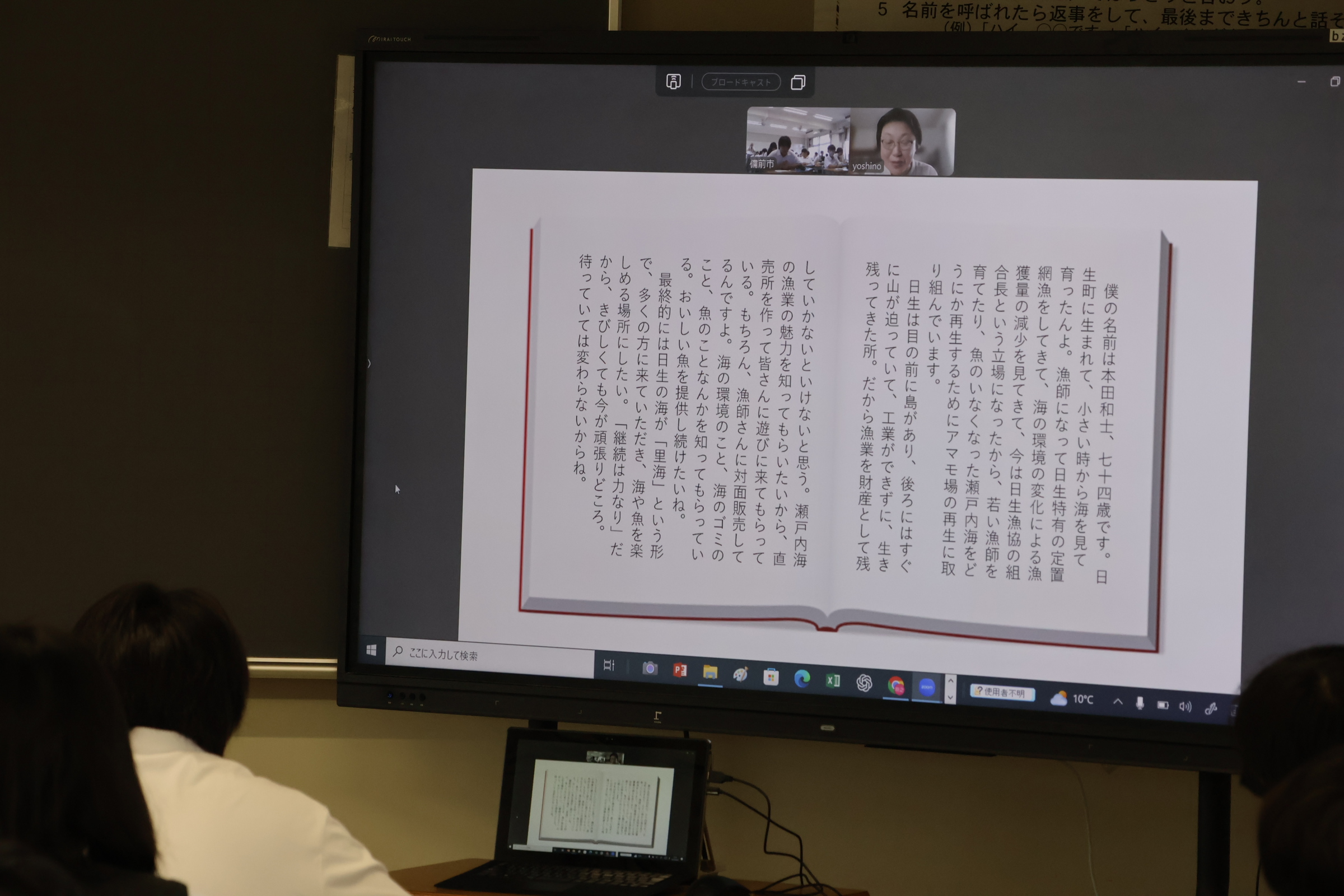
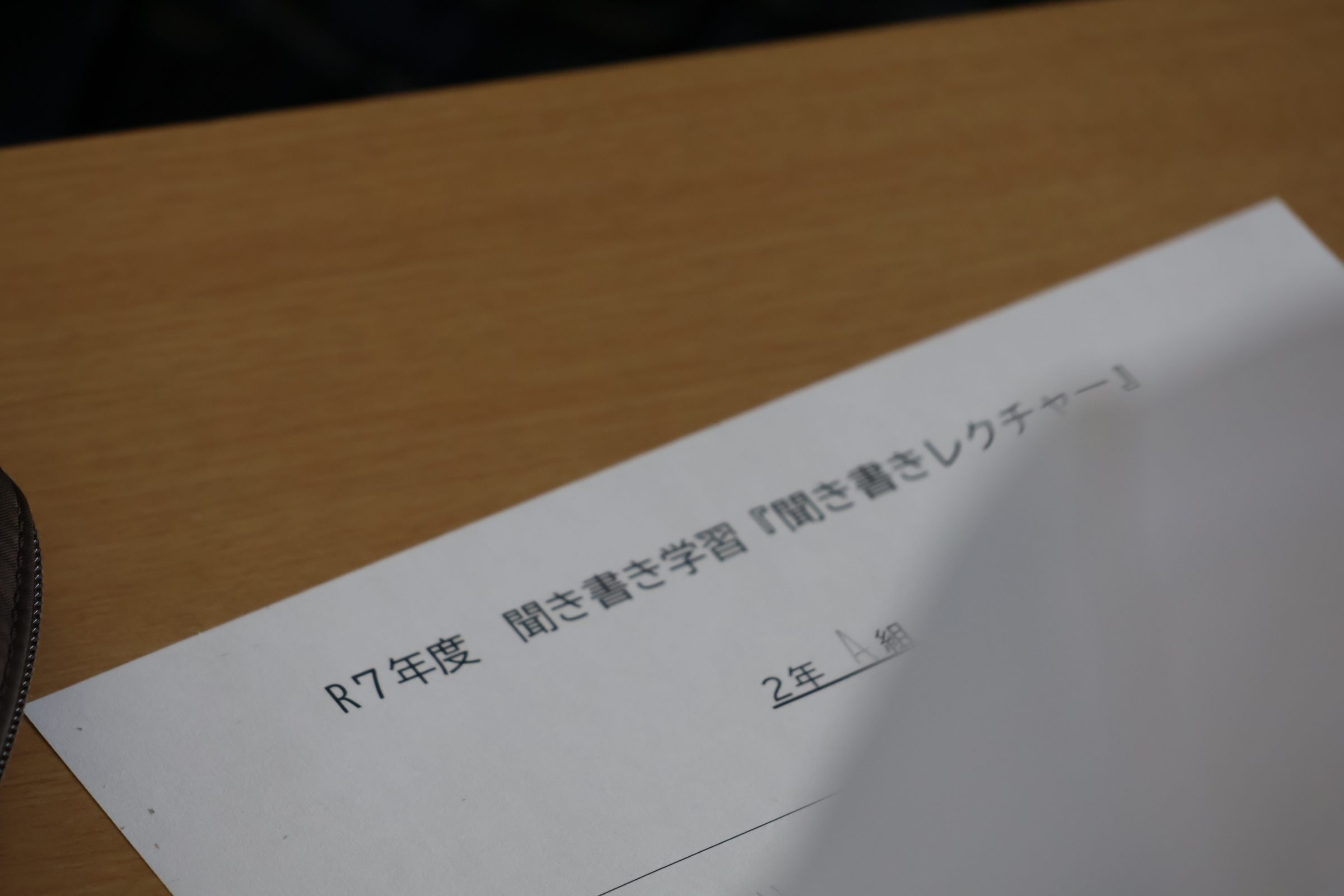
◎毎日が大切(6/25:岡山県教委AP訪問)
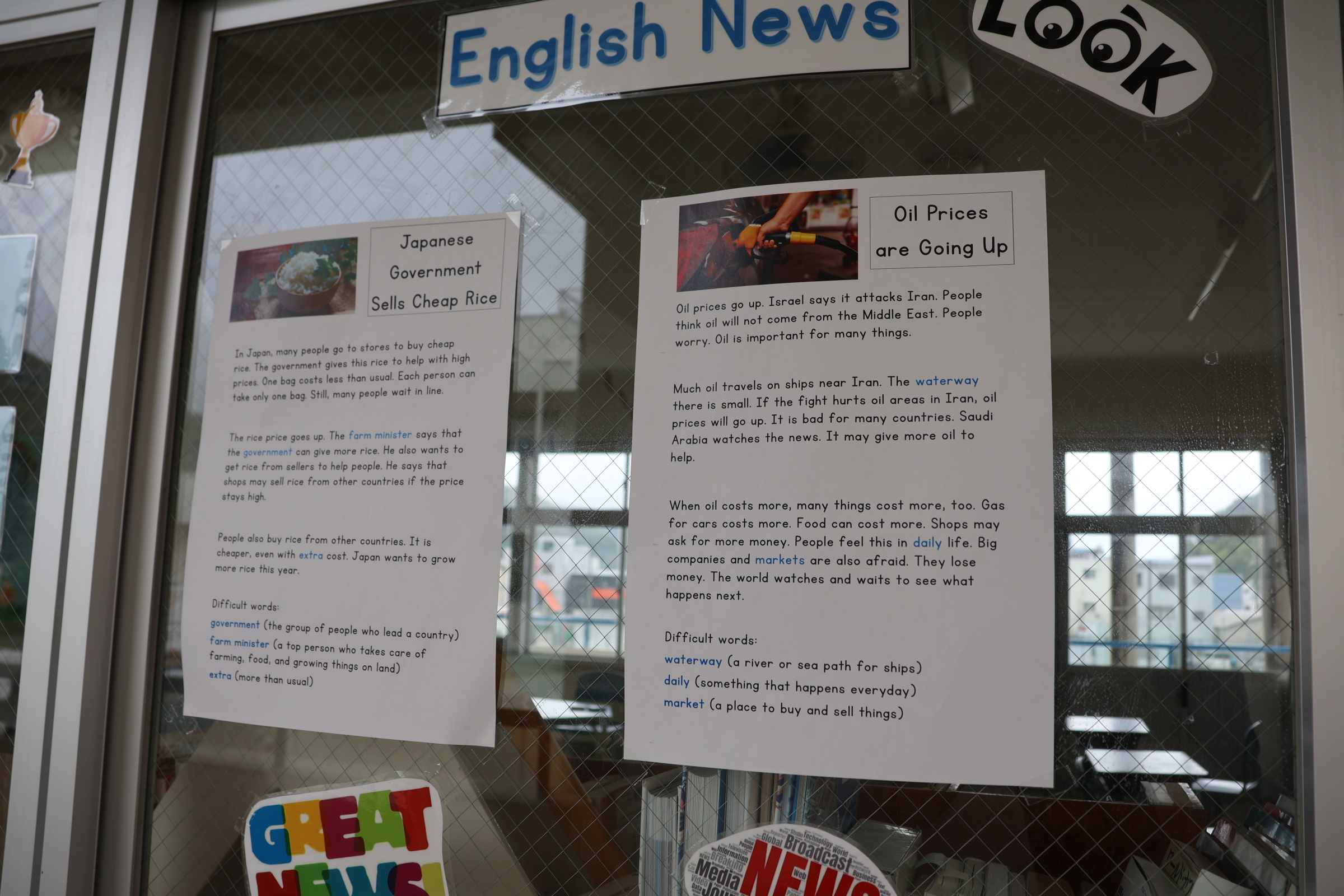

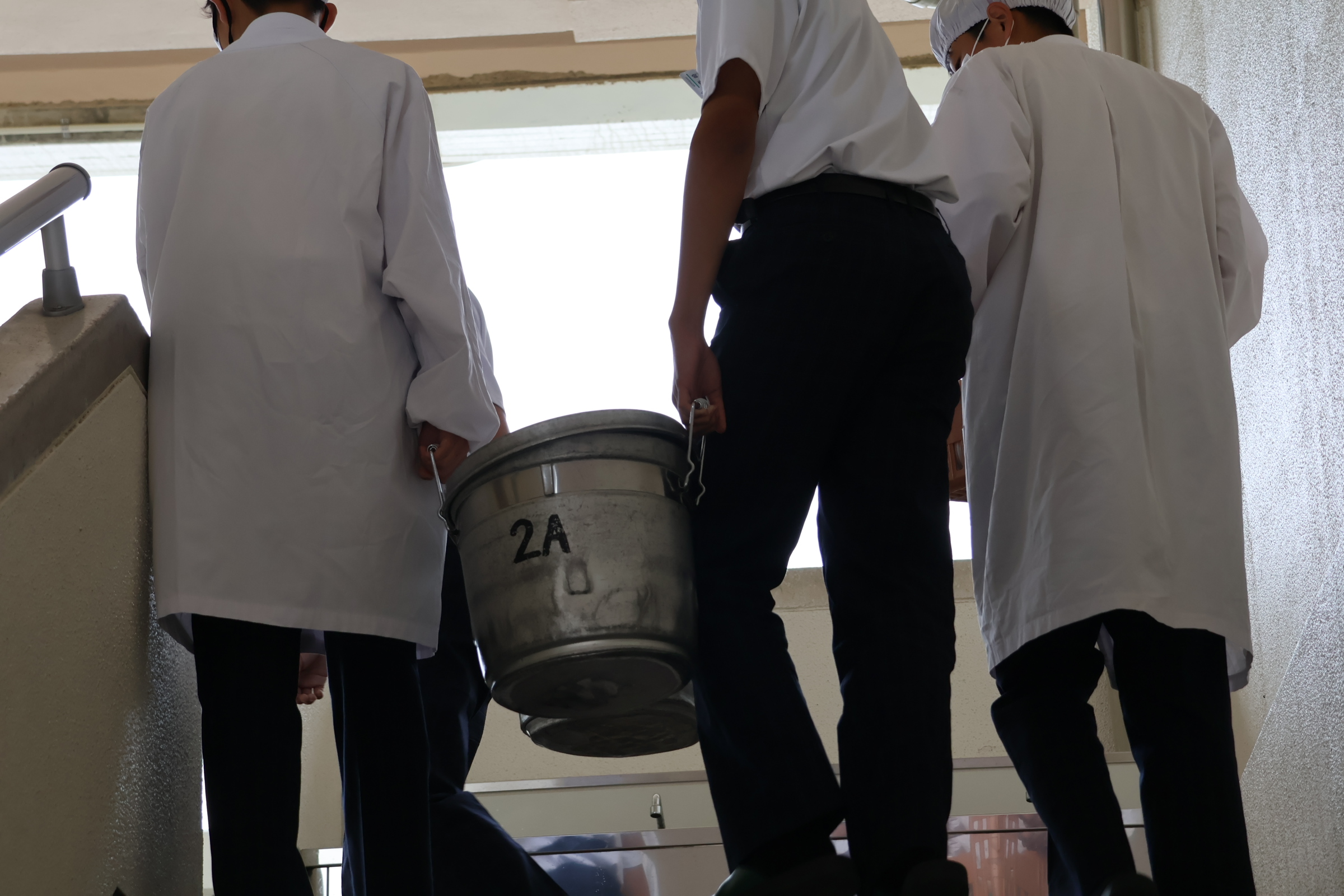

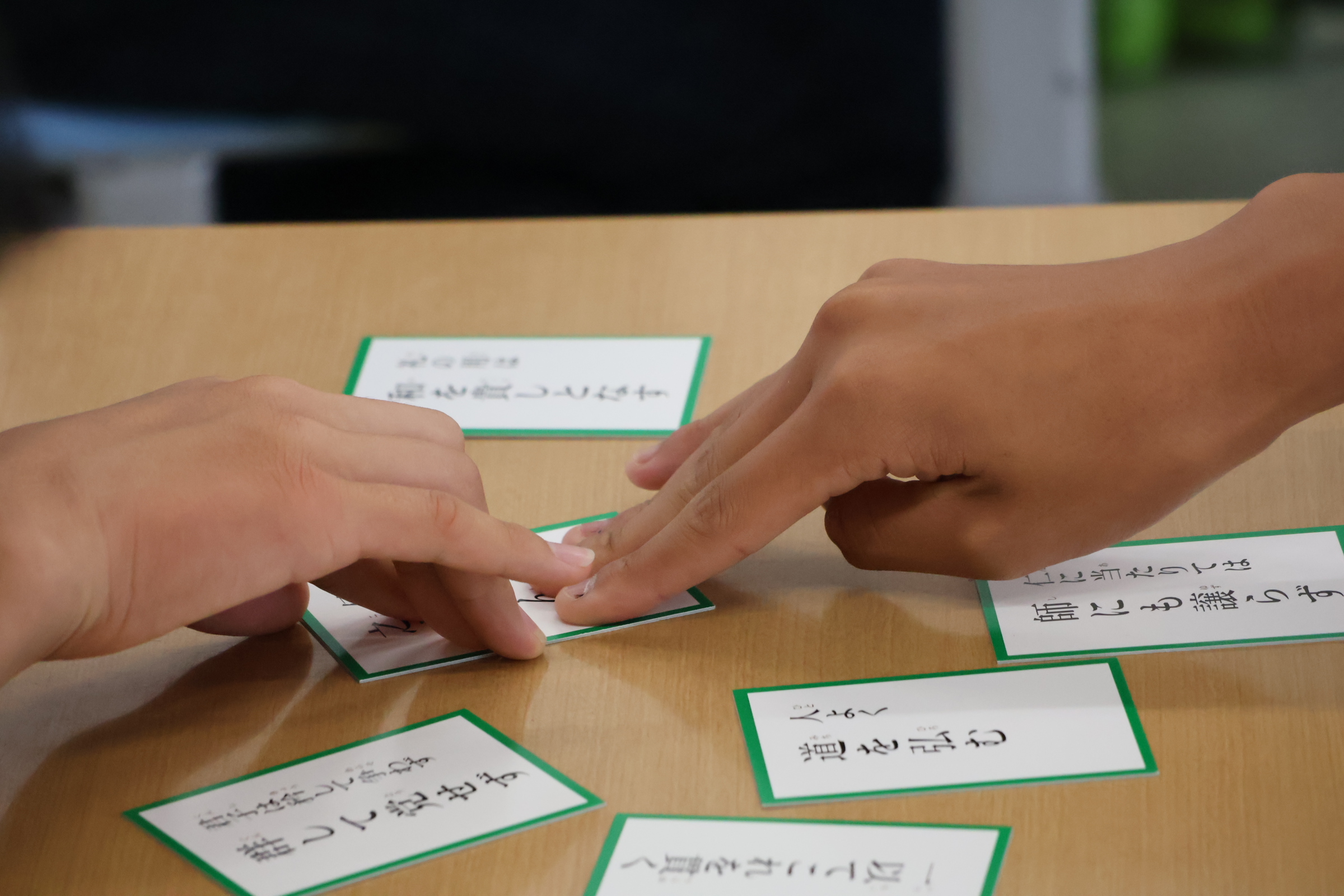
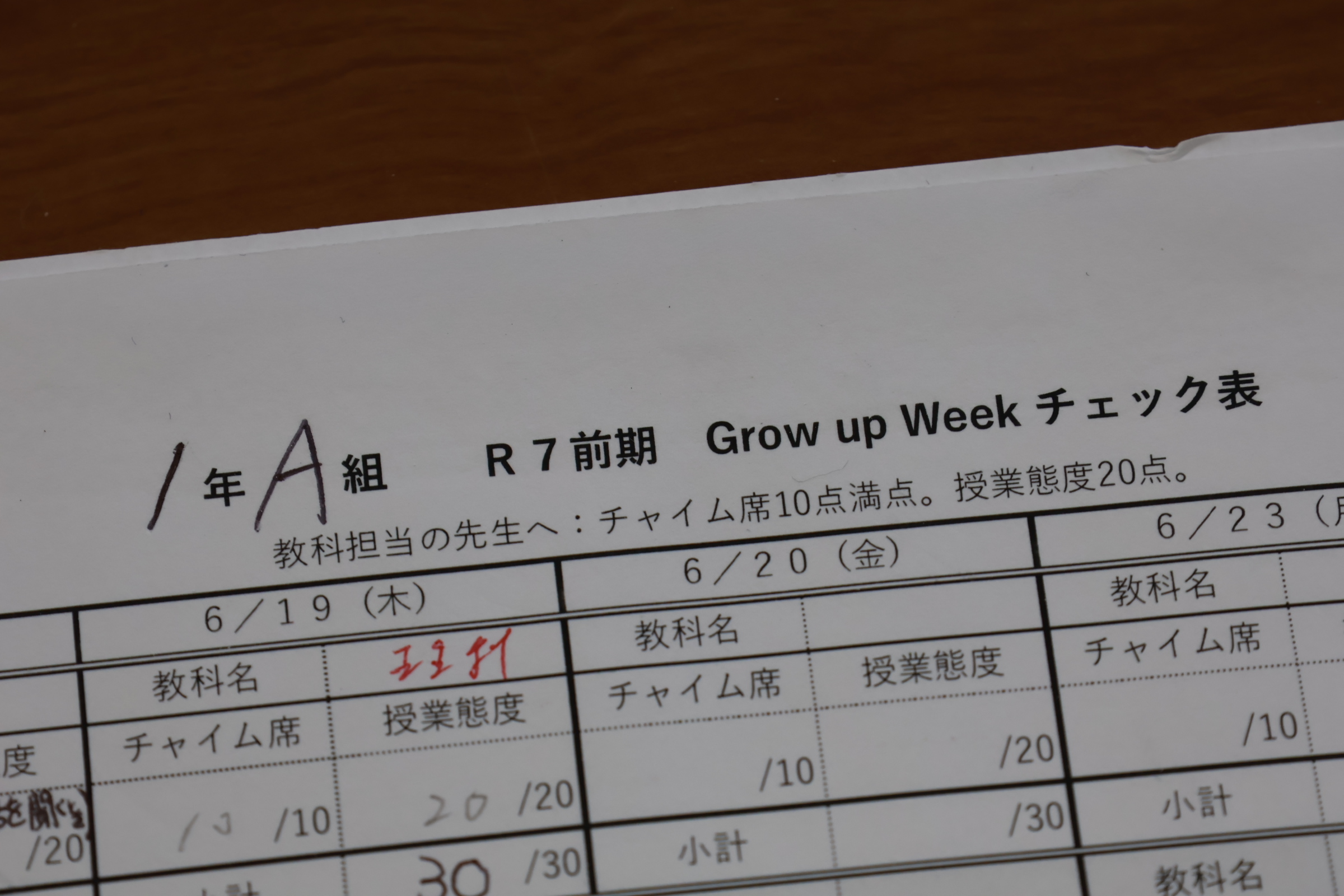
今日は、第1回AP(アクションプラン)訪問があり、岡山県教育庁・備前市教育委員会より合わせて5名の先生方が来られました。本校の重点取組についての説明、また、授業を参観していただき、課題等を共有した上で多面的な協議を行いました。共有実践事項を大事にして、1学期も後半、本日の学びを機に目指すところや修正点を確認しながら毎日の教育活動をさらに大切にしていきたいと思います。
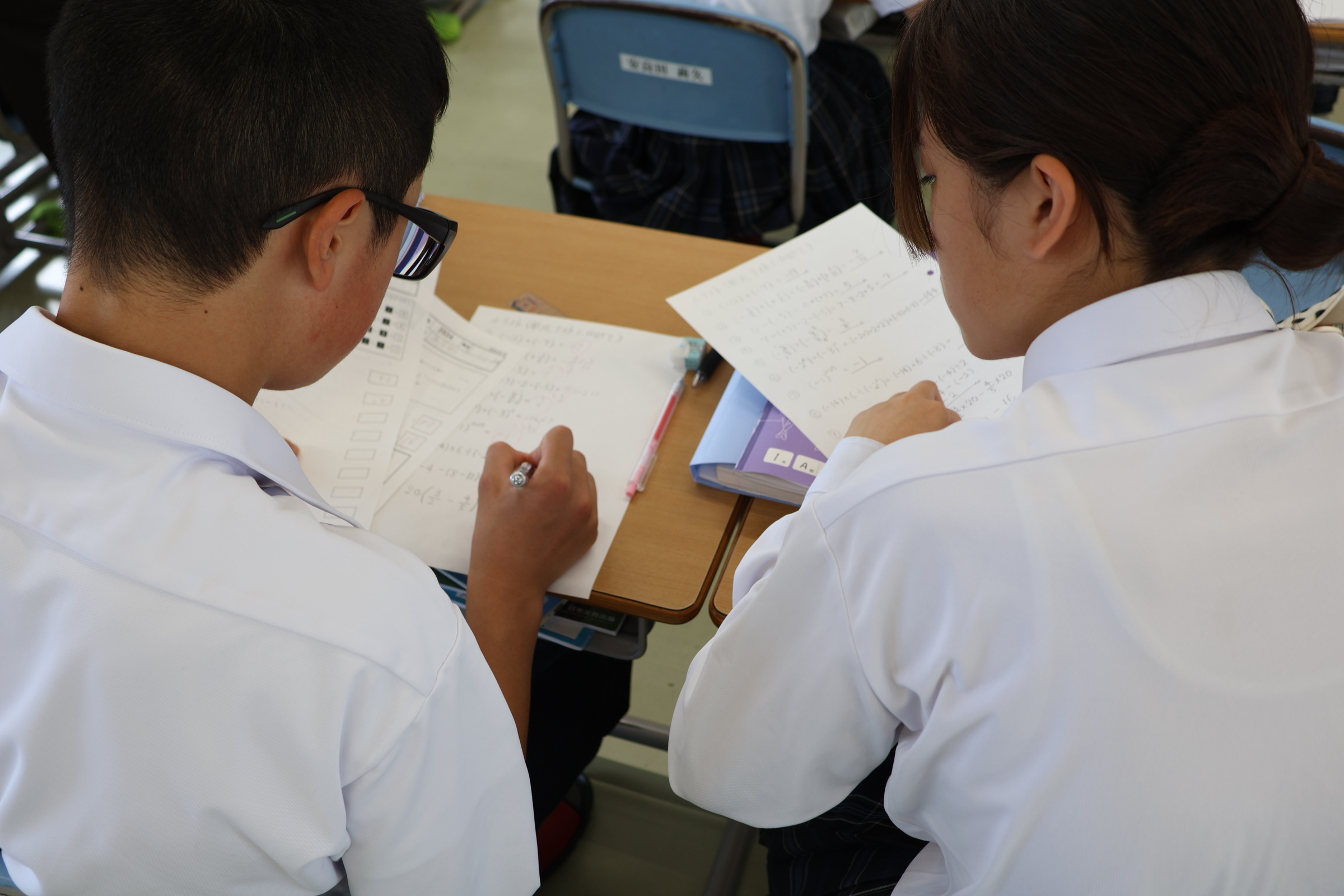


◎夏ボラ申込は今日25日(水)校内締め切り!

◎そうだよ、メディアはコントロールするのよ(6/24)
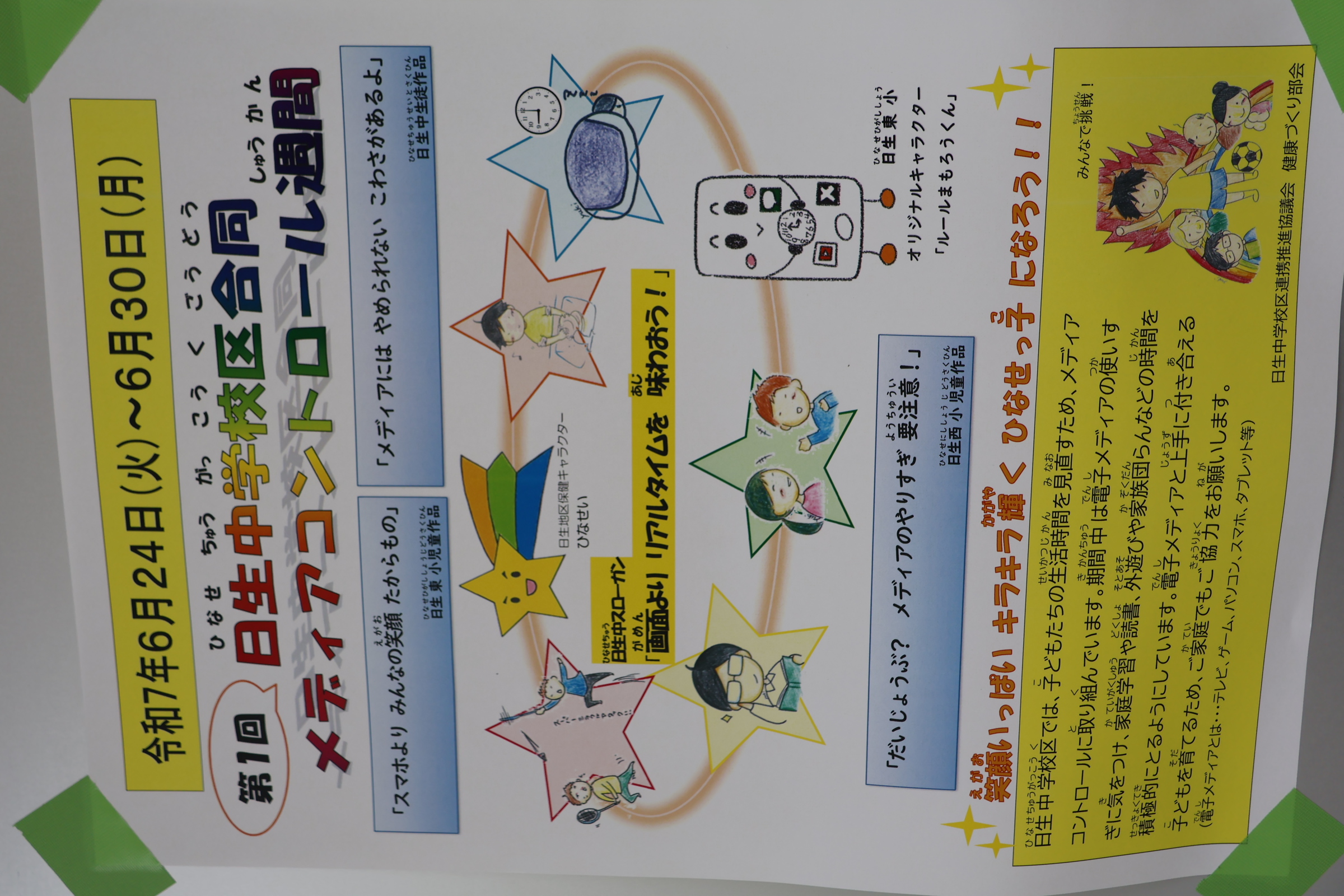
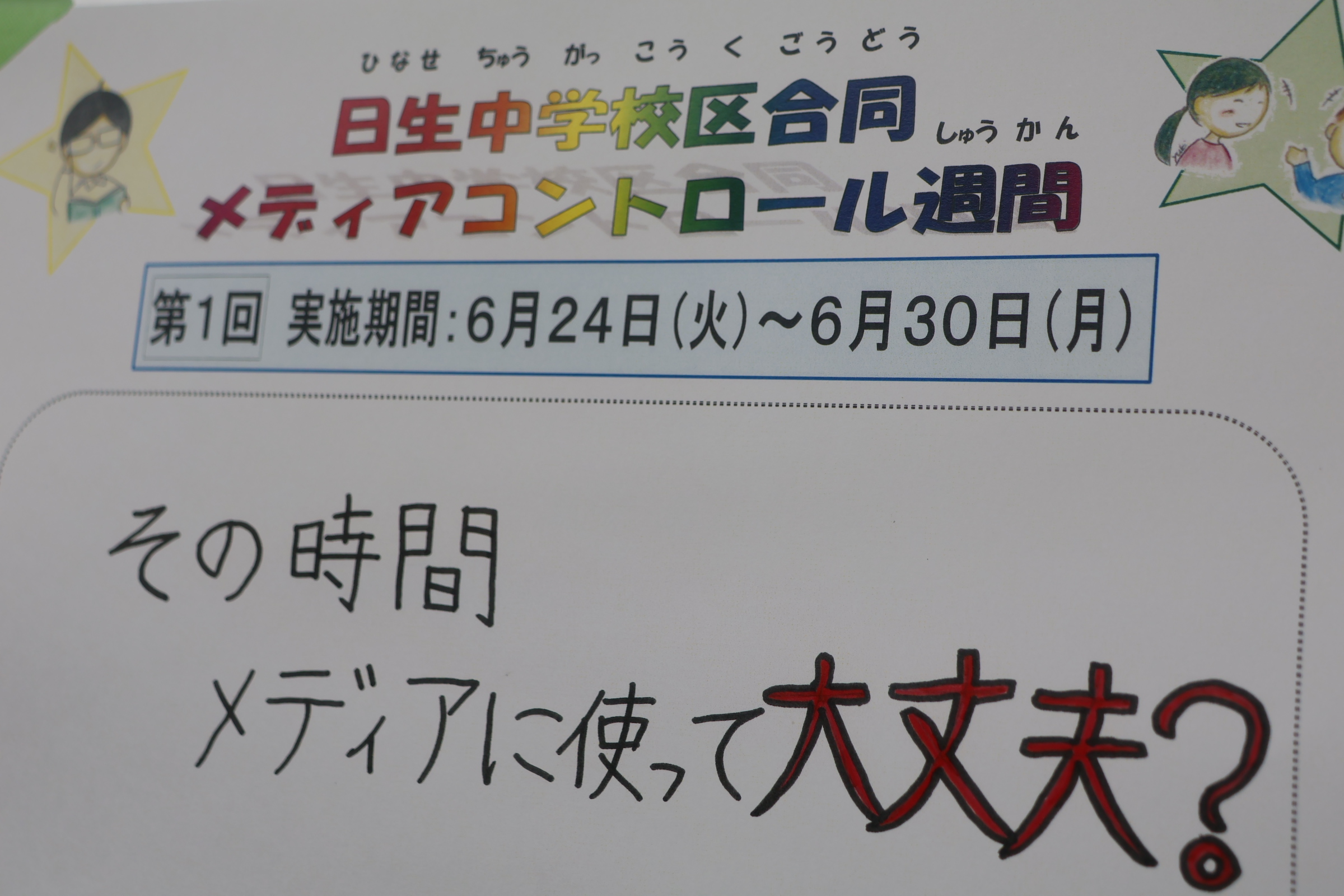
◎6.24一人ひとりが考える全校集会
生活を大切にすること。自分を大切にすること。仲間を大切にすること。



◎みんなが幸せになる人権学習 (6/23:校内研修)
土田光子さん(大阪多様性教育ネットワーク)をお招きして、研修会を開催しました。本校だけでなく、和気、瀬戸内、赤磐から来られた方々と共に、「みんなが幸せになる人権学習~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~」をテーマに、教職員としての学びを深める〈熱い90分〉でした。


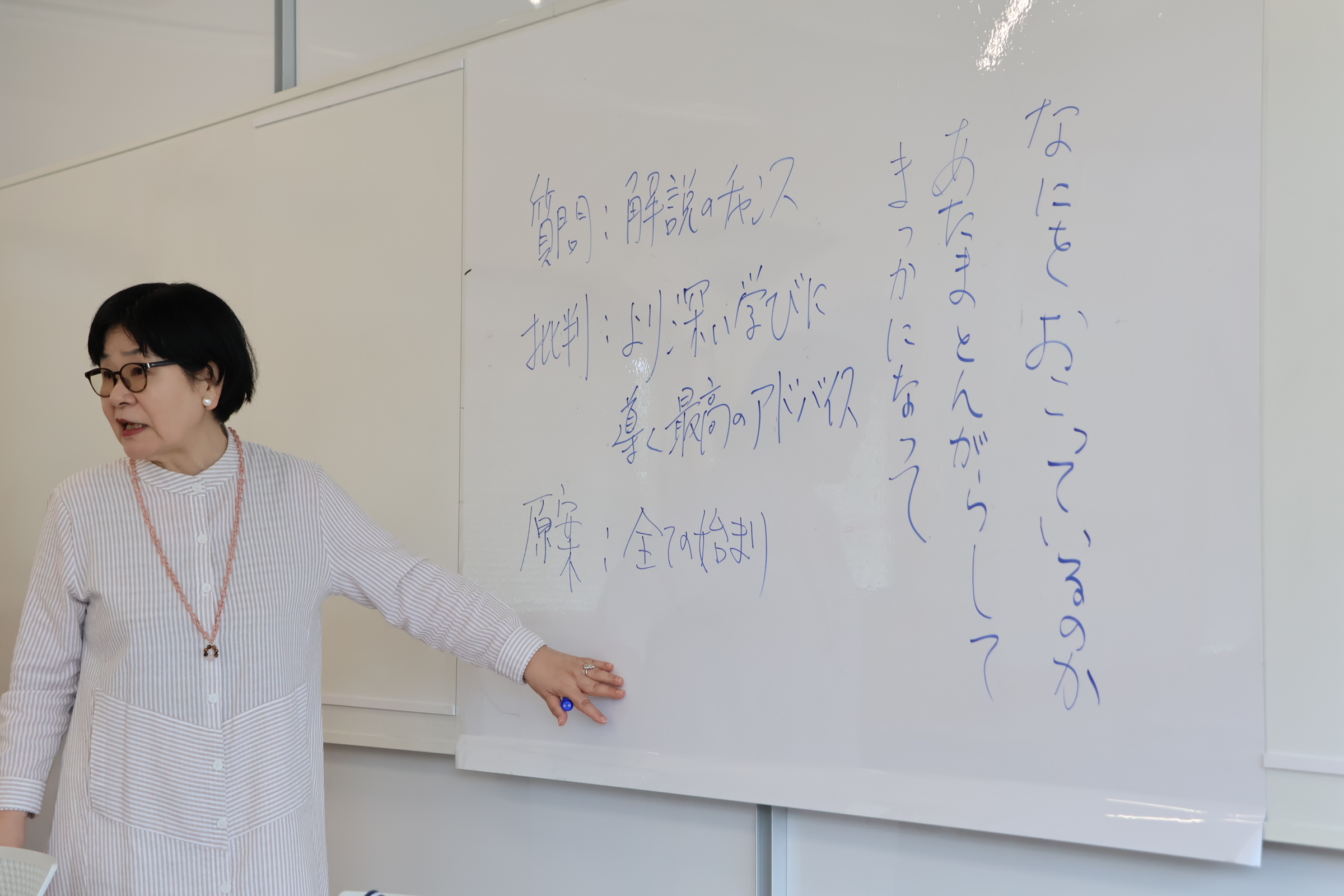
◎ヒロシマ・オキナワから、オカヤマで
2年生は広島研修、3年生は沖縄修学旅行で、反戦・平和学習に取り組んできました。今日6月23日は、沖縄では、組織的な戦闘が終わったといわれる慰霊の日です。また、6月29日は岡山大空襲があった日です。山陽新聞(6/23)の記事について「ひとのあいだ」で生徒に紹介をしています。戦後80年という節目の年です。子どもたちと共に読んでいただけると幸いです。
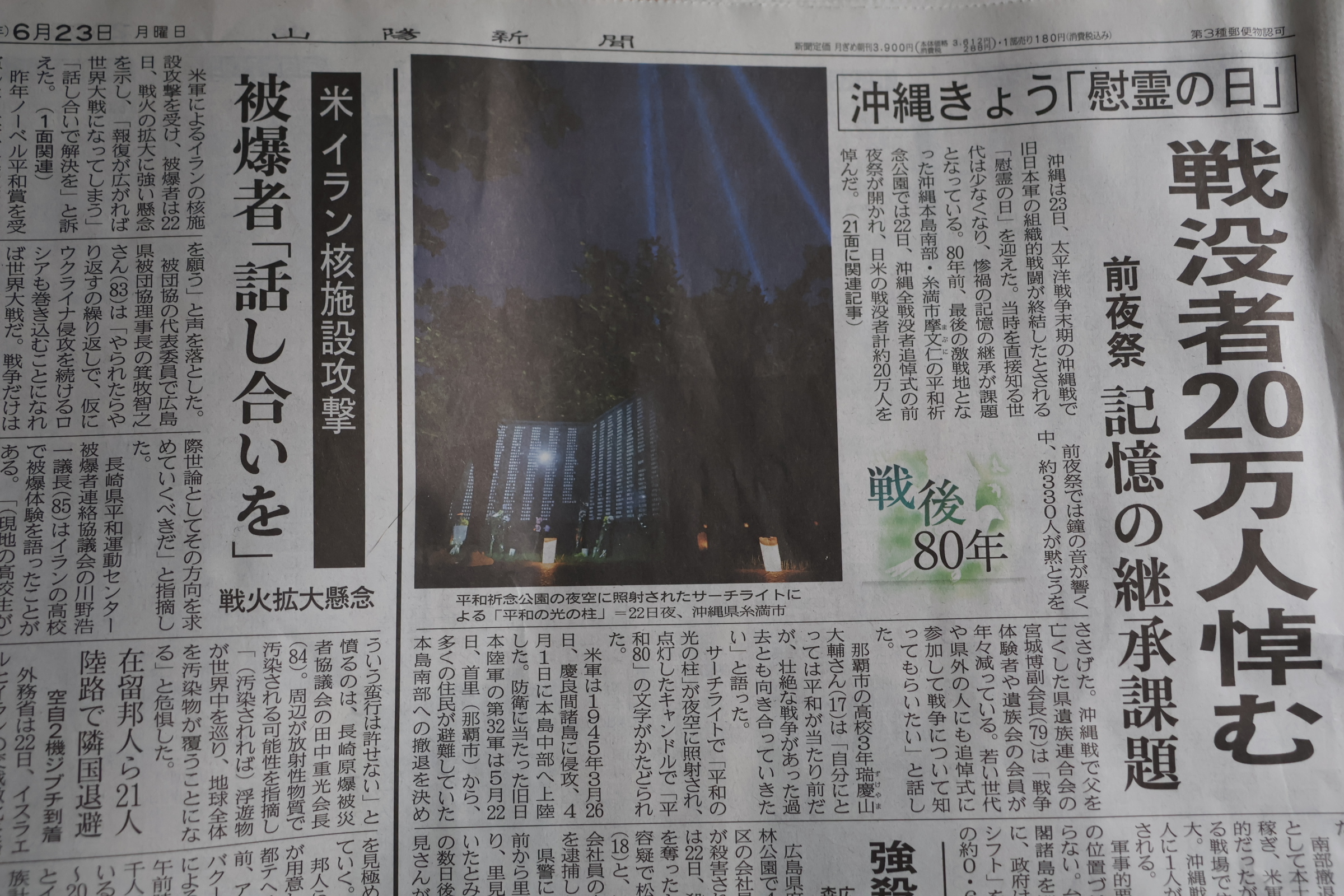
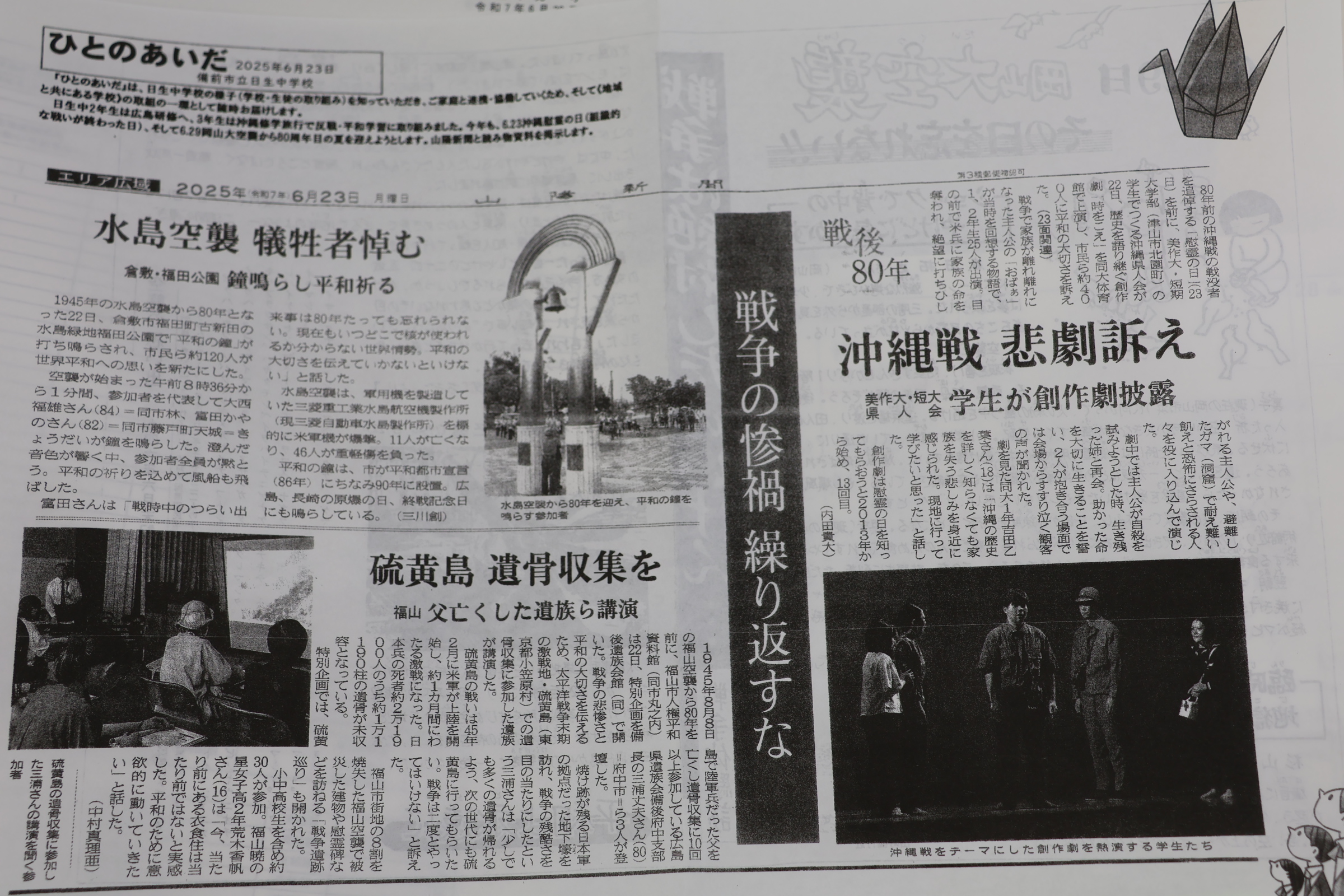
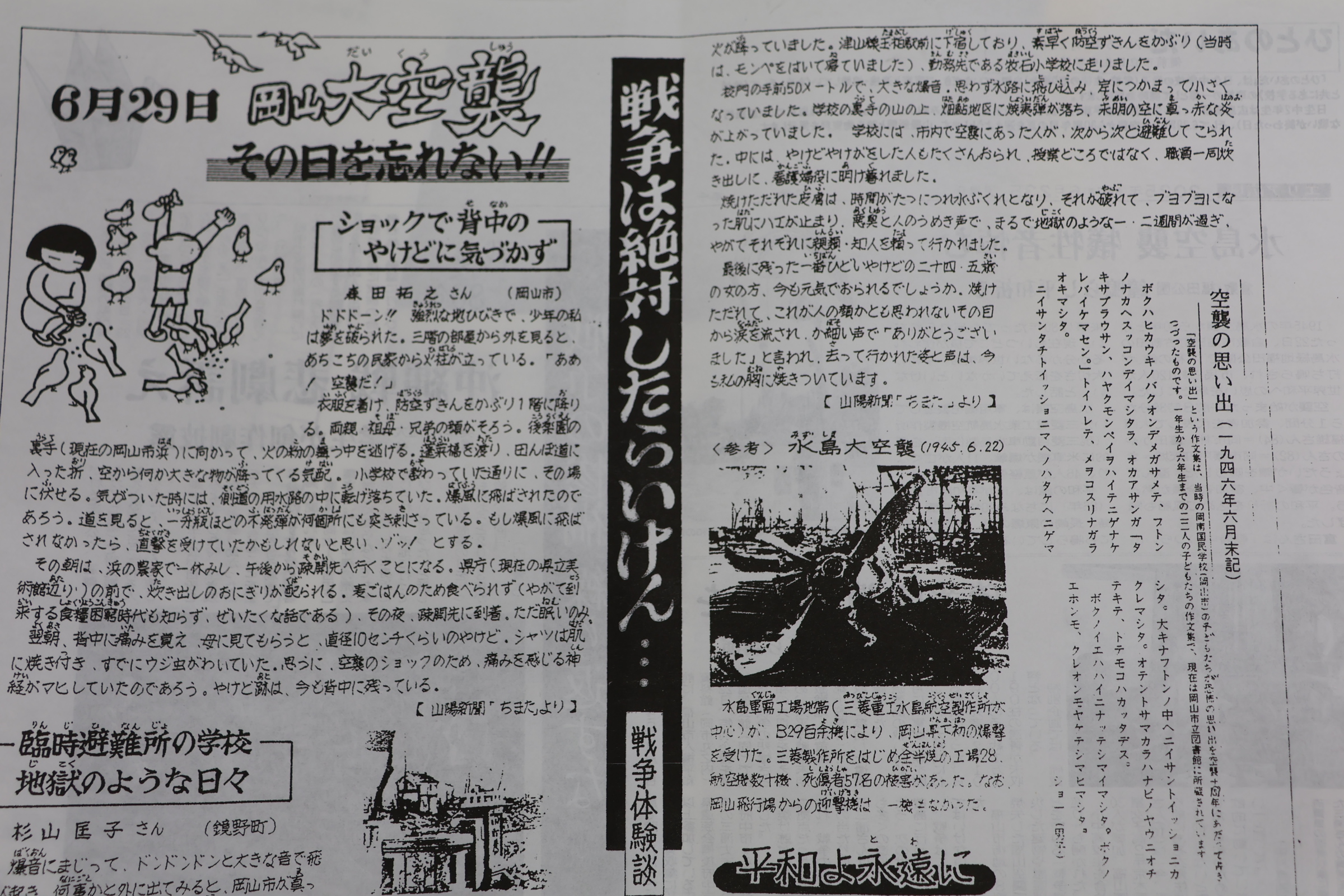
◎こ小中の確かな連携を進めています(6/20)
こども園での人権講演会に参加しました。「親子を幸せをするわらべうた~心の安全基地~」として、梶谷恵子さん(どんぐり文庫)のわらべうた遊びを楽しみました。また、ひなせ親の会(次回は7/5)の紹介をしました。
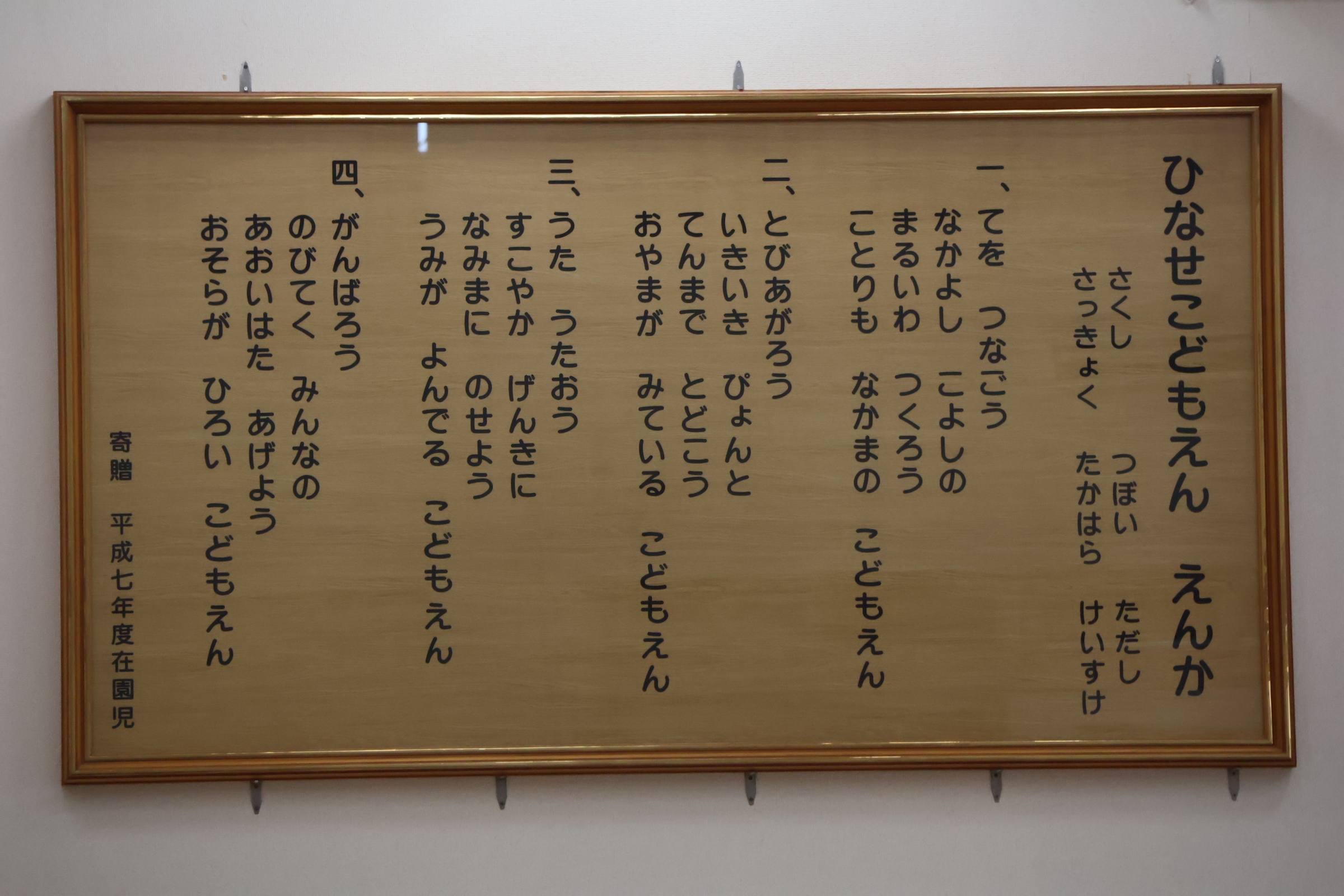





◎生活を高める取り組み✨(6/19)
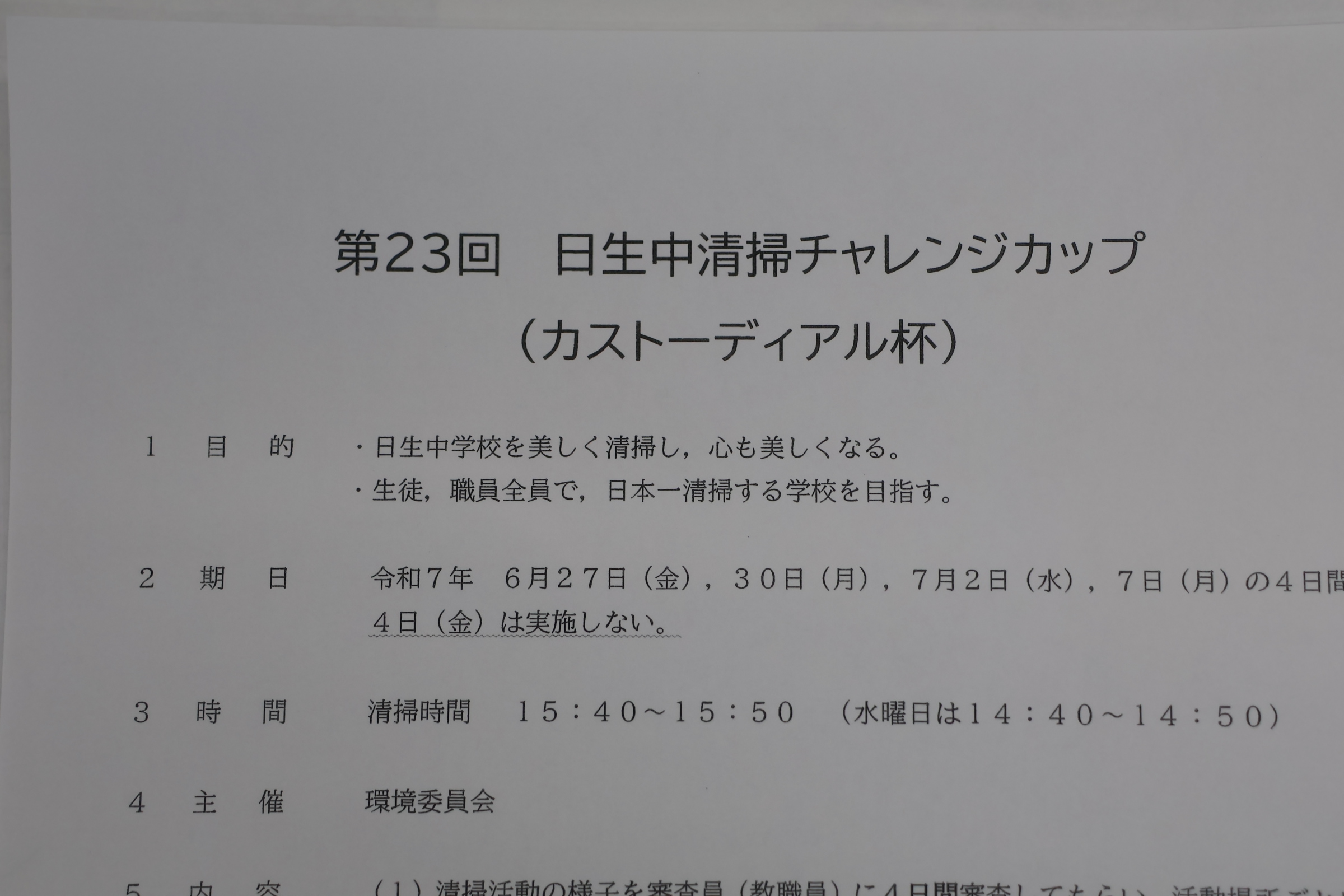
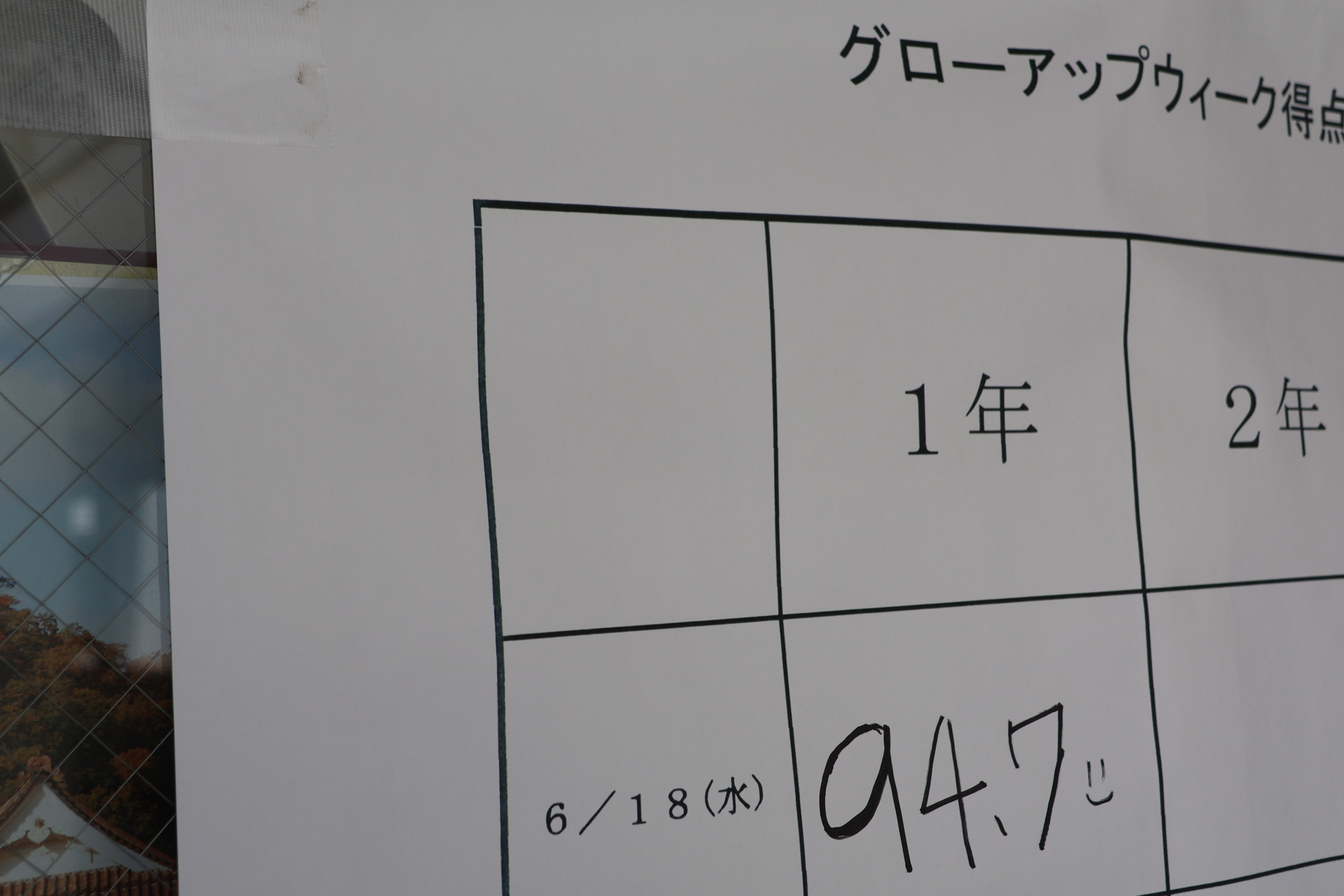
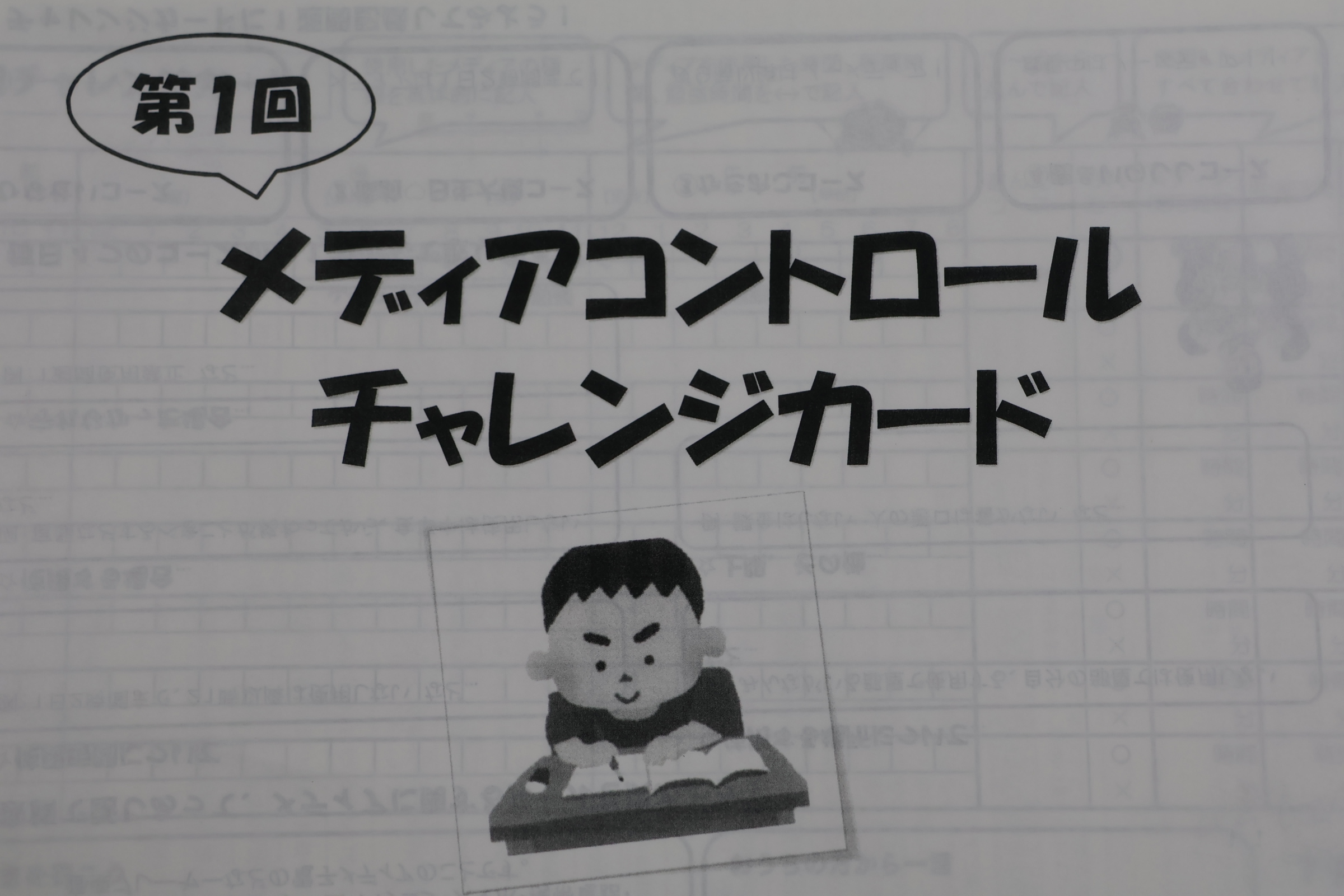
◎次のステージへ(6/19)

〈人間はしっぽがないから焼きたてのパン屋でトングをかちかち鳴らす 岡野大嗣〉


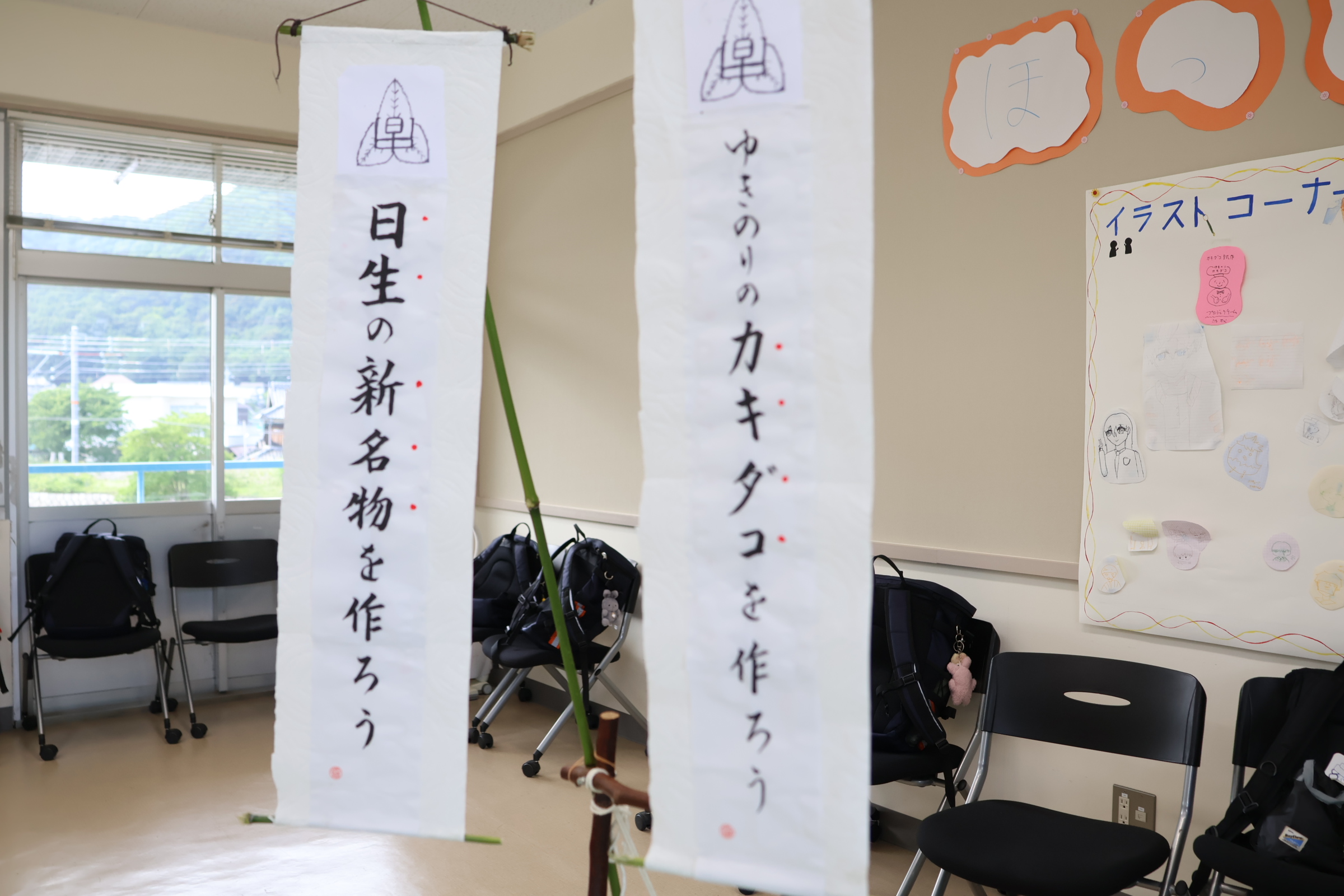
豊かな放課後の時間。私たちの大切な時間として。(6/18:英会話教室・ほっとスペース)
◎そんなひな中に惚れました(6/18)

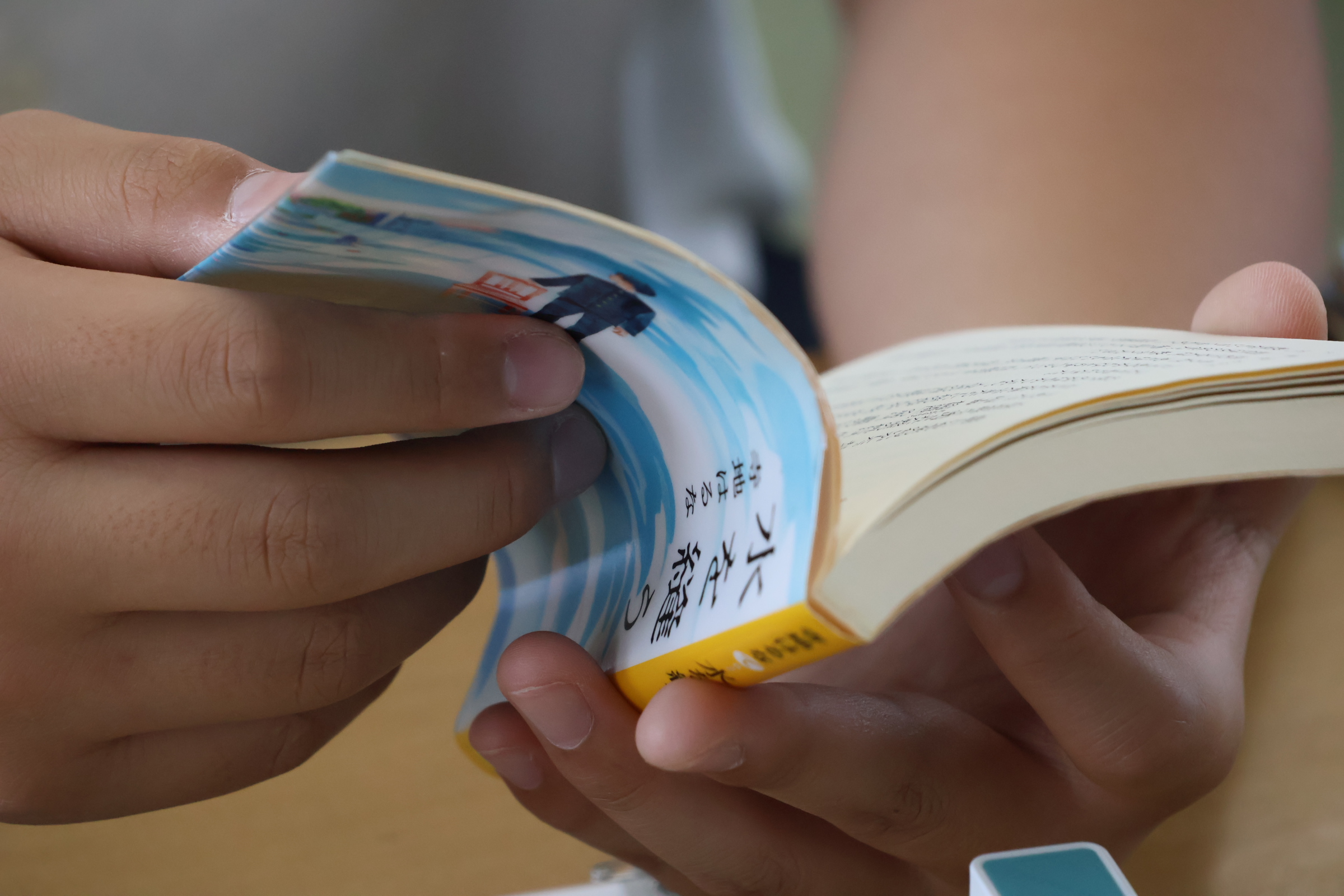
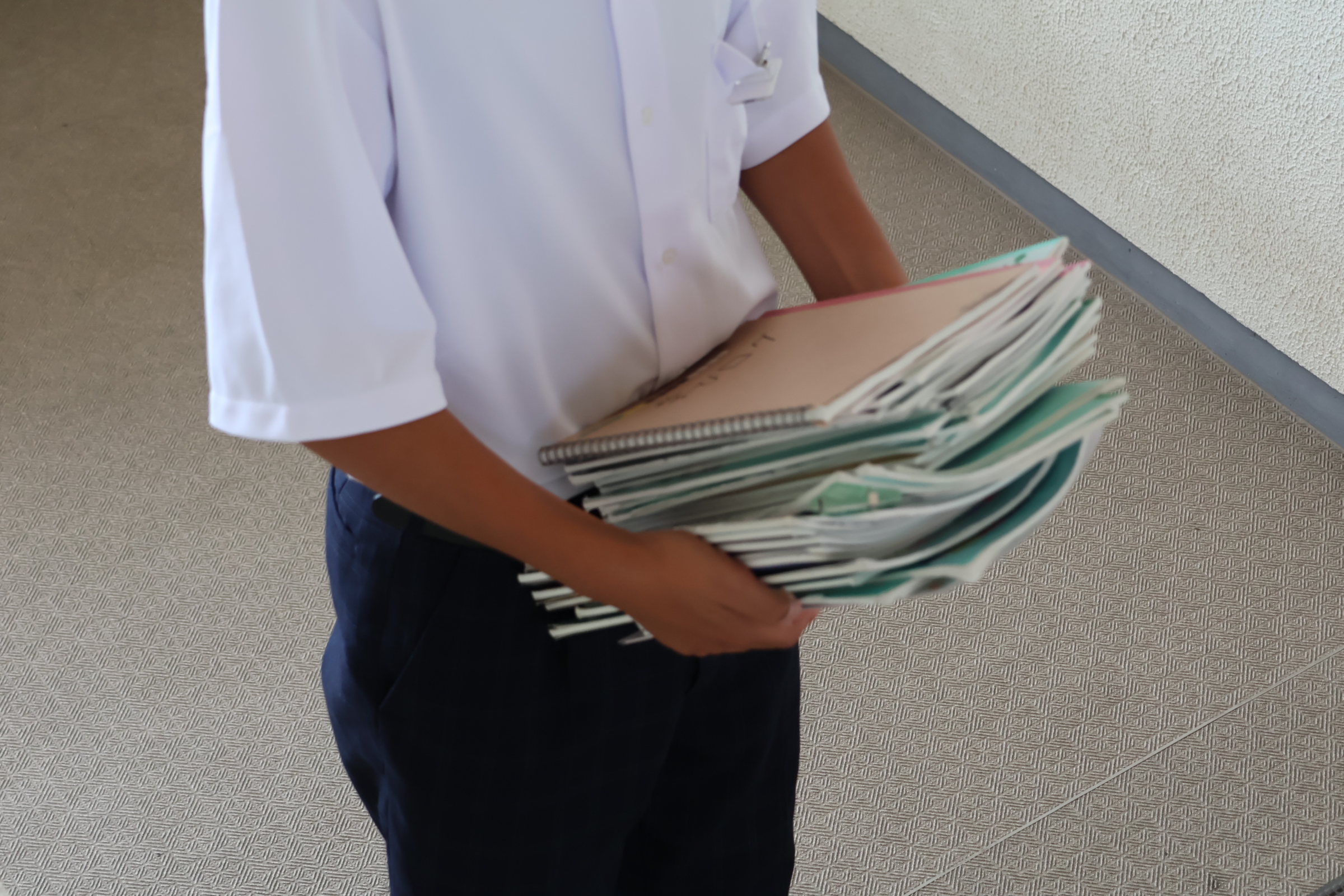
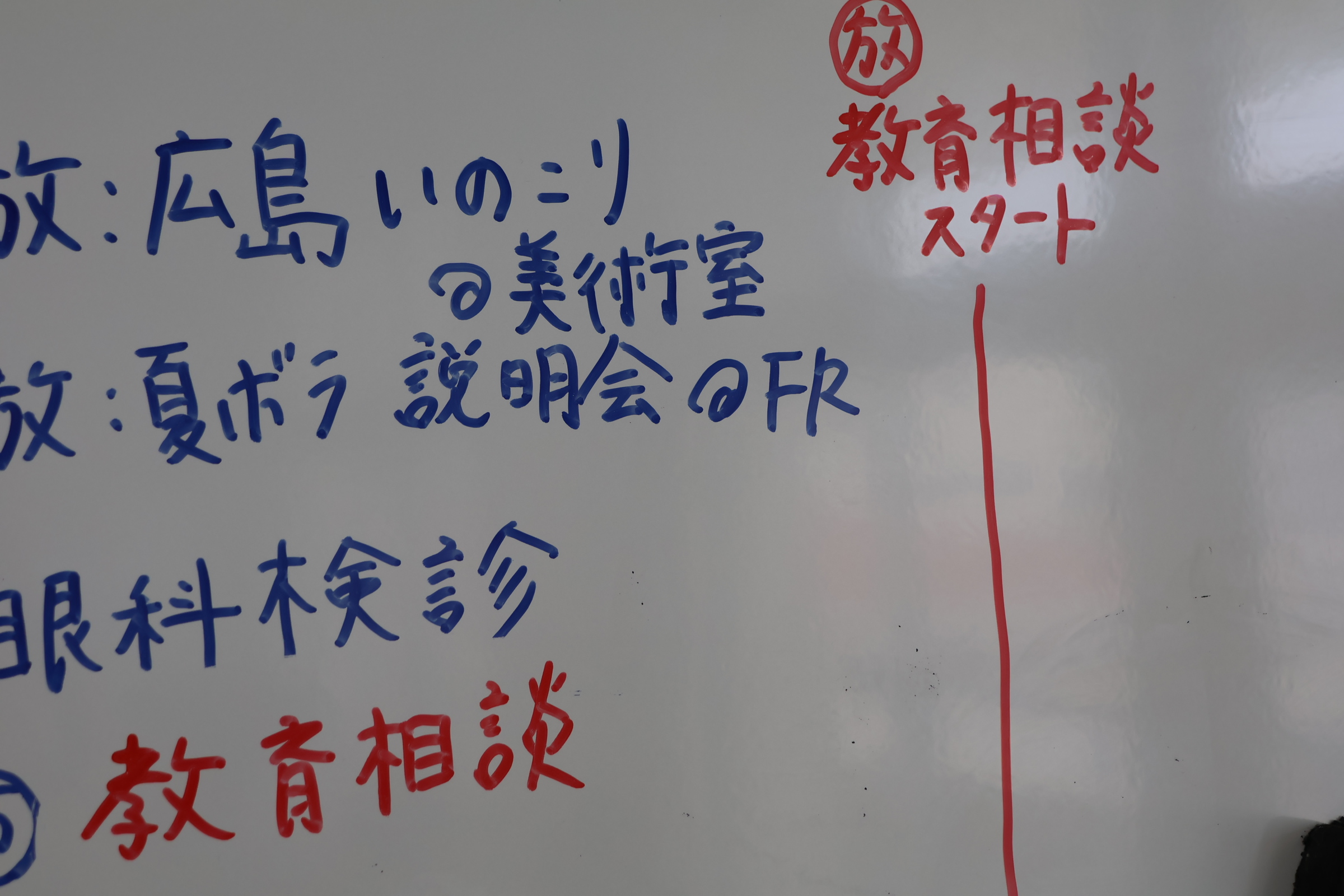


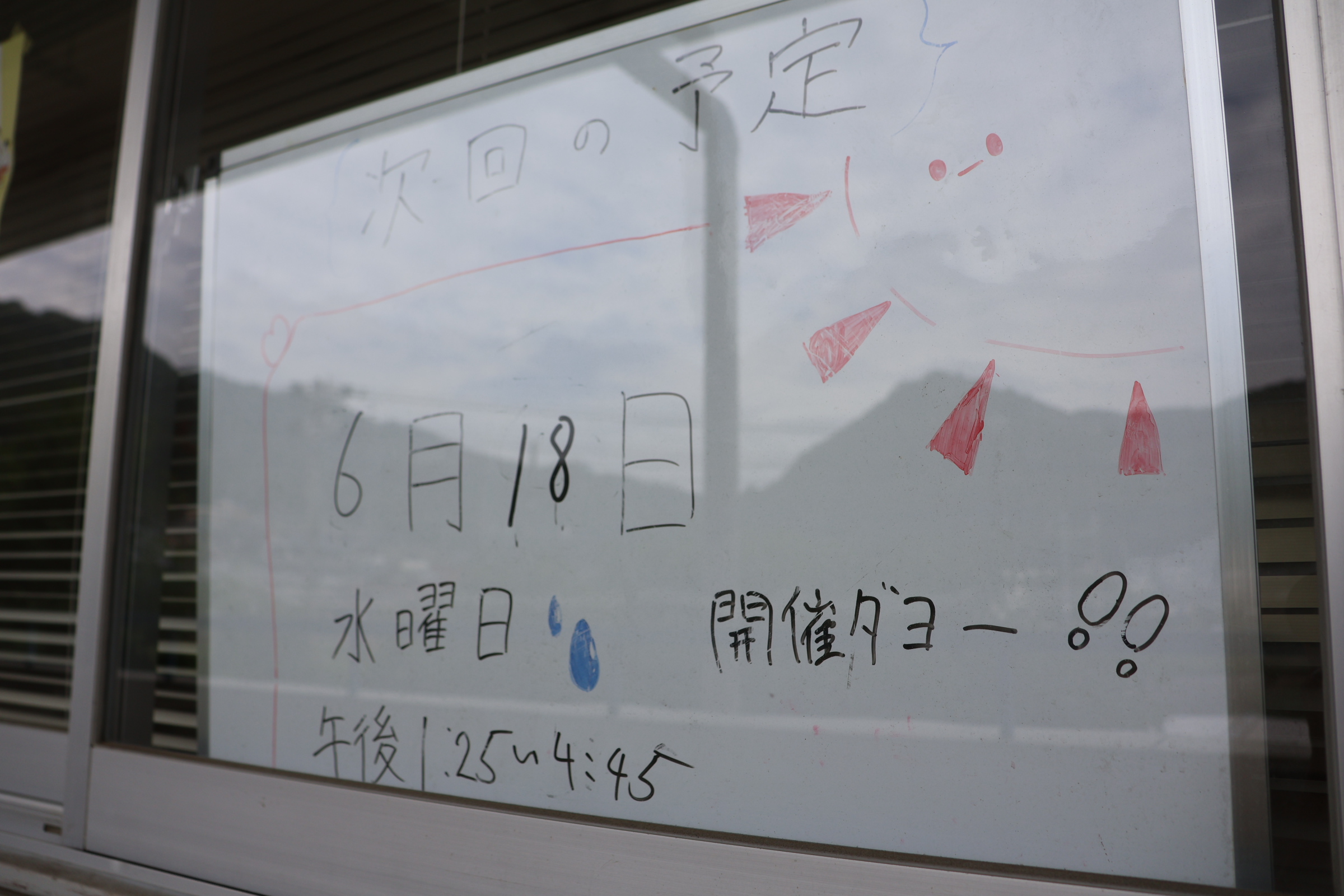
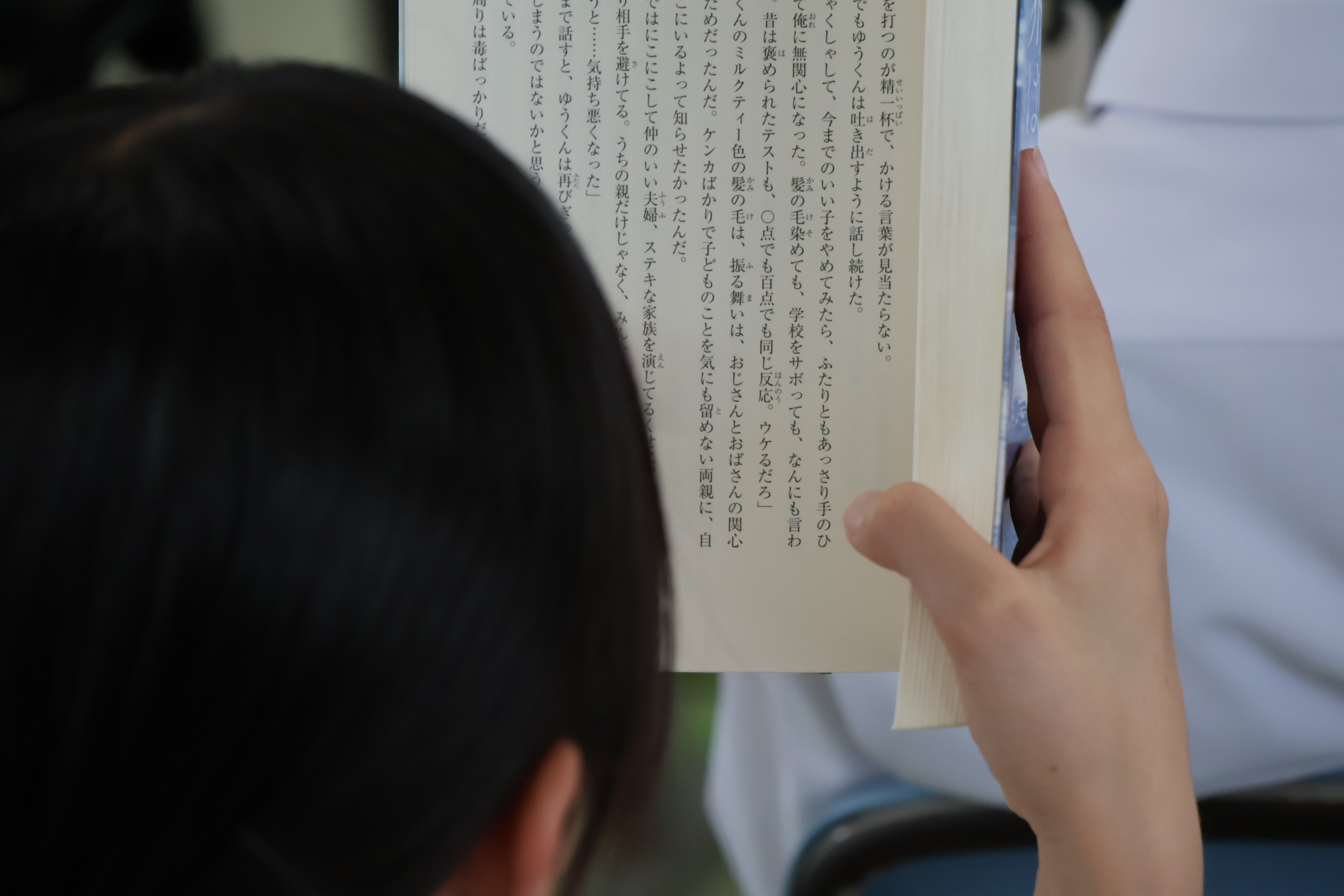
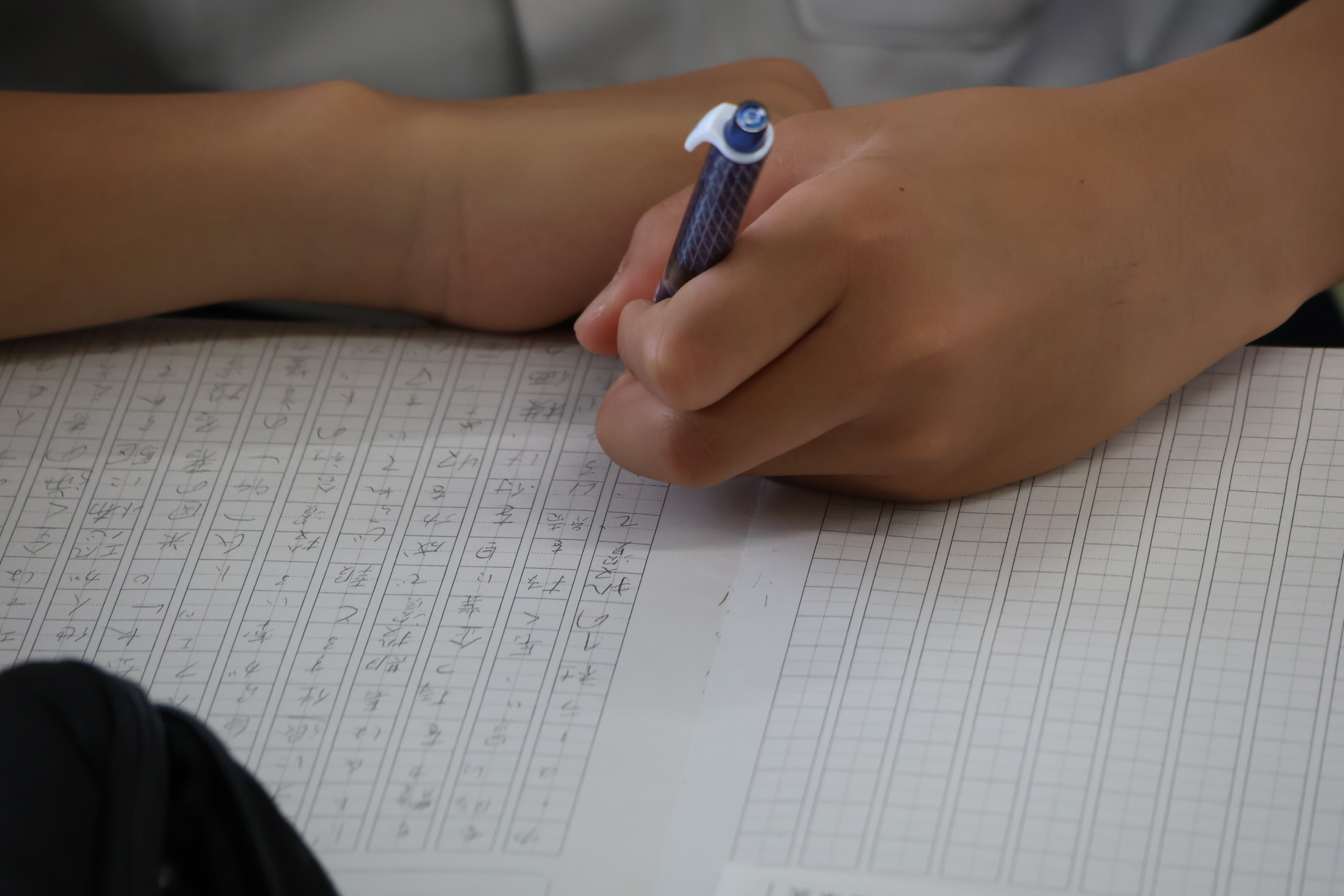
毎日を大切にしています
◎ひな中の熱
~待ってろよ!夏(6/17:夏ボラ校内説明会)

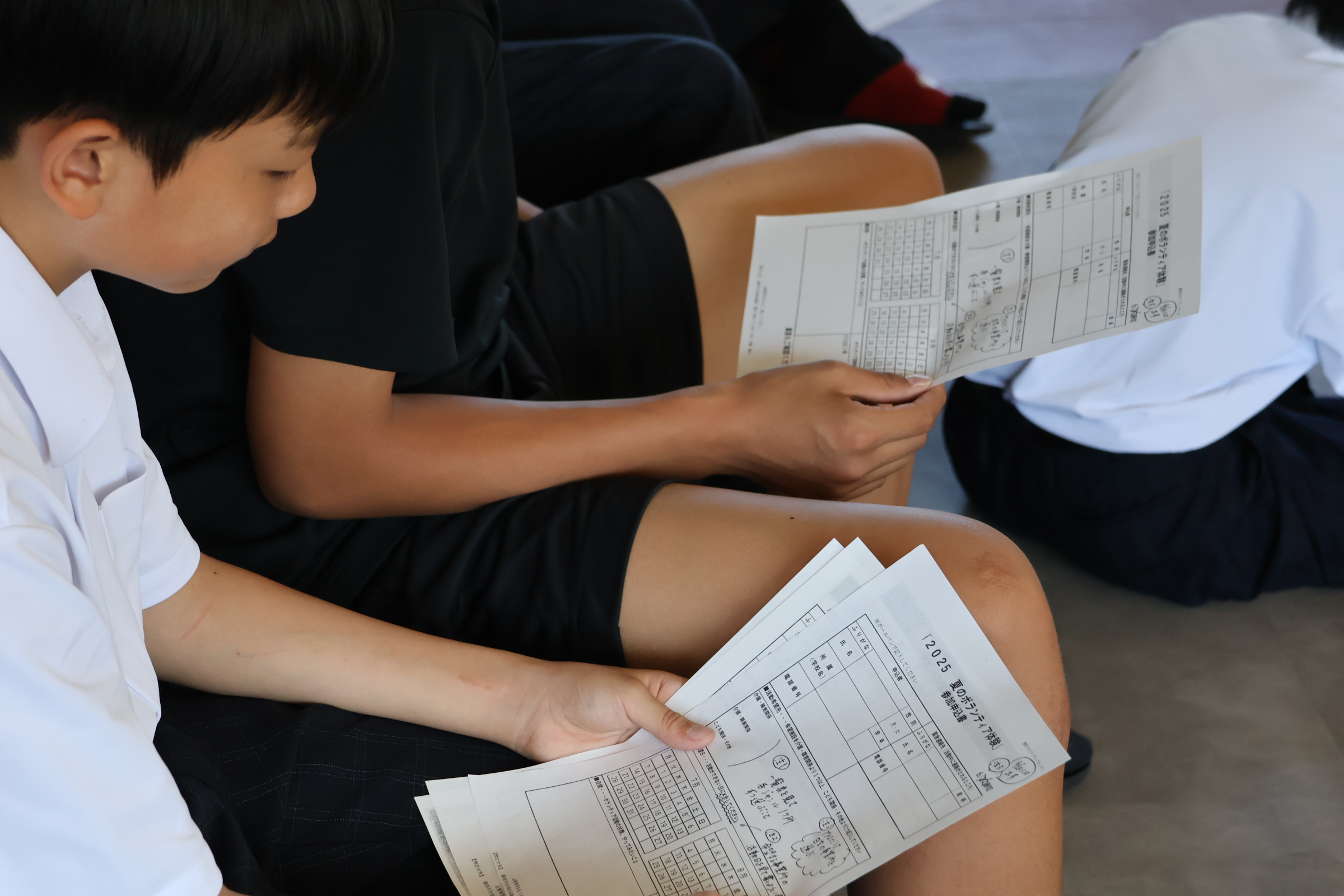
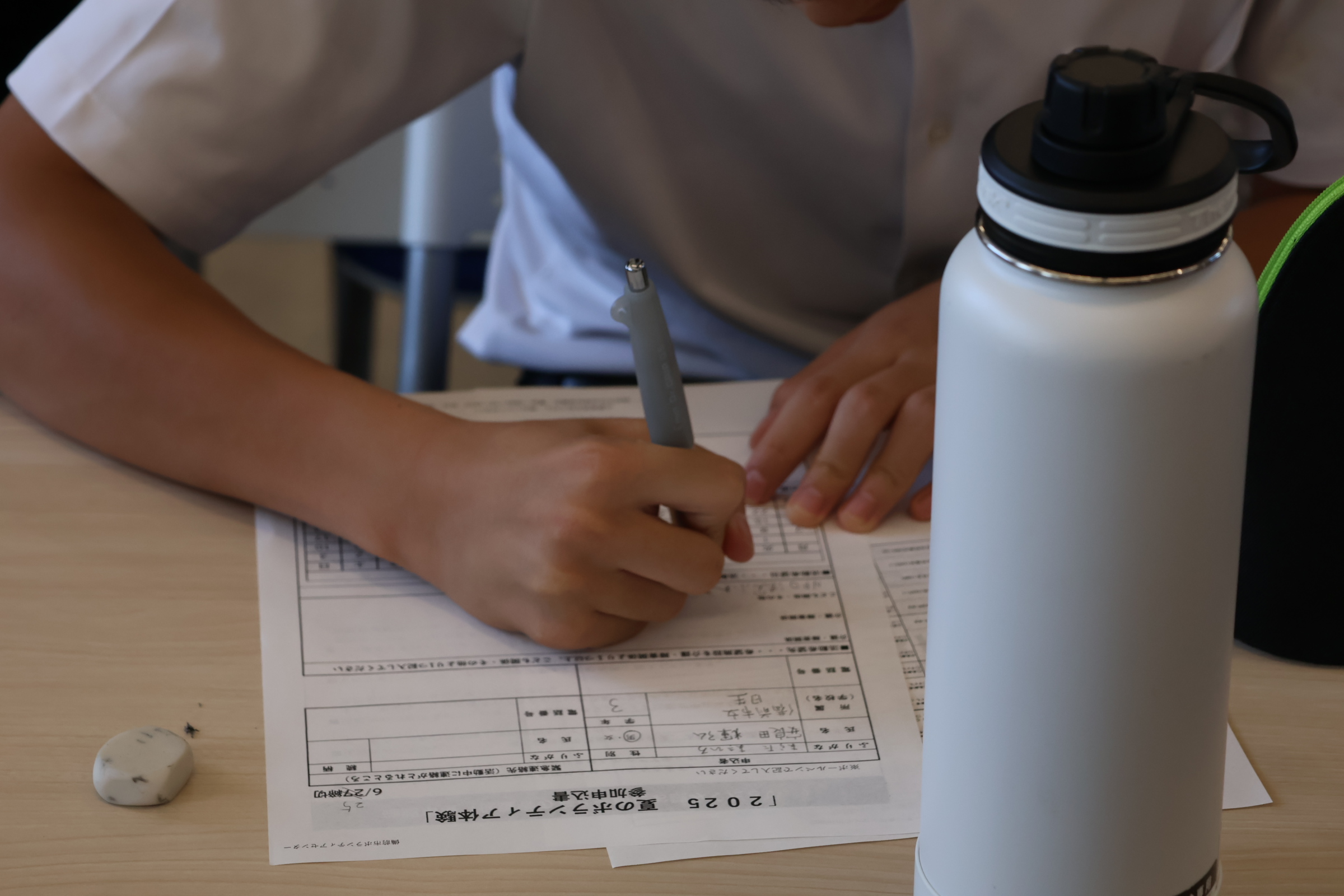
説明会場にいっぱい。
・校内締め切り(6/25(水))*保護者署名・押印、自分のスケジュールを確認。
・社会福祉協議会さん来校、受け入れ施設との調整会議(7/9(水))
〈「ありがとうございました。」と後輩の声受け最後の部活動終わる〉


◎私たちの始まりの風景18
ここはどこでしょう?(6/16校内編)






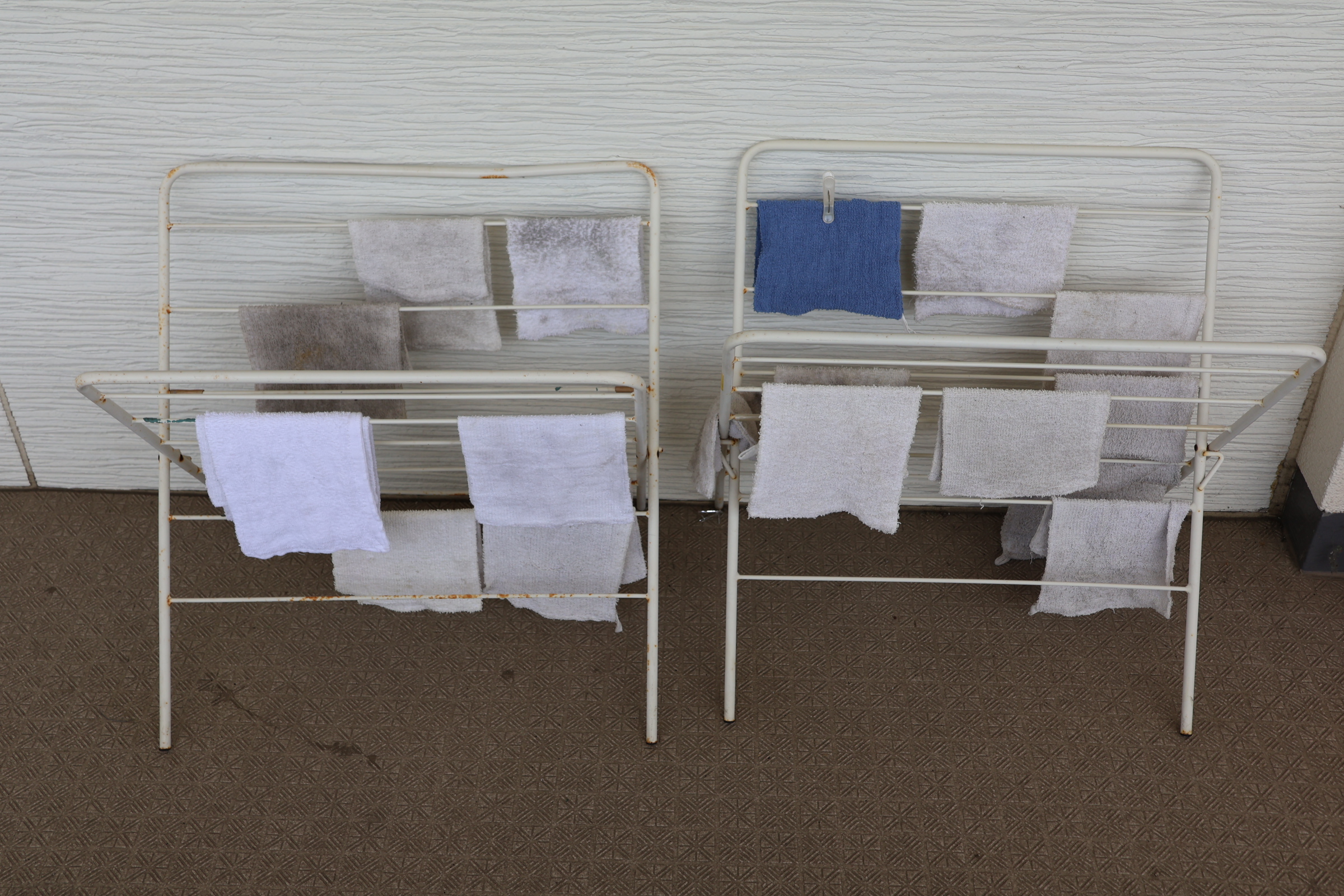

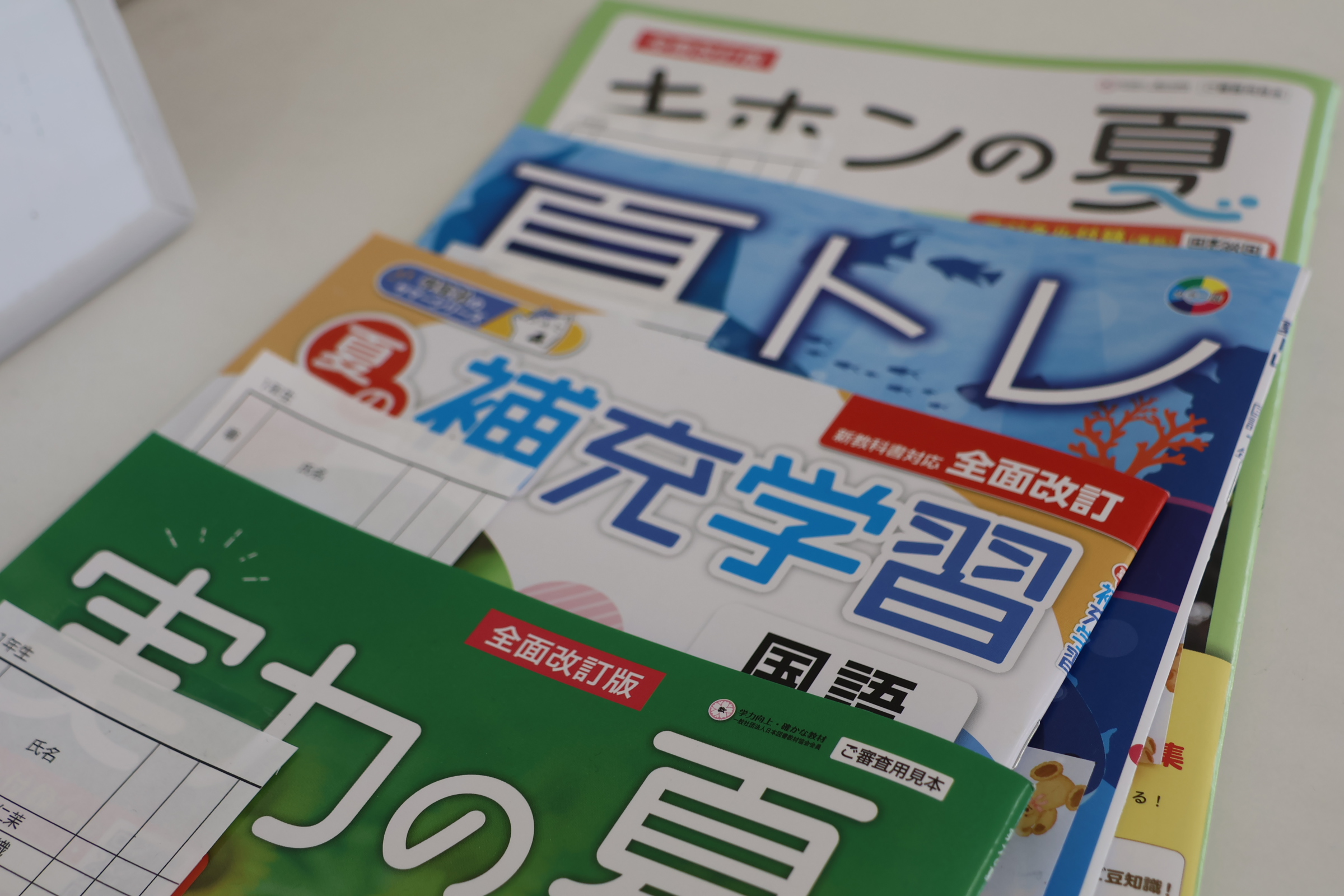
◎あめつち (6/13)









6/14~15 総体・吹奏楽祭 仲間と共に、一所懸命。
◎多くの人に支えられて(6/13)
給食調理場から北川先生が食育指導で来校されました。
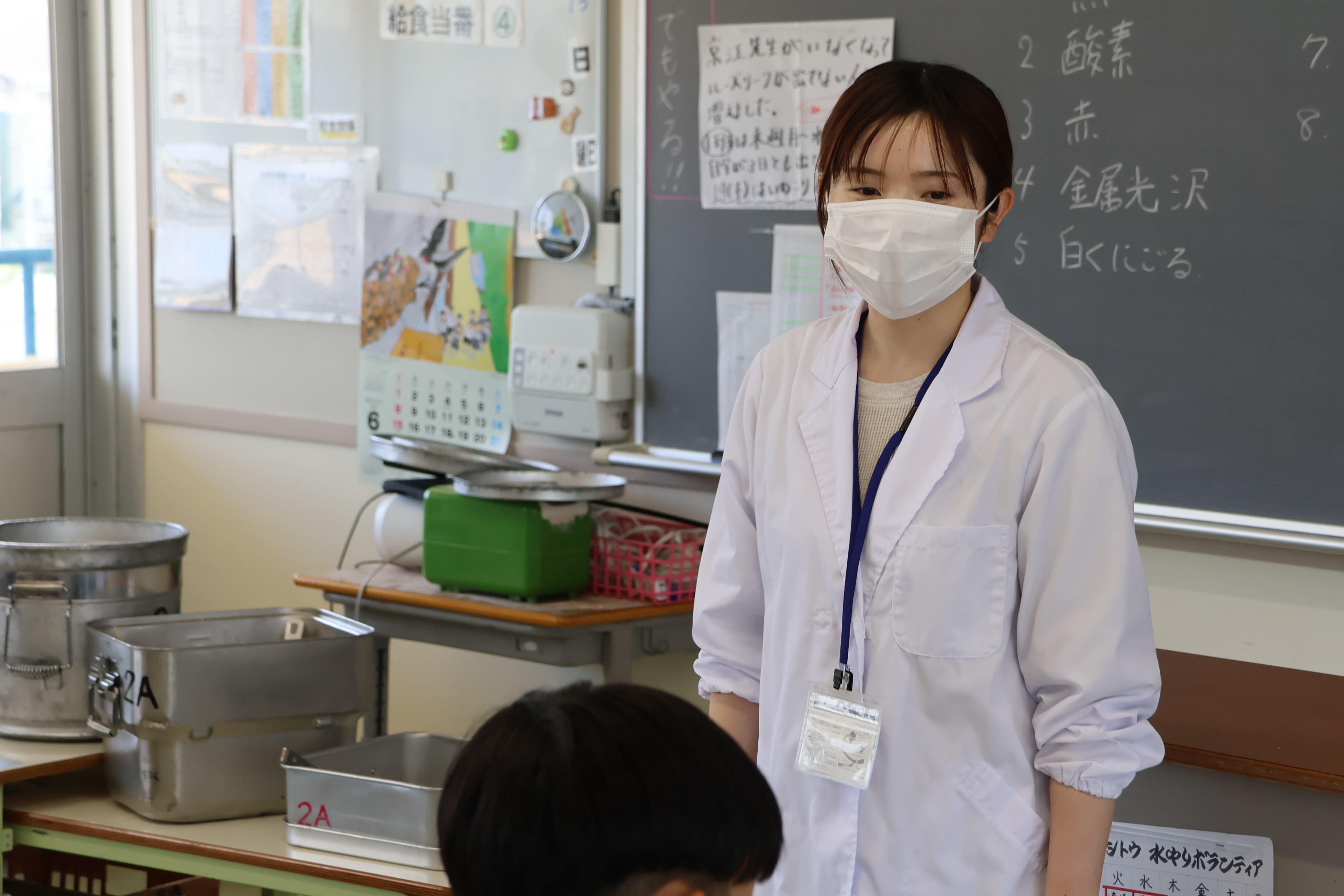
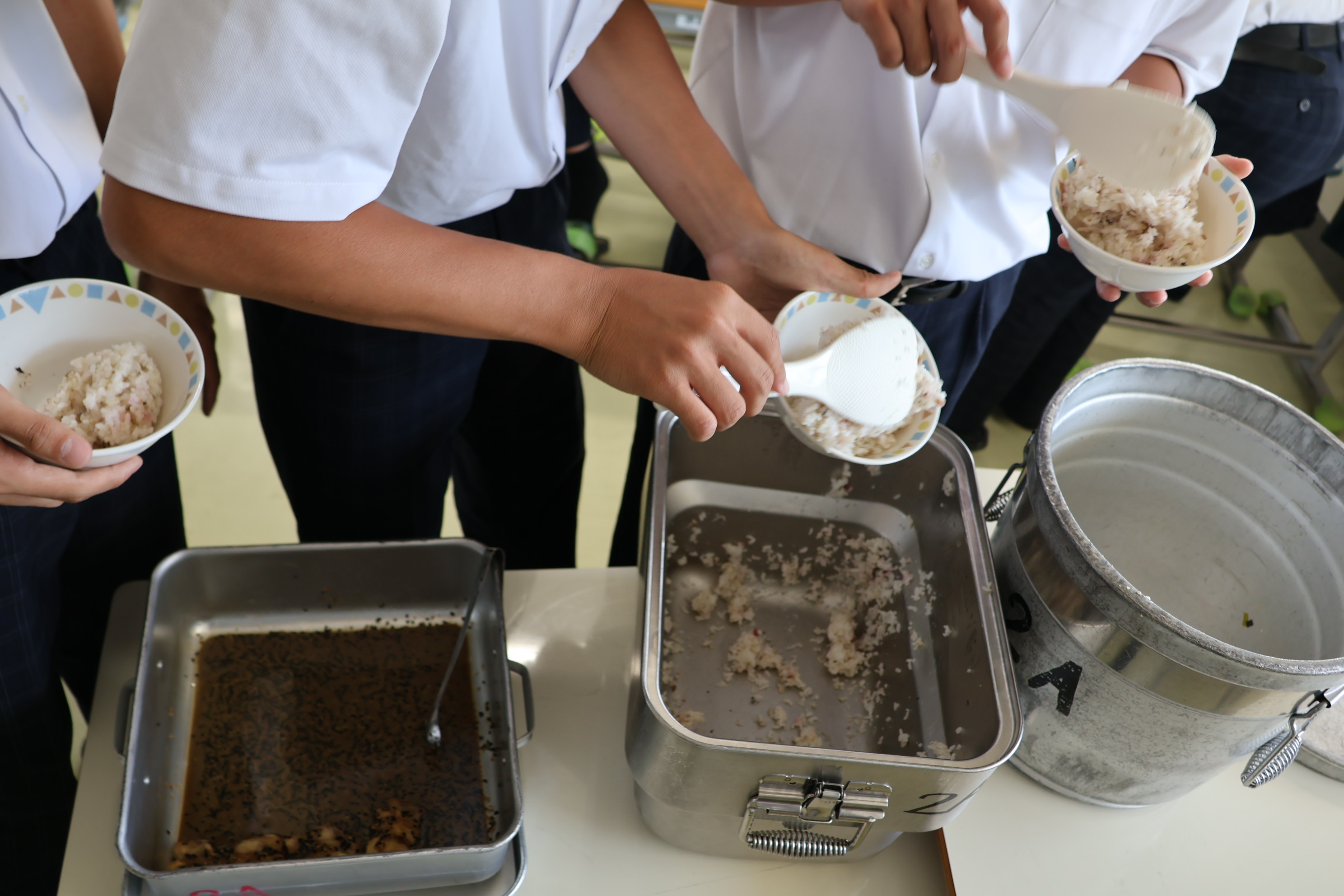

◎地域と共にある学校(6/13)

社協さんからのご案内です。
〈梅干すといふことひとつひとつかな 石田郷子〉(6/13)

◎学び続ける者が教壇に立つことができる(6/12)

自己目標シートをもとに、全教職員が面談をおこなっています。
◎願いと思いを共に
春15の会 第2回実行委員会開く



6月11日に、本校の教頭先生も実行委員のひとりとして参加してこられました。今年度の案内の文言が少し変わりました。〈~特別支援教育のニーズのある子どもたちの進路・自立にむけて~〉です。進学に関する相談ブースだけでなく、学校(高校も含む)生活や、福祉、行政サービス、親の会など自己実現に向けての多ブースの開設も準備します。実施計画案を一部紹介します。
1 目的
(1)特別支援教育のニーズのある生徒の進路・進学や就職についての最新の情報を、本人・保護者や教育関係者、支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。
(2)動画配信や情報交流学習会を通じて高等学校生活を紹介し、進路に関する情報が収集できる会にする。
(3)視聴者が実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。
2 実行委員会の方針
(1)持続可能な会の開催ができるように積極的に工夫・改善を進める。
①目的が達成できるように有機的なヒト・組織・コトの協力(後援)や助言を仰ぐ。
②特別支援教育の推進のために、また本会の開催案内が必要とされる多くの方々に届くように、様々な組織と連携を図り、ネットワークを拡げる。
3 具体的実施計画(内容等)
◎動画配信 卒業後の進路について、申込者に対して高校・関係機関の紹介動画を期間限定で配信(東備地域自立支援協議会ホームページ上にて)する。
<期 間> 令和7年8月8日(金)~11月28日(金)
<内 容> 各校の作成動画には以下の内容を盛り込む。①別支援教育のニーズのある子どもの入学試験についての相談や受験時の配慮、サポート等②学校生活の様子(支援の実際)③卒業後の進路や就職の状況④相談窓口担当者 各校10分程度の動画とする。
◎参集方式(200人程度)
<内 容> 座談会、学校紹介、特設相談会(相談ブース)
<日 時> 令和7年8月23日(土)12:30~16:30
<場 所> 備前市立日生中学校(備前市日生町日生241-14) *案内(申し込み)チラシは7月初旬に案内予定です
◎この夏、新しい自分に出会う(6/11)
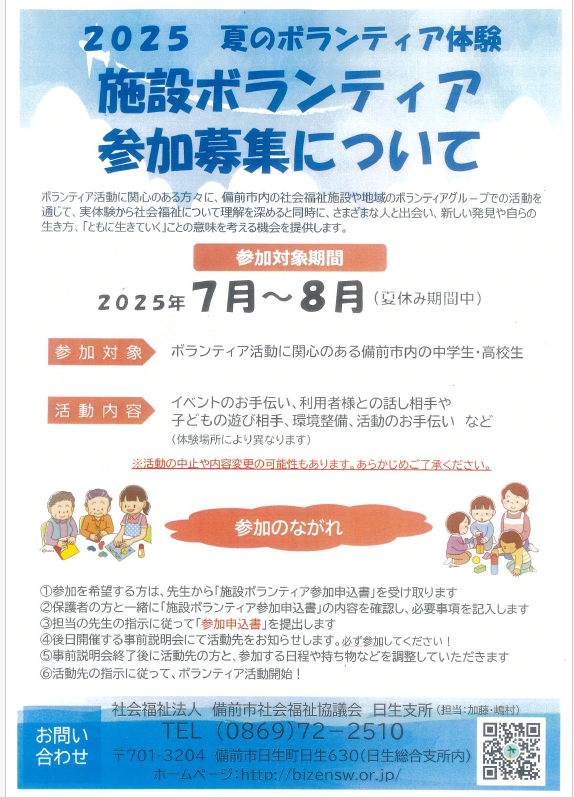
6/17(火)放課後にフューチャールームにて説明会を開催!!

備前市社会福祉協議会の嶋村さんらが来校されました。『今年もたくさん参加を待っています!」
◎英会話を楽しもう 世界を拡げよう
ALTの先生らとの英会話教室(^_^)は、基本的に毎週水曜日開催中です。(6/11)

◎はじまりはいつも雨(6/10)

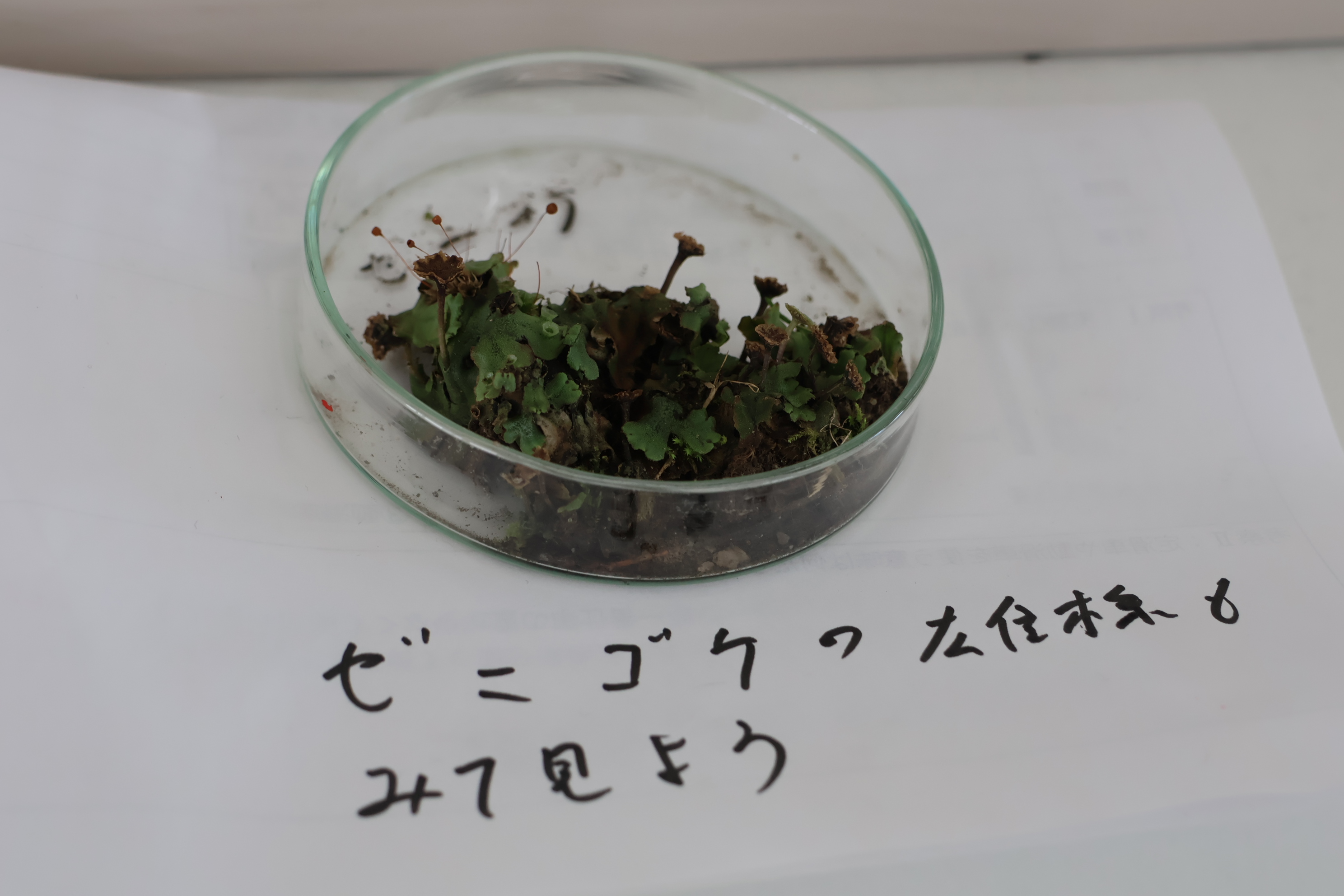

ふだんあまり四季を気にすることのない人でも、梅雨の時期は、「今日はかさがいるかなあ」「洗濯物を外に干していって大丈夫かしら」などと思いながら「もう梅雨か」と、季節を意識するのではないでしょうか。梅雨入り、梅雨明け、梅雨前線などのことばは、ニュースなどでも耳にすることがあると思います。梅雨とは、本格的な夏が始まる前に雨やくもりの日が続く時期のことで、日本を含む東アジア(朝鮮半島南部、中国南部、台湾など)に特有の気象現象です。沖縄・奄美諸島を除く多くの地域では、だいたい6月から7月にかけての1か月から1か月半ほどの期間が梅雨にあたります。
梅の実が熟するころなので「梅雨」という漢字をあてたとされます。また、カビ=黴が生えやすい時期の雨であることから「黴雨(ばいう)」と書かれたものが「梅雨」に転じたともいわれます。梅雨になる時期を梅雨入り、終わる時期を梅雨明けといい、南から北にかけて次第に梅雨入り、梅雨明けが移動していきます。沖縄では、ゴールデンウィークが終わったころに早くも梅雨入りし、梅雨の地域が九州から四国、本州へと移り、約1か月後には東北地方が梅雨入りとなります。北海道には梅雨はないとされています。
梅雨は農業や生活に与える影響も大きいことから、気象庁が各地の梅雨入りと梅雨明けと思われる時期を発表しています。これらは「梅雨入り宣言」「梅雨明け宣言」ととらえられることもあるようですが、気象庁は“宣言”しているわけではなく「梅雨入りしたと見られます」といった控えめな表現をしています。天候の変化の見極めは難しく、後日、春から夏にかけての実際の天候の経過を考慮した検討が行われると、梅雨の入りや明けの時期が発表されたものから変更されることもあるのです。
春を過ぎ、本格的な夏へと移り変わる時期には、日本の南にある温度が高くしめった気団と、日本の北にある温度が低くしめった気団がとなり合い、前線ができます。これが「梅雨前線」で、日本付近にとどまったまま(停滞)、厚い雨雲を発生させるために雨やくもりの日が続くのです。梅雨前線は5月ごろにでき、しだいに北上していきます。そのために梅雨の時期が南から北へと移っていくのです。この時期の天気図を見ると、日本付近に長い梅雨前線があることがわかります。テレビや新聞の天気図で見たら思い出してください。
◎私たちの絆・輝き・そして、誇り(6/7:第15回星輝祭体育の部)



◎From Bonds To Billance(6/6)









『練習の成果を精一杯発揮してください!
一人ひとりが自信を持てば大丈夫!!
素晴らしい思い出をつくって楽しんでください。
応援しています。』(保護者からの『ひとのあいだ』応援メッセージより) ありがとうございます。
◎多くの人に支えられて(6/5)
今年度も、エコロジー東備の山﨑さんが来校され、ゴーヤやパッションフルーツなど多種の苗をくださいました。ありがとうございました。また、先日はタケジ農園さんからもゴーヤの苗をいただきました。グリーンカーテンづくりを通して環境保全活動に取り組んでいきます。ちなみにALTのShena先生に聞くと、ゴーヤは、英語でBitter melonで、お家のプランターでも栽培してるそうですよ。どんな料理を作られるのかな?

◎星輝祭の絆・私たちの絆を(6/5:体育の部予行)












◎我が星輝祭は永久に不滅です(6/4)

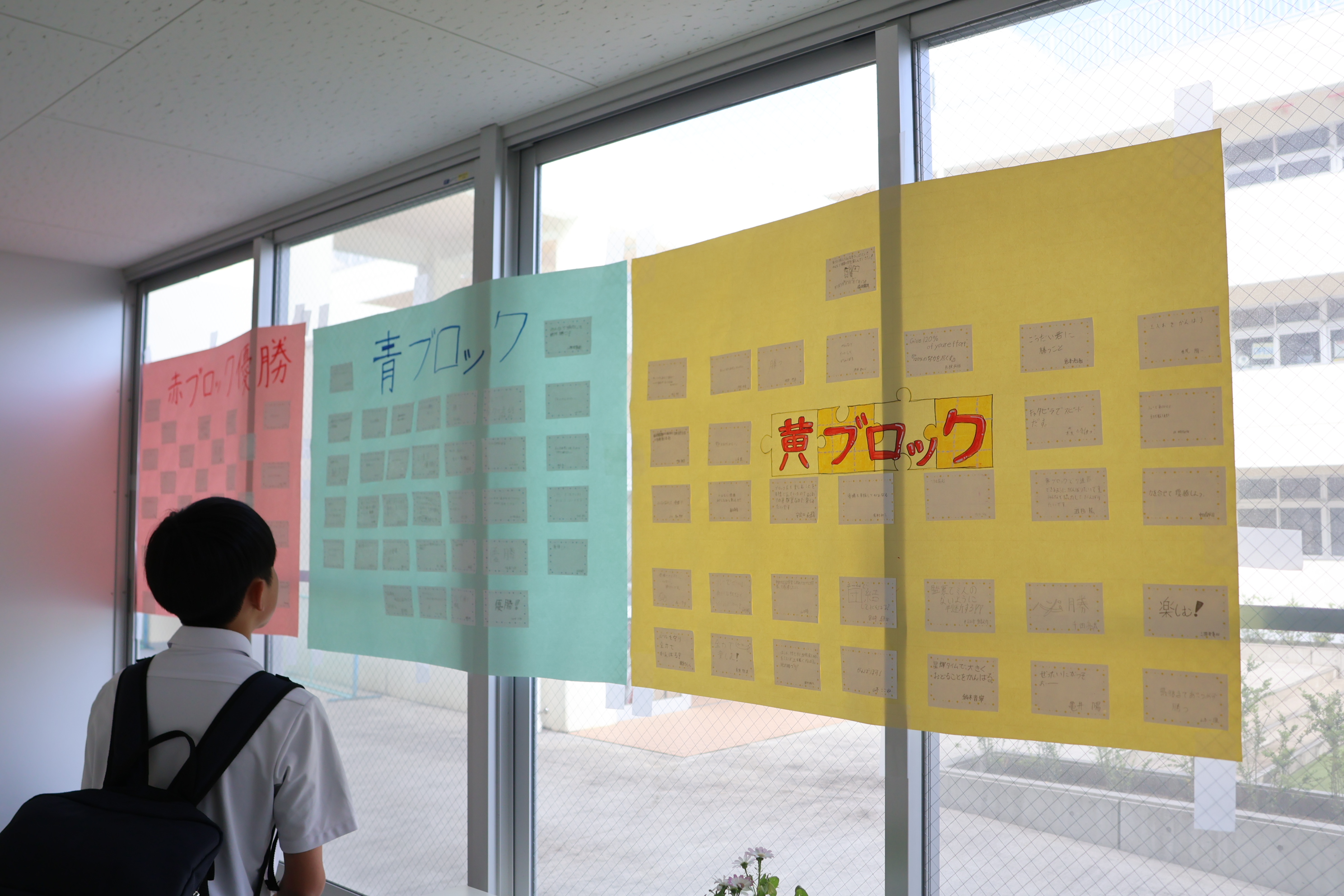
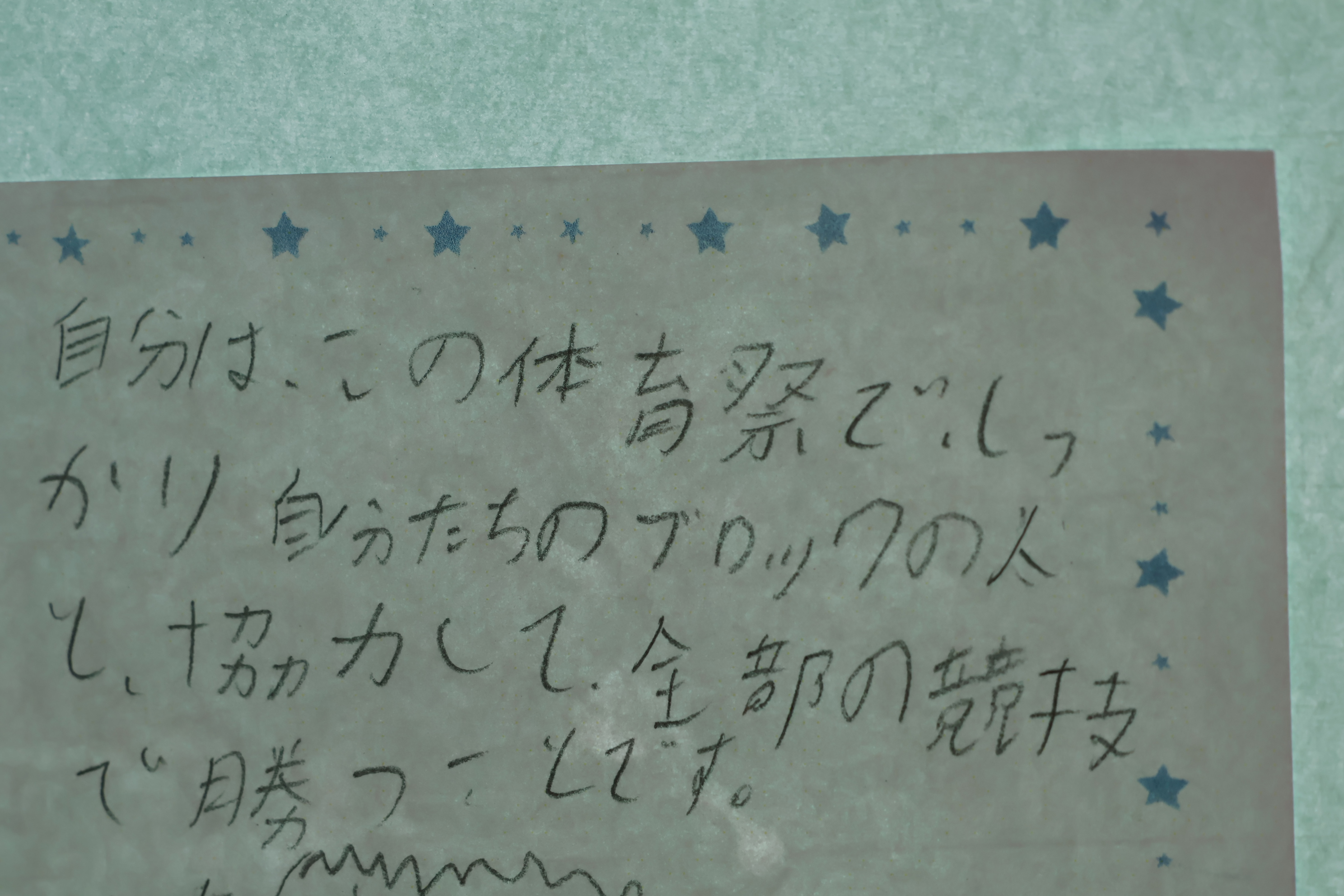
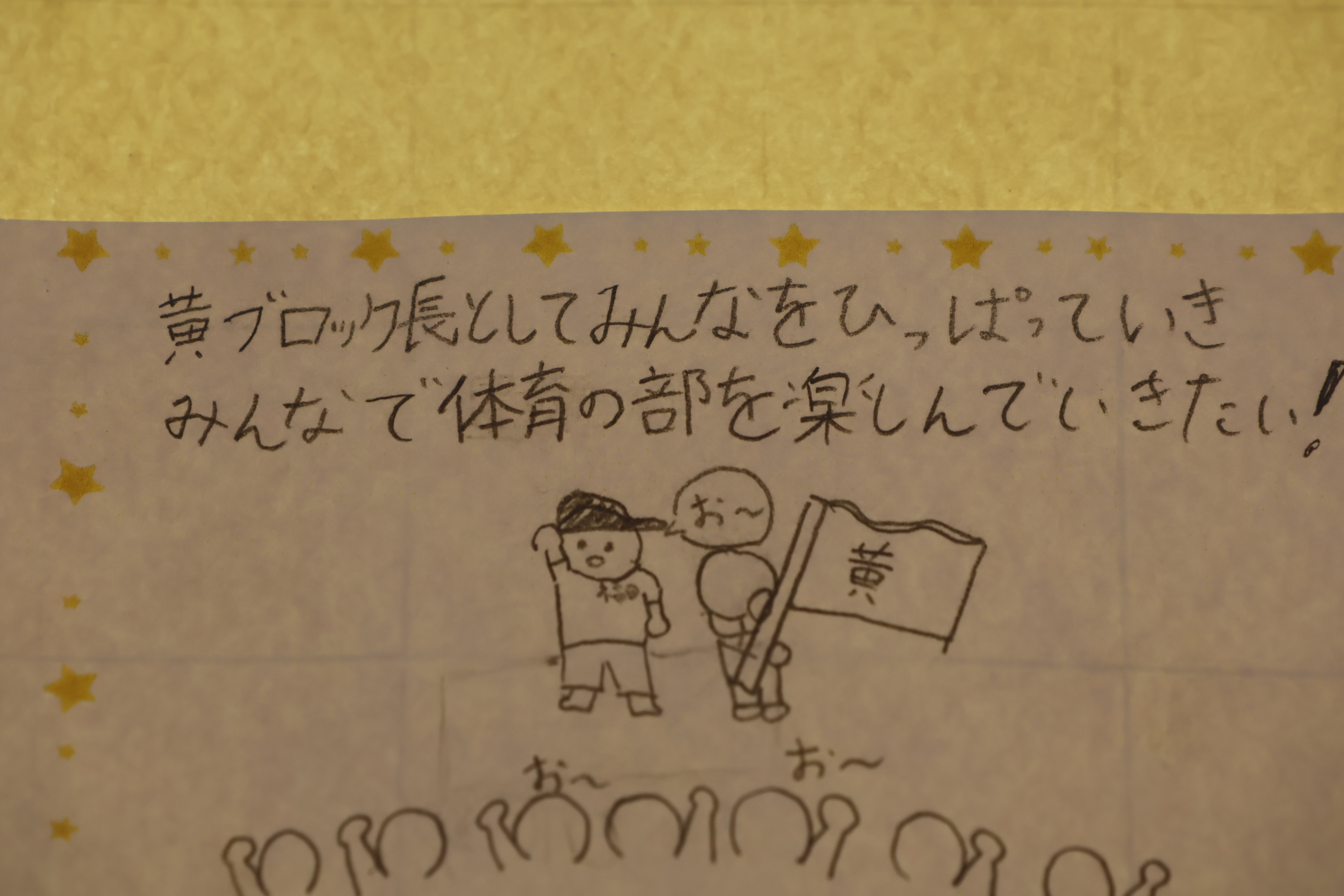
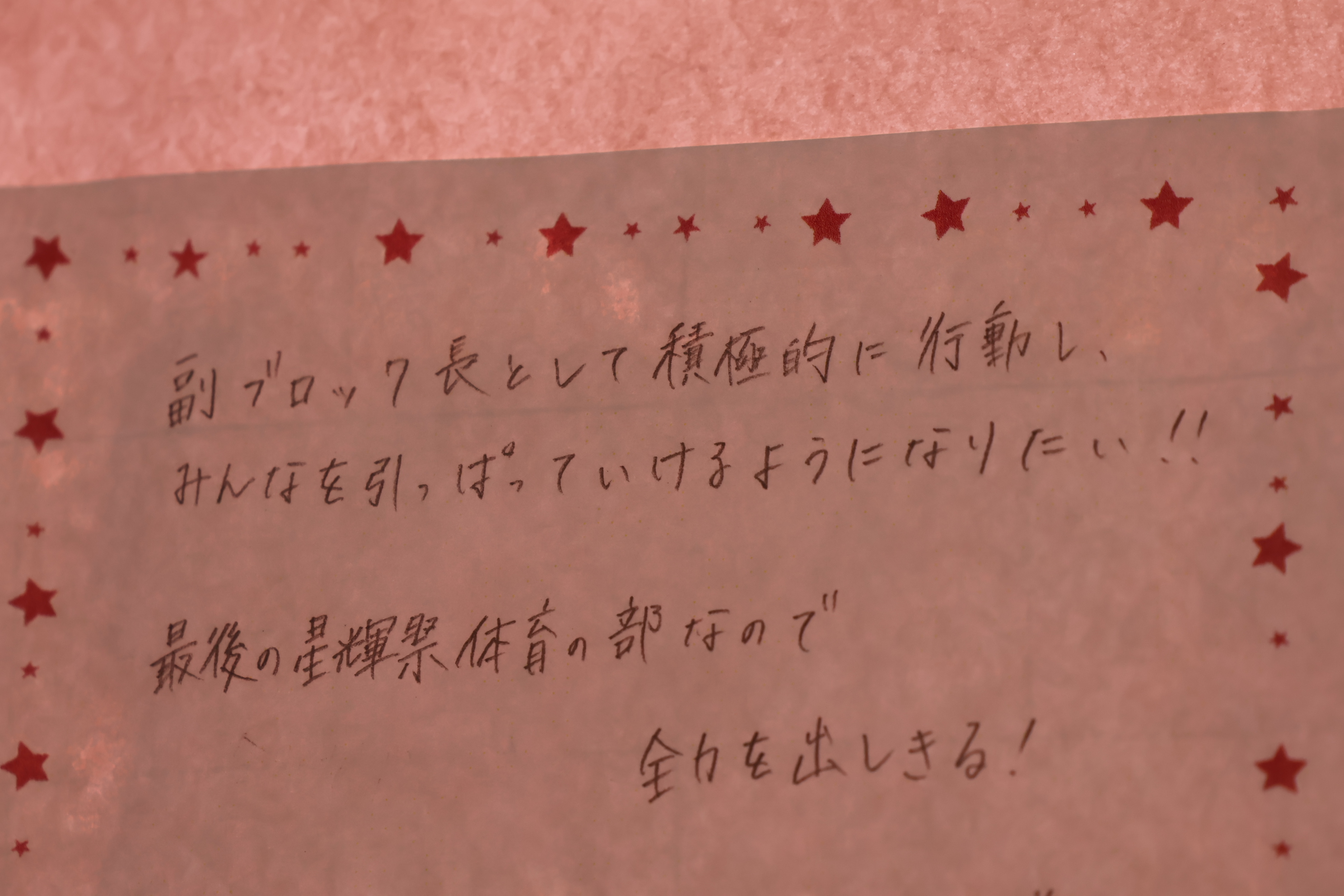
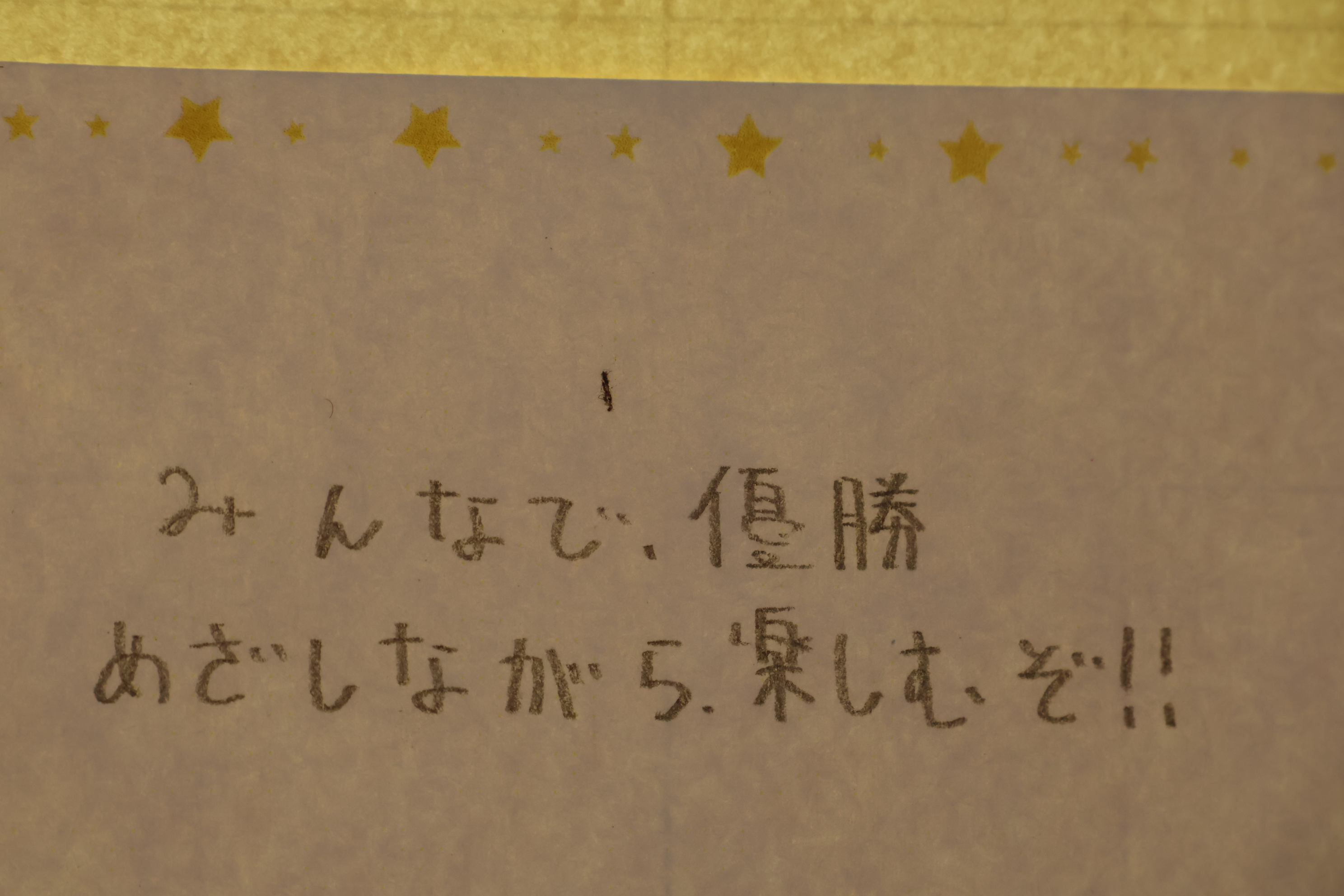
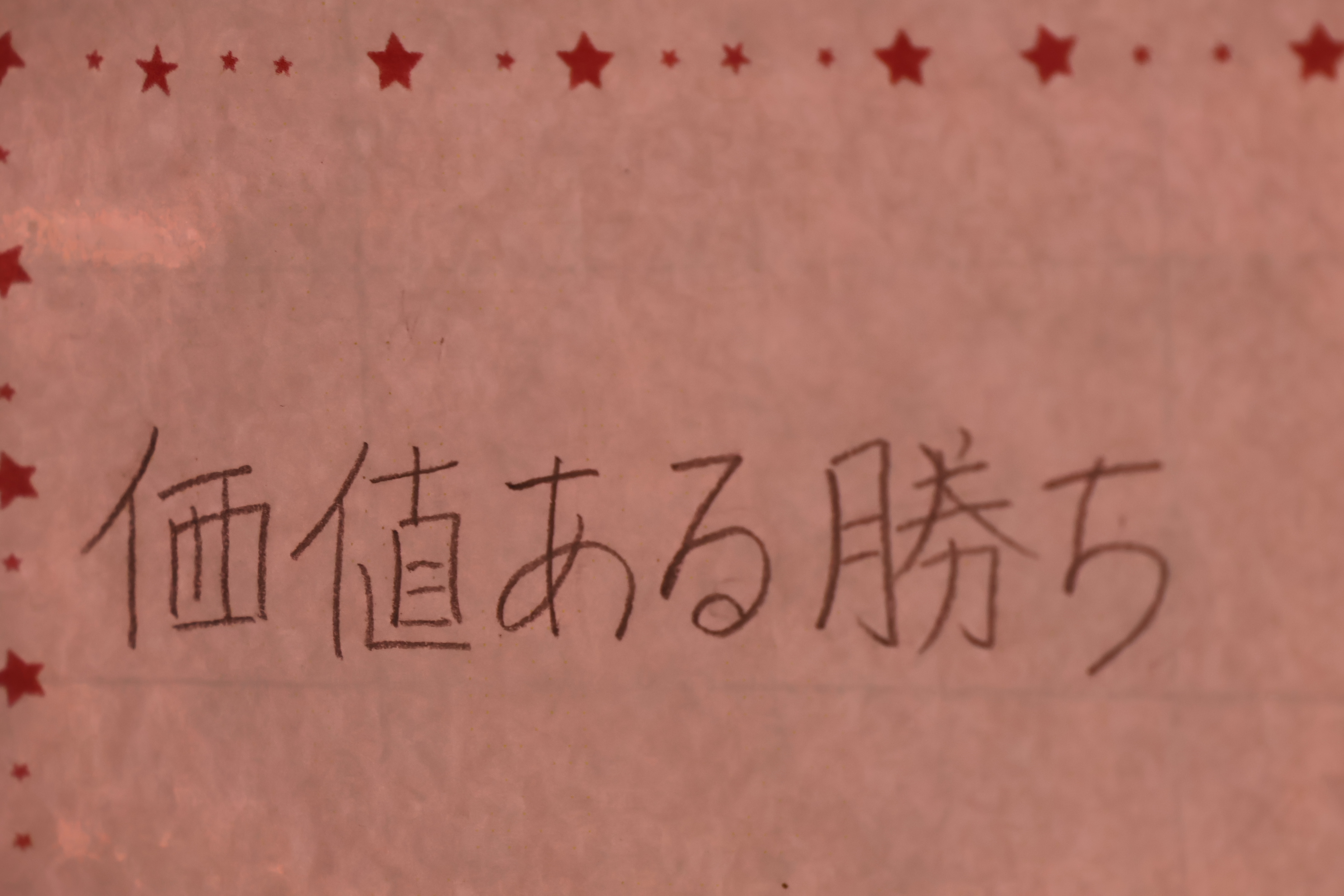
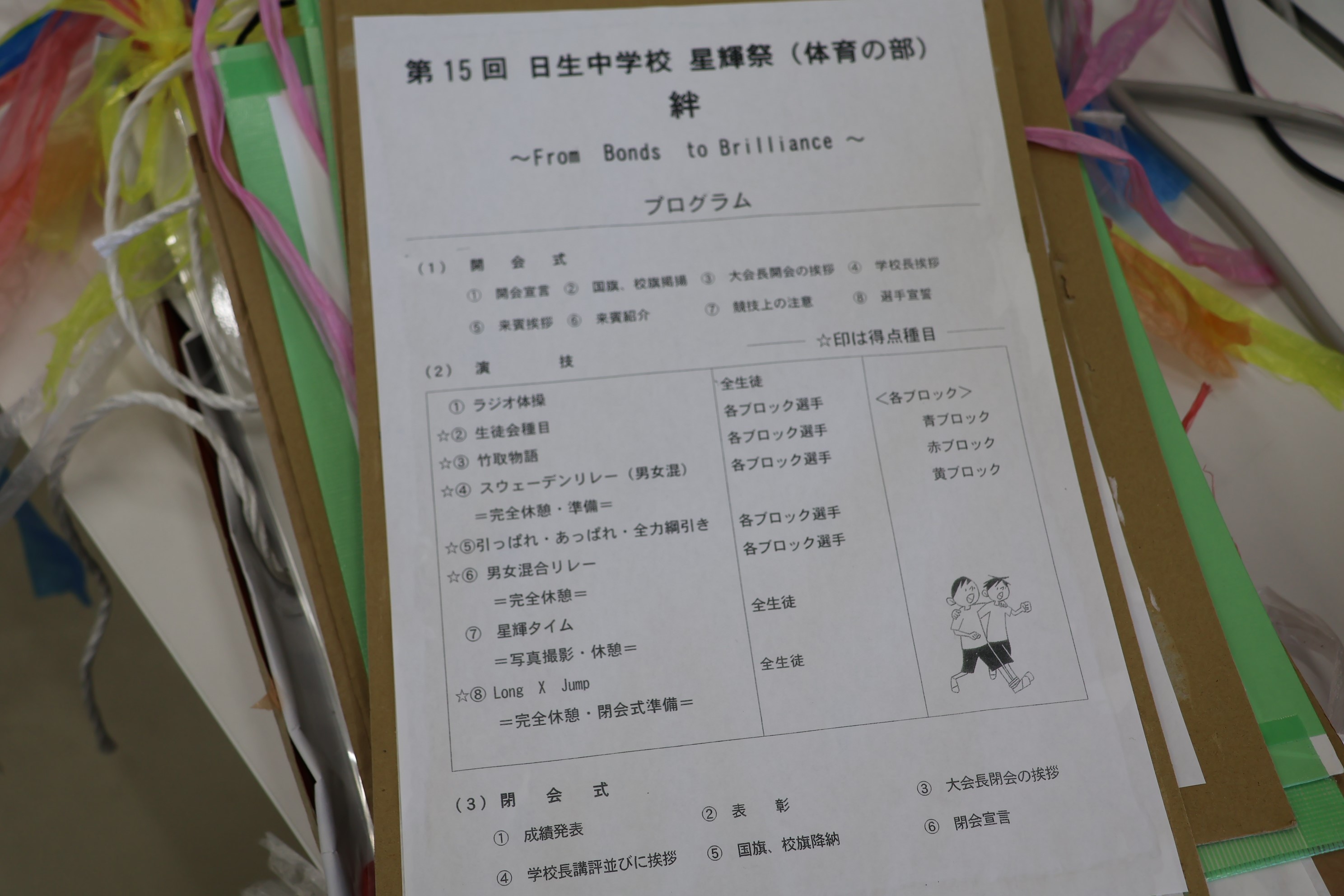

I’m passionate about learning. I’m passionate about life.Tom Cruise
(僕は学ぶことに情熱的だ、そして生きることに情熱的だ。)
◎チャレンジ!(6/4)
~話すことは、お互いを知ること。英会話を通して、豊かな視野を広げよう。



5月のENGLISH CUP受賞メンバーがクラスで讃えられました。おめでとう!
また、火曜日に実施しているALTによる放課後の英会話教室は、毎週水曜日開催に変更します。さらにうれしいことに時間延長もしてくださいます。これまで通り、友達と誘い合ってどんどん参加しよう。
◎雨の日は雨の日(6/3)


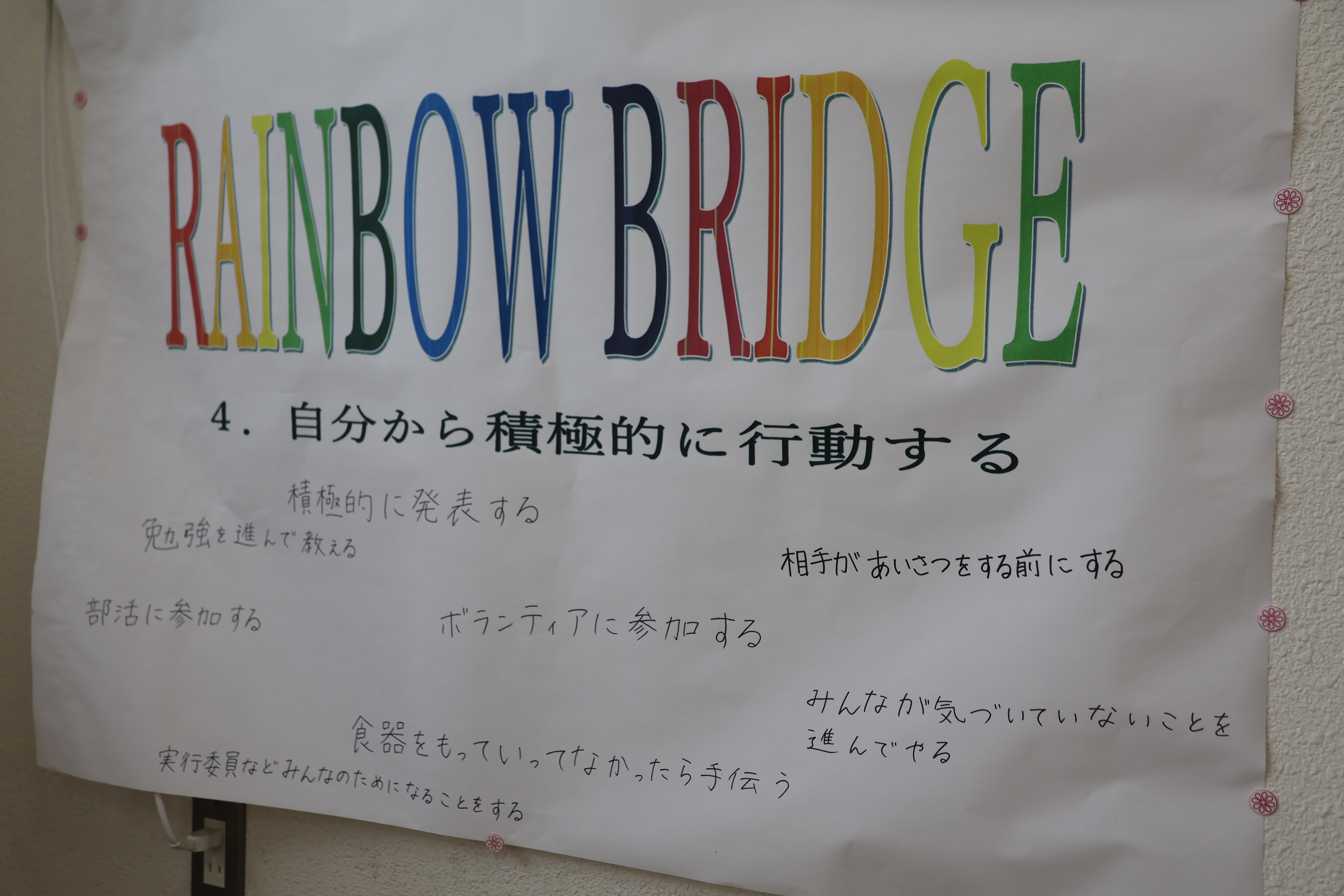









◎6月 水無月 JUNE(6/2)

6月に入りました。6月といえば雨の季節で多くの地域で梅雨入りを迎えます。6月の代表的な和風月名は、「水無月(みなづき)」です。雨が続く月なのに、水が無い月とはどういうことでしょうか。
『二十四節気と七十二候の季節手帖』などの著者で作家の山下景子さんは、水無月の由来について以下のように書かれています。〈じつは旧暦の6月は、現在の7月頃。いよいよ梅雨も明け、暑さの厳しい日が続く時期なのです。そこから、水が涸れ尽きて無くなるという意味の「水無し月」が変化したものだといわれます。ですが、最も有力な説は、田んぼに水を張る月という意味の「水な月」だという説です。“な”は“の”という意味の古語で、“無”は当て字というわけです。ほかに、田植えも終わり、大きな農作業をすべてし終える月であることから、“皆仕月(みなしづき)”。これが変化したという説もあります〉
6月…Juneの短縮・略語は、「Jun.」となり、頭文字は大文字で頭から3文字でドット「.」を付けます。ただし、「Jun.」と省略しても、発音は「June(ジューン)」です。
「6月」の英語の由来は、古代ローマの月名でラテン語の「Iunius」に遡ります。これは、古代ローマの神である「ユノー(Juno)」にちなんでいて、ユノーは結婚、女性、家族の守護神であり、ローマの神話では6月が彼女に献呈された月とされています。そのため、英語の「June」はこのラテン語の「Iunius」から派生したもので、古代の神話や文化に基づいています。「6月」や女性の名前だけではなく、他の英語でも使われることがあります。例えばjune beetle:June beetle:コガネムシ ※May beetle(bug)とも言われます。
June bride:ジューン・ブライド(6月の花嫁) ※6月に結婚すると幸せになるとの言い伝えがあります。また、「June」の由来は、古代ローマの女性の守護神「Juno」となります。因みに、花婿は「groom(グルーム)」と言います。
◎いつも 今日も(6/2)

◎私たち 日生で輝く 日生が輝く(6/1)



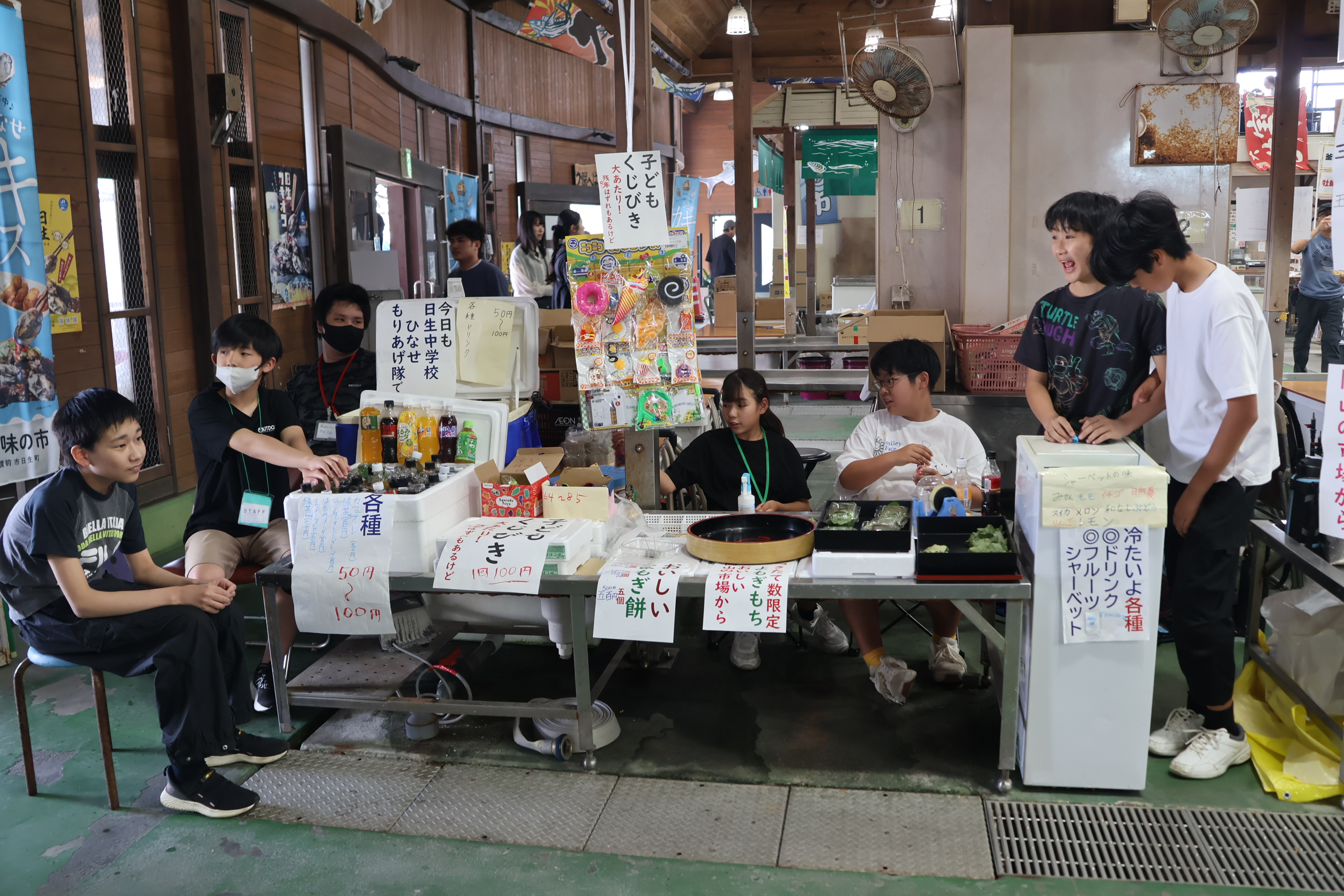








The greatest virtues are those which are most useful to other persons. Aristotle
(最大の美徳は、他人の役の立てることだ。)
◎ほっとスペースでも学ぶ(5/30)
備前未来プロジェクトの難波さんが来校され、次回(6/4)のほっとスペースでのミニ学習会について案内されました。マリールイーズさんが6/21~22に備前市に来られるのに合わせて、日生中ほっとスペースでのイベントのひとつとして計画しているものです。

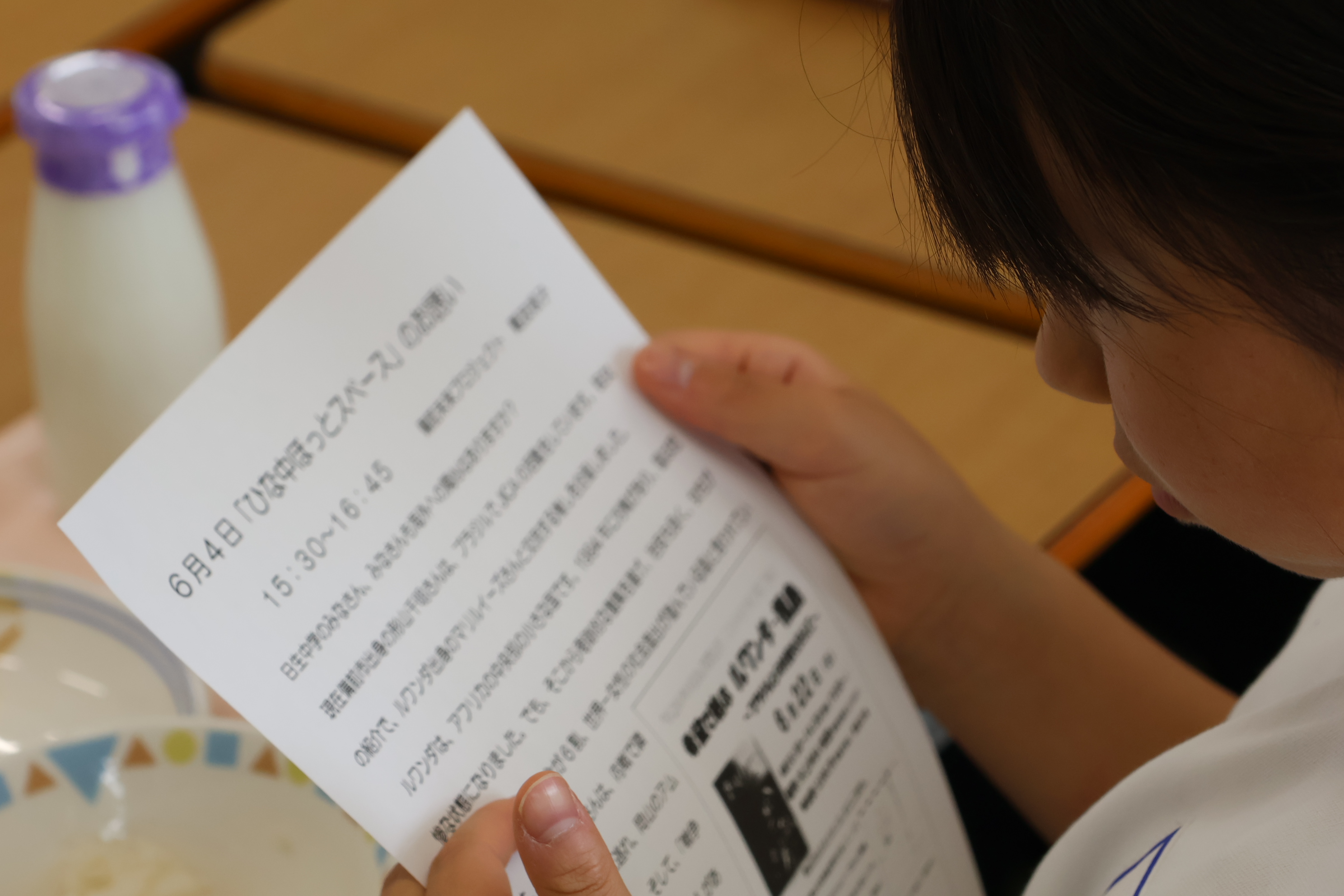
◎ひな中の風~~ カキフェス〈6/1〉へ
今回も、多くのボランティア生徒、ALTの先生方が参画します。ALTの先生方は、母国フィリピンのお菓子を頒布してくださいます。


◎ひなQ1の答え(5/30:今日は2年生が海洋学習)

◎空と大地の間に(5/29:係会)
準備・練習・仲間・誇り・責任









◎日生で学ぶ私たちの未来(5/29:1・3年生アマモの回収)









◎「みんなでがんばっているなあ~(⌒∇⌒)」上空のつばめより(5/30)



◎語り合うひな中の 生徒集会✨(5/30)





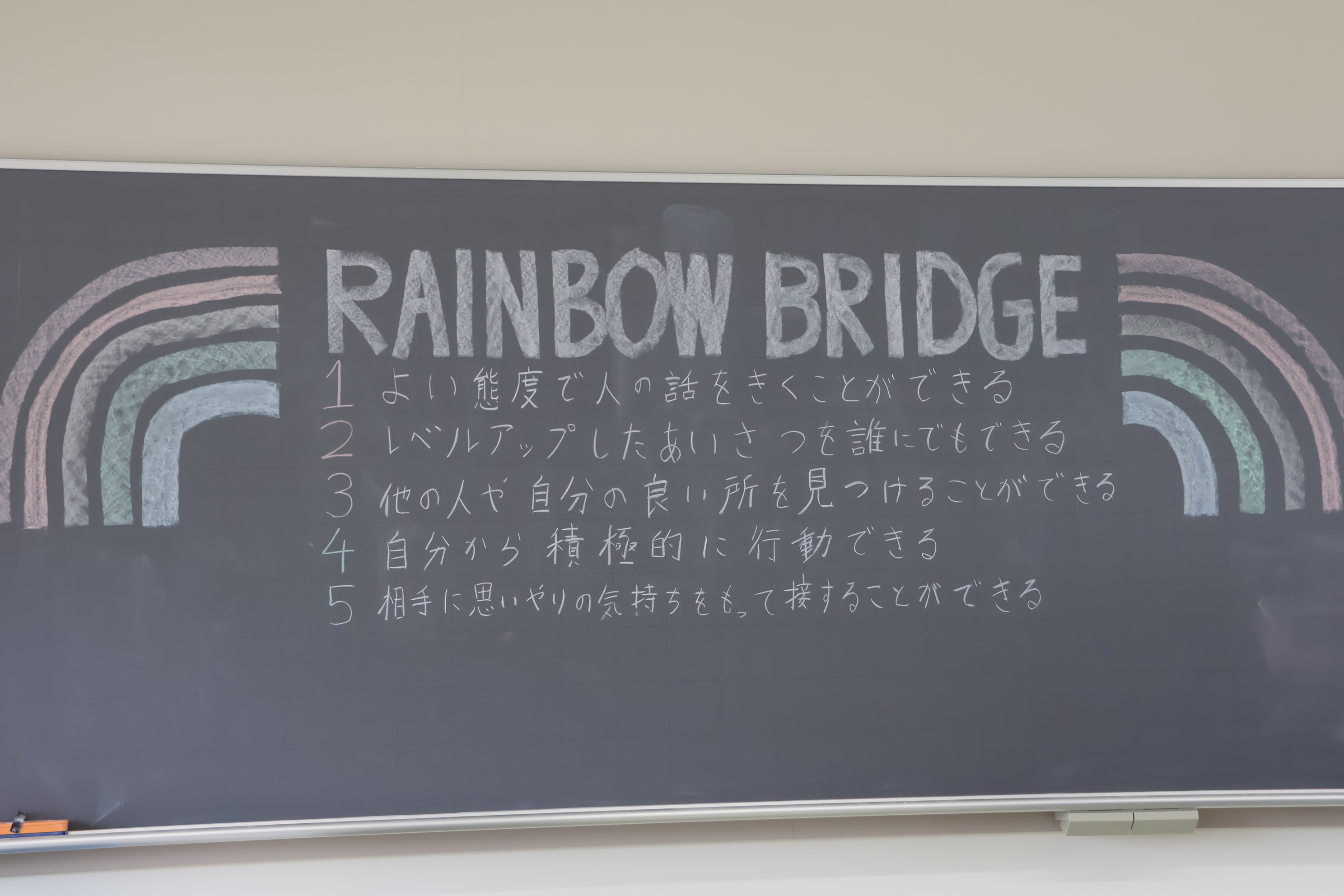
ひなQ1:下足箱の上にみんなが置いてあるモノは何でしょう? ヒント・日生中学校名物。
◎未来とは今である Margaret Mead(5/29)

◎確かな絆に。



◎ひな中の頑張っている姿を!
市教委が学校訪問(5/28)

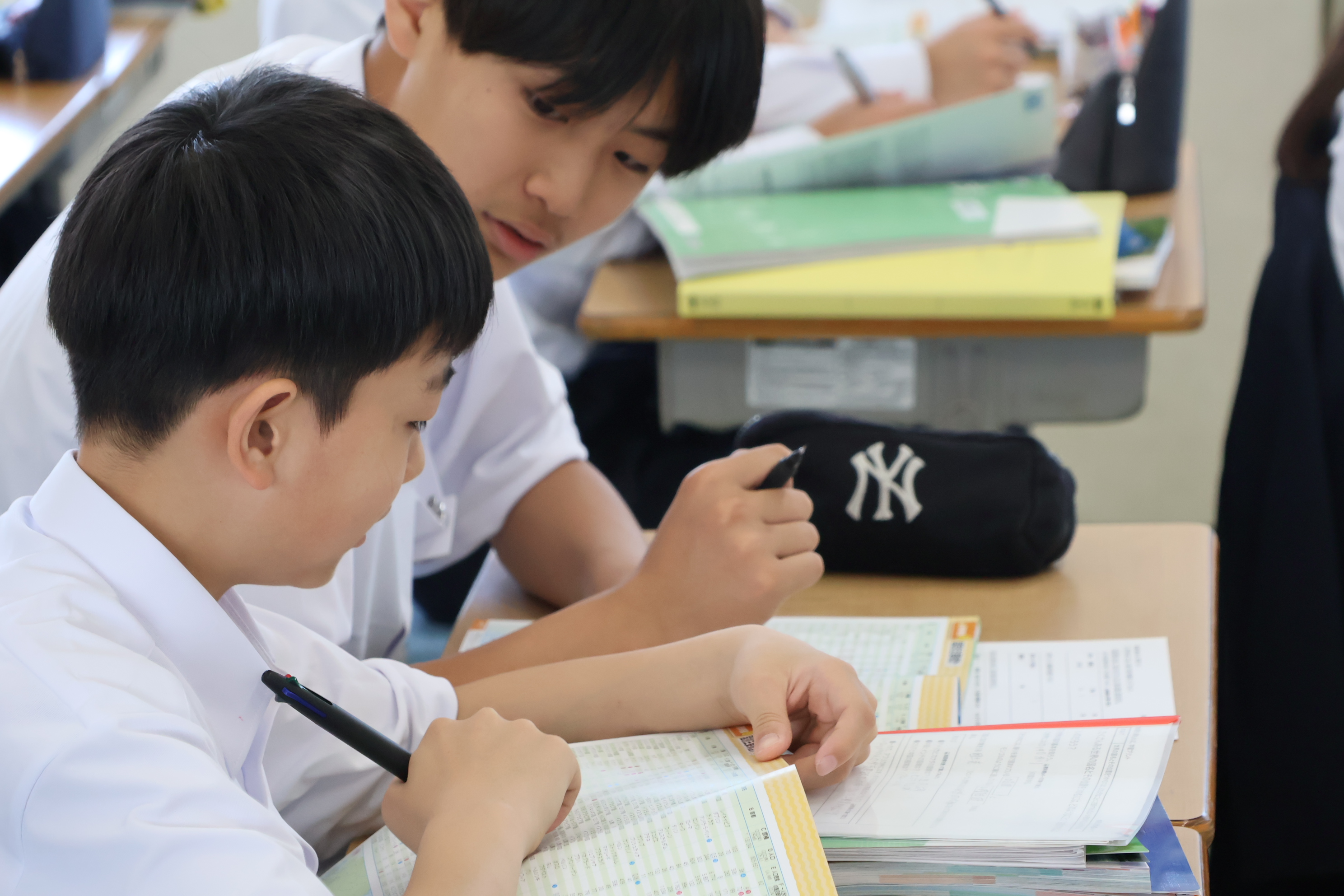




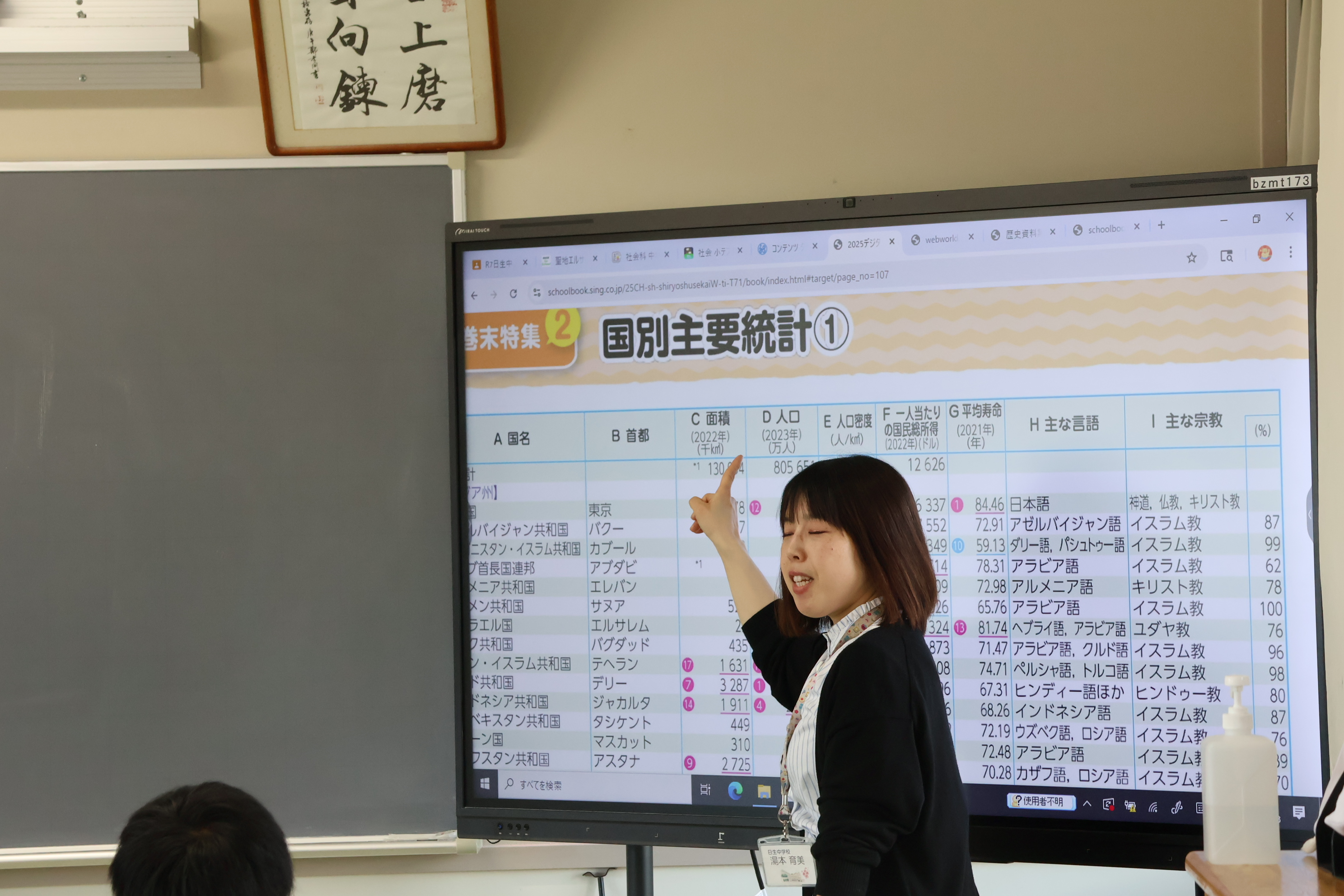
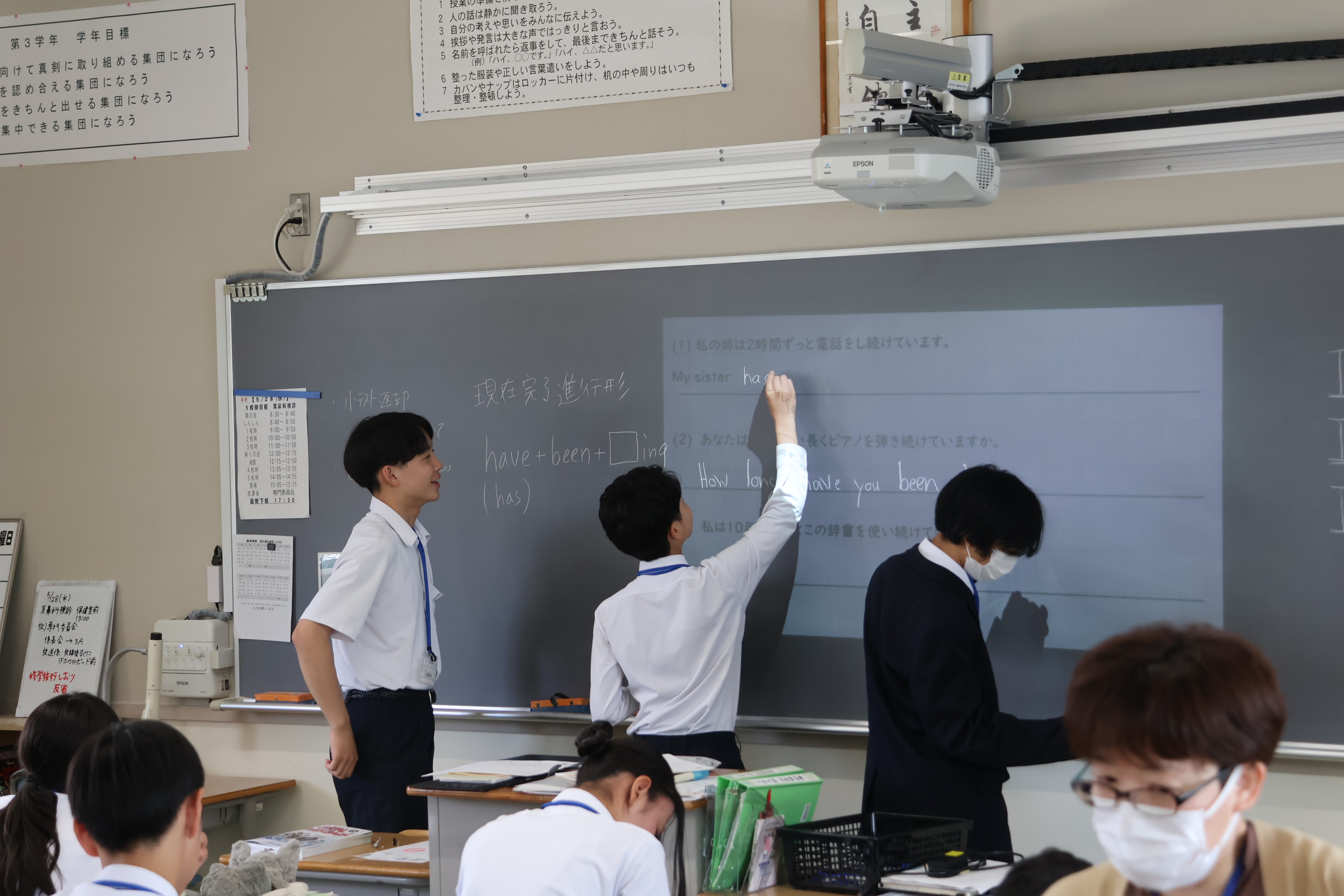
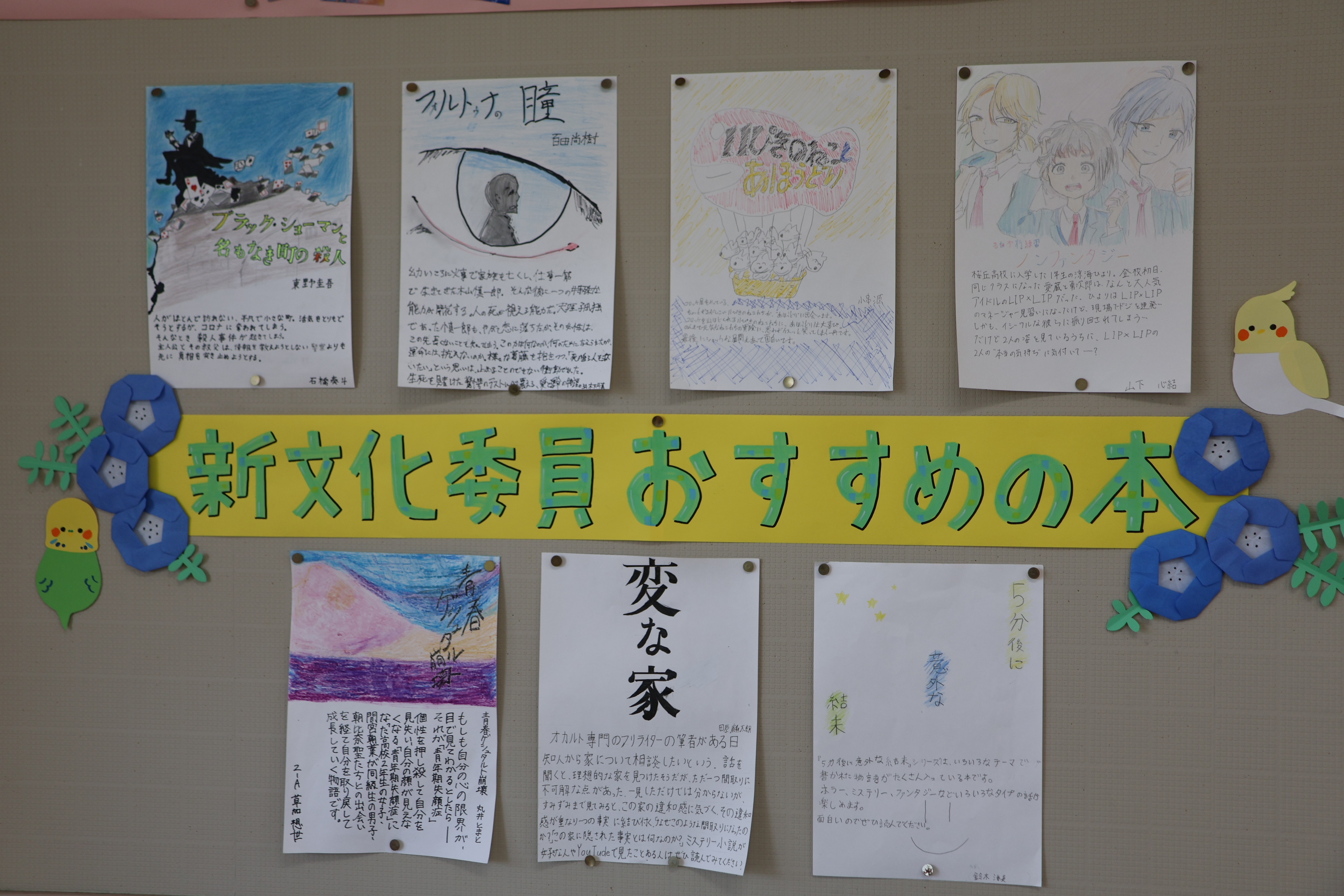
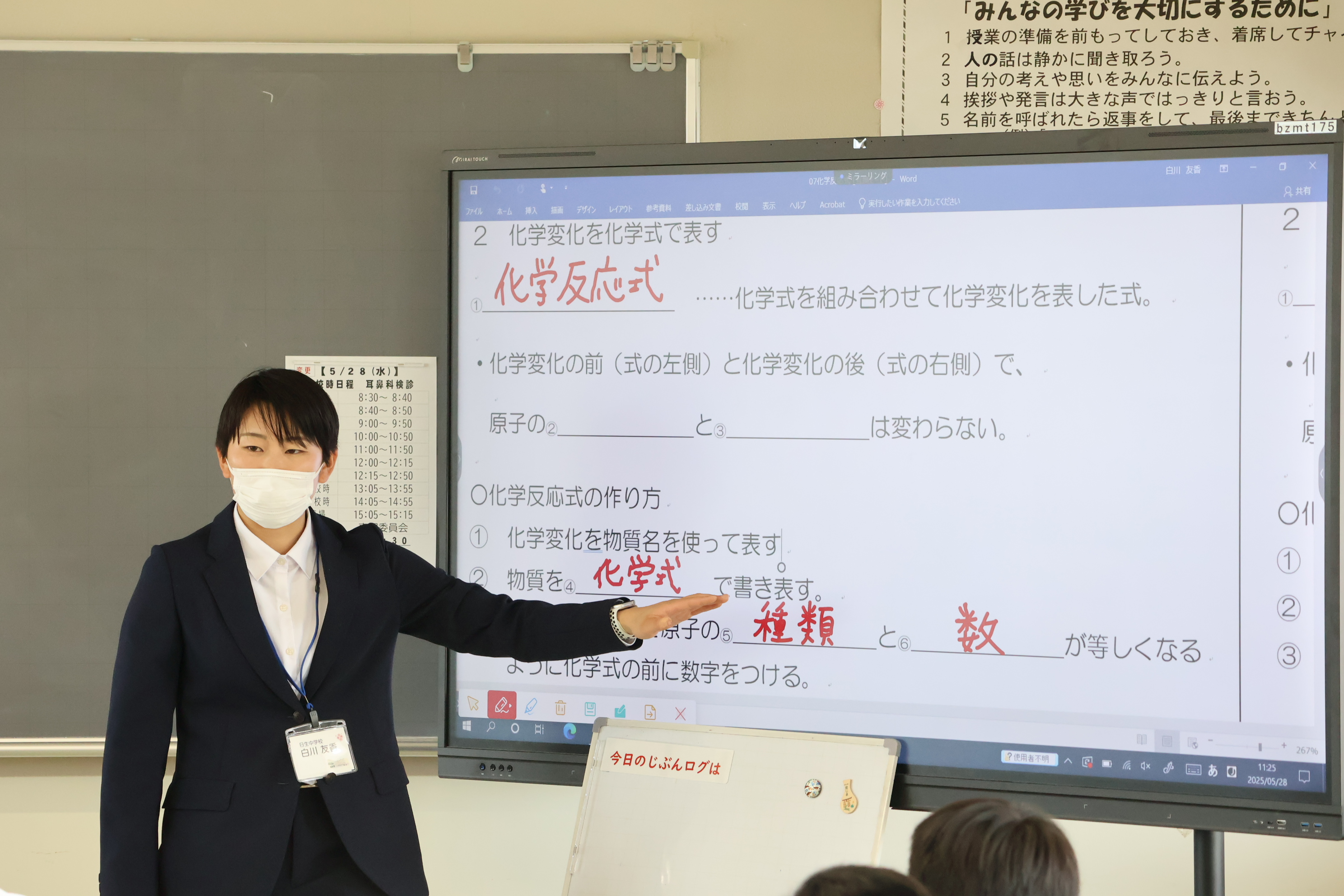


◎私たちの星輝祭(体育の部)の創造へ(5/27)
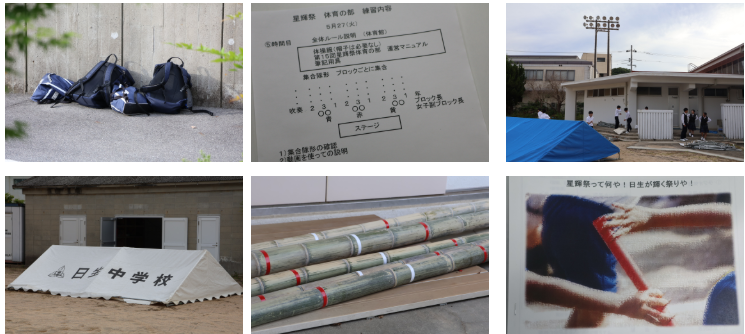
◎多くの人に支えられて(5/26)
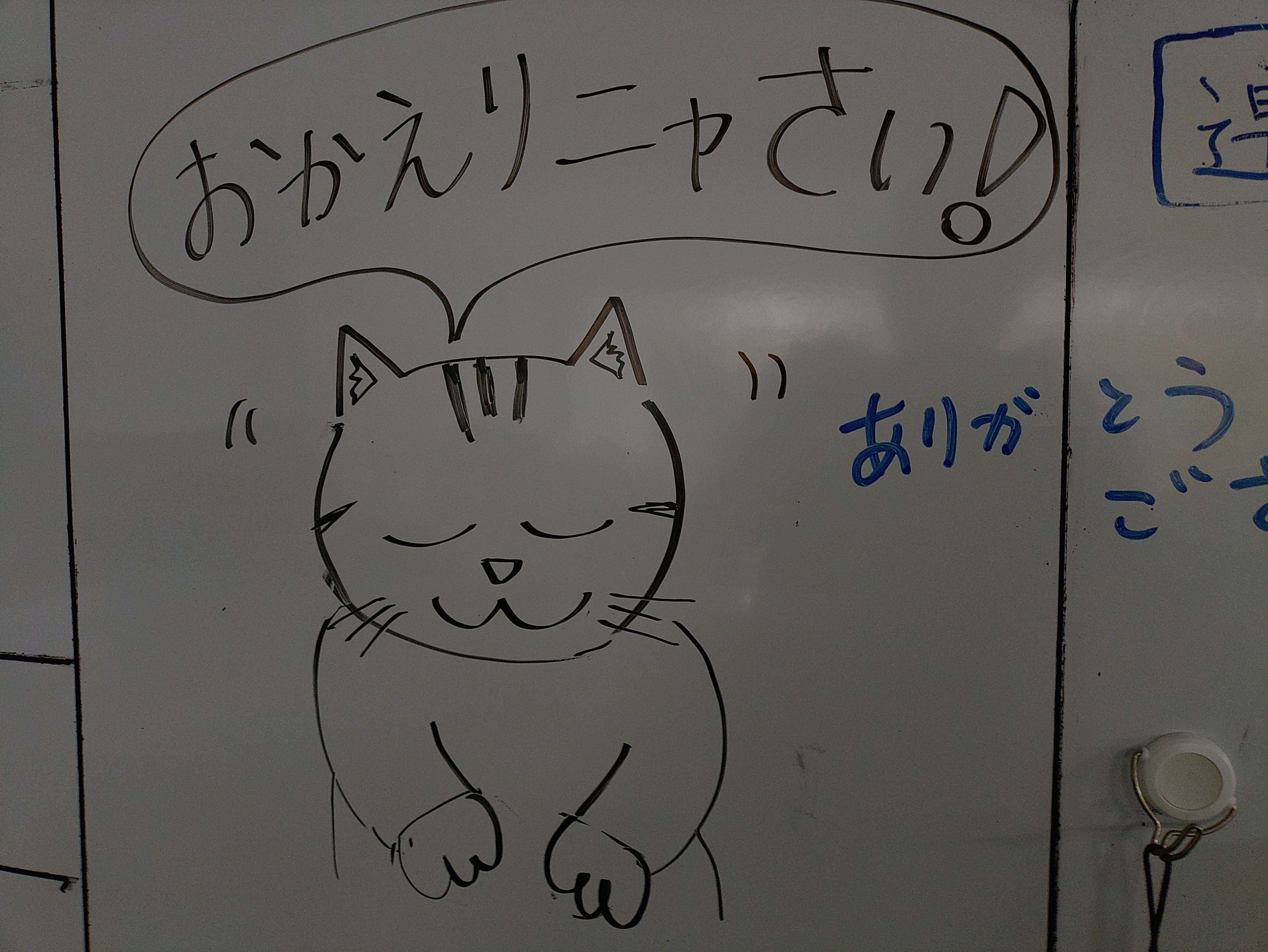
◎ひとの右にはひとがいる。左側にもひとがいる。前も後ろも、ひとにひと、ひとの上には、ひとはなく、ひとの下にも、ひとはなし。頭にかぶるは、青い空。足に履くのは、黒い土。わが道を行く、独立者。ひとさまざまに、生きながら、誰かを支え、支えられ、東西南北、ひとだらけ。持ちつ持たれつ、仲間として。南北東西、虹の波、下にも上も虹の色。多くの人に支えられながら、いま、そしてこれからも。









◎修学旅行を私たちが創るということ(5/21~23)



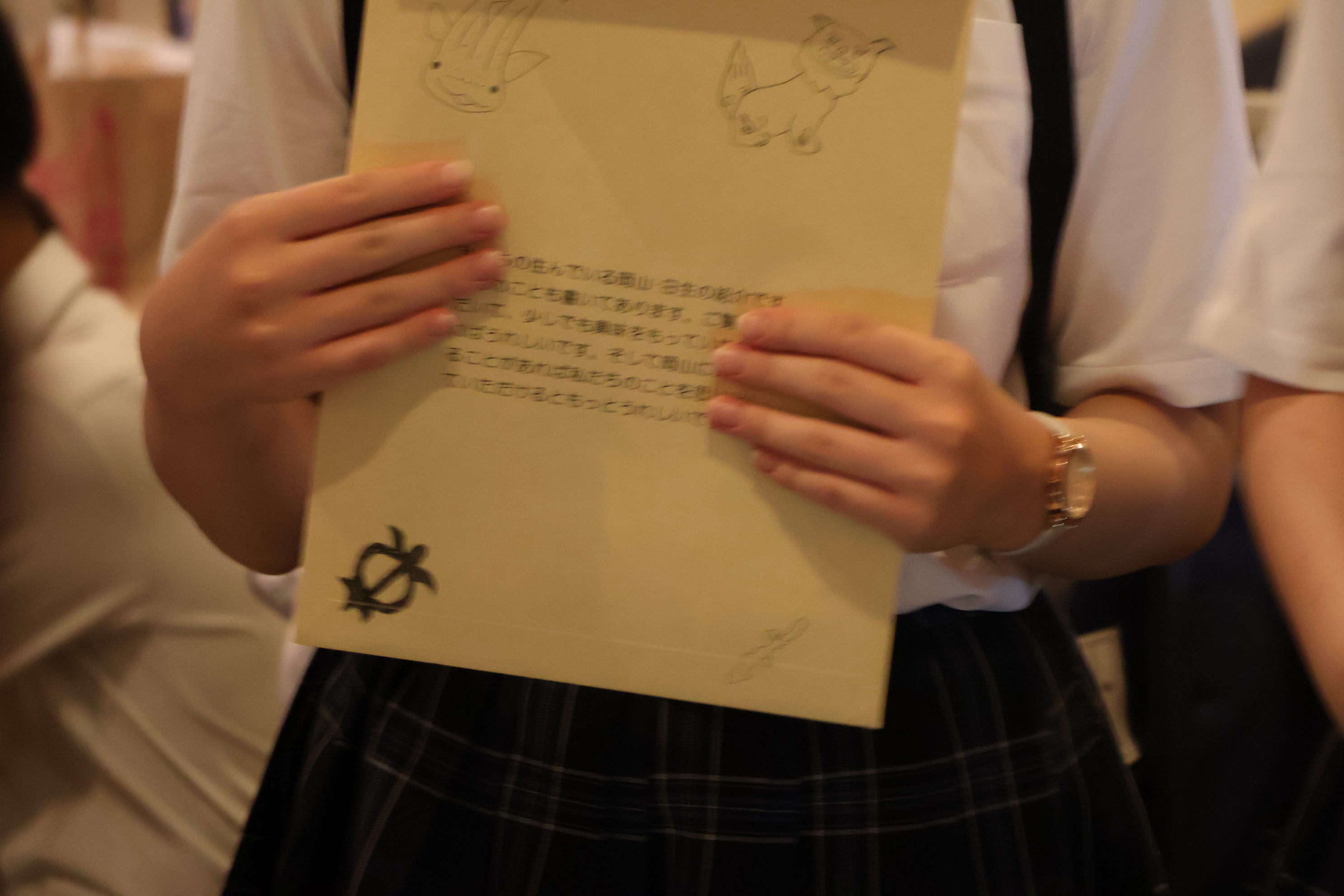



◎知ることは考えること 考えることは生きること(6/21:修学旅行)






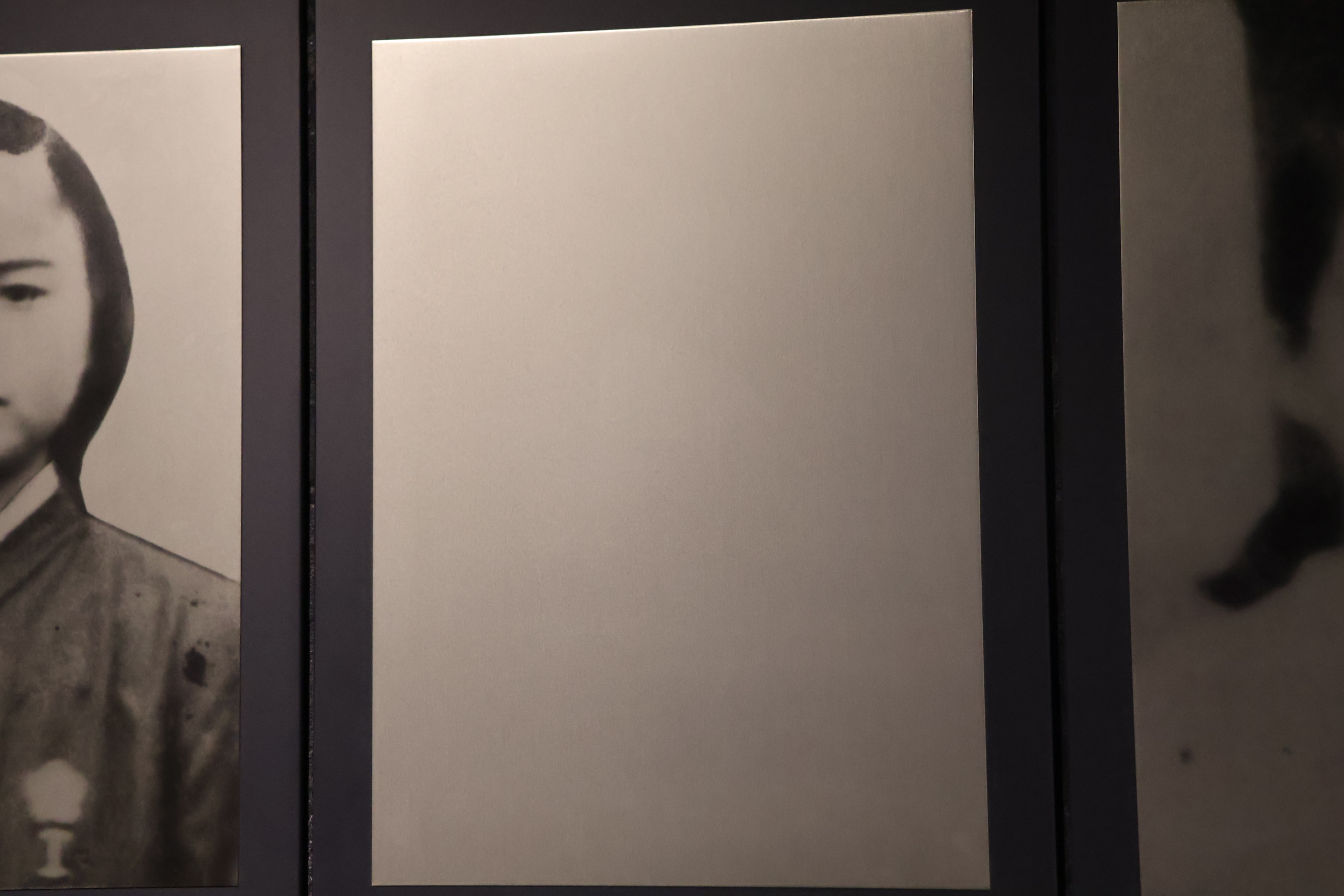
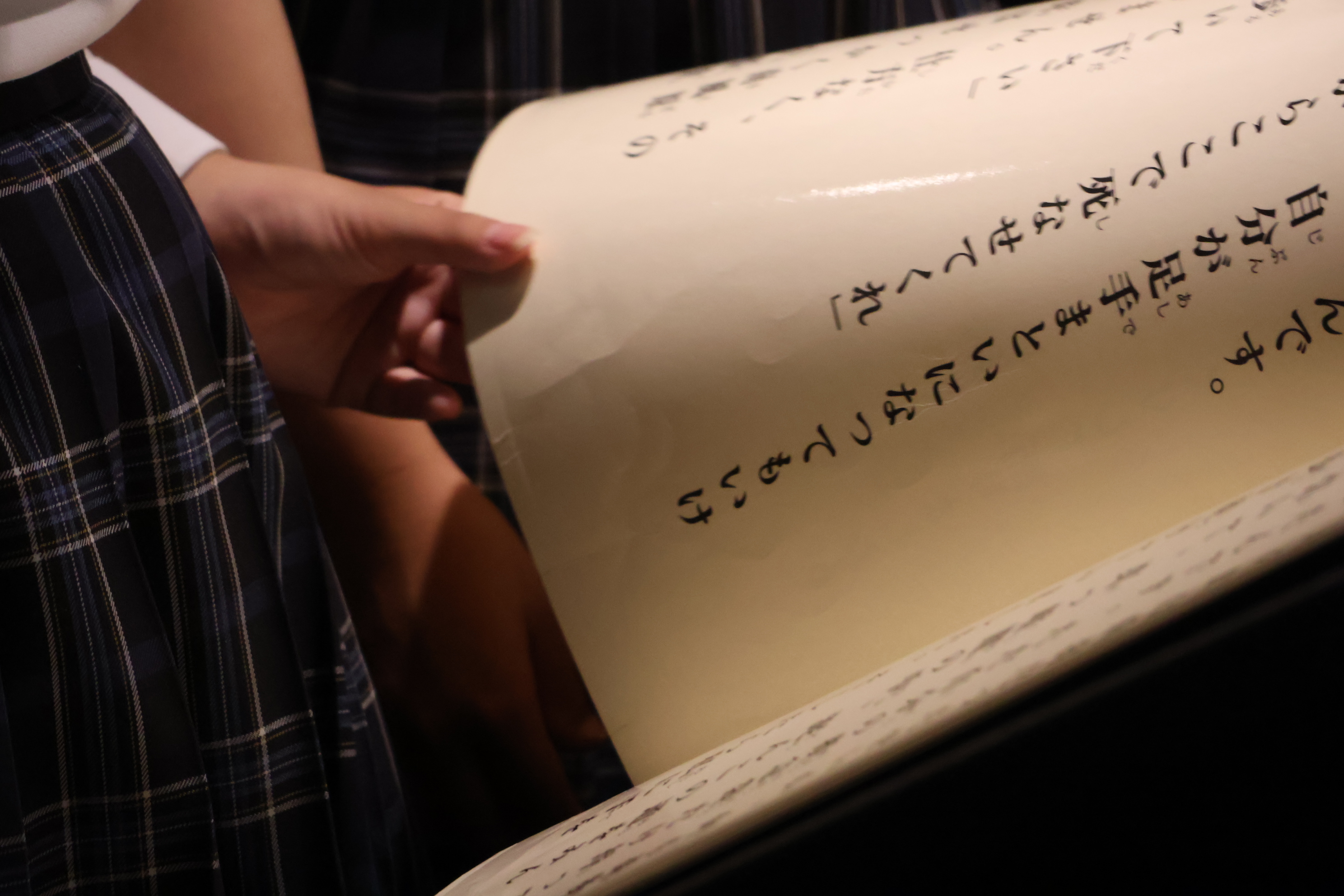
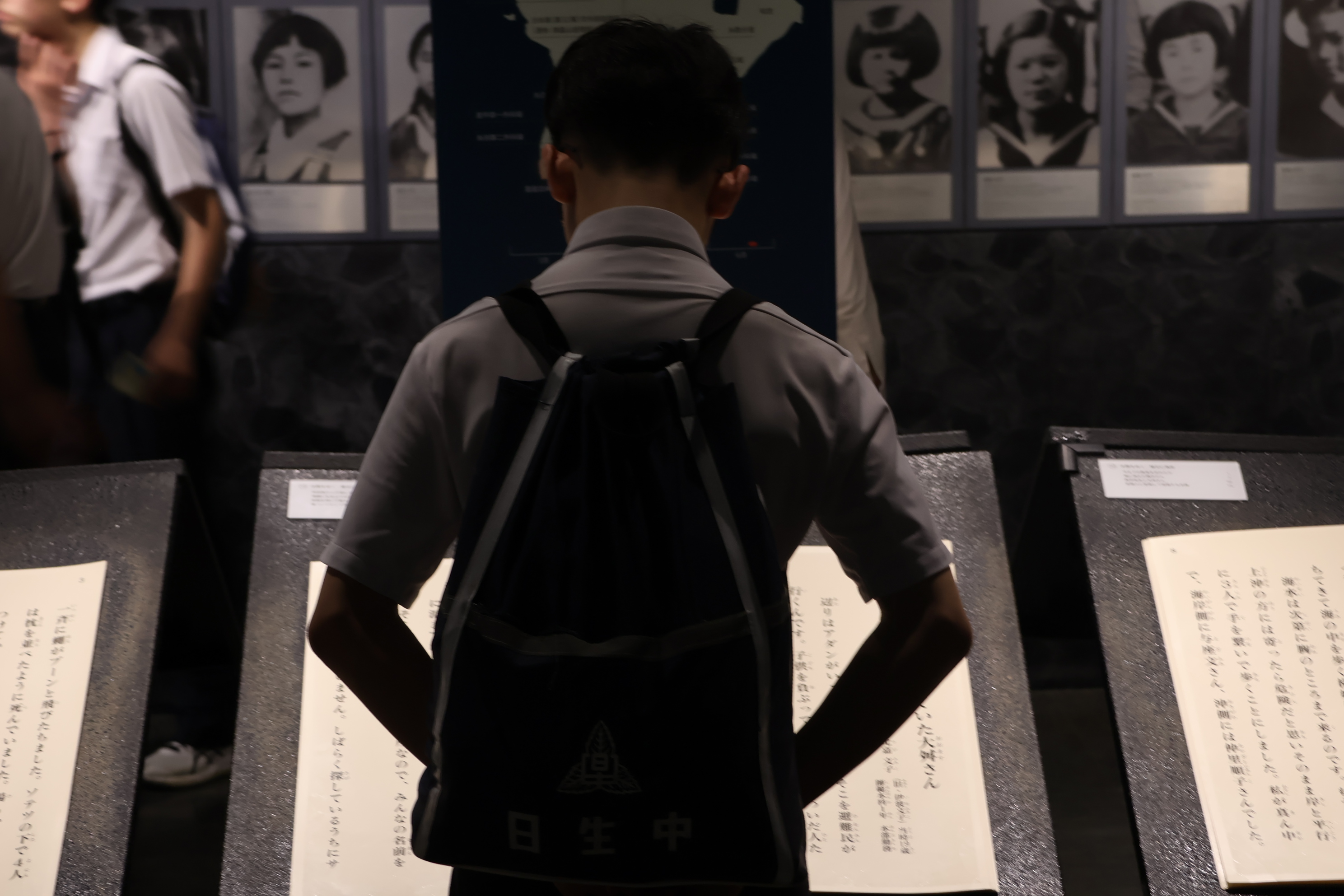
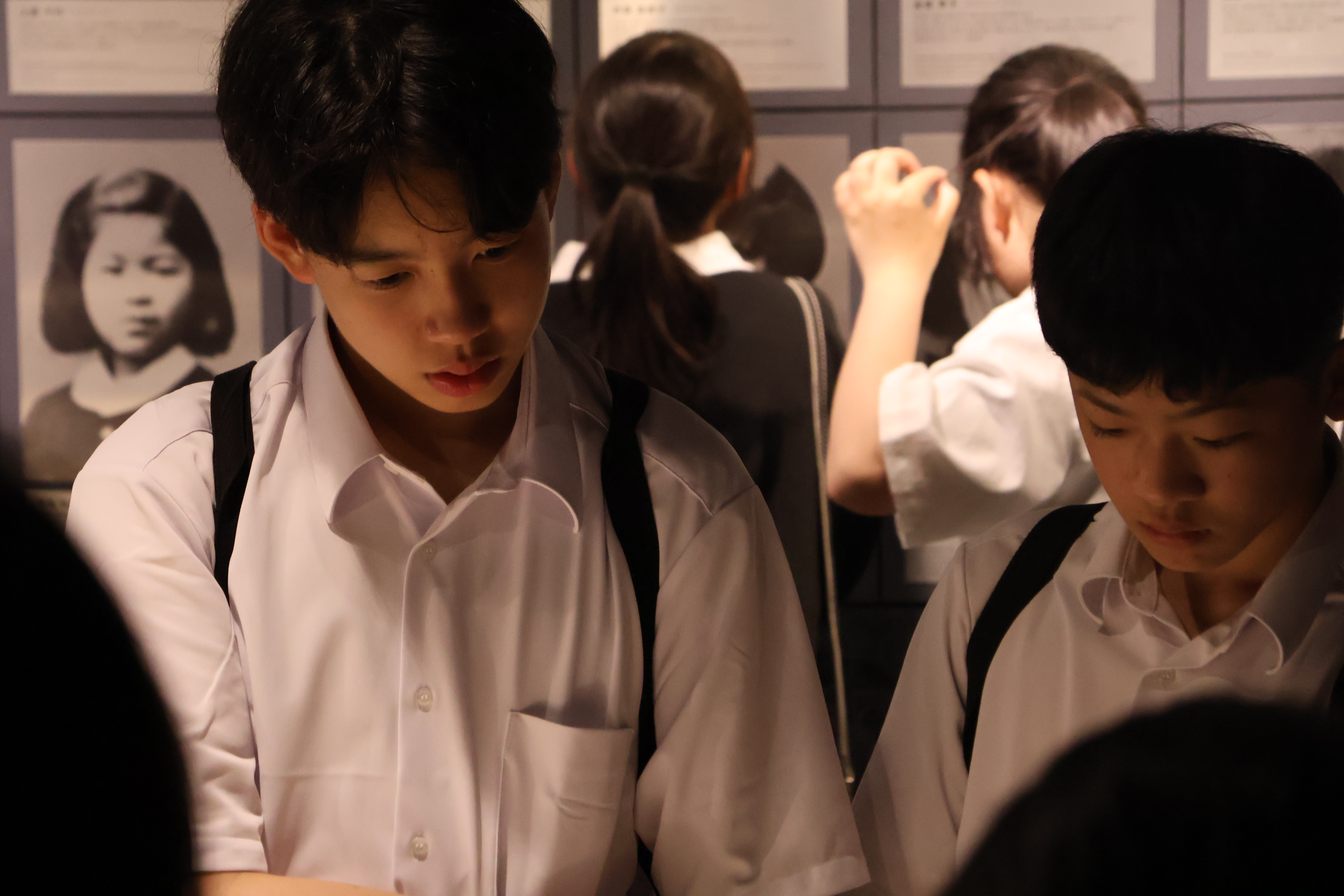
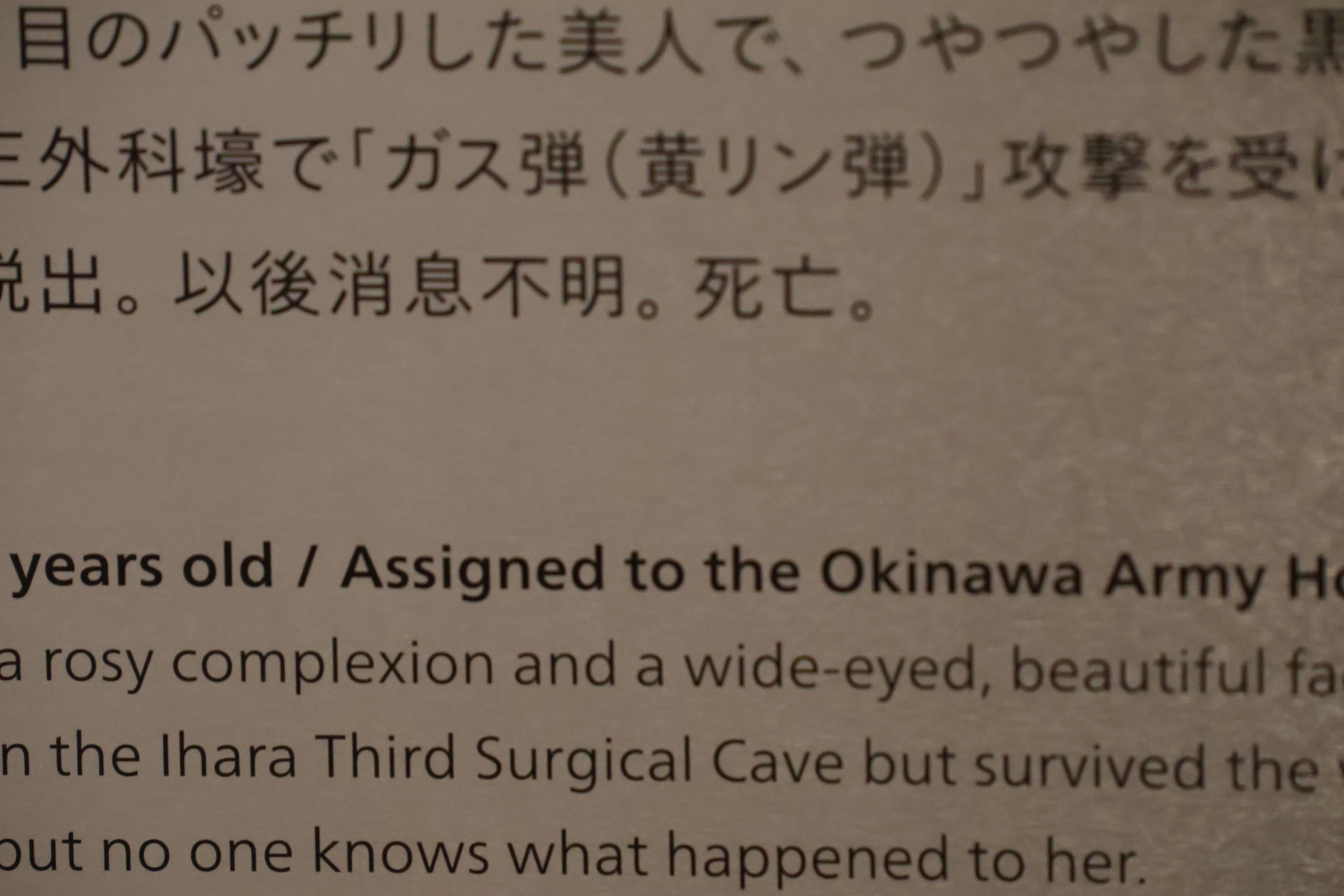
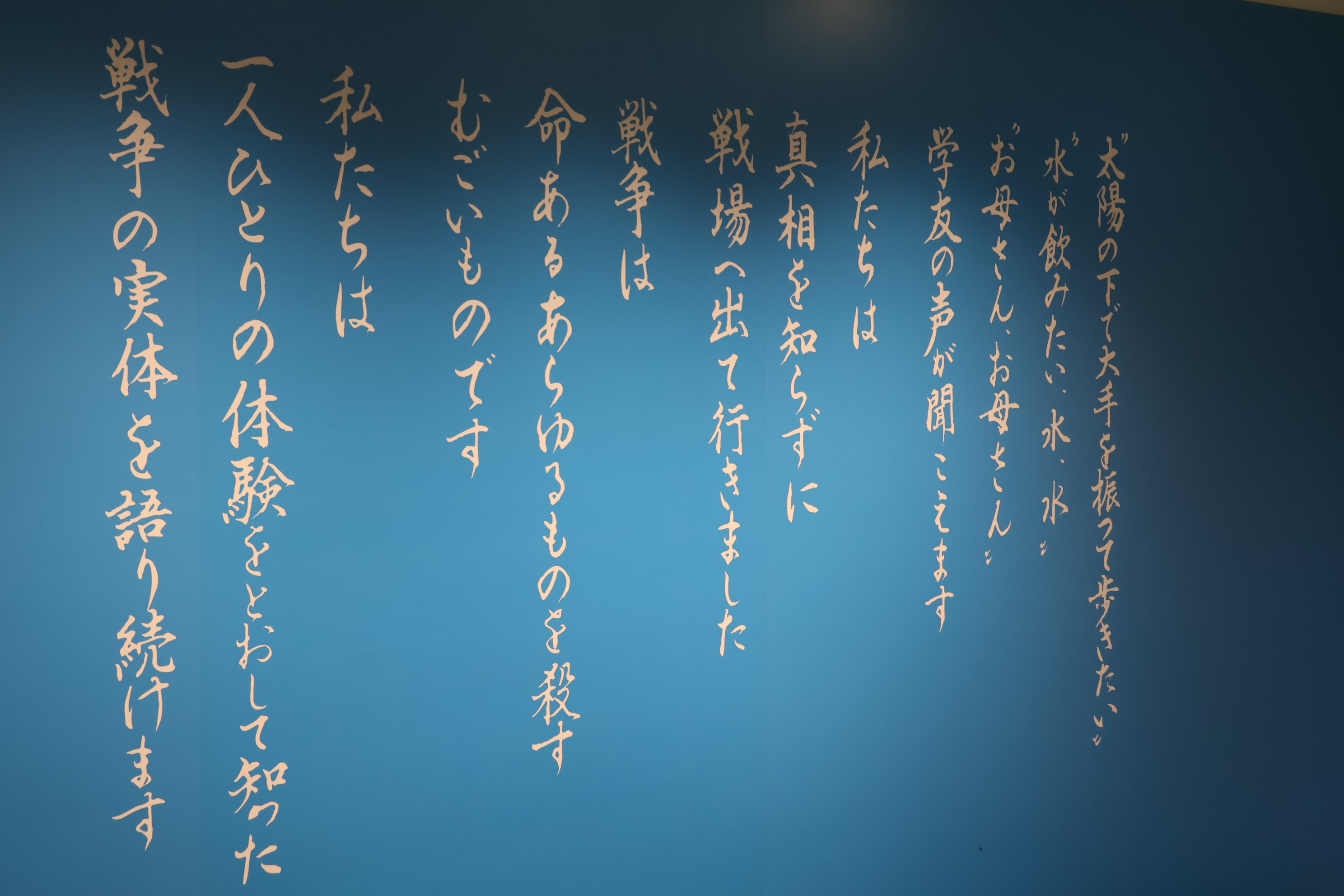

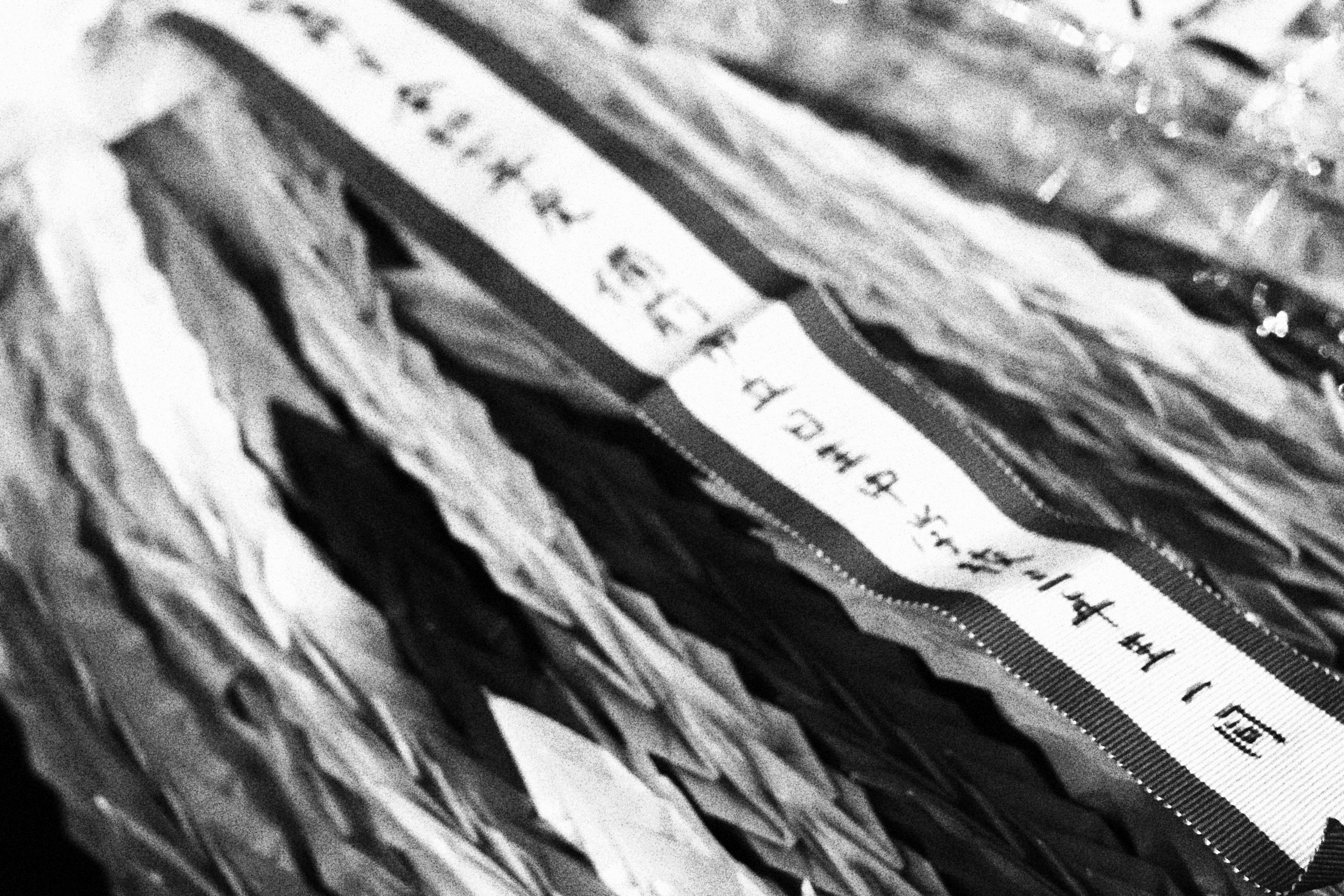




◎この地に立って
明日から3年生は沖縄修学旅行(~23日)、2年生広島研修(23日~24日)です。仲間と共にたくさんのことを学んできます。旅行の準備や応援をしてくれるお家の人に感謝して行ってきます。三年生の事前打ち合わせ会には、備前市観光協会の村上さんが来てくださりエールをおくってくださいました。ありがとうございました。
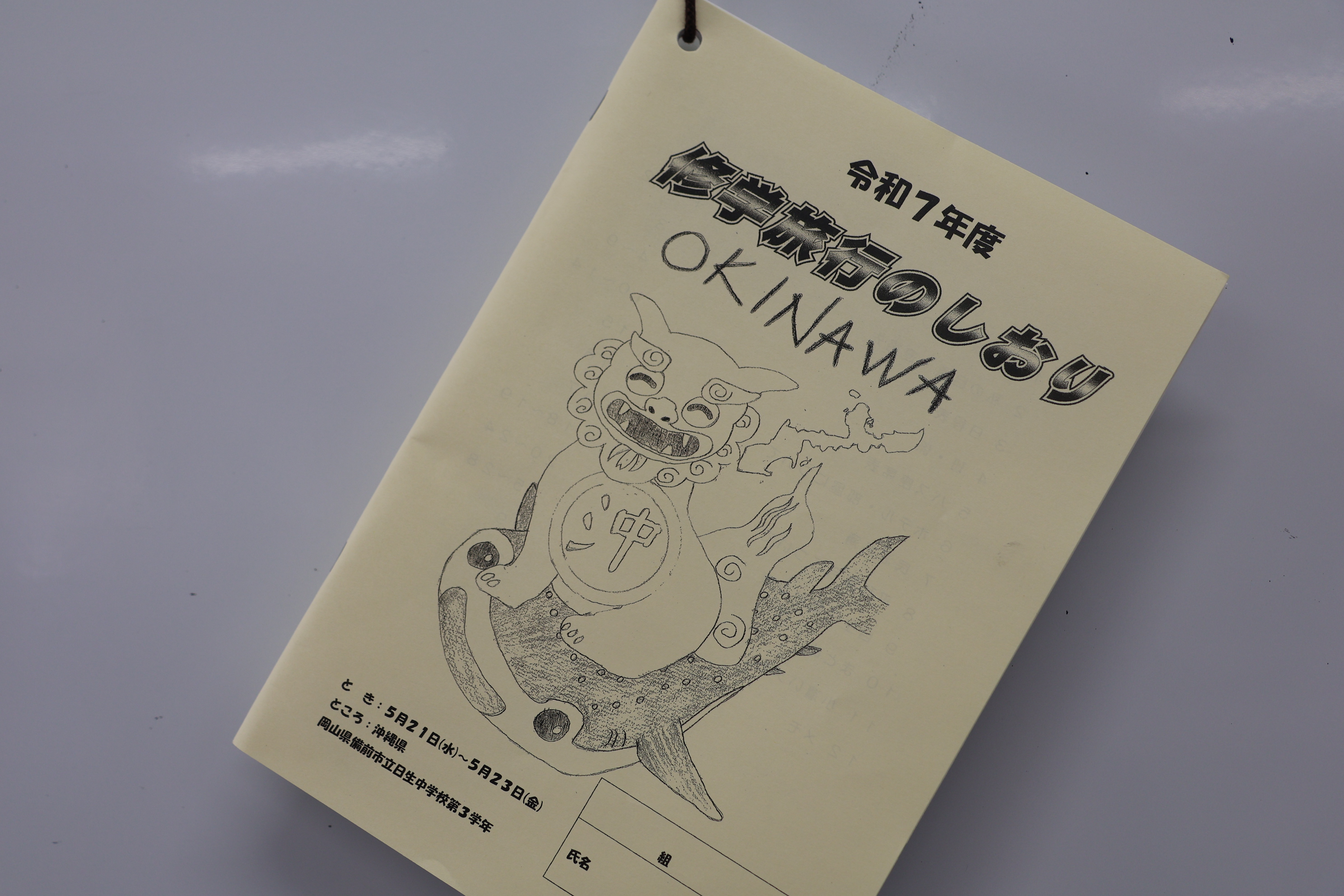

◎ひな中の風✨
~豊かで、確かな学びを(5/20)
今日の山陽新聞を紹介します。
◎♬ことば、リズム、笑顔を。(9/19)
妹尾先生をお招きして、「島唄」の歌唱練習に取り組むことができました。

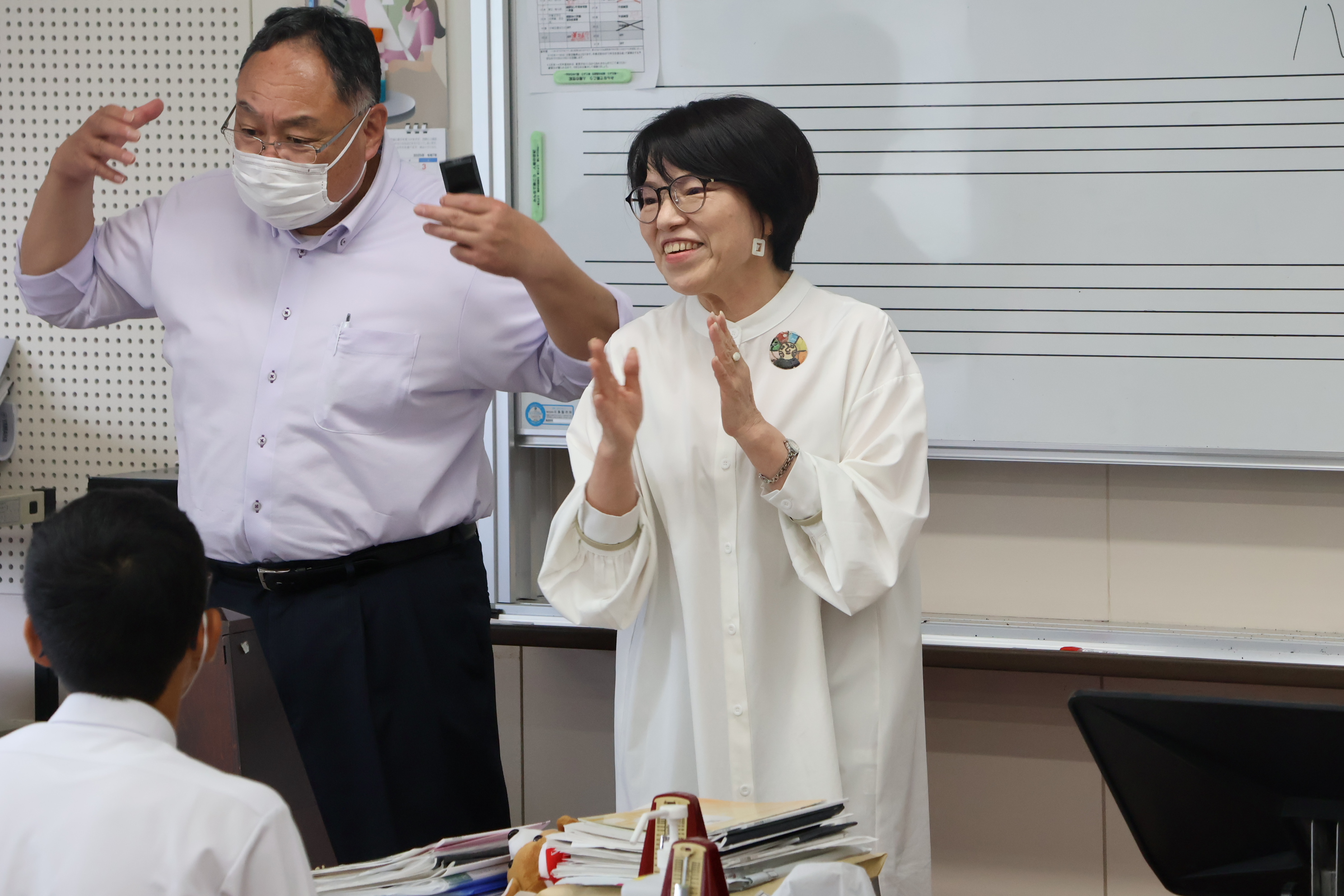

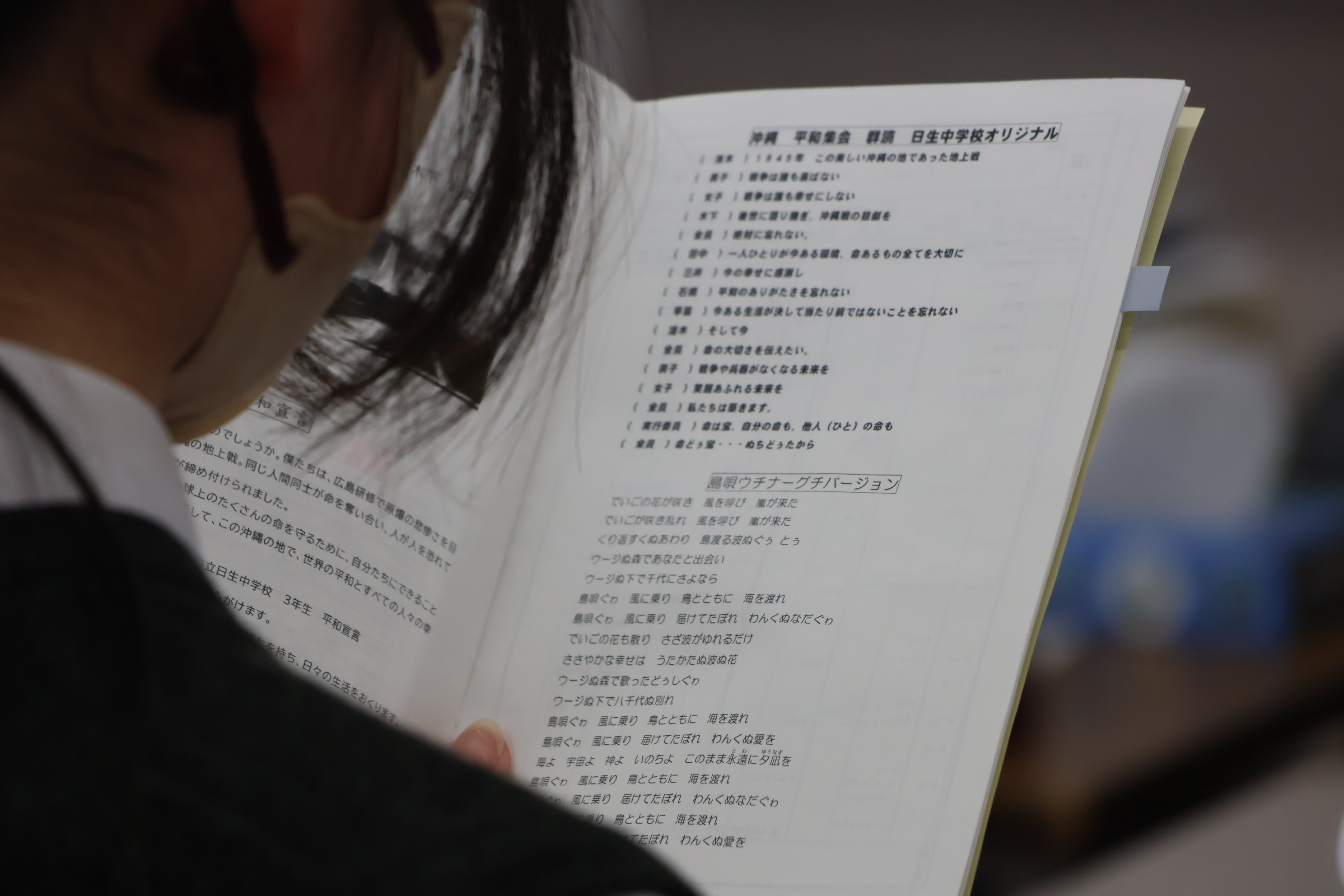

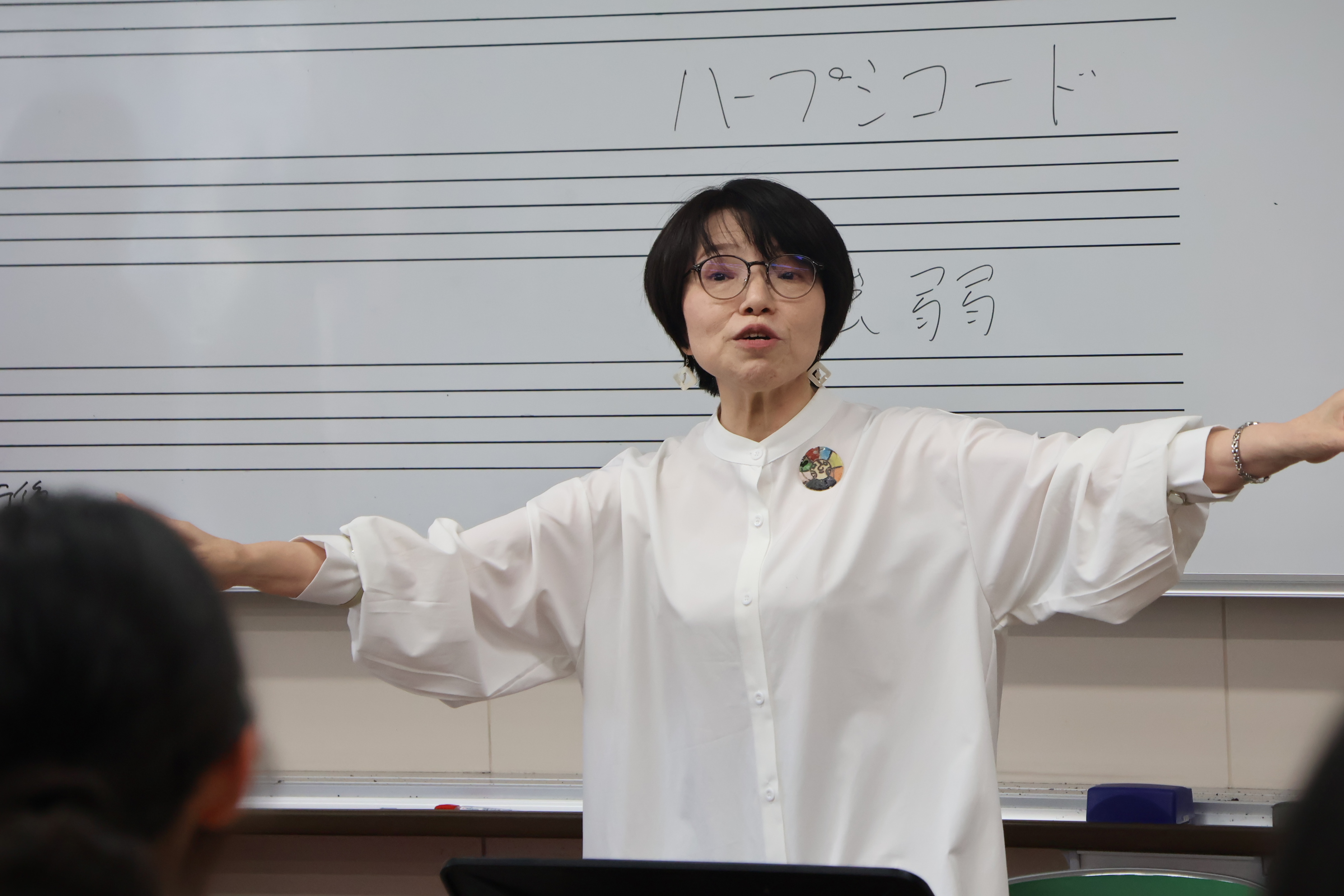
多文化共生社会は、今・ここから。(5/19)
make conversation



◎多くの人に支えられて(5/16)
AEDの点検とバッテリーの交換をして頂きました。ありがとうございます。

◎多くの人に支えられて(5/16)
新しく来られた先生方の取材にひなビジョンさんが来校されました。


◎十五の春へ 確かな〈こ小中連携〉を。
昨日、第1回日生中学校区連携推進委員会を開催しました。この日生中学校連携協議会の目的は、15年間を見通した系統的。継続的な指導により、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を図ることとして、3つの部会(学力向上 生活指導、特別支援教育)を中心に、こども園、小学校、中学校の全教職員で取り組んでいます。



◎日生から学ぶ未来。(5/15)
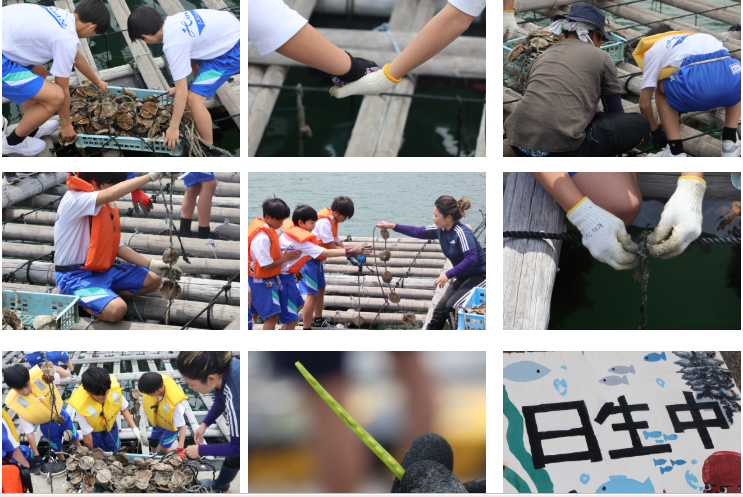
第1学年 海洋学習 「カキの養殖体験活動(カキの種付け)」
1 目的
(1) 「総合的な学習の時間」の海洋学習の一環として、カキ養殖の体験活動を通して、日生町の基幹産業である漁業の現状や特色について理解を深める。
(2) 実際の作業に取り組むことで、働くことの意義や大変さを実感し、勤労の尊さを学ぶ。
(3) 地域の方々のご指導を受けながら活動することで、地域に対する親しみや感謝の気持ちを育てるとともに、地域社会との交流を深める。
*NHK、KSB、ひなビジョンの放送ニュースもご覧ください。
◎よりよい生活をつくる (5/15)
全校アンケートをもとに「ひな中クールビズ」についてまとめ、今日は各クラスでの説明を行いました。タブレット端末を使い、詳細を確認することができました。
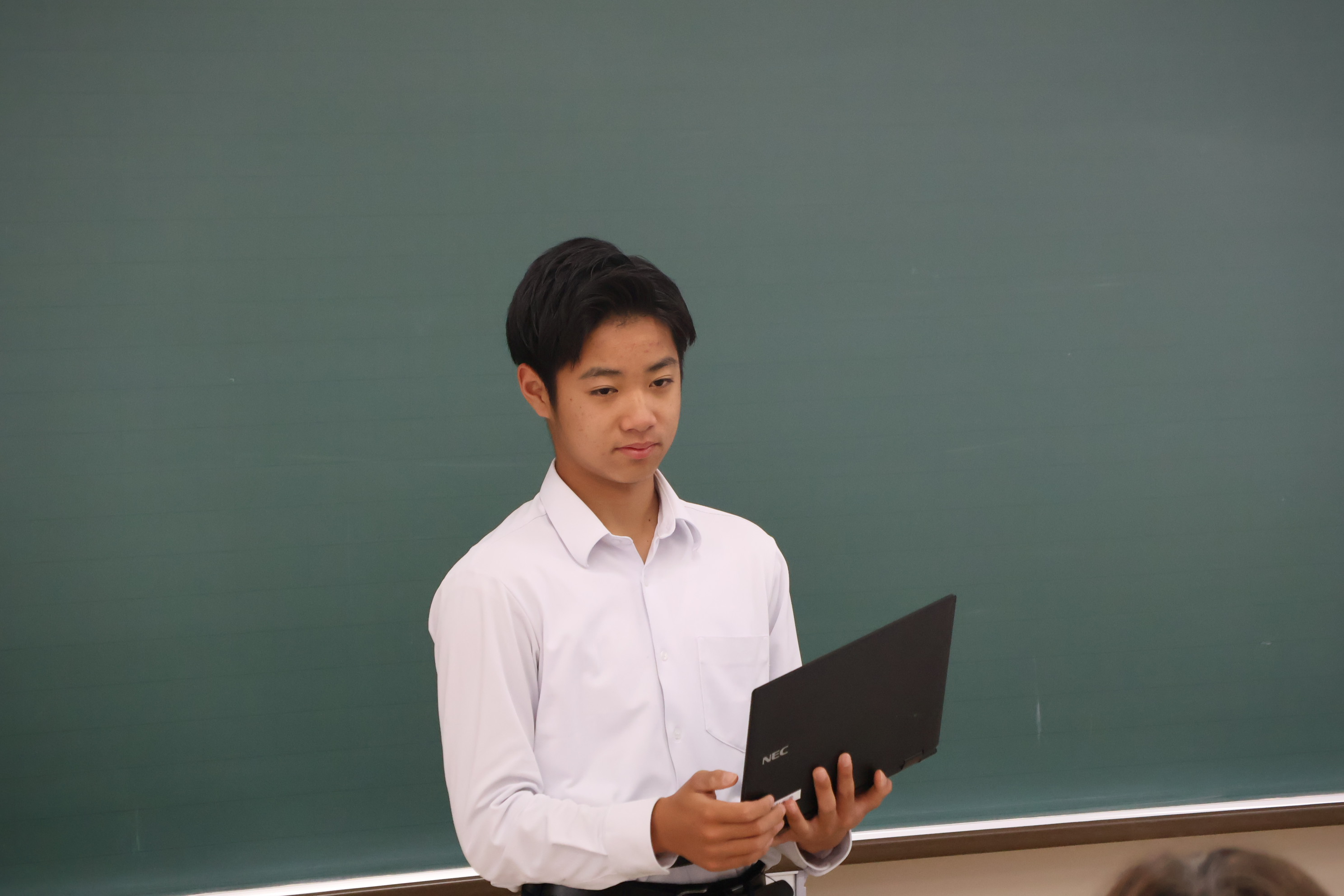
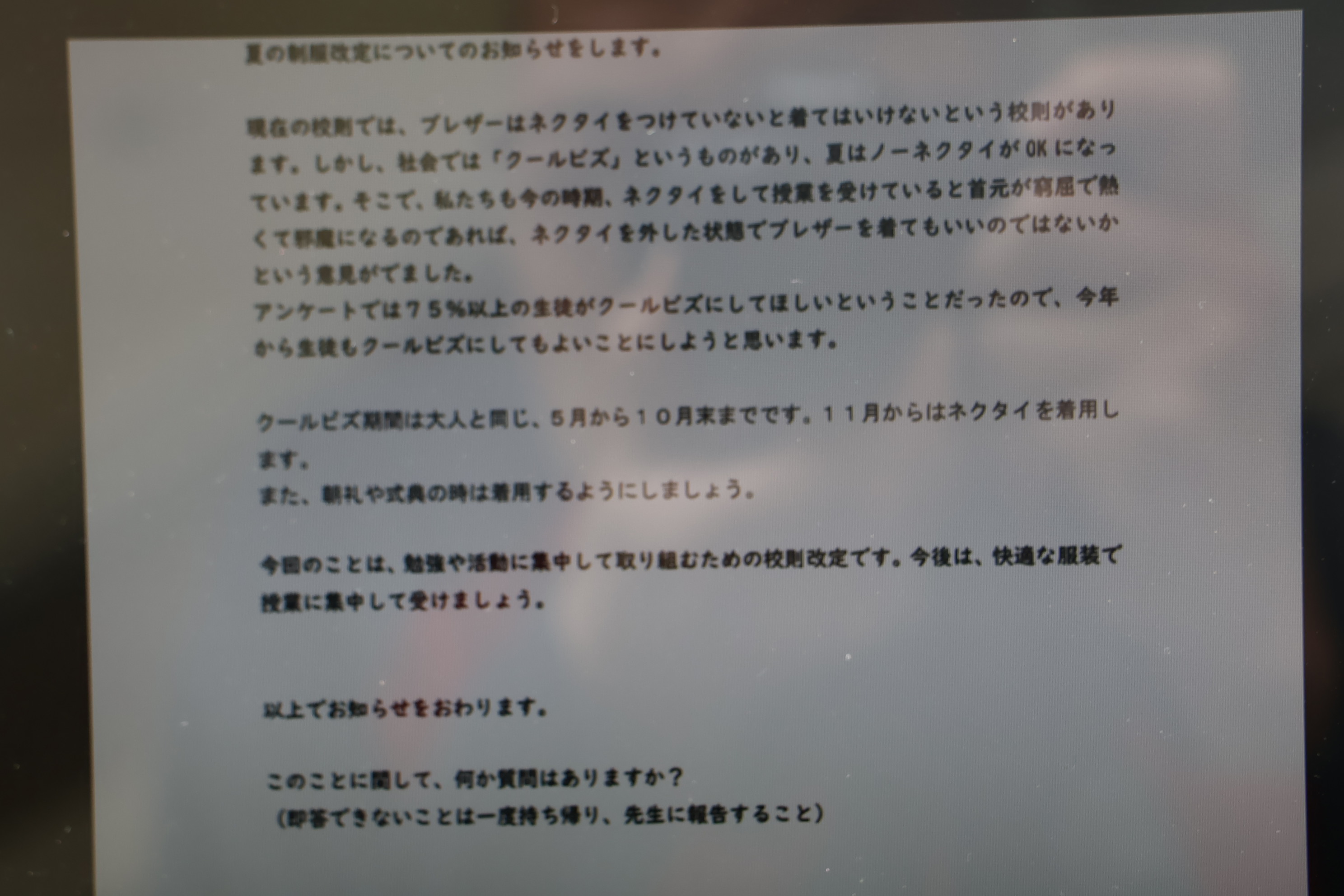

〈新緑やかぐろき幹につらぬかれ 日野草城 5/14〉



日生中学校グラウンドで、備前サンラッキーズが練習に励んでいます。
◎自分らしく せいいっぱい

◎責任・誇り・絆(5/14:体育の部 放課後・係会)
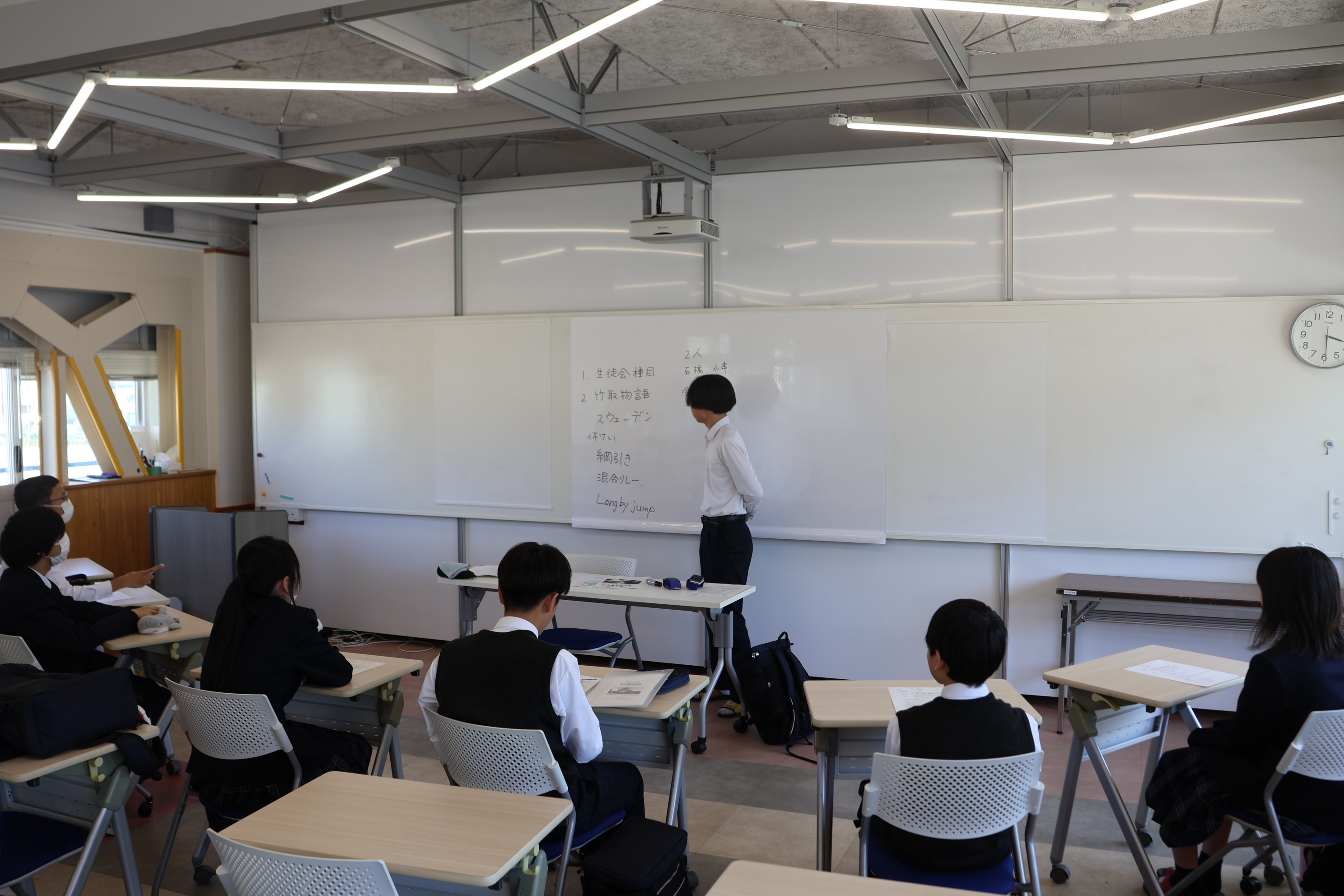
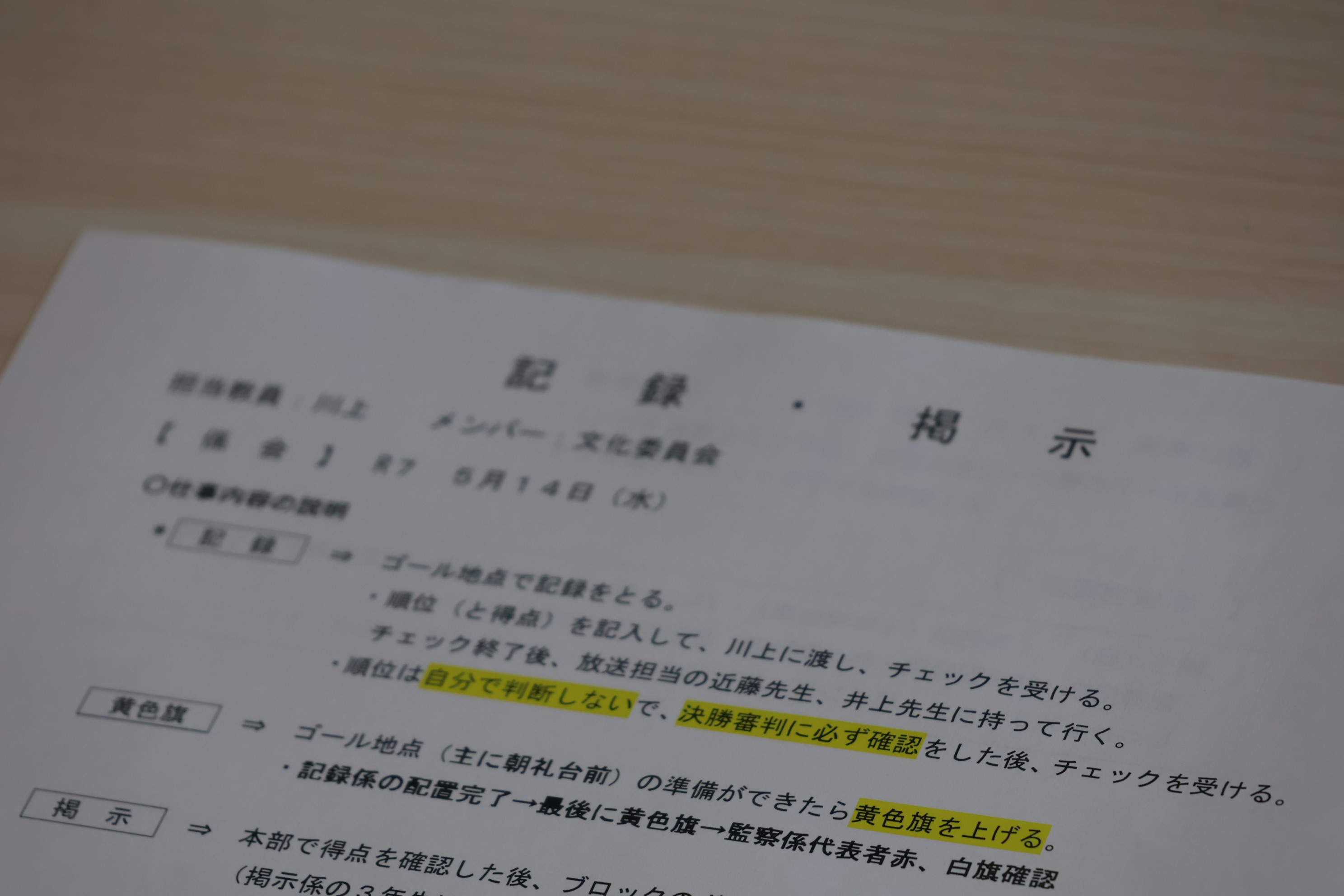
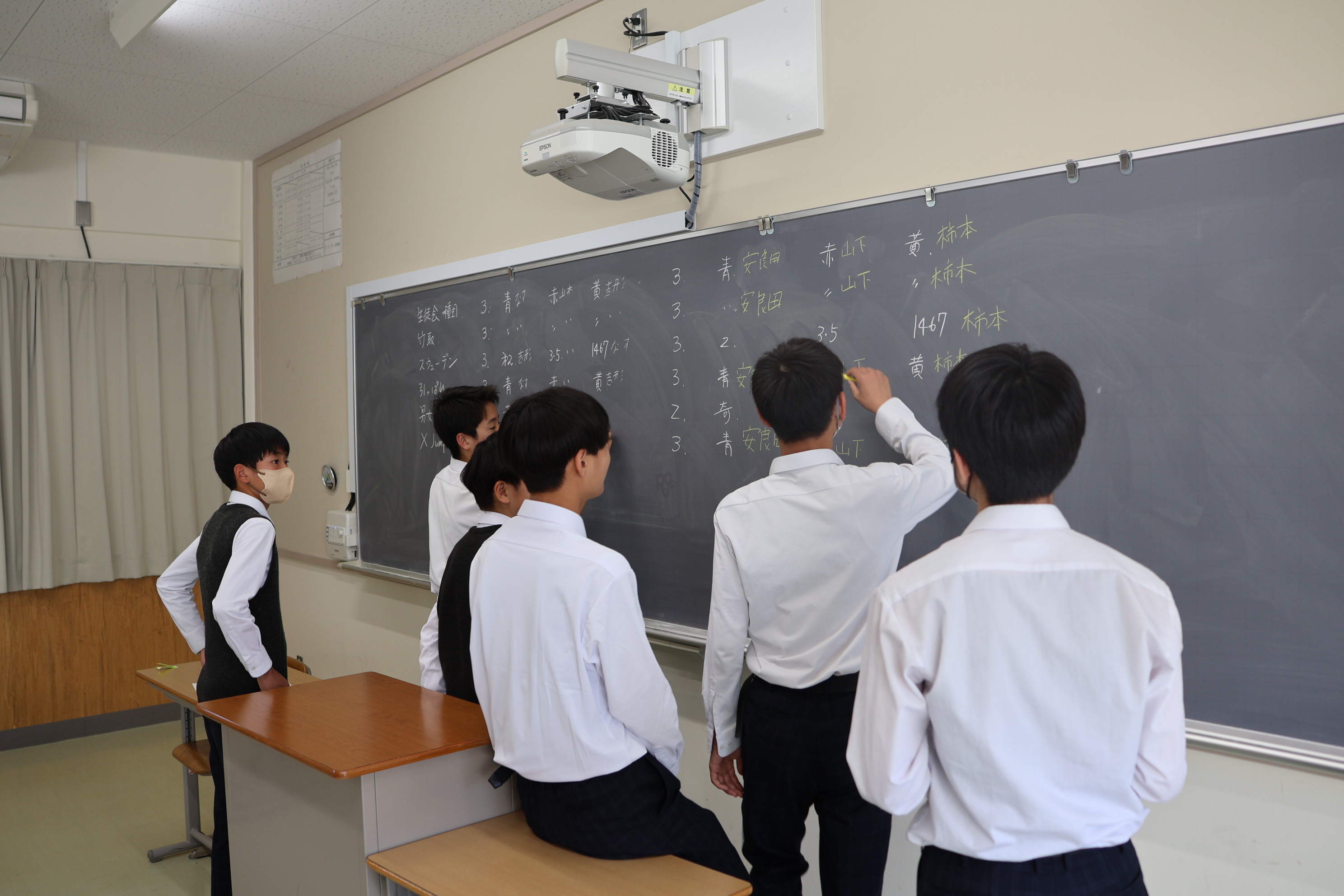
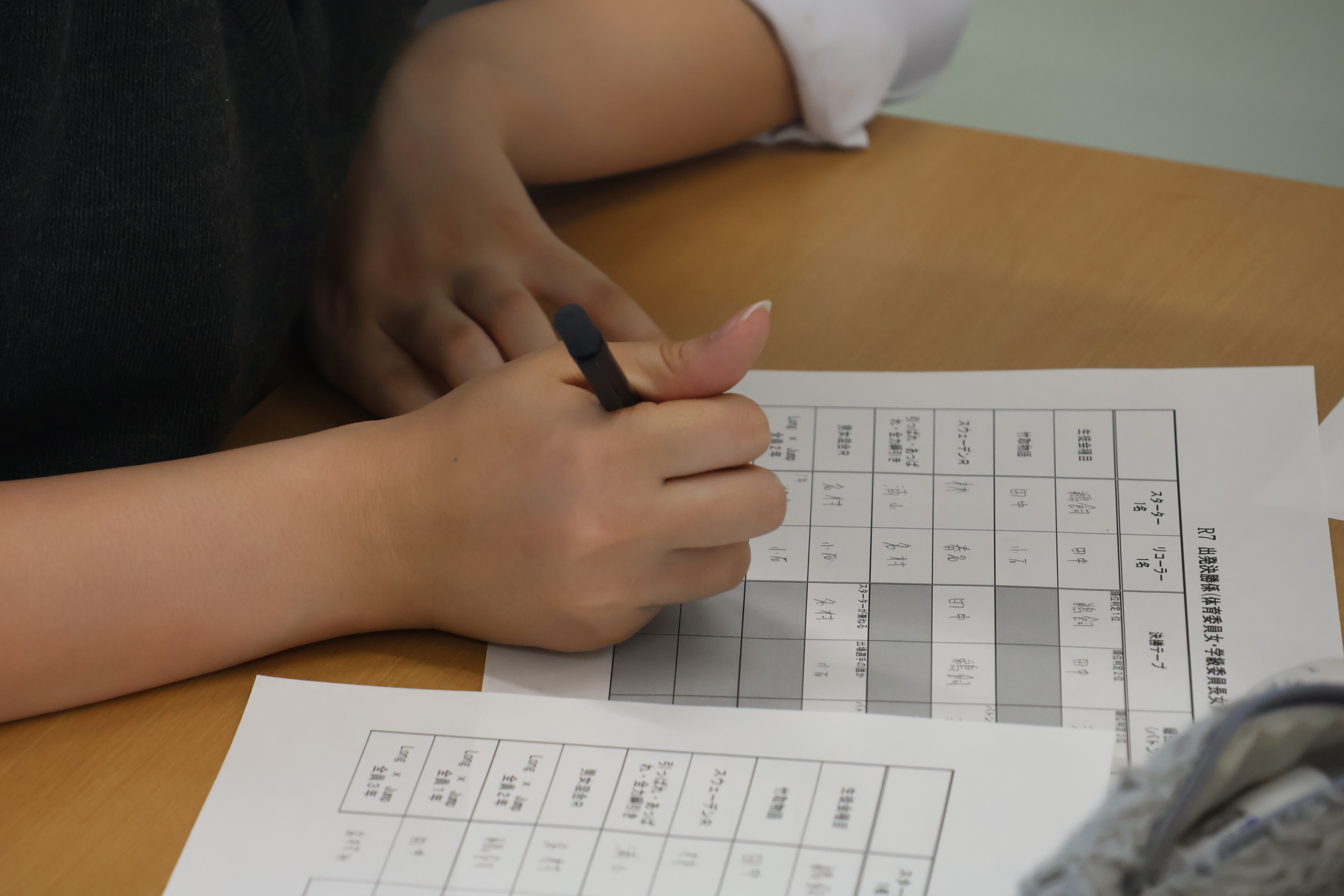


◎進む 仲間 わたし 一生懸命(5/14:3年授業風景から)

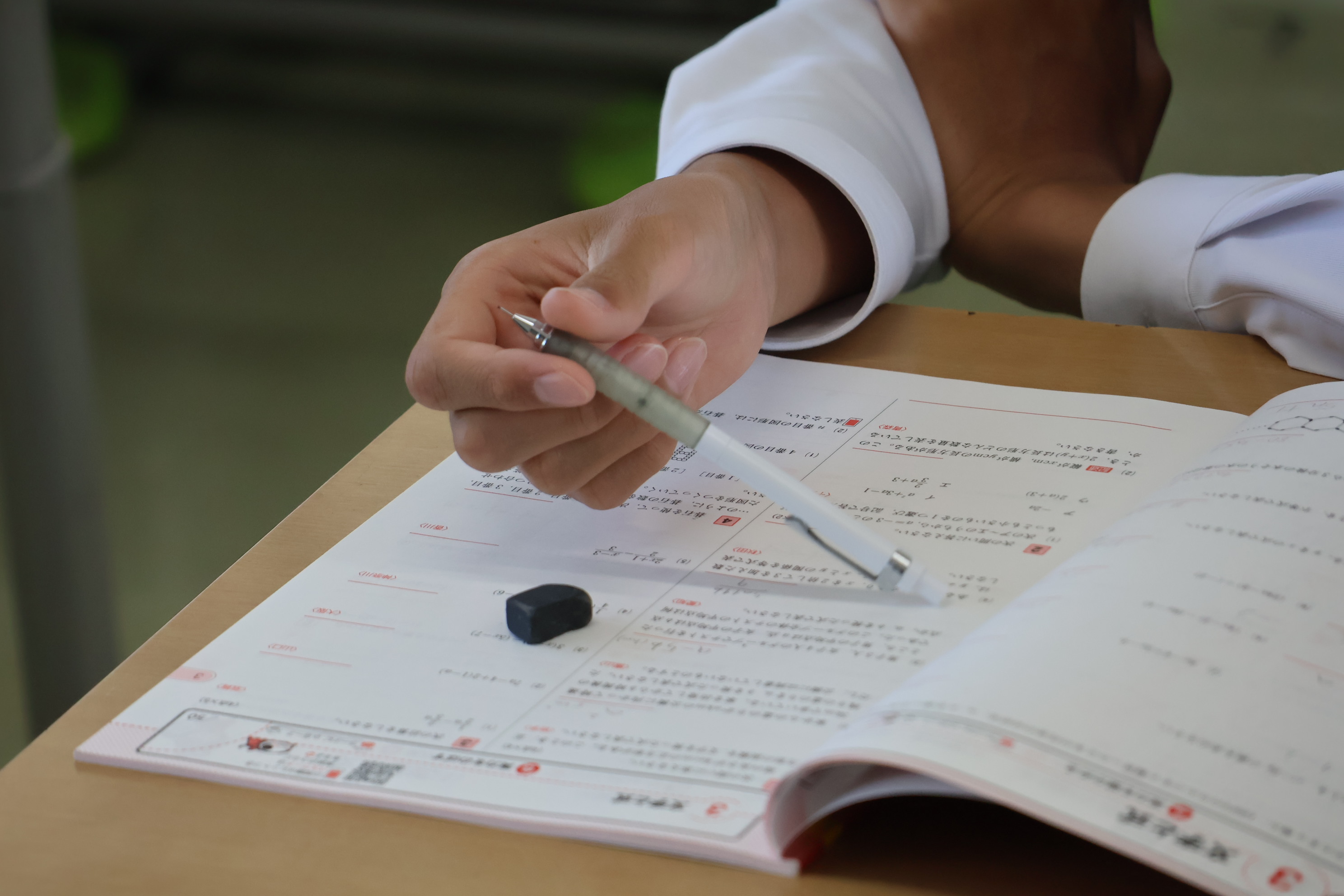


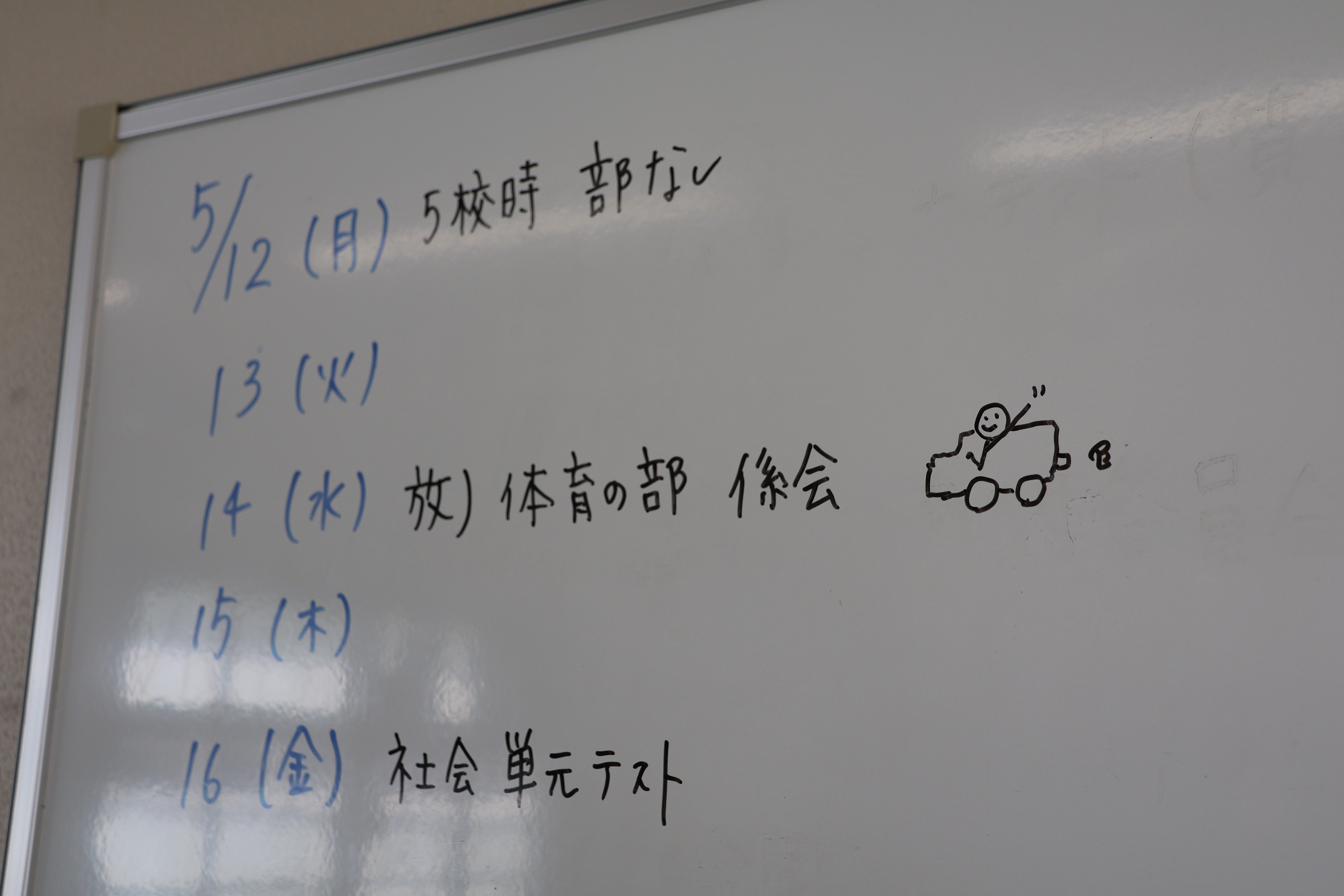

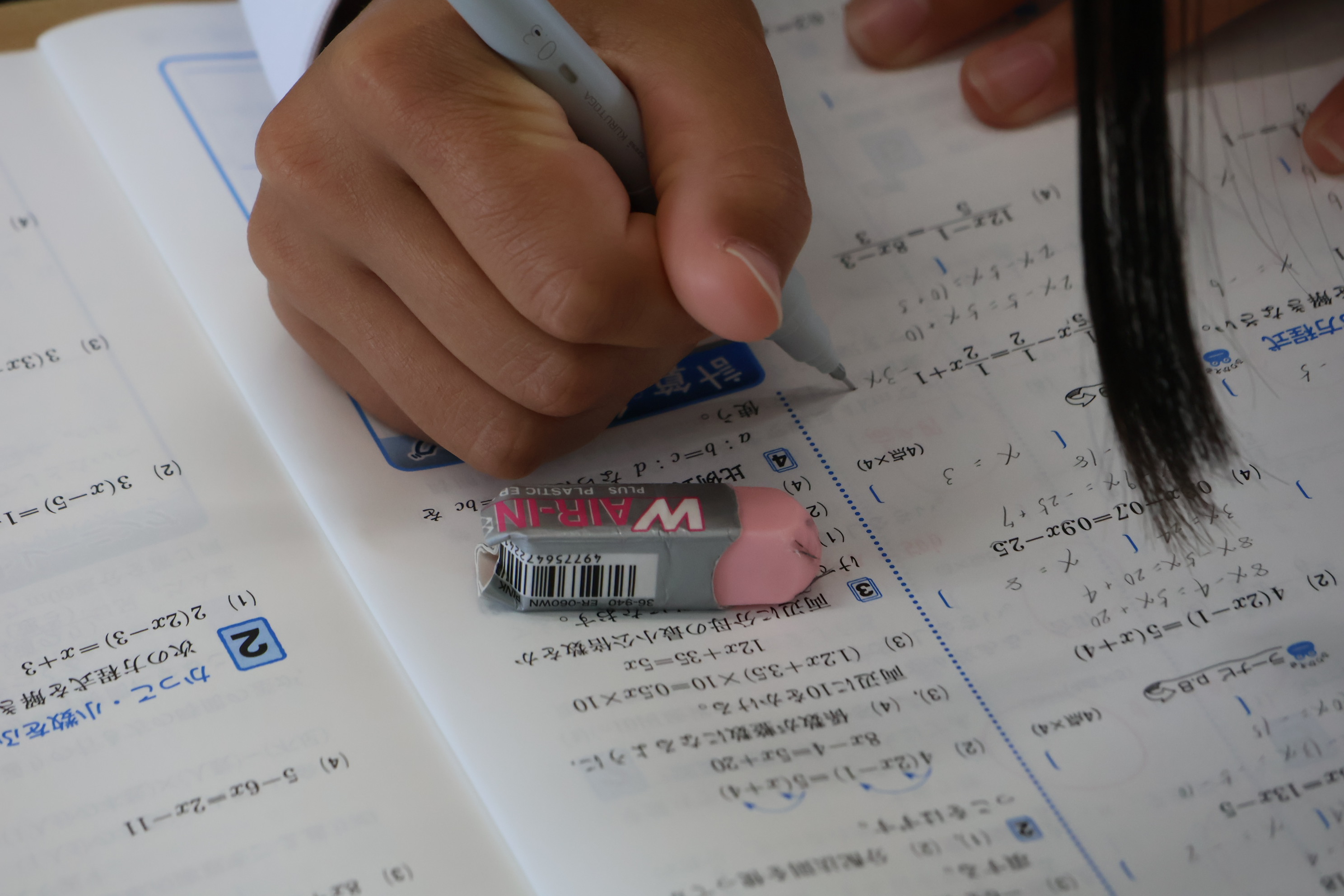


楽しそうに沖縄学習をしている?写真も混ざっている?
◎6.7竹取物語へ
支えてくれる翁(おきな)ありけり(5/14)



◎FLOUR MOON(5/13)

アメリカの先住民は季節を把握するために、各月に見らる満月に名前を、動物や植物、季節のイベントなど実に様々につけていました。農事暦(The Old Farmer's Almanac)によると、アメリカでは多くの花が咲くことにちなんで、5月の満月を「フラワームーン(Flower Moon/花月)」と呼ぶことがあるそうです。満月という現象は、太陽、月、地球の位置関係で決まります。月は自ら光っているわけではなく、太陽の光を反射することで輝いて見えています。そして、太陽の光が当たっている月面の半球が地球から見てどちらを向いているかによって、三日月や上弦、満月、下弦など、見かけ上の形が変わります。
地球から見た太陽の方向を基準に、太陽の方向と月の方向の黄経差が0度の瞬間が朔(新月)、90度の瞬間が上弦(半月)、180度の瞬間が望(満月)、270度の瞬間が下弦(半月)と定義されていて、およそ1か月弱で1周します。と、いうことで、満月は、地球から見て太陽と月が正反対の方向にならぶ瞬間(太陽、地球、月の順に、ほぼ一直線にならぶ瞬間)を指します。
◎ENJOY ENGLISH(5/13)
ALTの先生たちが、グローバルルームを利用して、英会話教室を開設(毎週火曜日)しています。楽しく英語に触れ、人と多文化に豊かに出会う時間を創出しています。
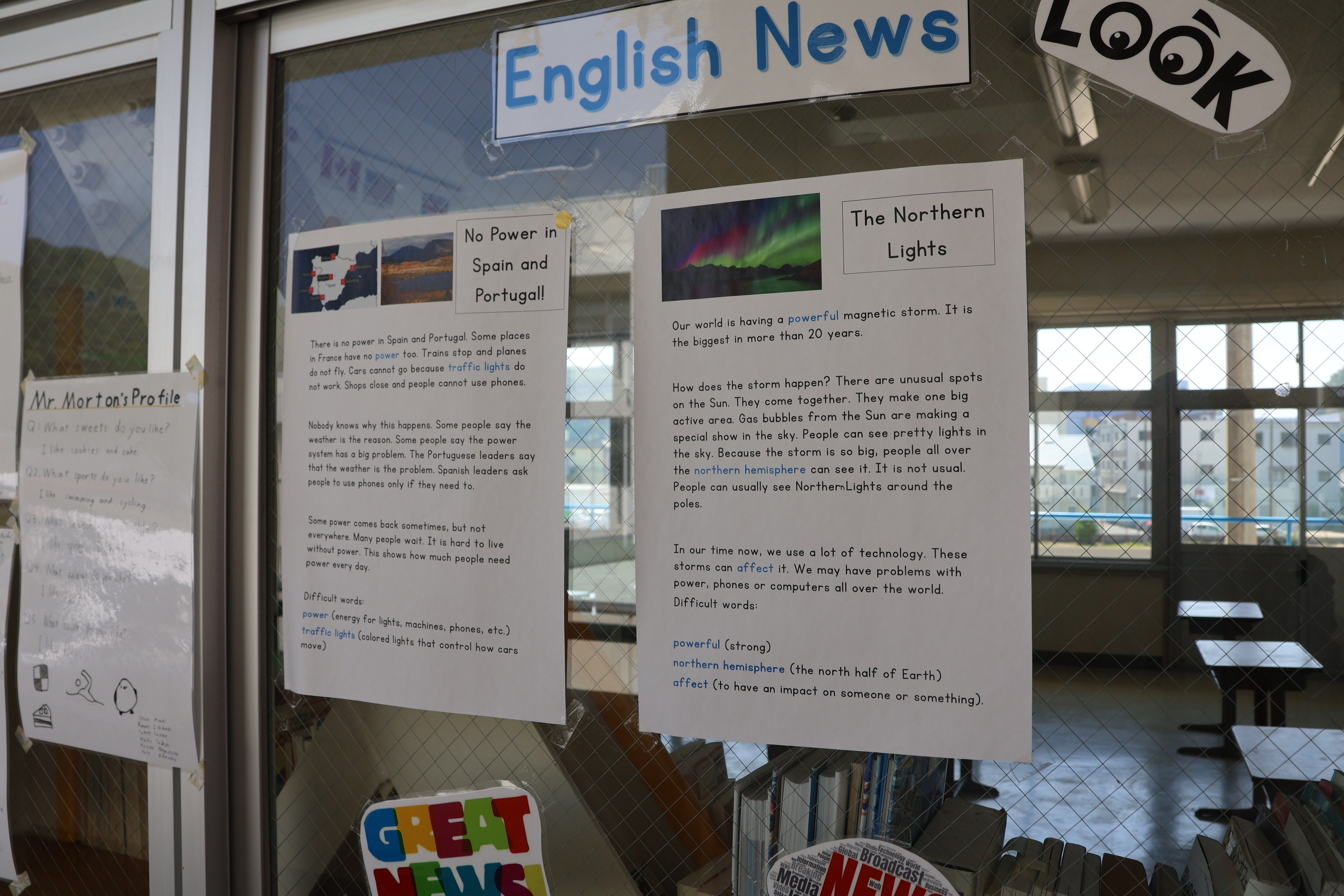
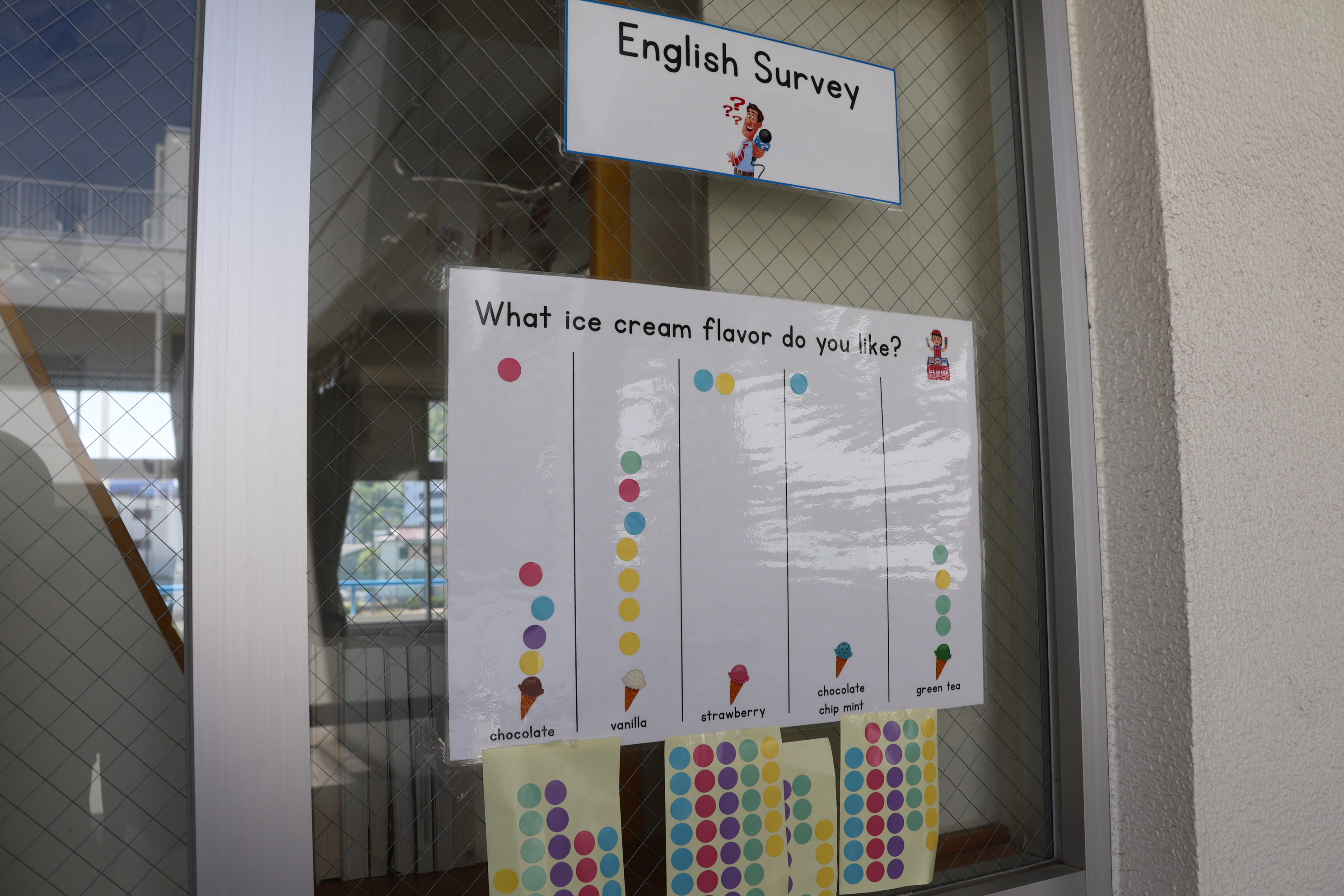

◎PS.新しい生活、頑張っています(5/13)
今日は小中連絡会を開催します。小学校の先生方が来校され、授業参観や情報交換会をもちます。


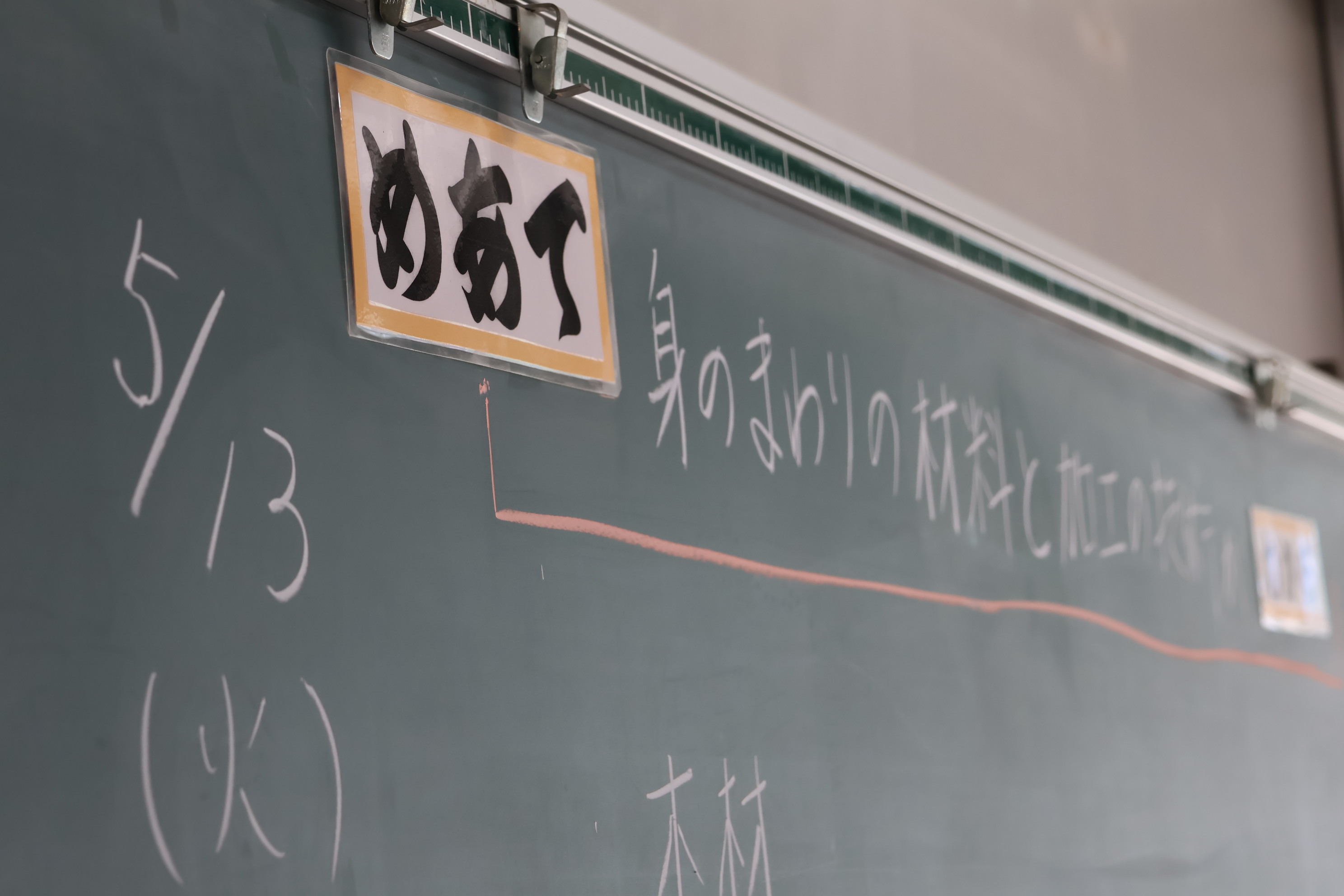


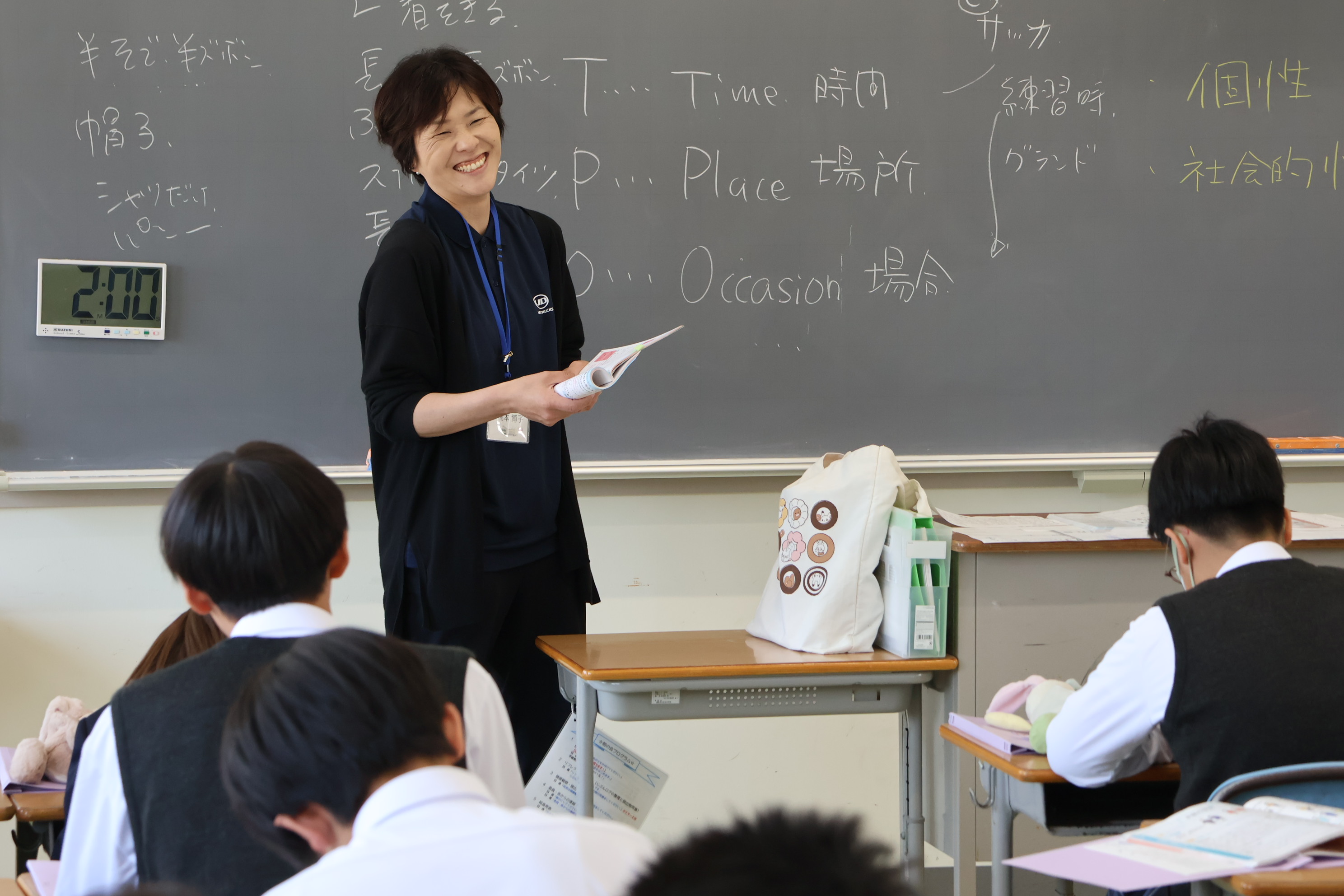
◎多くの人に支えられて(5/12)


備前警察署から根木スクールサポーターが来校され、「防犯」に関する作文募集と資料の提供をいただきました。また、備前市こどもまんなか課から赤堀さんと鷹取さんが来校され、家庭の支援・サポート等について情報交換をしました。
◎多くの人に支えられて(5/12:民生委員・児童委員の日)
民生委員・児童委員さんが、朝のあいさつ運動に来校されました。1917年(大正6年)、岡山県で済世顧問制度が創設されました。これは、民生委員制度の前身とされ、地域の貧しい人々を支援するための画期的な取り組みでした。貧困の予防という視点から、その後の社会福祉の基盤を築くことになります。5月12日、民生委員・児童委員の日は、その済世顧問制度の創設を記念して、1977年(昭和52年)に全国民生委員児童委員連合会(全民児連)によって制定されました。この日を通じて、社会福祉の歴史を振り返り、今後の福祉の在り方を考える機会としましょう。
また、民生委員は、地域住民の福祉向上のために、地域で起こる様々な問題に対応し、生活困窮者の保護指導や福祉事務所への協力を行います。これは、民間の奉仕者としての大変貴重な役割を担っています。また、児童委員は、児童や妊産婦の生活環境を支援し、子どもたちが健やかに成長できるようにという願いを込めて活動しています。この二つの委員は、私たちの生活を支える大切な存在です。

◎心理的安全性の高い職場づくりを目指しています(5/9)
校内のコンプライアンス研修を継続的に実施し、また支え合う職場づくりを進めています。

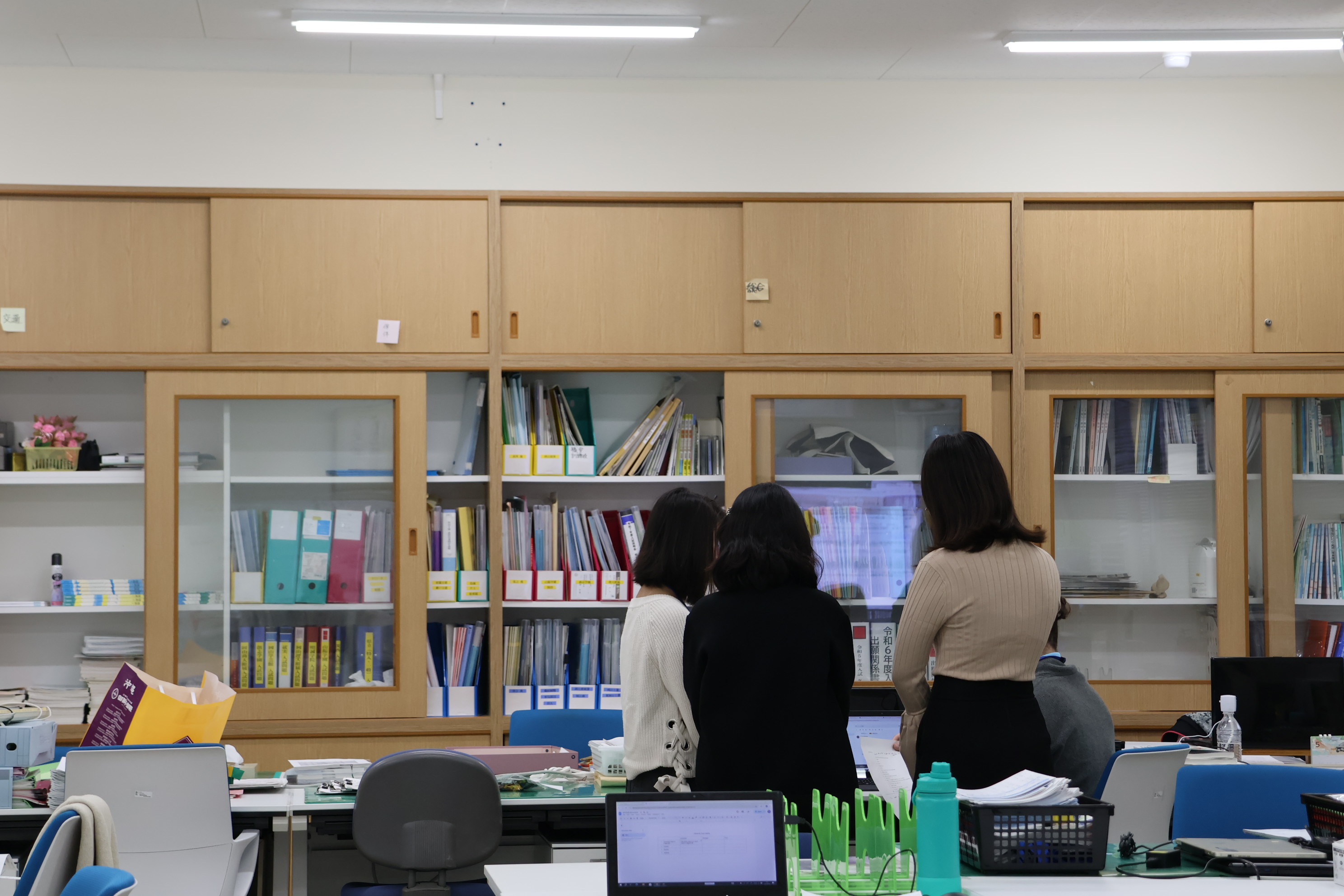

◎私たちのはじまりの風景17
ここはどこでしょう?









◎シン・生徒会活動へ(5/8:生徒朝礼・臨時生徒総会)
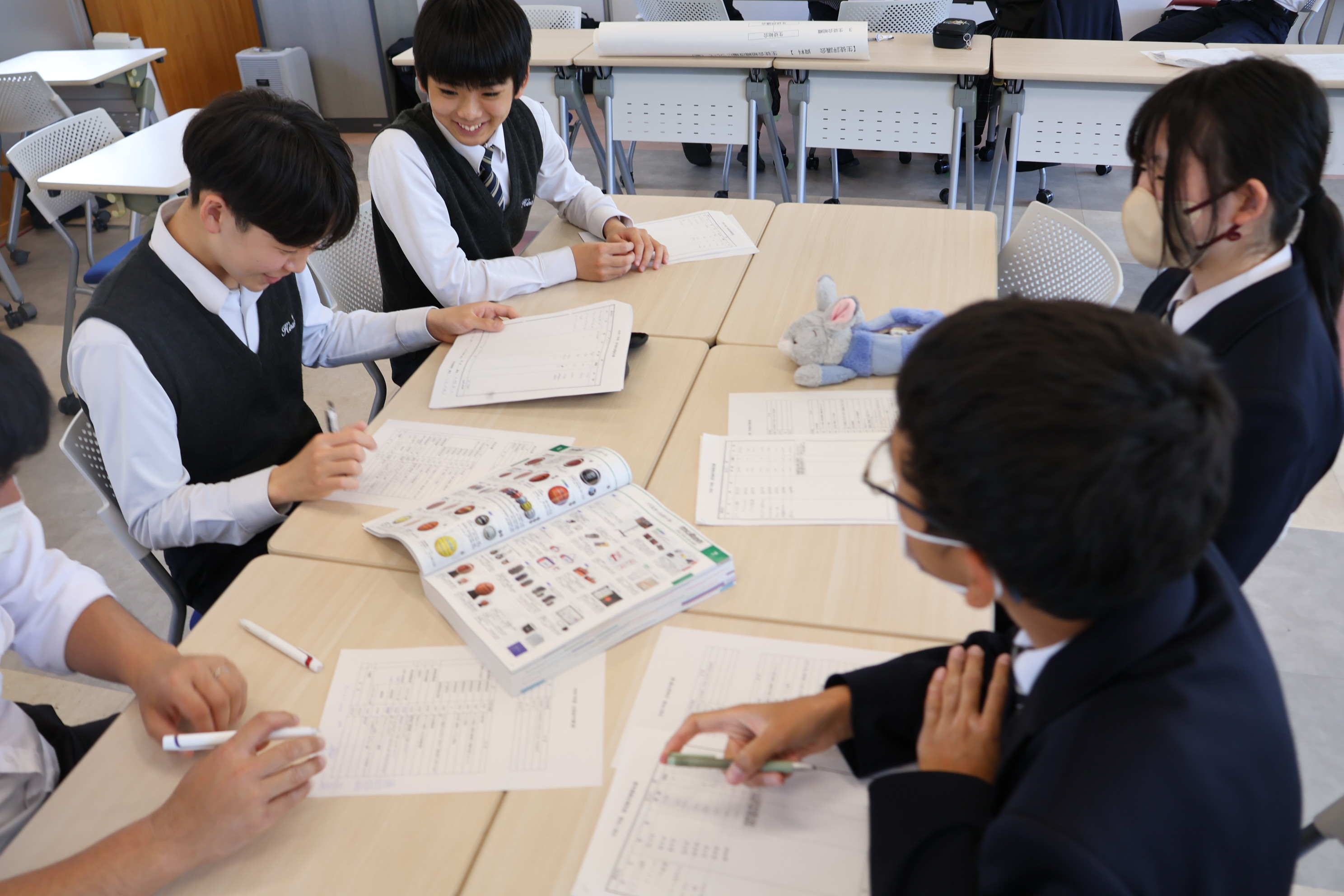

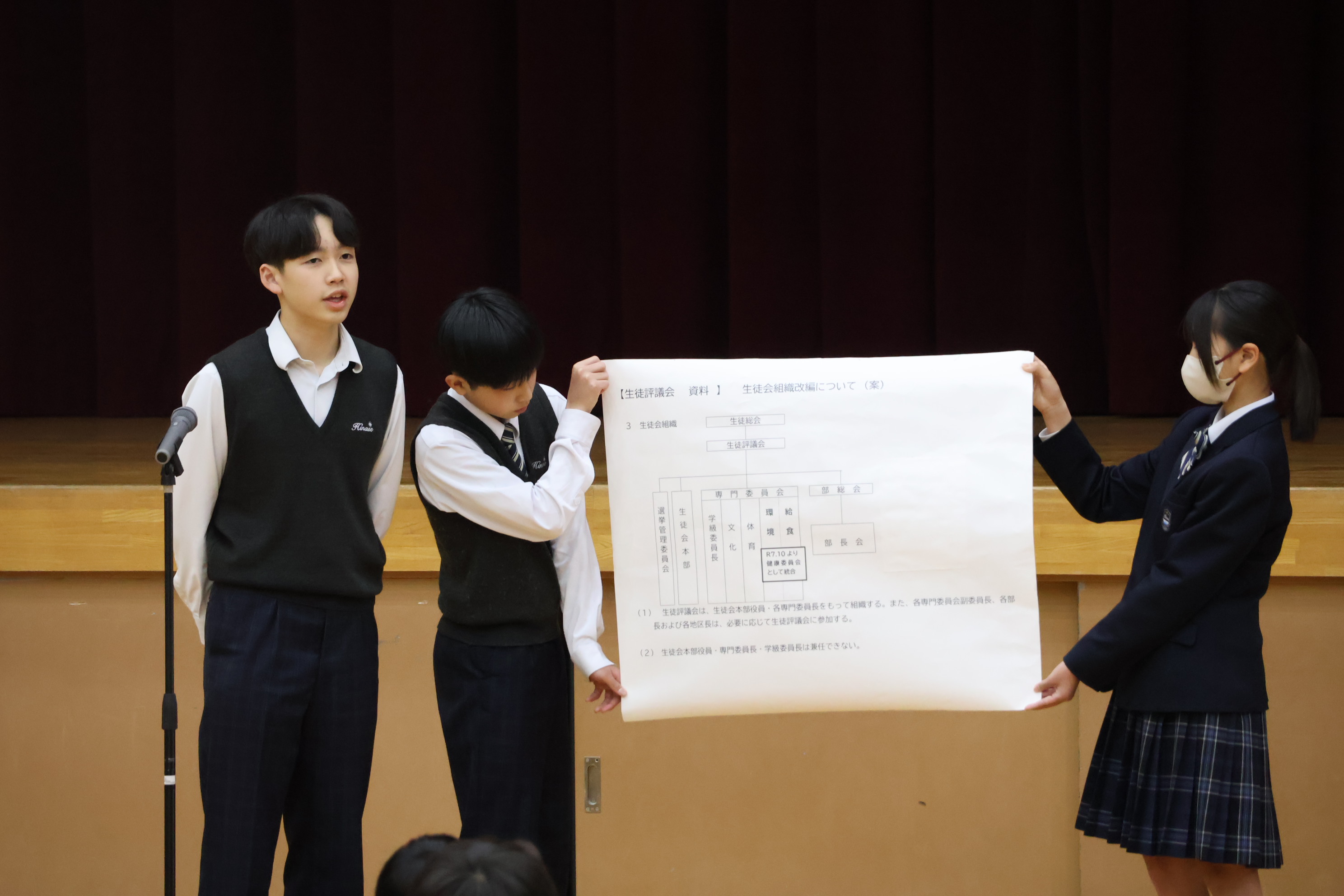
昨日は部活動予算折衝。
◎わいわい、にこにこ、今日もほっとスペース(5/7)

6/4には、ミニ学習会(マリルイーズさんの動画上映会)も予定しています。
◎Green Green(5/7)

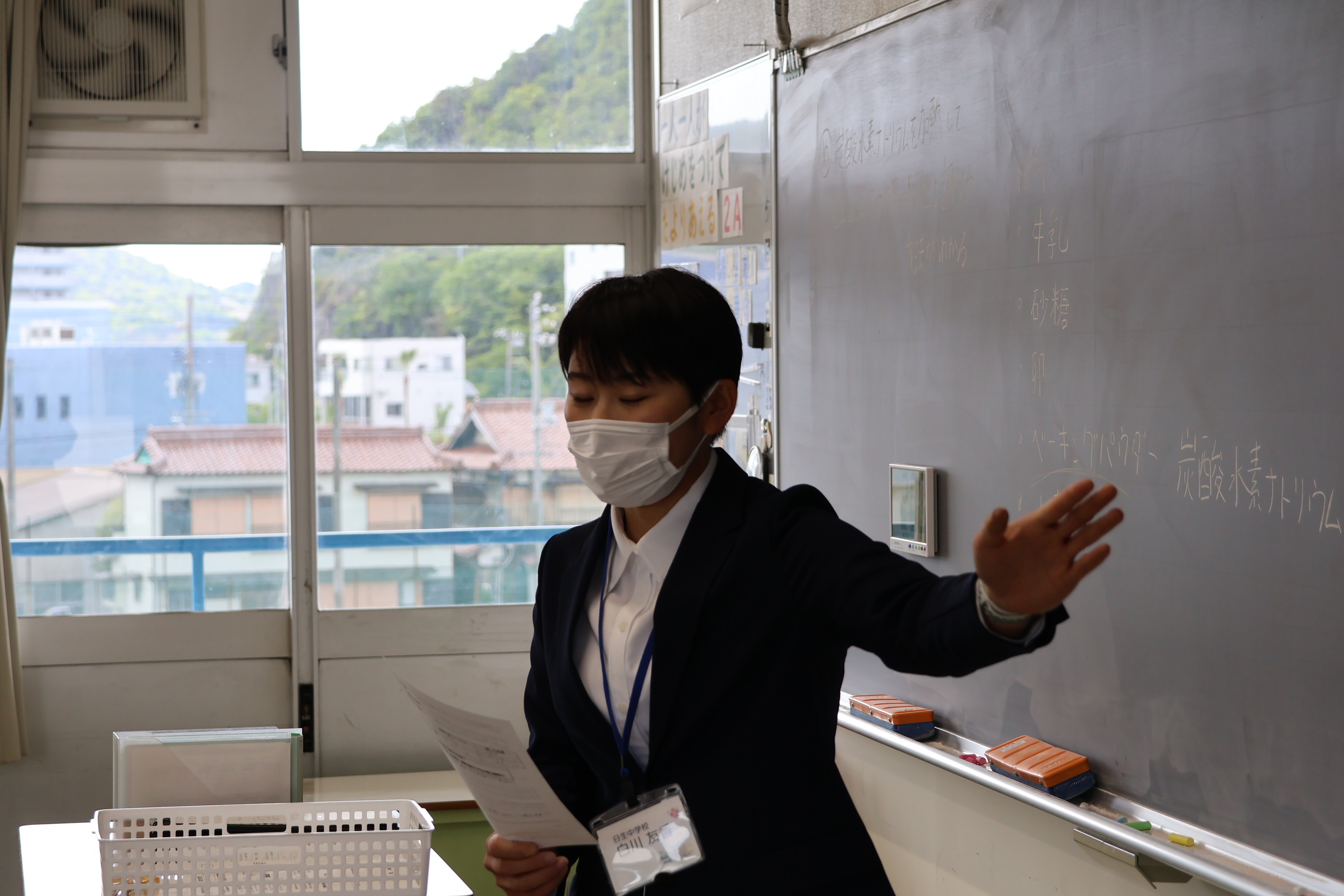
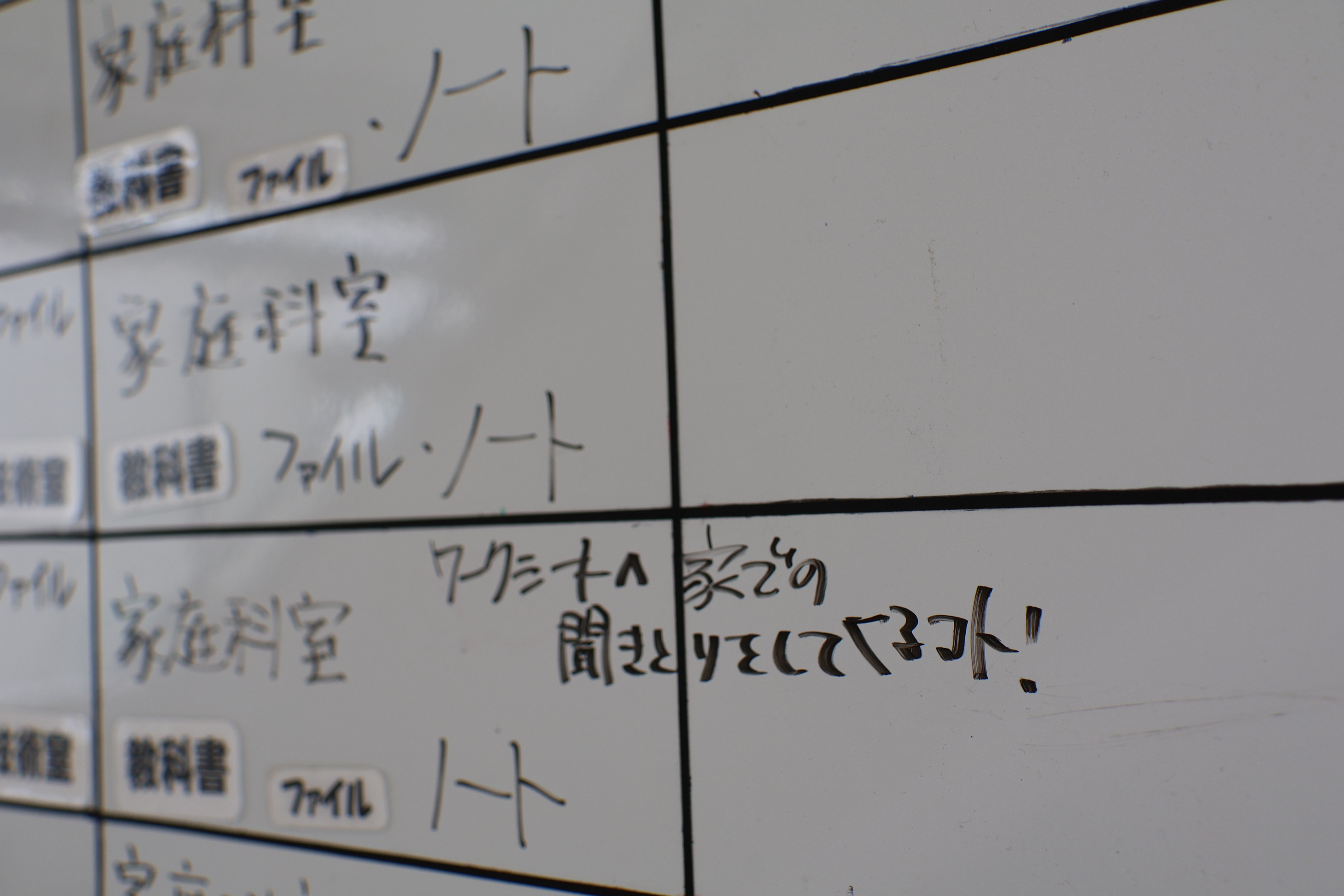



Do we need to make a special effort to enjoy the beauty of the blue sky? Do we have to practice to be able to enjoy it? No‚ we just enjoy it. Thich Nhat Hanh
(青空の美しさを楽しむのに、何か特別な努力が必要だろう?楽しむのに、練習が必要でしょうか?ただ楽しもう。)
◎ヒロシマ・オキナワへ(5/2)
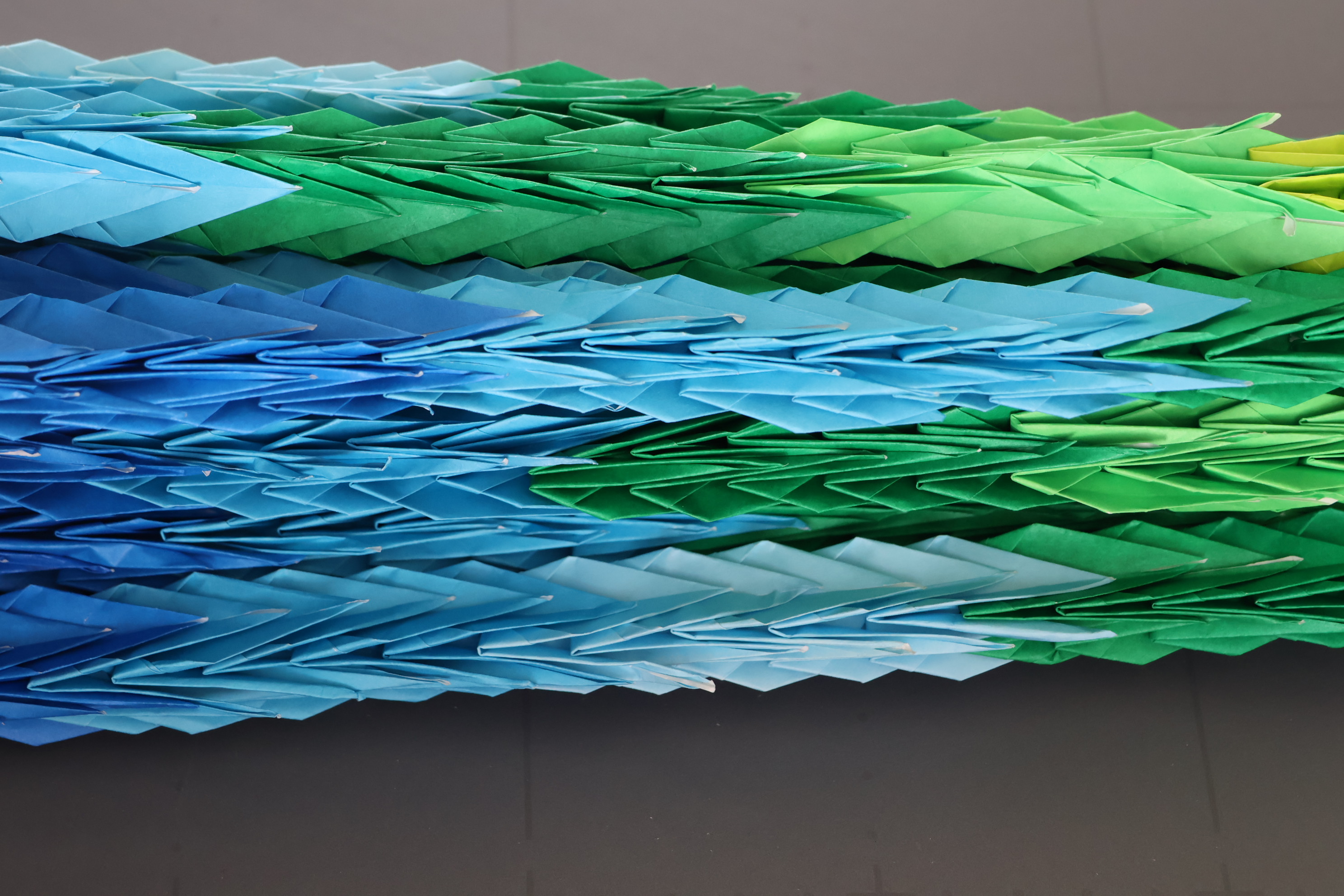
◎春15(いちご)の会 実行委員会(5/2)
特別支援教育のニーズのある子どもたちのための進路情報交流学習会(春15の会)の実行委員会が市役所で開かれ、教頭先生も参加されました。今年度も多様な進学先の情報をYouTube配信、また8月23日(土)12:30から、対面式での学校説明及び個別相談会を開催(会場:備前市立日生中学校)する予定です。準備をこれから進めていきます。
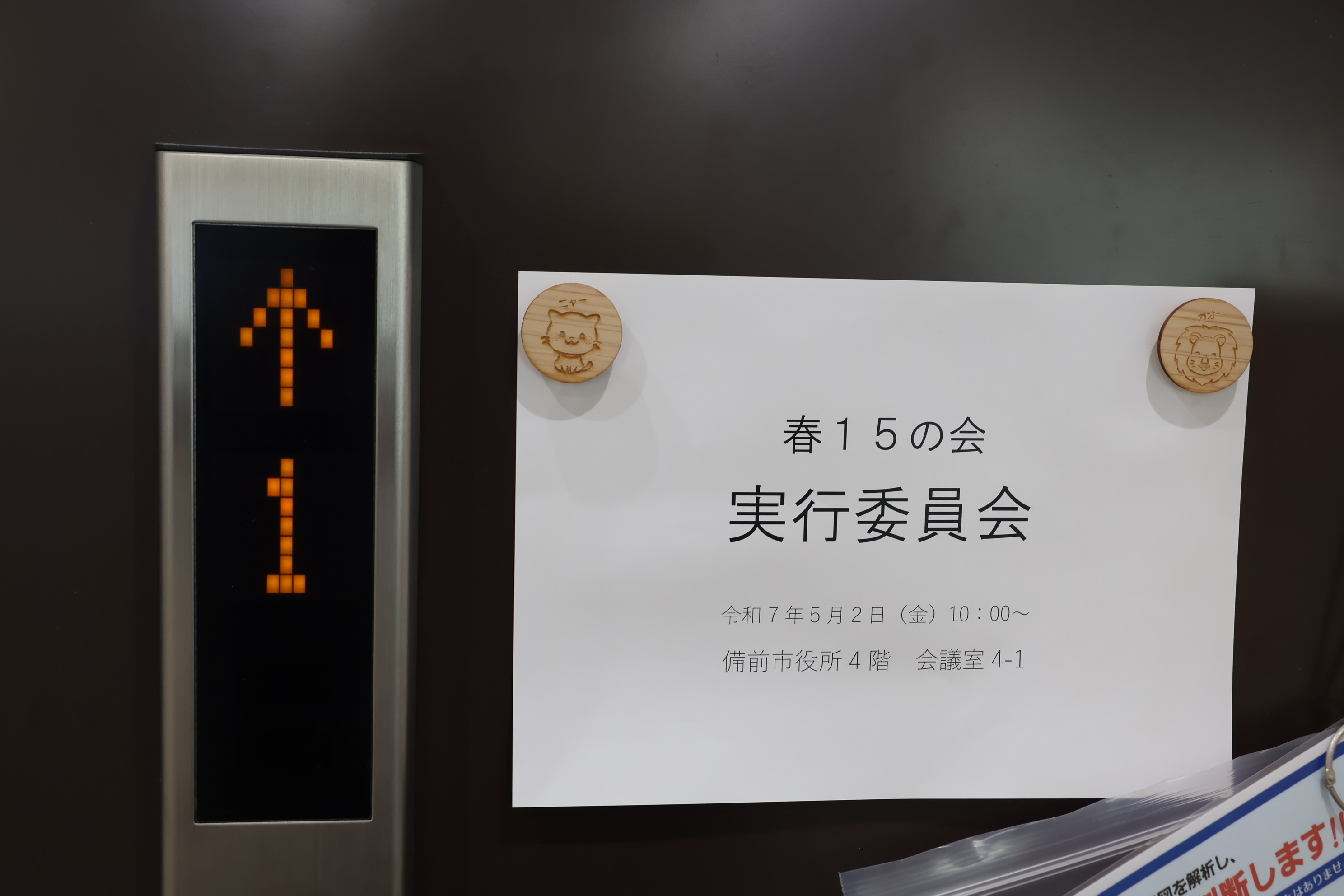


◎誠実を胸に刻むこと 共に希望を語ること(5/1)
第1回参観日を開催しました。たくさんのご参加をありがとうございました。
1年生が海洋学習に取り組んでいます。この日は天倉さんをお招きして、日生町の漁業の歴史と現状、アマモ場の再生活動について、質疑応答形式で学習を深めました。次回(5/15)は、カキの種付けに挑戦します。



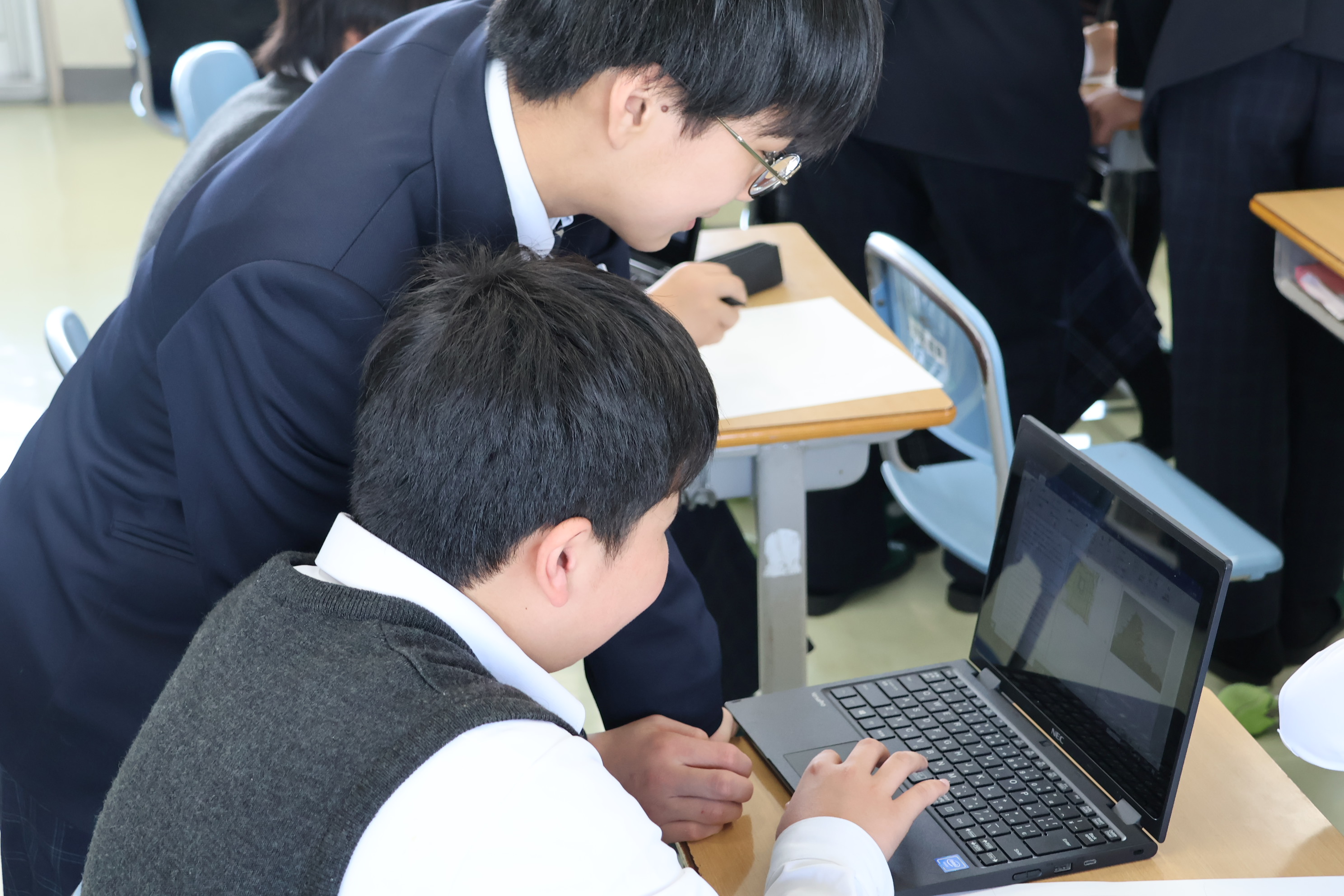
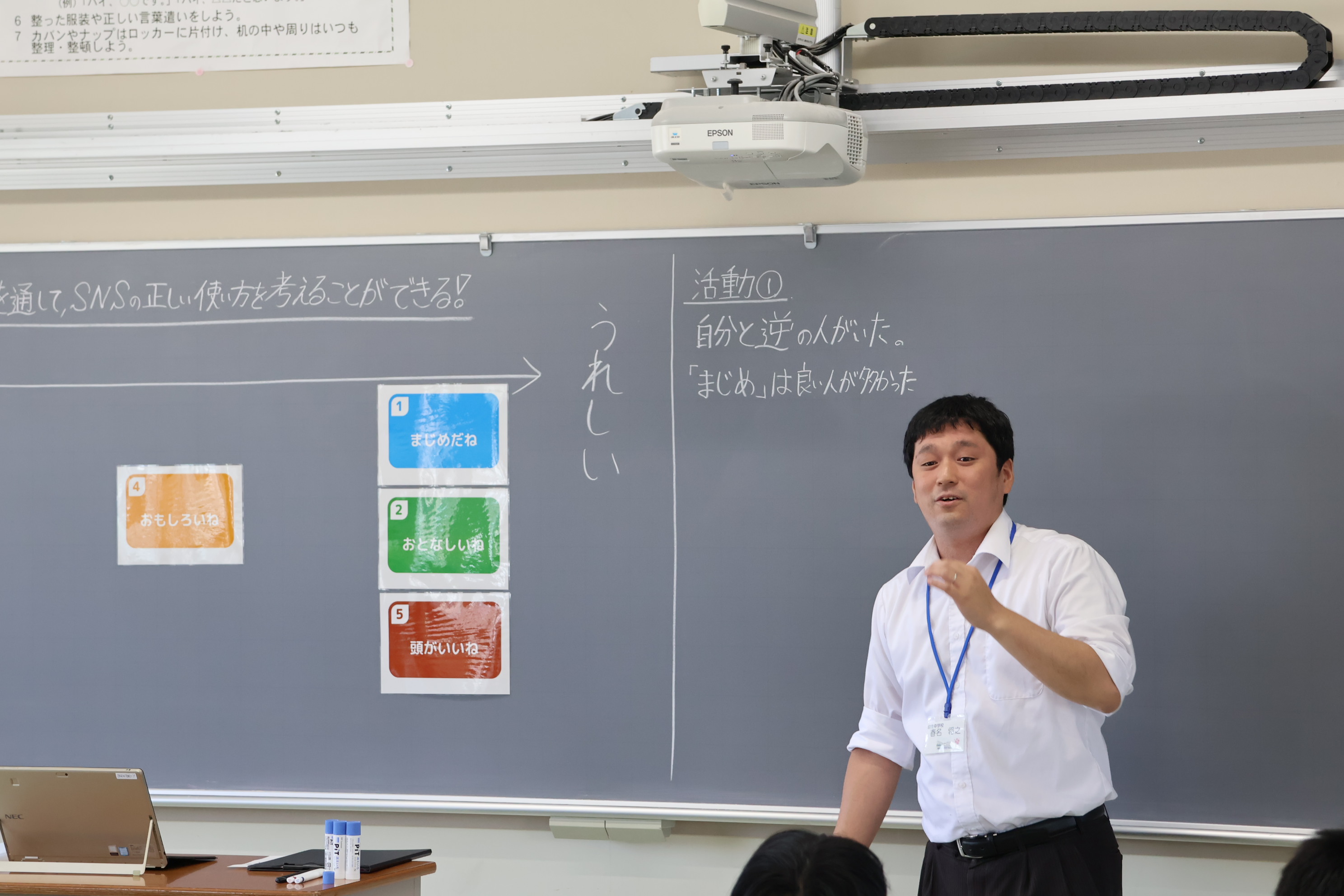




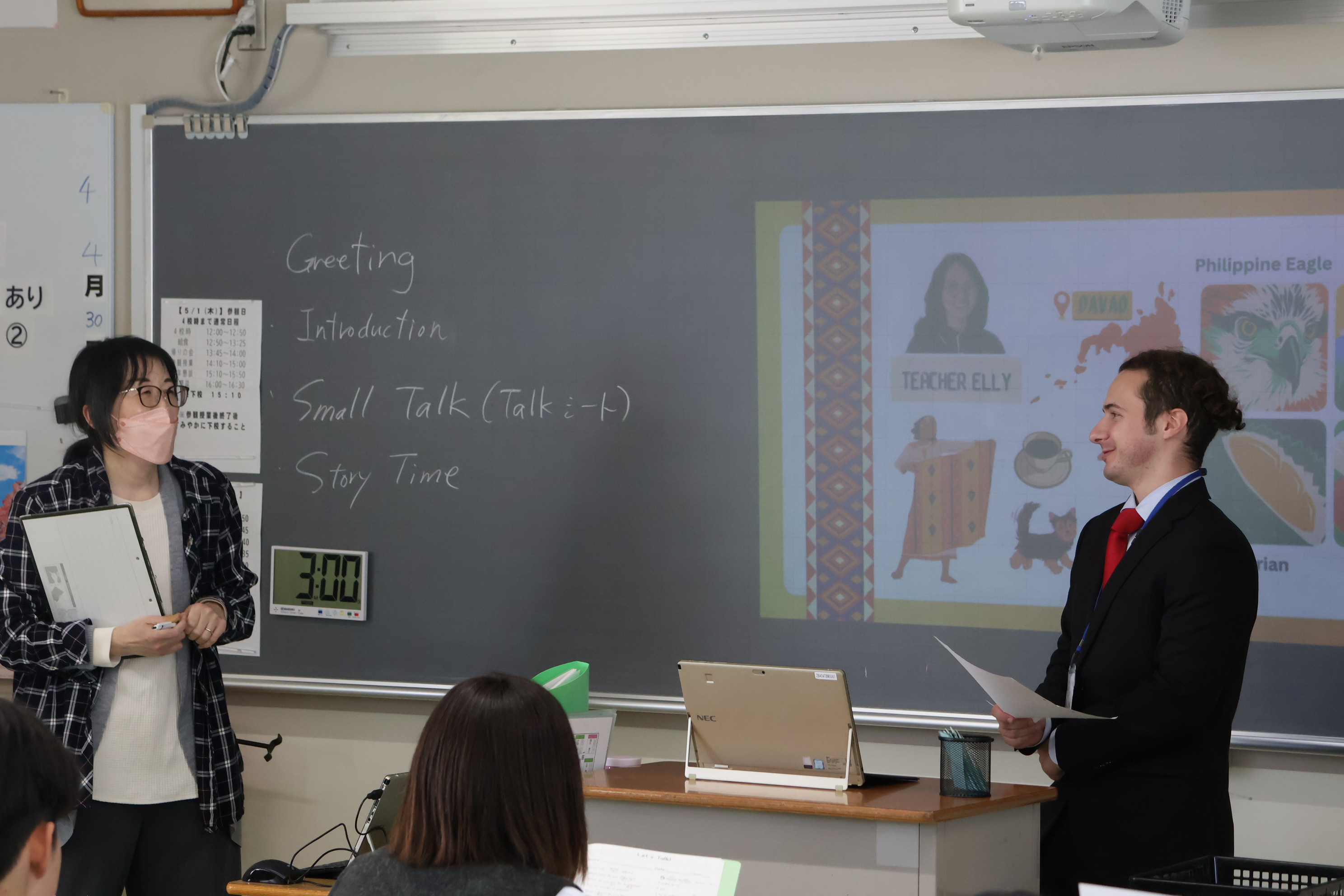


◎出会いに心をこめて(5/1)
新しい先生との出会いを大切にして、授業での学び、学校生活での学びを豊かにしていきましょう。左から、北脇先生、白川先生、アンジェリー先生、ブリ先生、シェナ先生です。

◎メーデー(5/1)

メーデー(May day)とは、毎年5月1日に世界各地で開催している労働者の祭典です。もともとはヨーロッパで春の訪れを祝うお祭りでしたが、19世紀のアメリカで「労働状況改善を求め、労働者が声を挙げる日」となりました。メーデーの社会的影響は大きく、ヨーロッパをはじめ世界各地に広がります。現在は労働者の日として、各地で集会やパレードを行うのが慣例です。メーデーはアメリカのほか、社会主義国やヨーロッパ、ラテンアメリカ、ASEAN諸国など、多数の国々で祝日となっています。当日は労働者団体による集会やデモなどのほか、人々が集まり歌やダンスを楽しむこともあるようです。メーデーは、労働組合が中心となって開催されています。
ちなみに、メーデーはほかの意味を指す場合もあります。それは、船舶や航空機の遭難信号で「メーデー・メーデー・メーデー」と3回繰り返すときは、緊急事態を知らせる言葉です。遭難信号における「メーデー」は世界中で使われており、「助けに来てほしい」という意味のフランス語の「ヴエ・メデ(venez m’aider)」が語源です。英語圏で分かりやすいよう、労働者の祭典と同じMaydayと表記するようになったといわれています。
さらに、世界各国でメーデーが祝日となっているのに対して、日本で祝日ではない理由に2つの説があります。5月1日は日本では大型連休中にあたるため祝日にならない1つ目の説としては、メーデーにあたる5月1日はゴールデンウィーク中であることが関係しているといわれています。5月1日も祝日にすると連休がさらに長くなり、経済活動が停止してしまうと懸念されているためです。2つ目は、11月23日に勤労感謝の日があるためです。内閣府の「国民の祝日について」によると、勤労感謝の日は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」と定められています。メーデーと趣旨が似ているため、メーデーは祝日にならないといわれているようです。
メーデーの起源と歴史は、19世紀アメリカに遡ります。起源は19世紀アメリカ、労働者の祭典として最初のメーデーは、1886年5月1日に第1回大会がアメリカのシカゴで開催されました。労働者たちが8時間労働制を訴えたのが始まりです。12~14時間労働が当たり前だった時代、労働状況の改善を求めて35万人もの労働者が結集し、大規模なストライキを敢行しました。しかし、労働時間の改善は見られなかったため、毎年5月1日に労働者たちが集結し、声を挙げるようになったといわれています。1889年には、パリで社会主義・労働者連合の国際組織である第二インターナショナル(国際社会主義者大会)が発足されます。アメリカのメーデーが「8時間労働の実現を目指す活動」と承認されたのをきっかけに、メーデーは世界各地に広がりました。当時の第一次世界大戦に影響を受け、メーデーは労働時間だけでなく戦争反対運動の側面も持つようになります。なお、第二次世界大戦で一度衰退を見せるものの、現在では80ヵ国もの国々で定められている労働者の祭典です。
◎季節の中で(5/1:参観日)
5月1日は、今年度最初の参観日となります。学年懇談、部活動懇談会、そしてPTA意見交流会も予定しています。また1年生は、漁協から天倉さんをお招きした海洋学習に取り組みます。ご参会をどうぞよろしくお願いします。

また今日は八十八夜です。八十八夜とは、立春を1日目と数えて、88日目にあたる日のこと。現代の暦か旧暦かにかかわりなく、毎年ほぼ一定であることがポイントです。日本では長く、月の満ち欠けをもとにした太陰太陽暦(旧暦)が使われてきました。旧暦は季節とずれやすいため、農業の目安とするには不便な点もあったようです。そのため、太陽の動きを基準にした「二十四節気」や、日本の気候風土を上手に言い表した「雑節(ざっせつ)」という暦日が使われてきました。入梅(にゅうばい)、土用、二百十日、八十八夜などが雑節です。雑節は日本人の経験から生まれた、生活の知恵。八十八夜は毎年、5月の初め。春から初夏へと移り変わる季節です。「八十八夜の別れ霜」といわれ、この日までは遅霜(おそじも)に注意が必要でした。逆に言えば、この日からは農作業本番。種まき、田植えと、農家さんは忙しくなります。
2025年の八十八夜は5月1日(木)です。です。八十八夜は立春から数えるので、立春が動けば八十八夜も変動します。また、うるう年には、途中に1日加わるので、1日早くなります。毎年だいたい2日間の間に収まります(まれにズレるときもあります)。
なぜ八十八夜といえば新茶なのでしょうか?お茶の葉は、1年に3~5回の収穫が可能です。中でも最初に収穫される「新茶」がもっとも美味しいとされています。甘み・旨み成分であるテアニンが、二番茶以降の3倍以上も含まれているとか。新茶の収穫は、タイミング勝負。お茶は、発芽する前は寒さに強いのですが、発芽後は急に霜に弱くなります。また、伸びれば伸びるほど、テアニンの含有量も減っていきます。かといって早すぎると、ほとんど収穫できない…という結果になるかもしれません。農家さんは、成長の具合や、季節の進み具合を見極めて一気に収穫します。八十八夜はまさにそのタイミング。現代では収穫が早めの鹿児島から、遅めの滋賀・奈良県まで、だいたい4月上旬から5月中旬にかけて新茶を収穫します。八十八夜のころが新茶収穫のピークであることは、今も昔も変わらないようです。
◎日生中がもっと楽しくなる(4/30:生徒会プレゼンツ)

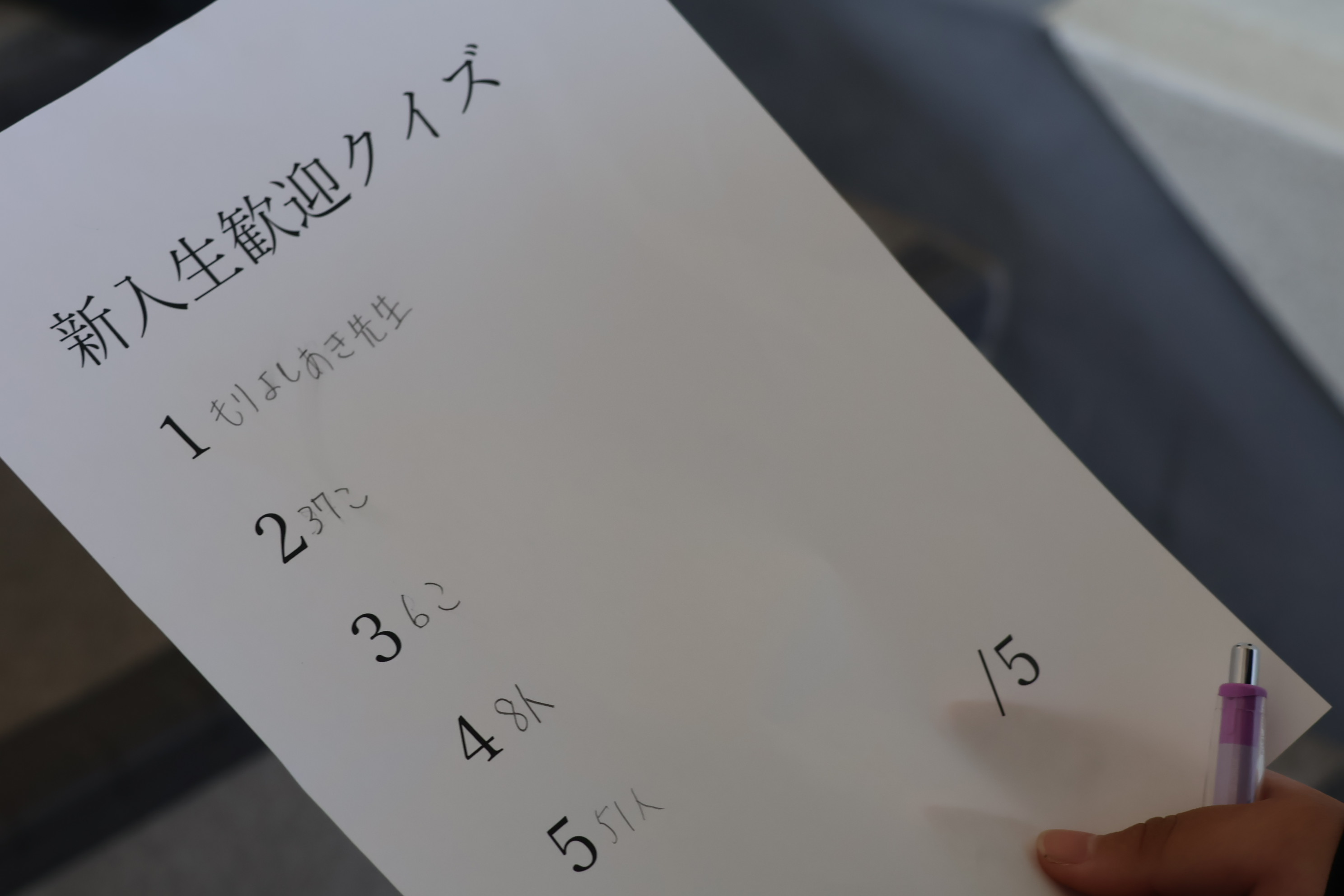
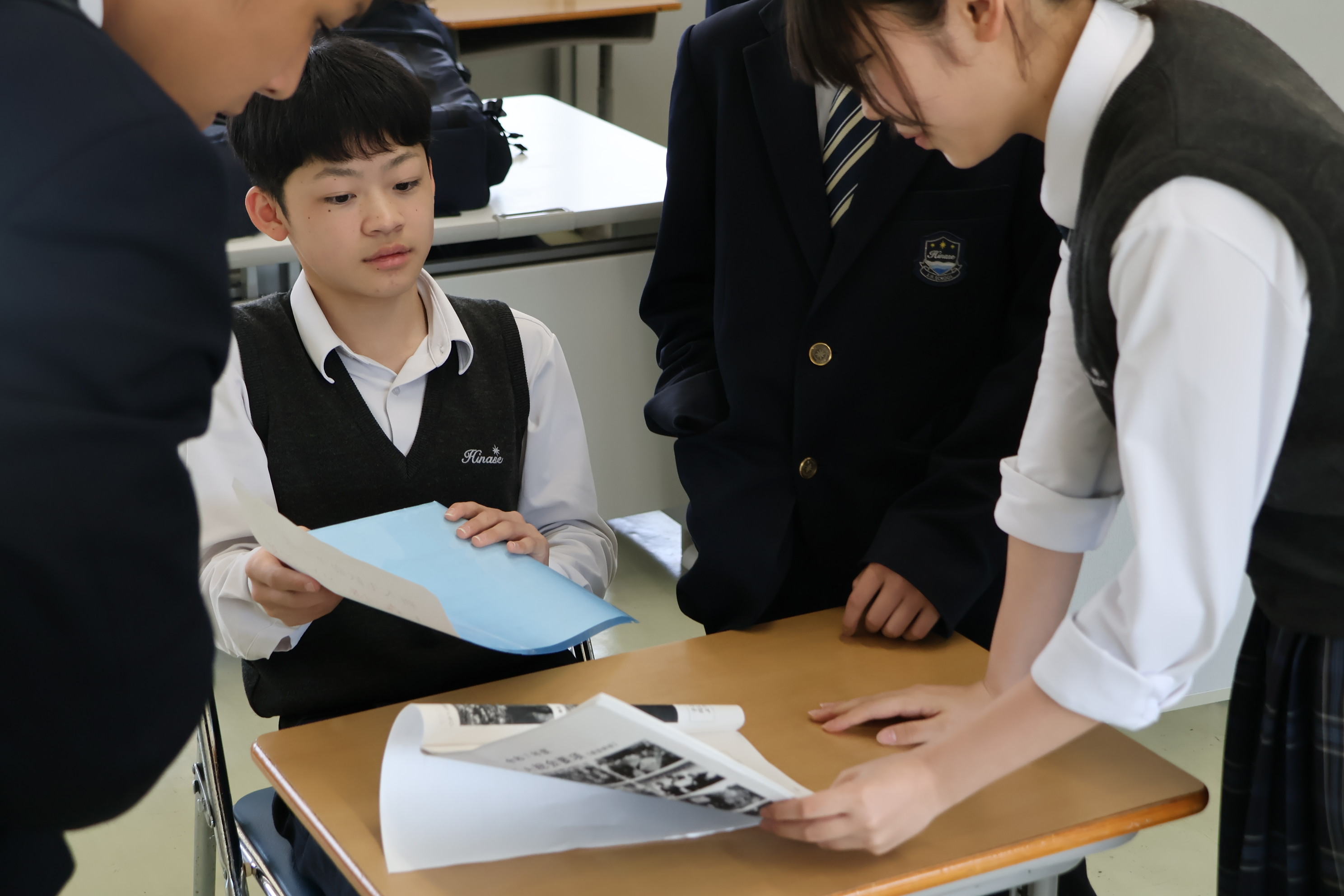
◎備前サンラッキーズを応援しています。(4/30)

日生中グラウンドで練習中
◎よい時間を過ごしたいね(4/30)



「ゴールデンウイーク」(黄金週間)は、連休で観客の入りがよかったため、この期間中に大作をぶつけるようになった映画界が、宣伝も兼ねて作り出したことばで、昭和27~28(1952~53)年ごろから一般にも使われるようになったようです。しかし、1970年代の「石油ショック」以降、「のんきに何日も休んではいられないのに、なにがゴールデンウイークだ」といった電話が放送局に何本もかかってくるなど抵抗感を示す人が目立ってきました。また、「外来語・カタカナ語はできるだけ避けたい」「長すぎて表記の際に困る」など、放送の制作現場の声もありました。そのうえ、週休2日制の定着で前後の土曜・日曜を加えると10日ぐらいになることもあり、ウイーク(週間)も的確な表現ではなくなってきました。このため、放送では原則として「ゴールデンウイーク」は使わず、「大型連休」を使っています。
ところで、この「大型連休」という言い方も、同じニュースや番組の中で何度も繰り返して言われると耳障りな場合があります。さらに、おととし以来の厳しい経済状況の中で、この言い方に抵抗感を持つ人も増えているものと思われます。このため、原則として「大型連休」という語を使いながらも安易に繰り返すのではなく「今度の(春の)連休で…」「この連休中(連休期間中)に…」「4月末からの(この○○日から始まる)連休で…」など、ときには別の言い方や伝え方を織り込むような表現上の配慮やくふうをすることも必要でしょう。
* 主な新聞社や通信社は、記事の中で以前は「ゴールデンウイーク」と「大型連休」をほぼ同じ率で混在した形で使っていましたが、最近は「大型連休」を使うほうが多いようです。同じ活字メディアでも、雑誌は旅行案内や若者向けの情報誌を中心に「ゴールデンウイーク」や頭文字をとった「GW」の表記が引き続き多く使われているようです。
(「こどもの日小さくなりし靴いくつ」(林 翔)) NHK放送文化研究所のHPより一部紹介しました。
◎子曰、学而不思則罔、思而不学則殆。(4/28:一年生閑谷研修)
子曰く、学びて思わざれば則ち罔し(くらし)、思いて学ばざれば則ち殆し(あやうし)。















孔子先生はおっしゃいました。「学んで、その学びを自分の考えに落とさなければ、身につくことはありません。また、自分で考えるだけで人から学ぼうとしなければ、考えが凝り固まってしまい危険です」と。
◎施錠を解く鍵は人である(4/25)


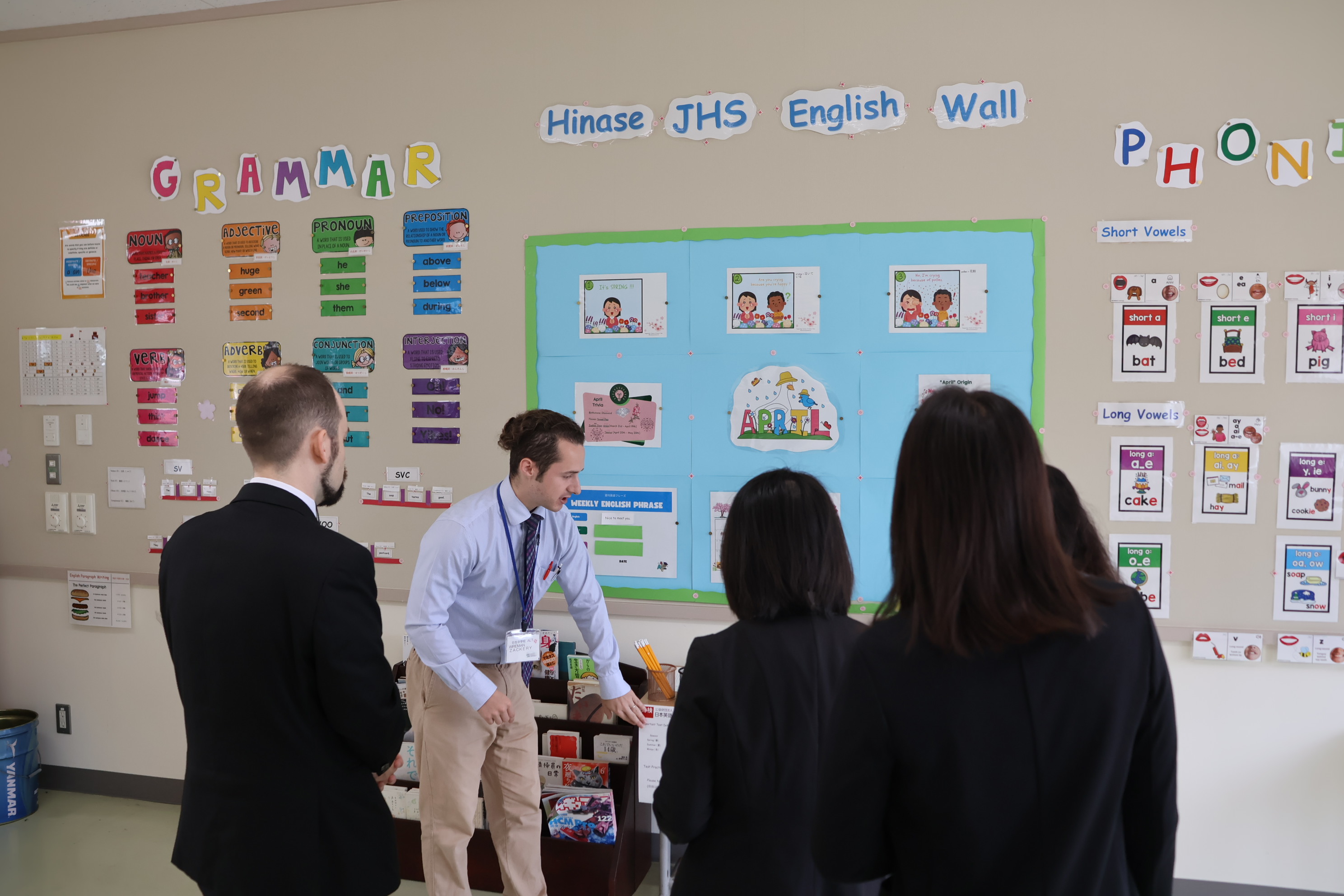
新しいALTの先生が来校されました。5月1日から、子どもたちと多くの時間を過ごす中で、英語に触れ合う機会を増やし、生徒の学習意欲の向上をすすめます。
◎日生で学ぶ 未来へつなげる
1年生も海洋学習スタート(4/24)
漁協さんからお話を聴く学習は5月1日、カキの種付け実習は15日、アマモの回収実習は29、30日です。〈日生中では、長ぐつ必須。〉
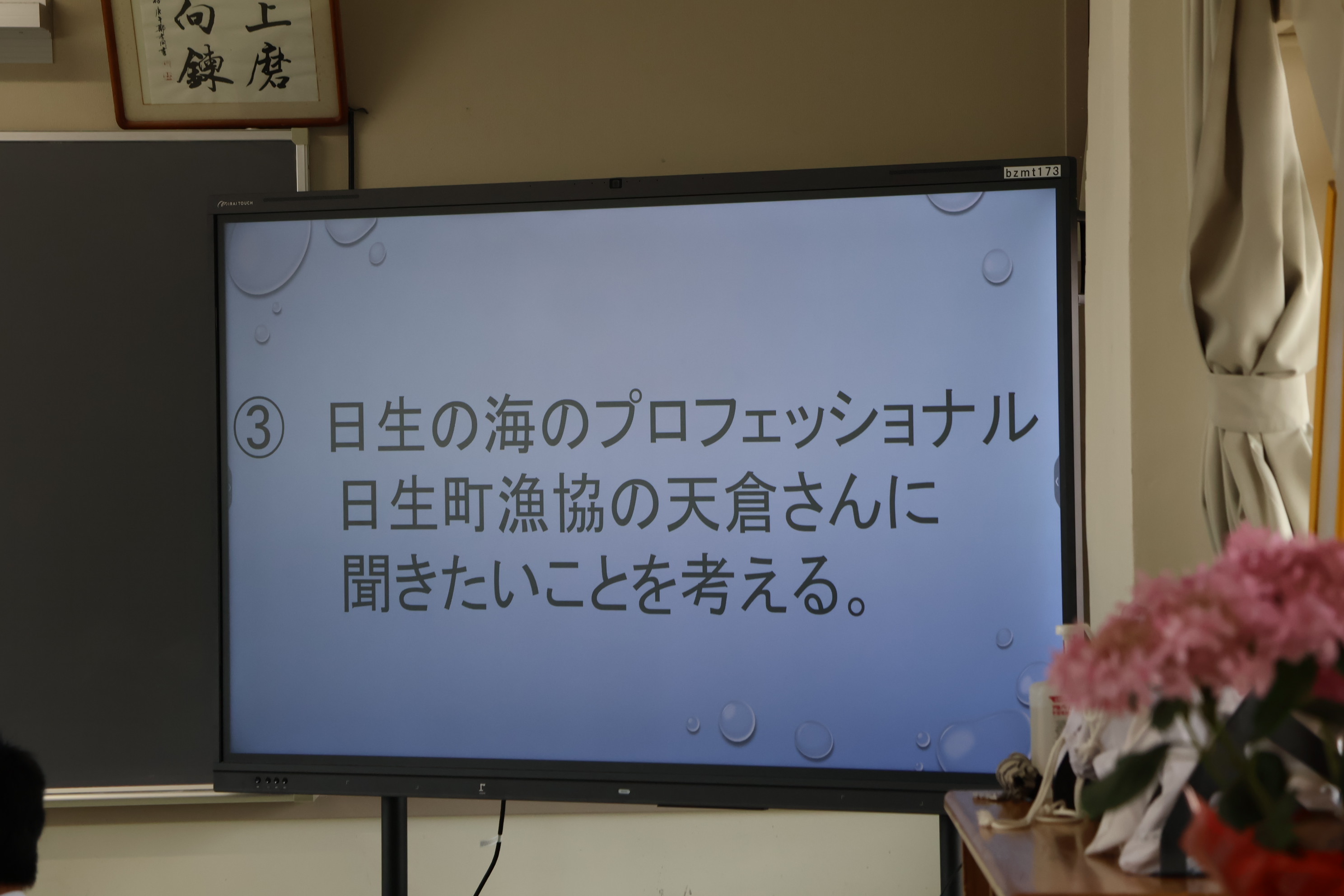



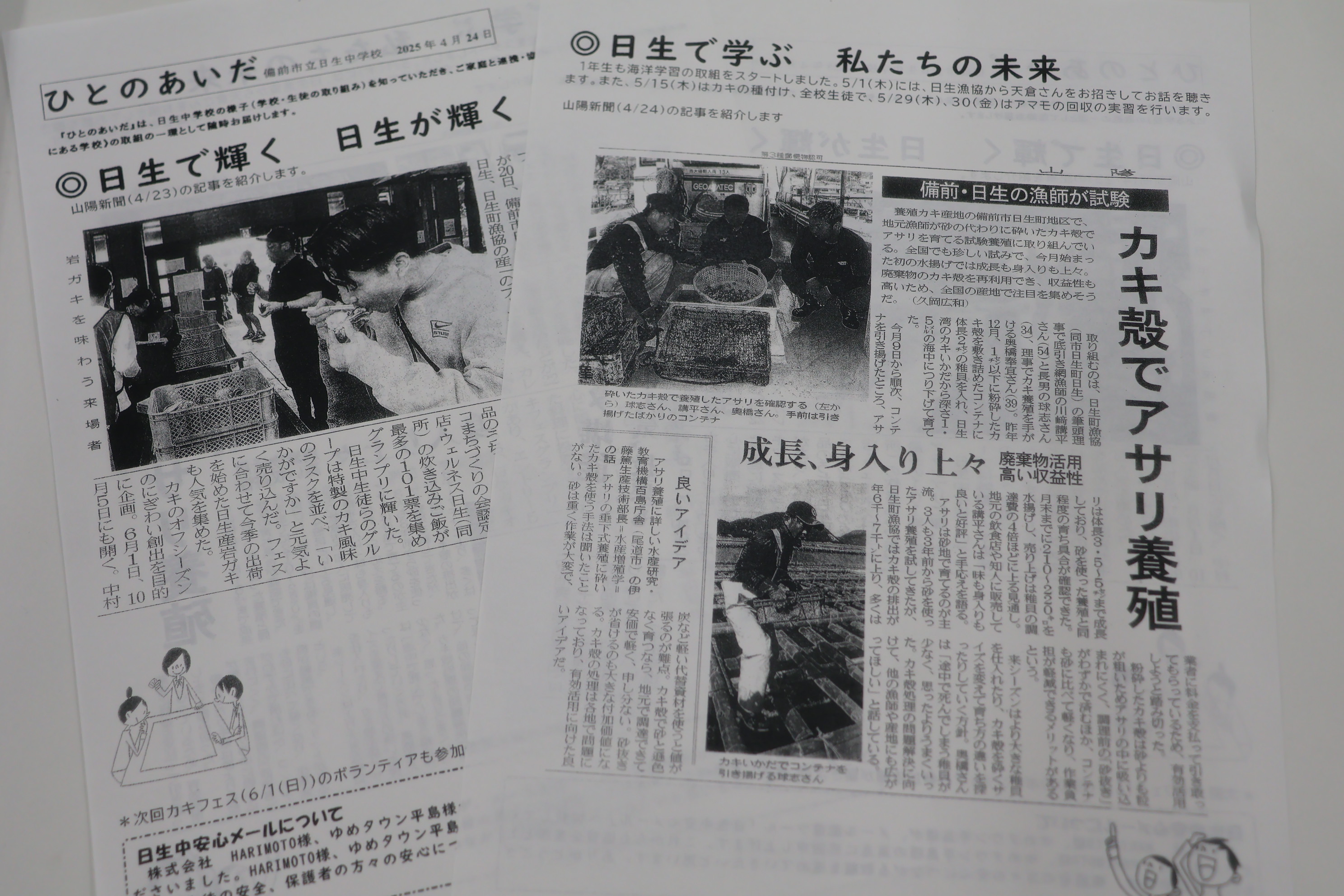

◎正しくみる・行動する(4/23:第1回避難訓練)
備前県民局の中務さんをお招きして、今年も避難訓練を実施しました。また、南海トラフ地震を意識した2次避難訓練も行いました。参照:https://www.nhk.or.jp/shutoken/chiba/articles/101/015/93/(NHK 福田村事件の記事です)








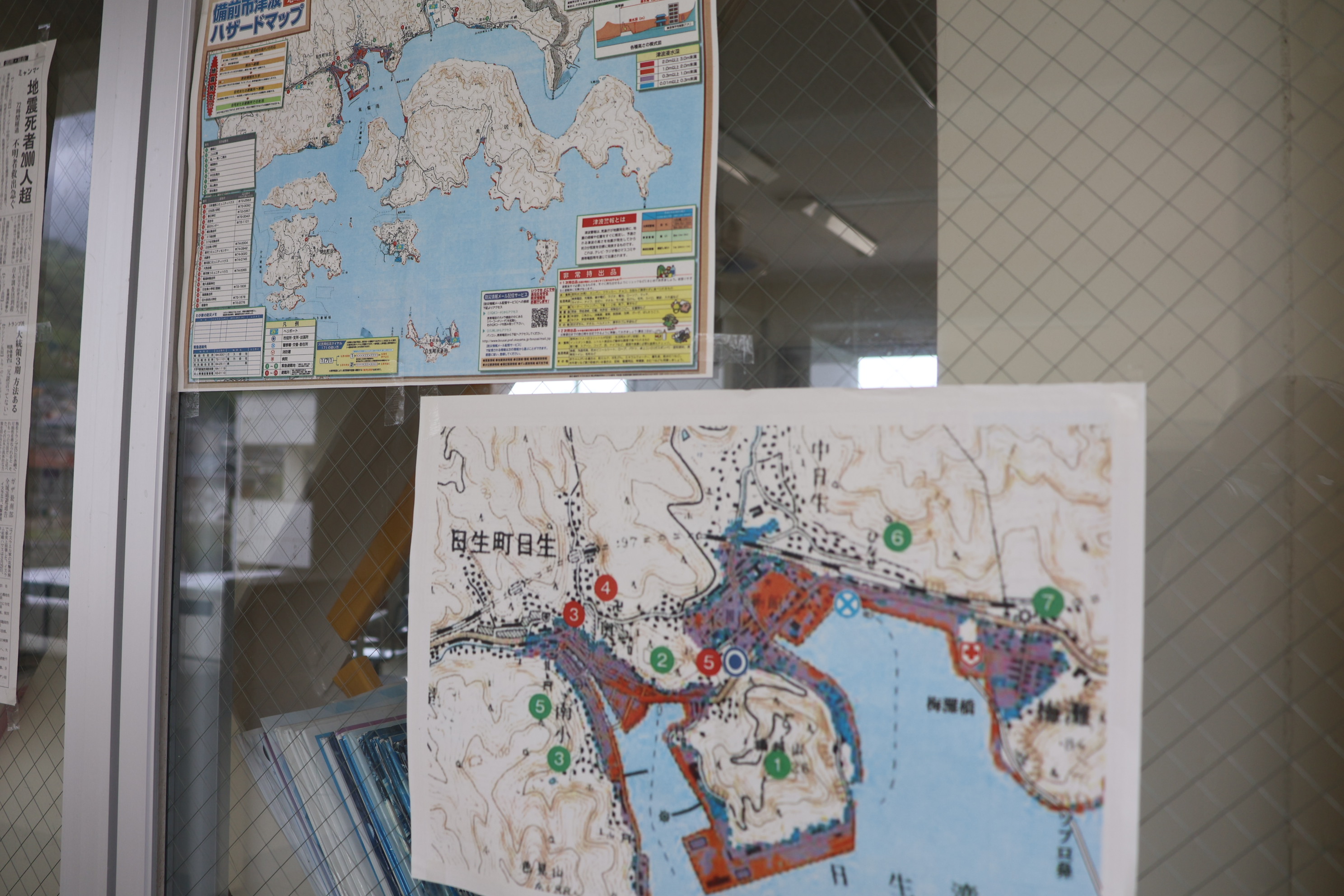
そして、「想像力」 中務さんありがとうございました。
◎エースをねらえ(4/23)
部活動見学・体験は26日(土)まで。





◎学校生活を創る(4/22)




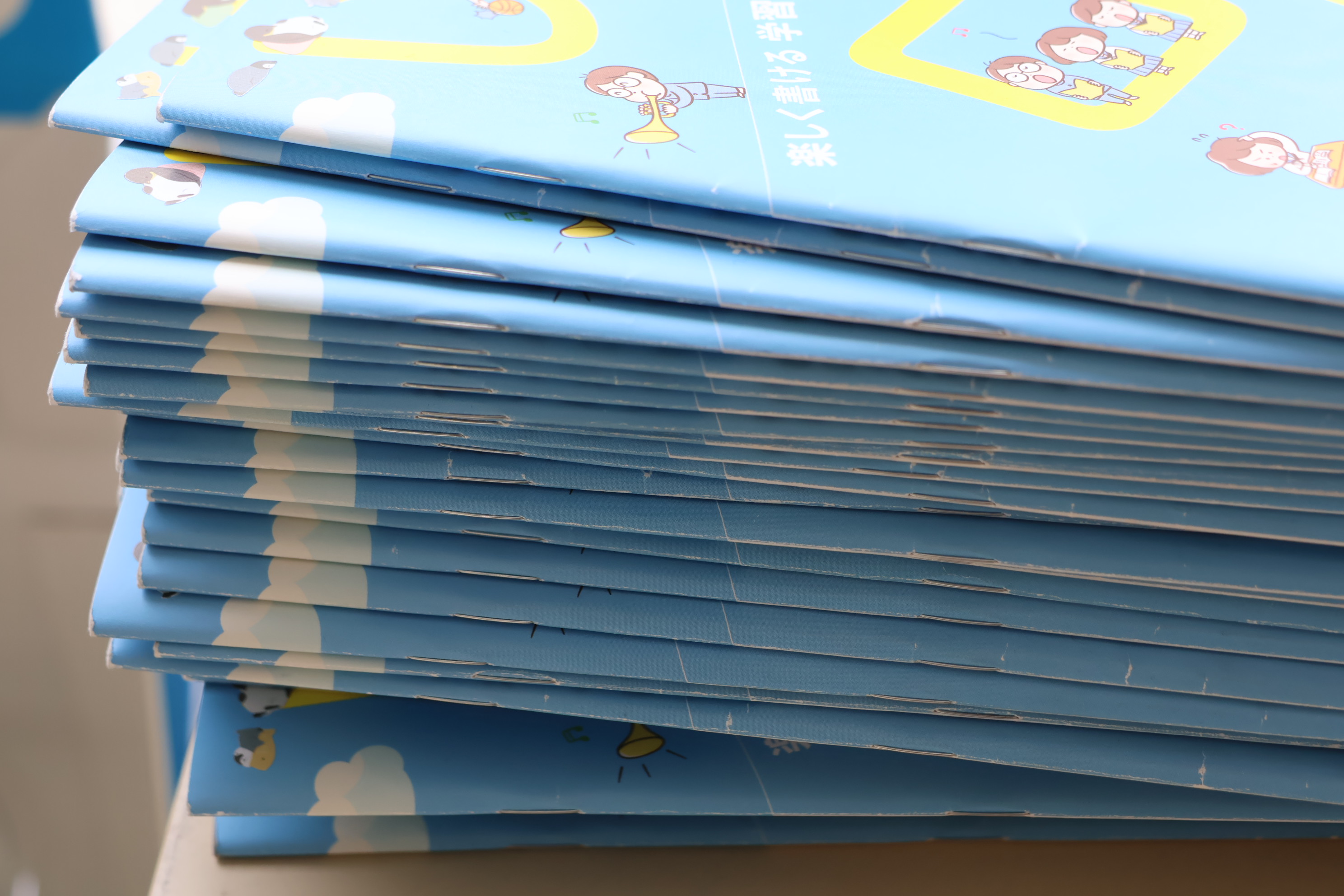

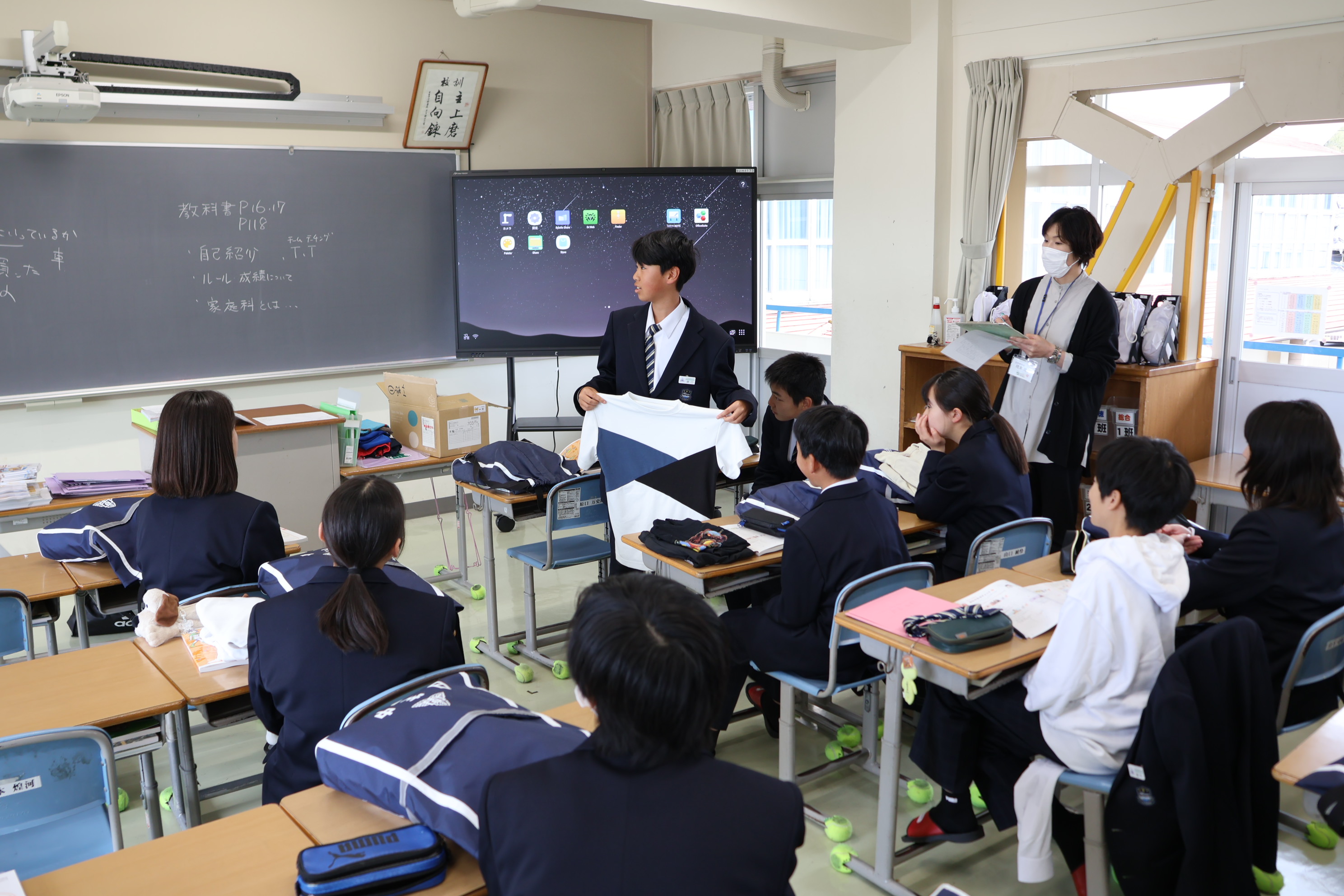


You define beauty yourself‚ society doesn’t define your beauty. Lady GaGa
(美しさは自分で決めるものであり、社会が決めるものではない。)
◎みんなあ カギをしょうで!(4/21:体育委員会より)



忘れていたら?!
◎日生で輝く いま、ここから 未来(4/20)
日生カキフェスに参加してきました。次回(6/1(日))も、多くのボランティアで盛り上げようね。









◎ワタシノブカツ ワタシノジカン (4/18:吹奏楽部中庭コンサート)
1年生の部活動入部届は30日(木)までです。

◎自分がつくる、交通安全で自分を守る。
多くの人に支えられて(4/18)
備前警察署からエリアテーチャーをお招きして、1年生交通安全教室を開催しました。


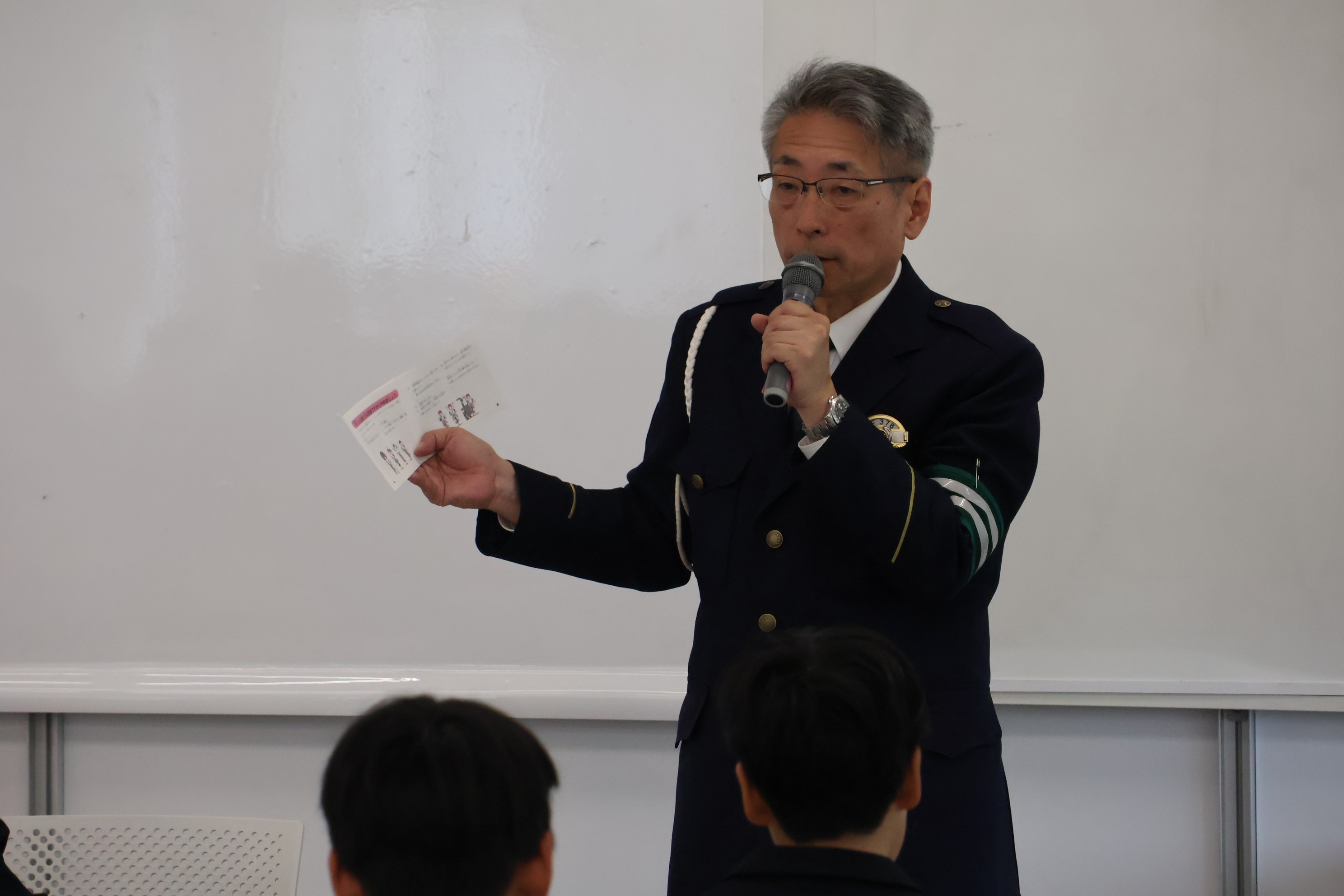
◎日生中LEGACY(4/18)



◎わたしたちの活動 新しい風は日生から
PTA幹事会・委員総会開催(4/17)

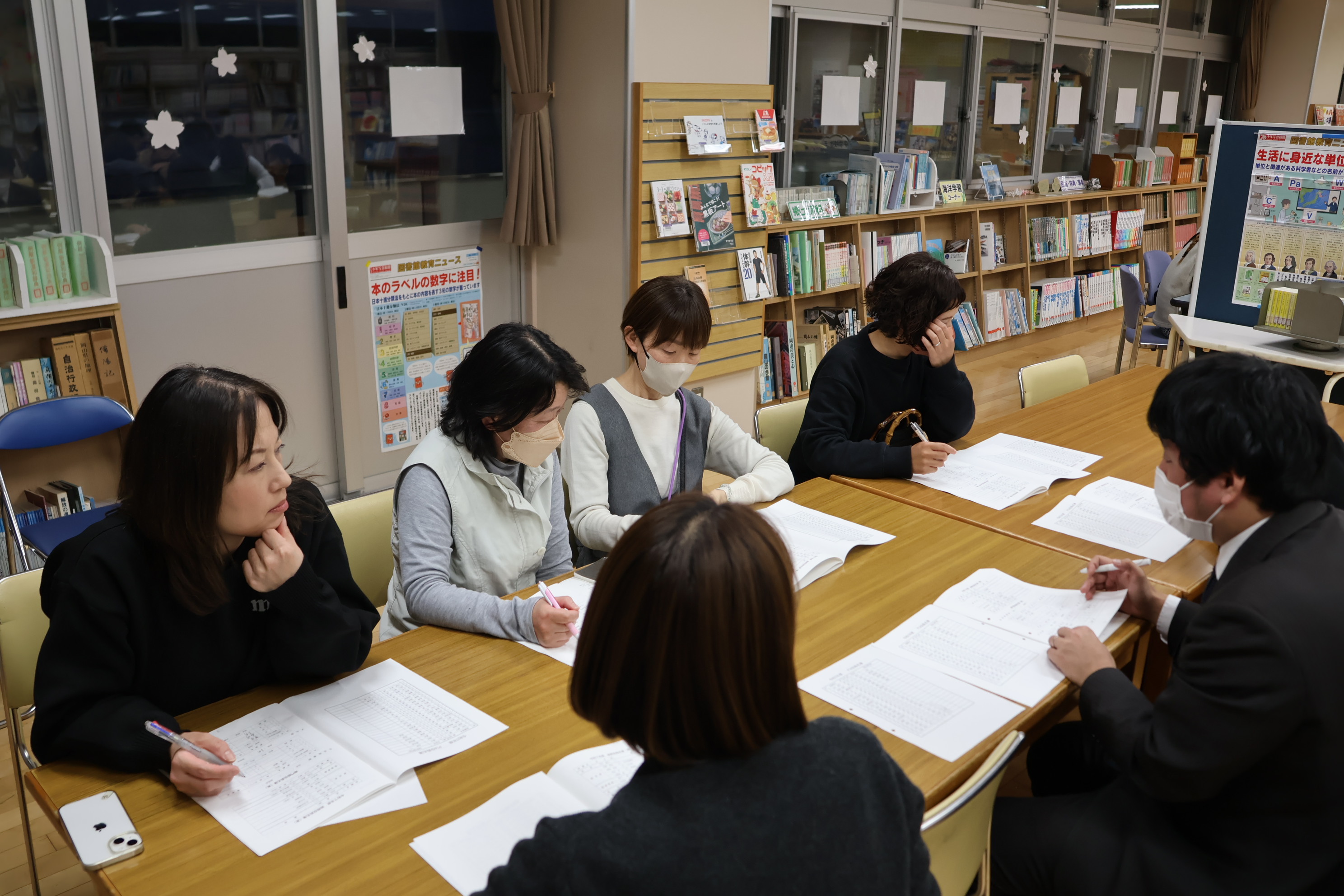

◎全国、県の学力・学習状況調査(4/17)
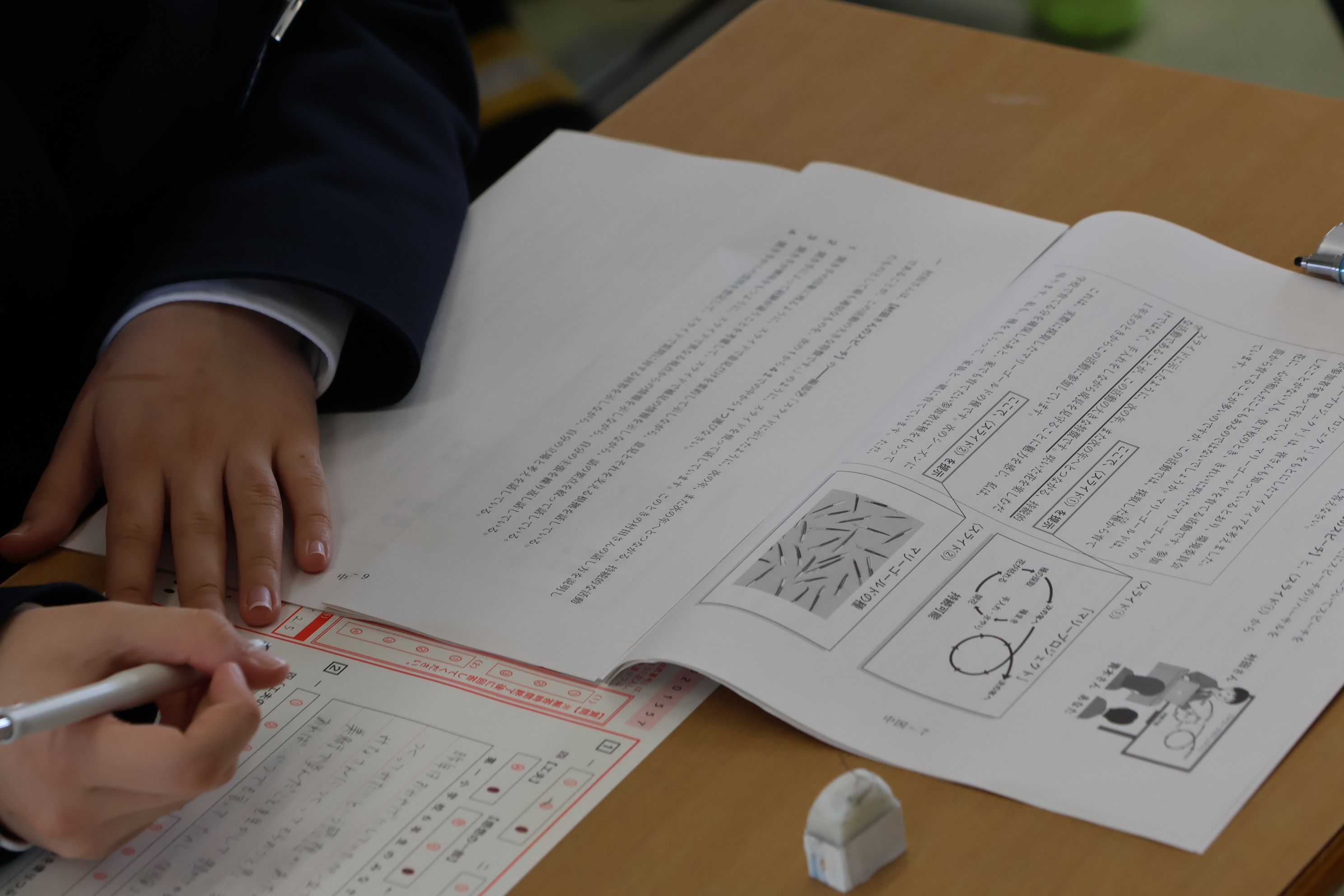
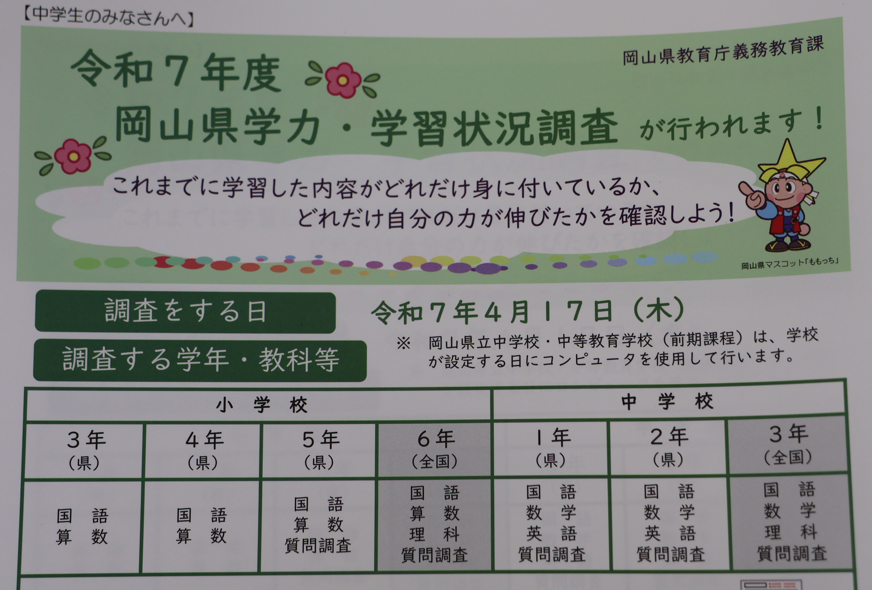
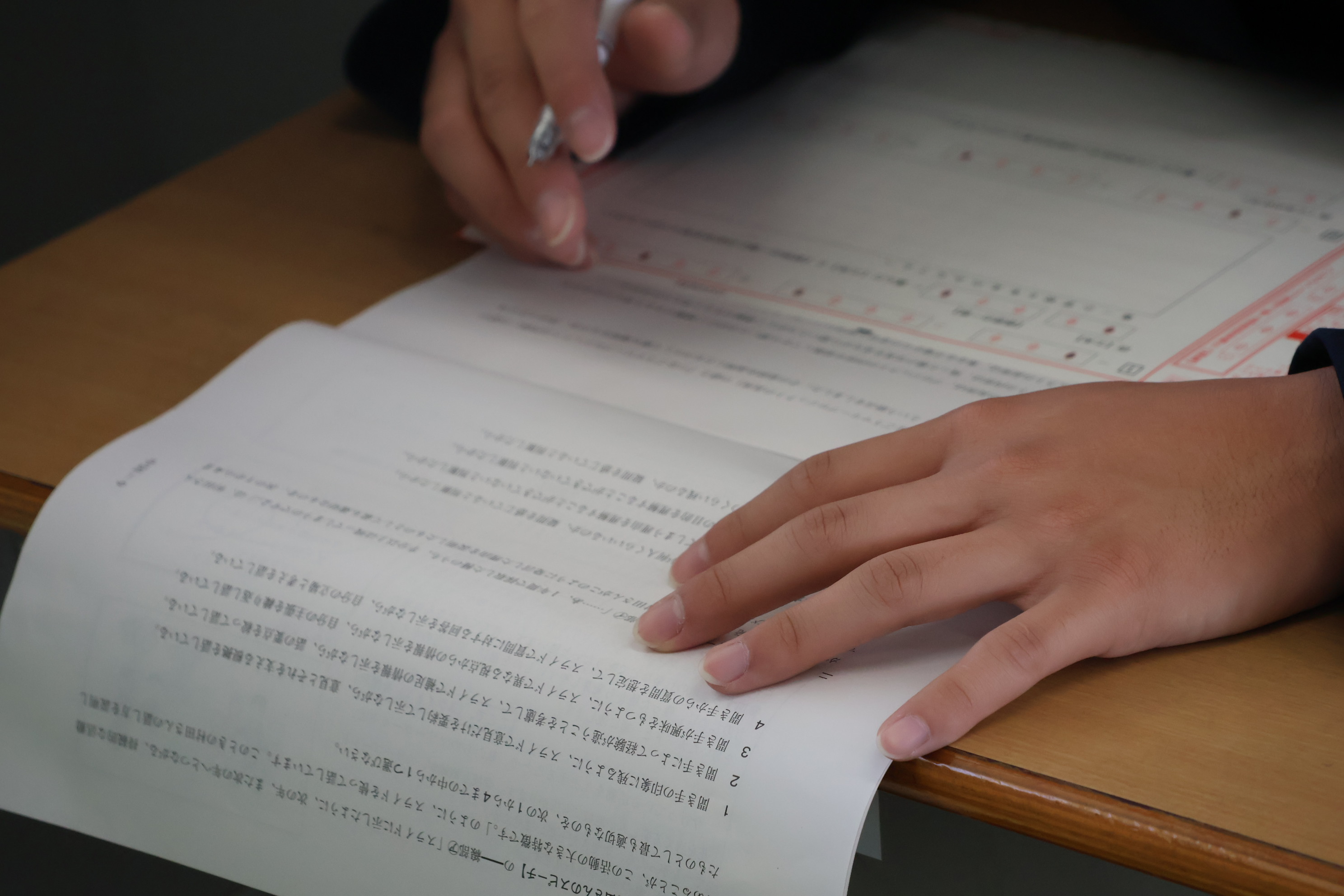
◎アクティブな授業 追及・深まる学びを進めています(4/16)



◎責任と誇りを胸に。がんばり合う仲間であり。(4/16)
仲間のために、クラスのために、自分のために、確認し合う生徒会専門委員会認証式。
そして、自分の目標に向けて、〈毎日の生活の中での「取り組み・行動」〉を積み重ねていくことが、目標達成・夢の実現につながっていく。



◎私たちは輝くために(4/15)
星輝祭(6.7体育の部)に向けてブロック会開催。
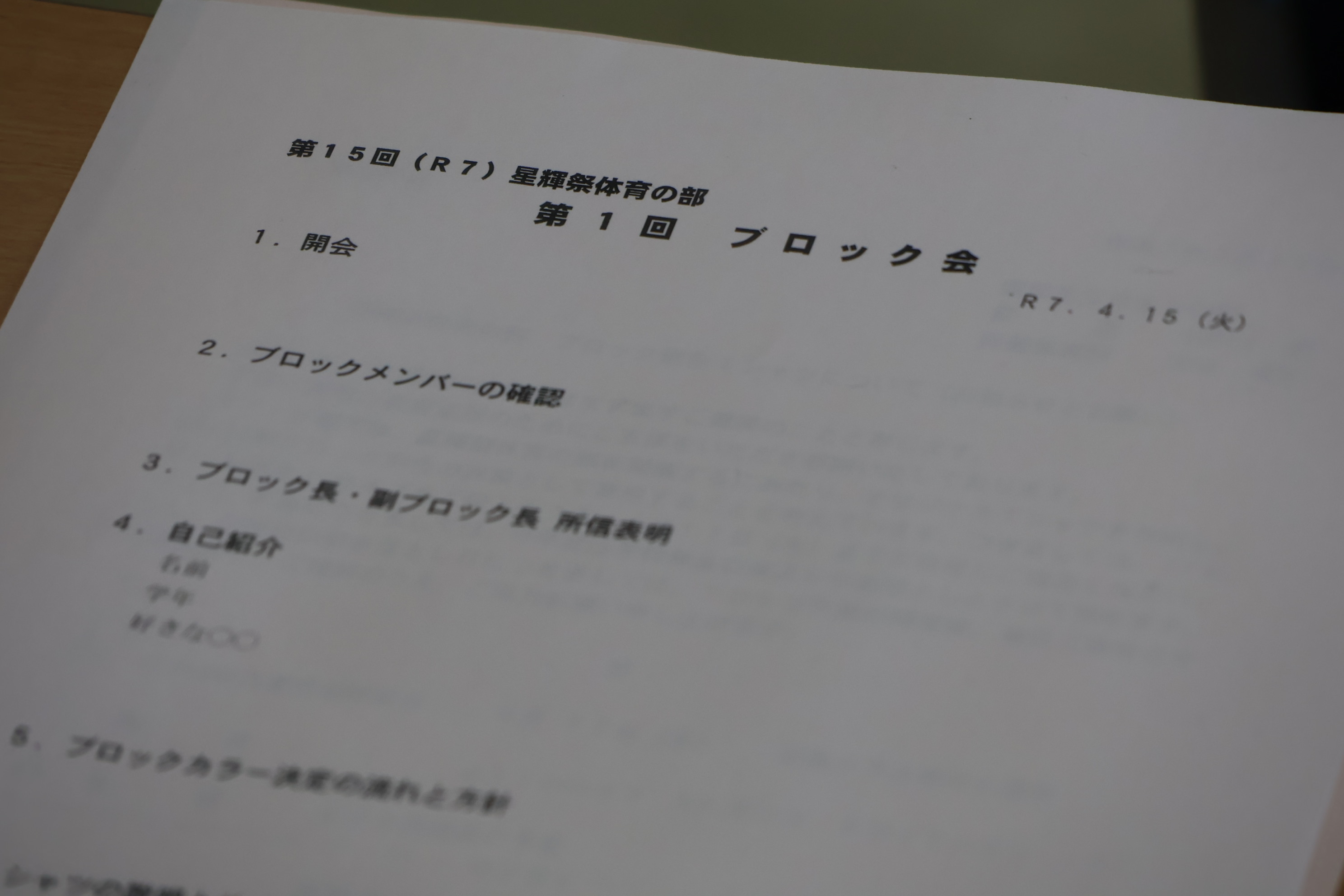
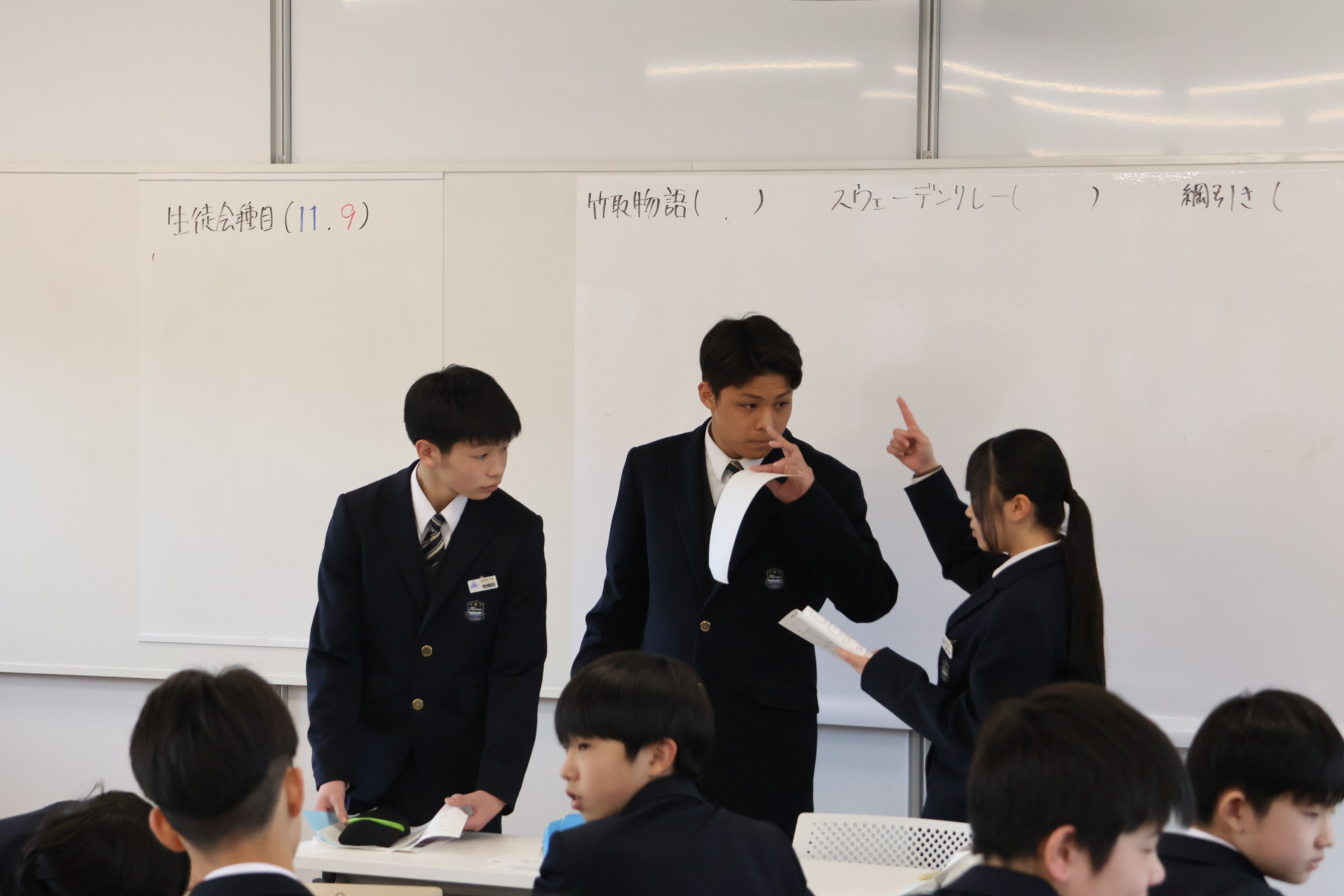
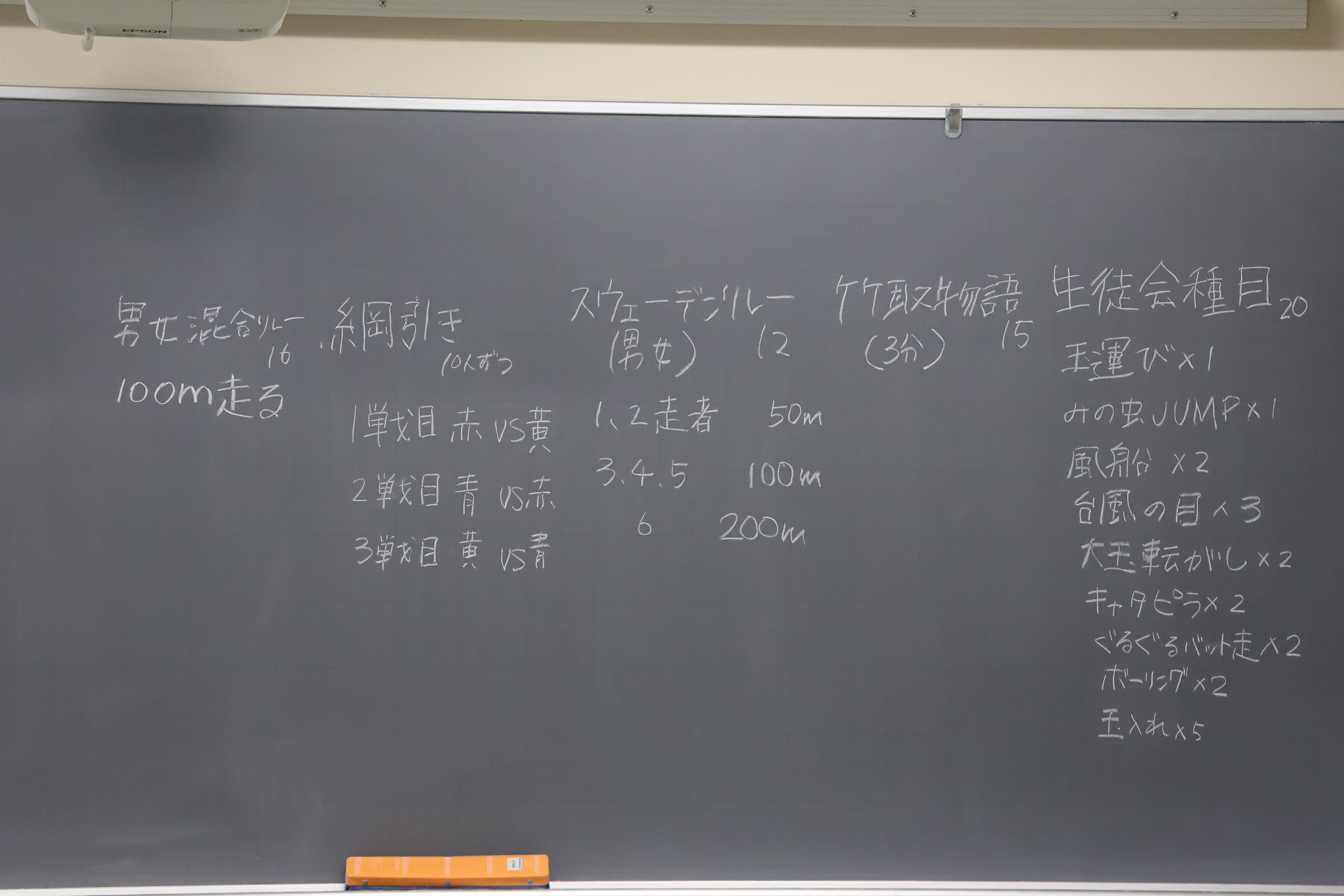
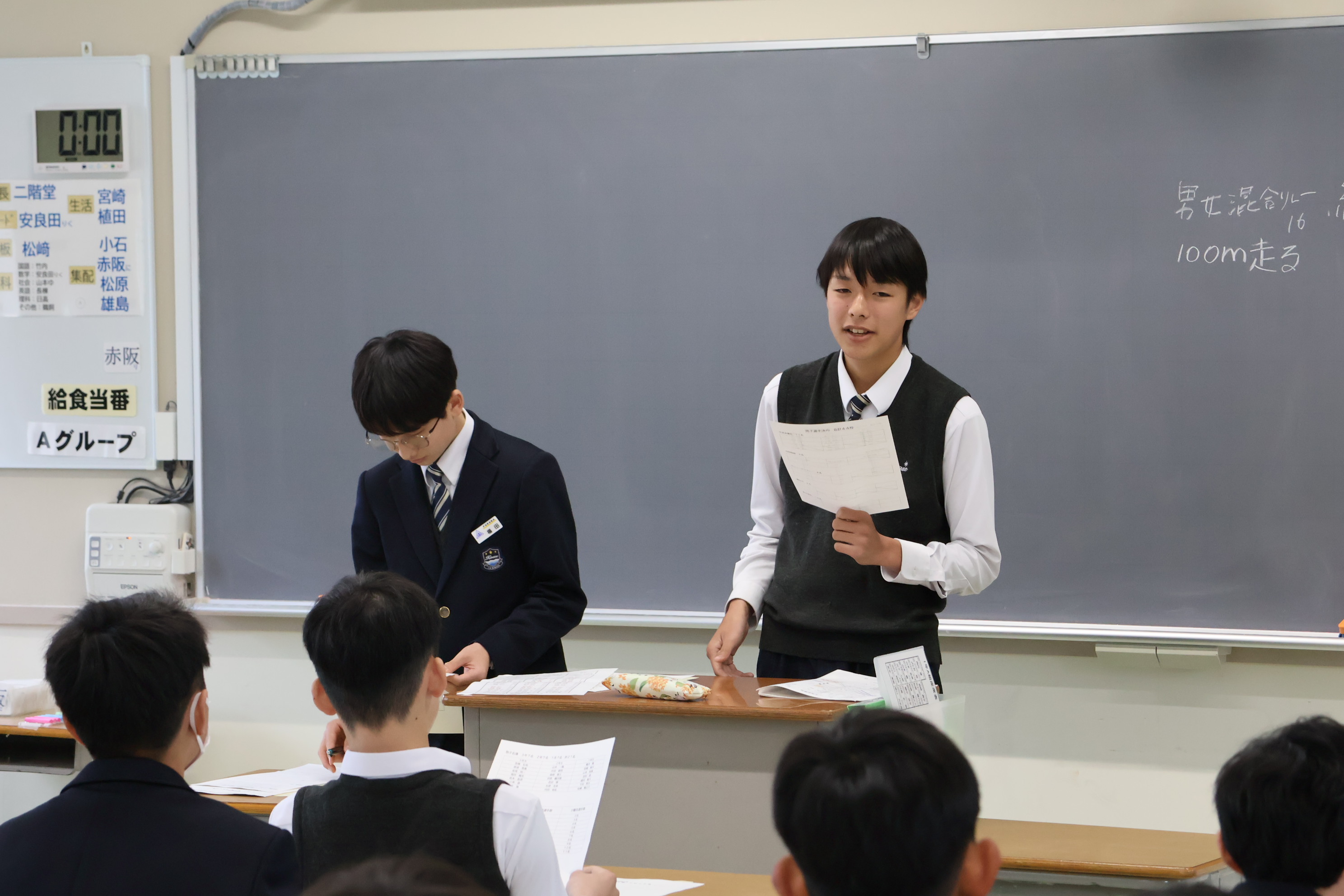





Do not judge me by my successes‚ judge me by how many times I fell down and got back up again. Nelson Mandela
(成功で判断しないで、何回転んで何回起き上がったかで判断してください。)
◎自分を開き、仲間を知る授業
1年生の家庭科では、生徒一人ひとりが宿題として、自分の私服をひとつ持って来てました。授業で学んだ「
TPO」をもとに自分の衣服について発表し、互いに聴き合いました。さらに、これが自己紹介も兼ており、個性豊かな、お互いを分かり合う楽しい授業となりました。

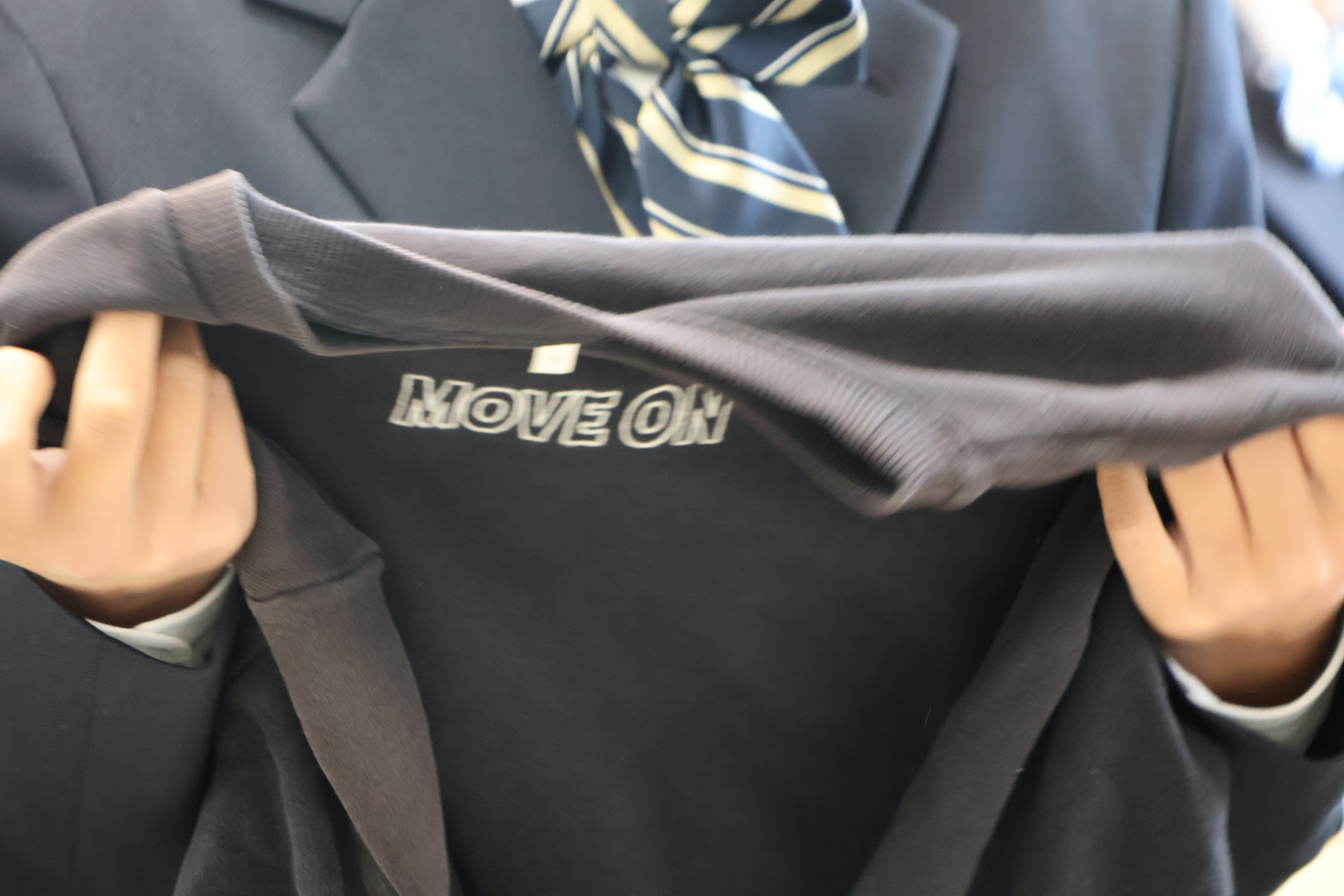

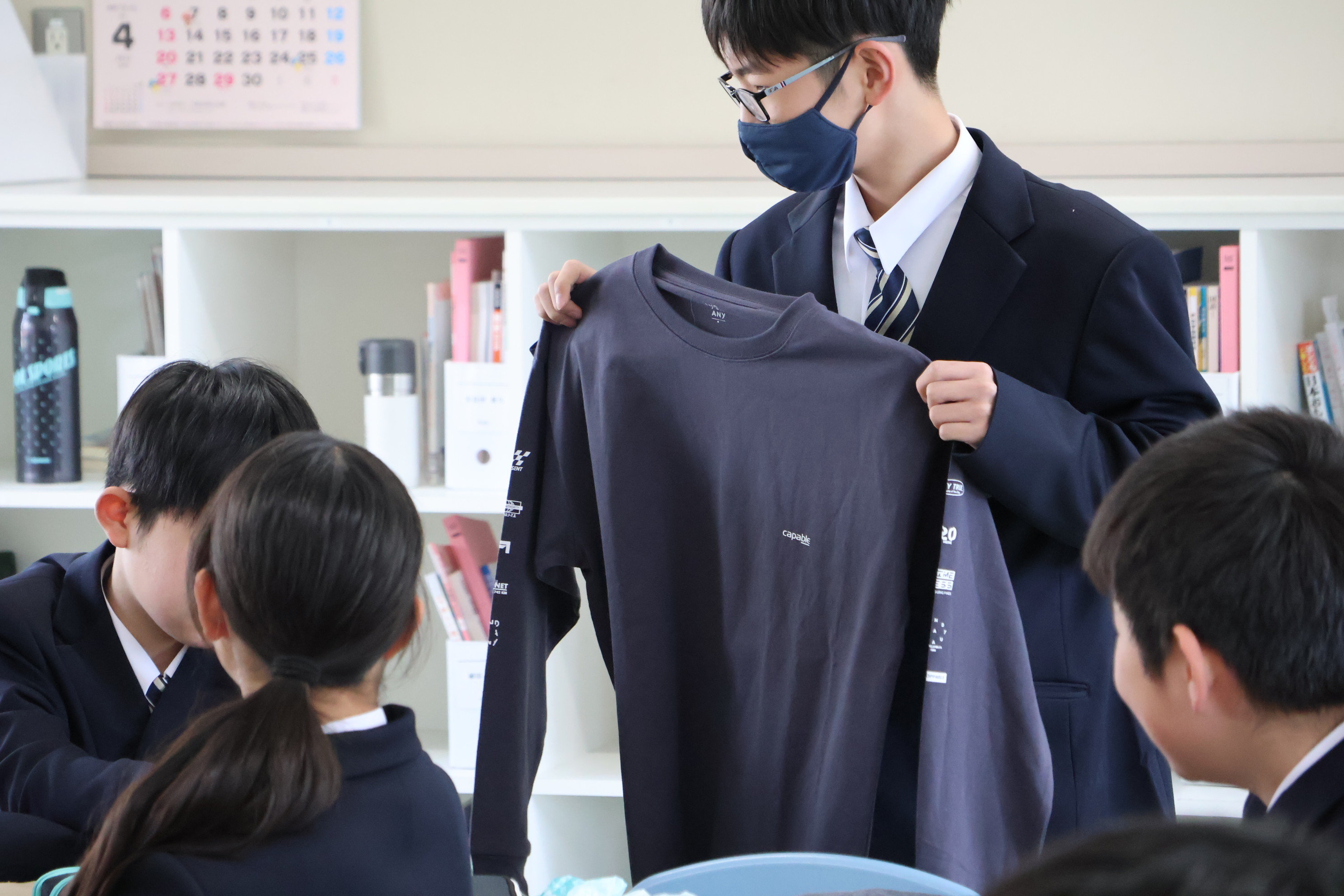
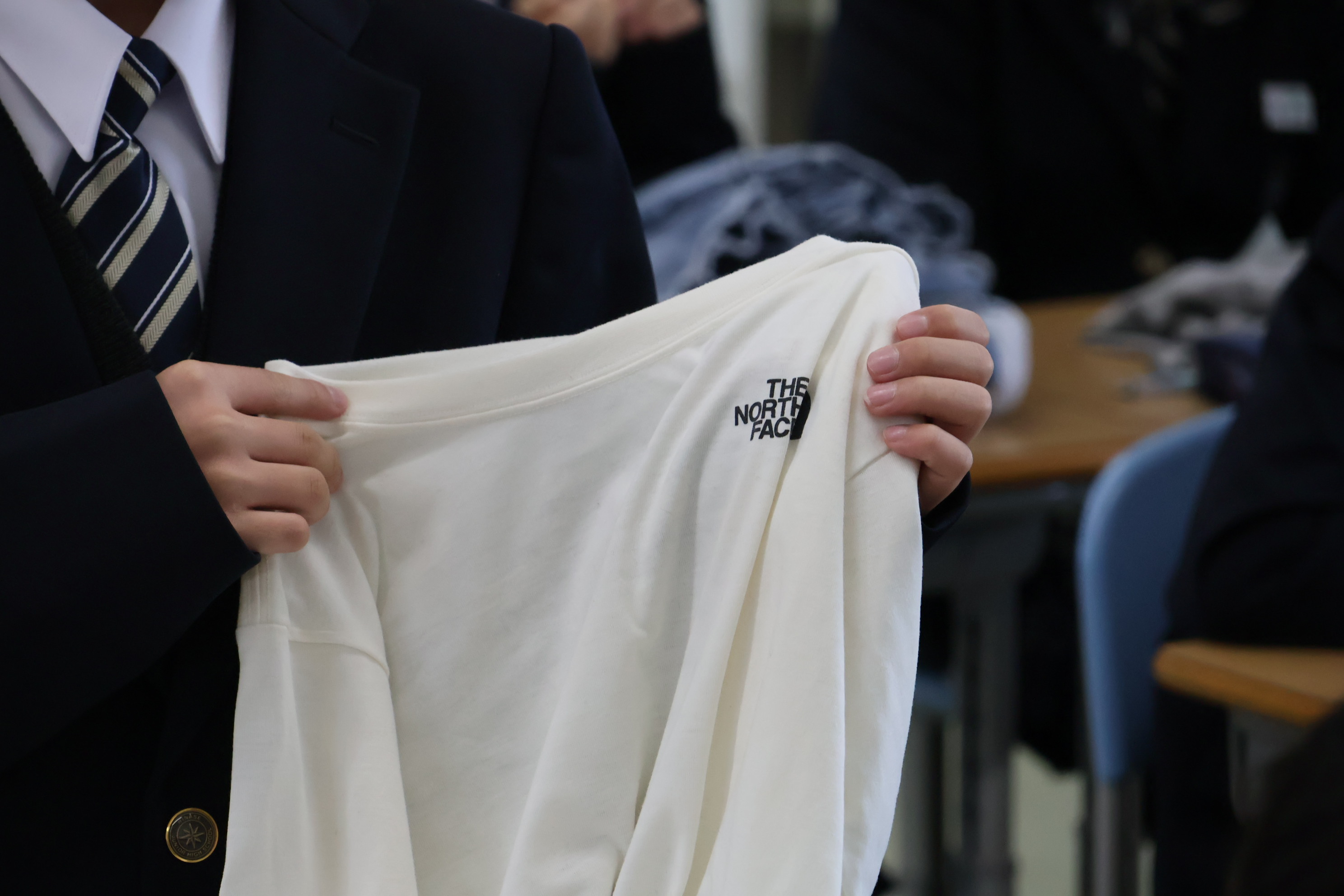

◎新年度も、多くの人に支えられて(4/15)
14日、調理場から、北川先生が来校されました。今年も「食育」を大切に進めていきます。
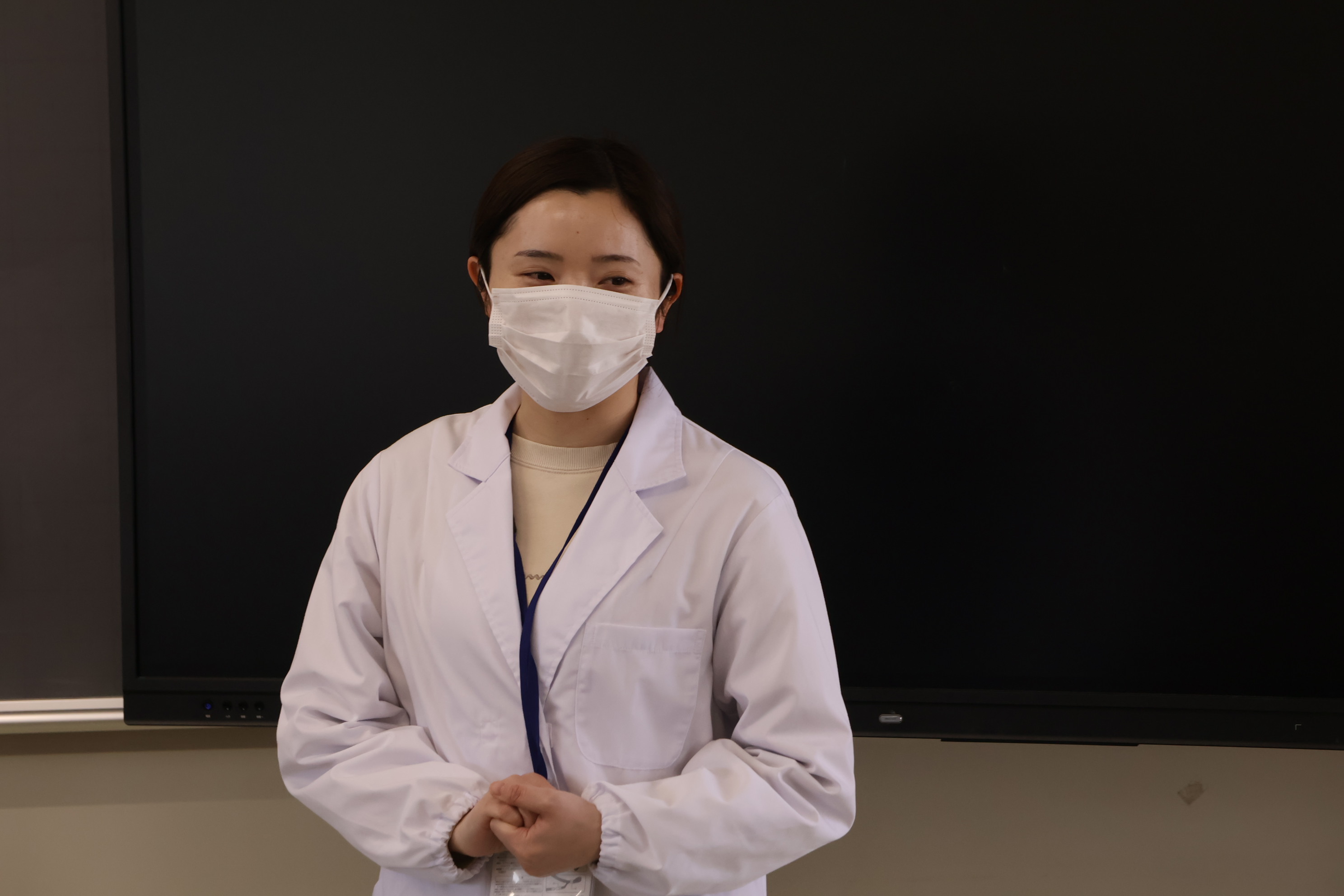


◎生活を創るクラス(4/14)


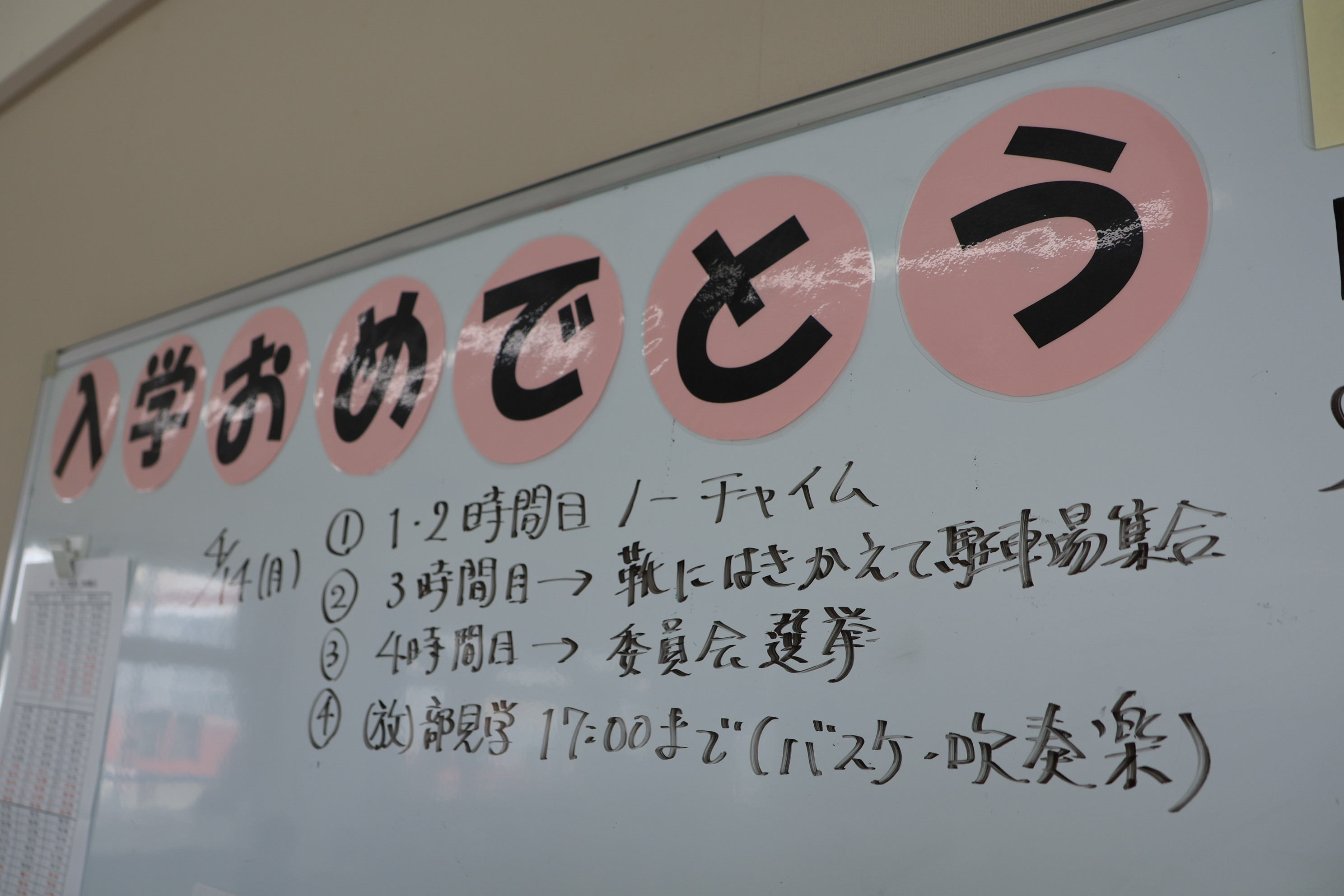






◎もくもく もくもく ひな中LEGACY(4/11)
*レガシーとは、「遺産」や「伝統」などの意味があり、転じて「次の時代に受け継がれていくもの」を指します。



◎春は過ぎゆく(4/11)


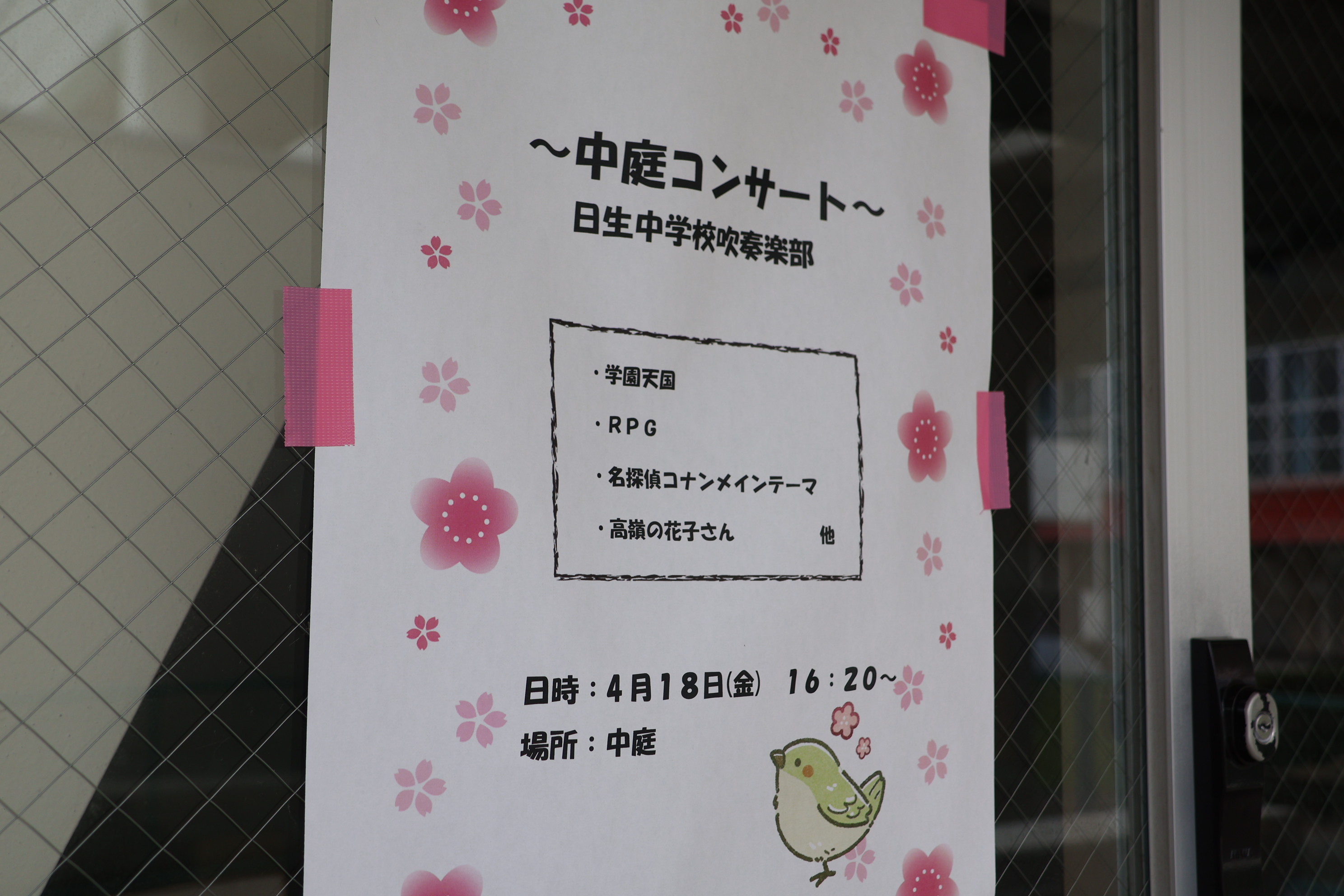
I travel not to go anywhere‚ but to go. I travel for travel's sake. The great affair is to move.
Robert Louis Stevenson
(私はどこへ行くでもなく、行くために旅をする。旅のために旅をするのです。大いなる悩みは移動すること。)
◎ひな中の風(4/10)



◎日生で輝く 日生が輝く日々を(410:入学式)





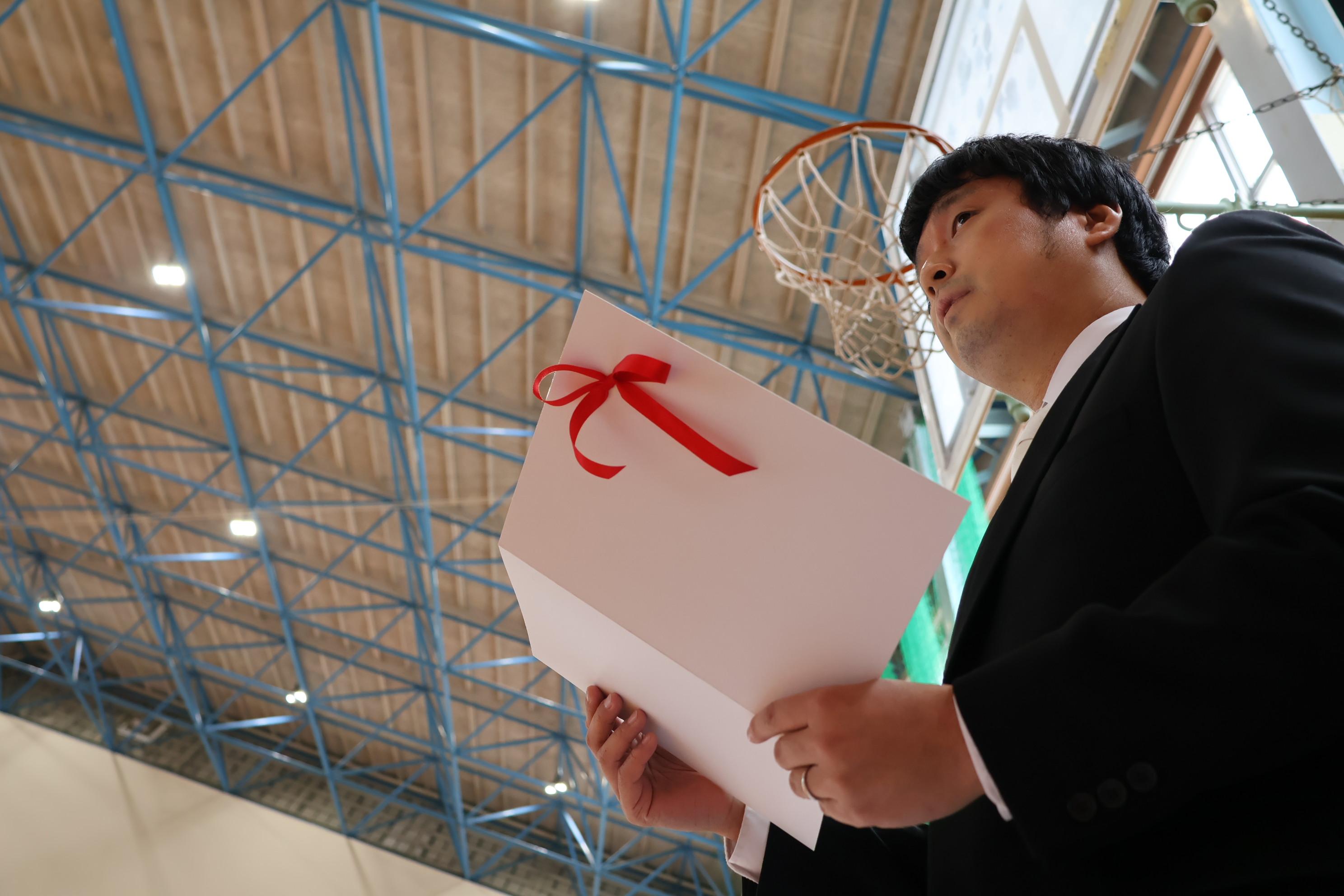









◎出会いに心をこめて(4/9:明日は入学式)


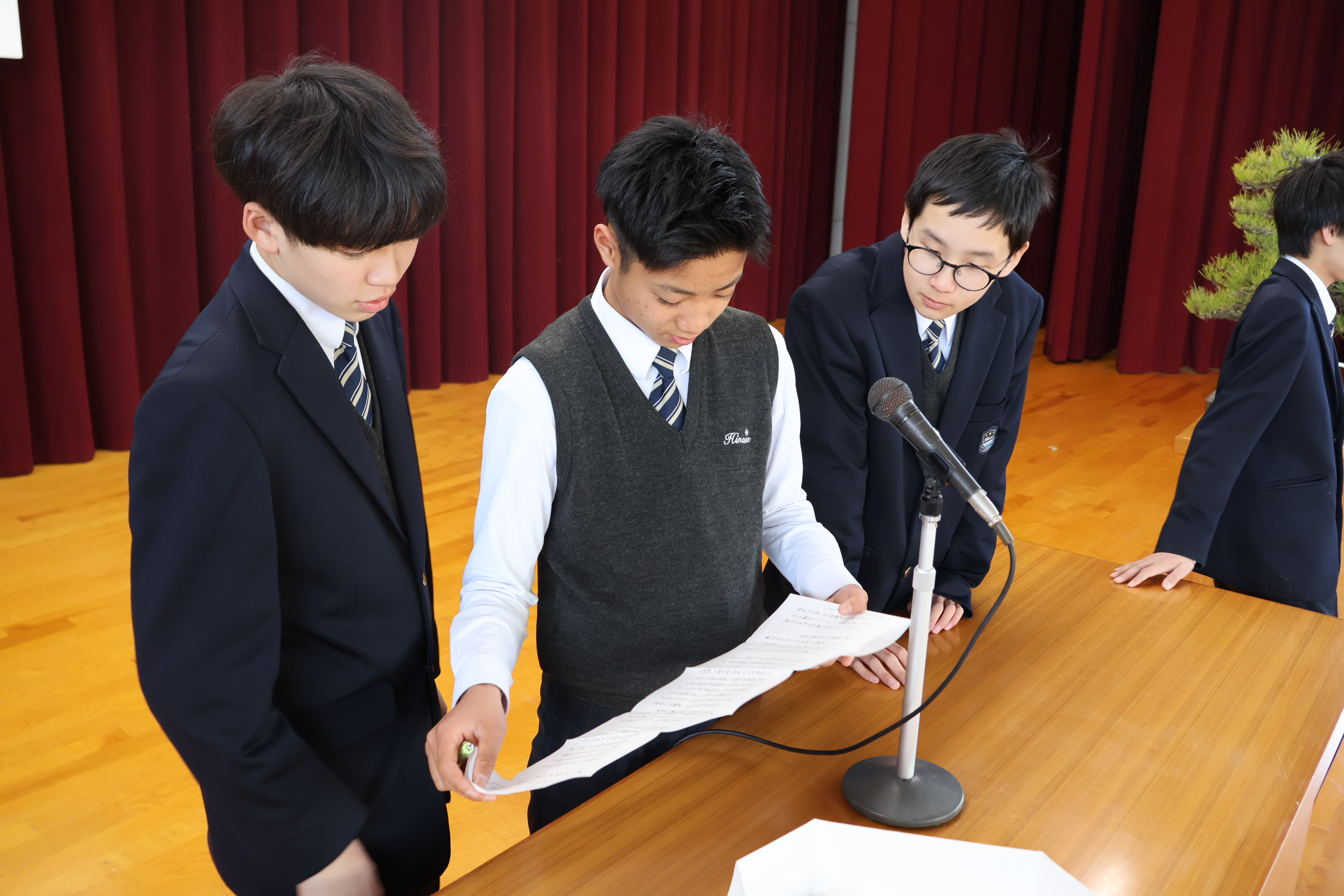


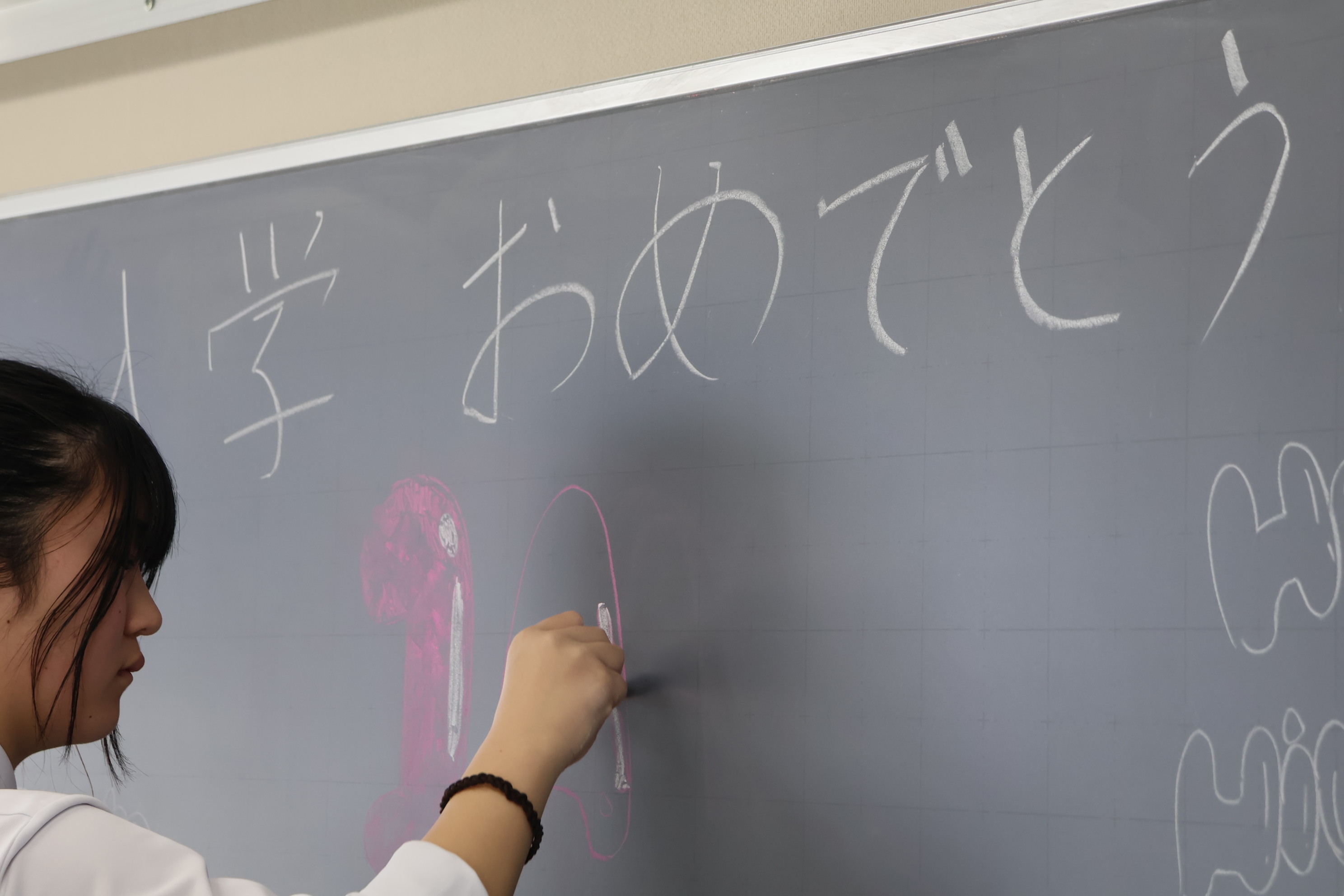
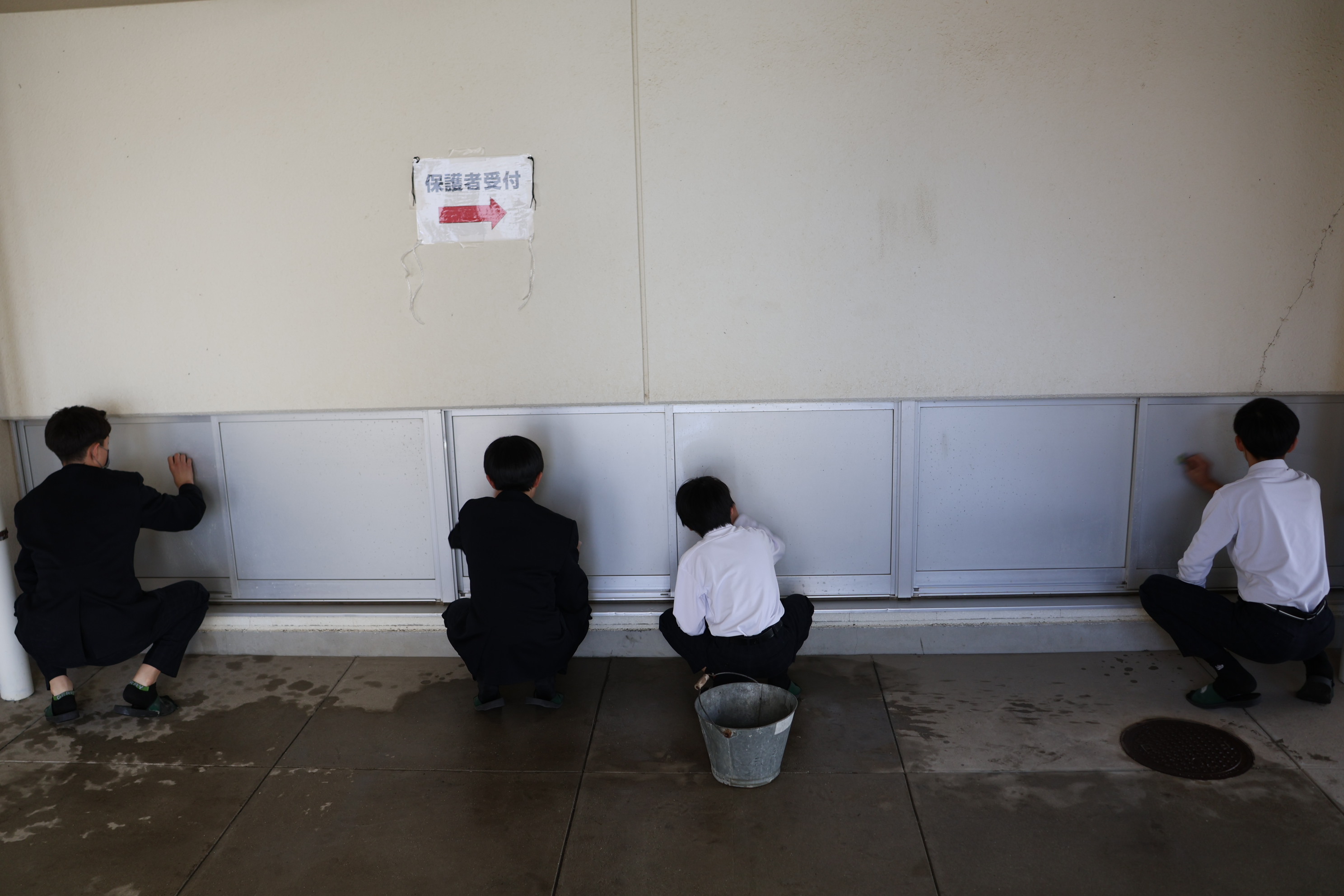


The best thing to hold onto in life is each other. Audrey Hepburn
(人生において、しっかり捕まえておきたい最高のものは「お互いの存在」)
◎わたしたちのはじまりの風景15(4/9)
ここはどこでしょう?









◎挑む 進んでく 開いてく(4/8:到達度確認テスト)


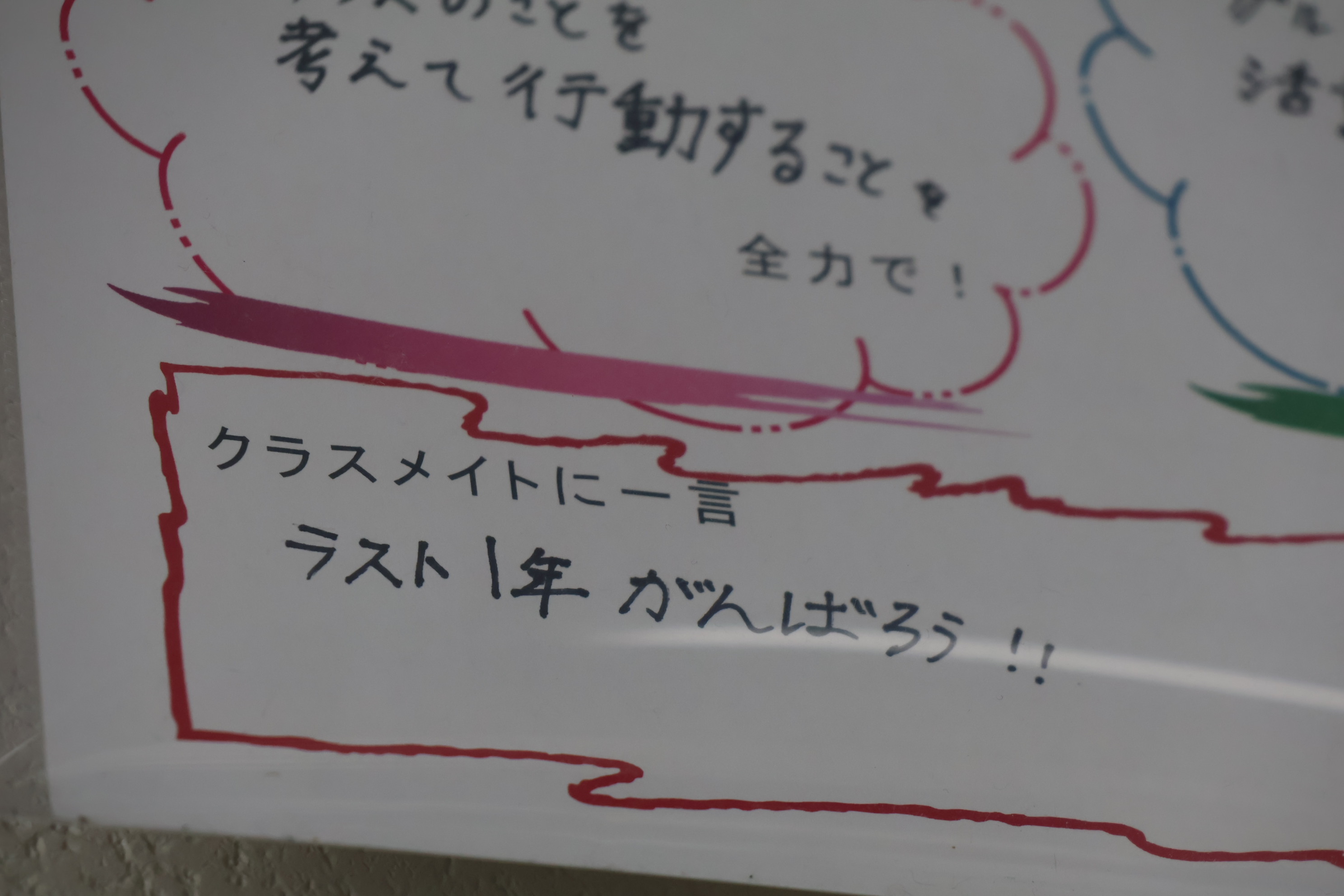

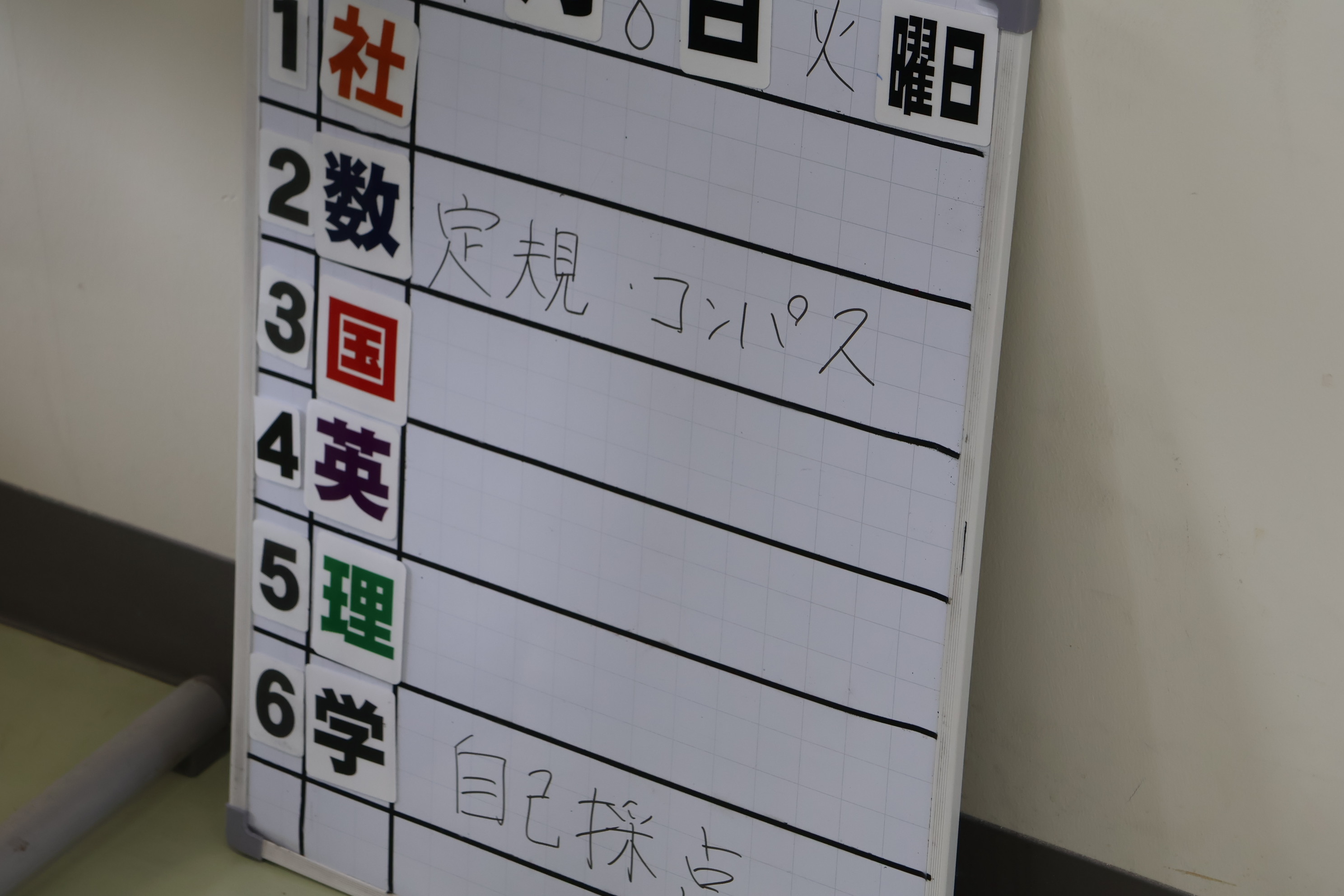
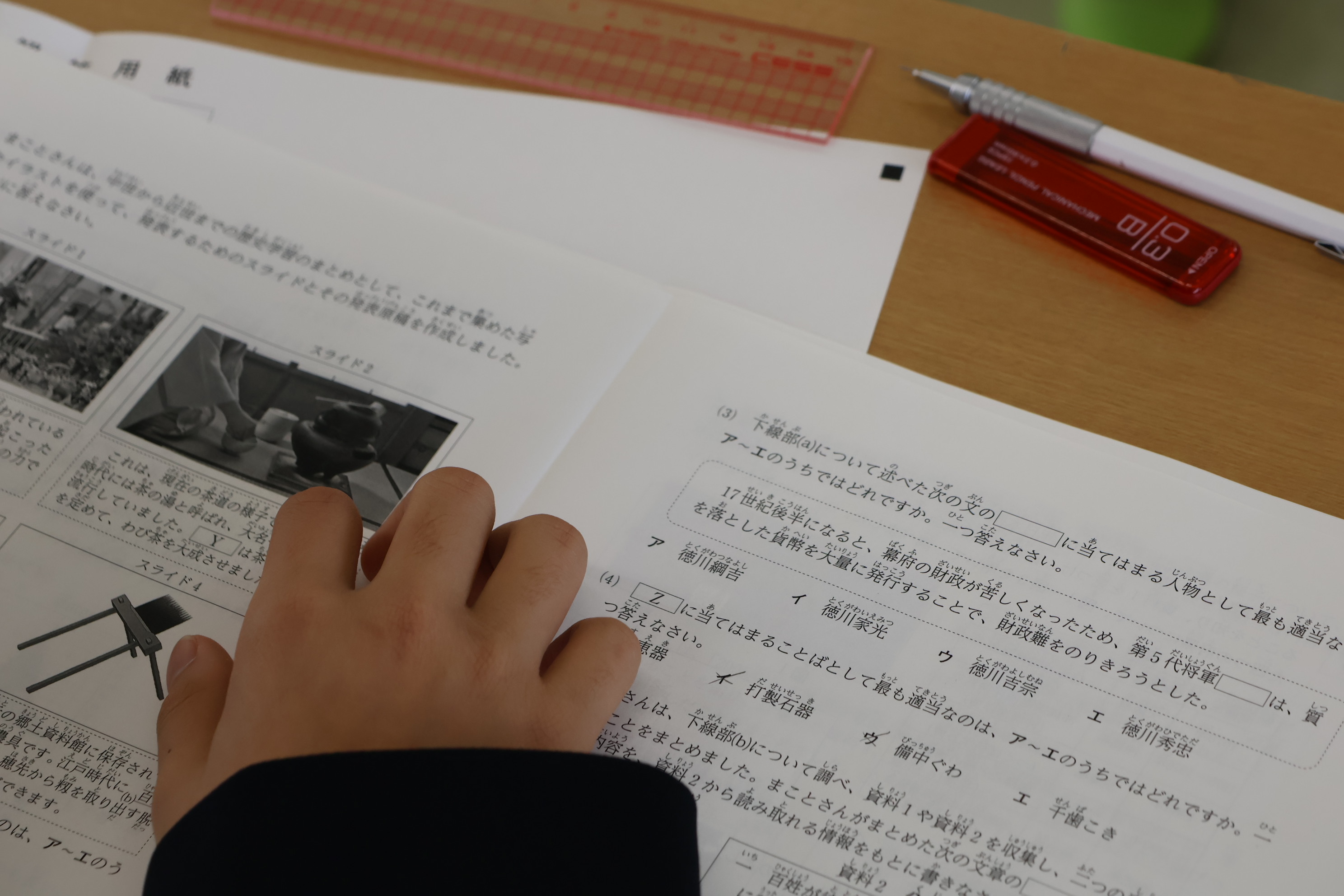

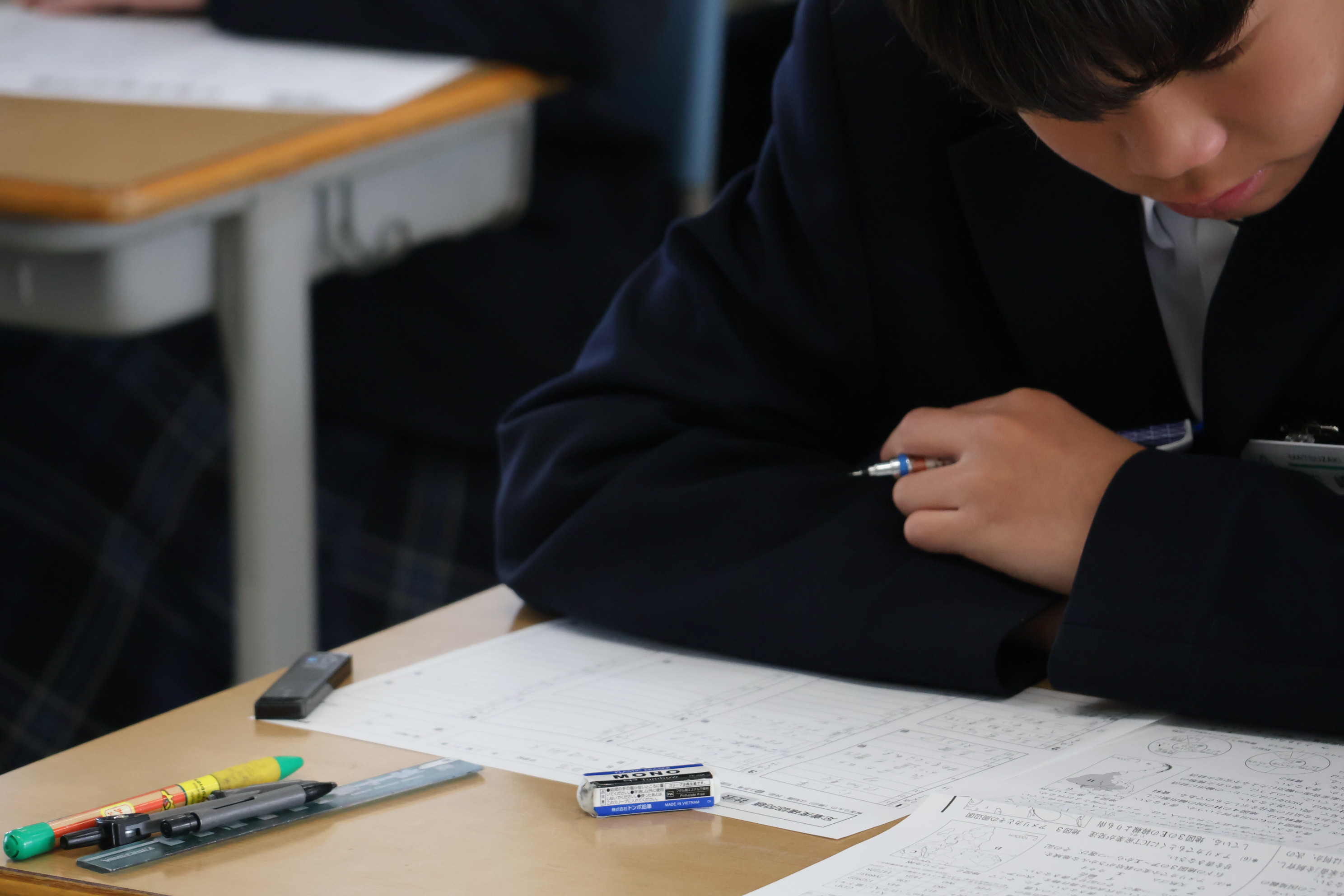

〈学び続ける者だけが教壇に立つことができる 佐藤 学〉
校内研修を中心に私たちも学んでいきます。(4/7:校内研修会)


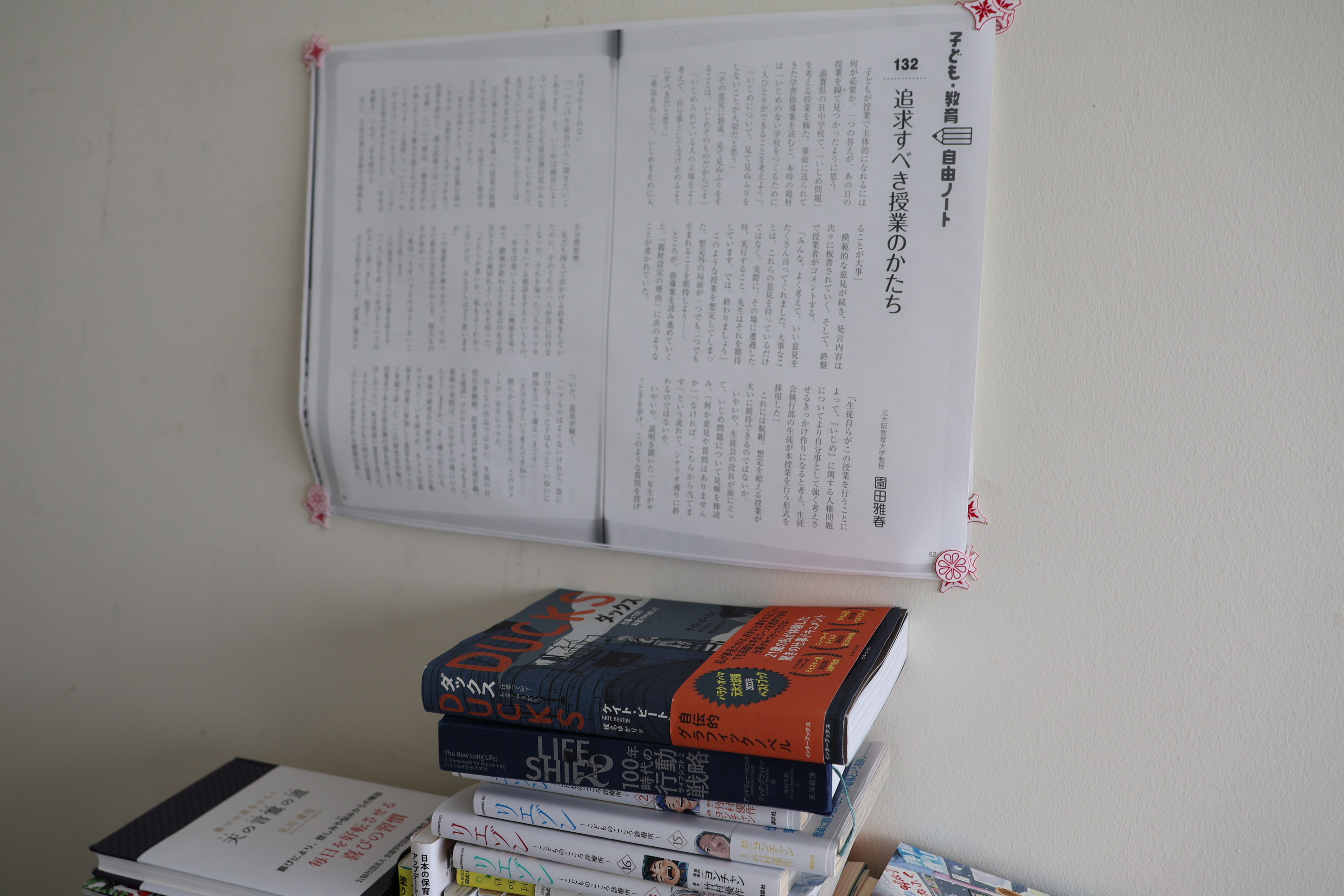
◎はじめよう 仲間と共に(4/7:着任式・始業式)
~学ぶとは誠実を胸に刻むこと 教えるとは共に希望を語ること ルイ・アラゴン~



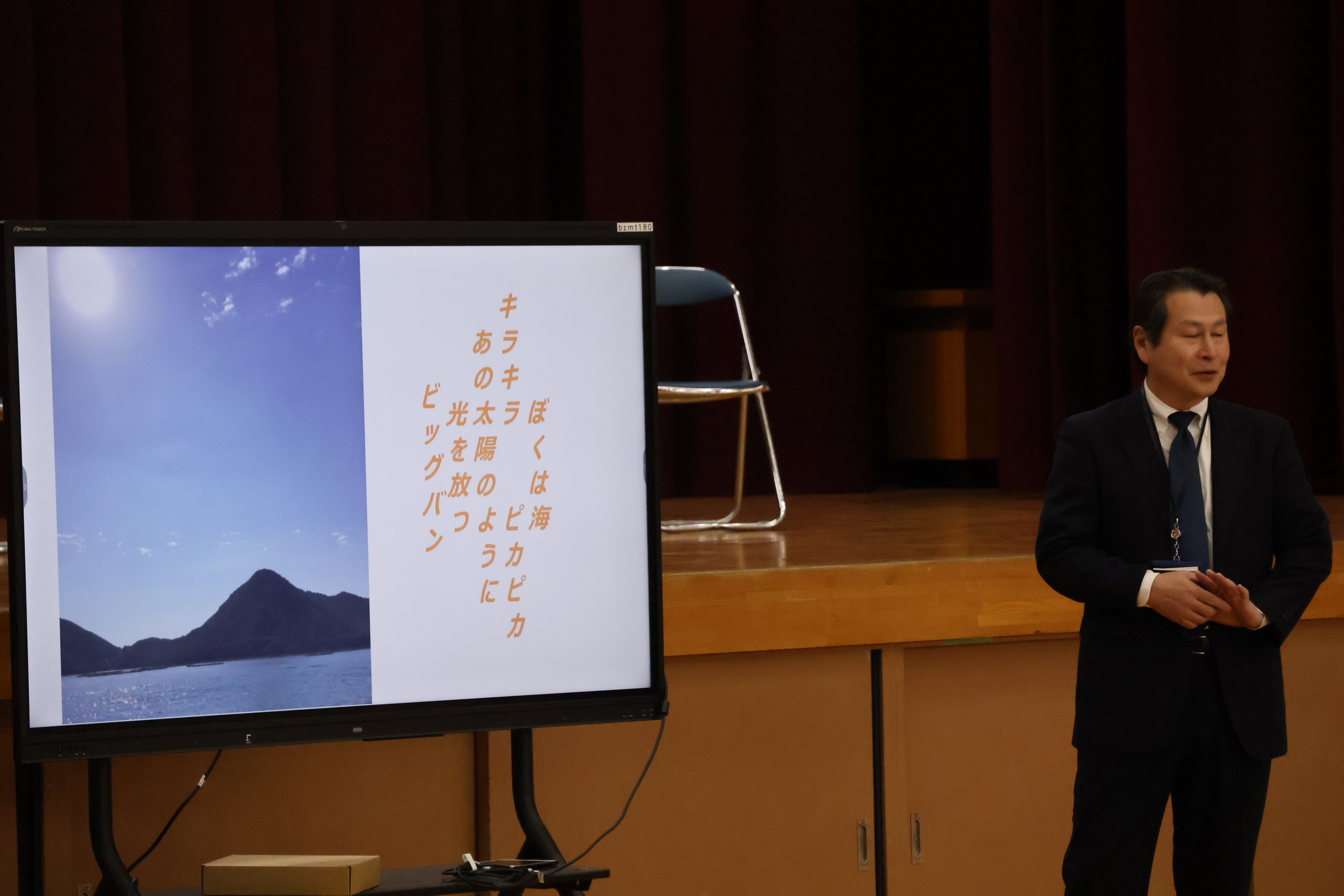




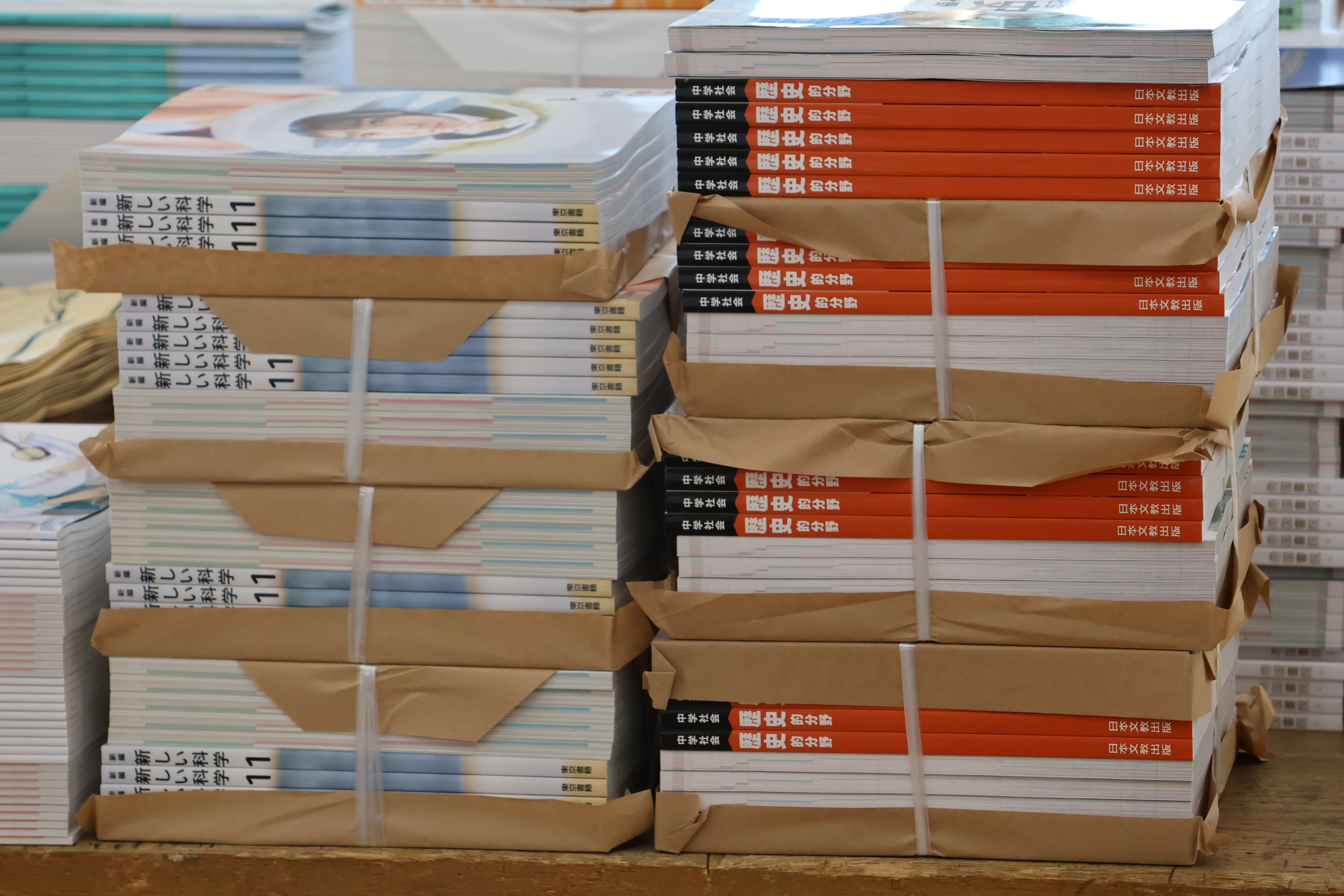
◎また元気に会おうね!新年度、始業式は4月7日(月)

〈風景はわたくしである眠ければ眠ってしまうわたくしである
やわらかに僕のかたちを確かめる風景であり 満開であり 吉野裕之〉

〈パソコンと引き出しまるごと持っていく、職員室の机移動日
新年度の仕事に取り組む席 古いけど「新しい席」と言う
引き出しの奥に眠っていた手紙また読む 春が来るたびに読む 千葉聡〉(4/4)



◎この旗がもつ意味って?(4/3)

新学期にむけて、、グローバルルームを整備しています。その教室に掲示されている旗が気になったので調べてみました。
『レインボーフラッグとは、LGBTQ+の尊厳と連帯、社会運動のシンボルとして使われている旗です。
1978年にサンフランシスコのアーティストであるギルバート・ベイカーがデザインし、「Gay Freedom Day Parade」で使用されたものが始まりと言われています。この時は手染めで8色(ピンク、赤、橙、黄、緑、ターコイズ、青、紫)で構成されていました。その後、何回かの社会運動の中で大量に確保する必要性などから、現在の6色に変わってきました。
性のあり方は多様で、グラデーションとなっているため、美しい虹で表現されています。
現在、最も広く使われてるレインボーフラッグは、6色(赤、橙、黄、緑、青、紫)で表現されています。赤はライフ、オレンジは癒やし、黄は太陽、緑は自然、青は調和、紫は精神の意味が込められていると言われています。レインボーフラッグは、LGBTQ+を象徴する旗としては最もメジャーなものの一つと考えられますが、多様な性を象徴する「プライドフラッグ」にはほかにも様々な種類があります。「あの旗は何だろう?」と興味を持ったら、ぜひ調べてみましょう。
〈花の名は思い出せねど近寄りぬ 香りをかぎぬ 生きてこの春 藤島秀志〉(4/2)
新年度の準備をしています。


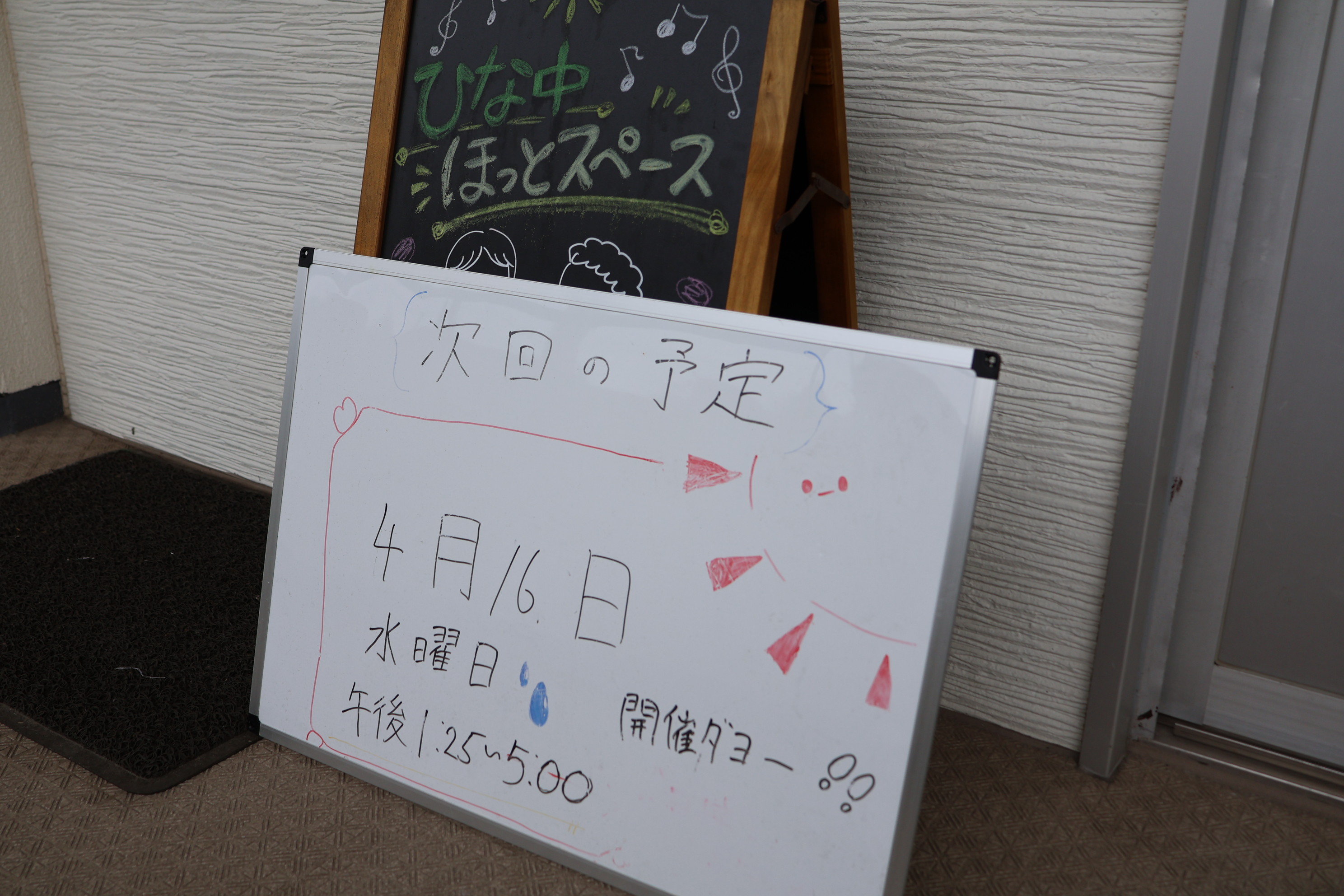





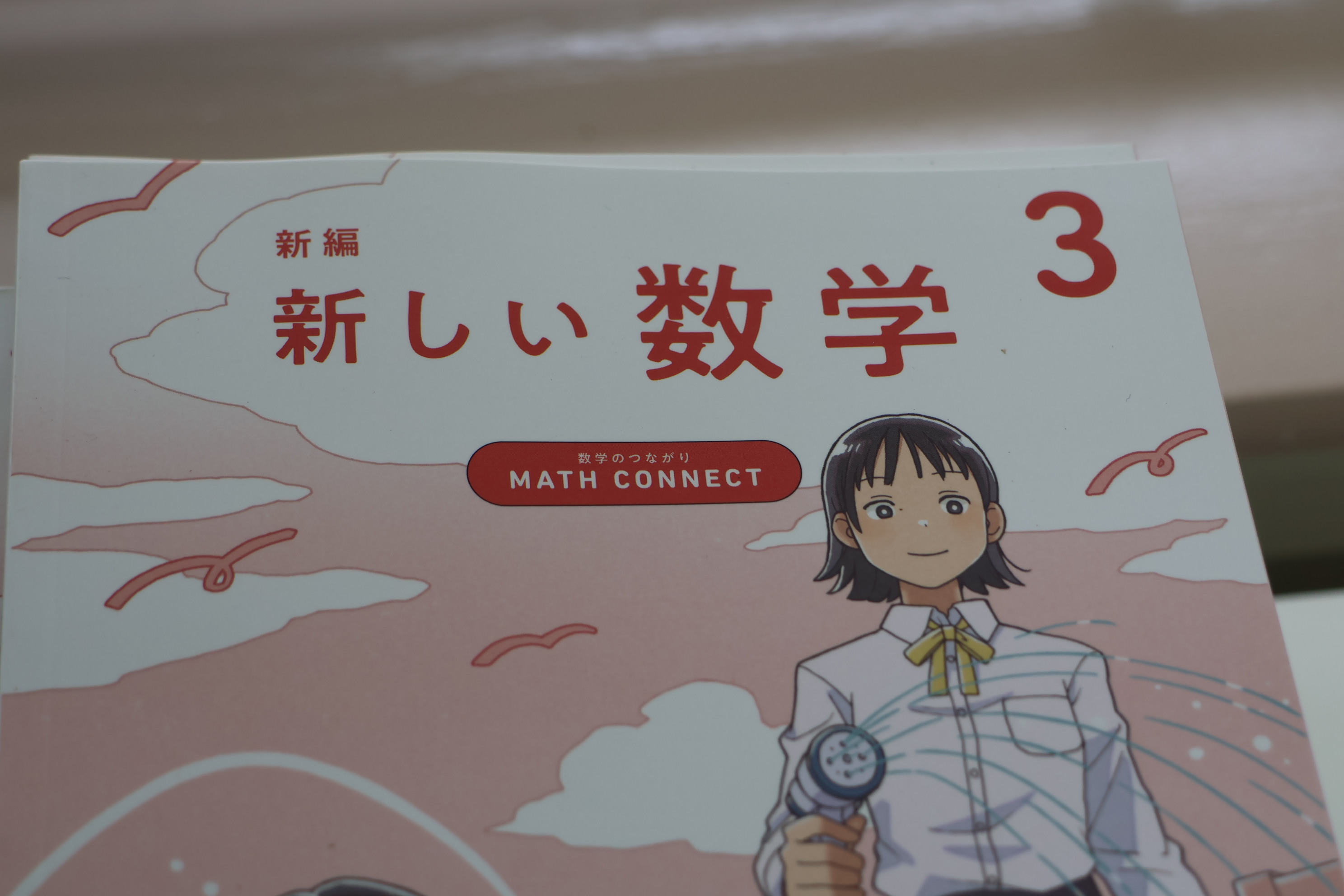


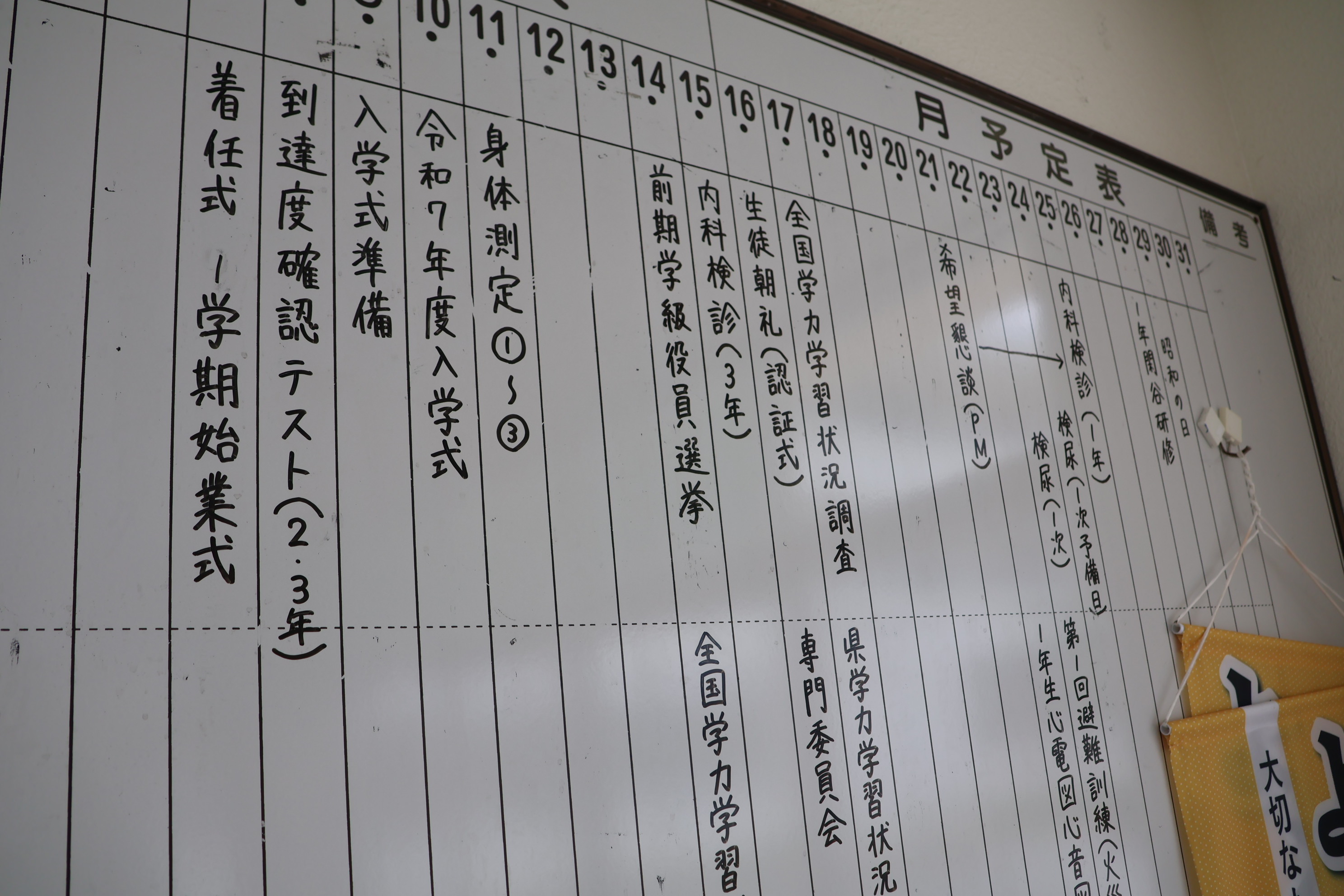
◎春からも、なかまとともに(4/1)

◎地域とともにある学校
~日生で輝く 日生のラスク つくっています(3/31)
ひな中ほっとスペースに集まる仲間が、天gooカフェさん、カメイベーカリーさんのご支援を受けて、新商品を開発しています。今日は中学校の先生たちに試食してもらました。いただいた感想や意見をもとに、工夫・改善をすすめます。



◎十五の春にむけて、確かな連携(3/27:日生学区小中連絡会開催)
新年度・新学期に向けて、小学校の先生方と引継ぎの会をしました。子どもたちのこれまでの小学校での成長をもとに、中学校でのさらなる成長を目指した、連携・協働を進めることができました。

◎ひな中の風~ みんなの協力のおかげで(3/27)
ペットボトル回収にご協力をありがとうございました。今年度もワクチン等の社会貢献活動に役立たせていただきます。本日、護美飼料株式会社さんへもっていきます。ご協力をありがとうございました。生徒会

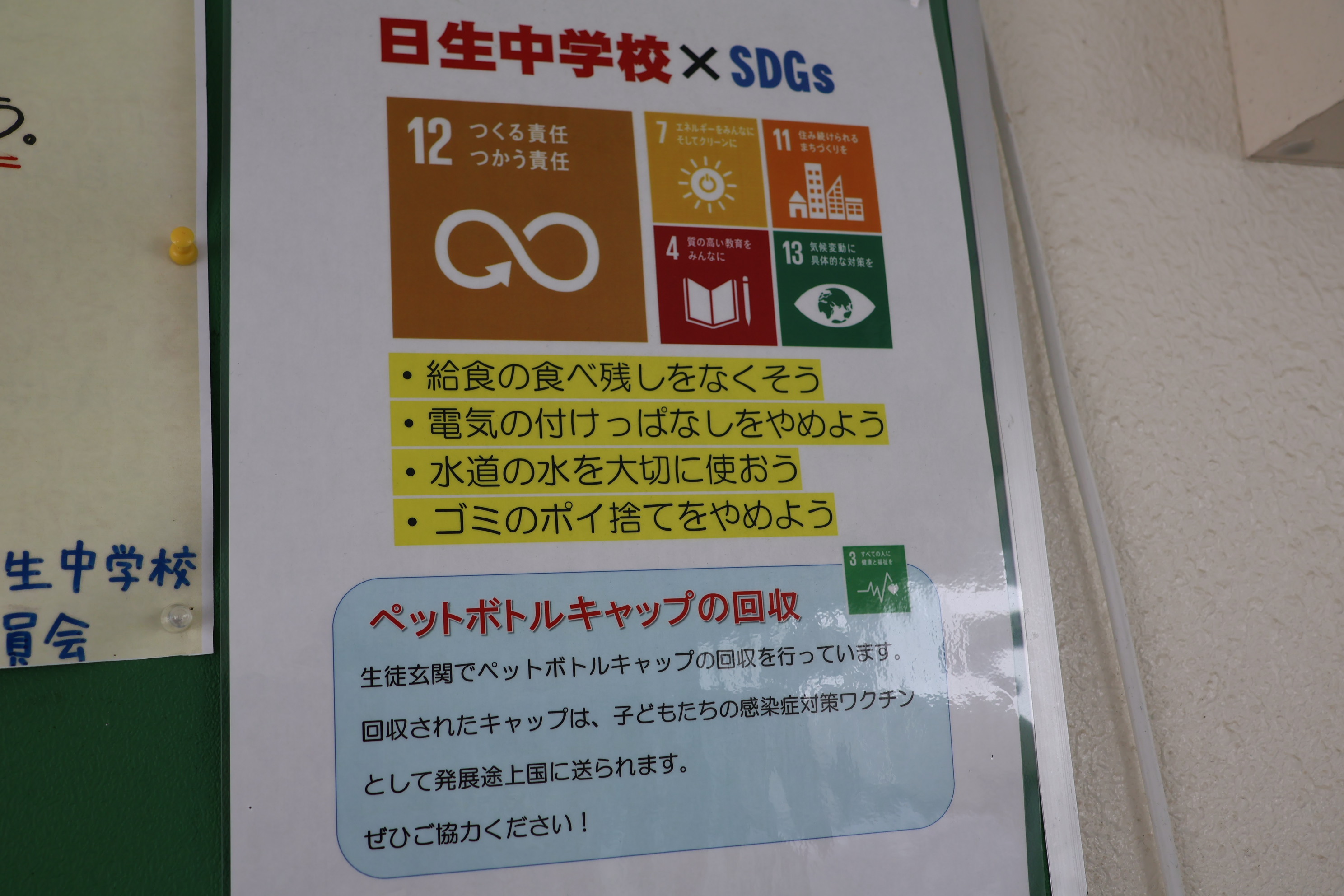
◎ひな中の風~ みんなの協力のおかげで(3/26)
今年度も、たくさんの使用済みカイロを回収することができました。本日、GO GREEN JAPANさんへ郵送しました。ご協力をありがとうございました。体育委員会


◎多くの人に支えられて(3/26)
週末から引き続いて、校門の修理をしていただきました。ありがとうございます。

◎サヨウナラの向こう側(3/26:退任式)




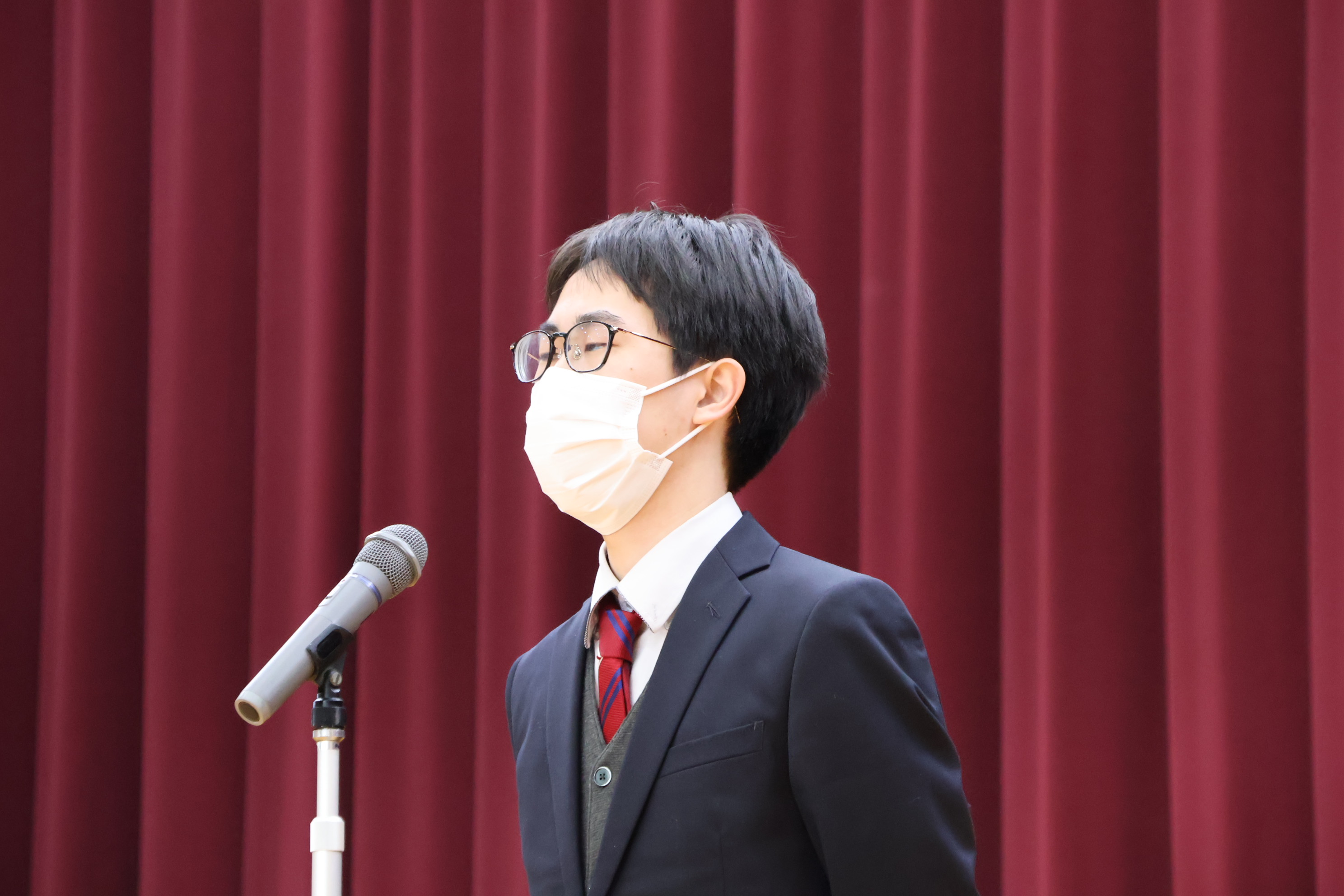




Thank you for your kindness
Thank you for your tenderness
Thank you for your smile
Thank you for your love
Thank you for your everything
〈「愛の」字の中にたくさん 、(たね)がある 書き続ければいつか芽が出る〉
千葉 聡
(3/26:修了式・表彰式)


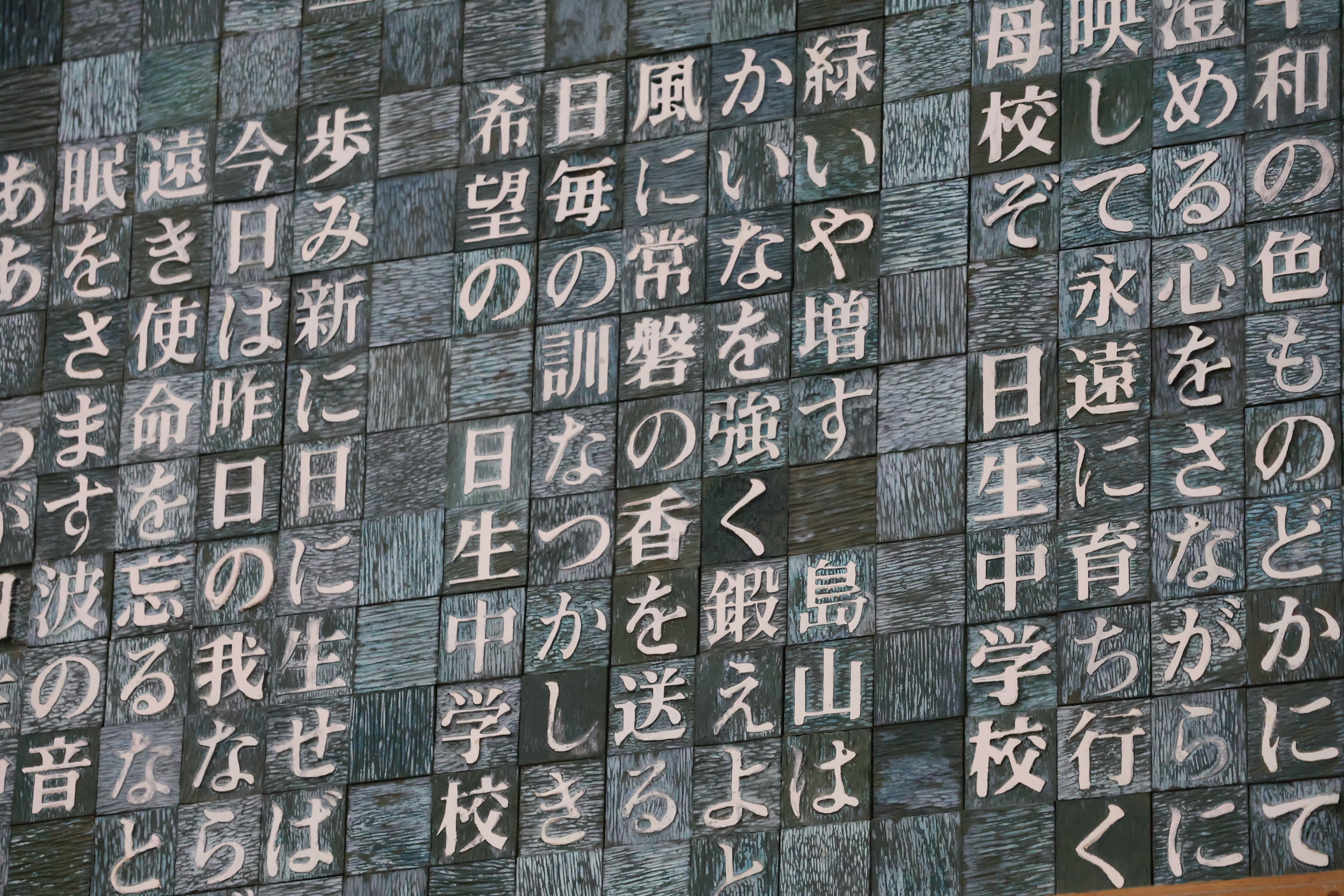






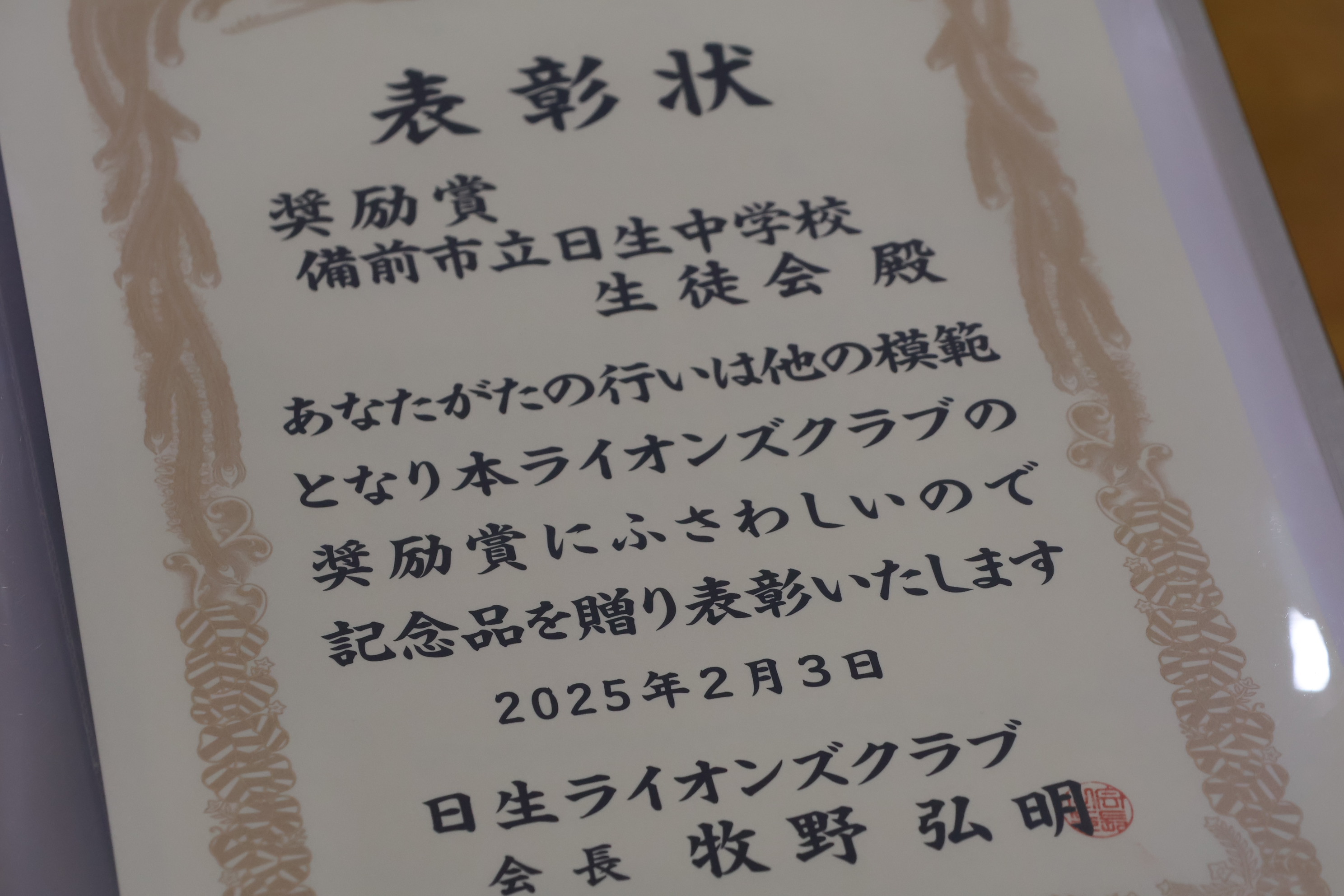

なりたい人は自分の中にいる。
◎次のステージが待ってる(3/25:学年末清掃)



◎明日は修了式(3/25)
過ぎ行く時を捉(とら)えよ。
時々刻々を善用せよ。
人生は短き春にして人は花なり。




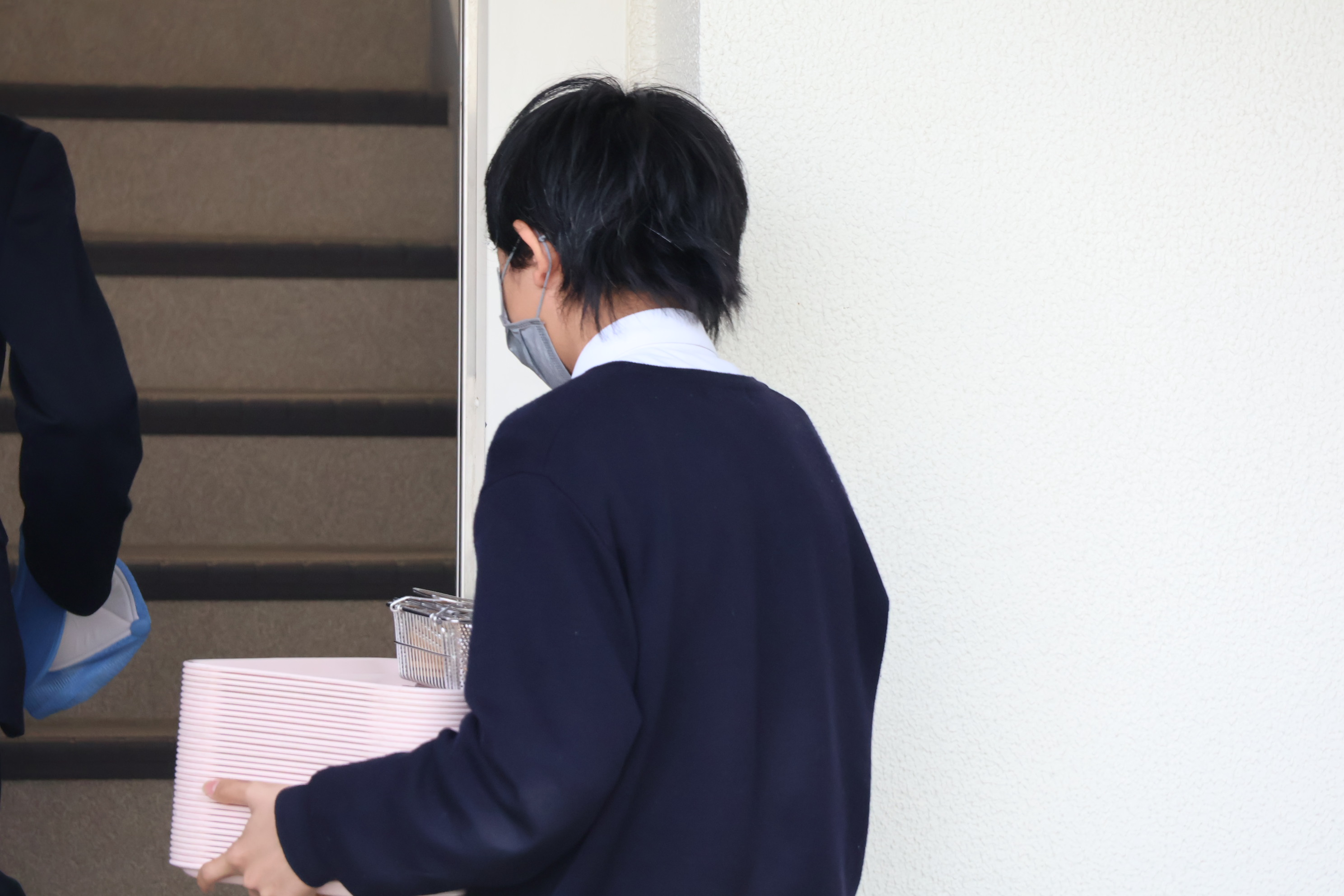




◎正しく知り 正しく行動する 金泰九 kim teagoo
日生中学校生徒の学んだことが、岡山県「教員向けハンセン病啓発動画 ~若者に伝えたい 人権感覚を養うために~」に紹介されました。(3/24公開)
教員や教員を目指す学生が、ハンセン病問題を学び、授業を実施する際の参考となる啓発動画を作成しました。動画は、学生が療養所での宿泊研修を行う様子や、学んだことをもとに地域の人と授業の組み立てを考えるワークショップ等を撮影したものです。岡山県疾病感染症対策課
https://www.pref.okayama.jp/page/965554.html (3)中学校での授業実施例をご覧ください。
◎今日も「おはよう」(3/24:あいさつ運動)
わたしの中にも 新川和江
つくし つばな
つんつん伸びる
丘のポプラには較ぶべくもないけれど
天に向かって
まっすぐ 背伸びして
わたしの中にも そのように
せいいっぱい伸びようとするものがある
どんなに低くとも そこはもう天
光がみち 天上の風が吹いている
もんしろ蝶 もんき蝶
ひらひら舞い立つ
羽化したばかりの
まだ濡れているういういしい羽をひろげて
はじめての空に
わたしの中にも そのように
ことばのひらく気配がある
たくさんの人に
春のよろこびを伝えることば
ひとりのひとに
思いを告げるただひとつのことば

◎日生から学ぶ進路・生き方学習(3/21:1年生進路学習)
「日本のくらしを支える海運」をテーマに 、中国運輸局、備前日生信用金庫、広島銀行、日生地区海運組合、椙原さんをエリアティチャーにお迎えして、進路学習に取り組みました。




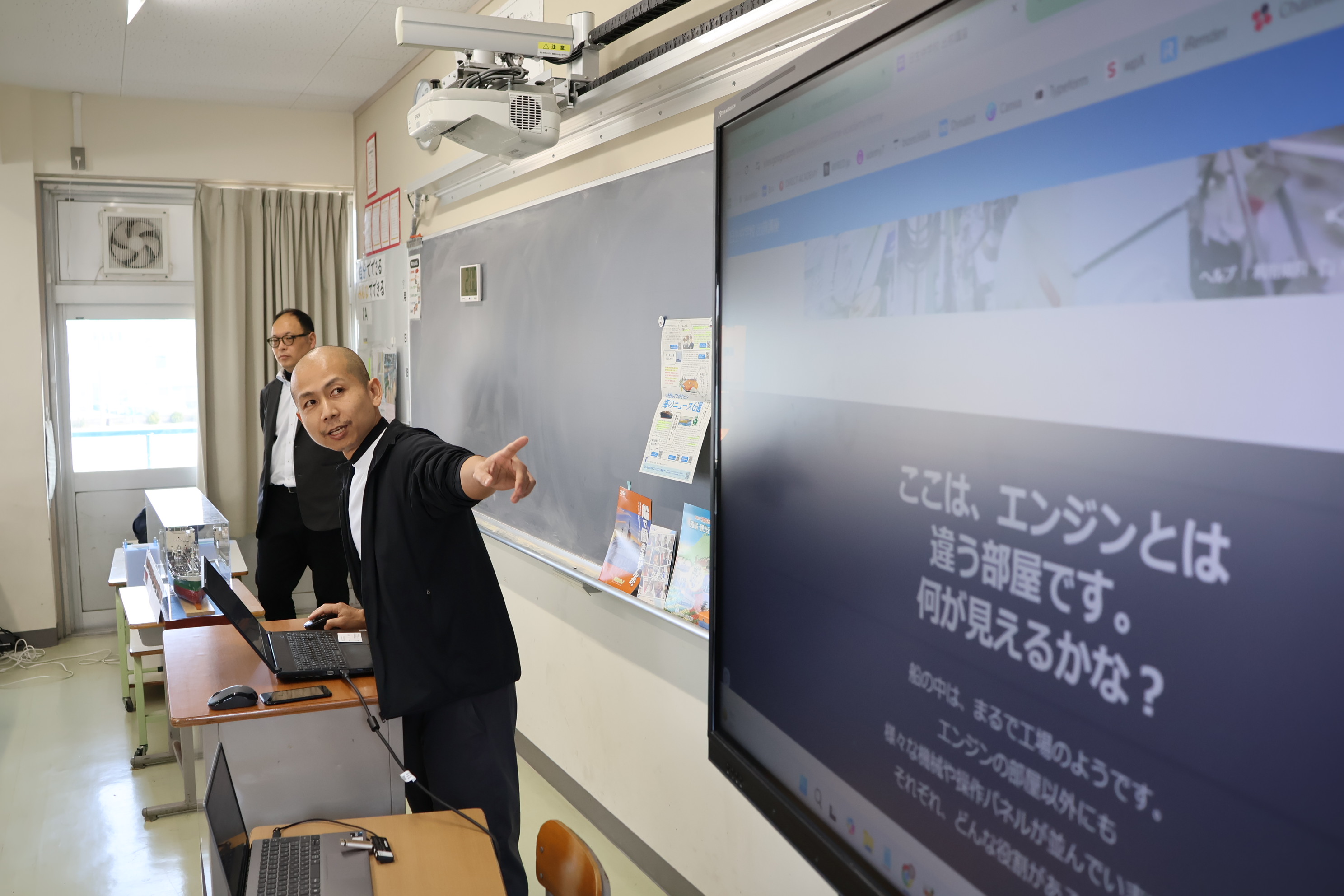


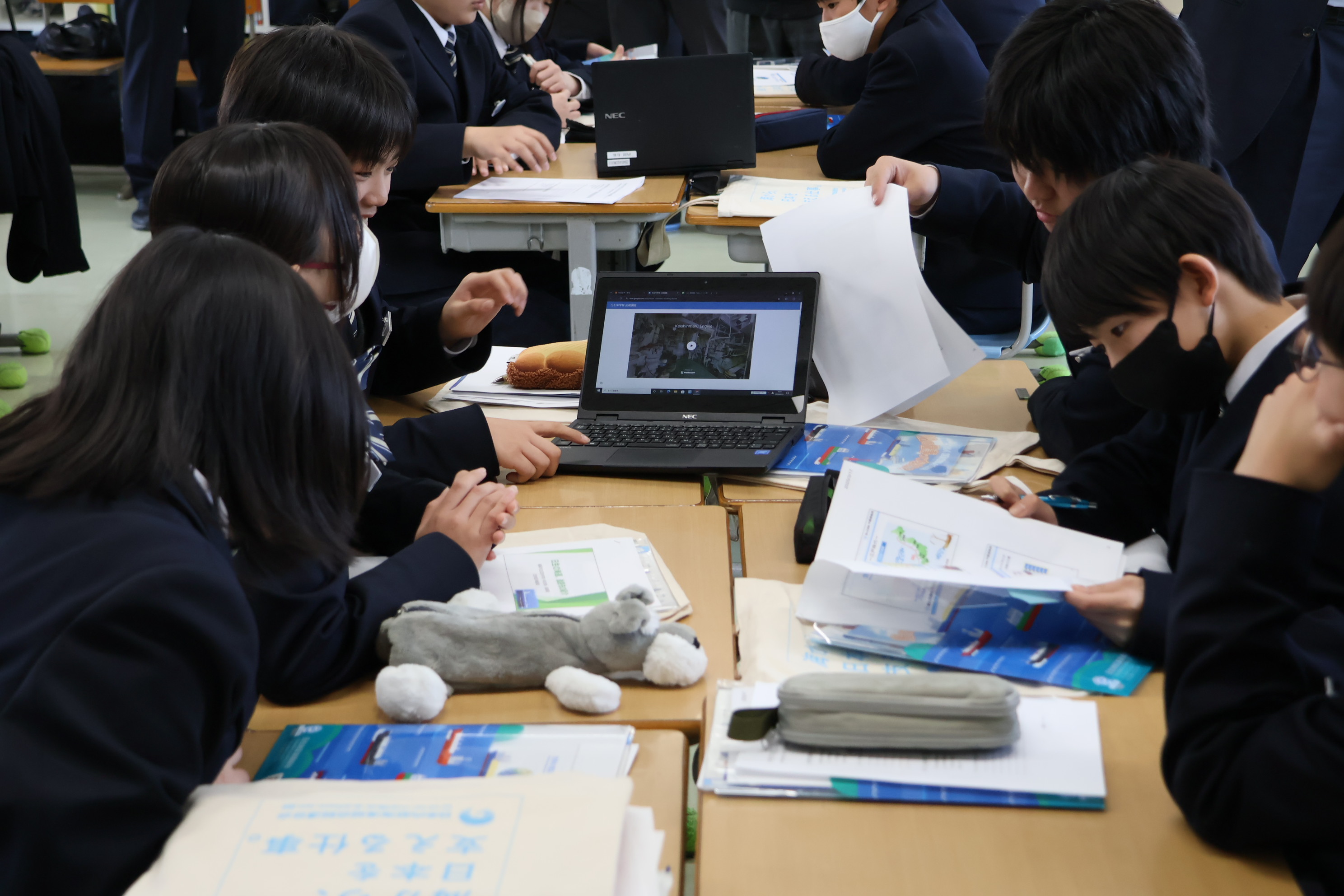

◎春へ(3/21:備前市立片上高校願書出願~)
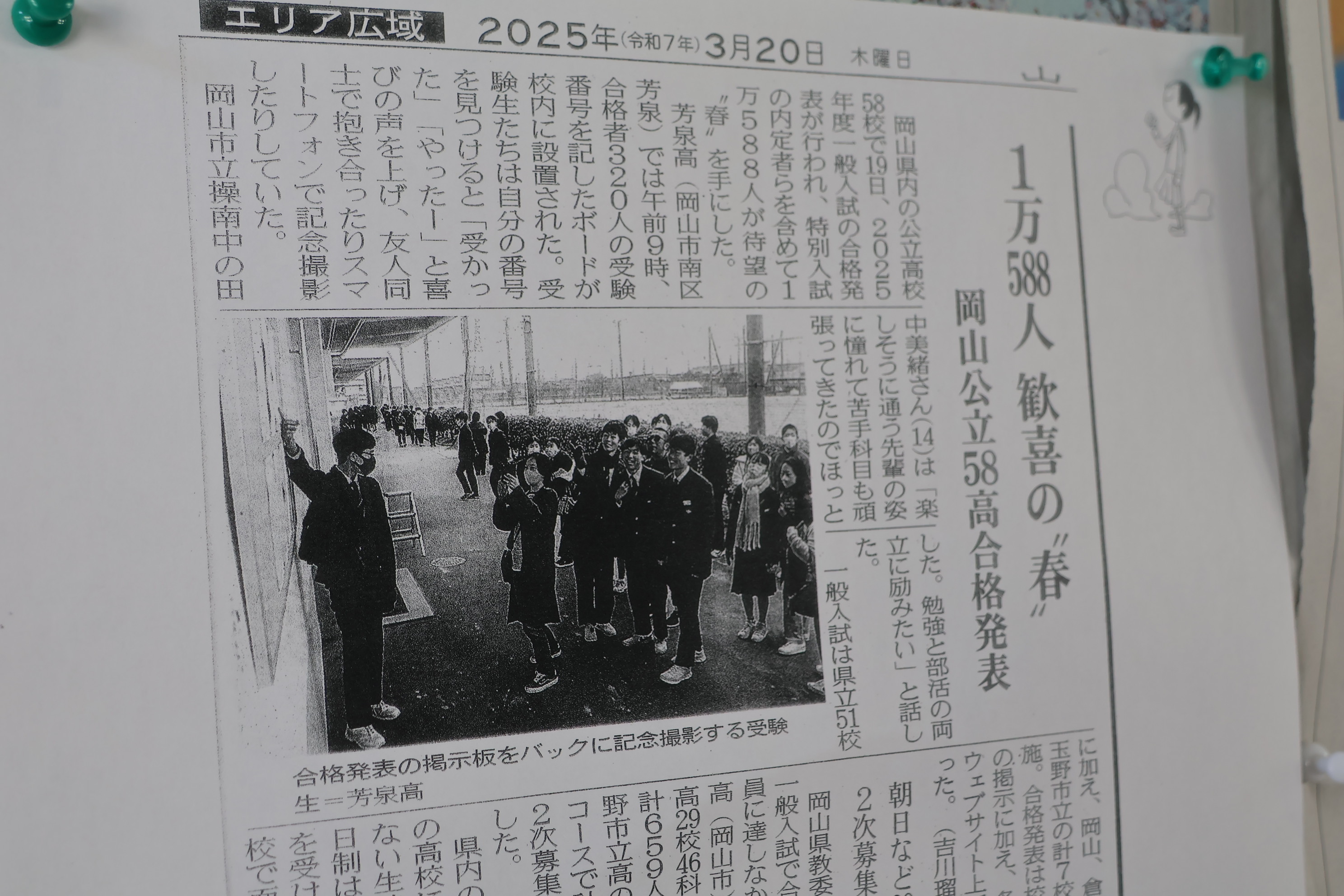


〈やわらかき春の土の上に立つてゐた父かな鍬には体(たい)をあづけて 時田則雄〉(3/20:春分の日)


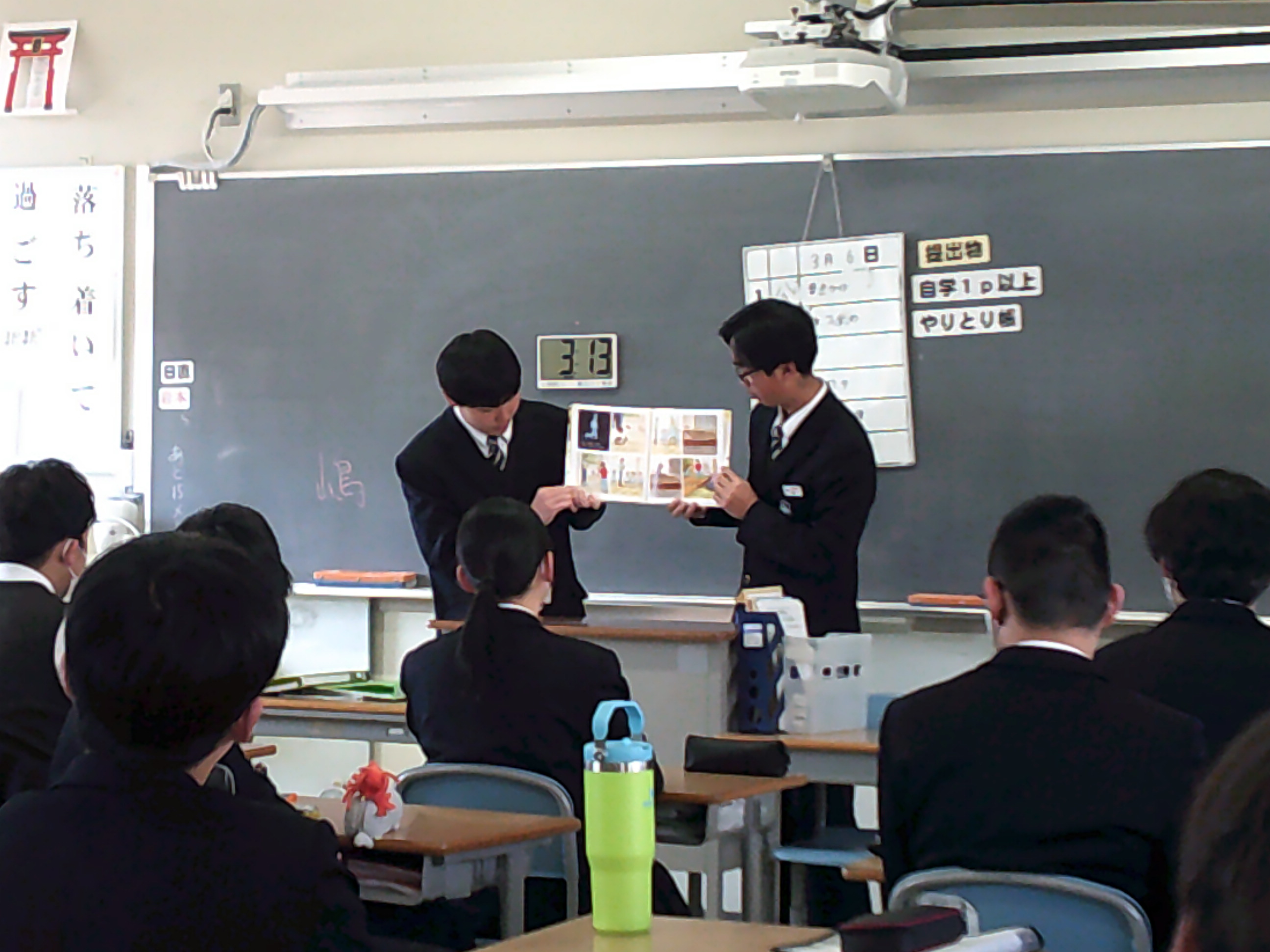
春分の日とは、内閣府「国民の祝日について」の資料によると、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日として説明しており、簡単にいうと生き物や自然の大切さを知る日ということになります。
春は、冬眠していた動物や植物が目を覚ましたり、新たな生命の誕生を感じられる季節です。そのため春分の日は、生き物や自然の大切さを知りながら、春の訪れを楽しむことができる日といえるでしょう。
春分の日の前後3日はお彼岸ともいわれていて、春分の日はお彼岸の中日(ちゅうにち)として、お墓参りをする日でもあります。そもそもお彼岸とは仏教からきている言葉で、仏様の世界を彼岸、三途の川を挟んで、今自分たちが生きている世界を此岸(しがん)と呼ぶそうです。ある一説によると、極楽浄土が西の方角にあり、春分の日は太陽が真西に沈むため、極楽浄土に一番近くなる日として太陽を拝むことは極楽浄土に向かって拝むことになる、といわれています。そこから、春分の日に太陽を礼拝し、ご先祖様を供養するようになったことが、お墓参りをする日として広まっていったようです。
春分の日と秋分の日の違い
春分の日と同様に国民の祝日とされているのが、秋分の日です。秋分の日は春分の日と同じく、地球と太陽の位置により、昼と夜の長さがほぼ同じ長さになる日として知られています。春分の日と秋分の日の違いは、春と秋という季節の違いはもちろんですが、祝日の意味に違いがあります。内閣府「国民の祝日について」の資料によると、秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」という意味を持つ日と説明しています。また、春分の日を過ぎると昼の時間が少しずつ長くなります。一方、秋分の日を過ぎると昼の時間が少しずつ短くなるため、昼の時間の長さにも違いがあります。春分の日は以前、春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)と呼ばれていました。春季皇霊祭とは、歴代の天皇など皇室に関わる先祖の霊を祀る儀式を行う日で、儀式自体は今でも皇居内で行わているそうです。
春分の日はお彼岸の中日(ちゅうにち)でもあるため、ぼたもちをお供えしたり、食べたりすることもあるでしょう。春分の日にぼたもちを食べる理由は、あんこの原料となる赤い小豆に「魔除け」の効果があるからだといわれています。もともと古くから、赤には魔除けの力があると考えられており、食べることによって邪気を払い、災難から身を守ることにつながったそうです。そのため、春分の日にぼたもちを食べるのですね。
◎多くの人に支えられて(3/19:新入生物品販売)
〈わたしたちどこでも行けると不意を聞く言葉じわじわ嬉しくなりぬ 富田睦子〉



◎二年生から三年生として(3/19:授業風景)

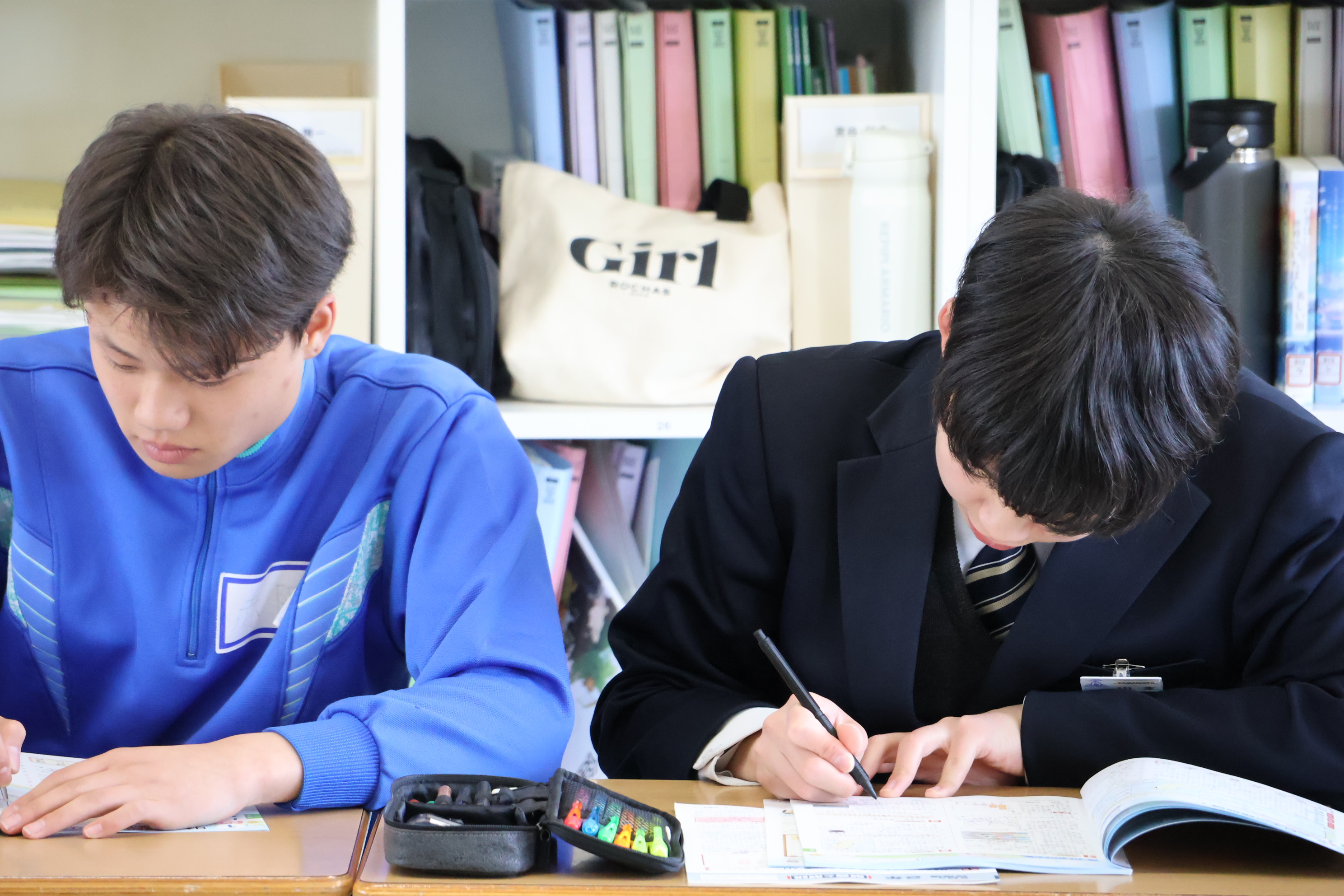







◎今 在りき
県立一般入学者選抜合否発表日(3/19)
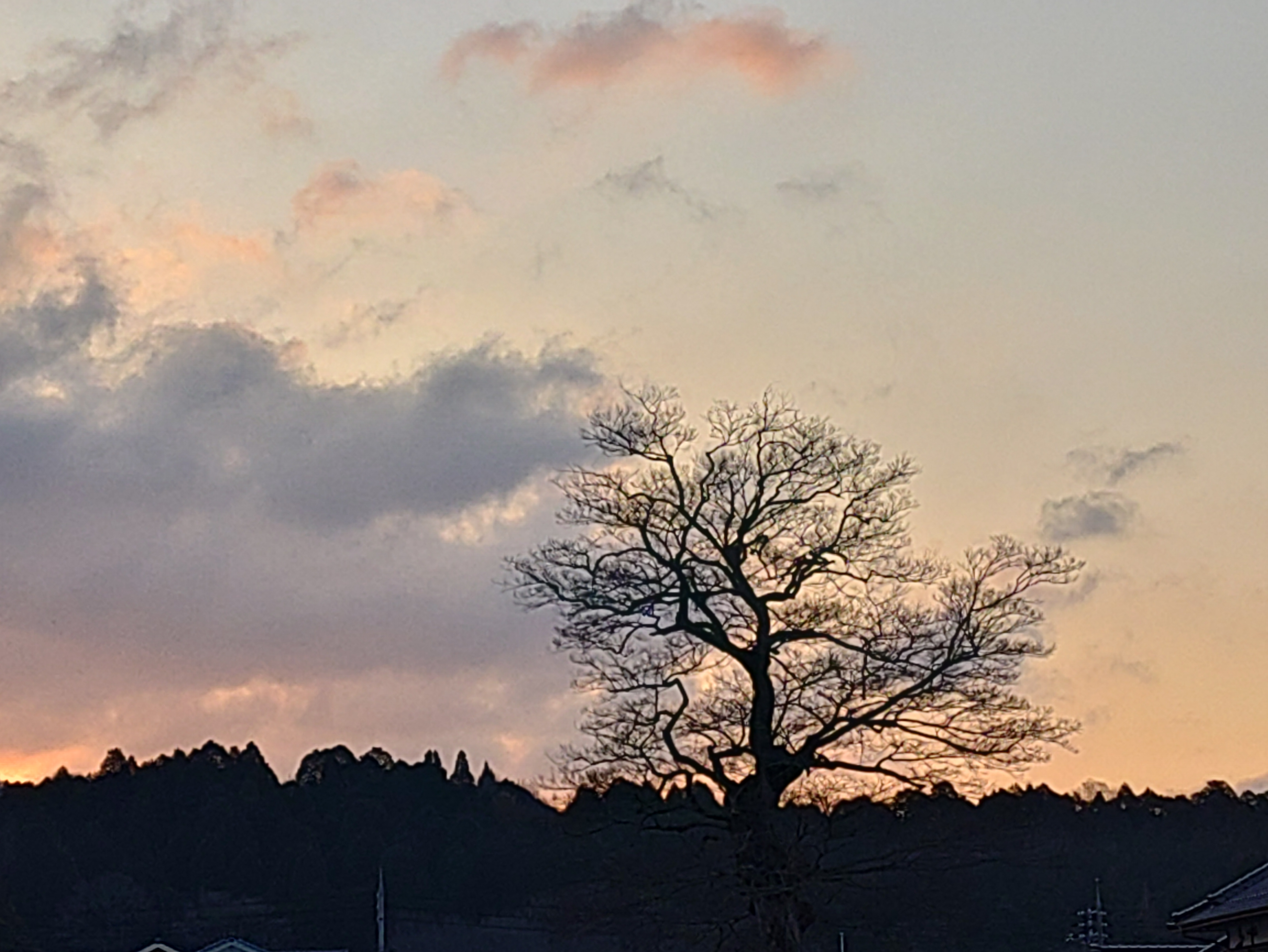
〈苺のへたに花びらひとつ残ってる だれもがここまでを生きてきた 初谷むい〉
◎新しく 清掃場所を引き継ぐ(3/18)



もくもくと、仲間たちと。
◎多くの人に支えられて(3/17)

防火シャッターの不具合を点検・修理していただいています。早速の対応をありがとうございます。
◎多くの人に支えられて(3/17)

日生ライオンズクラブ会長が来校され、今年も新入生へ交通安全のための夜行タスキをいただきました。ありがとうございます。
◎小学校との、豊かで・確かな連携を進めています(3/17)
新入生となる6年生の授業見学に行ってきました。西小は卒業式の練習、東小は国語、算数の授業をみさせていただきました。両校の6年生どちらも、集中して一生懸命に学習に取り組む姿は、さすが最上級生ですね。

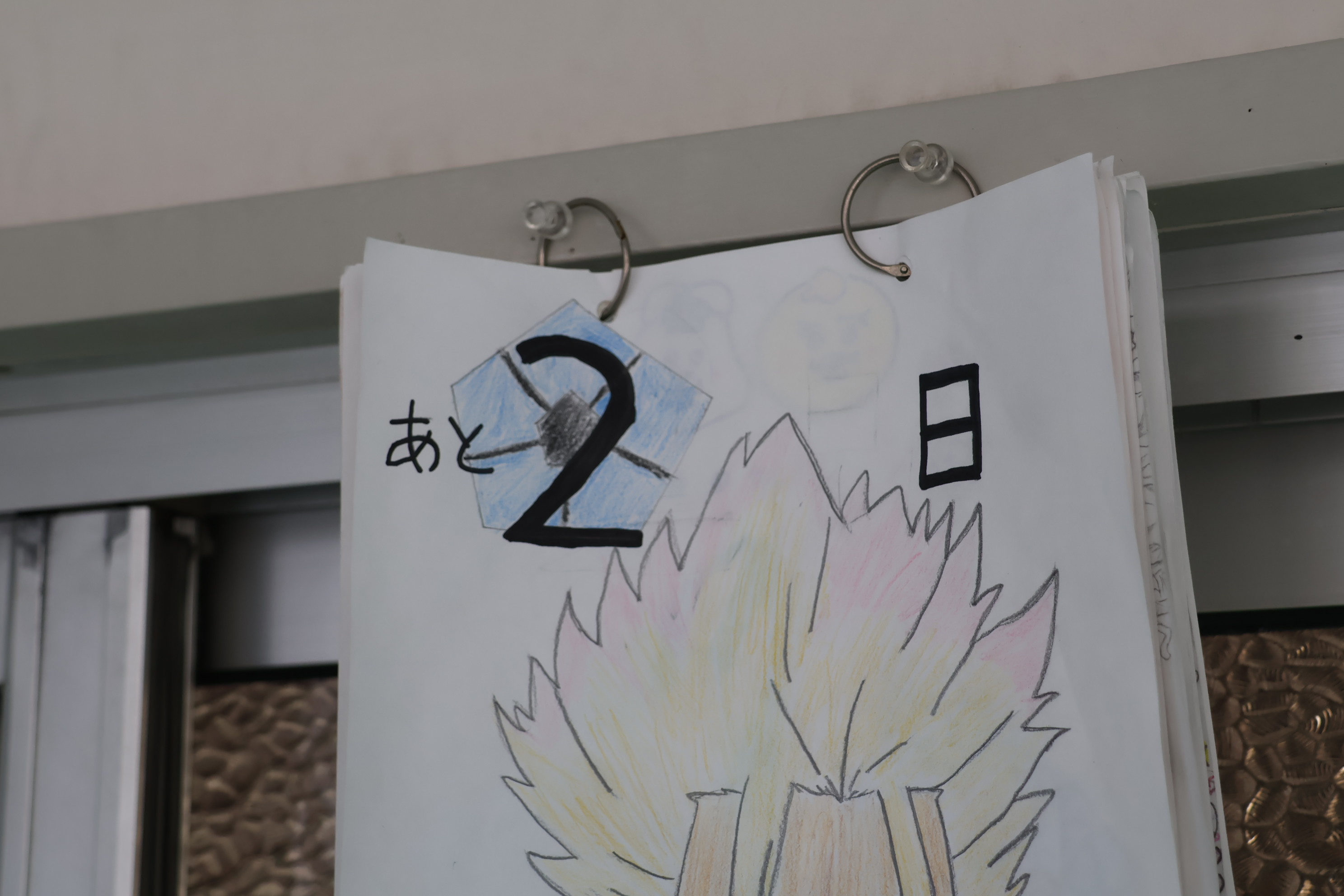


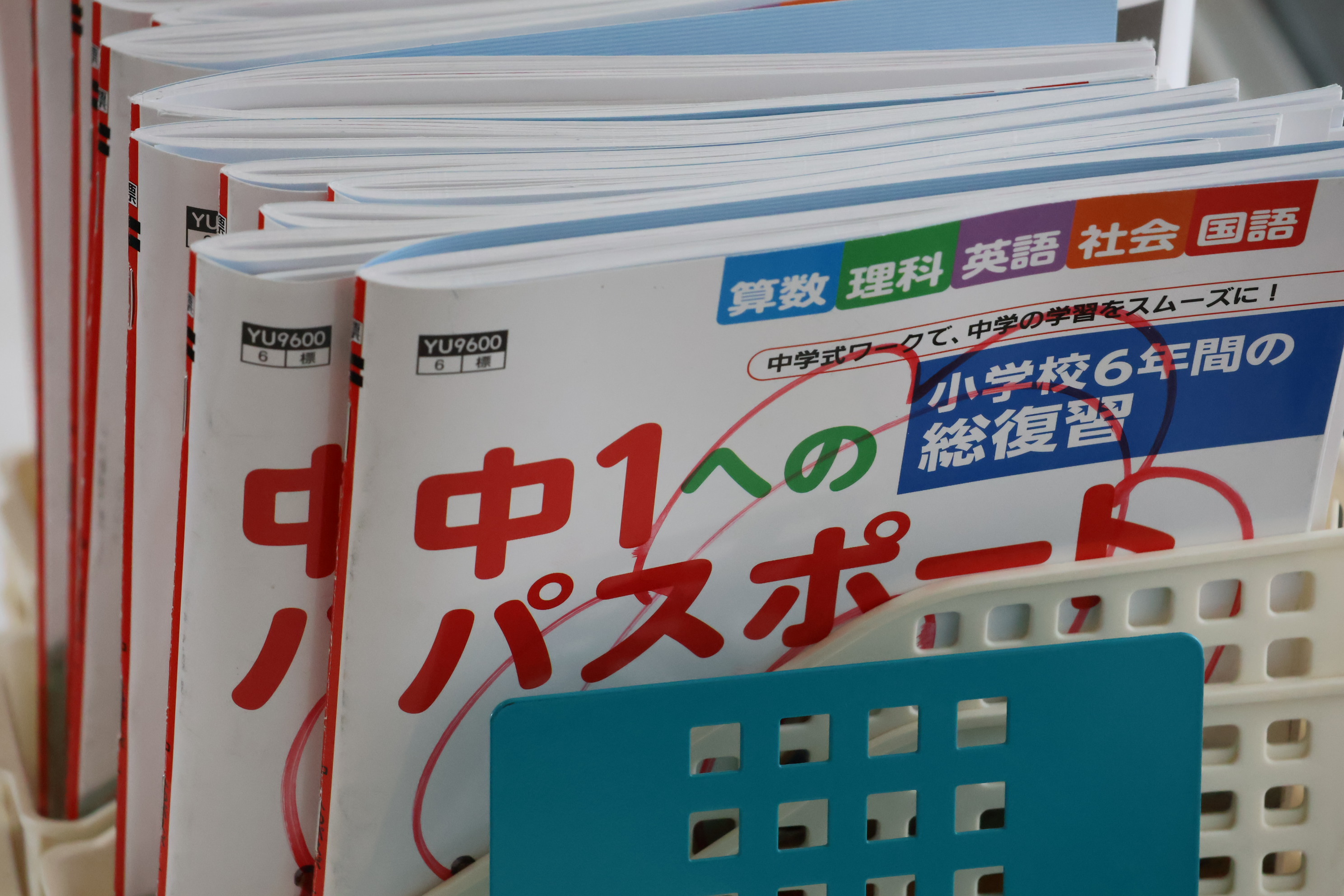
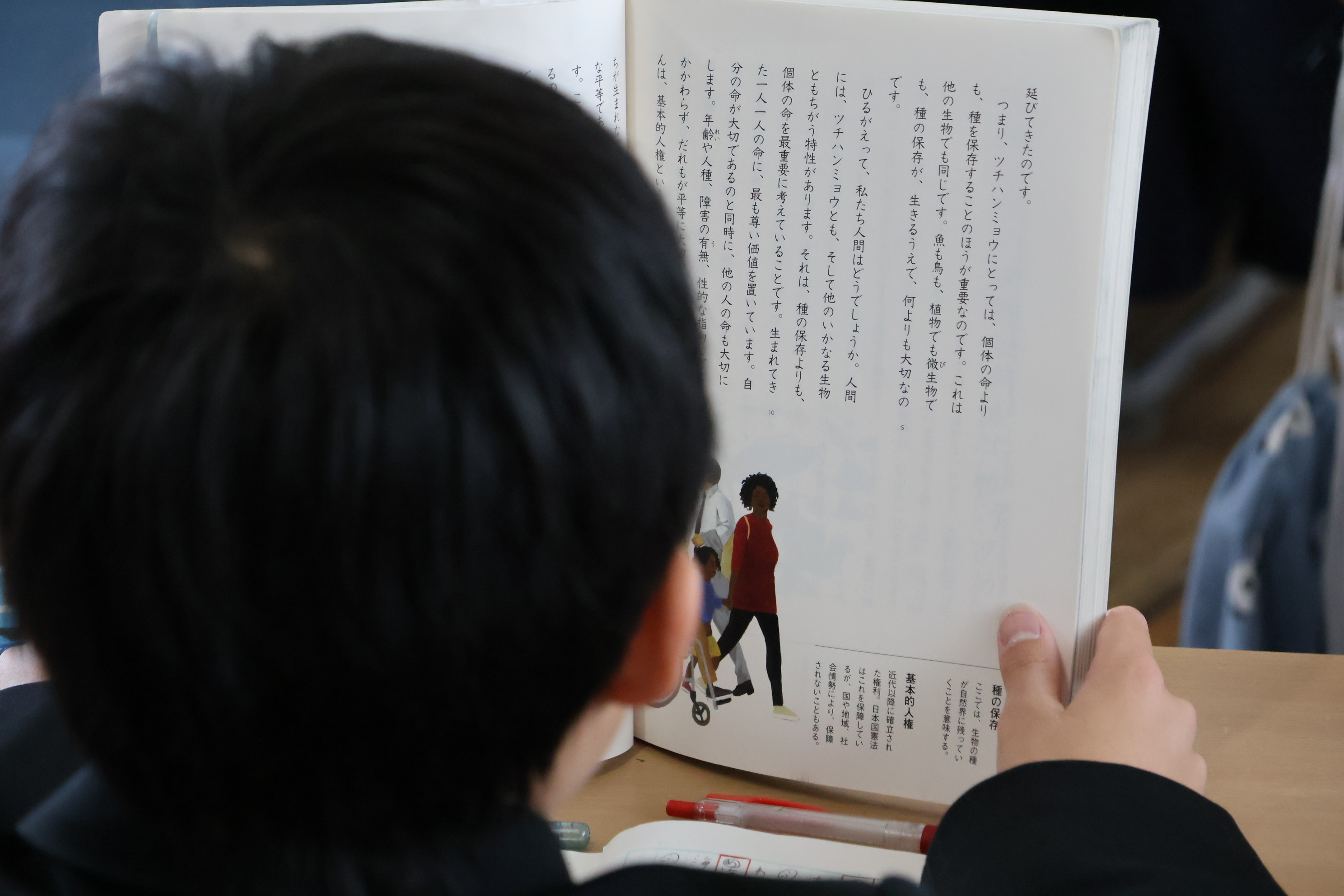
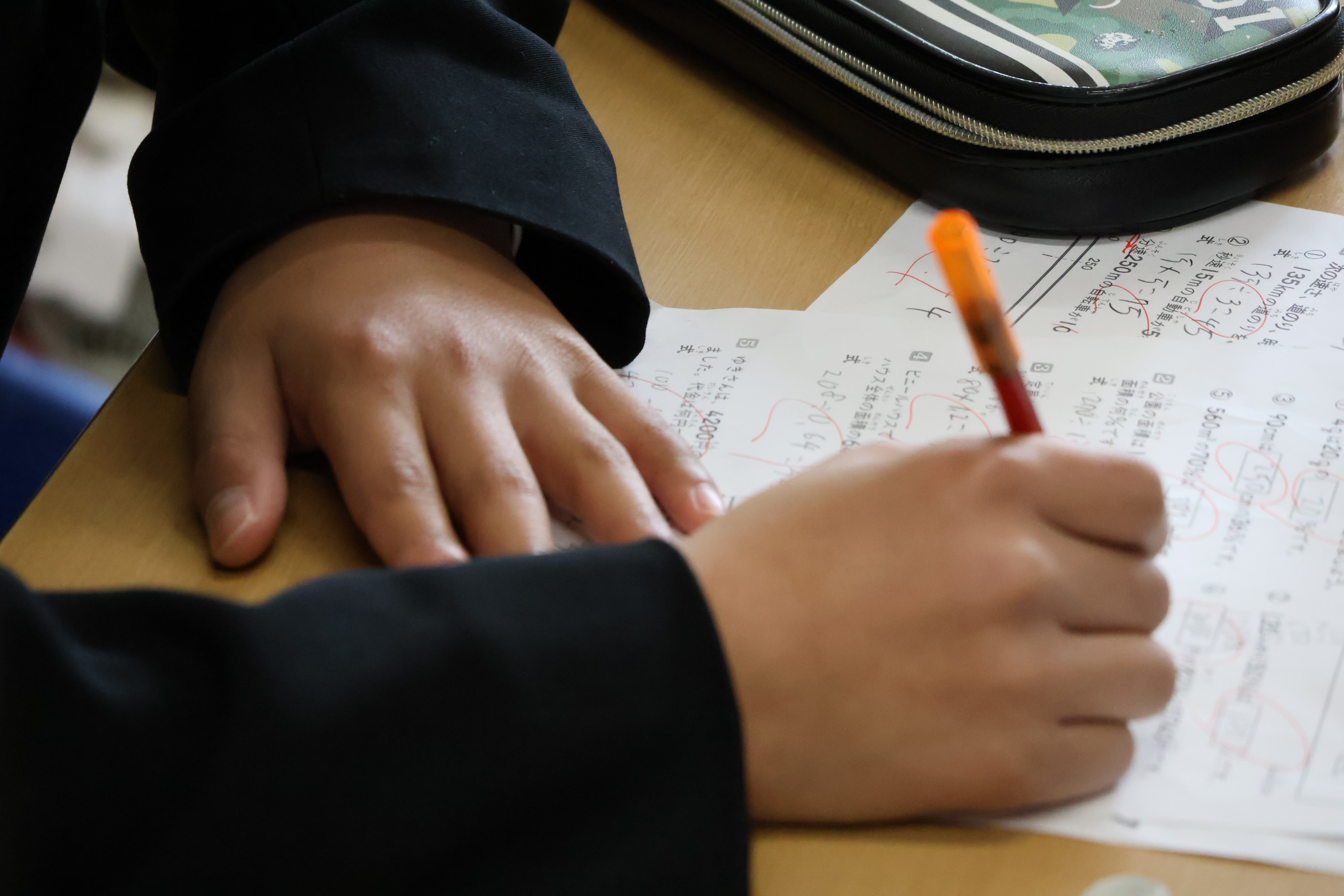
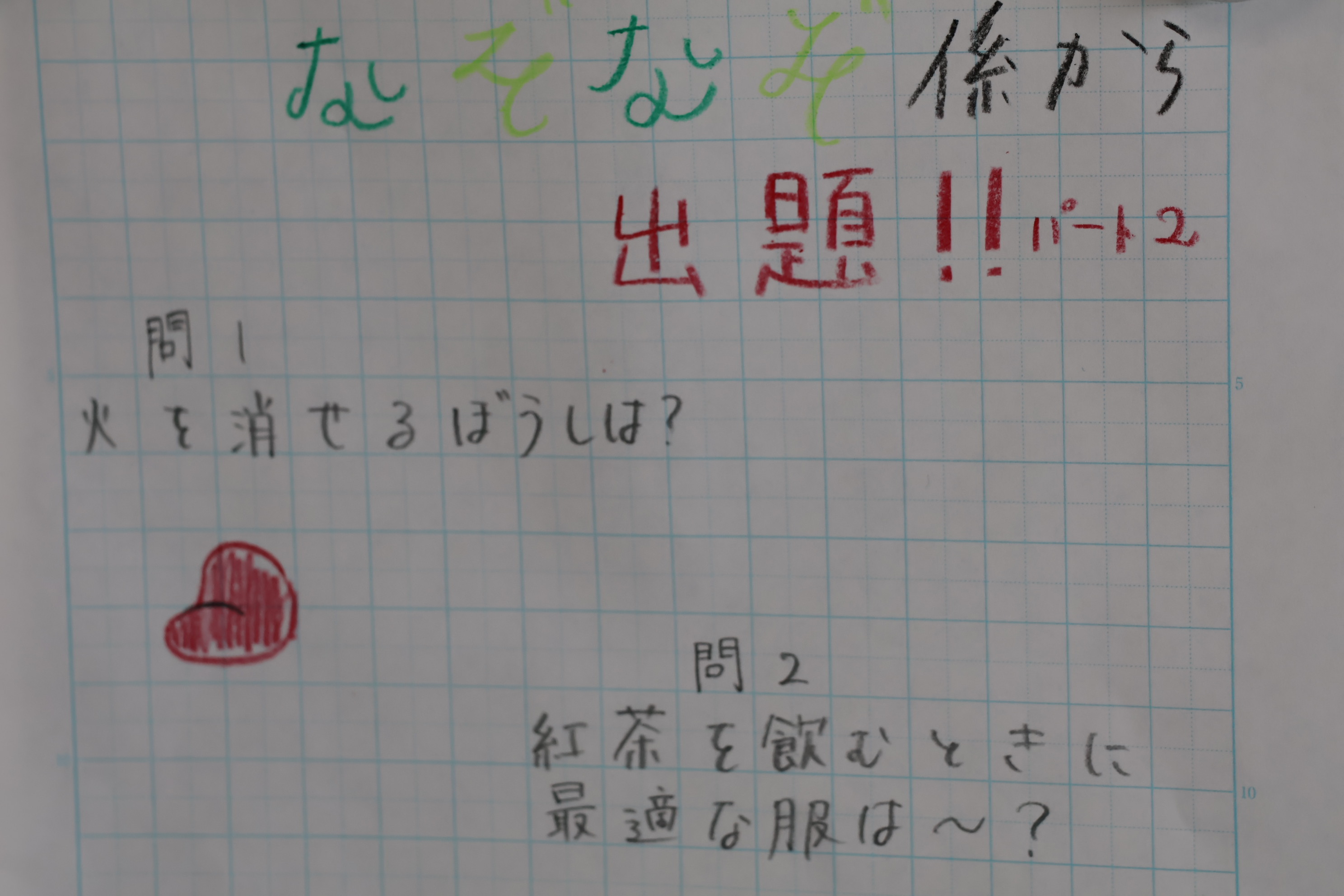

小学校の卒業証書授与式は、3/19です。午後からは、本校で新入生物品販売をおこないます。
◎ありがとう
◎♬ことば、リズム、笑顔を。(9/19)
妹尾先生をお招きして、「島唄」の歌唱練習に取り組むことができました。

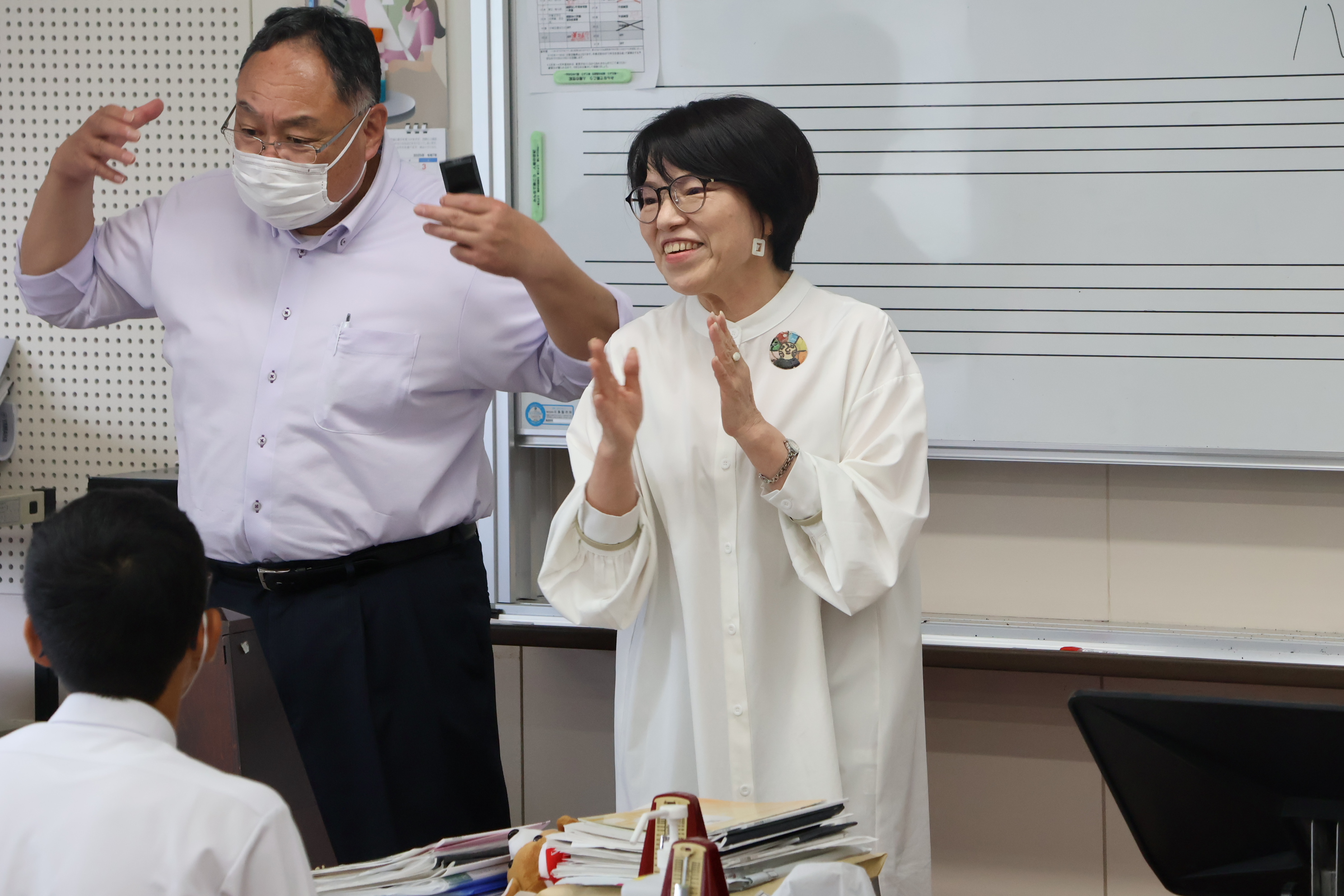

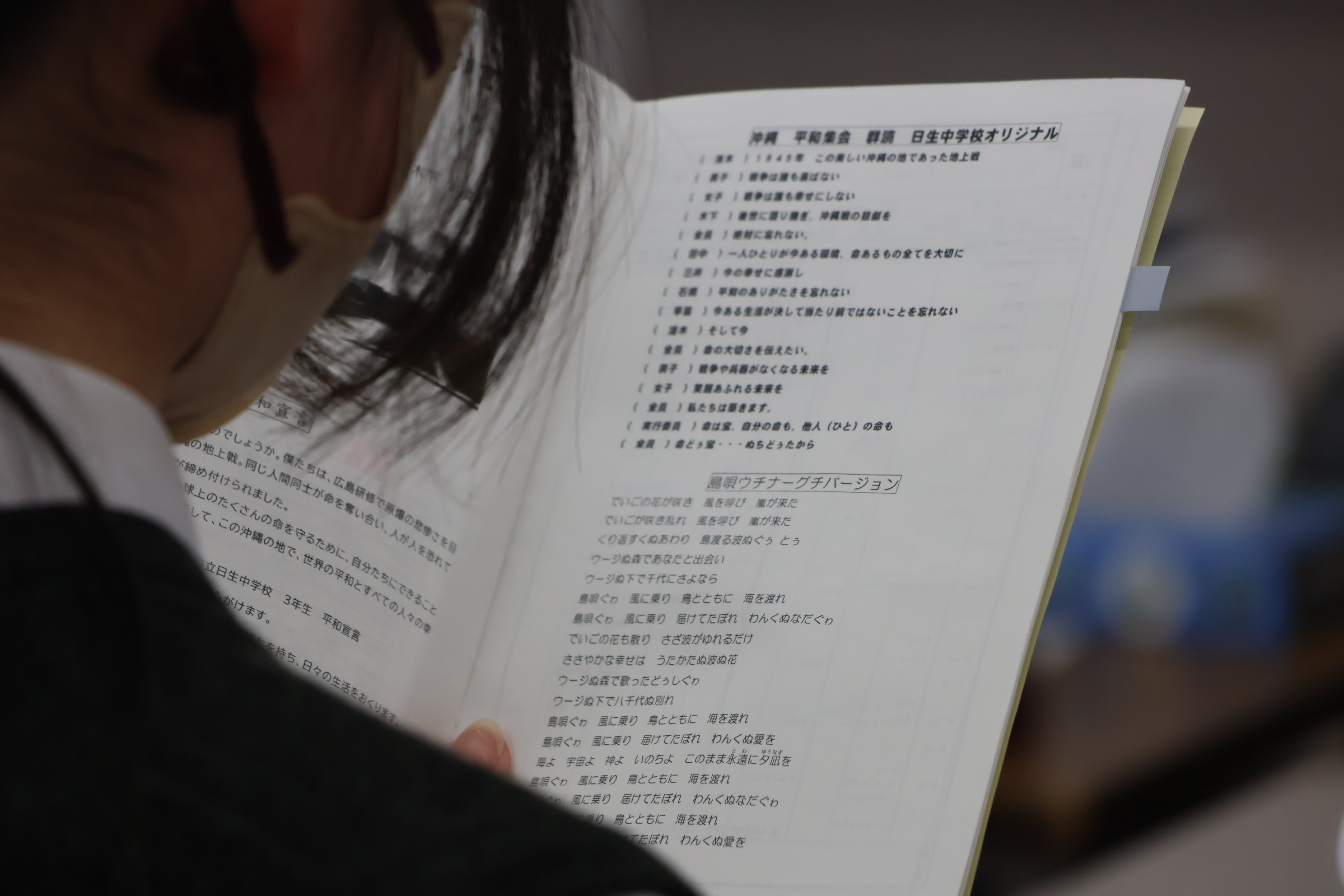

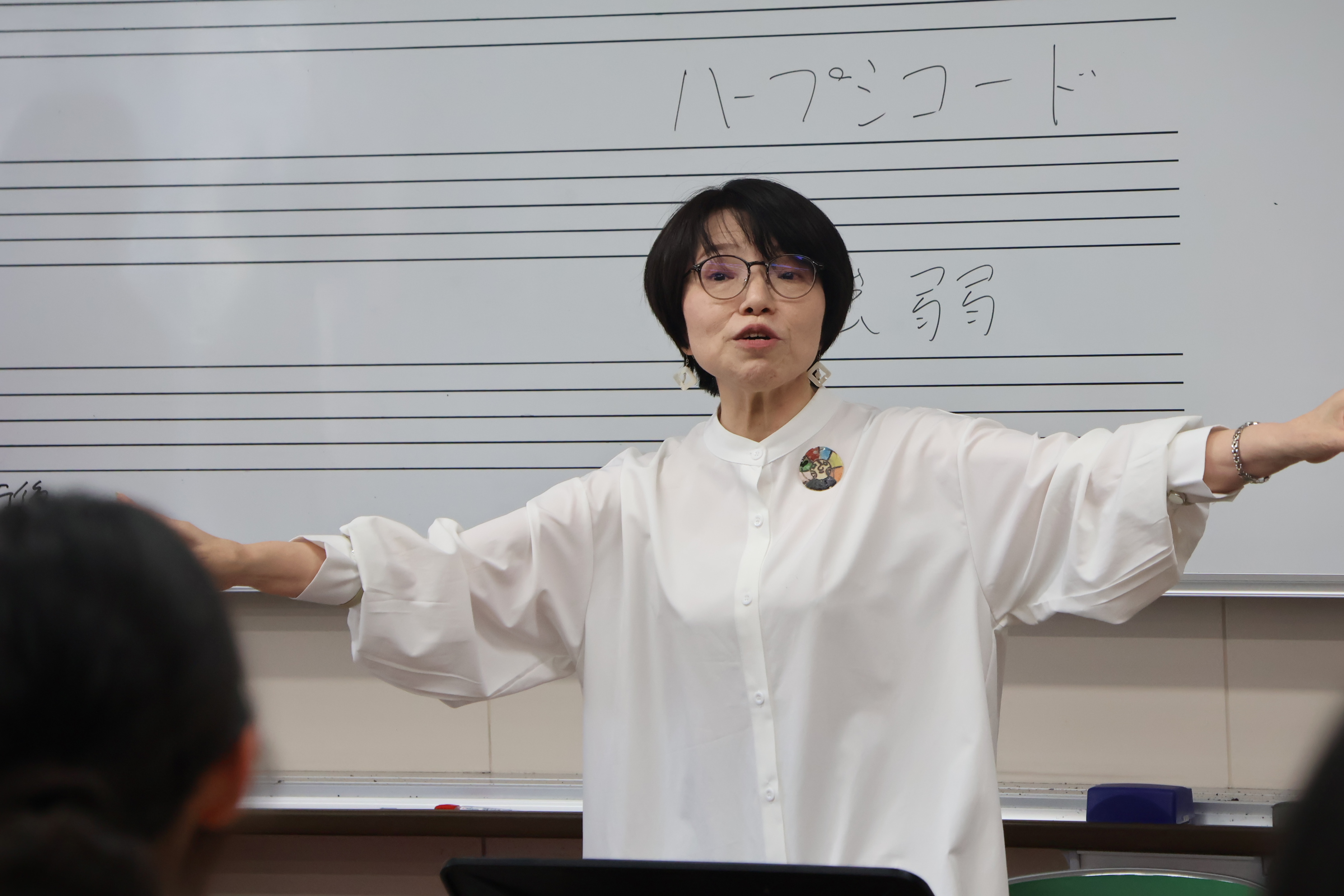
多文化共生社会は、今・ここから。(5/19)
make conversation



◎多くの人に支えられて(5/16)
AEDの点検とバッテリーの交換をして頂きました。ありがとうございます。

◎多くの人に支えられて(5/16)
新しく来られた先生方の取材にひなビジョンさんが来校されました。


◎十五の春へ 確かな〈こ小中連携〉を。
昨日、第1回日生中学校区連携推進委員会を開催しました。この日生中学校連携協議会の目的は、15年間を見通した系統的。継続的な指導により、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を図ることとして、3つの部会(学力向上 生活指導、特別支援教育)を中心に、こども園、小学校、中学校の全教職員で取り組んでいます。



◎日生から学ぶ未来。(5/15)
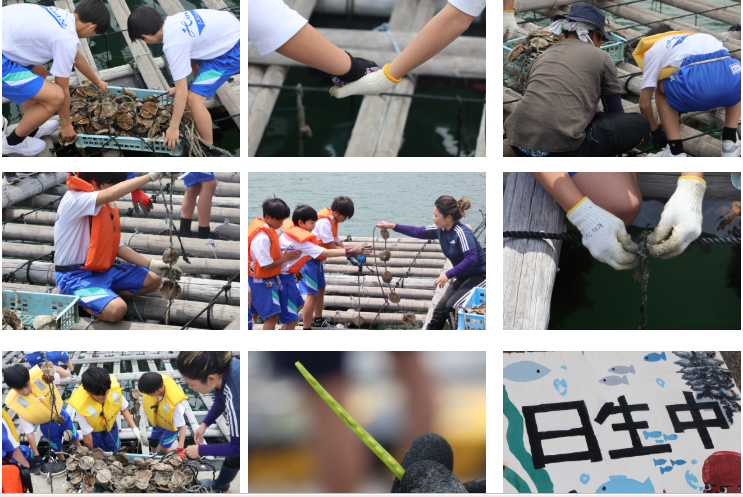
第1学年 海洋学習 「カキの養殖体験活動(カキの種付け)」
1 目的
(1) 「総合的な学習の時間」の海洋学習の一環として、カキ養殖の体験活動を通して、日生町の基幹産業である漁業の現状や特色について理解を深める。
(2) 実際の作業に取り組むことで、働くことの意義や大変さを実感し、勤労の尊さを学ぶ。
(3) 地域の方々のご指導を受けながら活動することで、地域に対する親しみや感謝の気持ちを育てるとともに、地域社会との交流を深める。
*NHK、KSB、ひなビジョンの放送ニュースもご覧ください。
◎よりよい生活をつくる (5/15)
全校アンケートをもとに「ひな中クールビズ」についてまとめ、今日は各クラスでの説明を行いました。タブレット端末を使い、詳細を確認することができました。
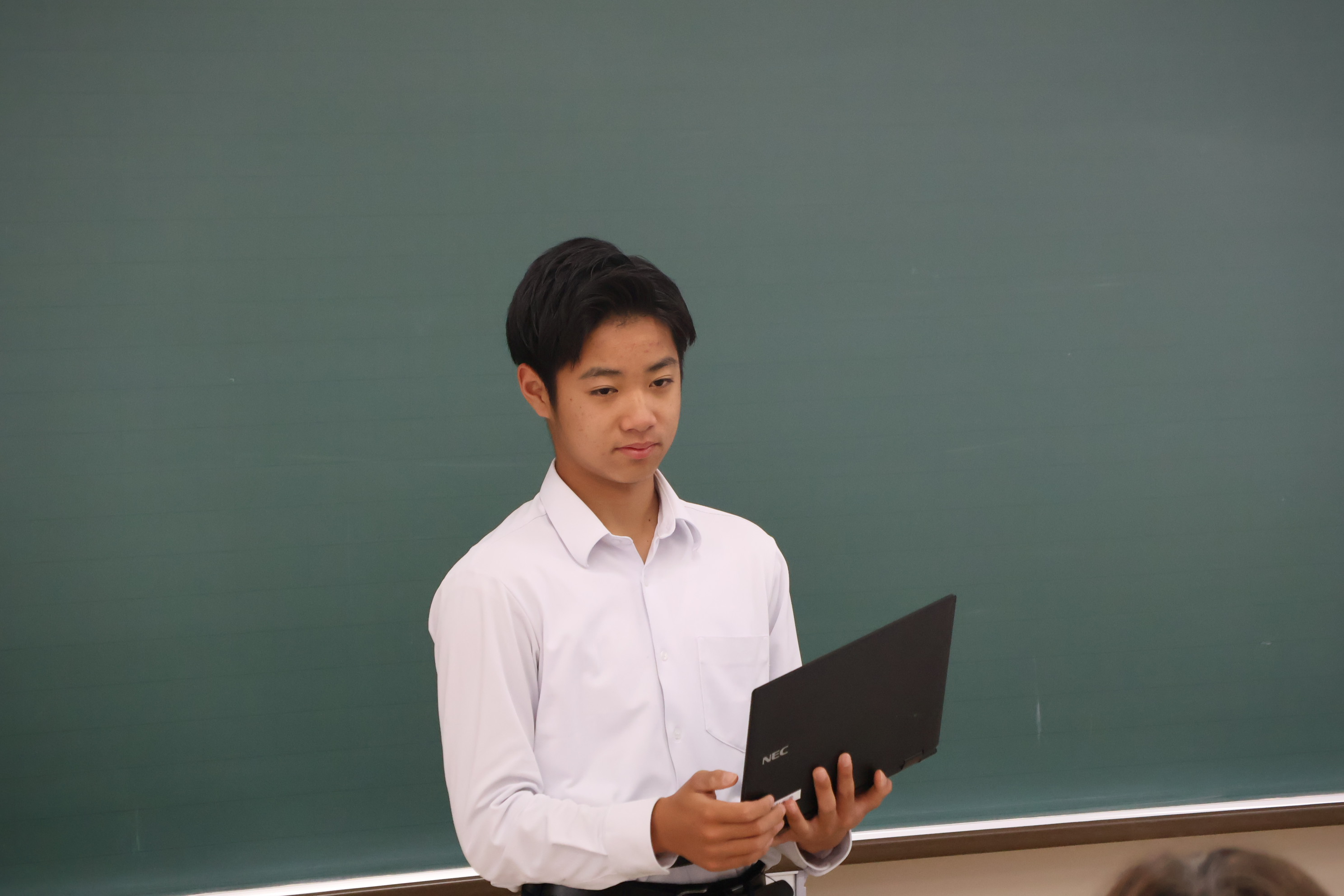
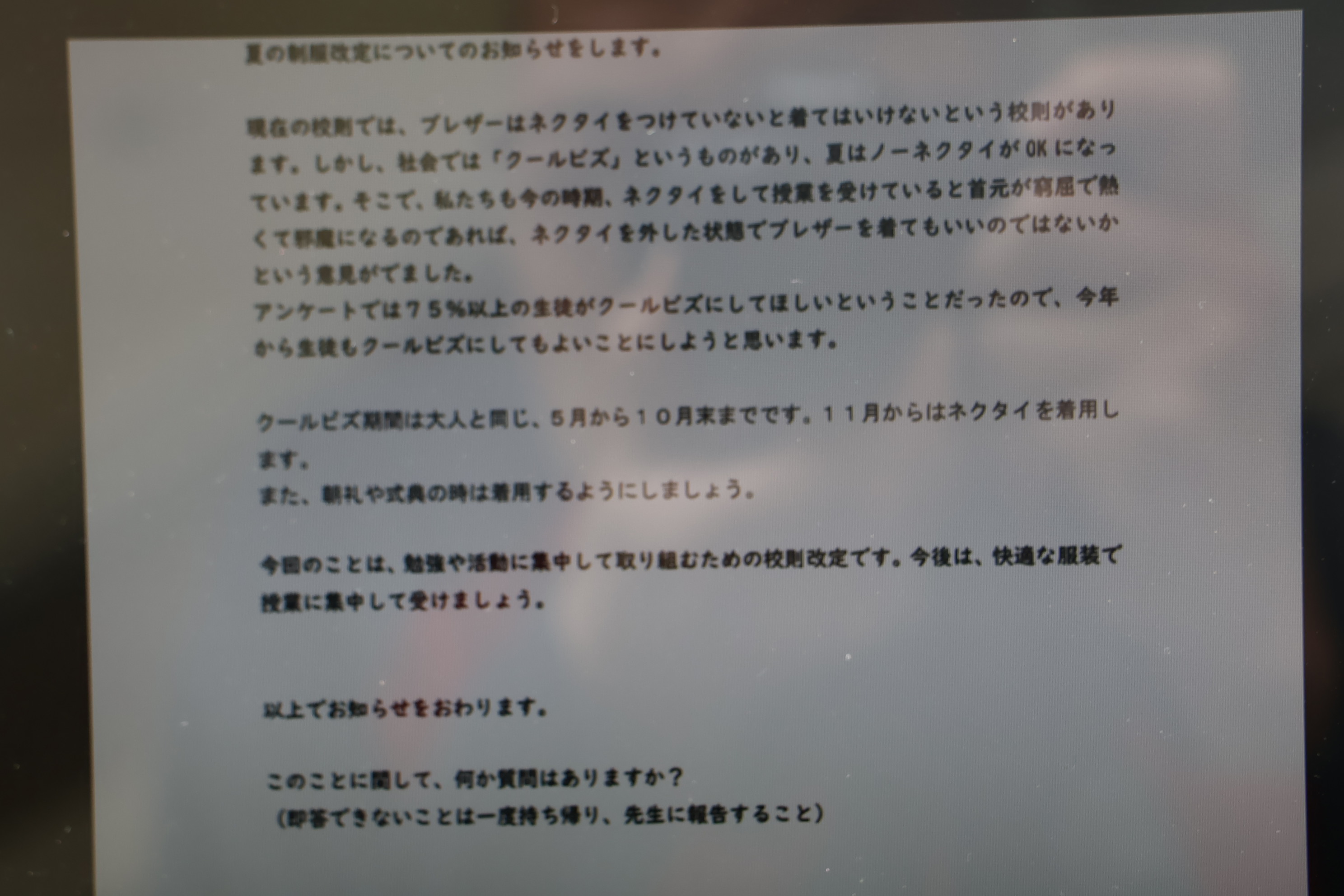

〈新緑やかぐろき幹につらぬかれ 日野草城 5/14〉



日生中学校グラウンドで、備前サンラッキーズが練習に励んでいます。
◎自分らしく せいいっぱい

◎責任・誇り・絆(5/14:体育の部 放課後・係会)
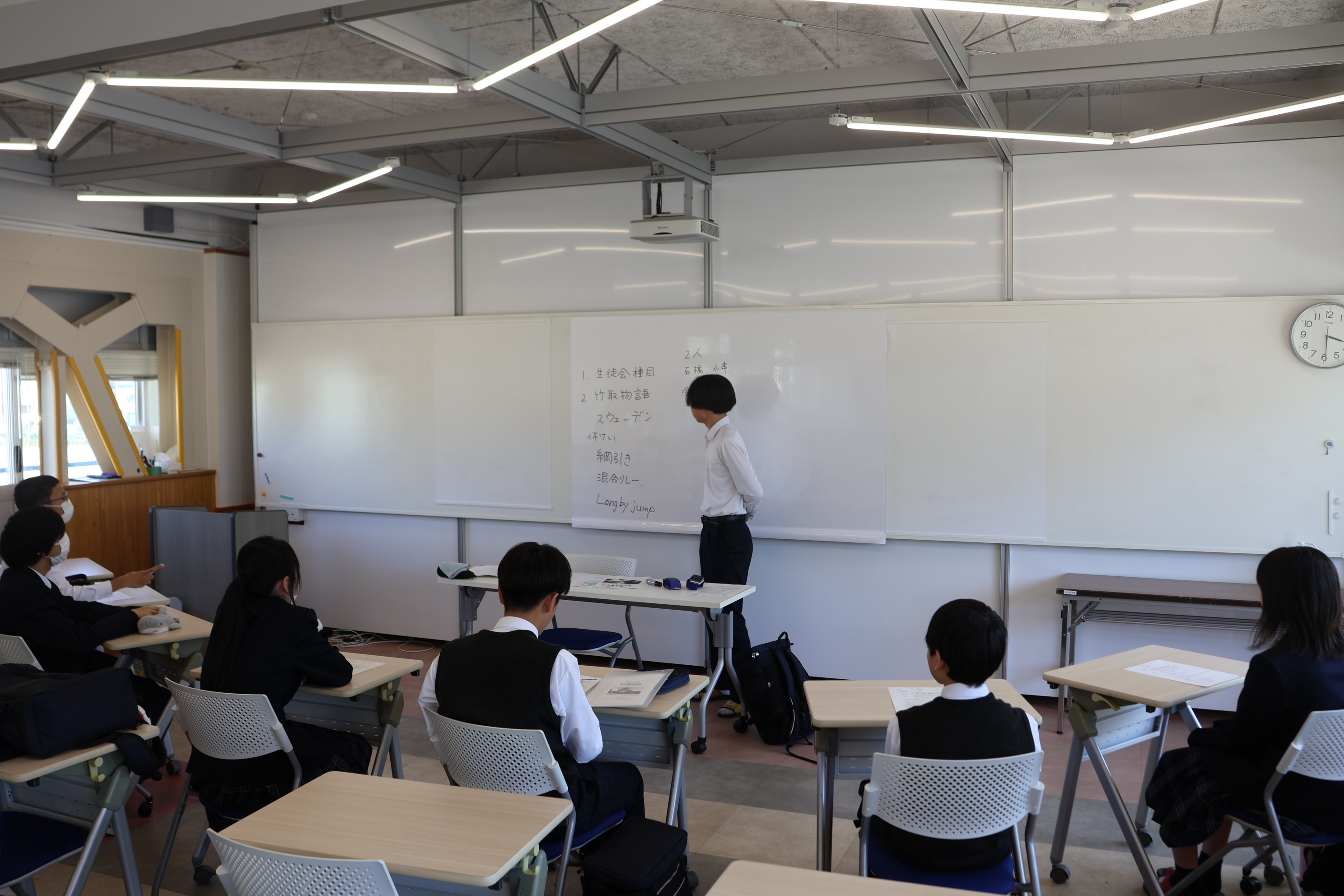
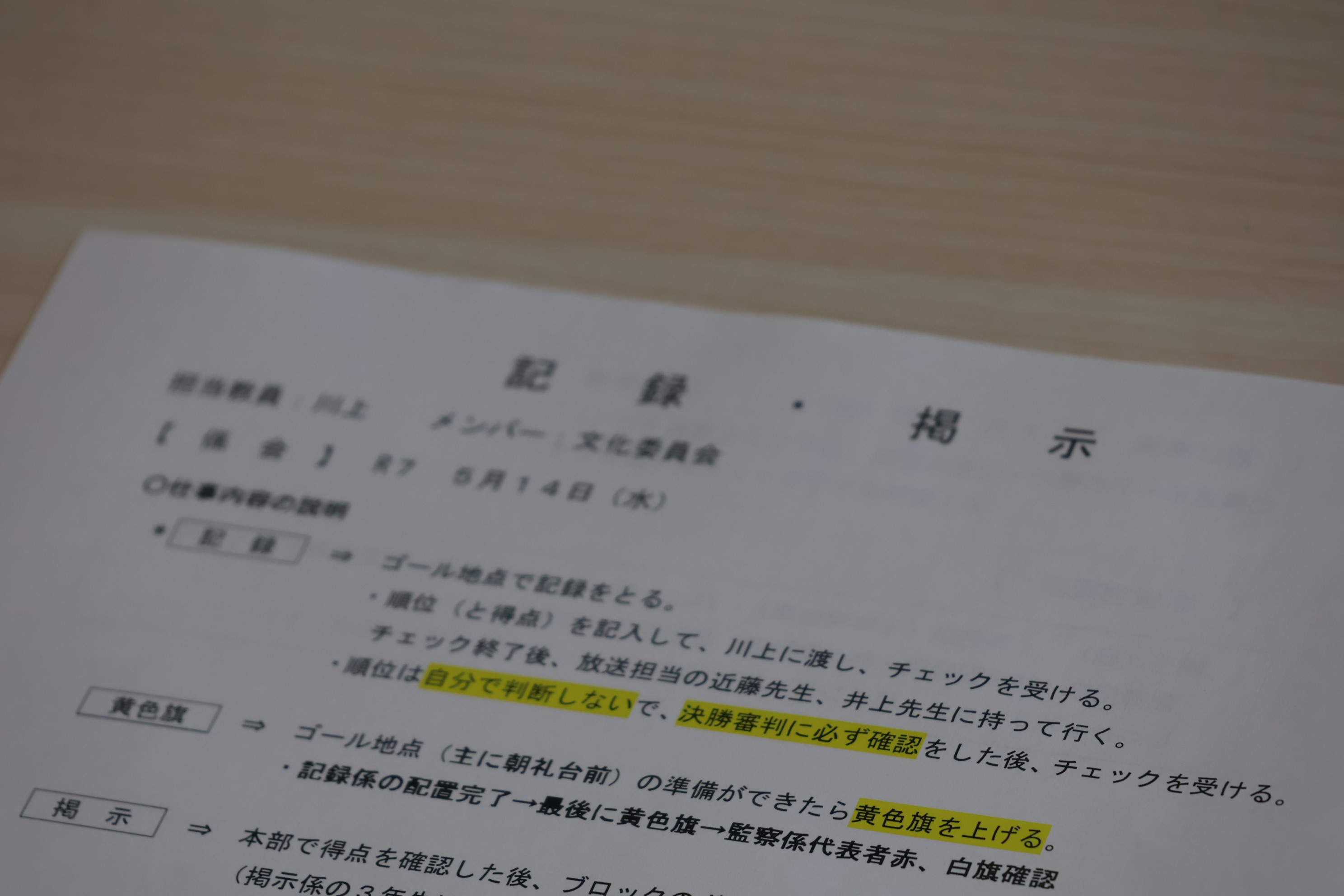
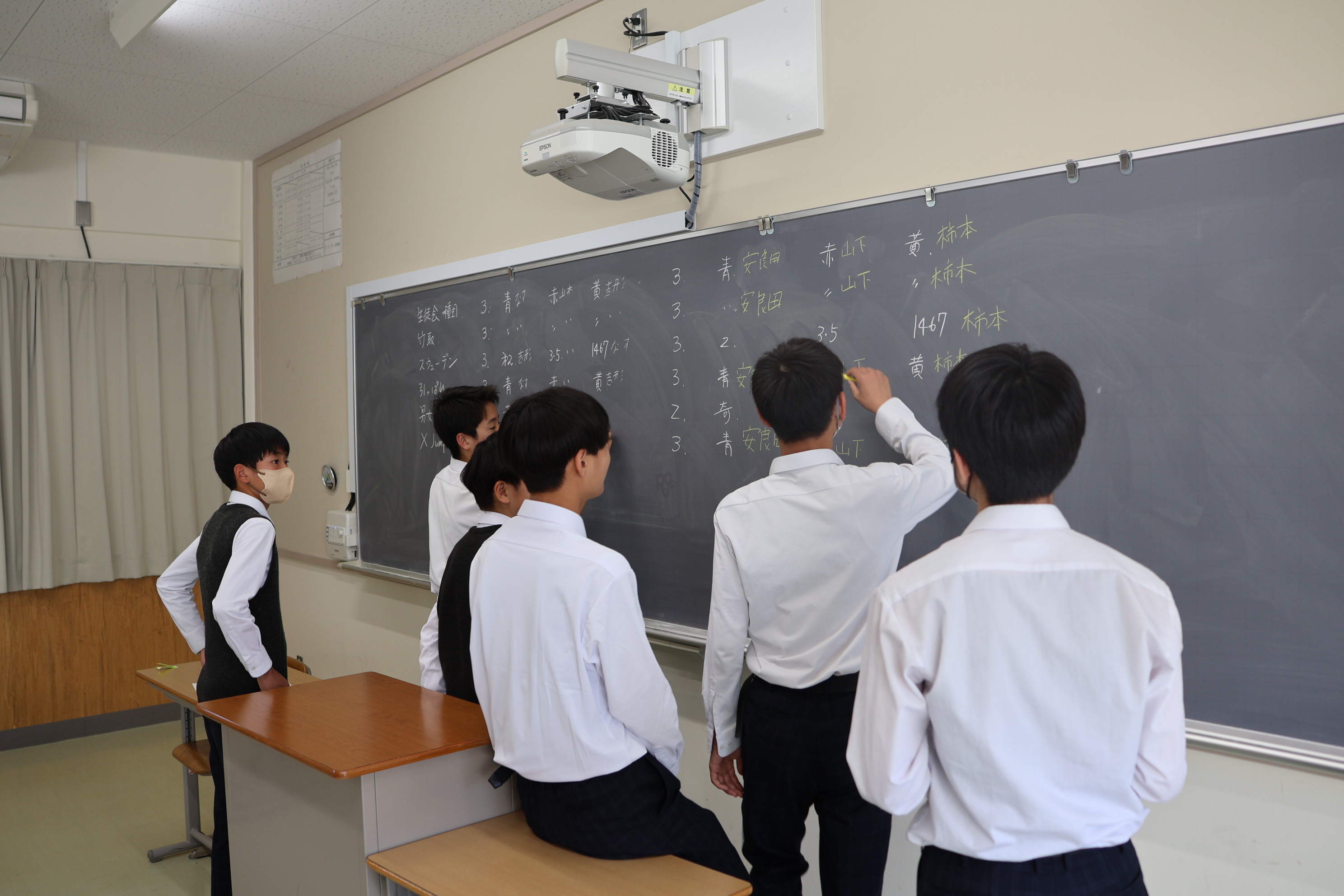
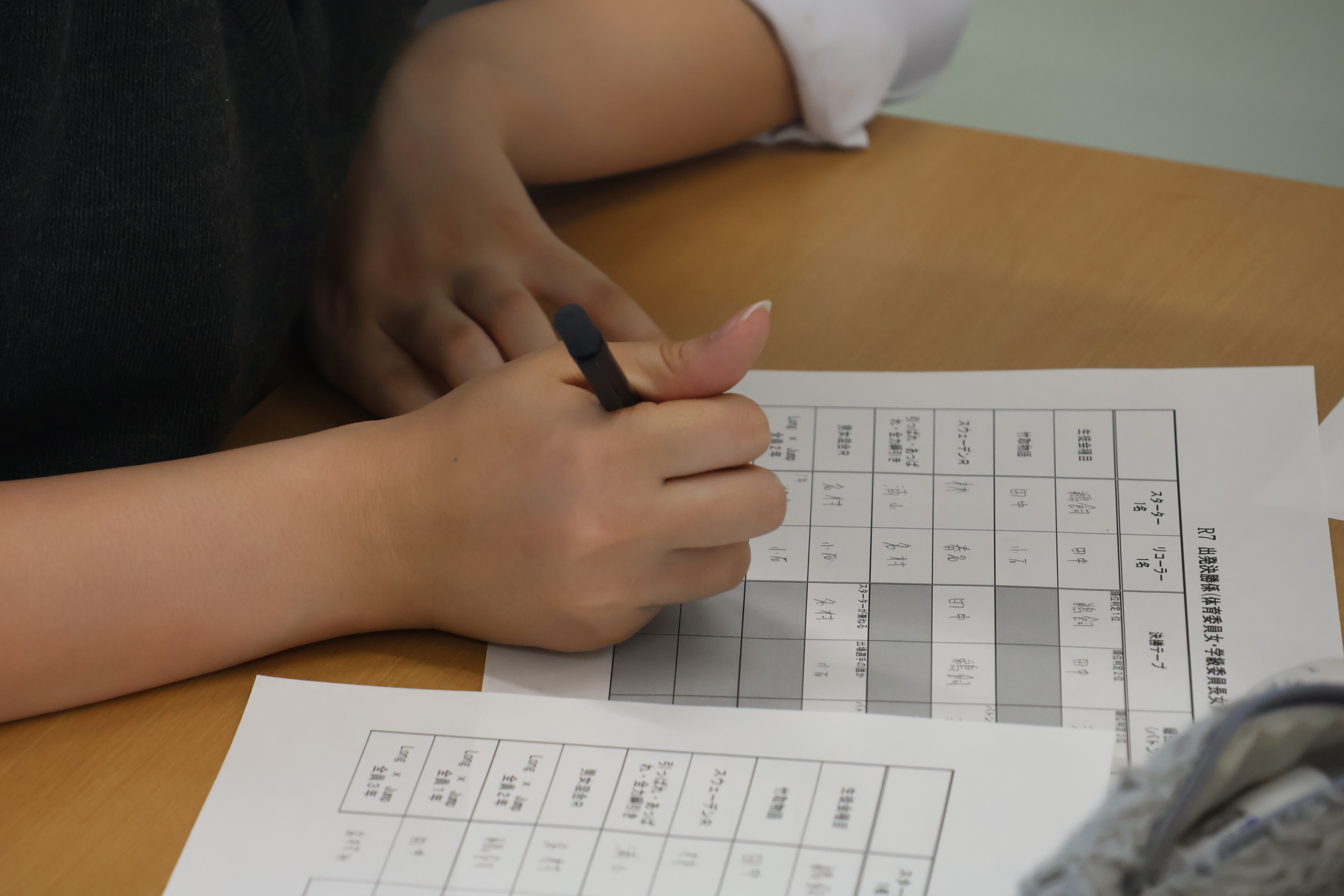


◎進む 仲間 わたし 一生懸命(5/14:3年授業風景から)

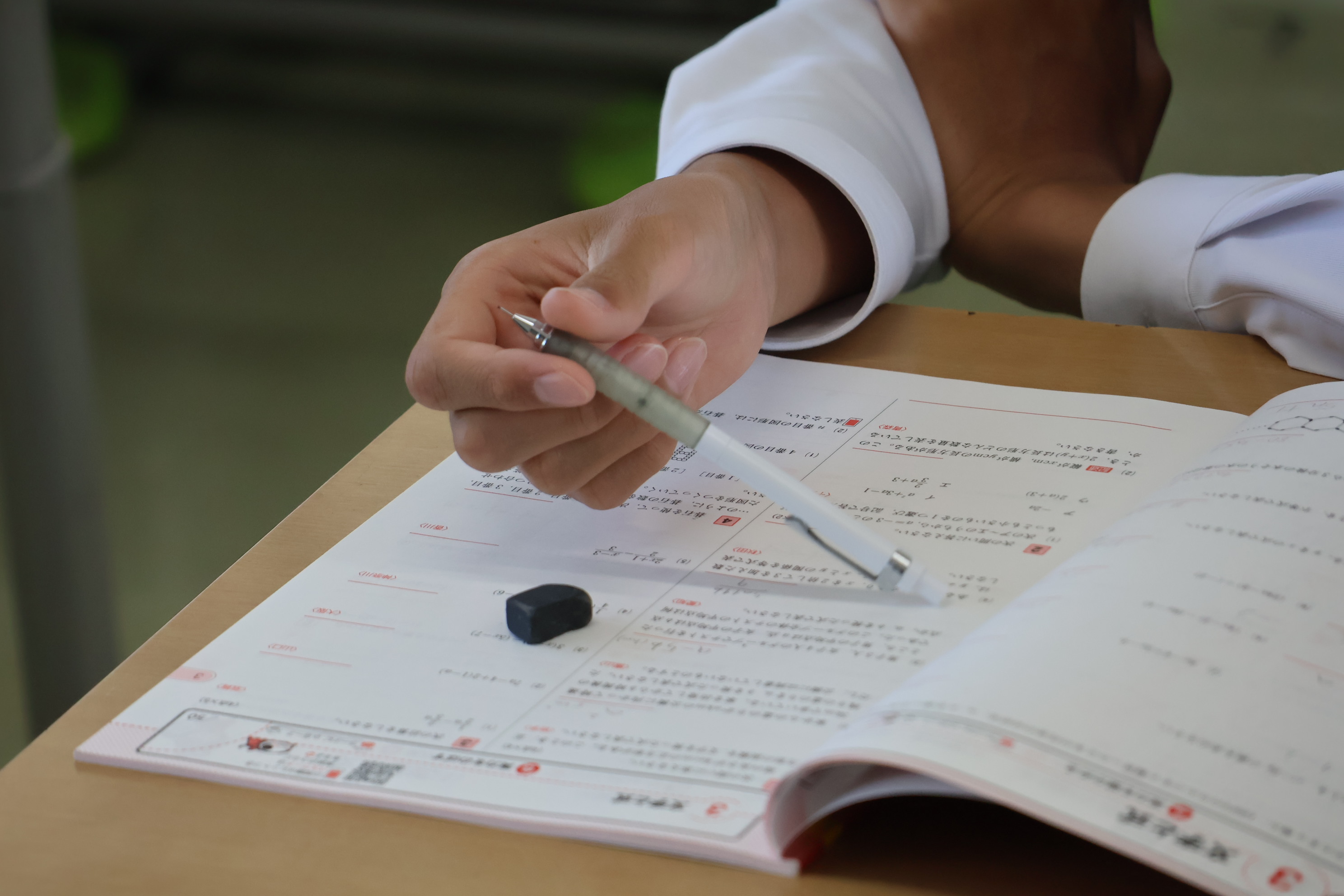


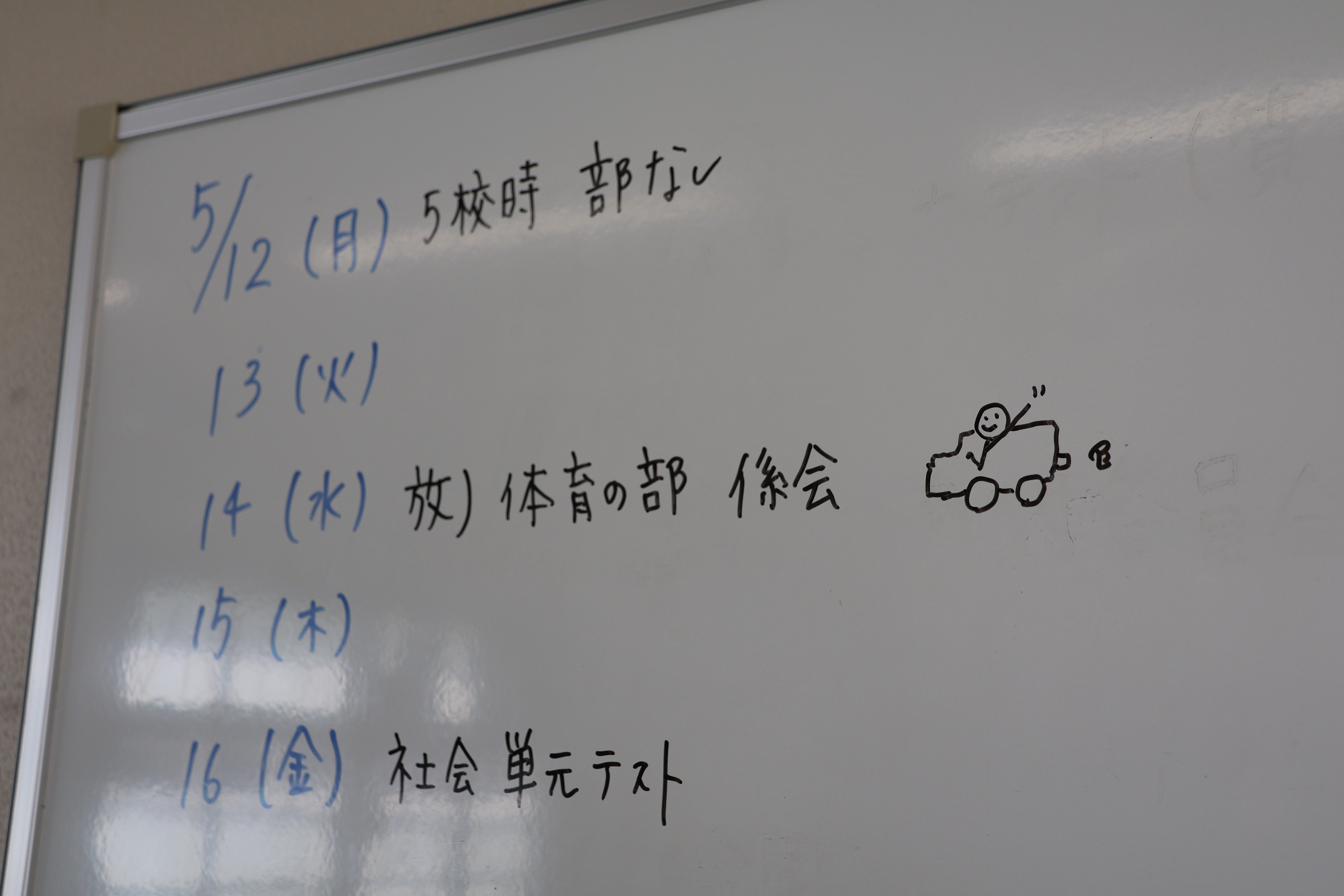

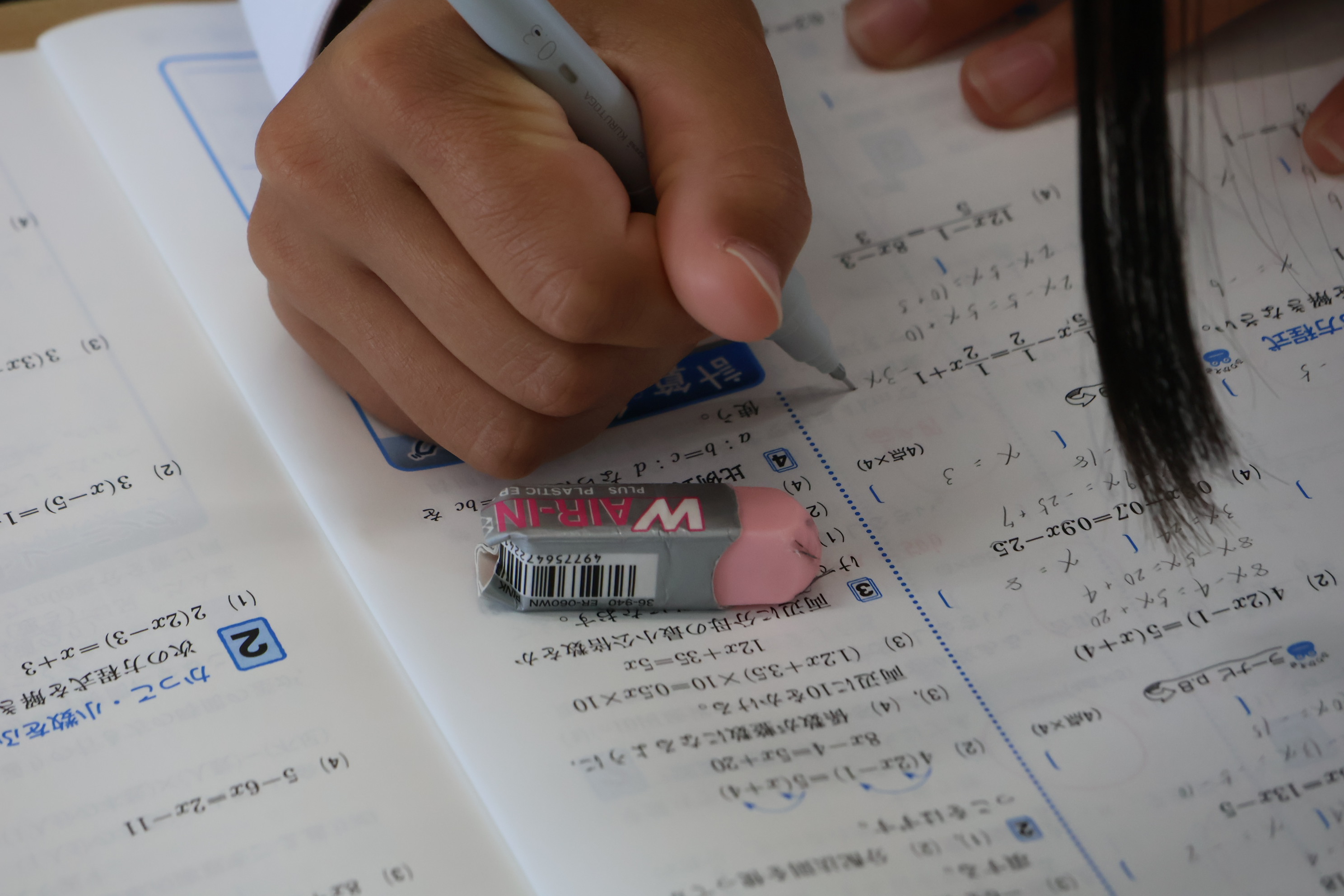


楽しそうに沖縄学習をしている?写真も混ざっている?
◎6.7竹取物語へ
支えてくれる翁(おきな)ありけり(5/14)



◎FLOUR MOON(5/13)

アメリカの先住民は季節を把握するために、各月に見らる満月に名前を、動物や植物、季節のイベントなど実に様々につけていました。農事暦(The Old Farmer's Almanac)によると、アメリカでは多くの花が咲くことにちなんで、5月の満月を「フラワームーン(Flower Moon/花月)」と呼ぶことがあるそうです。満月という現象は、太陽、月、地球の位置関係で決まります。月は自ら光っているわけではなく、太陽の光を反射することで輝いて見えています。そして、太陽の光が当たっている月面の半球が地球から見てどちらを向いているかによって、三日月や上弦、満月、下弦など、見かけ上の形が変わります。
地球から見た太陽の方向を基準に、太陽の方向と月の方向の黄経差が0度の瞬間が朔(新月)、90度の瞬間が上弦(半月)、180度の瞬間が望(満月)、270度の瞬間が下弦(半月)と定義されていて、およそ1か月弱で1周します。と、いうことで、満月は、地球から見て太陽と月が正反対の方向にならぶ瞬間(太陽、地球、月の順に、ほぼ一直線にならぶ瞬間)を指します。
◎ENJOY ENGLISH(5/13)
ALTの先生たちが、グローバルルームを利用して、英会話教室を開設(毎週火曜日)しています。楽しく英語に触れ、人と多文化に豊かに出会う時間を創出しています。
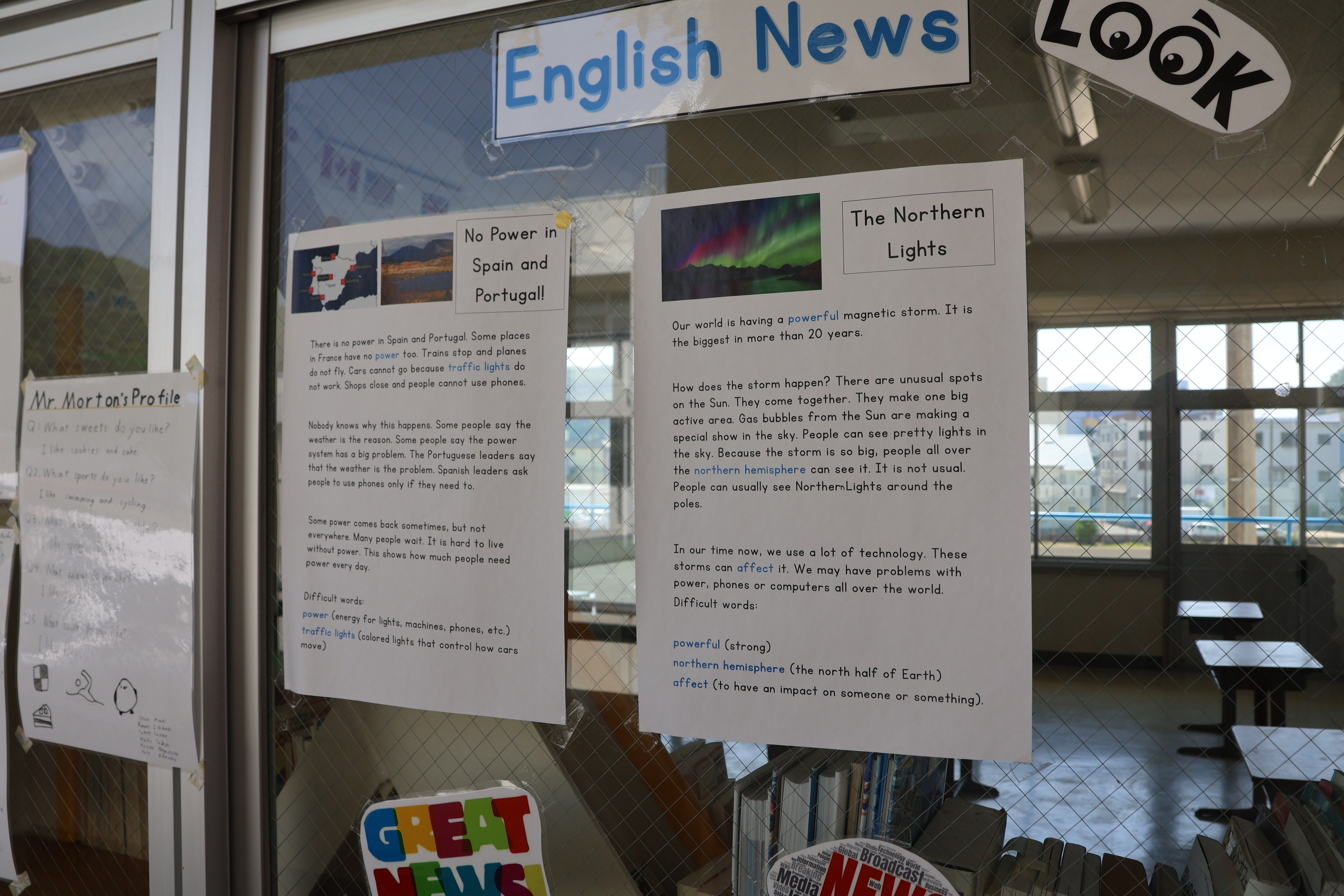
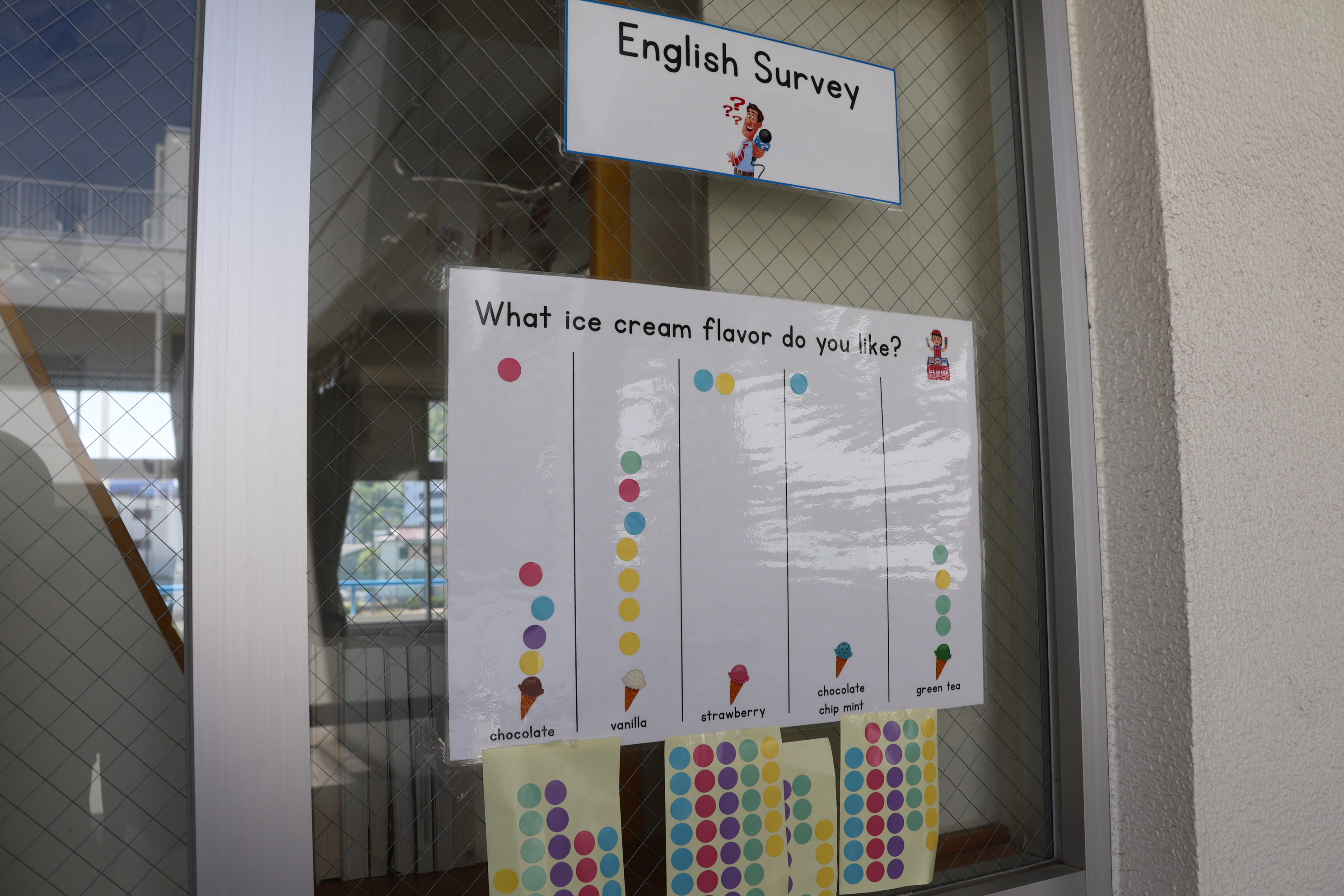

◎PS.新しい生活、頑張っています(5/13)
今日は小中連絡会を開催します。小学校の先生方が来校され、授業参観や情報交換会をもちます。


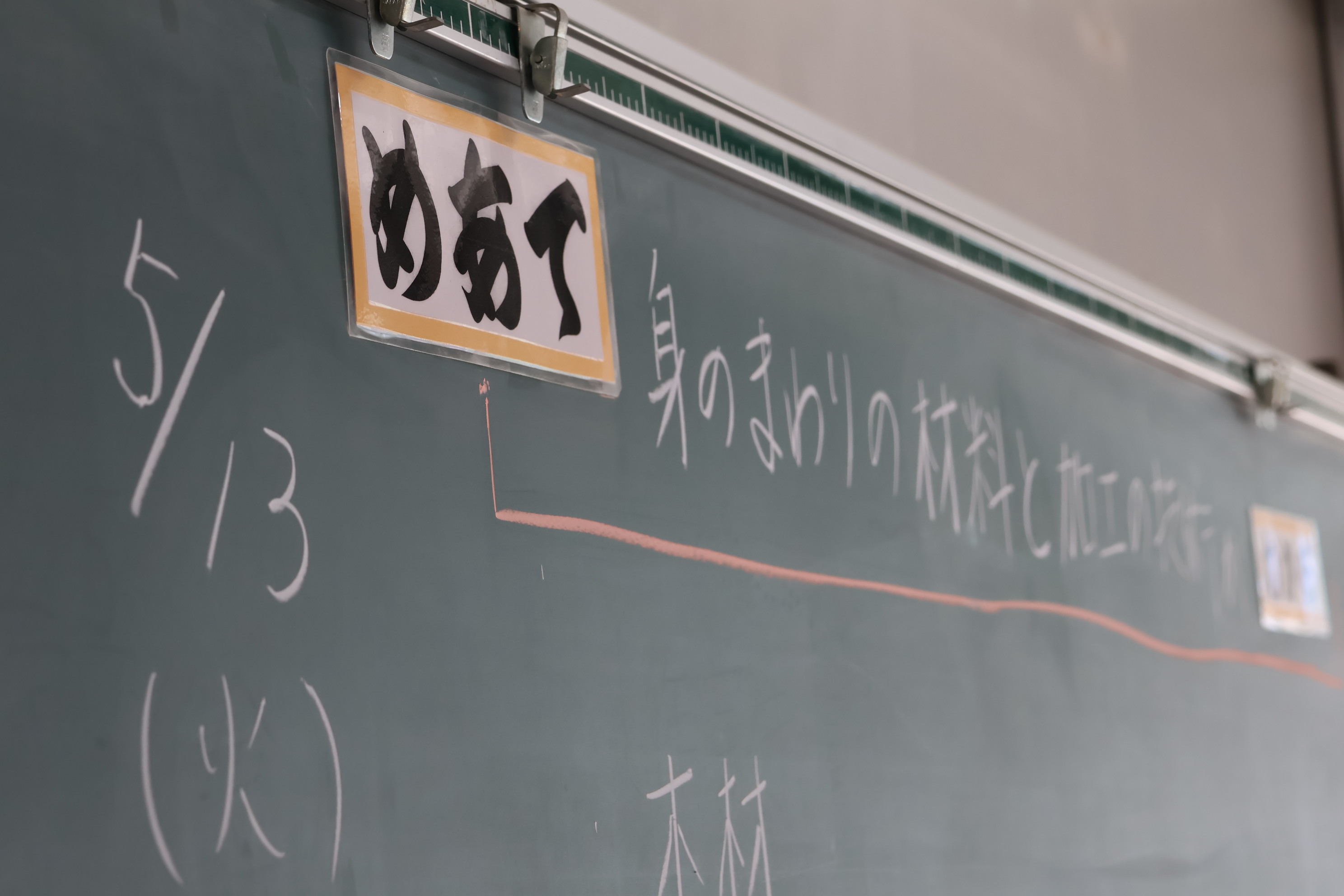


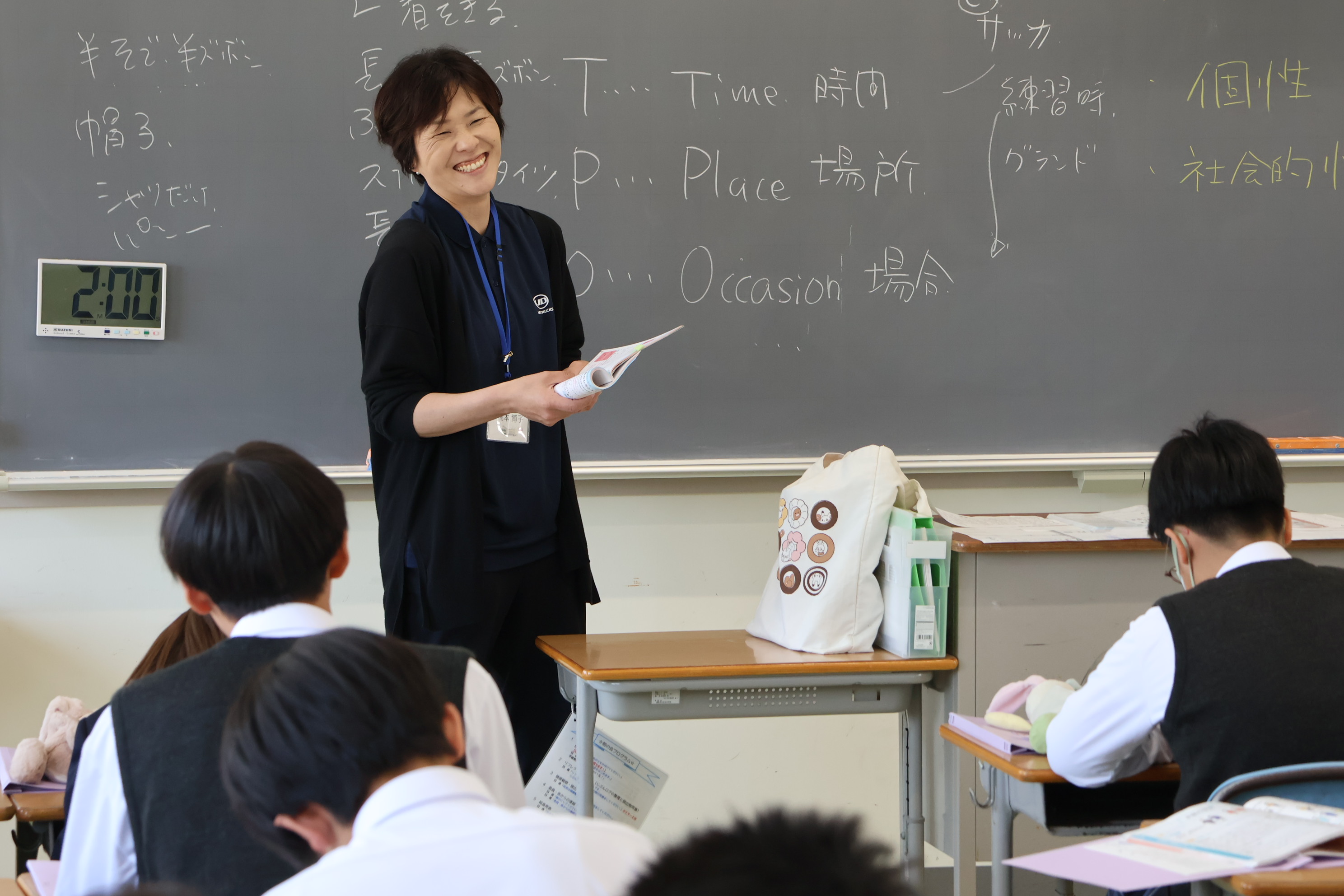
◎多くの人に支えられて(5/12)


備前警察署から根木スクールサポーターが来校され、「防犯」に関する作文募集と資料の提供をいただきました。また、備前市こどもまんなか課から赤堀さんと鷹取さんが来校され、家庭の支援・サポート等について情報交換をしました。
◎多くの人に支えられて(5/12:民生委員・児童委員の日)
民生委員・児童委員さんが、朝のあいさつ運動に来校されました。1917年(大正6年)、岡山県で済世顧問制度が創設されました。これは、民生委員制度の前身とされ、地域の貧しい人々を支援するための画期的な取り組みでした。貧困の予防という視点から、その後の社会福祉の基盤を築くことになります。5月12日、民生委員・児童委員の日は、その済世顧問制度の創設を記念して、1977年(昭和52年)に全国民生委員児童委員連合会(全民児連)によって制定されました。この日を通じて、社会福祉の歴史を振り返り、今後の福祉の在り方を考える機会としましょう。
また、民生委員は、地域住民の福祉向上のために、地域で起こる様々な問題に対応し、生活困窮者の保護指導や福祉事務所への協力を行います。これは、民間の奉仕者としての大変貴重な役割を担っています。また、児童委員は、児童や妊産婦の生活環境を支援し、子どもたちが健やかに成長できるようにという願いを込めて活動しています。この二つの委員は、私たちの生活を支える大切な存在です。

◎心理的安全性の高い職場づくりを目指しています(5/9)
校内のコンプライアンス研修を継続的に実施し、また支え合う職場づくりを進めています。

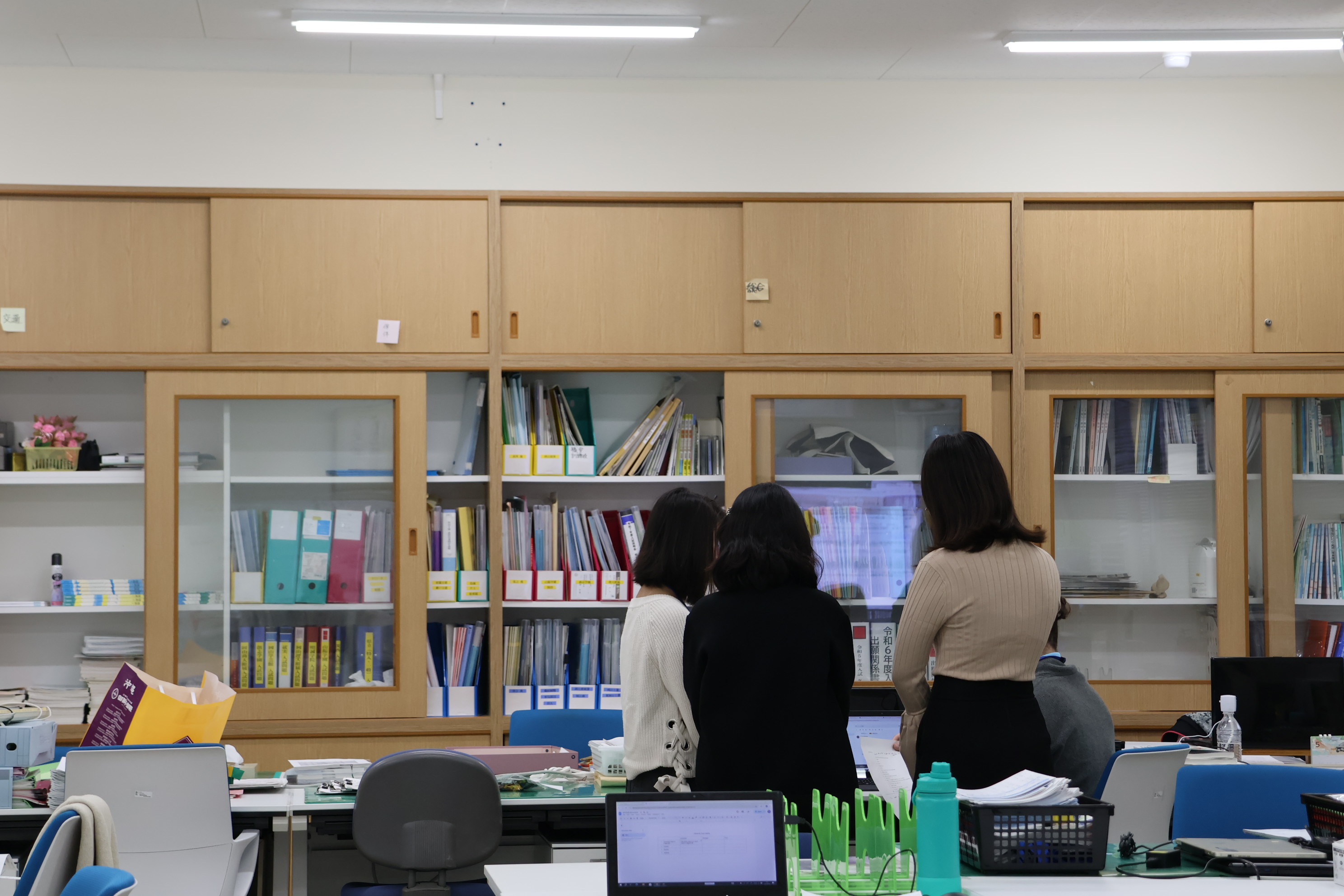

◎私たちのはじまりの風景17
ここはどこでしょう?









◎シン・生徒会活動へ(5/8:生徒朝礼・臨時生徒総会)
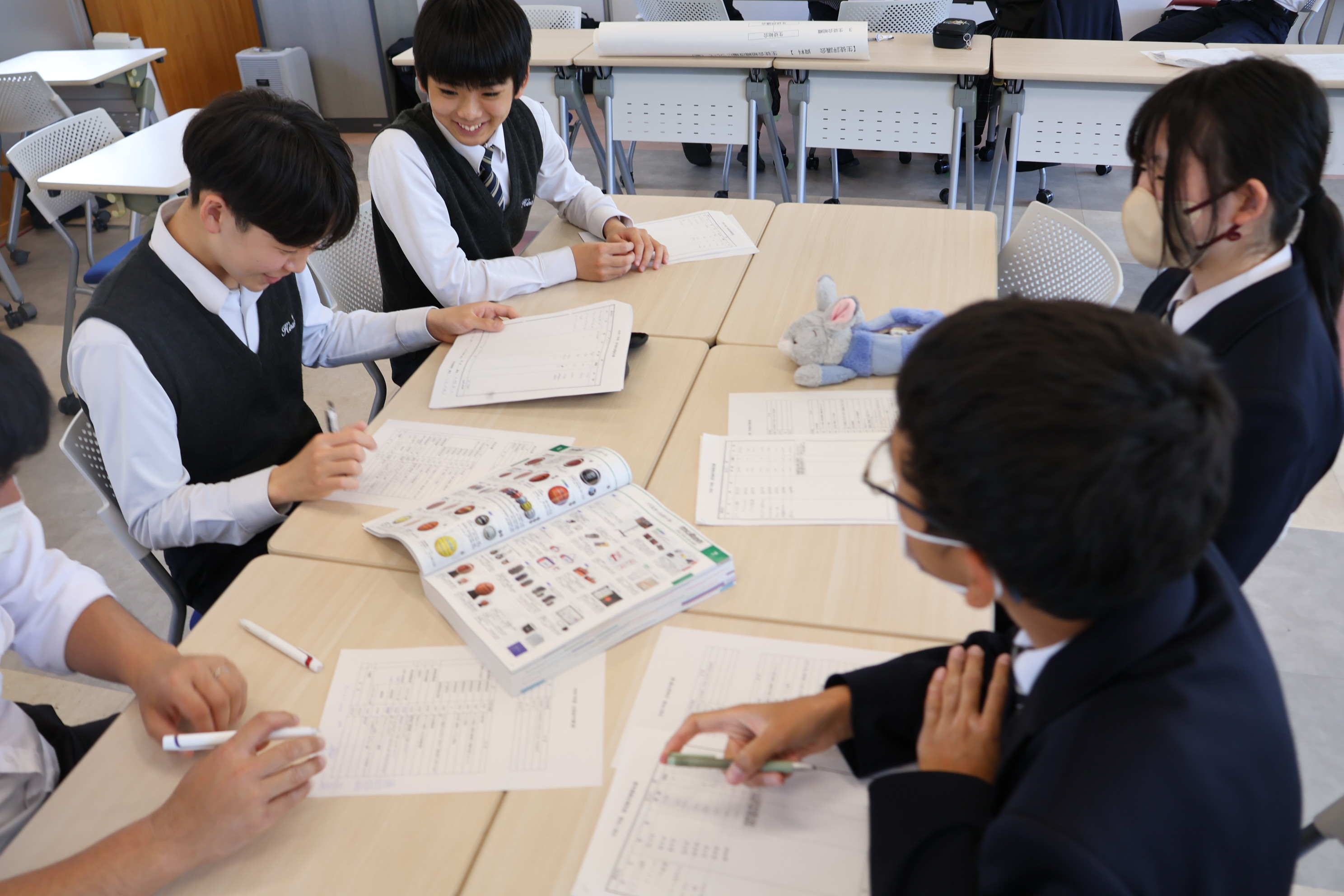

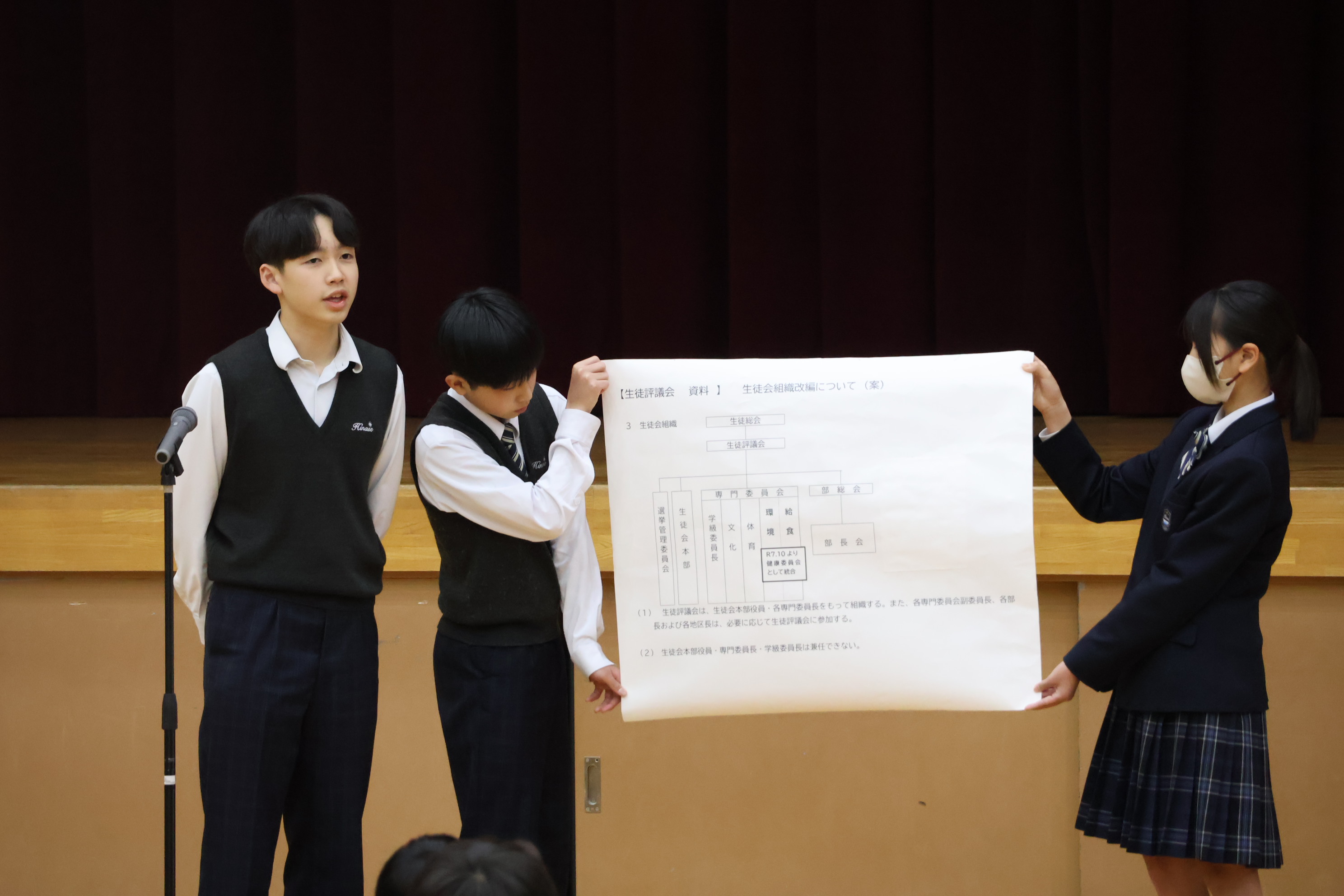
昨日は部活動予算折衝。
◎わいわい、にこにこ、今日もほっとスペース(5/7)

6/4には、ミニ学習会(マリルイーズさんの動画上映会)も予定しています。
◎Green Green(5/7)

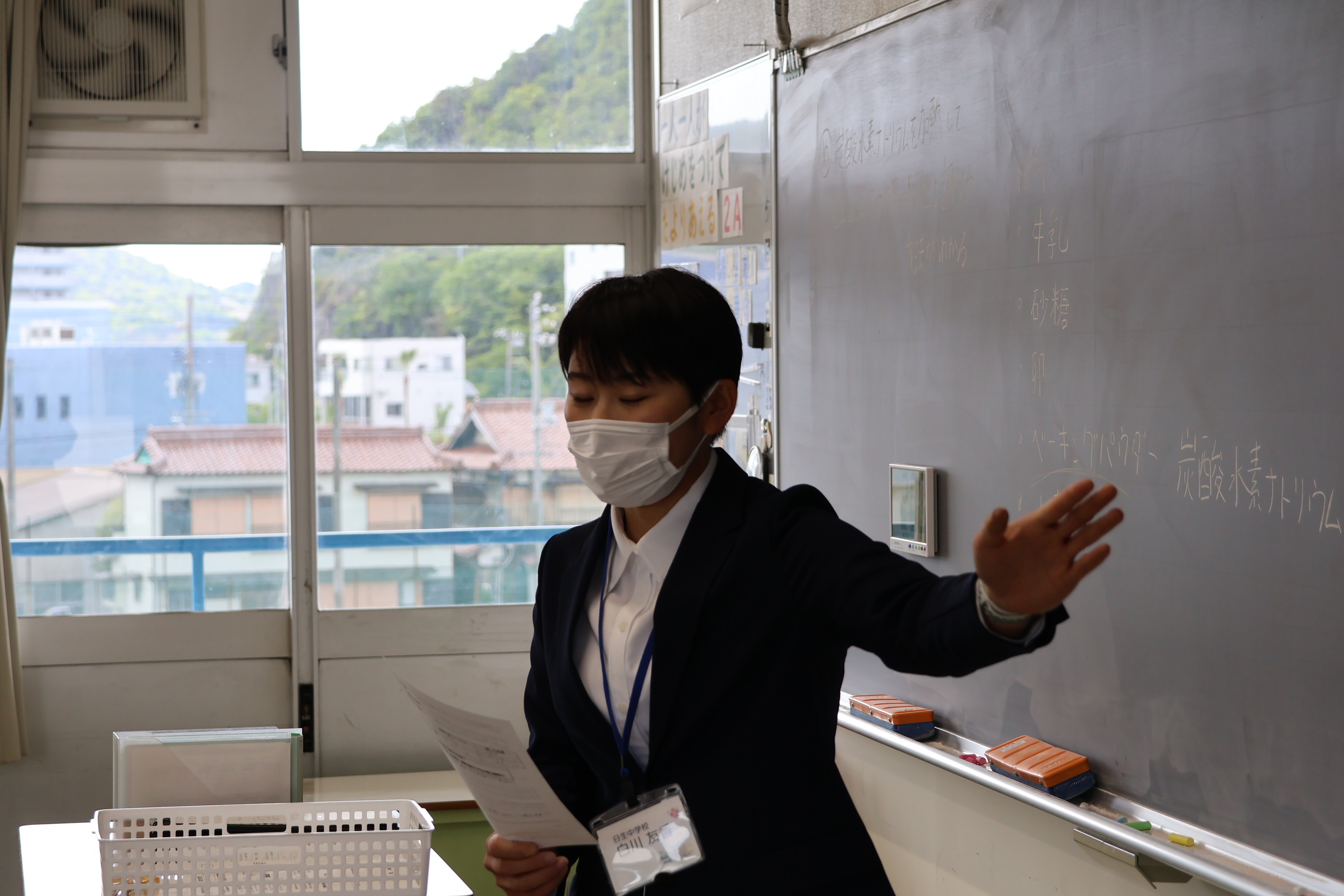
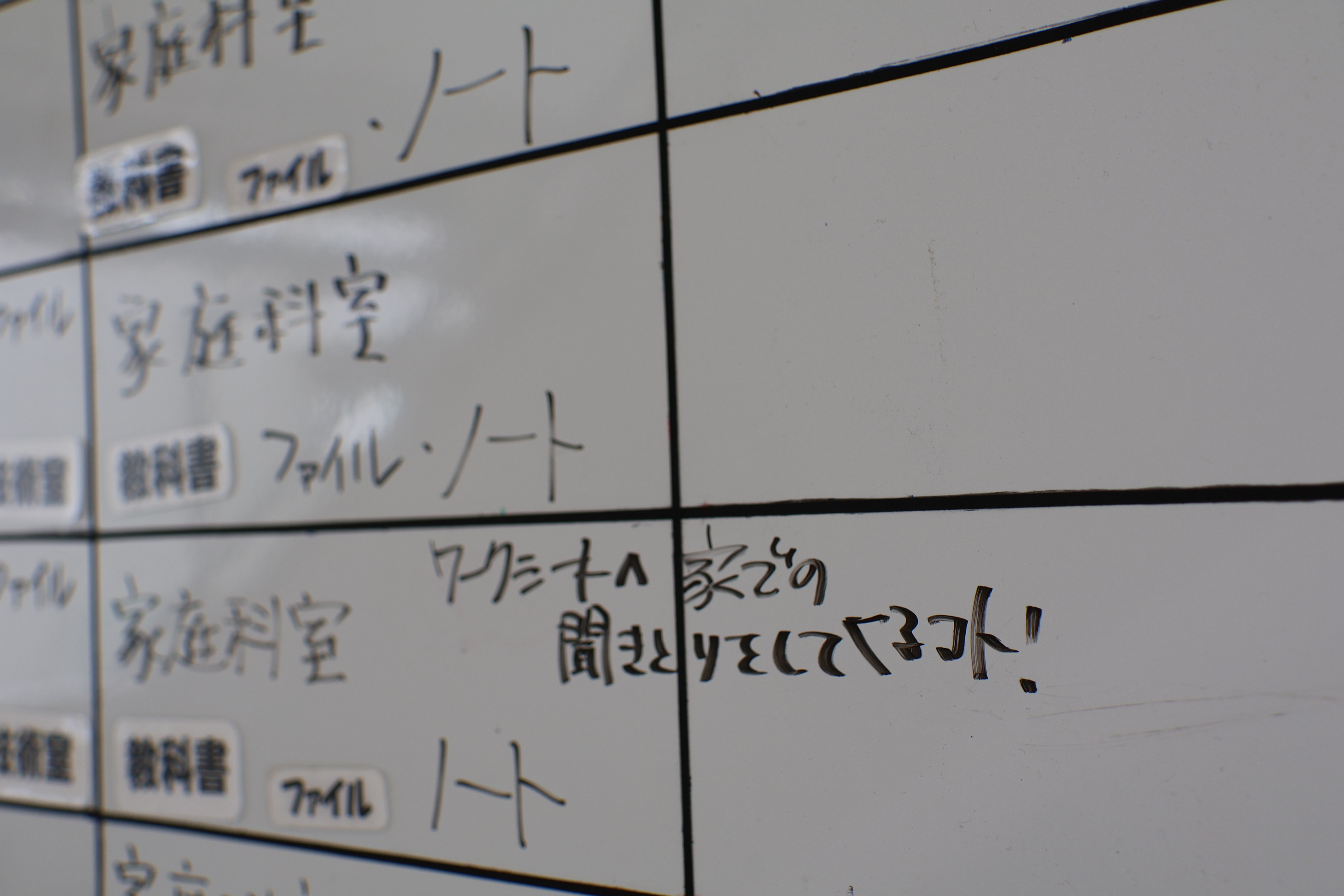



Do we need to make a special effort to enjoy the beauty of the blue sky? Do we have to practice to be able to enjoy it? No‚ we just enjoy it. Thich Nhat Hanh
(青空の美しさを楽しむのに、何か特別な努力が必要だろう?楽しむのに、練習が必要でしょうか?ただ楽しもう。)
◎ヒロシマ・オキナワへ(5/2)
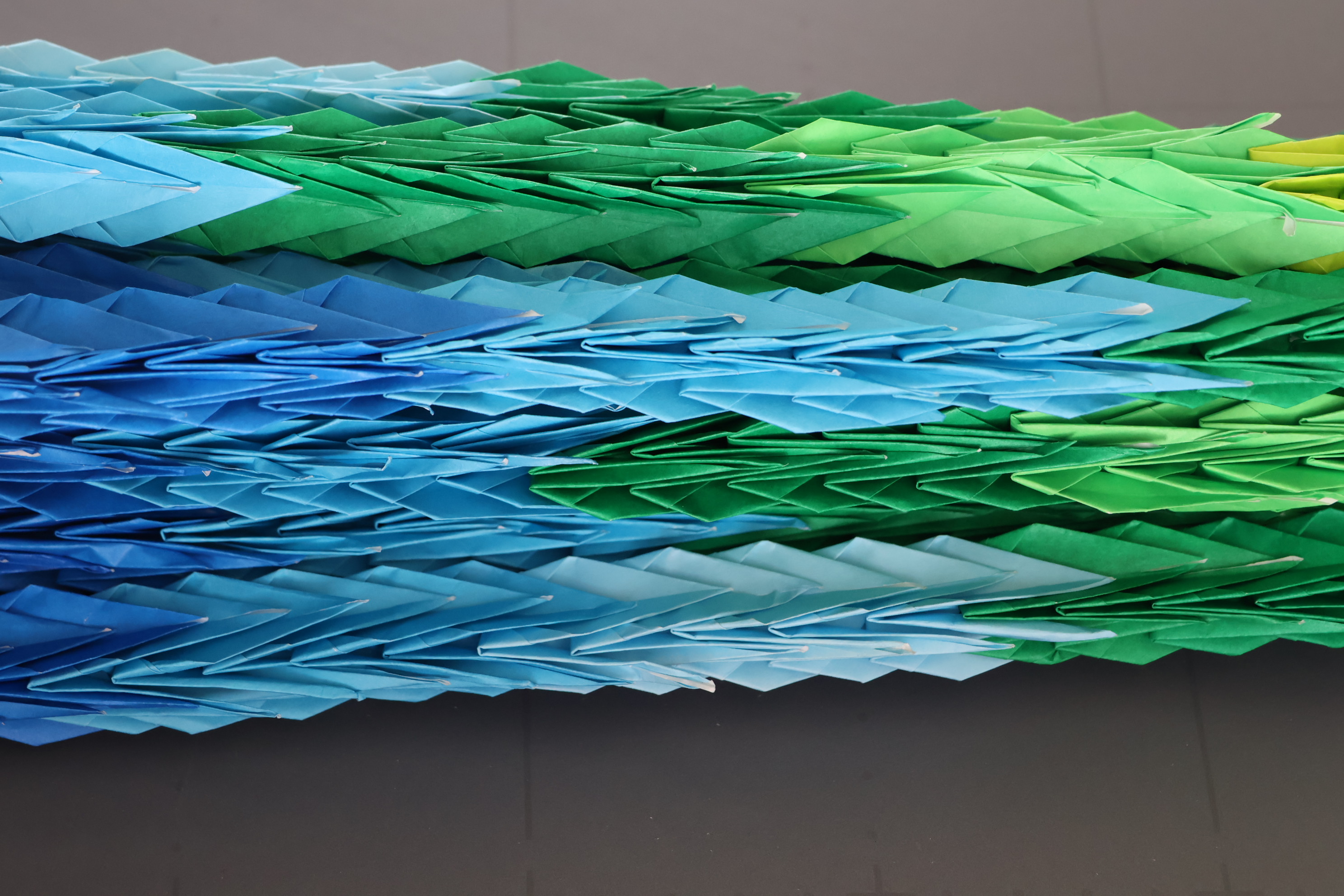
◎春15(いちご)の会 実行委員会(5/2)
特別支援教育のニーズのある子どもたちのための進路情報交流学習会(春15の会)の実行委員会が市役所で開かれ、教頭先生も参加されました。今年度も多様な進学先の情報をYouTube配信、また8月23日(土)12:30から、対面式での学校説明及び個別相談会を開催(会場:備前市立日生中学校)する予定です。準備をこれから進めていきます。
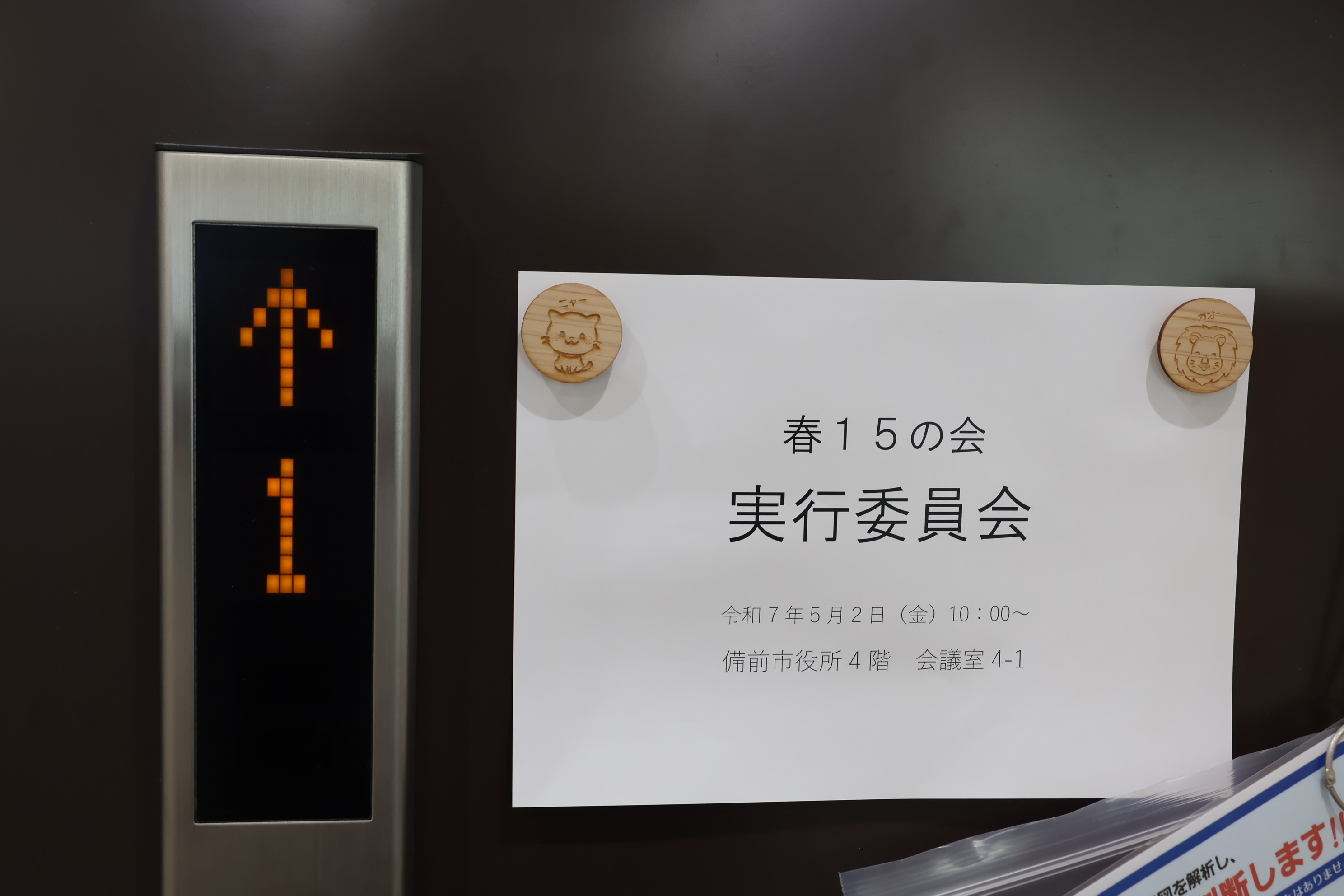


◎誠実を胸に刻むこと 共に希望を語ること(5/1)
第1回参観日を開催しました。たくさんのご参加をありがとうございました。
1年生が海洋学習に取り組んでいます。この日は天倉さんをお招きして、日生町の漁業の歴史と現状、アマモ場の再生活動について、質疑応答形式で学習を深めました。次回(5/15)は、カキの種付けに挑戦します。



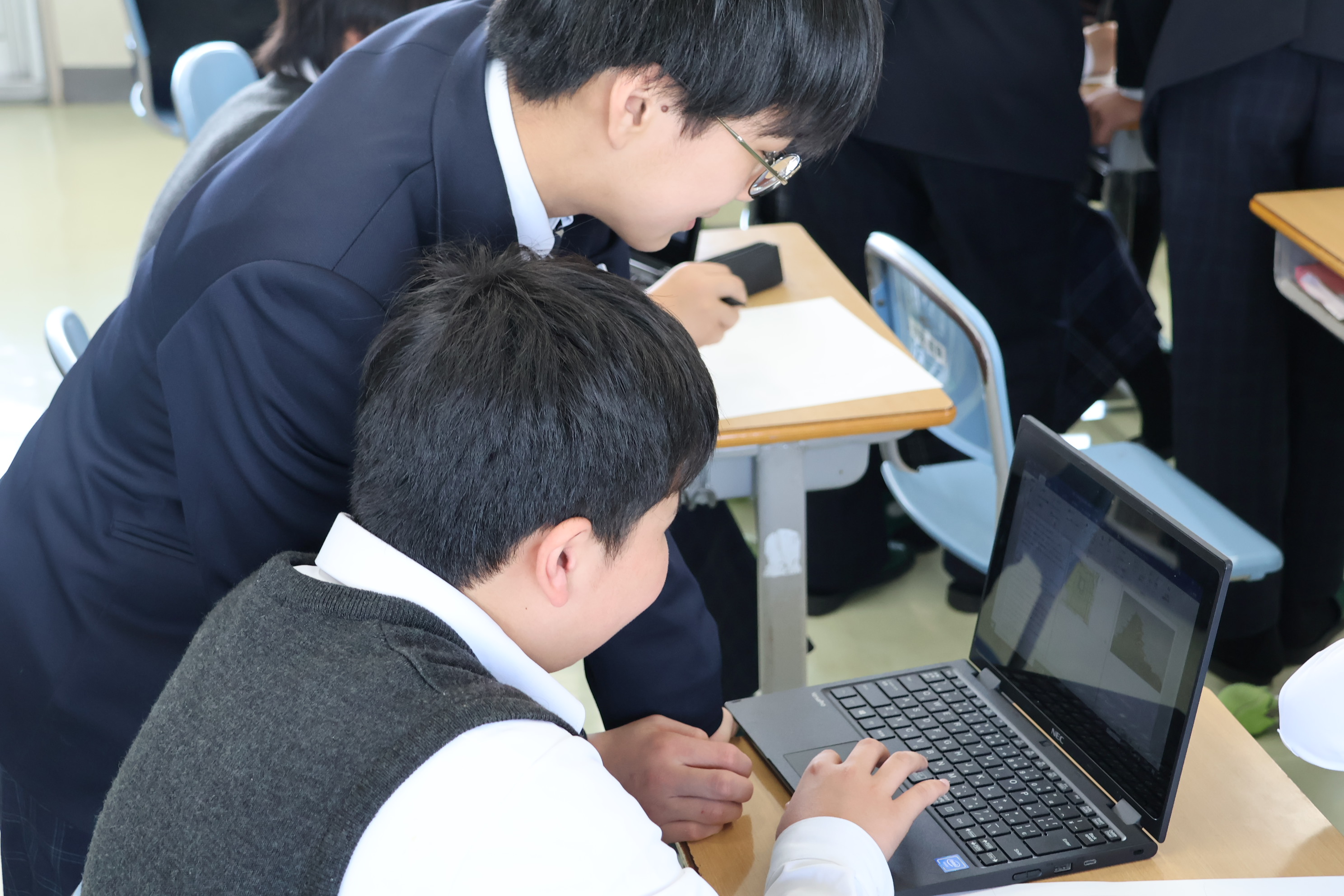
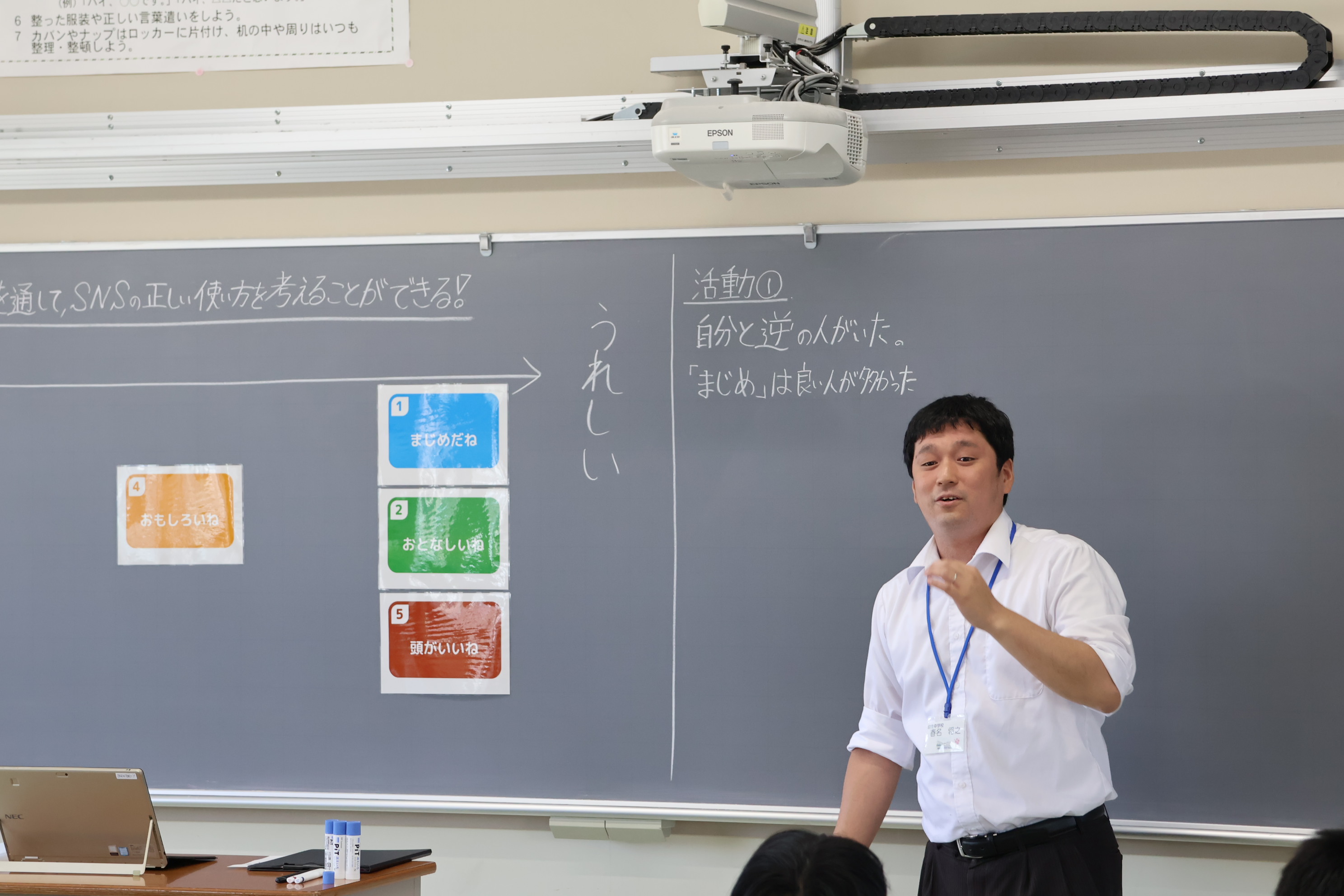




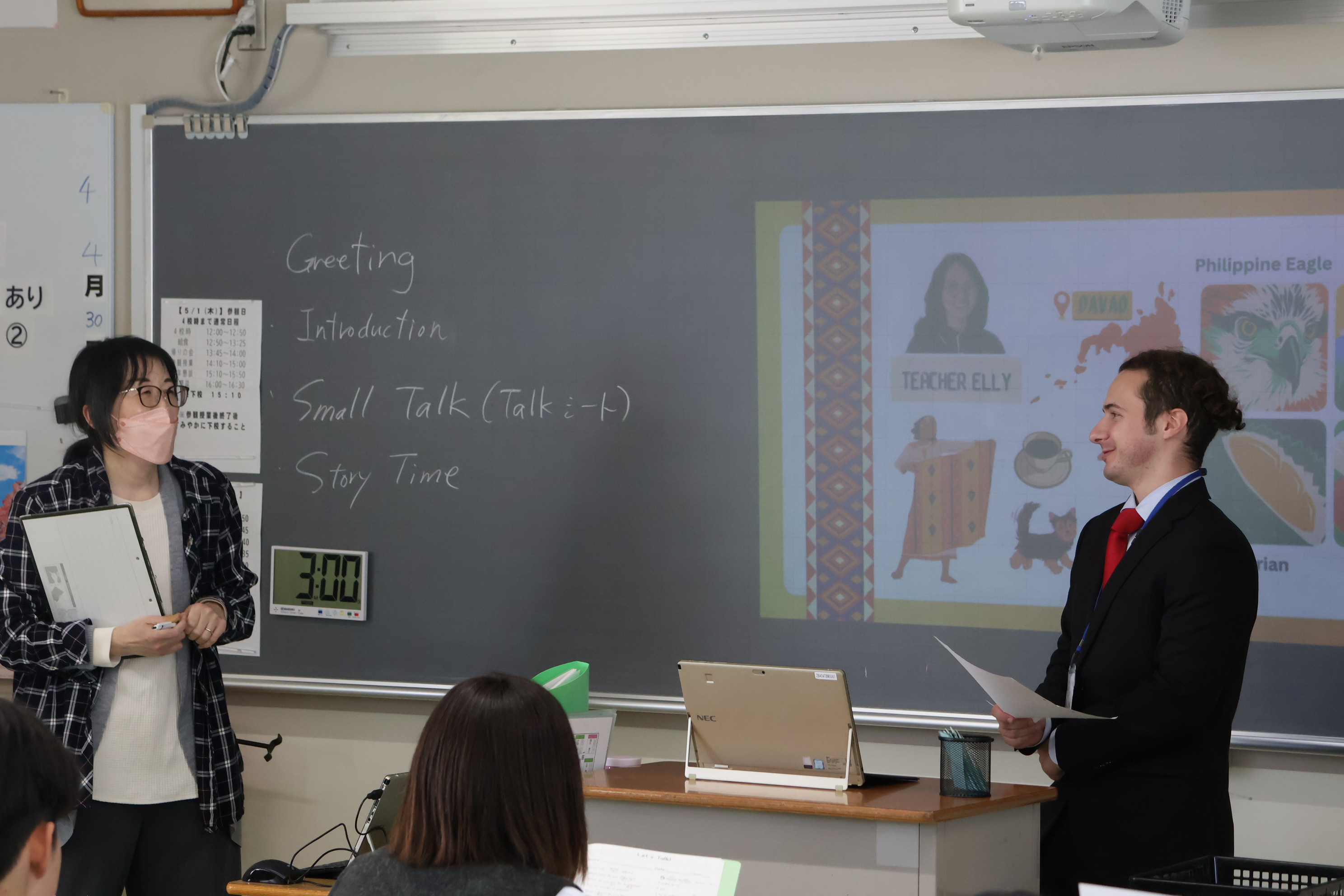


◎出会いに心をこめて(5/1)
新しい先生との出会いを大切にして、授業での学び、学校生活での学びを豊かにしていきましょう。左から、北脇先生、白川先生、アンジェリー先生、ブリ先生、シェナ先生です。

◎メーデー(5/1)

メーデー(May day)とは、毎年5月1日に世界各地で開催している労働者の祭典です。もともとはヨーロッパで春の訪れを祝うお祭りでしたが、19世紀のアメリカで「労働状況改善を求め、労働者が声を挙げる日」となりました。メーデーの社会的影響は大きく、ヨーロッパをはじめ世界各地に広がります。現在は労働者の日として、各地で集会やパレードを行うのが慣例です。メーデーはアメリカのほか、社会主義国やヨーロッパ、ラテンアメリカ、ASEAN諸国など、多数の国々で祝日となっています。当日は労働者団体による集会やデモなどのほか、人々が集まり歌やダンスを楽しむこともあるようです。メーデーは、労働組合が中心となって開催されています。
ちなみに、メーデーはほかの意味を指す場合もあります。それは、船舶や航空機の遭難信号で「メーデー・メーデー・メーデー」と3回繰り返すときは、緊急事態を知らせる言葉です。遭難信号における「メーデー」は世界中で使われており、「助けに来てほしい」という意味のフランス語の「ヴエ・メデ(venez m’aider)」が語源です。英語圏で分かりやすいよう、労働者の祭典と同じMaydayと表記するようになったといわれています。
さらに、世界各国でメーデーが祝日となっているのに対して、日本で祝日ではない理由に2つの説があります。5月1日は日本では大型連休中にあたるため祝日にならない1つ目の説としては、メーデーにあたる5月1日はゴールデンウィーク中であることが関係しているといわれています。5月1日も祝日にすると連休がさらに長くなり、経済活動が停止してしまうと懸念されているためです。2つ目は、11月23日に勤労感謝の日があるためです。内閣府の「国民の祝日について」によると、勤労感謝の日は「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」と定められています。メーデーと趣旨が似ているため、メーデーは祝日にならないといわれているようです。
メーデーの起源と歴史は、19世紀アメリカに遡ります。起源は19世紀アメリカ、労働者の祭典として最初のメーデーは、1886年5月1日に第1回大会がアメリカのシカゴで開催されました。労働者たちが8時間労働制を訴えたのが始まりです。12~14時間労働が当たり前だった時代、労働状況の改善を求めて35万人もの労働者が結集し、大規模なストライキを敢行しました。しかし、労働時間の改善は見られなかったため、毎年5月1日に労働者たちが集結し、声を挙げるようになったといわれています。1889年には、パリで社会主義・労働者連合の国際組織である第二インターナショナル(国際社会主義者大会)が発足されます。アメリカのメーデーが「8時間労働の実現を目指す活動」と承認されたのをきっかけに、メーデーは世界各地に広がりました。当時の第一次世界大戦に影響を受け、メーデーは労働時間だけでなく戦争反対運動の側面も持つようになります。なお、第二次世界大戦で一度衰退を見せるものの、現在では80ヵ国もの国々で定められている労働者の祭典です。
◎季節の中で(5/1:参観日)
5月1日は、今年度最初の参観日となります。学年懇談、部活動懇談会、そしてPTA意見交流会も予定しています。また1年生は、漁協から天倉さんをお招きした海洋学習に取り組みます。ご参会をどうぞよろしくお願いします。

また今日は八十八夜です。八十八夜とは、立春を1日目と数えて、88日目にあたる日のこと。現代の暦か旧暦かにかかわりなく、毎年ほぼ一定であることがポイントです。日本では長く、月の満ち欠けをもとにした太陰太陽暦(旧暦)が使われてきました。旧暦は季節とずれやすいため、農業の目安とするには不便な点もあったようです。そのため、太陽の動きを基準にした「二十四節気」や、日本の気候風土を上手に言い表した「雑節(ざっせつ)」という暦日が使われてきました。入梅(にゅうばい)、土用、二百十日、八十八夜などが雑節です。雑節は日本人の経験から生まれた、生活の知恵。八十八夜は毎年、5月の初め。春から初夏へと移り変わる季節です。「八十八夜の別れ霜」といわれ、この日までは遅霜(おそじも)に注意が必要でした。逆に言えば、この日からは農作業本番。種まき、田植えと、農家さんは忙しくなります。
2025年の八十八夜は5月1日(木)です。です。八十八夜は立春から数えるので、立春が動けば八十八夜も変動します。また、うるう年には、途中に1日加わるので、1日早くなります。毎年だいたい2日間の間に収まります(まれにズレるときもあります)。
なぜ八十八夜といえば新茶なのでしょうか?お茶の葉は、1年に3~5回の収穫が可能です。中でも最初に収穫される「新茶」がもっとも美味しいとされています。甘み・旨み成分であるテアニンが、二番茶以降の3倍以上も含まれているとか。新茶の収穫は、タイミング勝負。お茶は、発芽する前は寒さに強いのですが、発芽後は急に霜に弱くなります。また、伸びれば伸びるほど、テアニンの含有量も減っていきます。かといって早すぎると、ほとんど収穫できない…という結果になるかもしれません。農家さんは、成長の具合や、季節の進み具合を見極めて一気に収穫します。八十八夜はまさにそのタイミング。現代では収穫が早めの鹿児島から、遅めの滋賀・奈良県まで、だいたい4月上旬から5月中旬にかけて新茶を収穫します。八十八夜のころが新茶収穫のピークであることは、今も昔も変わらないようです。
◎日生中がもっと楽しくなる(4/30:生徒会プレゼンツ)

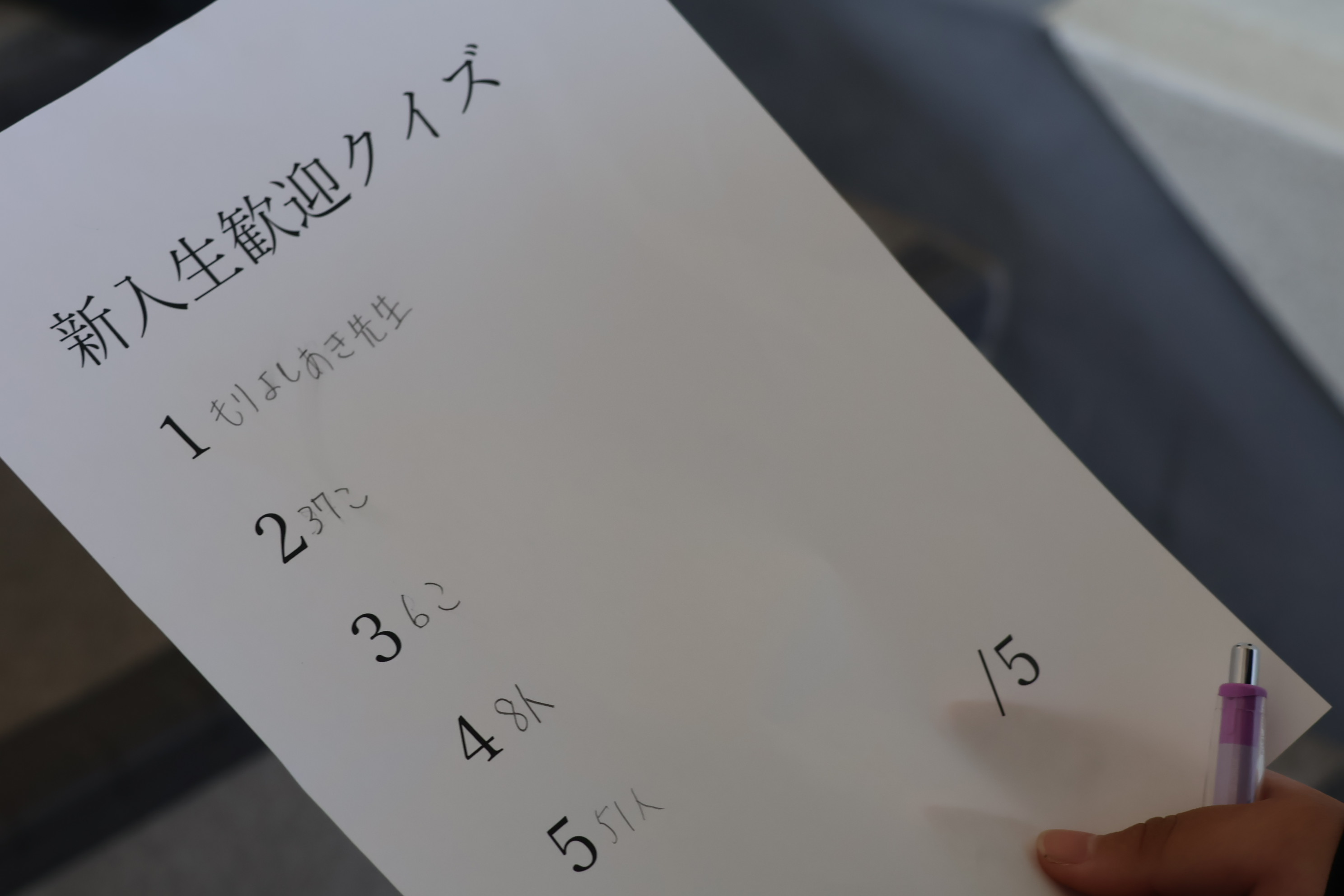
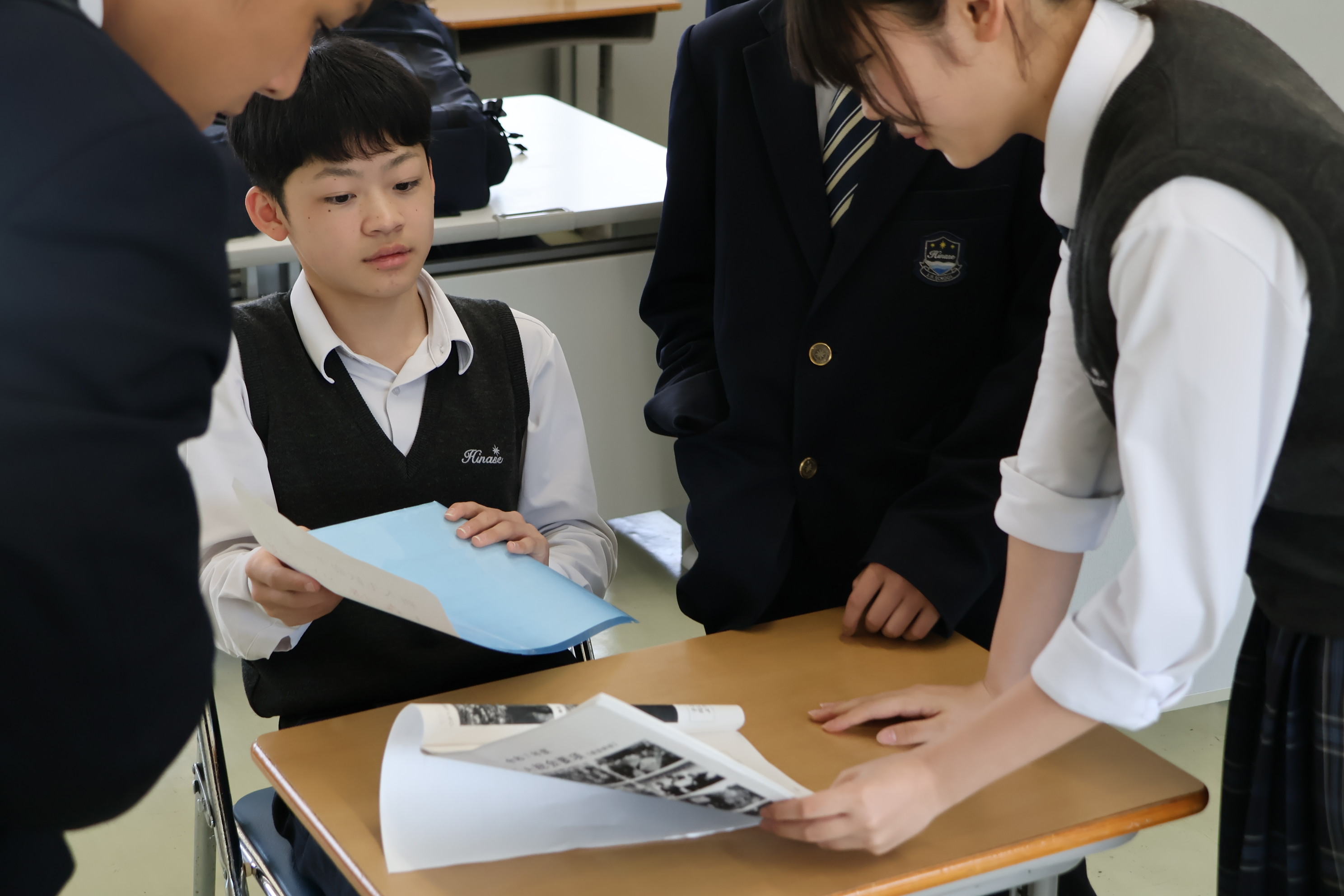
◎備前サンラッキーズを応援しています。(4/30)

日生中グラウンドで練習中
◎よい時間を過ごしたいね(4/30)



「ゴールデンウイーク」(黄金週間)は、連休で観客の入りがよかったため、この期間中に大作をぶつけるようになった映画界が、宣伝も兼ねて作り出したことばで、昭和27~28(1952~53)年ごろから一般にも使われるようになったようです。しかし、1970年代の「石油ショック」以降、「のんきに何日も休んではいられないのに、なにがゴールデンウイークだ」といった電話が放送局に何本もかかってくるなど抵抗感を示す人が目立ってきました。また、「外来語・カタカナ語はできるだけ避けたい」「長すぎて表記の際に困る」など、放送の制作現場の声もありました。そのうえ、週休2日制の定着で前後の土曜・日曜を加えると10日ぐらいになることもあり、ウイーク(週間)も的確な表現ではなくなってきました。このため、放送では原則として「ゴールデンウイーク」は使わず、「大型連休」を使っています。
ところで、この「大型連休」という言い方も、同じニュースや番組の中で何度も繰り返して言われると耳障りな場合があります。さらに、おととし以来の厳しい経済状況の中で、この言い方に抵抗感を持つ人も増えているものと思われます。このため、原則として「大型連休」という語を使いながらも安易に繰り返すのではなく「今度の(春の)連休で…」「この連休中(連休期間中)に…」「4月末からの(この○○日から始まる)連休で…」など、ときには別の言い方や伝え方を織り込むような表現上の配慮やくふうをすることも必要でしょう。
* 主な新聞社や通信社は、記事の中で以前は「ゴールデンウイーク」と「大型連休」をほぼ同じ率で混在した形で使っていましたが、最近は「大型連休」を使うほうが多いようです。同じ活字メディアでも、雑誌は旅行案内や若者向けの情報誌を中心に「ゴールデンウイーク」や頭文字をとった「GW」の表記が引き続き多く使われているようです。
(「こどもの日小さくなりし靴いくつ」(林 翔)) NHK放送文化研究所のHPより一部紹介しました。
◎子曰、学而不思則罔、思而不学則殆。(4/28:一年生閑谷研修)
子曰く、学びて思わざれば則ち罔し(くらし)、思いて学ばざれば則ち殆し(あやうし)。















孔子先生はおっしゃいました。「学んで、その学びを自分の考えに落とさなければ、身につくことはありません。また、自分で考えるだけで人から学ぼうとしなければ、考えが凝り固まってしまい危険です」と。
◎施錠を解く鍵は人である(4/25)


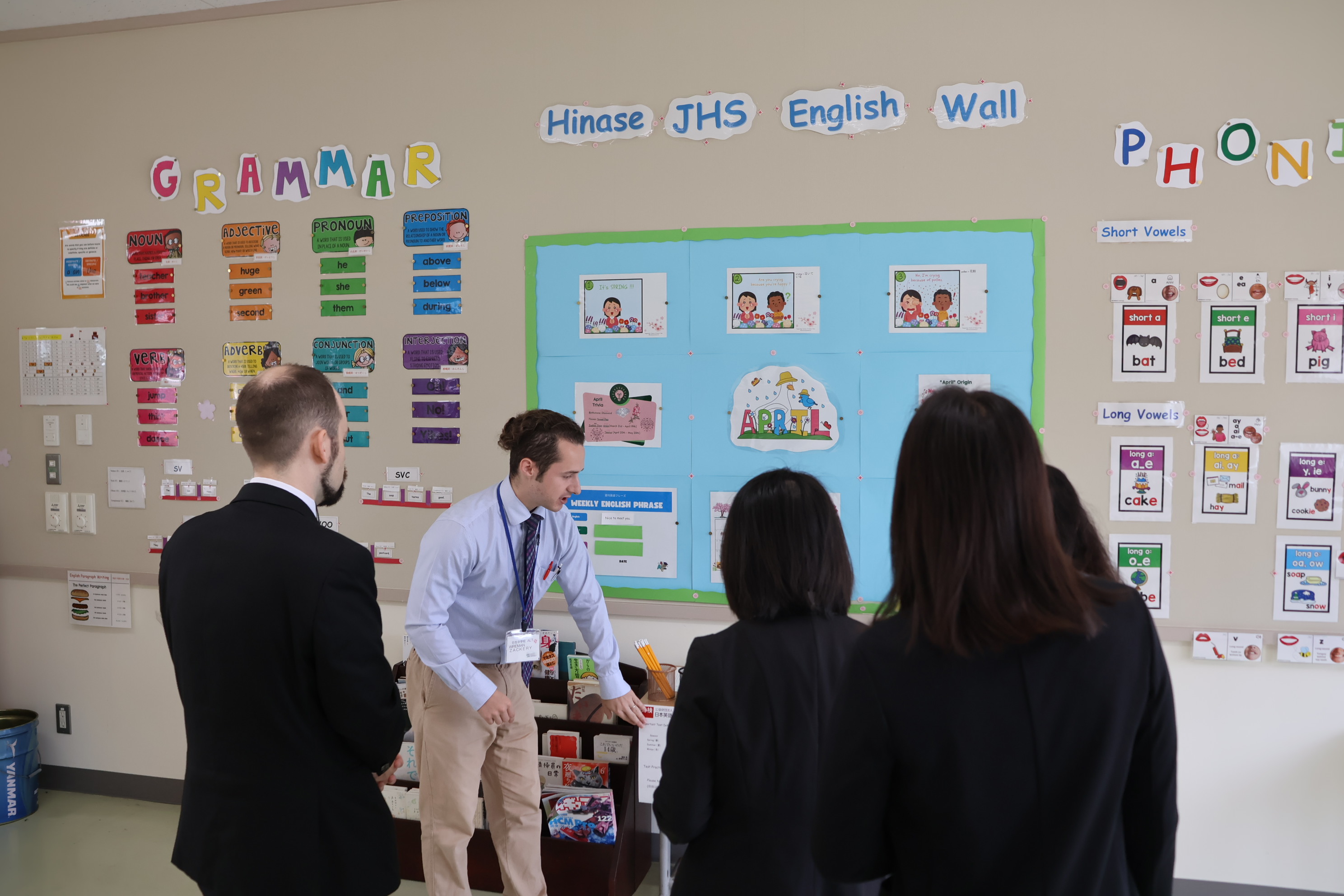
新しいALTの先生が来校されました。5月1日から、子どもたちと多くの時間を過ごす中で、英語に触れ合う機会を増やし、生徒の学習意欲の向上をすすめます。
◎日生で学ぶ 未来へつなげる
1年生も海洋学習スタート(4/24)
漁協さんからお話を聴く学習は5月1日、カキの種付け実習は15日、アマモの回収実習は29、30日です。〈日生中では、長ぐつ必須。〉
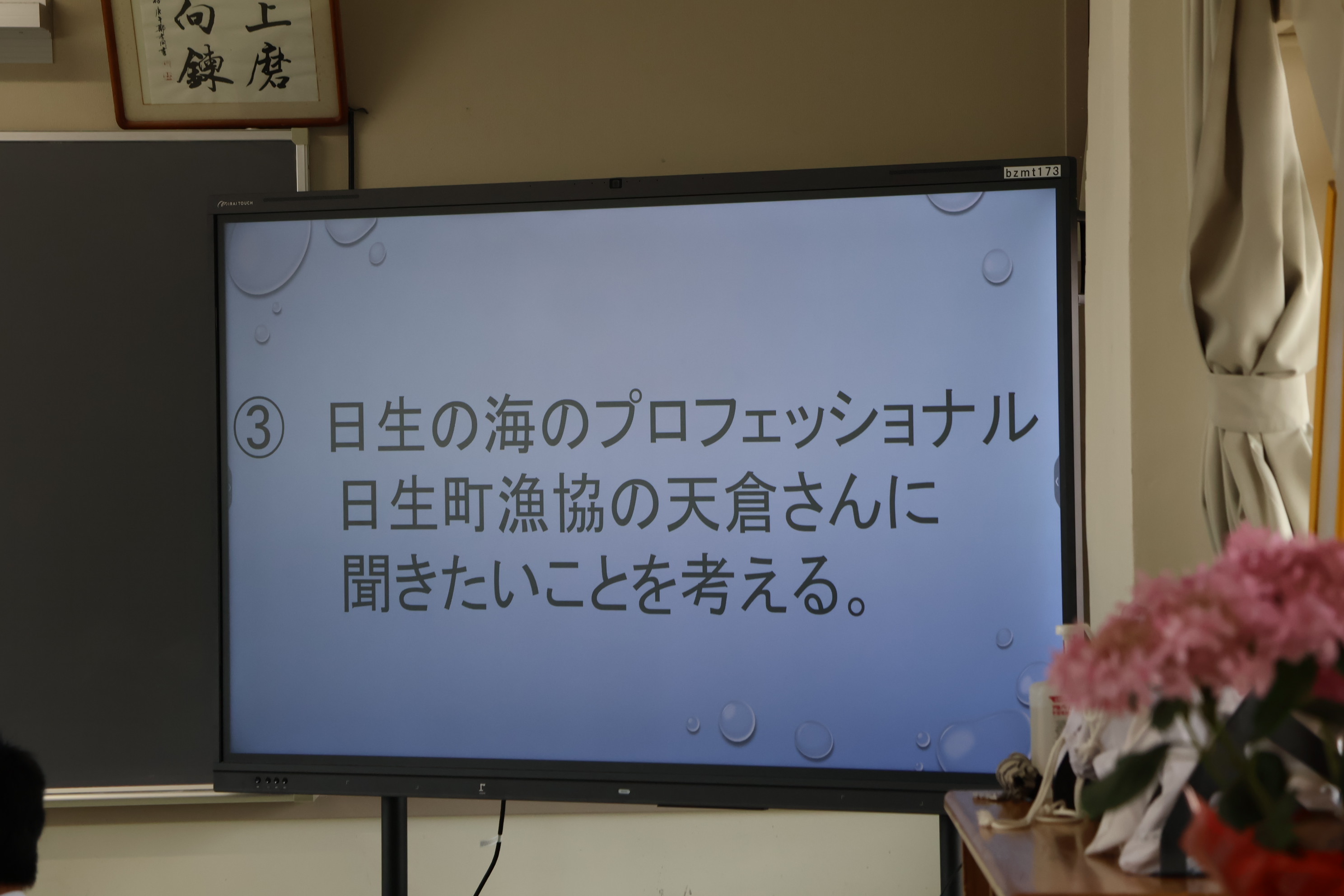



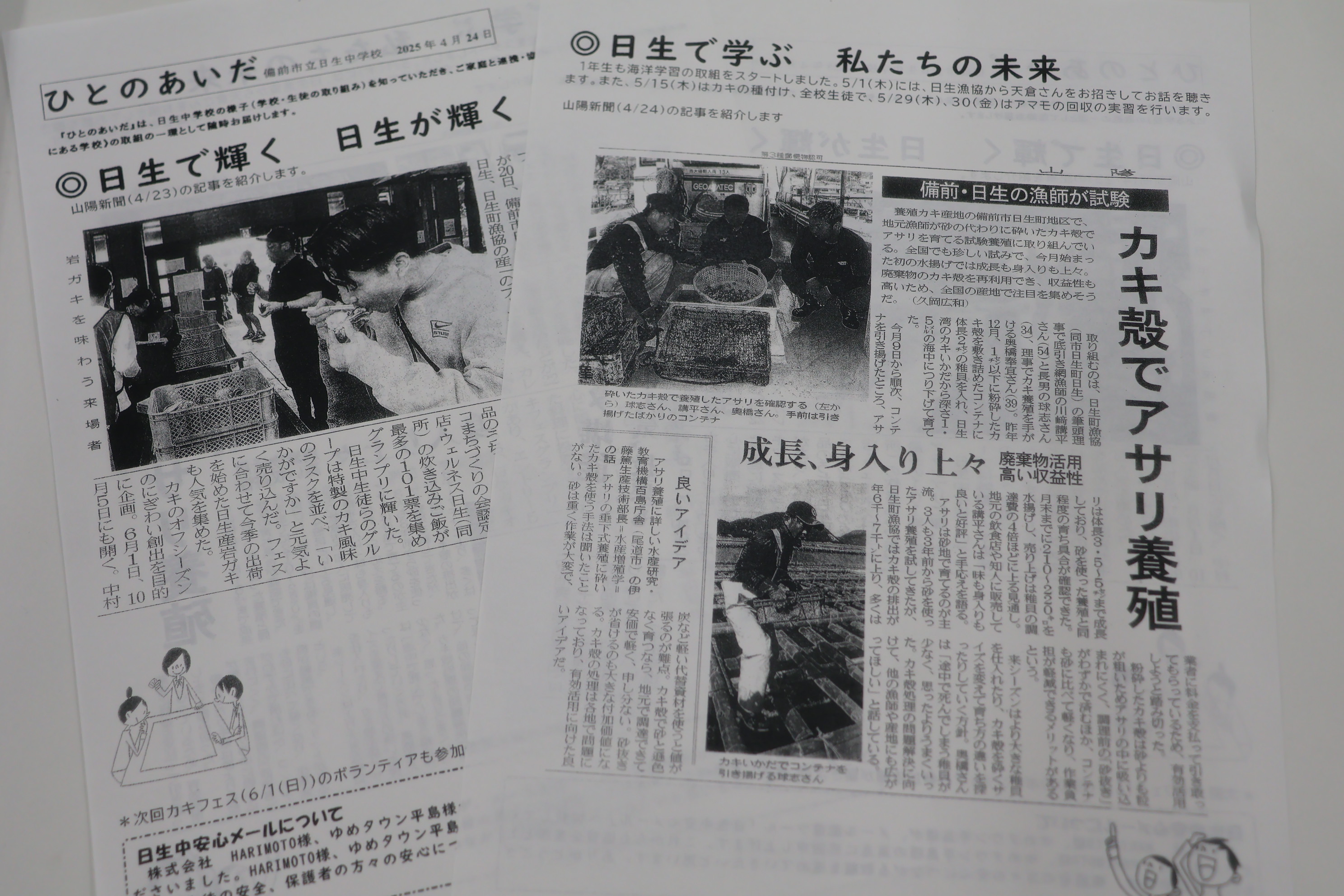

◎正しくみる・行動する(4/23:第1回避難訓練)
備前県民局の中務さんをお招きして、今年も避難訓練を実施しました。また、南海トラフ地震を意識した2次避難訓練も行いました。参照:https://www.nhk.or.jp/shutoken/chiba/articles/101/015/93/(NHK 福田村事件の記事です)








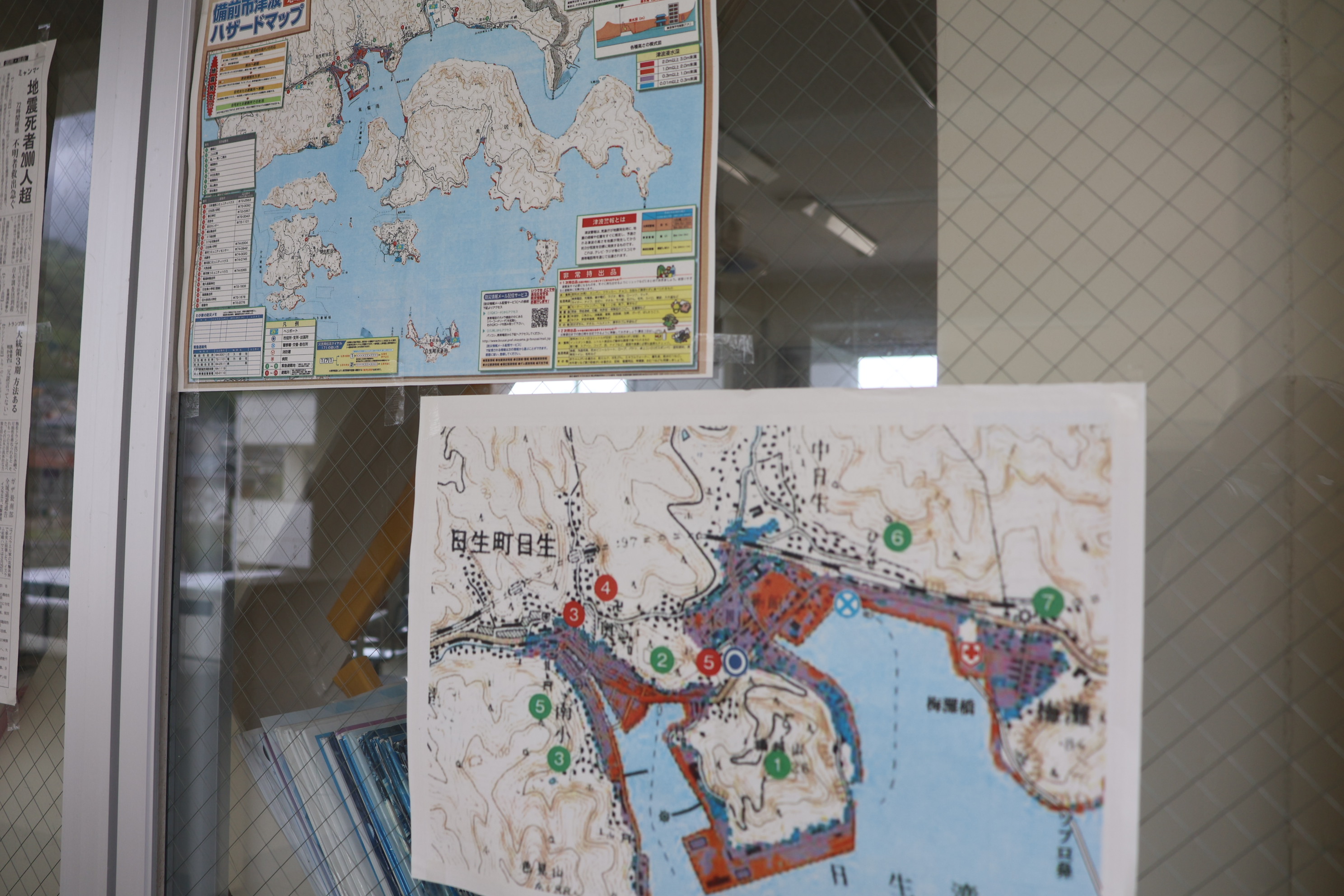
そして、「想像力」 中務さんありがとうございました。
◎エースをねらえ(4/23)
部活動見学・体験は26日(土)まで。





◎学校生活を創る(4/22)




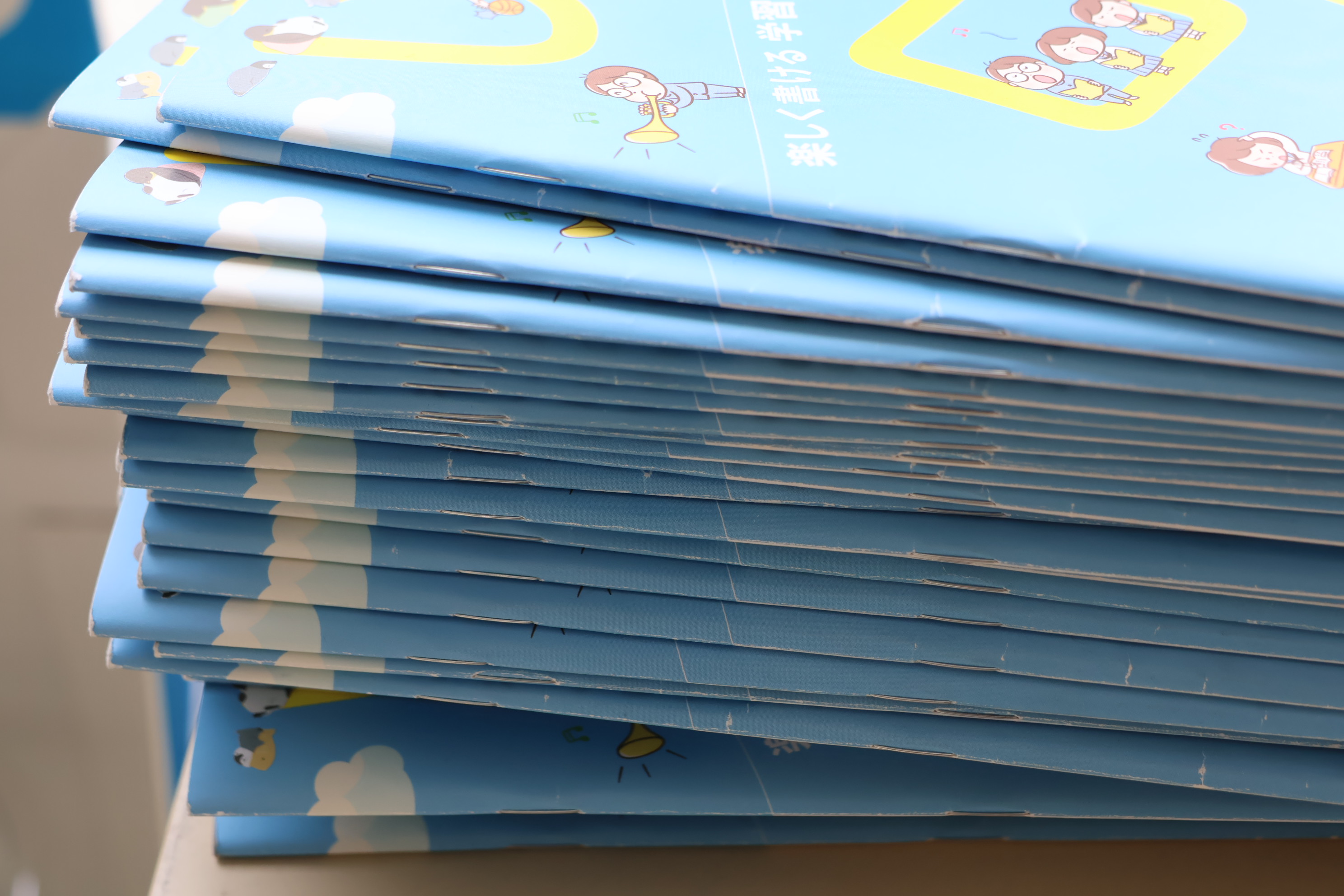

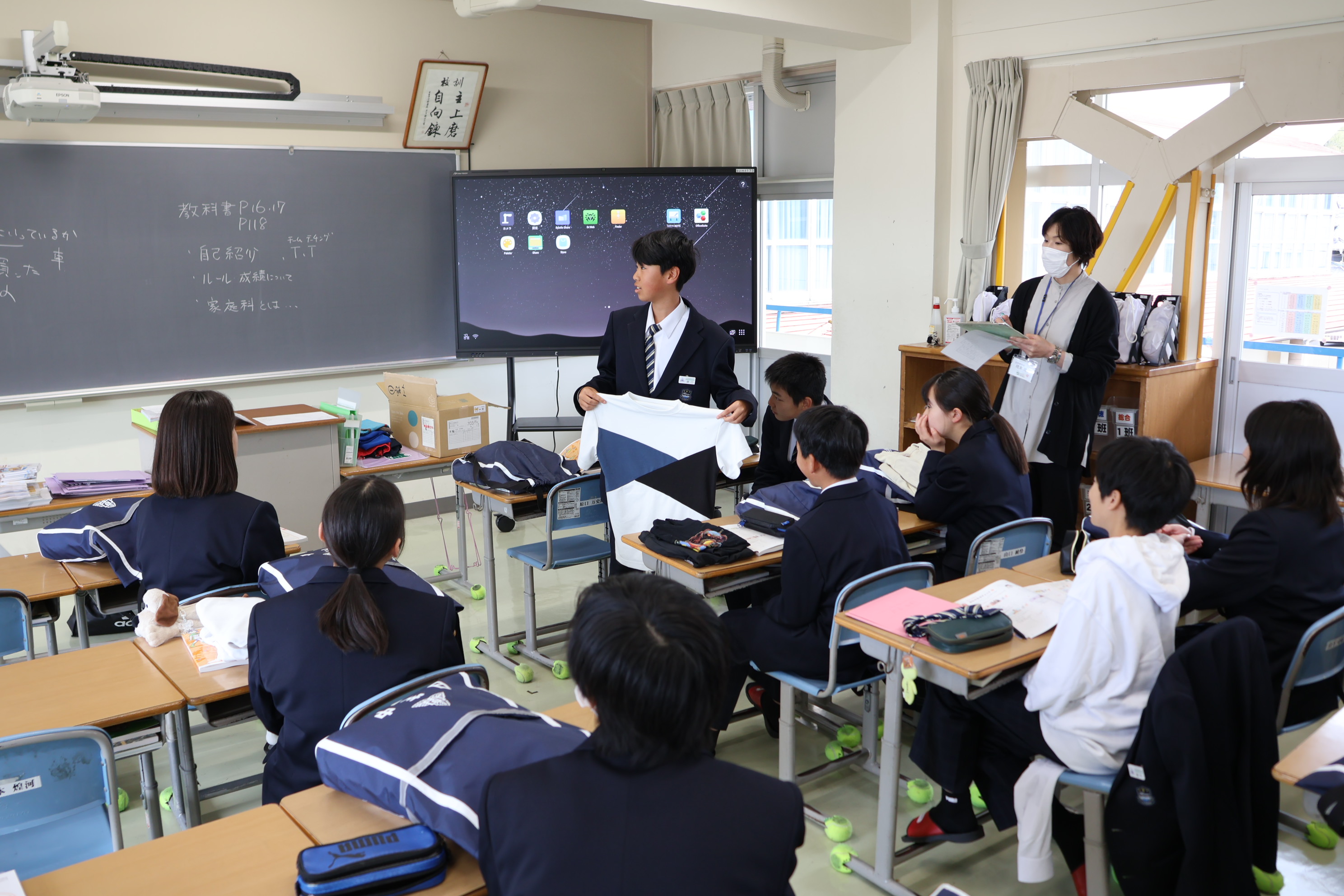


You define beauty yourself‚ society doesn’t define your beauty. Lady GaGa
(美しさは自分で決めるものであり、社会が決めるものではない。)
◎みんなあ カギをしょうで!(4/21:体育委員会より)



忘れていたら?!
◎日生で輝く いま、ここから 未来(4/20)
日生カキフェスに参加してきました。次回(6/1(日))も、多くのボランティアで盛り上げようね。









◎ワタシノブカツ ワタシノジカン (4/18:吹奏楽部中庭コンサート)
1年生の部活動入部届は30日(木)までです。

◎自分がつくる、交通安全で自分を守る。
多くの人に支えられて(4/18)
備前警察署からエリアテーチャーをお招きして、1年生交通安全教室を開催しました。


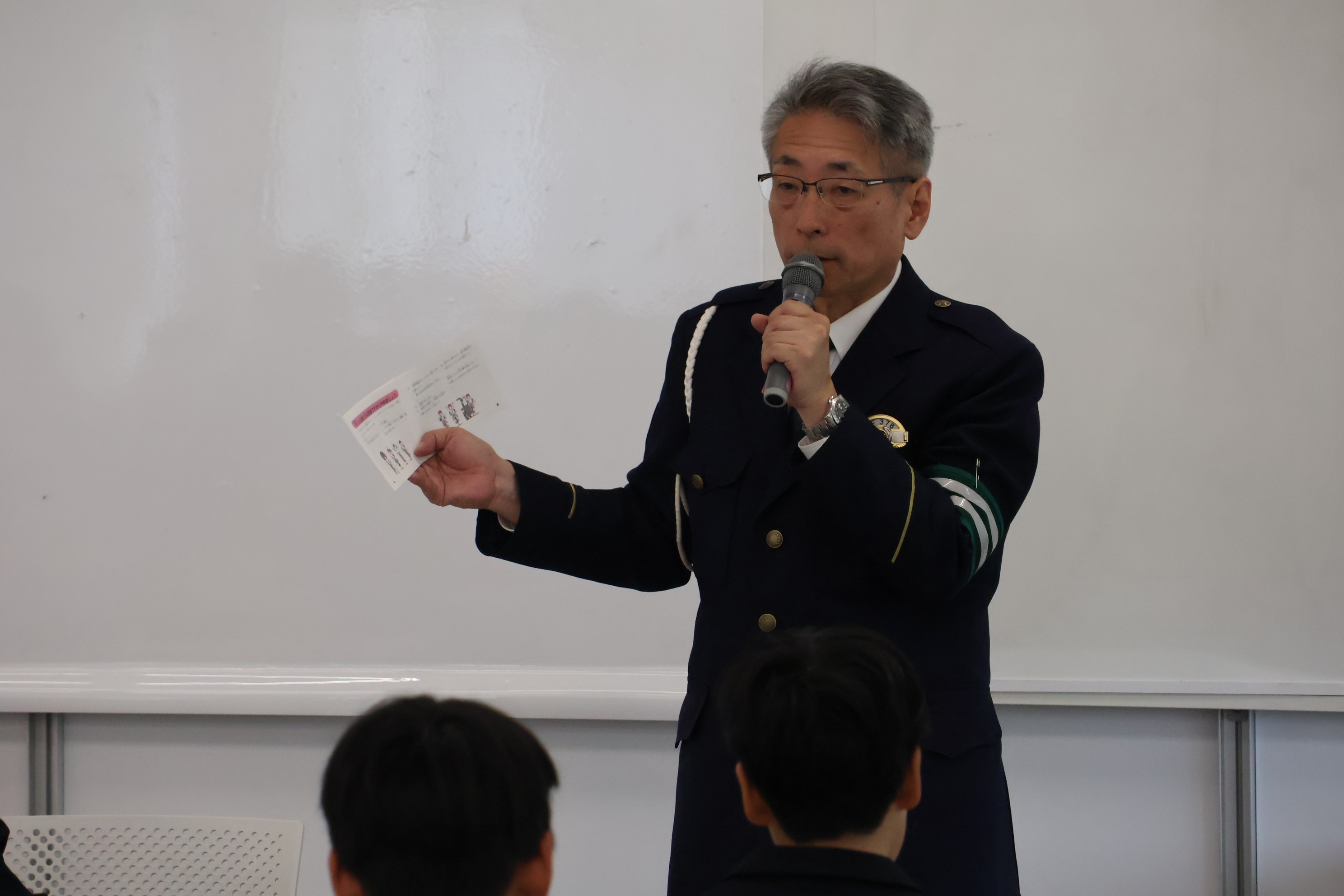
◎日生中LEGACY(4/18)



◎わたしたちの活動 新しい風は日生から
PTA幹事会・委員総会開催(4/17)

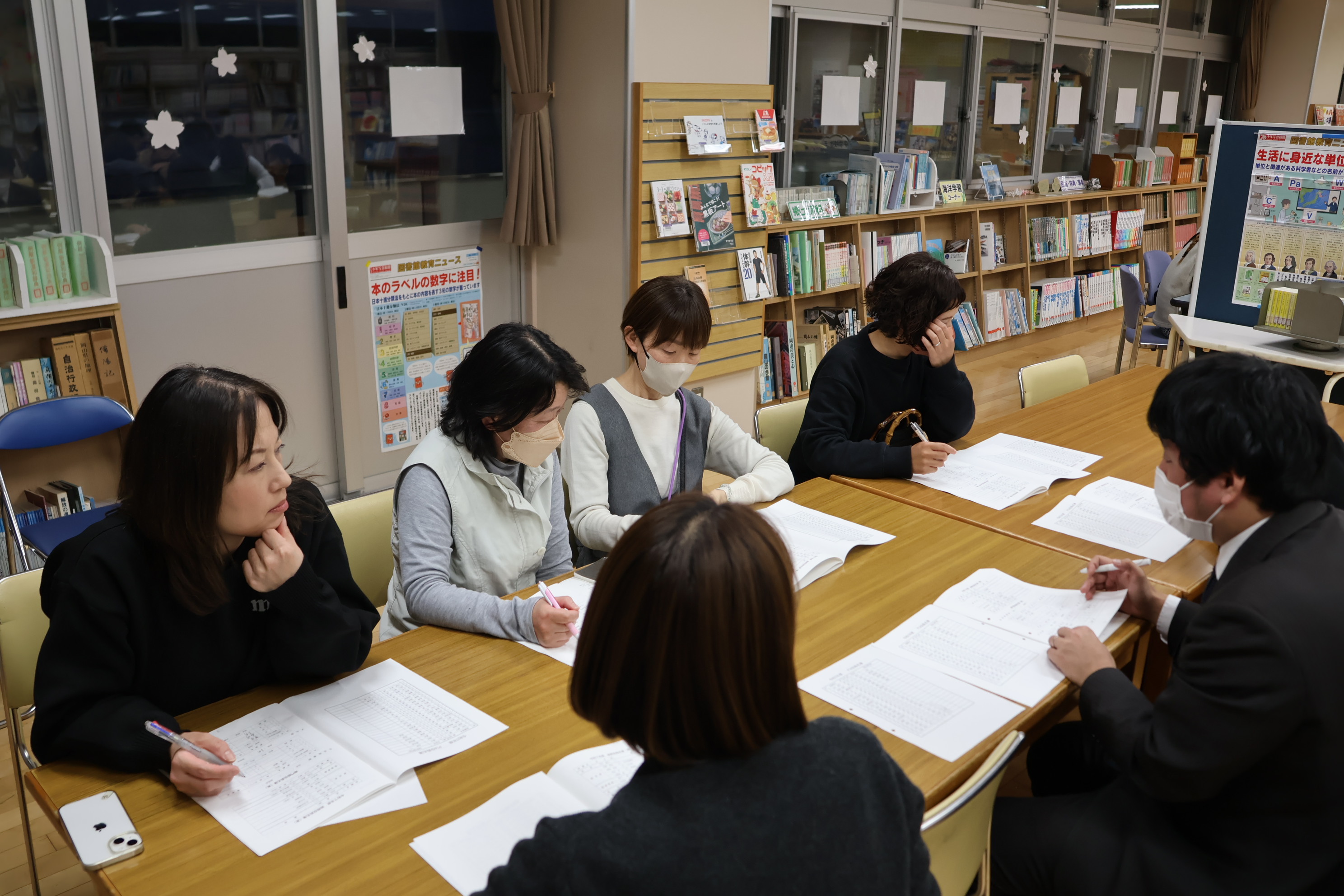

◎全国、県の学力・学習状況調査(4/17)
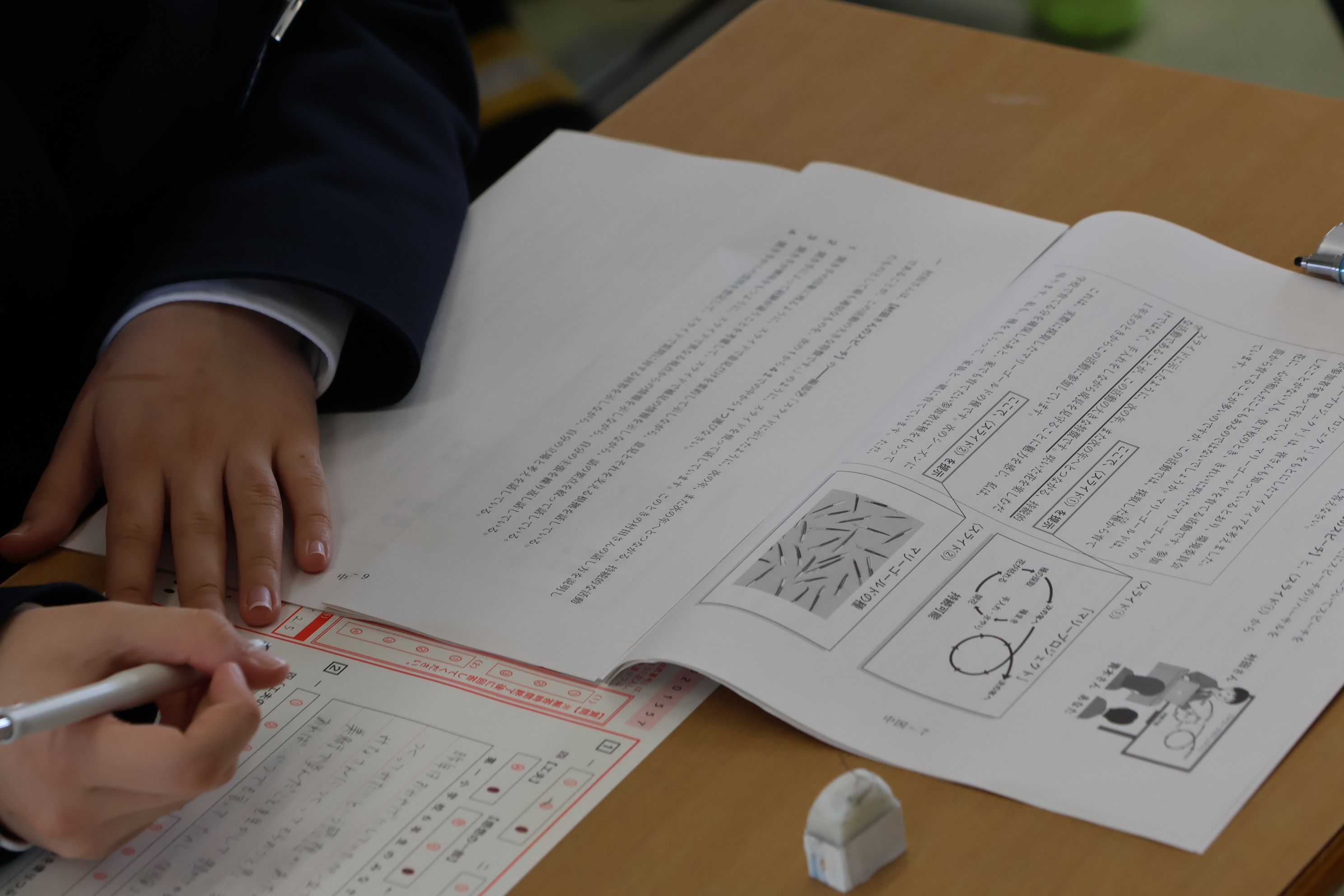
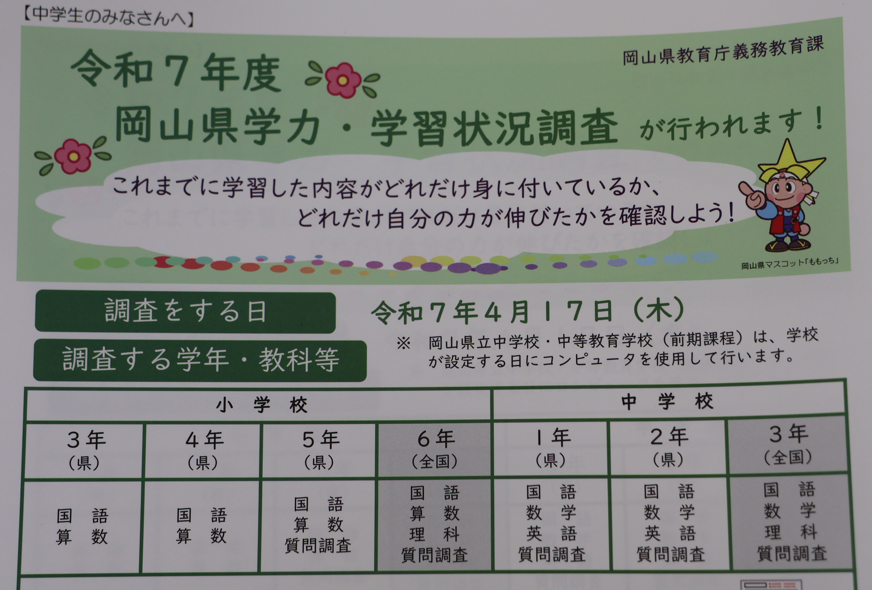
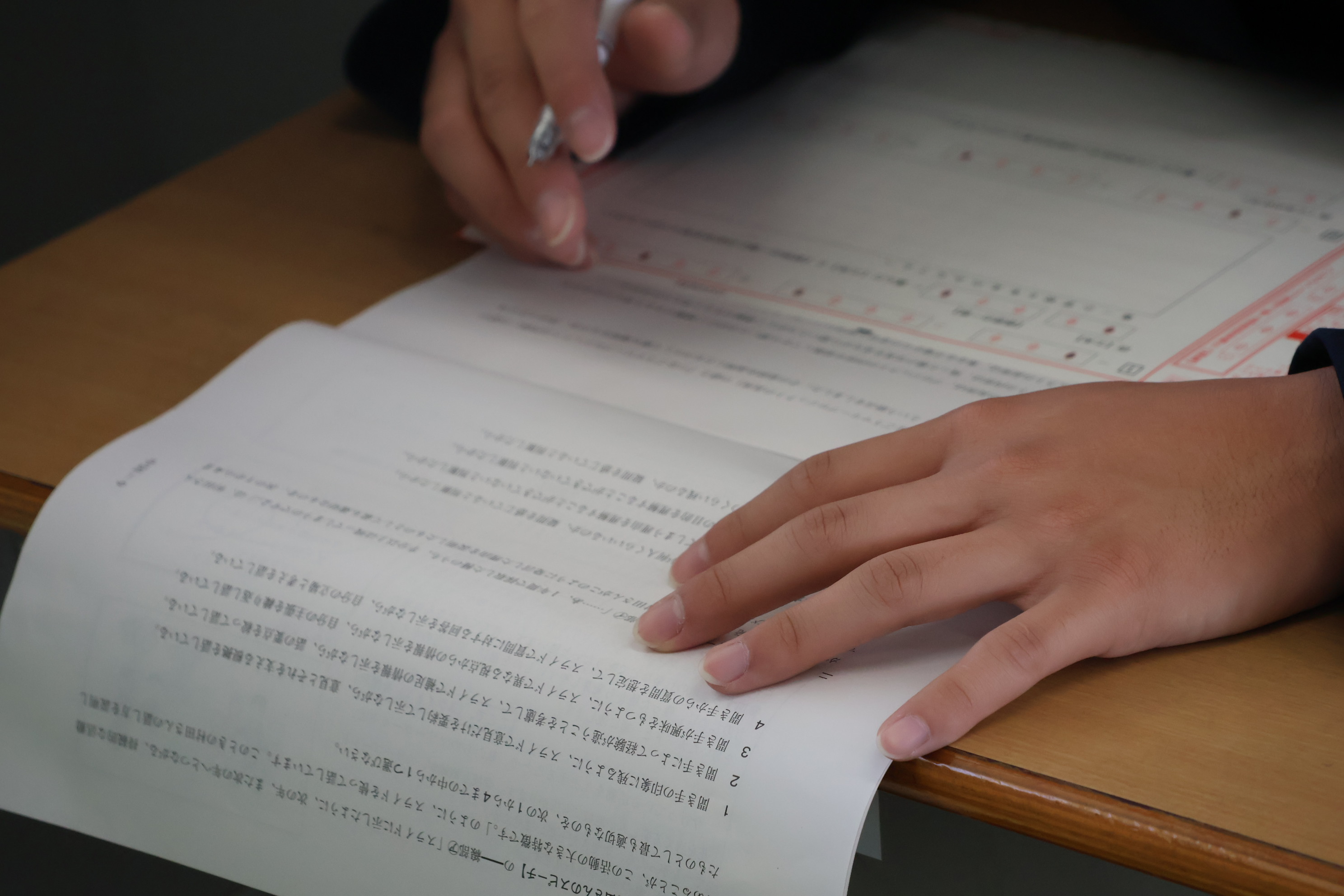
◎アクティブな授業 追及・深まる学びを進めています(4/16)



◎責任と誇りを胸に。がんばり合う仲間であり。(4/16)
仲間のために、クラスのために、自分のために、確認し合う生徒会専門委員会認証式。
そして、自分の目標に向けて、〈毎日の生活の中での「取り組み・行動」〉を積み重ねていくことが、目標達成・夢の実現につながっていく。



◎私たちは輝くために(4/15)
星輝祭(6.7体育の部)に向けてブロック会開催。
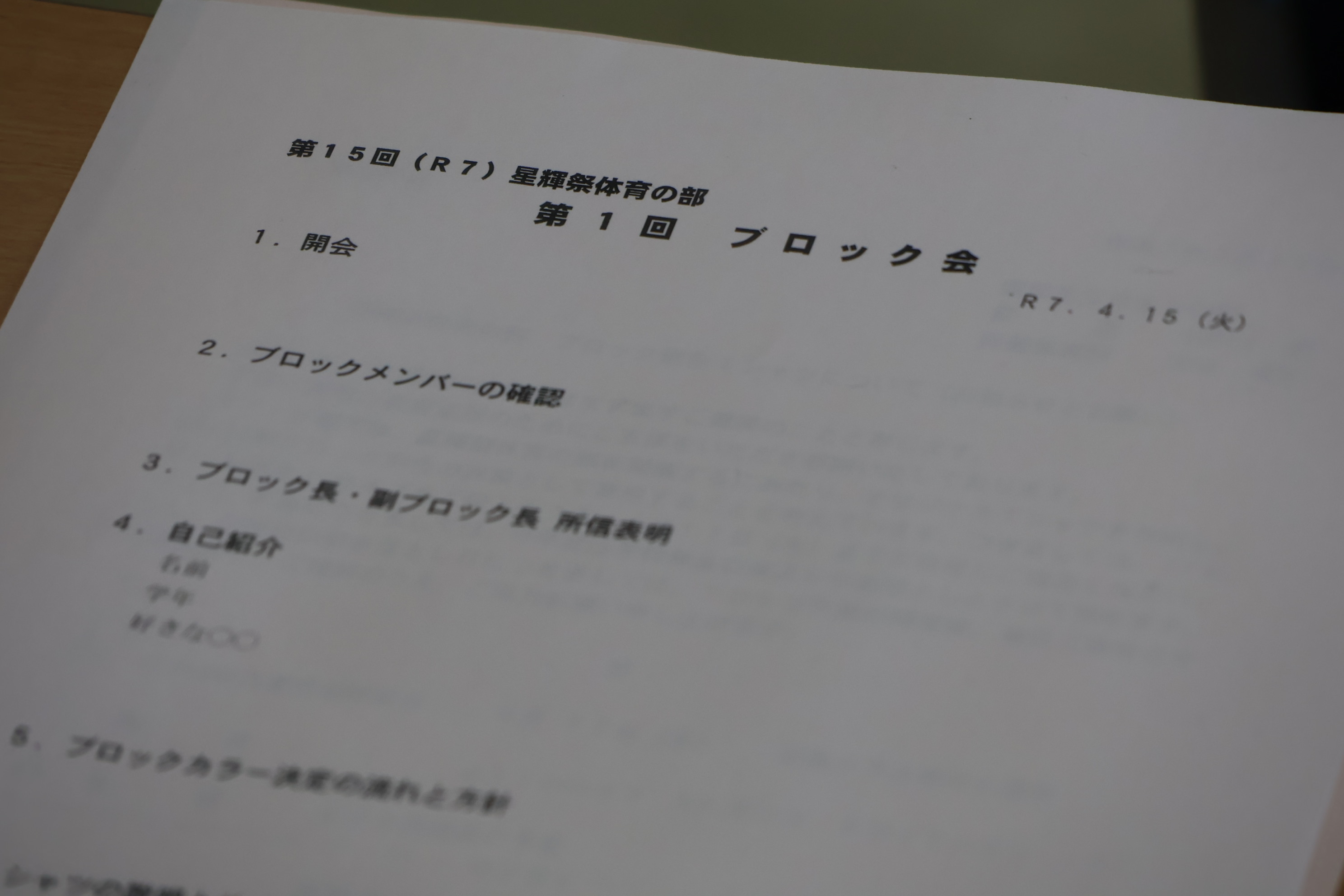
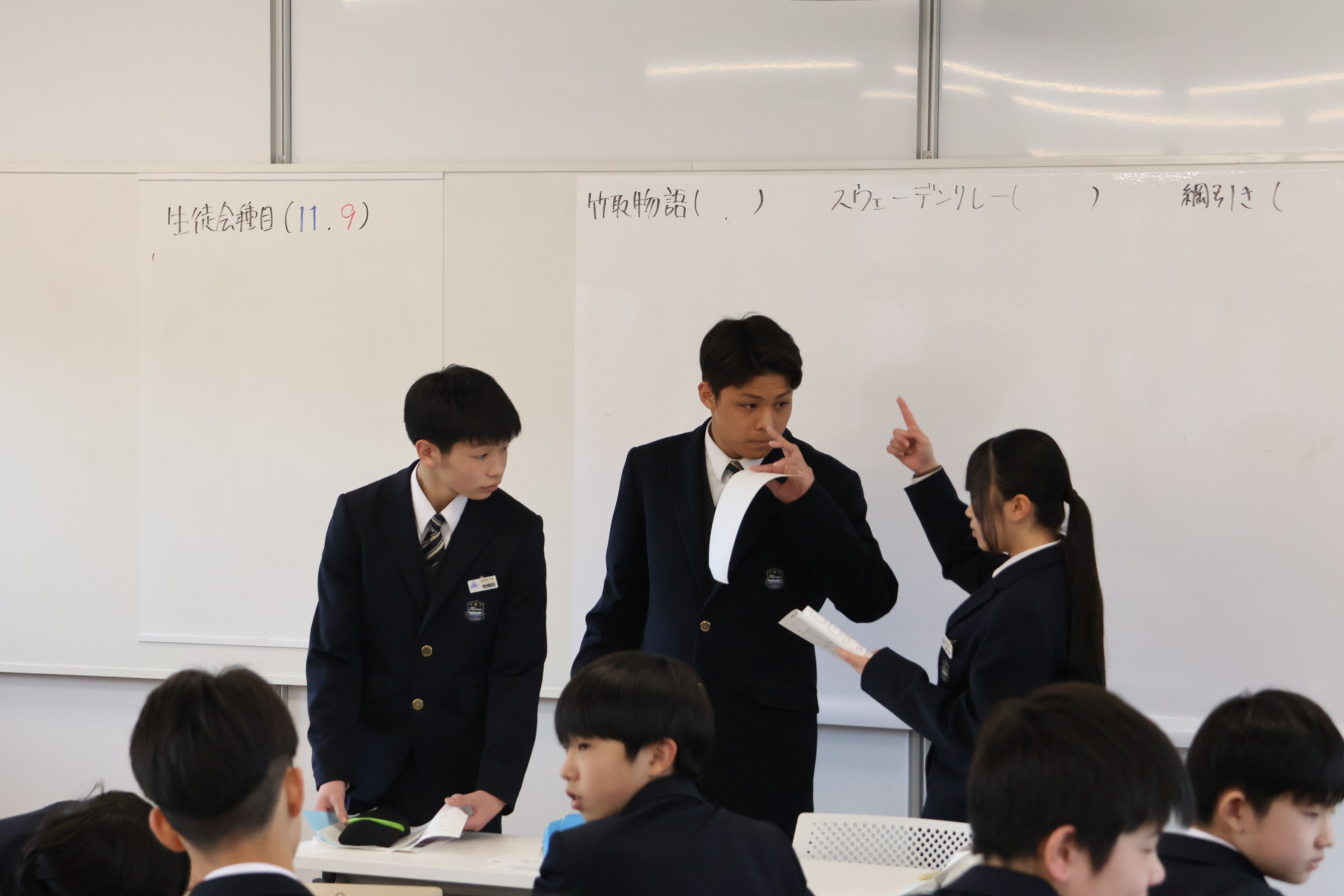
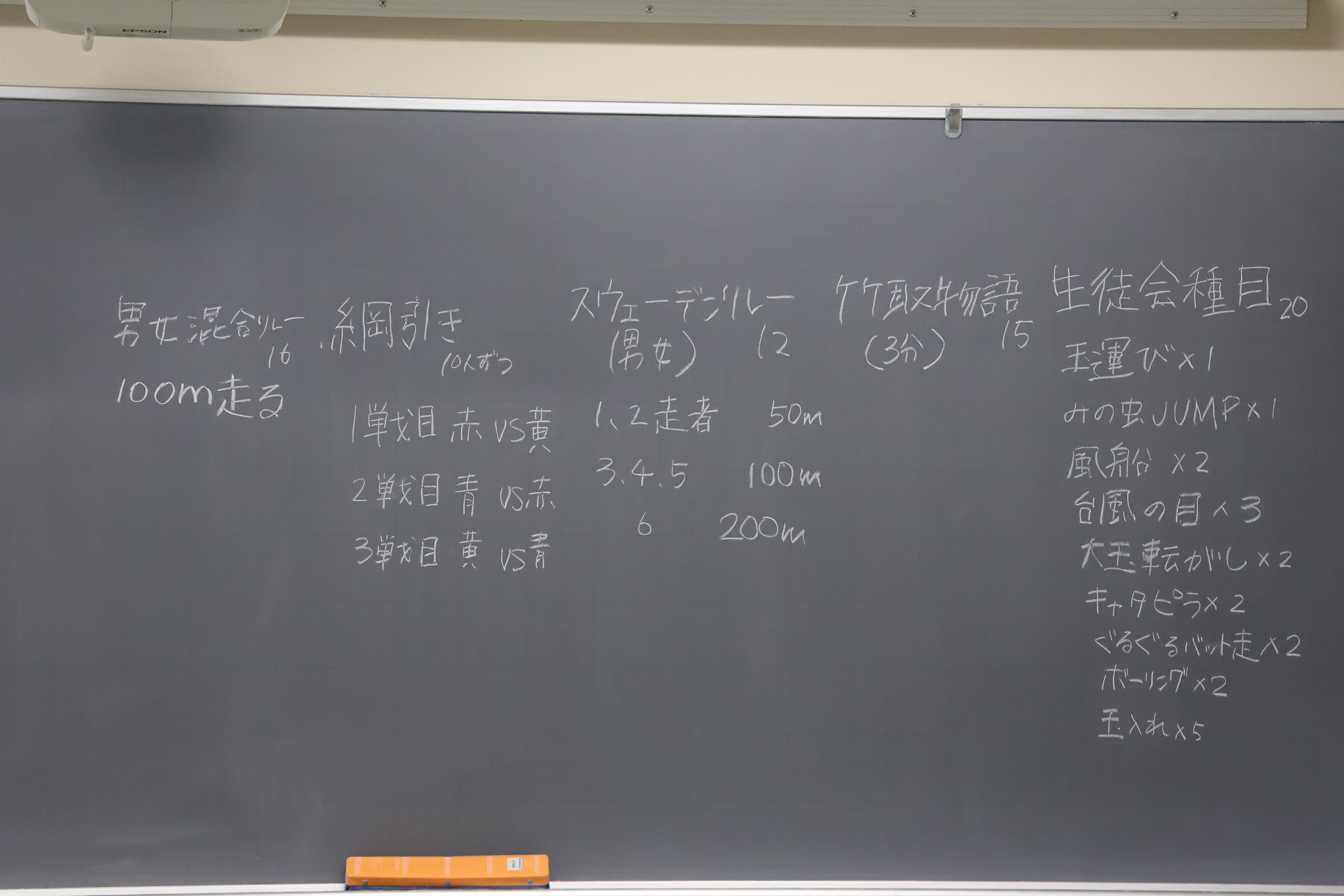
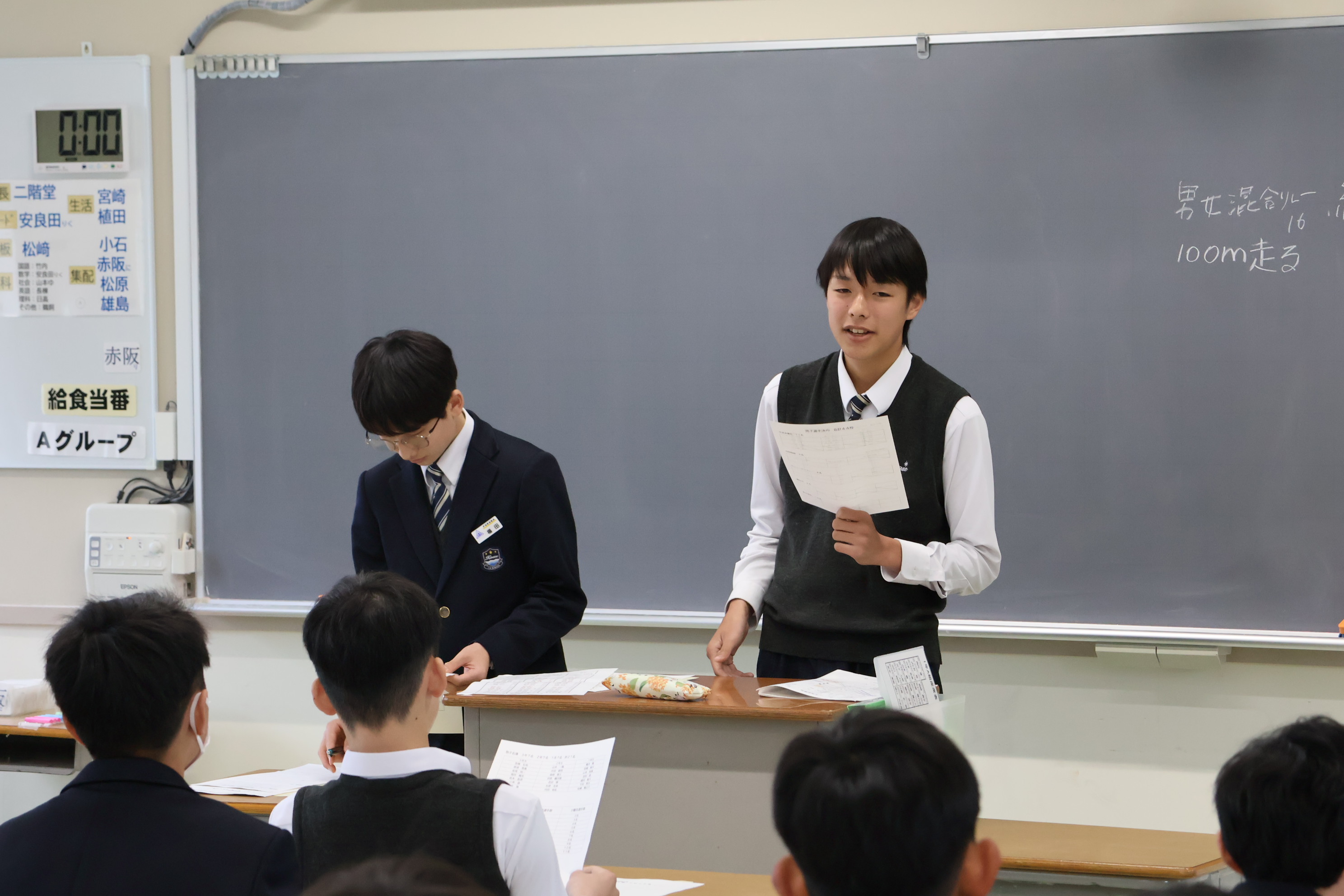





Do not judge me by my successes‚ judge me by how many times I fell down and got back up again. Nelson Mandela
(成功で判断しないで、何回転んで何回起き上がったかで判断してください。)
◎自分を開き、仲間を知る授業
1年生の家庭科では、生徒一人ひとりが宿題として、自分の私服をひとつ持って来てました。授業で学んだ「
TPO」をもとに自分の衣服について発表し、互いに聴き合いました。さらに、これが自己紹介も兼ており、個性豊かな、お互いを分かり合う楽しい授業となりました。

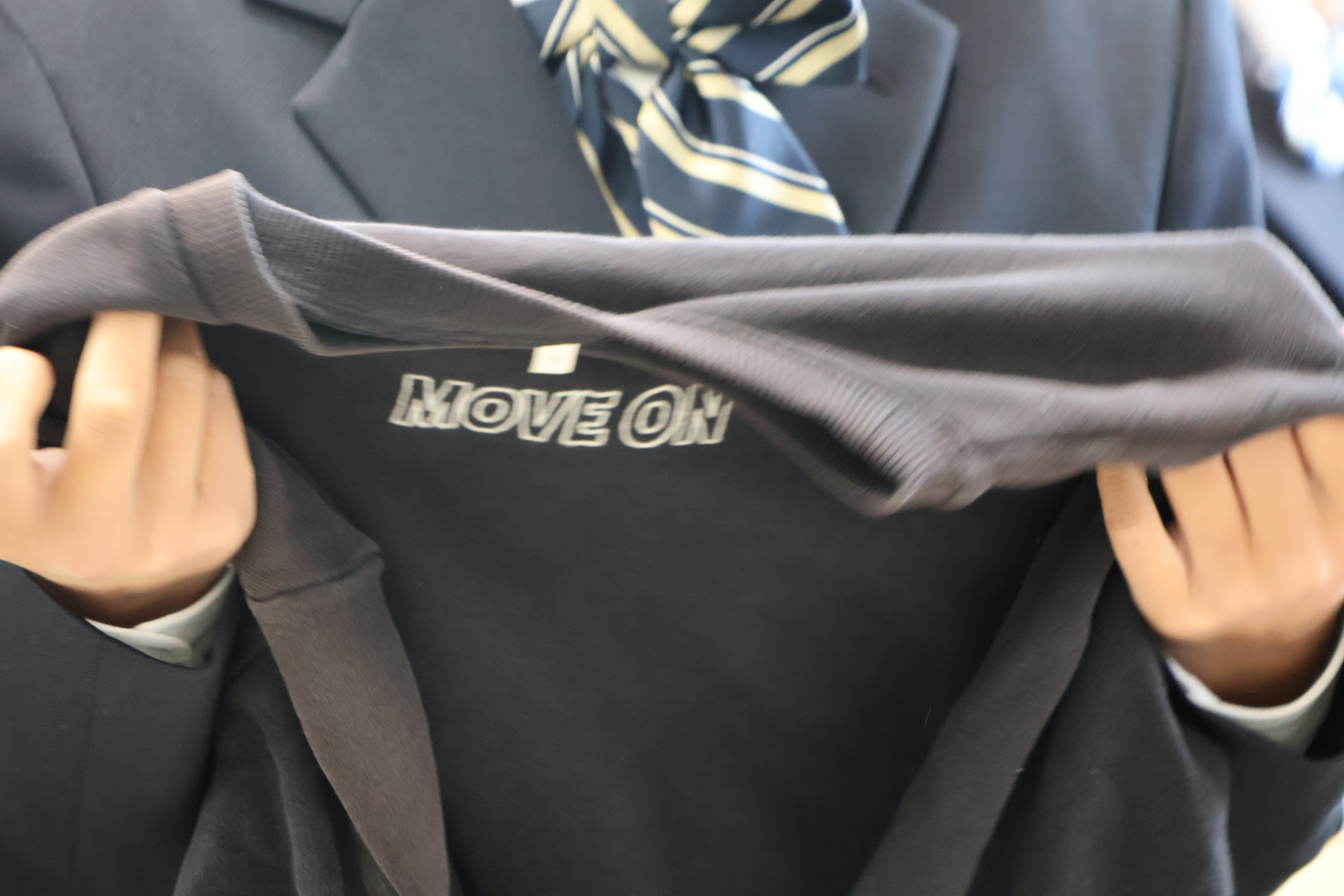

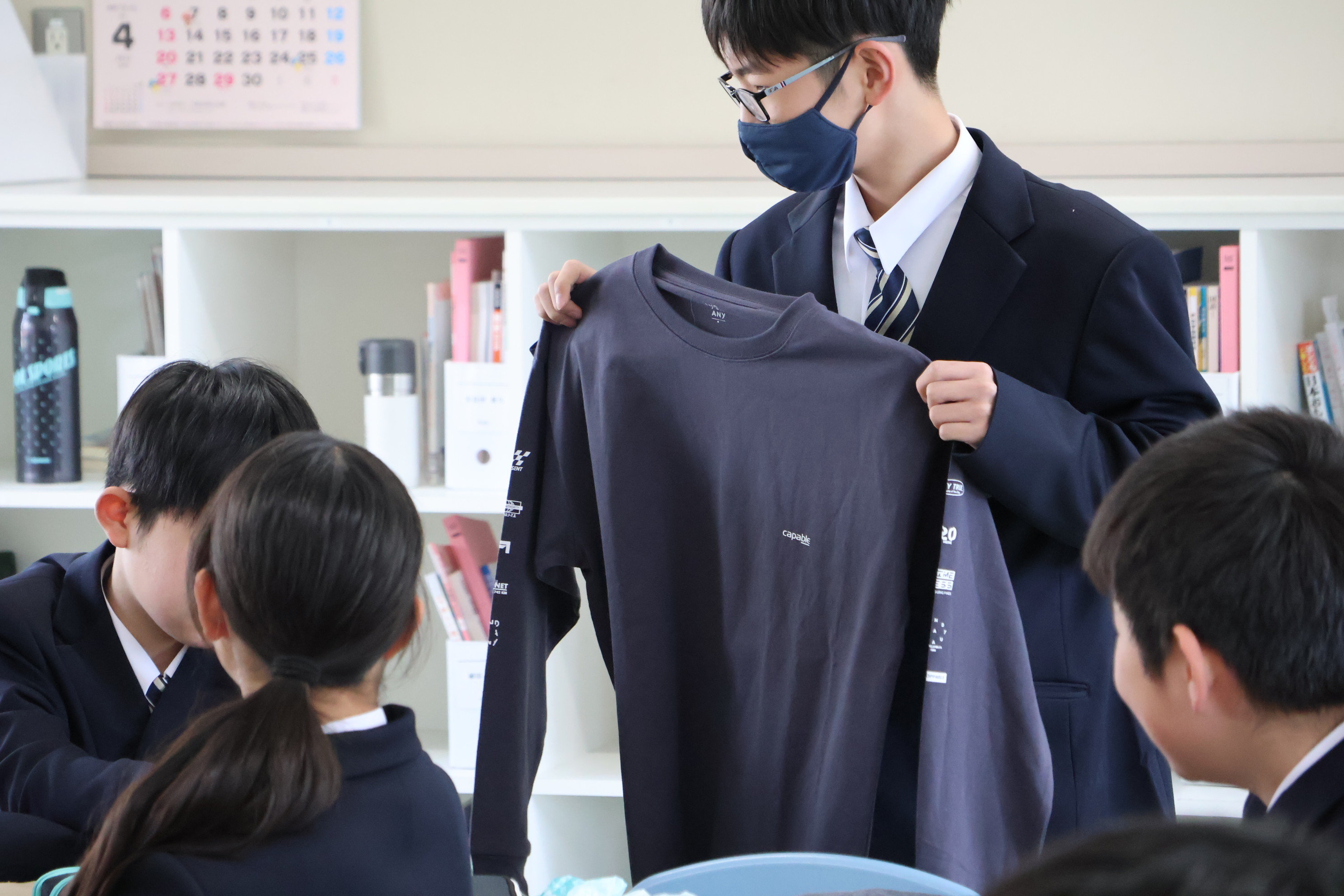
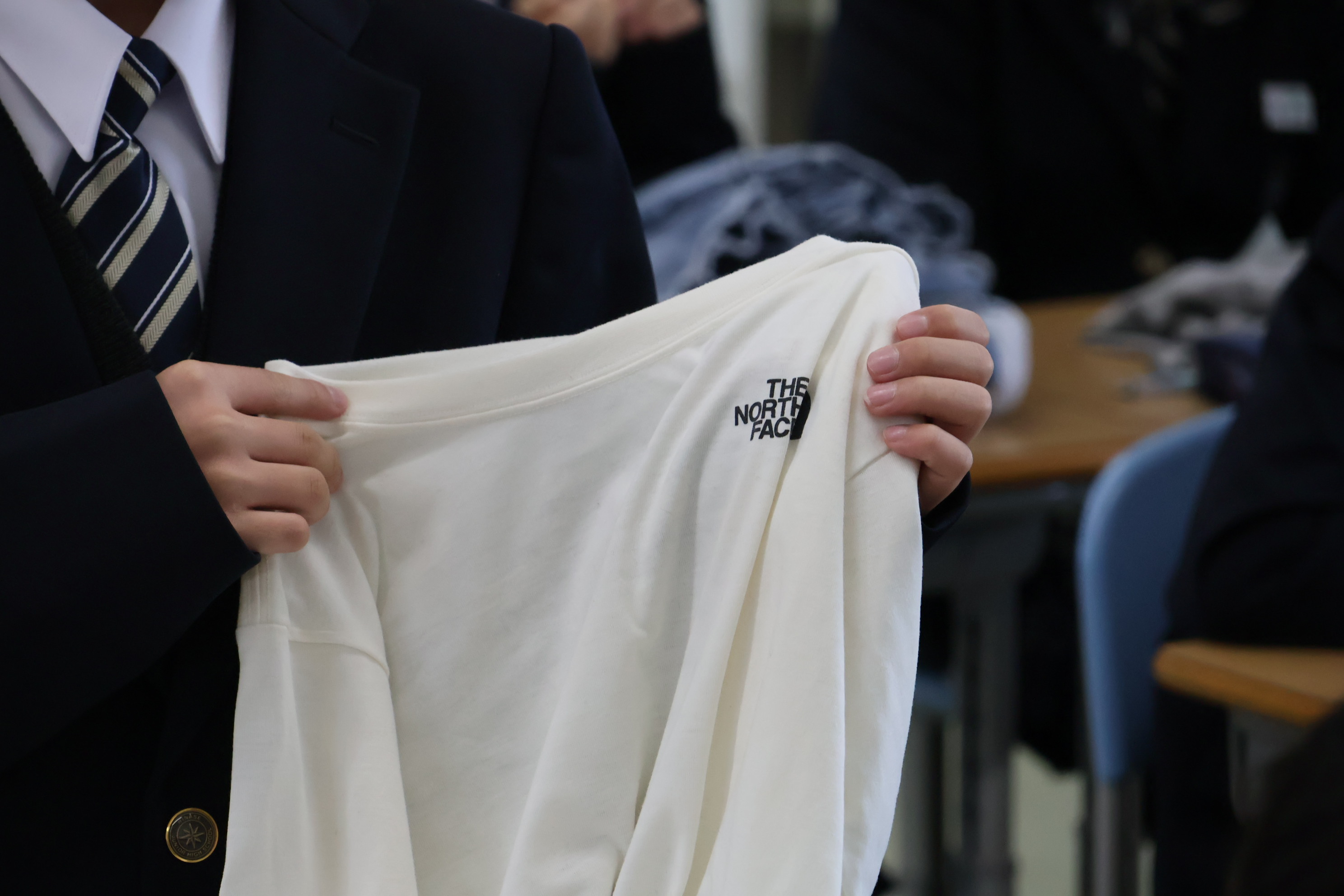

◎新年度も、多くの人に支えられて(4/15)
14日、調理場から、北川先生が来校されました。今年も「食育」を大切に進めていきます。
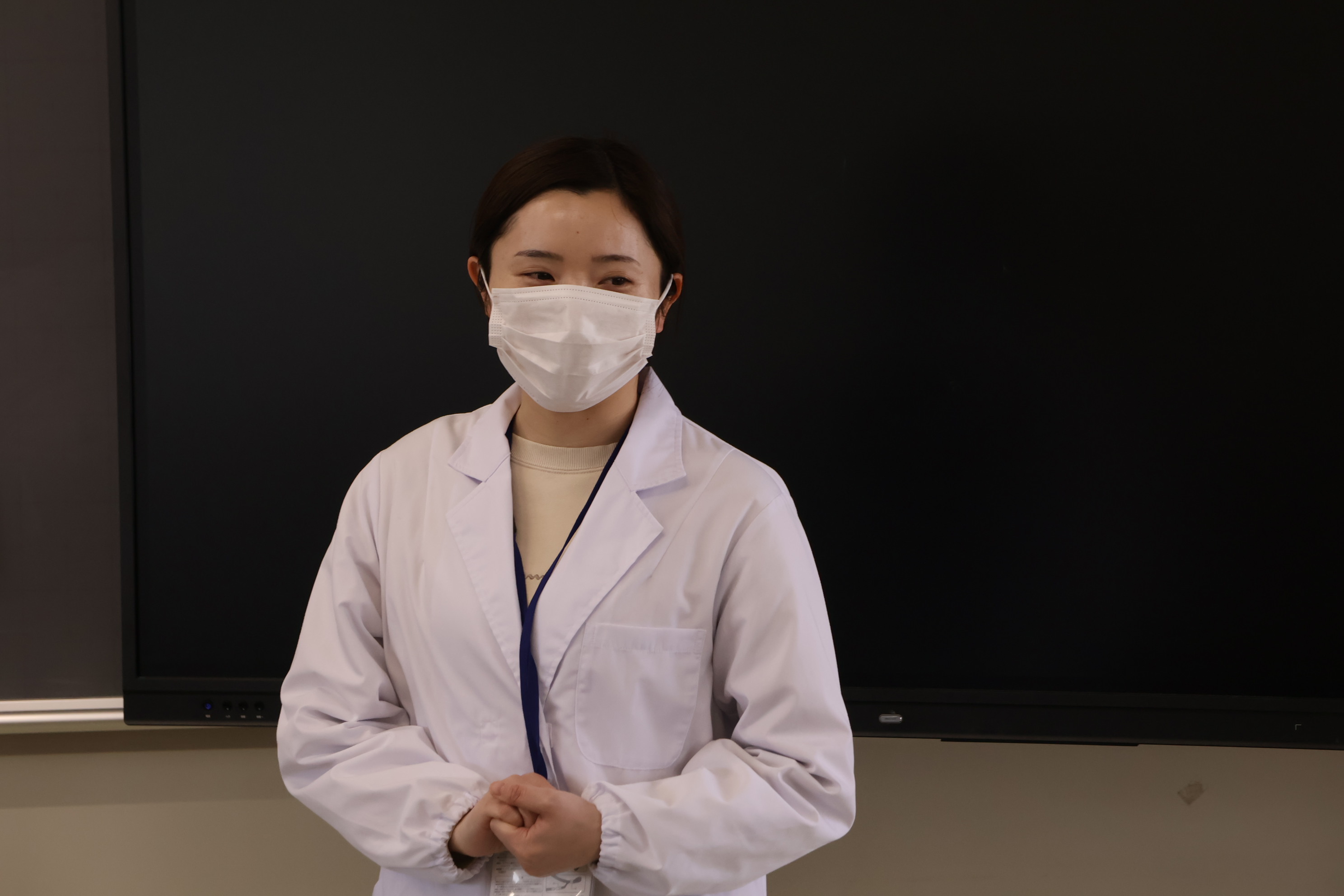


◎生活を創るクラス(4/14)


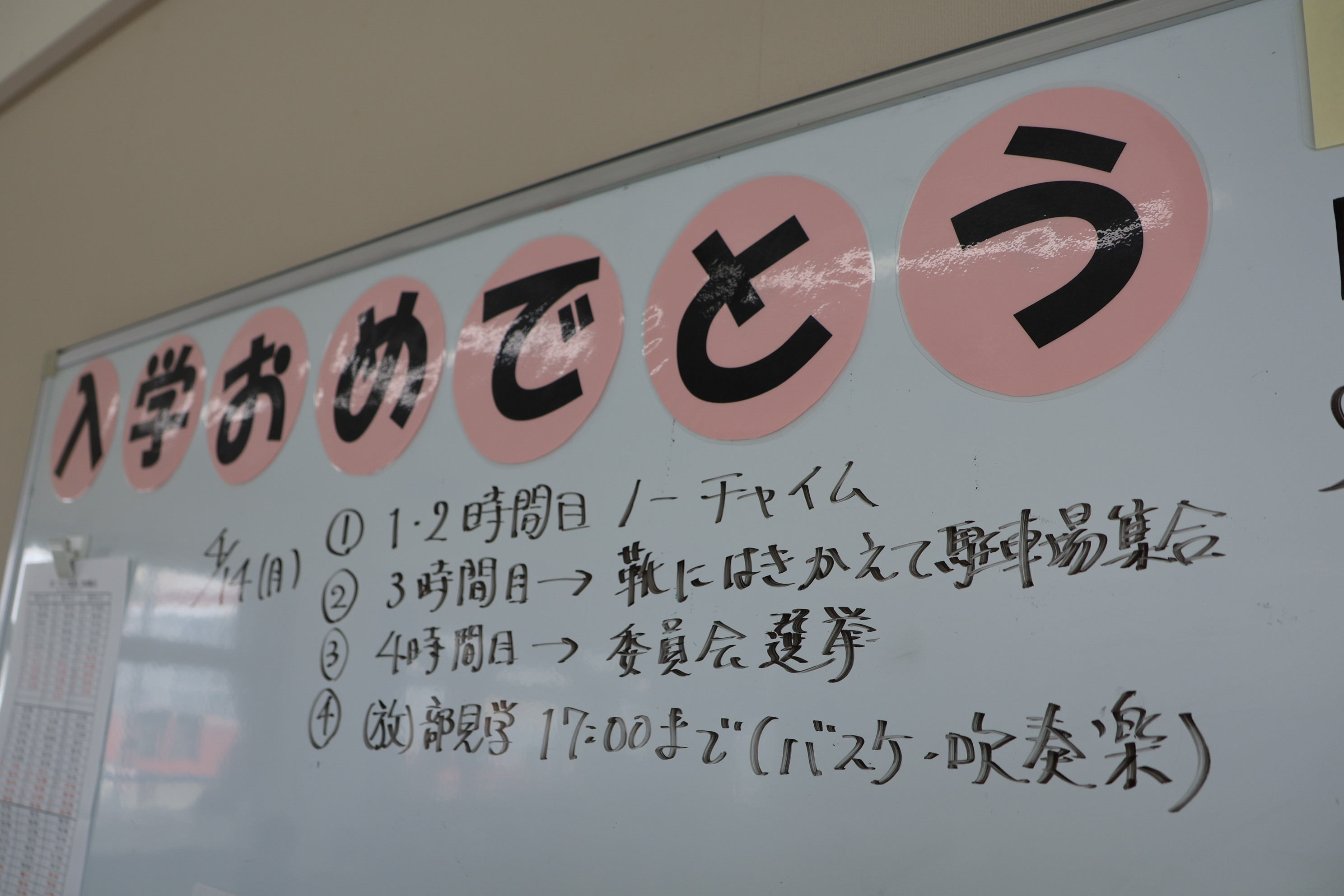






◎もくもく もくもく ひな中LEGACY(4/11)
*レガシーとは、「遺産」や「伝統」などの意味があり、転じて「次の時代に受け継がれていくもの」を指します。



◎春は過ぎゆく(4/11)


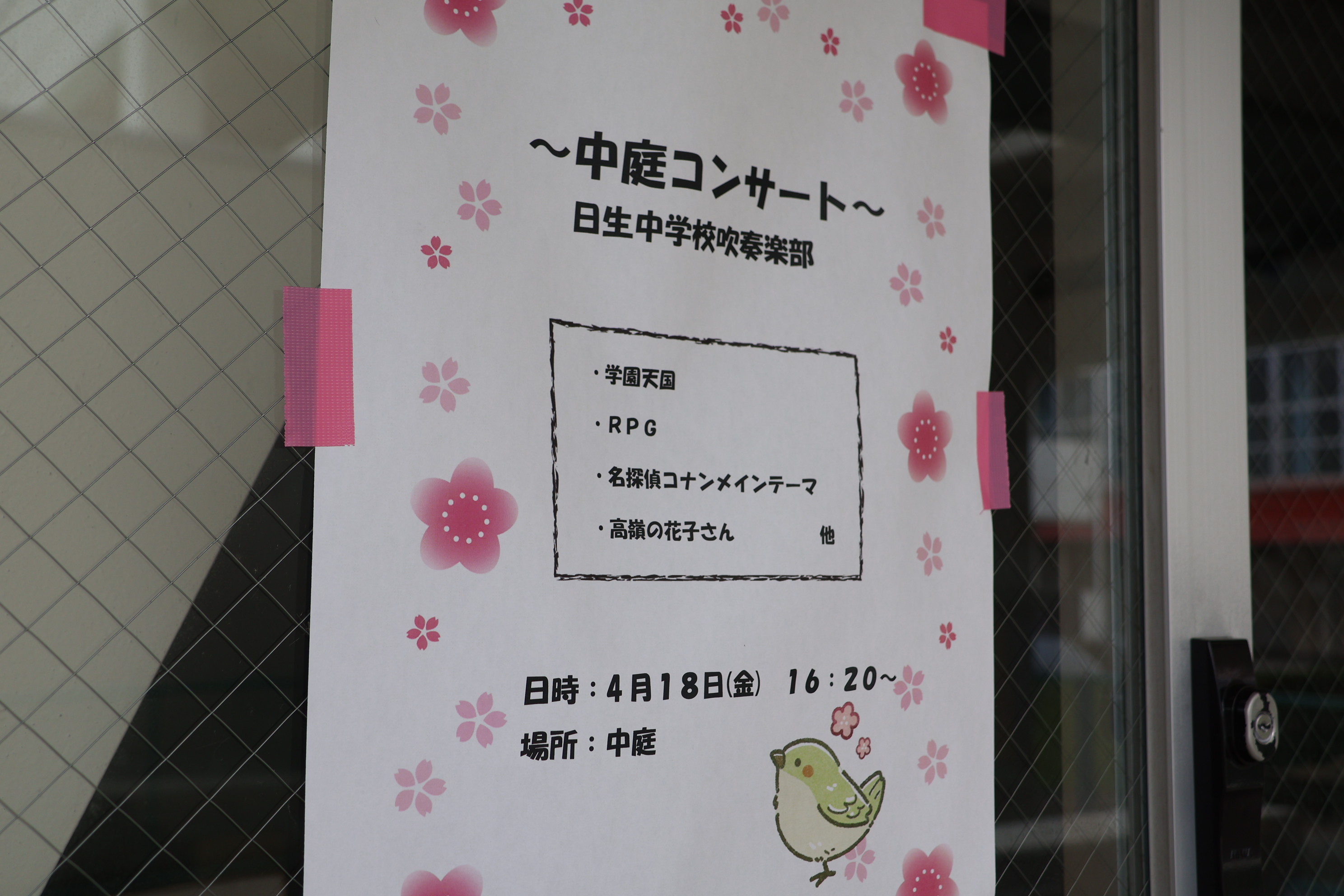
I travel not to go anywhere‚ but to go. I travel for travel's sake. The great affair is to move.
Robert Louis Stevenson
(私はどこへ行くでもなく、行くために旅をする。旅のために旅をするのです。大いなる悩みは移動すること。)
◎ひな中の風(4/10)



◎日生で輝く 日生が輝く日々を(410:入学式)





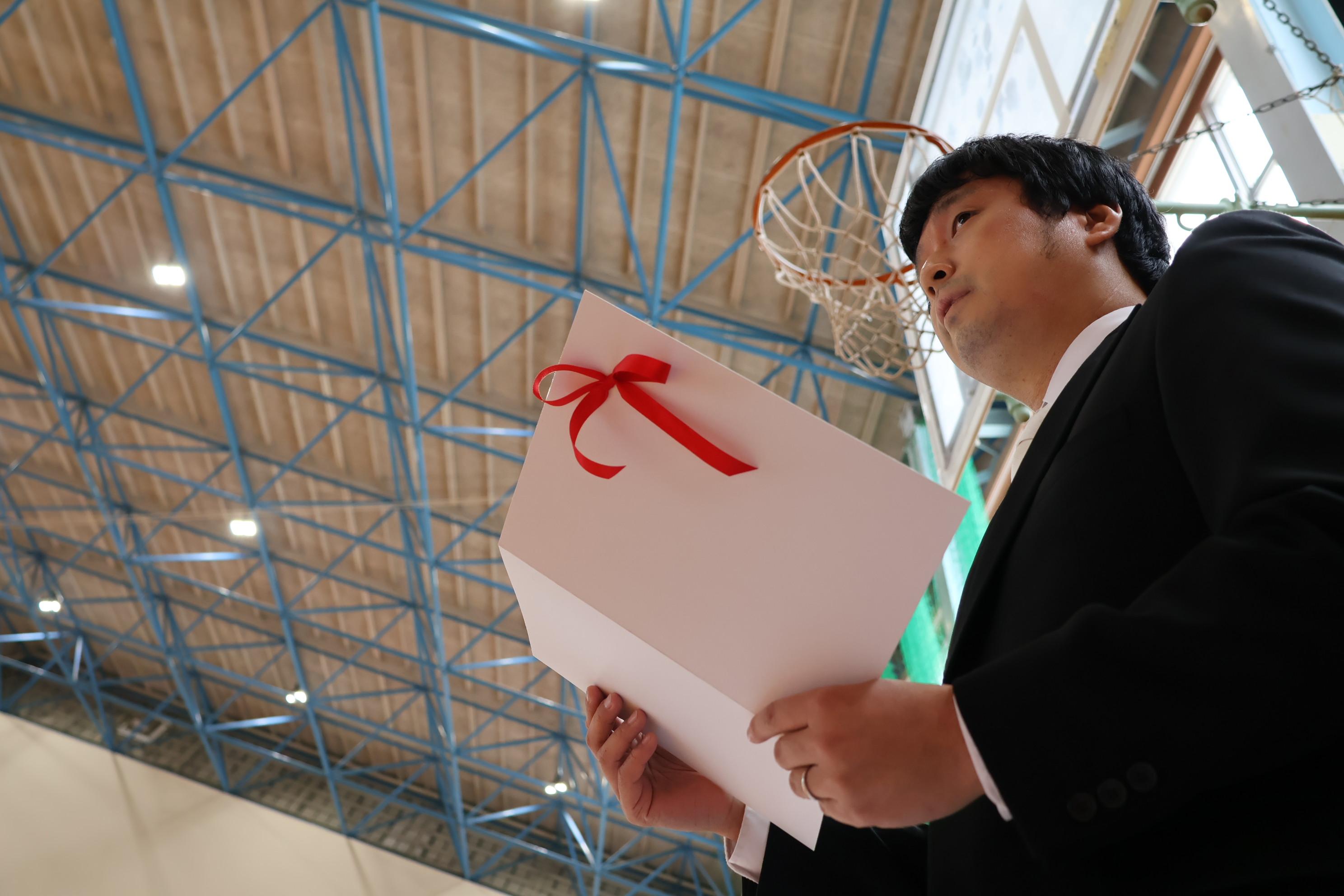









◎出会いに心をこめて(4/9:明日は入学式)


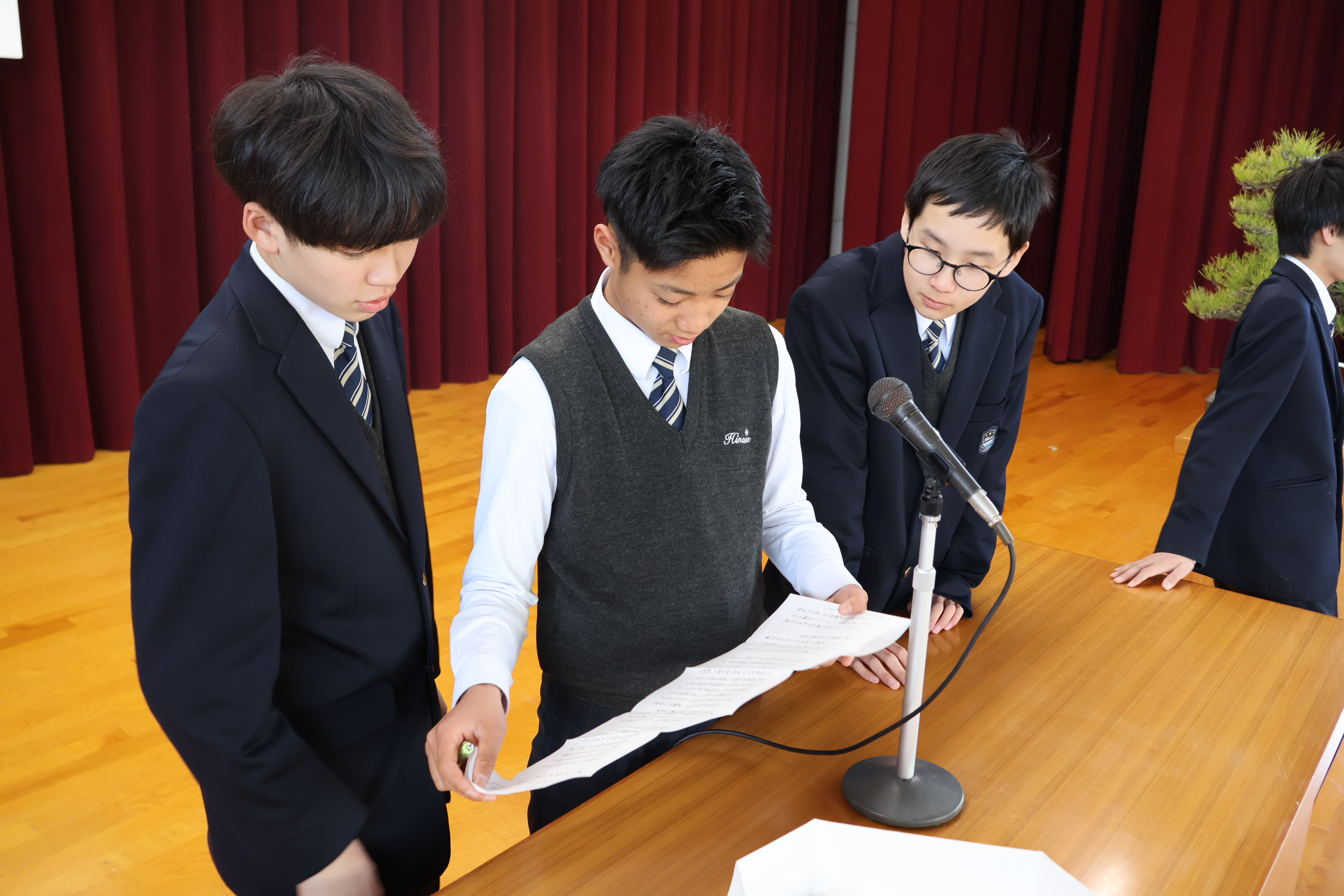


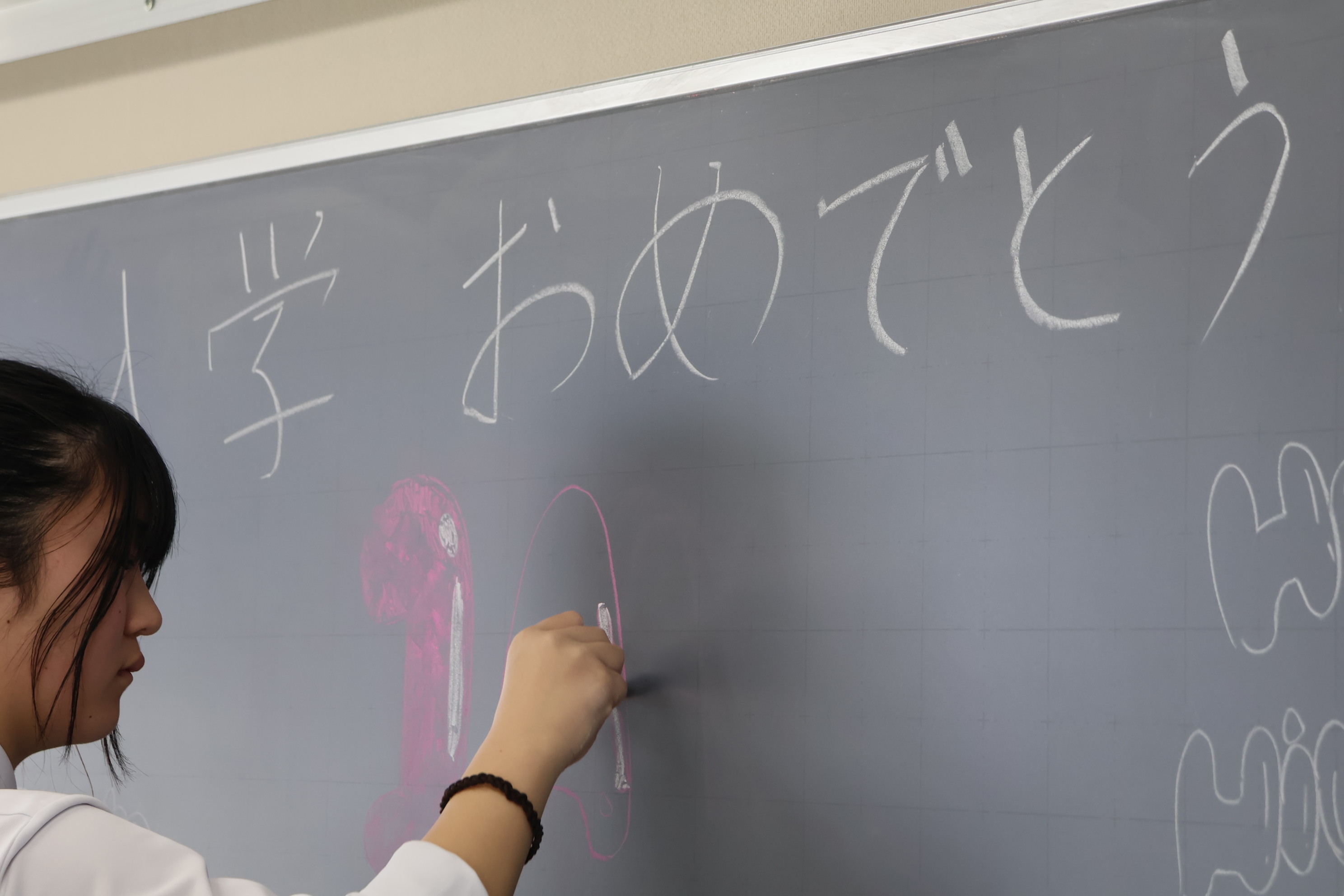
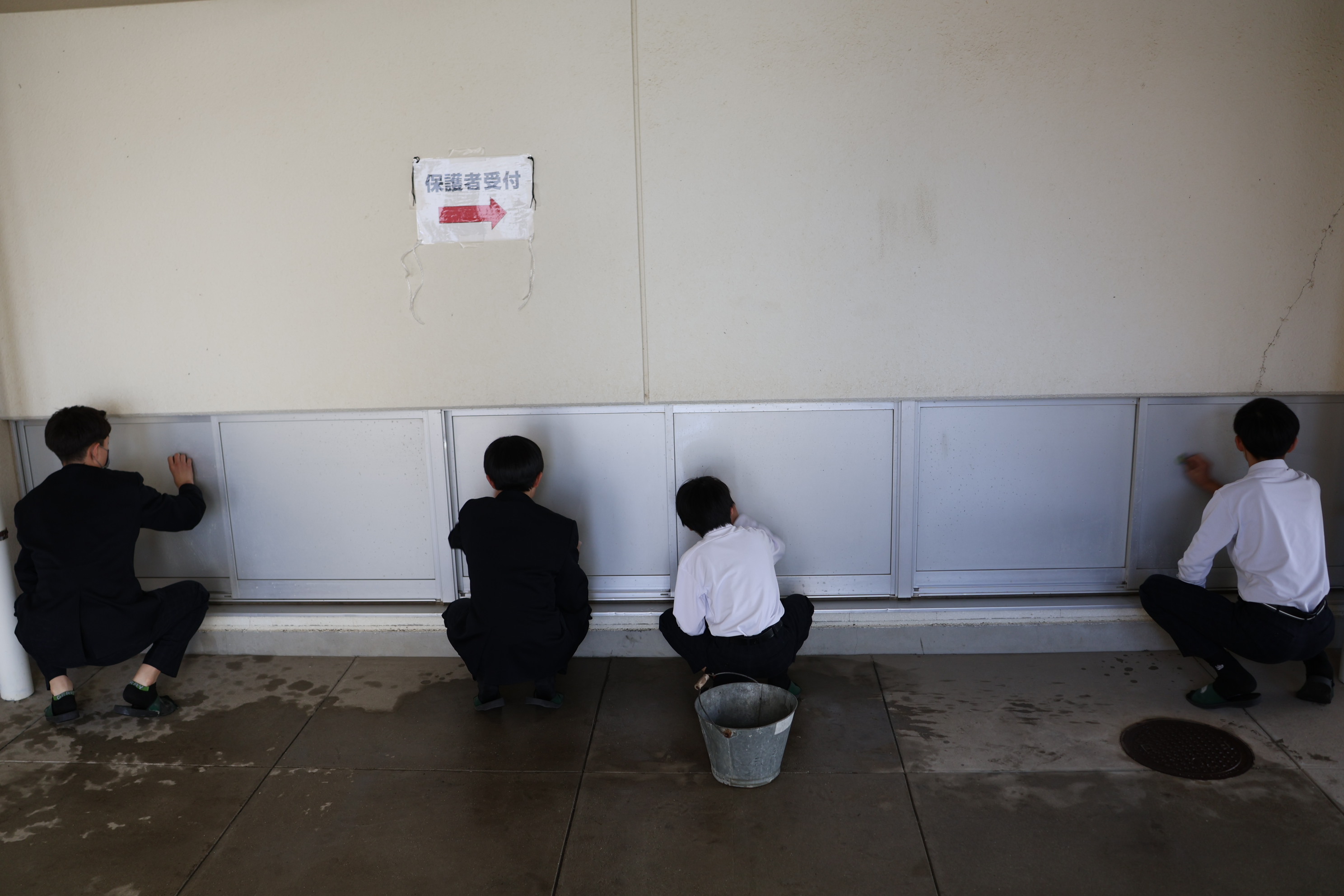


The best thing to hold onto in life is each other. Audrey Hepburn
(人生において、しっかり捕まえておきたい最高のものは「お互いの存在」)
◎わたしたちのはじまりの風景15(4/9)
ここはどこでしょう?









◎挑む 進んでく 開いてく(4/8:到達度確認テスト)


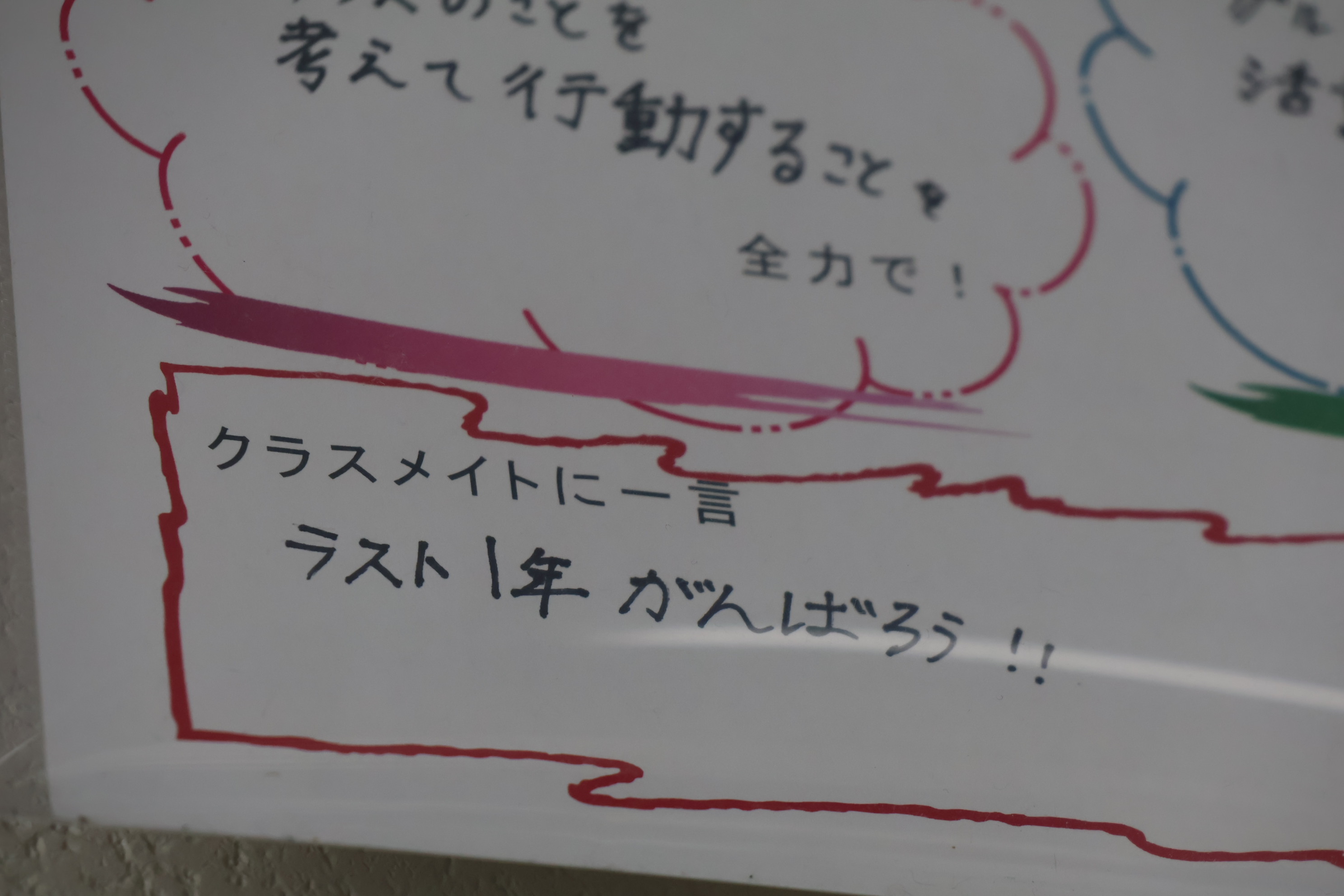

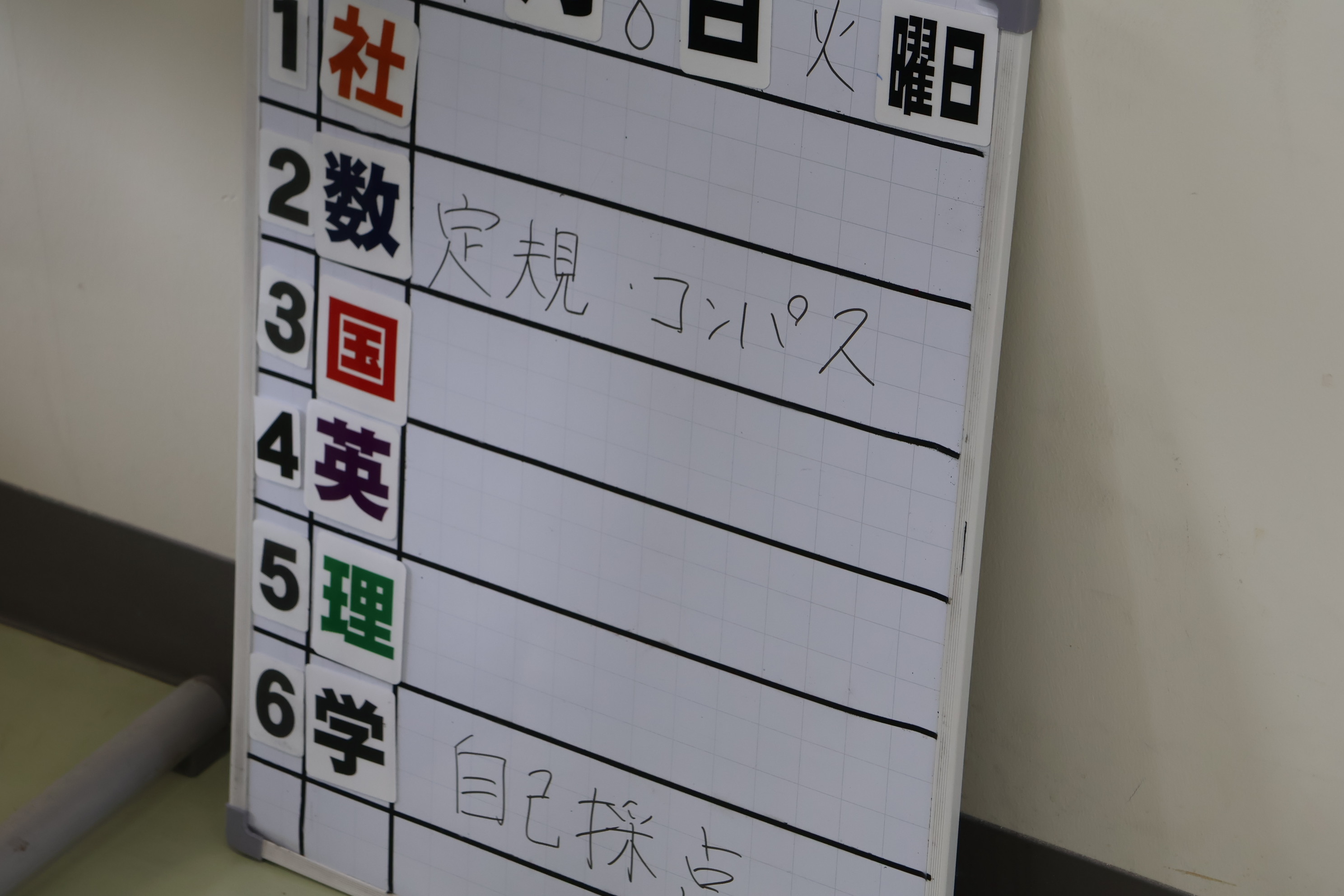
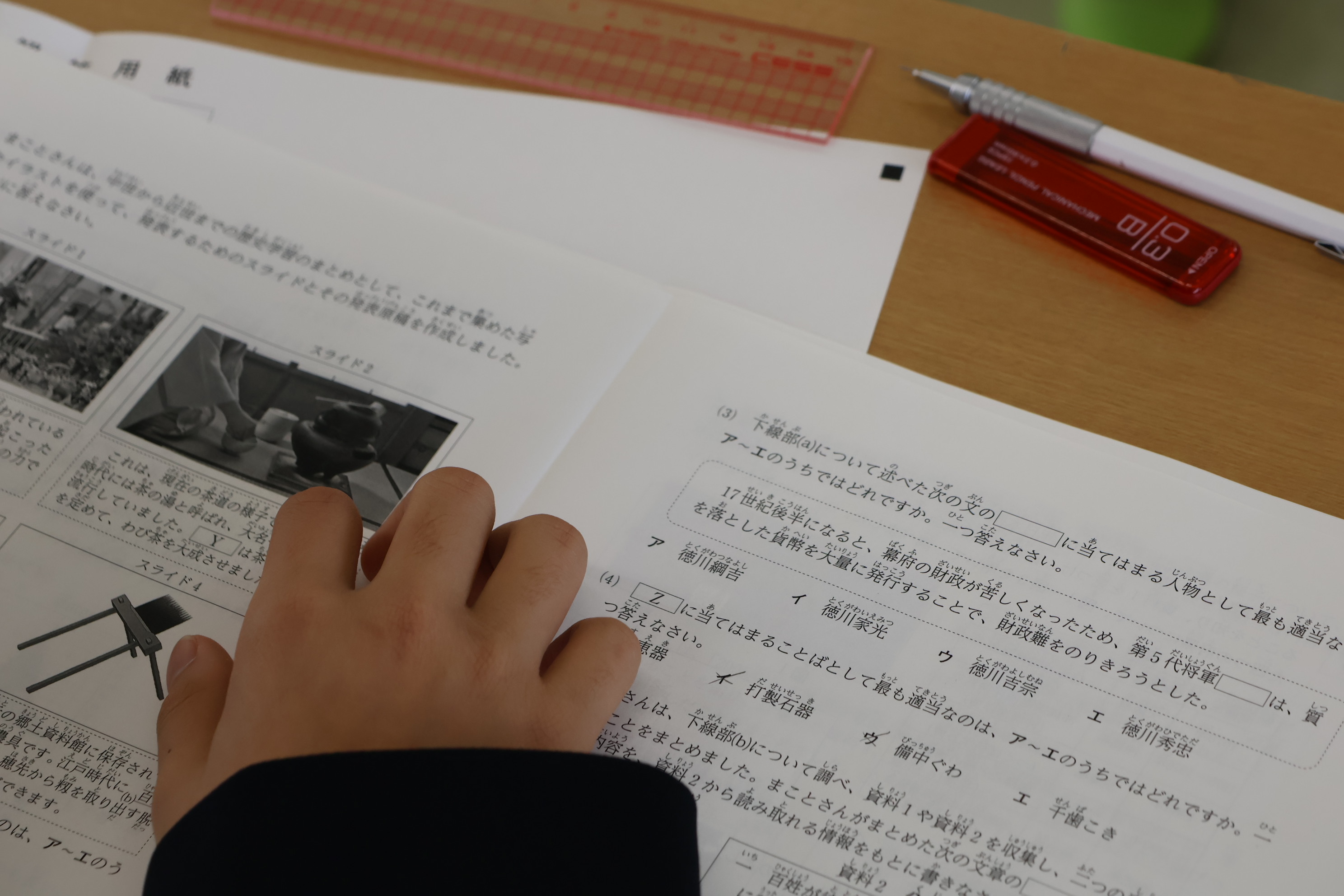

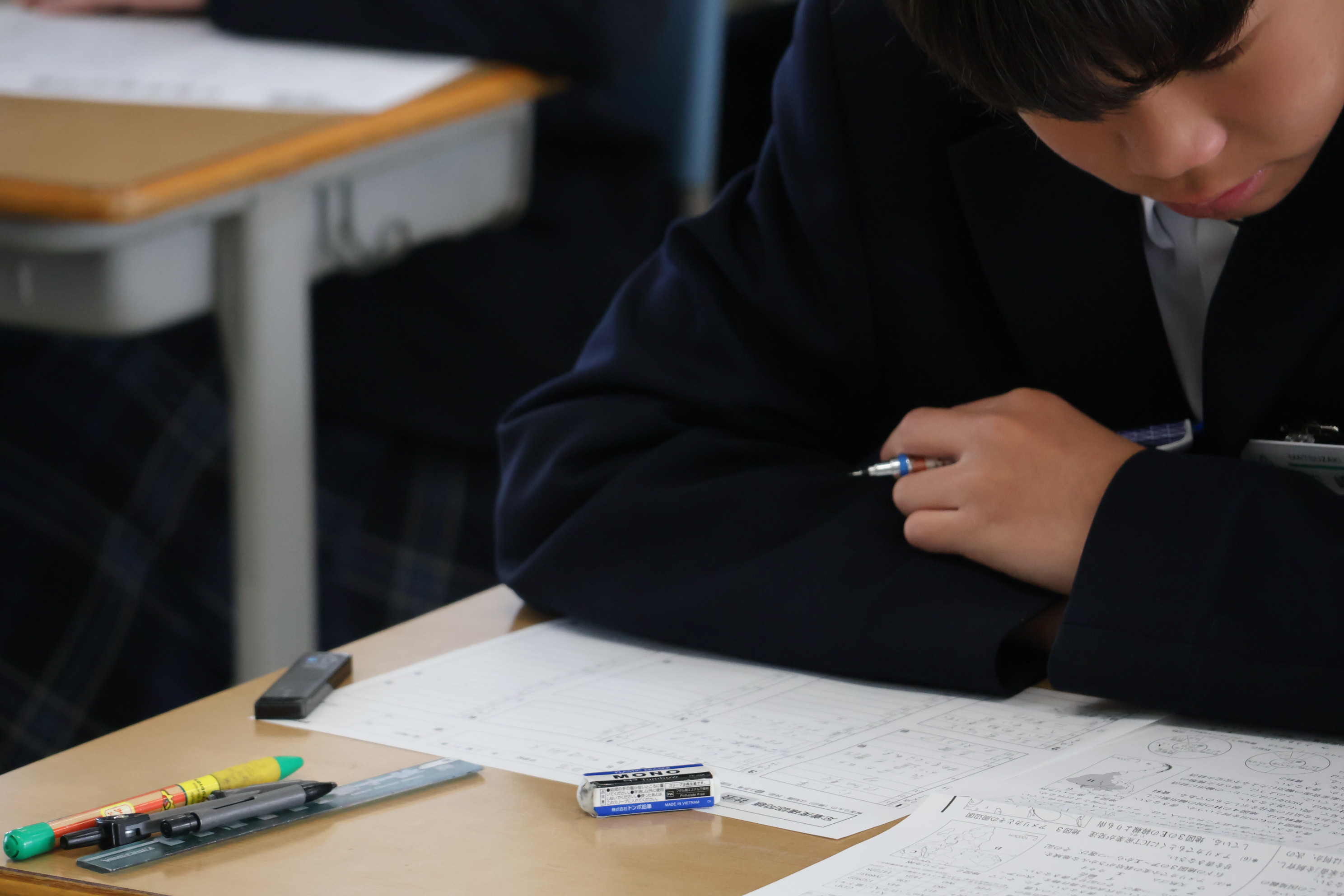

〈学び続ける者だけが教壇に立つことができる 佐藤 学〉
校内研修を中心に私たちも学んでいきます。(4/7:校内研修会)


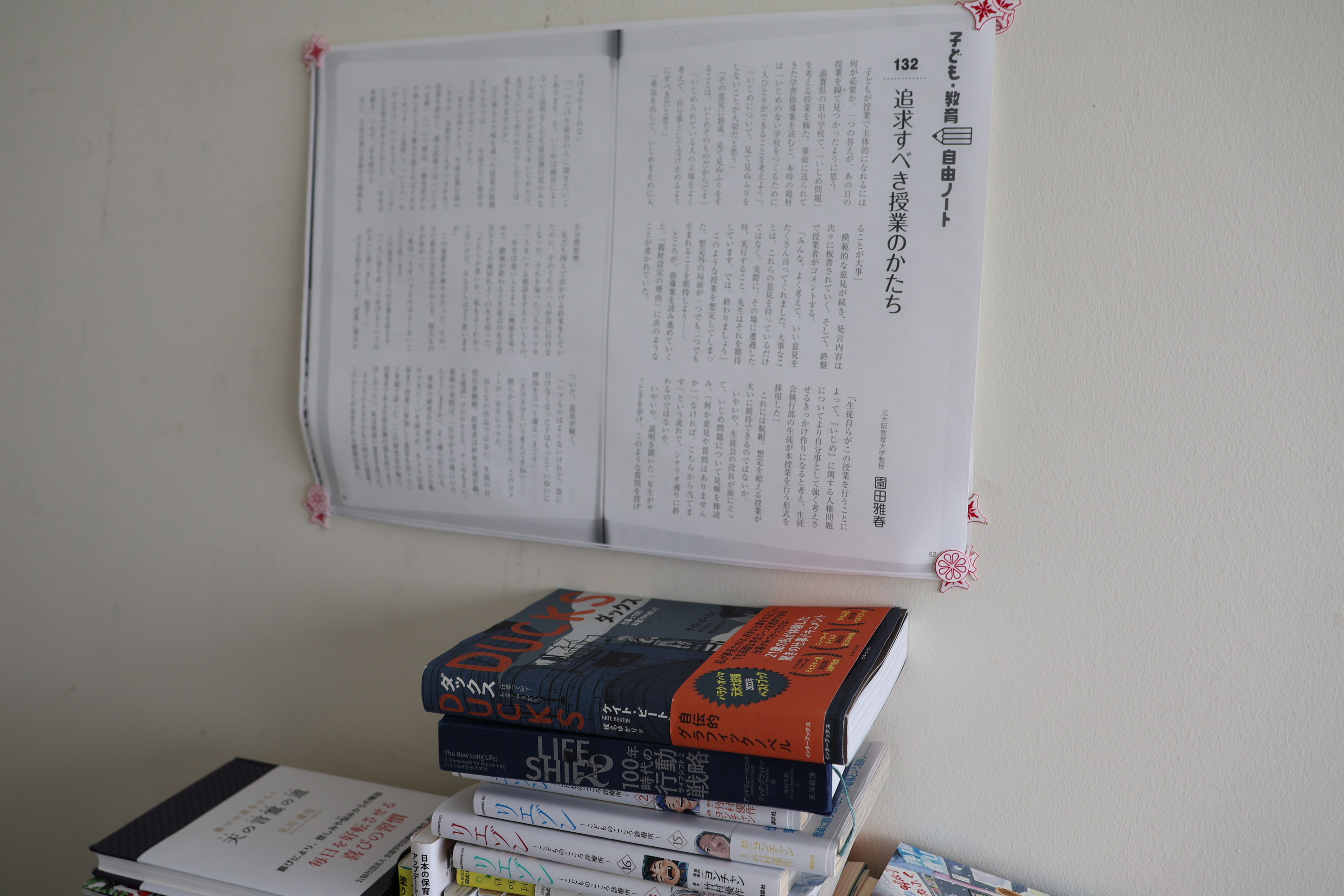
◎はじめよう 仲間と共に(4/7:着任式・始業式)
~学ぶとは誠実を胸に刻むこと 教えるとは共に希望を語ること ルイ・アラゴン~



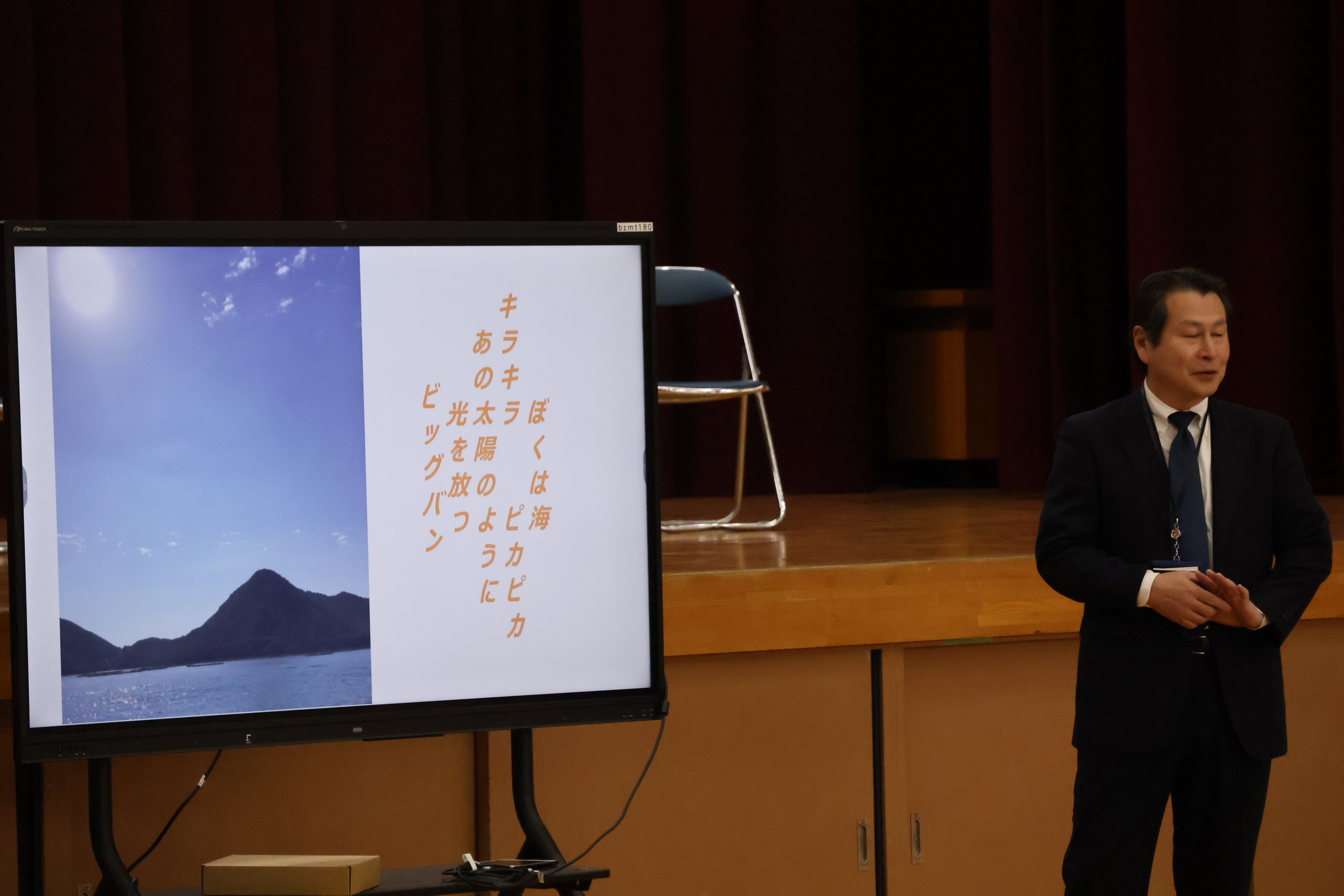




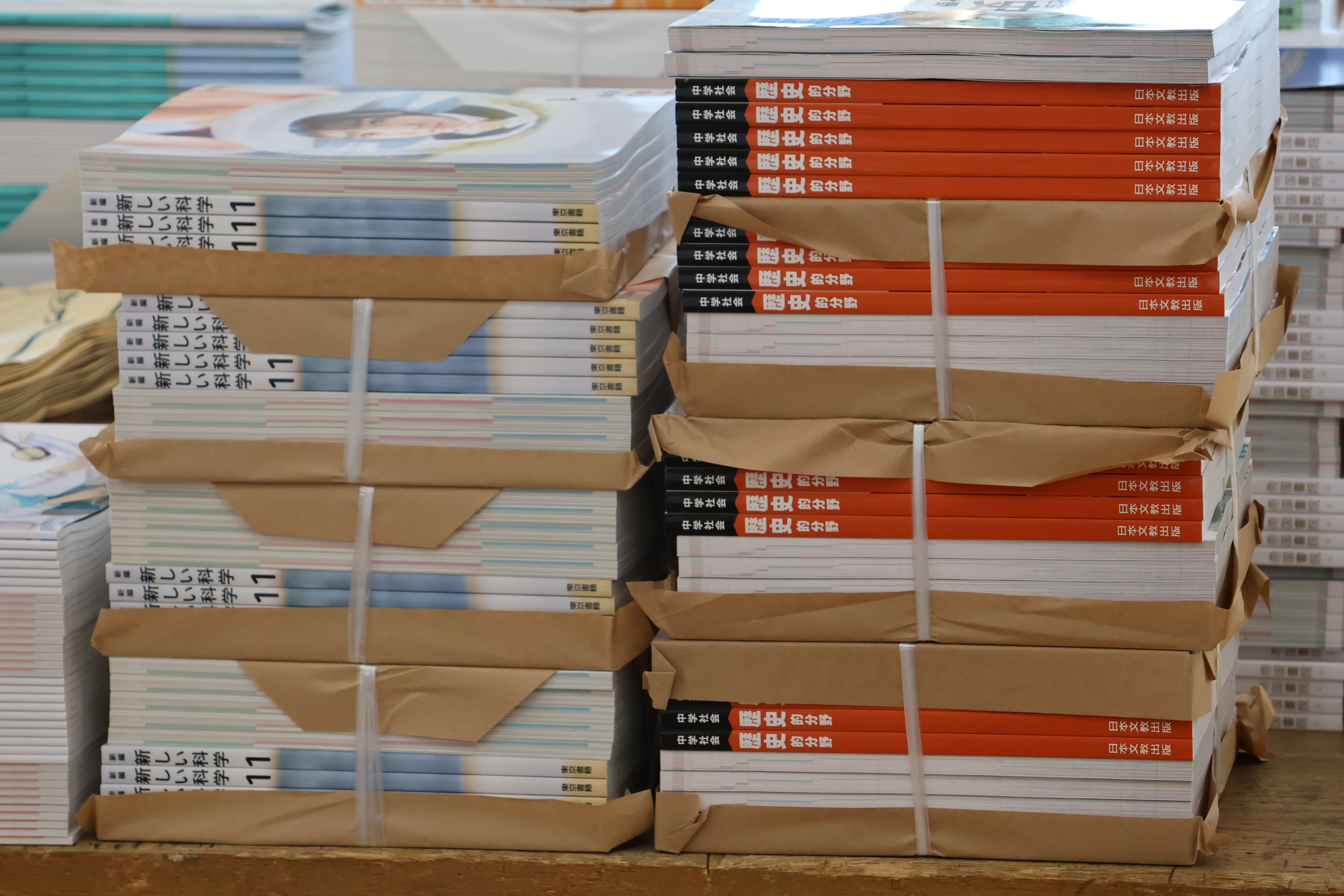
◎また元気に会おうね!新年度、始業式は4月7日(月)

〈風景はわたくしである眠ければ眠ってしまうわたくしである
やわらかに僕のかたちを確かめる風景であり 満開であり 吉野裕之〉

〈パソコンと引き出しまるごと持っていく、職員室の机移動日
新年度の仕事に取り組む席 古いけど「新しい席」と言う
引き出しの奥に眠っていた手紙また読む 春が来るたびに読む 千葉聡〉(4/4)



◎この旗がもつ意味って?(4/3)

新学期にむけて、、グローバルルームを整備しています。その教室に掲示されている旗が気になったので調べてみました。
『レインボーフラッグとは、LGBTQ+の尊厳と連帯、社会運動のシンボルとして使われている旗です。
1978年にサンフランシスコのアーティストであるギルバート・ベイカーがデザインし、「Gay Freedom Day Parade」で使用されたものが始まりと言われています。この時は手染めで8色(ピンク、赤、橙、黄、緑、ターコイズ、青、紫)で構成されていました。その後、何回かの社会運動の中で大量に確保する必要性などから、現在の6色に変わってきました。
性のあり方は多様で、グラデーションとなっているため、美しい虹で表現されています。
現在、最も広く使われてるレインボーフラッグは、6色(赤、橙、黄、緑、青、紫)で表現されています。赤はライフ、オレンジは癒やし、黄は太陽、緑は自然、青は調和、紫は精神の意味が込められていると言われています。レインボーフラッグは、LGBTQ+を象徴する旗としては最もメジャーなものの一つと考えられますが、多様な性を象徴する「プライドフラッグ」にはほかにも様々な種類があります。「あの旗は何だろう?」と興味を持ったら、ぜひ調べてみましょう。
〈花の名は思い出せねど近寄りぬ 香りをかぎぬ 生きてこの春 藤島秀志〉(4/2)
新年度の準備をしています。


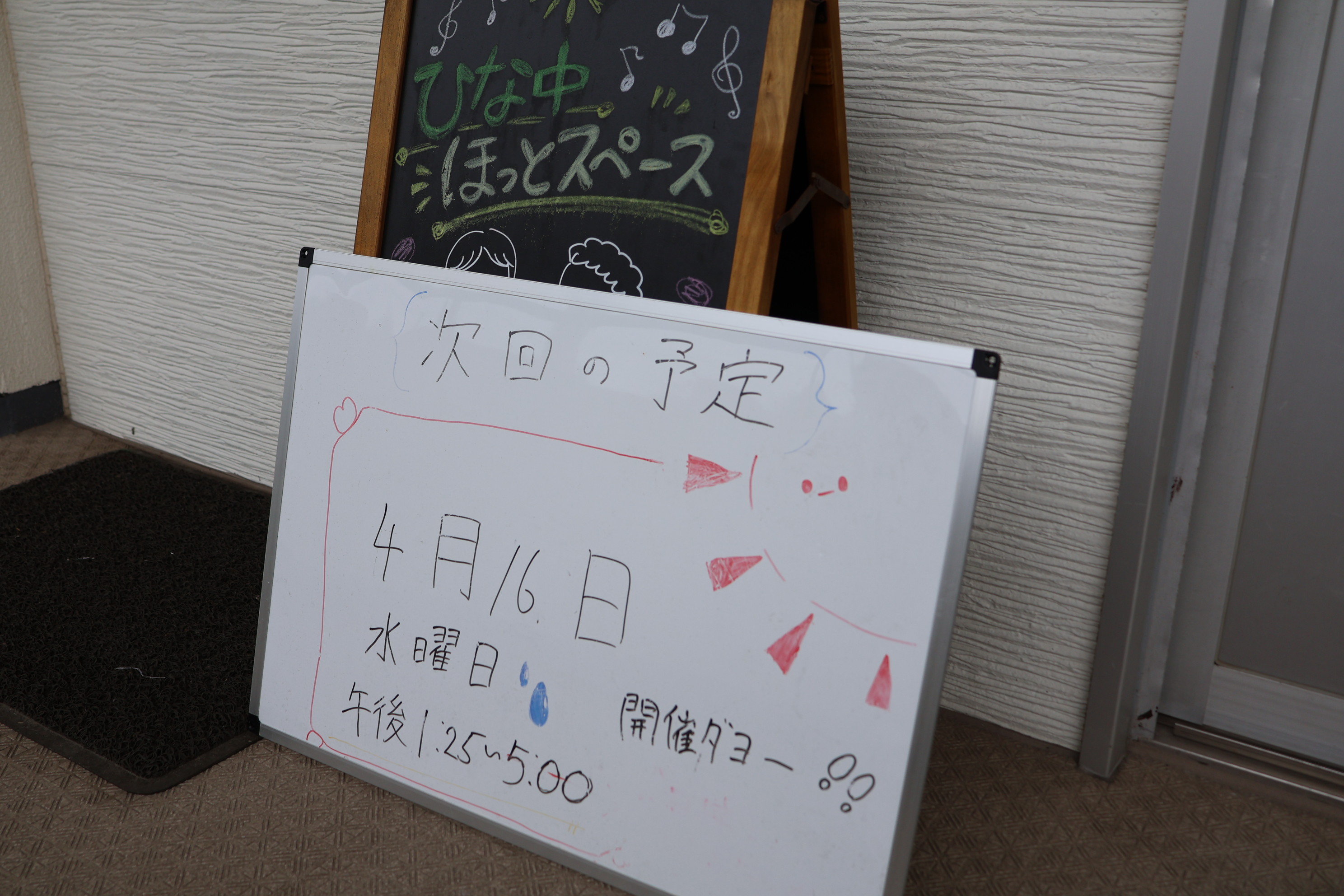





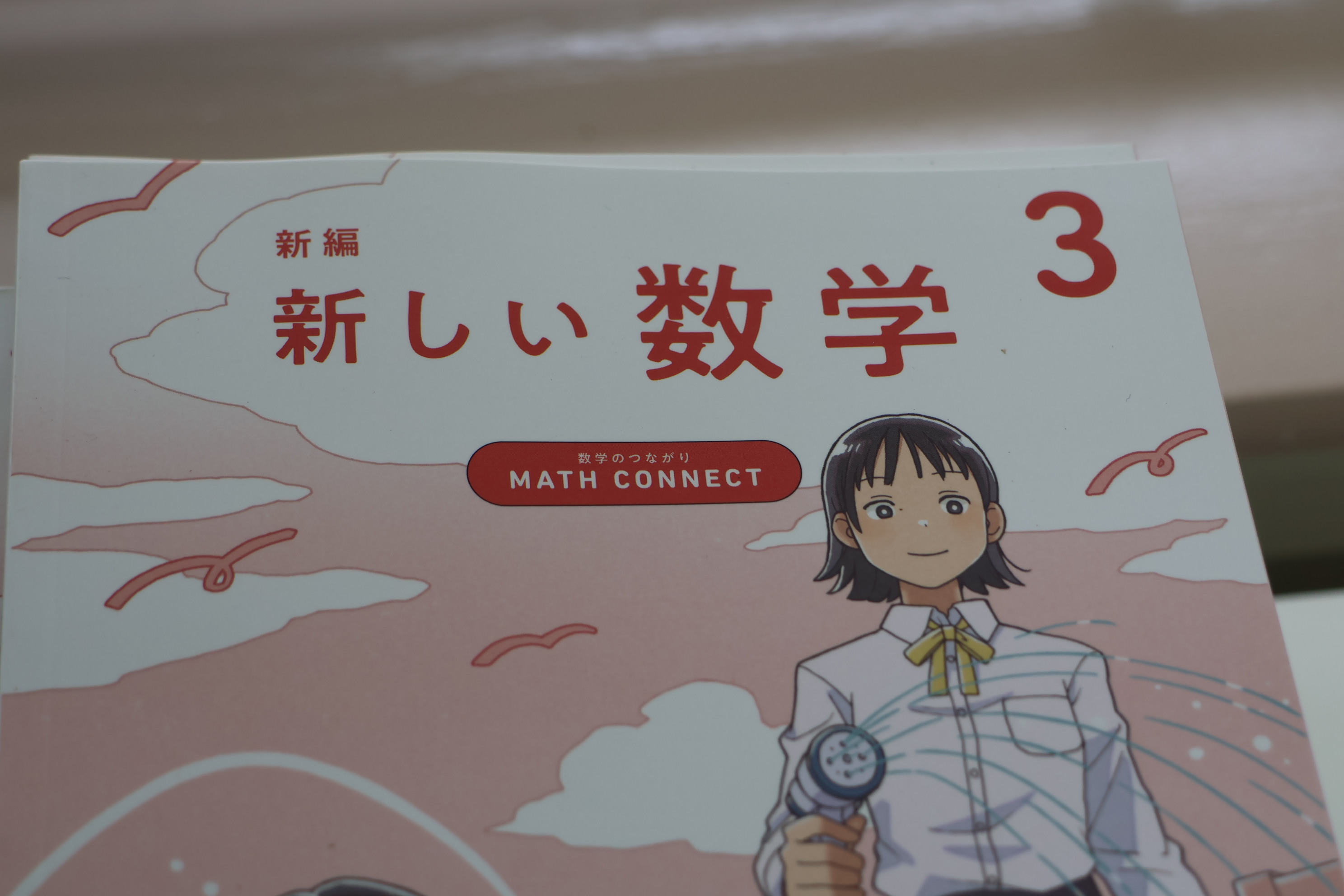


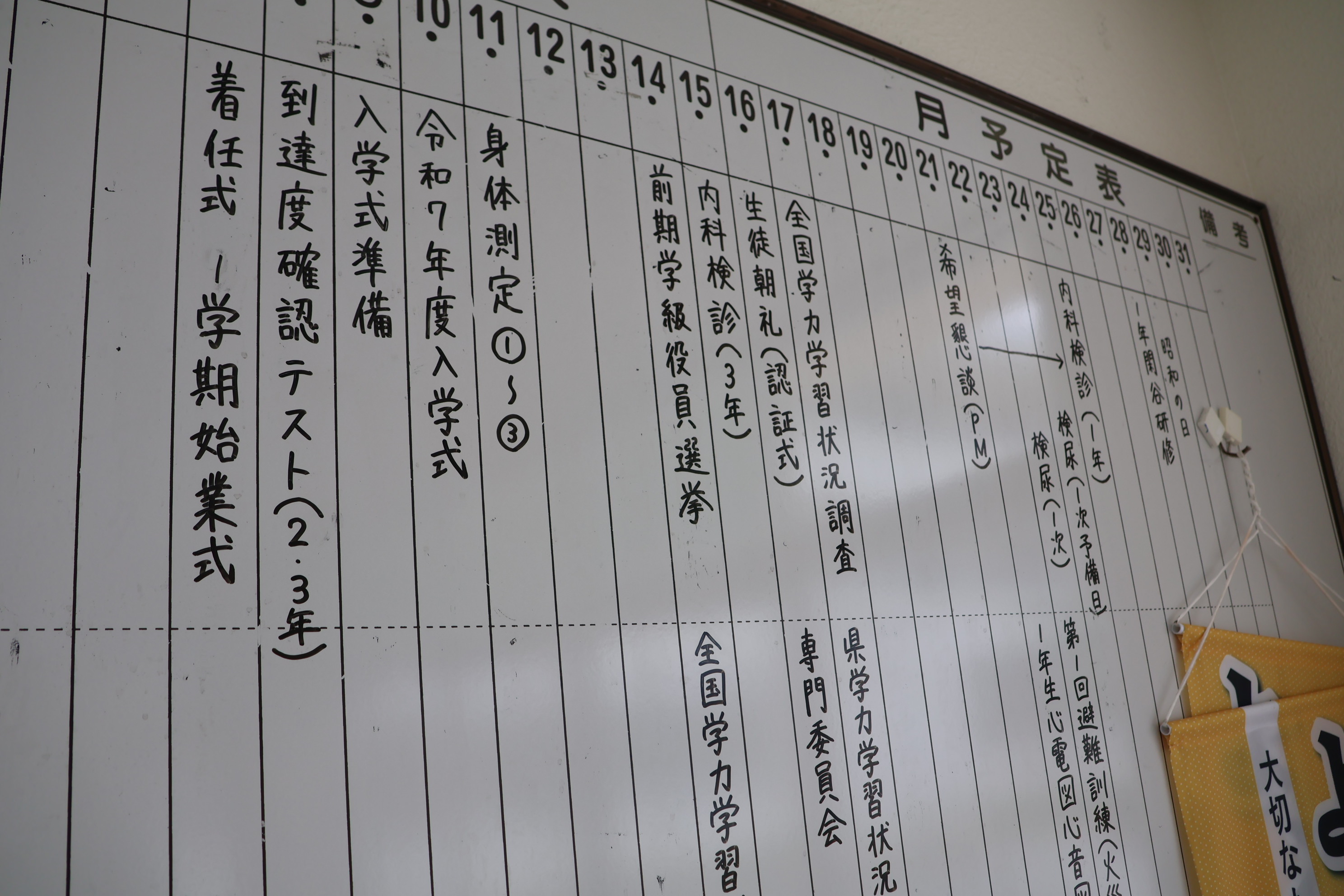
◎春からも、なかまとともに(4/1)

◎地域とともにある学校
~日生で輝く 日生のラスク つくっています(3/31)
ひな中ほっとスペースに集まる仲間が、天gooカフェさん、カメイベーカリーさんのご支援を受けて、新商品を開発しています。今日は中学校の先生たちに試食してもらました。いただいた感想や意見をもとに、工夫・改善をすすめます。



◎十五の春にむけて、確かな連携(3/27:日生学区小中連絡会開催)
新年度・新学期に向けて、小学校の先生方と引継ぎの会をしました。子どもたちのこれまでの小学校での成長をもとに、中学校でのさらなる成長を目指した、連携・協働を進めることができました。

◎ひな中の風~ みんなの協力のおかげで(3/27)
ペットボトル回収にご協力をありがとうございました。今年度もワクチン等の社会貢献活動に役立たせていただきます。本日、護美飼料株式会社さんへもっていきます。ご協力をありがとうございました。生徒会

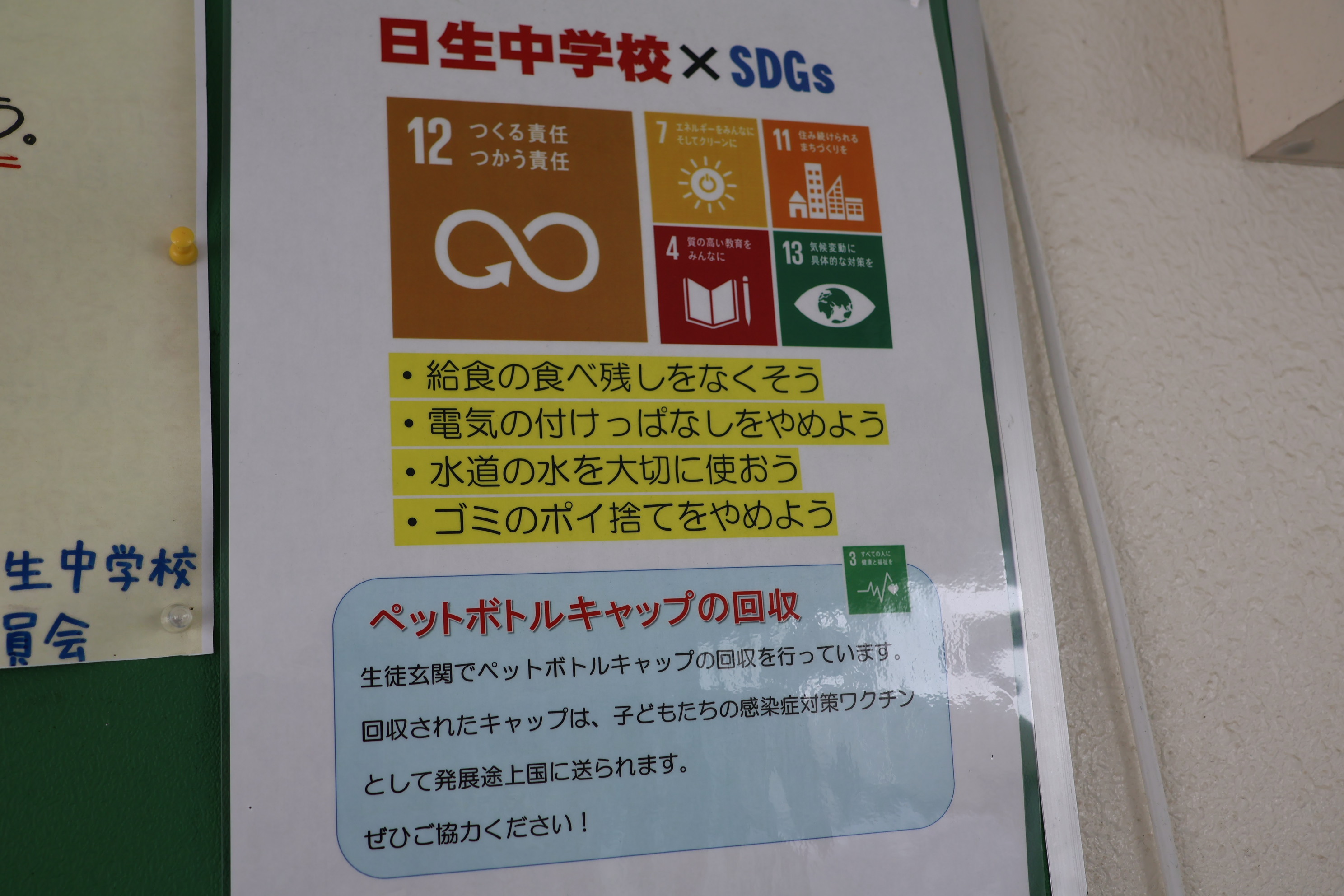
◎ひな中の風~ みんなの協力のおかげで(3/26)
今年度も、たくさんの使用済みカイロを回収することができました。本日、GO GREEN JAPANさんへ郵送しました。ご協力をありがとうございました。体育委員会


◎多くの人に支えられて(3/26)
週末から引き続いて、校門の修理をしていただきました。ありがとうございます。

◎サヨウナラの向こう側(3/26:退任式)




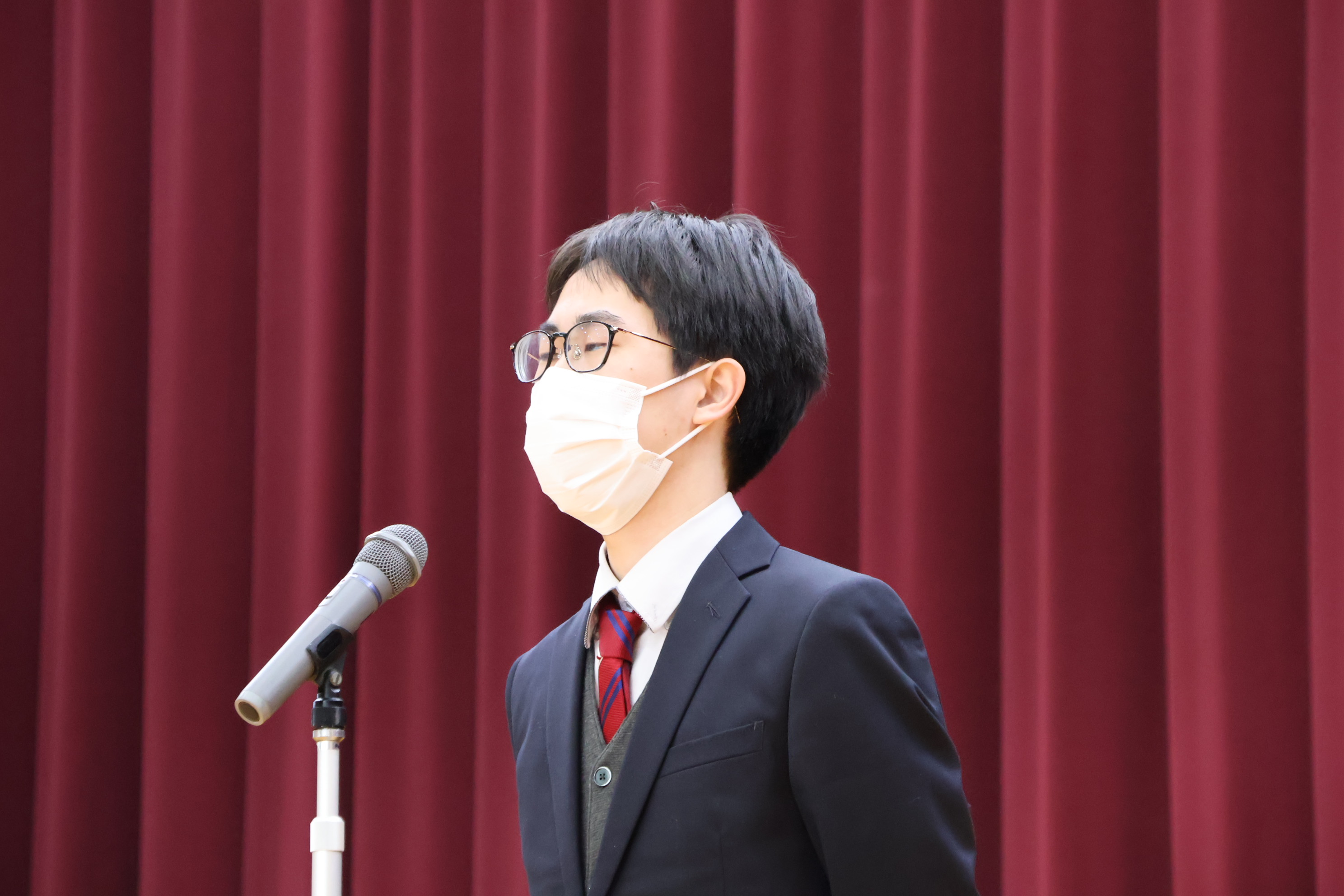




Thank you for your kindness
Thank you for your tenderness
Thank you for your smile
Thank you for your love
Thank you for your everything
〈「愛の」字の中にたくさん 、(たね)がある 書き続ければいつか芽が出る〉
千葉 聡
(3/26:修了式・表彰式)


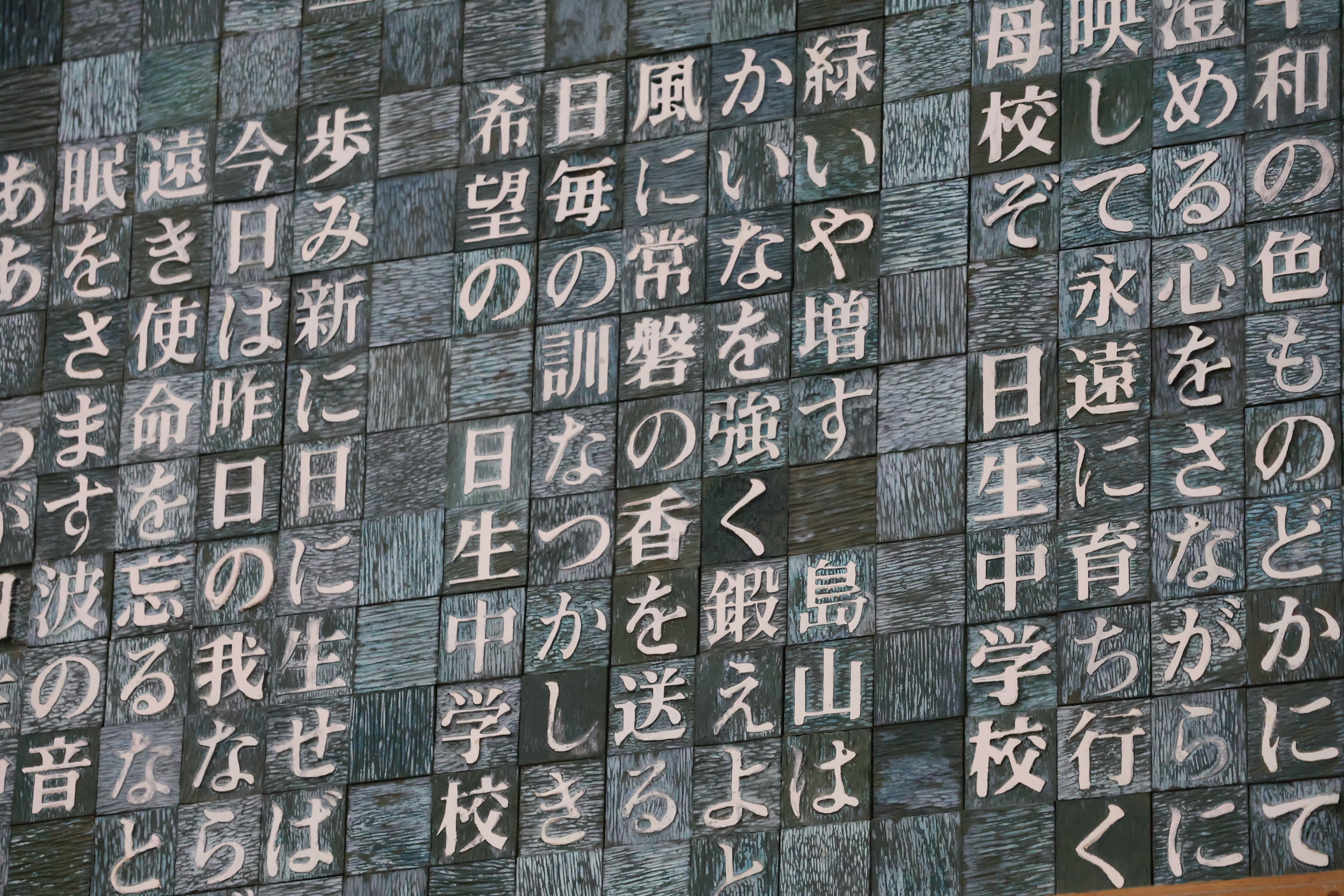






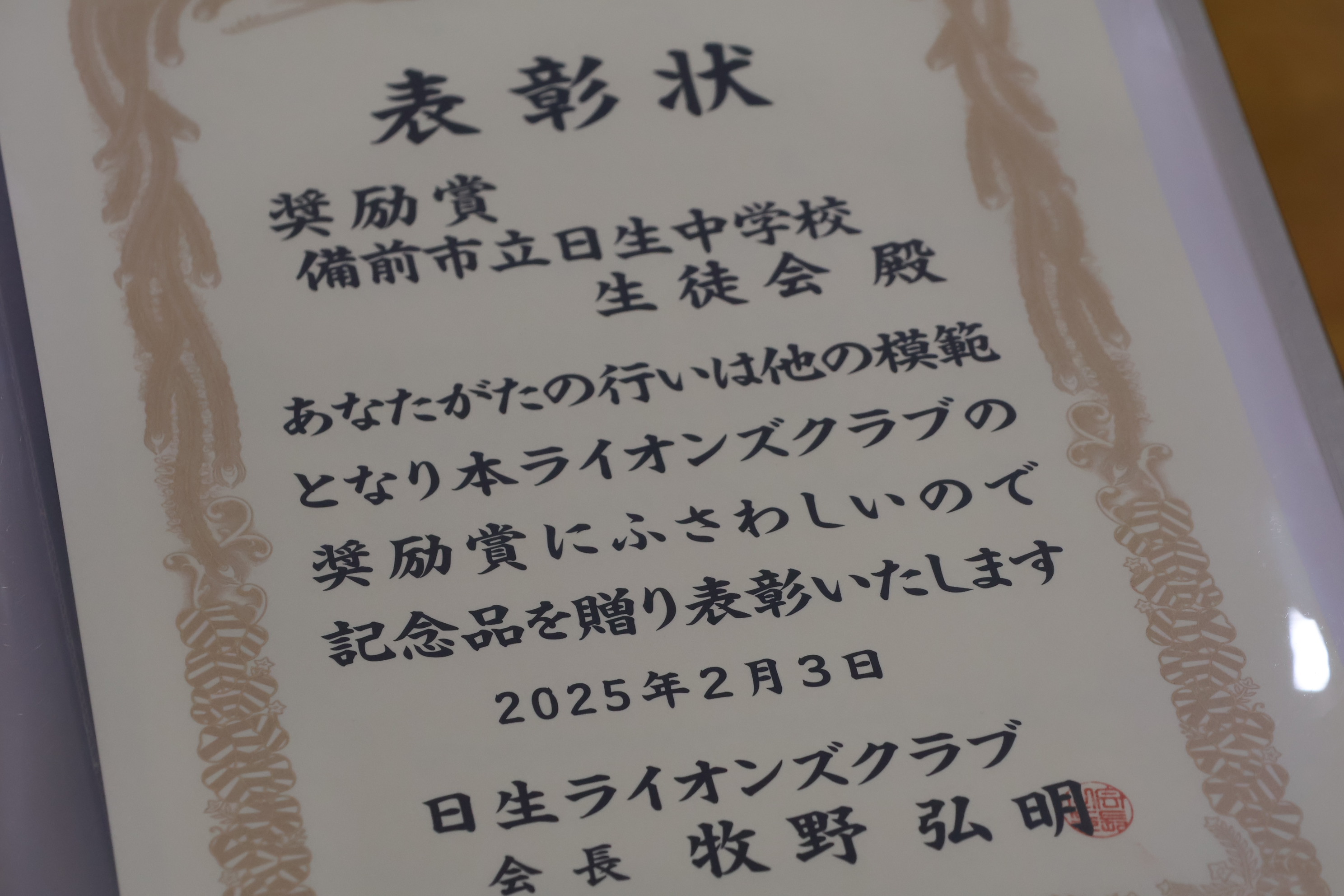

なりたい人は自分の中にいる。
◎次のステージが待ってる(3/25:学年末清掃)



◎明日は修了式(3/25)
過ぎ行く時を捉(とら)えよ。
時々刻々を善用せよ。
人生は短き春にして人は花なり。




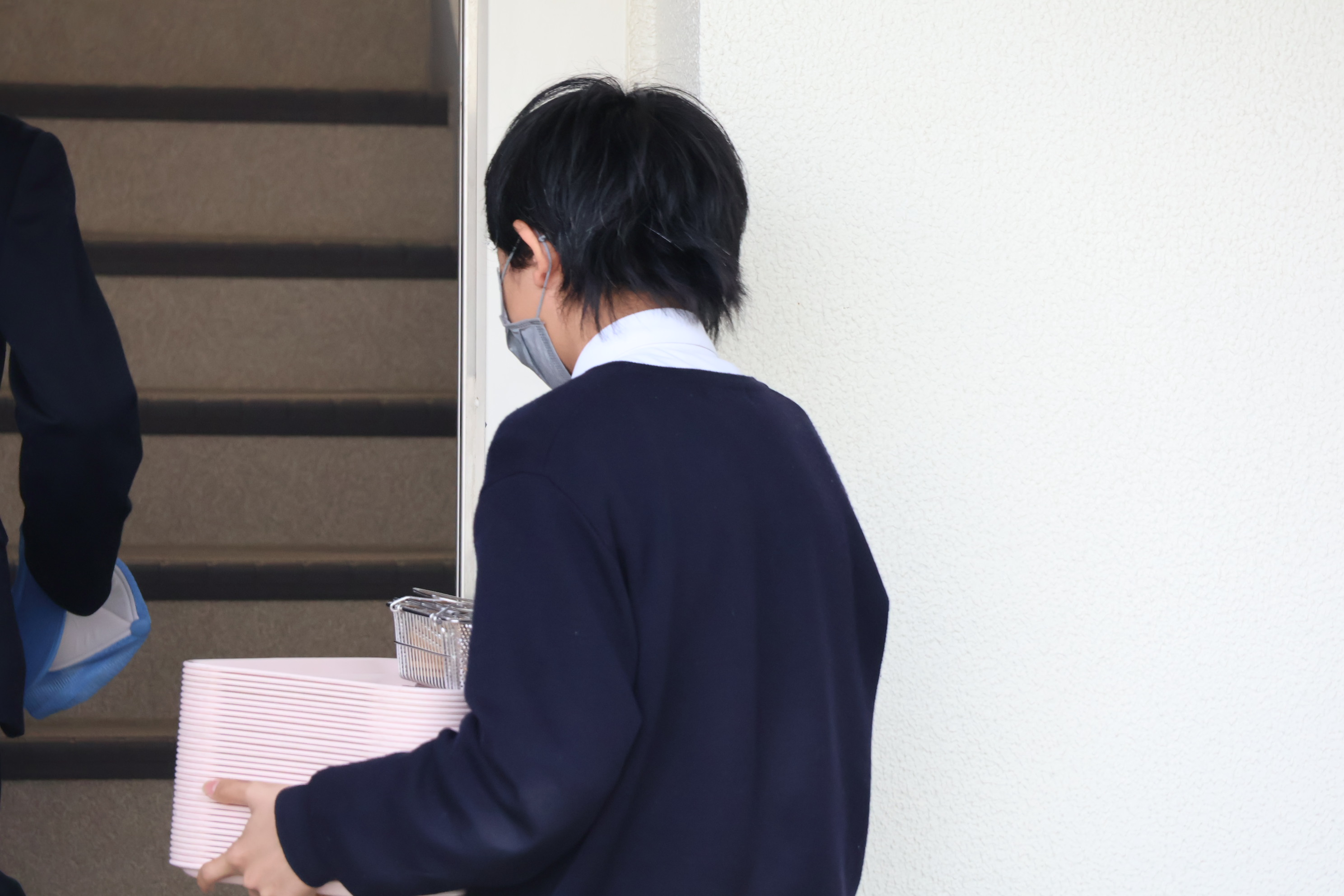




◎正しく知り 正しく行動する 金泰九 kim teagoo
日生中学校生徒の学んだことが、岡山県「教員向けハンセン病啓発動画 ~若者に伝えたい 人権感覚を養うために~」に紹介されました。(3/24公開)
教員や教員を目指す学生が、ハンセン病問題を学び、授業を実施する際の参考となる啓発動画を作成しました。動画は、学生が療養所での宿泊研修を行う様子や、学んだことをもとに地域の人と授業の組み立てを考えるワークショップ等を撮影したものです。岡山県疾病感染症対策課
https://www.pref.okayama.jp/page/965554.html (3)中学校での授業実施例をご覧ください。
◎今日も「おはよう」(3/24:あいさつ運動)
わたしの中にも 新川和江
つくし つばな
つんつん伸びる
丘のポプラには較ぶべくもないけれど
天に向かって
まっすぐ 背伸びして
わたしの中にも そのように
せいいっぱい伸びようとするものがある
どんなに低くとも そこはもう天
光がみち 天上の風が吹いている
もんしろ蝶 もんき蝶
ひらひら舞い立つ
羽化したばかりの
まだ濡れているういういしい羽をひろげて
はじめての空に
わたしの中にも そのように
ことばのひらく気配がある
たくさんの人に
春のよろこびを伝えることば
ひとりのひとに
思いを告げるただひとつのことば

◎日生から学ぶ進路・生き方学習(3/21:1年生進路学習)
「日本のくらしを支える海運」をテーマに 、中国運輸局、備前日生信用金庫、広島銀行、日生地区海運組合、椙原さんをエリアティチャーにお迎えして、進路学習に取り組みました。




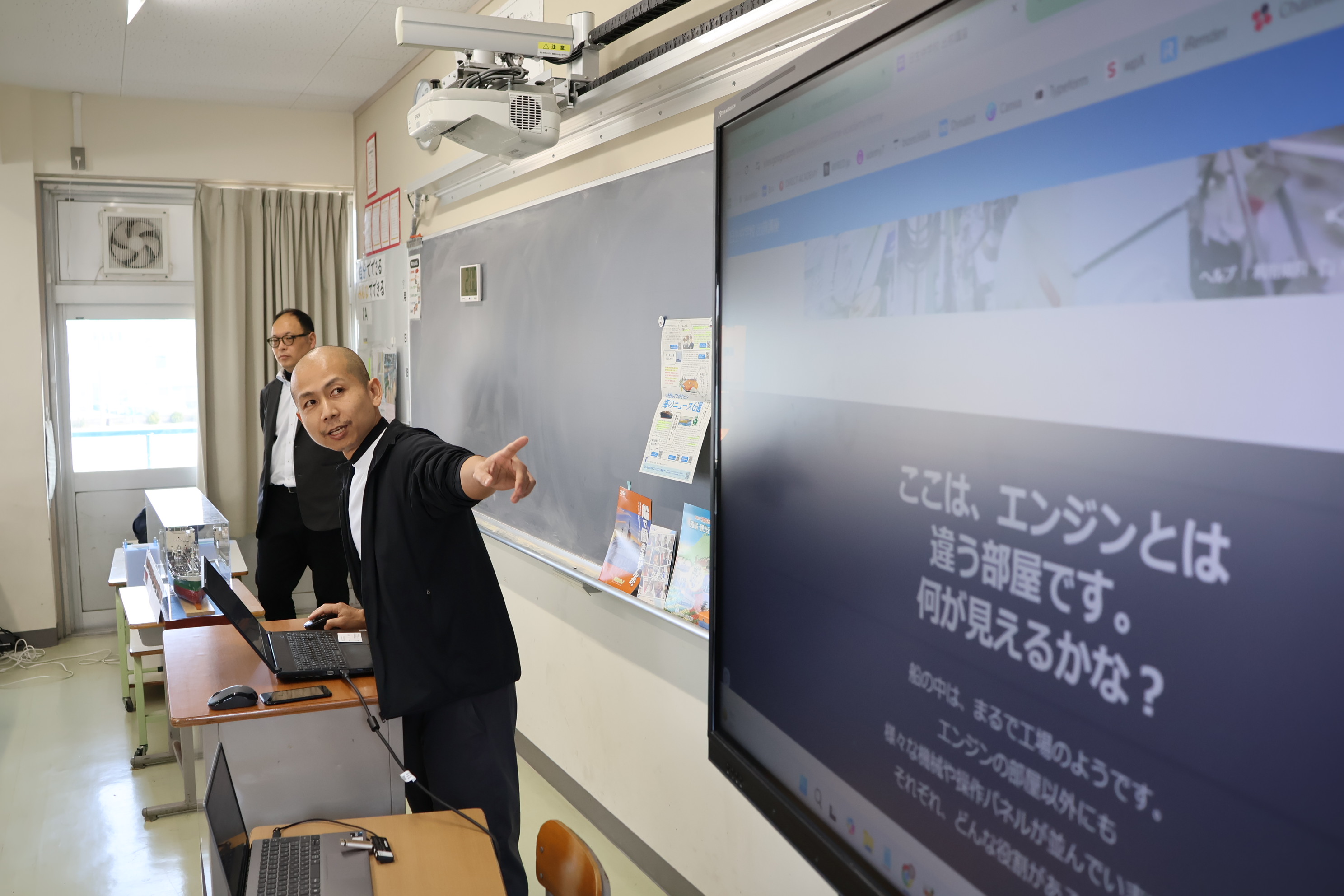


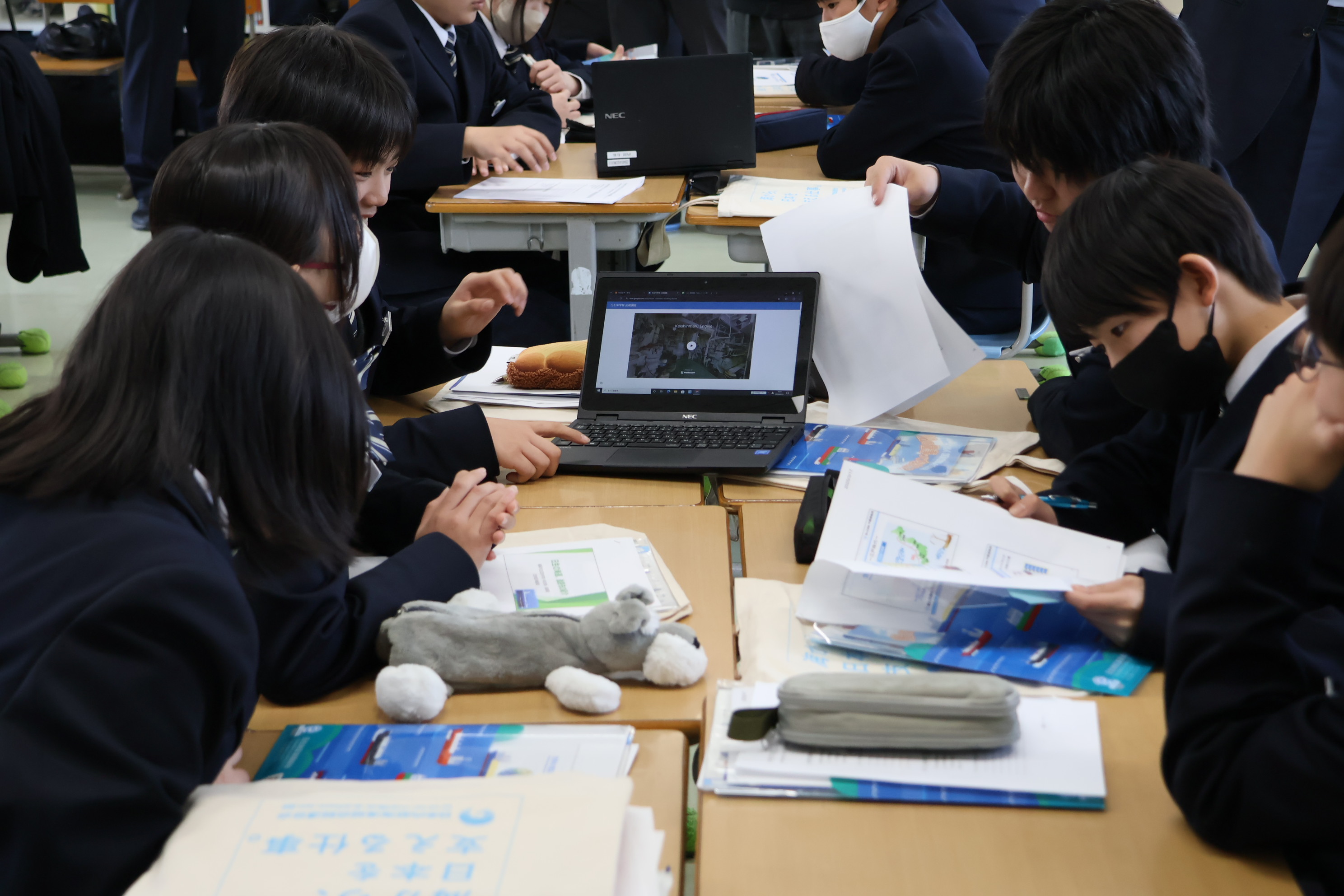

◎春へ(3/21:備前市立片上高校願書出願~)
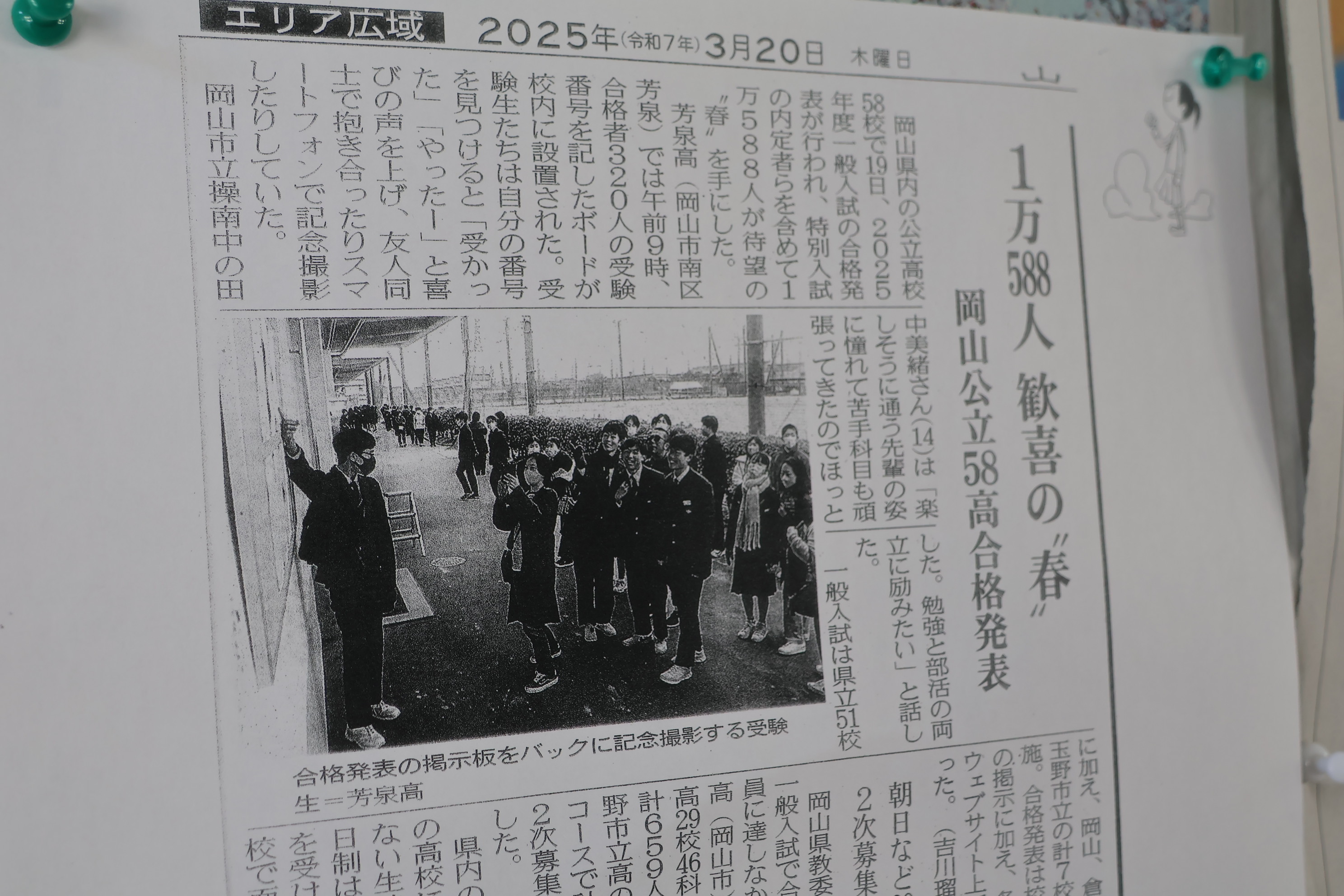


〈やわらかき春の土の上に立つてゐた父かな鍬には体(たい)をあづけて 時田則雄〉(3/20:春分の日)


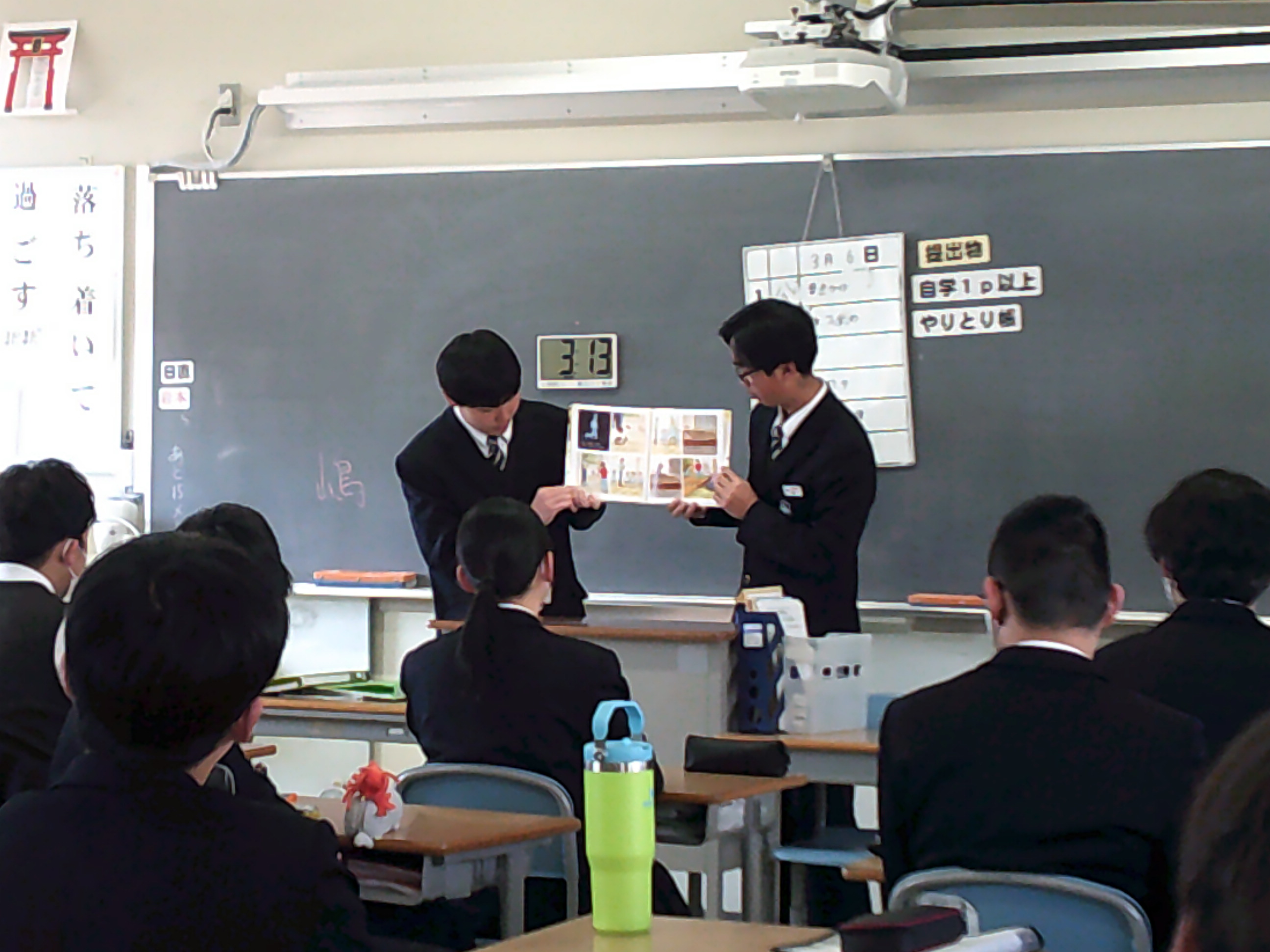
春分の日とは、内閣府「国民の祝日について」の資料によると、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日として説明しており、簡単にいうと生き物や自然の大切さを知る日ということになります。
春は、冬眠していた動物や植物が目を覚ましたり、新たな生命の誕生を感じられる季節です。そのため春分の日は、生き物や自然の大切さを知りながら、春の訪れを楽しむことができる日といえるでしょう。
春分の日の前後3日はお彼岸ともいわれていて、春分の日はお彼岸の中日(ちゅうにち)として、お墓参りをする日でもあります。そもそもお彼岸とは仏教からきている言葉で、仏様の世界を彼岸、三途の川を挟んで、今自分たちが生きている世界を此岸(しがん)と呼ぶそうです。ある一説によると、極楽浄土が西の方角にあり、春分の日は太陽が真西に沈むため、極楽浄土に一番近くなる日として太陽を拝むことは極楽浄土に向かって拝むことになる、といわれています。そこから、春分の日に太陽を礼拝し、ご先祖様を供養するようになったことが、お墓参りをする日として広まっていったようです。
春分の日と秋分の日の違い
春分の日と同様に国民の祝日とされているのが、秋分の日です。秋分の日は春分の日と同じく、地球と太陽の位置により、昼と夜の長さがほぼ同じ長さになる日として知られています。春分の日と秋分の日の違いは、春と秋という季節の違いはもちろんですが、祝日の意味に違いがあります。内閣府「国民の祝日について」の資料によると、秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」という意味を持つ日と説明しています。また、春分の日を過ぎると昼の時間が少しずつ長くなります。一方、秋分の日を過ぎると昼の時間が少しずつ短くなるため、昼の時間の長さにも違いがあります。春分の日は以前、春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)と呼ばれていました。春季皇霊祭とは、歴代の天皇など皇室に関わる先祖の霊を祀る儀式を行う日で、儀式自体は今でも皇居内で行わているそうです。
春分の日はお彼岸の中日(ちゅうにち)でもあるため、ぼたもちをお供えしたり、食べたりすることもあるでしょう。春分の日にぼたもちを食べる理由は、あんこの原料となる赤い小豆に「魔除け」の効果があるからだといわれています。もともと古くから、赤には魔除けの力があると考えられており、食べることによって邪気を払い、災難から身を守ることにつながったそうです。そのため、春分の日にぼたもちを食べるのですね。
◎多くの人に支えられて(3/19:新入生物品販売)
〈わたしたちどこでも行けると不意を聞く言葉じわじわ嬉しくなりぬ 富田睦子〉



◎二年生から三年生として(3/19:授業風景)

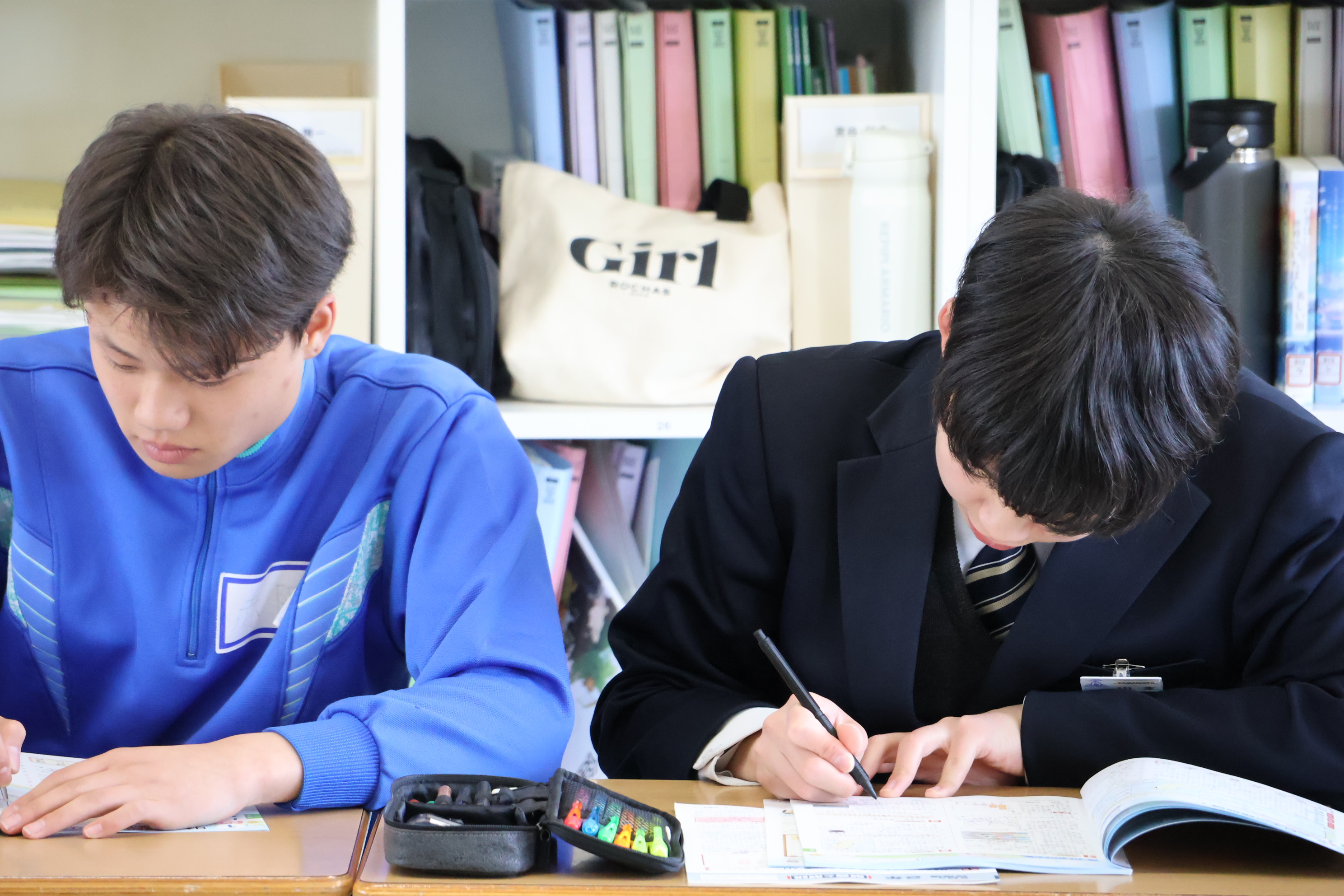







◎今 在りき
県立一般入学者選抜合否発表日(3/19)
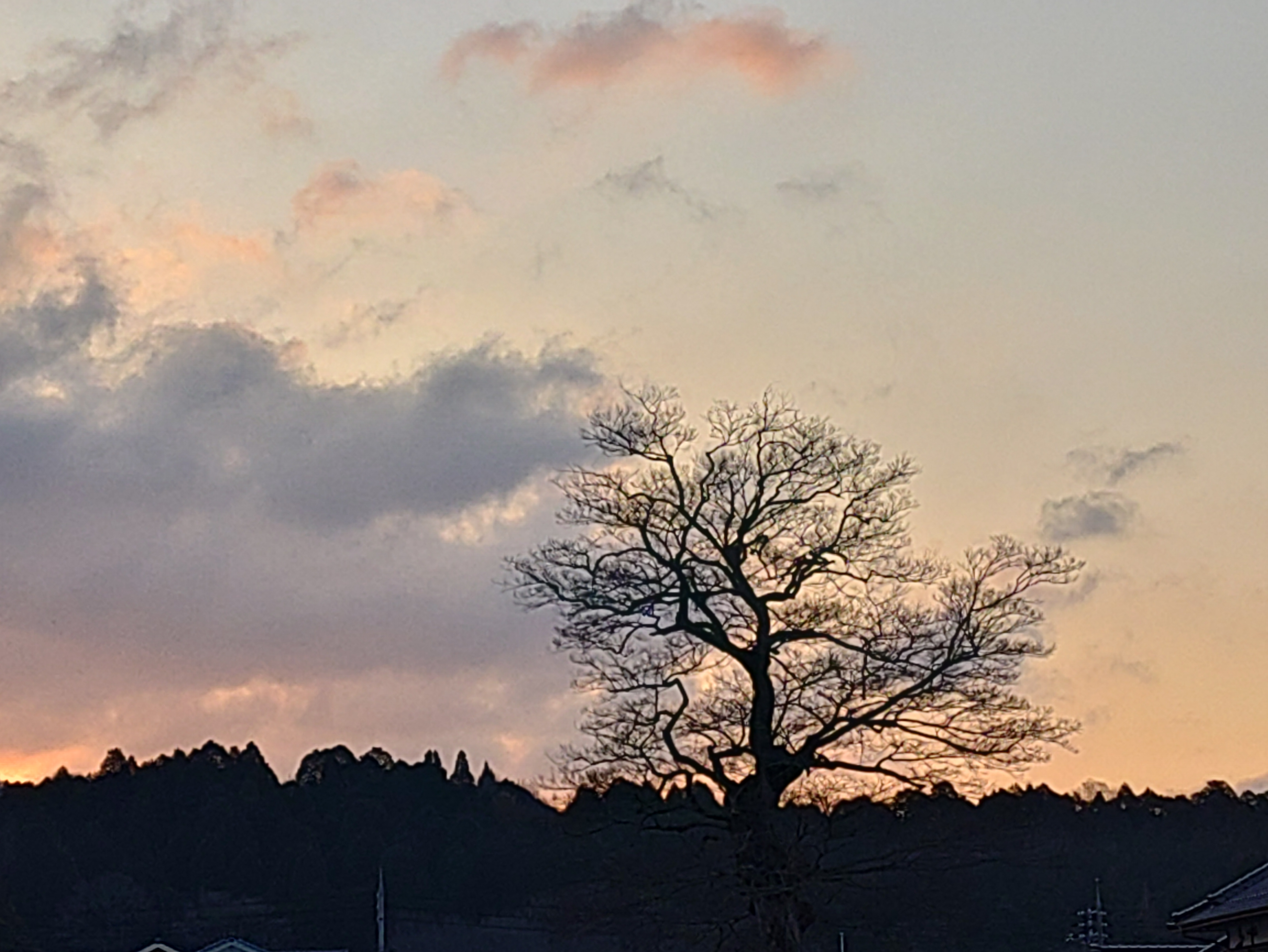
〈苺のへたに花びらひとつ残ってる だれもがここまでを生きてきた 初谷むい〉
◎新しく 清掃場所を引き継ぐ(3/18)



もくもくと、仲間たちと。
◎多くの人に支えられて(3/17)

防火シャッターの不具合を点検・修理していただいています。早速の対応をありがとうございます。
◎多くの人に支えられて(3/17)

日生ライオンズクラブ会長が来校され、今年も新入生へ交通安全のための夜行タスキをいただきました。ありがとうございます。
◎小学校との、豊かで・確かな連携を進めています(3/17)
新入生となる6年生の授業見学に行ってきました。西小は卒業式の練習、東小は国語、算数の授業をみさせていただきました。両校の6年生どちらも、集中して一生懸命に学習に取り組む姿は、さすが最上級生ですね。

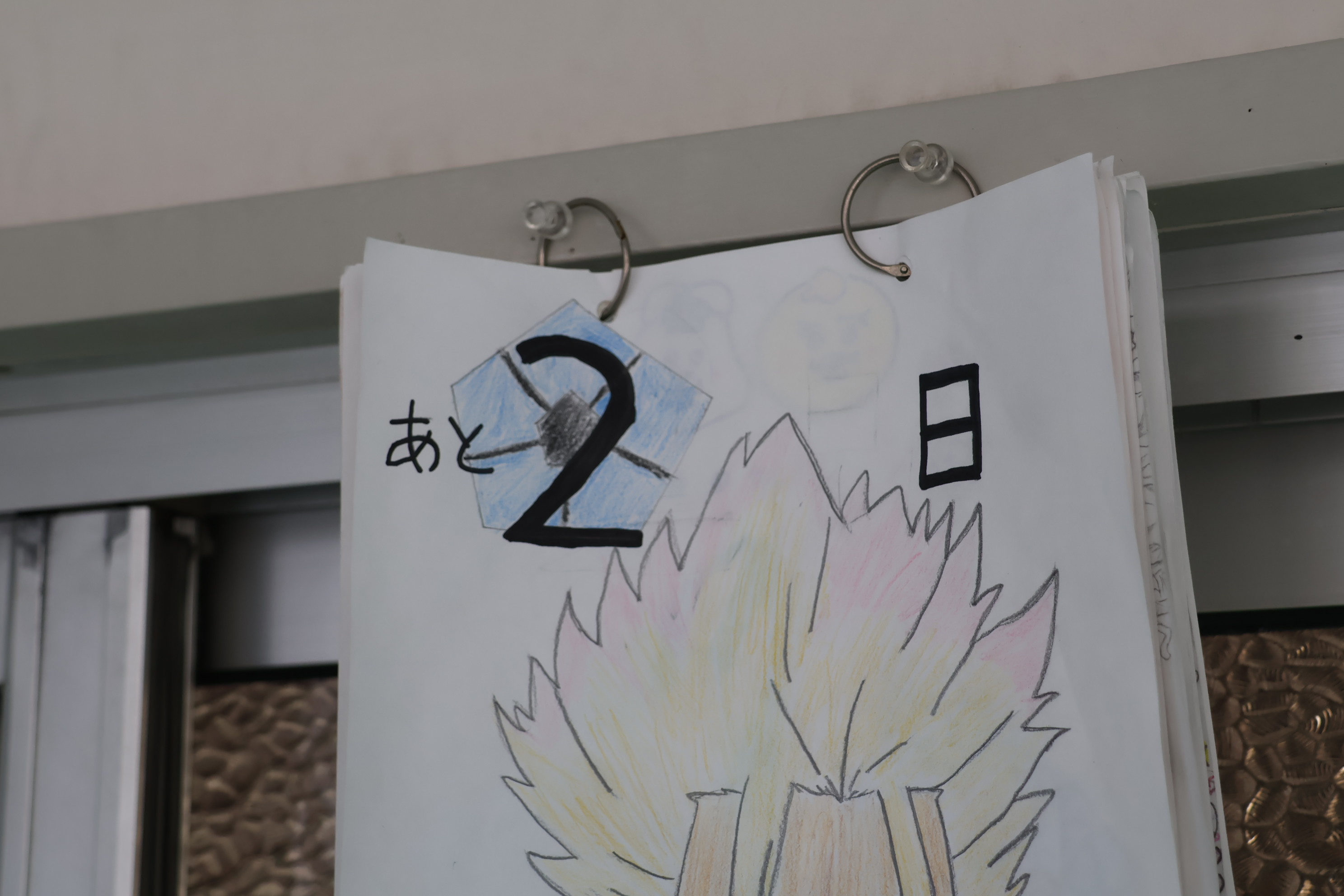


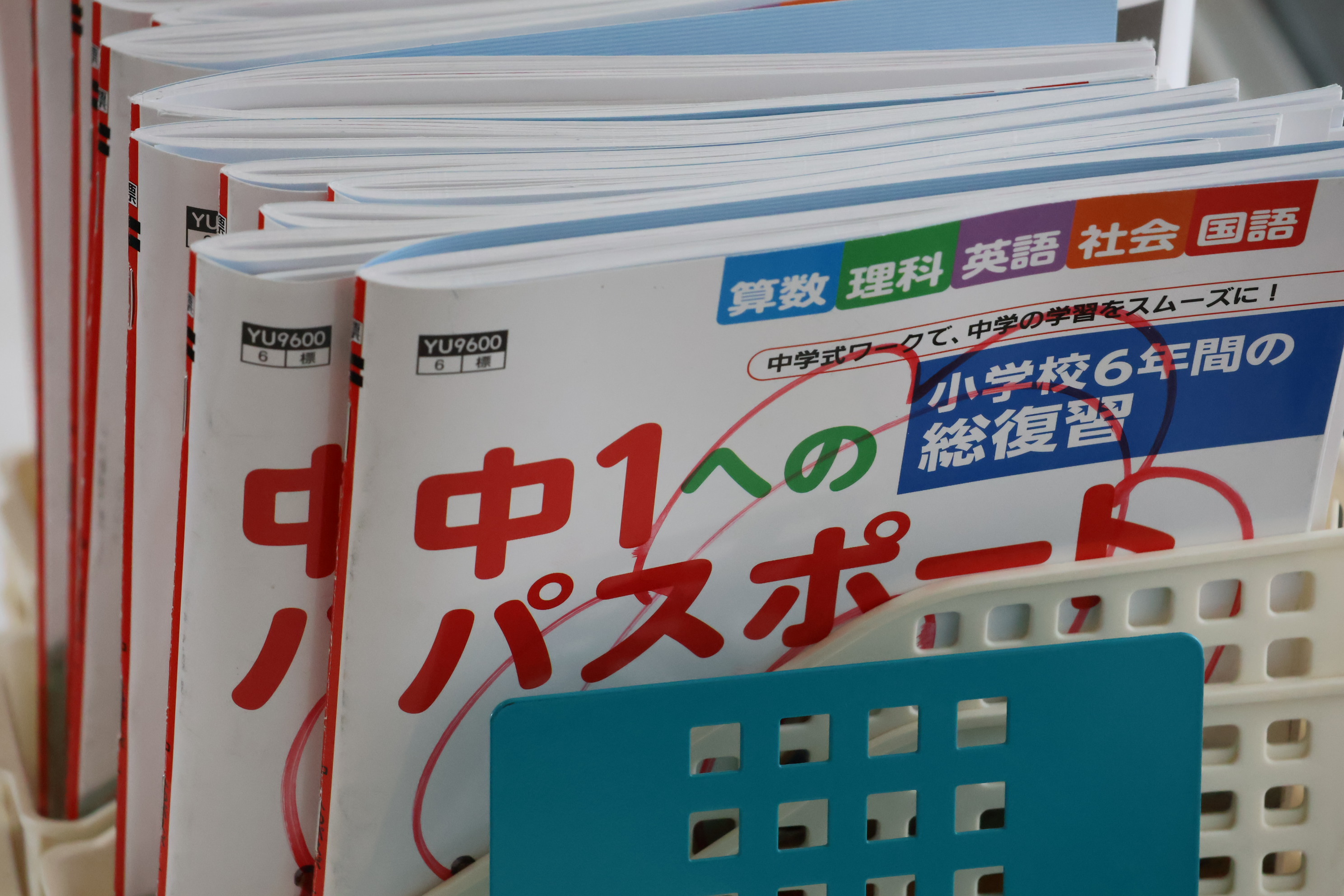
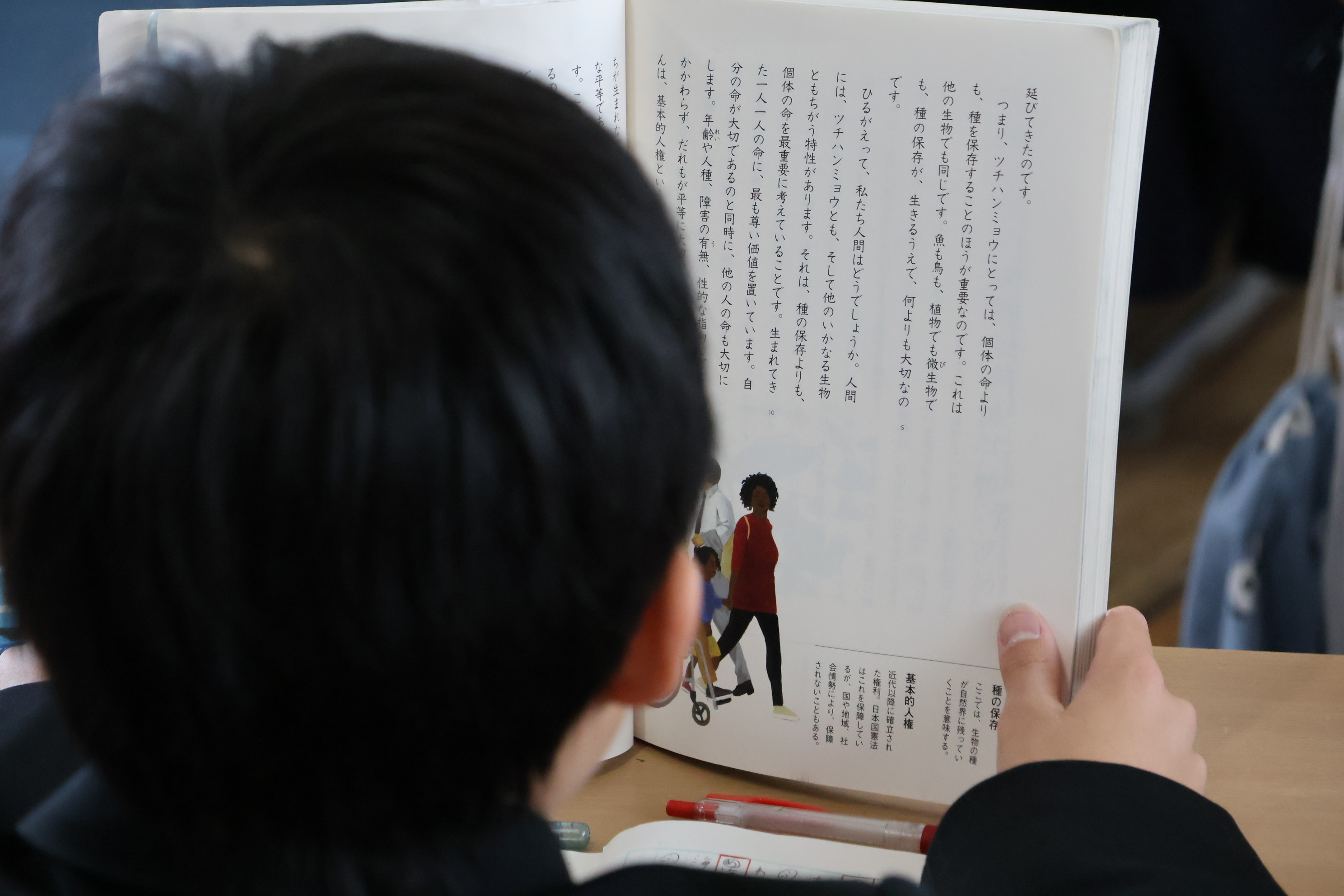
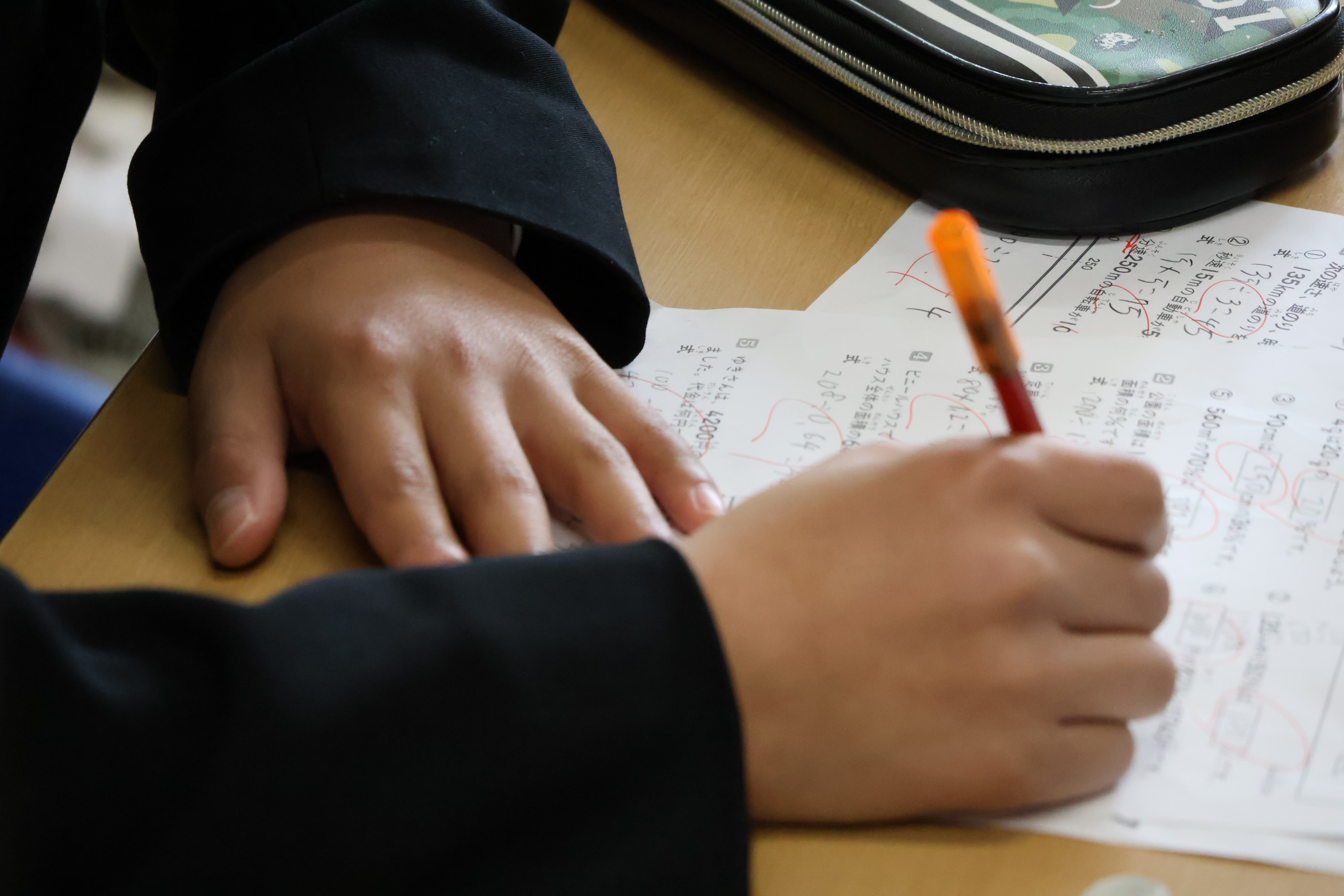
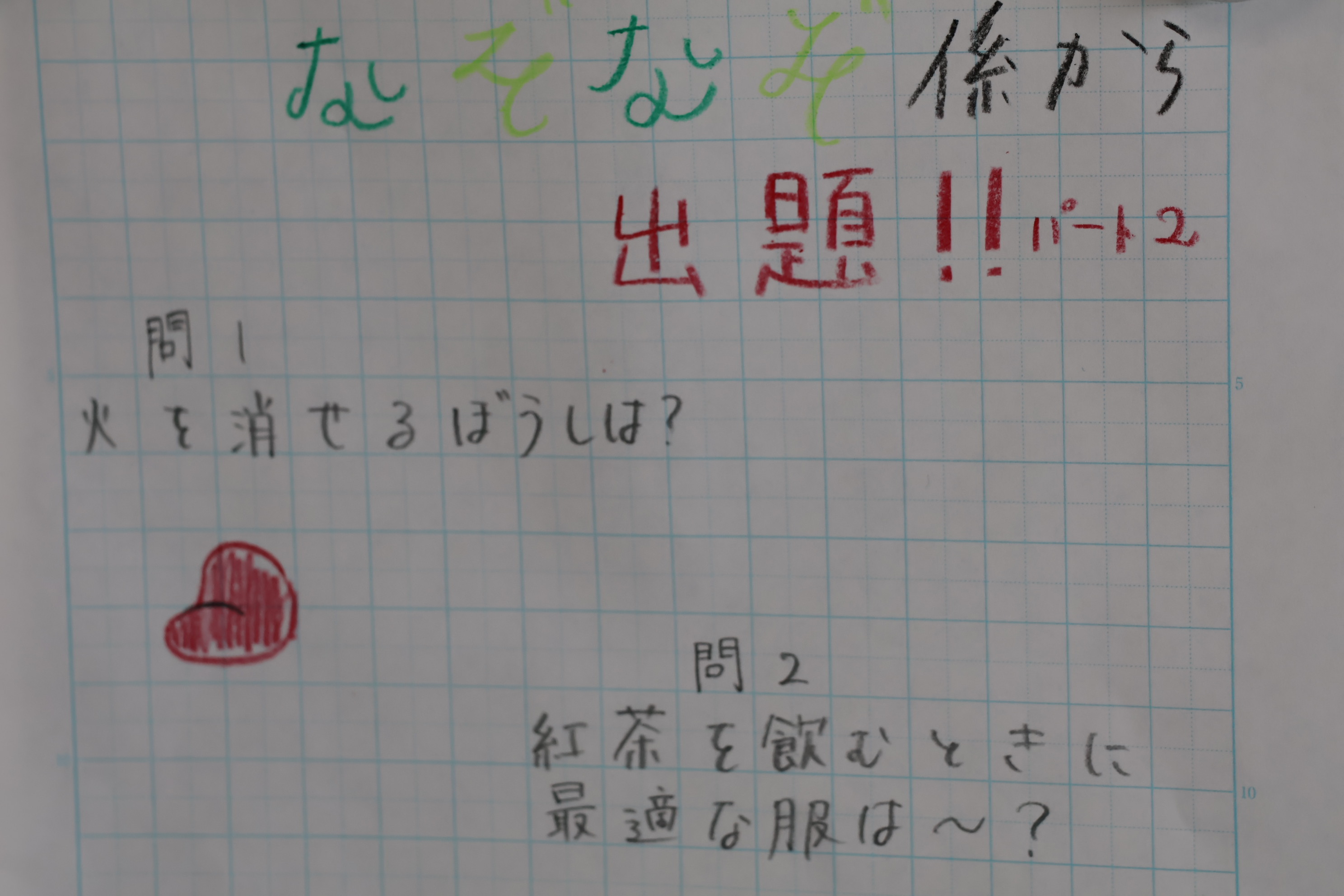

小学校の卒業証書授与式は、3/19です。午後からは、本校で新入生物品販売をおこないます。
◎ありがとう


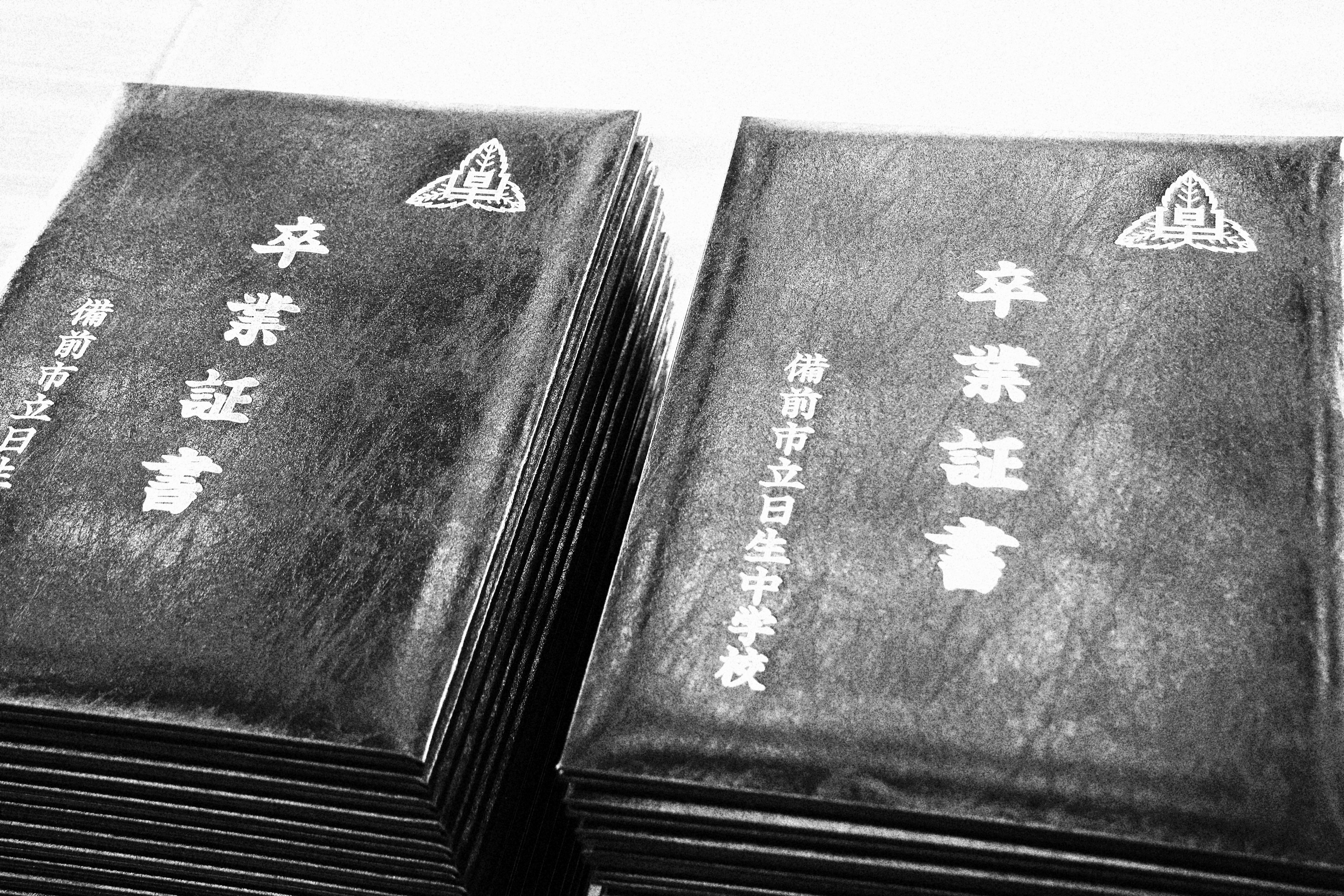












そして さようなら(3/14)
◎引き継ぐということ(3/13)

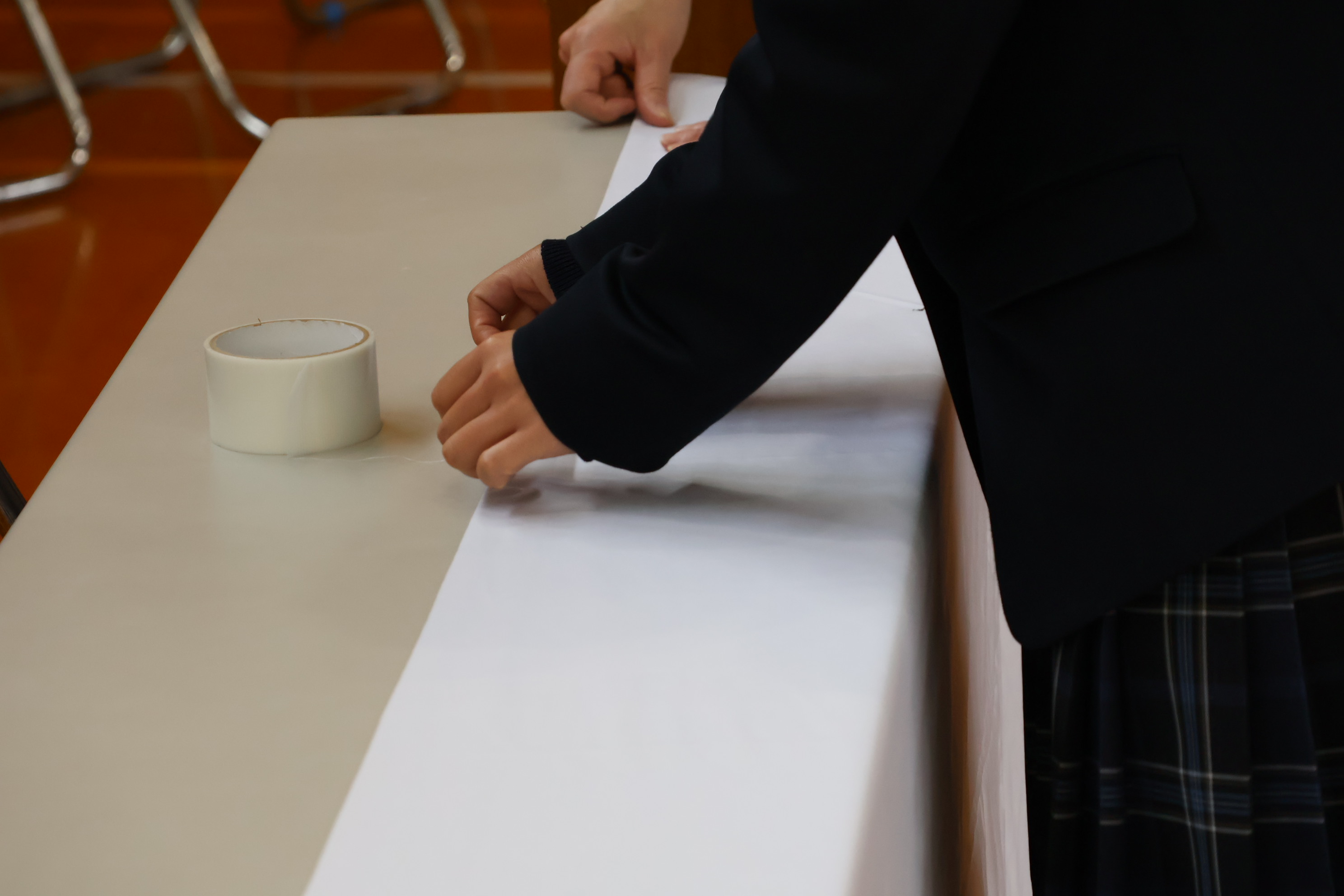




◎大切なもの(3/13:明日は卒業式予行)
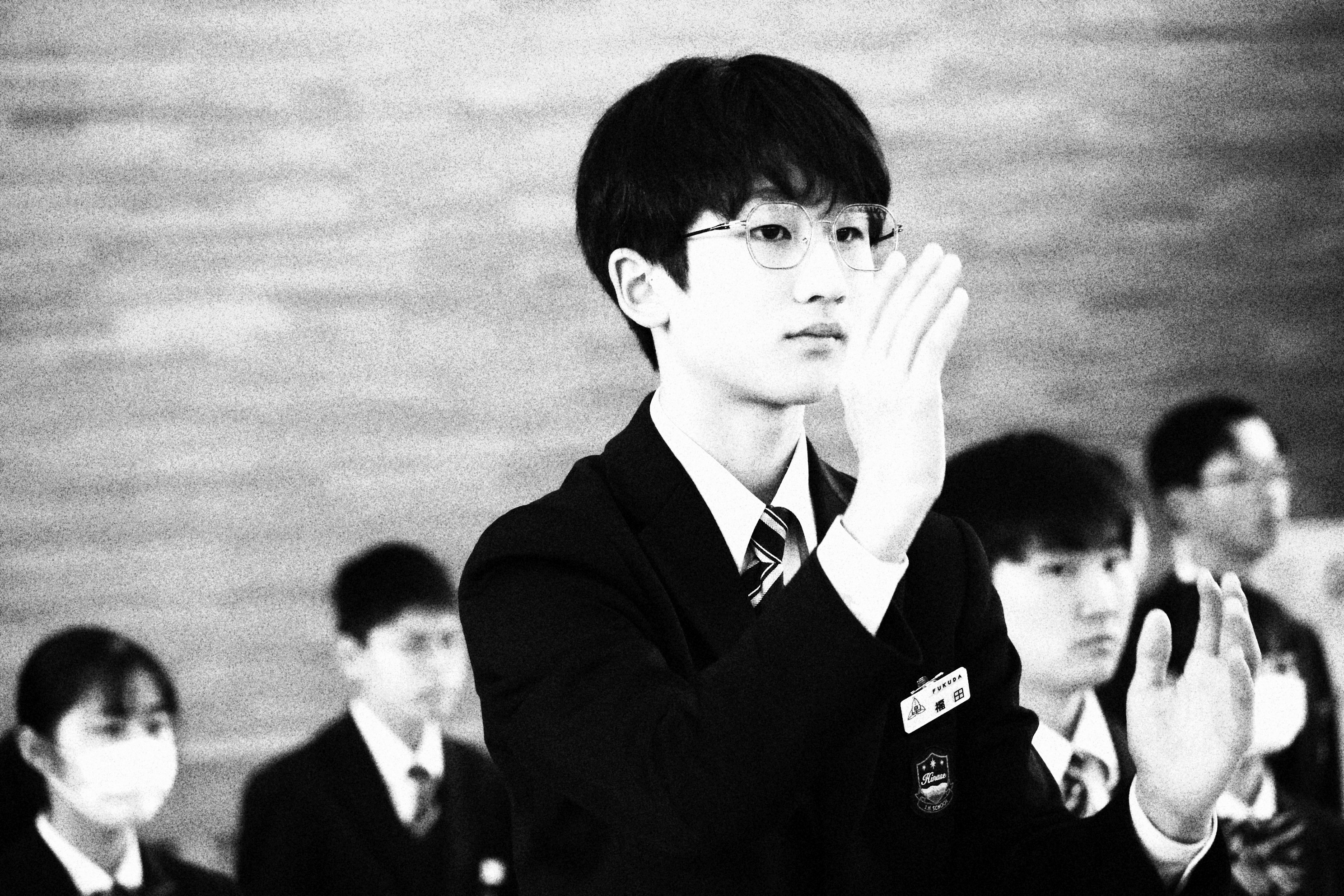


〈三月や草木萌動(そうもくきざしうごく)なりものの始めの予兆うれしも 青木昭子〉
◎澄める心をさながらに(3/13:明日は卒業証書授与式)




今日は生徒会プレゼンツ、3年生を送る会。
◎ありがとう私たちの先輩(3/12在校生ボラ清掃)
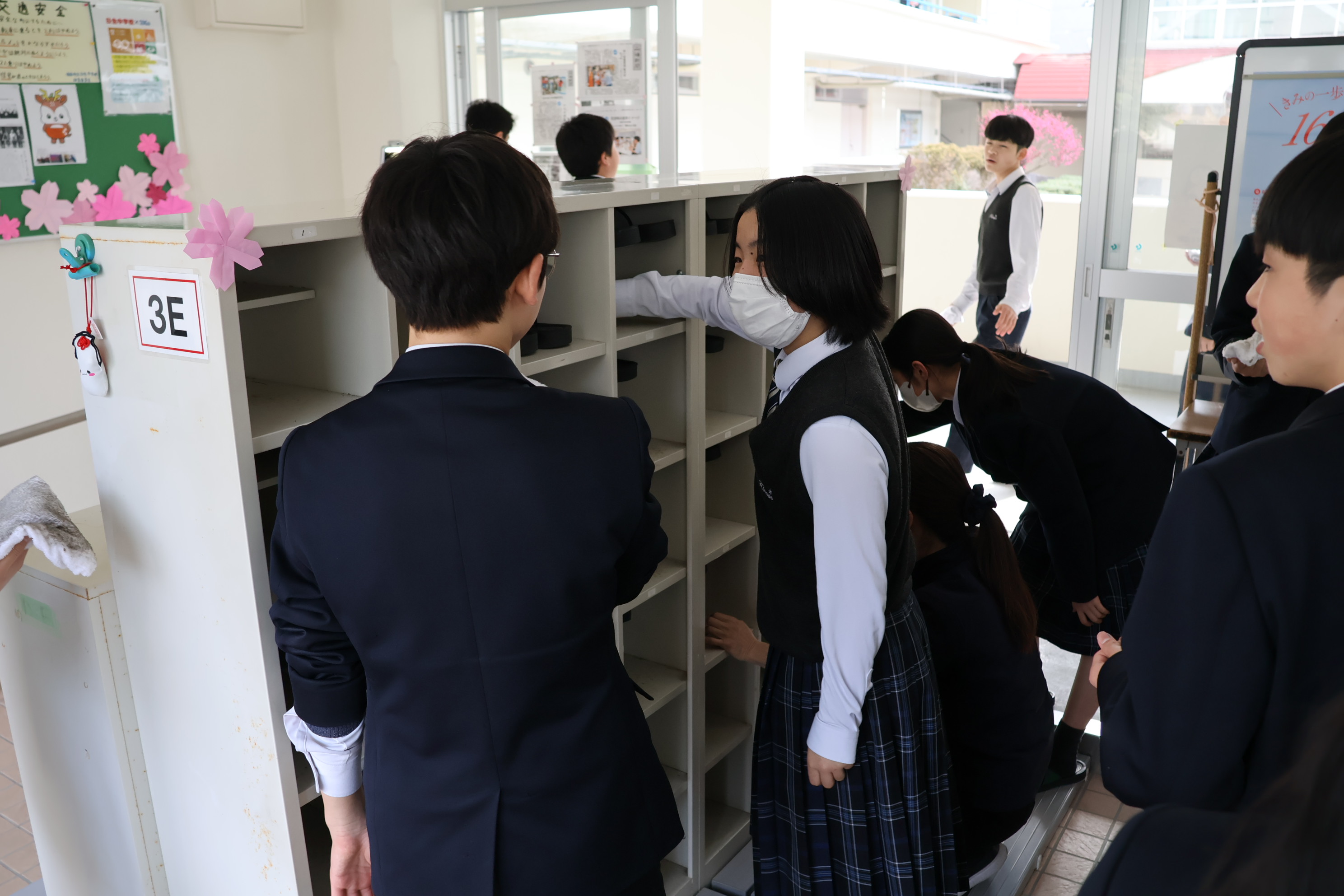


◎ありがとう私たちの学び舎(3/12:三年生清掃)








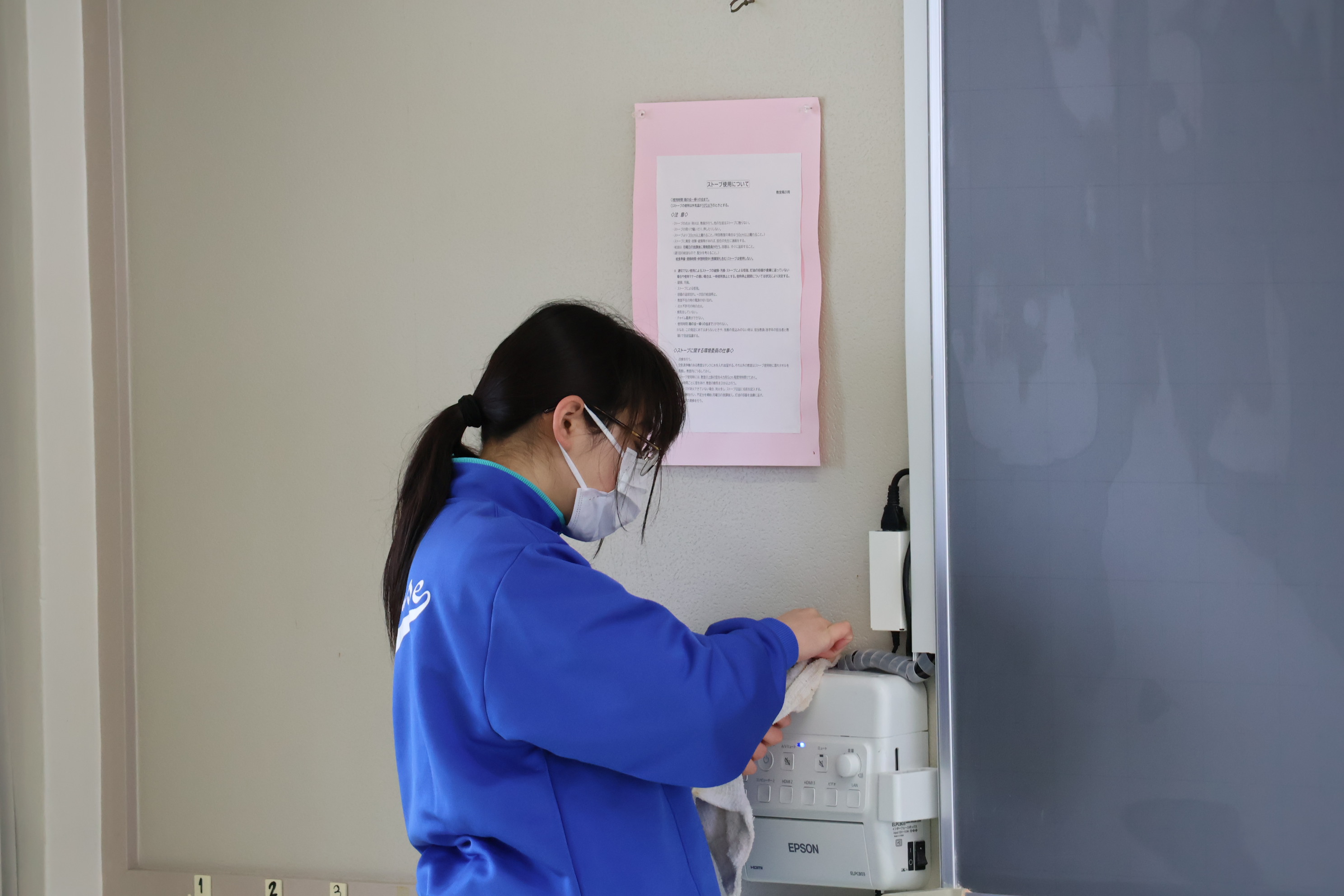



◎次は私たちだ。毎日の生活が進路を切り拓いていく(3/12)

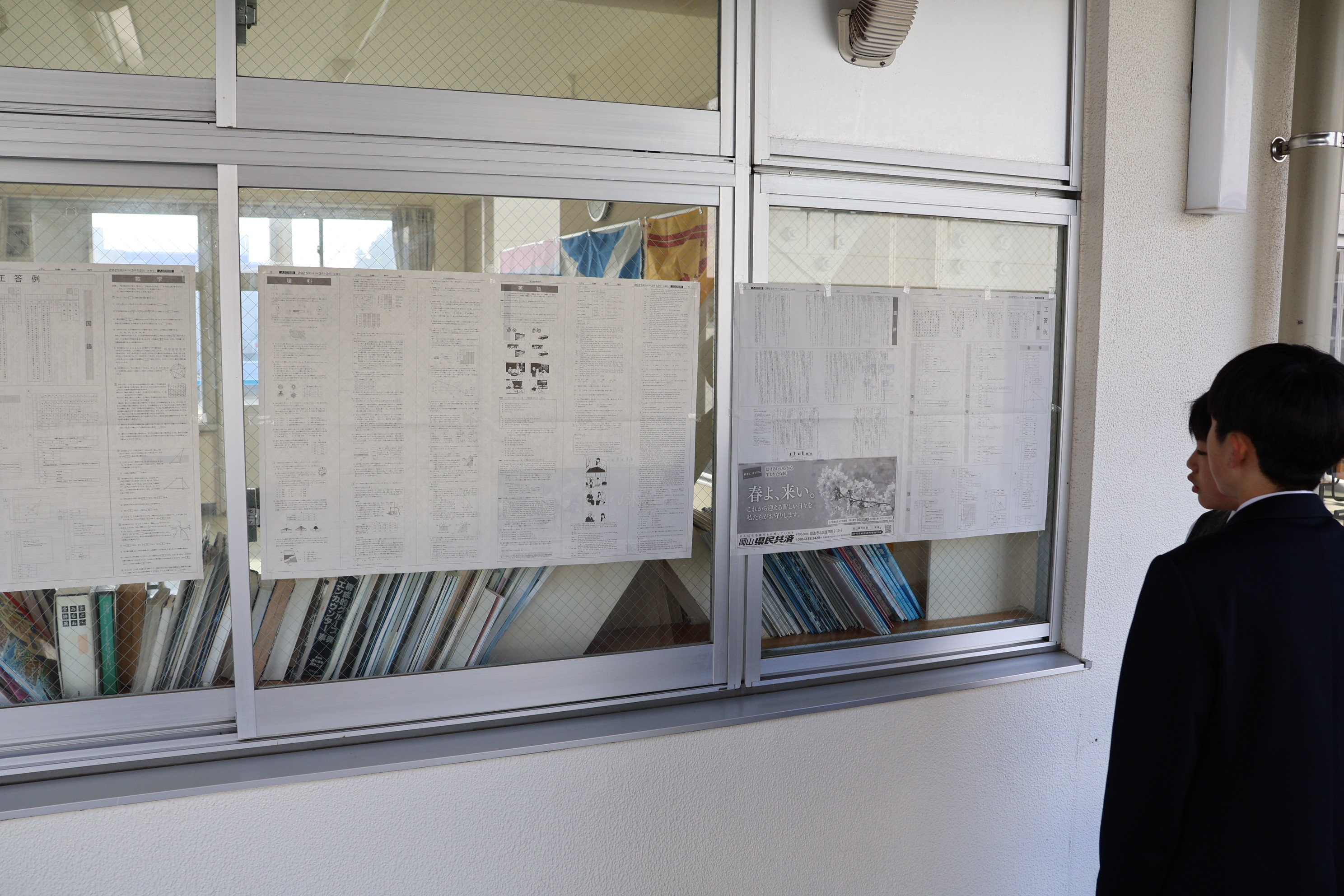

「これ、解けるよ!」出題された問題を仲間と見合う。(山陽新聞の県立入試問題掲示中)
◎祝 完成! (3/12)
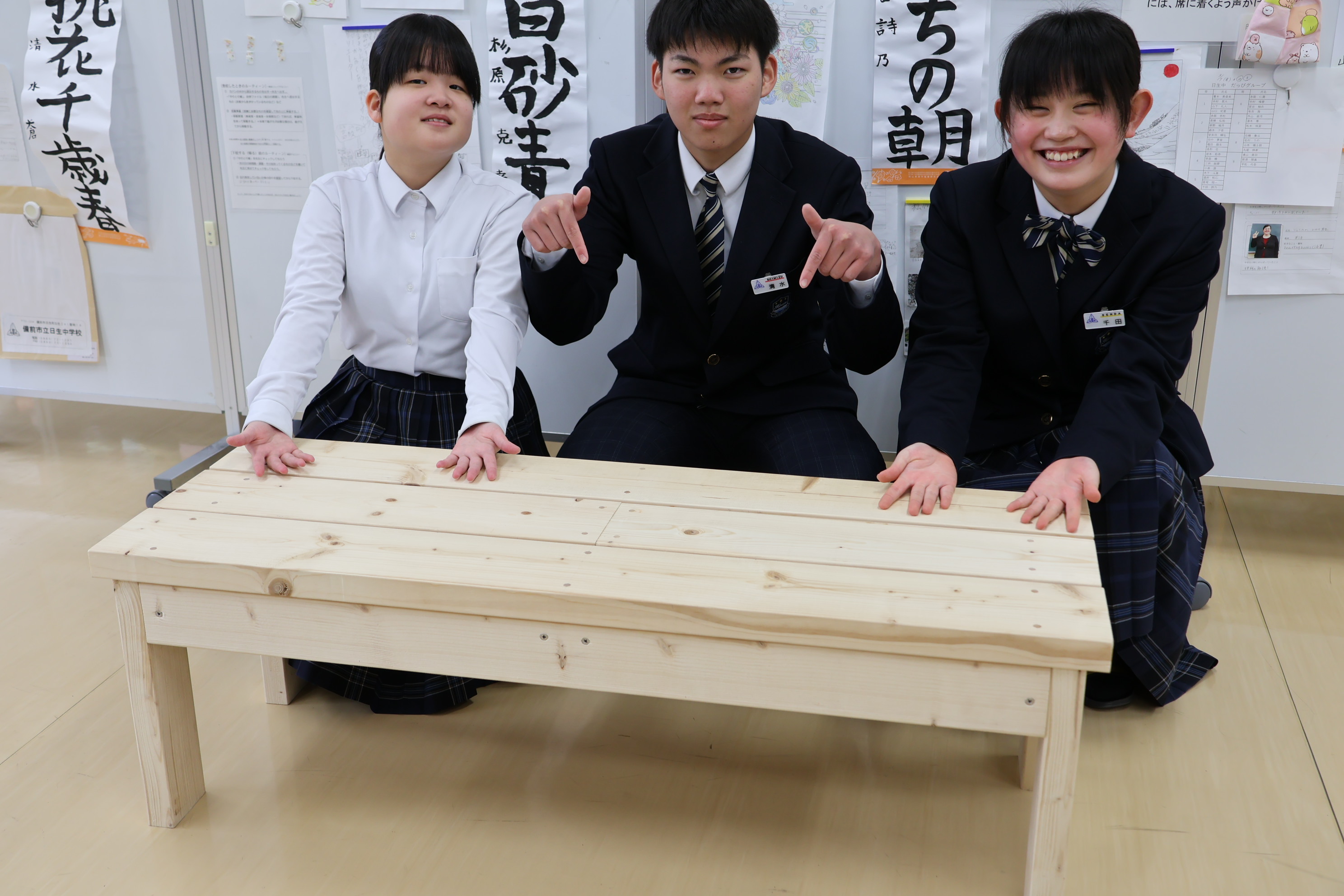
技術の授業でみんなで作りました。やっと出来上がりました。〈憩いのひな中ベンチ(仮名称〉として使ってくださいね。
◎挑む!県立一般入試(3/11~12)


友よ! 自分らしく せいいっぱい がんばってこよう

◎3.11東日本大震災を忘れない


東日本大震災から13年
〈東日本大震災・原子力災害伝承館のHPから紹介します。〉2011(平成23)年3月11日に発生した東日本大震災から丸13年となりました。
東日本大震災・原子力災害伝承館は犠牲となった方々の御霊に、深い哀悼の意を表しますとともに、今もふるさとを離れて避難生活を強いられている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
2011年3月11日に何があったのか。覚えていない世代や、生まれていない子どもたちも増えてきました。この日、午後2時46分に三陸沖を震源としてマグニチュード9.0、最大震度7(福島県内は震度6強)という日本観測史上最大規模の地震が発生。大津波が東日本の沿岸部を襲い、東京電力福島第一原子力発電所事故が起きました。
東北を中心に北海道から関東地方にかけた広域かつ甚大な災害となり、死者は19‚775人、行方不明者は2‚550人に上ります。
福島県では4‚174人がお亡くなりになり、このうちの2‚343人が避難生活での体調悪化や過労など間接的な原因で亡くなる「震災関連死」で命を落としました。震災と原発事故から14年目を迎える今も7市町村に帰還困難区域が設定され、2万6千人を超える方々が避難生活を余儀なくされています。
昨年から帰還困難区域内に特定帰還居住区域が認定されるなど、復興に向けて一歩ずつ前進はしていますが、原子力災害は現在進行形です。
福島第一原発で発生し続ける処理水や廃炉、放射性物質を取り除く除染で出た土壌の県外最終処分のゆくえ、風評被害への対応など、多くの課題が山積しています。
今年1月1日には最大震度7の能登半島沖地震が発生し、死者241人、避難者は今も1万人を超える大きな被害を受けています。自然災害はいつ、どこで起きてもおかしくないのだと改めて意識するとともに、災害を過去のものとせず、未来へ向けて教訓を伝え続けることが重要だと再認識しました。
伝承館はこれからも、福島で起きた未曽有の複合災害と、復興に向かう姿を伝え、教訓を未来へつないでまいります。
◎私たちの星輝祭に向けて
多くの人に支えられて(3/10)



◎限りある日々を 仲間とともに(3/10)
今 君が見上げる空は どんな色に見えていますか?
友 僕たちに出来ることは 限りあるかも知れないけれど
確かな答えなんて何一つ無い旅さ 心揺れて迷う時も
ためらう気持ち それでも 支えてくれる声が 気付けば いつもそばに


◎多くの人に支えられて(3/10)
体育館入口の外壁の修理を、卒業式に間に合うように工事していただいています。ありがとうございます。



◎みんな!今日もおはようおはよう(3/10 )


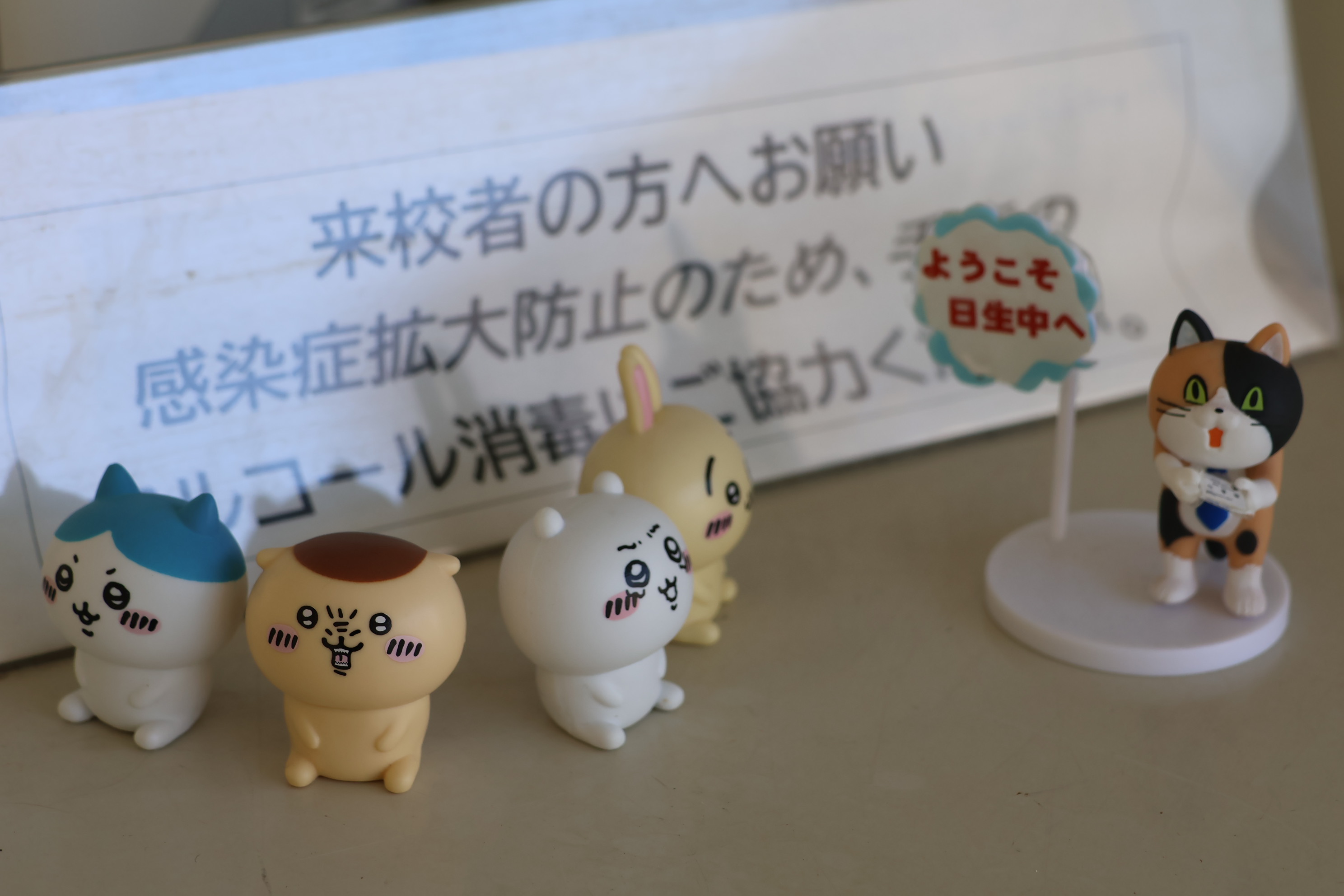
三年生のメンバーは、今日であいさつ運動がおしまいです。今週末(3.14)は卒業式です。
◎つながるわたしたち(3/9:備前♡日生マラソン大会 )



天gooカフェさんと一緒に大会をサポートさせていただきました。
◎流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます せわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く 3月の風に想いをのせて桜のつぼみは春へとつづきます♪
(3/9)
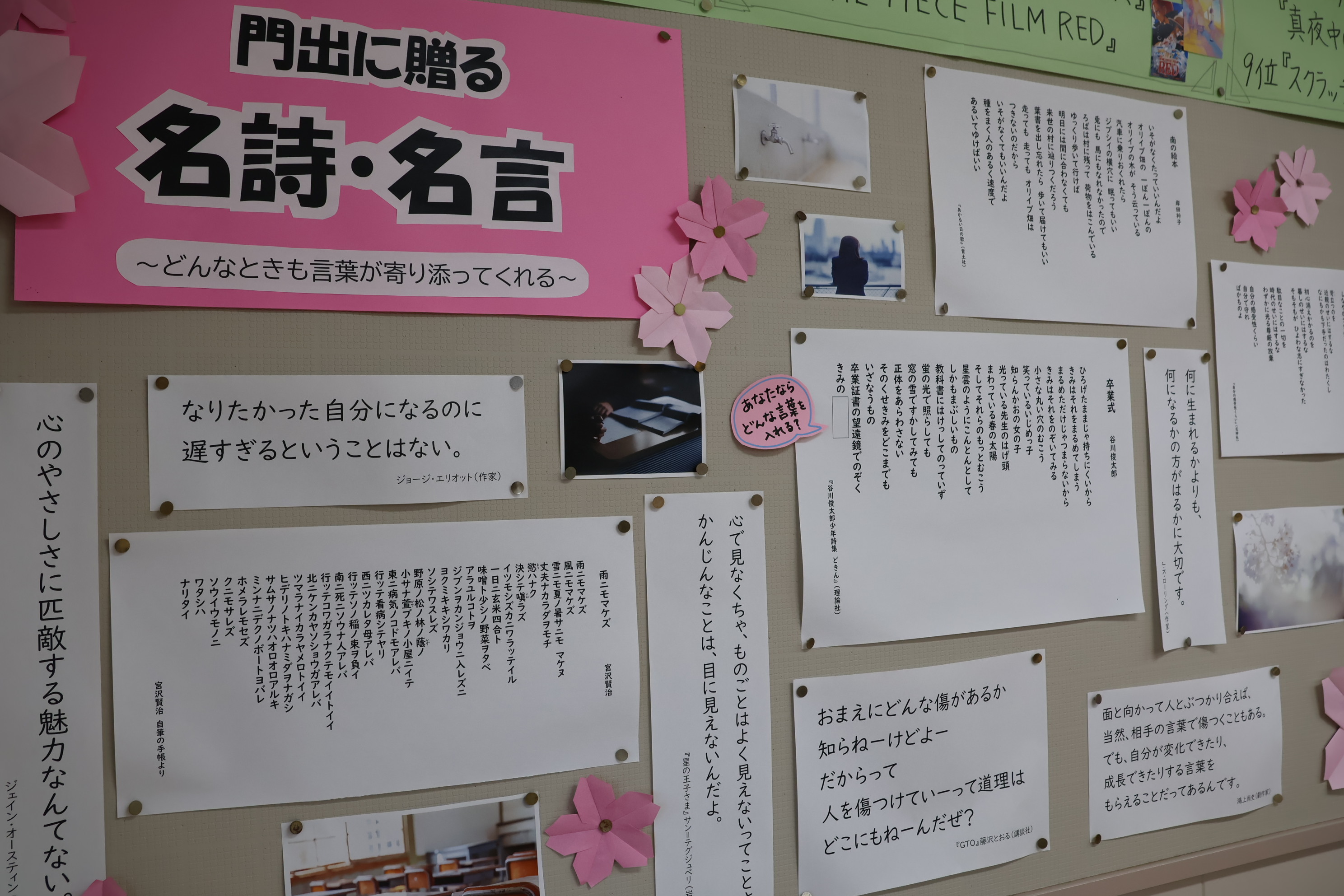


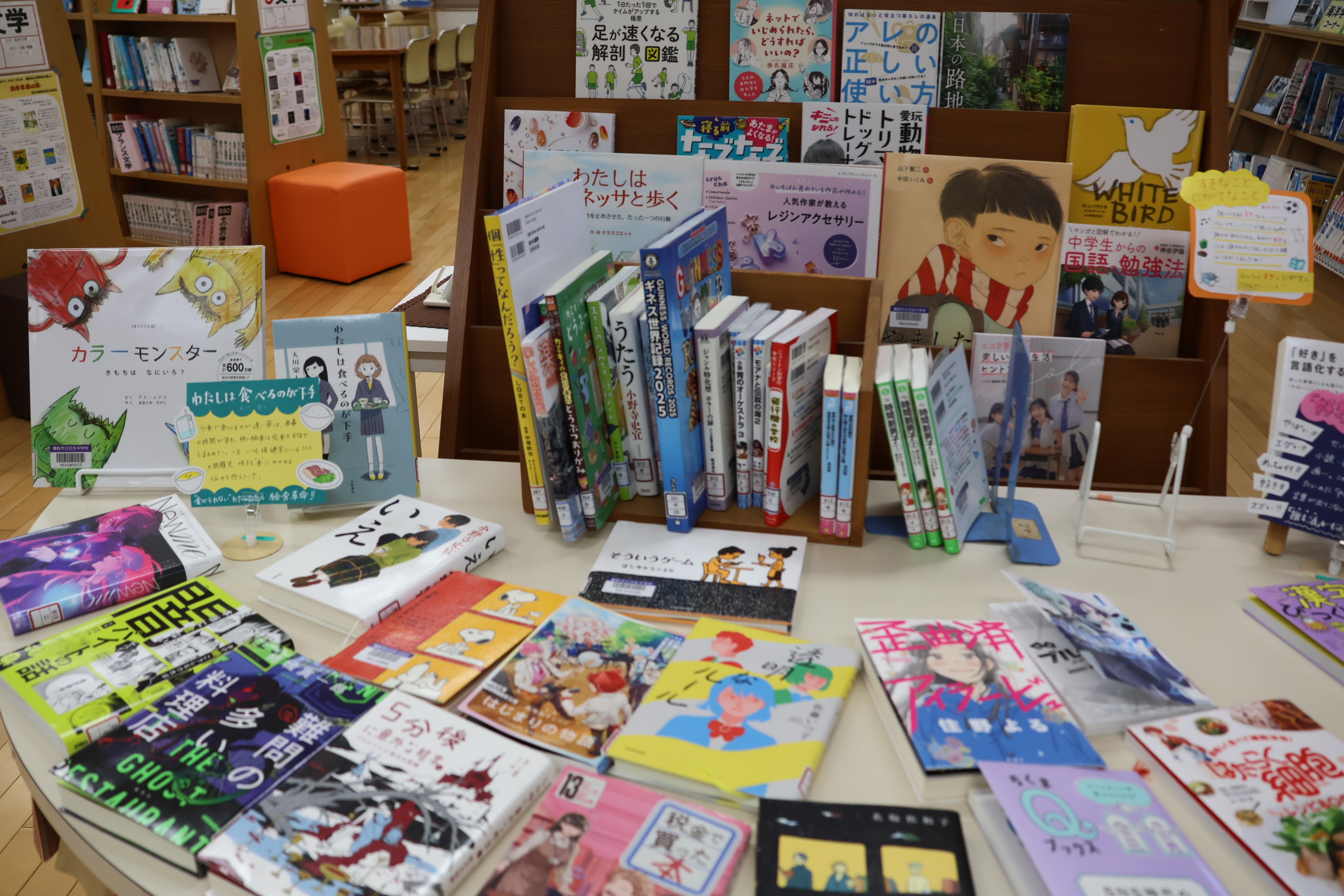
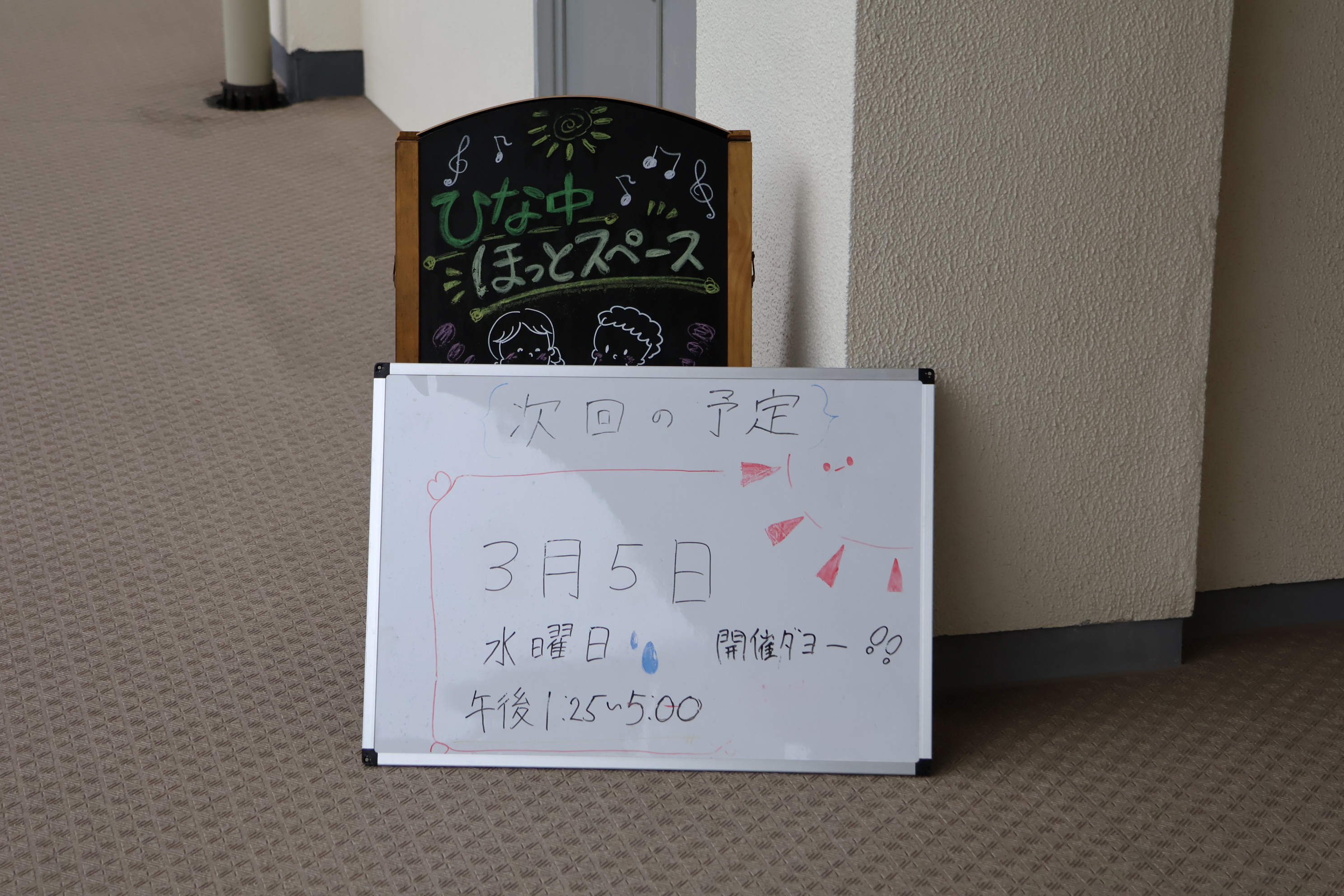

◎出会い+対話×(私×大学生×大人)=なりたい自分を考える
7日、多くの方々のご支援・ご協力で、日生中だっぴを実施することができました。ありがとうございました。


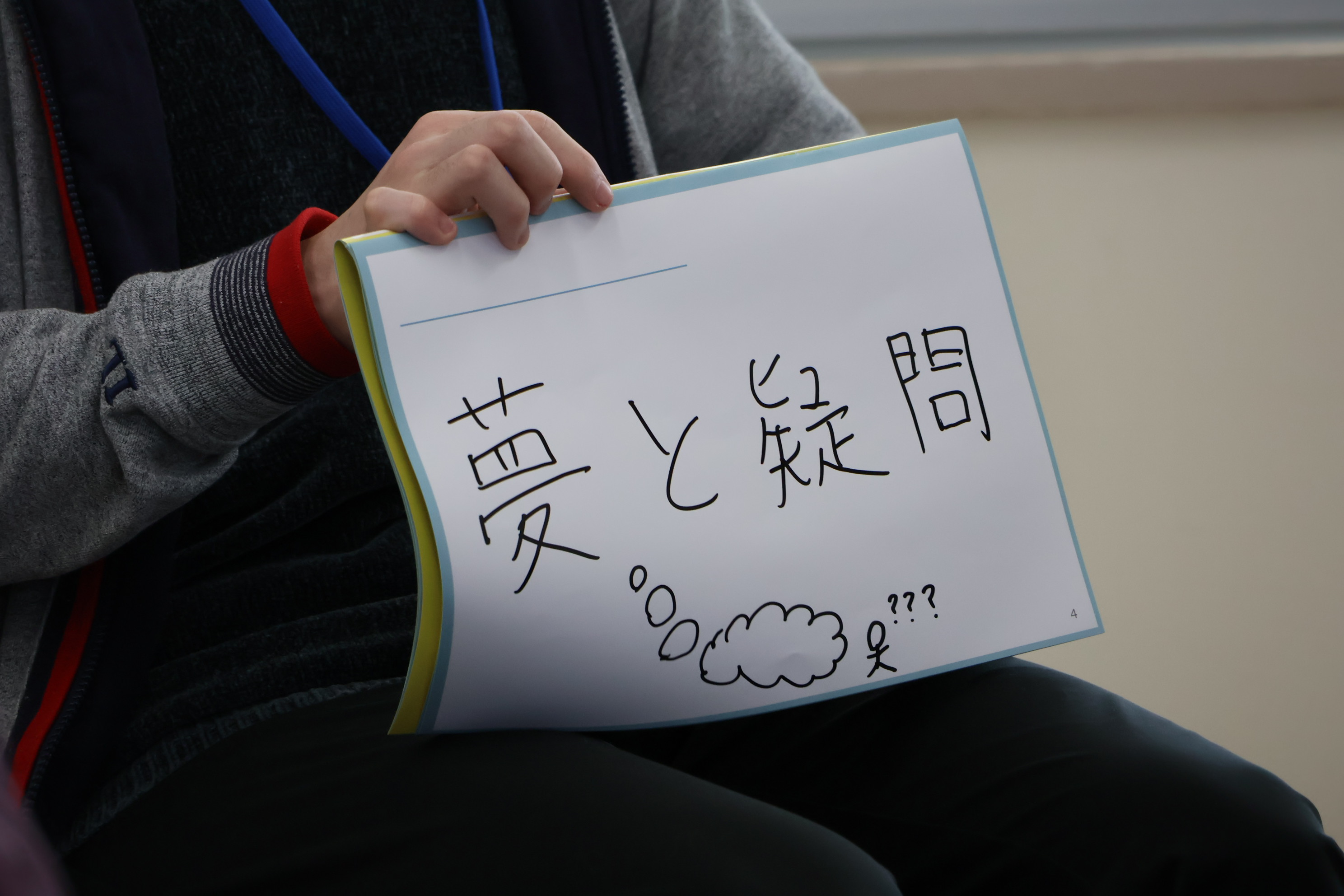
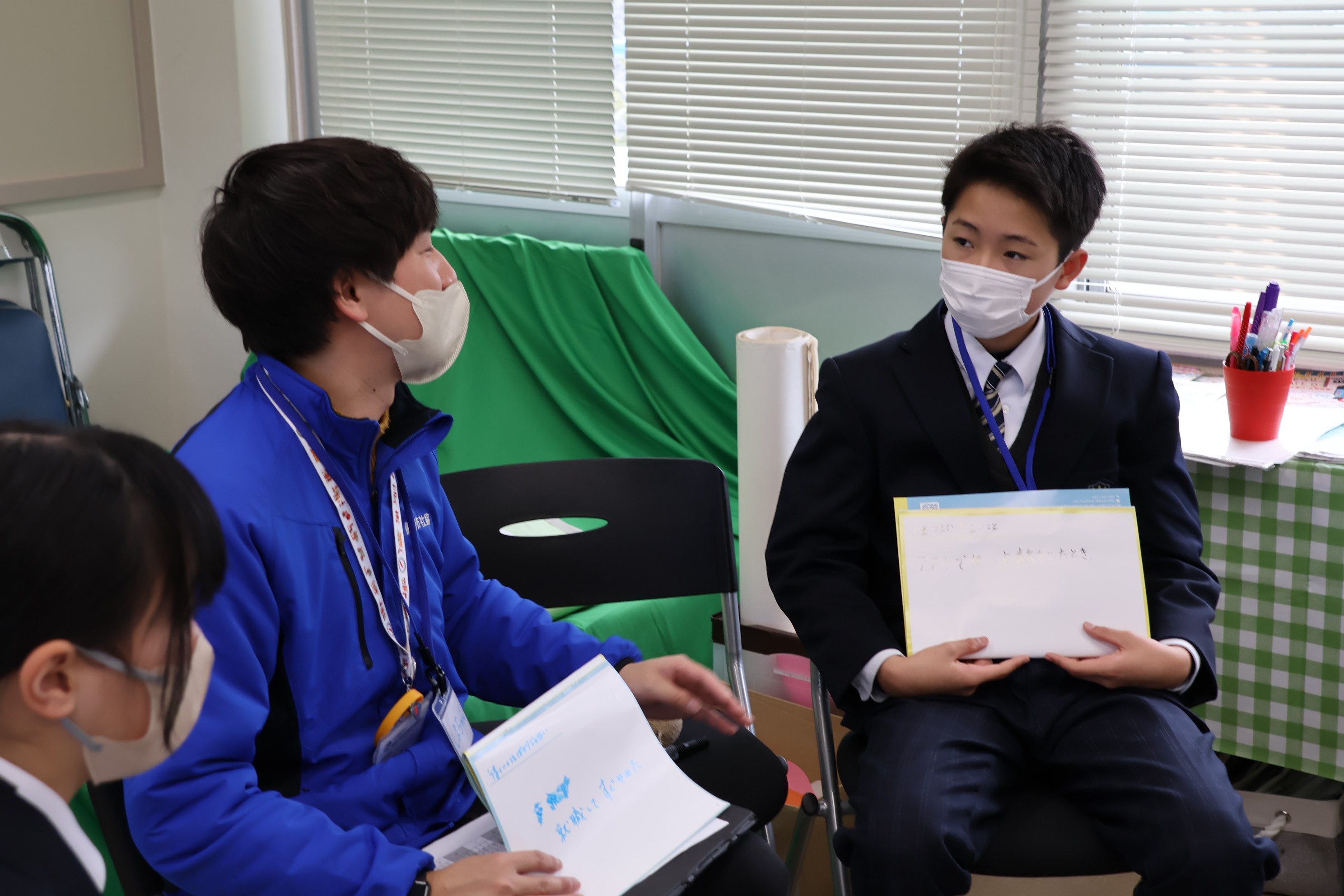
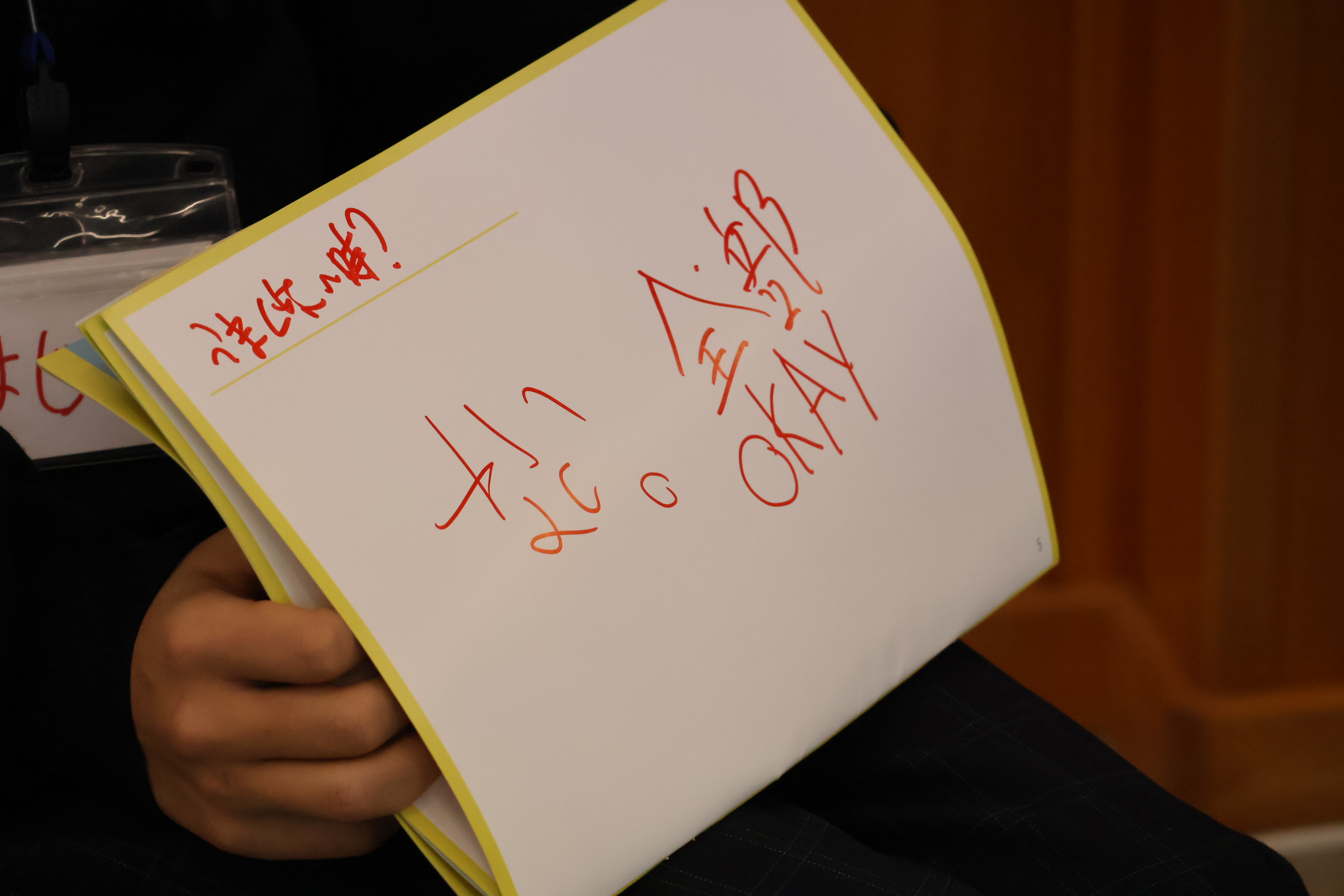

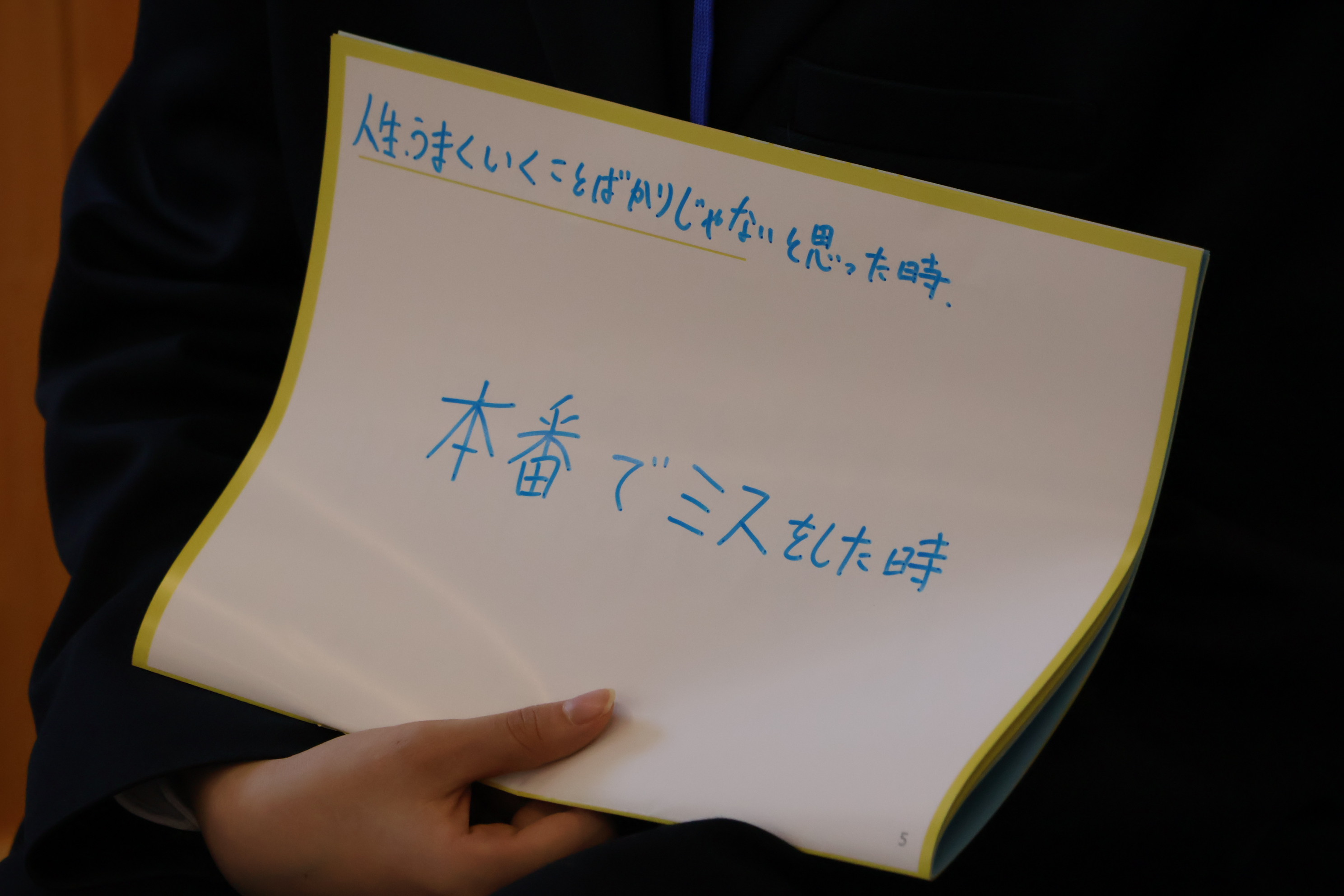


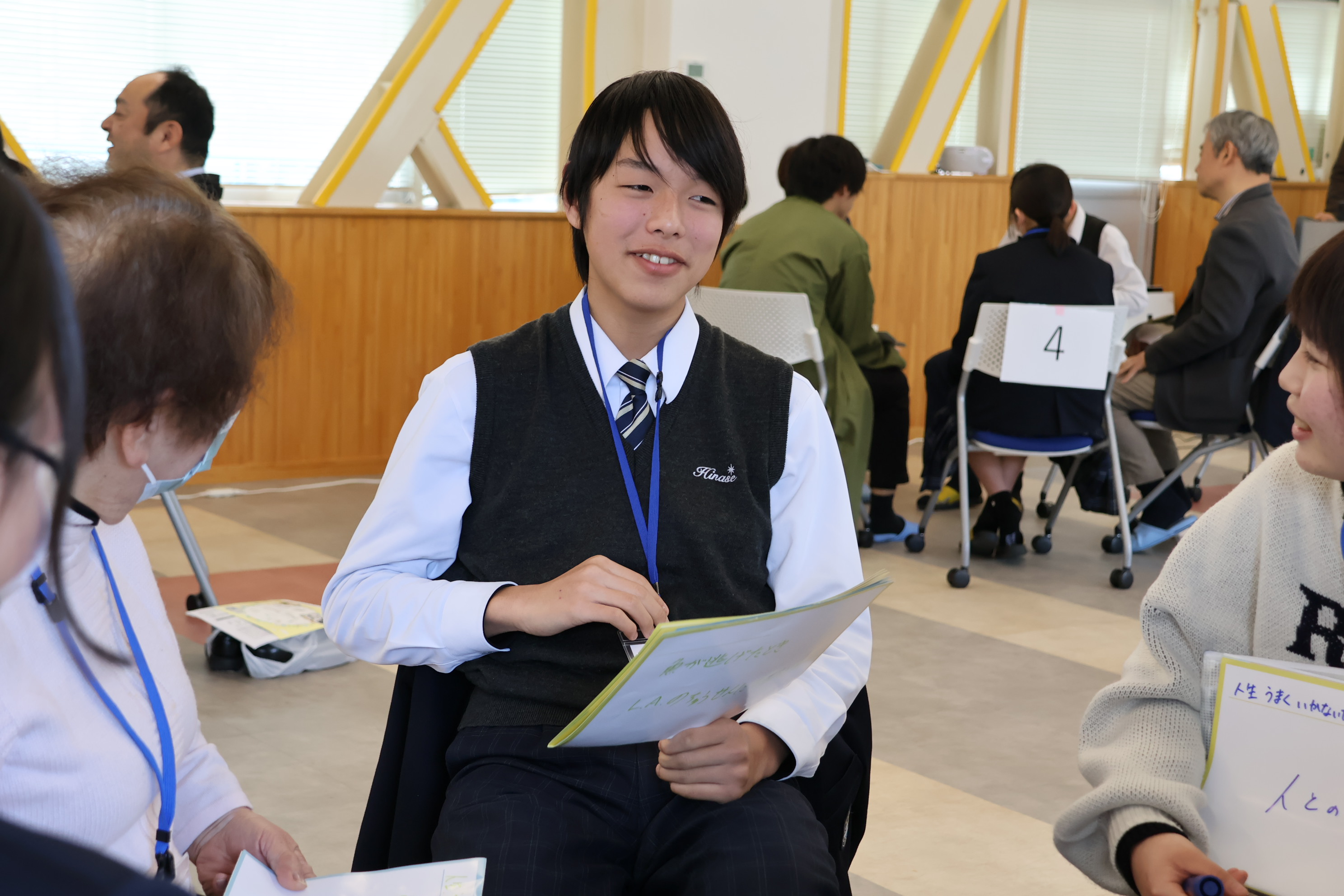


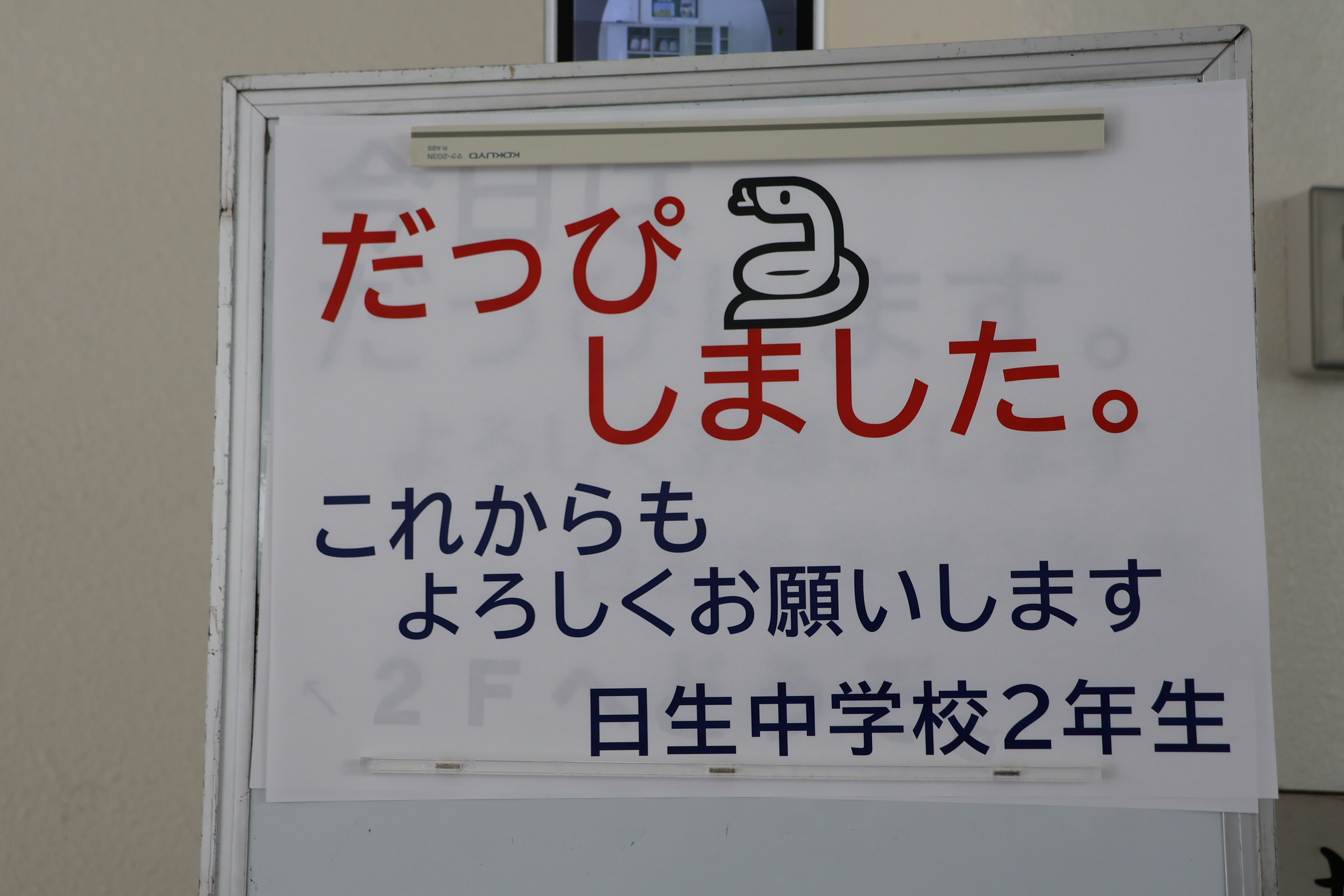
◎「しかみん」です。
~地域と共にある学校(3/7)
備前市社会福祉協議会のマスコットキャラクターのネーミング公募で、本校の山下さんが考えたネーミングが採用(6名の一人)されました。この日、社協の嶋村さんからグッズを贈呈していただきました。ありがとうございました。

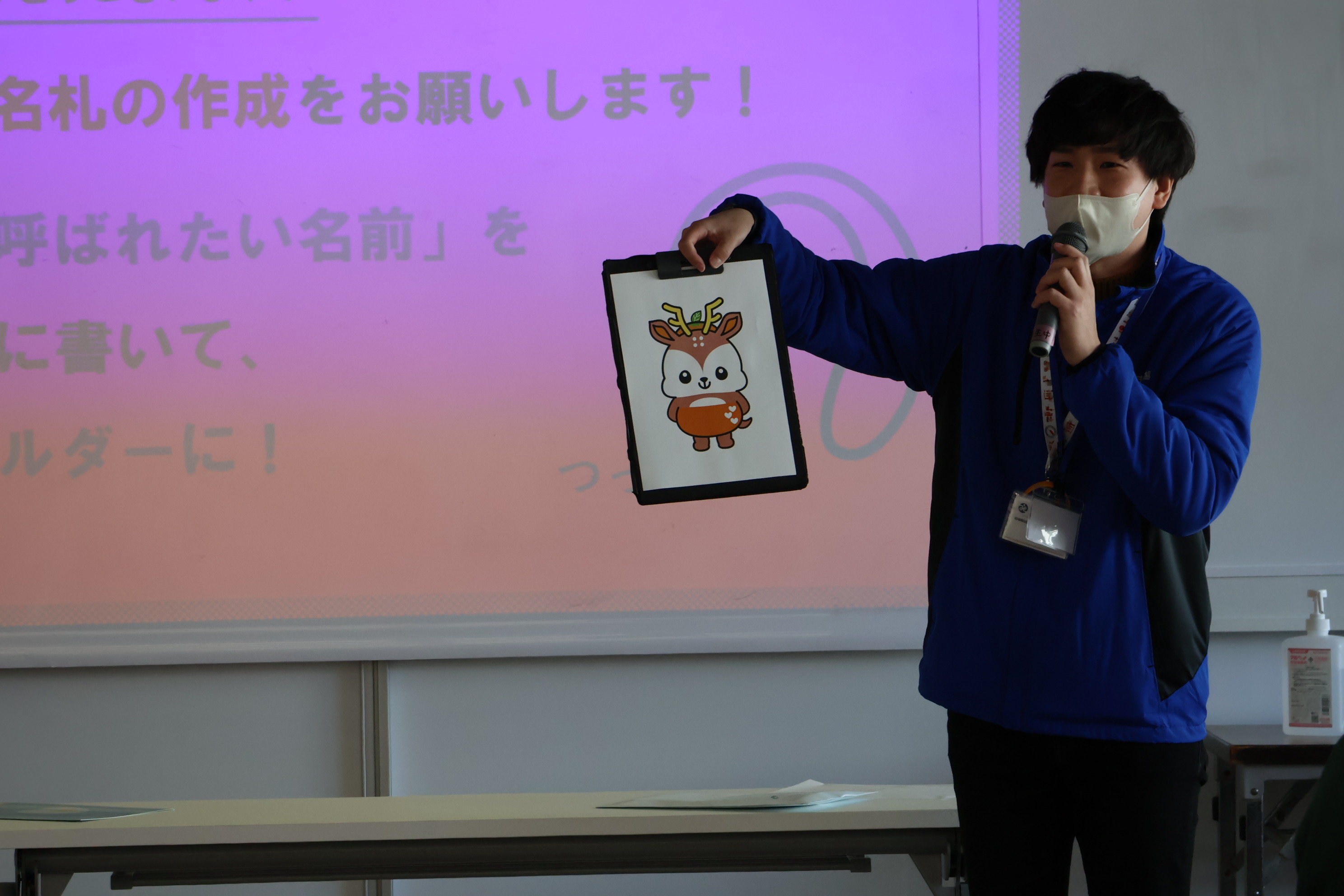

◎多くの人に支えられて(3/7:日生中だっぴ)

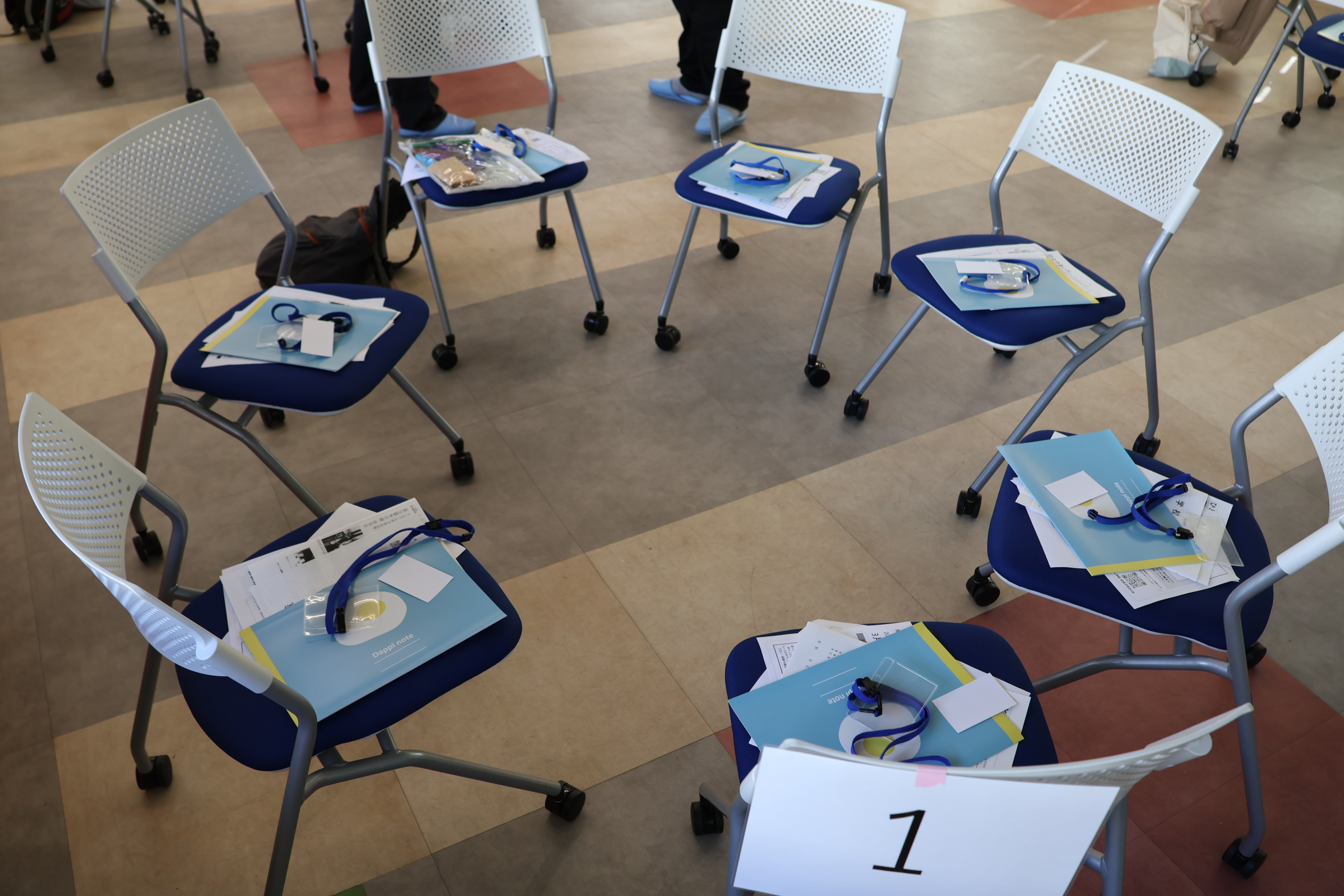

◎備前♡日生マラソン(3.9)を私たちは応援します。
ボランティアスタッフや、出店スタッフとして私たちも参加します。



◎明日私たちは、だっぴします。(^O^)/
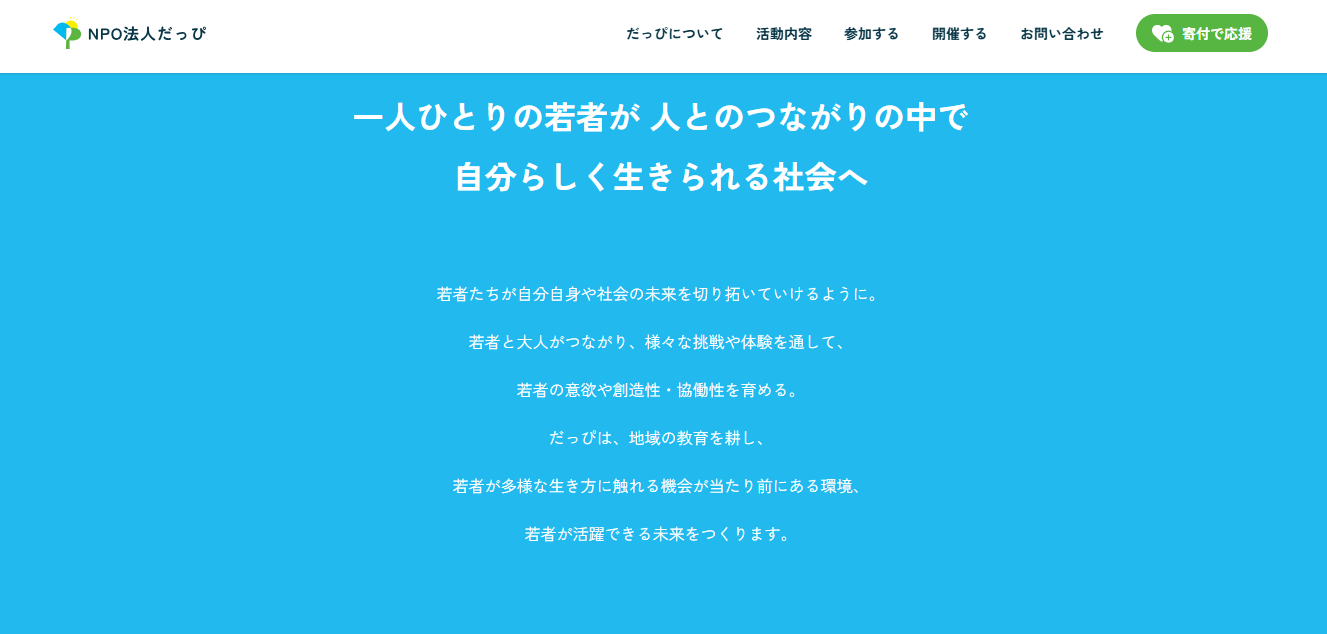
だっぴHPより
◎3.14旅立ちの日へ向けて(3/6)

◎豊かな学びをつくりだす われら日生教職員集団(3/5:校内研修)
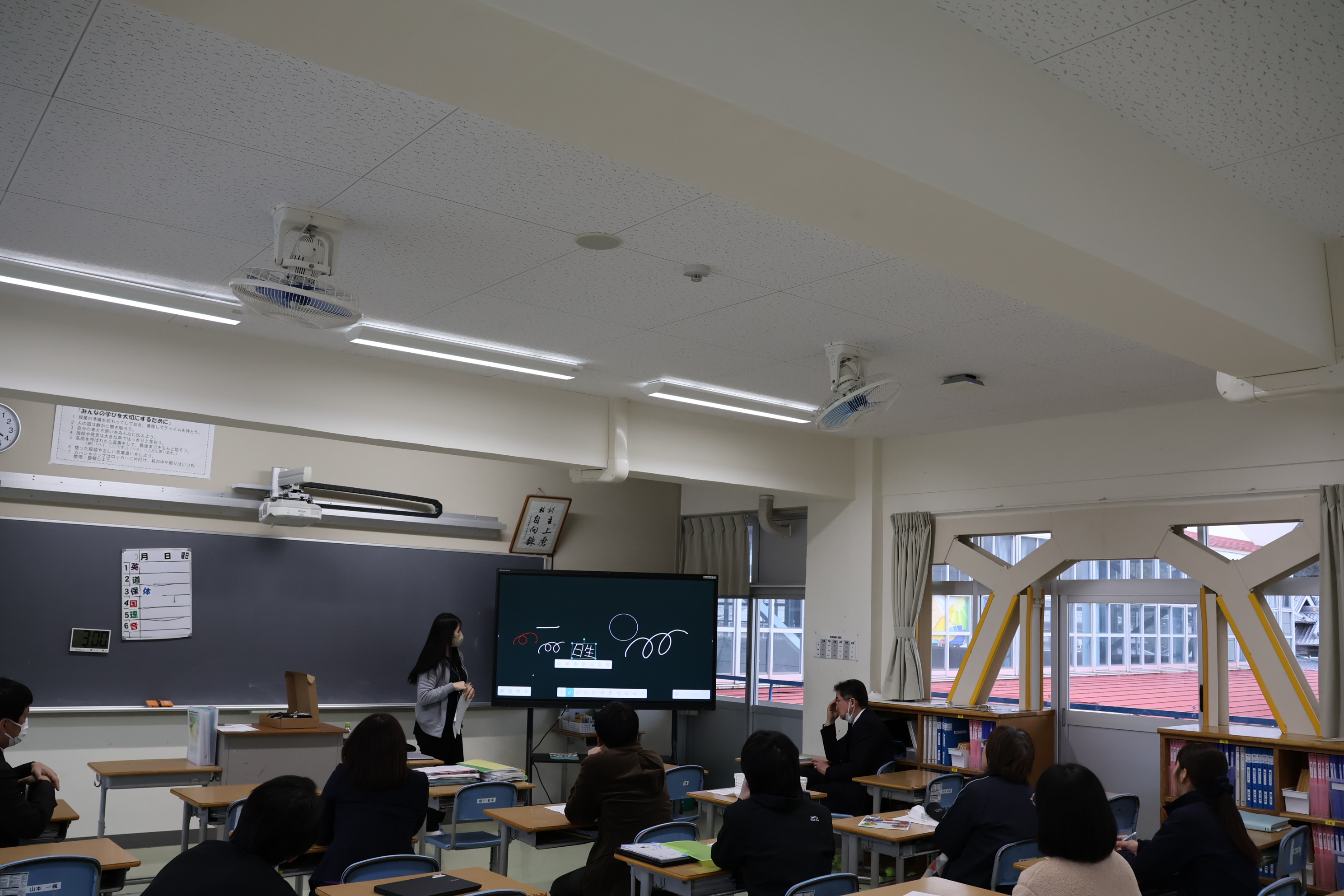


◎多くの人に支えられて(3/5)
今年度も、本の読みがたりのボランティアをありがとうございました。ステキな本との出会い、ステキな地域の方々との出会いが、未来を創っていきます。これからもよろしくお願いします。
また、ほっとスペースも、多くの方々のご尽力で開設することができ、地域協同の大切な拠点のひとつとなりました。今日は一年間の活動の振り返り会を行い、次年度以降の活動について協議しました。
地域の方々で、子どもたちとや学校との協同活動のプランや取組を考えておられる方がいましたら、ご相談ください。


◎子ども・学校・地域のミライへ
第2回PTA委員総会開催(3/4)
雨夜の中、来校ありがとうございました。PTA役員の皆さんと、今年度の活動のふりかえりと新年度の活動内容について協議をしました。次々年度(2026年度(R8))の組織改編案や役員選出方法についても意見を交わすことができました。一年間、PTA活動へのご理解・ご協力をありがとうございました。
役員の皆様もお世話になりました。ありがとうございました。新組織草案については多くの方々のご意見やアイデアをいただければありがたいです。PTA事務局(学校)までぜひご連絡ください。



◎歩み新たに 生徒集会(3/4)
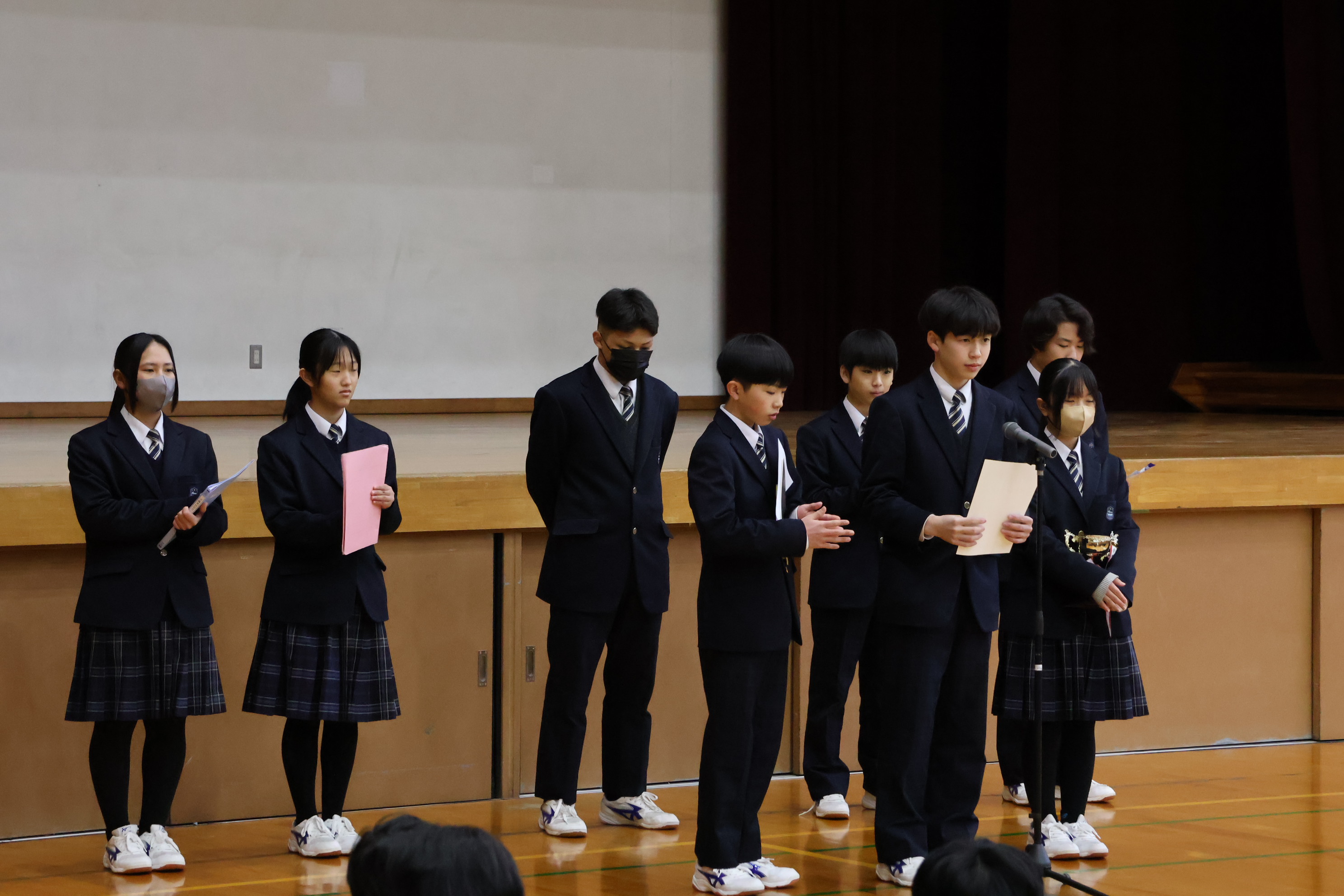

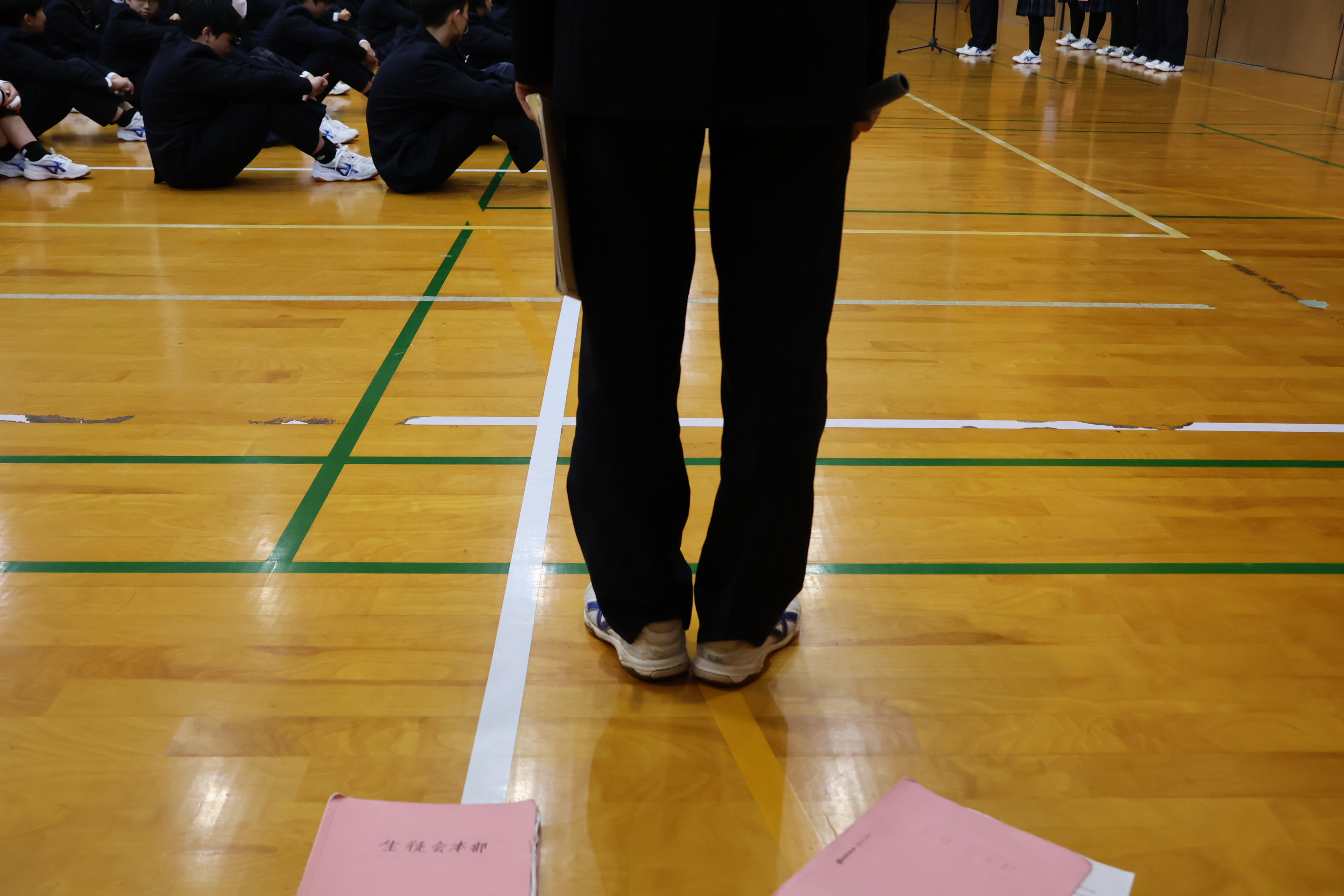
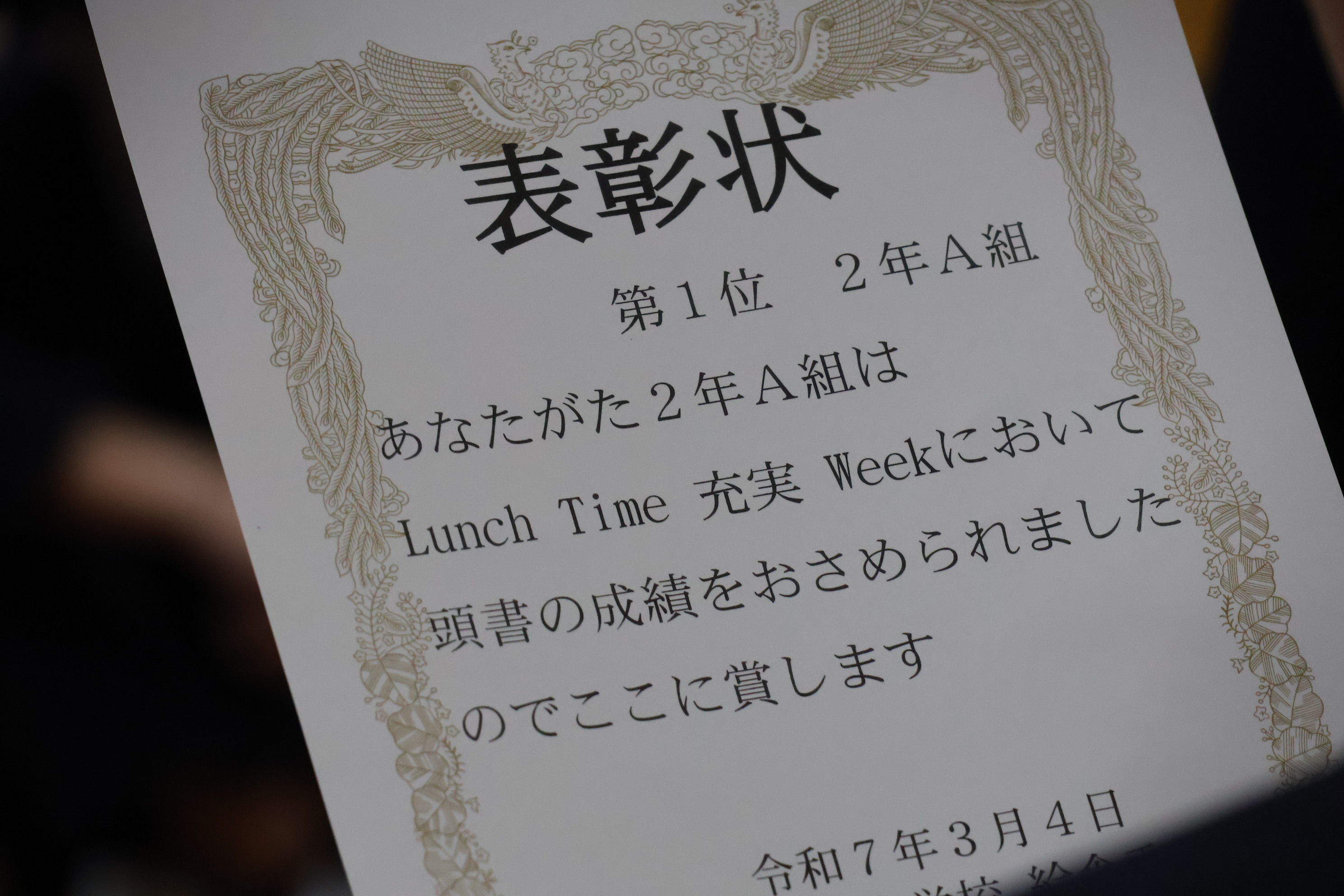

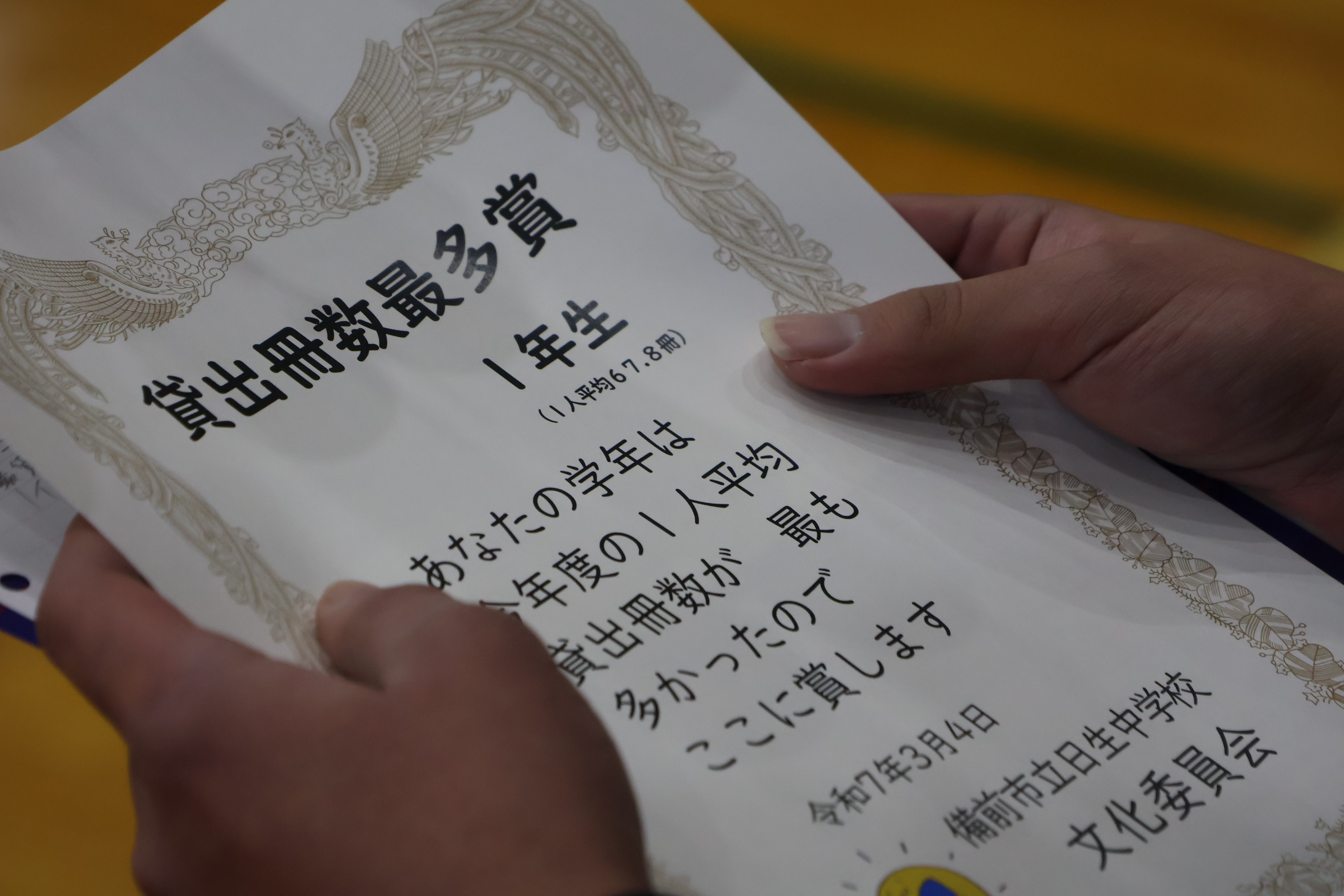






はじまりのほのぐらき地にのびゆける〈種をもつ草〉〈種をもつ実をつける果樹〉 横山未来子
◎私たちも学ぶ、教育を創造する(3/3)
備前市が導入した電子黒板についての研修会に参加してきました。明日の校内研修でも全教職員で学び合います。

◎寒のもどり(3/3)

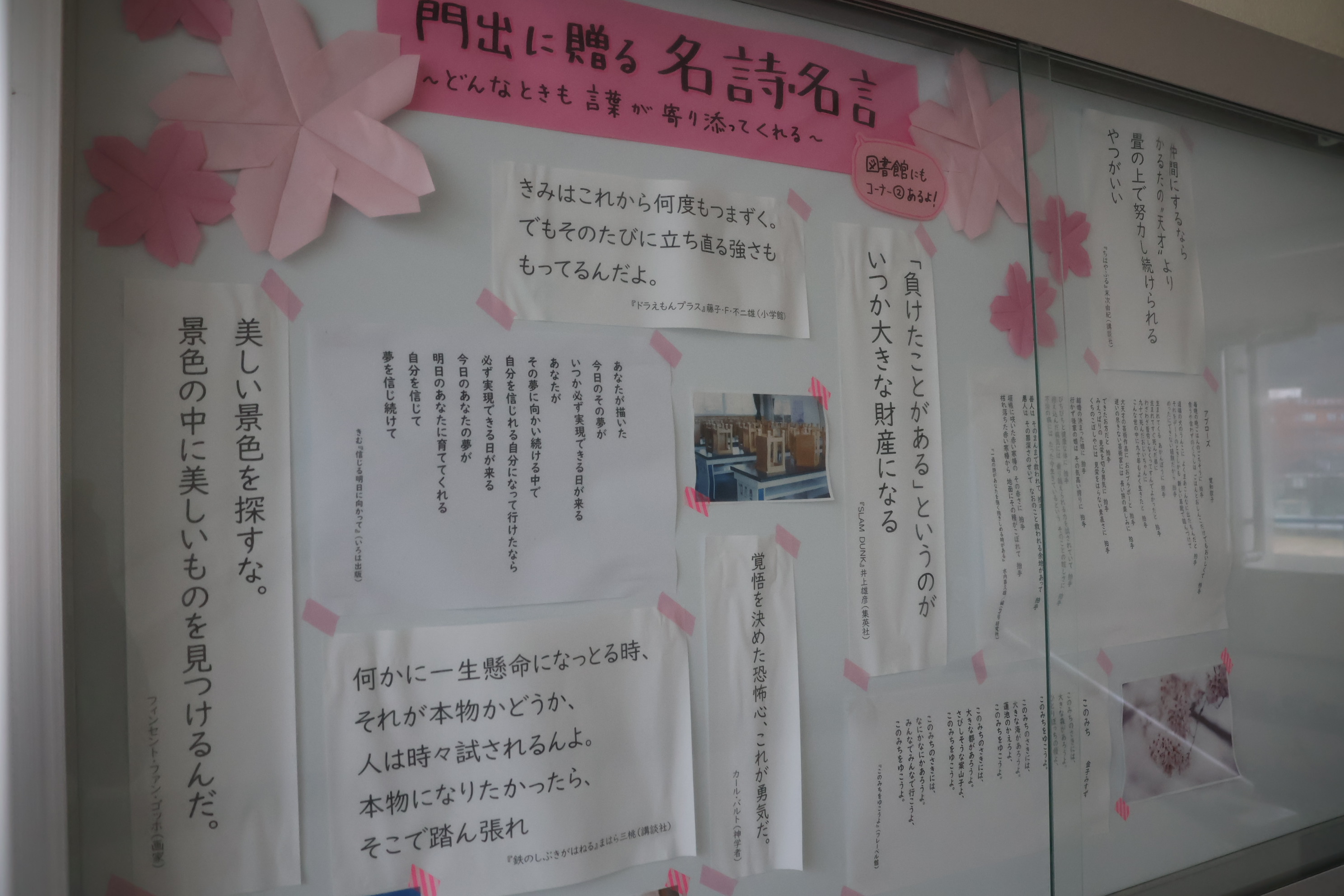




立春を過ぎたあとに冬のような寒さが戻ってくることを「寒の戻り」といいます。また、花見の季節の寒の戻りは「花冷え」という言葉が使われることもあります。
なぜ、寒の戻りがあるのでしょうか。それは、春が少しずつ暖かくなっていくものではないからです。春になると、大陸から偏西風に乗って移動性高気圧と温帯低気圧が日本列島にやってきます。移動性高気圧はポカポカと暖かい空気でできた高気圧です。そして温帯低気圧は、暖かい空気と冷たい空気が出合ったときにできるものです。この温帯低気圧は、温暖前線と寒冷前線を伴っていることがあります。温暖前線が通過したあとは、春一番に代表されるような暖かい南寄りの風が吹いて気温が上がります。しかしそのあとには寒冷前線が通過します。すると、今度は冷たい北寄りの風が吹いて気温が下がるのです。寒の戻りというのは、この寒冷前線が通過した後の状態ということです。春から夏にかけては、温帯低気圧が何度も通過し、暖かくなったり寒くなったりを繰り返しながら気温が上がっていきます。3月、4月はまさにそんな時期なのです。
この時期は週間天気予報を注意深くチェックしながら、どこまで厚着が必要かを判断し、賢く乗り切っていきましょう。
◎備前楷の木大賞 受賞✨
3月2日に行われた授賞式には生徒会の代表と校長が参加しました。とても名誉ある賞をいただきありがとうございました。これからも、多くの方々のご支援のもと、精進してまいります。本当にありがとうございました。


「地域と共にある学校」を目指して(再掲)
○活動のきっかけ、開始時期
長年、本校では、継続的・計画的に、総合的な学習の時間で日生地域での海洋学習に取り組んでいる。海洋学習は、5月:流れ藻の回収・カキの種付け、7月:漁業関係者の方々からの「聞き書き」、9月:アマモの種取り・播種、11月:小学生とアマモポット作成、2月:カキの水揚げ・洗浄・選別である。また、生徒会主催で7月と12月に行っている地域清掃ボランティア活動にはいつも50人を超える生徒が積極的に参加し、周辺地域と日生駅、幹線道路の清掃・美化活動を行っている。このような「地域」を意識した学習・活動は今後も大切にしていくが、生徒数の減少(クラス数の変化・教職員数の削減)に伴い、現在、本校では、教育課程や校内校務分掌の工夫改善や見直しの必要がある。そこで、これまで取り組んできた学校の様々な教育活動においても、整理・統合、再定義化を図り、試行的実践を行いながら、十五年先を見据えた「地域と共にある学校」づくりを進めている。
○活動内容(具体的な経緯・基盤整備)
1 PTAと協議し、ボランティア保険(全国社会福祉協議会)に全生徒加入のための予算化を図り、生徒が校外の活動に進んで参加できる学習環境を整えた。
2 社会福祉協議会日生支所と連携し、〈日生中ボランティア推進プロジェクト〉の体制を整えた。
3 2に合わせて、ホームページや学校便りにより、保護者や地域への情報提供・広報活動を行い、地域から学校へのボランティア(参画)依頼を募った。この活動で、「地域とともにある学校を目指して、未来のまちづくりのために、学校と地域が協働して、双方向での教育活動を推進していきたい。」という学校の思いを多くの方々に知っていただくことが出来た。
4 一般社団法人ジンジャーエールとNPO法人f..saloonと協働で、〈ひな中ほっとスペース〉を開設した。このスペースの目的は、地域でモデルとなる大人に出会うことで、豊かな生き方(ひと・モノ・コト)に触れたり、地域活動についての熱い思いを聴いたりする中で、シティズンシップ(市民性)の涵養、地域社会への関心を高めること、進路・進学の意欲を喚起すること等で、毎月第1・3水曜日には、スタッフが常駐、毎回20人を超える生徒が足を運んでいる。このスペースでの出会いは、生徒の大きな「地域社会への参画の入口」となっている。
(具体的な活動の中で)
1 3年生は、これまで総合的な学習の時間で取り組んできた海洋学習や地域学習の総括のひとつとして、日生地域の方々との協議(聴き取り等)を重ね、『日生の応援団』をまとめ、中学校のホームページでの情報発信を行った。
2 地域ボランティア推進プロジェクトを中心とした地域からのボランティア参加依頼(12月現在、21件の依頼)を受けて、のべ180人の生徒が地域のイベントや清掃活動に主体的に参加した。
3 社会福祉協議会日生支所との連携を密にし、7月と12月に行う地域清掃ボランテイア活動は、中学生(生徒会)だけで行う活動ではなく、川東地区協議会の方々と協働で実施することができ、ネットワークも広がった。
また、校内でもボランティア活動や地域学習の見直し・再定義を図り、地域ボランティアや地域協働活動への意識を高めることとなった。例えば、秋の交通安全週間に際し、校内での意識向上の取組はもちろんのこと、今年度は、地域住民にも交通安全を働きかける啓発ポスターを作成し、町内要所に掲示していただき、交通安全啓発活動に寄与できたのも教職員の高い意識の表れのひとつであると考える。
4 地域ボランティア推進プロジェクトを中心とした参加依頼で、生徒らが参加・参画したイベントや行事の主なものは、こども服・学用品リユース会、街頭での赤い羽根共同募金活動、カキかきフェスティバル、日生みなと祭り、頭島あかり祭り、てんてかんか、寒河秋祭り、日生文化祭、備前10代まんなか会議、歳末助け合い演芸会&楽市、もちつき大会(NPO法人こども達の環境を考えるひこうせん)、備前♡日生大橋マラソン大会(3月予定)である。「日生盛り上げ隊」として中学校で単独参加もするが、一般社団法人ジンジャーエール等の地域団体の出店スタッフとして参加するスタイルもある。また、頭島あかりまつりでは、実行委員会の方々が来校され、クラス全員で行灯の制作に取り組むなど、地域との関係性が密になる中で、より柔軟な活動・取組が展開できるようになっている。
○具体的な成果・活動の将来的な目標、展望
1 子どもたちは、地域社会での経験・体験を増やす中で、自分たちの住む地域の「魅力」をリアルに感じ取るだけでなく、地域の「課題」も自覚する貴重な機会となっている。それが、未来の担うためのシティズンシップ(市民性)の意識の涵養にも繋がっていくと考える。
備前10代まんなか会議に参加した生徒は、一般社団法人ジンジャーエールのサポートを受け、子どもたちの豊かな発想を生かした地域創出活動のチームを立ち上げて、活動を始めている。
2 「地域と共にある学校」は、学校や地域からの一方向の働きかけではなく、双方向のやりとりであり、地域社会で子どもたちを豊かに育てていく協働的な営みだと考える。
地域の方々の多くの支援を受けて、不登校傾向の生徒や他者とのコミュニケーションが苦手な生徒も、多様な(ボランティア)活動に参加している。このことは、生徒自身の自己有用感や自己肯定感が高まることとなり、生きていく大きな自信につながっている。
「学校」だけでなく、地域の中に「多様な活動の場」をネットワーク化するということは、「多様な学びの場」が在るということになる。今日的な学校現場での様々な教育課題の解決に向けては、チーム日生中学校として多機関連携・協働が必須であるが、そこには「地域」も包括したチームづくりを目指したい。
3 まちづくりに決まったゴールはない。地域の強みや課題と本校の教育課題を重ね、さらに豊かで確かな教育内容を創造していきたい。具体的な活動の中で「為すことで学び」ながら、「学びのまちづくり」を今後も粘り強く進めていきたい。
◎私たちの大切なまち・出会い・ひと
片上で開催された〈ひなめぐり 3月1.2日〉イベントに、ジンジャーエールさんと共に参加してきました。来場された方々、ご支援くださった方々、ありがとうございました。また、4/20に予定されている日生春のカキカキフェスには、<ひな中地域もりあげ隊>として参加予定です。一緒に私たちのまちを大切にしてい取り組みを進めていきましょう!


◎日に生(な)せば、今日は昨日の我ならず
2月28日に生徒評議会を開催し、専門委員会の再編について協議しました。

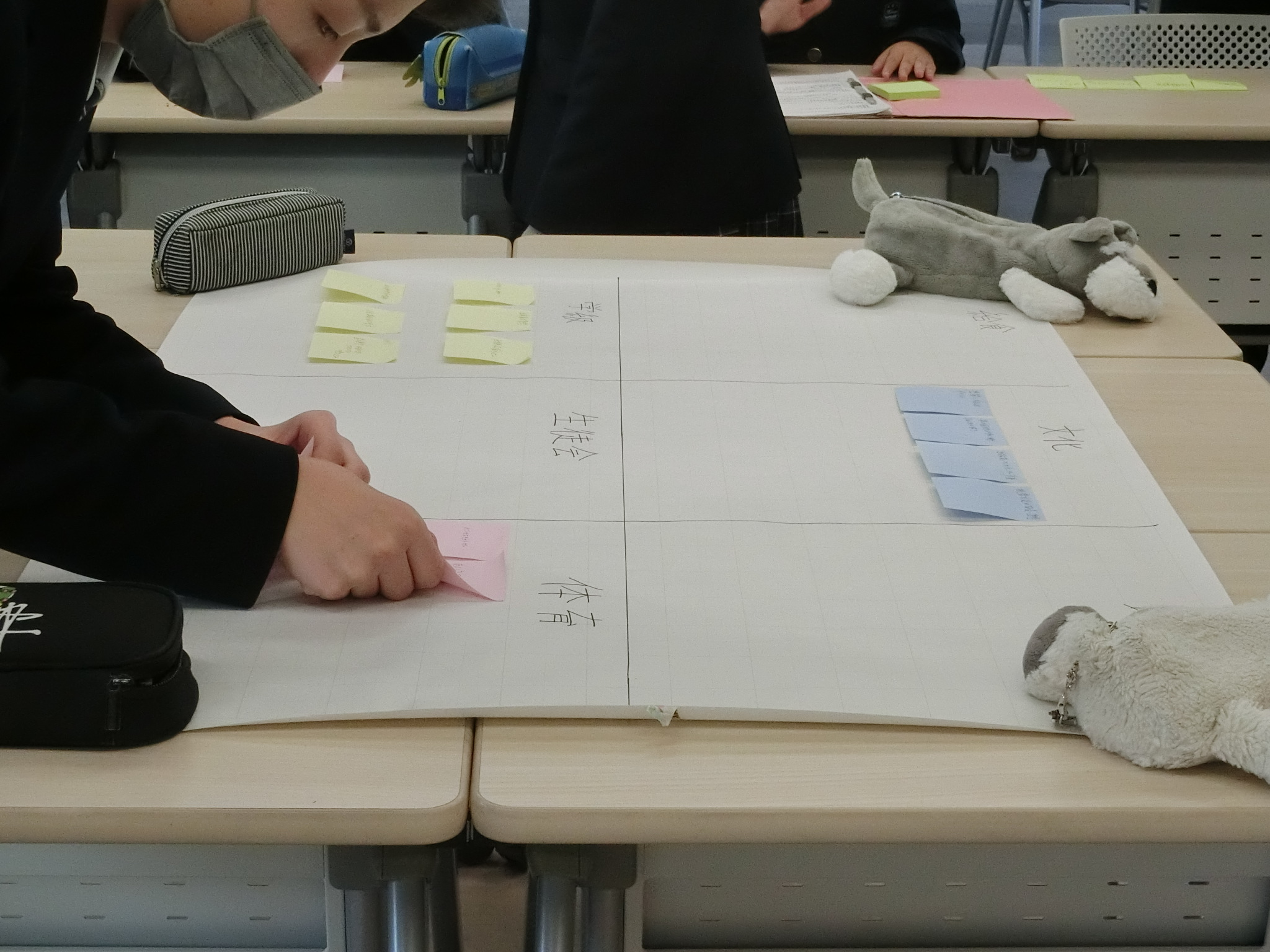

〈いままでのすべてを過去にした月がきょうもきれいあしたもきれい 工藤玲音〉(3/2)



〈三月や草木萌動なりものの始めの予兆うれしも 青木昭子〉(3/1:弥生)
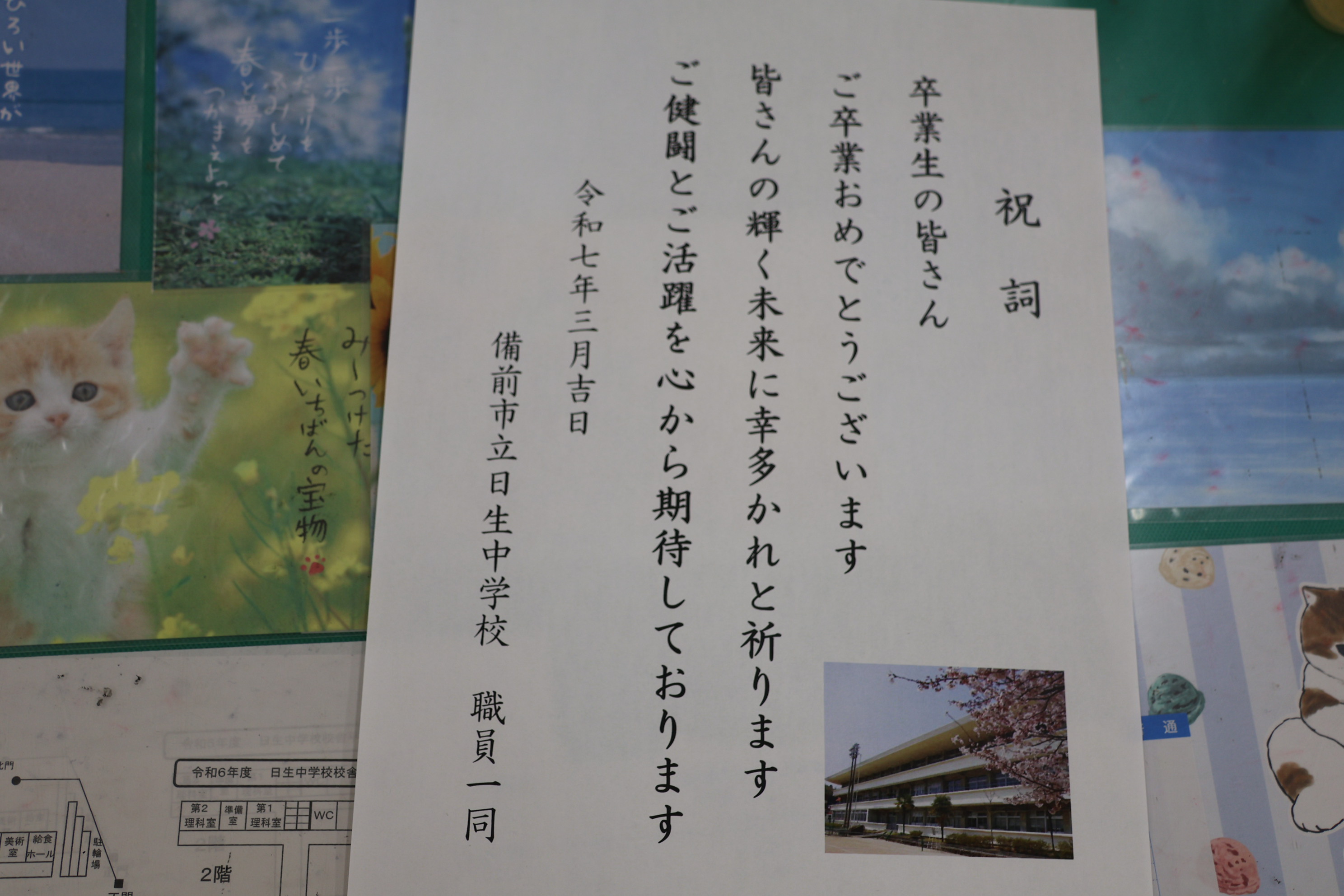
◎地域と共にある学校 片上ひなめぐり(2/28)

3月1・2日には、日生中も天gooカフェさんらと参加・お手伝いします。みんな来てね!(*^o^*)
◎地域と共にある学校 日生駅にて
メディアコントロール週間は日生中学校区全体での取り組みでした。掲示をありがとうございました。(2/27)

◎私たちが創る日生中だから(2/26)

今週末(2/28)には生徒評議会を開催します。
五年前、日生中の先輩たちも、自分たちの日生中、自分たちの学校生活を〈創る〉取組を進めてきました。今、生徒会(生徒)のみなさんはその最前線にいます。取り組んでいる内容は今とは違いますが、紹介します。
制服の変更にあたって
後輩たちへのメッセージ
私たちは、これまでの制服に対する不便さや機能性の低さを解消し、これからの日生中学校の生徒が快適な学校生活を送ることができるよう、よりよい制服づくりに励んできました。
日生らしさを考えて、色合いやデザインなど細かいところまでこだわりました。また、ワッペン・ボタンには全校生徒からデザイン画を募集して決定したエンブレムをあしらいました。そして、新しい制服に私たちの想いを込めました。
日生中のみんなには
日生の太陽のような温かい心、
日生の海のような広くて優しい心、
日生の山のような揺るがない強い心
をもっていてほしい。
そして、
どんなときも星のように輝いていてほしい。
私たちはこの制服を着ることはありませんが、これから何十年も続く制服の制作に携われたことはとても光栄です。この制服を着たみなさんの中学校生活が充実したものになるよう願っています。
2020年10月 日生中学校制服検討委員会
◎誇り・絆・地域と共にある学校(2/25)
西日本放送さんが、先日のカキの実習の取材をしてくださり、ステキな映像にまとめてくださいました。皆さんもHPでご覧ください。

◎地域と共にある学校 2025ひなせカキまつり(2/23)
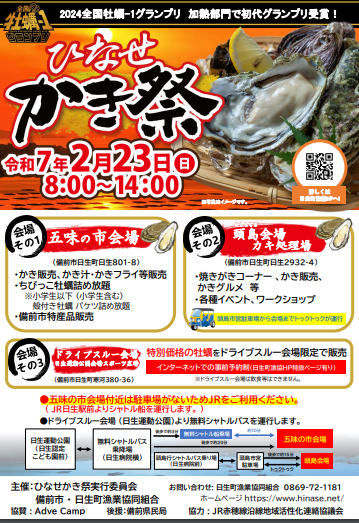

◎岡山が輝く✨私たちの三年間の学び(2/22)
~みんなで岡山の魅力発信プロジェクト~ おかやま旅プランコンテスト 2024の表彰式に参加しました。岡山商科大学専門学校が、秋から冬の岡山の魅力を見付け発信する「おかやま旅プランコンテスト」を開催し、 「おかやまにこんなところがあった!」「秋や冬の旅は、おかやまに行ってみたい!」と思われるような旅プラン案を、これまで学習した内容をもとに考え、中学生の部で日生中の4名が入賞しました。ありがとうございますした。
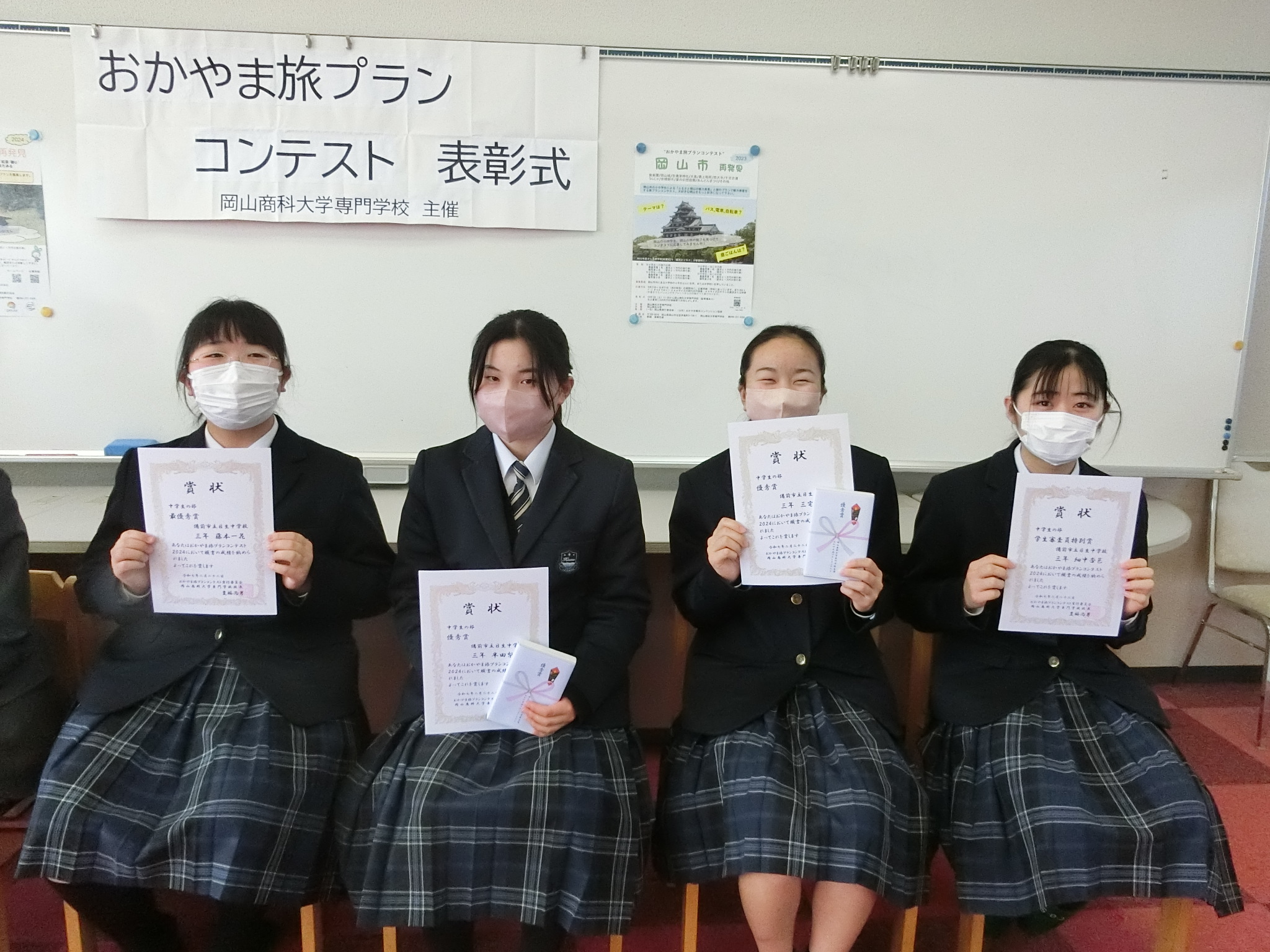
◎2月22日ってなに?

〈冬日向(ひなた) 先に見つけた 猫ももの 寝子〉 文化委員会俳句コンテストより
◎豊かな学びを(2/21)
自立活動に系統的・計画的・柔軟に取り組んでいます。自立活動とは、個々の生徒が自立を目指し,障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培うことです。
内容
1 健康の保持
(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。
(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。
(4) 健康状態の維持・改善に関すること。
2 心理的な安定
(1) 情緒の安定に関すること。
(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。
(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。
3 人間関係の形成
(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。
(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。
(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。
(4) 集団への参加の基礎に関すること。
4 環境の把握
(1) 保有する感覚の活用に関すること。
(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。
(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。
(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
5 身体の動き
(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。
(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。
(4) 身体の移動能力に関すること。
(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。
6 コミュニケーション
(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。
(2) 言語の受容と表出に関すること。
(3) 言語の形成と活用に関すること。
(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。



◎非情なる物語り生み戦争は人ある限り終焉あらず(2/21:三年目の春を迎えました)

◎さあ、今日もよい一日にしょう!(2/20:あいさつ運動の日)





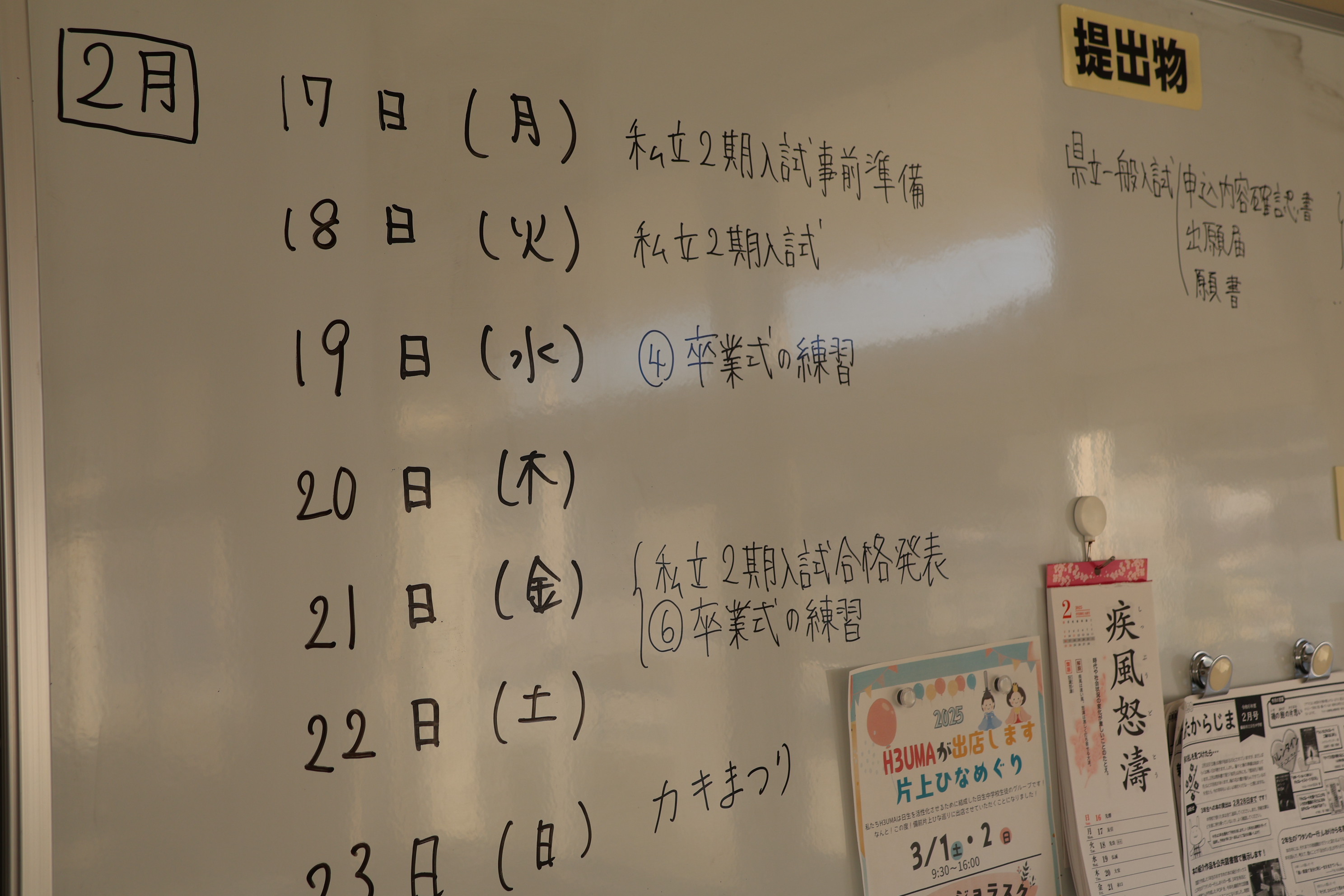

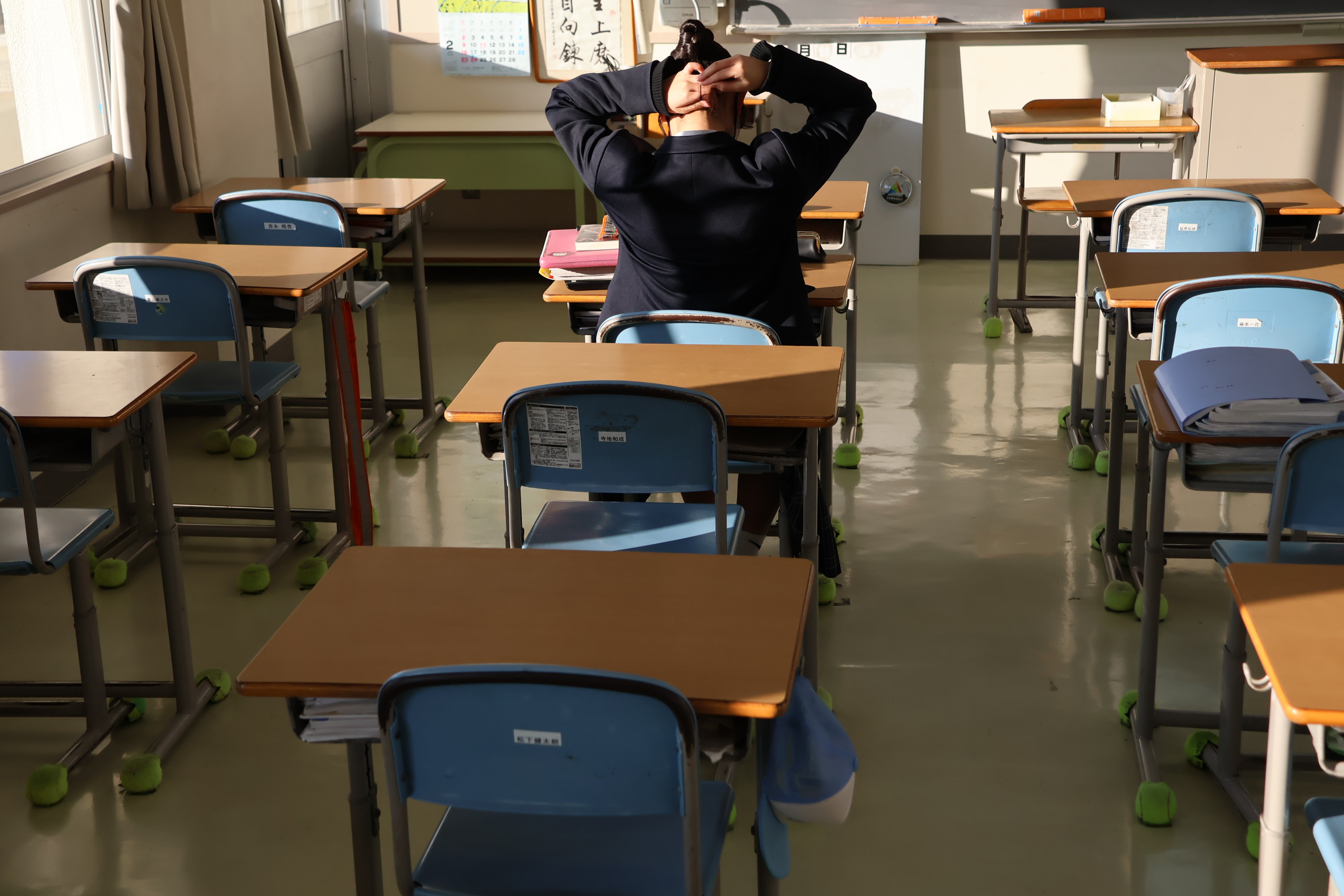

春よ来い
◎ハンセン病問題学習展示会終了(2/19)
たくさんの方々に来会していただきました。ありがとうございました。書いてくださったアンケートを紹介します。
〈中学生たちが自分の目で見て、話を聞いて、考えることの大切さを感じました。リアル感をもつこと、自分でそれぞれが(大人も国も)考えること、他人ごとにしないことをこれからも続けていくべきだと思います。自分たちの身近な場所でのできごとを中学生たちがしっかり見ていること、文章にしていることがよかったです。ぜひ続けてほしいです。〉



◎地域と共にある学校
海の恵みとたくさんの人に感謝(2/19)
今年も、海洋学習での日生中学校のいかだから水揚げしたカキの洗浄・選別活動をおこないました。総合的な学習の 時間での海洋学習では、5月:流れ藻の回収・カキの種付け、7月:漁業関係者の方々からの「聞き書き」、9月:アマモの種取り・播種、11月:小学生とアマモポット作成、そして、今日(2/19)のカキの水揚げ・洗浄・選別の活動をおこなっています。日生漁協や観光協会をはじめ多くの方々のご支援・ご協力でこの学習に取り組めていることに感謝します。ありがとうございます。









感謝して、いただきます。
◎地域と共にある学校
私たちのおすすめの本です(o^―^o) 2/19~



中学生のおすすめの本展を、市立図書館日生分館さんとコラボ企画でスタートしました。3月4日まで開催します。ぜひお立ち寄りくださいませ。
また、中学校のまちかど図書室(予定)にも教育・歴史・人権などに関する本を置いています。関心がある方はお問合せ(教頭)ください。
◎ひなせ親の会で、学ぶ・つながる・歩む
2月18日に開催した第10回ひなせ親の会は、「なんでも相談会」と銘打った学習会は〈療育」ってどんなことなの?いつから?どこで相談すればよい? 〉〈子どもの育ち、「発達」について、中・長期的な視野で考えてみよう!〉〈今どきの進路・進学、自立について、 新しい情報を手に入れ、見通しをもとう! 元気になろう〉をテーマに、 小・中学校が教職員、保護者、地域、行政・事業所の方々が多く参加してくださいました。今回は、相談支援専門員の湊さん、市社会福祉課 杉山さんをお招きして、ワークショップやオープンダイアローグ形式で、ゆったりと〈子どもたちのこれから〉について、楽しく・学び合 うことができました。ご参加のみなさんありがとうございました。
ひなせ親の会は、次回も、日頃思っていることや気になること、お子さんの「発達・そだち」など素朴な質問なども含めて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。お気軽に、お申し込み・ご参加ください。第11回は4月7日(月)17:30~19:00(仕事や用事が終わり次第どうぞ😀)を予定しています。会場は、日生中学校 ほっとスペース(南棟2階)です。


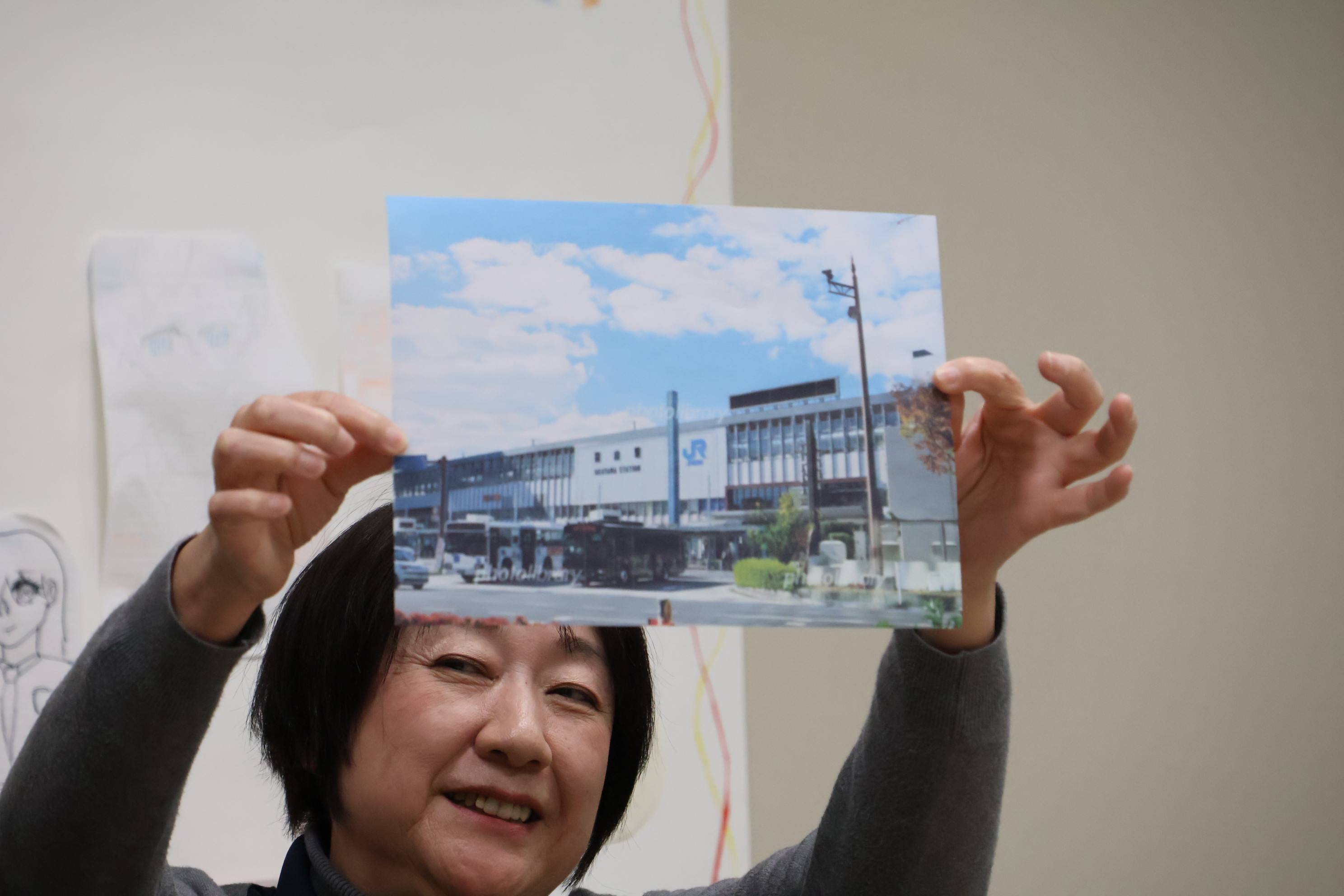
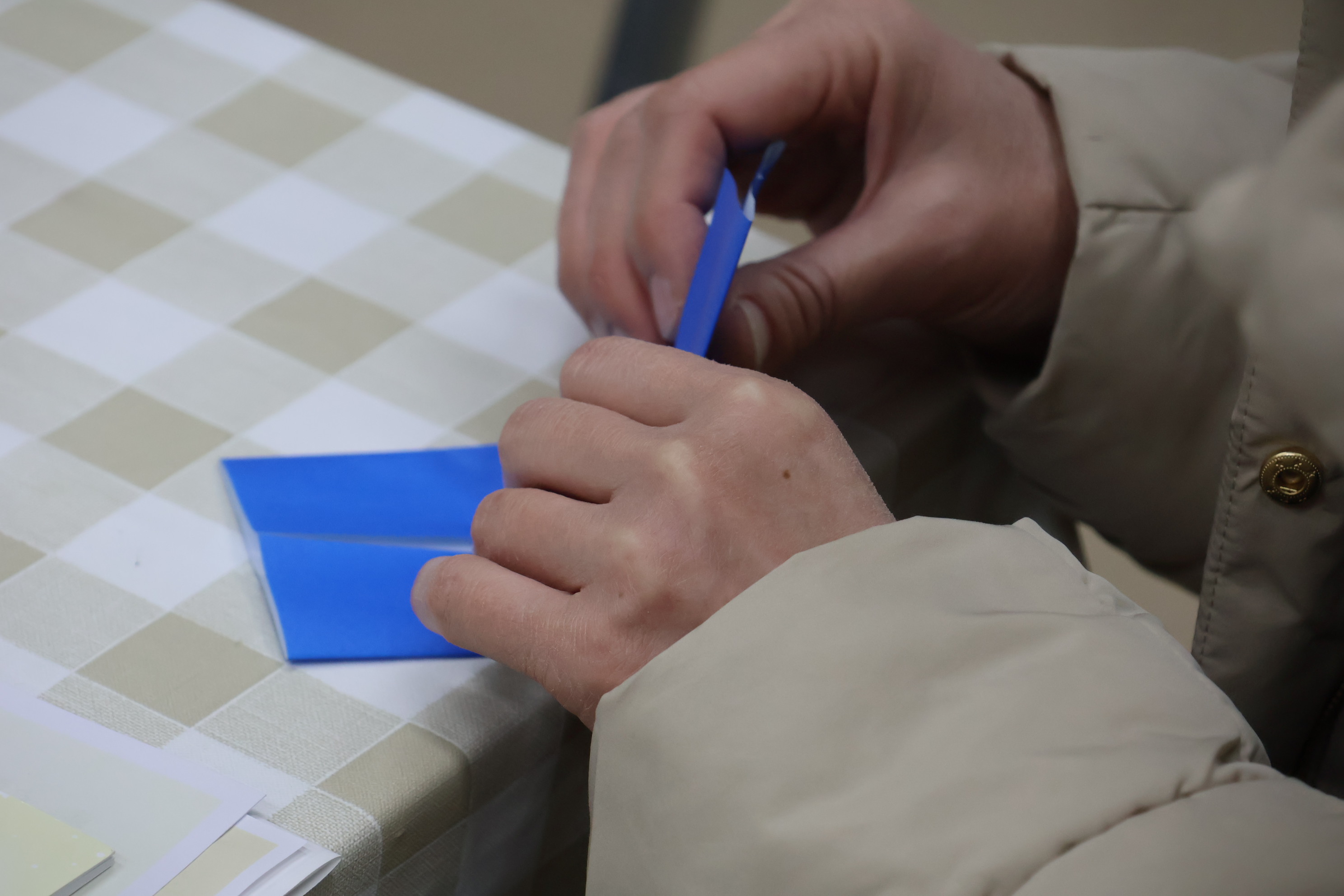


◎備前で輝く 備前が輝く
ボランティア(餅つき大会のお手伝い)に行かせていただいたNPOひこうせんよりお礼状をいただきました。ありがとうございました。

◎ネットより 大切なもの 見つけよう メディア標語より(2/19~)
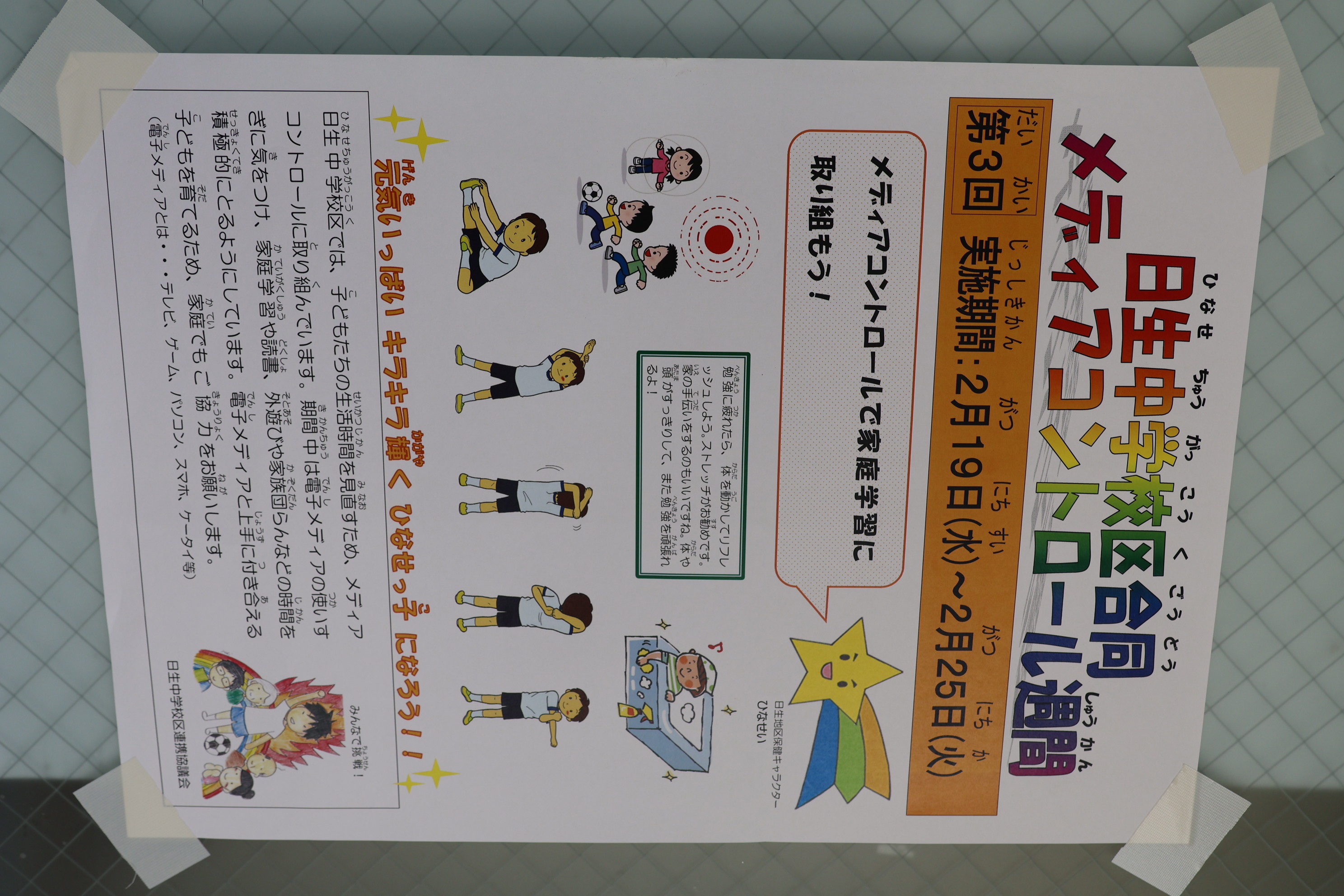

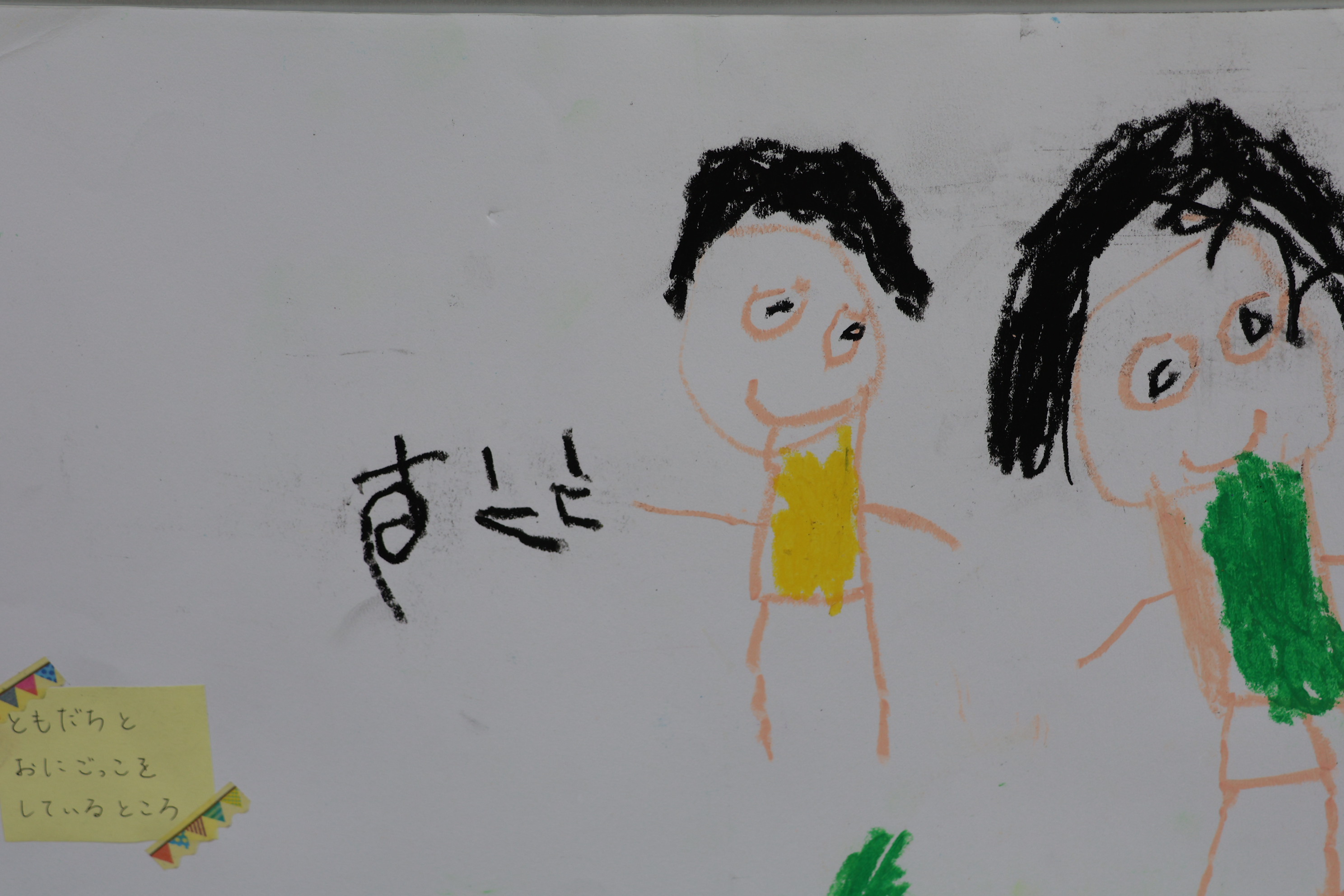
日生中学校区みんなの取り組みです!
◎今日も授業がいのち
三宅授業改革推進員と一緒に、授業づくりについて振りかえりや協議で、ベテランも若い教員も共に磨きあっています。(2/18)
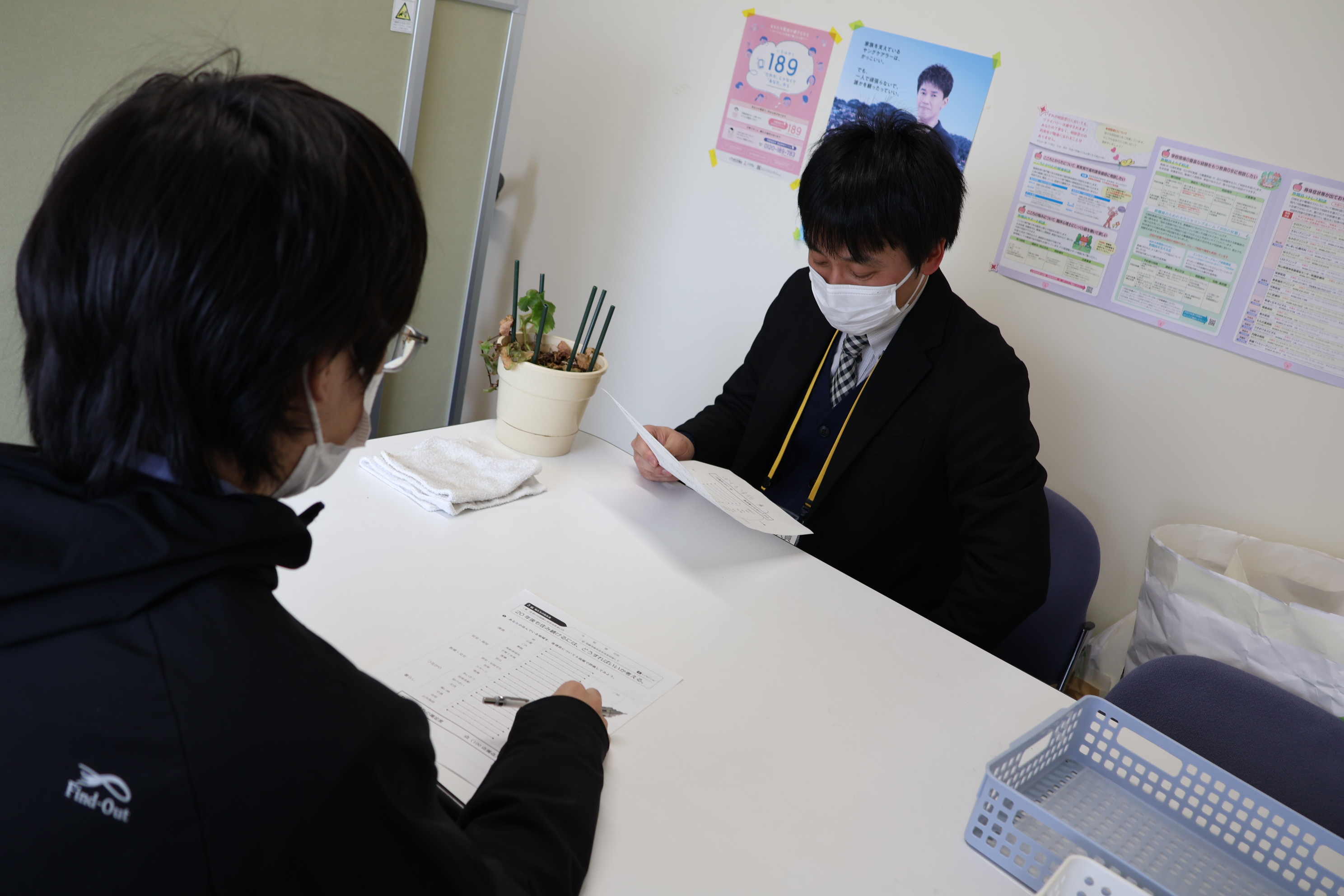

◎風に常盤の香を送る♬ようこそ日生中へ
6年生一日体験入学(2/18) 生徒会執行部と。校内めぐり。体験授業。中学校での新しい生活に向けて!




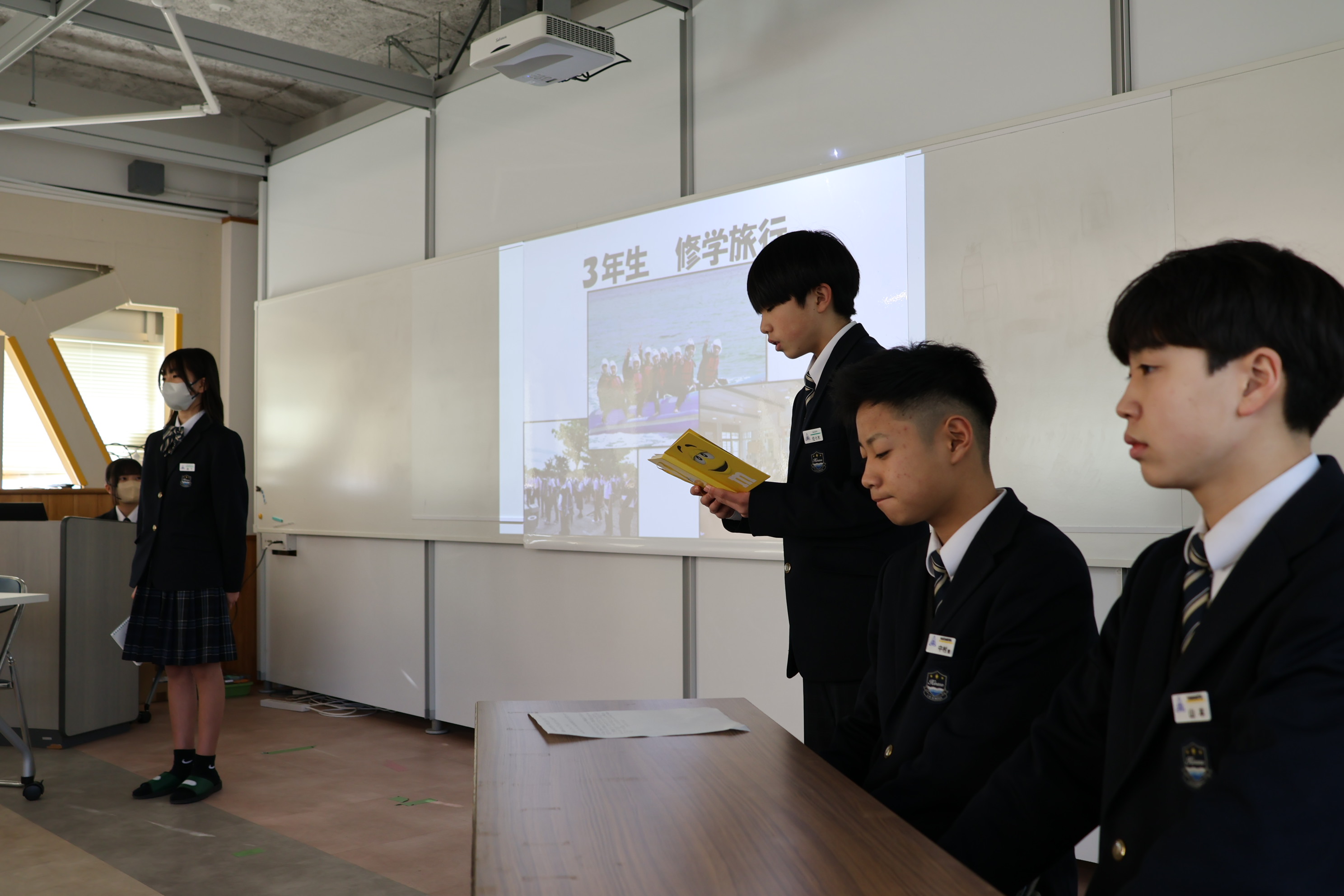


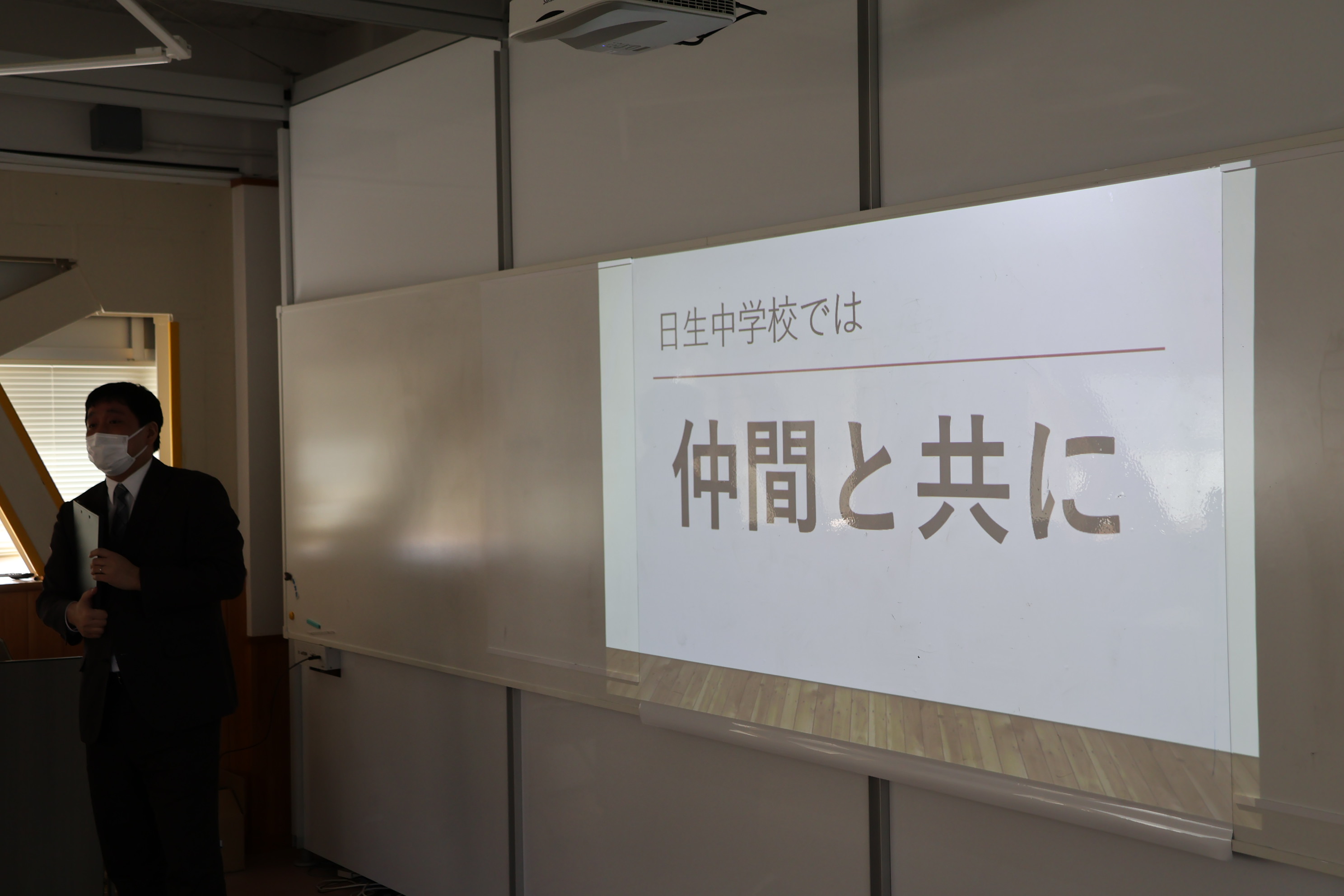

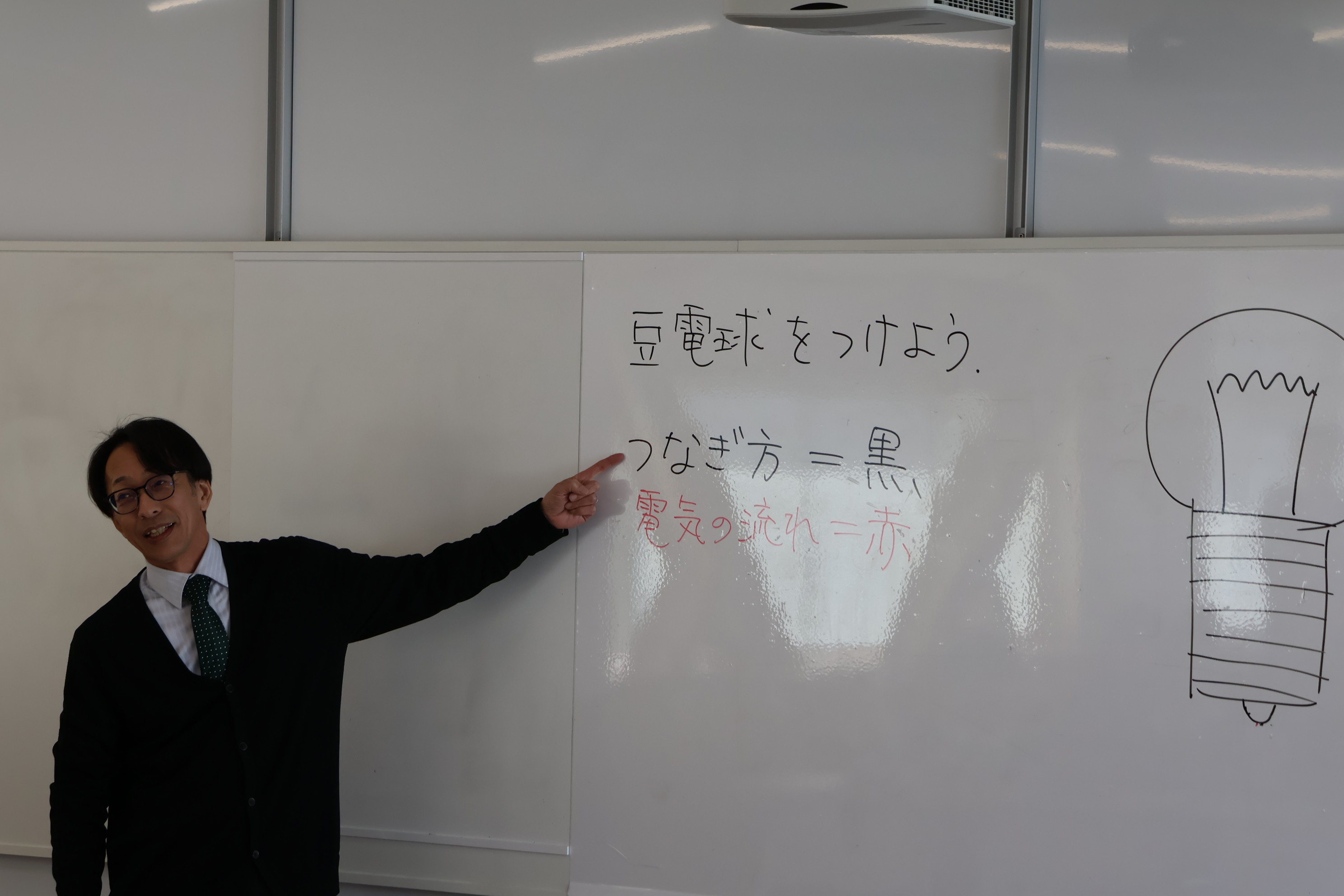




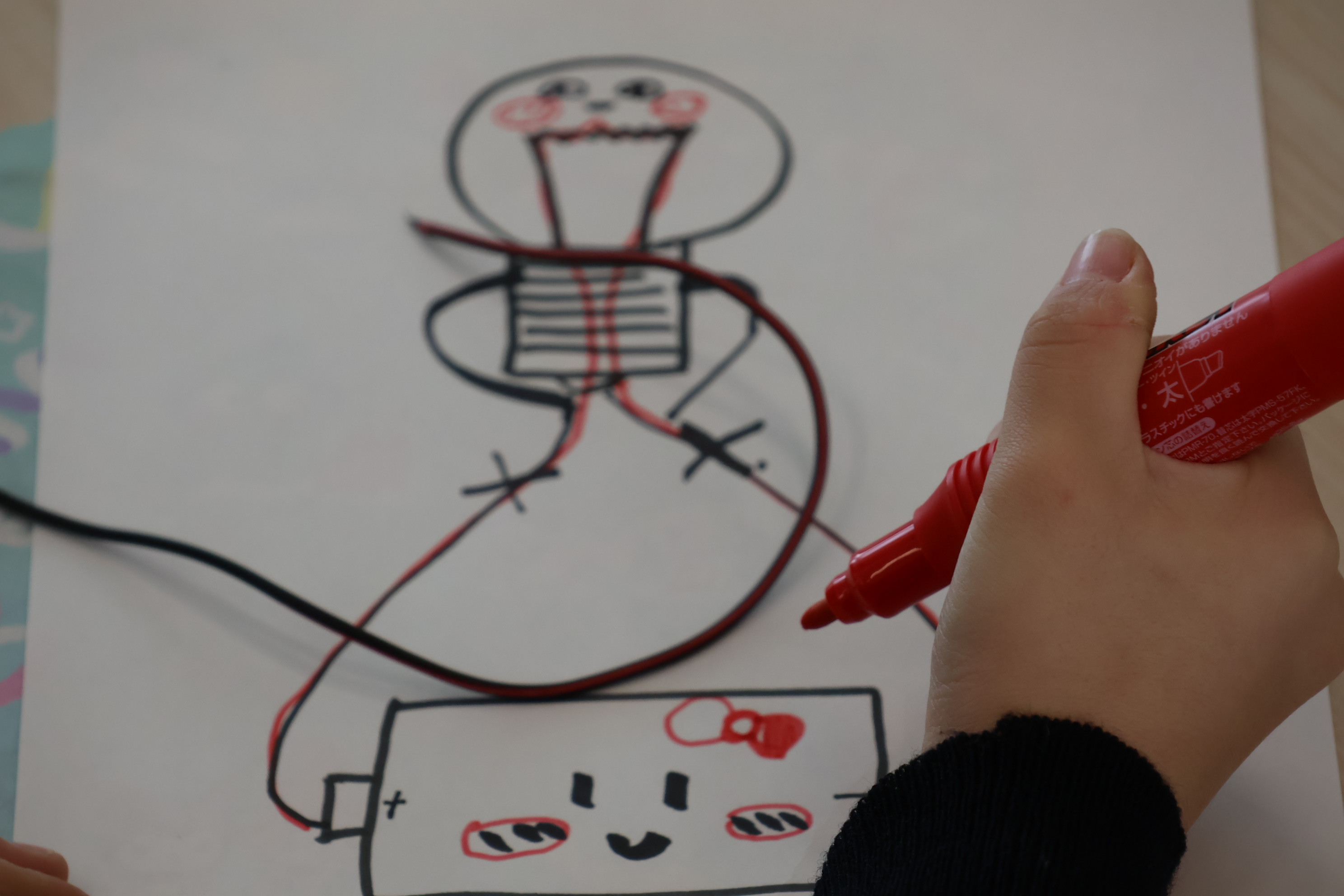
◎新しく、豊かで・確かなPTA活動をめざして
PTA幹事会(2/17)を開催しました。議題は、第2回委員総会(3/4)にむけての議案検討、新年度の活動計画、生徒ボランティア保険の活用状況(報告)、役員選出方法及び会則の改定検討をおこないました。


◎明日は雨水(2/17)
雨水は「うすい」と読みます。雨水とは、雪が雨へと変わって降り注ぎ、降り積もった雪や氷もとけて水になる頃という意味。実際にはまだ雪深い地域もありますが、厳しい寒さが和らぎ暖かな雨が降ることで、雪解けが始まる頃です。凍っていた大地がゆるんで目覚め、草木が芽生える時期。雨水になると雪解け水で土が潤い始めるため、農耕の準備を始める目安とされました。
二十四節気では、雨水の前は暦のうえで春となる「立春」、雨水の次は、冬ごもりしていた生き物が活動し始める「啓蟄(けいちつ)」となります。

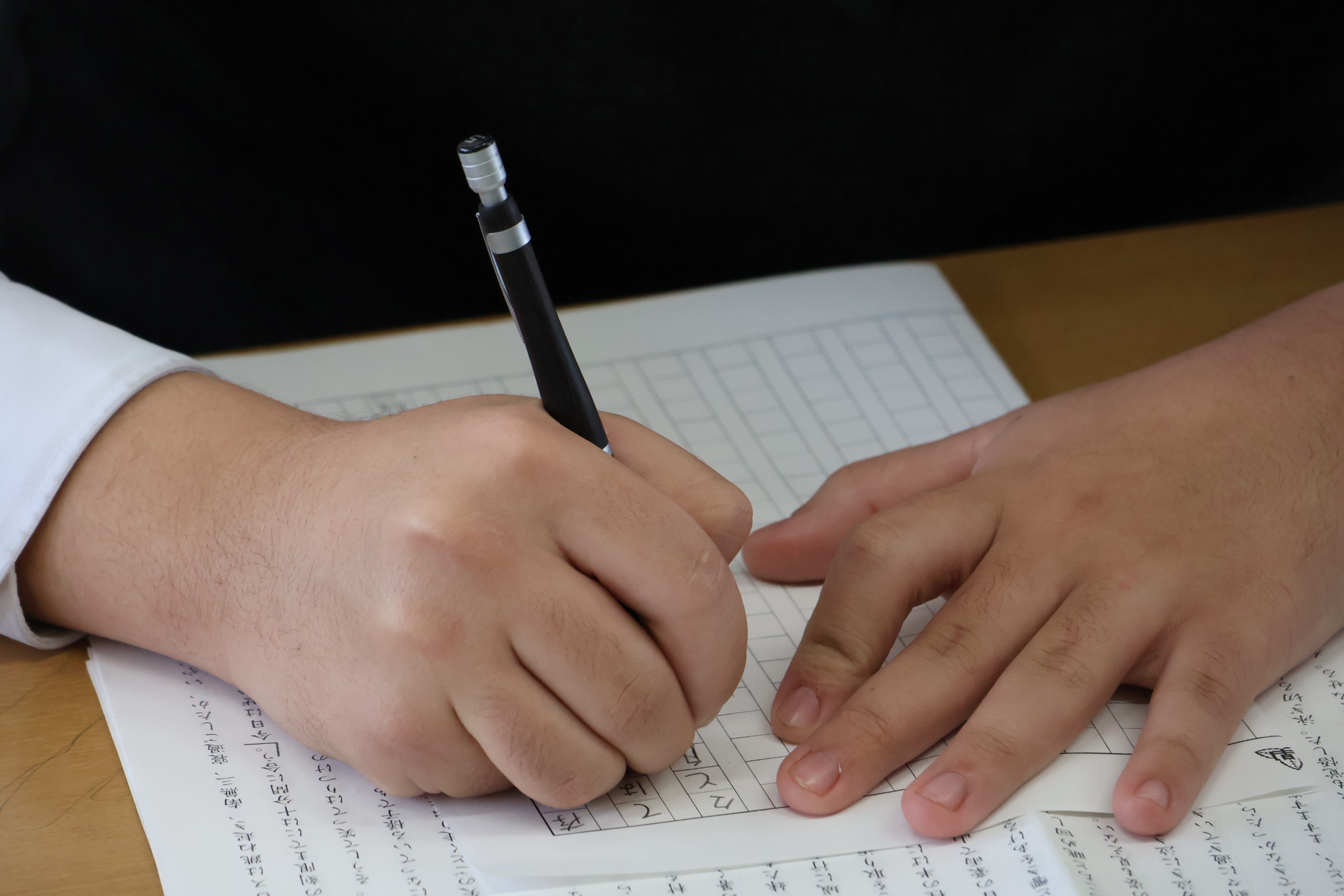

〈降りしきる雨くぐるごと迎うるや一期一会のまぼろしにて 岡田 恭子〉
◎どれにする?
ひなせいコース?備前♡日生大橋コース?かきおこコース?鹿&猪コース?(2/17)
19日から第3回メディアコントロール週間(~25日(水))でメデイアと上手に付き合う力を養います。
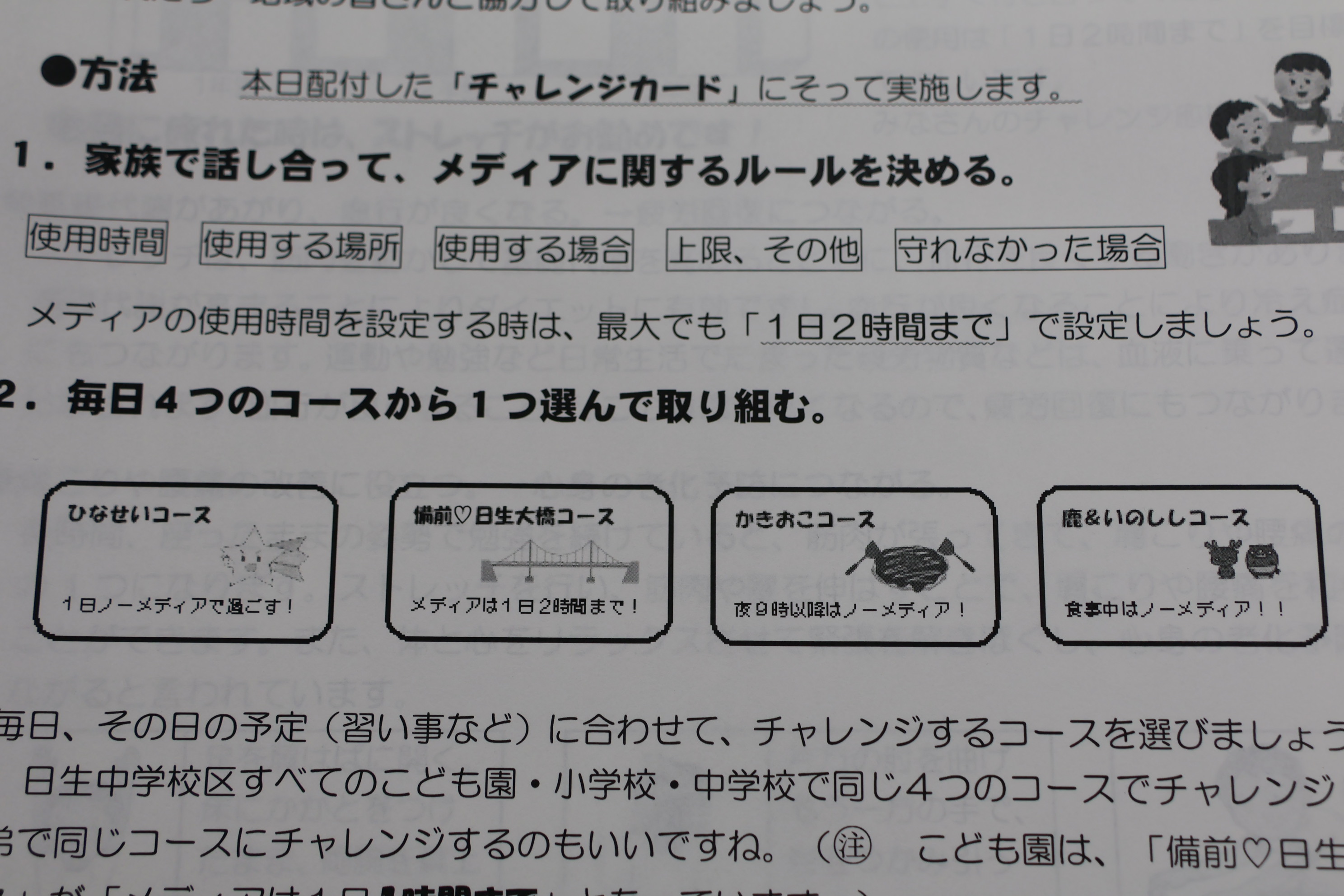
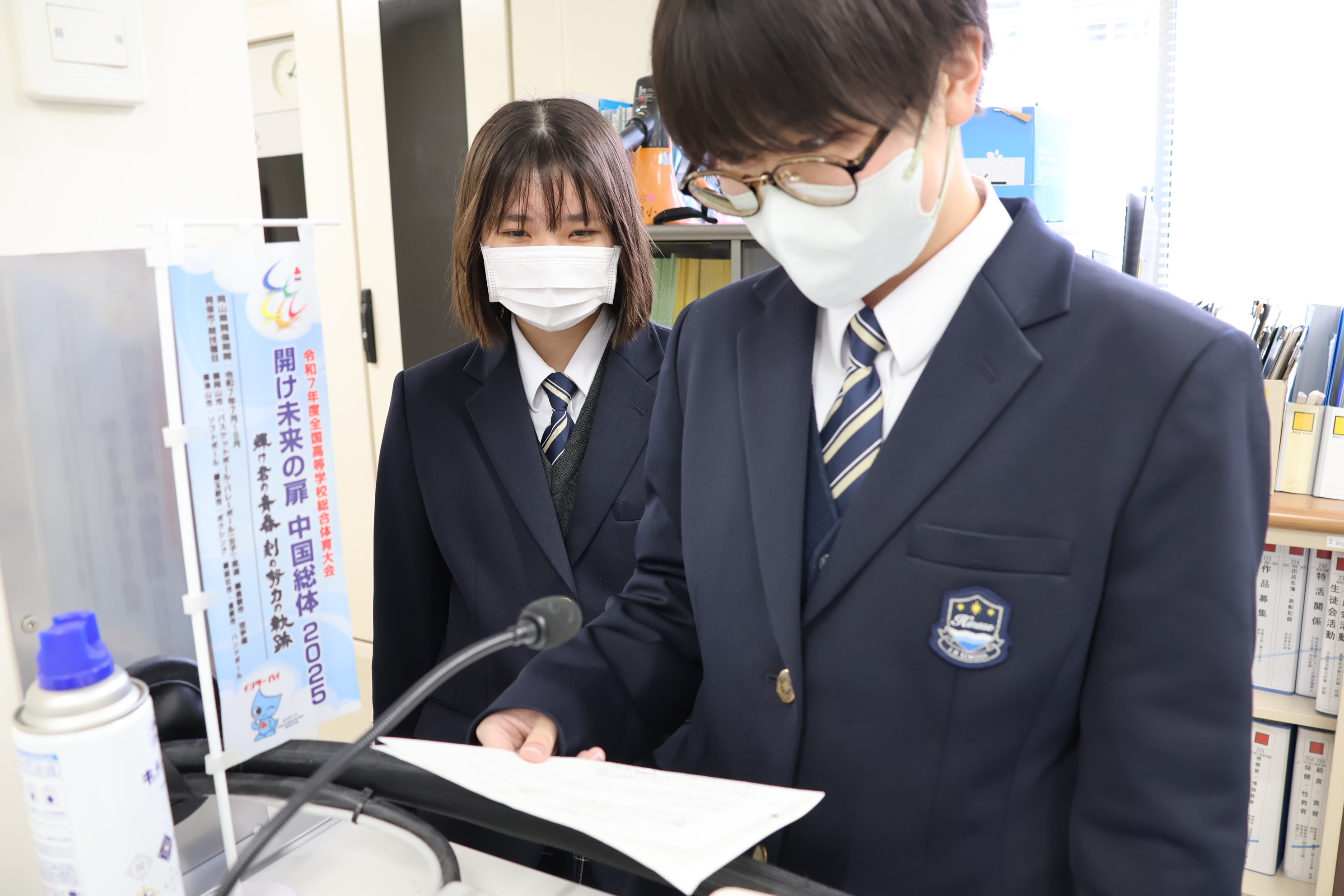
みんなは何コース?
◎ひな中の風✨(2/17)
~備前楷の木賞(学び賞)及び楷の木大賞
受賞のお知らせが届きました。
備前楷の木賞とは・・・「備前市では、住民の主体的な学びを促進するため、ふるさと納税制度を通じて頂いた寄附金をもとに「米百俵基金」を創設し、人づくりのための施策を展開しています。備前楷の木賞では、「学びのまちづくり」を、自らが問題意識を持ち(主体性)、人と関わりながら(協働性)、物事を進めていく(実践)取り組みととらえ、評価を行います。」と募集要項にありました。
今回の受賞は、中学校の活動だけでなく、地域の支えがあっての取組だったとあらためて思います。日生中学校を支えてくださる多くの方々に感謝して、3月1日の表彰式に参加させていただきます。ありがとうございました。日生中学校生徒会

「地域と共にある学校」を目指して
○活動のきっかけ、開始時期
長年、本校では、継続的・計画的に、総合的な学習の時間で日生地域での海洋学習に取り組んでいる。海洋学習は、5月:流れ藻の回収・カキの種付け、7月:漁業関係者の方々からの「聞き書き」、9月:アマモの種取り・播種、11月:小学生とアマモポット作成、2月:カキの水揚げ・洗浄・選別である。また、生徒会主催で7月と12月に行っている地域清掃ボランティア活動にはいつも50人を超える生徒が積極的に参加し、周辺地域と日生駅、幹線道路の清掃・美化活動を行っている。このような「地域」を意識した学習・活動は今後も大切にしていくが、生徒数の減少(クラス数の変化・教職員数の削減)に伴い、現在、本校では、教育課程や校内校務分掌の工夫改善や見直しの必要がある。そこで、これまで取り組んできた学校の様々な教育活動においても、整理・統合、再定義化を図り、試行的実践を行いながら、十五年先を見据えた「地域と共にある学校」づくりを進めている。
○活動内容(具体的な経緯・基盤整備)
1 PTAと協議し、ボランティア保険(全国社会福祉協議会)に全生徒加入のための予算化を図り、生徒が校外の活動に進んで参加できる学習環境を整えた。
2 社会福祉協議会日生支所と連携し、〈日生中ボランティア推進プロジェクト〉の体制を整えた。
3 2に合わせて、ホームページや学校便りにより、保護者や地域への情報提供・広報活動を行い、地域から学校へのボランティア(参画)依頼を募った。この活動で、「地域とともにある学校を目指して、未来のまちづくりのために、学校と地域が協働して、双方向での教育活動を推進していきたい。」という学校の思いを多くの方々に知っていただくことが出来た。
4 一般社団法人ジンジャーエールとNPO法人f..saloonと協働で、〈ひな中ほっとスペース〉を開設した。このスペースの目的は、地域でモデルとなる大人に出会うことで、豊かな生き方(ひと・モノ・コト)に触れたり、地域活動についての熱い思いを聴いたりする中で、シティズンシップ(市民性)の涵養、地域社会への関心を高めること、進路・進学の意欲を喚起すること等で、毎月第1・3水曜日には、スタッフが常駐、毎回20人を超える生徒が足を運んでいる。このスペースでの出会いは、生徒の大きな「地域社会への参画の入口」となっている。
(具体的な活動の中で)
1 3年生は、これまで総合的な学習の時間で取り組んできた海洋学習や地域学習の総括のひとつとして、日生地域の方々との協議(聴き取り等)を重ね、『日生の応援団』をまとめ、中学校のホームページでの情報発信を行った。
2 地域ボランティア推進プロジェクトを中心とした地域からのボランティア参加依頼(12月現在、21件の依頼)を受けて、のべ180人の生徒が地域のイベントや清掃活動に主体的に参加した。
3 社会福祉協議会日生支所との連携を密にし、7月と12月に行う地域清掃ボランテイア活動は、中学生(生徒会)だけで行う活動ではなく、川東地区協議会の方々と協働で実施することができ、ネットワークも広がった。
また、校内でもボランティア活動や地域学習の見直し・再定義を図り、地域ボランティアや地域協働活動への意識を高めることとなった。例えば、秋の交通安全週間に際し、校内での意識向上の取組はもちろんのこと、今年度は、地域住民にも交通安全を働きかける啓発ポスターを作成し、町内要所に掲示していただき、交通安全啓発活動に寄与できたのも教職員の高い意識の表れのひとつであると考える。
4 地域ボランティア推進プロジェクトを中心とした参加依頼で、生徒らが参加・参画したイベントや行事の主なものは、こども服・学用品リユース会、街頭での赤い羽根共同募金活動、カキかきフェスティバル、日生みなと祭り、頭島あかり祭り、てんてかんか、寒河秋祭り、日生文化祭、備前10代まんなか会議、歳末助け合い演芸会&楽市、もちつき大会(NPO法人こども達の環境を考えるひこうせん)、備前♡日生大橋マラソン大会(3月予定)である。「日生盛り上げ隊」として中学校で単独参加もするが、一般社団法人ジンジャーエール等の地域団体の出店スタッフとして参加するスタイルもある。また、頭島あかりまつりでは、実行委員会の方々が来校され、クラス全員で行灯の制作に取り組むなど、地域との関係性が密になる中で、より柔軟な活動・取組が展開できるようになっている。
○具体的な成果・活動の将来的な目標、展望
1 子どもたちは、地域社会での経験・体験を増やす中で、自分たちの住む地域の「魅力」をリアルに感じ取るだけでなく、地域の「課題」も自覚する貴重な機会となっている。それが、未来の担うためのシティズンシップ(市民性)の意識の涵養にも繋がっていくと考える。
備前10代まんなか会議に参加した生徒は、一般社団法人ジンジャーエールのサポートを受け、子どもたちの豊かな発想を生かした地域創出活動のチームを立ち上げて、活動を始めている。
2 「地域と共にある学校」は、学校や地域からの一方向の働きかけではなく、双方向のやりとりであり、地域社会で子どもたちを豊かに育てていく協働的な営みだと考える。
地域の方々の多くの支援を受けて、不登校傾向の生徒や他者とのコミュニケーションが苦手な生徒も、多様な(ボランティア)活動に参加している。このことは、生徒自身の自己有用感や自己肯定感が高まることとなり、生きていく大きな自信につながっている。
「学校」だけでなく、地域の中に「多様な活動の場」をネットワーク化するということは、「多様な学びの場」が在るということになる。今日的な学校現場での様々な教育課題の解決に向けては、チーム日生中学校として多機関連携・協働が必須であるが、そこには「地域」も包括したチームづくりを目指したい。
3 まちづくりに決まったゴールはない。地域の強みや課題と本校の教育課題を重ね、さらに豊かで確かな教育内容を創造していきたい。具体的な活動の中で「為すことで学び」ながら、「学びのまちづくり」を今後も粘り強く進めていきたい。
〈孤独をしる者どうしこれからも仲間としての日々 受験短歌より〉
(2/14:県立特別入試結果受領)

◎ひな中の風✨(2/14)
~地域と共にある学校
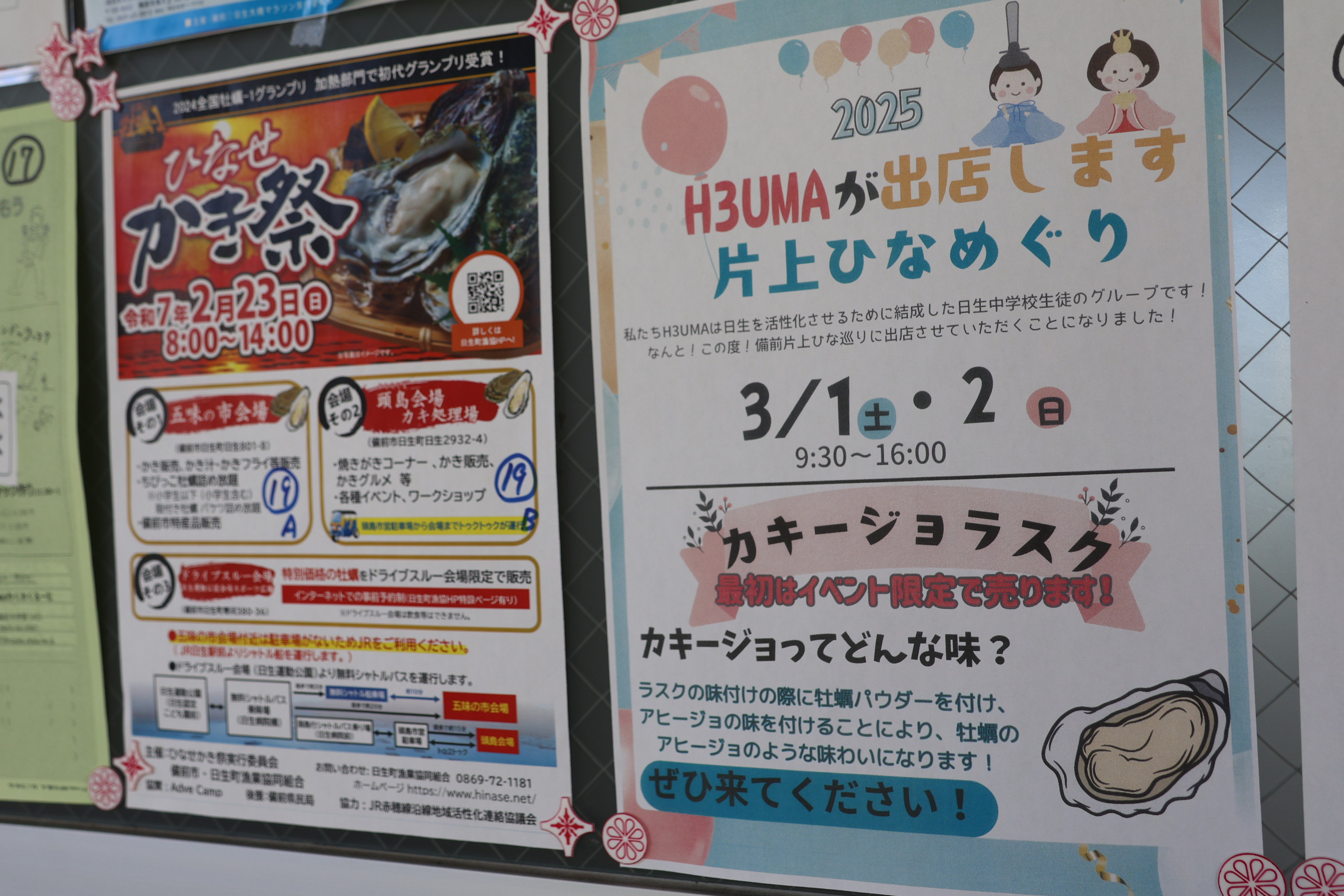
〈ただしくよりたのしく歩く 光っている水がみたくて すこし小走り 岡本真帆〉
◎多くの人に支えられて(2/13)
備前市青少年健全育成センターから真鍋さん、今吉さんが来校され、情報交換をさせていただきました。朝のあいさつ運動や日生地域内の安全パトロール等、いつもご尽力くださっています。ありがとうございます。

◎多くの人に支えられて(2/13)
この日、学校環境衛生検査で、学校薬剤師さんが来校くださり、教室内の空気・騒音・照度を検査していただきました。ありがとうございました。整った学習環境での教育活動を今後も進めていきます。



◎自己目標は達成されたか、どうだったか?(2/13)
年度末が近くなり、各人の自己目標シートをもとに、全教職員が最終面談を行いました。ふりかえりを大事にして、新年度に向かいます。



◎授業が大切 私たちも学び続ける(2/13)
2月12日に第2回校内授業研究会を行い、授業や学級づくりについて熱く協議しました。働き方改革で生み出した時間は、子どもたちに向き合うための授業研究や仲間づくりの創出につながらなくてはいけません。貴重な授業公開と研究協議の時間でした。学びあった内容を今後の教育実践に生かしていきます。
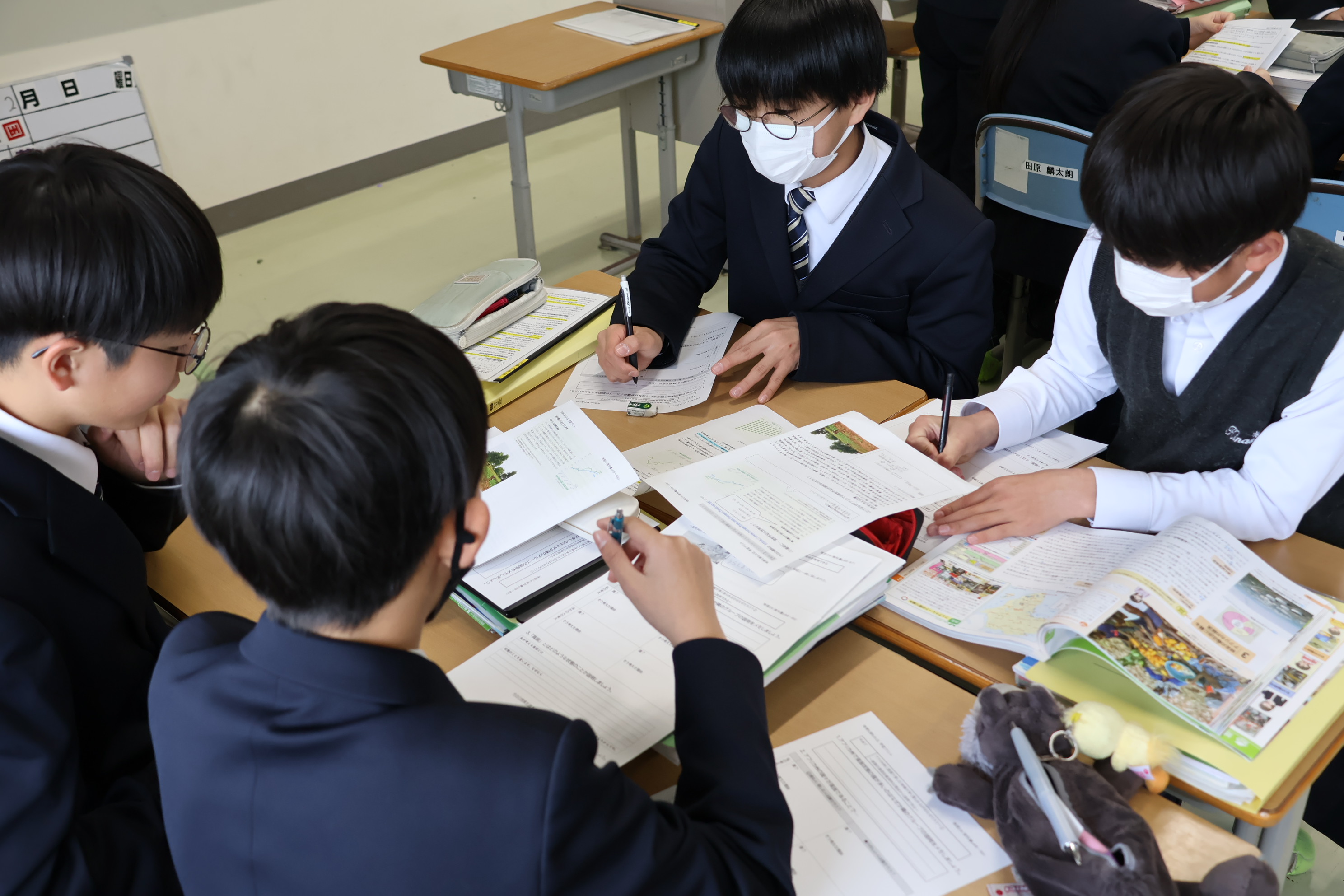



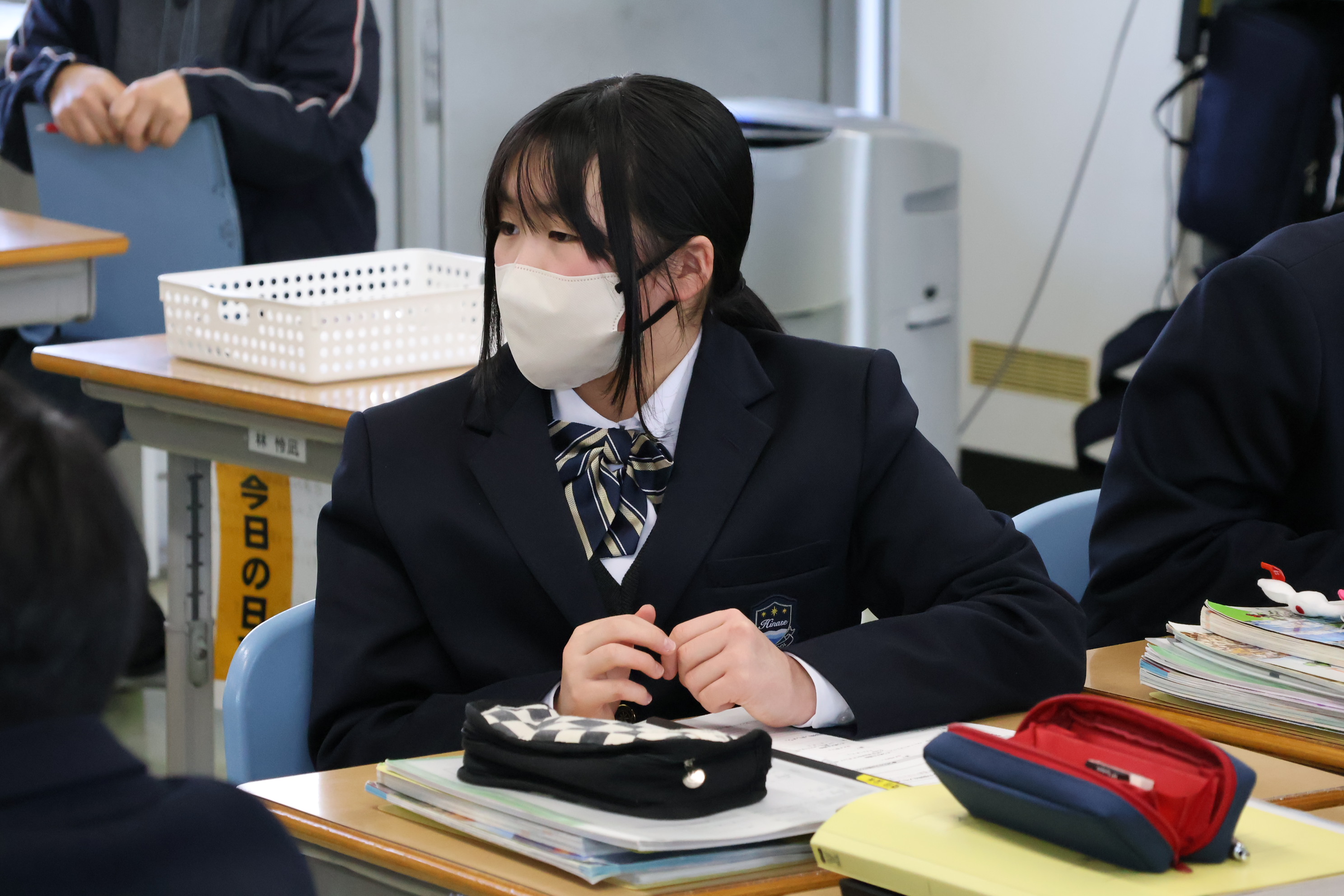
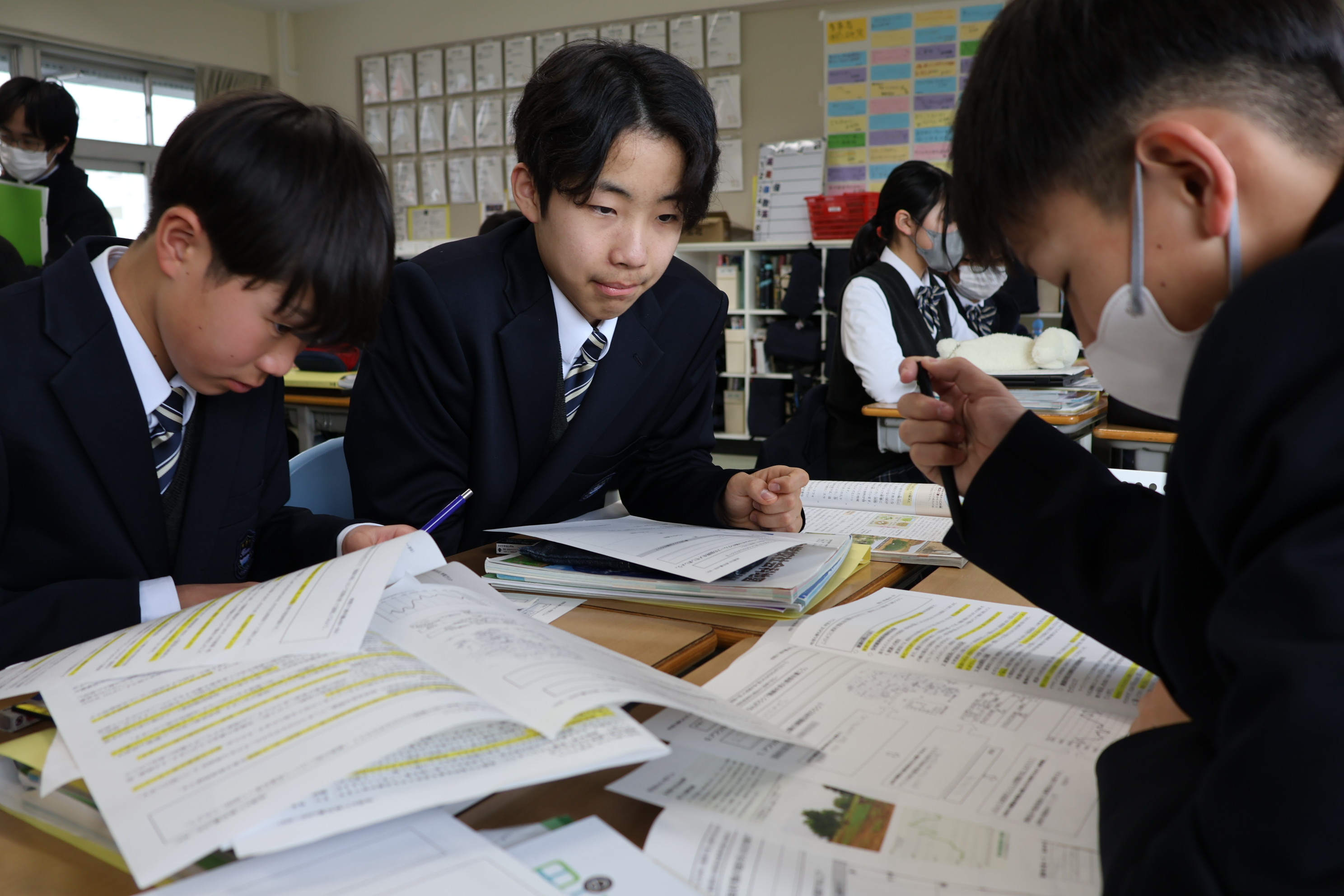

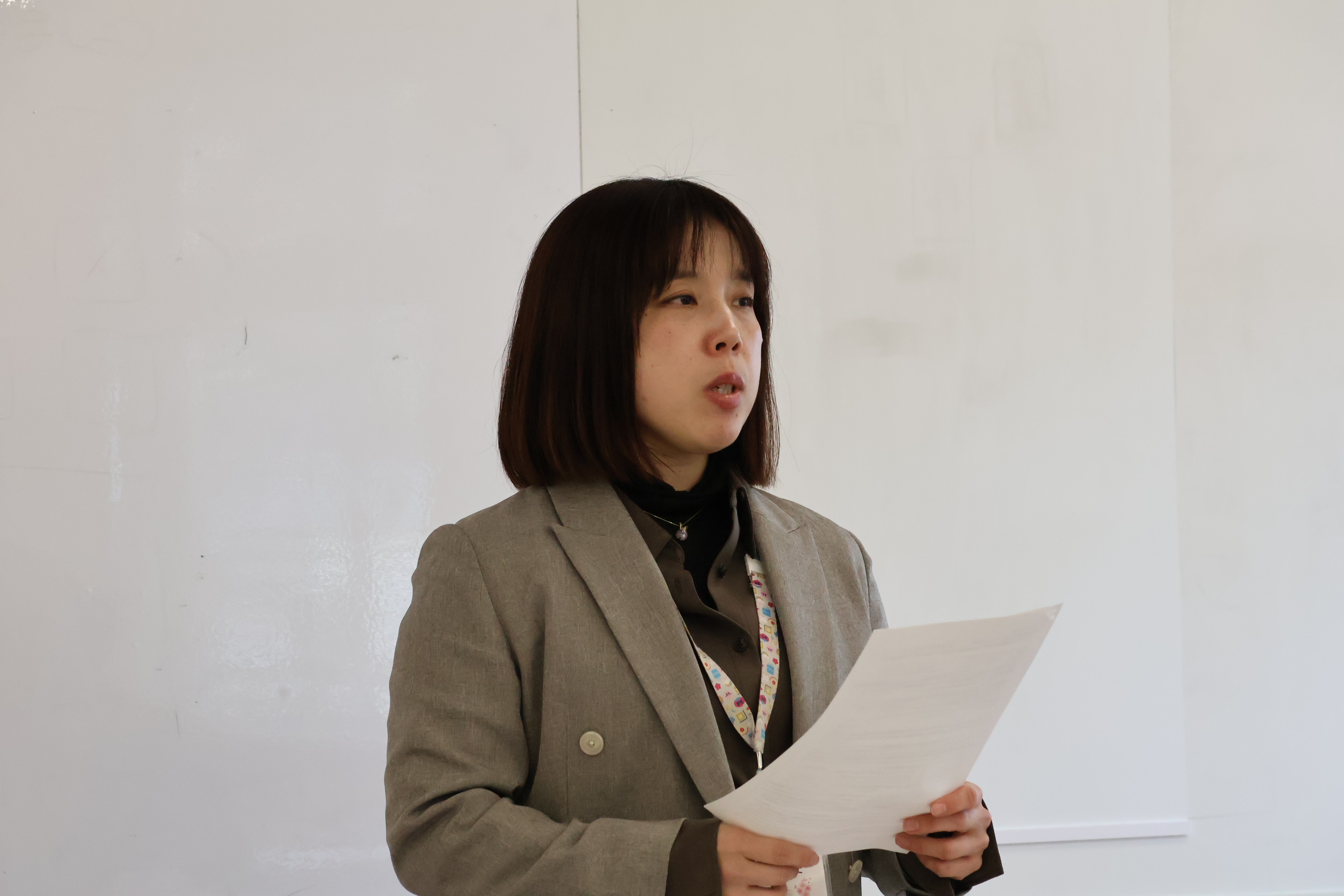

◎だっぴします 聴く・語る・夢をもつために
ひな中の風✨(2/12)
延期としていました「だっぴ〈8.30予定でした〉」を、3月7日に開催する予定で、準備を進めています。,
「だっぴ」とは,地域の大学生や大人と交流するプログラムです。中学生2人〜3人・大学生・保護者など地域の大人の5人程度のグループを中学生の人数分つくり, 働き方や生き方などについてテーマに沿って自由に話し合うキャリア教育プログラムです。たくさんの大人の方々のご支援・ご協力で実施できます。ありがとうございます。この日は、市教委 生涯学習課の富松さんと打ち合わせをおこないました。
「だっぴ」は
【地元や社会へ関心が高まる!】
自分たちの地域の人や知らない分野で生きる人の多様な価値観と出会うことで,社会のつながりに気づ いたり,地元への興味関心を高めることができます。
【未来を考えるキッカケに!】
少し先の未来を生きる大学生や様々な経験を経て働くいろんな大人の話を聞き,自分のこれからをイメー ジしやすくなります。
【行動する勇気が育つ!】
地域の大人やお兄さんお姉さんが生き生きと真剣に話してくれた言葉,そして中学 生自身が自分と向き合い話した言葉。その一つ一つが心を支えてくれる力になり,行動する勇気が育ちます。
【みんなで育てる地域に】
中学生と直接お話することで,子どもたちへの理解や関心が高まります。地域の力を学校に取り入れるキッカケにもなり,地域みんなで子どもを育てるつながりが生まれます。 (NPO法人だっぴ HPより)
◎ひな中の風✨(2/12)
おかやま旅プランコンテスト2024 おかやま秋から冬再発見
入賞おめでとう!
岡山商科大学専門学校が主催するコンテストに応募した三年生の中から、4名が最優秀賞・優秀賞(2名)・学生審査員特別賞を受賞しました。三年生は、総合的な学習の時間で取り組んできた三年間の学習内容を活用し、岡山・備前・日生の魅力を発信するプランを考えました。表彰式は2月22日、同専門学校で行われます。
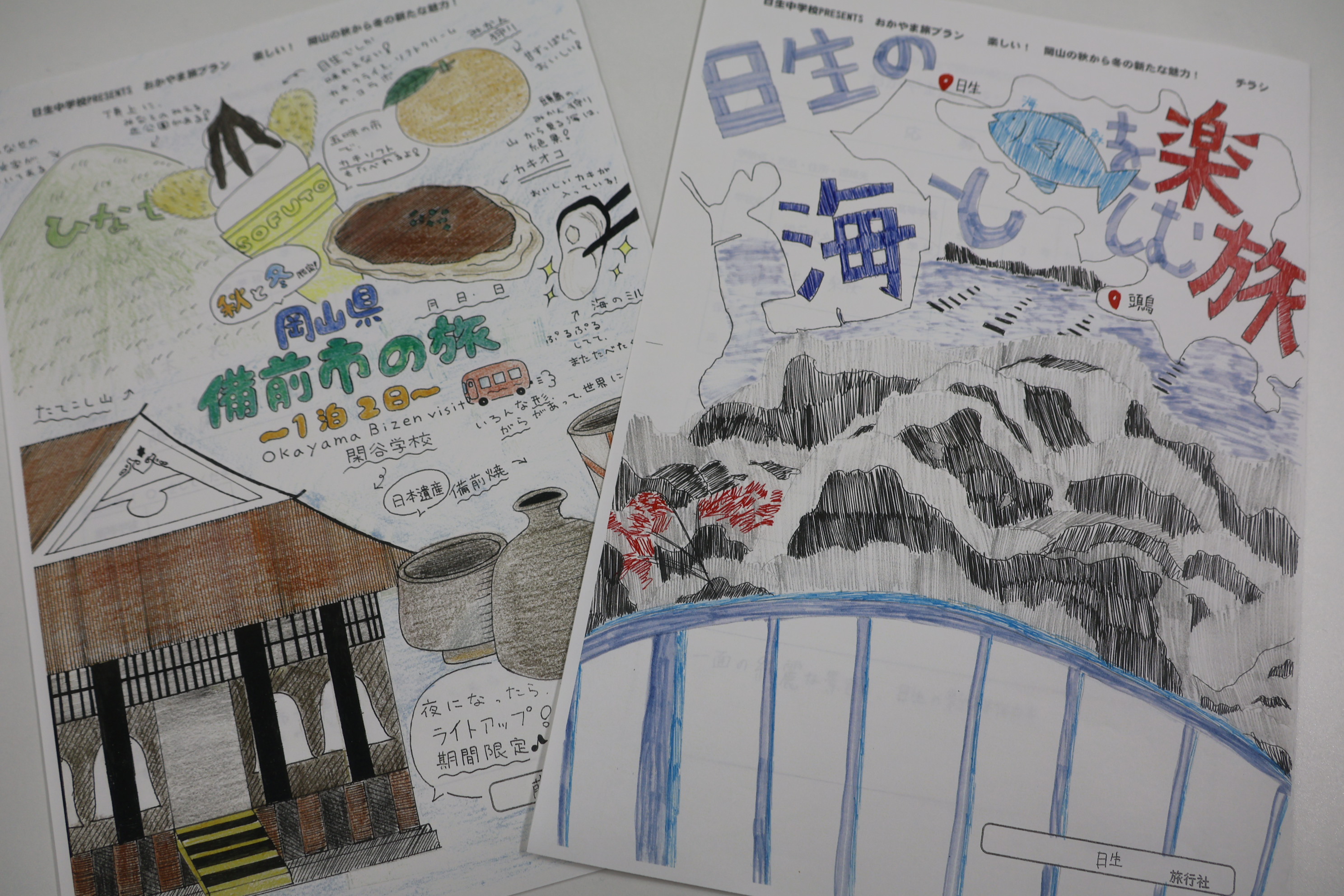
◎ひな中の風✨(2/10)
鍵かけコンテスト表彰式へ
岡山県内の中学や高校が学校対抗で自転車の施錠率を競う県警の「鍵かけコンテスト」の表彰式が10日、県警本部であり、上位24校に知事表彰が贈られた。コンテストは昨年9~11月に開催し、過去最多の197校(中学132校、高校62校、義務教育学校2校、中等教育学校1校)が参加。警察官らが各校の駐輪場で月に1回抜き打ちで調査し、平均施錠率が高い学校を登録台数別の3部門でたたえた。式には約30人が出席。県警の河合弘文生活安全部長が各校の代表者に賞状と盾を手渡した。県警によると、昨年の自転車盗の認知件数は2906件(前年比298件増)で、そのうち約8割が無施錠。参加校の平均施錠率は75・2%だった。
本校は標語部門で入賞し、取組を推進している体育委員会(体育委員長)が、代表で表彰式に参加した。



◎厳しい寒さの先に(2/10)


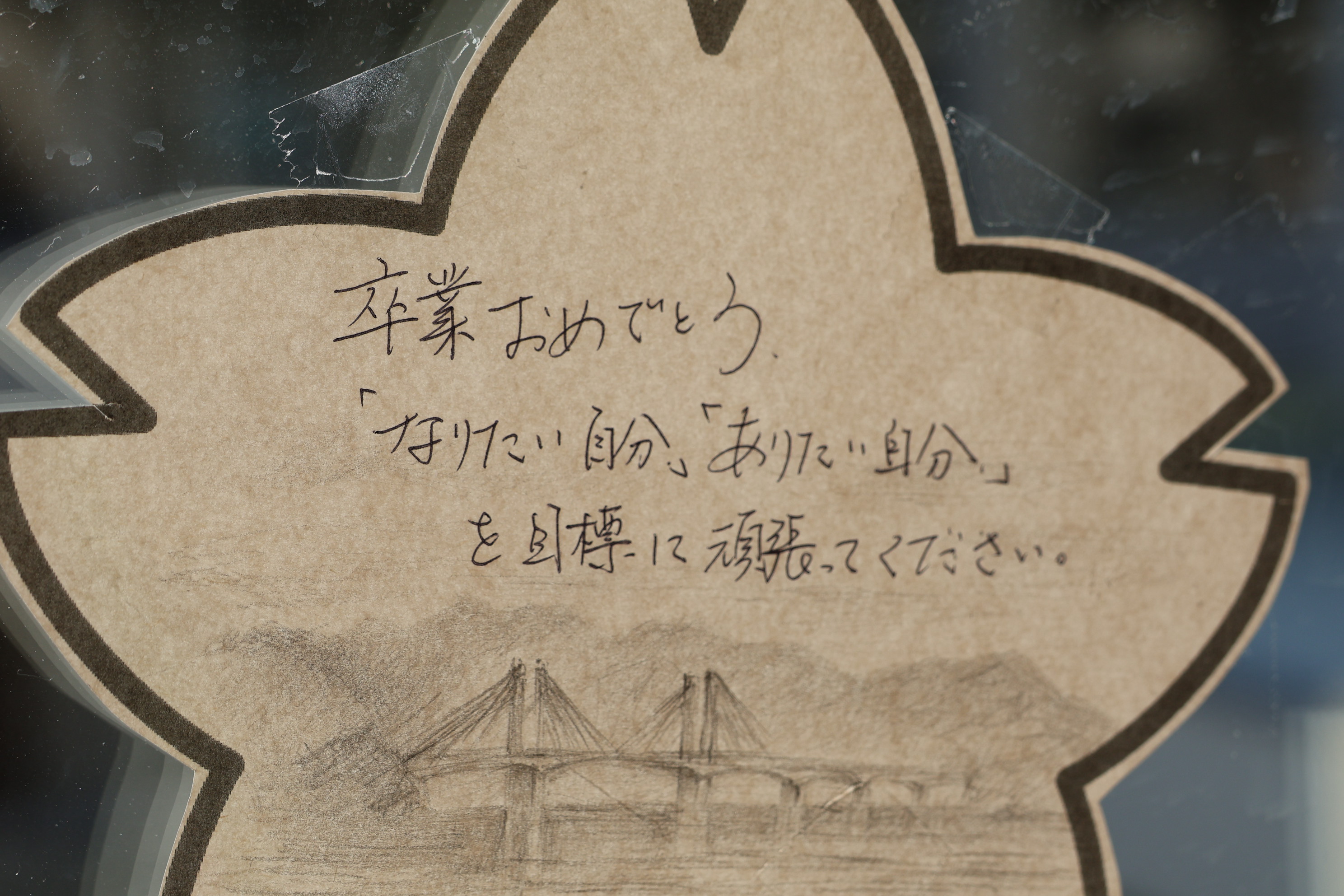



さくらさくらつよくなりたいほんとうはつよくなくてもいいとしりたい 塚田千束
◎ご安全に。天候に注意(2/7)



強い寒気が南下する影響で、東北日本海側から北陸、山陰にかけては断続的に雪が降り、積雪がさらに増える見込みです。立ち往生など交通障害や屋根からの落雪、山間部では雪崩などにも警戒してください。除雪が必要になりますが必ず複数人で行い、安全を最優先するようにしてください。沿岸部を中心に風も強く吹いて、吹雪になるおそれがあります。視界不良にも注意してください。
東海や西日本太平洋側では変わりやすい天気で、日差しが届いてもにわか雨や雪の可能性があります。西の空から灰色の雲が近づいてきたら天気の急変に注意してください。風が強く、吹雪や横殴りの雨になるおそれもあります。夜遅くになると、名古屋周辺から滋賀県や京都周辺にかけて雪雲が流れ込みやすくなります。翌朝にかけて雪が積もることも考えられるので、早めの帰宅が良さそうです。
◎地域とともにある学校
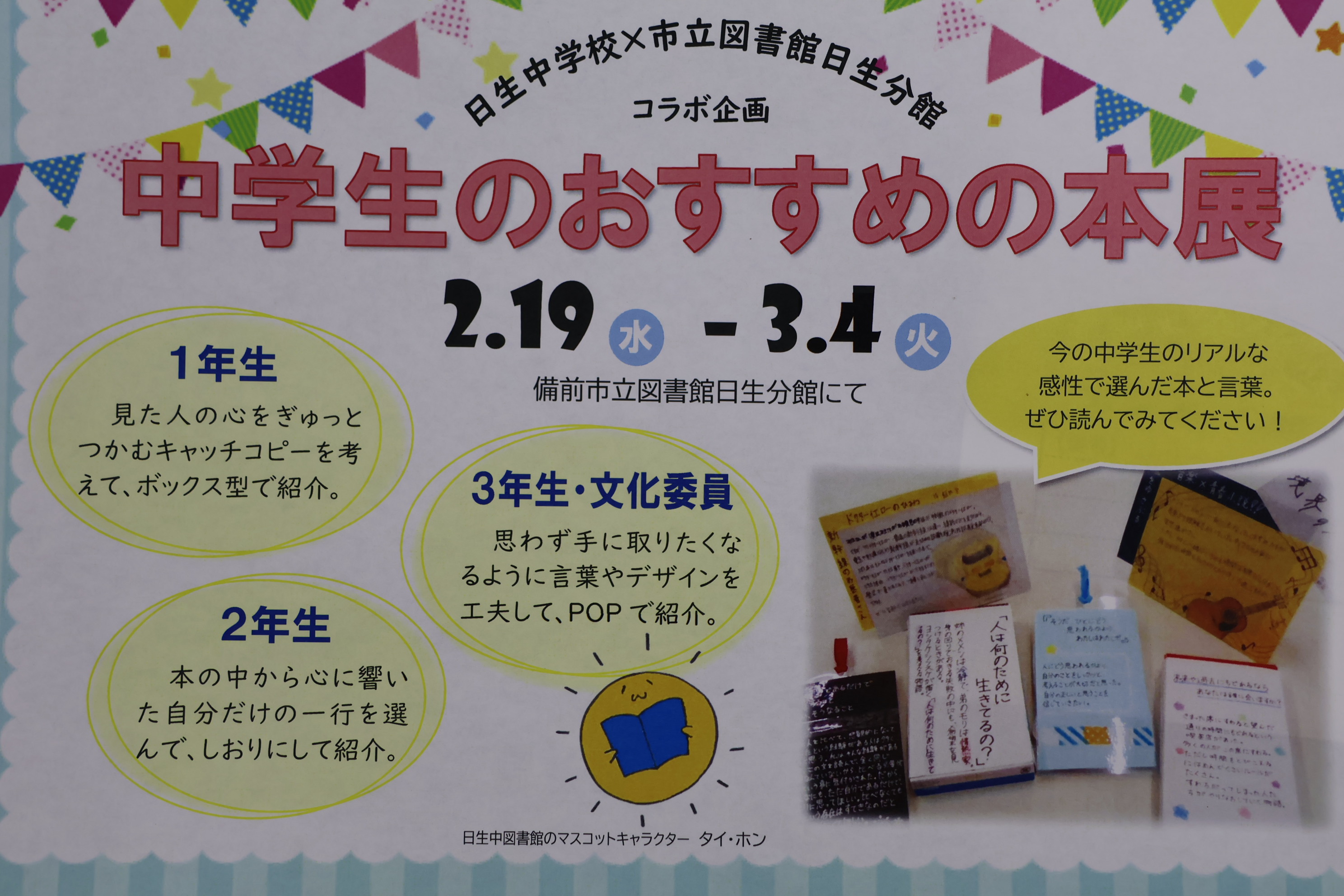
◎進路を切り拓(ひら)く、「待っててね!未来・夢」
特別入試問題を解いてみる(2/6)
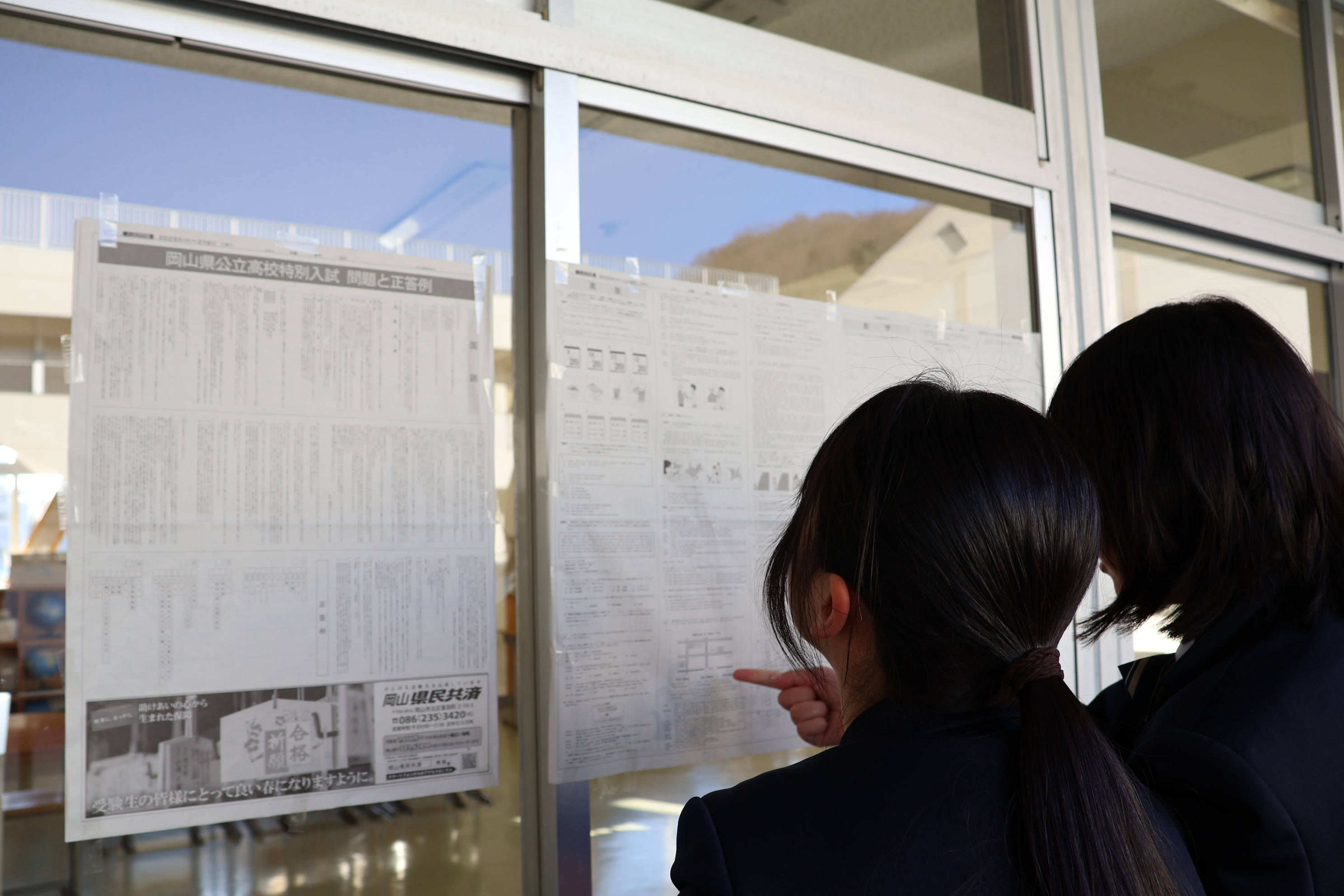
◎ひな中の風(2/5)
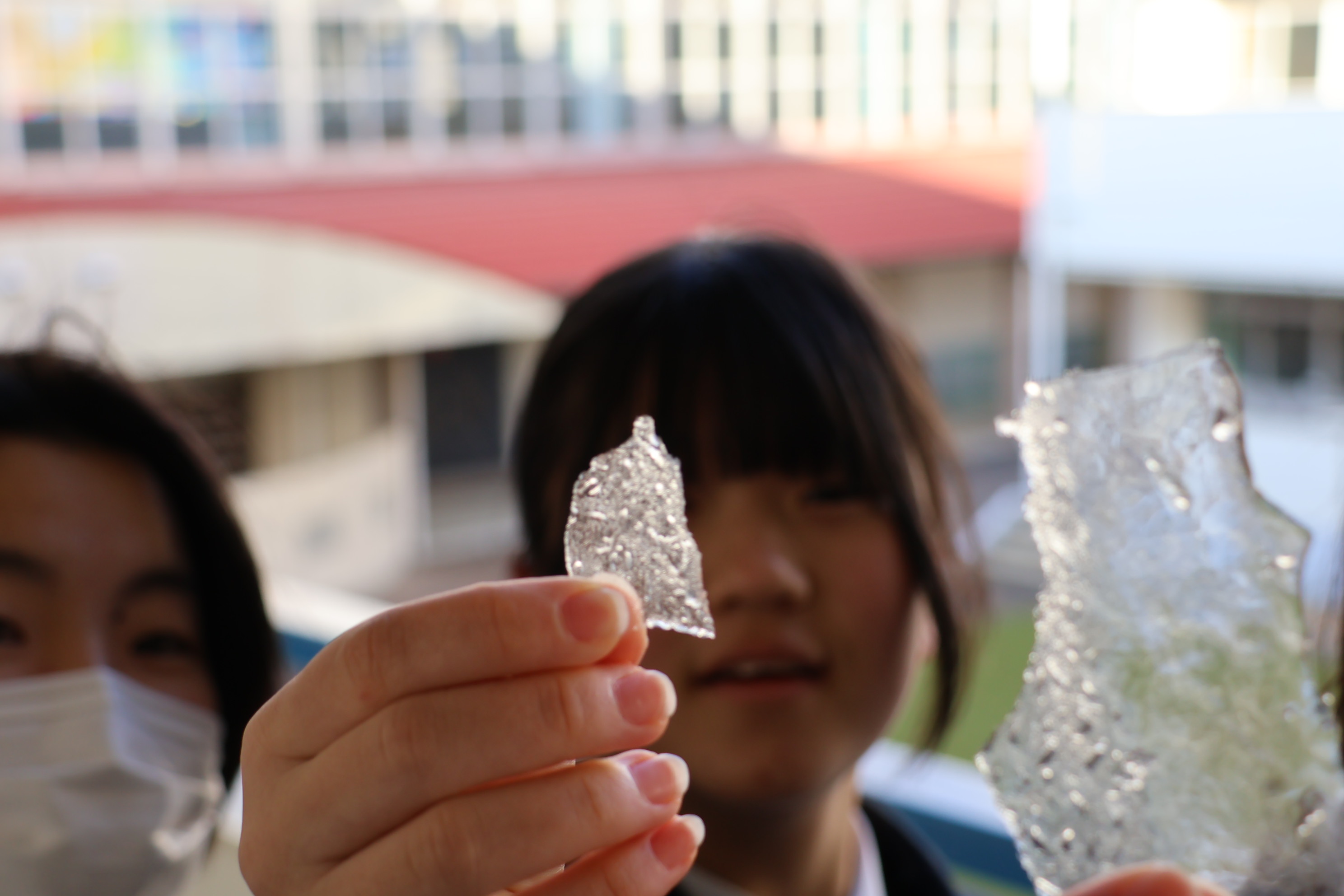

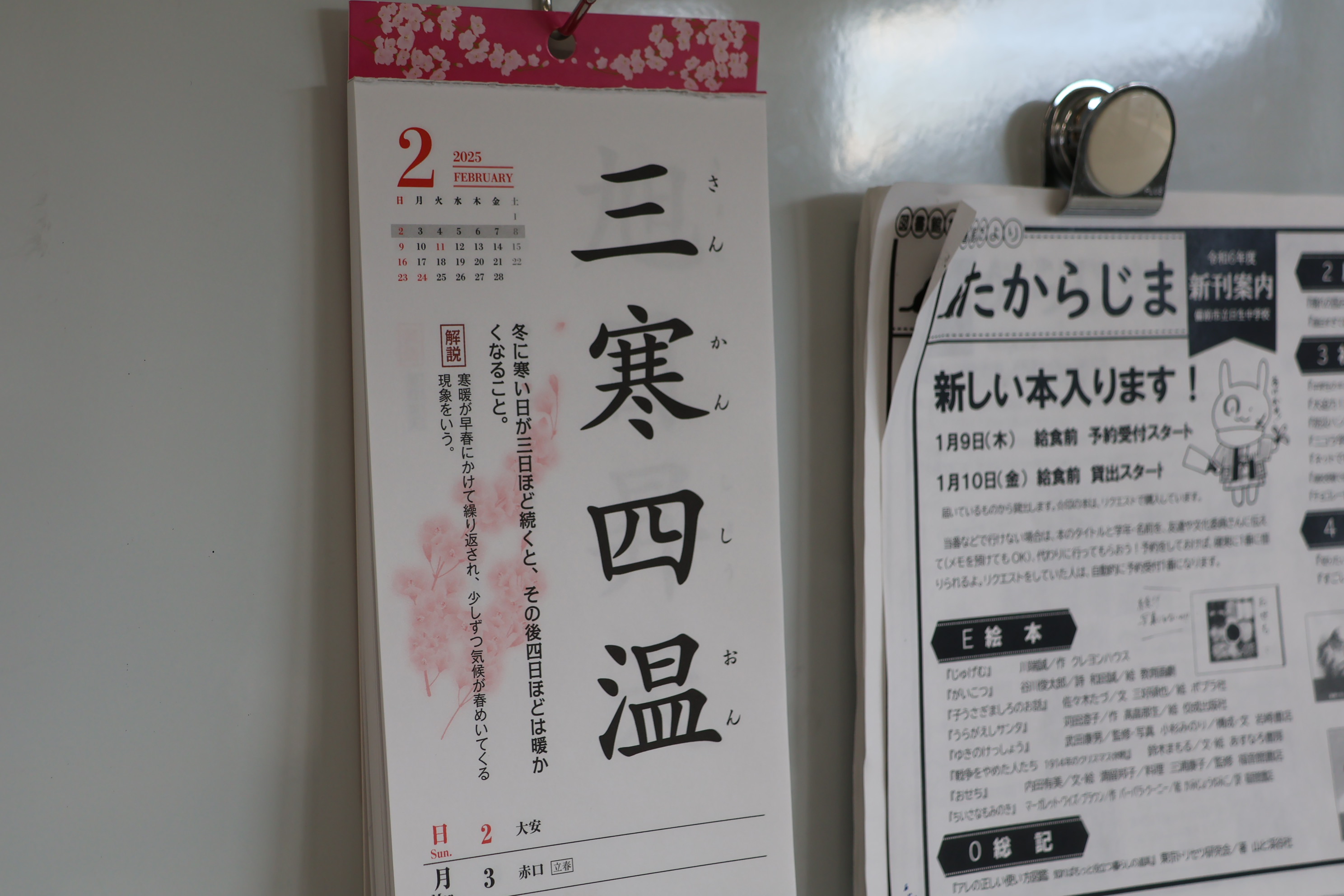
◎正しく知り 正しく行動するために
ハンセン病問題学習展示 後半スタート(~2/18)



~観ていただいた市民の方々アンケートの一部を紹介します
○中学生たちが、自主的に学びまとめていることに感動しました。これからも、学んだことを周りに伝え、学びの輪を広げてほしいです。
○生徒の、心からのメッセージを感じました。「差別は、無関心から生まれる」とありました。その通りですね。私自身ももう一度振り返ってみようと思いました。残り少なくなった中学生活をしっかり楽しんでください。
〈もう一押し更に二押し生きるとは考えること種を握れば 春日真木子〉
(2/5~6:県立特別入試)



岡山県内の公立高校49校で5日、2025年度特別入試が2日間の日程で始まった。約7300人が出願しており、3月の一般入試に先立ち、生徒たちが共通の学力検査や面接、各校独自の作文などに挑んだ。
試験会場へ入室後、生徒たちは注意事項の説明を聞いた後、午前9時20分から国語、数学、英語の学力検査に臨んだ。午後は実技や口頭試問を行い、6日は面接がある。
生徒の多様な能力や適性をみて選抜する特別入試は14年度に導入され、定時制を含む県立43校と岡山、倉敷、玉野、井原市立の6校で実施。県立全日制では50校の総定員1万625人の44・0%に当たる4674人を特別入試で募った。
合格内定者は14日に中学校を通じて通知する。一般入試は3月11、12日に行われる。
◎ファイト! 闘う君の唄(2/4:明日を前に)
ファイト! 闘う君の唄を 闘わない奴等が笑うだろう ファイト! 冷たい水の中を ふるえながらのぼってゆけ 暗い水の流れに打たれながら 魚たちのぼってゆく 光ってるのは傷ついてはがれかけた鱗が揺れるから いっそ水の流れに身を任せ 流れ落ちてしまえば楽なのにね やせこけて そんなにやせこけて魚たちのぼってゆく(中島みゆき FIGHTより)


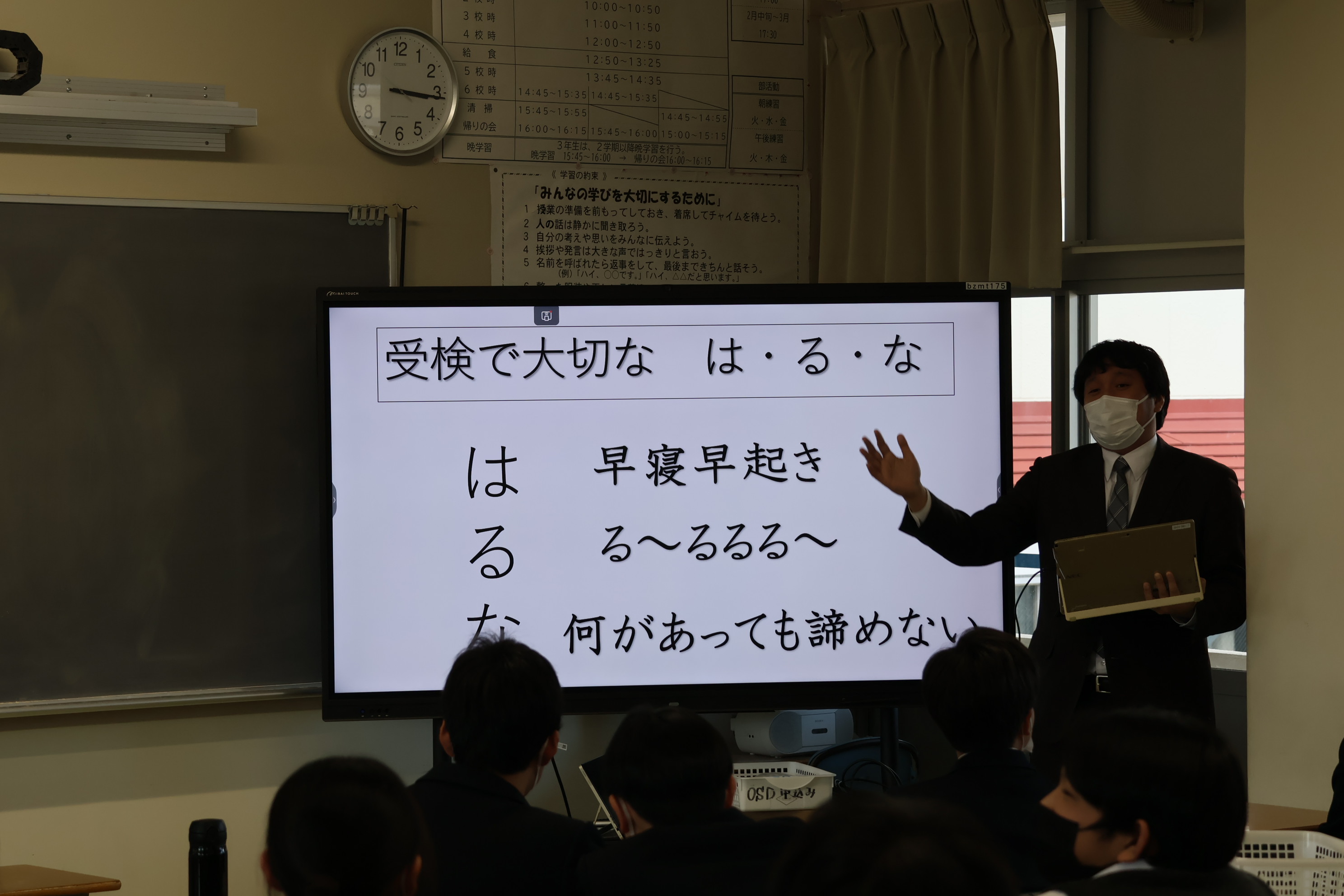

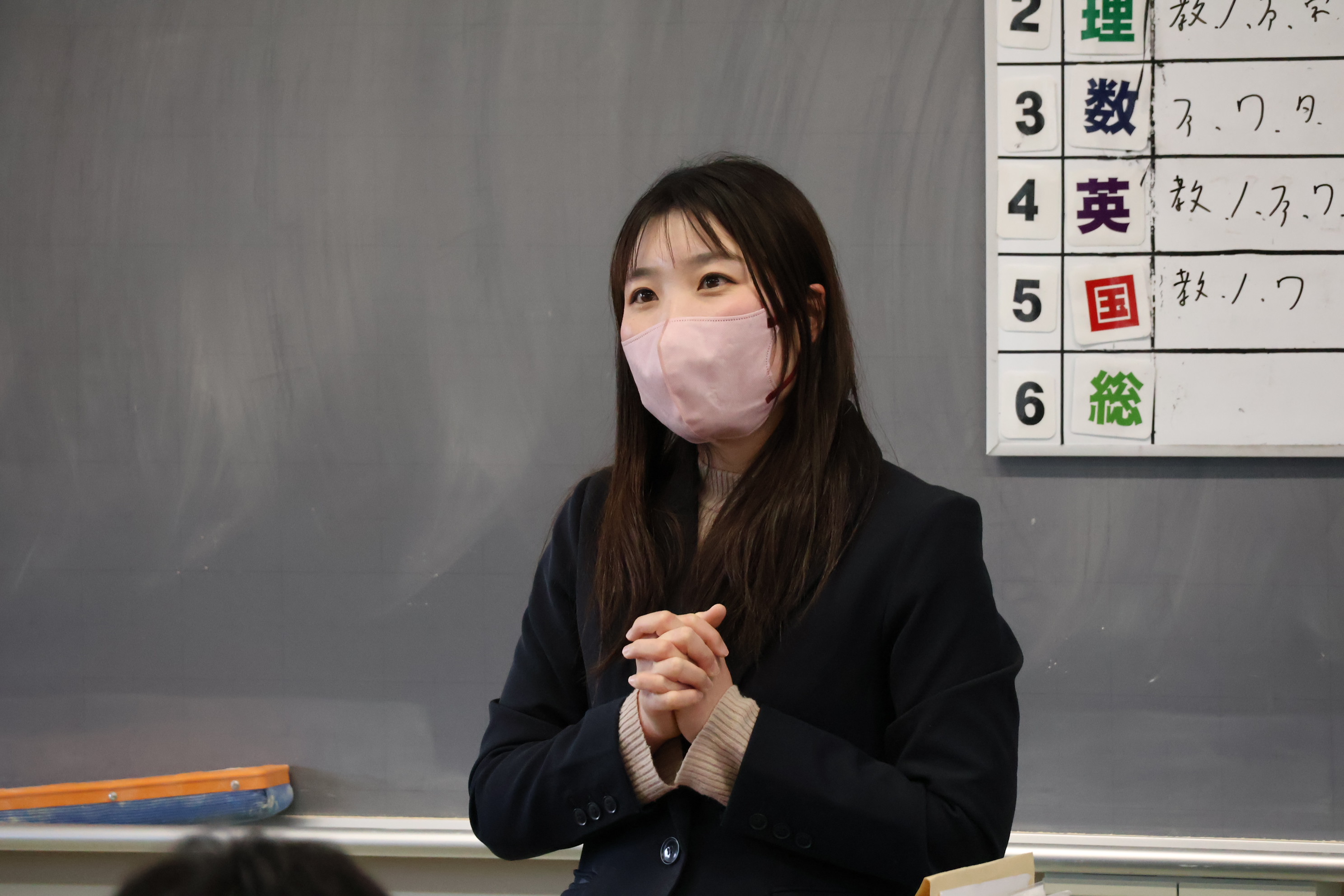
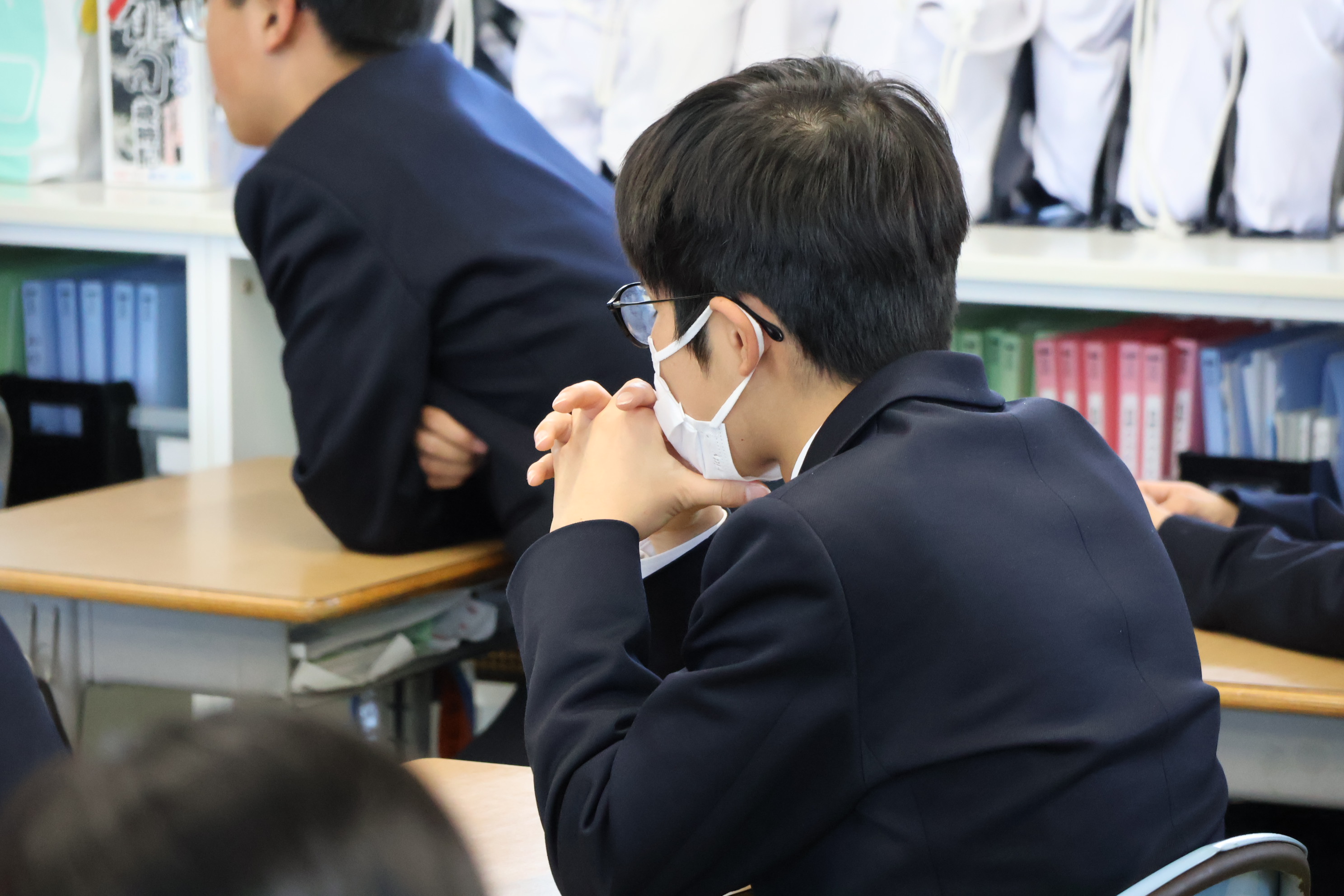
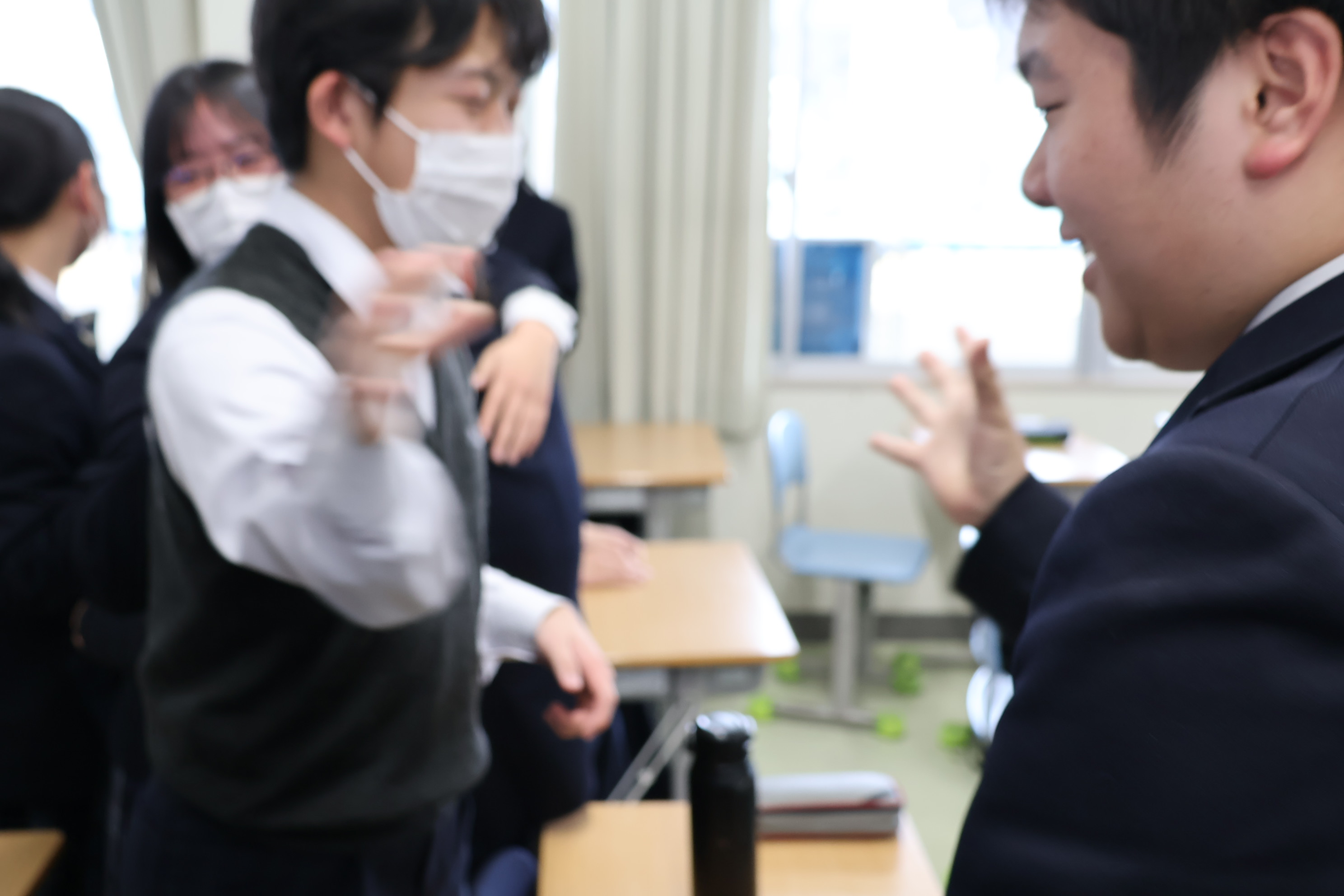


◎多くの人に支えられて(2/4)
調理場の皆さんへ。いつもありがとうございます。感謝を込めて、給食委員会でまとめたメッセージをお渡ししました。(給食週間)
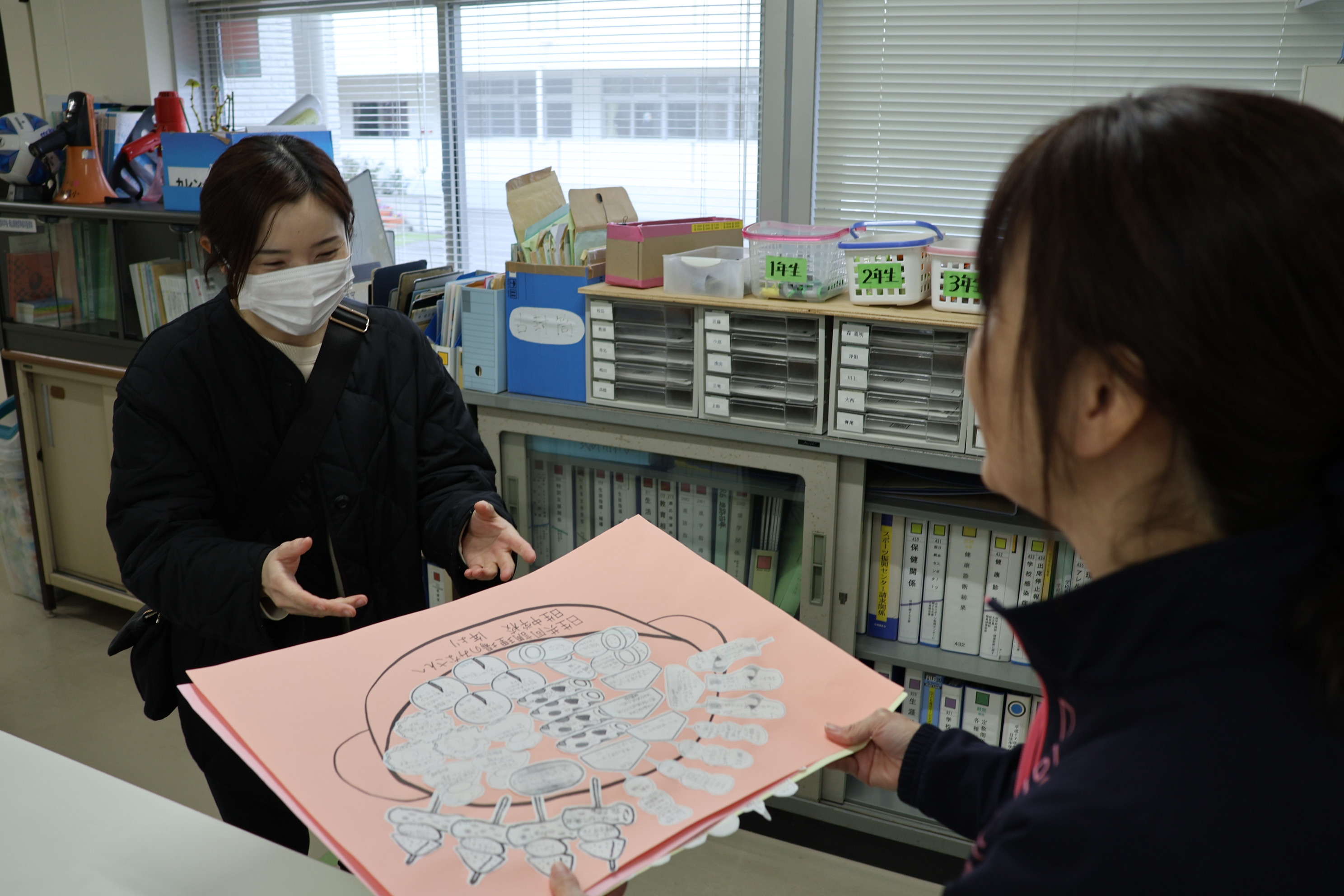
◎多くの人に支えられて(2/4)
昭和56年度日生中卒業(還暦)の方々から中学校へ寄付を頂きました。ありがとうございました。生徒の教育環境の充実に活用させていただきます。
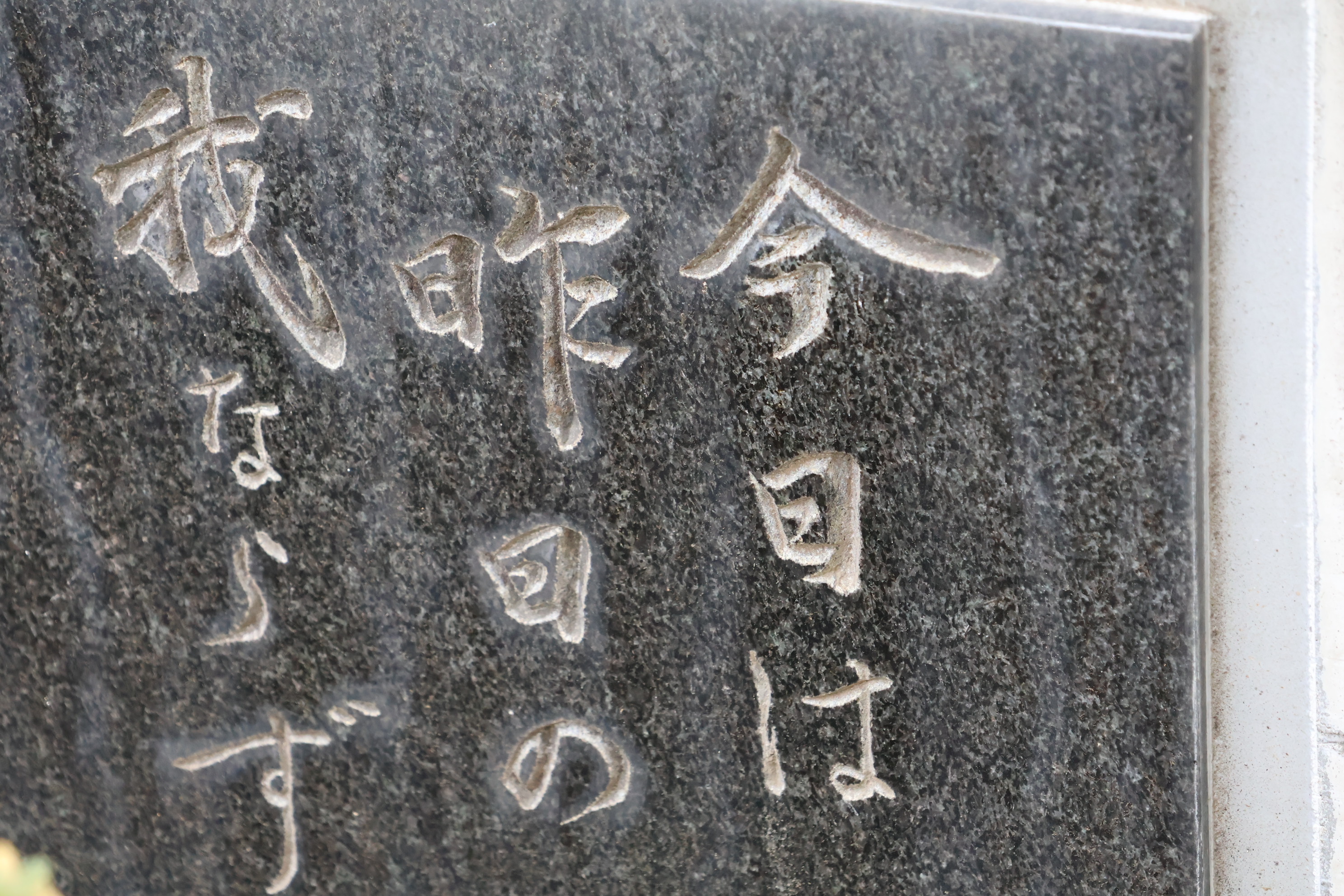

◎自分らしく精一杯 仲間とともに
~県立特別入試に挑むよ(2/5~6)
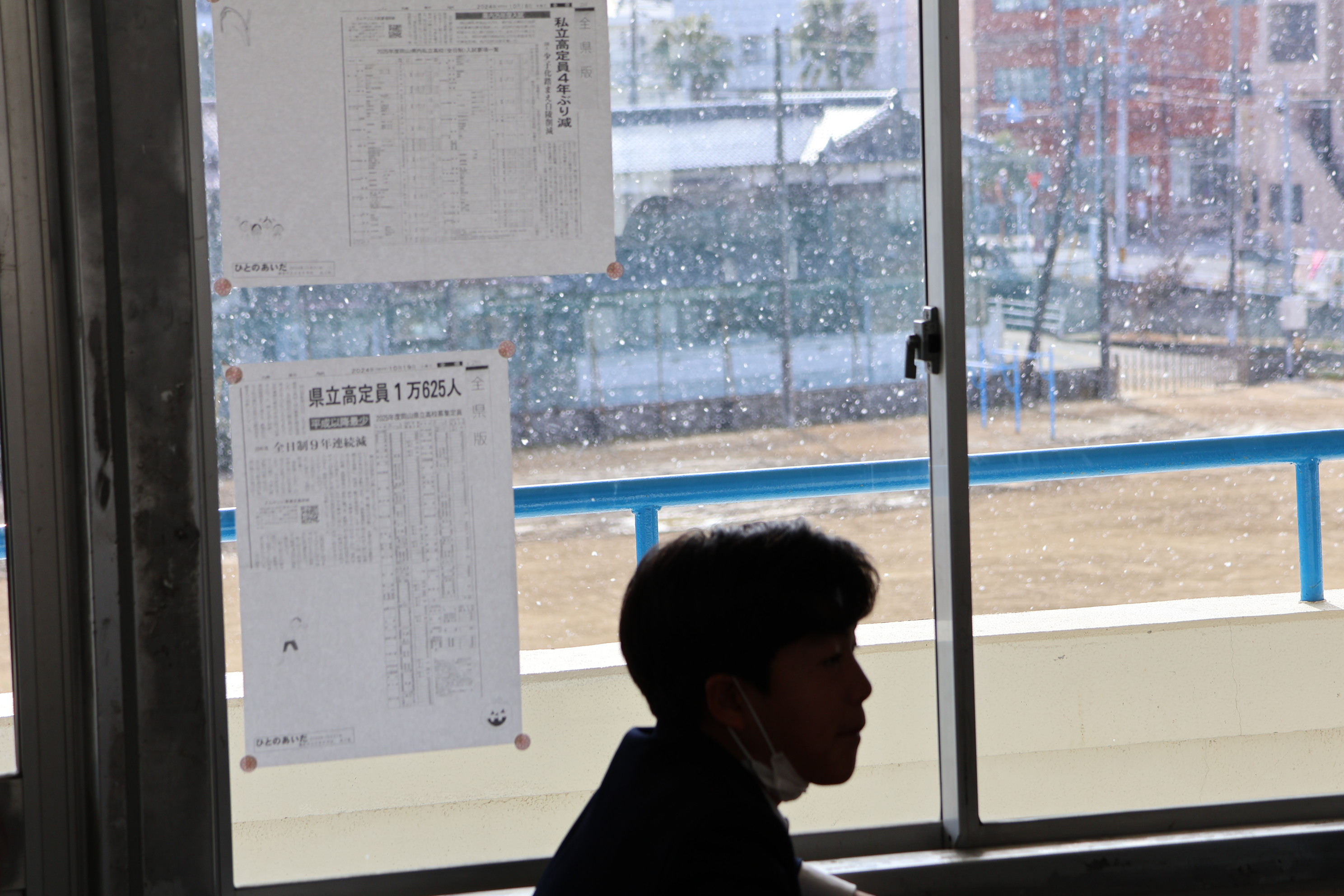
◎わたしたちの食を大切にしたい
(2/4:二年生家庭科・調理実習)


サポートに、地元の竹田さん、荒木さん、調理場から北川先生に来ていただきました。ありがとうございます。
◎いきる授業
~みんなが笑顔の備前市をどうつくるか?(2/4:三年生社会科公民分野)
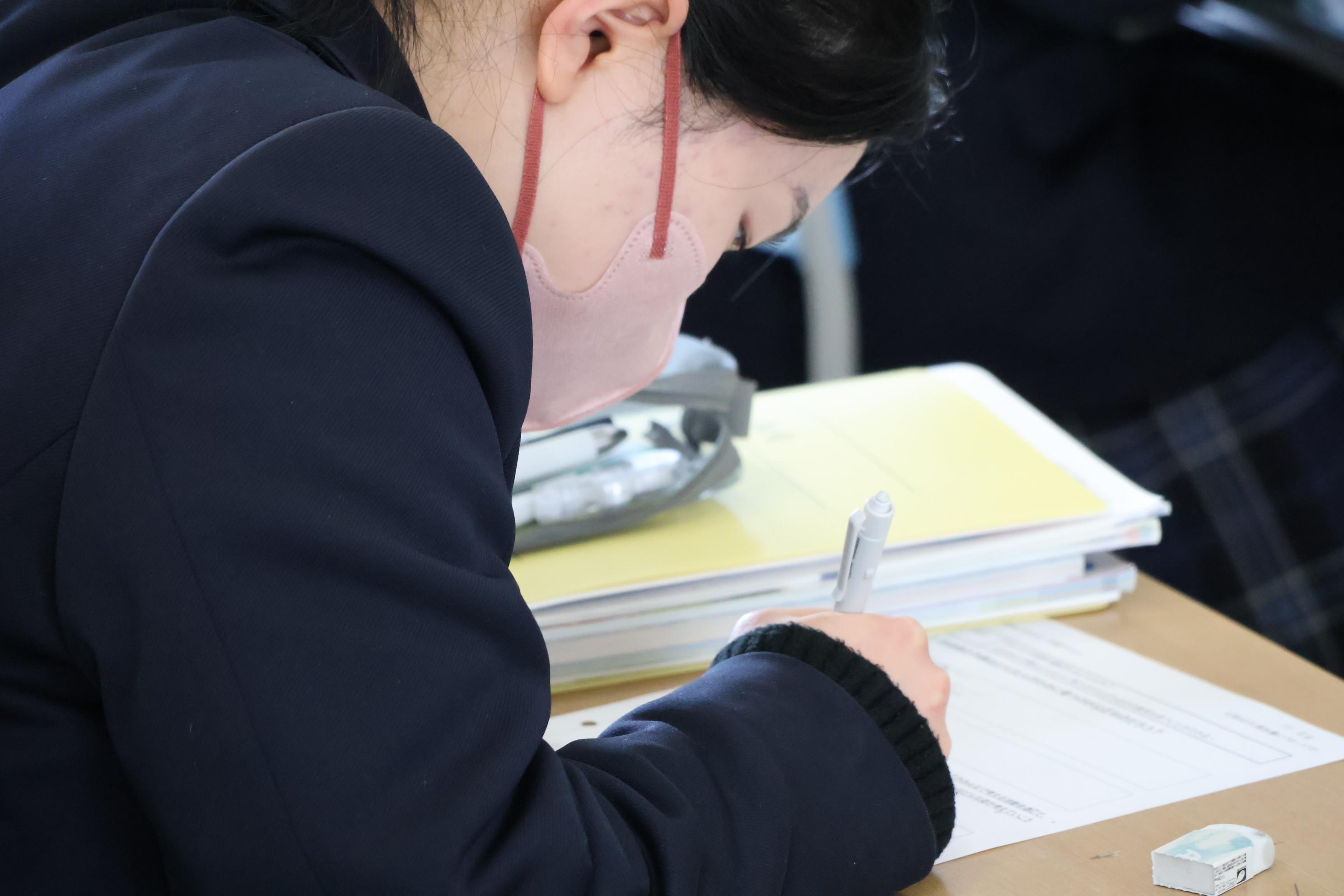

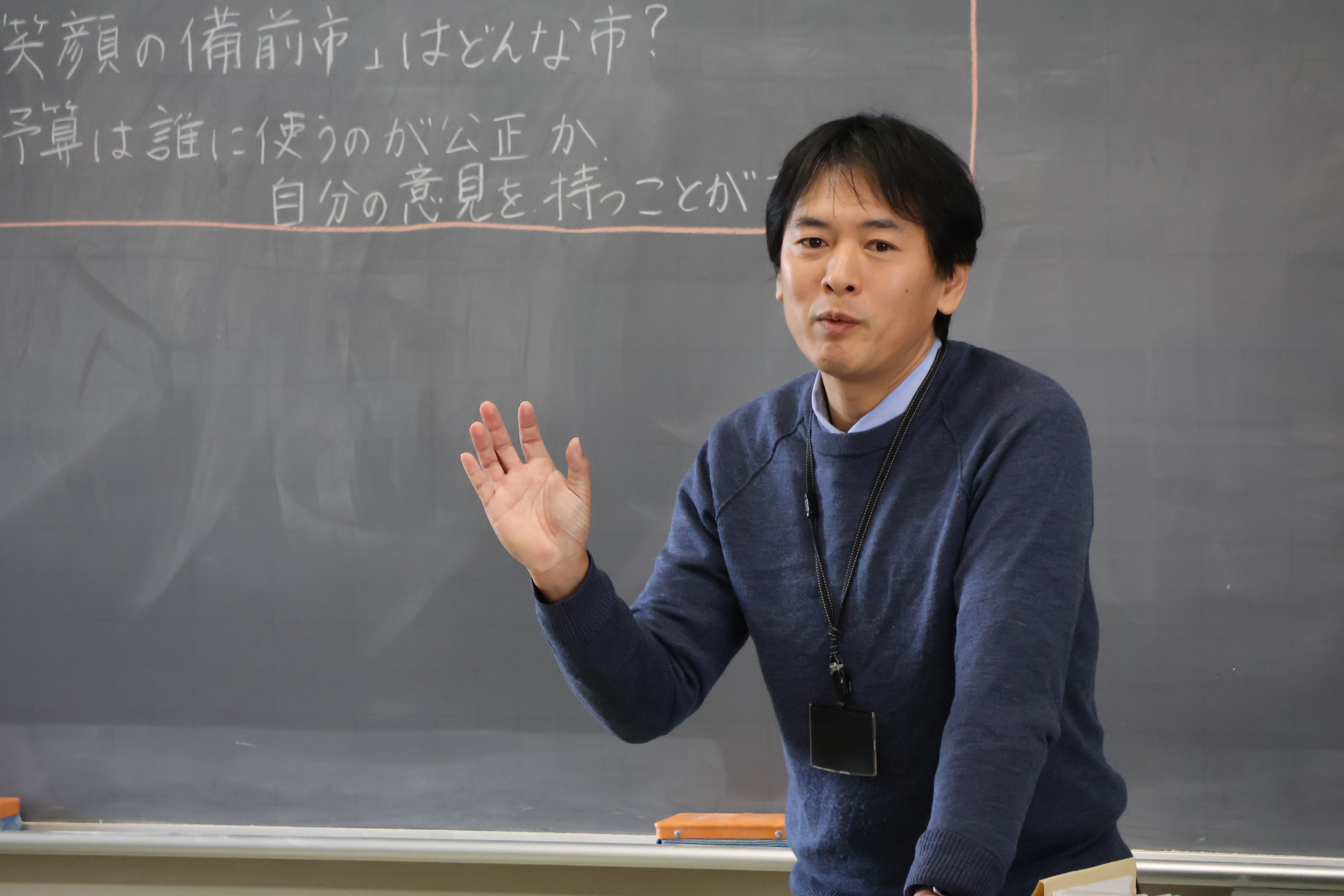
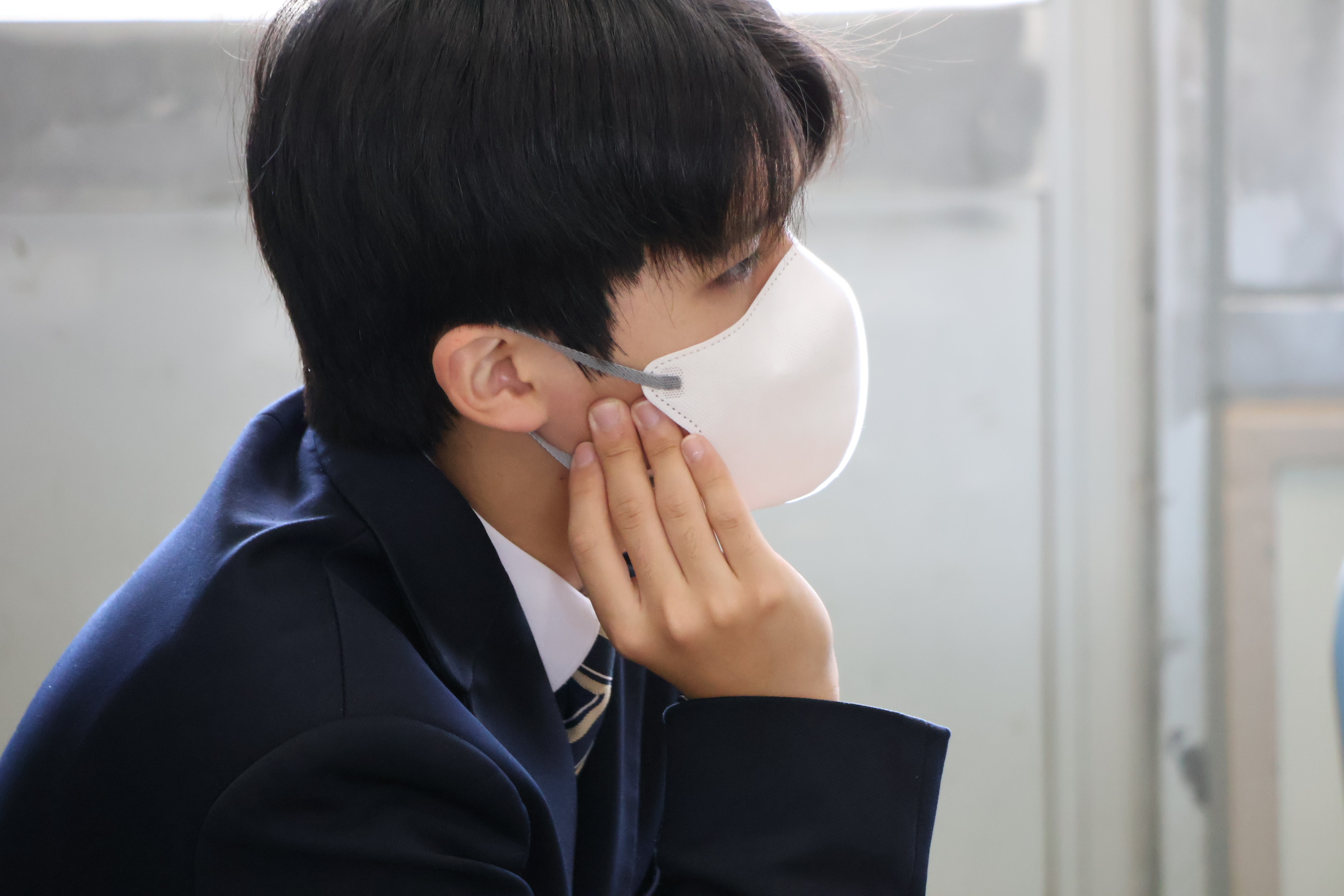
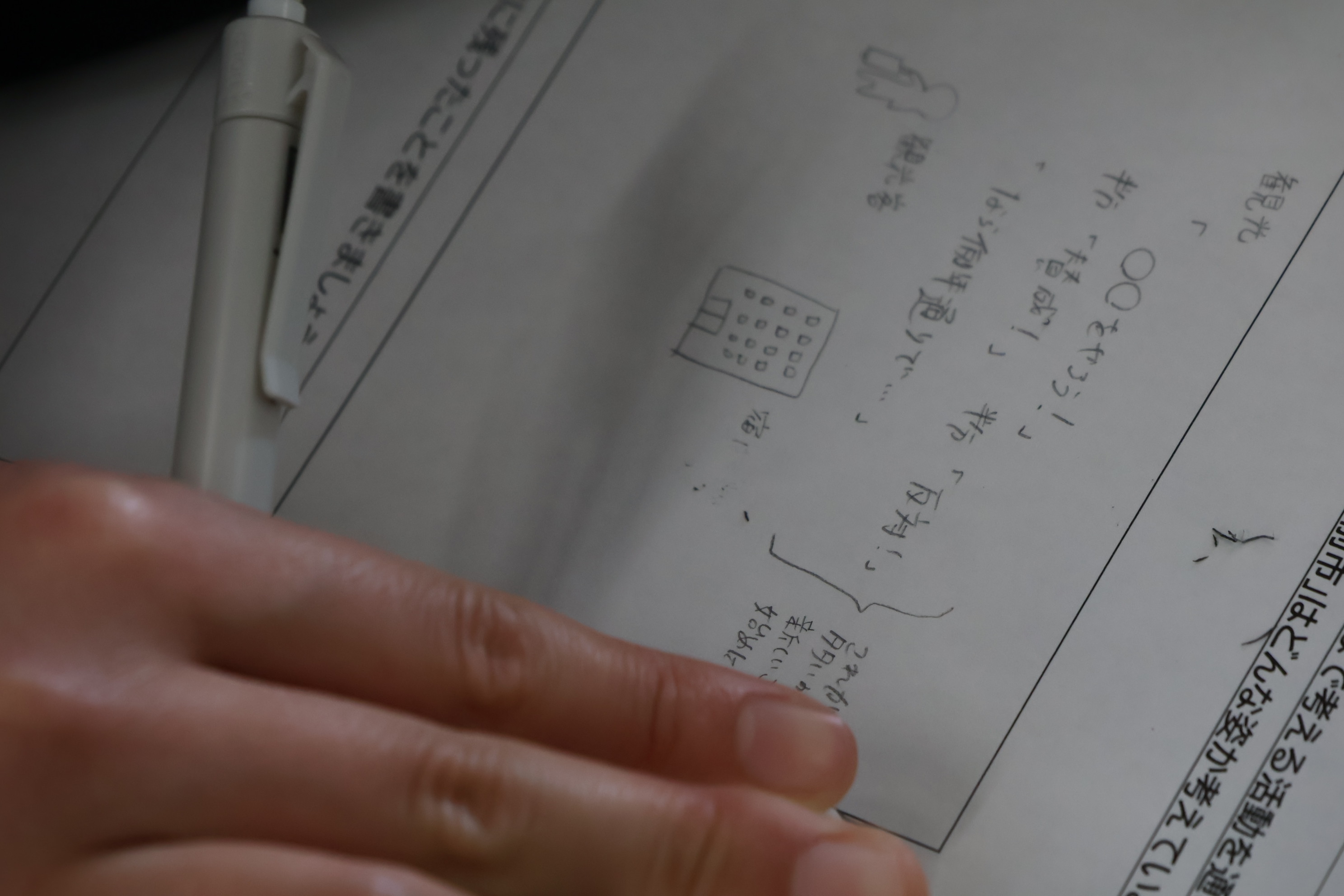
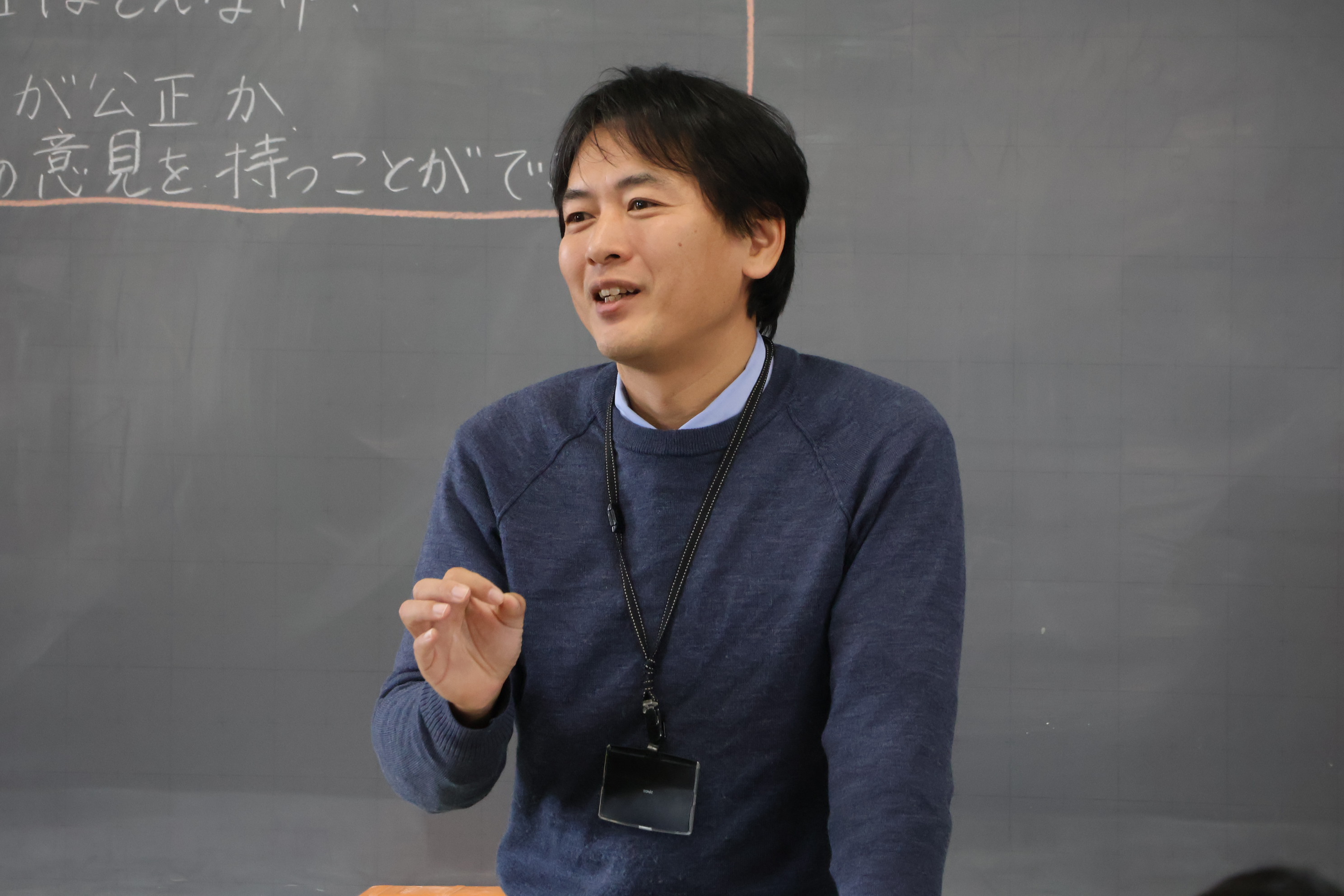




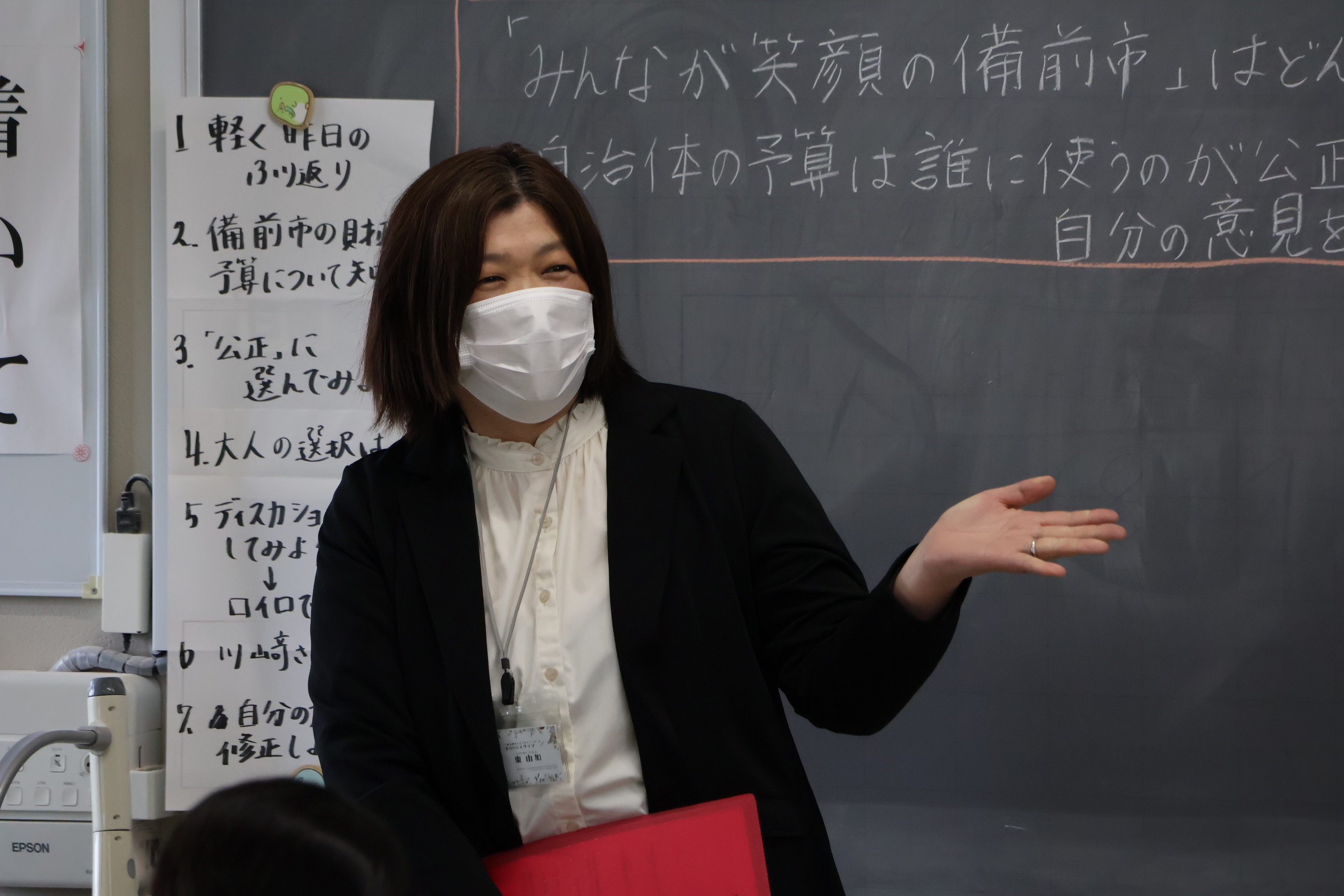
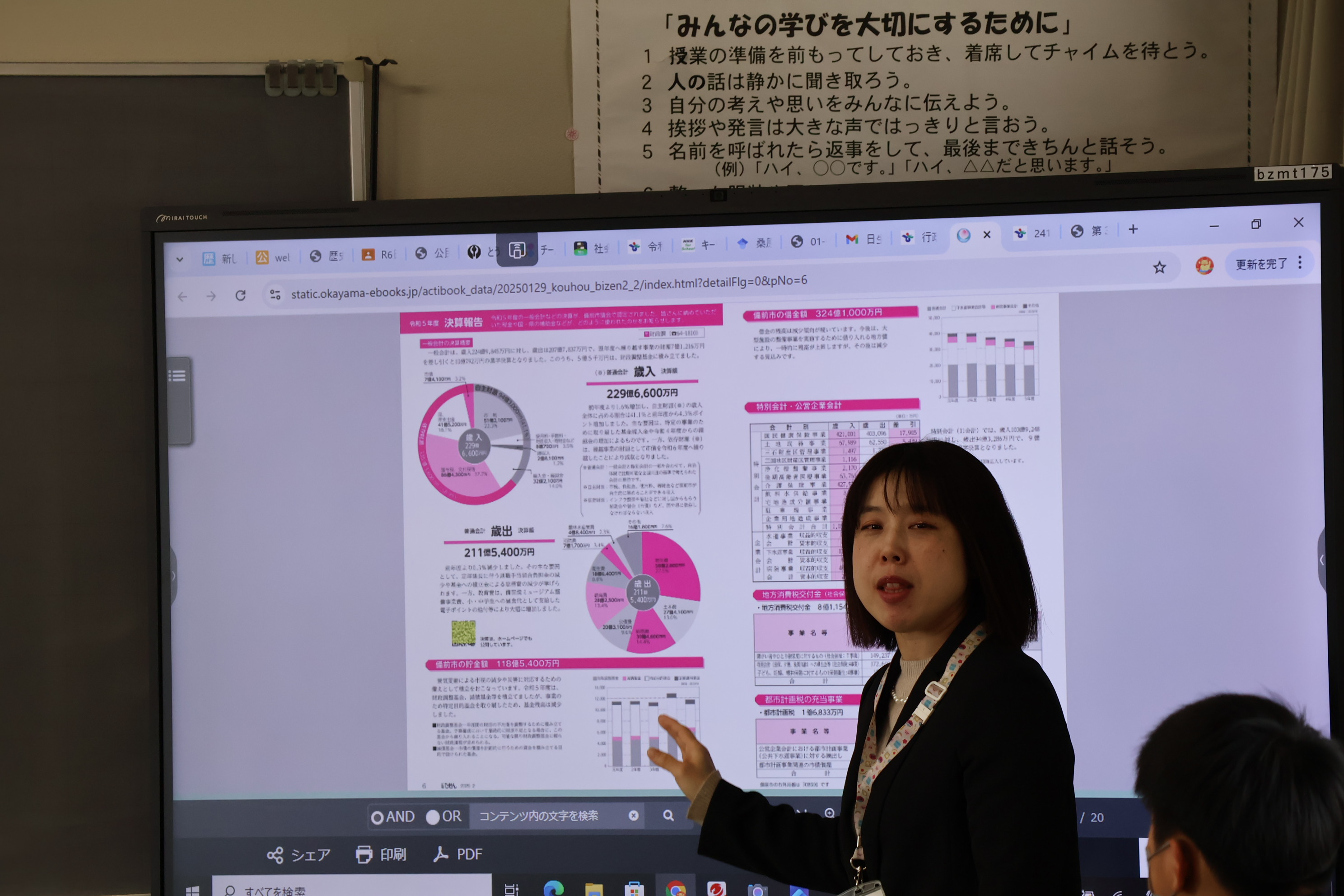
◎ひな中の朝 私たちの生徒朝礼(2/4)



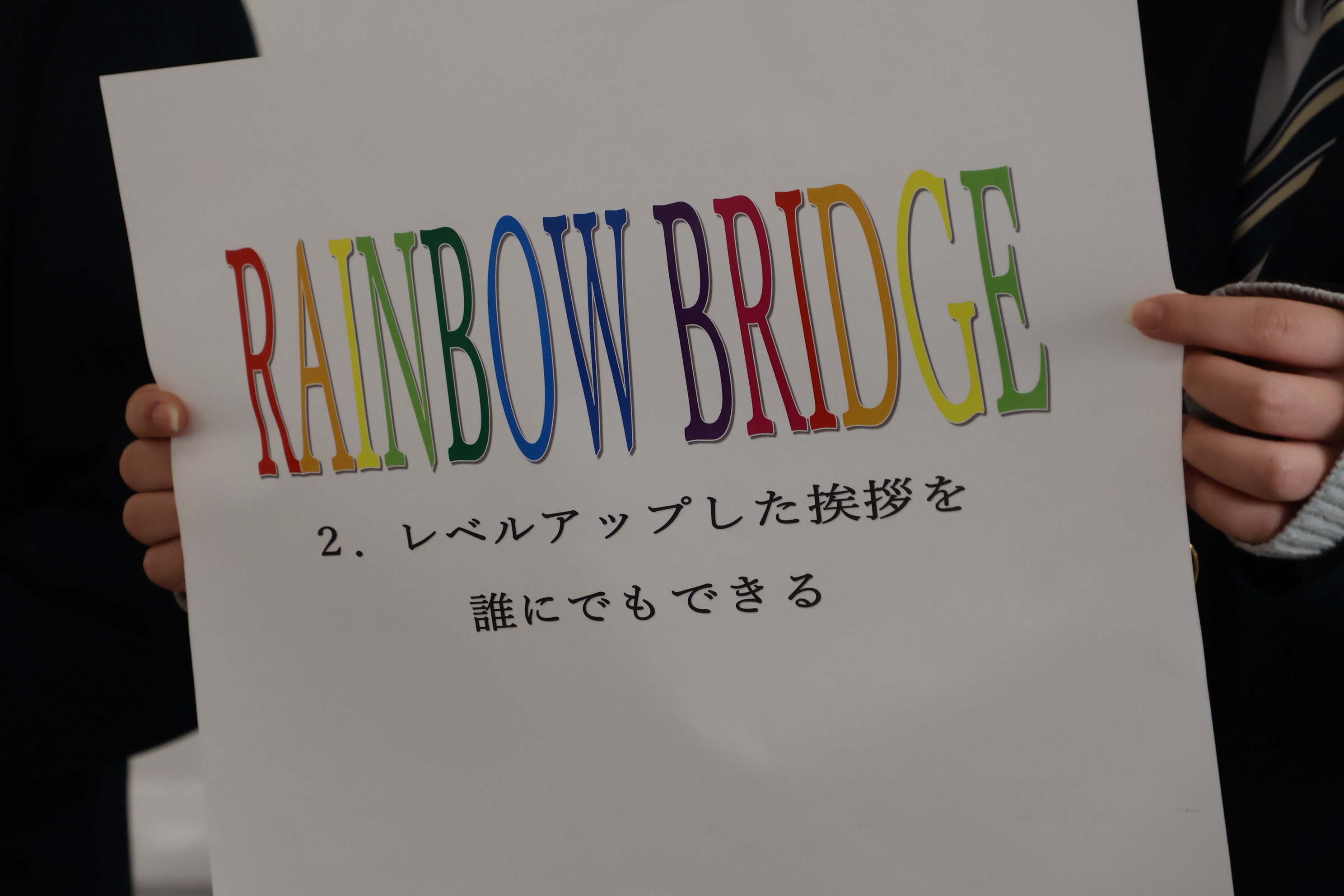

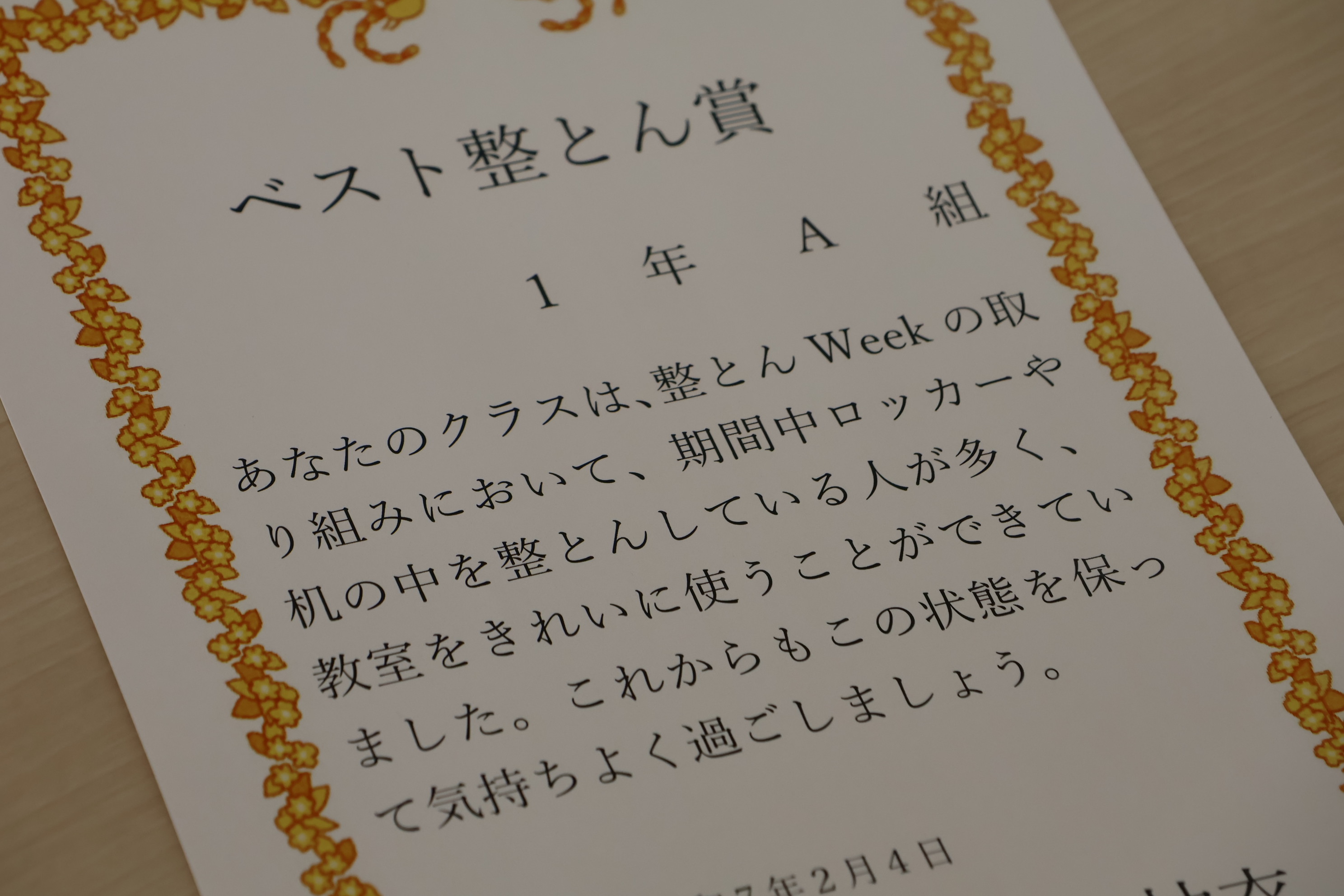
◎ひな中の風✨(2/3)
草野信子さんの「カレーライス」という詩を紹介します。
カレーライスを
ひとにめがけて
ぶっつけたことがある。
一瞬
泣きそうな顔をみせて
そのひとは
皿を拾い
ごはん粒を拾い
ごはん粒を拾い
胸のカレーを拭いた。
こするほどに
黄色い染みがひろがって
食べ汚した幼な子のようだった。
それから
ゆっくりと
トレーナーを脱ぎ
トレーナーを脱ぎ
裏返して
それを また
すっぽりと着たのだった。
記憶が匂いを放つので
カレーライスの日は
あの夜
私を送る電車の中で
「匂うね」
と 笑ったひとを
思い出す。
ひょいと
トレーナーを裏返せば
何もなかったのも同じ。
くらしとは
そのように
許すことなのだと
私にもわかった
いくつもの
いくつもの夕暮れの中で。

◎福は内 福は内 みんなに福を(2/3)
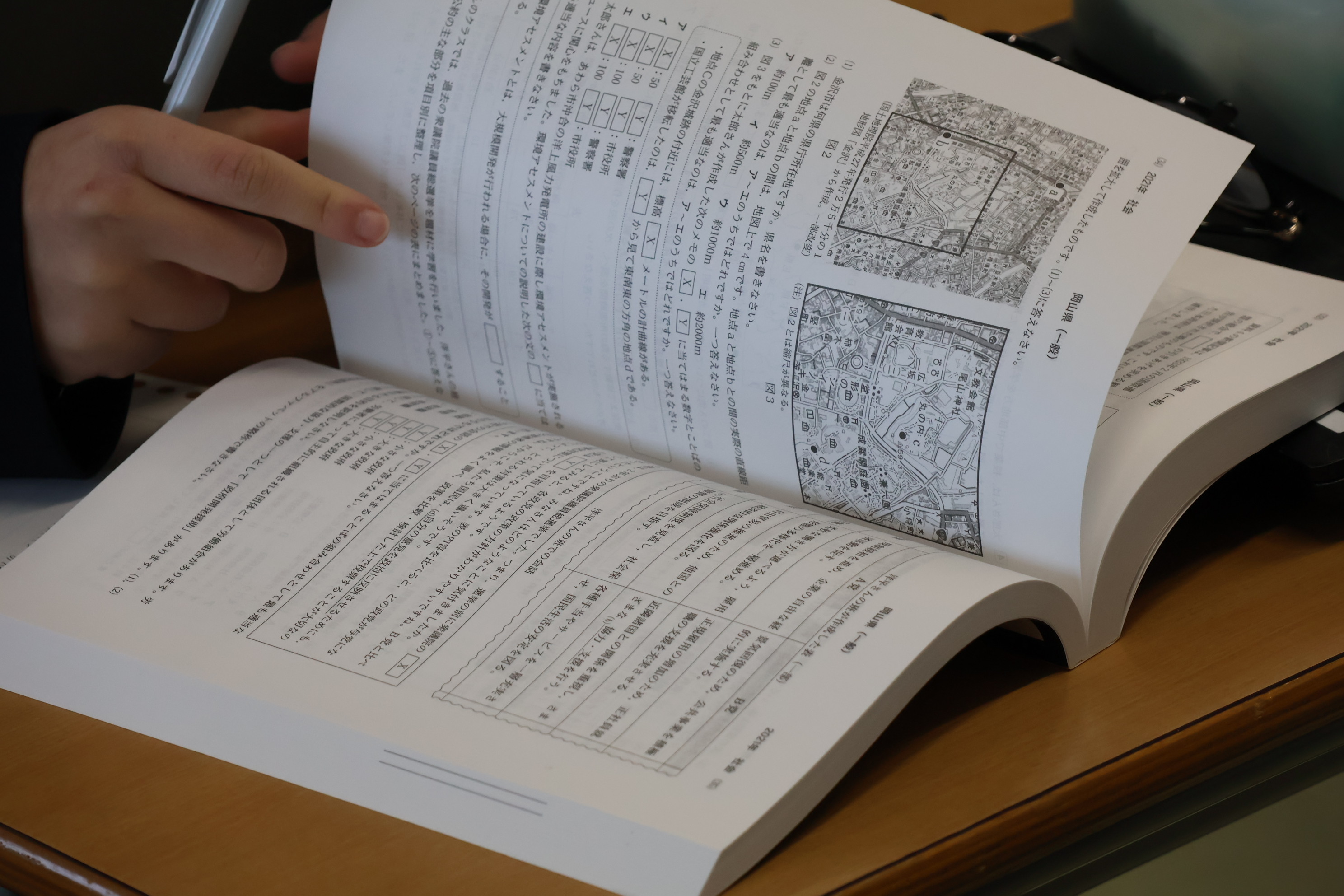

~少しの時間も大切に(三年生の帰りの会で)
節分は「2月3日」と覚えている方も多いかもしれませんが、実は必ずしも2月3日であるとは限らないのをご存じでしょうか。2月の節分は「立春の前日」とさだめられており、立春は年によって変わることがあるため、2月2日や2月4日になる場合もあるのです。立春とは「二十四節季」の1つで「春のはじまり」をあらわします。二十四節季とは「春」「夏」「秋」「冬」の四季のうち、各季節を6つの節目に分けたもので、春の中では立春の次に「雨水(うすい)」「啓蟄(けいちつ)」などの節目があります。ほかに「立夏」「立秋」「立冬」もあるため、厳密にいうと節分は年に4回あることになります。4つの節分の中でも、立春前の節分が特に重んじられるのは、昔の旧暦と季節の考え方が関係しています。1月を「新春」というように、昔は春が新しい年のはじまりとされていました。旧暦の1月は現在の2月にあたり、新しい年へと切り替わる2月の節分が大切であると考えられたようです。
立春は、節目のうえでは冬から春へと季節が変わる日となります。古来より、季節の変わり目にはいつもと違うことが起こったり、予期せぬ出来事に見舞われたりしやすいとされてきました。そこで、立春となる前日に悪いものを追い払い、幸運が舞い込むようにと願って節分の行事がおこなわれるようになっていきました。節分のはじまりは平安時代や室町時代など諸説ありますが、日本に古くからある伝統的な行事の1つとなっています。
豆まきをする際に「鬼は外、福は内」と言うのを耳にしたことがある人も多いでしょう。節分の豆まきは、鬼を外へ払い、福を家内へ呼び込むことを目的としています。「鬼」と聞くと、桃太郎などの昔話に出てくる、角の生えた架空の生き物に豆をぶつけて退治するようなイメージですが、昔は病気や不幸といった災い招くのが鬼だと考えられており、豆は鬼退治というよりも、邪気を払う目的でまいていたようです。現代の節分では豆をまきますが、もともとは米など他の穀物も使われていました。五穀豊穣が幸せの象徴であるように、穀物をまくと幸せが訪れると考えられていたことにくわえ、古くからの言い伝えとして「毘沙門天が鬼の目に豆を投げて退治した」とされる逸話もあります。穀物の中でも特に豆が選ばれるようになるとともに、現代のような鬼退治のイメージも定着していったようです。ちなみに、幼稚園などで子どもたちと豆まきをする際には「心の中の意地悪な気持ちや苦しい気持ち、わがままな気持ちなど、心の中にある鬼を追い払いましょう」のように説明されることもあります。
鬼を呼び込むユニークな掛け声や風習には、地域ごとにさまざまな想いが込められています。
○群馬県藤岡市鬼石地域「鬼は内、福は内」
鬼石(おにし)地域は、その名にちなんで鬼を招き入れる「鬼恋(おにこい)節分祭」をおこなっています。全国で追い出された鬼を招き入れる、鬼にやさしいユニークな行事です。
○茨城県つくば市鬼ケ窪「あっちはあっち、こっちはこっち、鬼ヶ窪の年越しだ」
あちこちで追い出されて鬼を気の毒に思い、鬼を呼び寄せる意味のある掛け声です。
○紀伊半島「鬼は内、福は内」
昔、紀伊半島や伊勢志摩地域をおさめていた領主が「九鬼(くき)」という名前だったそうです。そのため「鬼」を追い出す掛け声をかけられなかったことが始まりとされています。
○宮城県仙台市「福は内福は内、鬼は外鬼は外、天打ち地打ち四方打ち、鬼の目ん玉ぶっつぶせ!」
「鬼を退治する時には、特別な力のある''目''からやっつけるのがよい」との理由から、仙台にはこのような掛け声で豆まきがおこなわれている地域があります。勇ましい掛け声に鬼も驚いてしまいそうですよね。
○東京都台東区・浅草寺「千秋万歳 福は内」
「千秋万歳」とは長寿を願う意味で使われる言葉。浅草寺では「観音様の前には鬼はいない」という理由で「鬼は外」とは言わずに「千秋万歳 福は内」という掛け声をかけるそうです。
○千葉県成田山・新勝寺「福は内」
千葉県成田山の新勝寺にまつられている不動明王は「鬼さえ改心させる強い力を持っている」といわれることから「鬼は外」は言わず「福は内」だけを唱えます。
○京都福知山市「鬼は内、福は外」
福知山市にある大原神社の掛け声は、一般的なものとは真逆の「鬼は内、福は外」。「鬼を神社の内に迎え入れて、改心して福となったものを地域の家に出す」という意味が込められているそうです。
〈傘いりますか? いらないですか? もう春と誰かが言つて春になりゆく〉
田中 塊
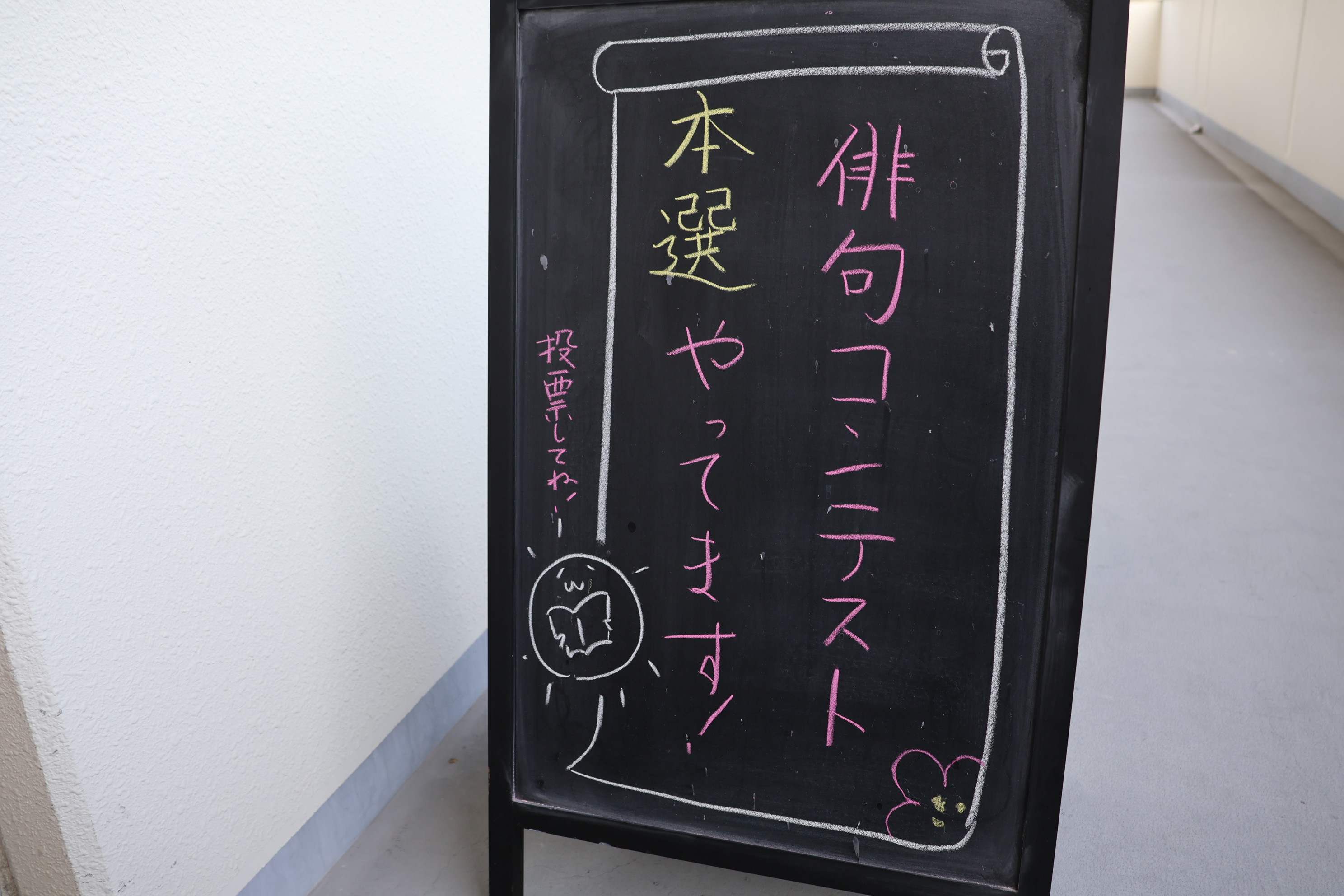
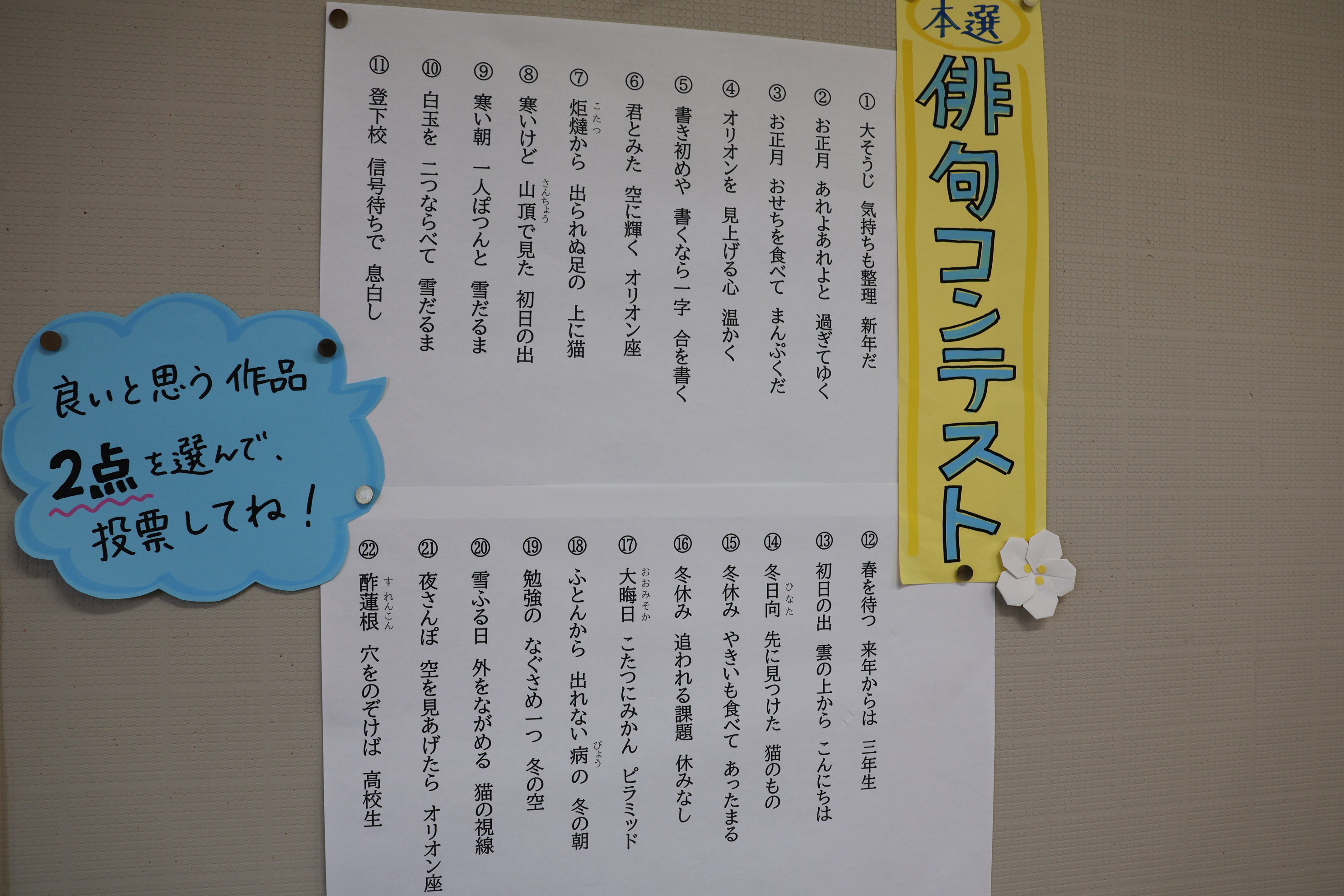
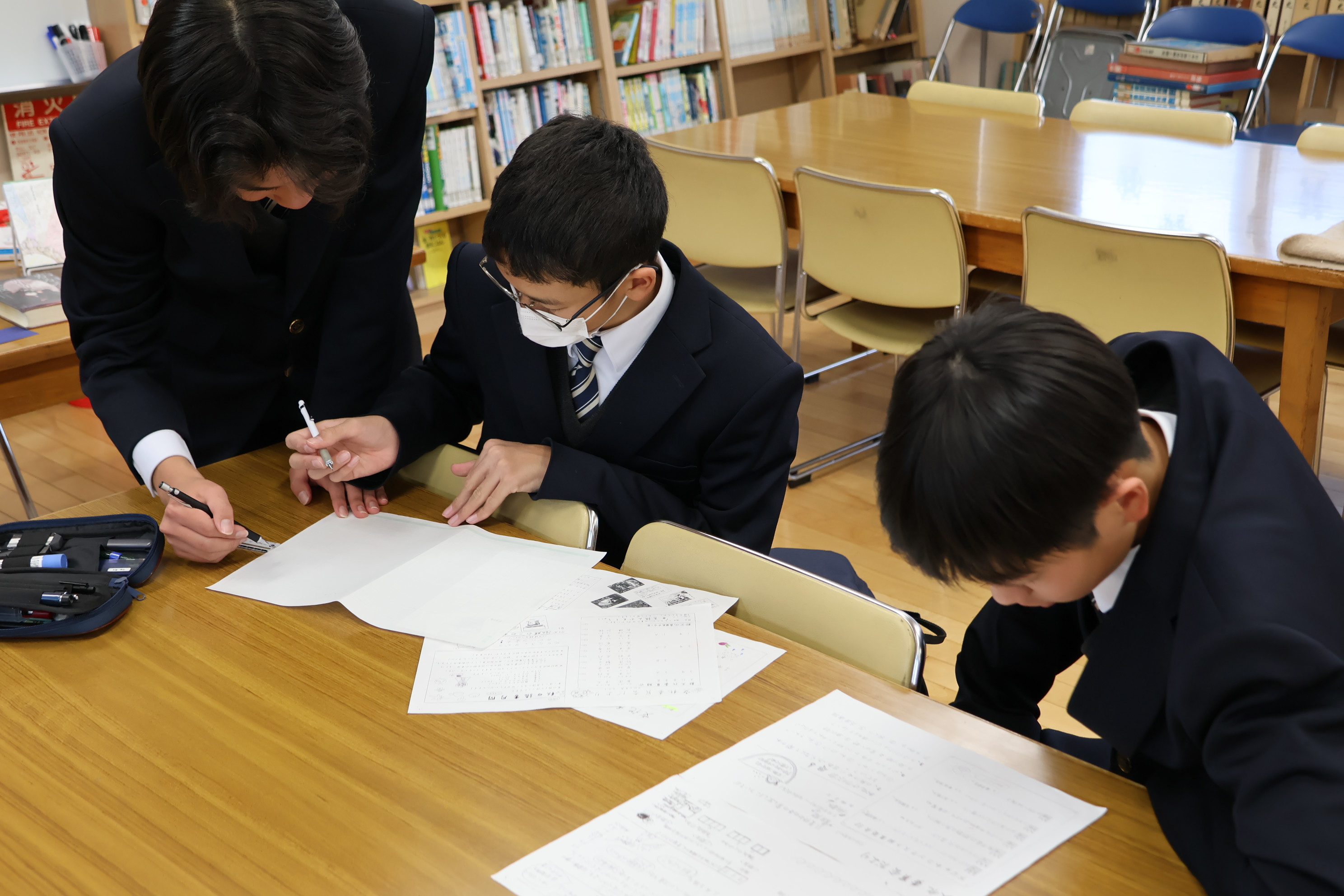



星輝祭体育の部ダンス実行委員会も動き出しています。(2/3:立春)
「二十四節気」とは、太陽が動く道である黄道(おうどう)を24等分して名称を付けたもので、季節を知るために古来より生活に根差してきました。立春は例年2月4日頃です。
二十四節気において、各季節は6つの節気で構成されており、春は「立春」「雨水」「啓蟄」「春分」「晴明」「穀雨」によって成り立っています。立春は春の始まりであるとともに、旧暦において新しい1年が始まる日でもありました。
現在の暦では太陽暦が採用されていますが、6世紀頃から明治時代初期までの日本では太陰太陽暦が用いられていました。月の動きを基準として一部に太陽の動きを取り入れた暦で、一般的に旧暦として知られています。しかし、太陰太陽暦では季節と月日にずれが生じるため、四季の指標となる二十四節気が編み出されました。
立春は春の始まりを告げる日であり、昔の人々にとっては1年の始まりの日でもありました。昔は立春と正月の時期が近いことから「迎春」「早春」「新春」という言葉が生まれ、今でも年賀状などで使われています。
昔の日本では、立春を始まりとして八十八夜や入梅などの雑節(季節の変化をつかむための目安として日本で補助的に作られた暦。八十八夜、彼岸、土用などなど)を決め、生活の目安を立てていました。季節と共に生きる日本人にとって、立春はとても重要な日であったと言えます。また、旧暦では、立春近くに元日が巡ってきますが、必ずしも立春=元日とならないのは、二十四節気は太陽の動き、元日は月の動きで決められていたからです。ちなみに、豆まきで馴染み深い(春の)「節分」は、この立春の前日となります。
立春にまつわる風習を3つ紹介します。1つめは「立春大吉」があります。立春の早朝には、禅寺で「立春大吉」と書かれた厄除けの札が貼りだされます。新年が始まる立春の朝に「立春大吉」の札を貼ることで、1年間の無病息災を願います。「立春大吉」の文字は左右対称で、縦書きにすると表から見ても裏から見ても 立春大吉 と読むことができます。そのため、家に入ってきた鬼が振り返って札を見た時に、「この家にはまだ入っていない」と勘違いして家から出ていくとされ、厄除けになると考えられていました。2つめは、「若水を飲む」ことです。新年の早朝に井戸や湧き水から初めて汲んだ水のことを「若水」といいます。若水は1年の邪気を払うとされ、神棚に供えたあとに雑煮を作ったりお茶を淹れたりしていました。若水を使って淹れたお茶は縁起物として「福茶」と呼ばれます。平安時代では立春に天皇へ捧げた水のことを若水といいましたが、のちに元旦の行事として庶民の間に広まります。若水を汲みにいくことを「若水取り」や「若水迎え」といい、地域により汲む際の作法が決まっていました。現代は井戸へ水を汲みにいくことが難しいため、蛇口から出てくる水を若水としても構いません。立春の朝には、清い気持ちで若水をいただきましょう。最後は「豆腐を食べる」ことです。古来より「白い豆腐は邪気を払う」とされ、身を清める食べものとして扱われてきました。節分に豆腐を食べると穢れや罪を払い、立春に食べると清めた身体に福を呼び込むことができるといわれています。節分・立春に食べる豆腐のことを「立春大吉豆腐」といいます。立春大吉豆腐を食べる際は、縁起がいいとされる白い豆腐のままいただきましょう。立春が近づくと、豆腐屋などでは神社で祈祷した大豆を用いて作った立春大吉豆腐が販売されることもあります。ぜひ、縁起のいい立春大吉豆腐を求めて、立春の日に食べてみてください。
◎私たちのはじまりの風景18(2/2)
備前市消防団日生方面隊放水訓練は、源平放水合戦と呼ばれています。消防団員たちが紅白の旗を掲げて、源平に分かれた相手の舟を狙って放水合戦が行われます。この源平放水合戦は、毎年2月第一日曜に備前市消防団日生方面隊による公開放水演習です。由来は消防団員の士気を高めようと出初式の日に毎年行っているそうです。スタートは1950年。74年以上前から行われ、新しい年のはじまりを告げるお祭りとしての歴史があります。5つの分団の若者たちが源氏側と平家側に分かれ、船の上から放水合戦を行います。放水演習(源平放水合戦)は水圧が激しいこと、水は刺すように冷たく、精神力と体力がないと参加はできませんね。
この日、正午、祭りのはじまりは、サイレンを鳴らす消防車を先導に東西の岸壁に分かれ、団員は100人近く集まり、それぞれ6隻ずつの小舟に乗り込み、30メートル先の相手方を目がけ一斉に放水しました。激しい水圧に耐える合戦は、約10分。最後は双方の健闘を称えあい、赤や青や黄とオレンジと緑に着色した水を空高く噴射しました。

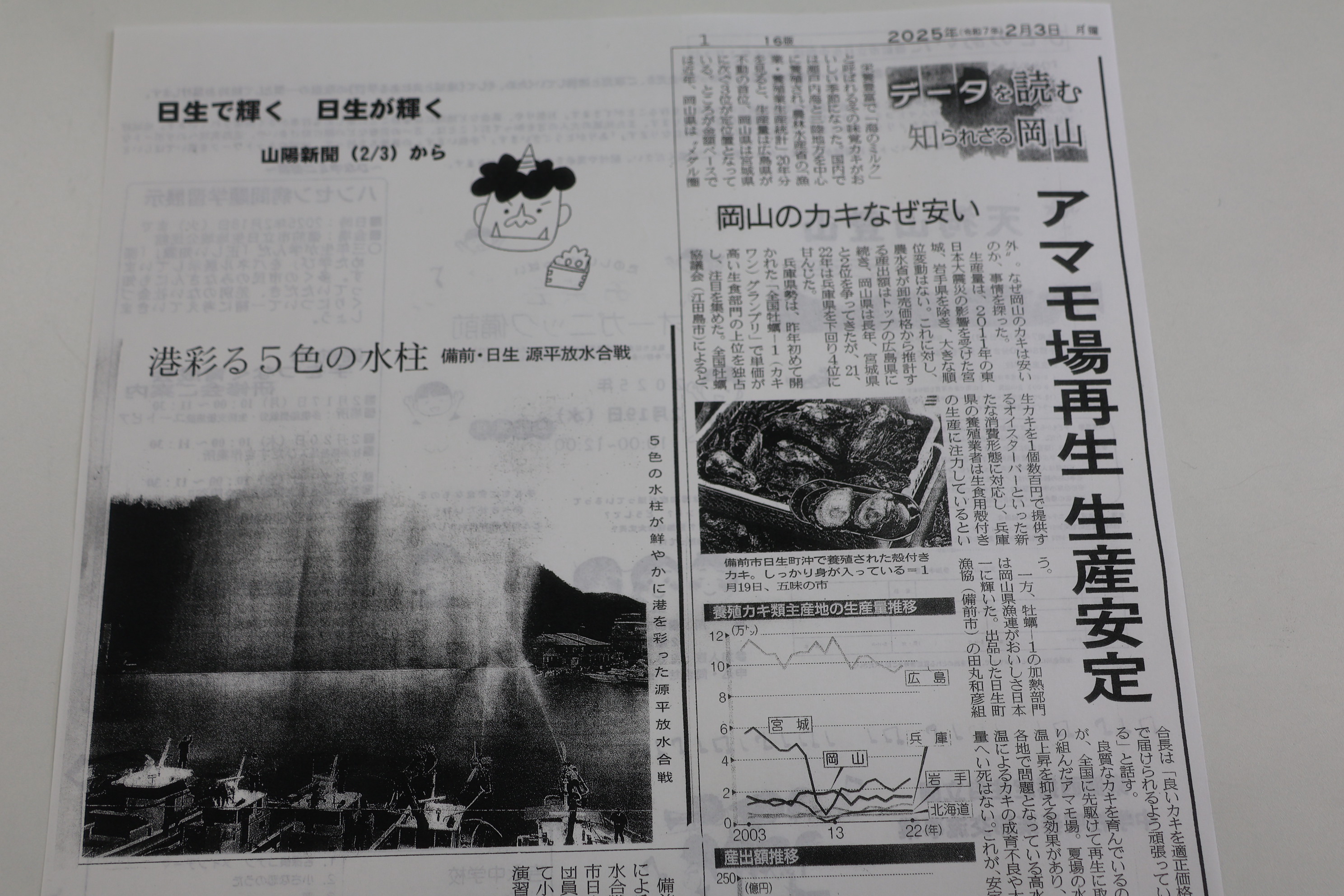

◎十五の春へ(1/31:私立Ⅰ期入試結果発表の日)



The best thing to hold onto in life is each other. Audrey Hepburn
(人生において、しっかり捕まえておきたい最高のものは「お互いの存在」)
◎大切な私たちの食
いただきますとごちそうさまのあいだに(1/31:調理実習で学び 2年生家庭科)
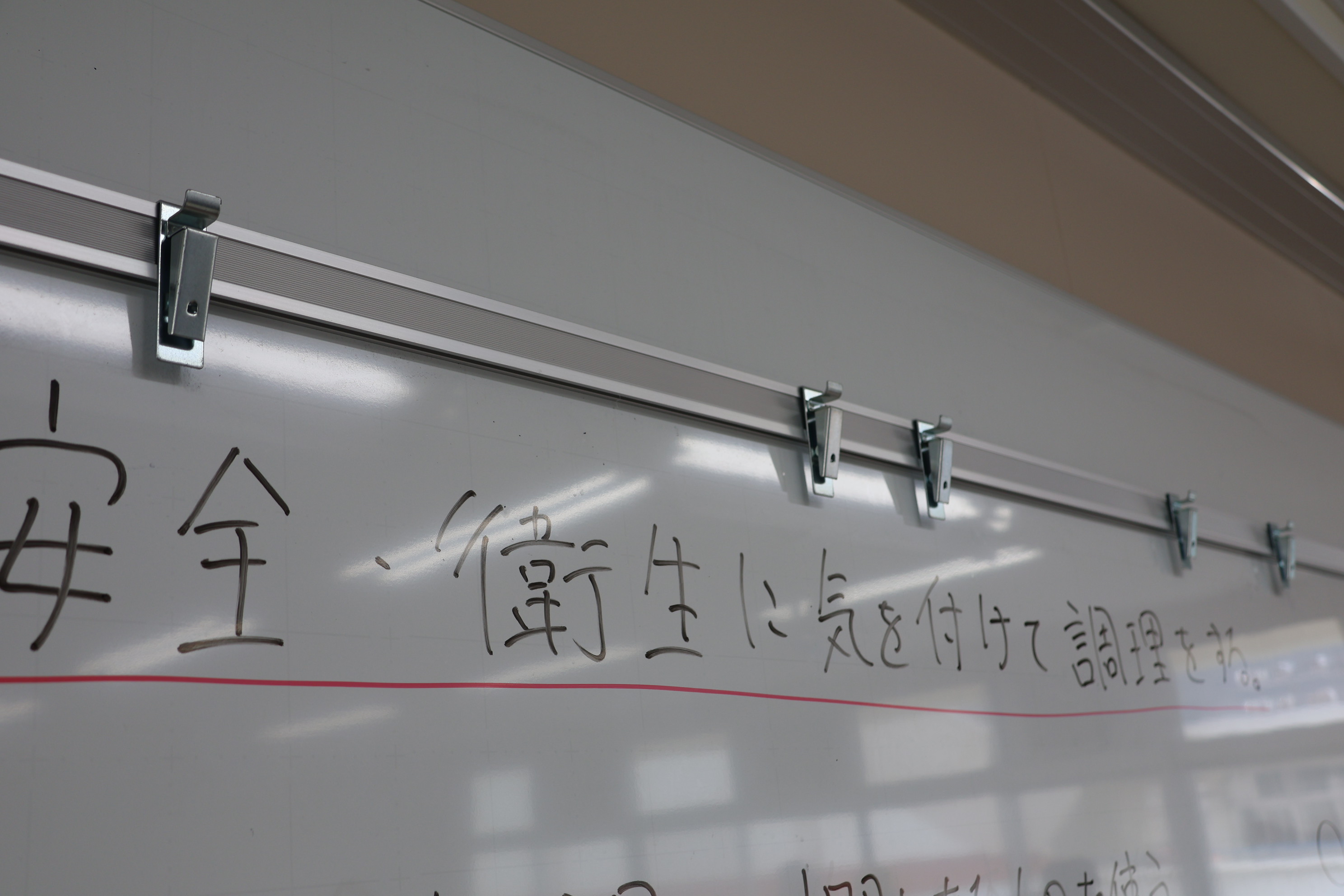











竹田さん、宗兼さんサポートをありがとうございました。次週(2/4(火)には、もう一つのグループが実習します。
◎感謝をこめて(1/31:学校給食週間を受けて)
1月24~30日は「全国学校給食週間」です。
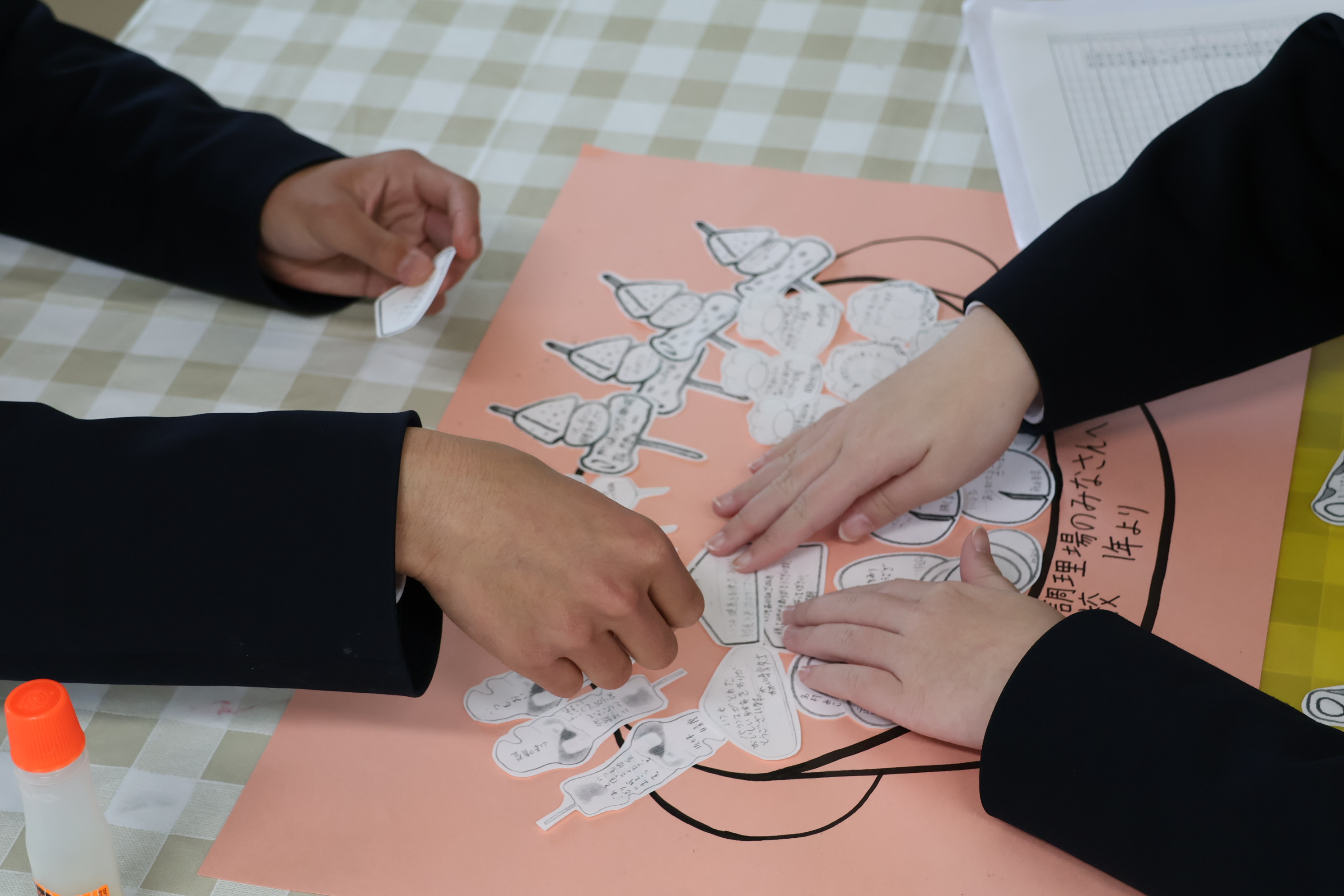


この期間は、「学校給食の意義、役割等について児童生徒や教職員、保護者、地域住民等の理解と関心を高め、学校給食のより一層の充実発展を図ること」を目的としています。いくつかのミニ情報をお伝えします。
【学校給食はいつから始まったの?】
今では当たり前となっている給食ですが、その始まりは明治22年。山形県鶴岡町の小学校でした。当時は貧困児童を対象に無料で提供され、その献立は「おにぎり・焼き鮭・漬物」のようなシンプルなものだったようです。その後、全国に広まり実施されるようになりましたが、戦争による食料不足により一時中断せざるを得なくなりました。やがて戦争が終わり、昭和21年12月24日に東京・神奈川・千葉の3都県の学校で試験給食が実施されました。それ以来、12月24日を学校給食感謝の日と定めていましたが、冬休みと重なるため、1月24日から30日までの1週間が「全国学校給食週間」となりました。また、農林水産省は毎年1月を「食を考える月間」として各種取組を進めることとしています。
【どうして給食の飲み物は“牛乳”なの?】
瓶や紙パックなど、形状は違えど給食で出される飲み物と言えば・・・
そう!“牛乳”です!小さいころ、牛乳が苦手だったひとは「献立との組み合わせを考えると、お茶の方がよいのに・・・。なんでいつも牛乳なの?」と思っていたのではないでしょうか。しかし、それにはちゃんと理由があります。成長期の子どもたちにとって、通常の食事だけでは必要なカルシウムやたんぱく質を十分に摂ることは難しいとされています。そのため、栄養豊富な牛乳を給食で提供し、補っています。独立行政法人日本スポーツ振興センターの調査によると、学校給食のない日は子どもたちのカルシウム摂取量が基準値よりも3.5割ほど不足しているという結果が出ました。手軽に栄養が取れて、おいしい牛乳。ご家庭でも、ヨーグルトやチーズなどの乳製品でカルシウムを意識的に摂るのがおすすめです。
◎ICTを活用(1/30)
今日は、岡山県教頭会 令和7年度発表提言者会をオンラインでおこないました。

ちなみに文科省では教員のICT活用指導力の重要性について、以下の内容があります。
『社会のあらゆる分野で情報化が進展し,携帯電話やブロードバンド等の普及率が示すとおり情報化の主役は個人となっている。情報社会の進展の中で,一人一人の子どもたちに情報活用能力を身に付けさせることは,ますます重要になっている。
また,教員あるいは子どもたちがICTを活用して学ぶ場面を効果的に授業に取り入れることにより,子どもたちの学習に対する意欲や興味・関心を高め,「わかる授業」を実現することが求められている。
こうした社会的な要請を踏まえ,教員のICT活用指導力の向上は,政府の「e-JApAn戦略」(平成13年1月IT戦略本部決定)のもと重要な政策課題として位置付けられ,「概ね全ての教員がコンピュータ等を使って指導できるようにする」ための様々な取組みが実施されてきた。
「IT新改革戦略」(平成18年1月IT戦略本部決定)では,学校におけるIT環境の一層の整備を進めるとともに,「ITを活用した学力向上等のための効果的な授業や,学ぶ意欲を持った子どもたちがITを活用して効果的に学習できる環境の実現」等のため「全ての教員のICT活用能力を向上させる」ことが目標とされ,そうした能力の基準の具体化・明確化を行うことが求められた。
当該基準については,次項で述べる「教員のICT活用指導力の基準(チェックリスト)」として文部科学省により策定・公表されたが,その範囲は,授業におけるICT活用の指導だけでなく情報モラルの指導ができることや,校務にICTを活用できることも含まれている。このことは,「教員のICT活用指導力」が,これからの教育の情報化の時代において,全ての教員に求められる基本的な資質能力であることを意味するものである。』
◎力を合わせて調理実習!(1/31、2/4:二年家庭科)

美味しい○○○をつくります(*^o^*) 調理実習には地域の竹田さん、宗兼さん、荒木さんがサポートに来てくださいます。ありがとうございます。
◎自主・向上・錬磨の日々を(1/30)
毎週、生徒の生活に関する会を開催し、情報の共有と支援・指導について話し合っています。この日は、部活動での集団づくり、受験の指導、新年度に向けてのケース会の実施、インフルエンザへの予防対策など協議内容は多岐にわたりました。

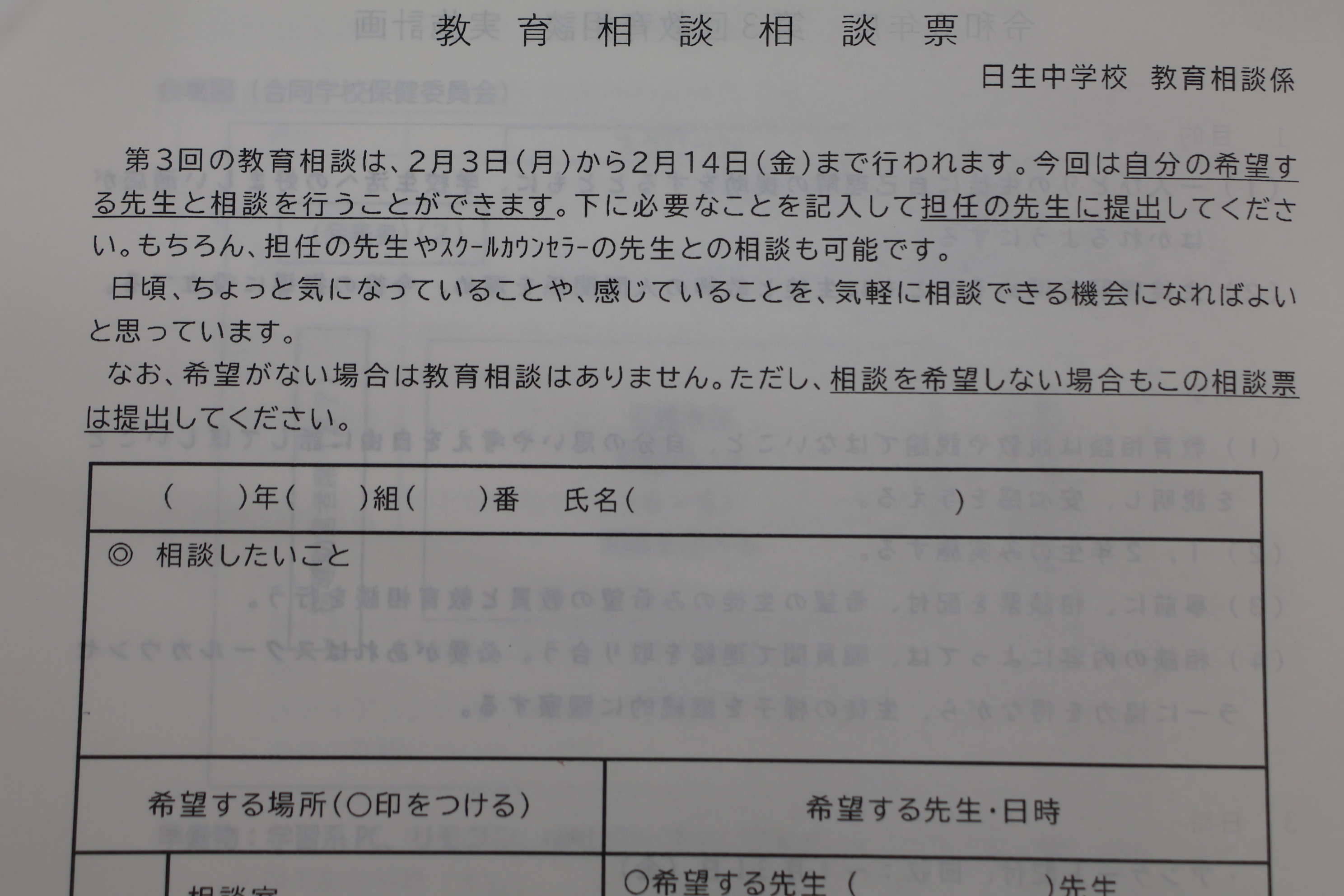
追記:来週から、今年度最終の教育相談週間(2/3~2/14)に入ります。これまでの生活を振り返り、新年度に向けてのステップアップとなるよう、相談週間を活用しましょう。また、保護者の方も何か気になるようなことがあれば、お気軽に学校へご相談ください。学校72-1365(教頭)
◎歩こう 歩こう 私は元気♬
参観日・学年懇談(1.2年生)(1/29)


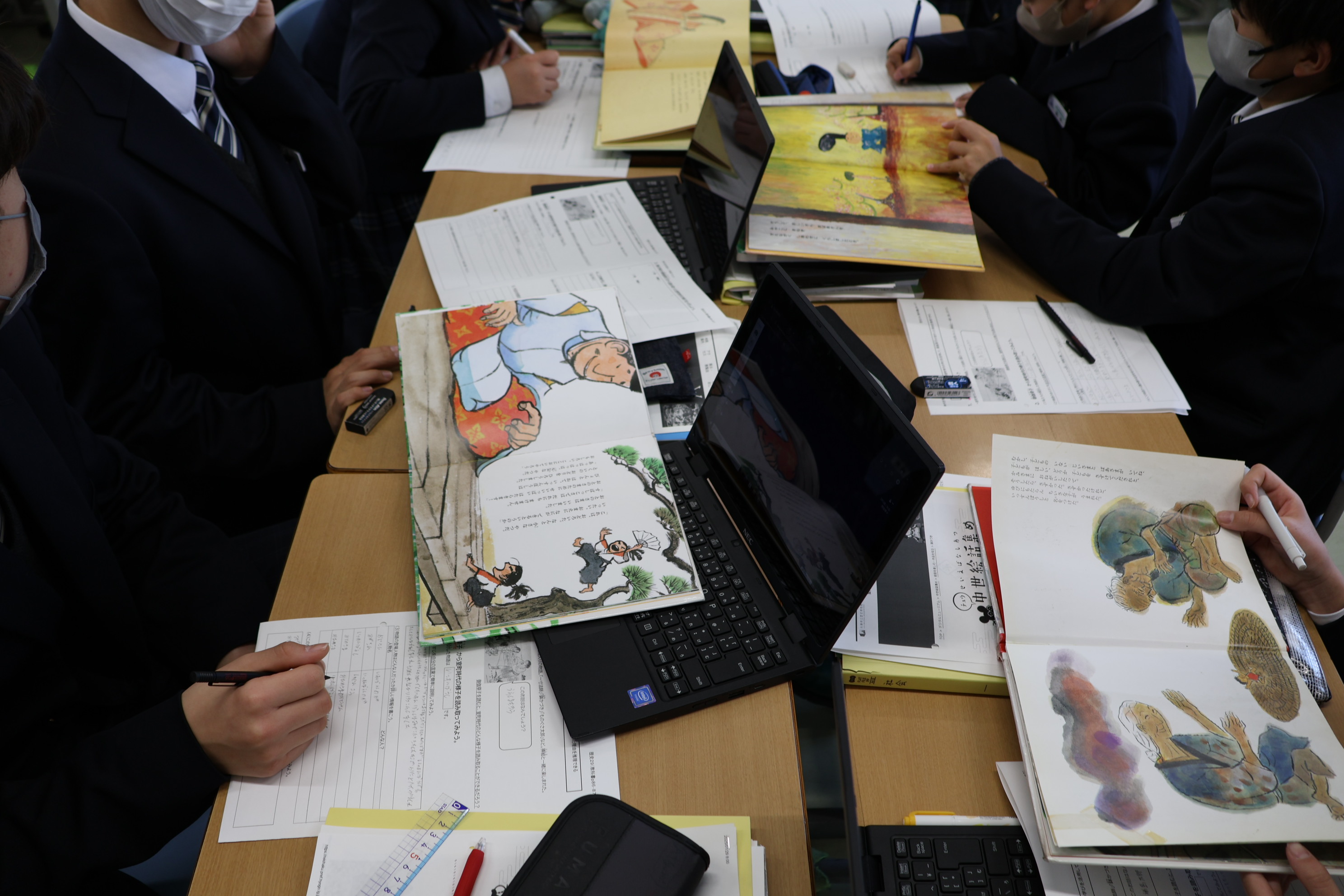
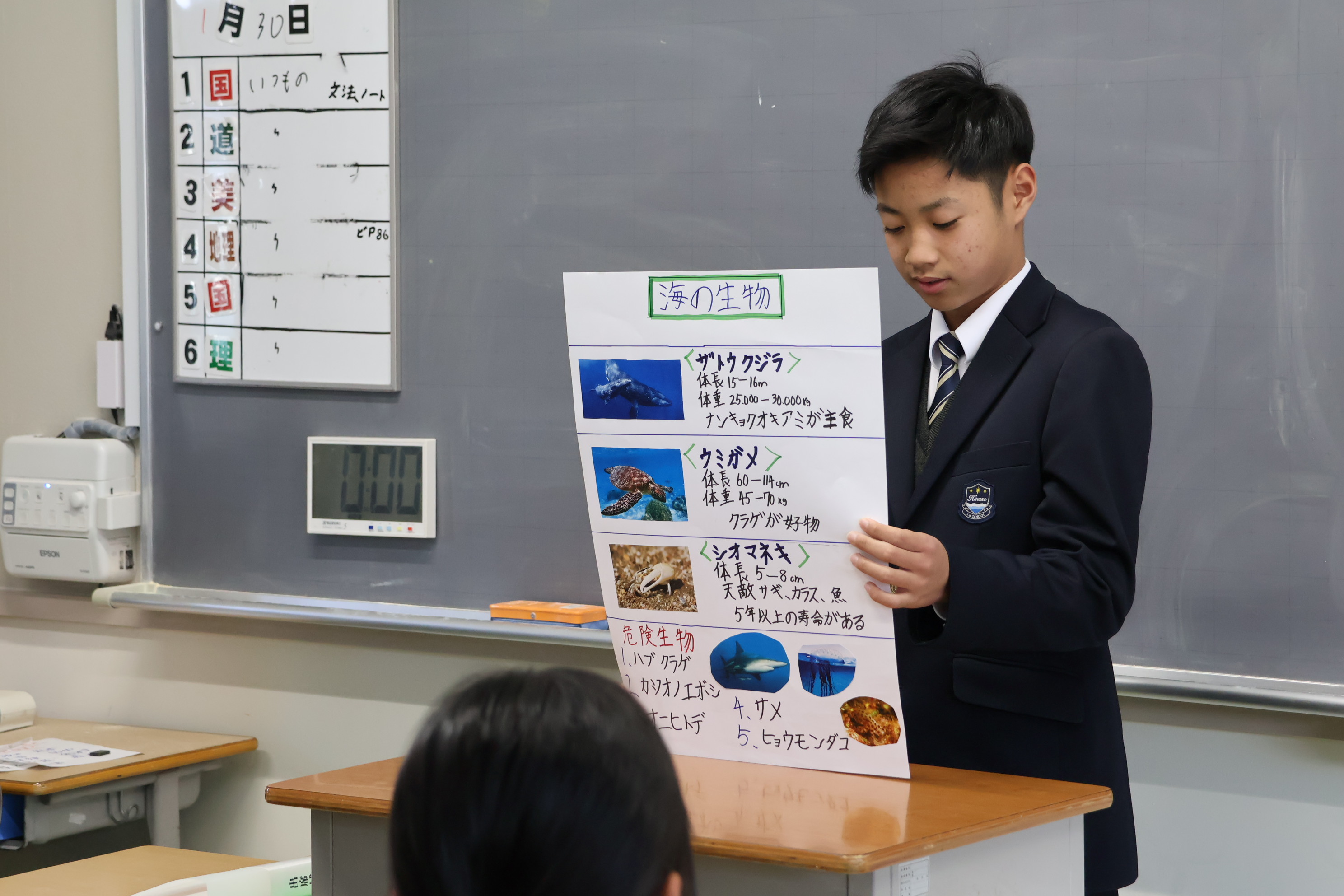

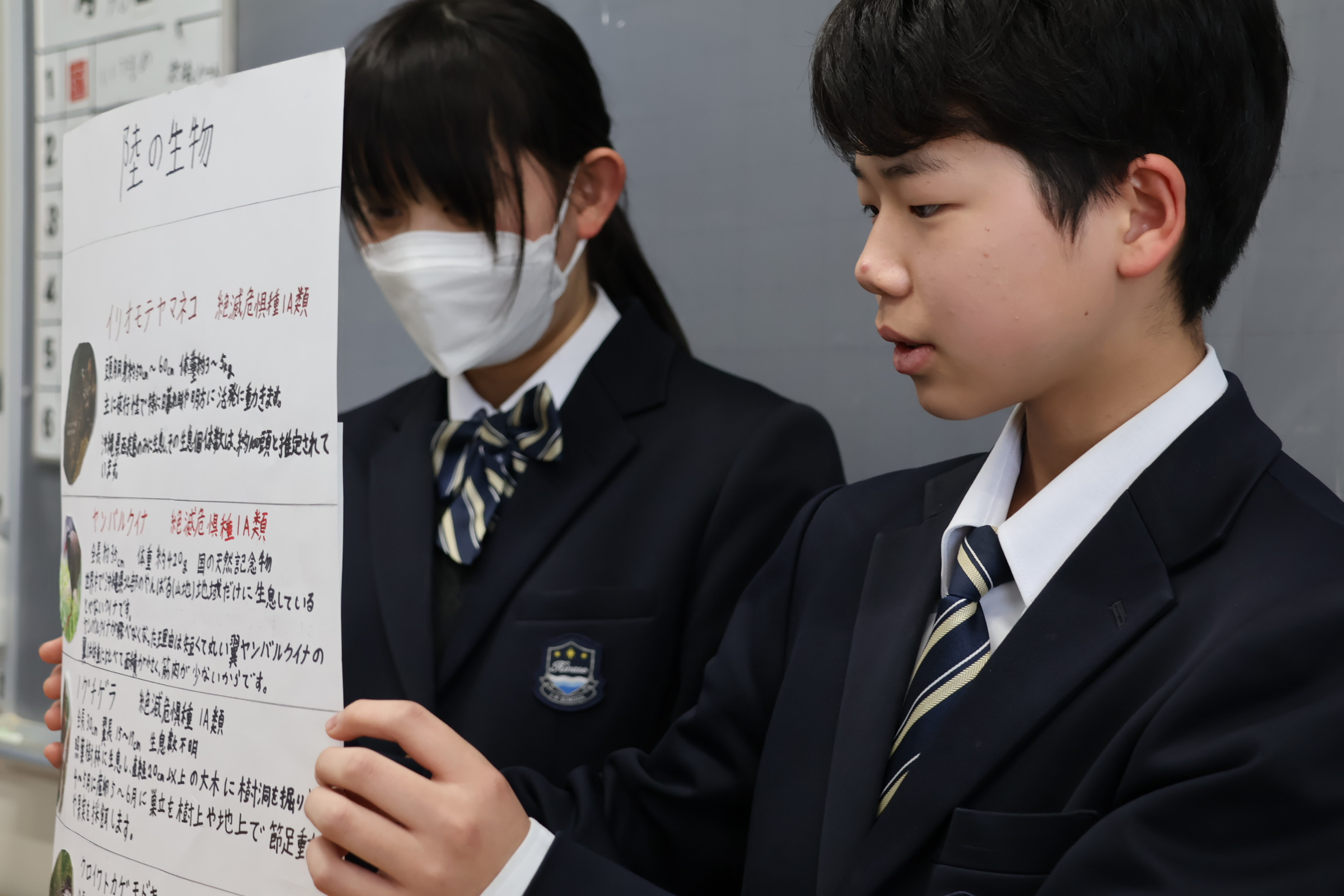



授業参観及び学級懇談会への参加をありがとうございました。
追記:今年度のPTAの会議は、幹事会:2/17(月)、委員総会:3/4(火)です。新年度(令和7年度)第1回幹事会及び委員総会は4/17(木)を予定しています。
◎ひな中の風✨
「こんどは今度 いまは今」(1.29)




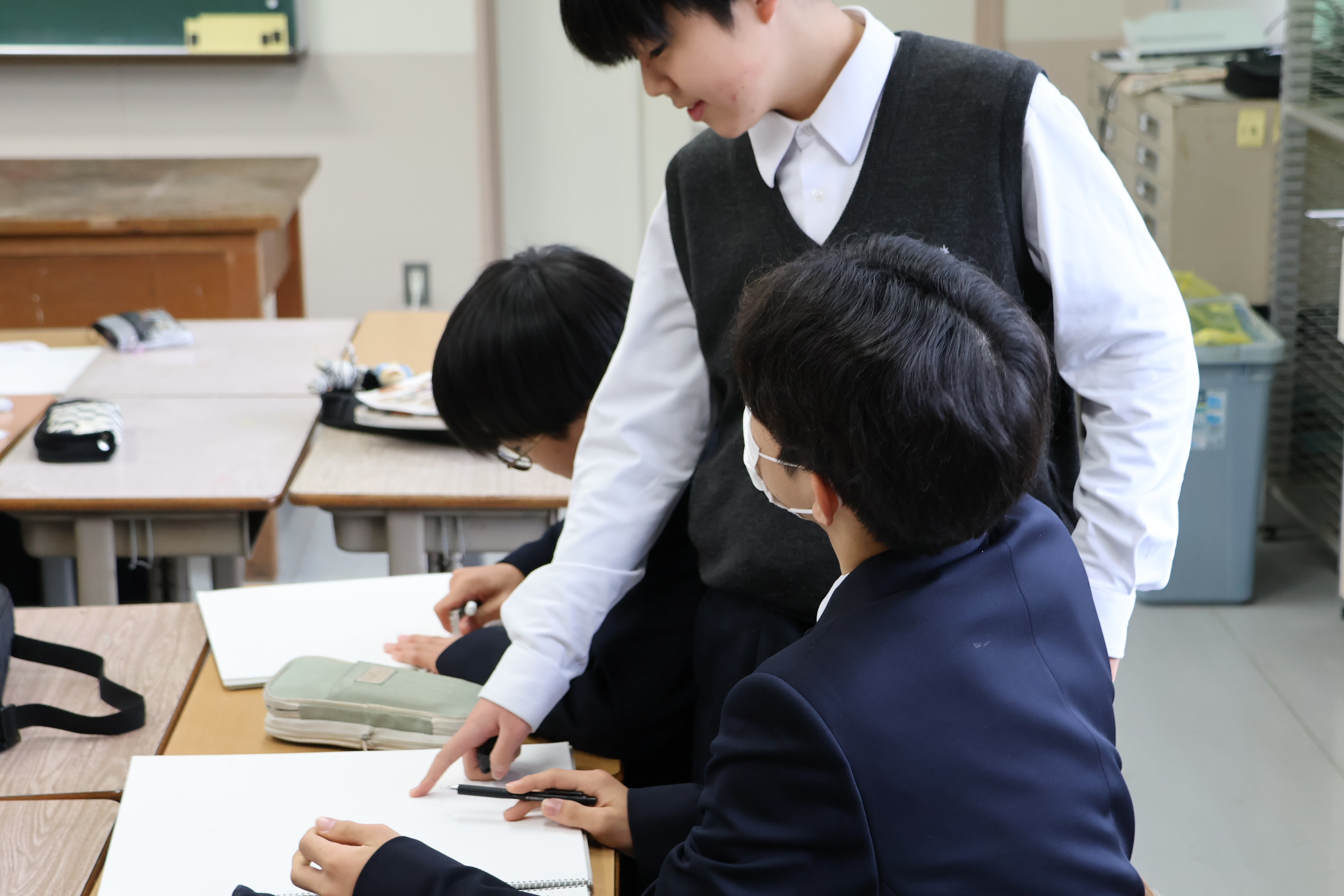

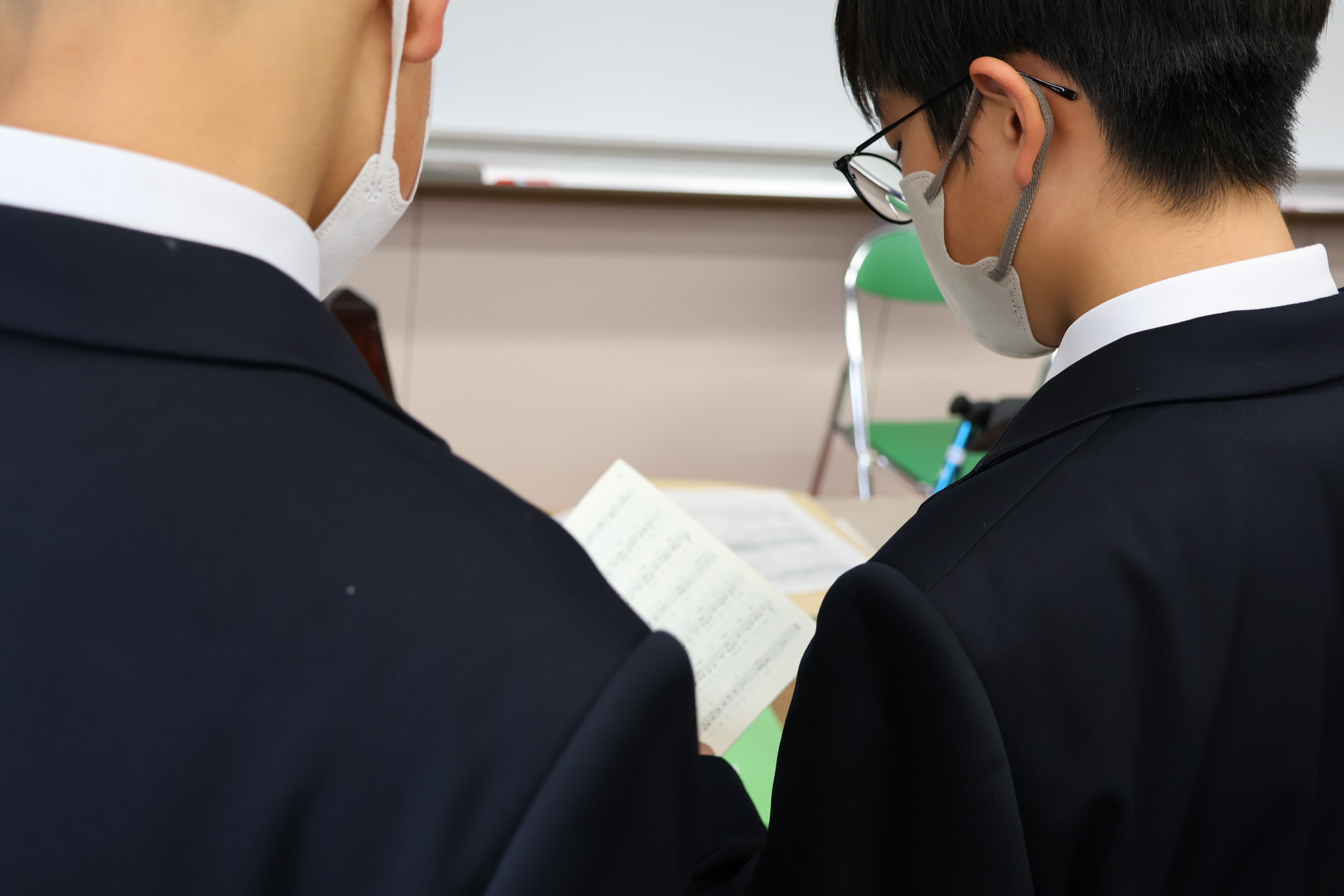
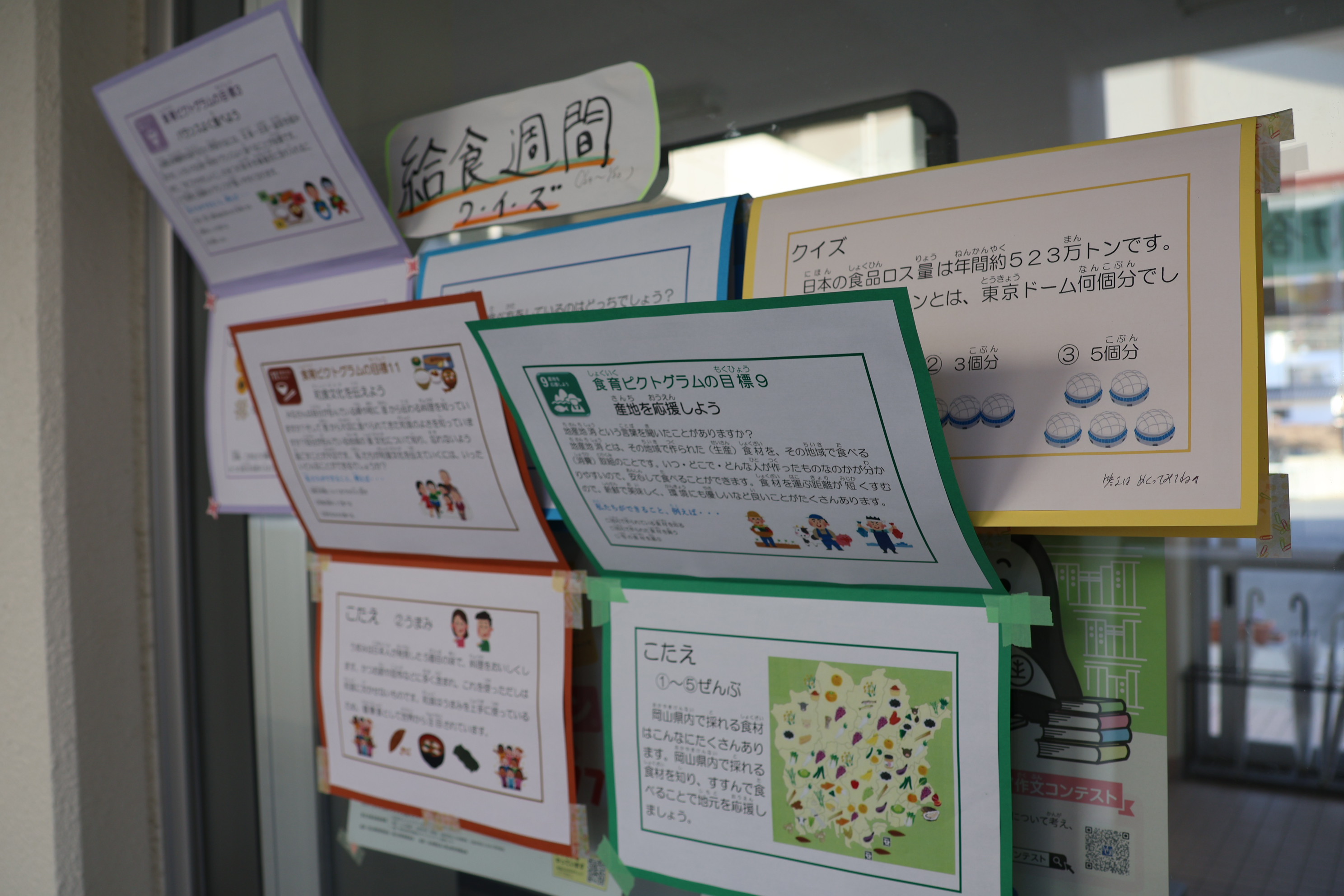

〈空は月を月は想いを生み出して私にも春、あなたにも春 カン・ハンナ〉
◎早春のひなせから
備前市消防団日生方面隊出初め式及び式典(2.2)



日生支所の方と会場設営の打ち合わせをしました。祈☀
〈自らを鼓舞せねば虚(うつ)けの姿なるぞ身の養ひに啜る一椀 青木昭子〉(1/28)
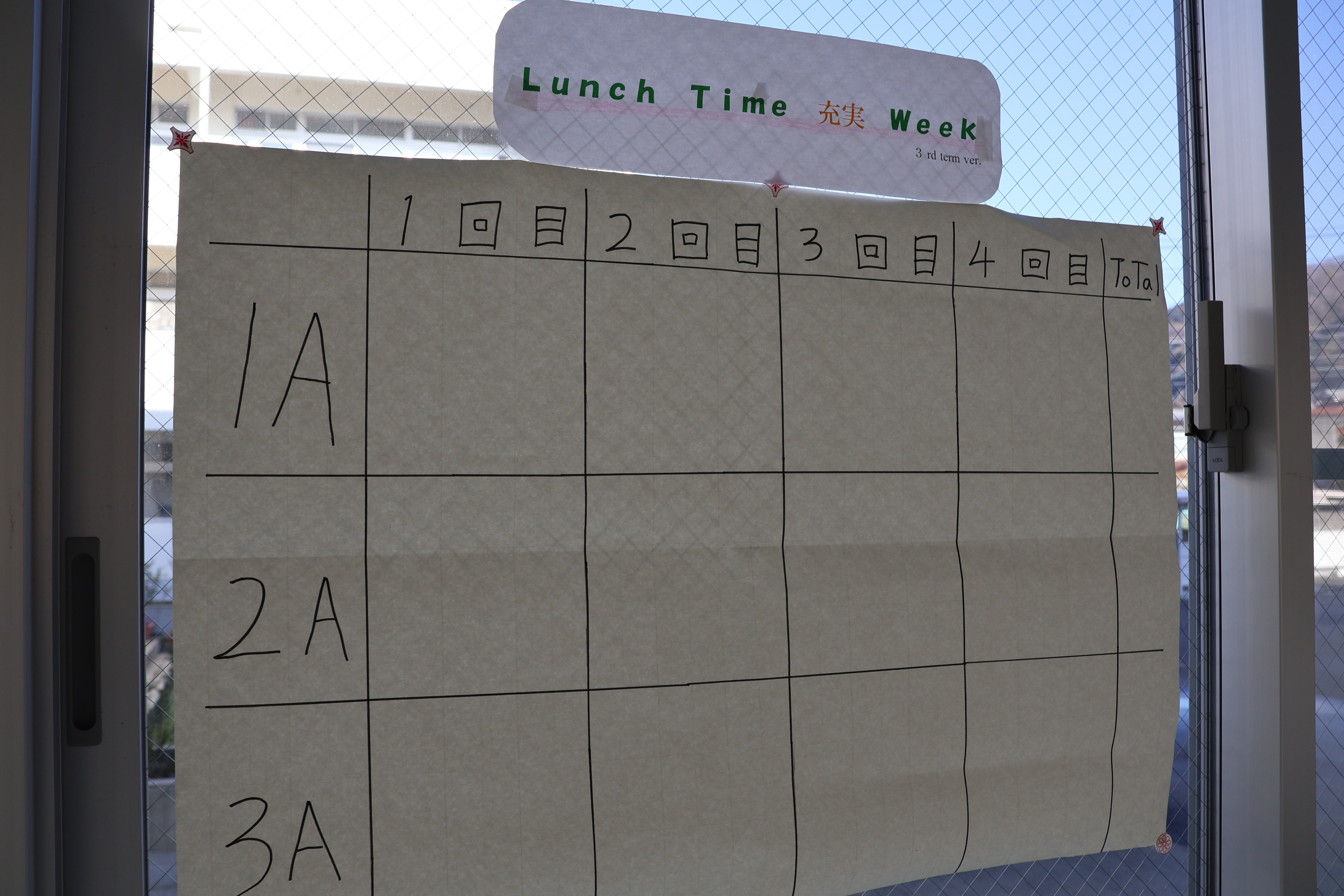
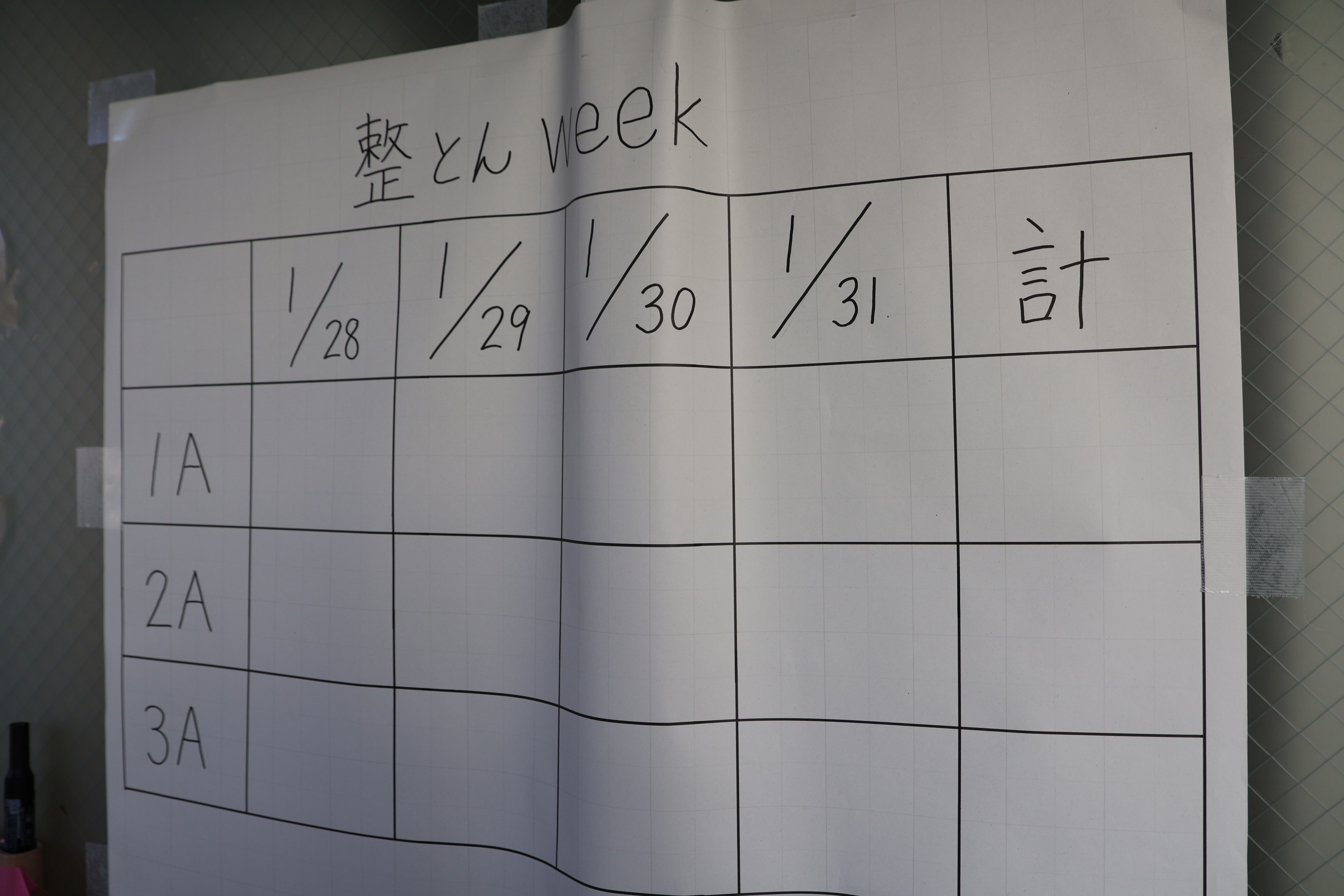
◎3.9日生大橋マラソン
日生で輝く 日生が輝く(〆切~2/5)
26日、備前市文化スポーツ振興課から山本さんらが来校され、マラソン大会での中学生ボランティア募集の呼びかけをされました。
3月の日生の風を感じながら、マラソン選手を応援するスタッフとして参加しましょう。

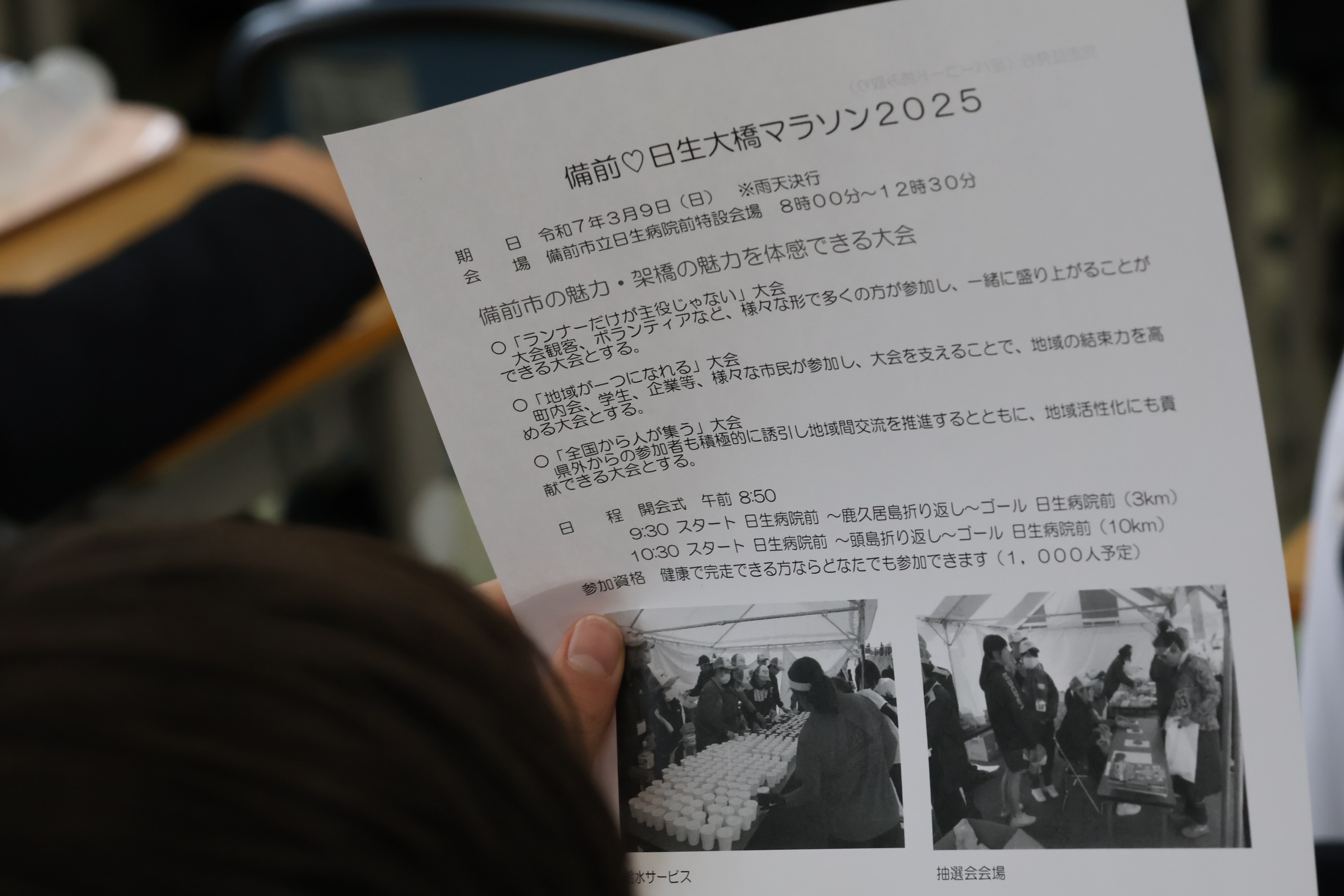

◎校長室から(1/26)

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Warren Buffett
(今日、誰かが木陰に座っているのは、ずっと前に誰かが木を植えたからだ。)
◎冬のあとに春がやってくるよ(1/24)
岡山県内の私立21高校が共通日程で行う2025年度選抜1期入試が昨日スタートした。今日も行われ、2日間で延べ約2万7千人が臨んでいる。
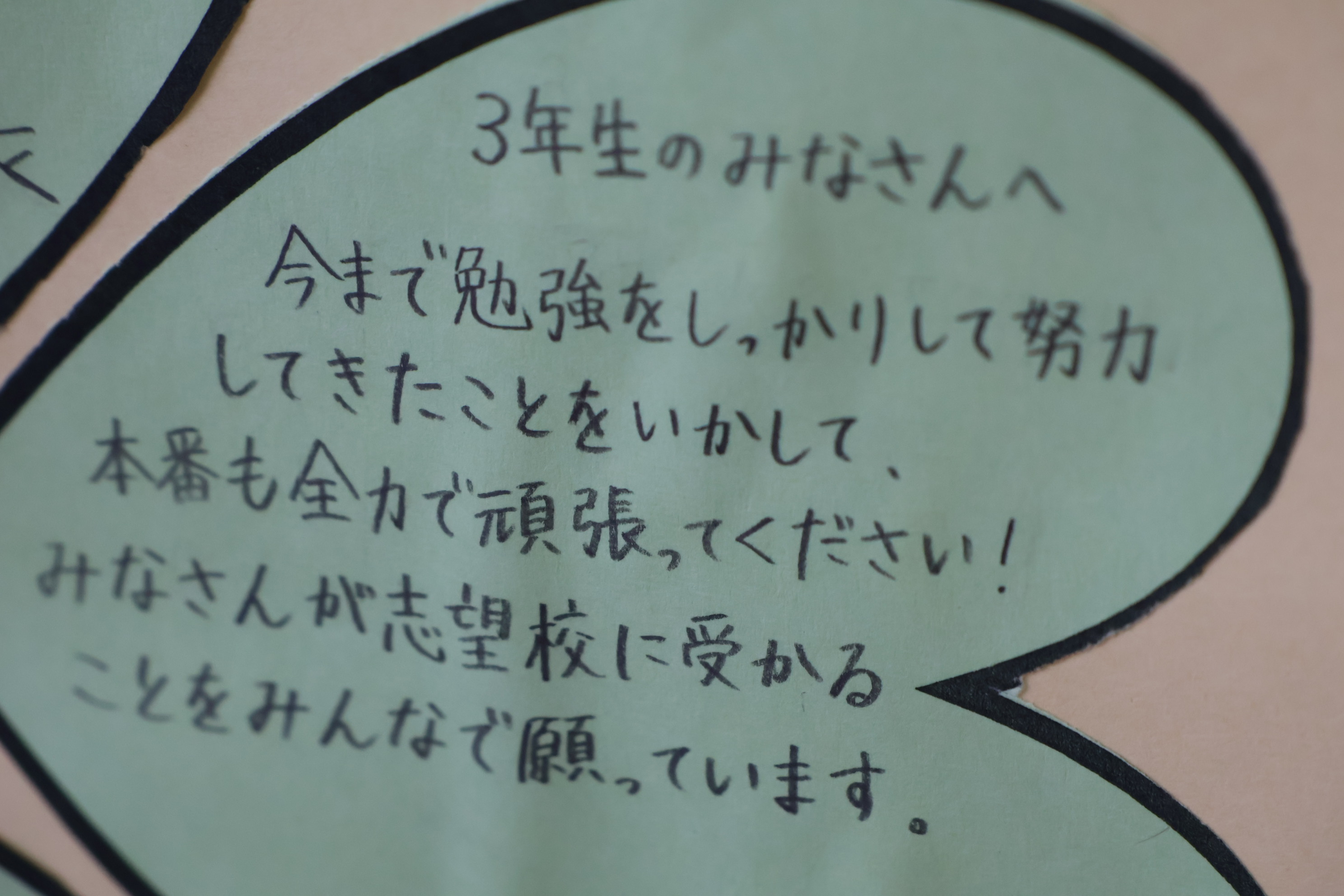
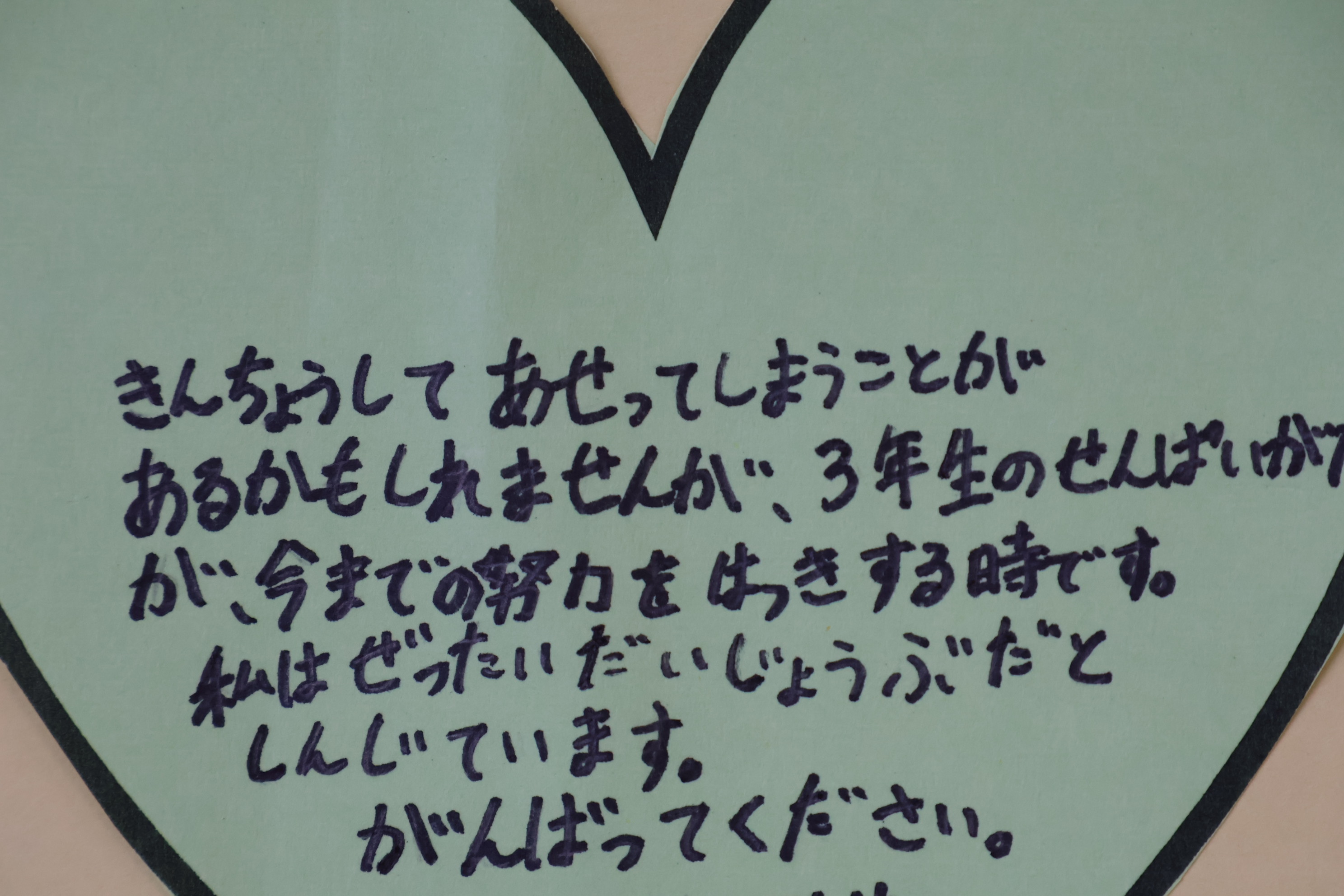
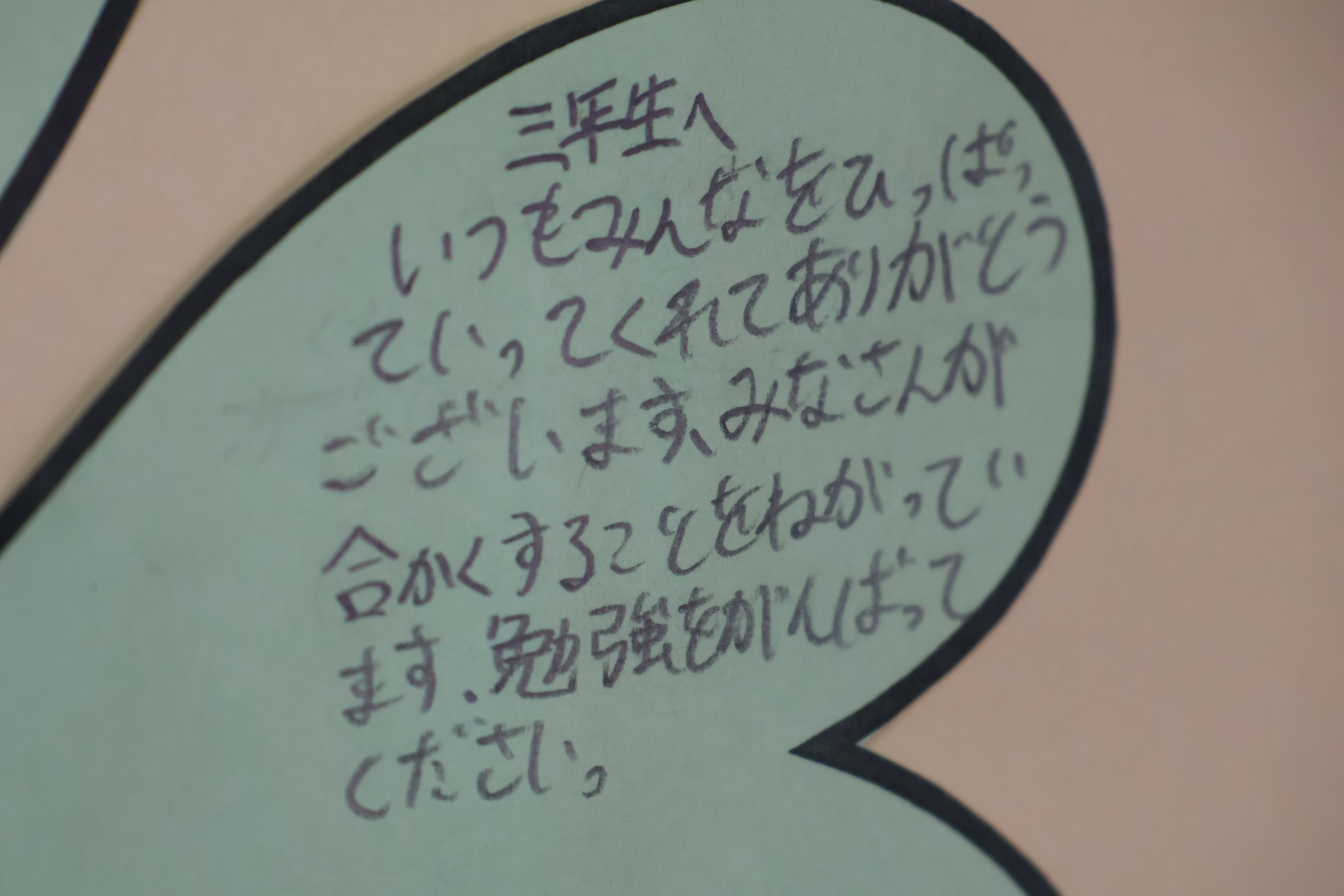
◎多くの人に支えられて
電子黒板搬入(1/23)



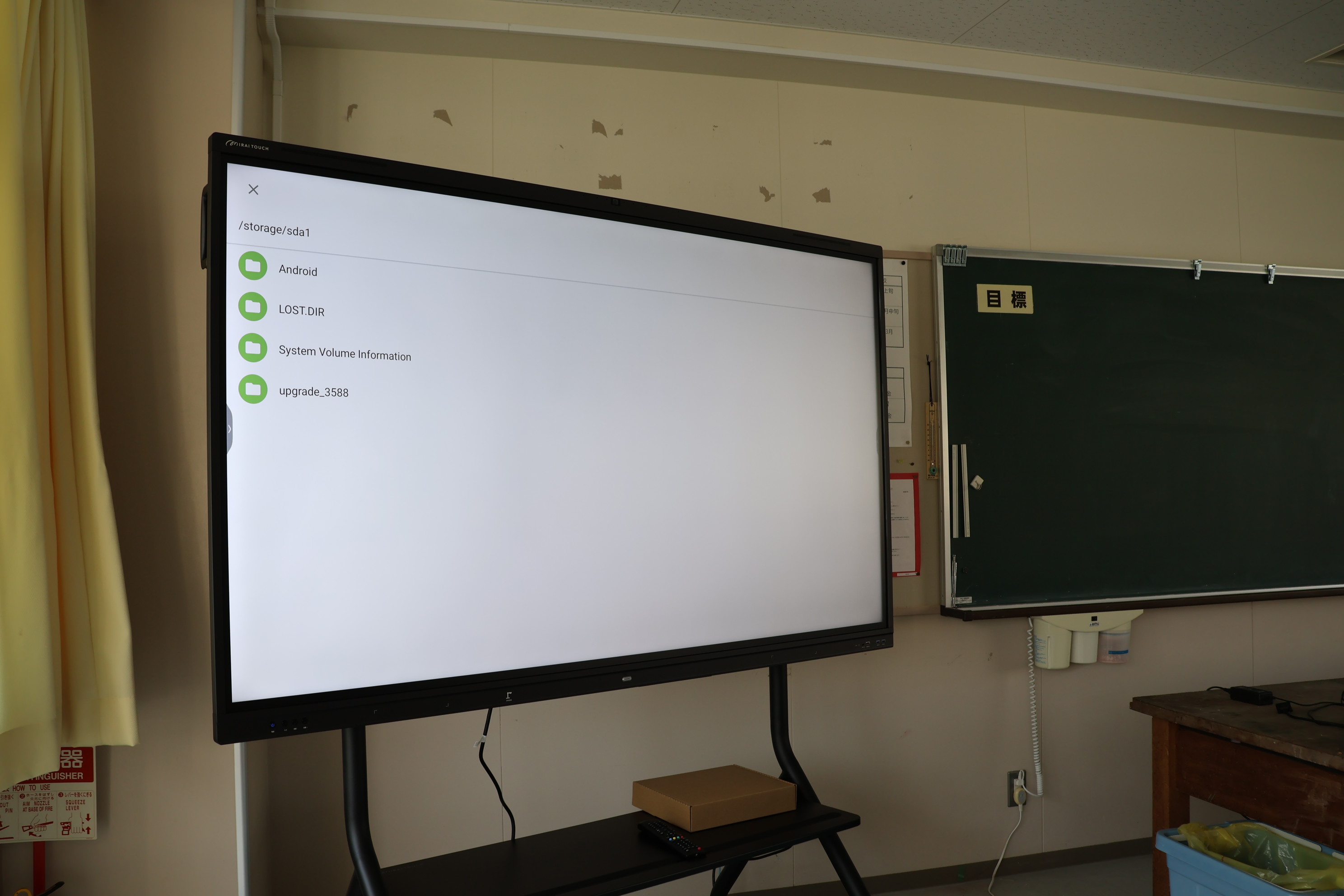


ありがとうございます。
◎自分らしくせいいっぱい(1/23)


県私学協会は、県内21の私立高校選抜1期入試の出願状況を発表した。定員5455人(前年度比30人減)に対して、2万7038人(同104人減)が出願した。倍率は4・96倍(同0・01ポイント増)だった。少子化が進む中、5倍近くの高水準を維持しており、同協会は「各校が進路の希望に応じた特色あるコースを設置し、オープンスクールなど積極的にPRに努めてきた結果だ」と分析している。
例年同様、難関大学への進学を目指すコースが高倍率だった。就実の普通・特別進学コース・ハイグレードクラスが54・95倍と最も高く、岡山龍谷の普通・特別進学コース(44・05倍)、就実の普通・特別進学コース・アドバンスクラス(20・04倍)と続いた。倍率が10倍を超えたのは5校10コース(クラス)だった。一方、関西の普通・サイエンスフロンティアコースや岡山の普通など7校7学科・コースで定員割れとなった。前年度よりも出願者数が100人以上増えたのは作陽学園(280人増)、倉敷(230人増)など6校。100人以上減少したのは、倉敷翠松(644人減)、美作(138人減)など3校だった。
入試は23日(一部は24日も実施)で、31日(岡山白陵は25日)に合格者が発表される。川崎医科大付と吉備高原学園は入試、合格発表とも別日程で実施している。
◎備前サンラッキーズ練習中(1/22)


◎一人ではない(1/22)

◎がんばってこような みんな!(1/22:明日挑む)


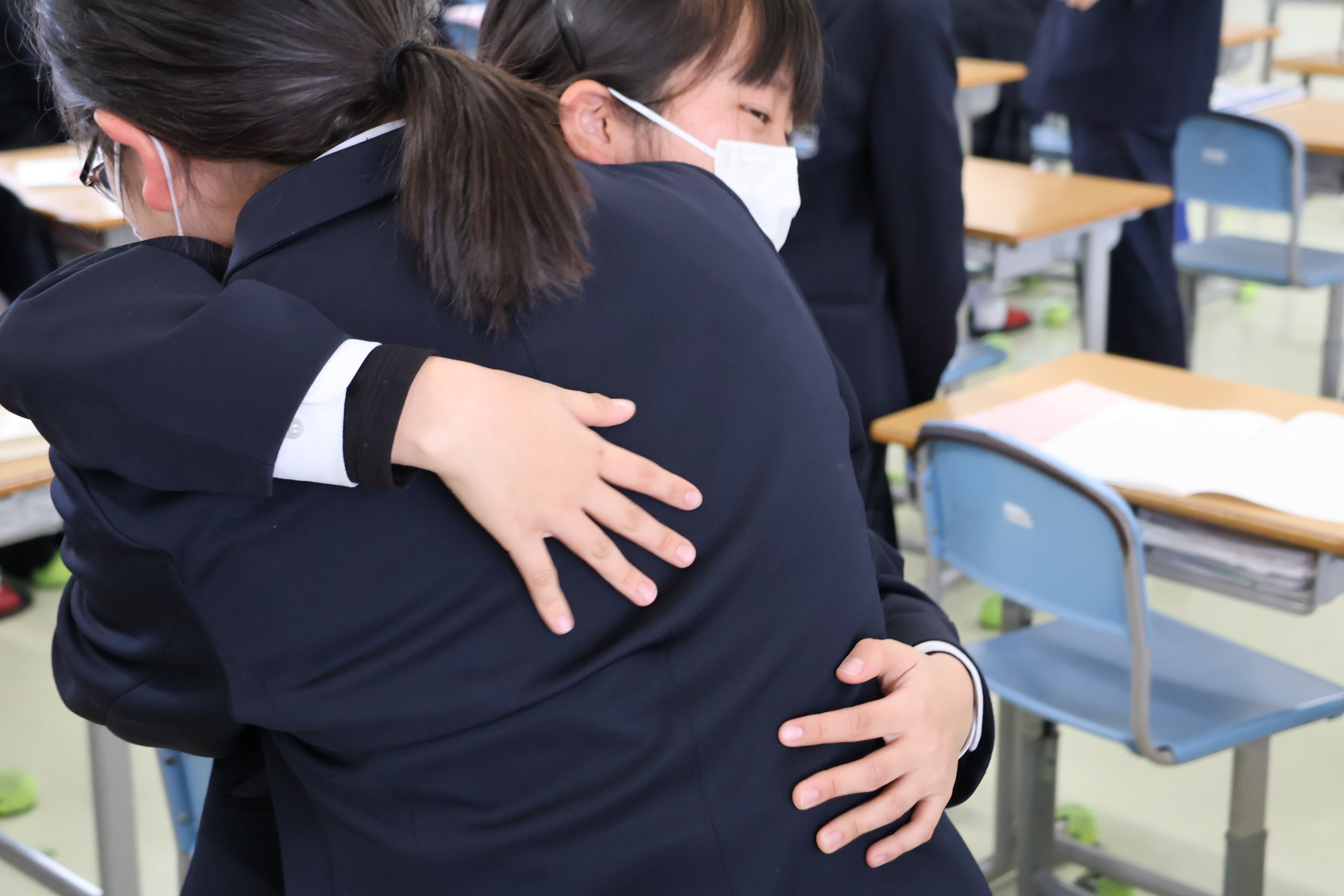



◎受験を前に
~日に生(な)せば(1/22)
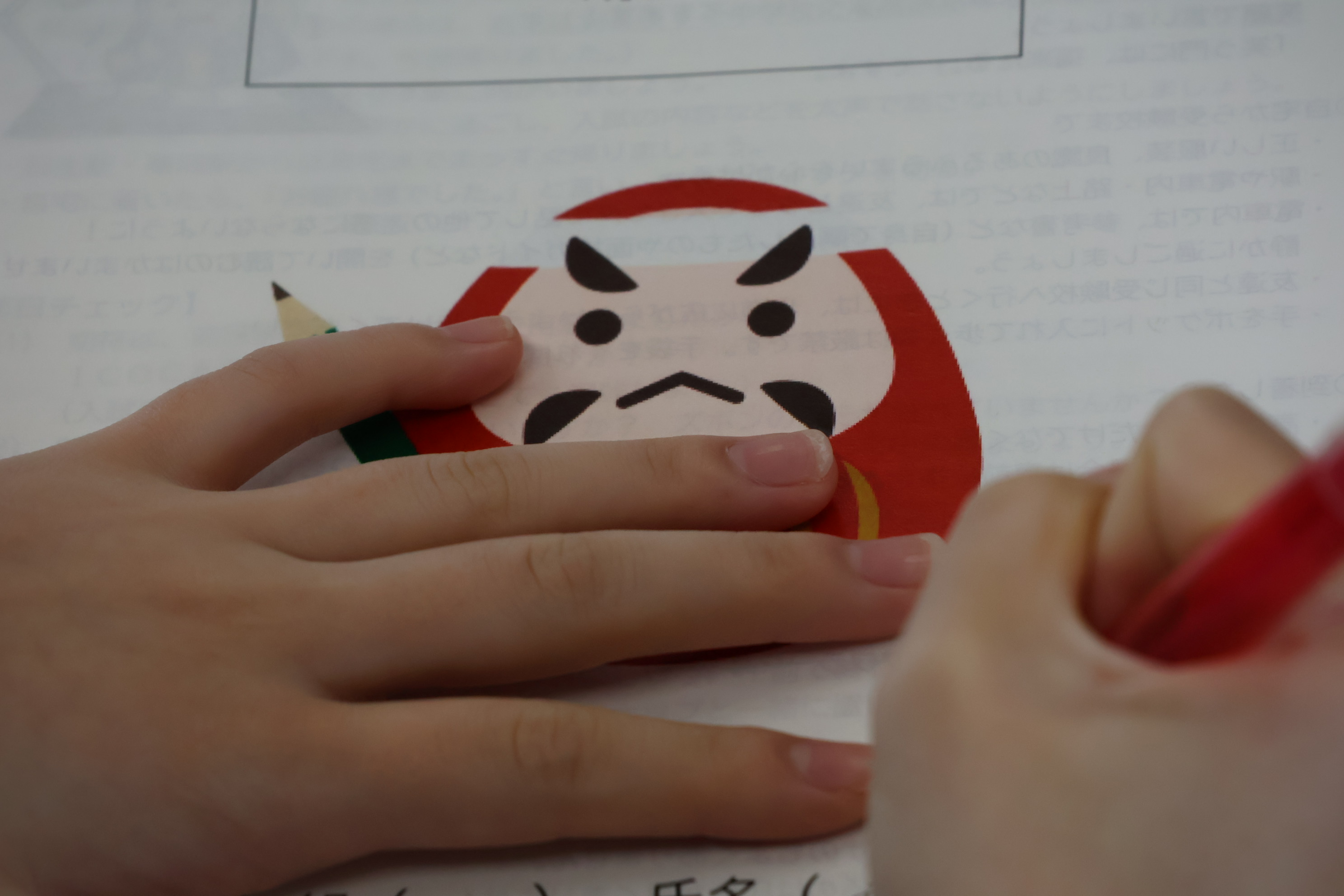


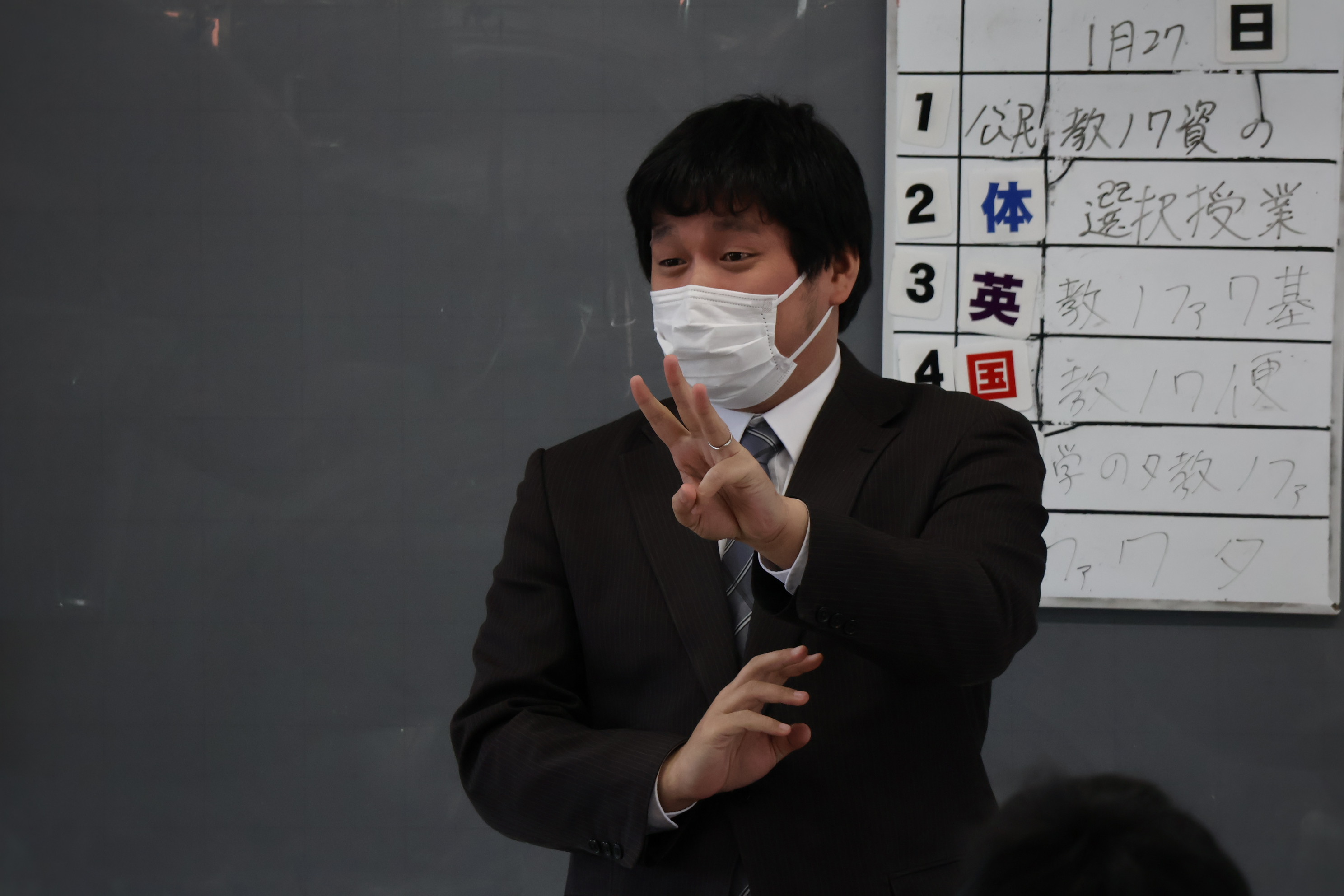
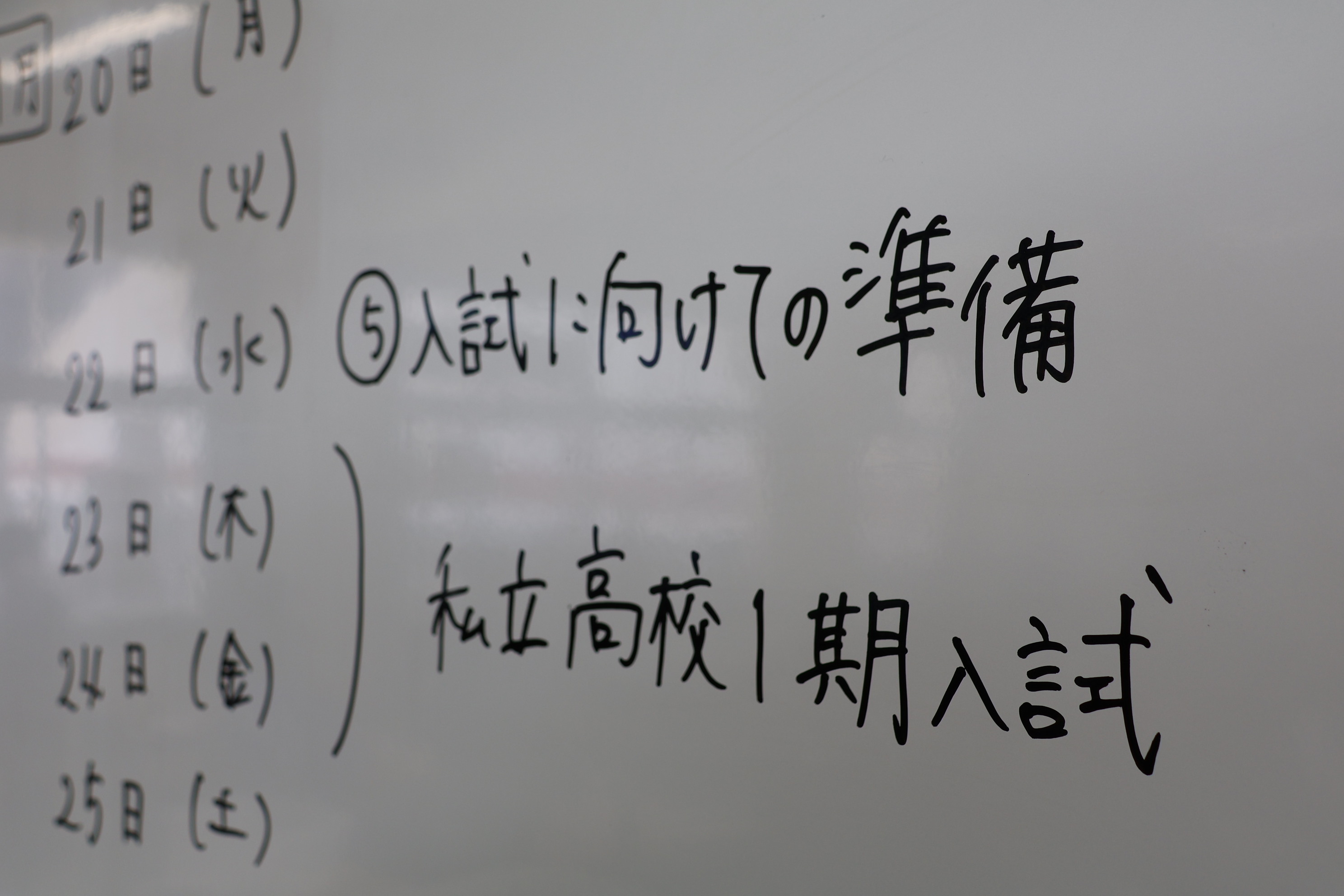



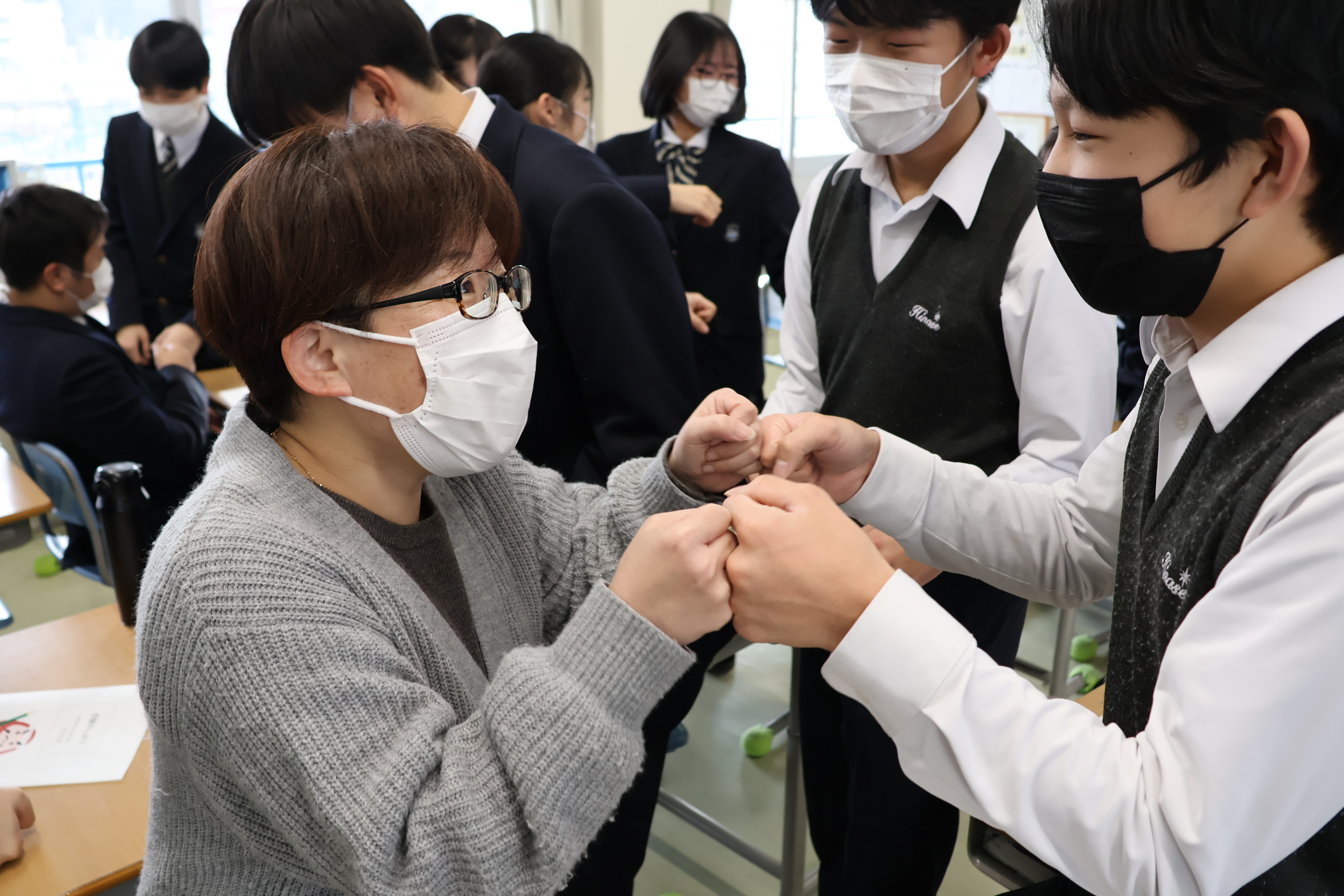
◎がんばるよ(1/22:明日挑む)

アリガトウ。後輩たちのメッセージを受けて。
◎私たちのはじまりの風景17(1/22)
ここはどこでしょう?









◎祝 岡山県少年警察協助員会連合会長賞(スローガン優秀)受賞
日生中学校では、体育委員会を中心に継続的に自転車鍵かけコンテストに取り組んでいますが、今年度、上記の賞を受賞しました。2月10日に岡山県警察本部で開催される表彰式には、代表で体育委員長が出席する予定です。今後も、「自転車の盗難の被害者にも加害者にもならない」という防犯・規範意識を高めていきたいと思います。ありがとうございました。
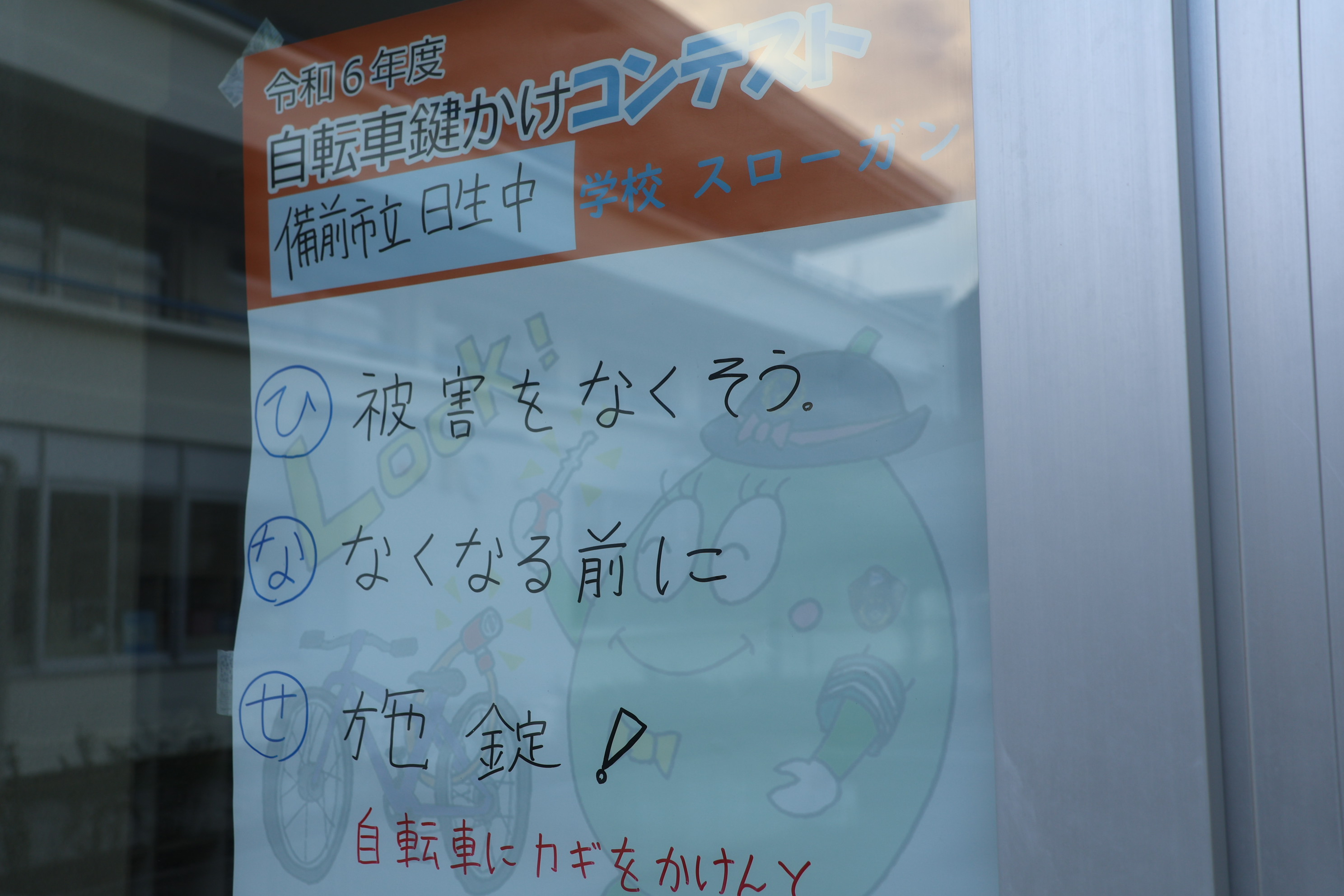
◎今日も、MORTON’s ENGLISH CAFE のような(1/21:原則毎週火曜日)
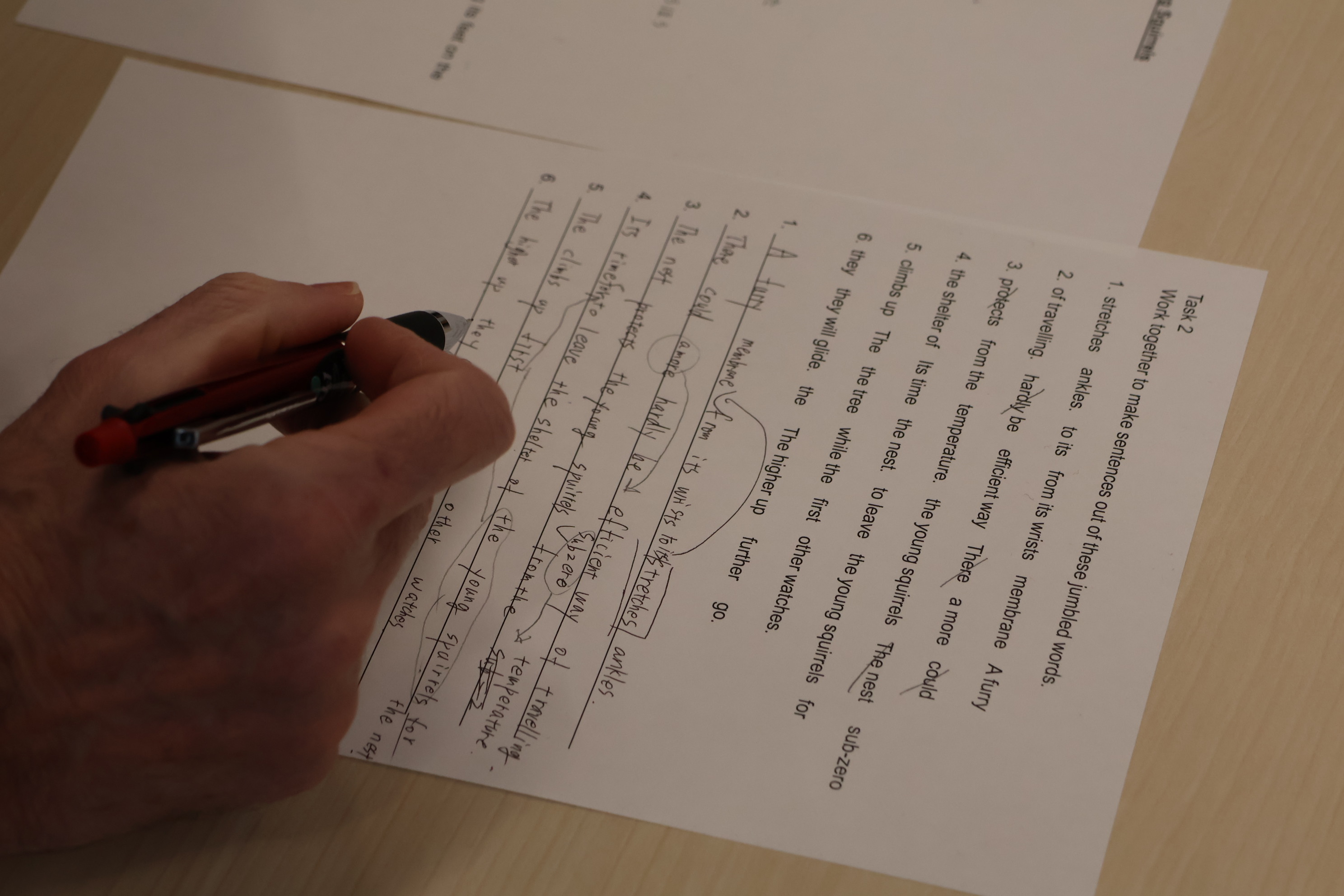

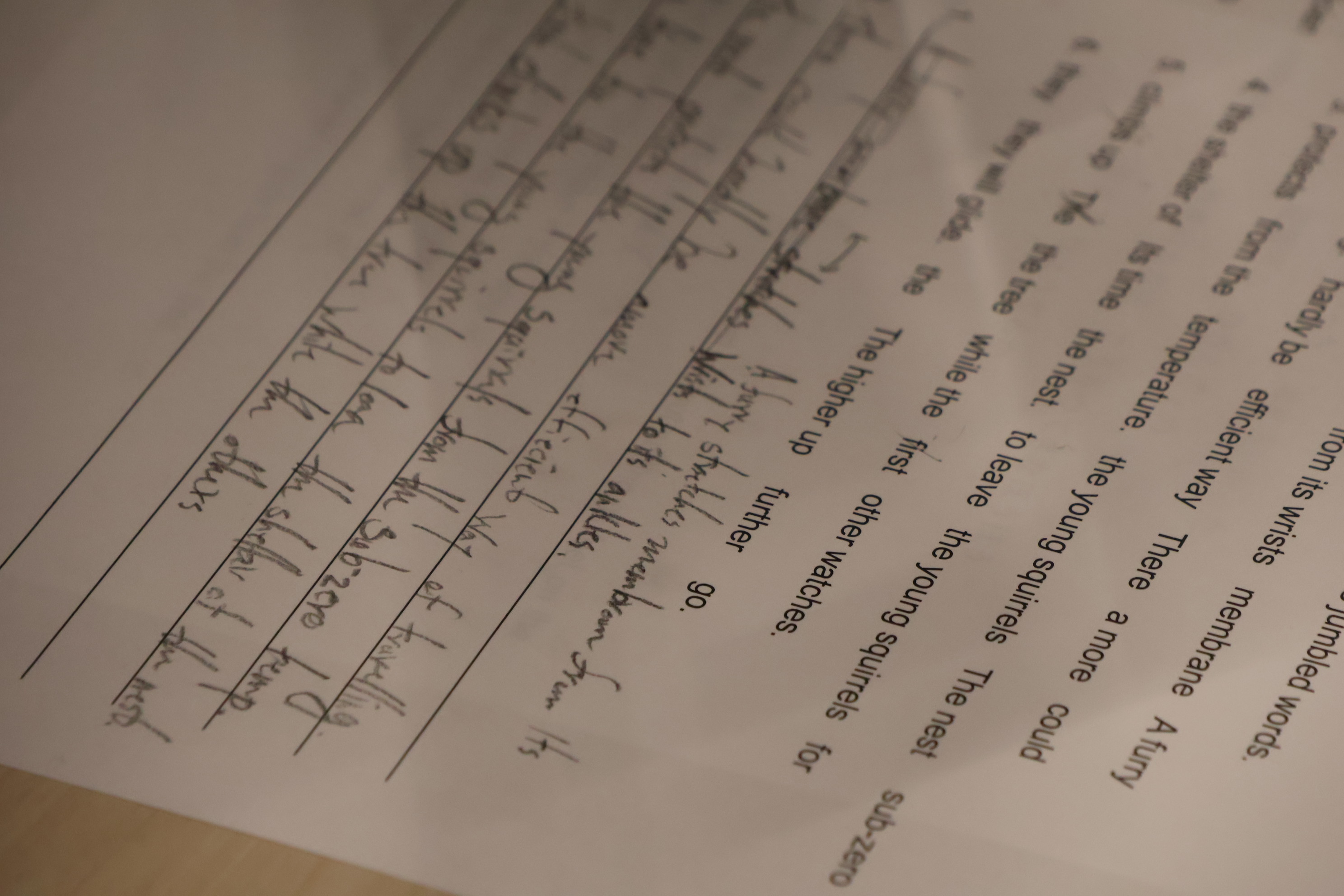
ひな中チャレンジ企画です。
◎求めよ さらば拓かん(1/23・24:私立Ⅰ期入試へ挑む)
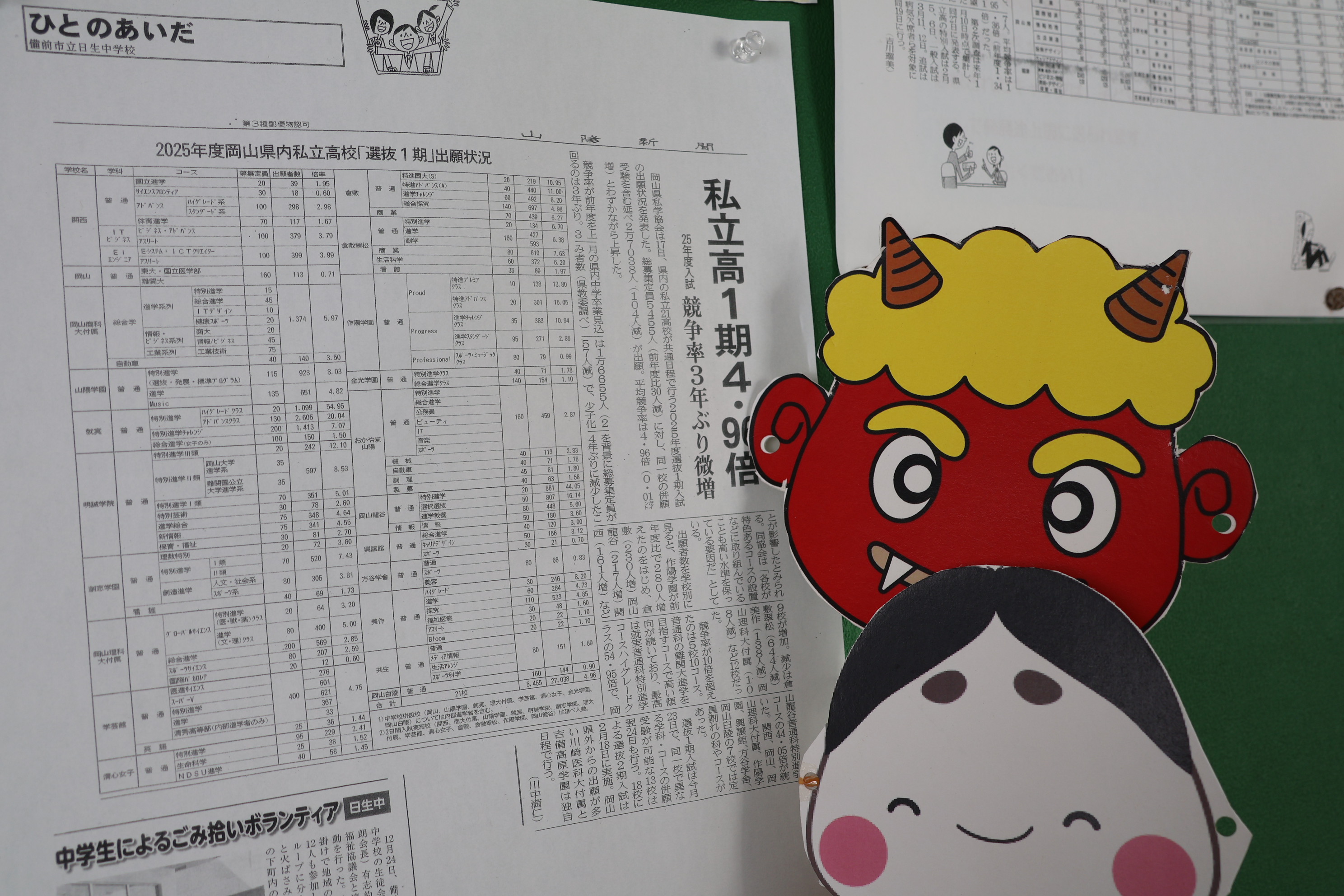
◎ひな中の風 ~毎日が大切(1/21)


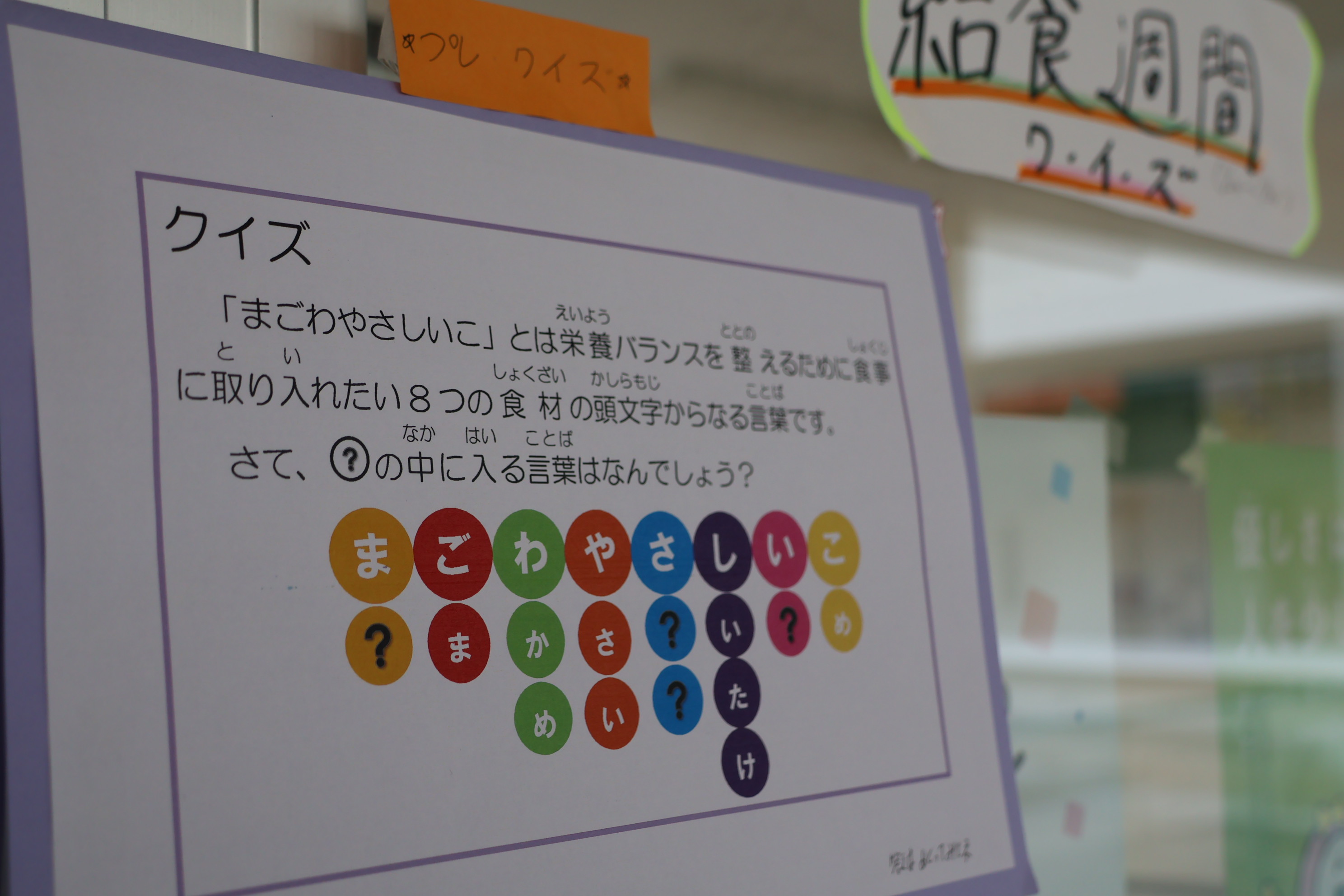

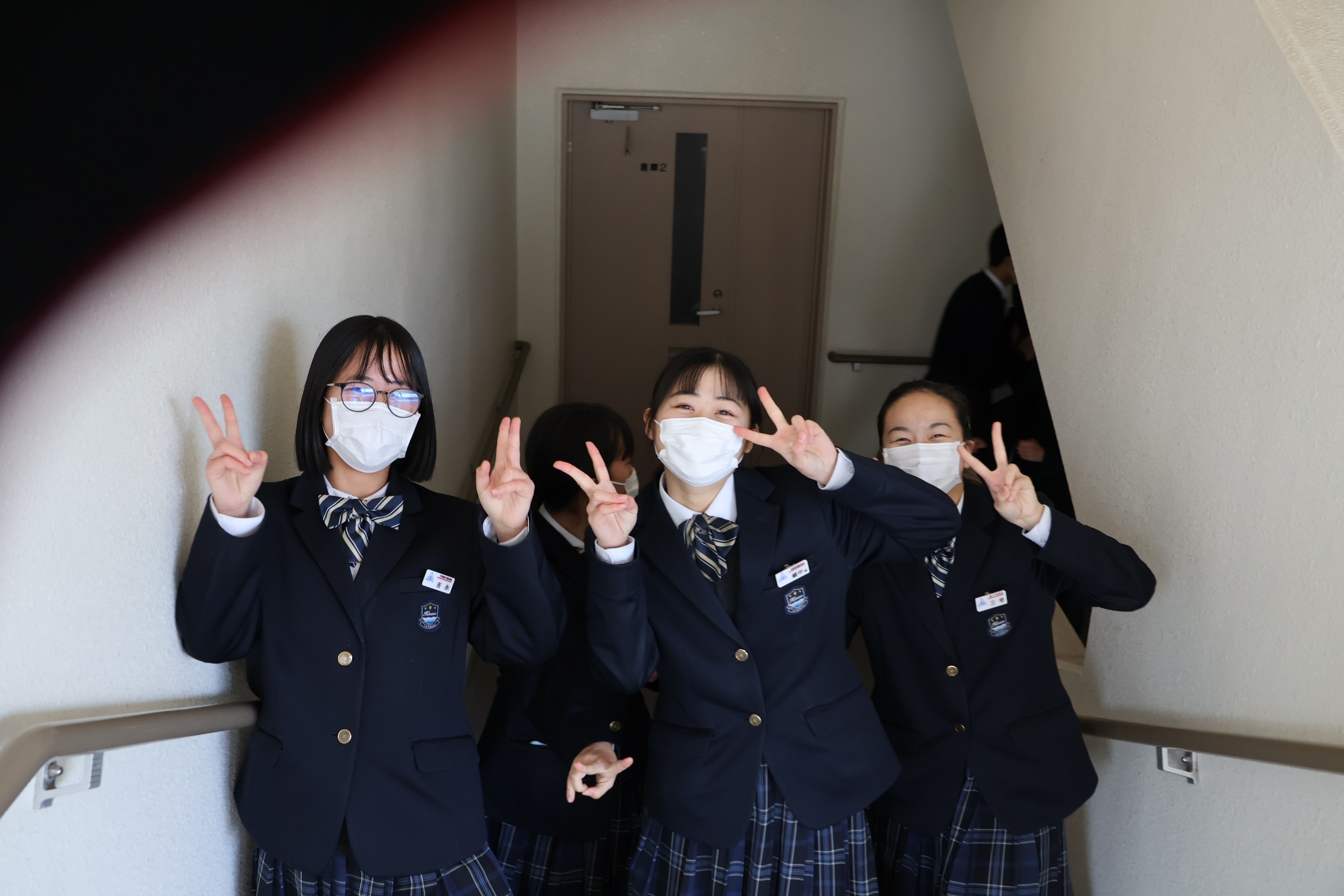
◎私の予防、私の対策、私の休息・栄養で。(1/21)
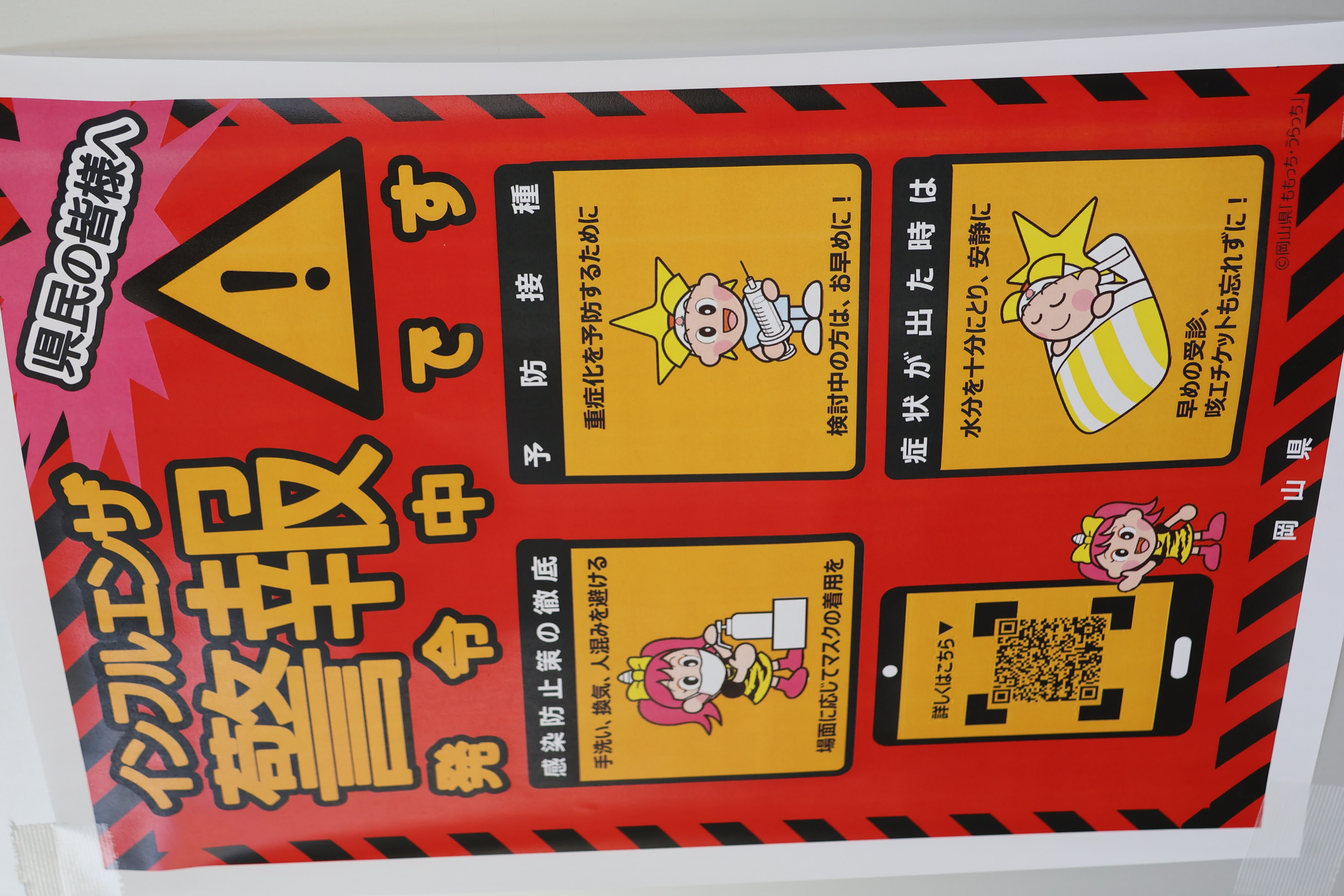
◎おはようおはよう(1/20:体育委員と)

◎大寒の頃(1/20)

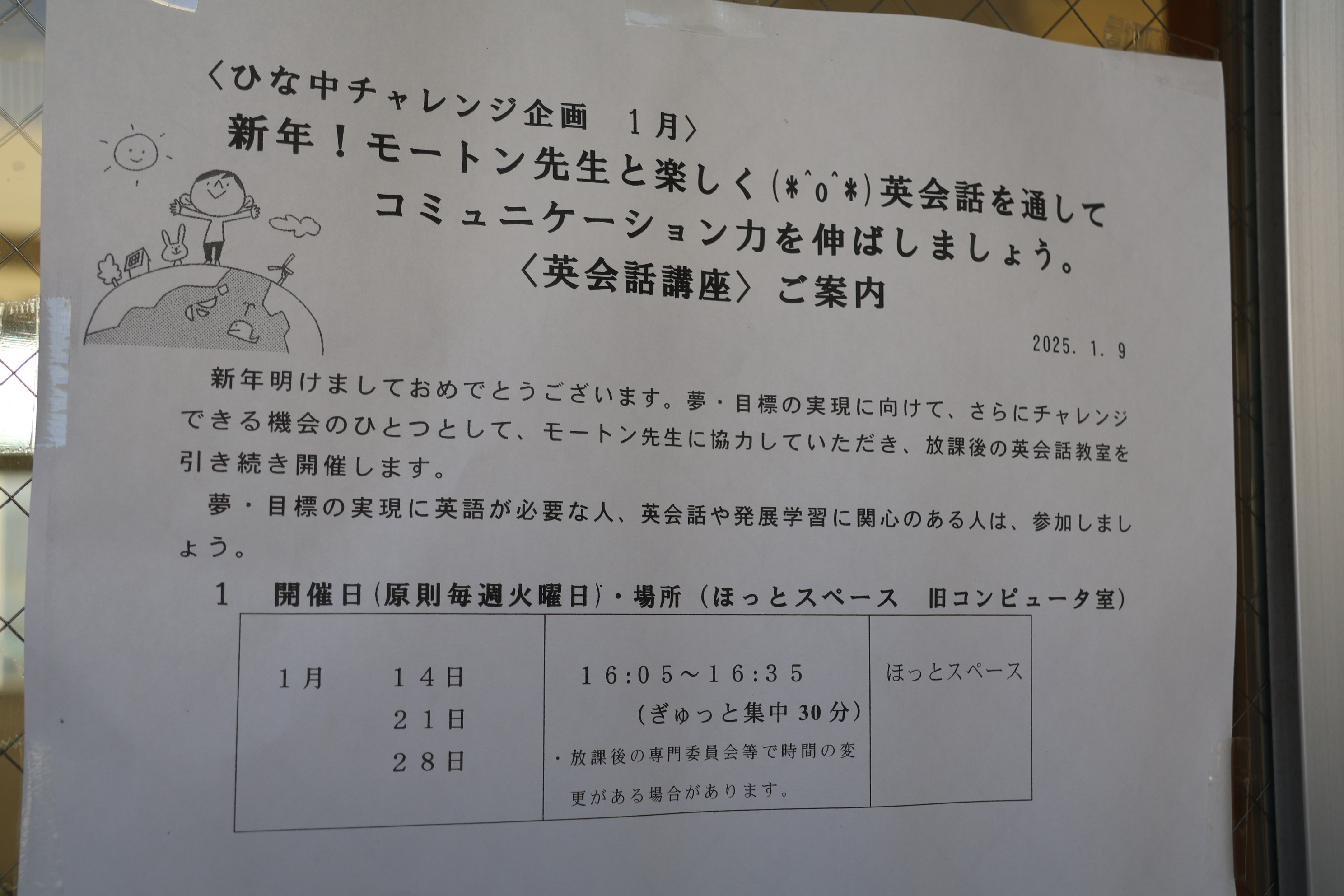
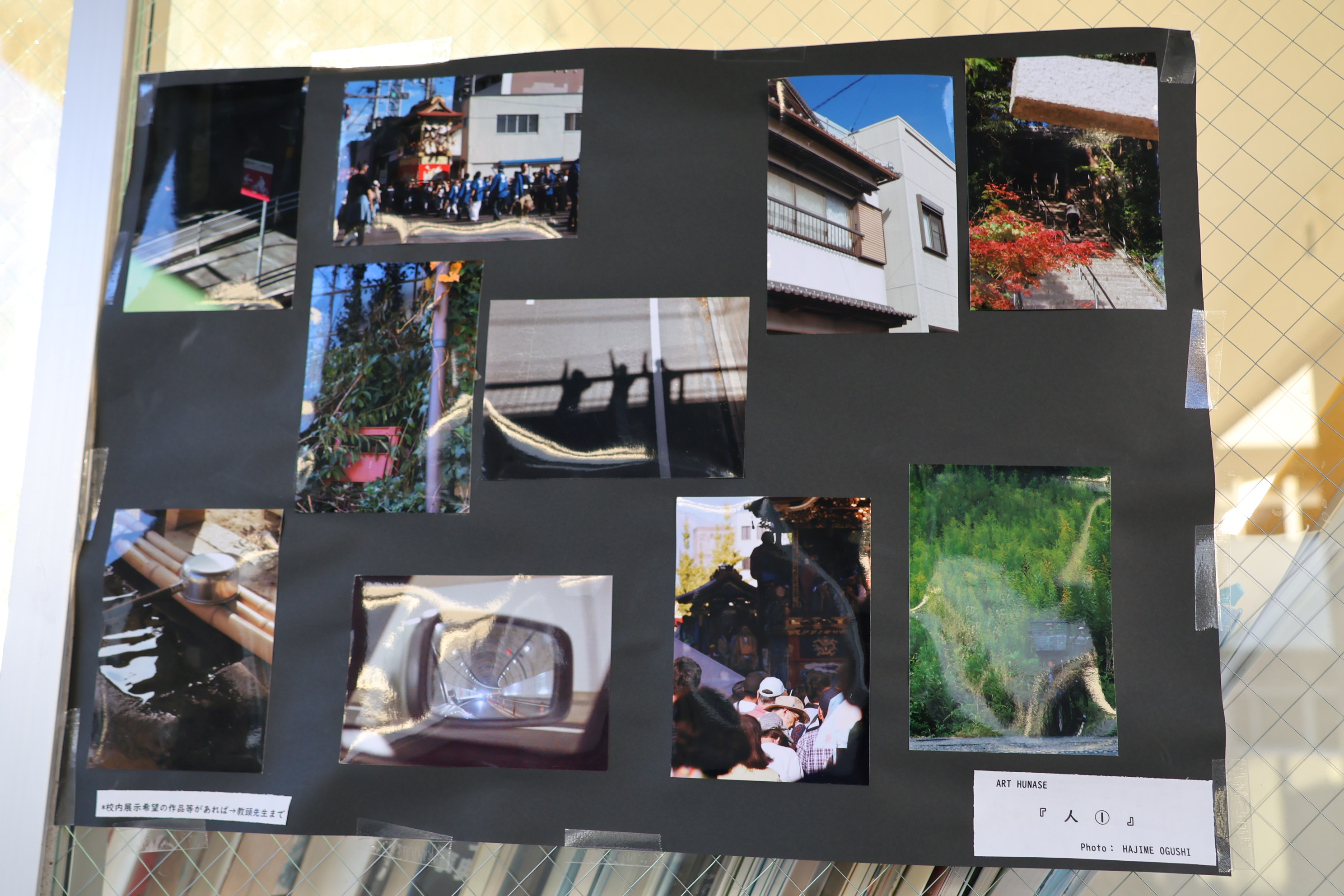
大寒とは
「大寒」とは二十四節気のひとつであり、文字の通り、一年で最も寒いと言われる期間を指します。二十四節気というのは古代中国で生まれたとされる暦で、日本にも伝わってきました。一般的に季節は「春」「夏」「秋」「冬」の4つに分けられますが、二十四節気はよりわかりやすく季節の移り変わりを感じられるように各季節をさらに6つに分けたもので、今回テーマである大寒のほか、12月の冬至や2月の立春なども含まれます。また、大寒は「大寒に入るその日のことのみ」を指す場合もありますが、実は15日間(閏年の場合14日間)設けられています。
二十四節気の上では、先ほど少し触れた「立春」が春の始まり且つ一年の始まりとされているため、大寒はそこから数えて24番目にあたる季節、つまり一年を締めくくる最後の期間ということになるのです。
ちなみに、立春の前の日が豆まきや恵方巻などでおなじみの節分です。立春が一年の始まりであるということからわかるように、旧暦で節分は大晦日にあたる日だったということになります。そう考えると、一年の締めくくりである節分の行事が現在でも当たり前に行われている理由がわかりますよね。
大寒の前の二十四節気は「小寒」:大寒を説明するうえでもう一つ覚えておきたい二十四節気の暦があります。大寒の前にやってくる「小寒(しょうかん)」です。小寒の始まりから大寒が終わるまではおよそ30日間あり、その期間のことを「寒の内(かんのうち)」や「寒中(かんちゅう)」「寒(かん)」と呼びます。また、小寒に入る日のことを「寒の入り(かんのいり)」、そして大寒の最終日は「寒の明け(かんのあけ)」と呼び、一年のうちで一番寒い時期が終わることを表しています。その後、立春を迎え、春がやってくるのです。
「寒仕込み(かんじこみ)」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、これは大寒の時期に行われる習わしのひとつです。寒の内の期間中に行われる行事や習慣をいくつか紹介します。
○寒の水を汲む:寒の水(かんのみず)とは、一年の中で一番寒い寒の内の期間中に汲まれた水のことを指します。この時期に汲まれる水は手が痺れるほど冷たく清らかで、昔から神秘的な力があると言われてきたのだそうです。飲むと体によいとされていたほか、この時期の水を汲み置いて料理などに使う家庭もあったようです。ちなみに、寒の内の9日目の水は「寒九の水(かんくのみず)」と呼ばれ、とくに効能があるとされていたのだとか。「この水で薬を飲むと長寿の助けになる」とも言われていたため、大切に飲まれていたのだそうですよ。
○寒仕込み:寒仕込みとは、上記で触れた寒の水を使って醤油や味噌、酒などを仕込むことをいいます。厳しい寒さの中で汲まれた寒の水は、冷たさが極まっていて不純物が少なく雑菌が繁殖しにくいため、腐りにくいと言われてきたのだそうです。また、口あたりがやわらかく発酵もゆっくり進むため、質の高いものに仕上がるとも言われています。醤油や味噌、酒だけではなく、高野豆腐(凍み豆腐)や寒天などもこの時期に仕込むのが最もよいとされているんですよ。
○大寒卵って:これは大寒が始まる日に生まれる卵のことを指し、食べるとよいとされる縁起物なんです。大寒卵以外にも、大寒に作られたものや旬を迎えた食べ物はそれぞれ栄養価が高くおいしいとされ、昔から大切に食べられてきました。大寒卵とは、大寒の初日に生まれた鶏卵のことを指します。現在では技術の進歩により、温度管理された鶏舎で一年中卵を産むことができるようになりましたが、昔はそうではありませんでした。鶏は本来、冬には卵を産まない生き物です。冬に入る前には寒さに耐えるため、餌をたくさん食べて水分はあまり取らずに栄養を蓄えます。そして、冬本番を迎えると卵を生まずにじっとしていたのだそうです。そのため、寒い時期に卵を産むことは稀でした。このような理由もあり、大寒の時期に生まれる卵は貴重で栄養価も高く、縁起のよいものとされてきたのです。
冬に入る前に蓄えていた栄養がぎゅっと凝縮された大寒卵は「無病息災」や「健康運」、また黄身の色が濃いことから「金運アップ」の願いも込められているのだそうですよ。近年はスーパーや百貨店、通販などでも大寒卵が予約販売されていることもあるようです。
○寒餅:寒の水で炊いた米を使ってついた餅、もしくは大寒の時期についた餅のことを「寒餅」といいます。寒の水には神秘的な力があると言われていたため、この水を使って作られる食べ物はありがたく、大切に食べられてきたのだそうです。来週25日には、NPOひこうせんさんから、子どもたちのもちつきボランティアの依頼が来ています。この機会を活用してみてもどうでしょう。
◎道を切り拓け そこが道となる(1/18・19:大学入学共通テスト)
2021年度から、それまで行われてきた大学入試センター試験が大学入学共通テストに変更されました。高校での基礎的な学力の到達度を測る試験で、1月中旬〜下旬の土曜日・日曜日の2日間で、全国一斉に行われます。大学入学共通テストの結果は、国公立大学はもちろん、多くの私立大学の入試にも利用されるので、多くの受験生が受験します。
大学入学共通テストで出題される教科は、2025年度から国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報の7教科です。各教科に地理歴史なら「歴史総合、日本史探究」「歴史総合、世界史探究」など、理科なら「物理」「化学」などの科目があります。どの教科・科目を受験するかは、受験生が志望する大学・学部によって異なります。国公立大学をめざす場合は、多くの大学が6教科8科目を課します。大学入学共通テストを利用して私立大学をめざす場合、志望する大学・学部によって課される教科・科目は異なります。1教科1科目から5教科7科目まで、多様な入試が実施されています。
高校で2022年度から始まった学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びが重視されています。大学入学共通テストもその方針に沿って作問されます。つまり、教科書レベルの知識や技能が身についているかを問われるだけではなく、その知識や技能を活用して、思考力・判断力・表現力などを発揮して解くことが求められます。また、どの教科・科目も、グラフや地図、会話文など、読み取る資料の分量が多いのも特徴で、そこから得た情報をもとに考察し、課題を解決する力を問う出題もあります。解答はマークシート方式で行われます。
◎明日は、隣の学校で合同練習。(1/18)

がんばってきます。
◎日常からつなげる、防災・備災・減災を(1/17)
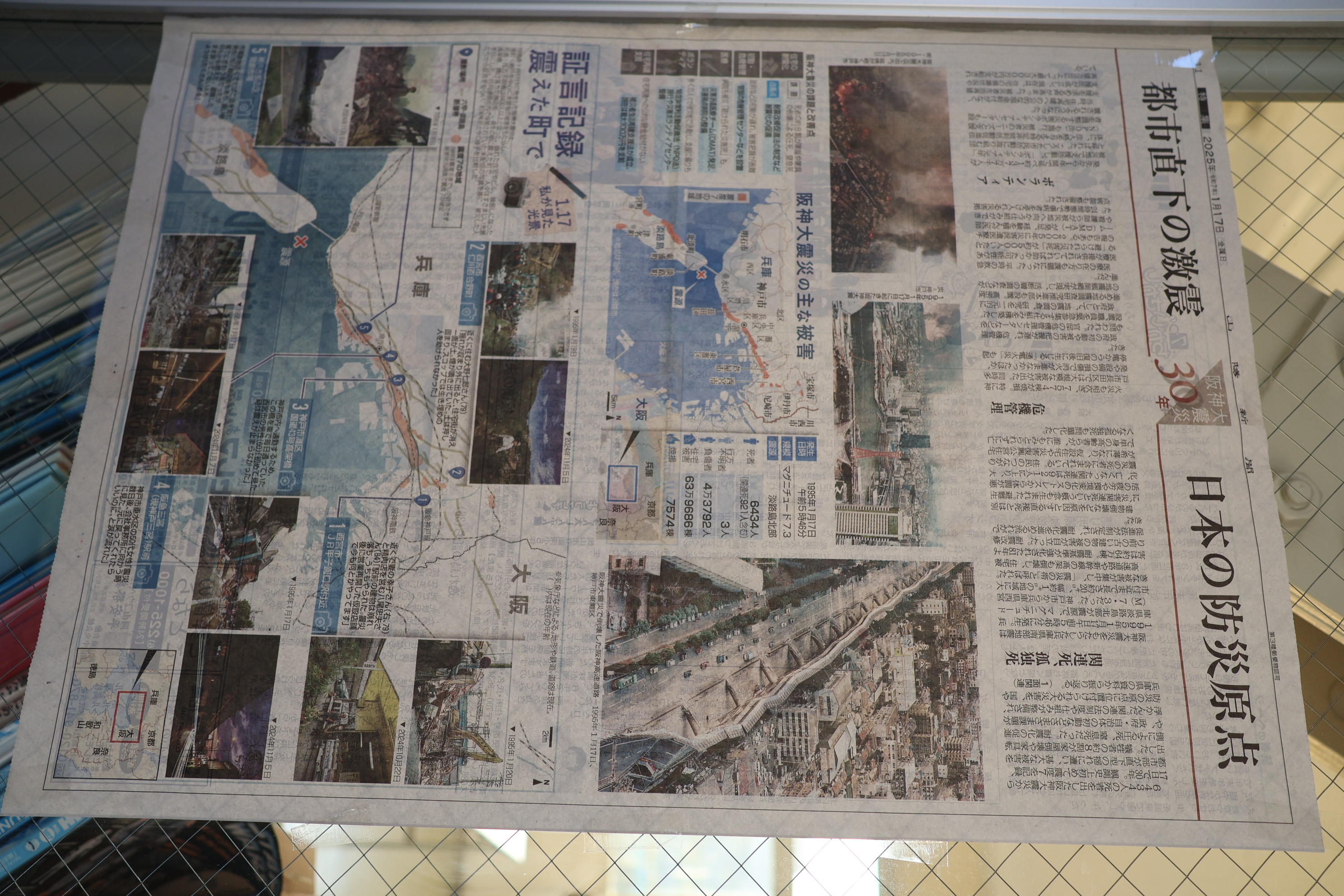
◎おはようを大切にしています(1/17)
生徒会では朝のあいさつ運動を、継続的に取り組んでいます。

『絆が生まれる瞬間』(リッツカールトンホテルの元日本支社長高野さんの本)には・・・「挨拶」の語源を紐解いてみると、禅宗で問答を交わして相手の悟りの深浅を試すことを「一挨一拶」という、その言葉に由来するそうです。「挨」には「押し開く」「互いに心を開いて近づく」、「拶」には「迫る」「擦り寄る」といった意味がある。「出会った人が互いに心を開いて相手に迫っていく」ということが挨拶とされています。
ノートルダム清心学園理事長だった渡辺和子さんの『置かれた場所で咲きなさい』には・・・あいさつは「あなたはご大切なひとなのですよ」と伝える最良の手段であり、お互いが、お互いのおかげで生きていることを自覚し合う、かけがえのない機会なのです、とあります。
禅にも「挨拶」という語があります。これは昔、修行仲間であったりお師匠さんと弟子が、その悟りの境地というものを推し量る言葉として使われていました。人間は、相手から働きかけられたことに対して、必ず反応をしています。たとえば、こちらから「おはよう」と言って、元気よく「おはよう!」と返す人もいれば、「おはよう…」とぼそぼそ言う人も、明らかに無視する人もいるでしょう。これらはすべて、こちらの働きかけに対して何かしらの反応をしている、ということになります。「無視をした」というのも「反応」。挨拶というのは、人と人とが関係をつくっていくときに、相手がいまどのような状態であるかということを知るためにとても大切なものなのです。人間の心は毎日違う。朝気分よく迎える人もいれば、気分悪く迎える人もいる。でも、目の前の相手と一緒に生活をするのであれば、その人と、せっかく同じ時間・同じ空間を過ごすのであれば、出会ったときに、まず、その人がいまどういう状態にいまあるのかを知って、相手との関係をより良くつないでいく、という積極的な方法として挨拶というものがある、ということ。・・・人間関係の基本は、挨拶だと言われるその所以なんですね。挨拶とは、相手の反応を推し量るためのもの。目の前の相手と良い人間関係を築いていくための方法である、ということです。参考までに。
◎1.17を忘れない(1/16)

阪神淡路大震災1.17のつどい実行委員会HPより
〈1995年1月17日 午前5時46分。阪神淡路大震災が発生し、私たちの大切なものを数多く奪っていきました。あの震災から、まもなく30年を迎えようとしています。震災でお亡くなりになられた方を追悼するとともに、震災で培われた「きずな・支えあう心」「やさしさ・思いやり」の大切さを次世代へ語り継いでいくため、2025年1月17日(金)に「阪神淡路大震災1.17のつどい」を、神戸市中央区の東遊園地で行います。〉
この震災では、高層ビルや、高速道路までもが大きく倒壊し、現代の文明の脆弱さを思い知らされました。死者の数は6434人、負傷者は4万3792人。財産を多く失い、愛する我が家を失った人は、全壊、半壊合わせて24万9170棟で、全焼建物は7036棟でした。失ったのは数字に表れるものだけではありません。復興に際し、被災地域住民のそれまでのコミュニティも失われたとも言う人もたくさんいます。失ったことについていくら語っても切りがありませんが、想像を絶する痛みに耐え、この大震災 により私たちが未来に向けて得た、かけがえのないものは「多文化共生」と「ボランティア」といわれます。大震災が発生したこの年はボランティア元年ともされ、1月17日は「ボランティアの日」と定められました。実際に被災地に足を運んだ者は3ヶ月間で116万人、1日平均2万人を超えました。このボランティア文化が、後の東日本大震災にも、また、多くの海外の現場にもしっかり引き継がれるようになりました。教育現場では、小中高・大学などもボランティアが重要になり、本校でもボランティアは大切な取組となっています。
災害での被災者は何も日本人ばかりではありませんでした。多くの外国人も負傷し、200人の外国人が死亡しました。被災地となった兵庫県内の10市10町において被災時には8万人の外国人が居住していました。そのうちの4人に1人が日本語の読み書きが出来ませんでした。被災者を助けようとする情報がいくら被災地で行き交っても一向に恩恵を受けられない人がいること、日本社会の住人が日本語がわかる人ばかりではないということが震災で明らかになりました。そこから多言語での紙媒体やラジオ、インターネットコンテンツが日本で次々に生まれるようにもなりました。「言葉の壁」を取り払う活動は、その延長線上に社会の壁は言葉の壁だけではなく「制度の壁」や「心の壁」に撤廃の取組につながっていきました。今、全国で、違う者同士が、〈共に生きる〉という目標に向かって、個として、組織として、精力的な取組が進んでいると感じます。たくさんのものを奪い去った震災ですが、1995年1月17日にうまれた「ボランティア」や「多文化共生」の樹を引き続き大切に育てて行けたらと思います。(にしゃんたさんの記事を編纂)
◎進路を切り拓いてく我ら、なかま
~〈適性と能力〉三年生面接練習に取り組む



〈自分らしくせいいっぱい〉
1/15(水)、三年生は、全学年の先生に協力していただき、模擬面接を行いました。面接官役の先生のアドバイスや指導をもとに「進路を切り拓いていくちから」をこれからも磨いていきます。
1/23・24は、私立1期入試です。
面接では、
「中学校でのがんばったことは何ですか?」
「部活動で学んだことは何ですか?」
「毎日の生活や勉強の取組はどうでしたか?」
「高校でどんな事をがんばりたいですか?」
「将来の夢や目標は何ですか?」など
自分の未来指向や積極的な姿勢がとても重視されています。1.2年生諸君も、心配や不安があるとは思いますが、自分自身が〈夢や目標を育てるために〉《毎日の生活を大切にしていくことや自主的な家庭学習》をすることが何より大事です。保護者の方々の励まし・支援も今後もよろしくお願いします。
◎正しく知り 正しく行動するために
地域と共にある学校 ハンセン病問題学習展示中(1/16~)


■日時:2025年1月16日(木)~2月18日(火) *最終日は11時まで
■会場:日生地域公民館(1階ロビー)
日生中学校の生徒が学んだ「正しい知識」「深めた学び」をパネル展示しています。多くの市民のみなさんにも知っていただき、差別を許さない社会づくりについて一緒に考えていきましょう。
正しく知り 正しく行動するために
今年度も日生中学校3年生は、ハンセン病問題学習に取り組みました。回復者のひとりである金泰九(キムテグ)さんの生き方を知り、そして現地研修で長島愛生園を訪ねました。また、帰校後は、長島愛生園の田村学芸員さんと大学生をお招きし、〈未来につなぐ〉意見交流学習で学びを深めてきました。
そして、学習したことをもとに、〈ハンセン病問題学習パネル展示〉の準備を進め、日生地域公民館での展示を行います。
次世代に生きる私たちは、ハンセン病問題学習を通して、いま・これからの社会のあり方を見つめ、自分の生き方について、《深く考え》《行動して》いきたい と思っています。
◎備前サンラッキーズ 練習開始(1/15)
備前市の施設として、日生中学校グラウンドを利用して、今日から備前サンラッキーズが野球の練習をされます。


[備前サンラッキーズのHPより]
〈2021年、岡山県備前市を拠点とした女子硬式野球クラブチームを創設しました。女子野球は年々発展し、今では女子の高校野球が甲子園・東京ドームで開催されるようにもなりました。また、NPBのチームが女子チームを持つなどここ数年で環境は一気に変わり、選手数も少しずつ増えてきています。一方、地方に目を向けると関東・関西圏に比べて、卒業後野球を続ける環境が少なく、続けるために県外へ出て行ってしまうというのが現状です。
そこで、新たにチームを創設し、1人でも多くの女子選手が地方でも野球を続けられる場所を創りたい!という想いからスタートしました。
まだ現役でできるのに、続ける環境が無くて野球を辞めてしまうという選手も少なくありません。また、野球が好きで始めたはずなのに、人間関係がうまくいかず馴染めない・野球が嫌いになってしまった。チームによっては選手数が多く試合への出場機会が少なかった。ケガの影響で試合にあまり出られなかったという選手も中にはいると思います。そういった選手にぜひ備前サンラッキーズで野球を続けてほしいと思っています。
野球が好きで、野球がやりたくて始めた野球を嫌いにならないでほしい。できるところまで、やりきったと思うまで、思う存分野球を続けてほしい。そう願っています。このチームが、選手を後押しできるチームでありたいと思っています。〉
勝つことを目標にするのもそうですが、何よりもまずはこのチームで『野球が楽しい!』と思えるようにしていきたいと思っています。私たちと一緒に、野球を楽しみましょう!!
◎多くの人に支えられて(1/15)
読み語りでの「本のワクワク」をいつもありがとうございます。
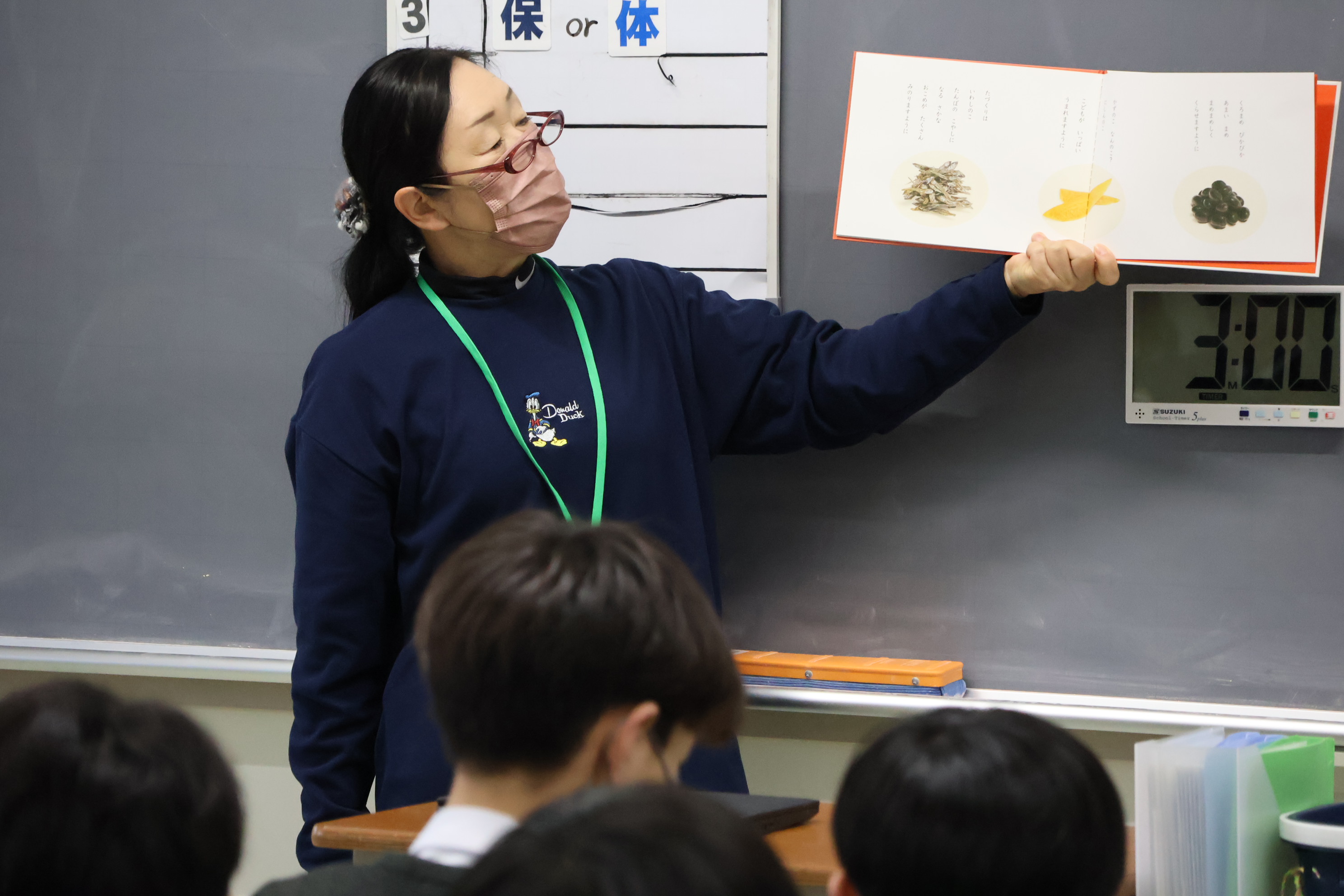
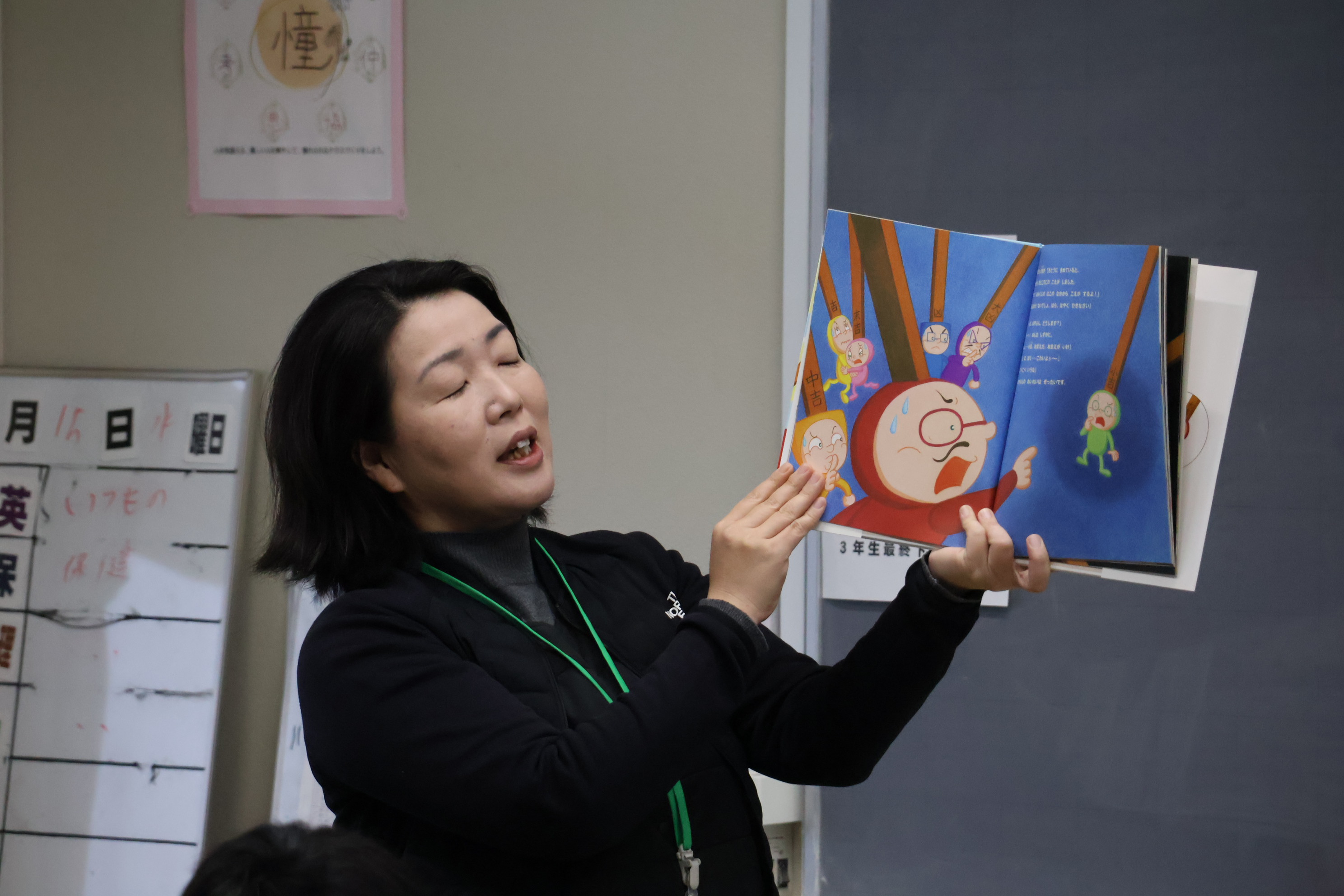
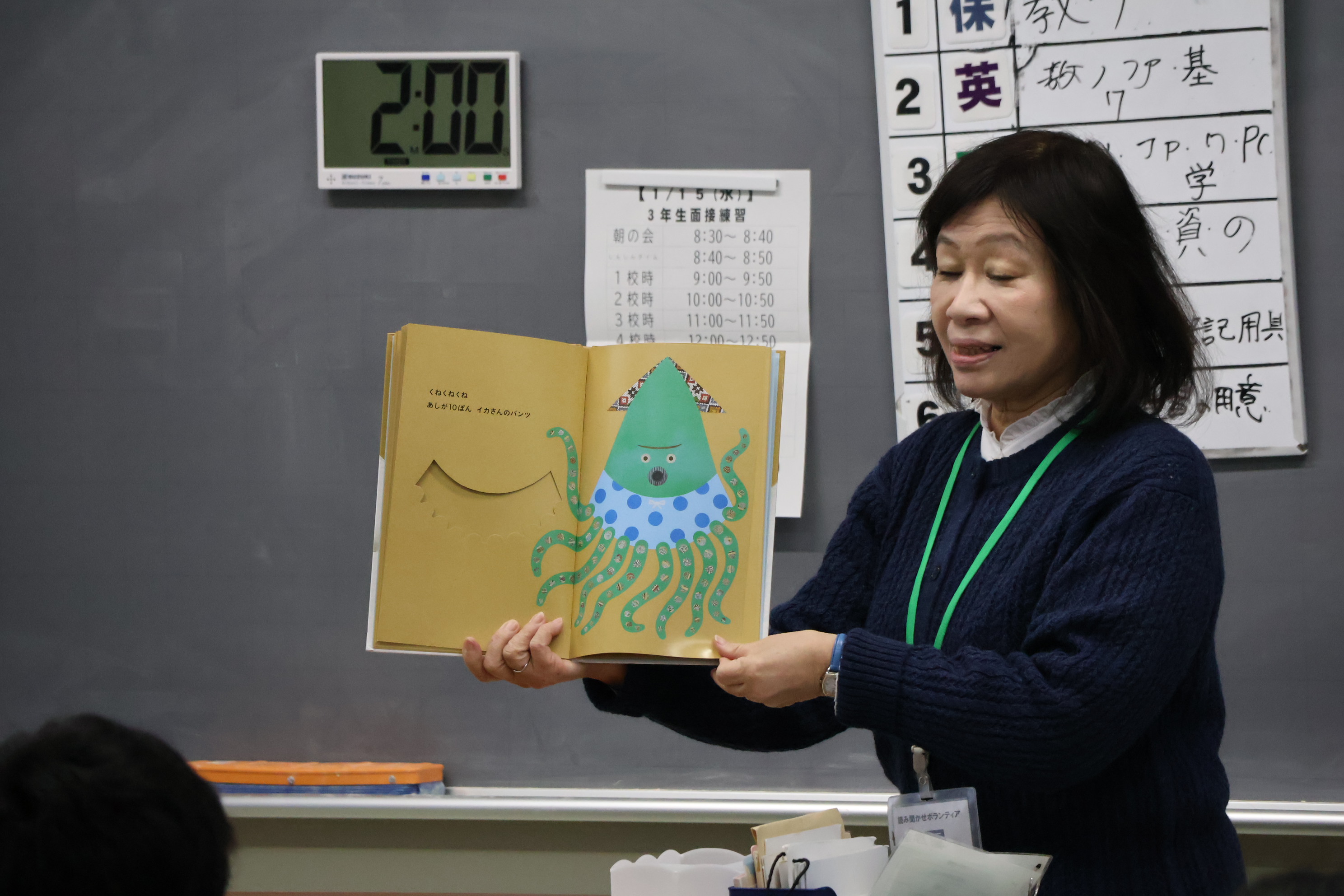
◎多くの人に支えられて(1/15)
青少年健全育成センターさんの朝のあいさつ運動をいつもありがとうございます。



◎地域と共にある学校(1/15)
根木スクールサポーターから、施錠に関する啓発の垂れ幕をいただきました。


◎美しい冬の景色が浮かぶ「俳句コンテスト」実施中(~1/27〆:文化委員会)
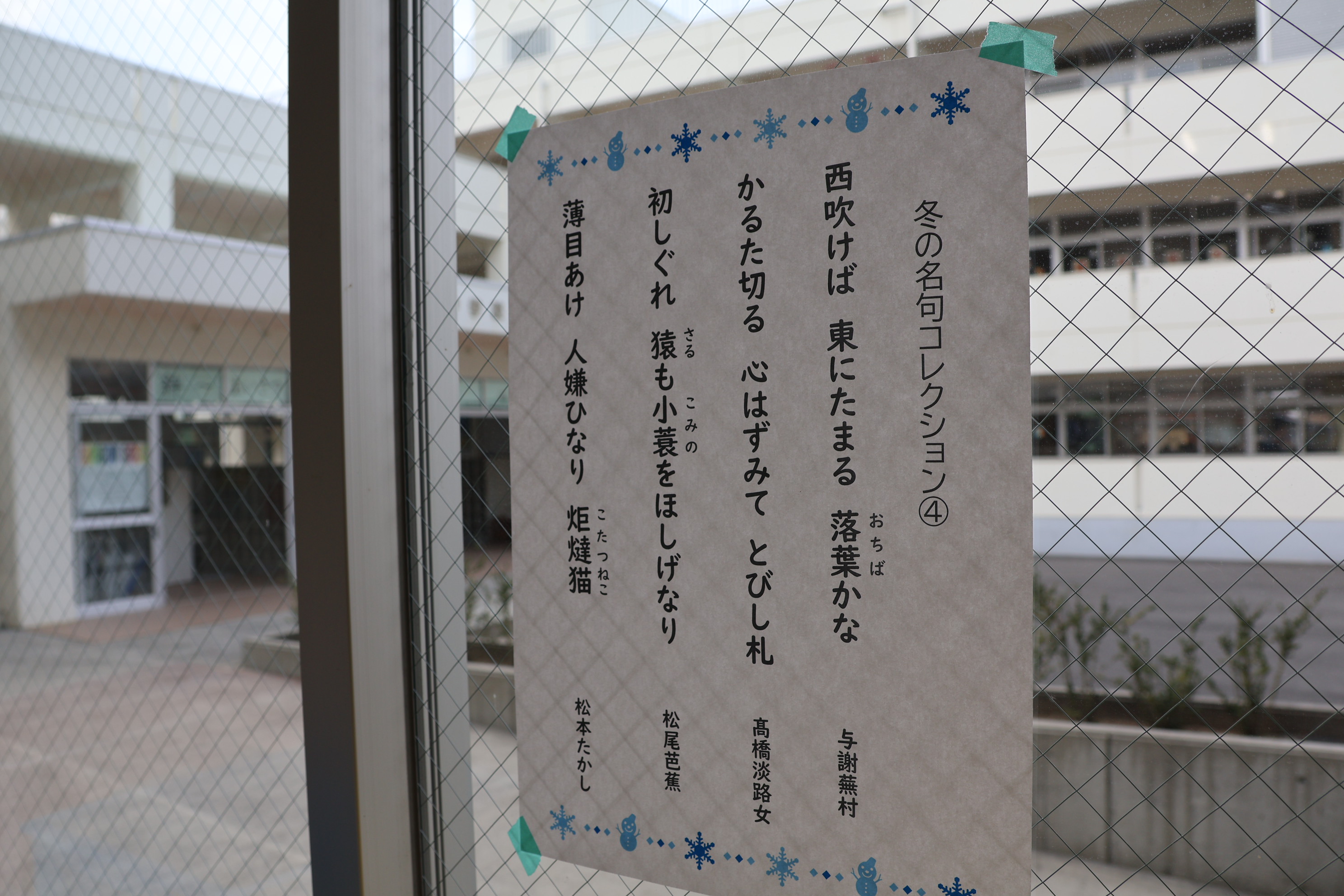
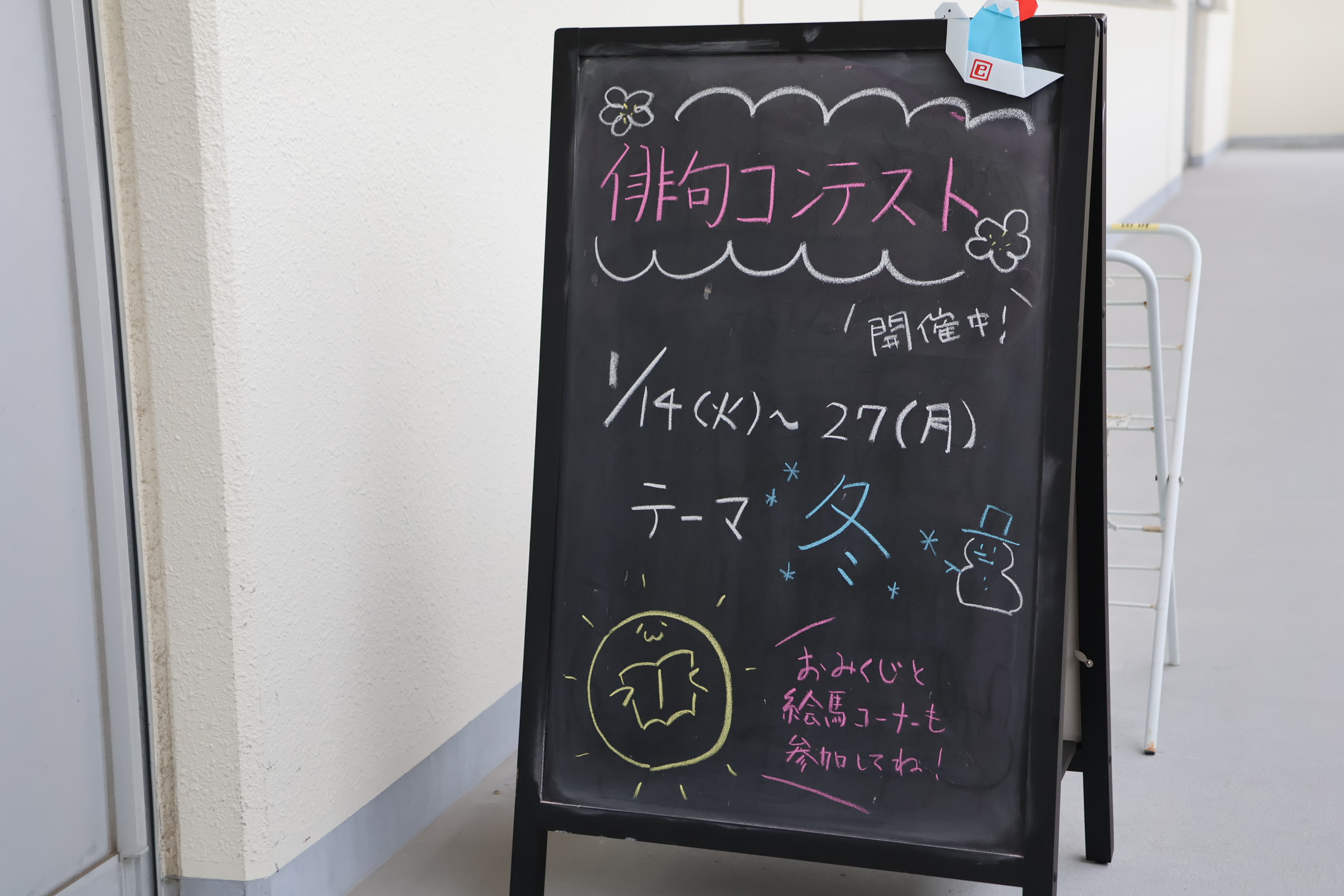
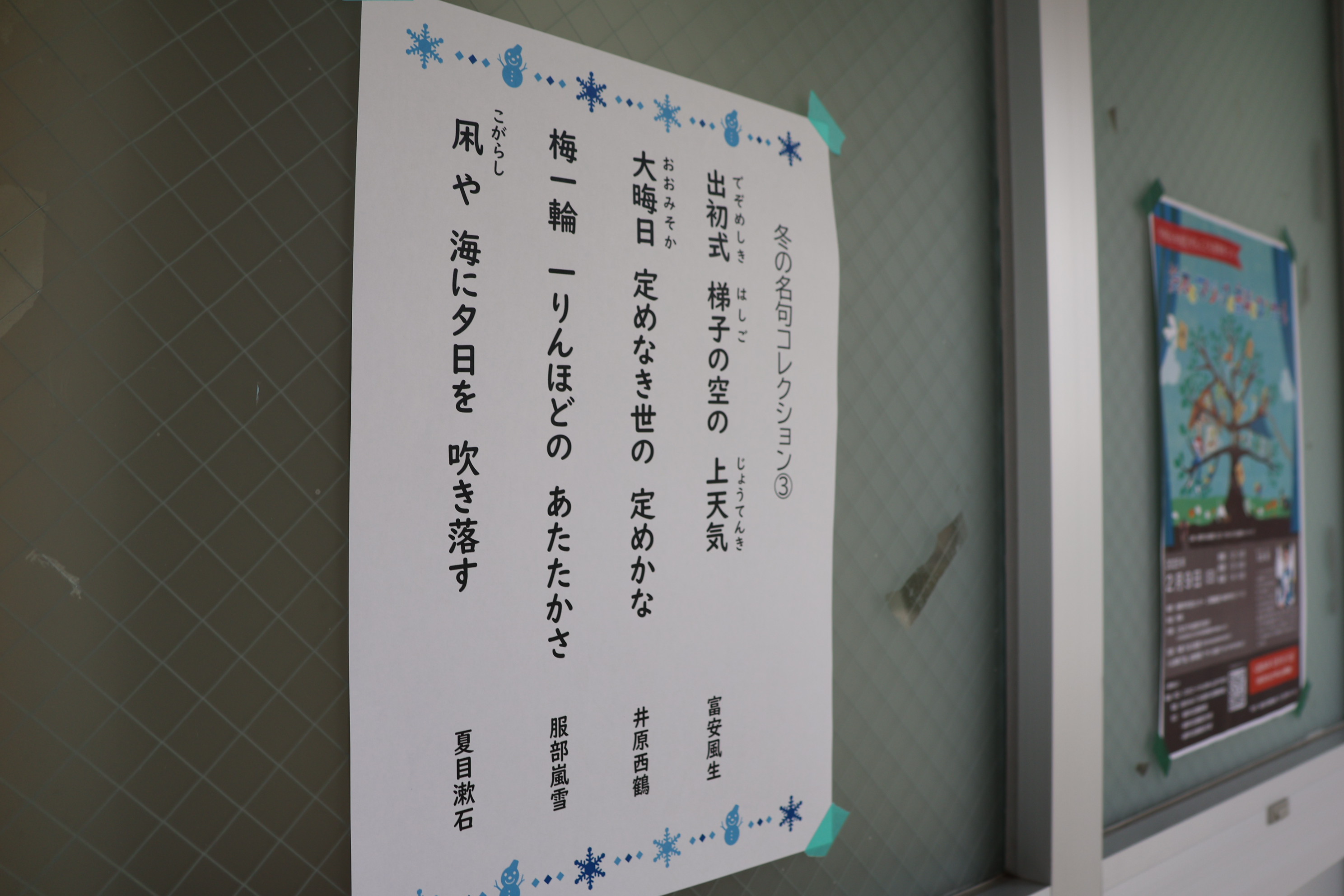
◎教員も学び続けることが大事(1/14)
今年も授業改革推進員の三宅先生と共に、授業改善に取り組んでいます。(授業参観後の振り返り)


◎いない人へ(1/14)
二十歳の集いに参加された方から教えていただいた、新成人への「お祝いのコトバ」の一部を紹介します。
「・・・今日の日をこうしてお祝いしてもらえることを感謝すると新成人のみんなは言います。大人として大切なことですね。たくさんの方からいろんなお祝いの言葉をいただいていると思うので、頂いたコトバを大切にしてください。付け加えることはそうありませんが、ひとつだけ。それは、自分の小・中・学校、高校のクラスメートだった級友は、あなたと同じように、この晴れの会場に来ることが出来ていますか?探してみよう。
すでに働いていて、残念ながら空けられない仕事で来れなかった級友、あるいは、病気やケガで療養や治療で来ることができない級友、もしかしたら、「そんな集まりには行かない」と思っている級友がいるかもしれない・・・。今日久しぶりに会えた級友との出会いを喜ぶことと、出来たら、ここにいない、来られてない級友にラインやメール、電話をしたり、難しかったらそんな級友らに思いを馳せるだけでも、大人として、成人の日にふさわしいのではないかなあと思います。・・・」

◎地域と共にある学校(1/14)
三年生は、これまでの総合的な学習の時間等で学んだり体験してきたりしたことを活用して、「おかやま旅プランコンテスト(岡山商科大学専門学校主催)に応募します。後援団体である備前観光協会さんからの案内があり、12月末からプラン製作に取り組んでいました。
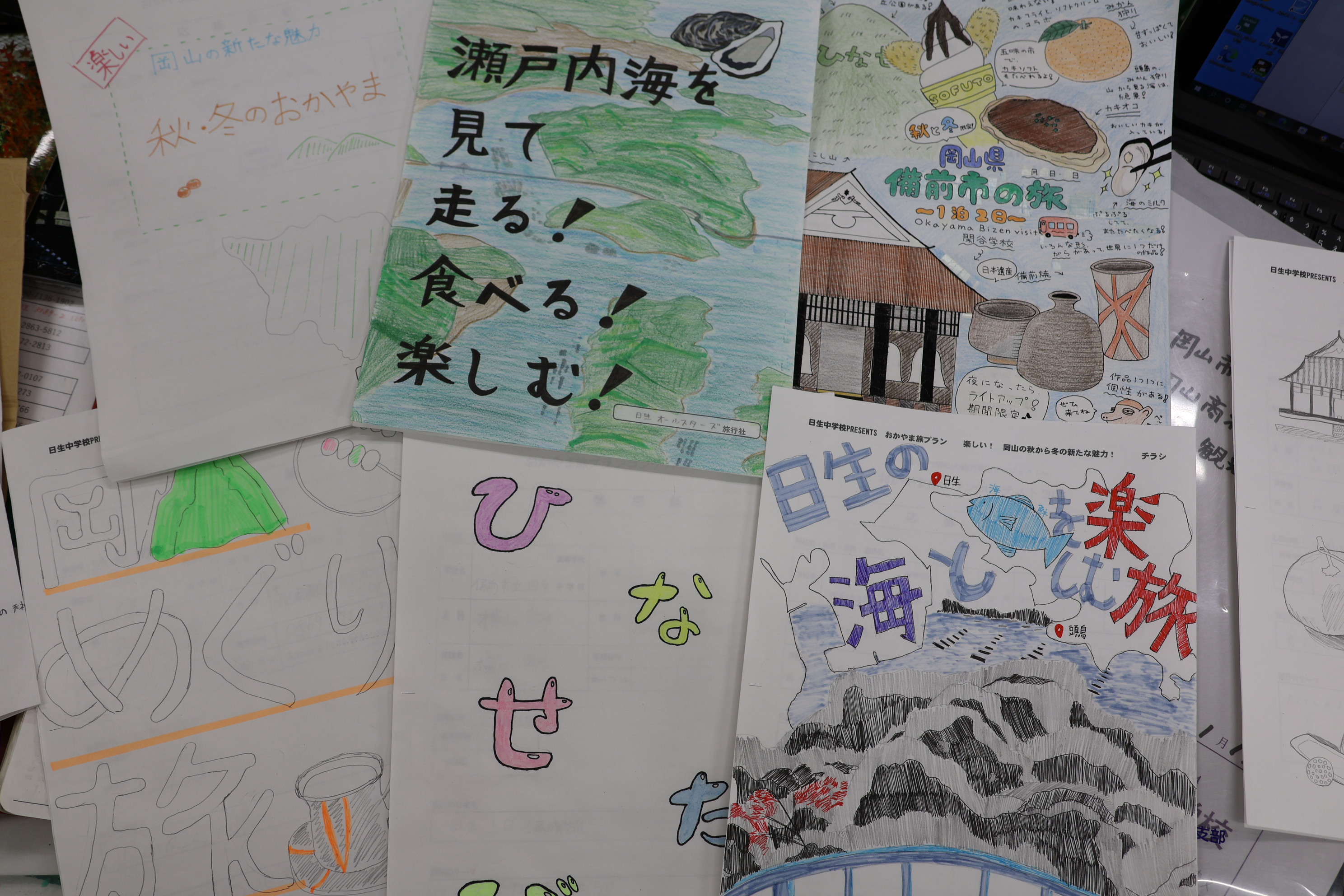
◎五年後の私たちは何をしてるかな。
~成人の日に(1/13)
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.:ラルフ・ワルド・エマーソン(常にあなたを他の何者かにしようとする世界で、自分自身でいることこそ最大の成果だ。)

成人の日は満20歳を迎えた青年男女を祝う国民の祝日で、毎年1月の第2月曜日です。
日本の古い儀式である『元服(げんぷく)』や『裳着(もぎ)』に代わるものとして設けられ、意義は「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」です。
成人の日は昭和23年に国民の祝日として制定されました。成人式の始まりはその2年前の昭和21年。敗戦後の日本をこれから担う若者たちに対して、励ましたり勇気づけようと開催された「青年祭」が由来と言われています。当初、成人の日は1月15日でした。2000年に制定されたハッピーマンデー制度により、現在の1月の第2月曜日となりました。2025年は1月13日になります。022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げになったことは記憶に新しいと思います。成人のお祝いは、18歳でも20歳でも問題はありません。成人式については、開催時期や対象年齢は、あくまで主催となる市区町村の判断にゆだねられています。備前市は名前を「二十歳の集い」とし、成人の日の一日前の1月12日(日)に、今まで通り20歳を対象に行われる予定です。
・・・さて、18歳での成人で、具体的にどんなことができるでしょうか?
18歳でできることは、
・契約ができるようになる
・親の同意がなくても、クレジットカードやローン、携帯電話、賃貸物件などのさまざまな契約ができるようになります。
・薬剤師、医師免許、公認会計士や司法書士などの国家資格の取得ができるようになります。
・未成年のパスポート有効期限は5年ですが、18歳になると10年間有効のパスポートを取得できます。
・女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳で結婚できるようになりました。
・多様な性別の取り扱いの変更審判を受けることができます。
・親権に服することがなくなるので、進学や就職などの進路を自分の意思でできるようになります。
・所得135万円以下でも個人住民税が課税されることになります。(現在)
・18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされ、選挙権を得ます。ちなみにアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど諸外国でも選挙権は18歳からというのが一般的です。
20歳までできないこと
・飲酒・喫煙、競馬などの公営競技。これらは、健康面への影響や青少年保護の観点から、今まで通り20歳になるまで認められていません。
ステキな成人になれるよう、中学校生活の中でも、市民性(シチズンシップ)や人権意識を高めていきましょうね。
◎日生中は食育に取り組んでいます。
調理場から北川先生が来校されました。(1/10)
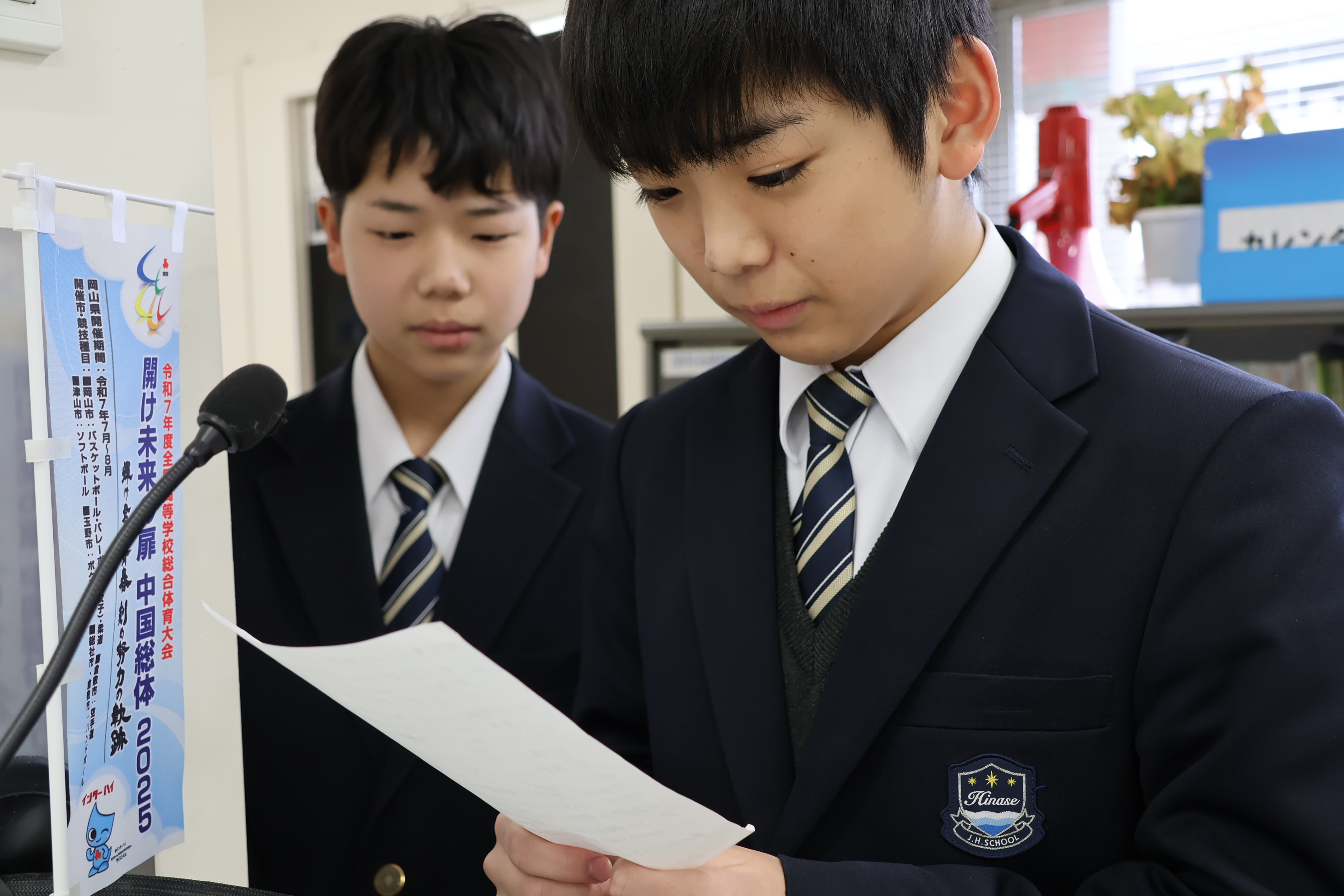
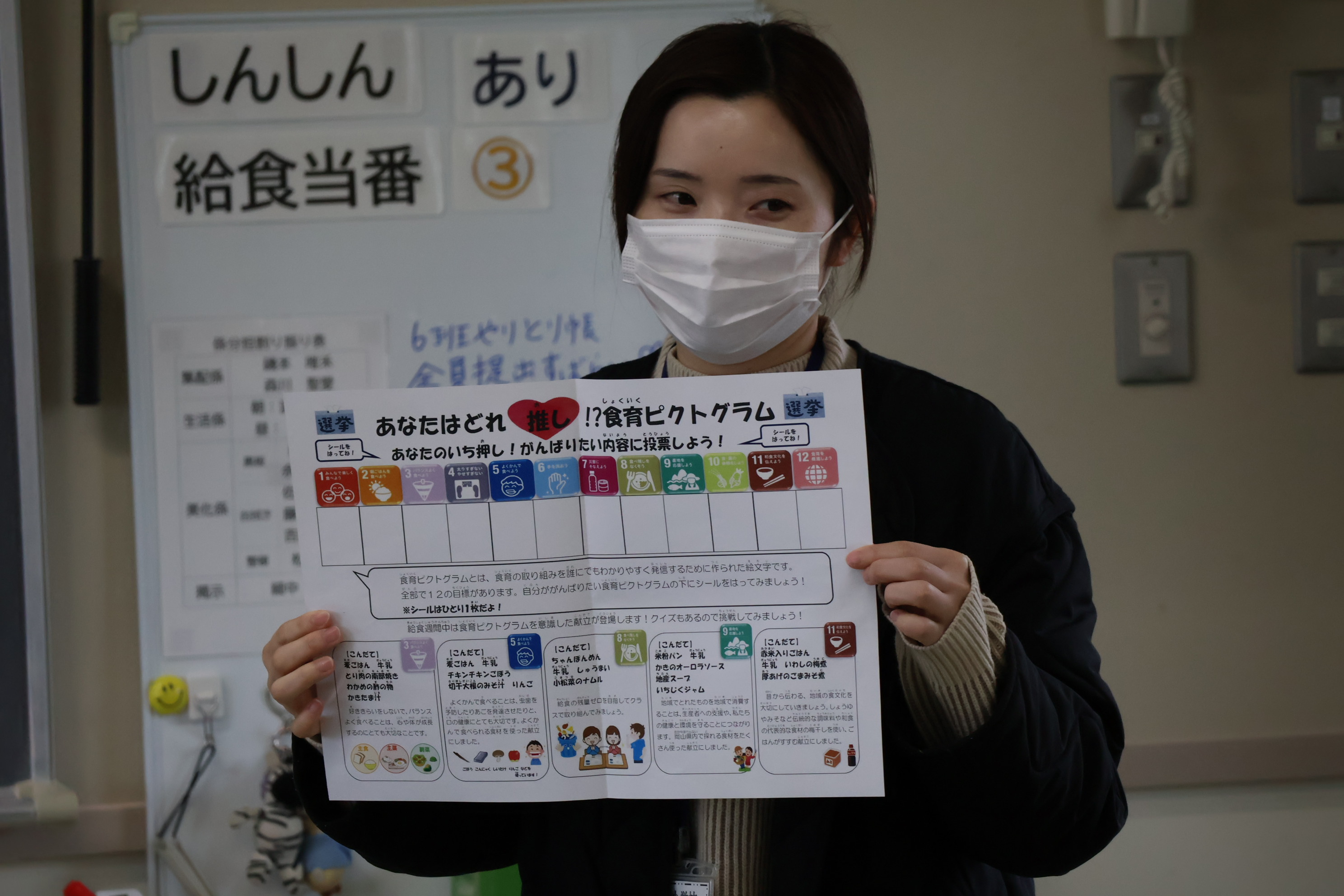

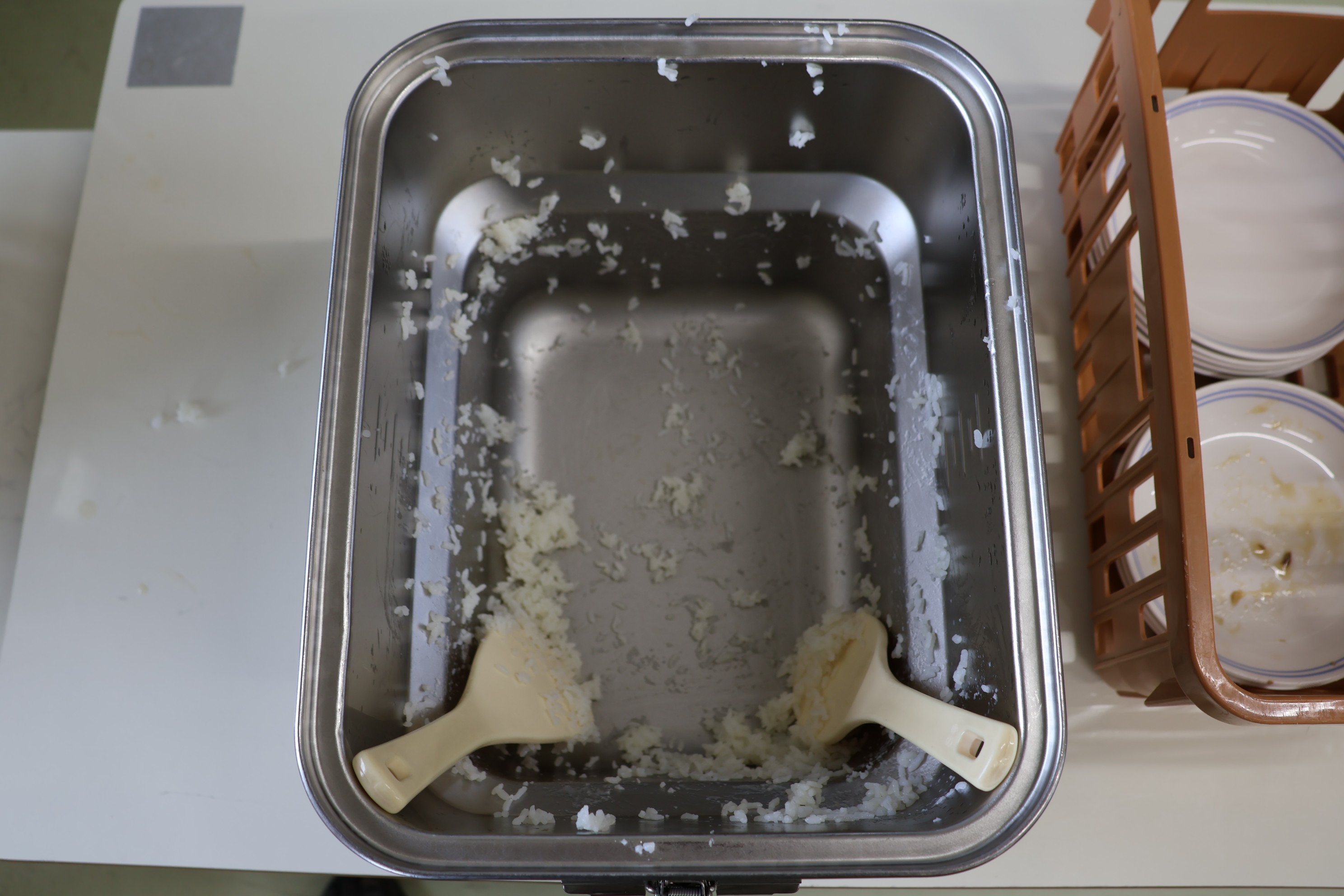
◎疲れてませんか?元気にぼちぼちと!
~七草の節句のころ(1/10)

七草の日とは、1月7日に行われる「人日(じんじつ)の節句」を指します。この日は七草粥を食べて邪気を払い、一年の無病息災を願う日本の伝統行事です。
「人日の節句」は、五節句の一つとして知られています。五節句とは、季節の移り変わりを象徴する一年の中でも重要な5つの節目を指し、それぞれの節句で邪気を払い、健康や幸運を祈る風習があります。他の節句としては、3月3日の「上巳(じょうし)の節句」(ひな祭り)、5月5日の「端午(たんご)の節句」(こどもの日)、7月7日の「七夕(たなばた)の節句」、そして9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」(菊の節句)が挙げられます。それぞれの節句には、健康や長寿、繁栄を願う思いが込められています。七草粥とは、春の七草を細かく刻んで入れたお粥のことです。日本では古くから、七草粥を食べることで長寿や無病息災を願う風習が続いてきました。
現代においては、正月料理で疲れた胃腸を休めるという意味も加わり、より親しまれています。
七草粥の由来
七草粥の文化は中国に由来しています。中国の唐の時代には、1月7日に「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」と呼ばれる7種類の野菜が入ったスープを食べ、無病息災を願う習慣がありました。一方、日本では奈良時代から新芽を摘んで食べることで生命力を取り入れる「若菜摘み」という風習が存在していました。この二つの文化が融合し、七草粥が生まれたとされています。
平安時代には、米や粟など7種類の穀物を用いた「七種粥」が一般的でしたが、鎌倉時代以降になると青菜が取り入れられるようになり、現在の七草粥の形に近づきました。江戸時代には、幕府が「人日の節句」を五節句の一つに定めたことで、七草粥の文化は庶民の間にも広まりました。
「セリ、ナズナ、コギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これぞ七草」と詠まれた和歌にあるように、七草粥にはこれらの七草が使われています。それぞれの草には縁起の良い意味や健康効果が込められており、詳しく解説していきます。
セリ(芹)
セリは、渓流や水辺の日当たりの良い場所に生息する多年草で、香りが強く、食感がさっぱりとしていることが特徴です。健胃や解熱効果があるとされています。セリには「競り勝つ」という意味も込められているそう。
ナズナ(薺)
ナズナはアブラナ科の越年草で、小さなハート型の葉が特徴的で、三味線のバチに似ているため、ペンペン草とも呼ばれます。春には花を咲かせ、若葉はミネラルが豊富です。「なでて汚れを払う」という意味が込められており、解毒作用、利尿作用などがあると言われています。
ゴギョウ(御形)
ゴギョウは、キク科の越年草で、「ハハコグサ」(母子草)とも呼ばれます。道端や田んぼなどの日当たりの良い場所に生育しています。ゴギョウには「仏さまの体」を意味する言い伝えがあり、咳止めや利尿効果があるとされています。
ハコベラ(繁縷)
ハコベラはナデシコ科の野草で、道端や畑に自生します。秋に発芽し越冬することが特徴で、市販されているのは主にコハコベという種類です。柔らかく食べやすく、意味としては「繁栄がはびこる」とされ、縁起の良い草とされています。
ホトケノザ(仏の座)
本来、ホトケノザはシソ科の植物ですが、七草に登場するホトケノザは、実際にはキク科の「コオニタビラコ(小鬼田平子)」という別種です。田んぼやあぜ道など湿地で見かけることが多いです。茎がなく、地面からバラの花びらのように放射状に葉を広げる様子から、仏さまの座る場として見立て「ホトケノザ」と名付けられたそうです。縁起の良い草として親しまれ、食欲増進や歯の痛みに効果が期待できます。
スズナ(菘、鈴菜)
スズナは、実際にはカブのことを指し、冬が旬の根菜です。七草粥では小さなものを使い、葉や根を一緒に食べます。「神さまを呼ぶ鈴」という意味が込められています。整腸作用や消化促進、しもやけなどに効果があるとされています。
スズシロ(蘿蔔)
スズシロはダイコンの古名で、消化を助けるジアスターゼを豊富に含んでいます。ビタミンAも豊富で、七草粥では小さなものを葉と根とともに使用します。「清白」という意味があり、「汚れのない純白」を象徴しています。
◎なんでも相談・まんまるハートへ参加して(1/9)
東備地域自立支援協議会は、障がい者(児)の地域生活を支援し、自立と社会参画を促進するため、地域における障がい者等への支援体制の整備に関して中心的な役割を果たす場所であるとともに、障害者総合支援法の円滑な推進を図ることを目的として、備前市・和気町で共同して設置しています。 同協議会は、4部会・2連絡会で構成(令和6年6月1日現在)されており、各種事業や啓発活動等に取り組んでいます。その中の子ども部会では発達等に関することについて、協議・企画運営を行っています。
この日は、「なんでも相談・まんまるハート」(お子様の発達が気になる保護者の方を対象とし、学習の場や相談会)が開かれ、本校の教頭が参加し、中学校での生活や進路情報についての情報共有と意見交流ができました。学習会の案内等は自立支援協議会で検索を(^_^)。

◎厳冬も仲間と共に(1/9)
上の雪
さむかろな。
つめたい月がさしていて。
下の雪
重かろな。
何百人ものせていて。
中の雪
さみしかろな。
空も地面じべたもみえないで。 金子みすゞ



◎ストレスとうまくつきあおう Presents byやまちゃん先生(1/8)
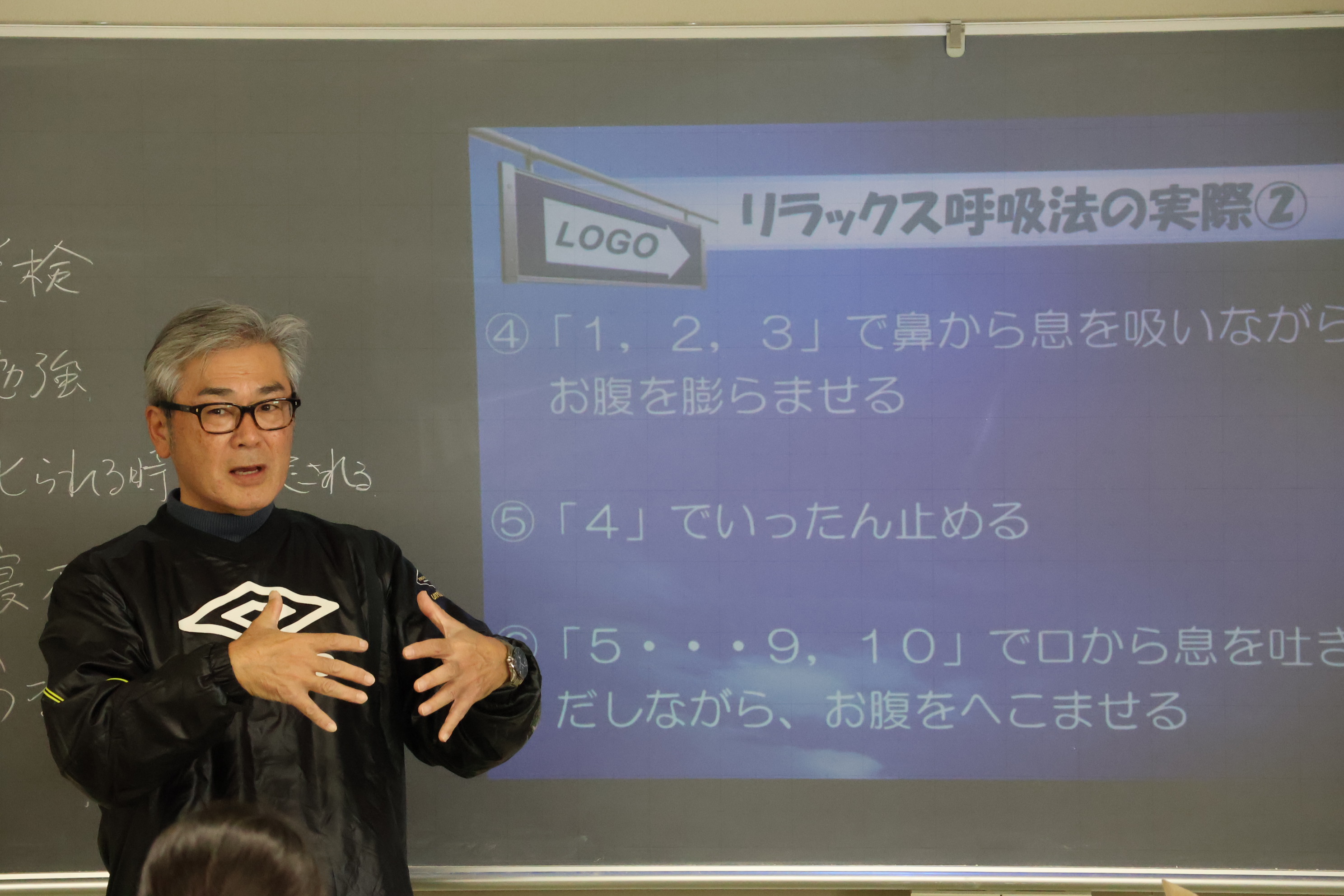
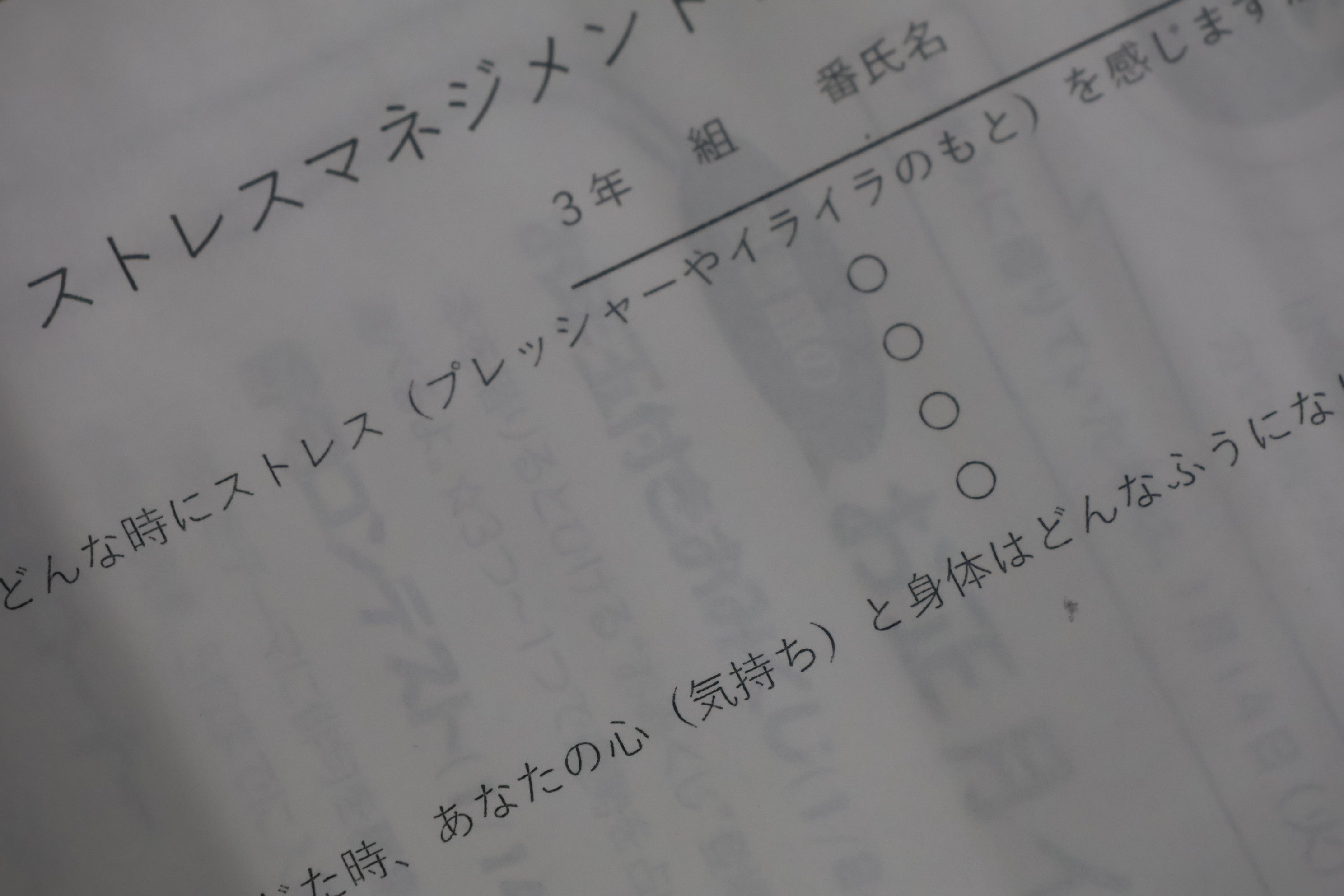




◎インフルエンザ警報発令中〈12/26→〉
岡山県では、2024年11月21日に『インフルエンザ注意報』を発令し、注意喚起を図ってきたところですが、第51週(12月16日から12月22日)には県全体の定点あたり報告数が31.95人となり、インフルエンザ警報発令基準の30.00人を上回りました。
流行時期等から今後も流行拡大の可能性があるため、岡山県は12月26日に『インフルエンザ警報』を発令し、さらなる注意喚起を図っています。
本校でも、流行のため急拡大する心配があるため、感染防止策の徹底、予防接種等、感染予防・感染対策を引き続きお願いします。

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-115995.html(岡山県HP)
◎ひな中の風(1/7:1月の十二景)
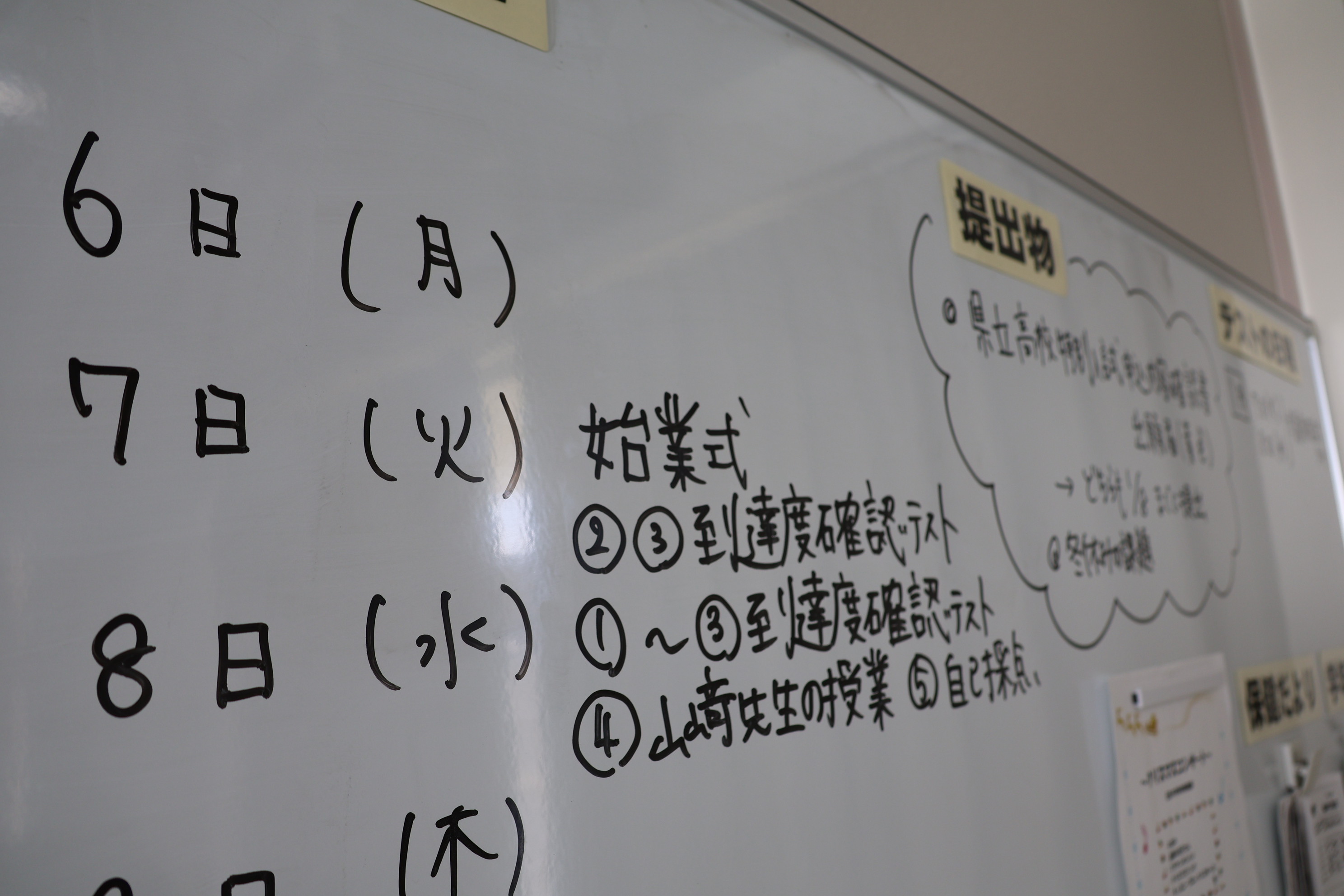
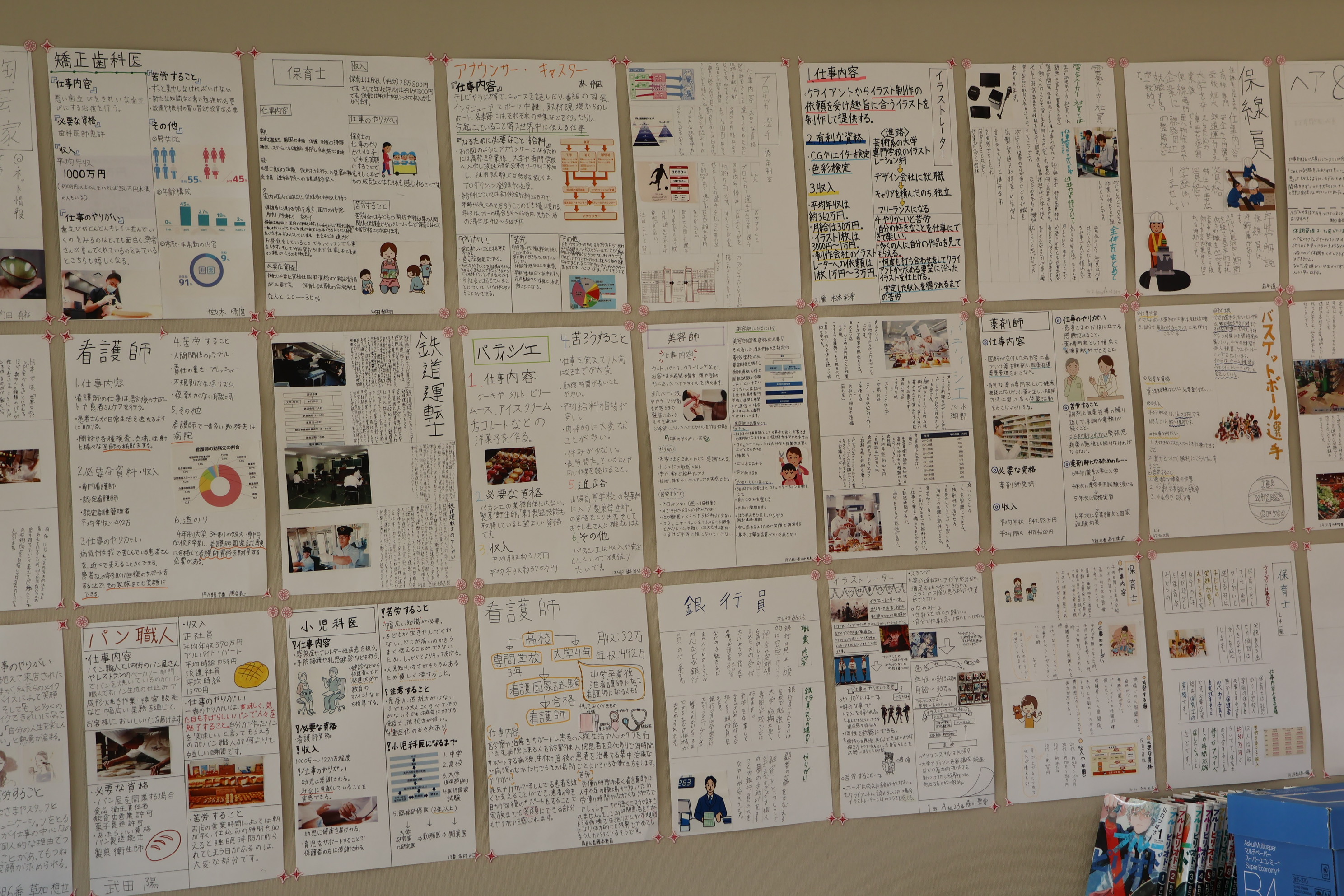
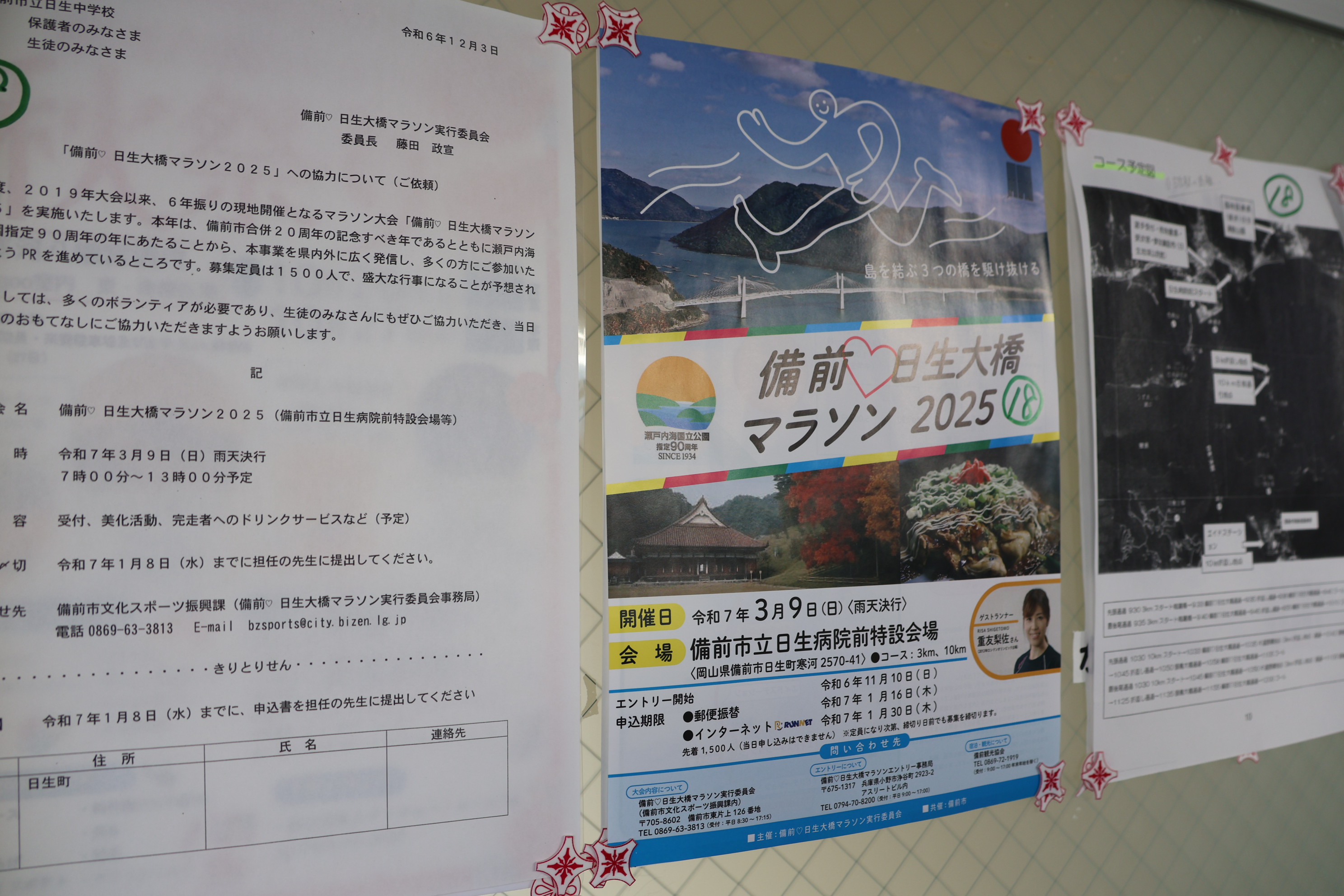
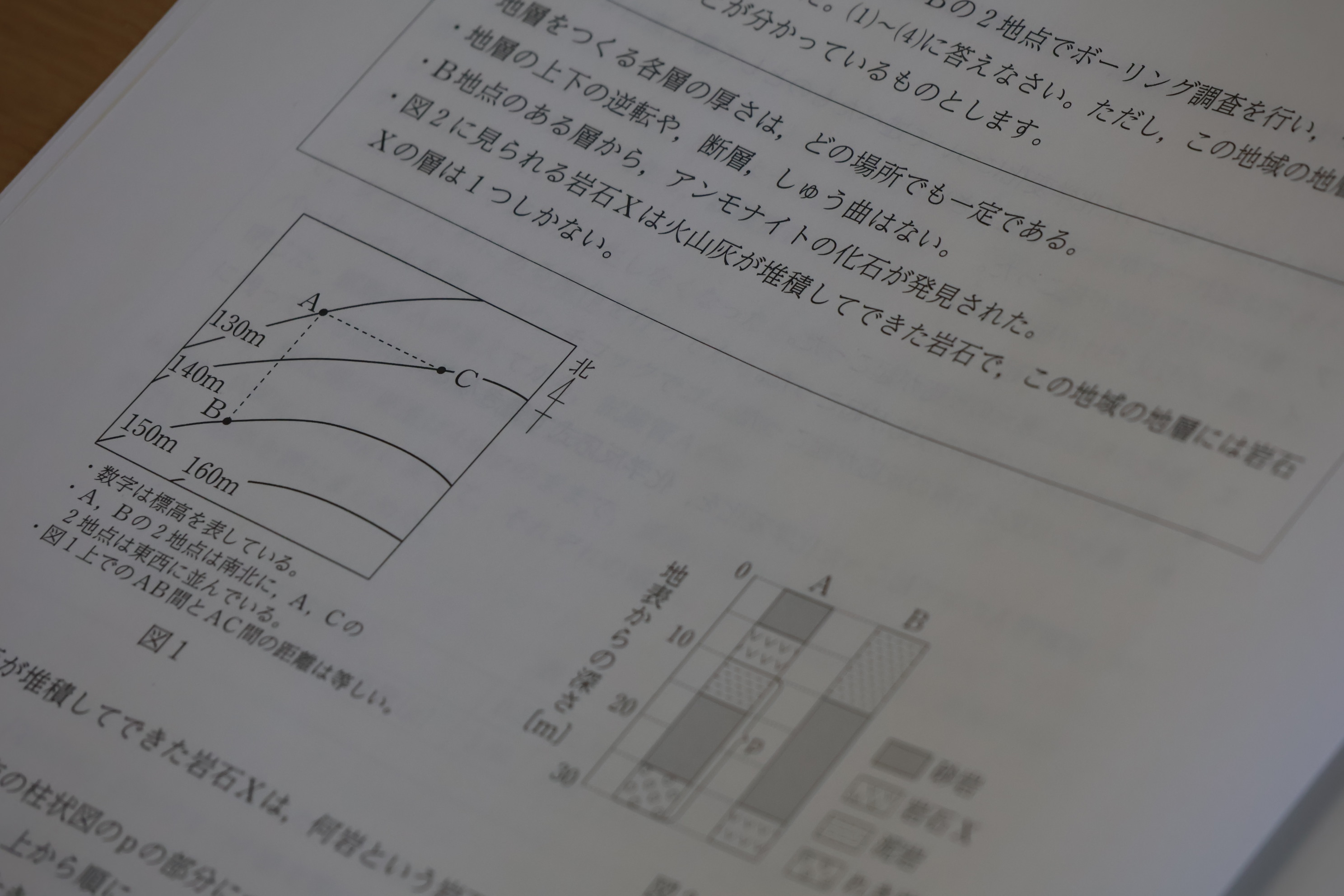
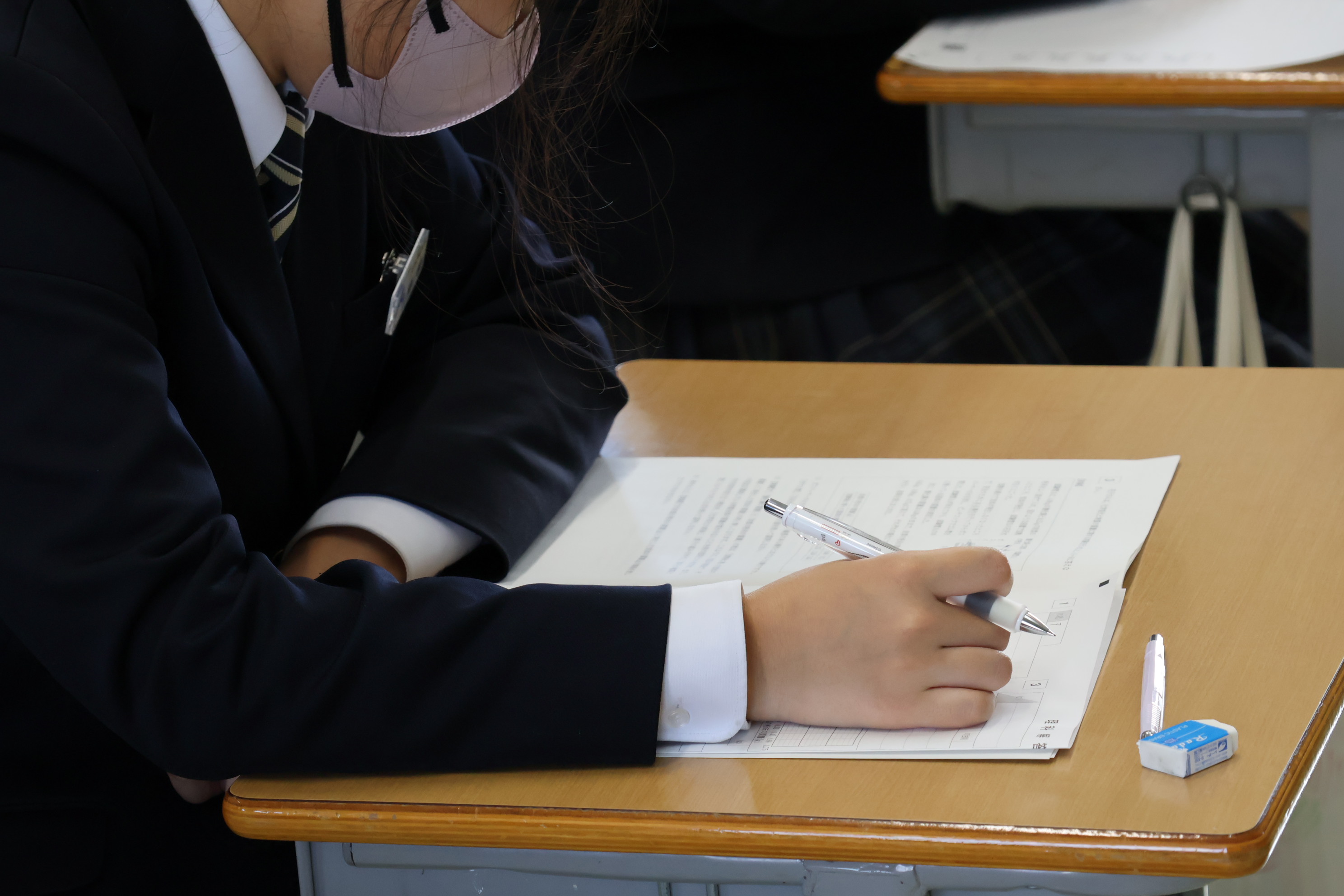

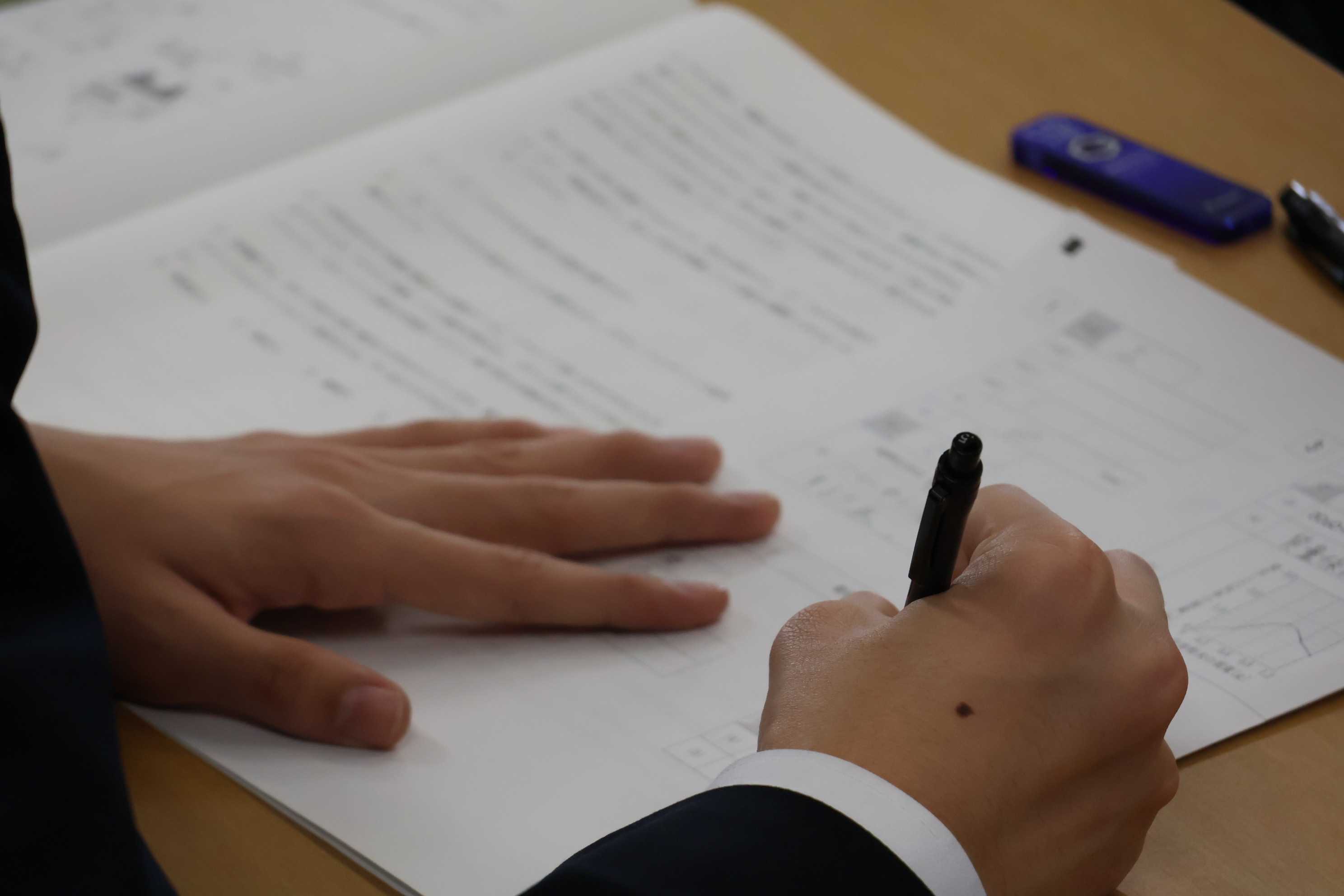

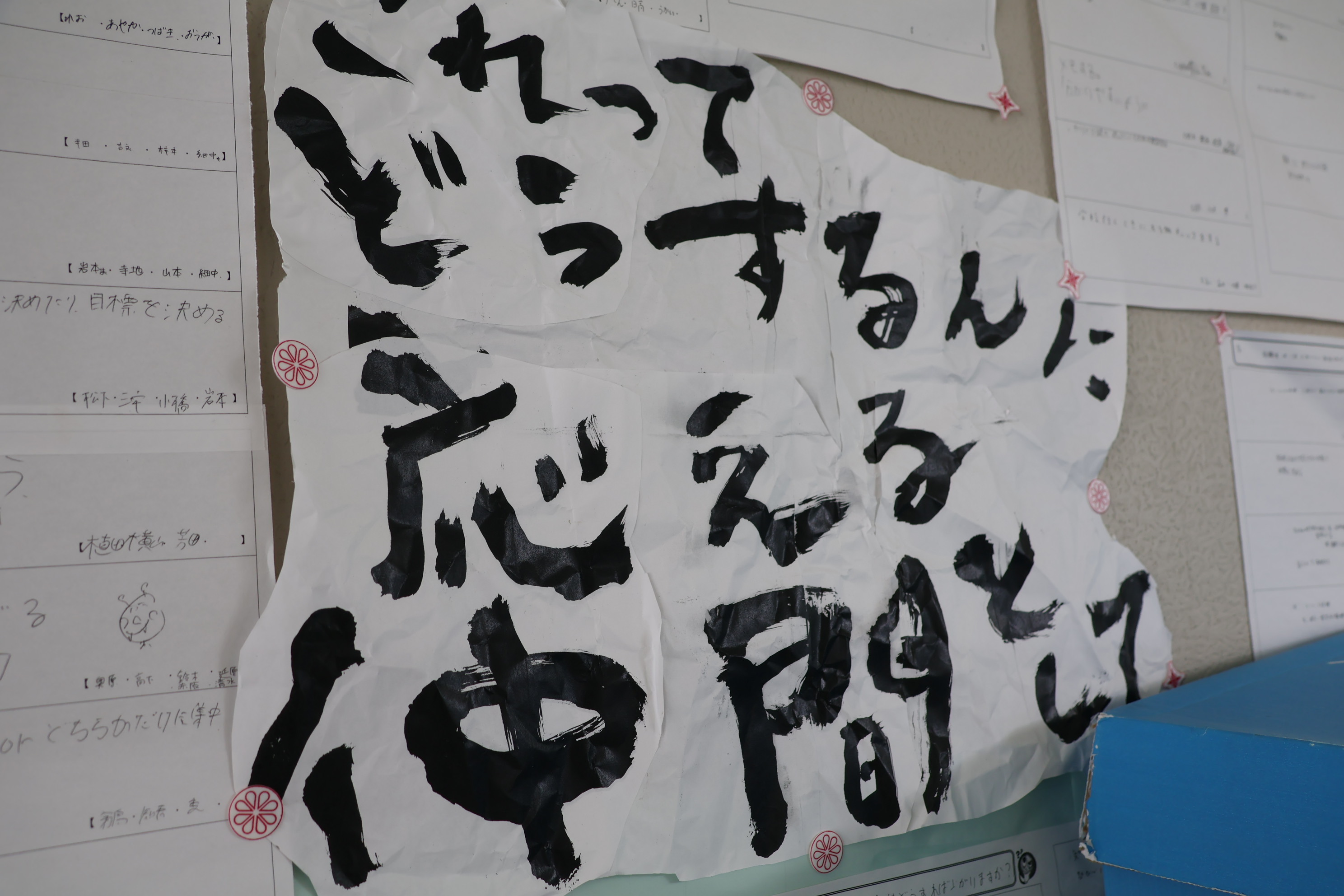

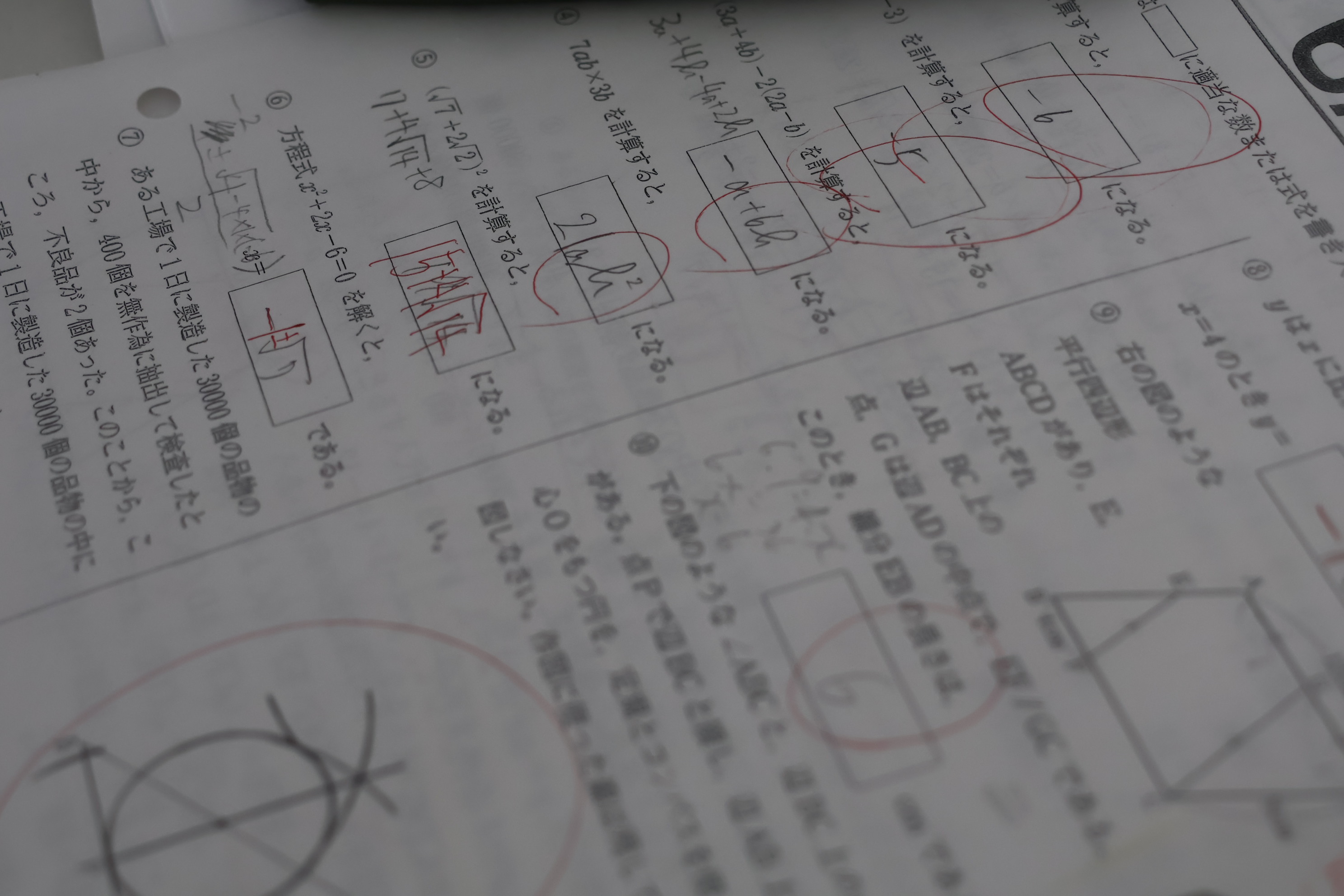

◎うったて(1/7:三学期始業式)





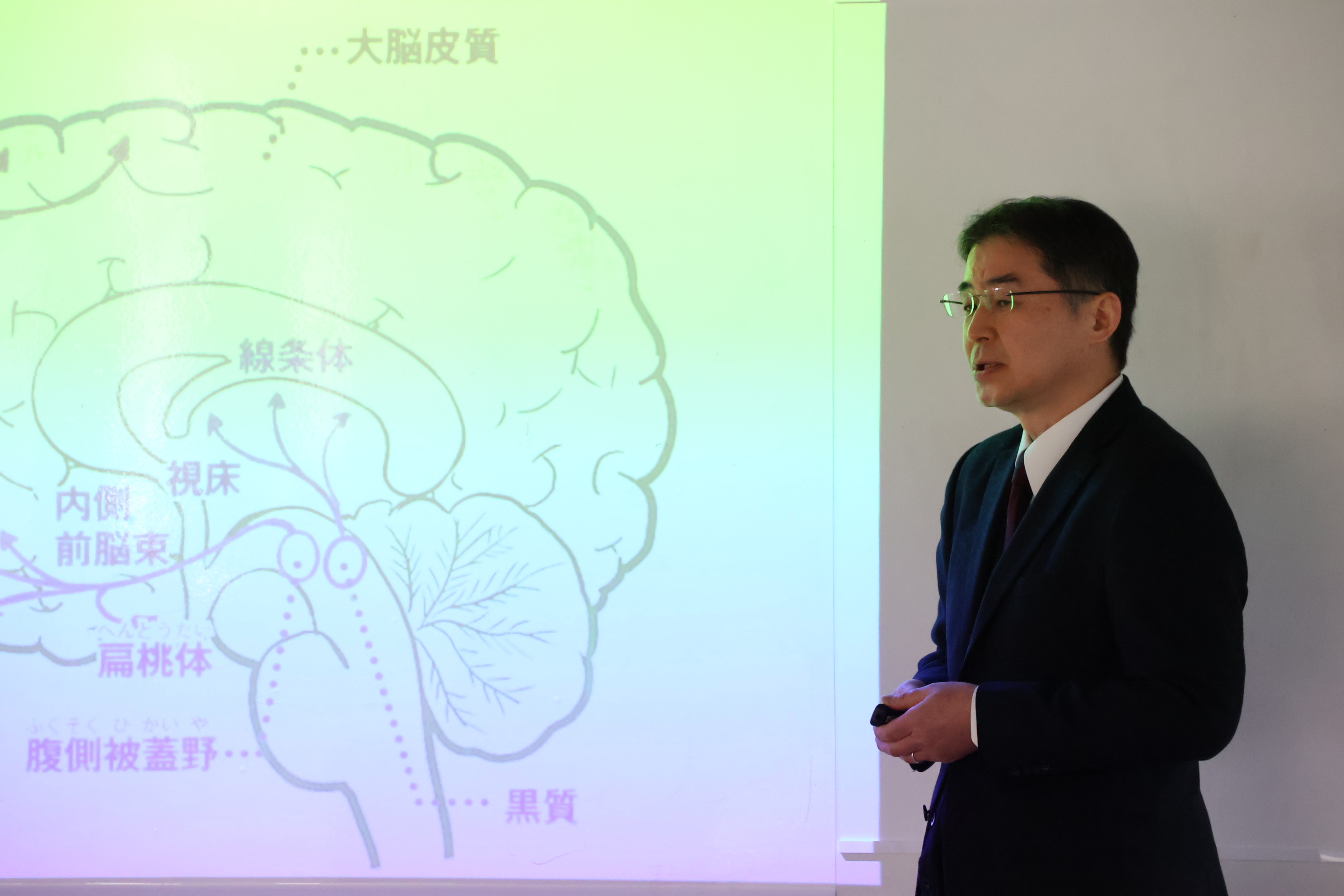
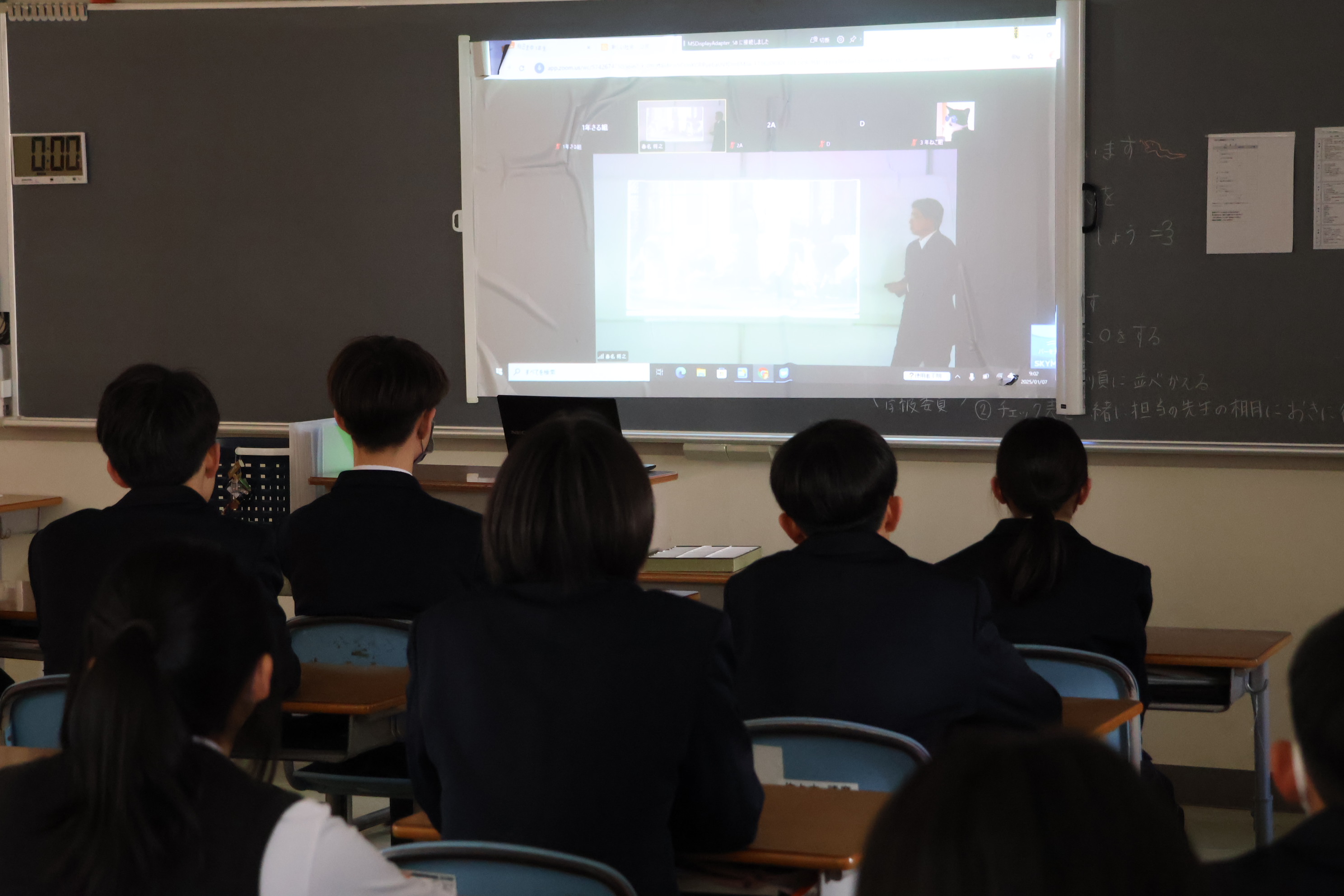
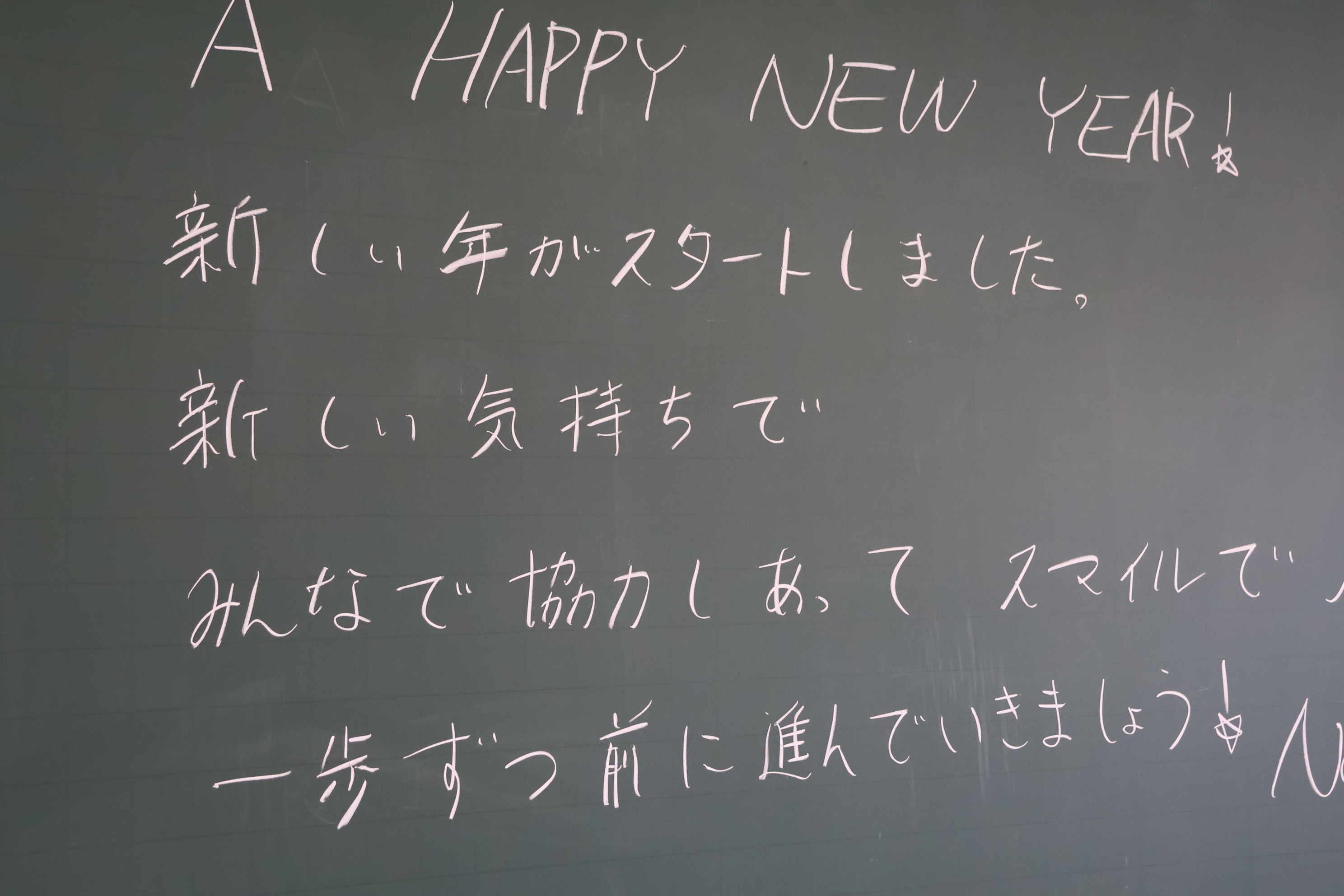
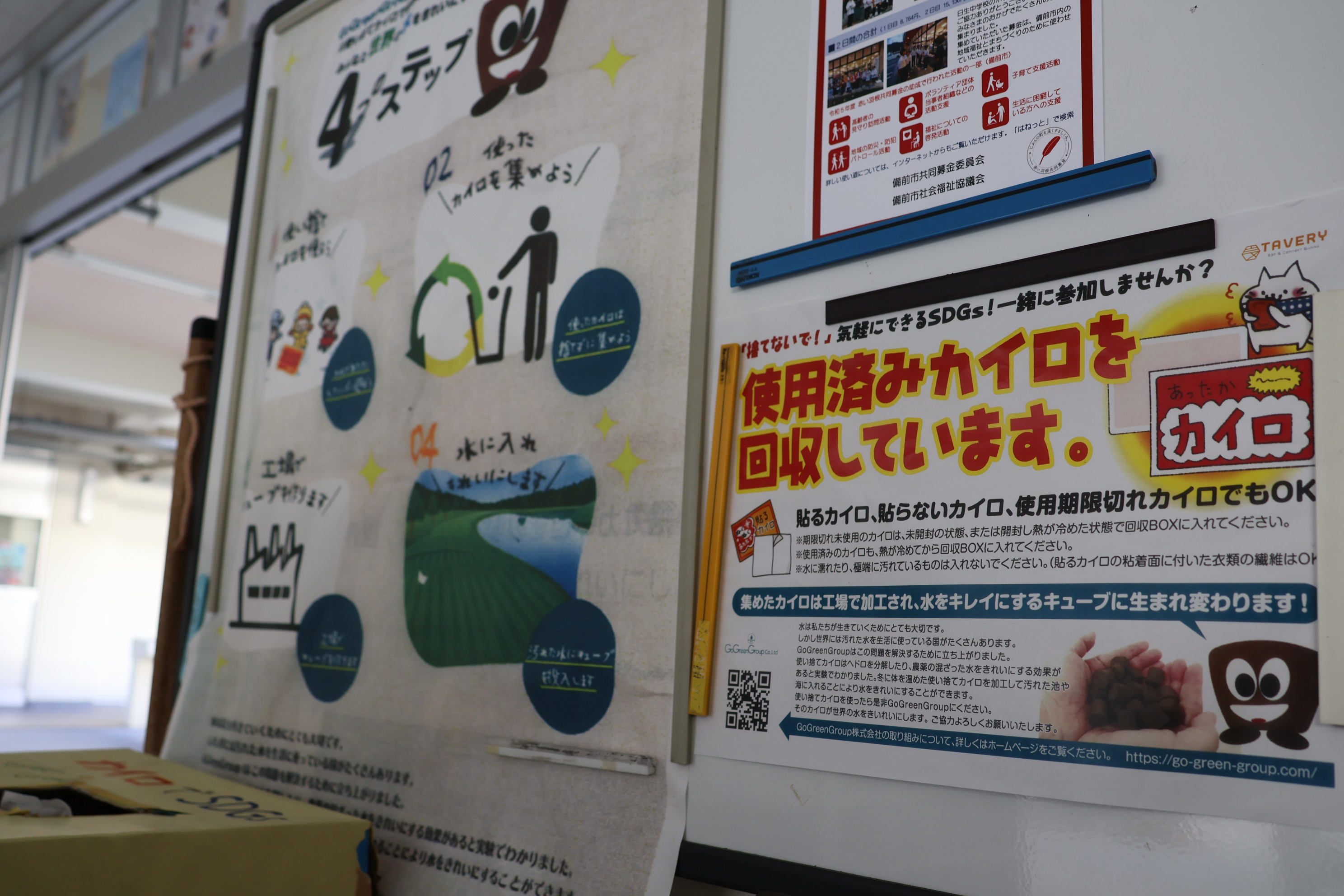
◎2025 仲間と共によい年にしようね。(1/6)

〈空の咽喉にカシオペア座は引つかかり 明日から早寝早起きをせむ 石川美南〉
◎べらぼう!開催中 備前市小・中学校美術展覧会(~1/6:市役所)
The best color in the whole world is the one that looks good on you. Coco Chanel
(全世界で最高の色というのは、あなたに似合う色だ。)
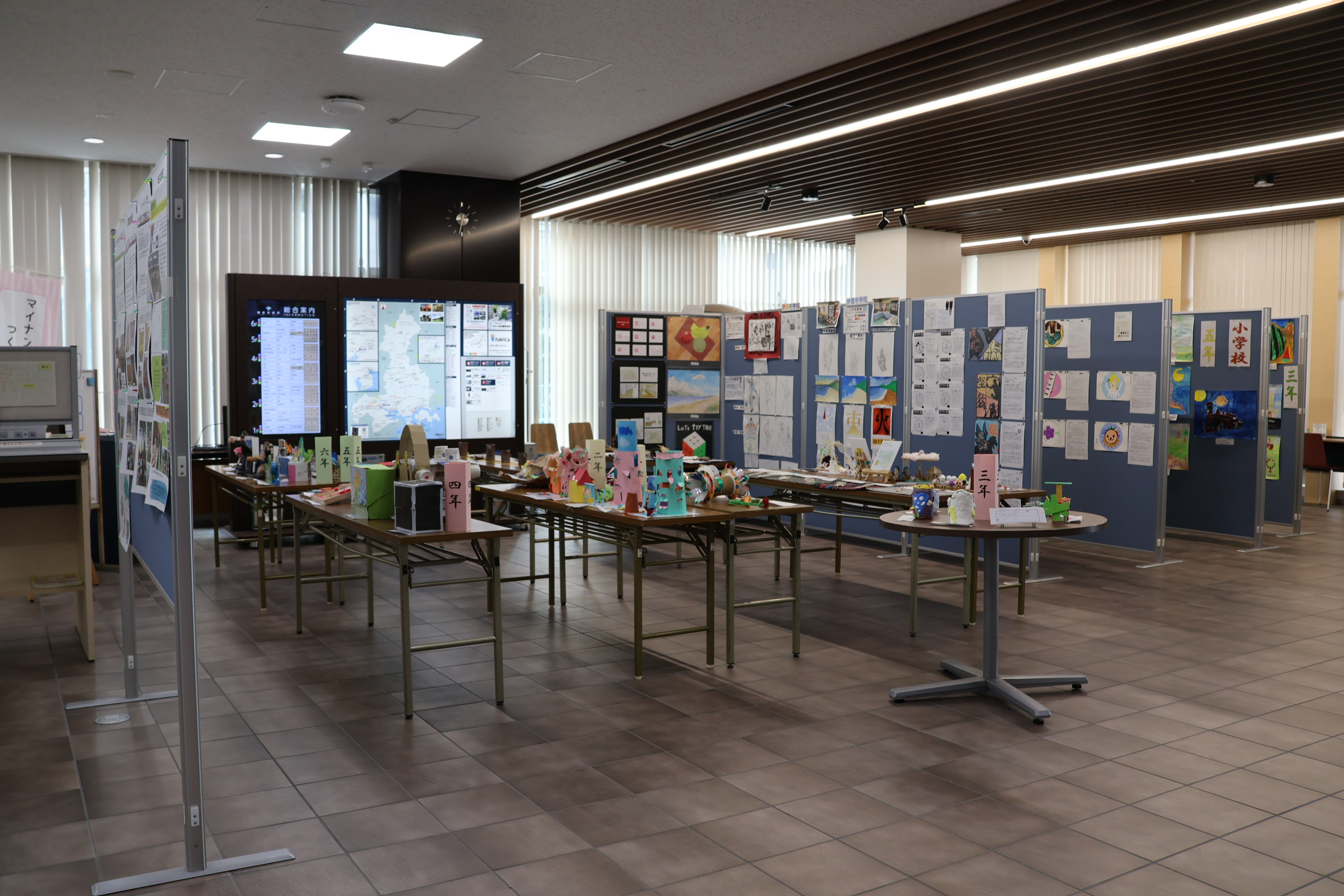
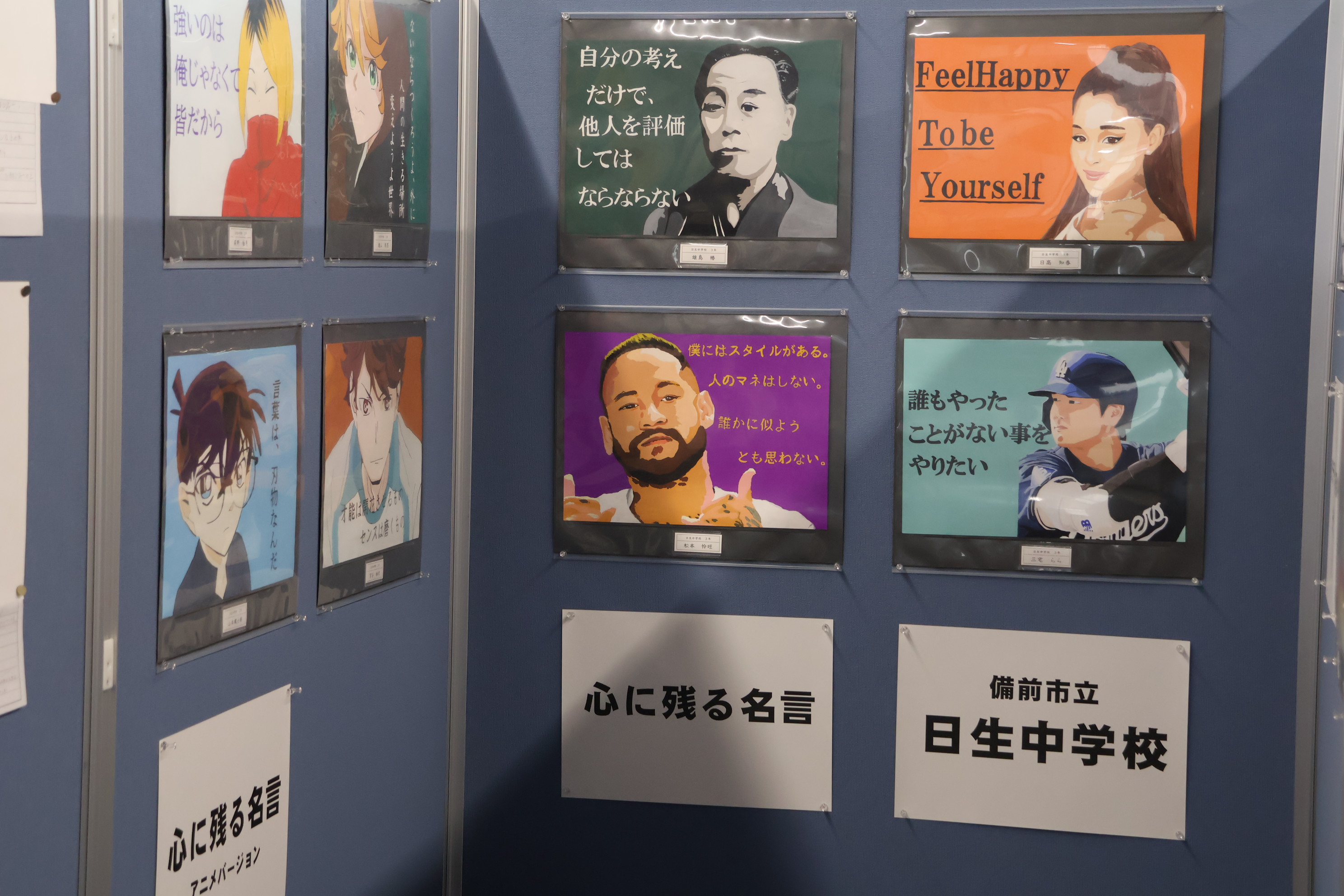
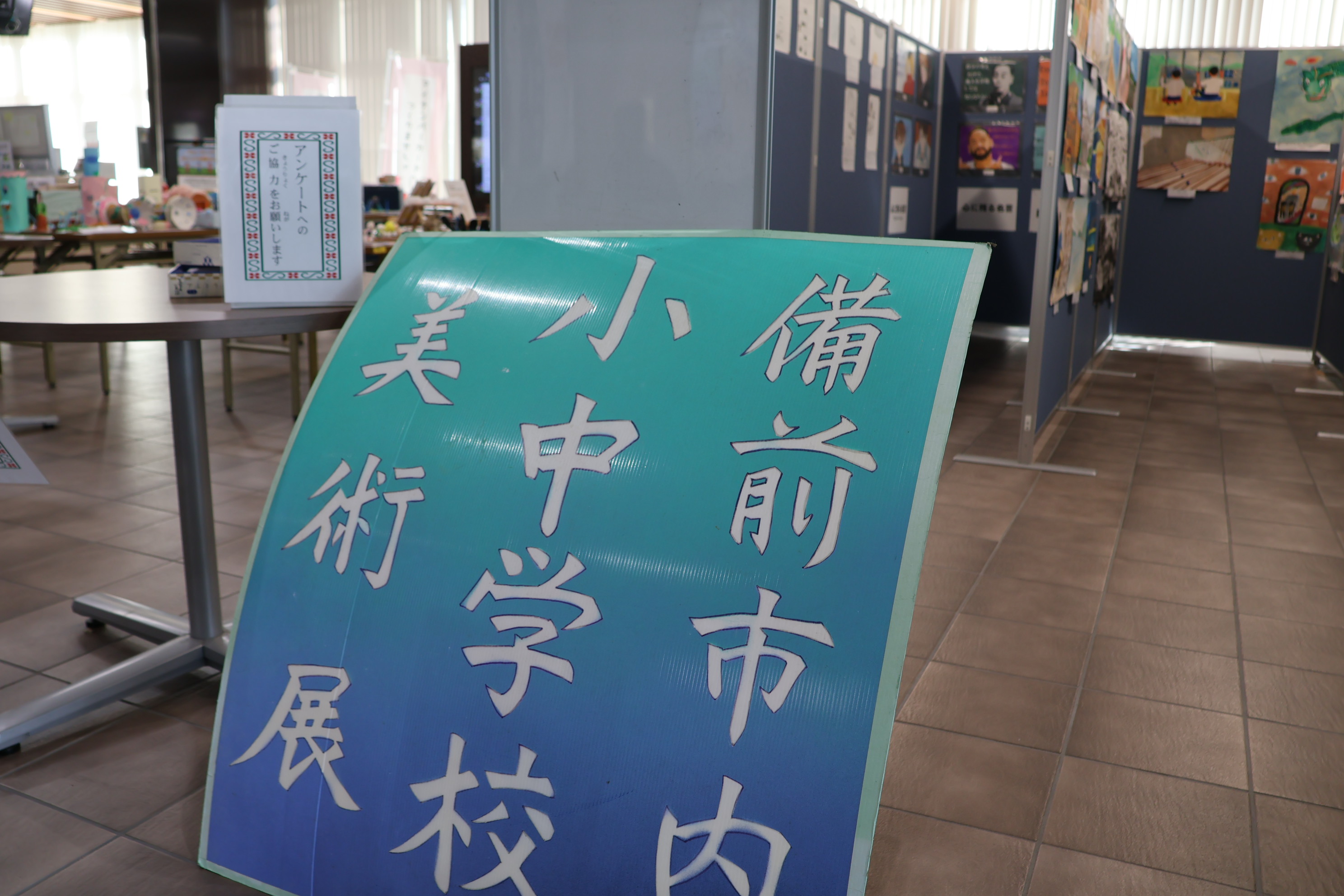
◎今年も多くの人に支えられて(12/26)



理科室に新しいイスをいれて頂きました。ありがとうございました。
◎陽はまたのぼる(12/25)
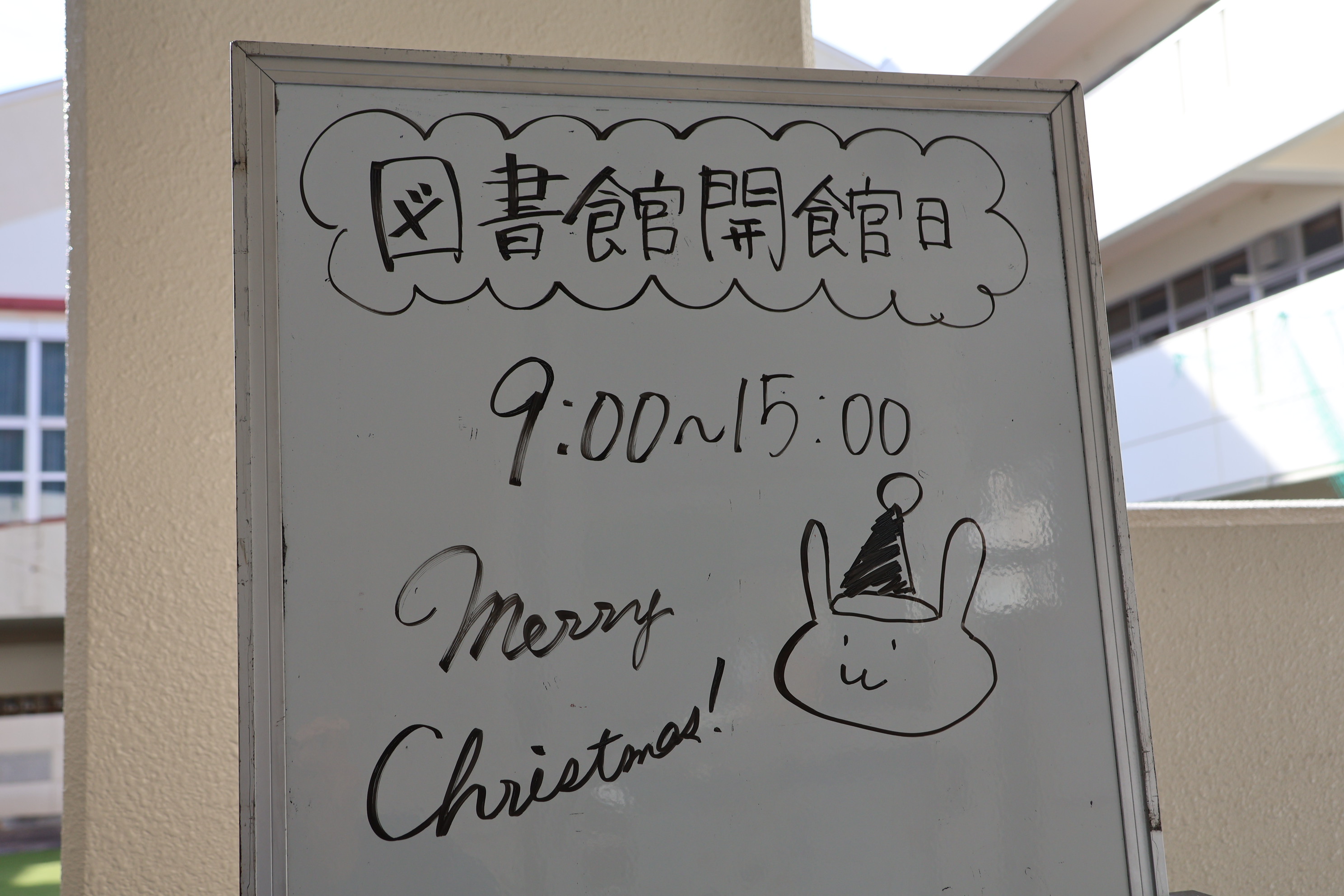
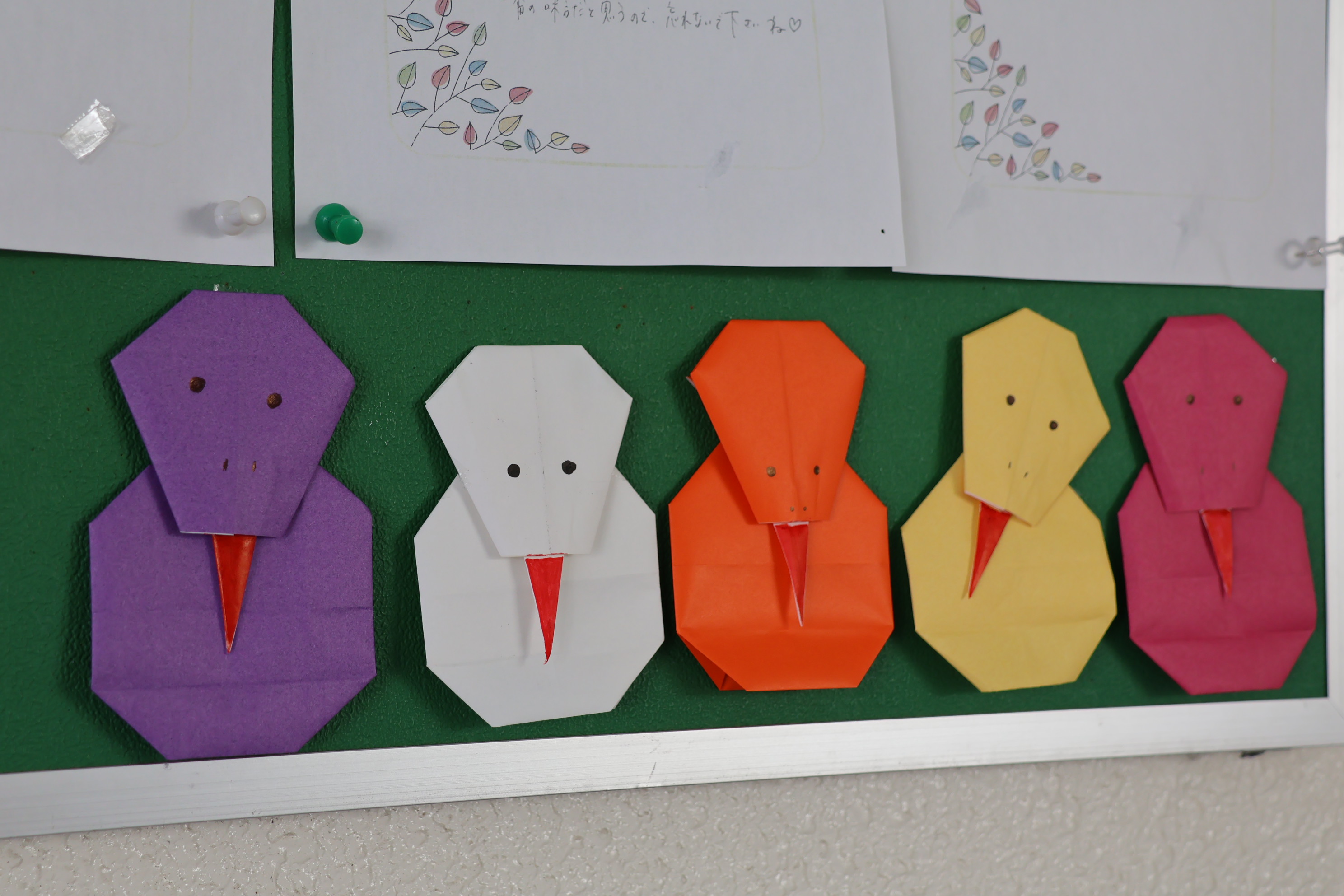

◎今日までの経験が 未来へのチケットだ
Coming Soon
君も僕もチャンスは平等 自分を信じて♪(12/25)
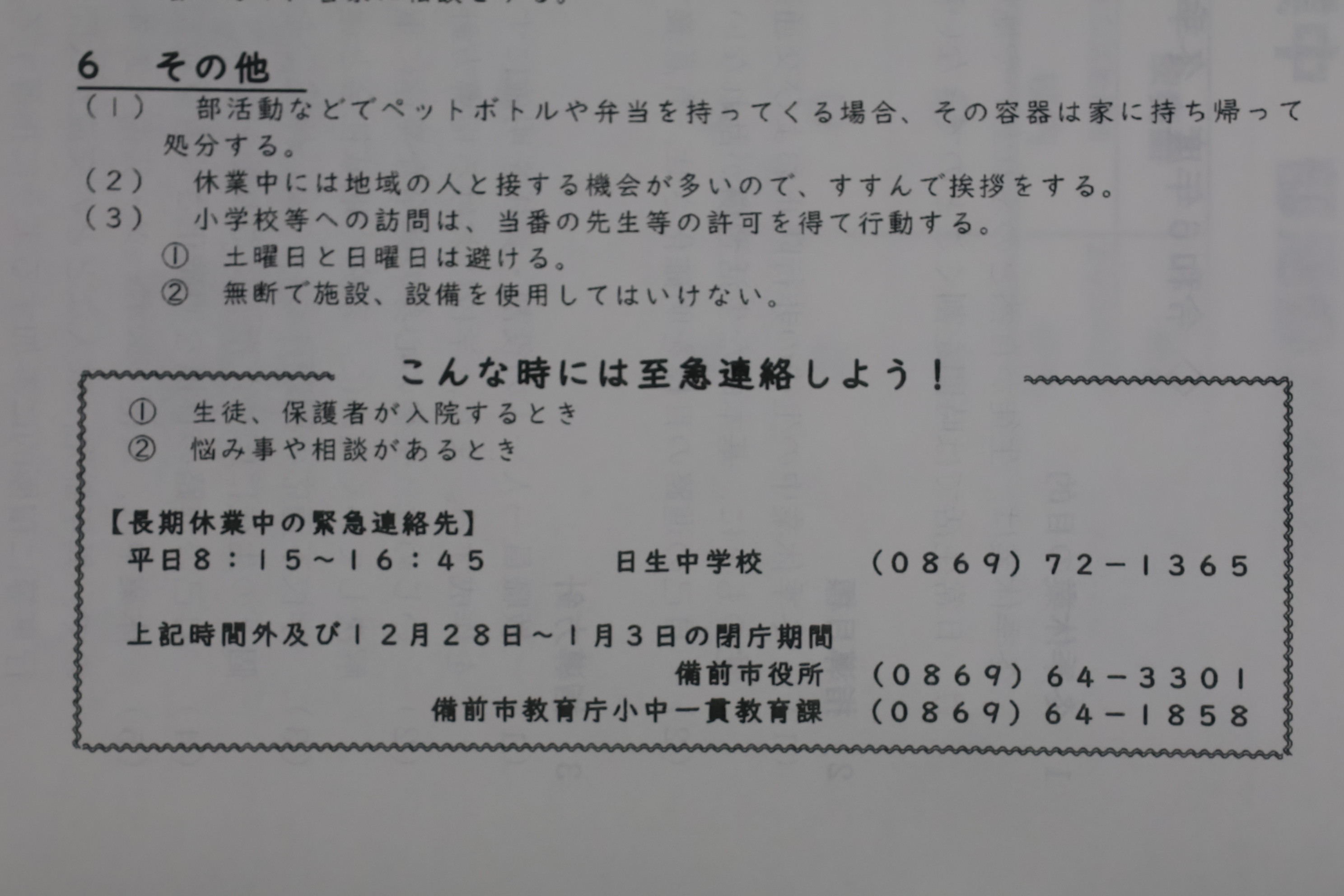
〈さようなら さようなら また会いましょう また別れたら また会いましょう〉枡野浩一(12/24)
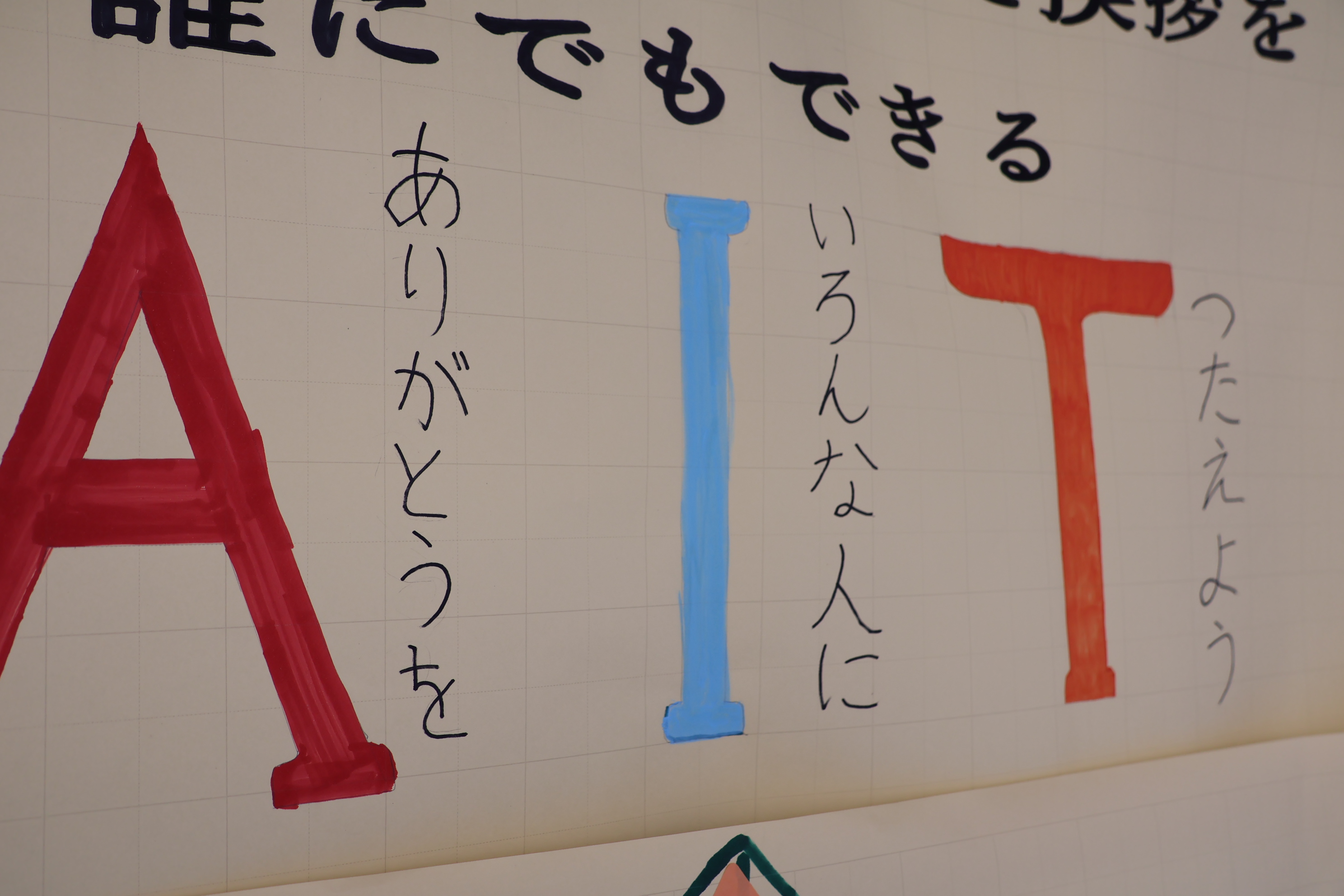


◎教育公務員として、社会から信頼される行動を。
24日は、全教職員でコンプライアンス研修に取り組みました。

◎私たちのまちだから 川東地区の皆さんと共に
~生徒会清掃ボランティア活動(12/24)






社会福祉協議会の嶋村さんより、赤い羽根共同募金(パオーネでの2日間の募金活動:23‚900円)の報告を受けました。
◎仲間と共に よい年を迎えよう
吹奏楽部クリスマスコンサートへようこそ♬(12/24)



◎仲間と共に よい年を迎えよう✨。(12/24)
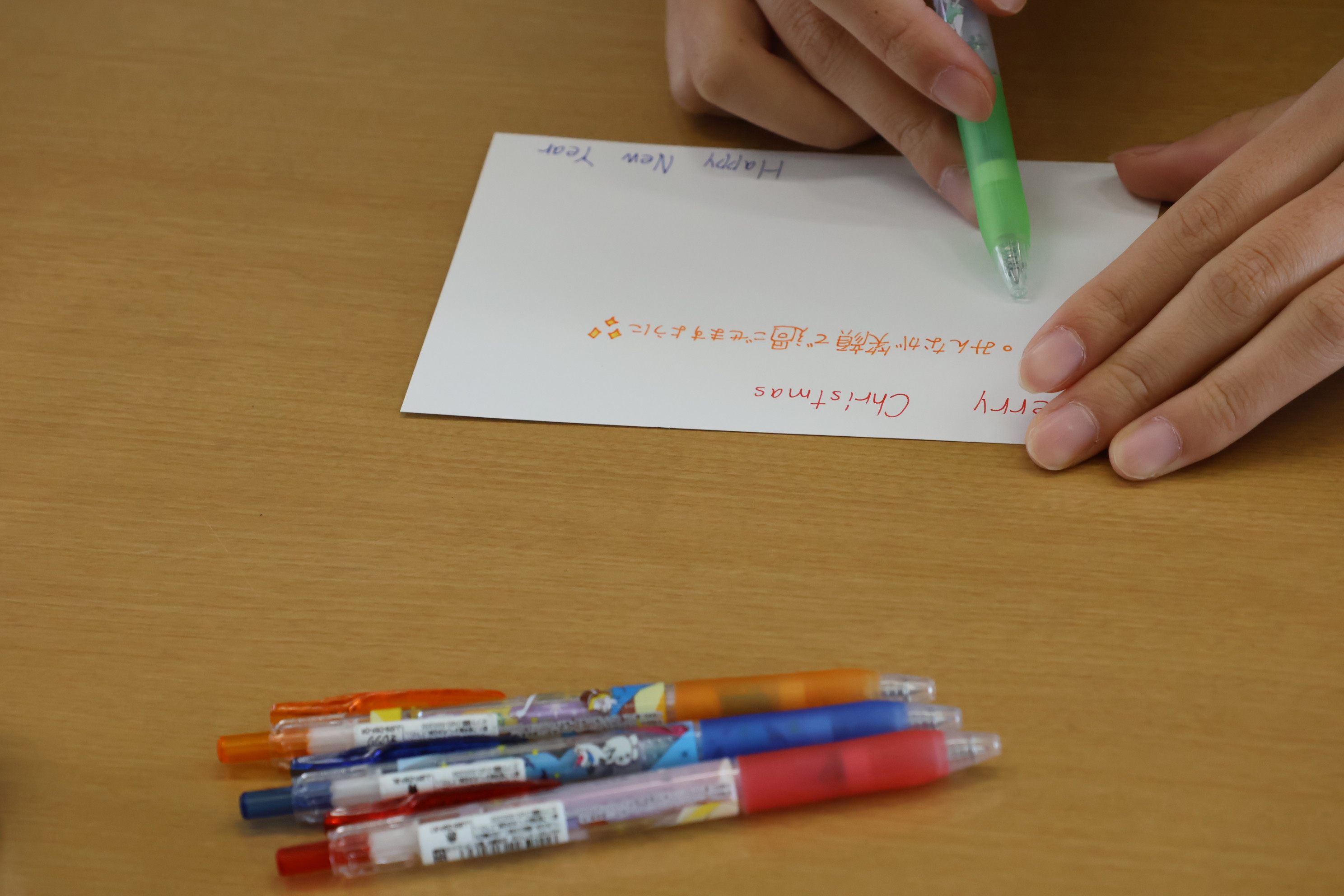
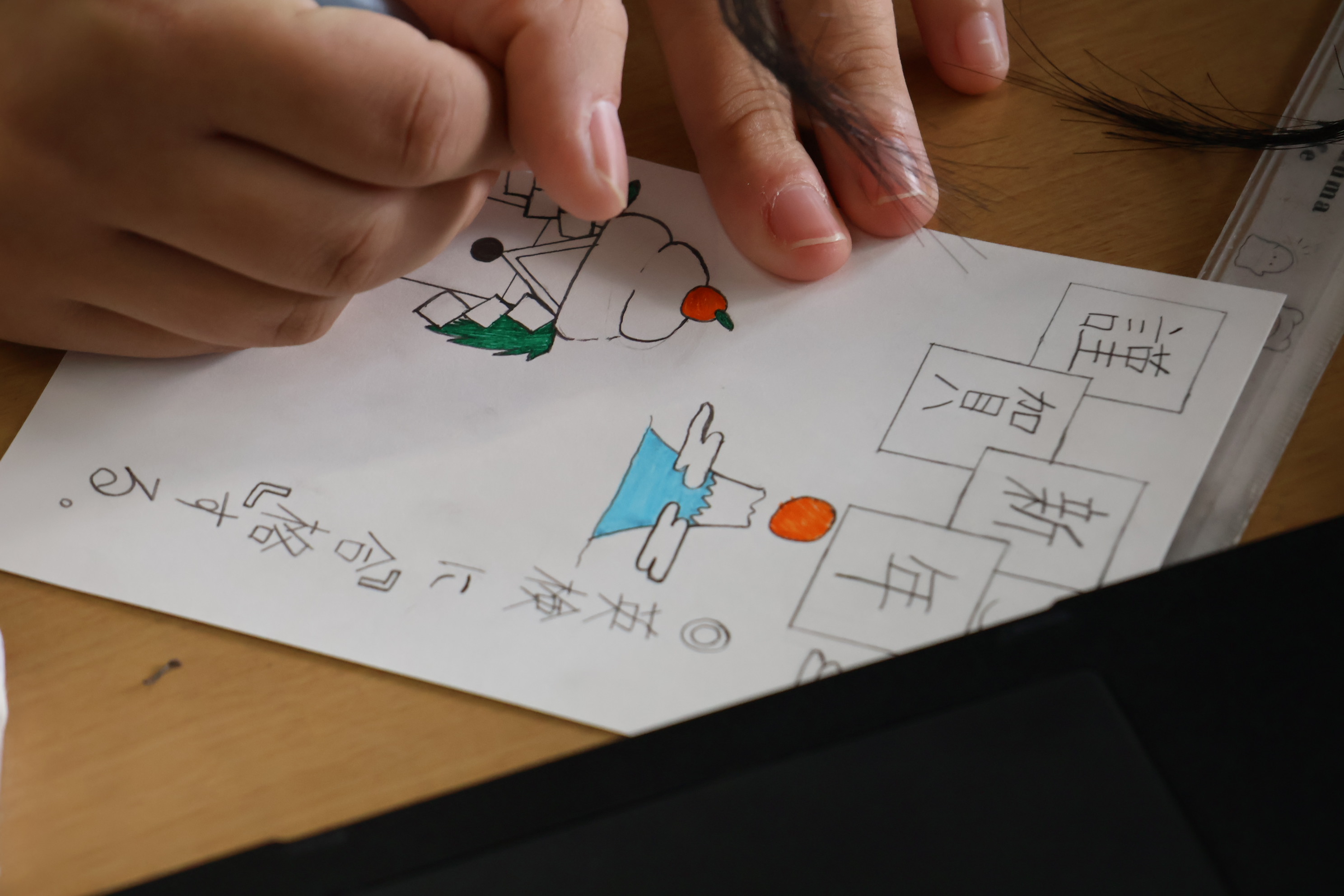

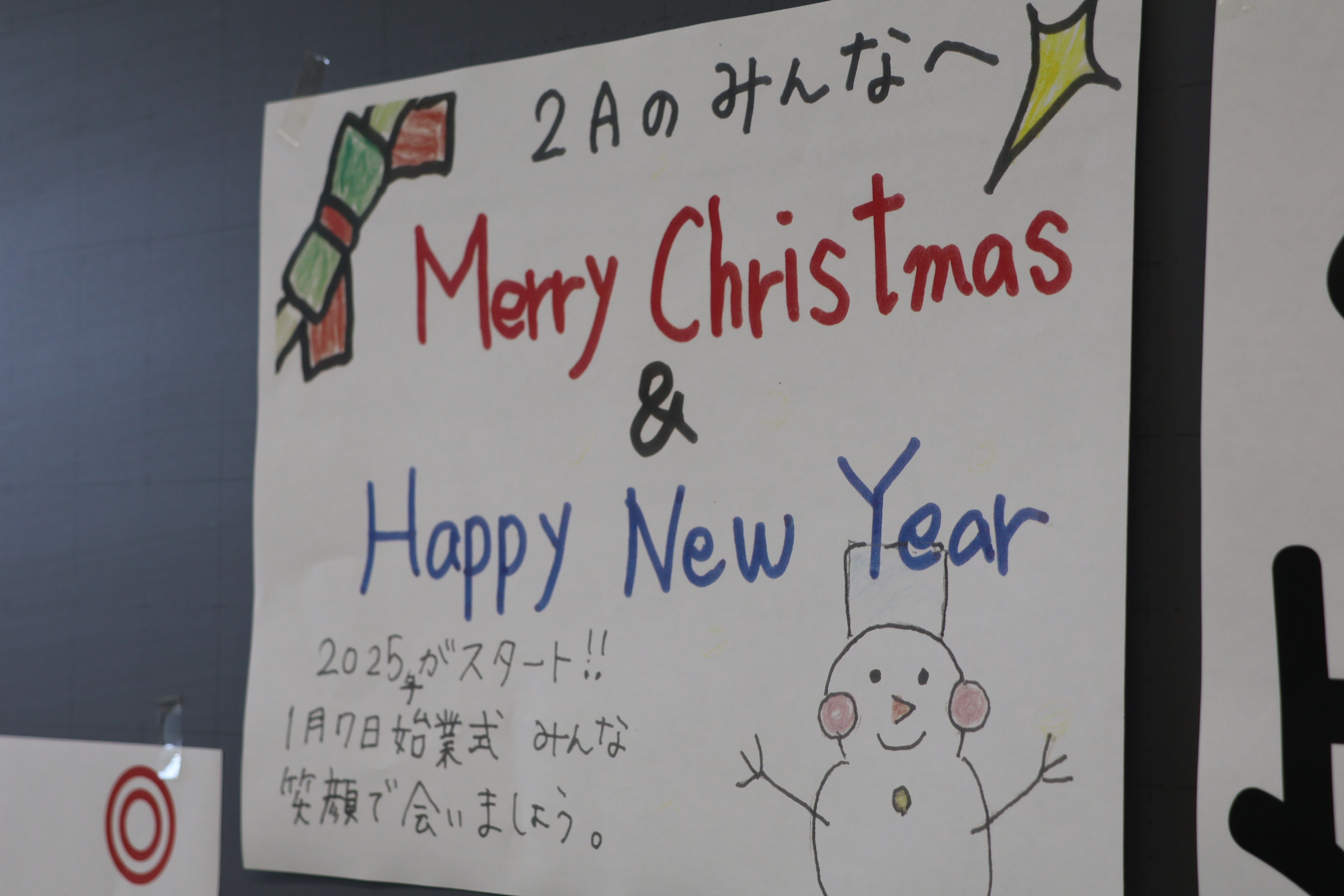
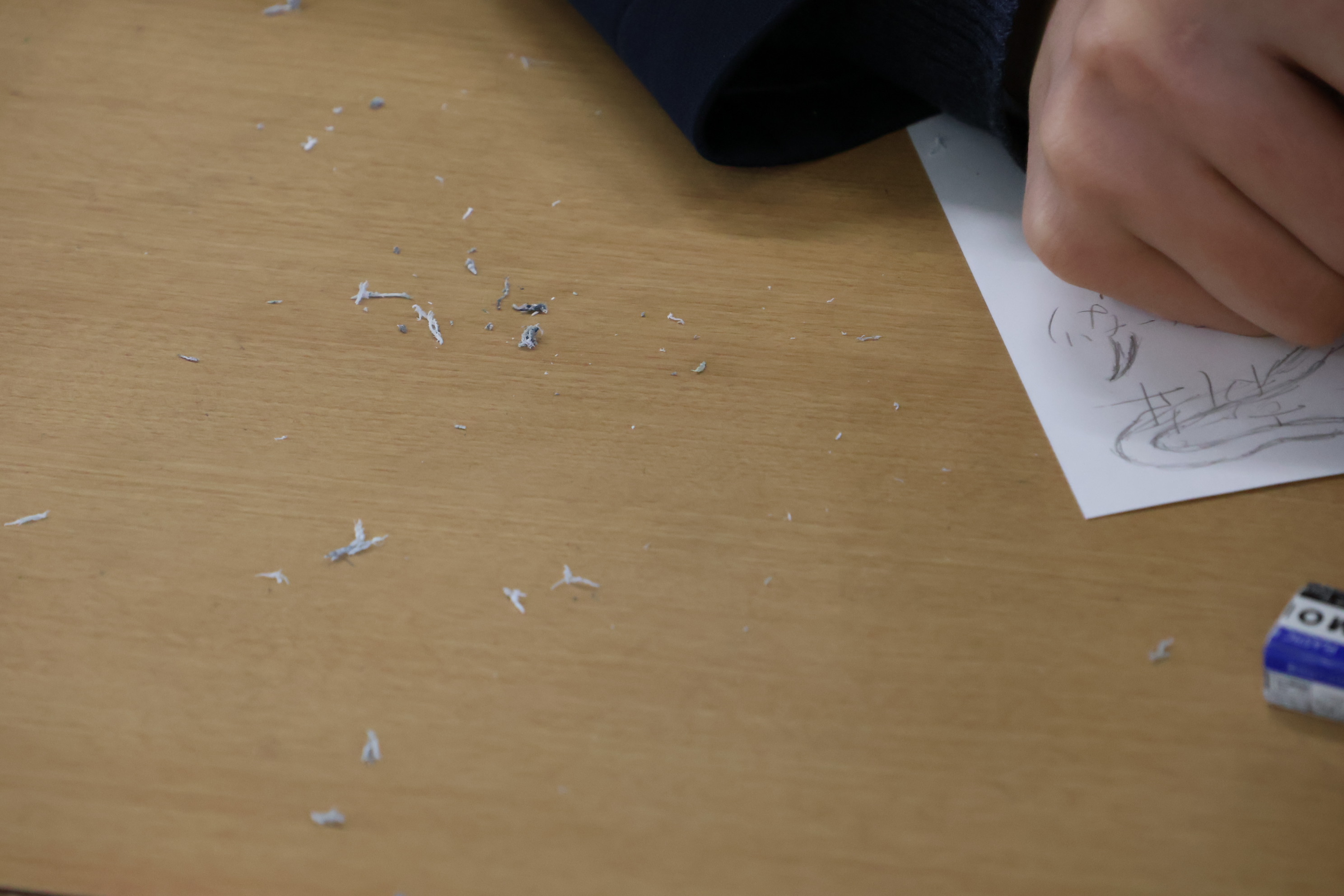
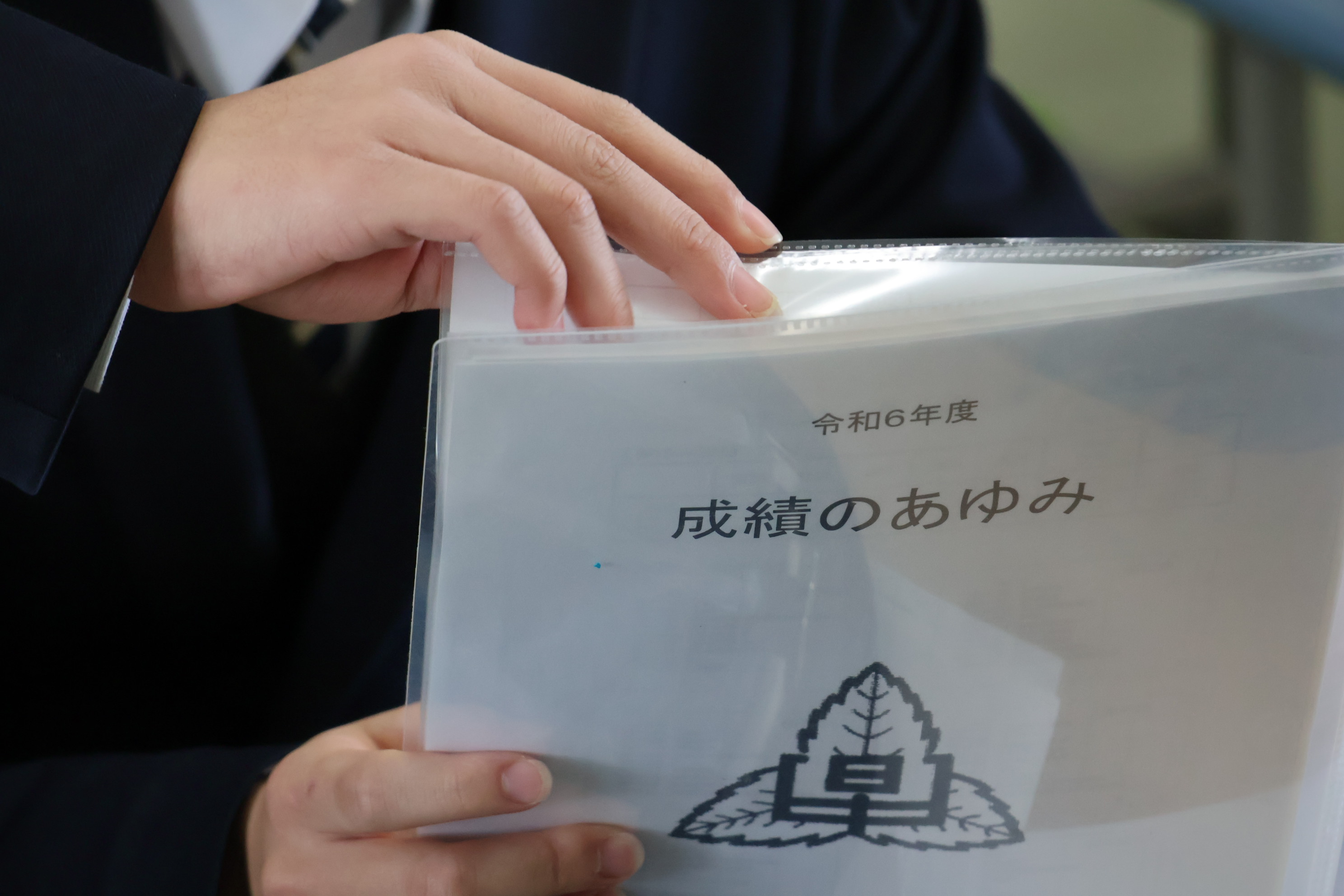
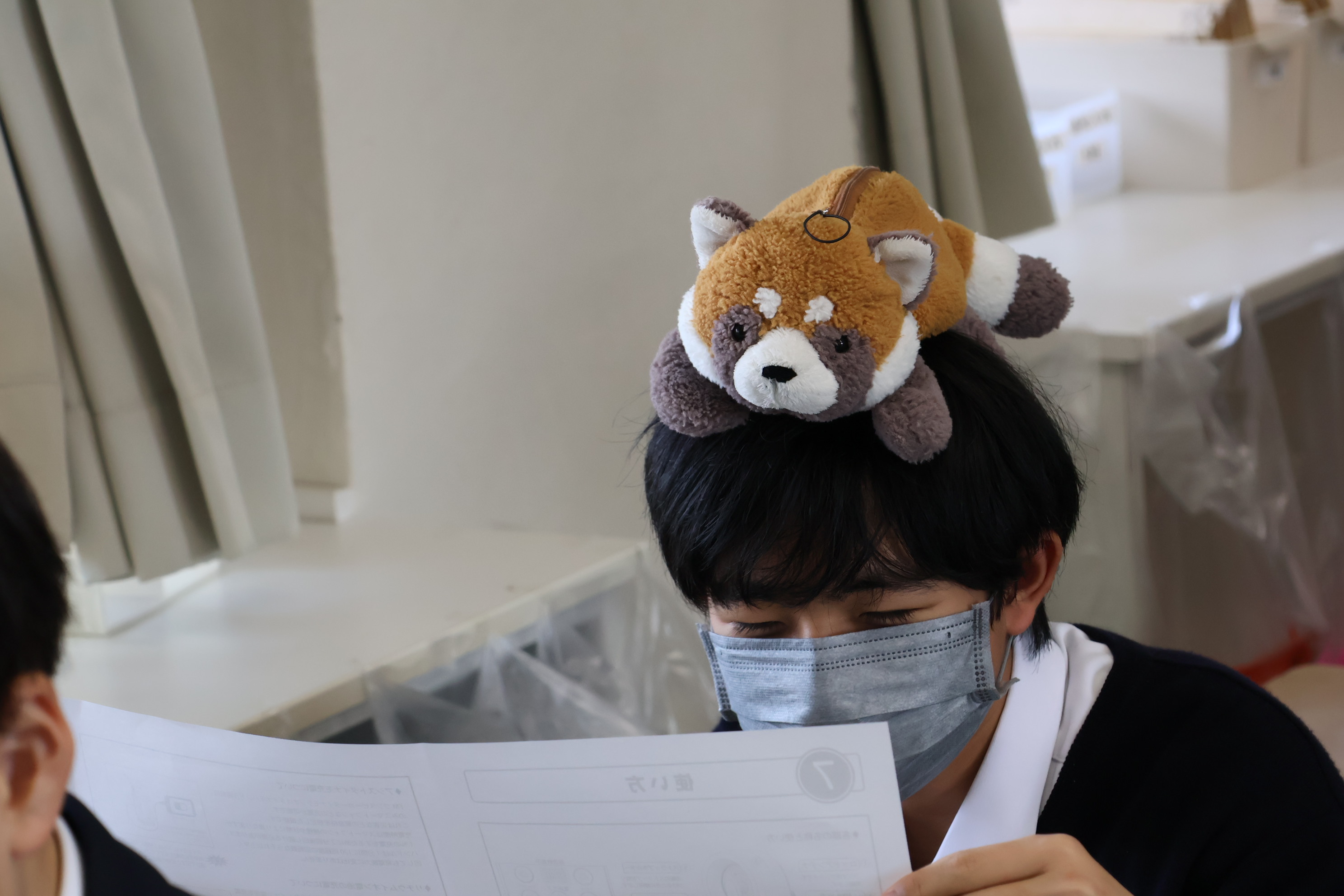

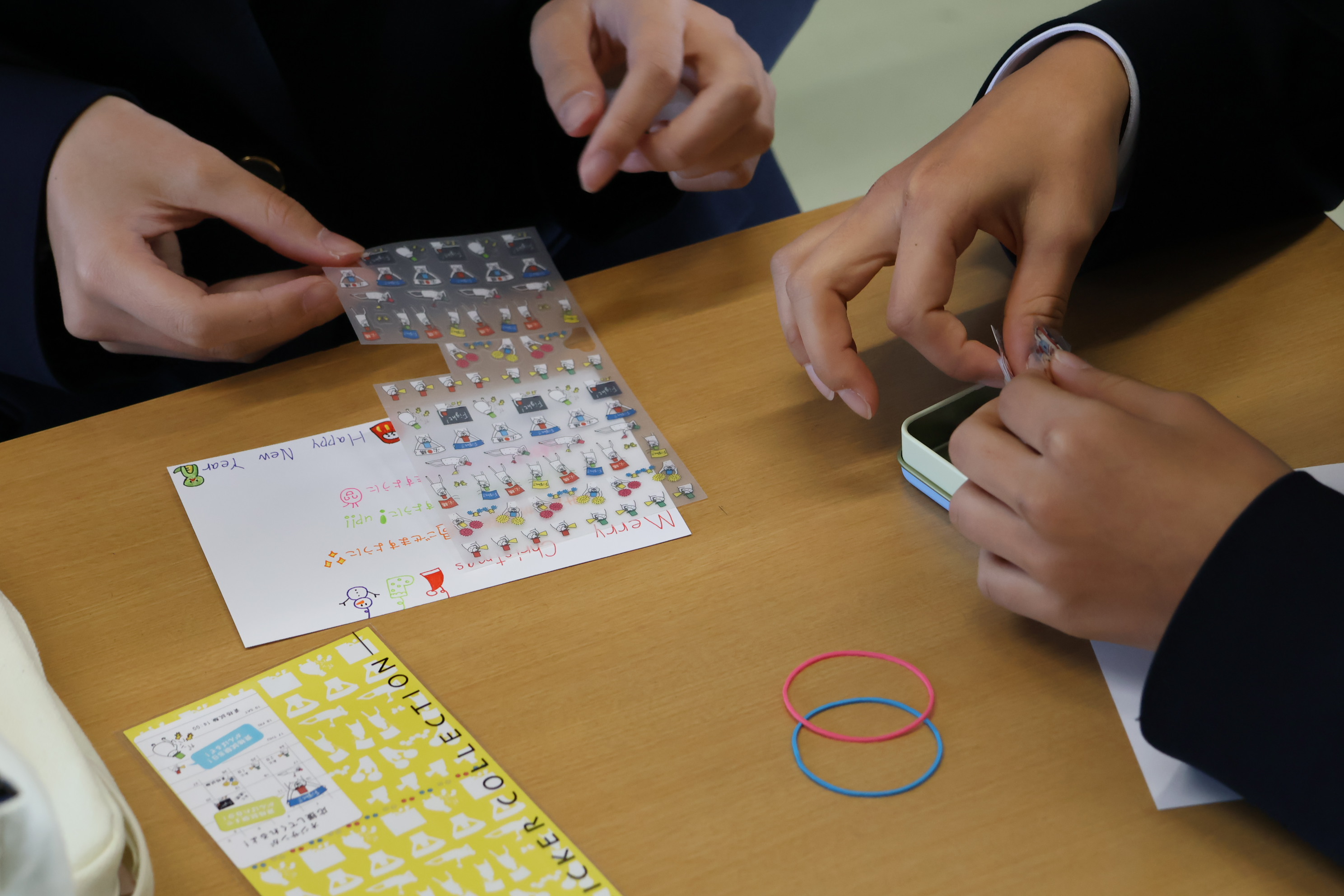
◎仲間と共に78日間✨。(12/24:2学期終業式)
感染症予防のため、オンラインでの終業式としました。



◎ひな中の風✨
~ひたむきに(12/23:クリスマスコンサートを前に)





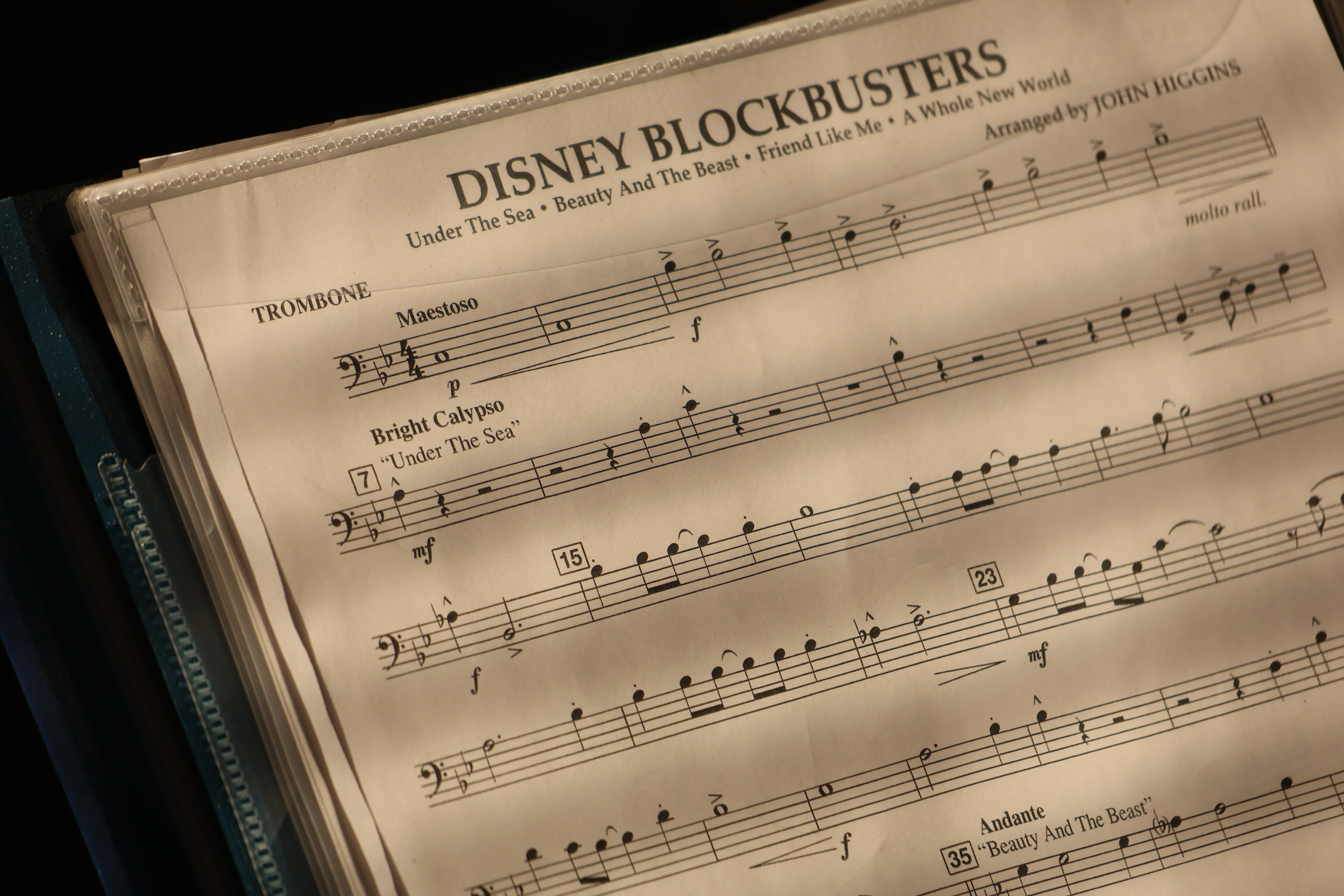



◎ひな中の豊かな学び(12/23:英語科)
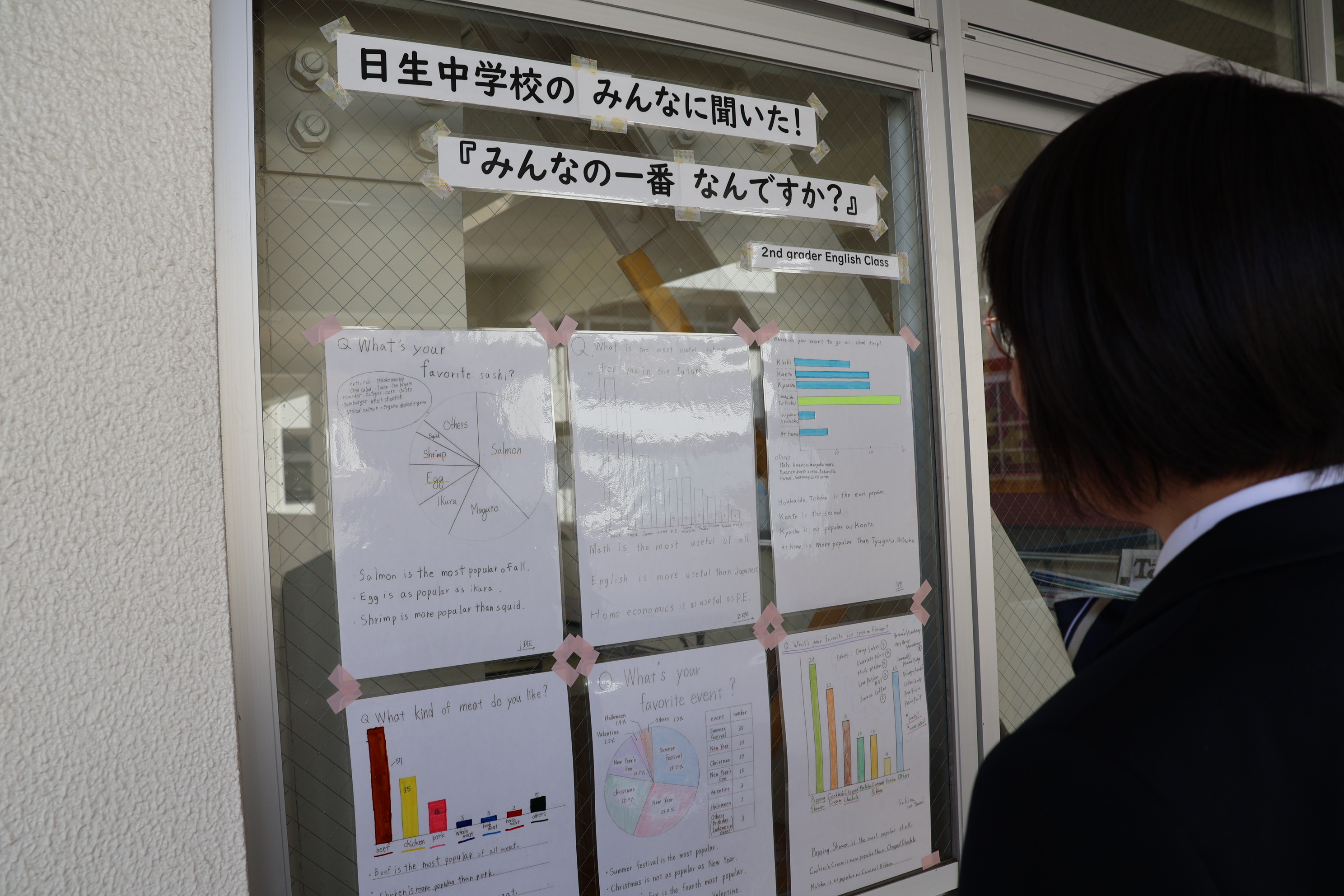
◎2学期を越えて。
~ありがとう学校 ありがとうみんな(12/23:大掃除)


◎自分らしい学習のスタイルが大切。(12/23:一生懸命な2年生です!)
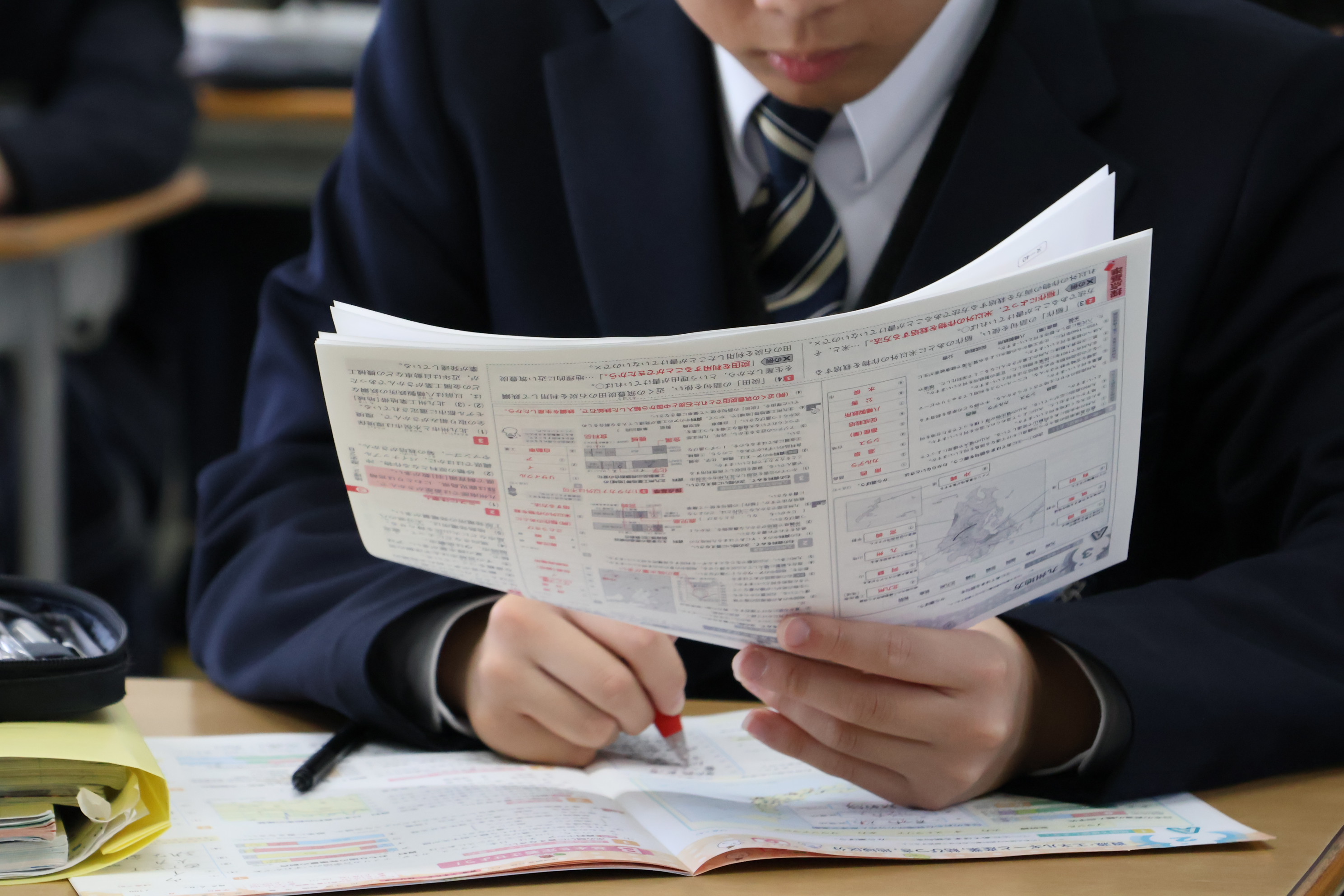
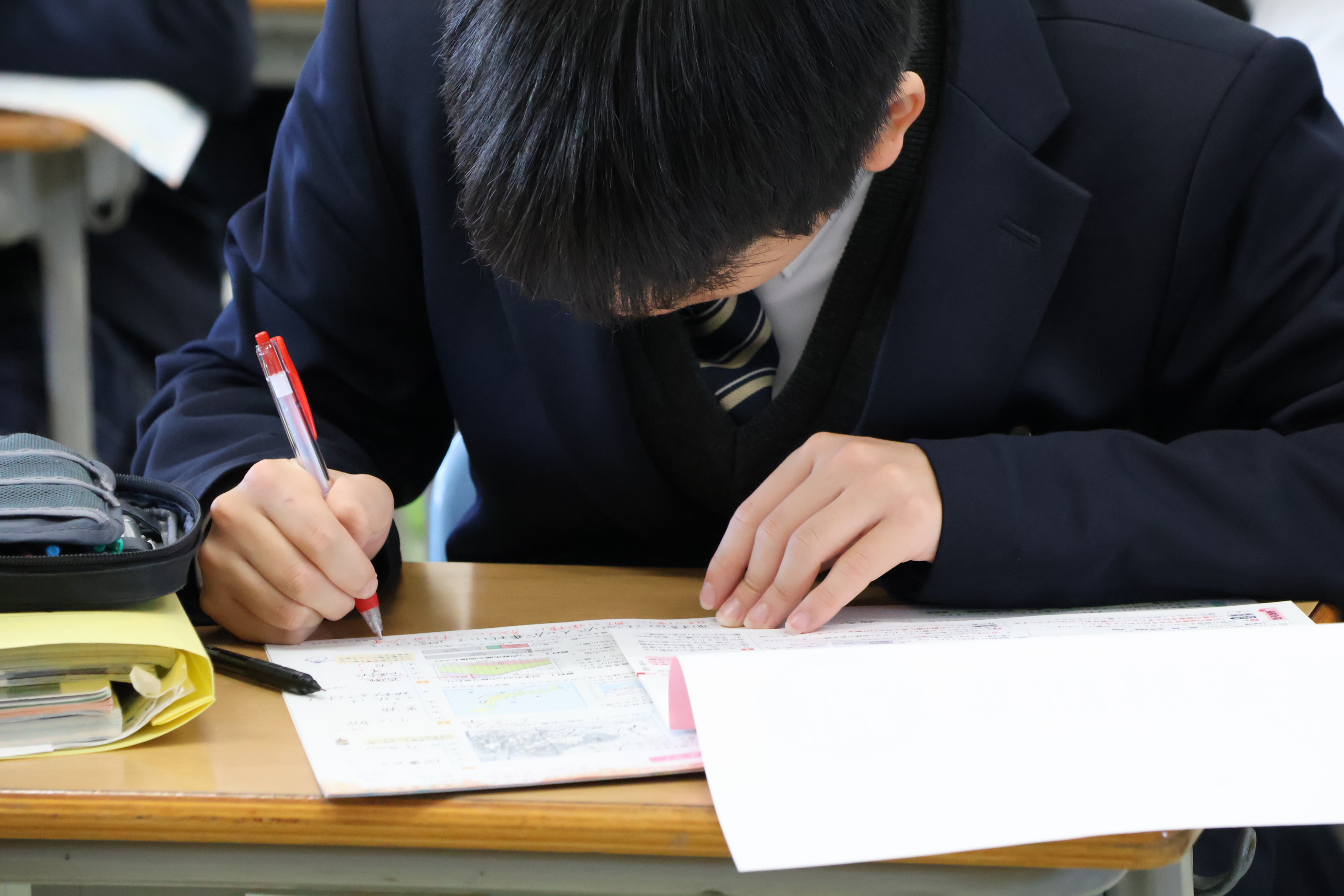
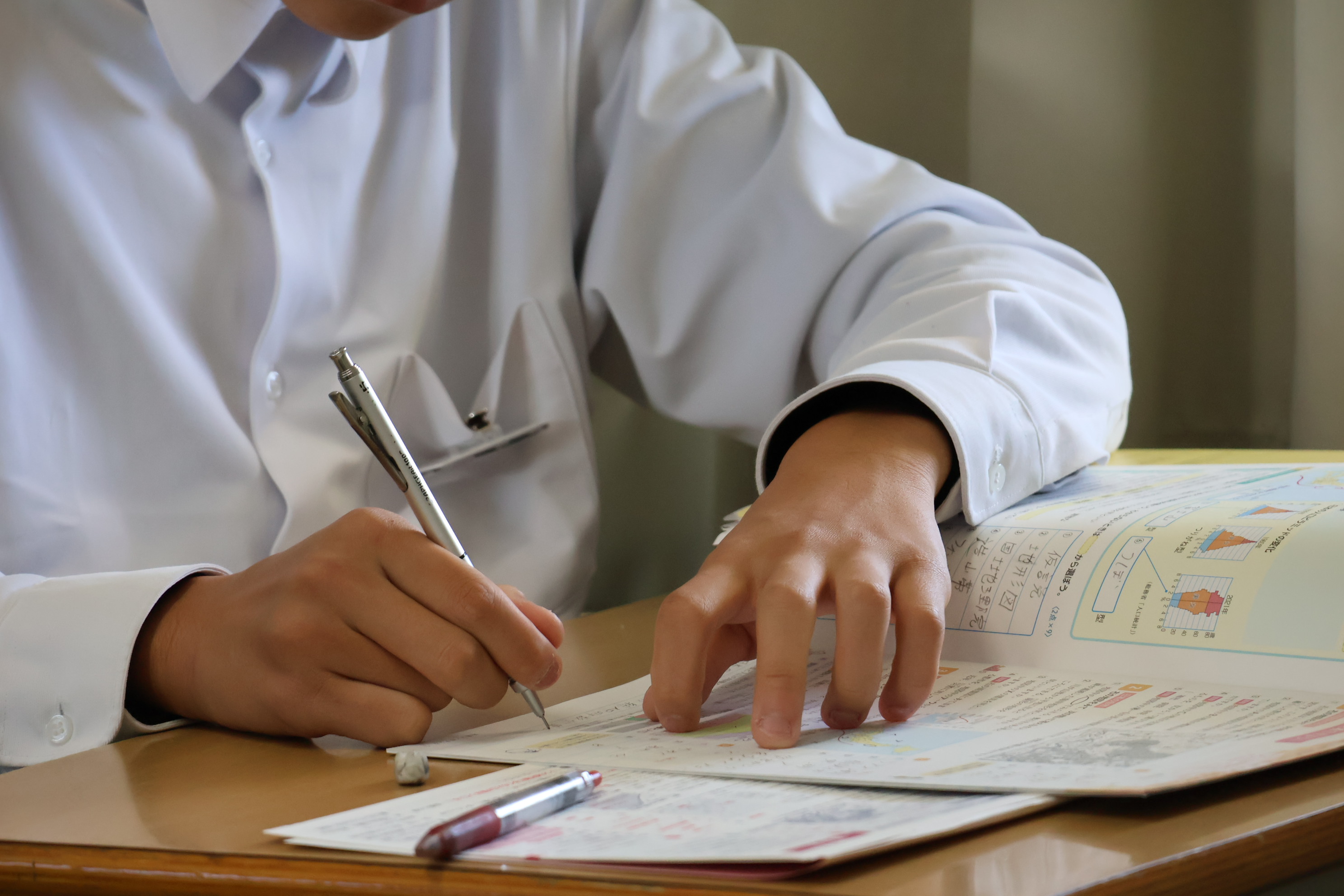
To forget one’s purpose is the commonest form of stupidity. Nietzsche
(目的を忘れることは、愚かな人間にもっともありがちなことだ。)
〈人生はただ一問の質問にすぎぬと書けば12月のかもめ〉改 寺山修司 (12/23)

◎冬至(12/21)



冬至は二十四節気(にじゅうしせっき)の一つで、昼が最も短く夜が最も長い特別な日です。この日は太陽が黄道上で最も南に位置し、北半球では日照時間が最も短くなります。具体的には、冬至の日は太陽が地平線の下に沈む時間が早く、また日の出の時間も遅いため、昼の時間が非常に短くなります。この現象は、自然界のリズムを感じさせるものであり、冬至を境に日照時間は再び増え始めるため、古くから新たな始まりや運気の向上を象徴する日とされています。
冬至は、日の出が最も遅い日や日の入りが最も早い日とは異なり、昼の時間が最も短いことが特徴です。この短さは、自然のサイクルの中で特に重要な意味を持ち、私たちに季節の変化を意識させるきっかけを与えます。また、冬至は夏至と対に成る節気で、昼と夜のバランスが最も極端に表れる時期でもあります。これにより、私たちは自然のサイクルをより深く理解し、感謝することができます。
日本では冬至の日にかぼちゃを食べたり、ゆず湯に入る習慣があります。かぼちゃは栄養価が高く、特にビタミンが豊富なため、健康を願う意味が込められています。また、ゆず湯は温まる効果があり、風邪予防や体調管理に役立つとされています。このように、冬至に行うこれらの風習は、単に伝統的な行事であるだけでなく、健康や運気を祈願する大切な意味を持っています。冬至は天文現象だけでなく、文化とも深く結びついており、その時期に行われる様々な行事は、私たちの生活に温かみを与え、家族や友人との絆を深める機会ともなっています。
2024年の冬至は12月21日(土曜日)です。この日は一年の中で最も昼が短く、夜が長い日とされています。冬至は、太陽の位置が最も低くなるため、昼の時間が最も短くなりますが、その後は徐々に日が長くなり、春へと向かっていく重要な節目でもあります。
◎これまでの豊かな学びをもとに。(12/20:三年生学級活動)
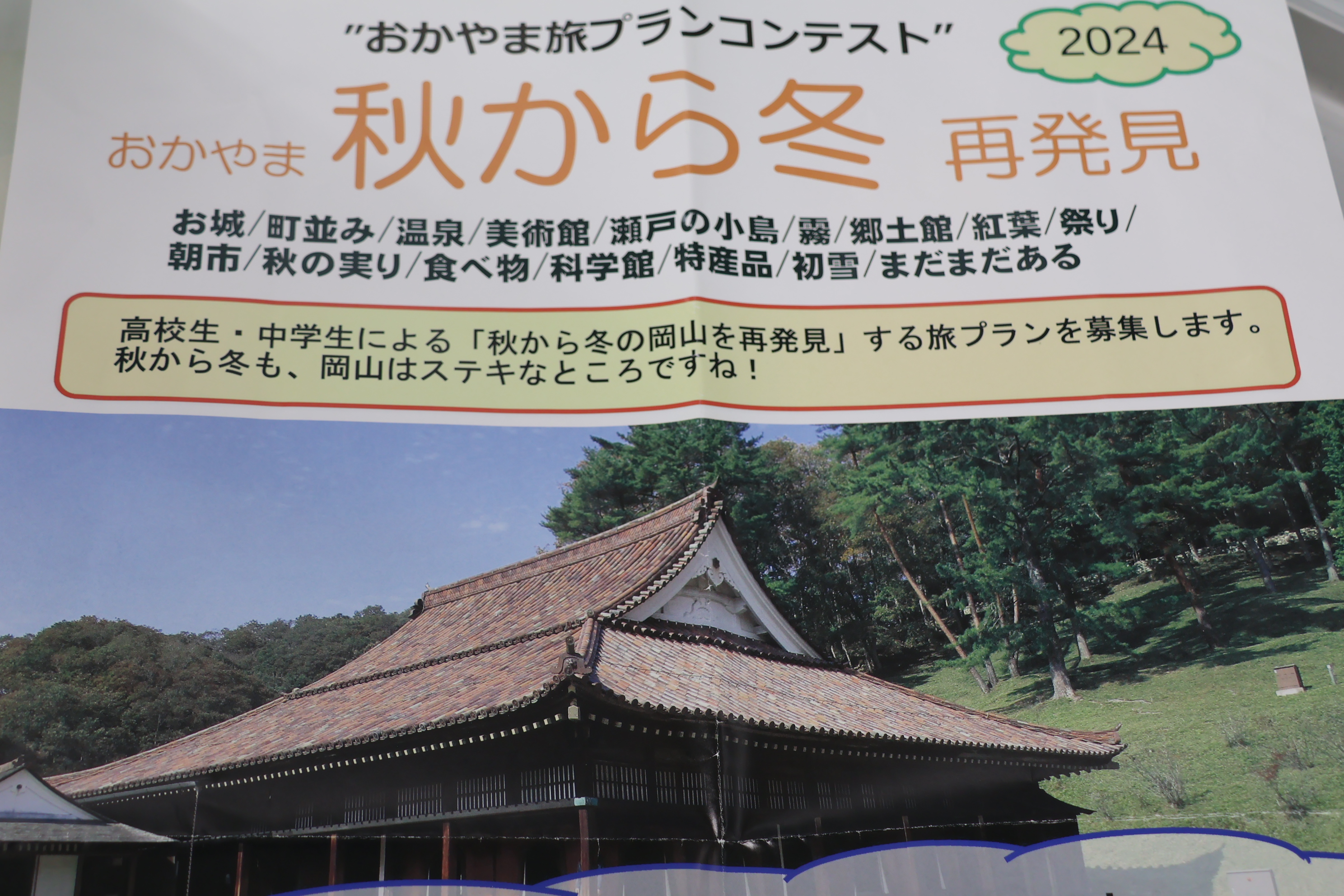
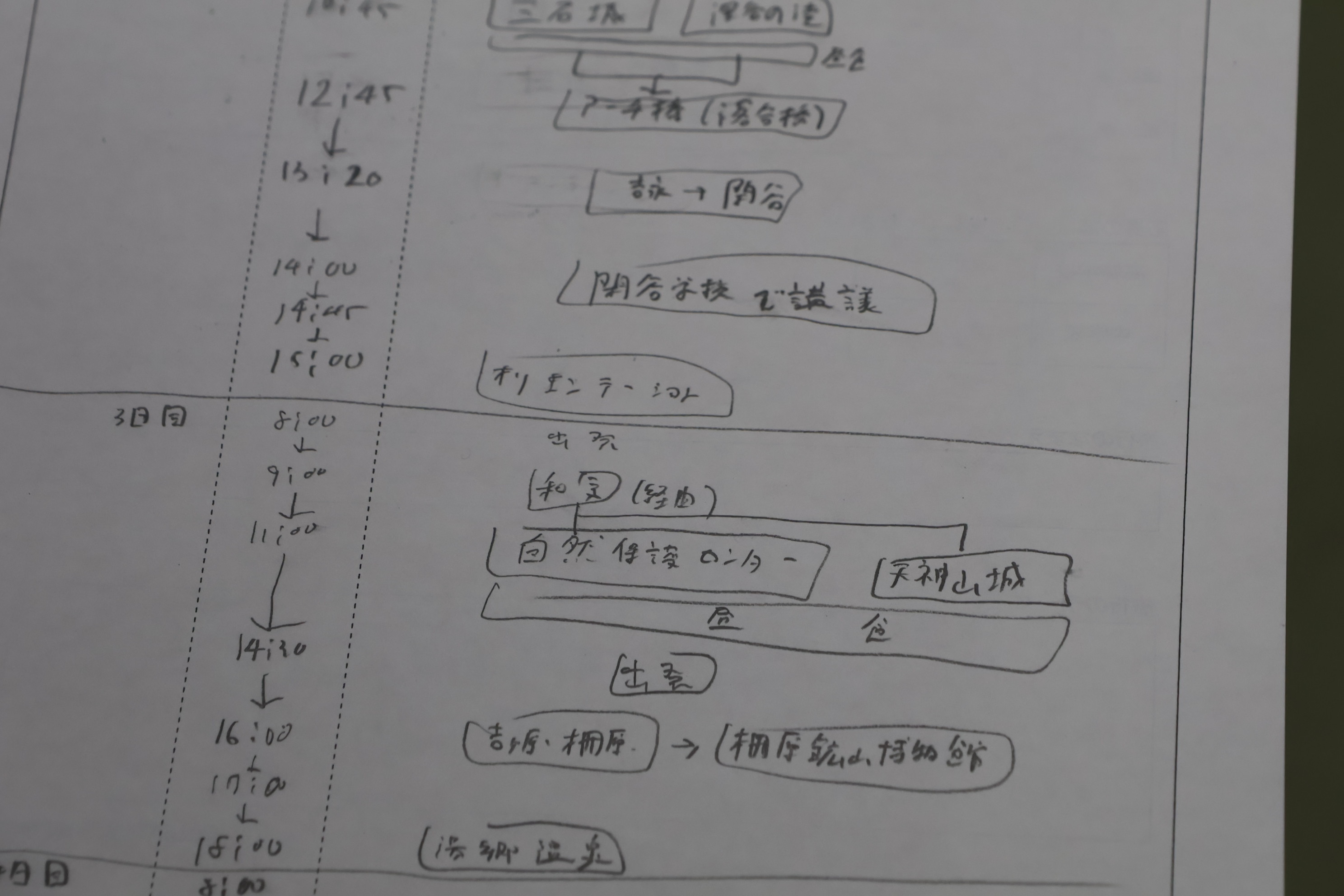
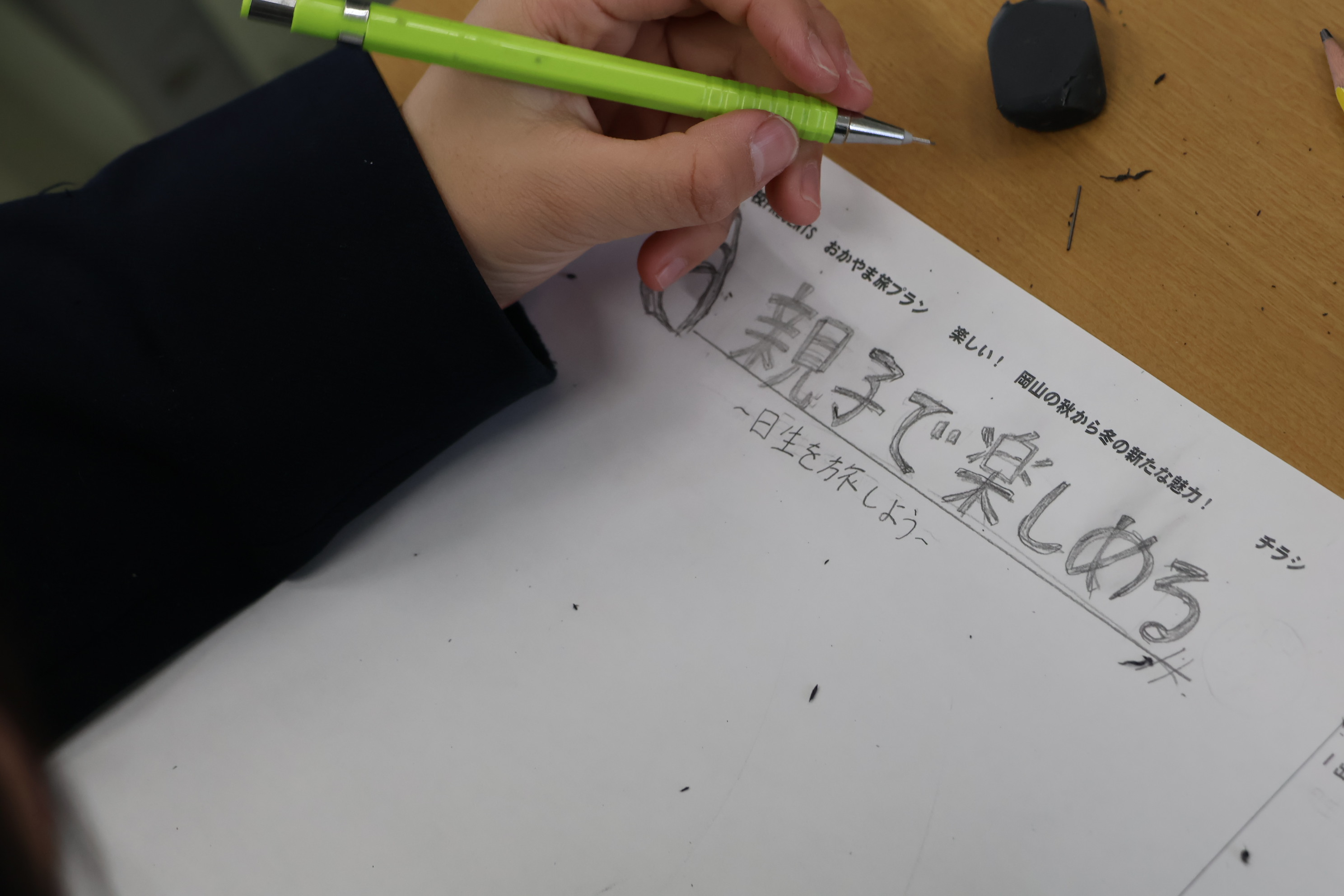
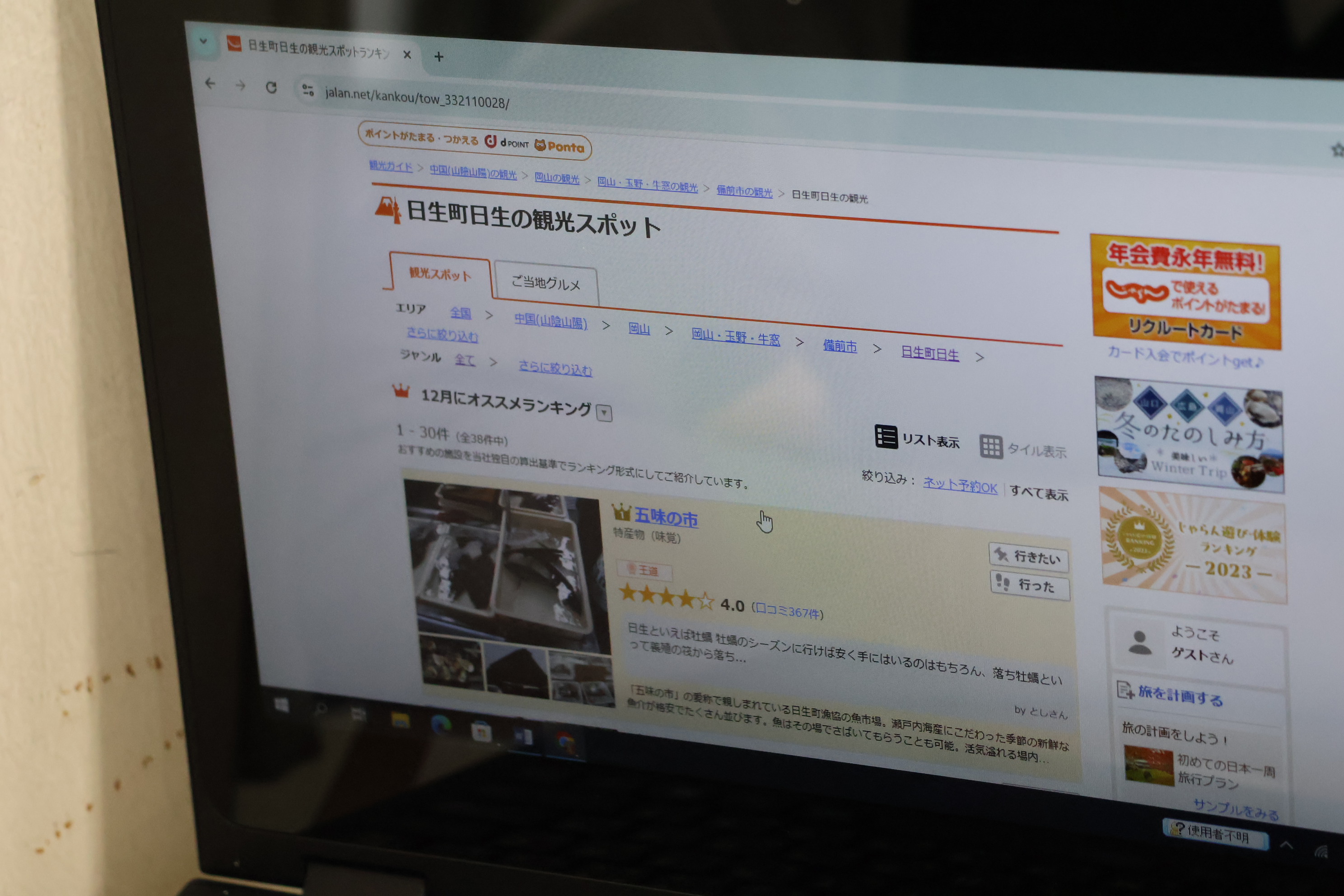
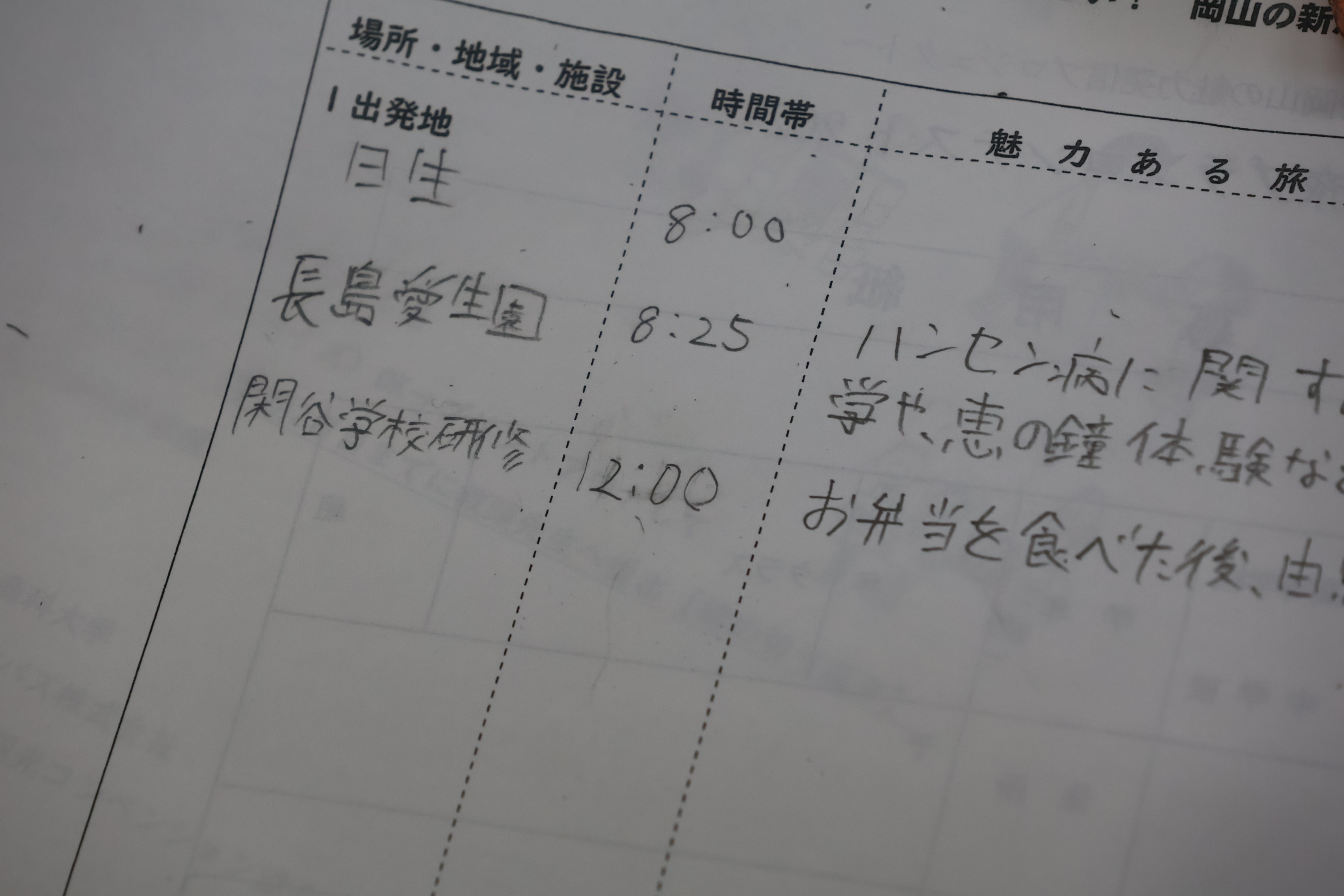


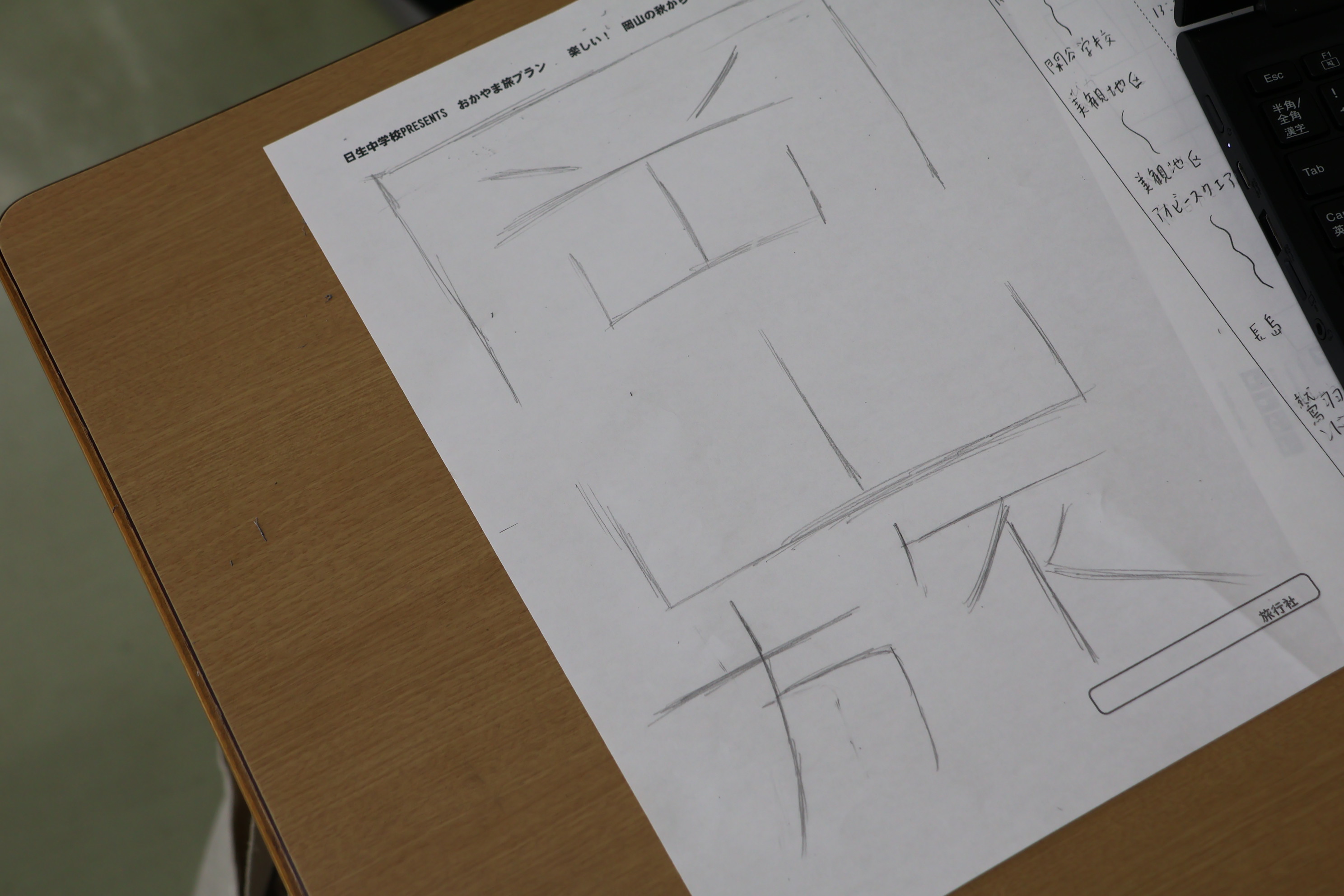

2025.1.8提出〆切です。
◎Santa Claus Is Coming to Town(12/20)

◎校長室から(12/20)
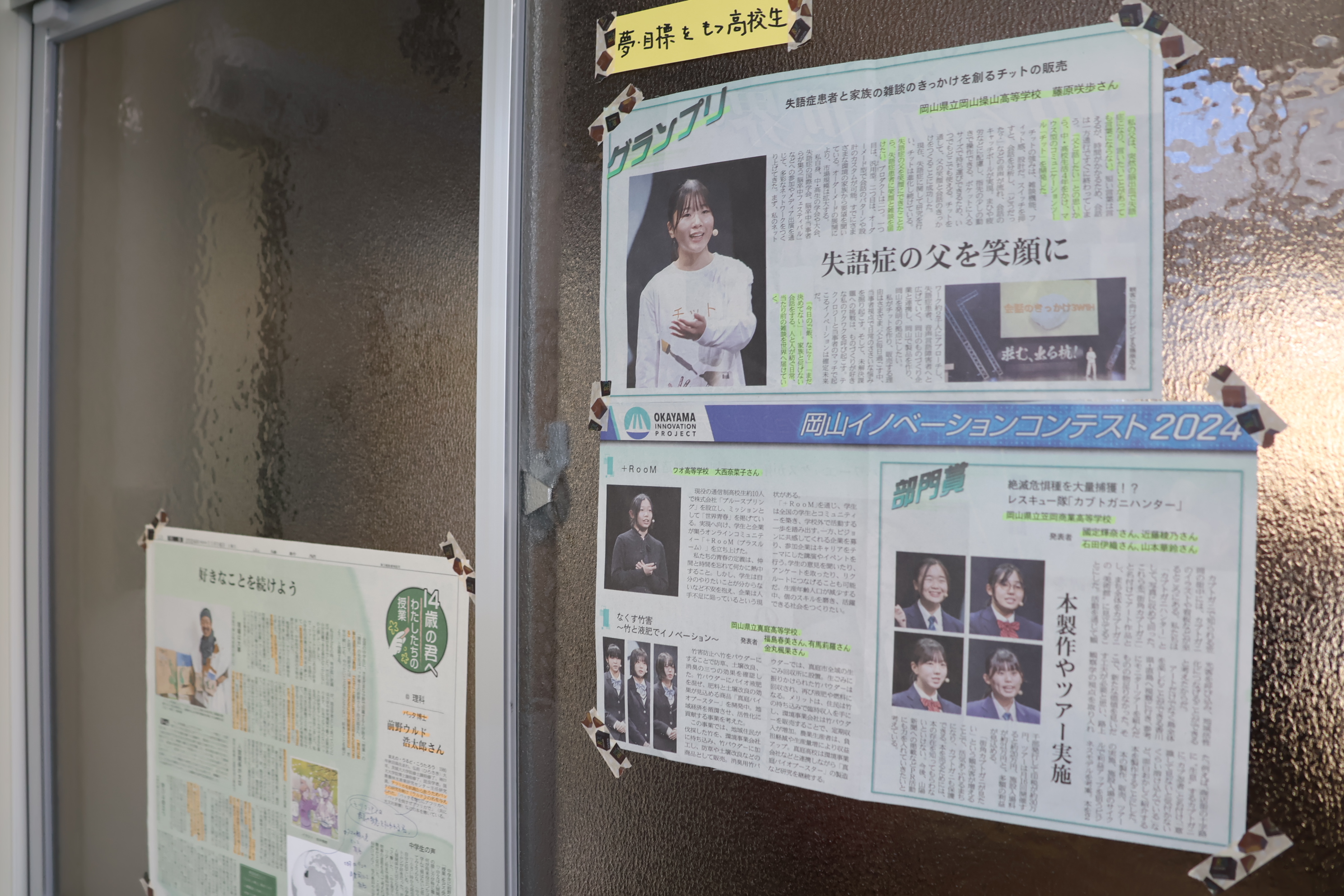
Maybe the goal really should be a life that values honor‚ duty‚ good work‚ friends and family. Robert Downey Jr.
(本当に目指すべことは、名誉、義務、良い仕事、友人、家族を大切にする人生なのかもしれません。)
◎多くの人に支えられて(12/19)
大切に整備して使っていきます。ありがとうございます。

◎ひな中の風✨
~姿は似せ難く、意は似せ易し 本居宣長(再掲)(12/18)



◎ひな中の風✨
静かにいく者は健やかにいく
健やかにいく者は遠くまでいく(12/18:07:37)



◎朝の来ない夜はない(12/17:個別懇談中)

人間の生存は自然に抱かれているから、人世の因果が自然の摂理に似るのは当然である。
万難とたたかって一つの仕事をやりおえた人は、きっと〈朝のこない夜はない〉という思いを深めるであろう。私は夜のあいだじゅう書きものをして疲れると戸外に出てみるが、夏であれ冬であれ、暗黒がまるで手でつかむことができるように濃いことに驚く。
月は消え星はまばらとなり、ほどなく太陽がのぼるべき時刻であるのに、万物は全く暗く全くだまっている。このような暗い静寂の中に立っていると、私は未明に倒れていった先人をしのび、おのれの怠慢が責められ、そしてまさにこのような時刻にこそ人はためされるのだ、という思いに胸うたれる。
しばしば人はこのようなときに迷い、このような状況の中でくずれてしまうのではなかろうか。一つの仕事の成就に要する努力をかりに一〇とすれば、奮励して八か九までに至ることは少なくあるまい。残りの一か二をやりおおせることは真にむずかしい。それをやりおおせたとしても状況はおそらくまだ暗黒であろう。最も暗いかもしれない。人は力がつきて倒れてしまうかも知れない。だが、暗黒の地面におもてをうずめてそのまま果てまいとするなら、一〇をやりおえたところから更に一歩、もう二歩前へ進まねばならないだろう。
そうしてこそ、はるかに微光をあおぎ、微光はたちまち東天紅にかわるのを見るであろう。『詞集 たいまつⅠ』(むのたけじ著 評論社刊)より引用
◎ありがとう いろんな人に 伝えよう(12/16:生徒会)
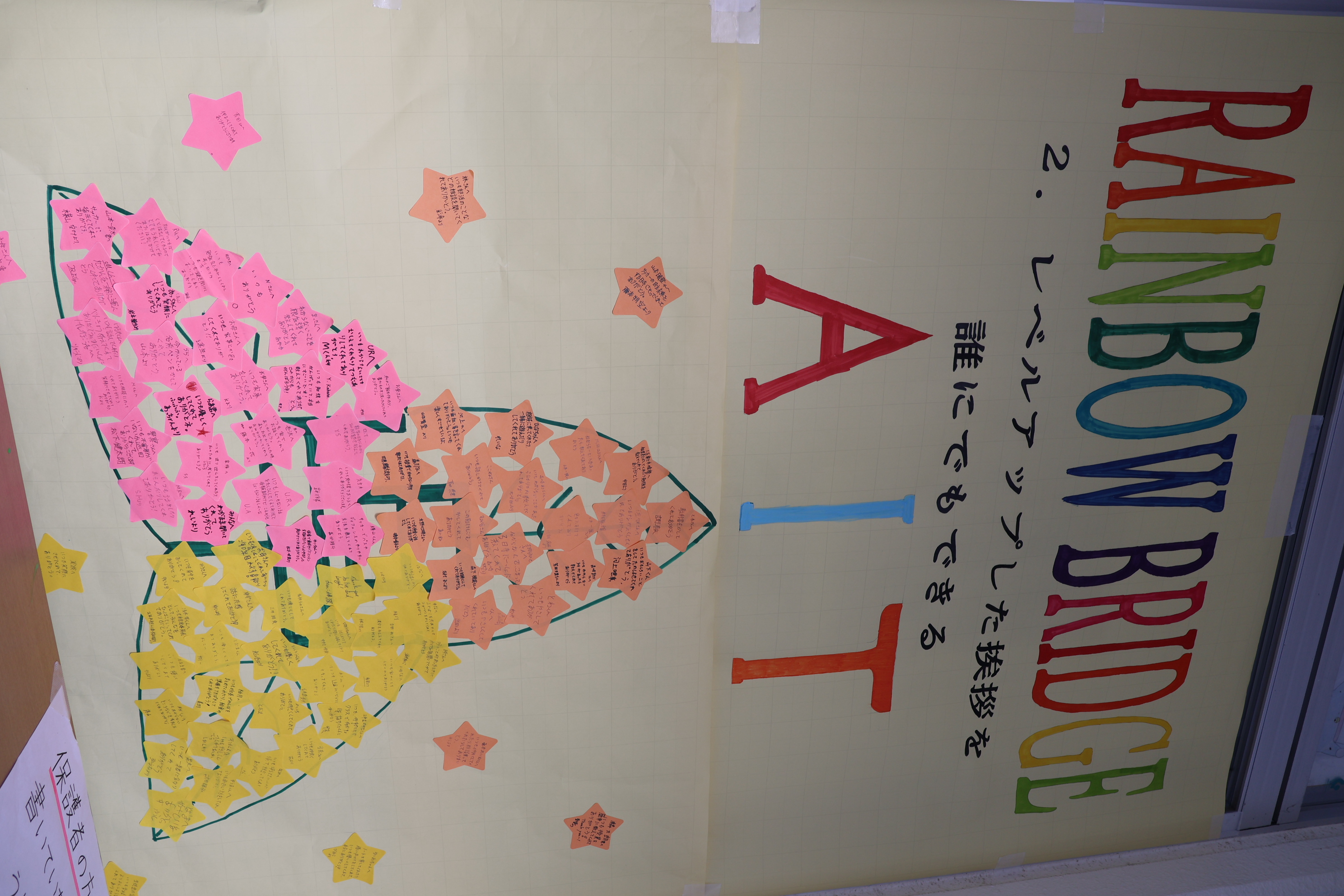
◎私たちのはじまりの風景16
ここはどこでしょう?
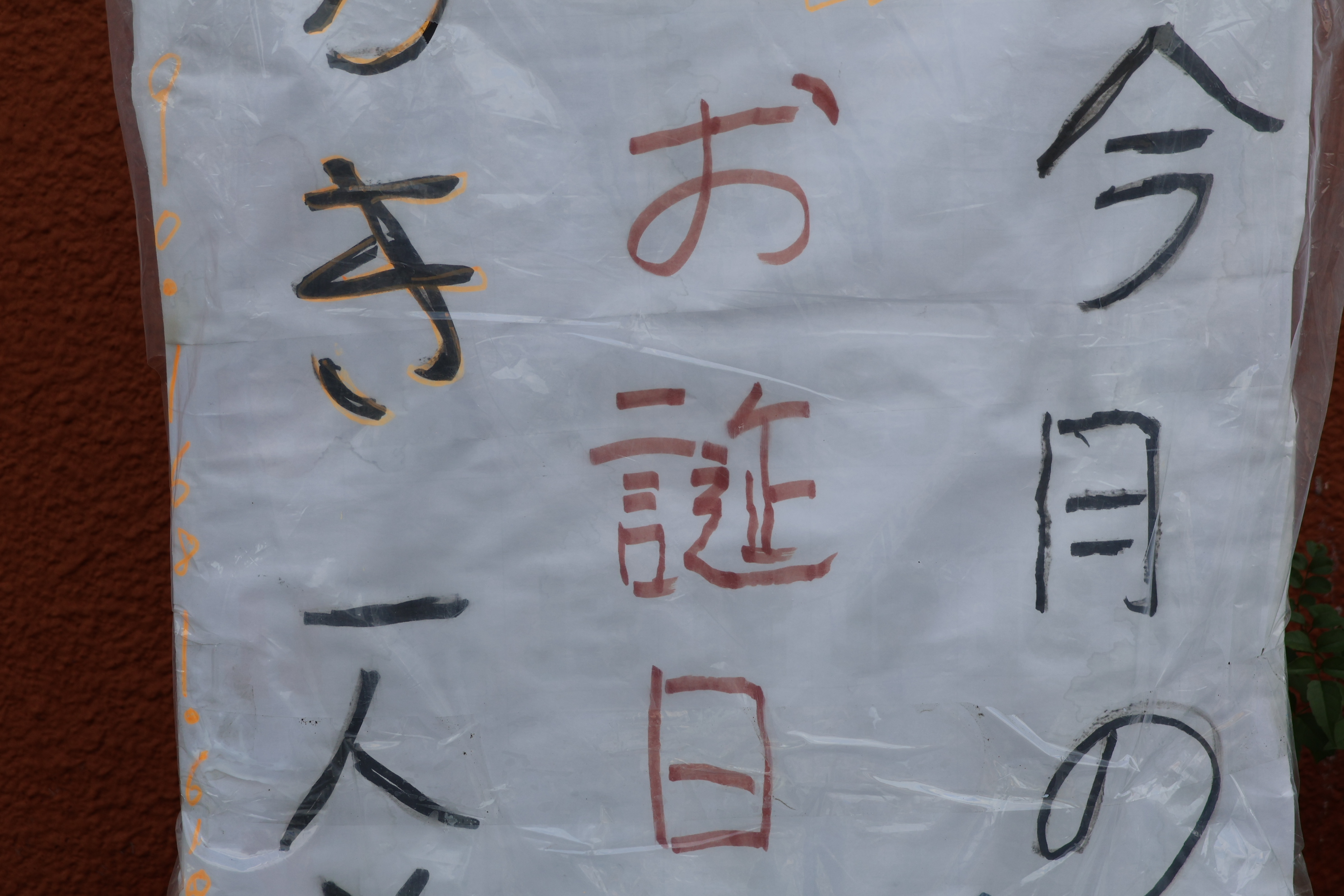


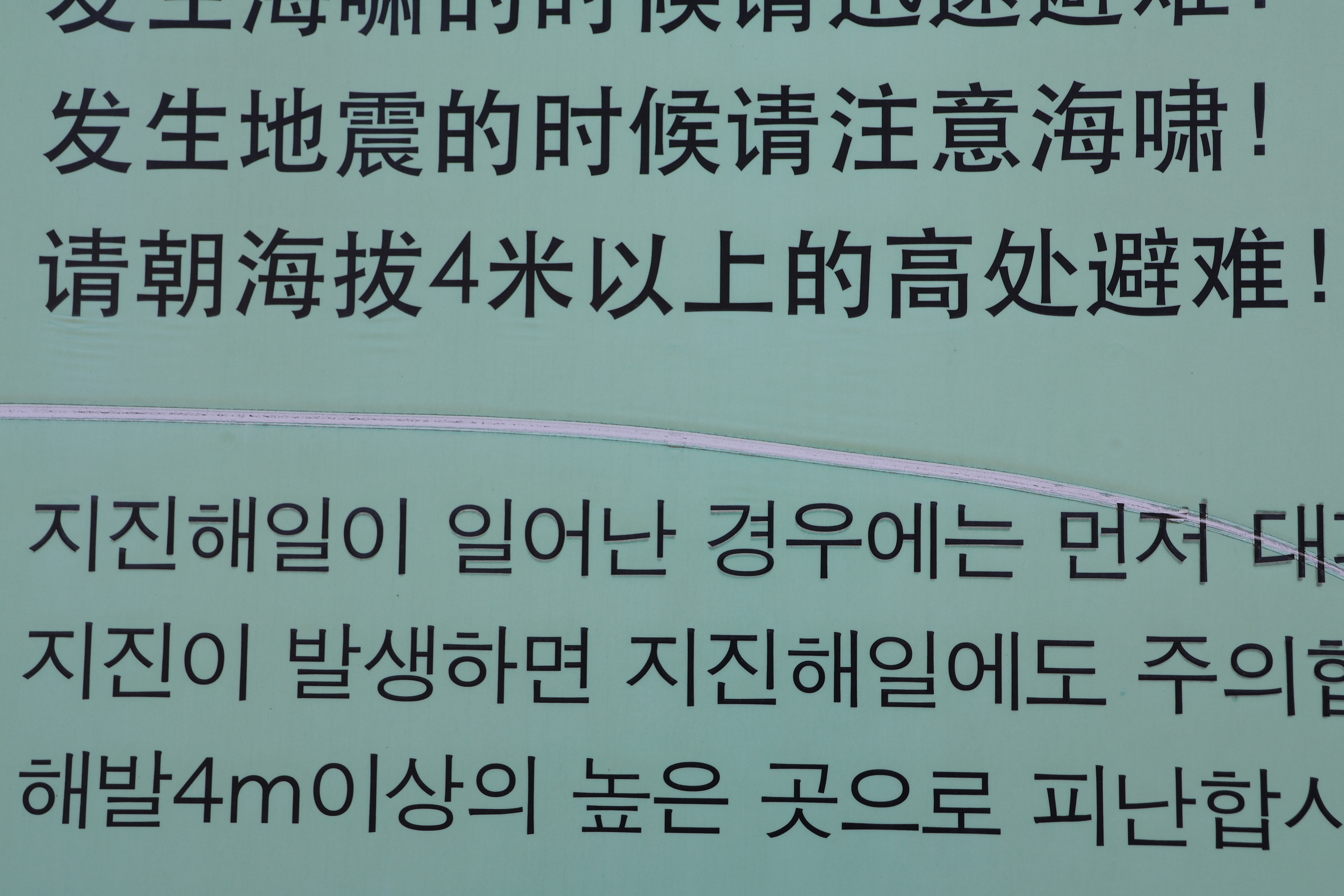





◎師走、しわす?ぼくわ、走らない とまらない。一歩づつ。
個別懇談(12/16~)も、「自分のこれから」の糧にしよう。

◎ひな中の風
子どもは風の子 がんばる子✨(12/16:体育)

◎多くの人に支えられて 日生で輝く 日生が輝く
ご来場ありがとうございました(12/14:歳末助けあい演芸会&楽市まつり)



◎日生で輝く 日生が輝く 日生中ひなせもりあげ隊参画!(12/14)
「歳末助けあい演芸会&楽市まつり」(実行委主催)が、14日正午~午後4時半、備前市日生町日生の日生市民会館で開かれます。地区出身で今年名誉市民となった作曲家・岡千秋さん(74)を特別ゲストに迎えます。このイベントは、新年を明るく迎えようと日生地区の老人クラブ連合会・ゆうあいクラブ日生が中心となって、かつて開かれていた演芸会の復活を計画しました。和太鼓の日生甚九郎太鼓をはじめ、傘踊り、太極拳、フラダンス、バンド演奏、愛好者によるカラオケなどが披露され、岡さんも約1時間ステージが予定されています。
琴伝流大正琴アンサンブルひなせは、十人が出演して岡さん作曲の「河内おとこ節」と、「津軽海峡・冬景色」「与作」の3曲を奏でます。日生市民会館で4日、仕上げの練習に取り組み、山口清美代表は「一年の締めくくりに元気な演奏を届けて地域の皆さんに楽しんでもらいたい」と張り切っておられます。チケットは2千円(全席自由)。備前観光協会が日生観光情報センターサンバース(備前市日生町寒河)で取り扱っており、収益はチャリティーに充て市社会福祉協議会に寄付します
屋台村も設けられ、ぜんざい、パン、おでん、特産ミカンの加工品などが販売されます。中学校からも、日生中ひなせもりあげ隊も出店します。【山陽新聞の記事をもとに】
◎ゆく年 来る年に本の世界を。 (12/13:図書室)

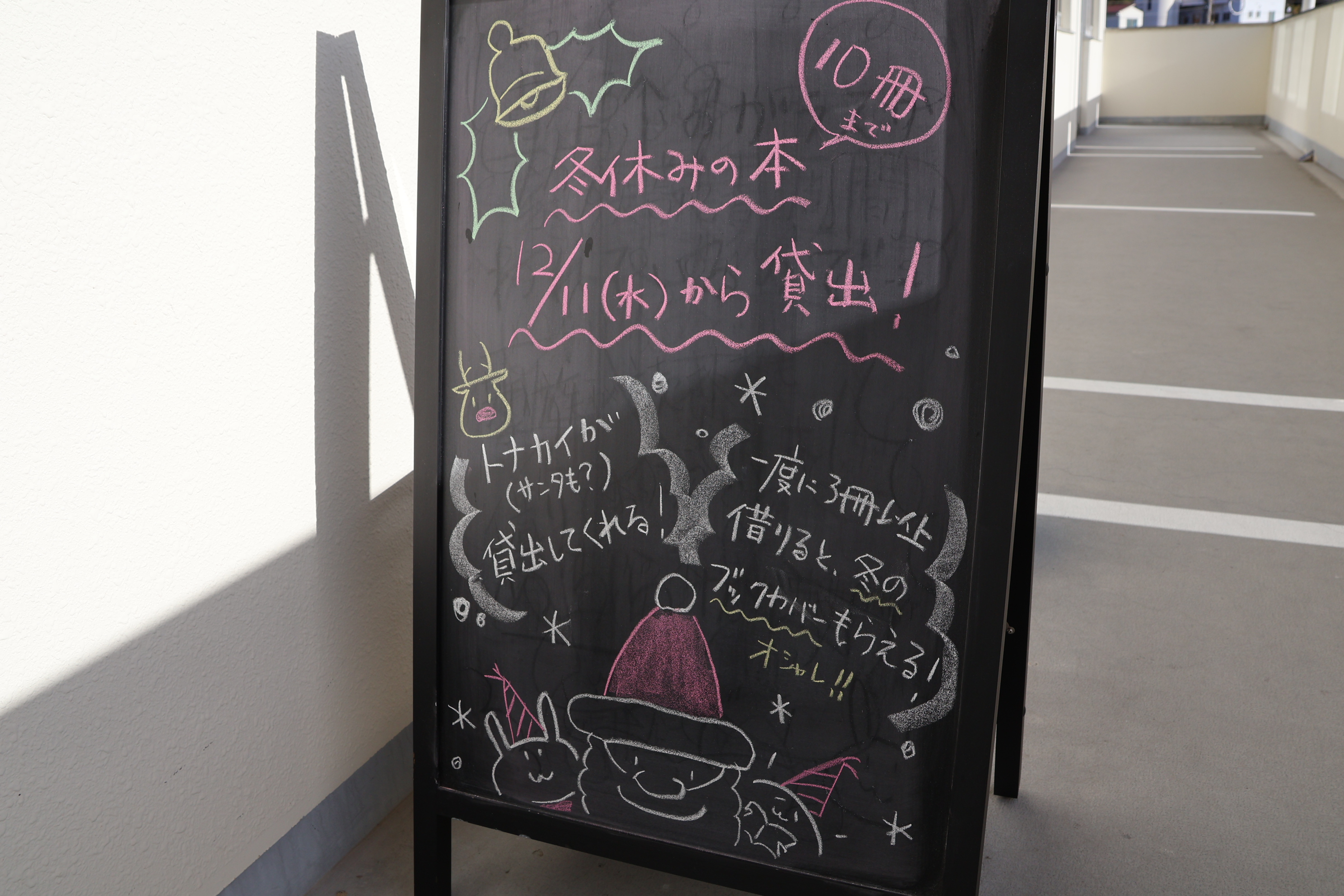

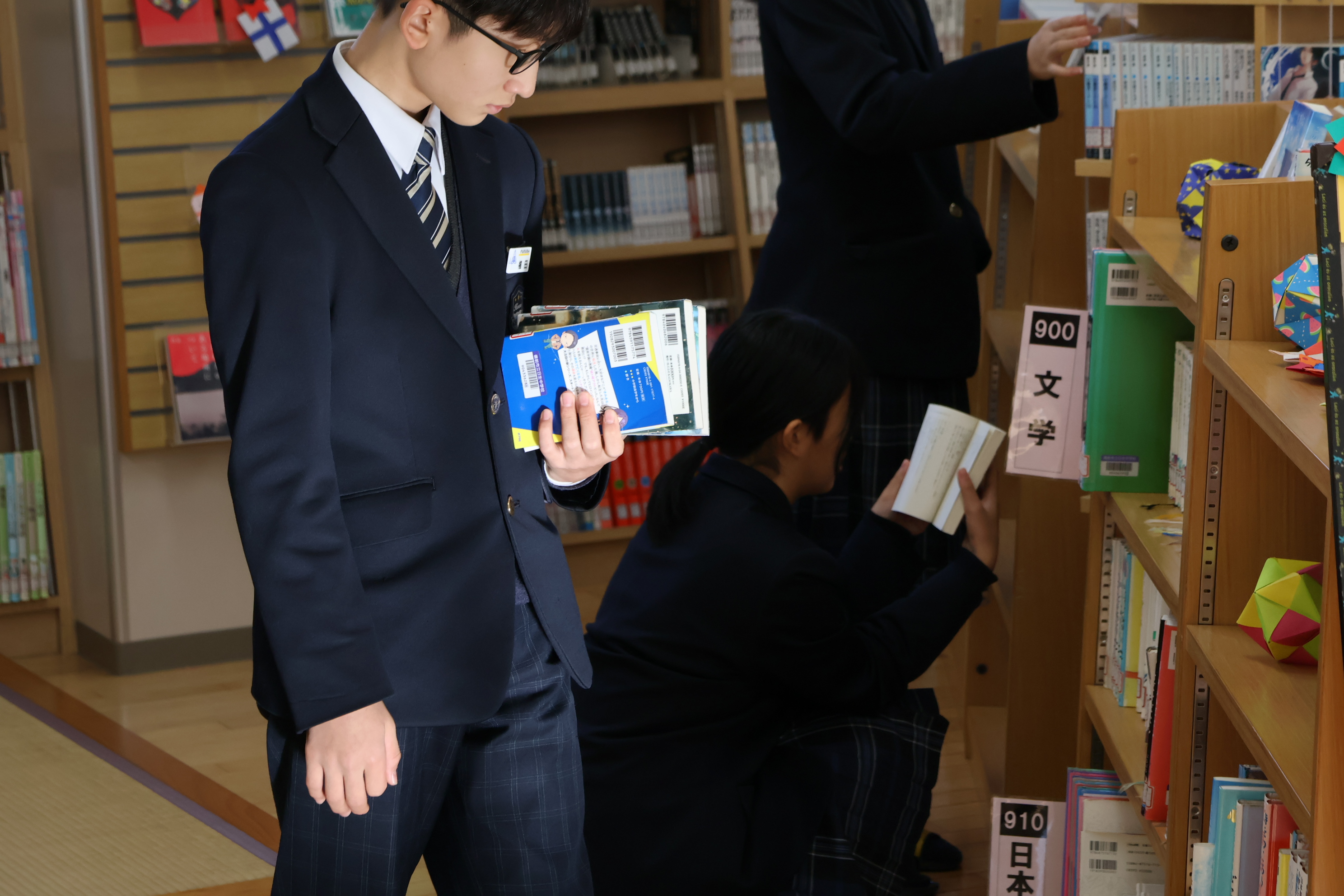
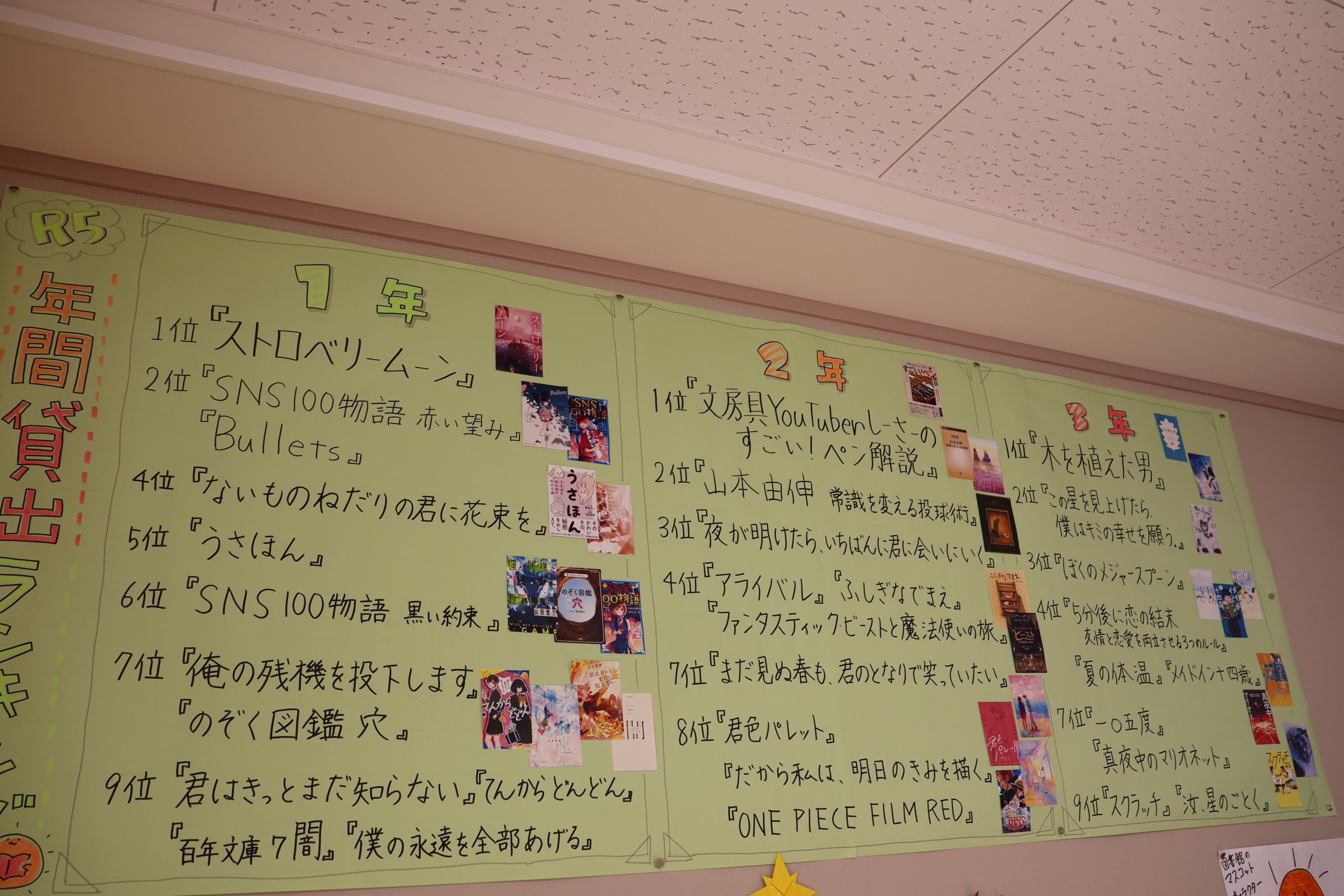

◎ハンセン病問題学習から
学ぶこと、考えること、そして生きること~
13日に、エリアティチャー(AT)として、長島愛生園から田村学芸員さん、岡山大学から学生のみなさんをお招きして、学習を深めました。
「未来へつなぐとはどういうことか」を、「これまでの自分の生き方や課題」を見つめて(重ねて)考え、語りました。また、個人モデルではなく、社会モデル(社会のありよう)の視座で考え、「差別をなくそうとする主体者」としての意識を高める時間となりました。(PTA人権教育研修会(参観授業)としても位置づけ)



◎豊かな学びから、確かな学びに(12/13)
一年生の国語では、『「ワタシの一行」を見つけよう』、三年生の社会科公民では株式学習で実際の株の売買(経済分野)に、チャレンジしています。

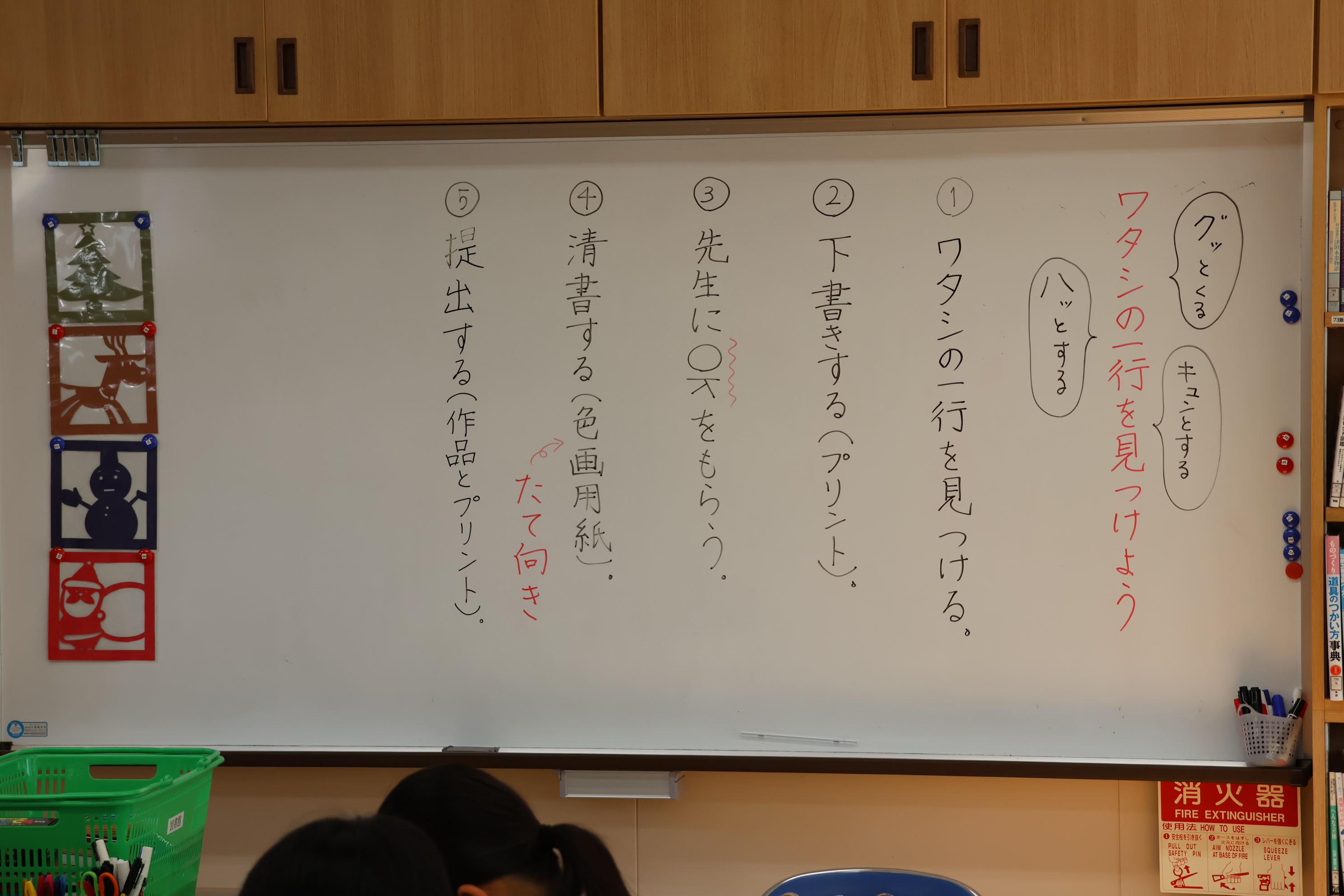



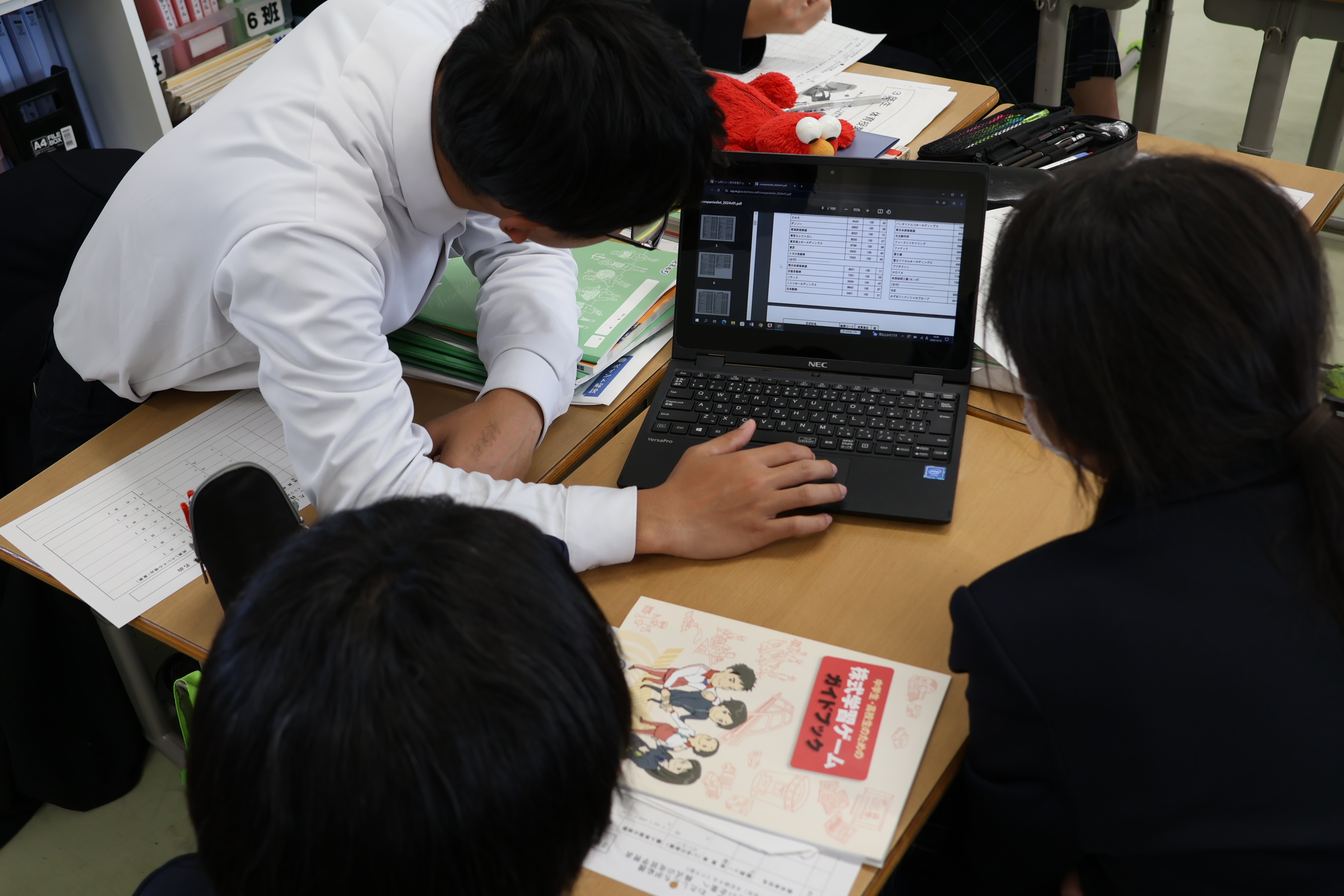
◎岡山県学力定着状況確認テスト(12/12:二年生、/13:一年生)
学力定着状況確認テスト(以下、確認テスト)に取り組みます。確認テストは、学校の組織的な授業改善を進めるにあたり、年度途中における取組状況を検証し、年度内の取組を改善し、次年度につなげることを目的としています。
また、「CBT」は「Computer Based Testing」の頭文字をとった言葉で、コンピュータ上での試験方式を指します。世界各国でさまざまな分野・業界の資格試験、検定試験、社内試験、学力検査などに採用されているこの方式で確認テストを行います。

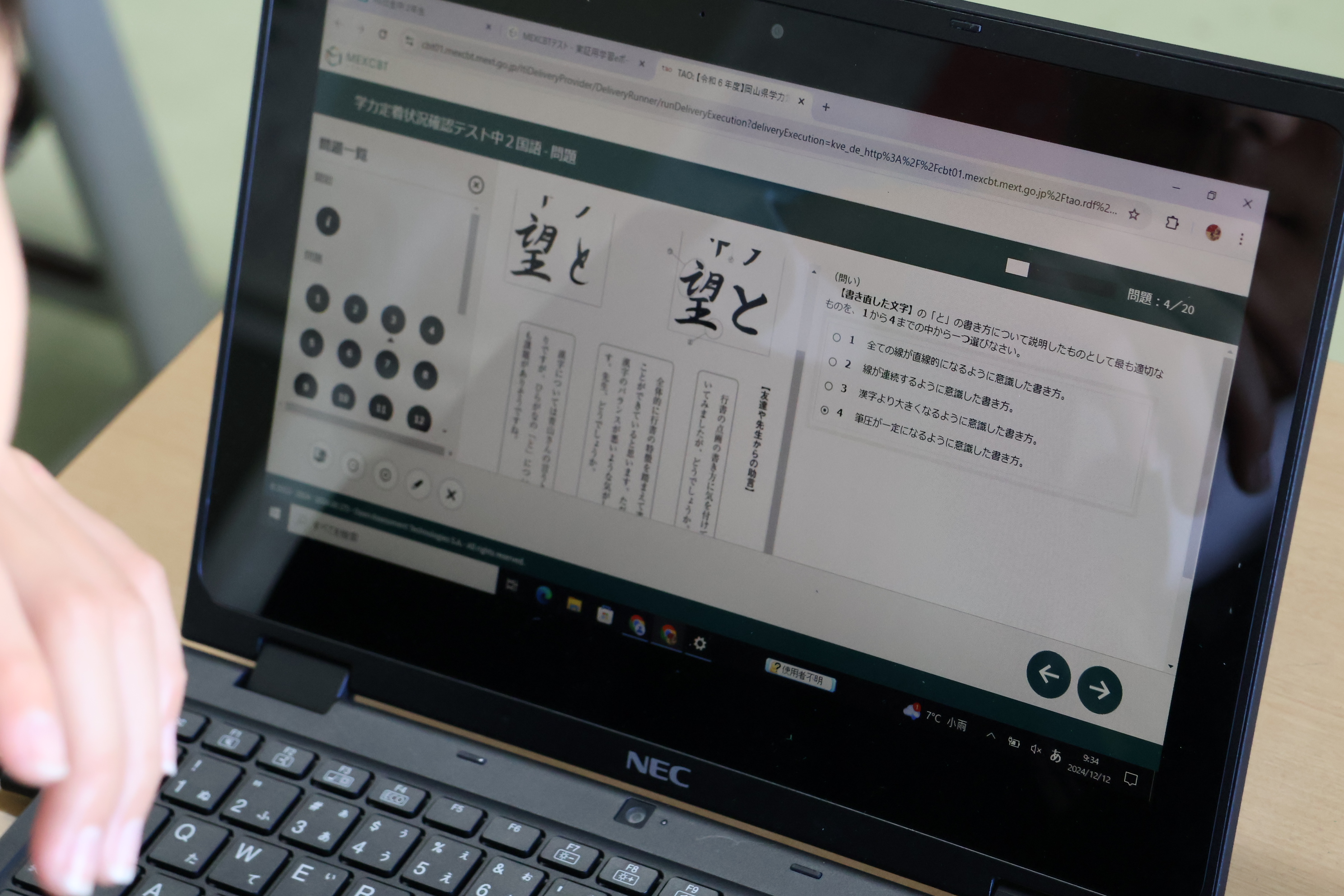
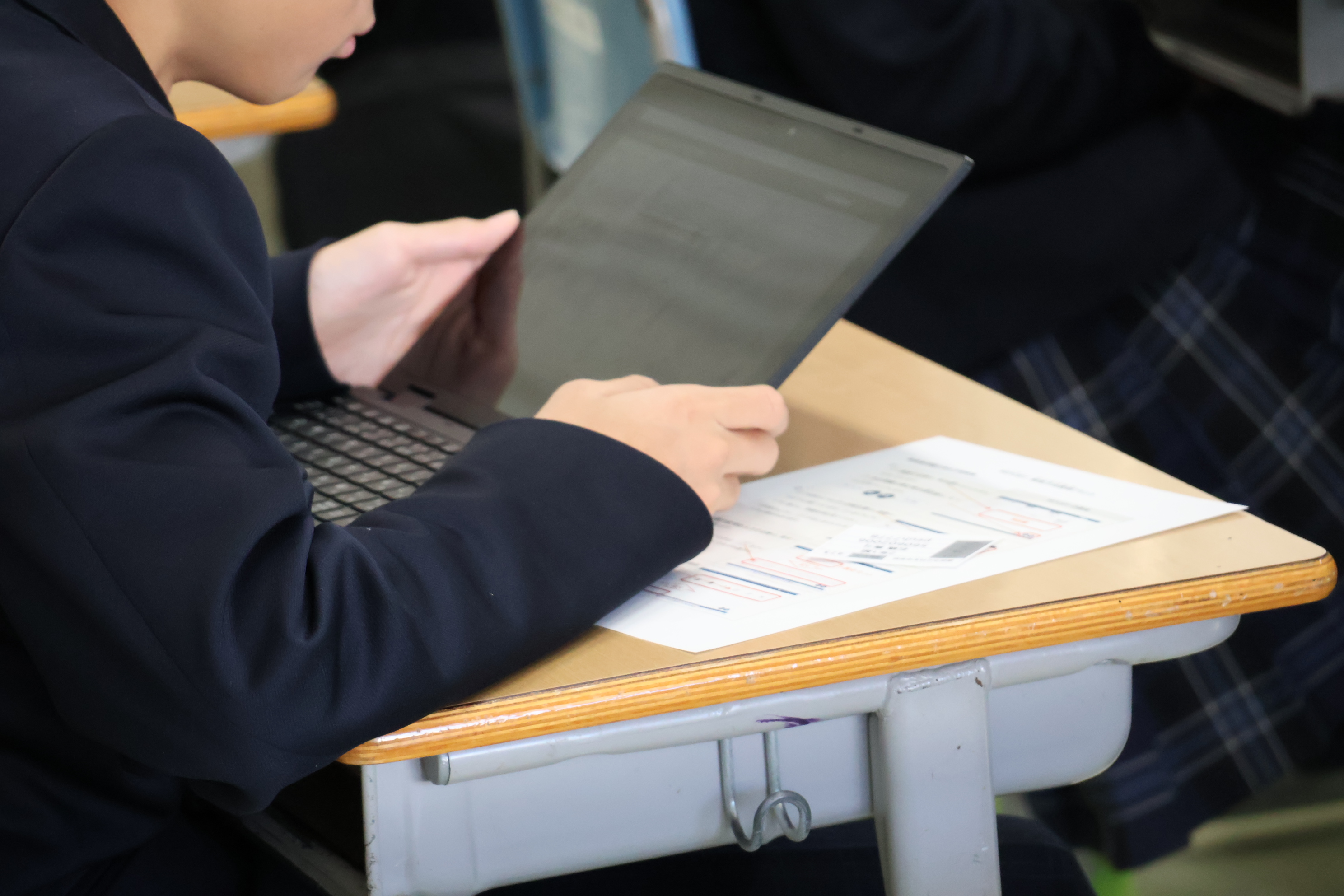
◎あいさつは「ひらく」(12/13:生徒会の取組を受けて)
山陽新聞から投稿記事(12/12)を紹介します。
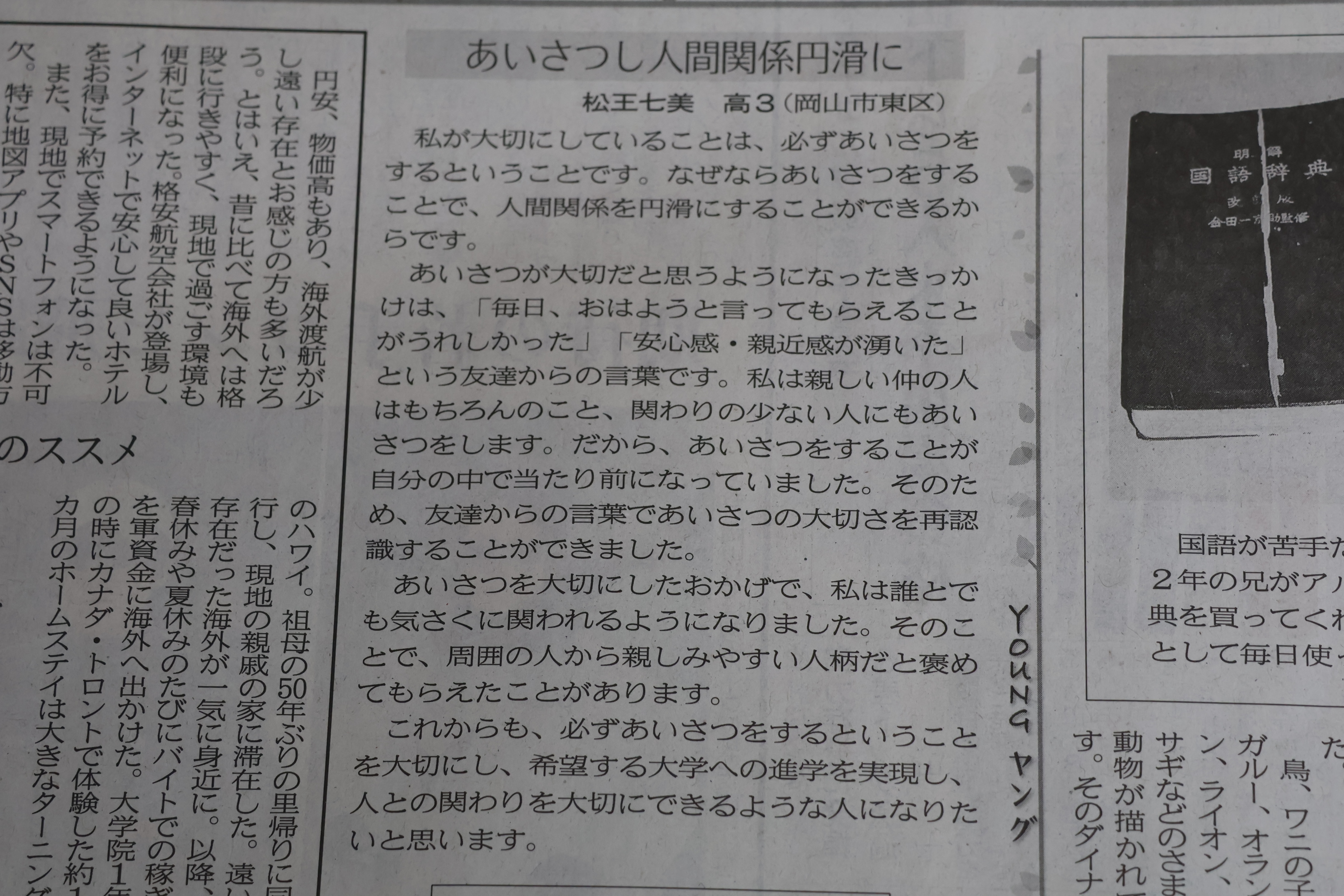



◎寒い中おはよう あたたかいおはようと。
(12/12:生徒会あいさつ運動)



◎一年生も、昨年度の先輩に引き続き、
「クラスで暮らす」取組
~自分を知る・開く、そして、お互いを理解する・がんばり合う仲間として(12/12)
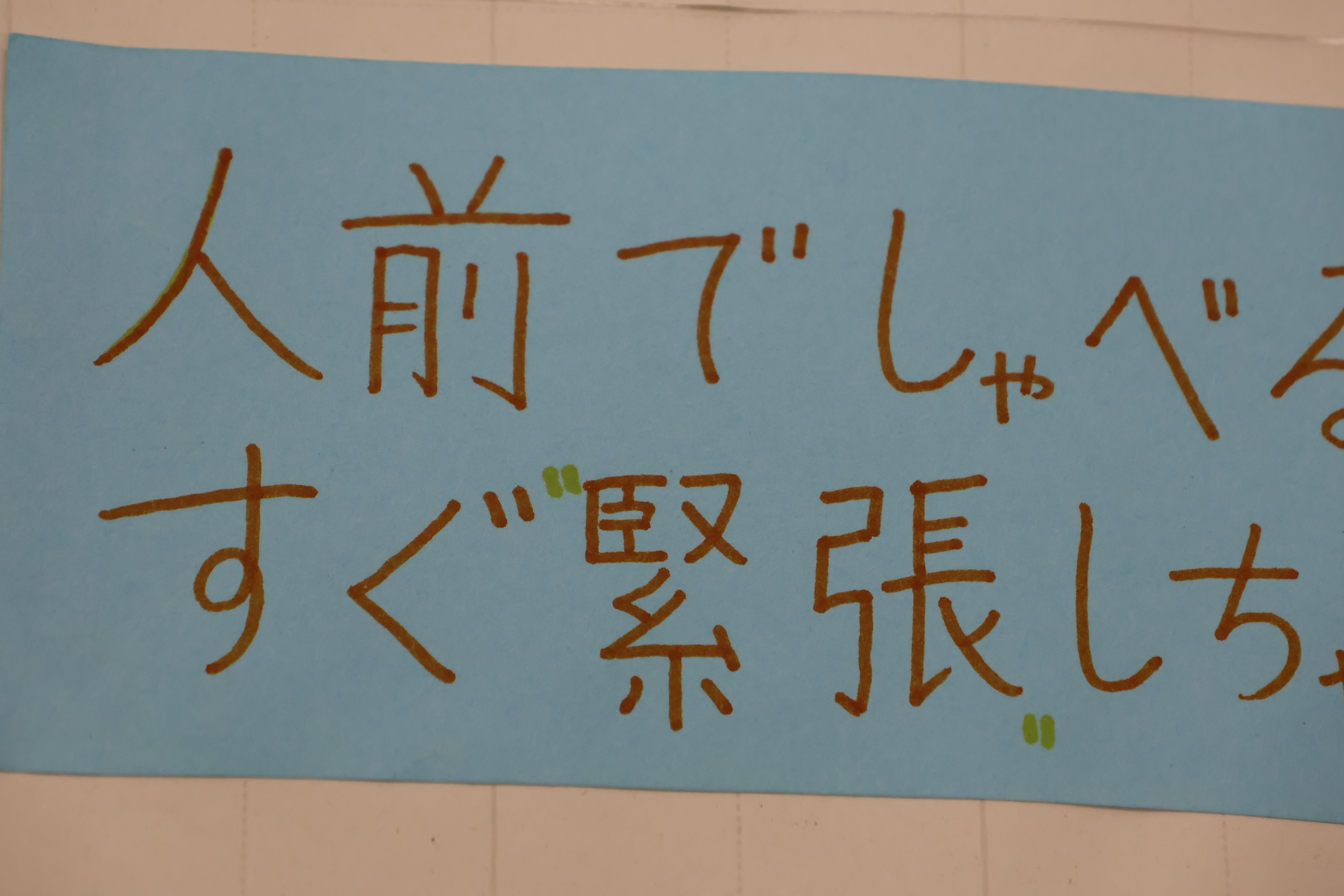
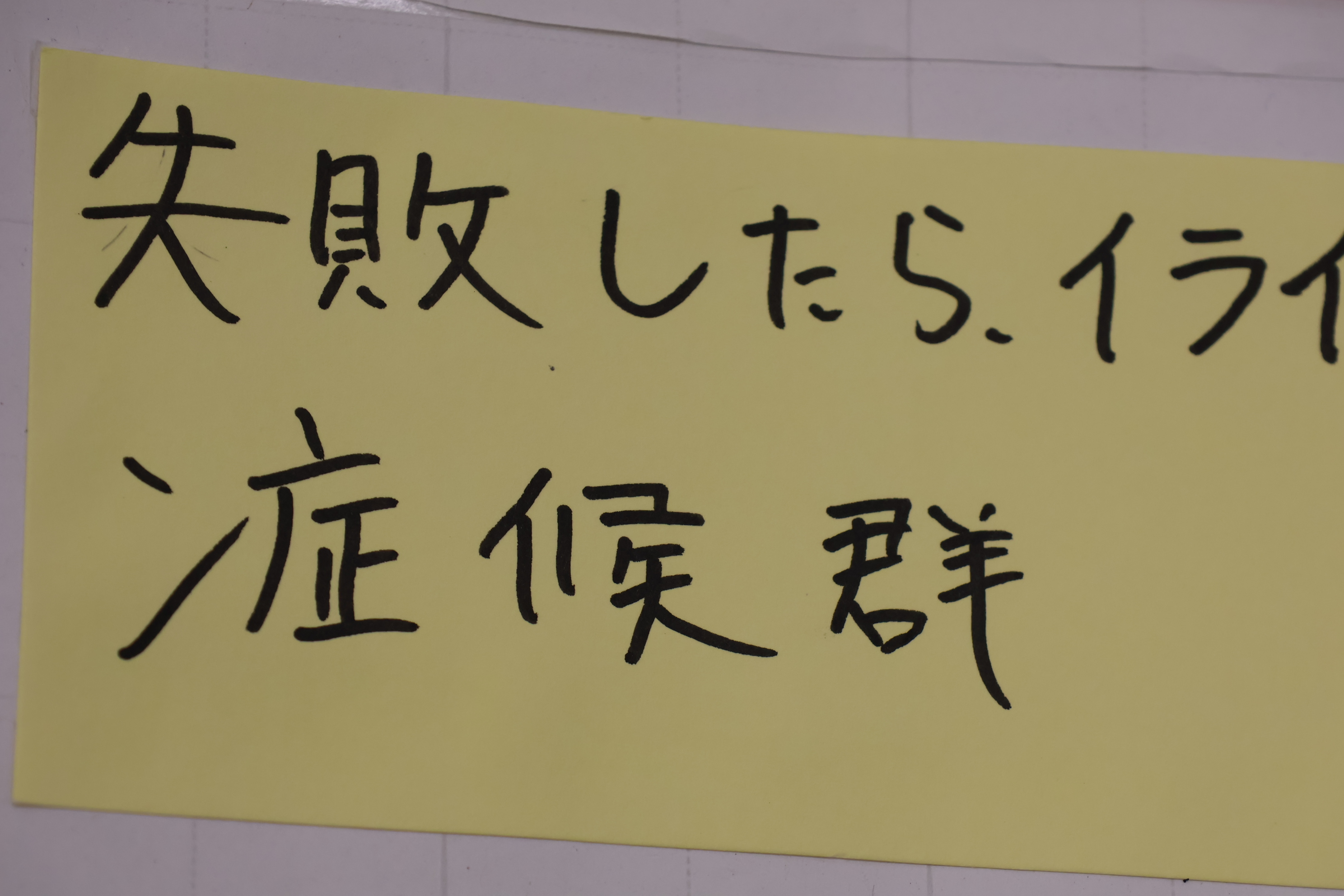
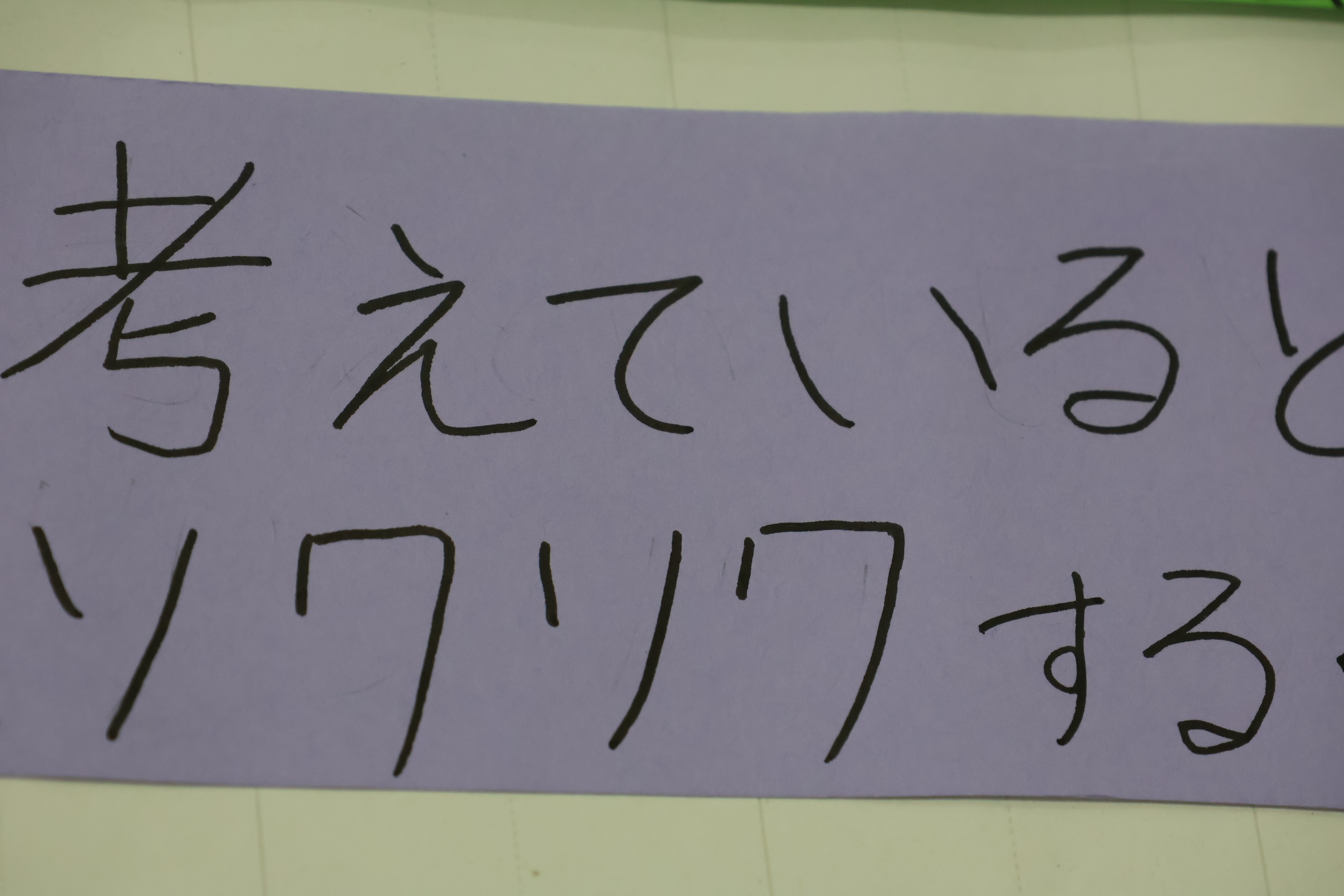

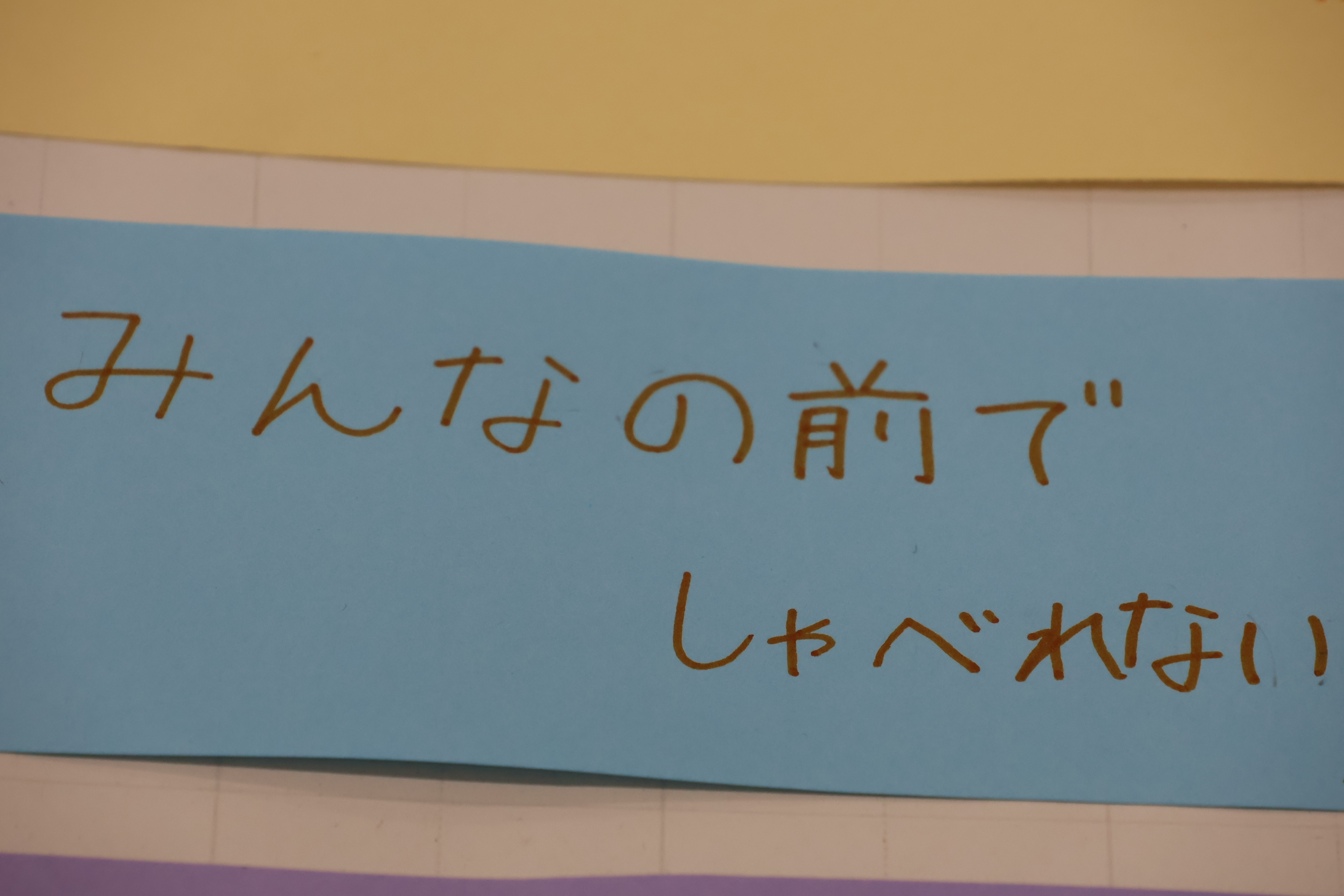
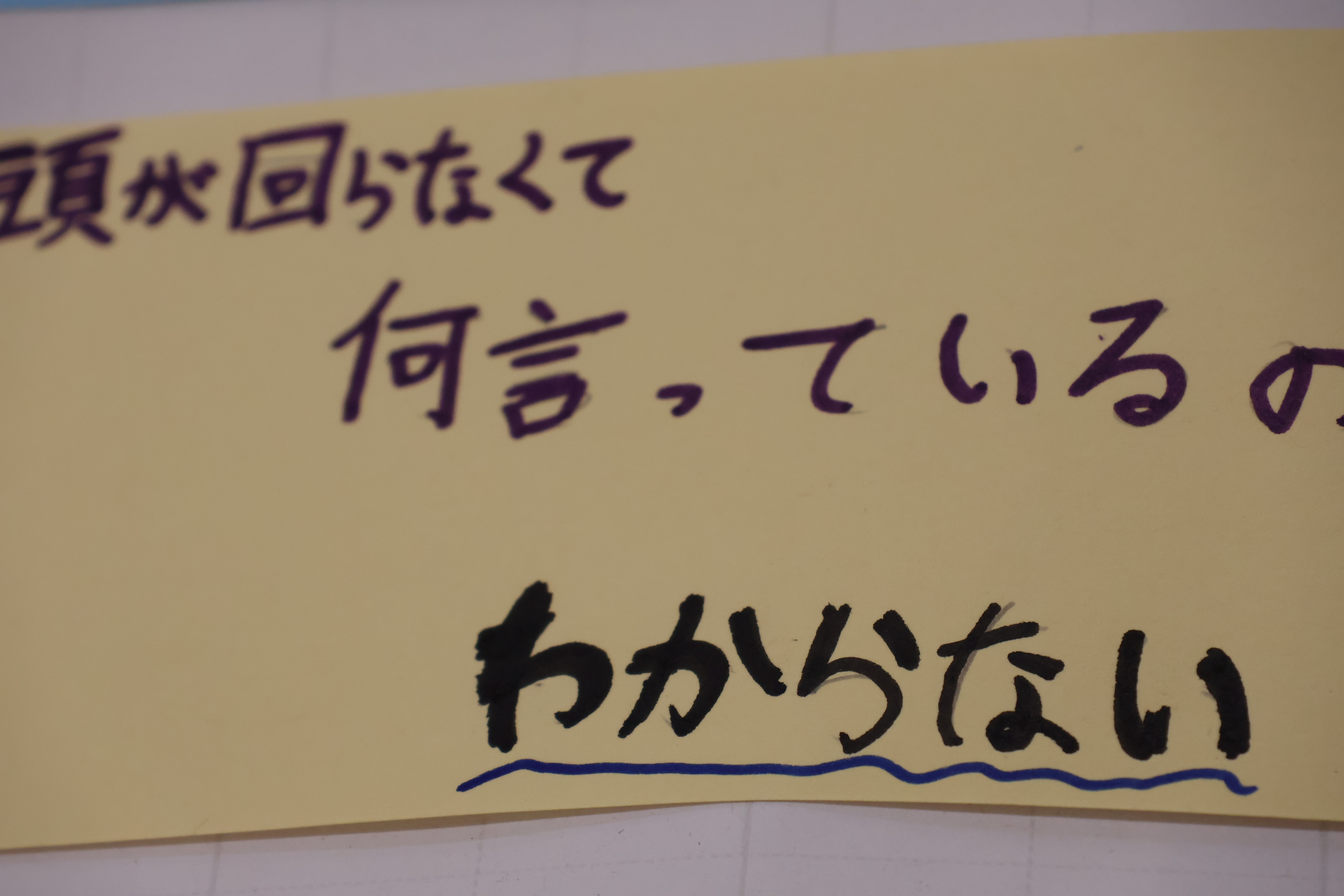
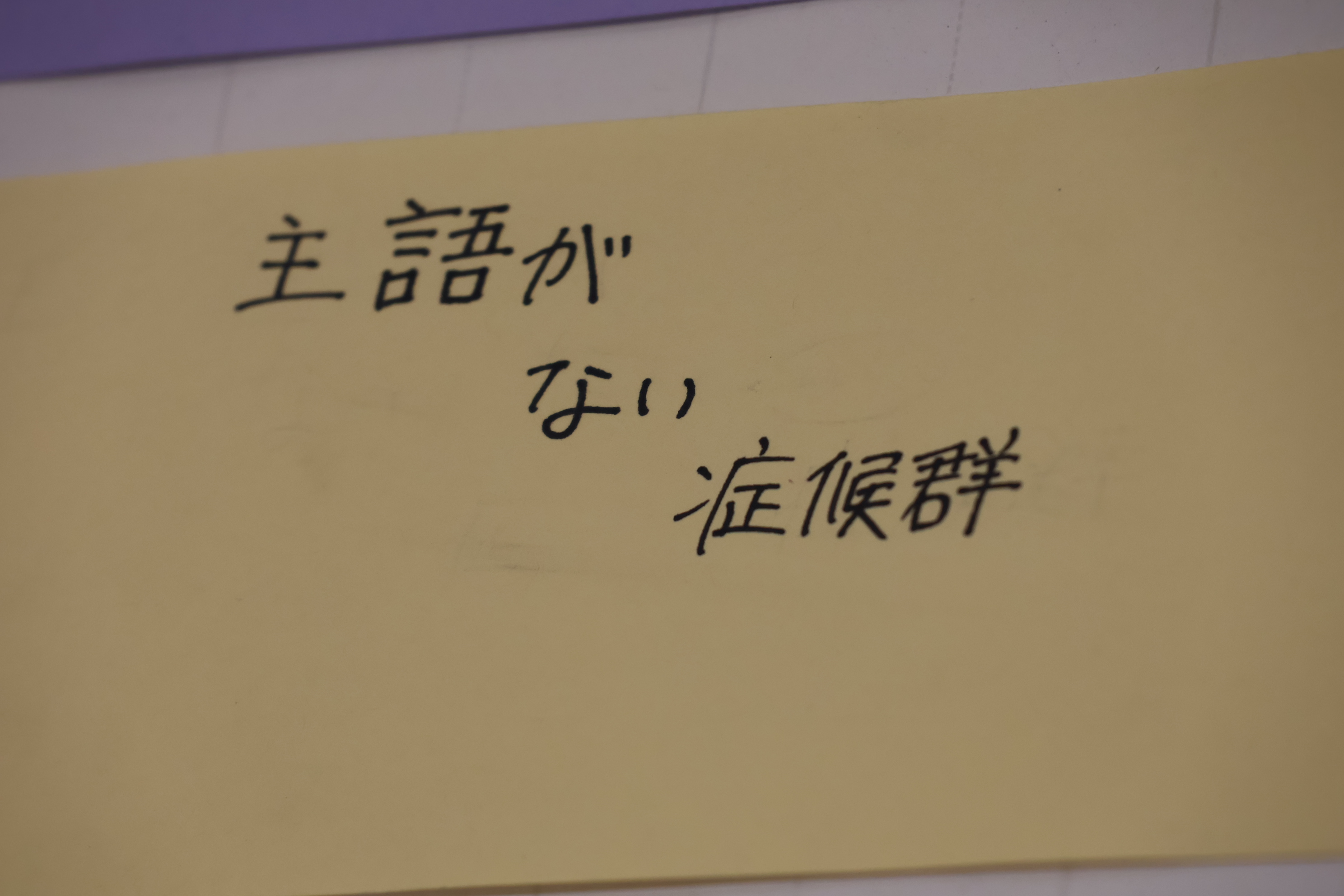
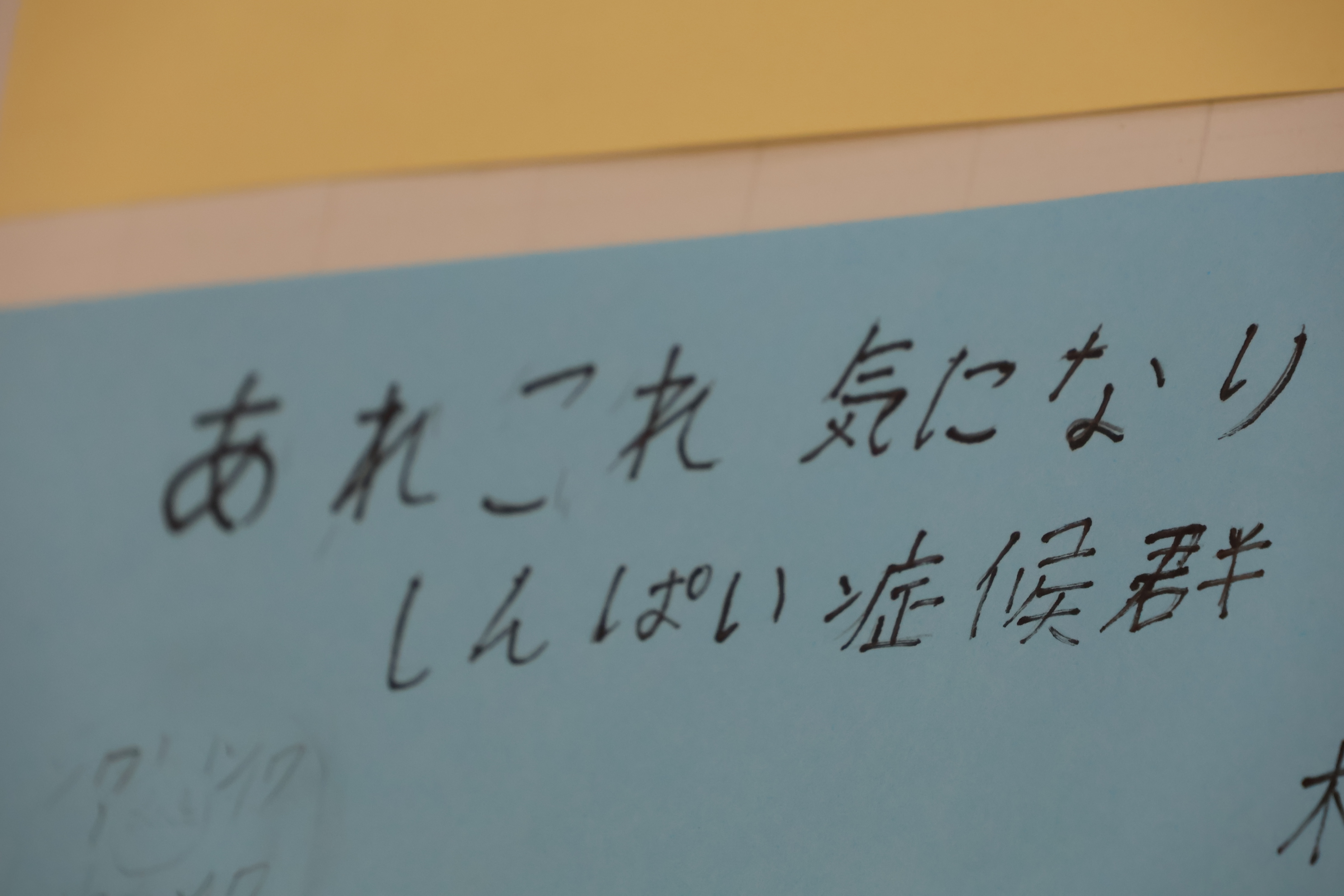
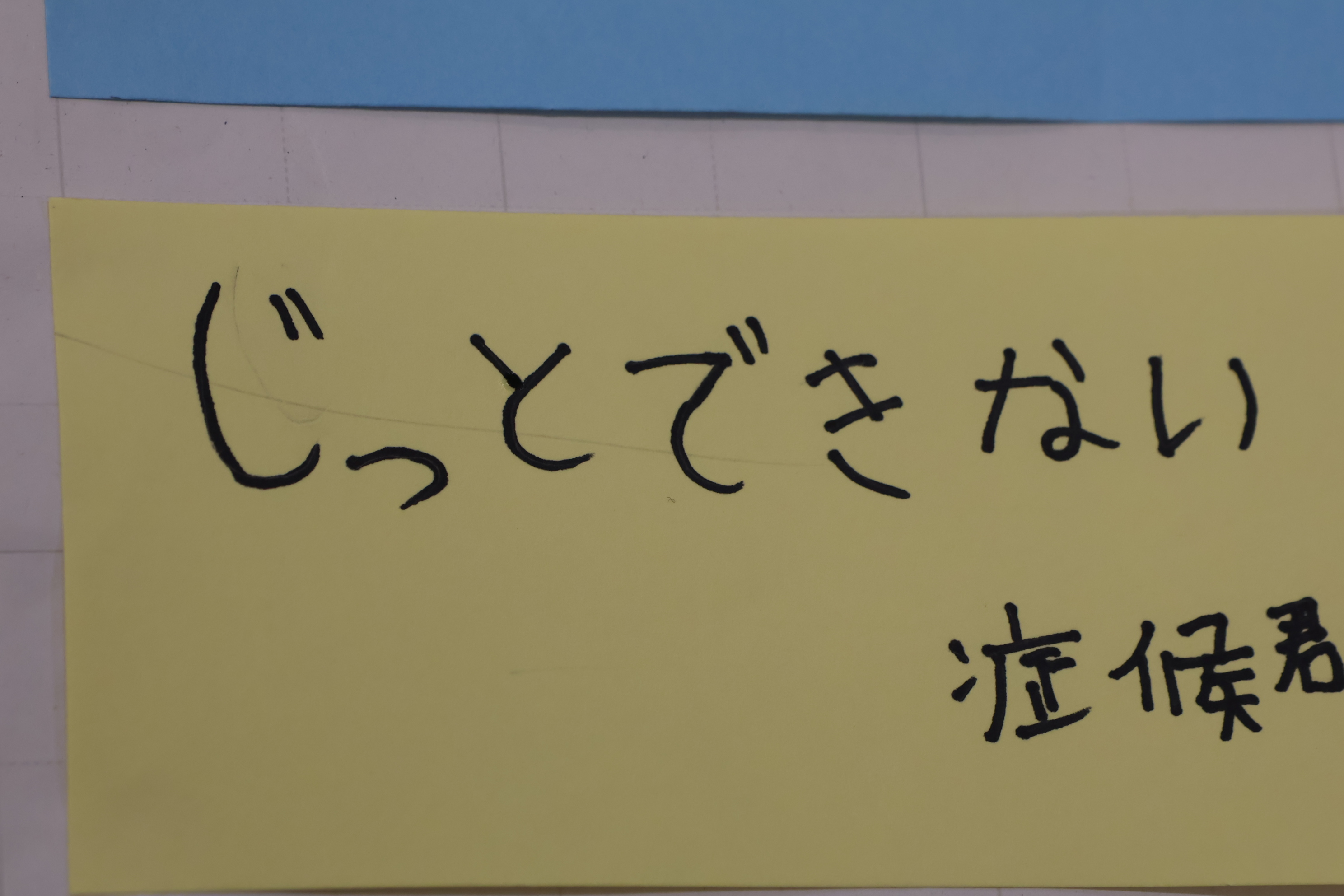
この取組は、べてるの家の当事者研究を参考にしています。
以下に、自分を助ける方法としての「当事者研究」とは(TOKYO人権 第97号(令和5年2月28日発行)を転載します。
―「自分自身で、ともに」で社会とつながる
自らの生きづらさにアプローチする方法として、近年、「当事者研究※1」が注目を浴びています。「自分の苦労の研究者になってみる」というアイデアで、2001年に精神障害などを経験した当事者の自助活動の一つとして生まれました。現在では、病気や障害だけでなく、引きこもり、子育てなど幅広い分野で実践が広がり、2022年3月には『子ども当事者研究』として出版されるなど、子どもたちも取り組めるような内容として咀嚼(そしゃく)されてきました。「当事者研究」の魅力などについて、社会福祉法人浦河べてるの家※2理事でソーシャルワーカーの向谷地 生良(むかいやち・いくよし)さんにお話を伺いました。
自分ごととしての研究
当事者研究は、病気が原因で「爆発」を繰り返す青年に、向谷地さんが「一緒に研究してみない?」と提案したところから始まりました。以来、共通の悩みを抱えた人が、経験を共有しながら「自分の助け方」を見出す方法として全国で運用されてきました。困り事を研究対象として一旦自分から切り離して捉え、家族や仲間たちと語らいながら対処法を探るというスタイルが特徴で、実験感覚でワクワク感を持って取り組めることが魅力といわれています。
例えば、こんなエピソードがあります。自罰傾向が強く発作的に顔面を叩いてしまう人が浦河にやってきました。その人は、発作のたびに病院を受診して鎮静剤を打っていました。浦河に来て間もなく発作が起きたとき、そこにいた仲間が一緒に「発作の止め方」についてワイワイと研究をはじめ、一人のメンバーがその人の脇腹をくすぐると本人が大笑いして、発作が止まりました。その人は、「今まで専門家に任せきりにしていたけれど、自分のことだったんだ」と気づいたそうです。お互いに助け合い、新しい発見をし合う中で、自分の苦労を自分ごととして取り戻す、そんな作用を生む試みとして、当事者研究は知られるようになりました。
困難さは社会とつながっている
「自分自身で、ともに」をキーワードとする当事者研究には他に、「他者を助ける」という重要な作用があります。現在、困難を抱えていない人たちが、困難な状況を生きてきた人たちから学べることは大きいと向谷地さんは指摘します。「精神障害がある人たちの困難さと、一見何事もないように暮らしている人たちの日常は、つながっています。メンタルヘルスの危機というのは、個人的にたまたま不調になったというわけではありません。周囲や地域の事情とも関連していて、社会環境的に生み出されている部分があります。閉鎖された病棟の中で治療されるよりは、その人たちが発信することによって、多くの人にとって、回復の手がかりを得ることができます。社会の側が学ぶ、気づいていける部分がとても大きいのです」。
「人」と「出来事」を分けて考える
もう一つ、人権を考える上での重要な視点を、当事者研究に垣間見ることができます。「当事者研究では、『人』と『出来事』を分けて考える工夫をします。そうすることで、どんな問題や困難が起きても、その人が問題ではなく『問題が問題なのだ』と捉えることが可能になります。何か失敗したとき、自分自身を『ダメな人間だ』と思い込んだり、問題を起こした人を『問題な人』にすり替えて考えたりなど、人と問題を同一視する思考に陥りがちです。人間の存在価値は、本来、失敗や成功、問題の大小によって損なわれるものではありません。当事者研究で、多くの人たちと現実を共有することによって、その現実を生きている人たちをみんなで応援しようという社会の空気をつくっていく作業ができるようになったと思います」と向谷地さんは語ります。
「人づくり」「地域づくり」の可能性
実践の中でお互いの「弱さ」や「苦労」を持ち寄ることで、人と人が繋がり、その場に信頼と助け合いが生まれます。「当事者研究には『自分のことだけれども、みんなのことだ』という、共同性のような土俵をつくる力があります。対話を通じた『人づくり』であり『地域づくり』の活動の一つにもなる」と向谷地さんは考えています。
「当事者研究にマニュアルはない」と向谷地さん。「大切なのは、『ちょっと研究してみようかな』という思考を持ちながら暮らし、その考察を共有すること。一人で抱え込まないで、みんなで助け合って知恵を出し合い、身近なところで生かしていく。そうすることで、地域も社会も元気になるのでは」と呼びかけています。
・向谷地 生良(むかいやち・いくよし)
・インタビュー・執筆 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター専門員)
※1 参考になる情報:向谷地さん執筆の『レッツ!当事者研究』(べてるしあわせ研究所)のほか、メンタルヘルスマガジン『こころの元気+』で毎月、べてるの家の当事者研究を紹介しています。
◎私たちのはじまりの風景15(12/12)
ここはどこでしょう?









◎これってどうするん?に応える仲間として(12/11:1年技術の授業)

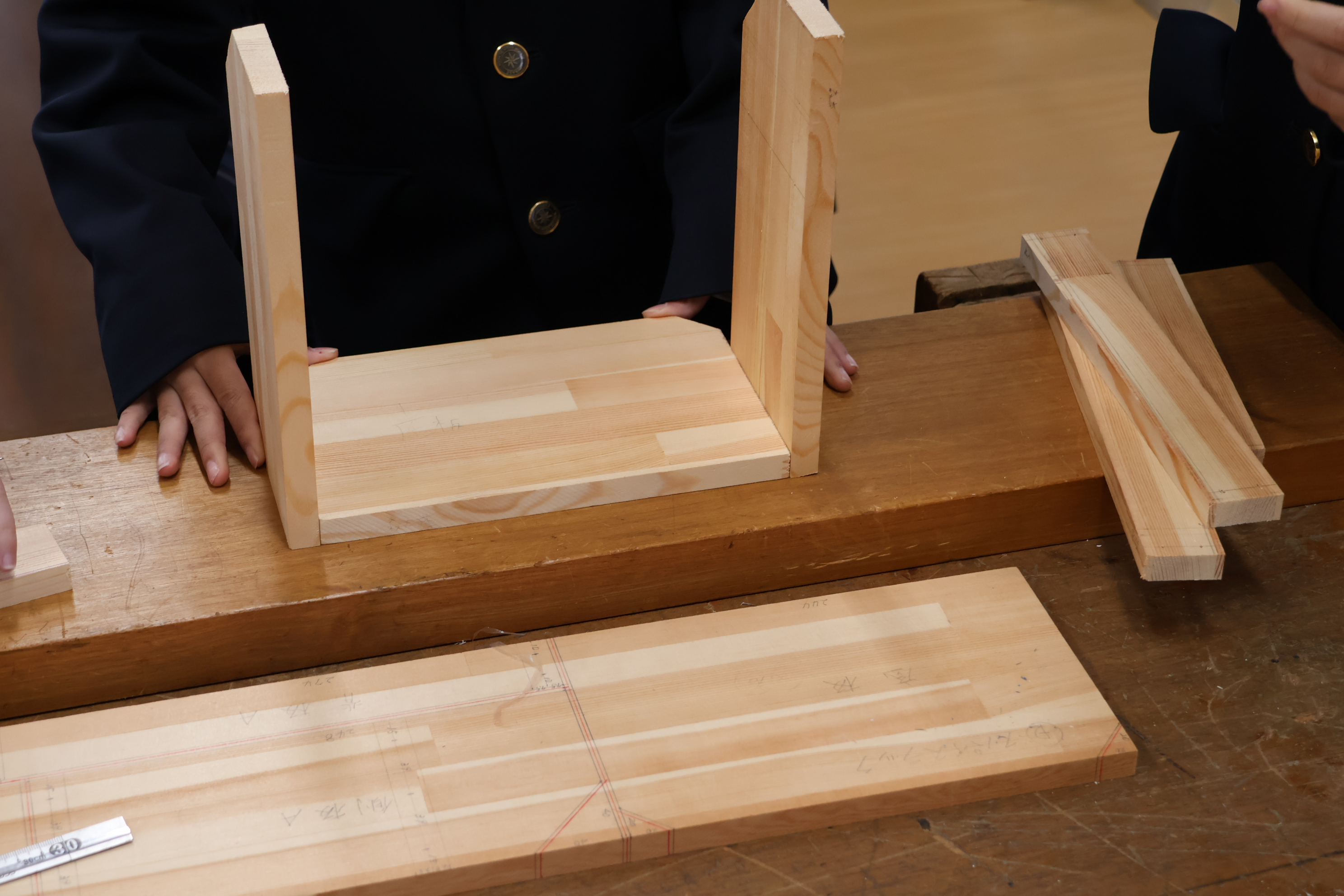

◎クリスマスキャルロが流れる頃には(12/11)
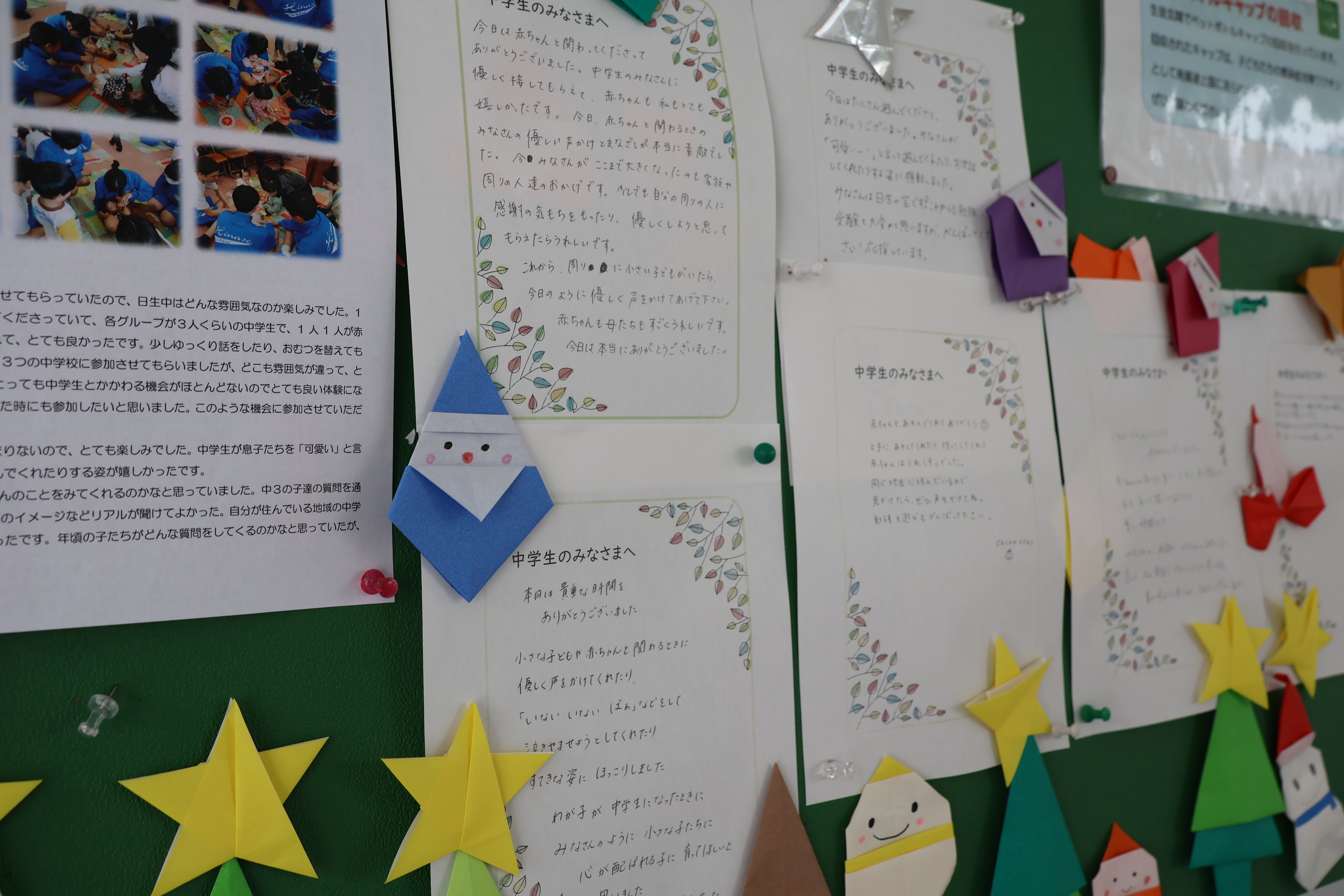
11月に取り組んだ赤ちゃん登校日に、来校してくださったお母さんから日生中学校へメッセージが届きました。玄関掲示板に紹介していますので、個別懇談時(16日~20日)にもご覧ください。
〈金色のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に 与謝野晶子〉(12/10)

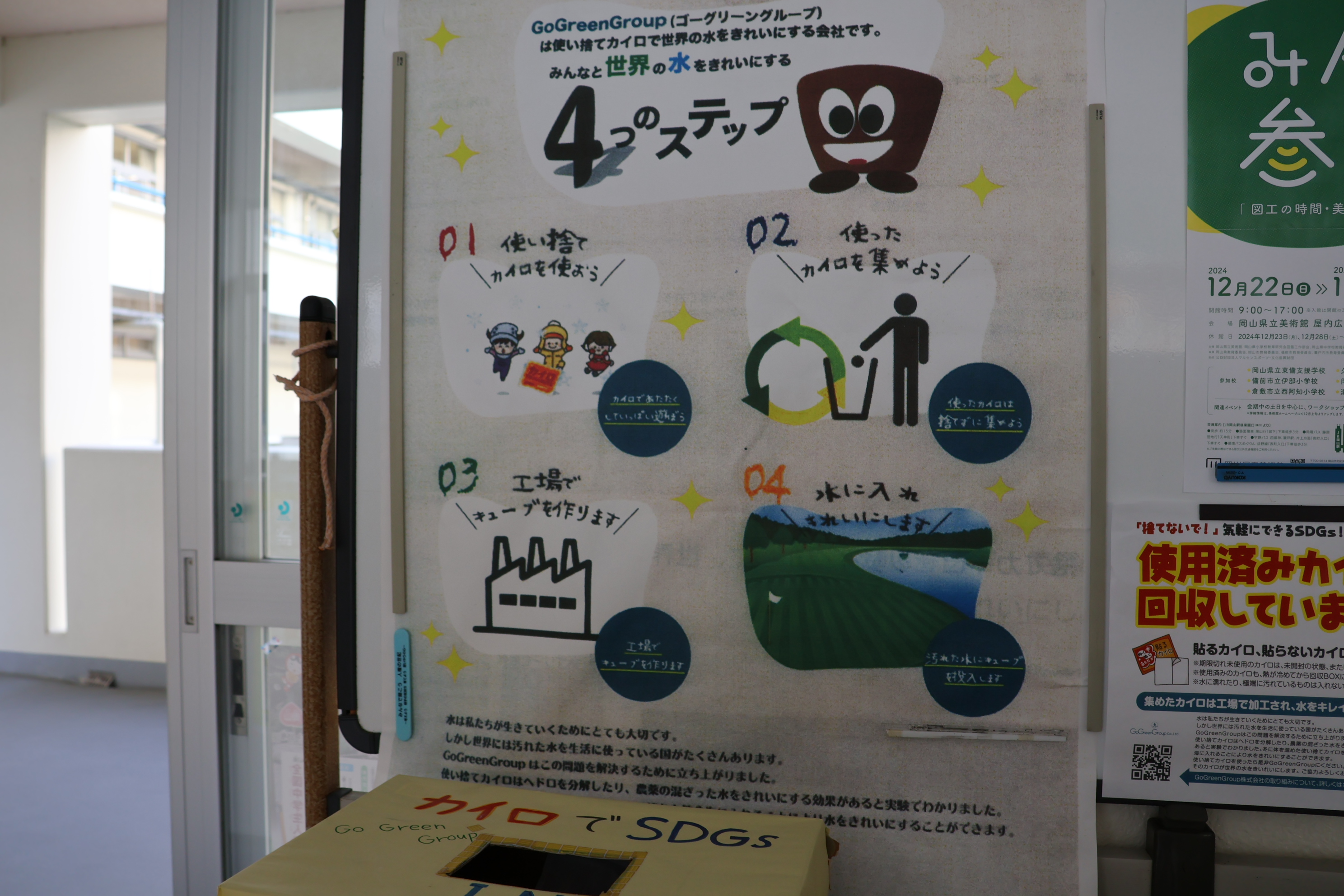
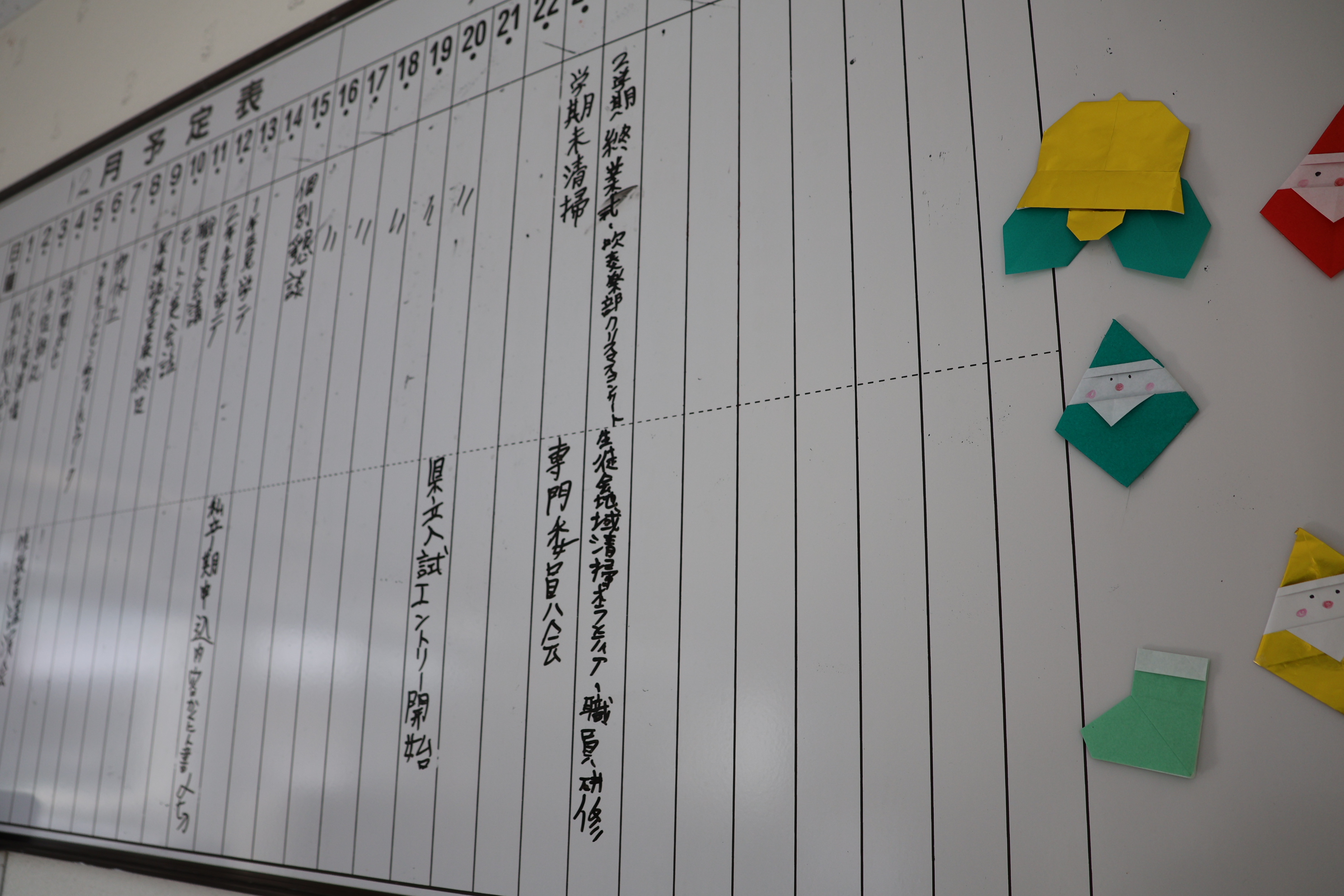
〈新しきうたの末踏に至らむと生き来ん姿樹ならば何か 芦田高子〉(12/9)

◎歩く・知る・考える、未来へつなげる
~長島愛生園フィールドワーク(12/6)









◎金泰九さんから学ぶ(12/5)
3年生は道徳で、『虎ハ眠ラズ』を活用した視聴学習に取り組みました。明日は長島愛生園のフィールドワークへ出発します。
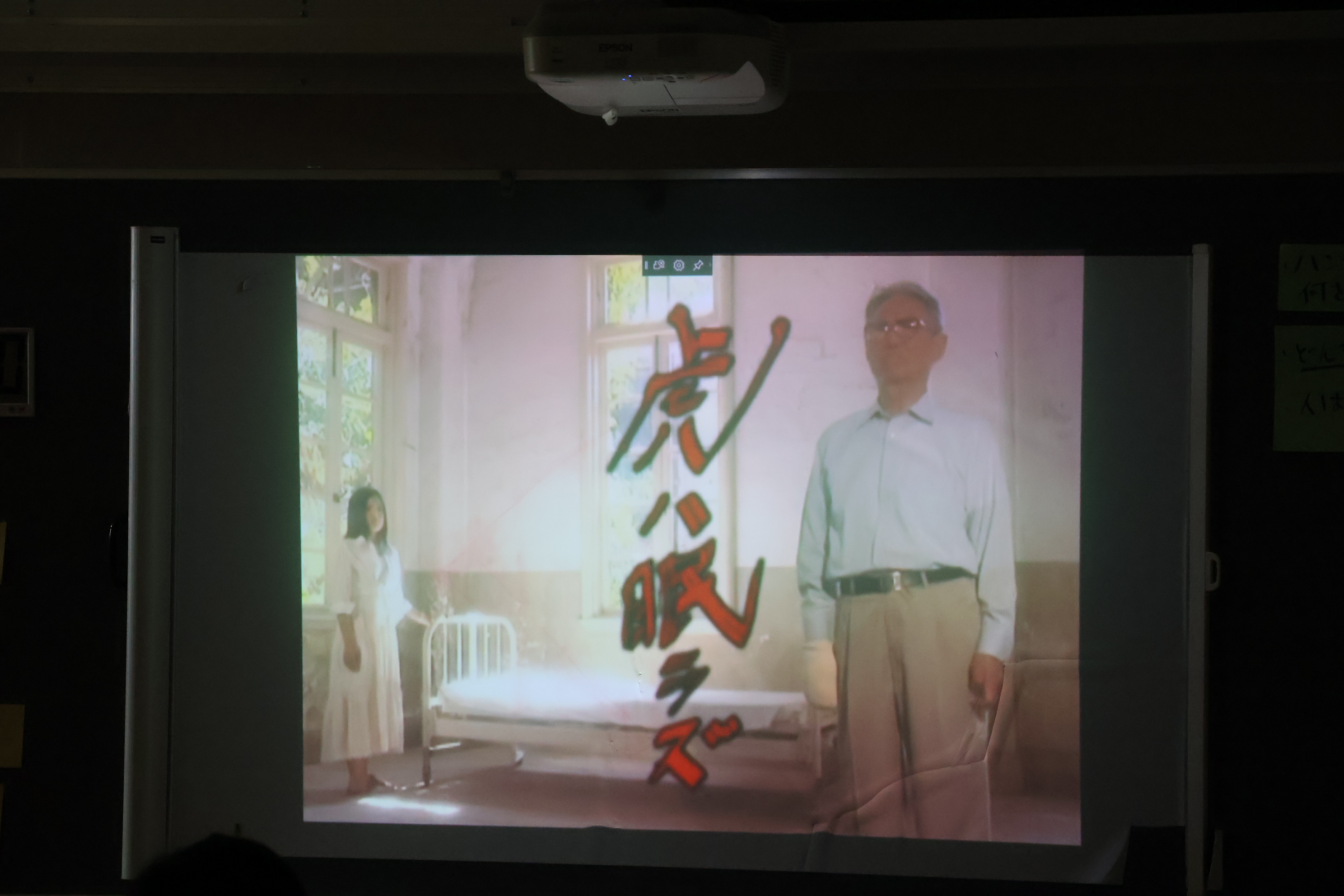


金さんの生き様から自分の生き方をみつめること
想像を絶するような過酷な人生を歩んでこられたはずなのに、限りなく、やさしく、豊かで深く、そして勁(つよ)い。大らかな人柄と穏やかな語り口が醸しだす何とも言えぬ柔らかさに誰もが引きつけられ、全国各地に息子や娘が次々と生まれました。私たちの仲間たちもそのひとりだと自負しています。金泰九(Taegoo Kim)さんが亡くなり、はや9年が経ちました。その年の夏祭りでは花火が打ち上がる夜空を見上げ、江州音頭の太鼓の音に酔いました。10月には近しい仲間らと90歳のお祝いをし、コカコーラを飲み、アリランを一緒に歌い、楽しい時間を過ごさせていただきました。また来園することを約束して別れましたが、2016年11月19日早朝に逝去の知らせがありました。
金さんは1926年現在の韓国陜川(ハプチョン)生まれ、12歳で父を頼って日本に渡って来られました。1945年旧陸軍兵器学校卒業直前に日本の敗戦で復員します。1949年旧大阪市立商科大学(現大阪公立大学)在学中に発病し、1952年に強制隔離され、亡くなるまでの約60年間の大半を長島愛生園で暮らされました。原告に先頭となって加わった国賠訴訟は2001年、熊本地裁が国の強制隔離政策を違憲と判断し、勝訴します。その後は戦時中、日本の統治下で強制隔離政策が行われた韓国・台湾の元患者の補償問題も支援されました。2007年にまとめた自伝『我が八十歳に乾杯~在日朝鮮人ハンセン病回復者として生きた~』(牧歌舎)には金さんの生き様の一部が書かれています。
『…人権侵害のらい予防法を廃止するにおいて、法廃止に消極的態度をとっていた私は自分を恥じるのである。その理由なるものは、「功利的」な考えでしかなかったからである。それ以来私は「人権を」全てに優先して考えるようになった。「自他ともの人権を」である。全ての事象が人権と関わっている気もするのである。その場合、人権を最優先にして考えてみると、ことに理非が明瞭にみえてくる気がするのである』
つい先月、2024年11月19日は金さんが亡くなられて9年目の秋となりました。それに近い16日(土)には、第3回金泰九さんに学ぶ教育実戦交流会を開催しました。全国の各地から、金さんの在りし日を偲ぶとともに、教育に携わる者として、金さんからの学びや意志を引き継ぎながら、各地ですすめている実践を交流することができました。
明日、三年生は、長島の地を歩き、「過去・現在・未来」をつなぐための学習を進めていきます。
◎ひな中の風✨(12/5)
2024人権週間にあたって~歩み新たに日に生せば~
(1)1948年12月10日
フランスのパリで開かれた国際連合総会において、第二次世界大戦の悲惨な結果を反省し、人権尊重が世界における自由・正義・平和の基礎であるとの『世界人権宣言』が採択されました。この宣言は「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」という人間の尊さを基本に、人間らしい暮らしをしていくための権利を宣言しています。
1950年の第5回国連総会で、毎年12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」として世界中で記念行事を行うことが決議されました。それを記念して、12月10日に至る1週間(12月4日から12月10日まで)が人権週間となっています。
日生中学校でもこの時期を中心に、「いじめや他人を傷つける言動がないか。友だちとともに、自分らしい生活をおくることができているか。」について考え、3日の全校朝礼では、「ありがとう」「ごめんなさい」など、より人とのかかわりを大切にしようと、話し合いました。
1年生は、備前市自立支援協議会の椙原さん・森下さん、小寺スクールソーシャルワーカーをお招きして、自分自身の特性を理解すると同時に、「自分研究」をもとに「クラスで暮らす仲間」をお互いが理解し合う学習に取り組みました。2年生は、職場体験学習の取組に重ねて、NPO法人きずなの川元さんをお招きして、社会モデルとしての「ホームレス問題」について学び、勤労観や福祉、社会のありようについて深く考えることができました。3年生は、ハンセン病回復者である金泰九さんの生き方を視聴学習し、明日6日には、長島愛生園フィールドワークで、「自分たちが生きるこれからの社会をどのように創っていくか」について探求していきます。12日には、長島愛生園の田村学芸員さんをお招きし、シチズンシップ(市民性)の意識を高める学習を進めます。
(2)あらためて大切にしたいこと。「いじめ」は人権侵害
ある友達と口をきかない、無視する、一緒に遊ばない、筆箱をかくす、机に落書きをする、カバンをかくす、などという「いじめ」の話は、テレビやインターネットで、残念ながら今も聞きます。
「いじめ」をする人たちが言う理由として「あいつはうざい」とか「背が低い」「女、男のようだ」「うっとうしい」「どんくさい」など聞くにたえない理由をあげるのです。
学校のなかまが、動作が遅かろうが丸顔であろうが、それはその人の「個性」「ちがい」「持ち味」なのです。個性に干渉して、自分に合わせようとしたり、いじめたりすることは、なかまの〈人権〉を侵すことなのです。いじめるほうが、わがままで自分勝手で他人の人権がどれほど大切なものであるのかがわかっていないのです。「いじめ」は許すことのできない人権侵害の事件なのです。
(3)クラスの中の人権侵害
私たちの身近な人権とはどんなものがあるかな。
ひとには個性があるね。育ってきた家庭のちがい、男・女、LGBTQ+、生年月日、顔、身体がそれぞれ違うように、ひとは、それぞれ違った性格をもっている。考え方も感じ方もちがってくるね。すばやい動きのひともいれば、ゆっくりなひともいるし、ほがらかで友達とよく話ができるひともあれば、その反対で無口なひともいるね。それらのちがったひとたちの集まっているのが私たちの「社会」というわけ。それは学校でもクラスの中でも同じだね。
大切なことはそれら他の人・なかまの「ちがい」を認め合うことじゃないかな。ちがった性格やちがった生き方をするひとが、自分らしく、みんなと共に遊んだり、話し合ったり、喜びや悲しみを分かち合ってたりしていけたら。このことを〈人としての自由権〉と言うんだよ。もちろん、自由ということは、自分がわがままで勝手なこととはちがうよ。みんながそれぞれの自由を尊重しあうと同時に、学校やクラスではみんなが安心して遊んだり、勉強したりするために最低のきまりや規則が必要になってくるね。きまりや規則というのはみんなの自由を守るためにあるといえるんじゃないかな。
ひととしての自由権を守るためには、お互いの生き方やちがいを認めるだけでなく、積極的に尊重していく〈個人の尊厳〉を守るという強いものが必要だね。
みんなは安心して学校に登校し、自分の進路の実現に向かって学習できるという〈生存権〉をもっています。また一人ひとりがもっている「勉強する権利」を〈学習権〉と言うんだ。授業中に自分勝手にさわいだり、友達の発言をひやかしたり、ものを投げたりするのは、みんなの学習権を侵害することなんだ。
(4)個人の尊厳を守る
個人の尊厳を守るということは、自分を大切にするのと同じように、他人を大切にし、人を傷つけないことだね。
ひとの性格や行動、顔や身体のかたち、学校の成績などによって差別してはいけないね。もちろんその人の家の職業や出身や宗教、考え方、男女の性別、民族などによって人を差別してはいけないのはわかるよね。就職や結婚の際にそのことで差別することは許されないね。
以上のことをまとめていうと、『人間が人間らしく生きていくうえで、欠かすことのできない自由や権利のことを〈基本的人権〉というんだ。基本的人権が大事で、他のひとの人権を侵す差別がいけないことだということは、君たちはわかっているはず。
でも
「差別がなくなればいい」と考えているだけでは見当違いです。いくら差別が悪いことだとわかっていても、それだけで「差別をなくす力」にはならないからです。
みんなが安心して登校し、静かにゆったりした気持ちで勉強し、遊び、そしてスポーツや生徒会活動にうちこめるようにみんなで努力し合うことが、身近な人権尊重の一歩となります。
(5)江戸時代の末(1855)にあった『渋染一揆』に学ぶ
つい先日、2年生が社会科で学習した「渋染一揆」。この一揆を成功させた人々のうごきを調べてみると、私たちが差別をなくし、共に生きる社会(クラス)をつくるための方法を知ることができます。簡単にまとめていますが、とても大事な視点です。人権週間にあたってみなさんに紹介します。
①差別がここに、こんなかたちであるという事実に気がつくこと!(高い人権感覚)
②その差別はどれほど私たちを苦しめているか、怒りをおぼえること!
(相手の立場に立って、そのつらい気持ちをかんがえてみること)(正しい人権意識)
③その差別のなりたちや、しくみがどうなっているかを学び、差別をなくする道筋を明らかにすること!
(仲間としっかり語り合う 冷静に状況を分析する)
④差別をなくするために、なかまと共に、どういう働きかけをしたらよいか、差別をなくする力(行動力)を身につけること!
(みんなで正しく行動する うごかす(すべ)を整える)
◎✨Which is nicer‚ Yoshinoya or Sukiya?(12/5)
子どもたちのアイデアを活用して、豊かに・楽しく英語!
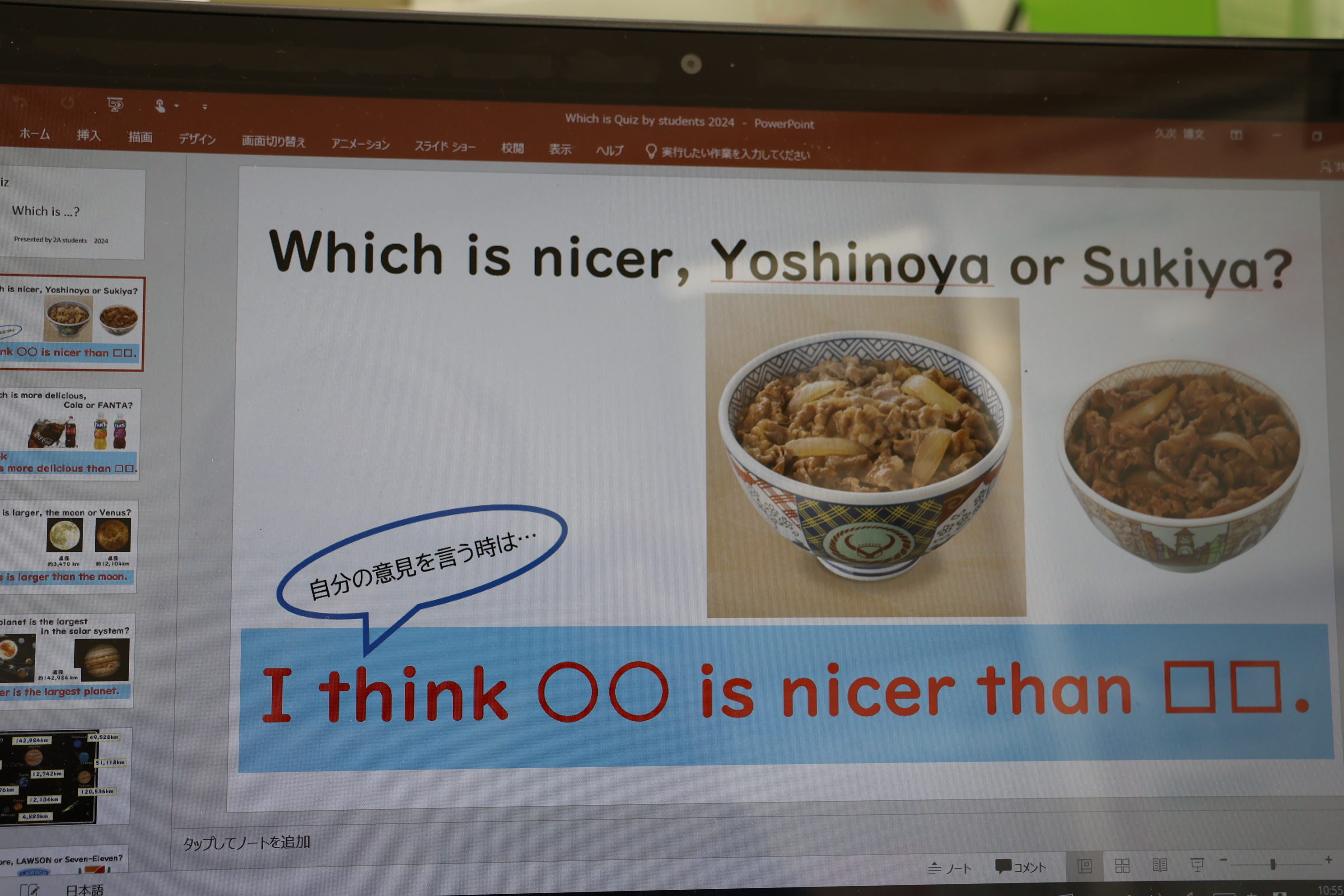
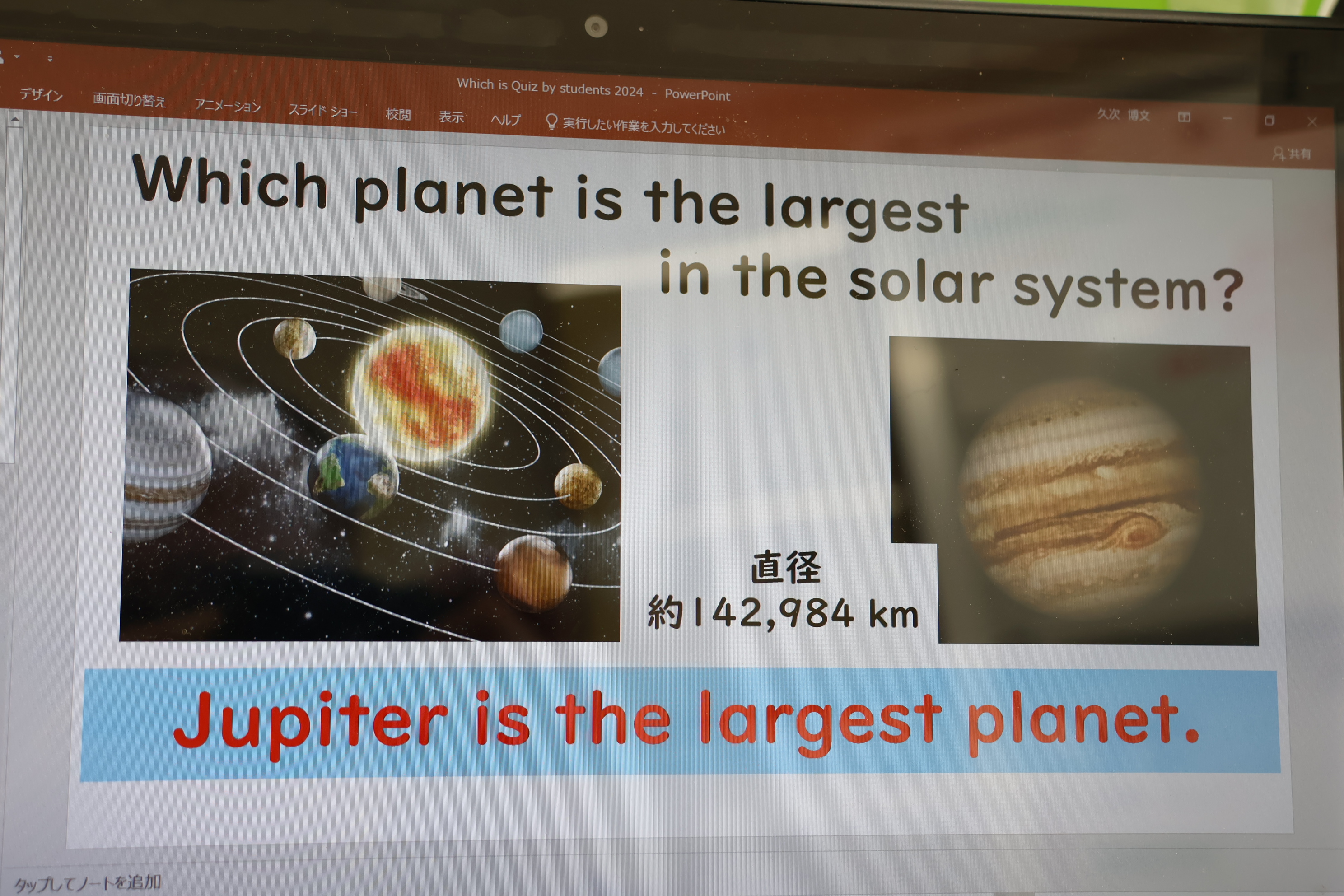
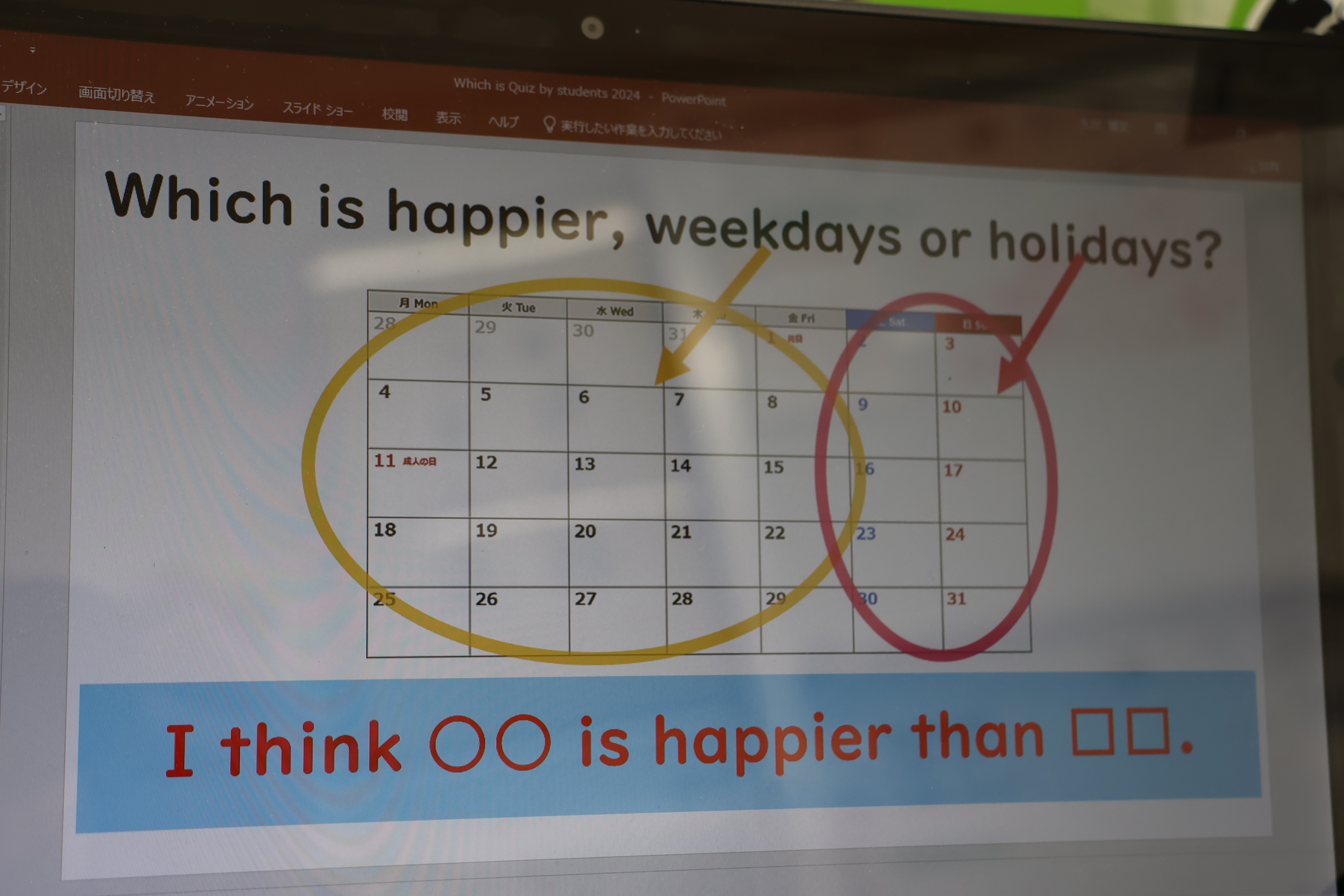
◎未来の選択~未来のパパ&ママを育てる出前講座(12/4)
佐藤久恵さん(川崎医療福祉大学 保健看護学科)をお招きして、3年生は、性感染症や望まない妊娠の予防(避妊・中絶・出産)、妊孕性などについてお話を聴きました。

◎ひな中の風✨(12/4)
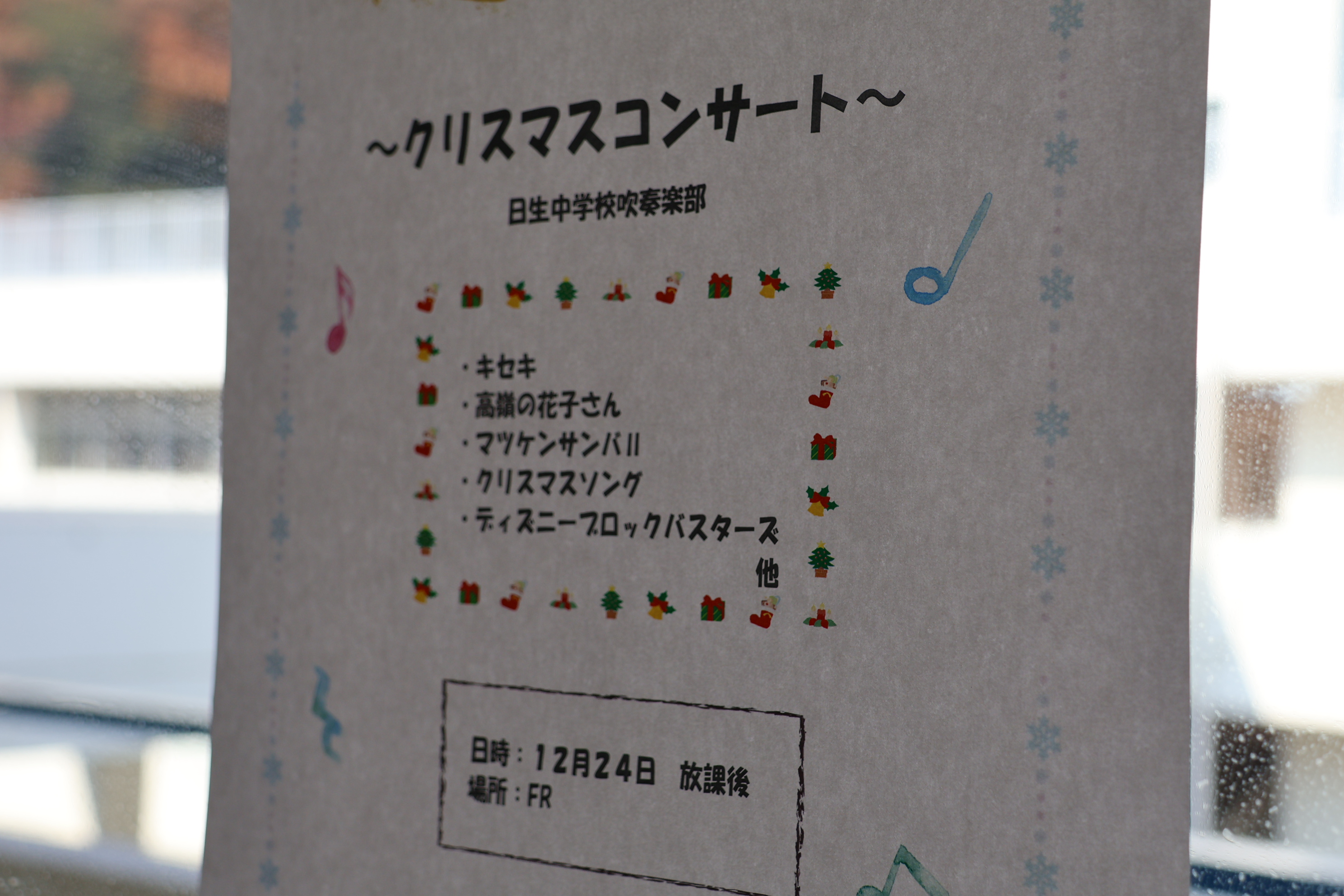
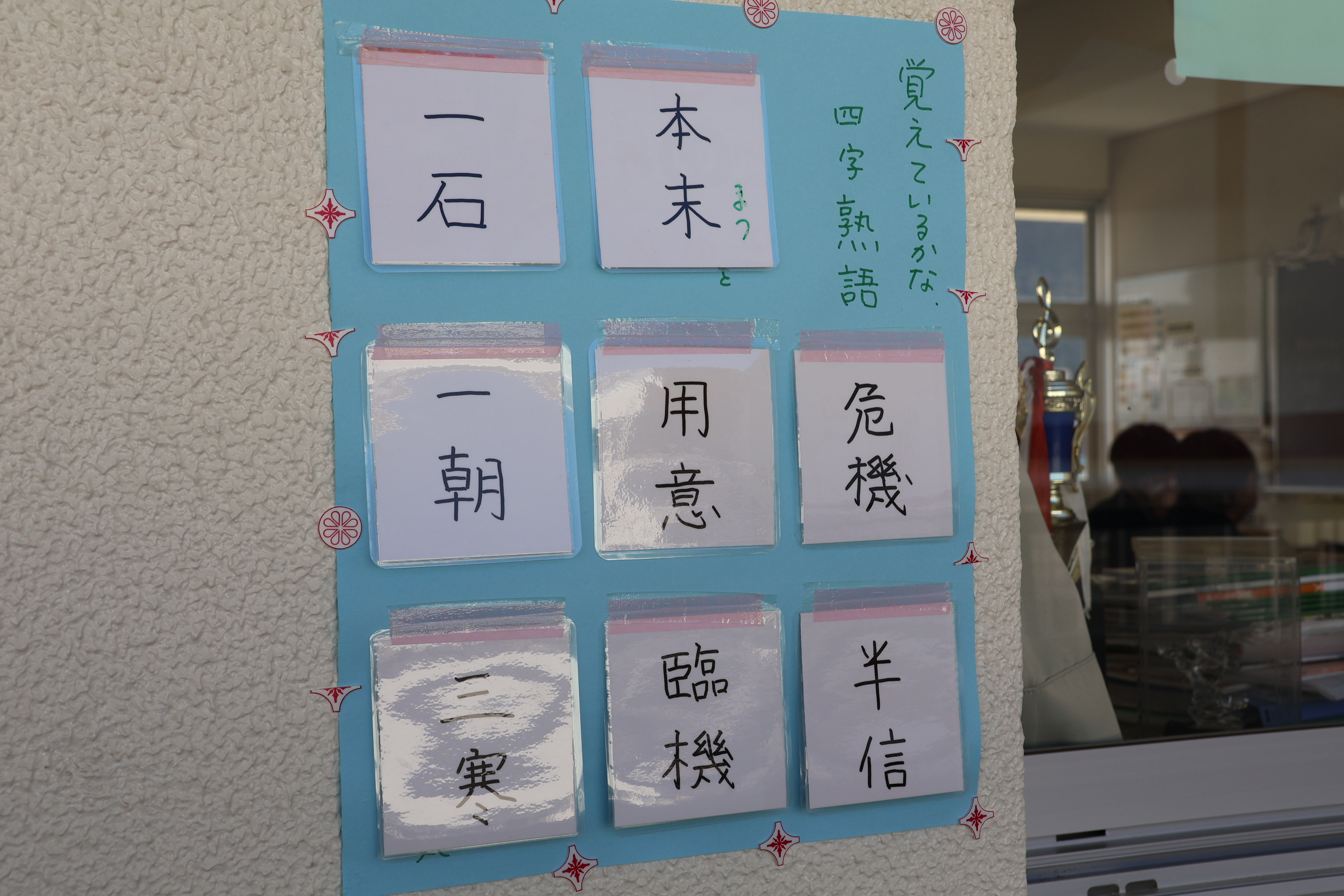

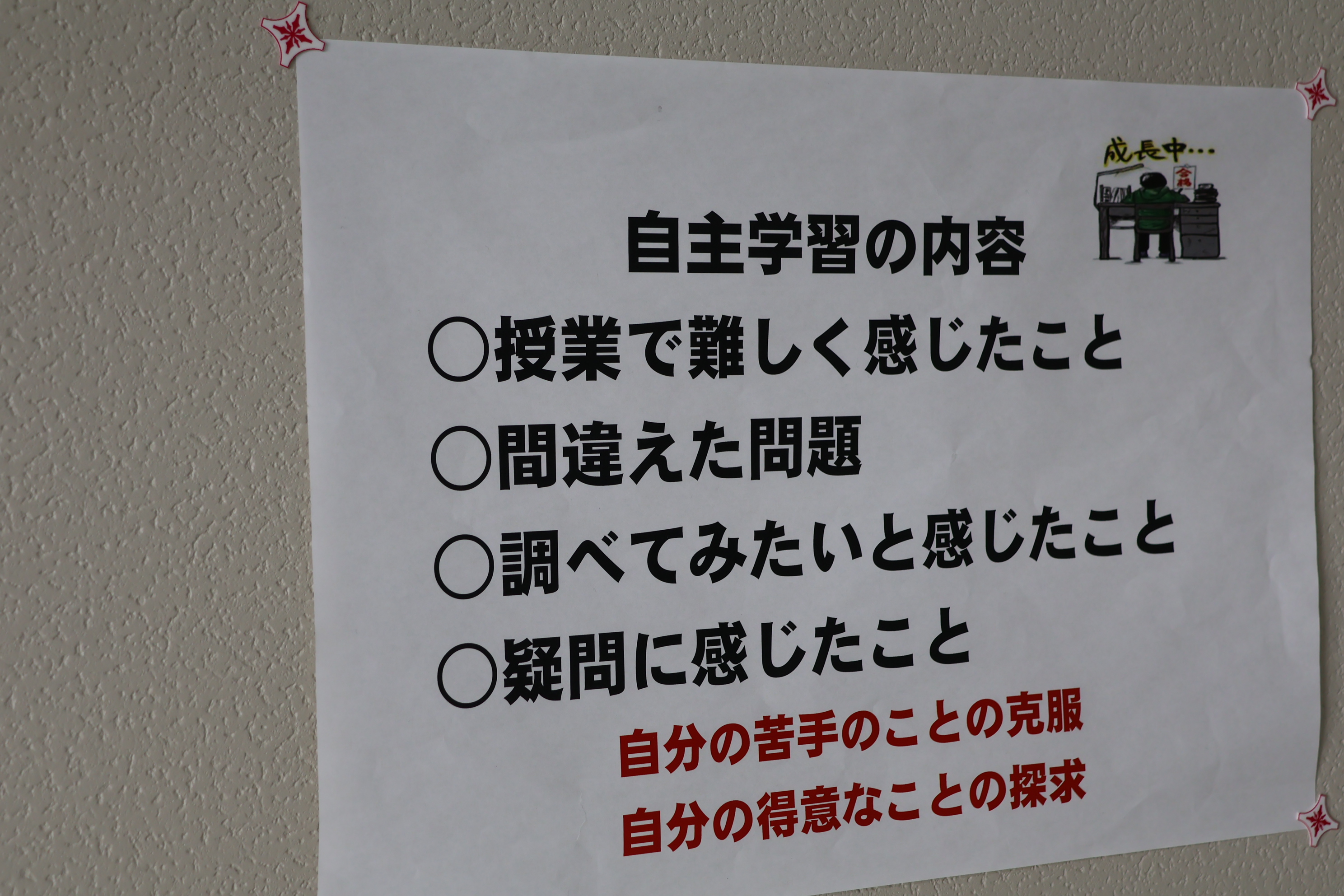
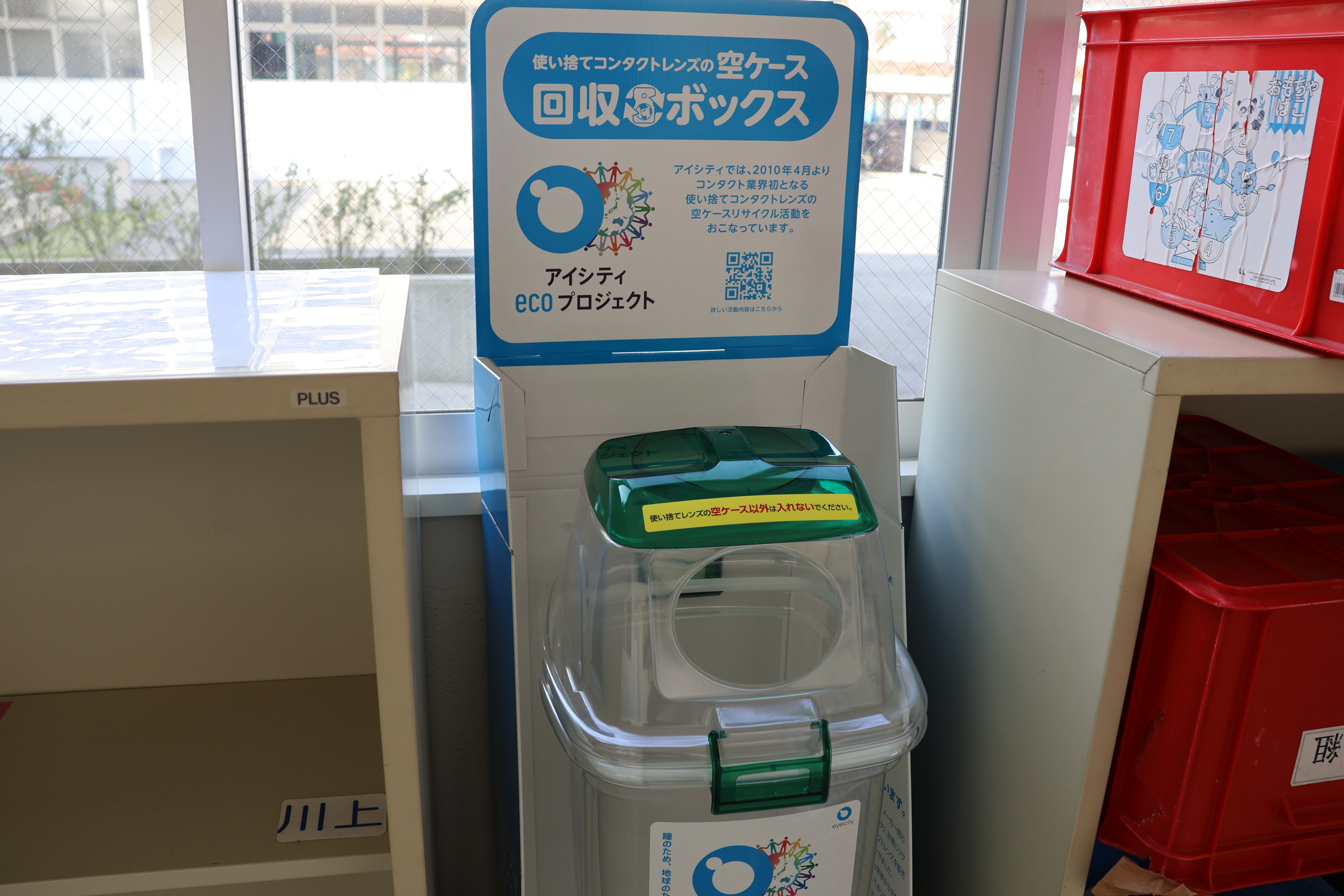

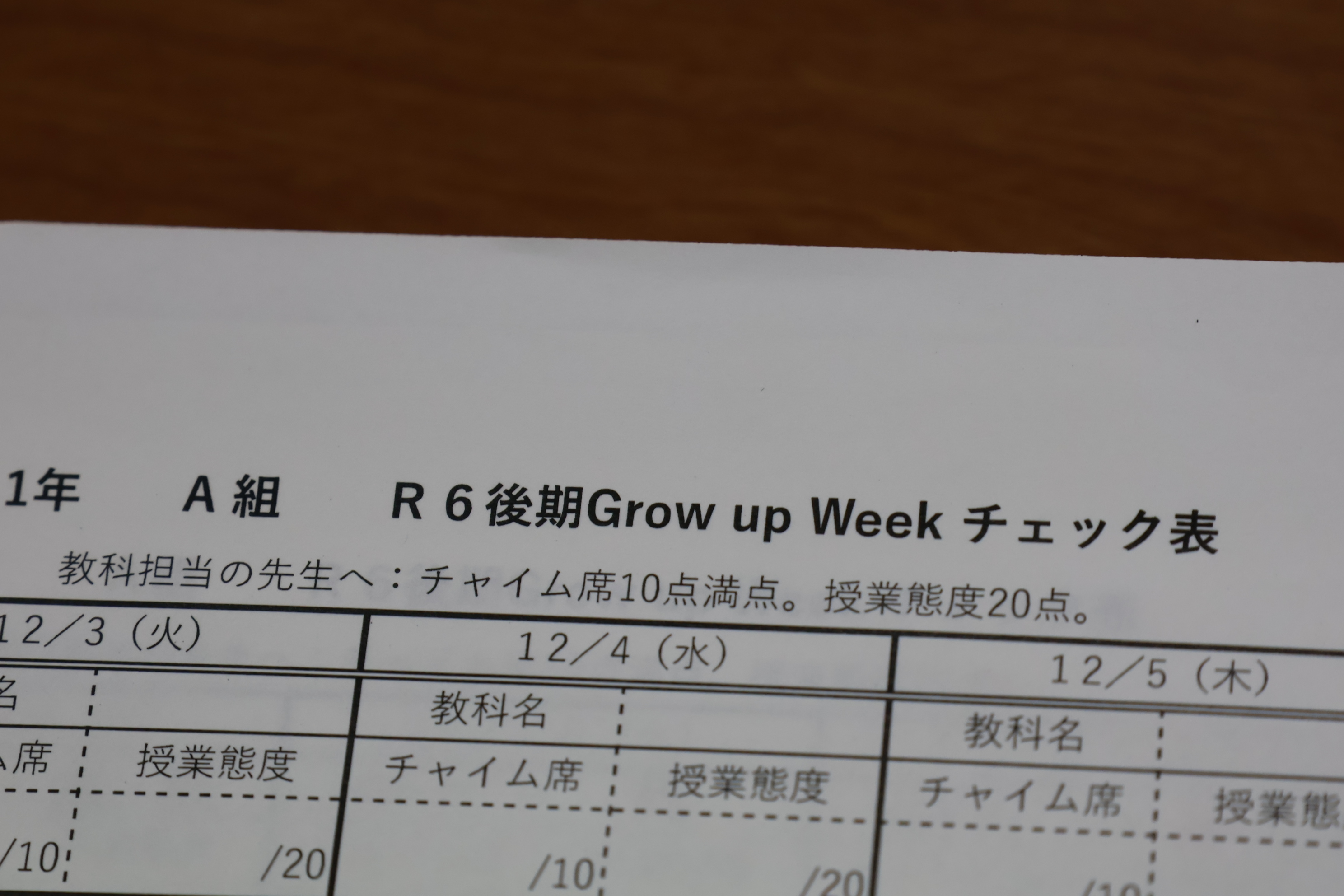


◎日生で輝く 日生が輝く ひな中のちから。
~備前♡日生大橋マラソン2025ボランティアスタッフ 大募集中
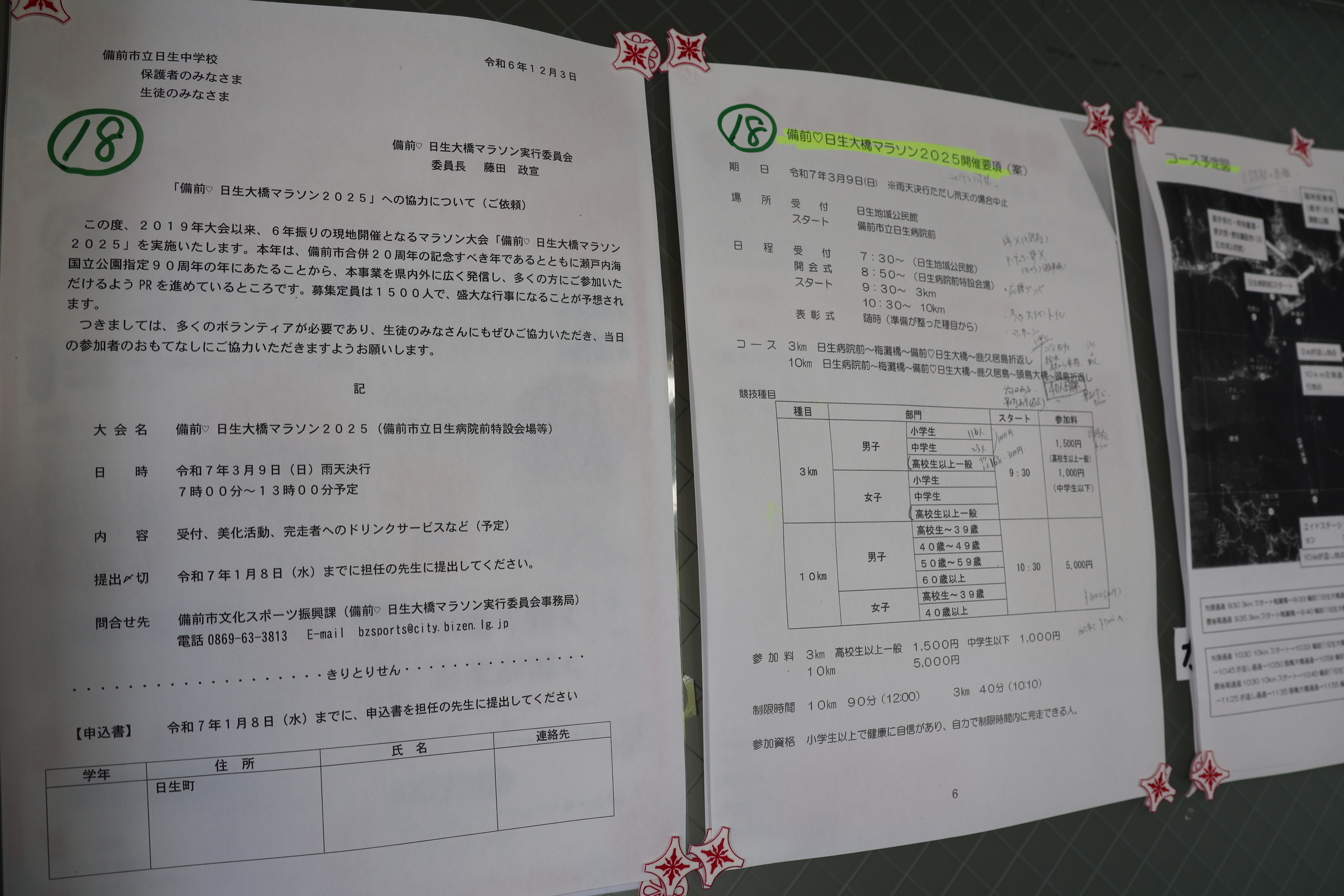
〈ただ、今日ただいま、この場では、人類はすなわちわれわれ二人だ ベケット〉
~子どもの育ち・進路保障を、教育・福祉・家庭・地域との協働で~
今日(12/3)は、第8回ひなせ親の会(子どもの育ちを考える情報交流学習会)でした。朝倉さんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。次回ひなせ親の会は2月18日(新入生1日体験日)を予定しています。

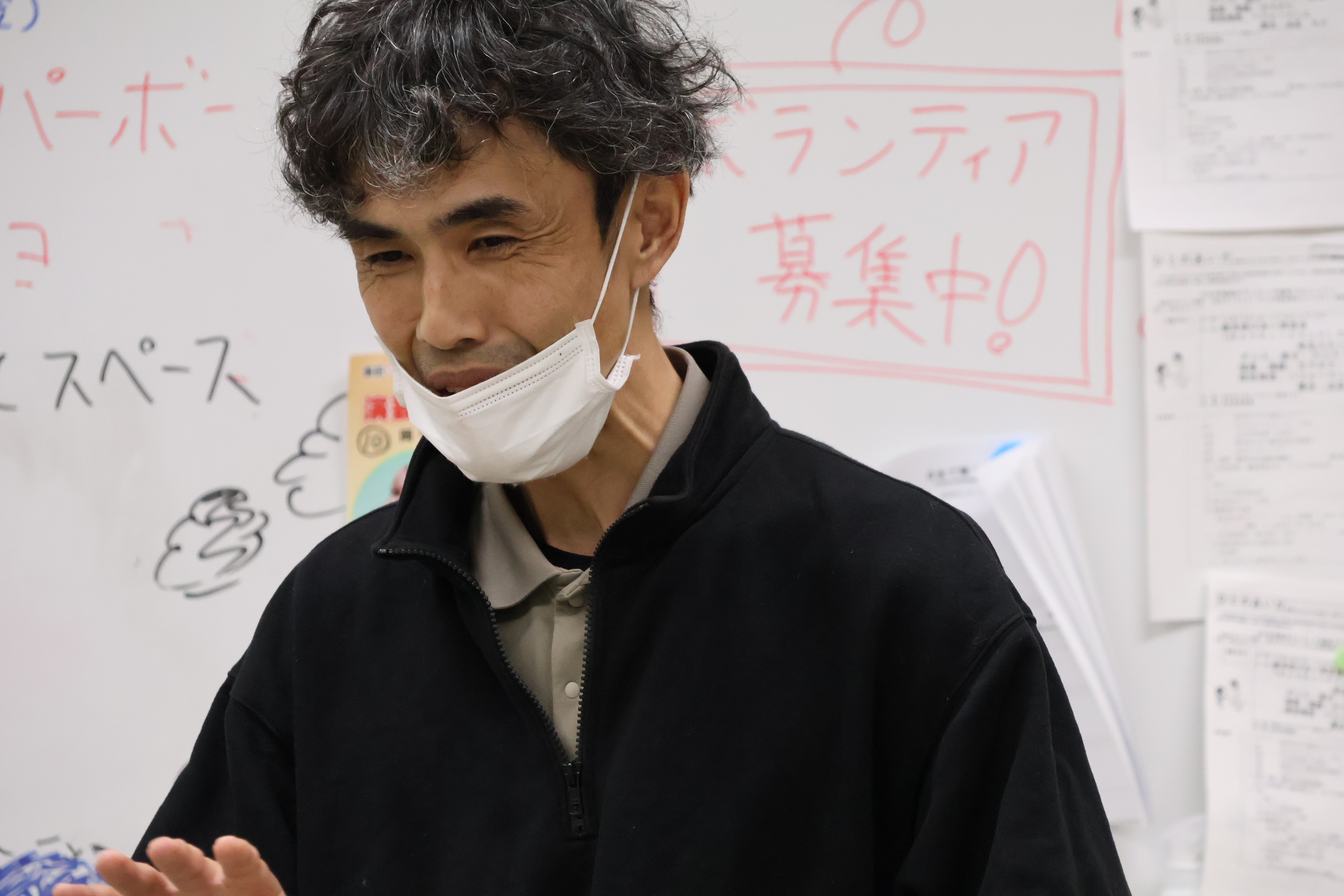
◎月日がたつのははやいなあ
~ようこそ ひな中へ(12/3:新入生保護者説明会)
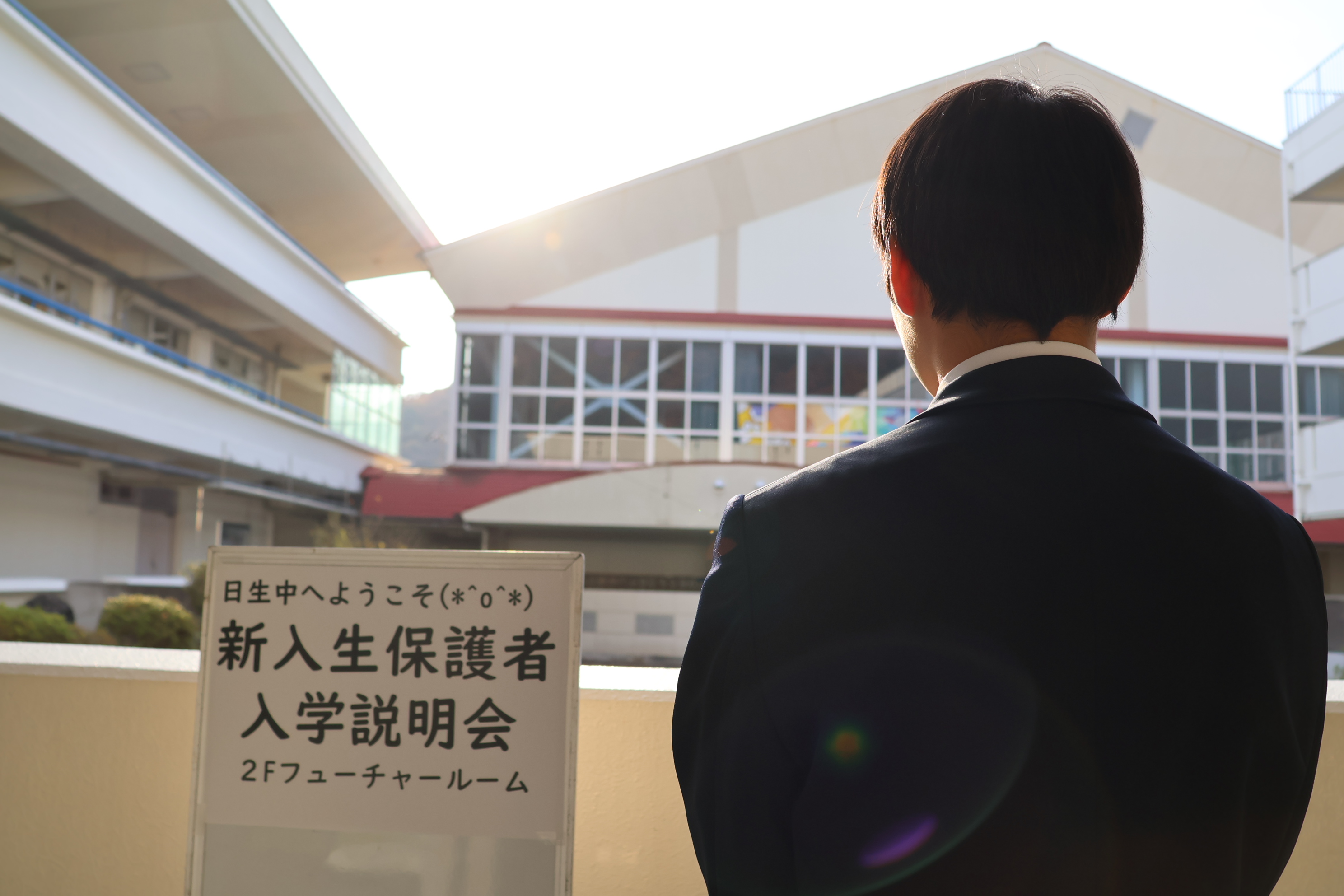


一人ひとりが大切
◎家族読書週間です。楽しく 読む 語る機会に(^_^)

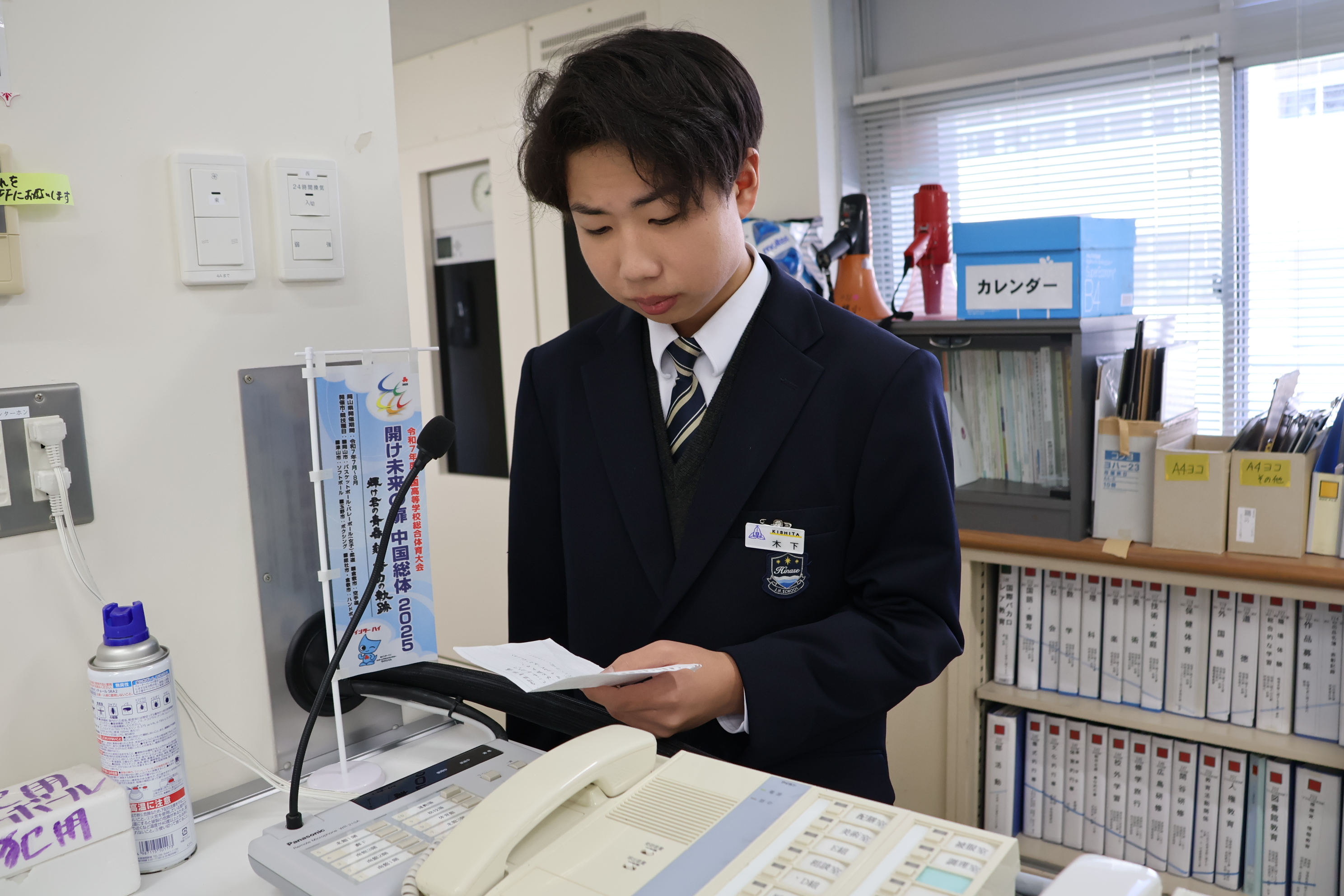

◎渋染一揆に学ぶ すごいぞ2年生!(12/3:社会科授業)
今年度も、2年生社会科では、渋染一揆に学ぶ授業に取り組みました。
渋染一揆とは・・・江戸時代末期、岡山藩は、出費の増大などによって大坂商人からの借銀が増加していました。さらに天保以後、自然災害が相次ぎ、凶作のために年貢の未納が増加し、また黒船の来航による房総半島の警備を幕府から命じられ、これに要する出費や兵制改革などのため、藩の財政は一層危機に瀕しました。岡山藩は、これを克服するため、1855(安政2)年、29ヵ条の「御倹約御触書」を出しました。
この「御触書」の最後の5ヵ条は被差別部落の人々を対象としたもので、「着物の類は無紋・渋染・藍染に限る」「雨天の時、村内の仲間の家に行くときは、どろ足では迷惑だろうから、栗下駄を履くことは許すが、顔見知りの百姓に出会ったら下駄をぬいであいさつすること」「他村へ行くときは下駄を履くことは許さない」など不当な差別を強いるものでした。
これに対し、藩内50余りの被差別部落の人々は何度も寄合を開いて歎願書を差し出すことを決め、知恵を出し合ってまとめあげました。しかし、郡会所へ差し出した歎願書は、期待に反して差し戻されました。
その後、役人の厳しい強要に屈して「御倹約御触書」に請印する村々も出はじめました。歎願の望みを断たれた被差別部落の人々は、岡山藩の筆頭家老である虫明の伊木若狭守忠澄に強訴((注釈)集団直訴)をすることに踏み切ったのです。
1856(安政3)年6月、八日市河原に結集した千数百といわれる一揆勢は、武器も持たずに整然と虫明に向かいました。このことを知った伊木若狭の軍勢は亀井戸に出張って陣を構え、一揆勢は榎塚(※亀井戸、榎塚ともに現在の備前市佐山)で互いに対峙しました。2夜に及ぶねばり強い交渉の末、一揆勢は歎願書の差し出しに成功しました。
以後、被差別部落の人々が渋染・藍染の着物を強制されることはありませんでした。一切の暴力を用いず、御触書を空文化させることに成功したのです。
このことが、「封建制度の時代にあって、他に例を見ない人間の尊厳を守り抜くすばらしい闘い」と評価される所以です。
しかし、この行動は法度を犯すものであったため、藩の取り調べの結果12名が入牢となり、その内の6名は獄死しました。その後、残りの6名は牢内外の部落の人々の歎願運動や協力者の働きによって2年後に釈放されました。
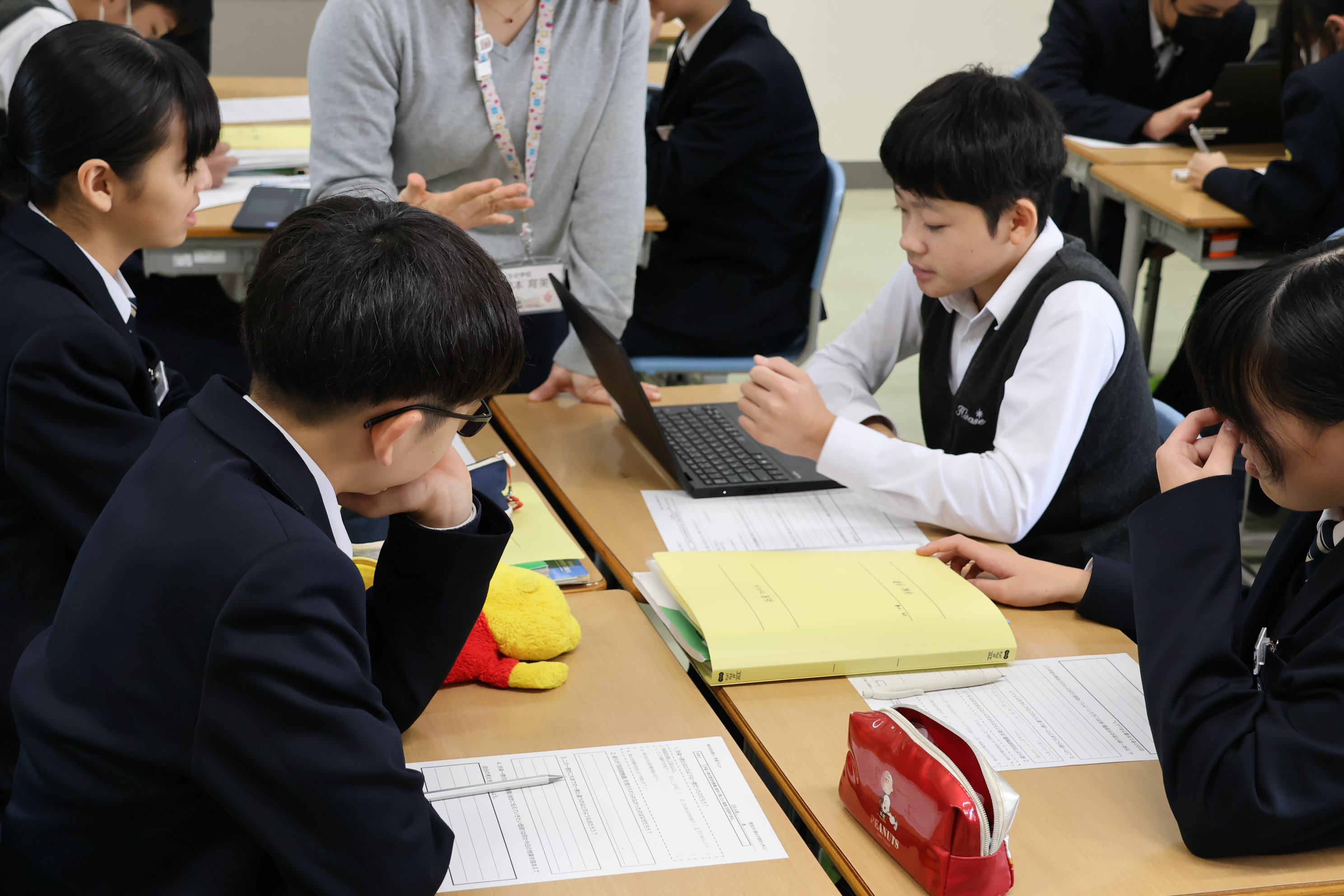
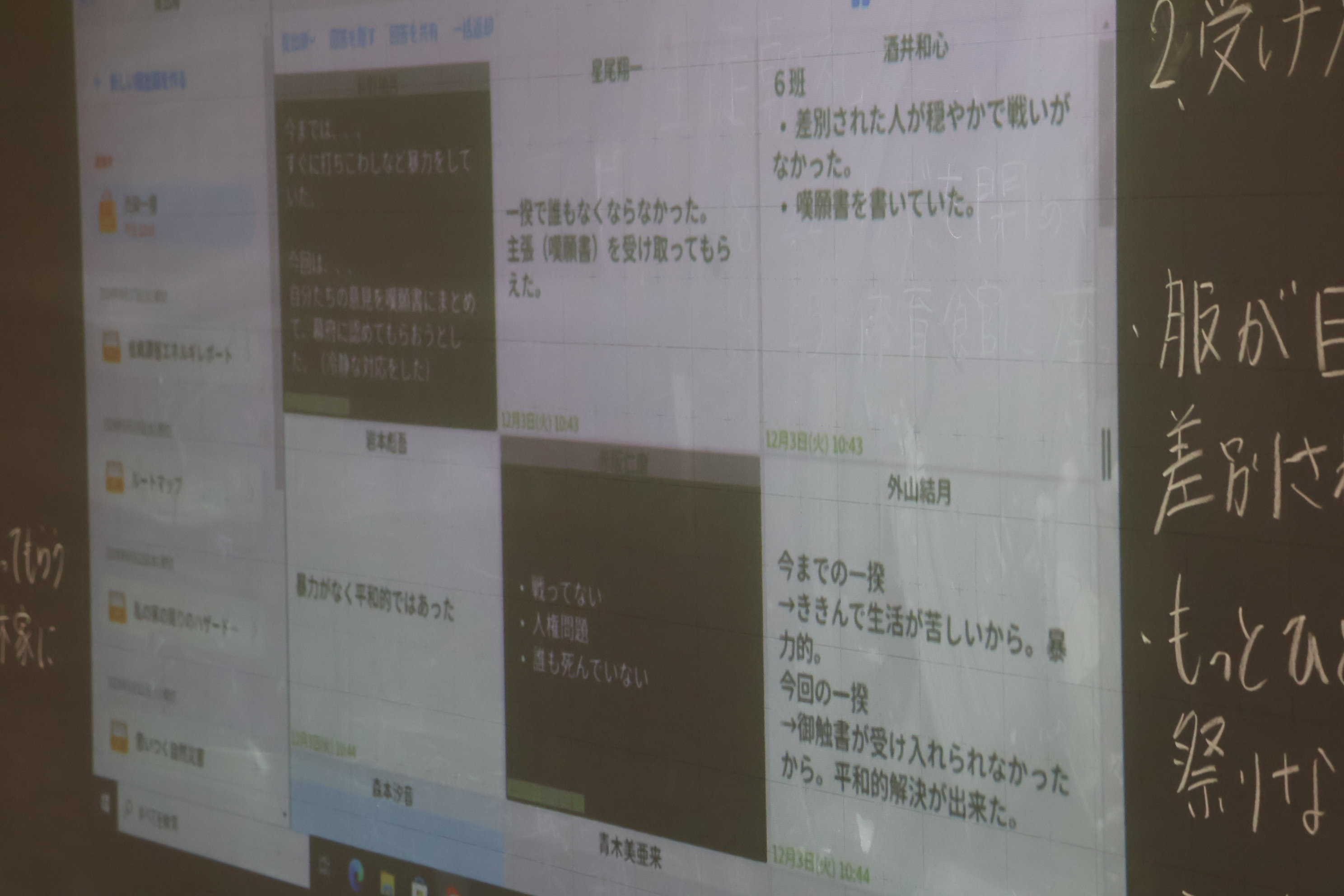

〈乾きたる地面をめがけ降つてくる「もみじ」の終止形を答えよ 石川美南〉
(12/3)



◎ありがとう・ごめんなさいを大切に(12/3:語る全校朝礼)









◎私たちの大事な時間(12/3:全校朝礼)



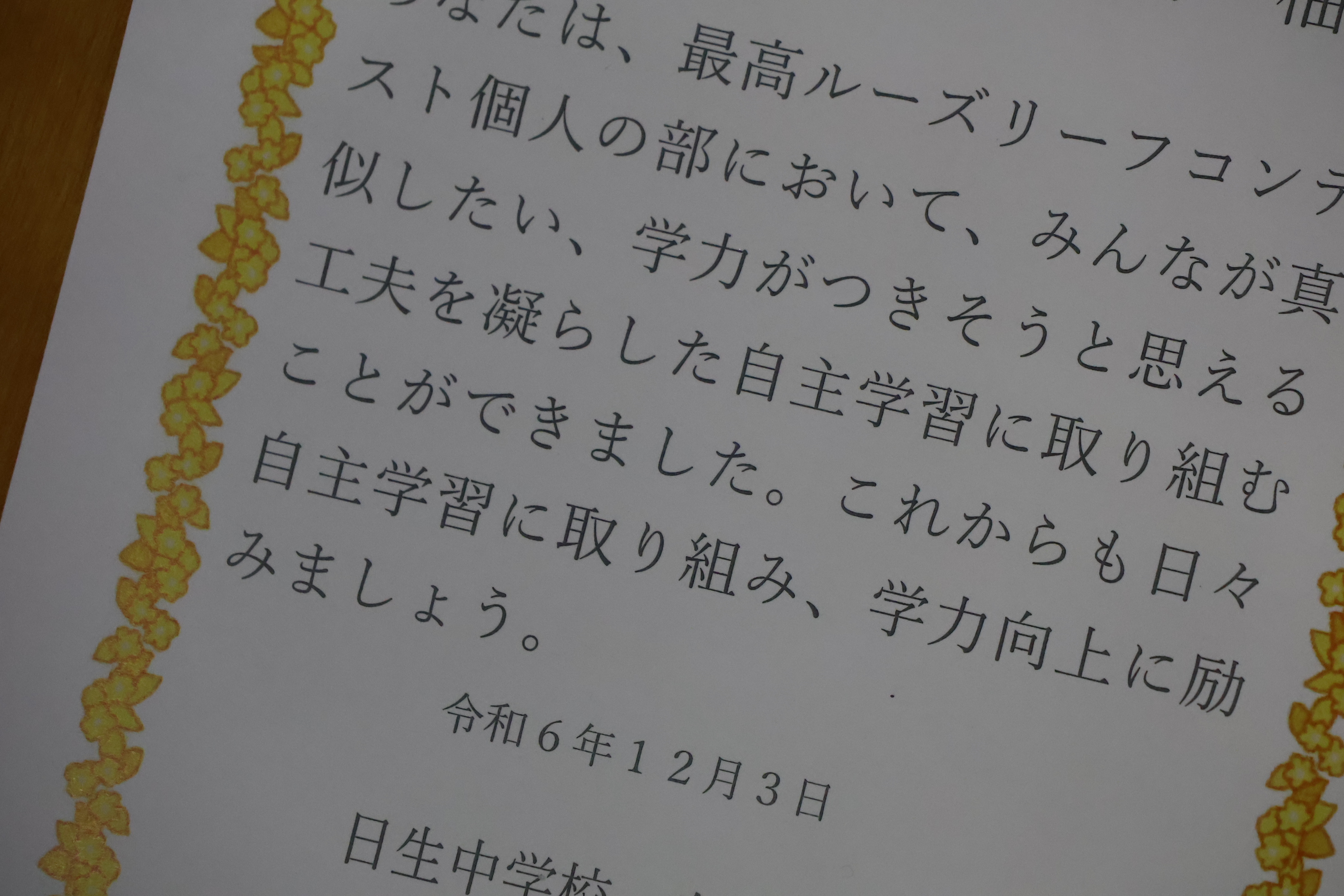


◎発信力・多文化共生社会の担い手として!すごいぞ3年生!(12/2:英語)

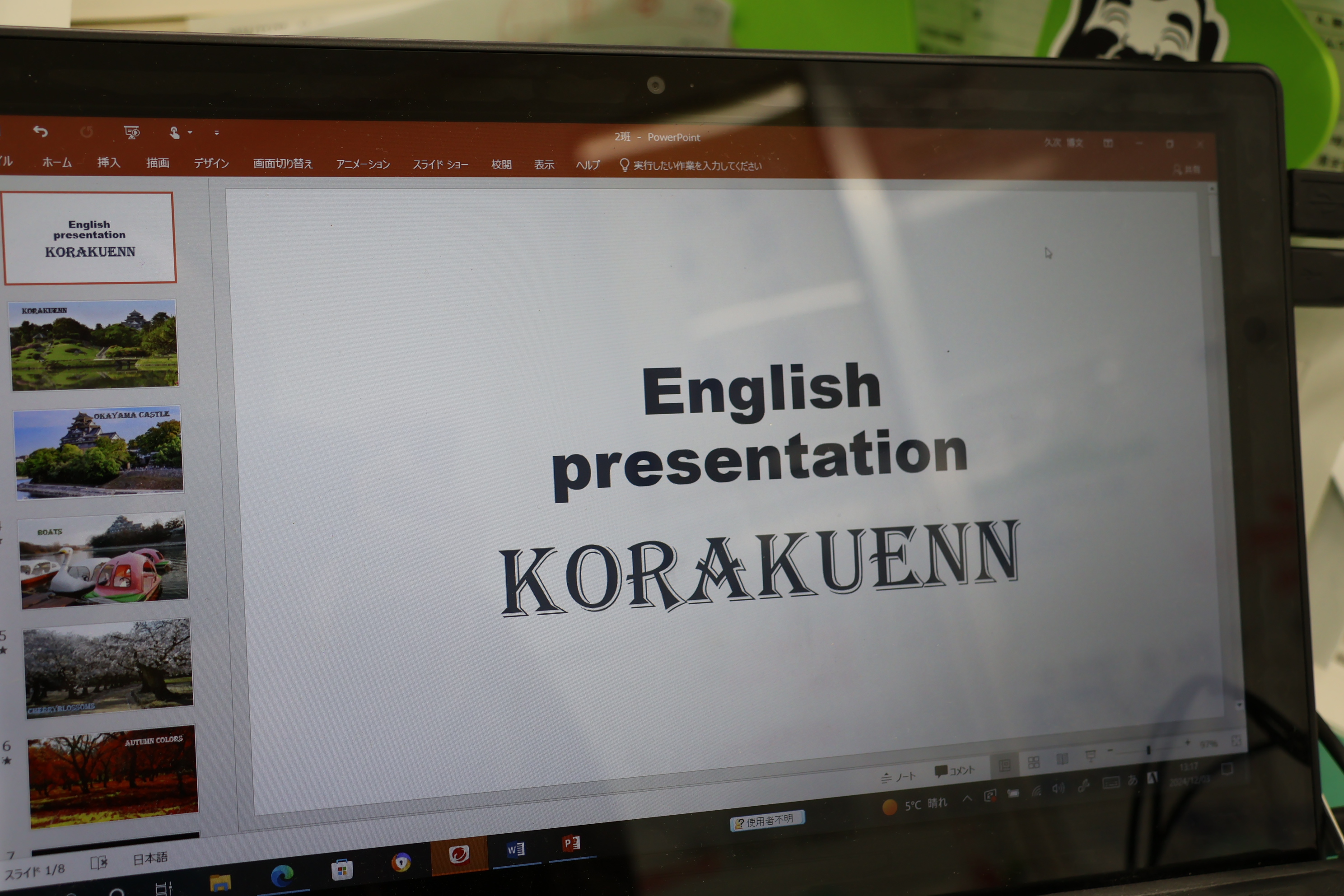
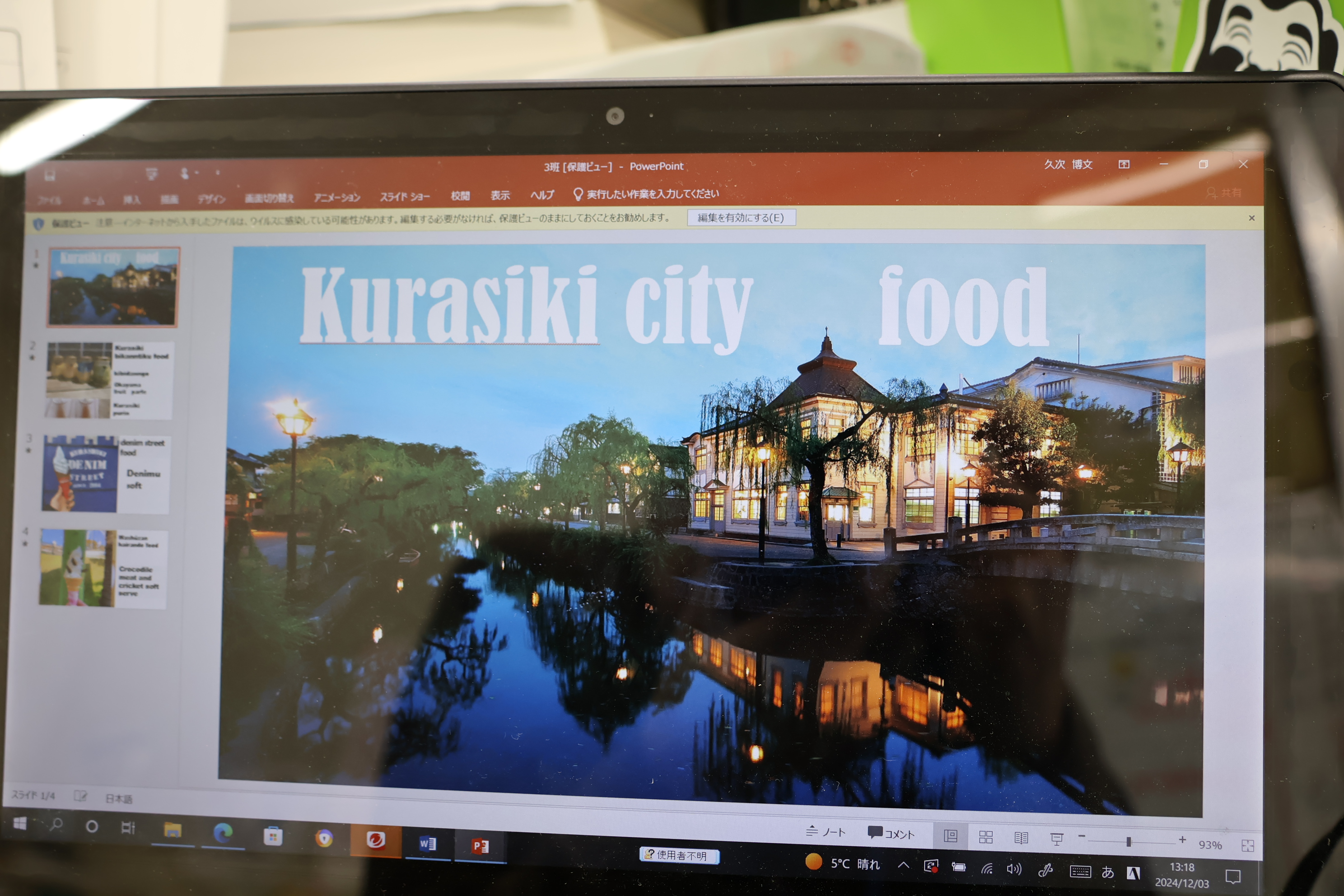



◎集中力・やる気の自主学習に!すごいぞ1年生!(12/2)
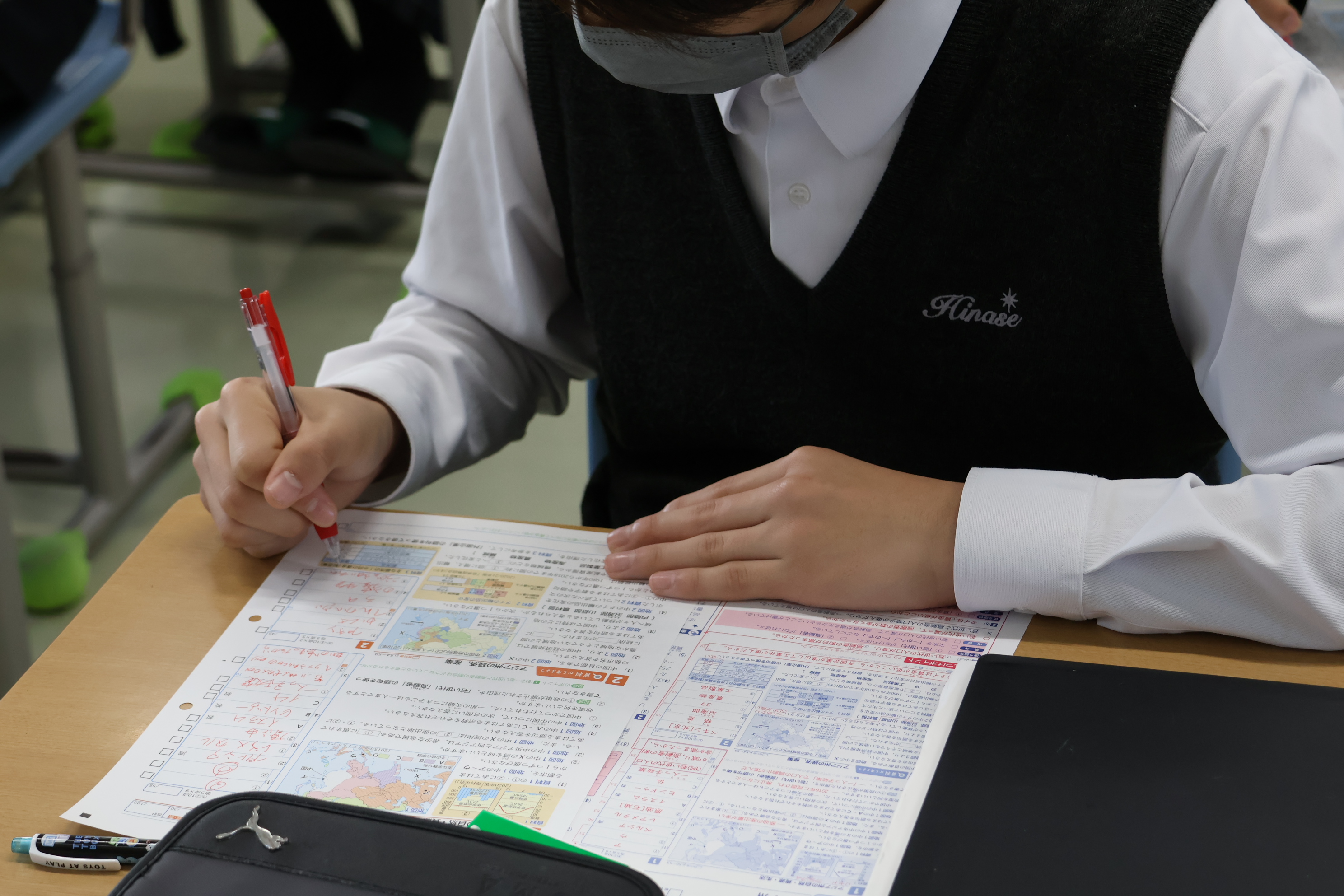
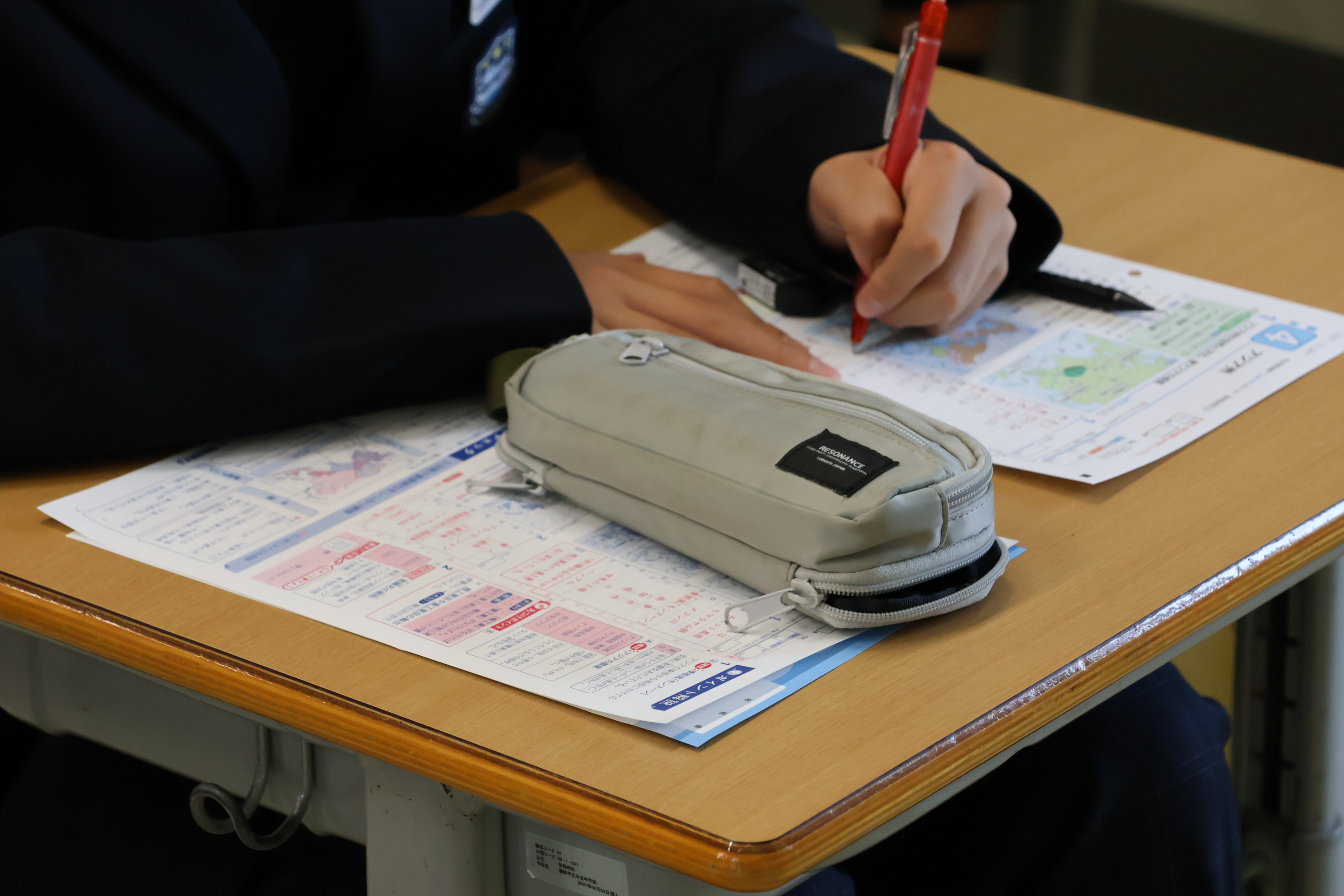
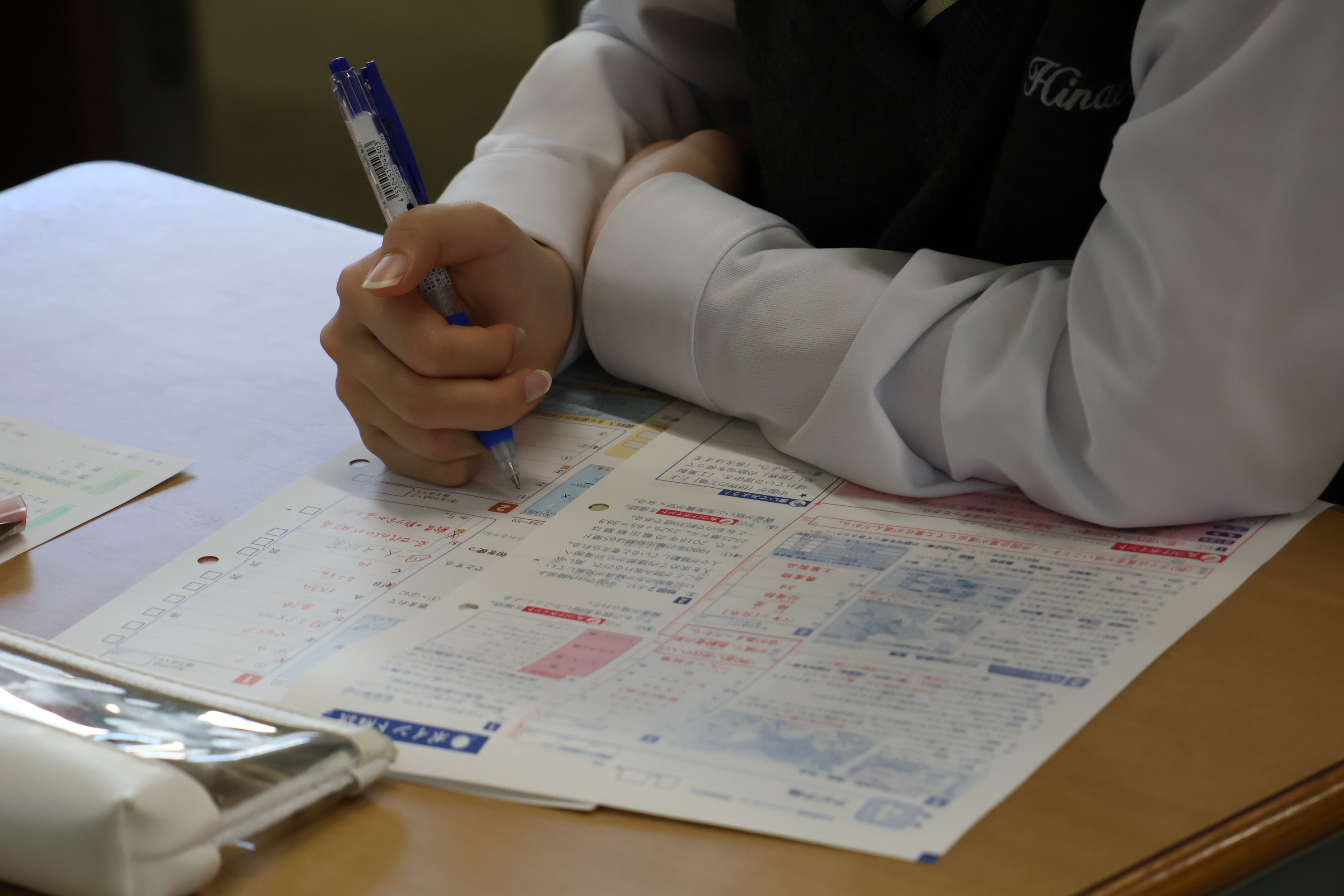
◎何かあるの、おひげ姿のモートン先生? (12/2)

◎生きて働くちからを(12/2:三年生:株式学習から学ぶ日本経済スタート)

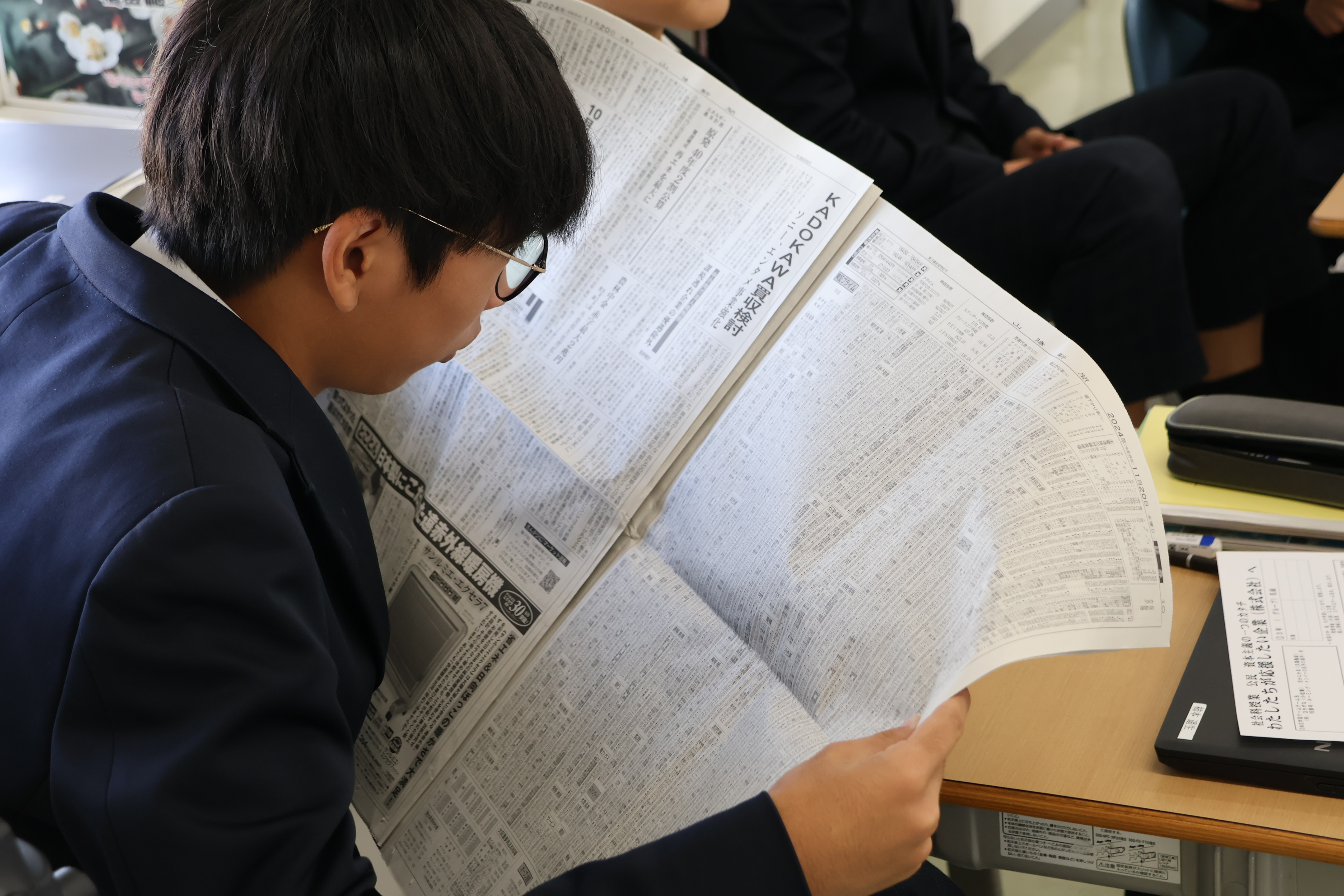
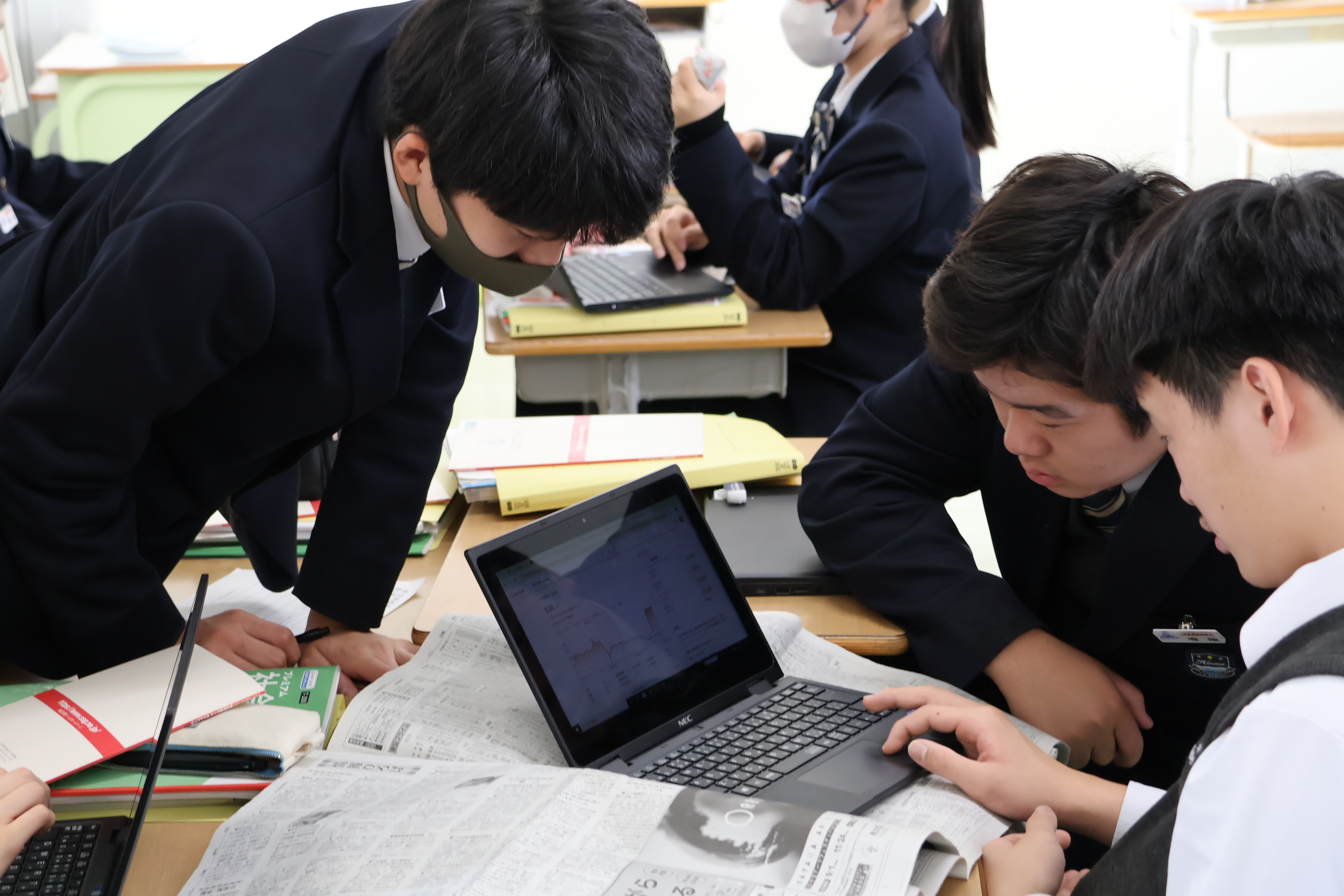

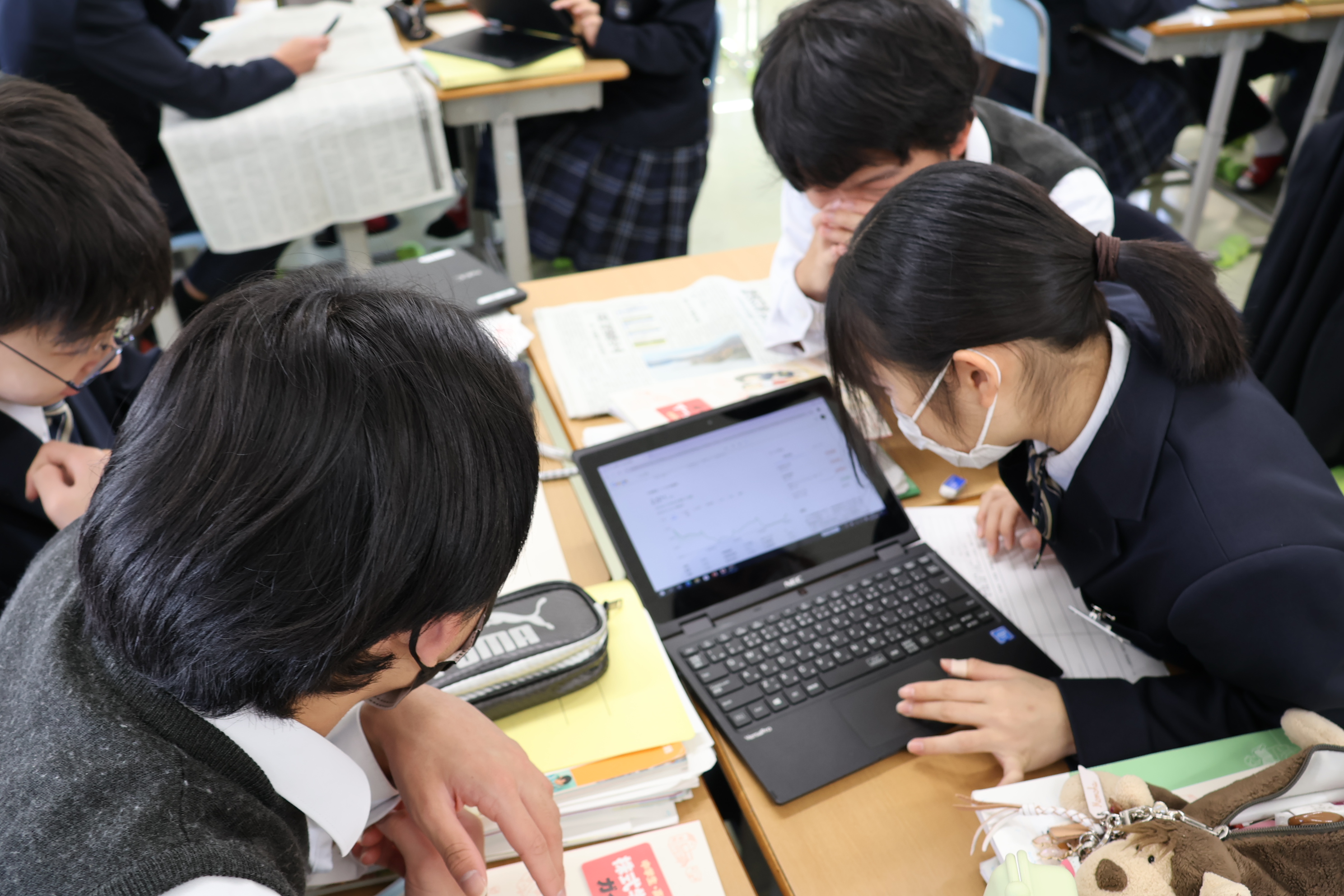
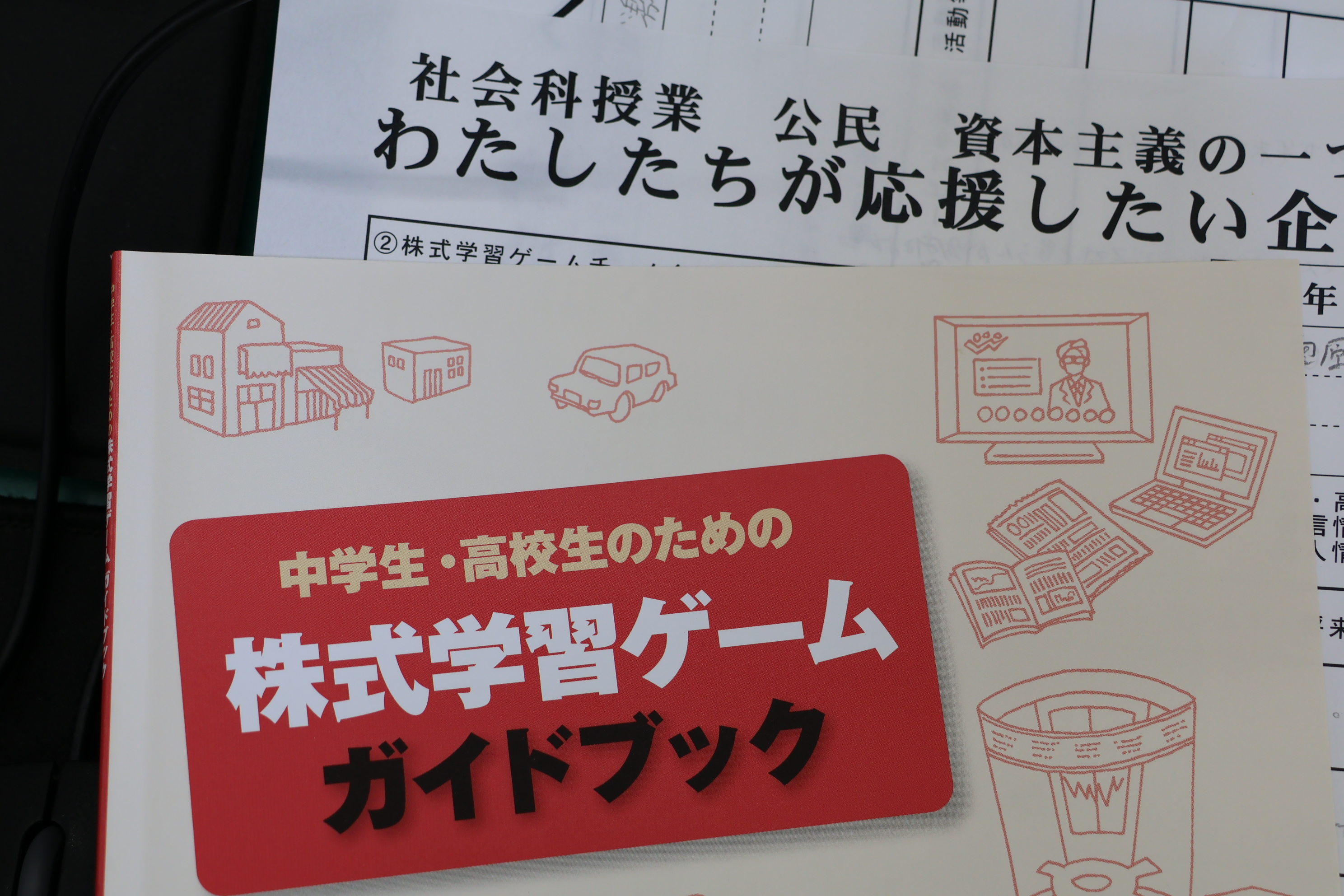
◎多くのひとに支えられて
安心・安全な私たちのまちで・学び舎で。(12/2)
通学路の危険区域や修繕箇所について、地区会や生徒会から出た意見をもとに、警察署と市役所の担当者の方が、現場の状況を調べてくださり、対応してくださいました。横断歩道舗装は新年度に塗装していただく予定です。また、日生東小学校西側の通学路は、除草・樹木の伐採していただき、視界が広がり、安全確保が出来るようになりました。ありがとうございました。道路の舗装修繕もお願いをしています。



〈流れつつ藁も芥も永遠に向ふがごとく水の面にあり 宮柊二〉(12/1:師走)

師走とは、12月のことです。「和風月名」という呼び名のひとつになります。和風月名のなかでも、師走はかなり有名な月名ですよね。和風月名は、日本に昔からあります。
また昔の日本では、旧暦を使っていました。そこで旧暦の師走(旧暦12月)を、現在の暦(新暦)に置き換えると以下のとおりです。
・月始 12下旬〜1月中旬 ・月末 1月下旬〜2月中旬
新暦と旧暦を換算すると、日にちの計算の仕方が異なるため、毎年ズレが生じます。正確な旧暦の日付が知りたいときは、旧暦の日付が書かれた暦やカレンダーを見てください。
さて、12月はなぜ師走と呼ばれるのでしょうか。由来や意味が気になりますよね。よく知られているのは「師とは僧侶のことで、年末になると読経などの仏事が多く、僧侶が忙しく走り回る」というもの。でも実は、「僧侶が走り回る」は漢字の意味から生まれた俗説といわれています。「師走」という漢字は当て字なので、字面どおりの意味ではないんです。
『日本国語大辞典』では、一年の終わりの月なので「としはつる月(歳果月、年果月、歳終月、歳極月)」が変化したという説が載っていました。「としはつる月」が「しはつる月」→「しはす月」となり、「月」が略され、「しはす」に「師走」の漢字が当てられたのです。「としはつる月」説は、多くの古い書物に載っています。
◎HINASE LEGACY(11/29)
授業前に。

ありがとう!
◎私たちのはじまりの風景14(11/29)
ここはどこでしょう?









◎過去・現在・未来をつなぐために✨
~三年生ハンセン病問題学習スタート(11/28)
ハンセン病問題から学ぶ~「人はなぜ差別するのか」「私たちはどんな社会を創るのか」

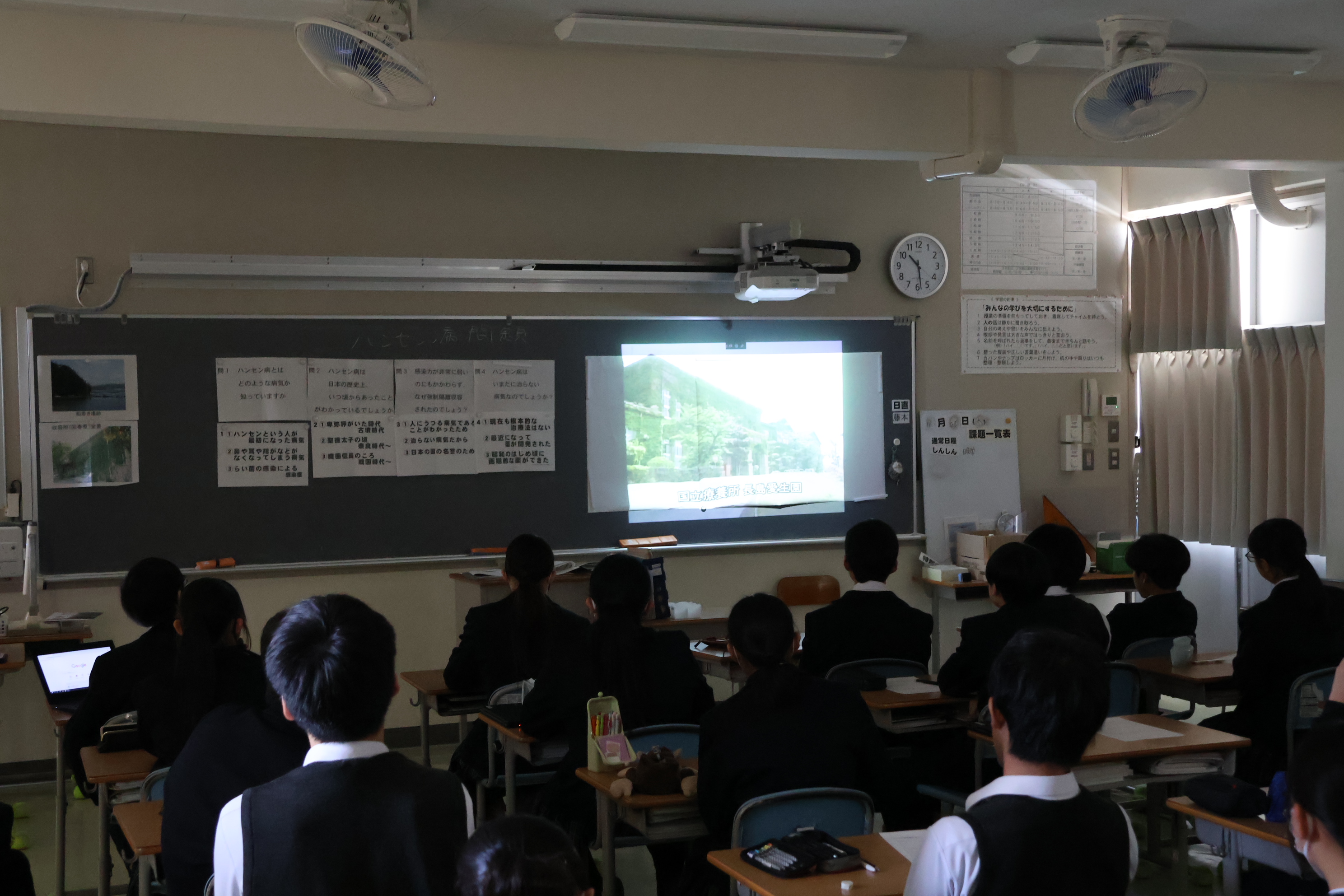
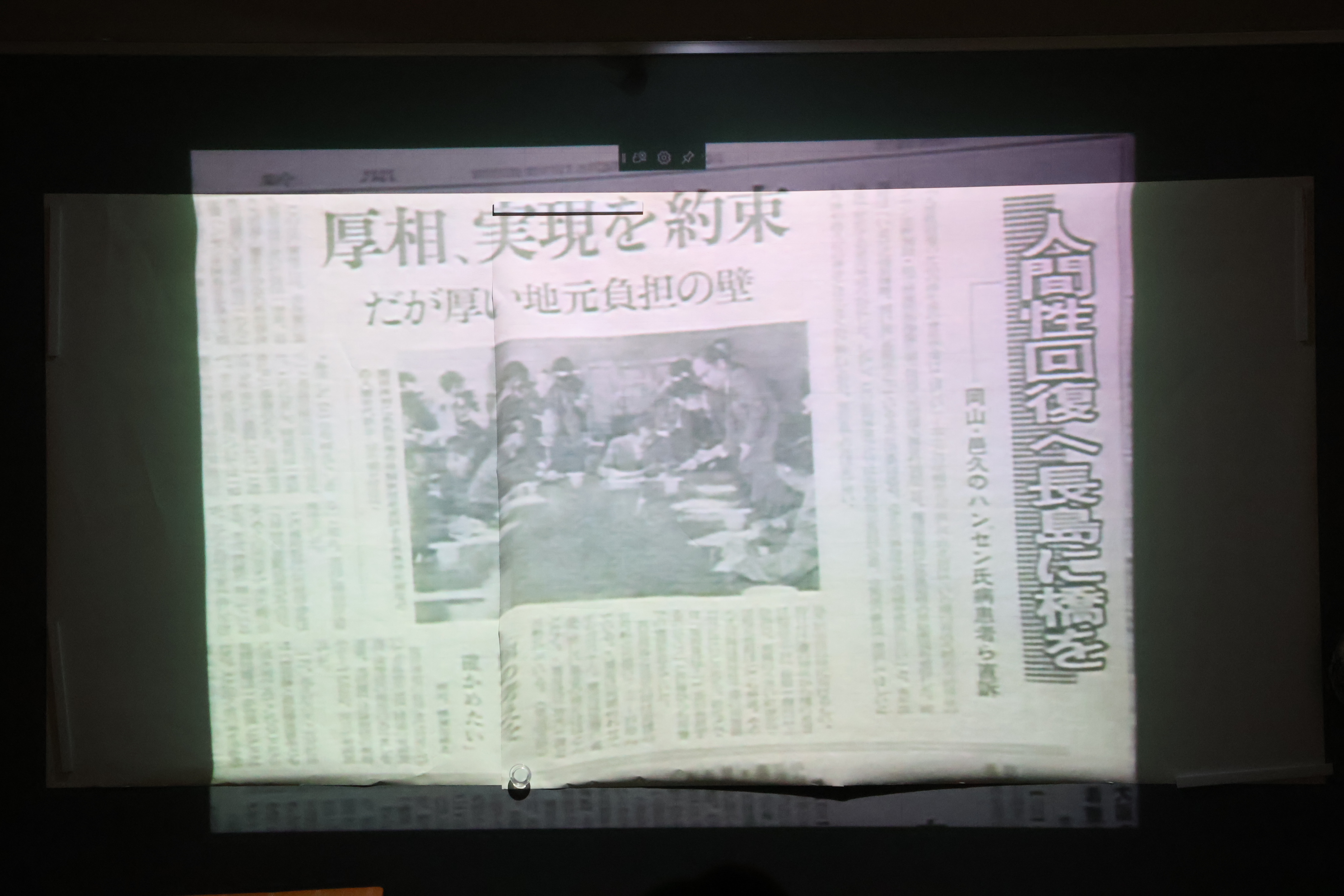
〈それがある場所にはきっとあるんでしょ あたし自身も忘れていたわ 枡野浩一〉
(11/28:生徒会あいさつ運動 ∈^0^∋)



◎進路を切り拓く力を
~学び合う 高め合うルーズリーフ
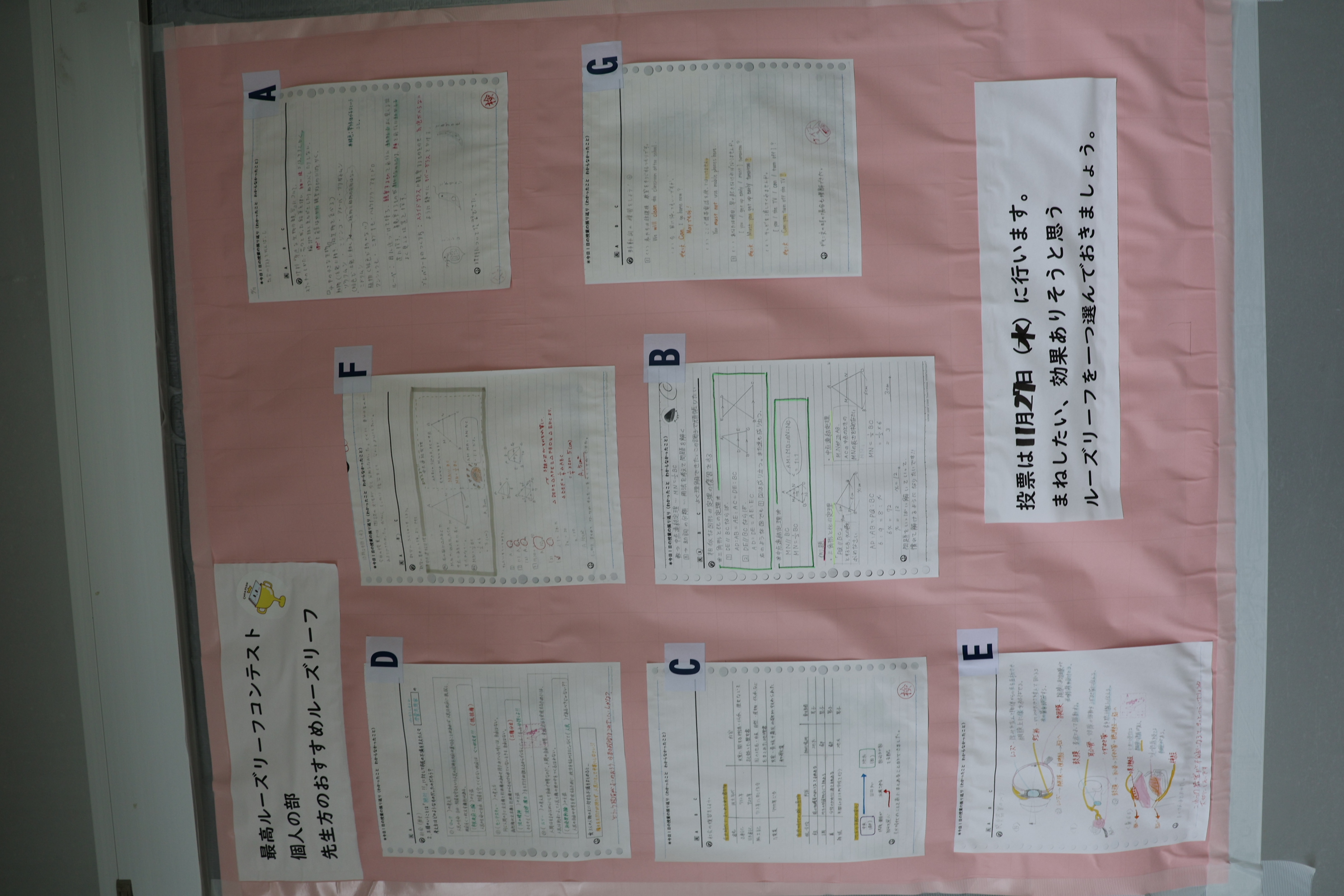
◎学びはどこでも いつでも ~校長室より(11/28)
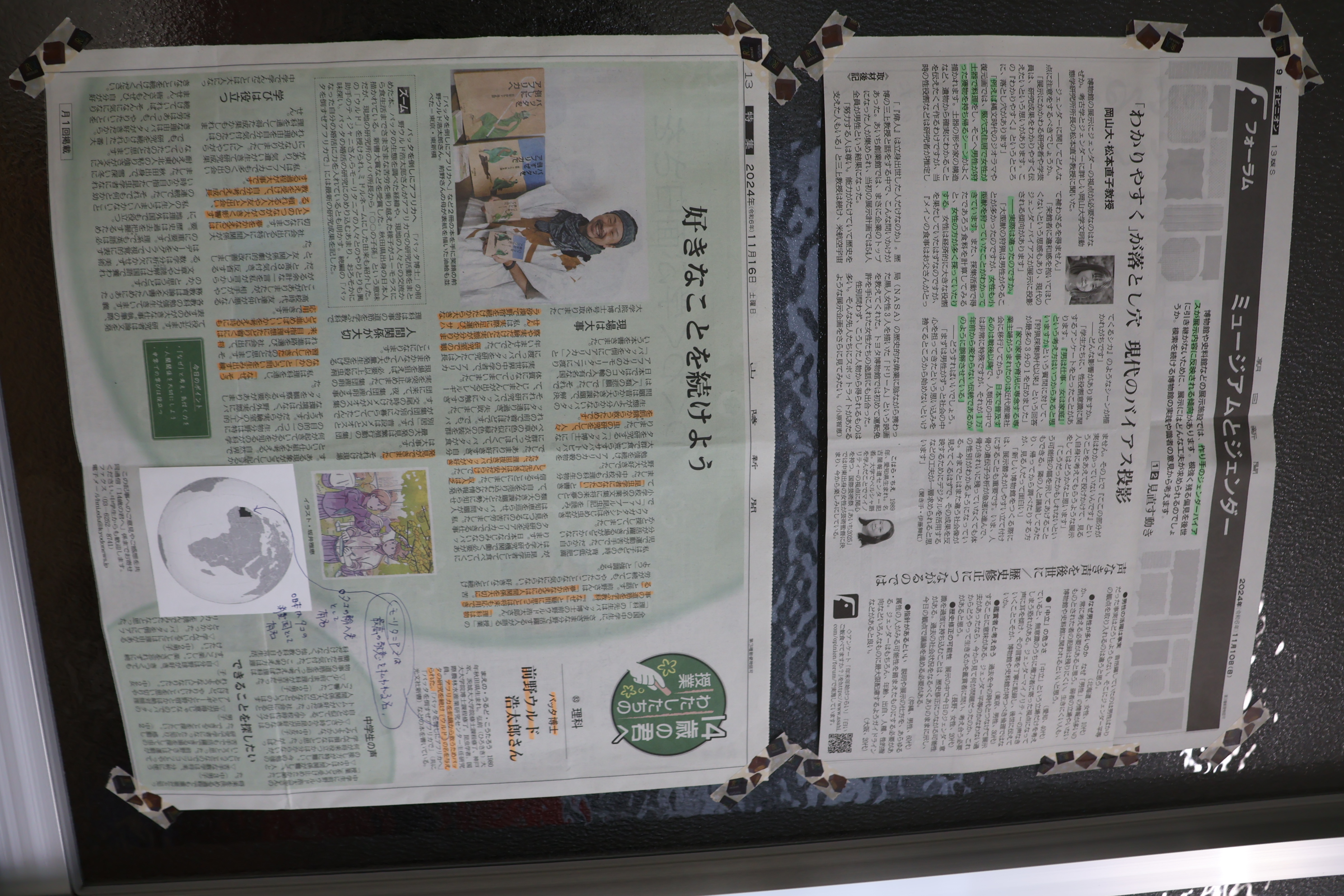
◎OVER THE RAINBOW✨
~美しいと思える感性を大切にしたいね(11/27:放課後)

◎仲間と学ぶ・進む✨~〈単元テスト〉も乗り越えるぞ!(11/27)



◎ひな中の風✨~私たちの誇り・絆
11月22日(金)備前警察署にて日生中学校生徒会(108名)が、善行少年表彰されました。年間を通じて学校近隣の清掃活動や赤い羽根共同募金街頭活動、地域のお祭りやイベントへの出店など、多様なボランティアに取り組んだことが認められました。引き続き地域との協働、参画、貢献できるよう取り組んでいきたいと思います。



◎ひな中の風
~自分らしく生きる 仲間と共に 多様で、豊かな生き方へ(11/26:校内掲示物より)
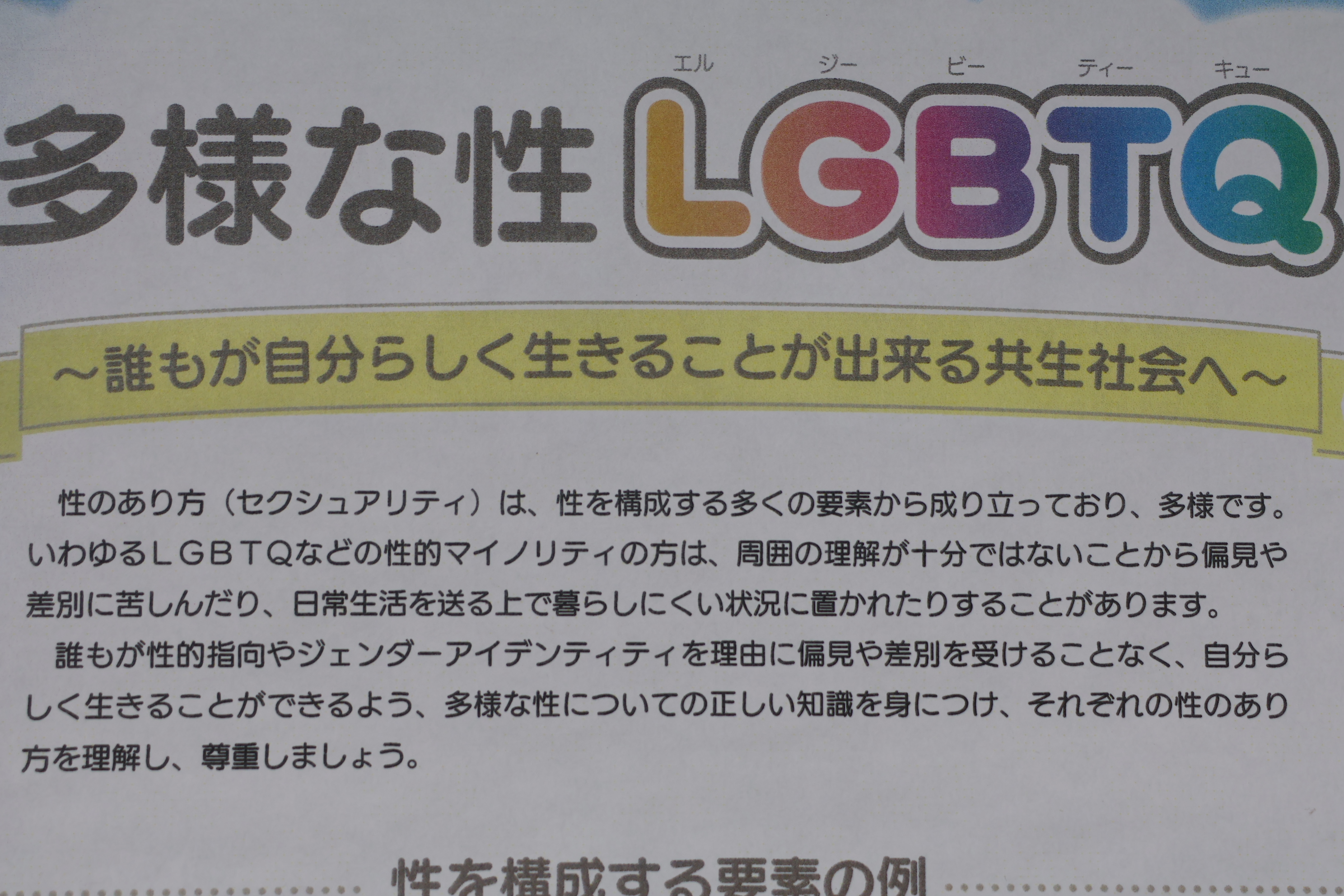
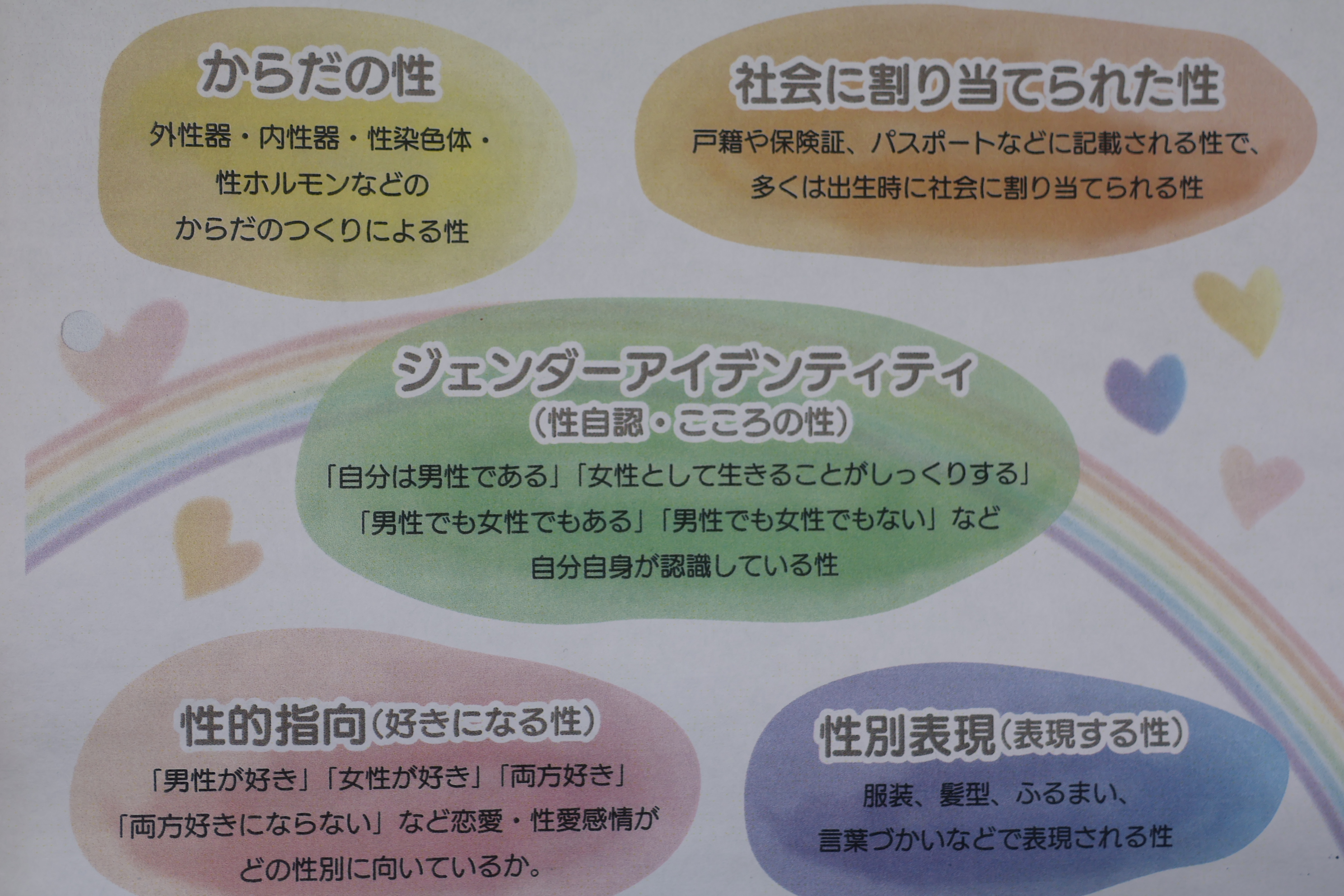
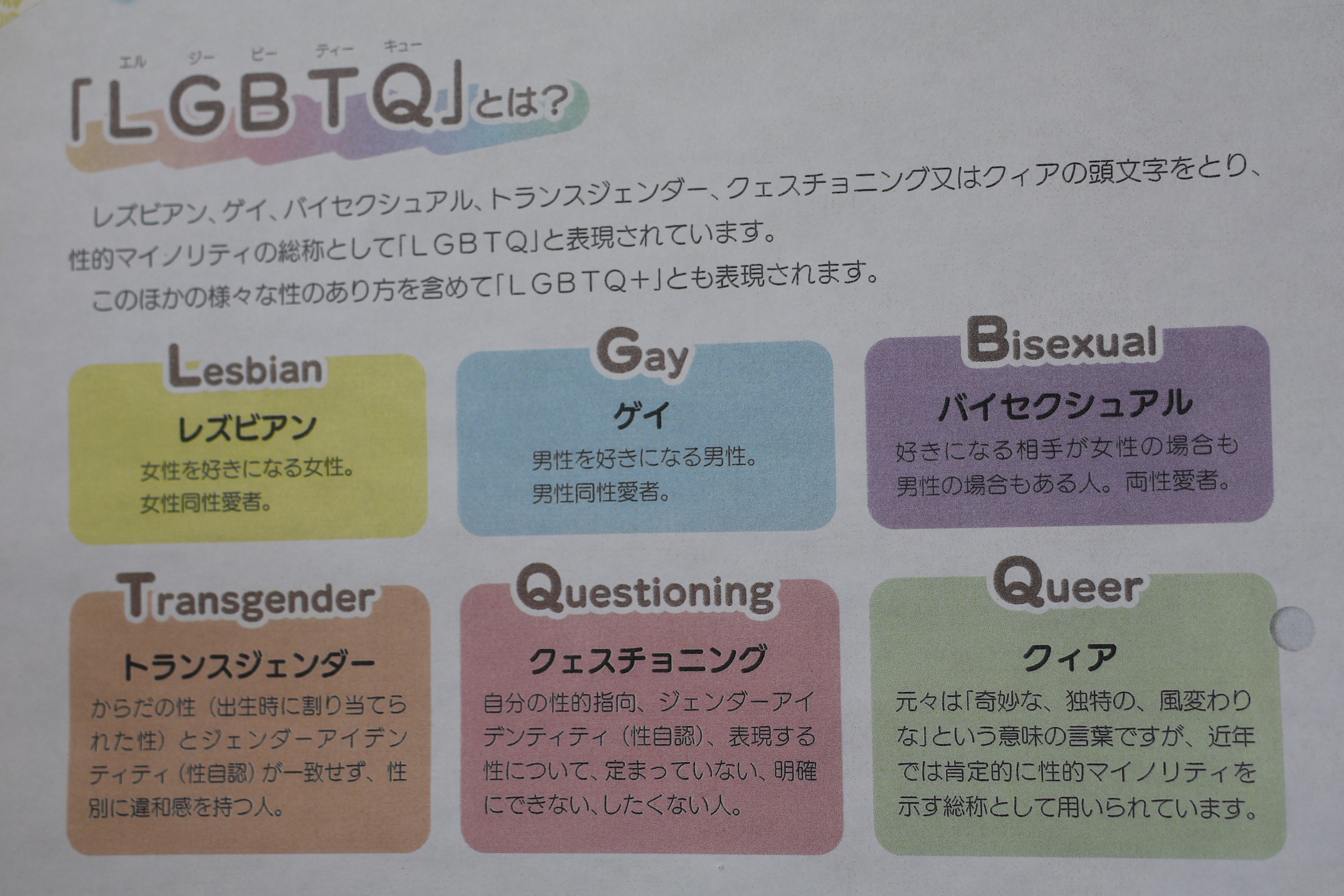
◎ひな中の風~生活を高めていこう(11/25)
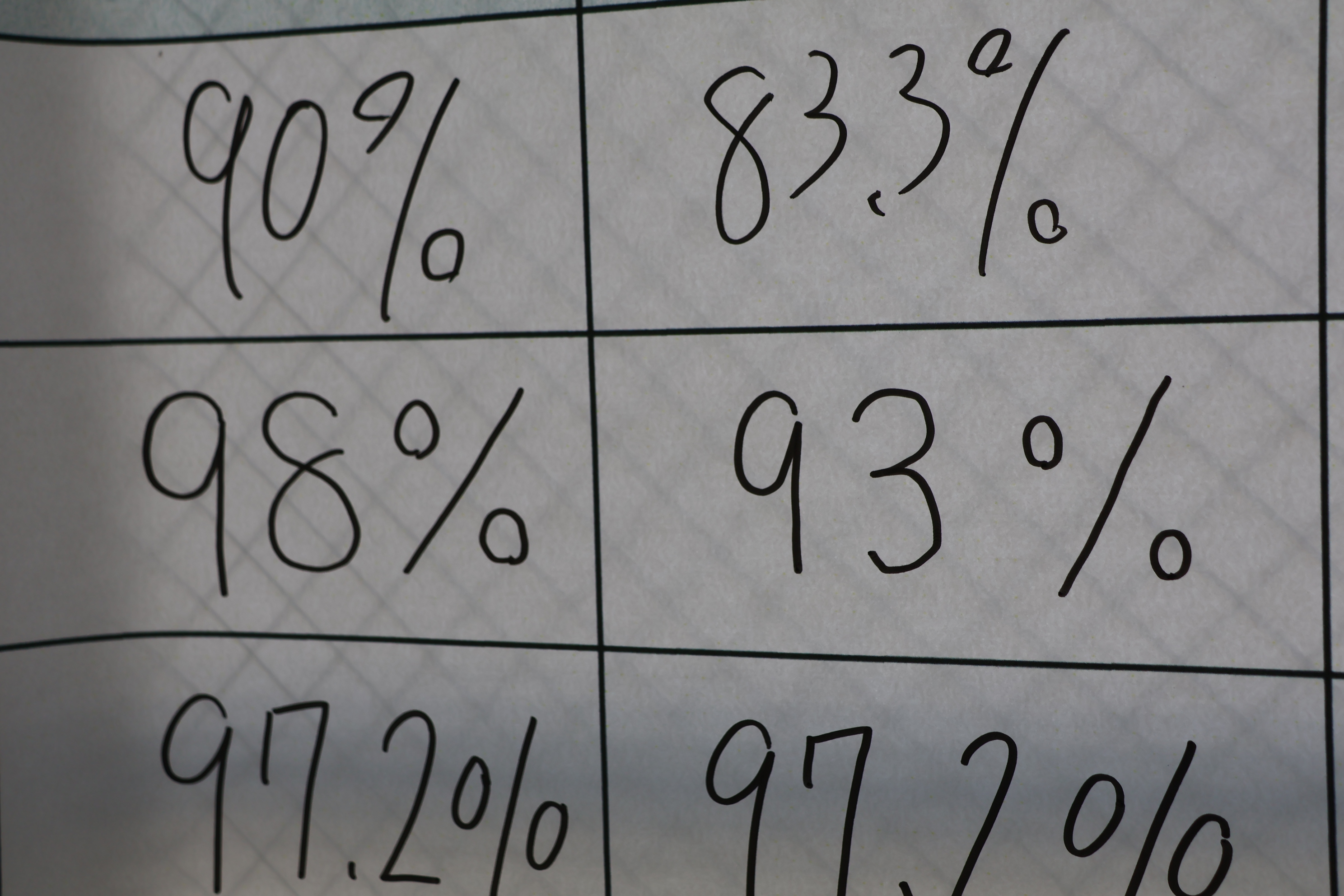

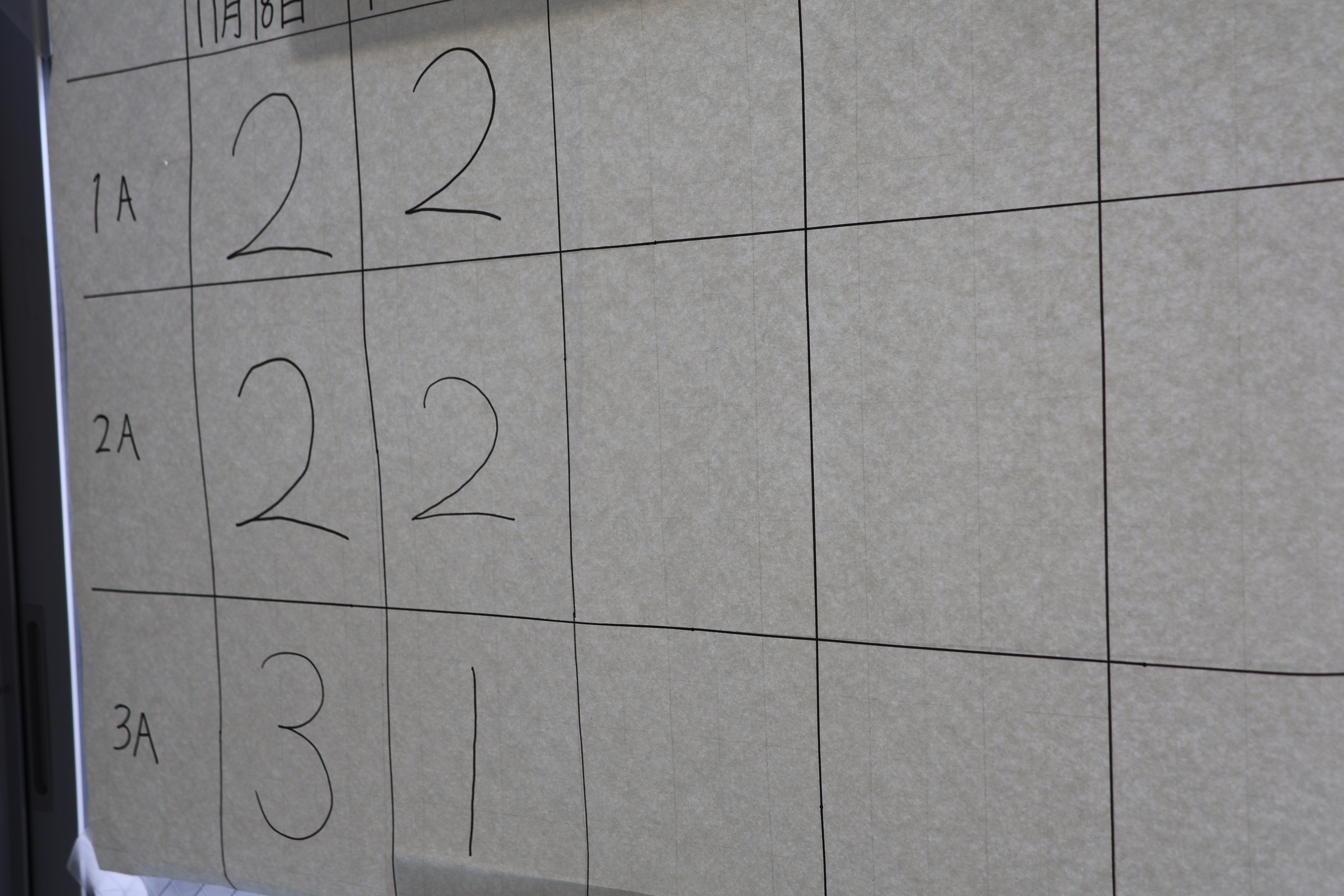

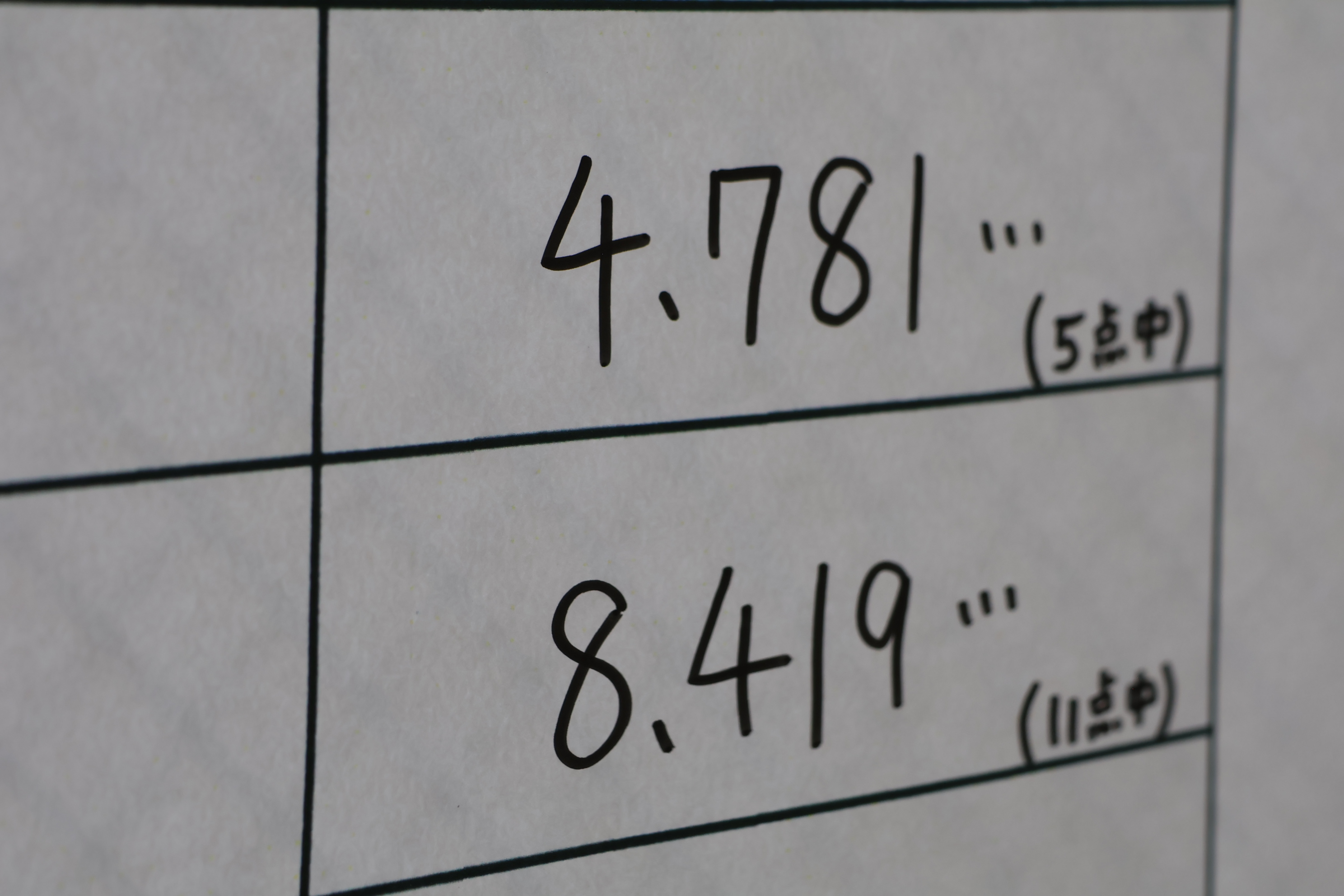

◎よむ・かんがえる・みつめる(11/25)
~11月20日の世界子どもの日につなげて~
わかりやすい言葉であらわした谷川俊太郎さんの「世界人権宣言」を紹介します。

第1条 みんな仲間だ
わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。
第2条 差別はいやだ
わたしたちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによって差別されるべきではありません。 また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。
第3条 安心して暮らす
ちいさな子どもから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、わたしたちはみな自由に、安心して生きていける権利をもっています。
第4条 奴隷はいやだ
人はみな、奴隷のように働かされるべきではありません。人を物のように売り買いしてはいけません。
第5条 拷問はやめろ
人はみな、ひどい仕打ちによって、はずかしめられるべきではありません。
第6条 みんな人権をもっている
わたしたちはみな、だれでも、どこでも、法律に守られて、人として生きることができます
第7条 法律は平等だ
法律はすべての人に平等でなければなりません。法律は差別をみとめてはなりません。
第8条 泣き寝入りはしない
わたしたちはみな、法律で守られている基本的な権利を、国によって奪われたら、裁判を起こし、その権利をとりもどすことができます。
第9条 簡単に捕まえないで
人はみな、法律によらないで、また好きかってに作られた法律によって、捕まったり、閉じこめたり、その国からむりやり追い出されたりするべきではありません。
第10条 裁判は公正に
わたしたちには、独立した、かたよらない裁判所で、大勢のまえで、うそのない裁判を受ける権利があります。
第11条 捕まっても罪があるとはかぎらない
うそのない裁判で決められるまでは、だれも罪があるとはみなされません。また人は、罪をおかした時の法律によってのみ、罰をうけます。あとから作られた法律で罰を受けることはありません。
第12条 ないしょの話
自分の暮らしや家族、手紙や秘密をかってにあばかれ、名誉や評判を傷つけられることはあってはなりません。そういう時は、法律によって守られます。
第13条 どこにでも住める
わたしたちはみな、いまいる国のどこへでも行けるし、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどることも自由にできます。
第14条 逃げるのも権利
だれでも、ひどい目にあったら、よその国に救いを求めて逃げていけます。しかし、その人が、だれが見ても罪をおかしている場合は、べつです。
第15条 どこの国がいい?
人には、ある国の国民になる権利があり、またよその国の国民になる権利もあります。その権利を好きかってにとりあげられることはありません。
第16条 ふたりで決める
おとなになったら、だれとでも好きな人と結婚し、家庭がもてます。結婚も、家庭生活も、離婚もだれにも口出しされずに、当人同士が決めることです。家族は社会と国によって、守られます。
第17条 財産をもつ
人はみな、ひとりで、またはほかの人といっしょに財産をもつことができます。自分の財産を好きかってに奪われることはありません。
第18条 考えるのは自由
人には、自分で自由に考える権利があります。この権利には、考えを変える自由や、ひとりで、またほかの人といっしょに考えをひろめる自由もふくまれます。
第19条 言いたい、知りたい、伝えたい
わたしたちは、自由に意見を言う権利があります。だれもその邪魔をすることはできません。人はみな、国をこえて、本、新聞、ラジオ、テレビなどを通じて、情報や意見を交換することができます。
第20条 集まる自由、集まらない自由
人には、平和のうちに集会を開いたり、仲間を集めて団体を作ったりする自由があります。しかし、いやがっている人を、むりやりそこに入れることはだれにもできません。
第21条 選ぶのはわたし
わたしたちはみな、直接にまたは、代表を選んで自分の国の政治に参加できます。また、だれでもその国の公務員になる権利があります。 みんなの考えがはっきり反映されるように、選挙は定期的に、ただしく平等に行なわれなければなりません。その投票の秘密は守られます。
第22条 人間らしく生きる
人には、困った時に国から助けを受ける権利があります。また、人にはその国の力に応じて、豊かに生きていく権利があります。
第23条 安心して働けるように
人には、仕事を自由に選んで働く権利があり、同じ働きに対しては、同じお金をもらう権利があります。そのお金はちゃんと生活できるものでなければなりません。人はみな、仕事を失わないよう守られ、だれにも仲間と集まって組合をつくる権利があります。
第24条 大事な休み
人には、休む権利があります。そのためには、働く時間をきちんと決め、お金をもらえるまとまった休みがなければなりません。
第25条 幸せな生活
だれにでも、家族といっしょに健康で幸せな生活を送る権利があります。病気になったり、年をとったり、働き手が死んだりして、生活できなくなった時には、国に助けをもとめることができます。母と子はとくに大切にされなければいけません。
第26条 勉強したい?
だれにでも、教育を受ける権利があります。小、中学校はただで、だれもが行けます。大きくなったら、高校や専門学校、大学で好きなことを勉強できます。 教育は人がその能力をのばすこと、そして人ととしての権利と自由を大切にすることを目的とします。人はまた教育を通じて、世界中の人とともに平和に生きることを学ばなければなりません。
第27条 楽しい暮らし
だれにでも、絵や文学や音楽を楽しみ、科学の進歩とその恵みをわかちあう権利があります。また人には、自分の作ったものが生み出す利益を受ける権利があります。
第28条 この宣言がめざす社会
この宣言が、口先だけで終わらないような世界を作ろうとする権利もまた、わたしたちのものです。
第29条 権利と身勝手は違う
わたしたちはみな、すべての人の自由と権利を守り、住み良い世の中を作る為の義務を負っています。 自分の自由と権利は、ほかの人々の自由と権利を守る時にのみ、制限されます。
第30条 権利を奪う「権利」はない
宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。

◎ひな中の風(11/22)



Life is very short and there’s no time for fussing and fighting‚ my friends. John Lennon
(人生は短い。空騒ぎしたり、争ったりする暇なんてないよ。)
◎降りつむ(11/22)
先日、大山に冠雪があったニュースを聞きました。今日は暦の上で、小雪。岡山の詩人 永瀬清子 (1906~1995)さんの作品を今年も紹介します。
降りつむ
かなしみの国に雪が降りつむ
かなしみを糧として生きよと雪が降りつむ
失いつくしたものの上に雪が降りつむ
その山河の上に
そのうすきシャツの上に
そのみなし子のみだれたる頭髪の上に
四方の潮騒いよよ高く雪が降りつむ
夜も昼もなく
長いかなしみの音楽のごとく
なきさけびの心を鎮めよと雪が降りつむ
ひよどりや狐の巣にこもるごとく
かなしみにこもれと
地に強い草の葉の冬を越すごとく
冬をこせよと
その下からやがてよき春の立ちあがれと雪が降りつむ
無限にふかい空からしずかにしずかに
非情のやさしさをもって雪が降りつむ
かなしみの国に雪が降りつむ

◎訓練はいのちを守る(11/21)
20日、地震発生を想定した避難訓練を実施しました。消防署の藤本さんから講評をいただきました。落ち着いて(けがをしないように)避難場所まで歩いてたどりつくまでが「避難」であること、そして、自分ごととして訓練に取り組むことが大切であるなど、大事なアドバイスいただきました。ありがとうございました。






◎一人ひとりが大切(11/20)
進路保障に向け、今日、第1回調査書作成委員会を開きました。生徒一人ひとりの進路実現をめざし、15歳の春に向け、全教職員でこれからもがんばります。次回は12月11日を予定しています。


◎World Children’s Day
子どもたちの権利の実現へ(11/20)
11月20日の「世界子どもの日」は、1954年、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的として、国連によって制定されました。
毎年の11月20日には、子どもの権利の認識向上と子どもの福祉の向上を目的として、世界中で子どもたちが主体となって参加する催しが行われています。子どもに関わるすべての人が、子どもの権利条約にうたわれている権利の実現に向けて取り組むことはもちろん、子どもたち自身が、自分たちの持つ権利について知り、学び、声を上げていくことがとても大切です。
1959年11月20日には国連総会で「子どもの権利宣言」が採択され、その30年後の1989年の11月20日、すべての子どもに人権を保障する初めての国際条約『子どもの権利条約』が、国連総会で採択されました。この条約が生まれたことにより、世界中で子どもの保護への取り組みが進み、これまでに多くの成果が生まれました。(詳しくはユニセフ等でのHPで)

創る、私たちの学校・クラス。これってどうするん?に応える仲間として!
◎ひなせ親の会[12/3]で学びましょう(^_^)
◎子どもの育ち、「発達」について、中・長期的な視野で考えてみよう!
◎今どきの進路・自立・就労について、新しい情報を手に入れ、見通しをもとう!
◎子どもが小さいからまだまだ先の話?ではないって?
◎備前市の福祉サービスはどうなってるの? どう利用できるの?
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。
今回は、備前市の相談専門員の朝倉吉宣さんをお招きして、上記の内容についてあれこれ尋ねたり、相談したりできる会とします。参加者がゆったりと〈子どもたちのこれから〉について、学び合う会です。(秘密厳守です。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、お子さんの「発達・育ち」の素朴な質問なども含めて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。お気軽に、お申し込み・ご参加ください。
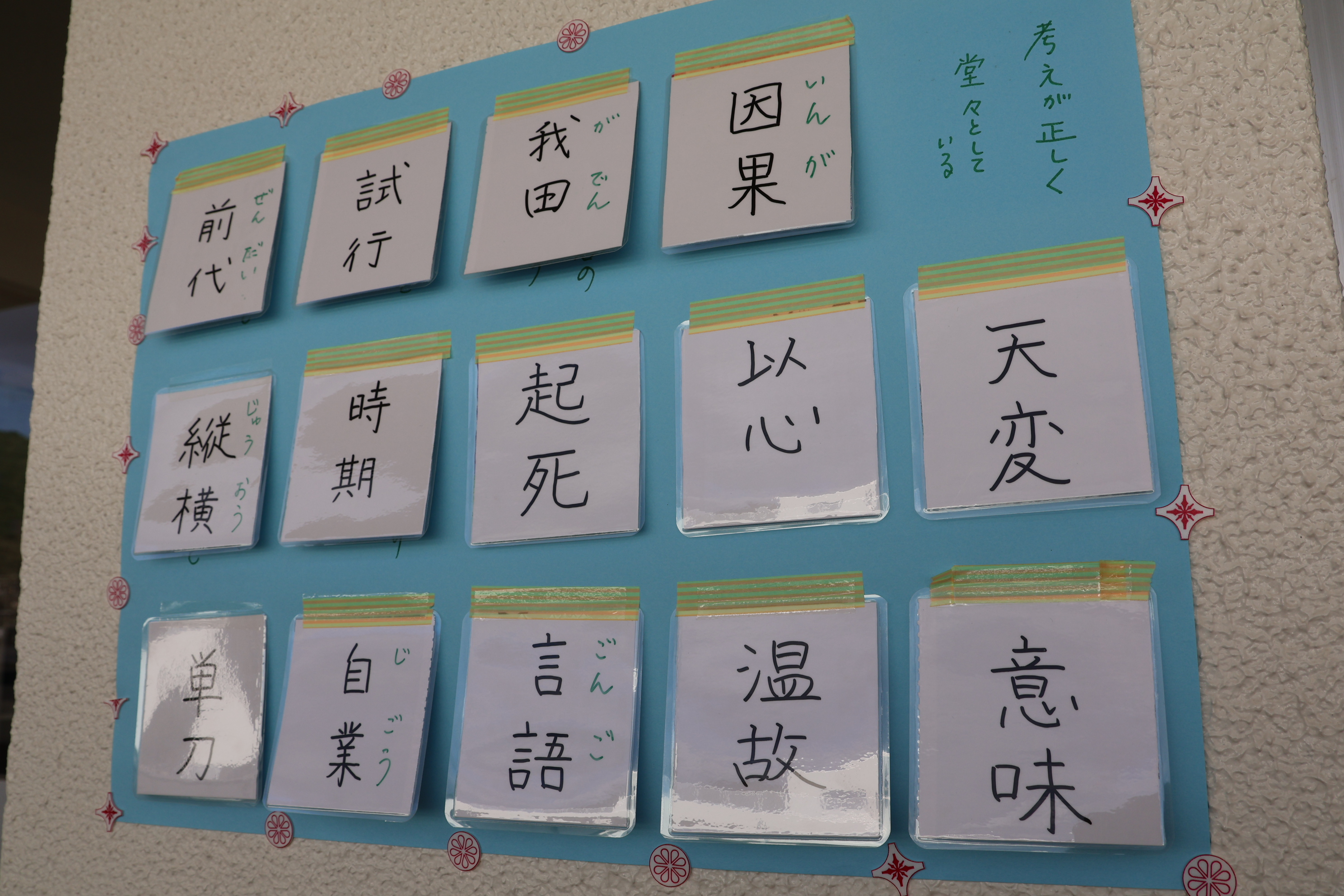
◎私たちのはじまりの風景13(11/19)
ここはどこでしょう?









◎だれもが安心して暮らせるまちへ(11/19)
~日生中学校 中学生認知症サポーターとして
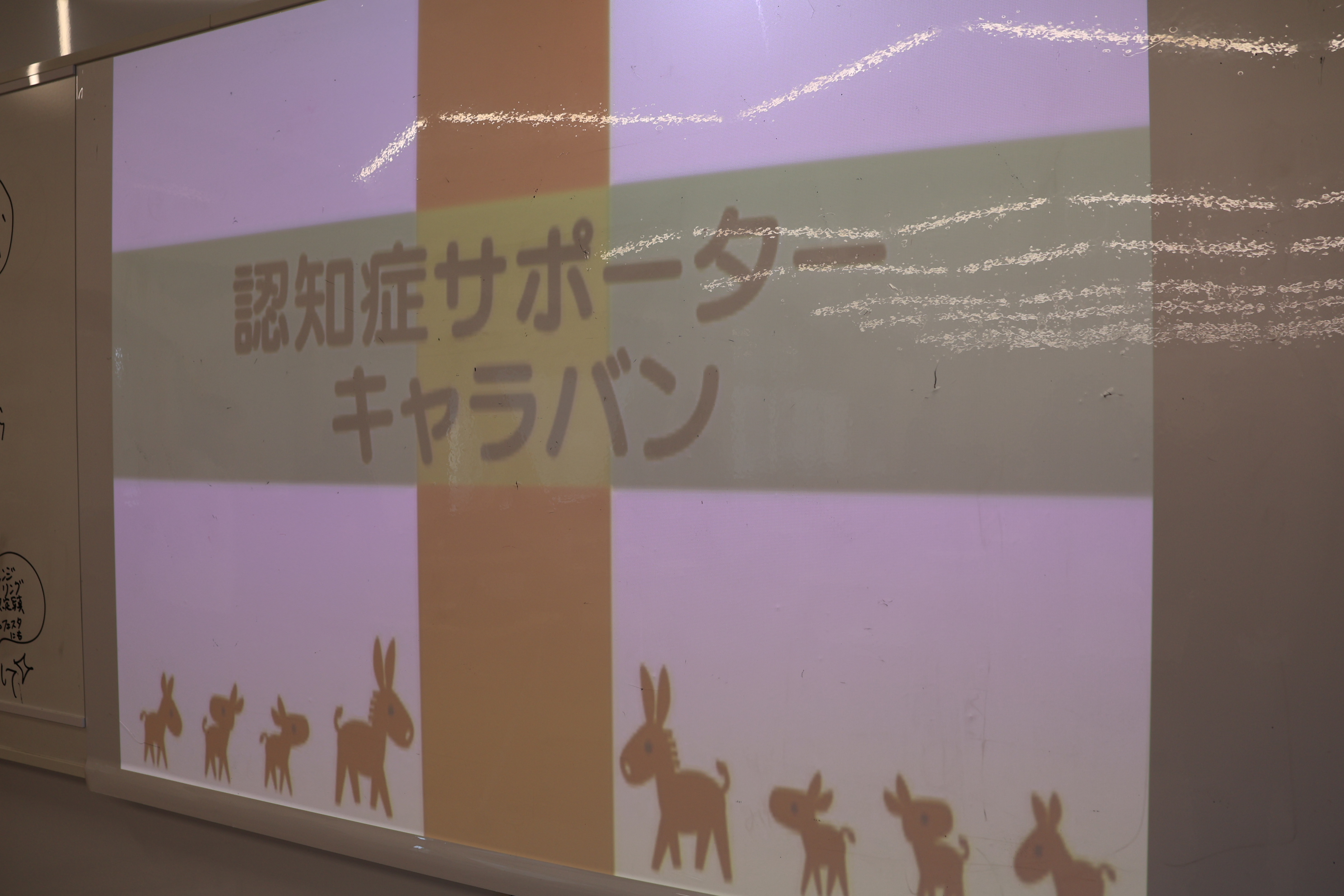

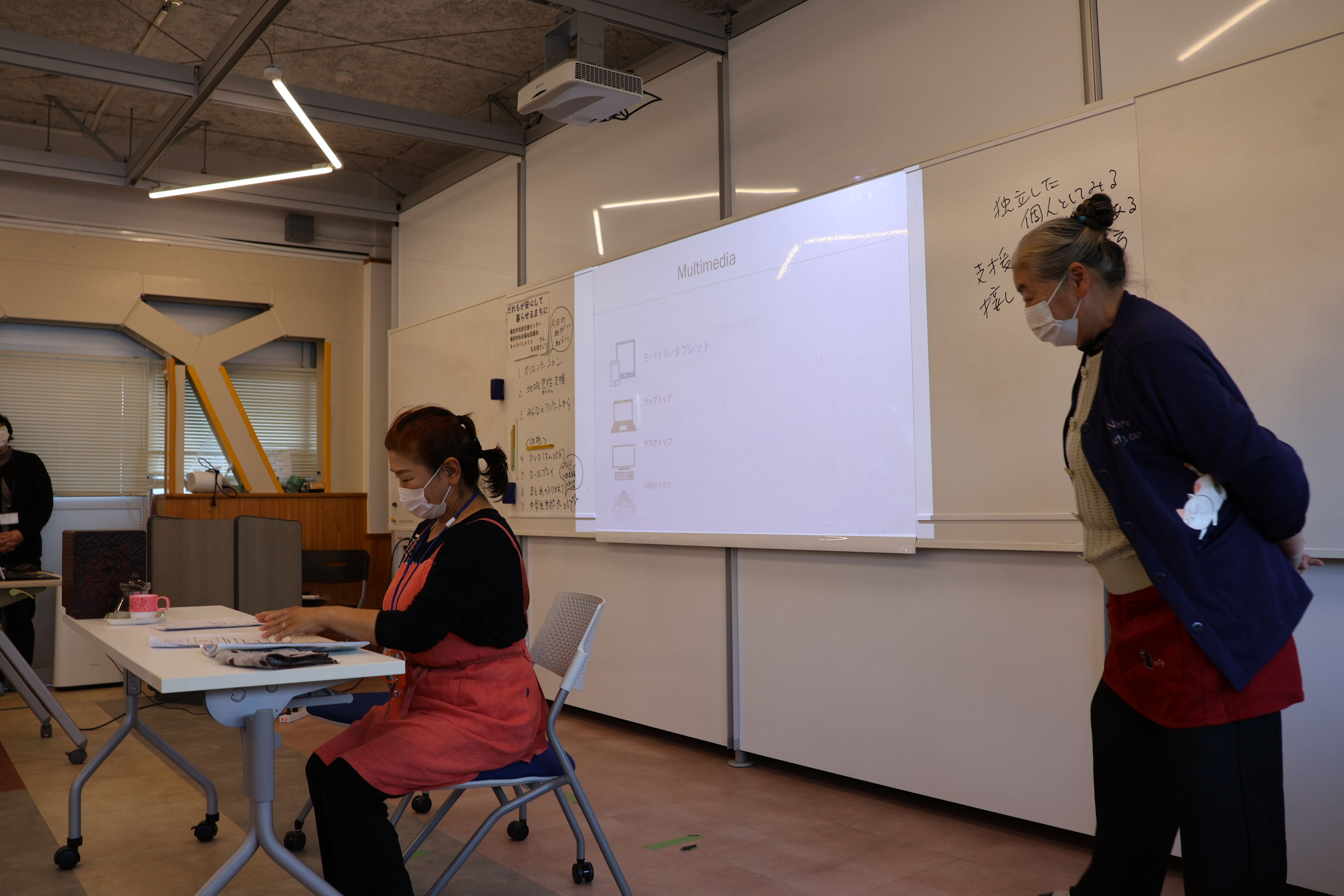
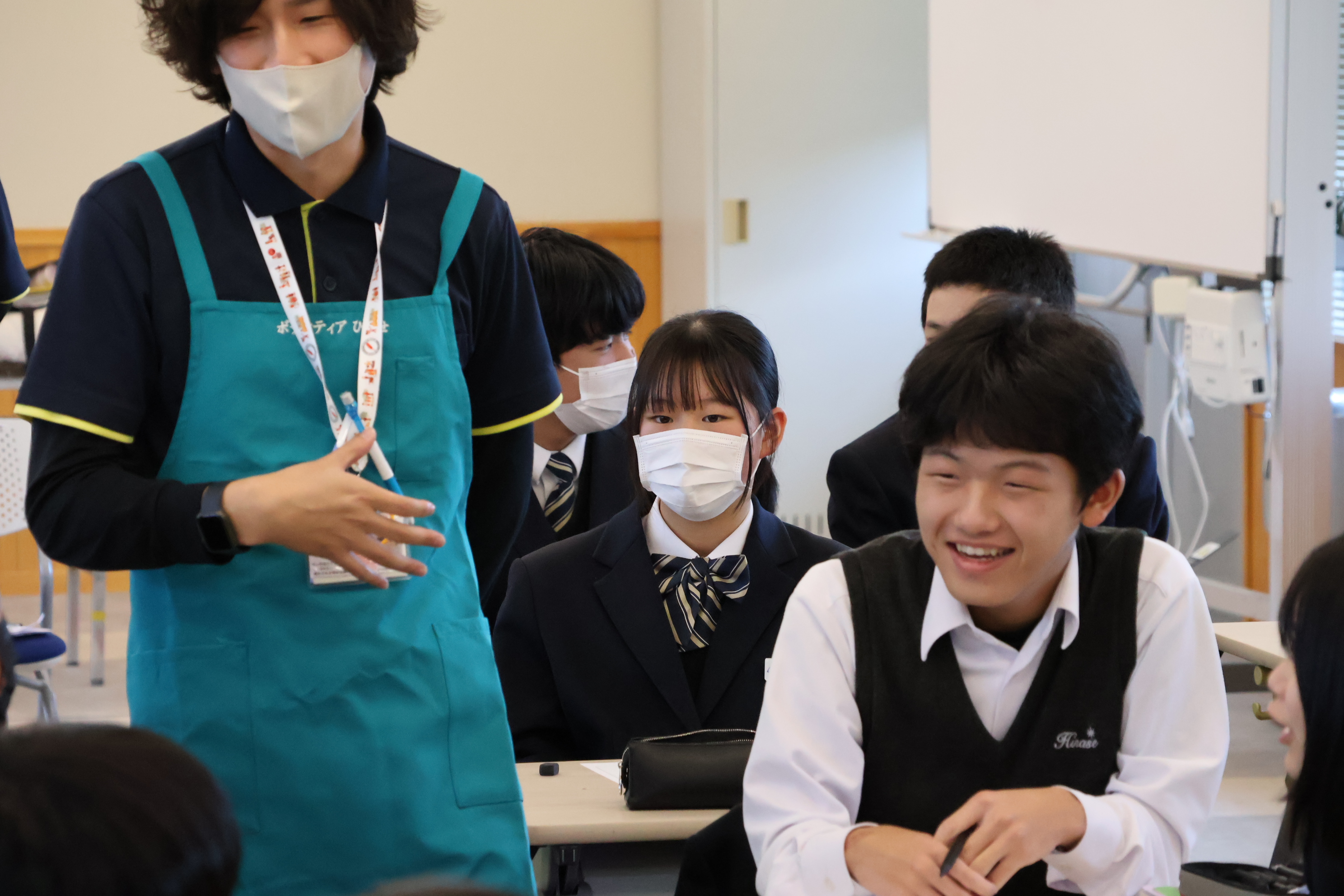




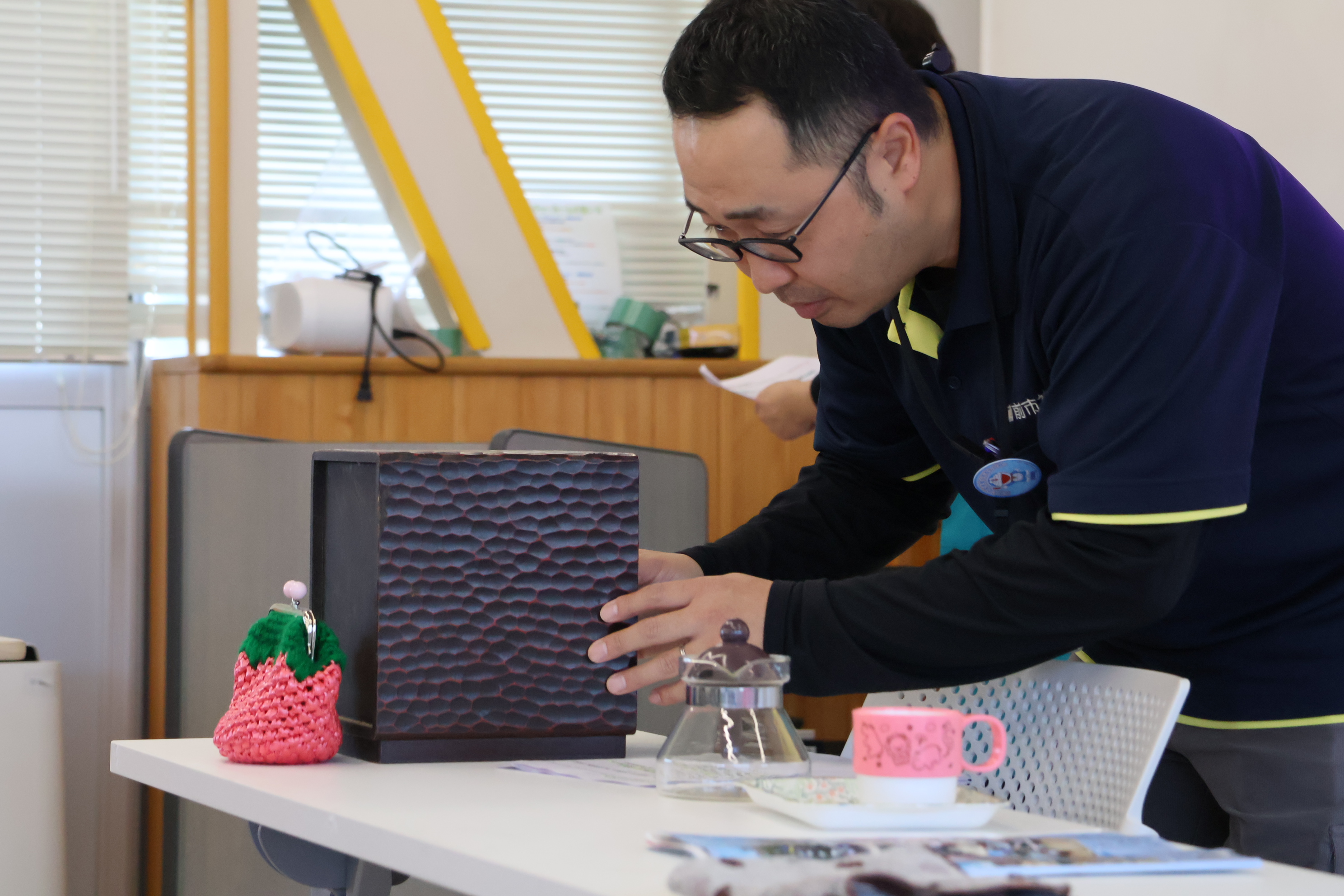

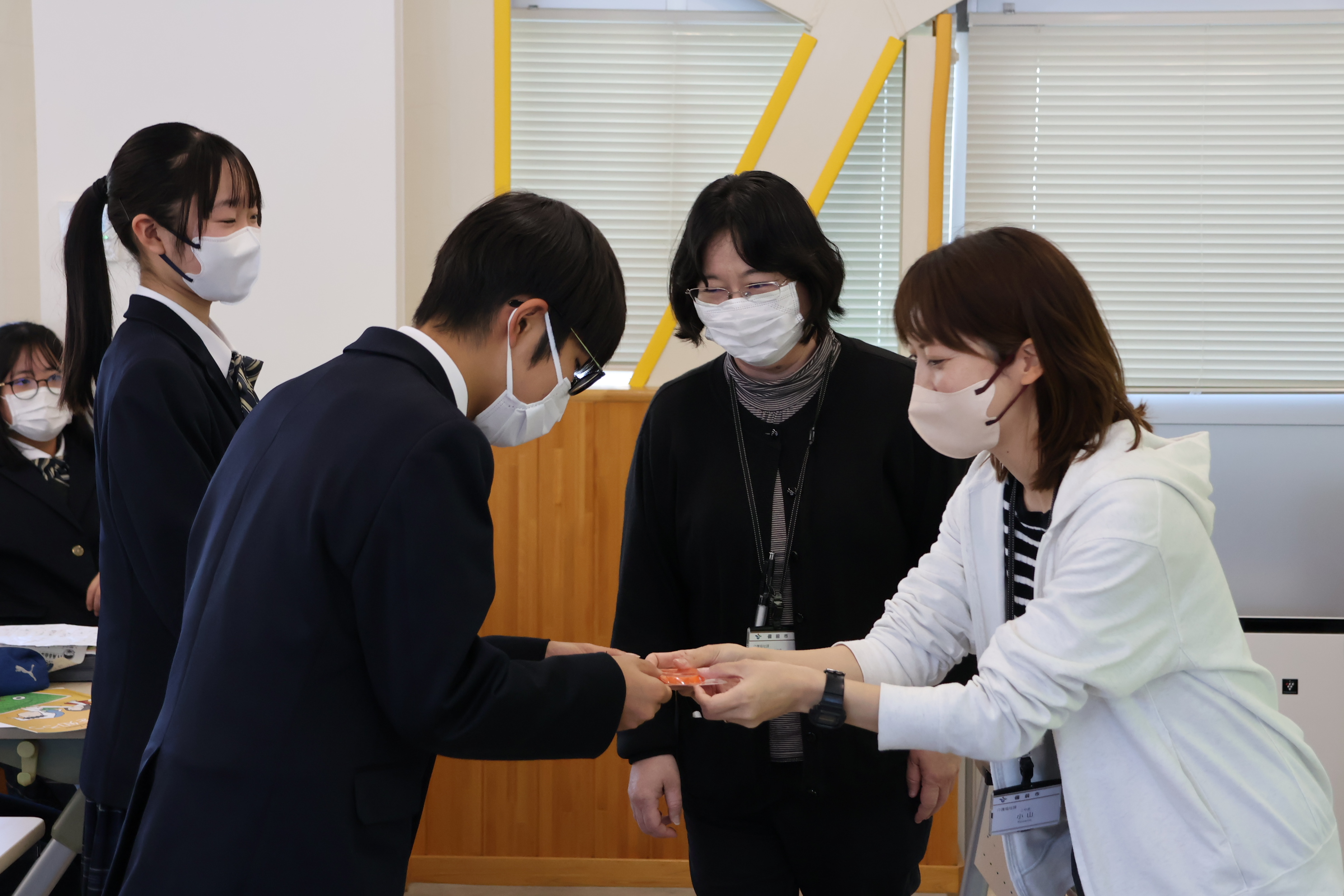

認知症サポーターとは?
認知症サポーターはなにか特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を見守る応援者(サポーター)です。認知症サポーター養成講座を受講したら認知症サポーターとなり、そのしるしとしてオレンジリングをいただきました。オレンジリングを身につけていることで、まちの中で「この人は認知症かな」と思って声をかけるときでも、周囲にも「あの人は、認知症の人のお手伝いをしているんだな」と一目でわかる場合があります。岡山でも若い世代への認知症サポーター養成にも力を入れており、小学校高学年を対象にした認知症キッズサポーター養成講座、中学生を対象にした認知症サポーター中学生養成講座も実施しており、オリジナルバッジ又はオレンジリングを持った児童・生徒もたくさんいます。日生中学校では家庭科の単元に重ねて、中学生向けの認知症サポーター中学生養成講座の以下の内容について学びました。①認知症の知識や具体的な対応方法を知ること。 ②認知症の人を介護されている家族の思いを知ること。 ③自分たちができることはなにかを考えること。
◎日生中の先にあるもの(11/18)
校内清掃ボランティアには、60名を越える有志が集まりました。



◎日生中の先にあるもの(11/18)
今日は、環境委員会が呼びかけて、校内清掃ボランティアを行います。また、今週は、Grow Up Week、LunchTime充実Weekです!

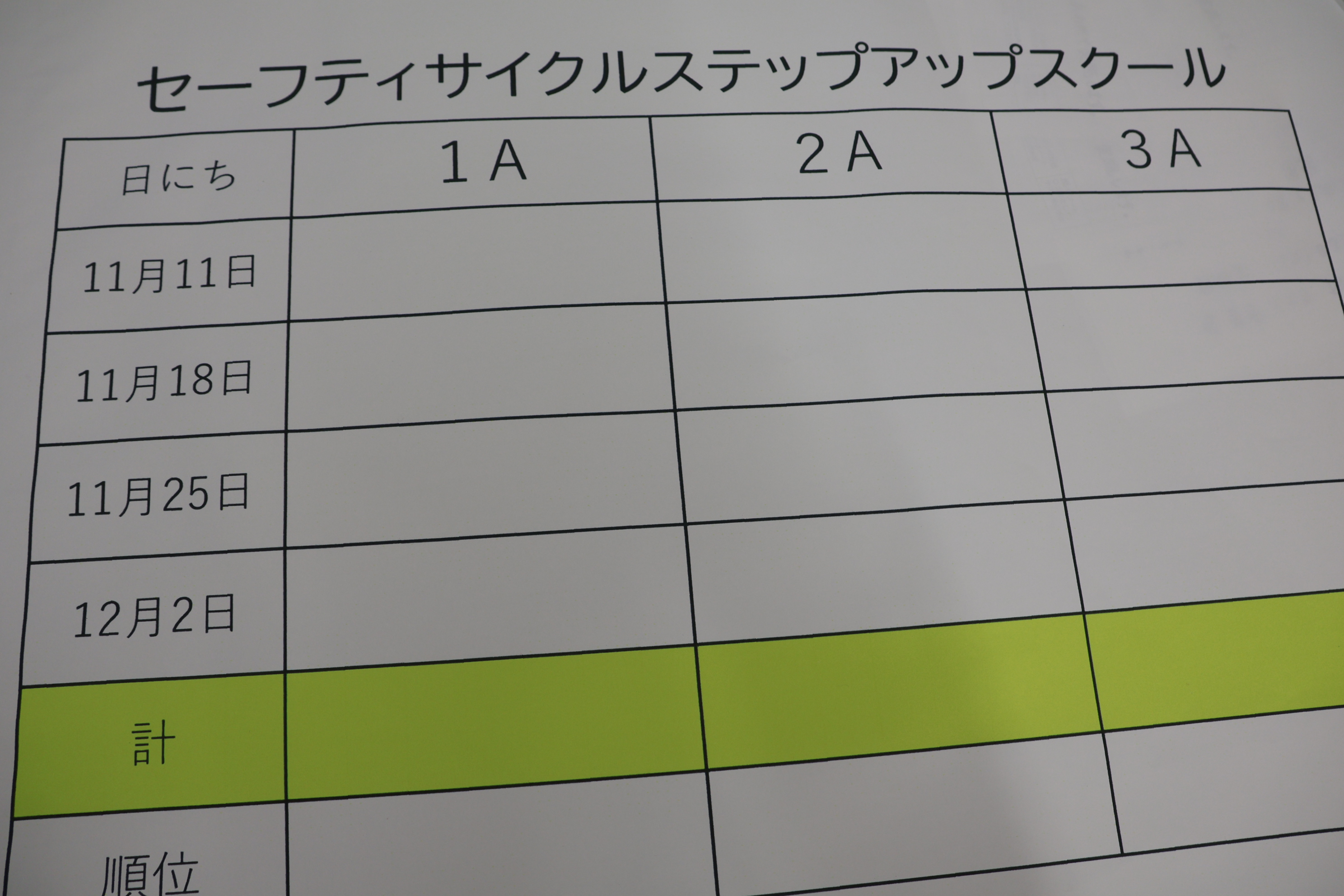

追記:[セーフティサイクルステップスクール]の取組って?・・・これは、岡山県教育委員会及び岡山県警察との間で交通安全教育に関して協力体制の中で、学校において、児童生徒の交通ルールの遵守及び交通事故防止が図られることを目的につくられた教材を活用した取組です。日生中学校でも継続的に学習に取り組んでいます。
日生中学校で取り組んでいる内容は、
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
・車道は左側を通行
・並進の禁止
・携帯電話、スマホをしながら運転の禁止
・傘さし運転の禁止 です。ご家庭においても話題にしていただければと思います。
◎多くの人に支えられて(11/18)
この夏もたくさん利用しました。クーラーのフィルター清掃をありがとうございました。今冬は、灯油等の燃料高騰も鑑み、エアコン利用を中心に学習環境を整えていきたいと思います。生徒のウオームビズ(制服の下を暖かいものに)もよろしくお願いします。

◎七五三
~いくつになっても、子どもの健やかな成長を(11/16)
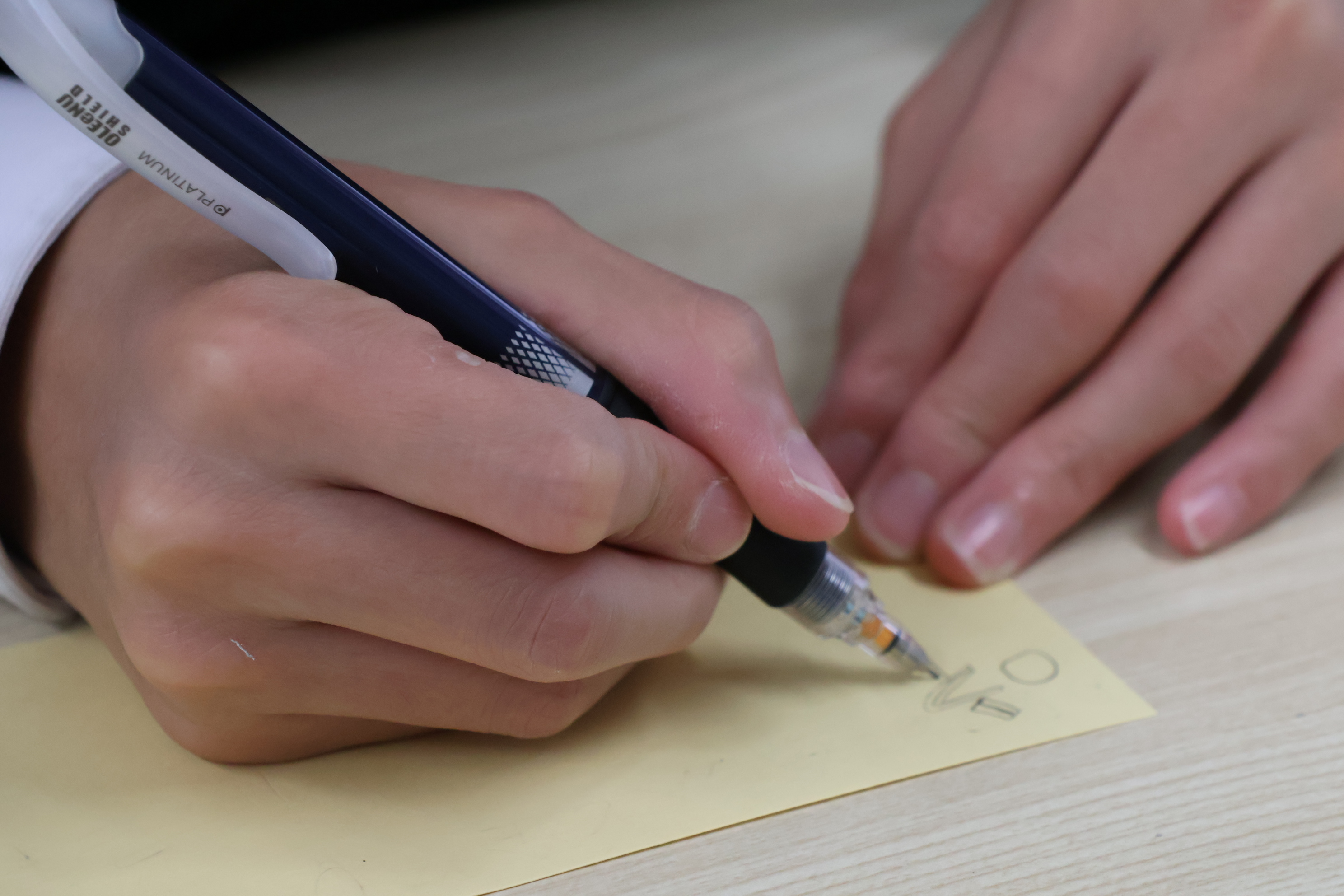

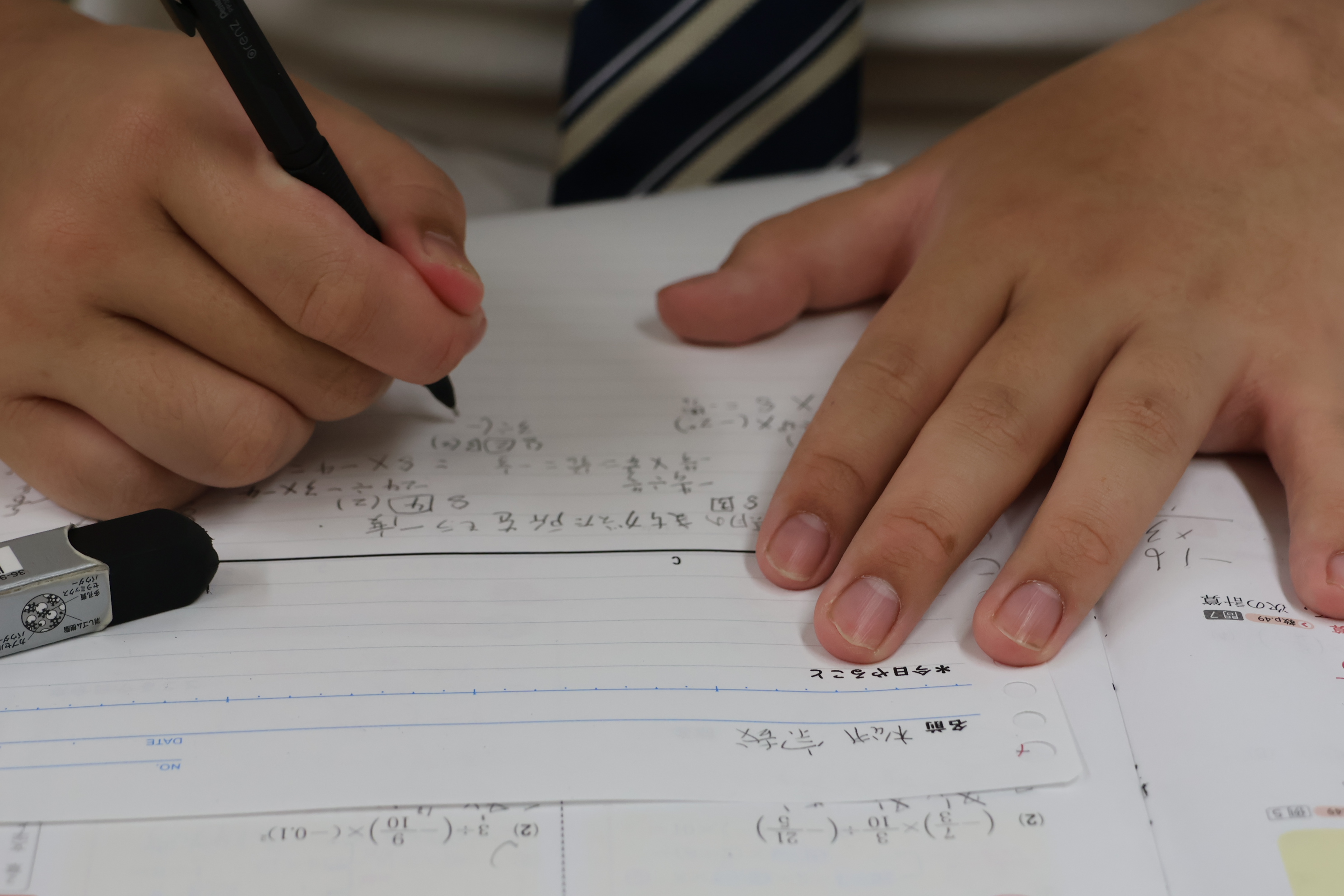
The essentials to happiness are something to love‚ something to do‚ and something to hope for. William Blake
(幸福の重要な部分は、愛すべき何か、すべき何か、そして希望とすべき何かをいう。)
◎MOON RIGHT BRUCE♩(11/15)

今週の夜空の見どころは、2024年最後の「スーパームーン」だ。16日(土)に昇る満月は、通常より大きく見える。週末に極大を迎えるしし座流星群はちょっと見えにくいかもしれないが、おうし座北流星群は週前半に見ごろを迎え、月明かりを気にすることなく明るい「火球」を観察できそうだ。
光害の影響を受けない地域や、大型望遠鏡を使った観測では、天王星を観察するのにもってこいの週でもある。天王星は太陽から遠く離れた暗い天体だが、まもなく年に一度、いつもより明るく見える「衝(しょう)」となる。
おうし座北流星群は12日ごろに極大を迎える。はっきりとした極大がなく、1時間あたりの流星数は5個程度と大きな流星群ではないが、今週見られる「流れ星」はおうし座北流星群とみて間違いない。
今週は月が明るく流星群の観測条件はあまりよくないように思えるかもしれないが、おうし座流星群は「火球」と呼ばれる明るい流星が多く流れる。母天体は「エンケ彗星(2P/Encke)」で、太陽系を通過した際に軌道上にばらまいた塵や破片が流星となって地球に降りそそぐ。
○11月16日(土):スーパー・ビーバームーン
今年11回目、最後から2番目の満月は、通常より大きく明るい「スーパームーン」を拝める年内最後のチャンスだ。東北東からの月の出を待ち構えて、壮観な眺めを楽しんでほしい。満月の後を追って木星も昇ってくる。11月の満月は、冬に備えてビーバーが巣作りをする時期であることにちなんで「ビーバームーン」と呼ばれる。「フロストムーン(霜月)」や、冬至前の最後の満月をさす「モーニングムーン」という呼称もある。
○11月17日(日):しし座流星群が極大
多い時には1時間に100個以上の流星が出現する「流星雨」となることで知られている流星群だが、今年は期待しすぎないほうがいいだろう。夜半過ぎに1時間あたり15個ほどの流れ星が見られそうだが、スーパームーンの満月の翌日とあって夜空はかなり明るい。
今週の夜空の見どころは、2024年最後の「スーパームーン」だ。16日(土)に昇る満月は、通常より大きく見える。週末に極大を迎えるしし座流星群はちょっと見えにくいかもしれないが、おうし座北流星群は週前半に見ごろを迎え、月明かりを気にすることなく明るい「火球」を観察できそうだ。
光害の影響を受けない地域や、大型望遠鏡を使った観測では、天王星を観察するのにもってこいの週でもある。天王星は太陽から遠く離れた暗い天体だが、まもなく年に一度、いつもより明るく見える「衝(しょう)」となる。
おうし座北流星群は12日ごろに極大を迎える。はっきりとした極大がなく、1時間あたりの流星数は5個程度と大きな流星群ではないが、今週見られる「流れ星」はおうし座北流星群とみて間違いない。
2年生はチャレンジワーク、三年生は進路懇談を越えた夜、仲間と共に進路を切り拓いてく覚悟を確かめよう。


◎仲間を知る クラスで暮らす一歩一歩
~わたしあなたそして仲間(続き)(11/14)

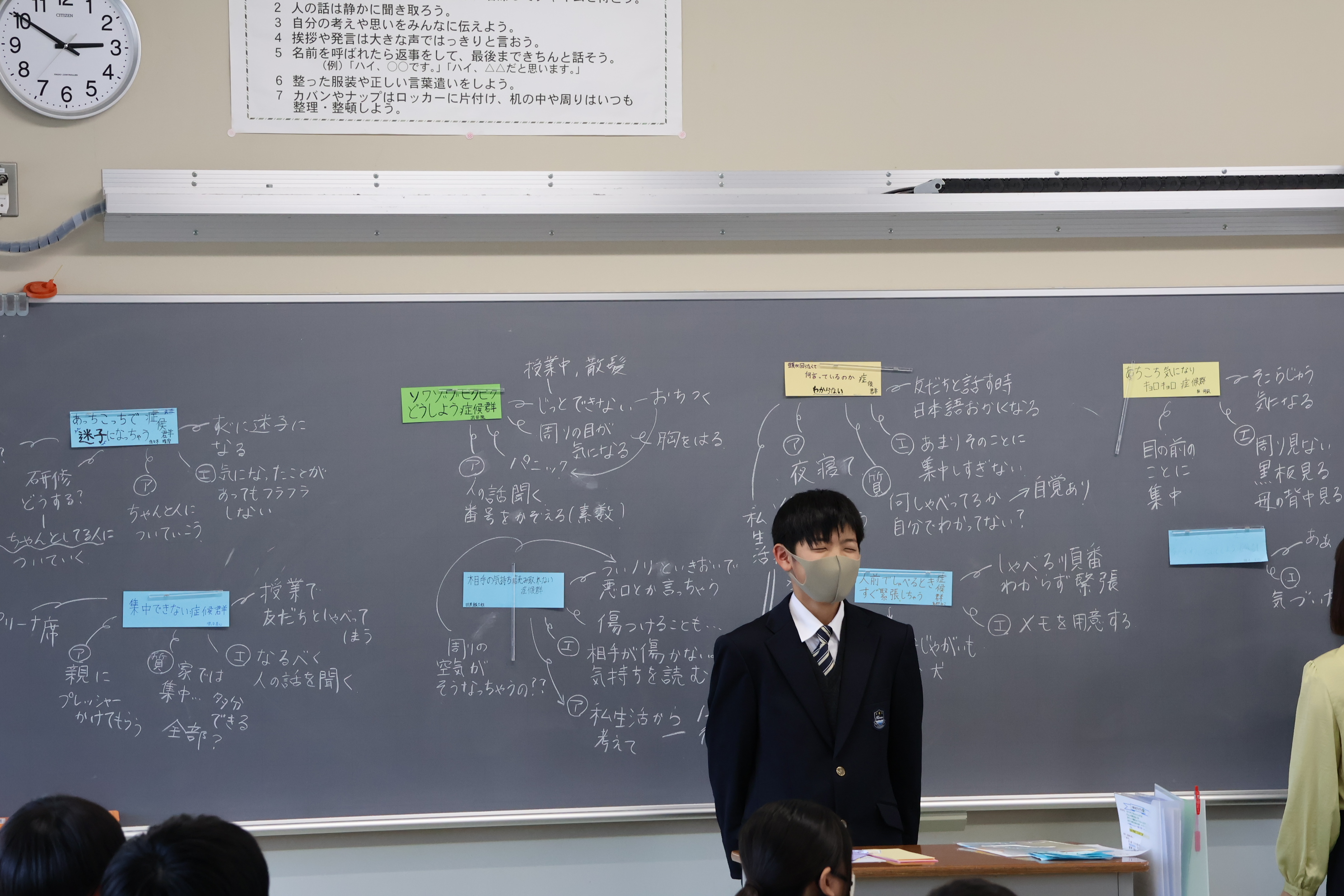
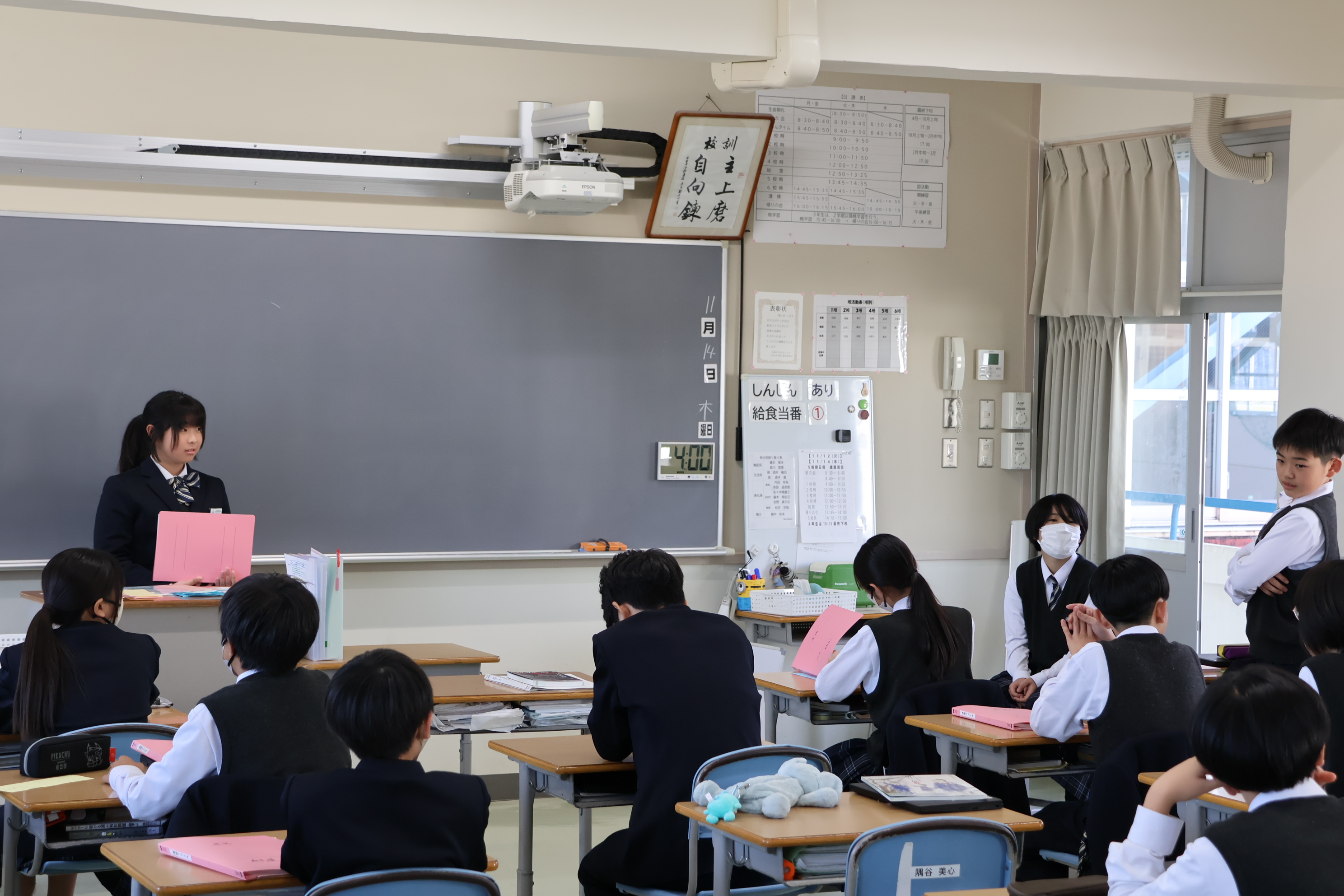
◎「後半 いってみよう~!」
同じ空の下、がんばる仲間と(二年生チャレンジワーク:11/14~)







〈あんまんは冷えたらただのまんじゅうになるよだなんて真っ白な嘘 千葉聡〉 (11/13)

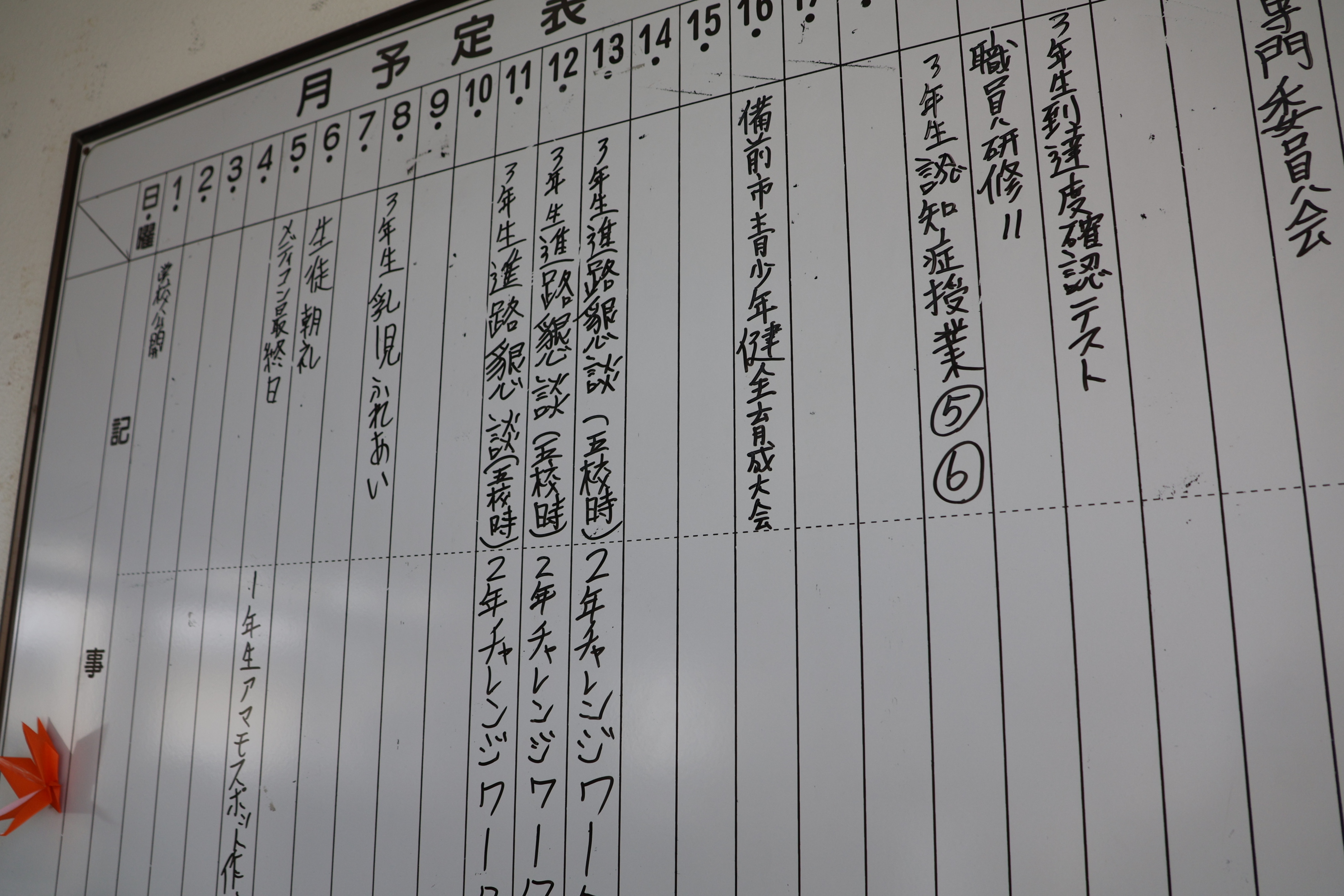
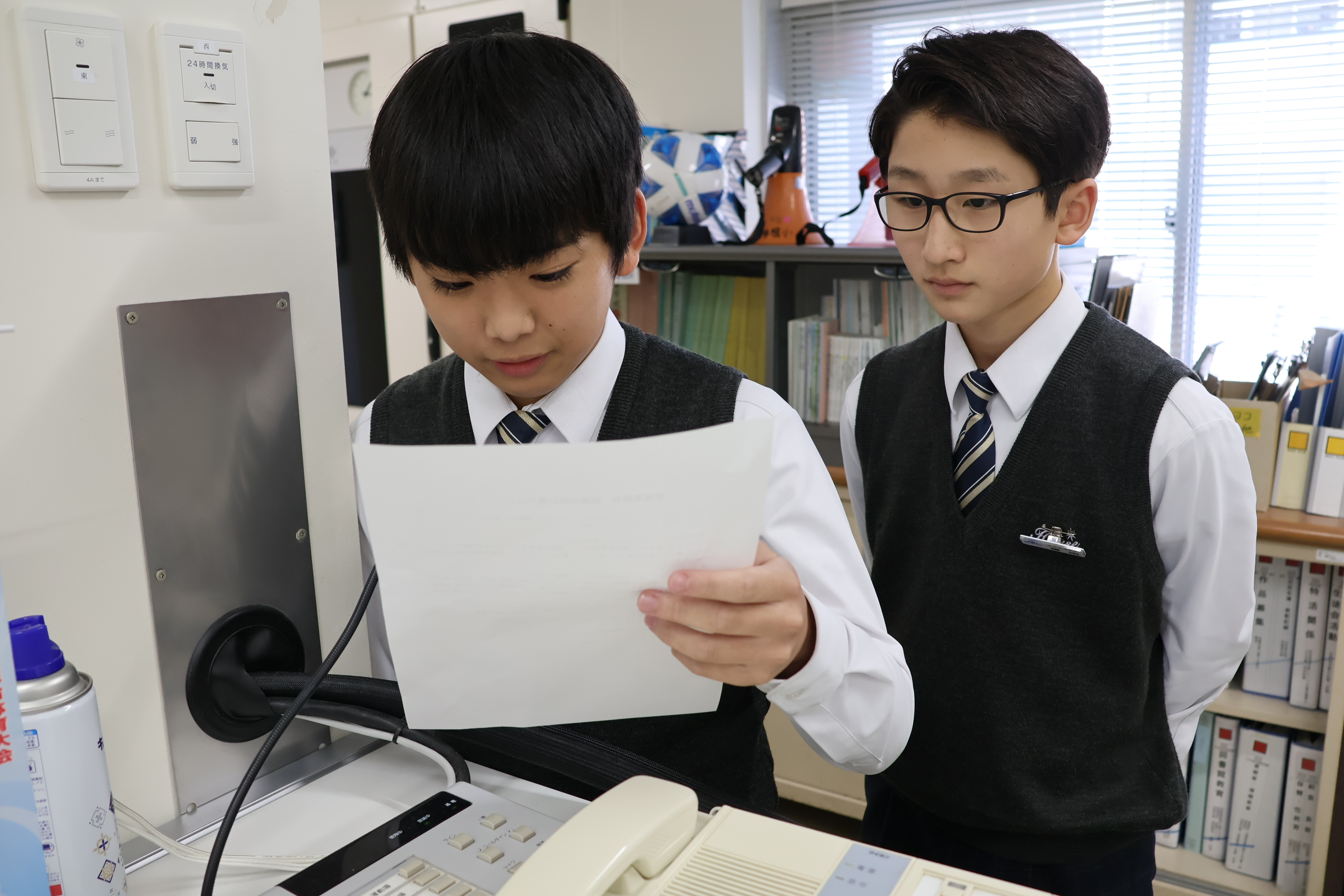
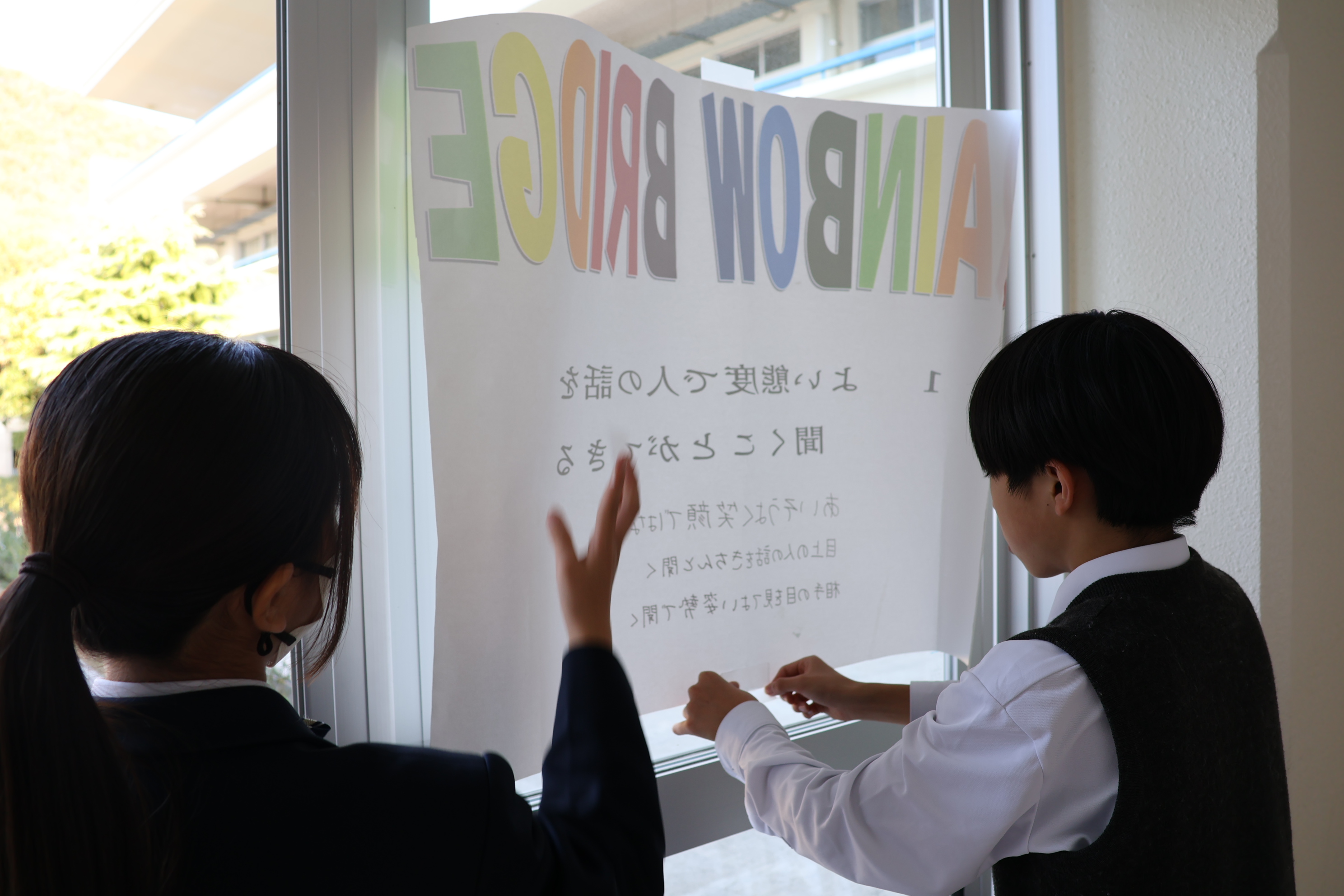


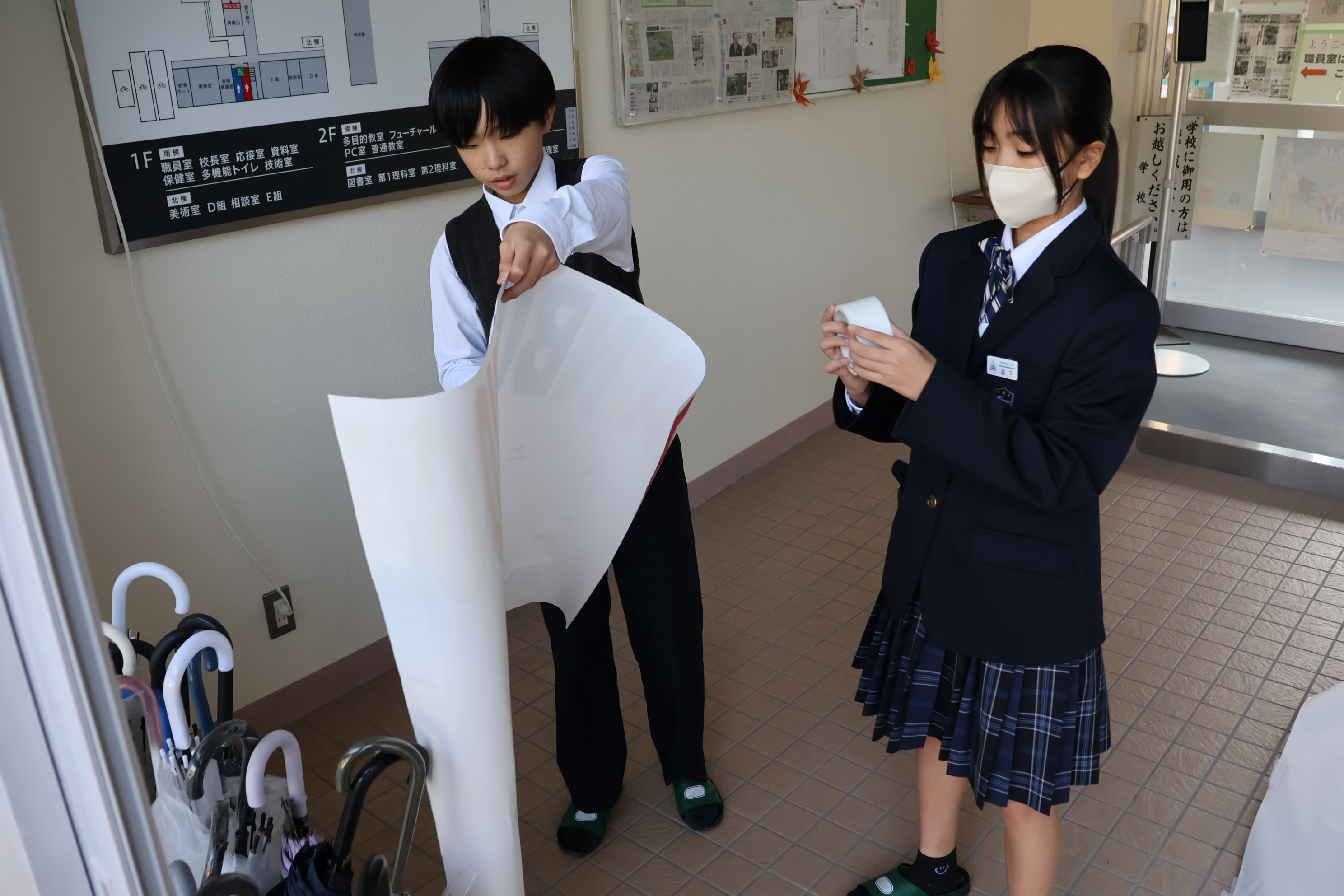
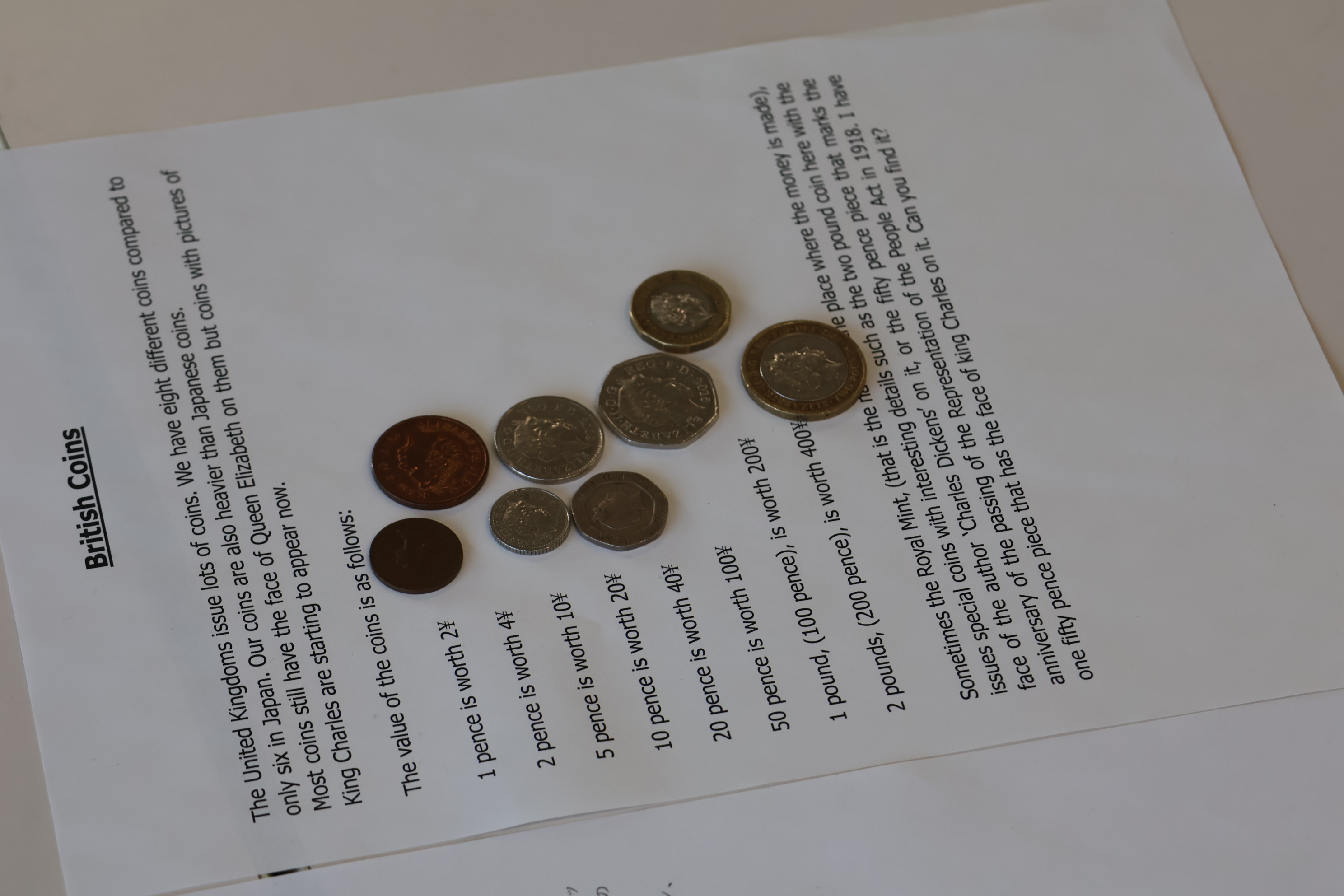

◎明日がある 明日があるさ (三年生進路懇談~)

◎CHALLENGE HINASE!
MORTON’s ENJOY ENGLISH ! (毎週火曜日OPEN:11/12)

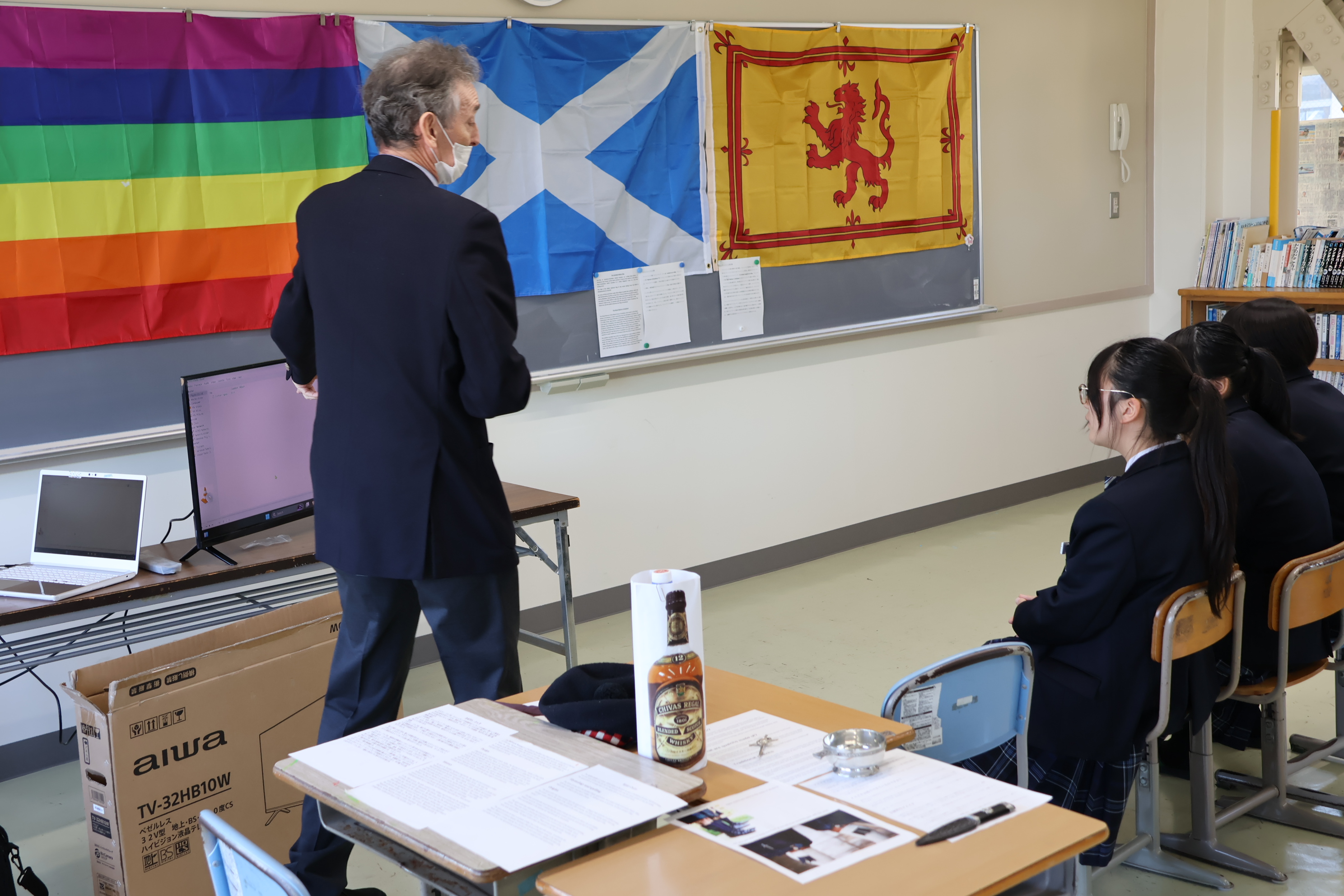
◎Tomorrow (A Better You‚ Better Me)
(feat Tevin Campbell)
二年生がいよいよ職場体験学習(11/12~15)に取り組みます。叱咤激励をどうぞよろしくお願いします。事業所の皆様もどうぞよろしくお願いします。
中元写真館 日生図書館 カメイベーカリー 日生町漁協・五味の市・しおじ 奥本生花店 café RAD マクドナルド赤穂フレスポ店 (有)磯 ステラカフェ カフェ天goo 一般社団法人ジンジャー・エール レストラン夕立 THE COVE CAFE すき家250号赤穂駅前店 日生認定こども園 日生西小学校 日生東小学校 伊里認定こども園 セブンイレブン岡山備前インター店 山陽マルナカ穂浪店 ホームプラザナフコ備前店 旬鮮食彩館パオーネ日生店 ホームセンタータイム備前店 ダイレックス赤穂店(順不動・敬称略)

◎切り拓いてく私・未来 (11/11~三年生進路懇談)
今週は5校時日程で、三年生は15:15最終下校となります。
『道程』
僕の前に道はない
僕の後ろに道は出来る
ああ、自然よ
父よ
僕を一人立ちにさせた広大な父よ
僕から目を離さないで守る事をせよ
常に父の気魄きはくを僕に充みたせよ
この遠い道程のため
この遠い道程のため

◎あれからぼくたちは 何かを信じてこれたかなぁ…
夜空のむこうには 明日がもう待っている♬
新入生を迎える準備を進めています。(11/11)


◎あたたかいんだからぁ ここ、なかま(11/8)


◎今日もいただきます。(いい歯の日)




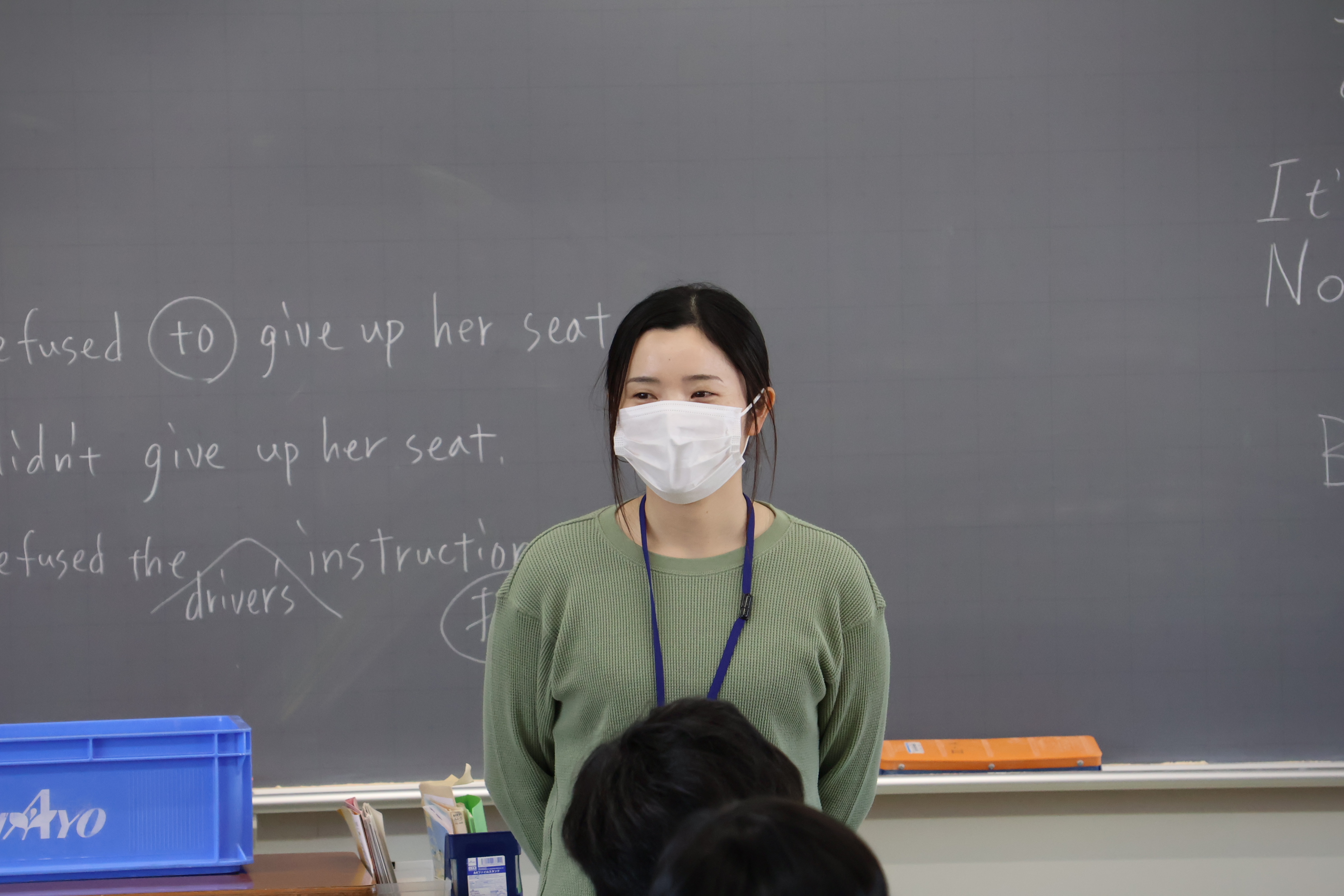
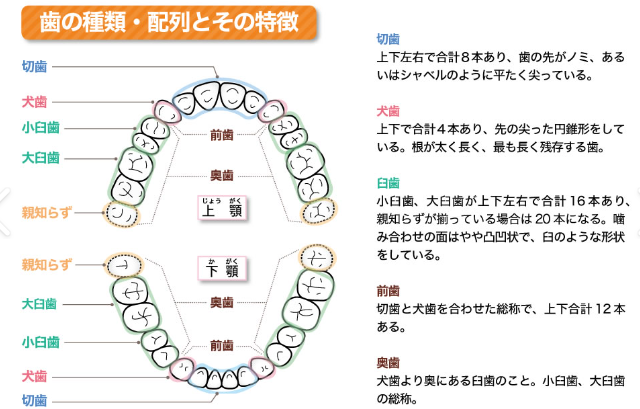
◎赤ちゃん登校日(11/8)
~ようこそひな中へ ようこそパパママ ようこそ未来のワタシ
赤ちゃん登校日は、未来のパパ・ママとなる中学生が、子育てへの期待や、親から大切に育てられた存在であることの気付きを得ることを目指した体験型授業です。地域のNPOひこうせんさんとが中学校と連携して取り組みます。毎年、子育て中のママパパが赤ちゃんを連れて中学校に訪問し、世代を越えたあたたかな交流が生まれています。これからの時代を生きる中学生が、赤ちゃんやママパパと交流することで、多世代への理解を深め、地域社会とのつながりを学ぶ場になることを目指しています。













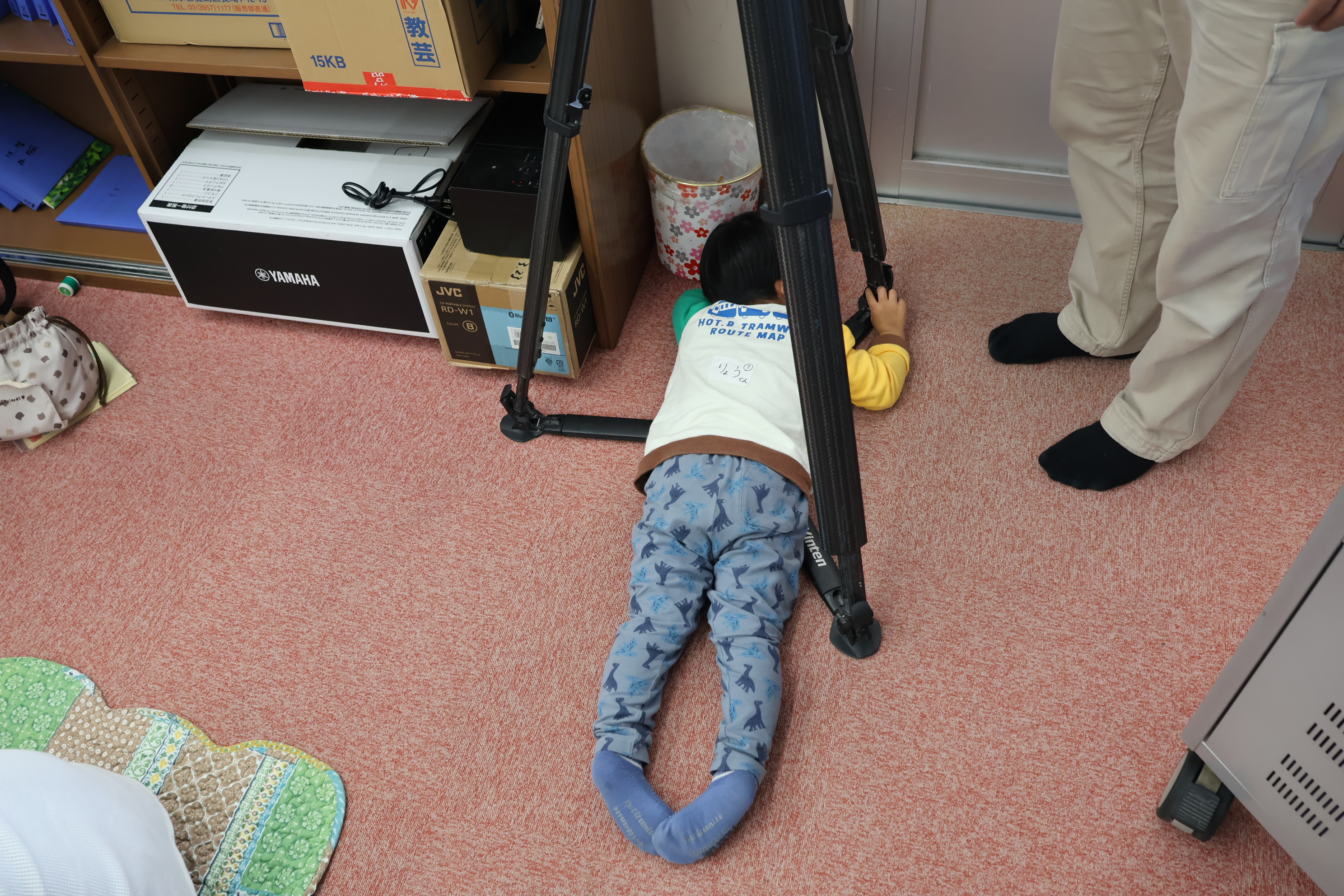

Just be yourself‚ there is no one better. TAYLOR SWIFT
(あなた自身でいるの、あなた自身よりも良い人なんていない)
◎「ぐわし」と心をつかむ読み語りも。
秋の読書月間を楽しもう~(11/7)
今日は、しんしんタイムで、校長・教頭・春名・髙橋先生らの「読み聞かせ」がそれぞれのクラスでありました。

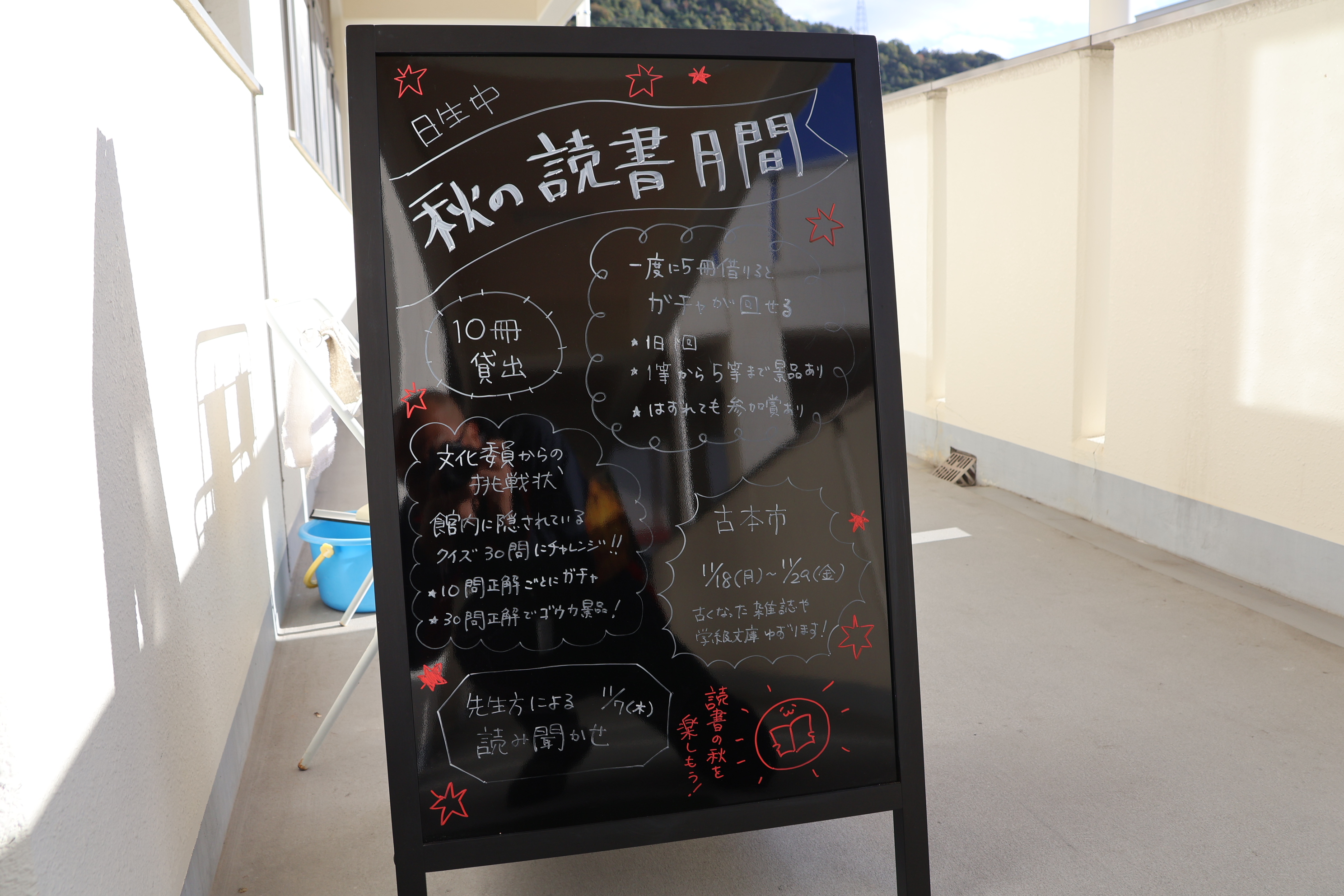

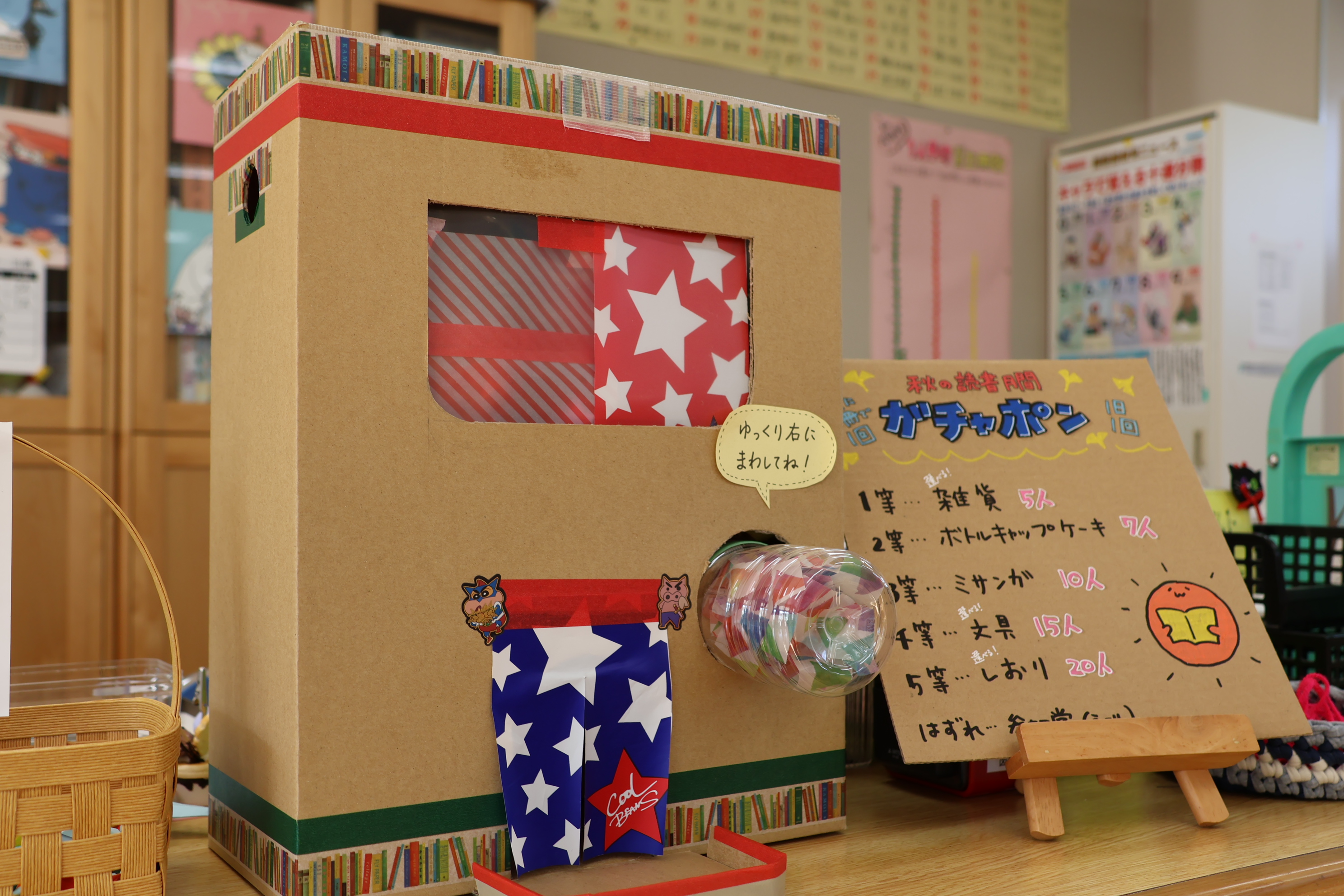
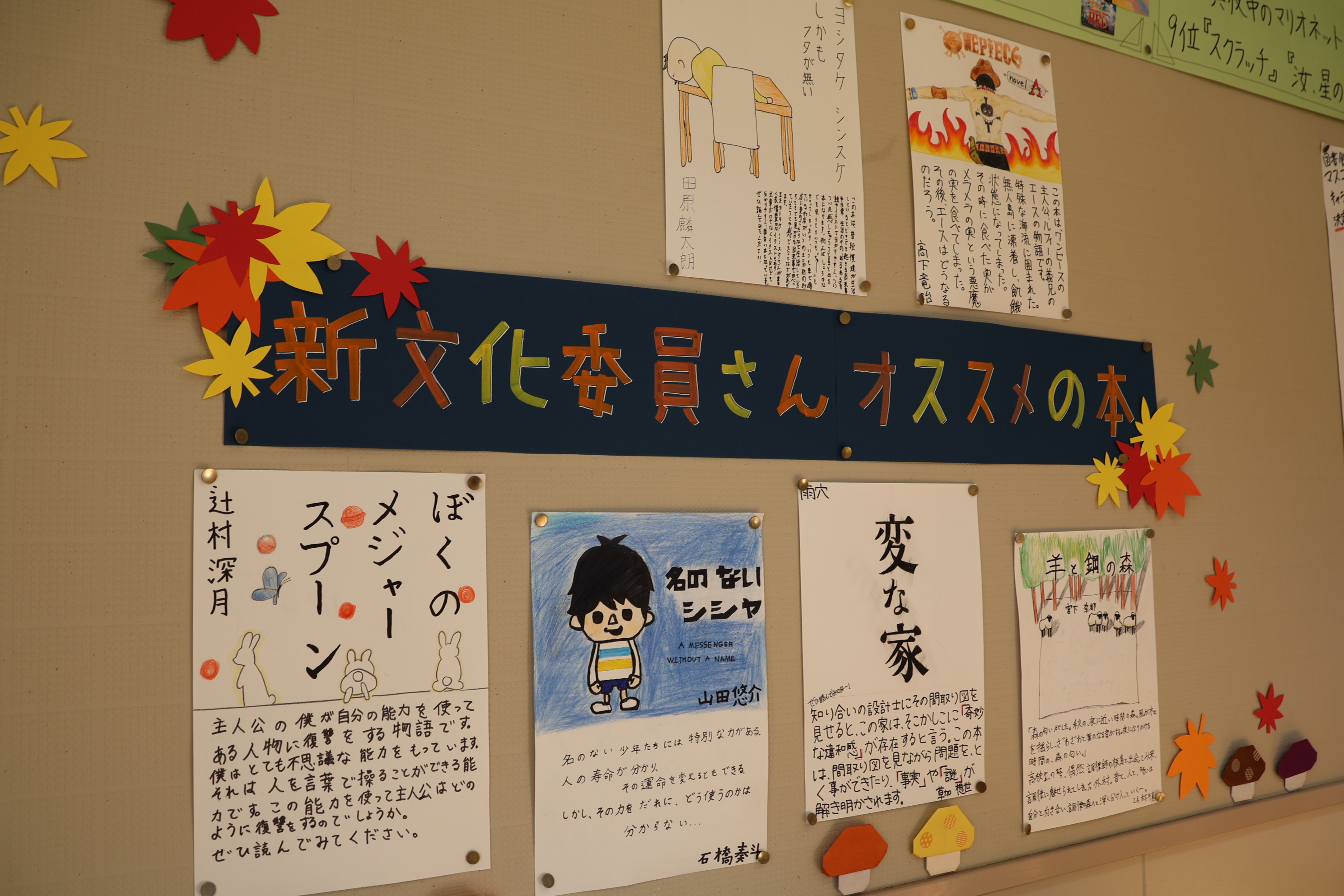

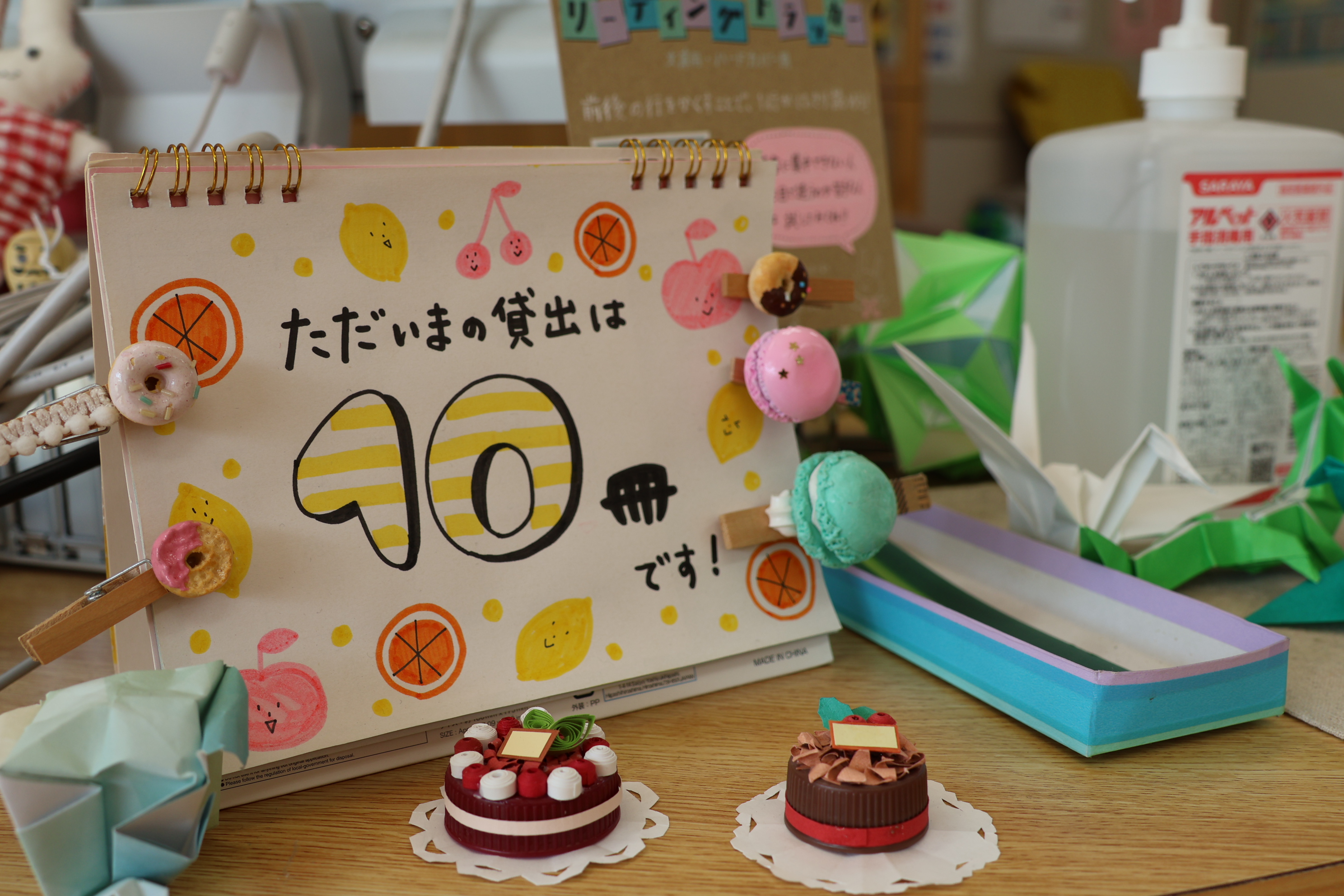

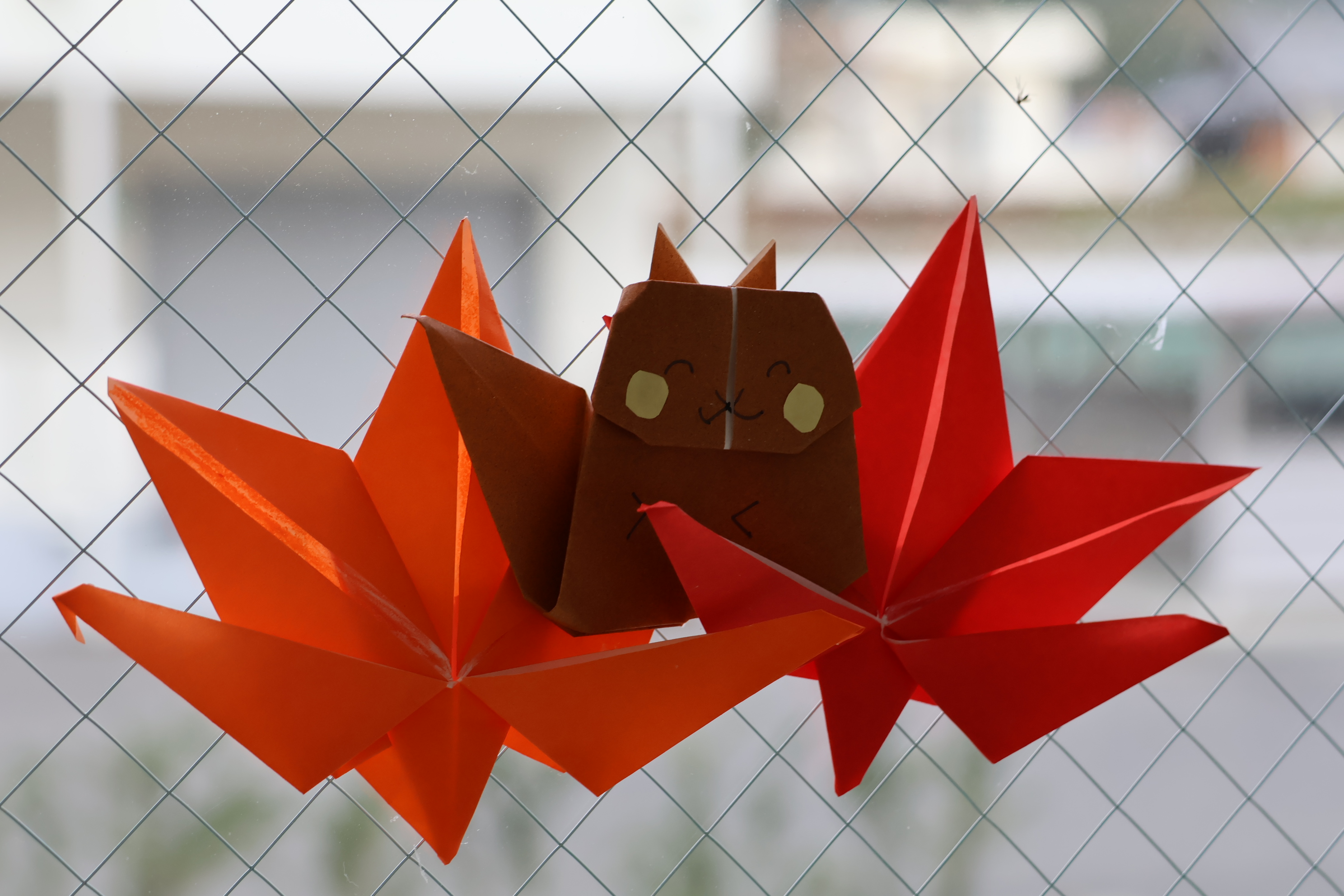



◎〈わたし あなた そして仲間(続)〉(11/7)
人権学習に1年生が継続的に取り組んでいます。前回のエリアティーチャーさんから頂いたアドバイスをもとに、「自分について深く考え、それを仲間に知ってもらおう」と、今日は、発表に向けて、「自分の思いや願い」を綴っていきました。

[閑話休題]マルティン・ブーバー(1878-1965)は、〈わたし〉がまず存在して、それからその他の人やものがあり、それらに出合うという見方を根本から考え直しました。ブーバーは、〈わたし〉が独立してまず存在しているのではなく、つねに〈わたし-あなた〉という人間の対応関係がもっとも根源的なものであると述べます。
わたしたちは日常的に、自分を起点として世界をとらえています。別の言い方をすれば、まず〈わたし〉があって、それからわたし以外の人やものがある、ということになるでしょう。しかしブーバーは、このような自己を中心におく世界観に疑問を投げかけました。ブーバーは〈わたし〉がスタート地点になる関係性を〈わたし-それ〉と呼び、〈わたし〉と〈それ)はどこまでいっても別のものであり、相互的な結びつきをもつことができないと指摘します。
〈わたし〉とその他の人やものというとらえ方は、物質に極端にこだわったり、エゴイズム的にふるまったりすることにもつながる可能性があります。ドイツ語圏で活躍したユダヤ人哲学者であるブーバーのこのような指摘は、後のナチスドイツが招いた悲劇を予見させるものともいえます。
その一方で、〈わたし〉と〈あなた〉は、出合い、呼びかけ合い、話し合うことで成立する関係です。〈わたし〉はまた同時にだれかから〈あなた)と呼びかけられる存在でもあります。この世の中に〈わたし〉だけで生きることができる人はおらず、必ずどこかで誰かと関係をもちながら生きています。そのなかで〈わたし-あなた〉という視点をもつということは、「呼びかけ、呼びかけられる」関係をスタートさせることでもあるのです。
◎Time goes by(11/7)



PTAのご支援・ご協力により、新しく付け直すことができました。
◎HINASSE LEGACY✨
~やっぱり大事にしたい。もくもくもくもくもく清掃(11/7)

◎出会いにこころをこめて
~ひな中ほっとスペースOPEN(11/6)
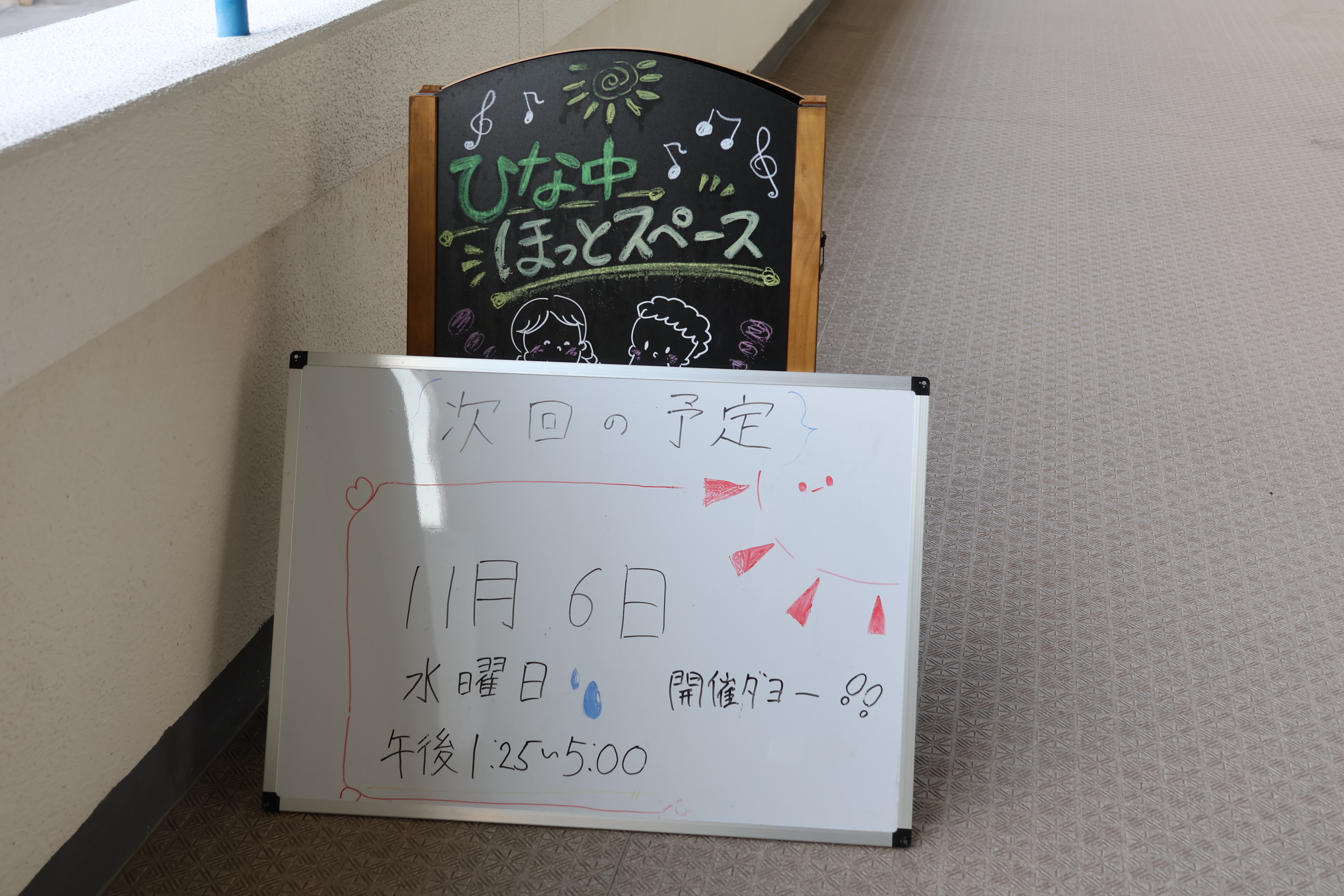


◎ひな中の進化・深化・真価
~聴く、考える、語る 私たちの朝礼へ(11/6)









◎めぐる季節の中で 立冬へ(11/6)



2024年の立冬は、11月7日から11月21日です。毎年11月7日頃~11月21日頃にあたりますが、日付が固定されているわけではありません。二十四節気は季節の移り変わりを知るために、1年を約15日間ごとに24に分けたものですが、太陽の動きに合わせて1年を24等分して決めるので一定ではなく、1日程度前後することがあるからです。
そのため、立冬といっても、立冬に入る日を指す場合と、立冬(二十四節気の第19)から小雪(二十四節気の第20)までの約15日間をいう場合があります。この時期になると、冬の使者「木枯らし」がやってきます。その名の通り、吹くたびに葉を落とし、まるで木を枯らしてしまうように見えることからそう呼ばれています。西高東低の冬型の気圧配置になってから、風速8m以上の北寄りの風が吹くと「木枯らし1号」と発表されます。二十四節気をさらに3つに分けた七十二侯は、立冬の間にこのように移り変わります。
日付は、2024年の日付です。
●初侯:山茶始開(つばきはじめてひらく)11月7日頃
山茶花(さざんか)の花が咲き始める頃です。昔からサザンカとツバキはよく混同されてきたため、「山茶始開」と書いて、「つばきはじめてひらく」と読まれました。もともと山茶花はツバキを指していましたが、混同され、サザンカの名称として定着したといわれています。
↓
●次侯:地始凍(ちはじめてこおる)11月12日頃
大地が凍り始める頃。地中の水分が凍ってできる霜柱がみられるようになります。舗装が多くなり、霜柱をみる機会も減りましたが、サクサクと霜柱を踏みしめる感触が楽しめる季節になります。
↓
●末侯:金盞香(きんせんかさく)11月17日頃
スイセンの花が咲き、よい香りを放つ頃。通常、スイセンは「水仙」と書き、キンセンカという別の花もありますが、ここでいう金盞は金の盃(さかづき)という意味で、花の内側の黄色い部分を金の盃に見立て、スイセンを指しています。なお、スイセンには、黄色い内側を金の盃に、白い外側の部分を銀の台に見立てた「金盞銀台」という異名があります。日々寒さが増すなかで、本格的な冬に向け準備を始める時期です。衣類や寝具のみならず、暖房器具もそろそろ準備しておきたいですね。
ちょうどこのころ「亥の子の日」がめぐってきます。「亥の子の日」とは、本来は旧暦10月の最初の亥の日のことですが、今は11月の第一亥の日(2024年は11月7日)を指すのが一般的です。日本の文化に深く関わる陰陽五行説において「亥」は水にあたり火に強いとされているため、「亥の子の日」に「こたつ開き」や「炉開き」(火を使うこたつや炉を使い始めること)をすると火事にならないと言われてきました。現在は火を使うこたつではありませんが、暖房器具を準備する好機になっています。
◎多くの人に支えられて(日生文化祭を終えて:11/5)
グラウンド整備をありがとうございました。

◎チャレンジ企画✨
モートン先生と多文化共生社会へ(11/5:英会話教室)
今日の最初の会は、スコットランドの伝統的な踊りを視聴してはじまりました。

I always look for a challenge and something that’s different. Tom Cruise
(僕は常に挑戦することと普通とは違う何かを求めている。)
◎未来は僕らの手の中(11/5:今年もアマモポット作成 西小で)



◎日生で輝く 日生が輝く(11/3:日生文化祭)
この日も、ボランティアプロジェクトで参加した生徒らは、子どもの服リユース会、ひな中日生盛り上げ隊のバザーと子どもくじに取り組み、来会された方々にとても喜んでいただきました。また、吹奏楽部の演奏には、たくさんのあたたかい応援を頂きました。ありがとうございました。地域でのイベントや中学生がお手伝いできることがあれば、「ひな中地域ボランティア推進プロジェクト」で、校内で参加を呼びかけます。学校にご連絡くださいね。
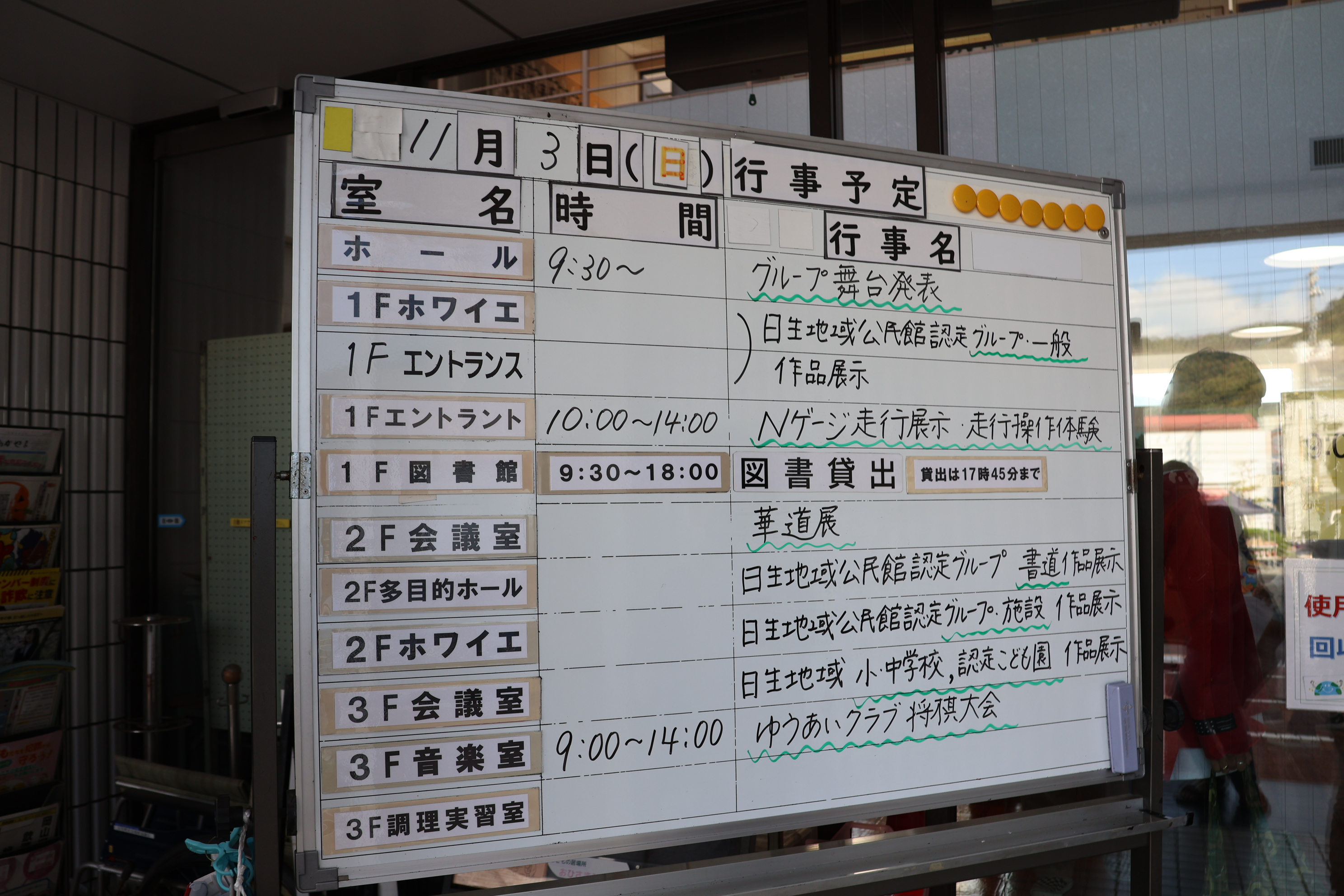





Life must be lived as play. Platon
(人生は演劇のように生きるべきだ。)
◎確かで・豊かな学びを日々の授業で。
~無関心は無視につながる 関心は尊重につながる
NPOきずなから川元さんと三宅さんをエリアティチャーさんにお迎えして、2年生がホームレス問題学習に取り組みました。(11/1)

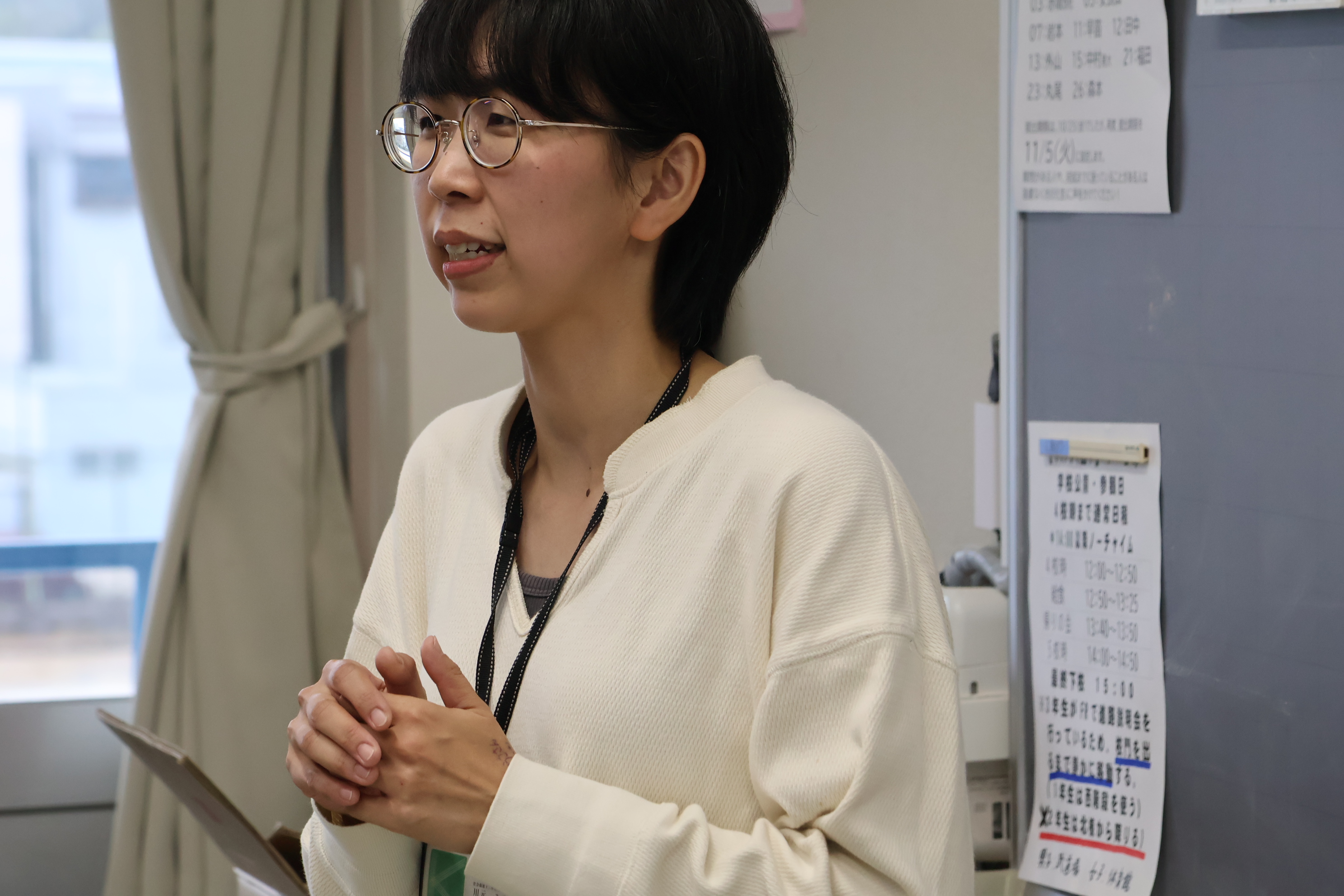

~クラスで暮らす
椙原さん、森下さん、小寺さんをお招きして、特性・クセ・タイプを、クラスでお互いが理解する学習に取り組みました。そして、小寺さんからのアドバイスで、次時は、自分(当事者)研究を進め、自分の特性についての理解と対処法を深め、さらに、クラスの仲間に知ってほしいことを語り合います。(11/1)





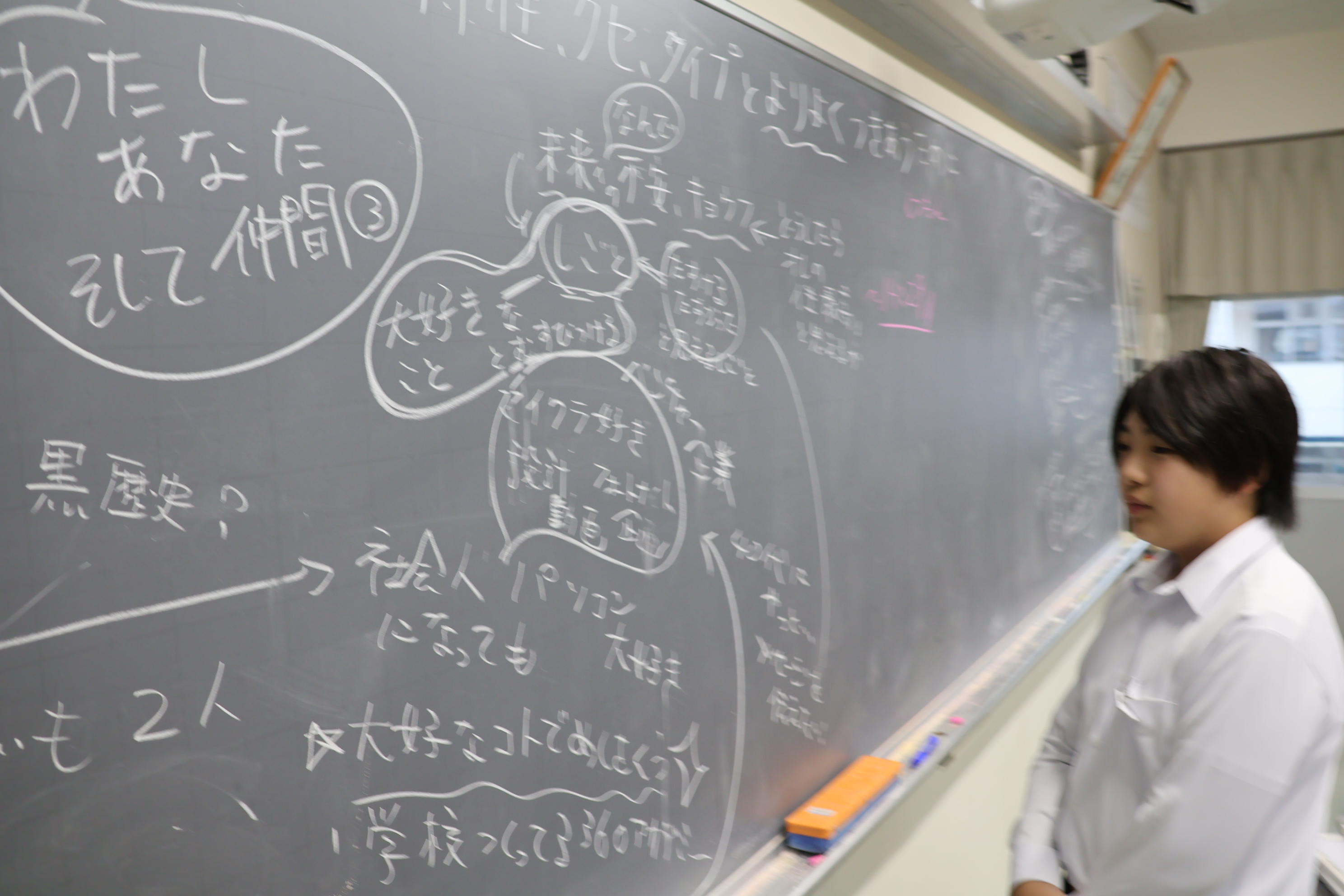
そして、3年進路(事務)説明会(11/1)
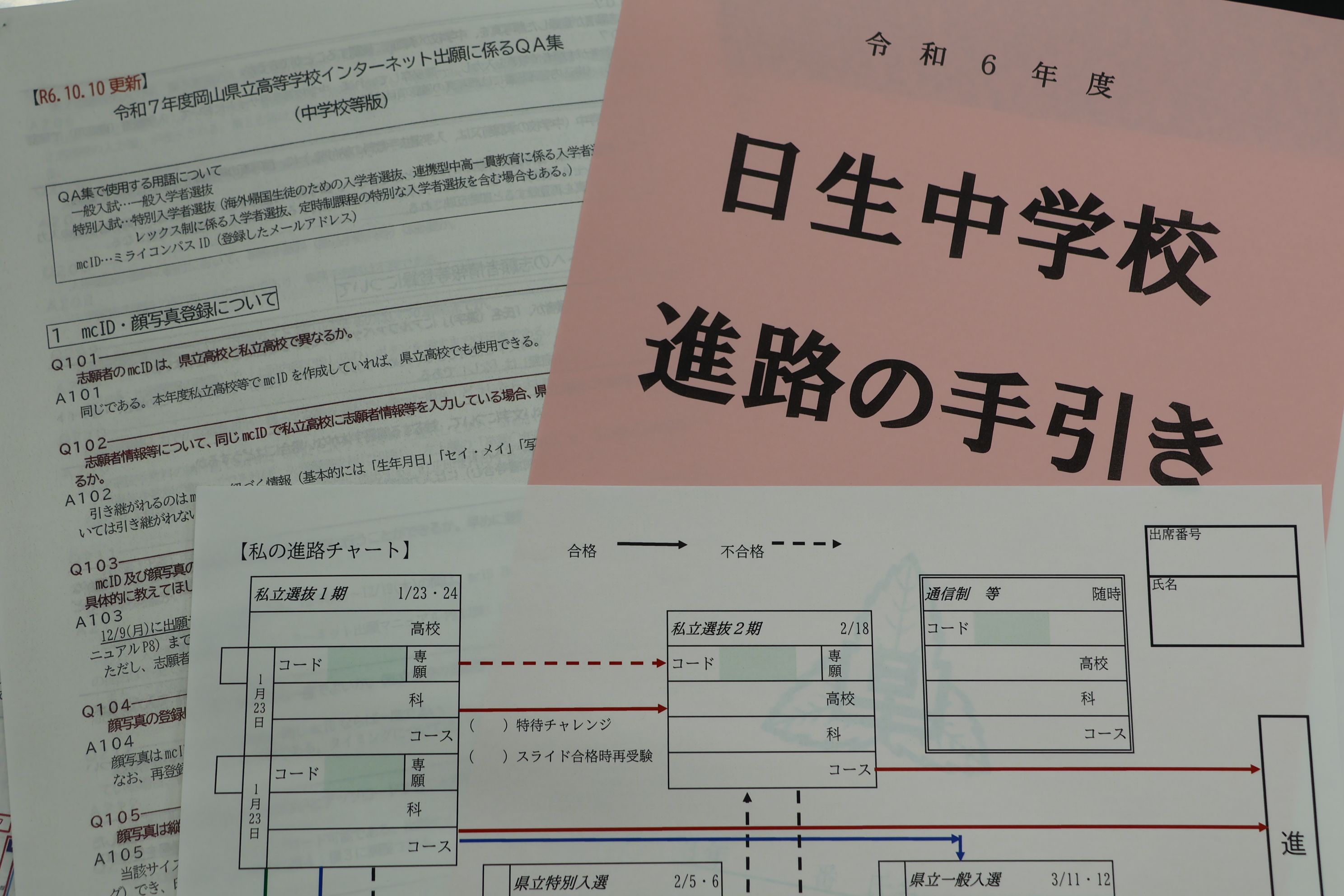
一人ひとりの進路実現に向けた「進路保障」を進めます。
◎ありがとう ありがとう
私たちと共にこれからも(11/1)

今日から教育・文化週間です。本校では、永年勤続表彰をさせていただきました。感謝!
◎校長室から(10/31)
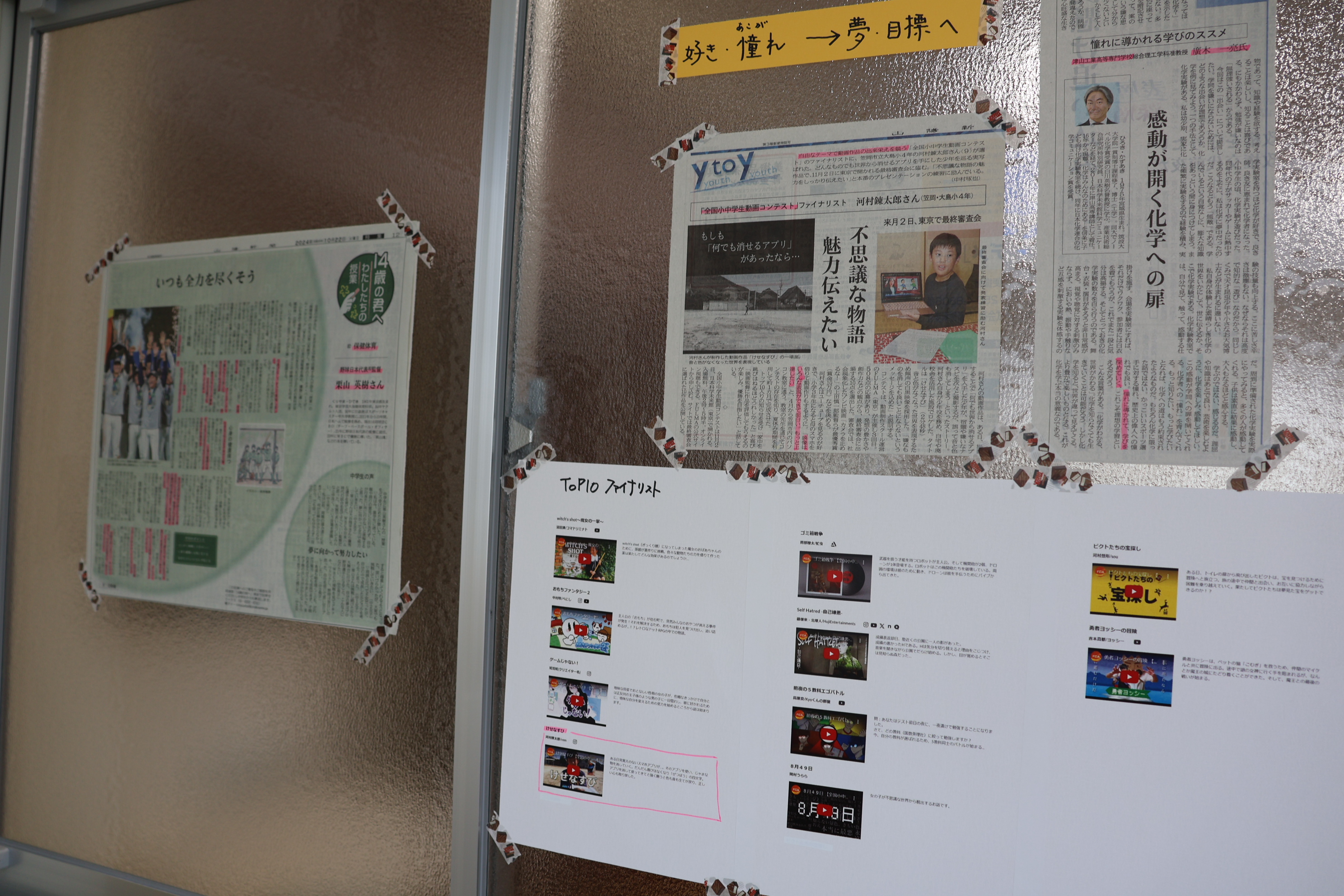
◎わたし あなた そして仲間
~おかやま教育週間 学校公開(1.2年生参観日 3年進路説明会)11/1)



◎可能性だけがある私たち✨
~専門委員会始動(10/31)
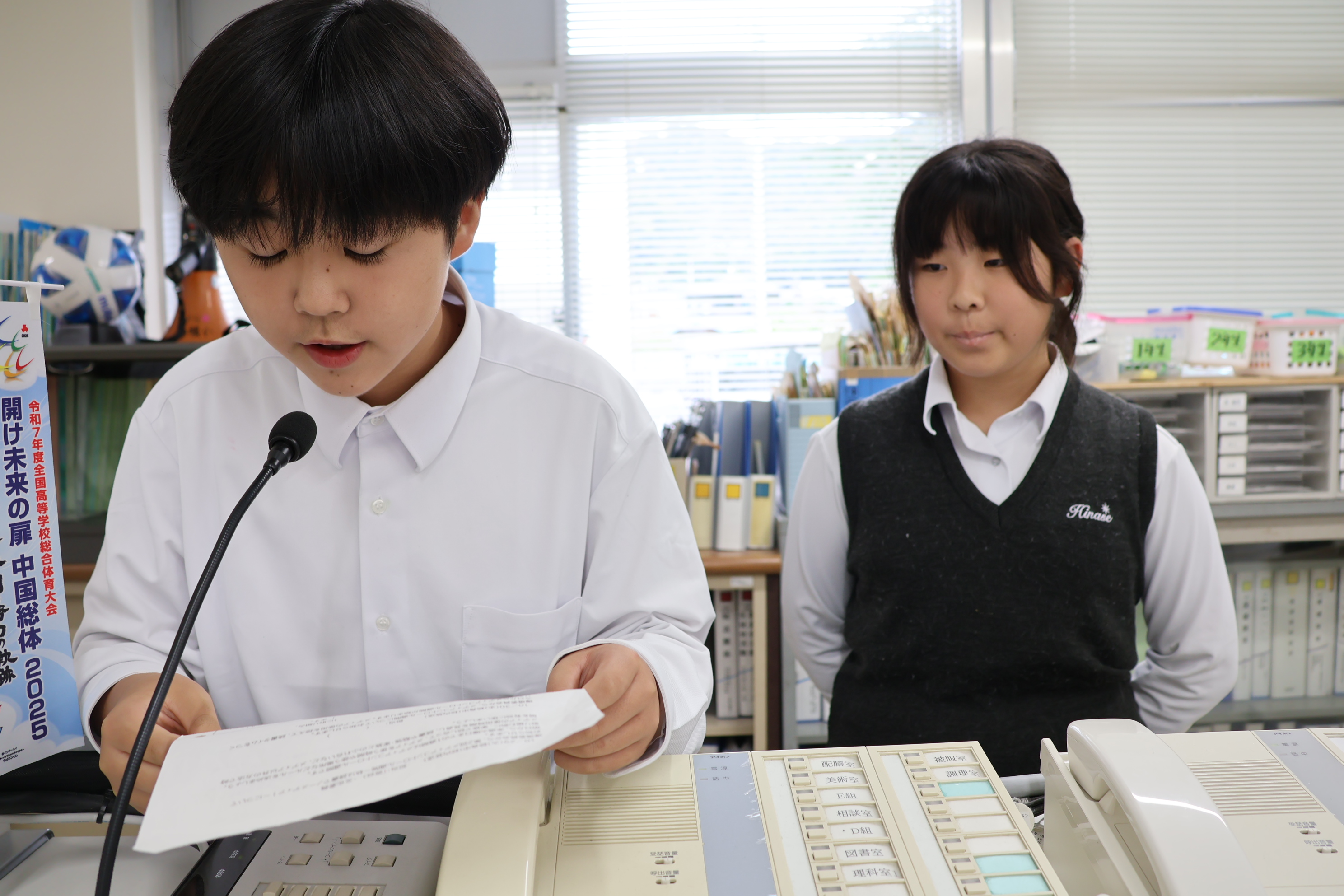
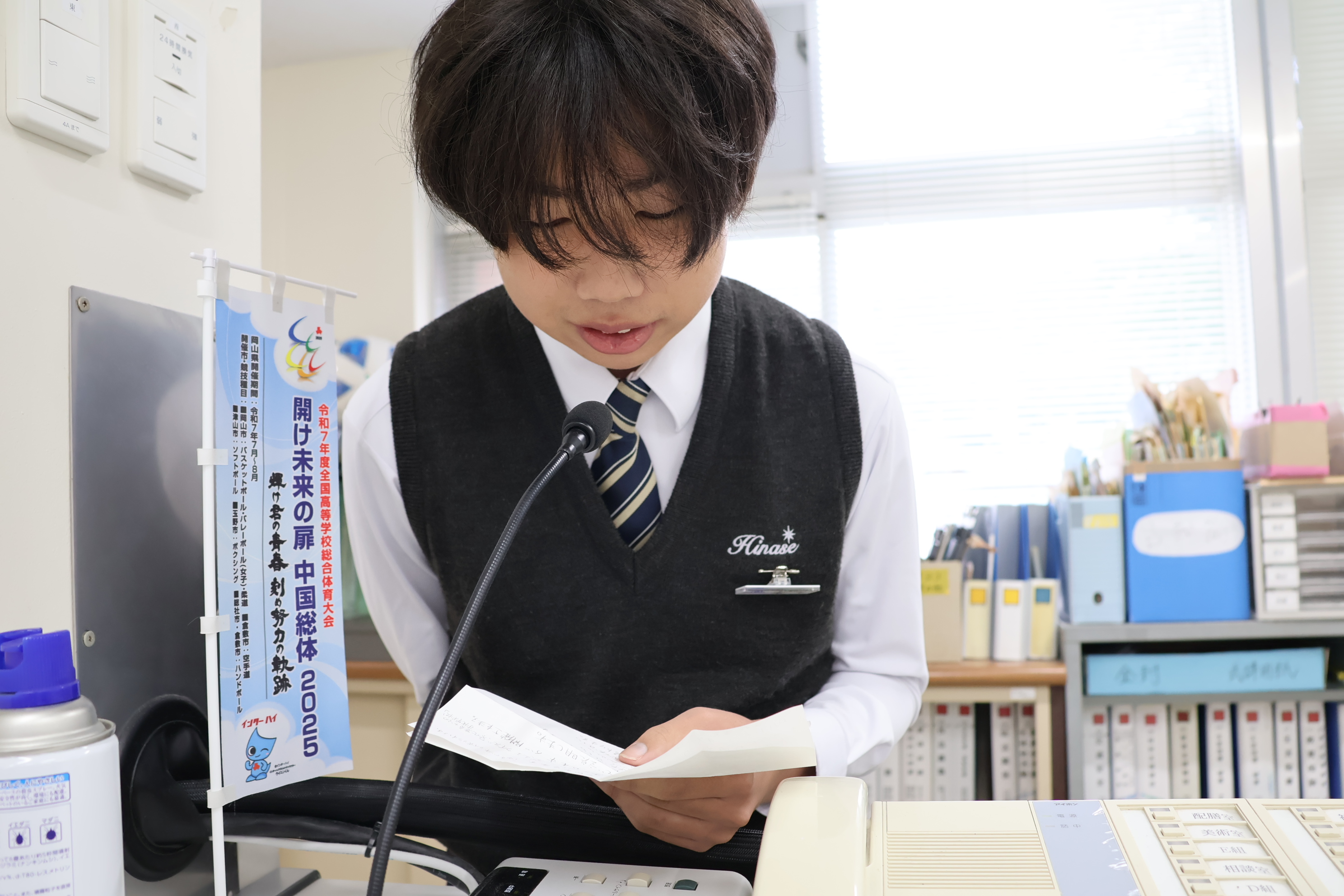
◎We are twice armed if we fight with faith. Platon
(信念を持って戦うのなら、武力は倍増である。)(10/31)
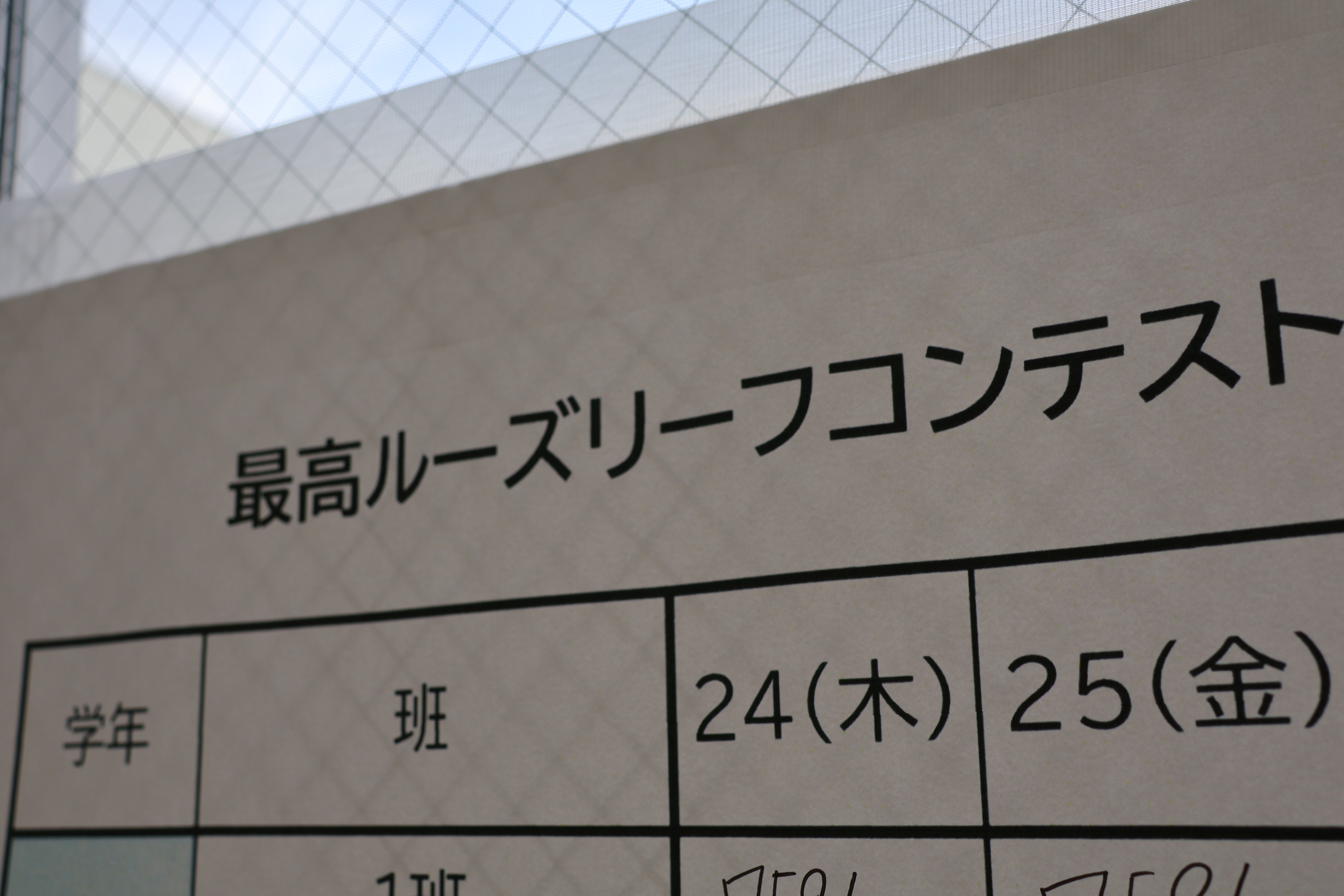

未来を切り拓くちからですね
◎多くの人に支えられて(10/30)
認知症サポーター養成講座(家庭科授業)に3年生が11月19日に取り組みます。今日は事前の準備会でした。

◎多くの人に支えられて(10/30)
長い間、修繕できていなかった体育館トイレの便座を直して頂きました。山下設備さんありがとうございました。大切に使わせていただきます。


◎Happy Halloween! Happy School Days!!(10/31)
味わう秋 仲間と楽しく・豊かに行事から季節を感じよう。


「ハロウィン」とは、毎年10月31日に行われるヨーロッパを発祥とするお祭りのこと。もともとは、秋の収穫を祝い、悪霊を追い出す宗教的な意味合いのある行事でした。
しかし、現在では「ハロウィン」本来の宗教的な意味合いを意識することはほとんどなくなり、日本を含む多くの国々で民間行事として楽しまれています。また、現在は10月31日のみがハロウィンとして定着していますが、正確な期間は10月31日から11月2日。この期間、国によっては死者の魂を慰める行事が行われます。ちなみに「ハロウィン」の語源は「All Hallows Eve」。11月1日のカトリックの聖人の日「All Hallows Day(万聖節)」の前夜に行われるお祭りであることから「All Hallows Eve」と呼ばれ、それを短縮して発音した「Halloween(ハロウィン)」が通称となっています。
「ハロウィン」の発祥の地は、モートン先生が生まれたアイルランドやイギリスといわれています。古代ケルト、古代ローマ、キリスト教の3つの文化が融合して生まれたとされており、原点はケルト民族の宗教儀式の一つ「サウィン祭」だそうです。古代のケルトでは、1年を11月1日から10月31日とし、大みそかの10月31日には死んだ人の魂が家族の元へ帰り、さらに悪霊や魔女が町を訪れると信じられていました。そのため、当時の人々は悪霊たちが悪さをしないようにと、仮装をしたり、魔除けの焚き火を焚き、悪霊を驚かせて追い払うことを思いついたのです。やがて、この風習がキリスト教の文化圏にも広がっていきました。
しかし、現在では宗教的な意味合いを意識する人は少なくなり、子供たちが精霊やお化けに仮装してお菓子を貰ったり、ホラー映画を楽しんだりするイベントとして多くの国で親しまれています。特に、アメリカやカナダではホームパーティーを開催する家庭も多く、「ハロウィン」仕様にお家を可愛く装飾するのも人気の楽しみ方の一つです。

◎味わう秋(10/30)





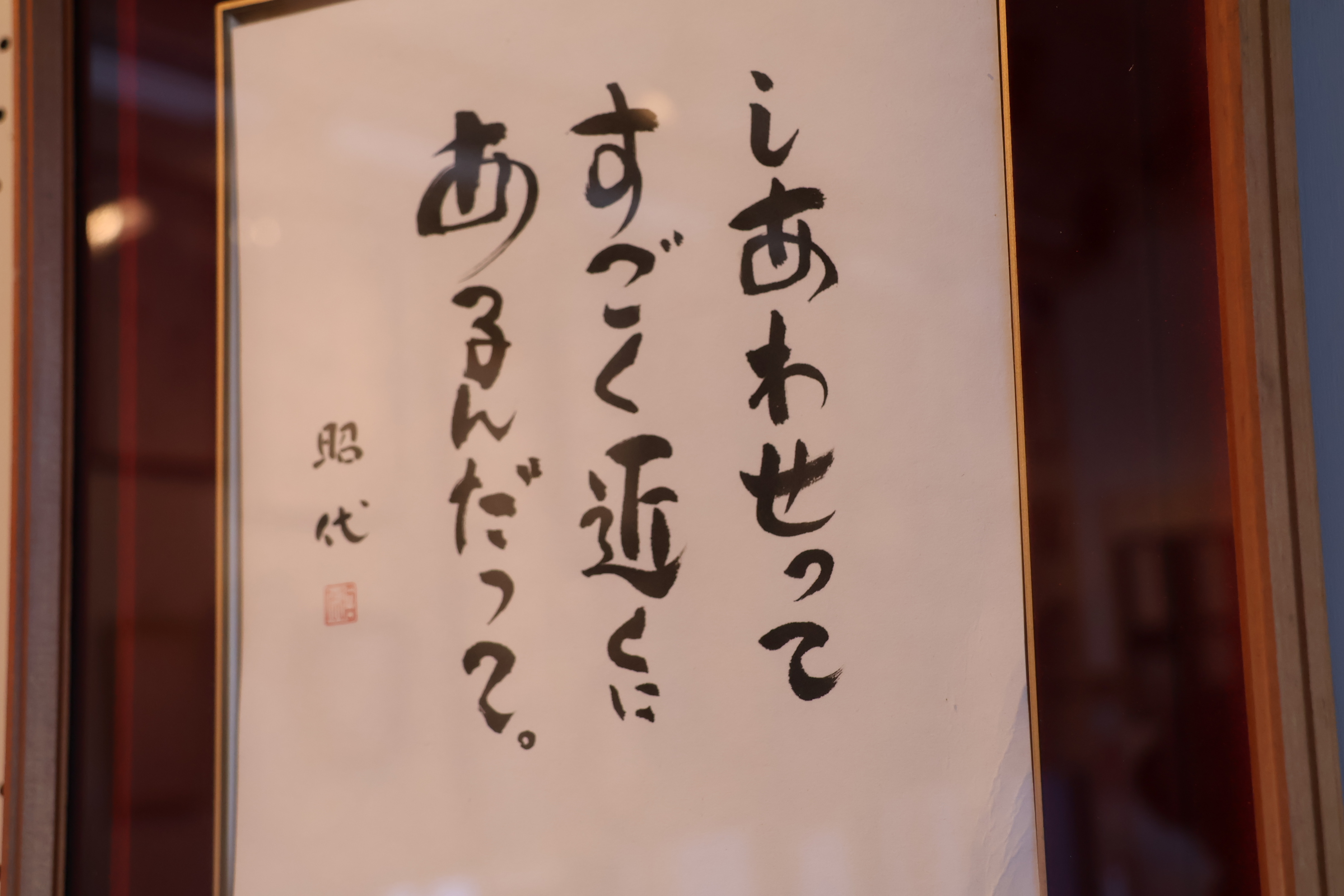

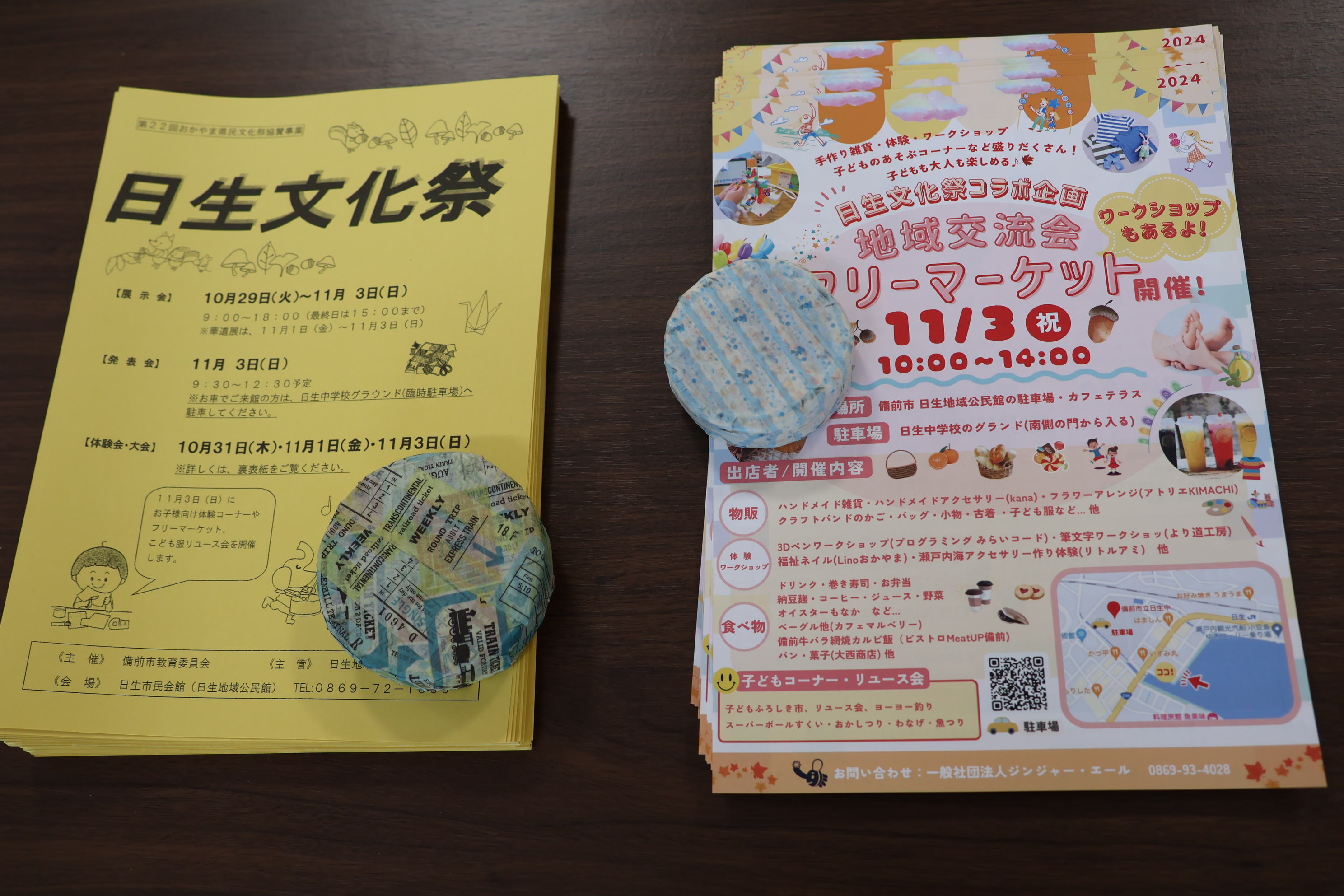

◎さあ!メディアコントロール週間(10/30~)

The best color in the whole world is the one that looks good on you. Coco Chanel
(全世界で最高の色というのは、あなたに似合う色だ。)
◎「学校のリスクを みえる化する」(10/29)
この日、岡山県公立小中学校教頭会研修大会がピュアリティまきびで開催されました。記念講演は、内田良氏が冒頭のテーマで講演され、多くの学びを得ることができました。午後からは6つの分科会に分かれて、それぞれの研究テーマで協議しました。日生中も、「真の「地域・保護者」ともにある学校づくりをこれからも進めていきます。いきます。

◎実りの秋へ(10/29)
備前市弁論大会が、吉永中学校で開催されました。本校代表の三宅さん、山﨑さんも堂々とした態度で発表を行いました。

◎「クラスでくらす」ためのワークショップ1(10/28)
1年生は、人権学習とひとつとして、カレーライスワークショップを通して多様性を、そしてすBBCニュースから、思考の柔軟性について、深く・豊かに、そして楽しく学びました。次時の学習は、「わたし・あなた・そして仲間」ワークショップを行い、11月1日(金)は、自分の特性・クセ・タイプを深く知り、それと付き合うためのアドバイスを、AT(エリアティチャー)さをお招きして学びます。
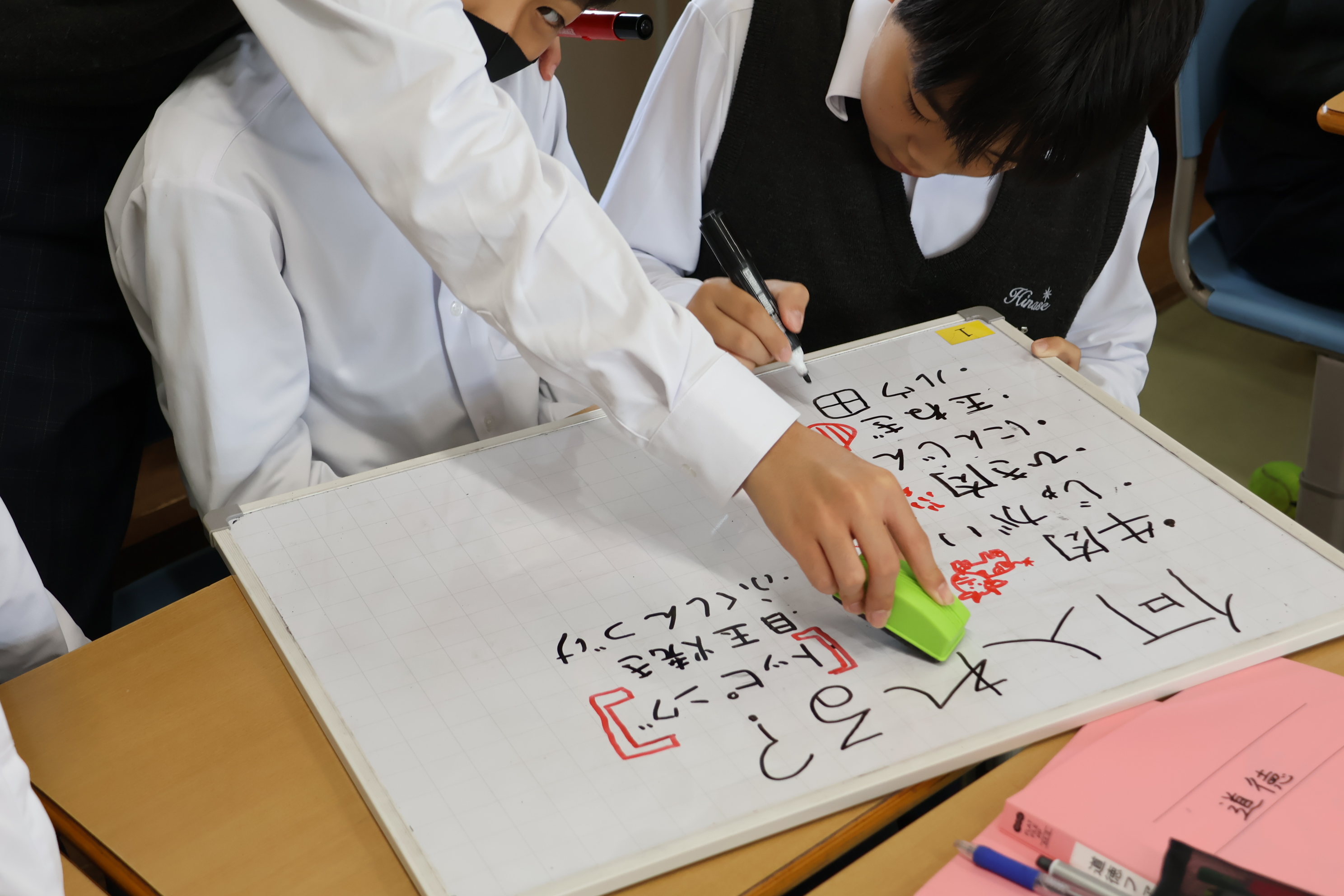

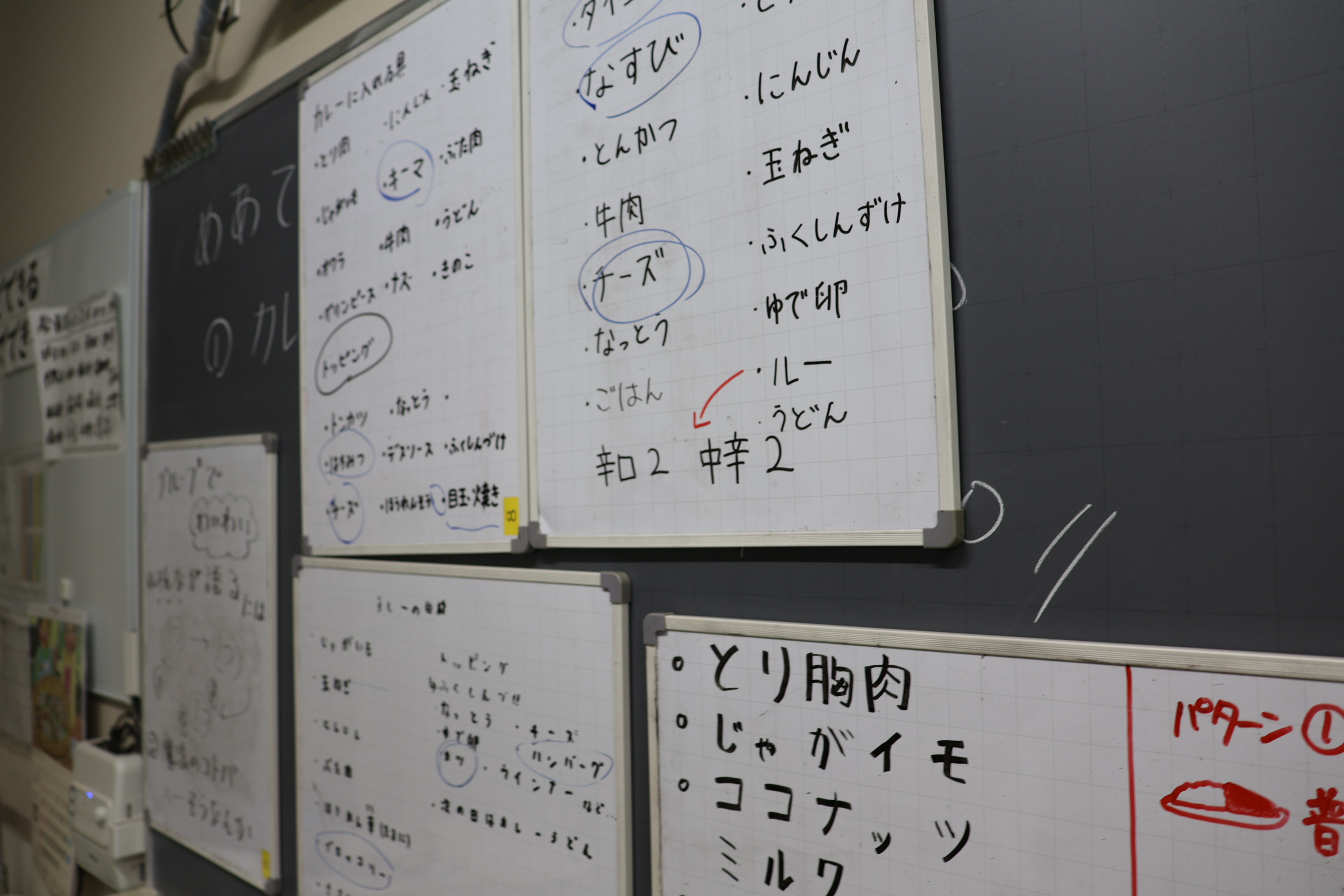
◎「ホームレス問題」から、見えること・考えること(10/28)
今年度も、2年生は、人権学習のひとつとして、また、職場体験学習の一環として、「ホームレス問題」学習に取り組んでいます。勤労観・職業観・社会のありよう・福祉など、多面的な視座で学んでいます。11月1日は、岡山でホームレス問題に取り組んでいるNPOきずなさんからAT(エリアティチャー)さんをお招きして、さらに学習を深めます。

大阪の「子ども夜回り」の映像を視聴しています。
◎知らなくちゃ。
~私たちの今・未来につながるのだから(10/29)
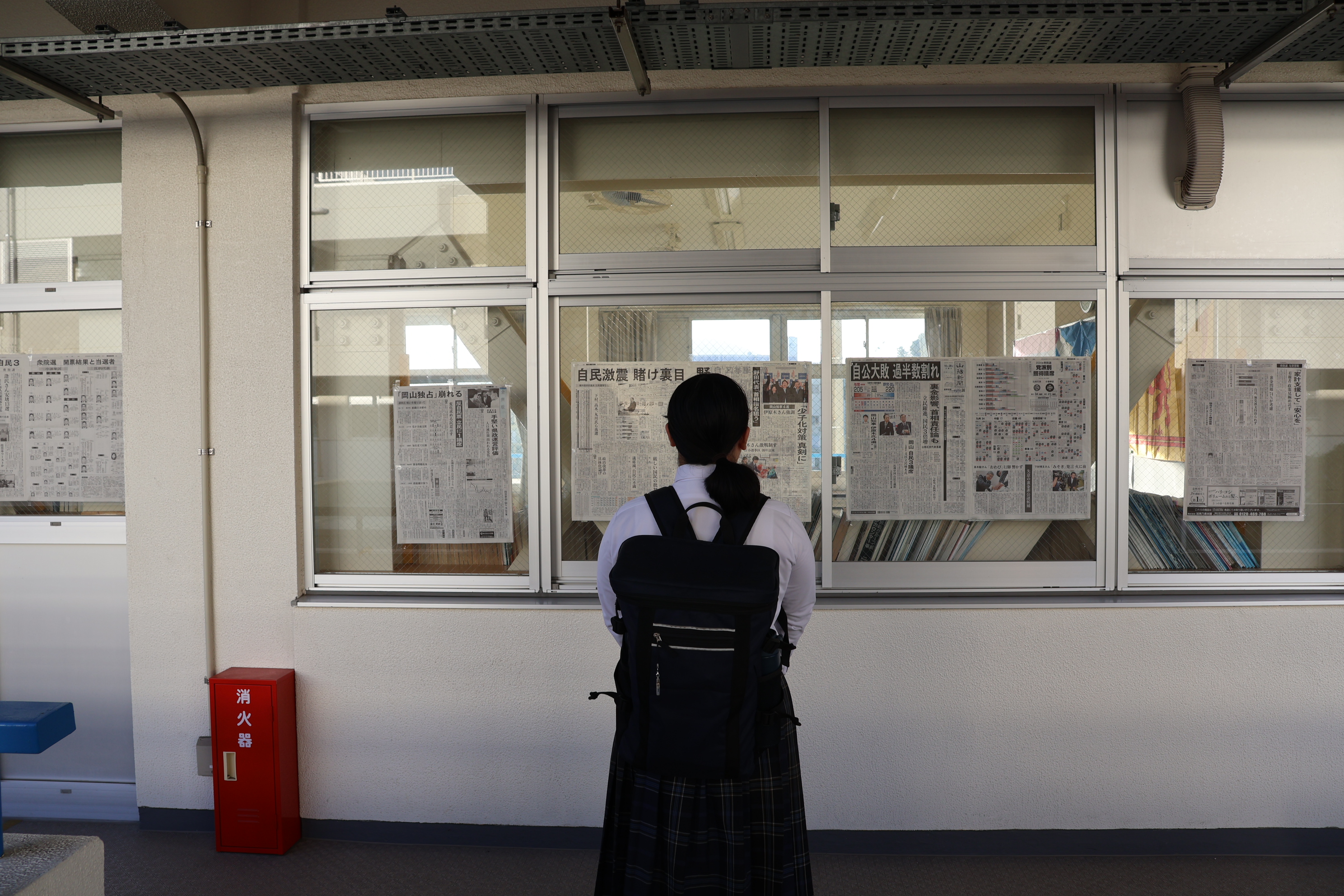
◎私たちのはじまりの風景の中に(10/26.27:寒河秋祭りにて)
ボランティア推進プロジェクトに参加した生徒が、お祭りのお手伝いをさせていただきました。ありがとうございました。



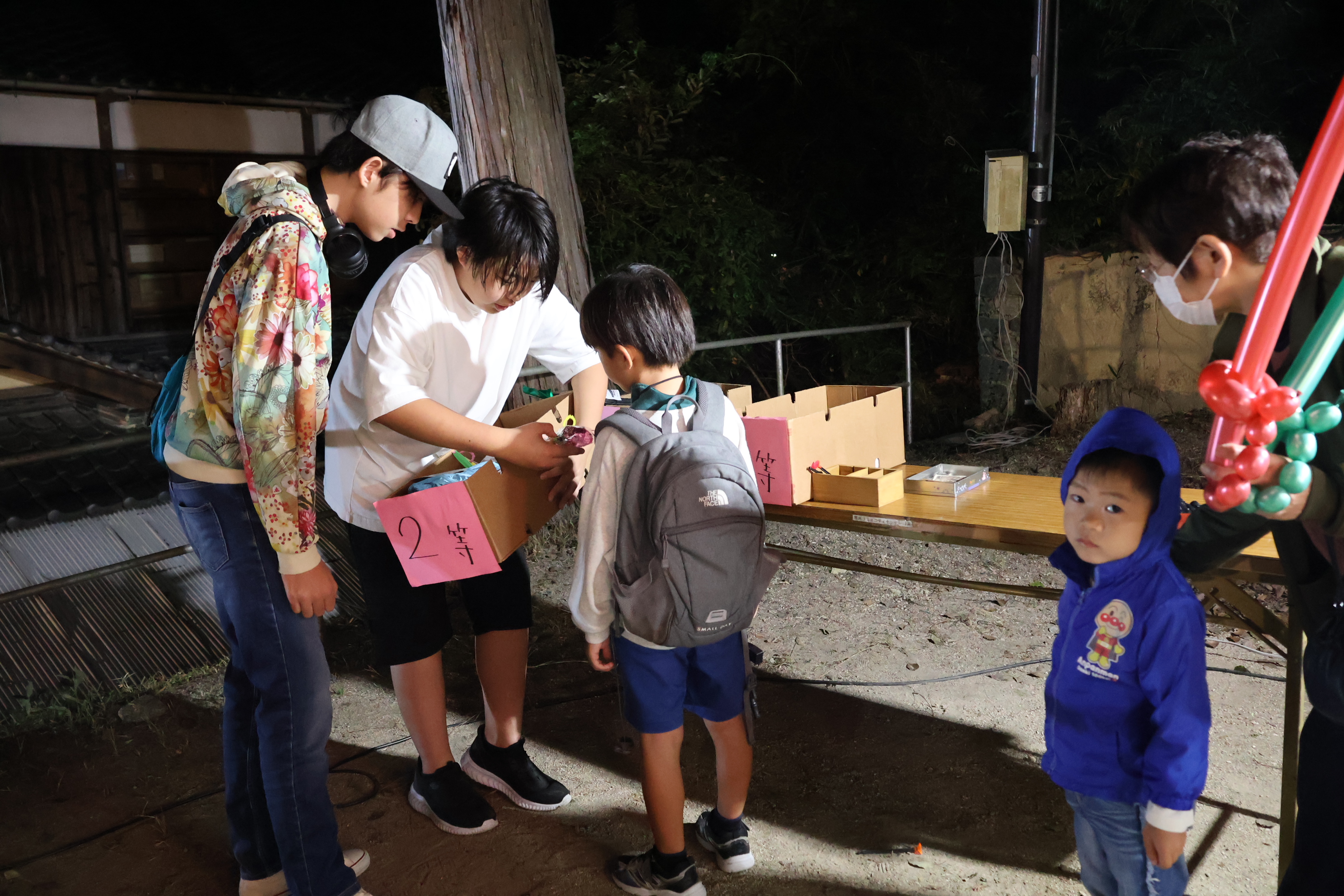


〈なんでもない会話なんでもない笑顔なんでもないからふるさとが好き 俵 万智〉
◎ヒナセを創る生徒総会(10/25)

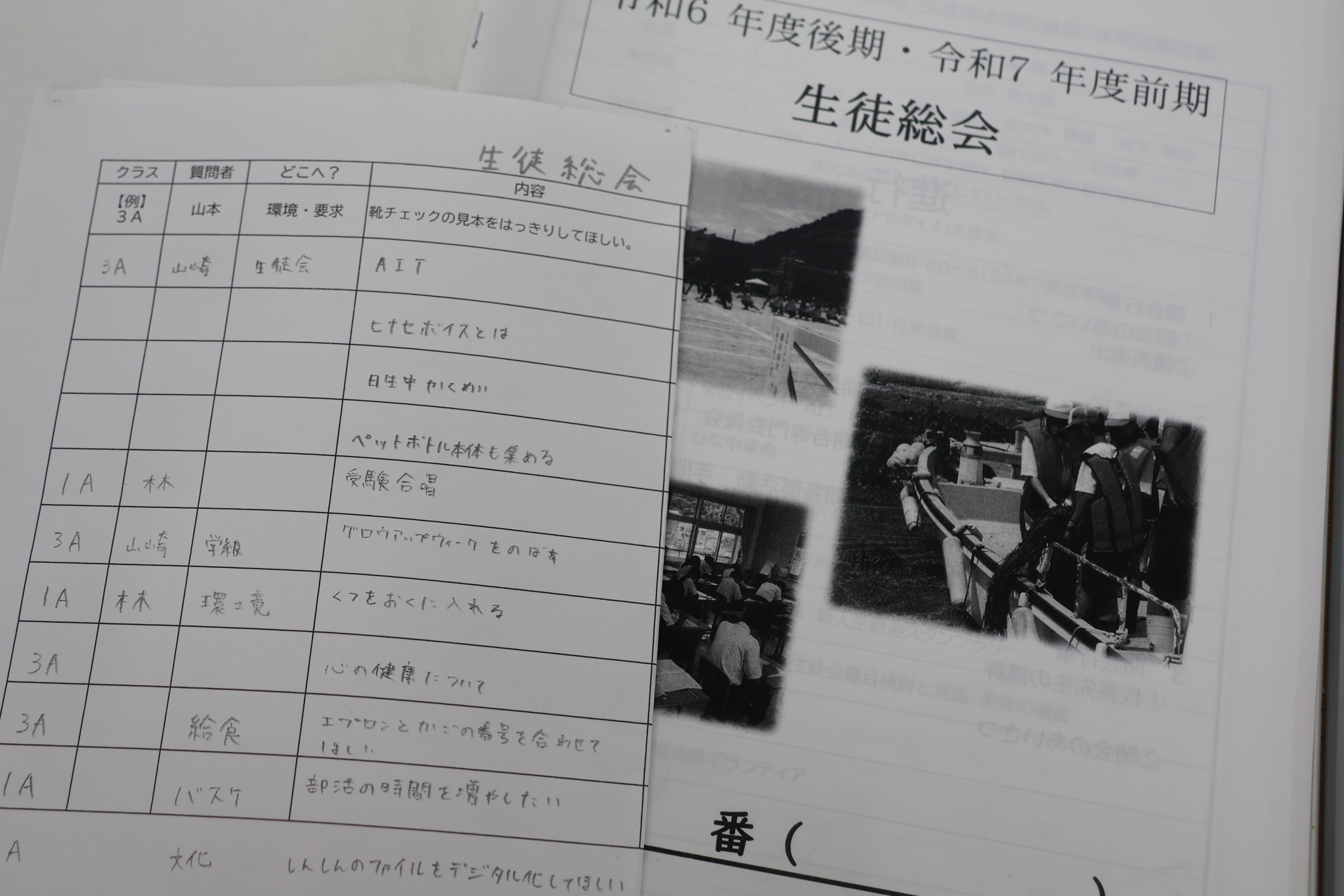

Fight and push harder for what you believe in‚ you’d be surprised‚ you are much stronger than you think. Lady GaGa
(自分が信じていることのために、もっと戦い、押し進めよう。驚くほど、自分が思っているよりもずっと強いことに気がつくから)
◎ひな中 チャレンジ企画!
モートン先生よろしくお願いします。(10/25)
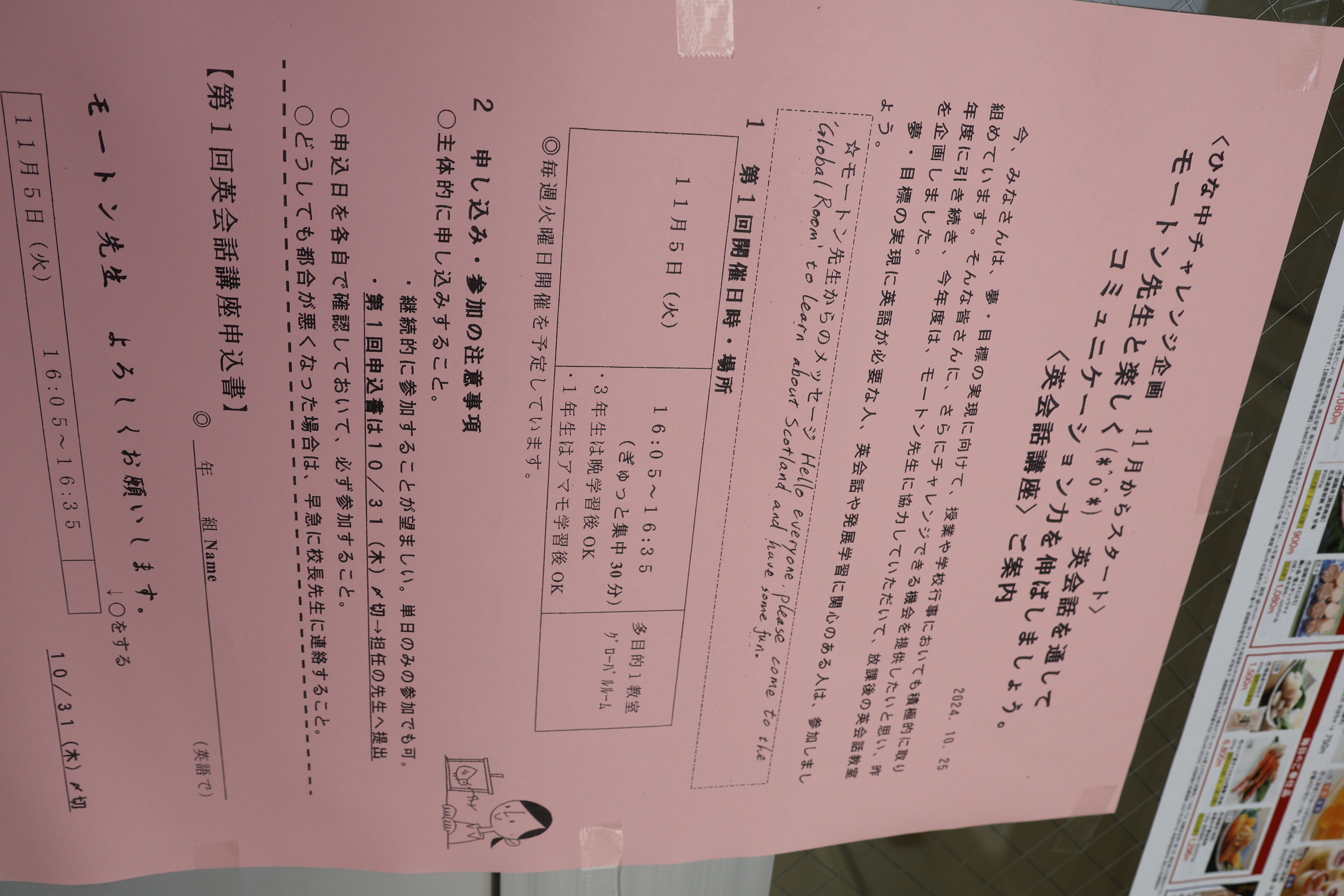
◎備前市消防団日生方面隊消防操法大会
〈10.26 17時~21時まで〉

◎一生懸命に「わたし」(10/24)
~よろしくお願いします。事業所訪問
実際の職場での体験活動を通して、望ましい職業観や勤労観の育成を図ることと、事業所で働く人々とのふれあいを通して、社会人としての礼儀や教養を身につけることを目的に今年度も2学年 職場体験学習(チャレンジ・ワーク14)に向けて準備を進めています。今日は、お世話になる事業所へ事前訪問に行かせて頂きます。どうぞよろしくお願いします。

中元写真館 日生図書館 カメイベーカリー 日生町漁協・五味の市・しおじ 奥本生花店 café RAD マクドナルド赤穂フレスポ店 (有)磯 ステラカフェ カフェ天goo 一般社団法人ジンジャー・エール レストラン夕立 THE COVE CAFE すき家250号赤穂駅前店 日生認定こども園 日生西小学校 日生東小学校 伊里認定こども園 セブンイレブン岡山備前インター店 山陽マルナカ穂浪店 ホームプラザナフコ備前店 旬鮮食彩館パオーネ日生店 ホームセンタータイム備前店 ダイレックス赤穂店(順不動・敬称略)
◎わたし あなた そしてなかま
~たしかな人権学習の中で(10/24)



〈クラスでくらす〉1年生が、自分自身を見つめ(自分の特性・クセ・タイプ)し、クラスの仲間としてさらに深く知り」学習に取り組んでいます。この日は、東田直樹さんのDVDを視聴しながら、自分の思い込みや偏見について振り返ったり、自分が「他者に理解されているのか」についても考えたりしました。次の学習では、クラスの仲間を解り合うワークショップを行います。11月1日(金)はエリアティチャーさんをお招きしてさらに学びを高めます。
〈流れつつ藁も芥も永遠に向ふがごとく水の面にあり 宮柊二〉
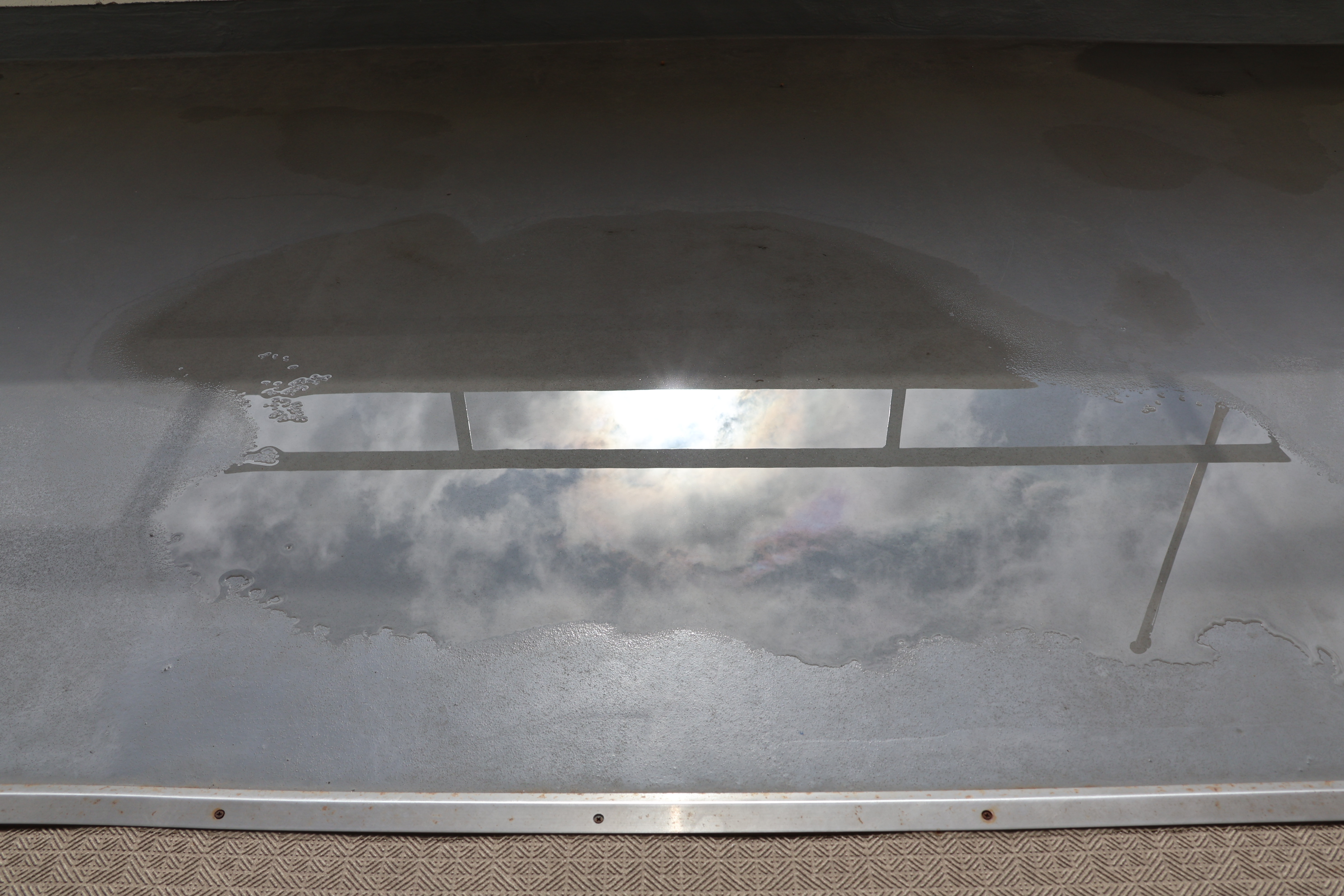

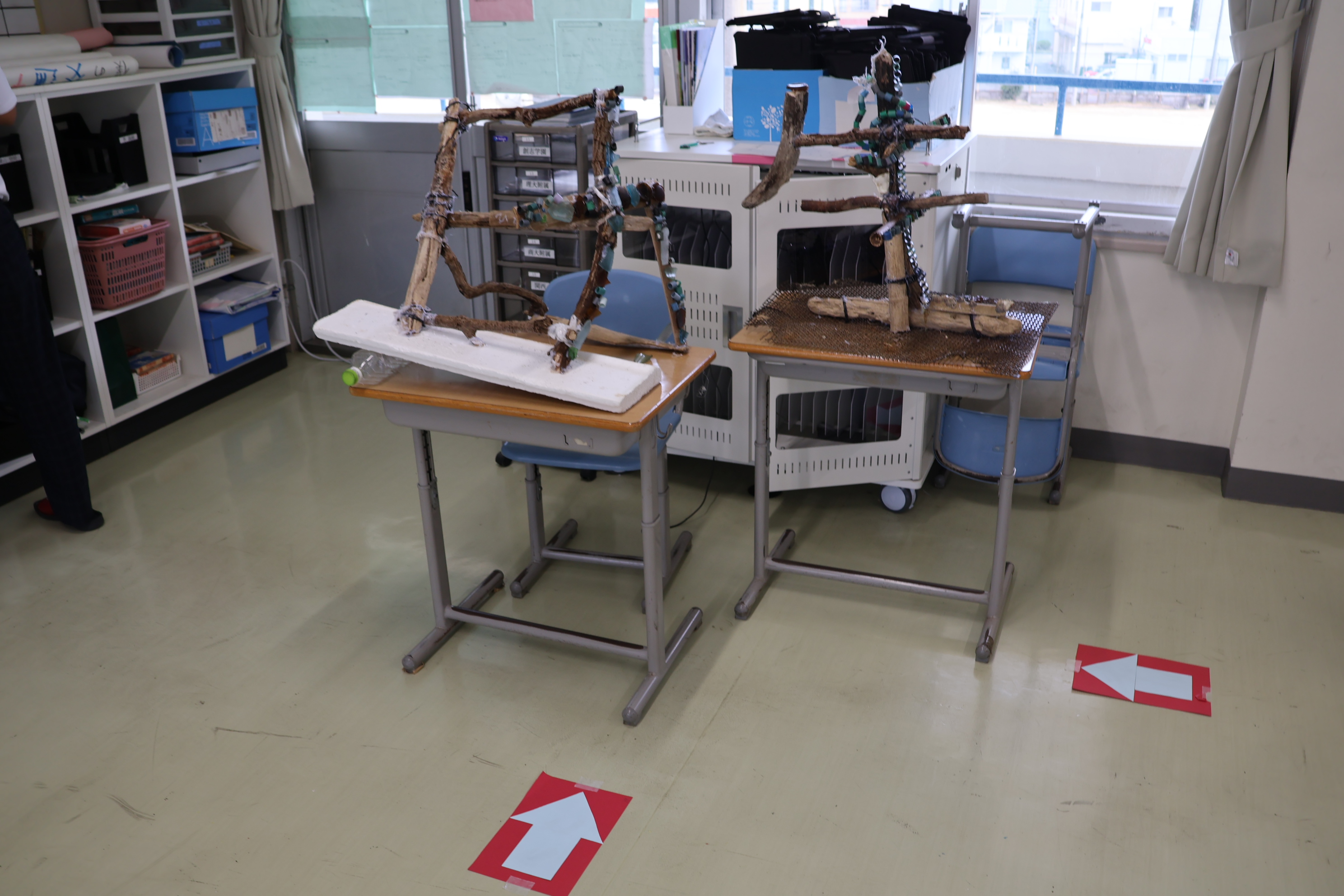
◎最高ルーズリーフは、最高の道を拓く(10/24)
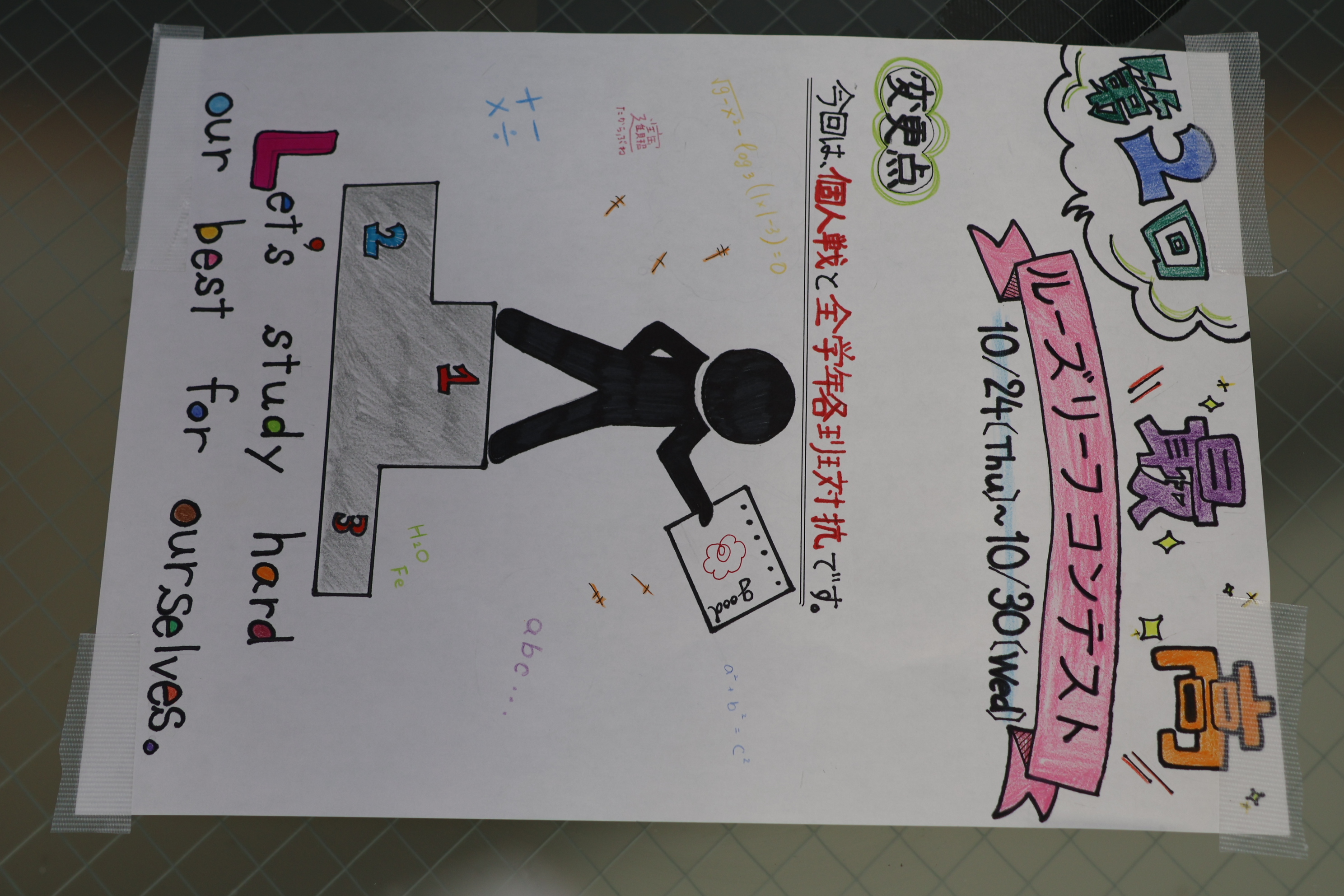
◎導きたまへ
~公開授業および第11回校内研究会(10/23)


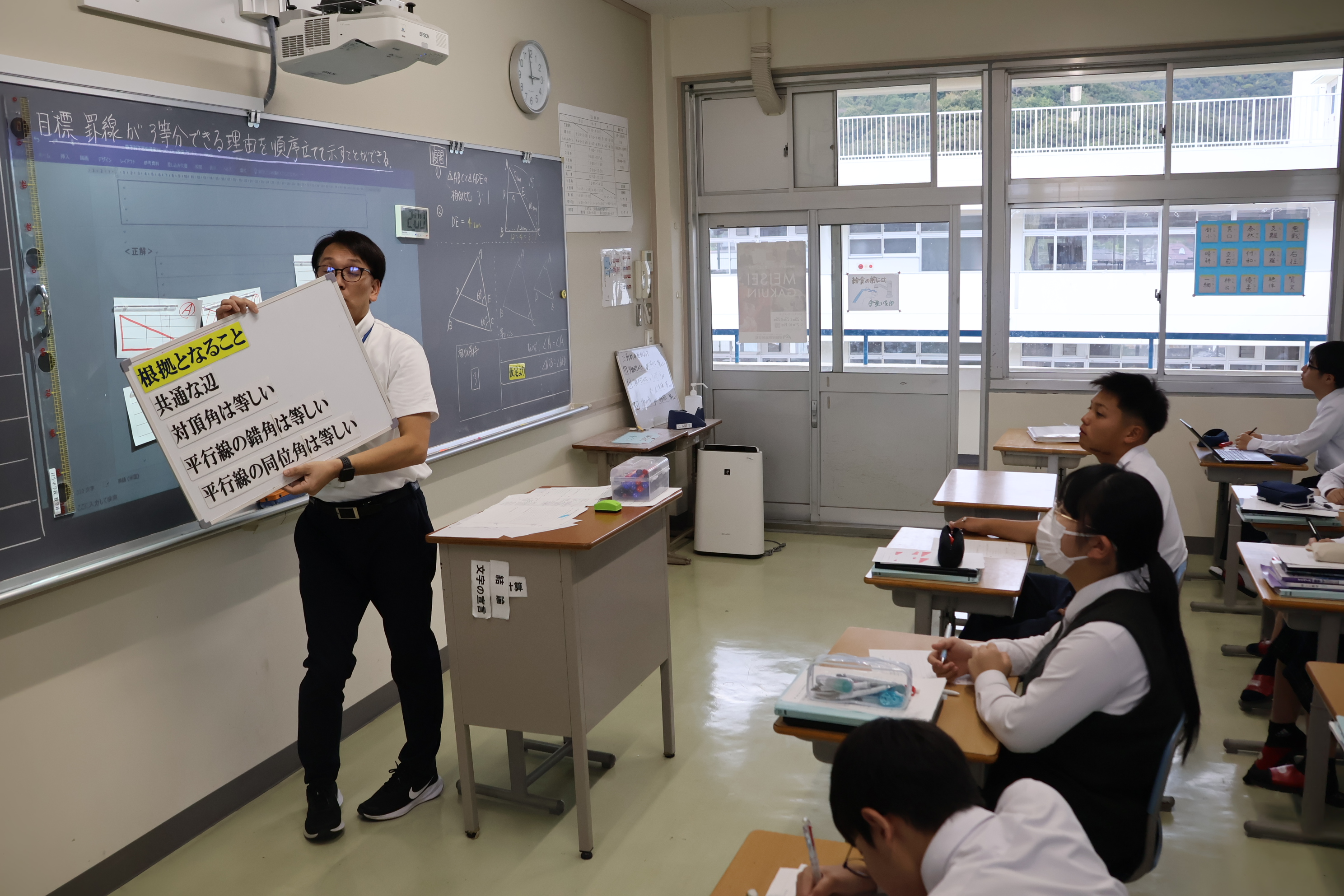
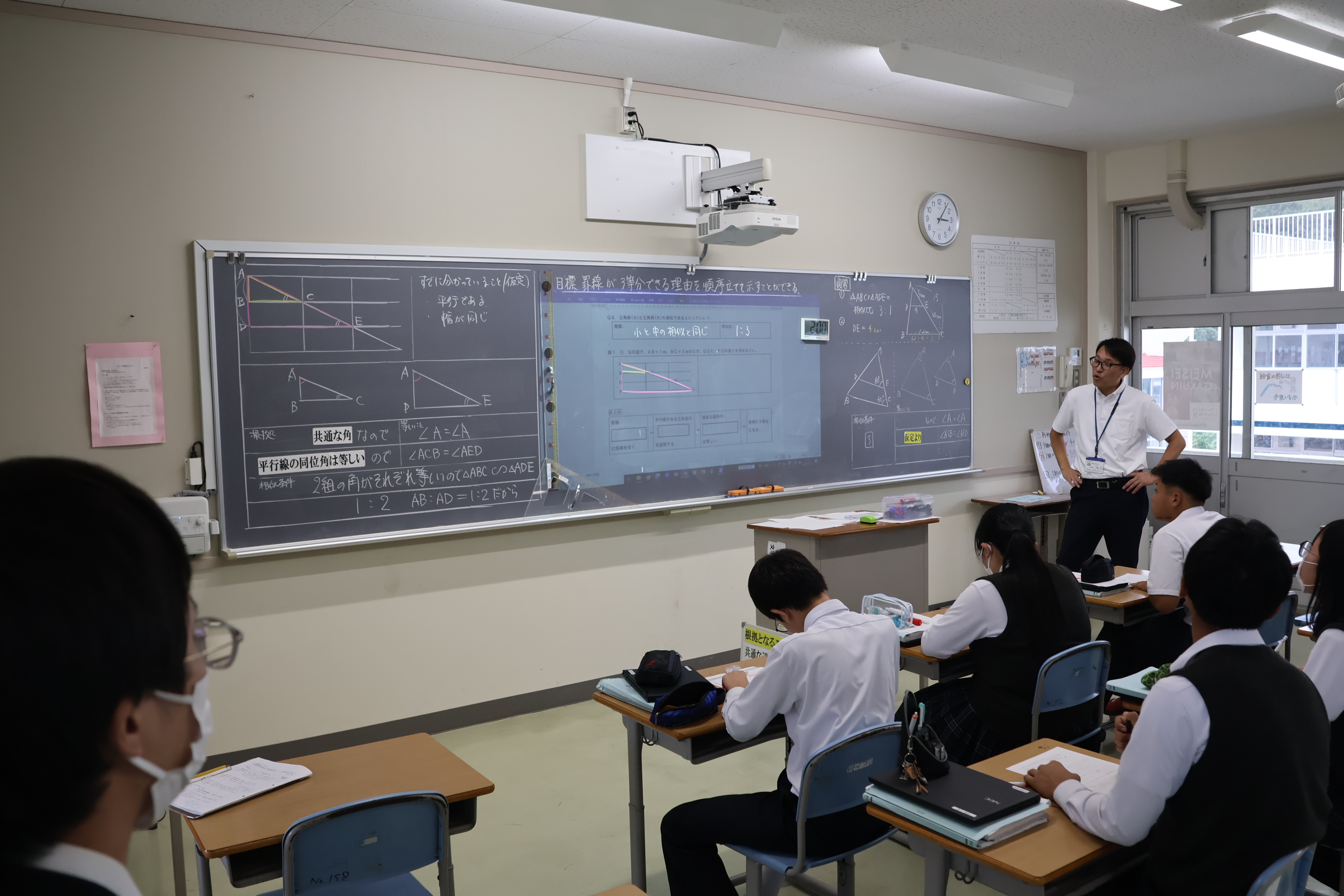
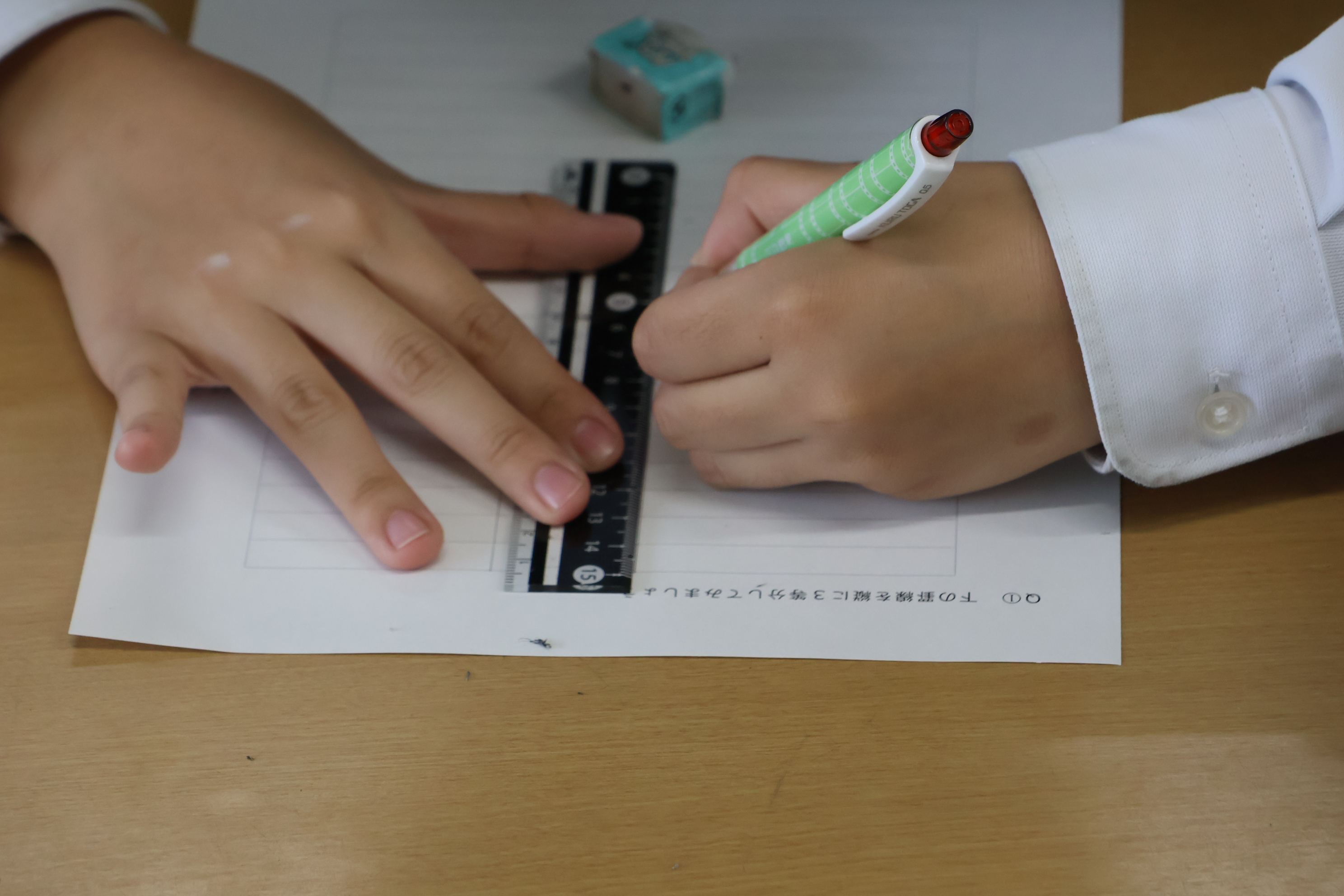
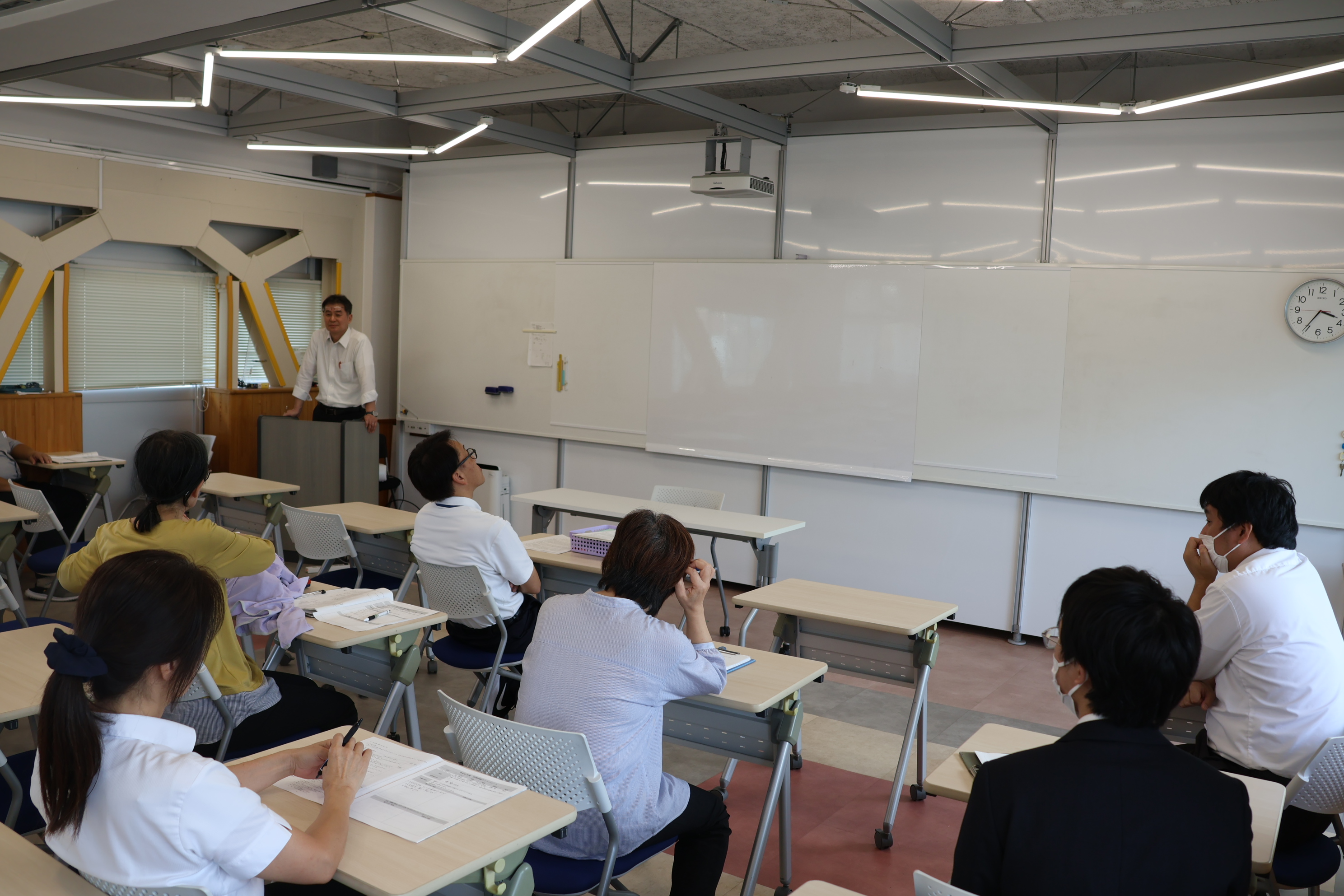
◎出会いに心をこめて。ありがとうございました。
皆様のさらなるご活躍をお祈りいたします。(10/23)

◎出会いに心をこめて(10/23)
2年生はチャレンジワークを前に、今年度も楠本さんをお招きして、社会人マナー講座に取り組みました。元気をいただきました。ありがとうございました。
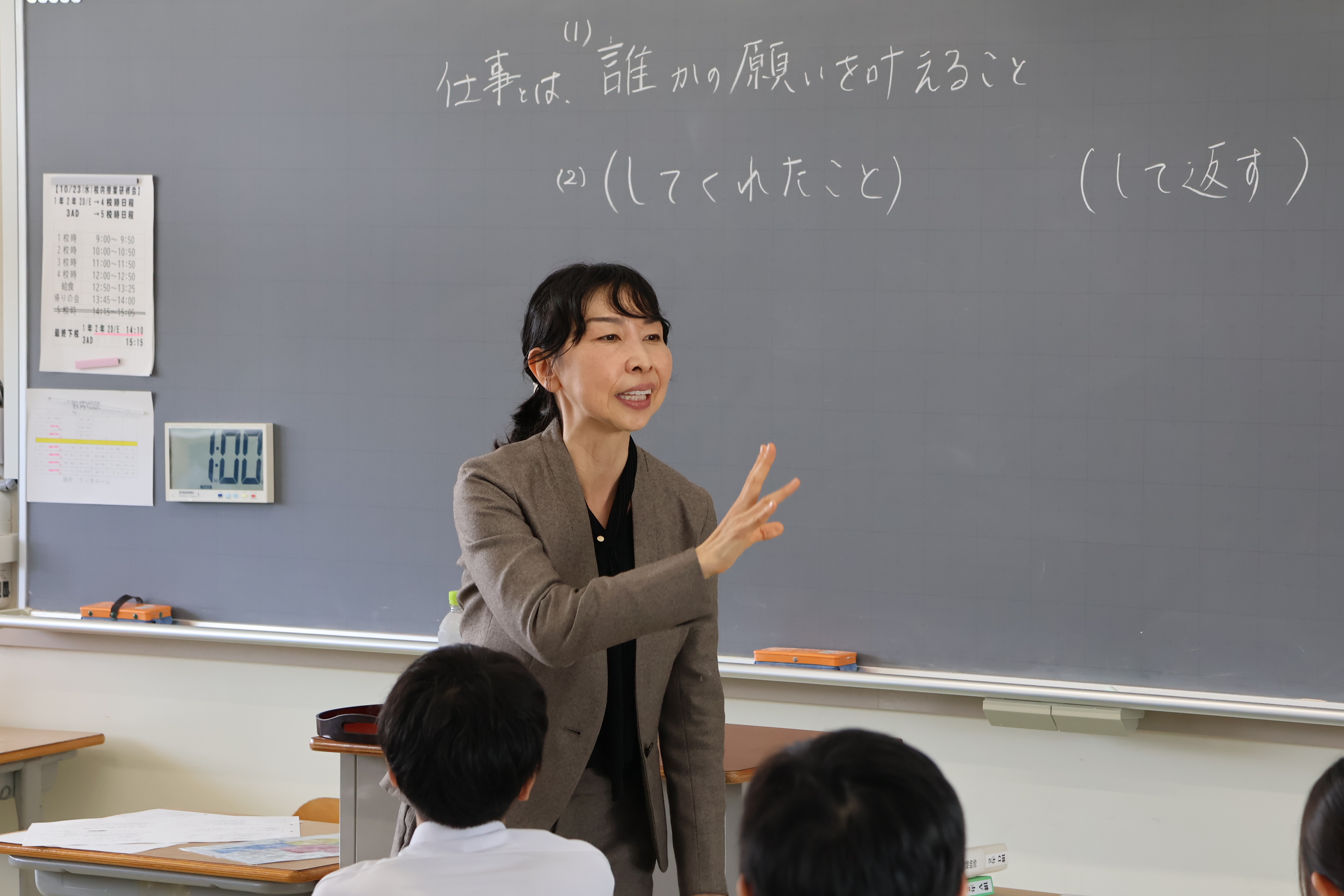








◎〈わたしの道を歩くひと〉から学ぶ(10/23)
大相撲鳴戸部屋から、峰洲山さん、山根さん、江元さん、式守さん、床欧さんをお招きして、進路(生き方)学習に取り組みました。















To travel hopefully is a better thing than to arrive‚ and the true success is to labour. Robert Louis Stevenson
(希望を抱いて旅をすることの方が、到着することよりもよいことだ。真の成功とは目的に向かって努力することである。)
◎ひな中の風(10/22)



◎ひな中の風

よく言われる天気についてのことわざに「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」というものがあります。これは観天望気(かんてんぼうき)のひとつで天気がどう変わっていくかを直感的に理解する指針になります。
日本上空では、西から東へ流れる偏西風が吹いています。高気圧や低気圧は西から東に運ばれ、それに伴って天気が変わりやすくなります。したがって、このことわざがあてはまりやすいのは低気圧と高気圧が交互にやってくる春と秋です。
朝焼けが見える時、日が昇る方角の東の空は晴れて、あまり雲がない状態です。晴れをもたらす高気圧が東へ離れてしまい、その代わりに低気圧が近づいて、西から天気が崩れやすい条件が整っていると言えます。一方で、夕焼けが見える時は、日が沈む西の空が晴れていて、高気圧が西から近づいており、すっきりと晴れる可能性が高いと言えます。
このように、日本の気候と天気の変化についての昔ながらの知恵が詰まったことわざを知ることで、毎日の天気予報をさらに楽しむことができるかもしれませんね。
◎ひな中のかぜ
体育で柔道の授業がスタートしました。〈自分に正しく 相手を思いやる 柔の道〉(10/21)



◎日生の秋🍁
この26、27日は寒河秋祭りの日です。ボランティア推進プロジェクトで参加する生徒たちも、天gooさんのお手伝いを頑張ります。(また、26日の晩は、日生中地域盛りあげ隊が、ピカピカお楽しみくじ引きを用意しています。小さなお友達みんな来てね~。)


◎アリガトウ・サヨウナラ 公衆電話(10/21)

今後必要な時は、職員室で申し出て、電話機を借りましょう。
◎上手くなるためには理由がある(10/19・10:23)









◎日生 地域のちから(10/19)
日生中グラウンドで、消防操法訓練をされています。

◎ひな中の風 金木犀(キンモクセイ)
登下校時に甘く芳しい香りがしませんか。小さな花から漂うキンモクセイの香りは、なんだか懐かしい気持ちにさせてくれますよね。また、オレンジ色の花びらと濃い緑色の葉っぱのコントラストは鮮やかで印象によく残ります。ちなみに金木犀の花言葉をいくつか紹介します。
『謙虚・謙遜』・・・強い香りが印象的な一面とは裏腹に、咲かせる花は直径1cmにも満たないと小さくつつましい様子にちなんでつけられました。
『気高い人』・・・季節の変わり目に降る秋雨の中で、潔くすべての花を散らせることが「気高い人」という花言葉の由来となっています。また中国では位の高い女性の香料などに加工されたキンモクセイが使われていたなど、この花言葉の由来となっているとも言われています。
『真実』・・・キンモクセイのその香りの強さから、開花時を隠すことやごまかすことができず周囲の人が知る。そのような嘘のつけない香りが「真実」の由来になっているようです。
『陶酔』・・・陶酔という花言葉は、その強い香りに由来します。原産国の中国で、香りを活かしてお茶やお酒、お香などに利用されていたこともあり、「陶酔(気持のよいほろ酔い気分にさせてくれる)の香り」にちなんでつけられました。キンモクセイの香りは、3~7日間ほどの短い開花期間のみ感じることができるので、後に目が覚める陶酔という言葉はぴったりですね。
『初恋』・・・「初恋」もキンモクセイ特有の甘い香りが由来です。人生で誰もが経験し忘れられない「初恋」、そしてキンモクセイの香りも一度かいでしまったら忘れられません。その一生に一度の忘れることのできない経験がこの花言葉に結びついているのでしょう。
金木犀は、モクセイ科・モクセイ属の常緑性の小高木樹です。中国南部が原産で、江戸時代に日本に伝わってきました。もともとはギンモクセイの変種です。本来は雌雄異株ですが、輸入された際に雄株しか入ってこなかったことから、日本にあるキンモクセイには実(種)がつきません。大きい樹木で10mほどまで育ち、日本では観賞用として公園や庭先でよく栽培されています。原産地の中国では、丹桂(たんけい)や桂花(けいか)という別名で知られており、観賞用以外にお茶やお酒(白ワイン)、お菓子、漢方薬など花びらを食用や薬用に扱える植物としても親しまれています。
名前の由来・・・学名の Osmanthus は、ギリシャ語のosme(香り)とanthos(花)に由来しています。また、fragransは「芳しい香り」、aurantiacusは「橙色の」という意味があり、学名全体を通してキンモクセイの花の様子が伝わってきます。
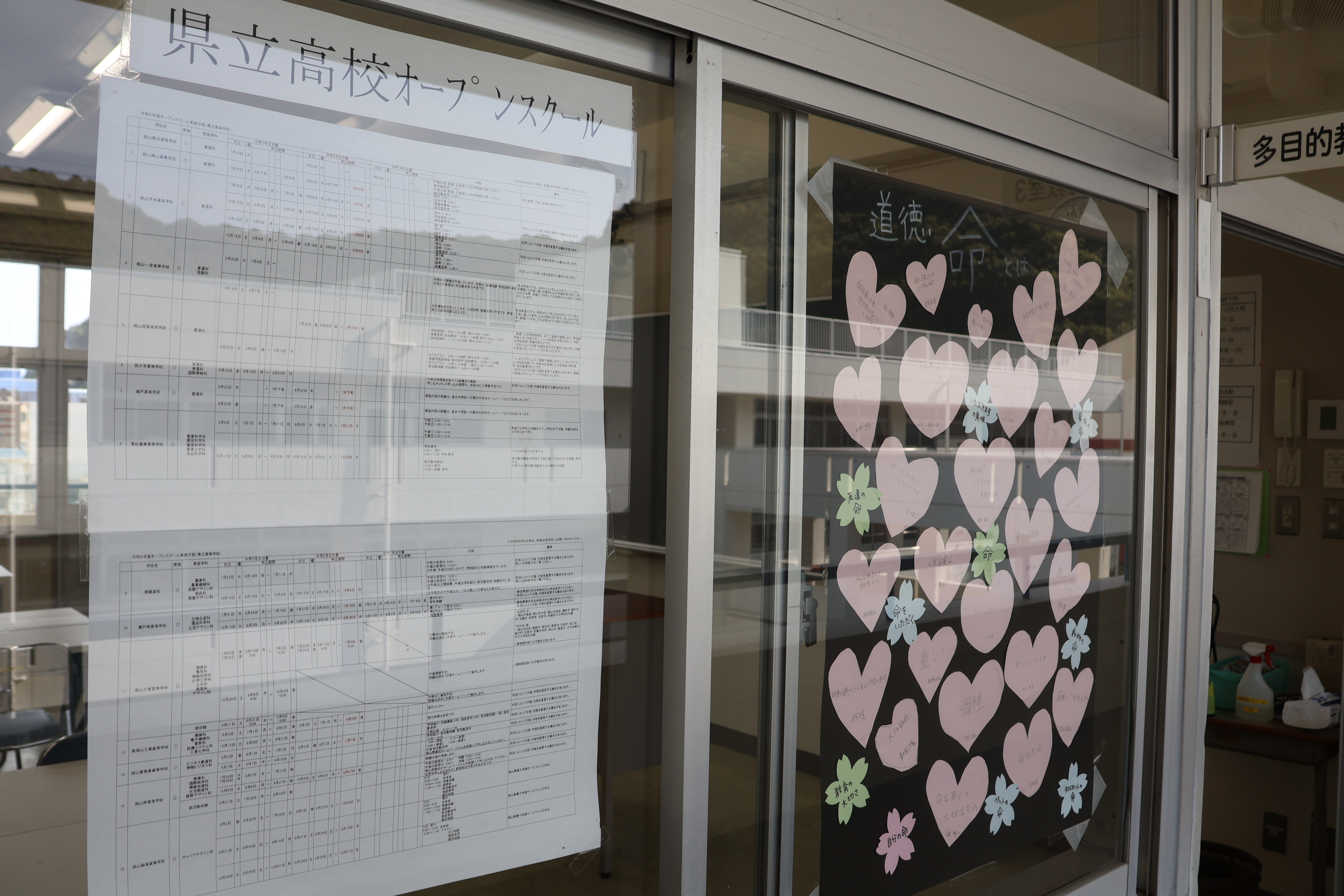
◎ひな中の風
イツモドウリノコトデスガ 👍(10/18)

◎私のまちだから 私の仲間だから(10/17:赤い羽根共同募金 街頭活動2日目)









◎開かれた学校として
~備前市教育研修所数学部会研修会で磨く(10/16)
備前市内の数学の先生方が来校され、春名先生の公開授業をもとに、学習指導についての技術を磨きました。一生懸命にしっかりと考えることができた2年生でした。





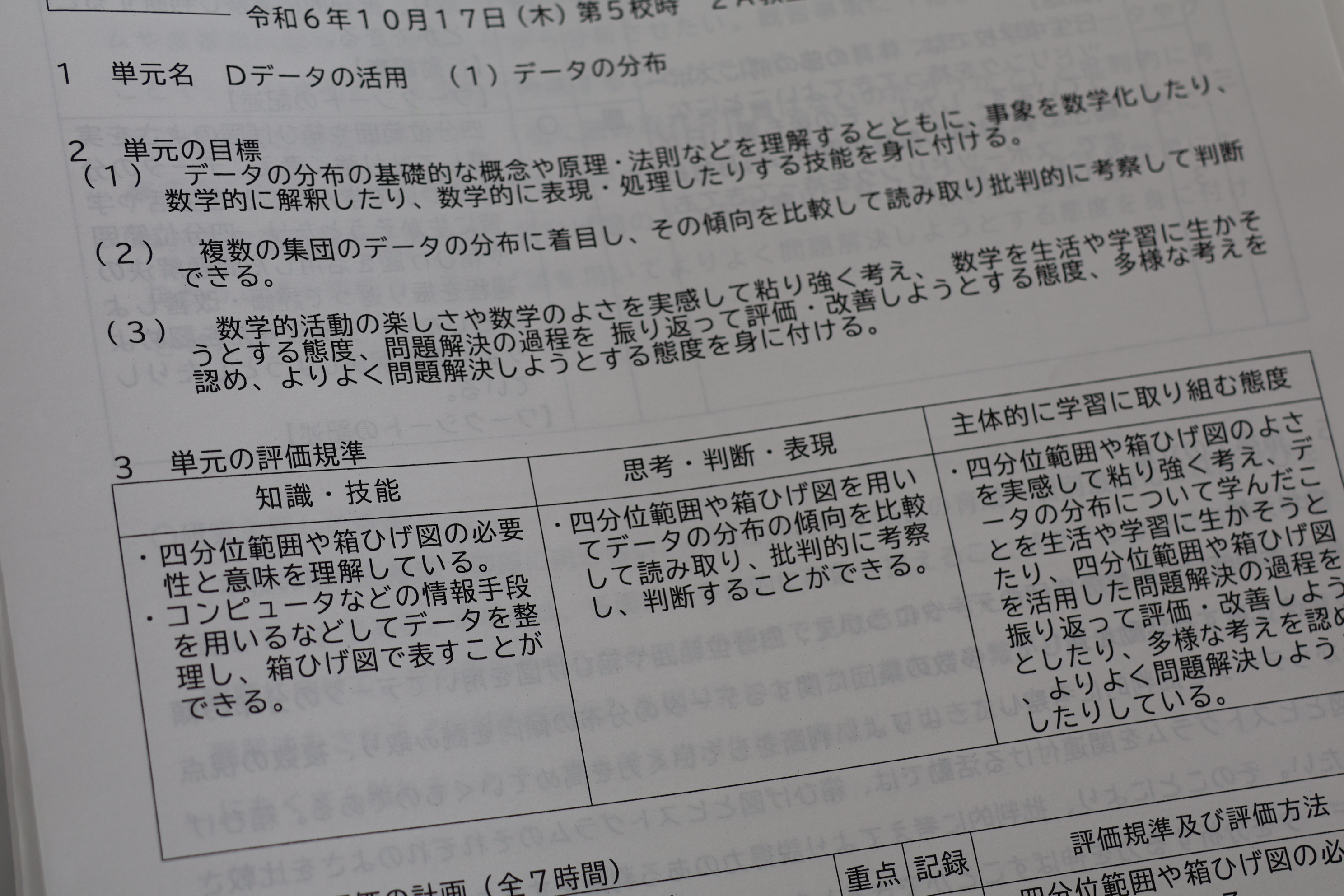
◎仲間と共に 道を切り拓く
~三年生到達度確認テスト(10/17)乗り越える
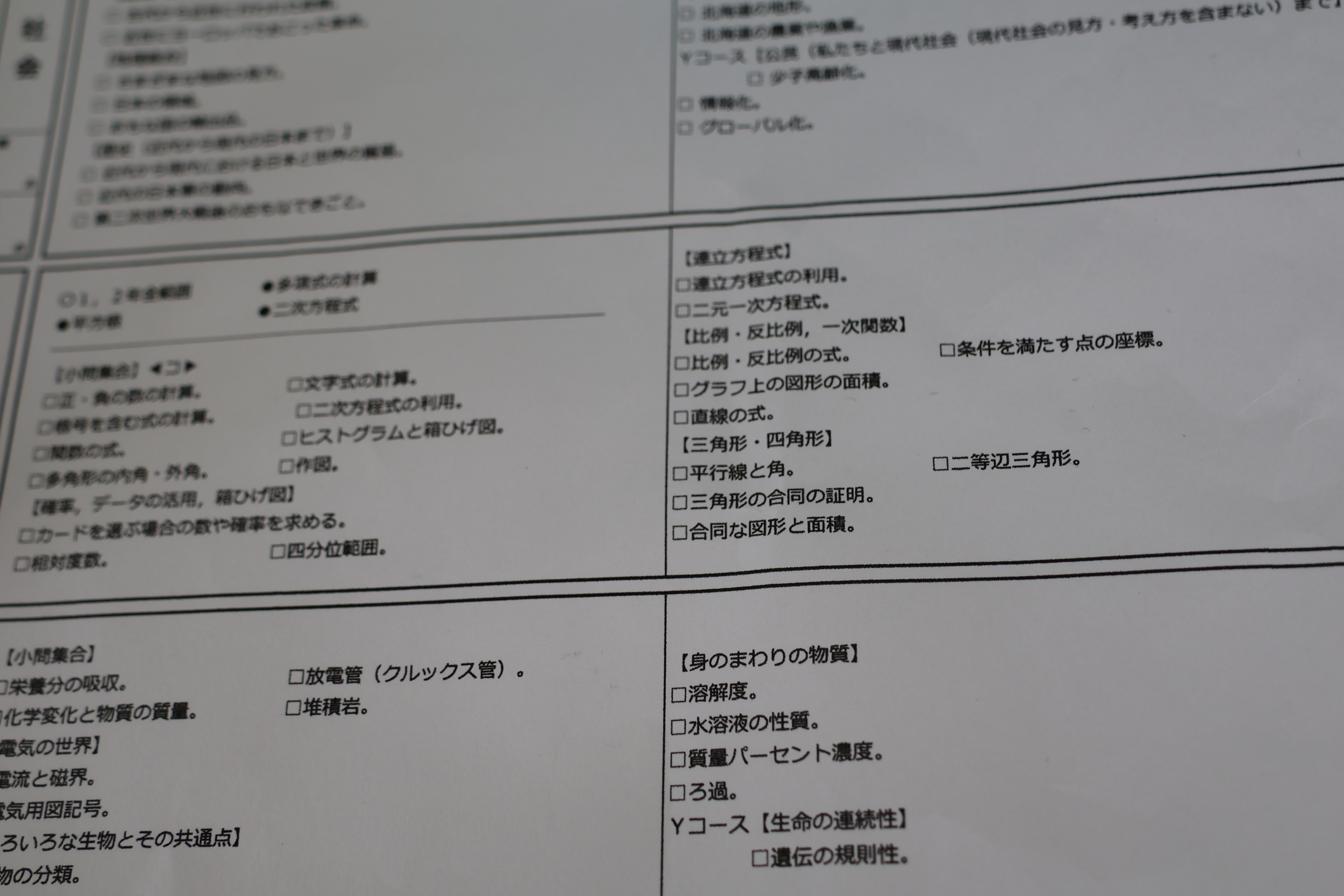

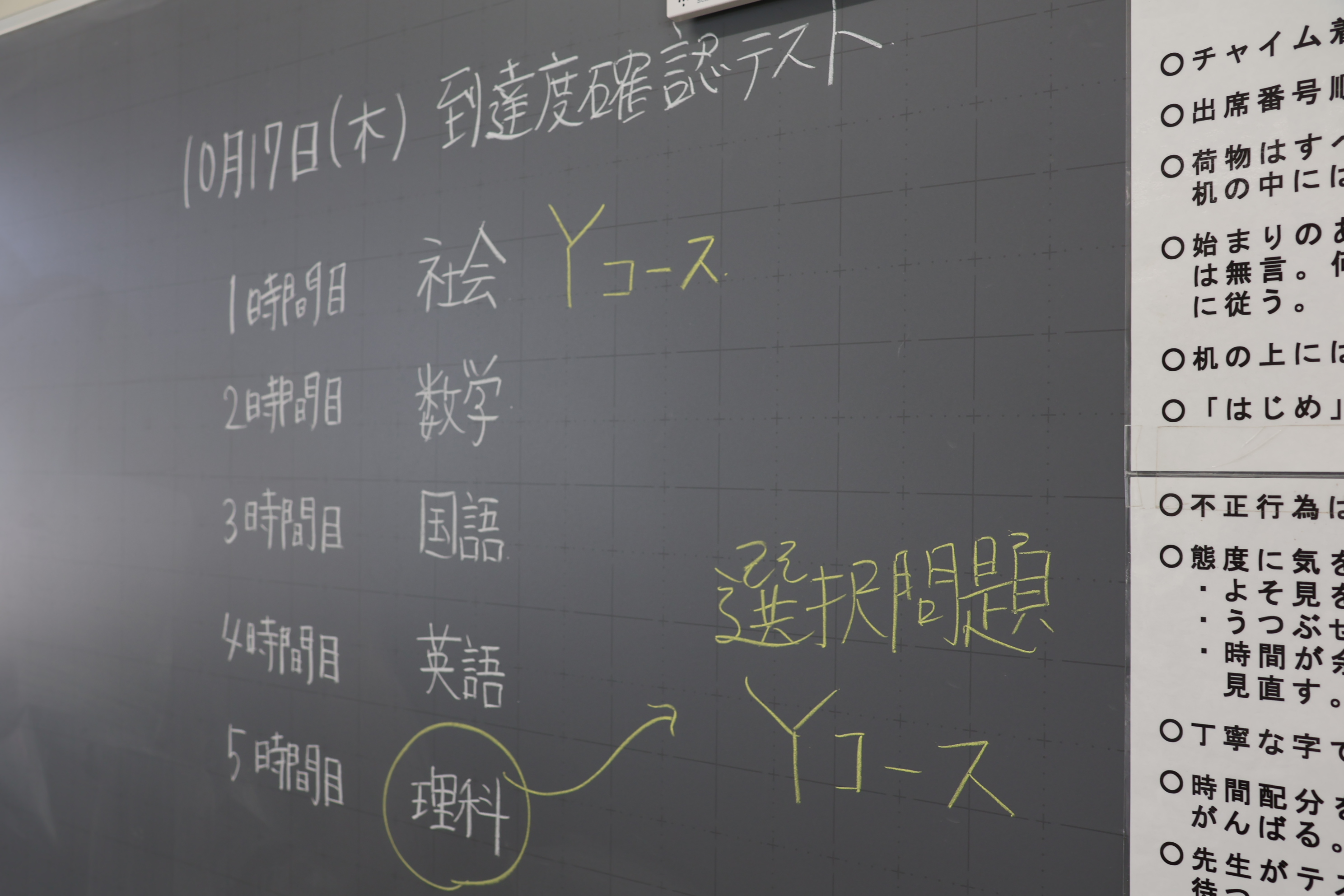
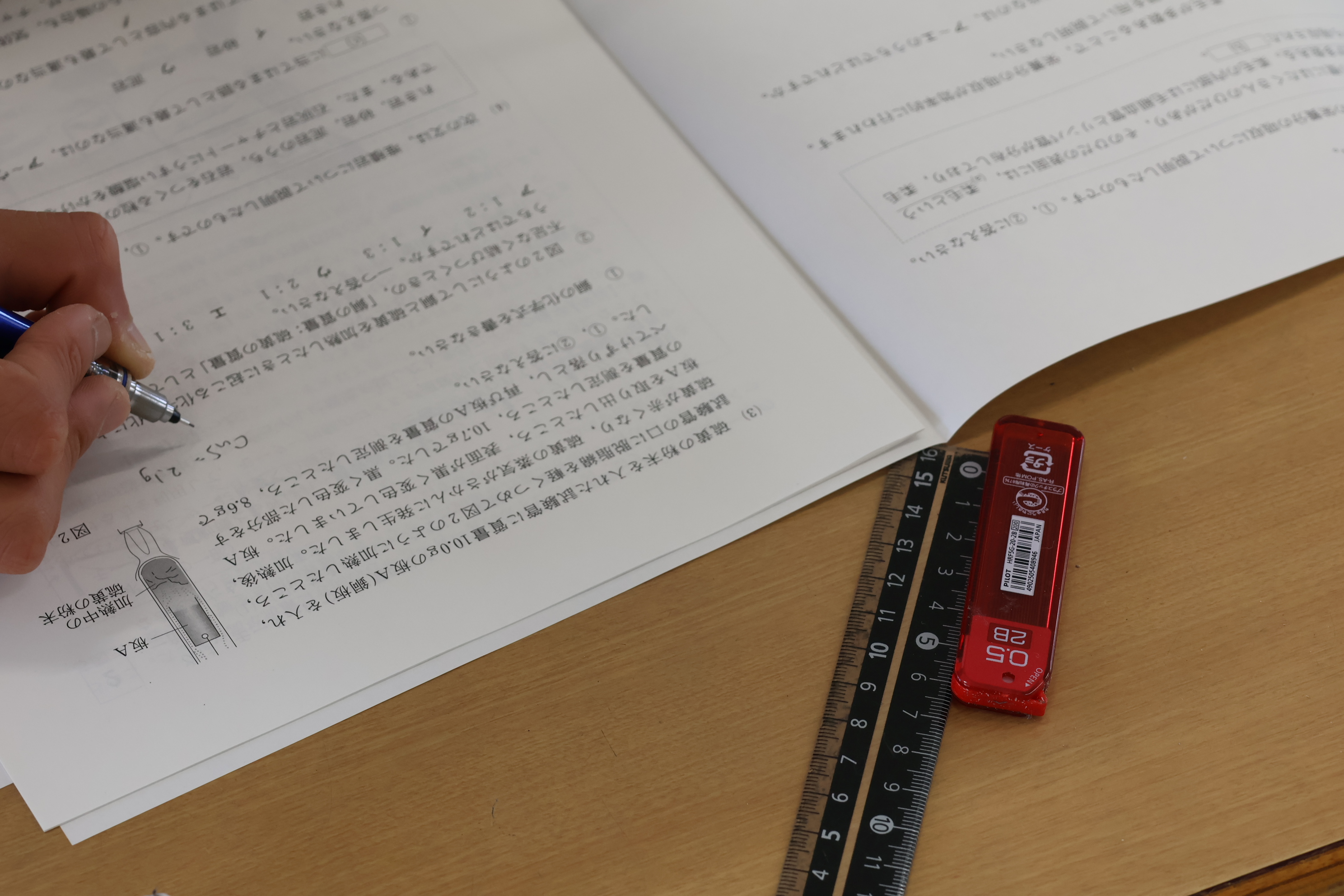
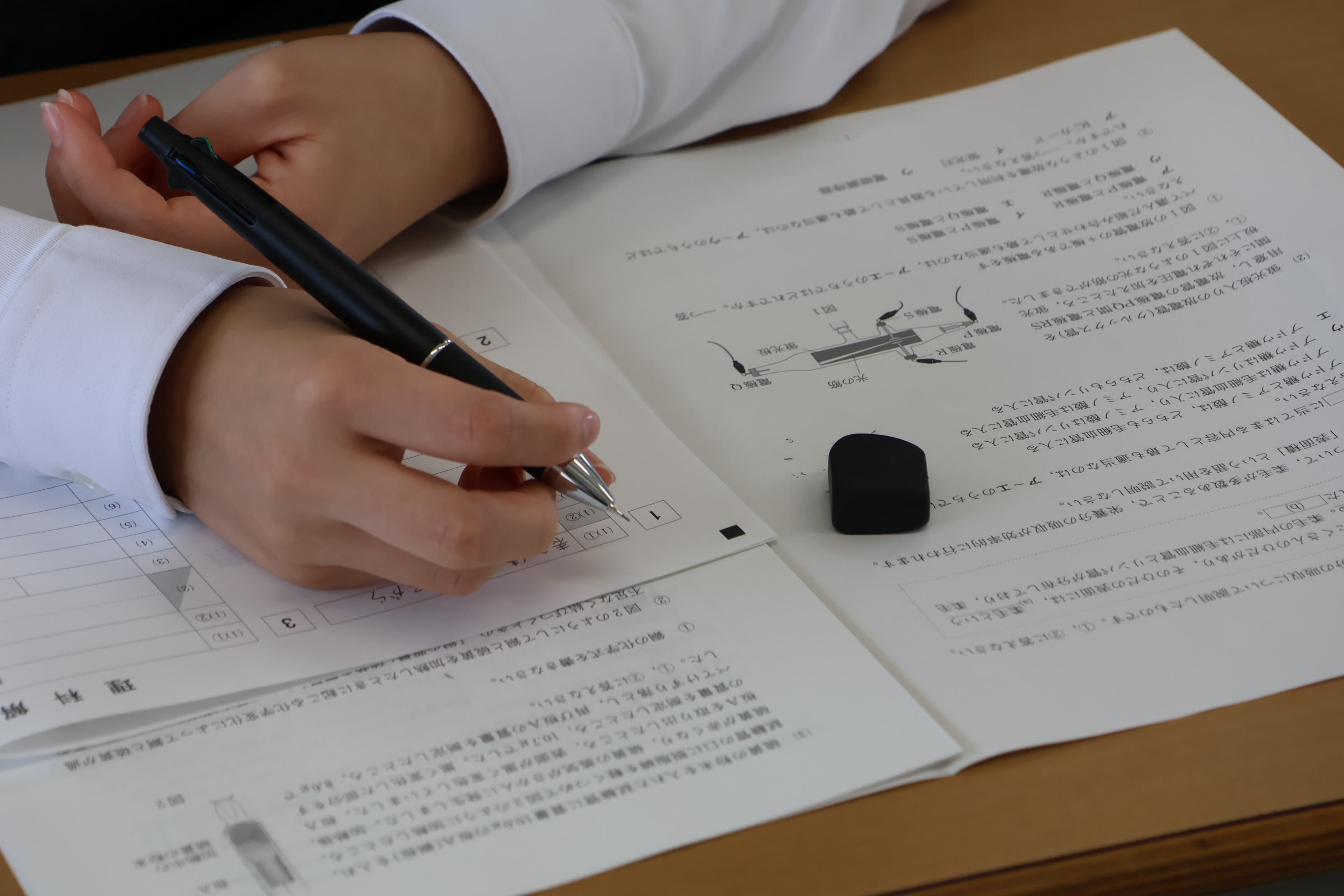

◎薬物乱用防止教室(10/17:2年生)
今年度も、薬物乱用防止教室を開催しました。水島税関支署片上出張所から山﨑さん、上田さんをお招きして、薬物乱用の危険性・有害性について正しい知識をもち、薬物乱用への勧誘に対する対応方法を学ぶことで、薬物乱用を拒絶する規範意識を高めることができました。

◎星に願いを
~ようこそ天文学へ(10/17)

9月下旬に太陽に最接近した「紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)」が、夕方の空に出現するようになりました。条件が良い所ではぼんやりと肉眼で見えるほどになっています。見える方向や時間帯などを解説します。紫金山(ツーチンシャン)・アトラス彗星は昨年、中国の紫金山天文台と南アフリカのアトラス望遠鏡によって発見された非周期彗星です。今年9月28日(土)頃に太陽と最接近し、その後も尾を引く様子が観測されています。
(明るさ)・・・紫金山・アトラス彗星は10月前半が最も明るく見える時期で、明るさは3等以上になっている模様です。
今週からは彗星の明るさは次第に暗くなっていく見通しですが、地球から見たときの太陽方向から離れていくため、背後の空が暗くなって見つけやすくなりそうです。特に20日(日)頃にかけては背後の明るさと彗星の明るさのバランスがよく、観測に一番適した時期になりそうです。再来週になると彗星が地球からかなり離れていくため、どんどん暗く小さくなっていく見通しです。
(方向と時間帯)・・・10月初週までは明け方の東の空に登っていましたが、今の時期は日没後の西の空に出現する状況に変わっています。日没後の18時前くらいからが観測のチャンスです。同じ時間帯で比較すると高度は日に日に高くなり、同じ高度になる時間帯は日に日に遅い時間になります。西の空がひらけた所では20日(日)頃になると19時台の観測も良さそうです。5日(火)頃から20日(日)頃にかけては、紫金山・アトラス彗星をぼんやりと肉眼で観察できるかもしれません。ただ、尾を見たりするのは難しく、ぼんやりと彗星の存在がわかる程度になりそうです。
その時期は、望遠鏡や双眼鏡を使えば彗星を自分の目で見られそうです。なるべく西の低い空がしっかりと開けた所で観察し、星図アプリなどで彗星の方向を確認し、金星などを目印にして探してみてください。今回の紫金山・アトラス彗星は、2020年のネオワイズ彗星に近い明るさになる可能性もあり、4年ぶりの明るい彗星になるかもしれません。
彗星は周期的に近づいてくるものだけでなく、今回の紫金山・アトラス彗星のように新しく発見されるものも多くありますので、時々情報をチェックしておくと良さそうです。
◎ひな中の風✨
~深化 進化 真価(10/17)

◎ひな中の風✨
日毎(ひごと)の訓(おしえ)なつかしき 希望の(10/16)

◎ひな中の風✨
映して 永遠に 育ちゆく 母校ぞ(10/16)





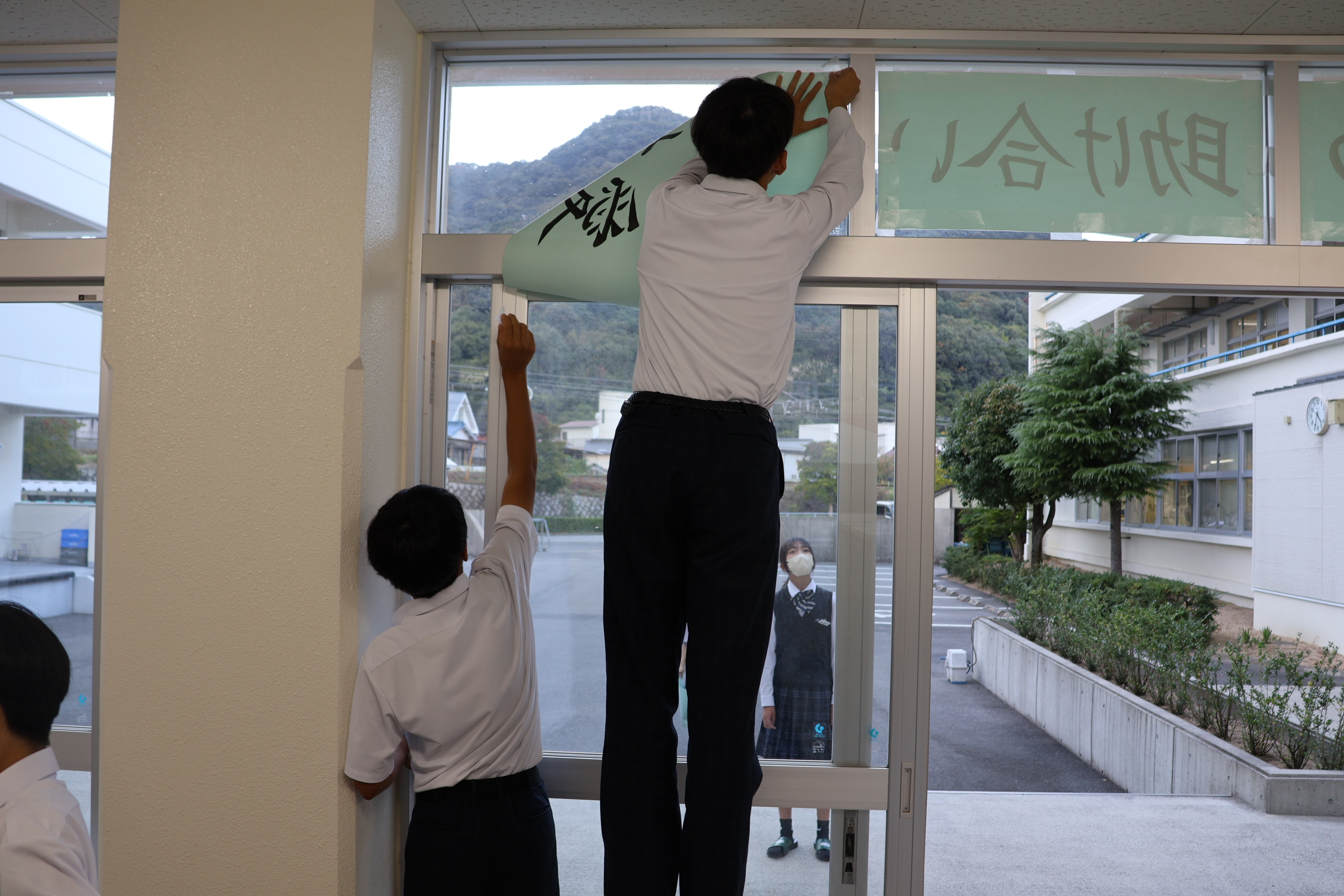
◎ひな中の風
イツモドウリノコトデスガ 👍(10/16)

私たちの二年生ロッカー✨
◎ひな中の風✨
ホウカゴヒナチュウ(10/17)
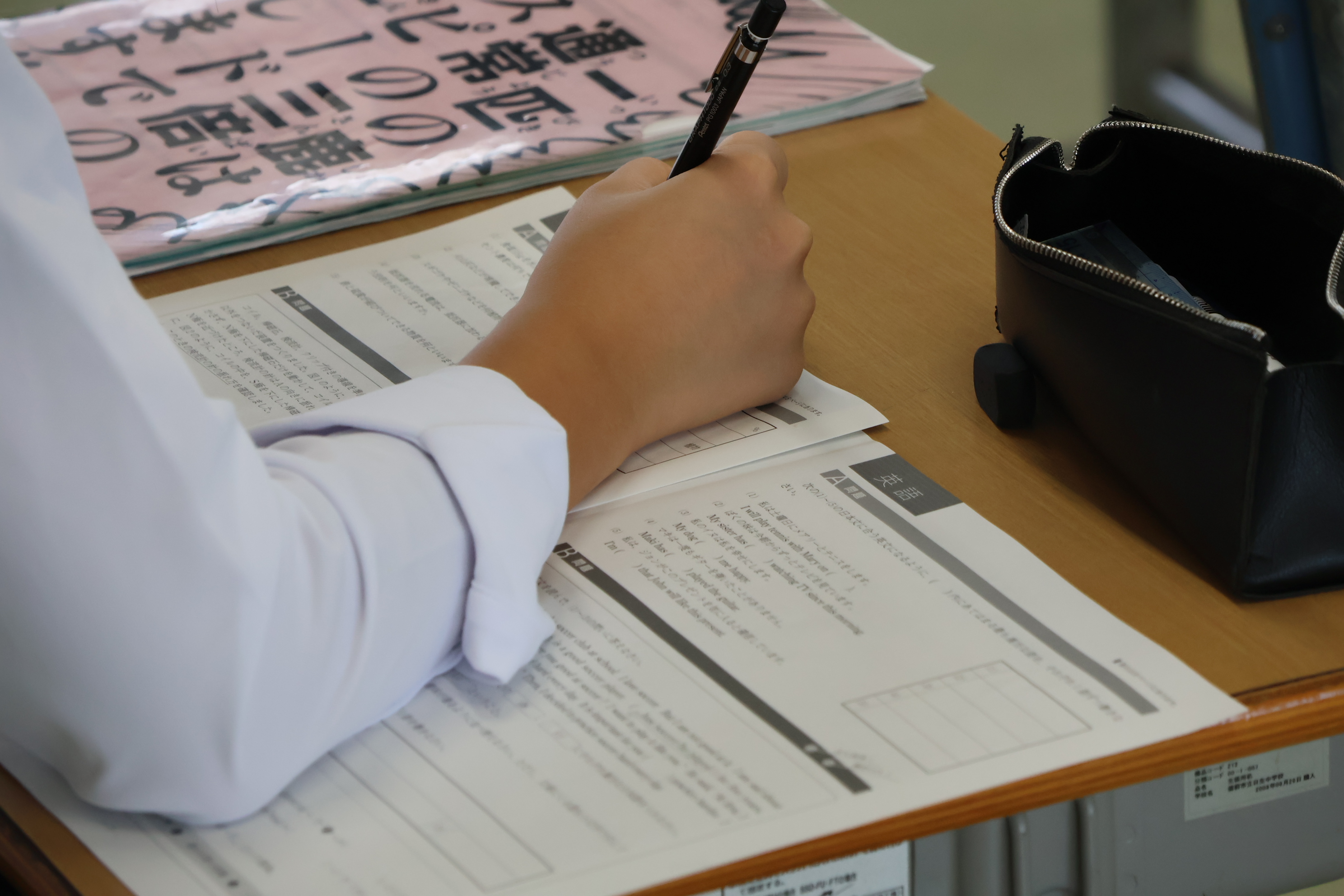


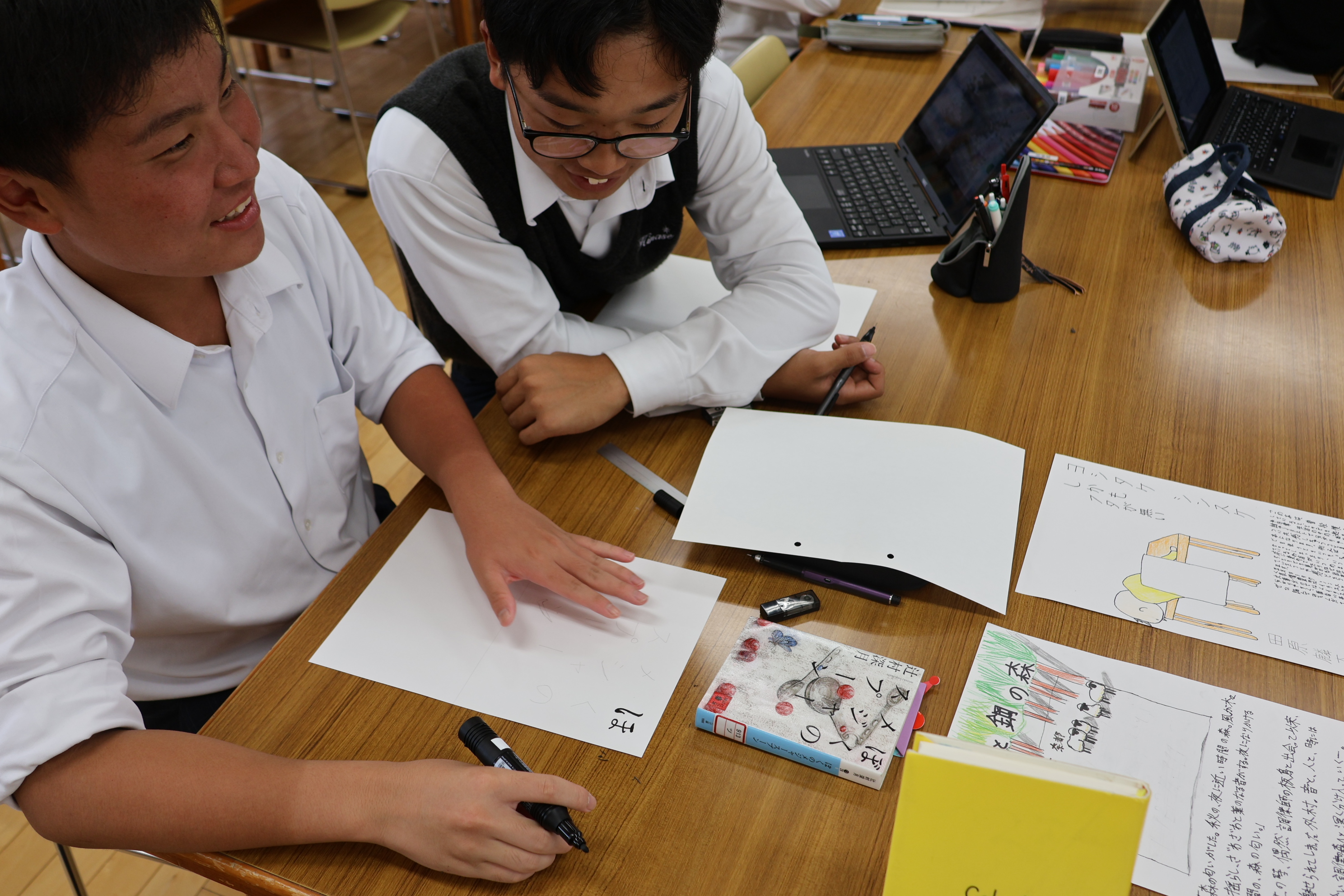
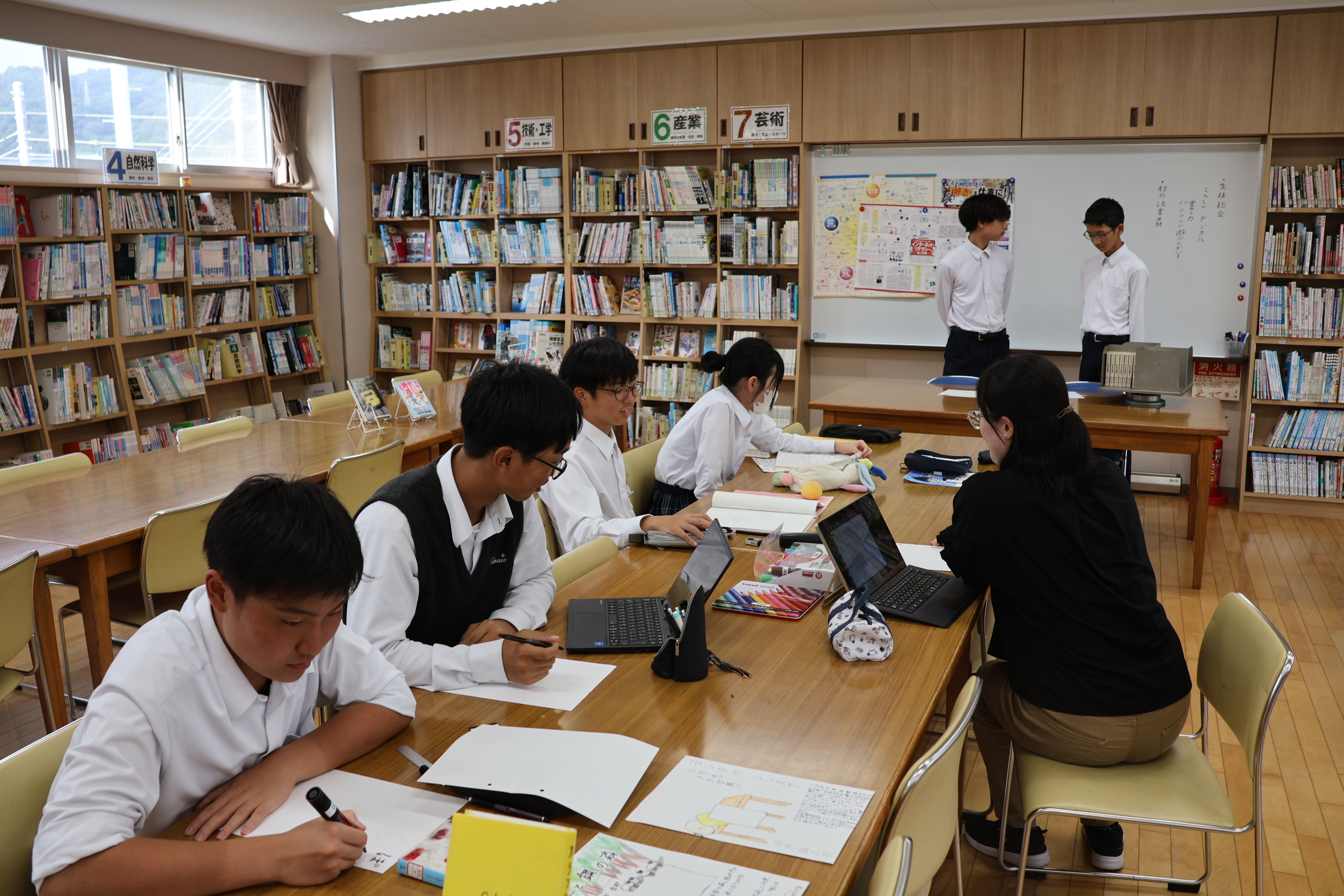

ほっとスペースもHOT
◎受け継がれた日生中(10/16)
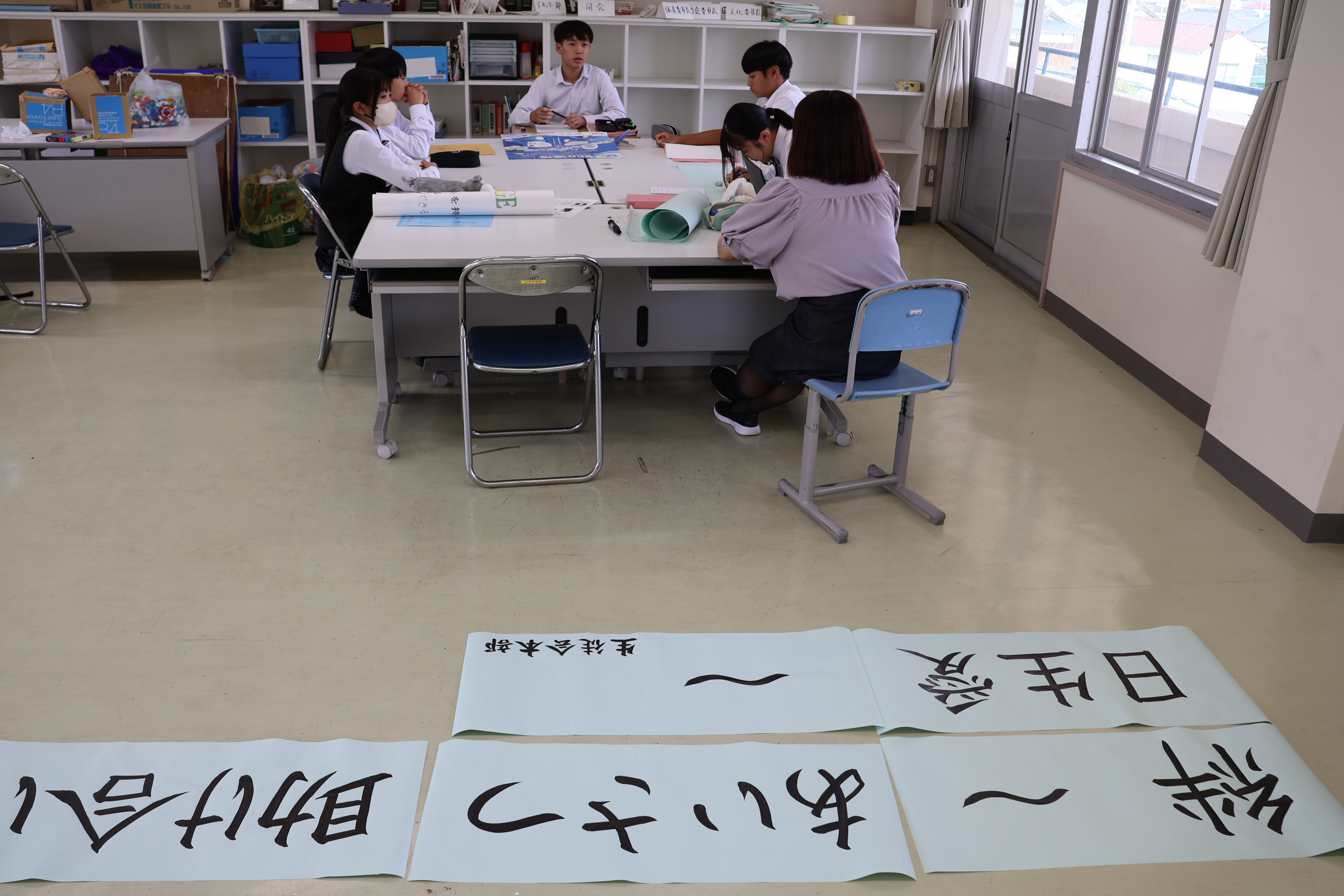
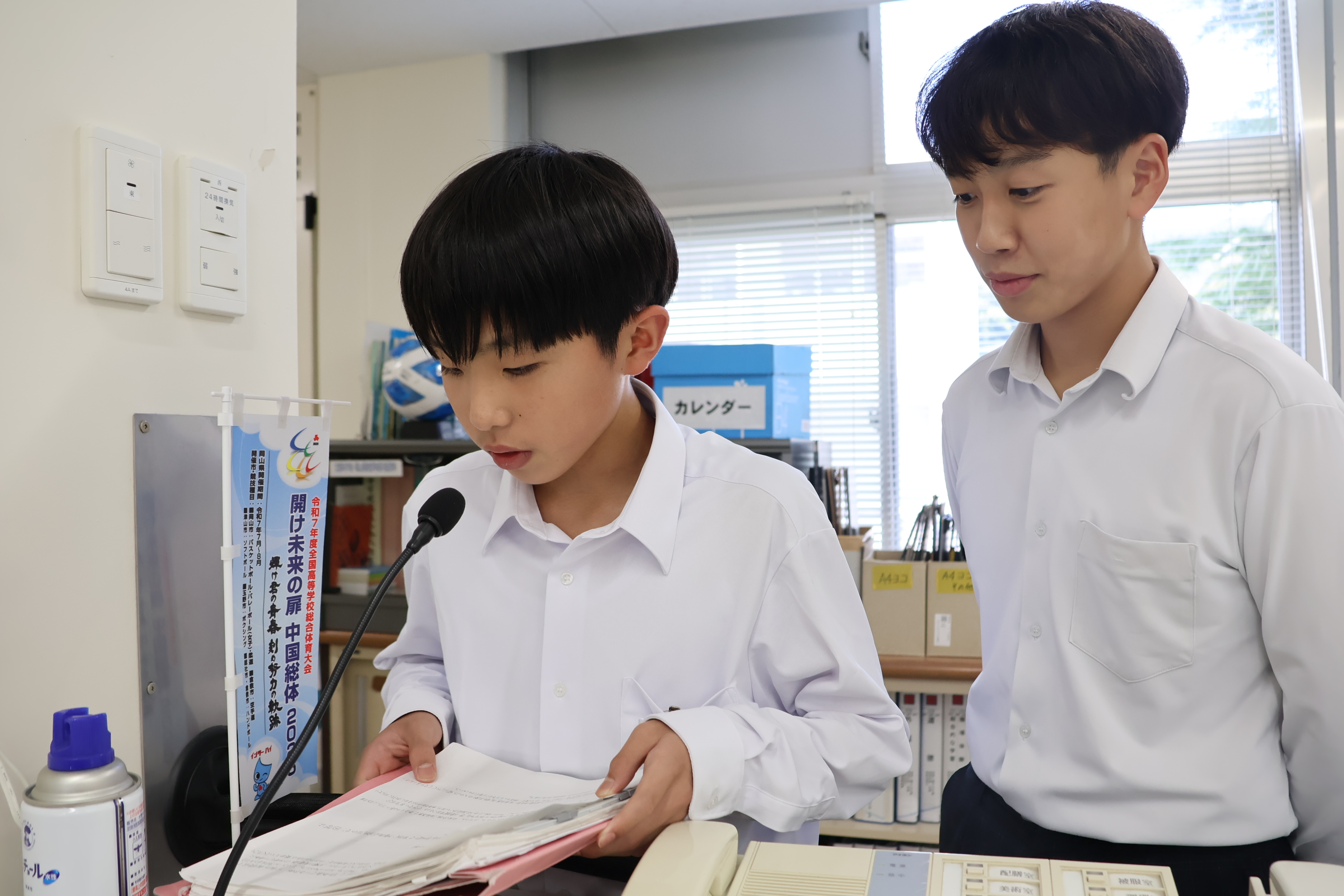
◎学び続ける者だけが教壇に立つことができる 佐藤学
15日から自己目標シートによる中間面談を行っています。10月も折り返しです。



◎校長室から
~夢は意外なところから~(10/16)
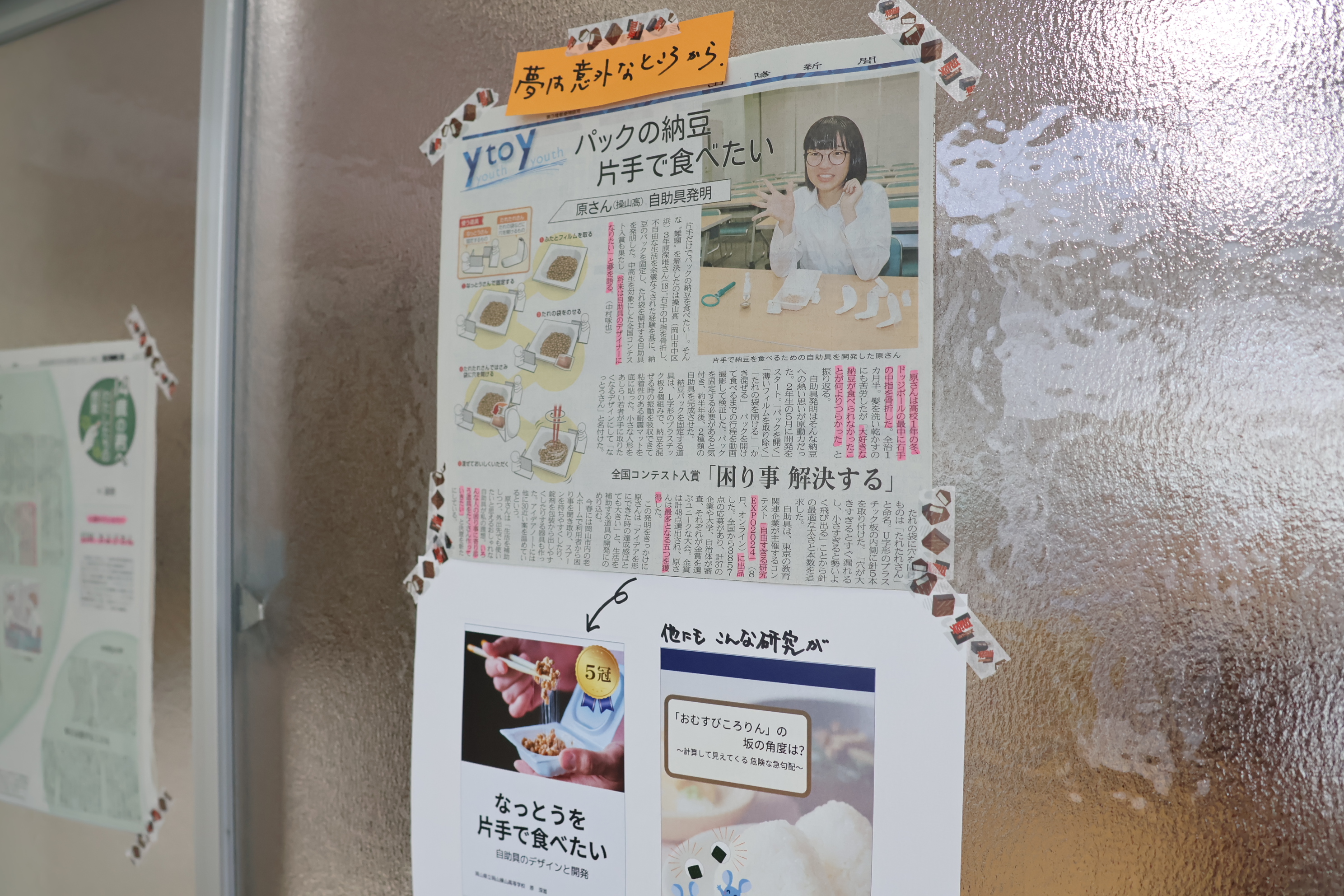
◎秋の夜長 本を読もう🎃(10/16)
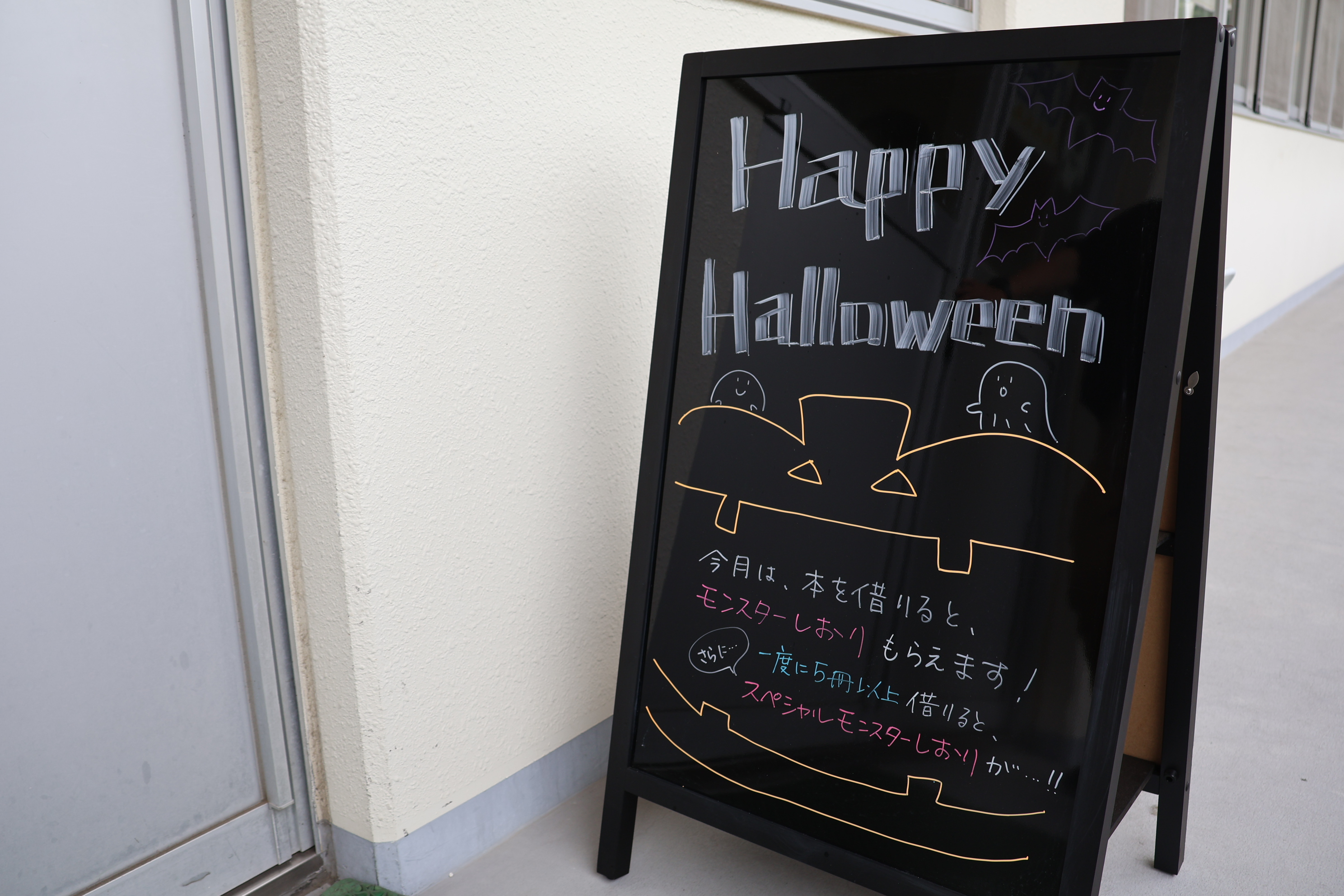

今日は、読み聞かせボラさんが6名来校されました。ありがとうございました。
◎社会とつながる(NIE)学びを(10/16:選挙告示を受けて)


◎月を見ていた♬
~思い馳せるあなたの姿 羊を数えるように(10/16)
10月17日の空には、「スーパームーン」と呼ばれる満月があらわれます。この力強い名前には、どんな意味があるのでしょうか。また、この現象はなぜ起きるのか? 友達に教えたくなる「スーパームーン」について説明します。
「スーパームーン」とは、一般的に地球と月がもっとも近づいたときに見られる「1年で最大の満月」のことを指します。最近、TVやネットニュースなどでよく聞くようになりましたが、実はこのスーパームーンという言葉は天文学の正式な用語ではなく、定義もはっきりしていません。
国立天文台のHPでは、スーパームーンという表現は使わず、「2024年で地球にいちばん近い満月」と説明されています。もし、友達に意味を聞かれたら「今年、一番大きく見ることができる満月のことだよ」と伝えてあげると良いでしょう。
2024年にスーパームーンが見られるのは、10月17日(木)。夜の20時26分に満月を迎えるため、お天気が良ければ、夜空できれいに輝くスーパームーンを眺めることができますよ。
10月に見られる満月は、「ハンターズムーン」という呼び名もあります。これはアメリカ先住民が各月の満月に名前をつけ、季節を把握していた風習が由来。10月になると、冬に向けての準備として狩猟を始めることが、この名前がついた理由です。月は地球の周りを公転していますが、その軌道は円形ではありません。楕円形をしており、地球と月との距離は一定ではないため、スーパームーンという現象は起こります。
さらに、月の軌道は太陽や地球などの重力を受けて絶えず変化しており、地球と月との地心距離(天体の中心と地球の中心の距離)も変化します。つまり、地球からもっとも近い満月、もっとも遠い満月の距離も毎年変わっているのです。2024年で地球からもっとも近い満月、スーパームーンは10月17日ですが、地球からもっとも遠い満月は2月24日に起きました。今回のスーパームーンは、2月24日の満月に比べて、約14パーセント大きく見えるそうです。ただし、実際の夜空で月を2つ並べて比較することはできないので、スーパームーンを見ただけでは大きさの変化に気づくのは難しいでしょう。それぞれの日に、同じカメラ、同じ位置から撮影した写真を見比べると、月の大きさの変化がわかるので、ぜひ試してみてください。

◎多くの人に支えられて(10/15)
たくさんの〈星輝祭文化の部 がんばりメッセージ〉ありがとうございます。メッセージの一部を紹介します。
○文化の部、楽しみにしていました。吹奏楽部の軽やかな演奏や弁論大会。日頃の練習の成果を見させていただき、感動いたしました。また、合唱コンクールは、孫娘が毎日帰宅して「今日はみんな、声が出ていた」とか、「今日は私は不調だった」とか、聞かせてくれたり、課題曲・自由曲を歌ってくれたりするので、そのうちに私も一緒にハモリの練習のお手伝いをするようになっていました。
本番当日は、男子が安定した声で堂々と歌い、男女全員が一生懸命に歌っている素晴らしい勇姿を見て感慨深く、涙がとまりませんでした。来年は三年生です!今から楽しみでなりません。皆!益々、頑張って~!
○昨年に比べ、クラスがまとまり成長した合唱が聴けて感動しました。ホリゾント製作もがんばって通っていましたが、素晴らしい出来でした。また、来年が楽しみです。
○たくさん練習していた成果が出ていて、のびのびと歌っていて楽しく聞かせてもらいました。
○中学生になって初めての星輝祭文化の部の合唱。緊張しながらも頑張って歌っている姿に感動しました。クラスで協力しながらの練習の成果があったのではないかと思います。来年も楽しみにしています。
○3年生、2年生、1年生、すべての学年で、たくさん練習した成果が見られました。こどもたち一人ひとりが星光のようにとてもまぶしく輝いていました。これからも星輝祭文化の部、体育の部ともに楽しみにしています。(1年生が歌ったマイバラードが自分自身が中学生の時に歌った曲だったので、とてもなつかしく、うれしく心にしみました)
○夏休み中からのホリゾント制作、合唱の練習は朝練や放課後と直前までがんばって取り組んでいました。当日のクラス全員で心をひとつにして歌声を届けようとする一生懸命な姿は真摯でとてもステキでした。1年生、2年生の時より確実に進歩していて3年生らしいいいステージで、積み重ねることのすばらしさを感じました。
○最後の合唱に向けて友人達と朝早く学校で集まったり、休みの日も待ち合わせて練習したりと熱心に取り組んでいました。当日はその成果が出せたようで、一年生の頃と比べるととても成長したなと感じました。チームで協力して頑張る力を今後も持ち続けて欲しいと思います。

◎日生で輝く 未来を創ろう(10/13)
山陽新聞(10/12)を紹介します。

◎進路・キャリア〈生き方〉学習会
~鳴門部屋〈大相撲〉の皆さんをお迎えして
縁あって、鳴門部屋(親方は元琴欧州関*残念ながら当日は来校されません)の、若い力士さん、行司さん、床山さんらを学校にお迎えして、10月23日(水)に進路〈生き方〉学習に取り組みます。保護者・地域の方々も参観授業を大歓迎です。
〔問い合わせ・申し込み:日生中(0869)72ー1365(教頭)まで(*^o^*)〕
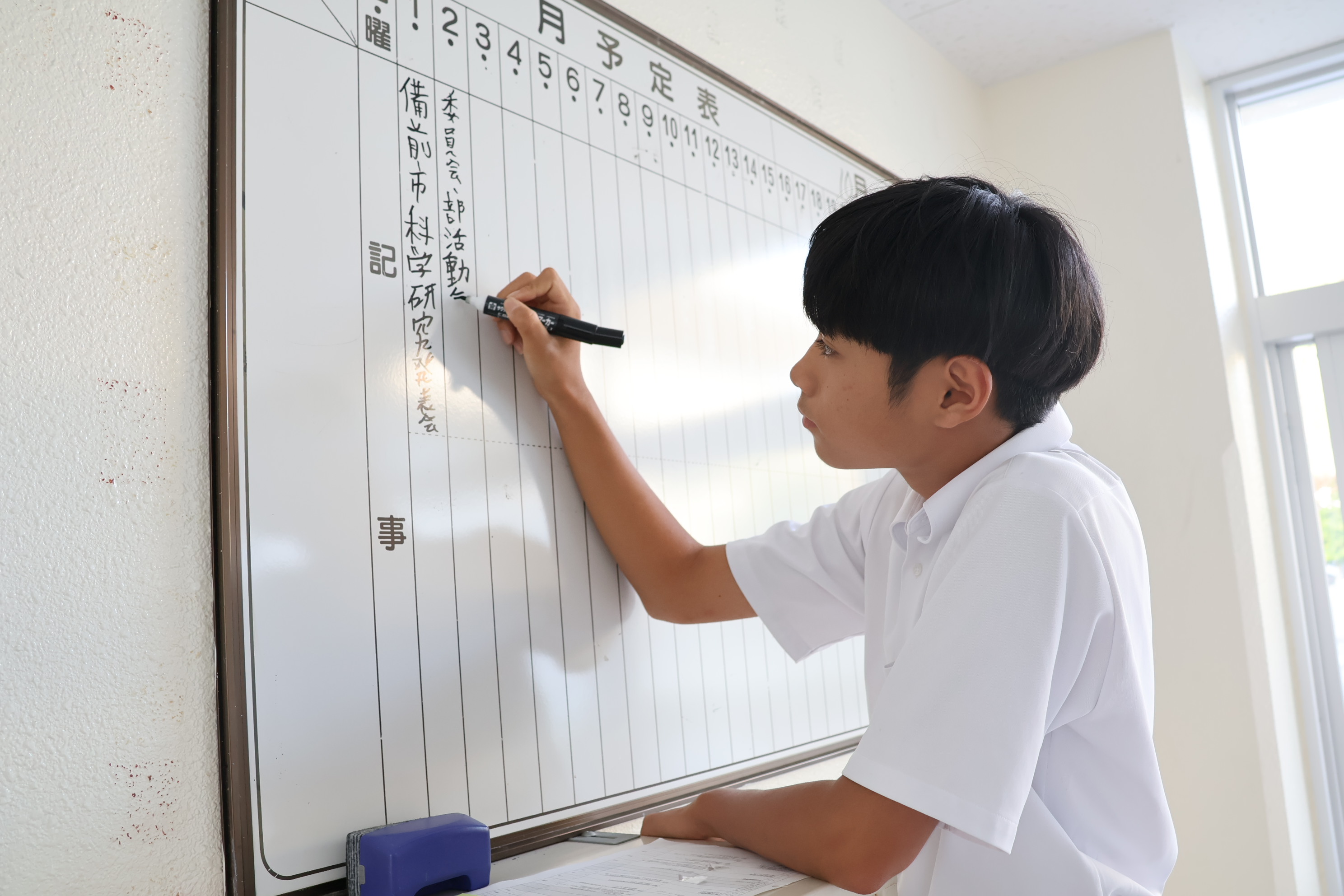
◎大切にしたい。〈交通安全〉〈時間を守る〉こと
17時下校(夜光タスキ着用)となりました。ご安全に(^_^)





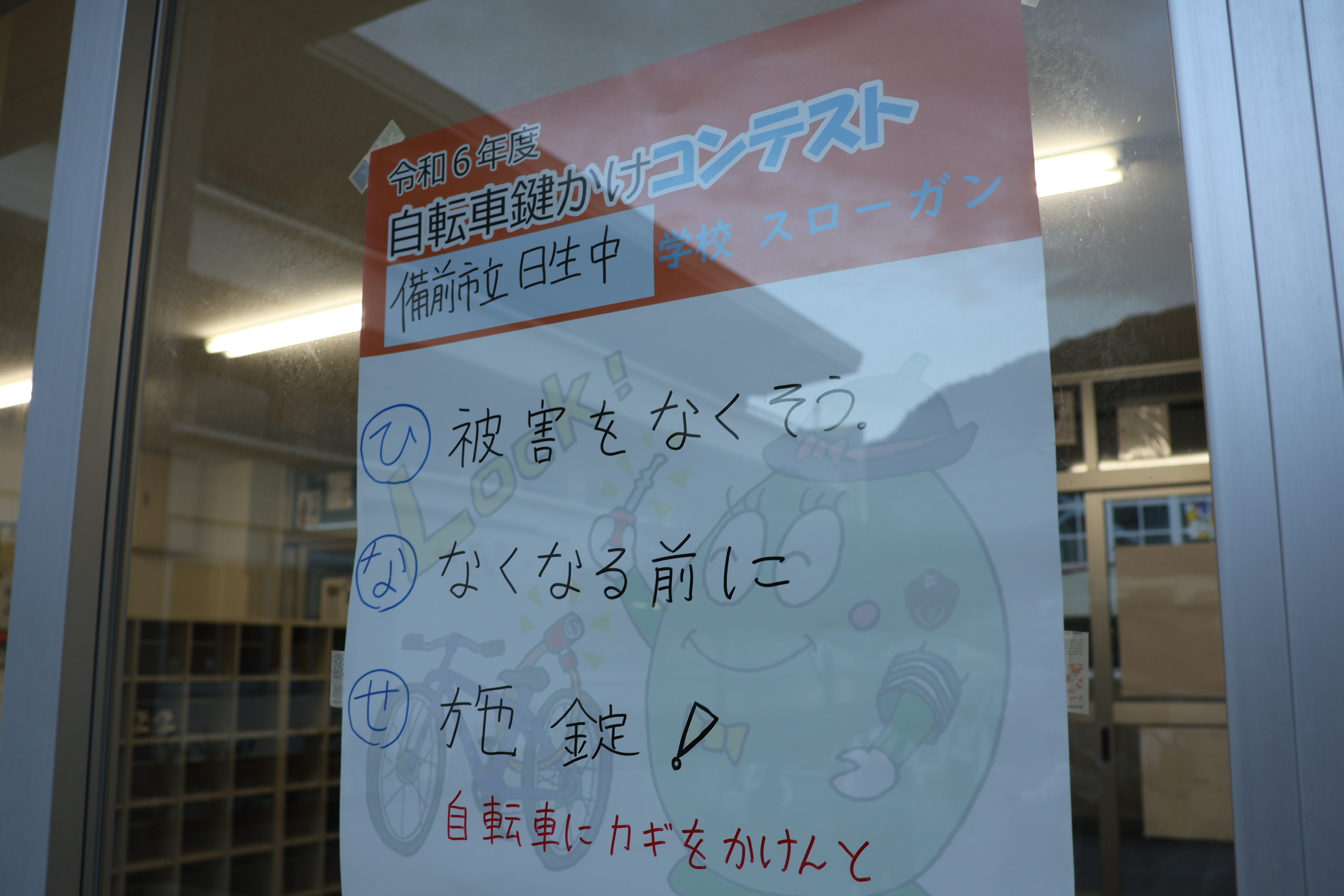
◎ひな中最前線~生徒評議会開催(10/10)


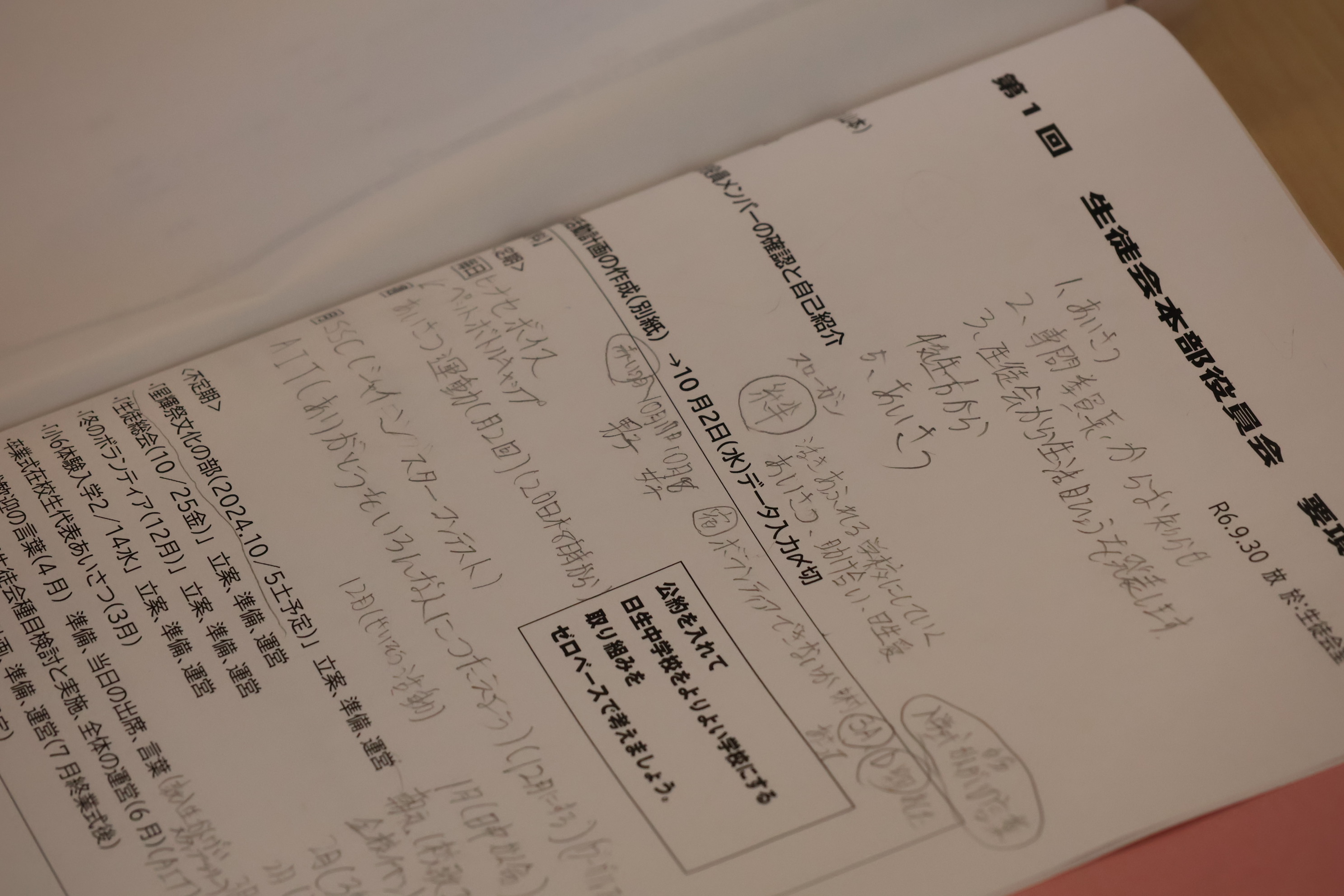
新役員による生徒朝礼に続いて、生徒総会(10.25)に向けての生徒評議会を開きました。
◎まだ見ぬ〈出会い〉を
日生中ボランティア推進プロジェクトをがんばっています。この秋もたくさんの依頼が来ています。(10/11)
参考に、夏ボラに参加した人の「振り返り」を一部紹介します。
○私は子供が大好きだけど、ふれあう機会があまりありません。だから、今回の夏ボラで、普段は体験できないことや、新たな気づきを感じることができました。まだまだ小さな体で、何かを一生懸命しようとしたり、小さなことで笑ってくれて、本当にかわいいなあという感情がうまれると同時に、私も「がんばろう」と思えました。そんな子どもたちのために明るい未来をつくりたいです。A
○ボランティア活動では、備前緑陽高校の人と、祭りの準備をしたり、掃除をしたりした。身についた事は、人とのコミュニケーション能力が身についた。N
○ボランティアを通して私が学んだことは、小さい子とのふれあい方です。去年もこども園に行かせてもらって改めて、日生のこども園は元気で、人なつっこい子が多いと思いました。私にとっても、いい経験になったし、将来につながる体験になりました。Y
○私はボランティアを行って、思ったことは、子供たちの視点や考え方が、私が幼稚園児の考え方が違うことです。男子の子に折り紙を作ってといわれて、30分かけて作ることができました。ゲームで遊んだり、着替えができたりしてほめてあげると喜んでいて、可愛いかったです。たくさんの子供たちとふれあうことができてよかったです。Y
○寒河キッズにボランティアに行きました。お皿洗いや、おかしのごみ捨ての手伝いをしました。大変だったけど、とてもいい経験になりました。また機会があればいってみたいです。H
○三歳児のお世話をするときに、あまり言うことを聞いてくれない子もいたので、こども園の先生はあらためてすごいなと思いました。一歳児のお世話のときは、ごはんやおやつを食べるときに、こぼしたり、食べなかったりしなかったのでとても大変でした。子どもと遊ぶのはとても楽しかったし、また、子ども園にボランティアに行きたいです。M

◎明日がある〈11月12日(火)~15日(金)の4DAYs〉
(10/10)
実際の職場での体験活動を通して、望ましい職業観や勤労観の育成を図ることと、事業所で働く人々とのふれあいを通して、社会人としての礼儀や教養を身につけることを目的に今年度も2学年 職場体験学習(チャレンジ・ワーク14)に向けて準備を進めています。今年度の生徒の受け入れをしていただける企業の方々です。ご協力をありがとうございます。事前学習を進めて、実習させていただく事業所を決めさせていただきます。どうぞご支援をよろしくお願いします。
中元写真館 日生図書館 カメイベーカリー 日生町漁協・五味の市・しおじ 奥本生花店 café RAD マクドナルド赤穂フレスポ店 (有)磯 ステラカフェ "カフェ天goo 一般社団法人ジンジャー・エール レストラン夕立 THE COVE CAFE すき家250号赤穂駅前店 日生認定こども園 日生西小学校 日生東小学校 伊里認定こども園 セブンイレブン岡山備前インター店 山陽マルナカ穂浪店 ホームプラザナフコ備前店 旬鮮食彩館パオーネ日生店 ホームセンタータイム備前店 ダイレックス赤穂店(順不動・敬称略)

大切な4日間にしよう!
◎ゆたかな学びを 仲間と共に(10/9)









◎地域とつながる 社会とつながる学校(10/8)
10月1日(火)から、令和6年度(第78回)の「赤い羽根共同募金運動」が始まりました。社会福祉法人中央共同募金会(会長 村木厚子)では、キックオフイベントを東京・霞が関ビル前広場「霞テラス」で実施しました。キックオフイベントでは、NHK大河ドラマ「光る君へ」藤原妍子(きよこ)役の女優 倉沢杏菜さん、大相撲の東関親方(元 高見盛関)らが、共同募金の助成で活動する団体の皆さんと共に、募金を呼びかけたそうです。
8日には、日生中学校でも、パオーネさんでの街頭募金活動をおこないました。あいにくの雨天でしたが、多くの方々のご協力をいただきました。ありがとうございました。17日にもう一度活動を行う予定です。
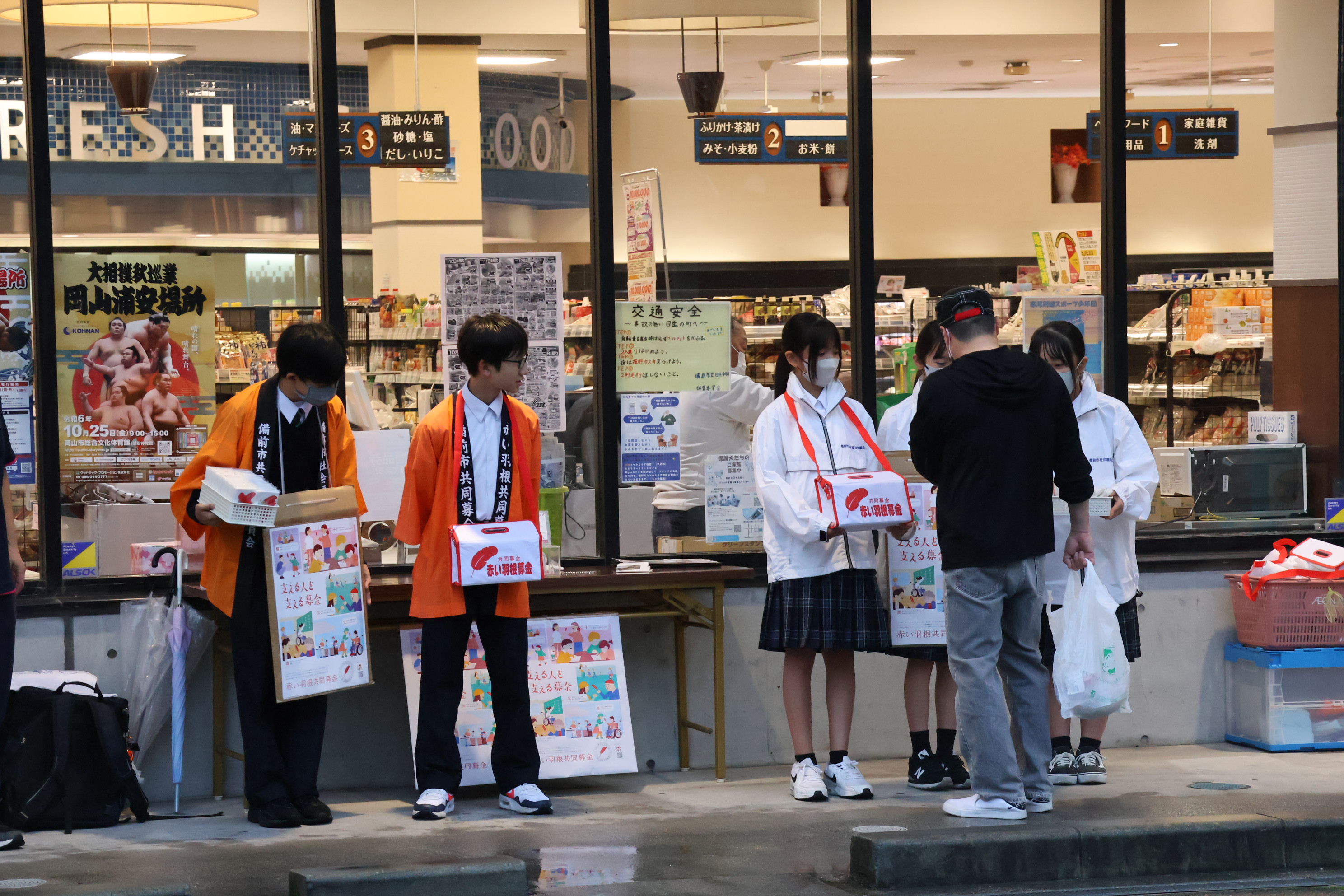




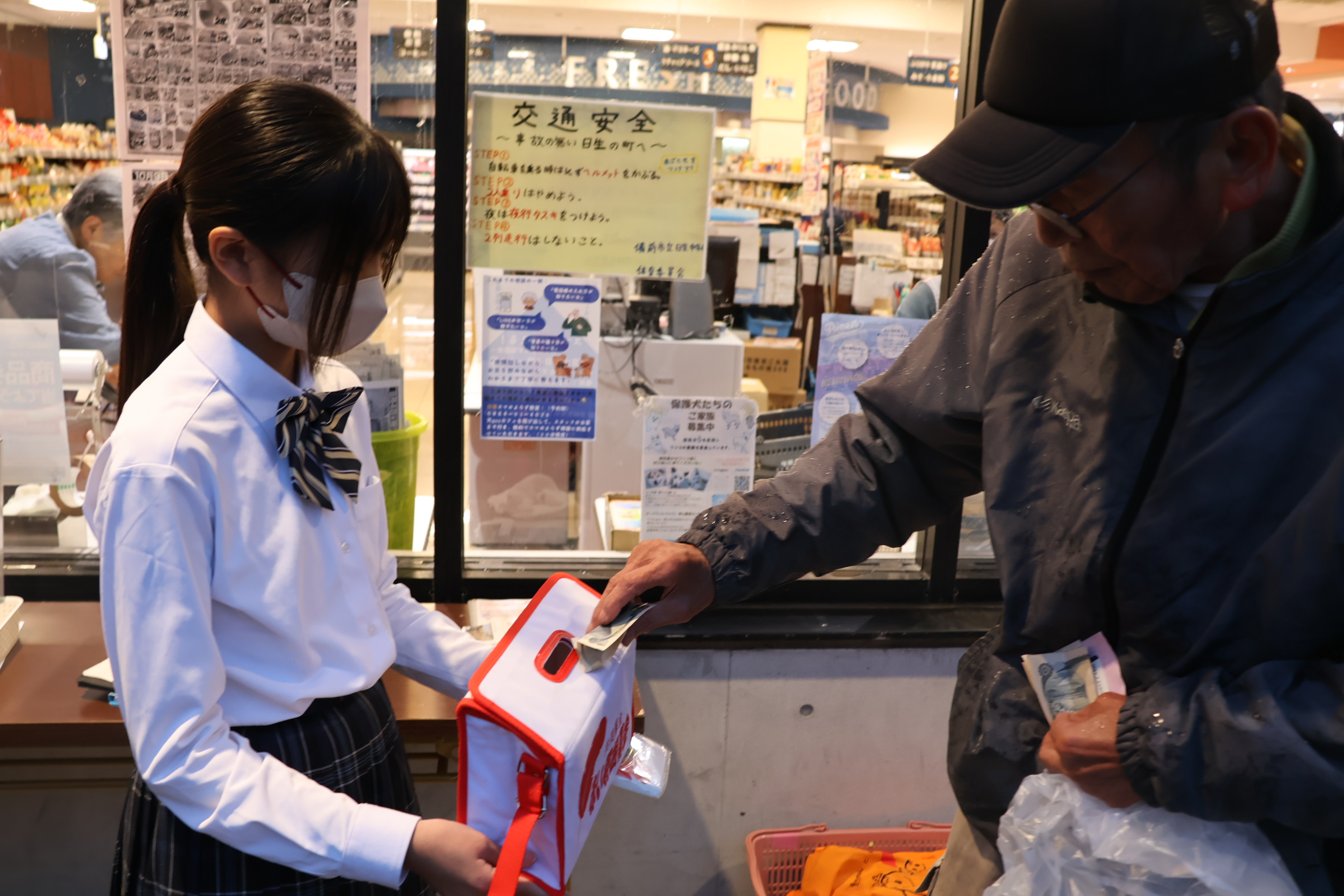
◎LAST MILE(10/8)



ラストマイルとは、物流の最後の接点であり、配送センターから消費者に向けての商品の配達の最終段階を指します。この配達は、より多くの労力や費用を必要とすることが多く、物流や運送において重要な役割を担っています。
◎歩み新たに日に生(な)せば
今日は昨日の我ならず(10/6)
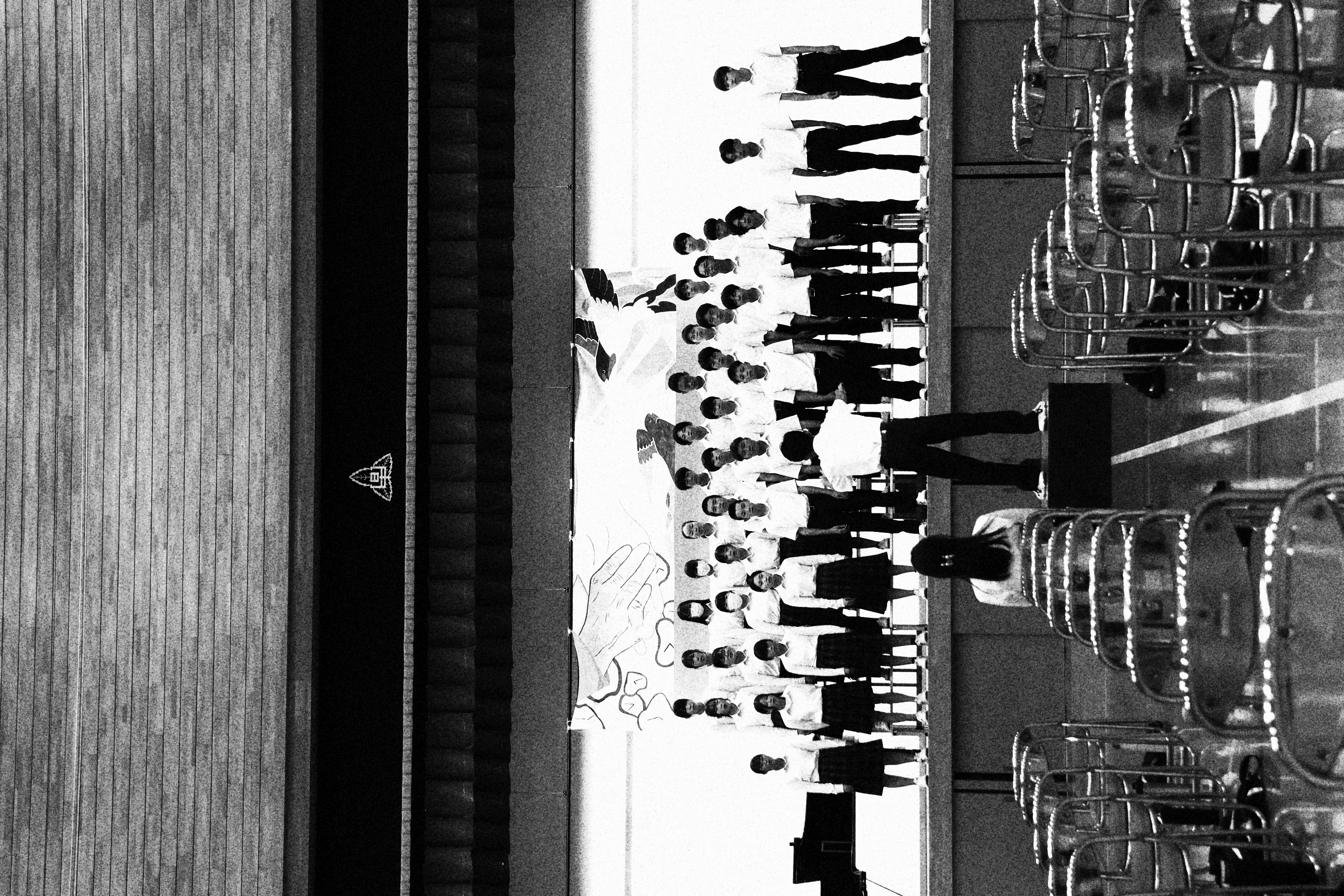
がんばり応援メッセージは10/18ぐらいまでに願いします。(^∧^)
◎"仲間とともに"って、こういうことさ(10/6)


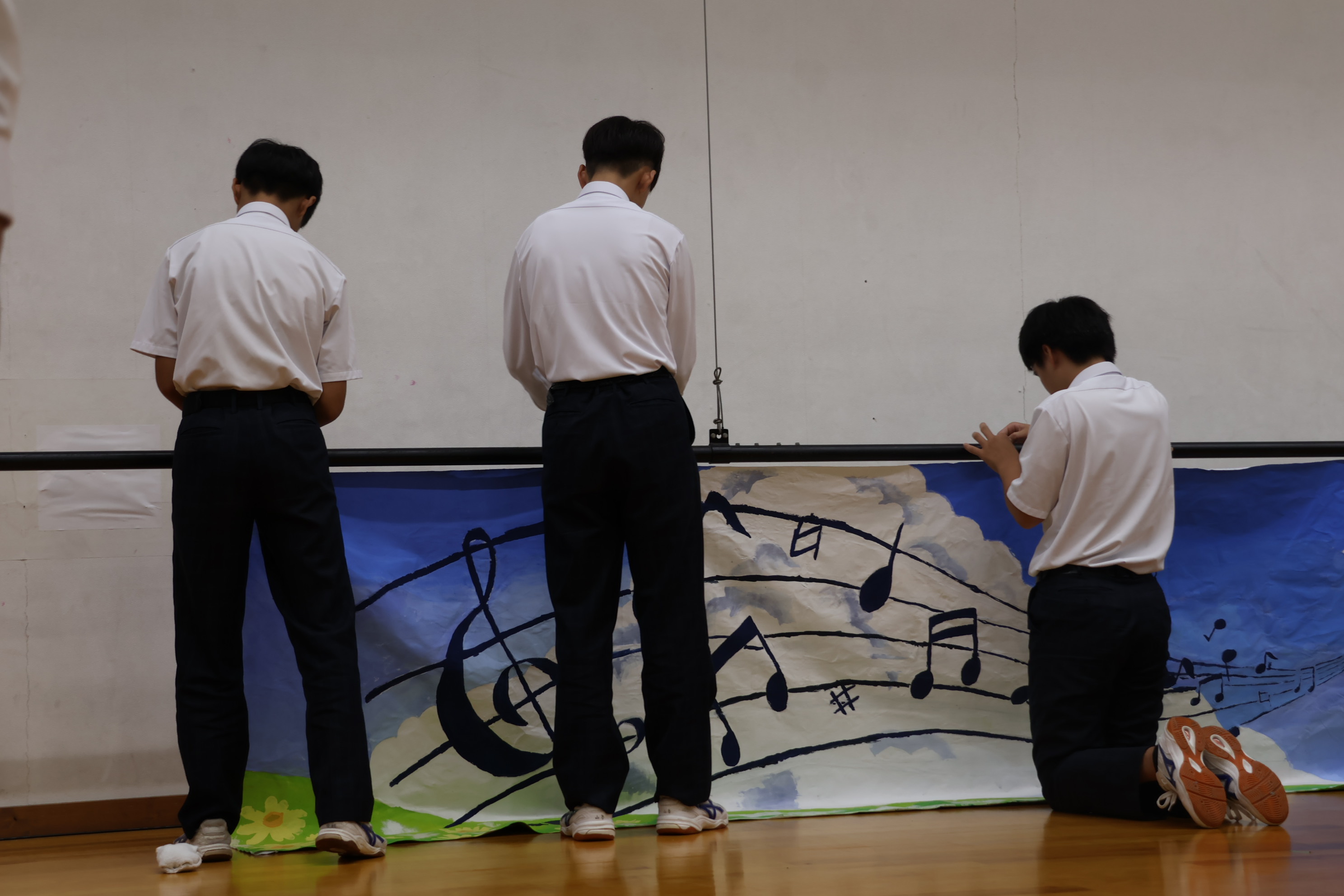









◎HINASE LEGACY 星輝祭 文化の部(10/6)

◎地域とつながる 社会とつながる学校(10/8)
この日、備前市保健課さん、日生愛育委員さんらと連携して、血圧測定や血管年齢チェックなどの健康相談コーナーを設置し、たいへん好評をいただきました。






健康で、元気でね
◎ありがとう、みんな(10/6、朝)
「自転車を運ぼう。よいしょ よいしょ」

自転車の空気圧や灯火の点検をあらためてチェックしよう。8日(火)から夜光タスキ着用となります。
◎2024星輝祭 文化の部〈10.6 8:45開会〉
~星 笑顔、光のようにどこまでも届け~

◎私たちが創る 私たちの星輝祭(10/4)







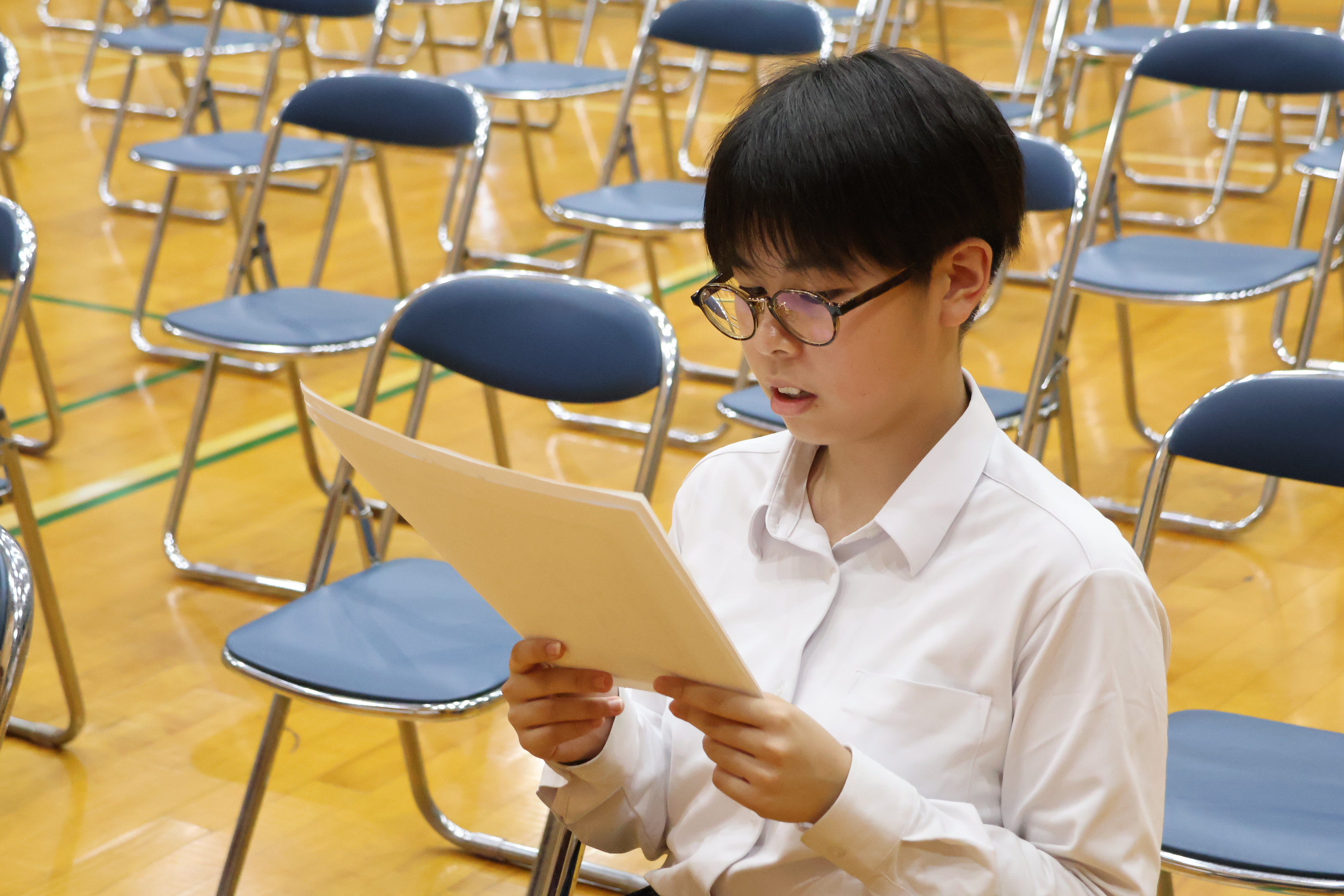
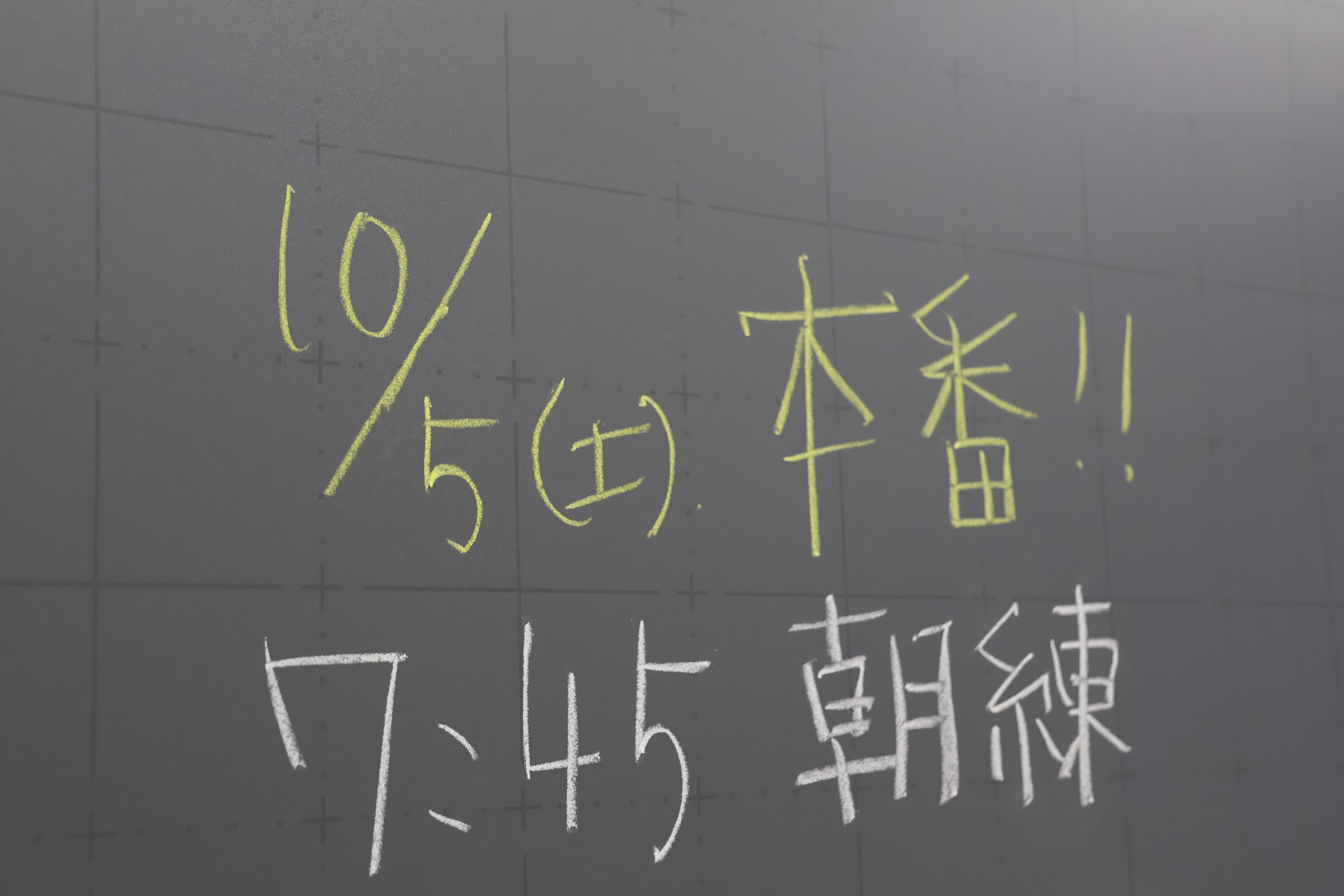
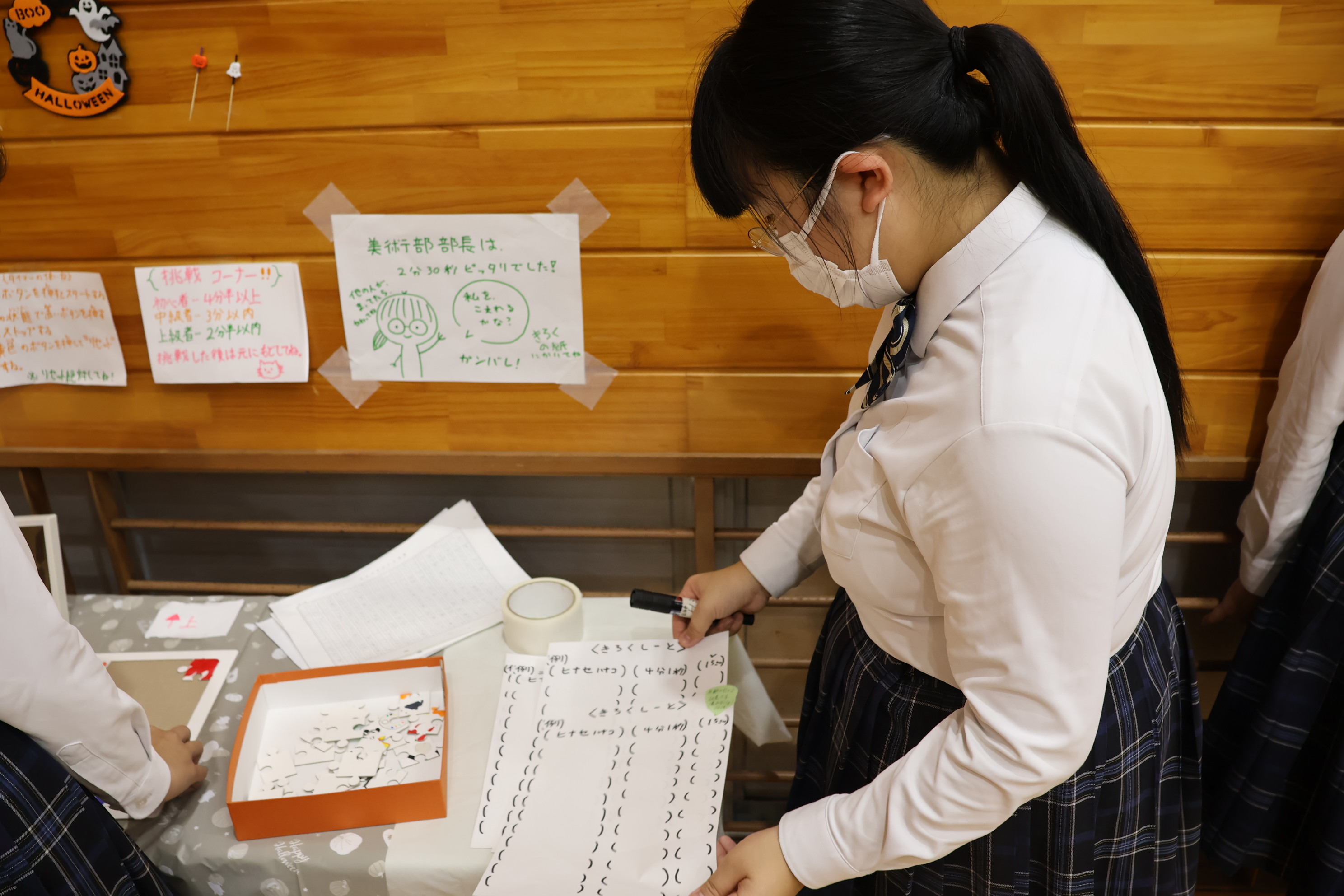


◎星 笑顔、光のように どこまでも届け(10/4)
明日、星輝祭 文化の部

◎With your smile(10/4)
明日、星輝祭 文化の部






明日、星輝祭 文化の部









The greatest treasures are those invisible to the eye but found by the heart. Judy Garland
(最高の宝物は、目には見えない、心で見つけるものである。)
◎私たちの生徒総会〈学級議案検討〉
いま・ここから、明日の日生中へ(10/4)

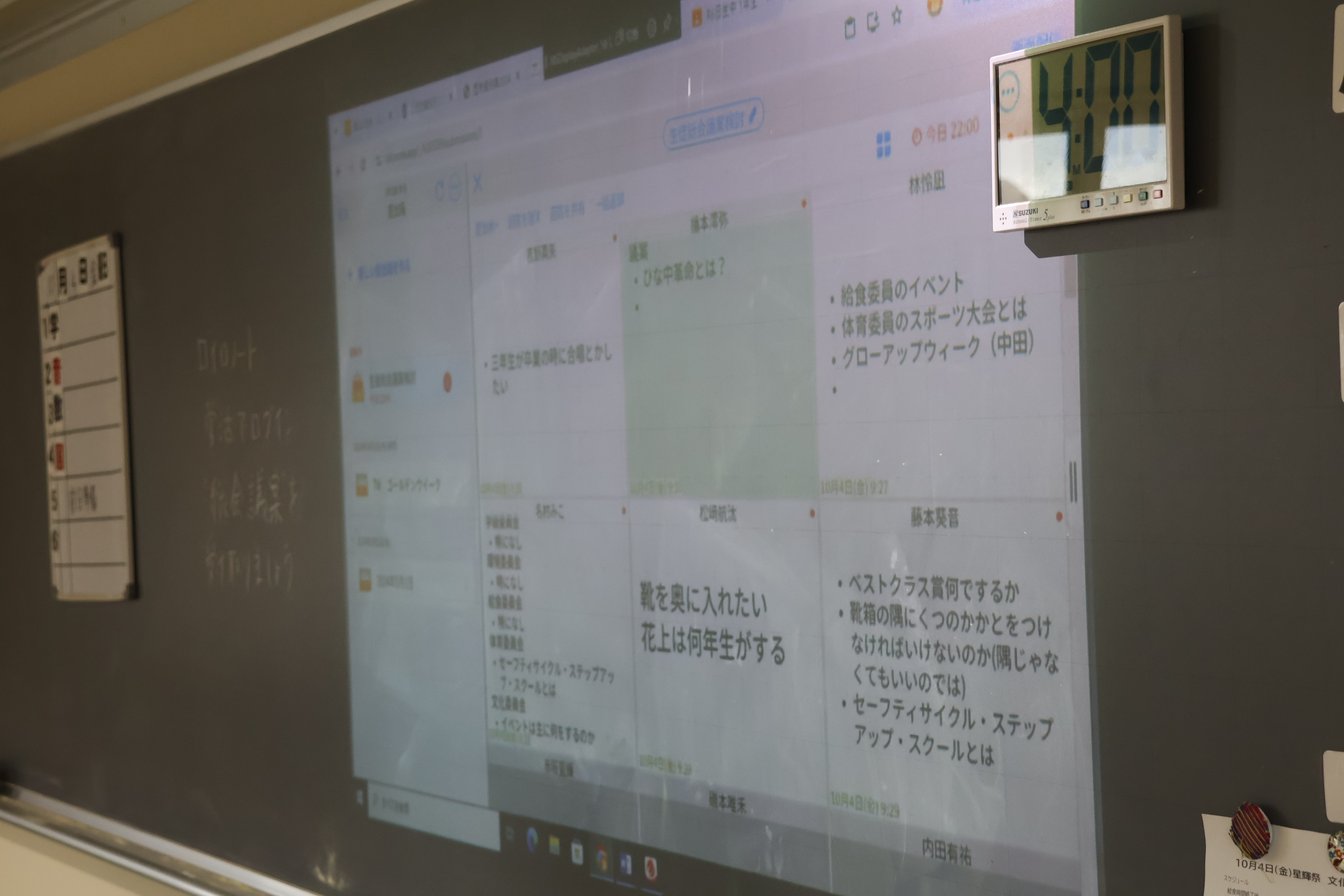
It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important. Conan Doyle
(小さなことが限りなく重要であるというのが、私の長年の原則だ。)
◎子どもの未来、明日の日生中へ。(10/3)
備前市PTA連合会代議員会が10月28日に開催されます。そのために、備前市PTA連合会の今後の活動に関する協議事項について、昨日、会長・副会長が集まって協議しました。また、本校PTA活動のさらなる活性化や、役員選出方法の改善やPTA組織自体の見直し・再編成にむけても意見交流をおこないました。
保護者(PTA会員)のみなさんでも、工夫・アイデア・ご意見などありましたら、PTA事務局(久次)まで、どしどしお寄せください。

◎ほっとほっとほっとスペース(10/2)

次回は16日(水)∈^0^∋
◎多くの人に支えられて
昨日も、ひなせっ子下校見守りをありがとうございました。(10/2)


中学校の教職員も登下校の安全指導をしています。(^_^)
〈好きだって思ったものを信じてる わたしの道はいつも明るい 武田穂佳〉(10/2)
パート練習パート練習パート練習。


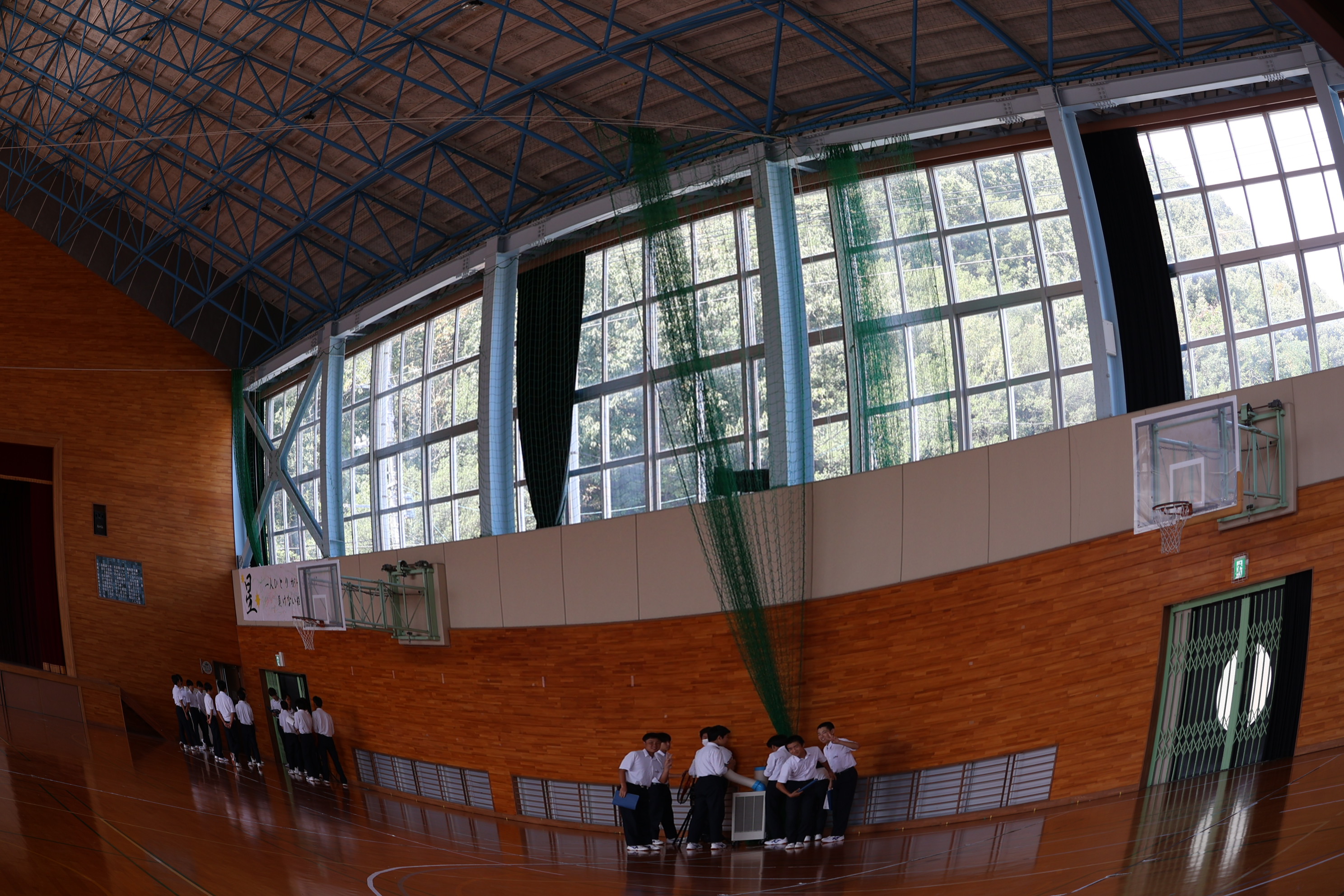
Everyone can rise above their circumstances and achieve success if they are dedicated to and passionate about what they do. Nelson Mandela
(人は誰でも、自分の仕事に専念し、情熱を注げば、状況を乗り越えて成功を収めることができるのです。)
◎10月 神無月 October
〈名もしれぬちひさき星をたづねゆきて住まばやと思う夜半もありけり 落合直文〉

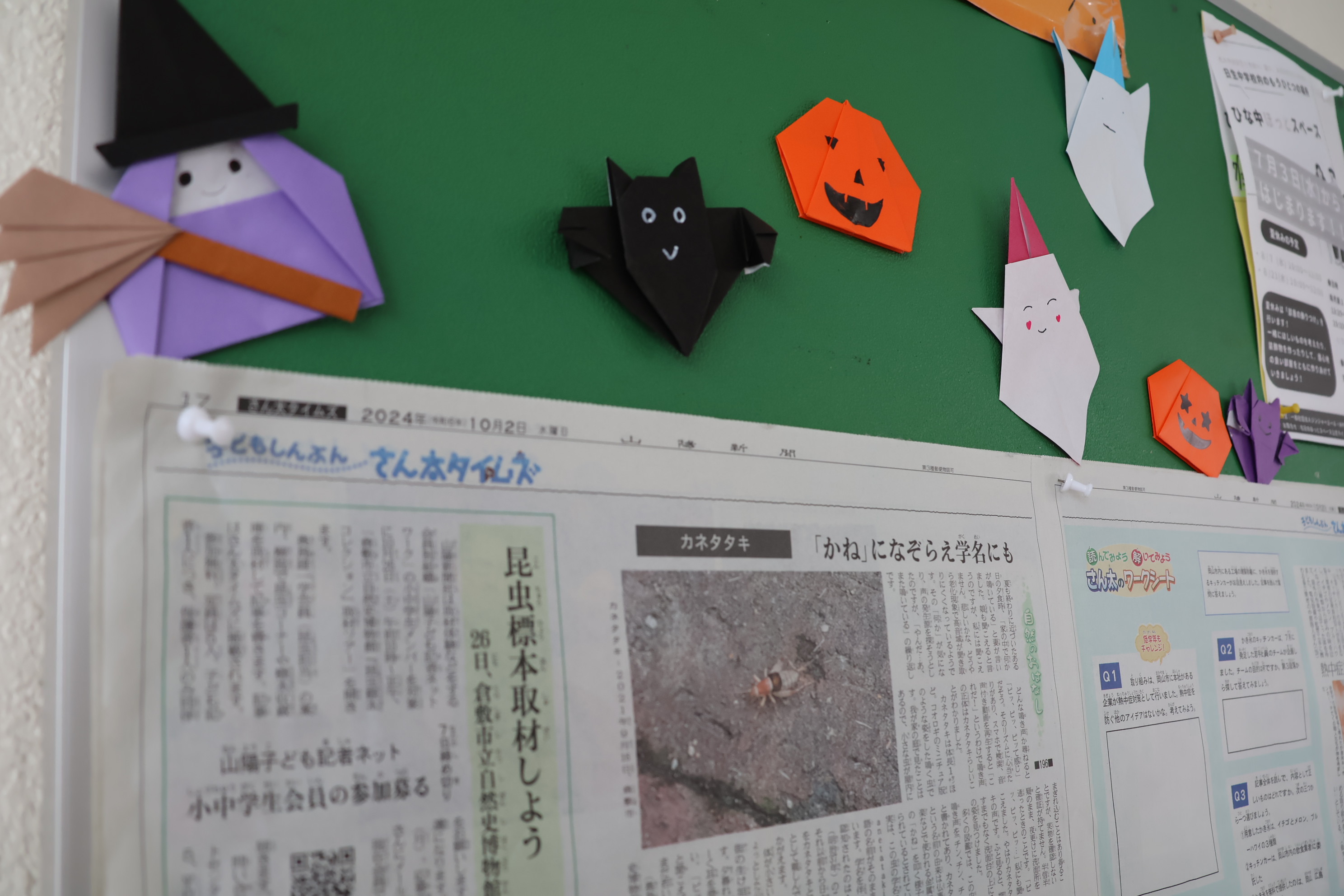
日本では、旧暦10月を『神無月(かんなづき、かみなしづき)』と呼び、新暦10月の別名としても用いています。10月は、出雲の出雲大社に全国の神様が集まって一年の事を話し合うため、出雲以外には神様が居なくなる月ということから神無月とするともいわれています。出雲では神在月といわれています。出雲へ行かず村や家に留まる田の神・家の神的性格を持つ留守神も存在し、すべての神が出雲に出向くわけではないとされているようです。
英語の月名 『October』は、これはラテン語で「第8の」という意味の「octo」に由来しています。実際の月の番号とずれているのは、紀元前46年まで使われていたローマ暦が3月起算なので、3月から数えて8番目という意味になります。「衣替え」は、10月1日を目安に夏服から冬服へ、6月1日を目安に冬服から夏服へと替える風習です。
衣替えは、平安時代に中国から伝わった習わしで、宮中行事として、年に2回、衣を替えるようになりました。当初は「更衣(こうい)」といいましたが、「更衣」という言葉が女官の役職名に用いられるようになったため、「衣更え(衣替え)」と呼ばれるようになりました。江戸時代になると着物の種類が増え、気候に合わせて年に4回の衣替えが武家社会で定められ、庶民にも広がっていきました。やがて明治時代に洋服が取り入れられると、役人や軍人などが制服を着るようになり、暦も新暦に変わったため、夏服と冬服を年に2回替えるようになりました。この衣替えの意識が学校や家庭にも浸透し、現在に至っています。
また、日本でも年々盛り上がり、仮装姿は秋の風物詩となっている10月31日のハロウィン(HeIIoween)は、11月1日の「諸聖人の日」「万聖節」(All Hallo)の前夜祭(All Hallo Eve)という意味で、紀元前5世紀頃にケルト人が行っていた祭に由来します。古代ケルトでは11月1日に暦がかわったので、10月31日は年の変わり目にあたり、旧い時と新しい時がうねりを起こし、闇と光、あの世とこの世が混ざり合い、先祖や親しい死者たちがこの世に戻ってくると信じられていました。そのため、10月31日は死者のことを思い、あの世から訪れた死者をもてなして供養する日として大切にされていました。それを怠ると霊たちは怒り邪悪なことを起こす、祖霊に便乗して悪い妖精、悪魔、魔女などがやってきて災いをもたらす、などと言われていたそうです。19世紀の後半、移民とともにアメリカに伝わったこの祭を子どもが大変怖がったため、子どもも楽しめる行事へと変化していきました。ハロウィンにやってくる災いをもたらす悪魔や魔女から身を守るために仮面をかぶったり、悪霊や魔女の恰好をして仲間にみせかけたりしたのが、仮装の始まりです。
◎街に出よう 生徒会・赤い羽根共同募金の取組(10/2)

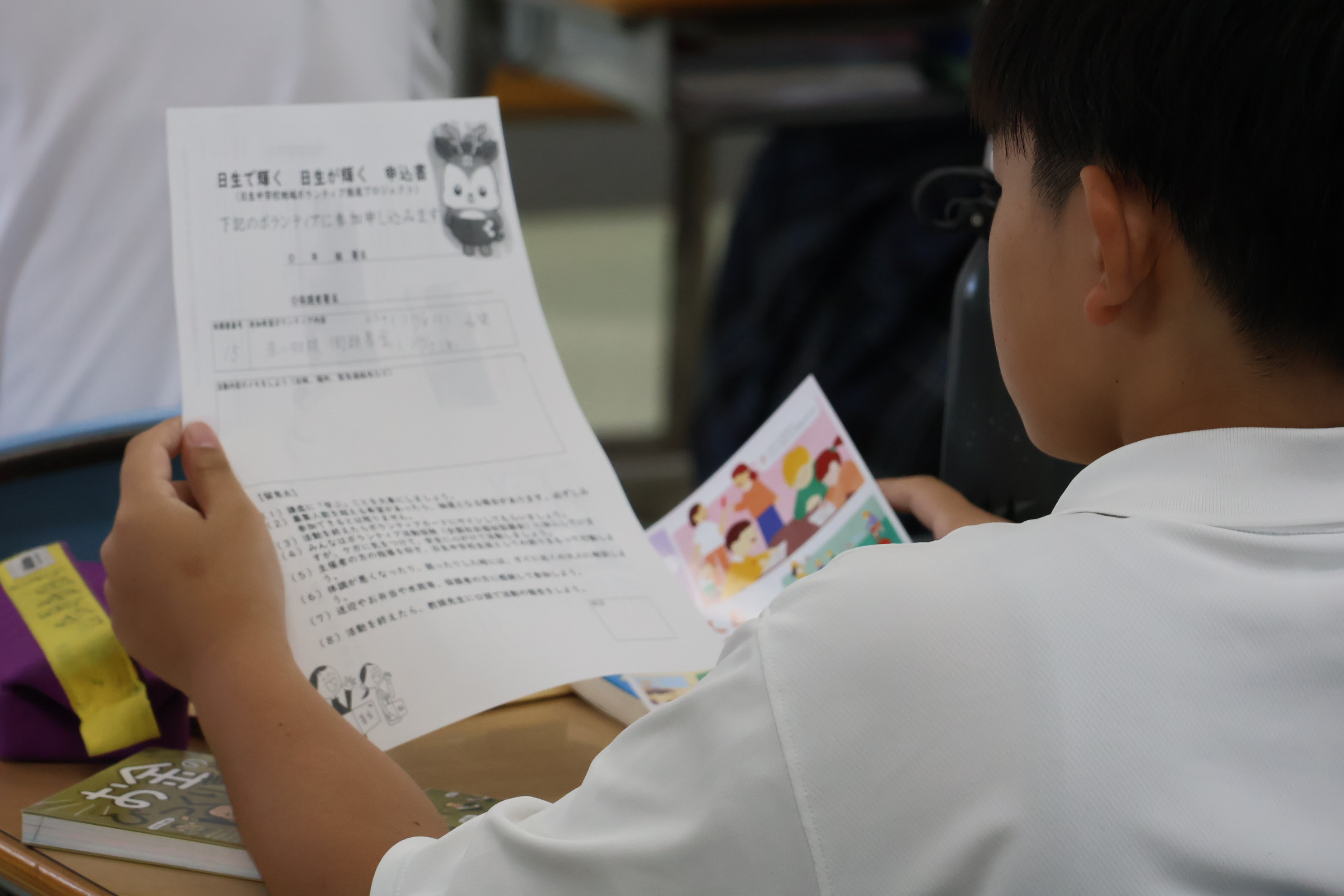
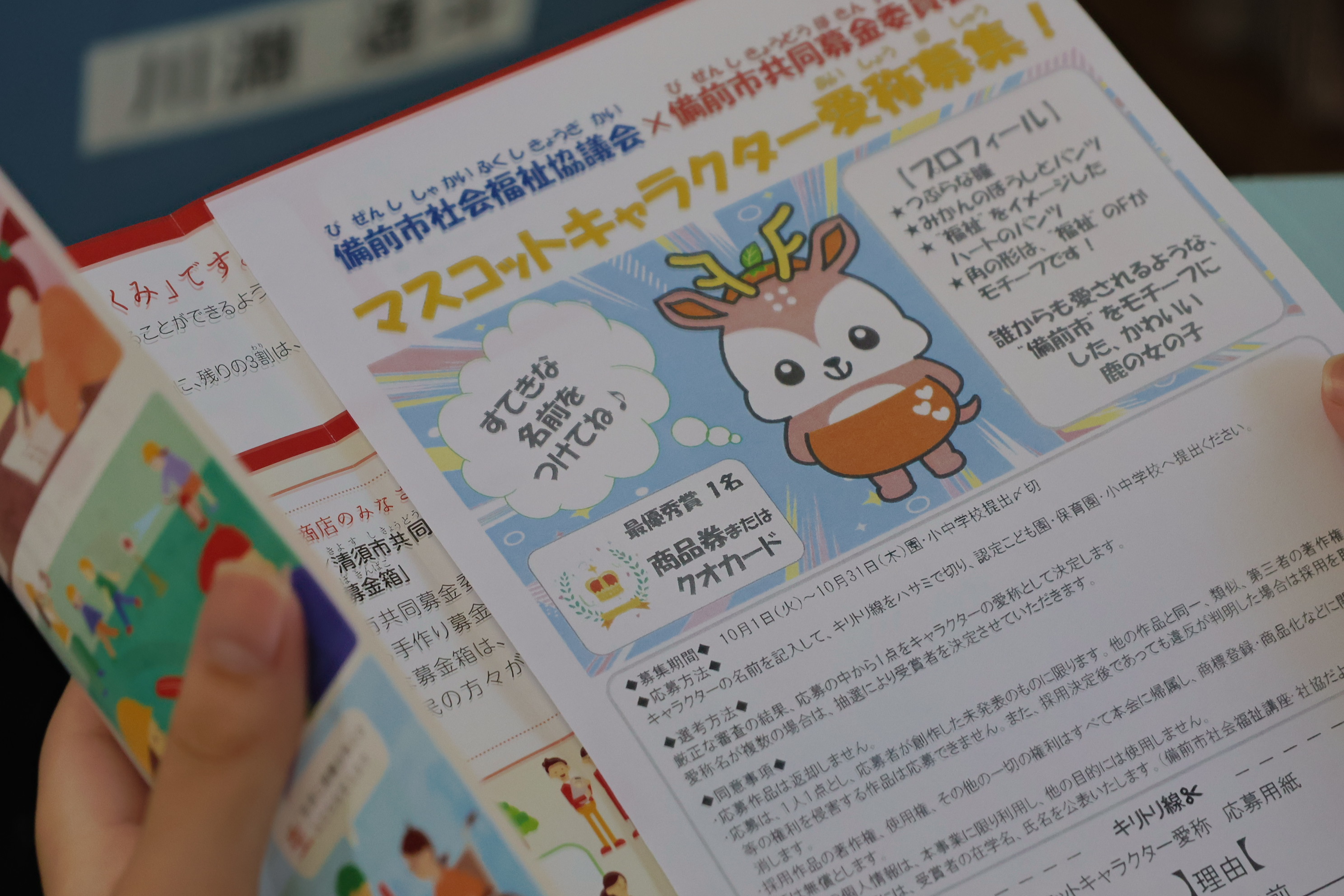
◎備前市科学研究発表会(10/1)
宮谷さんが「鏡が曇らないようにするためには」の研究で、三井さんが「牛乳を固めるものにして」の研究について日生中学校代表として会(伊里中学校会場)に参加しました。
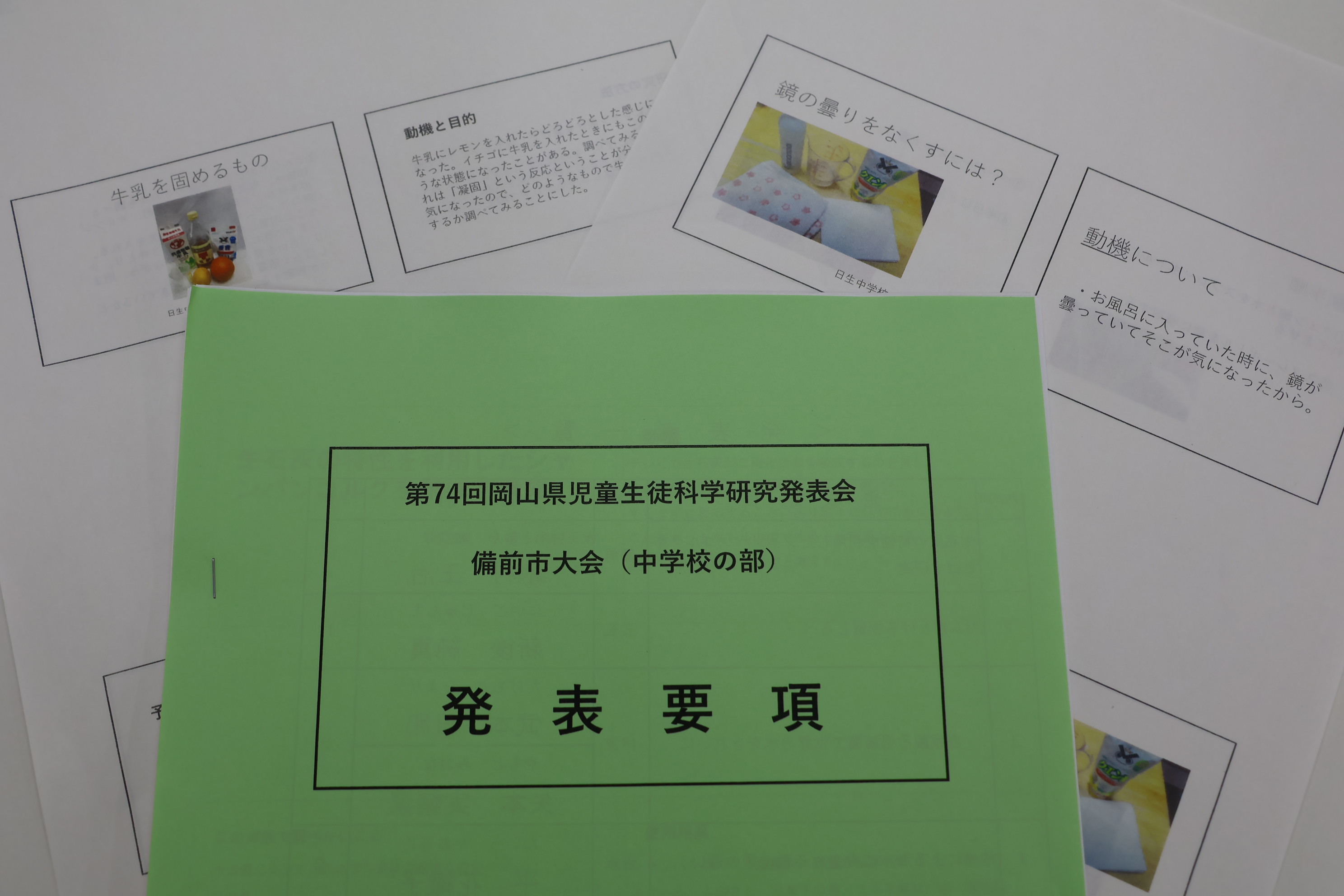
◎仲間と共にある学校♬(10/1)
COMING SOON 10月5日(土)
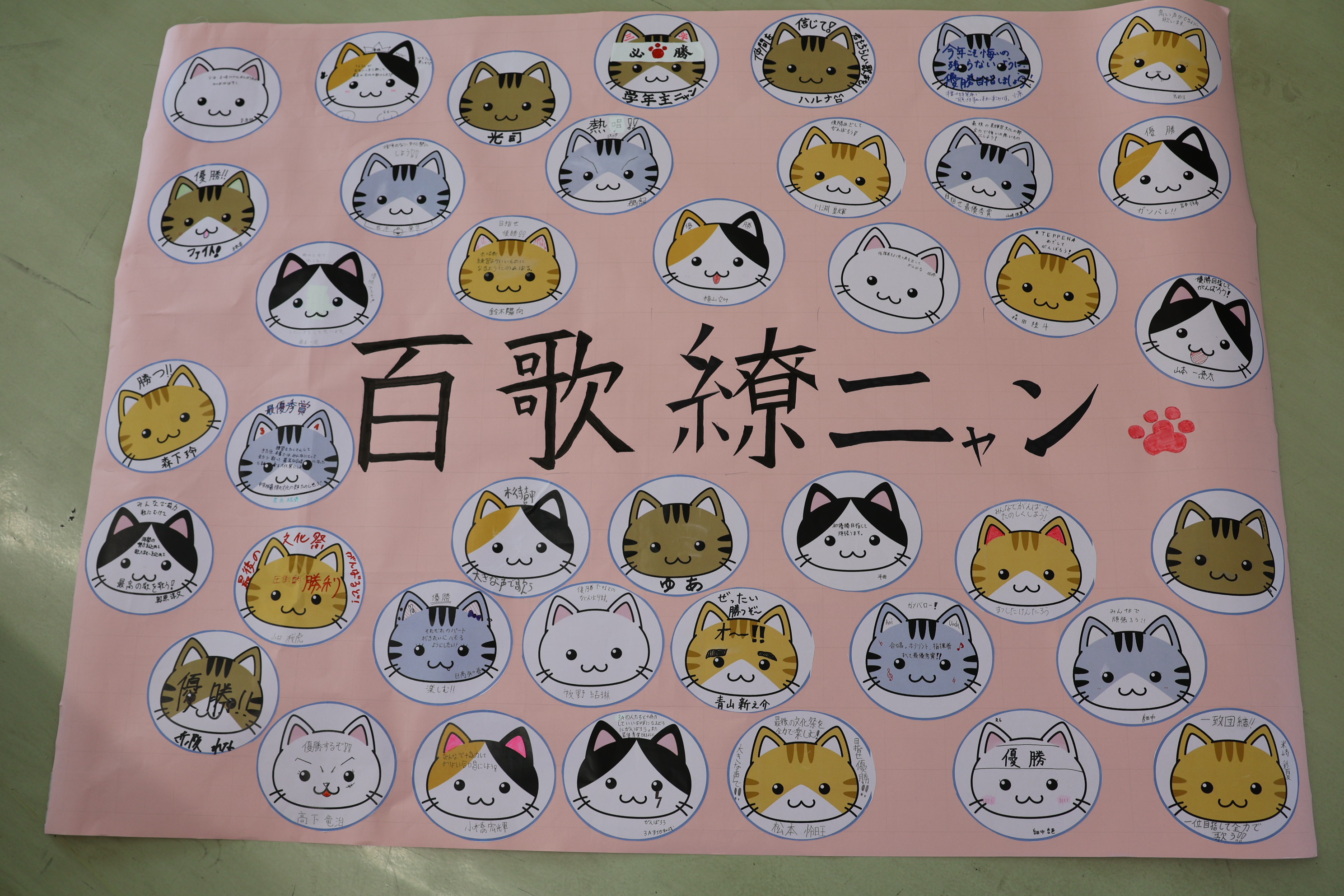

◎地域と共にある学校 日生中生徒会の赤い羽根共同募金の取組(10/1~)
今年度も(10/8、10/16)、パオーネでの街頭募金活動にも取り組みます。また、募金箱を職員室入口にも設置しています。
*赤い羽根共同募金とは・・・共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まりました。当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれています。
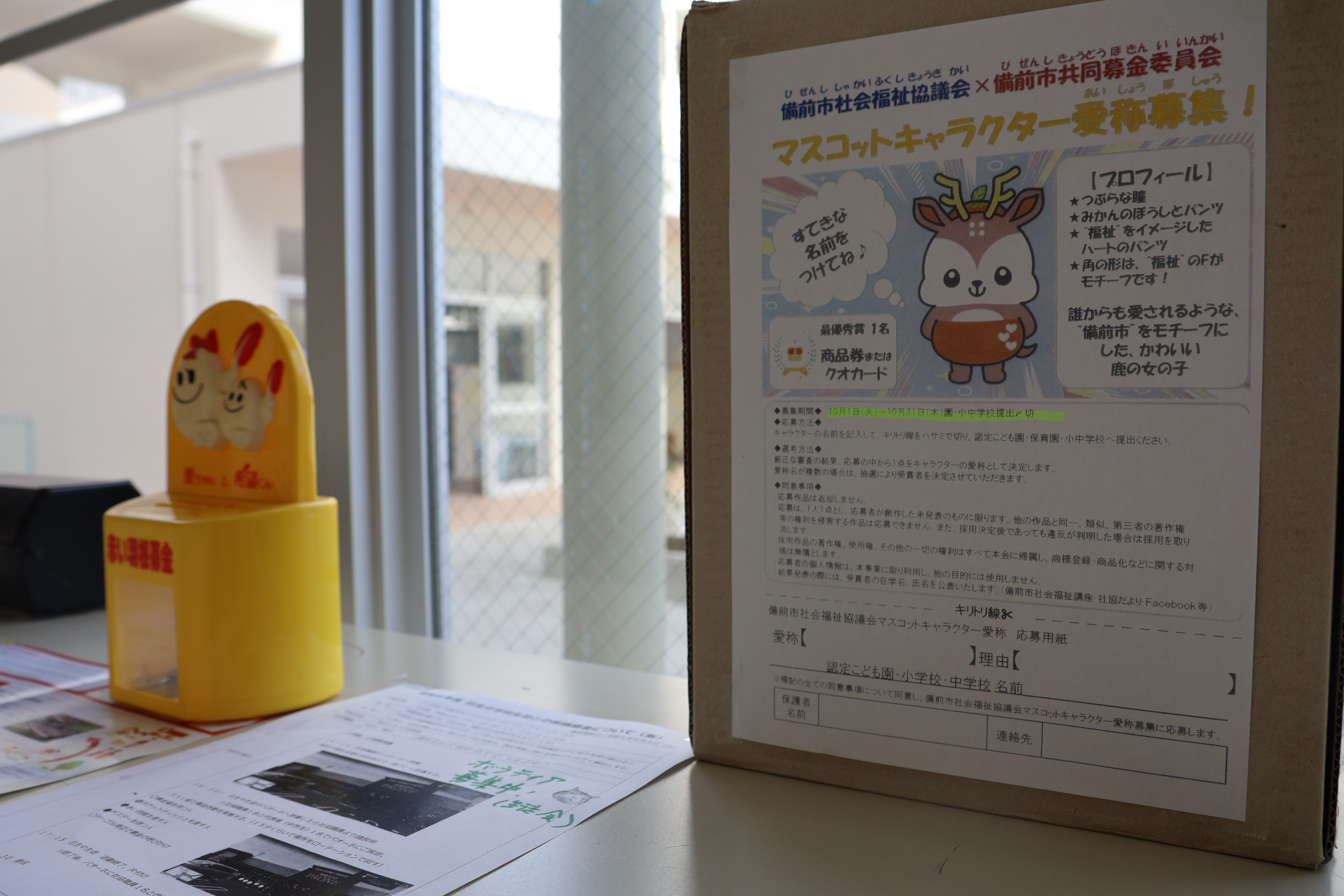

◎君は風に吹かれて 翻る帽子見上げ 長く短い旅をゆく 遠い日の面影 君が望むなら それは強く応えてくれるのだ 今は全てに恐れるな 痛みを知る ただ一人であれ(「M八七」 米津玄師)(9/30生徒会・専門委員会認証式)



◎友 進むべき道の先に どんなことが待っていても この歌を思い出して 僕らを繋ぐこの歌を♩(9/30、7:42)
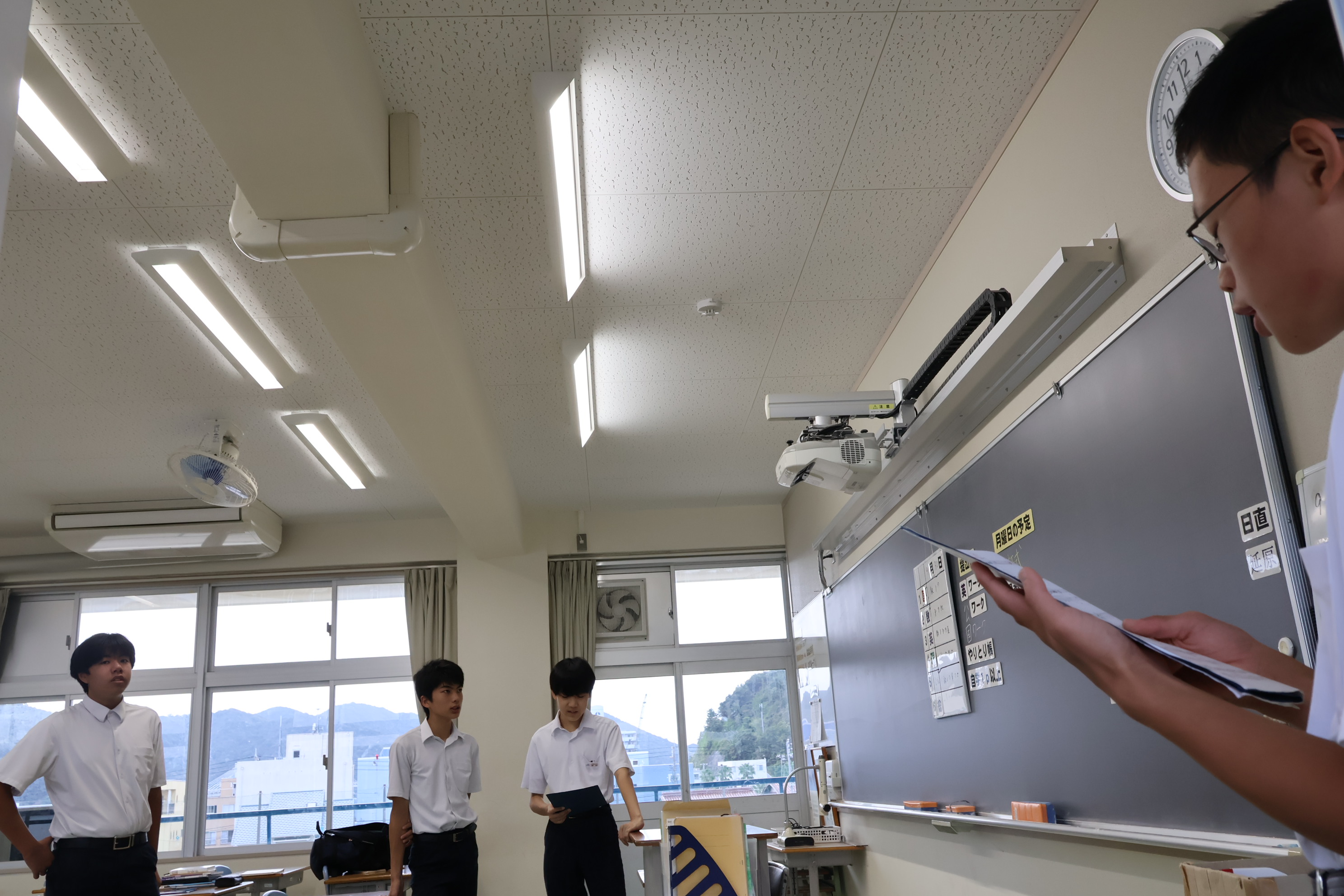

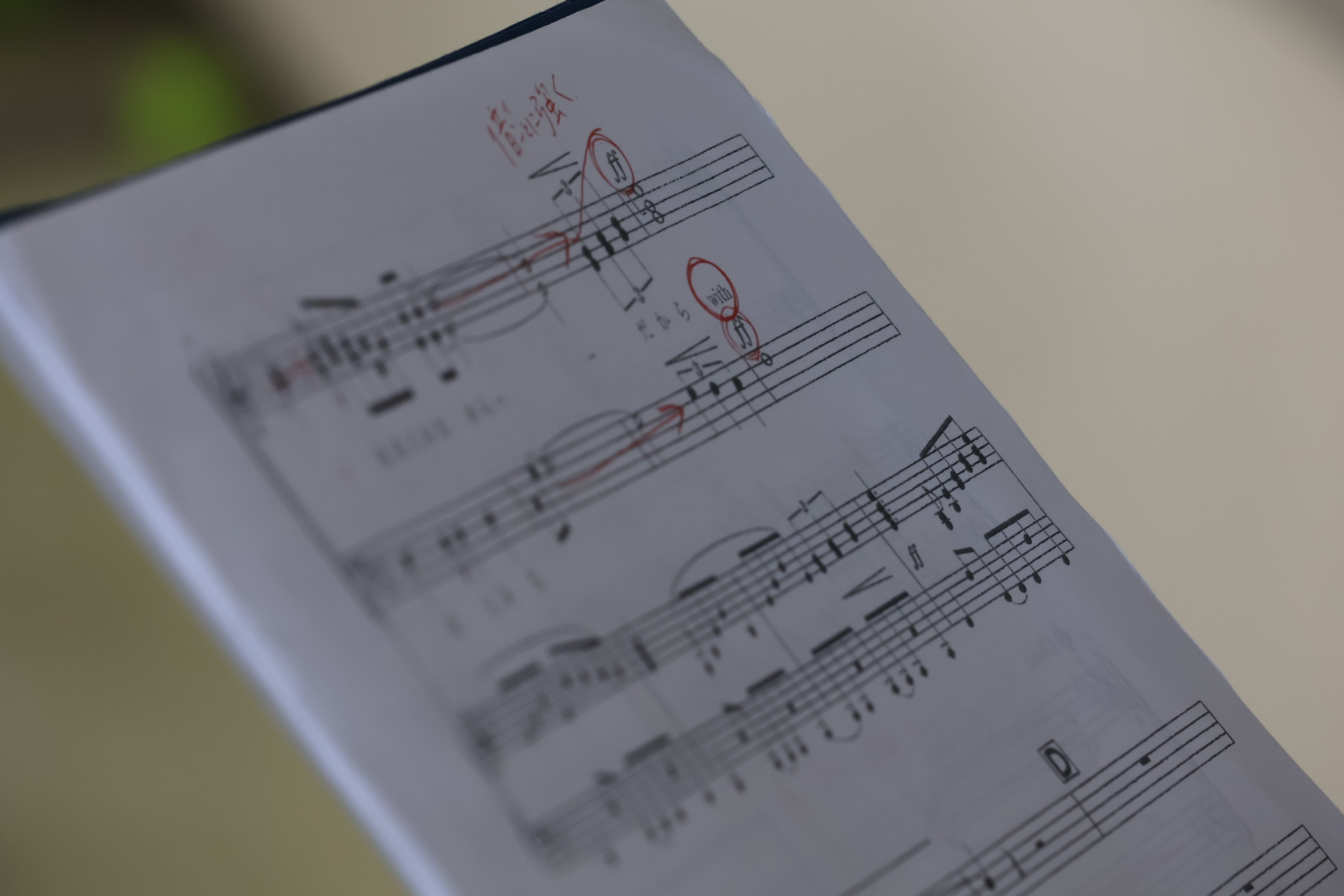
◎何したって自分は自分―新しくいこう
やりたいことをやりたいように―新しくいこう(9/27・後期学級役員選出)
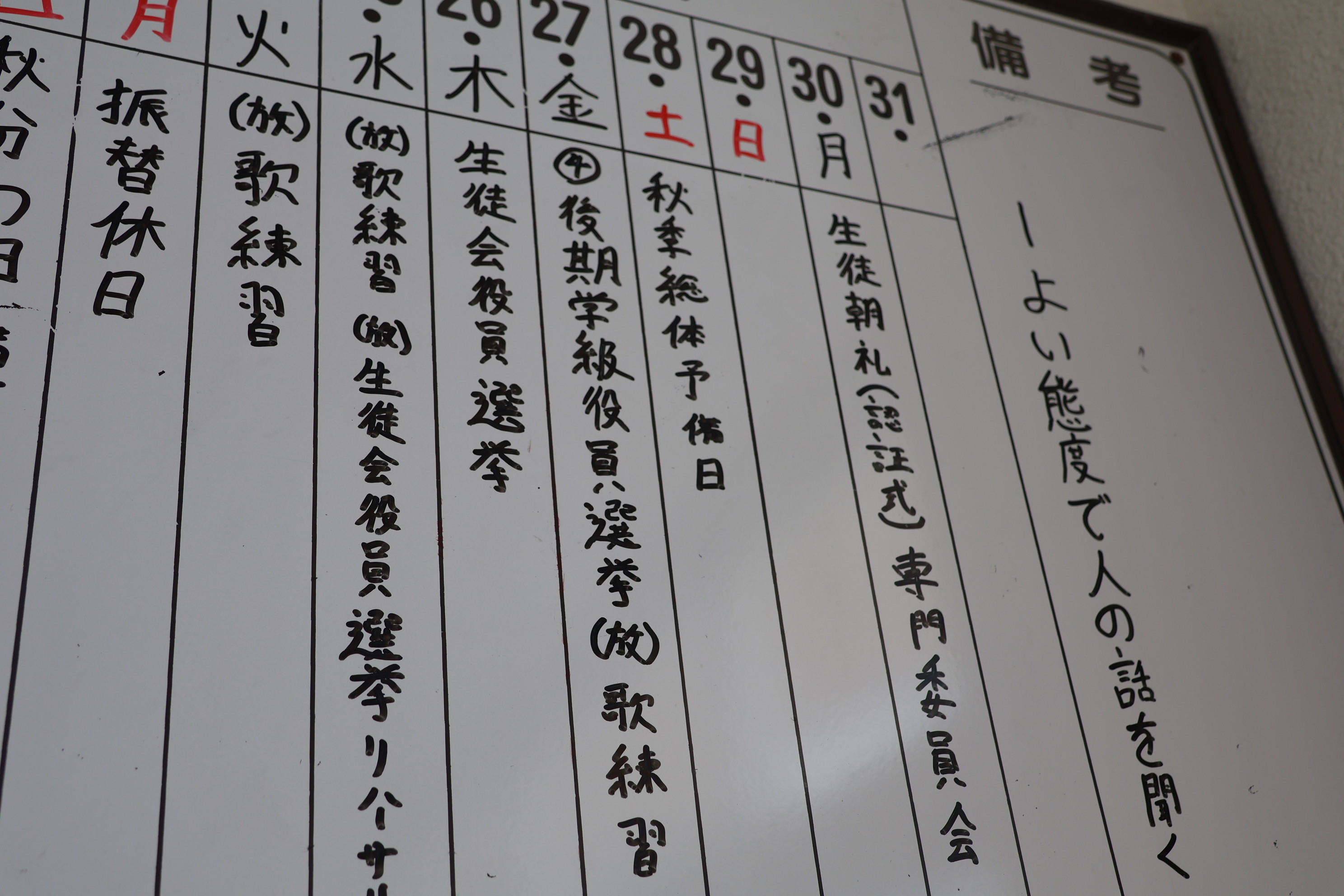
◎起こせ 沸かせ 轟け 動かせ 日生中✨
生徒会役員選挙・開票。信任・そして今からここから。(9/27)



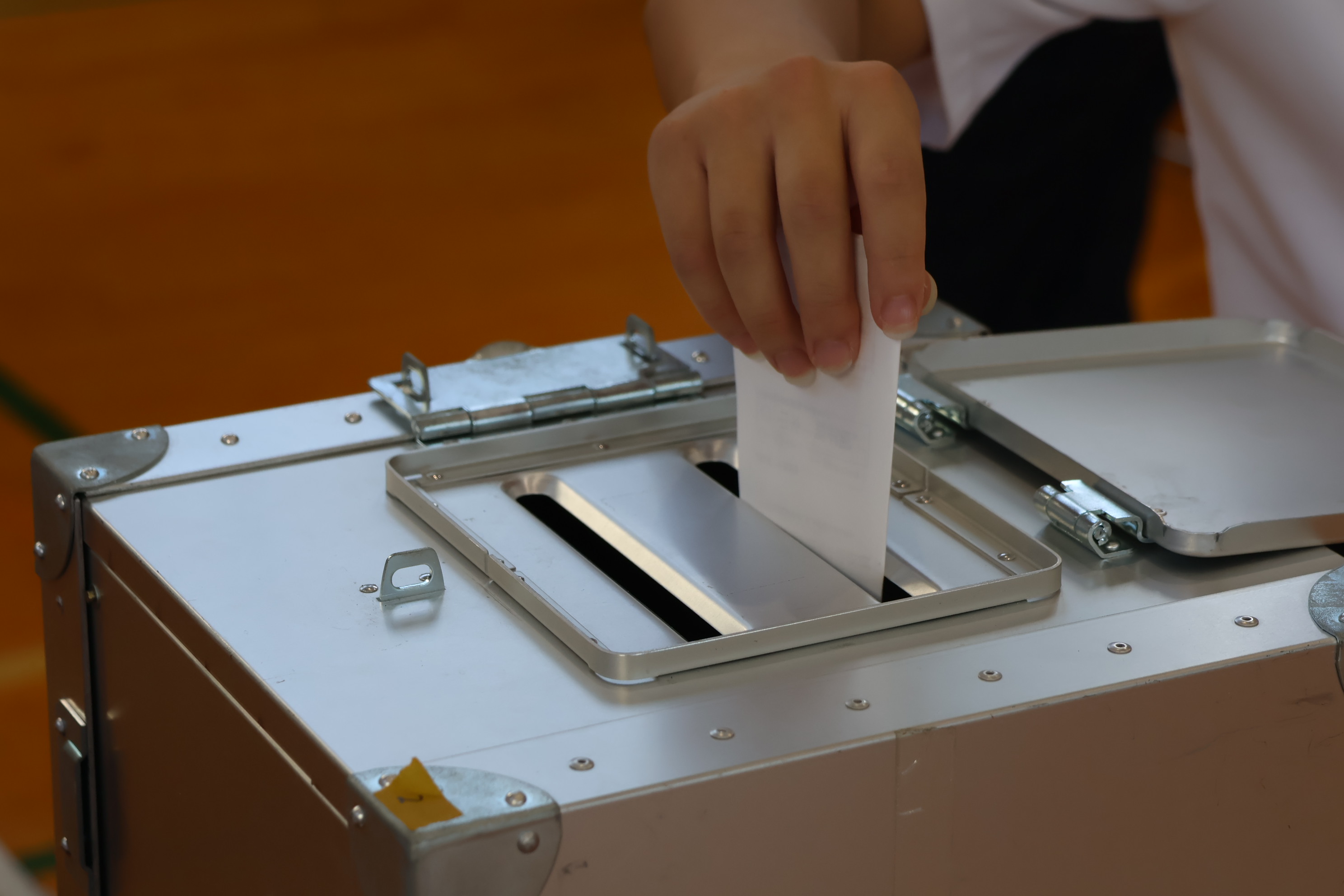

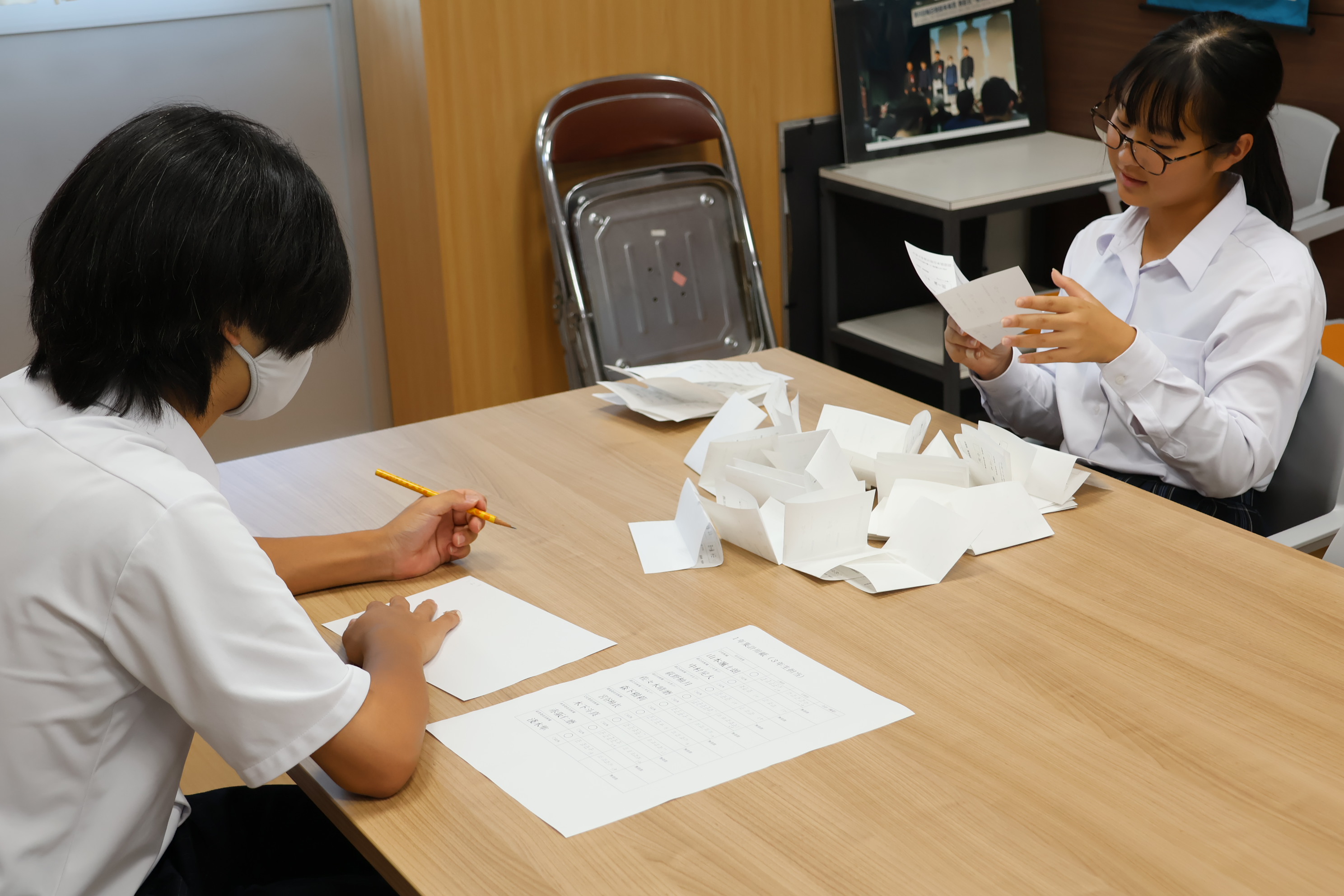


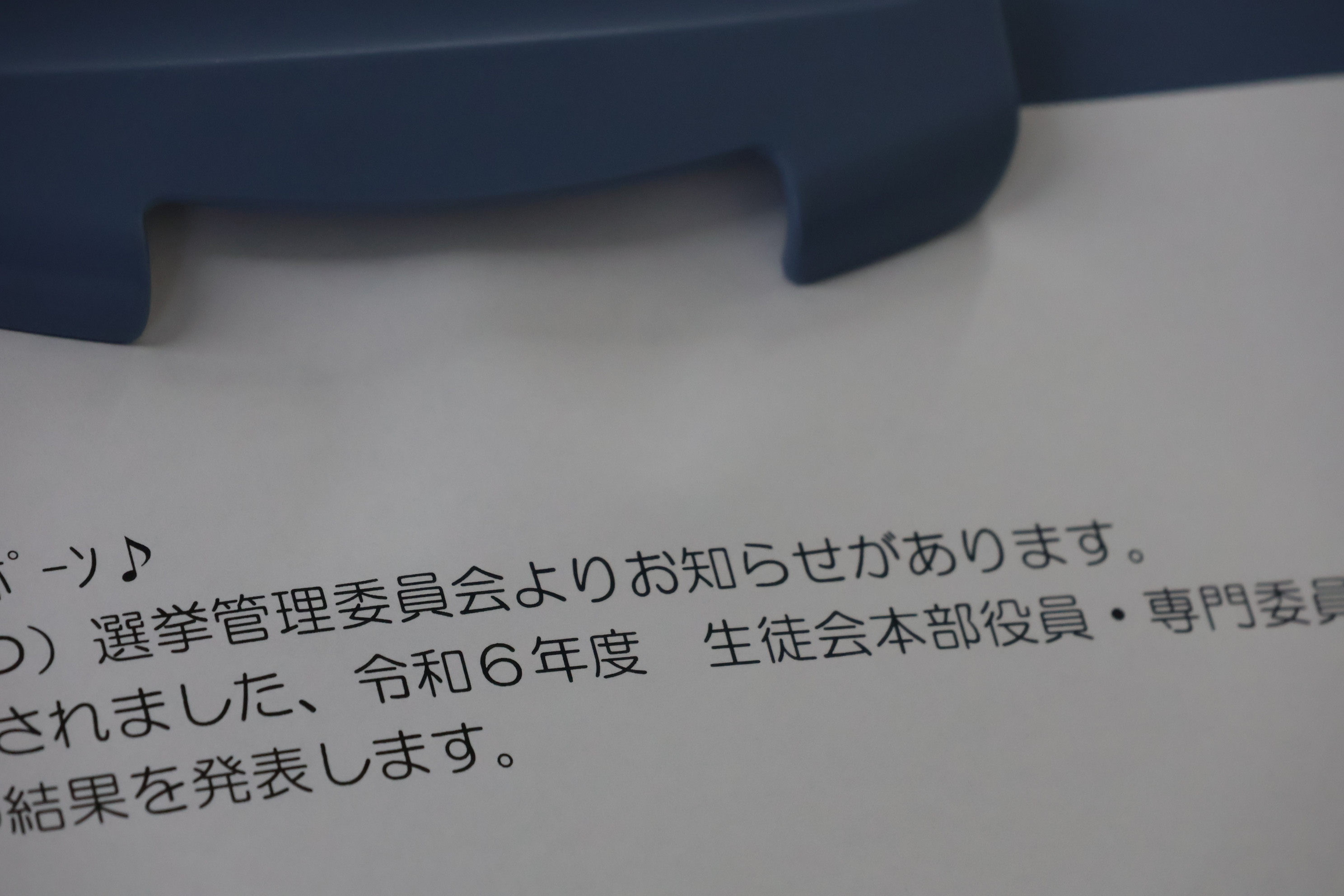
Happiness does not come from without‚ it comes from within. Helen Keller
幸福は外から来るのではなく、内から来るものだ。
◎日生中最前線 生徒会役員選挙(9/26)
日本国憲法前文:日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

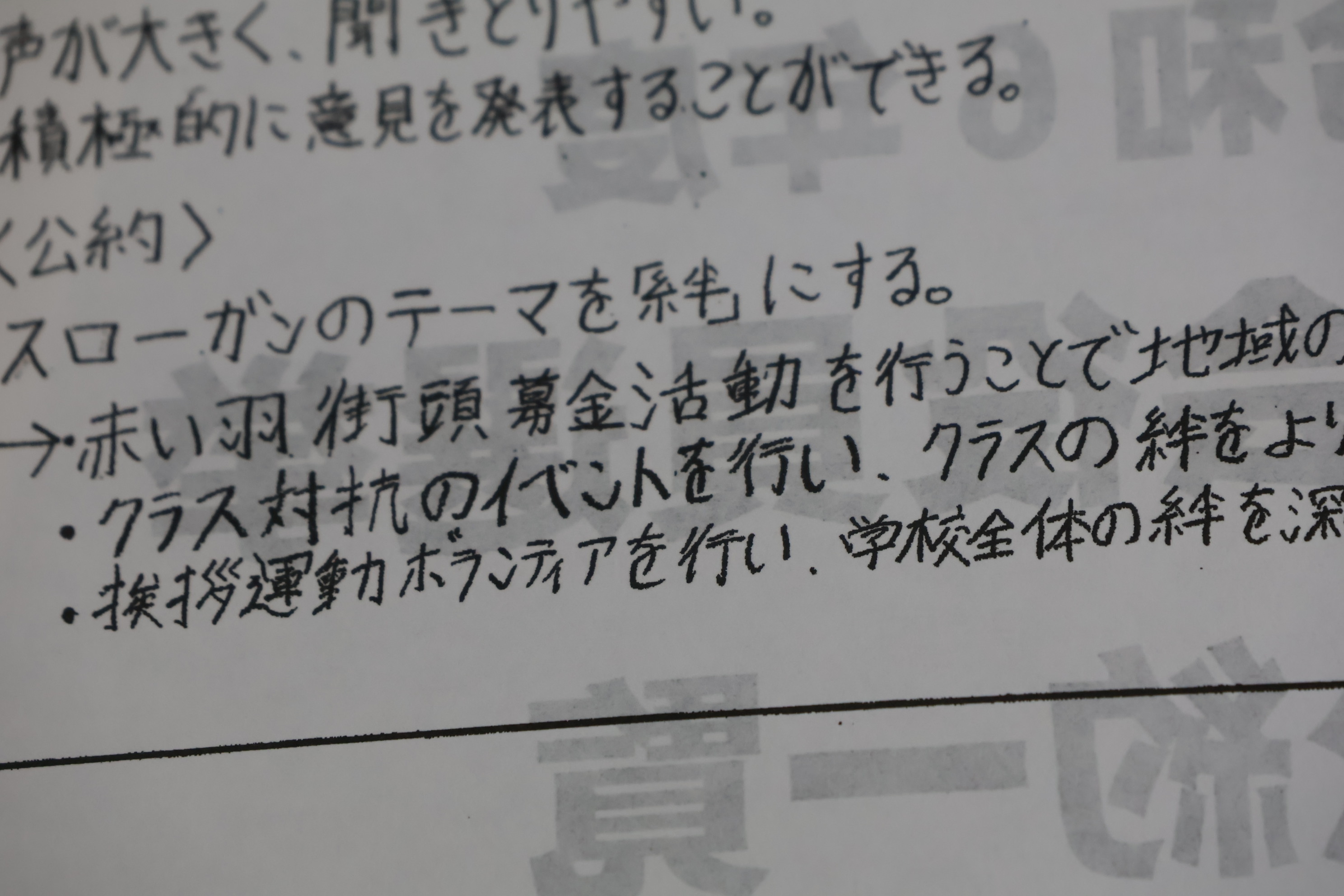
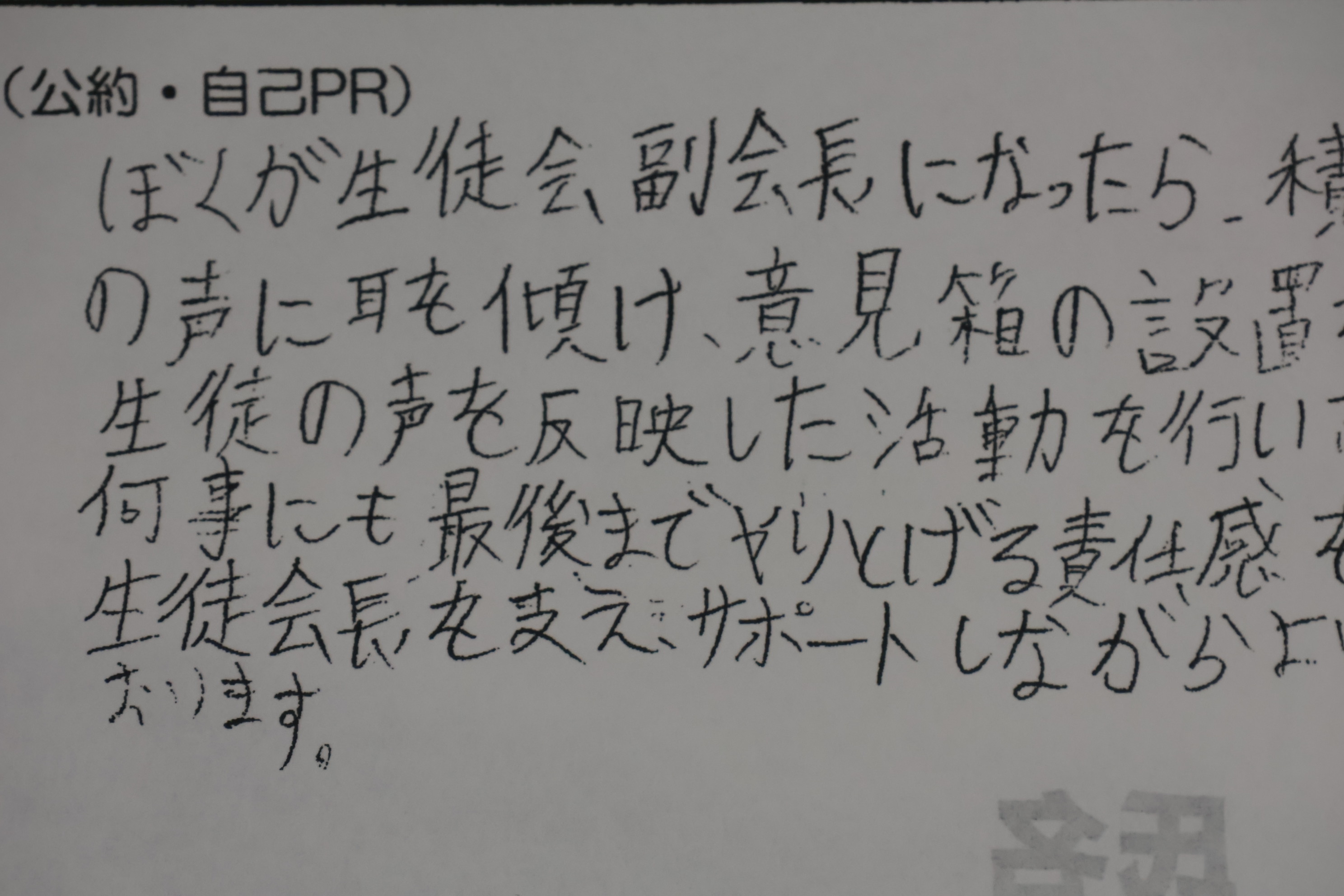
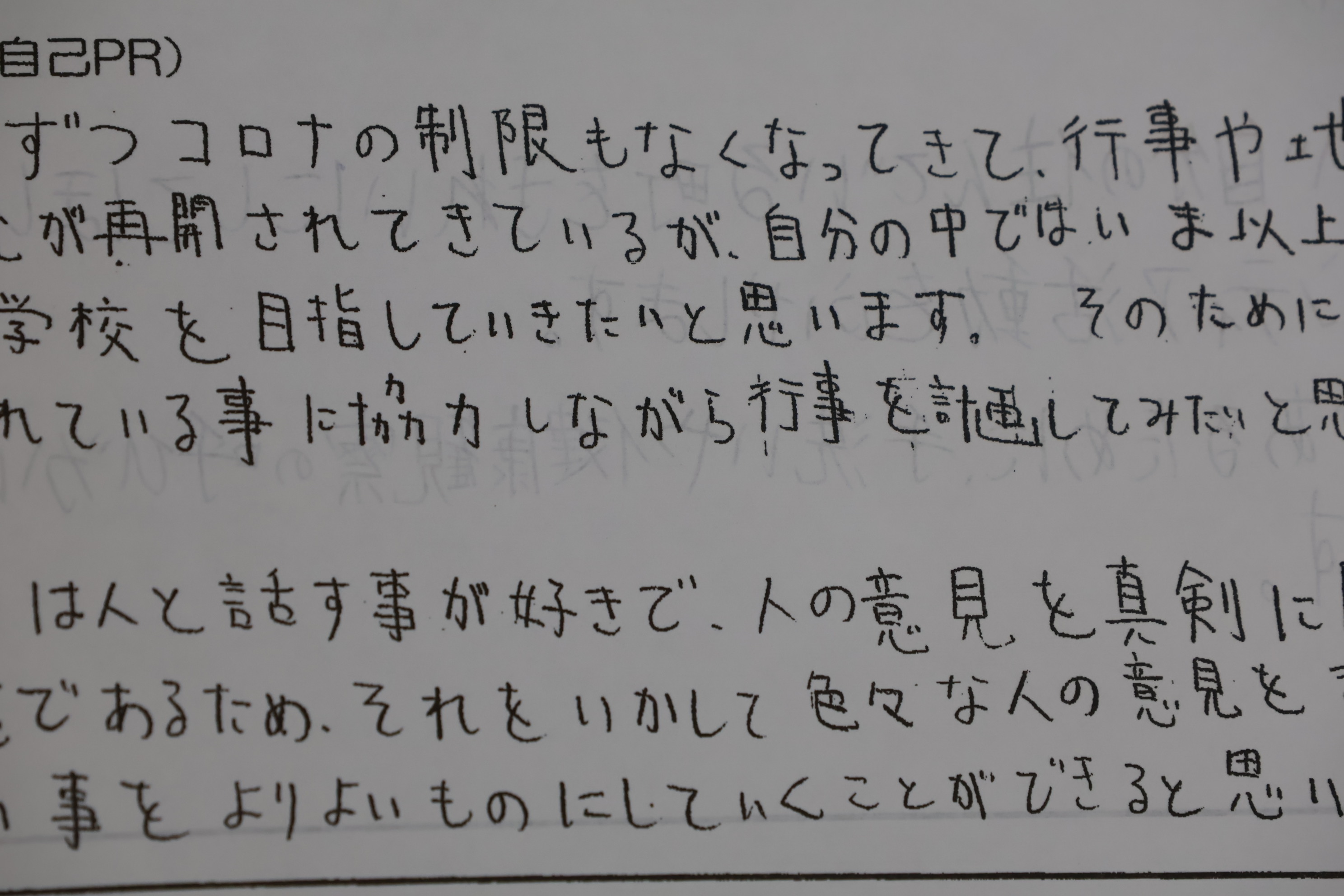
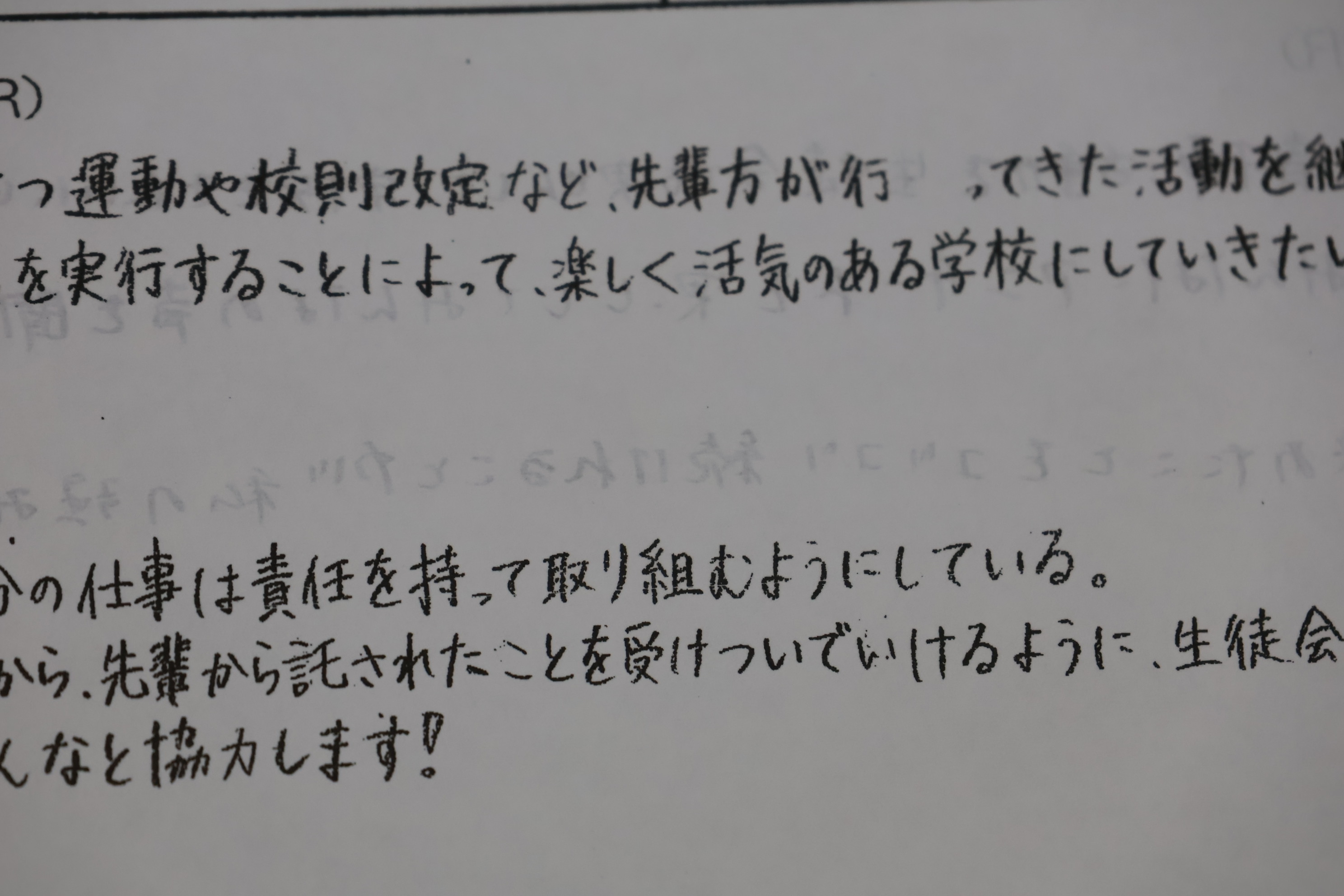

先日はある政党の代表選、明日はある政党の総裁選ですが。
◎安全は自分で手に入れる
~自転車安全点検(9/25)
日生地区の自転車販売店と備前市危機管理課の方々で自転車点検を行いました。ブレーキ、ベル、チェーン、ライト、タイヤの溝や空気圧など丁寧に確認していいただきました。タイヤに空気が入っていない自転車が特に多かったです。整備不良の自転車にはカードをつけていただいたので、早急に直して、安全に登校できるように整備してほしいと思います。早朝から、点検していただいた川崎商会さん、森下商会さん、本当にありがとうございました。
また、TSマーク(保険)の保証期間は1年間です。2,3年生の生徒の自転車は保証期間が切れています。自転車の任意保険の義務化の法的整備もあります。各ご家庭でご確認ください。
追記:交通安全週間中、中学校でも教職員が分担し、街頭での交通指導を行っています。保護者の方々も、生徒への交通安全の声かけをお願いします。





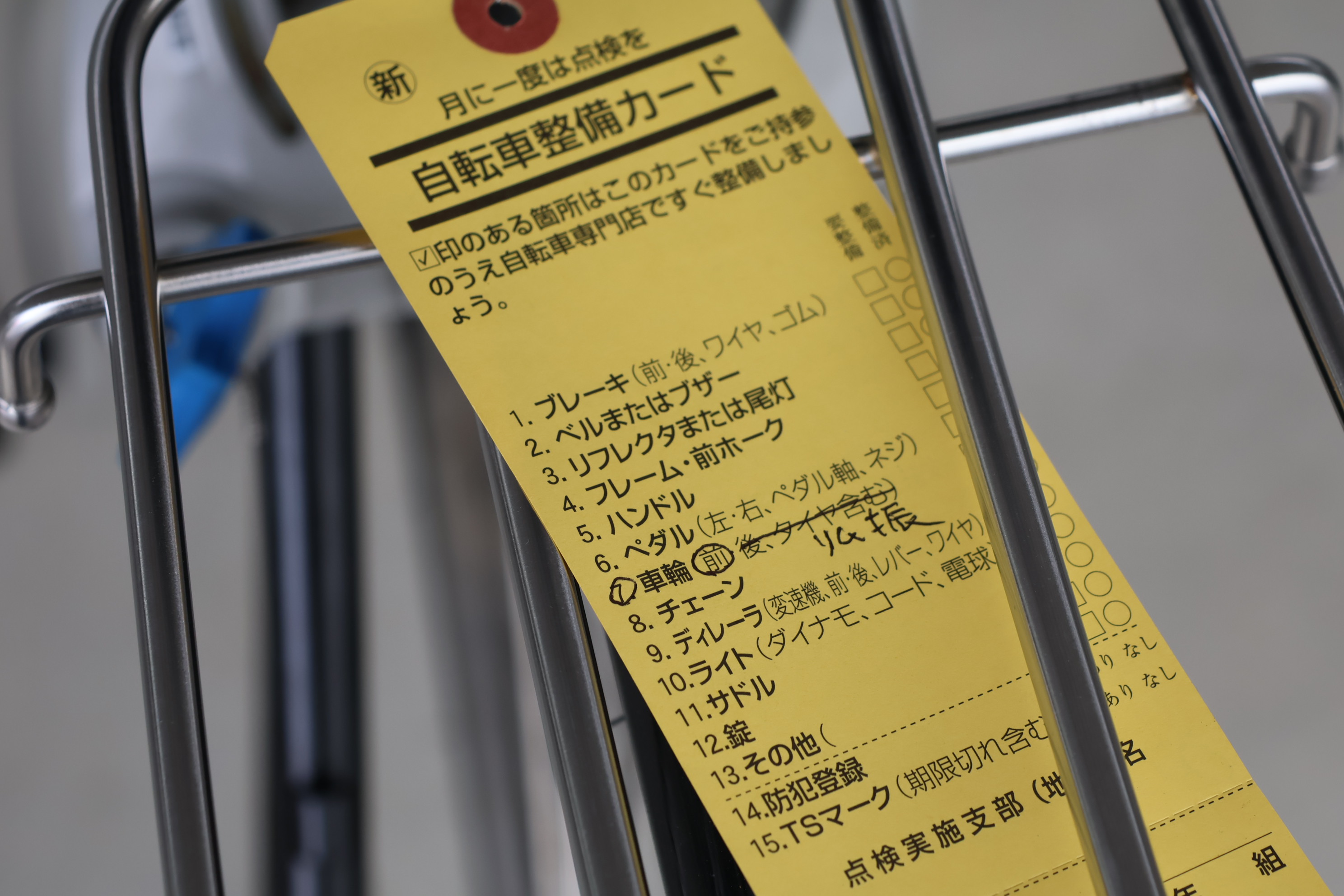
◎声が歌になるとき、そこにクラスがきっとある(9/25)
今日も放課後の練習に励みます。
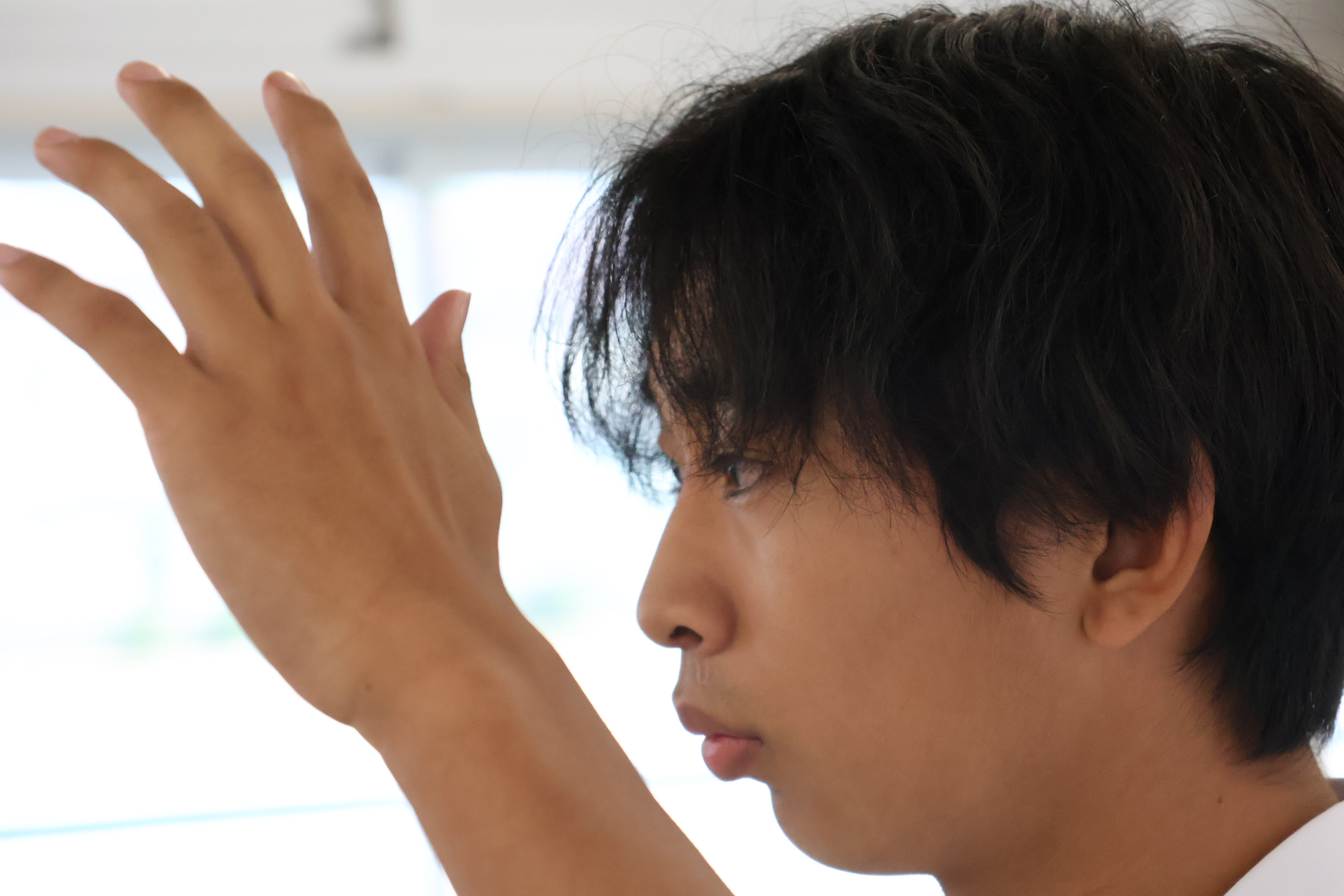
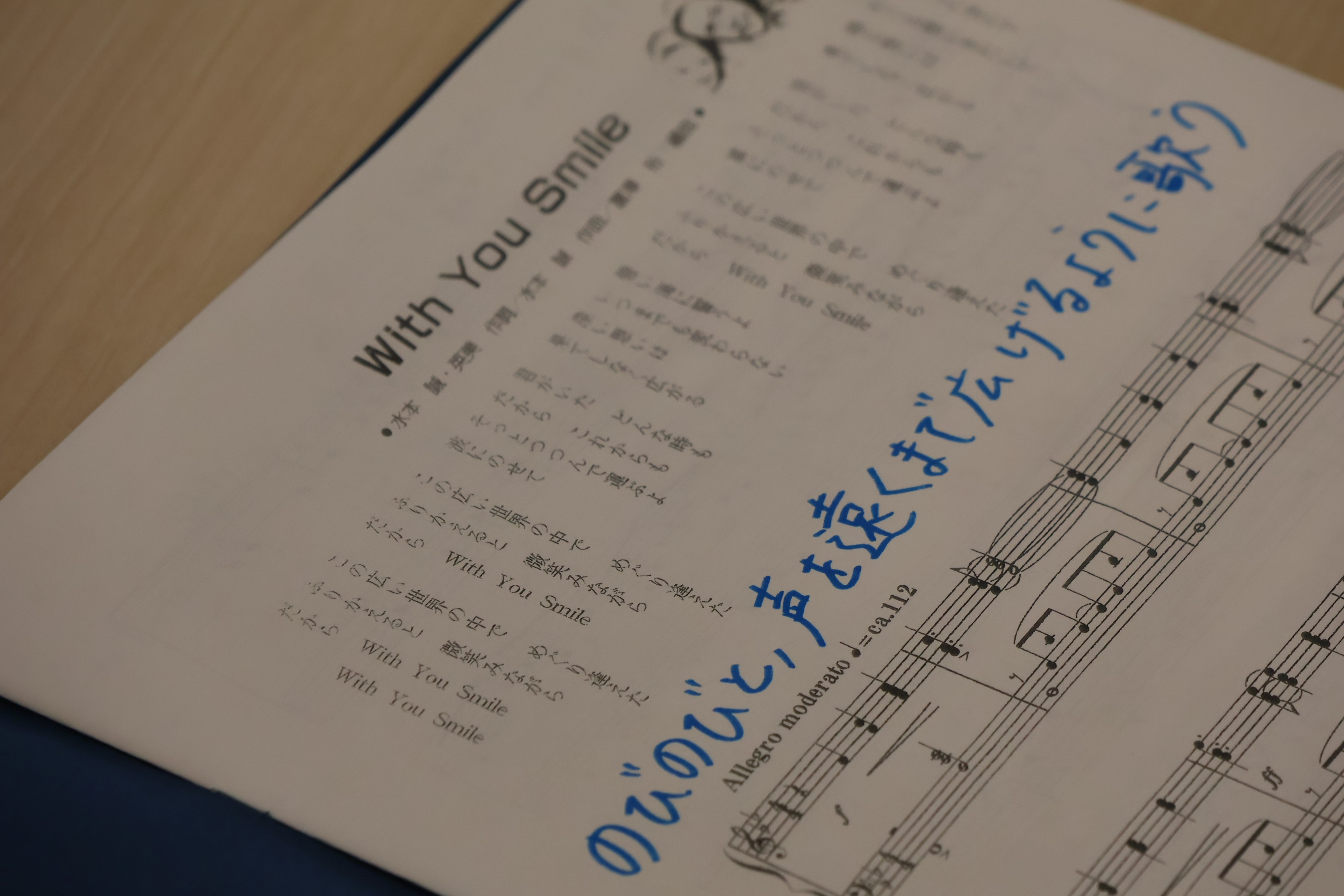

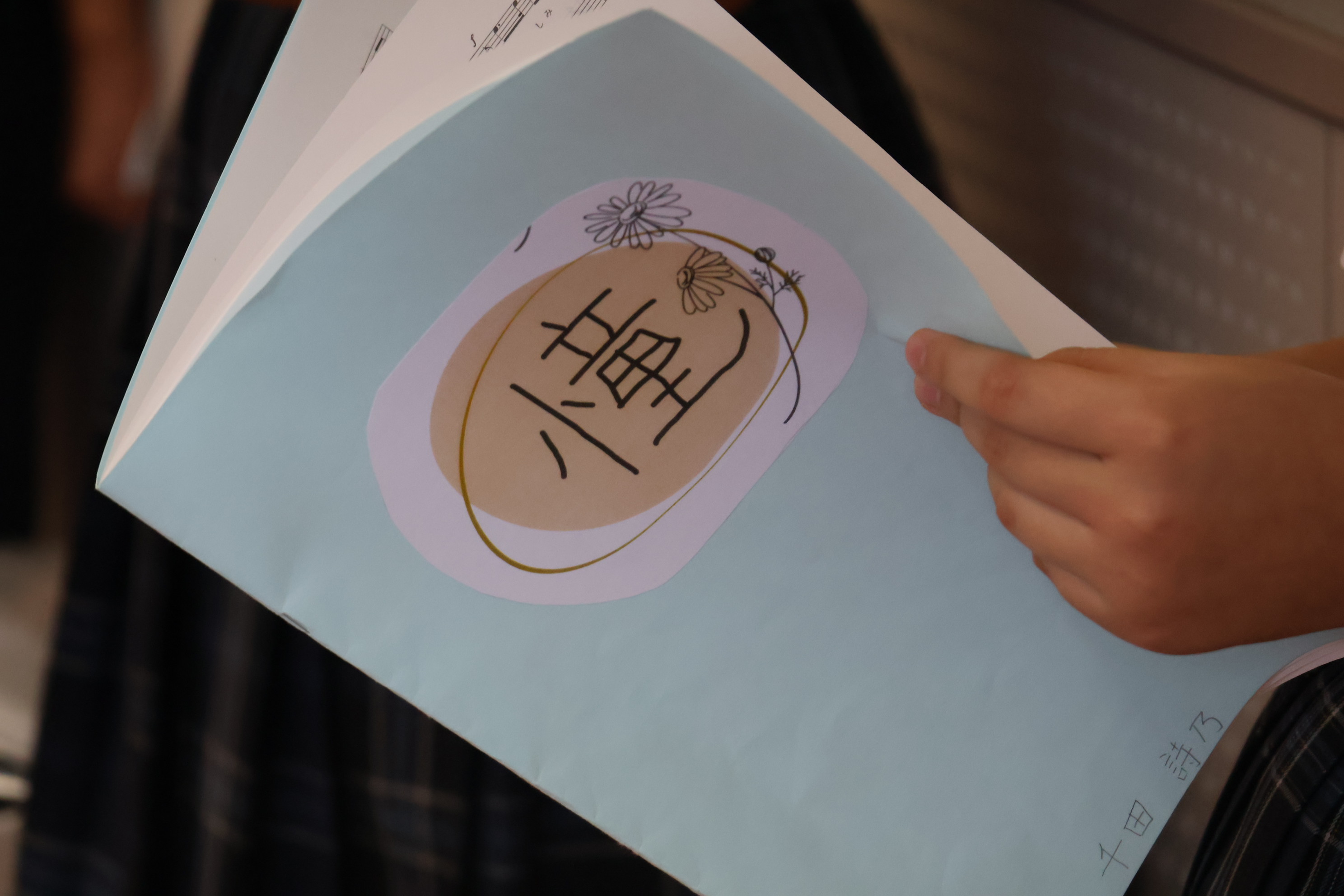

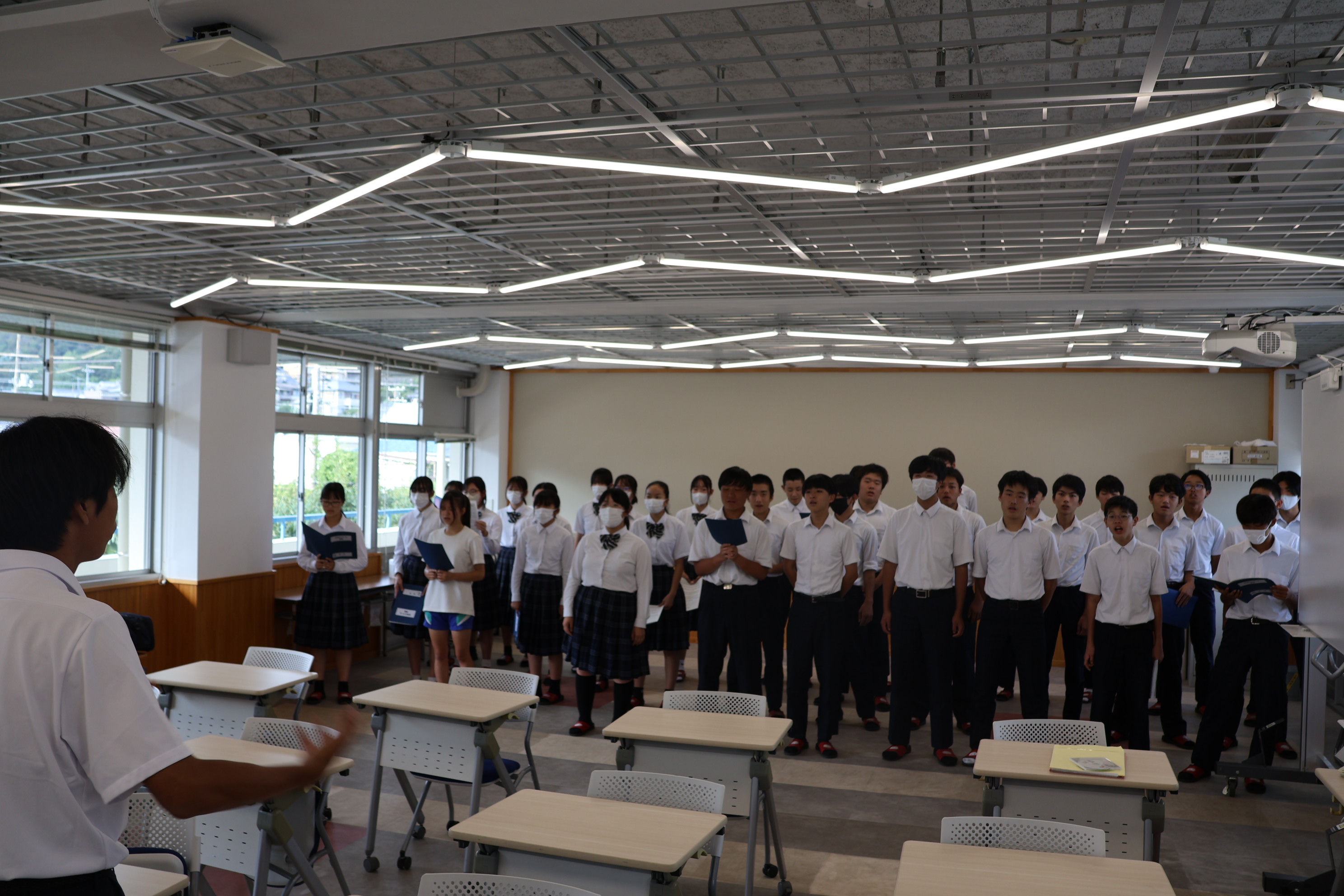
◎だから、一生懸命(9/25)
~ひな中の授業~

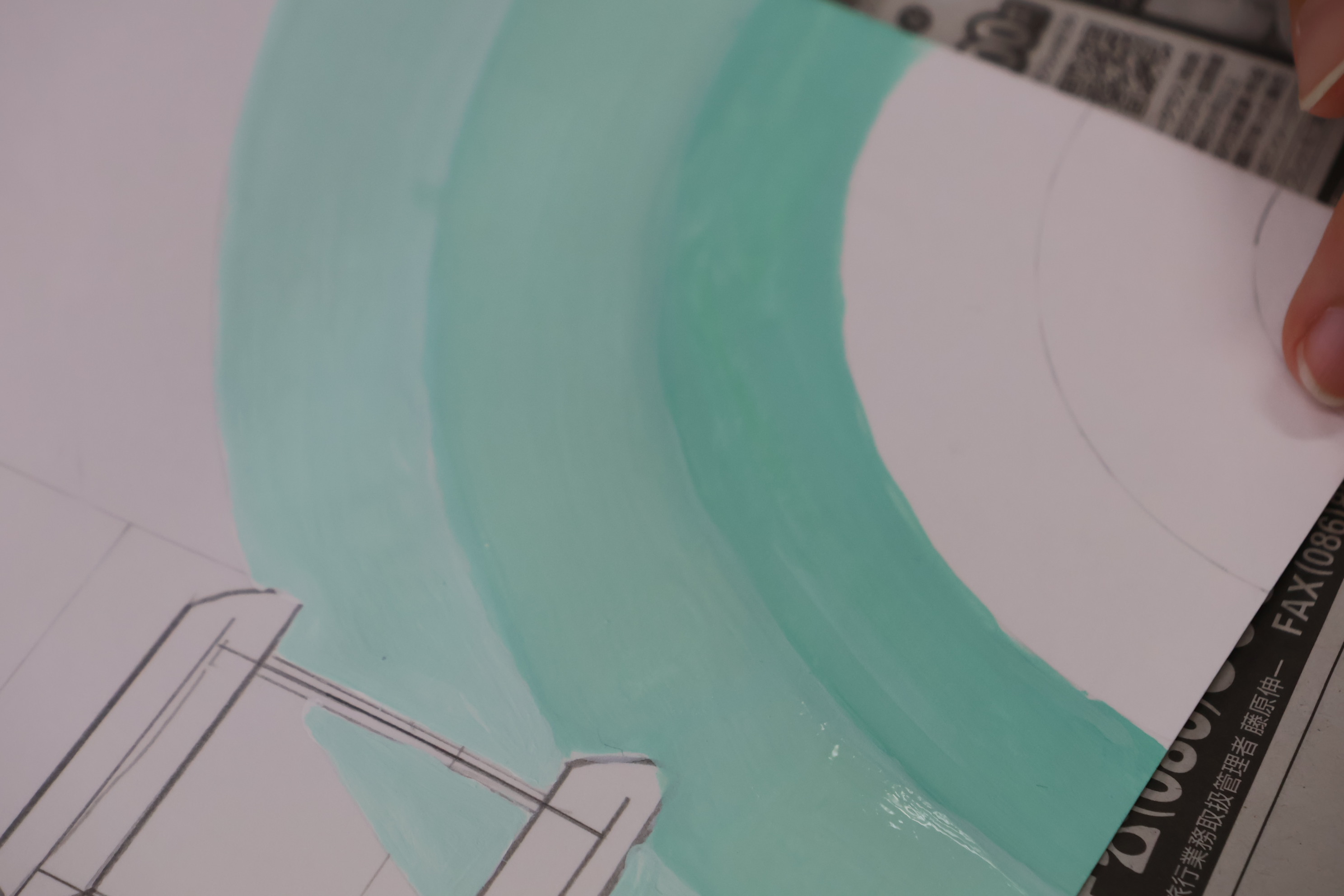

◎私たちの学び舎・私たちの確かな日々を。
多くの人に支えられて~
「ガチャッ」とドアの建て付けを修繕していただきました。ありがとうございました。

◎大切にしたい仲間・毎日・生活(9/24:今日は月曜日)


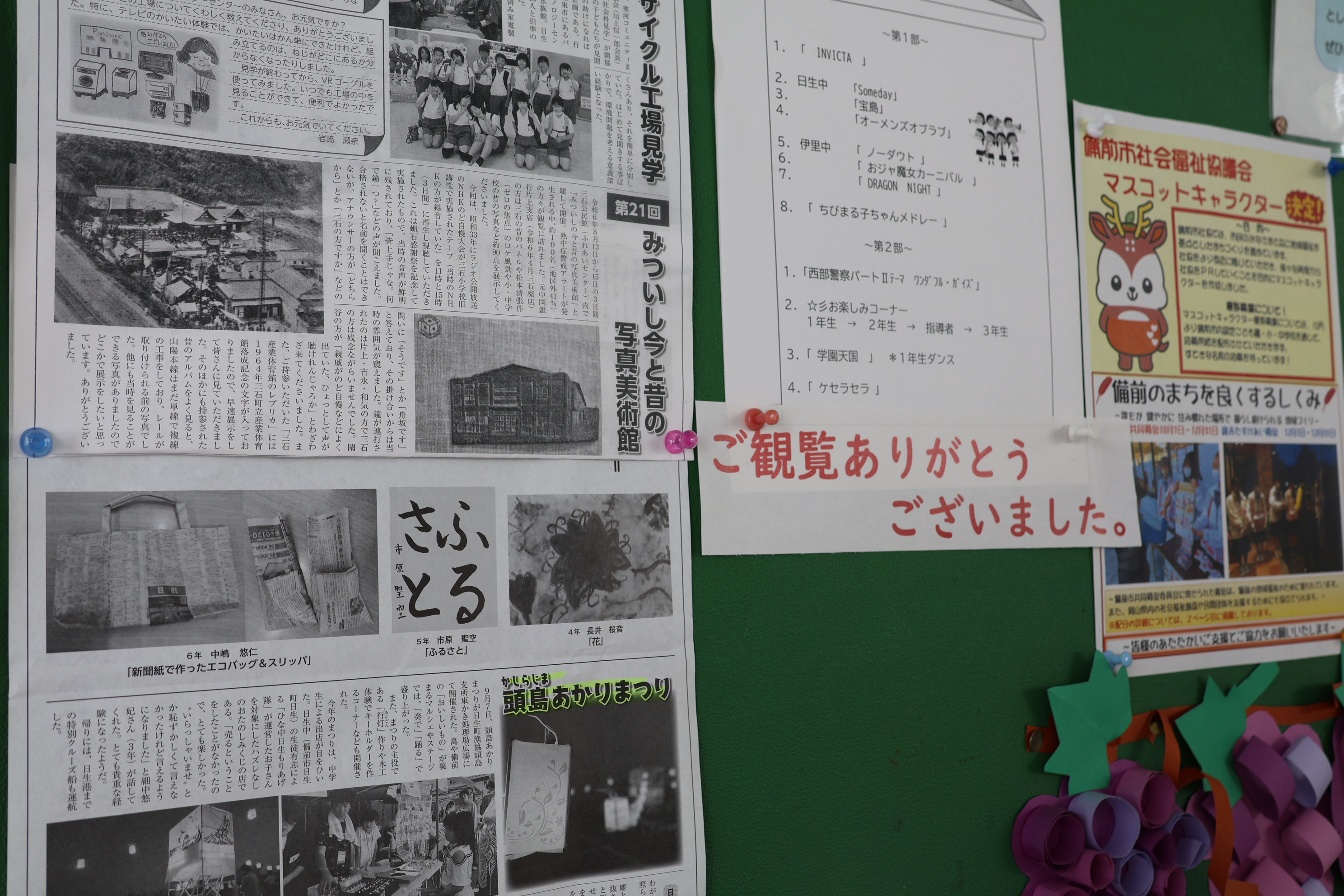
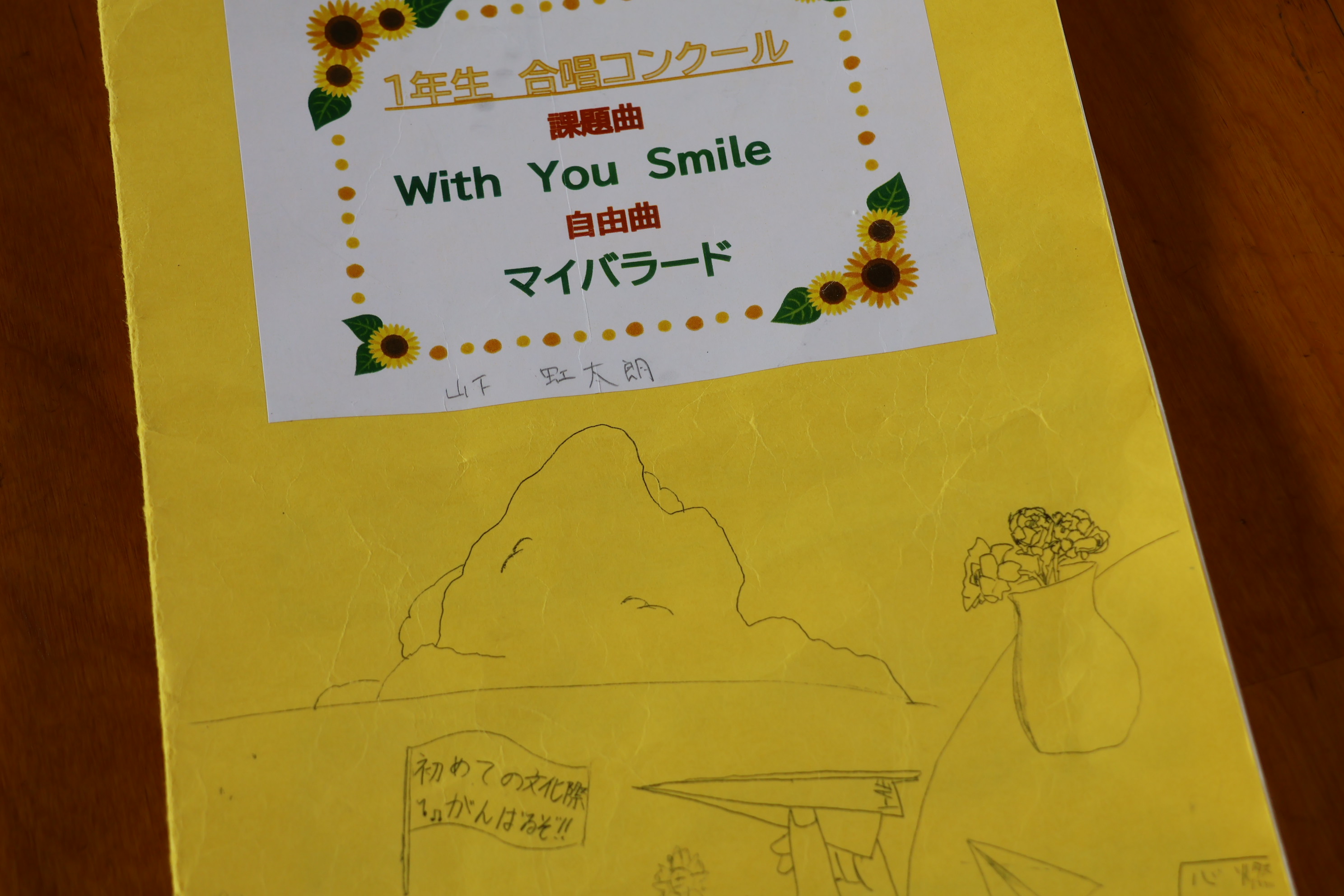





◎自分らしく精一杯! 仲間と共に精一杯!
秋季総体(9/21・/22)へ、いざ!
給食時間に、生徒会から「生徒会選挙の取組」について、そして、バスケットボール部キャプテンから「試合」へ向けての意気込みを放送しました。
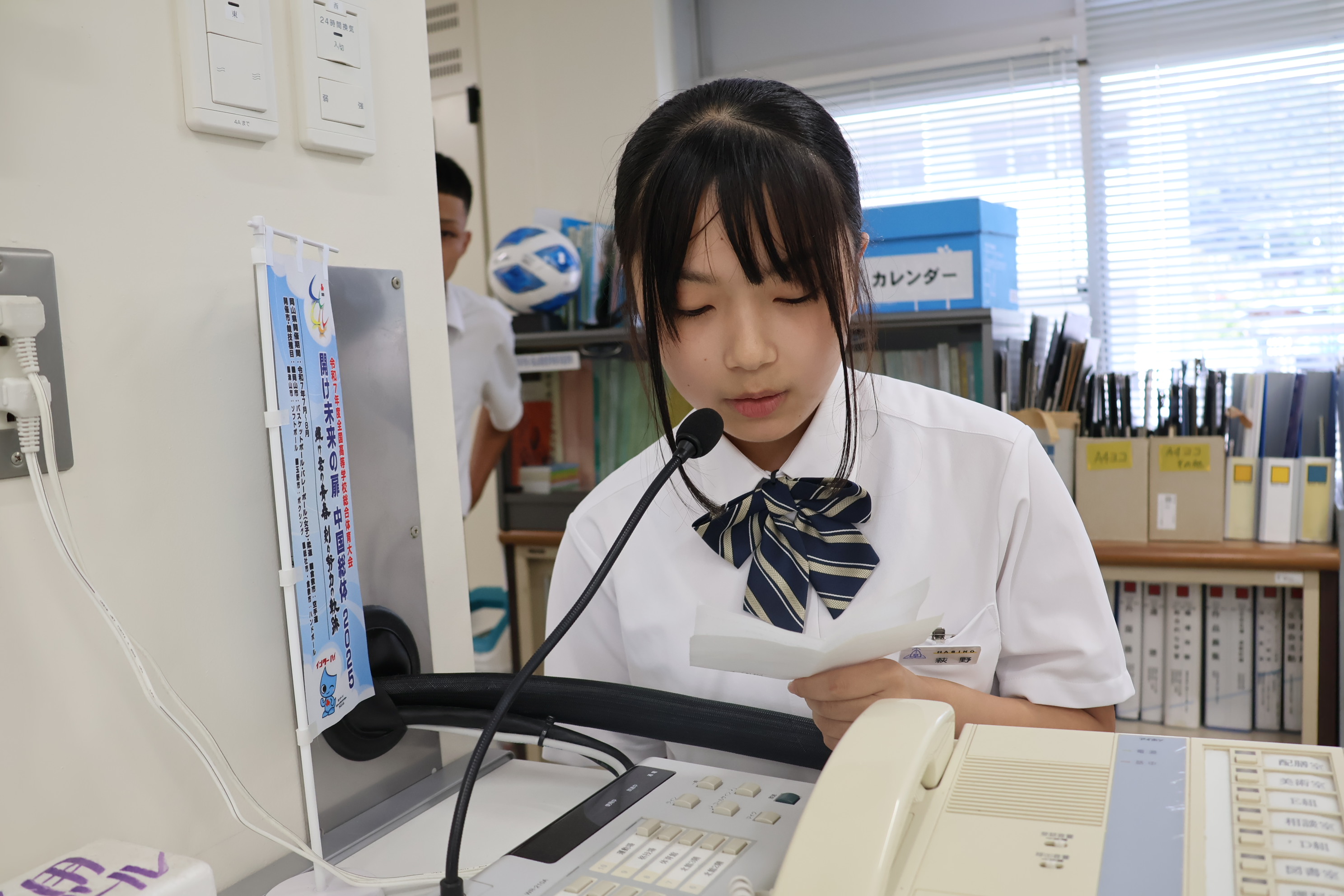
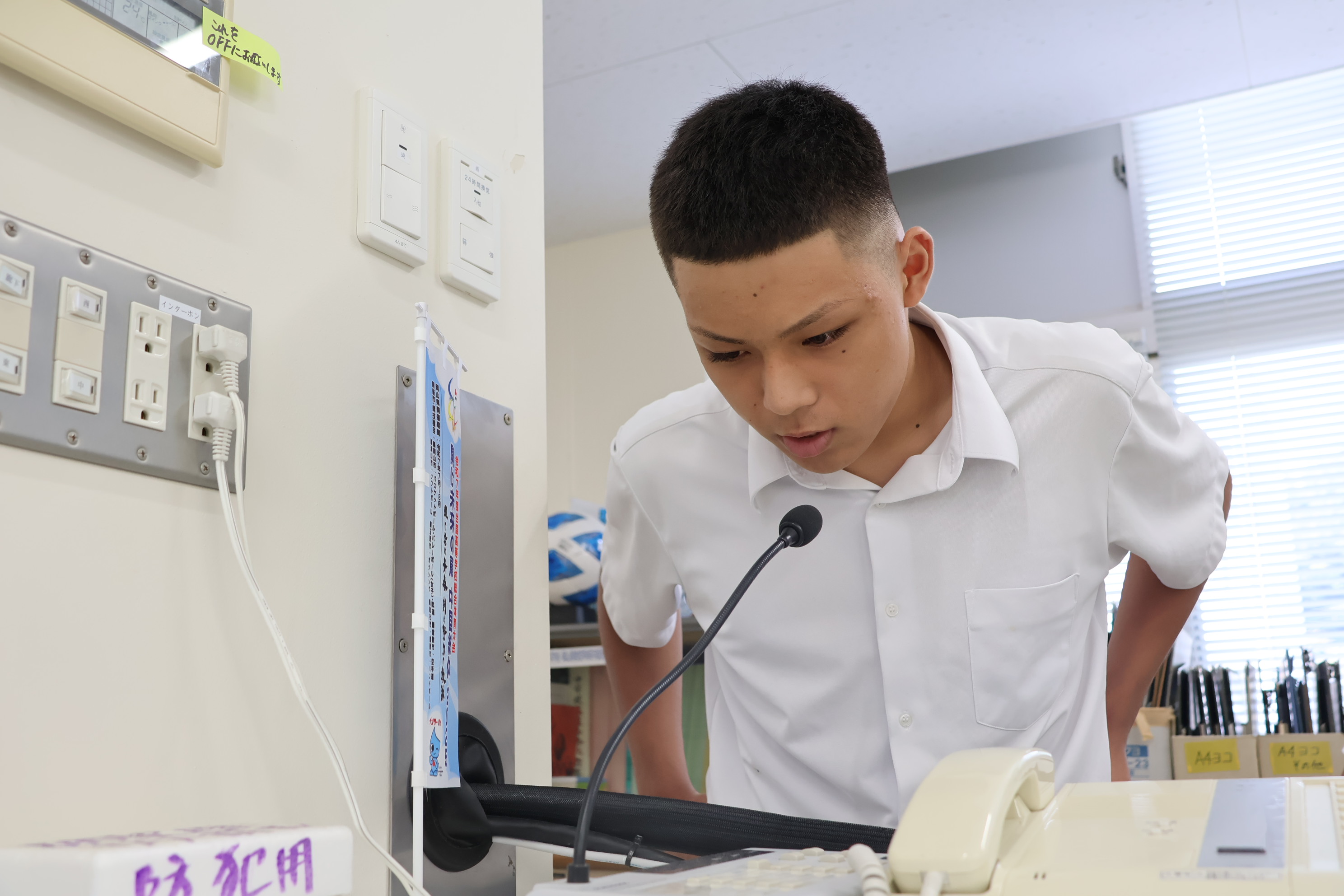
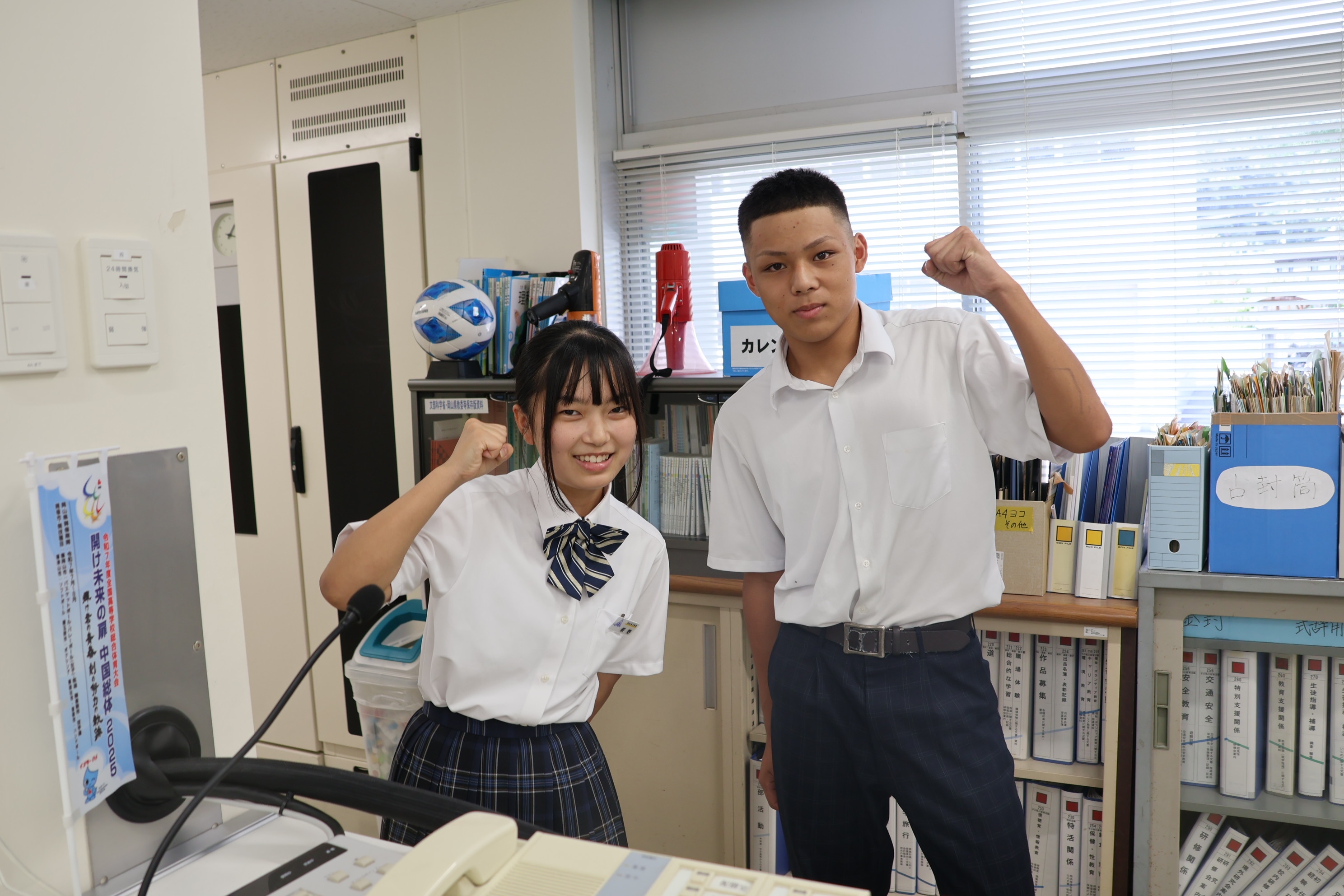
◎海に生きる 地域とともにある学校(9/20)
持続的な学びの中で・・・アマモは、水質を浄化する作用があるとされ、海の汚れの原因となる窒素やリンを吸収します。また、密集するアマモ場になると、海洋生物の産卵場や稚魚の成育場所にもなります。
19日、今年度もアマモ場の保全活動を通し、海洋資源の保全につなげる一歩として「アマモ種選別・アマモ種まき(播種)」を体験し、里海保全への理解を深めました。









◎いけませんよ 施錠して ヘルメットも定位置へ
by 体育委員会(9/20)






明日から秋の全国交通安全運動もスタート!
◎私の想い 私たちの主張 私とあなたの未来へ。
~学級弁論大会を開催中

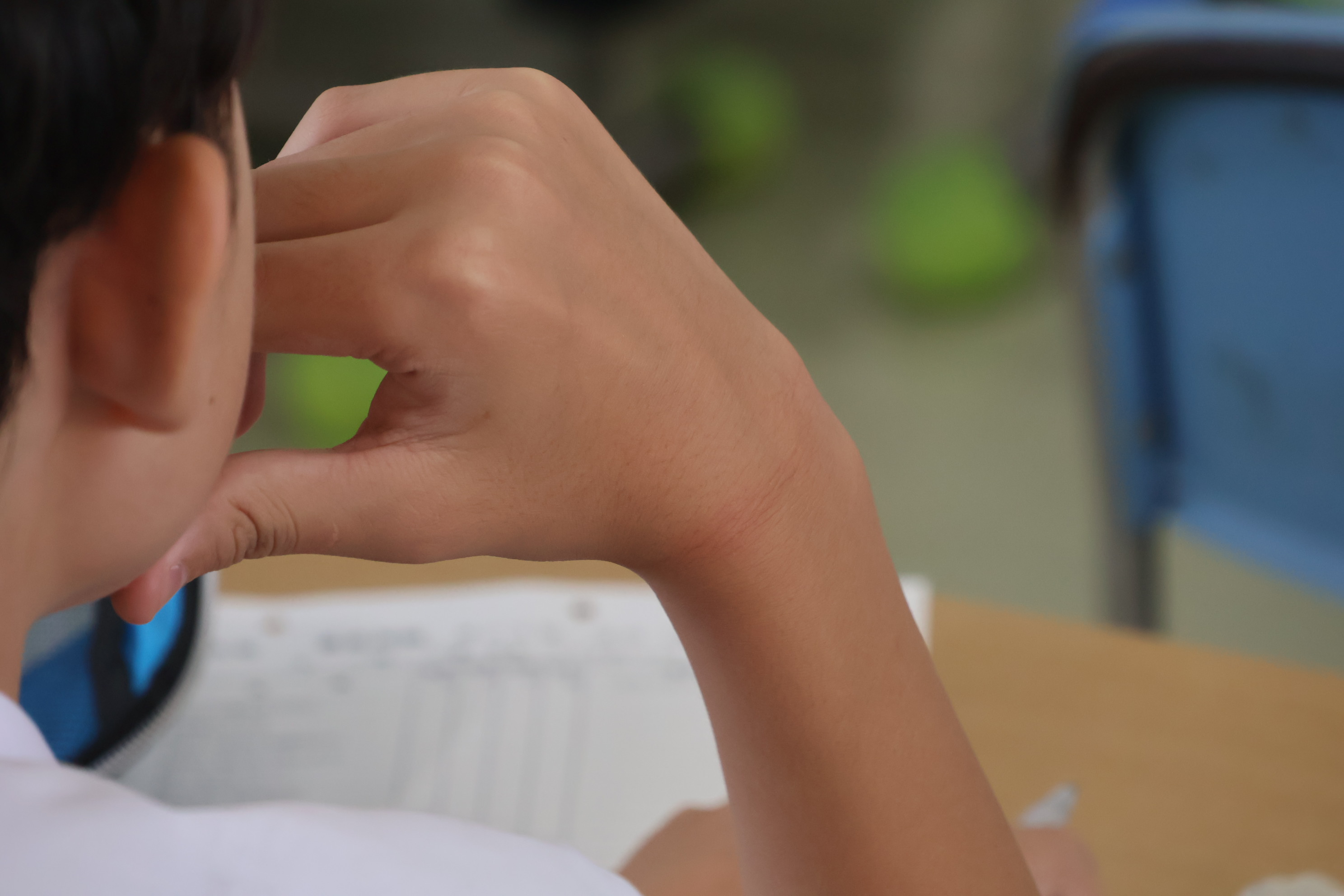
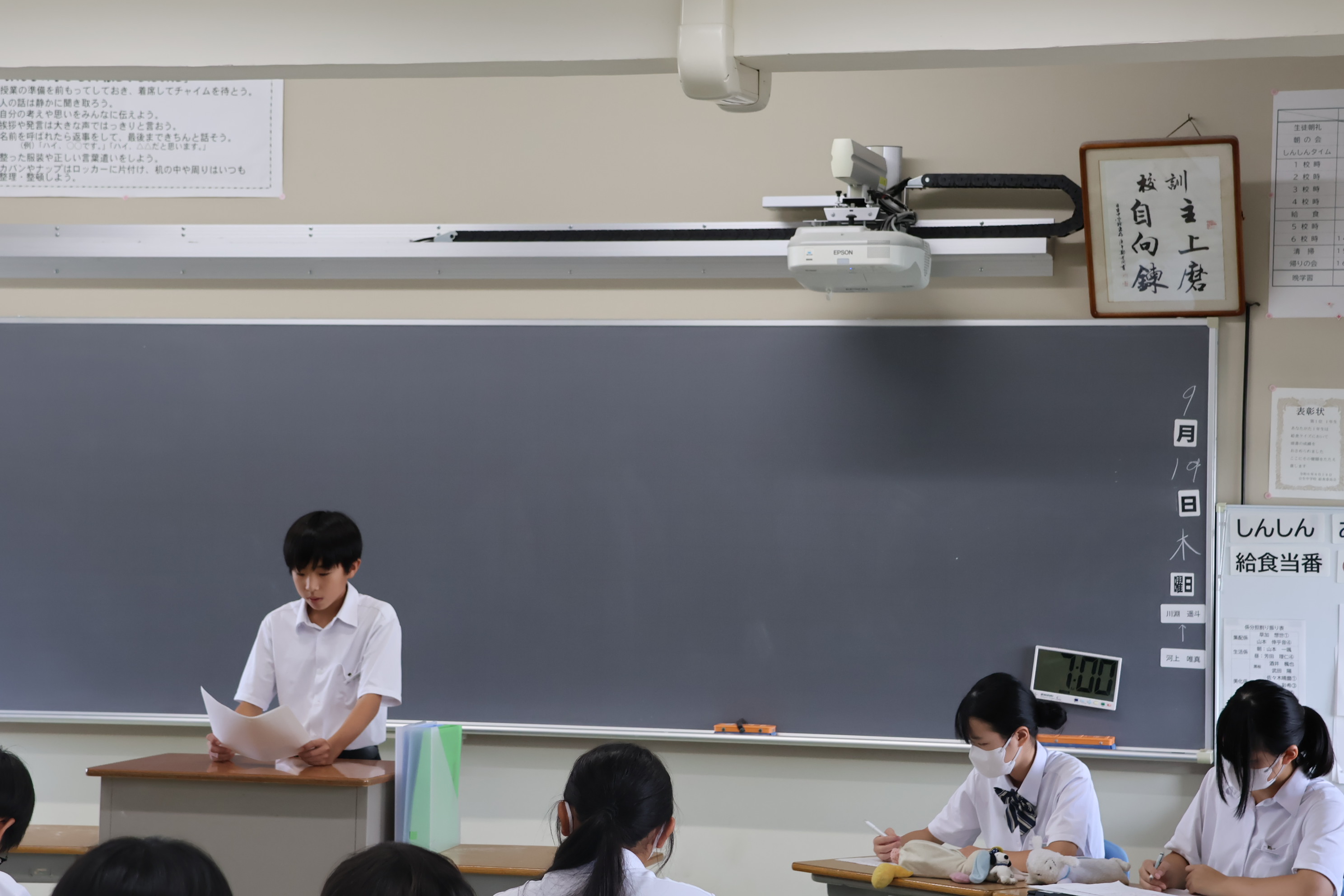





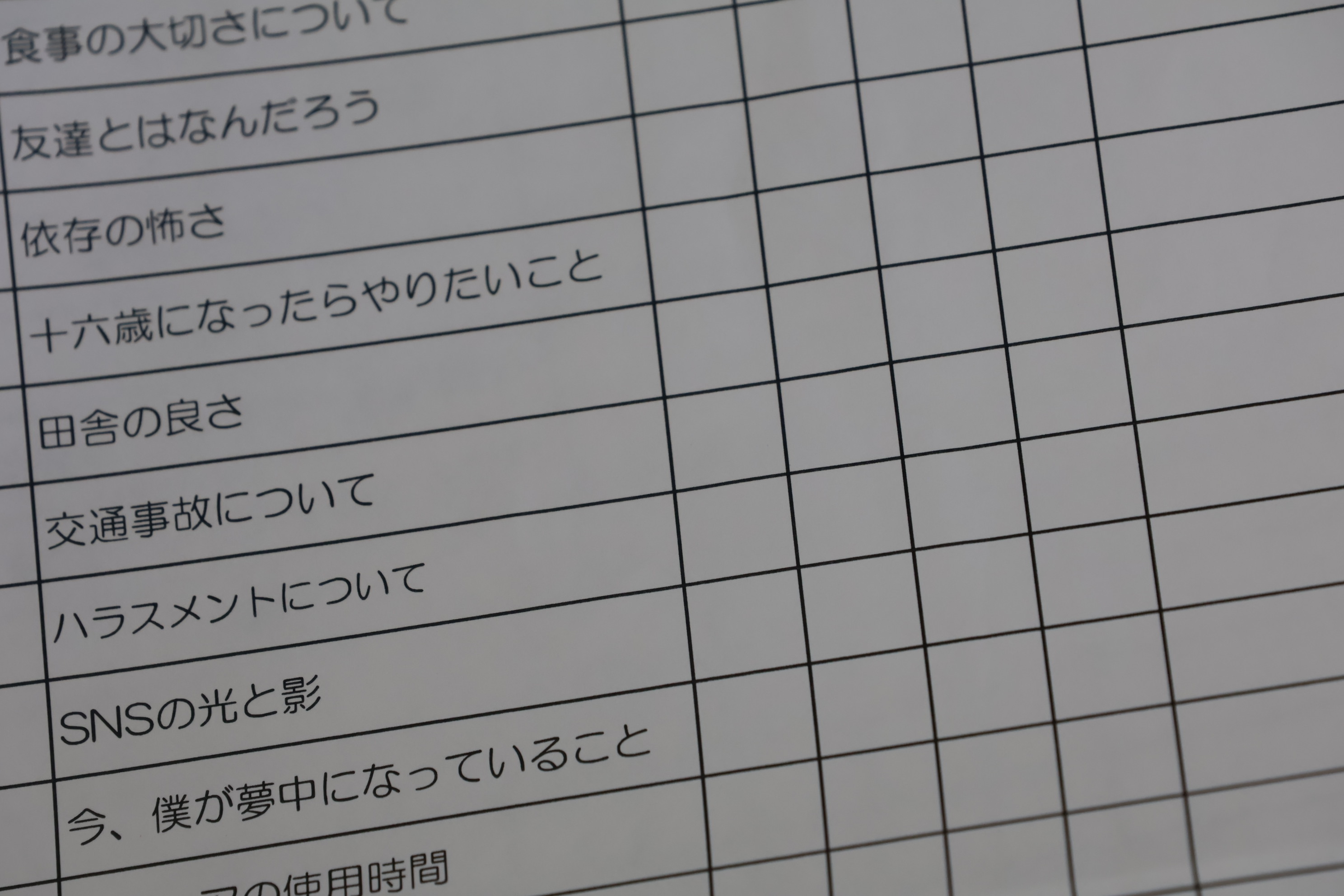
僕の挑戦~夢を追いかけて~ 音楽のもたらす力 目標の大切さ 私の友達について やってはいけないこと 自分の意見を大切に 健康の大切さ 戦争は本当に必要なのか ボランティアに参加してみて 依存の怖さ 十六歳になったらやりたいこと 田舎の良さ 今、僕が夢中になっていること 自然にあいさつをしよう ポイ捨てについて 私たちにできる防災 ゴミの分別について 言葉の力 僕が大切にしているもの 当たり前と思うな 1対1 睡眠時間について 家庭での役割 最近のニュース学校で勉強する理由 勉強をしてきて考えたこと 身近にある犯罪 健康である大切さ メデイアの使用時間 万博って何だろう 生徒会に携わってきて 家族の大切さ 見方を変えれば 後悔しないために 部活を通して ゲームとその危険性 なぜ、やりたいことがやりたくなくなるのか チャレンジワークで学んだこと 「私が考える家族とは」 一人一人の良いところ 交通事故について ハラスメントについて テンテカンカの祭りのボランティアに参加して お金について アニメの名言 レオが教えてくれたこと 僕にとっての部活動 これからの環境問題 中学校生活を通して ペットの命 ボランティア活動で学んだこと 私の悩み SNSの光と影 スマホゲームの良い点悪い点 日本の若者の死因 アーチェリーを通して 周りの人たちの優しさに支えられて 人を差別しないようにするには SNSについて 私の住む町 フェアプレーとは 広島の原爆について 日本とバリの違い 違法ドラッグの危険性 海を守りたい 人と関わること オリンピックの誹謗中傷 私の新しいチャレンジ ボランティアをして SNS 部活動とクラブチームの違い 「自分らしく生きる」って? 家族 日生の応援団を通して 人とのコミュニケーションについて 海洋汚染 三年生でやりたいこと スマホの影響 アメリカと日本の交通の違い 決まりの大切さ 人の目 中国への里帰り 継続は力なり あたり前とは 部活のやりがい 大切な特技 私が部活動で成長したこと 読書の影響 「有言実行」と「意志薄弱」 人のやさしさ 未来へつながるお手伝い 自分の意見を言うのは良いのか悪いのか 食事の大切さについて 友達とはなんだろう〈論題 9/19現在 順不同〉
◎彼岸入り(9/19)
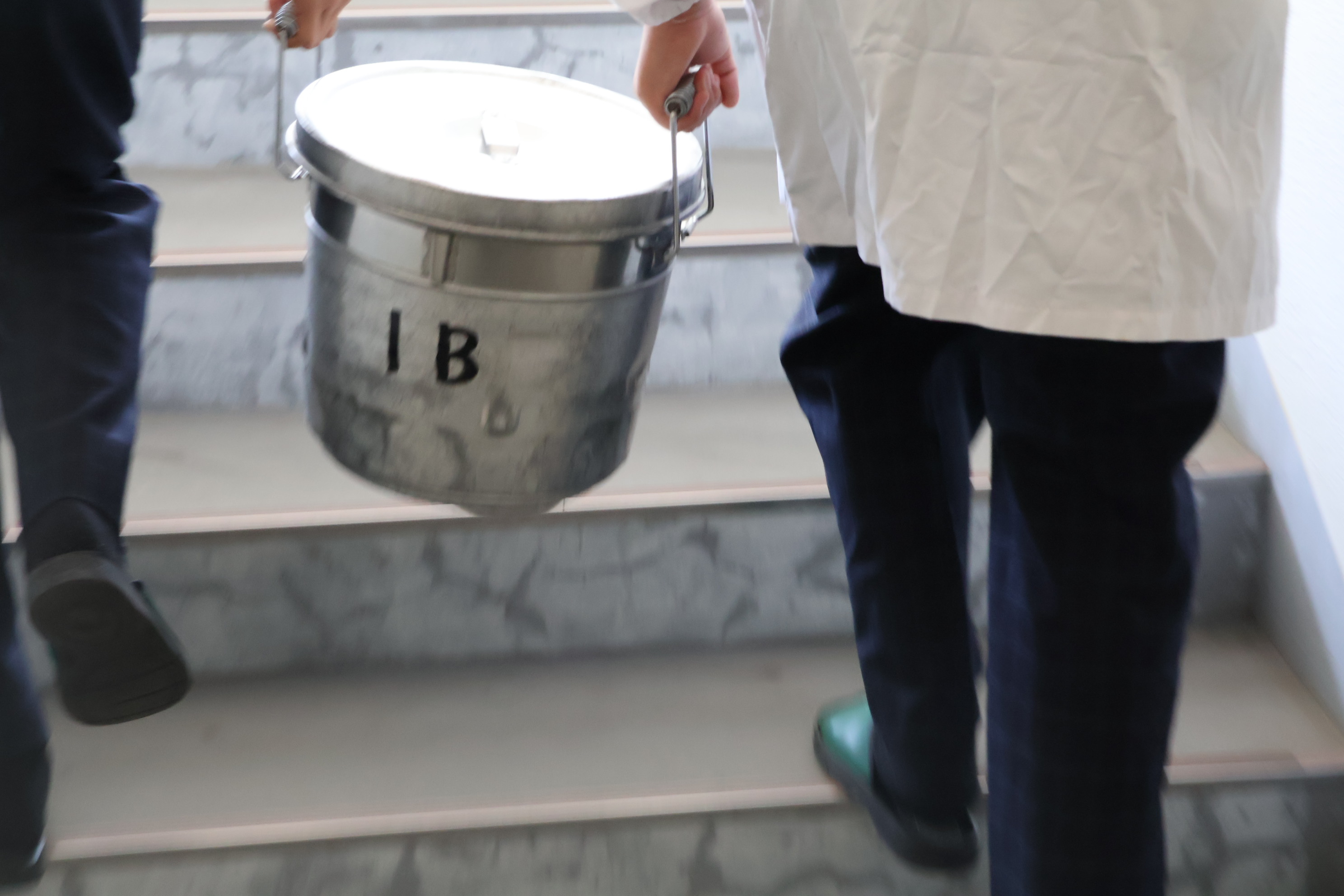
お彼岸とは、春分の日と秋分の日を中日とした前後3日、合わせて7日間をいい、雑節(二十四節気、五節句以外の特別な暦日)のひとつです。彼岸には、3月の春彼岸と9月の秋彼岸があり、春分の日(3月21日頃。その年により変動)、秋分の日(9月23日頃。その年により変動)を中日として、その前後の3日を合わせた7日間を彼岸といいます。また、最初の日を「彼岸入り」「彼岸の入り」と呼び、最後の日を「彼岸明け」と呼びます。春分と秋分は、太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日ですが、お彼岸にお墓参りに行く風習は、この太陽に関係しています。仏教では、生死の海を渡って到達する悟りの世界・あの世を「彼岸」といい、その反対側の私たちがいる迷いや煩悩に満ちた世界、この世を「此岸(しがん)」といいます。そして、彼岸は西に、此岸は東にあるとされており、太陽が真東から昇って真西に沈む秋分と春分は、彼岸と此岸がもっとも通じやすくなると考え、先祖供養をするようになりました。お彼岸はインドなど他の仏教国にはない日本だけの行事です。日本では、正月など神道にまつわる行事を行う一方、仏教を説いた釈迦の教えも受け入れてきました。お彼岸は「日願」でもあるため、太陽の神を信仰する神道と結びつきやすかったという説もあります。
また、春の種まきや秋の収穫とも結びつき、自然に対する感謝や祈りがご先祖様に感謝する気持ちにもつながって、お彼岸は大切な行事となりました。彼岸の中日である「春分の日」「秋分の日」は国民の祝日です。祝日法による趣旨はこのようになっています。
春分の日……『自然をたたえ、生物をいつくしむ日』
秋分の日……『祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日』
ちなみに、お彼岸の供物や食べものといえば、「ぼたもち」と「おはぎ」ですが、基本的には同じものです。その季節に咲く「牡丹」と「萩」の花から、春は「牡丹餅(ぼたもち)」、秋は「御萩(おはぎ)」と呼び分けるようになり、作り方にも花の姿が反映されるようになりました。また、小豆の収穫期は秋なので、秋の「おはぎ」には皮ごと使ったつぶあんを用い、春の「ぼたもち」には固くなった皮を除いたこしあんを用いていたそうです。現在はこうした違いにあまりこだわりませんが、昔の人の感性がわかりますね。
◎地域とともに在る学校(9/18)
ひな中ほっとスペースでほっともっと。次回は10月2日です。


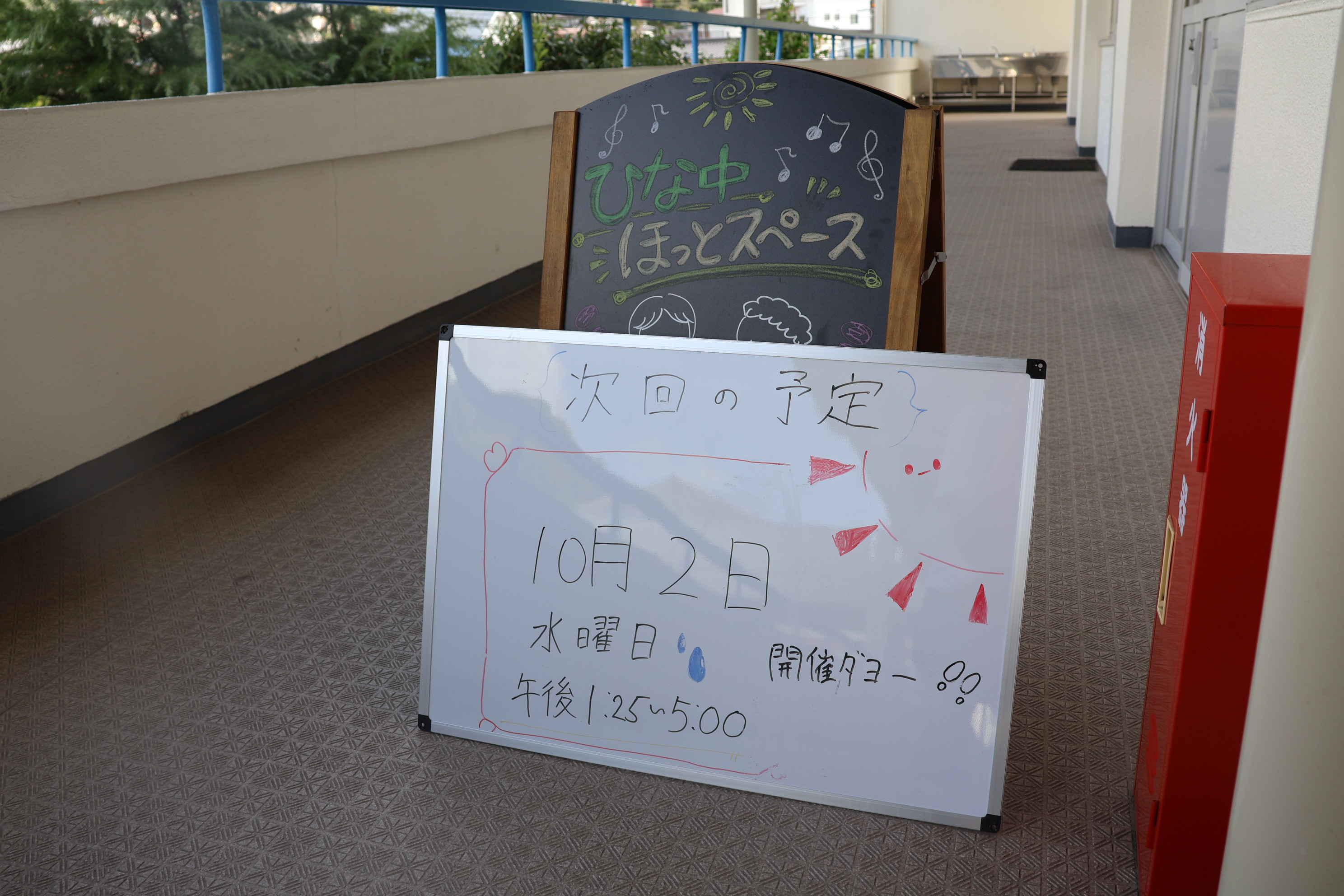
◎月はどっちに出ている。
9月17日は十五夜でした。少しだけ行事について紹介します。
十五夜とは、1年で最も月がきれいな夜のことです。昔の暦では太陰暦を採用していたため、8月15日(今の9月中旬)が満月にあたることから「十五夜(じゅうごや)」と呼ばれていました。大きな満月は「中秋の名月」と呼ばれ、お団子やすすきなどお供え物をしてお月見をします。
昔は7月〜9月が秋で、8月は秋の真ん中にあたることから「中秋(ちゅうしゅう)」と呼ばれていました。この頃の月がとても綺麗なことから「中秋の名月」と呼ばれるようになっています。昔の暦では月の満ち欠けを一月(ひとつき)とする太陰暦を採用していました。満月から満月までを1ヶ月と数えていたため、毎月15日の夜はほとんどの日が満月でした。以前は太陰暦だったので、必ず旧暦8月15日でしたが、今では太陽暦が採用されていることから、毎年十五夜の日が異なります。新暦を採用している今では9月中旬頃〜10月上旬頃に十五夜になります。
今年の十五夜は9月17日(火)でした。(※旧暦8月15日を十五夜(中秋の名月)と言います。新暦では必ずしも満月ではありません。約1日ずれることがあります)秋の美しい満月をながめる「お月見」の風習は、古くから中国にありました。それが日本に伝わり、奈良時代、平安時代の貴族たちを中心に、昔の暦の8月15日(今の9月中頃〜)の夜にお月見の宴をするようになりました。貴族たちは音楽を演奏したり、月の美しさを和歌に詠んだりしていました。その後、お月見の風習は、武士や庶民の間にも広まっていくようになりました。月見の風習は町の人たちにも広まり、特に農家では、秋の収穫の時期にもあたることから、新しい収穫物をお供えして豊作を祝い、実りを感謝するようになったのです。

◎第10回校内研修(9/18)
先生たちも、仲間とともに学んでいます。
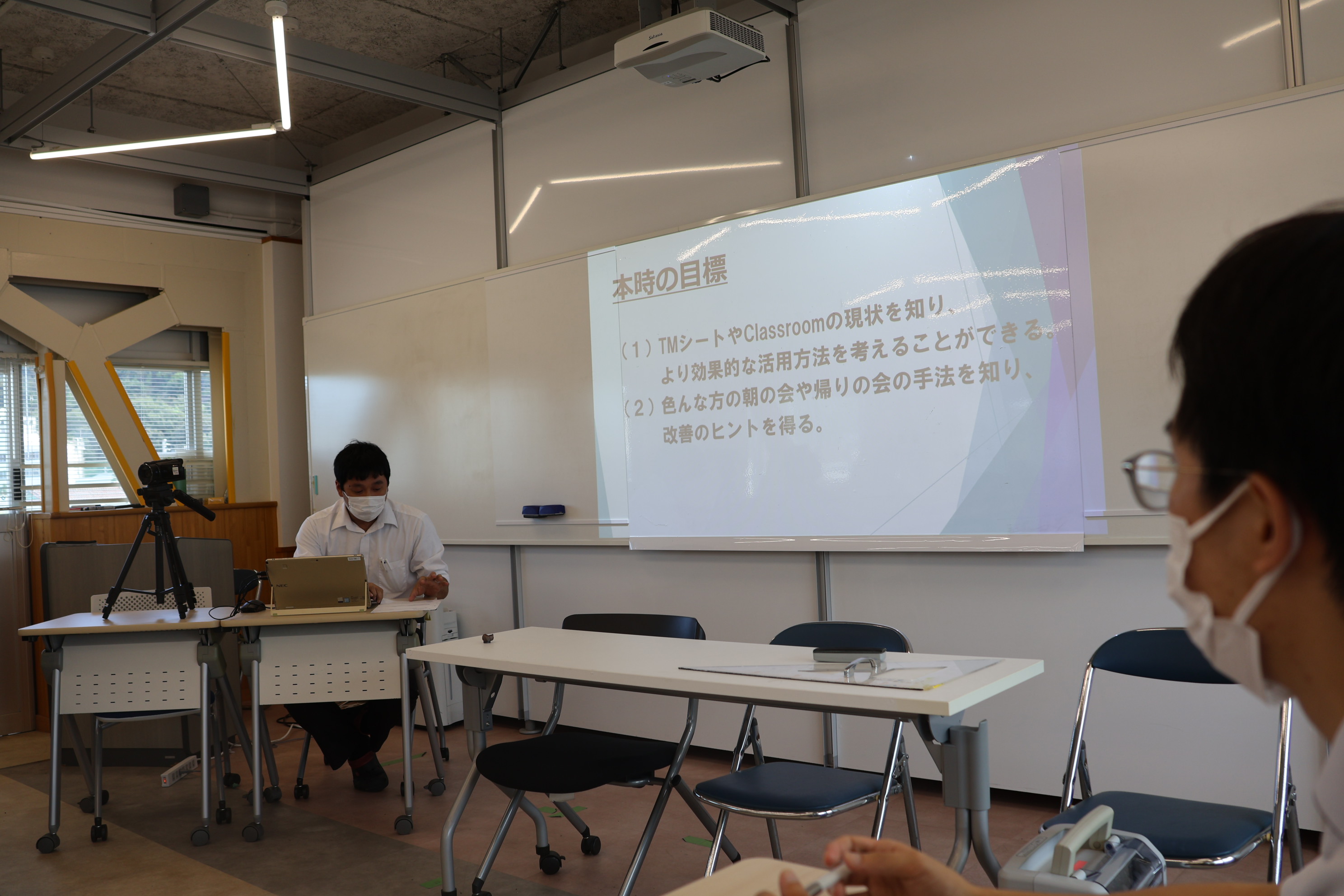

〈コピペしたような日記は消去して、今から明日を書きかえようぜ 寺井奈緒未 改〉
ひな中のかぜ~✨(9/18:水泳授業)



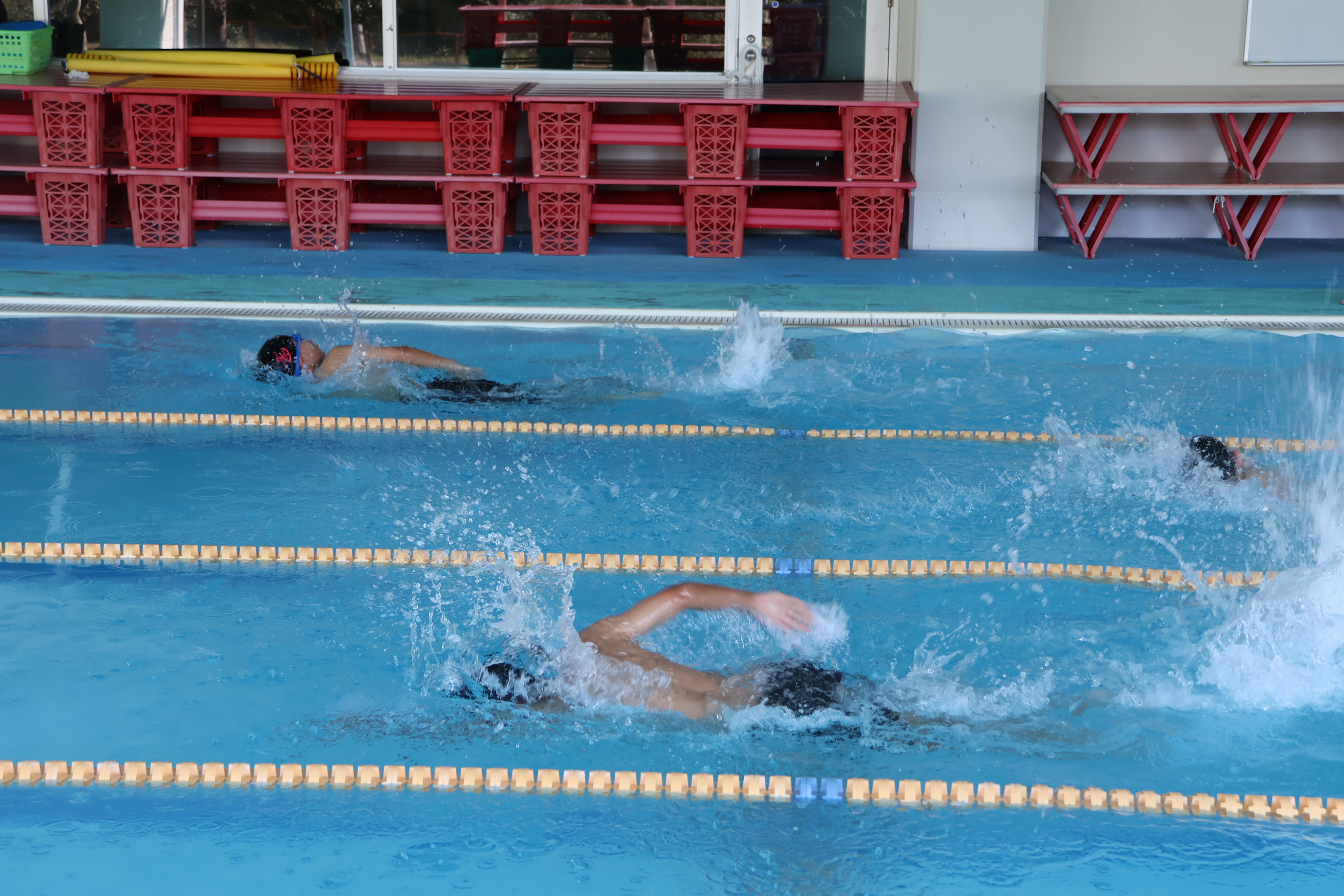
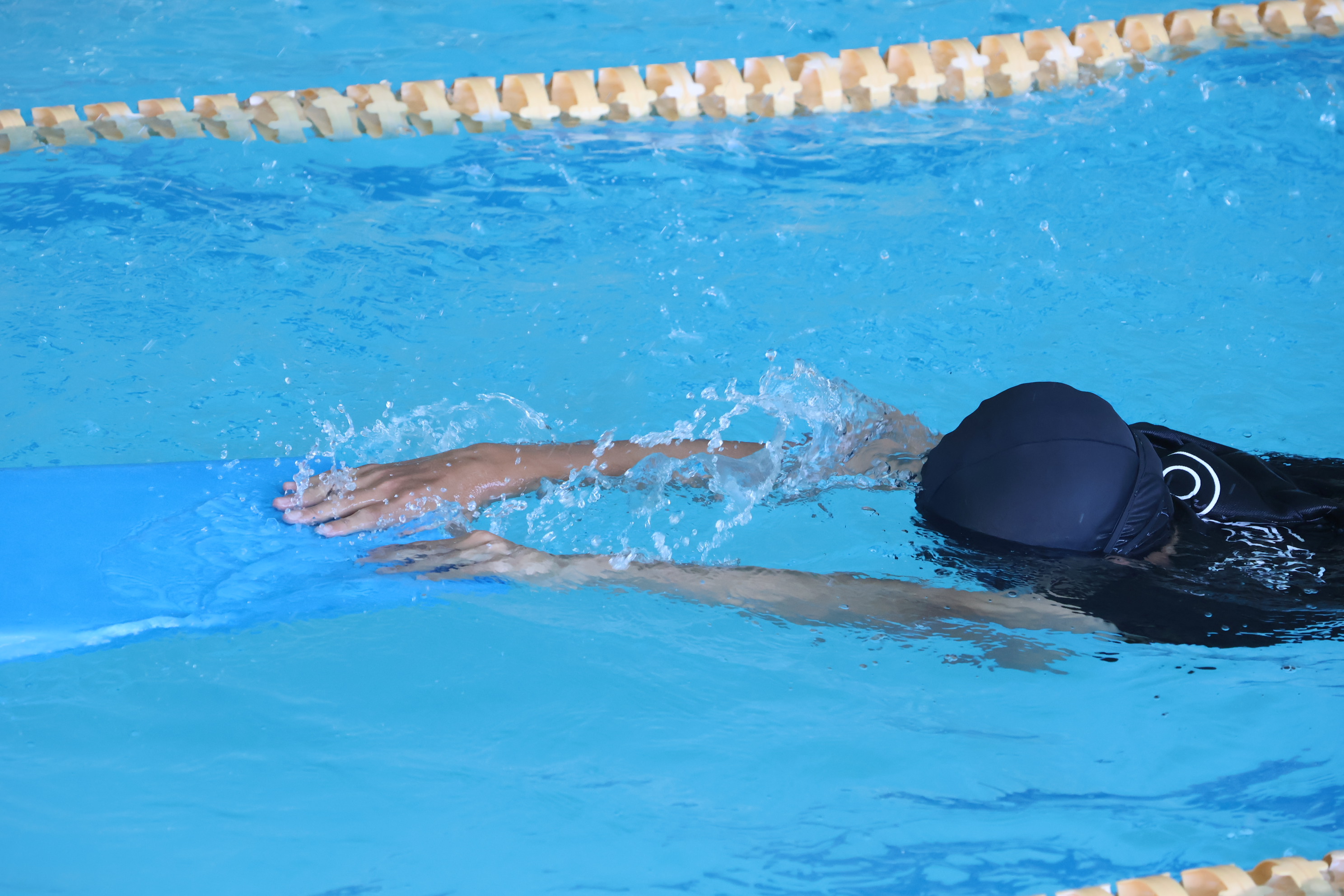




ちなみに、学習指導要領ではこう書かれています。
『「水泳」中学校 第1学年及び第2学年
次の運動について、記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい、泳法を身に付けることができるようにする。
ア クロールでは、手と足、呼吸のバランスをとり速く泳ぐこと。
イ 平泳ぎでは、手と足、呼吸のバランスをとり長く泳ぐこと。
ウ 背泳ぎでは、手と足、呼吸のバランスをとり泳ぐこと。
エ バタフライでは、手と足、呼吸のバランスをとり泳ぐこと。
水泳は、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライなどから構成され、浮く、進む、呼吸をするなどのそれぞれの技能の組み合わせによって成立している運動で、それぞれの泳法を身に付け、続けて長く泳いだり、速く泳いだり、競い合ったりする楽しさや喜びを味わうことのできる運動です。中学校では、小学校の学習を受けて、泳法を身に付け、効率的に泳ぐことができるようにすることが求められます。したがって、第1学年及び第2学年では、記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい、泳法を身に付けることができるようにします。泳法は、伏し浮きの姿勢で泳ぐクロール、平泳ぎ、バタフライ及び仰向けの姿勢で泳ぐ背泳ぎの4種目を取り上げています。これらの泳法を身に付けるためには、泳法に応じた、手の動き(プル)や足の動き(キック)と呼吸動作を合わせた一連の動き(コンビネーション)をできるようにする必要があります。また、水泳では、続けて長く泳ぐことや速く泳ぐことに学習のねらいがあるので、相互の関連を図りながら学習を進めていくことができるようにします。』
◎未来・夢・進路を切り拓いていく私たち✨
タイムマネジメントシートの活用に取り組んでいます(9/18)
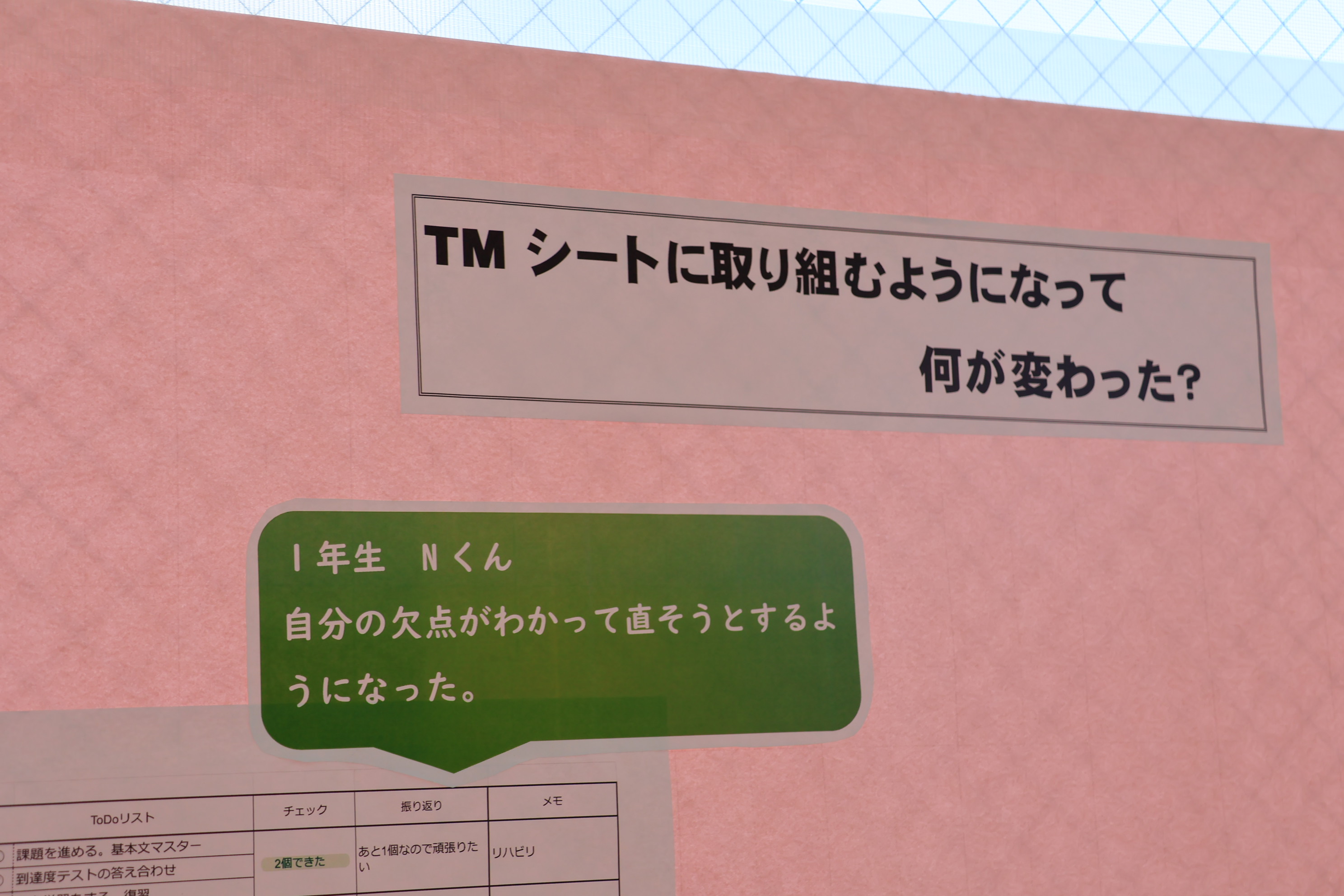
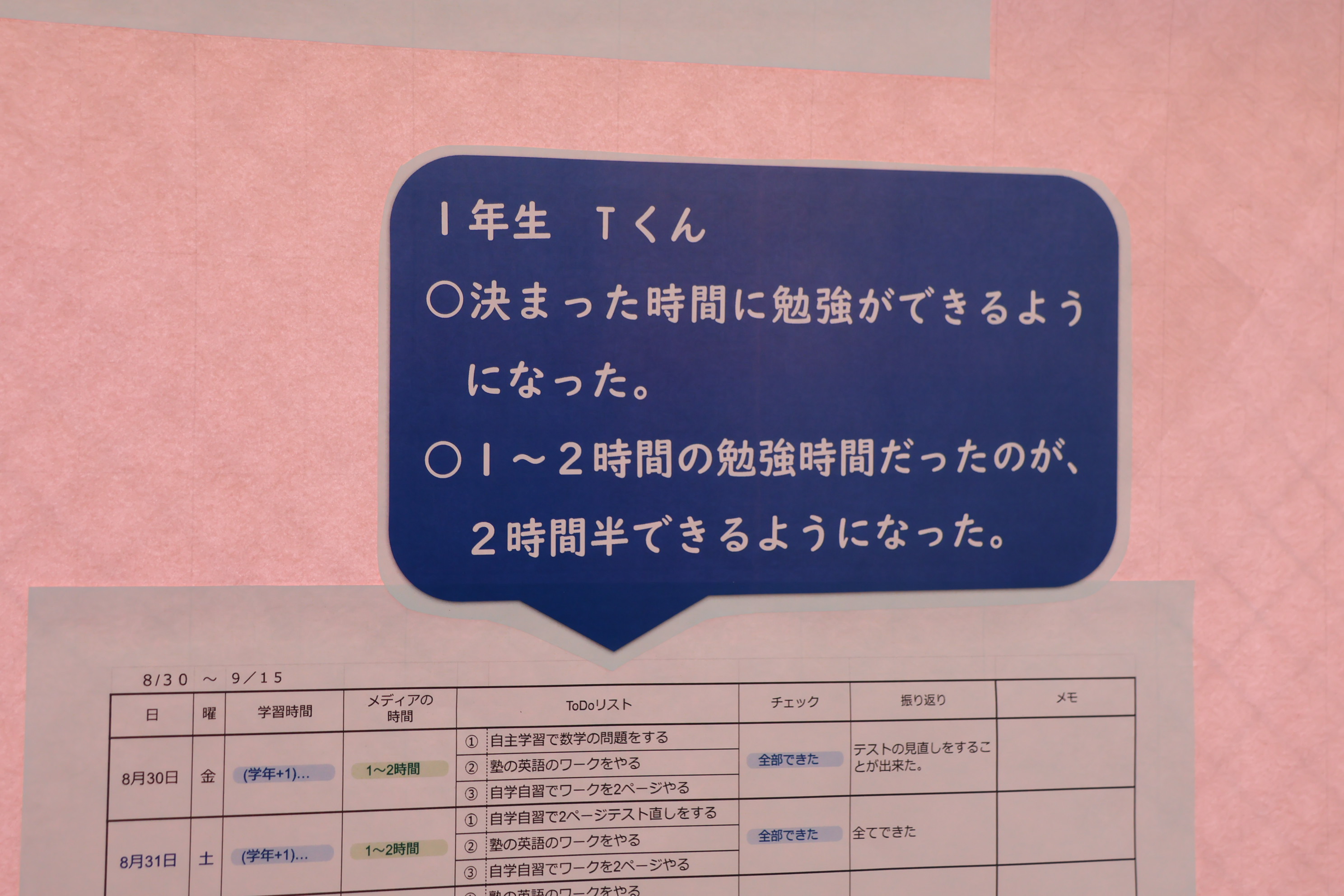
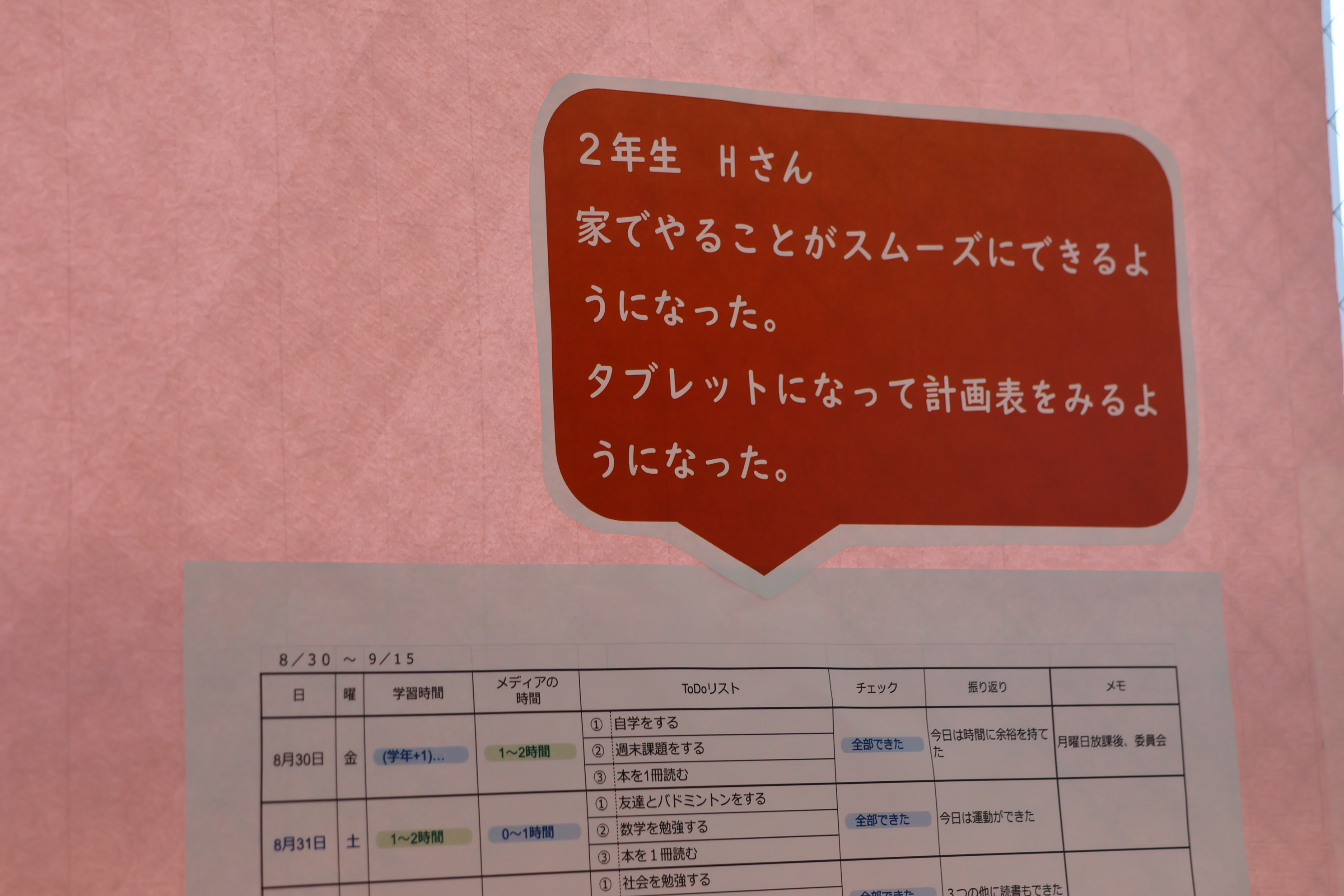
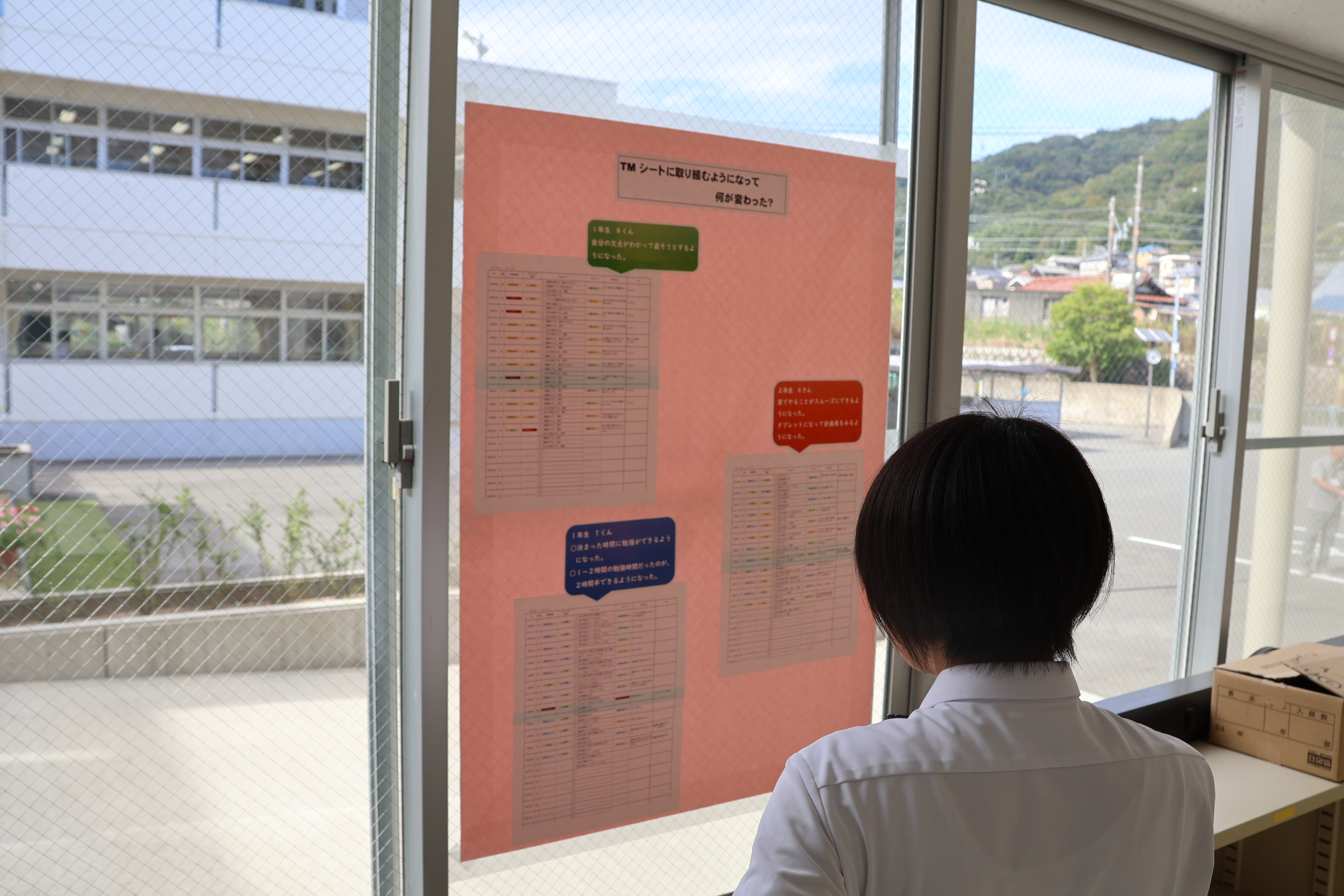
◎文化の部(合唱) 歌声はかぜにのって♪
みんなガンバロウ

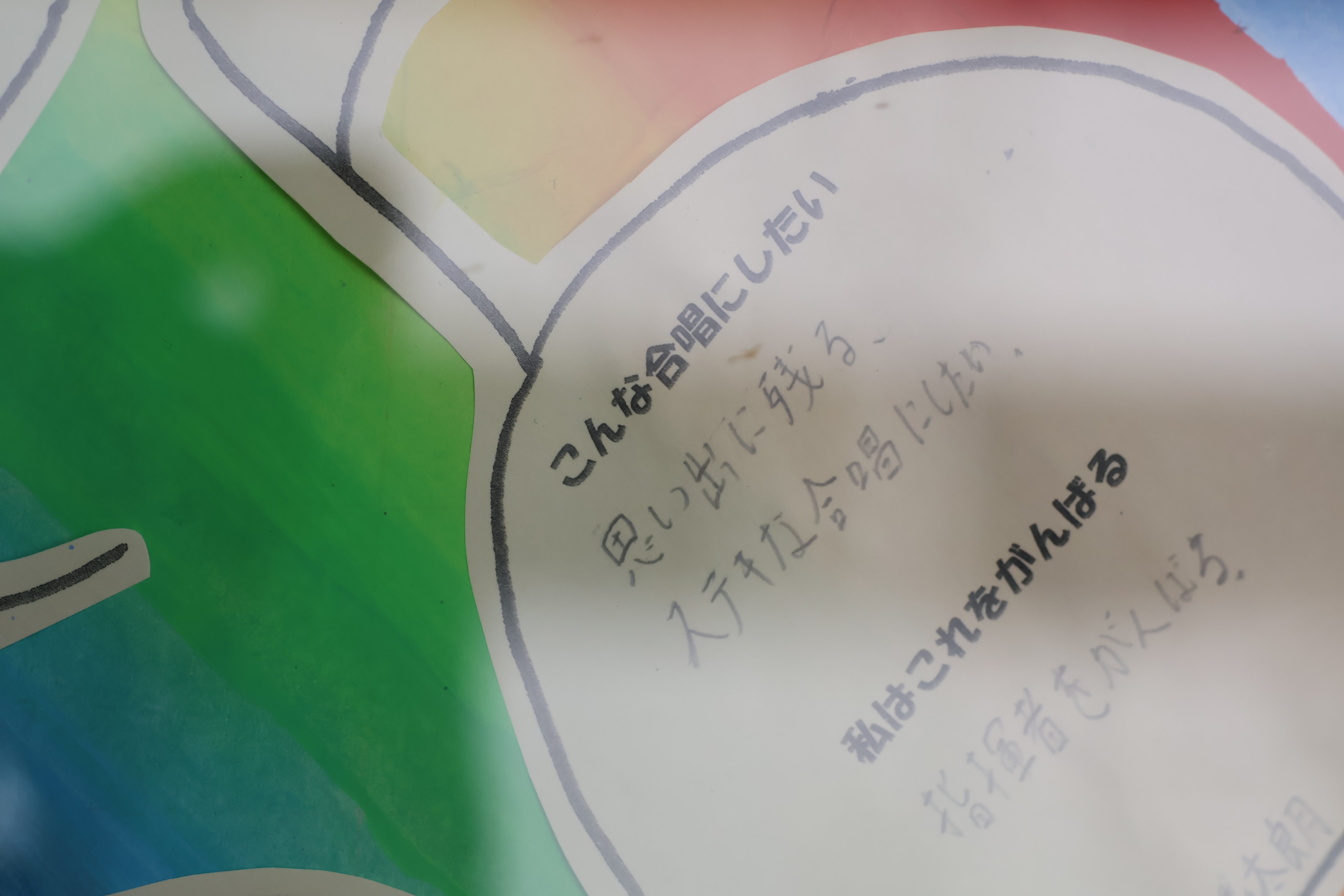
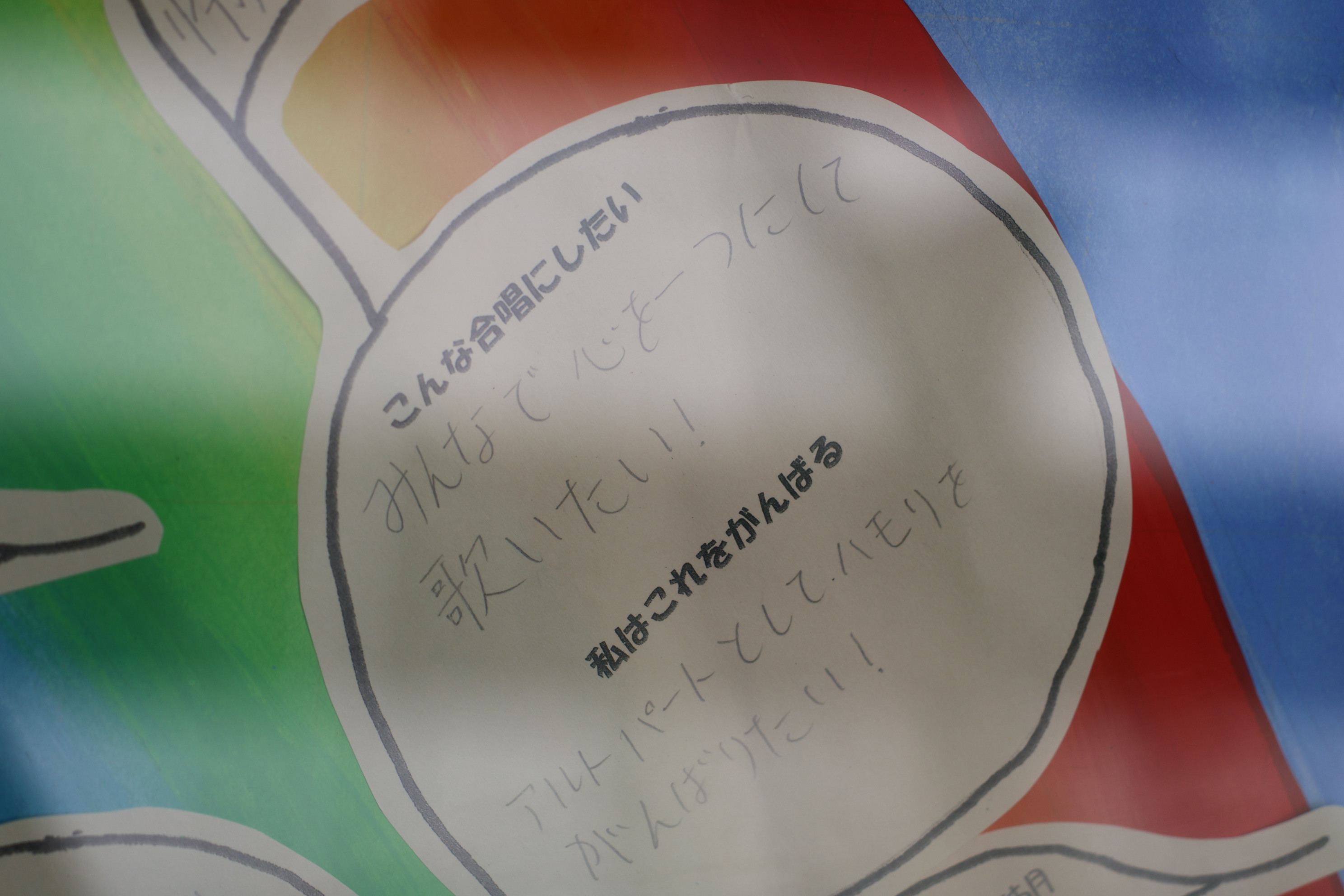
◎GLOBAL ROOMで、「広く・深い」視座を(9/18)
世界を拡げよう! 第1学習室の模様替えをしてくださいました。(モートン先生プロデュース)
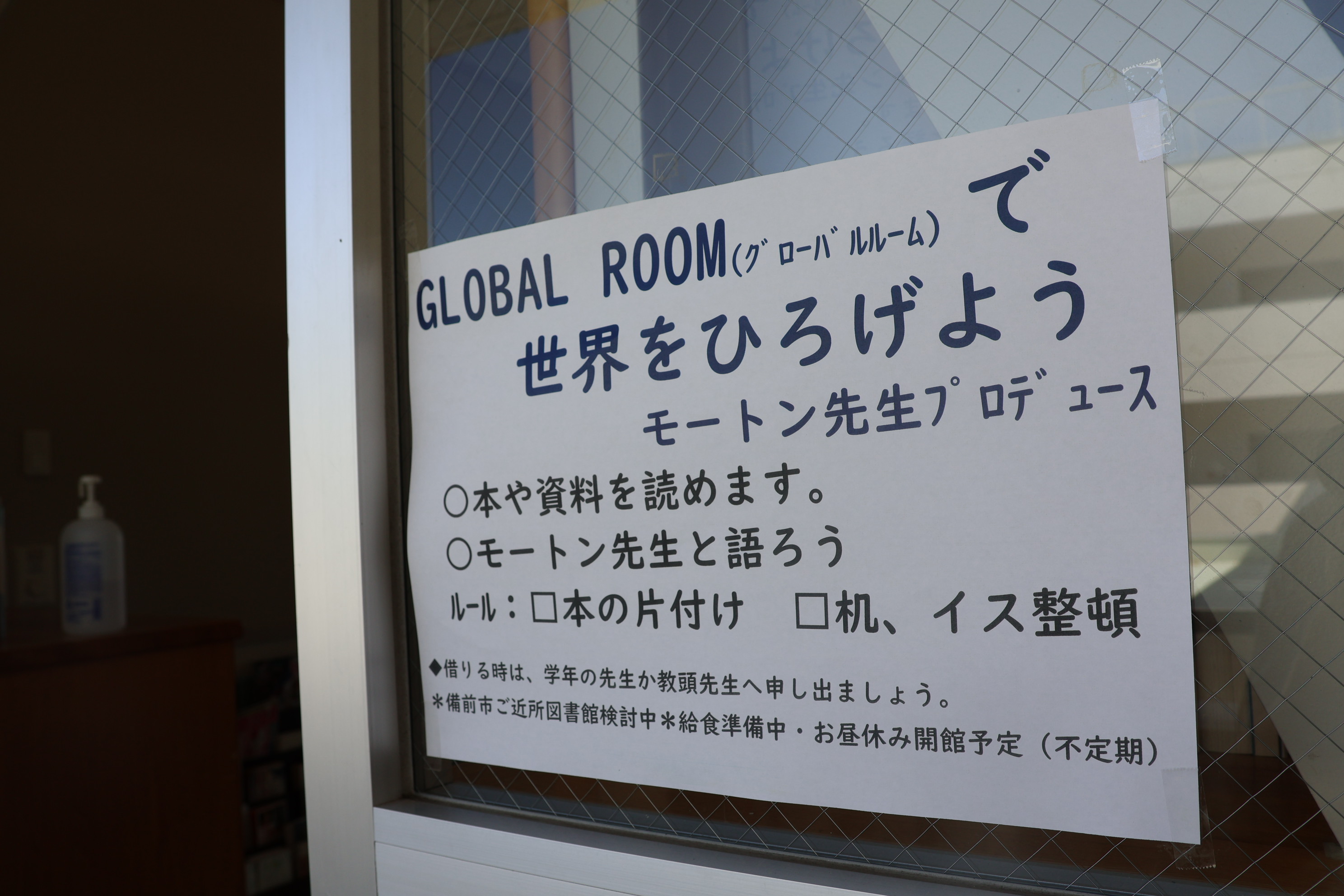

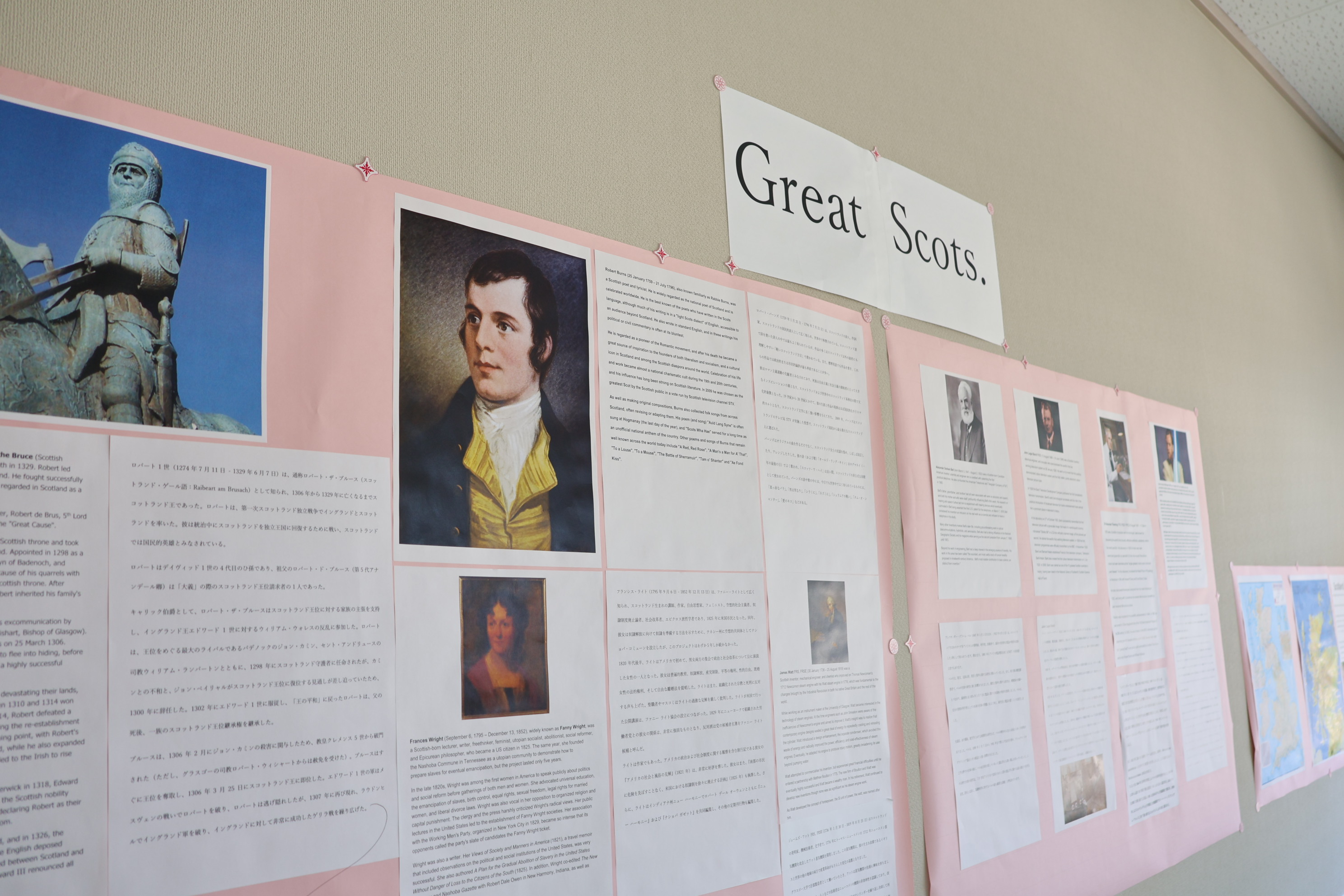
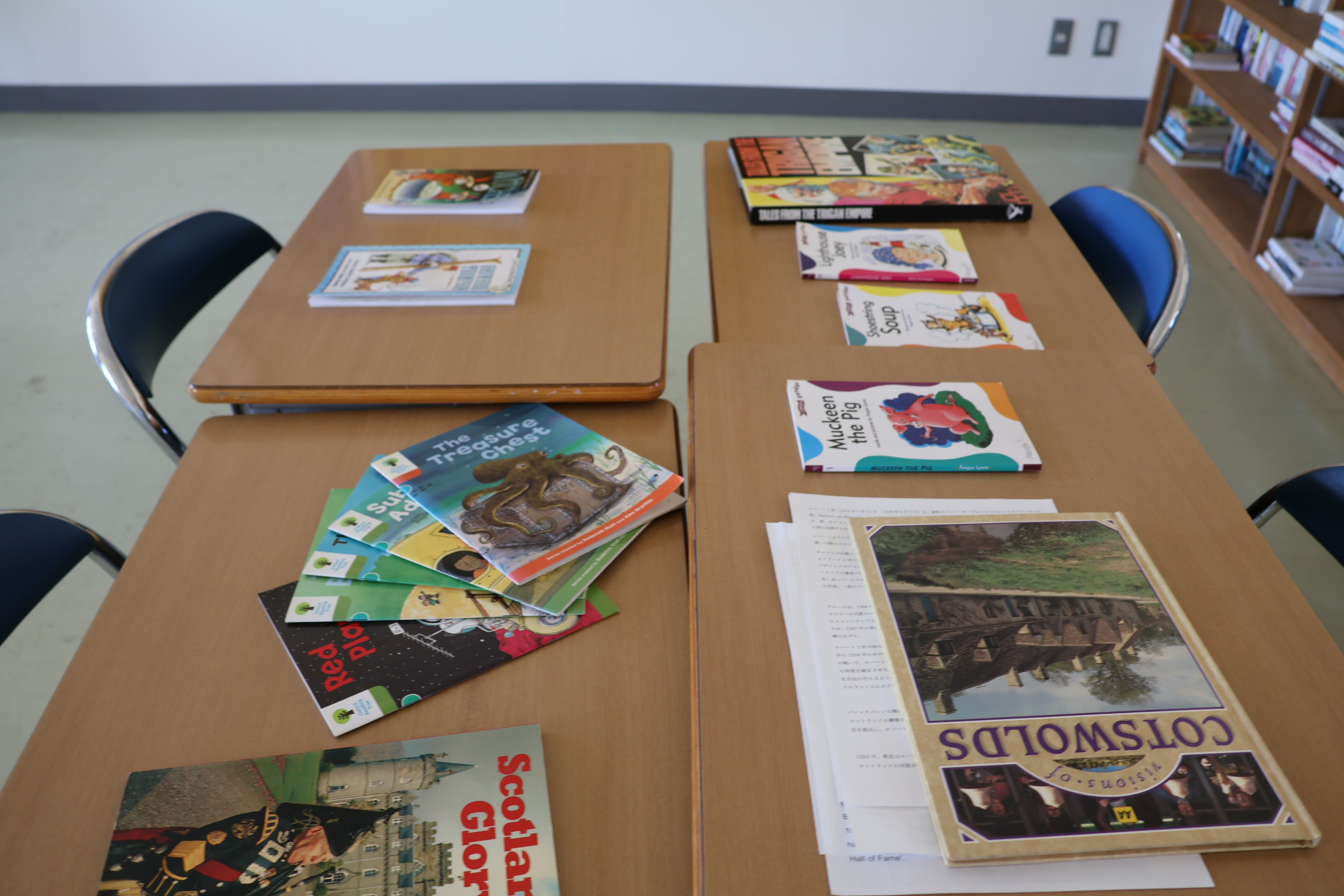


◎「こんにちは」「こんにちは」
今日も、ひな中が大切にしていること(9/18)

♬悲しいことがあると 開く皮の表紙 卒業写真のあの人は やさしい目をしてる 町でみかけたとき 何も言えなかった 卒業写真の面影が そのままだったから 人ごみに流されて 変わってゆく私を あなたはときどき 遠くでしかって



「思い出」となる学び舎で、グループごとで撮影しました。中元さん、残暑の中、撮影をありがとうございました。
◎明日は、ほっとスペース開設っ!(^_^)

◎確かな学びのために(9/17)
授業が大切。

授業準備が大切。
◎これからの日生中へ✨ 「自治・創造・仲間」が争点(9/13)
選挙運動スタート

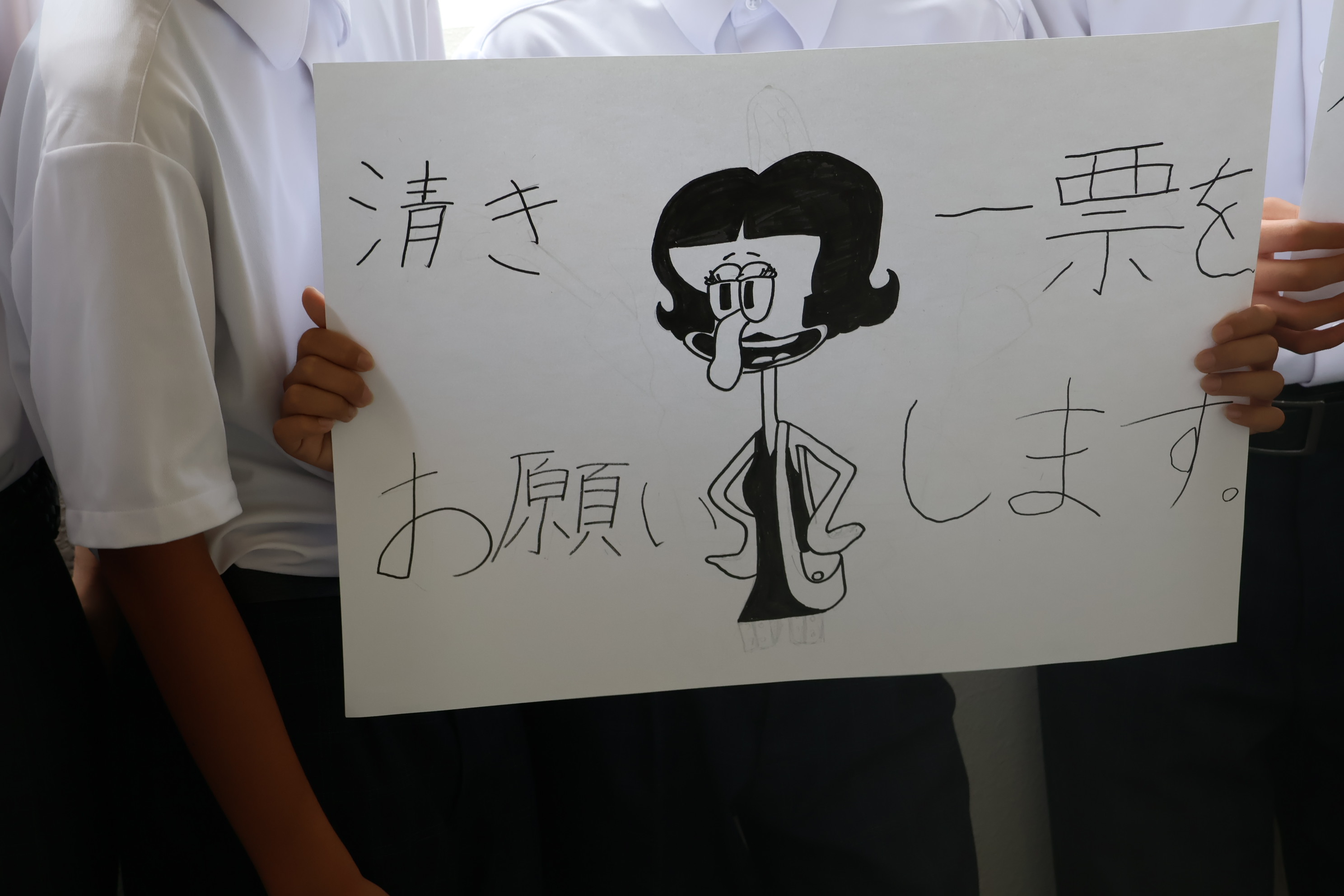

◎多くの人に支えられて(9/13)
昨日、学校薬剤士さんが来校され、水質検査をしていただきました。ありがとうございました。また、ウオーターサーバーで利用している水道水の安全性も確認していただきました。
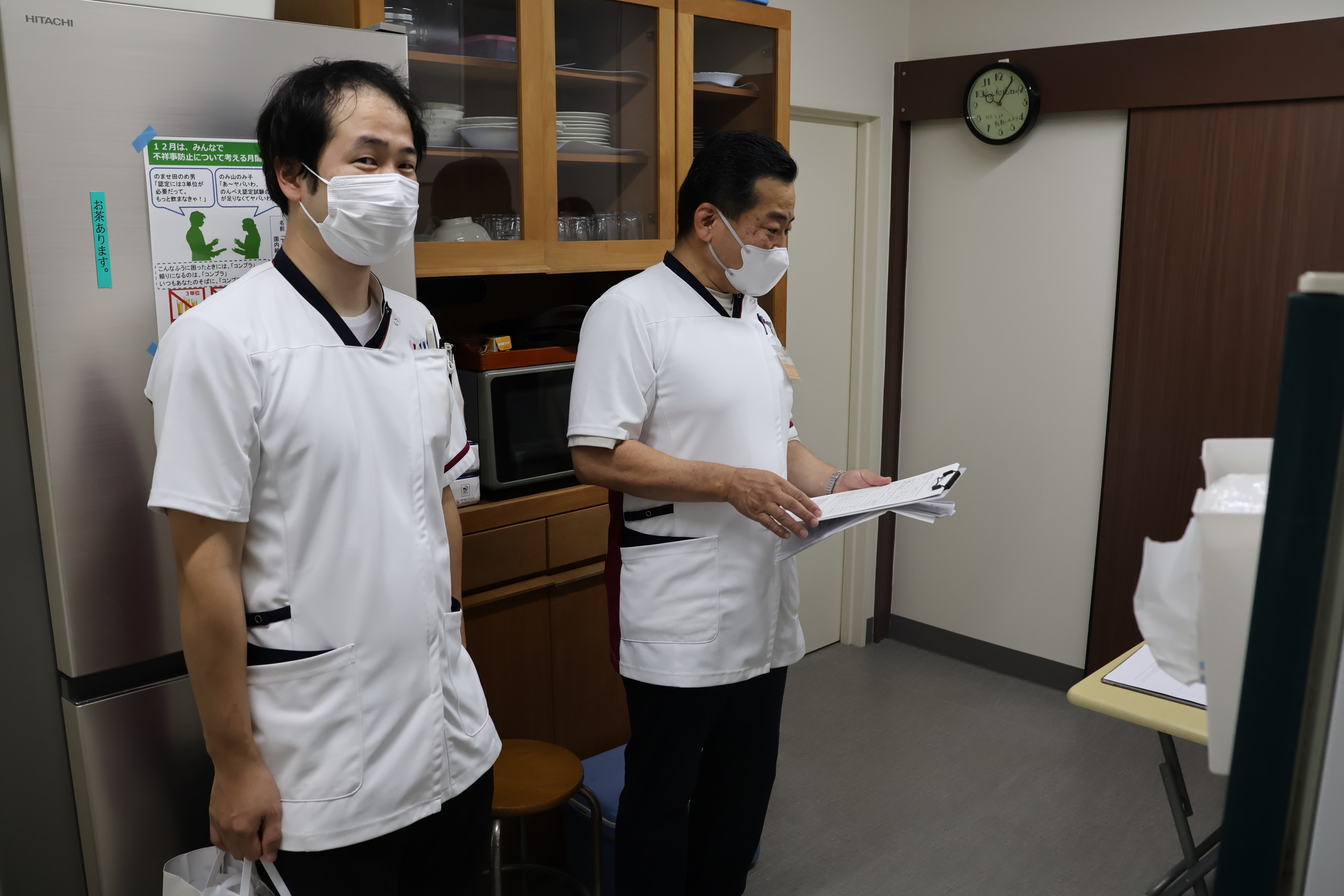


◎9.11と禎子さんの折り鶴(9/13)
いま、読み始めた、『現代思想入門 千葉雅也著』の冒頭にはこう書かれています。
「大きく言って、現代では「きちんとする」方向へといろんな改革が進んでいます。これは僕の意見ですが、それによって生活がより窮屈になっていると感じます。(P12 )「現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。それが今、社会および自分自身を秩序化し、ノイズを排除して、純粋で正しいものを目指していくという道を歩んできました。そのなかで、二〇世紀の思想の特徴は、排除される余計なものをクリエイティブなものとして肯定したことです。」(P14)・・・この著書は、教育そのものについて言及しているわけではありませんが、多様な視座や視点から、社会を視つめてみることへのヒントになるような気がしています。(読み手の勝手な解釈ですが)引き続き読んでいこうと思います。社会は何と何がつながっているのか考える記事として山陽新聞(9/12)の記事を紹介します。

◎なんということでしょう
ビフォアー・アフター・ヒナセチュゥ!


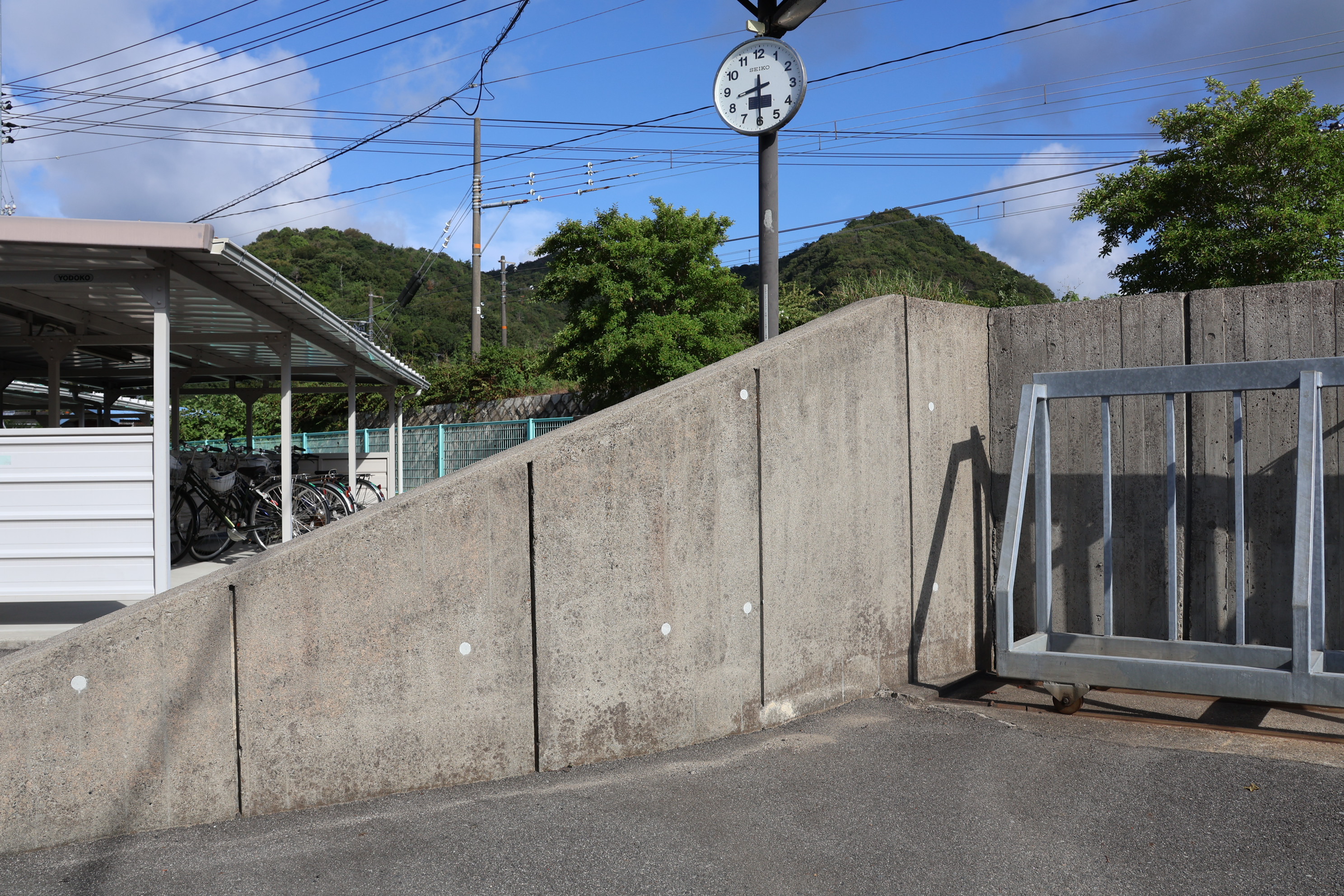



◎未来を拓く私たちの学校生活(9/12)
学校経営(AP)アクションプランについて、岡山教育事務所から東学校経営アドバーザー、大橋指導主事、備前市教委から坪井先生が来校されました。授業参観と「家庭学習」などについて協議しました。また、ひな中ホットスペースも見学していただきました。
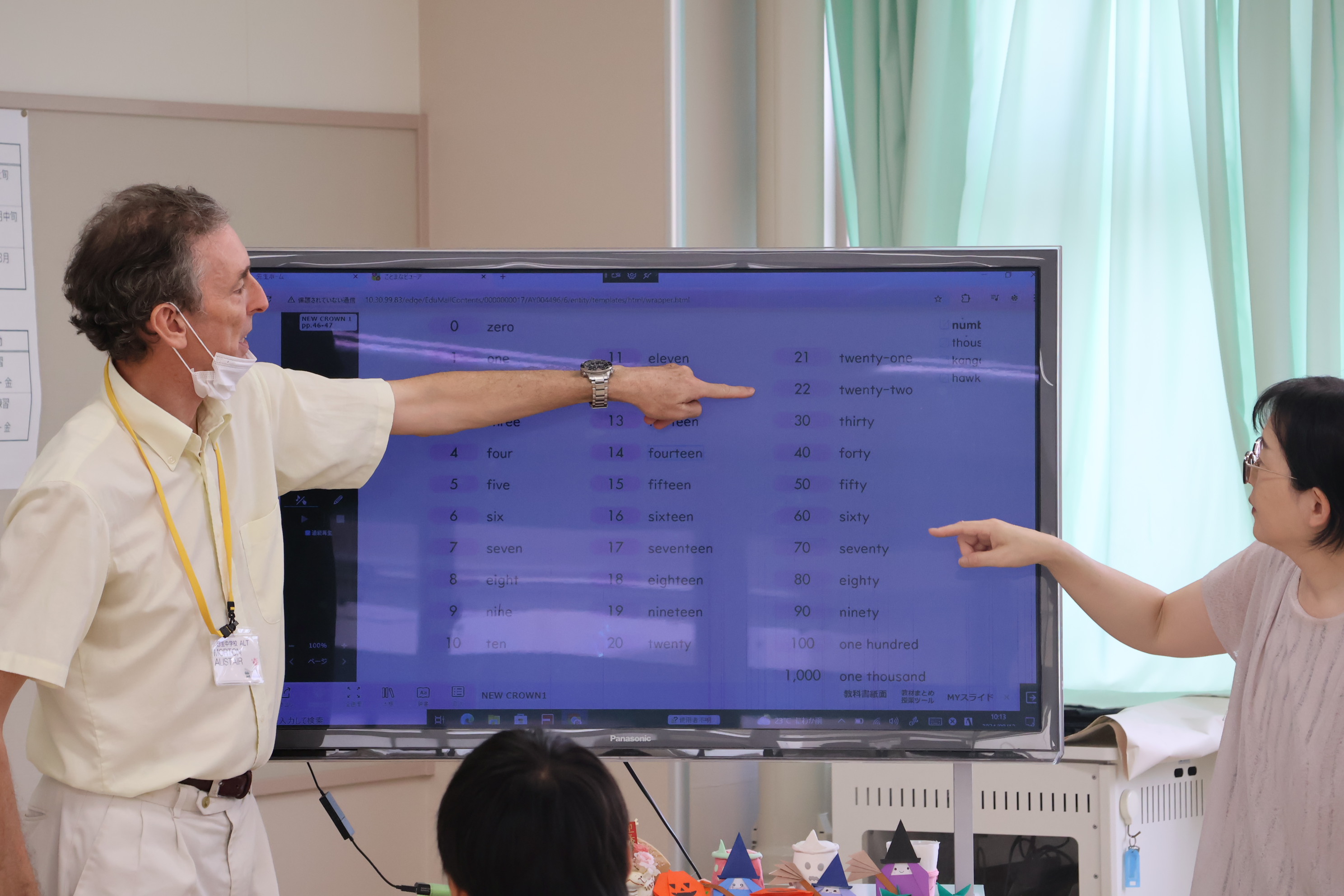

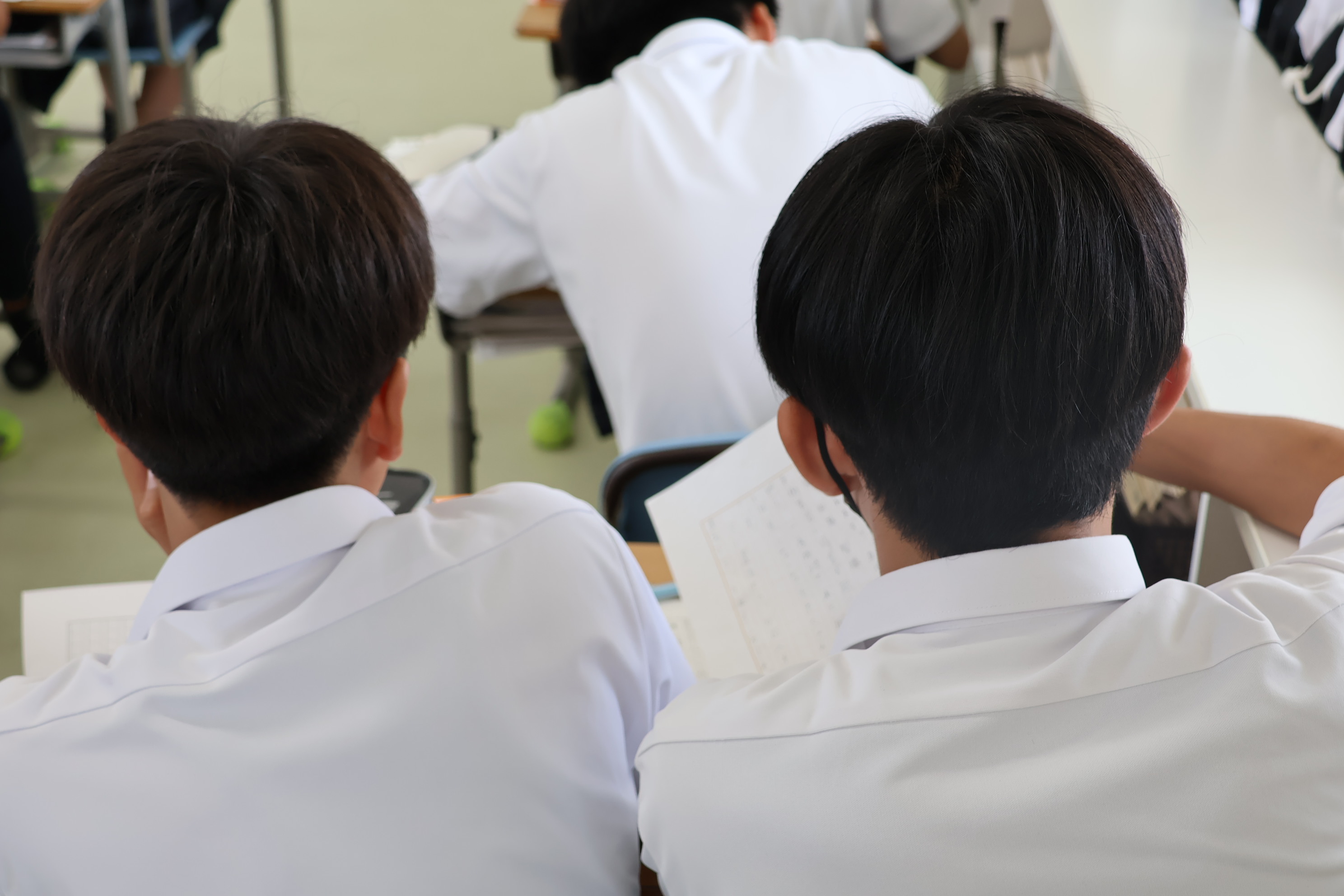

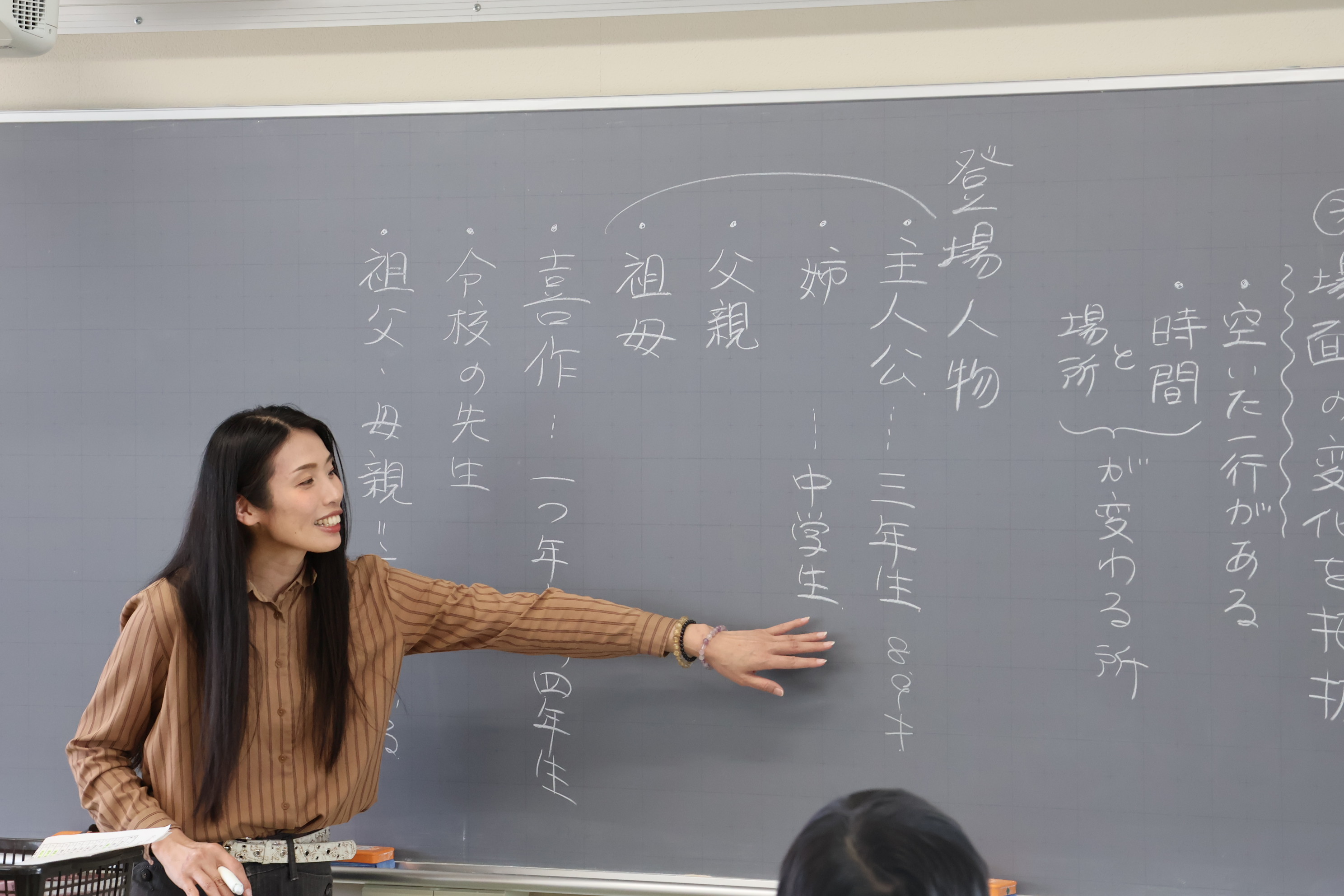
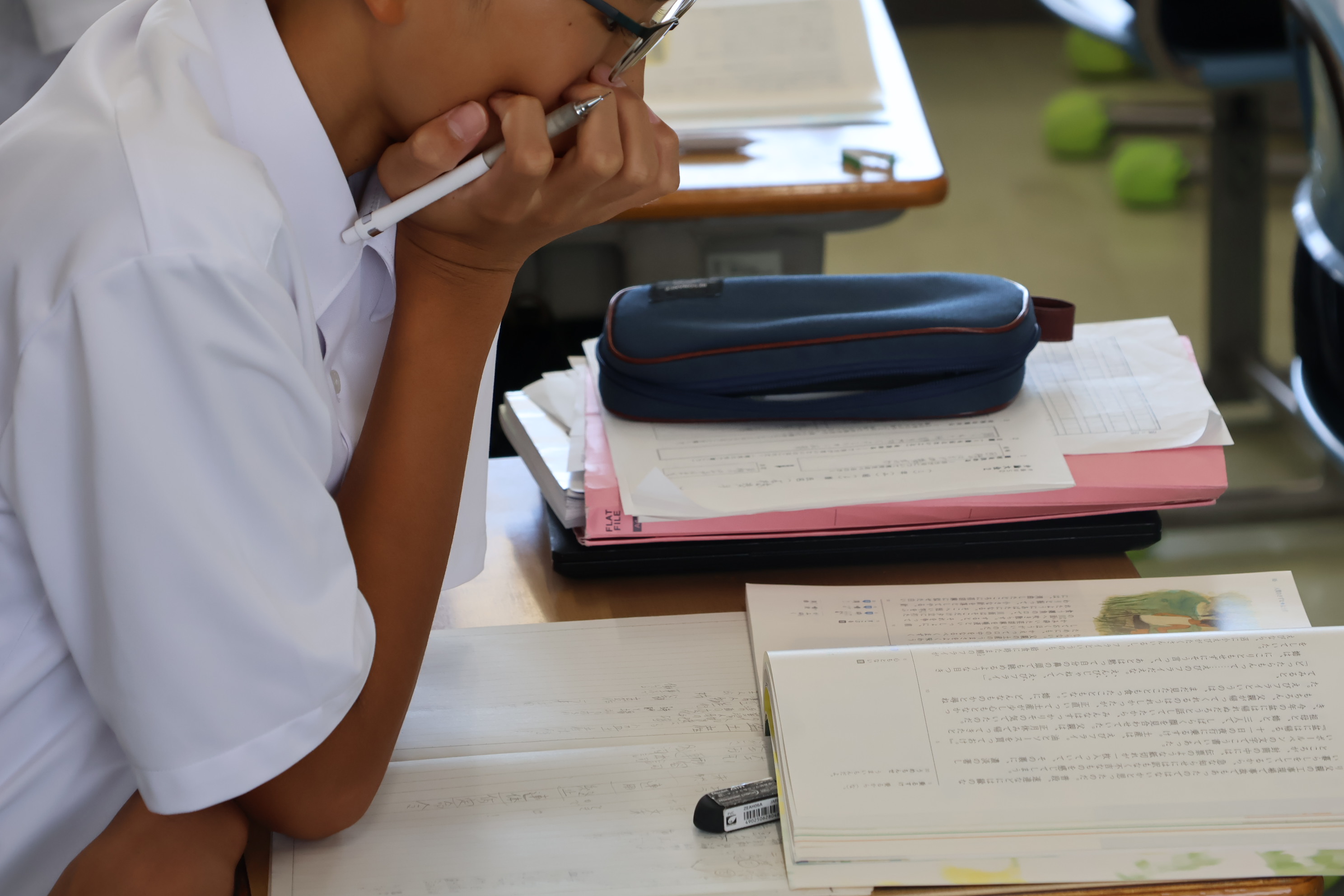
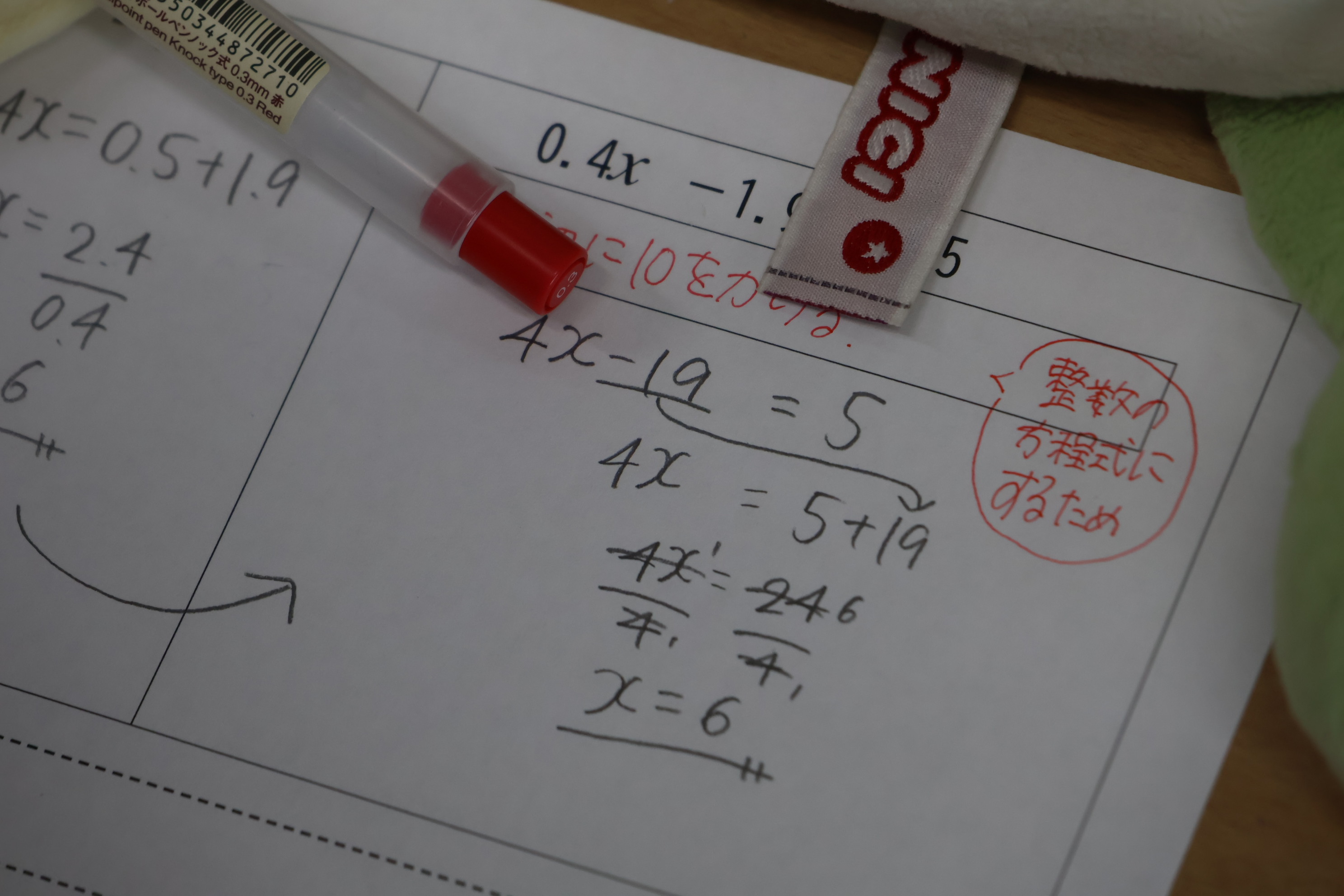


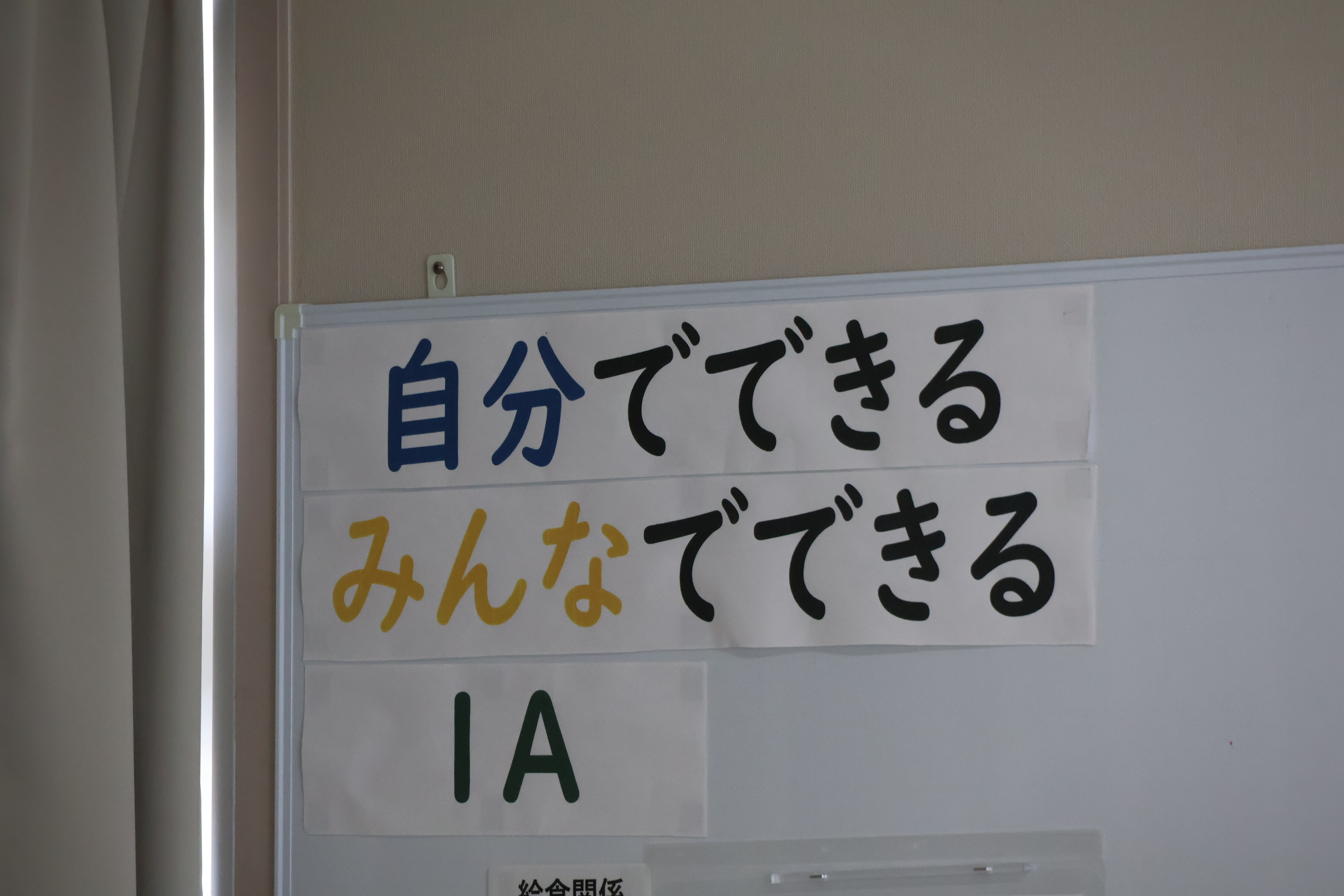


♬探しに行こうぜマイフレンド 海が見えるカーブの向こうへ
焦らないでなるべくスロウで 風の凪いだスピードで
なあきっと消えないぜ 目に映るもの全て
煌めく愛も嘘も傷も全て まあそれはそれで(LOST CORNERより)

〈今週も生徒会あいさつ運動〉
◎HINASE LEGACY(9/12)

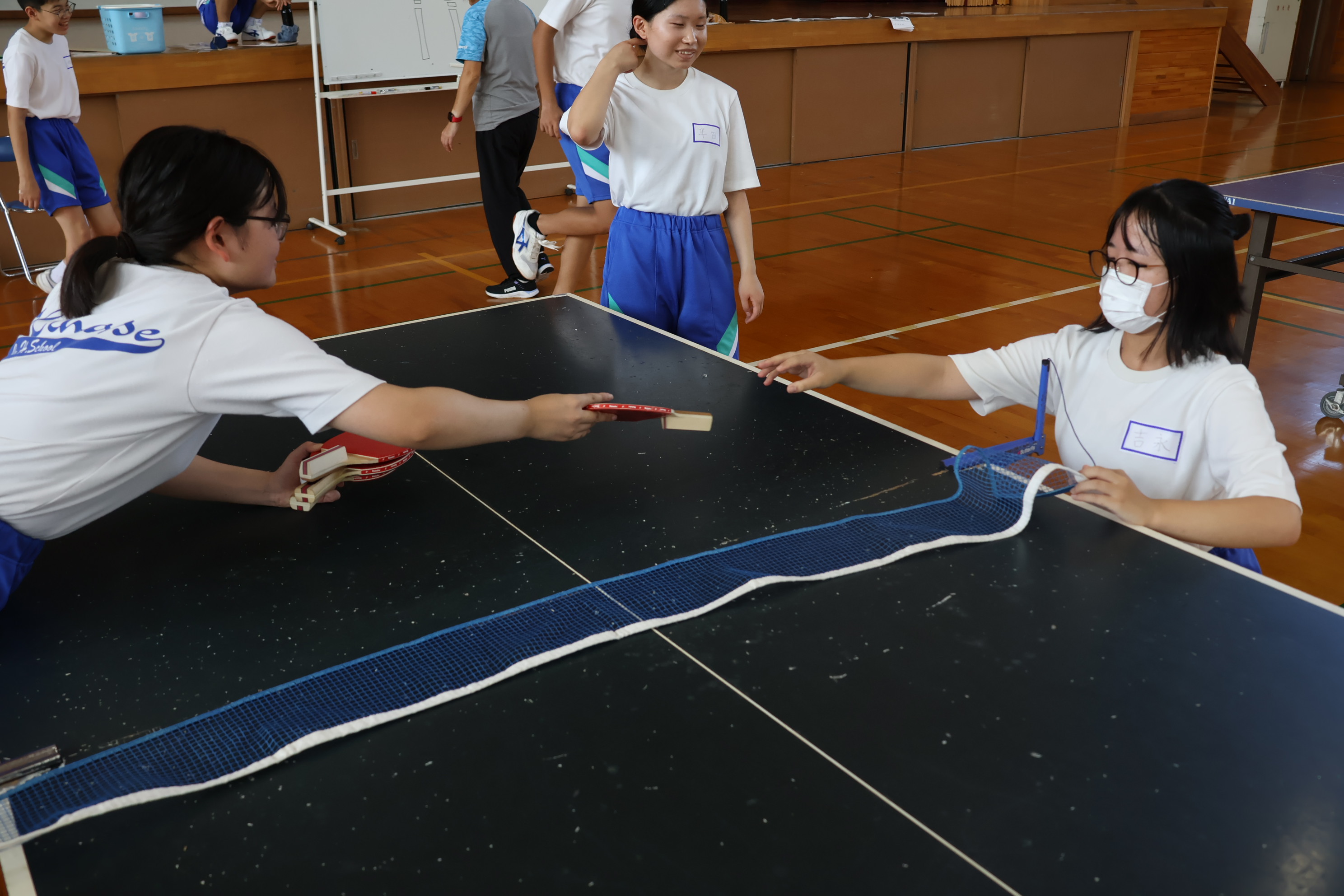




◎進む 進め 進むとき 9.26選挙✨
選挙ポスター掲示(9/11)
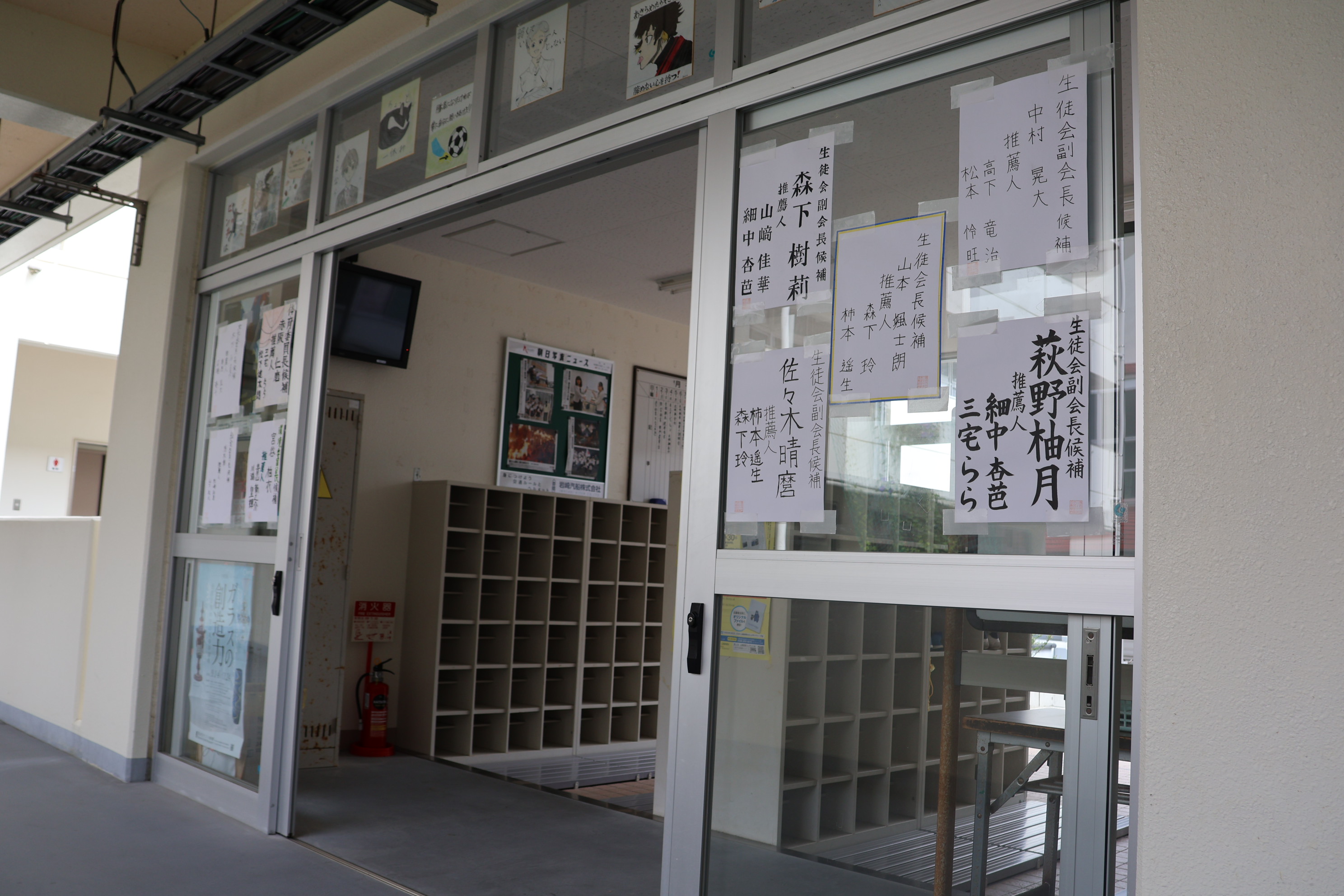
〈硝子扉の外はまばゆき朝なれば裁かるるごと風に入りゆく 中山 明〉
◎ひな中の風✨仲間とともに(9/11)
まだまだ厳しい暑さですが、みんなガンバロウね!



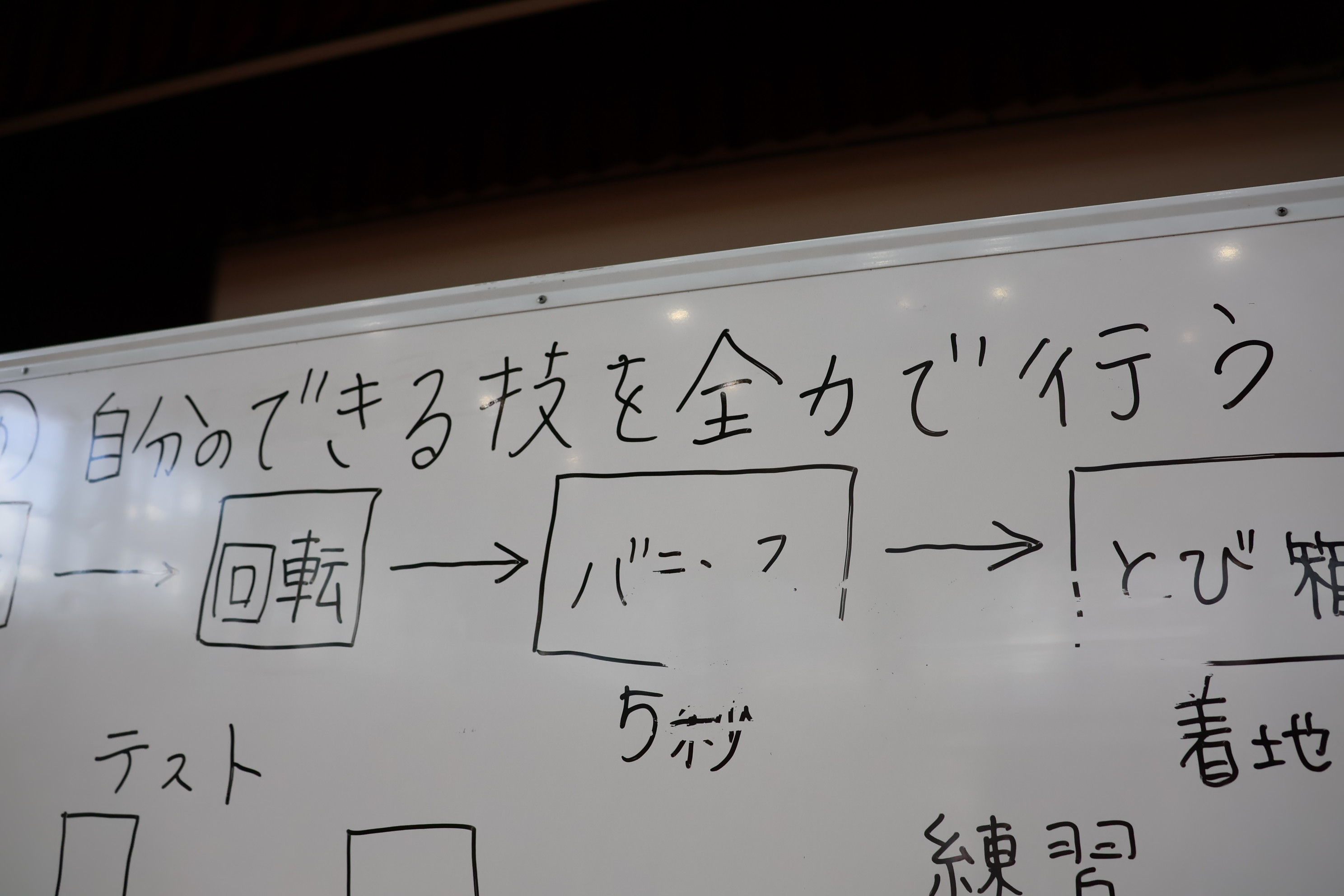


◎9.11の日に
今日、山陽新聞(9/11)には、日生地域の記事がたくさん掲載されていましたので、いくつかをピックアップして「ひとのあいだ」を発行配布しました。そんなこともあり、新聞を活用した取組について紹介します。NIE(エヌ・アイ・イー)は、「Newspaper in Education」といいます。日本では「教育に新聞を」と訳しています。新聞を教材として学校教育に役立てようという取り組みです。生徒に社会への関心を高めてもらうとともに、「情報を読み解く力」「考える力」「問題を解決する力」などを身につけてもらうことを目的としています。おりしも今日は、9月11日。2001年9月11日にイスラム過激派テロ組織アルカイダによって行われたアメリカ合衆国に対する4つの協調的なテロ攻撃があった日です。9.11事件(きゅういちいちじけん)や、9.11(きゅうてんいちいち)などと呼称される場合もあります。この一連の攻撃で、日本人24人を含む2‚977人が死亡、25‚000人以上が負傷し、少なくとも100億ドル(日本円換算1兆1465億9500万円)のインフラ被害・物的損害に加えて、長期にわたる健康被害が発生したといわれます。アメリカの歴史上、最も多くの消防士と法執行官が死亡した事件であり、殉職者はそれぞれ343人と72人でした。また、この事件を契機としてアフガニスタン紛争 (2001年-2021年)が勃発し、世界規模での対テロ戦争が始まりました。この出来事から23年が経ち、現在も多面的・多角的な見方や捉え方での様々な議論があります。新聞を含めて、多様な情報・メディアを正しく読み取り(リテラシー)、行動につなげていく力を養ってほしいと思います。

◎仲間と共に、9.15定期演奏会 9.21・22秋季総体に向けて。
~鍛えられるのはいま(9/10)





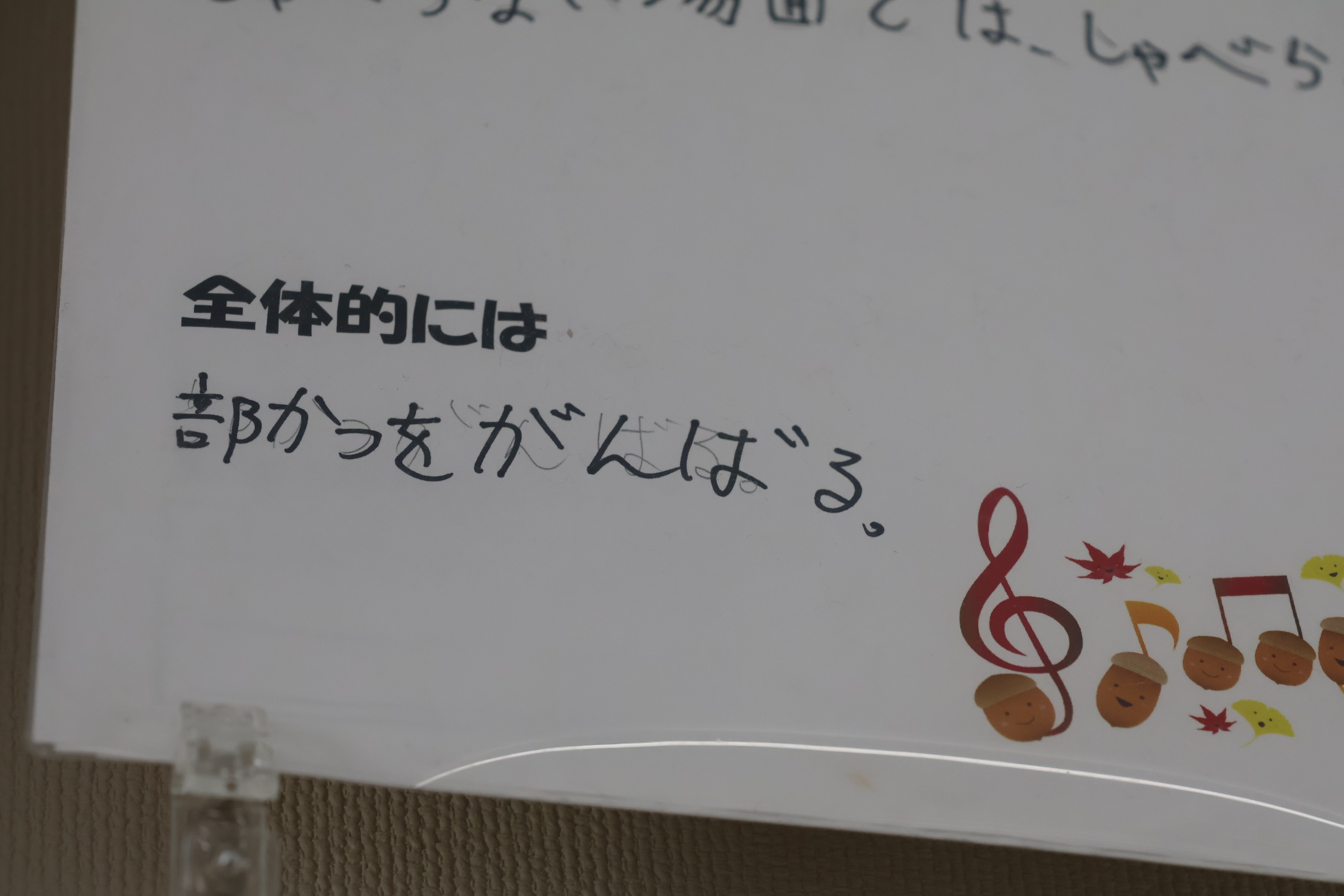
◎多くの人に支えられて(9/10)
学習環境を整える~
雨天時に雨水が入っていた玄関前廊下をDIYしました。傾斜のついたシートシステムを作製(手作り)し、雨水侵入を防ぎ、廊下が濡れて滑るのを防止します。立川先生ありがとうございました。

◎私たちのはじまりの風景17(9/10)
Mas Que Nada ここはどこででしょう??





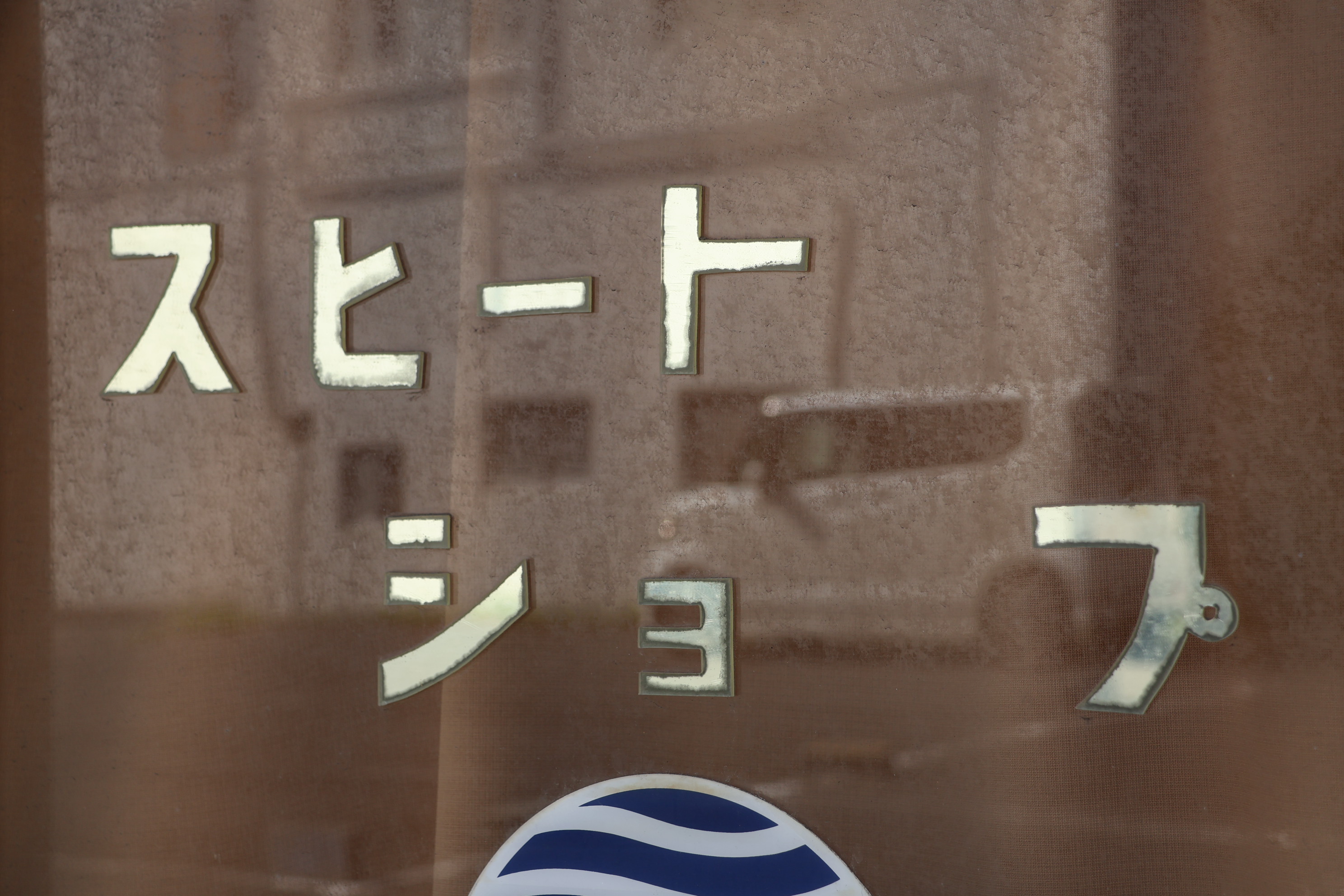
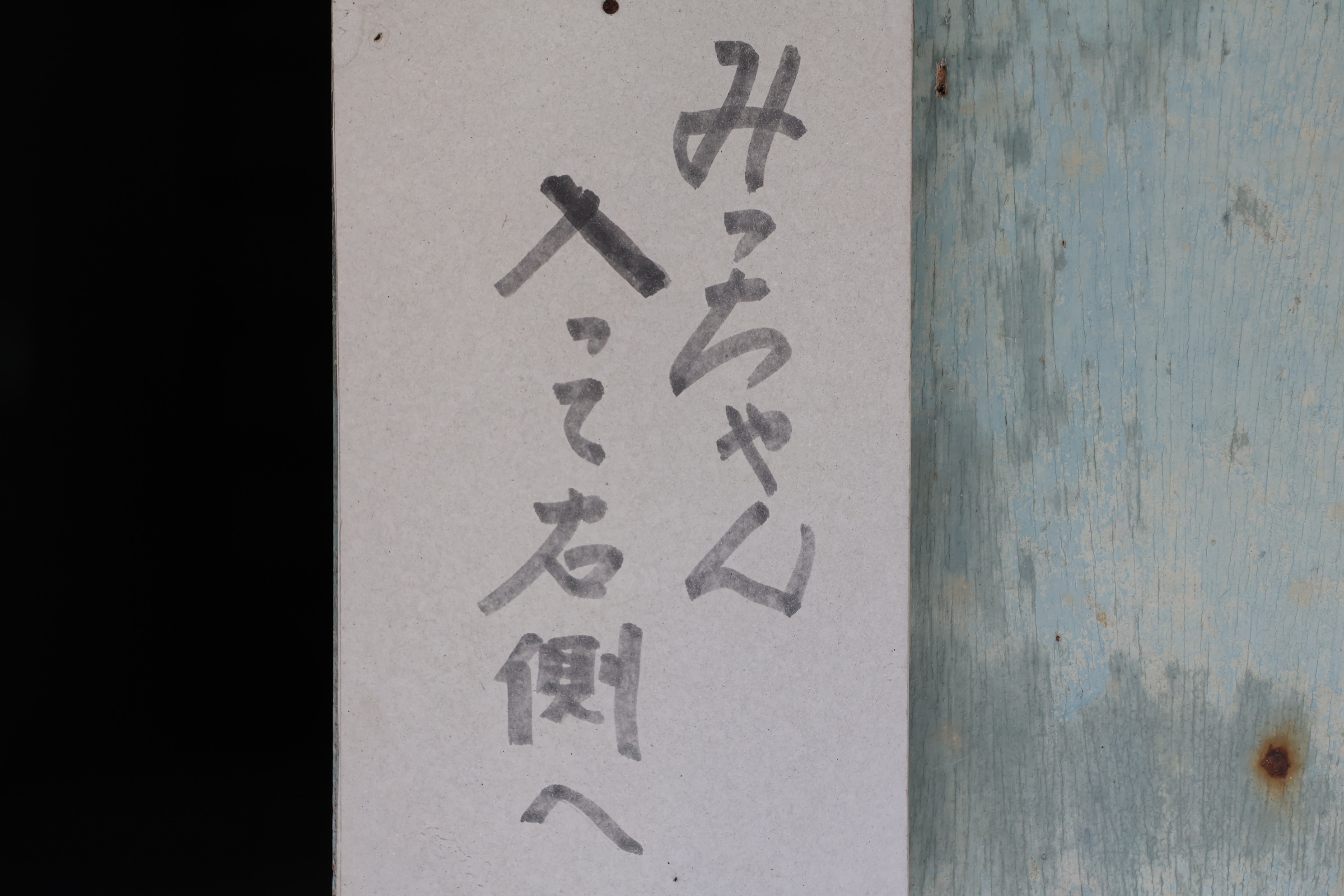


◎「おはよう∈^0^∋ おはよう(*^▽^*)」
今日も、委員会によるあいさつ運動(9/9)

◎真の多文化共生社会・インクルーシヴ社会へ一歩一歩。
今年も、 備前市手をつなぐ育成会賛助会員募集(9/9~)
「わたしたちは、いろいろな障害がある人たちが、一人のもれもなく、家庭・学校・職場で、また、地域社会のあらゆる場で、人間として明るく幸せに生活することができるように、お互いに力を出し合い、手をつなぎ合っていかなくてはなりません。そして、人権意識の高揚と、障害がある人の社会への「完全参加と平等」の実現に努めていきたいと考えております。
このような考えにたって、本会では、特別支援教育の啓発と推進、手をつなぐ親の会の育成などの事業をすすめてまいりたいと思っております。どうか、こうした趣旨にご賛同いただき、多くの方々が本会へご加入くださいますようお願い申し上げます。
なお、会員は毎年更新することになっており、会費は年額一口百円で、何口拠出いただいても結構です。また、この会は次の役員によって運営されております。」(趣意書より)
どうぞよろしくお願いします。

◎日生で輝く 日生が輝く 未来へ進む(9/7:頭島あかりまつりへ参画)
「ひなせみなとまつり」、「日生の応援団」活動などに引き続き、ボランティア推進プロジェクトのひとつとして、「ひな中日生もりあげ隊」が出店してきました。小さな子どもたち対象のお楽しみくじや、暑さ対策の冷たいフルーツシャーベットを提供(完売)し、来場された多くの方々に喜んでいただきました。ありがとうございました。

今後も、ひな中ボランティア推進プロジェクトへの依頼があります。進路を考える学習体験として、ま たボランティアに取り組んでみたいと思う生徒は一度チャレンジしてみよう!
子どもたちが主体となる「まちづくり」は、これまでも住民の主体的な参加によって住民自治を育みながら地域共同体として行われてきました。この活動は、各地で豊かな実践がすすめられ、様々な立場の人との出会いや連帯が生まれ発展してきた歴史があります。そんな実践から導かれたキーワードは「協働」と「参画」です。一つの目標に向かってともに情報を共有し、ともに協力して活動に取り組む「協働」と、様々な活動に企画段階から参加していく「参画」です。現在、子どもの命と人権を守り、育ちを支えるまちづくりの必要性は、ますます高まっていると思います。だからこそ、学校(こ・園・小・中)と家庭・地域、そして子どものために活動する様々な人々との協働といったボトムアップの活動がとても大切だと考えます。「子ども(学校)を支え、育てる未来のまちづくり」に向け、多くの方々、関係機関等の協働と参画をどう構築していくのか、取組を重ねながら、確かなあり方を明らかにしていきたいと思います。(地域連携担当)
◎私たちで創るうた、私たちをつくる歌。
〈星輝祭文化の部・合唱練習〉

いまのいまをより美しく、と心がけながら、じっくり生きよう。高くけわしい道を登るととき足に一層の力をこめるように、未墾の土に打ちこむクワには一層の力をこめるように、そのように生きるものが、未来の足音をきいているものである。(1960「定本たいまつ十六年(むのたけじ)より」
◎〈これってどうするん?に応える仲間として〉
進路を切り拓くちからを培う・磨く(9/5)
2学期から、三年生の晩学習がスタートしています。帰りの会の前の〈15分間〉を補充学習に取り組みます。この時間を大切にして、クラスの仲間と共に、進路を切り拓いていきます。(1学期より下校時刻が15分遅くなる日があります)

◎地域とともにある学校(9/4)
ひな中ほっとスペースOPEN。(第1・第4水曜日が開設日!次回は9月18日(水)(*^▽^*))
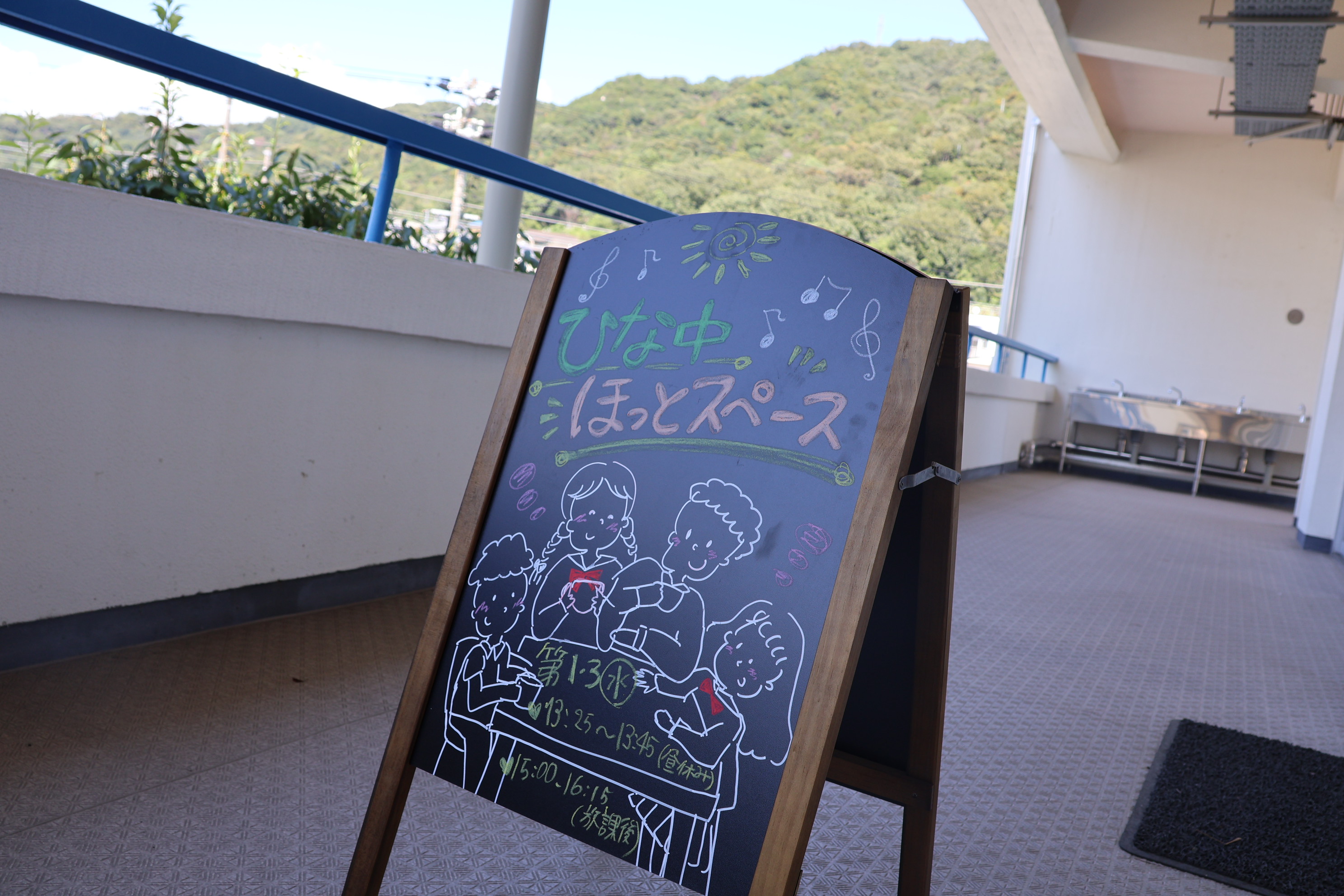

◎地域とともにある学校(9/5)
体育委員会は、自転車鍵かけコンテストを機会に、自転車の管理や防犯についての意識を高める取組を進めます。また。秋の交通安全週間に合わせて、交通安全に関する活動も進めています。
さらに、中学校だけでなく、日生地域全体にも視野を拡げ、日生交番、支所、公民館、観光協会、パオーネ、郵便局、中国銀行、備前日生信用金庫(順不同・敬称略)さんにも働きかけ、委員会で作成したポスター掲示していただく計画を進めています。
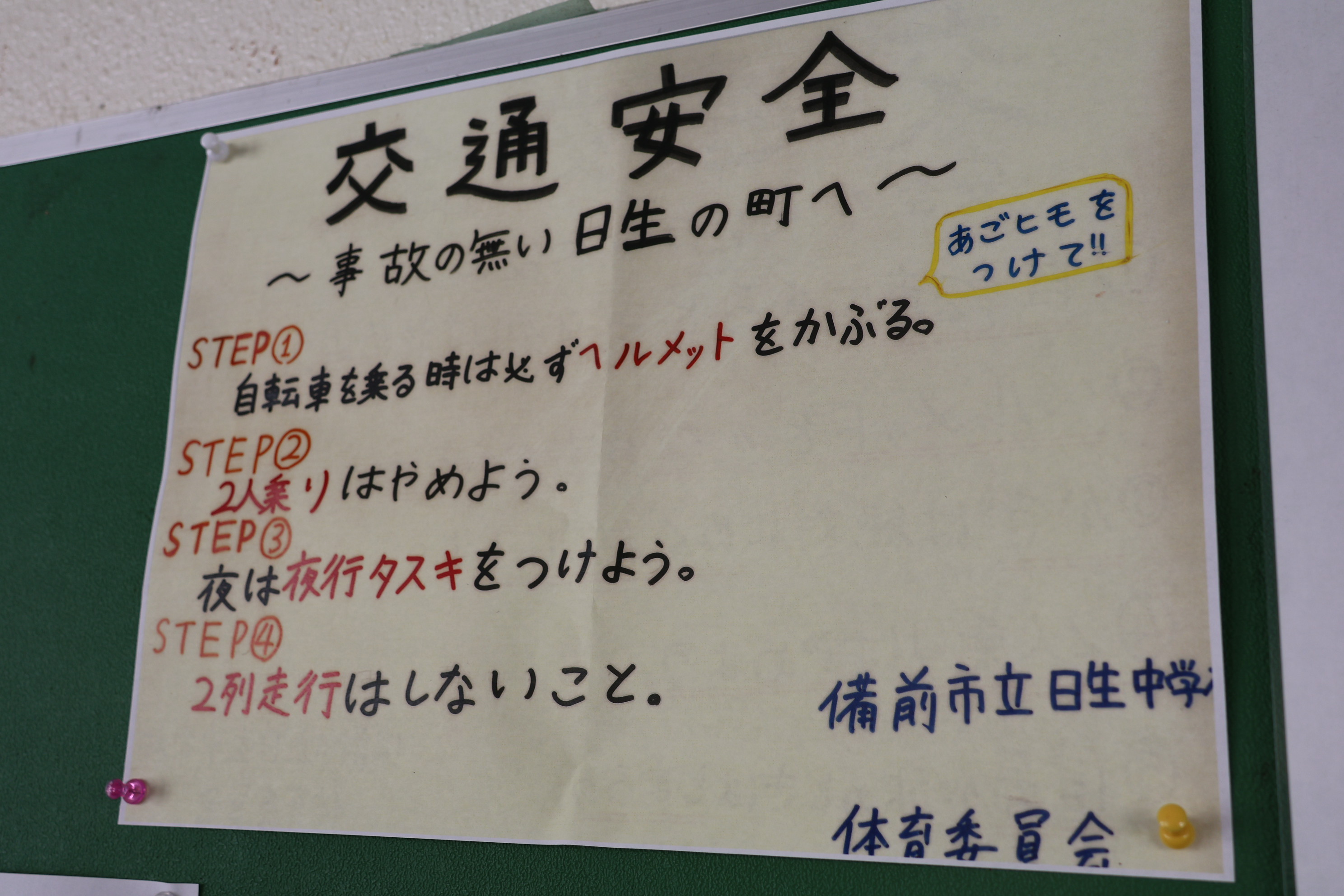
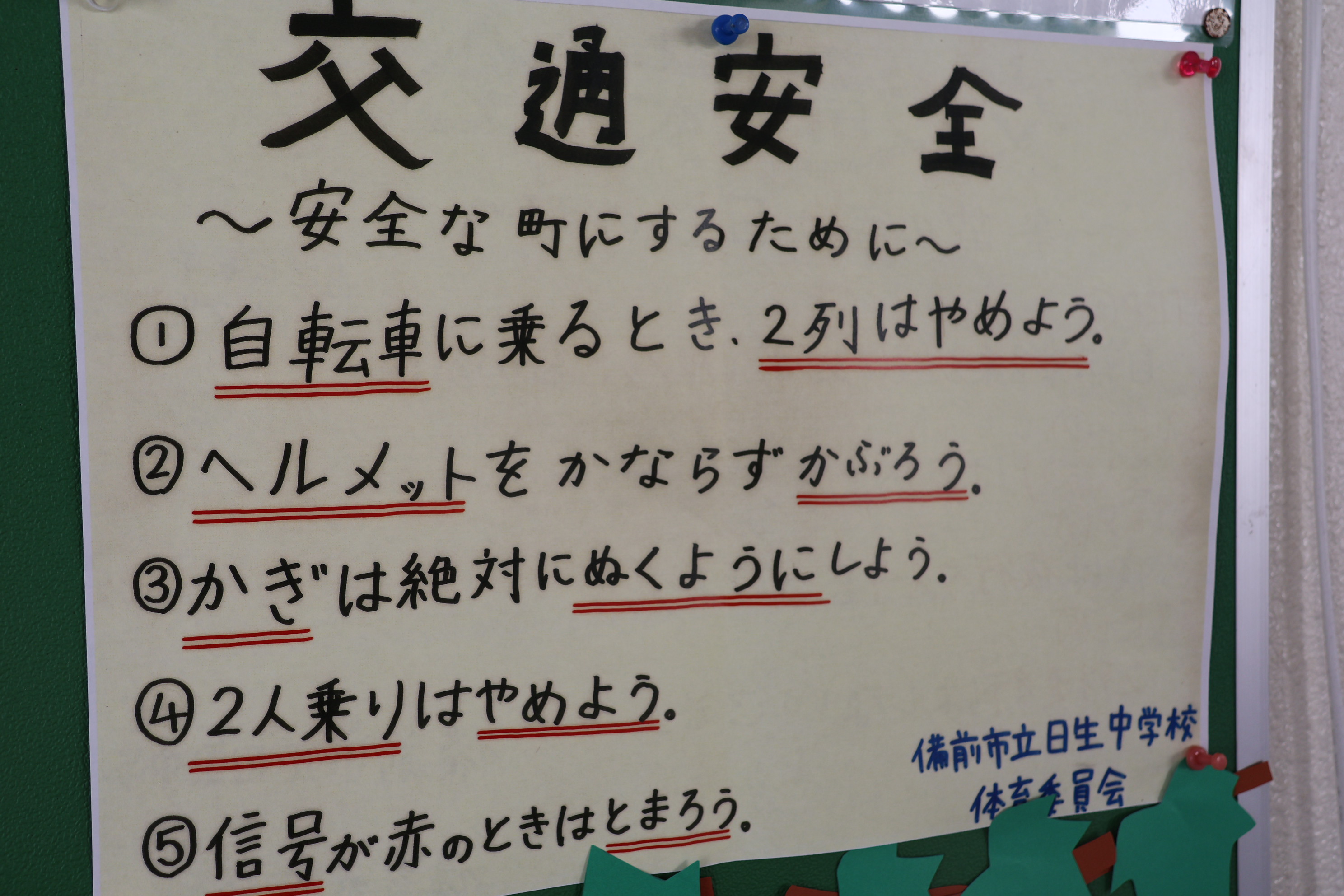
日生で輝く 日生が輝く
◎ひなせっ子あいさつ運動∈^0^∋(9/4)
~多くの人に支えられて。次回(10月2日(水))もよろしくお願いします。

◎日々の学びを大切に~多くの人に支えられて(9/4)
防災給食の取組について山陽新聞の平田さん(9/4)が取材していただきました。
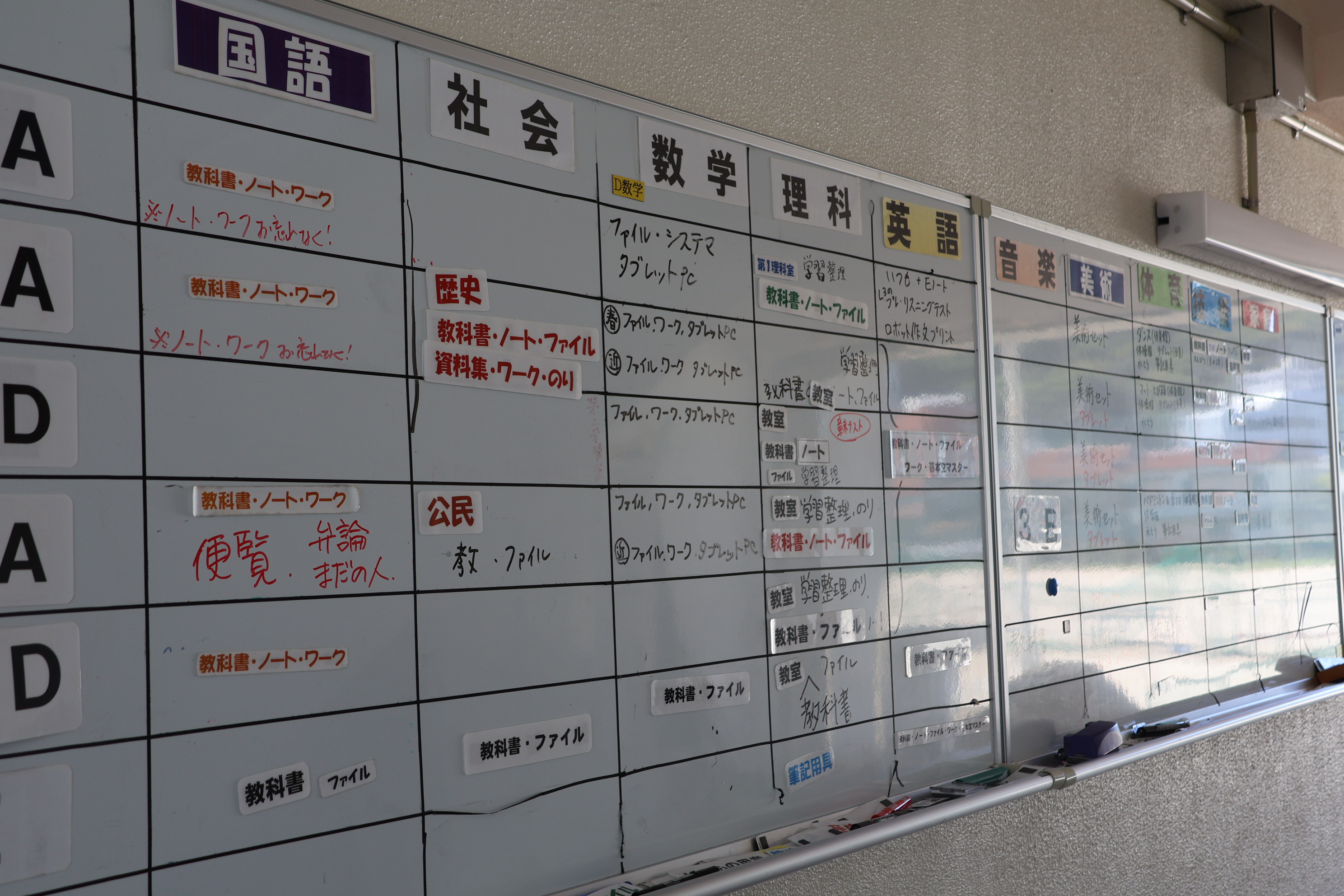
◎9月になって(9/4)
〈抜かれても雲は車を追いかけない雲は雲のやり方がある 松村正直〉
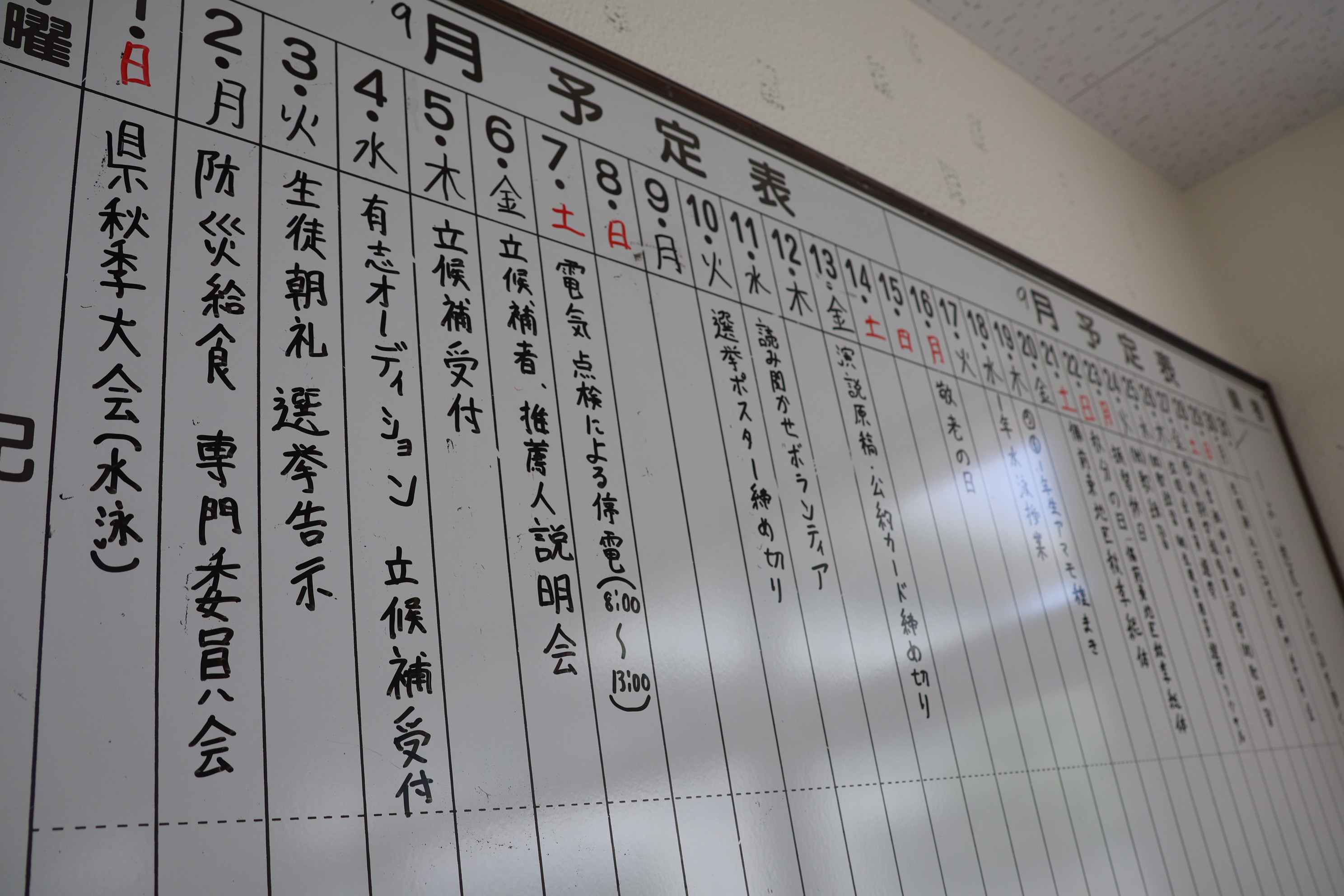

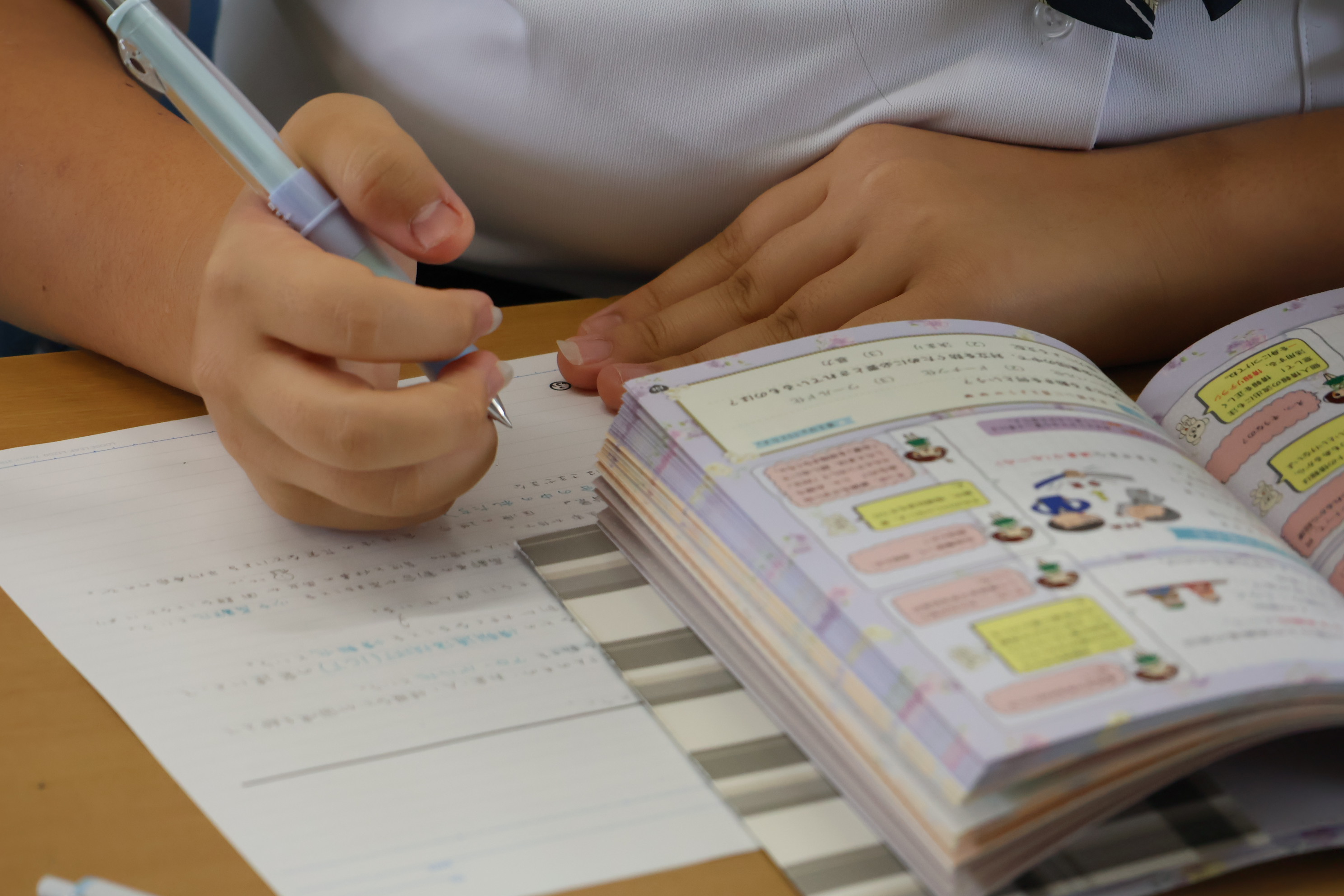

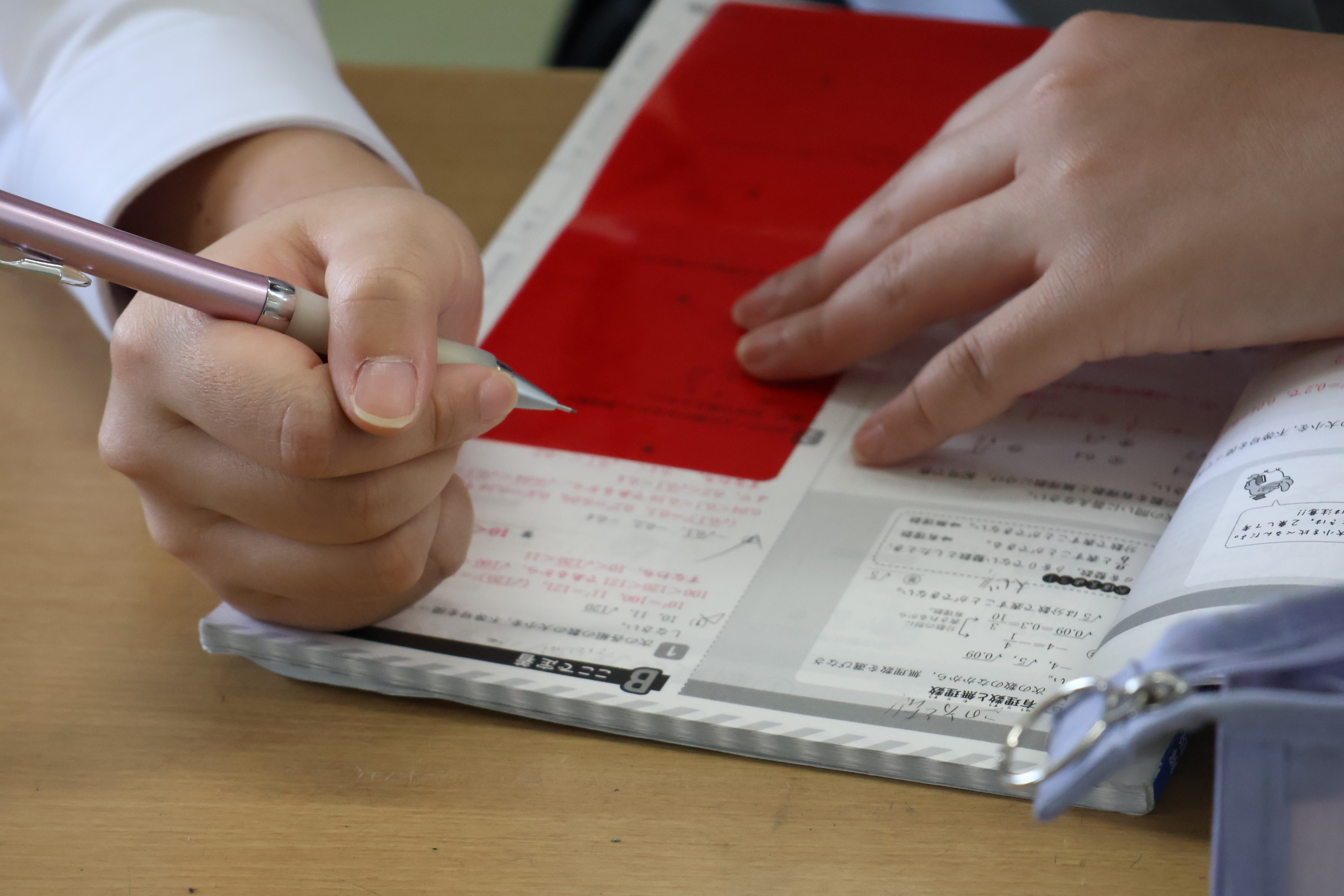

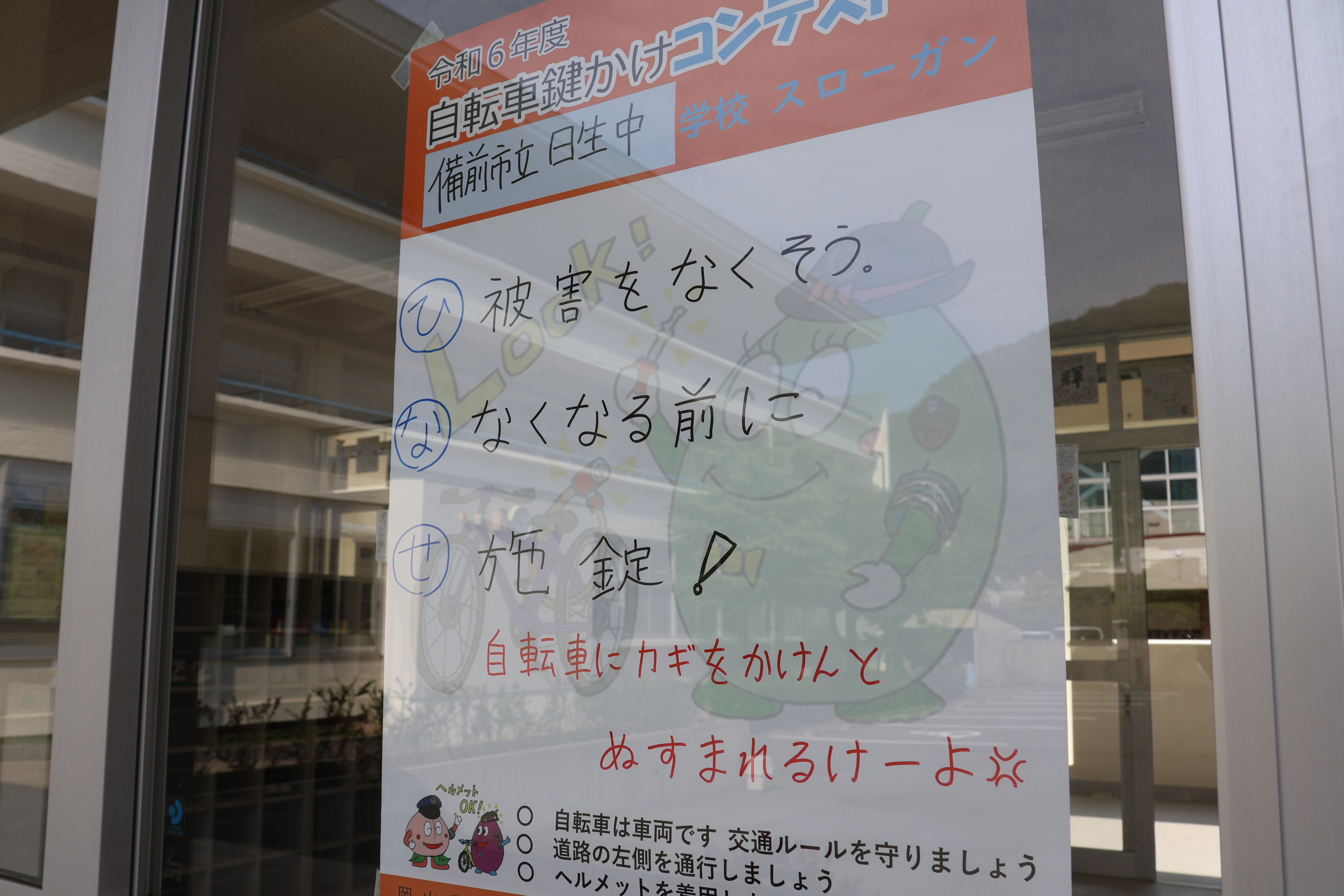


◎シン・ひな中生徒会役員選挙告示(9/3)

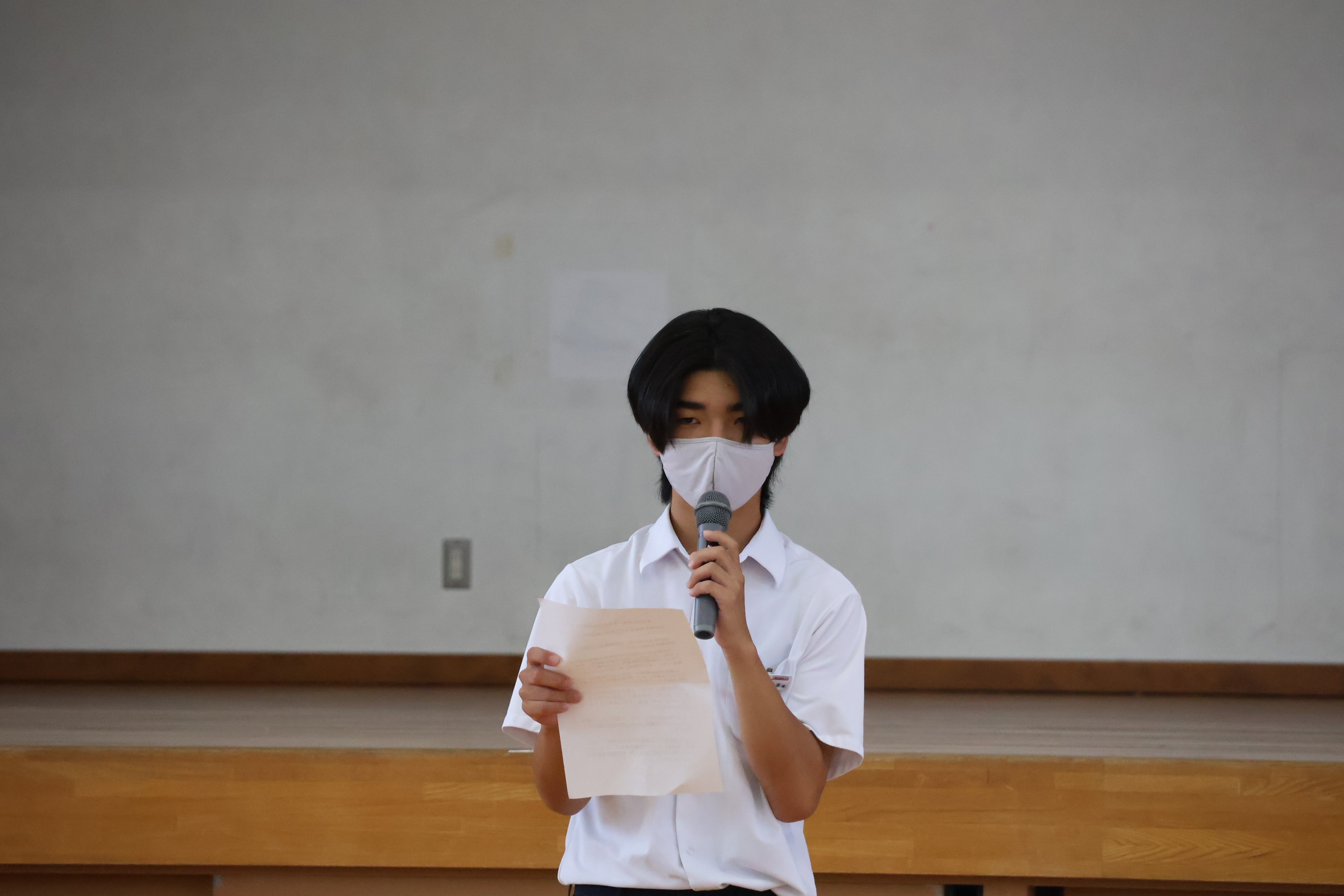
選挙管理委員長からみんなへ
・立候補者(推薦者)受付 ~9/5
・立候補者、推薦者説明会 9/6
・選挙ポスター提出〆 9/10
・マニフェスト提出〆 9/13
・生徒会選挙リハーサル 9/25
・生徒役員選挙 9/26
・学級役員選出 9/27
◎私たちの誇り・創造・絆。生徒集会(9/3)


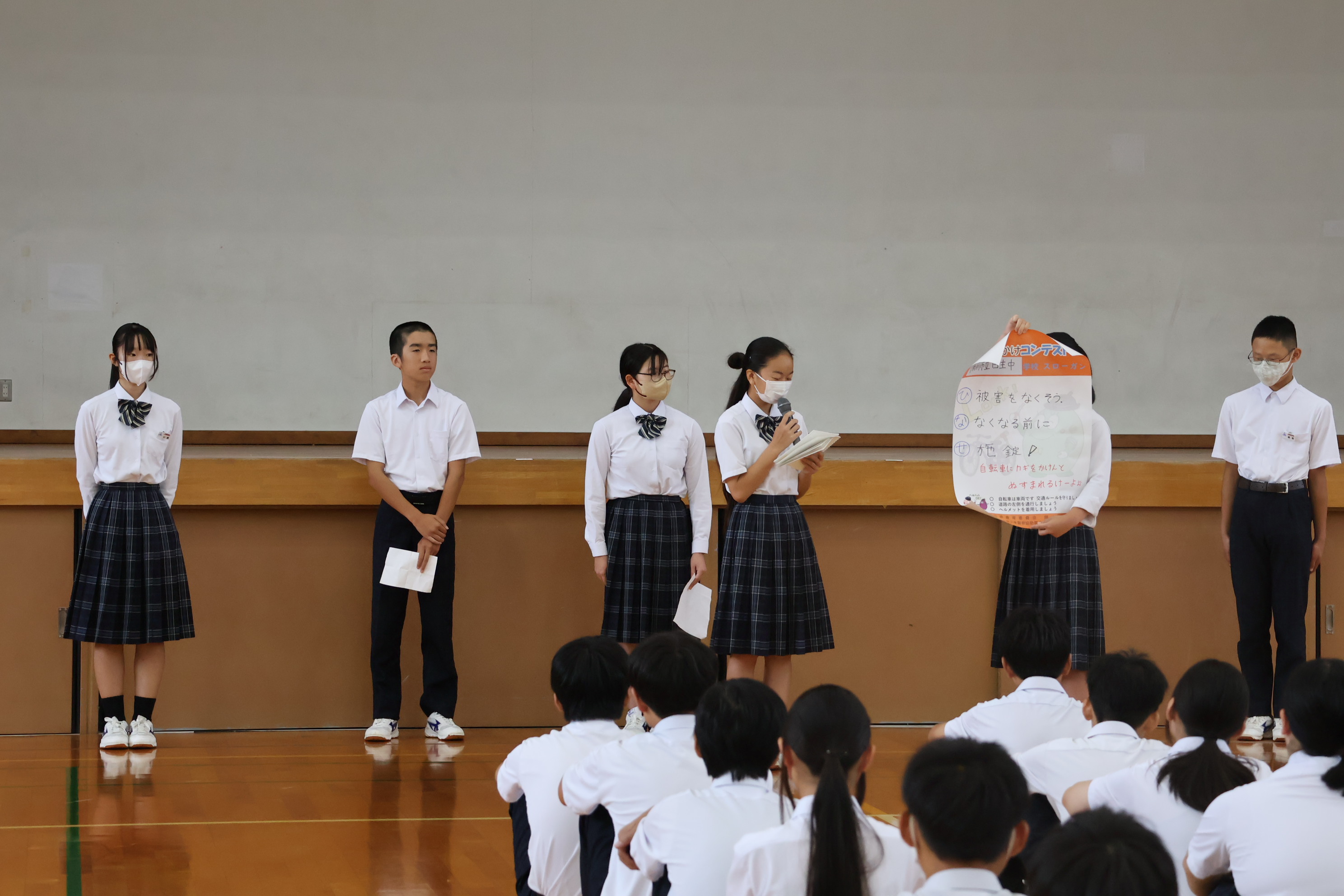
◎地域と共にある学校~日々の学びを発信

NHKニュースWEBで見ることができます。
◎私たちの誇り・創造・絆。委員会活動(9/2)
前期最後の委員会を行い、明日は生徒朝礼での報告です。
後期生徒会活動に向けて、9月3日は生徒会選挙告示があります。





◎日生で輝く 日生が輝く✨
ひな中ボランティア推進プロジェクト~週末(9/7)は、頭島あかりまつりでもがんばります。
ボランティアスタッフ参加申し込み〆切は明日(9/3)です。

◎自分らしく 過ごせる学校で。
いつでも待っているよ(^_^)
相談しよう
話をしよう!
2学期もあなたらしく、自分らしく生きていくために。
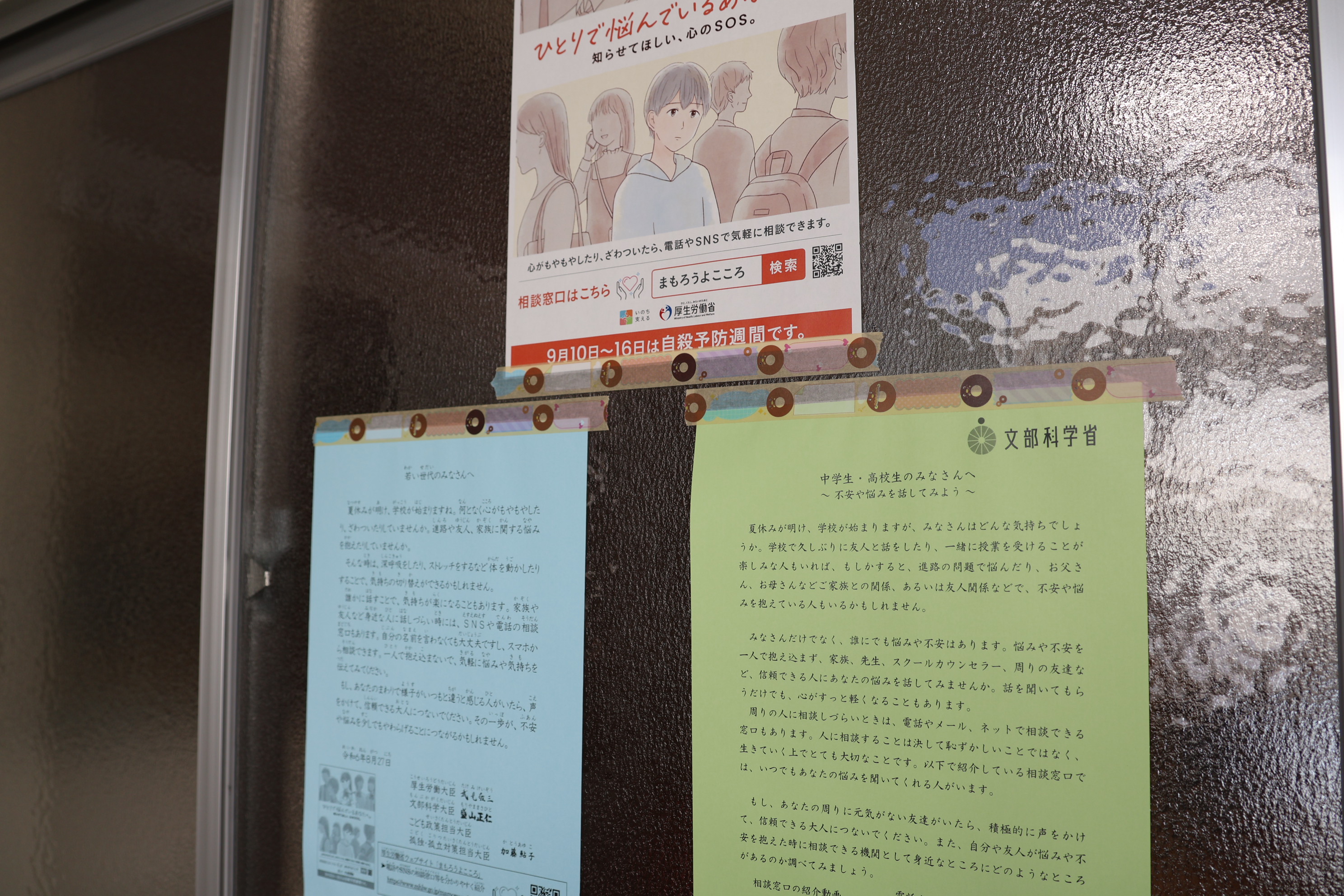
(校長室入口に掲示しています)
◎9.1 関東大震災、今日、防災給食の取組(9/2)
給食委員会からみんなへ 昨日は何の日か知ってますか?
9/1は、1923年に発生した関東大震災の犠牲者をしのび(今年で101年目)、災害からの復興を祈って1960年に国が制定した「防災の日」です。また、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、昭和34(1959)年の「伊勢(いせ)湾台風」によって、大きな被害がでたことも制定の理由です。
そこで、日生中学校でも、今日は、「防災給食」に取り組みます。
大規模震災などの非常時は、電気・水道・ガスや輸送等のライフラインが止まり、普段の食事ができなくなることが想定されます。そこで、災害時の食事をイメージできるように、学校給食に、災害時用に学校に置いておる「救食カレー」を提供していただきました。
さらに、今日の「防災給食」を通して)、「食べ物への感謝の心」や防災に対する意識をより高め、また家族や友達と話し合って考えるきっかけにしましょう。
今日の 献立は、(救給カレー・みかんゼリー、カンパン、牛乳です)。
ちなみに、
「救給カレー」とは、東日本大震災の教訓から、栄養バランス、体力のことを考え、救護物資が届くまでの「いのちをつなぐ」非常食として、全国の栄養教諭・学校栄養職員らが開発したものです。カレーとご飯が入っていて、封を開けるとそのまま冷たい状態でも美味しく食べることができるのはもちろん、国産の原材料を使い、アレルギー特定原材料等28品目不使使用だそうです。
それではいただきましょう。手を合わせましょう。いただきます



◎関東大震災は1923年9月1日に関東地域で発生。10万人以上の死者・行方不明者が出た。地震そのものの被害だけでなく、震災の混乱の中、「朝鮮人が井戸に毒を入れた」「朝鮮人が放火した」などのデマが流れ、自警団や警察、軍人らが在日朝鮮人を虐殺した。大韓民国臨時政府の機関紙「独立新聞」の記録によると、当時、虐殺された朝鮮人犠牲者は6661人とされる。
関東大震災でも拡散したフェイク・デマ 今も変わらぬリスク どうすれば- NHK

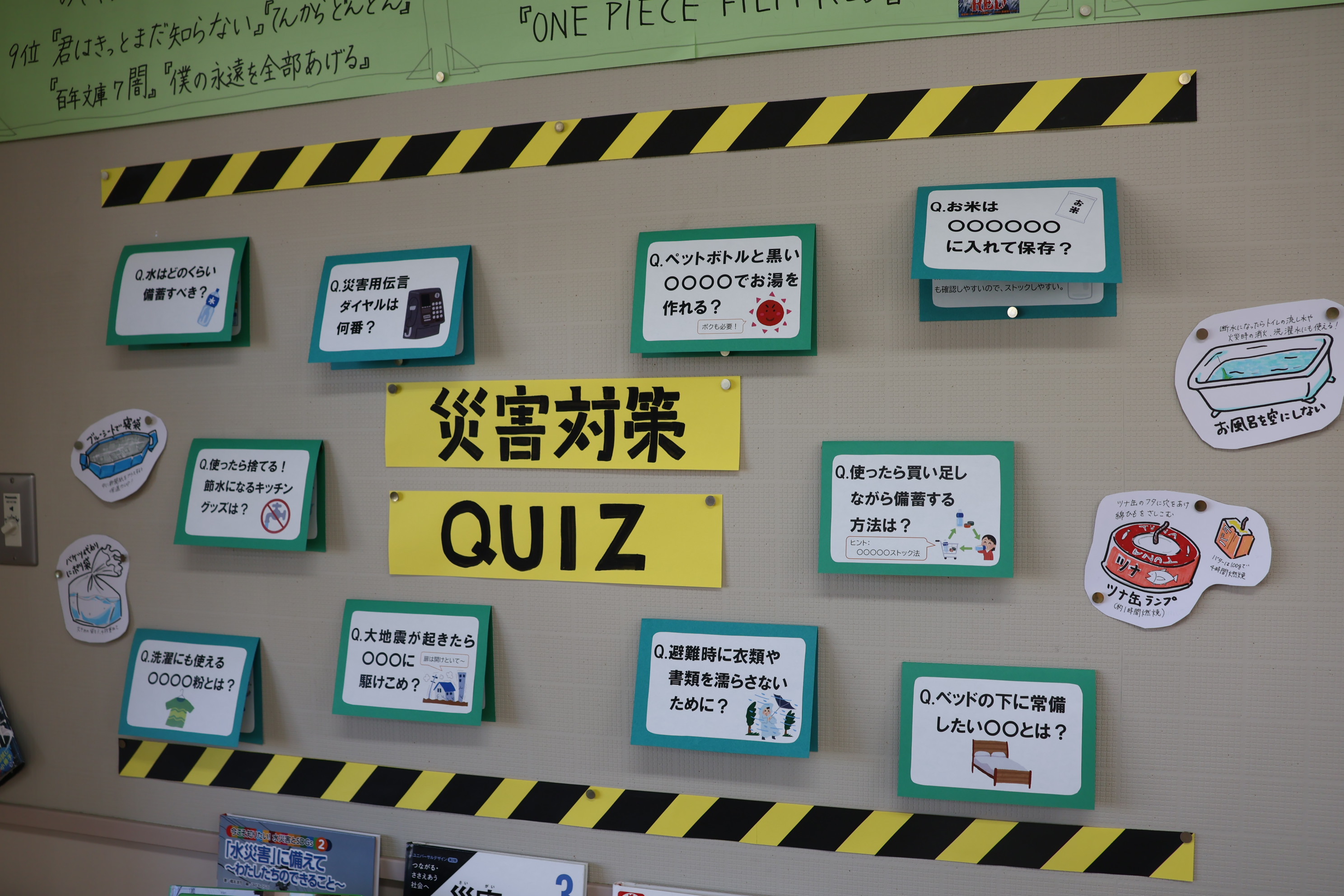
2階廊下掲示 図書室の特別展示
◎「ご安全に」 台風10号接近(8/31)
的確な情報を収集して、自分と大切な家族のいのちを守る行動をしよう。
 雲の動きが、とても速い朝でした。
雲の動きが、とても速い朝でした。 下校時、交通巡回指導中の日生大橋です。雨脚が強くなりました。
下校時、交通巡回指導中の日生大橋です。雨脚が強くなりました。◎〈春15の会〉進路情報交流学習会(8/31)中止のご連絡
春15の会の事務局をしている教頭先生から、学習会の中止連絡がありました。
*8/31の情報交流学習会の《中止》のお知らせ
『2024年度「春15の会」情報交流学習会(8/31開催)には120名を越える方々の申し込み・参加を予定しておりましたが、台風10号の現在及び今後の進路や速度等の状況を考え、警報発令の可能性も高く、参加者の方々の安全確保と、また、会場が避難所として開設準備を行うこと等に鑑み、主催者としては、誠に遺憾ではございますが《中止》とさせていただきます。
これまで、会に向けて、ご準備をしてくださった参加校・団体様には大変感謝いたします。ありがとうございました。
急な中止でご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。
春15の会は、今後も、特別支援教育のニーズのある子どもたちと保護者・支援の方々のための取組を進めていきますので、これからもどうぞよろしくご指導・ご協力をお願いします。』
春15の会実行委員会 委員長 西田 典子 事務局 久次

◎地域と共にある学校へ(8/30)
夏季休業中に地域の方から、学校施設の掲示が更新されていないので直した方がよいのではないか」とアドバイスをいただきました。それを受けて、校舎内の掲示等の点検を行いました。その結果、何カ所か古い掲示もあり、市教委と相談して取り替えを進めています。ありがとうございました。
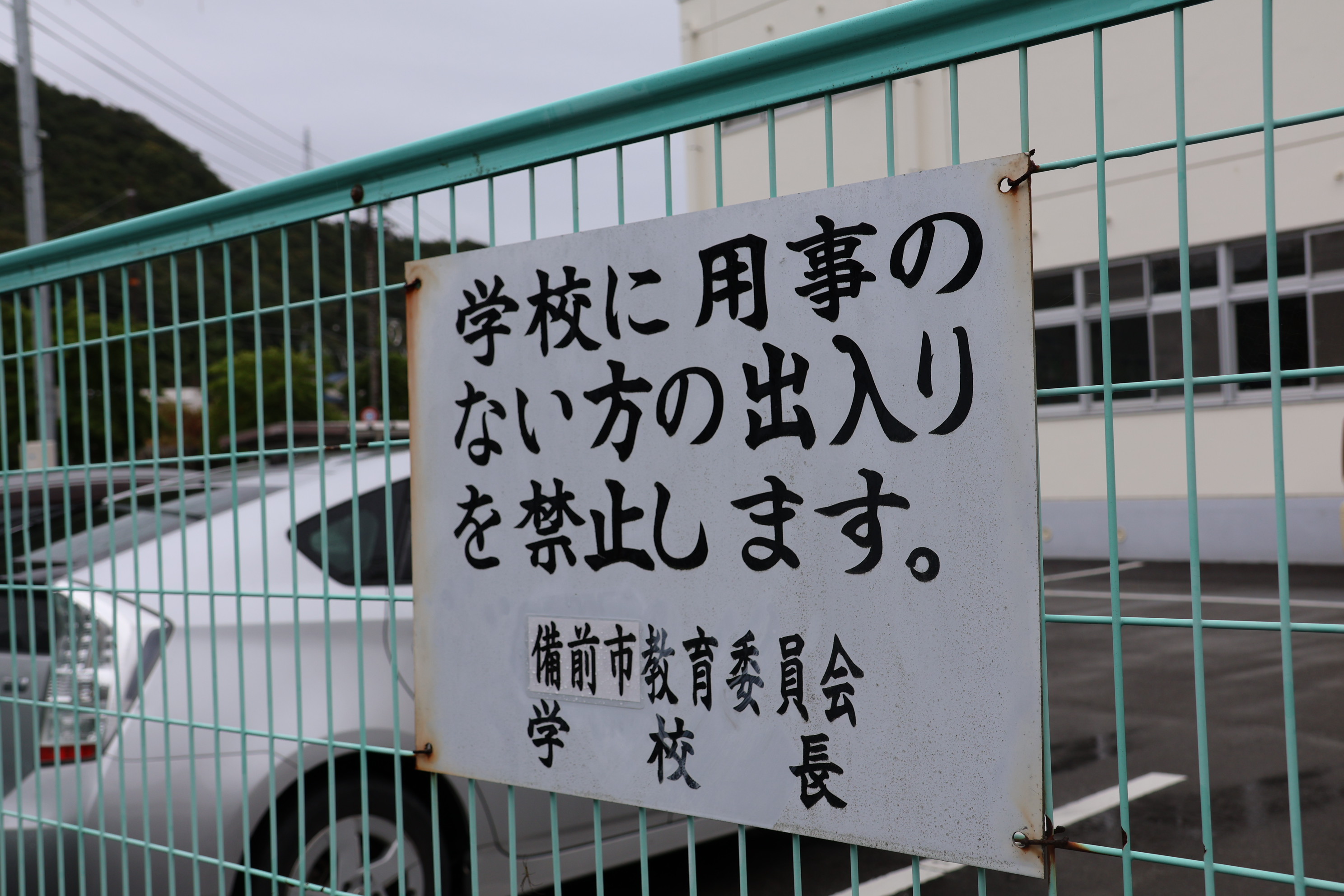
◎挑む!みんな乗り越えよう!到達度確認テスト(8/29)
〈好きだって思ったものを信じてる わたしの道はいつも明るい 武田穂佳〉
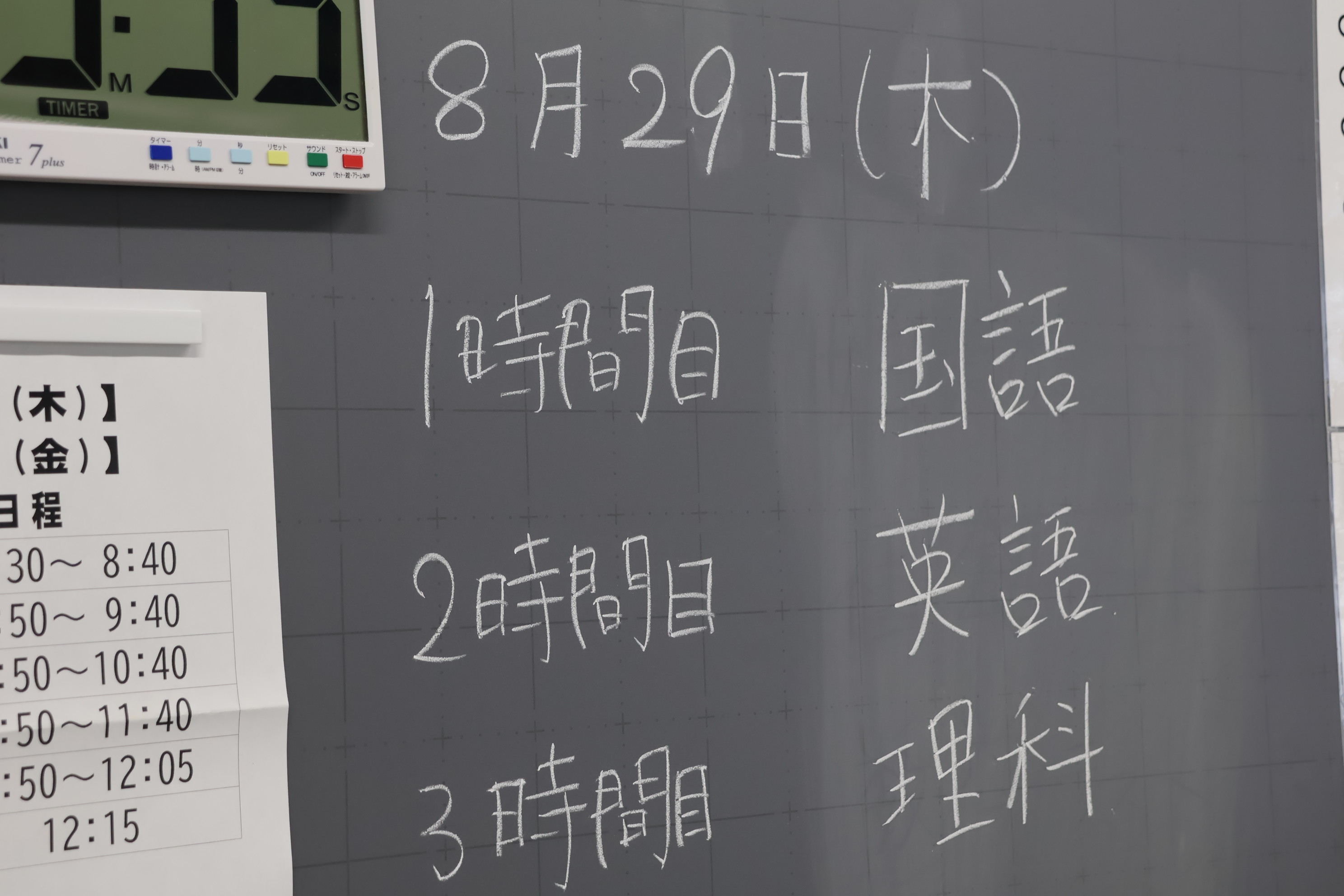
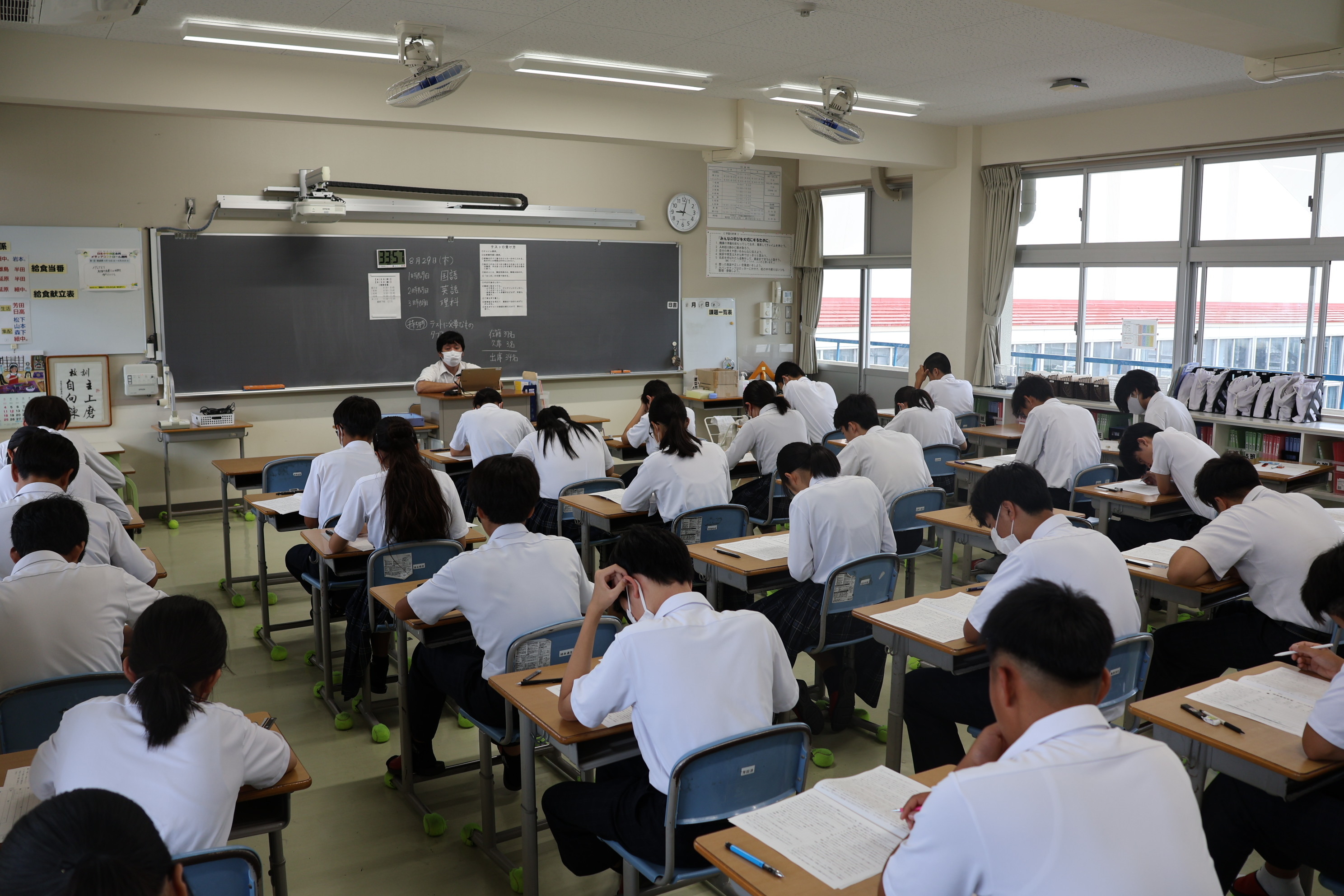

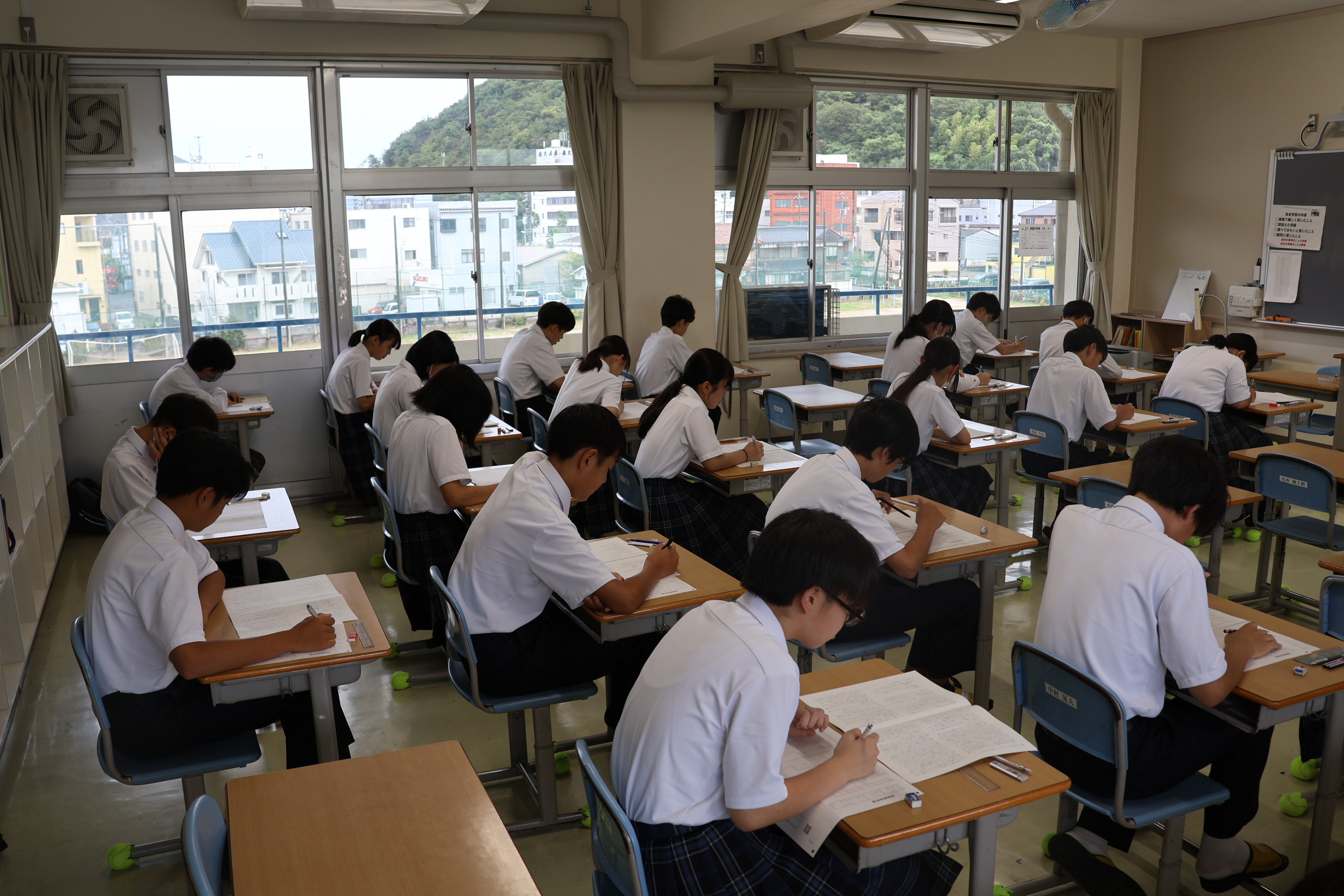


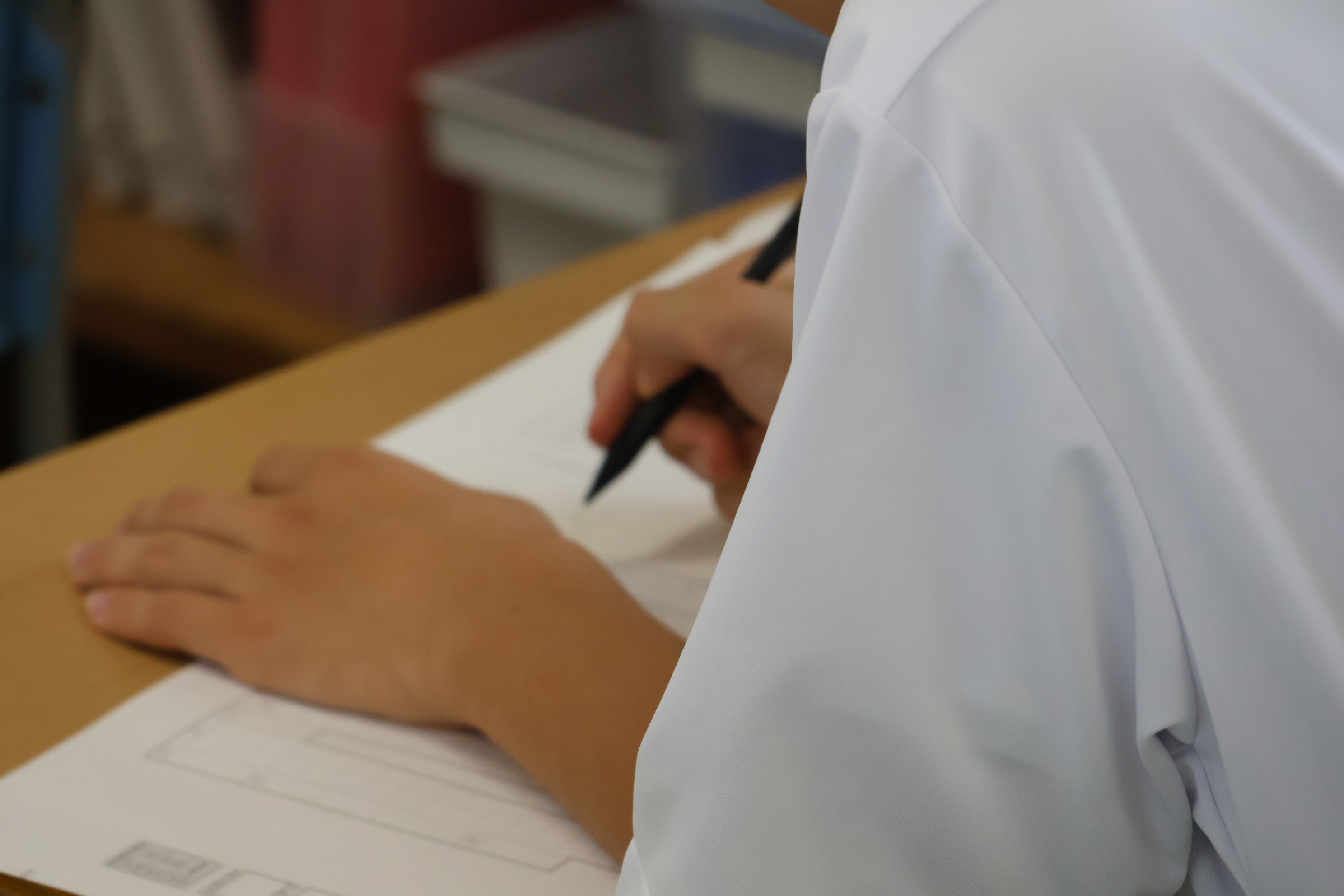
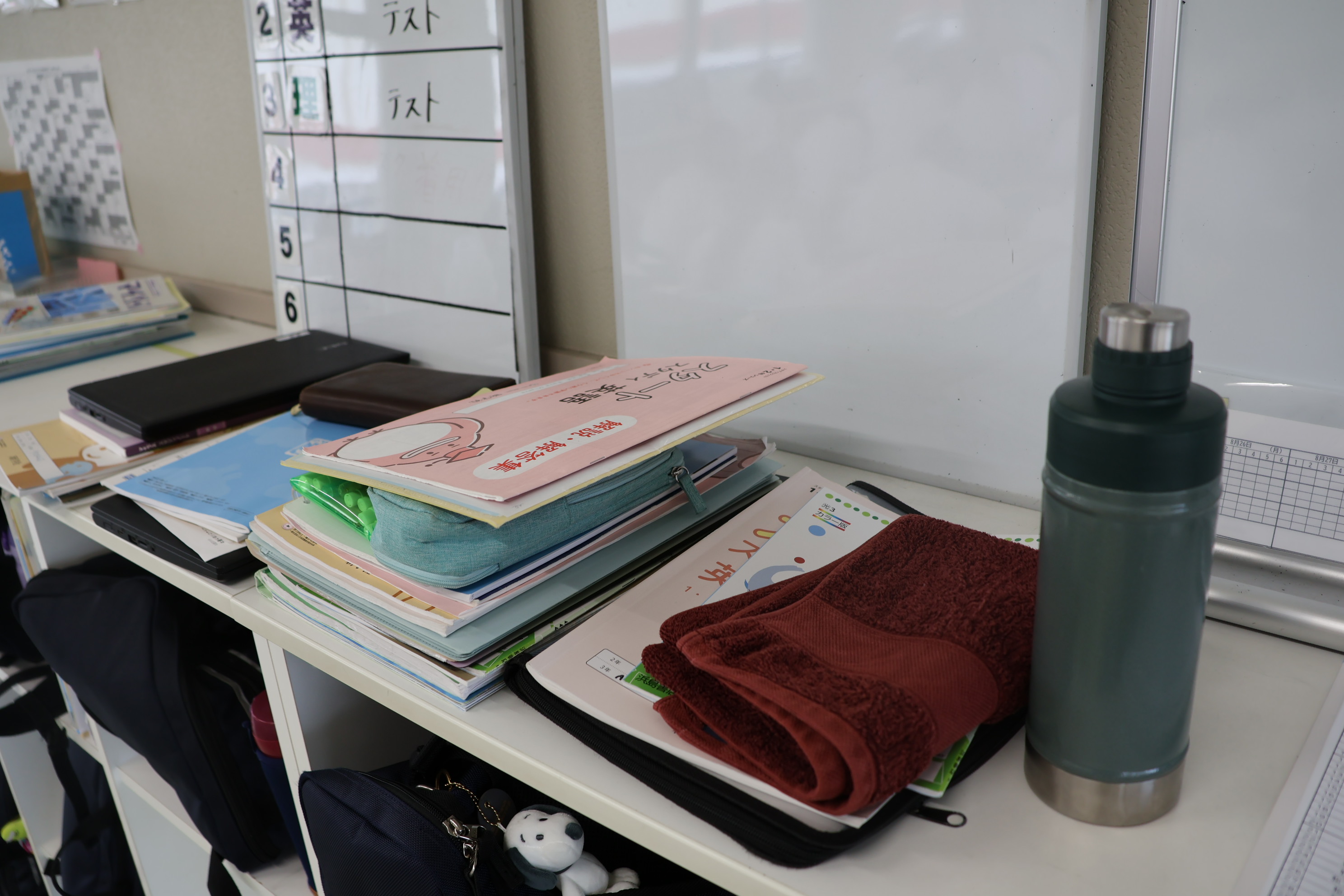
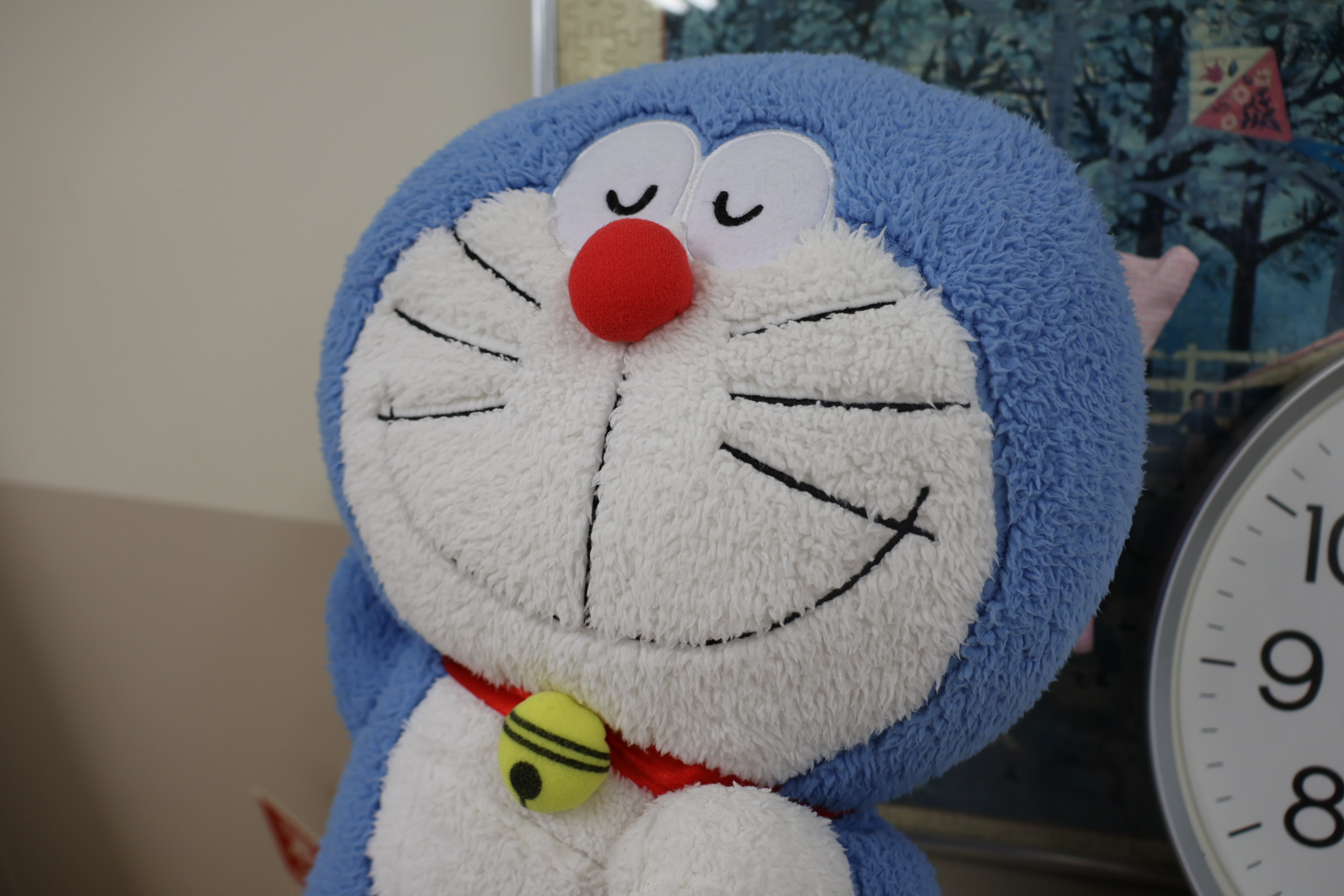
◎台風10号接近(8/29)
〈あの虹を無視したら撃てあの虹に立ち止まったら撃つなゴジラを 木下龍也〉

◎警報発令時の登下校の対応について(→*「お知らせ」で確認ください)
◎光
光は聲を持たないから
光は聲で人を呼ばない
光は光で人を招く 高見 順『抒想系樹木派前期』から
2学期始業式のつどい(8/28)

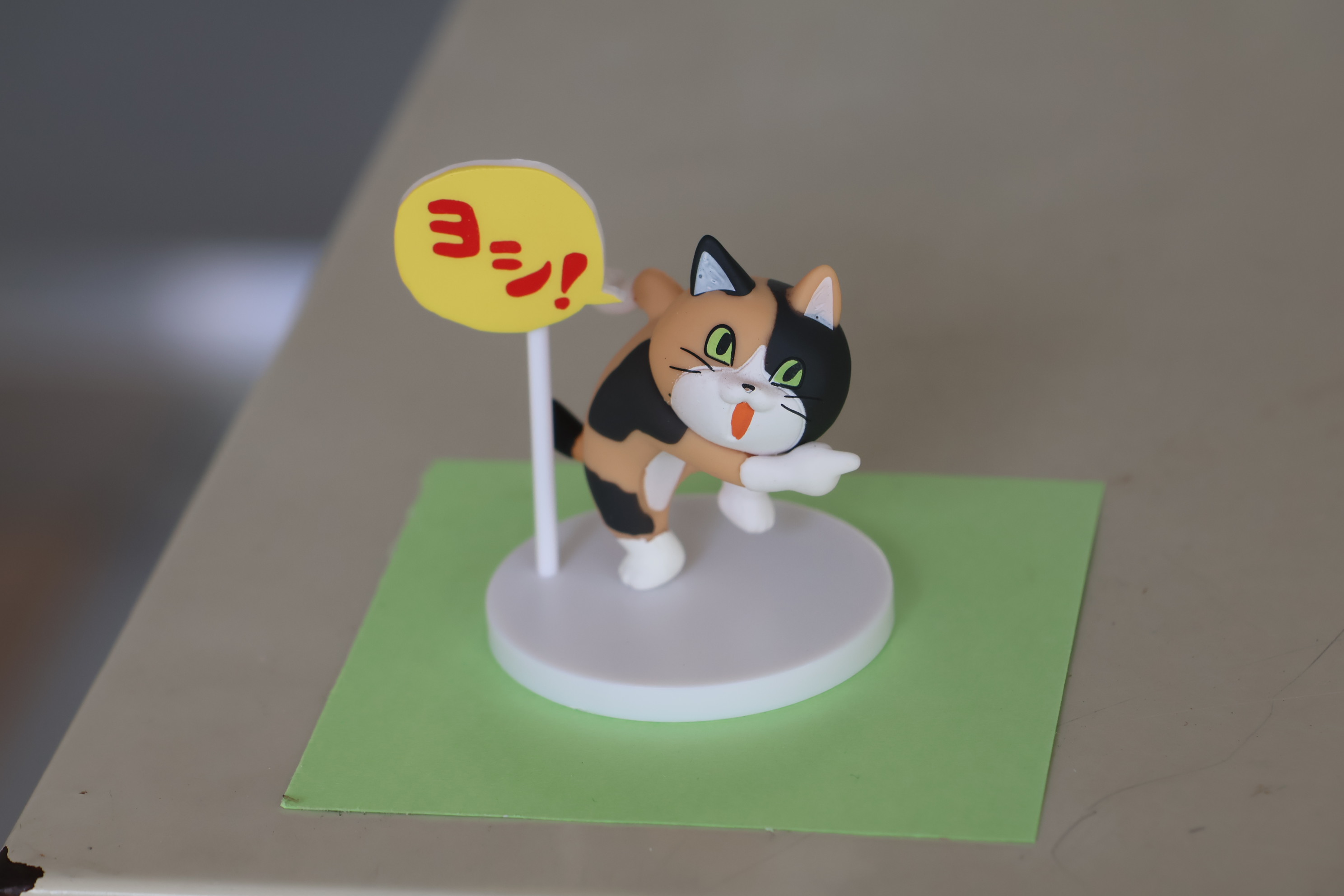
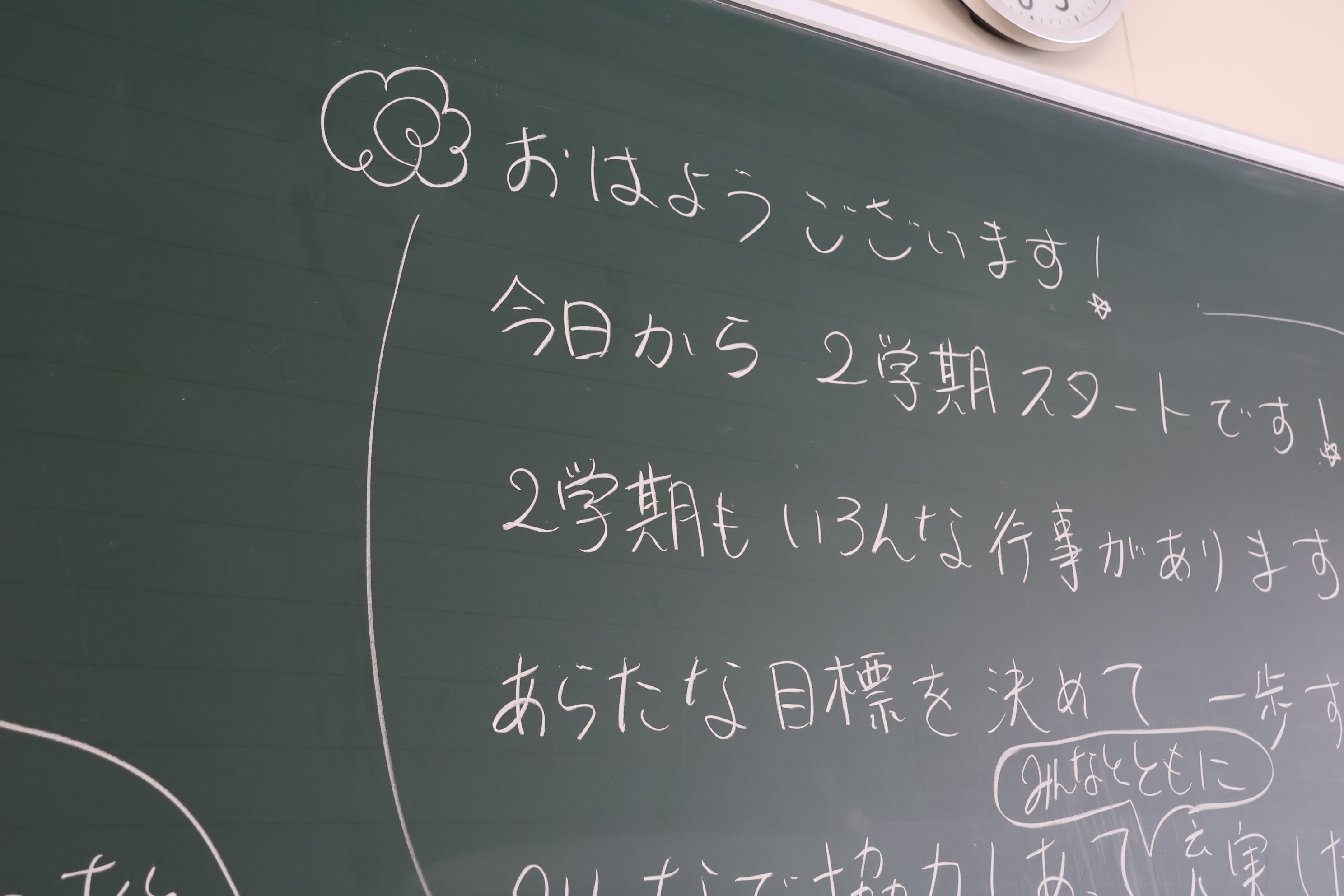




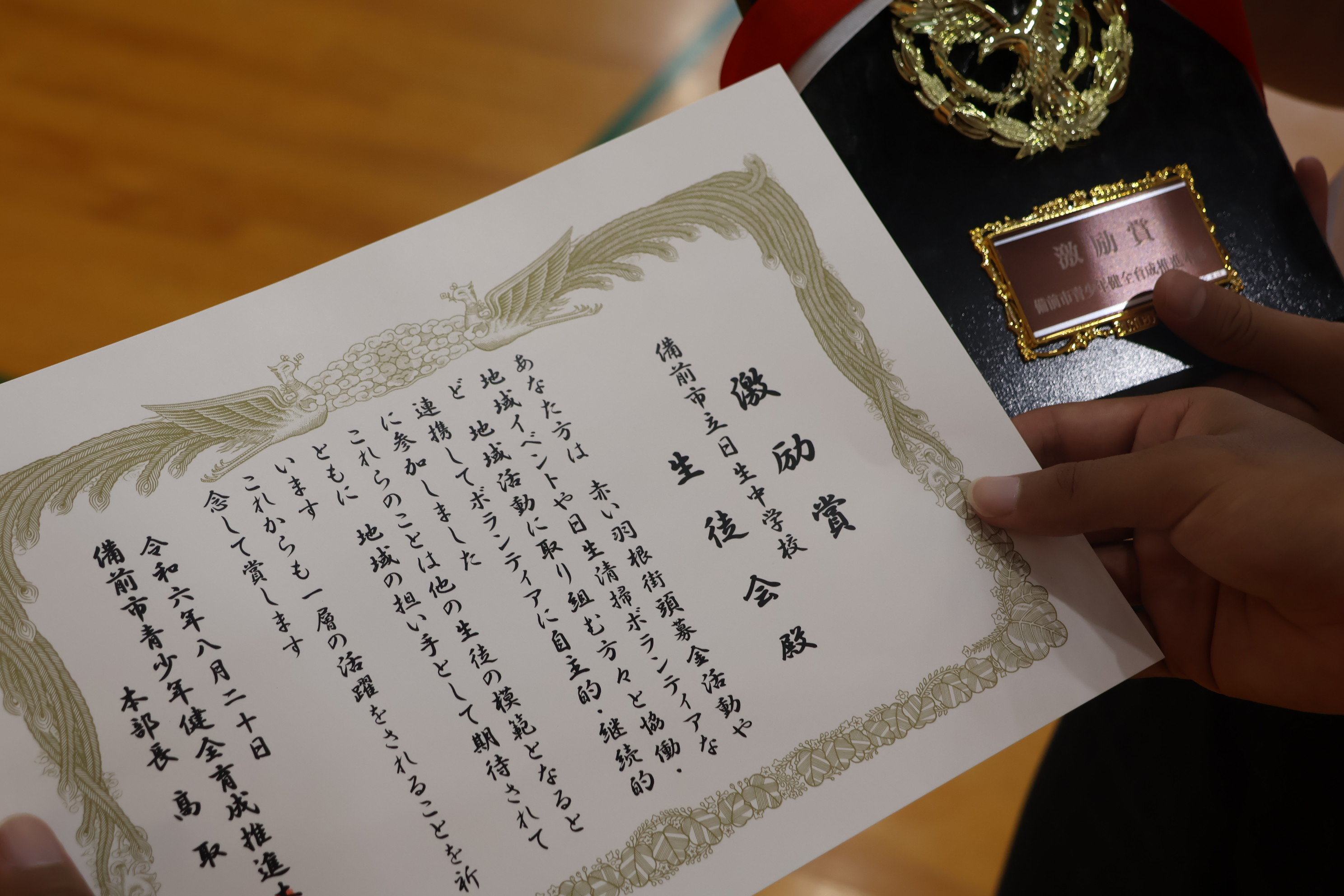

◎HINASE LEGACY(8/28)
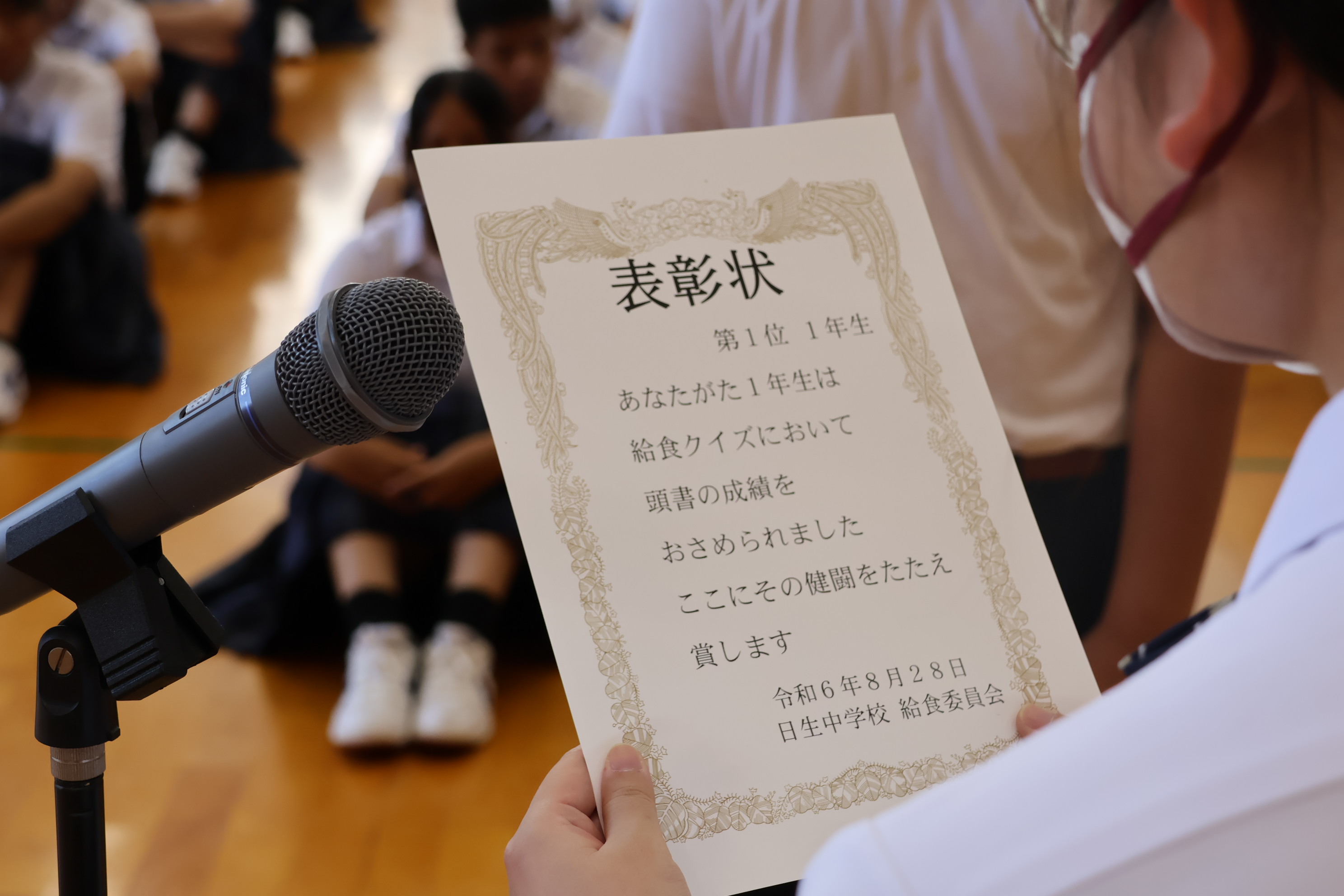







みんな!いい2学期にしような!
◎ひな中の風✨~私たちの学校 私たちの2学期へ(8/27)
1年生有志が、明日から始まる2学期へ向けて、教室整備に取り組みました。


よいしょ、よいしょ。
◎地域と共にある学校として(8/27)
日生地区栄養委員会・日生地区愛育委員さんが、星輝祭文化の部の日に、保護者対象の健康相談ブースを開設してくださいます。その打ち合わせを、この日市保健課健康係さんと行いました。文化の部に来校された際には、測定コーナーがあり、血管年齢、血圧測定、骨の健康チェック、握力測定等が無料で受けられます。
日生中は地域連携・協働活動を通した、〈地域・学校づくり〉をこれからも大切にしてきます。

◎すべての子どもたちの進路保障を。
8/27「春15の会」情報交流学習会の山陽新聞の記事を紹介します。

◎備災(8/27)

バスケットボール部のみんなありがとう
◎多くの人に支えられて(8/27)
熱中症対策のために備前市が、日生中学校にウオーターサーバーを設置してくださいました。各自の水筒への補充を中心に、学習環境の整備をさらにすすめていきます。
暑い中機器の設置をありがとうございました。


◎8月30日に、私たちはだっぴします
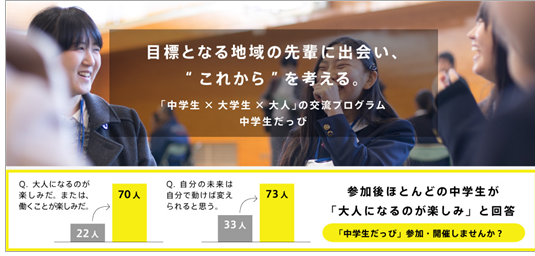
今年度も「だっぴ」で、聴こう・語ろう・夢を育てよう。今年は、吉永中と合同で「だっぴ」を行います。
中学生と大学生・保護者など地域の大人で小グループをつくり、働き方や生き方などについてテーマに沿って自由に話し合うキャリア教育プログラムです。
「だっぴ」とは(NPO法人だっぴHPより)
【地元や社会へ関心が高まる】
自分たちの地域の人や知らない分野で生きる人の多様な価値観と出会うことで、社会のつながりに気づいたり、地元への興味関心を高めることができます。
【未来を考えるキッカケに】
少し先の未来を生きる大学生や様々な経験を経て働くいろんな大人の話を聞き、自分のこれか らをイメージしやすくなります。
【行動する勇気が育つ】
地域の大人やお兄さんお姉さんが生き生きと真剣に話してくれた言葉、そして中学生自身が自分 と向き合い話した言葉。その一つ一つが心を支えてくれる力になり、行動する勇気が育 ちます。
【みんなで育てる地域に】
中学生と直接、話することで、子どもたちへの理解や関心が高まります。地域の力を 学校に取り 入れるキッカケにもなり、地域みんなで子どもを育てるつながりが生まれます。
◎職員会議・校内研修(8/26)さあ、2学期へ!おー!


〈うれいなく楽しく生きよ娘たち熊銀行に鮭をあずけて 雪舟えま〉
◎社・国・数・英・理!〈進路情報〉
岡山県教委は、2025年度県立高校入試の概要を発表しました。一般入試は来年3月11日に学力検査、12日に面接を行います。各校の具体的な募集定員は今年10月に公表されます。また、一般入試に先立って行う特別入試は2月5、6日で、学力検査や面接、独自選考を実施します。
入試の変更点はいくつかあるのですが、大きな変更のひとつは、一般入試2期として行っていた定時制の烏城普通科夜間部が一般入試に統合されます。それに伴い、学力検査の時間割が、社会、国語、数学、英語、理科の順番に変わります。そのため、日生中学校でも、進路指導の一環として、到達度テスト等の時間割を上記の順番に変更して実施します。
◎このナツ、わたしたちのアシアト・アカシ・アシタ
3年生日生の応援団

部活動(アーチェリー)





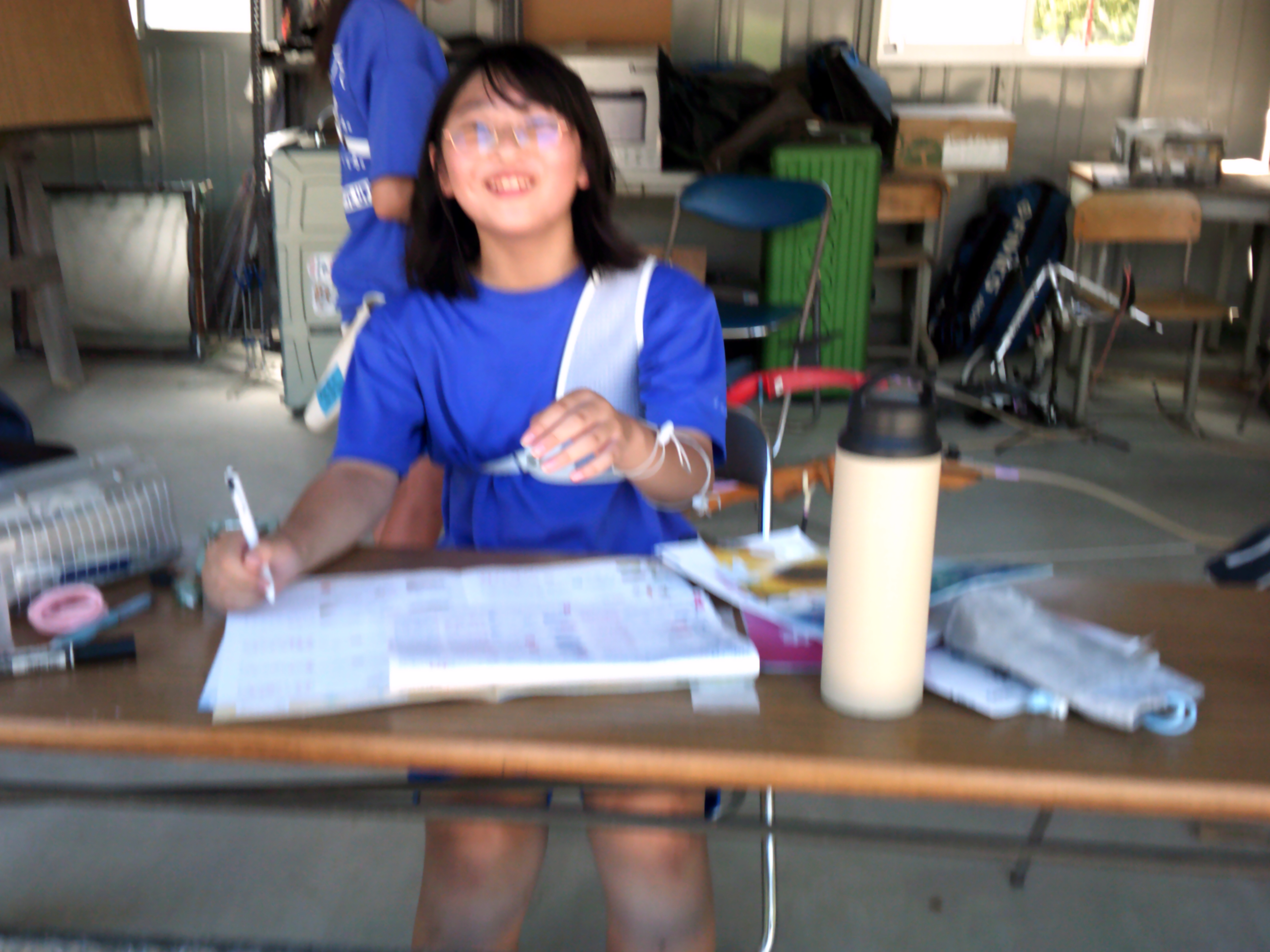
ペーパークイリング教室in図書館

出前おはなし会㏌西小、東小

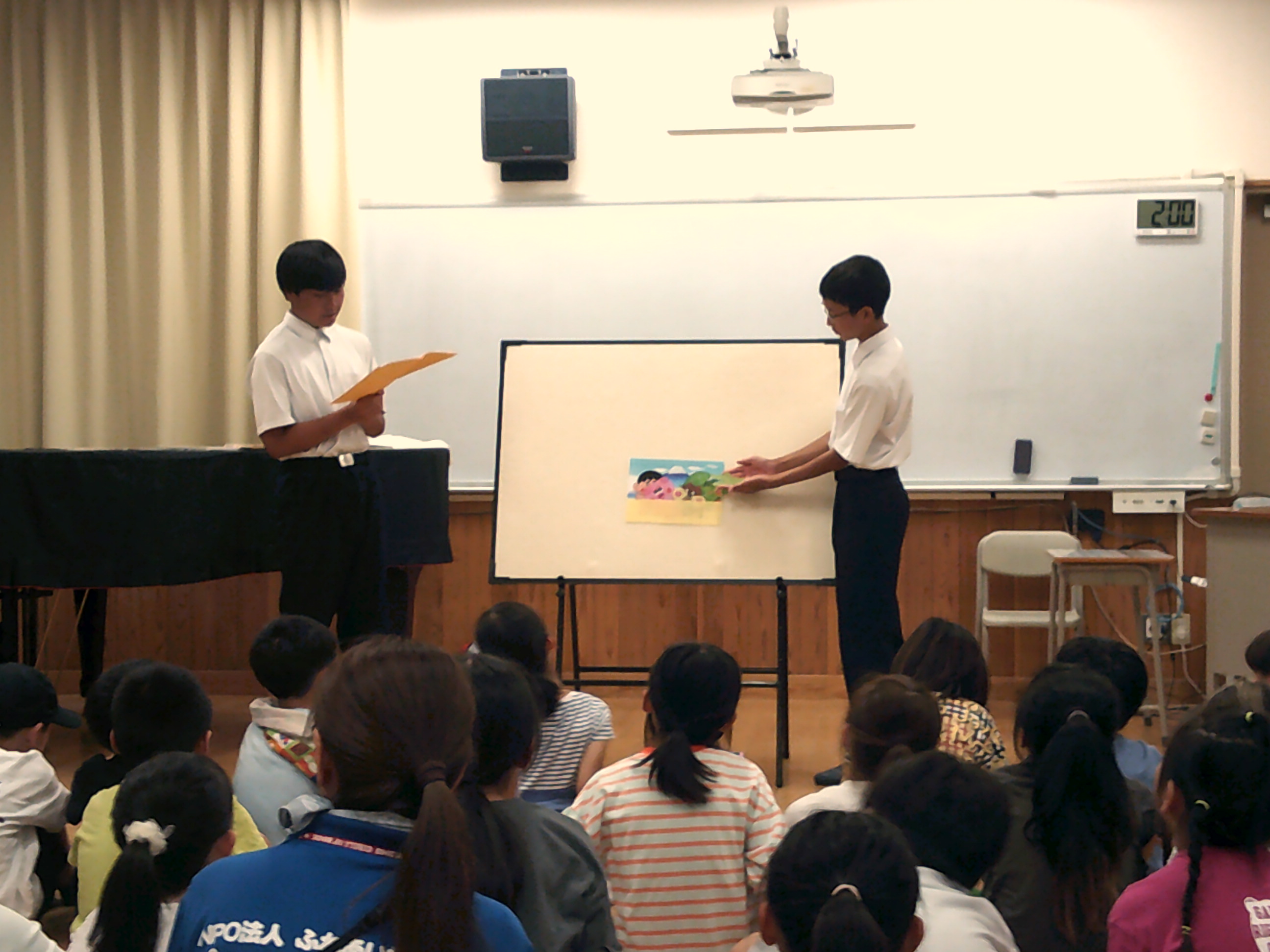
日生中学校地域ボランティア推進プロジェクト:ひなせみなとまつり(8.13)






◎備災(8/22)
地域公民館での防災学習の展示を終えました。南海トラフ地震の注意報発令のこともあり、期間を延長して展示をさせていだいていました。多くの方々のおご参観ありがとうございました。
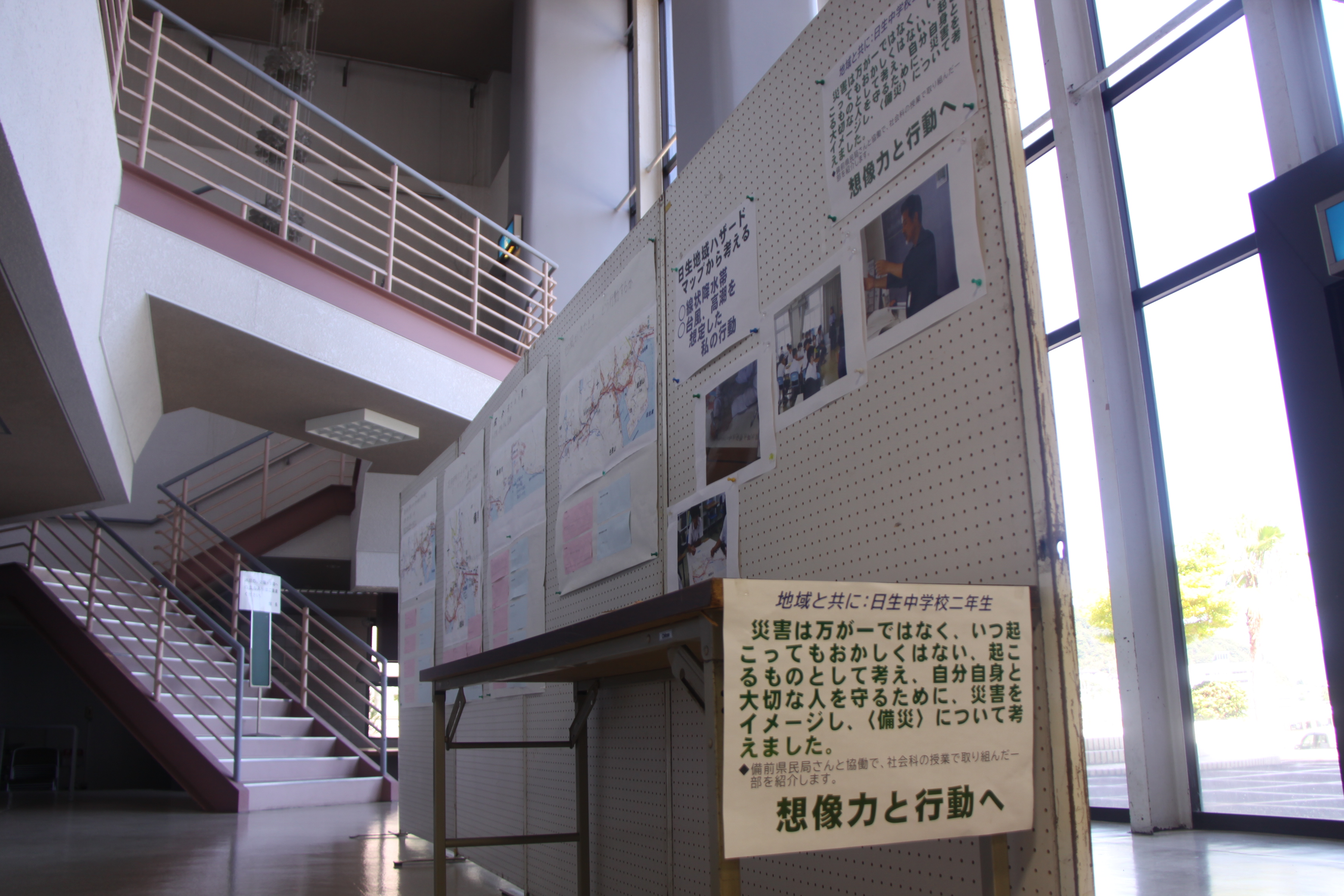

〈僕らには未だ見えざる五つ目の季節が窓の向こうに揺れる 山田 航〉(8/22)
2学期最初の時期は、みんな不安や悩みをもつことがしばしばあります。何かお子さんのことで心配やご相談がありましたら、お気軽に学年団やスクールカウンセラー(教育相談)へご連絡ください。〈0869ー72-1365〉(^_^)
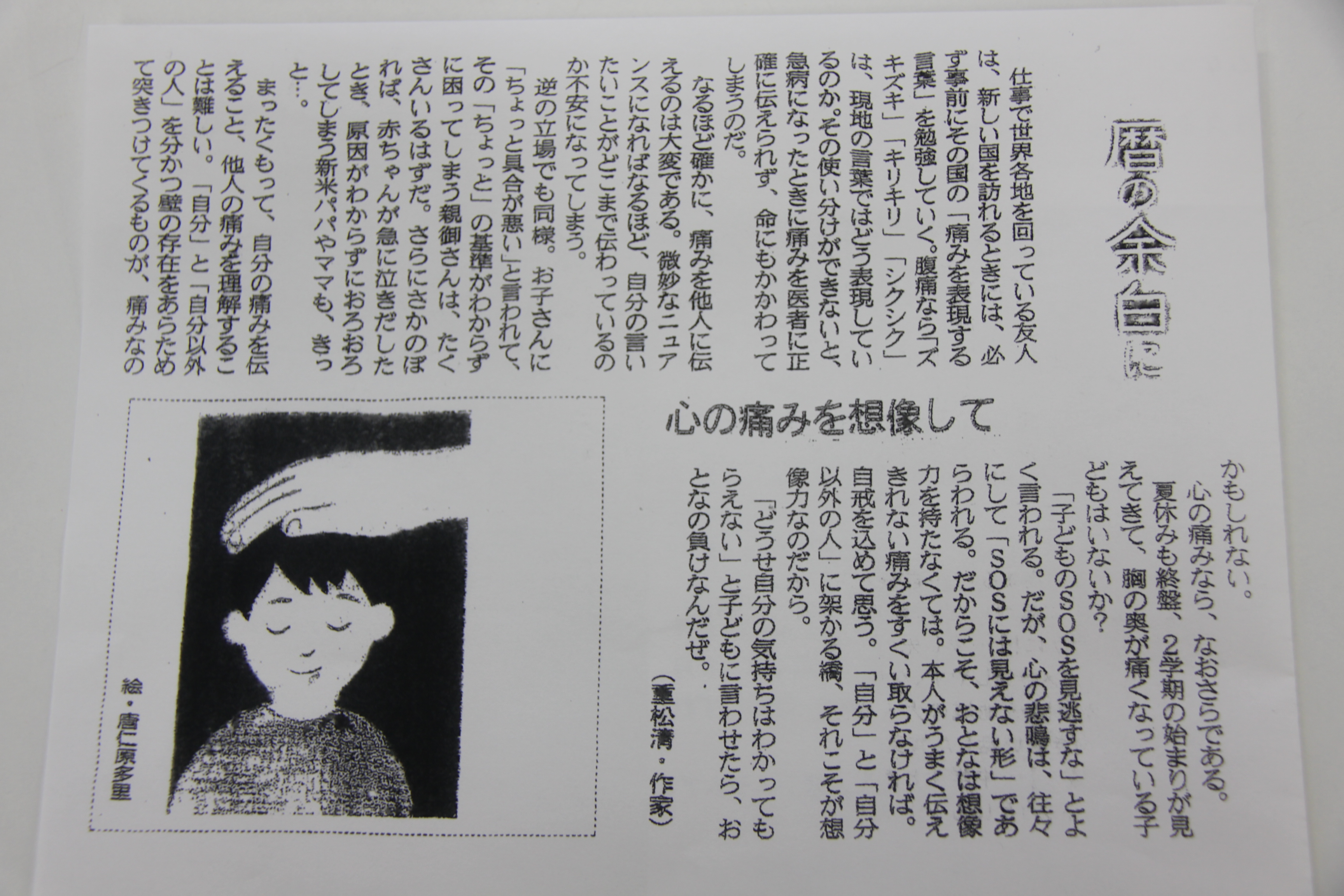
重松清さんの少し以前の記事(山陽新聞)を紹介します。
〈思いきること思いを切ることの立葵までそばにいさせて 永田 紅〉
(8/22)
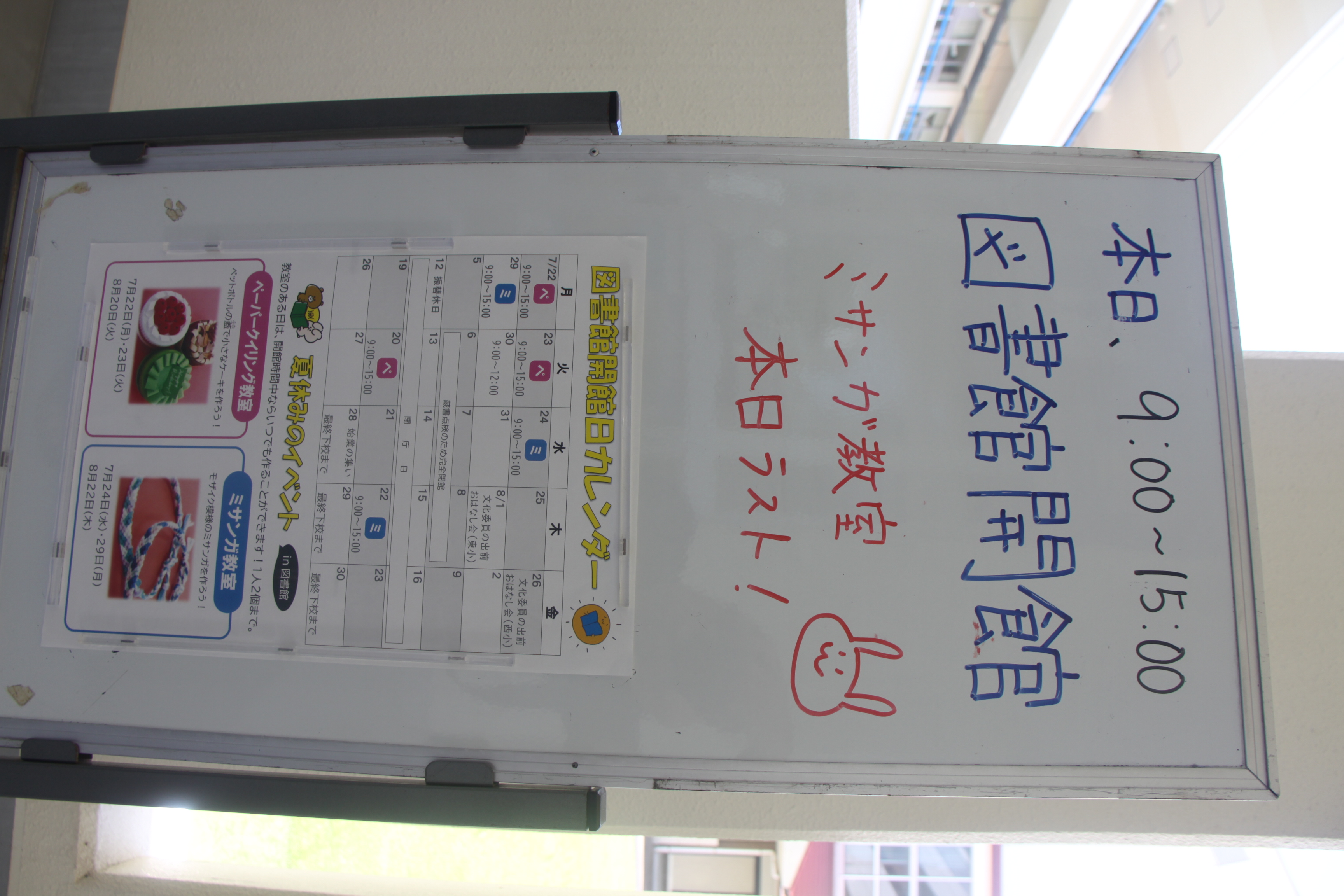
◎ゆたかで、未来を切り拓く教育内容の創造(8/21)
3年生家庭科で学習する福祉分野の授業の一環として、今年度は「認知症の諸問題」についてアプローチしていきます。この日は地域包括支援センターの小川さん、日生支所の横山さん、社協の嶋村さんと一緒に授業プロクラムについて協議しました。11月中旬の授業実践に向けて、地域連携を重ねて準備を進めていきます。

◎多くの人に支えられて
1年生が制作した備前焼を、この暑い夏、釜で焼き上げてくださった陶芸家の藤原宏先生が、生徒作品を持ってきてくださいました。ありがとうございました。
市の展示会や表彰は残念ながらなくなってしまいましたが、本校、星輝祭(文化の部)で展示をする計画です。

◎信頼される学校として
21日、備前市教育委員会が来られ、諸帳簿の点検がおこなわれました。

〈無心とは心在りてこと生まるべしこの厄介なこころといふもの 尾崎左永子〉
(8/21の風景)

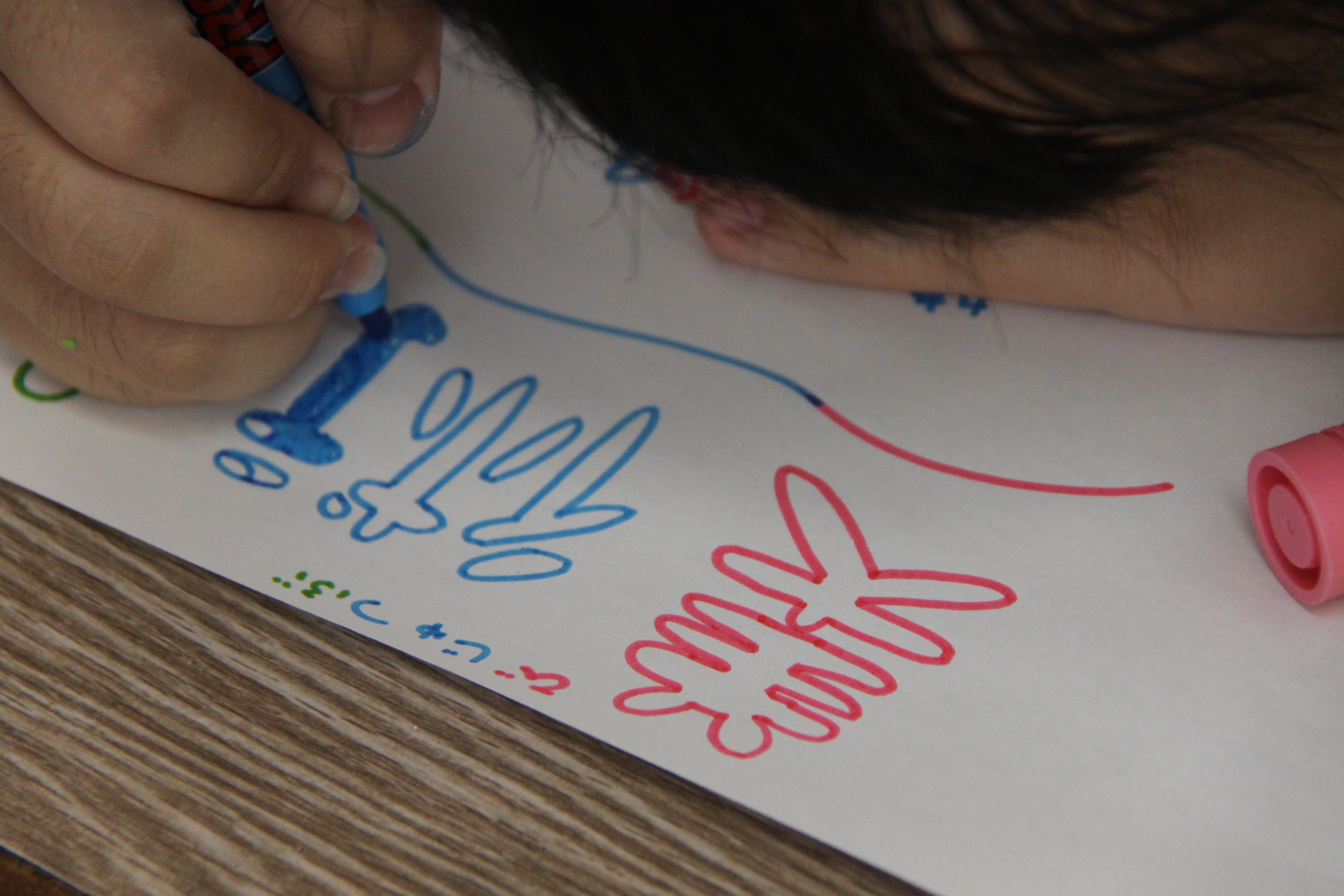

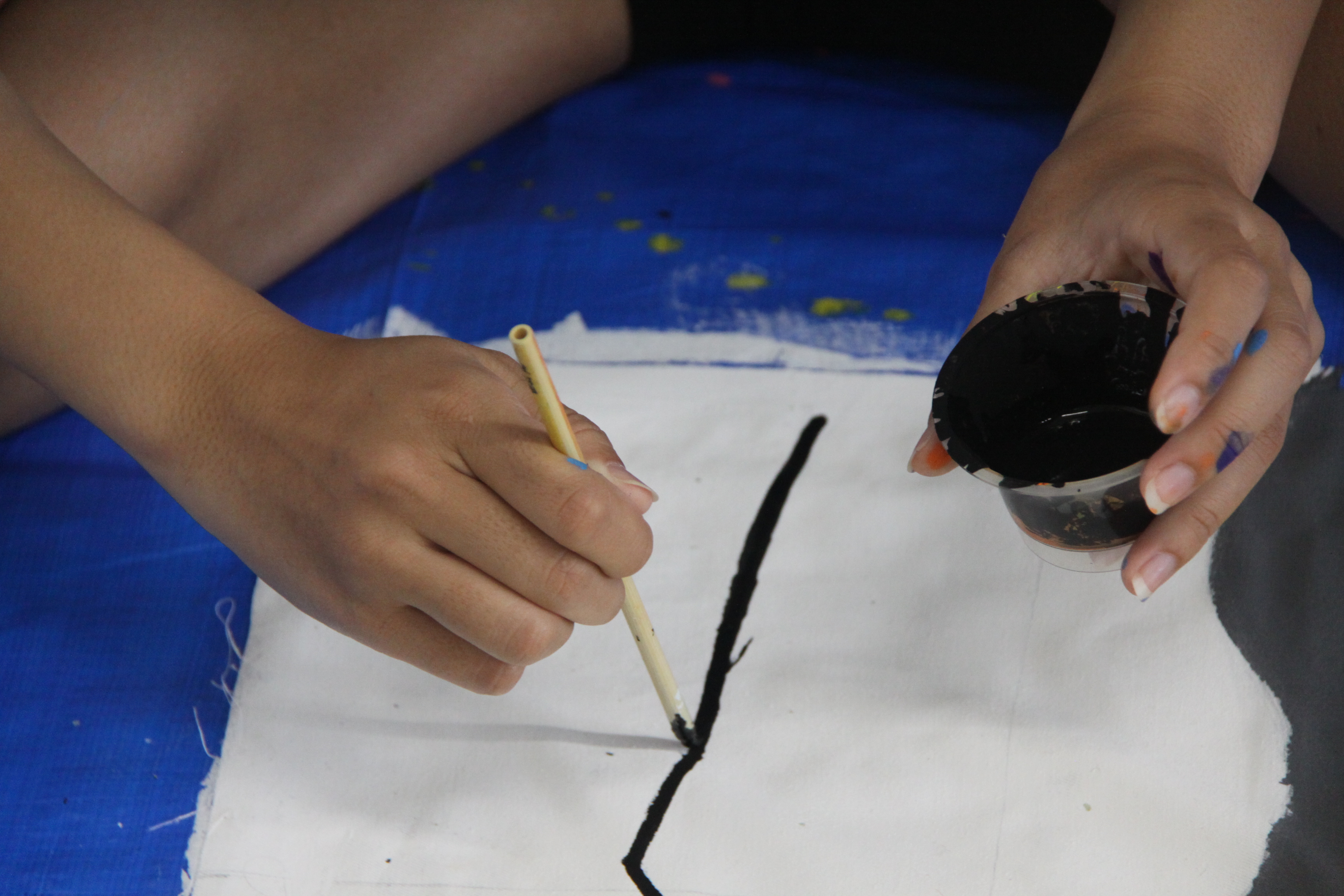


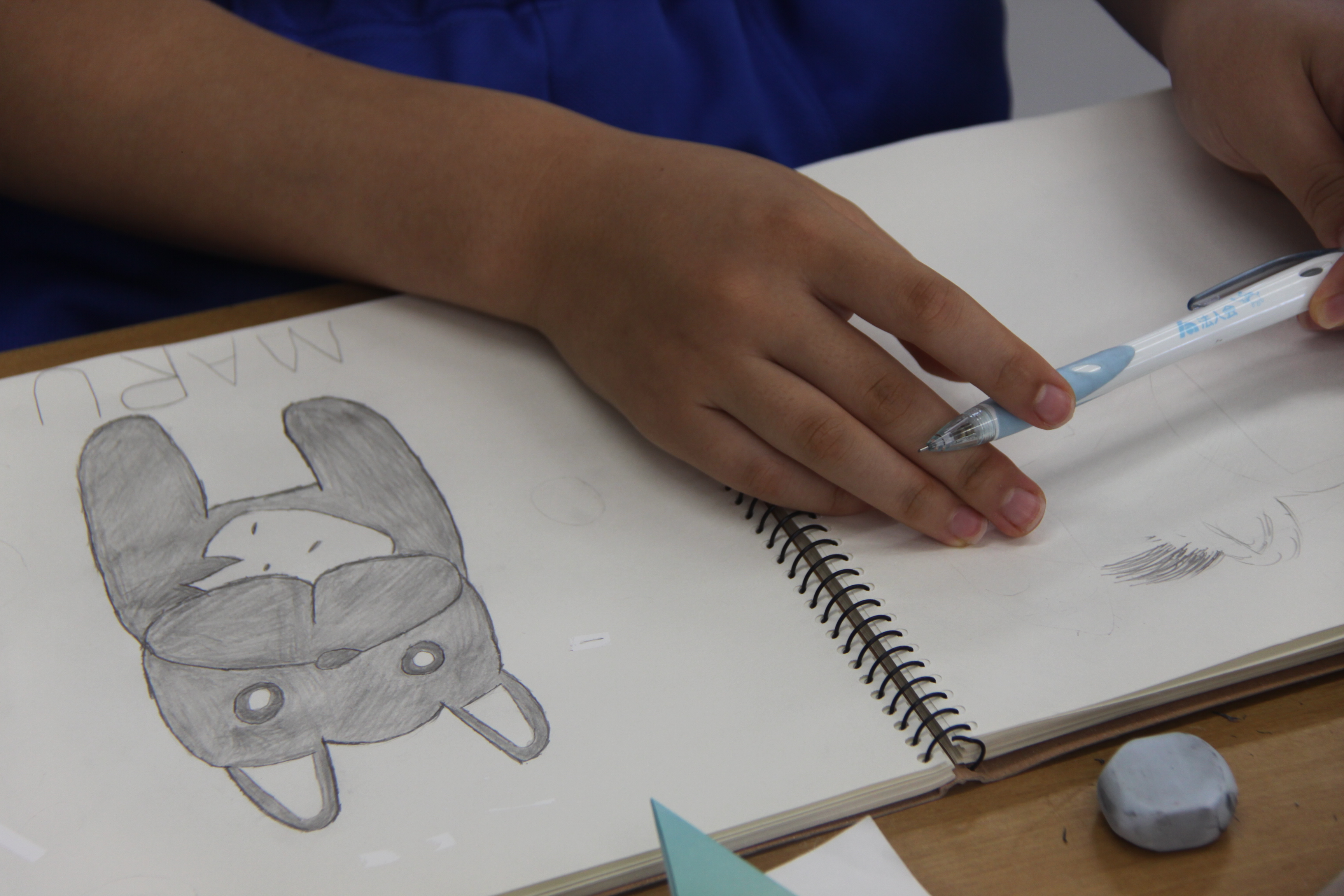

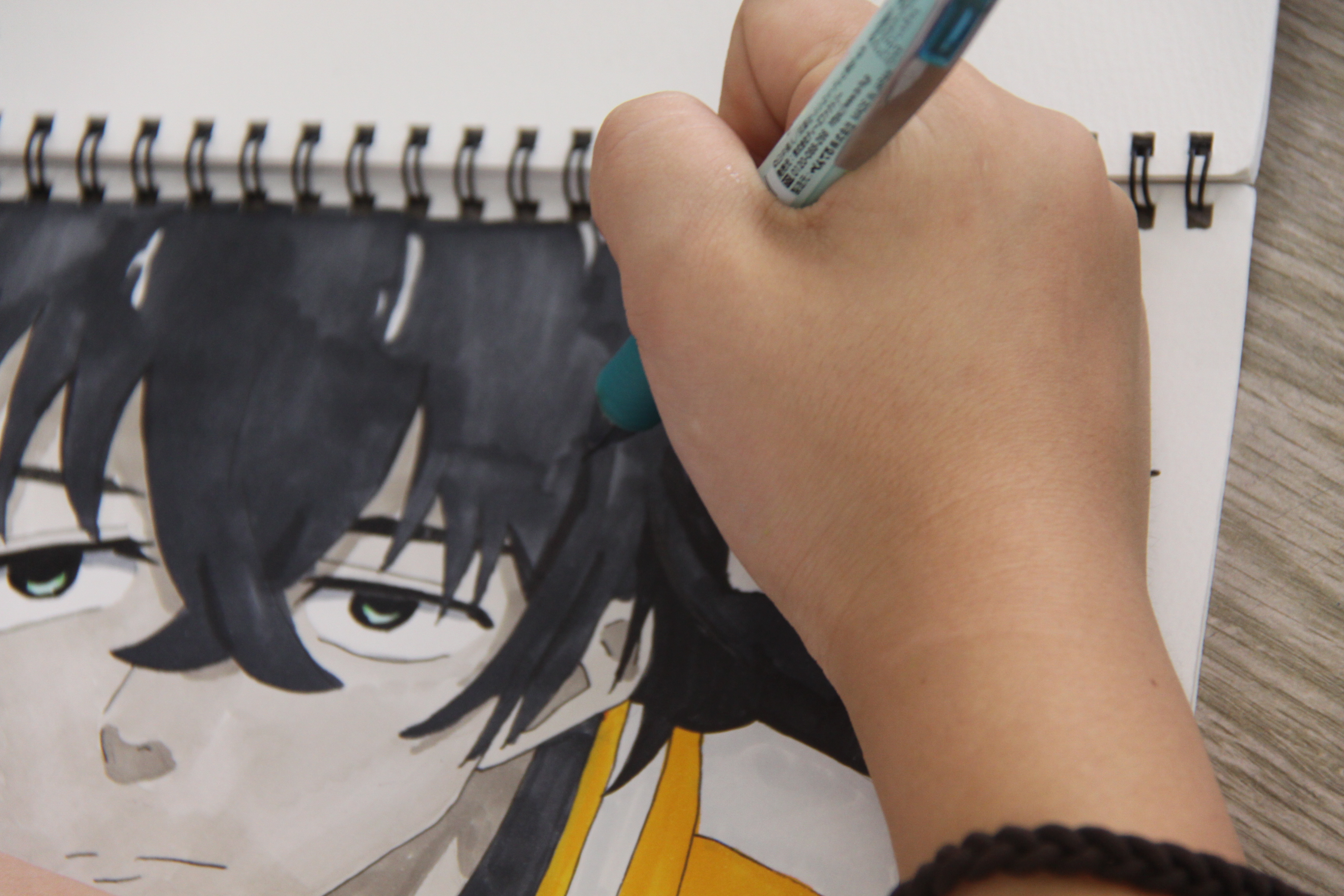



◎残暑お見舞い申し上げます(8/20)
明日(21日、10:00~)、〈ひな中ほっとスペース〉オープン(^_^)!

次回は9/4(水)オープン。みんなまってるよ。
◎「渋染一揆に学ぶ」フィールドワーク(8/8)
この日、教頭先生が、社会科の授業でも学習する「渋染一揆」に関するフィールドワーク(現地研修)に行きます。(東備地域の方々の研修のお手伝いです。)
渋染一揆とは・・・江戸時代も末期を迎えると幕府や藩の財政は苦しくなり、経済の引締めが相次いで行われました。「身分相応の暮らし」を命じる政策は、崩れかけていた身分制度を改めて強化することになりました。岡山藩では、庶民に出した倹約令を徹底するため、被差別身分の人々に、「柄のない渋染か藍染以外の着物の着用を許さない」というさらに厳しい御触れを出します。あからさまなこの「分け隔て」の「差別」を認めるわけにはいかないと藩内53ケ村の人々は、のちに「渋染一揆」と呼ばれる大規模な抵抗運動を起こしました。1856年、人々は、知恵を出し合って「嘆願書」を作成し抗議しますが、それが突き返されたことから1500名もの人々が「強訴」に立ち上がり、整然とした闘いでこの「特別の(別段)御触書き」を取り消させました。さらに、その責任者として入牢させられた12名を助け出すために「赦免」を求めて闘い続けました歴史です。
私たちは、人としての尊厳をかけ、社会情勢を見抜き、知恵と力を合わせて戦った人々の歴史から、たくさんのことを学ぶことができます。「関心がある方は、一緒にぜひ歩きましょう」と教頭先生が言われていました。
◎HINASE LEGACY(8/7)
小学校での「読み聞かせ」の取組を、ひなビジョンさんが取材してくださいました。
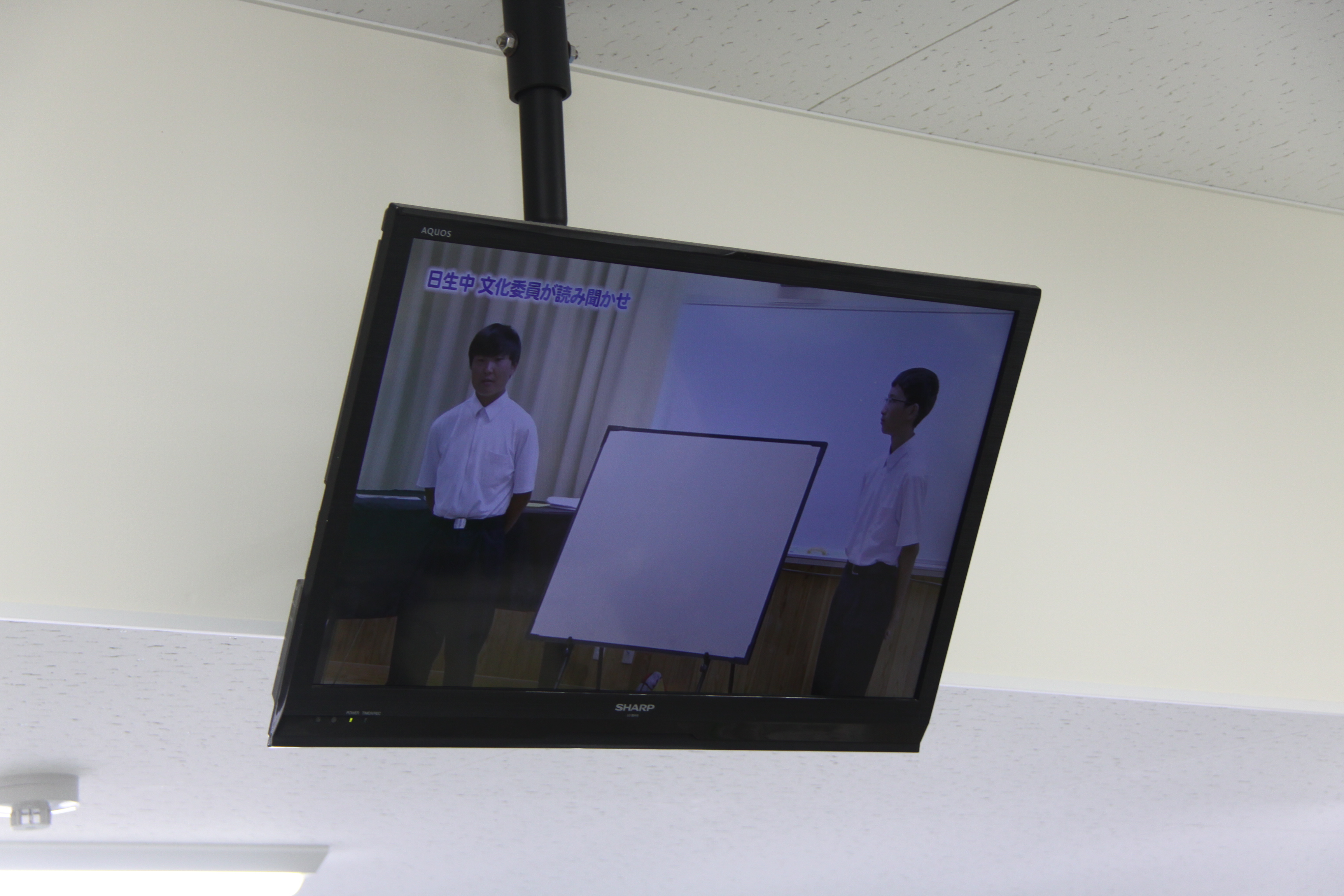

◎多くの人に支えられて(8/7)
校舎の修繕や整備をしていただいています。立川先生ありがとうございます。









◎立秋(8/7)
秋が立つと書くように、〈暦の上では〉秋に入り、少しずつ涼しくなって秋の気配が漂いだします。とはいえ、まだかなり暑い日が続くため、立秋以降の暑さを「残暑」といいます。ちょっとした挨拶も「暑さが厳しいですね」ではなく「残暑が厳しいですね」にすると季節感が出ます。「暑中見舞い」は、立秋以降「残暑見舞い」にかわるようです。なお二十四節気では、立秋の前が最も暑い頃という意味の「大暑」で、立秋の次は暑さが峠を超えて朝晩に初秋を感じる頃という意味の「処暑」となります。
しかし、立秋の今日、(暦の上では秋ということになりますが)秋が程遠く感じられるほど体に堪える暑さになっている所もあるようです。東海以西で広く猛暑日となり、中には体温を超える暑さも記録されています。関東や東北、北海道も30~33℃くらいで、蒸し暑く、引き続き、熱中症に注意し、対策をとりましょう。お盆休みも猛暑は続くそうです。

猛暑の中、仲間とともに。
〈さうか この軍服がみえてゐないのか王さまはうれしくなりました 平井 弘〉 (8/6)

子ども代表
平和への誓い
目を閉じて想像してください。
緑豊かで美しいまち。
人でにぎわう商店街。
まちにあふれるたくさんの笑顔。
79年前の広島には、今と変わらない色鮮やかな日常がありました。
昭和20年(1945年)8月6日 午前8時15分。
「ドーン!」という鼓膜が破れるほどの大きな音。
立ち昇る黒味がかった朱色の雲。
人も草木も焼かれ、助けを求める声と絶望の涙で、まちは埋め尽くされました。
ある被爆者は言います。
あの時の広島は「地獄」だったと。
原子爆弾は、色鮮やかな日常を奪い、広島を灰色の世界へと変えてしまったのです。
被爆者である私の曾祖母は、当時の様子を語ろうとはしませんでした。
言葉にすることさえつらく悲しい記憶は、79年経った今でも多くの被爆者を苦しめ続けています。
今もなお、世界では戦争が続いています。
79年前と同じように、生きたくても生きることができなかった人たち、明日を共に過ごすはずだった人を失った人たちが、この世界のどこかにいるのです。
本当にこのままでよいのでしょうか。
願うだけでは、平和はおとずれません。
色鮮やかな日常を守り、平和をつくっていくのは私たちです。
一人一人が相手の話をよく聞くこと。
「違い」を「良さ」と捉え、自分の考えを見直すこと。
仲間と協力し、一つのことを成し遂げること。
私たちにもできる平和への一歩です。
さあ、ヒロシマを共に学び、感じましょう。
平和記念資料館を見学し、被爆者の言葉に触れてください。
そして、家族や友達と平和の尊さや命の重みについて語り合いましょう。
世界を変える平和への一歩を今、踏み出します。
2024年8月6日 こども代表 広島市立祇園小学校6年 加藤晶 広島市立八幡東小学校6年 石丸優斗
追記:ハンセン病問題の学習会のチラシをいただきましたのでご案内します。
〈広島に大きな空のあることとあまの川のあること 8月 吉野裕之(改)〉(8/5)

コレガ人間ナノデス
原子爆弾ニ依ル変化ヲゴラン下サイ
肉体ガ恐ロシク膨脹シ
男モ女モスベテ一ツノ型ニカヘル
オオ ソノ真黒焦ゲノ滅茶苦茶ノ
爛レタ顔ノムクンダ唇カラ洩レテ来ル声ハ
「助ケテ下サイ」
ト カ細イ 静カナ言葉
コレガ コレガ人間ナノデス
人間ノ顔ナノデス
燃エガラ
夢ノナカデ
頭ヲナグリツケラレタノデハナク
メノマヘニオチテキタ
クラヤミノナカヲ
モガキ モガキ
ミンナ モガキナガラ
サケンデ ソトヘイデユク
シユポツ ト 音ガシテ
ザザザザ ト ヒツクリカヘリ
ヒツクリカヘツタ家ノチカク
ケムリガ紅クイロヅイテ
河岸ニニゲテキタ人間ノ
アタマノウヘニ アメガフリ
火ハムカフ岸ニ燃エサカル
ナニカイツタリ
ナニカサケンダリ
ソノクセ ヒツソリトシテ
川ノミヅハ満潮
カイモク ワケノワカラヌ
顔ツキデ 男ト女
フラフラト水ヲナガメテヰル
ムクレアガツタ貌ニ
胸ノハウマデ焦ケタダレタ娘ニ
赤ト黄ノオモヒキリ派手ナ
ボロキレヲスツポリカブセ
ヨチヨチアルカセテユクト
ソノ手首ハブランブラント揺レ
漫画ノ国ノ化ケモノノ
ウラメシヤアノ恰好ダガ
ハテシモナイ ハテシモナイ
苦患ノミチガヒカリカガヤク
火ノナカデ 電柱ハ
火ノナカデ
電柱ハ一ツノ蕊ノヤウニ
蝋燭ノヤウニ
モエアガリ トロケ
赤イ一ツノ蕊ノヤウニ
ムカフ岸ノ火ノナカデ
ケサカラ ツギツギニ
ニンゲンノ目ノナカヲオドロキガ
サケンデユク 火ノナカデ
電柱ハ一ツノ蕊ノヤウニ
日ノ暮レチカク
日ノ暮レチカク
眼ノ細イ ニンゲンノカホ
ズラリト河岸ニ ウヅクマリ
細イ細イ イキヲツキ
ソノスグ足モトノ水ニハ
コドモノ死ンダ頭ガノゾキ
カハリハテタ スガタノ細イ眼ニ
翳ツテユク 陽ノイロ
シヅカニ オソロシク
トリツクスベモナク
真夏ノ夜ノ河原ノミヅガ
真夏ノ夜ノ
河原ノミヅガ
血ニ染メラレテ ミチアフレ
声ノカギリヲ
チカラノアリツタケヲ
オ母サン オカアサン
断末魔ノカミツク声
ソノ声ガ
コチラノ堤ヲノボラウトシテ
ムカフノ岸ニ ニゲウセテユキ
ギラギラノ破片ヤ
ギラギラノ破片ヤ
灰白色ノ燃エガラガ
ヒロビロトシタ パノラマノヤウニ
アカクヤケタダレタ ニンゲンノ死体ノキメウナリズム
スベテアツタコトカ アリエタコトナノカ
パツト剥ギトツテシマツタ アトノセカイ
テンプクシタ電車ノワキノ
馬ノ胴ナンカノ フクラミカタハ
プスプストケムル電線ノニホヒ
焼ケタ樹木ハ
焼ケタ樹木ハ マダ
マダ痙攣ノアトヲトドメ
空ヲ ヒツカカウトシテヰル
アノ日 トツゼン
空ニ マヒアガツタ
竜巻ノナカノ火箭
ミドリイロノ空ニ樹ハトビチツタ
ヨドホシ 街ハモエテヰタガ
河岸ノ樹モキラキラ
火ノ玉ヲカカゲテヰタ
水ヲ下サイ
水ヲ下サイ
アア 水ヲ下サイ
ノマシテ下サイ
死ンダハウガ マシデ
死ンダハウガ
アア
タスケテ タスケテ
水ヲ
水ヲ
ドウカ
ドナタカ
オーオーオーオー
オーオーオーオー
天ガ裂ケ
街ガ無クナリ
川ガ
ナガレテヰル
オーオーオーオー
オーオーオーオー
夜ガクル
夜ガクル
ヒカラビタ眼ニ
タダレタ唇ニ
ヒリヒリ灼ケテ
フラフラノ
コノ メチヤクチヤノ
顔ノ
ニンゲンノウメキ
ニンゲンノ
永遠のみどり
ヒロシマのデルタに
若葉うづまけ
死と焔の記憶に
よき祈よ こもれ
とはのみどりを
とはのみどりを
ヒロシマのデルタに
青葉したたれ 『原民喜 原爆小景』
◎私たちのはじまりの風景16(8/2)
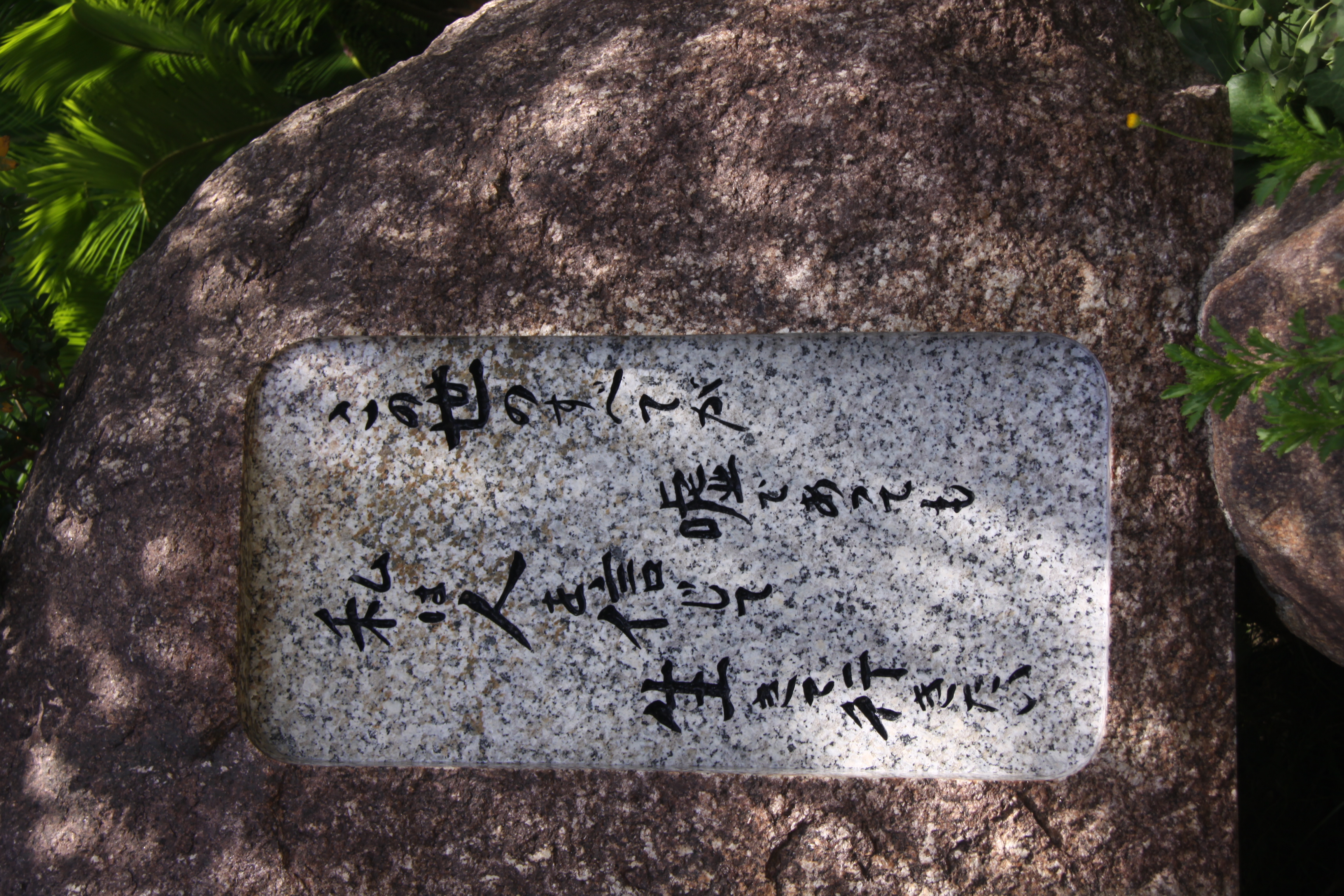
さて、ここはどこでしょう?
◎私たちのはじまりの風景15(8/1)
ここはどこでしょう?









◎確かな進路保障へ
「春15(イチゴ)の会」情報交流学習会が8月31日(土)に行われます。山陽新聞の平田さんの取材を受けました。まだ参加申し込みは大丈夫です。

◎校内研修(人権教育の推進、宿泊研修の検討(7/30))、そして日生中学校区連携協議会総会&研修会(会場:日生東小学校7/31)

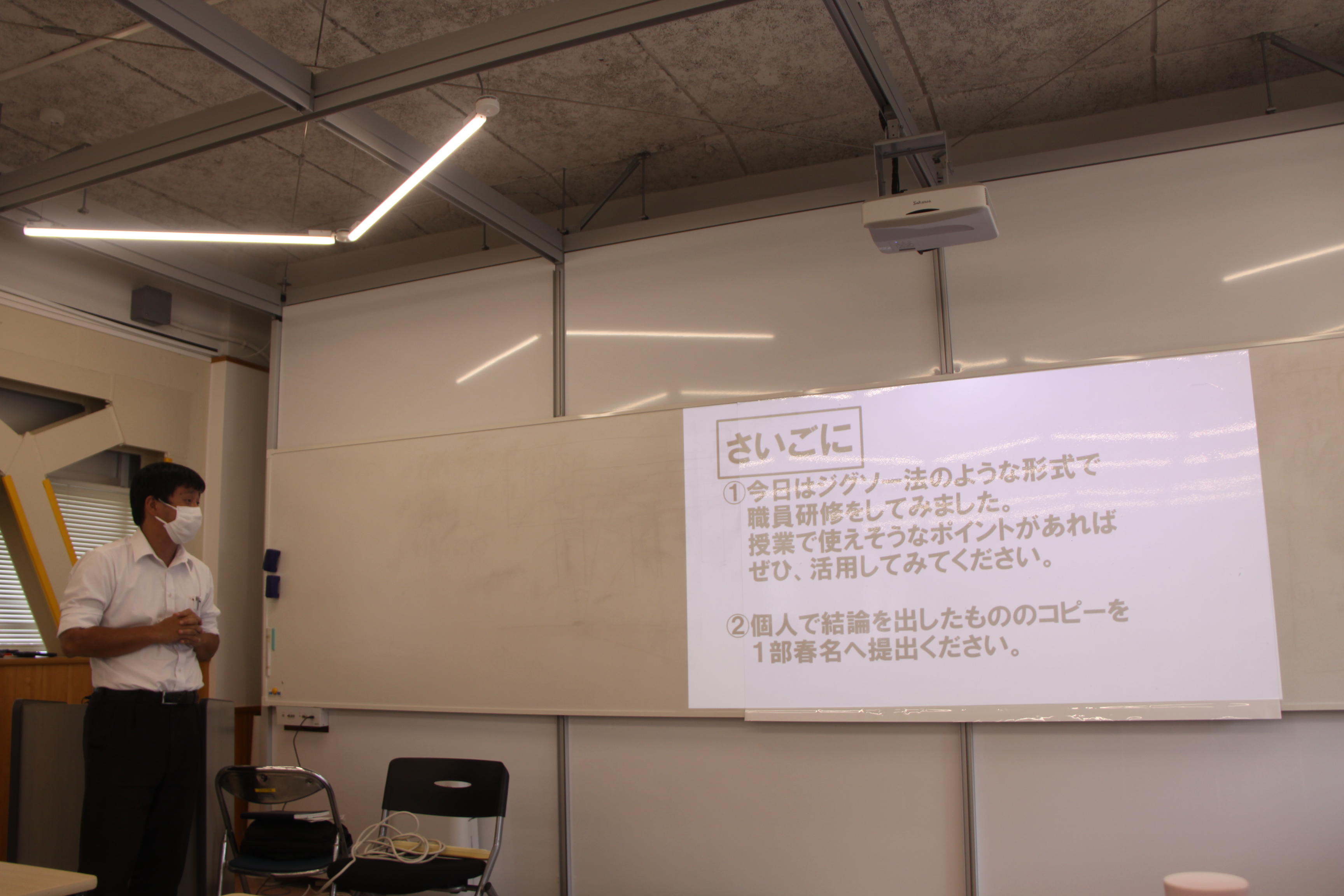

The lesson I've learned the most often in life is that you're always going to know more in the future than you know now. TAYLOR SWIFT
(今までの人生で学んだレッスンは、今を知っていることよりも、未来を知ろうとすること。)
◎多くの人に支えられて(7/30)
事務指導及び令和7年度予算ヒアリングに備前市教育委員会さんが来校されました。帳簿点検、今後のICTの運用にむけてのヒアリング、また、校舎や体育館の修繕について、理科室の薬品点検など、日生中学校の学習環境のさらなる充実のためにお話をさせていただくことができました。

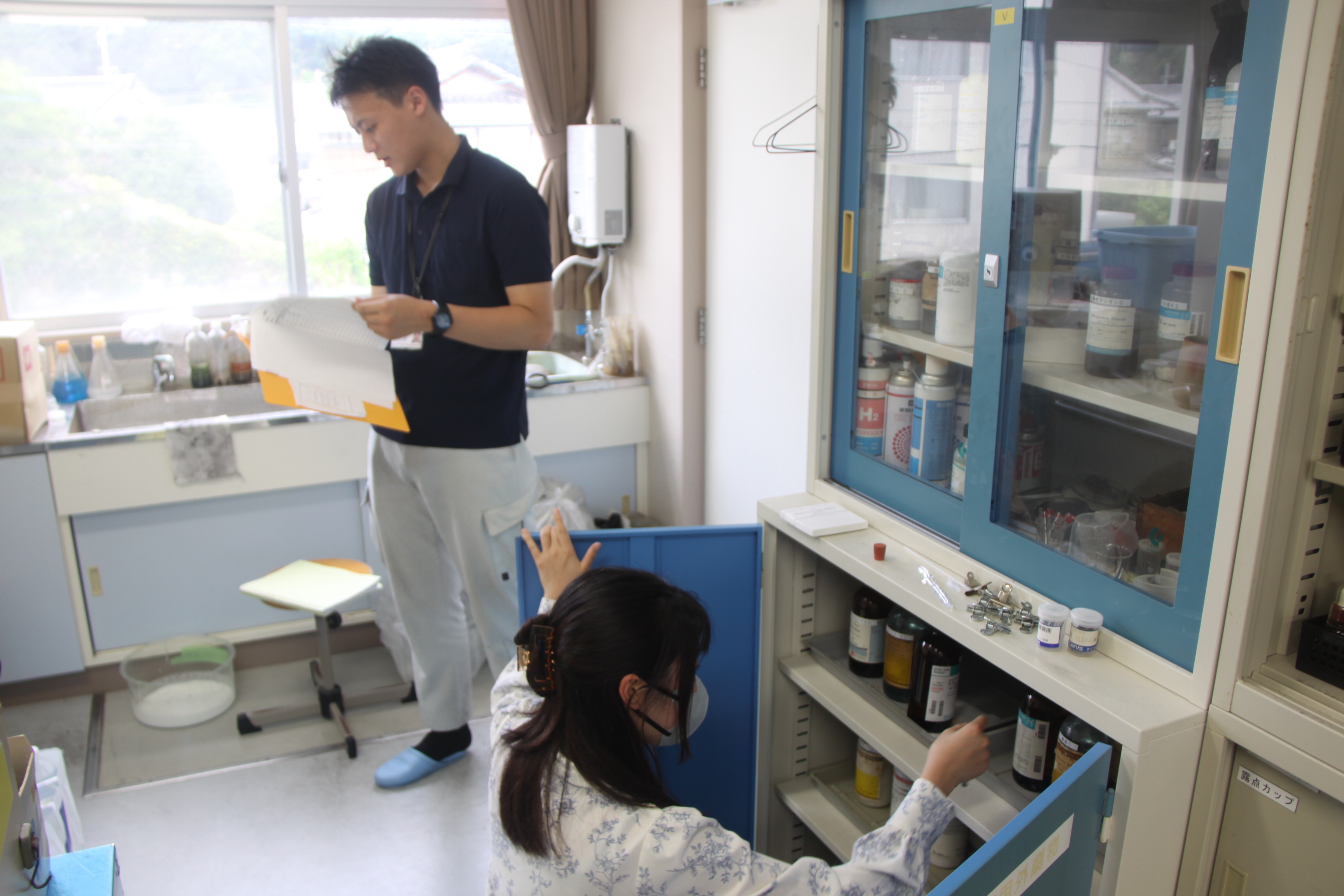

◎MY WAY (7/30)





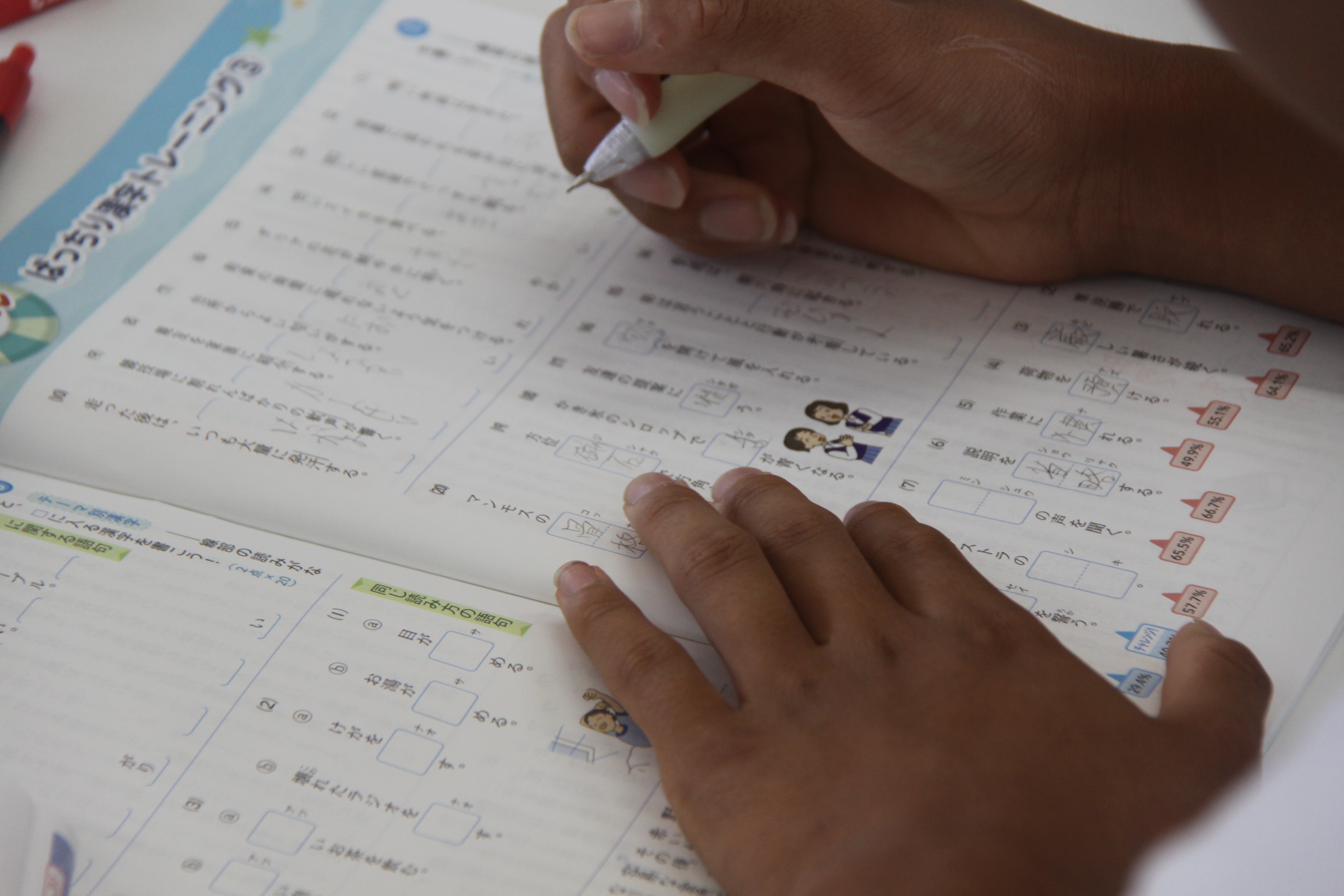




部活動 2年生補修学習 がんばり合える仲間、そして私の夏。
◎酷暑お見舞い申し上げます。「暑さにアチョー」(7/29)


◎地域と共に在るわたしたち。
~おひさまひろば夏祭りのお手伝い(7/26)









◎ほっと、ほっとスペースの次回は、8月7日

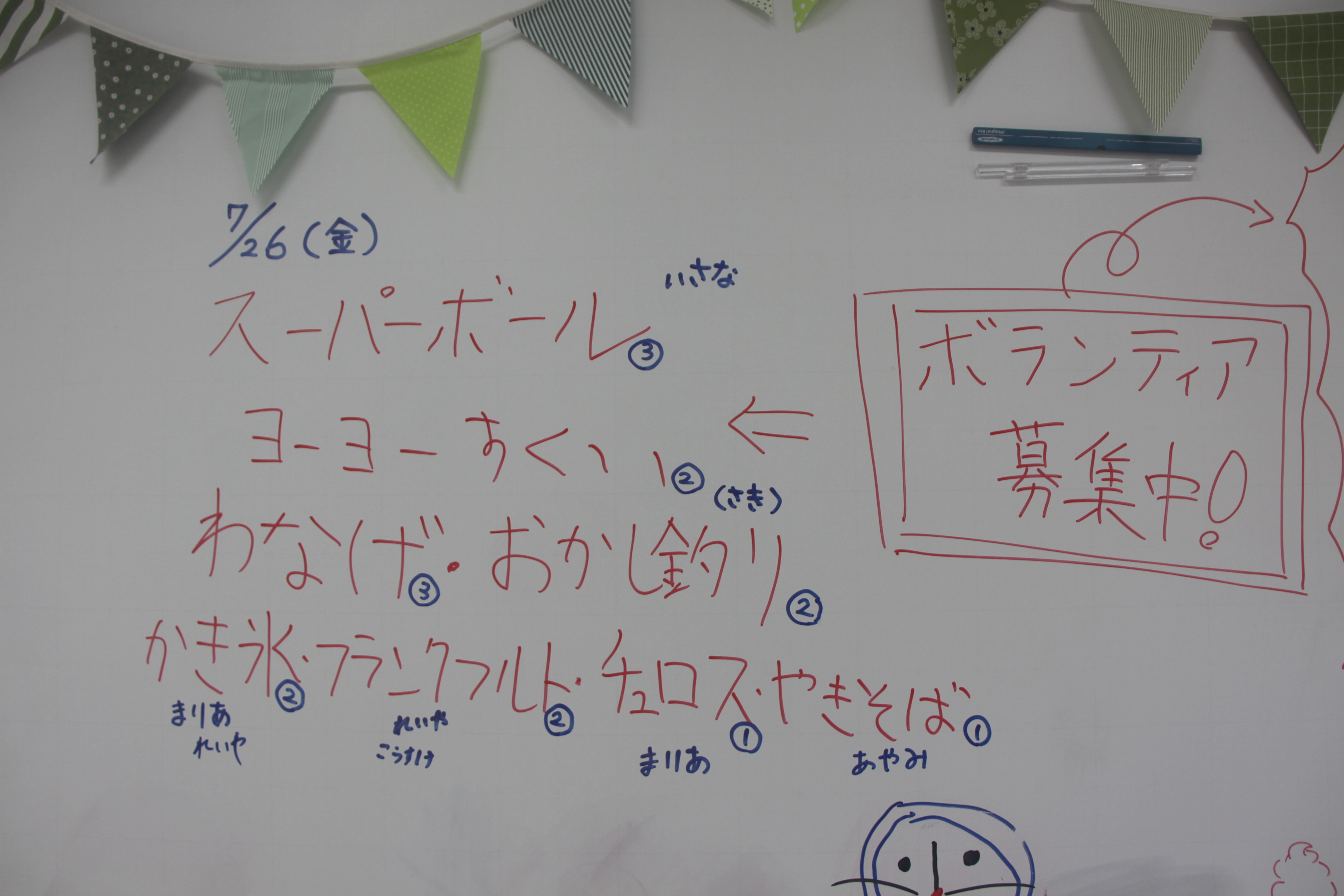

7/26のおひさまひろば夏祭りのお手伝いにひな中も参加(^_^)
◎ひな中からの風✨~本の楽しさを一緒に(^Д^)
この夏も、文化委員会が、「読み聞かせ」で「豊かな本の世界」を小学校へ届けます。(7/29(西小)8月1日は東小に行きます。楽しみに待っててね。)
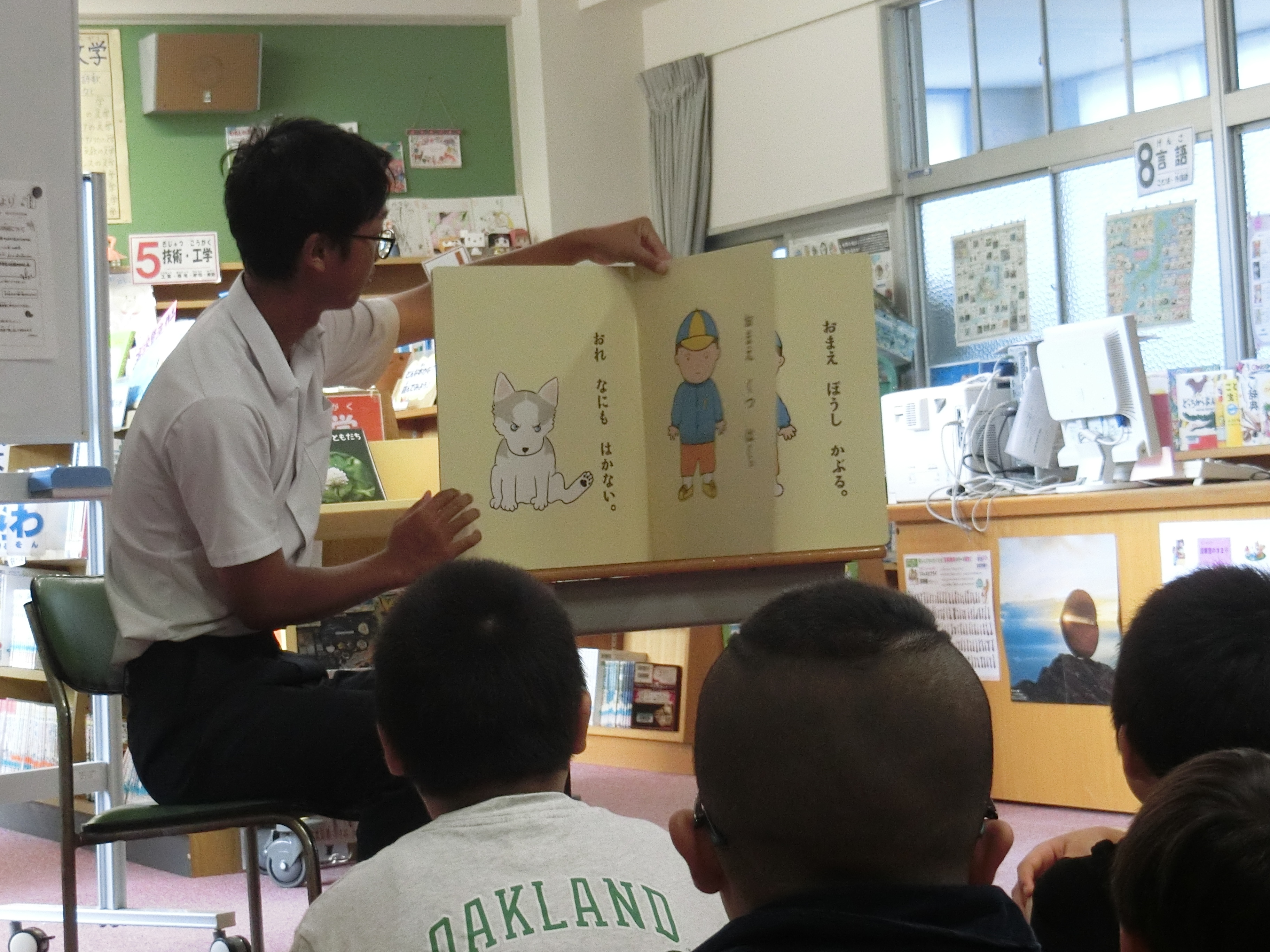

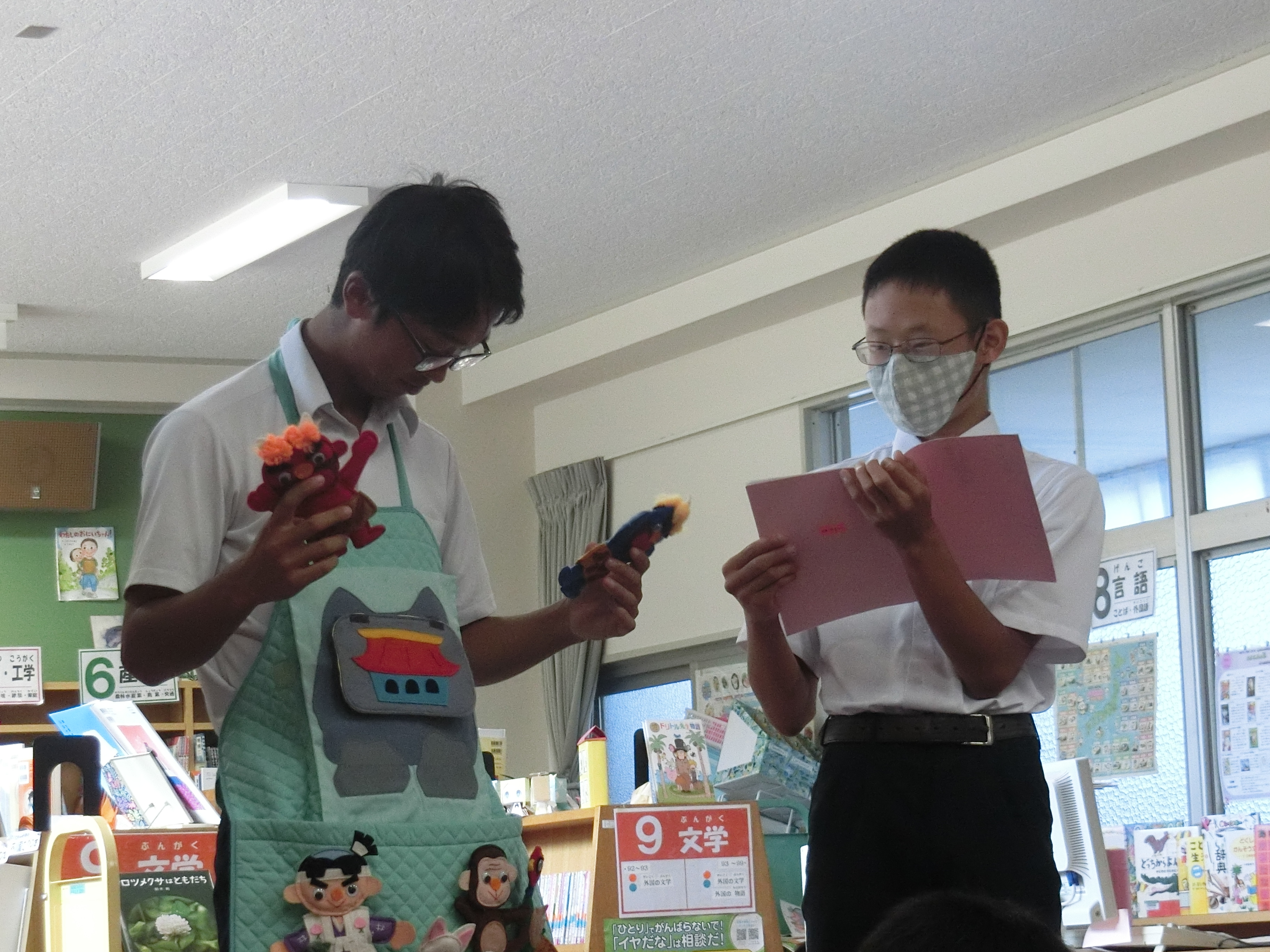
The love of books is among the choicest gifts of the gods. Conan Doyle
(本を愛することは、神々の最も優れた贈り物の一つである。)
◎暑中お見舞い申し上げます。




◎地域とともにある学校 ひな中からの風✨
~日生の応援団 活動中
三年生は、総合的な学習の時間に地域で活動されている方々からお話を聴いたことをもとに、夏季休業期間を活用して、地域貢献活動に取り組んでいます。第1グループは、海ラボさんと協働で、海ゴミを回収し、海ゴミアートを制作し、環境保全をアピールしていく計画です。第2グループは、日生観光協会さんと連携し、「日生ならでは」の情報をQRコードで読み込めるような情報提供の取組を進めています。第3グループは、ひなビジョンさんの協力をいただき、日生中学校が取り組んだこれまでの海洋学習を動画にまとめ、学校HPでの紹介や、校外へ発信していきたいと考えています。第4グループは、社会福祉協議会さんが主催する高齢者対象の交通マナー講座(8/7)運営のお手伝いを行い、参加者の方々との交流を深めます。第5グループは、8月14日に開催される「てんてかんか(寒河地区)」のお祭りに出店する天gooカフェさんの屋台の手伝いをします。とくに子どもたちが楽しめるゲームや屋台の運営に携わりますよ~。第6グループは天gooカフェさんの料理体験イベント(8/2、8/23)と、てんてかんか(8/14)のお手伝いをがんばります。


日生中学校は、地域連携・協働、まちづくりの活動に積極的に取り組んでいます。情報やご相談がありましたら学校までご連絡ください。ひな中ボランティア推進プロジェクト事務局(PTA事務局0869ー72-1365:久次(ひさつぐ))
◎眩しすぎる夏の陽差し 走り出す想いを胸に 一人問いかけてみれば 聞こえる本当の声 きっと辿り着ける 答えはここにある(7/25)



〈夕立に影深くなる部屋の中「どうするルパン」と聞く男たち 吉川宏志〉(7/25)

◎わたしたちの星輝祭へ。(7/24)
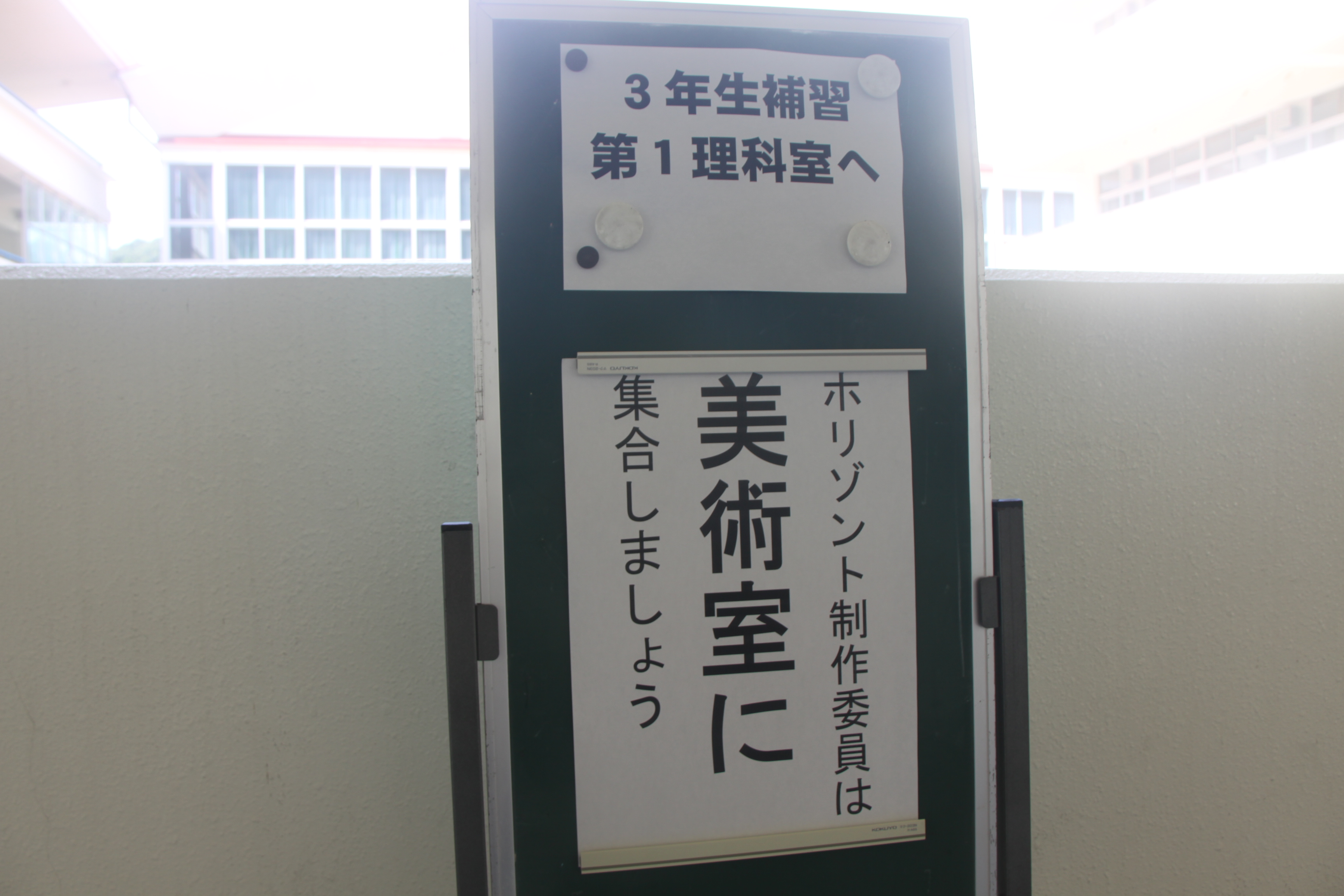


◎「大暑」でした。
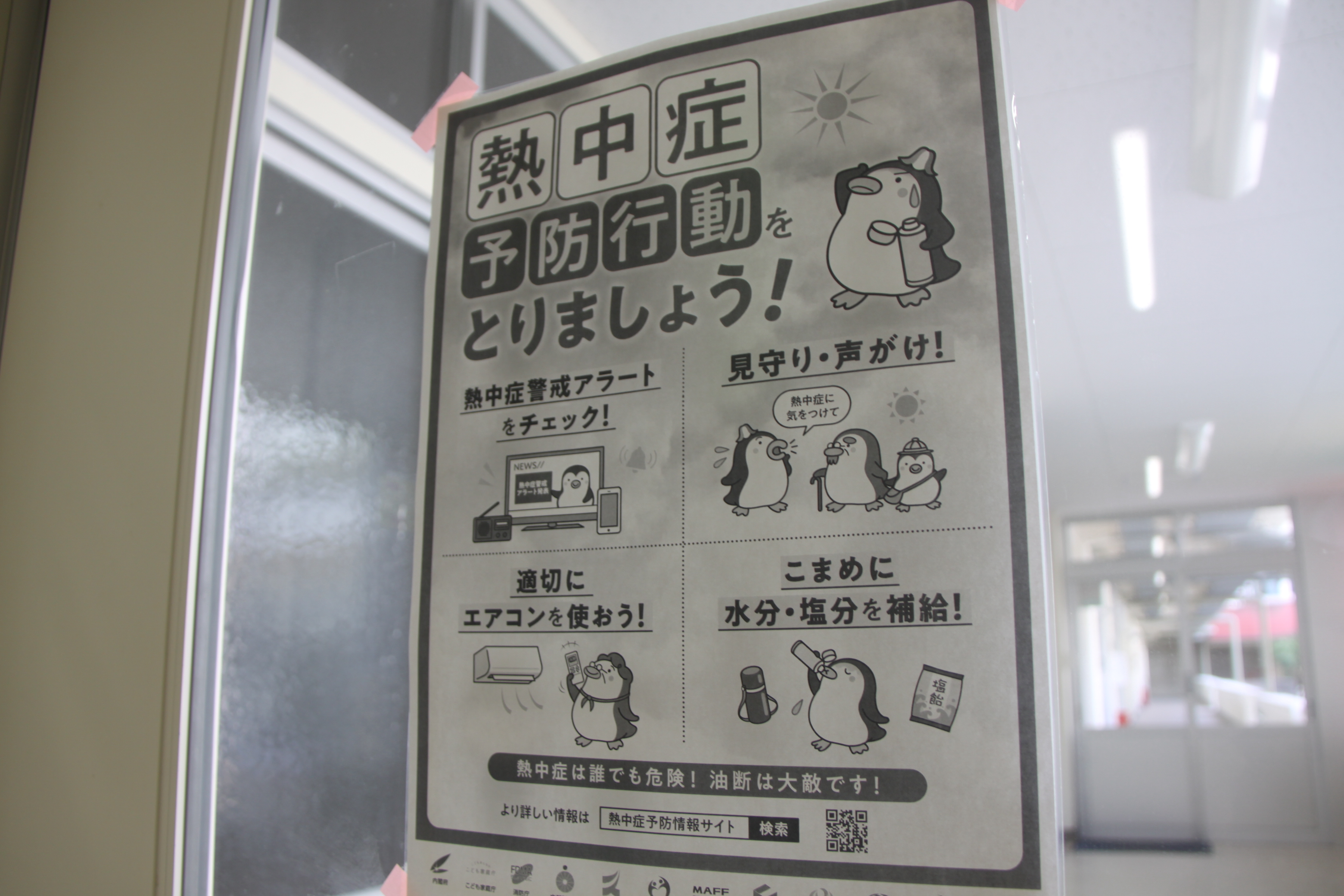
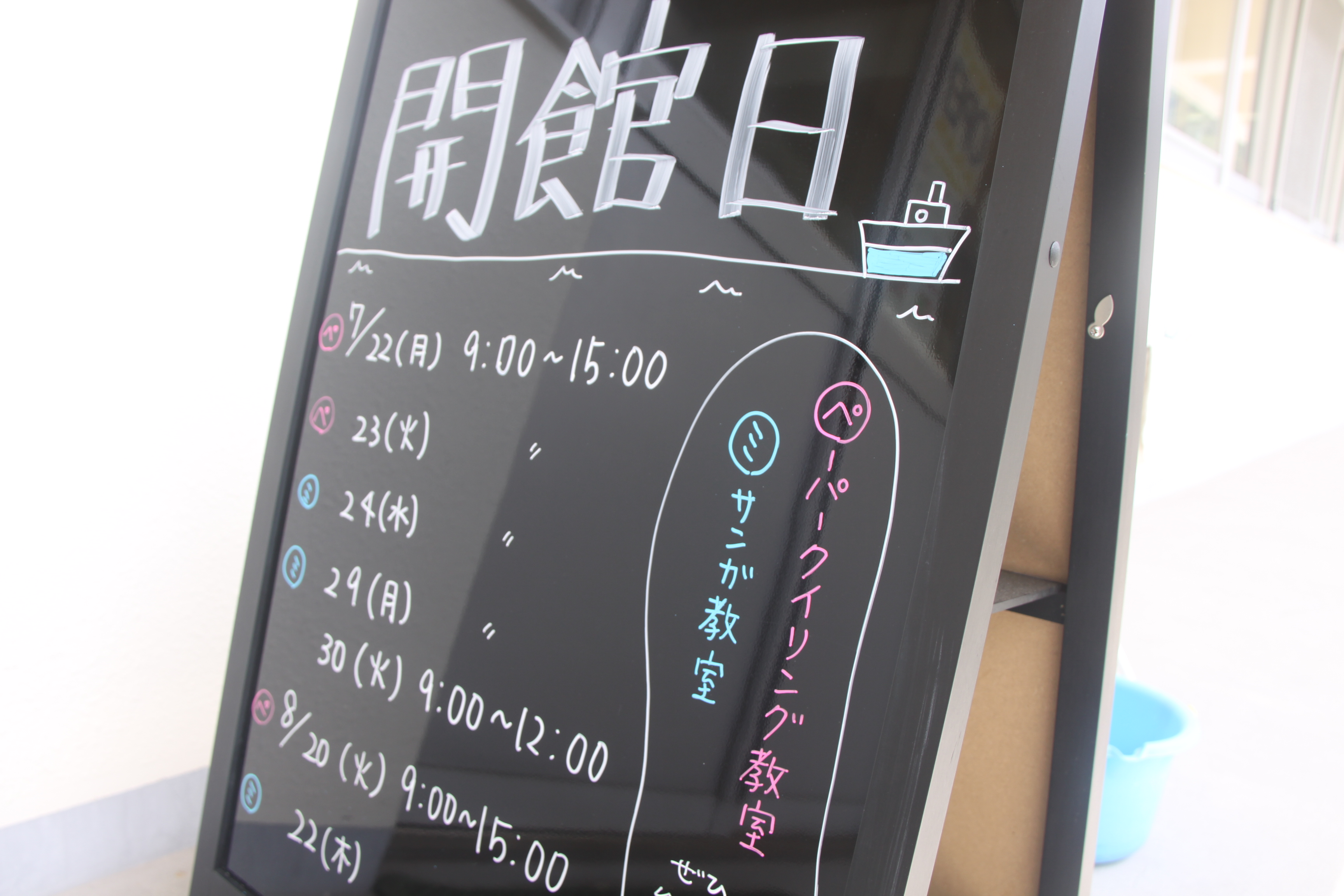

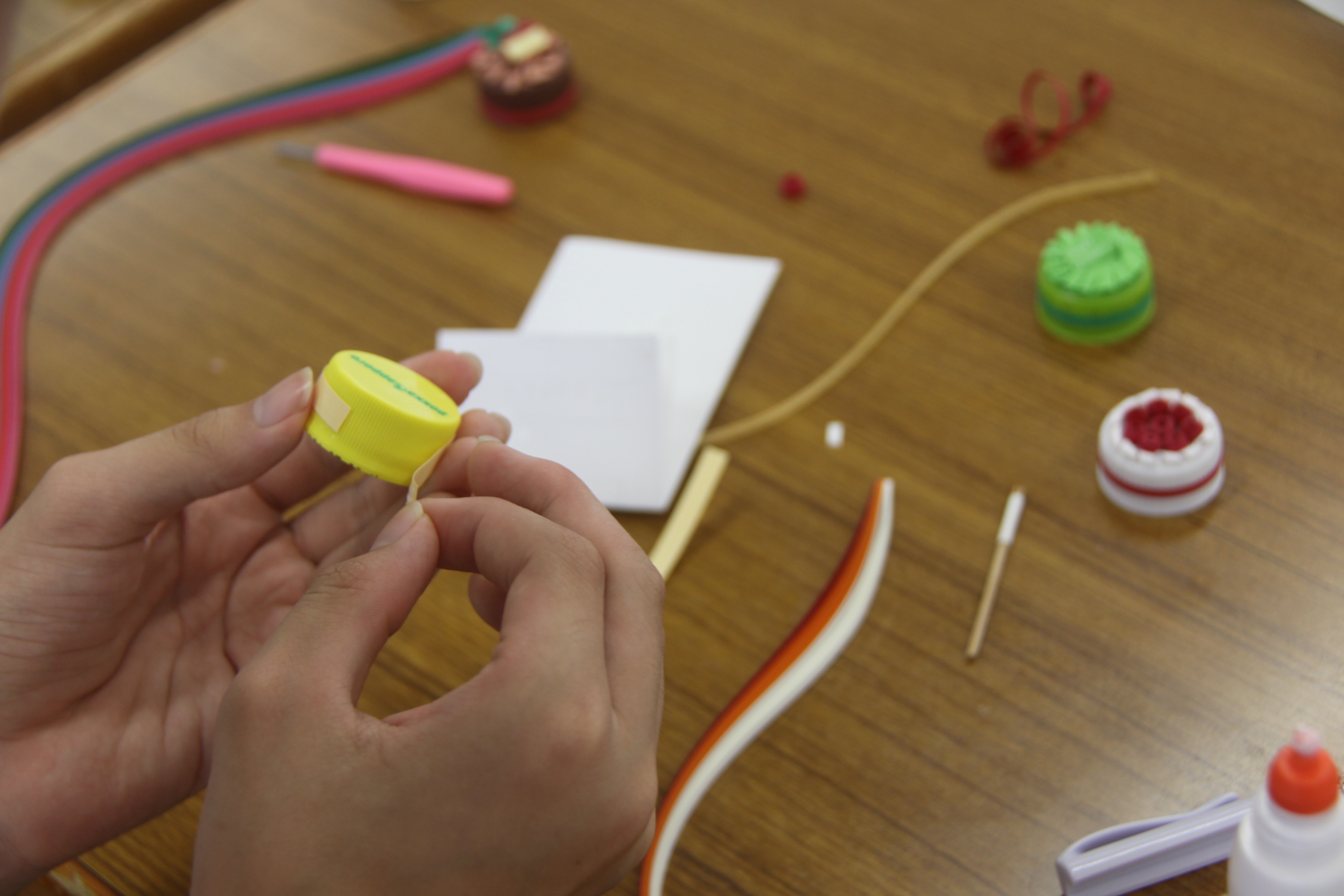


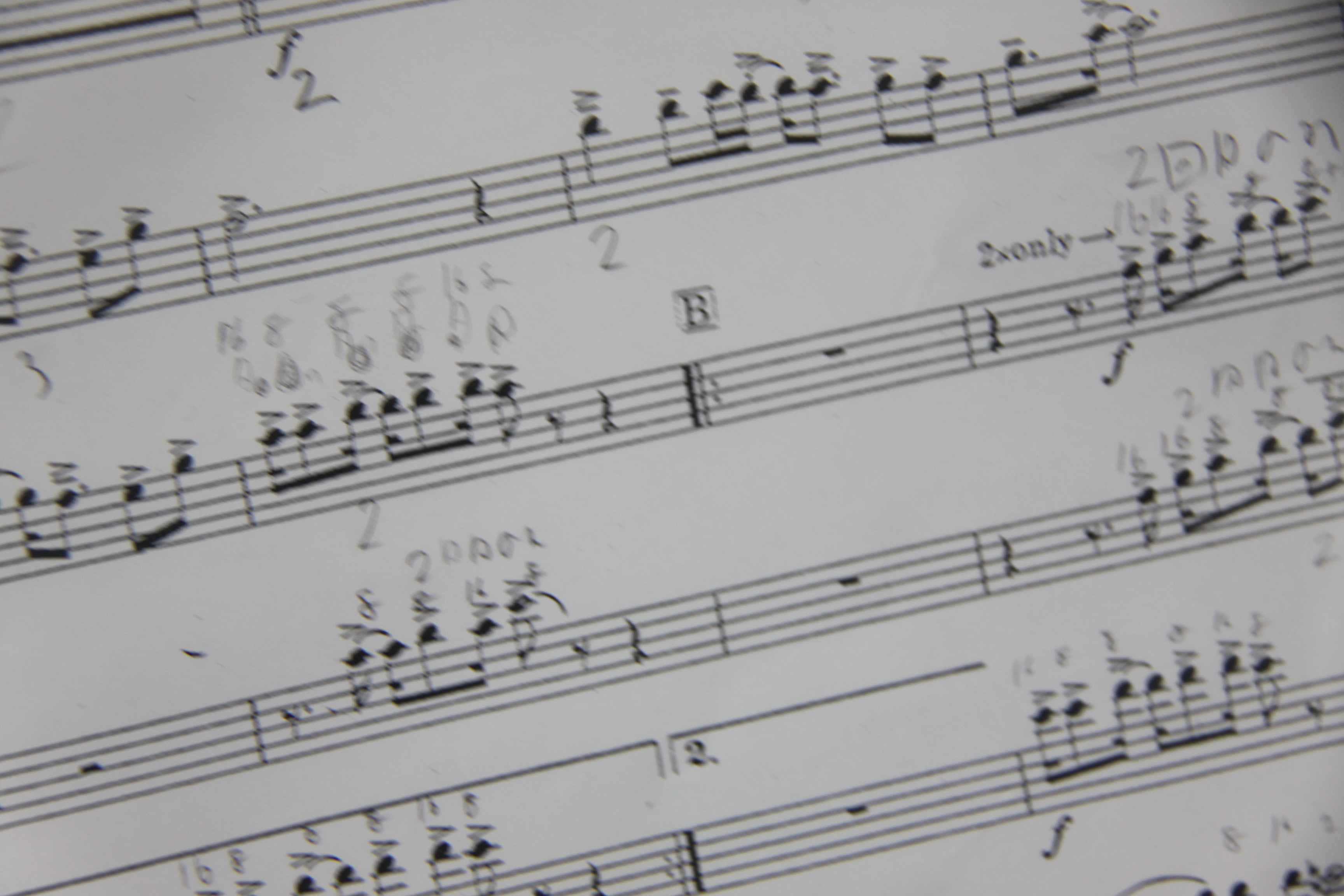


毎年7月23日頃~8月6日頃にあたりますが、日付が固定されているわけではありません。二十四節気は季節の移り変わりを知るために、1年を約15日間ごとに24に分けたものですが、太陽の動きに合わせて1年を24等分して決めるので一定ではなく、1日程度前後することがあるからです。また、大暑といっても、大暑に入る日をさす場合と、大暑から次の立秋までの約15日間をさす場合があります。
○うなぎでお馴染みの土用の丑の日は、夏の土用にめぐってくる丑の日をいいます。夏の土用は立秋前の約18日間なので、立秋前の節気である大暑(約15日間)と重なります。夏の土用や土用の丑の日の風習は、最も暑い時期を無事に乗り切るための暮らしの知恵であることがわかりますね。
○大暑には暑中見舞いを
「暑中見舞い」は大暑まで。立秋に入ると「残暑見舞い」になります。大暑は、暑中見舞いでおなじみの「暑中」にあたります。二十四節気の小暑と大暑の期間(7月7日頃から8月6日頃までのおよそ30日間)を「暑中」と呼び、暑さをいたわる手紙を出す習わしがあります。とはいえ、7月上旬や梅雨の最中はそぐわないので、暑中見舞いは梅雨明け後か夏の土用(立秋前の約18日間)に出すようになりました。立秋を過ぎると「残暑見舞い」となります。
○土がじっとりとして蒸し暑くなる時期。蒸し暑いことを「溽暑(じょくしょ)」といいます。昔に比べて暑さが増しているのか、2007年以降、最高気温25度以上は「夏日」、30度以上は「真夏日」、35度以上は「猛暑日」と定義され、使われるようになりました。
○夏の雨は大雨になりやすく、夕立になったり、ときどき大雨が降る頃です。夏の雨は大雨になりやすく、むくむくと湧き上がる入道雲が夕立になり、乾いた大地を潤します。大粒の雨は「鉄砲雨」、篠竹を突くように激しく降る雨は「篠突く雨」、滝のようなすさまじい雨は「滝落し」と呼びます。最近は、突発的で予測困難な局所的大雨「ゲリラ豪雨」も多くなりました。
○鰻以外にもある様々な食べ物・風習
最も暑い頃なので、暑気払いをするのにも最適の時期です。昔ながらの定番は、冷麦、そうめん、ビール、瓜(西瓜、胡瓜、冬瓜、苦瓜、南瓜)、氷(かき氷、氷菓子、氷料理)、甘酒などです。また「暑気払い」として風鈴、すだれ、金魚鉢、団扇など五感の涼を取り入れて、五感で感じる夏の涼を取り入れるのも一興でしょう。8月13日、ひなせみなとまつりにもぜひ浴衣で来場ください。ひな中日生盛り上げたい隊のお店も「冷たいもの」を用意していますよ(*^o^*)。
◎多くの人に支えられて(7/23:火災報知器点検)

◎暑い夏を、熱い夏に。
自分のために 仲間のために 汗をかく(7/23:部活動をがんばっています)


◎多くの人に支えられて(7/22:受水槽点検)
暑い中、ありがとうございます。明日は火災報知設備の管理点検を行います。

〈まぶしかる夏野のみどり照る昼の雑草(あらくさ)といえど花はおごれり 芦田高子〉7/22




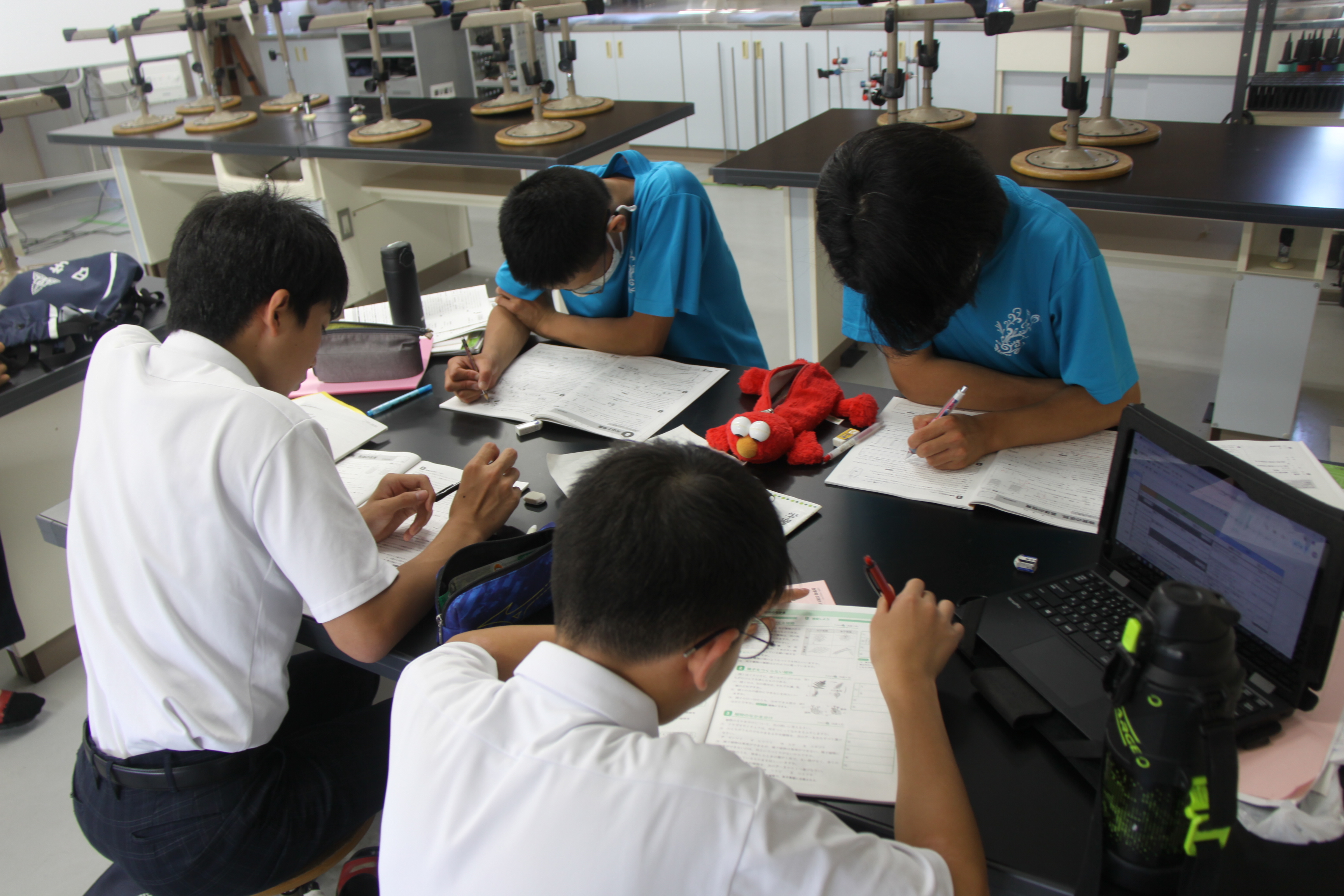

三年生補充学習。個別懇談会(22日~26日まで)∈^0^∋
〈「待ち人はこない」「自分で会いに行け」このおみくじは当たる気がする 枡野浩一〉7/22
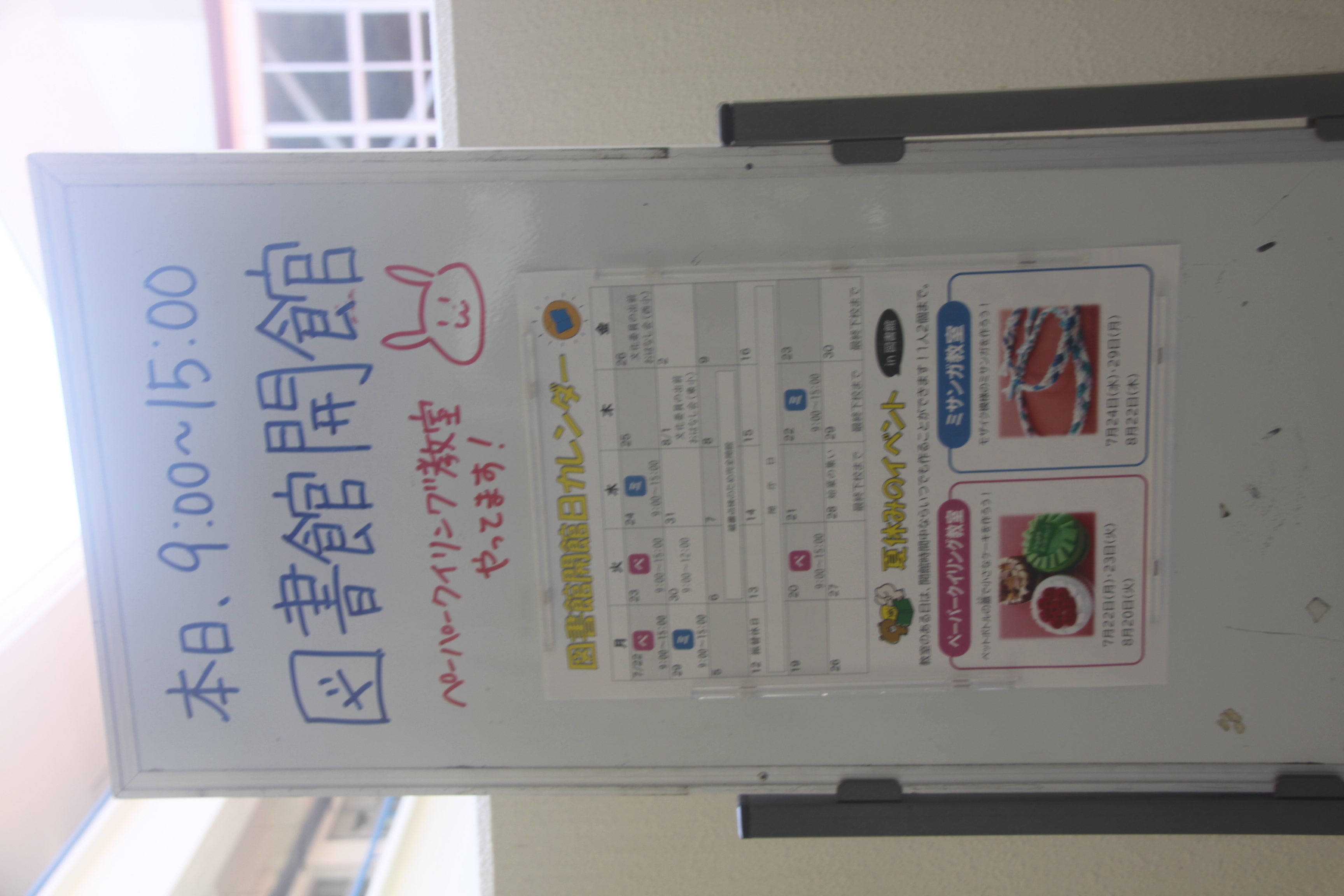
◎梅雨明ける(7/21)

◎もぎたて ひな中からの風✨(7/20)

◎HINASE LEGACY✨(7/19)



終業式を終えて。
◎地域と共にある学校(7/19)多くの人に支えられて
~頭島あかりまつり灯籠づくりワークショップ
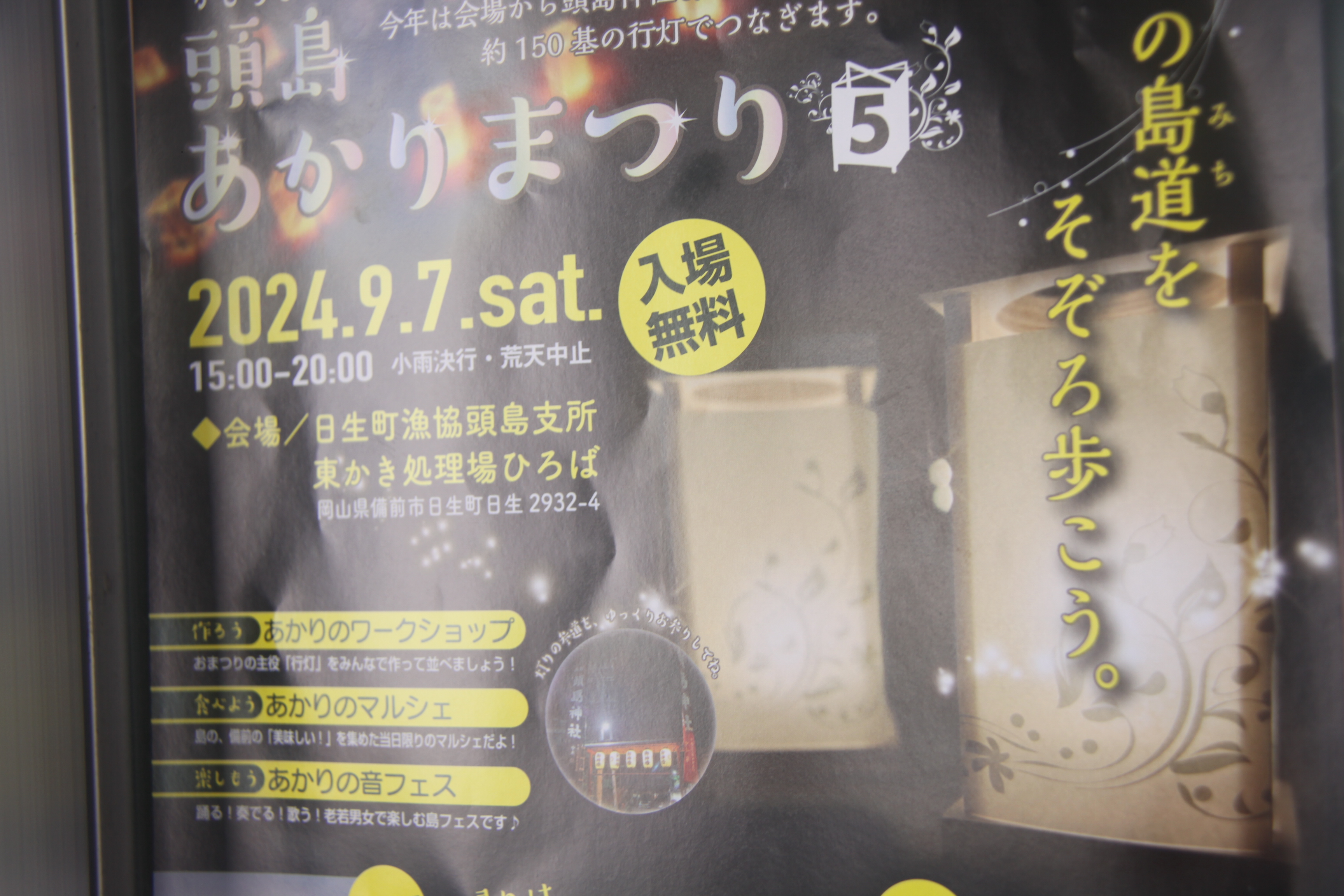








~生徒会 地域清掃ボランティア









「がんばっているね。ありがとう」と、活動中の子どもたちに地域の方々がお声をかけてくださいました。
~手作りボランティア教室(夏ボラ体験事業・社協)
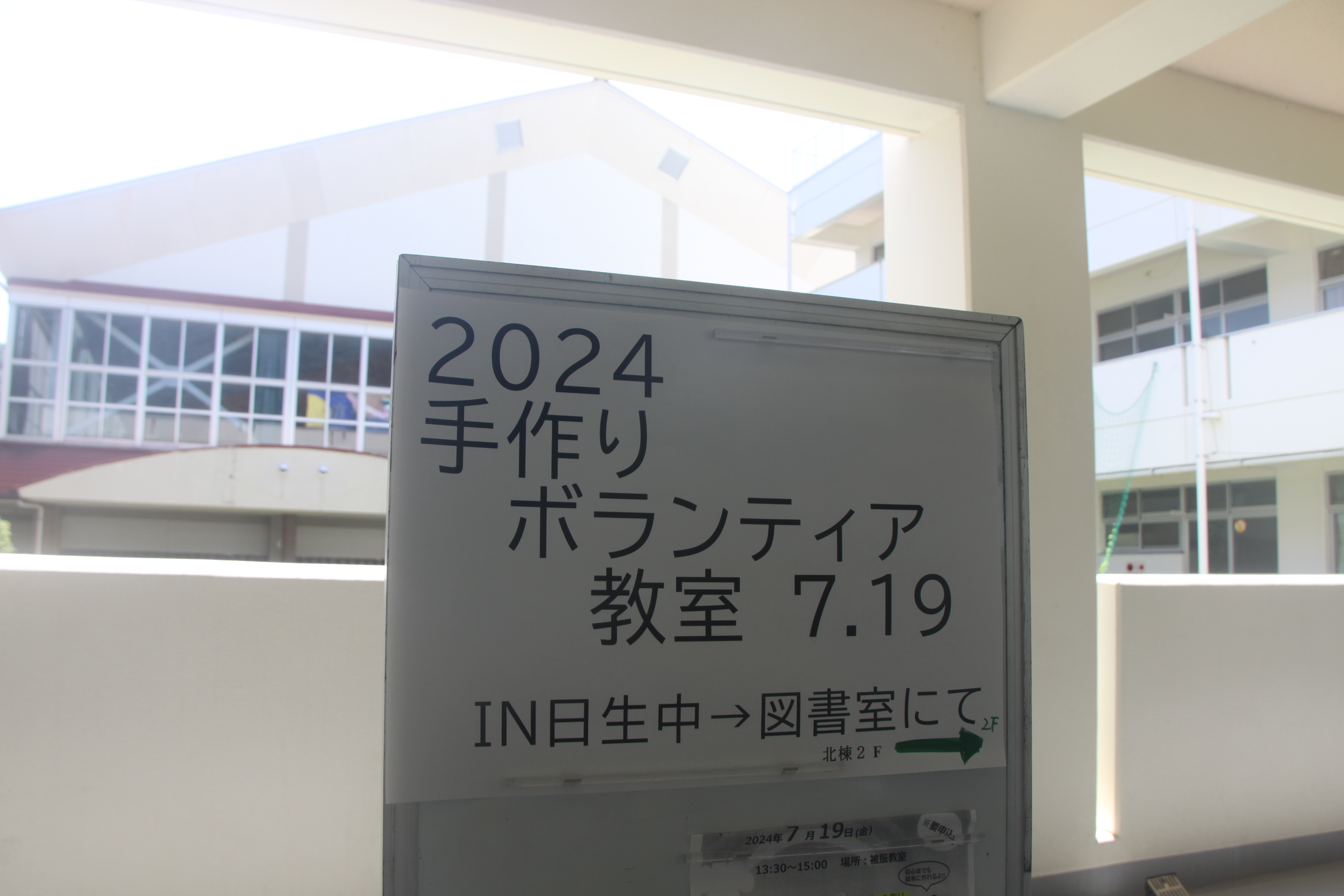

◎1学期終業式(7/19)
~ありがとうみんな、私たちの学校。
また2学期に元気に会おうね。



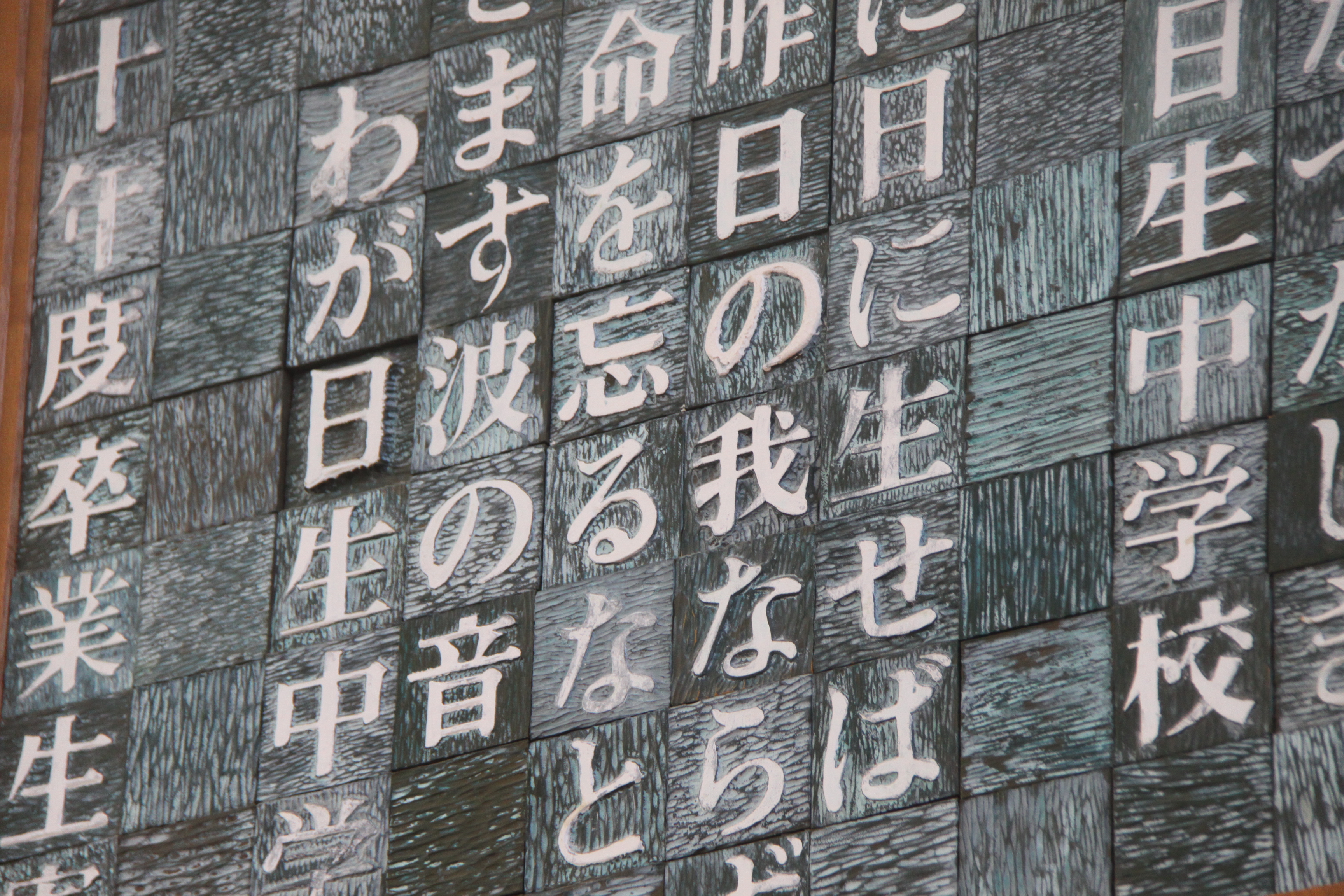

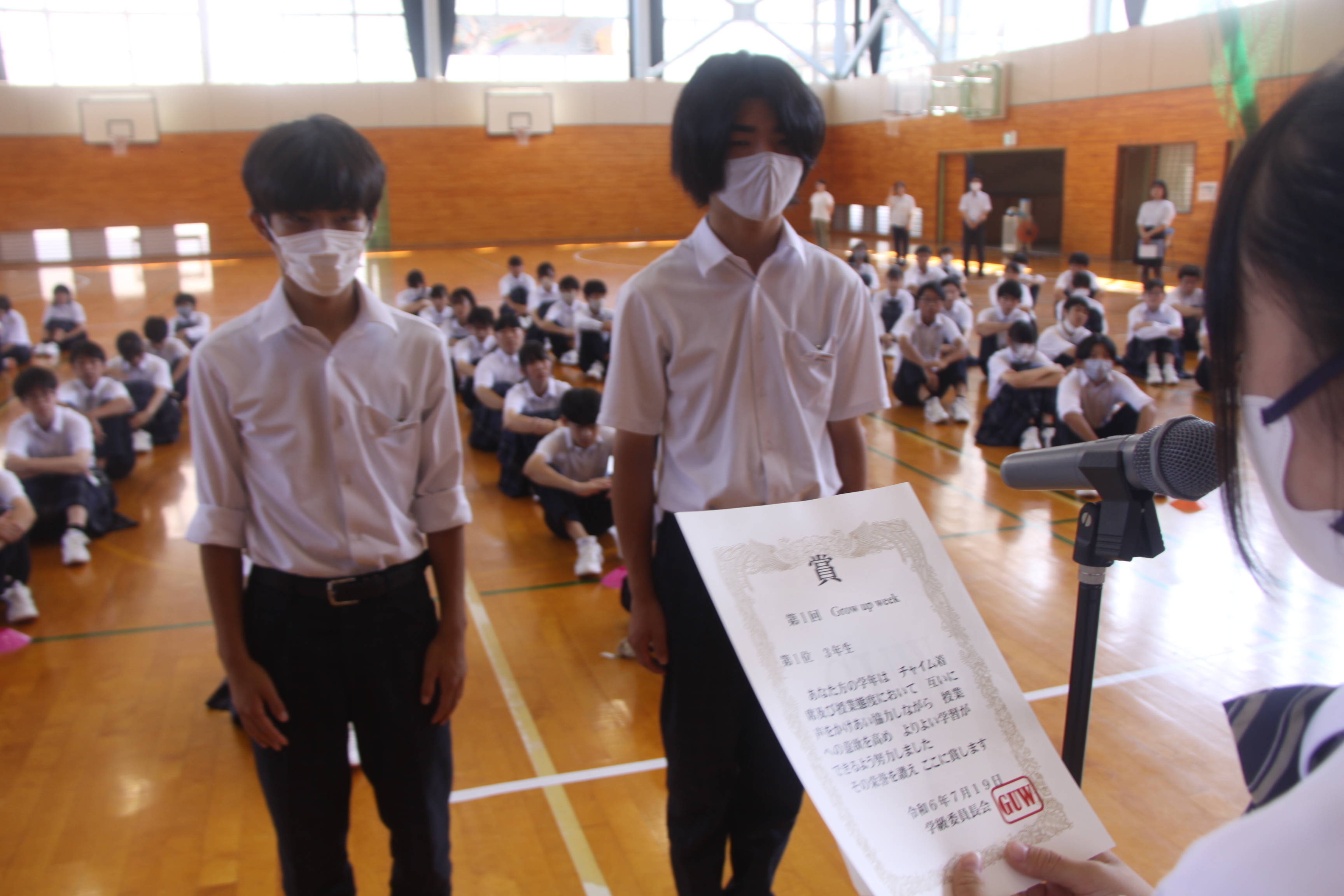



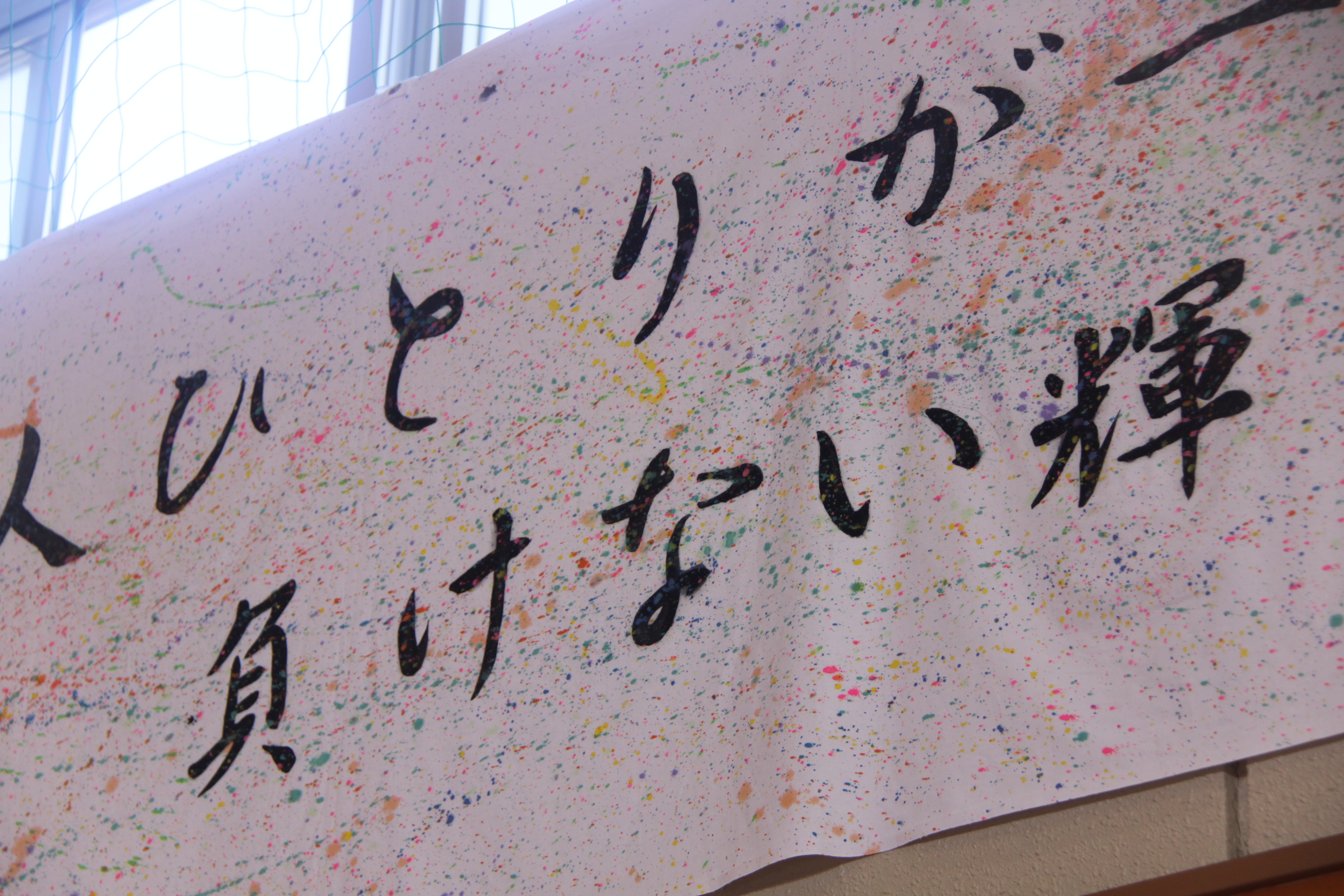


◎学び続ける者だけが教壇に立つことができる
(7/19:職員研修)



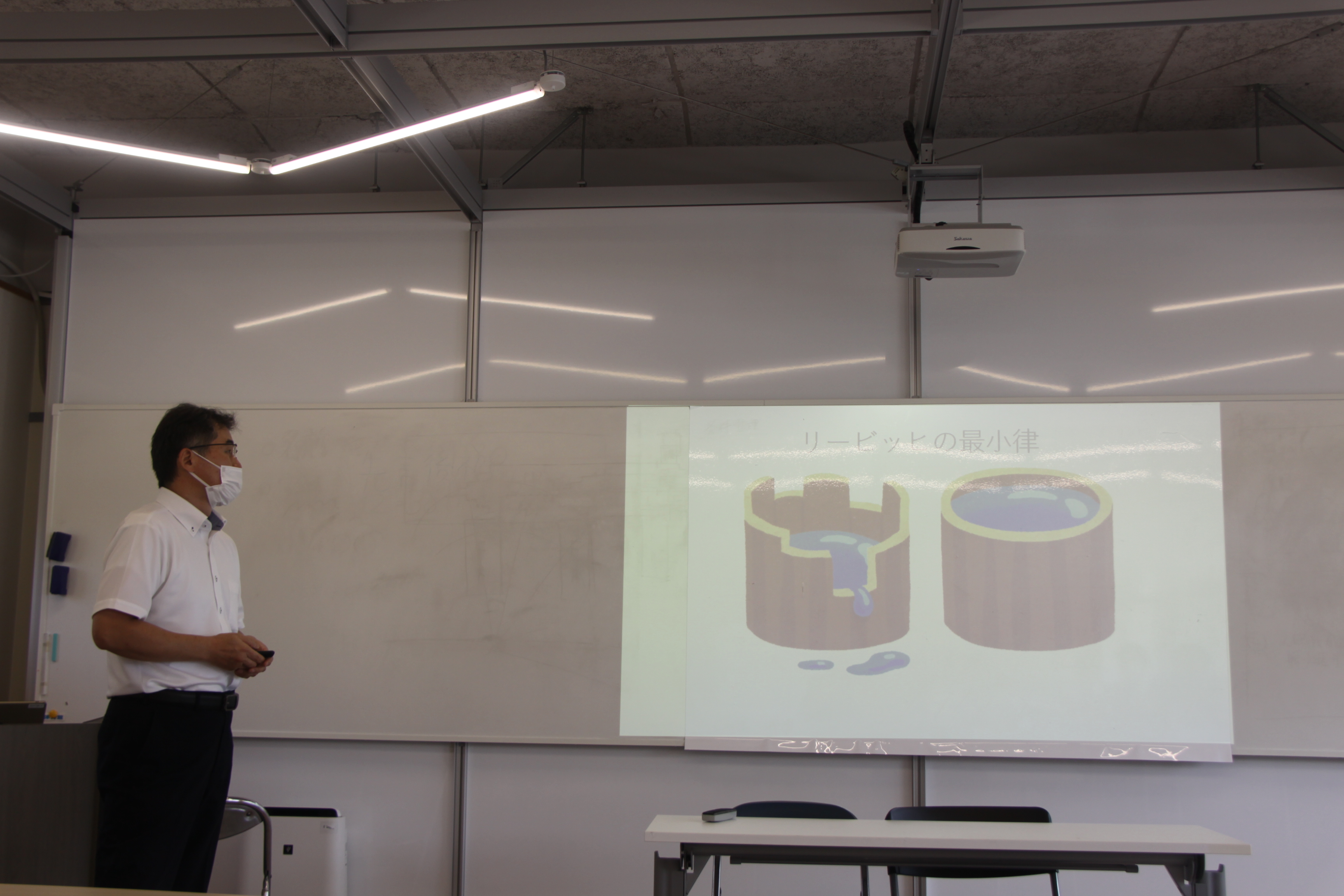
ねじをゆるめるすれすれにゆるめるとねじはほとんどねじでなくなる 小林久美子
◎ありがとう、わたしたちの学校。
~学期末大掃除(7/18)
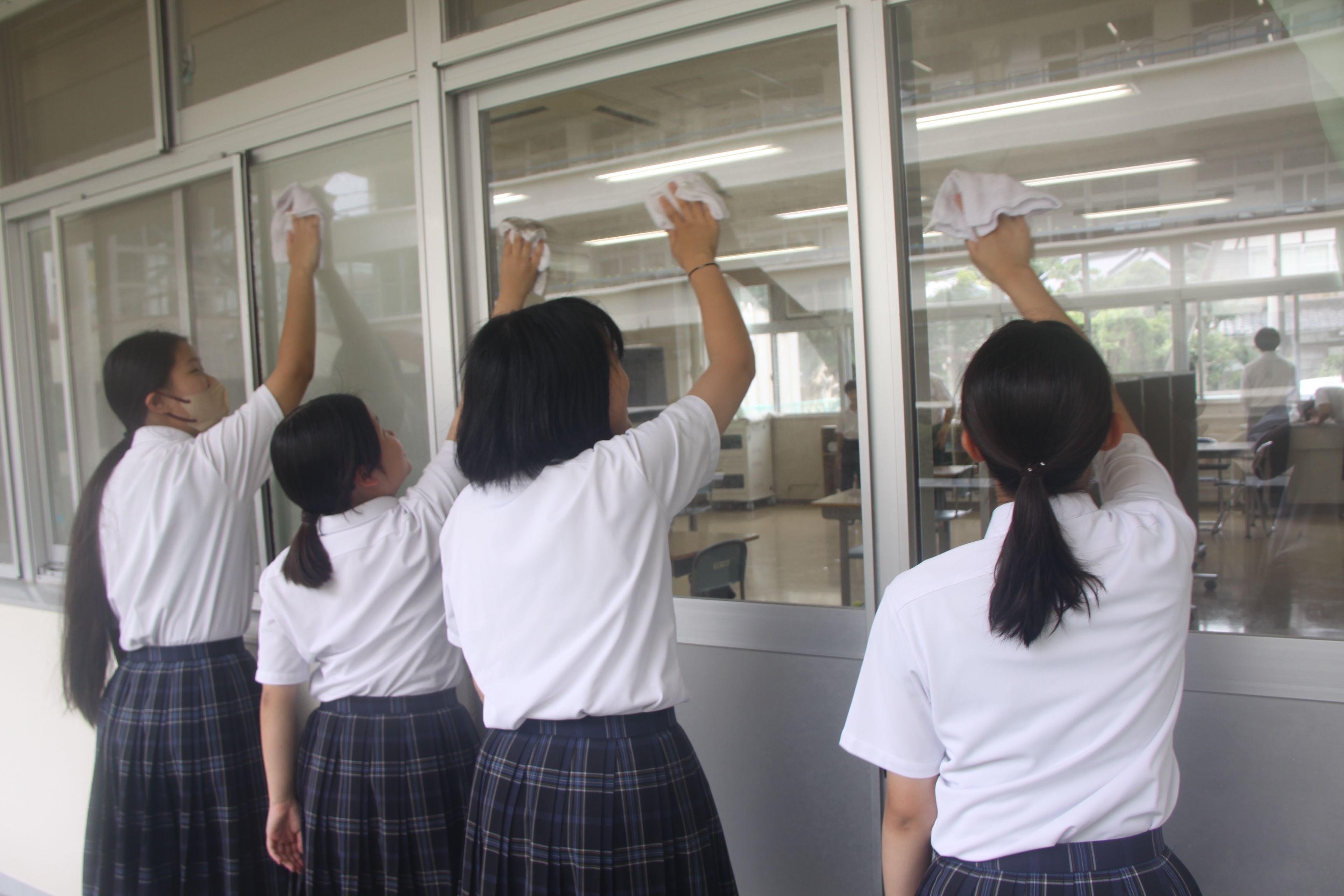








〈あの夏の数かぎりなきそしてまたたったひとつの表情をせよ〉
小野茂樹(7/18)
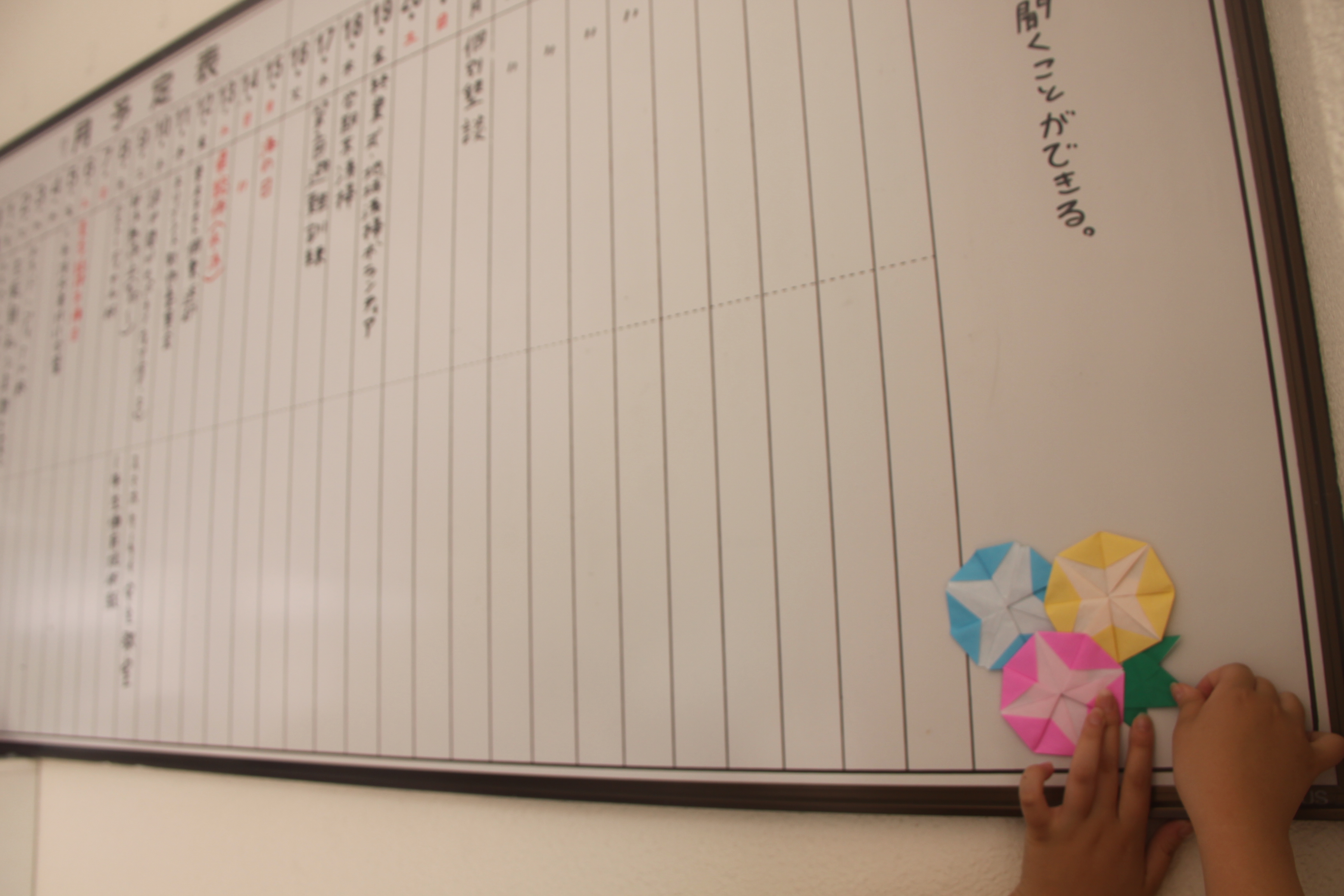
◎いのちを守る行動が取れるように。
~学ぶこと、知ること、訓練すること~
(7/17:第2回避難訓練・不審者侵入を想定して)



根木スクールサポーターさん、「不審者」役をありがとうございました。
〈成分のことは語らぬ約束で花火見てゐる理科部一同 石川美南〉
~日生で輝く 日生が輝く~
8.13ひなせみなと祭り【ひな中ボラ推進プロジェクト】出店スタッフ募集中!7月末〆切。
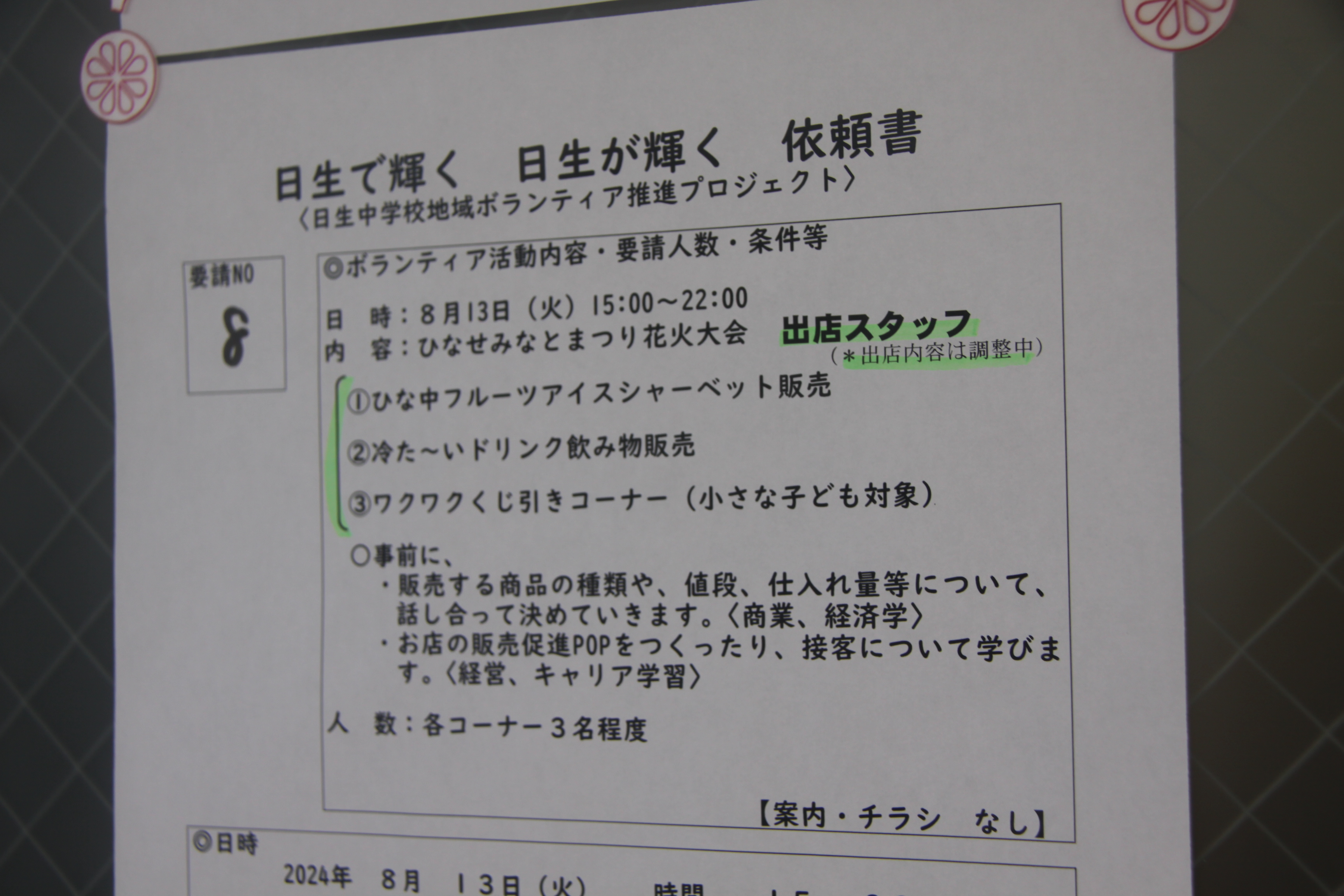
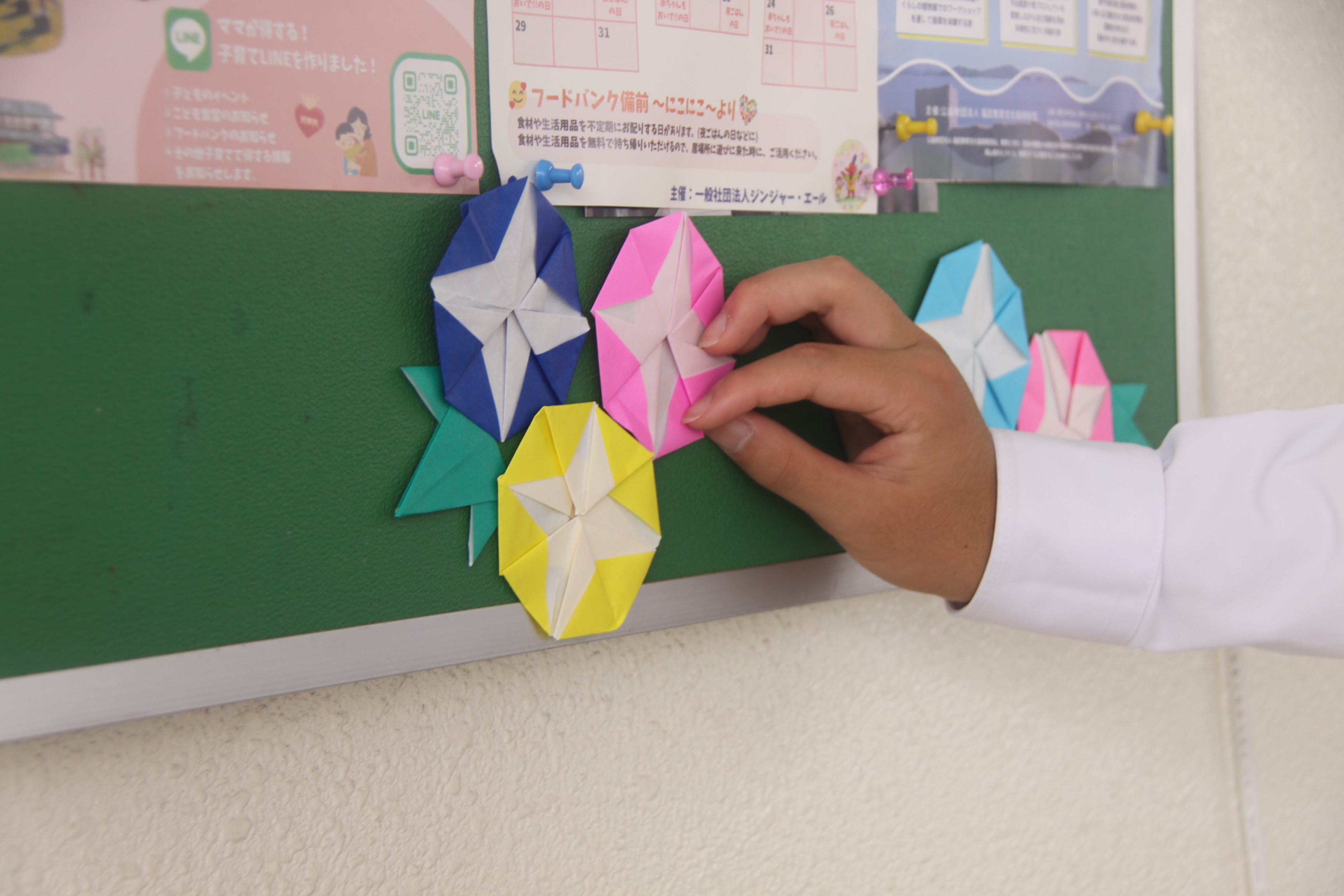
◎仲間と共に汗をかこう(スポーツ大会7.17)

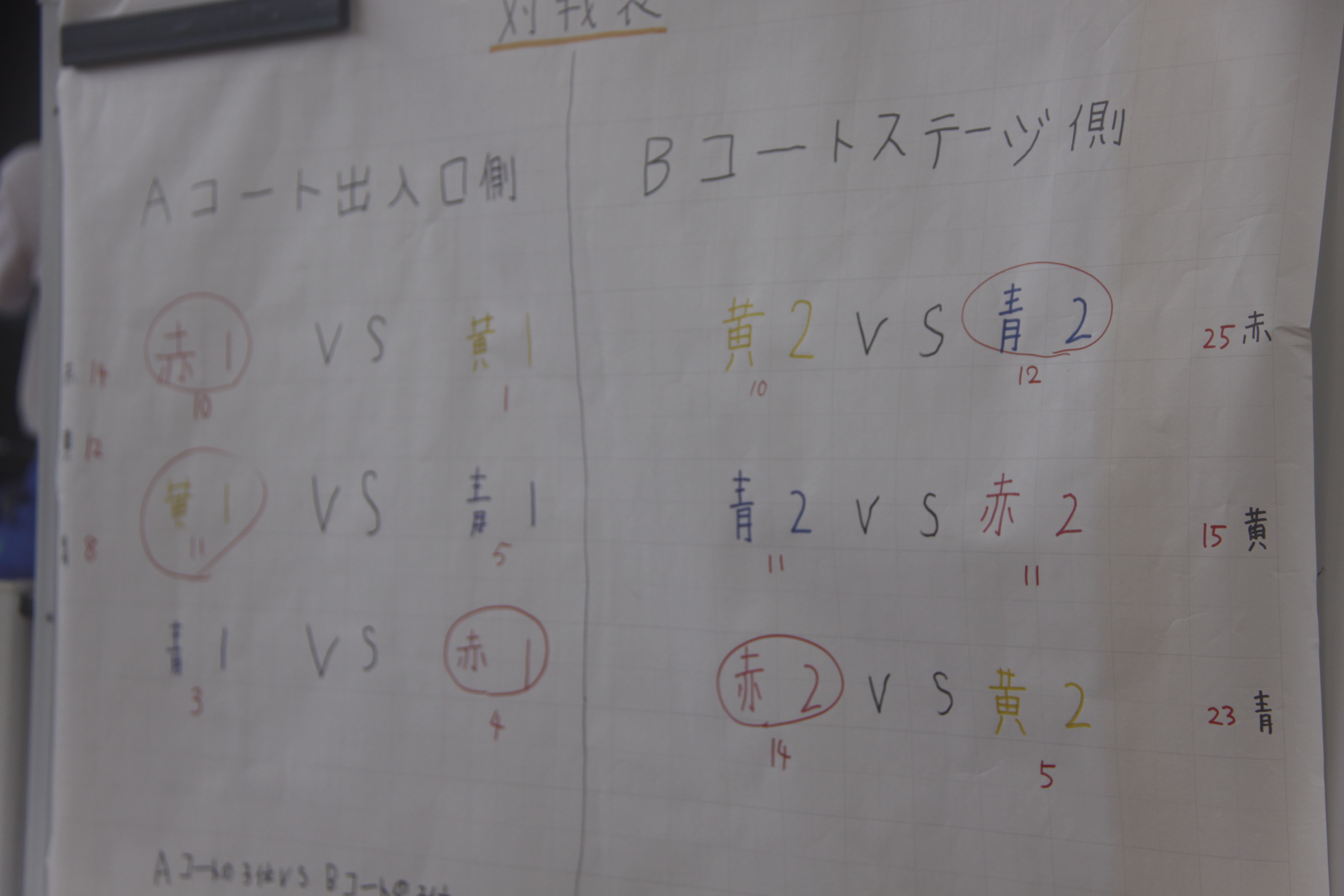




いつも水筒をありがとうございました。
◎びぜん未来学活動報告会へ行ってきました。(7/17:備前緑陽高校)
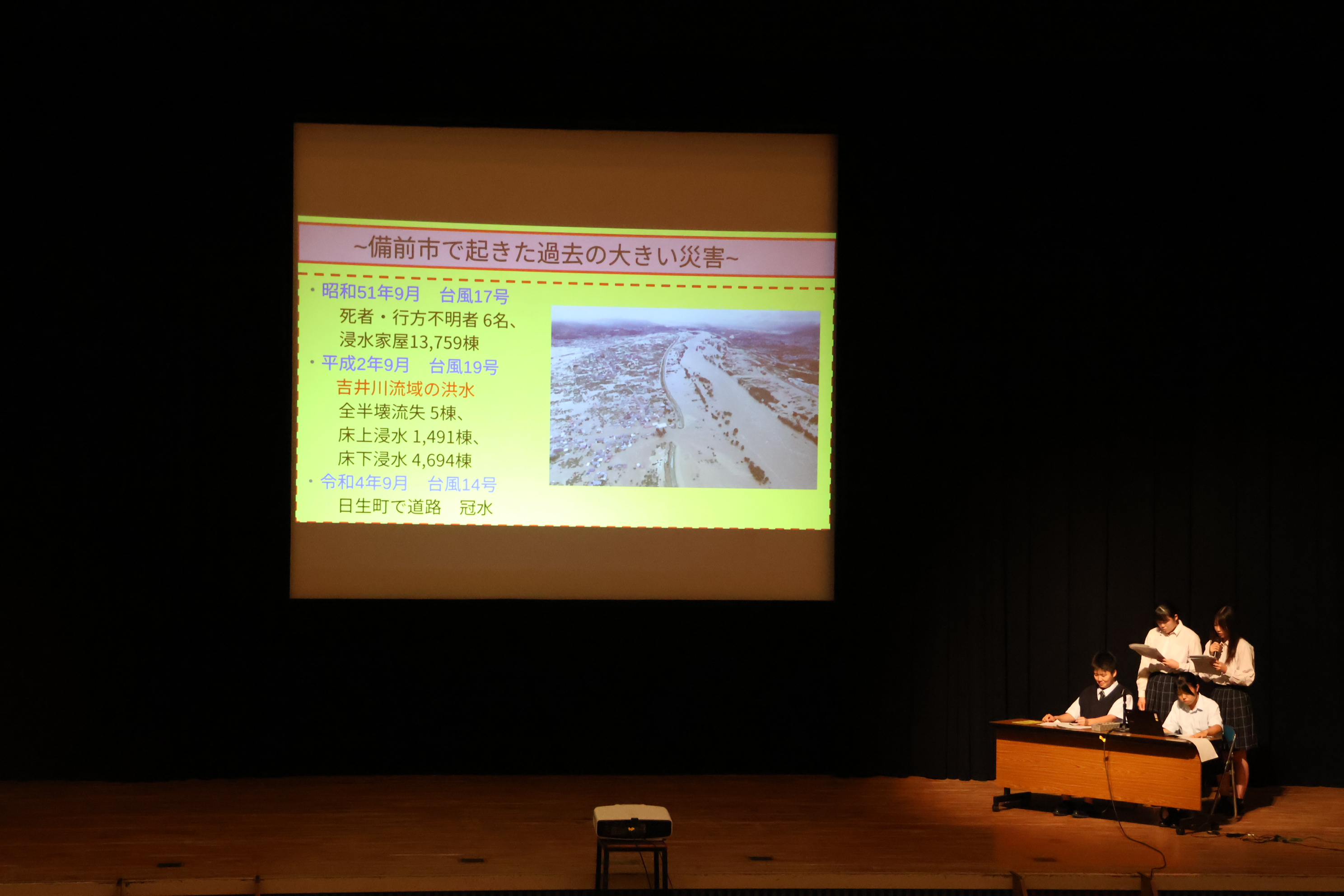
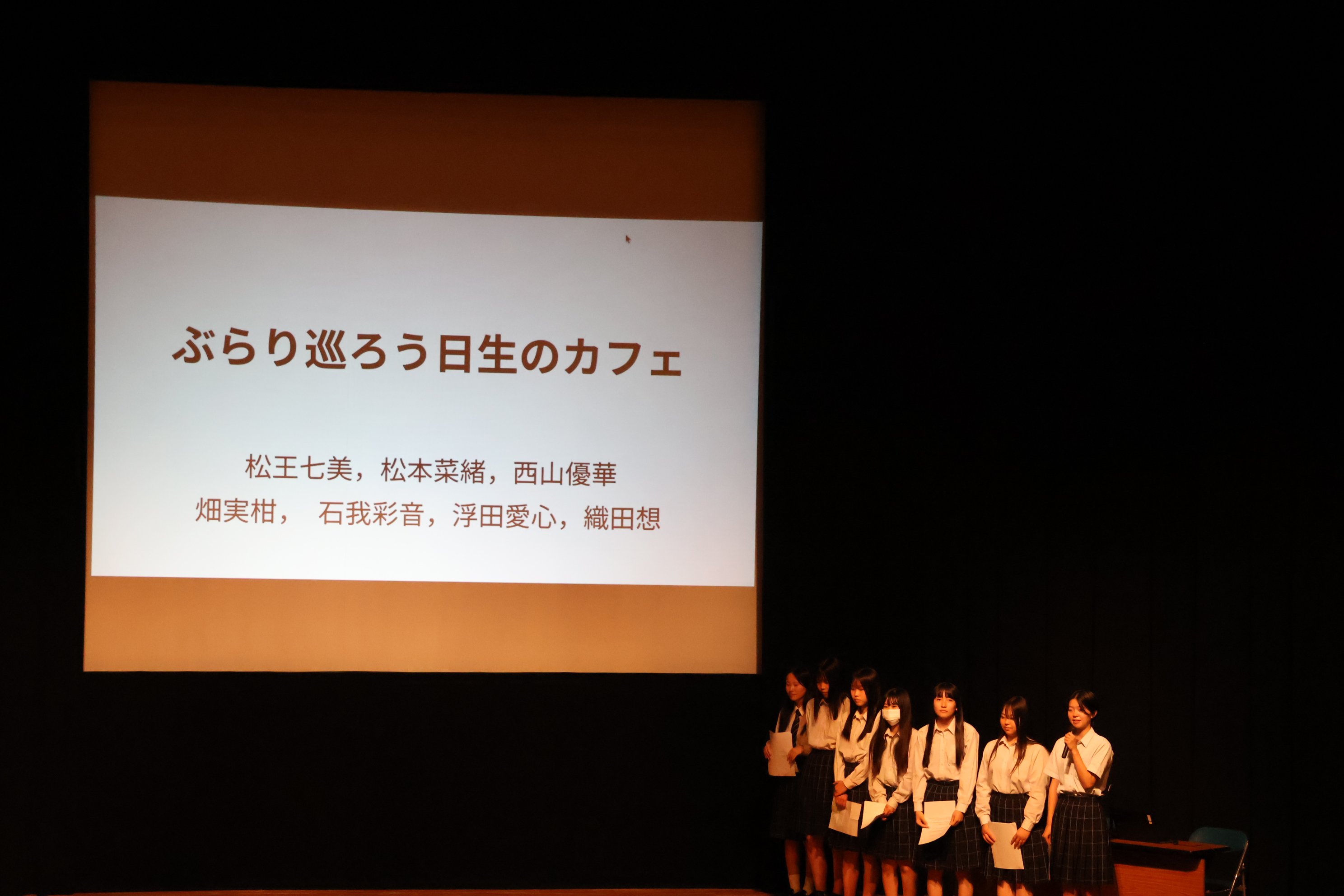
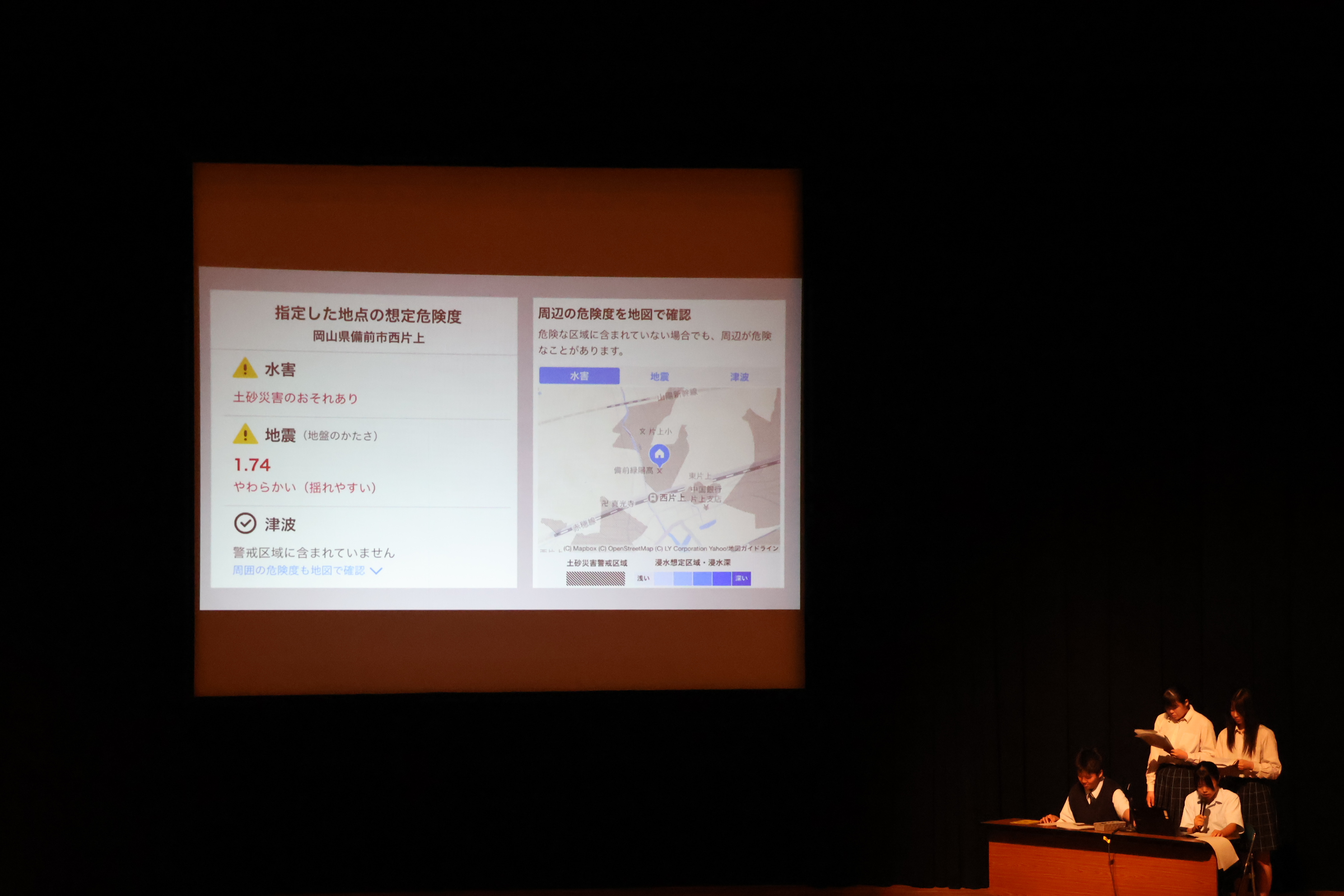
◎多くの人に支えられて
今日は、山本スポーツさんが来校され、柔道着の販売をしてくださいました。ありがとうございましした。(7/18)

柔道一直線・・・、2学期からの授業です。
◎がんばりあう仲間として(7/16)

職員室では、週の初めの日には朝礼を行い、そのあと、各学年団で打ち合わせをして、教室へ向かいます。1学期も残り4日となったこの日、3年団は、いつものように「今日も一日ガンバロウ!」(^_^)と声をかけ合っていました。
◎これからも 元気に 健やかに (7/14)
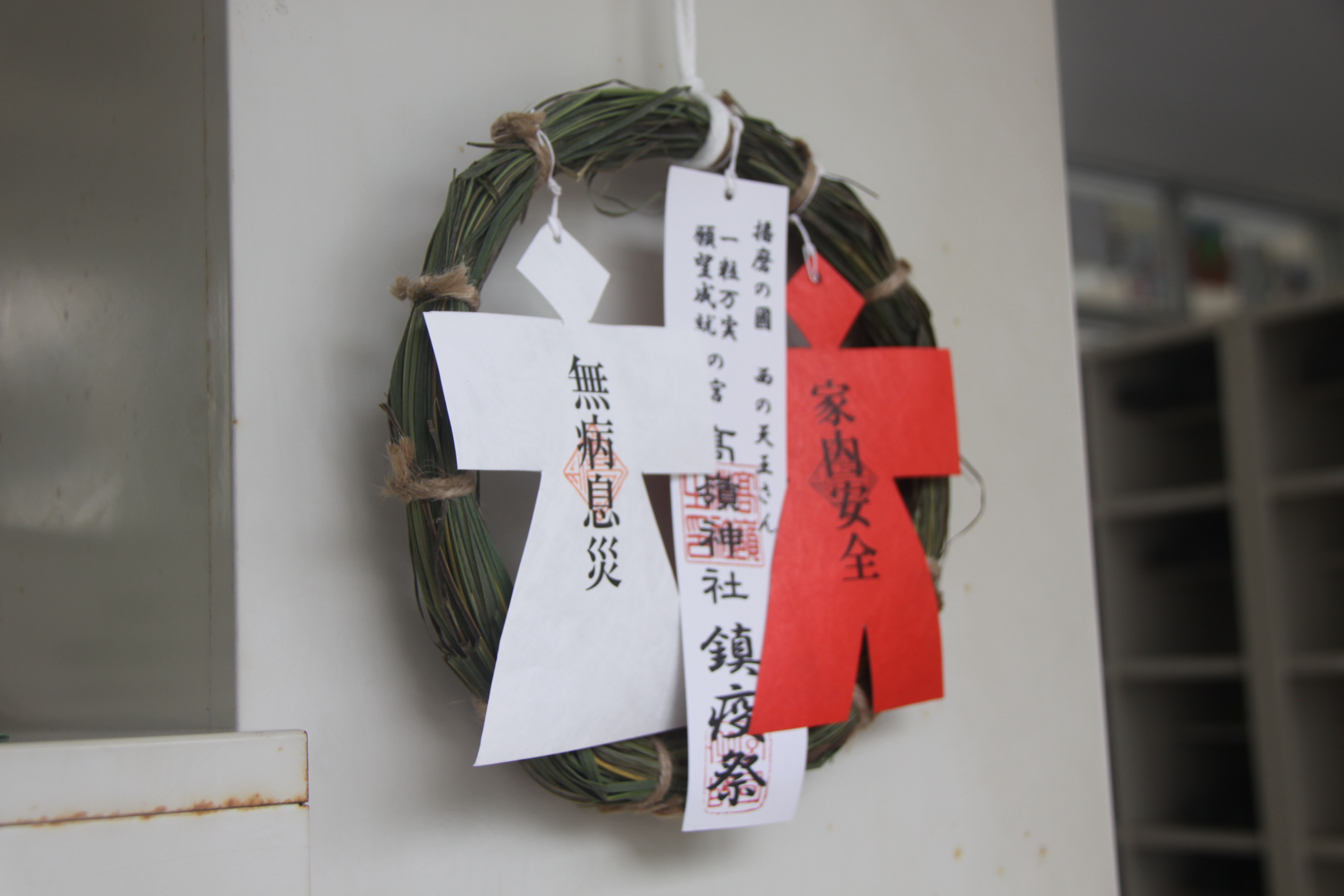
立川先生が住んでいる高嶺神社(上郡)のお祭りがあり、新しい「茅の輪」を頂きました。これからも、一人ひとりが、自分らしく、元気で、健やかに学校生活を送ってくれることを願います。
◎Summer Time Blues2024 (7/12)
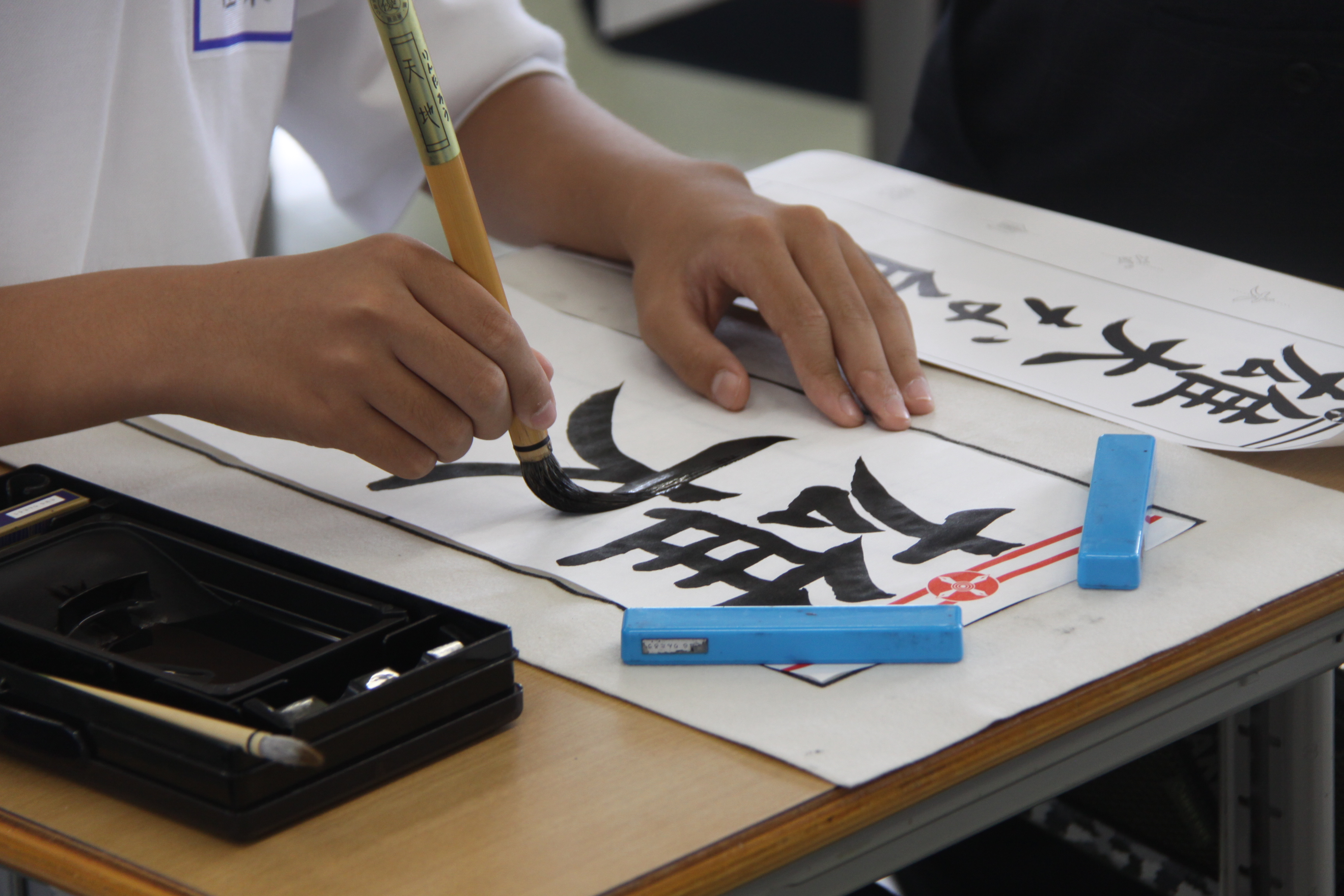

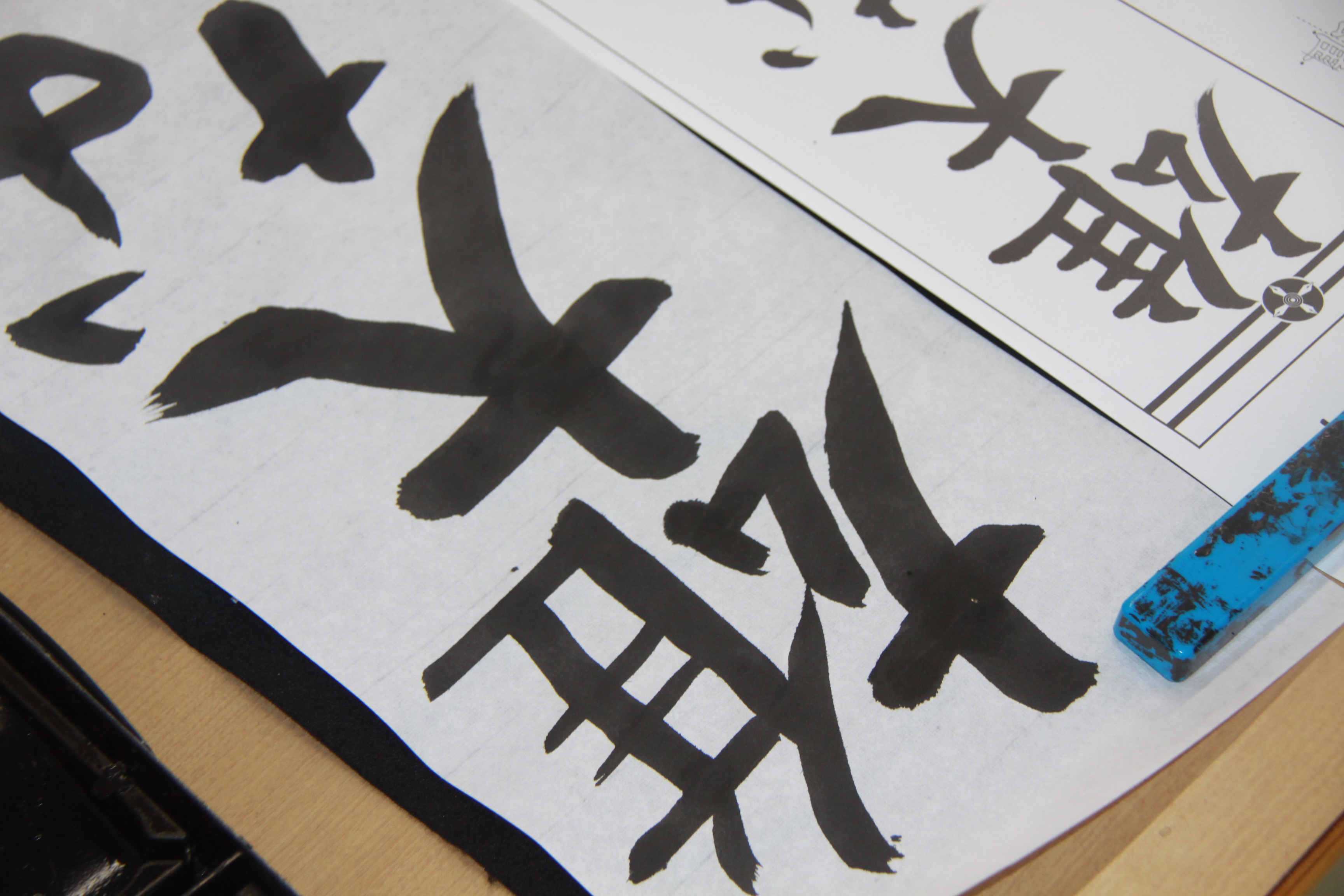
◎世界はだれかのしごとでできている(7/12)

◎ひな中チャレンジ企画(AR2日目:7/11)
~知ることで、世界は拡がる 自分が拡がる。
椙原さんをお招きしての2回目の講座。


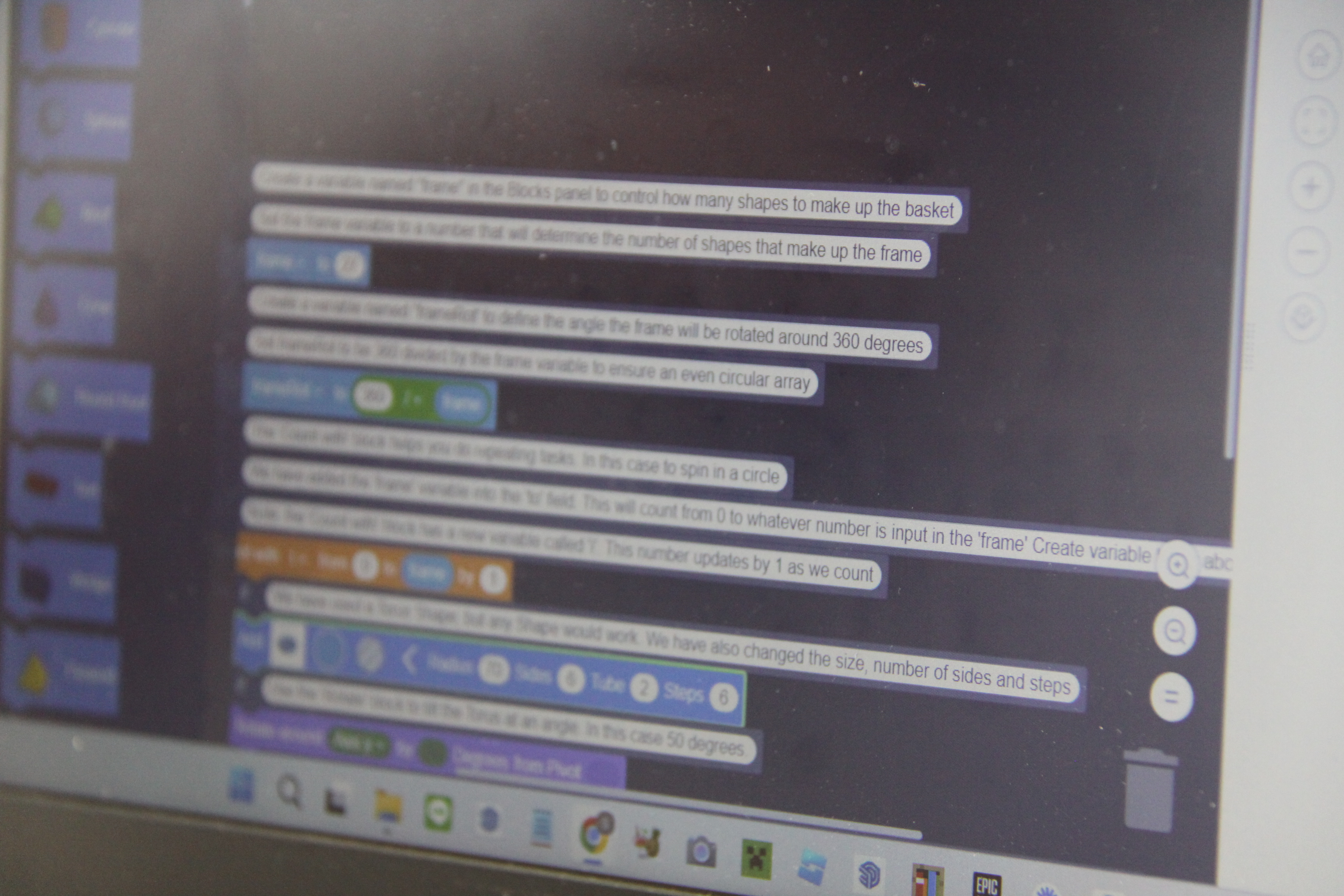
◎ホリゾント制作委員会開催(7/11)
~届け、私たちの熱量。 動く、私たちの星輝祭。



◎多くの人に支えられて(7/11)
~教えの庭にもはや幾年(いくとせ)思えばいと疾しこの年月。
中元写真館さんに来ていただいて、「卒業アルバム」の制作にとりかかっています。時が経つのはやいものです。

今日は先生方も(^0^)で、個人写真撮影です。
◎今日も「おはよう」からはじまるひな中(7/11)
~生徒会あいさつ運動

◎多くの人に支えられて(7/10)
私たちの「頑張り(体育の部ふりかえり)」を、掲示していただきました。ありがとうございます。
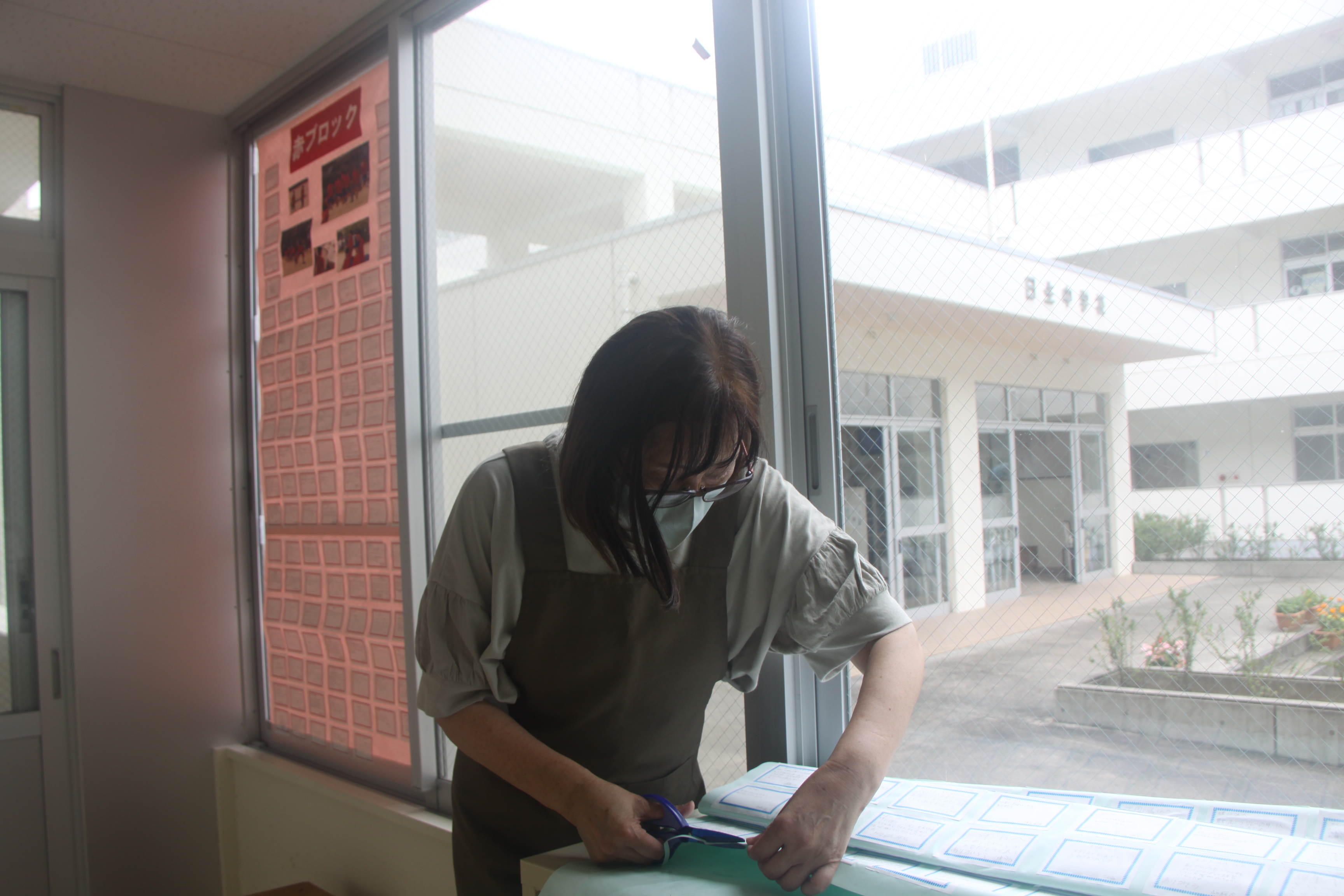
◎なんてったってスマホ・ケイタイ・パソコン(7/10)
安全教室(日生中学校区連携協議会)を西小、東小、日生中と協働して開催しました。ソーシャルメディア研究会の永峰、島方、田中さんをお招きして、よりよい利用方法について学びました。

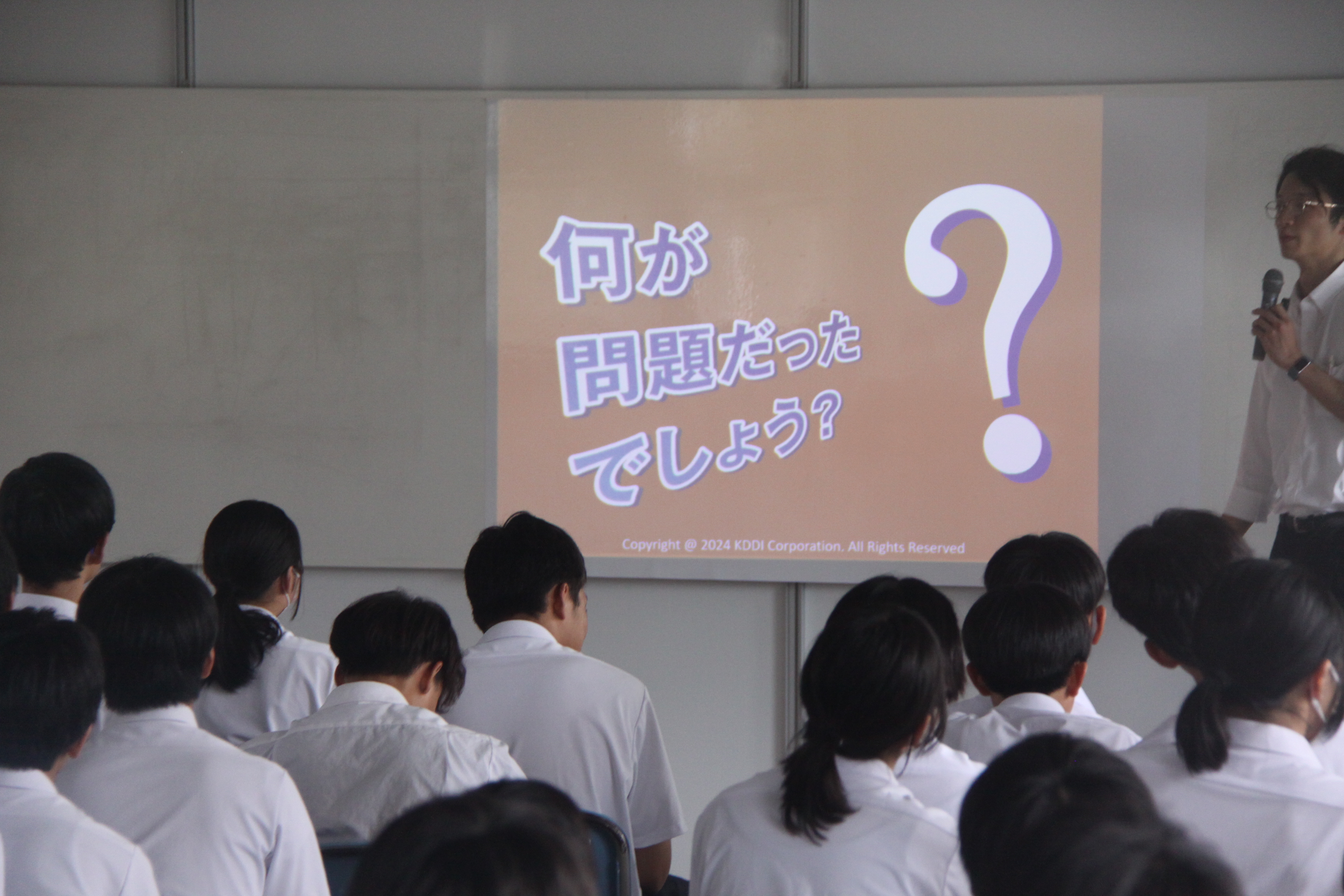

◎生み出す楽しさ
生み出す喜び、
生み出す力を、仲間と共に。(7/9)
地元、陶芸家の藤原宏さんをお招きして、今年も1年生が「備前焼」づくりに取り組みました。ありがとうございました。












◎子どもたちのために わたしたちのために
備前市第1回手をつなぐ育成会代議員会及び備前市PTA連合会代議員会(7/8)
日生西小学校(事務局)で開催され、今年度の計画、またこれからの市P連の活動にあり方について協議しました。また、単Pで意見集約を行い、引き続き、主体的な活動体制の構築にむけて議論していきます。

◎時間をどう使うか!?
~明日から部活動休止(7/9~11)
学期末週間に入りました。
単元末テストや小テストも実施中!「自分らしくせいいっぱい」
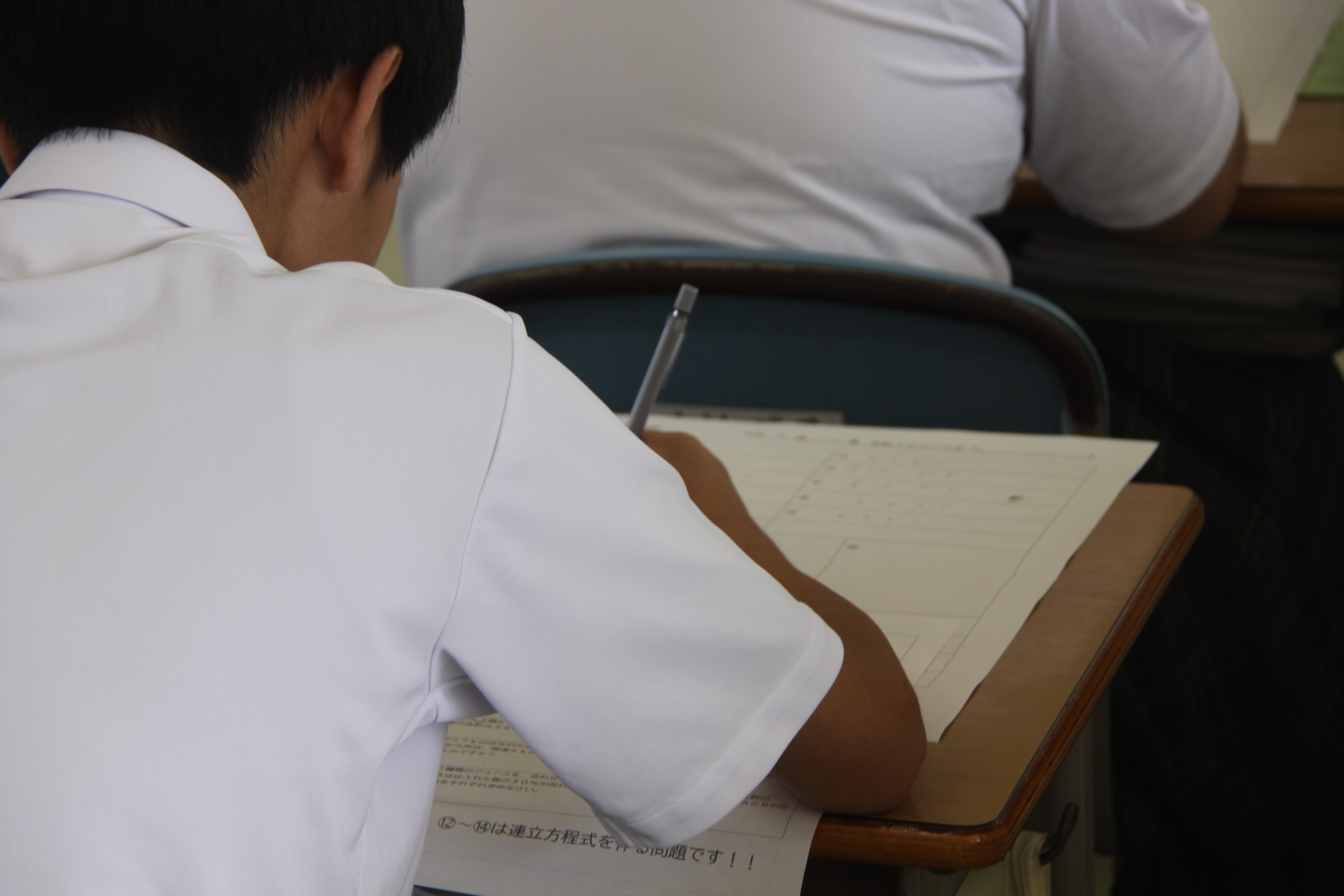
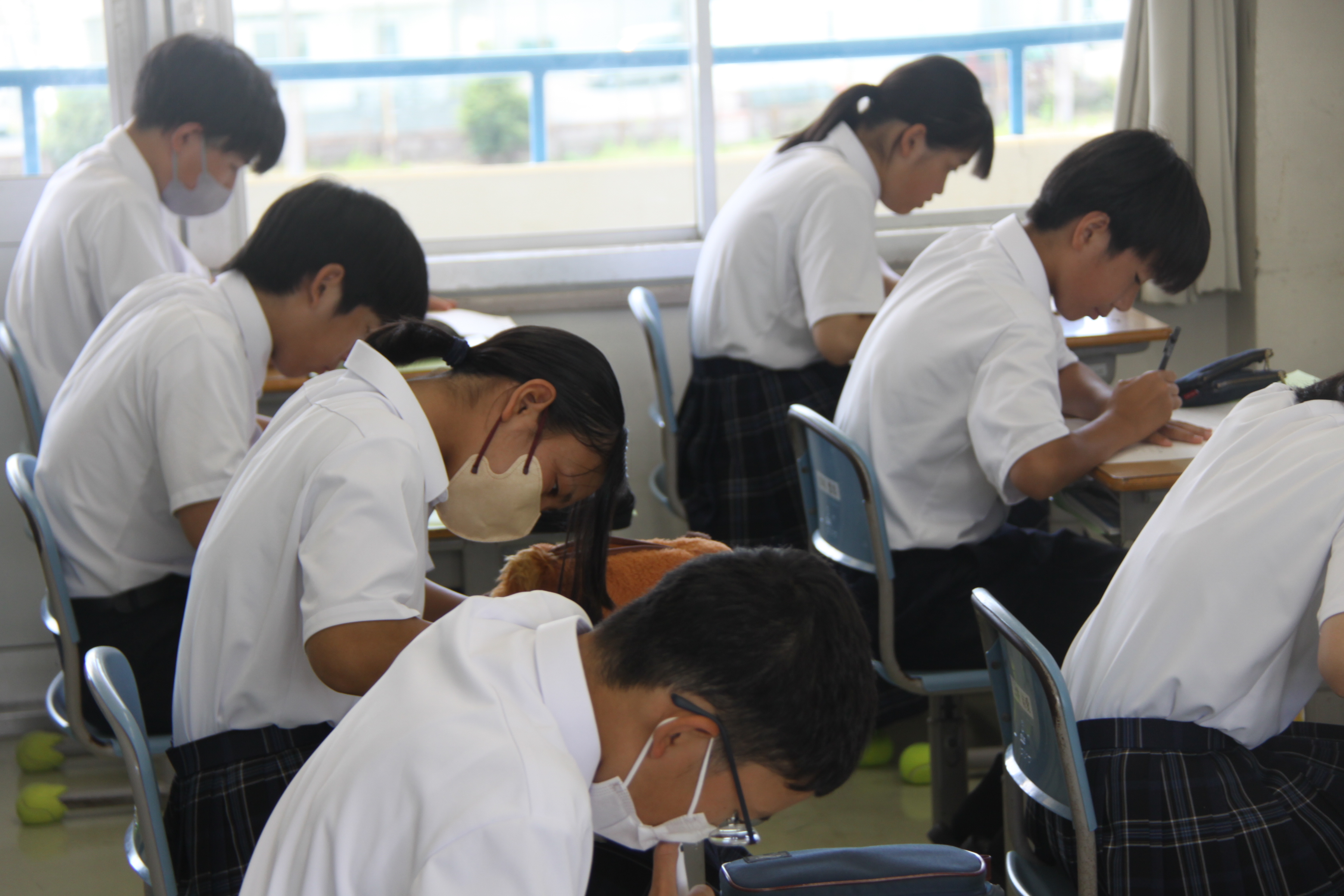

◎「洗濯」が宿題??
~生きる力、生活力を鍛えよう(7/8)
学校に花王さんが洗剤のサンプルをいただきました。これをもとに、夏季休業中に「洗濯」の宿題はどうだろうか?と検討中です。もちろん全自動の機械が主流でしょうが、洗濯ものを、「干したり」、「たたんだり」、「アイロンをかけたり」、「仕舞ったり」することも視野に入れて、「家事」について学べたらと思っています。
生徒諸君!宿題になっているかは「夏のしおり」で確認をしよう。

◎ICE CREAM PROJECT(7/8:三年英語)
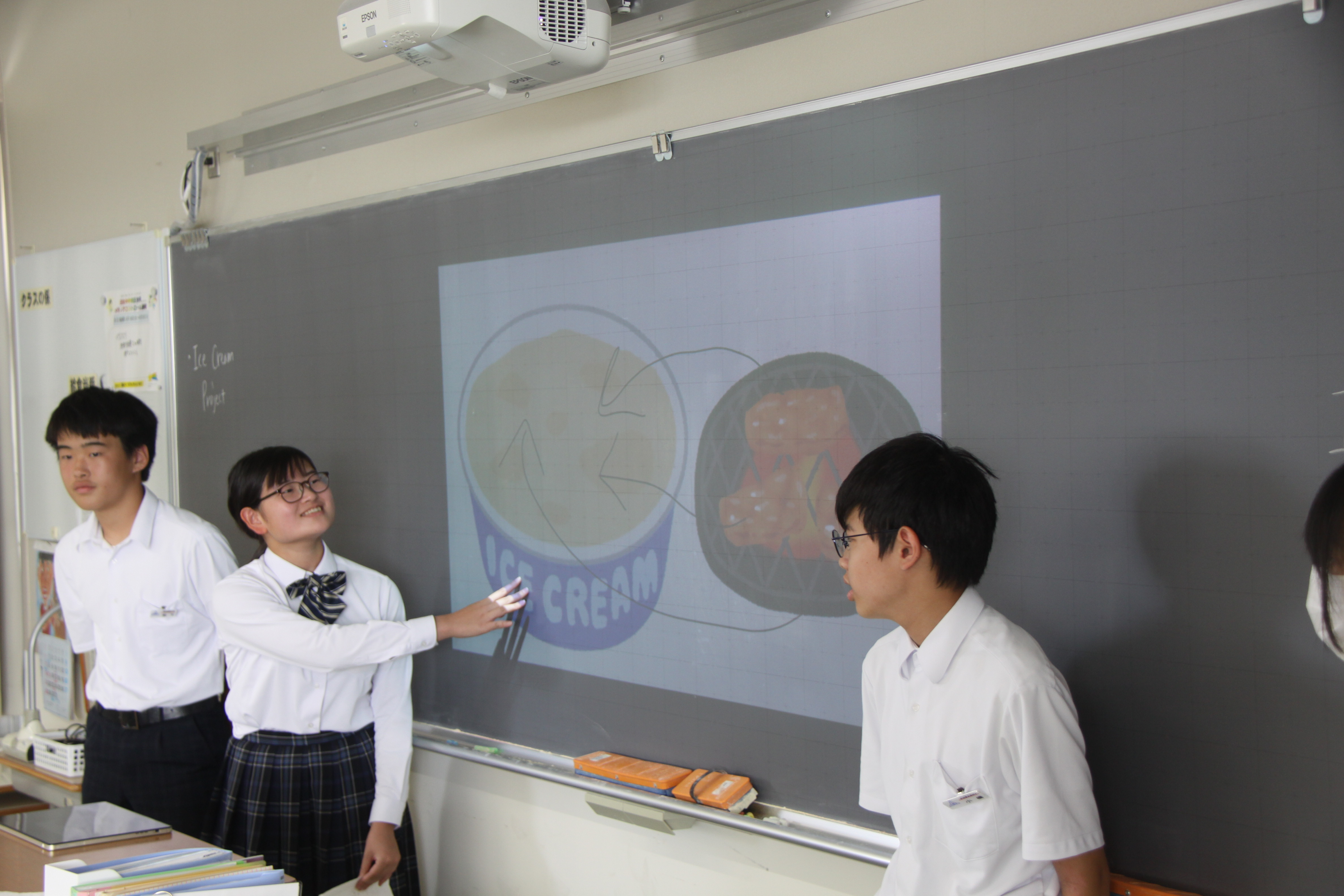
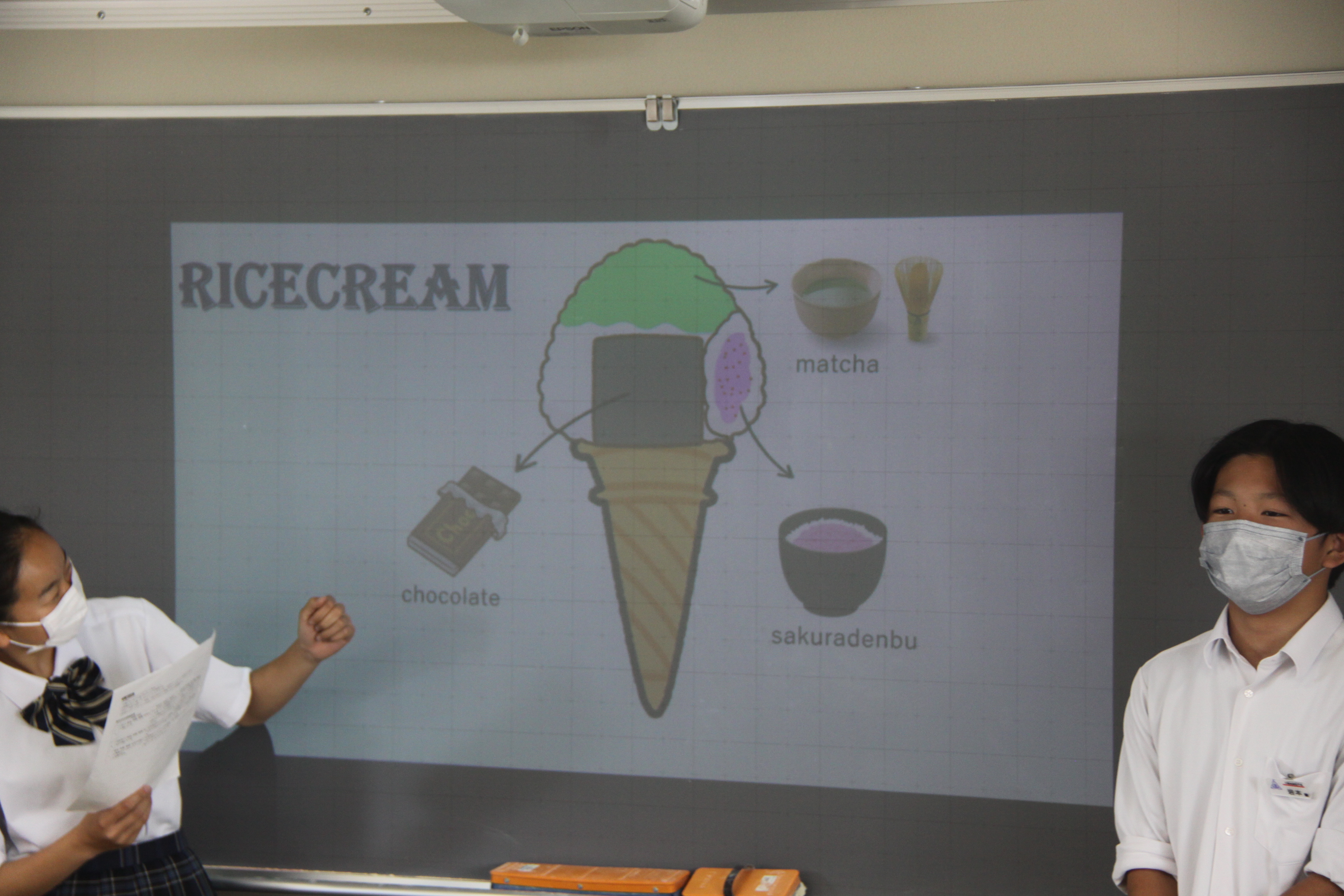
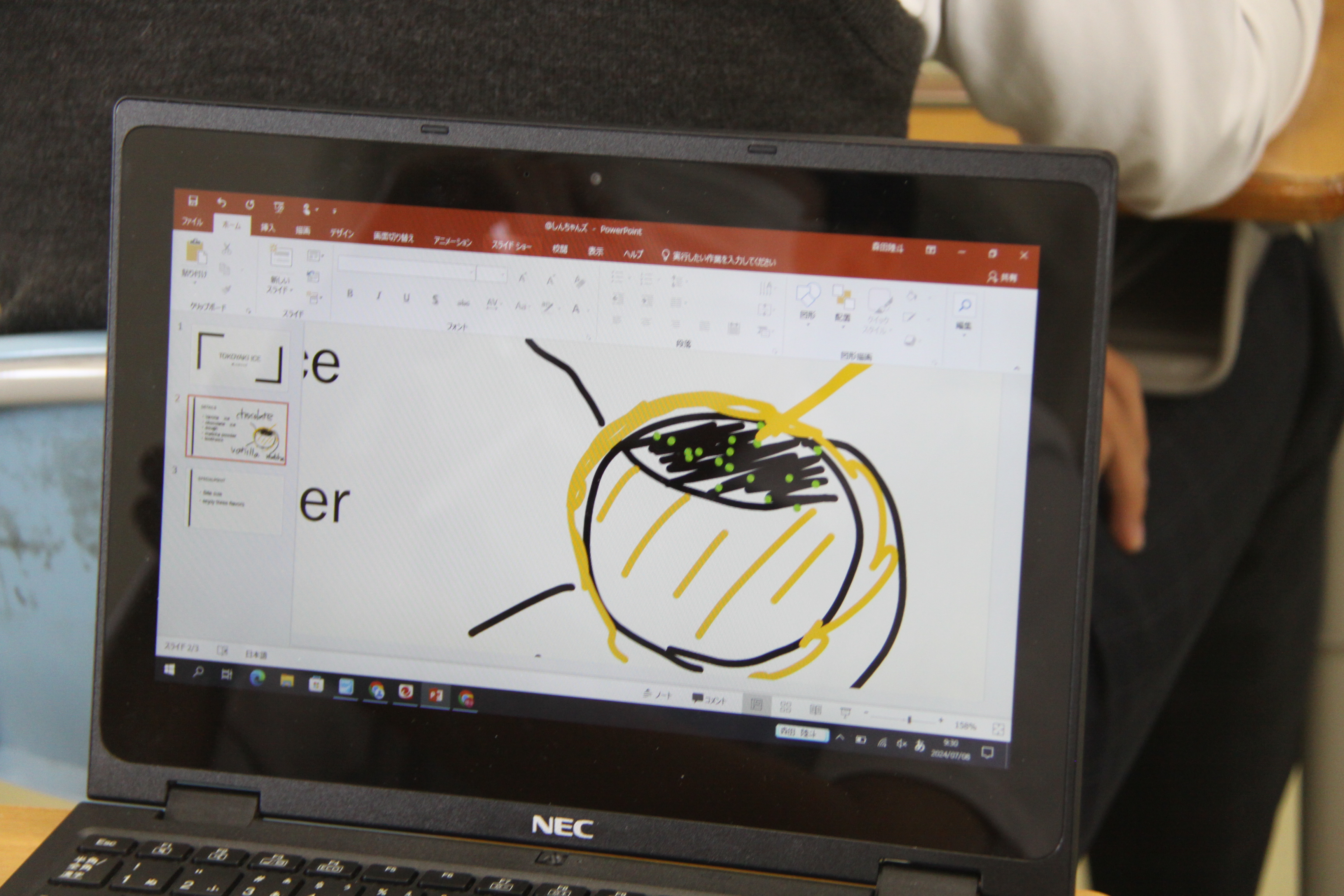
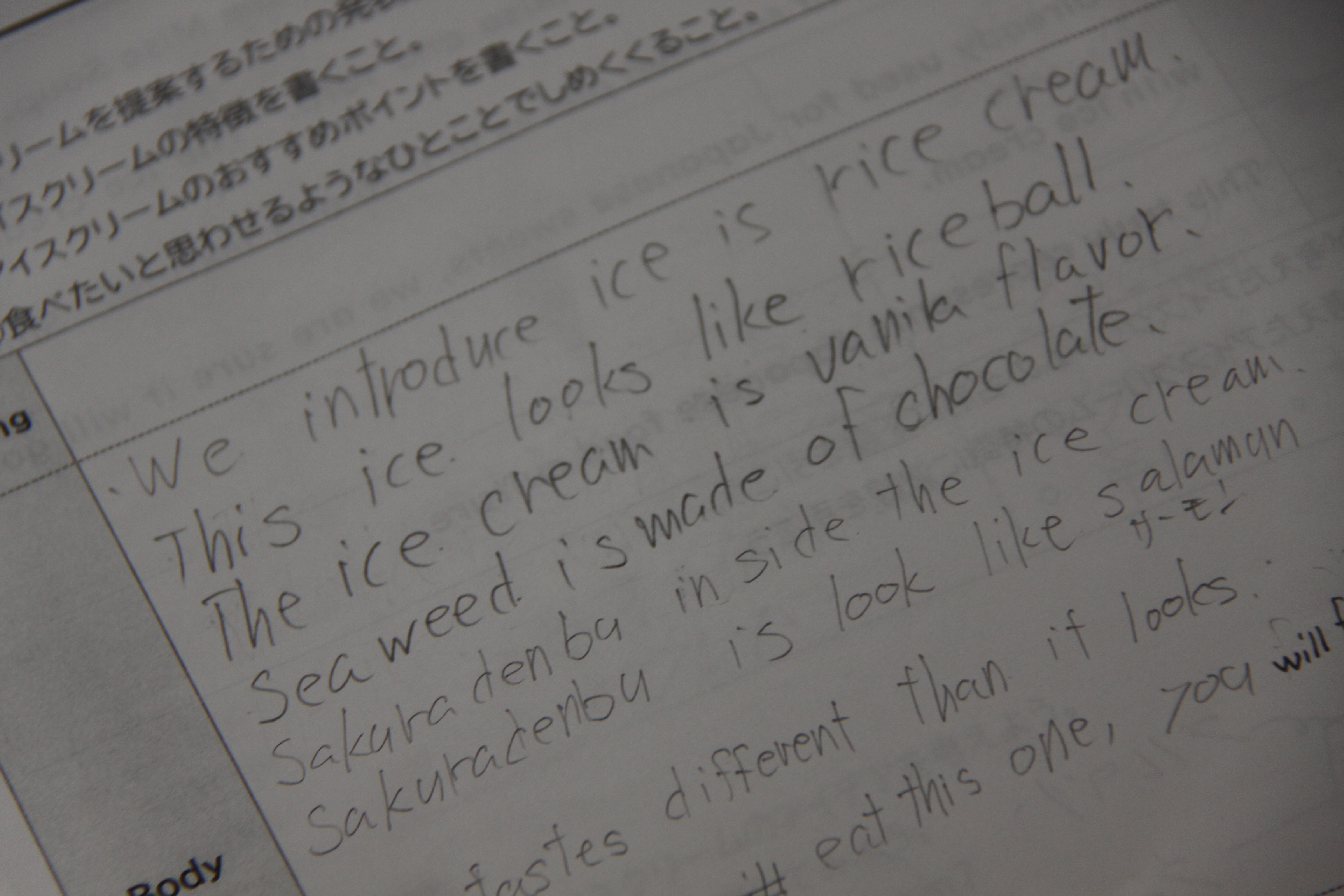
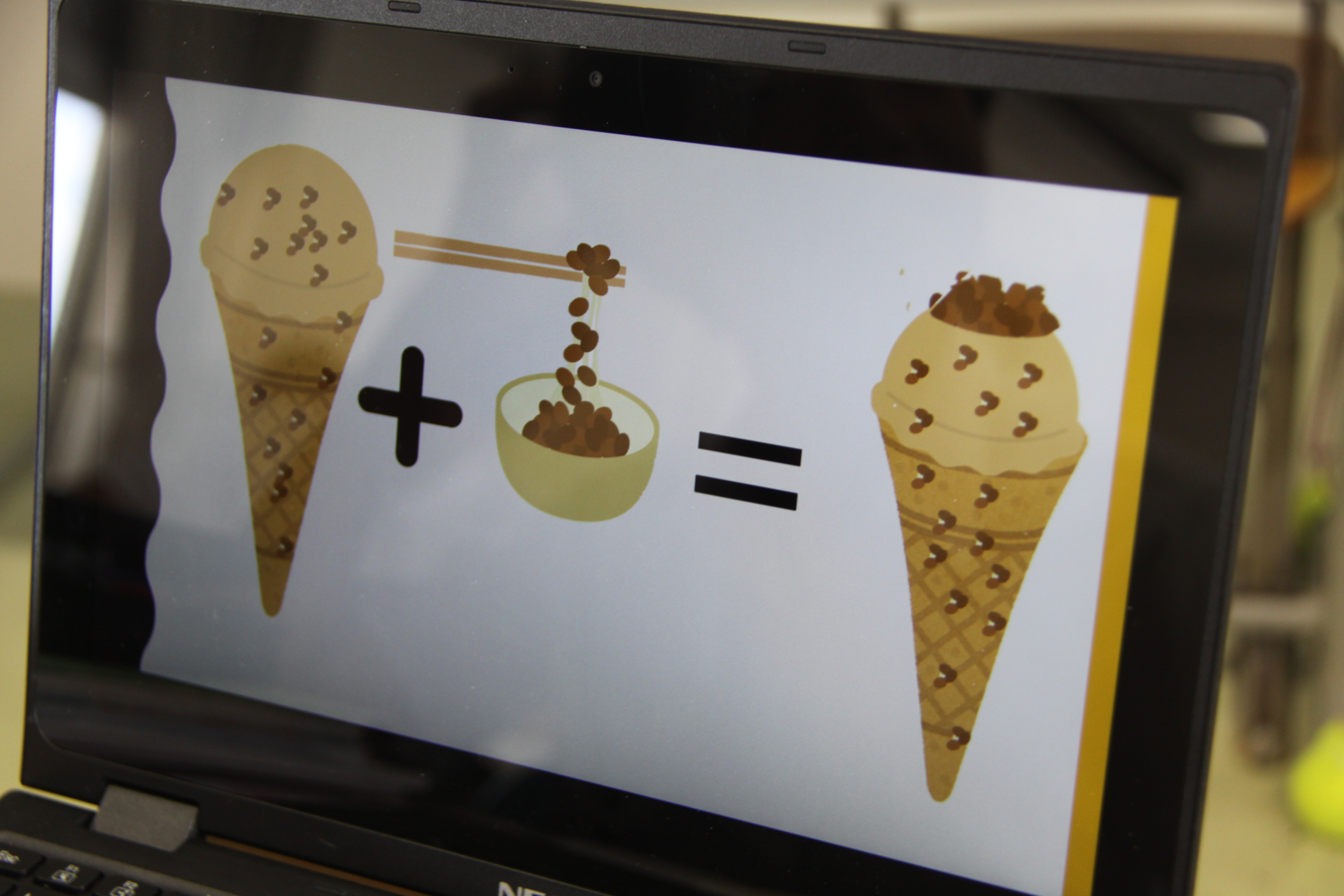
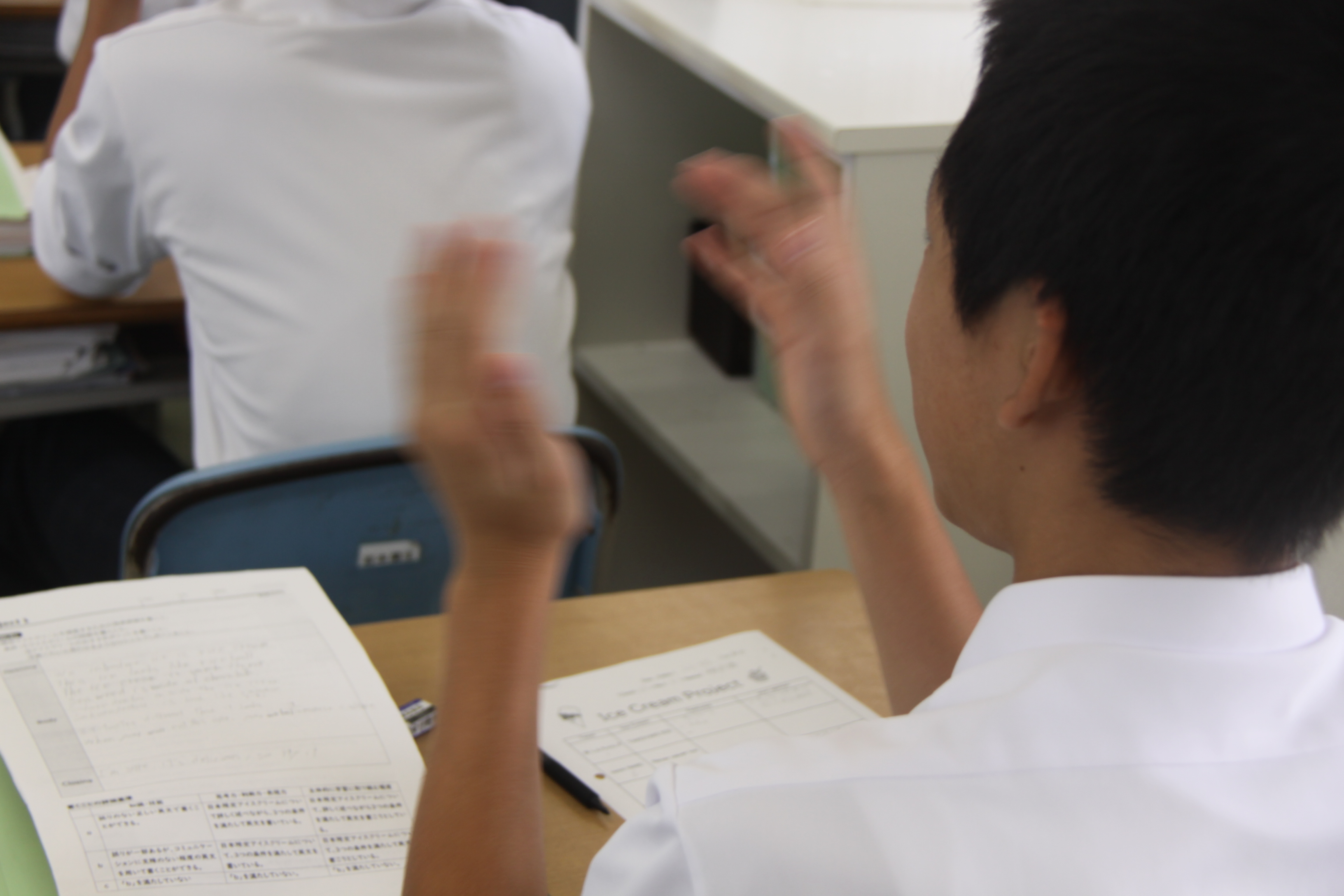

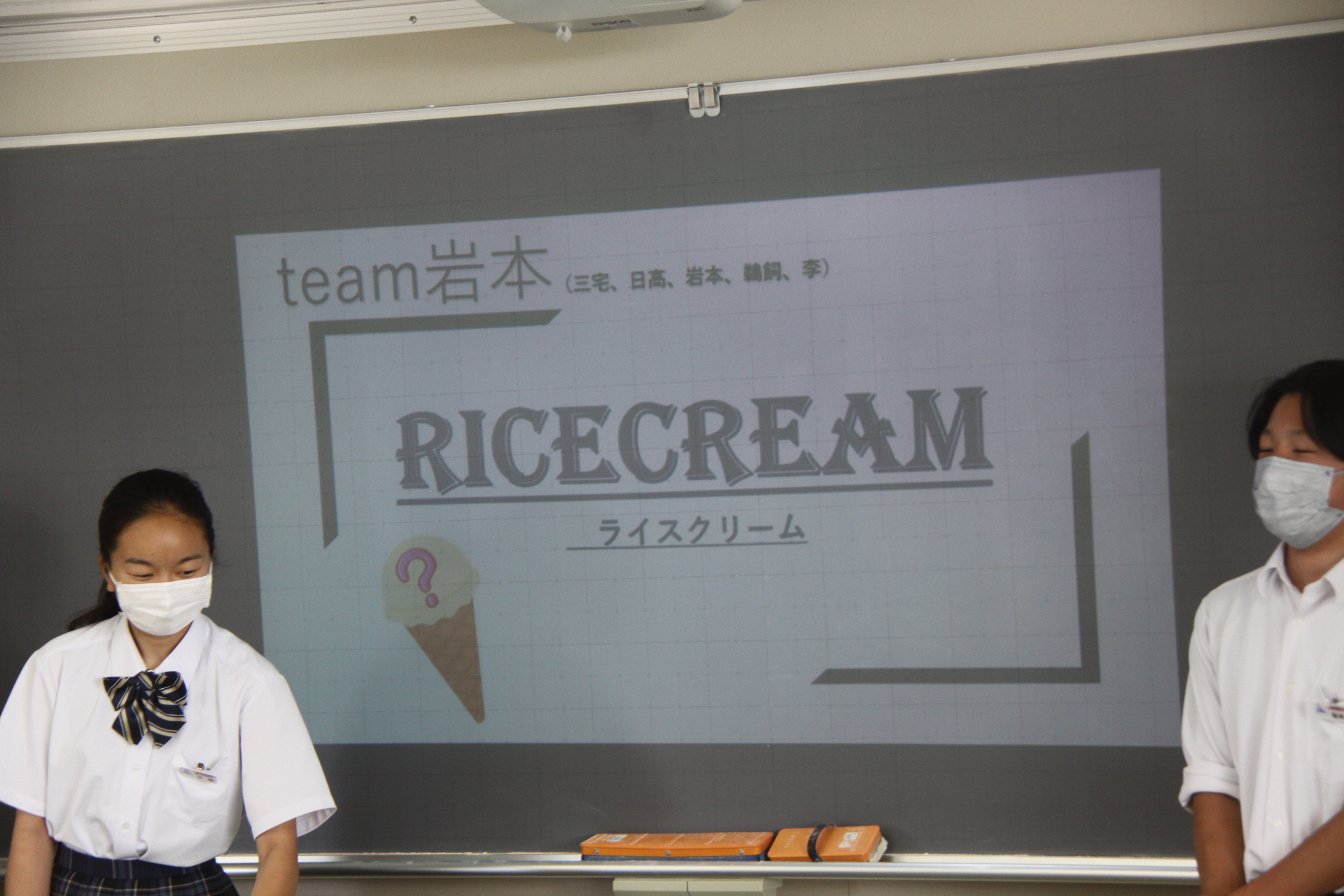
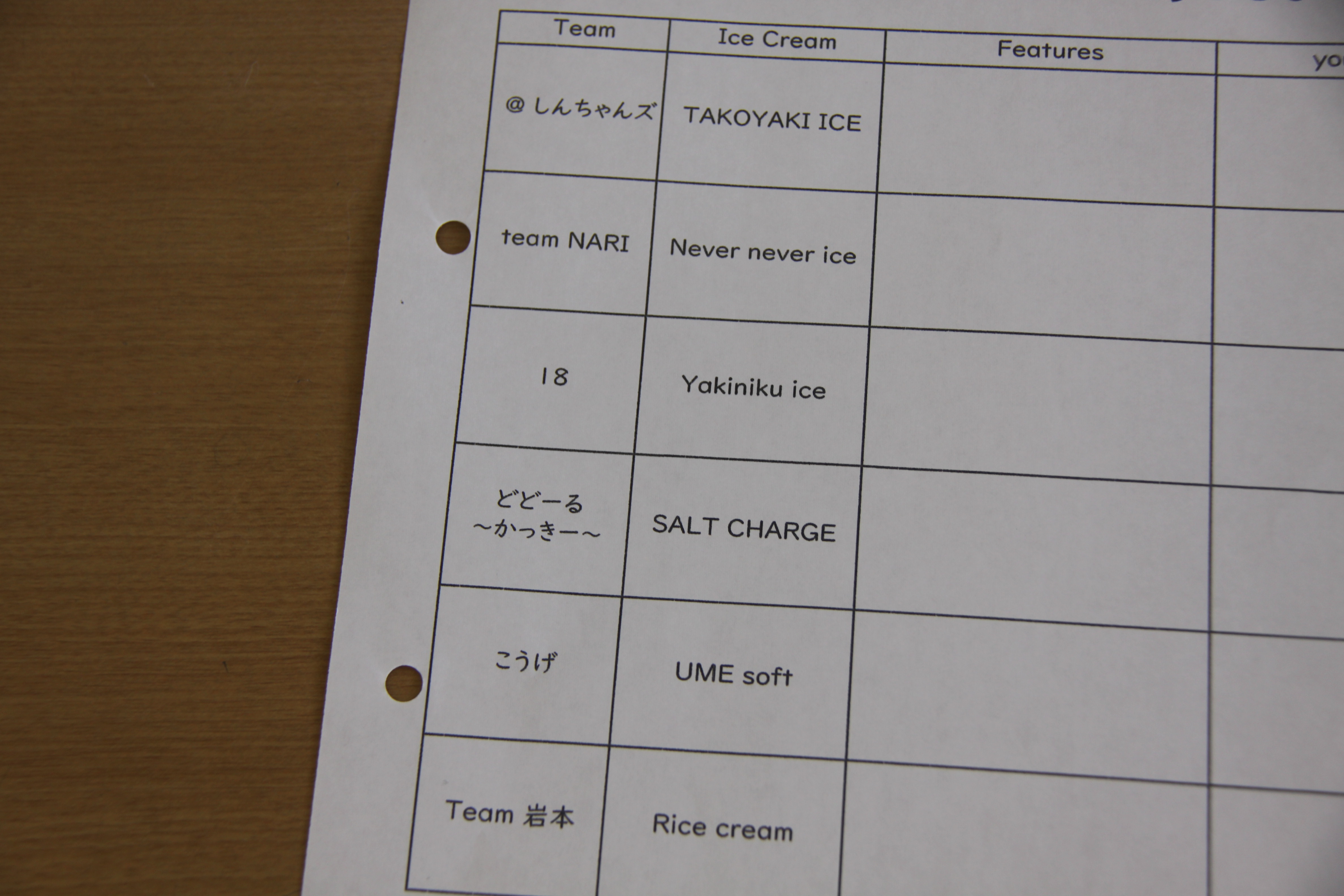
暑中お見舞い申し上げます。🍦
◎日生で輝く 日生が輝く(7/7)
ひな中地域ボランティア推進プロジェクト✨
日生カキかきフェスに参画してきました。多くの方々のご協力をいただき、フルーツアイスシャーベット完売しました。ありがとうございました。
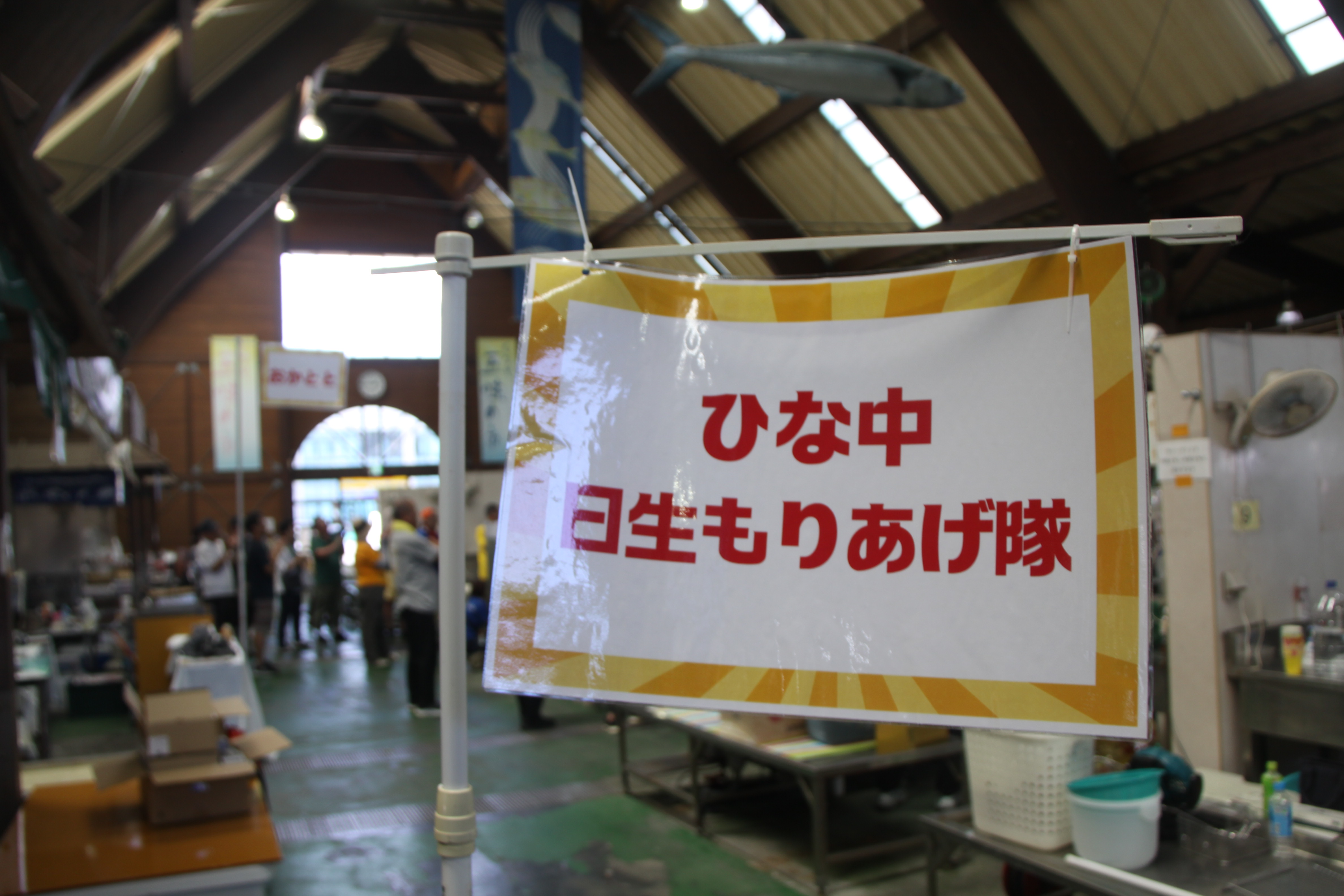




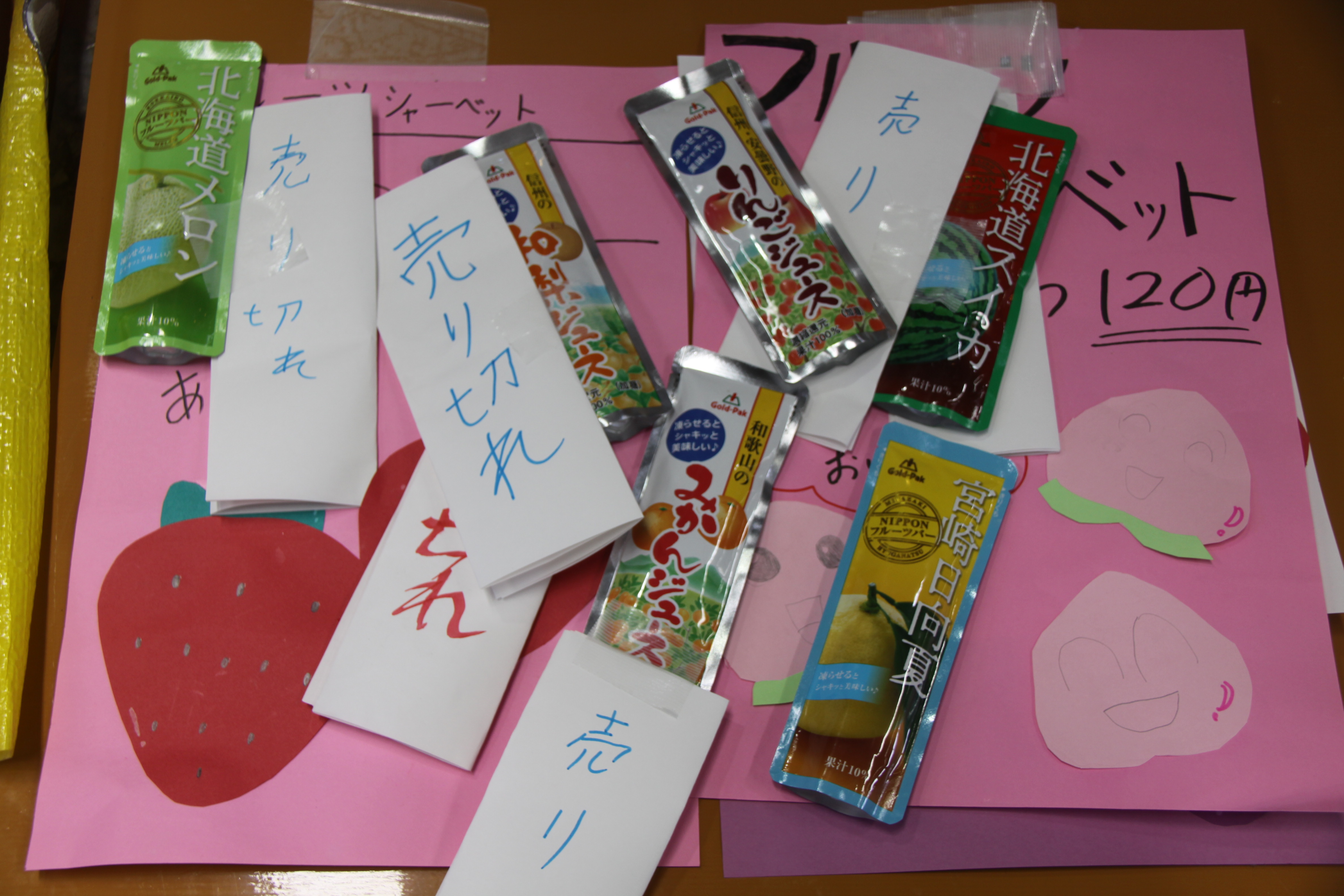
参加メンバーたちは、出店ブースの当番時間を相談し、係分担し・交代しながら、積極的に活動に取り組みました。
◎仲間がいるから、部活がんばっています(7/5)


◎仲間がいるから、あと一歩 もう一歩。(7/5(放課後))
新体力テスト。スポーツテスト再チャレンジ!



◎日生で輝く 日生が輝く(7/5)
備前市社会福祉協議会(日生支所)さんをお招きして三年生「日生の応援団」授業しました✨



◎浴衣着付け体験、日生おんど体験学習(7/5)





実際に着付けるという体験を通して、自分で浴衣を着られた喜び、和服を着た時に感じる普段とちょっと違う特別感や精神的な豊かさを味わってもらい、和装に関心を持つ子たちが少しでも増えて欲しい、そして次世代へ伝えていって欲しいという願いのもとに活動に取り組む近藤さんらが今年も来校されました。合わせて、日生地域の方にもサポートに入っていただきました。
現在の学習指導要領では「伝統・文化の尊重」などを各教科書・科目に反映させようと、中学校の技術・家庭では「衣食住などに関する実践的・体験的な学習を通じて、生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識及び技術を習得する」を目標とし、その内容は「布を用いた物の製作を通して、生活を豊かにするための工夫ができる」「和服の基本的な着方を扱うこともできる」(一部抜粋)とされています。
◎昨日より今日の私は伸びた?
~新体力テストに再チャレンジするぜ(今日と明日)

実施準備をしてくれた生徒諸君、ありがとう!
◎地域と共にある学校へ
~自分事ととして、地域の一人として(7/4~)
2年生が取り組んだ防災(社会科)授業でまとめた、防災マップを、日生地域公民館へ展示しています。7月末まで展示の予定です。ご覧くだされば幸いです。
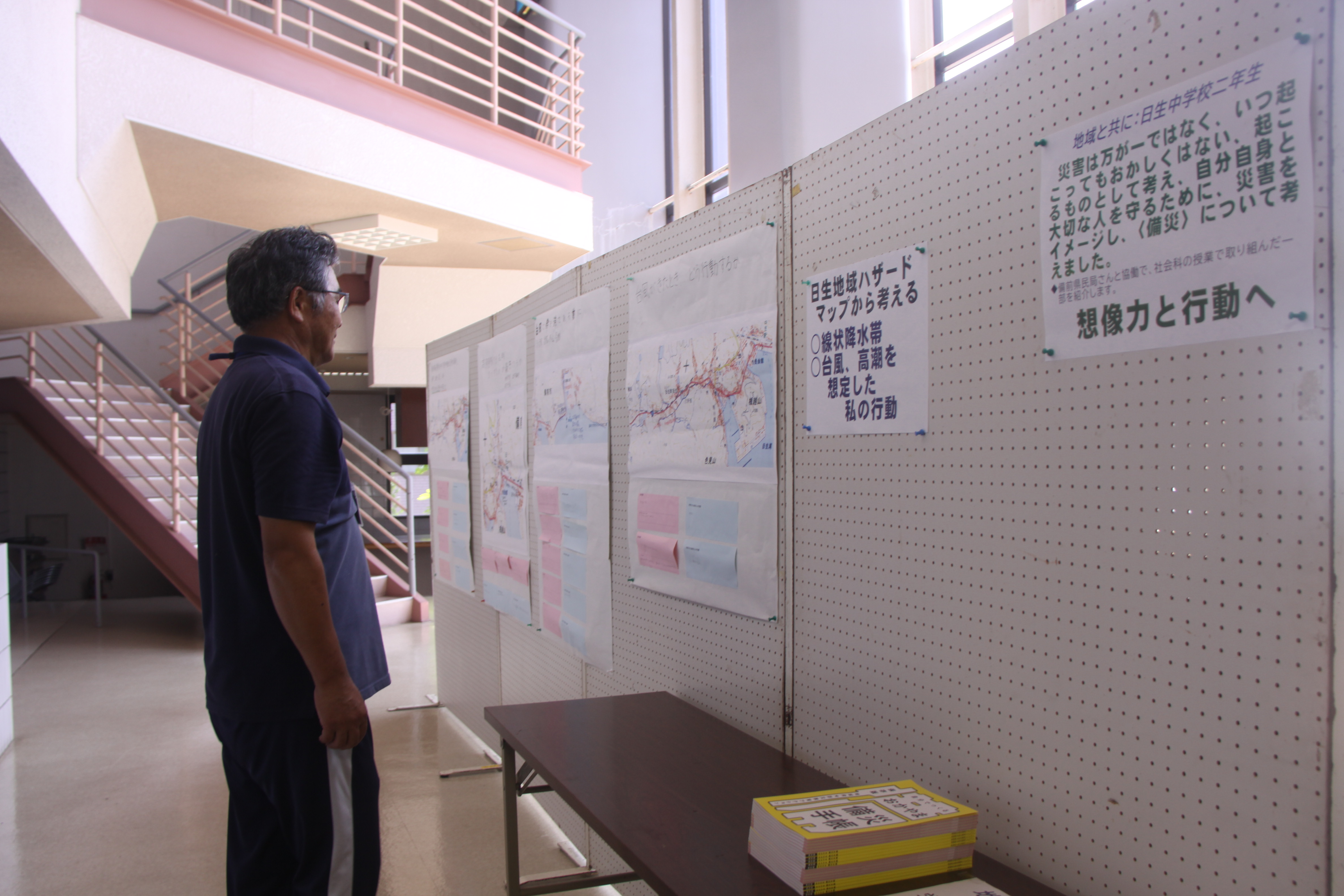
◎多くの人に支えられて
ひな中ほっとスペース開設(7/3)
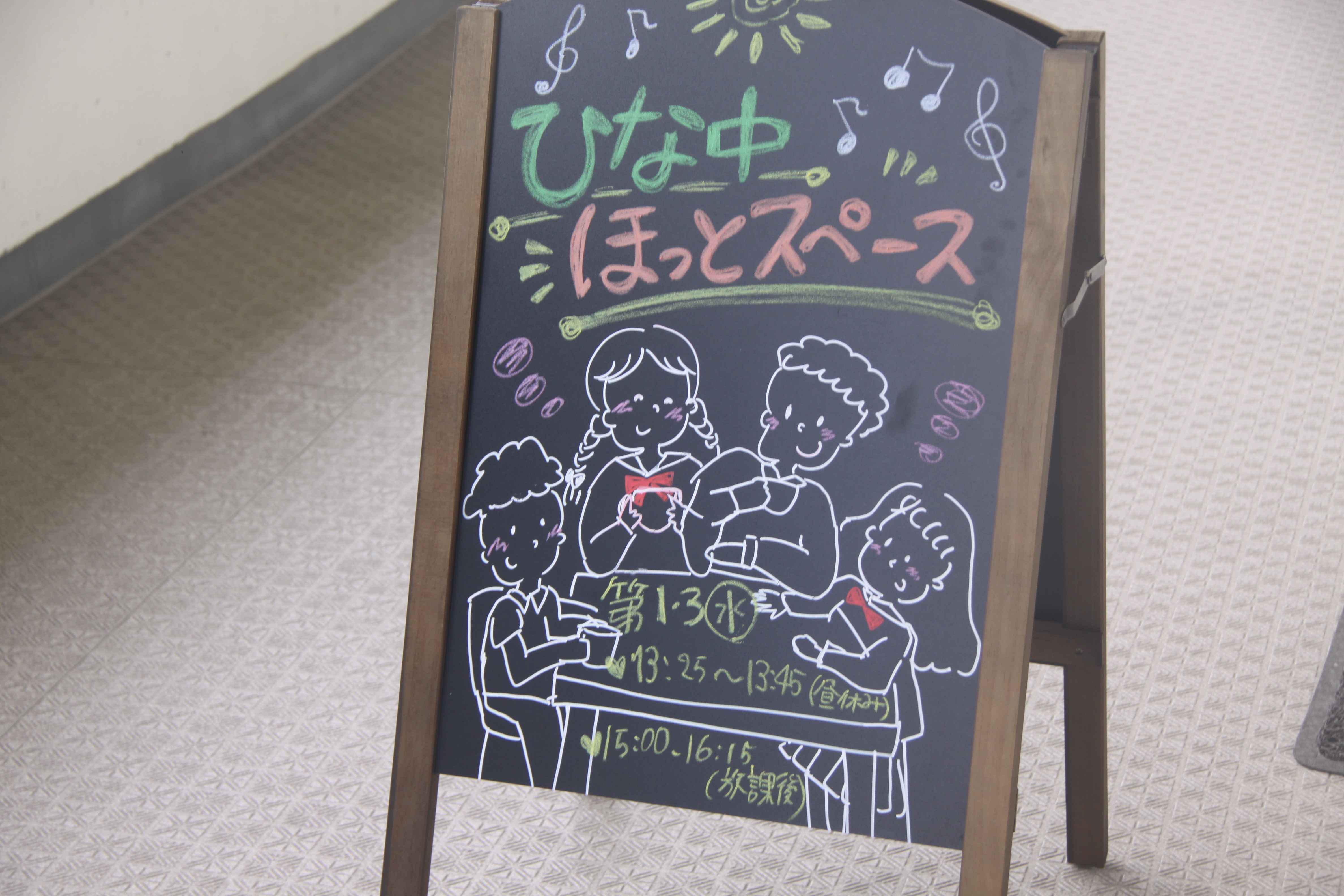

次回は、8/7、8/21です。(^_^)
◎多くの人に支えられて
第1回学校保健委員会開催(7/3)


学校保健委員会とは、学校・保護者・学校医等で、生徒の健康安全に関する課題や学校保健に関する諸問題を協議し、生徒・保護者の方、並びに教職員の健康への意識向上と健康の保持増進を図る目的で、開催しています。日生中の生徒たちの定期健康診断の結果、保健室の利用状況、保健委員会の活動の様子や調理場(食育)についての資料をもとに意見交流を行い、また、学校医の先生方からもご指導・ご助言をいただきました。ありがとうございました。次回は2月6日(木)に開催します。(^∧^)
◎HINASE LEGACY
第22回カストーディアル(6/28、7/3、8、12)



昨年度も紹介しましたが、今年は少し長めに。
「カストーディアル(custodial)」とは、英語で「維持する」を意味することば。東京ディズニーランドでは、開園中、白いコスチュームを着た「カストーディアルキャスト」を目にした覚えがある方も多いのではないでしょうか。カストーディアルキャストはゲストのご案内をしながら、開園中のパークを綺麗に「維持する」役割を担っています。対して、夜に活躍するナイトカストーディアルは、大きな機材を使ってパーク中を清掃したり、アトラクションの隅々を清掃したりと、役割が全く違います。彼らが『リセット清掃』と呼んでいるように、ナイトカストーディアルの役割は東京ディズニーリゾート®が誕生した1983年の状態に「リセット」し、その初々しい姿を維持することにあるのです。例えば、東京ディズニーランド®にある「キャッスルカルーセル」に使用されている真鍮(しんちゅう)は、毎日欠かさず拭き上げられています。想いと力を込めてピカピカになるまで丁寧に磨くことで、次の日訪れたゲストは光り輝く世界の中でこのアトラクションを楽しむことができるのです。
「ゲストがいないからこそできる清掃」とは何でしょうか。
青空を舞台とした東京ディズニーリゾート®は、屋外のエリア清掃が中心となっています。ゲストが1日遊んだ後の広大な地面は、水の勢いでキレイに洗い流してしまいます。また、屋内の施設も、開園中は目にすることのない大きな機材でキレイにしていきます。
カーペットが使用されたレストランの床は専用の掃除機でキレイにして、他にも、「ハイドロバキューム」や「メンテナー」など、私生活では聞いたこともないであろう様々な機材を使って徹底的に清掃します。休憩が終わり、しばらくしてから外に出ると、朝日が昇り始めています。明るくなったら、ゲストをお迎えするためのラストスパート。ゲストが触れるようなものは1つ1つ丁寧に拭き上げます。パークにあるものは思わず触ったり、写真を撮ったりしたくなるものばかりですから、どれも念入りに掃除します。
作業後は、上司が清掃の状態をチェックしていきます。まさにナイトカストーディアルの仕事は、単なる清掃の作業ではなく「ゲストが1日楽しむための準備」をすることといえます。
ナイトカストーディアルは、ゲストの目に触れることがほとんどありません。重い機材を使用して清掃した後はヘトヘトになりますが、ゲストから直接感謝されることはありません。しかし、彼らの仕事はゲストの笑顔に確実に繋がっています。
仕事を終え、着替えをして帰る頃。「今日はどんな楽しいことが待っているのかな」駅までの道ではそんな期待に胸をふくらませるゲストがパークに向かって続々と歩いていきます。さっきまで誰もいなかったパークは、1時間後にはこのゲストたちでいっぱいになるのです。これから思いっきり楽しむゲストの期待に必ず出会える。直接笑顔は見られないけれど、思いっきり楽しんだゲストの満足感を感じられる。それがナイトカストーディアルの仕事であり、この仕事のやりがいです。
◎私たちの委員会活動 私たちは生活を創る(7/3)

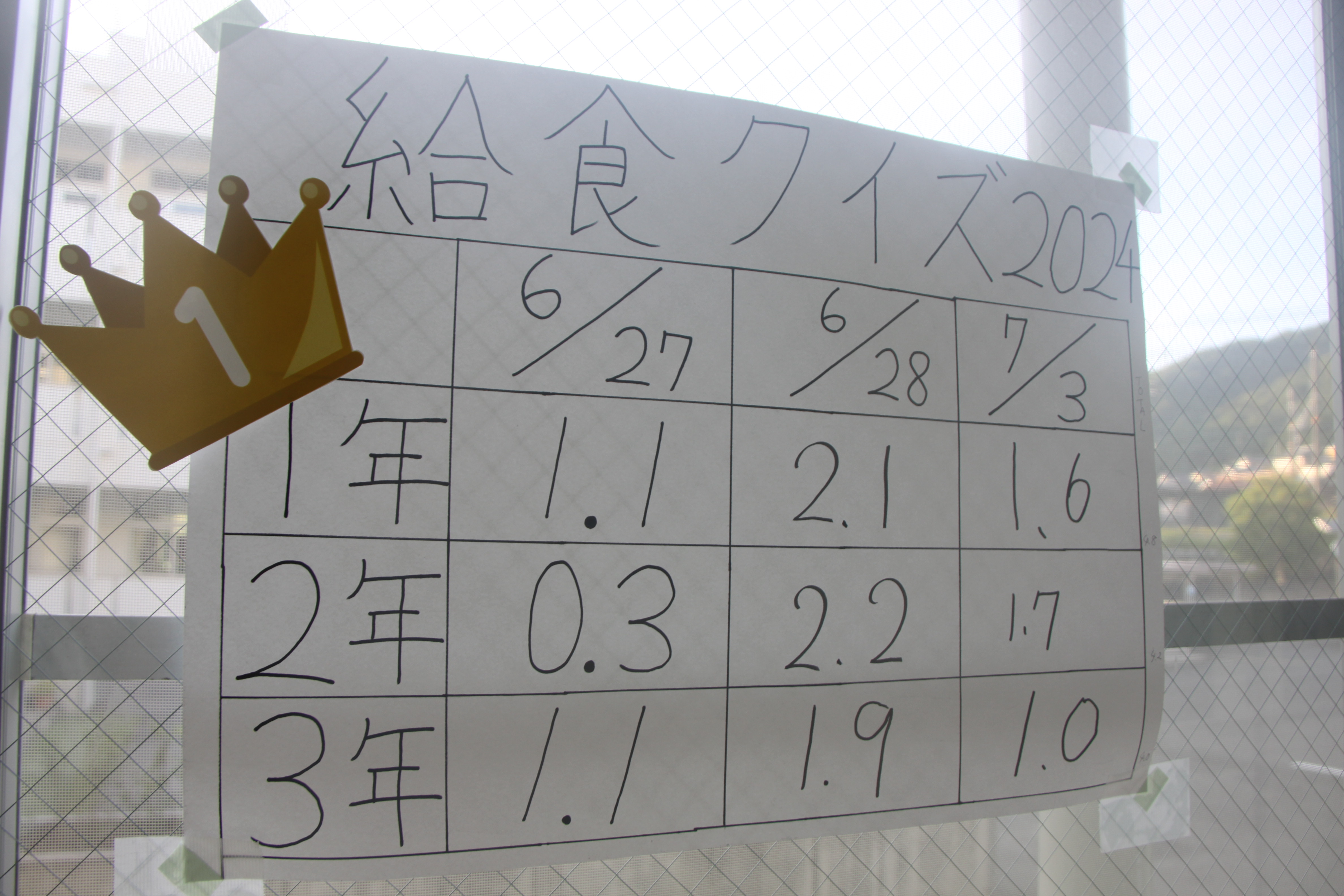
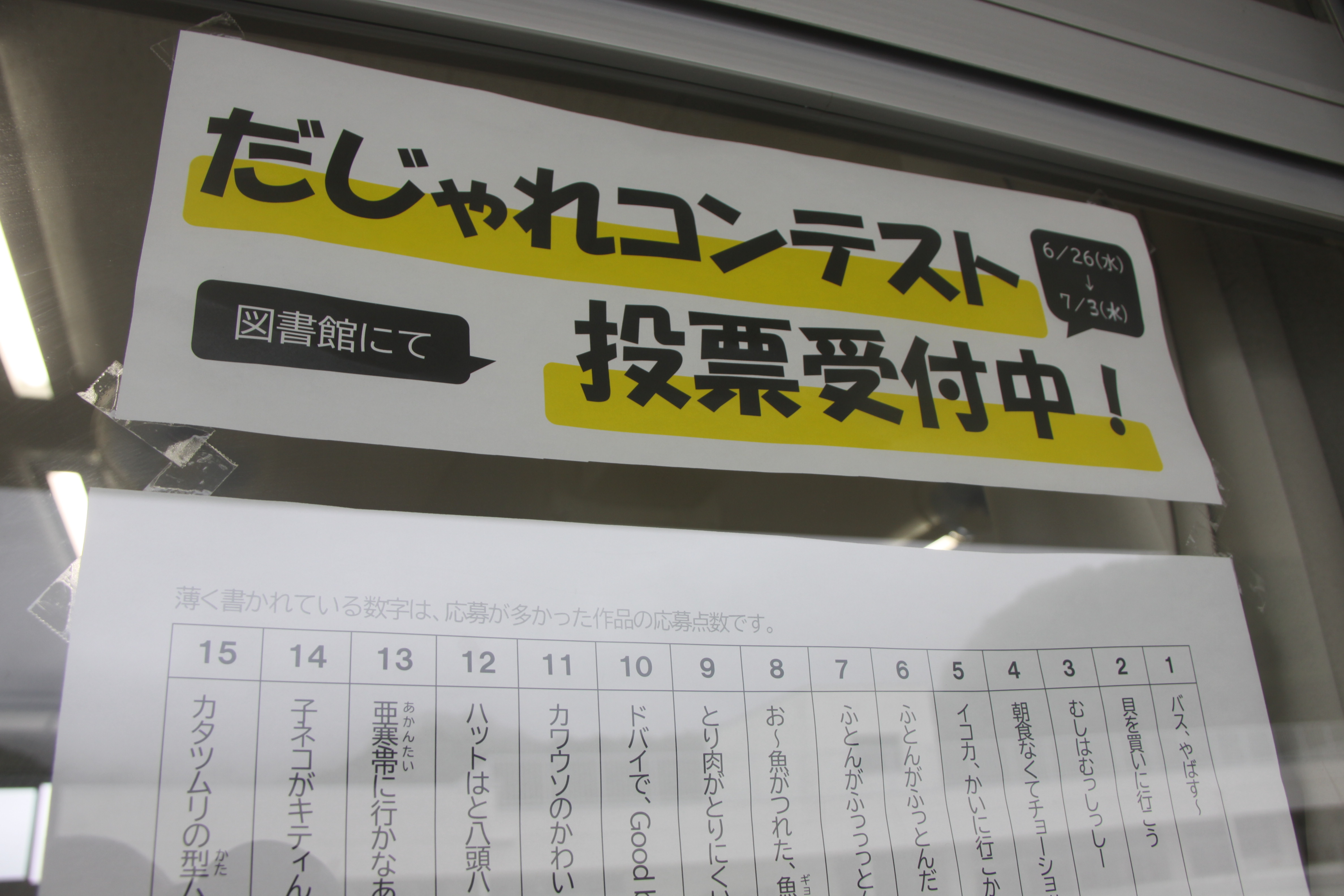


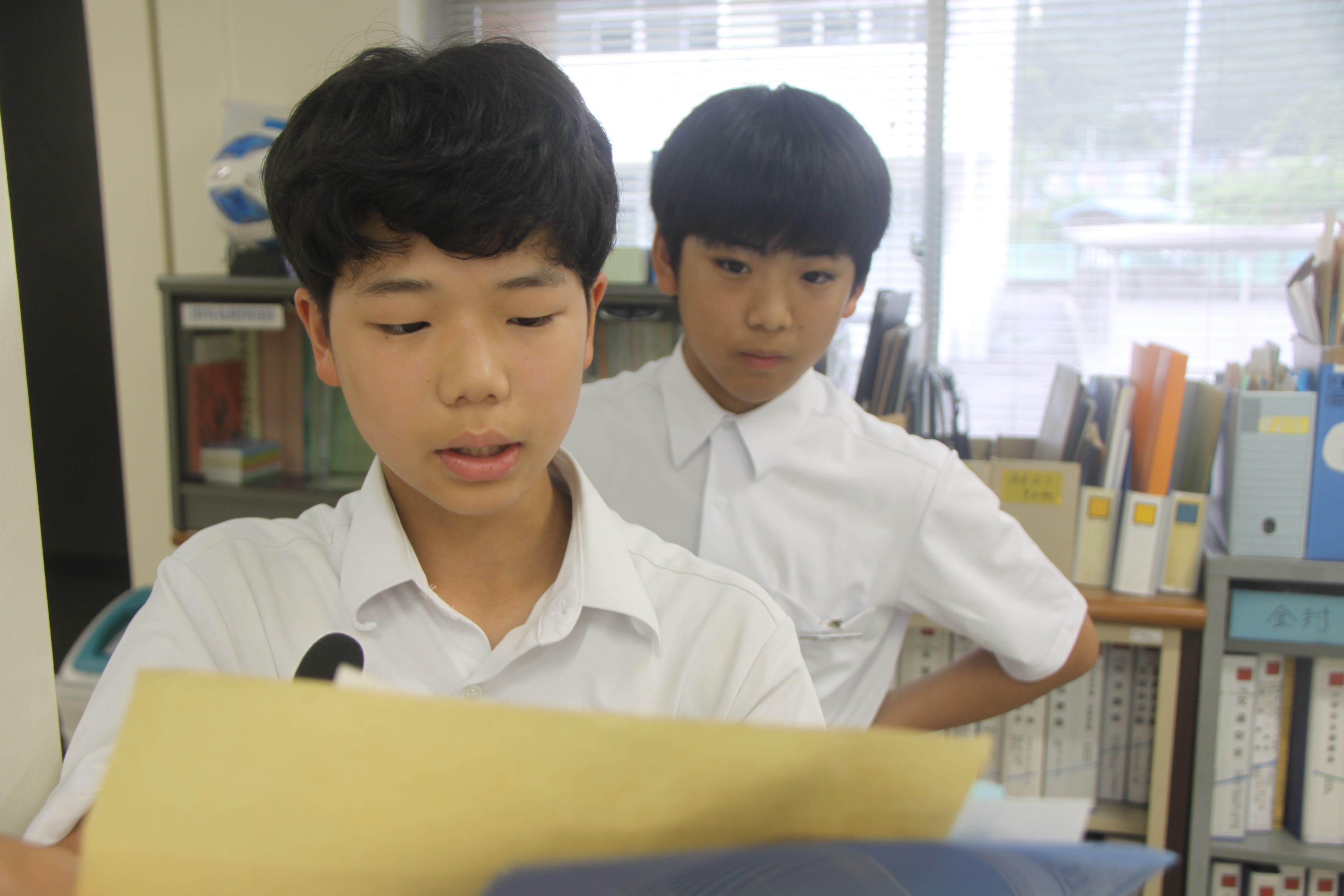
◎ひな中の風✨
~願いは叶う(7/3)


七夕(たなばた)に関する言い伝え
昔あるところに、神様の娘の織姫と、若者の彦星がいました。織姫は機織りの仕事をしていて働き者。彦星は牛の世話をしているしっかり者でした。やがて2人は結婚しました。すると、今まで働き者だった2人は急に遊んで暮らすようになり、全く働かなくなってしまいました。怒った神様は、2人の間に天の川を作って離してしまいました。
悲しみにくれた2人は泣き続けました。それを見た神様は、前のようにまじめに働いたら、1年に1度だけ、2人を会わせてくれると約束しました。それから2人は心を入れ替えて一生懸命働くようになったのです。そして、2人は年に1度だけ天の川を渡って会うことが許されるようになり、その日が七夕とされるようになりました。(その他にも、諸説言い伝えがあります。)
七夕の歴史
日本で親しまれている七夕は、中国という国の行事「乞巧奠(きっこうでん)」や「織姫・牽牛伝説(七夕伝説)」と日本に昔から語り継がれている「棚機津女(たなばたつめ)」という伝説、豊作を祈る風習などが合わさっているのだそうです。
短冊ってなあに?
短冊とは、細長く切った紙や木のこと。七夕には、この短冊に願い事を書いて笹に飾ります。短冊にお願い事を書くことについては、
昔の人が、織物の上手な織姫のように(織姫にあやかって)、「物事が上達しますように」と、お願い事をしたのが始まりだと言われています。笹の葉に飾ると、織姫と彦星の力で願いが叶えられたり、みんなを悪いものから守ってくれるという言い伝えがあるのだそうです。
◎仲間たちへ。進路を切り拓くために応えるよ(7/3~)
みんなで、応えた「友だちカウンセリング」を掲示しました。
「これってどうするん?に応える仲間として」これからも進んでいこう。
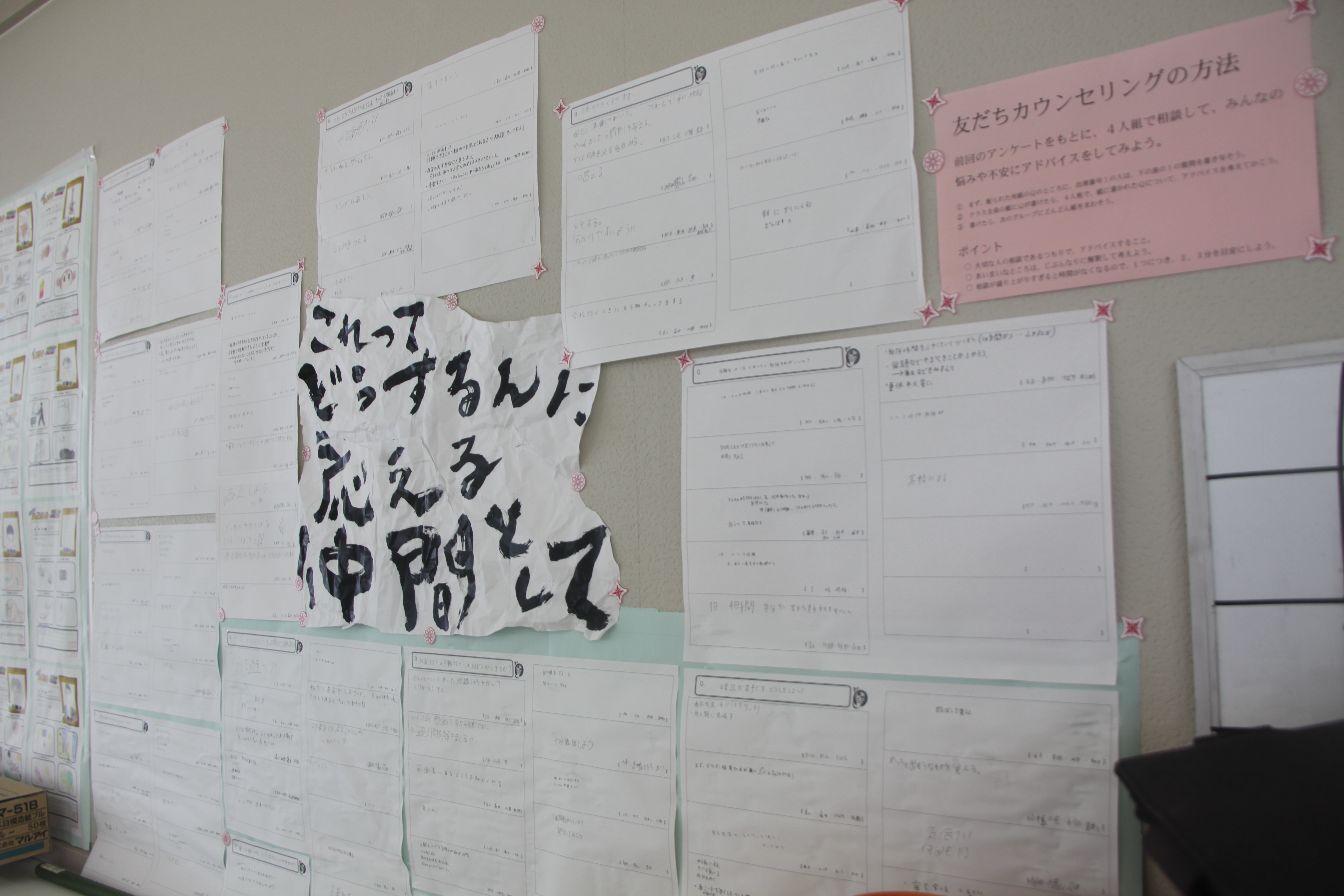
◎仲間たちと進路を切り拓く(7/2)
~みんなの悩みをみんなで応えるクラスです~
ピアサポートを取り入れたオリジナルSGE「友だちカウンセリング」(日生中オリジナル)に、三年生が取り組みました。
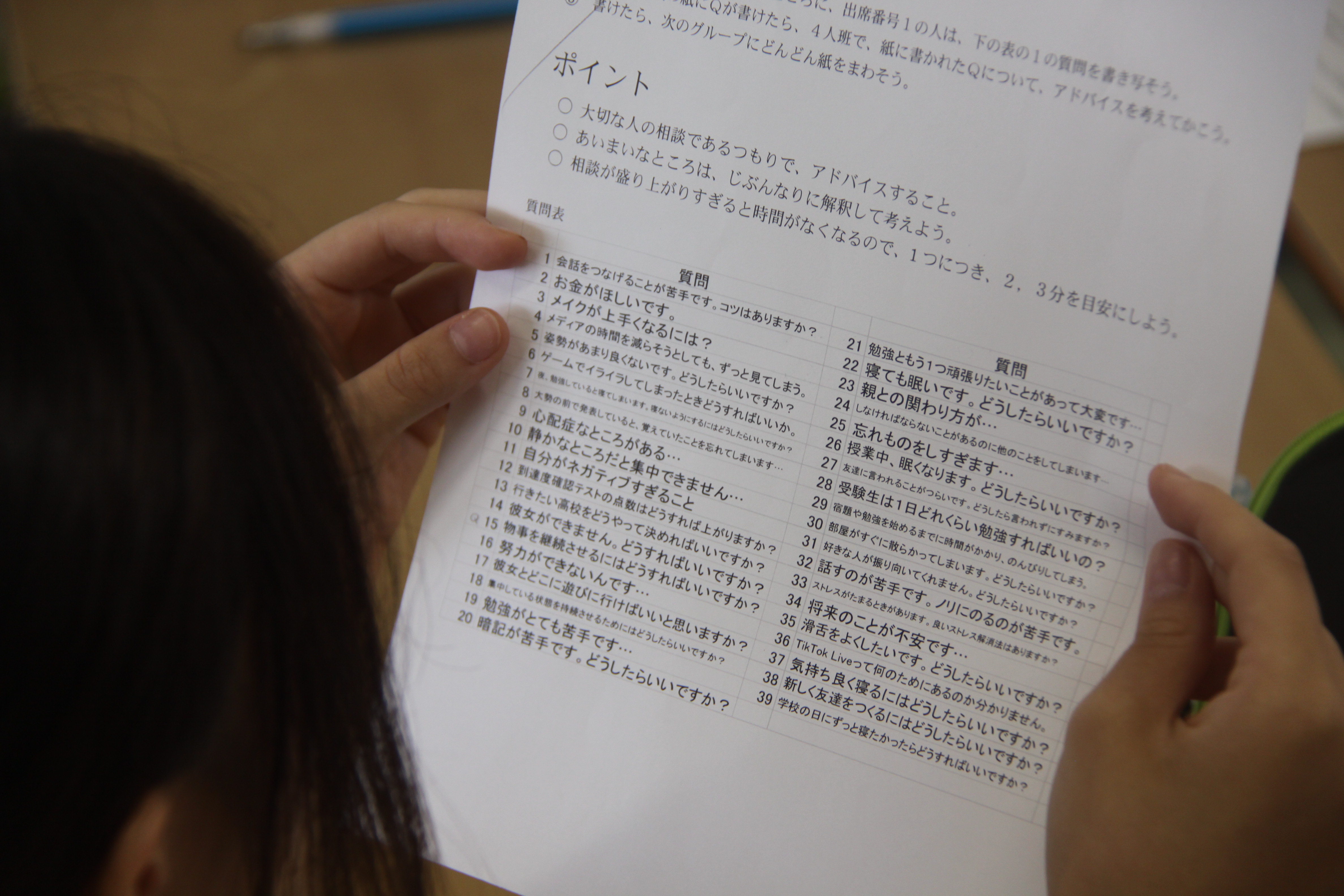



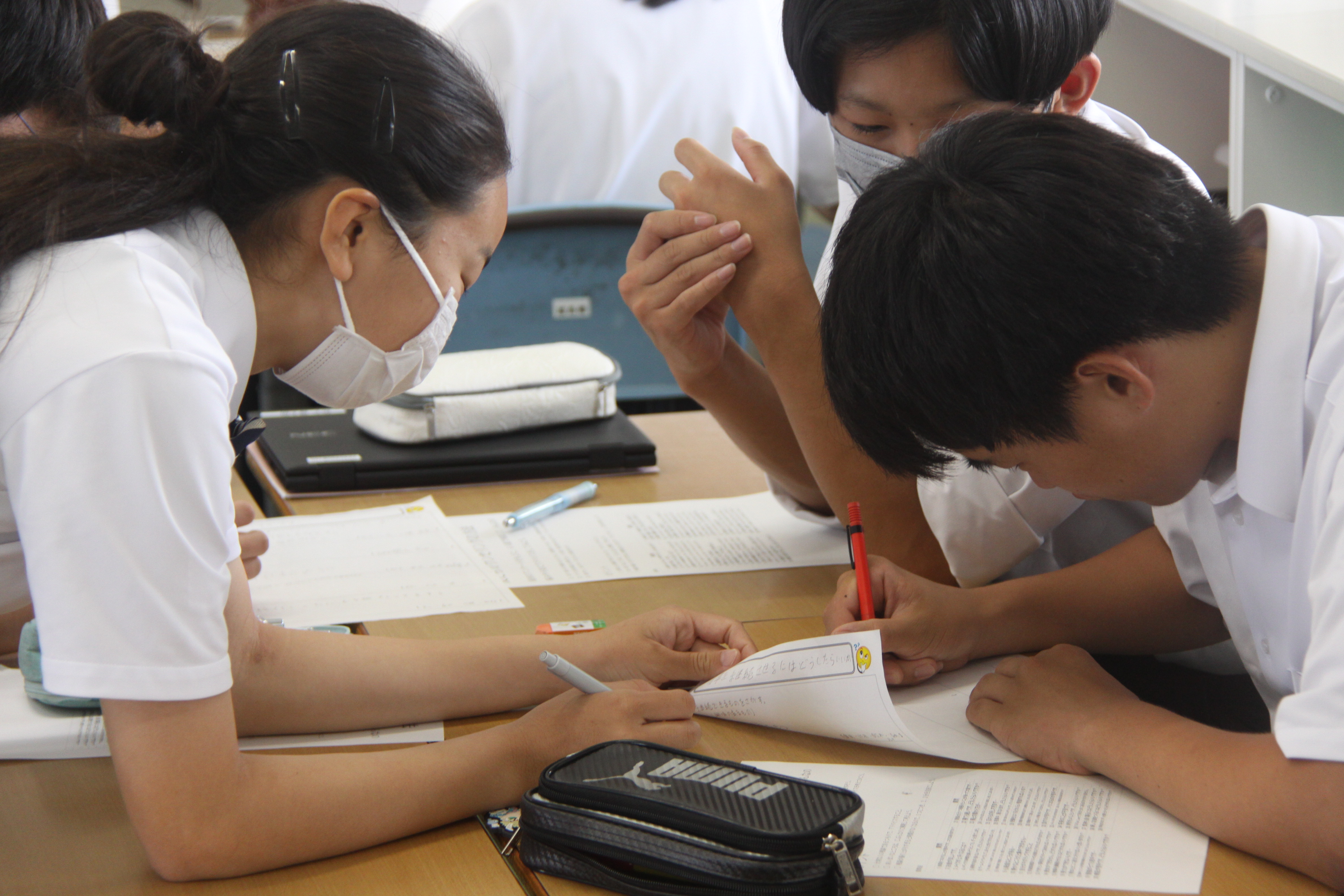

We are all travelers in the wilderness of this world‚ and the best we can find in our travels is an honest friend. Robert Louis Stevenson
(私たちは、この世の荒野を旅する者であり、旅の途中で見つけることのできる最高のものは正直な友人である。)
◎HINASE LEGACY 聞き書き2024
~私たちの海・まち・生き方のことを訊く









◎ひな中の風✨ 私たちの生徒集会(7/2)



昨日は「半夏生」でした。
半夏生(はんげしょう)は雑節の1つで、半夏(烏柄杓)という薬草が生える頃。様々な地方名があり、ハゲ、ハンデ、ハゲン、ハゲッショウなどと呼ばれます。
七十二候の1つ「半夏生」(はんげしょうず)から作られた暦日で、かつては夏至から数えて11日目としていましたが、現在では天球上の黄経100度の点を太陽が通過する日となっています。毎年7月2日頃にあたります。この頃に降る雨を「半夏雨」(はんげあめ)と言い、大雨になることが多いです。地域によっては「半夏水」(はんげみず)とも言います。なお、ハンゲショウ(カタシログサ)はちょうどこの時期に白い葉をつけることから名がついたとも言われます。
農家にとっては大事な節目の日で、この日までに「畑仕事を終える」「水稲の田植えを終える」目安で、この日から5日間は休みとする地方もあります。この日は天から毒気が降ると言われ、井戸に蓋をして毒気を防いだり、この日に採った野菜は食べてはいけないとされたりしました。なお、七夕にも農作業を休むとする伝承が多くの地域に伝わっています。
〈あの夏の数かぎりなきそして またたった一つの表情をせよ 小野茂樹〉(7/1)
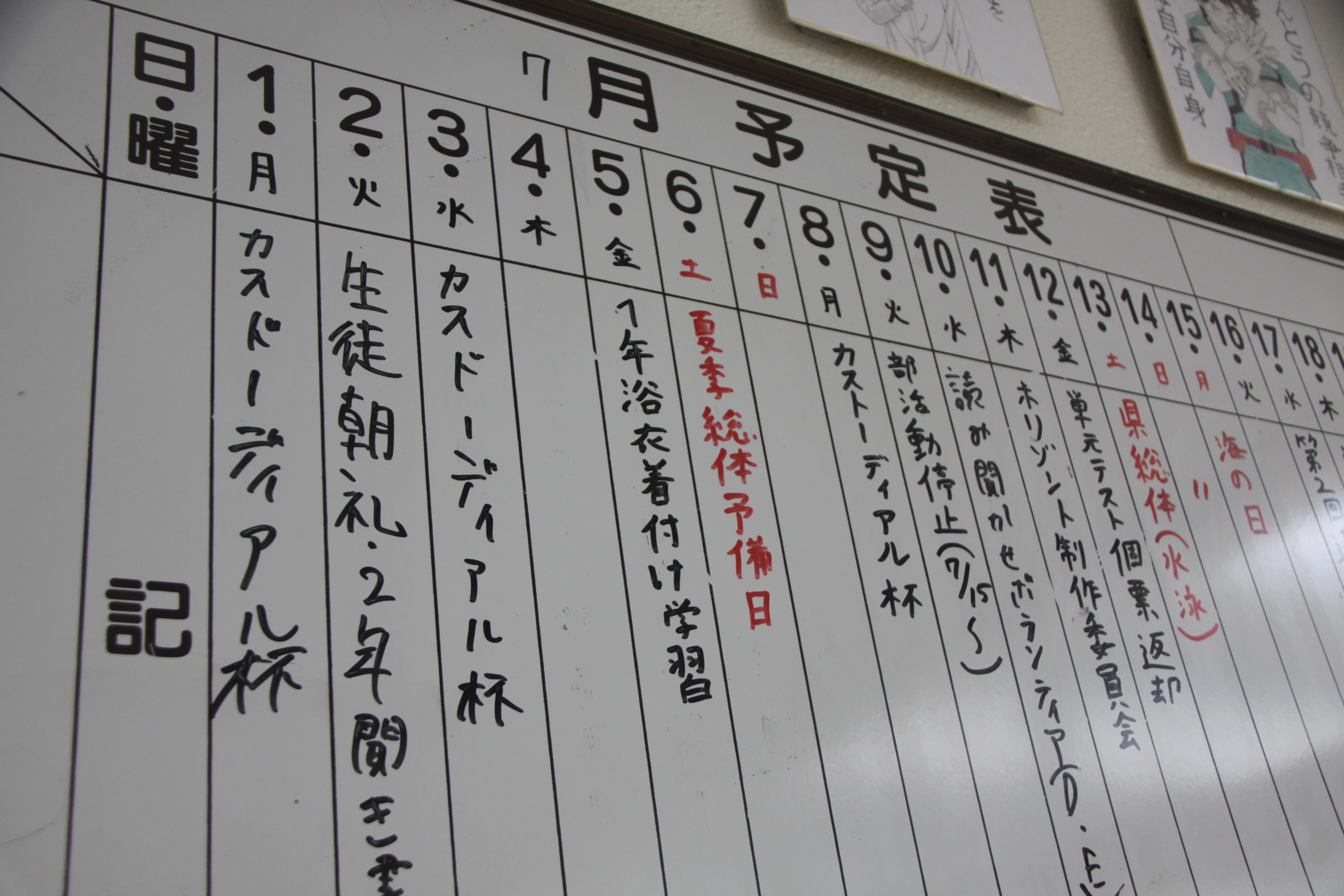
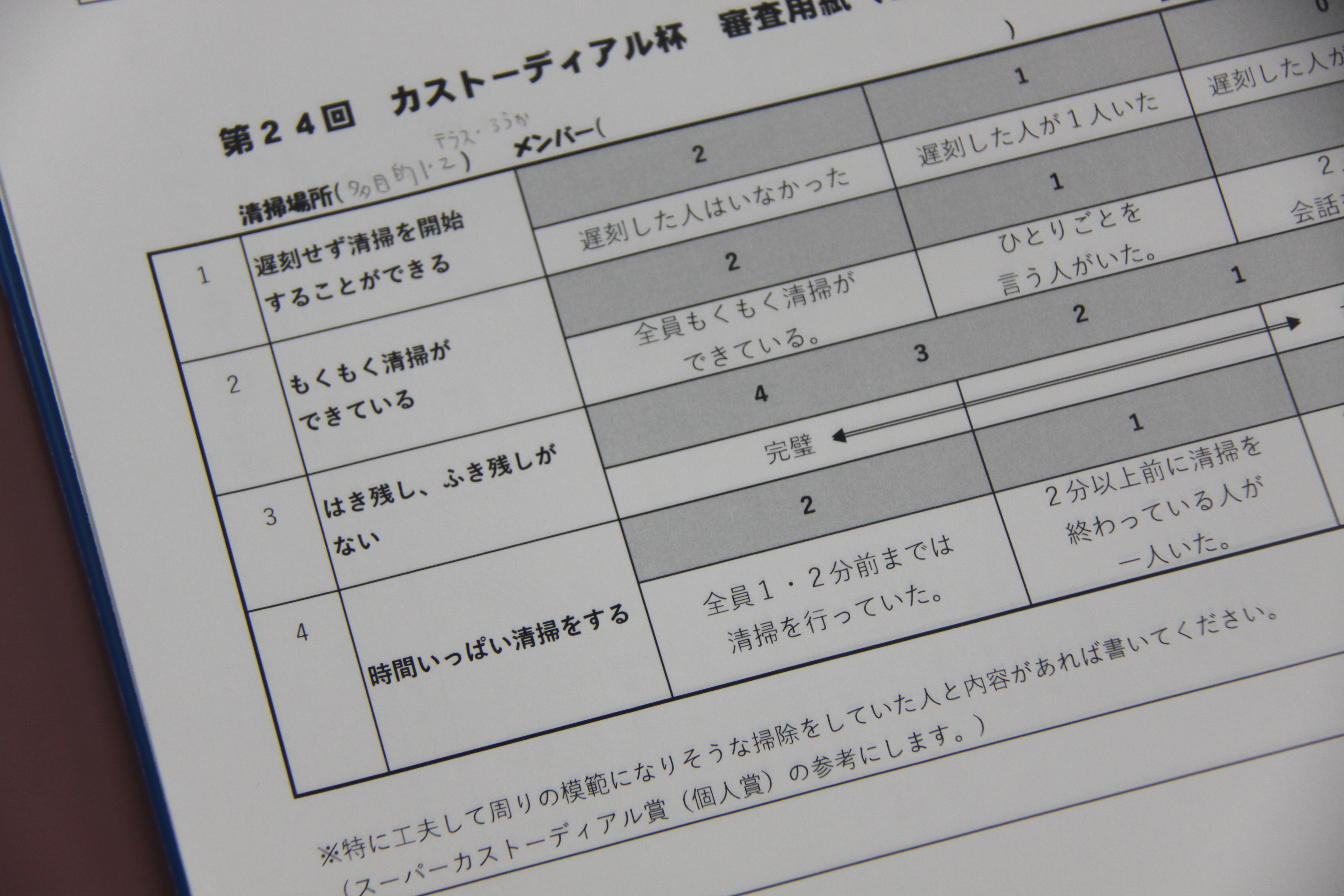

明治初頭より陽暦(新暦)を採用した日本では、12か月を1月〜12月の数字で表しています。しかし、それ以前は、季節感がわかるような和風月名で各月を表現しており、その7番目の月を「文月」としていました。現在では、これを陽暦(新暦)7月に当てはめ「文月=7月の和風月名」として用いています。
陰暦の7月は、陽暦の7月と時期が違います。陽暦は陰暦から1か月ほど遅れています。文月は「ふづき、ふみづき」と読み、その意味・由来・語源には諸説あります。なかでも、「文被月(ふみひろげづき、ふみひらきづき)」が略されて「文月」に転じたという説は有力です。この文被月とは、書道の上達を祈って、短冊に歌や願い事などを書く、七夕の行事にちなんだ呼び方だといわれています。しかし奈良時代に中国から伝わった七夕は、古来日本にはなかった行事であり、疑問視する声もあります。
ほかにも、収穫が近づくにつれて稲穂が膨らむことから「穂含月(ほふみづき)」「含月(ふくむづき)」が転じて「文月(ふづき)」になったという説、稲穂の膨らみが見られる月であることから「穂見月(ほみづき)」が転じたという説もあります。
他にも別名や異称で表されるさまざまな呼び名があります。そのいくつかを紹介しておきましょう。
○初秋(しょしゅう、はつあき)
陰暦では、7月から9月が「秋」になります。このため、7月である「文月」が、秋の最初の月になるため「初秋」とも呼ばれます。
○親月(おやづき、しんげつ)
陰暦7月の文月にはお盆があります。このため、親の墓参りをする月ということから「親月」とも呼ばれているようです。
○涼月(りょうげつ)
文月の終わりには暑さもやわらぎ、涼しい風を感じることもあるため「涼月」とも呼ばれていたようです。
◎多くの人に支えられて(6/29)
私たちの資源物回収・PTA活動






保護者のみなさんありがとうございました。生徒のみなさんお疲れ様でした。PTA・生徒会
◎Some people feel the rain. Others just get wet.(6/28)
雨を感じられる人間もいるし、 ただ濡れるだけの者もいる Bob Marley

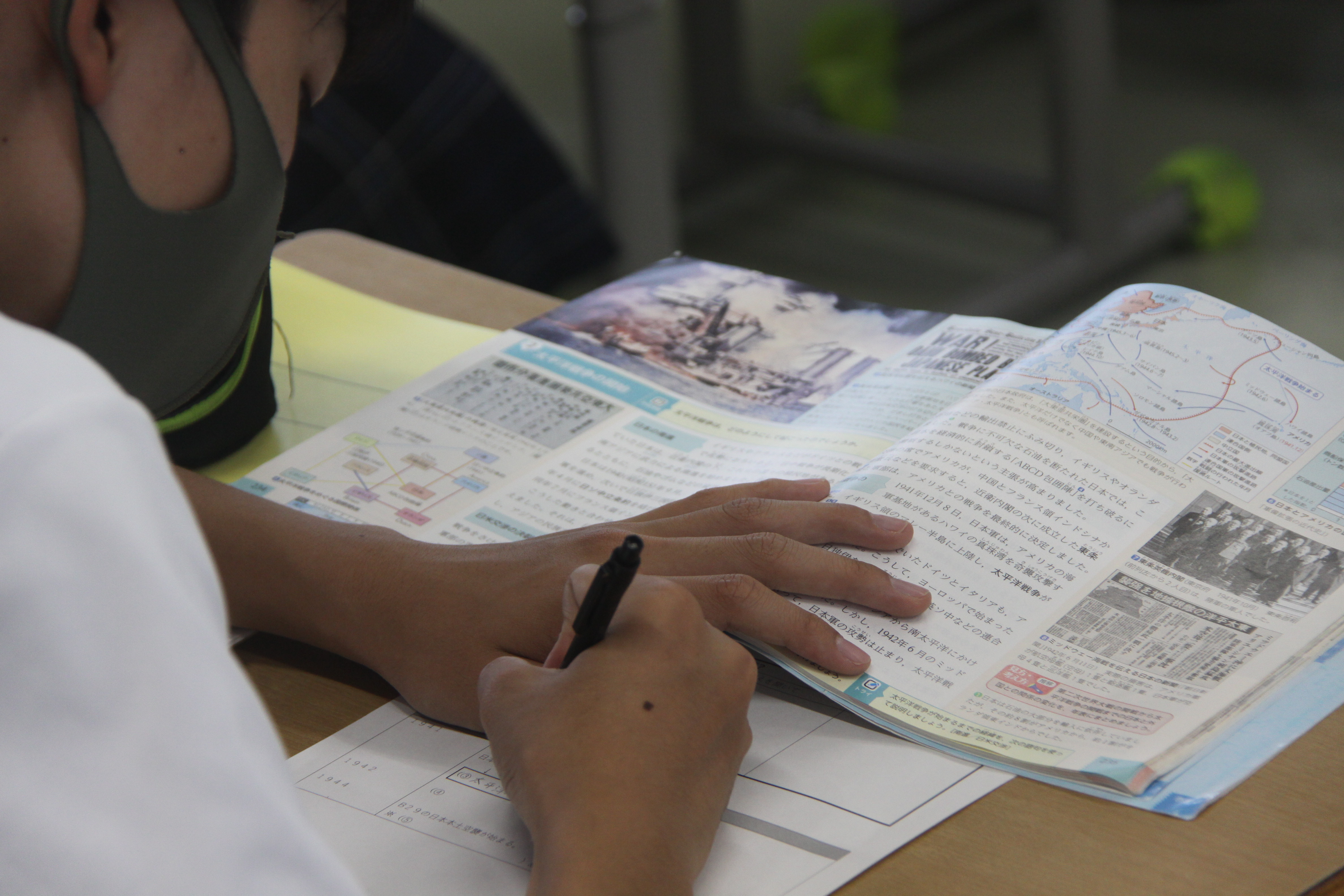
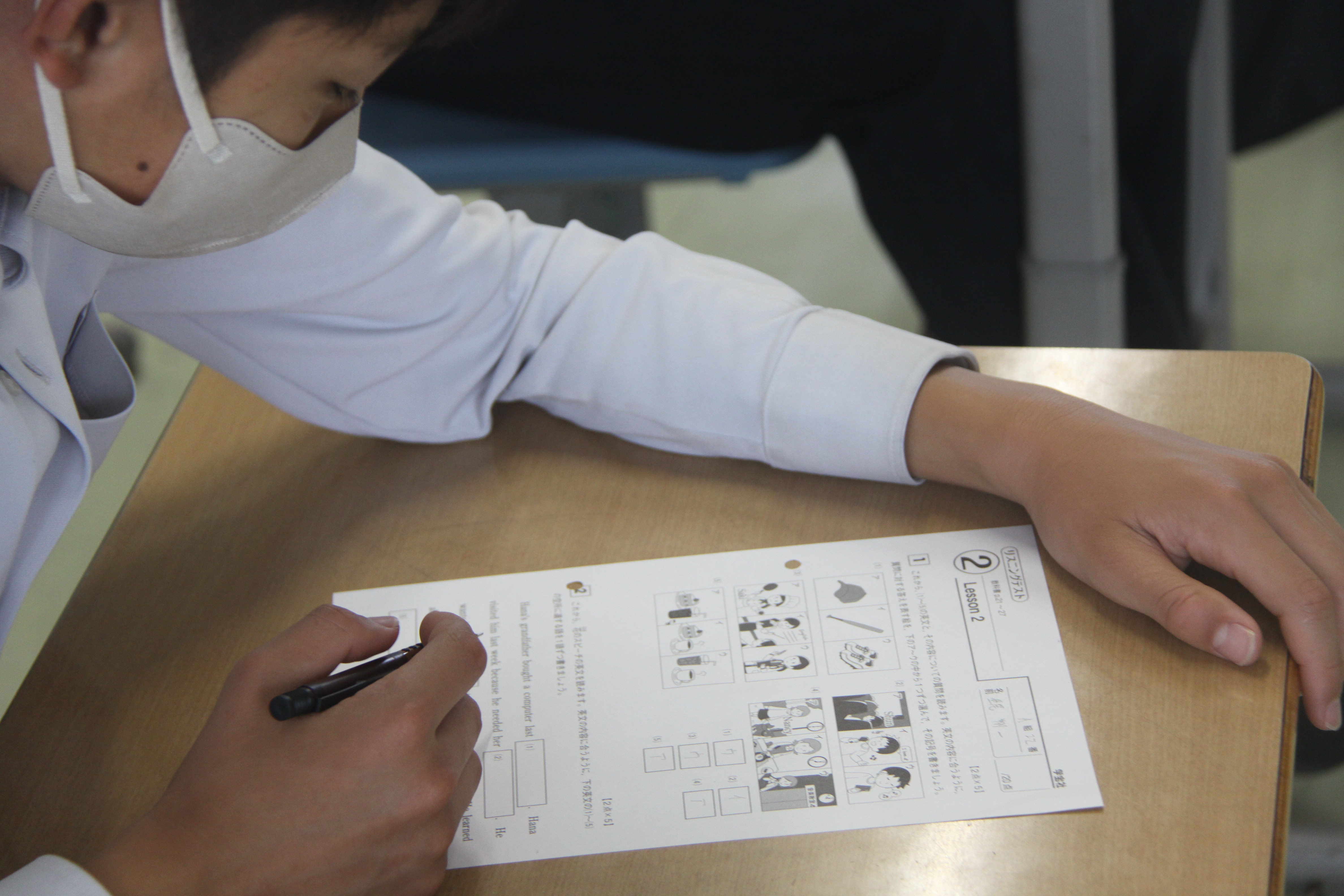
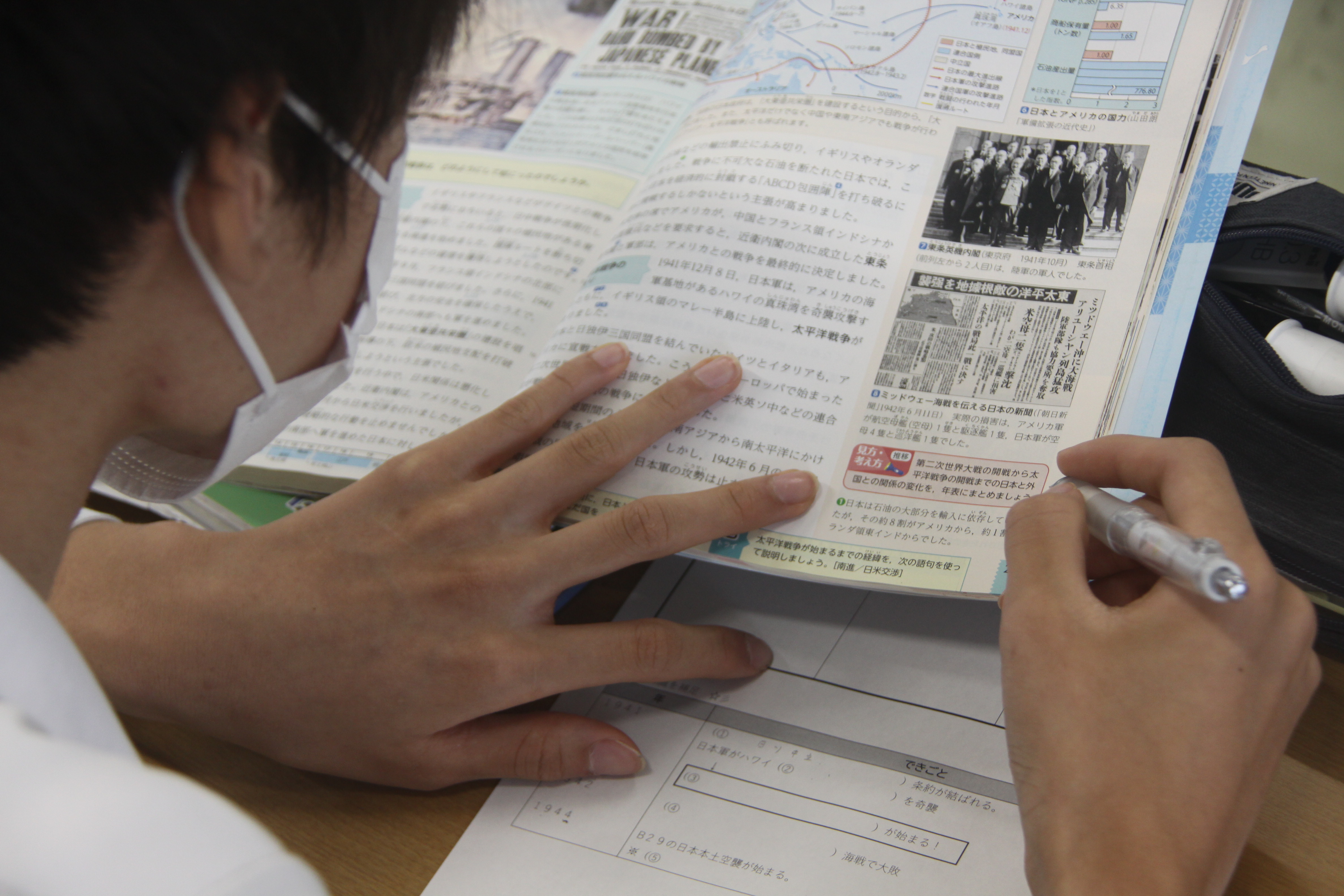

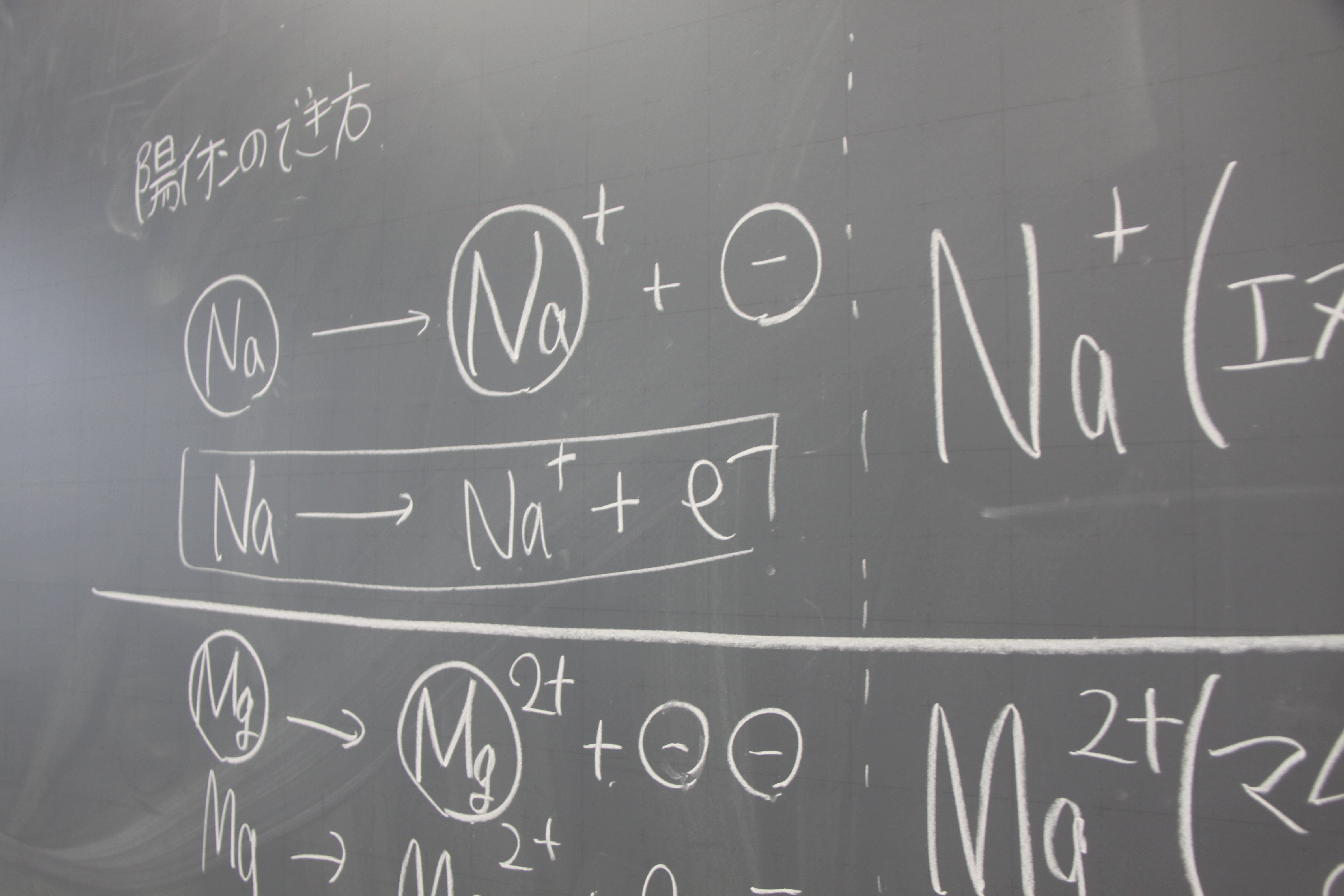



◎多くの人に支えられて(6/27)
私たちの安全な生活のために~東備消防署立ち入り検査



◎ひな中チャレンジ企画2024✨(6/27~)
~今日!新しい扉をひらく。


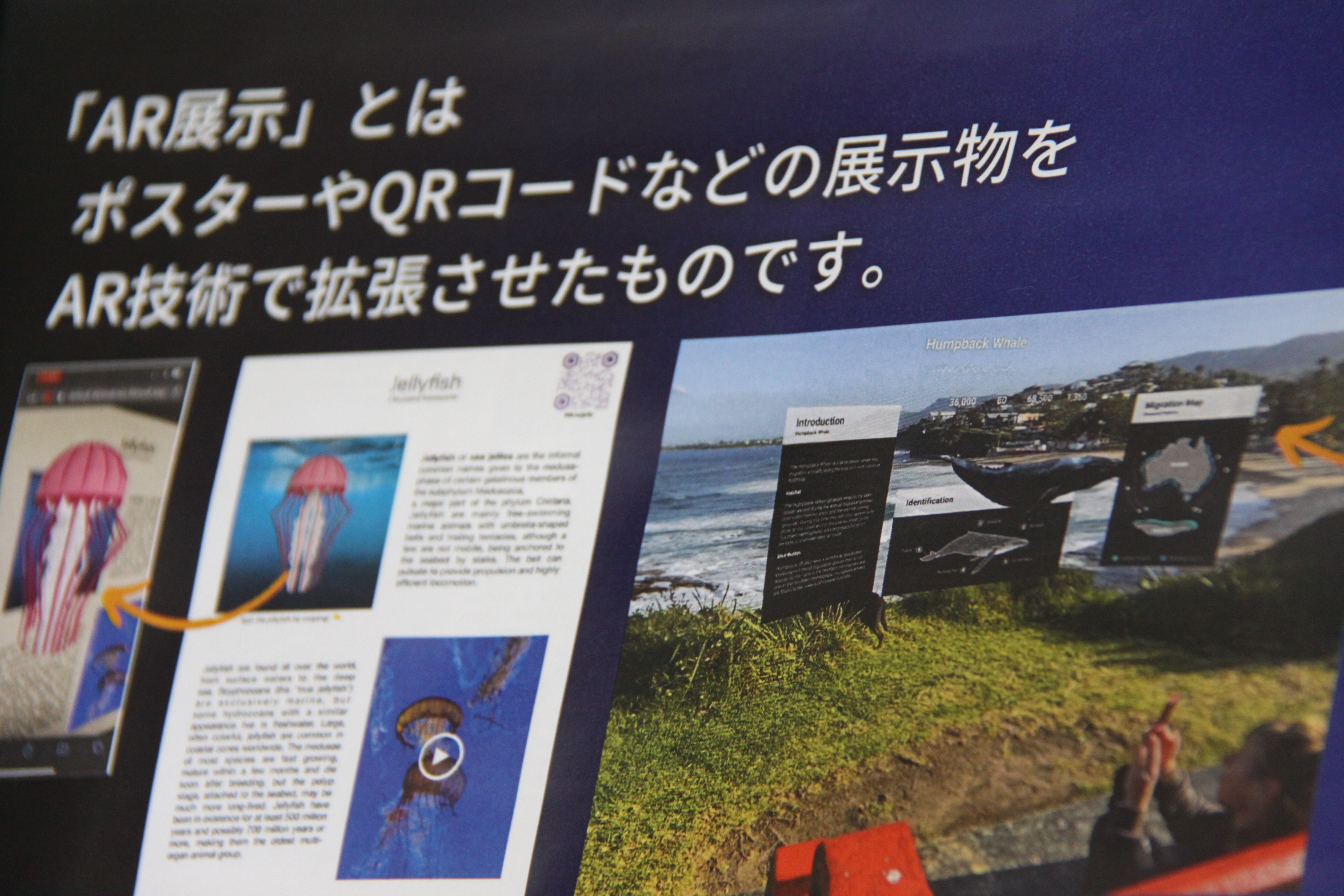



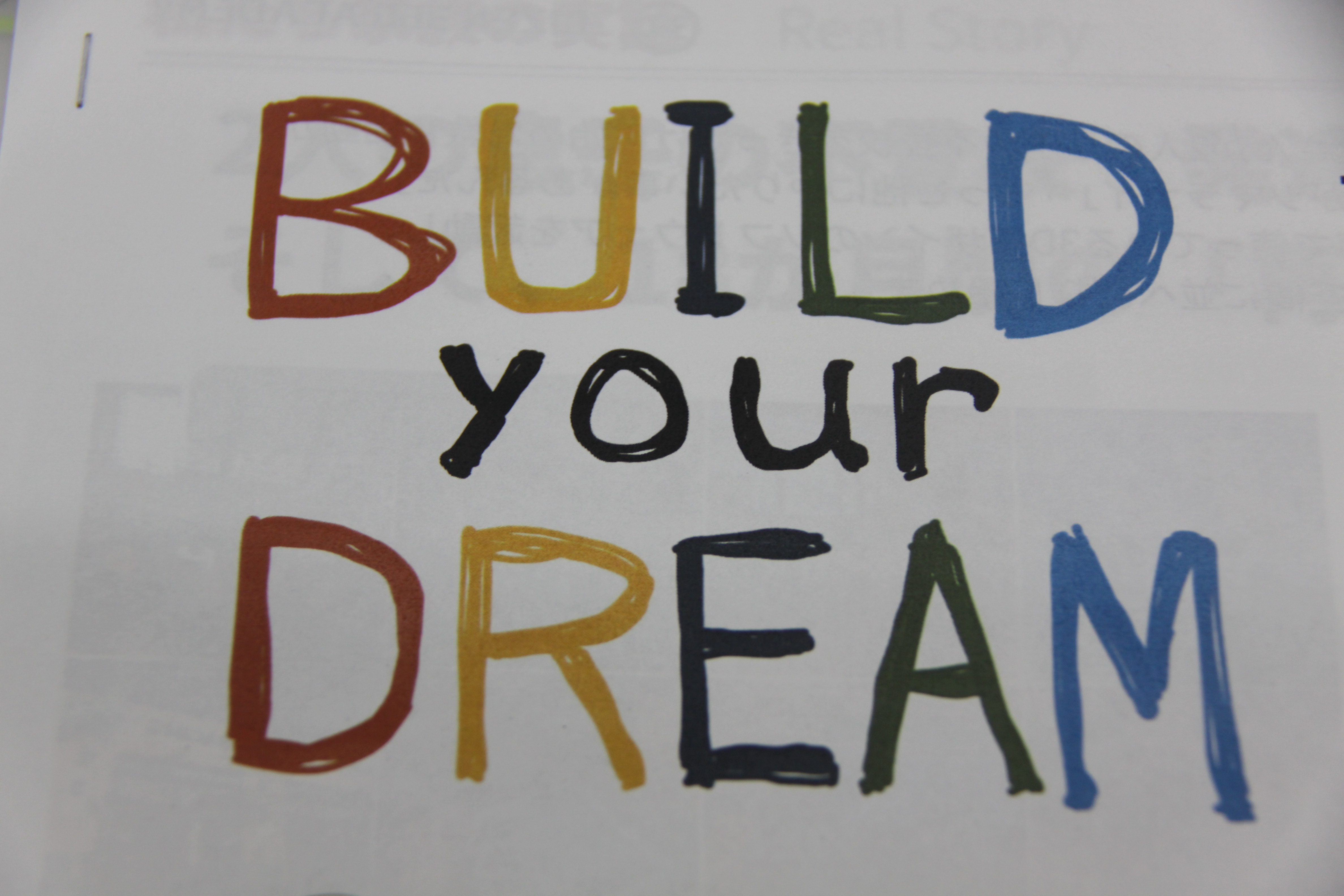

◎ひな中の風✨(6/27)

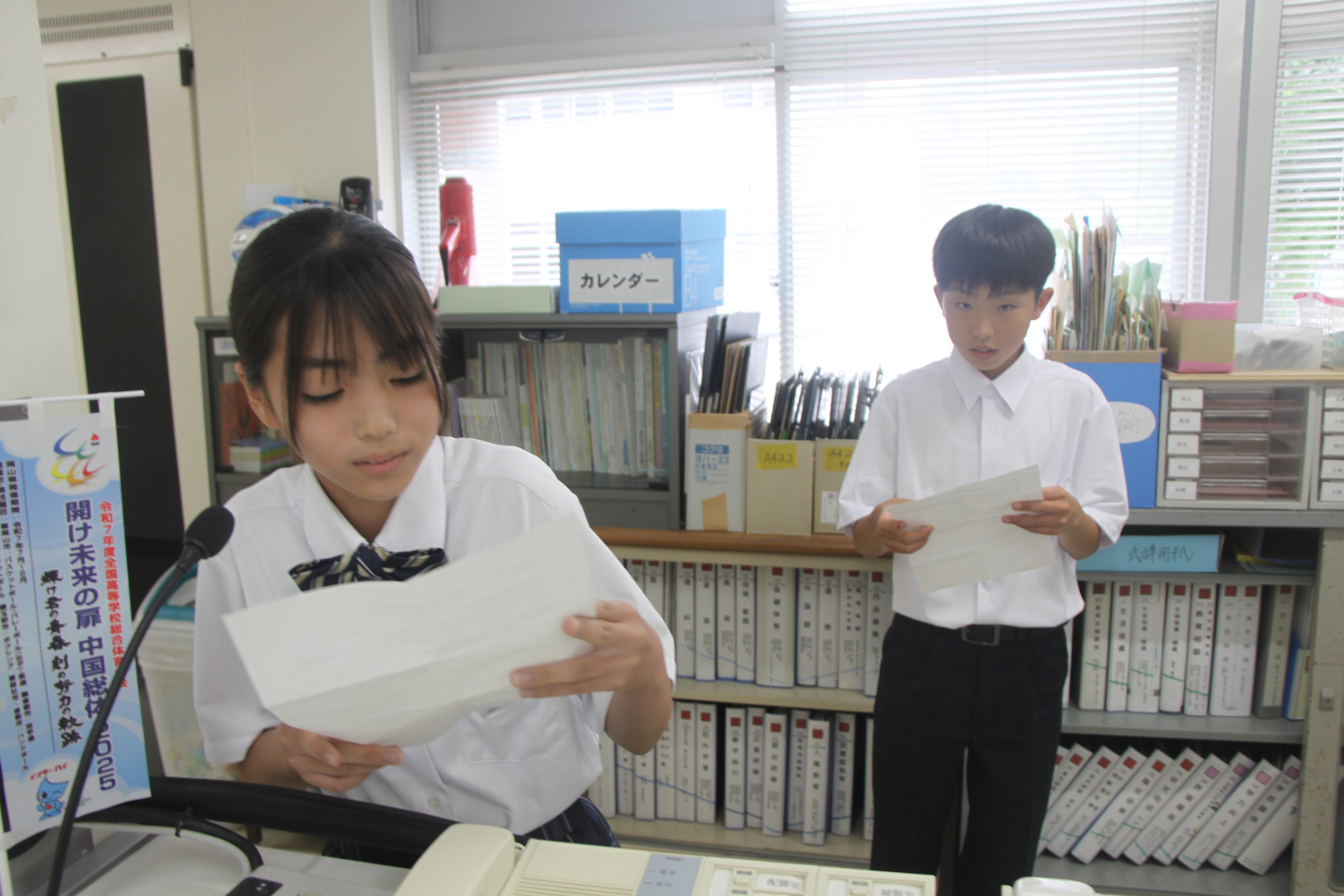






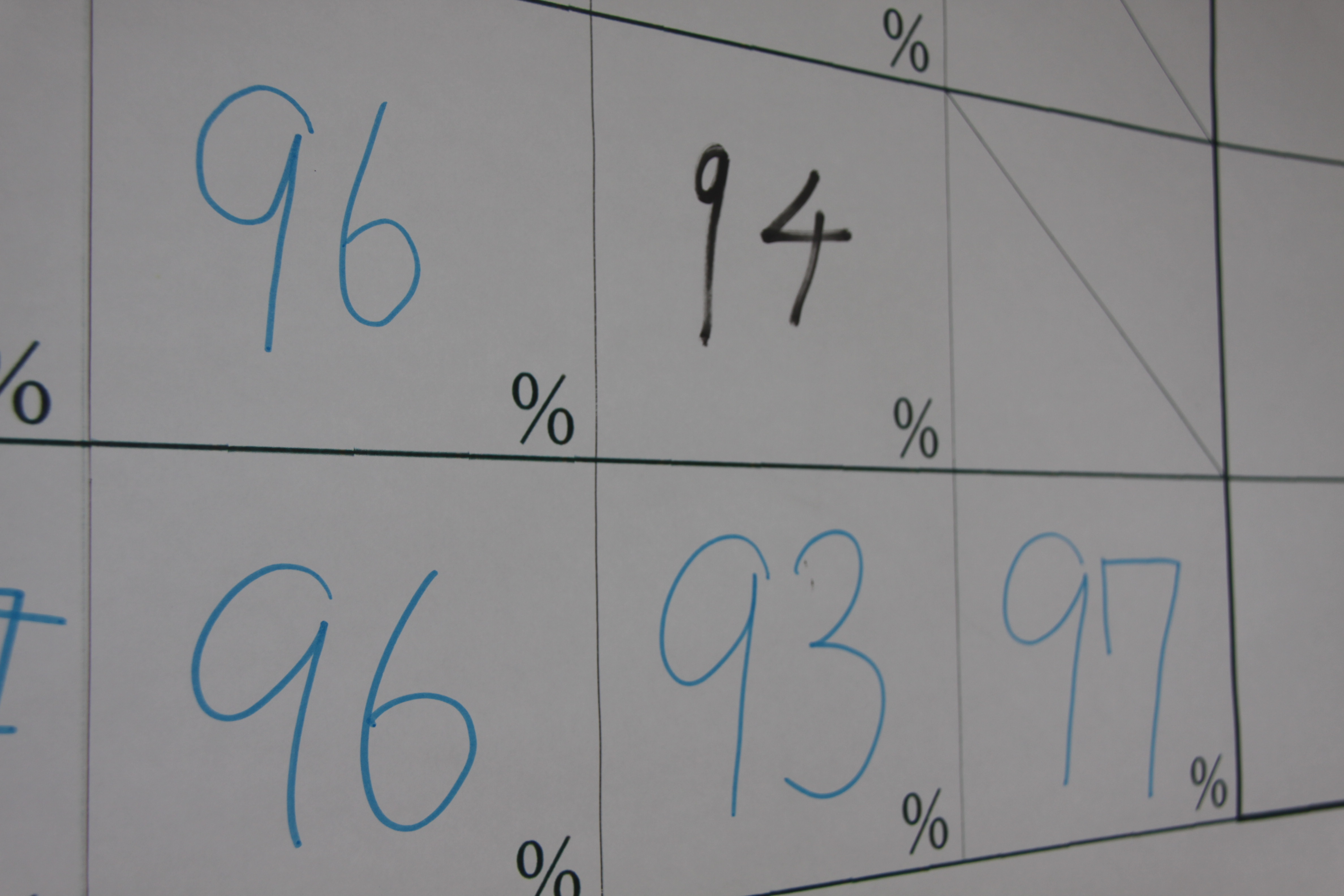
◎ぼくは~おばけのQ太郎~♬
「協力」と「コミュニケーション」を考えたよ(6/26)
やまちゃんスクールカウンセラーと「協力」について、1年生がワークショップ形式で体験学習に取り組みました。
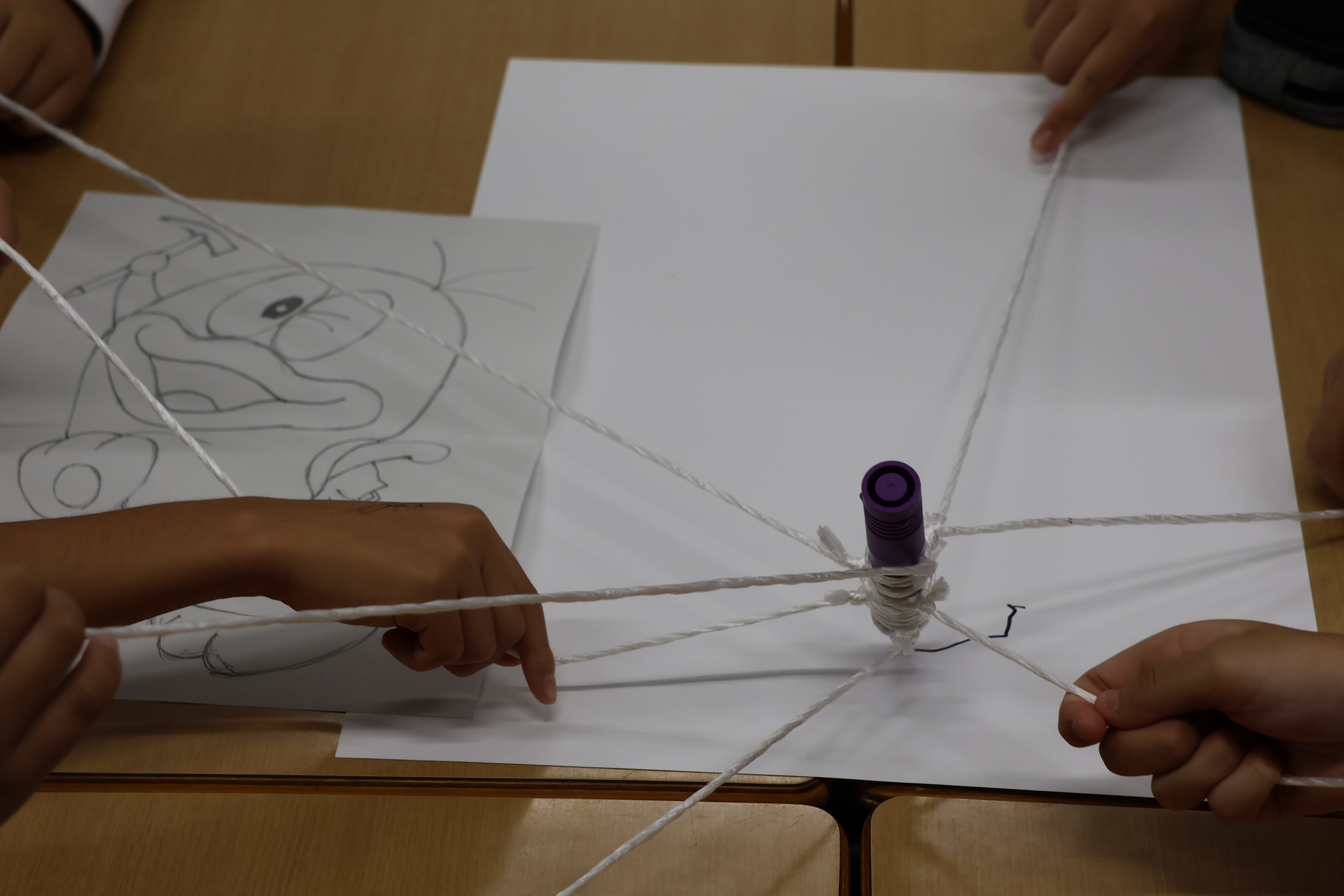
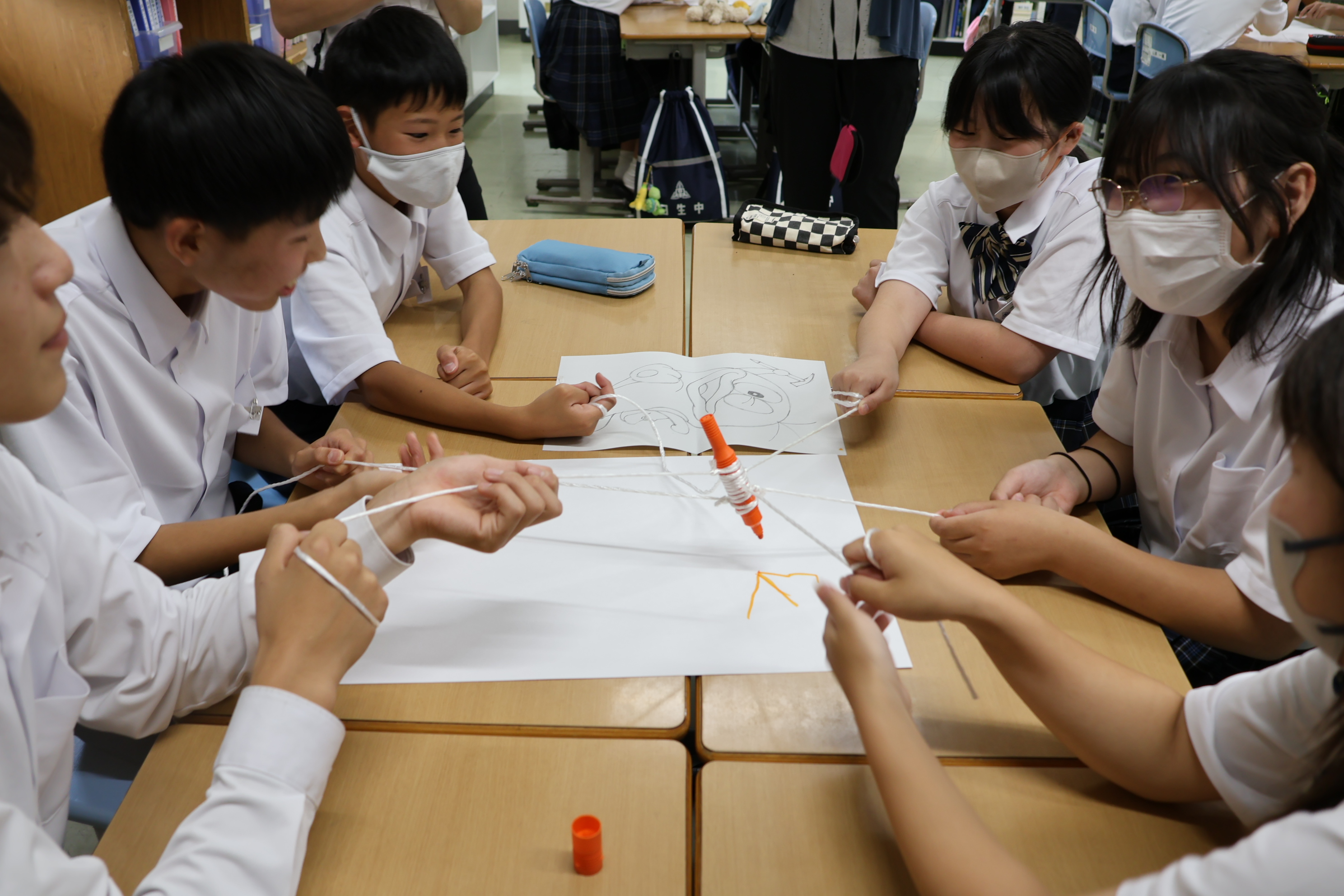
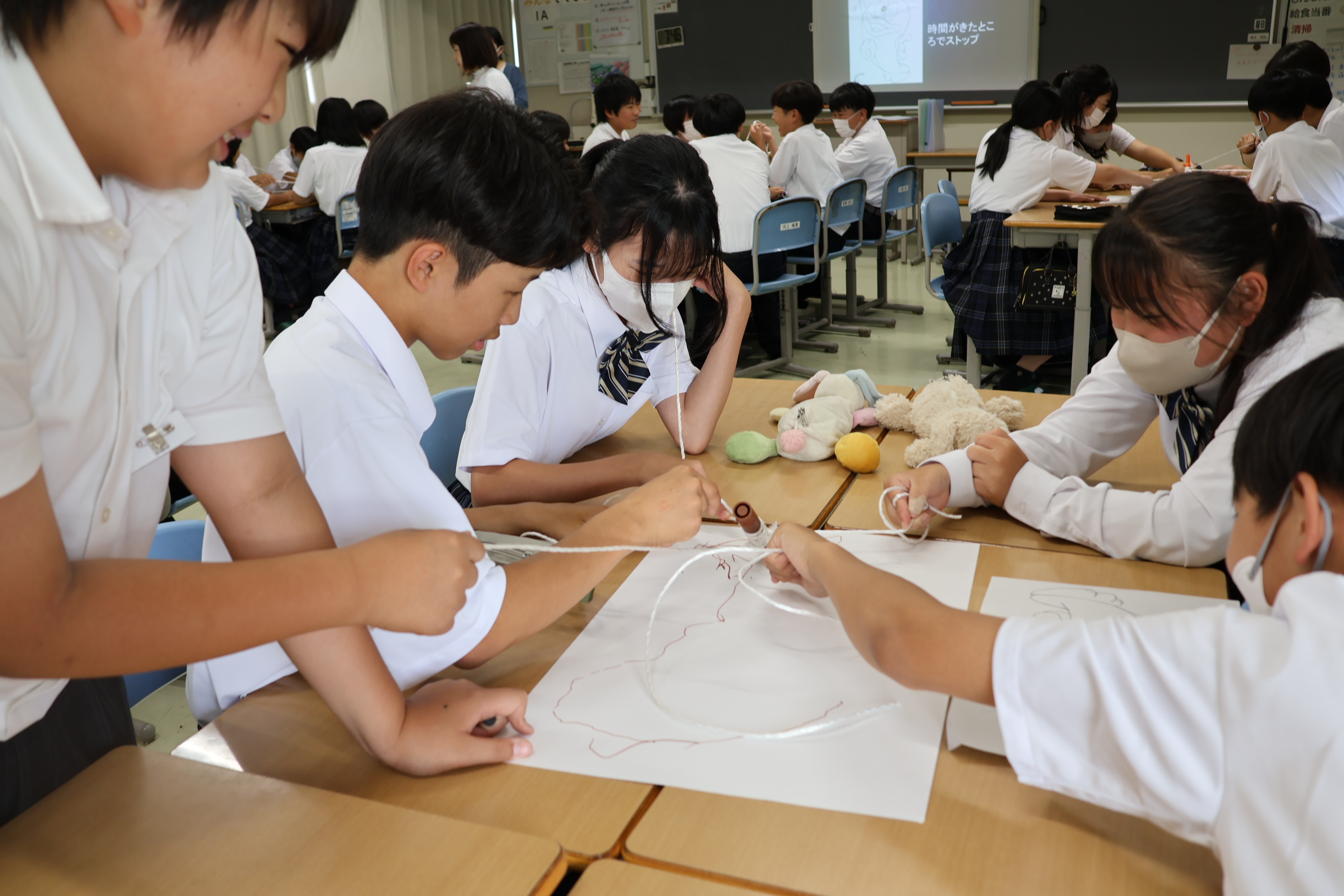
◎ひな中からの風を✨(6/25)
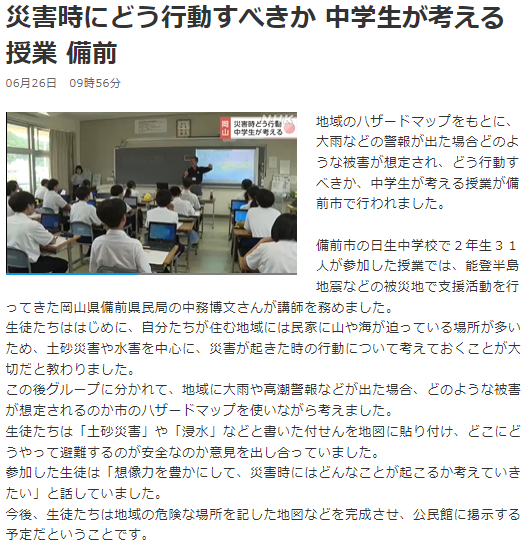
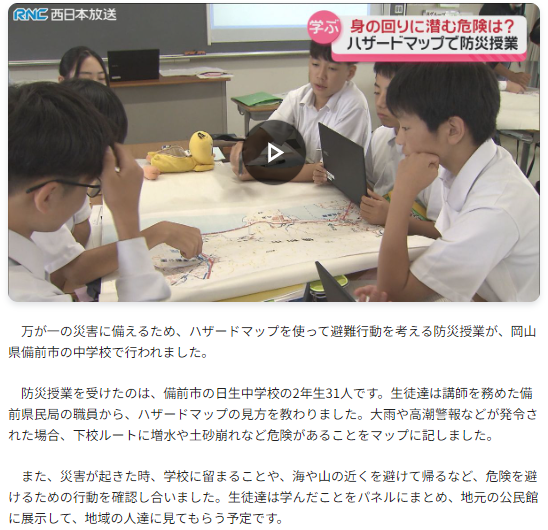
NHK‚西日本放送さんが来校されました。
◎深い学びへ リアルな学びを(6/25)
〈私たちは 自分の大切な人を守るために・・・その時 どう行動するべきなのだろう〉
備前県民局から中務さんをお招きして「防災(社会科地理的分野)」について取り組みました。
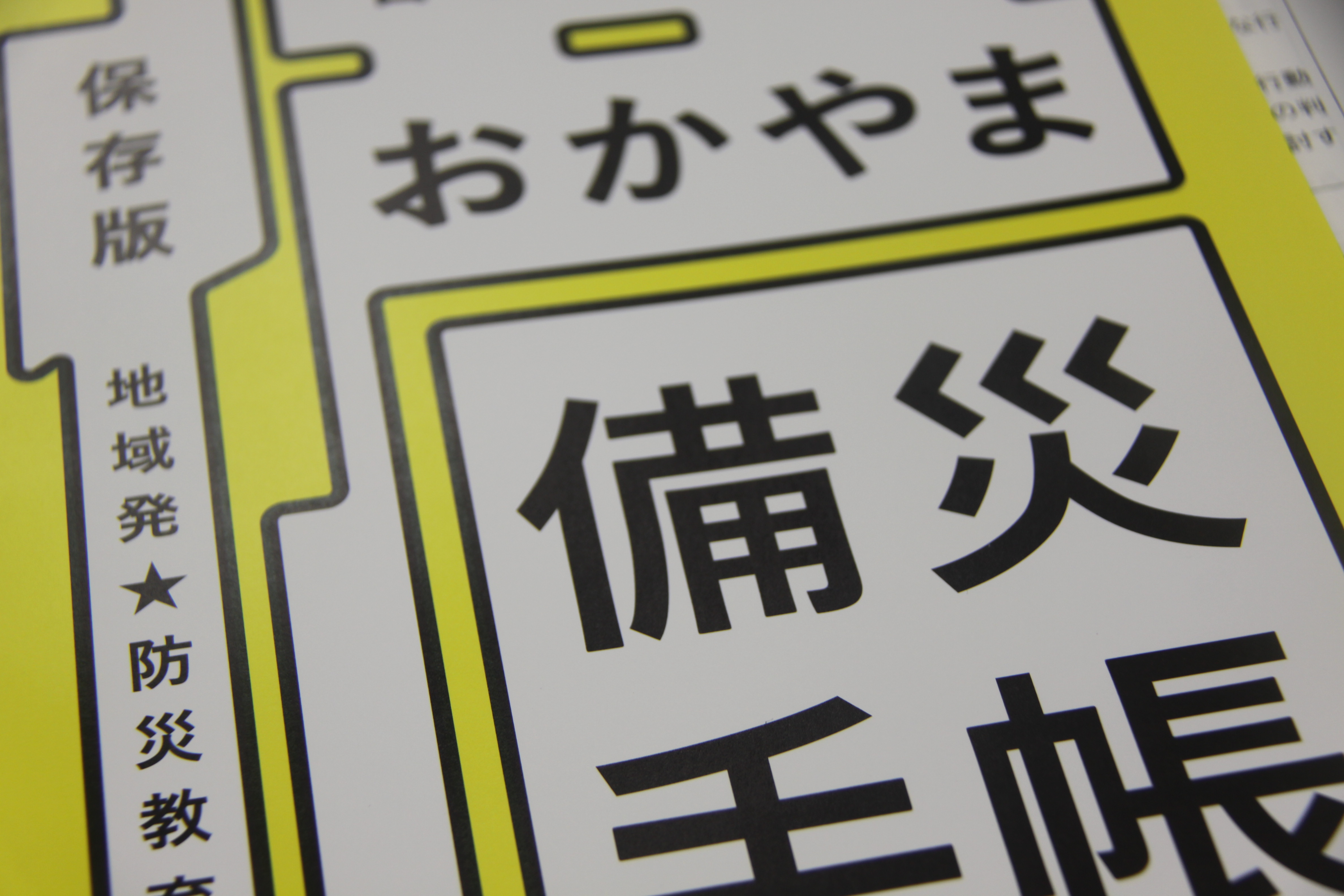


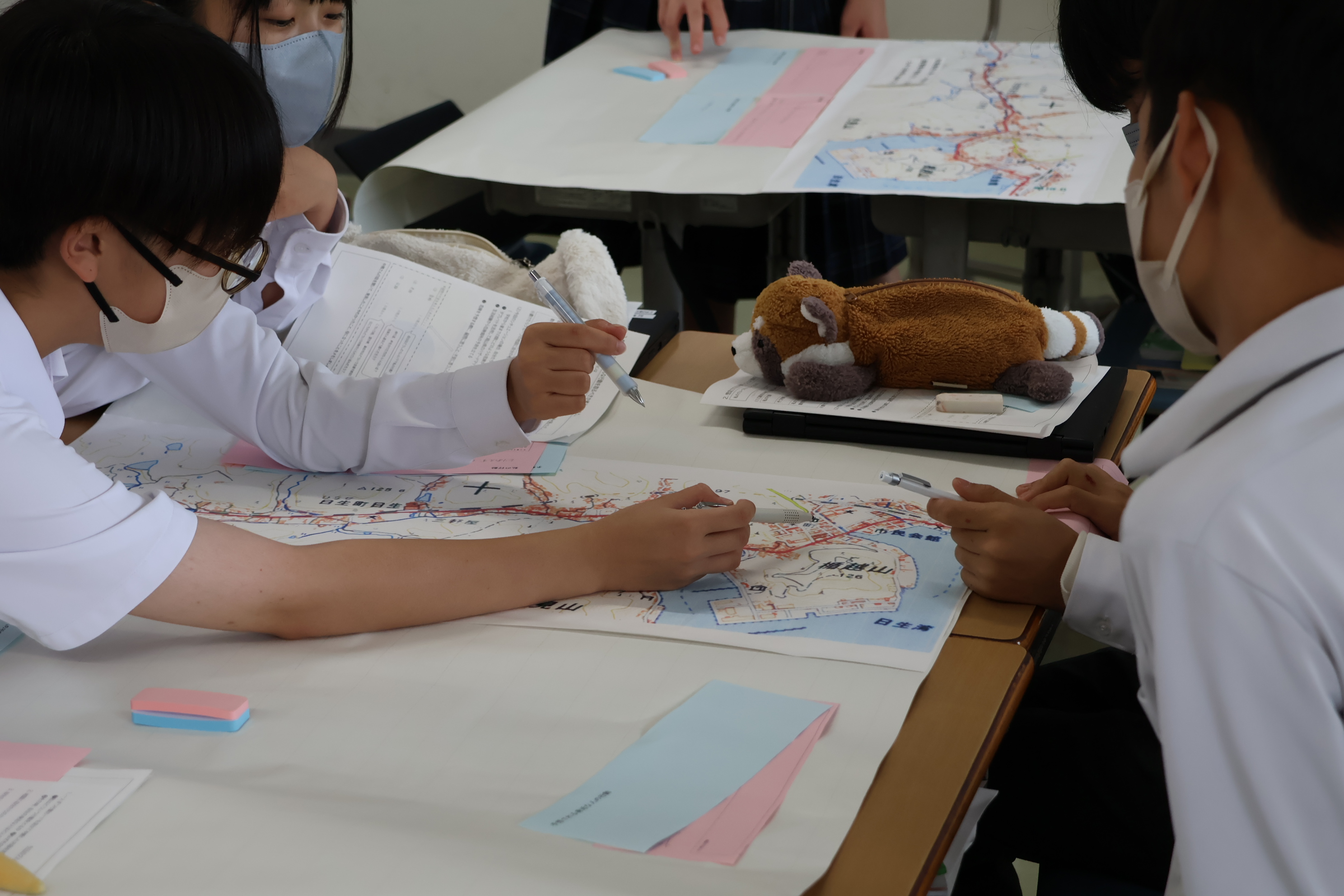
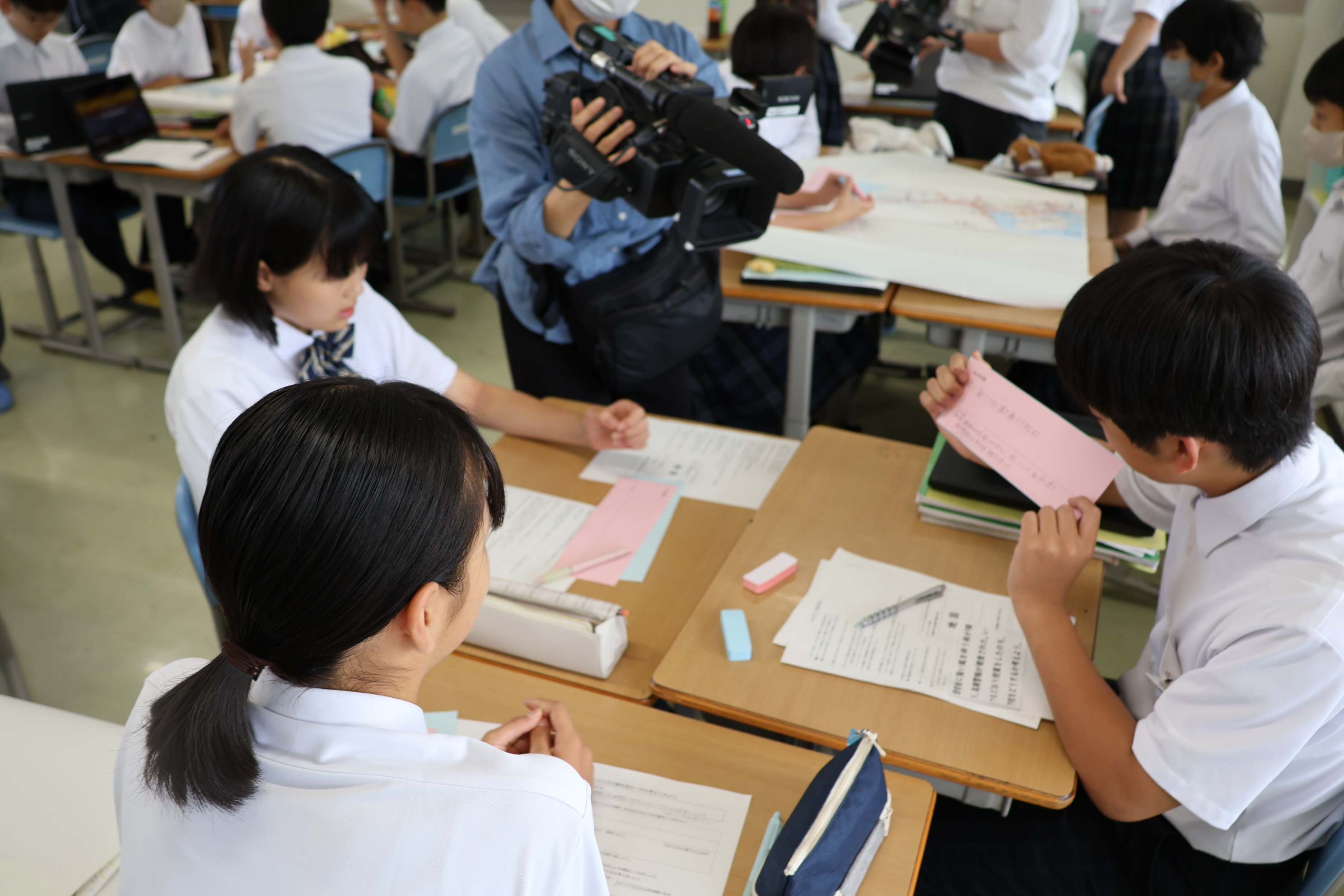
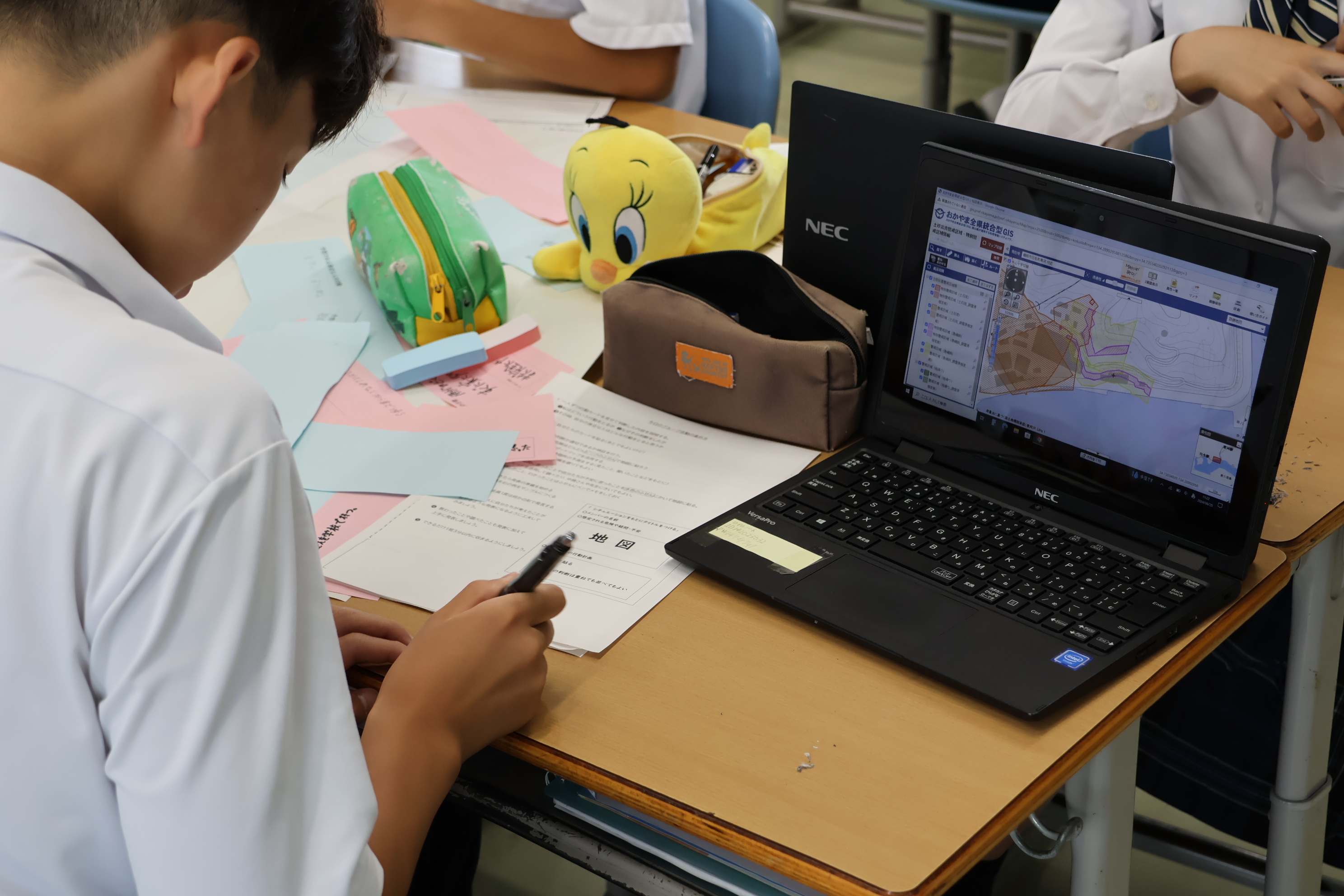
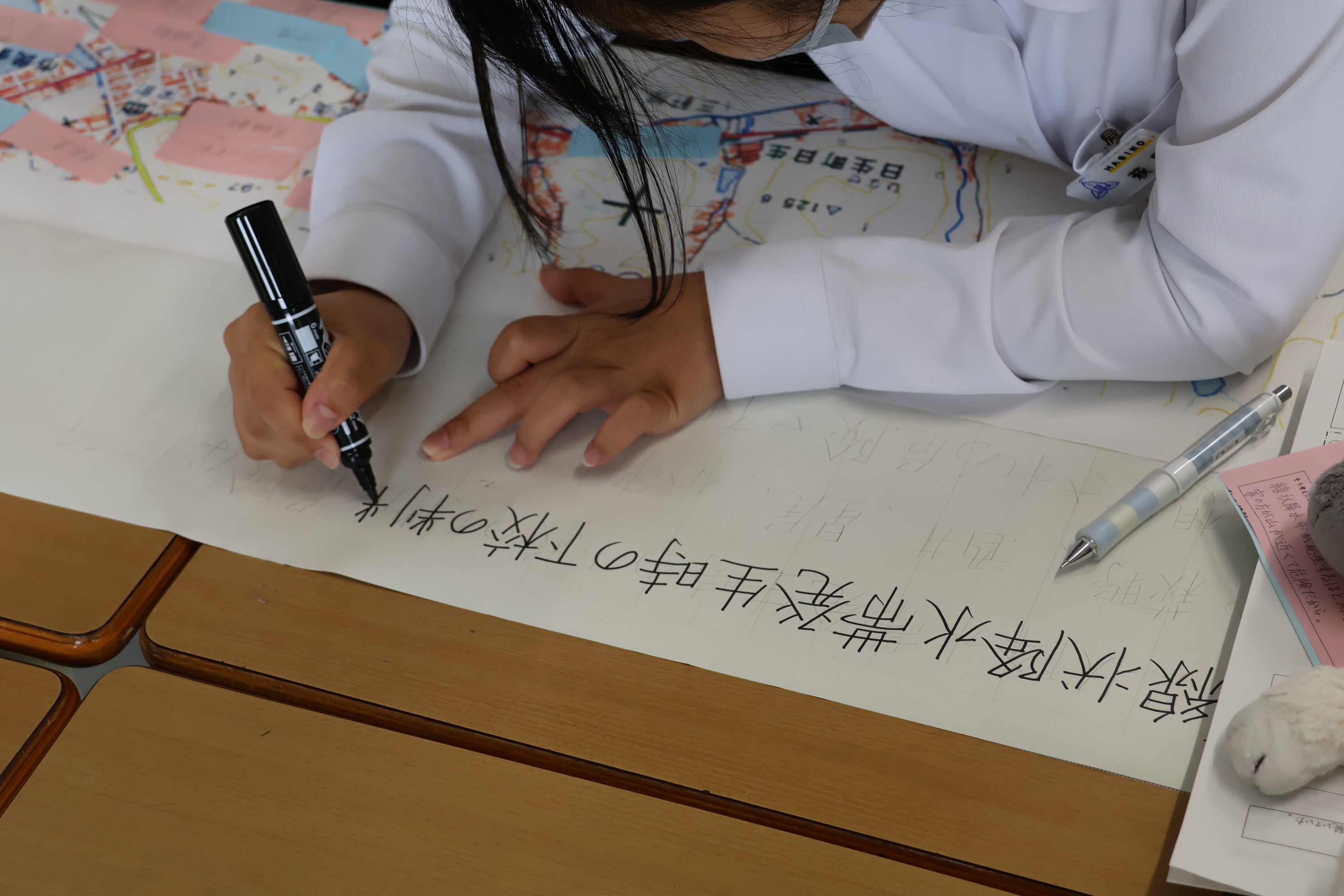

◎ひな中の風✨
仲間とのあいさつから始まる日々




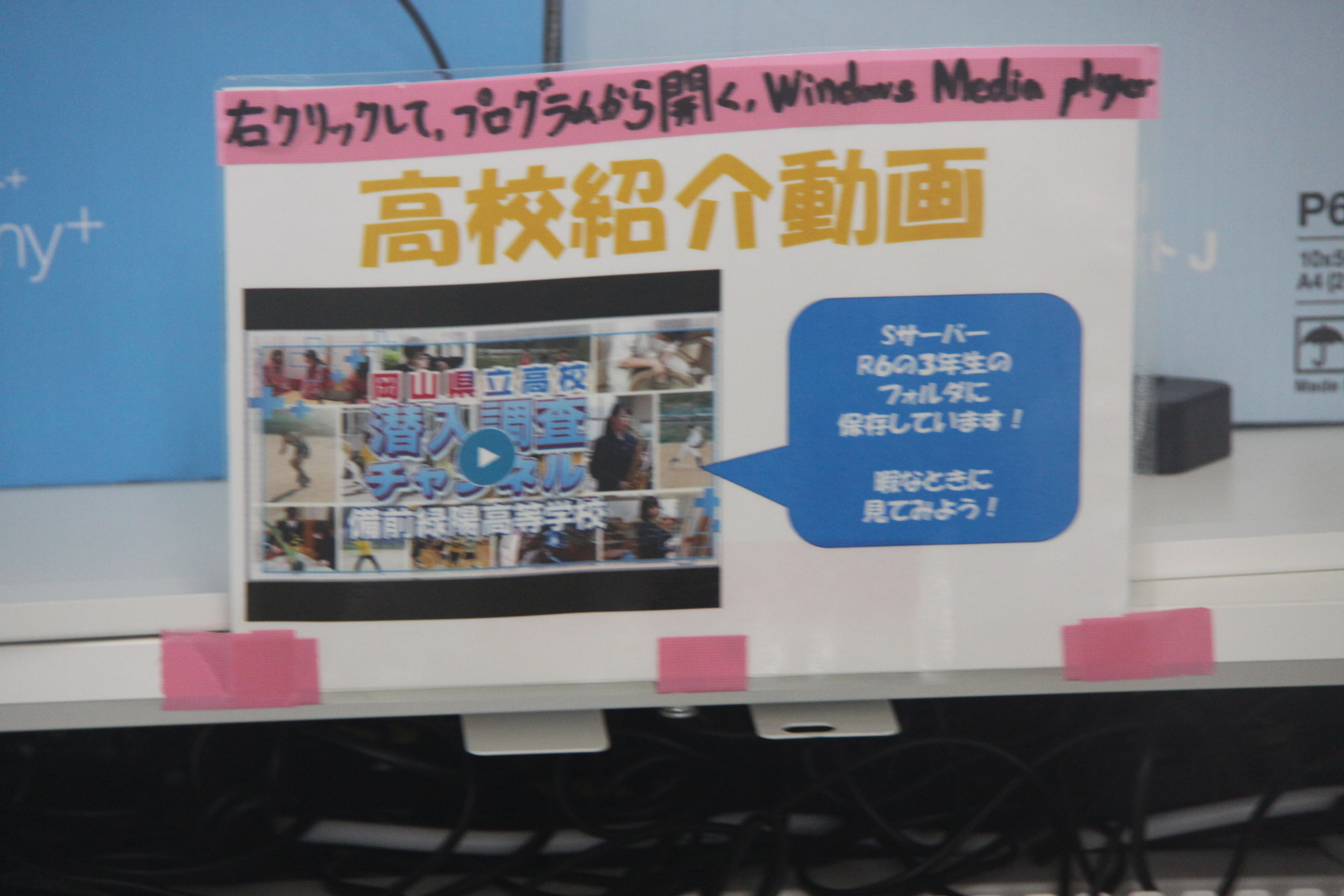



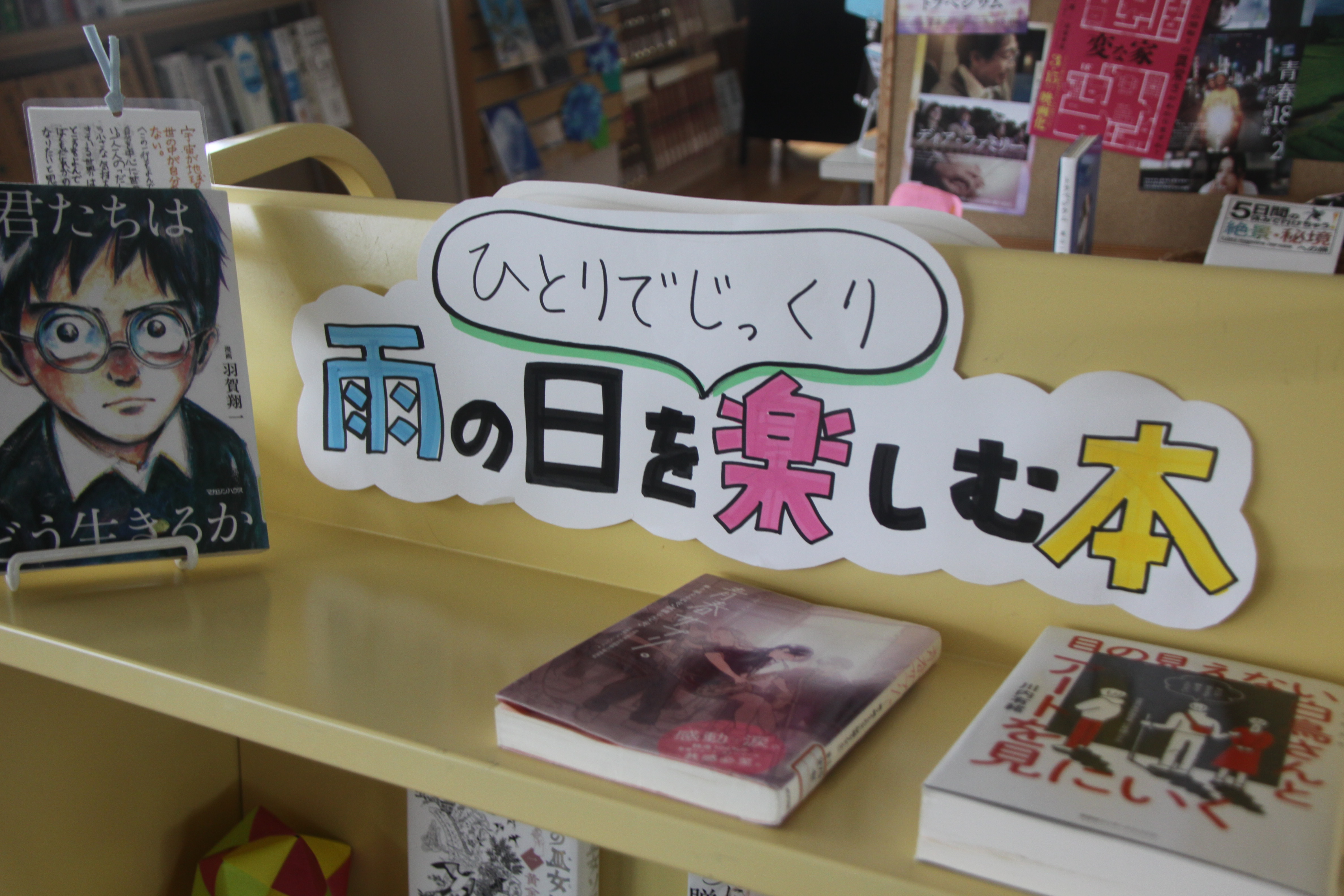
◎私たちの一生懸命。授業がたいせつ。
(6/24:学校訪問)
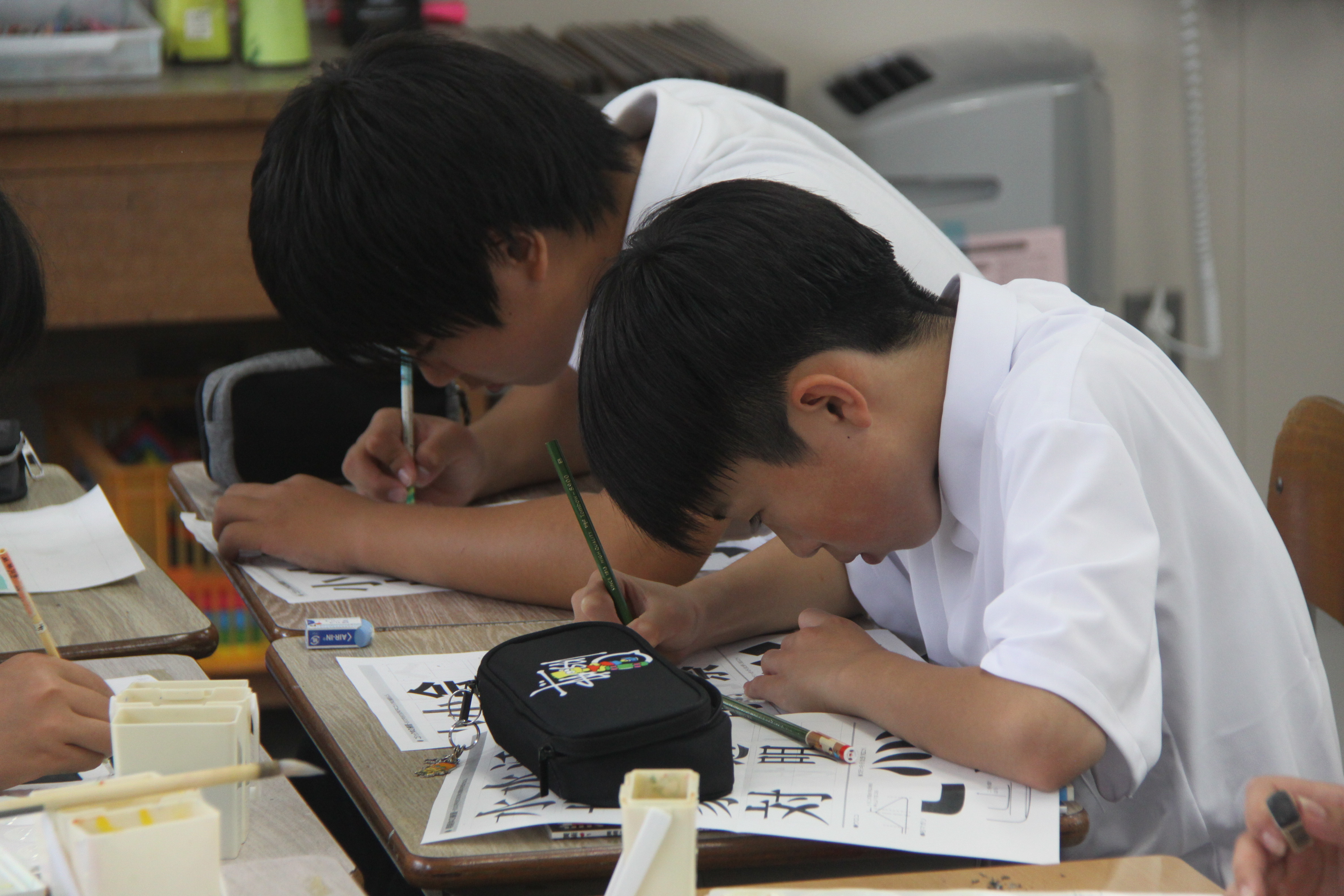
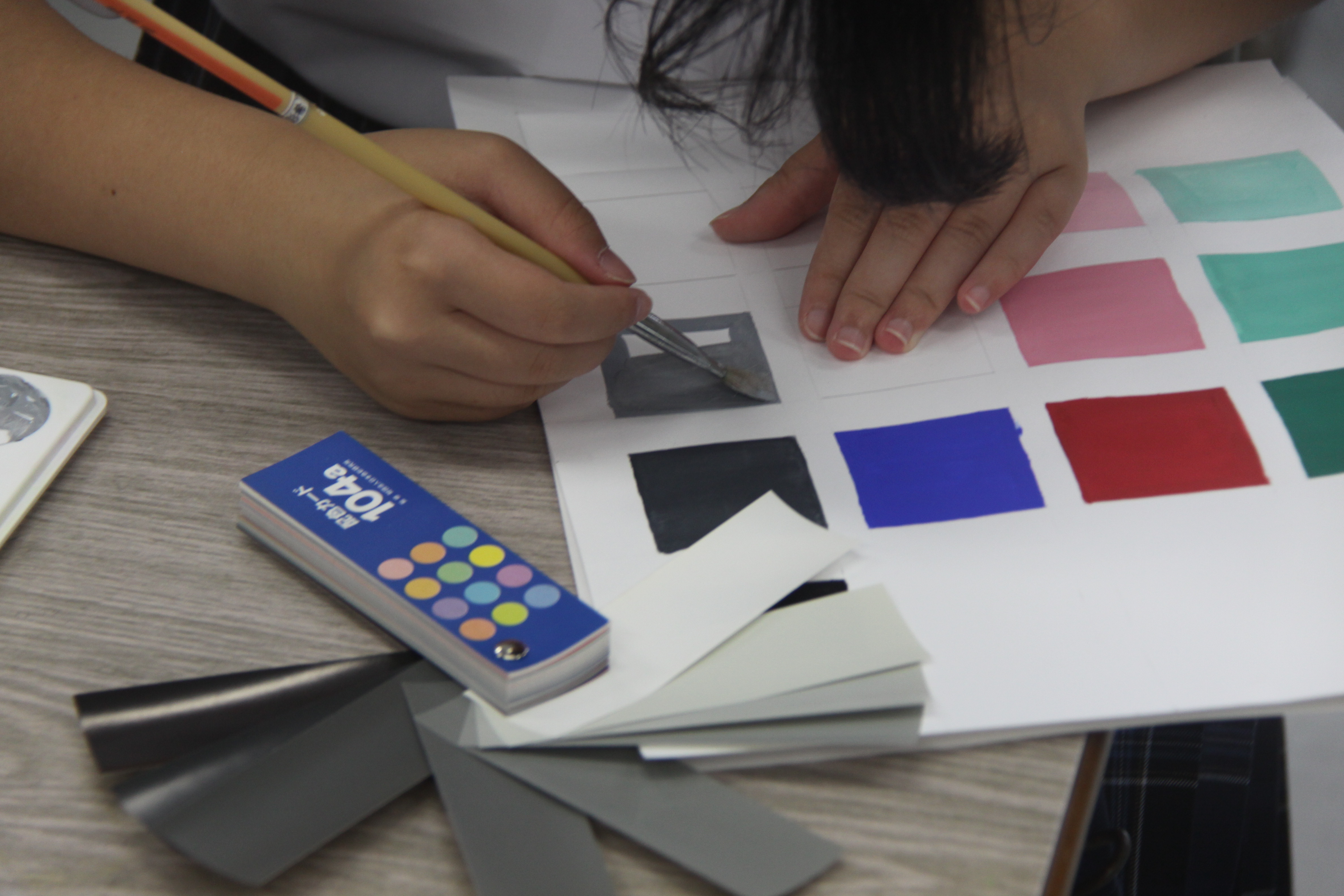
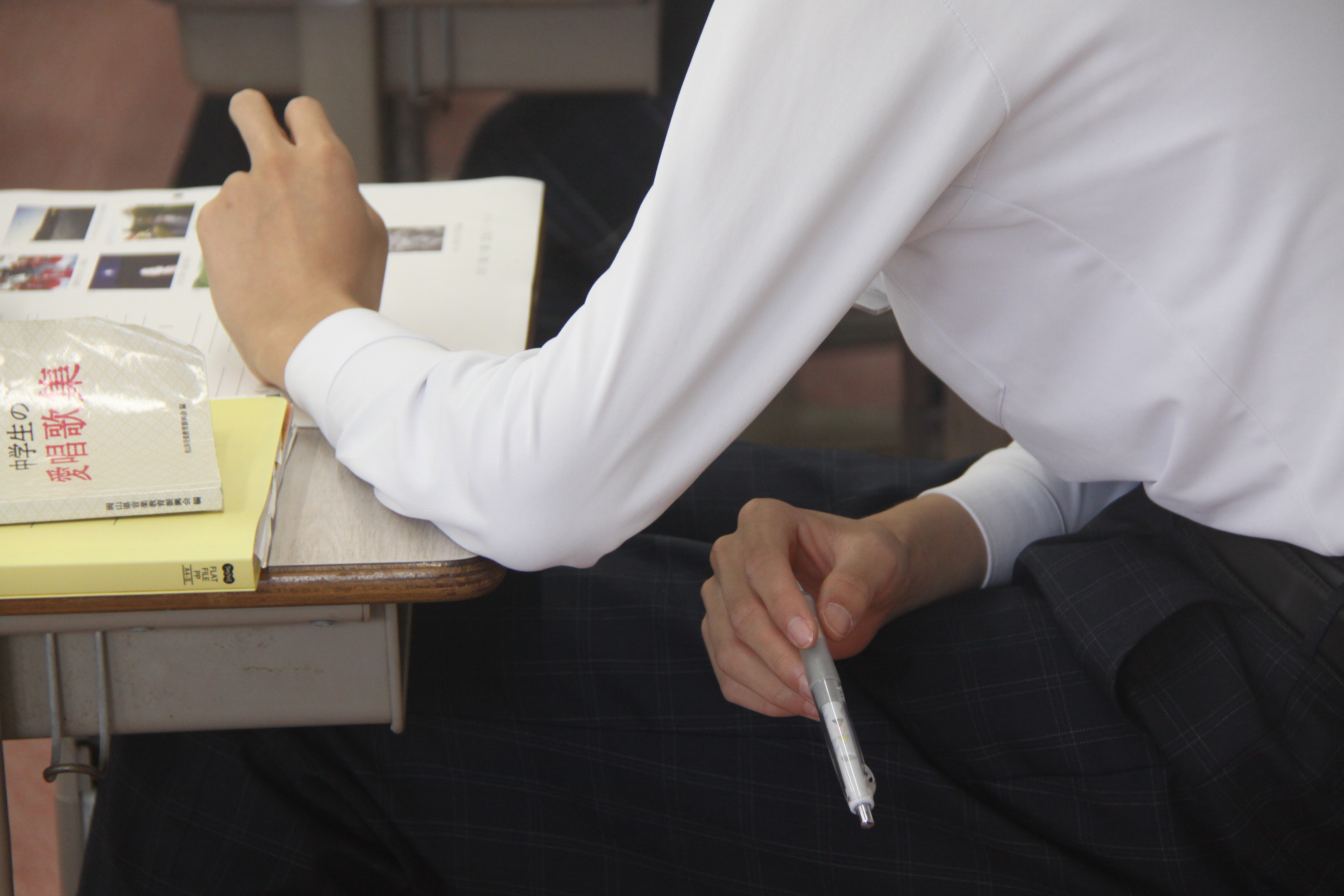



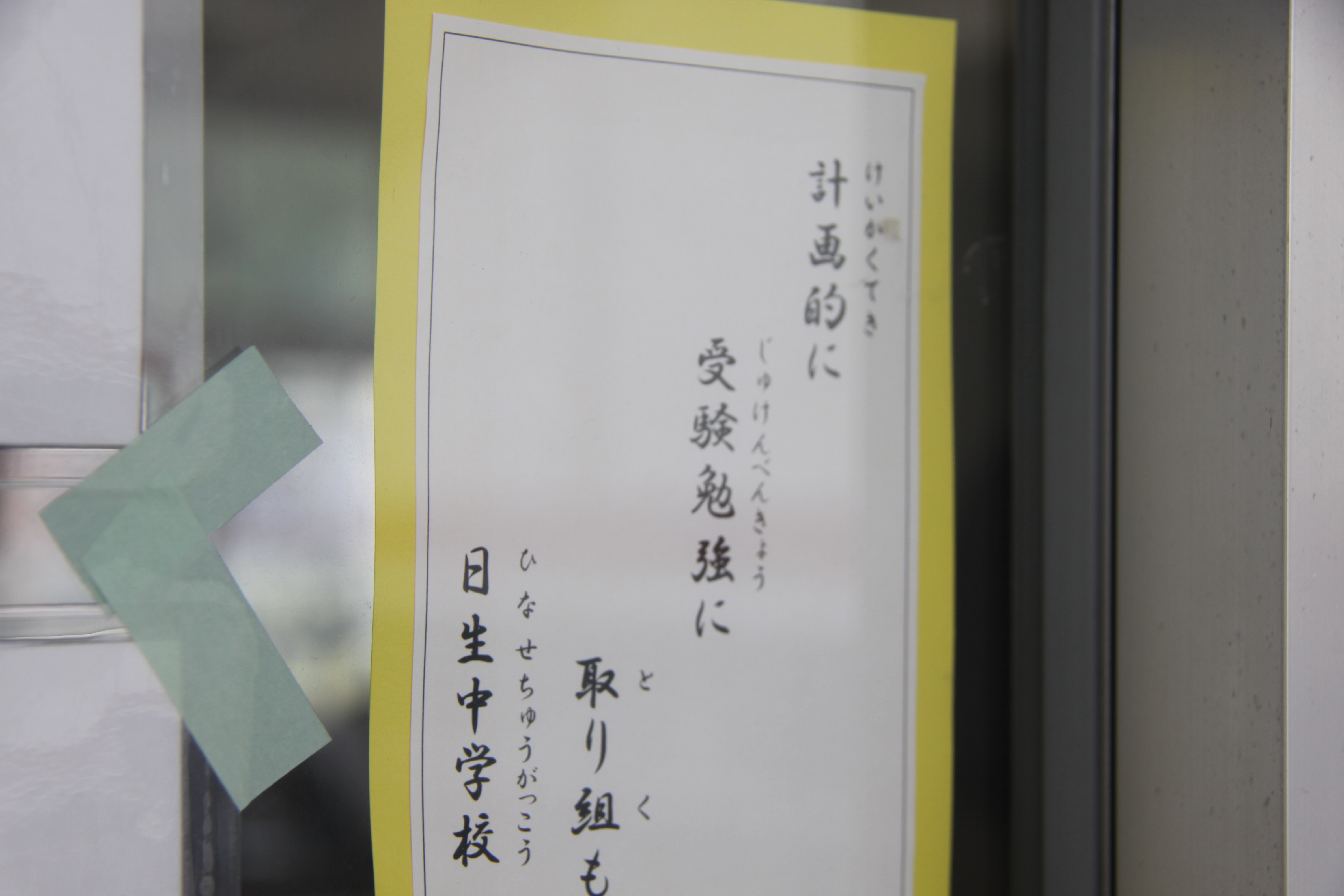



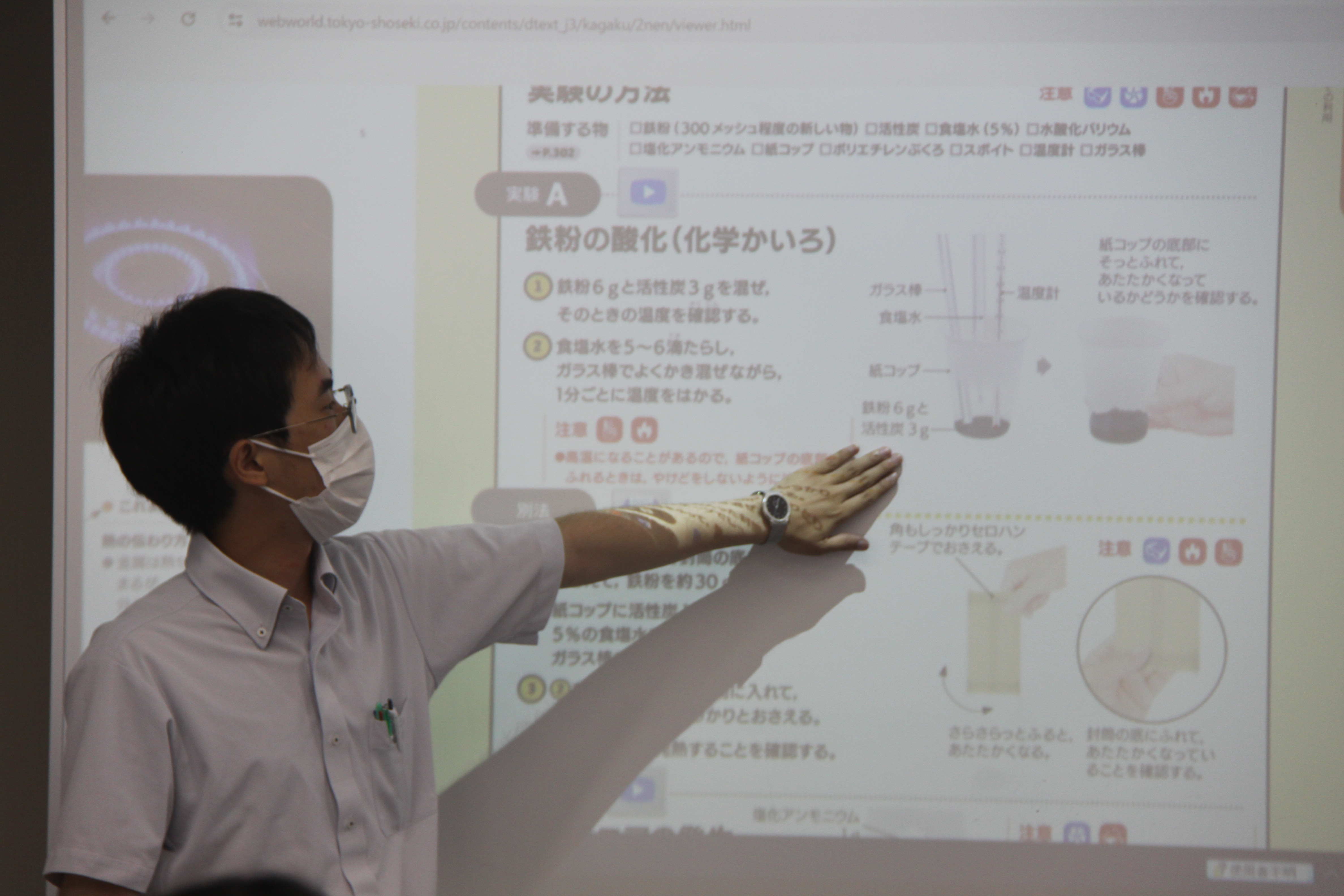

◎地域と共にある学校へ
~ひな中ほっとスペース開設へ(7/3~)

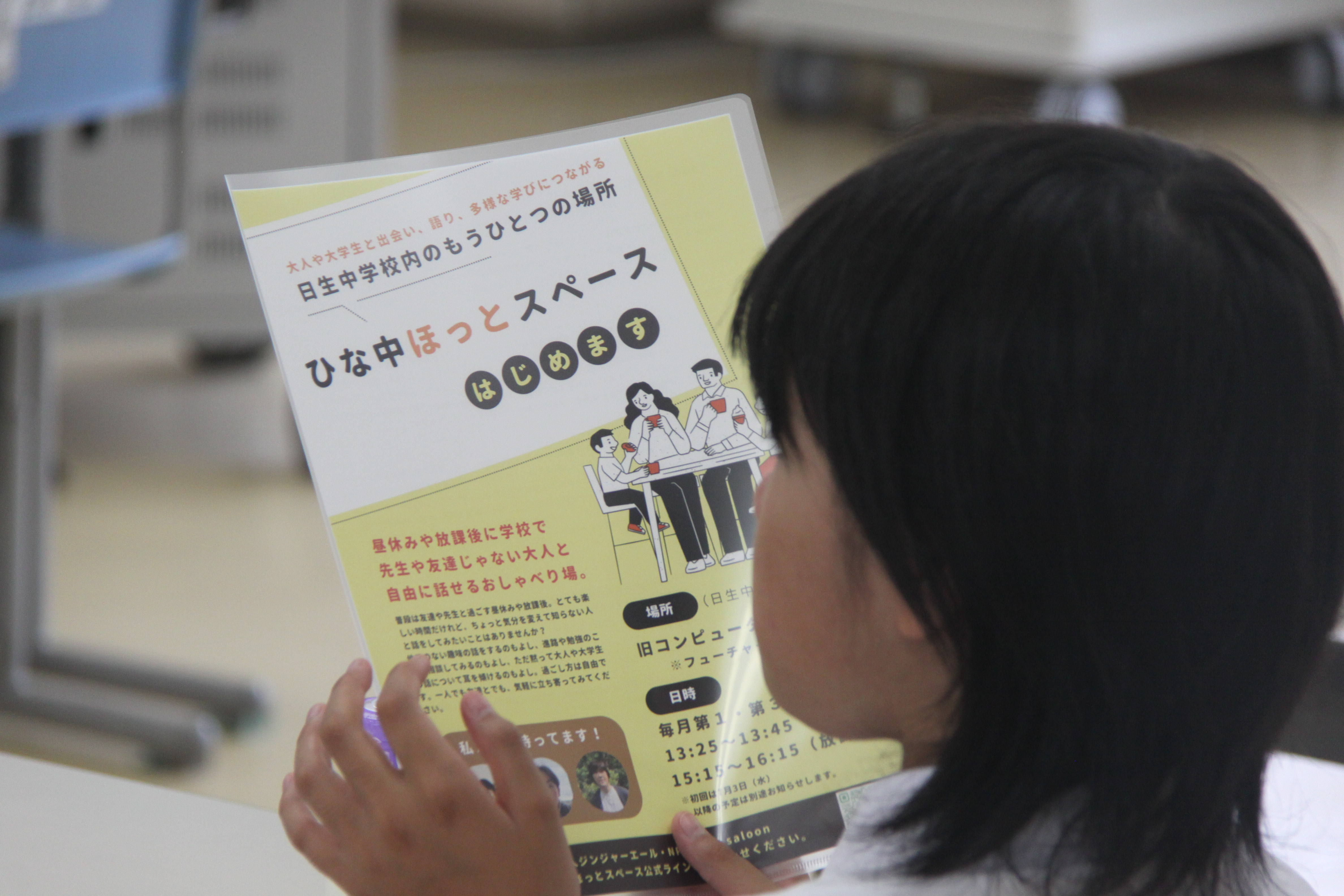


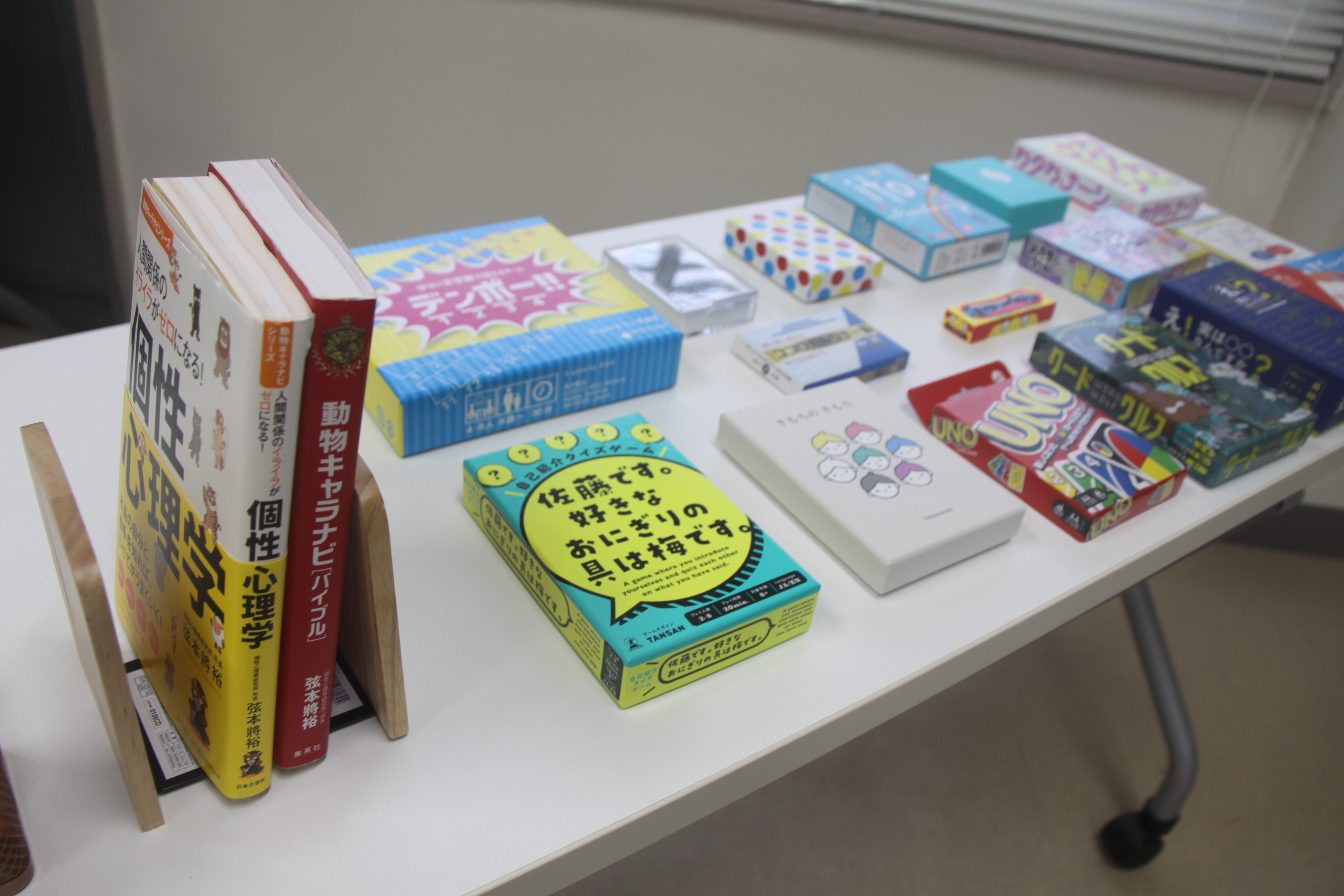

日生中学校保護者の皆様へ・生徒諸君へ(6/24)
【ひな中ほっとスペース開設について】
備前市内で地域の教育環境の充実を目的に活動している一般社団法人ジンジャーエールと、同じくNPO法人f.saloonと申します。この度本チラシの通り、日生中学校地域連携部と連携し、空き教室を活用して、「ひな中ほっとスペース」を開設させていただくこととなりました。以下その概要となりますので、ご理解いただき、多様な学びの場のひとつとして活用してくだされば幸いです。
概要
目的 ひな中ほっとスペースでは、学校の先生や保護者といった「タテの関係」でも、学校や部活動の友達といった「ヨコの関係」でもない、第三者による「ナナメの関係」の人と気楽に話せる場の提供を目的としています。ナナメの関係の人だからこそ話せること、得ることのできる情報や交流があると思いますし、そういった人との出会いが、例えば地域での課外活動やボランティア活動への関心など、新たな挑戦や進路、進学への意欲につながる刺激になるかもしれません。中学生は日々、忙しくてそのような機会にたどり着けない場合もありますので、日生中学校内のスペースと、お昼時間、放課後の時間を中心にこのような場を設けさせていただくこととなりました。
※1 学校の行事などの予定に合わせて変更になることもあります
※2 生徒と保護者、学校の了解の上で利用することができる時間帯もあります。
・まずは試行的な実施ですので、これから活動していく中で、開設日時などの変更があるかもしれません。その際は改めてご案内をさせていただきます。
〈一本の傘をひろげて降る雨をひとりしみじみ受けておりたり 山﨑方代〉

梅雨(つゆ、ばいう)は、北海道と小笠原諸島を除く日本、朝鮮半島南部、中国の南部から長江流域にかけての沿海部、および台湾など、東アジアの広範囲においてみられる特有の気象現象で、5月から7月にかけて来る曇りや雨の多い期間のことです。雨季の一種です。漢字表記「梅雨」の語源としては、この時期は梅の実が熟す頃であることからという説や、この時期は湿度が高くカビが生えやすいことから「黴雨(ばいう)」と呼ばれ、これが同じ音の「梅雨」に転じたという説、この時期は「毎」日のように雨が降るから「梅」という字が当てられたという説があります。普段の倍、雨が降るから「倍雨」というのはこじつけ(民間語源)でしょうね。このほかに「梅霖(ばいりん)」、旧暦で5月頃であることに由来する「五月雨(さみだれ)」、麦の実る頃であることに由来する「麦雨(ばくう)」などの別名もあります。
なお、「五月雨」の語が転じて、梅雨時の雨のように、物事が長くだらだらと続くことを「五月雨式」と言うようになりました。また梅雨の晴れ間のことを「五月晴れ(さつきばれ)」といいますが、この言葉は最近では「ごがつばれ」とも読んで新暦5月初旬のよく晴れた天候を指すことの方が多いです。気象庁では5月の晴れのことを「さつき晴れ」と呼び、梅雨時の晴れ間のことを「梅雨の合間の晴れ」と呼ぶように取り決めています。五月雨の降る頃の夜の闇のことを「五月闇(さつきやみ)」といいます。
地方名には「ながし」(鹿児島県奄美群島)、「なーみっさ」(喜界島での別名)があります。沖縄では、梅雨が小満から芒種にかけての時期に当たるので「小満芒種(スーマンボースー、しょうまんぼうしゅ)」や「芒種雨(ボースーアミ、ぼうしゅあめ)」という別名もあります。
中国では「梅雨(メイユー)」、「芒種雨」、韓国では「장마(チャンマ)」(「長い雨」の意味と推定される)という。中国では、古くは「梅雨」と同音の「霉雨」という字が当てられており、現在も用いられることがある。「霉」はカビのことであり、日本の「黴雨」と同じ意味ですね。中国では、梅が熟して黄色くなる時期の雨という意味の「黄梅雨(ファンメイユー)」もよく用いられます。
◎「真似(まね)び」、が「学び」となる(6/25)

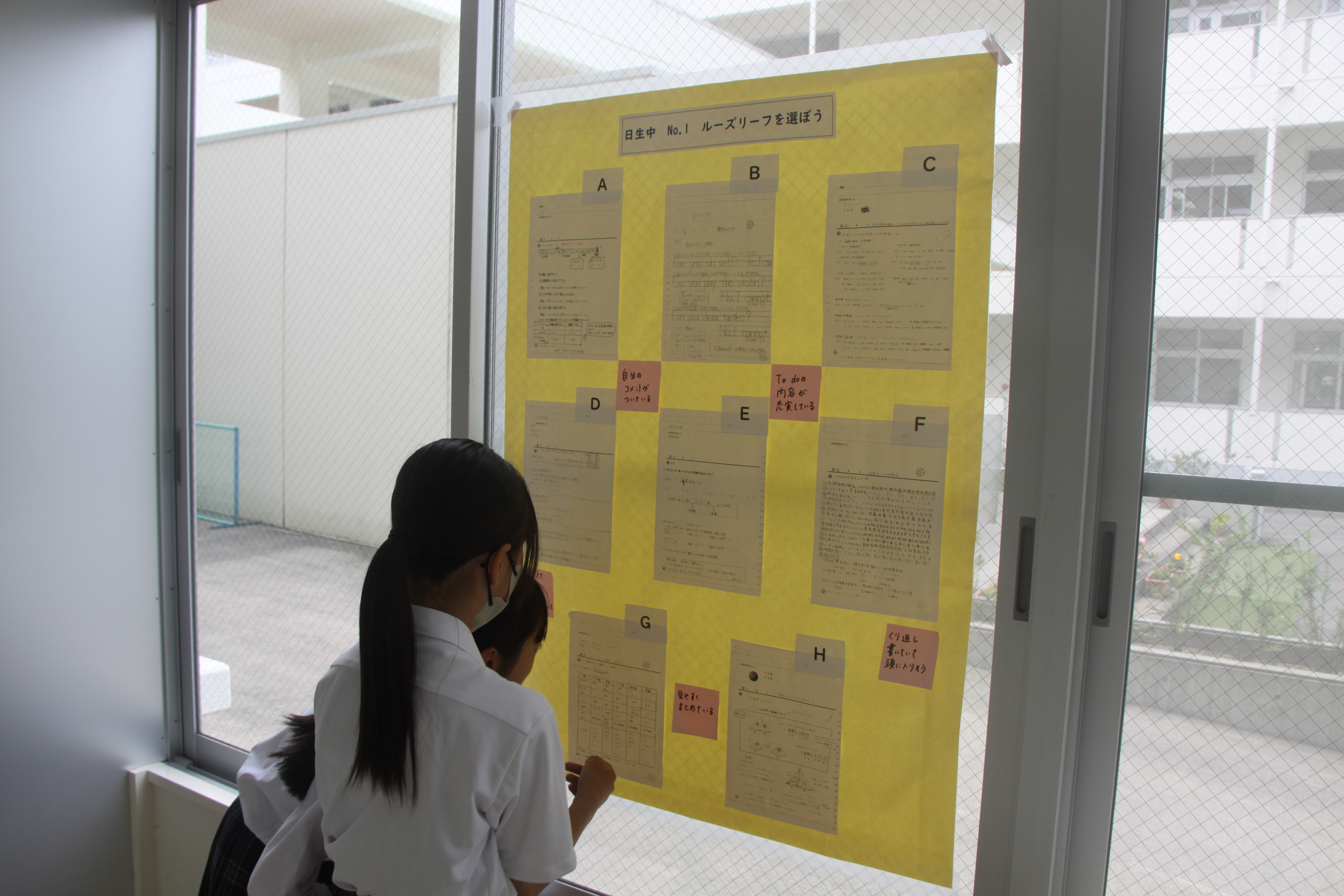
このルーズリーフはいいね!
〈今日は夏至孔子が足を投げ出して 坪内稔典〉(6/21)
今日は二十四節気の「夏至(げし)」。太陽が真南に来たときの位置が1年で最も高くなります。北半球では昼が最も長く、夜が最も短くなり、影の長さは1年で最も短くなる日です。
二十四節季は期間をあらわす場合もあります。その場合、今年の夏至は今日、6月21日から7月5日です。
夏至の時季について、「梅雨晴」というコトバについて少しだけ紹介します。「梅雨晴」には二つの意味があります。一つは「梅雨が明けたあとに晴れること」。もう一つは「梅雨の期間中に、一時的に晴れること」です。本来、梅雨晴は「梅雨が明けたあとに晴れること」の意味で使われていました。しかし、次第に「梅雨の期間中に、一時的に晴れること」という意味でも使われるようになりました。
もう一句、幕末の1867年に生まれ、俳句革新運動を導いた正岡子規の句があります。〈梅雨晴やところどころに蟻(あり)の道〉
子規はこの「梅雨晴」を「梅雨の期間中に、一時的に晴れること」の意味で使っています。「うっとうしい梅雨の時季だけれど、今は雨がやんで、晴れている。外に出てみると、ぬれた地面の上に蟻の行列がにできているよ」こうした心情を子規は五七五に詠んだのでしょう。

◎深く・一生懸命に・豊かな学びを(6月20日2時間目の風景)
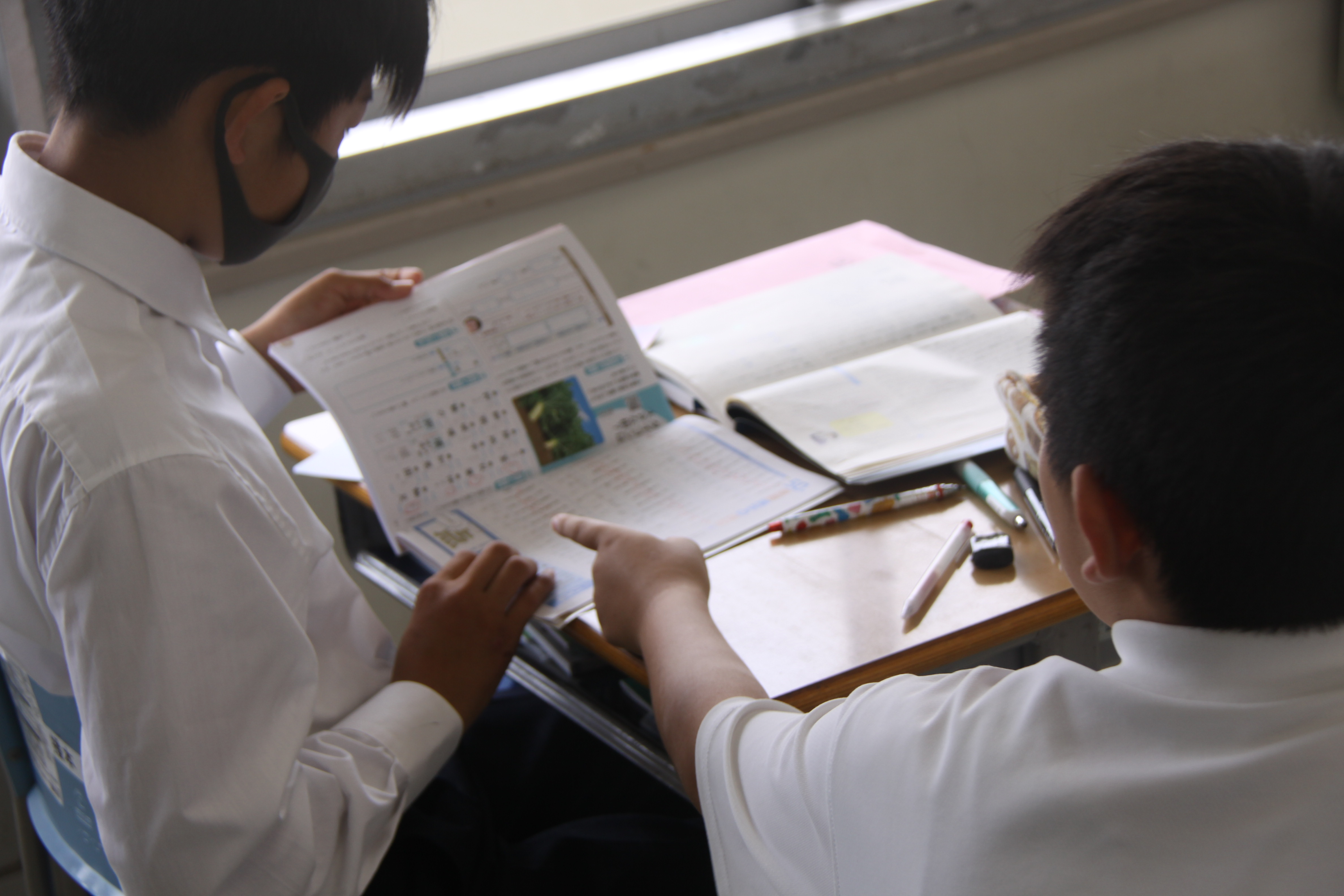
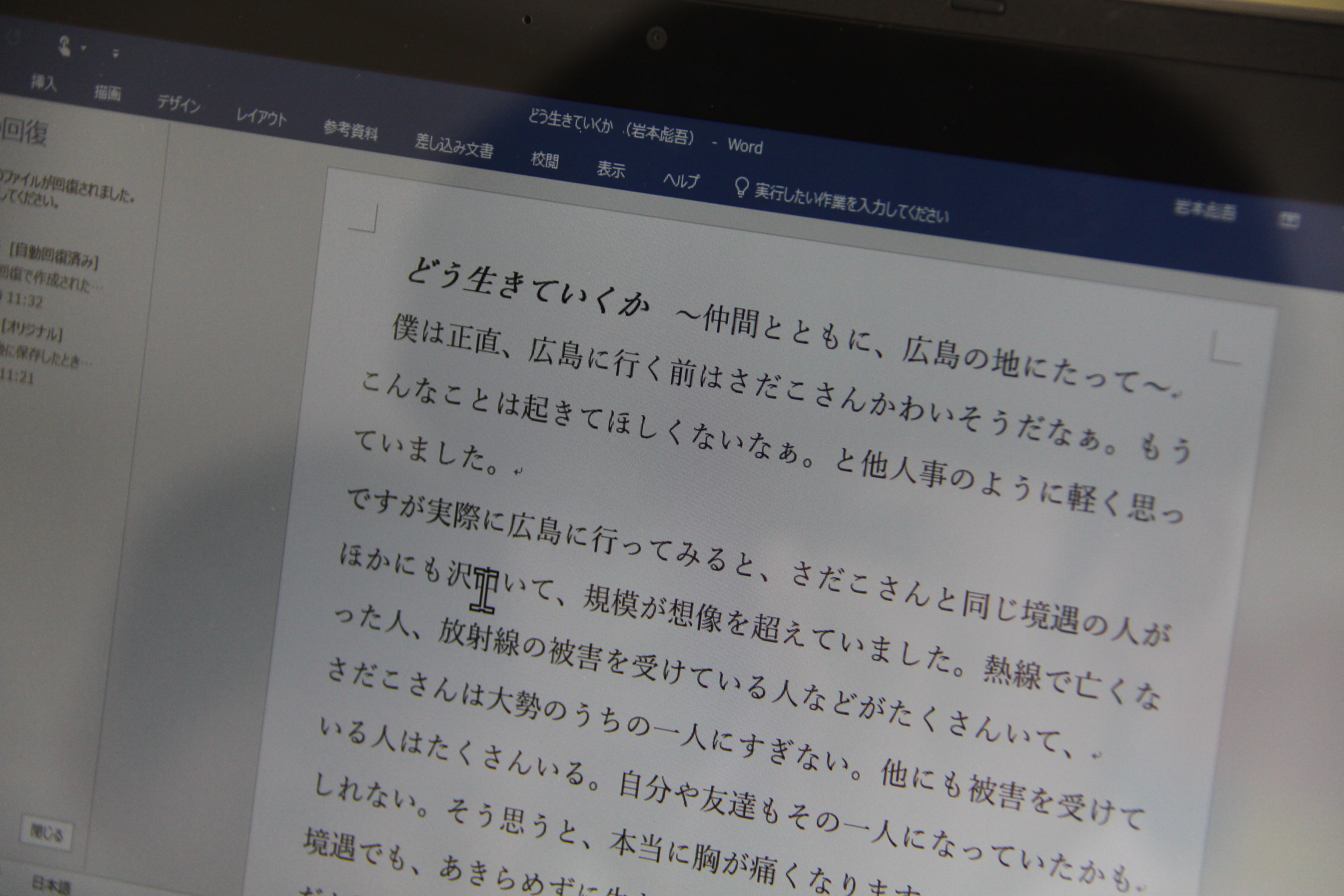
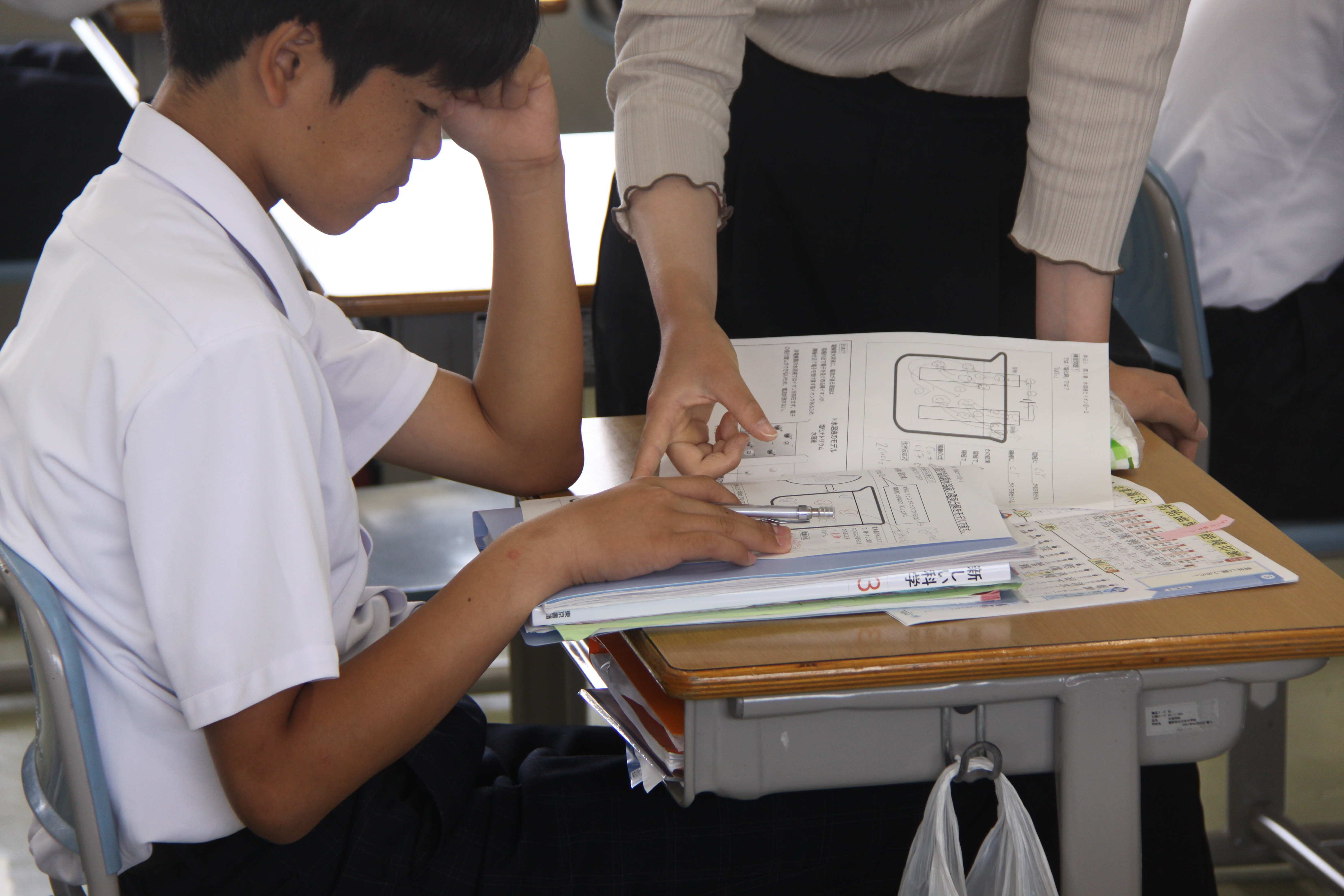

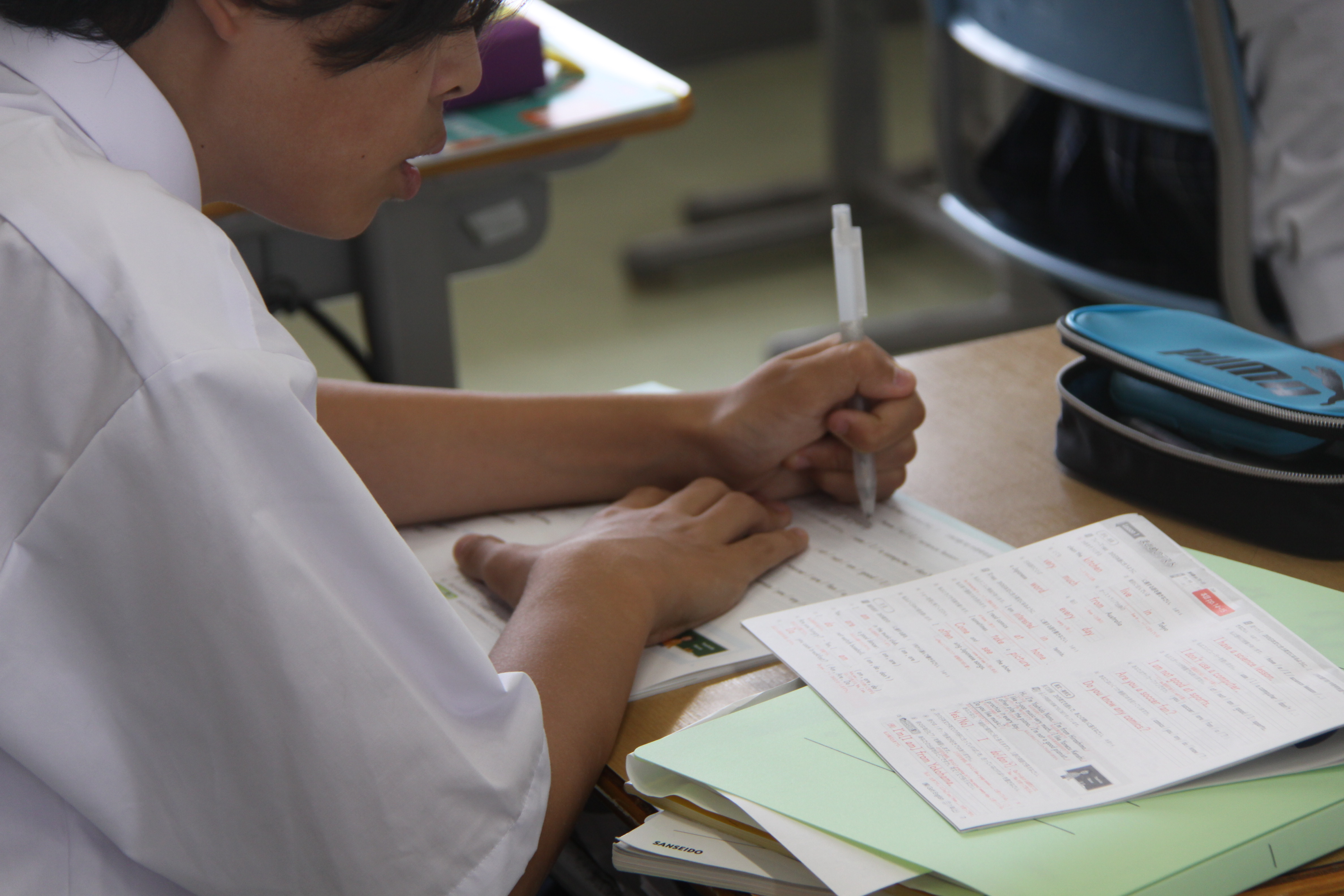

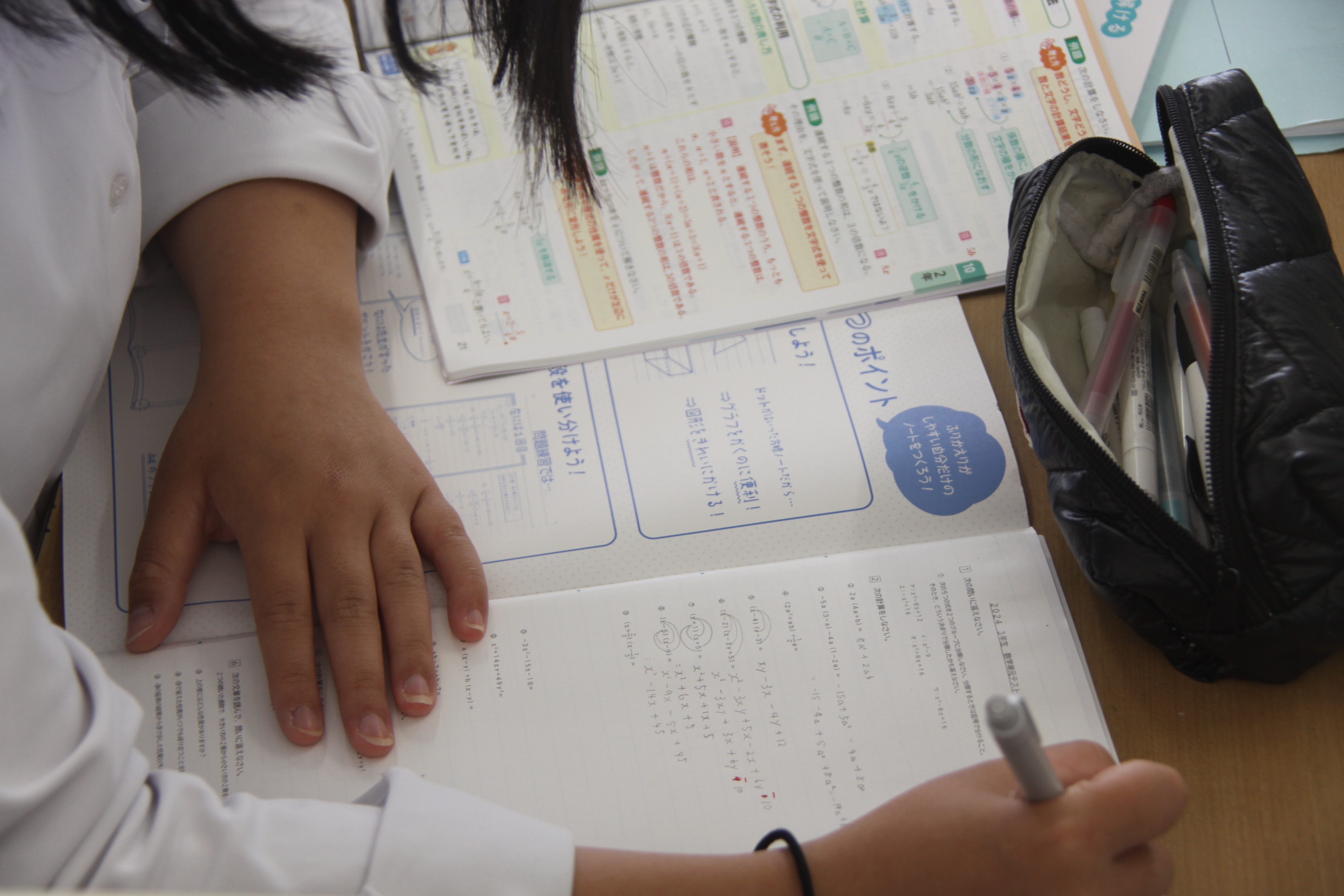
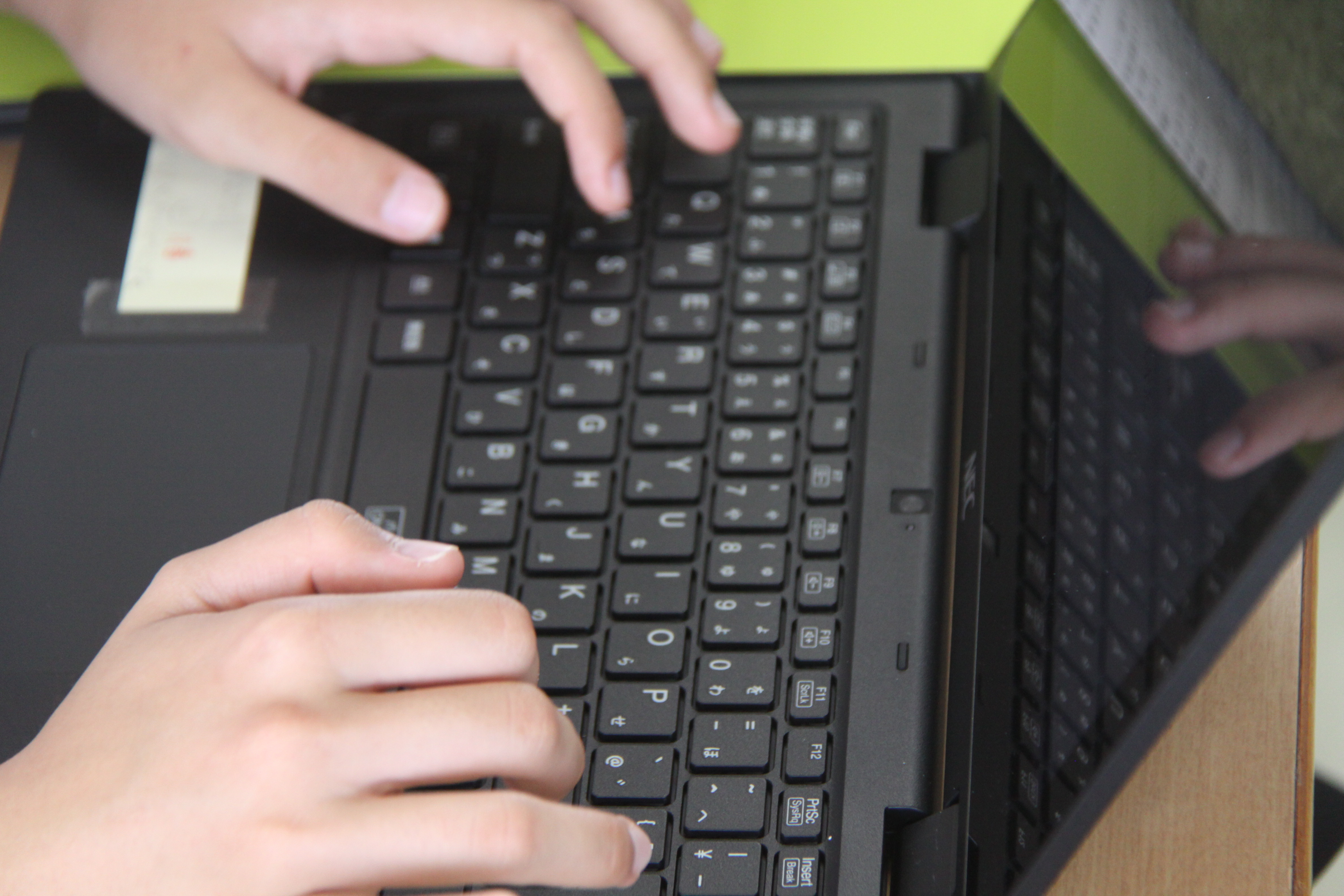
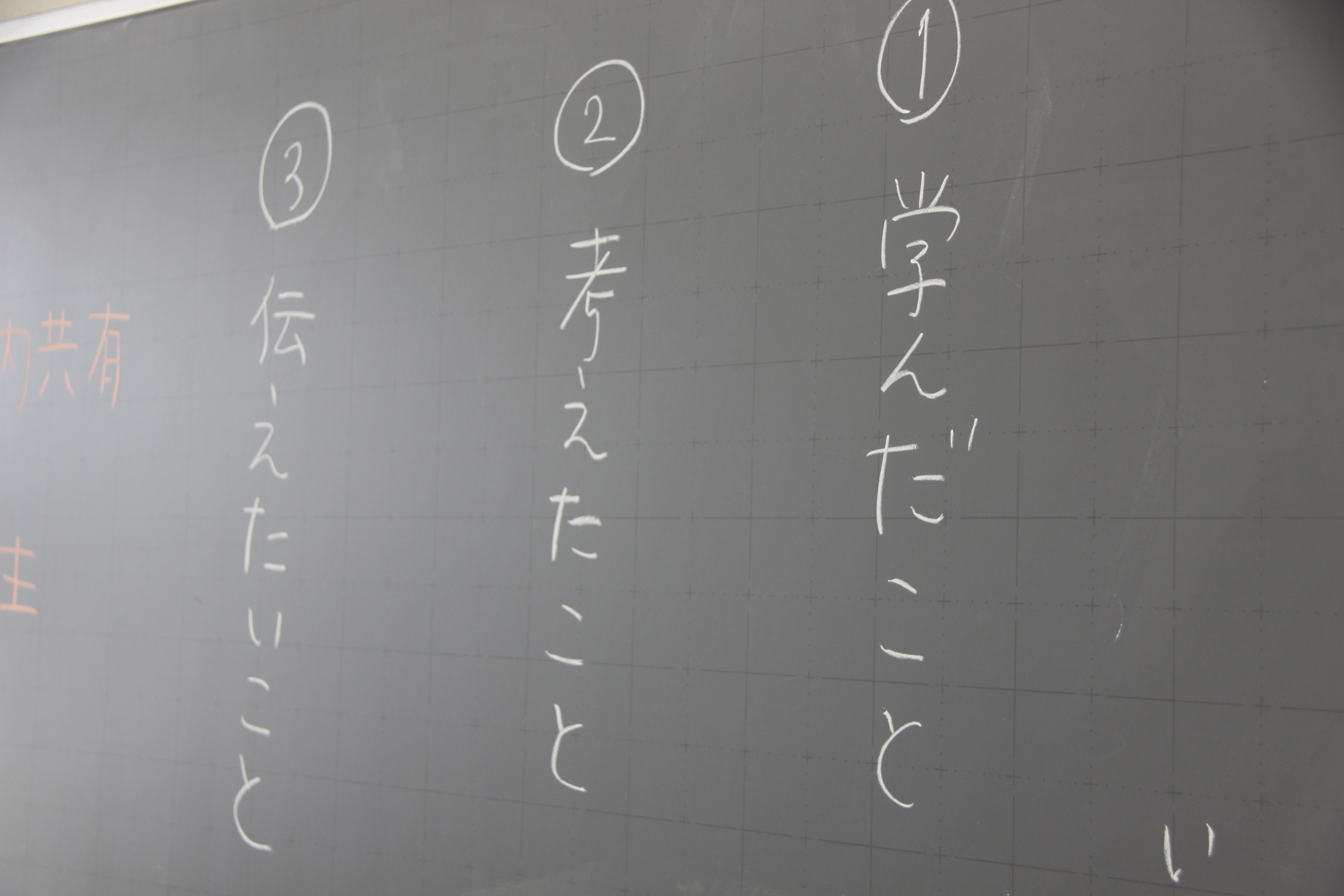
◎わたしたちの資源物回収(地区会より)
みんなでがんばろう!6/29(土)です!!


◎ひな中の風✨わたしたちの委員会活動

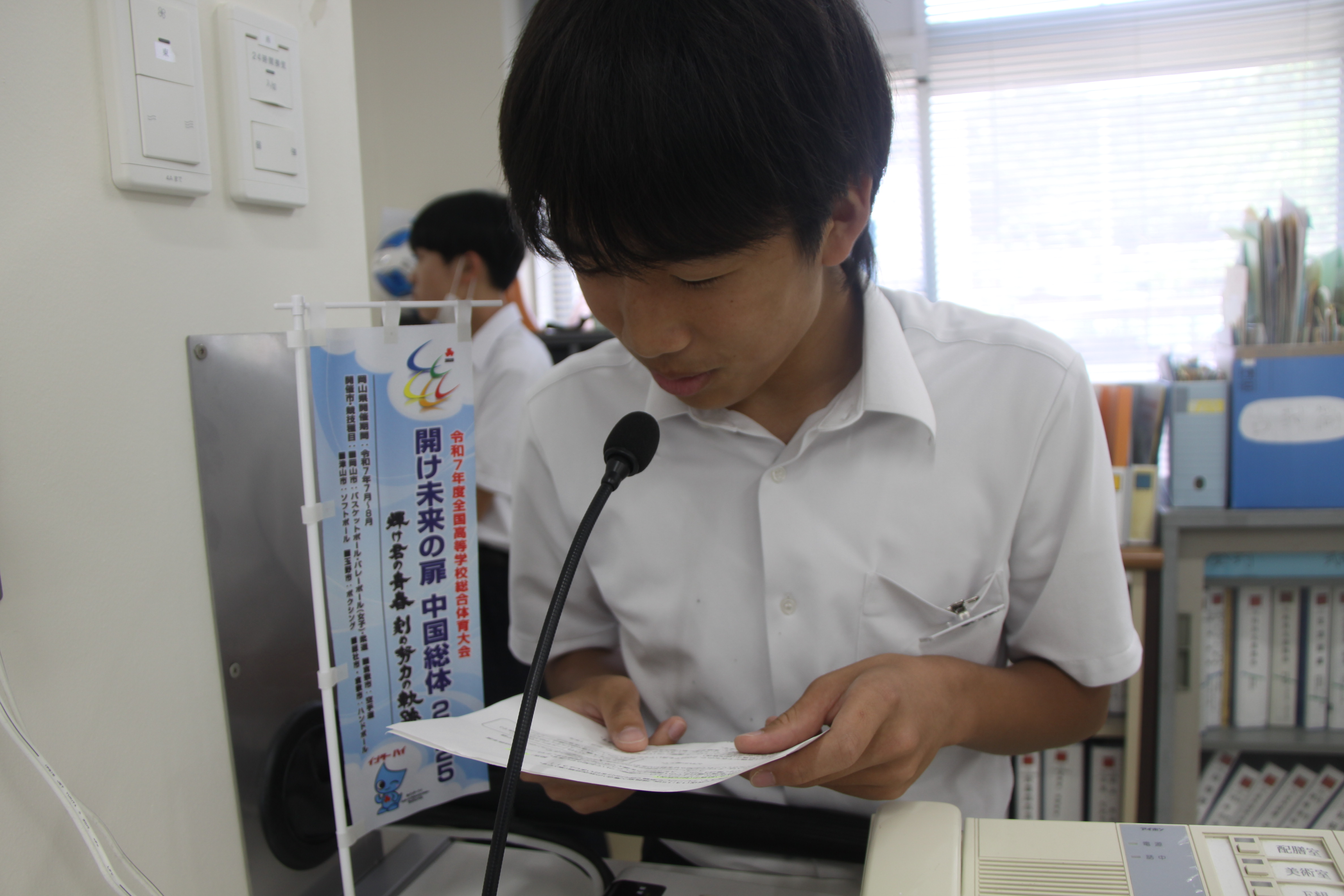

文化委員プレゼンツ。だじゃれ大賞の栄冠は誰じゃ(だじゃれ)?!
◎ひな中の風✨
〈夜の底にひかりをひとつひとつずつ預けて出でつ職員室を 染野太朗〉
第5回職員研修(6/19)は、安藤ICT支援員にサポートしていただき、GoogleClassroomの活用について勉強しましたよ。(夜の底ではなく、16時50分前には終えました。)


◎ひな中の風✨
~高め合う仲間として~
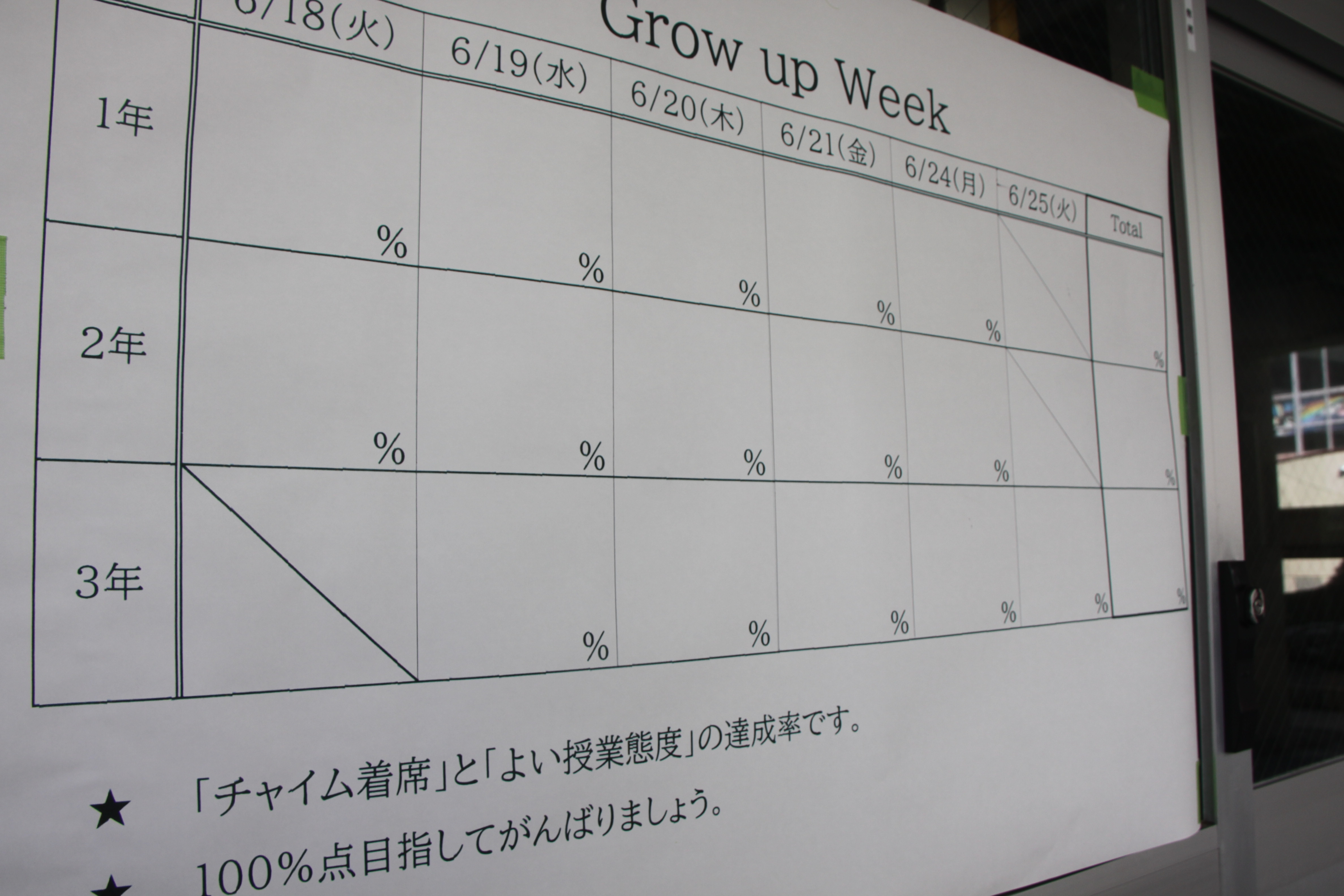
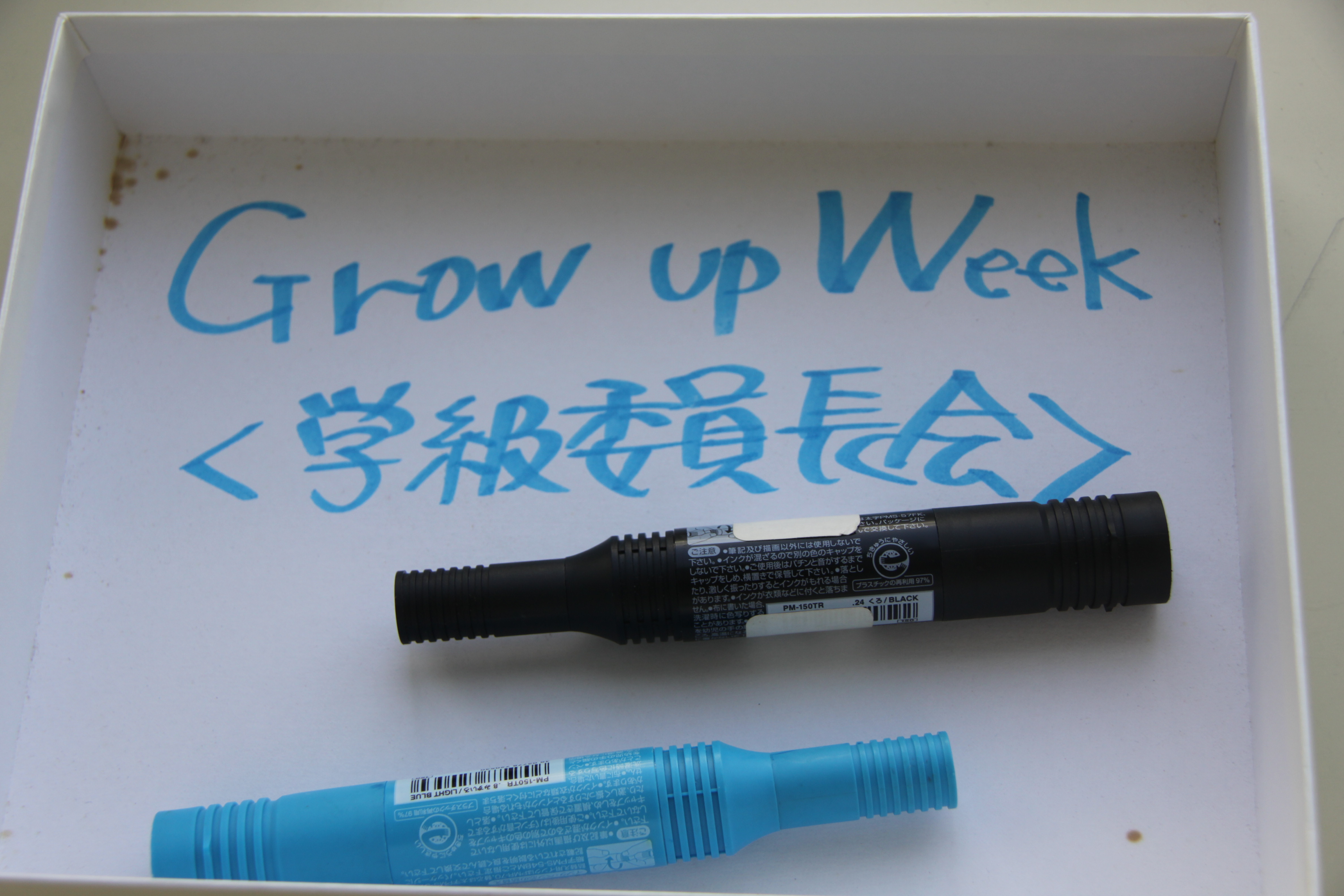
◎私たちのはじまりの風景14(6/19)
ここはどこでしょう?
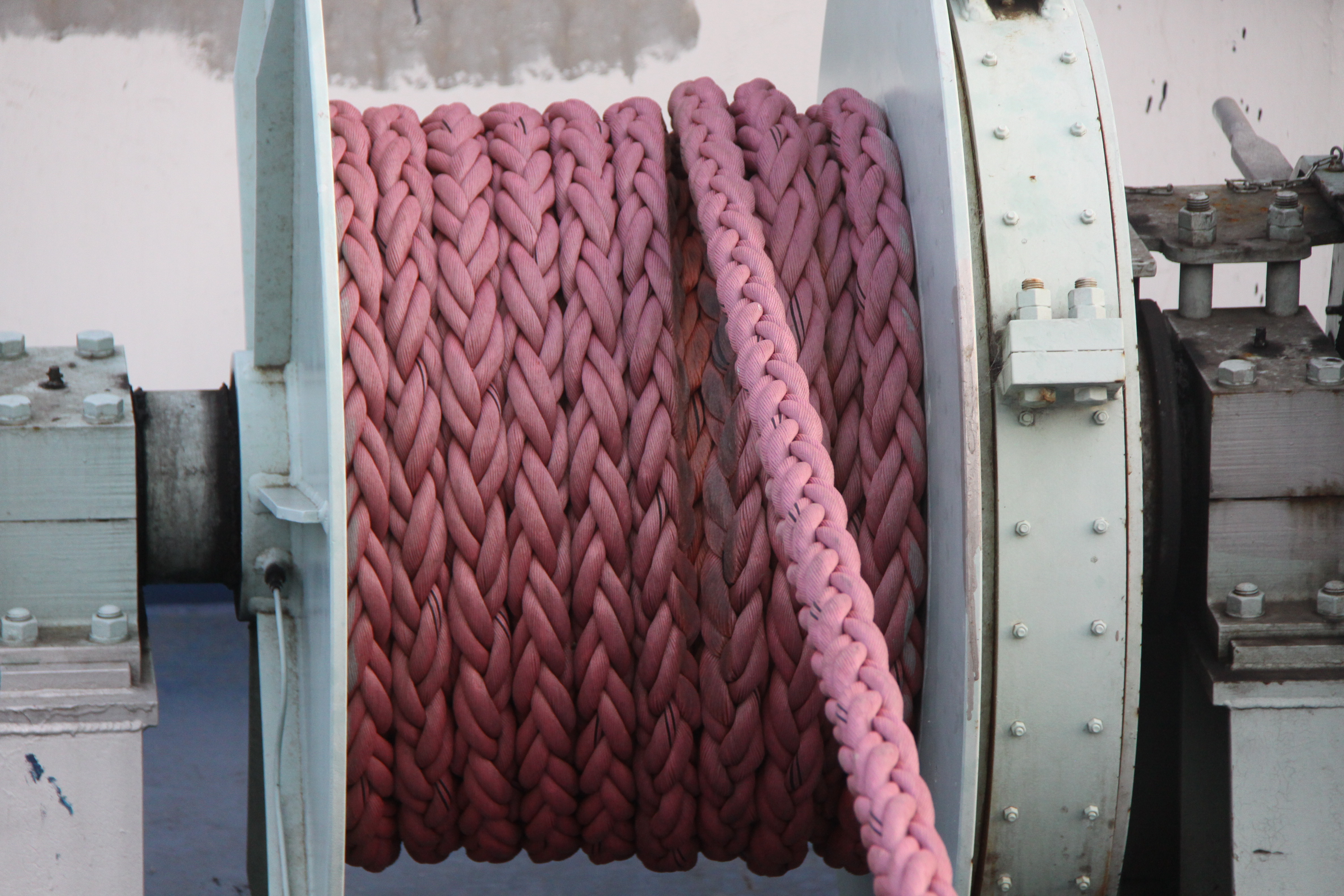








◎なりたい人は私のなかにいる(6/18)
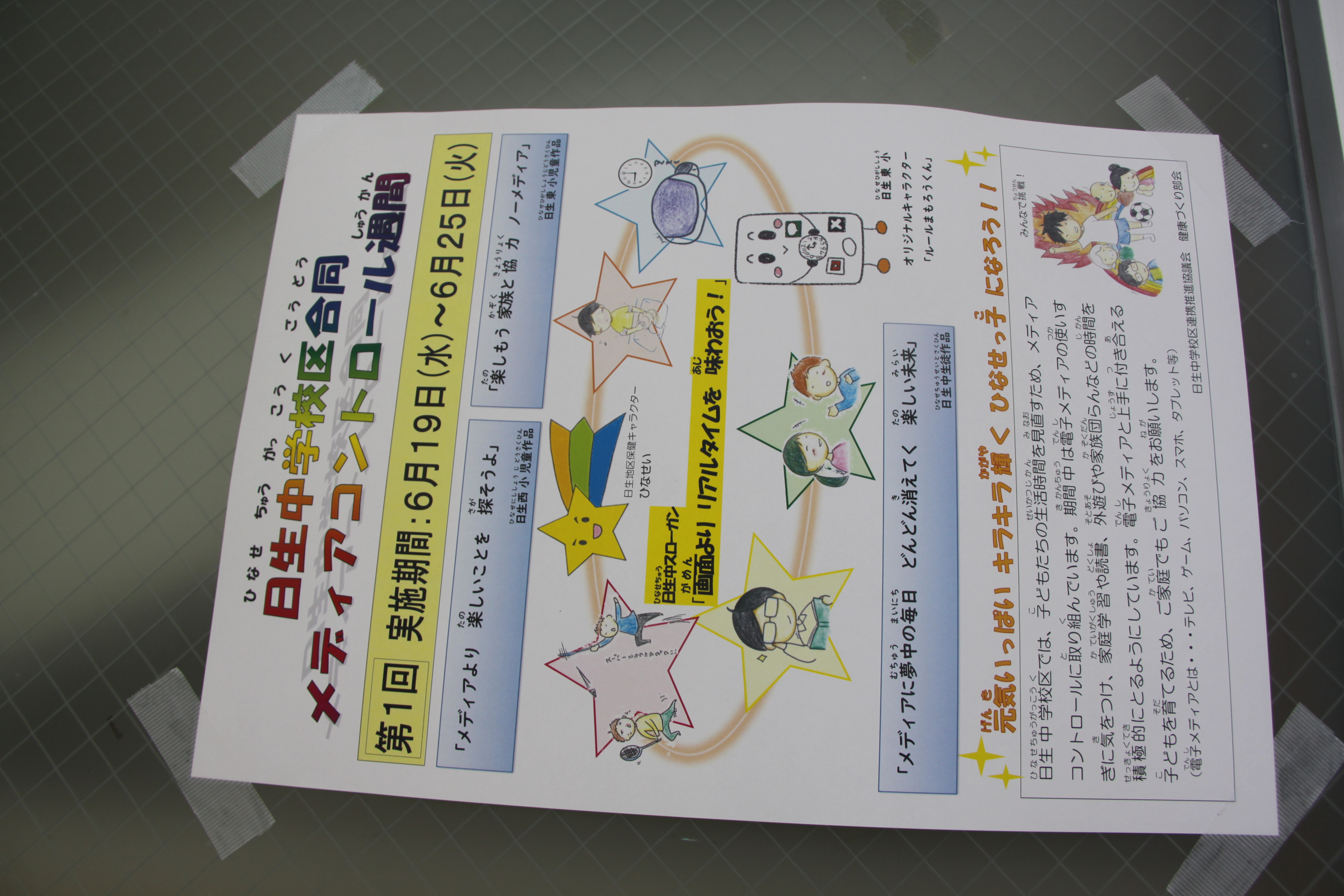
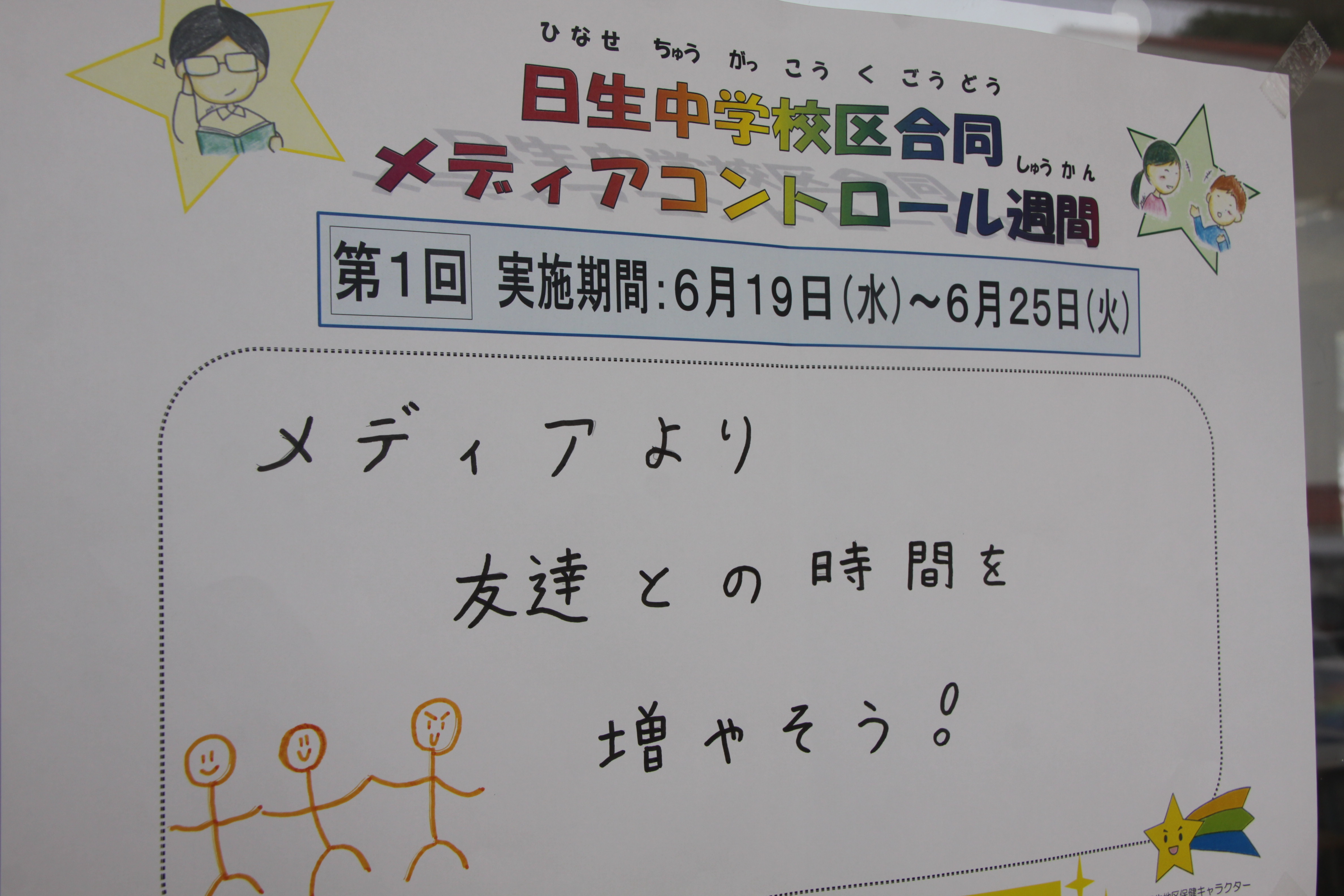
◎多くの人に支えられて(6/18)
有吉人権擁護委員さんが来校され、SOS人権ミニレター、人権作文募集のお知らせをしてくださいました。ありがとうございました。ミニレターは、もうしばらくして配布する予定です。
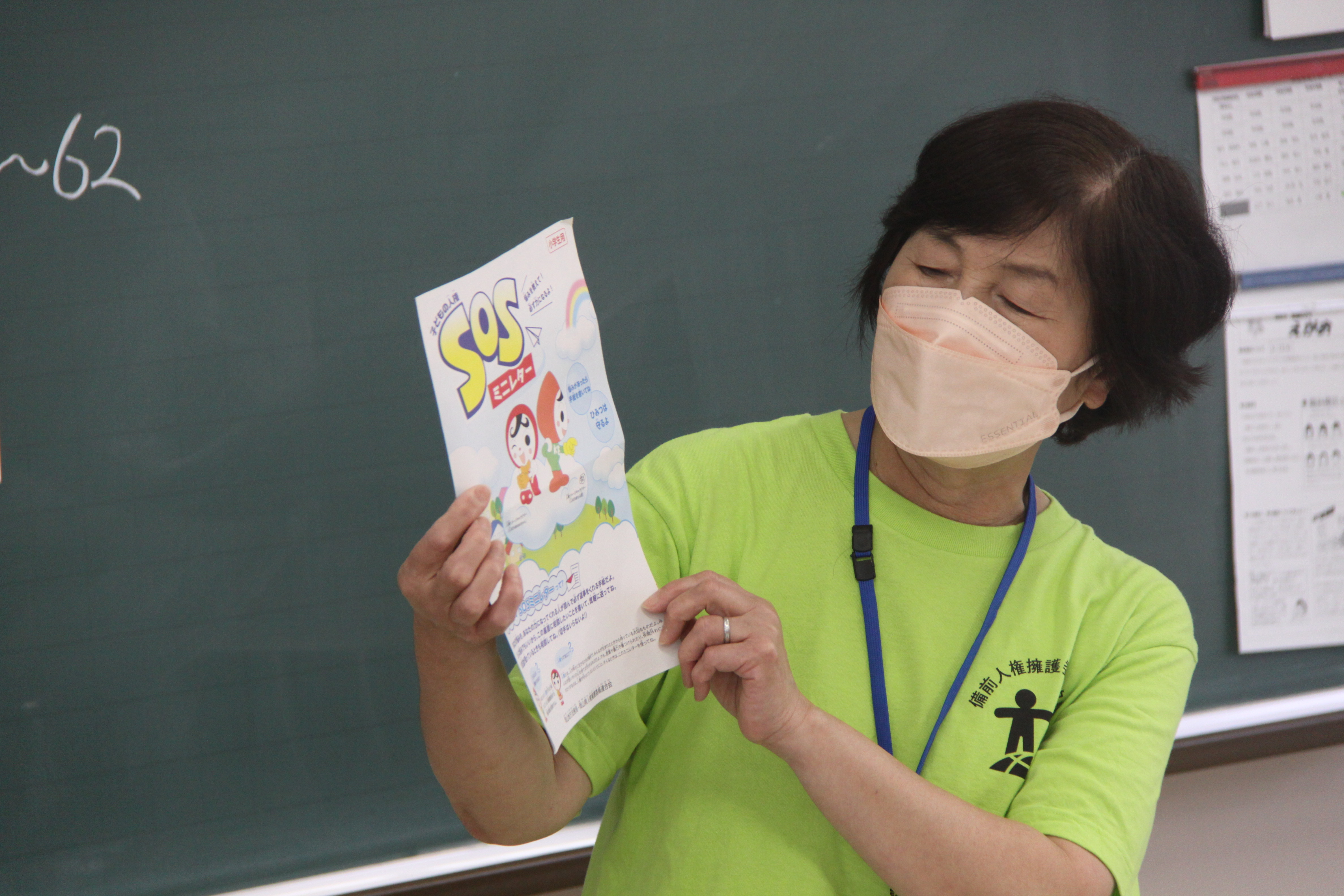
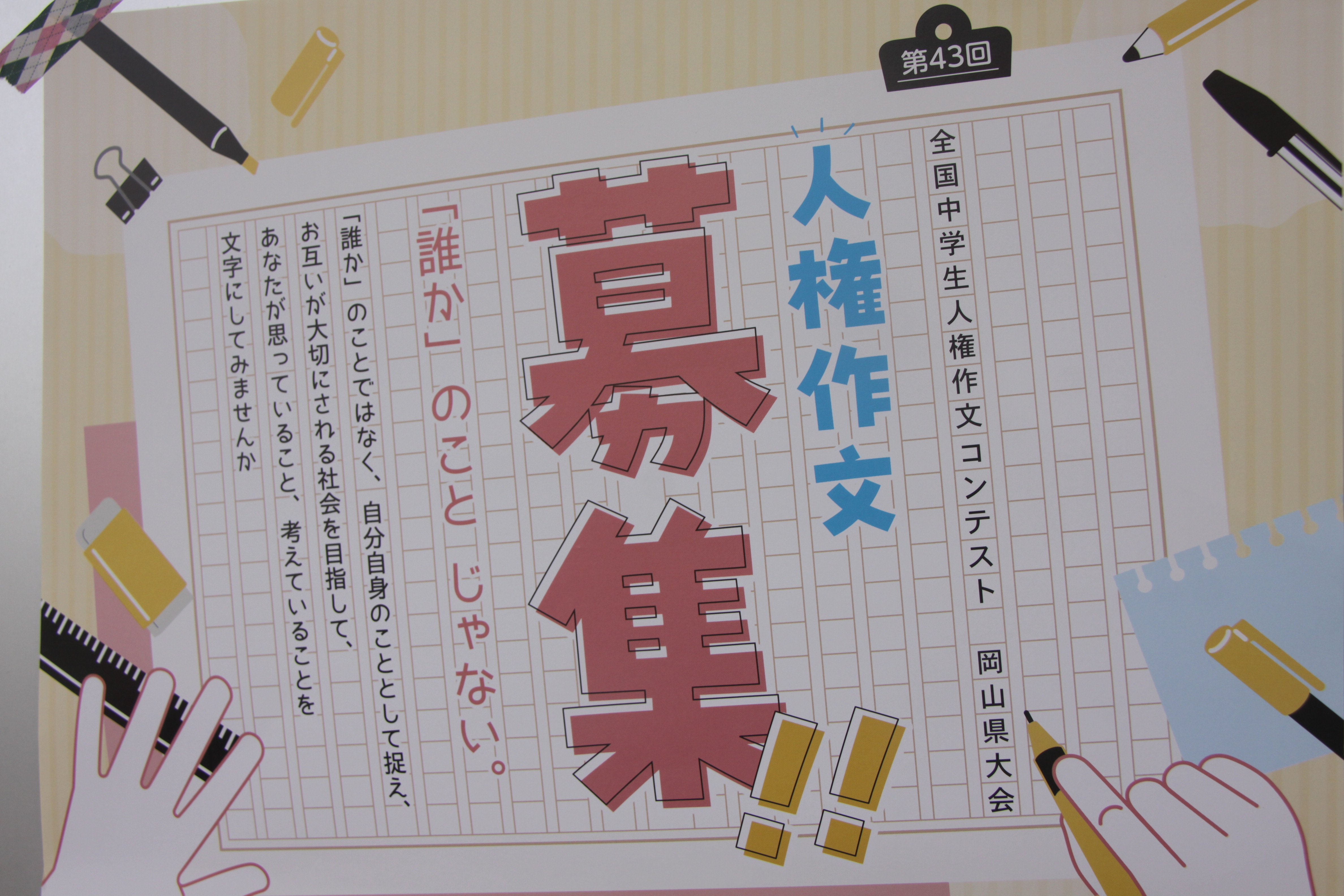
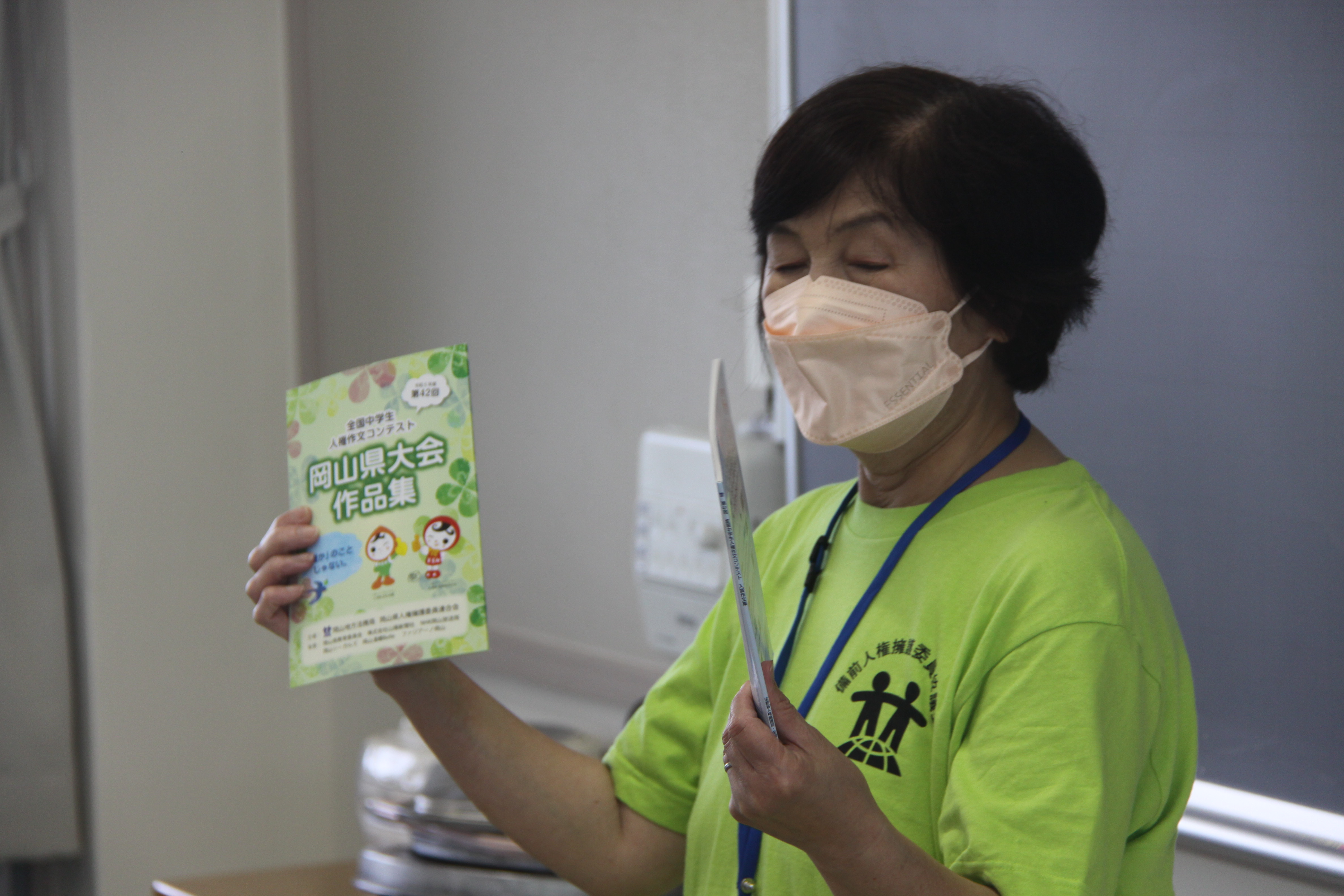
◎世界はだれかのしごとでできている(6/18)

◎ステキな大人になろう。大切な中学校生活を創ろう✨(6/18)
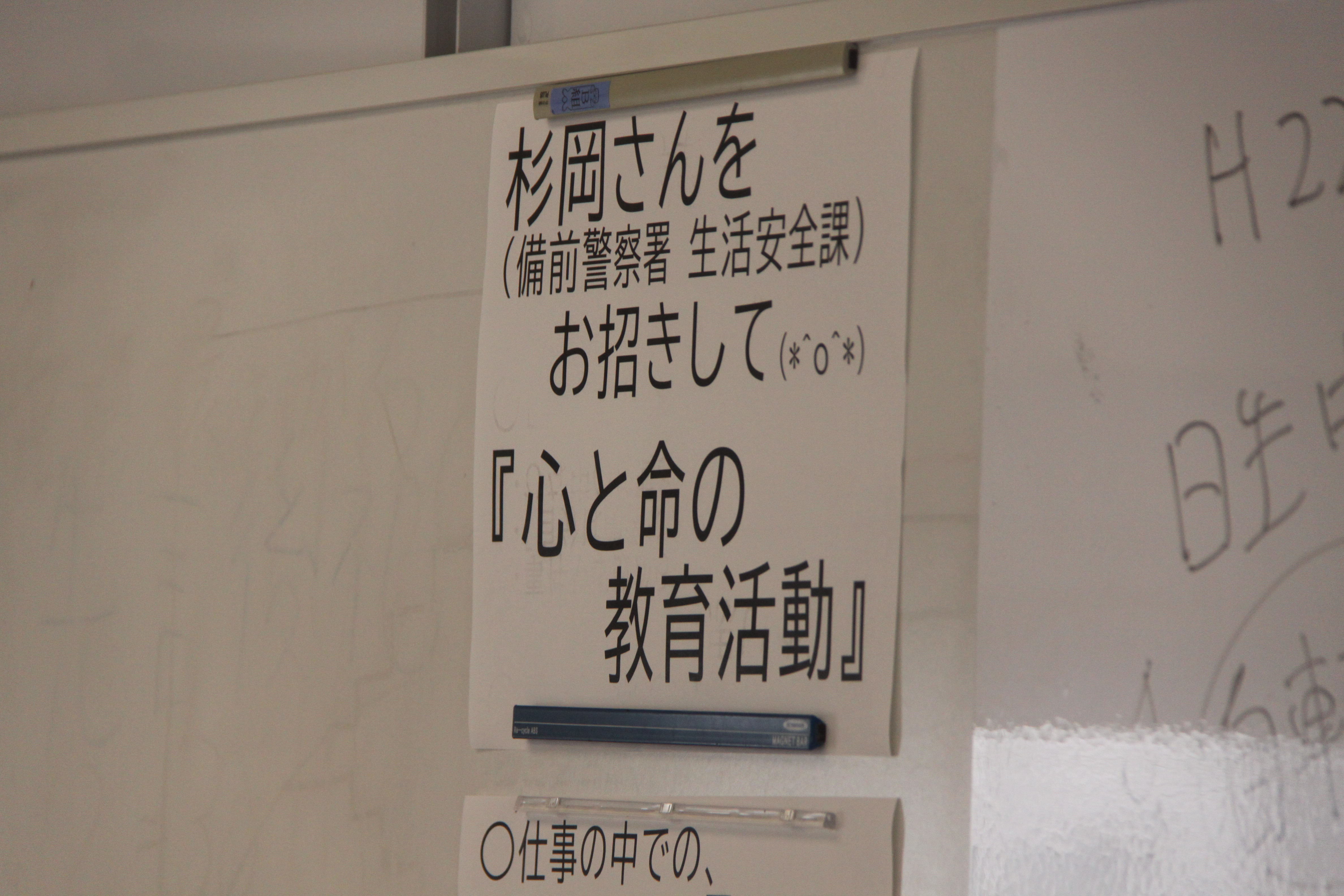


~「ふりかえり・メモ」の一部を紹介します~
○自分も、もしかしたら犯罪に巻き込まれてしまう可能性があるかもしれないと思った。気をつけて生活をしていかなければ!
○犯罪に誘われたら「断る」。法律を守る。
○自分には関係ないと思っていたけど、「これからのこともある」と思った。
○自転車の二人乗りの危険性もわかったけど、ヘルメットも大事なことを考えました。
○ものを壊したり、隠したり、無視するいじめは、犯罪につながることを学んだ。そして「死」につながる重大なことだと思った。
○友だちへの言葉遣いも気をつけたいと思った。
○私は刑事ドラマとかを昔から観ていて、「警察官になりたい」って思っていたから詳しい話を聴けて、警察官へのあこがれが強くなりました。
○日生や備前のまちを守ってくださって感謝したいです。
○困った時は、誰かを頼ることも大切だし、頼られるようにするのも大切だと思った。
○困ったら杉岡さんに相談します。
○ちゃんと、目標をもっておくのは大切。
○私は、SNSに名前を書かれたことがあって、とてもいやだったので、もしそんなことに出会ったら、周りのひとに「ダメだよ」と言っていきたい。
○中学生になったと思って、うかれずに、一つひとつのことに責任を持って行動したい。
◎ひな中の風✨
~自分らしく せいいっぱい(6/18)


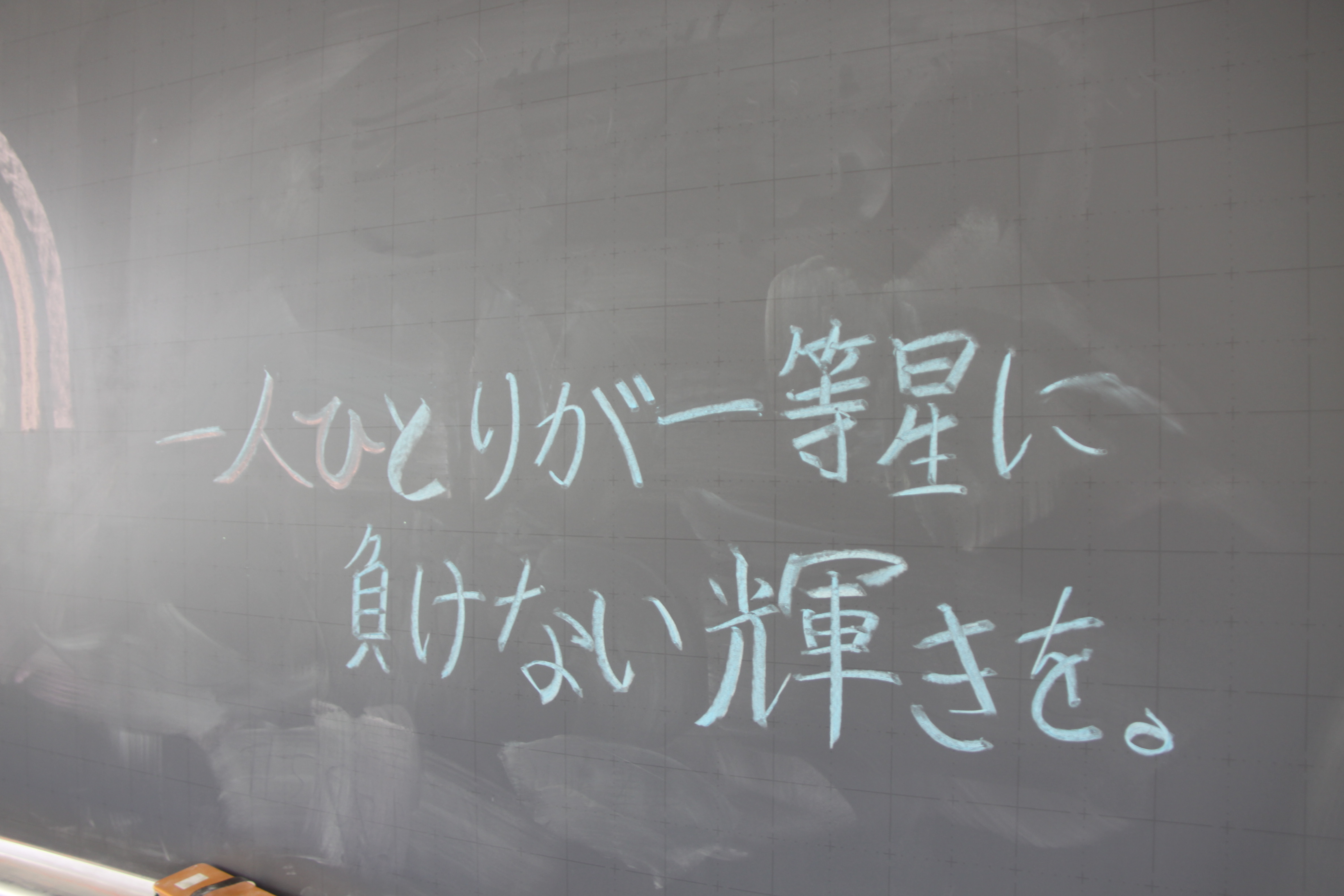
「がんばれ~(^_^)」
○20mシャトルランとは?
小学校の体力測定に用いられる運動テストの一つで、別名を往復持久走ともいいます。このテストは、20メートル間隔で引かれた2本の平行線の間を往復する持久走です。
参加者は、CDまたはテープから流れる電子音の合図にあわせて走りはじめ、音が鳴るごとに20メートル先の線に達し、足が線を越えるか触れたら向きを変えて戻ります。電子音の間隔が約1分ごとに短くなっていくのが特徴です。
20mシャトルランは、文部科学省が定める「新体力テスト」の実施種目の一つです。新体力テストは、平成11年度にスタートしたといわれています。このテストは、学校の体育授業や体力測定の場で広く実施されています。体力向上を目的として、さまざまな運動能力を測定するために設計されました。
◎ひな中の風✨私たちの学校(6/18)






◎あなたはどのコース?
ひなせい? 備前・日生大橋? かきおこ? 鹿&いのしし?(6/19~)
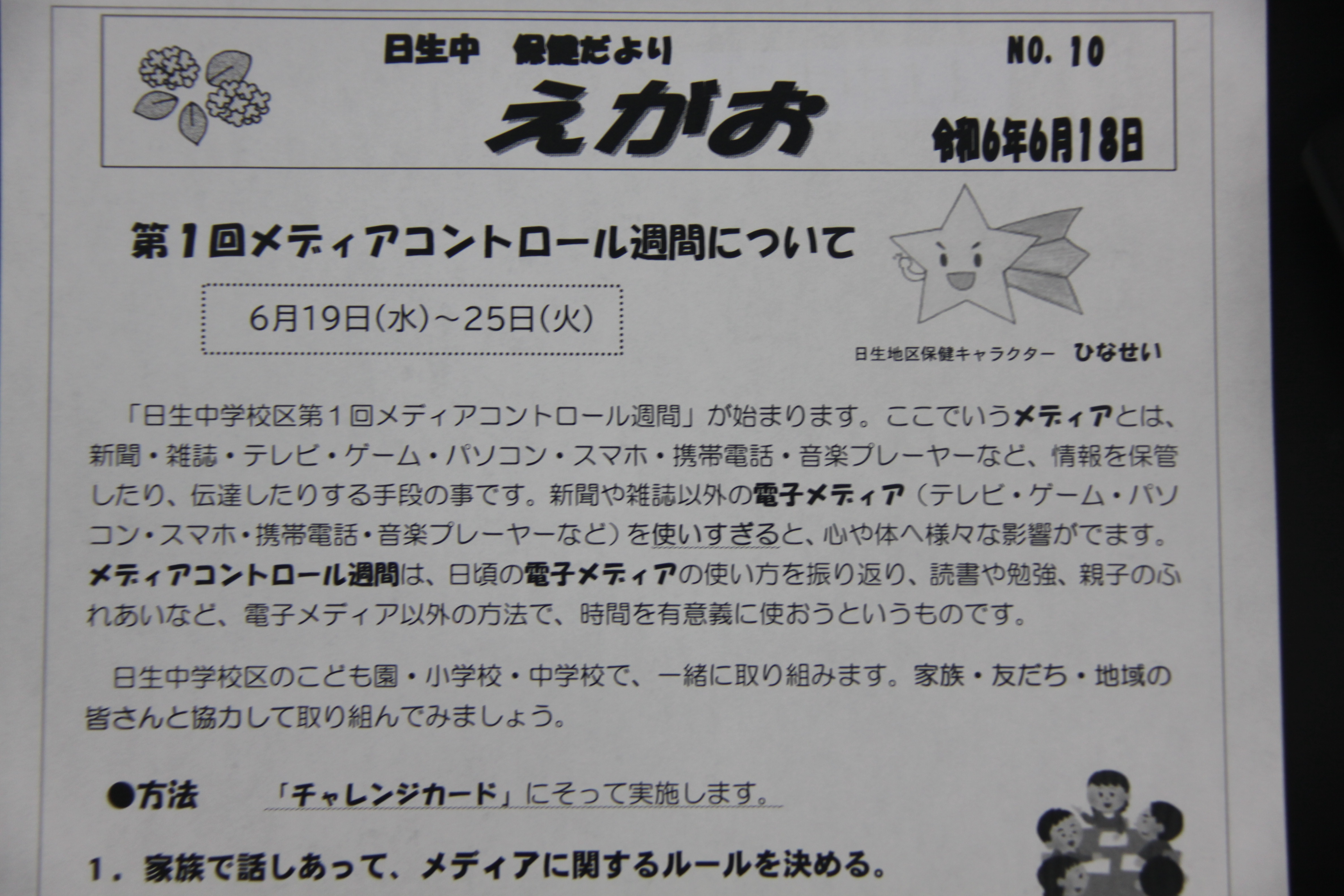
〈「ありがとうございました」後輩の声受け最後の部活動おえる〉

 6.14備前東地区総体
6.14備前東地区総体◎多くの人に支えられて(6/14)

今年の、ひな中チャレンジ企画(AR(拡張現実)クリエーター講座)の椙原さんが、日生駅前のSANシェアオフィスで、オープンアカデミーを開かれているところに寄らせていただきました。「オープンアカデミーは、第2.4金曜日(次回6/28)に継続的に開いています。気軽に寄ってみましょう。無料体験です」とのことです。
また、チャレンジ企画へは若干空きがまだありますので早急に申し込みましょう。
◎子どもたちの確かな進路保障へ
~春(15)いちごの会第2回実行委員会開催(6/14)

「令和6年度 春15(はるいちご)の会」~特別支援教育のニーズのある子どもの進路について(情報交流学習会)に本校の教頭先生も参加されました。実施概要を少しだけ紹介します。
1 目的
(1)特別支援教育のニーズのある生徒の進路・進学や就職についての最新の情報を、本人・保護者や教育関係者、支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。
(2)動画配信や情報交流学習会を通じて高等学校生活を紹介し、進路に関する情報が収集できる会にする。
(3)視聴者が実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。
2 実行委員会の方針
(1)持続可能な会の開催ができるように積極的に工夫・改善を進める。
①目的が達成できるように有機的なヒト・組織・コトの協力(後援)や助言を仰ぐ。
②特別支援教育の推進のために、また本会の開催案内が必要とされる多くの方々に届くように、様々な組織と連携を図り、ネットワークを拡げる。
3 具体的実施計画
(1)内容等
★動画配信
中学校卒業後の進路について、高校・関係機関の紹介動画を申込者に対して期間限定で、赤磐市ホームページにて配信する。
<期間>
令和6年8月9日(金)~9月11 日(水)予定
<内容>
・各校の作成動画には以下の内容を盛り込んでいただく。
①特別支援教育のニーズのある子どもの入学試験についての相談や受験時の配慮、サポート等
②学校生活の様子(支援の実際)
③卒業後の進路や就職の状況
④相談窓口担当者 ・各校10分程度の動画とする。
★参集方式(200人程度)
<内容>
・座談会
・特設相談会(相談ブース)、学校説明(希望の学校)
<日時>
令和6年8月31日(土)10:30~13:30
<場所>
備前市市民センター(備前市西片上17-2)
(2)参加対象 小・中学校生徒 保護者 教職員 特別支援教育に関わる方 支援者
(3)主 催: 春15(はるいちご)の会実行委員会 ※備前県民局委託事業
共 催 :赤磐市・備前市・和気町・瀬戸内市・赤磐市障害者自立支援協議会そだつ部会
(4)後 援 岡山県教育委員会・赤磐市教育委員会・瀬戸内市教育委員会・備前市教育委員会・和気町教育委員会・NPO 法人岡山県自閉症児を育てる会・瀬戸内市自立支援協議会・東備地域自立支援協議会・岡山県教職員組合・備前市 PTA 連合会(申請予定)
◎進路を切り拓くちからをつけるために(6/14)
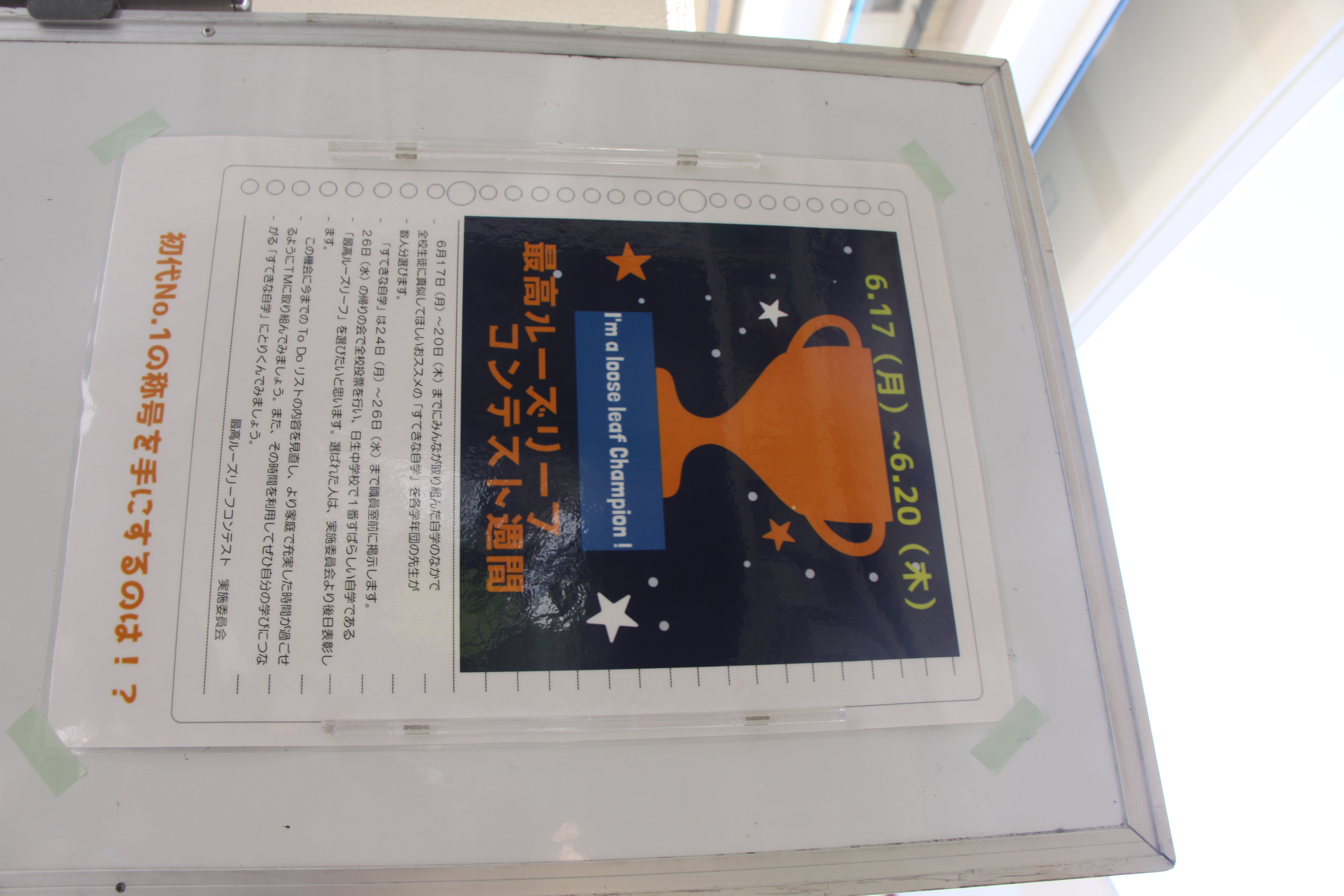
◎私たちのはじまりの風景(6/14 )
モートン先生から、育てられた藤の花の苗をいただきました。生徒がくつろいで語り合うことの出来る木陰(藤棚)となれば幸いです。THANK YOU!

◎多くの人に支えられて(6/13)
今年度も、学校薬剤師さんに来校していただきの照度検査、音・二酸化炭素濃度等の調査及び指導をしていただきました。ありがとうございます。
学校薬剤師さんは、学校環境衛生の維持・改善を目的として、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに委任委嘱されています。薬剤師が「薬学」を中心とした「専門的な知識」を発揮させ、法律に基づき活動します。照度検査は、目の疲労を抑制し、学習能率の低下を防ぐために行います。

人は五感により多くの情報を収集しており、視覚による情報収集は87%と非常に高いのです。児童生徒は授業中に、黒板を見たり、机の上のノートを見たりすることを繰り返しています。よって、「適切な明るさ」の確保と、「まぶしさのない」状態の維持は非常に大切です。( 照度:物にあたる光
の強さ 輝度:物の面から目の方向へ反射する光の強さ)
「適切な明るさ」の確保・・・照度の検査は、黒板9か所、机上9か所を「デジタル照度計」を用いて測定します。照度測定時、照度計は黒板面、机上面、コンピューター画面、TV面に背面をつけて測定します。測定場所は、教室、黒板、テレビ・ディスプレー画面、コンピュータ室、体育館、校庭、オープンスペース、廊下などです。
。
◎おはよう。お早う。オハヨウ。(6/13:生徒会スマイルあいさつ運動日)



◎教えること・学ぶこと・育つこと。(6/12:木下実習生研究授業)
ロールプレイを活用した、保健体育の授業に取り組みました。



◎元気な生活のために(6/12:眼科検診)
今日の眼科検診で、新年度予定していたすべての健康診断がおわりました。この後、保健だよりでの結果報告や個人への治療指示等を保護者の方にお渡しします。子どもたちが元気な青春時代を送れるますよう、ご支援、受診・治療等をよろしくお願いします。
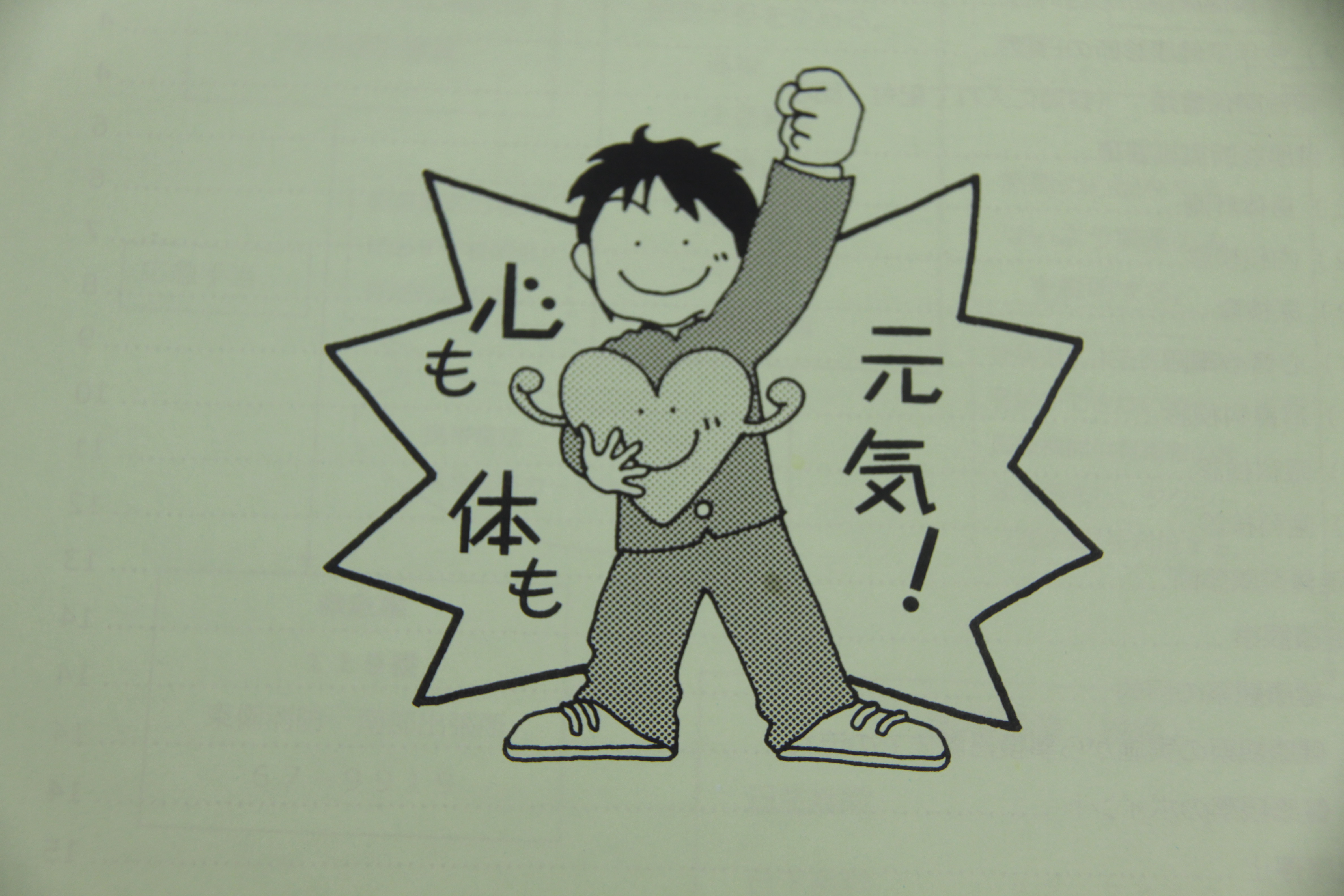
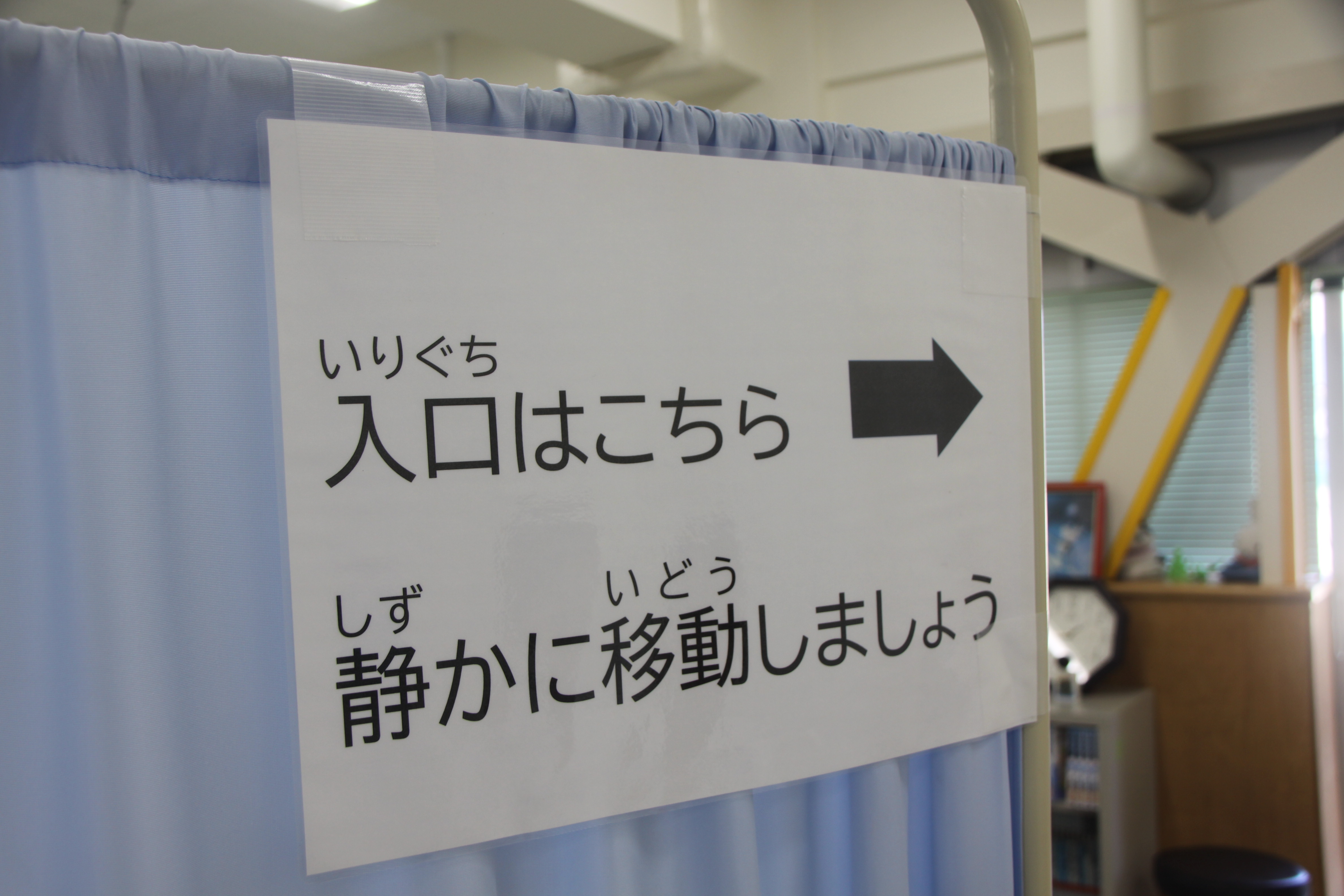

◎日生で輝く 日生が輝く
私が輝く地域ボラ推進プロジェクト始動(6/12)
ボランティア依頼NO1が届きましたので掲示しています。〈ひなせかきカキフェス(7/7)〉大募集
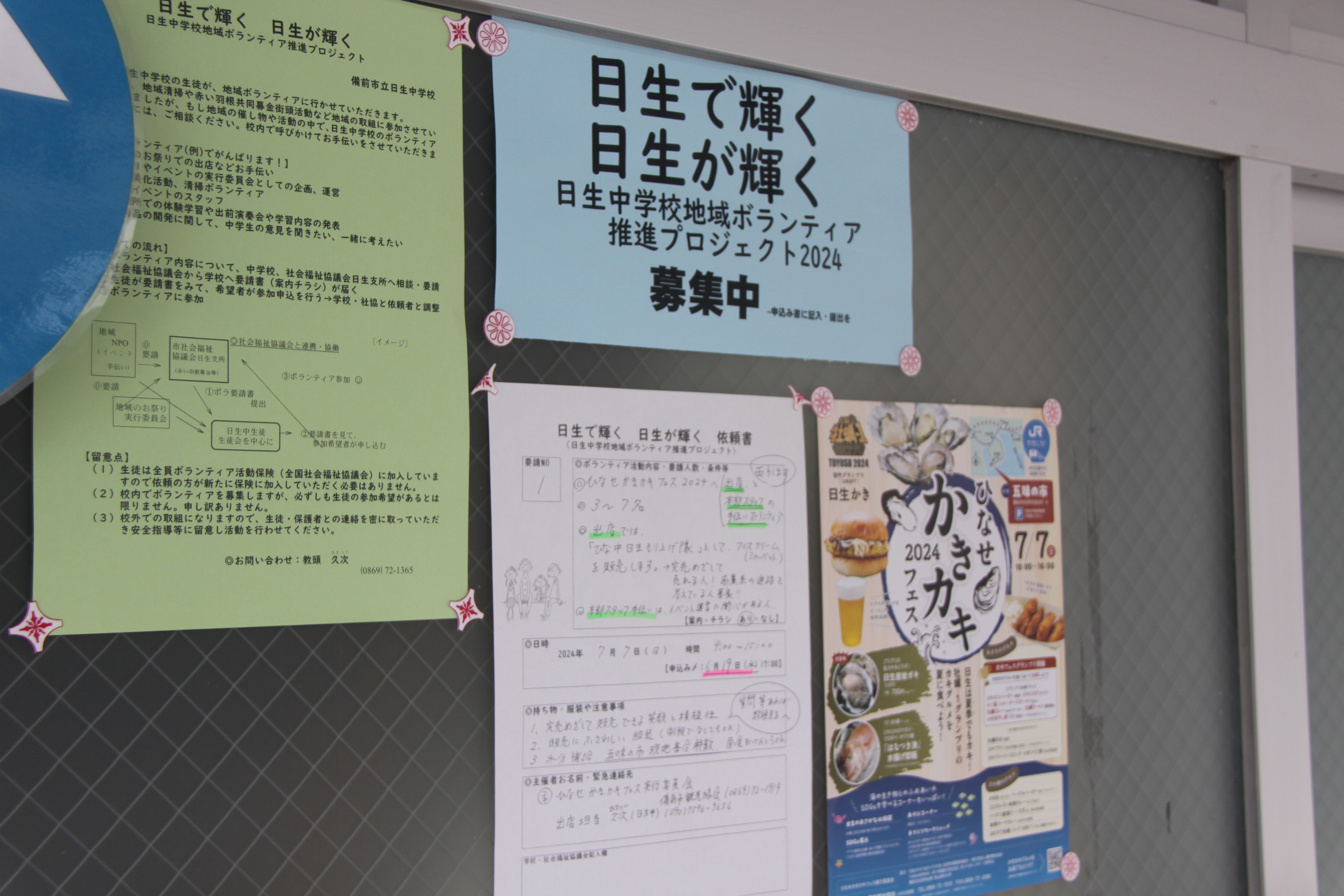
◎起こせ 沸かせ 轟け 動かせ 自分たち らしく精一杯。(6/11)
~15・16日備前東地区総合体育大会 6月16日岡山県吹奏楽祭出演~

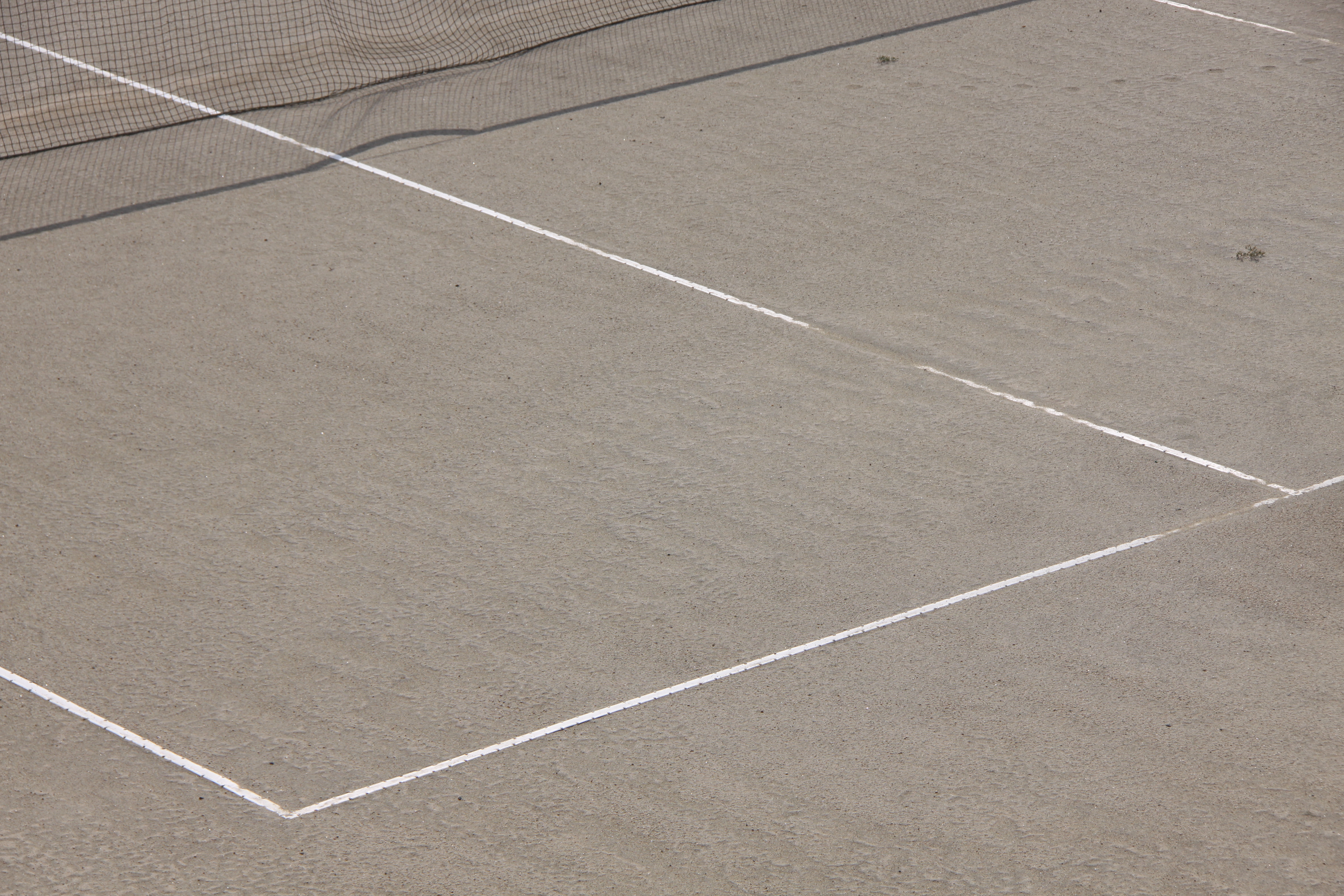

〈何度でも夏は眩しい僕たちのすべてが書き出しの一行目 近江俊〉(6/10)
社会福祉協議会日生支所から加藤さん、鈴木さん、嶋村さんが来校され、「夏ボラ」についての事前説明会を行いました。今年もたくさんのひな中生徒が、地域での活動に汗を流します。
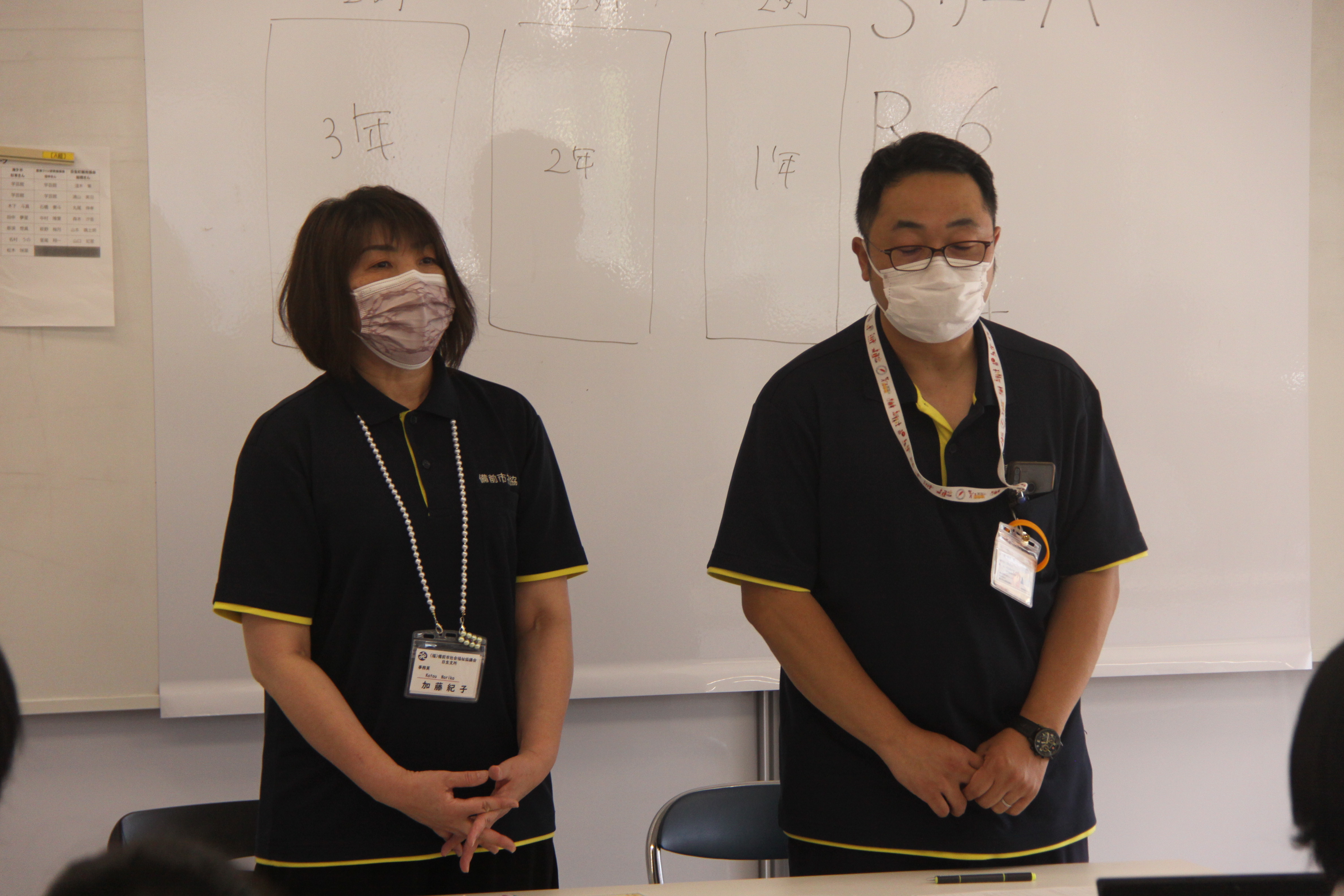

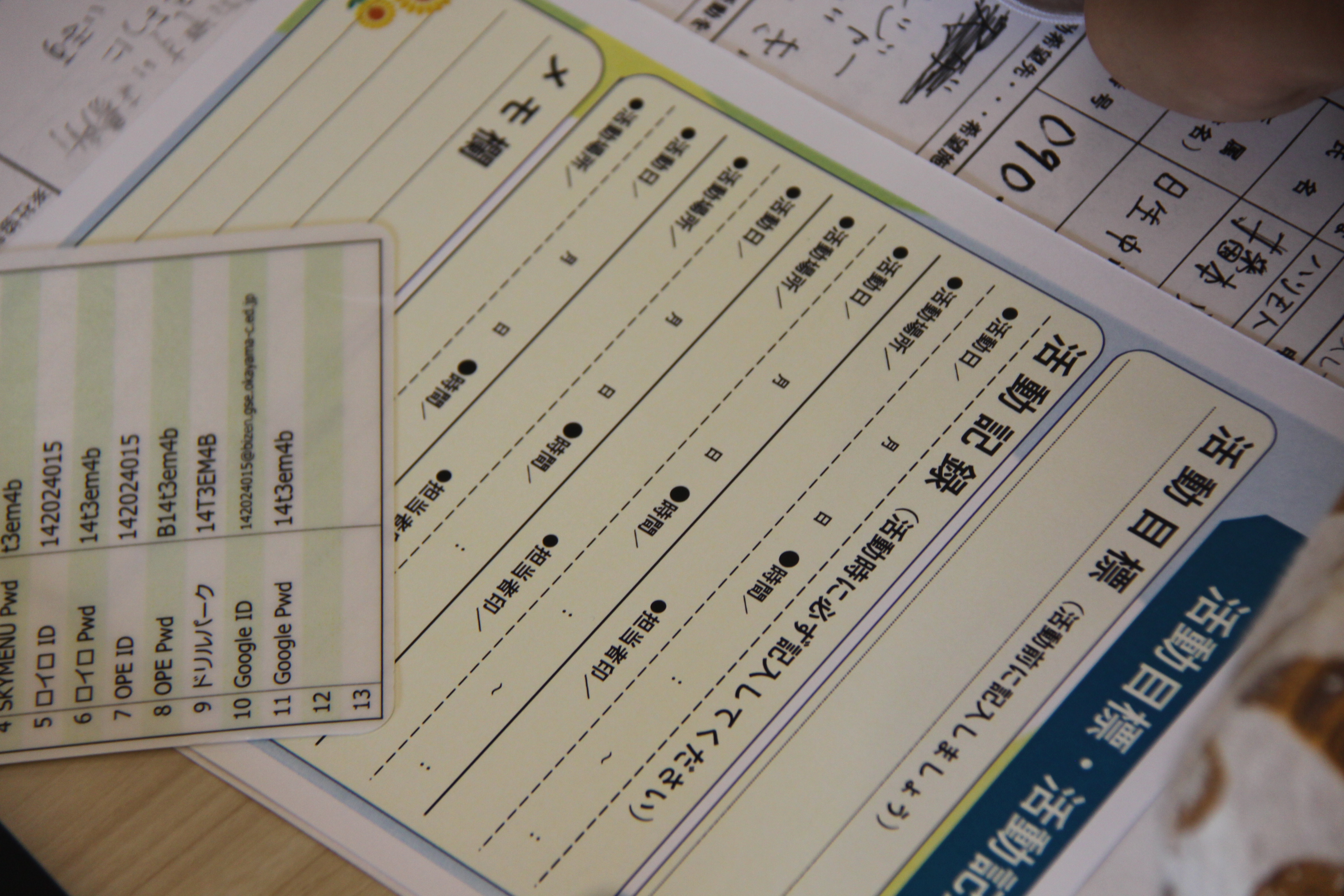
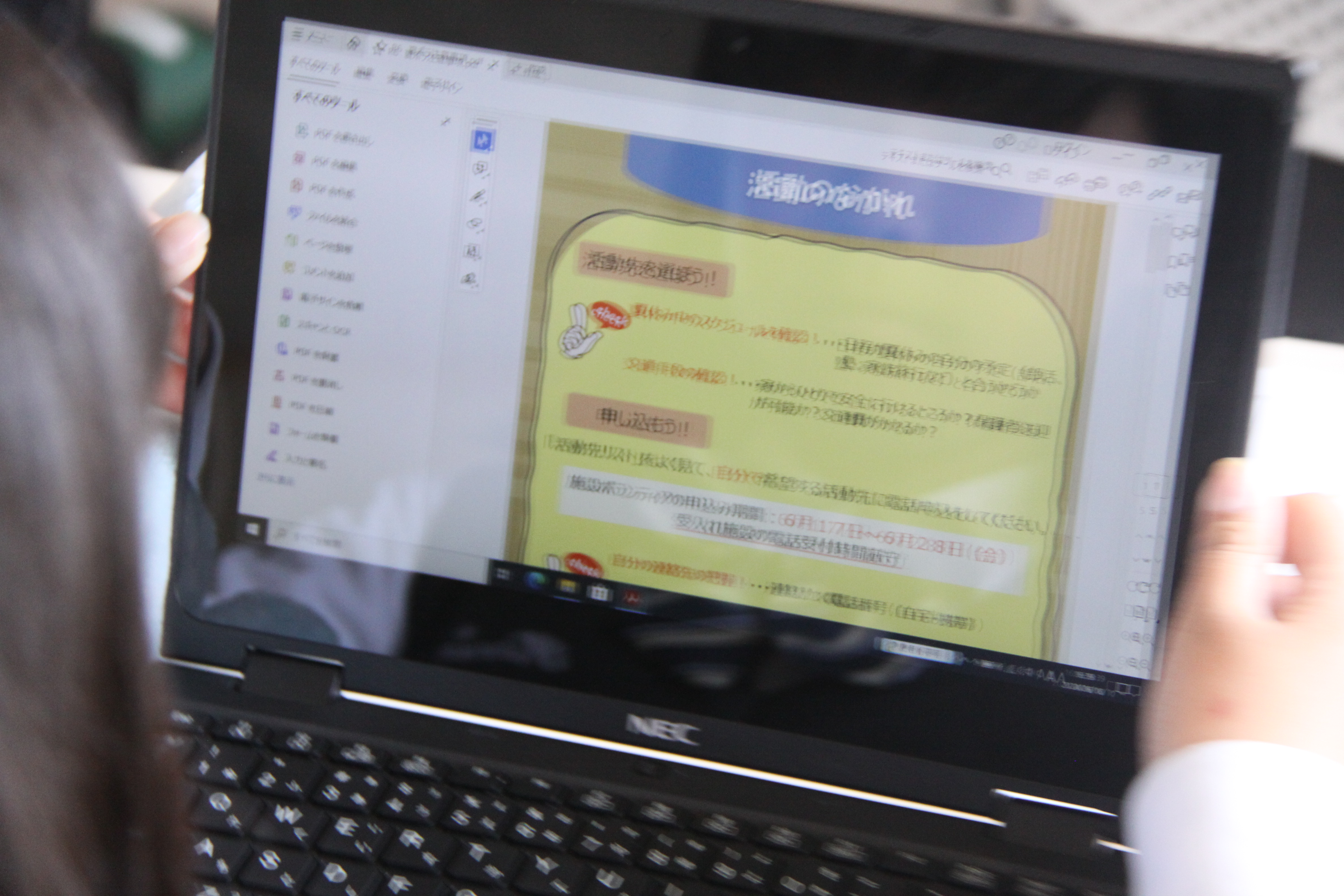


◎多くの人に支えられて
星輝祭・子どもたちへの応援メッセージをありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。(6/10)
 (PHOTO BY OGUSHI)
(PHOTO BY OGUSHI)☆『星輝祭の前から「今日は○○して練習したよ!!」などと楽しみにしている様子でした。家でも、ダンスの音楽を流して練習して、本番まで待ちどうしそうでした♪。当日も終わった後、清々しい顔で帰宅してきたのでよかったです。♬。楽しみながら取り組んでいたので嬉しかったです。』
☆『中学生最後の星輝祭、最高学年として一生懸命に練習取り組んでいるようでした。本番の前の日は、ソーラン節の練習で足が筋肉痛になり、当日のリレーが走れるか心配でした。でも、当日のリレーもがんばって完走し、ソーラン節でも素晴らしい演技を見せてくれました。星輝祭でのがんばりを忘れず、これからも一生懸命に何事でも取り組んでいってほしいです。』
☆『初めての星輝祭をとても楽しみにしており、自宅でダンスの練習をする姿を見ていると、当日応援に行くのが楽しみになりました。思い出に残るよう、友だちと協力してがんばっている姿に成長も感じます。』
☆『3回目の星輝祭、今年も前年度からの準備・練習を工夫しながらがんばっていました。当日はどの競技も一生懸命に取り組む姿はもちろんですが、各ブロックで学年のわくを越えて、声をかけ、熱い応援をしている姿や星輝祭ならではの「勝つぞ!」という気持ちを前面に押し出す姿は頼もしくもあり、印象的でした。
三年生が、1.2年生を巻き込んで盛り上げようとしている姿に成長を感じました。『熱い気持ち』を大切に、これからも色々な事にがんばってほしいです。』
◎多くの人に支えられて(6/10)
今日は日生中を支えてくださっているたくさんの方々が来校されました。セコムさんが定期点検と電池交換のために来校。備前市教育委員会が、モートン先生(ALT)の授業の様子を観にこられました。また、守安さん、奥寺さん(中国銀行日生支店)、が、地域イベント情報〈ひなせかきカキフェス2024(7/7)〉の案内を持って来られました。
さらに、本校で教育実習に取り組んでいる木下先生の授業参観に、天理大学から担当の先生が来校されました。






◎HINASE LEGACY 聞き書き(6/10)
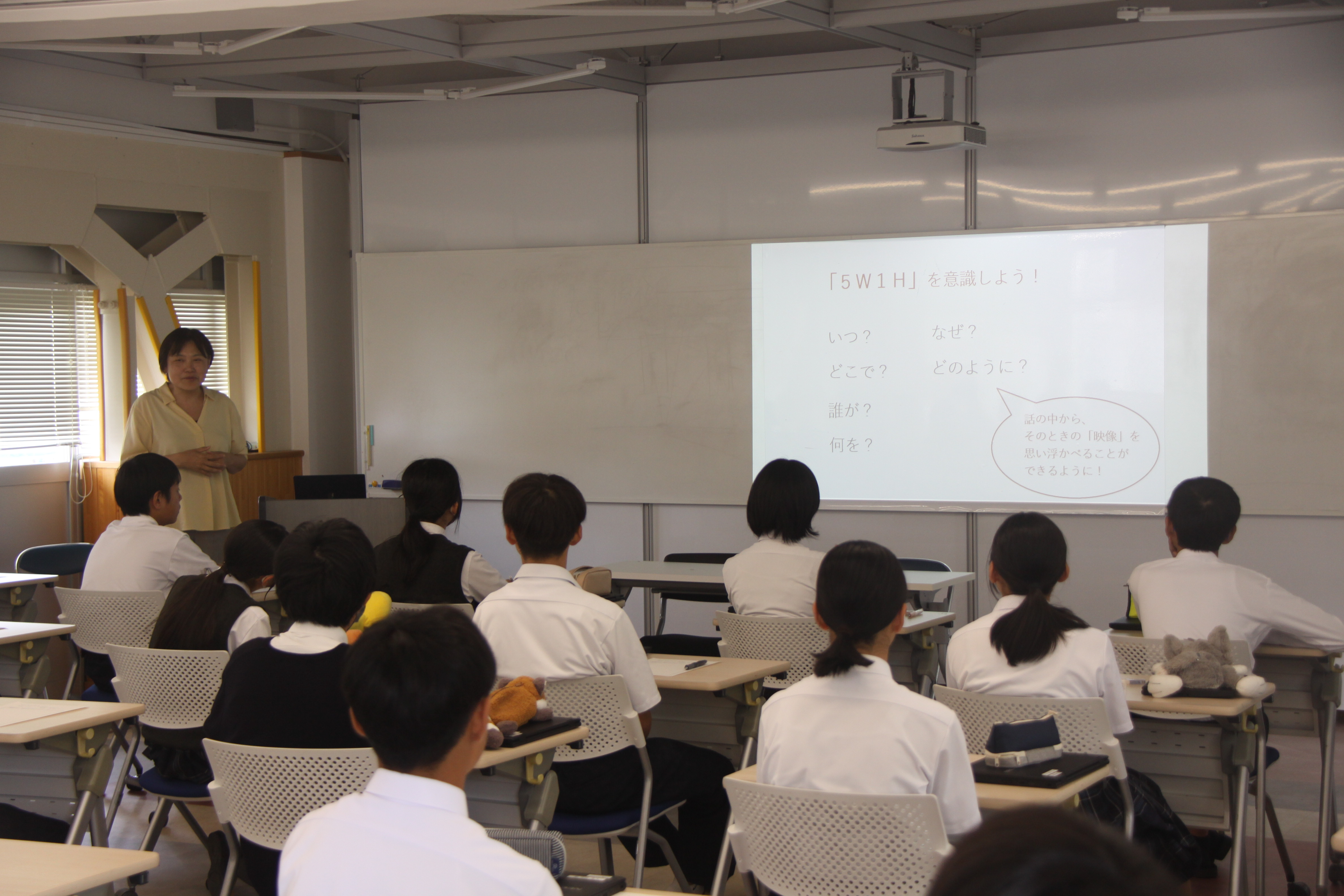

2年生は、吉野さんをエリアティチャーにお招きして、「聴き書き」の活動について学びました。7月2日には漁業に携わる方々からの「聞き書き」をおこないます。
追記:「聞き書き」については、多くの方が様々な意図で取り組んでおられます。小田豊二さんの著書『聞き書きをはじめよう』の紹介文には下記のように書かれています。ひな中聞き書きの参考に。
(「一人の老人が亡くなると、一つの博物館が無くなったことと同じだ」。
これは聞き書き作家・小田豊二が、日頃から口にしている言葉です。なぜ聞き書きを自分の仕事の中心に据えるようになったのか、聞き書きとは何か、聞き書きの特長は何か、聞き書きが聴き手と語り手に与える影響などについて、自分の体験をふまえつつわかりやすく解説した本です。
聞き書きとは何か、その意義について、小田豊二は本書の中で次のように述べています。
『「聞き書き」 とは、語り手の話を聞き、それをその人の「話し言葉」で書いて、活字にして後世に残すことです。特に、この「話し言葉」 で書くというところが、重要なのです。 なぜ、「話し言葉」 なのか。 「聞き書き」は、まず、人の話を聞かなければはじまらないないことはわかりますね。しかし、なぜ、聞いた話を、その人の「話し言葉」で書かなければならないのか、疑問に持つ方もきっといらっしやることと思います。』『きちんとした文章で書かれたほうに比べて、「話し言葉」 で書かれたほうが、語り手の 「人間性」がにじみ出ているように感じませんか。語り手の個性を生かす文章、たとえば、これが、語り手が地方の人であれば、さらに、たくさんの方言が混ざってくるでしょう。そうなれば、もっと、その人らしさが出るのが「話し言葉」なのです。人は年齢、育った場所や濁境、話す相手のちがいなどによって「話し言葉」が異なります。ということは、 人は人それぞれ、口癖や語尾まで含めて、「自分の言葉」 を持っているわけです。』実際、聞き書きボランティアの手によって、全国の老人や伝統文化保持者、有識者などからの聞き書き活動が行われています。被災地では被災者からの聞き書きも行われ、震災・津波の体験を後世に語り継ぐ活動が行われています。すべての人が貴重な人生経験や知恵を持っています。それが何も伝えられずに終わってしまうことは、一つの文化遺産がなくなることと同じです。本書が聞き書きを学びたいという人の貴重な道しるべであることは間違いありません。)
◎第5回ひなせ親の会開催

6月7日(金)、参加者同士で、体験談を聴き合ったり、有意義な情報を交流したりすることができました。ご参加ありがとうございました。
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。スクールソーシャルワーカー(SSW)さんからのアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。
次回も、お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。お気軽に、お申し込み・ご参加ください。
第6回「親の会」のご案内
1日 時 7月12日(金)6月7日(金)17:30~19:00(仕事や用事が終わり次第どうぞ😀)
2 場所 日生中学校 D組教室(北棟1階)
3参加者 小・中学校の特別支援教育のニーズのある生徒の保護者や関心のある方、日生西・東小学校、日生中学校の先生や地域のサポーターなど、久次(日生中)小寺(SSW)主催:日生中学校区連携推進委員会(特別支援教育部会)
4連 絡 参加の希望をお早めに各学校の担当までお知らせください。何かご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
日生西小:(℡72‐0050) 日生東小:(℡74‐0004) 日 生 中:(℡72‐1365)
◎スクールカウンセラーの教育相談やSSWへのご相談も各学校にお問合わせください。
5予定 ひなせ親の会 第7回:8月31日(土)*春いちごの会(特別支援教育のニーズのある生徒・保護者のための進路情報交流学習会)は、備前市民センターで個人相談会を開催します。
◎私たちのはじまりの風景13(6/9)
ここはどこでしょう?












◎私たちの全校集会(6/7)
〈「愛の」字の中にたくさん、(たね)がある 書き続ければいつか芽が出る 千葉 聡〉

◎多くの人に支えられて
~ひなせっ子健全育成会総会開催(6/6)
ひなせっ子健全育成会は、「日生地区住民の総意を結集し、次代を担う青少年の健全育成を図るとともに、明るく住みよい環境づくりに努めることを目的」としています。様々な活動の中で、9月4日(水)15:15~、10月2日(水)16:00~には、中学生下校時声かけ事業兼交通見守り事業が計画されています。ありがとうございます。

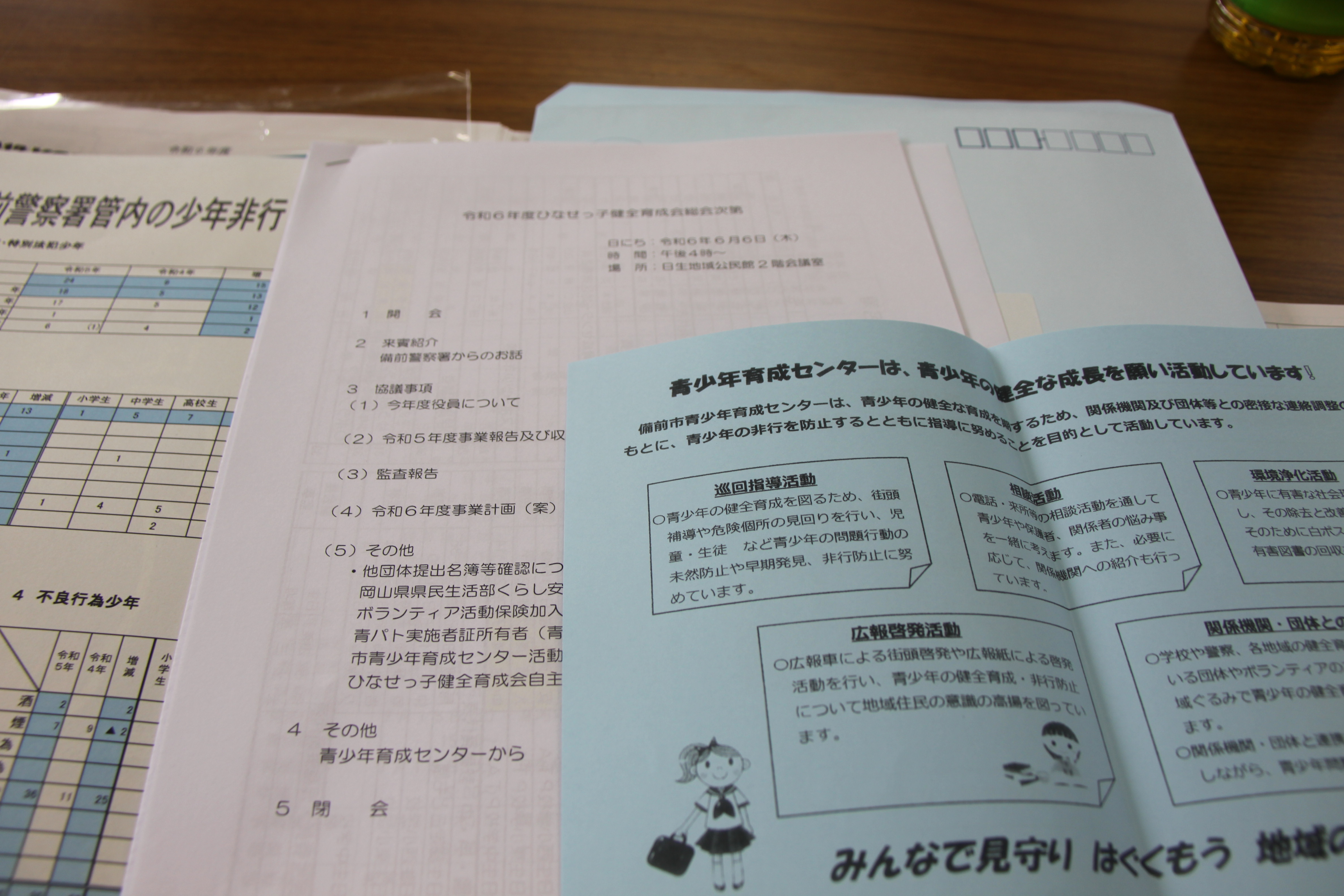
◎ひな中の風✨ 6月の日々。(6/6)
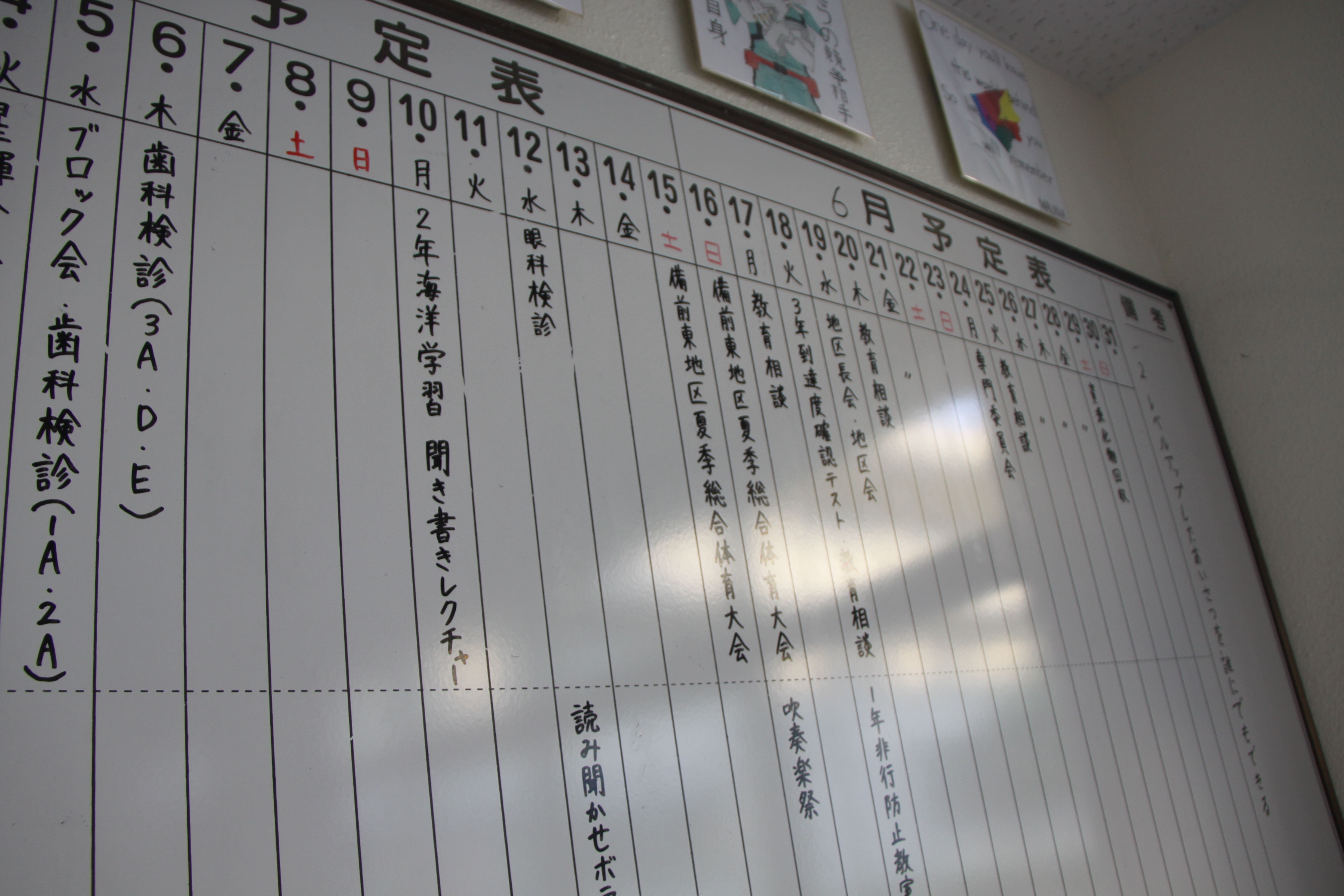

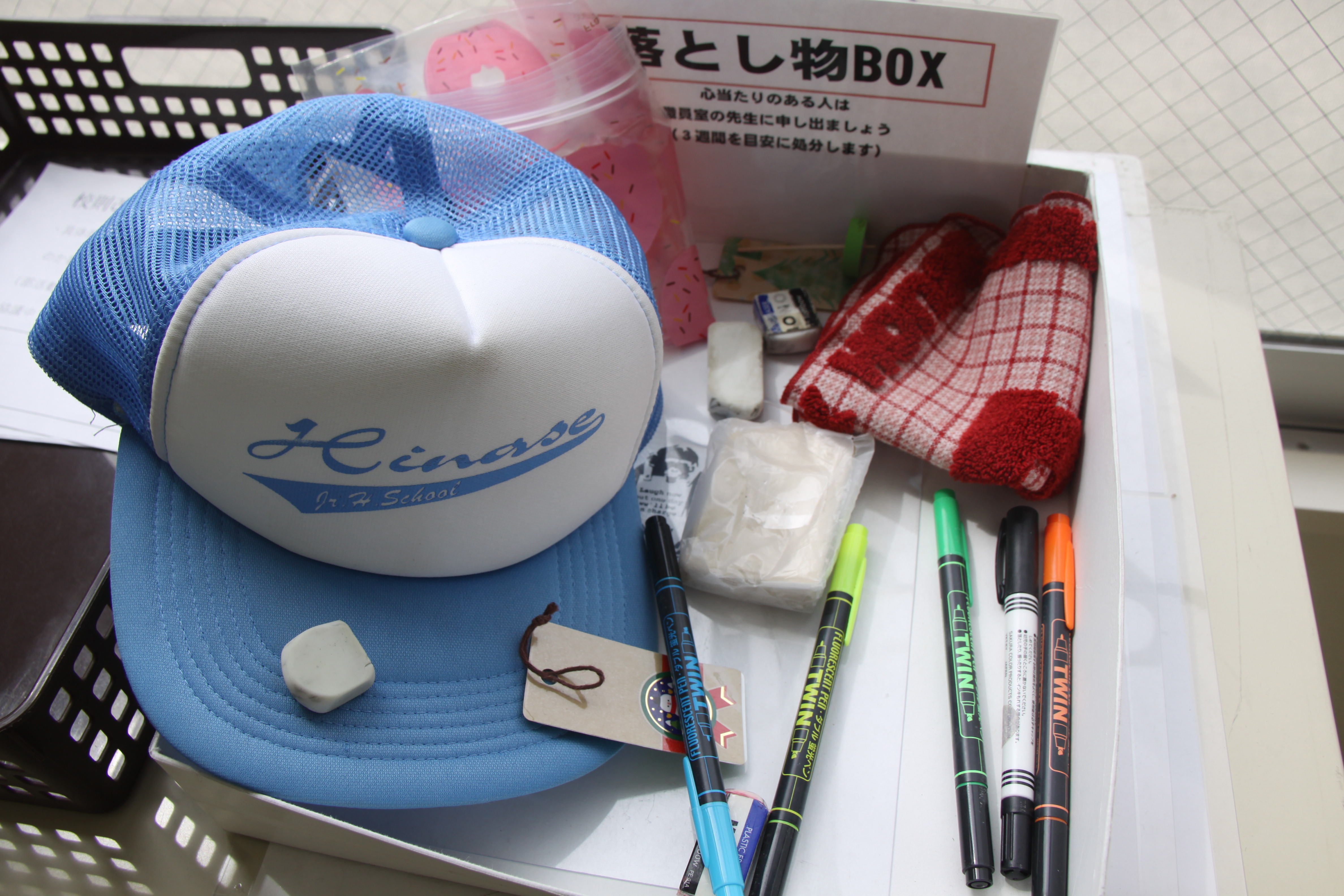
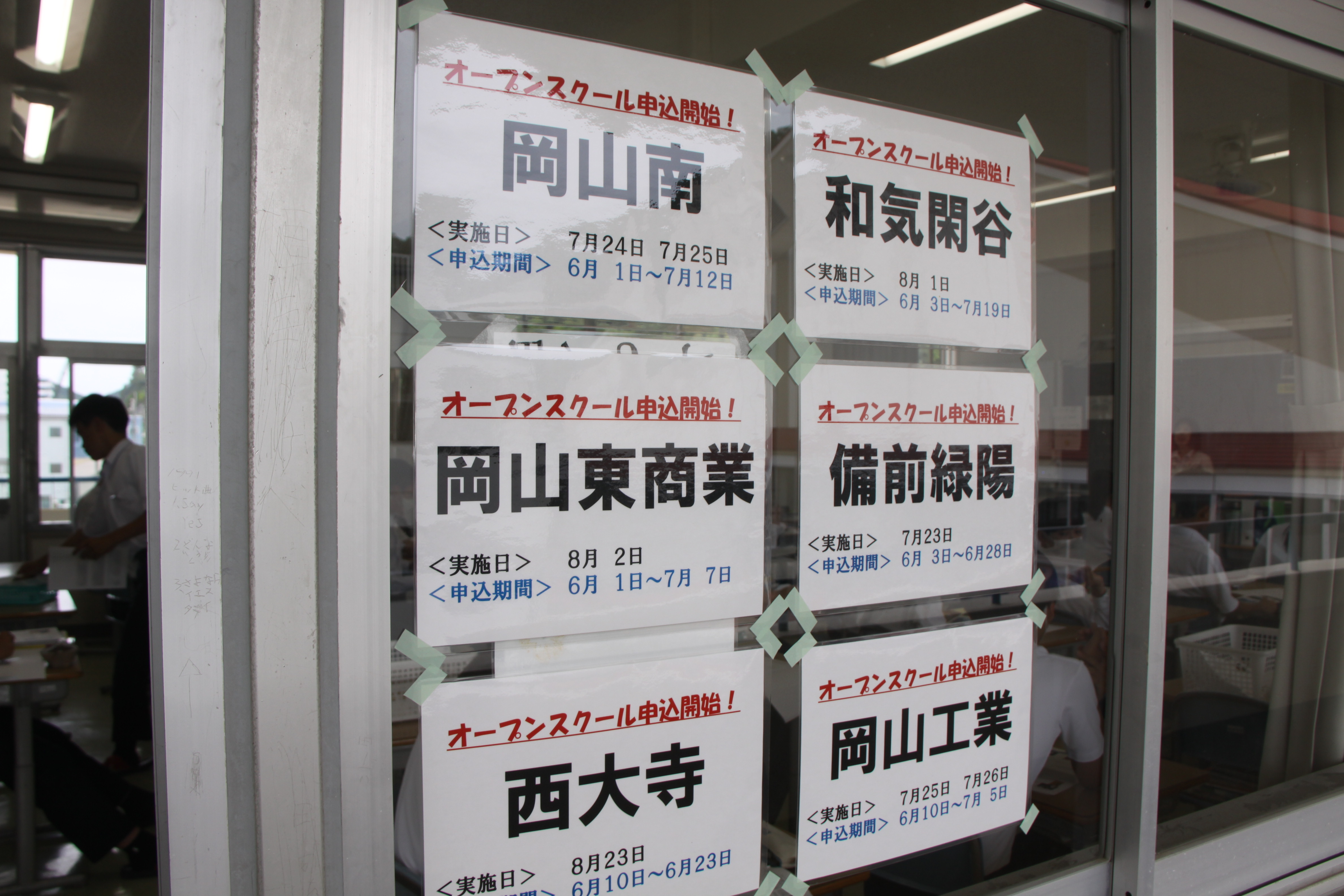


◎もくもくもくもくわたしたちのもくもく清掃✨
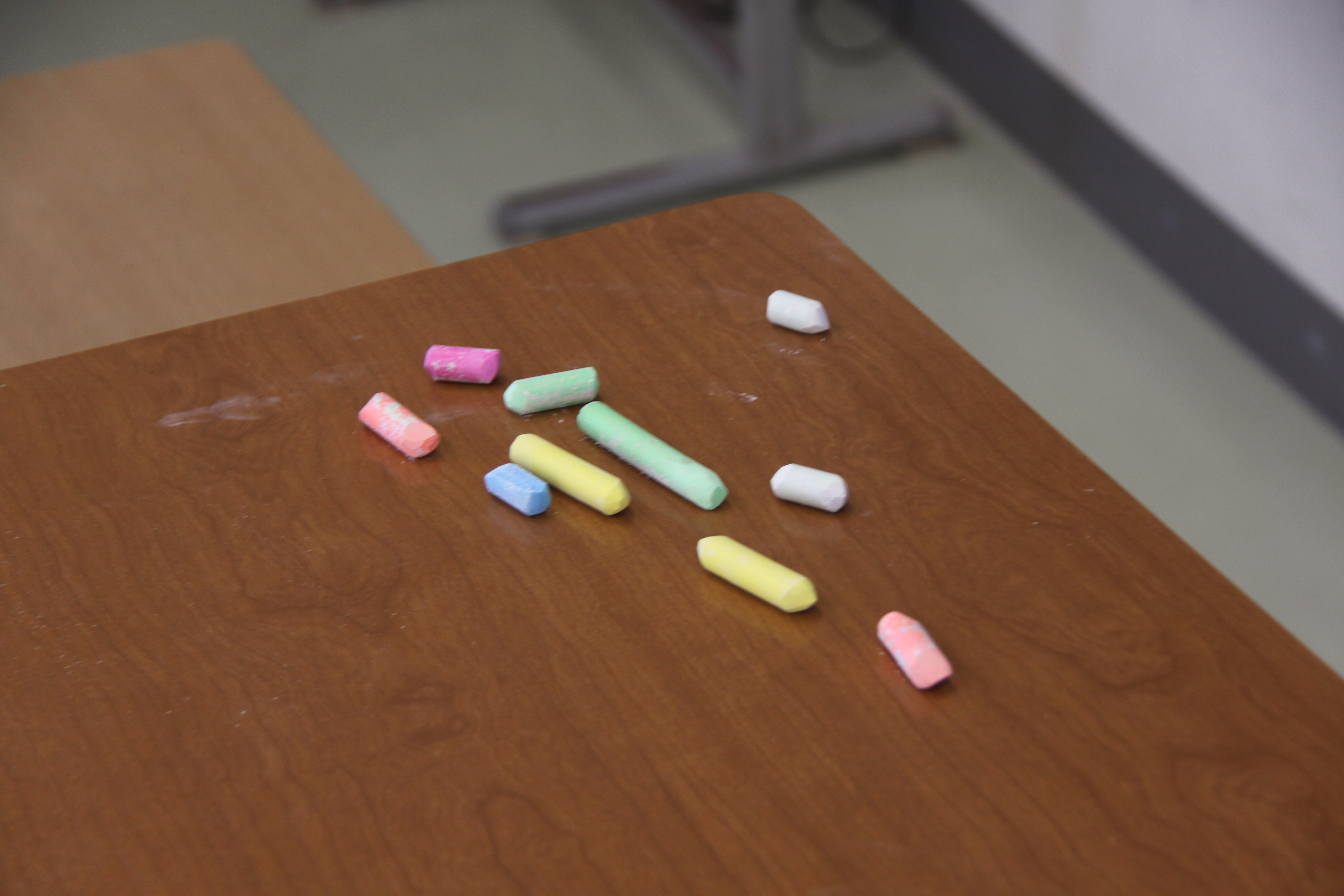


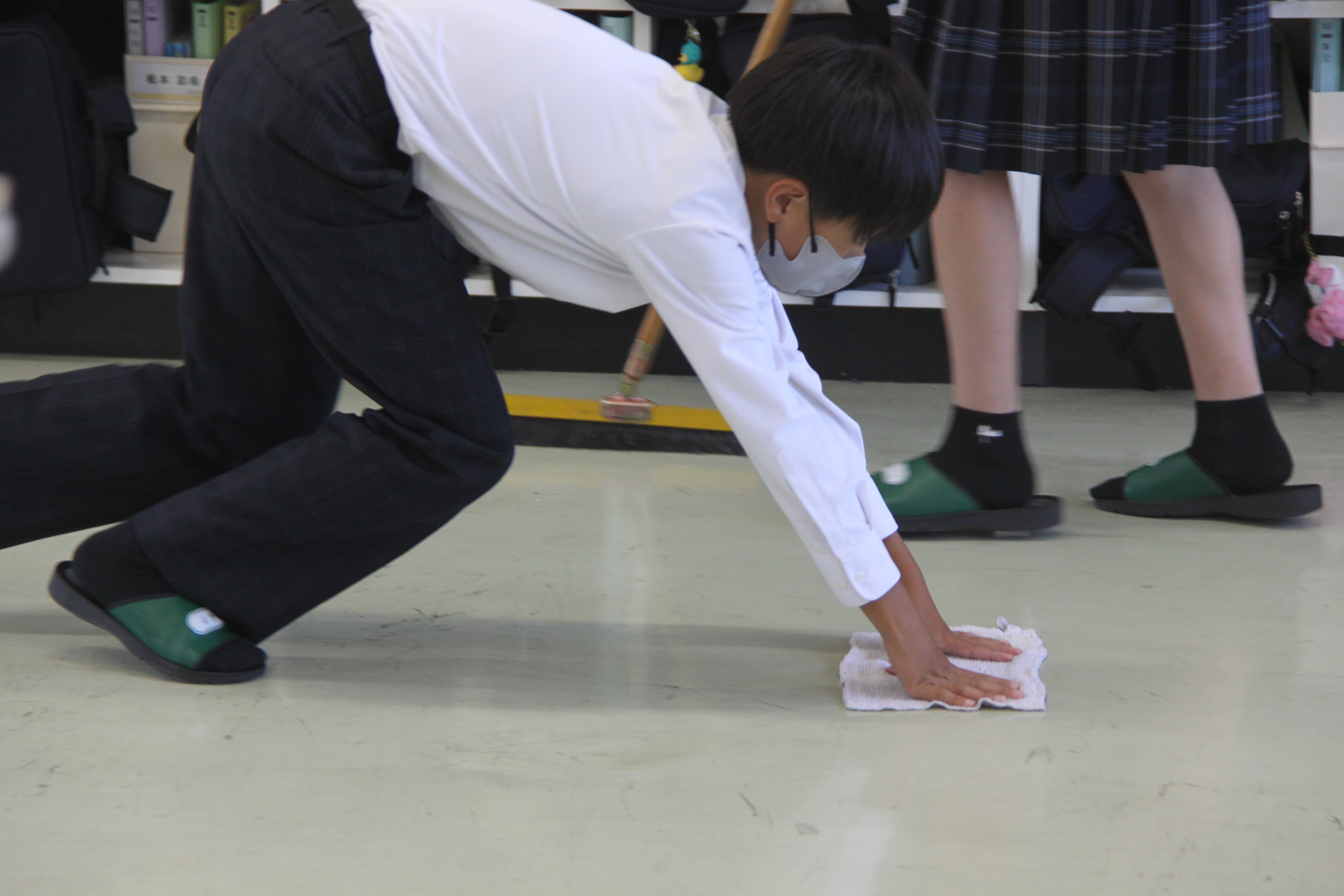


◎私たちが学ぶ。子どもたちのために、私たちのために。
自己目標シートをもとにした当初面談をしています(6/6)

岡山県市町村(組合)立学校教職員の「新しい教職員の評価システム」に関する実施要綱(趣旨)
第1条 岡山県市町村(組合)立学校に勤務する県費負担教職員の「新しい教職員の評価システム」(以下「評価システム」という。)の実施については、この要綱の定めるところによる。
(評価システムの目的及び構成)
第2条 評価システムは、教職員の資質能力の向上及び学校組織の活性化を図り、もって岡山県の教育の充実に資することを目的とし、自己申告による目標管理(以下「目標管理」という。)及び勤務評価で構成する。
(評価システムの実施の範囲)
第3条 評価システムは、次の各号に掲げる者を除く、岡山県市町村(組合)立学校に勤務する全ての県費負担教職員(以下「職員」という。)を対象として実施するものとする。
(1) 臨時的任用の職員
(2) 任期付短時間勤務職員
(3) 非常勤職員
(4) 勤務評価を実施する日の前日において、次に掲げる事由により評価の基礎となる勤務期間(以下「評価期間」という。)が3か月未満である者
ア 停職、休職、育児休業、大学院修学休業、病気休暇、特別休暇(産前産後休暇に限る。)又は介護休暇
イ 岡山県教育委員会の計画による1か月以上勤務場所を離れて行う研修
(5) 充て指導主事
(6) 前各号に掲げる者のほか、岡山県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)教育長が特に必要と認める者
2 前項第4号の規定にかかわらず、第5条に規定する目標管理の実施期間のうちで、実際に勤務する期間が3か月以上あると見込まれる者については、目標管理を実施するものとする。
3 第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、臨時的任用の職員及び任期付短時間勤務職員については、目標管理を実施することができる。
(評価者)
第4条 評価者は、第一次評価者及び第二次評価者とし、その区分は別表第1のとおりとする。
2 校長の第一次評価者及び教頭の第二次評価者は、市町村(組合)教育委員会教育長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、教頭が配置されていない場合には、評価は第二次評価者による評価のみとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、共同調理場における栄養教諭及び学校栄養職員に対する評価者は、市町村(組合)教育委員会教育長が別に定める。
5 第一次評価者及び第二次評価者は、被評価者に対して面談を行う。
(目標管理の実施期間)
第5条 目標管理の実施期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
(目標管理の手順)
第6条 目標管理は、次の各号に掲げる手順により実施する。
(1) 校長は、当該年度の4月の早い時期に、職員のうち目標管理の対象となるもの(以下「対象職員」という。)に対し学校経営目標を提示すること。
(2) 対象職員は、前号の学校経営目標を踏まえ、別表第2に定める職種ごとの職務分類の区分に従い自らの職務上の目標を自己目標シート(様式第1号)に記載し、校長が定める日までに校長に提出すること。
(3) 前号の自己目標を設定するときに第3条第1項第4号に定める事由により勤務場所を離れており、年度の中途において着任した対象職員については、速やかに自己目標シートを作成し、校長に提出すること。
(4) 校長又は教頭(副校長を含む。以下同じ。)は、自己目標シートに関し、対象職員と当初面談を実施し、適切な目標を設定できるよう指導及び助言を行うこと。この場合において、対象職員は、必要に応じて目標の追加又は修正を行うこと。
(5) 校長及び教頭(以下「校長等」という。)は、対象職員の職務遂行状況の観察等を通して、目標の達成に向けての取組状況の把握に努め、適宜、適切な指導及び助言を行うこと。
(6) 対象職員は、設定した目標の達成状況について自己目標シートに記載し、当該年度の中途における校長が定める日までに校長に提出すること。
(7) 校長又は教頭は、自己目標シートその他必要な事項に関し、対象職員と中間面談を実施し、指導及び助言を行うこと。この場合において、対象職員は、必要に応じて目標の修正又は変更を行うこと。
(8) 対象職員は、設定した目標の達成状況についての自己評価を自己目標シートに記載し、当該年度末における校長が定める日までに校長に提出すること。なお、自己目標シートに記載する場合においては、別表第3に定める自己評価の段階評価の区分に従い評価を行うこと。
(9) 校長又は教頭は、自己目標シートその他必要な事項に関し、当該年度の3月末日までに対象職員と最終面談を実施し、目標の達成状況、自己評価及び次年度への課題等について、指導及び助言を行うこと。
2 校長等が作成する自己目標シートは、市町村(組合)教育委員会教育長が定める日までに市町村(組合)教育委員会教育長に提出する。

得意分野・特技を生かしながら、これからもがんばっていきますよ(^_^)
◎日生で輝く 日生が輝く(6/5)
~日生中ボランティア推進プロジェクト
地域ボランティア活動をこれからもがんばります!


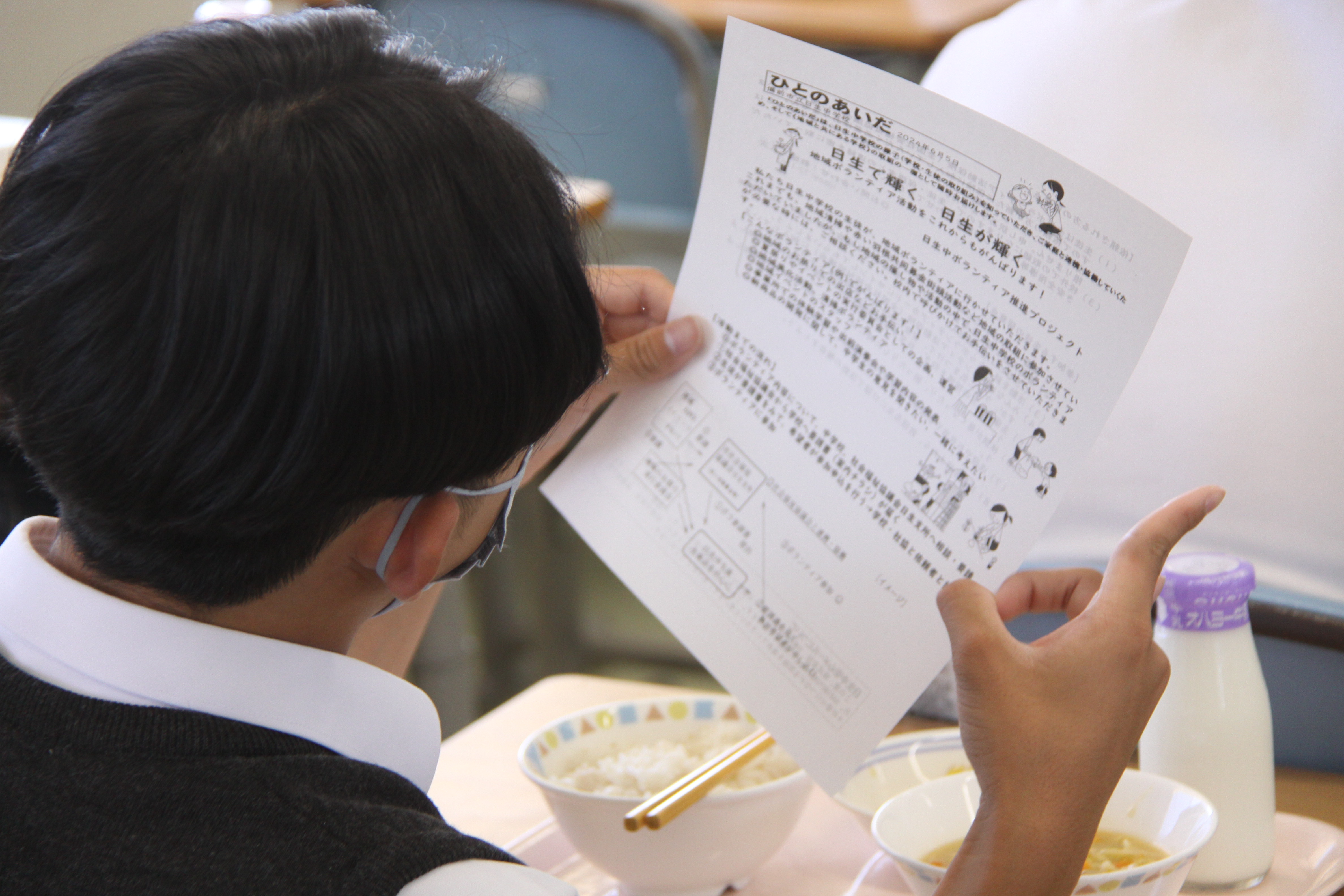
私たち日生中学校の生徒が、地域ボランティアに行かせていただきます。
これまでも、地域清掃や赤い羽根共同募金街頭活動など地域の取組に参加させていただいていましたが、もし地域の催し物や活動の中で、日生中学校のボランティアが必要な時には、ご相談ください。校内で呼びかけてお手伝いをさせていただきます。
【こんなボランティア(例)でがんばります!】
◎地域のお祭りでの出店などお手伝い
◎夏祭りやイベントの実行委員会としての企画、運営
◎地域美化活動、清掃ボランティア
◎地域イベントのスタッフ
◎事業所での体験学習や出前演奏会や学習内容の発表
◎新商品の開発に関して、中学生の意見を聞きたい、一緒に考えたい
【活動までの流れ】
⓪ボランティア内容について、中学校、社会福祉協議会日生支所へ相談・要請
①社会福祉協議会から学校へ要請書(案内チラシ)が届く
②生徒が要請書をみて、希望者が参加申込を行う→学校・社協と依頼者と調整
③ボランティアに参加
【依頼される方の留意点】
(1)生徒は全員ボランティア活動保険(全国社会福祉協議会)に加入していますので依頼の方が新たに保険に加入していただく必要はありません。
(2)校内でボランティアを募集しますが、必ずしも生徒の参加希望があるとは限りません。申し訳ありません。
(3)校外での取組になりますので、生徒・保護者との連絡を密に取っていただき安全指導等に留意し活動を行わせてください。
◎お問い合わせ:教頭(0869)72-1365
【参加する生徒の留意点】
(1)謙虚に「学ぶ」ことを大事にしましょう。
(2)募集人数を超える希望があったら、抽選となる場合があります。必ず参加できるとは限りません。
(3)活動を終えたらボランティアカードにサインしてもらいましょう。
(4)みんなはボランティア活動保険(全国社会福祉協議会)に加入していますがケガに気をつけて安全に心がけて活動しましょう。
(5)主催者の方の指導を仰ぎ、日生中学校生徒としての誇りをもって行動しよう。
(6)体調が悪くなったり、困ったりした時には、すぐに近くの大人に相談しよう。
(7)送迎やお弁当や水筒等、保護者の方に感謝して参加しよう。
(8)活動を終えたら、教頭先生に口頭で活動の報告をしよう。
◎みんな ありがとう。そしてこれからも (6/5)
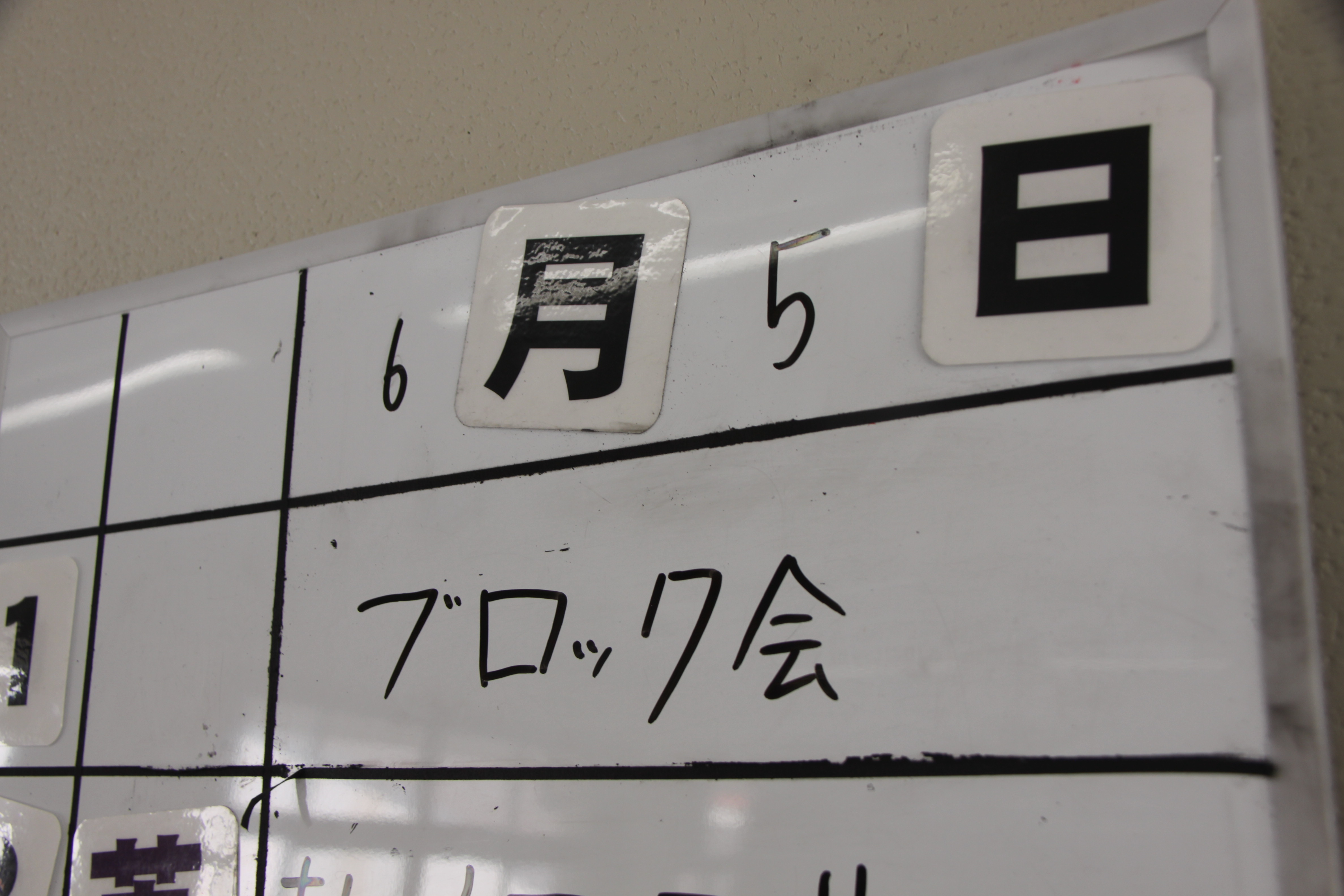


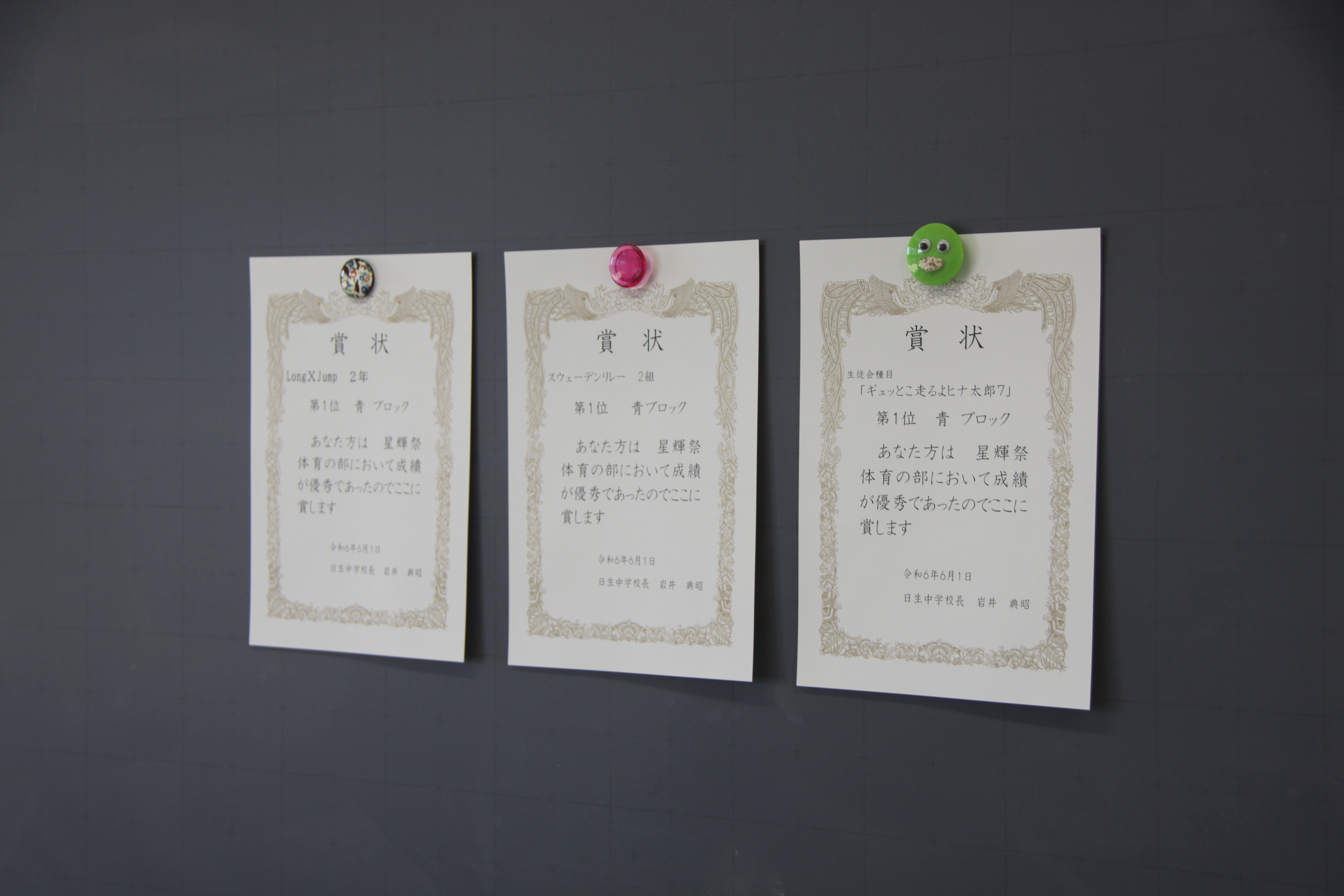


Friends accept you the way you are. Marilyn Monroe
(友達はありのままのあなたを受け入れてくれる。)
◎ひな中の風✨
明日へ続く私たちの帰りの会 (6/4)

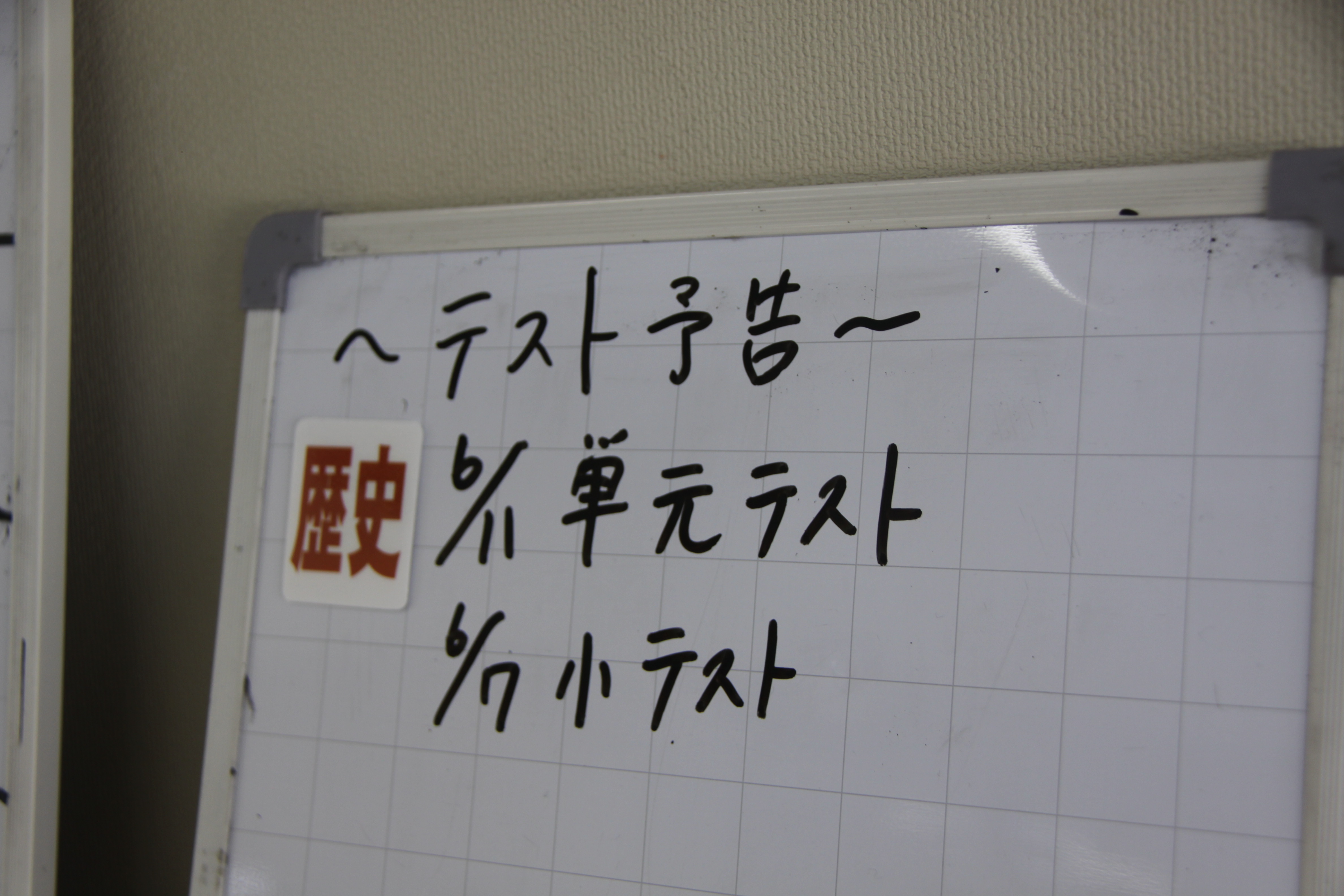
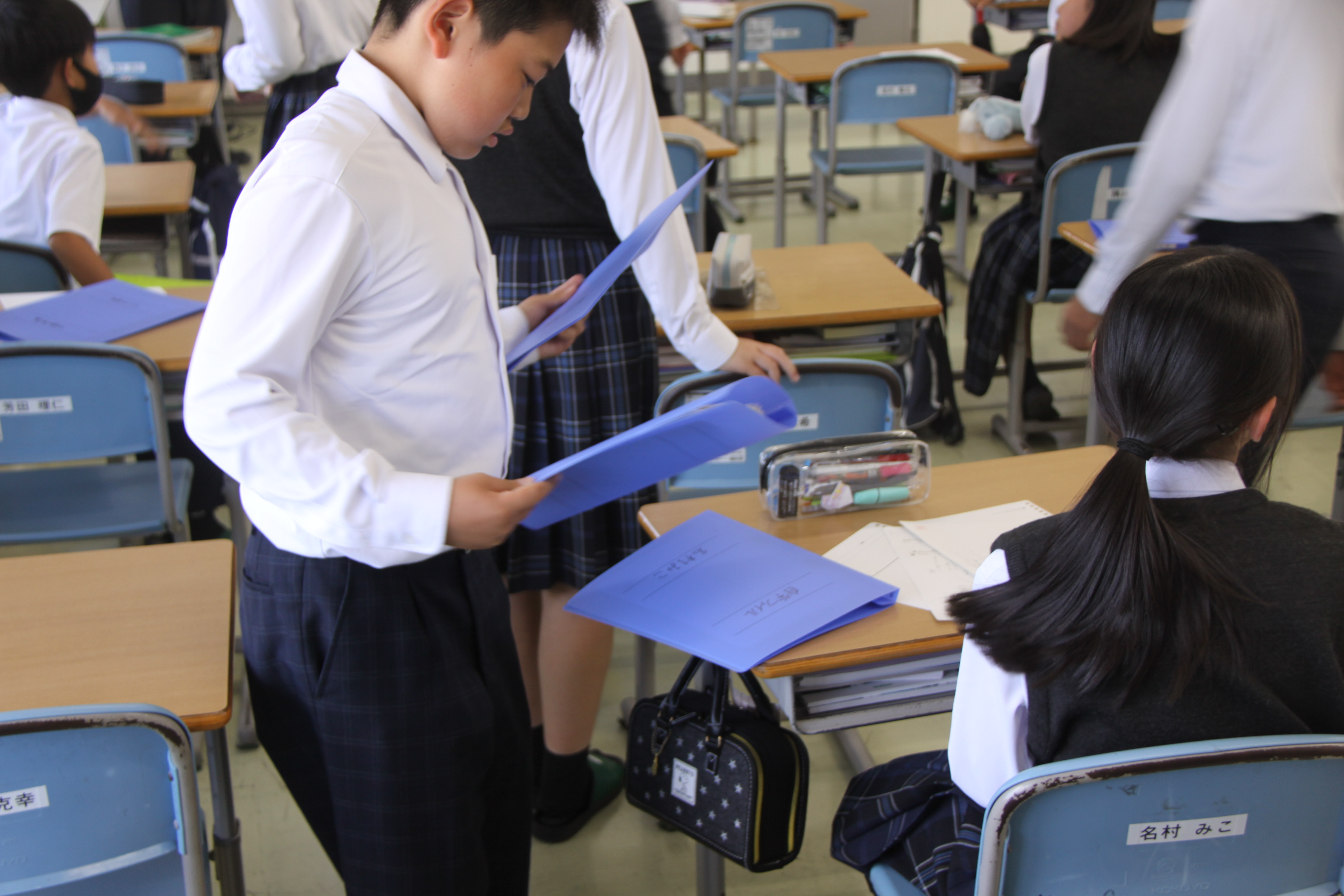

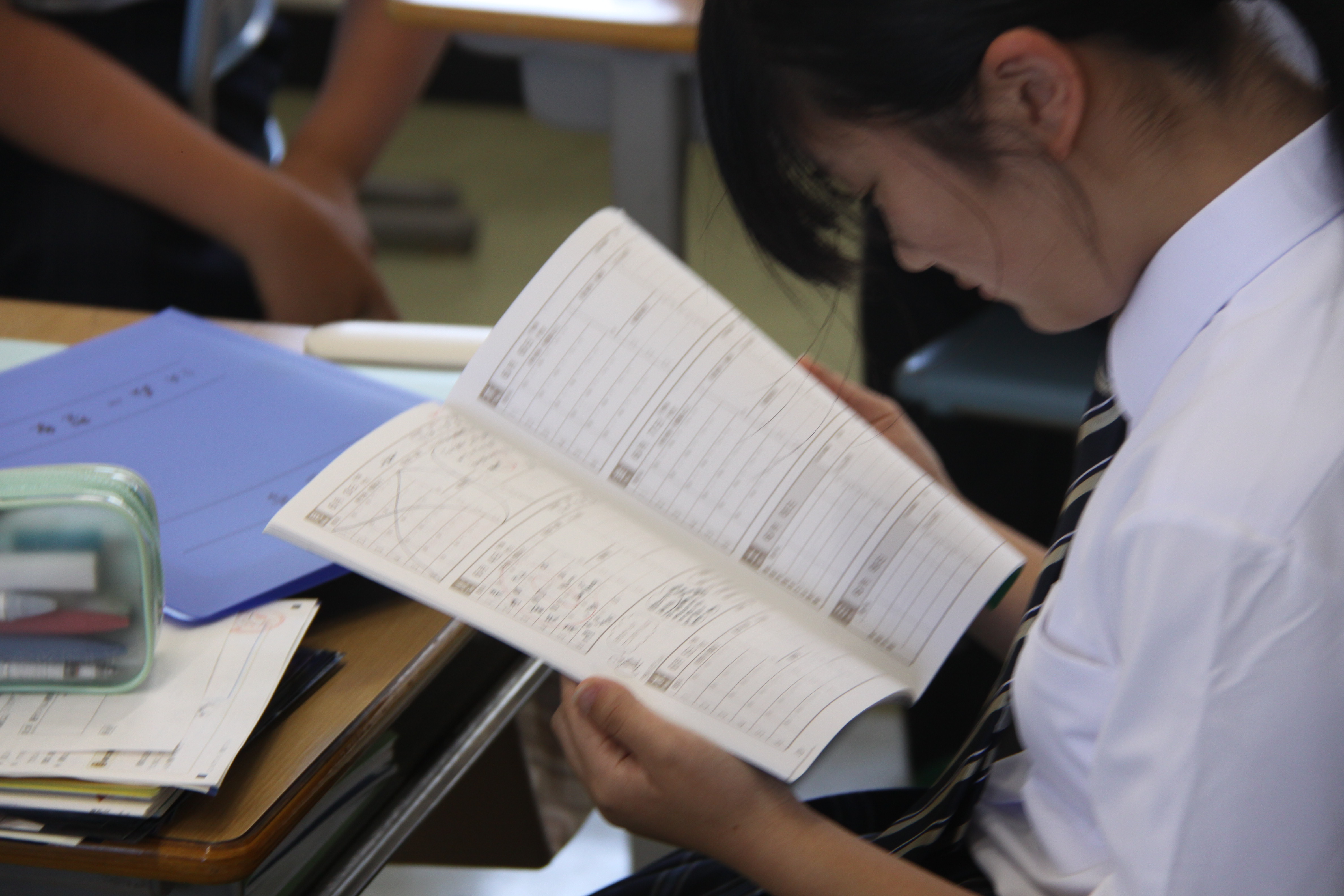
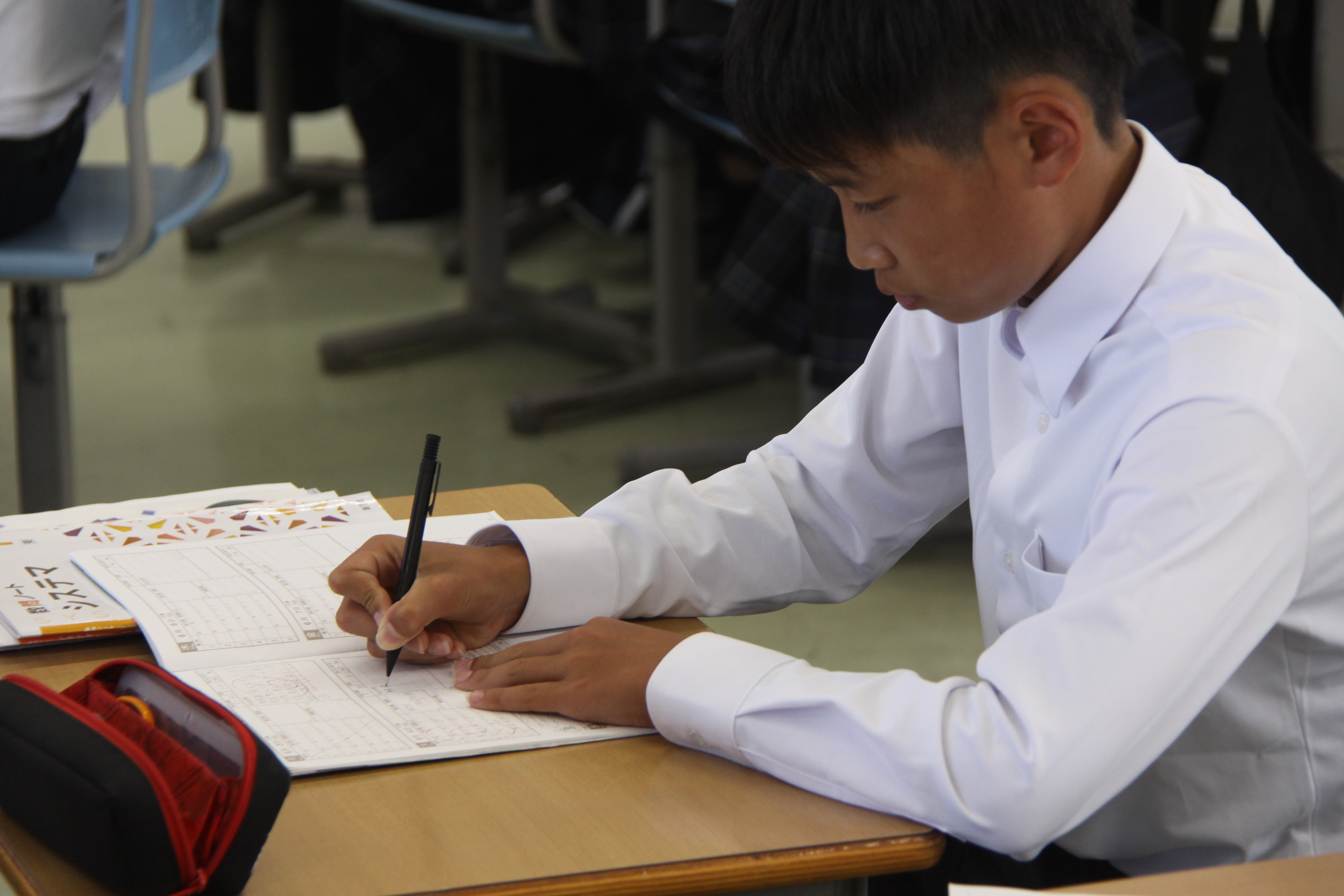
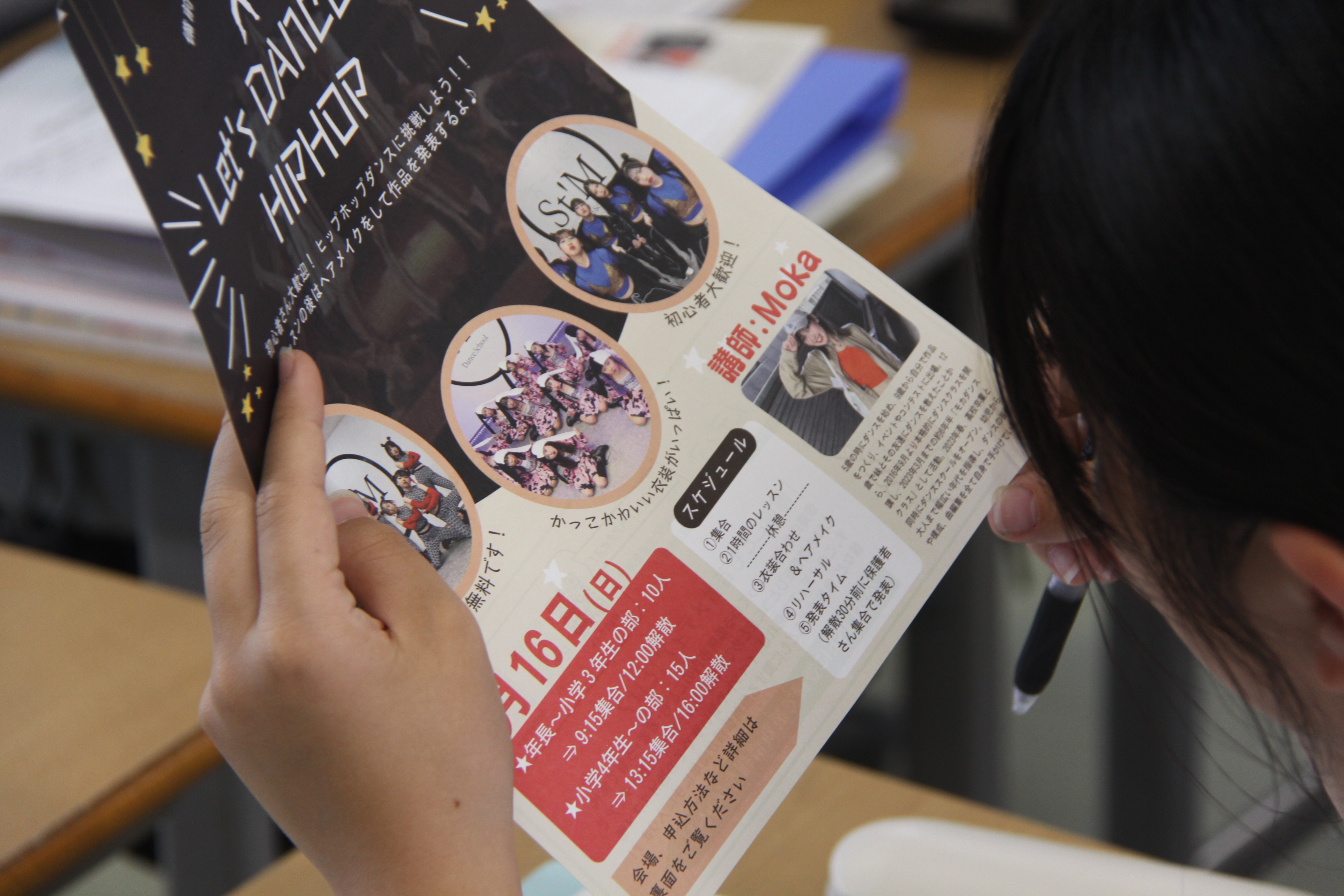
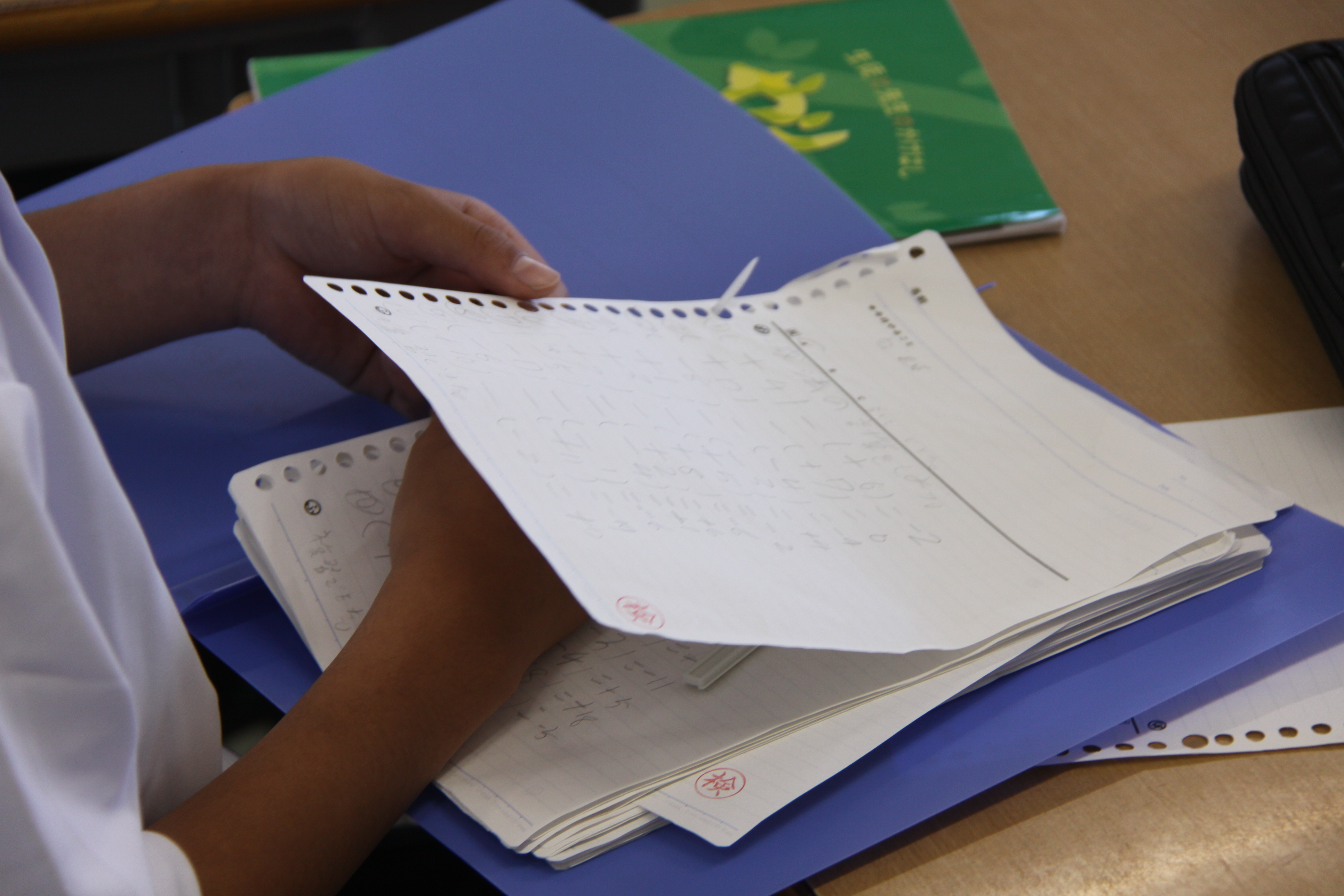
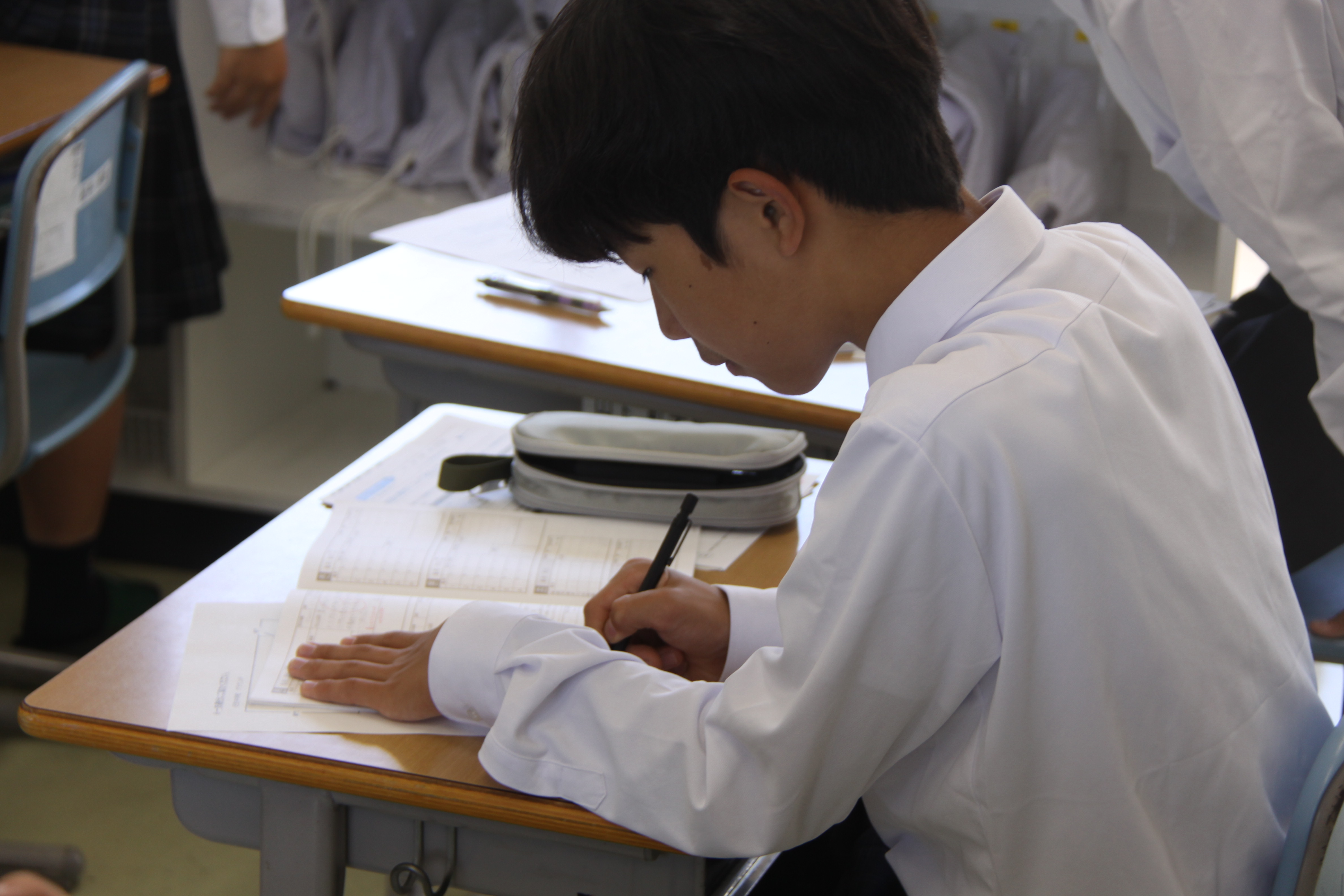
◎ひな中の風✨ 水無月(6/4)





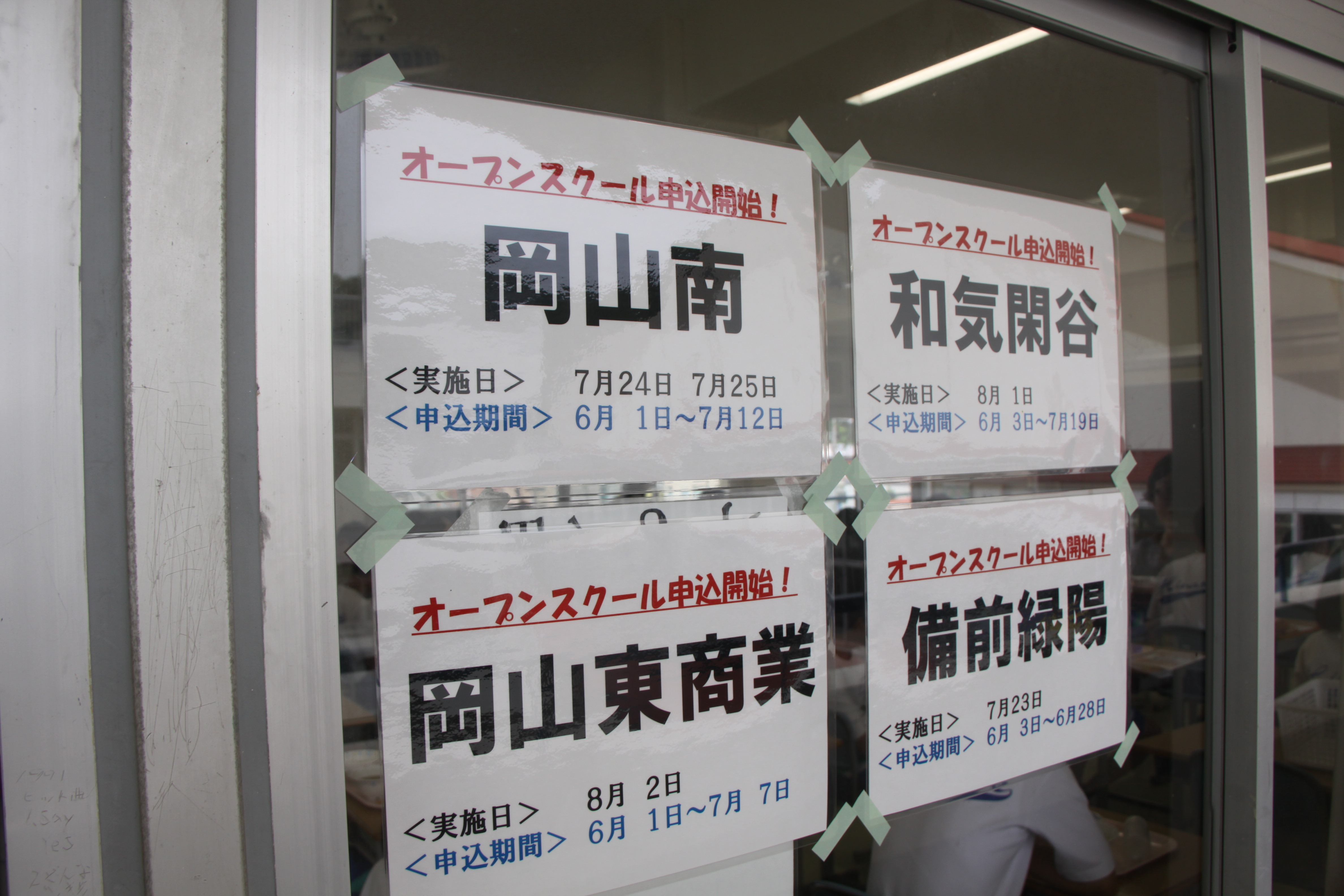
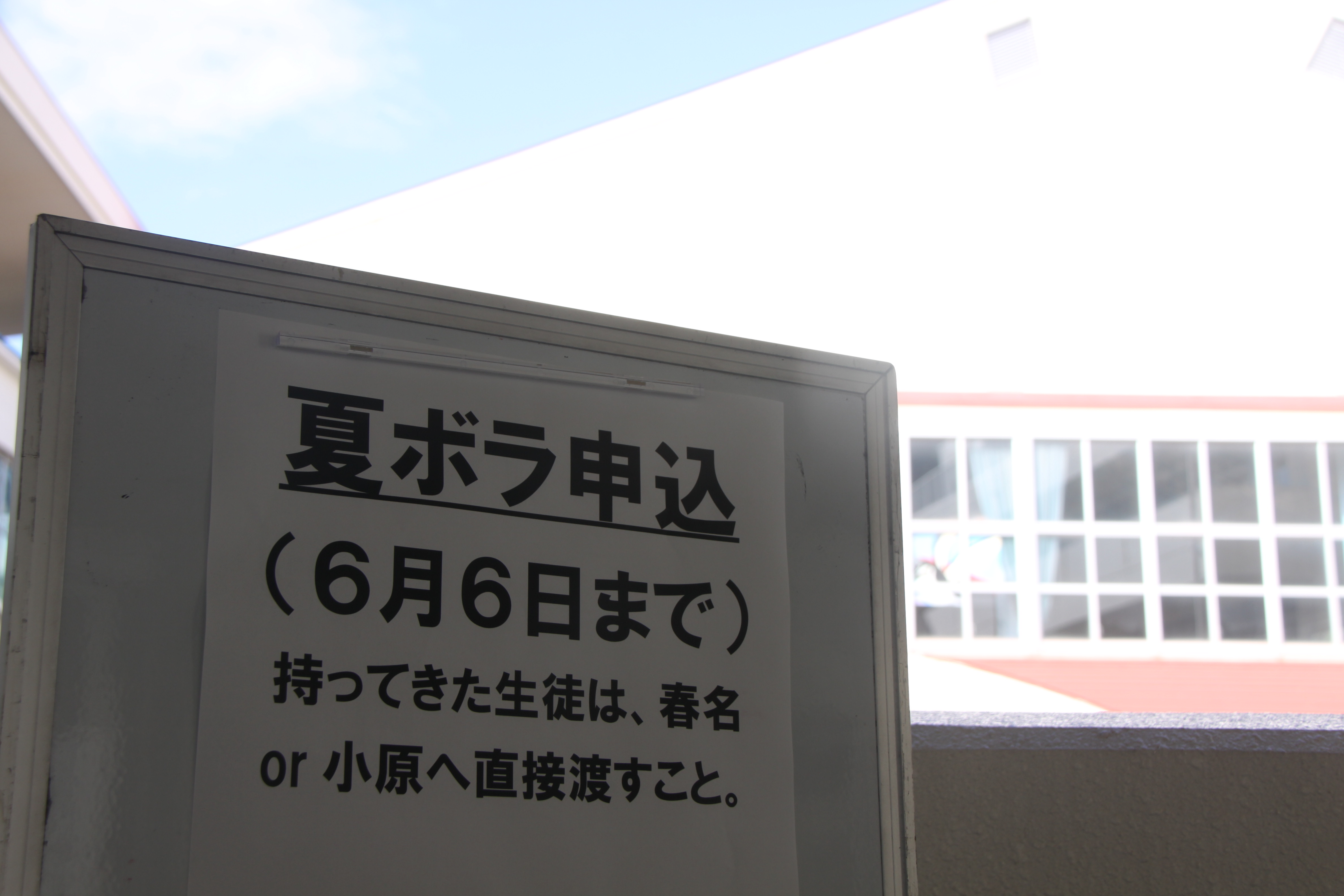


新緑に包まれた5月も終わり、6月になりました。
6月の異名として広く知られているのが「水無月(みなづき)」です。
梅雨時で雨の降りやすいにも関わらず、「水が無い」と表すのを不思議に感じたことのある方も多いのではないでしょうか。水無月の「無」は、「の」にあたる連体助詞「な」であるため、「水の月」という意味になります。今まで水の無かった田んぼに水を注ぎ入れる頃であることから、「水無月」や「水月(みなづき・すいげつ)」「水張月(みずはりづき)」と呼ばれるようになりました。この時期の雨は稲が実を結ぶために重要なものであるため、豊作を願う人々の思いがこの呼び名に表れている、ともいわれています。
ほかには、酷暑にたえて涼しい風を待つという意味の「風待月(かぜまちづき)」、「常夏月(とこなつづき)」、「炎陽(えんよう)」など、夏の厳しい暑さを感じさせる呼び名が多くあります。
一方で、「弥涼暮月(いすずくれづき)」や「涼暮月(すずくれづき)」など、夕暮れの涼しさを表現した異名もあります。また、「蝉羽月(せみのはつき)」という、蝉の羽のような薄い衣を着る月という意味の言葉もあります。かつての日本人のライフスタイルを表す、なんとも優雅な言葉選びですね。
今日はお弁当給食でした。
◎有漏路より無漏路へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け 一休 (6/3)

◎多くの人に支えられて
学校評議員会を、6月1日(土)、星輝祭(体育の部)の日に開催し、生徒たちの取組をみていただきました。藪内さん、有吉さん、米本さん、三木さん、山脇さん(敬称略・順不同)、来校ありがとうございました。以下に、評議員の規約を掲載します。

備前市立日生中学校 学校評議員運営規定
(趣旨)
第1条 この規定は,備前市立学校管理規則第23条の規定及び備前市立学校評議員設置要綱に基づき,日生中学校における学校評議員の運営等について定める。
(目的)
第2条 学校評議員は,学校が保護者や地域住民の意見を把握し,反映し,その協力を得るための方 策について,校長の求めに応じて意見を述べ,学校の自主性・主体性の確立と,より一層地域 に開かれた学校づくりのための支援を行うことを目的とする。
2 校長は,学校評議員の意見を参考にし,主体的な学校運営を行うものとする。
(運営上の基本方針)
第3条 学校評議員の運営は,校長の責任と権限において行うものとする。
(役割)
第4条 校長は,学校運営に関し,自己の権限と責任に属する事項のうち,次の事項について学校評 議員に助言や意見を求める。
① 地域住民の学校運営への参画のあり方に関すること。
② 学校の教育活動の自己評価と地域への説明に関すること。
③ 学校と保護者・地域の連携協力のあり方に関すること。
④ その他学校の運営の改善に関すること。
(会議の招集)
第5条 会議は,校長が招集し,これを主催する。
2 校長は必要があると認めたときは,学校評議員以外の者を会議に出席させ,説明を求め,ま たは,意見を聴取することができる。
第6条 学校評議員に関する庶務は,教頭,教務主任において処理する。
(その他)
第7条 この規定に関するもののほか,必要な事項は校長が別に定める。
◎〈終わったとみんな言うけどおしまいがあるってことは素敵なことだ 桝野浩一〉
(6/1)






















What we have once enjoyed we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us.
Helen Keller
(一度楽しんだものは決して失うことはない。私たちが深く愛するものはすべて、私たちの一部となる。)
◎今日、私たちは輝く。(6/1:第14回星輝祭(体育の部))

◎多くの人に支えられて(5/31)
守屋さんから、山陽新聞での日生中の活動記事をラミネートにしていただきました。いつもありがとうございます。また、今日は、日生、ザイングリッシュクラブから、難波さんとワーキングホリディで来岡しているヤンさんが3Aを訪問してくださり、多文化共生社会の一端にふれることができました。
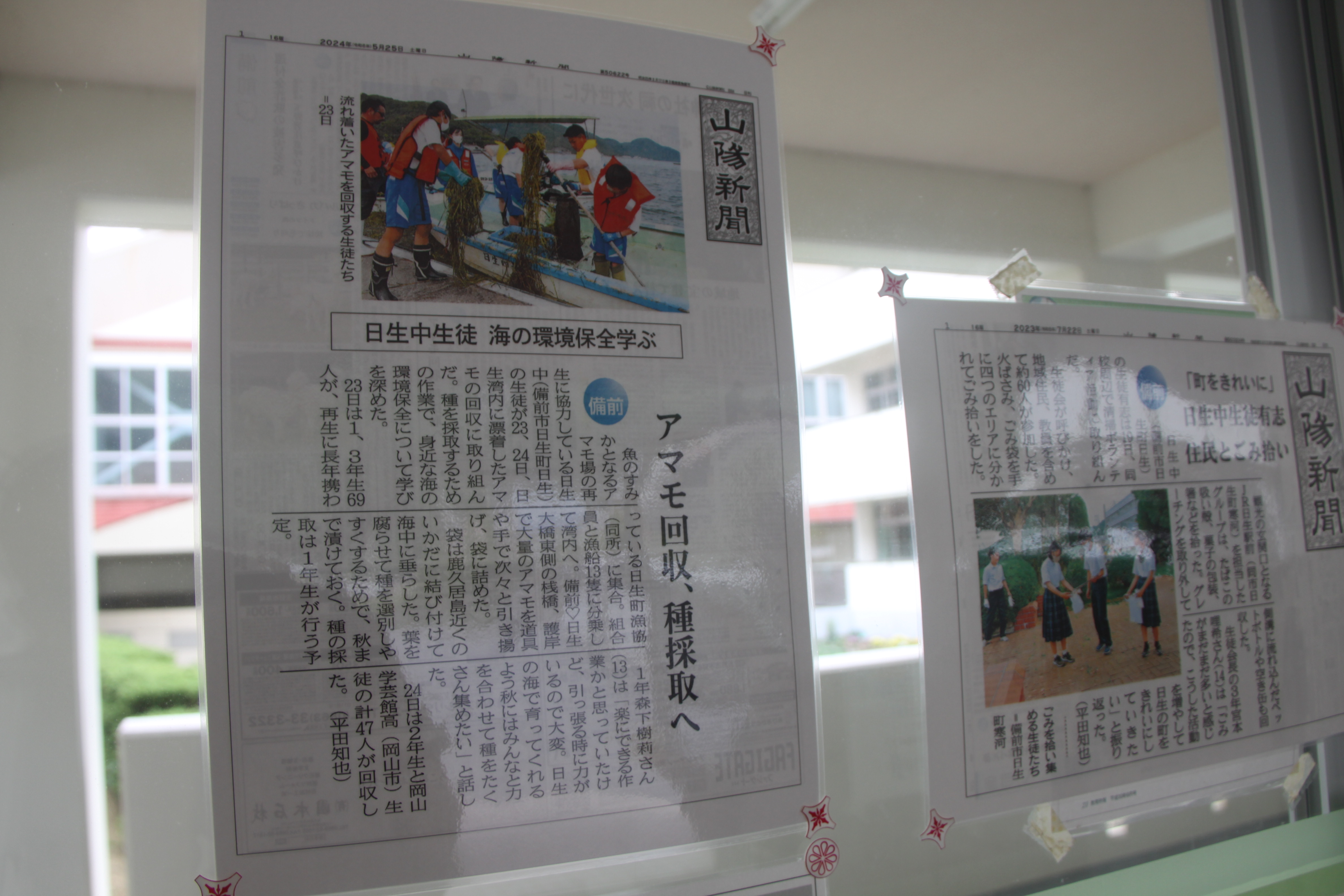


◎HINASE LEGACY(5/31.7:42)









レガシー(legacy)は、英語では「遺産」という意味です。 もともと亡くなった人が遺したものを指しますが、日本語のレガシーは「過去に築かれ、受け継がれていくもの」という意味で使われます。
◎〈「待ち人は来ない」「自分で会いに行け」このおみくじは当たる気がする 桝野浩一〉(5/31)
生徒らのアイデアを参考にして、備前市と連携して、看板を設置しましたよ。

◎ひとりでできるトライはない(5/30・予行練習)

◎多くの人に支えられて(5/30・予行練習)
『保護者の方からの応援メッセージより:日生中学校の星輝祭では、いつも子どもたちが協力し合って取り組んでいる姿が見られて、心を打たれています。限られた時間の中で、1年生はとくに、初めての中学校の体育祭で、覚えることもたくさんあると思いますが、1人ひとりが一等星に負けない輝きを出して、星輝祭本番に全力を出している姿を楽しみにしています。』
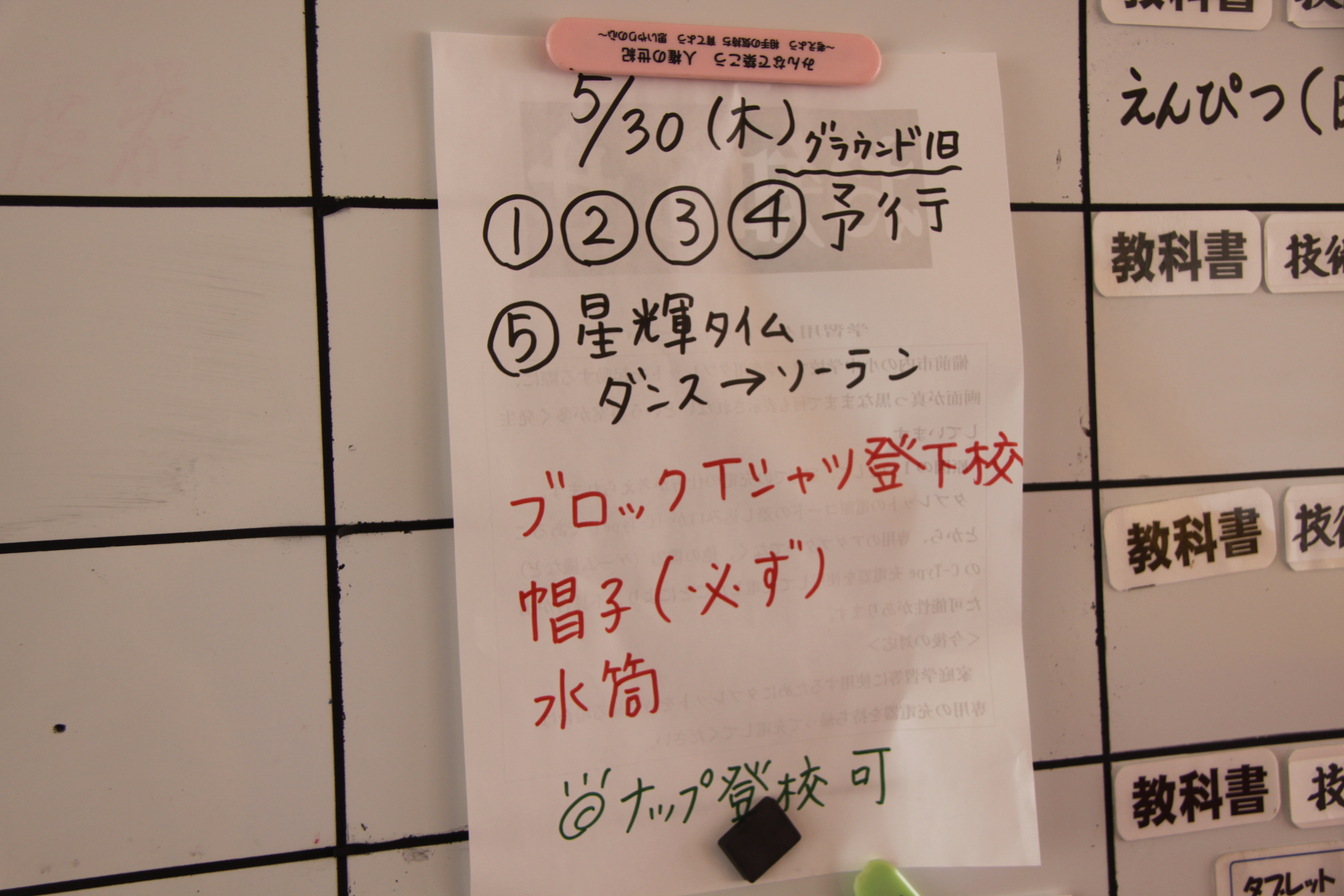

















◎多くの人に支えられて(5/30)
今年度も、エコロジー東備の山﨑さんが来校され、ゴーヤやパッションフルーツなど多種の苗をくださいました。ありがとうございました。グリーンカーテンづくりを通して環境保全活動に取り組んでいきます。

◎わたしたちのはじまりの風景12 (5/30)
ここはどこでしょう?






◎学校は学び合うところだ(5/29)
今日の山陽新聞には「教室はまちがうところだ(蒔田晋時さん)」が紹介されていました。本になって今年で20年になるそうですが、学校の意義をあらためて考える中で、色あせません。「教室」を「学校、行事。部活動・・・」に読み替えしても意味深いものになりますね。私たちの星輝祭(体育の部)は、今週末です✨。



まちがった意見を 言おうじゃないか
まちがった答えを 言おうじゃないか
まちがうことを おそれちゃいけない
まちがったものを わらっちゃいけない
まちがった意見を まちがった答えを
ああじゃあないか こうじゃあないかと
みんなで出しあい 言い合うなかで
ほんとのものを 見つけていくのだ
そうしてみんなで 伸びていくのだ
いつも正しくまちがいのない
答えをしなくちゃならんと思って
そういうとこだと思っているから
まちがうことがこわくてこわくて
手も上げないで小さくなって
黙りこくって時間がすぎる
しかたがないから先生だけが
勝手にしゃべって生徒はうわのそら
それじゃあちっとも伸びてはいけない
神様でさえまちがう世のなか
ましてこれから人間になろうと
している僕らがまちがったって
なにがおかしいあたりまえじゃないか
うつむきうつむき
そうっと上げた手 はじめて上げた手
先生がさした
どきりと胸が大きく鳴って
どぎっどきっと体が燃えて
立ったとたんに忘れてしまった
なんだかぼそぼそしゃべったけれども
なにを言ったか ちんぷんかんぷん
私はことりと座ってしまった
体がすうっと涼しくなって
ああ言やあよかった こう言やあよかった
あとでいいこと浮かんでくるのに
それでいいのだ いくどもいくども
おんなじことをくりかえすうちに
それからだんだんどきりがやんで
言いたいことが言えてくるのだ
はじめからうまいこと言えるはずないんだ
はじめから答えが当たるはずないんだ
なんどもなんども言ってるうちに
まちがううちに
言いたいことの半分くらいは
どうやらこうやら言えてくるのだ
そうしてたまには答えも当たる
まちがいだらけの僕らの教室
おそれちゃいけないワラッちゃいけない
安心して手を上げろ
安心してまがえや
まちがったってワラッたり
ばかにしたりおこったり
そんなものはおりゃあせん
まちがったって誰かがよ
なおしてくれるし教えてくれる
困ったときには先生が
ない知恵しぼって教えるで
そんな教室作ろうやあ
おまえへんだと言われたって
あんたちがうと言われたって
そう思うだからしょうがない
だれかがかりにもワラッたら
まちがうことがなぜわるい
まちがってることわかればよ
人が言おうが言うまいが
おらあ自分であらためる
わからなけりゃあそのかわり
誰が言おうとこずこうと
おらあ根性曲げねえだ
そんな教室作ろうやあ
◎陽はまたのぼる(5/28)
組織的・機動的・効率的な学校経営に関する調整力、適正な能力評価と人材育成や、連携・発信に関する校長の補佐等、副校長・教頭として求められる資質・能力の向上を図る目的で、今年度最初の、副校長・教頭全員研修講座がありました。今日は、本校教頭も参加(岡山県総合教育センター)し、「不祥事防止について」「労務管理」「教職員の育成・評価システム」「危機管理について」「校内研修・研究の充実に向けて」について学びました。日生中学校のすべての教職員は、子どもたちの教育活動がさらに充実していくように、今後も主体的に研修・研究を深めていきます。
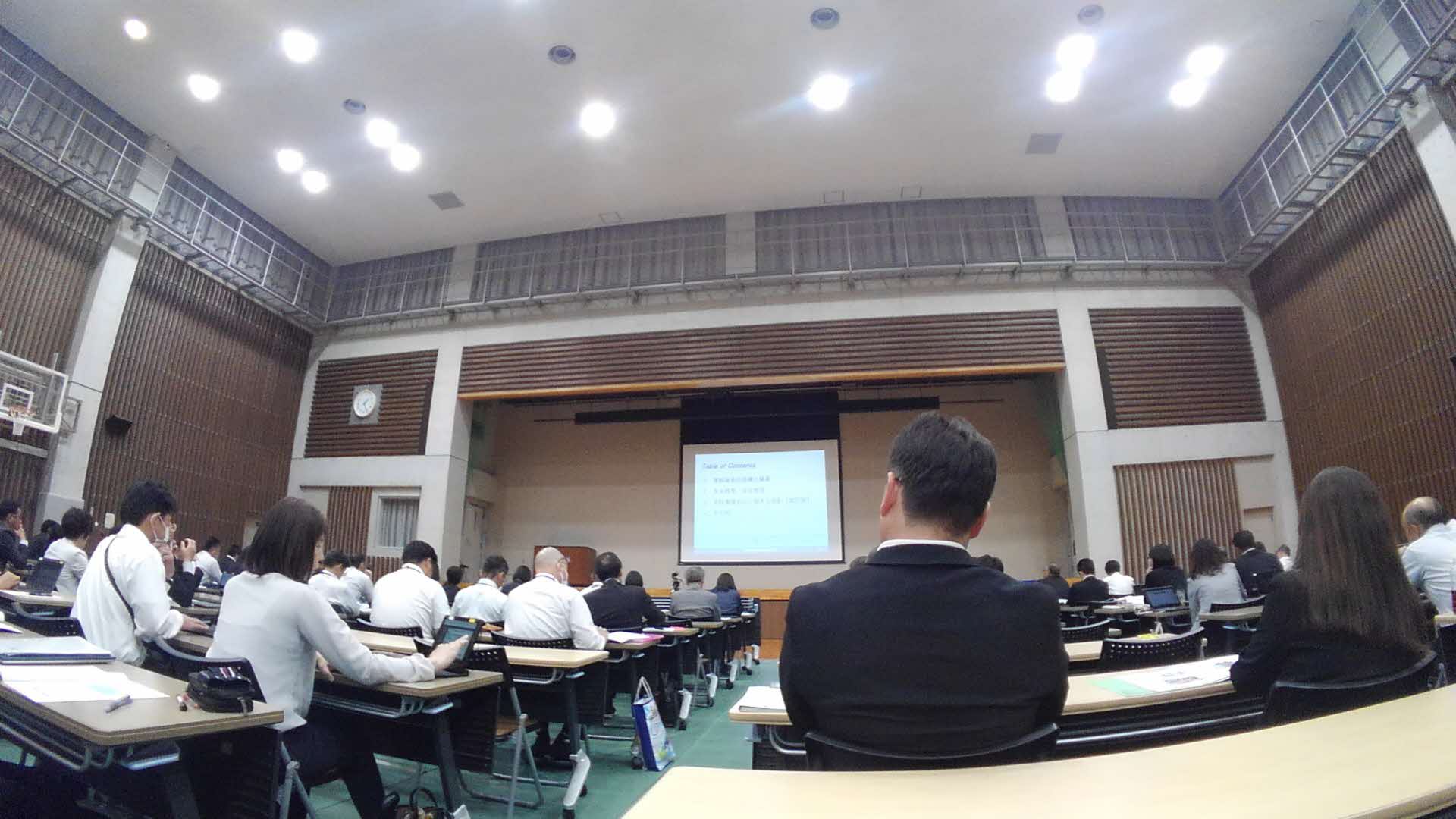
◎ひな中の風✨(5/29)
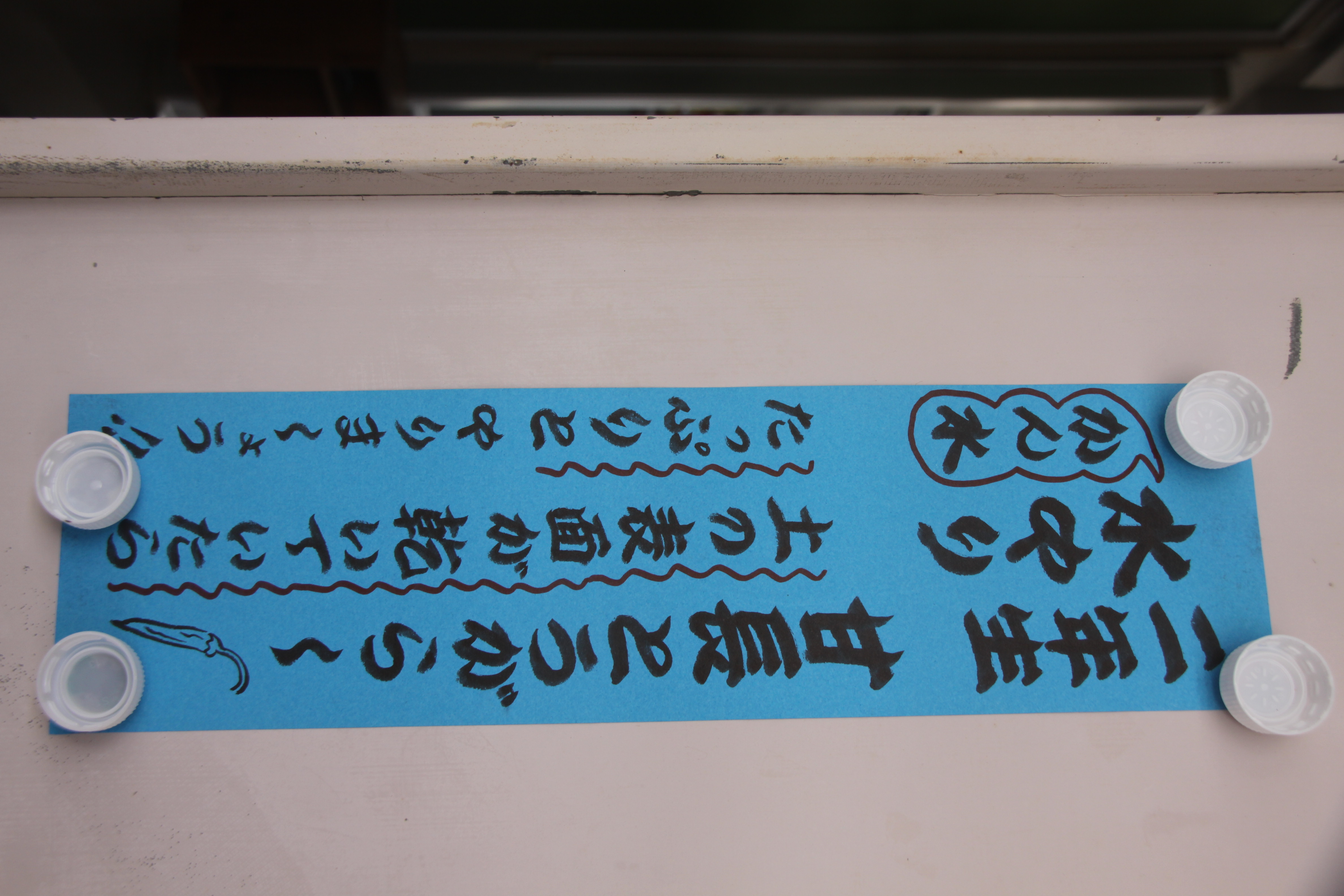

◎1人ひとりが輝きます
~可能性だけがある私たち~(5/28)
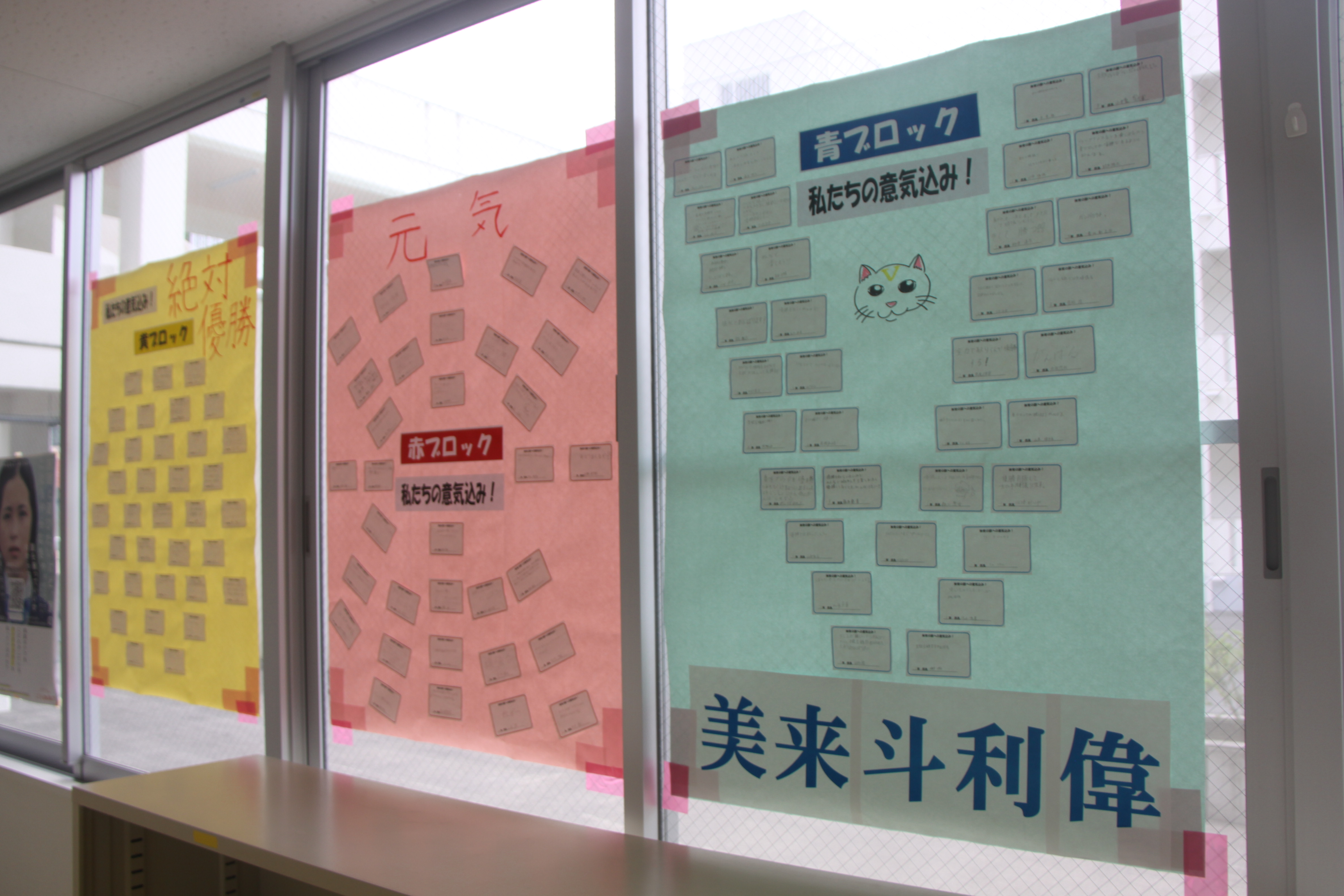
◎HINASE LEGACY
山陽新聞(5/25)を紹介します。










◎「先輩の背中を見て学ぶ・・・そんなヒマがあったら すぐに訊け」(5/27)
今日から木下先生が、教育実習生として、三週間、教育の最前線で「教師としての学び」を深めていきます。私たち教職員も全力で応援していきます。今週は、オンラインによる生徒朝礼でした。台風の接近によって、雨の月曜日スタートとなりました。天候の状況で、時間割の変更があるので、確認しましょう。
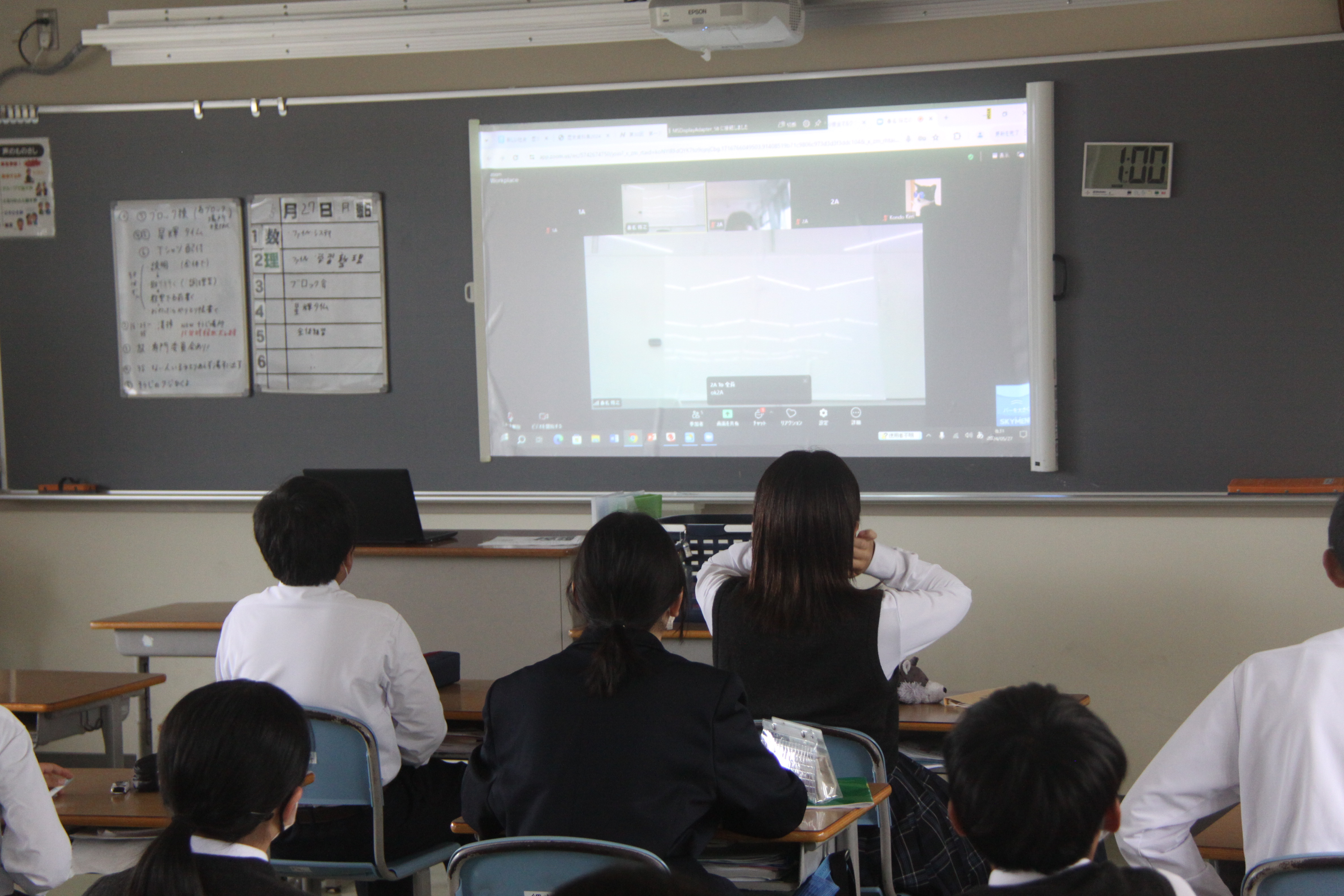


◎先へ 前へ(5/24:6月1日へ向かって)



◎AMAZING HINASE (5/23.24:海洋学習)


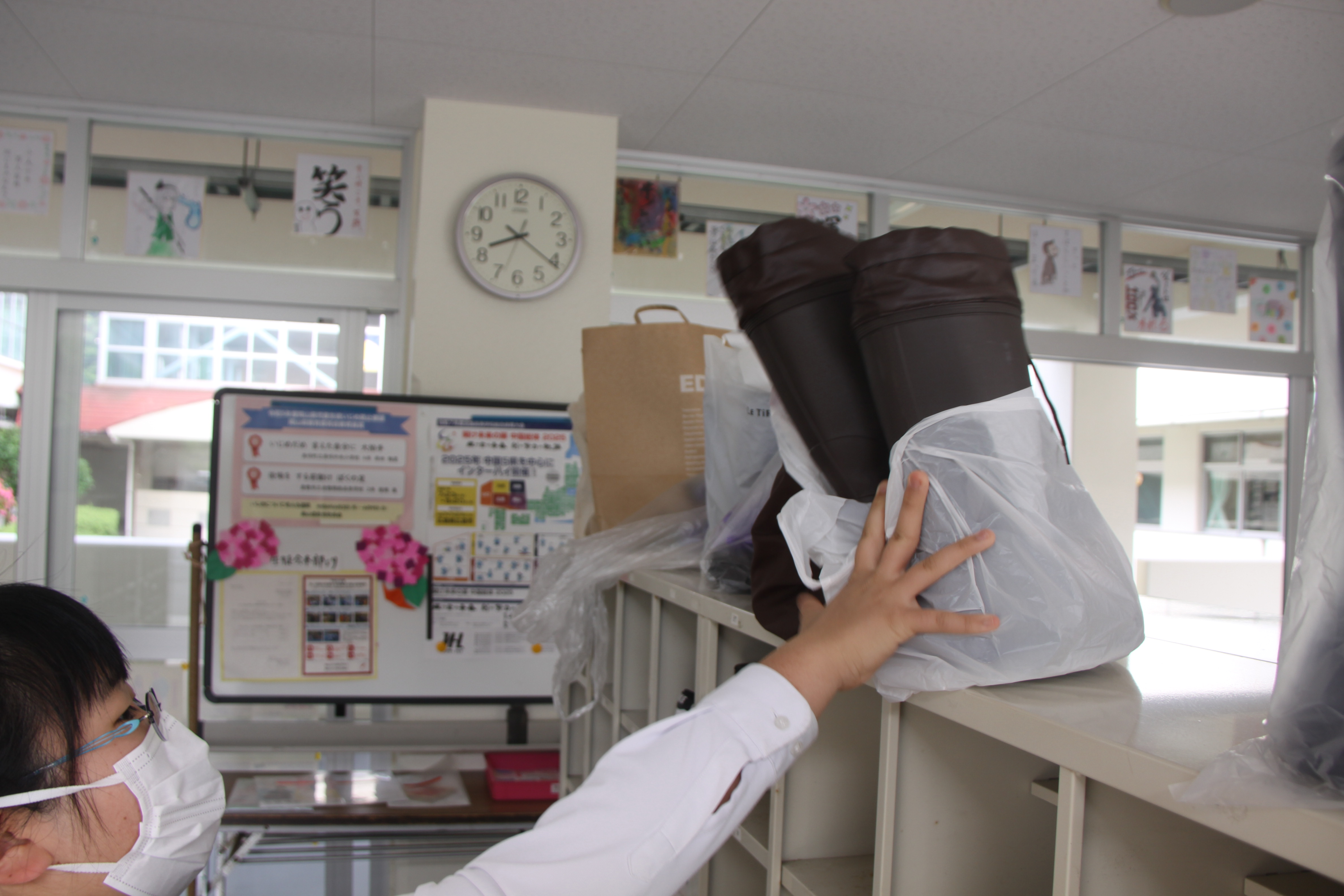



今日と明日、流れ藻の回収に取り組みます。
◎〈ニュースにはならない日には虹は出て消えて私がおぼえています。 桝野浩一〉(5/22:ブロック練)



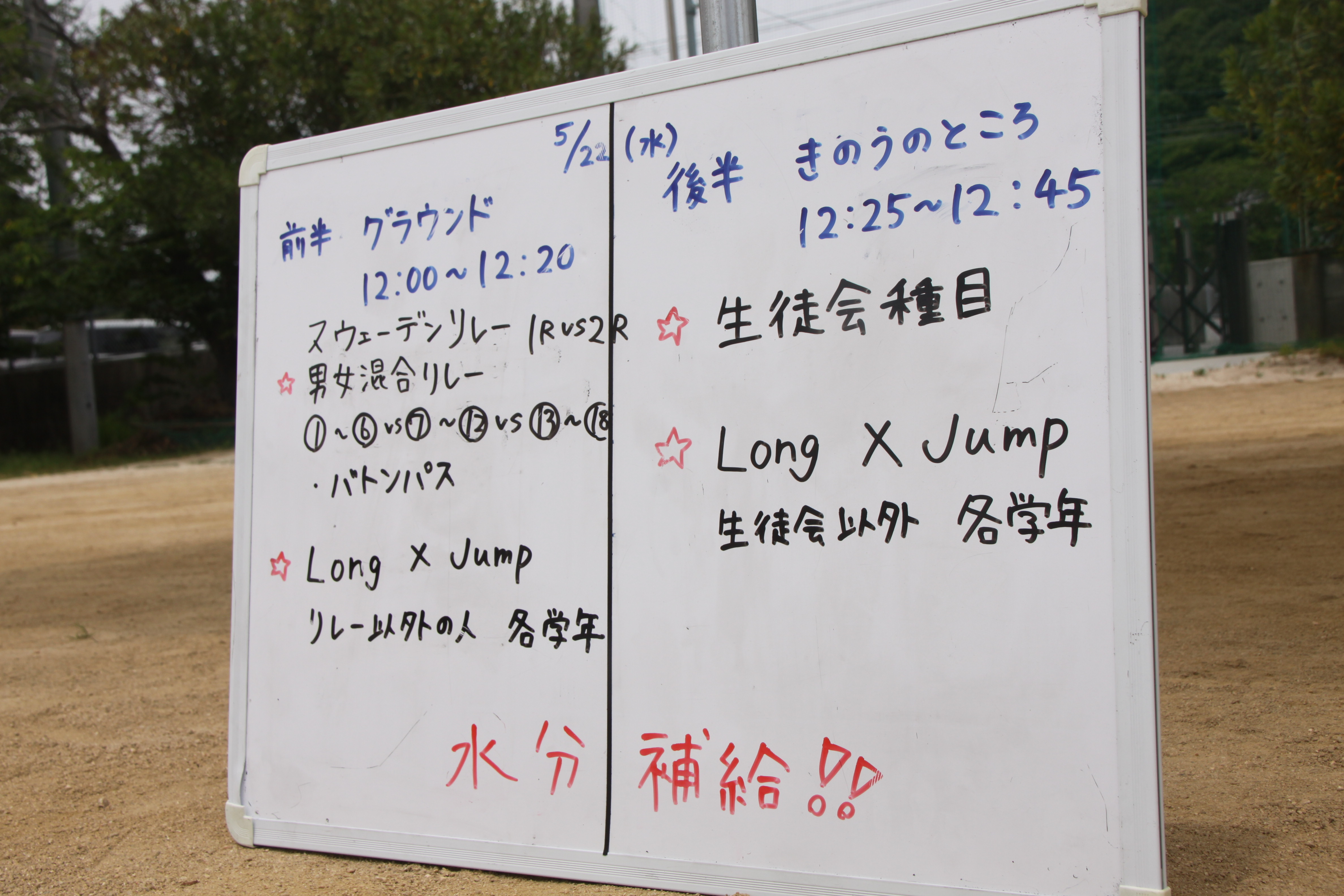





◎〈どの本棚からだつてほんたうのところアンネのへやへはひれます 平井弘〉(5/22:第3回校内研修)

今年度の校内研究テーマは、「課題に向き合い、自ら学ぶ生徒の育成~個別最適化された学びを通して」です。
◎「ナインは9人だけではない」 (5/22:多くの人に支えられて)


◎届けるよ わたしたちの熱量 (5/21~星輝タイム)






◎「心がうごく授業」を創るために。(5/21:学校訪問)
岡山教育事務所から東先生、大橋先生、備前市教育委員会小中一貫教育課から谷口課長、三宅授業改革推進員が来校されました。この日は、学校のビジョンと戦略を支援する日生中学校アクションプラン(AP)に関する学校訪問でした。(この訪問を通して、学校経営アドバイザーの視点で、各校における学校経営アクションプランに係る取組が促進されるように助言をいただきます。また、このホームページでの学校教育目標は、APの内容のひとつになっています。)会では、日生中学校アクションプラン基づいた面談、授業参観、そして「効果的な評価・改善のあり方」について協議を行い、今後の学校経営や校内研修に大いに有意義な時間となりました。授業参観では、生徒らの前向きに授業に取り組む姿は、いつもと同じく、とても素晴らしいものでした。✨


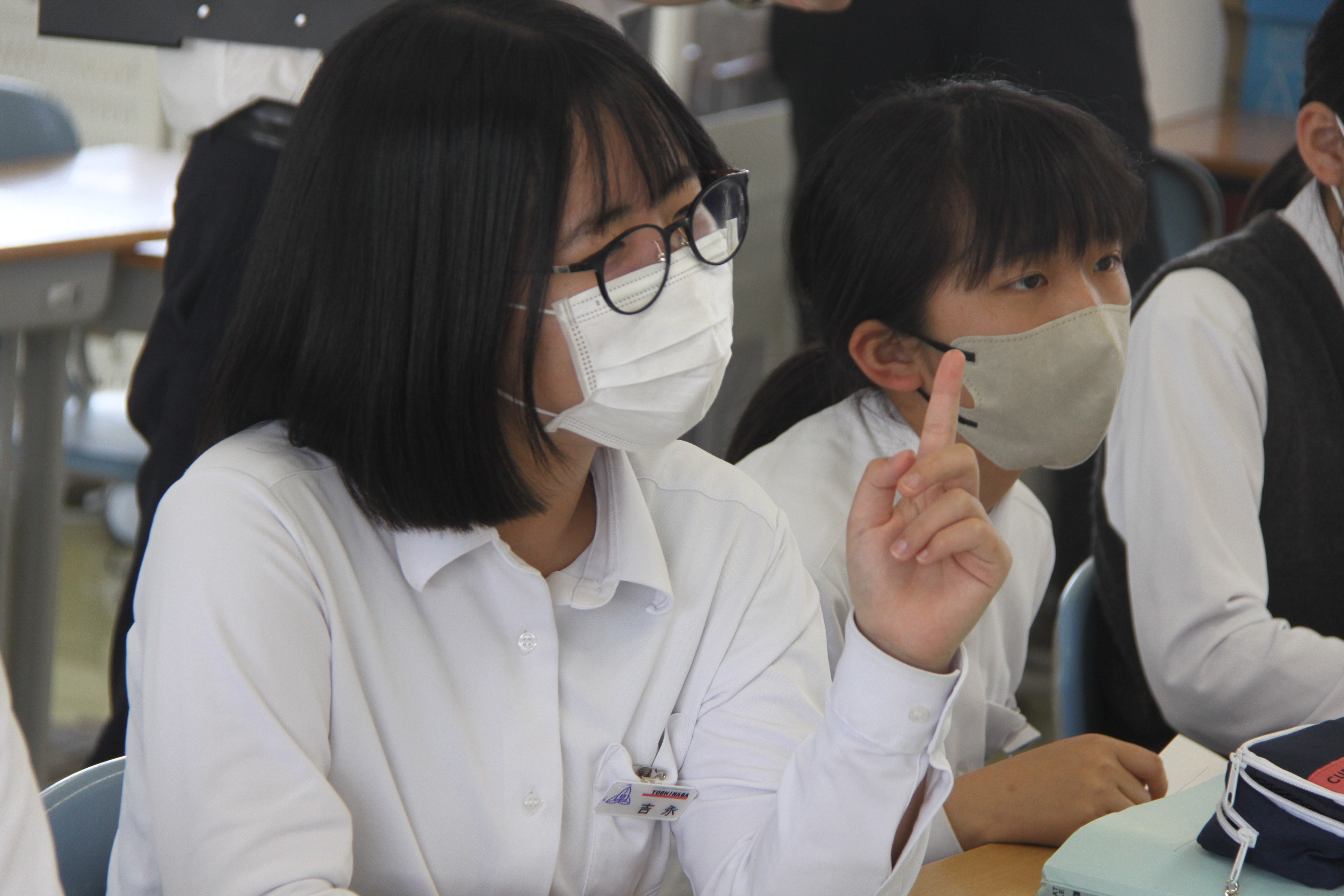







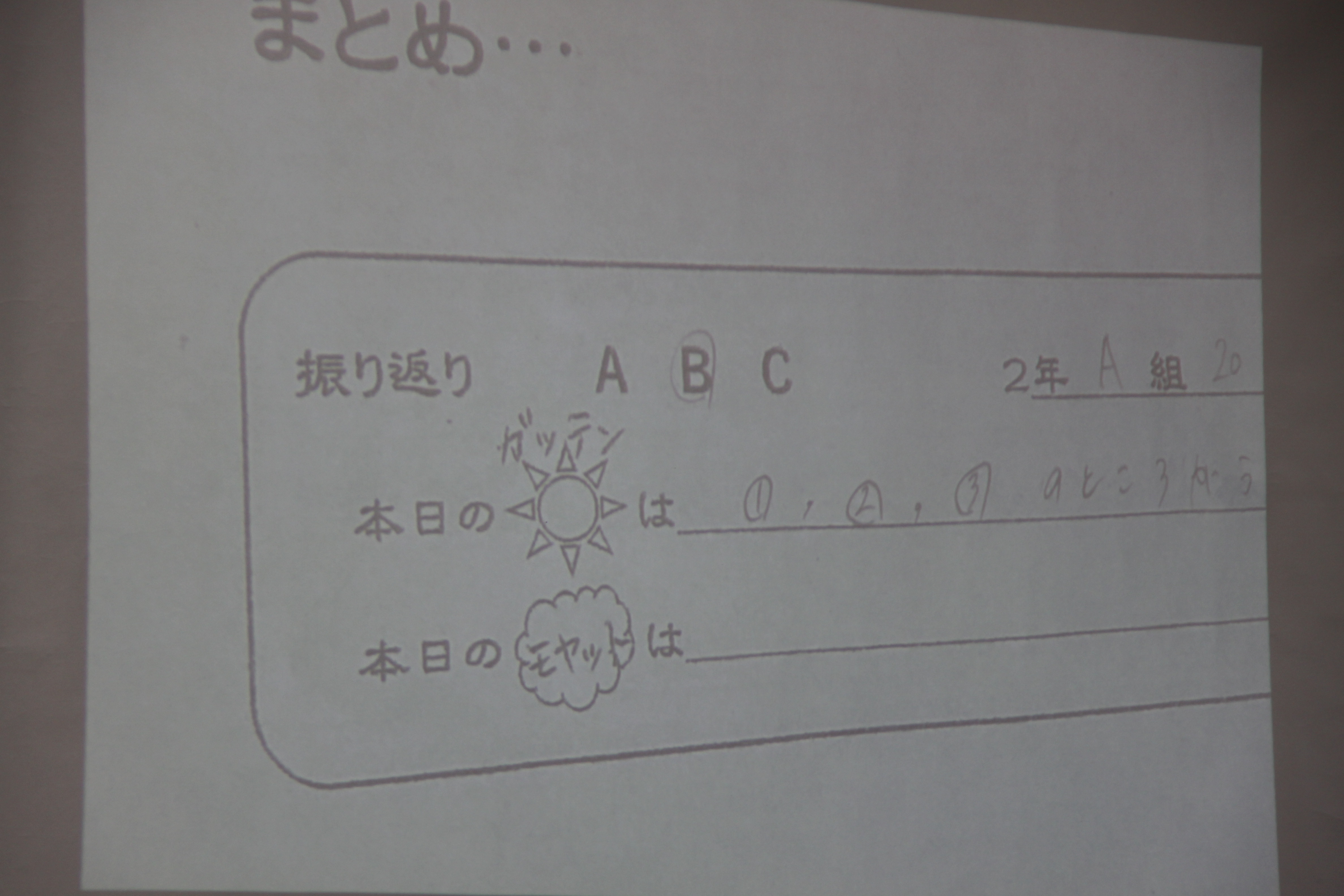
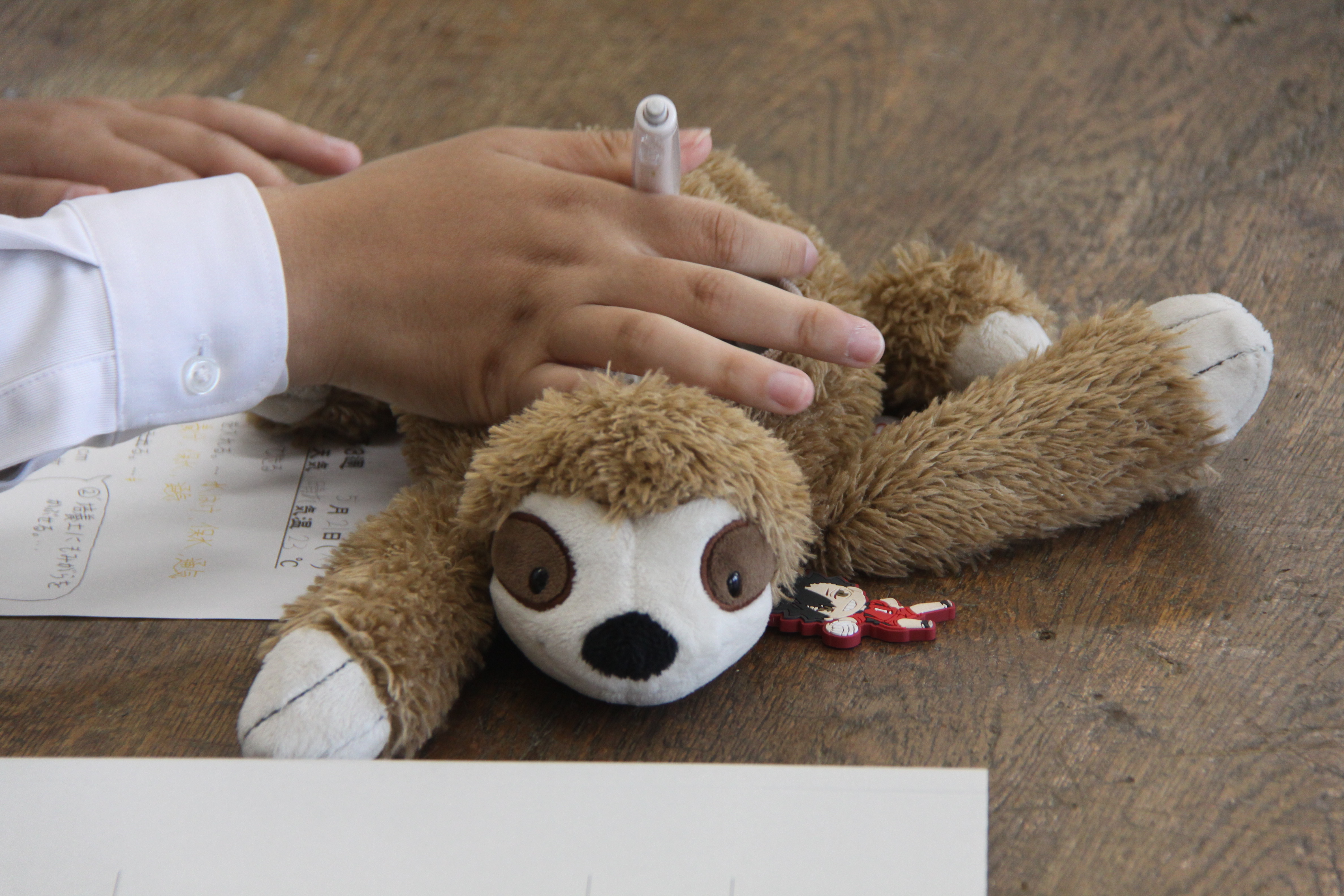
なりたい人は私の中にいる
◎私たちの星輝祭(5/21 7:40)






Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. Steve Jobs
取組において偉大なことは、一人の人間によって成し遂げられるものではなく、チームによってなされる。
◎ひな中の風景(5/20)
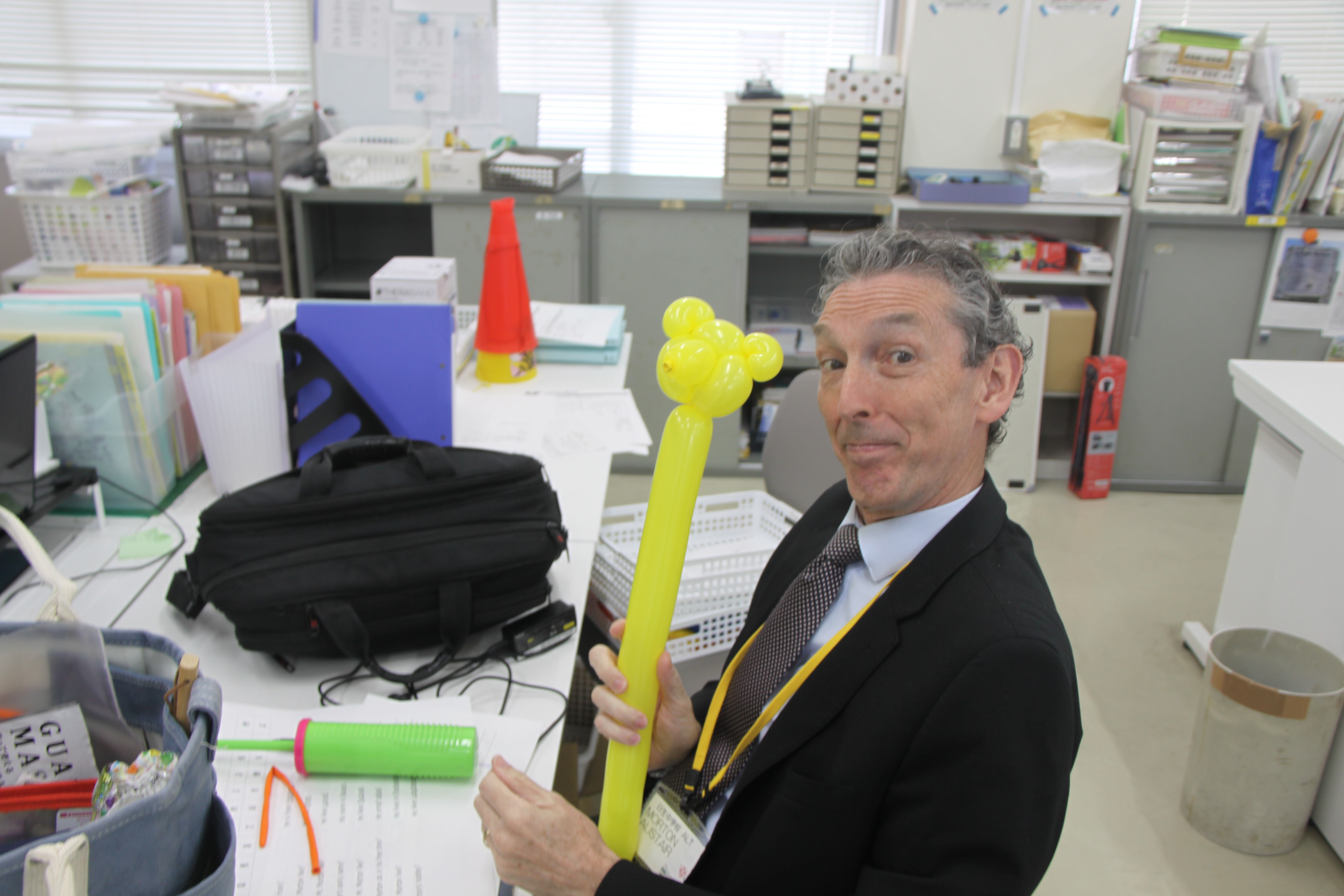

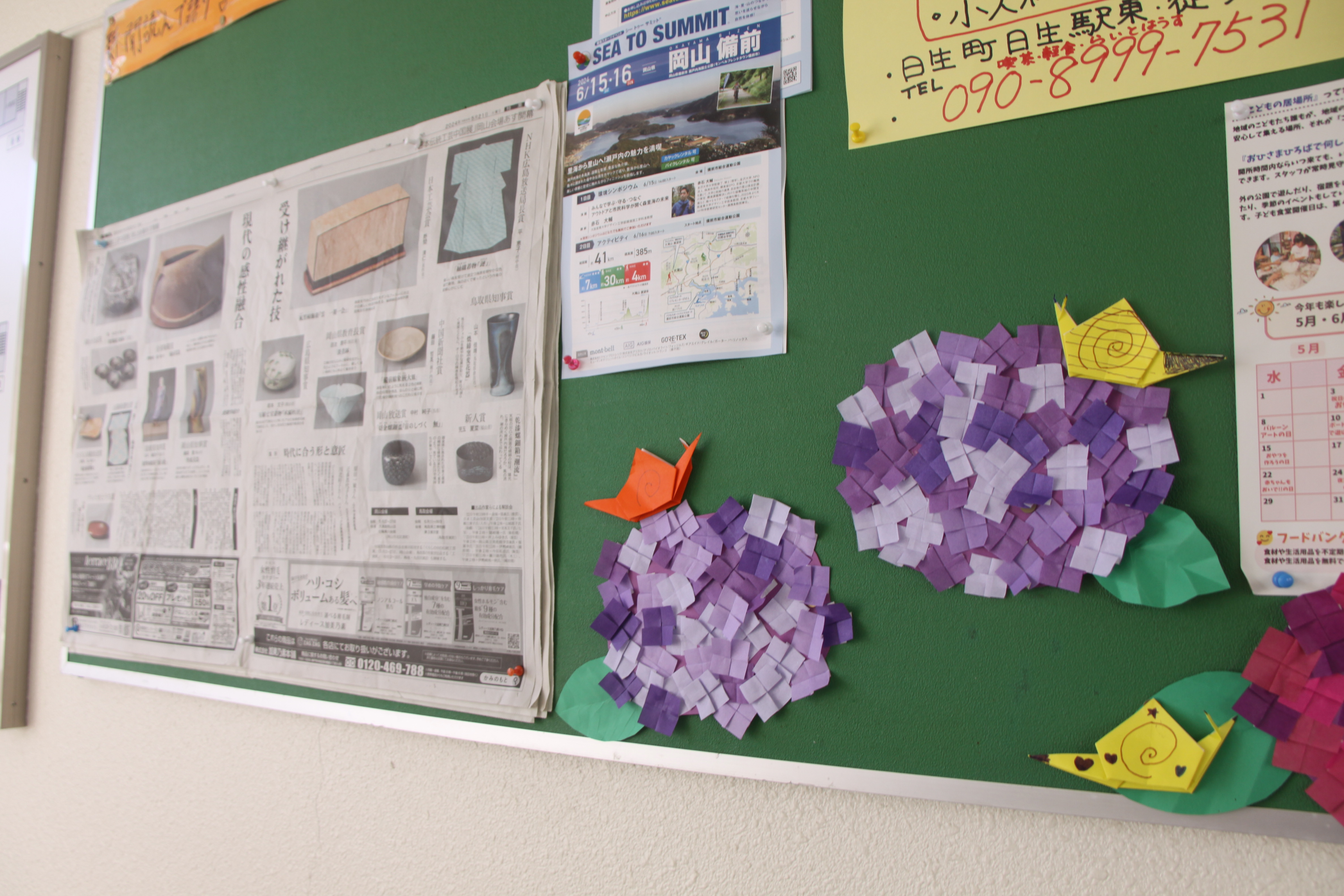
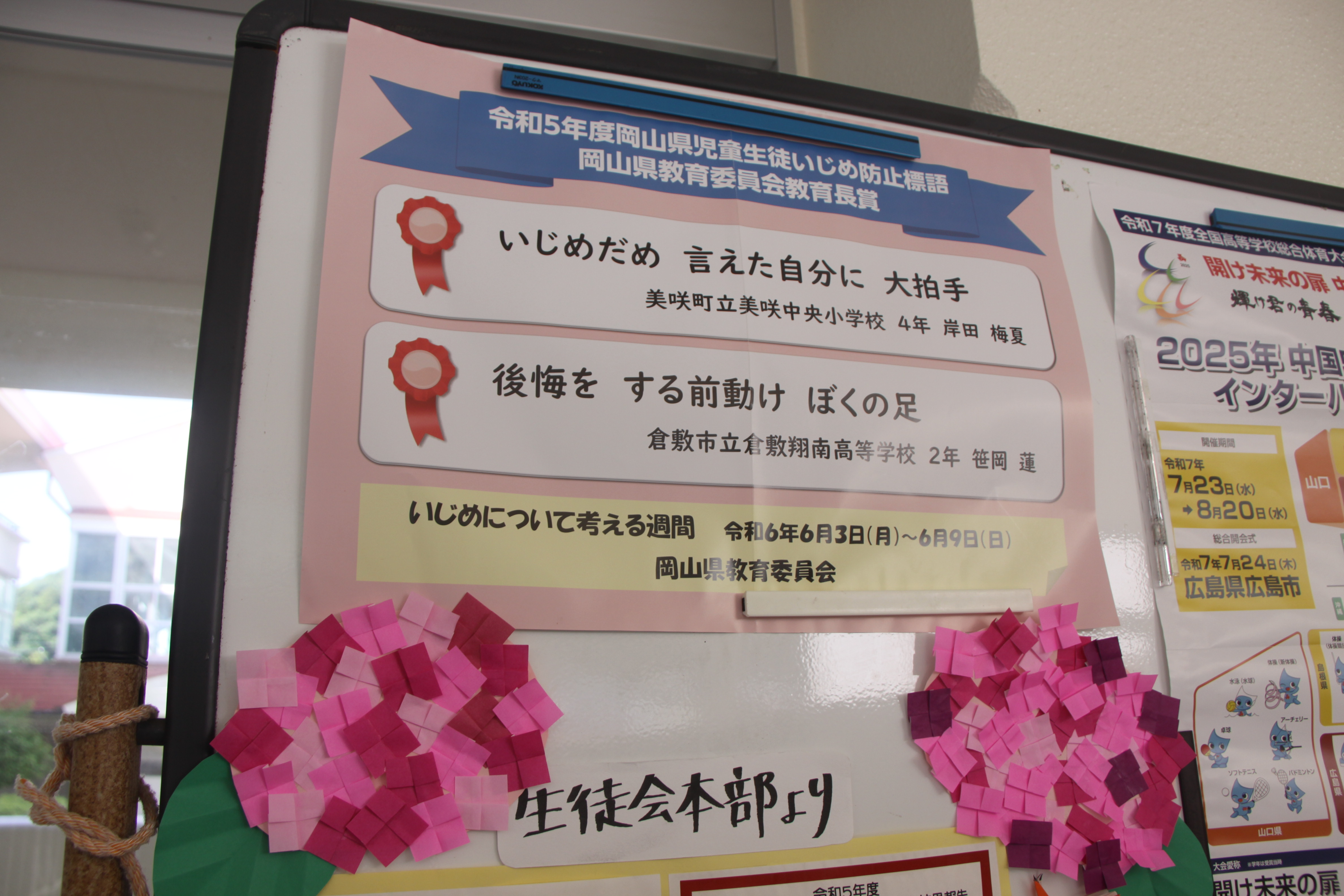


◎私たちの星輝祭
~多くの人に支えられて(5/20)
今日は、第2回ブロック会、環境委員会の呼びかけによる、校内ボランティア清掃を行います。そして、熱中症対策として、スポーツドリンク飲料可期間(~6/1)となります。一人ひとり、体調管理を大切に、仲間との練習に取り組んでいきましょう。
水筒の準備をいつもありがとうございます。さらに、PTAからも熱中症対策のサポートをありがとうございます。

◎私たちの星輝祭~HINASE LEGACY (5/17:3年生から1年生へ)



舞い 起こせ 沸かせ 轟け 動かせ 驚かせ
◎HINASE LEGACY(5/17)

◎「生きる」ためには「想像力」(5/16)
備前県民局建設部東備地域管理課長の中務さんをお招きして、二次避難(体験)を行いました。先日の避難訓練時に雨天だったので、1年生対象の上山公園への二次避難(体験)に、本日取り組みました。中務さんから、被災地支援に関する多くの経験から、「生き残るためには想像力が大切である」ことなど、的確かつ実践的なアドバイスをいただき、南海トラフ地震等の備災の意識と行動力を高めることが出来ました。ありがとうございました。
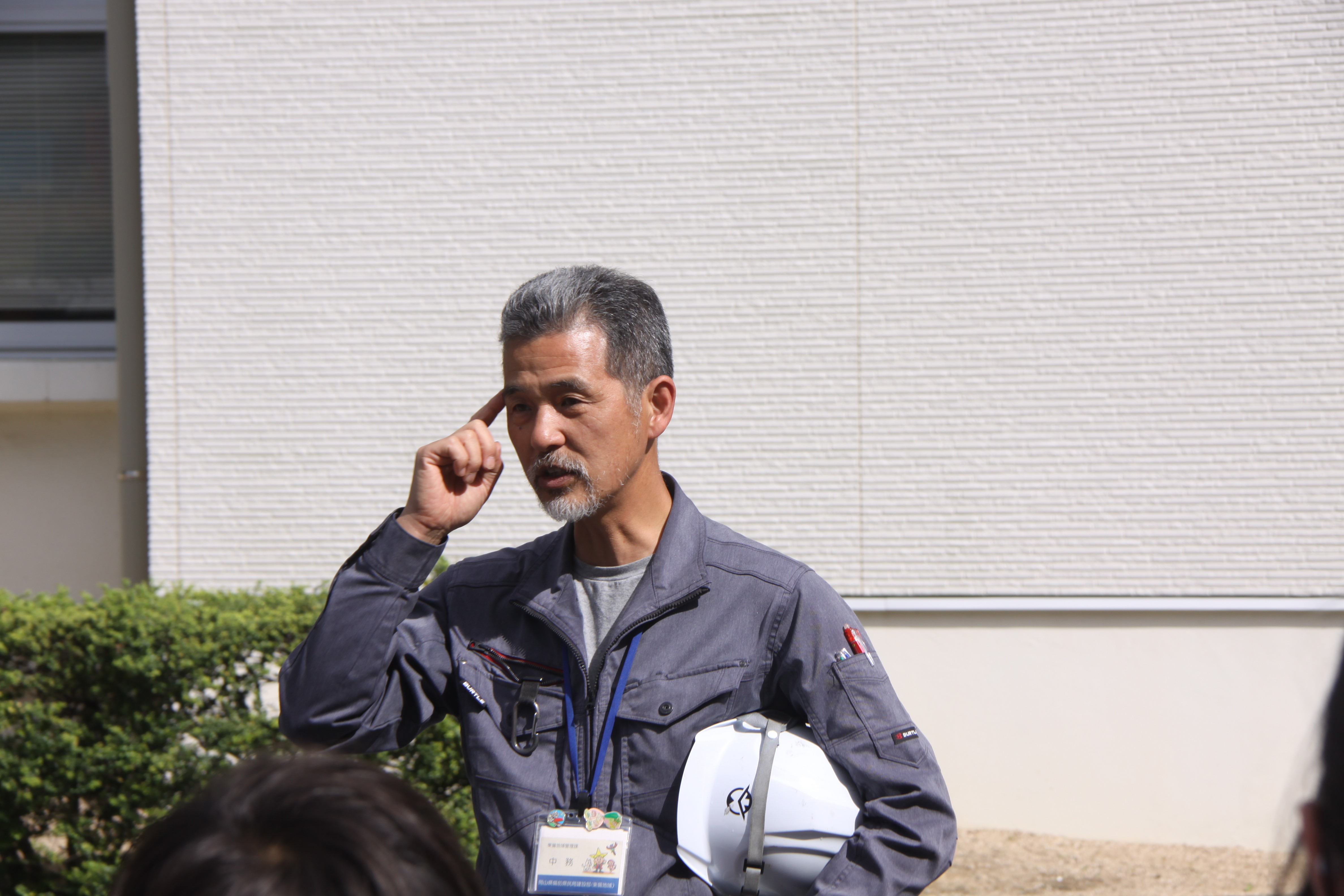
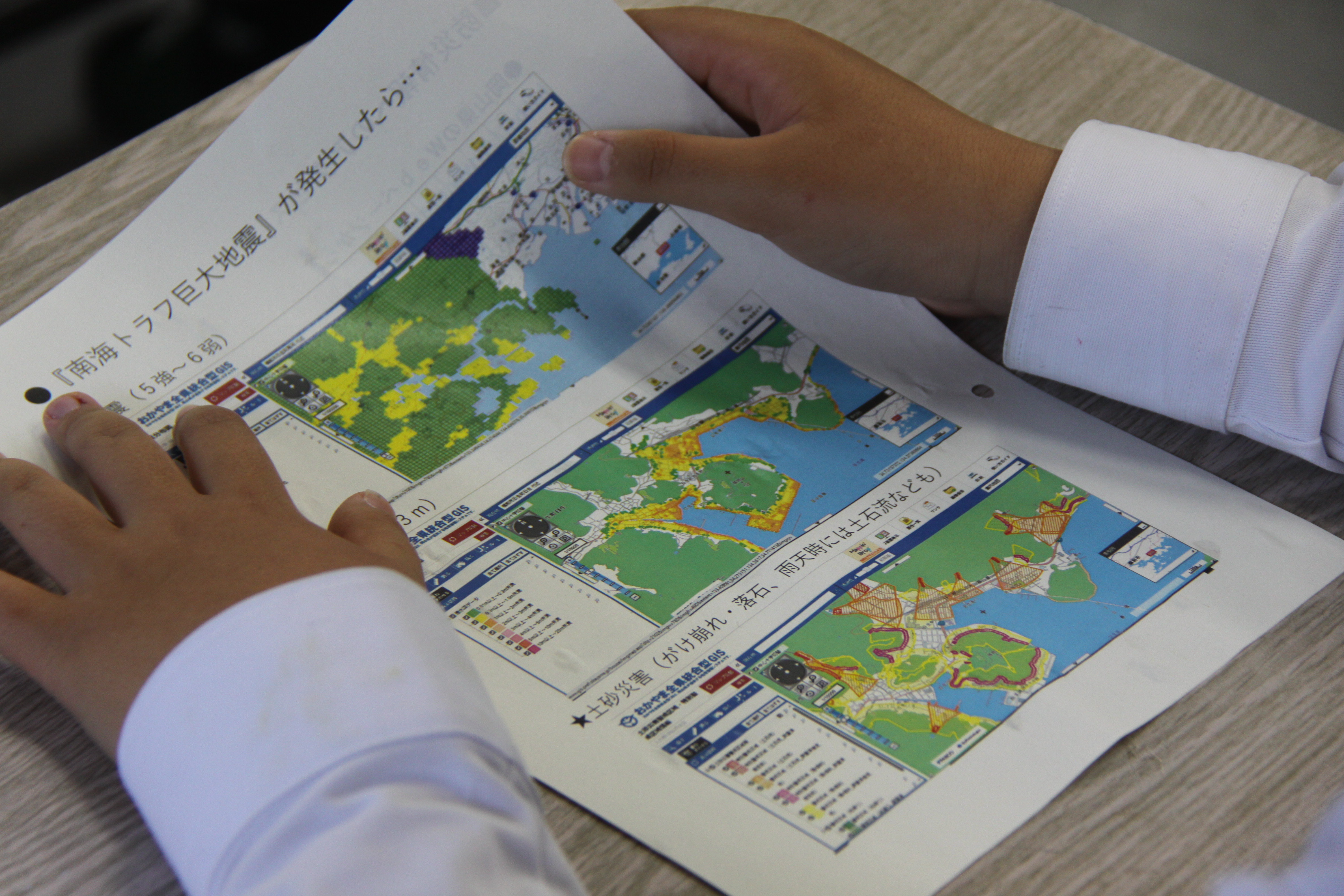




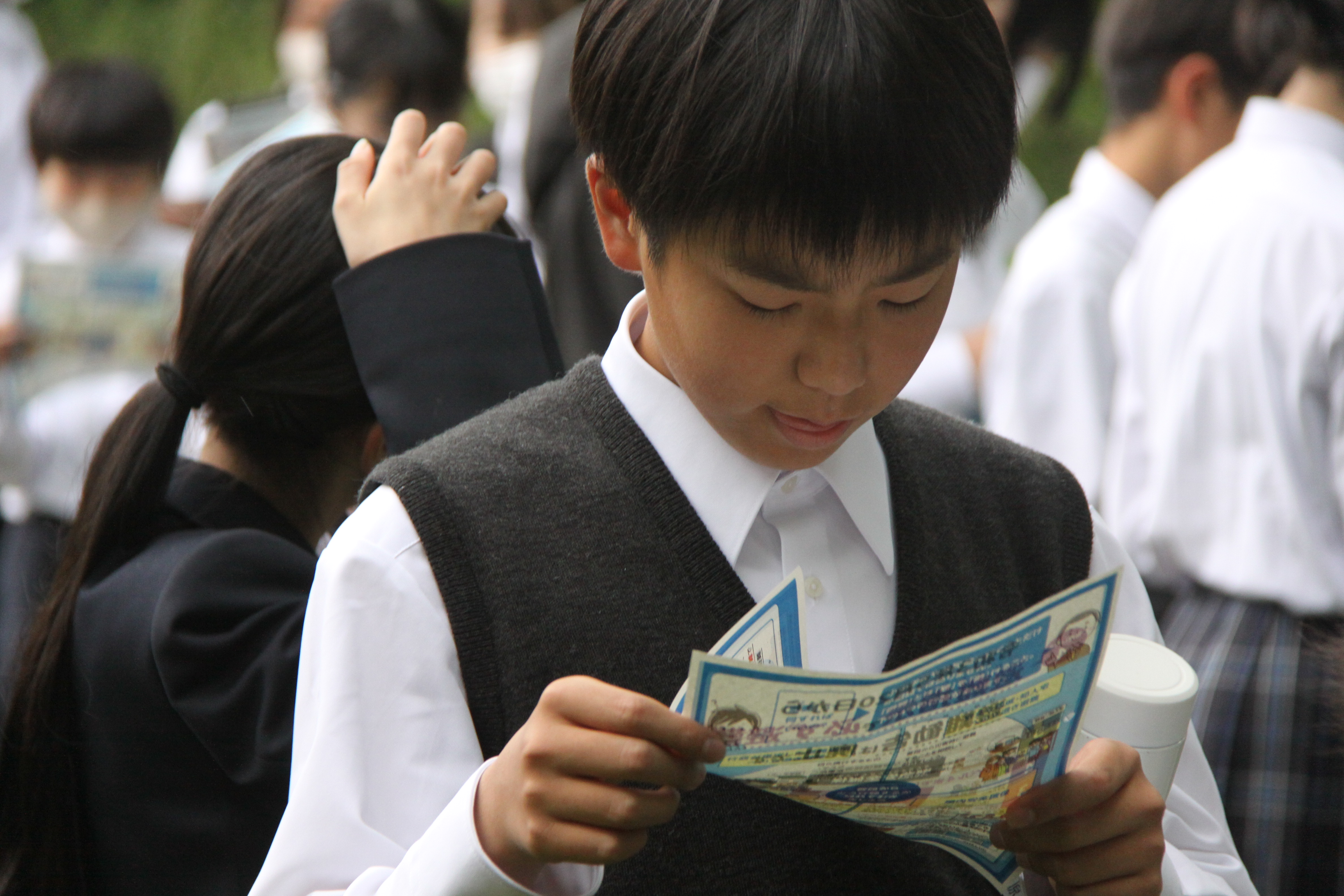
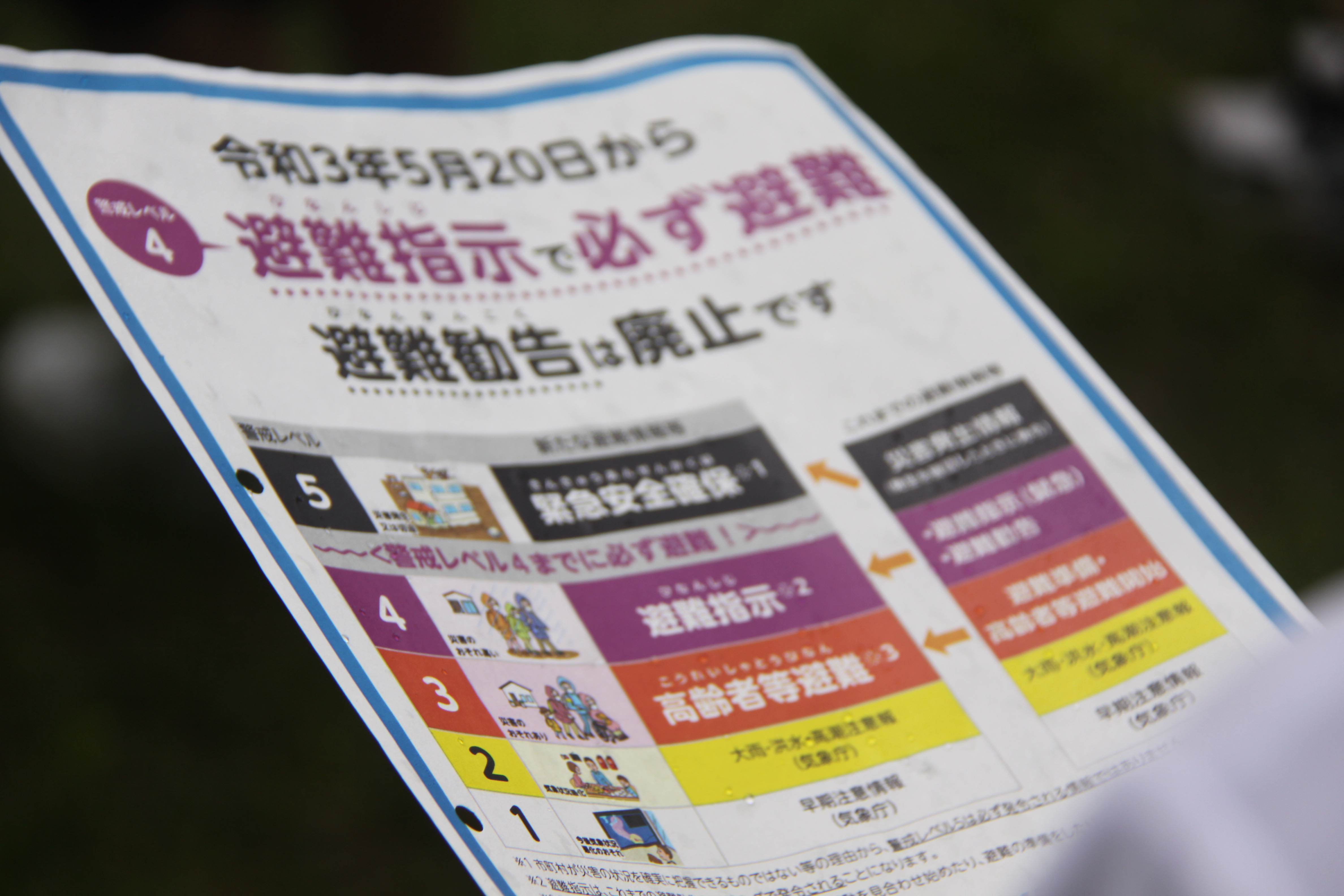

「【減災新聞】「山へ登れ」 津波当時の校長回想( 神奈川新聞 2019年2月10日(日)より)
「山へ登れ」。津波避難の経験はなかったが、とっさの判断で発した一言が児童92人の命を救った。避難場所でありながら、校舎3階まで浸水した岩手県陸前高田市立気仙小学校。東日本大震災当時の校長、菅野祥一郎さん(68)は、間一髪で逃げ込んだ裏山の足元まで巨大津波が迫った8年前の教訓をかみしめる。「守るのはマニュアルではない。命だ」
2011年3月11日午後2時46分、菅野さんは学校におらず、付近を流れる気仙川の対岸にいた。「戻らなければ」。すぐに踵(きびす)を返したものの、津波の恐れがあるため通行止めとなった橋を迂回(うかい)しなければならず、学校に着いたのは地震の30分後だった。
地域の津波訓練で避難場所となっていた同校には、児童や教職員だけでなく、大勢の住民が身を寄せていた。校庭に整列する児童の姿に一瞬、安堵(あんど)もしたが、カーラジオから聞こえた「津波」という言葉に思い直した。「山へ登らなければ」
もともと学校としての訓練は行っていなかった。しかし、児童らが並んでいた校庭は標高が低い。「何かあったら、あそこに逃げるしかない」。なんとなく頭に描いていた裏山への避難を決断できたのは、日頃から周囲の状況に目を配っていたからに他ならない。
斜面に丸太の階段が付いた裏山には、3階建ての校舎(高さ約16メートル)とほぼ同じ高さに広場がある。「低学年の児童から避難すると時間がかかり、後がつかえてしまう」と考え、6年生を先頭に急いだ。
校庭に津波が流れ込んできたのは、最後尾の菅野さんが登り終え、肩で息をしていた時だった。校舎は3階まで浸水し、全壊。「屋上の受水槽の上に逃れた人は大丈夫だったようだが、逃げ遅れて校庭などで巻き込まれた住民も少なくなかった。校舎や体育館への避難では助からなかった」。逃げ込んだ裏山でも、足元の1~2メートル下まで津波が押し寄せてきた。
自身が小学生だった1960年のチリ地震津波の際は「山側に住んでいたので避難はしなかった」という菅野さん。それでも震災時に避難を決断できたのは、「子どもの命を守るのは教師の責任」との思いがあったからだ。その教訓から、訴える。「過去の津波を経験した年配者はすぐに避難するが、最近はテレビやラジオの情報を確認してからという人が多いようだ。でも、とにかく急いで高台に逃げる。これしかない」
自助のヒント 陸前高田の被害
東日本大震災による岩手県陸前高田市の死者・行方不明者は計1806人(昨年9月時点、総務省消防庁集計)に上り、同県内で最も多い。沿岸部が広範囲に浸水したほか、津波が気仙川など複数の河川を遡上(そじょう)し、内陸部にも被害が広がった。浸水面積は13平方キロに及び、市立気仙小学校をはじめ、県の津波浸水予測を基に市が避難場所としていた67カ所のうち38カ所が被災。市の検証報告書では「避難が何より重要」「避難所に逃げたら終わりではない」と指摘している。
◎わたしたちのはじまりの風景11
ここはどうでしょう?



◎HINASE LEGACY(5/16)
今年も、今週も、生徒会中央役員によるスマイルあいさつ運動(仮称)。




レガシー(legacy)は、英語では「遺産」という意味です。 もともと亡くなった人が遺したものを指しますが、日本語のレガシーは「過去に築かれ、受け継がれていくもの」という意味で使われます。
◎十五歳の春へ
第5回ひなせ親の会(情報交流会)のご案内
特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。
◎これからの進級・進路について、新しい情報を交換できる会です。
◎お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。
(カウンセリングや講座ではありません)
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)さんからのアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。
お気軽に、お申し込み・ご参加ください。
ひなせ「親の会」のご案内
1日 時 6月7日(金)17:30~19:00(仕事や用事が終わり次第どうぞ😀)
2 場所 日生中学校 D組教室(北棟1階)
3内容
子どもが「学校へ行きづらさ」を感じたり、生活の中で「しんどい」時など、どのようなはたらきかけがよいのでしょうか?日常のサポートや支援の有り様について一緒に考えましょう。また、進路実現のために「いま」からしておくことや大切なことについても話しましょう。
4参加者 小・中学校の特別支援教育のニーズのある生徒の保護者や関心のある方、日生西・東小学校、日生中学校の先生や地域のサポーターなど、久次(日生中)小寺(SS
W)主催:日生中学校区連携推進委員会(特別支援教育部会)
5連絡 参加の希望をお早めに(5月末までに)各学校の担当までお知らせください。何かご不明な点がありましたら、ご連絡ください。
日生西小:(℡72‐0050) 日生東小:(℡74‐0004) 日 生 中:(℡72‐1365)
◎スクールカウンセラーの教育相談やSSWへのご相談も各学校にお問合わせください。
6予定 ひなせ親の会 第6回:7月12日(金)、第7回:8月31日(土)
春いちごの会8月31日(土)(特別支援教育のニーズのある生徒・保護者のための進路情報交流学習会)
◎6.1だけじゃない(5/15:星輝会体育の部 係会)


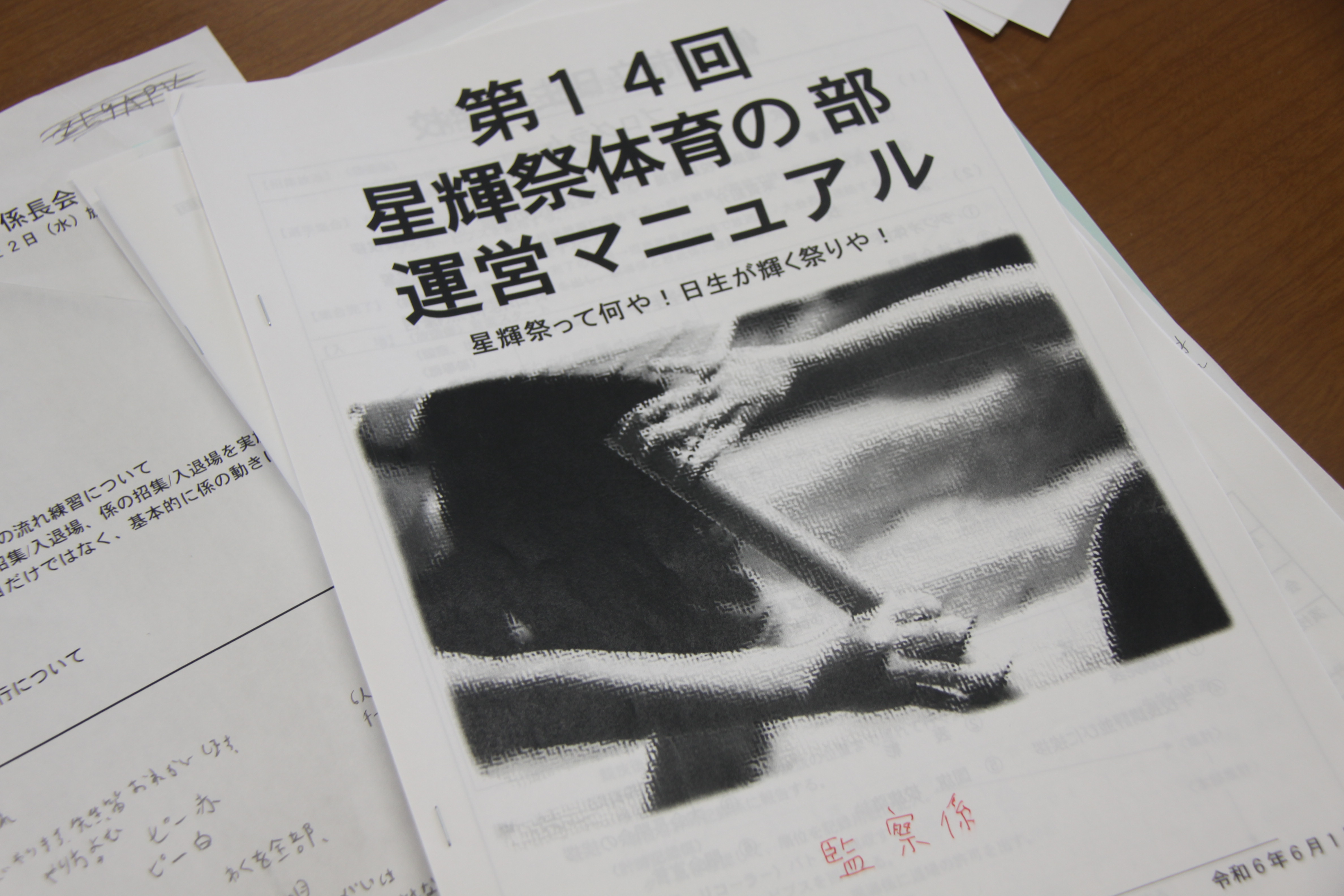
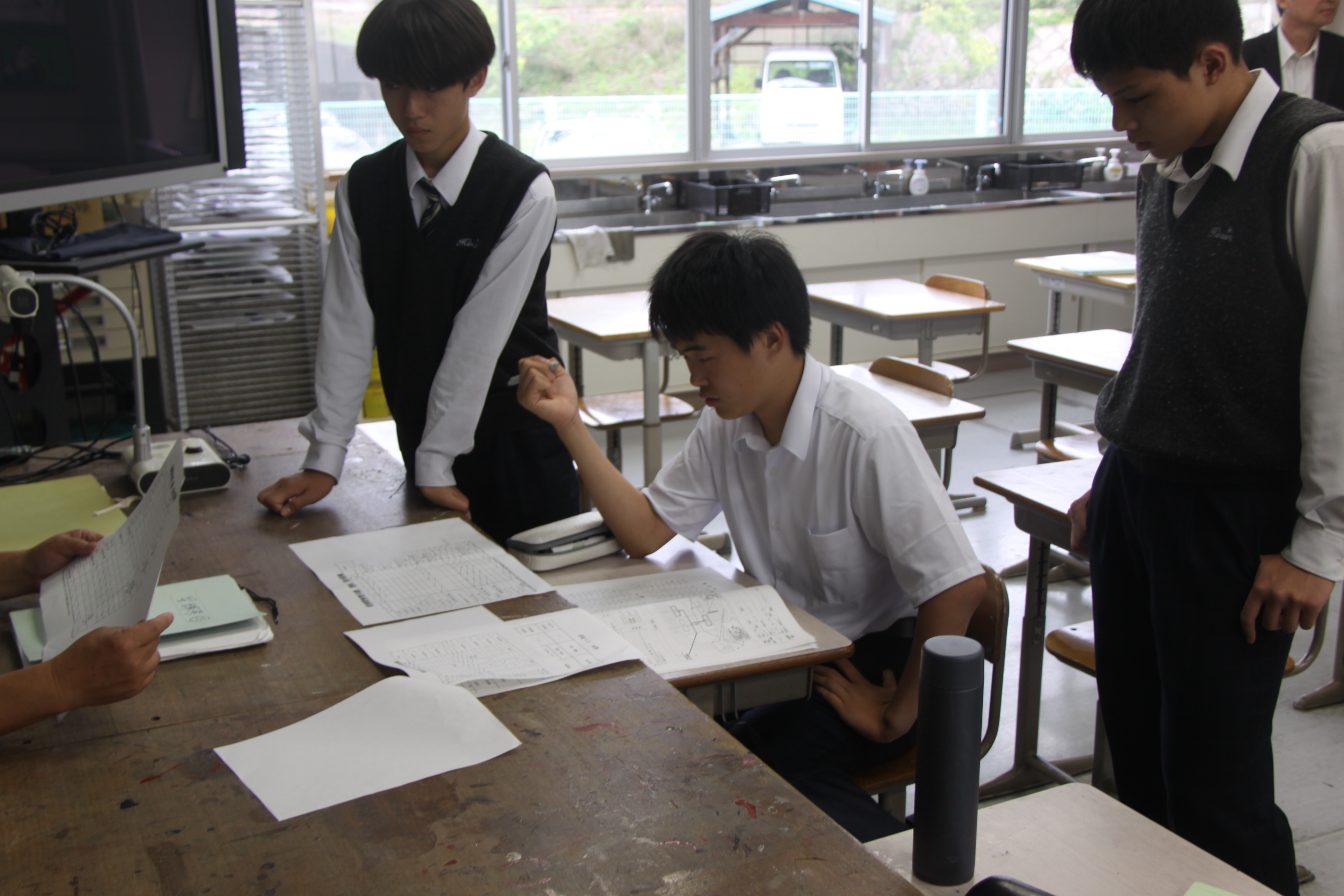
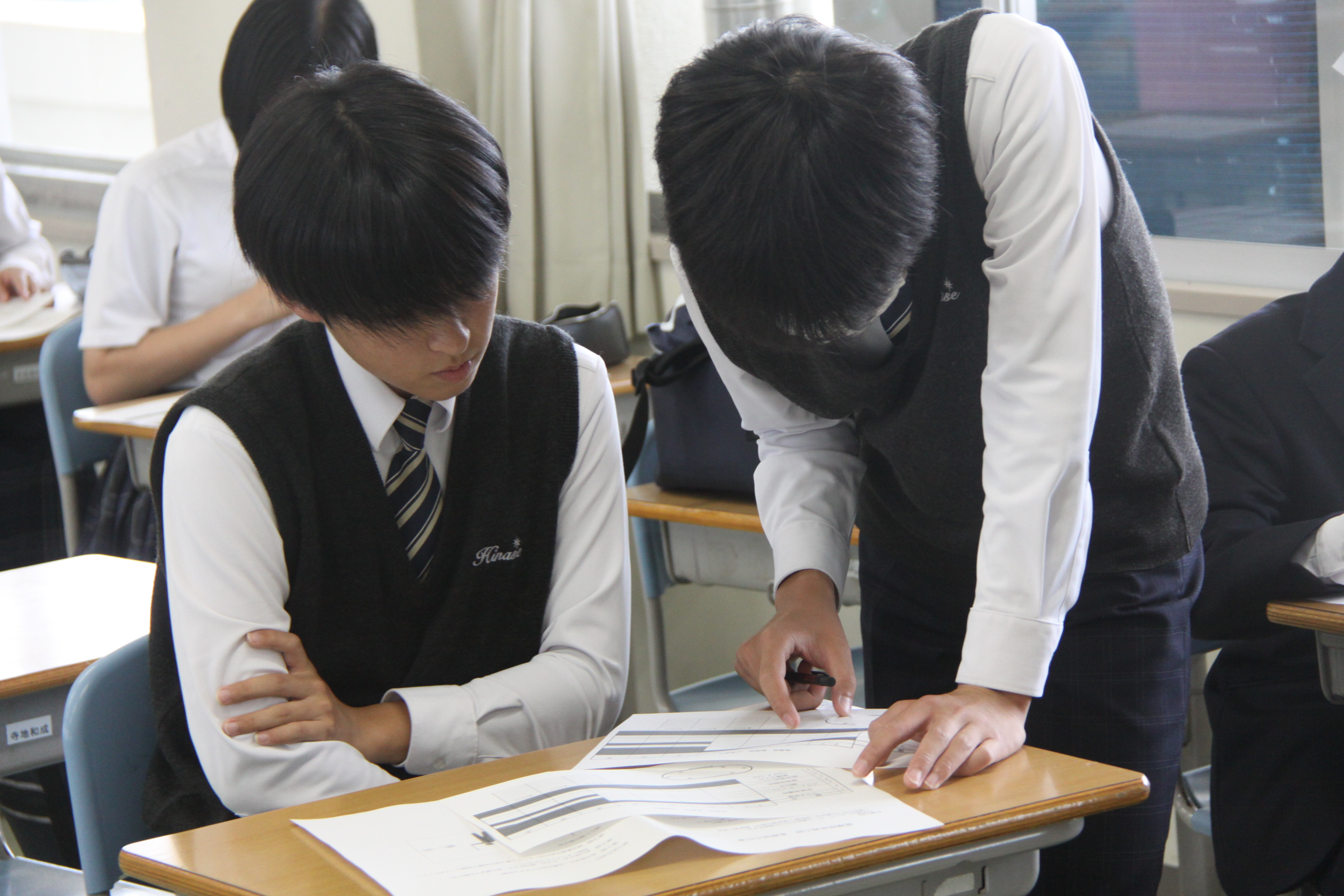
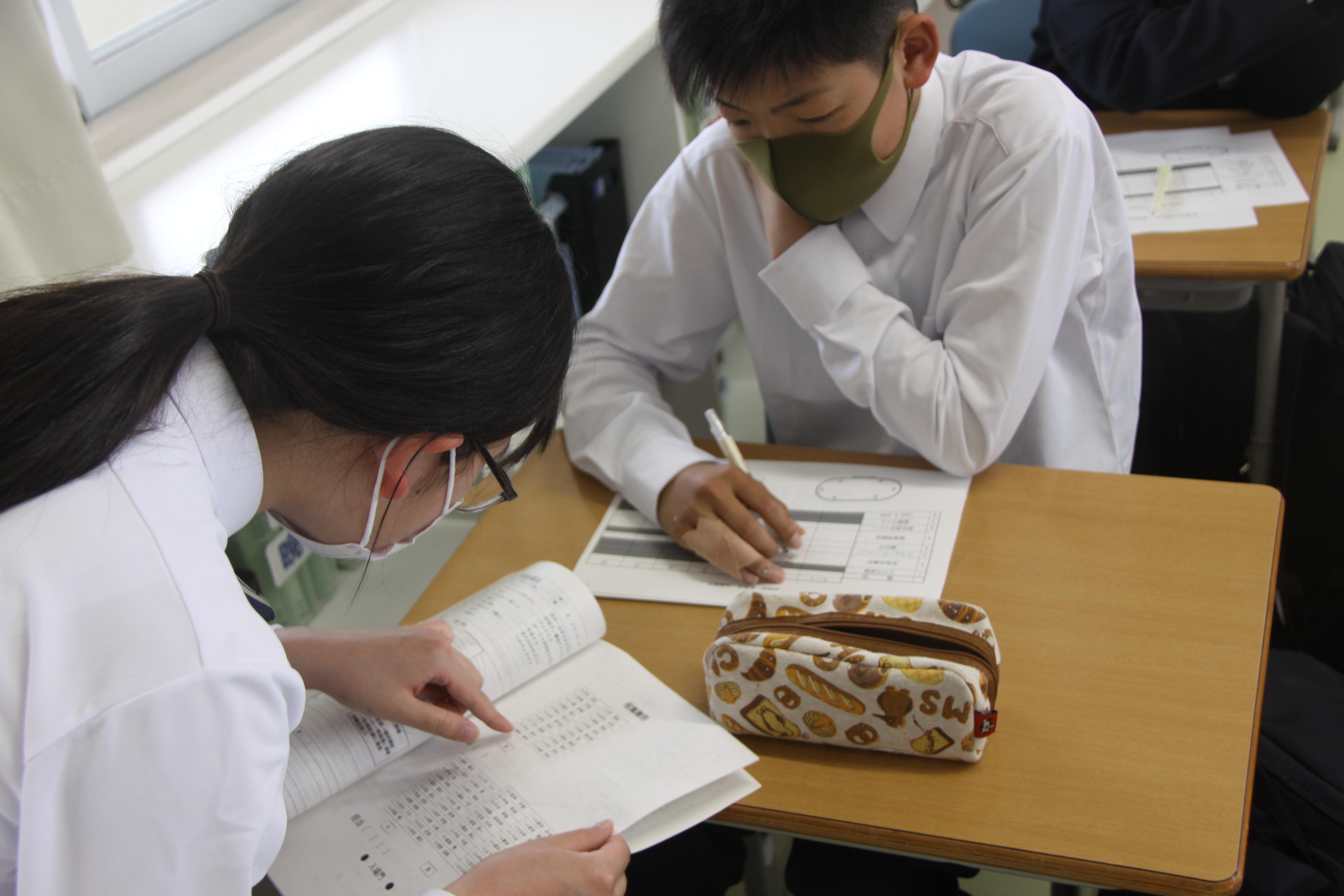
◎いま、ひな中を創っています。(5/15)


◎ひな中は多くの人とつながっている。(5/15・朝)
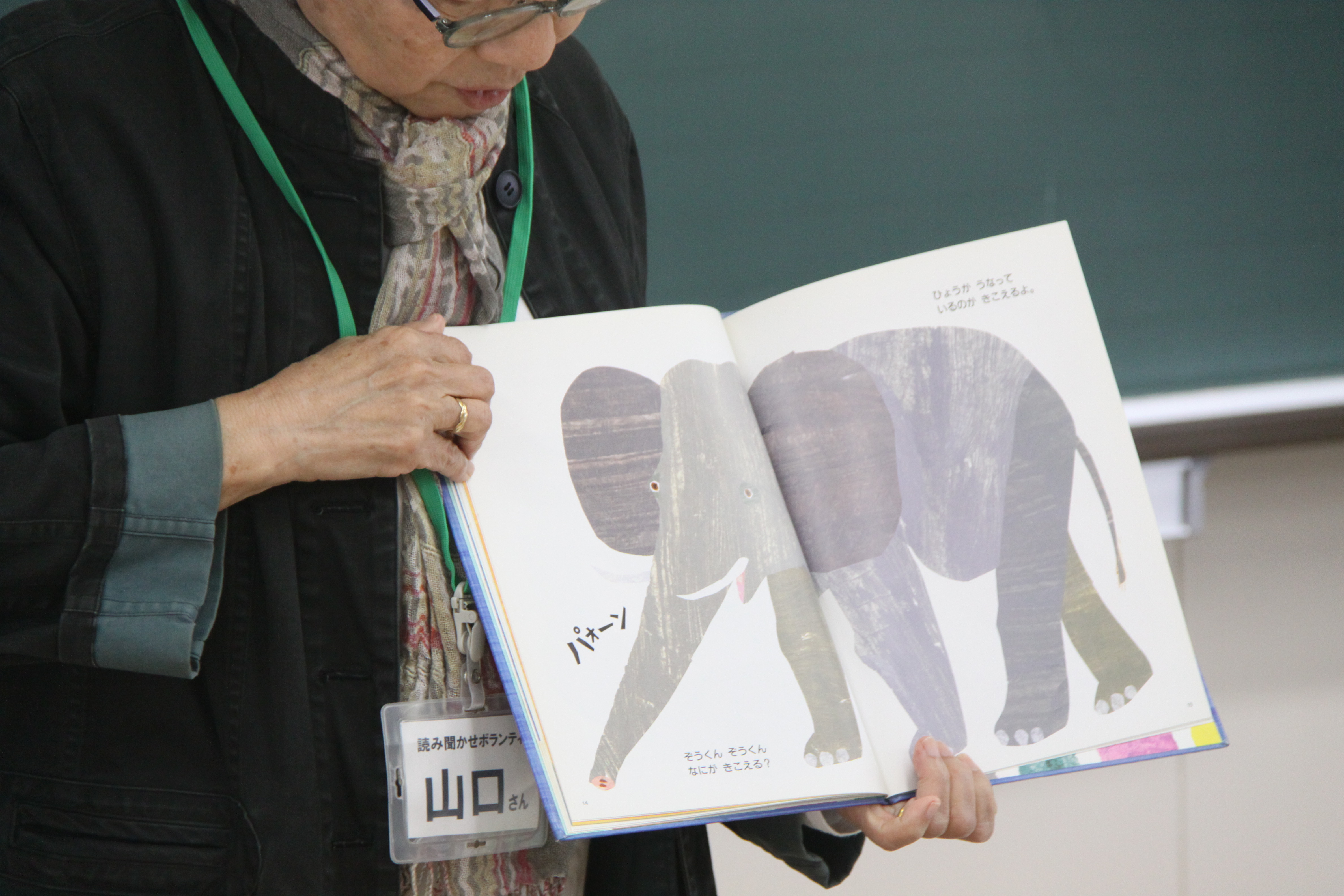


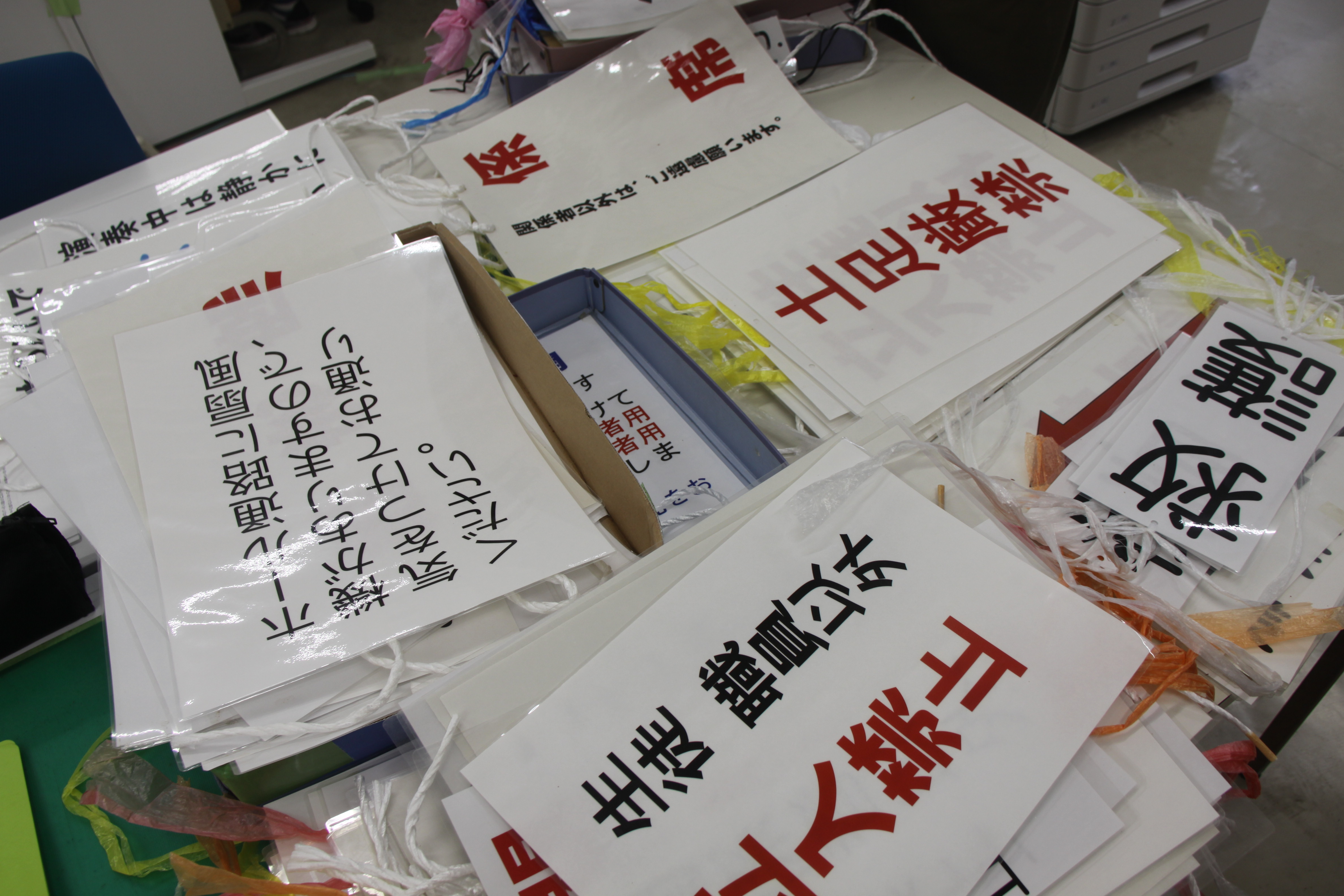

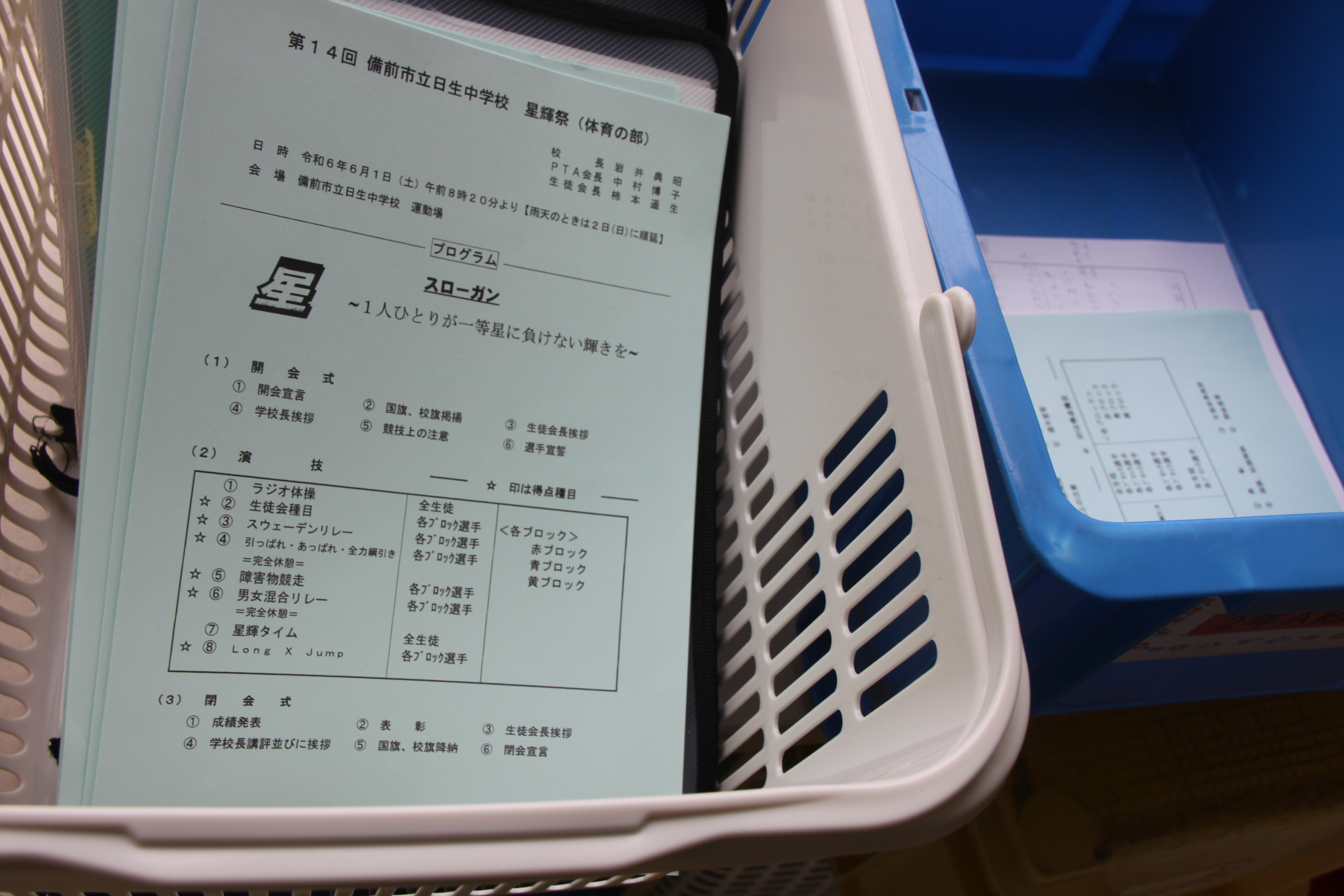
◎社会・地域とつながる目を。多くの方に支えられて
ひな中は、地域や社会の情報や、学校の仲間の活躍などの記事を掲示しています。地域でのイベント、生徒への告知等があれば、学校までご連絡・ご相談ください。



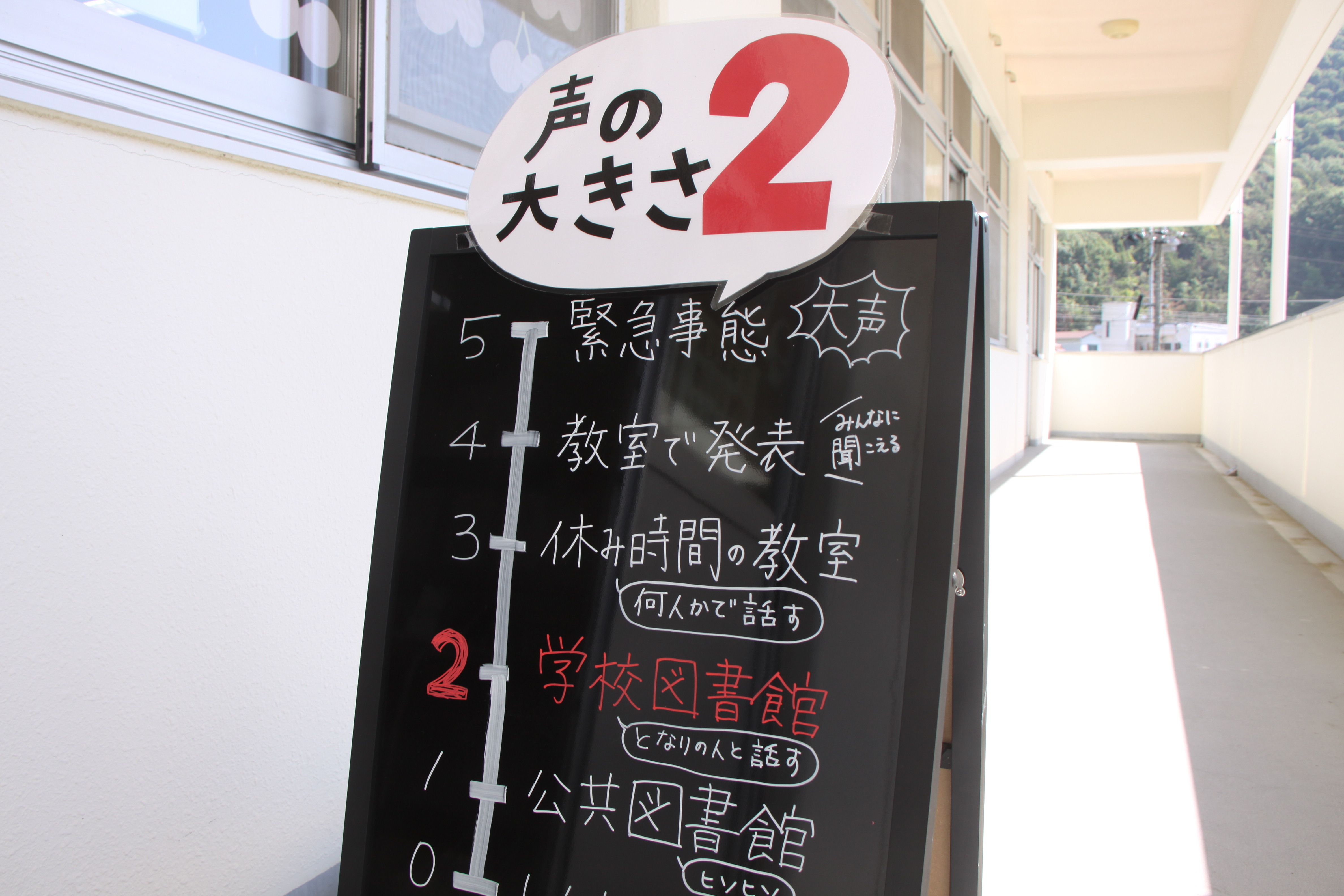
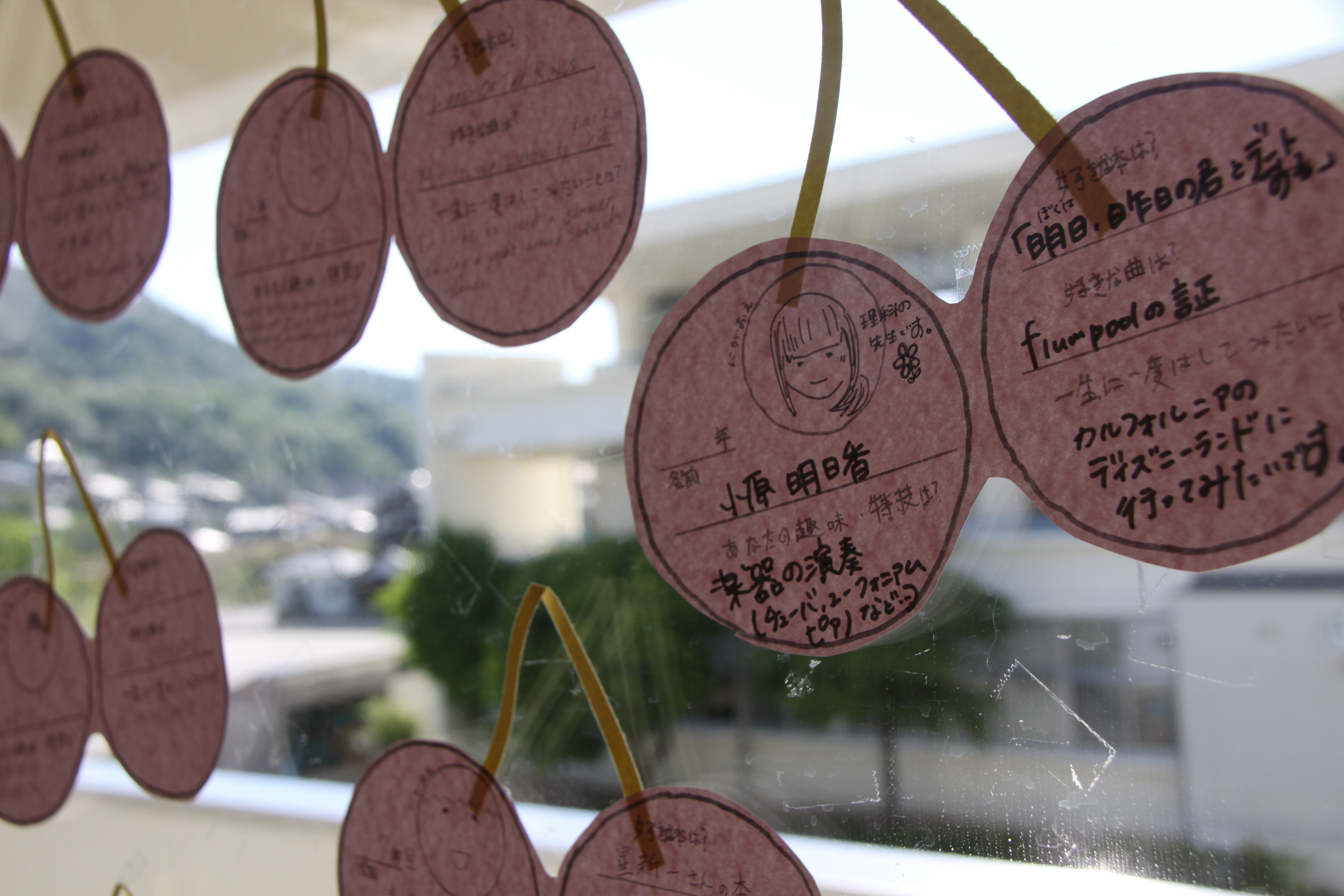

◎十五歳の春へ(5/14:小中連絡会)
小学校の先生方が、新1年生の授業参観に来校されました。中学校の授業に取り組む子どもらの姿はどう映ったでしょうか。参観授業後には、振り返りと情報交流議を行い、これからの小中連携について協議することができました。

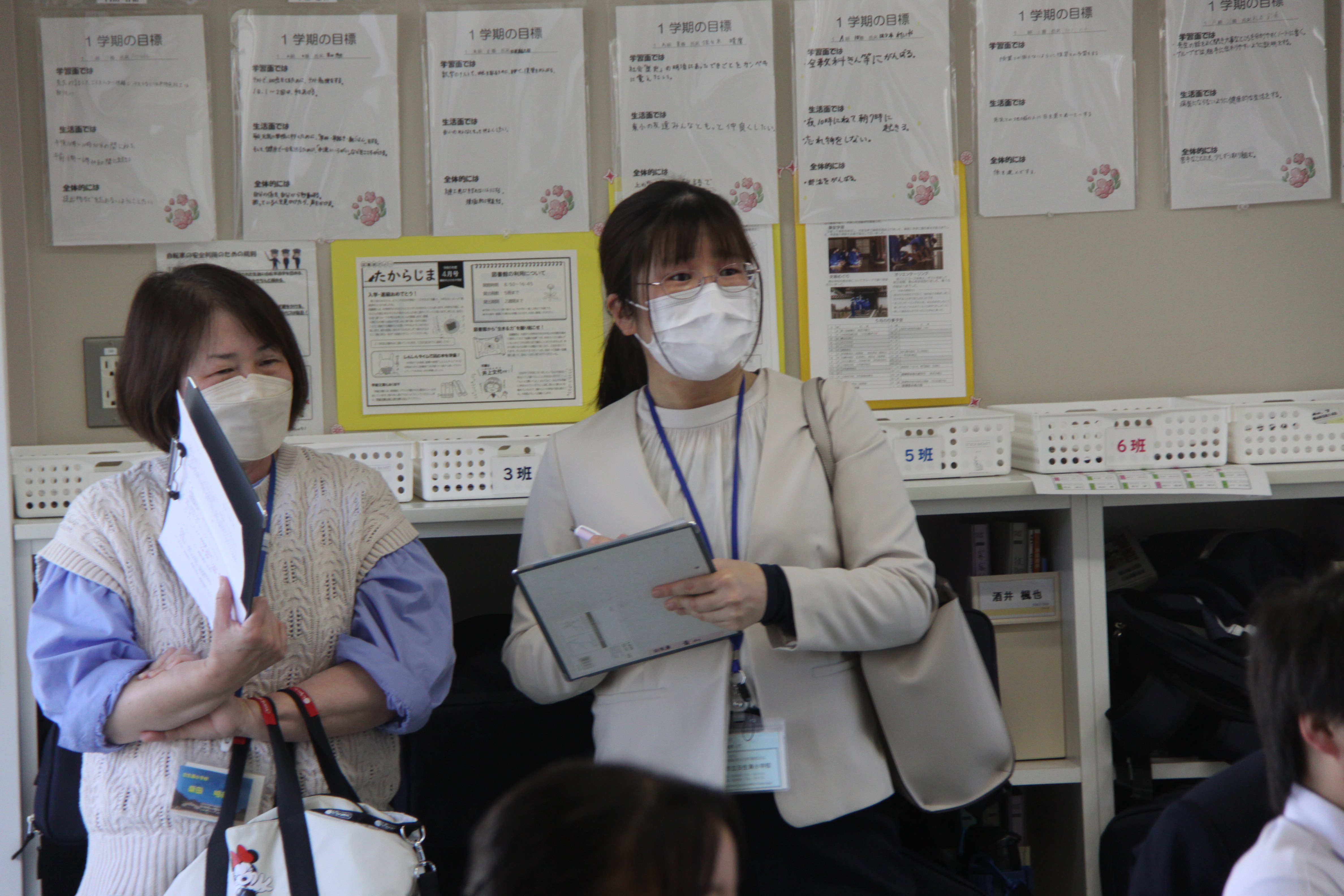







◎星✴
~1人ひとりが一等星に負けない輝きを~
私たちの星輝祭(体育の部)へ!(5/14:練習・準備・係長会)






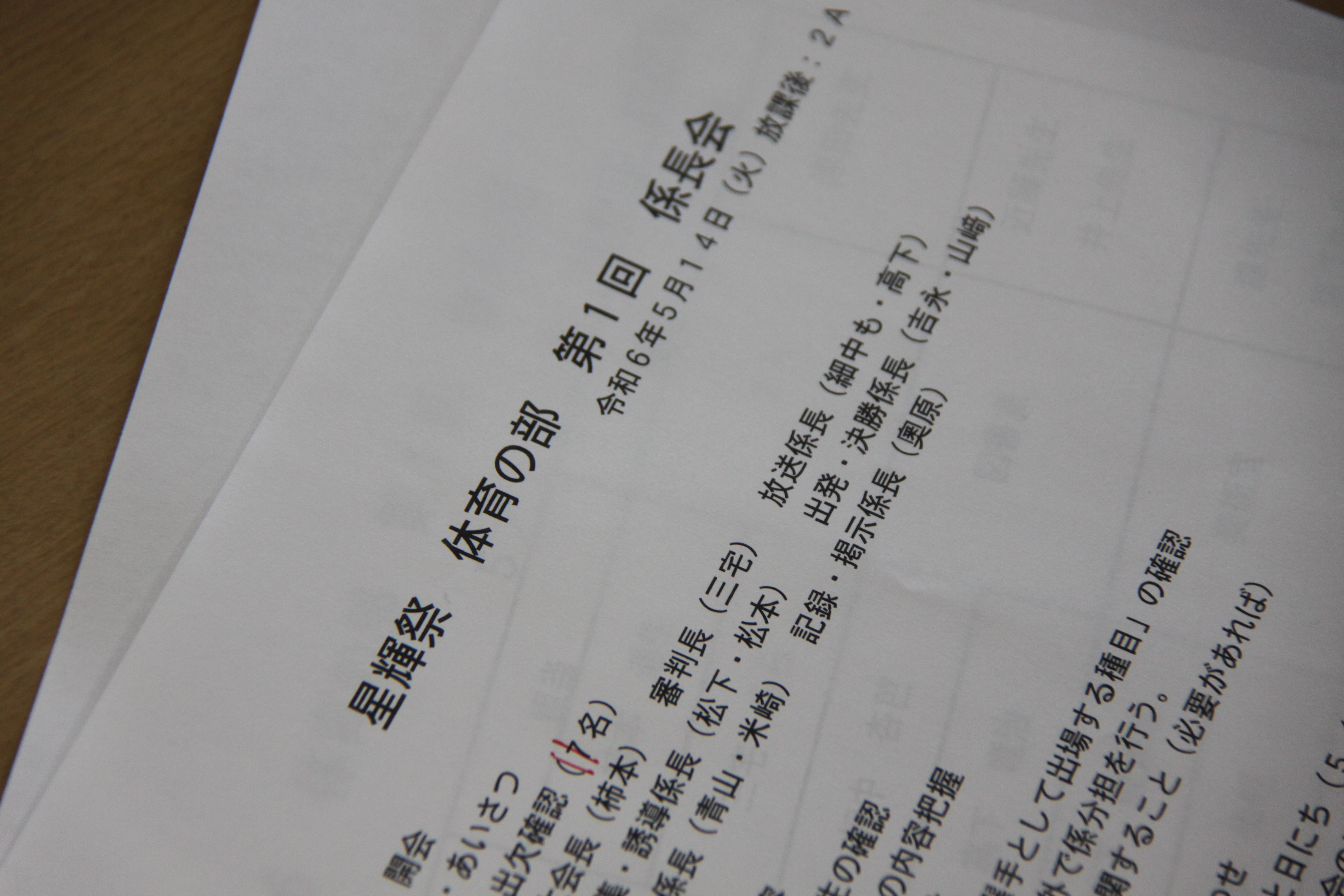
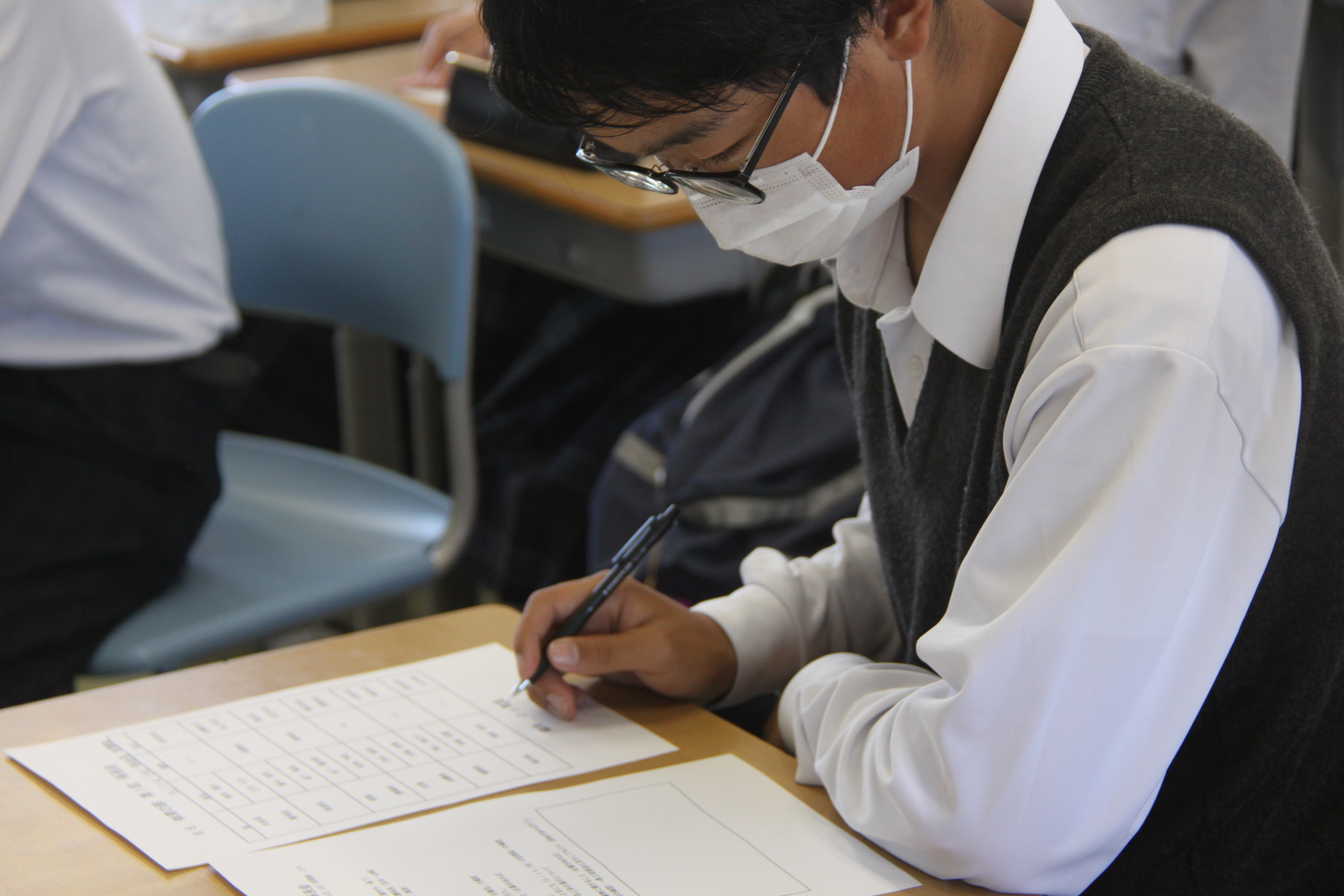

◎ひな中の風✨ 新しい風(5/13)
この4月に着任された先生方の取材に、ひなビジョンさんが来校されました。新しいメンバーとともに、がんばります。

◎PTA・PTO活動のChallenge・Change・Chance(5/13)
学習環境整備の一環として、生徒の机イスの脚に古い硬式テニスボールを履かせ、机イスの移動時の音を減らし、学習環境をよくします。また、教室床の傷みを軽減し、ワックスかけ回数を減らし費用縮減します。今日は、ボールにドリルで穴を開け、金属用はさみで十字に切る作業でした。ありがとうございました。

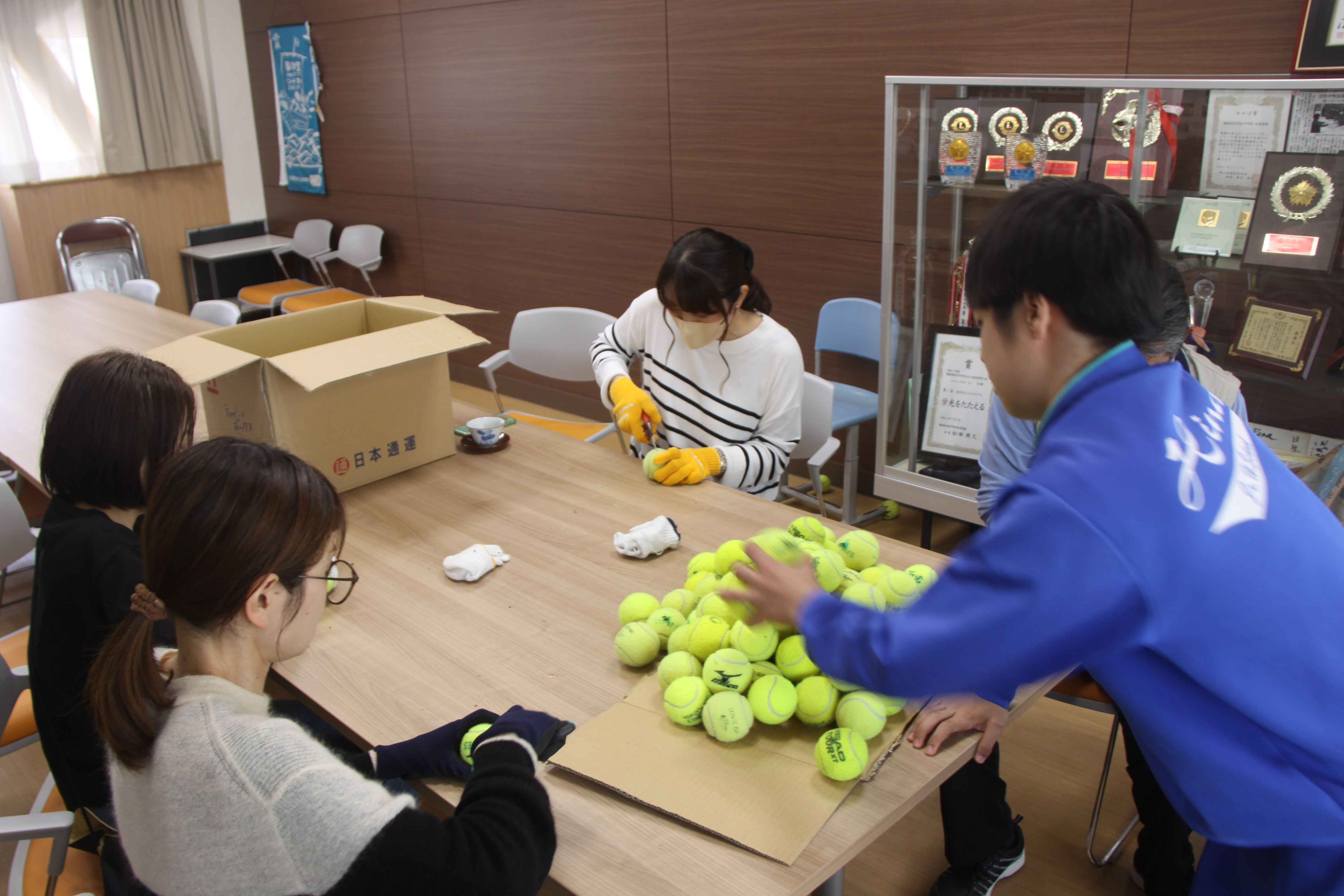

◎ガンバロウ ガンバラネバ ガンバロウナ~深化・進化・真価~
PTA総会議案集配布しました(5/13)
これまでも、日生中学校PTAでは、総会や各種会議、学習会のあり方などを工夫、改善し効果をあげてきました。そして今年度、さらに、みなさんのご意見を聞きながら、役員選出方法や、活動内容の吟味、生徒支援の強化、備前市PTA連合会の参加についても協議していきたいと思っています。みなさんのご協力をよろしくお願いします。(PTA役員会一同)*お名前の一部にミスがありました。大変失礼しました。差し替えをさせていただきます。申し訳ありませんでした。
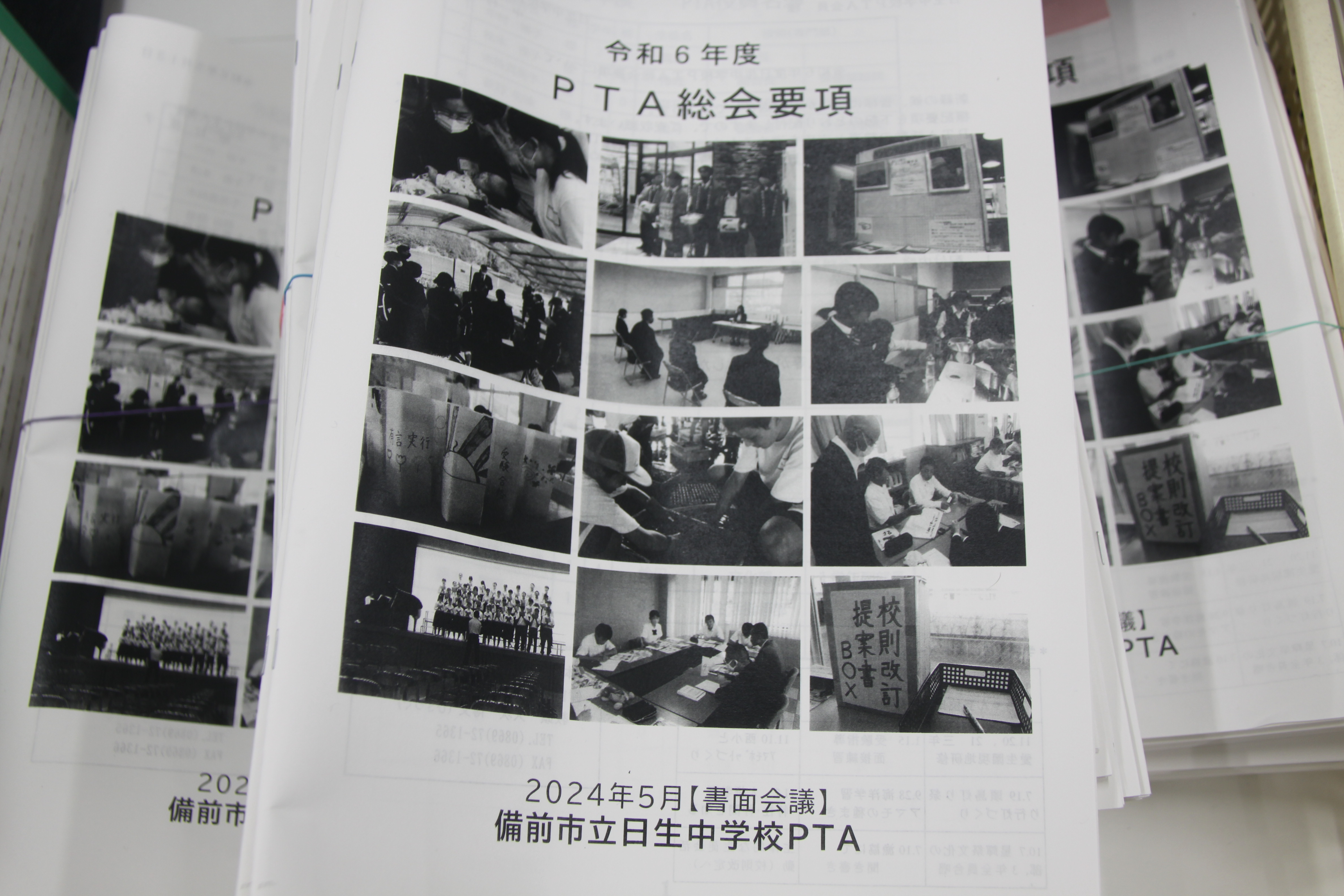
◎PTO活動って???〈参考読み物資料〉
PTA活動を見直して、PTO活動の取り組んでいる学校の文書を紹介します。
・・・PTO活動には、学校・地域と協力して親子で楽しめる活動の企画・運営、安全・防災に関する活動、会員が望む子供に体験させたい「夢」を実現するための資金作りなどさまざまなものがあります。
活動は「できるときに、できる人が、できることをやる」が基本です。
保護者がフルタイムで働いている場合や、さまざまな家庭の事情で活動になかなか参加できない場合もあると思います。父親、母親とも活動に参加しやすい仕組みを整えていきますので、できるときに自分の気に入ったボランティア活動に参加してみて下さい。PTOは保護者、教職員、子供が一緒になって「ボランティアとは何か」を学ぶ場でもあります。
会員同士が優しい心で支え合い、子供たちが入学して卒業するまでの期間、子供たちのためにいろいろな活動をしています。まず大きな違いは呼称。PTAは(Parent-Teacher Association)の略であるのに対し、PTOはもともとアメリカにある呼称である(Parent Teacher Organization)の略称。日本語訳ではどちらも保護者と教師の組合という意味になりますが、PTOの「O」は、学校「応援団」の「O」という意味もあるそう。
「各担当の呼称も、『PTA会長・副会長→PTO団長・副団長』、『役員会→ボランティアセンター(通称ボラセン)』、『行事係→サポーター』など、より親しみやすく感じられるよう工夫しています」
また、参加方法も異なります。PTAは、1年縛りの強制参加で、在学中に1回は必ずなにかしらの担当をしなければならず、共働きの方や参加が難しい環境の方の負担となりがちな現状があります。PTOは、完全自由のボランティア制。年度ごとの縛りもなく、1年だけでも参加でき、一方で数年間続ける方もいらっしゃいます。
さらに、多くの学校のPTA規約には「会員はすべて平等の権利と義務を有する」とあるように、権利だけでなく義務も広く負うべきと明文化されています。
「PTOでは『できるひとが、できるときに、できることを」を理念にしており、仮にPTO担当となっても無理なときはだれかにお願いする、あるいは一部の参加のみでも問題ないという形で運営しています』
PTOに参加したくなる仕組み4つ
学校
「かつて○○小学校でも、くじ引きやじゃんけんなど半強制的に役員や委員を決め、前例にのっとって義務的に活動を行うなど、ブラックな側面がありました。そんな活動内容に負担を感じていた保護者の悩みに答え、初代PTO団長の方が一念発起して大改革をして、『もっと負担が少なく、時代にあった新しい学校支援の形をつくろう』ということで立ち上がりました」と○○さん。そこから、今は参加率100%に! 参加したがる仕組みづくりの工夫を教えてくれました。
●1:気軽に参加できるボランティア制
「1年縛りでなく、その日だけ、その期間だけ、といった部分的な参加ができるため、負担が軽くなることで保護者の方が参加しやすくなっています」
●2:入学シーズンでの積極的な広報活動
「入学式や春の保護者会でPTOの理念をしっかりと伝えてご理解をいただくことで、『自分でもできるかも』という人を増やすような広報活動を積極的に行っています」
●3:ボランティアに参加してくれた人には特典も
「たとえば運動会のサポートに参加していただいた保護者の方は、自分のお子様が演技をする際に写真を取りやすい席を優先的に確保できるなどの特典を提供しています」
●4:夢プロジェクトの発案と運営
「学校やPTOが決めたイベントだけでなく、保護者の方発案の『夢プロジェクト』という機会を設けており、だれでもアイデアを出して実行していただけます」
(東京都大田区立嶺町小学校PTOホームページ参照)(『ひとのあいだ』より)
そこで、試行チャレンジ ★保護者ボランティア募集
○学習環境整備の一環として、生徒の机イスの脚に古い硬式テニスボールを履かせます。 そのために、900個(生徒数107名×8つ)のボールにドリルで穴を開け、金属用はさ みで十字に切る活動です。
〈ねらい〉机イスの移動時の音を減らし、学習環境をよくします。教室床の傷みを軽減し、ワックスかけ回数を減らし費用縮減します。
〈日 時〉2024年5月7日、13日14:00~15:00
〈持ち物〉手袋(滑り止め手袋が望ましい)、電動ドリルや金属などよく切れるハサミがある方は、持参してくだされば ありがたいです。
◎ひな中の風✨(5/10)
今年も大切に育てています。これは何の苗??かな(技術科)

◎春いちごの会実行委員会開催(5/10)
「特別支援教育のニーズのある子どもの進路について」情報交流学習会〈春いちごの会〉は、これまで10年間、多くの方々の協力をもとに取組を進めることができ、たくさんの子ども・保護者に希望を与えてくれました。その実行委員会が、今日、今年度の取組について相談する会を開き、本校の教頭先生も参加されました。
ここ、三年間は、中学校卒業後の進路への不安をもつ多くの保護者や進路情報を望む福祉・学校関係の方々の状況を鑑み、赤磐市・備前県民局等との共催で上記の会を準備することができました。そして今年は、東備地域の市町福祉課や自立支援協議会と協働体制で開催する運びとなりました。昨年度同様、動画配信も予定していますが、対面式の説明会・相談ブースの開催形式での開催(8/31(土)調整中)に向けて準備していくようです。また、情報発信しますので、ご参加・ご関係の方々にお声かけください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
会の目的は、「①会場で、高校等の説明を直接に聴き、相談ブースを活用し、進路実現に向けて、希望を持ち、不安を解消する機会とする。②動画配信(市ホームページ上、視聴申込者、期間限定)を通じて、高校等での学校生活の紹介をしていただき、進路に関する情報が収集できる会にする。③動画や会場での相談により、進路・進学や就職についての最新の情報を、本人、保護者や、小・中の教職員や支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。④実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。」こととしています。

◎多くの人に支えられて(5/10)
5月12日(木)から「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」が始まります。この日は、全国民生委員児童委員連合会が定める「民生委員・児童委員の日」です。
また、5月12日からの1週間は「活動強化週間」とされ、国民の方々に民生委員・児童委員の存在やその活動について一層の理解促進を図る等のために、全国各地で様々な活動やイベントを行うこととしています。
厚生労働省としては、この「活動強化週間」の取組を契機とし、民生委員・児童委員を身近に感じていただき、その活動に対する理解を深め、民生委員・児童委員活動の更なる活性化につながっていくことを期待しています。
今日、日生でも、地域の民生委員・児童委員さんらが校門でのあいさつ運動に来てくださいました。ありがとうございました。


民生委員とは(岡山県HPより)
・・・民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、また、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉を増進する方で、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱されます。また、民生委員は、児童福祉法により児童委員を兼ねることとなっています。
民生委員制度は、大正6(1917)年5月12日に岡山県で、当時の笠井信一知事が「済世顧問設置規程」を公布し、創設した「済世顧問制度」が起源とされています。現在、岡山県内では4,000人余りの民生委員がそれぞれの担当する区域で活躍しています。
その活動は、福祉事務所や保健所などの行政機関に協力するという公共性も持ち合わせていますが、皆さんに最も身近なところで、皆さんの立場に立った活動を展開していくことが一番大切なものとなっています。言い換えれば、地域のボランティアとして自発的に活動を行っていく方なのです。
日常生活の中でお困りごとはありませんか。介護のこと、子育てへの不安、経済的な悩みなど、皆さんが抱える問題は様々です。このような時にはお近くの民生委員・児童委員に、まずはご相談ください。中には、「相談したいが、隣近所に知られてしまうかもしれない」といった不安をお持ちの方もおられるでしょう。しかしご安心ください。秘密の保持は、法律によって委員一人ひとりに義務づけられています。そして何よりも委員の一人ひとりは、見識があって人望の厚い人として地域の中から選ばれている方々ですので、安心して相談いただければと思います。
◎私たちのはじまりの風景10
ここはどこでしょう??



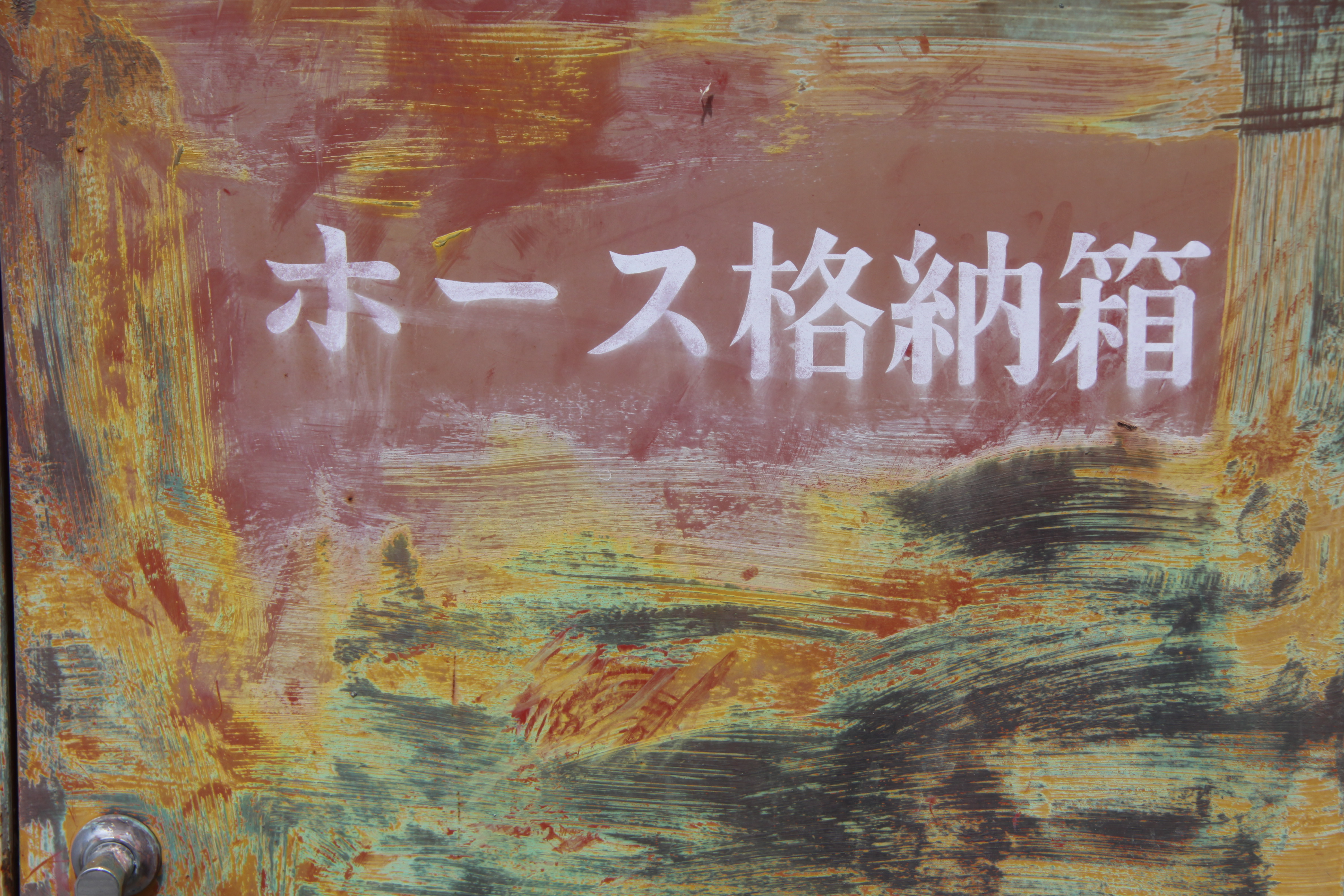





◎日生で輝く 日生が輝く
~深く、豊かな学びを、仲間とともに(5/9)
1年生が、たくさんの方々のサポートを受け、海洋学習に取り組みました。今日の学習は「カキの種付け」です。












参考読み物:カキは魚介類のなかでも古くから養殖されたもの のひとつで、ヨーロッパでは古代ローマ時代の紀元 前 1 世紀に養殖が行われていたといわれています。日本では、縄文、弥生時代の貝塚からマガキやイタボガキの貝殻が大量、出土しています。そのようなことより西日本の広島湾では、古くから天然カキが採れ、人々は岩や石についているカキを自由にとって食べていたことがわかります。広島湾は天然カキの宝庫だったことがわかりますね。また古代日本人の食生活に欠かせないものであったといえます。人々は長い間天然カキをとって食料としていましたが、室町時代の終わり頃、初めてカキの養殖が始まったとあります。
文献にも「天文年間(1532~1555)安芸国において養殖の法を発明せり」とのっています。
安芸国といえば広島でしょうね。
1カキの幼生から大きく成長するまでの流れ
資料には1600 年代(江戸時代)に広島で「ひび建法」による養殖が開始されたのが最初の記録とされています。前述の時代の後になりますが、牡蠣の養殖法は1500年代から1600年代に、おおよそ始まったことが伺えます。「ひび」とは竹や雑木を干潟に建てたもので、その場所のことを「ひび場」といいます。(引用元 松島湾の牡蠣図鑑)
(中略)明治中期から後期にかけて、広島の養殖技術 を取り入れながら、本格的なカキ養殖事業が始まりました。大正時代以降にはアメリカ向け、昭和40年代 にはフランス向けに大量の種ガキが輸出され、国内の多くの養殖場では宮城県産の種ガキが今現在も使われています。カキ養殖業に占める種ガキ生産の割合が高 いことが、松島湾を含む宮城県のカキ漁業の大きな 特徴となっています。
2養殖の流れ
カキの生産には、食用となる「身ガキ」の養殖と、 稚貝を別の生産地に出荷する「種ガキ」の生産があります。宮城県は国内の種ガキ生産量の7〜 8 割を占めるほどの供給地となっていて、特に牡鹿半島の 西側から松島湾にかけてのエリアで種ガキ生産が盛んです。種ガキ生産、身ガキ生産ともに、夏の産卵期に稚貝を得ることから始まります。
採苗した稚貝は抑制処理 を経て、種ガキとして出荷する分と身ガキ出荷に向けて養成する分とに分かれます。
採苗の年の暮れから 翌春にかけて本養成に入り、秋から次の春にかけて 収穫するのが「1年子」で、さらにもう 1 年育ててから収穫するのが「2年子」ですが、松島湾の身ガキ はほとんどが「1年子」で出荷されます。
3採苗
マガキの産卵期は夏です。幼生は 3 週間ほど海中 を浮遊しながら成長し、くっつく場所を見つけて固着 生活に入ります。このときに、ホタテの貝殻(「原盤」 という)で作った採苗連(原盤70 枚ほどをつないだ もの)を海に沈め、稚貝を付着させるわけです。ここ で採苗ができないと、種ガキも身ガキも生産できない ことになります。カキの産卵状況と幼生の分布は、天候や海水温、海流等に大きく左右されます。
そのため産卵期になると、研究機関などによって幼生の浮遊状況の観測 が実施され、漁師はその観測結果を見ながら採苗連の投入のタイミングを決めるのです。「あそこのヤマ ユリが咲いたら」など、漁師によっては独自のノウハウを決めている人もいます。
4抑制
原盤に付着した稚貝は殻を作りながら成長します。順調に生育すれば翌年の1月頃には 3 〜 5cmくらいになるのですが、あえて厳しい環境にさらして成長 を抑えることを「抑制」といいます。採苗後の秋、数mm の稚貝の付いた採苗連を、潮が引くと海面より高くなるような位置に設置した棚(抑制棚)に移 植するのです。カキは海水中にある間しかエサを食 べられないので成長が遅くなり、さらに日光や空気 にさらされることで鍛えられます。抑制処理を施すことで、長距離の輸送に耐えることができ、本養成に移してからの成長も早い、生命力の強い種ガキになります。
5養殖の種類
日本国内だけでもさまざまな地域でカキの養殖が 営まれていて、それぞれの海域特性にあった養殖方法 が採用されています。松島湾では、江戸時代から明治初期ごろに天然稚貝を適地に移して保護する程度の簡単な養殖が行われました。明治の中ごろに広島県 から教師を招いて養殖技術を取り入れ、大正時代には神奈川県で開発された垂下式養殖法が導入されました。さらに昭和に入って筏いかだ式、延はえなわ縄(のべなわともいう)式が普及すると、水深の深い場所での養殖が 可能となってカキの生産が大幅に発展しました。また近年では、カキ1 個の付加価値を高めたシングルシード法による養殖にも注目が集まっています。(後略):(インターネット 作成者: syuchan13さんの文書を紹介させていただきました。)
◎深く、豊かな学びを、仲間とともに(~5/11)
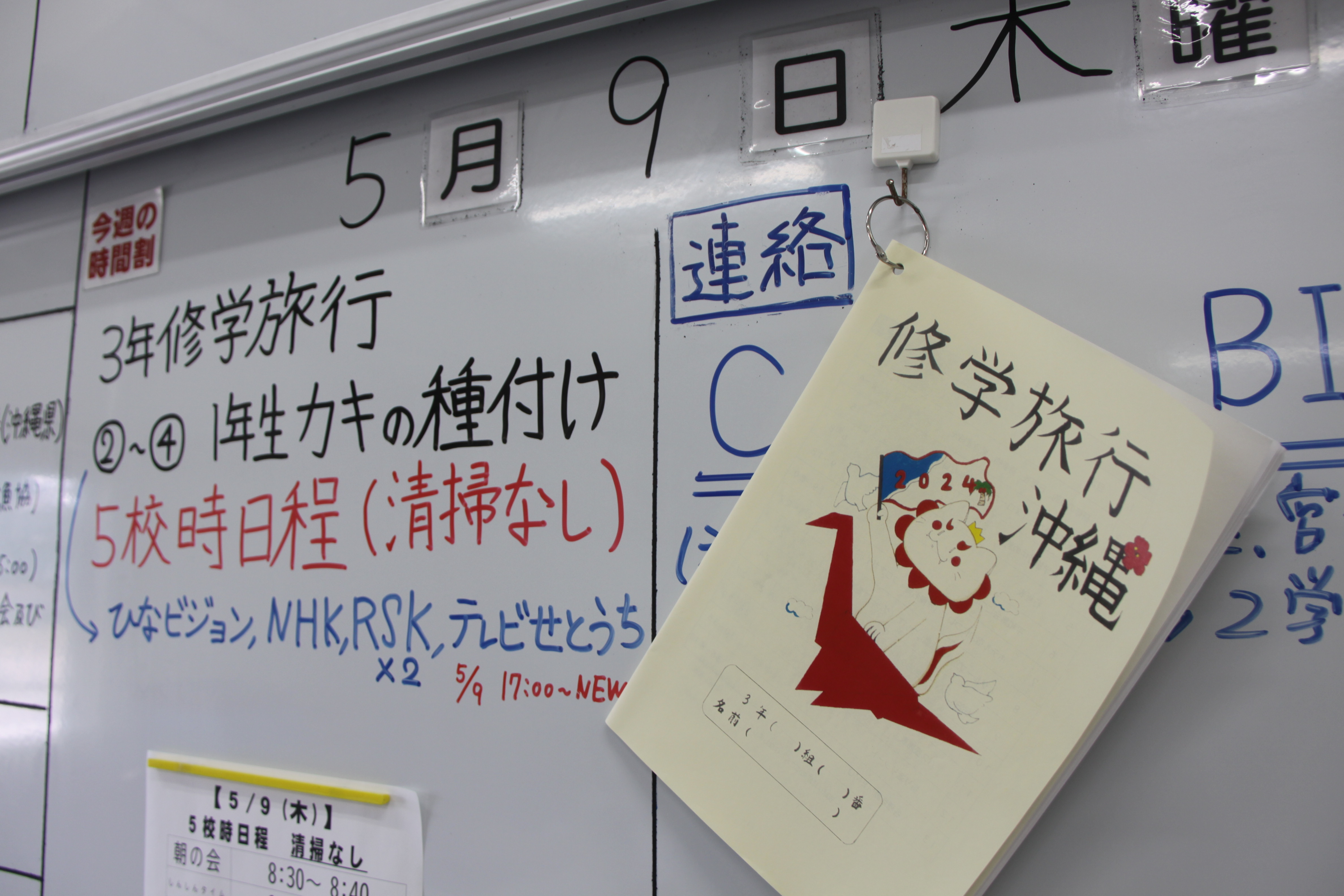
10:40 那覇空港に到着しました。
◎安全な登下校、生活のために。第1回地区会開催(5/8)
今年度初めの地区会を開催しました。1年生を迎えて、安全な通学路の登下校方法の確認と、各地区での危険箇所について情報交換等を行いました。保護者や地域の方々で、通学路や地域の危険箇所や交通安全に関する事由がありましたら、警察署や市役所、学校へご相談ください。



◎多くの人に支えられて(5/8)
地域で活動されている「こどもの居場所 おひさまひろば」の東さんが来校されました。誰でも安心して利用できる日生の場所、利用する人にとって居心地のいい場所になることを目指しているそうです。小学生の時に利用した子どもたちもたくさんいて、久しぶりの東さんとの対面にとても喜んでいました。これからも地域とのつながりを大切にしていきたいと思います。
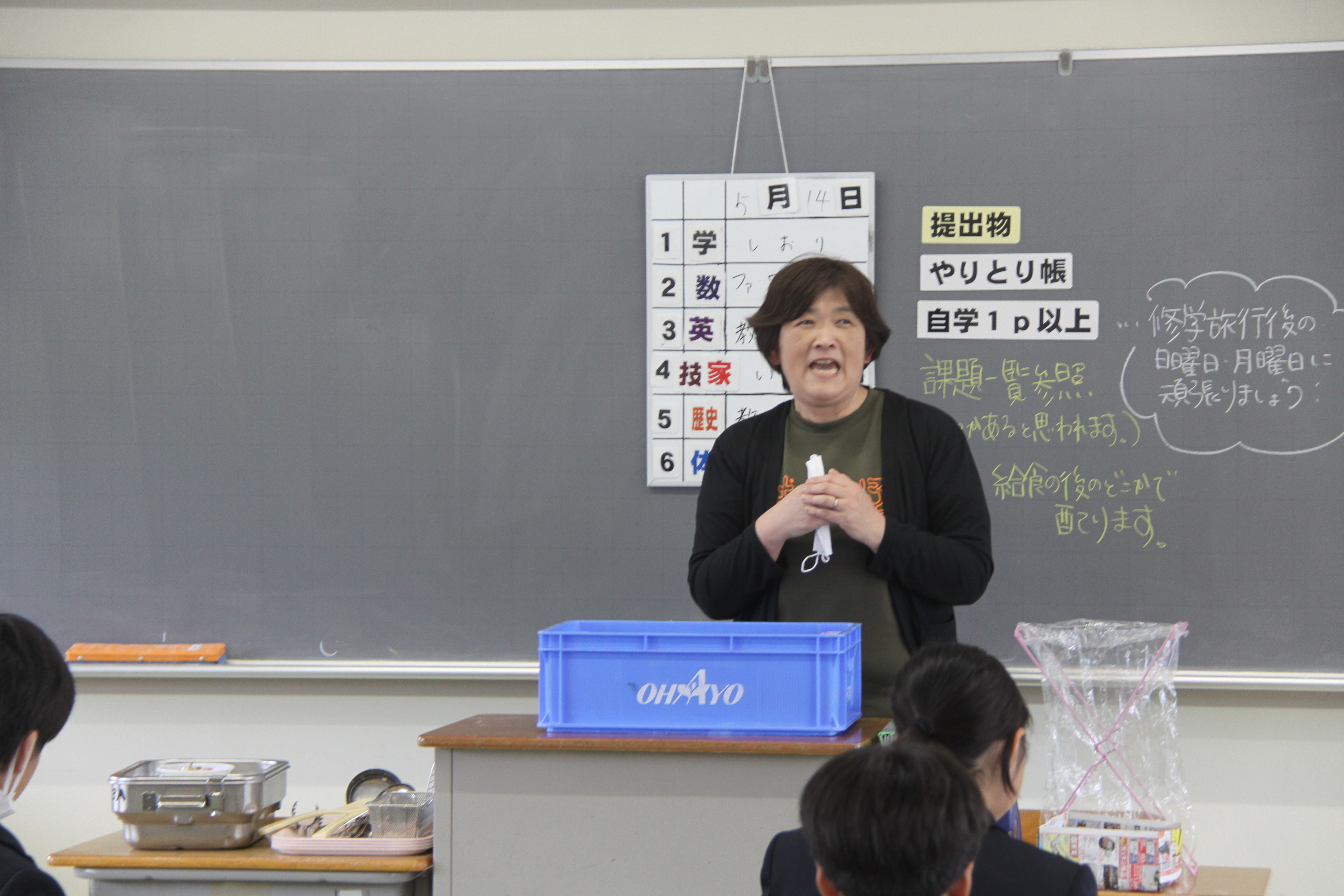





◎ひな中の風✨(5/8:私たちの生徒集会)






◎学び続ける者が教壇に立つことができるのさ。✨
三宅先生(授業改革推進員)のアドバイスを受けながら、一人ひとりが熱く、今日も「授業づくり」進めています。

◎鍛える、磨く、讃える、仲間たちとの大切な時間を。
(1年生を迎えての部会:5/7)
現在
| 部 名 | 人 数 | 部 名 | 人 数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| アーチェリー | 10 | 13 | 23 | 吹奏楽 | 11 | 12 | 23 |
| サッカー | 1 | 0 | 1 | 美術 | 6 | 3 | 9 |
| ソフトテニス | 4 | 4 | バスケット | 19 | 19 | ||
| 合計 | 47 | 32 | 79 | ||||



It's better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you'll drift in that direction. Warren Buffett
(自分より優れた人たちと付き合う方がいい。自分より行動が優れている仲間を選べば、その方向に流れていく)
◎届け オキナワへ (平和集会リハーサル:5/7)



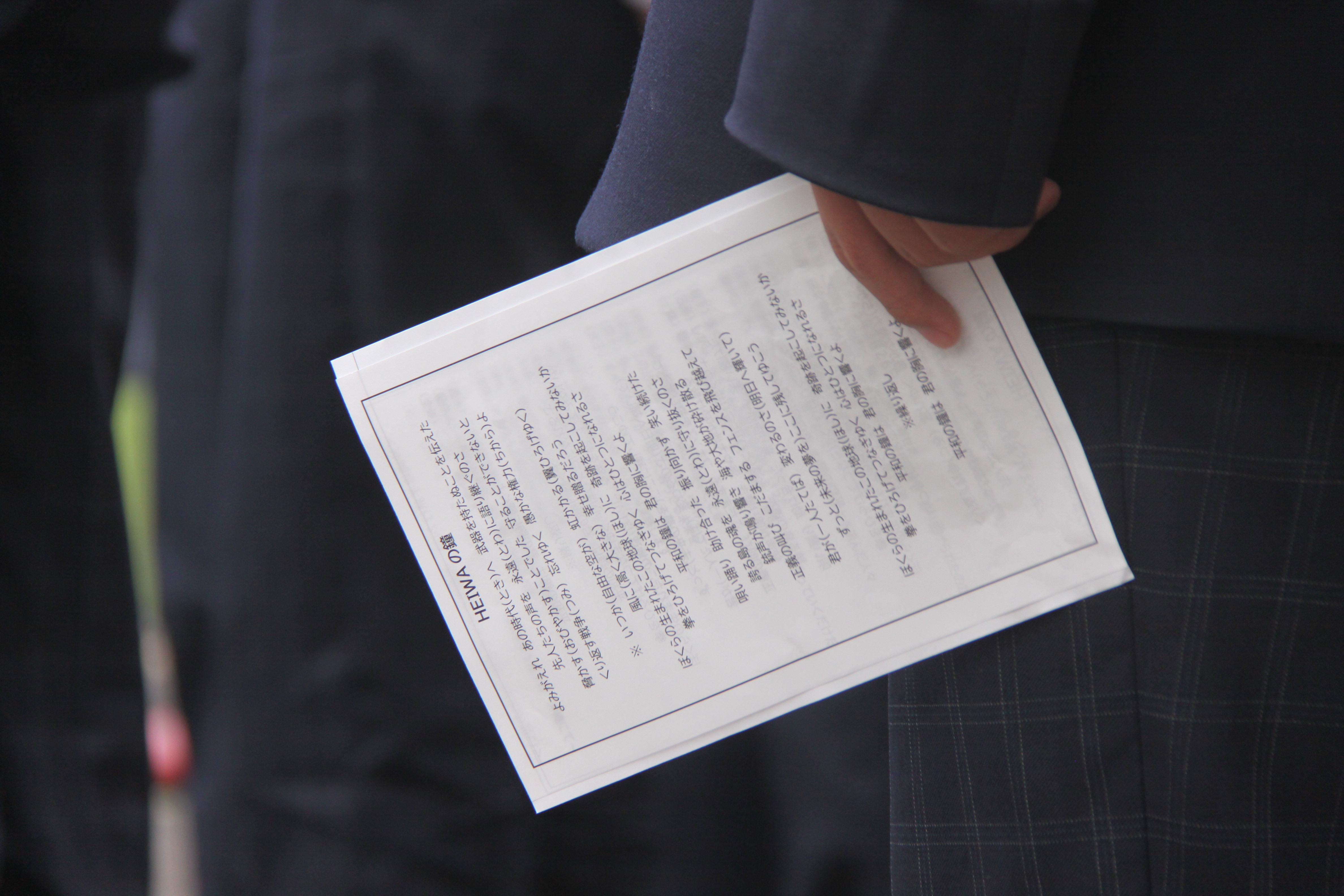



「ひとつ、お互いの良さを認め 高め合える集団を目指します」(2024日生中学校 平和の誓いより)
◎わたしたちの、社会につながる生徒会活動

You’ll give happiness and joy to many other people. There is nothing better or greater than that! Ludwig van Beethoven
(多くの人々に幸せや喜びを与えること以上に、崇高で素晴らしいものはない。)
◎♪丁寧に描くと 揺れたり震えたりした線で 丁寧に描く と決めていたよ
次も その次も その次もまだ目的地じゃない 夢の景色を探すんだ(5/7)
連休が明けて、また学校生活がスタートしました。新しい仲間(2年生に転入生が入り、生徒数は108名となりました)とともに、「歩み新たに日に生そう」。

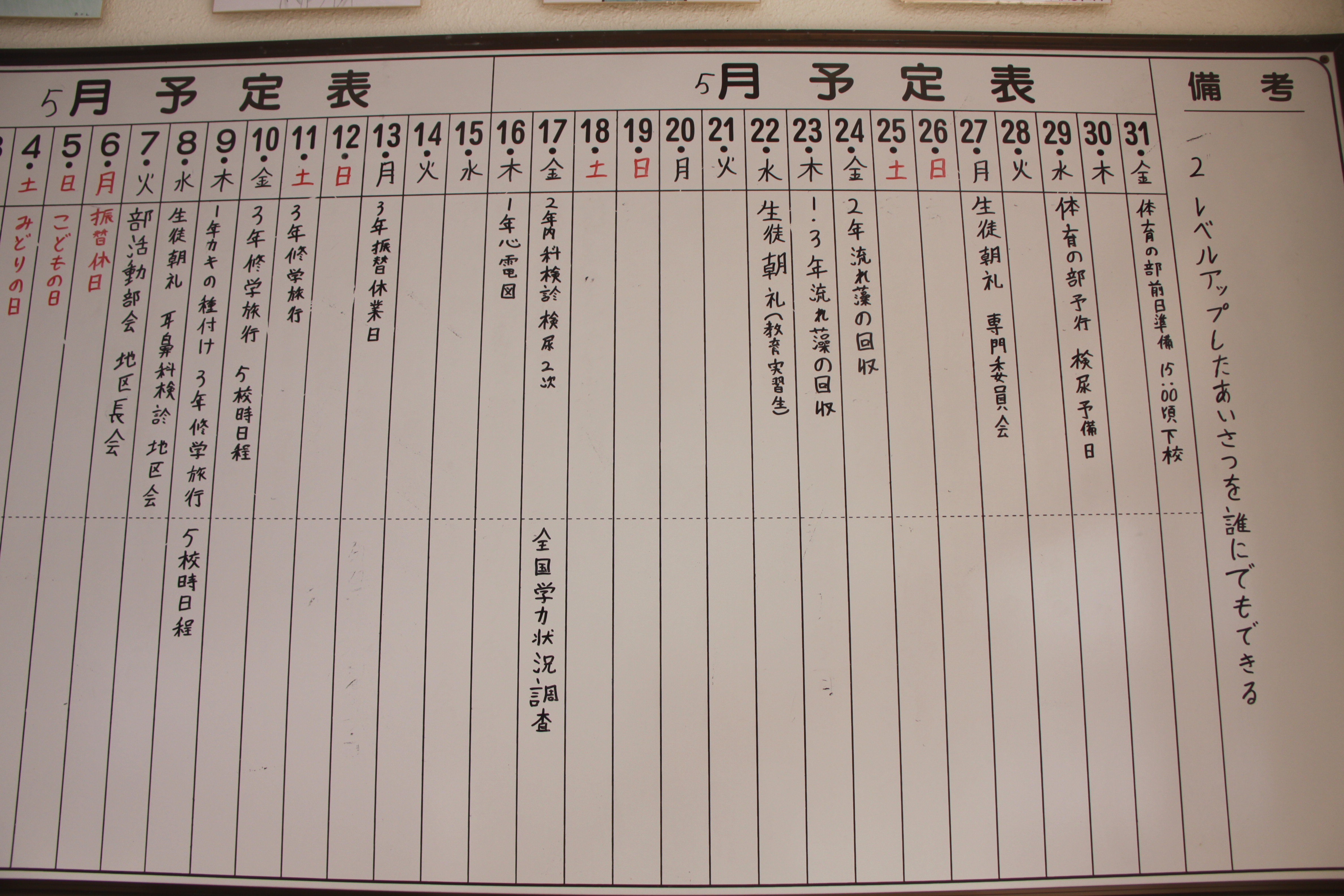


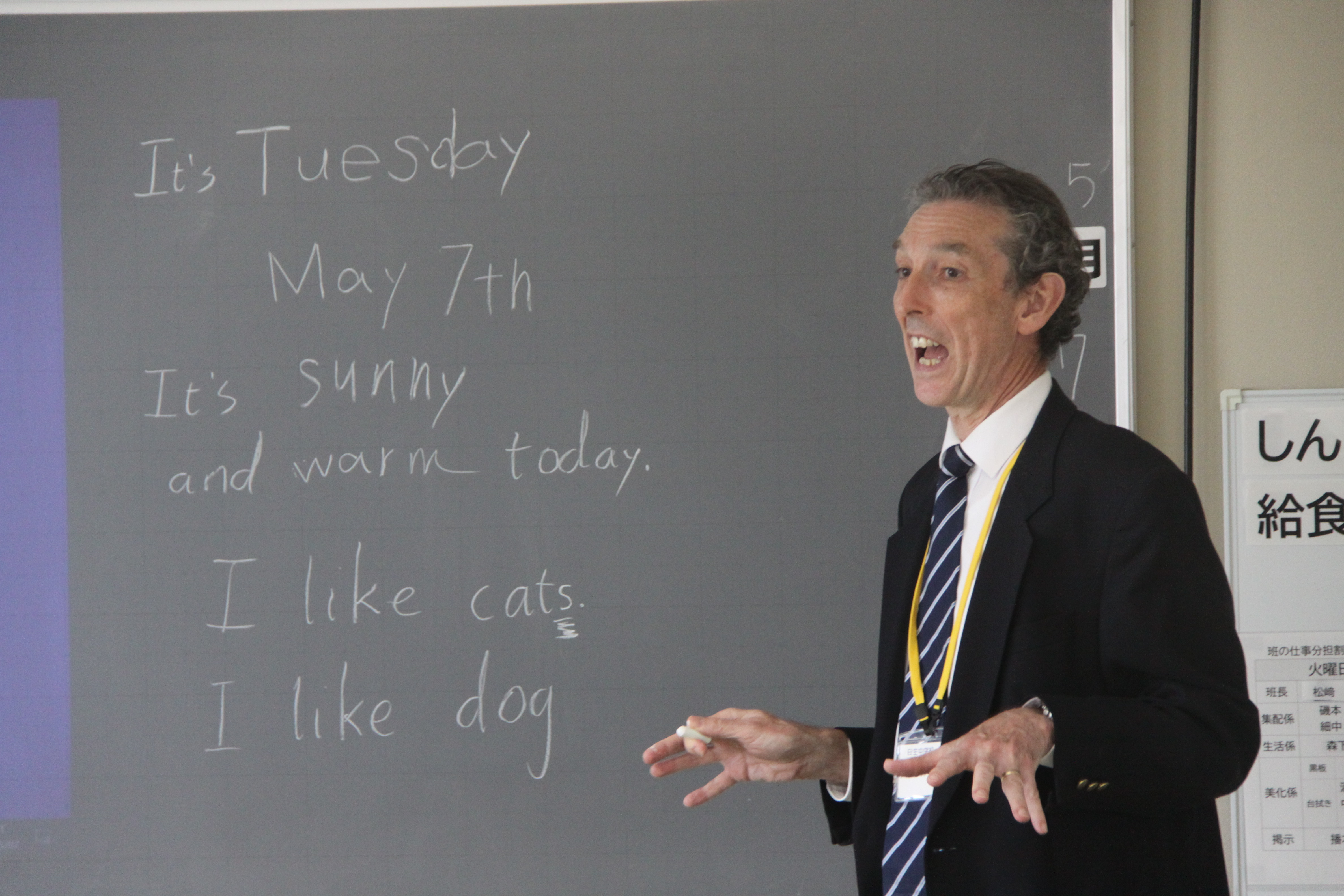
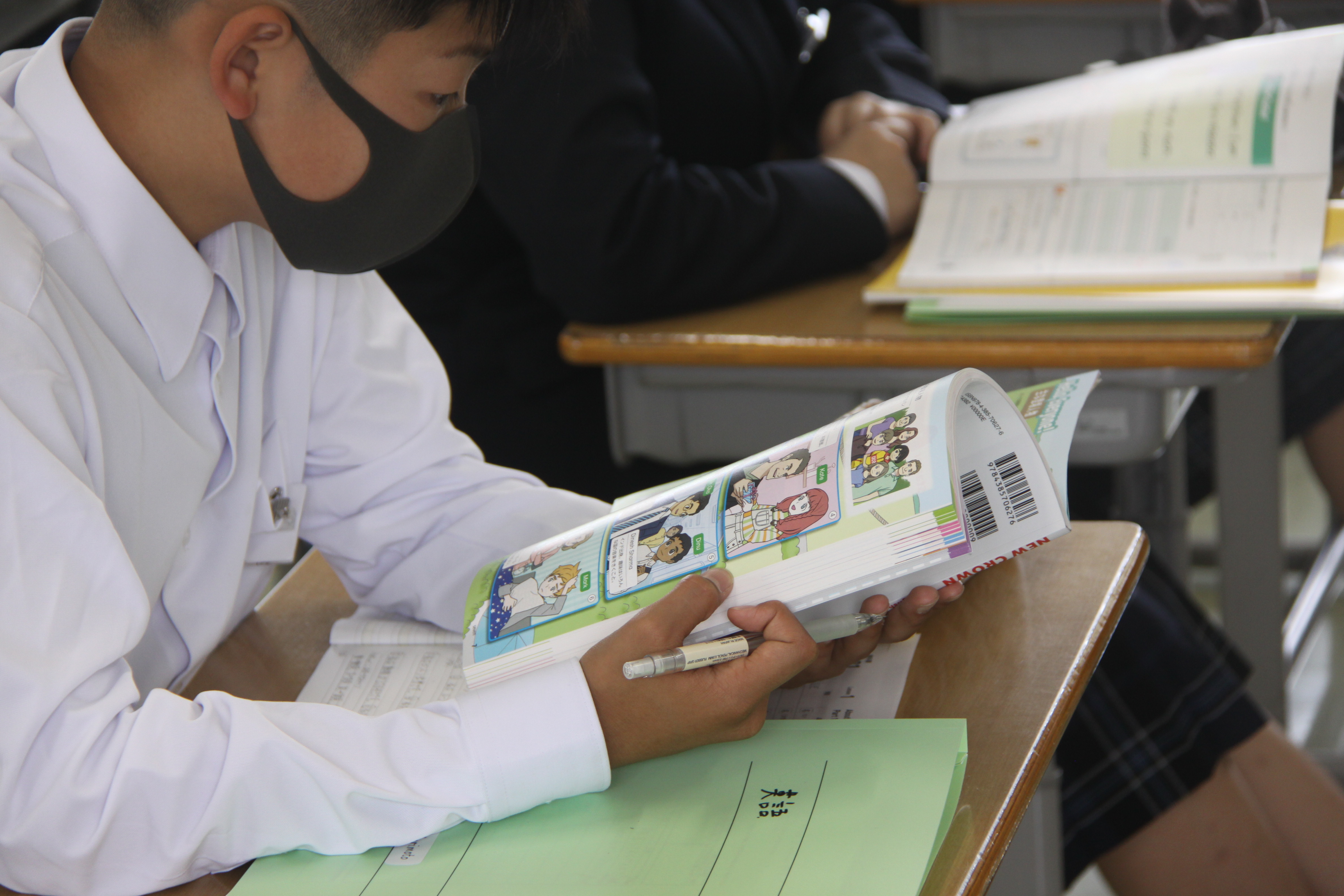



◎多くの人に支えられて(5/2)
今朝も、備前市青少年育成センターから今吉さん、真鍋さんが来校されて、あいさつ運動に参加してくださいました。ありがとうございました。明日から、大型連休の後半となります。交通安全に留意し、そして有意義な生活を送りましょう。また、7日に元気に仲間たちと会いましょう。




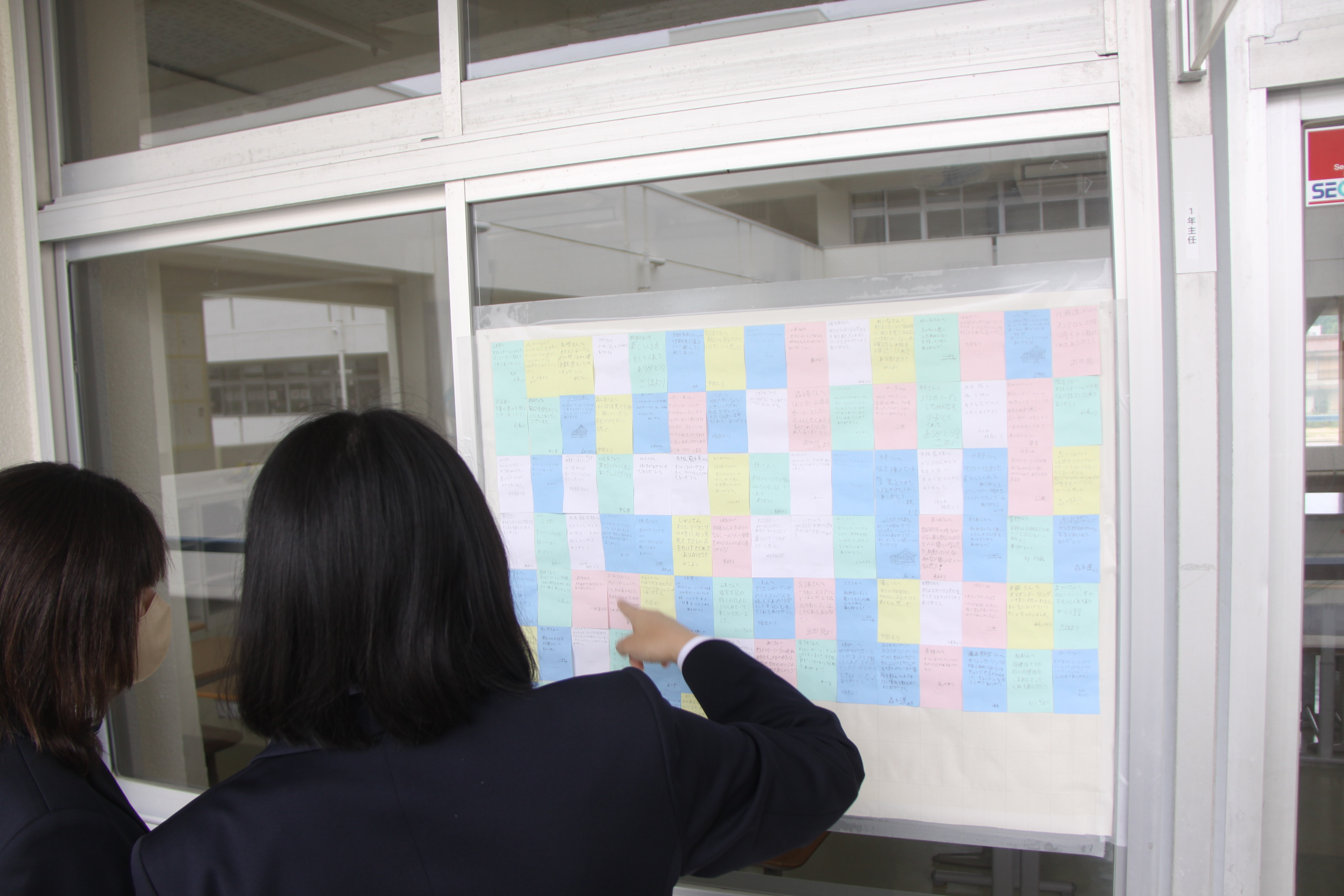

◎子どもたちの育ちをより豊かなものに、連携・協働を。
参観日へのたくさんの来校ありがとうございました(5/2)
重ねて、雨天の中、駐車のご理解・ご協力をありがとうございました。


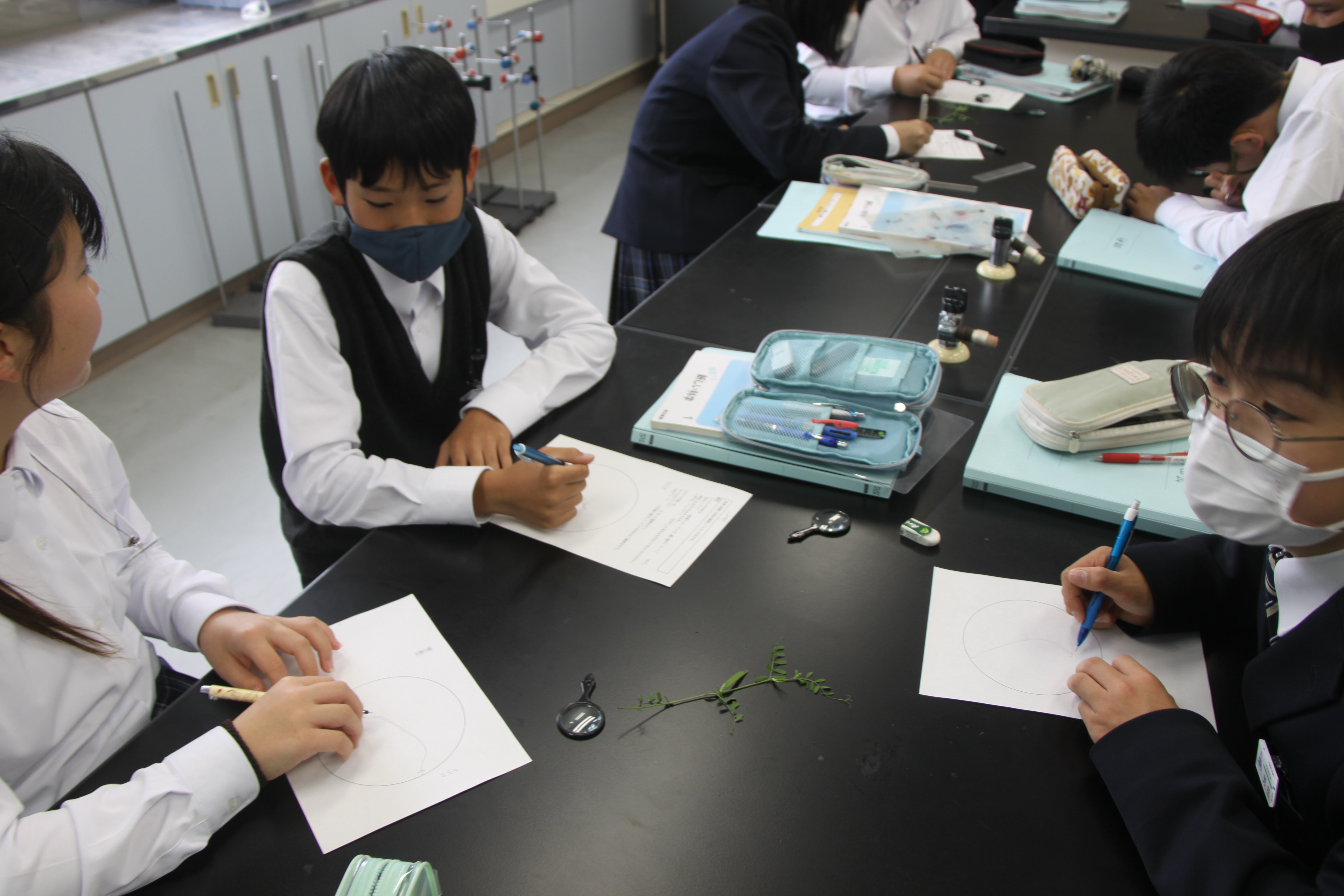

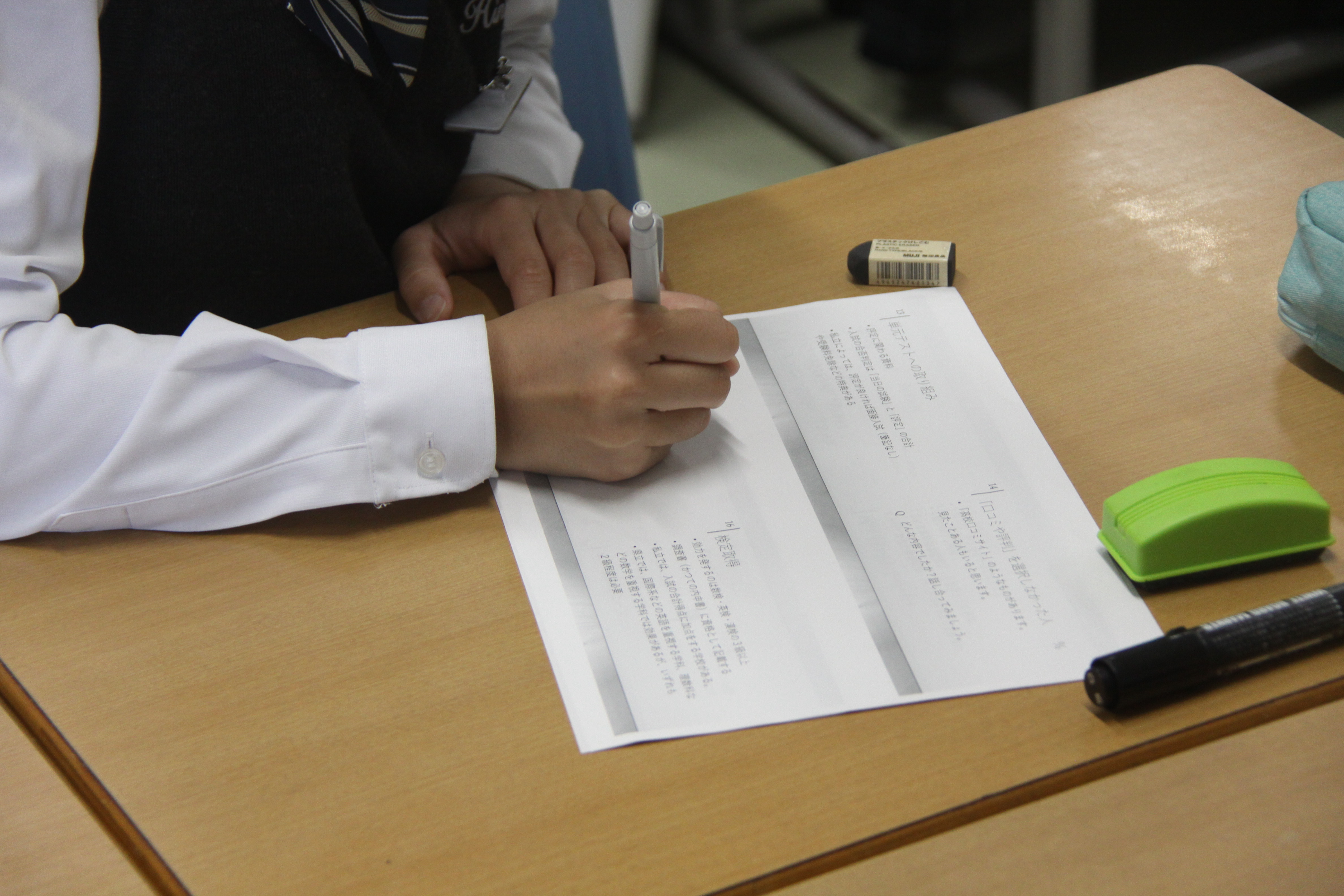

◎5月もみんなでがんばろうな(5/1)

十五夜といえば新月から15日目の満月をさしますが、八十八夜は立春から88日目という意味。昔から立春が暦の基準になっているので、立春を基準にさまざまな決まり事や節目があるのです。毎年5月2日ごろにあたりますが、その年の立春の日付によって八十八夜もずれます。
2024年の八十八夜は、今日、5月1日です。
八十八夜は季節の移りかわりの目安となる雑節(※)のひとつです。立夏(毎年5月6日ごろ)を控えた春から夏への境目で、この頃から気候も安定してきます。不意に訪れる遅霜も降りなくなるため「八十八夜の別れ霜」といわれ、八十八を組み合わせると「米」という字になることから、様々な農作業の目安にされてきました。
※雑節とは、季節の移りかわりの目安を把握するための暦日で、人々の暮らしと密接に関係し、農作業などの目安とされていました。「節分」「彼岸」「入梅」「土用」な
ども雑節です。
八十八夜といえば、茶摘み・新茶がおいしい時期。「夏も近づく八十八夜……」という歌詞で始まる文部省唱歌『茶摘み』の影響で、八十八夜といえば新茶のイメージ! 八十八夜は茶摘みを行う目安でもあったため、季節の話題として茶摘みをする様子がニュースになるわけです。とはいえ、実際の茶摘みの時期は産地によって違いますし、品種改良が進んで早期化傾向にありますが、絣にたすきがけの茶摘み衣装を着て茶摘みをする様子は季節の風物詩であり、産地のPRとしても大切なんですね。昔から、「八十八夜に摘んだお茶を飲むと長生きする」と言われています。
今はまさに新茶の季節。新茶はテアニンという旨味成分をたっぷり含み、リラックスさせたり、集中力を高めたりする効能があるといわれています。風味も抜群ですから、旬の味をぜひ堪能してください。柏餅や粽と一緒にぜひどうぞ。柏餅や粽を食べる理由を知るとさらに美味しいですよ。
八十八夜に夏じたくを始めると吉!?八十八夜にひとつでも夏じたくをしてみると、何かいいこと起こりそう♪
八十八夜は、農作業の目安だけではありません。八十八夜のすぐあとに立夏がやってきます。そこで、八十八は末広がりの縁起のいい数字でもあるため、夏じたくを始める吉日として親しまれてきたのです。そこで、八十八夜の当日に何かひとつでも夏の準備をしてみてはいかがでしょう。
例えば、夏用のガラスの器を出す、夏用の日傘、帽子、手袋などを出す、玄関のサンダル、スリッパを夏用に替える、など手軽にちょっとするだけで、運気も上昇し気分もいいかも!
薫風がカーテンを揺らします
八十八夜は大型連休の真っ只中ですし、気候のいいこの時期にインテリアや寝具も夏じたくしてしまいましょう。梅雨をさっぱりと過ごす知恵でもあります。カーテン、ソファーカバー、クッションカバーを夏用に替える、省エネにもなるすだれ、よしずを活用する、座布団やカーペットをい草に替える、夏掛け布団やタオルケット、夏用シーツに替える
初夏に出荷される「釣りしのぶ」に注目してみる…。八十八夜は現代でも暮らしのアクセントにできます。近づく夏を感じながら、大型連休中の活動のひとつに加えてみてはどうでしょう。
◎学びを深める日々・クラス・仲間があり(4/30)
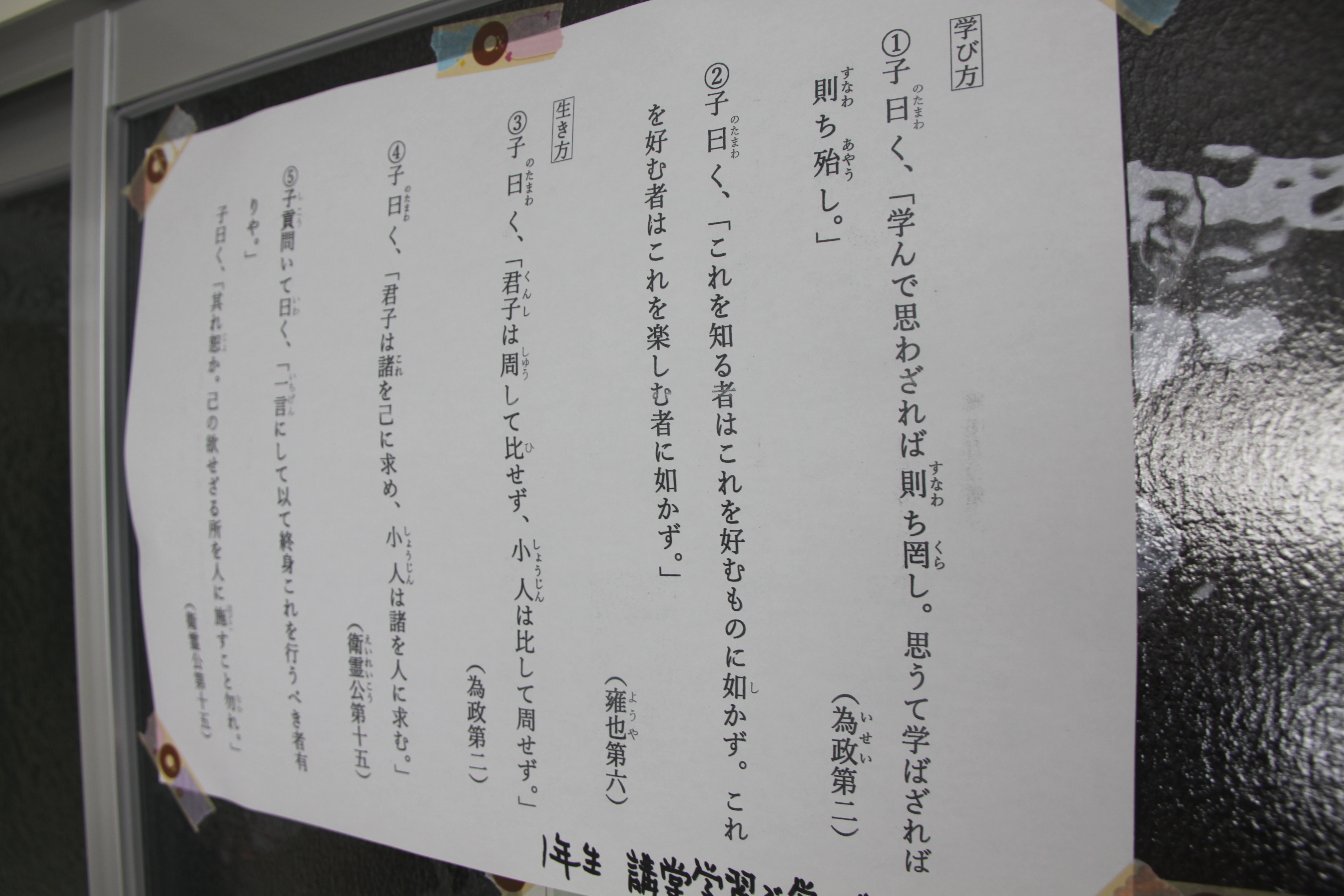


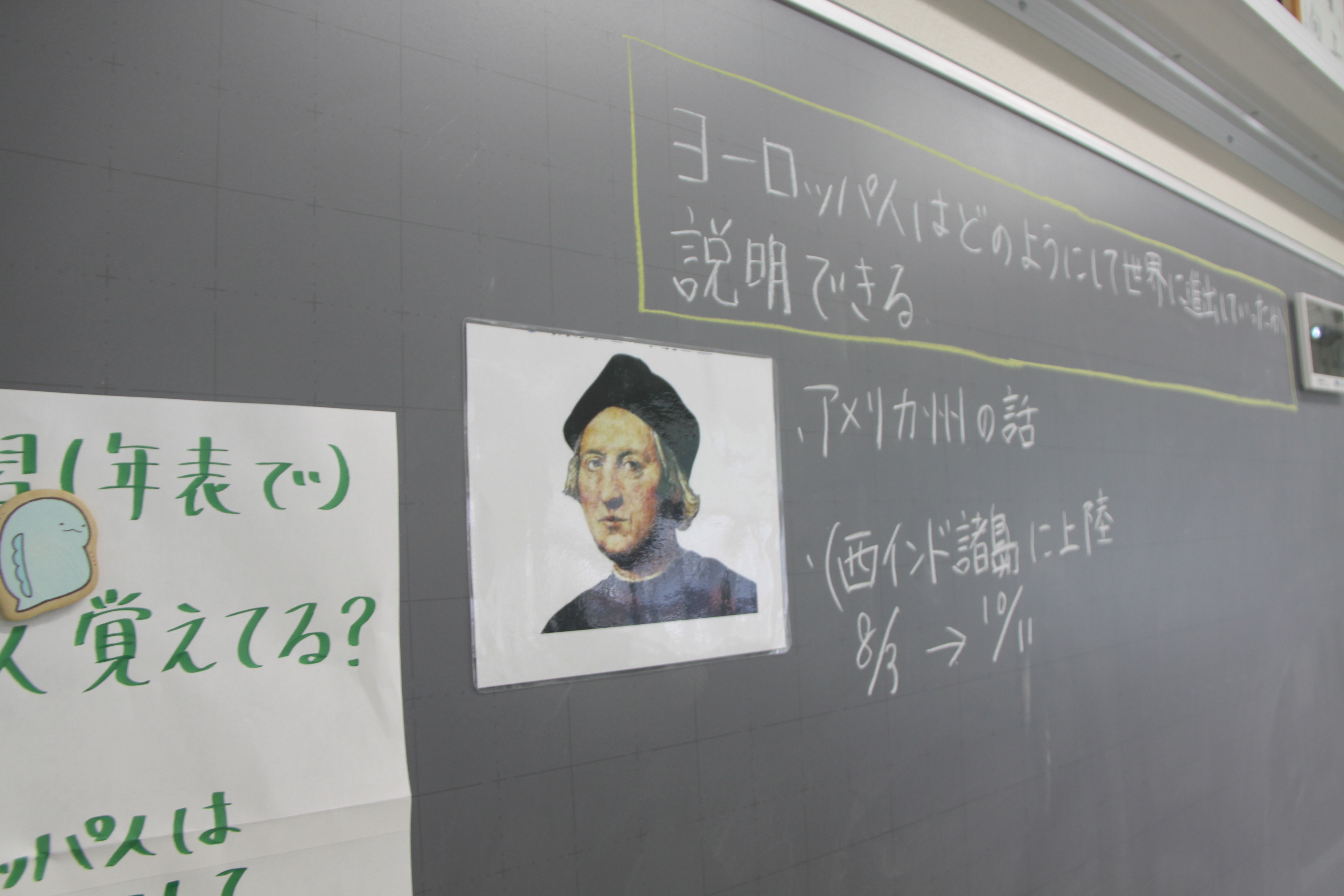
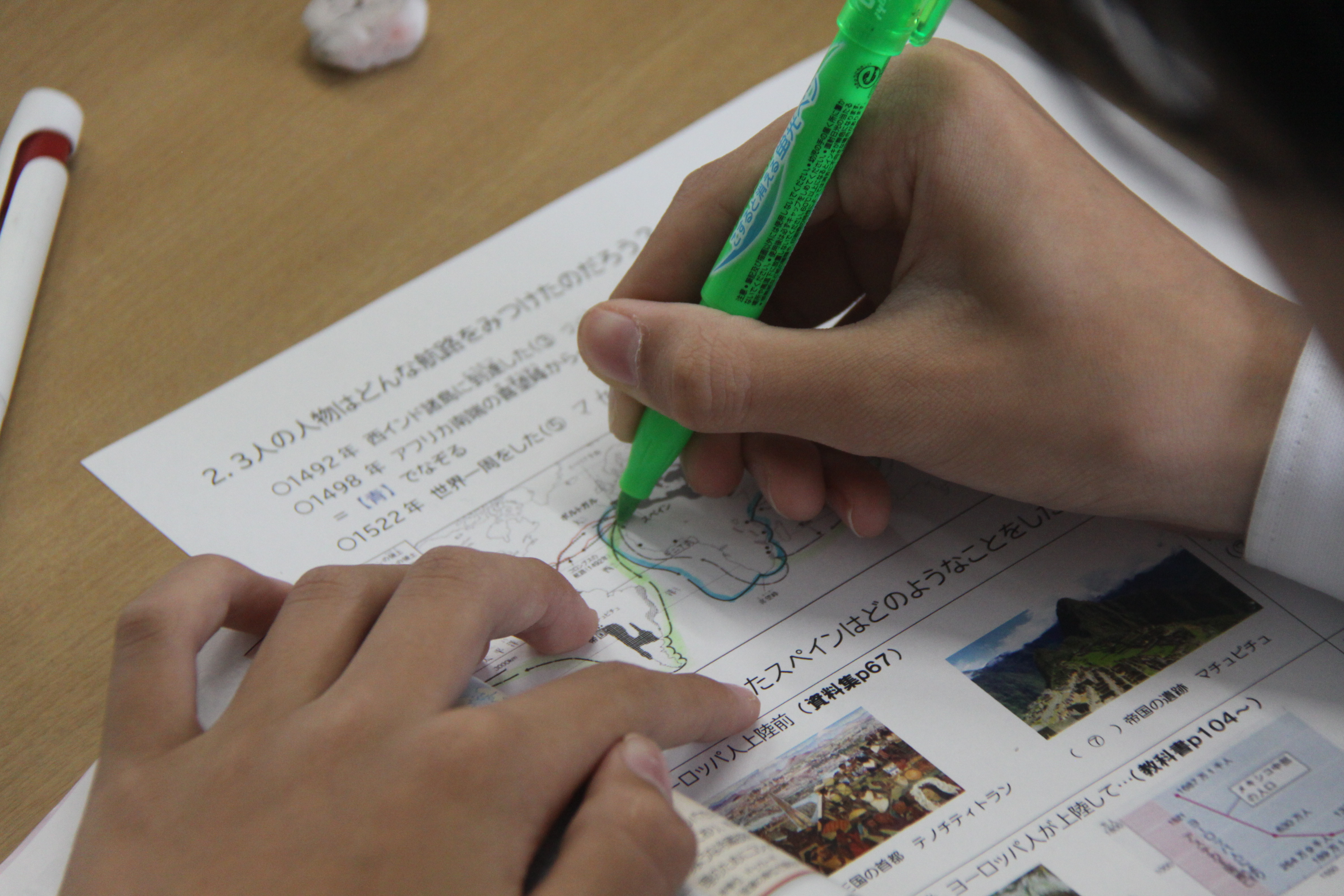







〈教材とつながる なかまとつながる 学びを深める〉 授業改革推進員とともに。
◎雨が降っても (4/30)






◎私たちの広島研修(4/25~26)










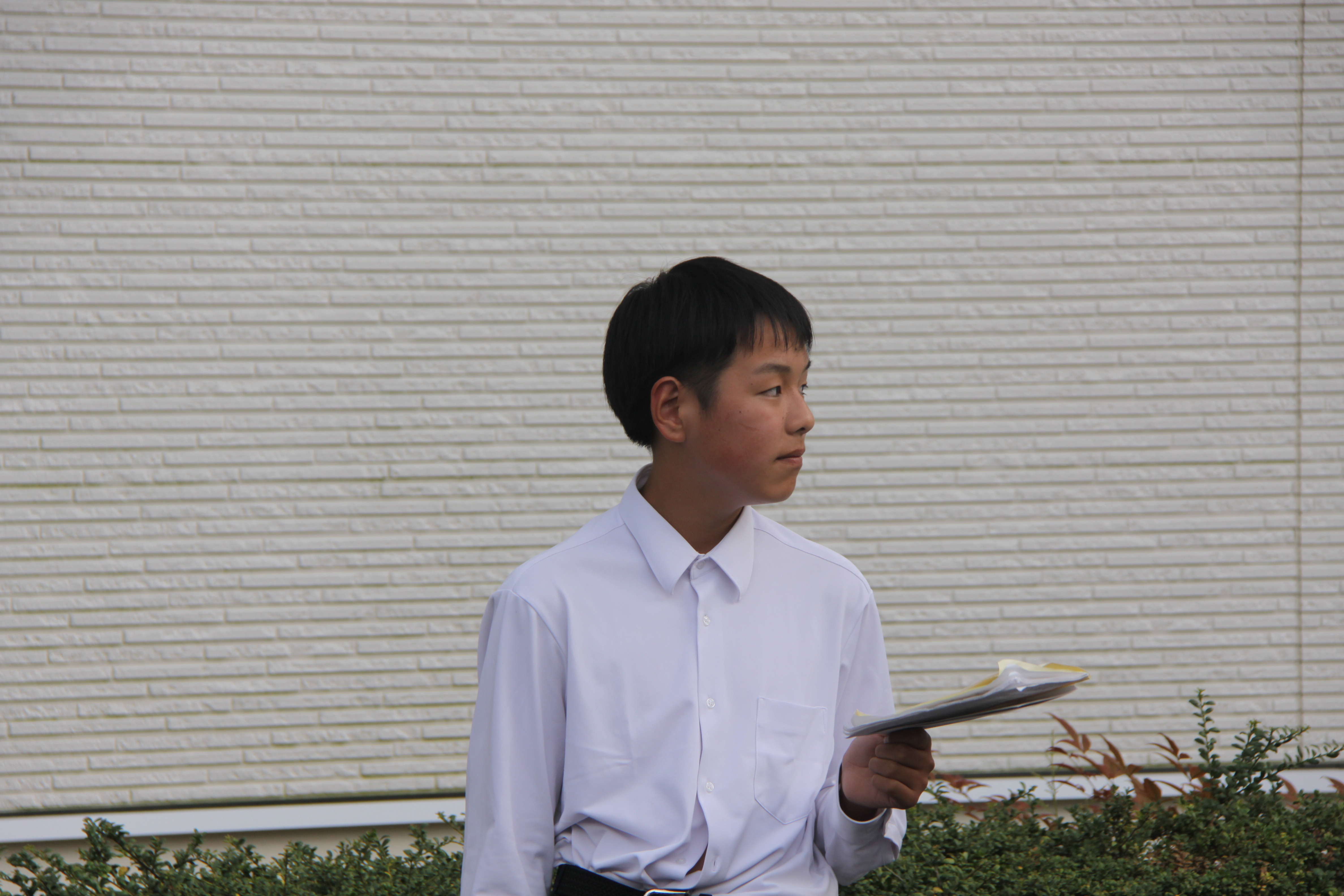


多くの方々に支えられての研修でした。ありがとうございました。
◎どう生きるか(4/25)


◎ヒロシマの地に立って(4/25)




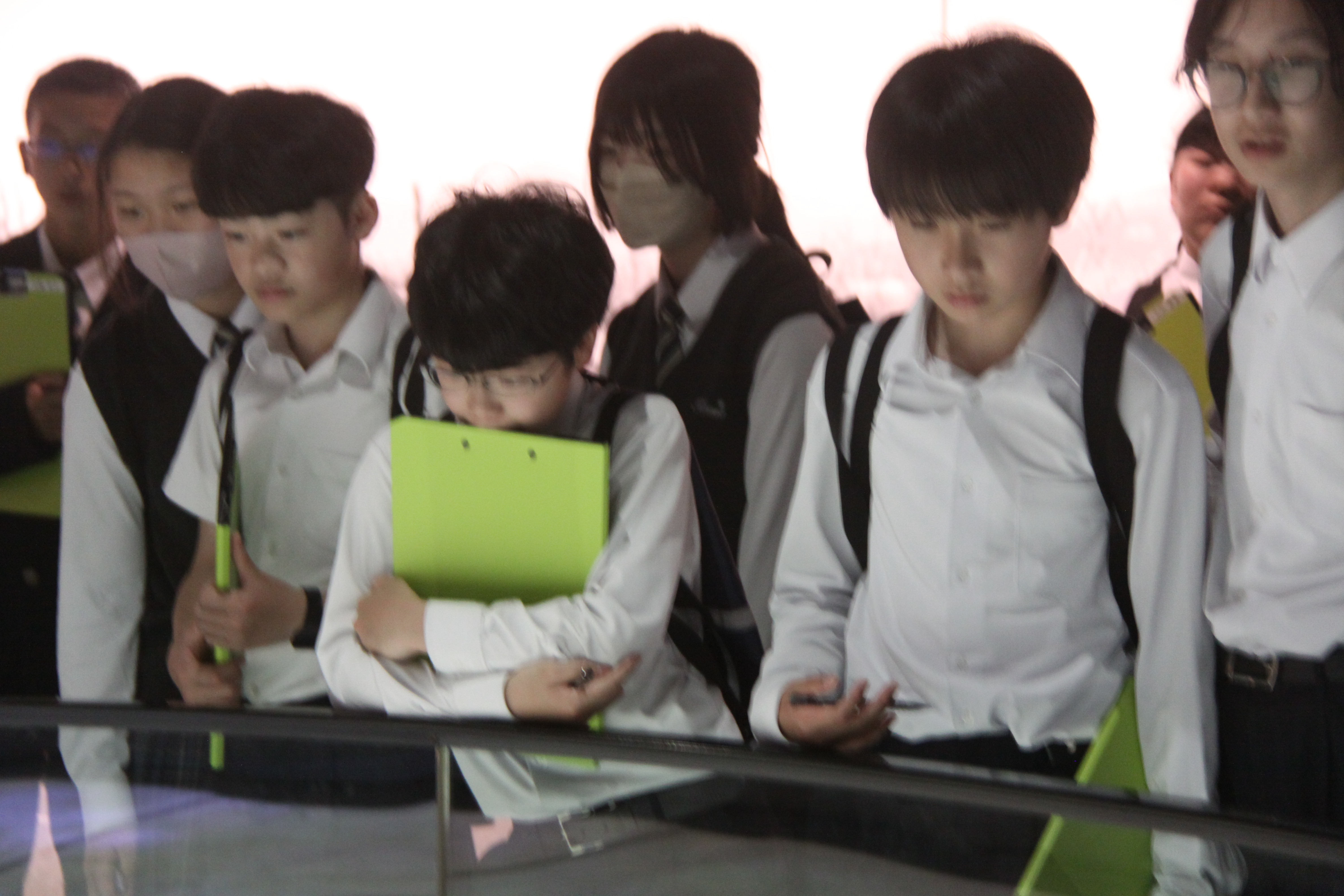

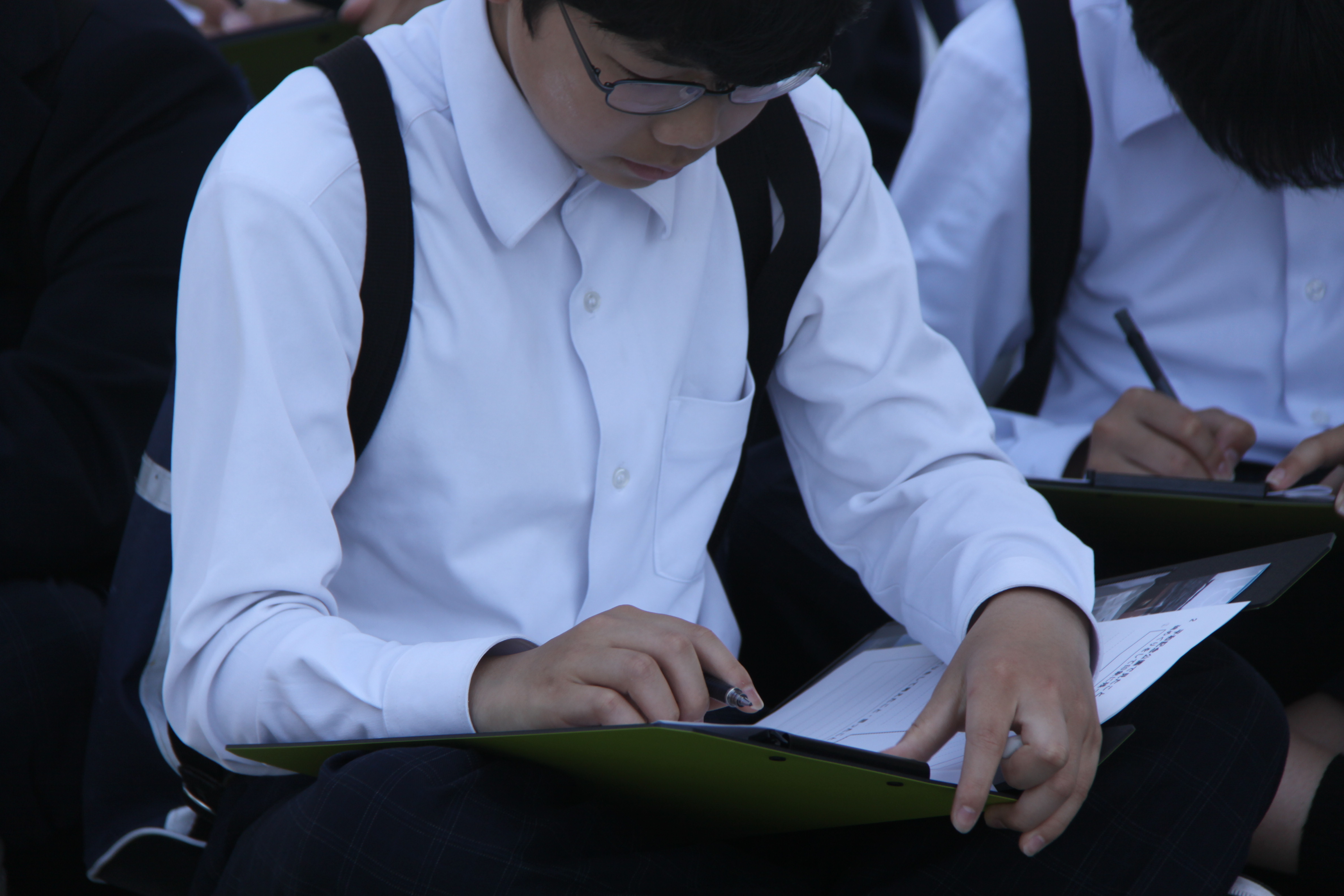



◎ヒロシマに学ぶ旅(4/25~26)
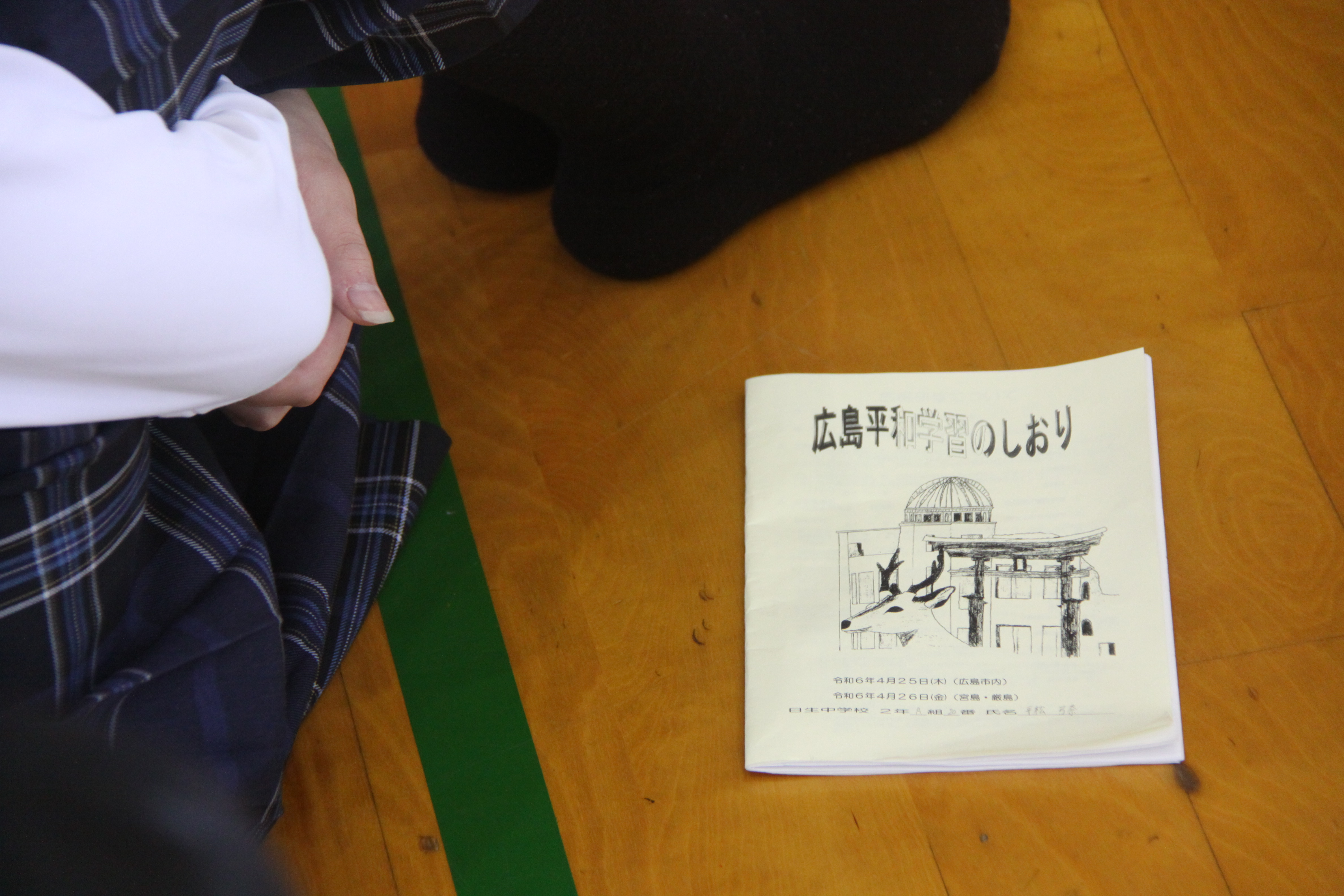
村山さんらの想いと一緒に。
◎シュタイテキナ ヒナンクンレン(4/24)
「ナンノタメニ」「ドウイウコトガ ヒツヨウナノカ」


◎私たちのまち・うみ・ひと✨~海洋学習スタート(4/24)
日生漁協組合の天倉さんをエリアティーチャーとしてお招きし、日生町の漁業の歴史や、日生中学校の海洋学習の取組について知り、「主体的に今後の海洋学習に取り組もう」とお話を聴きました。5月9日には、カキの種付け作業に取り組みます。
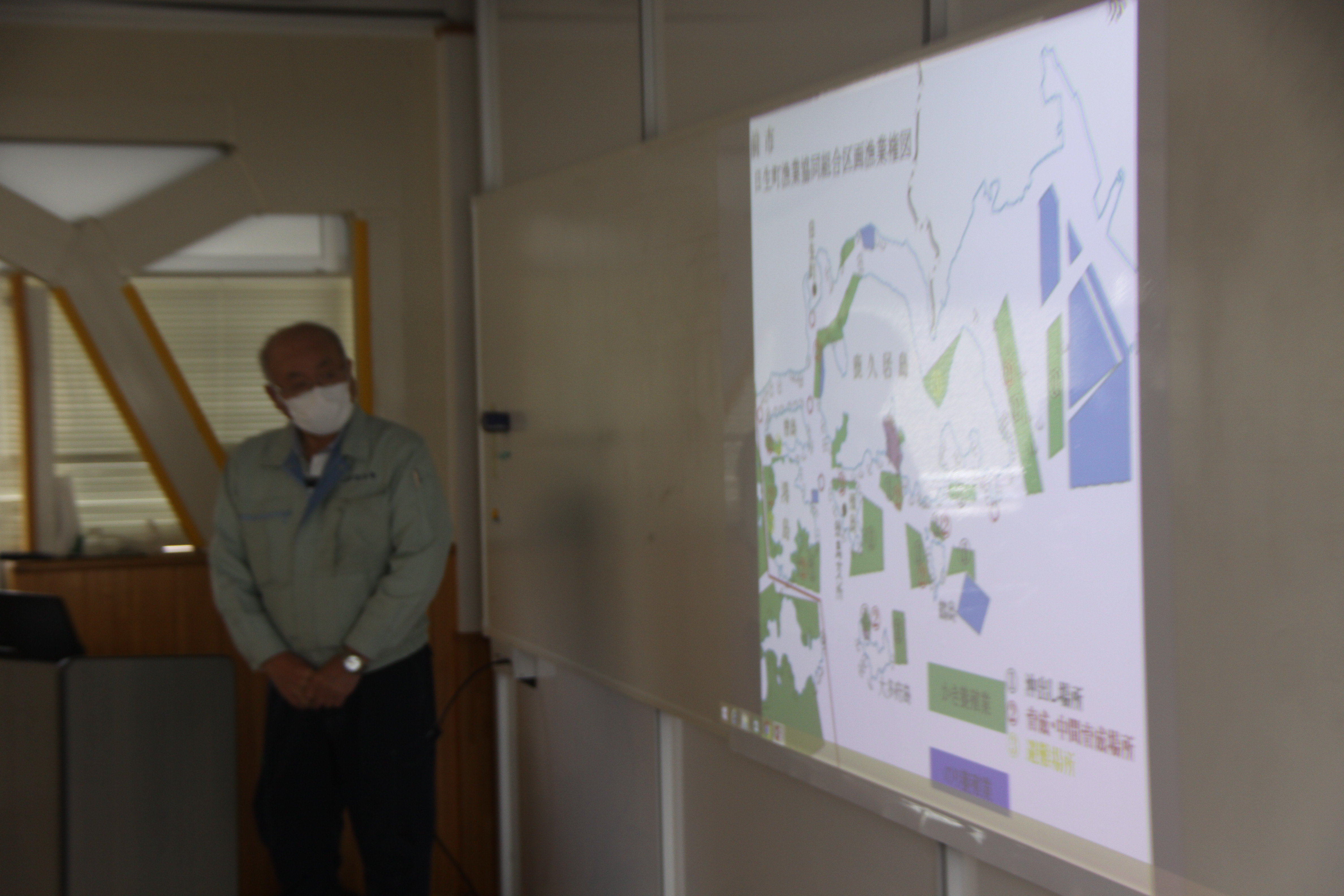
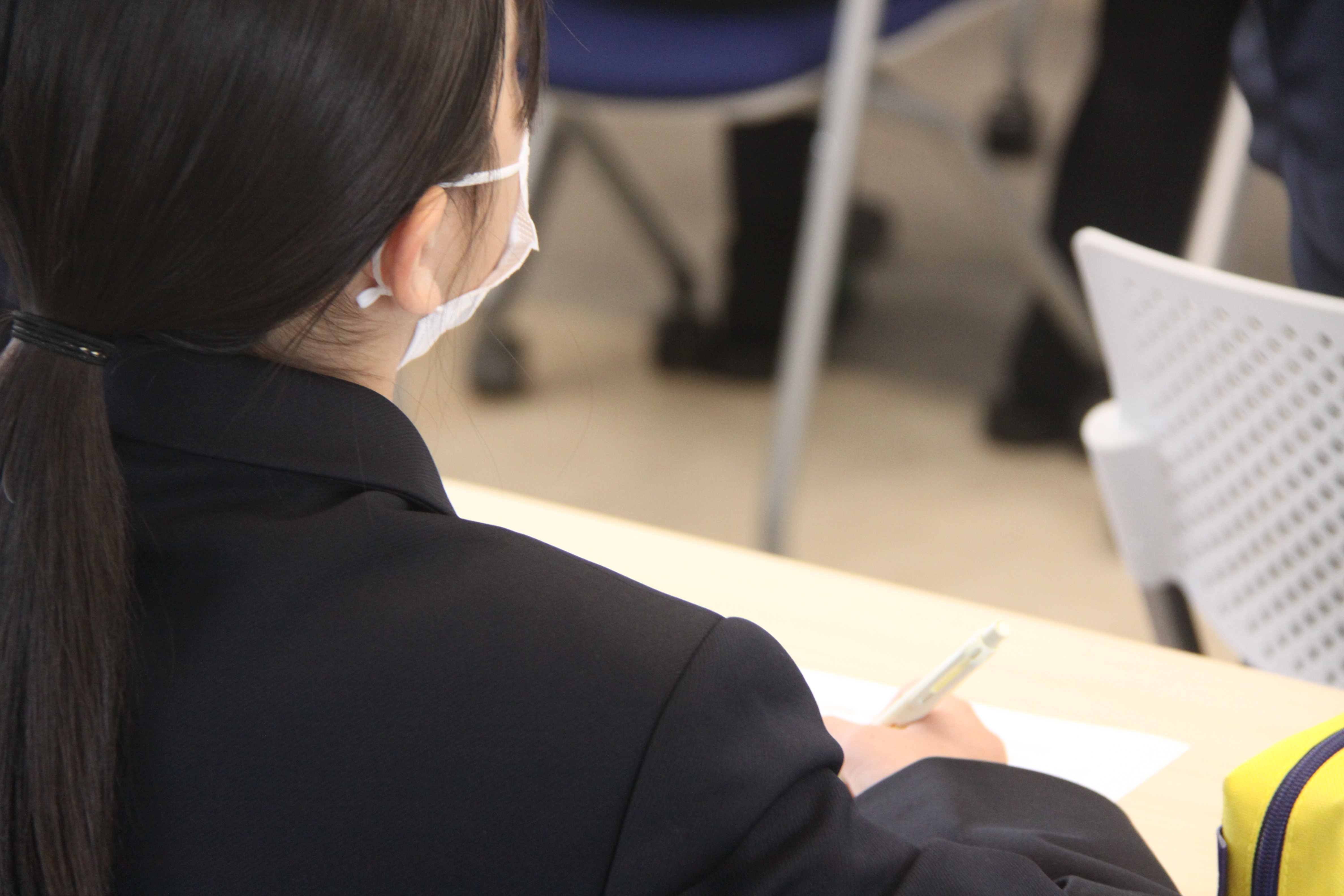

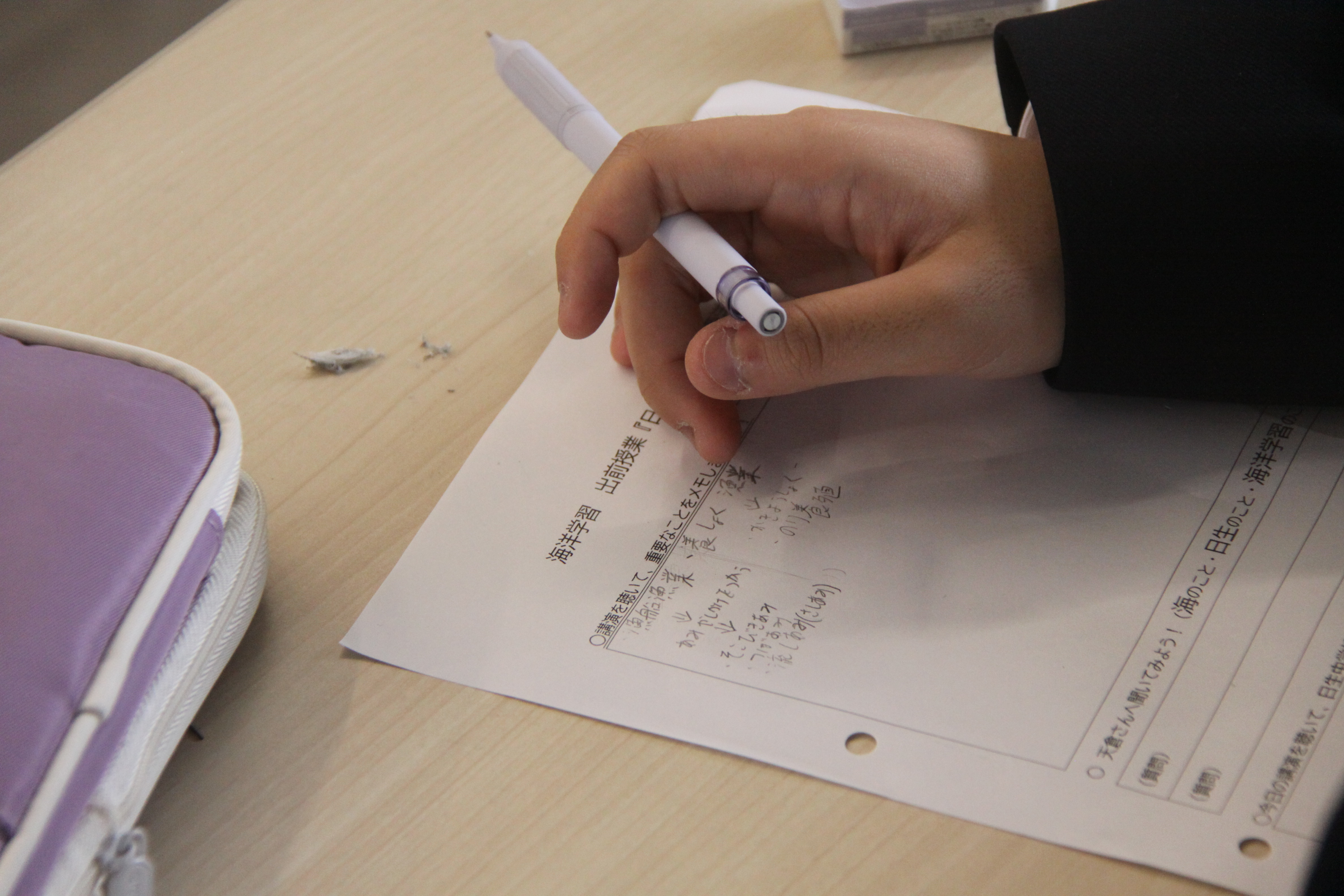
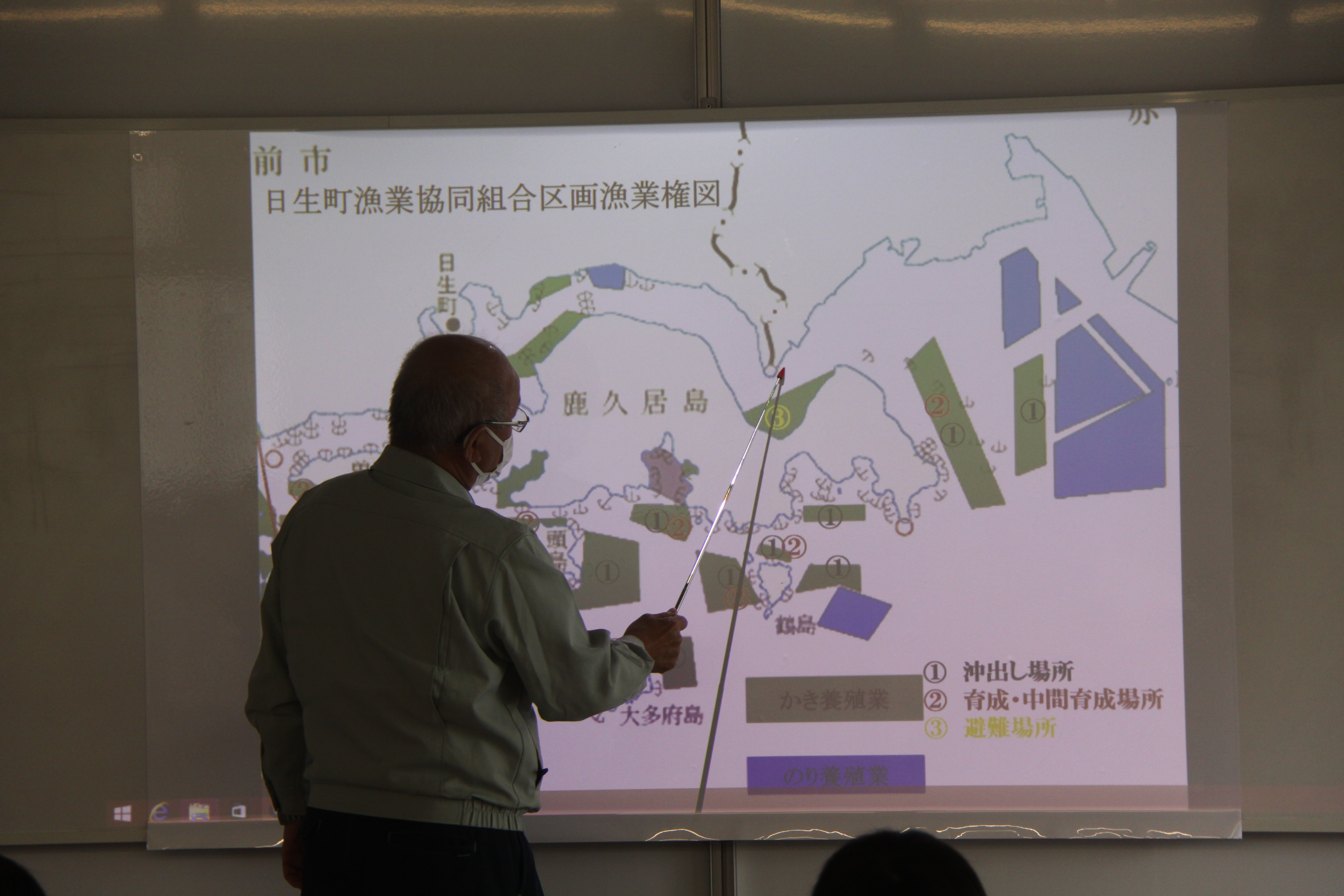

◎ひな中の風✨
~よい日を今日もつくるっ。(4/24)






◎ひな中の風✨
~大切にしている私たちの〈もくもく清掃〉(4/23)





整列っ(^_^)
◎おはよう おはよう よい日を今日もつくろっ。
(4/22:挨拶運動スタートしています)


◎私たちのはじまりの風景9
ここはどこでしょう??(ヒント:学校近郊と、校内中心ですよ)



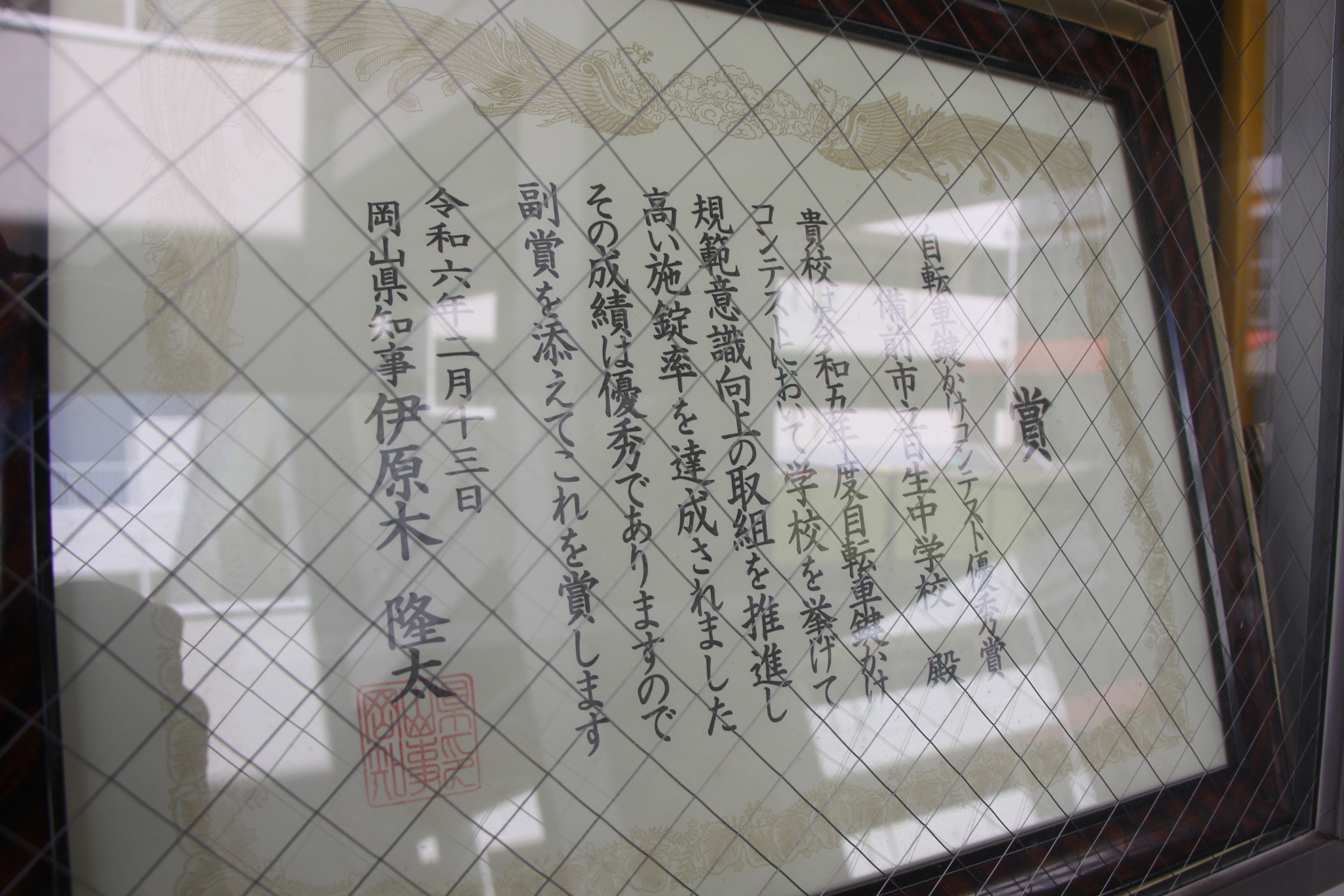



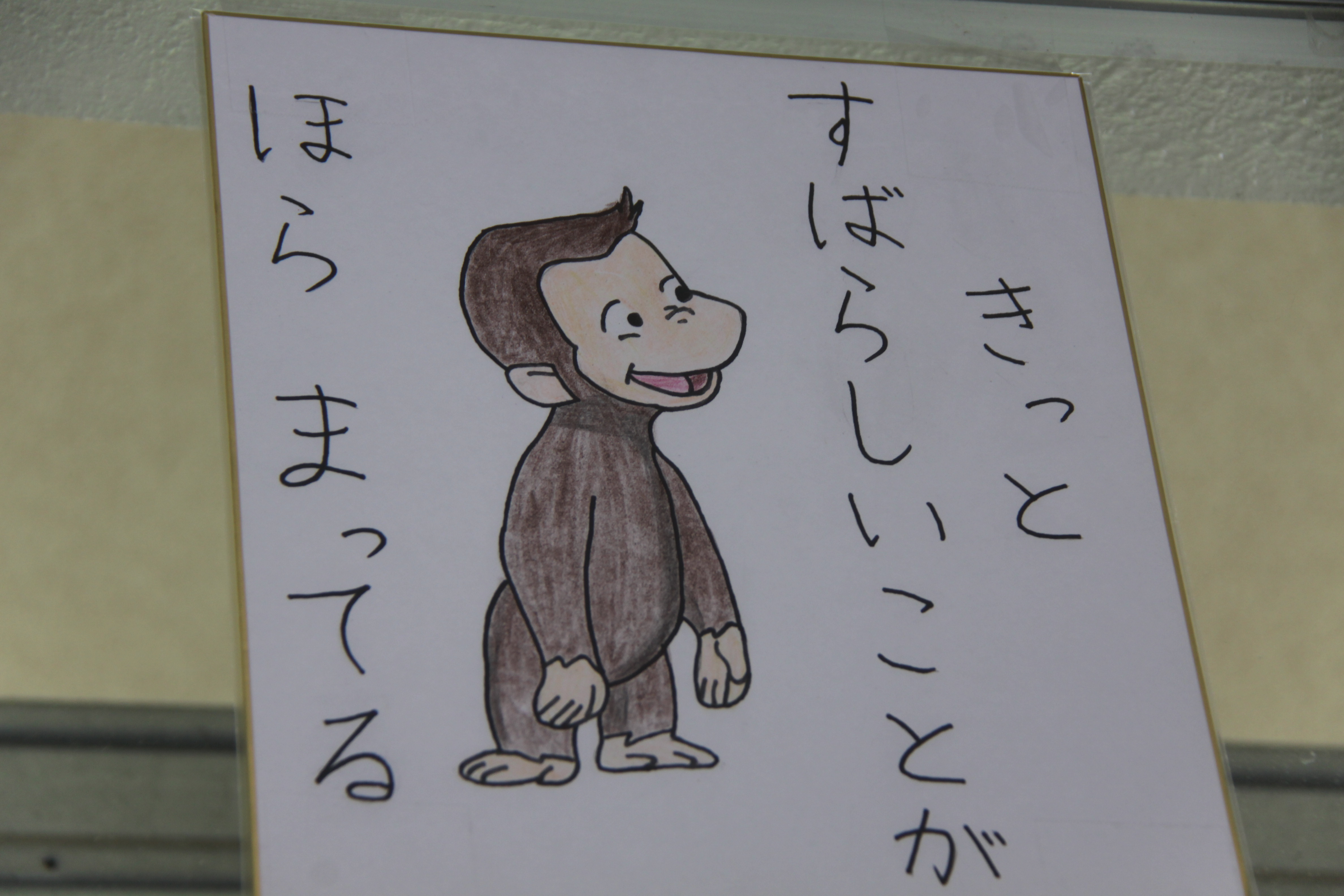

◎多くの人に支えられて(4/22)
~学びを確かなコトとするために~
昭和55年度卒業生同窓会様よりいただいた寄付金とPTAのサポートを受けて、活動・記録用カメラを購入させていただきました。カメラは、今週末の広島研修でのグループ学習や、沖縄修学旅行での班別自主研修に活用させていただきます。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

◎仲間と共に✨(4/20:閑谷研修)
〈これを知る者はこれを好む者に如(し)かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如(し)かず〉












◎いのちを守る(4/19)
備前警察署さんをエリア・ティチャーとしてお招きして、交通安全教室をおこないました。たくさんの質問にしっかりと答えていただき、学習をより深めることができました。ありがとうございました。
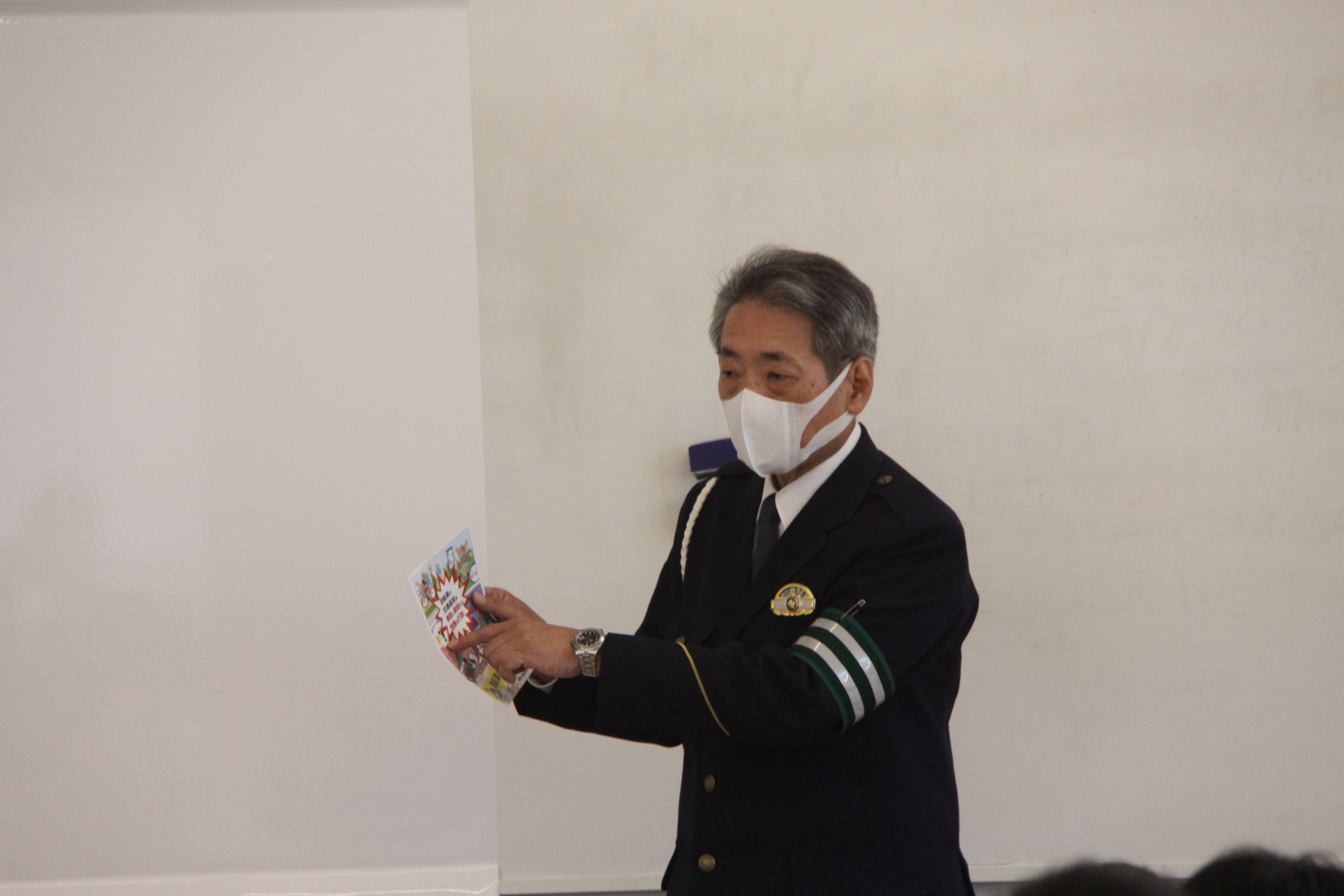

多くの人に見守られて
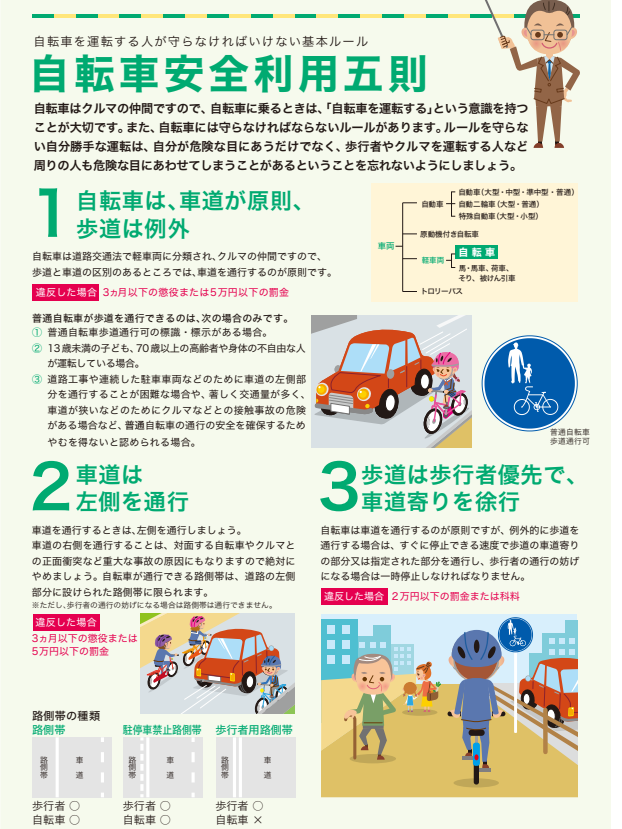
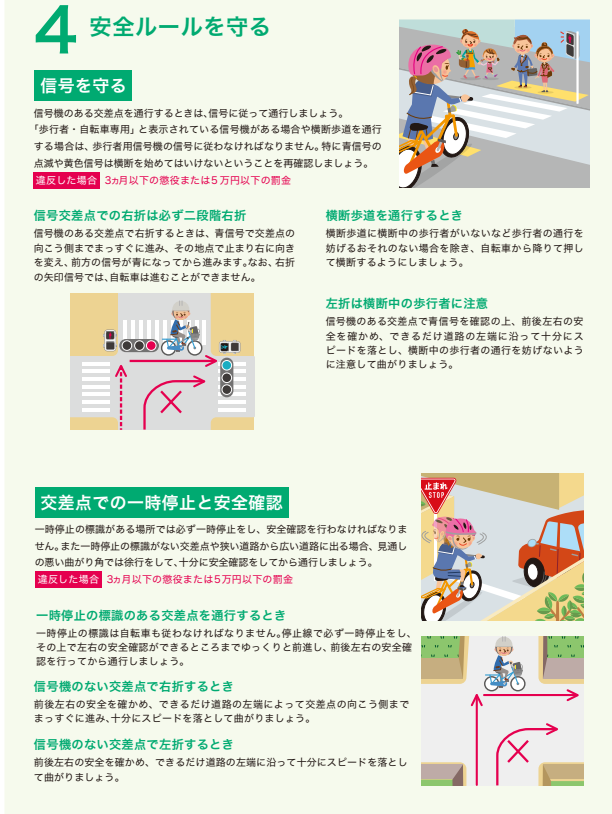
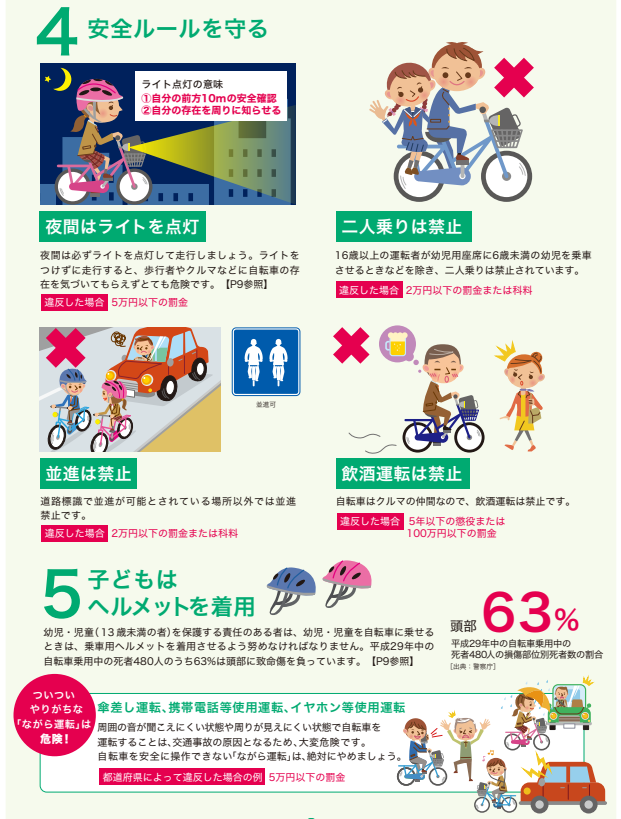
中高生は自転車事故での死傷者数が最も多い世代
自転車を運転中の死傷者数を統計で、年齢別に見ると、通学など自転車に乗る機会が増え始める中高生が多く、特に16歳の死傷者数が最も多くなっています。また、新生活が始まる4月より慣れてくる5月以降に注意せねばなりません。データで中高生の死傷者数を月別に見てみると、新生活が始まる4月よりも、5月、6月、7月の死傷者が増加しています。。その増加数は高校1年生と中学1年生に特に多く見られることから、通学路に慣れ始めることで注意力が下がってくることが考えられます。さらに、中高生の自転車事故で最も多いのは出会い頭事故です。中高生の自転車事故による死傷者数を事故の類型別に見ると圧倒的に多いのは、出会い頭事故です。出会い頭事故は、見通しの悪い交差点で起きることが多く、一時停止の標識の見落としなど安全確認をせずに交差点内に進入することが原因の大半です。(*出会い頭事故:交差点などで相交わる方向から進入してきたもの同士がぶつかる事故。ぶつかる相手はクルマとは限らず、自転車や歩行者の場合もあります)
大切なことを学んだ交通教室でした。今日からあらためて、高い意識をもって、登下校の安全に努めましょう。
◎東アジアとつながる黄砂 ~~~(4/18)

黄砂とは、東アジアのゴビ砂漠、タクラマカン砂漠などの砂漠域や、黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂やちりが、上空の風によって運ばれる現象です。 日本ではこの時期に観測されることが多く、空が黄褐色になることがあります。 各地の気象台では、空中に浮遊した黄砂で大気が混濁した状態を目視で確認しています。 黄砂の観測を開始した時間と終了した時間、決められた観測時間の視程(見通し)などを記録しています。 気象庁は、この16日昼過ぎから18日にかけて、北日本から西日本の広い範囲で黄砂が予想され、視程が10キロメートル未満となり、所によっては視程が5キロメートル未満となるという予報をしていました。
◎多くの人に支えられて
日生で輝く 日生が輝くチャレンジを!
4月18日、般社団法人ジンジャー・エールの東さん、BIZEN 360 STUDIOの椙原さんと、今年度の「ひな中チャレンジ企画」の打ち合わせをしました。昨年度はJessica先生との英会話教室を開催しましたが、今年度は、PTAと連携・協力したチャレンジ企画(6月~7月)を考えています。楽しみに!


◎全国学力・学習状況調査、岡山県学力・学習状況調査に取り組む(4/18)

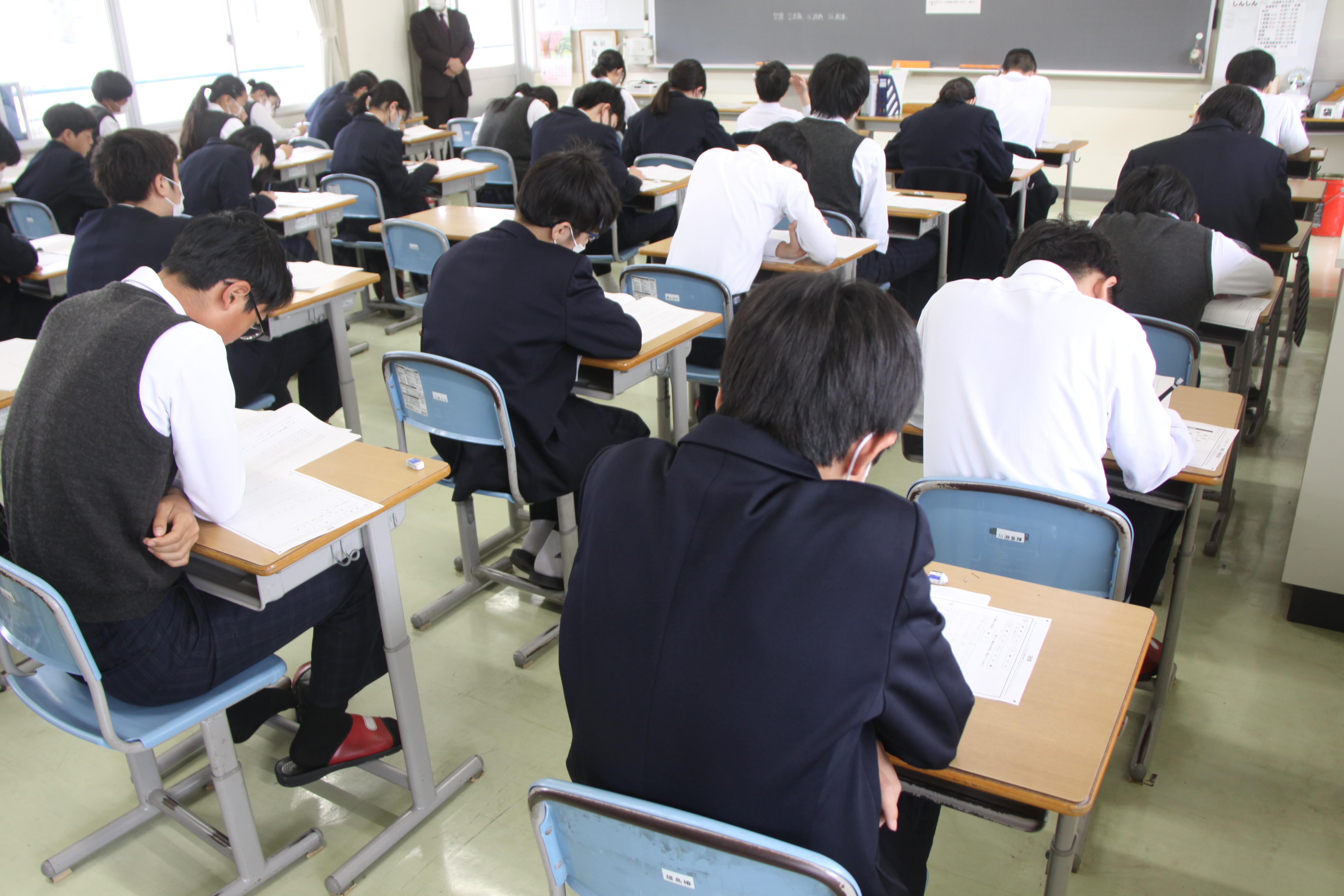
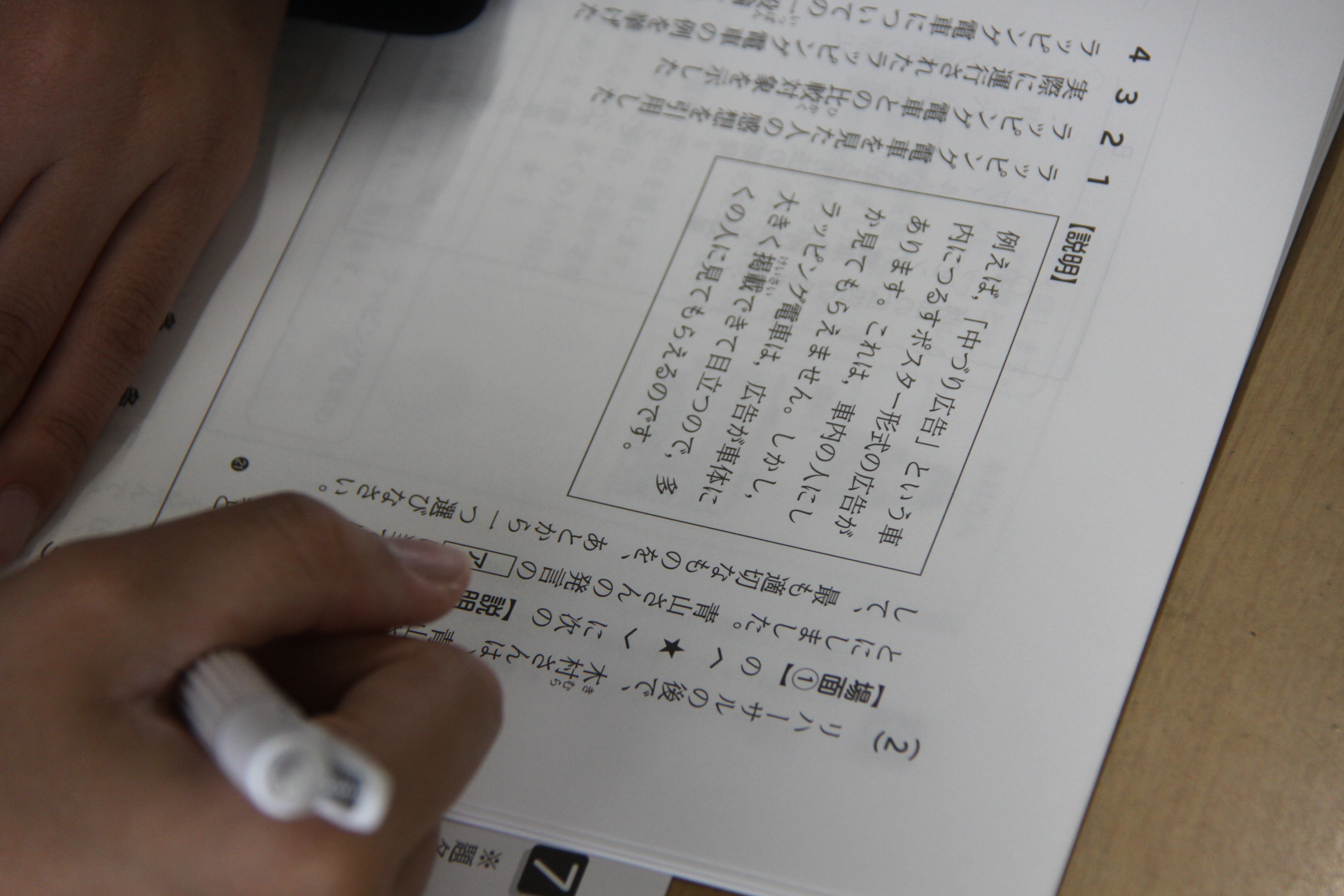

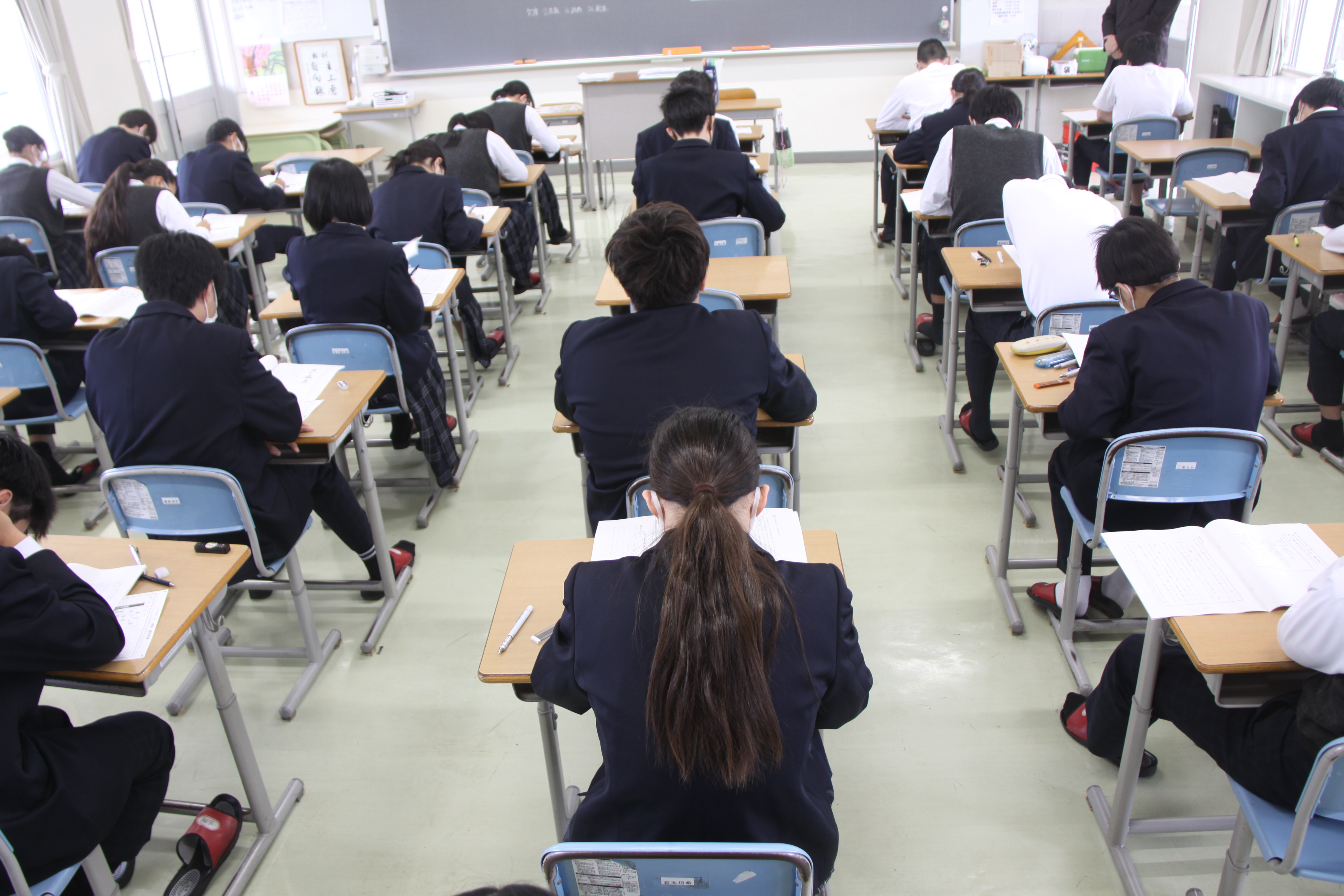
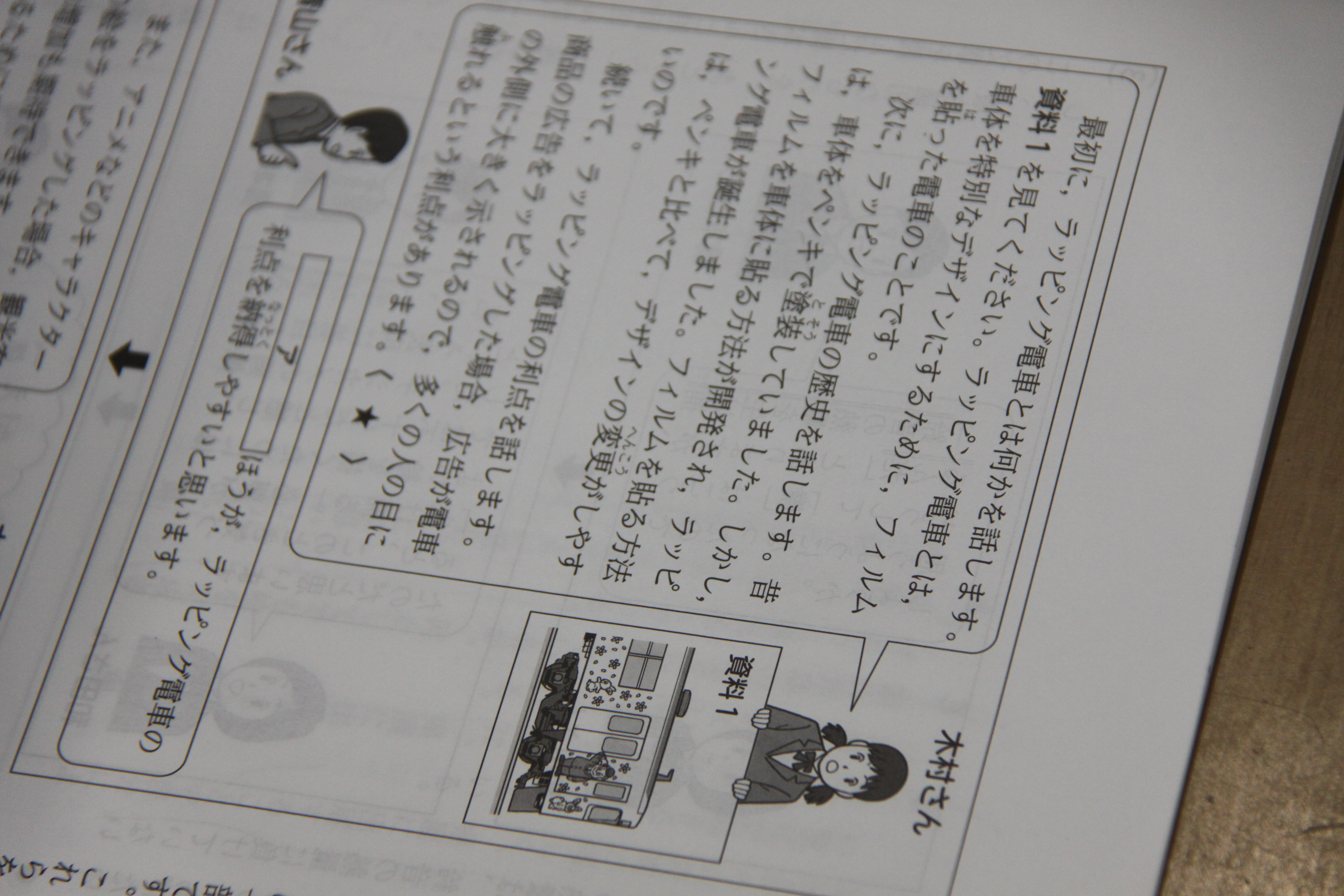
文部科学省は、全国学力・学習状況調査の目的を「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図り」、「学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる」「そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する」としています。
一年間を見通して、学力向上のプランを立てることそのものは、子どもの学力保障のためには、とても大切なことです。しかしそれが全国の競争にとなり、もはや一点を上げることに目的化した取組に変容してしまわないように、私たち学校現場は自覚しなければならないと考えます。また、近年、地方の自治体では、文部科学大臣と財務大臣宛の「全国学力調査に関する意見書」を採択したところもあります。意見書は、全国学力テストの点数をめぐって自治体間さらには学校間で競争がつづき、子どもと教員に深刻な影響が出ていると指摘し、全数調査から「抽出式の調査に改めることを求めます」とあります。また、さらに、その意見書では、OECDによる国際調査において日本の教員の労働時間が世界最長であったことをはじめ、教員の長時間労働にも言及しているようです。すなわち、ただでさえ過労死ラインを超える労働が蔓延しているなかで、教員のテストの分析と対策に追われていることを問題視しています。これは福井県議会も同様で、教員が学力向上のために多忙となり、子どもに向き合う精神的なゆとりを失っていることを指摘しています。
繰り返しになりますが、日生中も、本来の調査の目的を大切にして、「生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立て」ていきたいと思います。
◎PTA活動スタート(4/17 第1回委員総会開催)
ひな中のためにエンヤコラ もひとつおまけにエンヤコラ
中村新会長をはじめ、幹事、学級委員、教職員が第1回委員総会を開催しました。今年度の活動・予算、生徒ボランティア推進支援案などを協議しました。委員総会で決まったことは、PTA総会議案集にまとめ、5月1日の参観日に配布(書面協議)する予定です。また、会では、活動のさらなる改善・工夫のひとつのカタチとしてPTO(応援団)活動の資料もお配りしました。これからのさらなる充実のためのPTA活動、保護者活動へのご理解・ご協力をどうぞよろしくお願いします。PTA事務局






日生で輝く 日生が輝く(4/17)
備前市社会福祉協議会日生支所の嶋村さん、加藤さんと今年度の「夏ボラ」や赤い羽根街頭募金などの打ち合わせをしました。今年度も清掃活動や認知症サポーター養成講座(調整)など、地域と連携・協働した活動に取り組みたいと思います。地域の方々で、中学生ボランティアの要請がありましたら、社会福祉協議会(72-2510)か中学校へご相談ください。
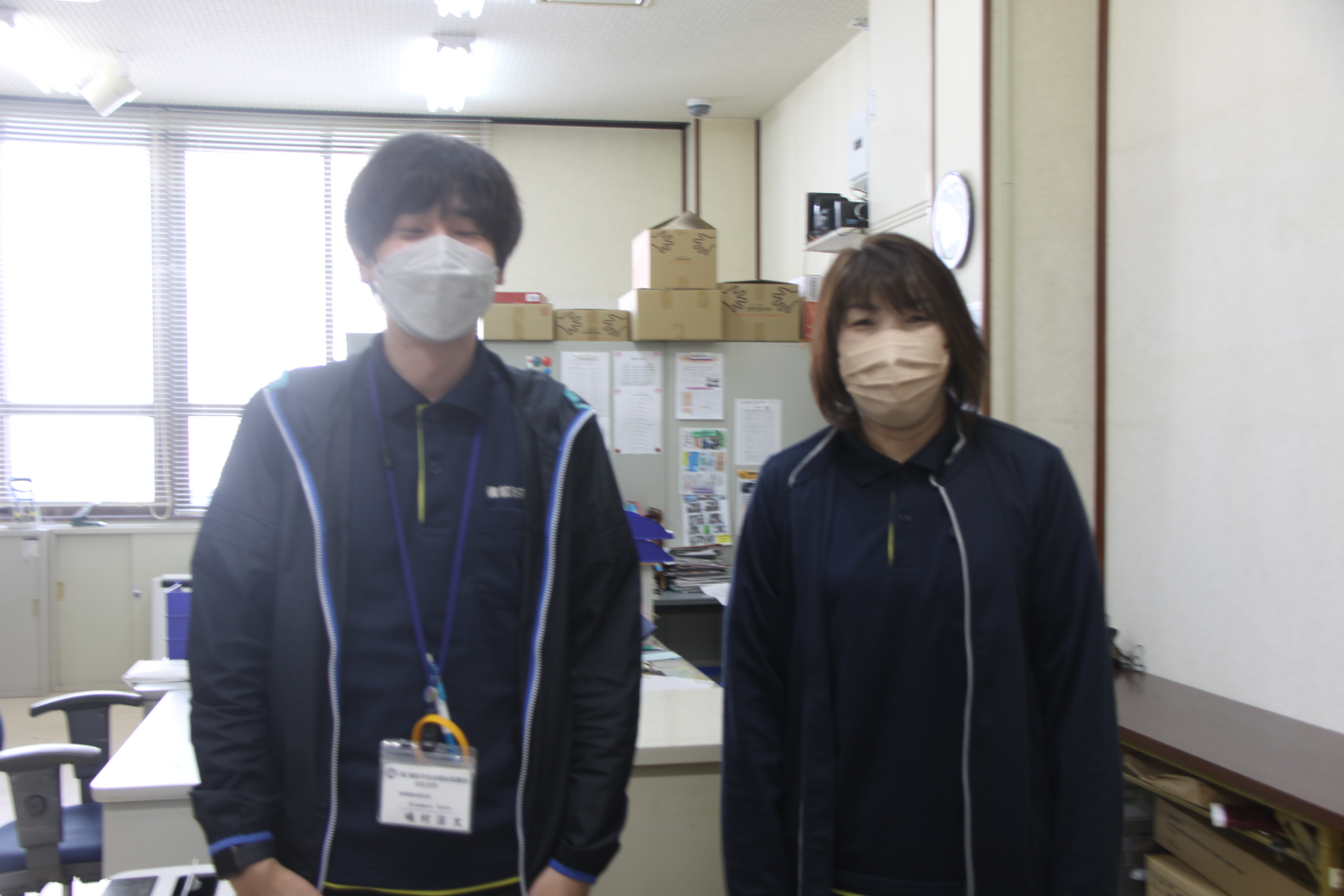
◎タノシイ セカイヲヒラク ワクワクスル ホンアリマス。
~オリエンテーションを終えて来室数UPUP↗
〈夕暮れにたまねぎむく指先の透くまま真理ほしがっており 鯨井可菜子〉





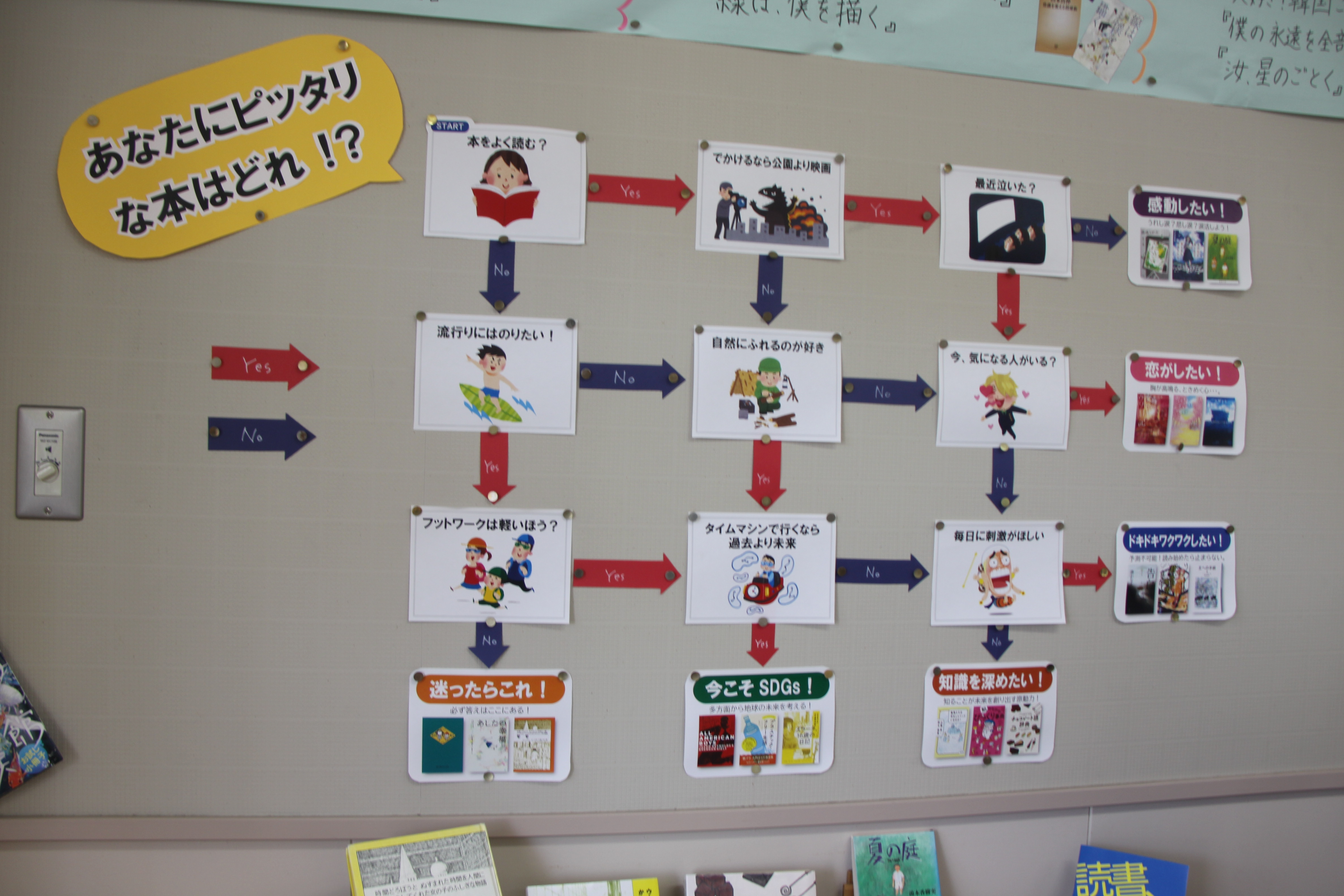


多目的1教室(備前市ご近所図書館検討中)も開館しています。
◎「明日のために その1」
係活動がスタートしています。


◎学校と保護者の連携を大切に
~希望懇談開催中
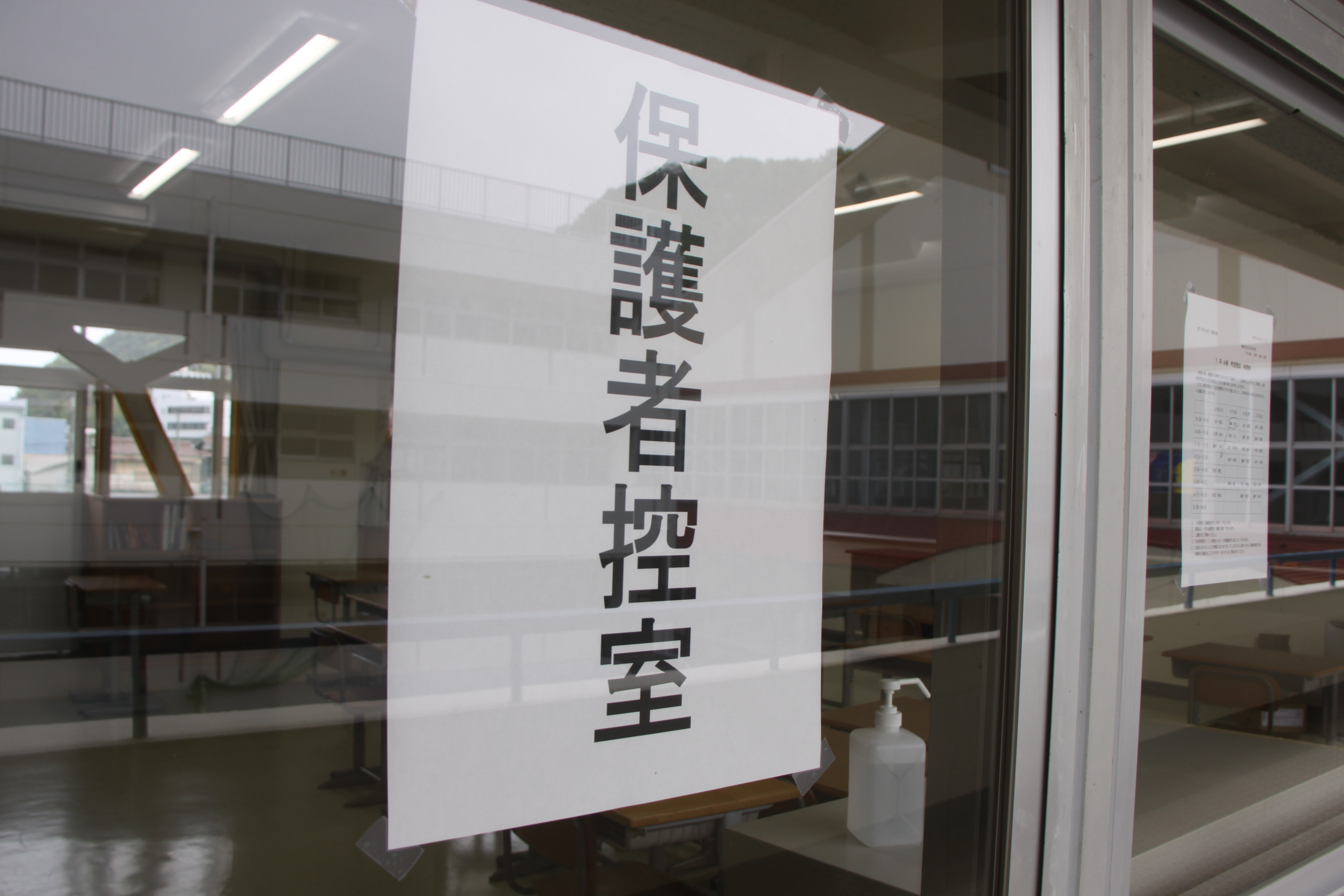
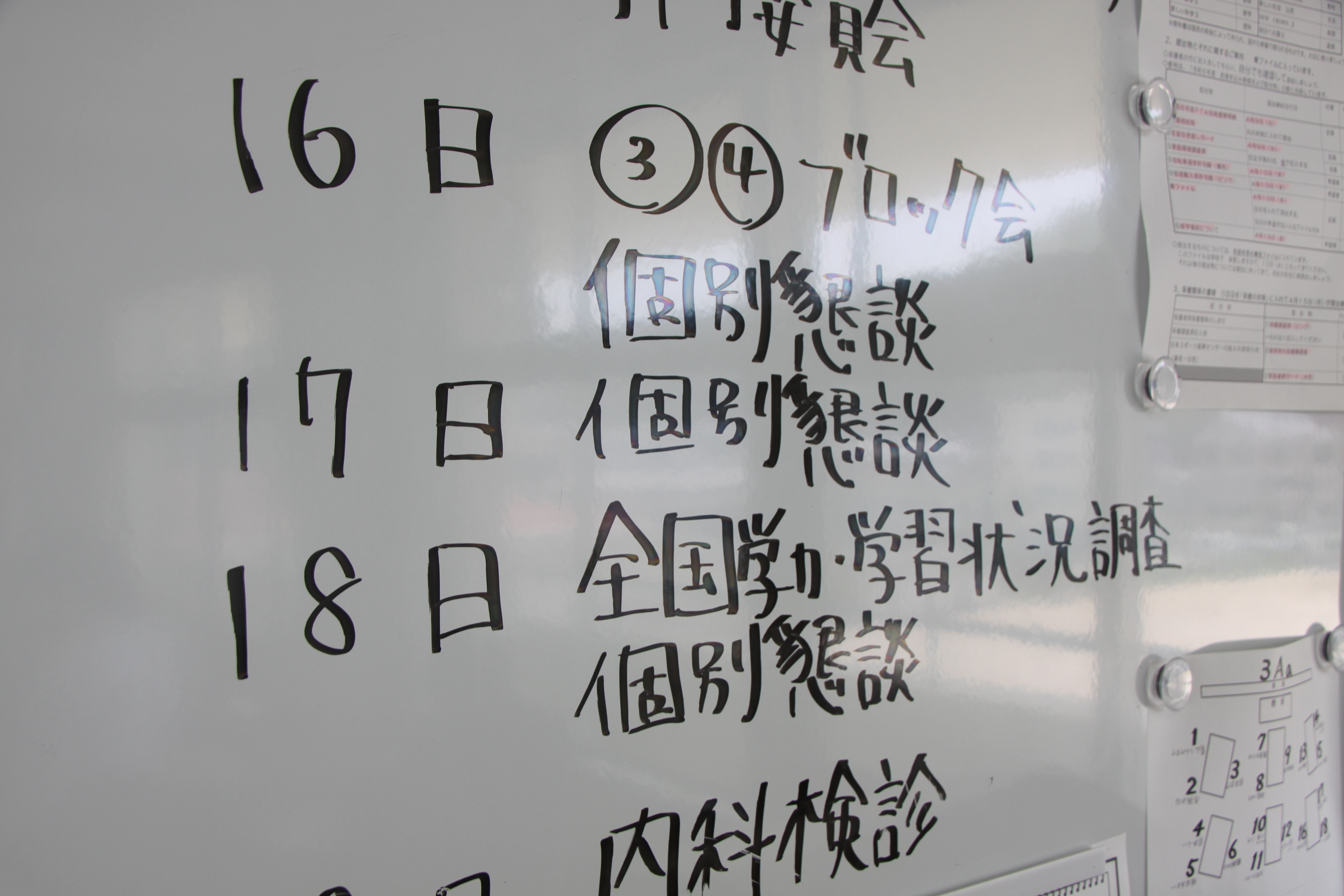
家庭訪問から希望懇談へ
家庭生活と学校をつなぐために家庭訪問はとても大切にされてきたものです。その信念を大事にしながら、日生中では4月のこの時期に希望懇談を開催しています。子どもを理解するためにはお家の方々と様々なお話を聴かせていただくことが必要です。家庭での親との関係が子どもの精神状態やものの考え方や感じ方をかたちづくっていきます。私たちは教室にいる子どもを相手に教科指導や生活指導をしていますが、お家の方がどんなふうに働き、どんな思いや期待をもって子どもを育てているのかなどもお聞かせていただいた上で様々な指導や支援をしていきたいと思っています。また、問題行動等が起こっても「一緒に手を取り合って子どもを育てていきましょう」というスタンスで日生中はお家の方と連携していきたいと考えています。短い時間ですが希望懇談が充実しますようよろしくお願いします。また、子育てや特別支援等なにかありましたら、いつでもご相談ください。
◎「明日はどっちだ?」
1年生教室に出向き、部活動紹介を行っています。この日(4/17)は、バスケットボール部(男子)、アーチェリー部が来室し、部活動勧誘の説明をしていました。日生中は、この他に、ソフトテニス(女子)、美術部、吹奏楽部が新入部員を募集しています。部活動見学可能日は16、18、23、25、26、27、28、29(休日は練習場でのアーチェリー部も可)です。1年生部活動入部届は5月2日〆切です。
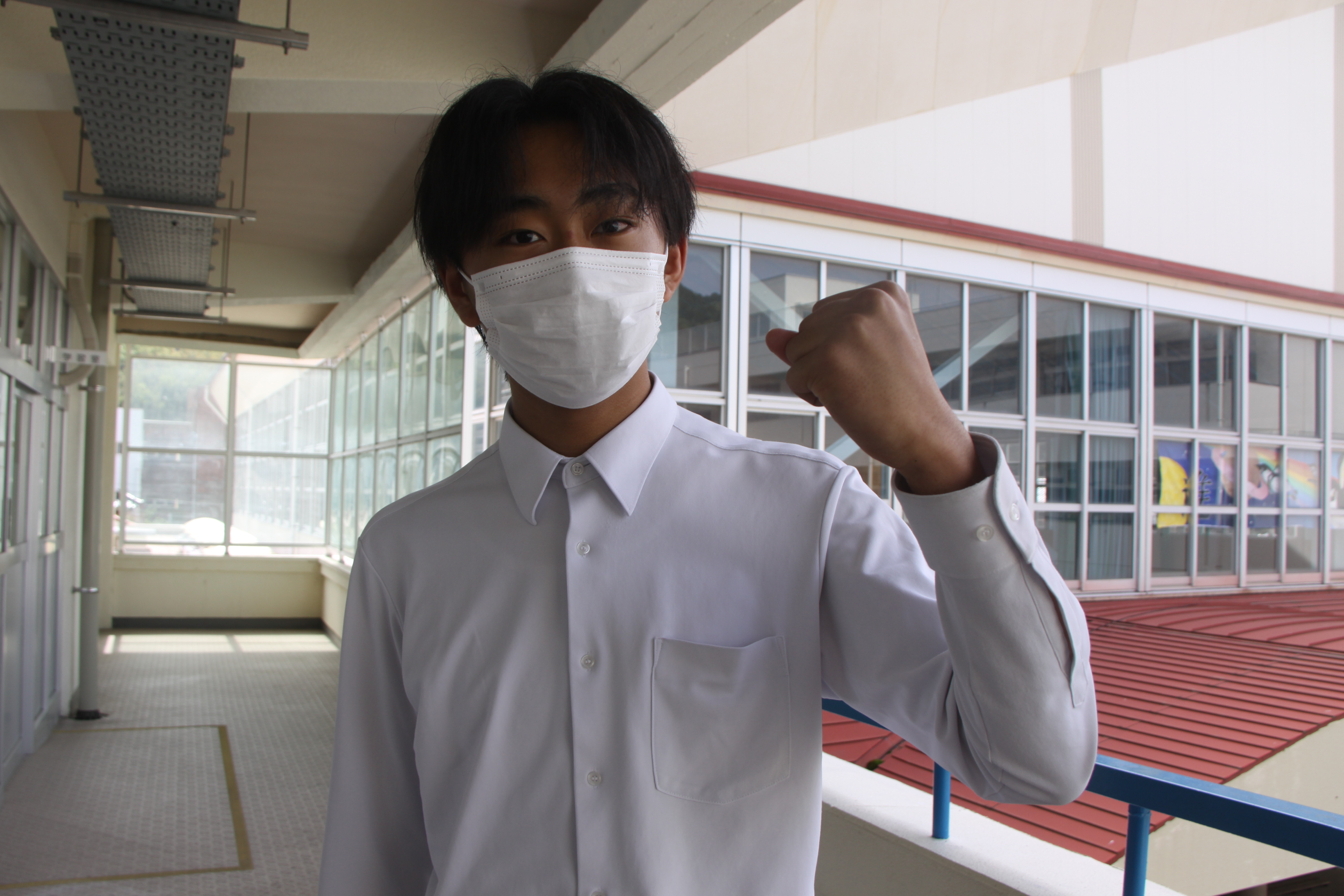

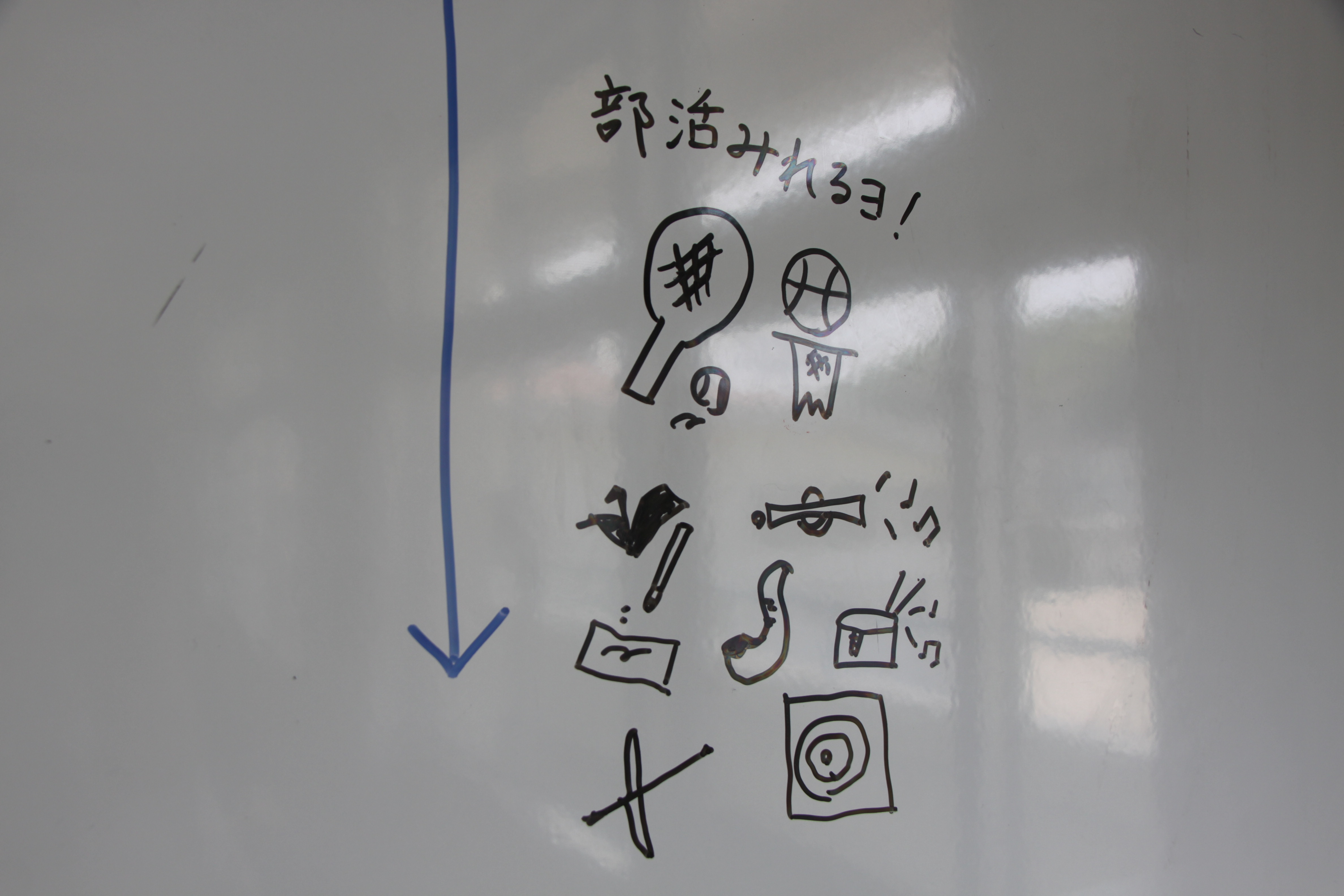
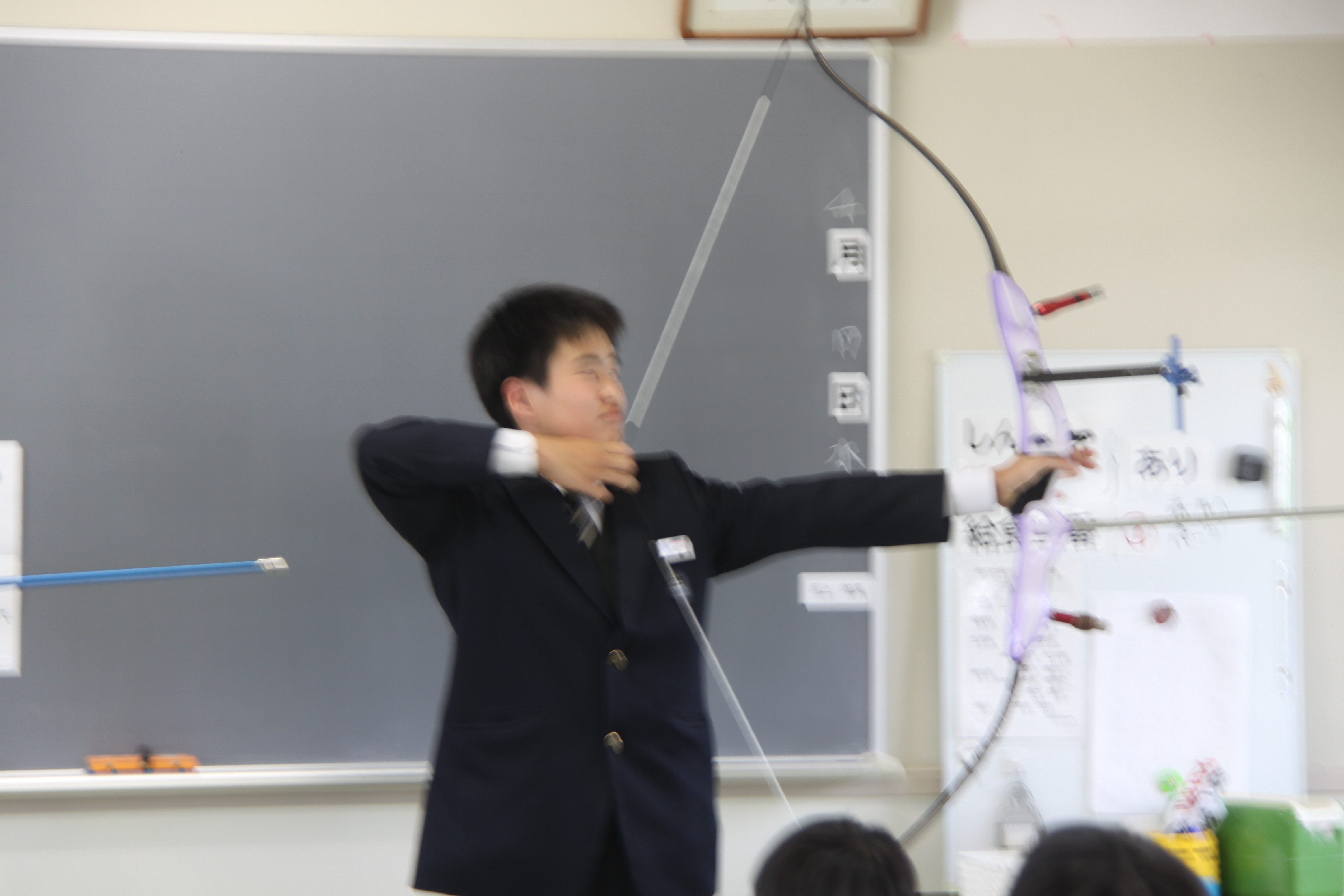








◎「やまちゃんもみんなを応援している一人です」(4/17)
本校、山﨑克磨スクールカウンセラーが1年生教室で出向き、「いろいろな相談にのるよ」と話しました。相談日は毎週水曜日午後が基本です。ご希望がありましたら、お気軽に、保健室の髙橋(養護教諭)先生に連絡してください(72-1365)。
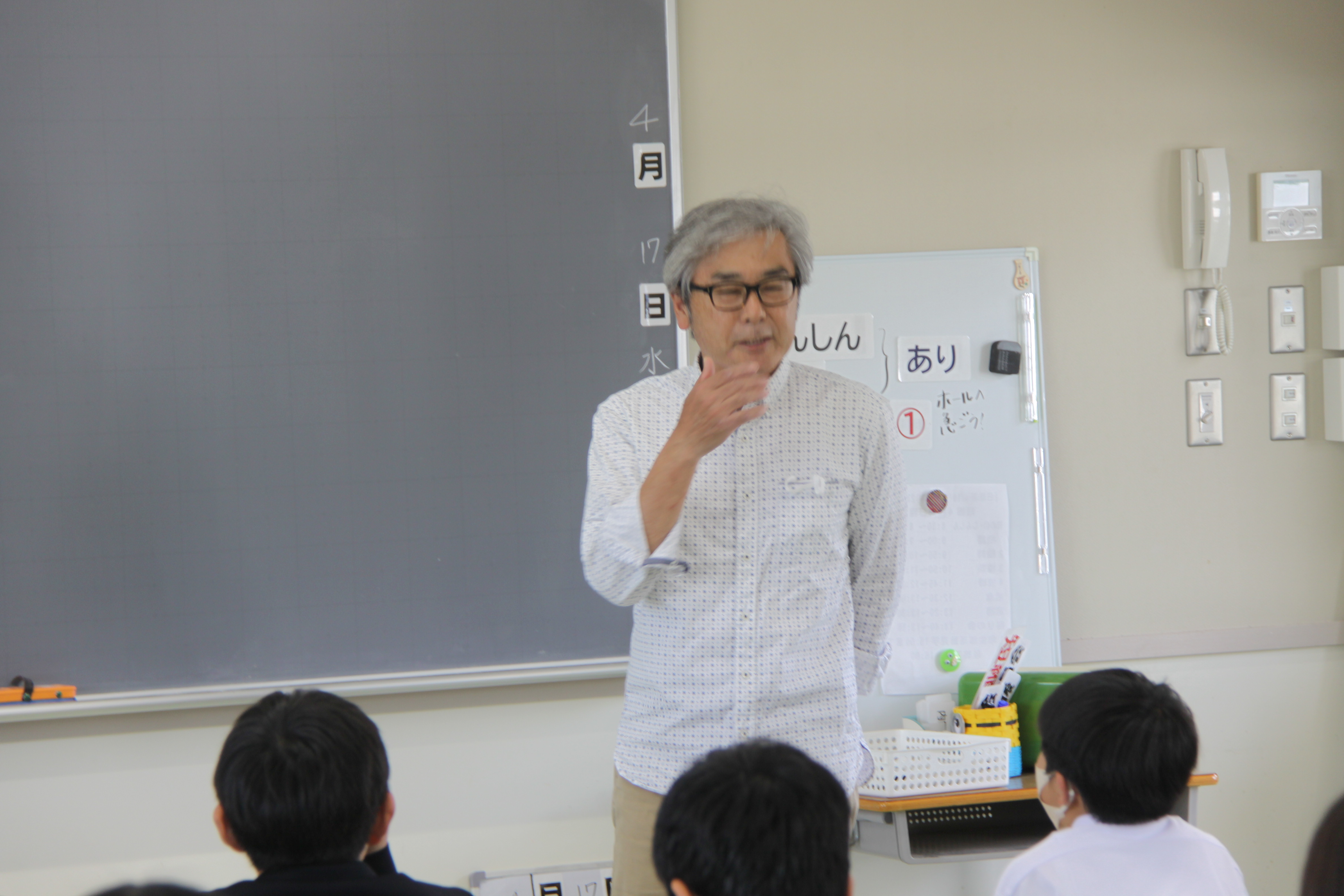
お話においで(^_^)。
◎「これってどうするん?に応えられる」仲間と共に。(4/16)
班やグループで話し合ったり、相談したりする活動を大切にしています。


◎仲間と共に
~日生が輝く祭りのために!(4/16ブロック会)
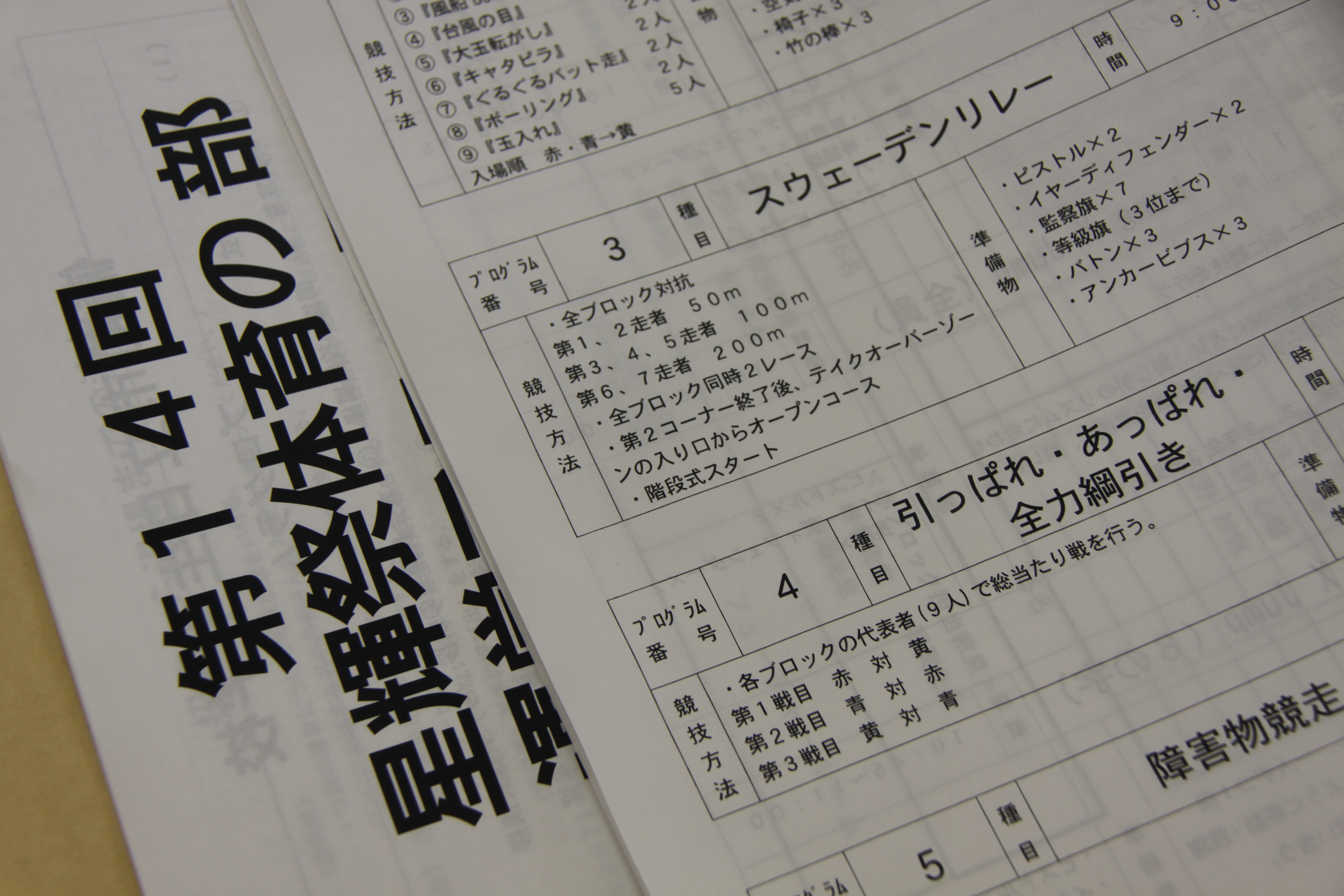
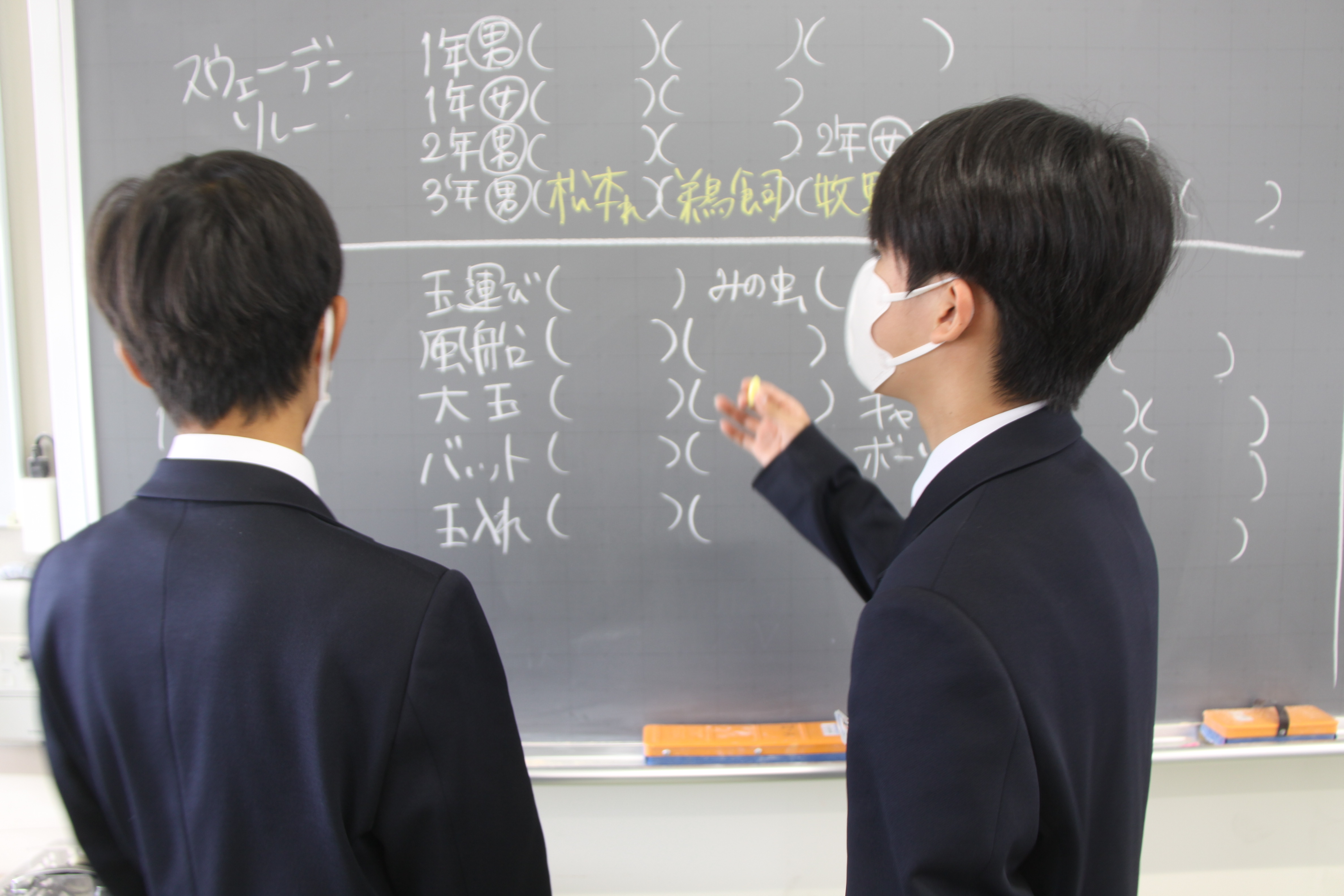






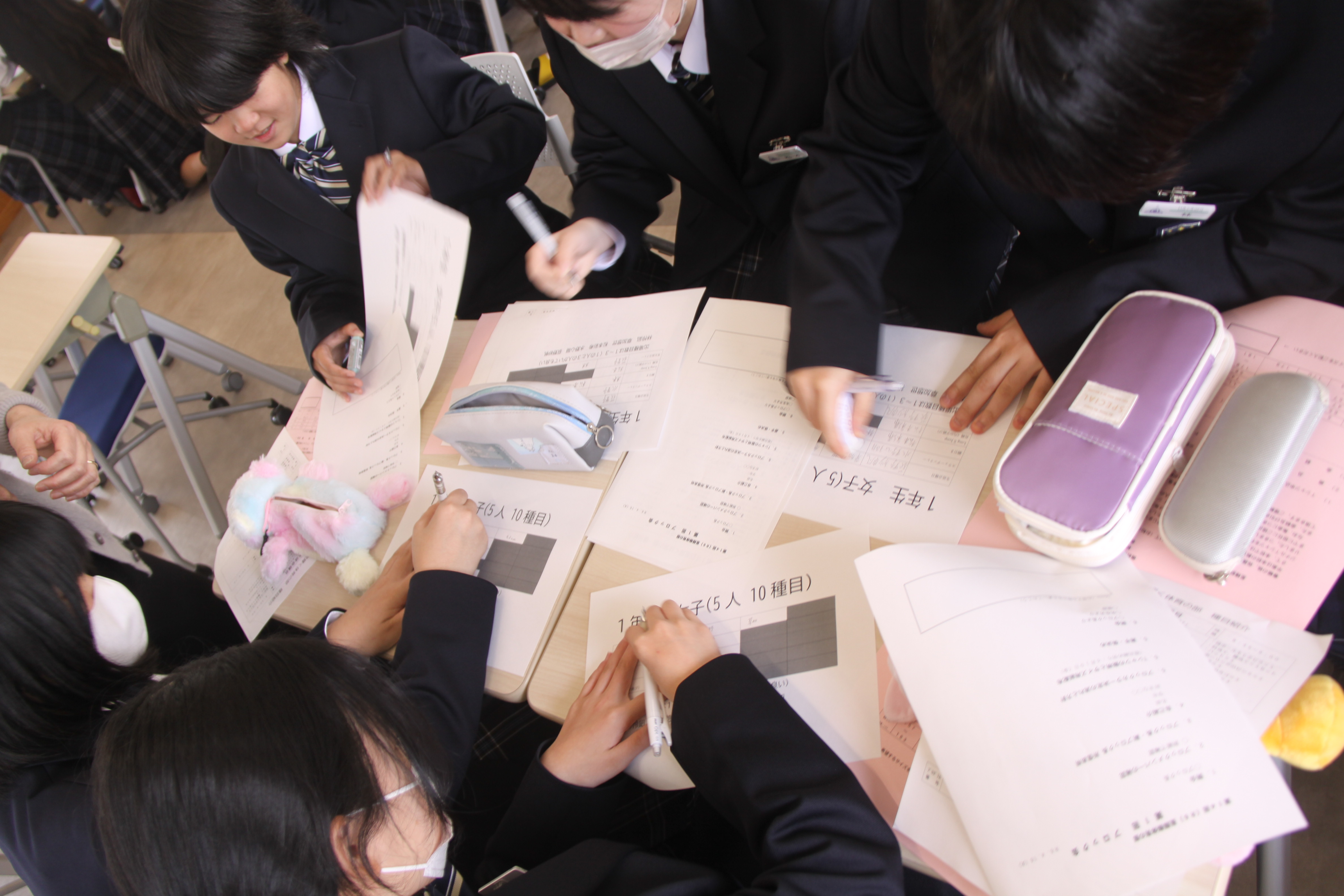
✨2024年6月1日(土)9時開会 (雨天順延時6月2日(日)予定)
◎授業が大切
~授業改革推進員の三宅先生と共に(4/16~)

岡山県は、各学校の教員の授業力向上や、学校の学力向上の取組を支援するための指導・助言を専門的に行うために、県内3つの地域(小学校:倉敷・津山・美作 中学校:倉敷・東備・西備)に授業改革推進員を配置して組織しています。今年度は、三宅先生が毎週火曜日に日生中学校に来校されます。
◎ひろく 深く おのがじし
~届け 私たちの想い
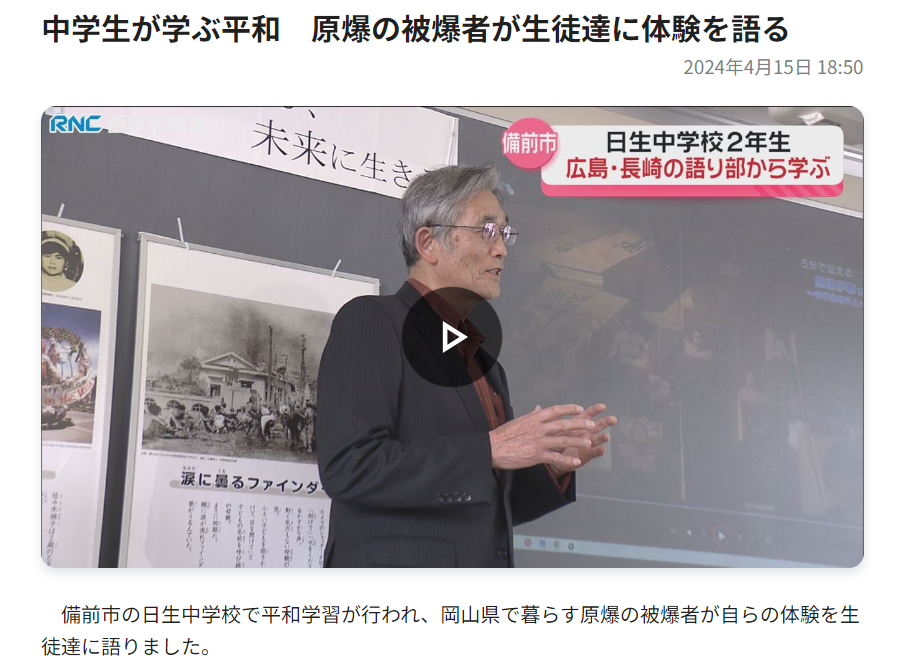
西日本放送局(画像はHPニュースエブリー)、NHK放送局、山陽新聞社さんが来校されました。
◎「私たちはどう生きるか?」
~ヒロシマ・ナガサキ・ヒバクシャの思いを受けて。(4/15)
語り部の村山さん、桑原さん、草加さんをエリアティーチャーに、2年生は、広島研修の事前学習を深めました。一人ひとりが平和探求テーマを持って、4月25日・26日には広島の地に立ちます。

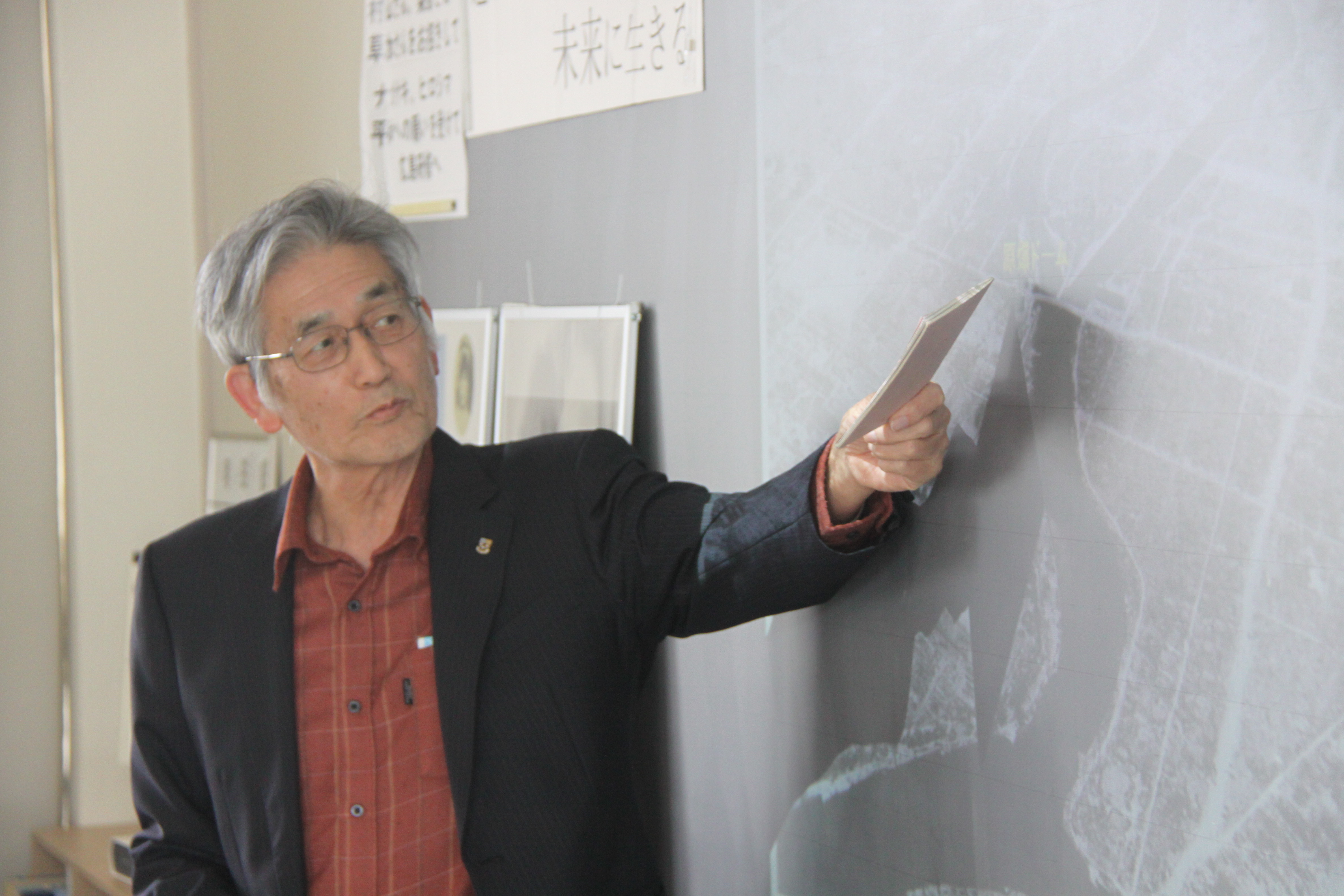

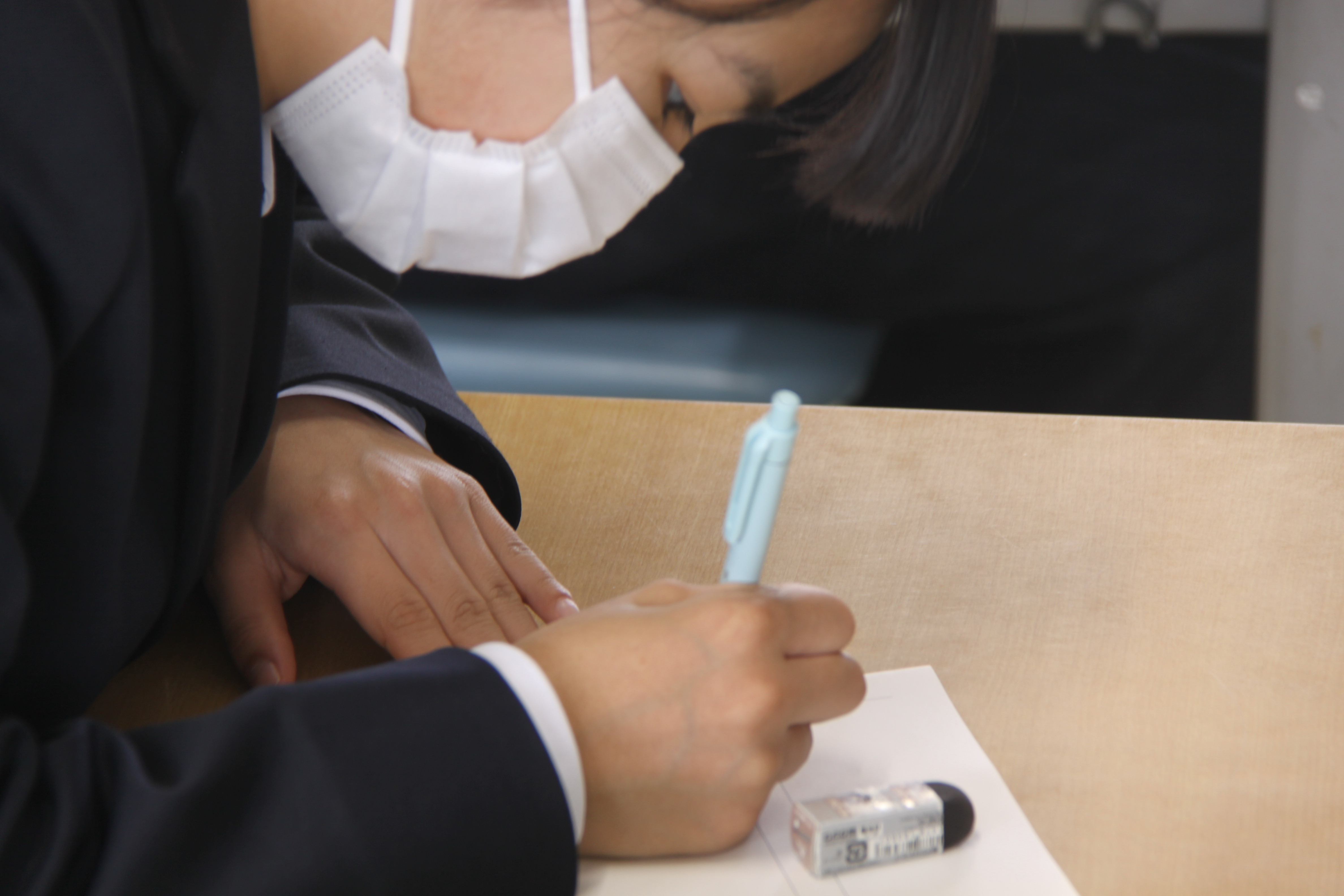





序(にんげんをかえせ)
ちちをかえせ ははをかえせ
としよりをかえせ
こどもをかえせ
わたしをかえせ わたしにつながる
にんげんをかえせ
にんげんの にんげんのよのあるかぎり
くずれぬへいわをへいわをかえせ 『峠三吉 原爆詩集』
◎多くのひとに支えられて(春の交通安全県民運動)
日生ライオンズクラブの方々や多くの方が、交通安全指導・見守りをしてくださっています。ありがとうございます。



交通ルール守って笑顔 晴れの国
◎仲間と共に
~生徒会専門委員会認証式・校則改定についての報告(4/15)
私たちがつくる生活・クラス・学校・そして日生✨

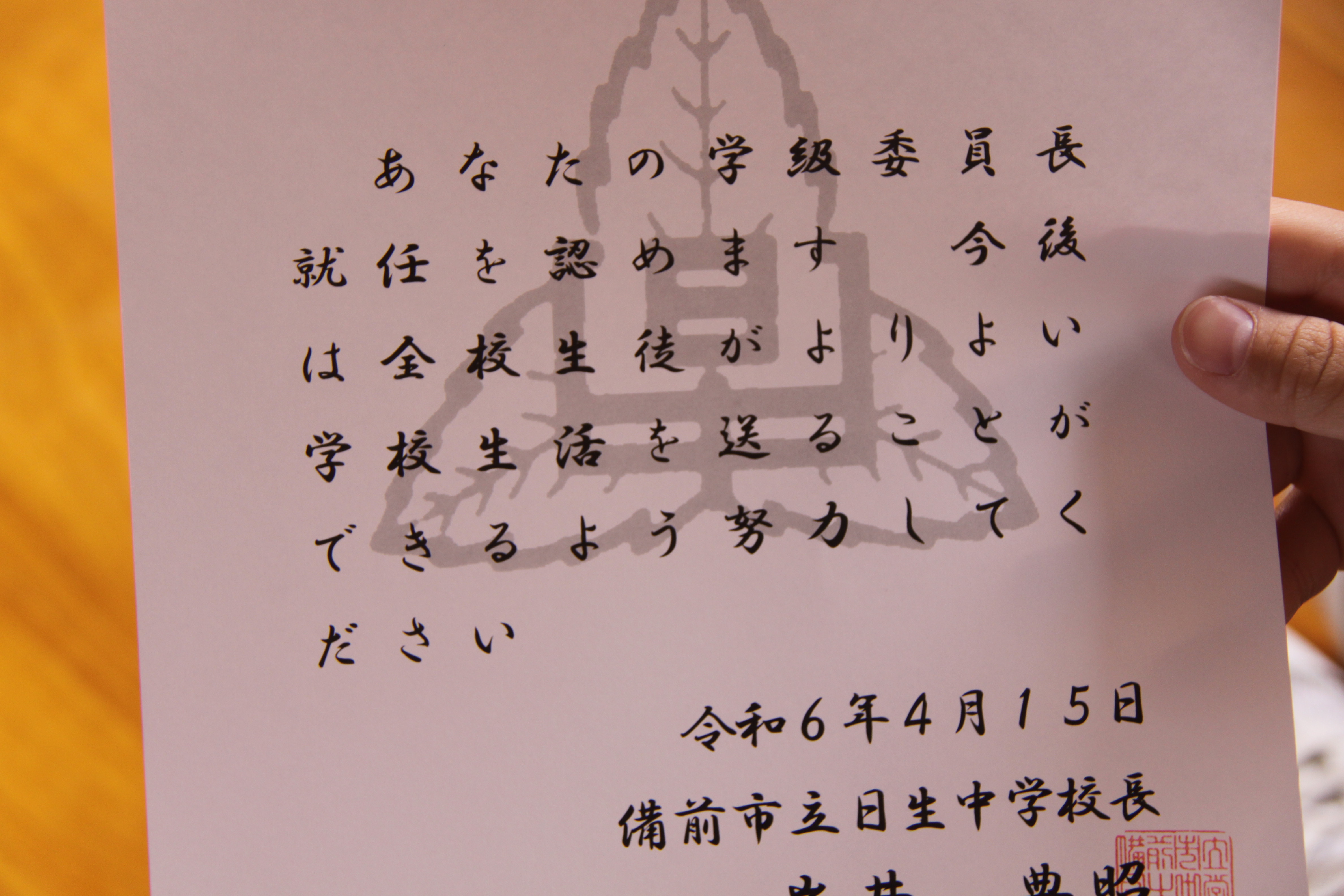





◎すくすくと🌱と(中学校給食スタート)
調理場の北川先生が来校してくださいました。日生中学校は今年度も「食育」を大切にしていきます。また、食物アレルギーに関する面談も来週から行います。気になる方がおられましたら、学校にお問い合わせください。


◎仲間とともに~自転車点検(4/12)
〈気をつけていらっしゃい 行きよりも明るい帰路になりますように 桝野浩一〉


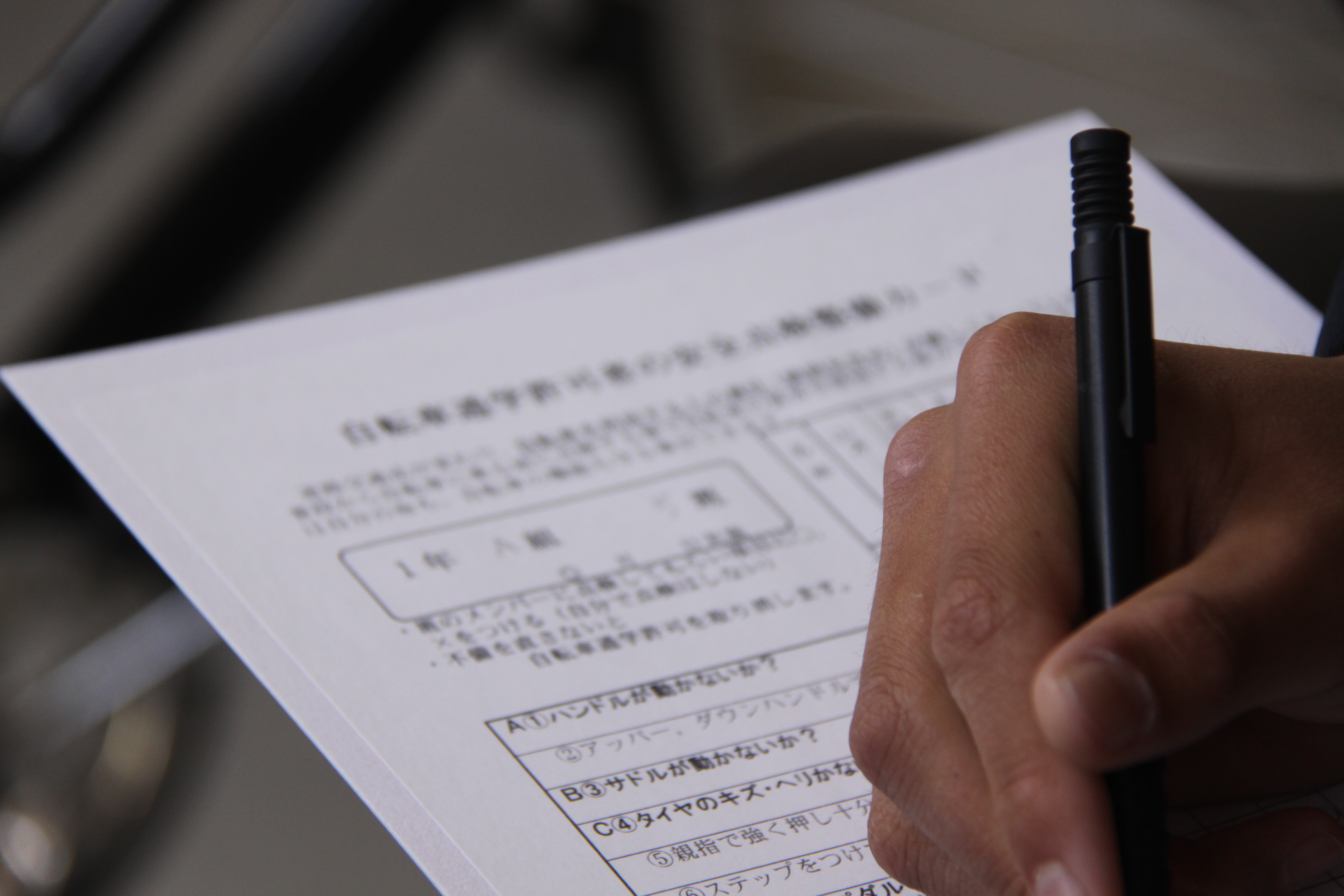



6日(土)から15日(月)の10日間にわたって実施されている「春の交通安全運動」。広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。
今年の本運動では3つの重点ポイントが設定されています。その中の1つはこどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践です。続けて「子どもを交通事故から守るための重点ポイントで、次代を担うこどものかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることは重要であるにもかかわらず、交通事故による幼児・児童(小学生)の死者・重傷者では歩行中や自転車乗用中の割合が高く、また、新学期が始まる4月から6月にかけて、死者・重傷者が増加する傾向にある。加えて、歩行中児童(小学生)の死者・重傷者の通行目的では登下校が全体の約4割を占めるなど、依然として通学路を始めとする道路においてこどもが危険にさらされている状況にある。また、こどもに限らず、交通事故死者数全体をみると、歩行中の割合が最も高く、歩行者側にも走行車両の直前・直後横断や横断歩道外横断、信号無視等の法令違反が認められる。このため、こどもが安全に通行できる道路交通環境を確保するとともに、全ての歩行者に対し、道路の安全な横断方法を実践するよう促していくことが必要である。」としています。
日生中では、今日(12日)に、自転車点検を行い、19日には、備前警察署さんをお招きして、交通安全教室を行います。また、教職員による街頭交通指導にも取り組んでいます。通学路で危険な箇所や安全安全に関することがありましたら、備前市役所日生支所や学校にご連絡をください。
◎ひな中の力~
Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. Bernard Shaw
(人生とは自分を見つけることではない。人生とは自分を創ることである。)






◎仲間とともに 入学おめでとう!
~ともに笑い、ともに泣き、ともに喜び、ともに悩み、ともに歩もう。
(4/11・入学式)





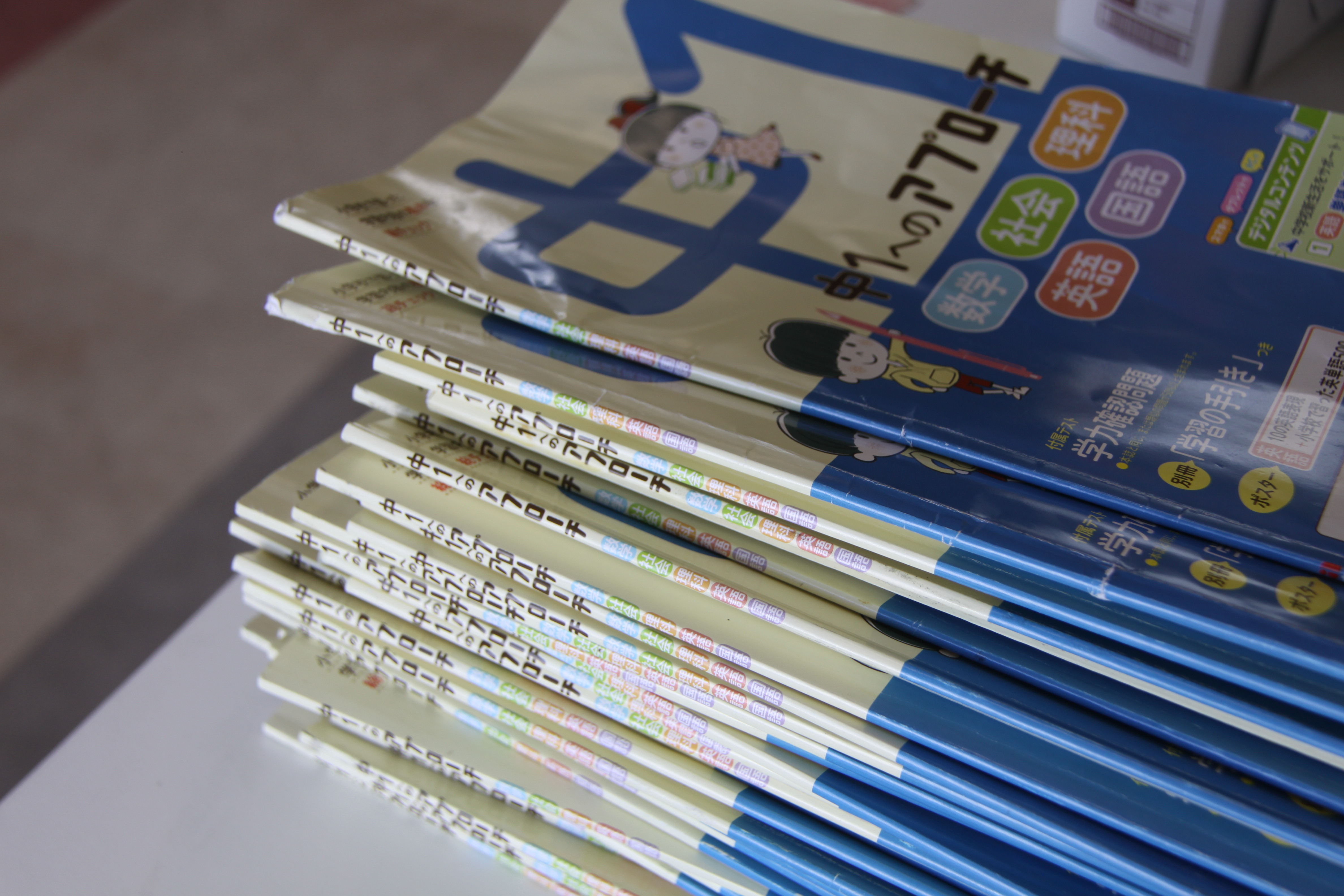






◎教科書は、よりよい社会をつくるために、これまで、たくさんの人々の努力によって、無償でみなさんに支給されています。
以下の文章は高知市立長浜小学校のホームページの一部です。「子どもたちは,新学期をむかえるたびに,真新しい教科書を手にし,ページをめくりながら,これからはじまる勉強に期待をいだき,進級した喜びをかみしめることができます。しかし,この教科書も今から50年ほど前までは,みんなが新しい教科書をただでもらえるというわけではありませんでした。
その頃,教科書は,毎年,新学期をむかえる前に各家庭でそろえることになっていました。3月になると保護者たちは,古い教科書をゆずってもらったり,古くて使えないものや,ないものだけを買いそろえたりして苦労していました。新しい教科書を全部そろえると小学校で700円,中学校で1200円ほどかかりました。一日働いても300円ほどの収入しかなかったのですから,子どもの数が今に比べて多かったその当時は教科書をそろえてやるだけでもたいへんな出費でした。
1960年(昭和35年)ごろになると,物価も値上がりをはじめ,教育費の保護者負担を軽くしようという動きも出はじめました。このころ,長浜地区の中でも,学校の先生たちや市民会館の館長さんといっしょにお母さんたちの読書会がはじまりました。2年ほどたつうちに,「わたしたちが習った歴史と今の子どもたちが習っている歴史は全然ちがう。わたしたちも子どもの教科書を使って勉強しなおそう。」という声が出はじめ,憲法の学習もはじまりました。
その中で,憲法26条に記されている「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。」という部分が問題になりました。「義務教育はこれを無償とするというのだから,教科書を買うのはおかしいのじゃないか。」「教科書はもともと政府が買いあたえるべきものだ。」「教科書がただでないということは,憲法で定められたことが守られていないということではないか。」ということが,話し合わされました。
そして,1961年(昭和36年)3月に,長浜地区で行われた会合の中で,「いくら請願しても効果はない。ただで配るまで買わずに頑張ろう。」という提案がなされ,校区のいろいろな団体が中心になって「長浜地区小中学校教科書をタダにする会」がつくられました。
この会は,各地で集会を開き,署名運動をはじめ,いっしょにたたかう団体もふやしていきました。教科書の無償要求は,憲法を守るための運動であるということに気づいた人々は,この運動をもりあげささえていきました。
その要求の正しさが理解され,1週間もたたないうちに長浜地区で1600名もの署名があつまりました。その要求を高知市の教育委員会にもちこみ,「憲法を守るために教科書を買わない。」というたたかいを始めました。運動は,新聞やテレビにもとりあげられ注目をあびました。
教育委員会は,「教科書をタダにする会」との交渉によって,無償の要求は正しいと認めましたが,全員に教科書を配るという約束は絶対にしませんでした。買える能力のある人は買ってほしいという教育委員会の要求をはねのけ,2000名の児童生徒のうち約8割にあたる1600名が,教科書を買わずに新学期がスタートしました。
学校では,教科書を持たない多くの子どもたちのために,先生たちはガリ版刷りのプリントを使って毎日授業を進めていきました。
その後,運動の正しさがたくさんの人々や団体・政党に支持され,全国的な運動に発展し,国会で大きな問題として取りあげられました。政府もついにこの要求の正しさを認め,1962年(昭37年)に法律をつくって,翌年から段階的に教科書が無償で子どもたちに配られることになりました。
私たちが,今なにげなく手にしている一冊一冊の教科書には,このような運動があったのです。
1961(昭和36)年からはじまった教科書無償の運動から今年で50年目を迎えました。この運動の歴史的な意義や当時のようすを,今の子どもたちや地域の方々など,たくさんの方々に知っていただきたく,教科書無償運動50周年記念パネル展を開催することになりました。高知市立長浜小学校【教科書無償運動50周年記念パネル展資料より】
〈「人間はよいものかしら」母狐ふはとつぶやき白綿のやう 米川千嘉子〉
◎仲間とともに
~明日は待ってるよ 1年生!(*^▽^*)(4/10)

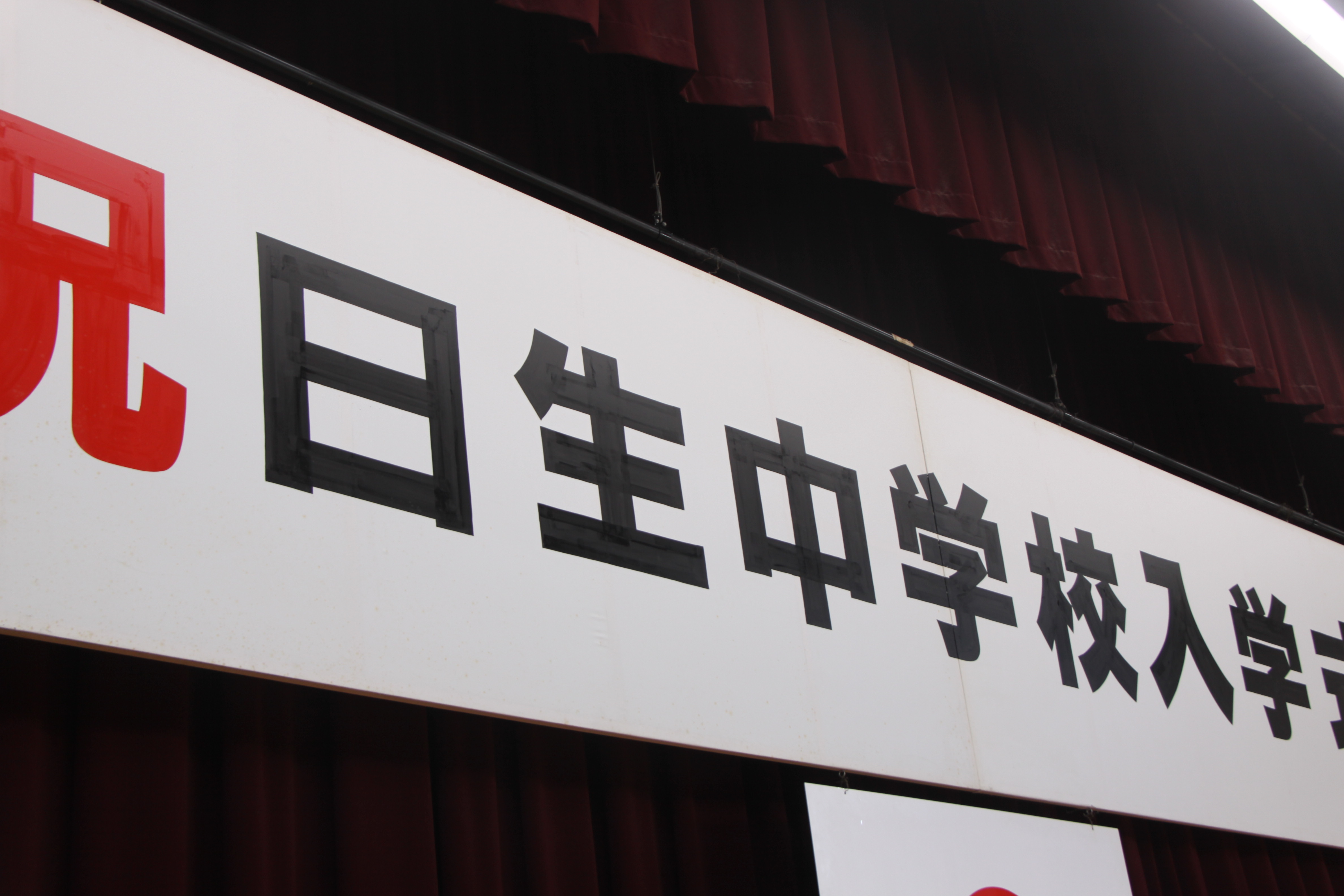
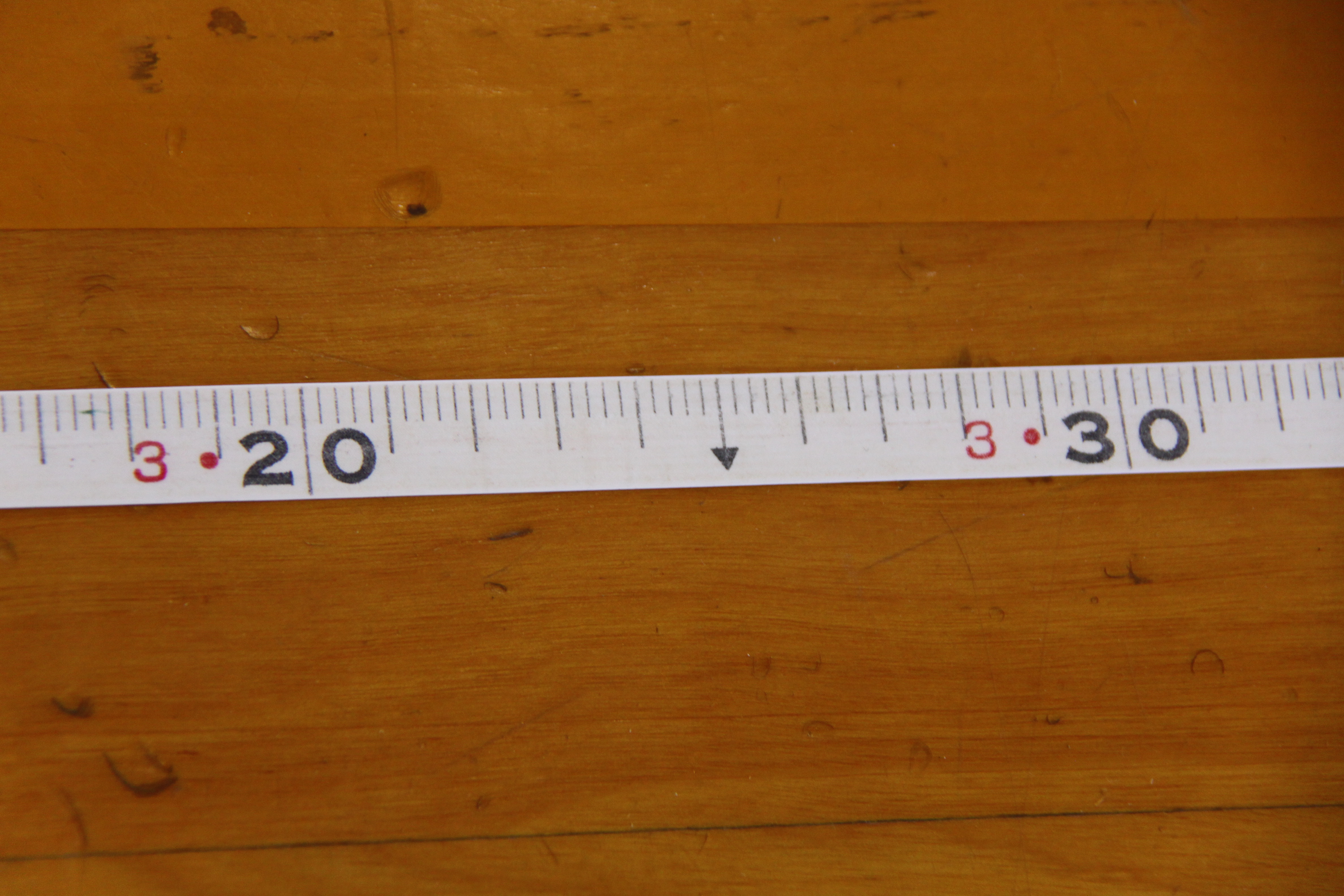






◎仲間とともに 学ぶ
~仲間へ次の日の用意を伝える(^_^)

◎仲間とともに いただきます
~語る、食べる、語る、食べる お互いを知る給食時間。(4/10)
二年生は、ランチルーム形式として多目的教室を活用して、会食を楽しんでいます。

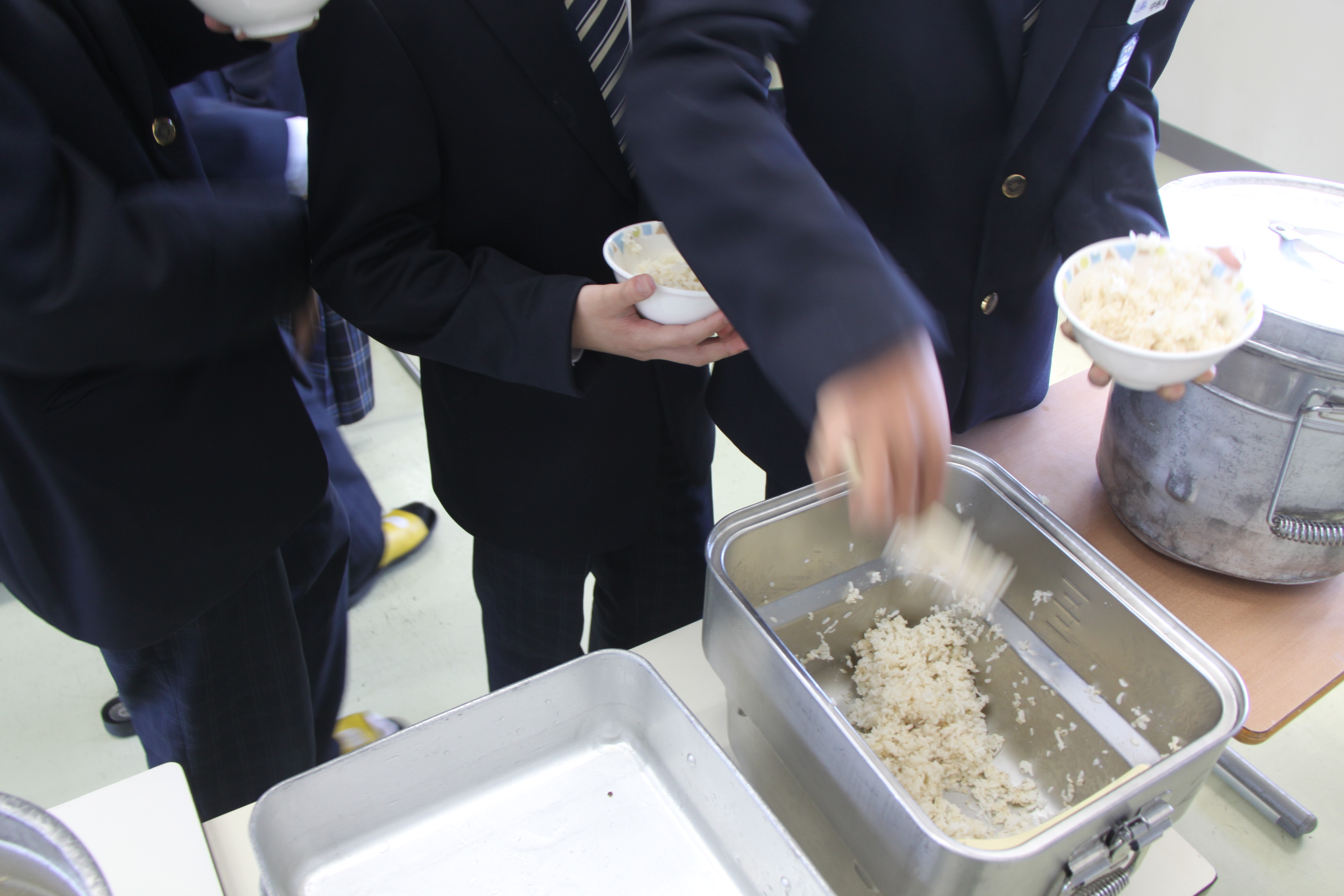




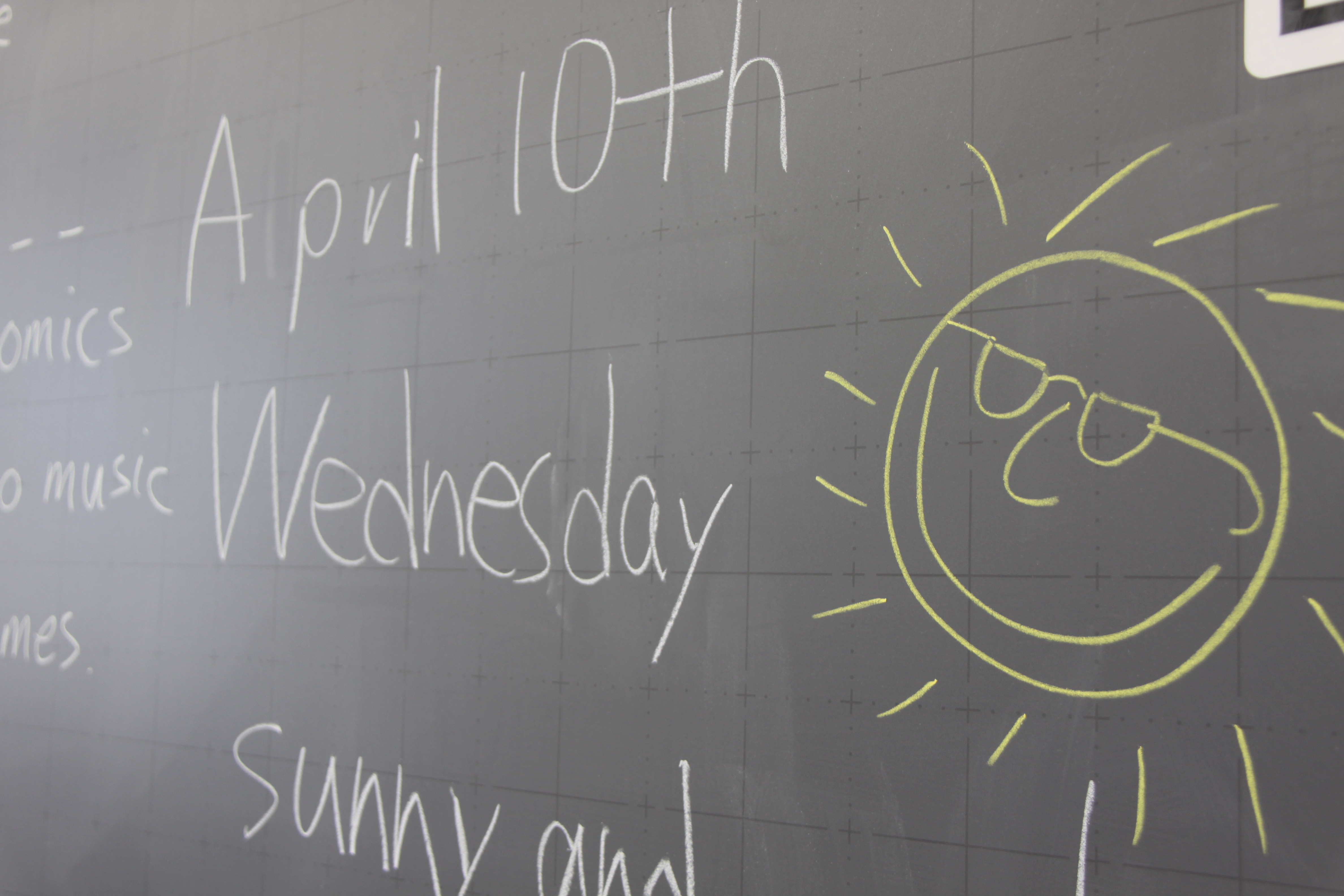
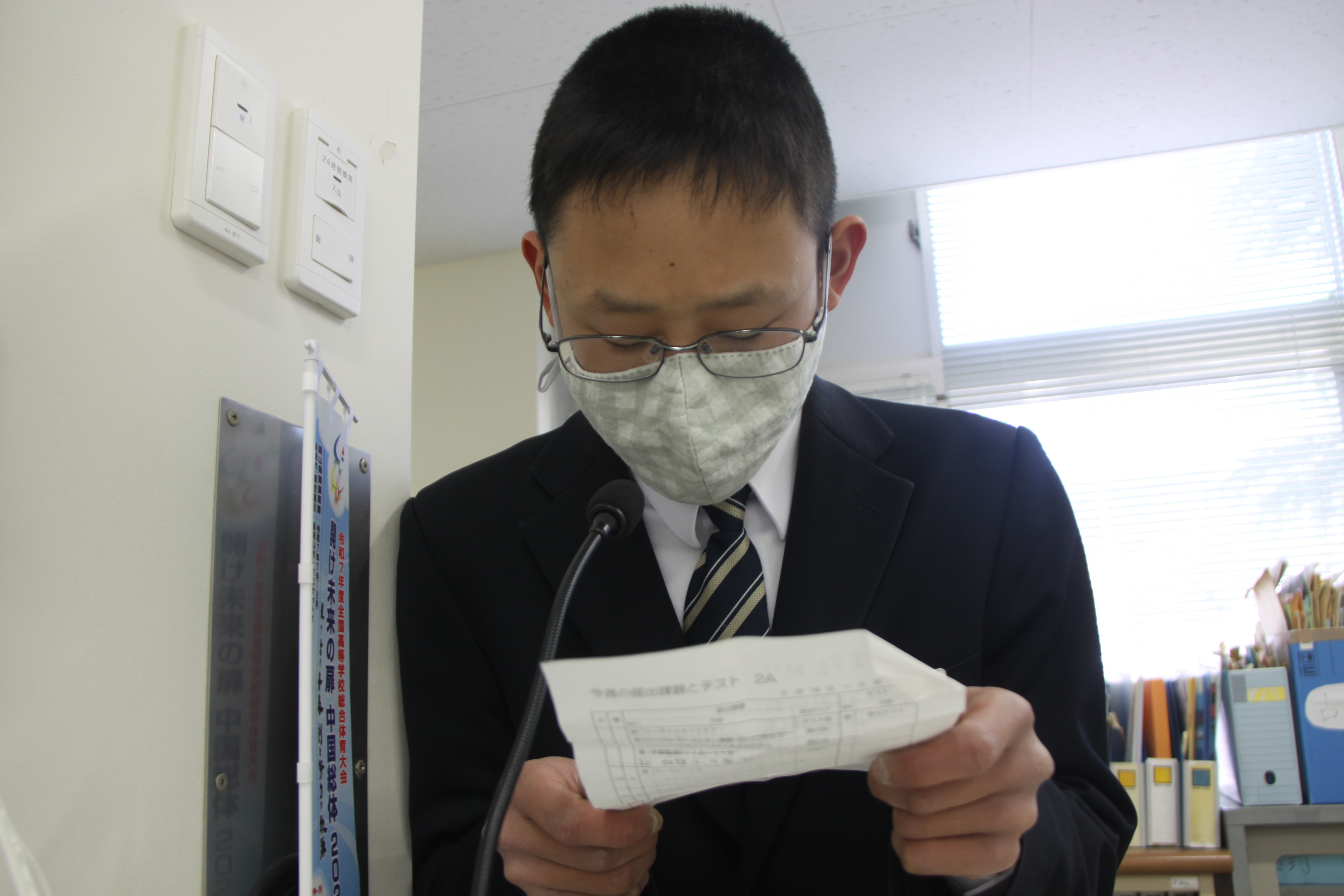

◎ひな中の力
~委員会での活動も活発です(4/10)
新入生に紹介する動画を撮影しています。ぜひ入って活動してみよう。生徒会・委員会活動は、学級委員会、給食委員会、環境委員会、体育委員会、文化委員会があります。

◎えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力をください 笹井宏之
(4/9)
三年生到達度テスト、二年生課題テストへ挑戦。


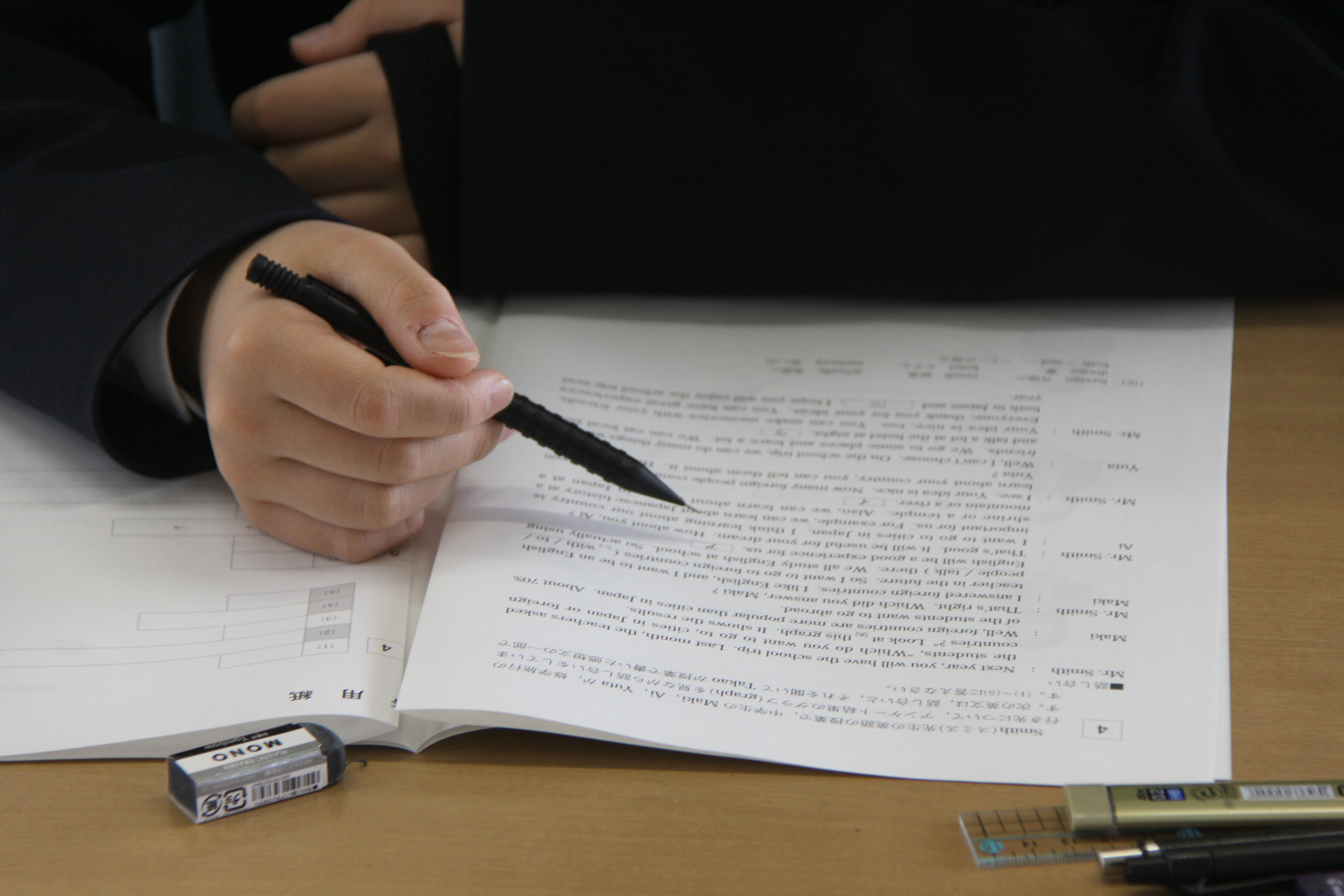

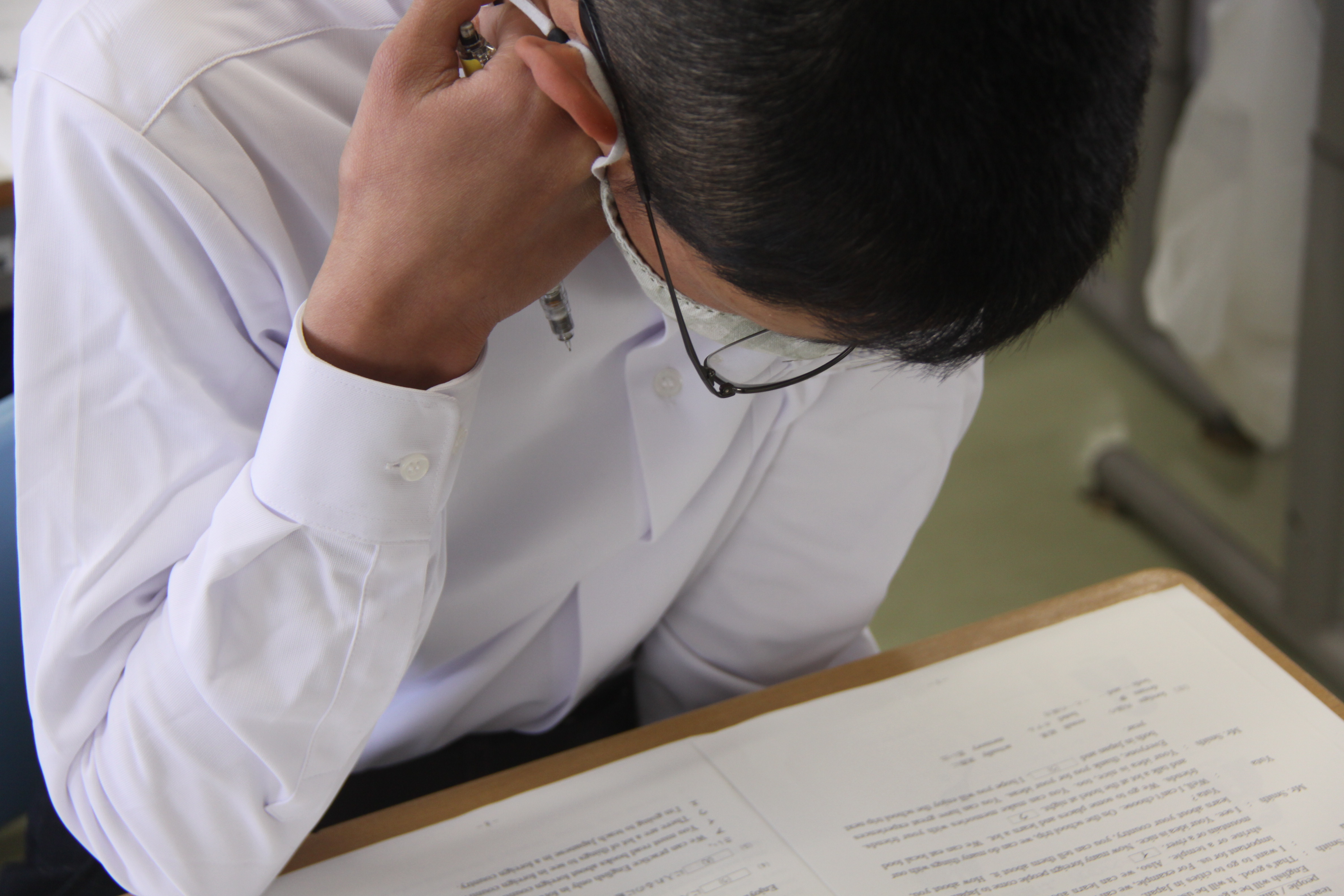

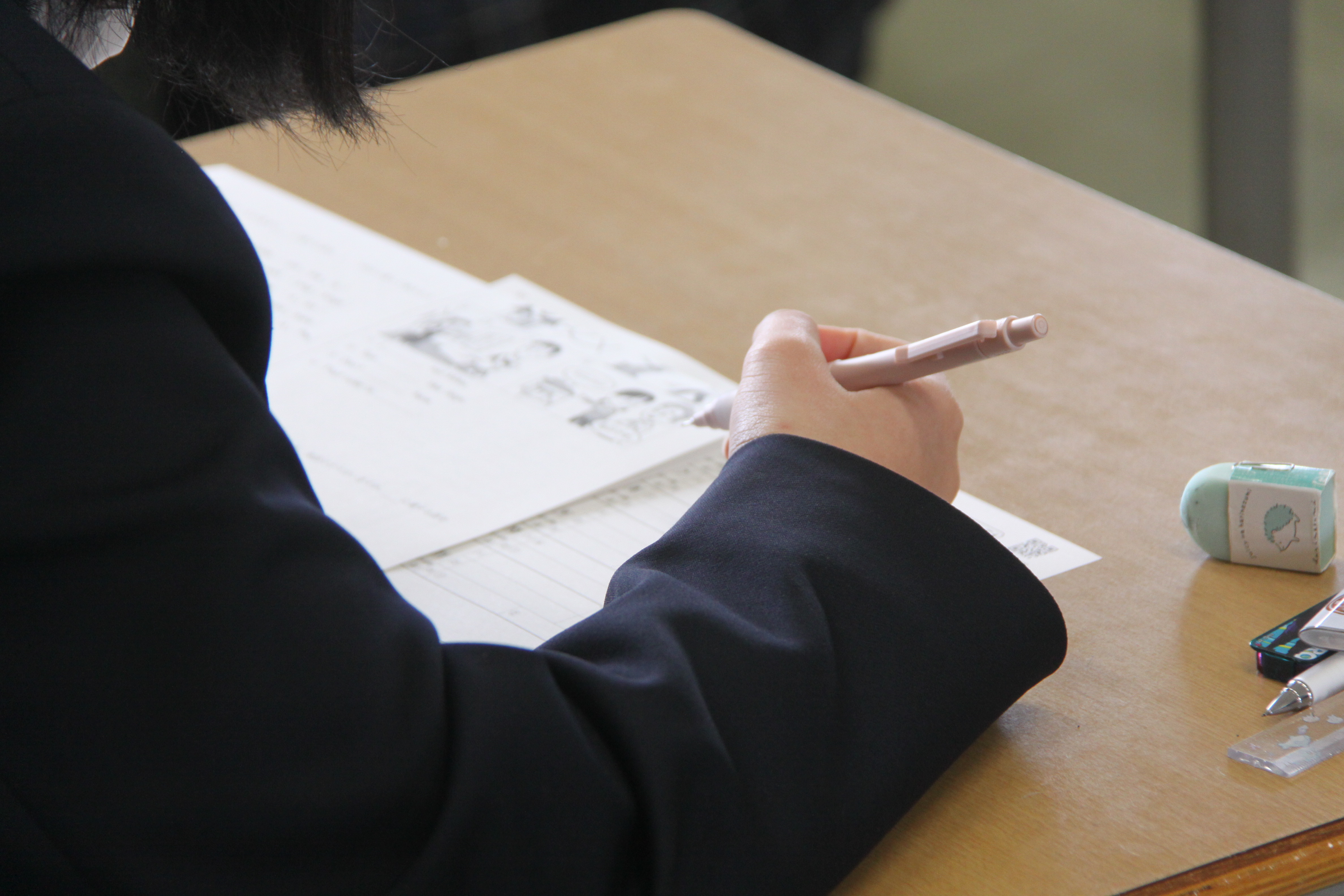


仲間となら乗り越えられる
♬止め処ない血と汗で乾いた脳を潤せ
あの頃の僕らはきっと全力で少年だった
セカイを開くのは誰だ?
◎多くに人に支えられて(4/9)
日生ライオンズクラブ 中磯会長さんが来校され、今年度も交通安全タスキをいただきました。ありがとうございました。あらためて、入学式でご紹介させていただきます。
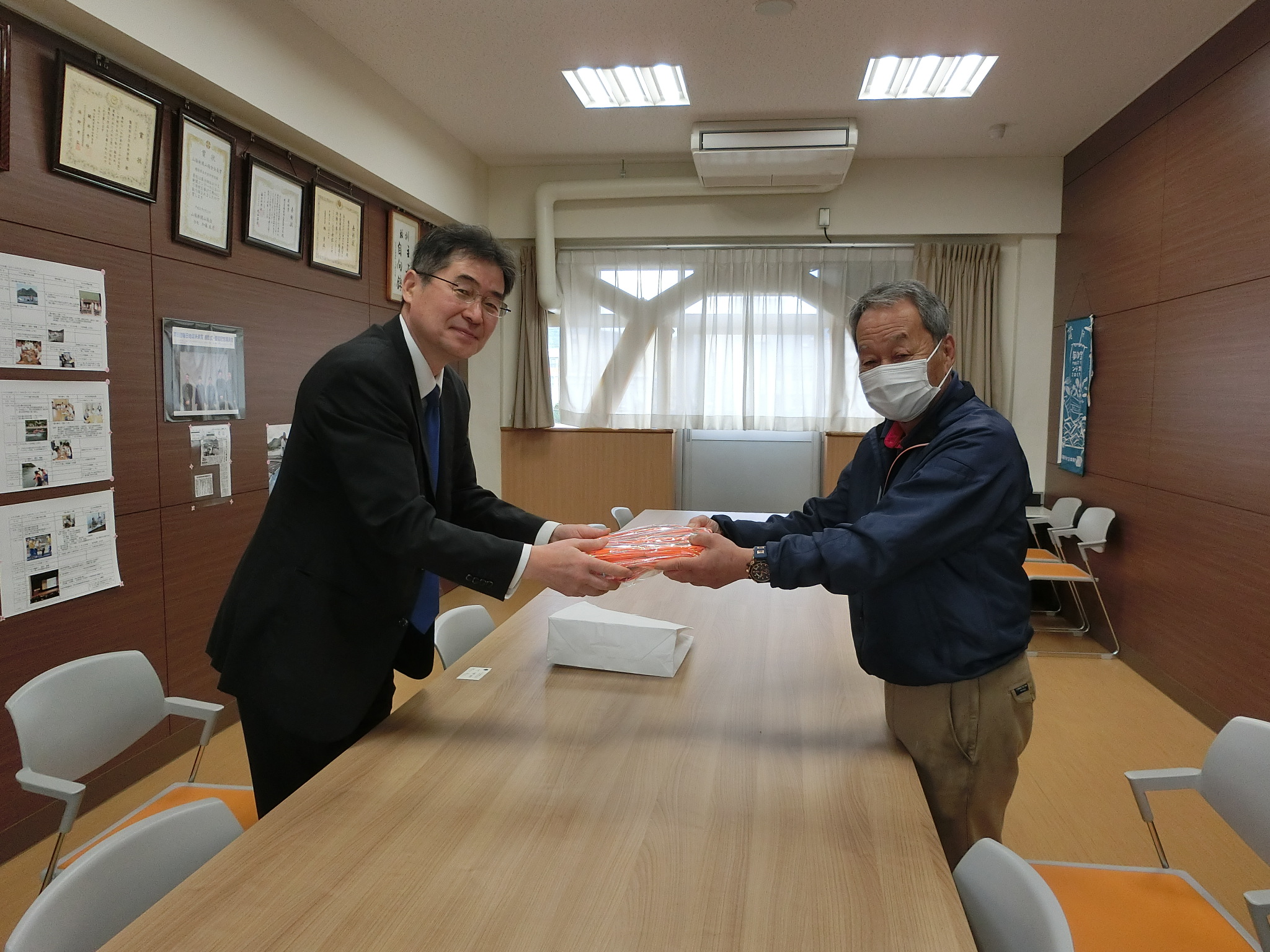
◎自分らしいフィールドで歩む(4/9:先輩たち)
岡山県立備前緑陽高校の入学式に参列させていただきました。厳粛な雰囲気の中で、盛大に行われました。まだ校歌斉唱ができない新入生(先輩たち)でしたが、一生懸命に歌詞を見ながら歌おうとする姿に、新しい高校生活への意欲を感じました。11日は、日生中学校も入学式です。大切にしている校歌を、一年生へしっかりと伝えましょうね。



◎「やりとり帳」を大切に。4月~
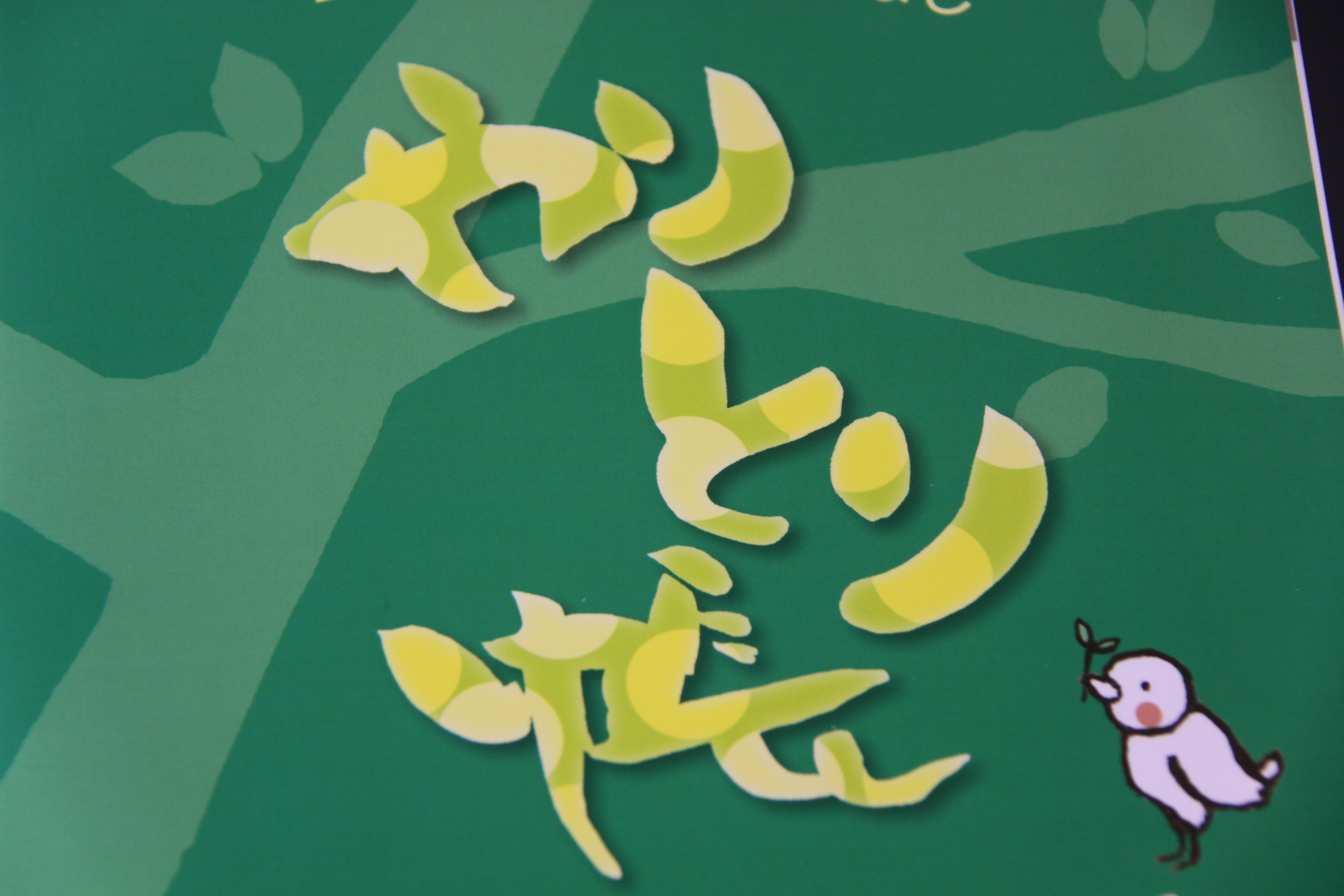
「やりとり帳」へのねがい
長い間、担任をしていて、『やりとり帳』」などの〈ひとこと日記〉や〈生活の記録〉の取組には、いろいろな思いがあります。おもなねらいは,「君たちことをよく知り、しっかり応援したい」という思いが大きかったように思います。記入の様子や内容から,「君たちの学校生活が充実しているのか」、「悩んだり、困っていないか」などの変化を見逃さず、話を聞いたり、相談を受けたりするために大切にしてきた取組です。日記に書いてくれた内容を、時には、学級通信に掲載して、クラスへの提案や学級会での話し合いにもつなげたり、クラスのみんなに紹介したりして、学級をよくしていくための活動にも役立ててきました。
だから、皆さんが、学校生活での出来事や日常の暮らしを「綴る(つづる)」ことによって、自らの生活をしっかり観察し、自分たちの生活を認識し、たくましく生きていく力を高めてほしいと思うのです。
何か心配なことがあるのか、弱々しい文字でのつぶやきが書かれた生活ノート、うれしいことがあったのか、はずんだ文字の生活ノート、何度も消したり書いたりした跡が残る生活ノート、消しゴムの消しカスがはさがっている生活ノート、好きなキャラクターのイラスト・・・などなど、「やりとり帳」の記述を通して、しっかりと君たちの生活を知り、応援しようと思います。
「書くことは考えること、考えることは生きること」というコトバがあります。
「ひとこと」日記」を書くというのは、表現や伝達の手段であることは間違いなく、伝えるための技術をみにつけることは、将来社会に出てからとても役立ちます。しかし「綴る」ことにはもうひとつ、だいじな役割があります。それは「認識」といいます。残念ながら、最初から作文が好きな人は、あまりいないかもしれません。それは難しいからです。自分の前にある「人・もの・できごと」にぴったりな単語をみつけ、次には単語どうしを結びつけ文にし、さらに組み合わせていくという、頭をフル回転しなければならない作業です。時には、できごとをよいととらえるか、悪いととらえるかなどという、価値判断もしなければなりません。自分の視点で書いているので、うそはかけません。鉛筆を進めるのは、大変な仕事です。
小さい頃、君たちは「話しことば」の中で生活しています。相手が目の前にいて、視線やしぐさ・表情なども伝達の手助けとなるため、多少コトバや言い方や文法がまちがっていても、おおよそ通じてしまいます。しかし「書きことば」ではそうはいきません。目の前に相手はおらず、頼りになるのは文だけなのです。だからこそ、必然的に対象をしっかりみつめ、掴(つか)もうとし、価値判断をすることになります。家族・友達・社会・自然などを題材として「綴る」なかで、君たちはしだいに「認識」を深めていきます。こういった「認識」を獲得する学習を基盤とし(あるいは並行して)、プレゼン発表の原稿やレポートを書いていくなら実生活に根差した、重みのあるものとなるはずです。飛躍的に認識の幅が広がる中学校のこの時期なのですから。
もうひとつ、書くことの基本は、身の周りのことを、あったことを、あったように、自分のことばで、です。時間軸に沿って、「○○でした」「○○しました」というふうに、過去形で書いていきます(展開的過去形表現といいます)。これがある程度できるようになってはじめて、前述のさまざまな機能を持った文章を書けるようになっていきます。
新しい『自主学習ノート』と『やりとり帳』を使った取組にを大切に、チャレンジしてみましょう。
◎学び続ける者だけが教壇に立つことができる 佐藤学(4/8)
今年度も校内研修に継続的に取り組んでいます。第2回研修の内容は、個別の教育支援計画、生徒理解の共有、GoogleClassroomの活用についてでした。次回は教科のカリキュラムマネジメント・評価について学びます。

◎ひな中の風✨~一生懸命に聴くということ。(4/8)










◎新しく来られた先生と。日生で輝く✨(4/6:着任式)


◎新年度も多くのひとに支えられて(4/5)
スクールサポーターの根木さんが来校されました。今年度も連携して子どもたちの安全・生活を守っていきましょう。

◎私たちのはじまりの風景8(4/5)









◎新しく来られた先生方をお招きして、
新年度の準備✨を進めています。∈^0^∋



「ごらん、そら、インドラの網を(宮沢賢治)」
・・・ダーウイン自身が「種の起源」に今や広く知られるようになったつぎの言葉を残している。〈最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き残るのでもない。生き残るのは、変わることのできる者である。〉自分とは違う人を理解しようとすることで人は相手よりむしろ自分自身を一層理解するという予期しなかった副産物を受け取ります。他の文化を知ることは自分の文化を知ることに他なりません。他者の価値観を知ることは自分の価値観を知ることです。同性愛の人々を知ることで異性愛の人は自分のセクシャリティを見つめることが出来るのです。・・・最近読んだ雑誌の一部(『部落解放4月号 ダイバーシティの今 森田ゆりさんP56 より』)を紹介しました。今年度も多様な教職員で、豊かな教育を創造していきたいと思います。
◎人生に花が咲こうと咲くまいと生きていることが花なのだ 上田雄太
4月1日。新年度(*^o^*)






◎健やかな成長は、小学校との連携・協働の中で。(3/27)
新入学に向けて、第3回小中連絡会を開催しました。


◎ひな中のちから。私たちのちから。



また、4月8日(月)に!(*^o^*)!会おうな。
◎退任式//歩み新たに日に生せば、今日は昨日の我ならず(3/26)
~先生方、ありがとうございました(_ _)~皆様のこれからの益々のご健勝を祈念いたします。




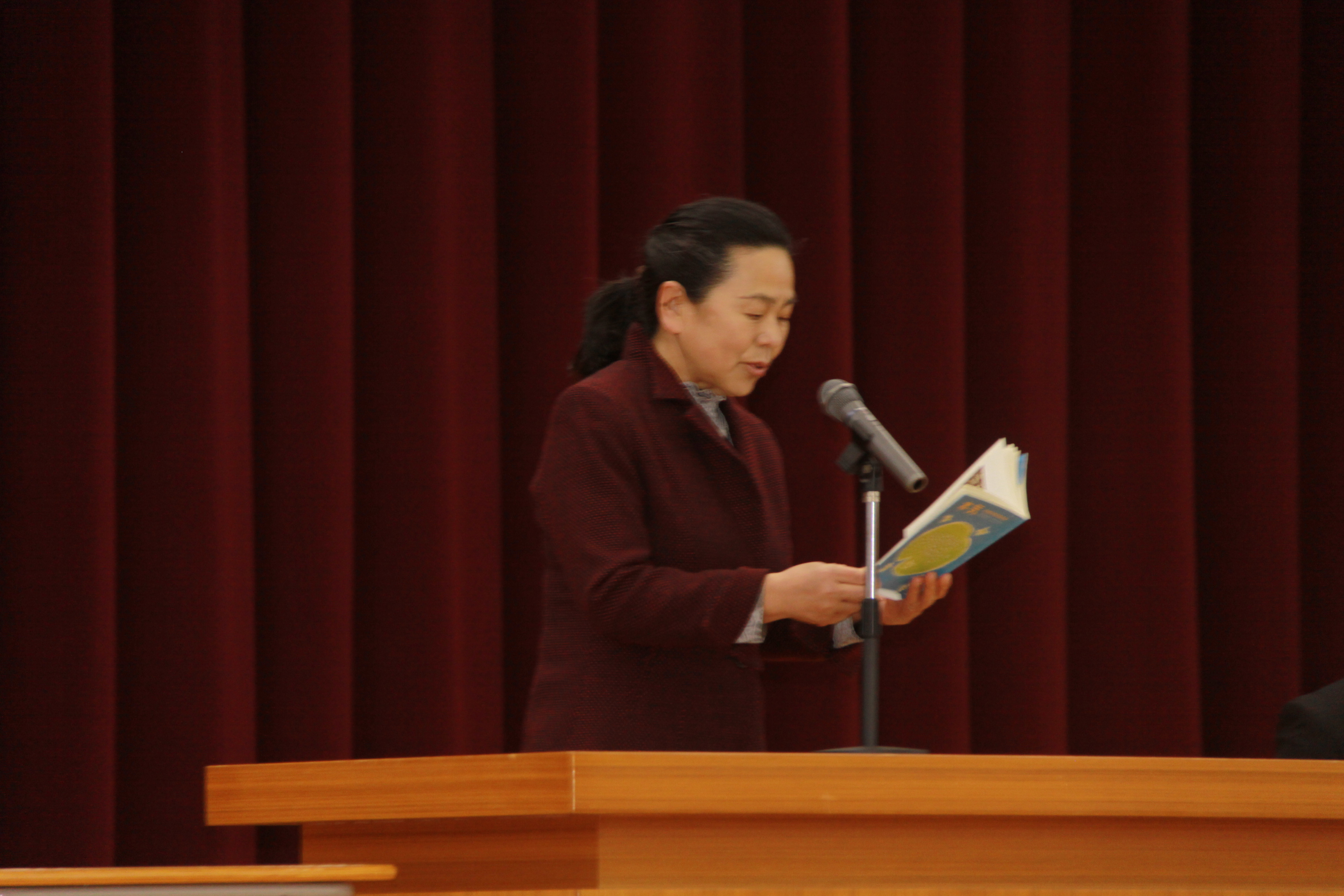




◎一年間の課程を終えて。(3/26)






成功の反対は、失敗ではなく、「挑戦しないこと」
◎「また来てね」「また来るよ」「また」と言うときに僕らは僕らのまま笑うのだ 千葉 聡
3月26日、修了式。


◎わたしたちの日生中を創るための。(3/25:校則改定の取組)
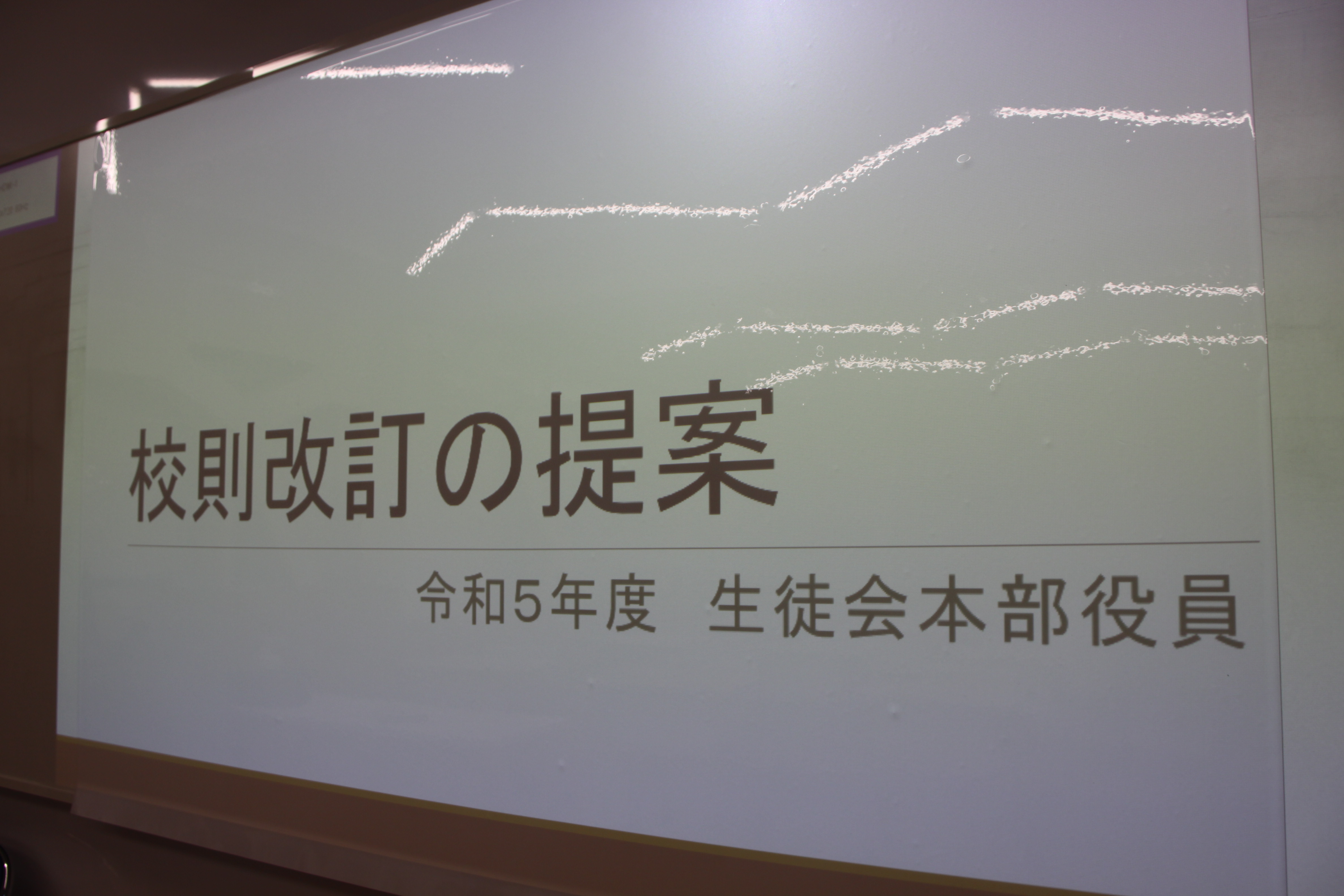

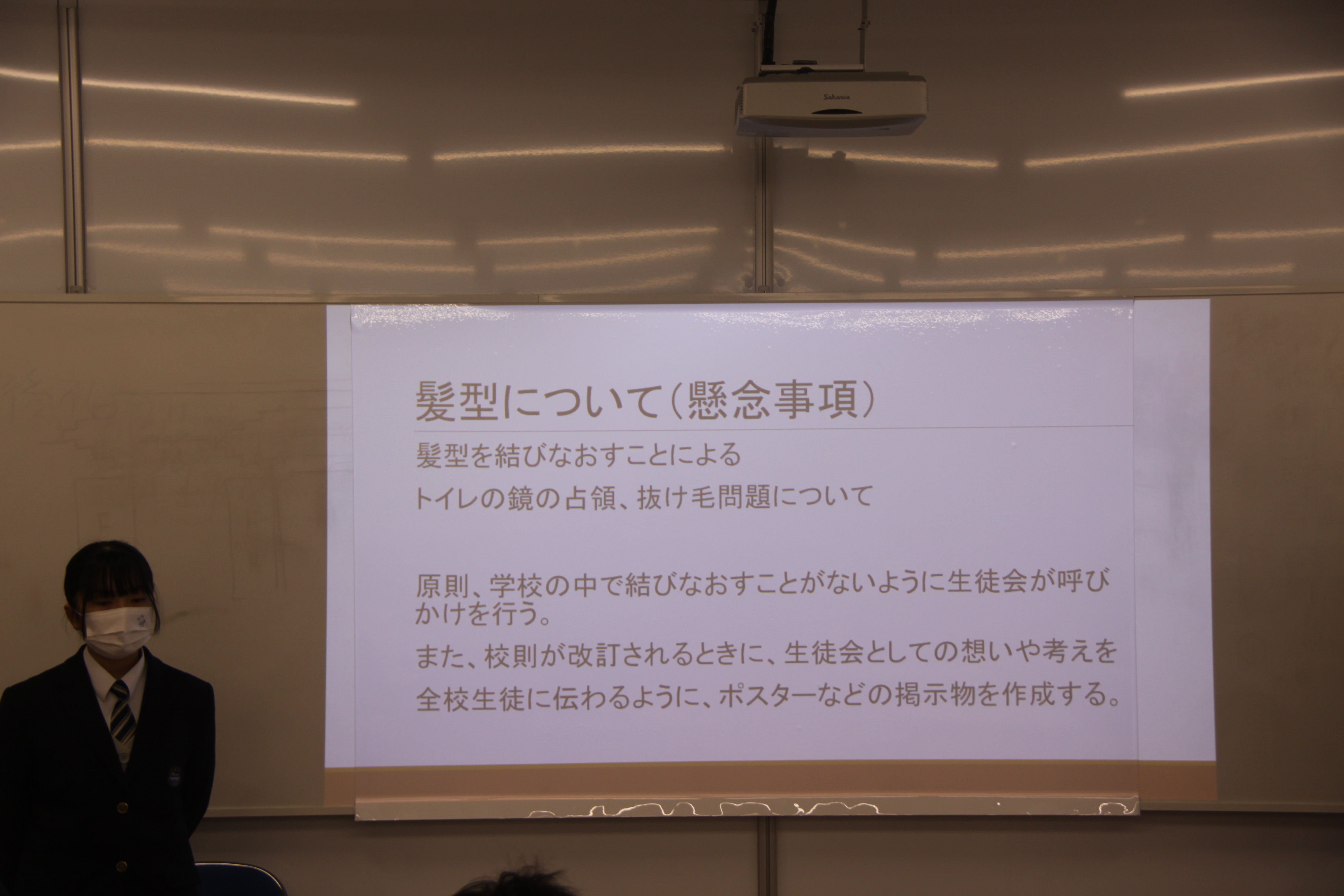

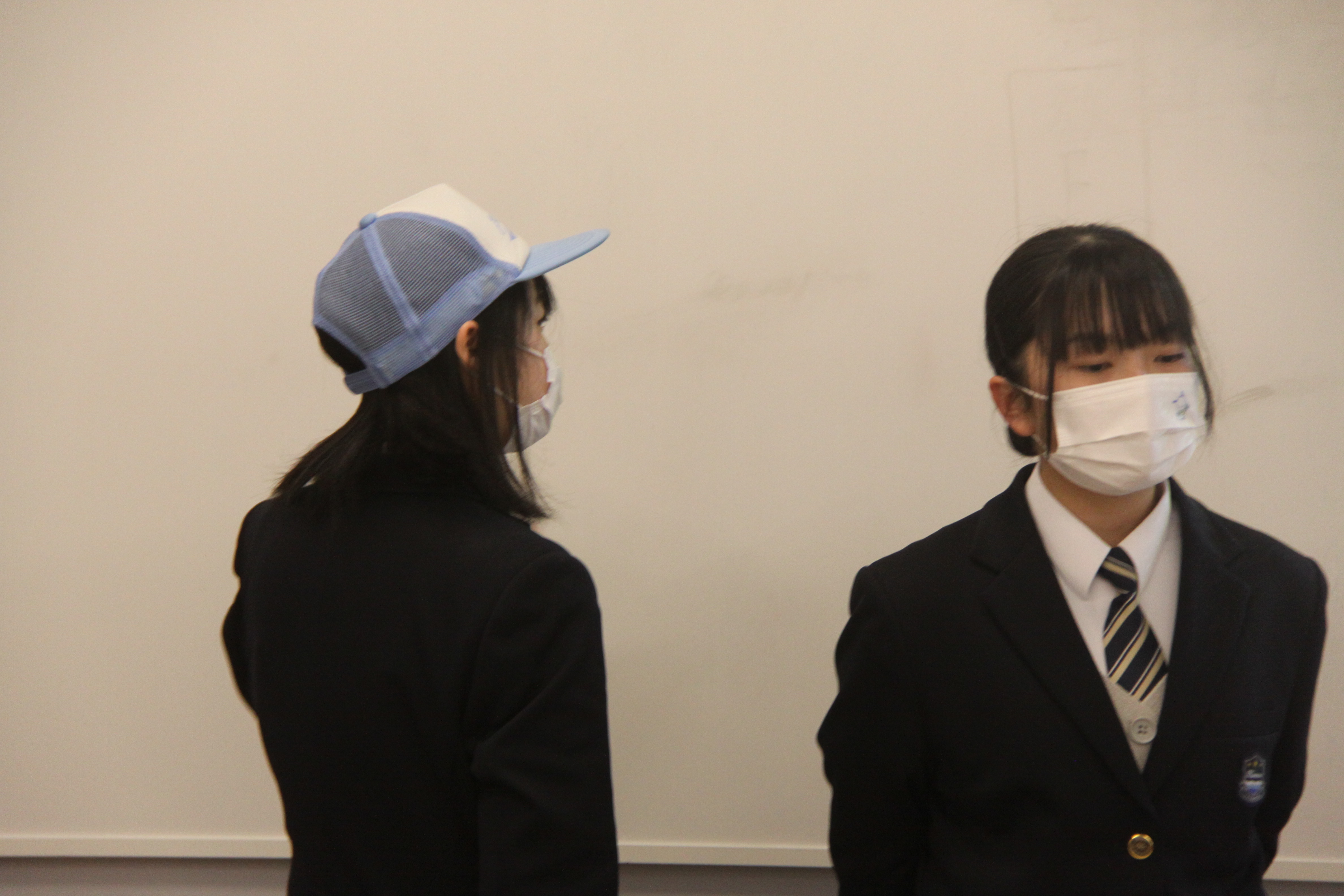




◎ありがとう、教室。ありがとう、みんな。(3/25:大掃除)
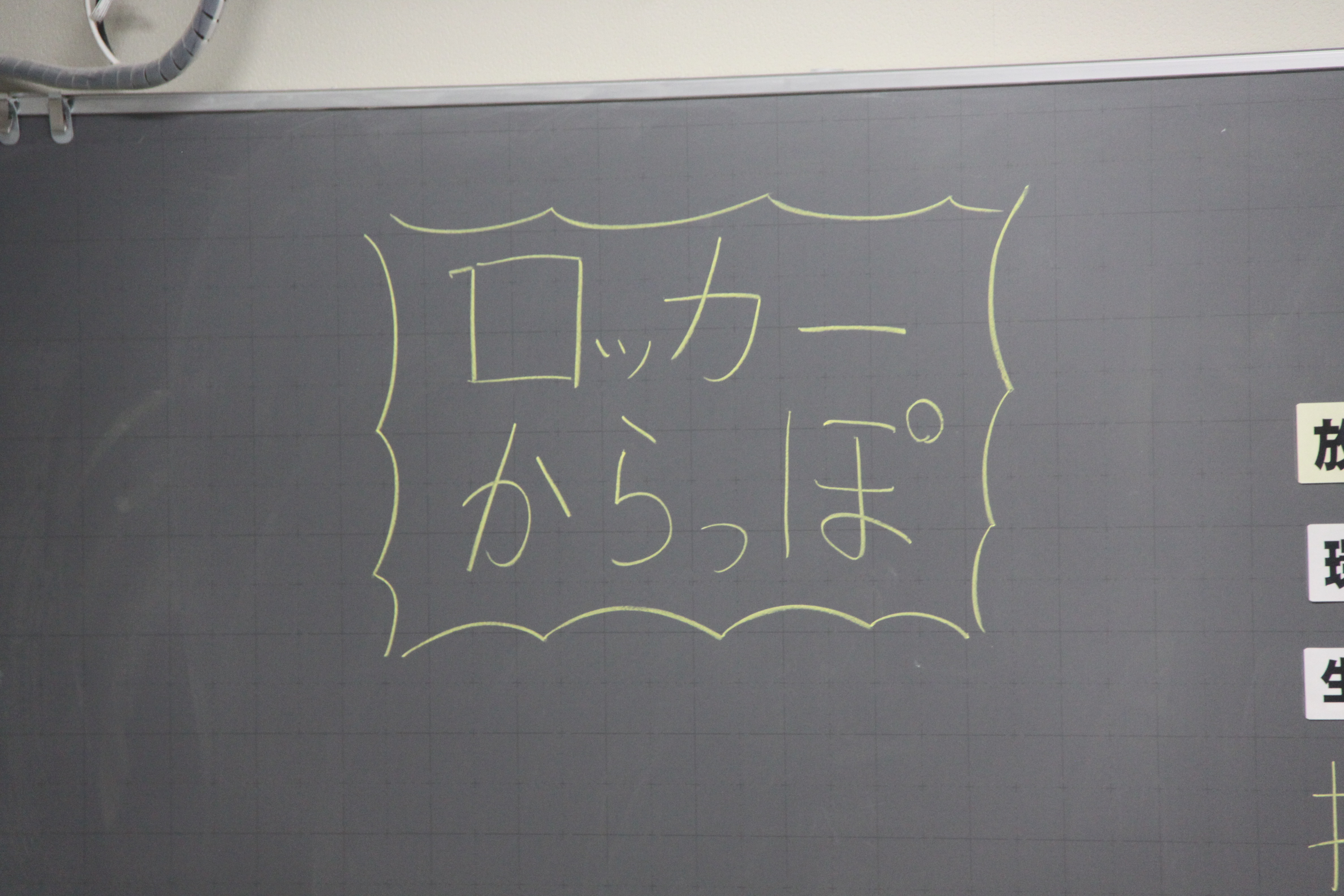











◎私たちは世界につながっている(体育委員会)


ゴミとして捨てられるだけだった使い捨てカイロの収集を全校によびかけました。中身を取り出して水質浄化剤や 土壌改良剤としてリサイクルしている企業に送る準備をし、3月末には郵送します。
生徒みんなの協力で30㎏以上のカイロを集めることができました。校内の活動にとどまらず、社会や世界に貢献できるように、これからも活動を続けていきます。
◎ヒロシマ(4・25~26)への道(3/25)
ヒロシマの地に立とう・学ぼう。クラスの団結をさらに深めよう。~実行委員会よりみんなへ

◎鬼なることのひとり鬼待つことのひとりしんしんと
菜の花畑なのはなのはな 河野裕子
3月25日(月)、雨の日の朝。




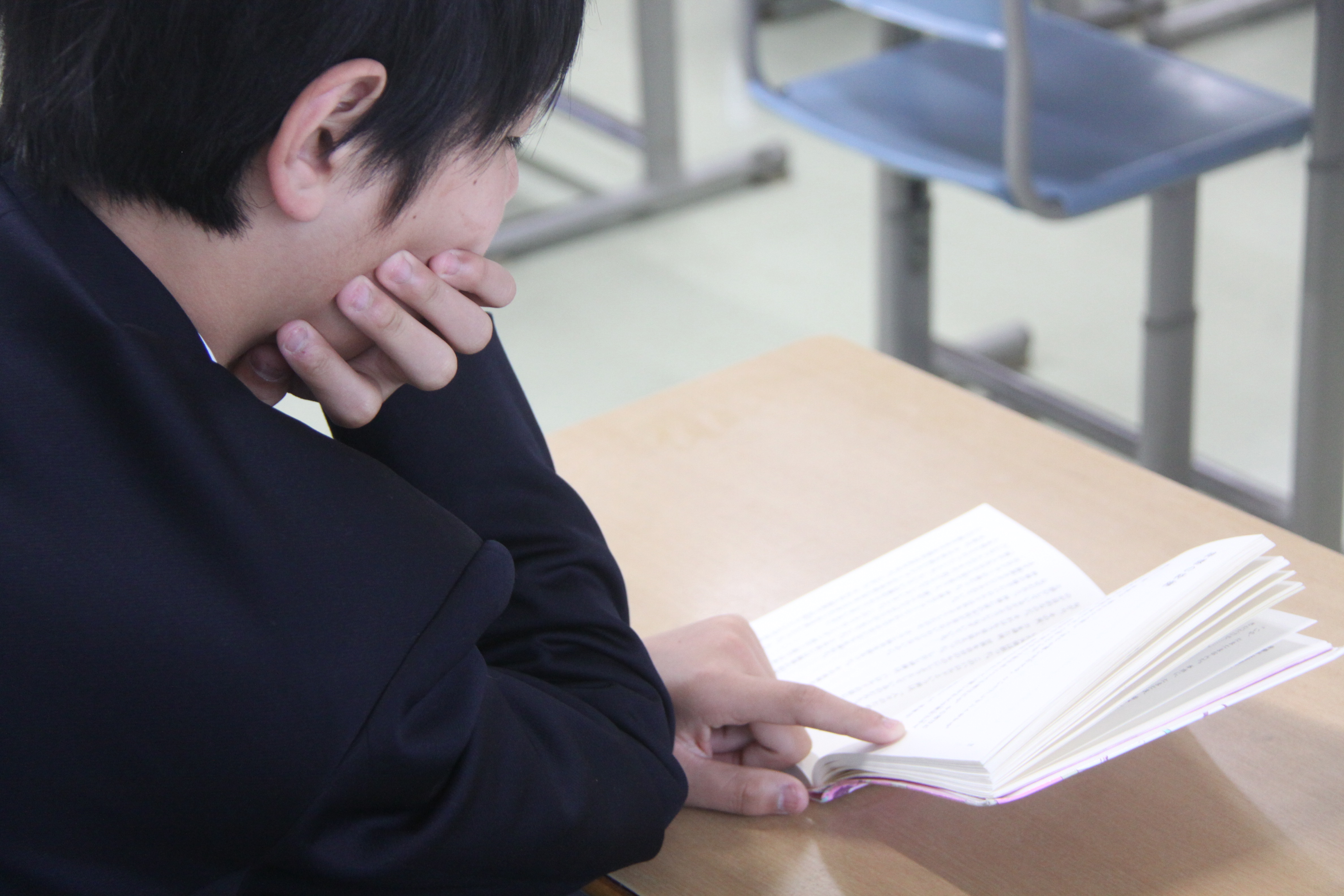

◎子ら去りて白くちらばる消しゴムのあと悔いなき授業をせしか 只野幸雄

追記:この日、環境委員会を中心にストーブを片付けました。新年度がやってきますね。

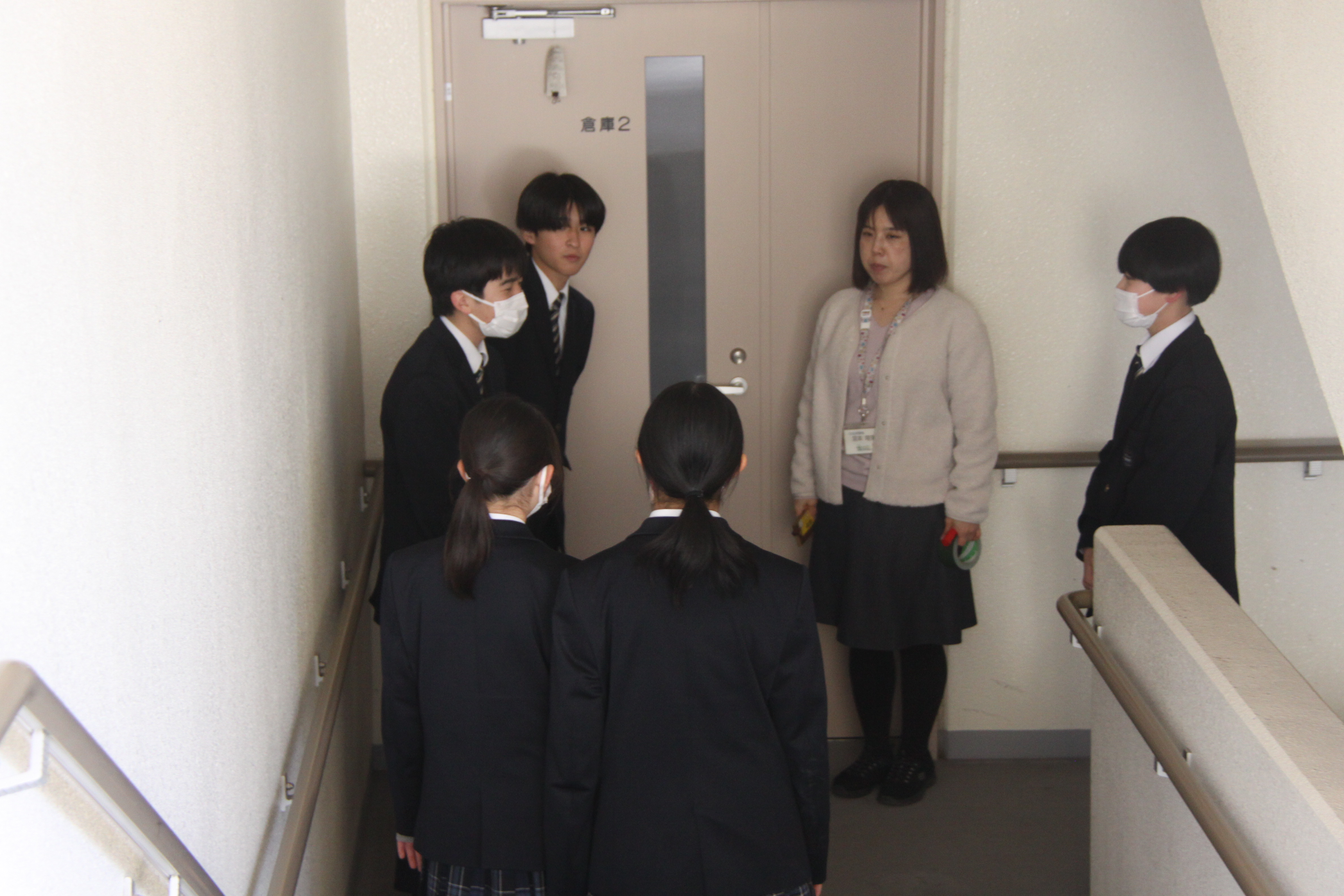
◎たくさんの進路選択があります。(3/22)

備前市役所(社会福祉課 障がい者福祉係)で、「特別支援教育のニーズのある子どもたちの進路について」の上映会がありました。この会では、「令和5年度春いちごの会」が、中学校卒業後の進路について参考となる高等学校学校等の情報をYouTube配信した動画データを借りて開催しました。開会では、久次先生(春いちごの会実行委員会事務局)が、進学機会の変化や多様な進路選択がある昨今の状況について説明をし、質問を受けました。進学・進路について不安や心配がある方はお気軽にご相談くださいね。
◎多くの人に支えられて
体育館LED化の工事も無事におわり、とても明るい環境での学習に取り組むことができるようになりました。照度もオフから100%までタブレットで調整ができます。活用させていただきます。ありがとうございました。
また、株式会社朝日写真ニュース社さんが、掲示板を贈って(リニューアル)くださいました。情報を見抜く「メディアリテラシー」力を鍛えることに役立てます。ありがとうございます。


◎知ることは広がること。
~さらなる委員会活動の活性化へ✨(3/21)
この日、環境委員会は、備前市内の五中学校の美化委員会等とオンライン会議を行い、活動の情報交換会をおこないました。お互いに各校の取組を聞き合う中で、新年度に向けての活動に関しておおいに参考になりました。昨年度から引き続いている大事な活動です。
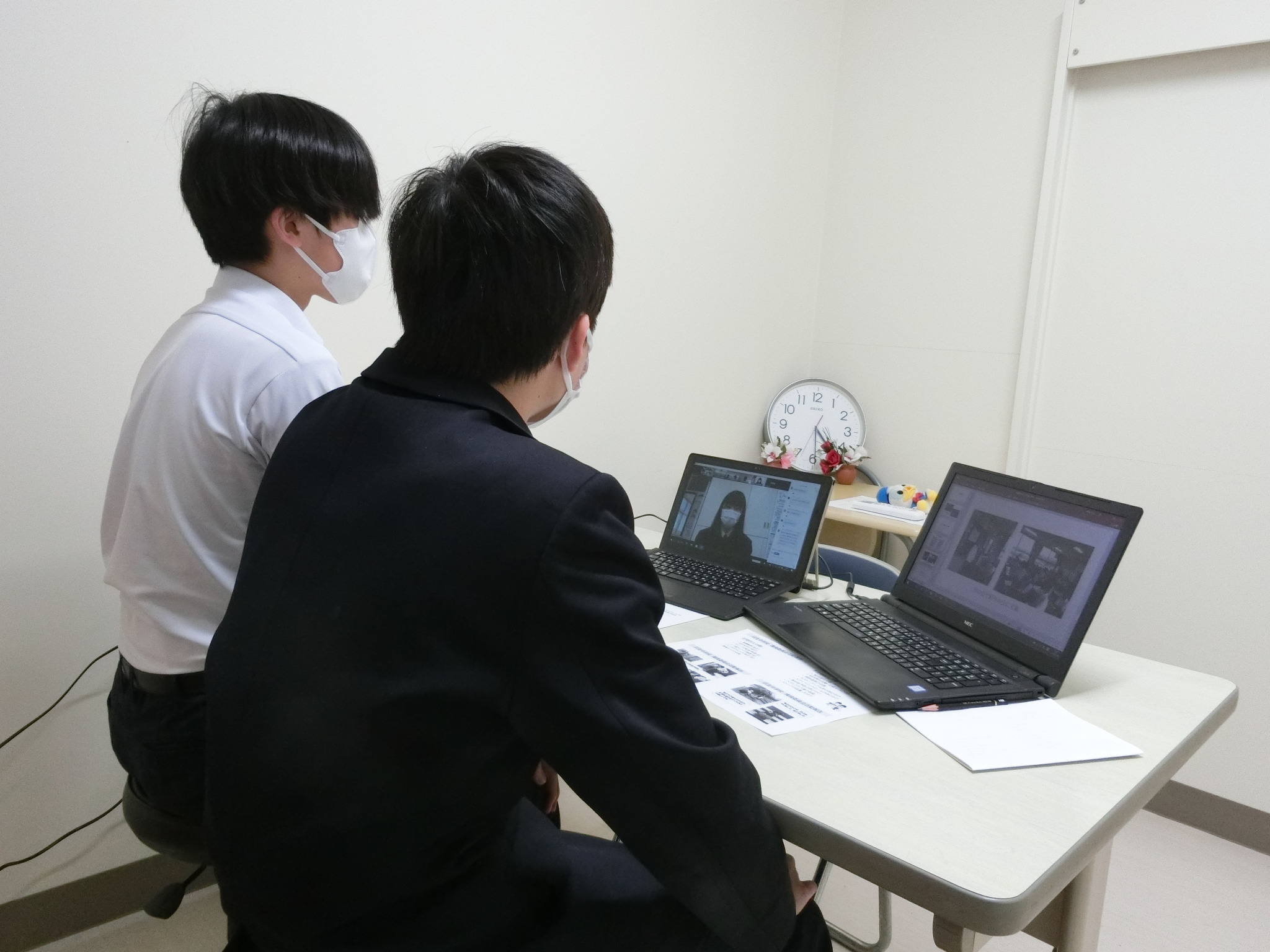
◎日生で輝くひとに出会う 日生が輝く学びを共に。(3/21)
今年も日生地域海運組合の豊福さんらをお招きして、一年生が地域学習に取り組みました。お忙しい中、多くの方に来校していただきました。ありがとうございました。

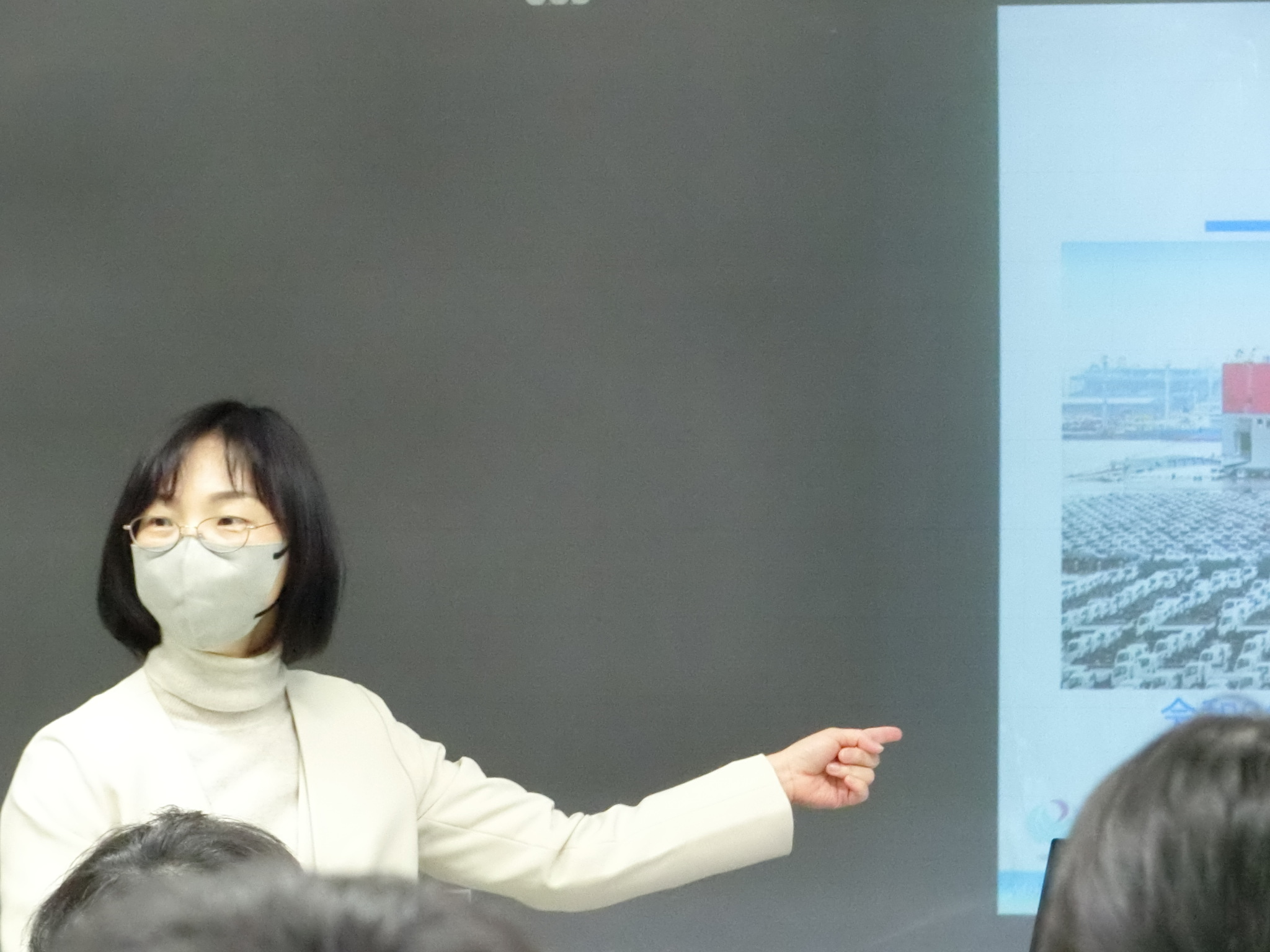
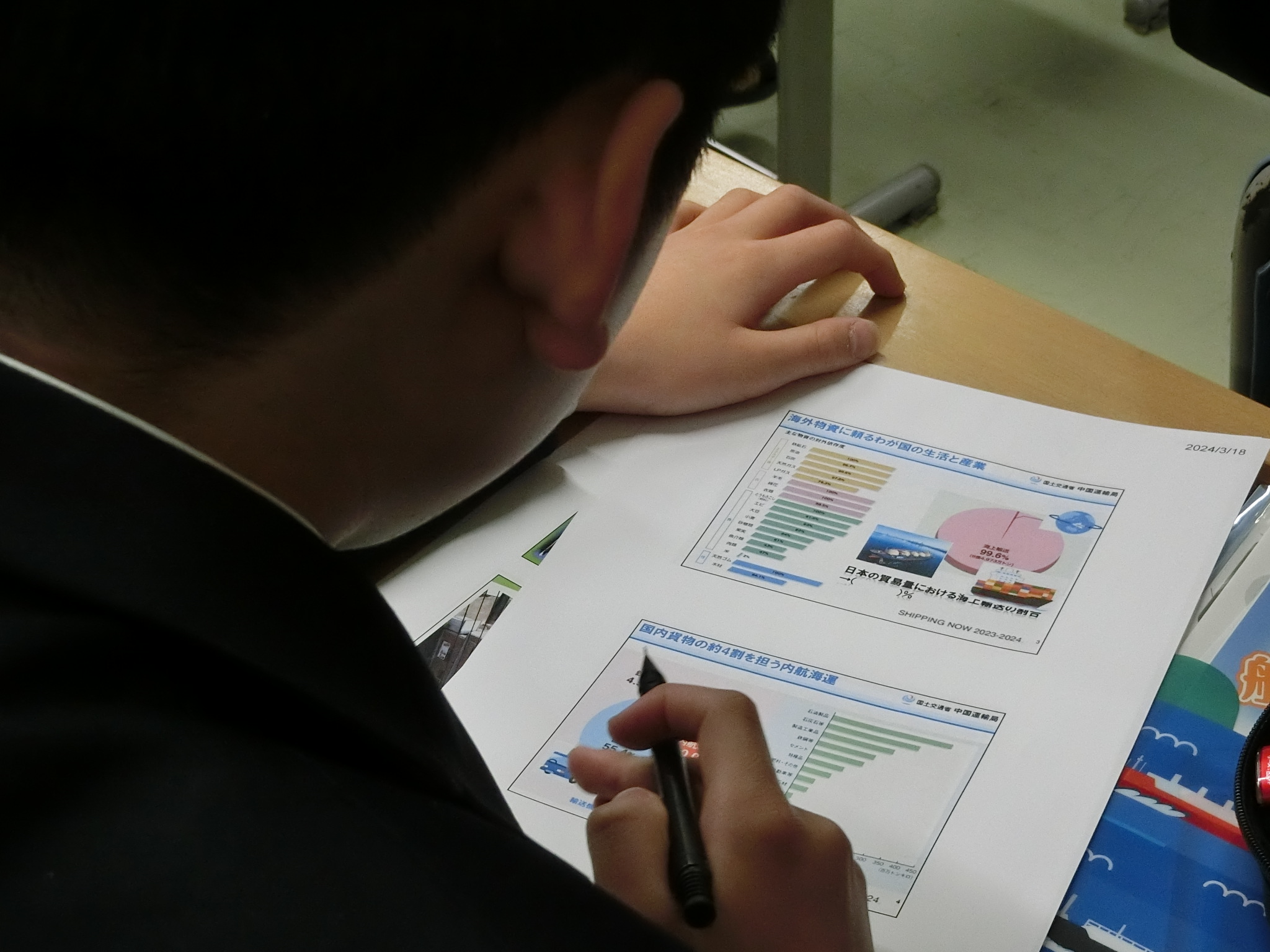



◎花立ての雨を捨てたりちちははの墓にも春の雨は降るらし 藤島秀憲

2024年の「春分の日」は3月20日。春分の日は、二十四節気の春分に入る日をさしていて、太陽が春分点を通過した日が春分の日となります。太陽が真東から昇って真西に沈むため、昼と夜の長さがほぼ同じになりますが、実際には昼のほうが14分程長いそうです。また、春分の日は彼岸の中日であり、「自然をたたえ、生物をいつくしむ」趣旨の、国民の祝日になっています。
春分の日を中日とした前後3日、合計7日間を「彼岸」といいます。秋にも秋分の日を中日とした彼岸があるため、「春のお彼岸(春彼岸)」「秋のお彼岸(秋彼岸)」などと呼び分けることもあります。
お彼岸といえば、お墓参りをする風習がありますが、その理由は、太陽が真東から昇って真西に沈むため、西にあるとされるあの世と東にあるとされるこの世が最もつながりやすいと考えられているからです。春分を迎えると、「暑さ寒さも彼岸まで」というように過ごしやすい穏やかな日が続きます。お彼岸やお花見など、まさに、自然をたたえ生命をいつくしむのにぴったりの季節です。今年の桜を愛で、ぜひ楽しみましょう。
◎永遠に育ち行く 母校ぞ 日生中学校 ♪
~小学校卒業おめでとう そしてひな中へ(物品販売(3/19))






◎〈ひなせが輝く 私たちが輝く 自分たちで創る祭り〉
始動中!(3/19)

◎ひな中のかぜ 3月の風景✨(3/19)



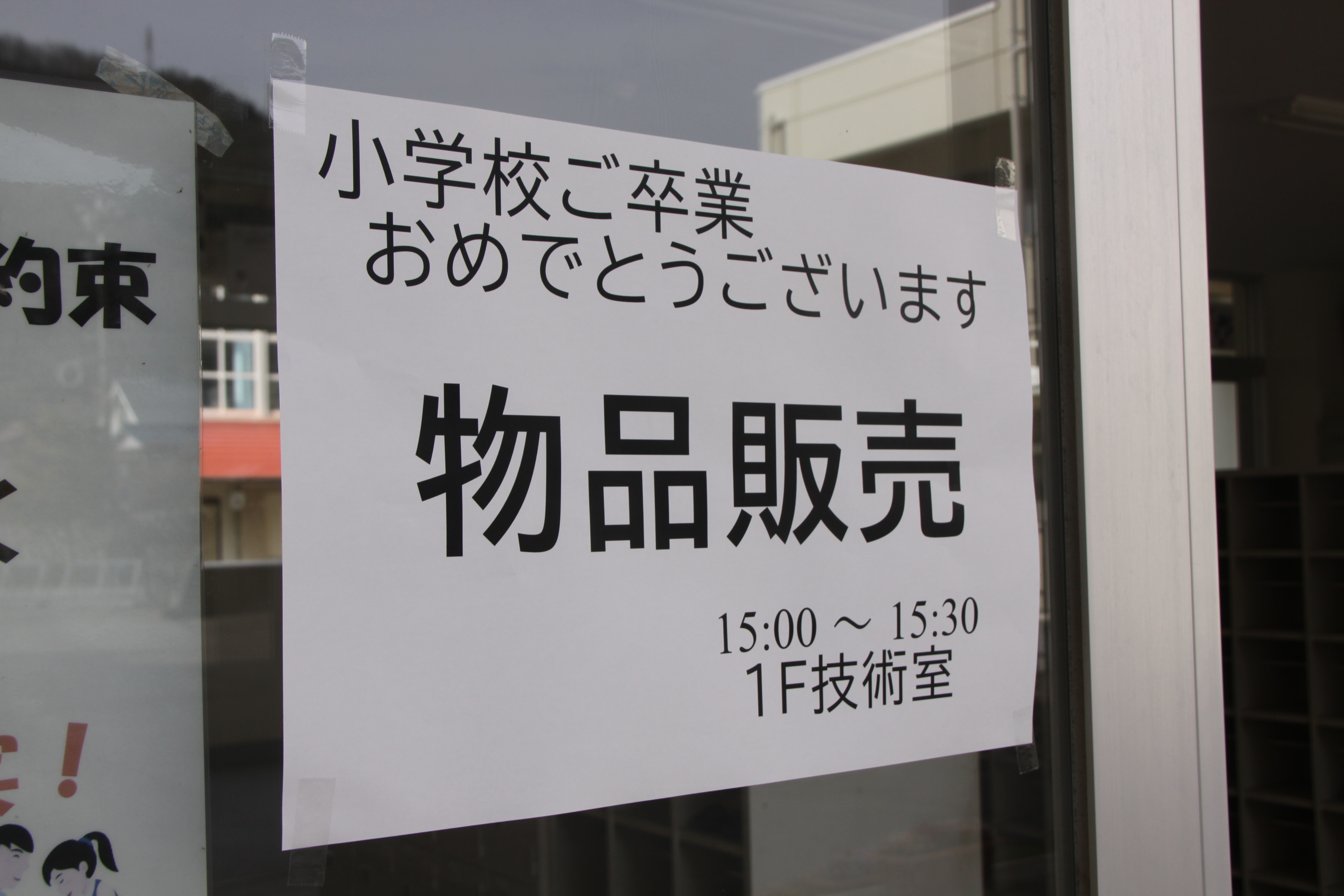

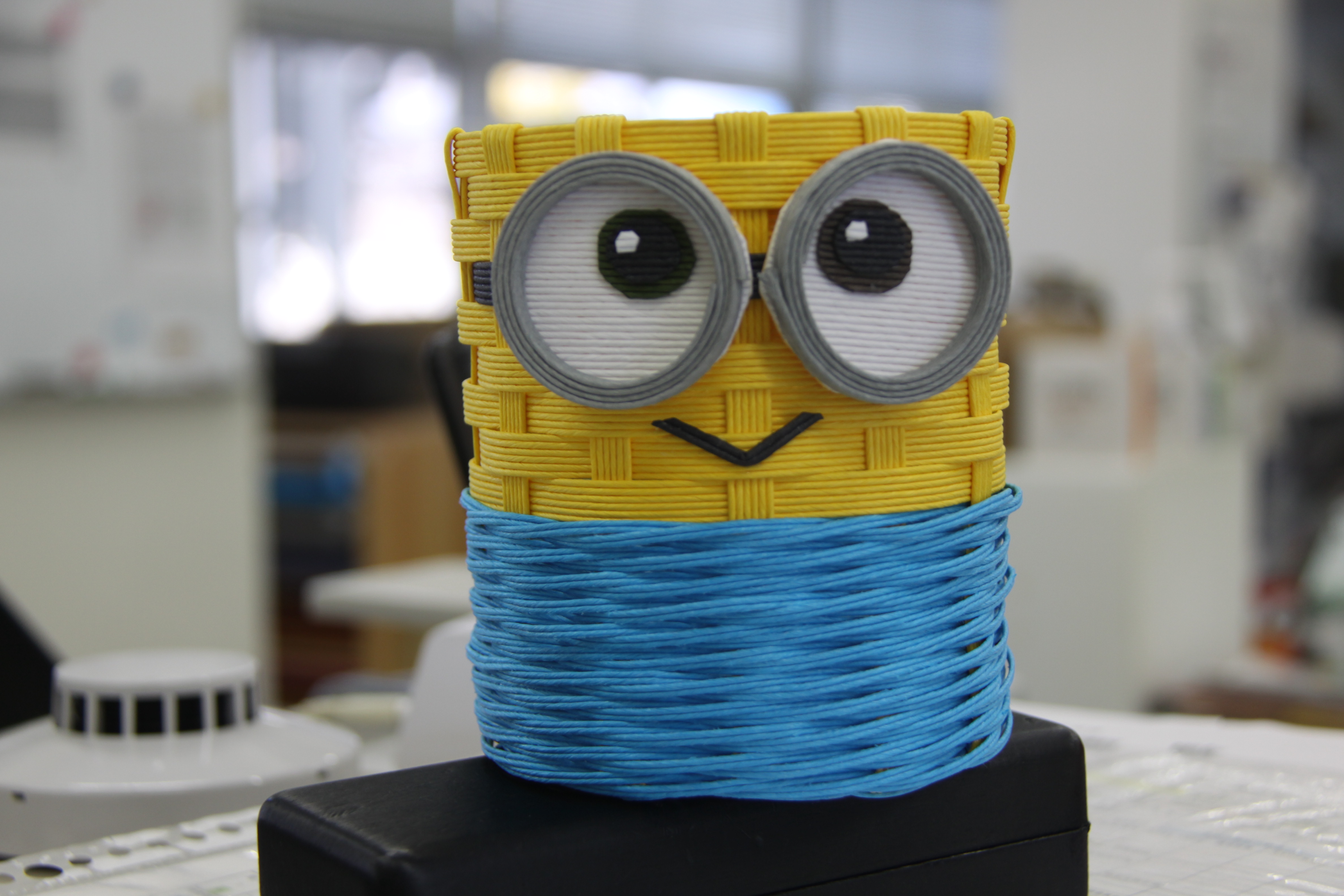
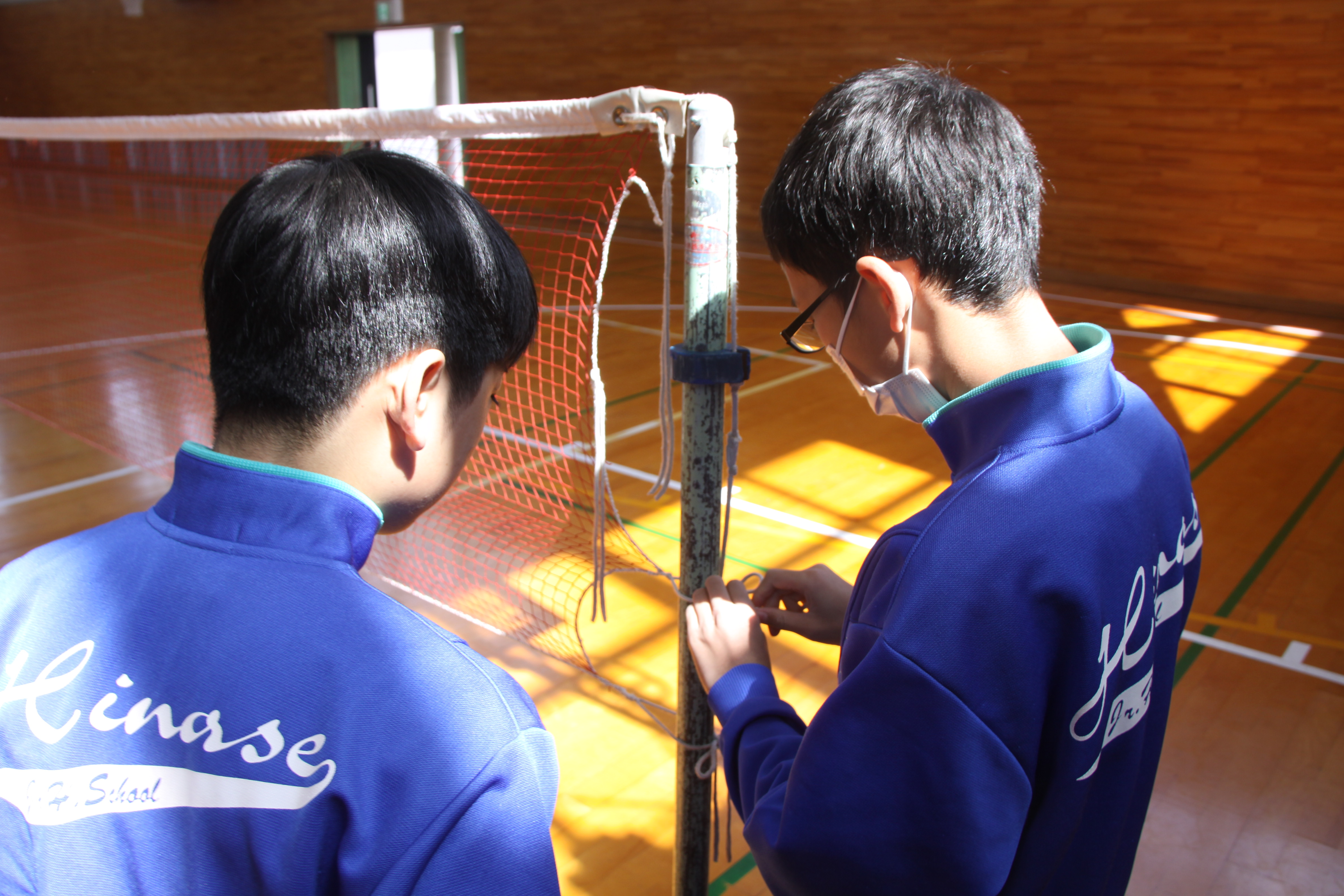


◎Born Free Spirit 体中 ハートのビート打ち鳴らせ♬
~県立一般入試合否発表日(3/18)
55の公立高校の一般入試で全日制と定時制合わせて5313人が合格しました。



I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. Michael Jordan
(これまでの人生で何度も何度も失敗してきたからこそ、成功するのです。)
◎持続的な連携・協働・創造
~ひなせの子どもたちの豊かな育ちのために(3/15)
日生東小へ授業見学に行かせてもらいました。一生懸命に取り組む姿、楽しく学ぶ姿、仲間と学び合う姿がすばらしいですね。


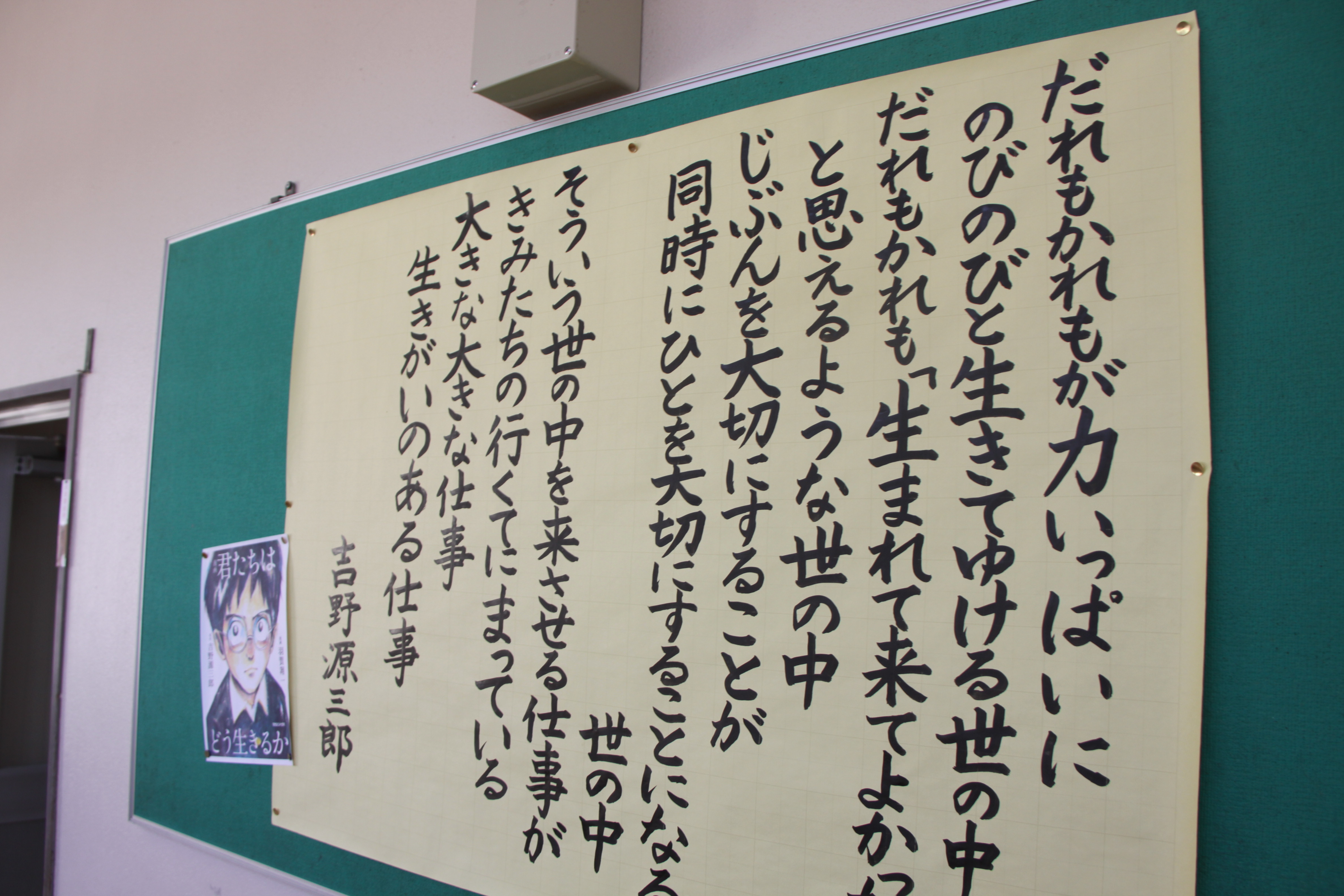

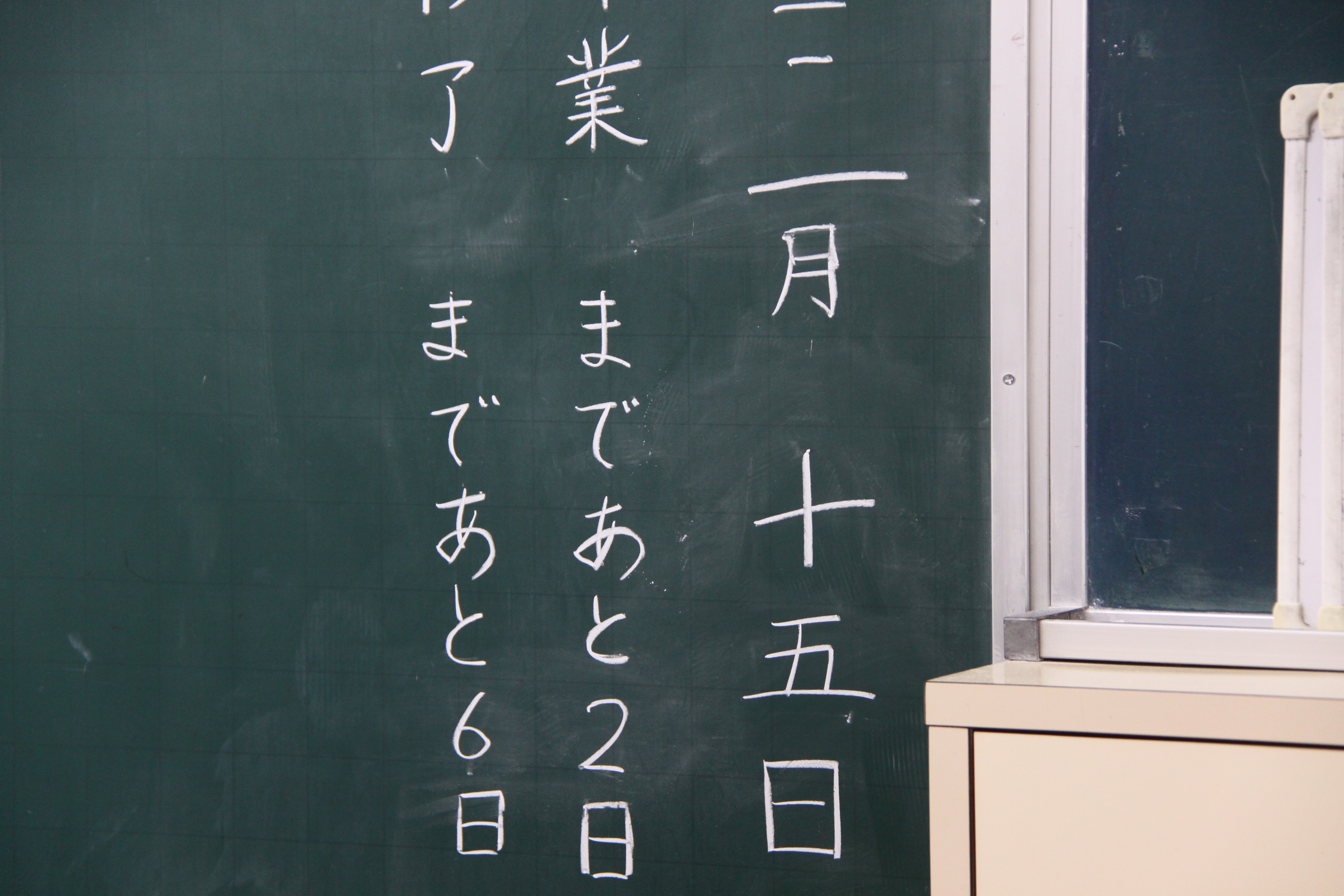
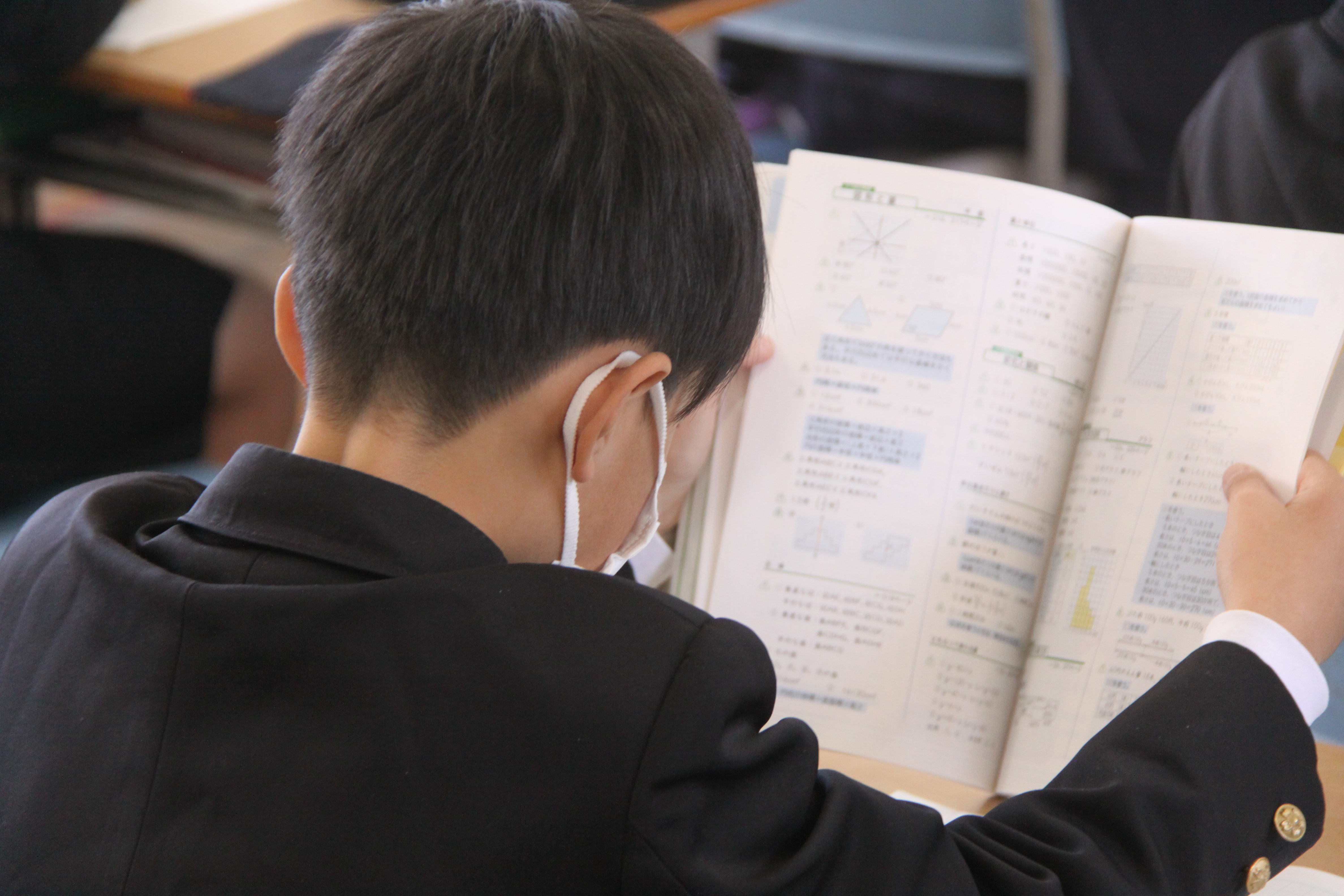


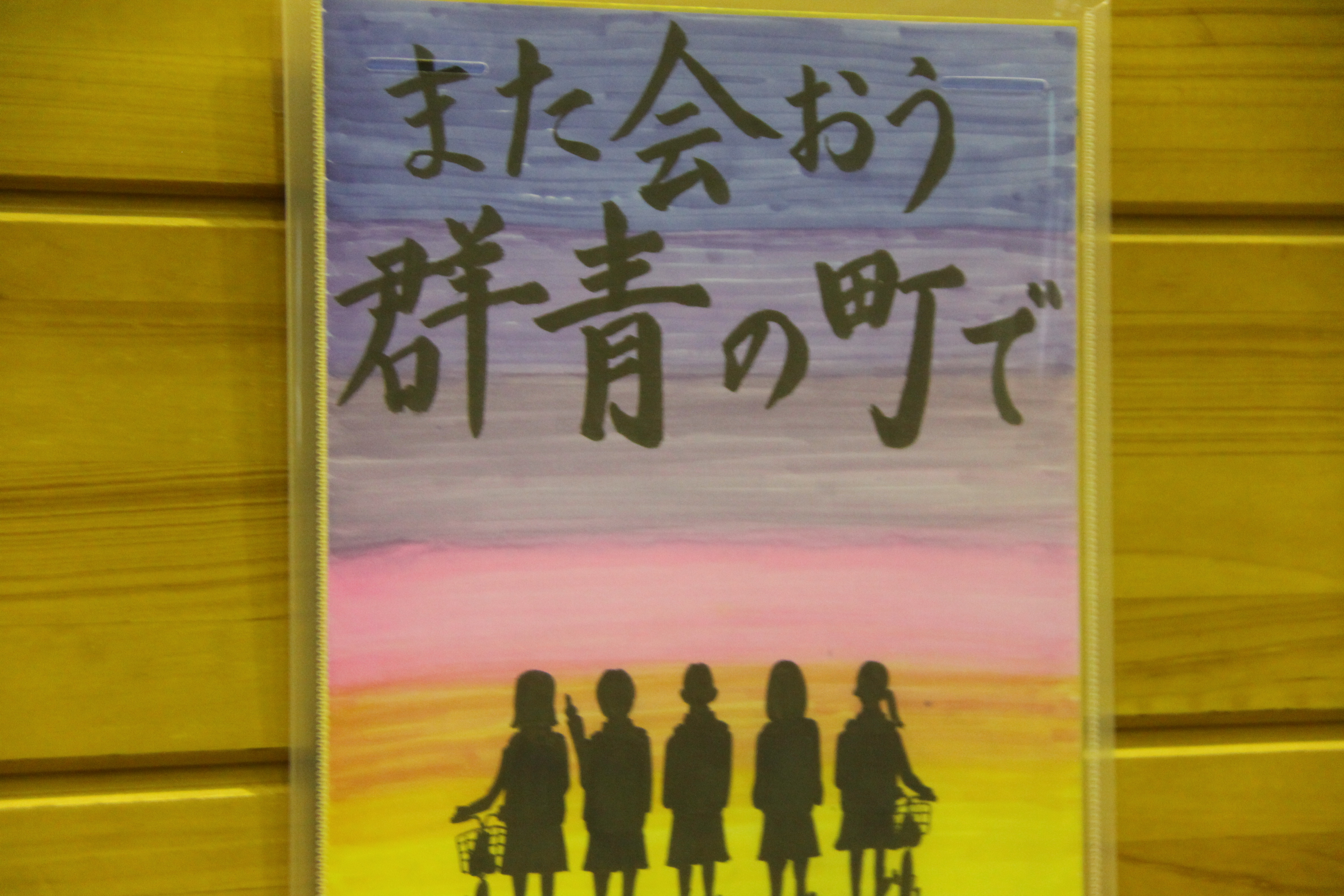
◎春よこい(3/15)
いとし面影の沈丁花 溢るる涙の蕾から ひとつ ひとつ香り始める それは それは 空を越えて やがて やがて 迎えに来る 春よ 遠き春よ 瞼閉じればそこに 愛をくれし君の なつかしき声がする(3/18県立一般入学者選抜合否発表)


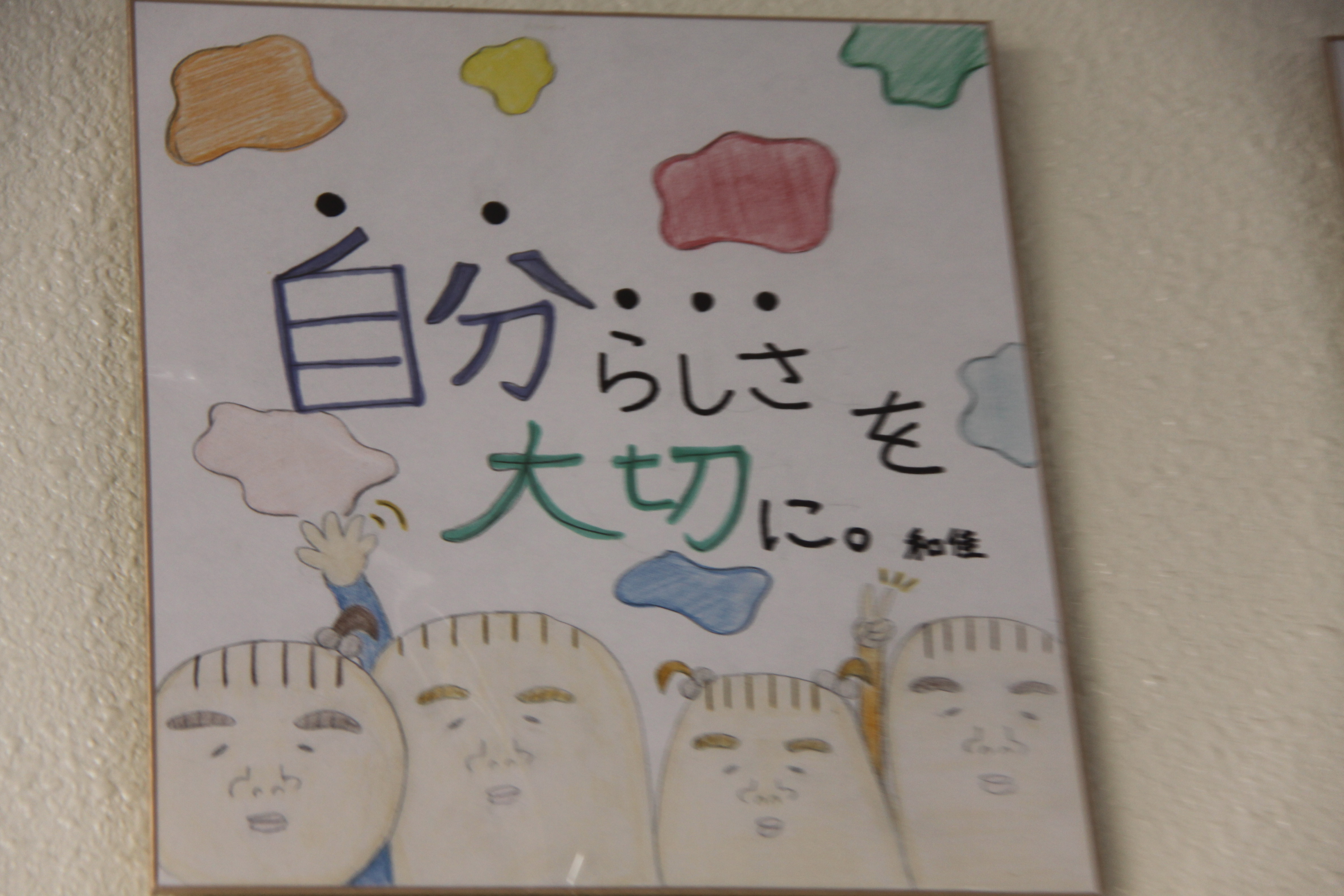
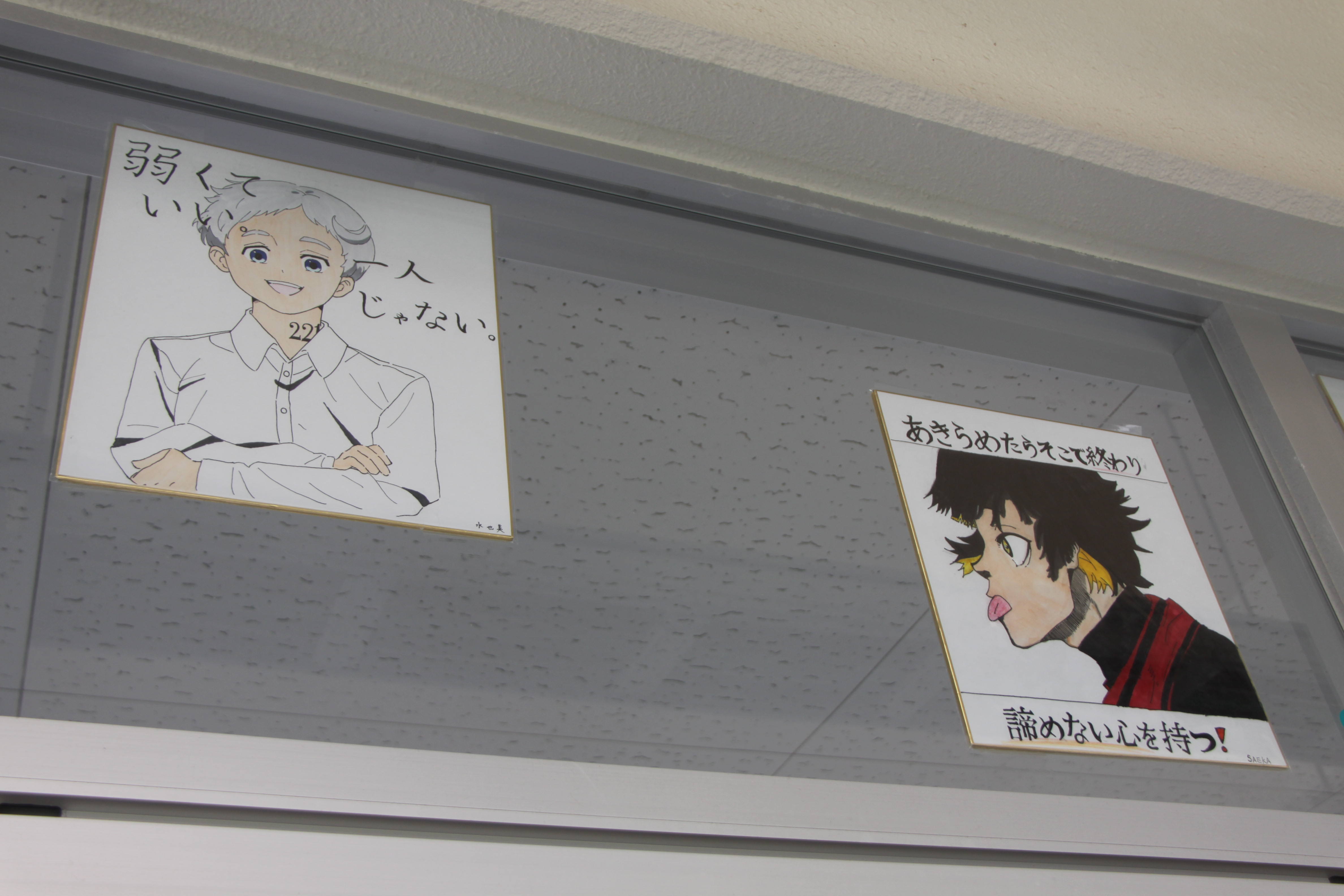
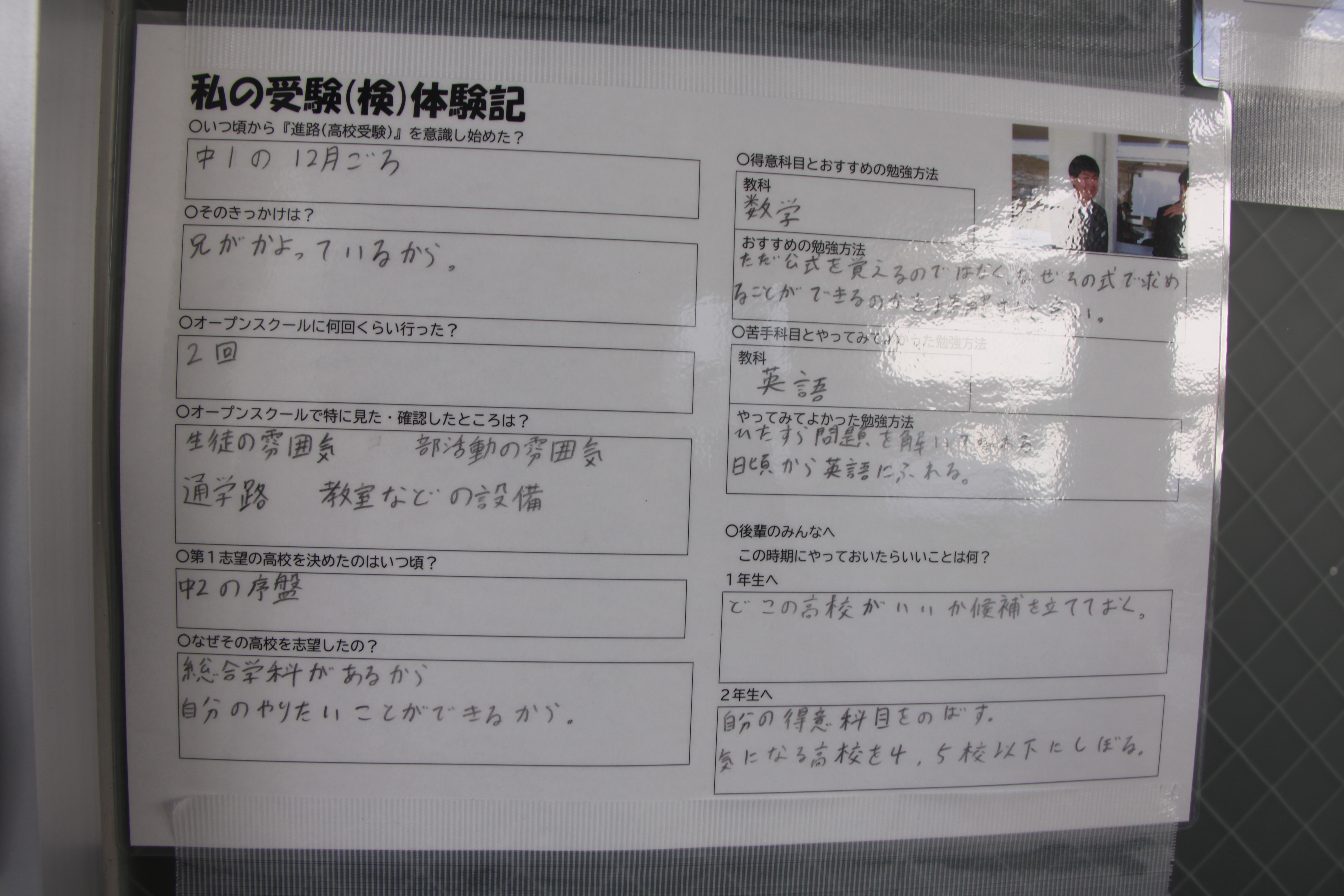
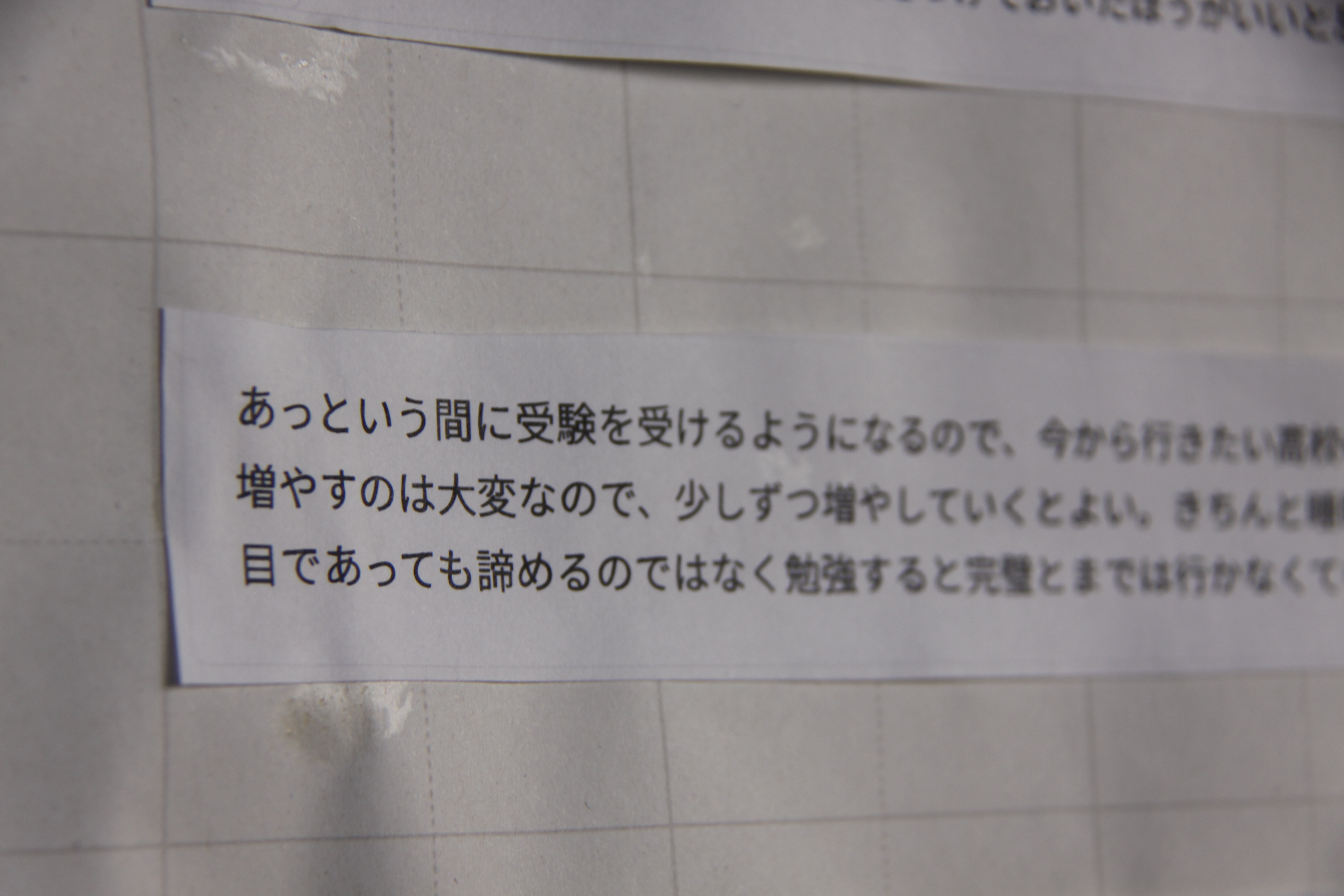
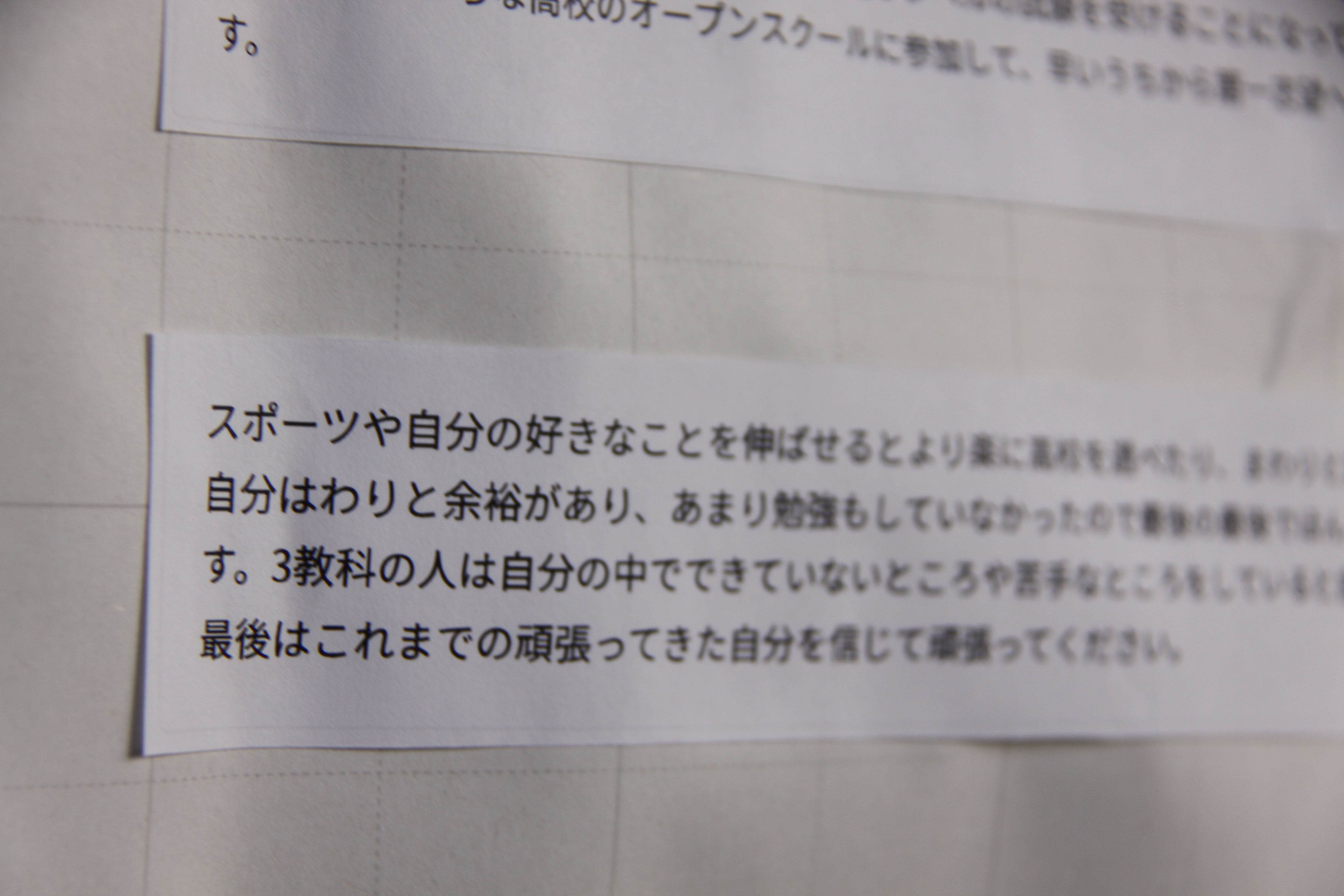
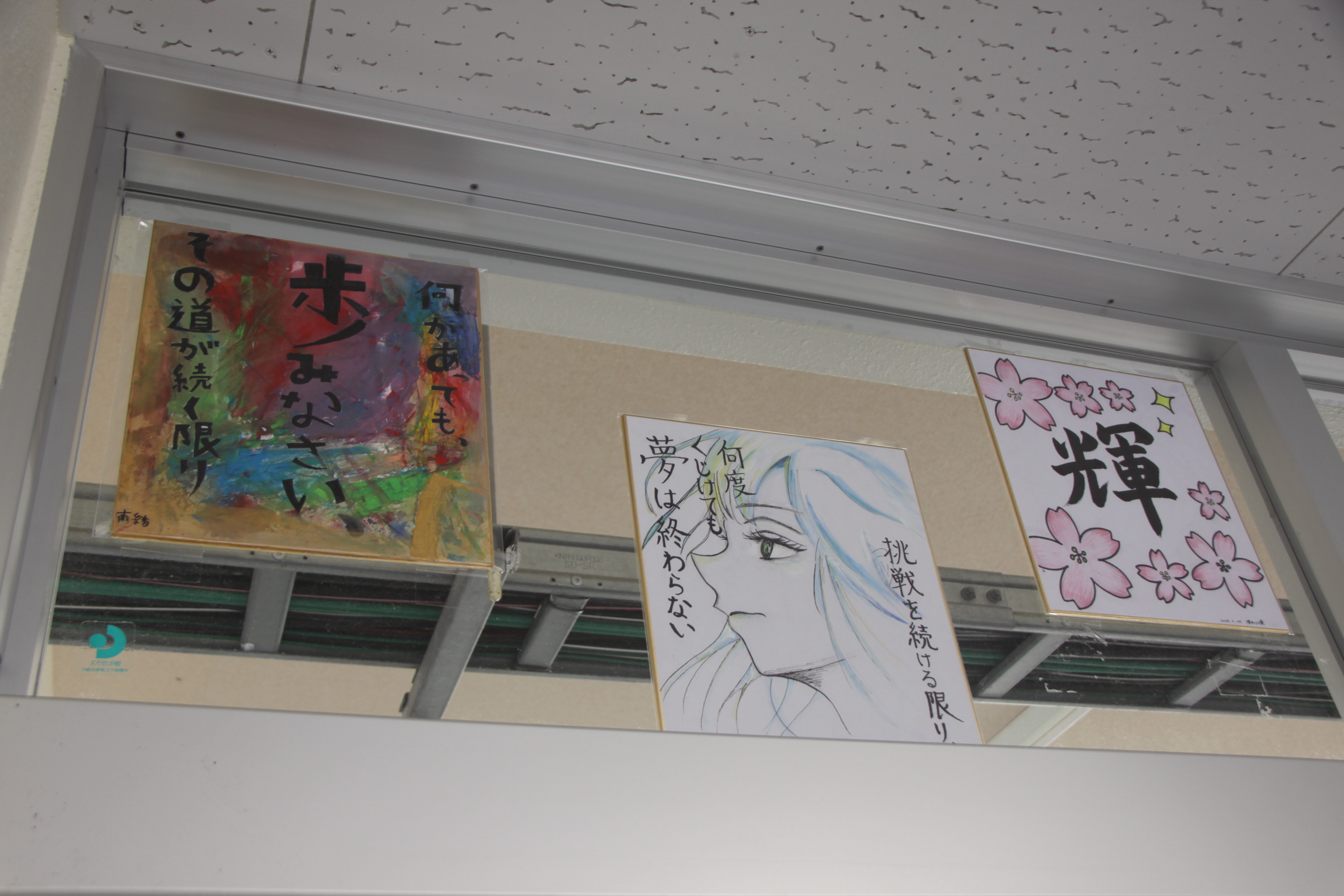
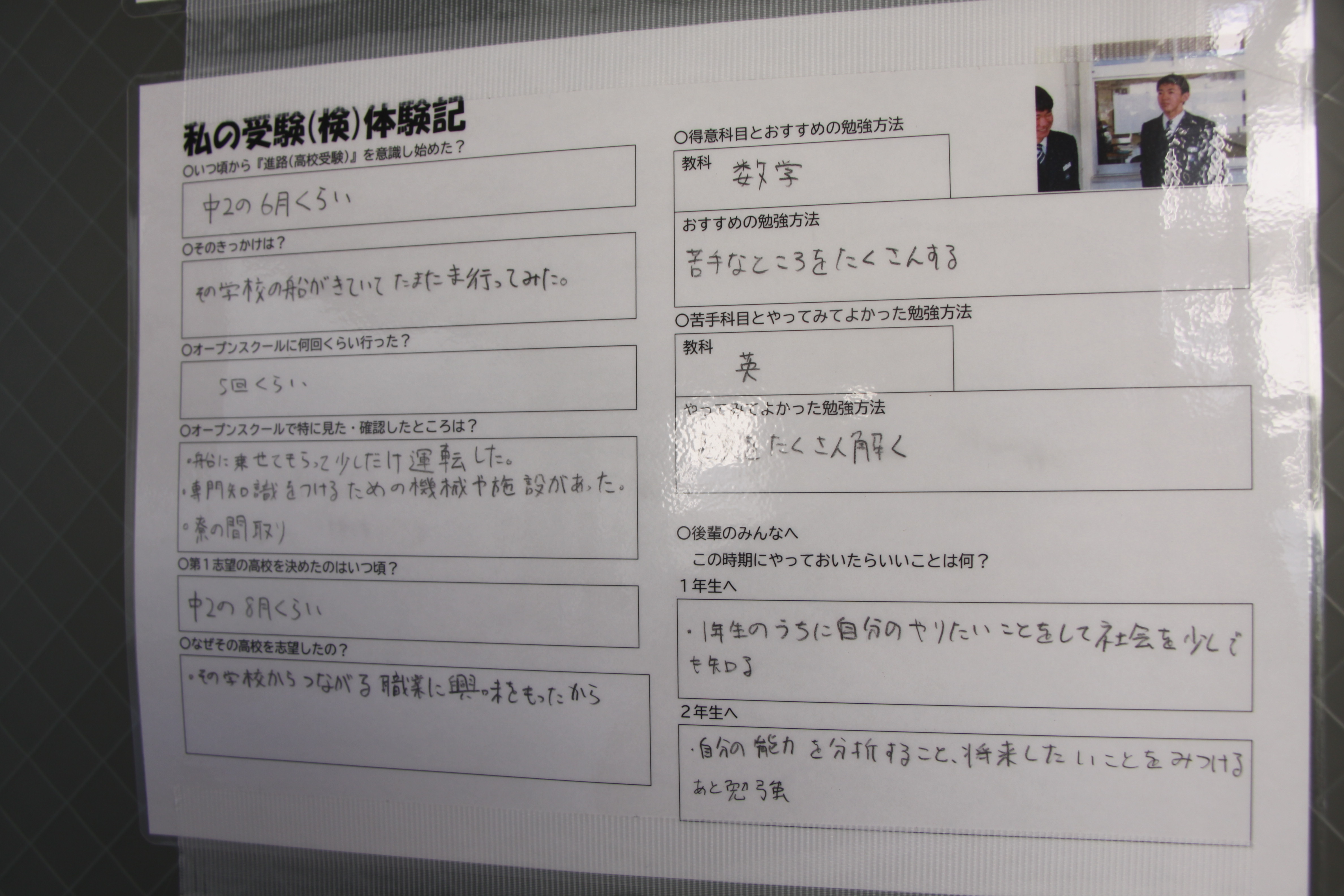
◎多くの人に支えられて(3/14)
備前市青少年健全育成センターから真鍋さん、今吉さんが校門でのあいさつ運動に来てくださいました。ありがとうございます。また、体育館では、11日~17日(予定)まで、照明をLED化する工事をしていただいています。



◎持続的な連携・協働・創造
~ひなせの子どもたちの豊かな育ちのために
中学校では、市・子ども園、小学校や様々な機関や組織と連携して、教育活動を進めています。
13日には、山﨑スクールカウンセラー市の保健課さんらと、生徒の支援やサポートの充実に向けて情報交換や、一緒に家庭訪問をおこないました。
また、14・15日には、日生東、西小学校へ訪問させていただき、六年生(新入生)の授業参観をさせていただきます。

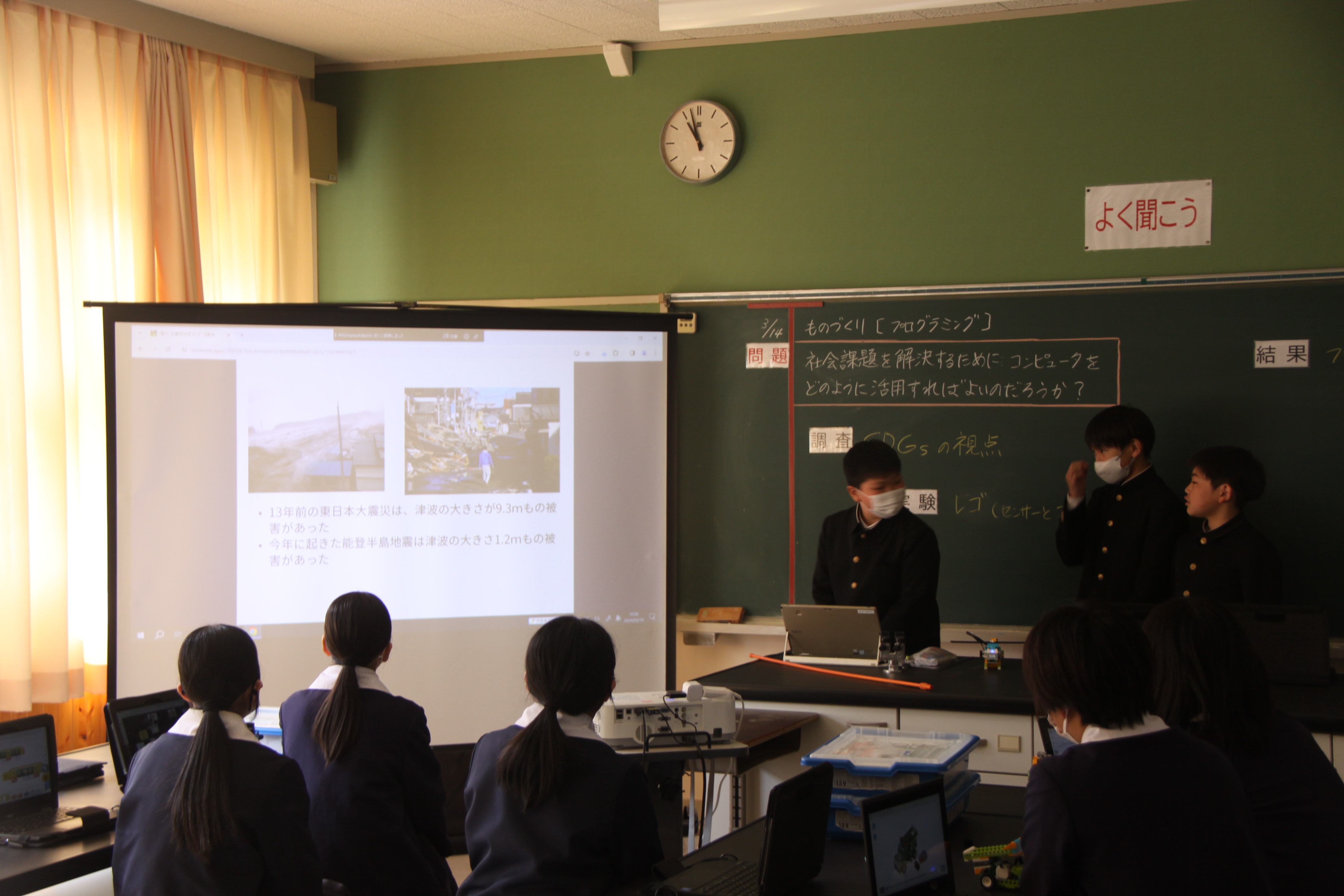

◎【お知らせ】学年閉鎖(3/13)
インフルエンザに伴う学年閉鎖について
本日、2年生において、インフルエンザ及び発熱を理由とする複数の欠席者がありました。
岡山県教育委員会により示されたインフルエンザ等の臨時休業の判断基準を参考に、学校医と相談した結果、2学年を学年閉鎖とすることに致しました。なお3月13日は、4校時終了後給食を食べた後に下校することにいたしました。保護者の皆様におかれましては、まん延防止のため、何卒ご理解・ご協力いただきますようお願いします。
また、ご家庭での手洗い・うがいの徹底や、マスクの着用等、予防及びまん延防止対策に努めていただきますようお願いします。
1 学年閉鎖の対象 2年生
2 学年閉鎖の期間 3月14日(木)から3月15日(金)まで 2日間
3 その他
(1) 期間中は、自宅で過ごさせてください。
(2) 期間中、急な発熱や咳等インフルエンザ様の症状がでた場合は、必要に応じて医療機関で受診をしてください。インフルエンザと診断された場合は、速やかに学校へ連絡ください。
(3) 週末の部活動は参加可能ですが、体調に留意し参加させてください。
インフルエンザの出席停止期間は、「発症後5日(発症の翌日が1日目)を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」となっています。(学校保健安全法施行規則第19条)(2023年4月1日改正)

お大事に。
◎All By Myself (3/13)

The best thing about the future is that it comes one day at a time. Abraham Lincoln
(未来の一番いいところは、一度に一日しかやってこないことだ。)
◎もうすぐ今日が終わる やり残したことはないかい
(3/12卒業証書授与式)
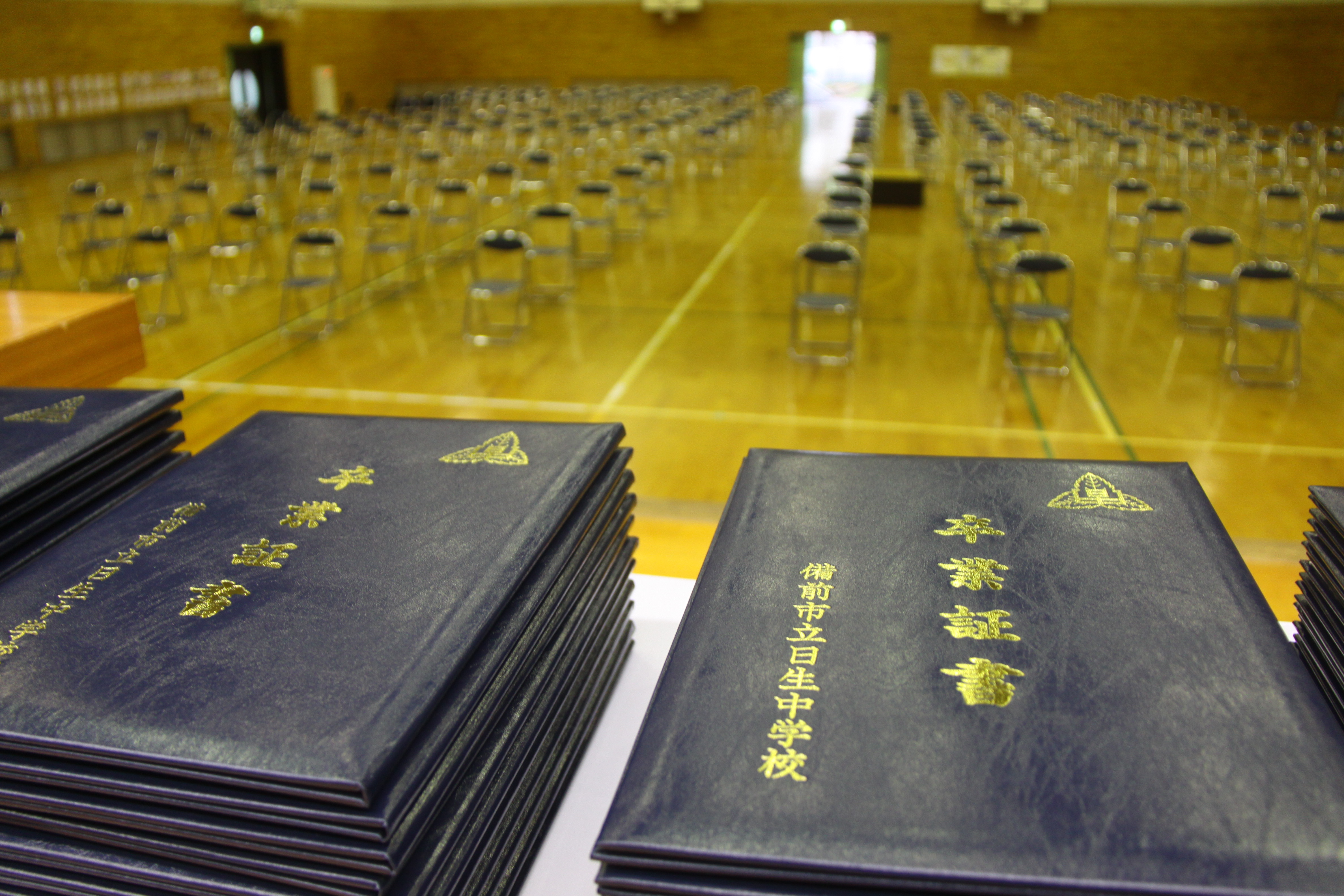





もうすぐ今日が終わる やり残したことはないかい
親友と語り合ったかい? 燃えるような恋をしたかい
一生忘れないような出来事に出会えたかい
かけがいのない時間を胸に刻み込んだかい
夕飯時 町 人いきれ「ただいま」と「おかえり」の色
せわしない 木漏れ日 花びら「おはよう」と「さよなら」の音
ありふれた日々が 君や僕の胸に積もって光る
もうすぐ今日が終わる やり残したことはないかい
◎引き継がれていくこと✨卒業書証授与式会場準備
幾千の学び舎の中で 僕らが巡り逢えた奇跡 幾つ歳をとっても変わらないで その優しい笑顔 教室の窓から桜ノ雨 ふわりてのひら 心に寄せた みんな集めて出来た花束を 空に放とう 忘れないで 今はまだ... 小さな花弁だとしても 僕らはひとりじゃない(「桜の雨♪」より)












◎3.11を迎える
~「あたりまえ」と思える日々や友達がどれだけ大切なのか

13年前の3月、気仙沼市立階上中学校、梶原さんの卒業式答辞を紹介します。
《 本日は未曽有の大震災の傷も癒えないさなか,私たちのために卒業式を挙行していただき,ありがとうございます。 ちょうど十日前の三月十二日。春を思わせる暖かな日でした。 私たちは,そのキラキラ光る日差しの中を,希望に胸を膨らませ,通い慣れたこの学舎を,五十七名揃って巣立つはずでした。 前日の十一日。一足早く渡された思い出のたくさん詰まったアルバムを開き,十数時間後の卒業式に思いを馳せた友もいたことでしょう。「東日本大震災」と名付けられる 天変地異が起こるとも知らずに…。 階上中学校といえば「防災教育」といわれ,内外から高く評価され,十分な訓練もしていた私たちでした。しかし,自然の猛威の前には,人間の力はあまりにも無力で,私たちから大切なものを容赦なく奪っていきました。天が与えた試練というには,むごすぎるものでした。つらくて,悔しくてたまりません。 時計の針は十四時四十六分を指したままです。でも時は確実に流れています。生かさ れた者として,顔を上げ,常に思いやりの心を持ち,強く,正しく,たくましく生きて いかなければなりません。 命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし,苦境にあっても,天を恨まず, 運命に耐え,助け合って生きていくことが,これからの私たちの使命です。 私たちは今,それぞれの新しい人生の一歩を踏み出します。どこにいても,何をしていようとも,この地で,仲間と共有した時を忘れず,宝物として生きていきます。 後輩の皆さん,階上中学校で過ごす「あたりまえ」に思える日々や友達が,いかに貴重なものかを考え,いとおしんで過ごしてください。先生方,親身のご指導,ありがとうございました。先生方が,いかに私たちを思ってくださっていたか,今になってよく 分かります。地域の皆さん,これまで様々なご支援をいただき,ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 お父さん,お母さん,家族の皆さん,これから私たちが歩んでいく姿を見守っていてください。必ず,よき社会人になります。 私は,この階上中学校の生徒でいられたことを誇りに思います。 最後に,本当に,本当に,ありがとうございました。 平成二十三年三月二十二日 第六十四回卒業生代表 梶原 裕太》
◎ひな中の風✨
~友、僕たちが見上げる空は(3/11)

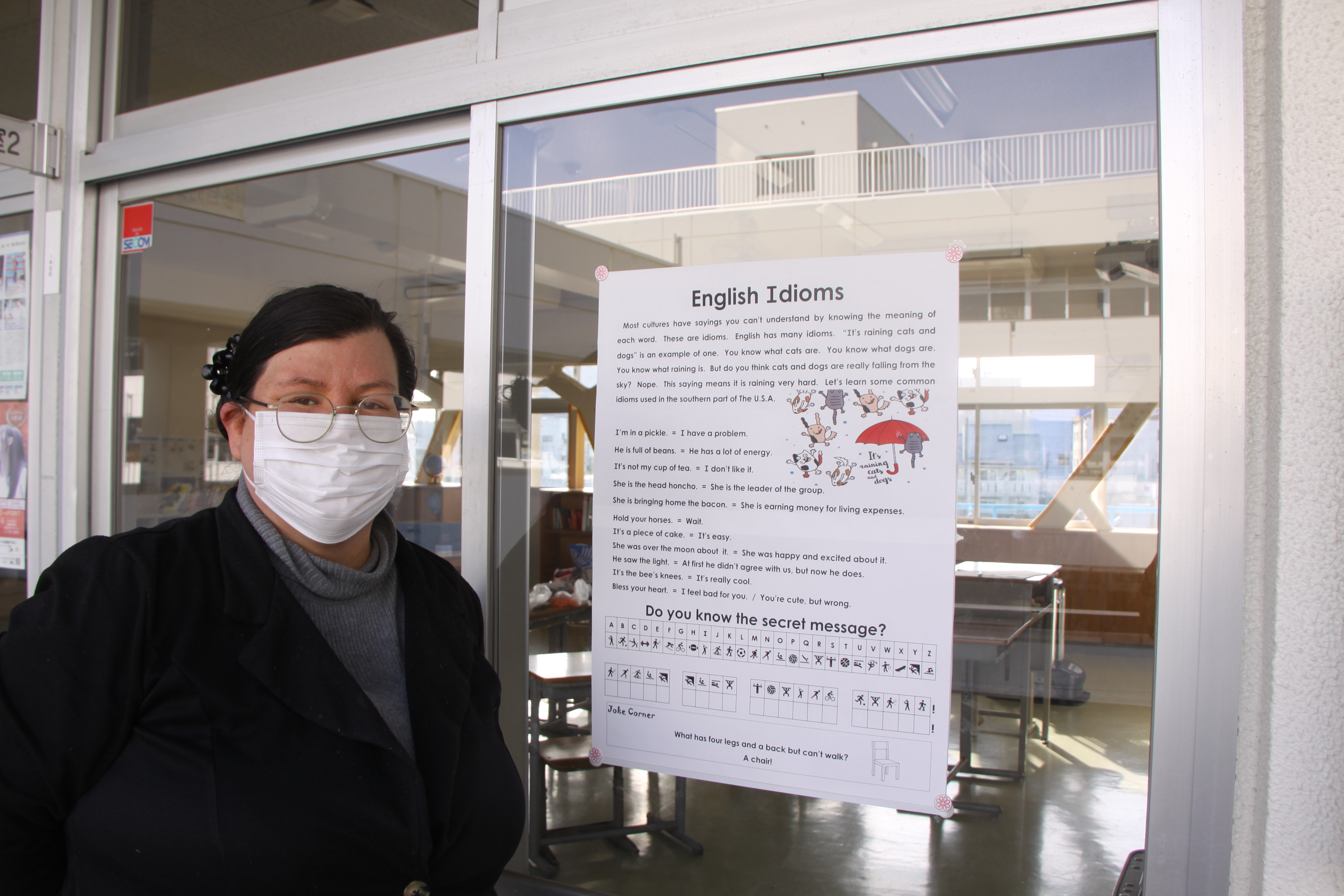


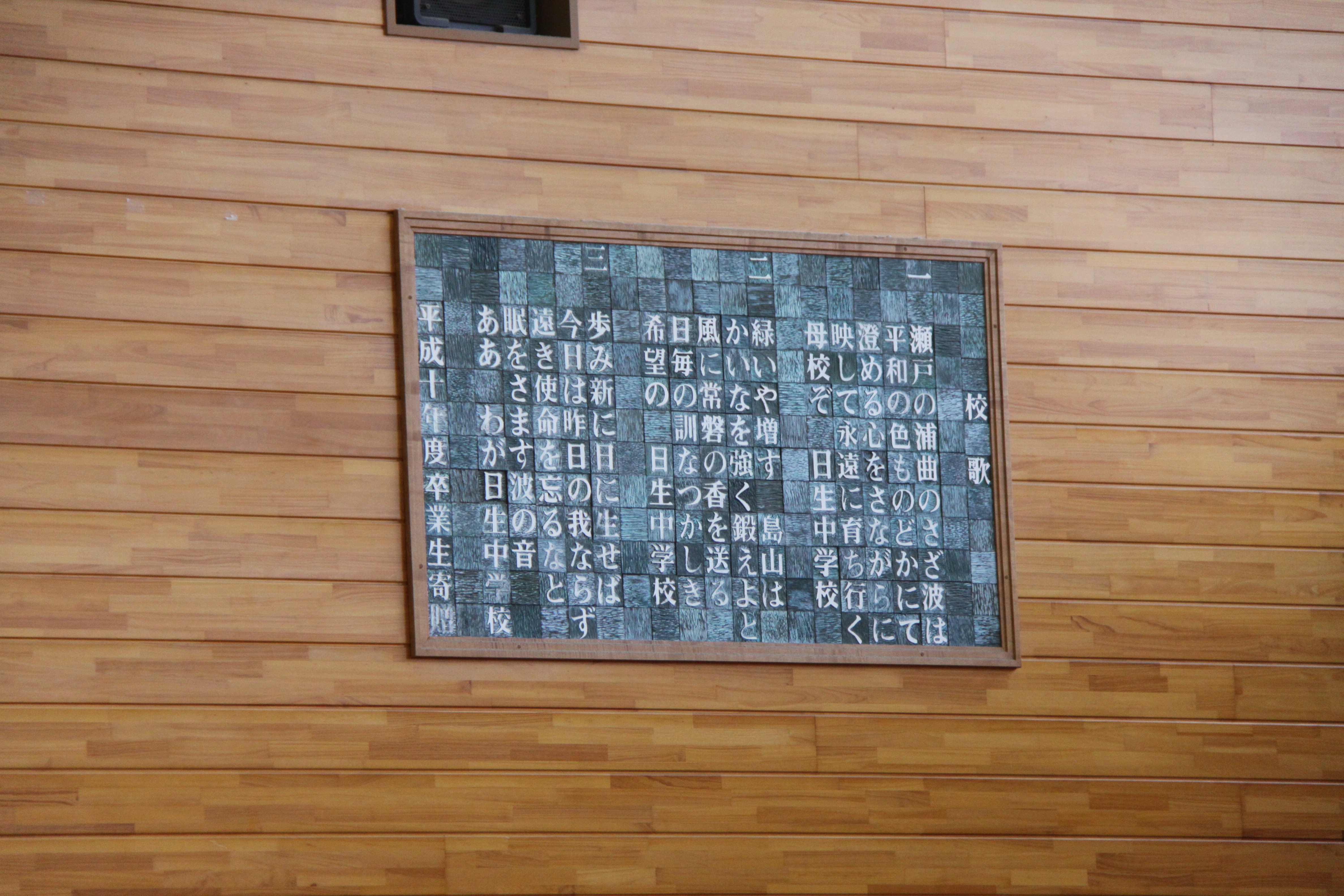


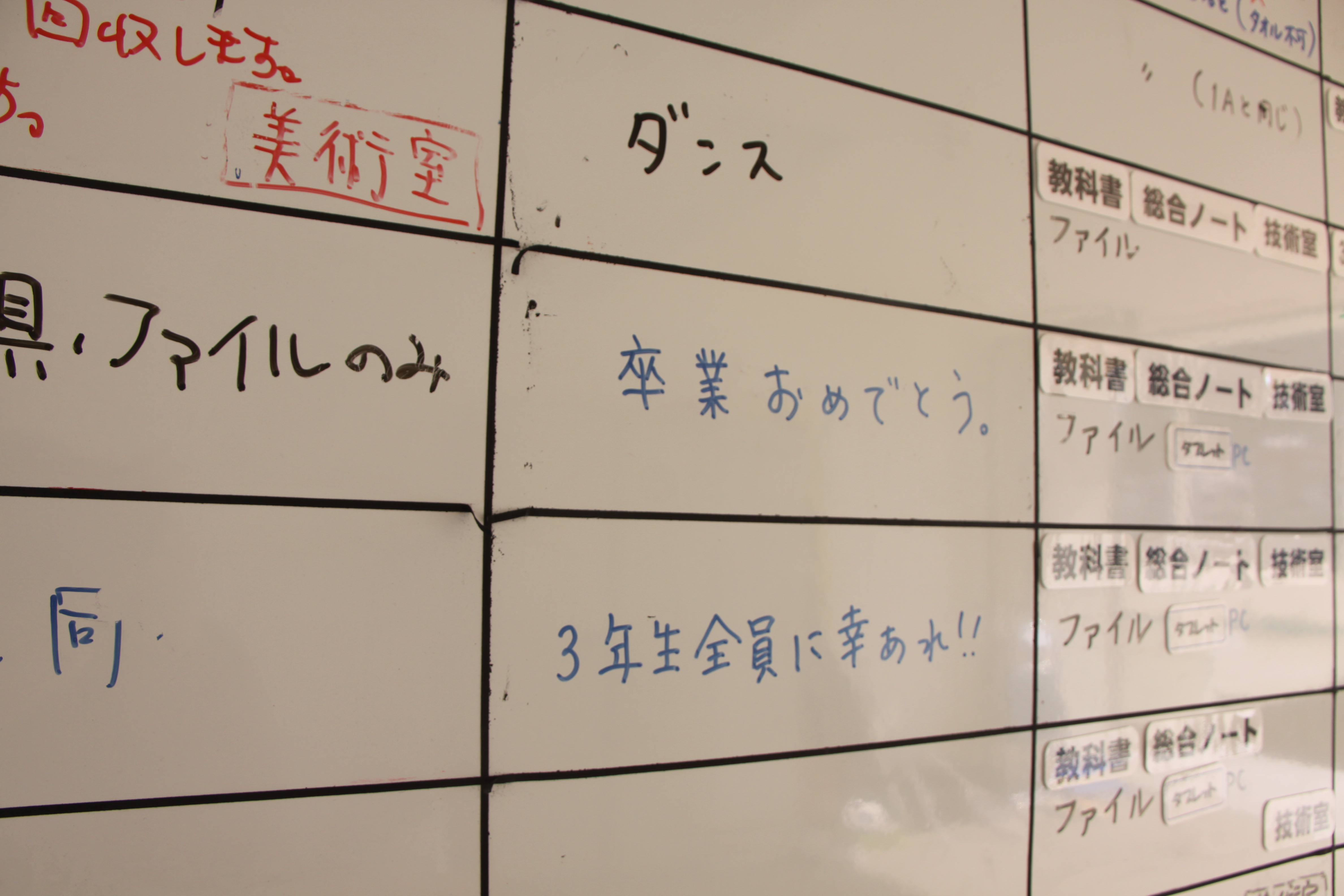




◎いま、ここからのPTA活動に向けて(3/9)

岡山県PTA連合会臨時常任委員会が、3月9日に(岡山青年会館)開催されました。会員への12月実施アンケートをもとに、今後の県P活動について、各地域の代表委員から様々な意見が出されました。協議された内容については、備前市PTA連合会の各単P事務局には、4月5日(金)に行う備前市教育研修所学校運営部会研修会で報告します。またそののち、備前市PTA連合会代議員会や総会でも随時、報告・協議していきます。(備前市PTA連合会事務局 日生中学校)
◎善き日のために(3/8)
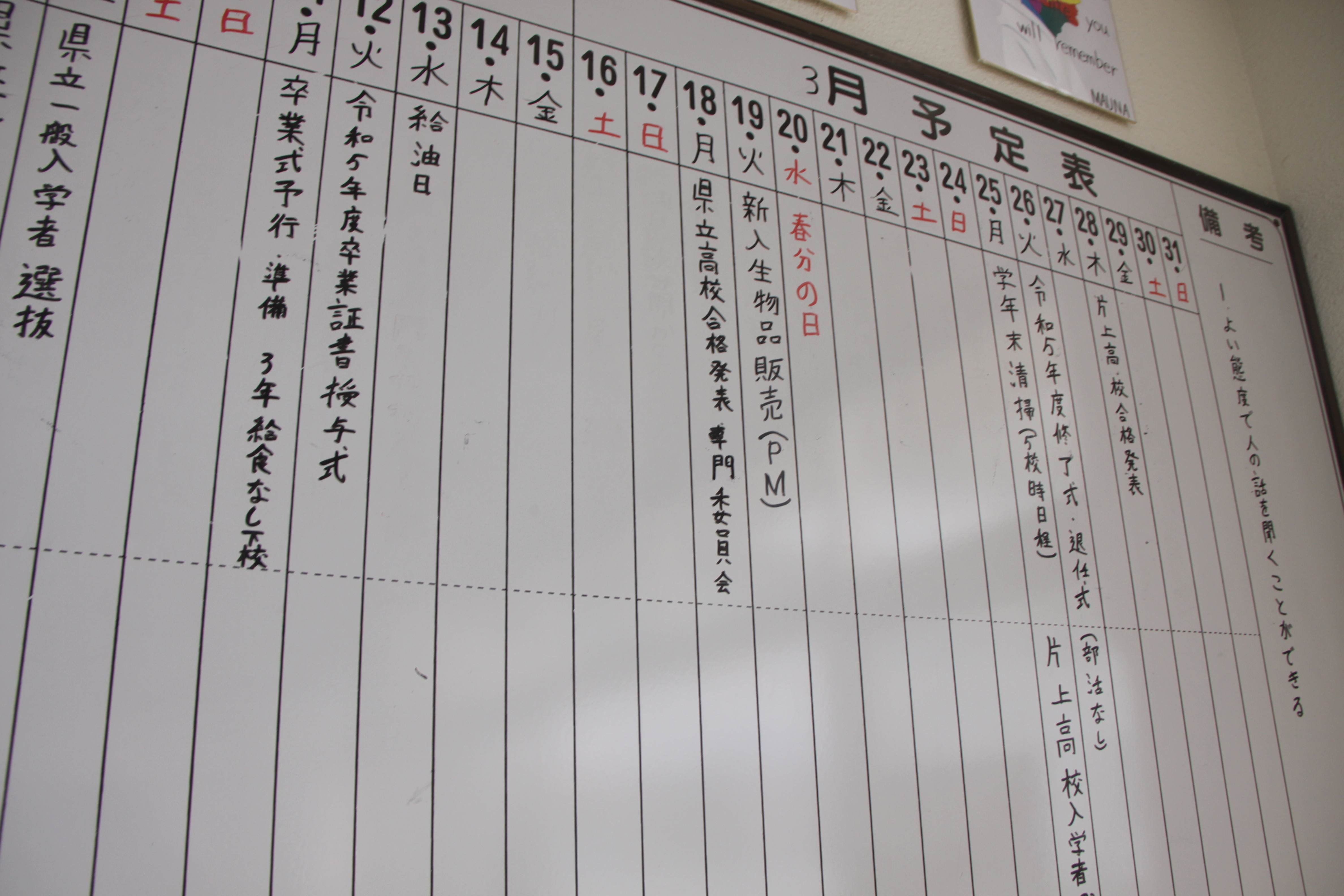

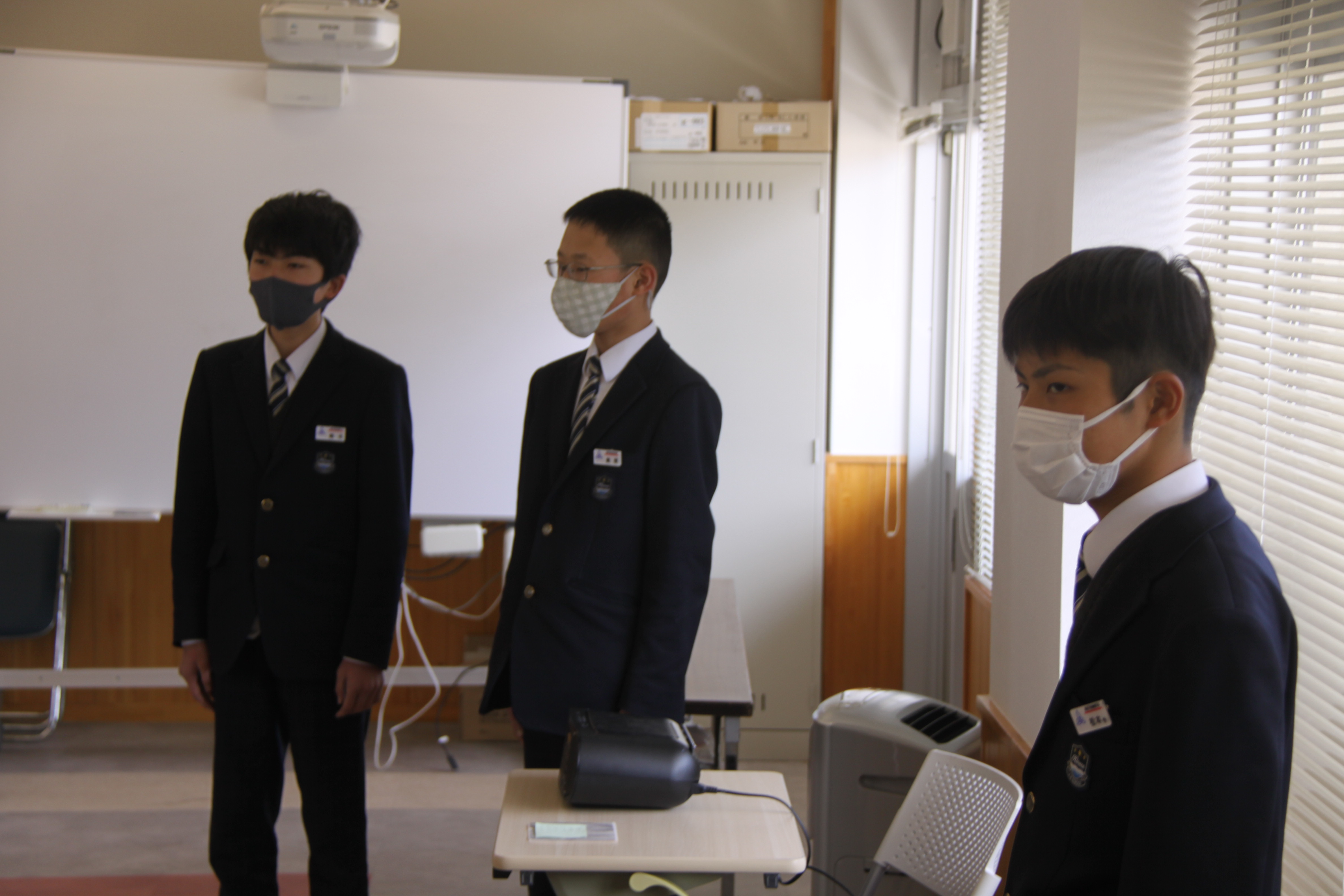










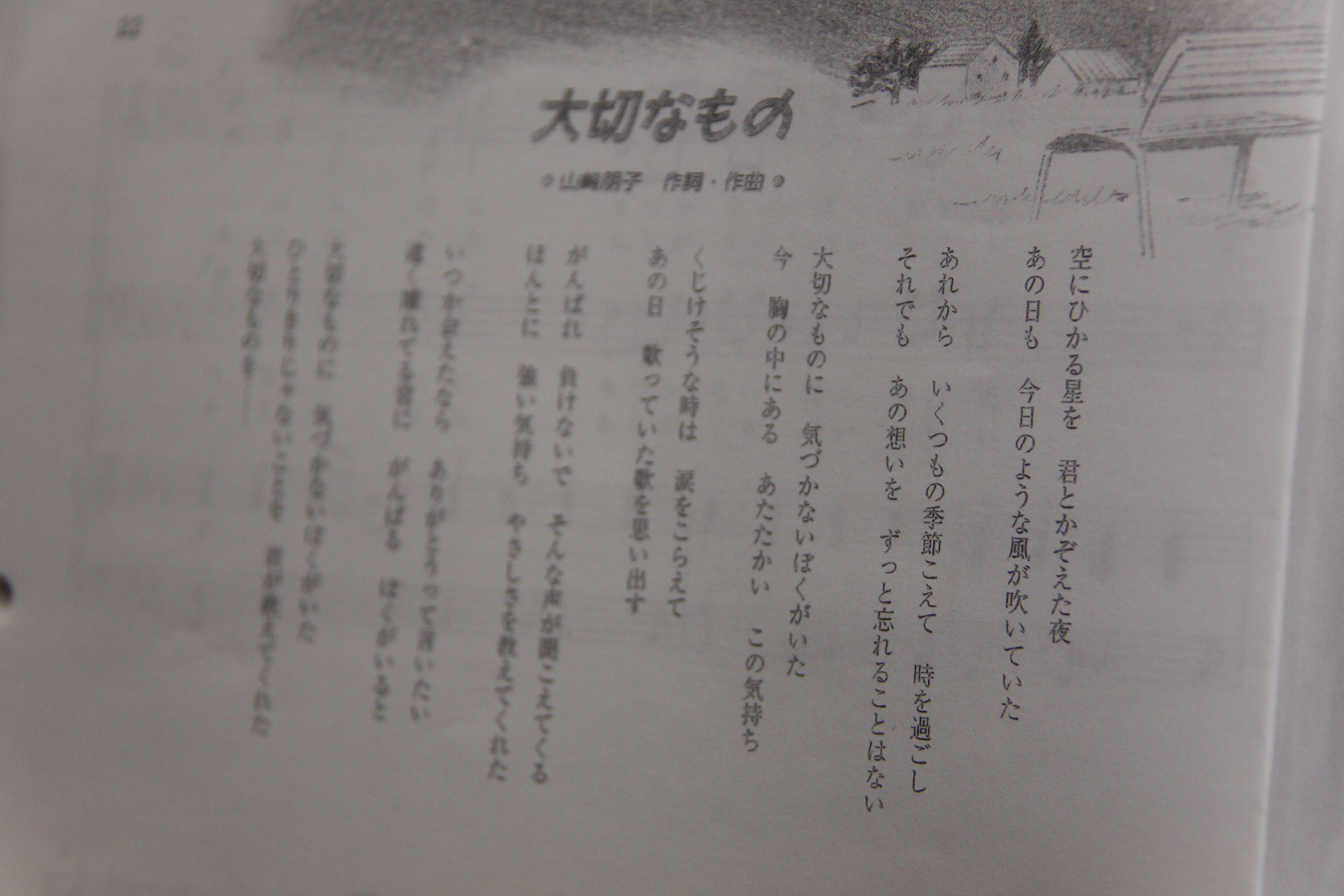
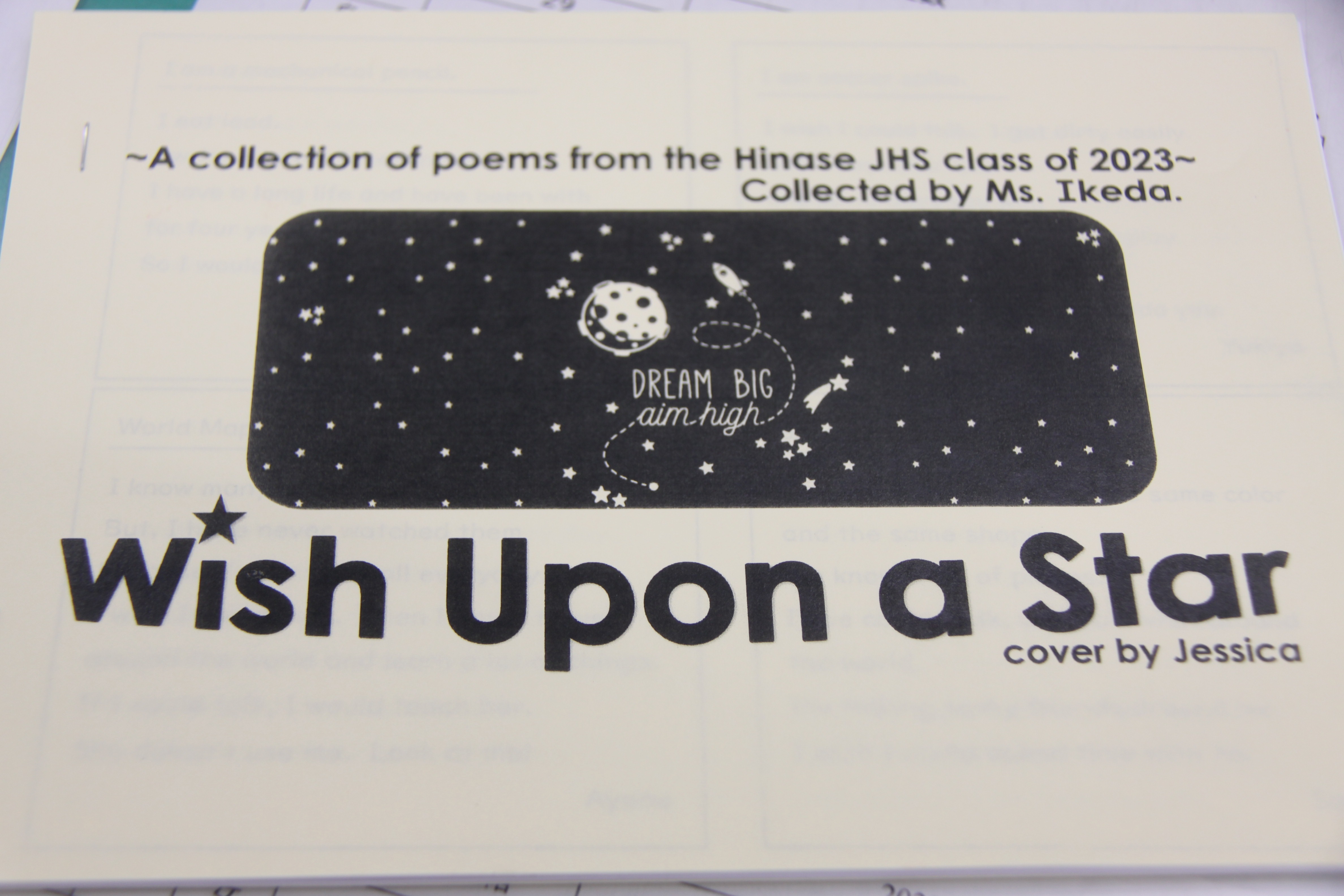
空にひかる星を 君と数えた夜
あの日も 今日のような風が吹いていた
あれから いくつのも季節こえて 時を過ごし
それでも あの 想いを すっと忘れることはない
大切なものに 気づかないぼくがいた
今 胸の中にある あたたかい この気持ち
くじけそうな時は 涙をこらえて
あの日 歌っていた歌を思い出す
がんばれ まけないで そんな声が聞こえてくる
ほんとに 強い気持ち やさしさを教えてくれた
いつか会えたなら ありがとうって言いたい
遠く離れている君に がんばる 僕がいると
大切なものに 気づかないぼくがいた
ひとりきりじゃないこと 君が教えてくれた
大切なものを……
◎一年後、まってろよ!私の進路・夢・未来!
(3/8:一般入試出題問題を目を通す)
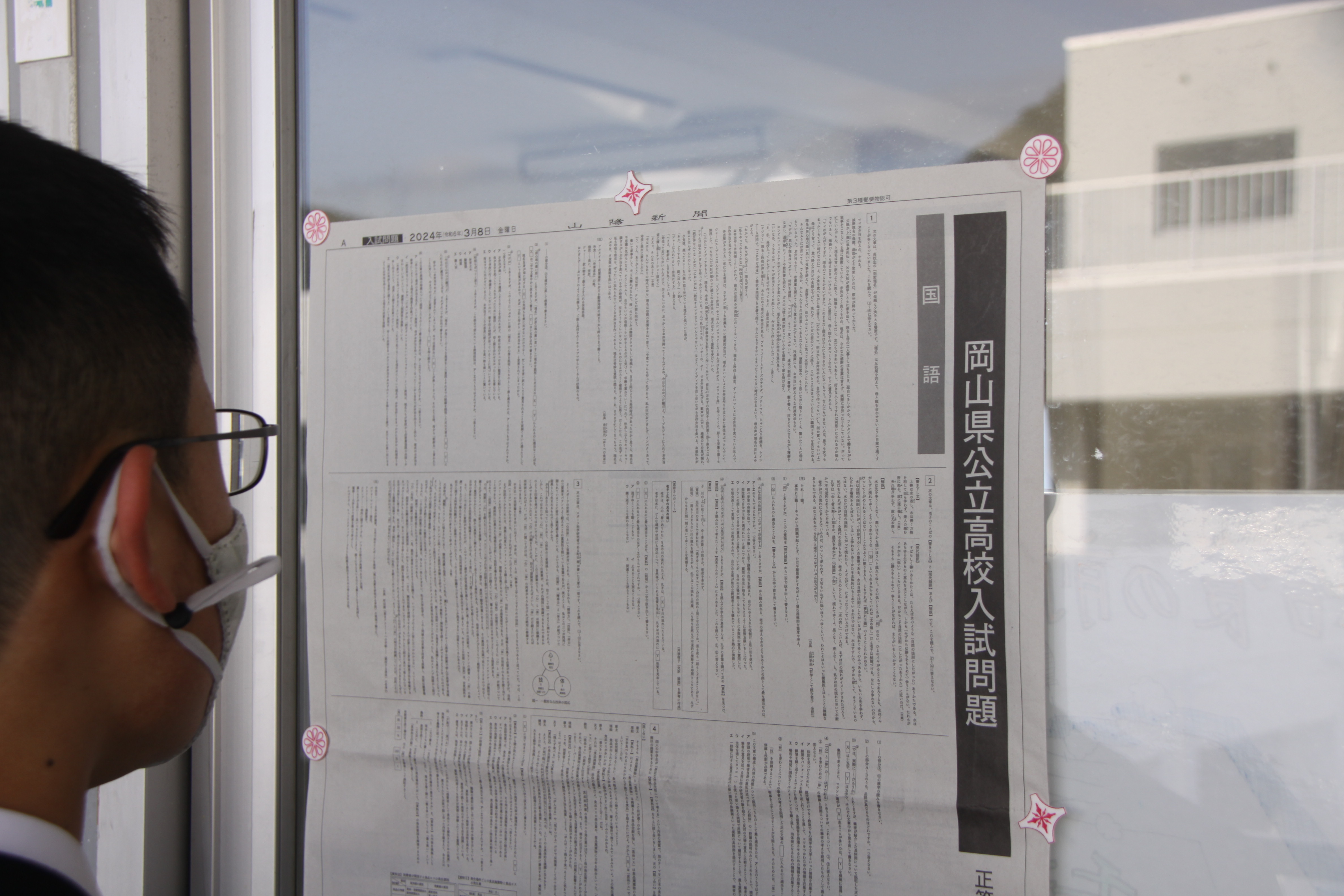
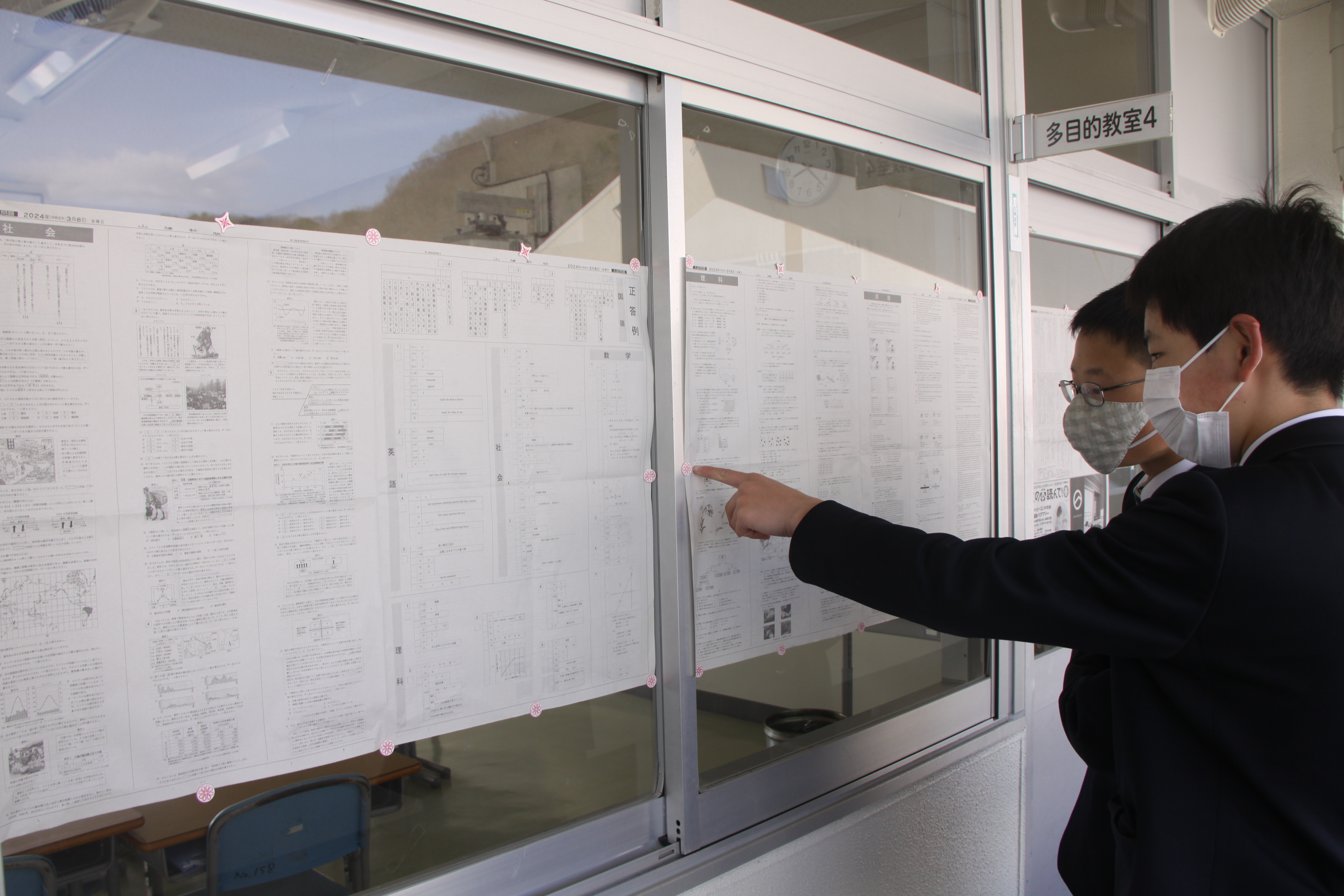
◎積み上がる受験参考書やすらかに古紙回収を持っている春 小林理央
祈 もうひとふんばり、みんなで乗り越えよう。県立一般入学者選抜(3/8・9)

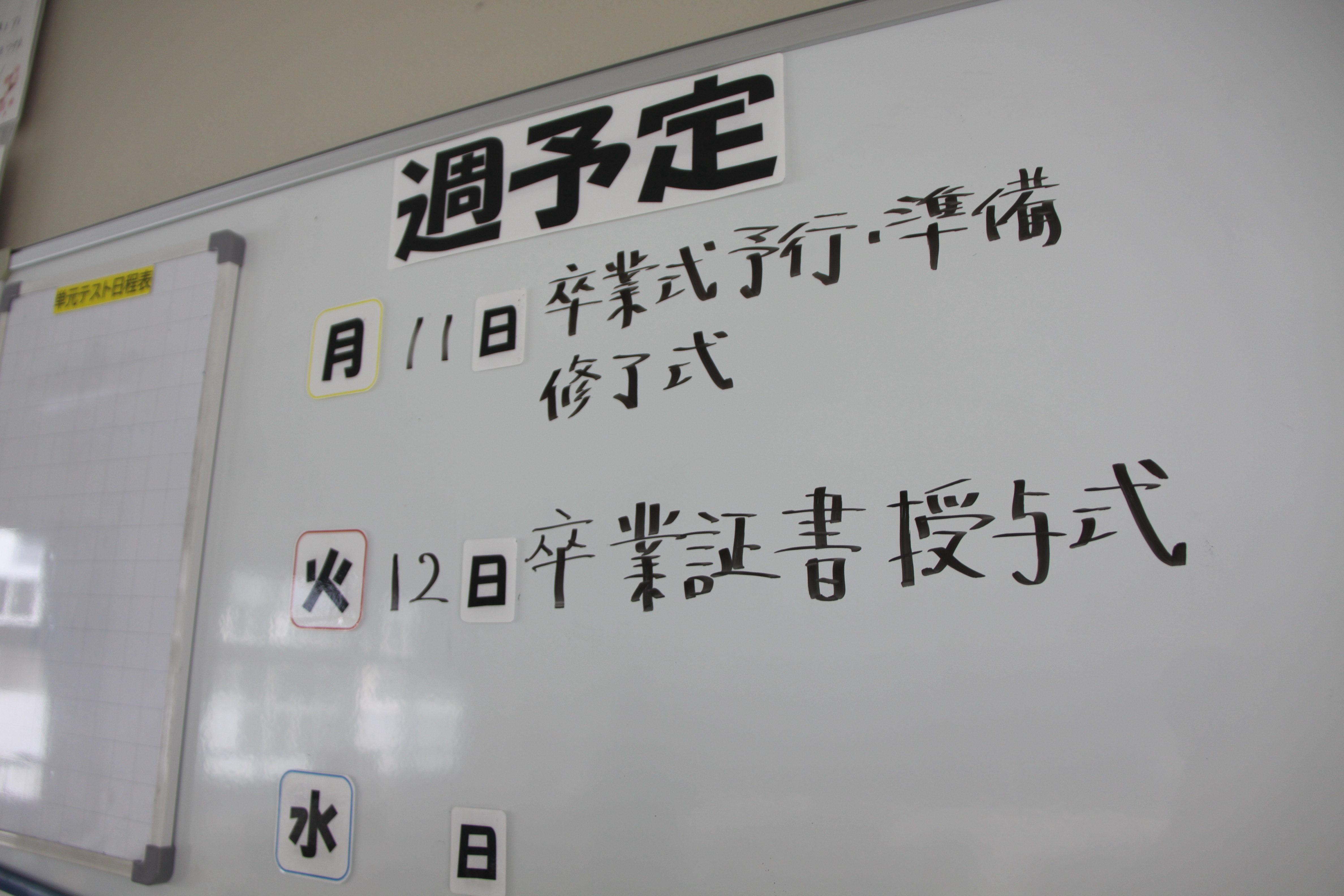
2024年度岡山県公立高等学校一般入学者選抜(第I期)は、2月21日から26日(土日祝日を除く)まで出願を受け付けました。県立全日制は、50校の募集人員5‚750人に対して6‚263人が志願し、志願倍率は1.09倍となりました。一般入学者選抜(第I期)は、今日、3月7日に学力検査、明日、3月8日に面接・実技、3月18日に合格者発表を行います。インフルエンザの罹患など、やむを得ない理由により欠席した者を対象とした追検査は、3月18日に実施します。
◎MISSION POSSIBLE(3/7)∈^0^∋
私たち1年生、《33のミッション》のひとつ〈給食を班のみんなで食べよう〉



◎3月の風景(3/6)
これが存在すれば、あれも存在する
これが生ずれば、あれも生ずる
これが存在しなければ、あれも存在しない
これが滅すれば、あれも滅する 比叡山天台座主 山田恵諦
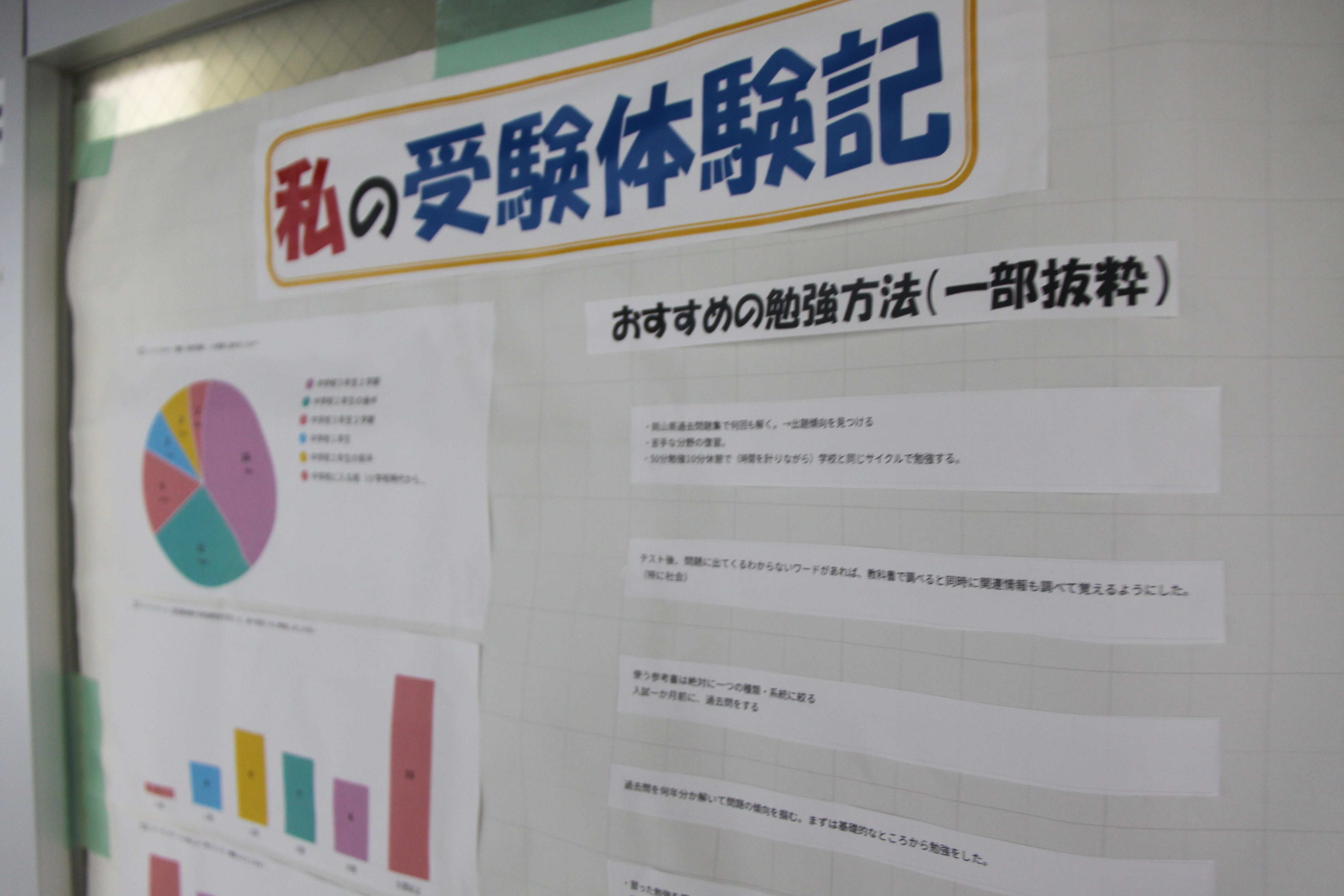


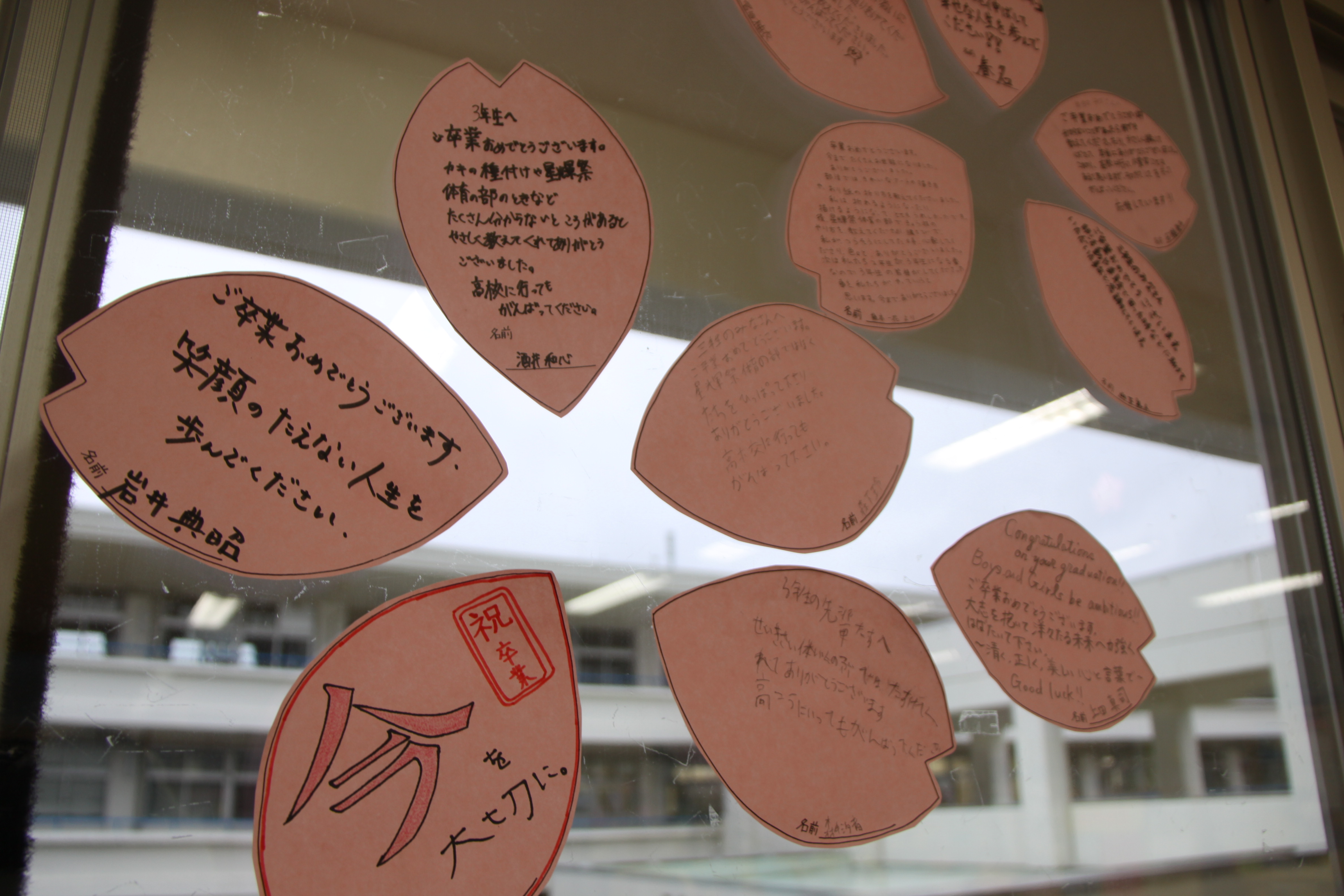
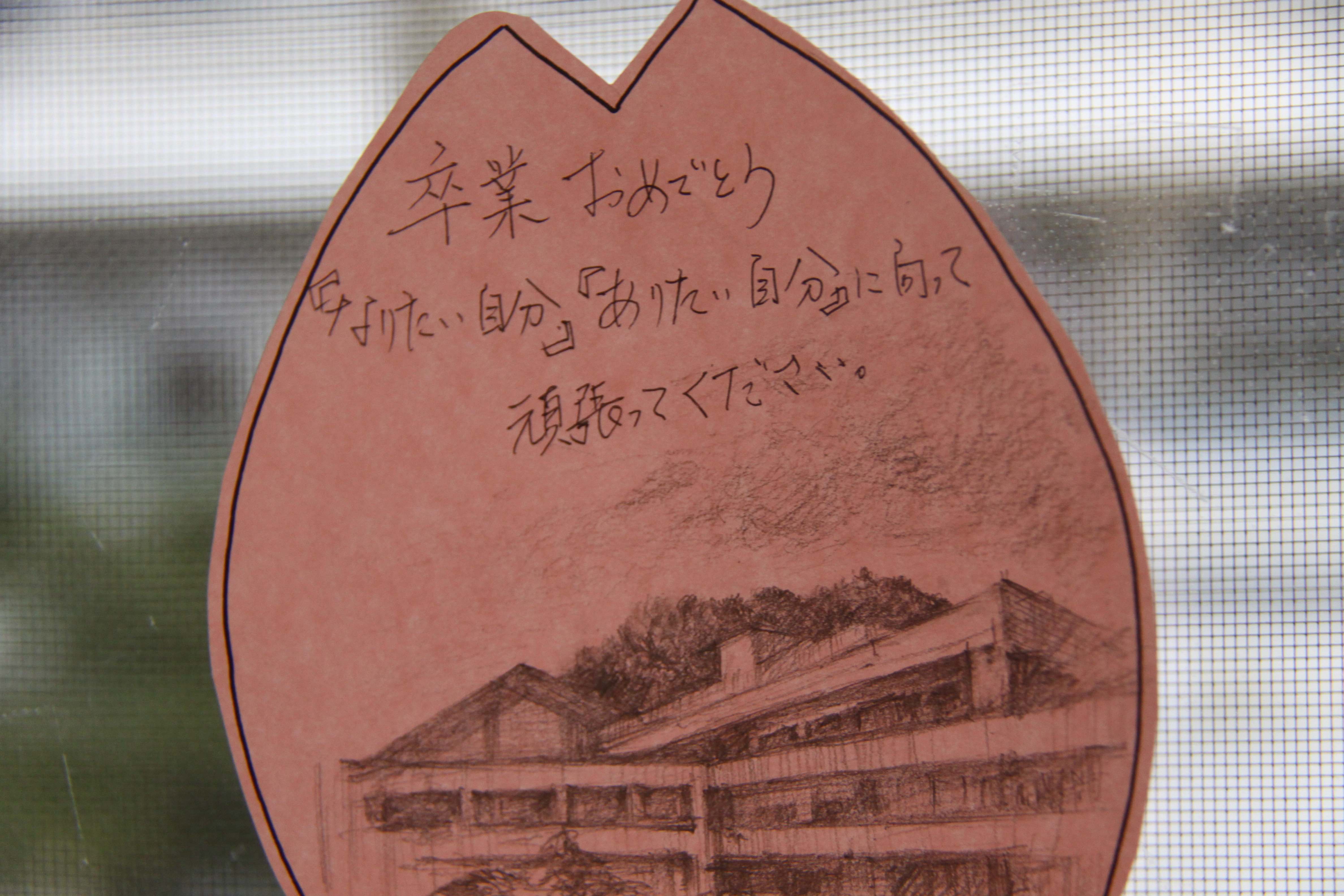

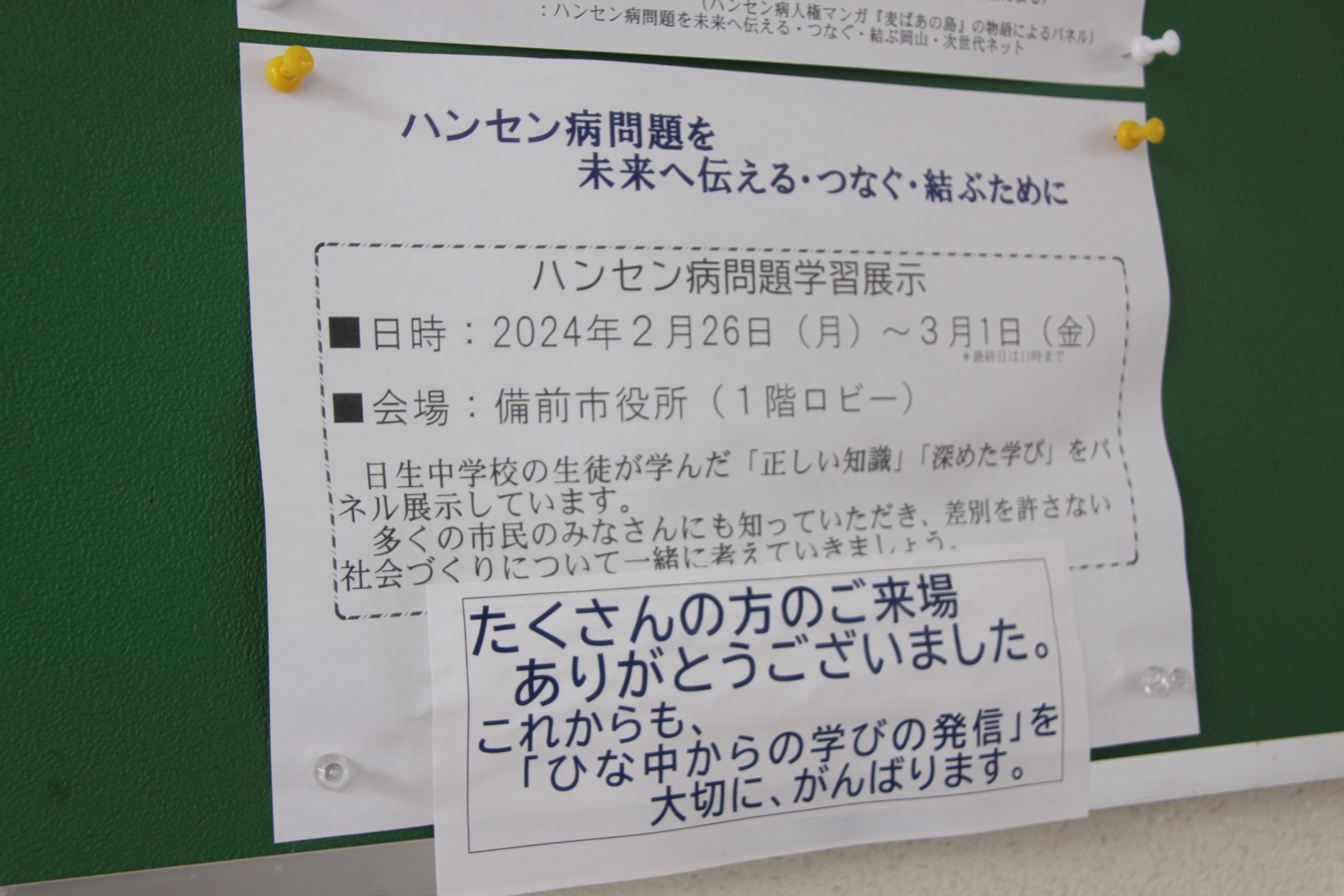


◎Thank you vary much Jessica
ひな中チャレンジ企画 第11回英会話教室(~3/6)
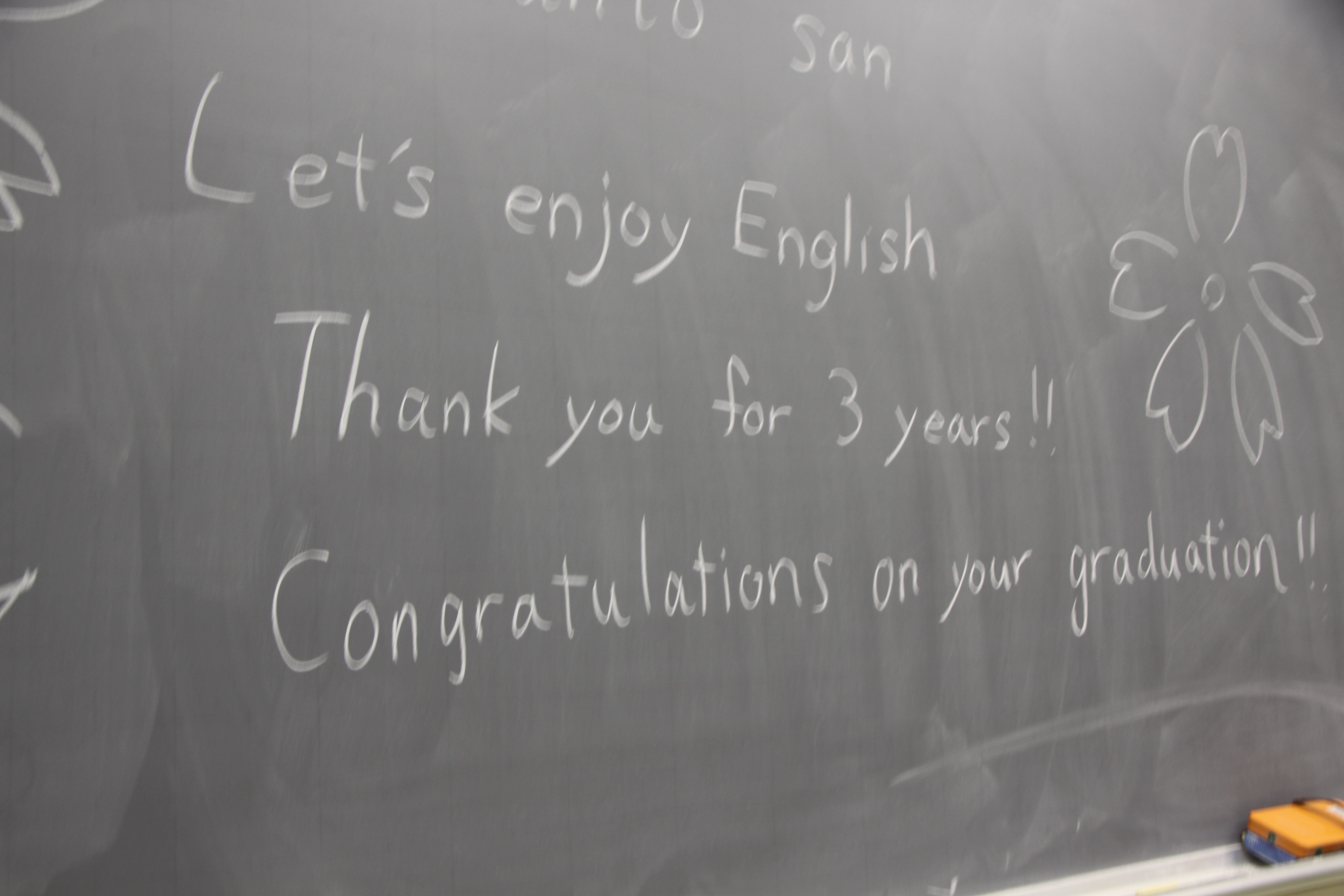

のべ30人のチャレンジ生徒が、さらにJessica先生・上田先生らとそして仲間たちと共に英会話の楽しさ・豊かさをたくさん体験することができました。参加した皆さん新年度もチャレンジ精神で、様々なことに積極的に取り組んでいきましょう。そしてJessica先生ありがとうございました。
◎啓蟄(3/5)

啓蟄(けいちつ)とは
日本には一年間を24分割し、それぞれに季節を表す言葉をつけた二十四節気という言葉があります。啓蟄とは、3番目の二十四節気のことを指します。啓蟄の前は雨水、後は春分と徐々に春が近づいてくる季節であると言えます。
「啓蟄」という文字を見ると、どんな意味なのかちょっと想像できないかもしれませんが、「啓」の字には「開く」という意味があり、「蟄」の字には「虫などが土などに隠れている様子」という意味があります。つまり土に隠れていた虫が外に出てくる、それほどに暖かくなってきたことを示す言葉でもあるのです。啓蟄に行われる行事は特に定められていないのですが、日に日に春に近づいてきて日差しも徐々に暖かくなり、「さぁ働くぞ」とやる気が出てくる人も多いのではないでしょうか。春野菜をいただくなどして、英気を養ってはいかがでしょうか。
ちなみに園芸では、冬囲いで使用したコモを焼く風習があります。コモとは藁で編んだ敷物のようなもので、冬になる前に木の幹に巻きつけ、害虫退治のために利用されるもの。コモを巻くと、暖かい場所を好む松の害虫はコモの部分に集まってきます。徐々に暖かさが感じられるようになる啓蟄の時期にコモを外し燃やすことで、害虫退治を行うそうです。
◎ステキな仲間 ステキなクラス
ステキなわたし ステキなひな中。
~私たちの生徒集会・表彰式(3/5)

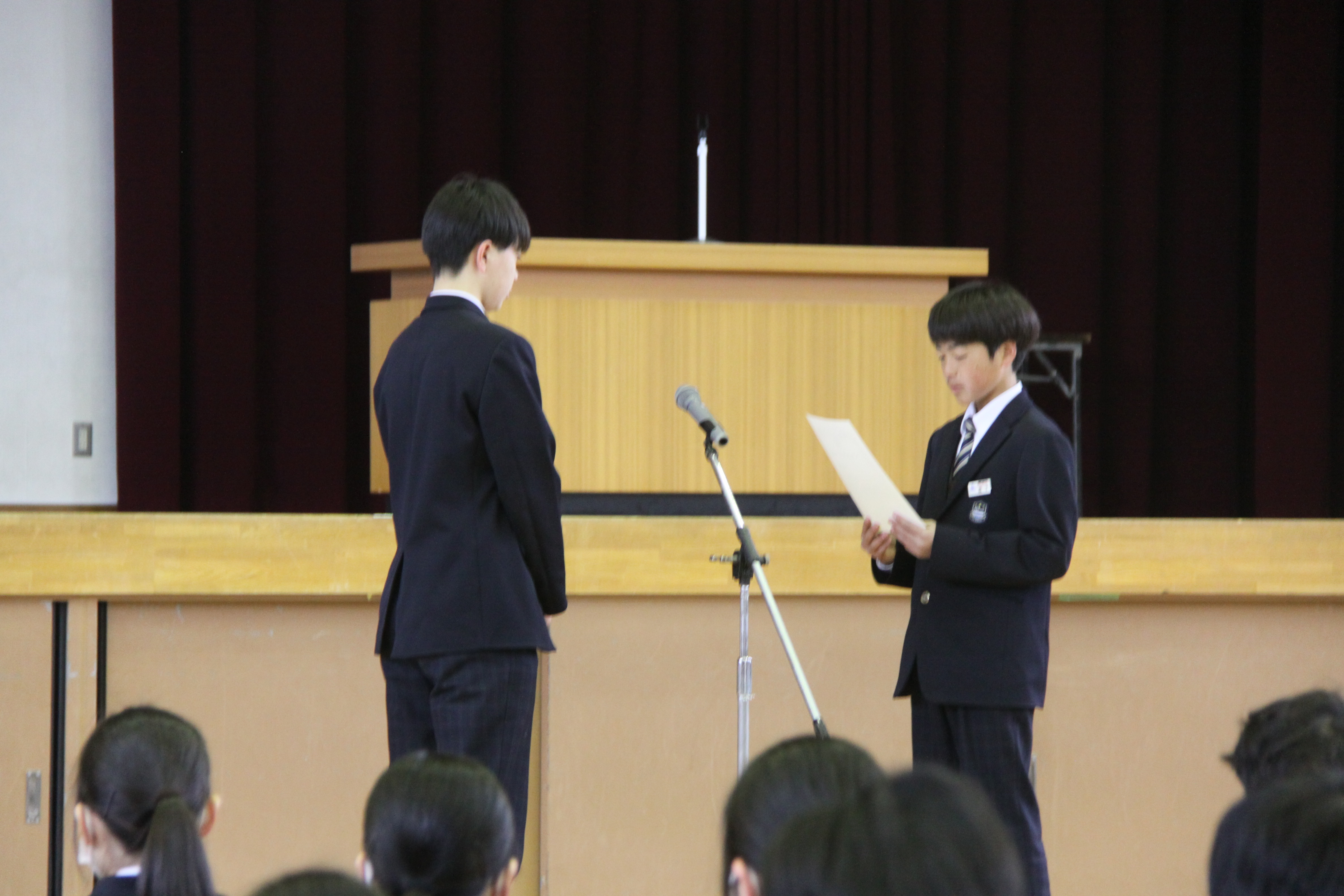




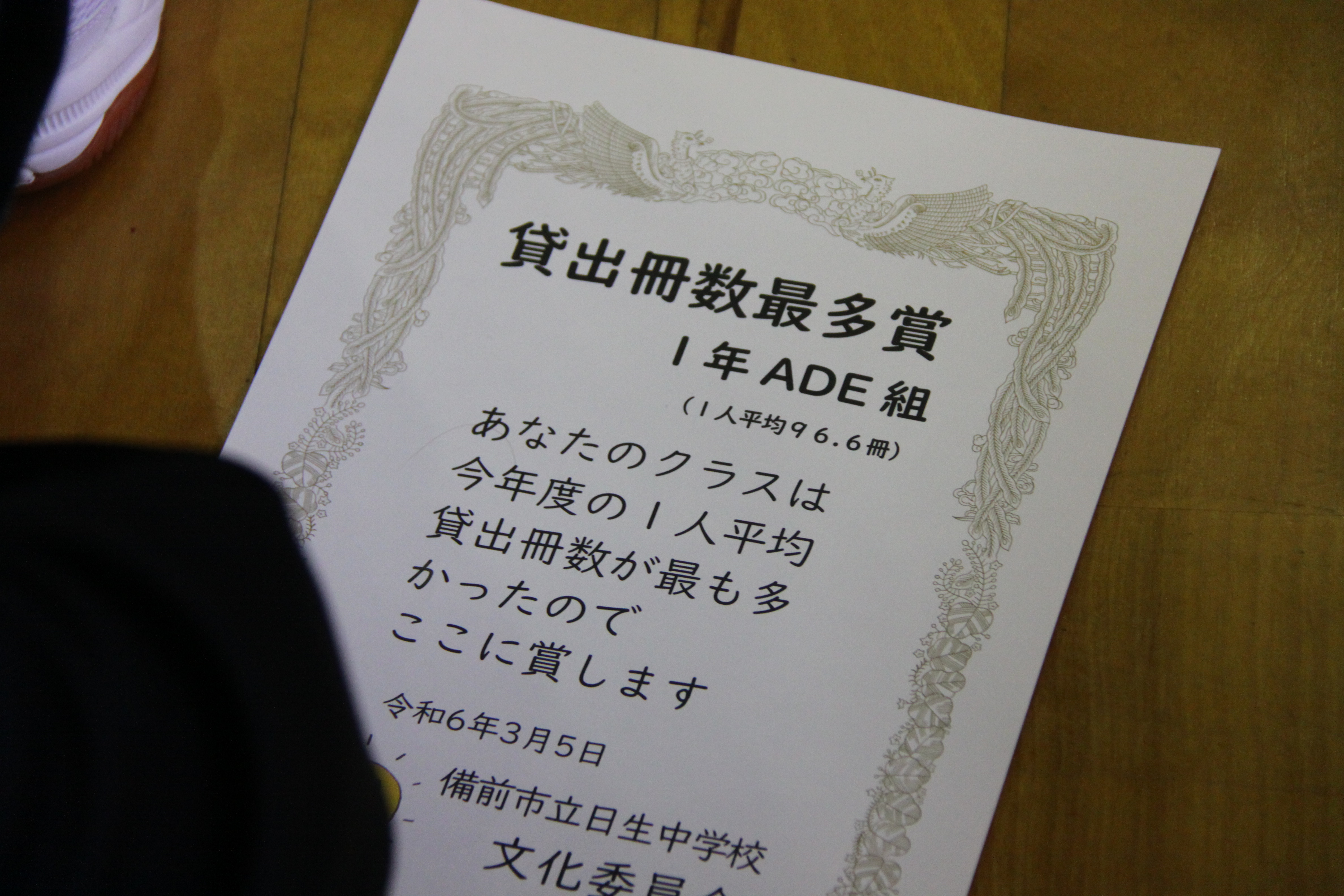
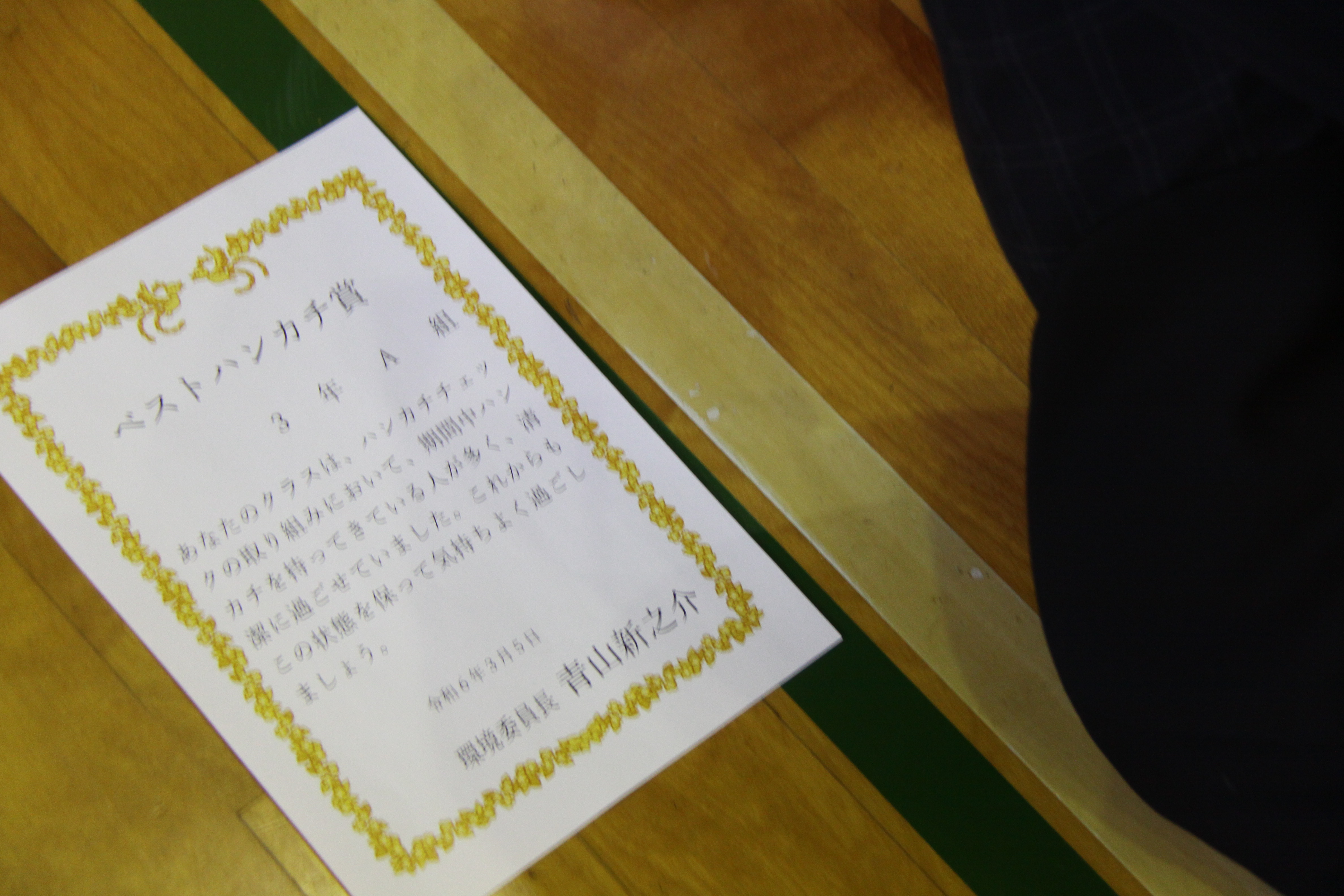
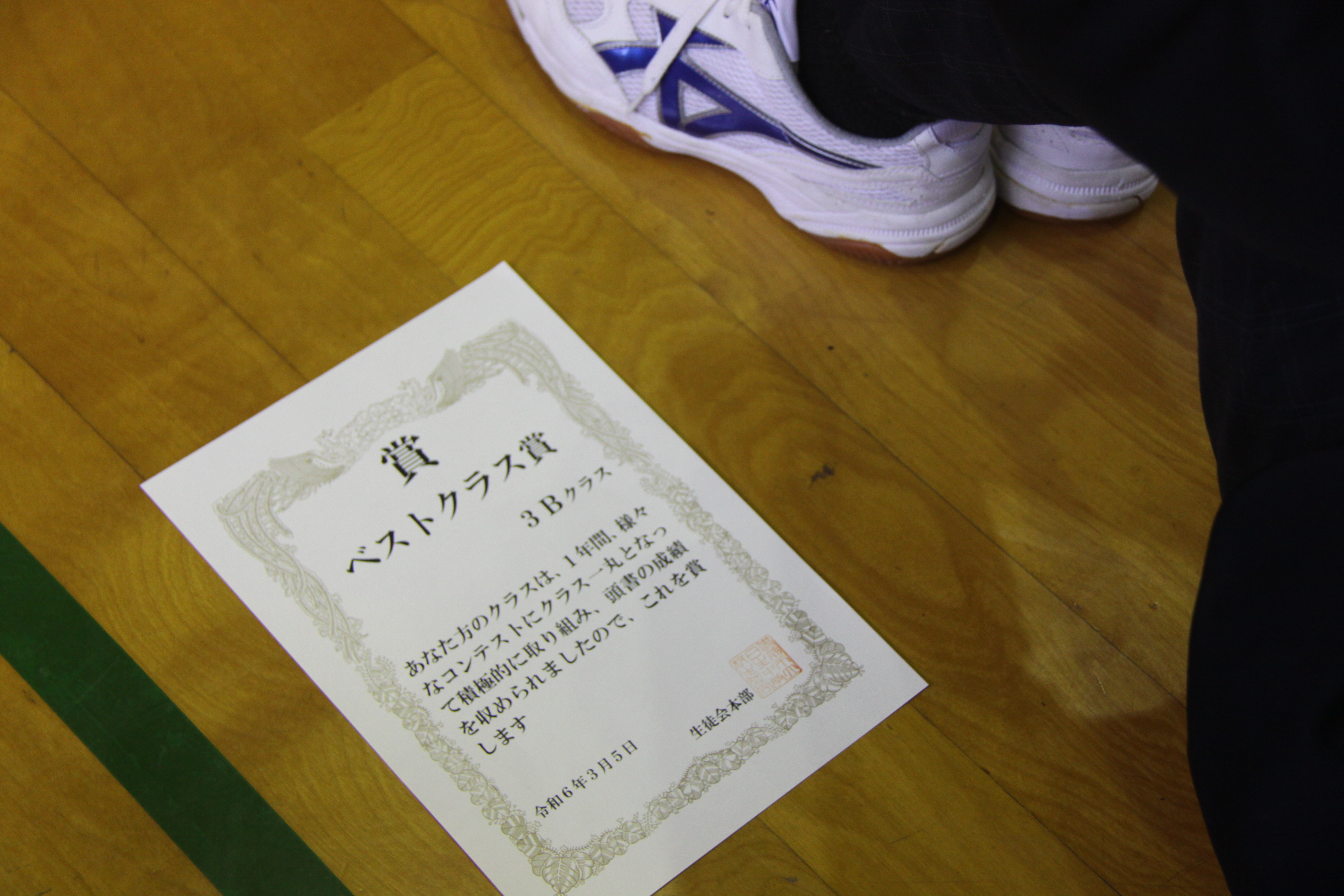




生徒会執行部はいつものように会の運営について振り返り
◎今日が明日につながるための。
PTA委員総会開催(3/4)
今年度の活動の振り返りを行い、新年度の取組について協議しました。子どもたちへの活動支援強化のための熱中症対策、生徒の地域ボランティア活動の推進のための保険加入サポート、能登半島地震への義援金協力、新しいPTA活動のありかたの検討など、積極的に活動案がだされました。新年度第1回PTA幹事会は4月17日(水)18時~、新役員さんによる第1回PTA委員総会は同日、18:30~図書室で開催予定です。また、学年役員・副会長選出についてのご協力をよろしくお願いします。PTA事務局


○この機会に、「日本PTA協議会」HPの文章を読んでみました。ご参考に紹介します。
PTAは『社会教育団体』です。
「社会教育」って聞き慣れない言葉かと思いますが、社会において行われる教育のことを言います。
学校で行われるのが「学校教育」、家庭で行われるのが「家庭教育」それと並んで、大切な教育が「社会教育」です。
子供は家庭・学校・地域を行ったり来たりしながら、生活し学び、成長します。
家庭のしつけが学校での学習に生き、学校で学んだ友人関係が地域に繋がります。
子供の成長は時と場所を選ばず継続しています。
またPTAは成人教育の場でもあります。
より良い保護者・先生であるためには、自ら学び研修に励む必要があります。より良い大人であることが、子供たちの健全教育のためには大切なことです。
PTAの幅広い活動を通して、私たちもともに学び、成長していけるそんな組織がPTAです。
PTAってなに?
どのようにできたのですか?
PTAは、昭和20年に当時の文部省が発表した「新日本建設の教育方針」から歴史が始まります。
その後、アメリカから派遣された教育の専門家による、戦後の日本の教育に関する基本的な方向性を示す、米国教育施設団報告書によってPTAの設立と普及を推奨する方針が掲げられ、文部省を通じて、全国的にPTAの指導、支援を行ったことから広まりました。
当時の文部省が作成したPTA結成手引書の中には、PTAの趣旨として、「子供たちが正しく健やかに育っていくには、家庭と学校と社会とが、その教育の責任を分けあい、力を合わせて子供たちの幸せのために努力していくことが大切である」と謳われています。
家庭教育の充実を図り、学校・地域と連携して子供たちのために活動する団体として全国に広まりました。
こうして始まったPTAはさらに、社会の宝である子供たちのために、地域ごとや都道府県単位の協議会が組織されるようになり、全国組織の必要性から日本PTAがつくられました。
はじめてみませんか?
はじめてPTAの話を聞くのは、小学校の入学説明会に参加した時だと思います。
いきなりPTA本部の方に、学年委員をやりませんか?と言われても困ってしまいますよね。
「そもそもPTAって何だろう?」と思うのもこの時かもしれませんね。
簡単に言ってしまいますと、自分の子供のために何かできる事はないかな。と思う保護者と先生の集まりです。
さらに、近所の子供たちのためになるのだったら、忙しいけど、少し協力してみようかと思う気持ちだと思います。
難しく考えないで気軽に参加してみてください。
今の学校に関する人は、先生、保護者の他に地域の人たちがいます。
自治会長さんや民生委員、学校ボランティアの方、地域によって呼び方は違いますが多くの方が子供たちのために協力をしていただいています。
子供たちにとっても、先生や保護者以外の大人と接する良い機会だと思います。
できることから少しずつ参加してみましょう。
どんなことをするの?
PTAの活動は、それぞれの学校によって色々あります。
それぞれのPTAが歩んできた歴史によるところが大きいかと思います。
例えば、バザー、廃品回収、書き損じはがきの回収、模擬店、ベルマーク集め等の活動をしているPTAは多いのではないでしょうか。
それぞれに所属する保護者が学校に集まり打ち合わせしたり、様々な場所で活動します。
多くの保護者に参加してもらいたいところですが、核家族化、共働き、ひとり親世代など家族のあり方の変化に伴いPTA活動も多様化し、それぞれの保護者ができる事を少しずつ持ち寄り活動するように変わりつつあります。
PTA活動の中には研修会への参加や会議の進行のやり方などを学ぶ機会があります。
自分自身が成長し、生活環境、教育環境の改善などにヒントを得られますし、学びの支援を考えるきっかけにもなります。
なぜ必要なの?
あなたは大切なお子さんを誰の手も借りず、安全な登下校をさせ、豊かな教育環境を育み、健全な成長をさせることができるでしょうか。
子育てには様々な悩みがあり、保護者だけでは解決できないことがいろいろありますよね。
子供たちの健全育成のため、子育ての当事者同士が連帯し、先生方とも子供たちを取り巻く状況・情報の共有をしながら学び合える場が必要となり誕生したPTA。
その活動は一人の百歩より百人の一歩でできることを皆で分担してすれば各負担も軽減されます。
また、連絡や活動をするにも何がしかの費用がかかりますが、会費という形で費用分担することで活動の進展ができます。
子供たちの健やかな成長を願って、多くの保護者と先生方が連携・協働し、互いに学び合いながらPTAの活動をする姿は、子供たちにとって大きな安心感を与えると共に、健やかな成長に大きく寄与することでしょう。
分担しながら・得意なことを・効率的に
運営は学校PTAによって様々ではありますが、会員の中から選出された役員が中心となります。
活動や行事毎に担当を決めて分担しながら行うことが一般的です。
それぞれが得意な分野などを担当しながら協力をして運営を行います。
PTAの組織は会長を先頭に、副会長、会計、庶務などいわゆる本部役員と会報(広報)や校外指導(登下校)、家庭教育などを担当する専門部の役員にて構成されることが多いです。
事業や行事を担当する専門部や委員会を設けて、効率的に運営できるよう工夫されています。
また、PTA活動の予算は会員から集めた会費によって運営されています。
年度毎に事業計画と予算を作成し、計画に合わせながら、会を運営し年度末に決算を行います。
子供の成長が見られる 友だちができる 学校がよくわかる
まず、PTAの行事に参加することで学校に行く機会が増え、学校のことがわかりだします。
先生の名前や学校の環境を知ることで、子供の学校での様子が子供の話の中だけでなく、実際によく分かります。
また、同じ年代の子供をもつ保護者と話す機会が増え、子育ての悩みや喜びを話すこともできます。
同じ学校や地域に、子育ての友達が増えることが、子育てにとても心強いです。
PTAの参加は、先生方のお手伝いにもつながります。
子供にとっても、多くの大人たちが近くで見守って応援しているという環境は、とても安心することです。
◎私たちのはじまりの風景7
~ここはどこでしょう?(3/2)









鶴島フィールドワークへ、日生、東備地域の先生方と一緒に教頭先生も行ってきました。この島は浦上四番崩れで大弾圧を受け捕らえられた3400人のうち117人が流刑され開拓を強制されながら改宗を迫られ、禁教が解かれるまでの三年半の間に、死者18名、改宗者55名を出す過酷な仕打ちを受けた地です。その後、私有地となり、ご家族がいなくなってから長い間、無人島となっていたため、日生港から、釣船に乗せていただき、島に着くことができました。伸び放題の木々の間を案内していただき、井戸の跡や石碑を見て、その後、18人の方のお墓と慰霊碑、そして真っ白なマリア像がある島の南側の丘陵地へたどり着きました。また、高台の上には改宗を迫った祠、そこに続く長い石段(強制労働で作らさられたものでしょう)を歩いて桟橋へ帰り、岐路につきました。舟橋さん、田原さん、中磯さん、雪のちらつく寒い中、ご案内を本当にありがとうございました。
〈補足説明〉日生諸島(岡山県備前市)の鶴(つる)島にキリシタン遺跡
明冶政府の外来思想排斥政策は、多くのキリスト教信者を心身ともに苦しめました。岡山城下から約50km離れた無人島「鶴島」に送られたキリシタンたち(長崎県浦上キリシタン教徒117名)は、自由な身になるまでの3ヶ年半をこの島で過ごしましましたが、すしづめ状態の長屋、土地の開墾、説教聴問などに耐えかね、改宗せざるえない人もいたといいます。この島は、草地で開墾するには適しており、大豆、麦、さつま芋などが作られていましたが、それらの作物を口にすることは許されていませんでした。この島で亡くなった18名のキリシタンたちは、島の南東の丘斜面に葬られています。
また、この島には、浦上の「四番崩れ」で、長崎から流された岩永マキさんがいました。彼女は、浦上に帰ったあと、神父をたすけ、看護婦、孤児院、十字会など社会奉仕の中心人物となりました。
1969年、岡山市のカトリック教徒により、殉教百年祭が盛大に行われ、殉教者碑・十字架などの建立とともに、めい福が祈られ、「殉教の島」となっています。
◎はたらくこと、生きること、学ぶこと
山陽新聞の就職に関する記事を掲示し、進路・キャリア学習の一助としています。
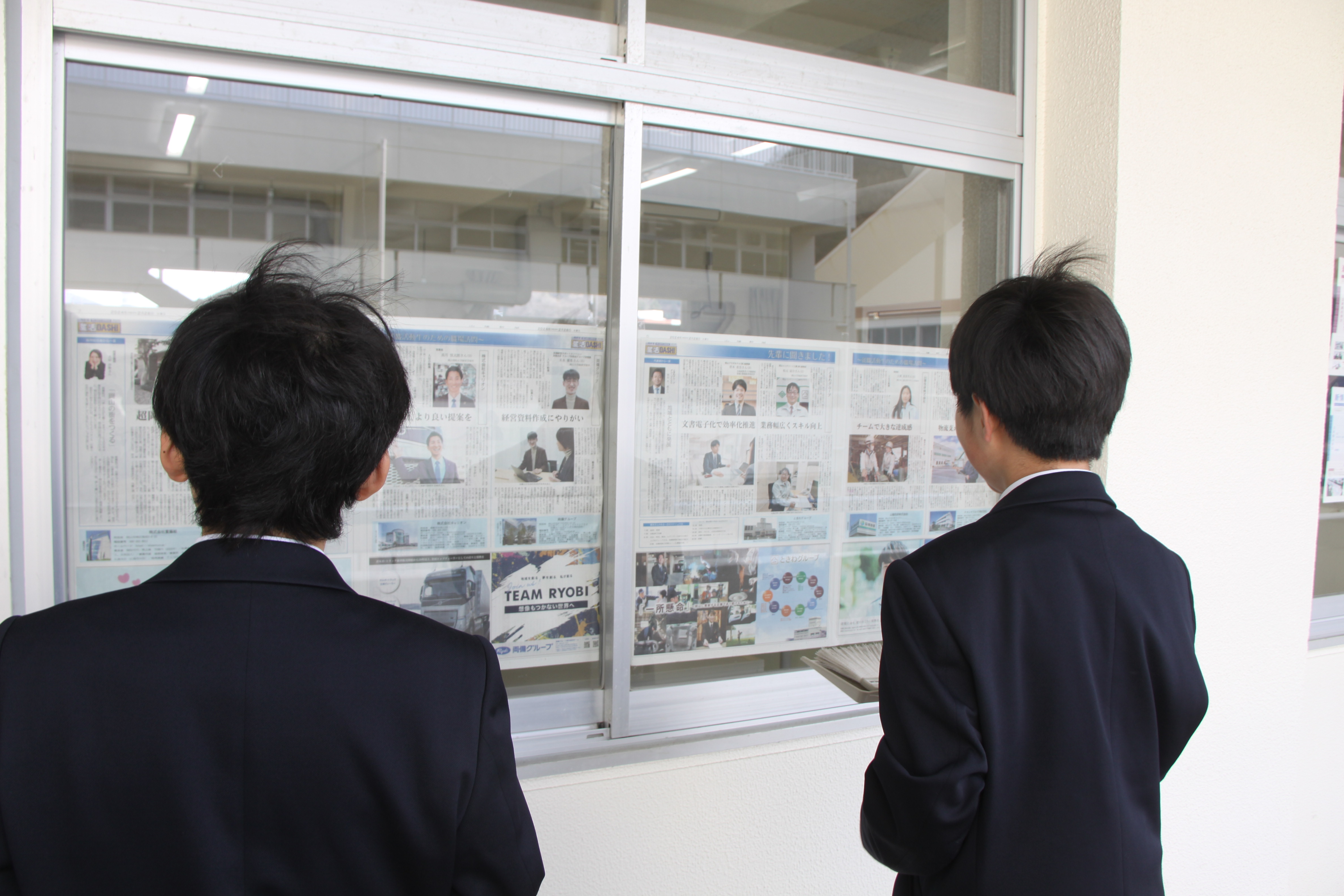
◎ひな中の風✨~たくさんの方々と共に(~3/1)
「日生中学校の生徒さんがハンセン病問題について詳しく調べて展示することにより、問題を理解することができた。今後もこのような取組をおこなってほしいです。」
「中学生がハンセン病問題を学ぶことは大切だと思います。ぜひ、これからも差別をなくす主体者として行動してほしいと思います。観させてもらって、元気になりました。ありがとう」
(ハンセン病問題学習パネル展示・日生地域公民館・備前市役所展示でのアンケートより)
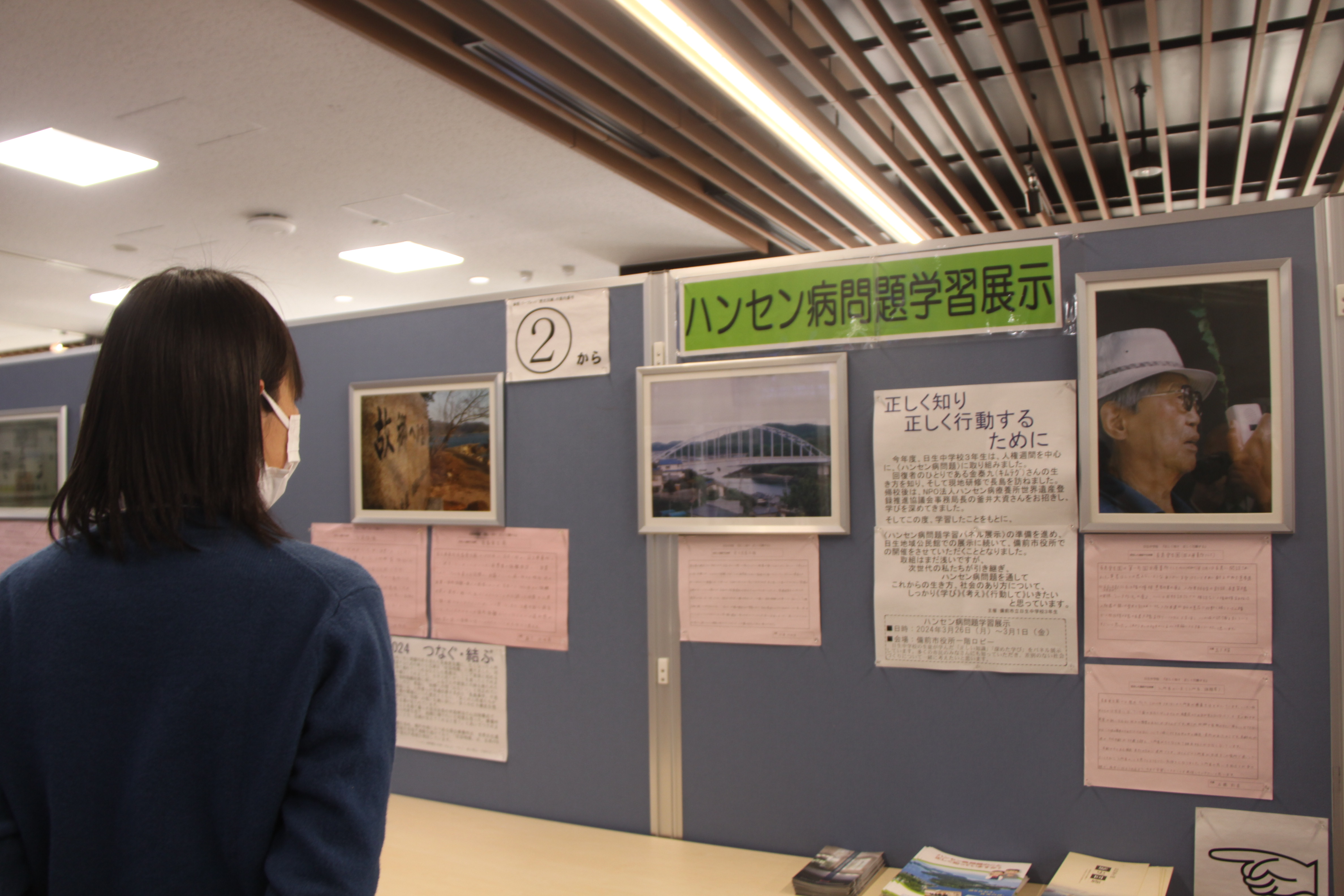
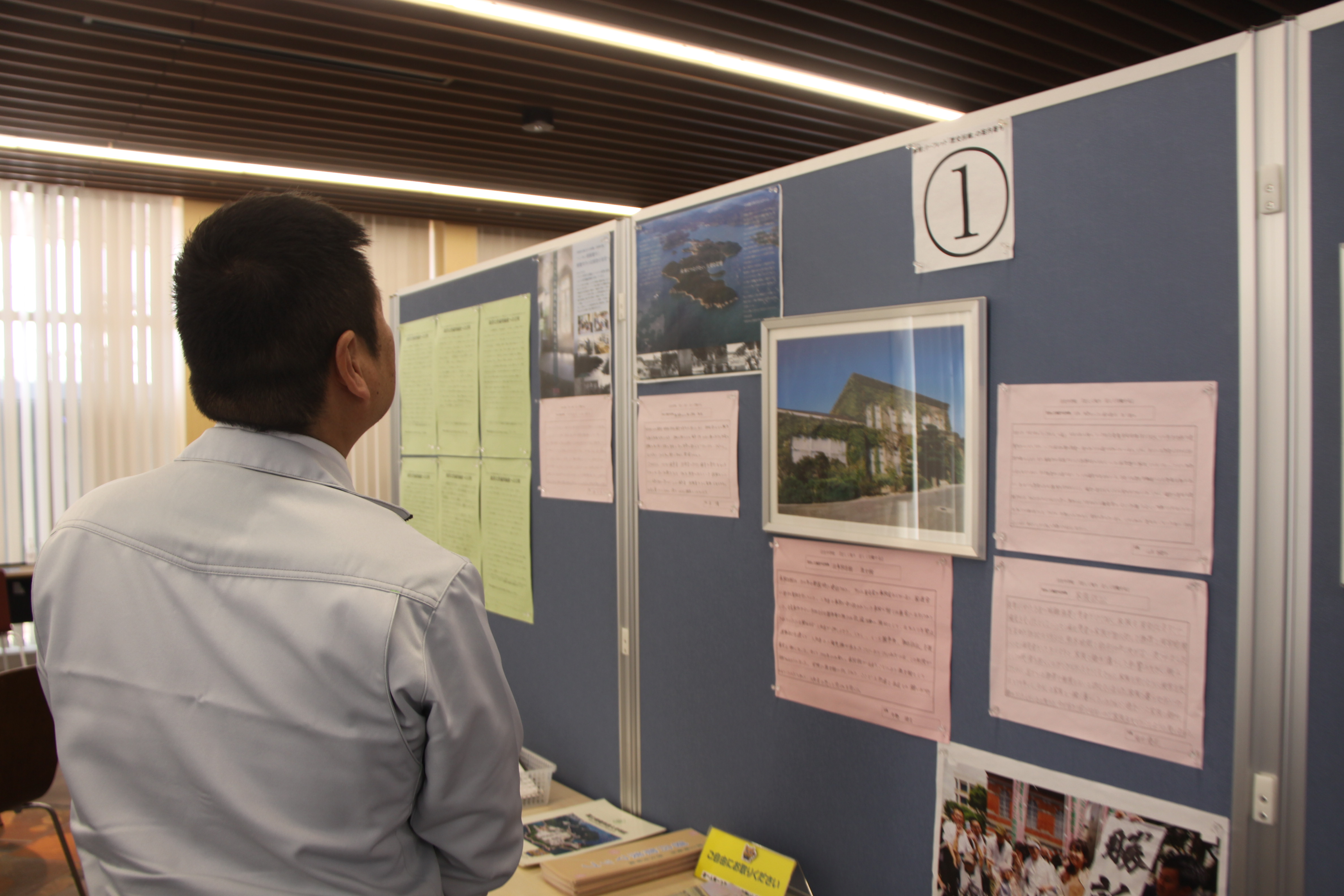
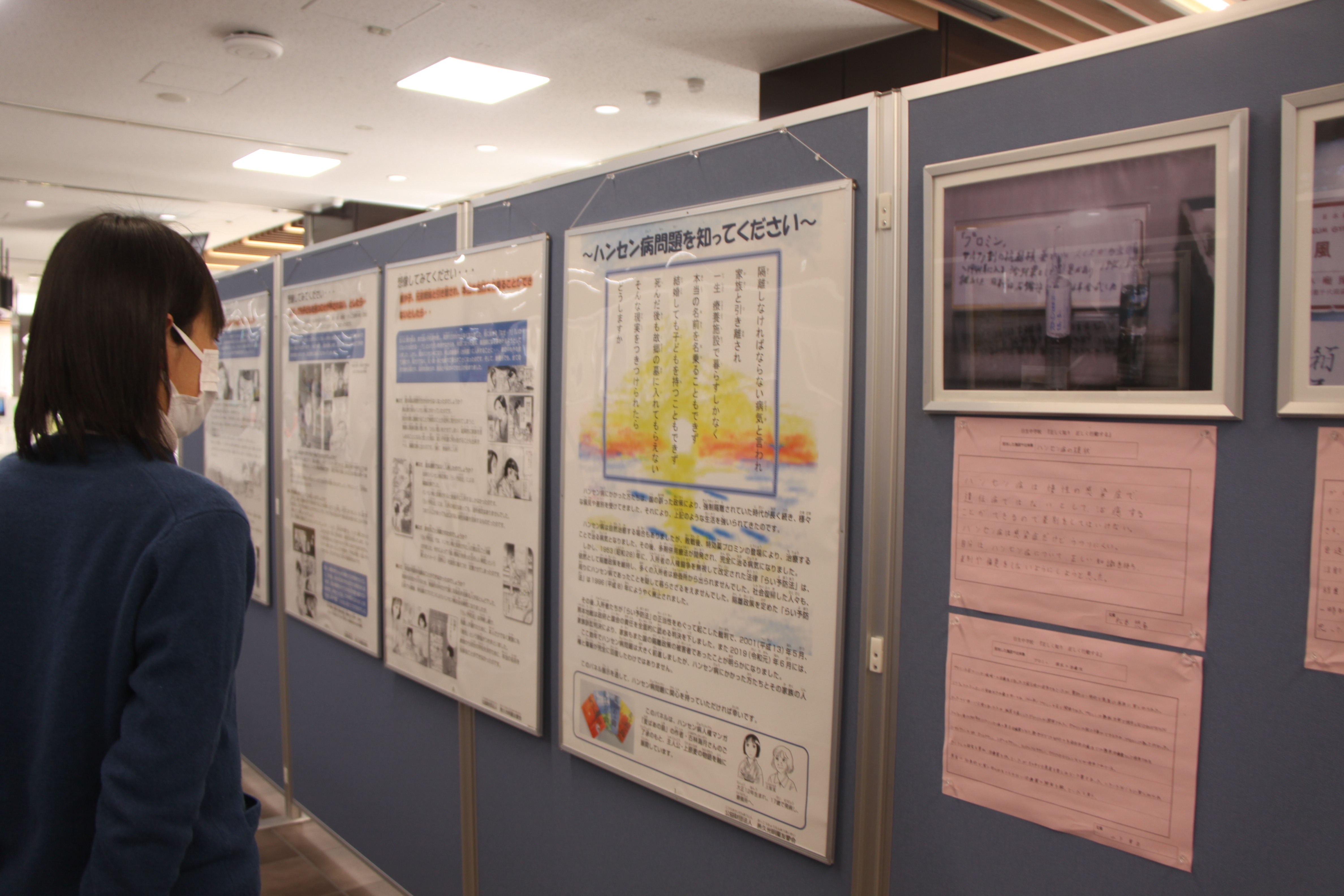
◎流れる季節のまん中で(3/1)


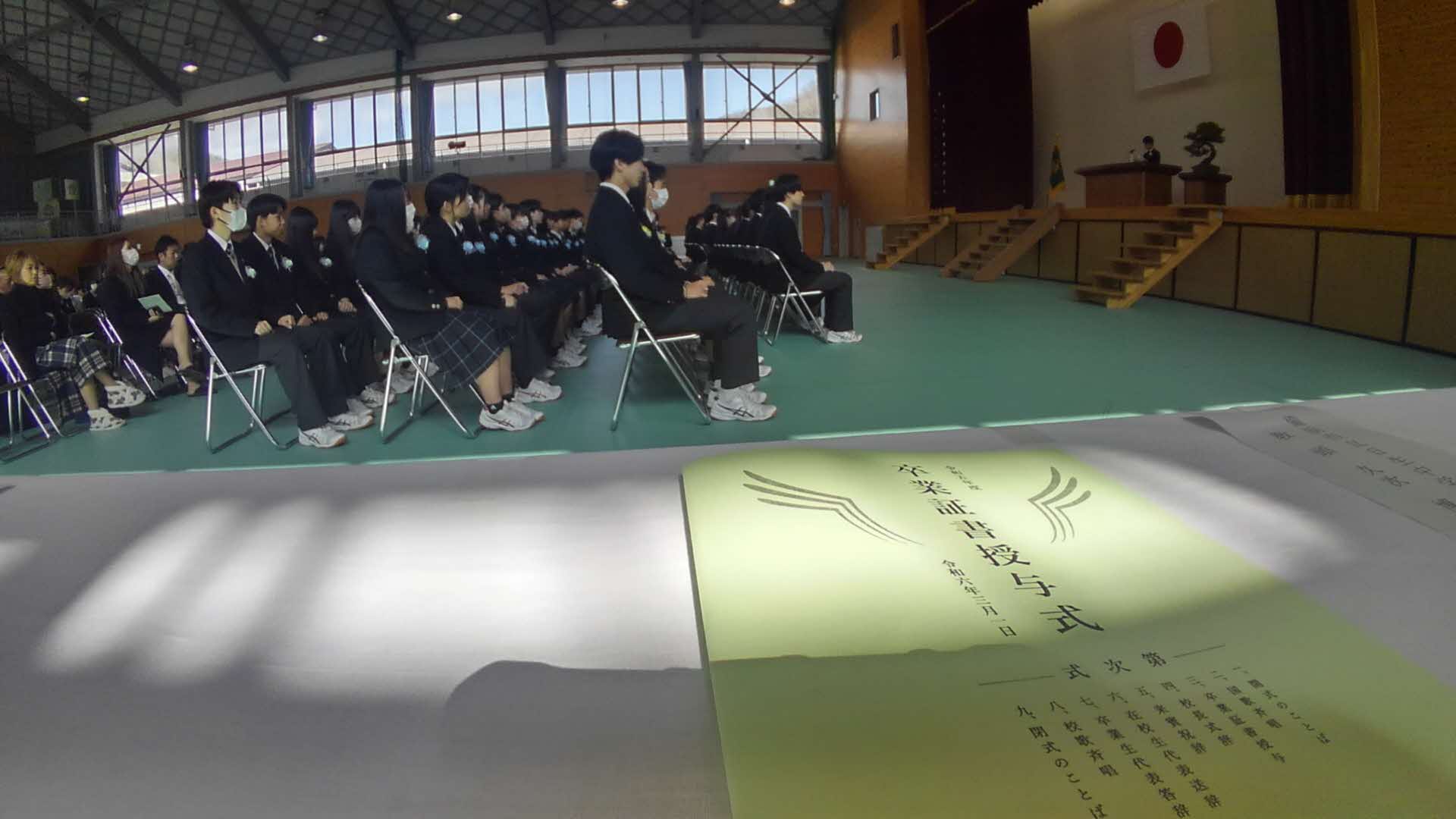
岡山県内の公立高57校で今日、卒業式が行われました。約9800人が恩師や友人との別れを惜しみつつ、将来への希望を胸に学び舎を旅立ちました。教頭先生が参列した備前緑陽高校は、新型コロナウイルス禍で見合わせていた全校生徒が集う4年ぶりの式となりました。在校生、保護者・来賓が見守る中、115人が臨みました。校長が生徒代表に卒業証書を手渡し、孔子の言葉を紹介してはなむけの言葉を贈られました。卒業生代表答辞では「家族や先生に感謝し、これからも「挑戦」していく」と答辞を述べました。県内公立高全64校では今春、約1万700人が卒業します。高校卒業式は4日まで行われます。
◎ともに(2/29)
先日の代議員会での決議を受けて、備前市PTA連合会(本年度日生中が事務局)は、「能登半島地震」への義援金を送付させていただきました。
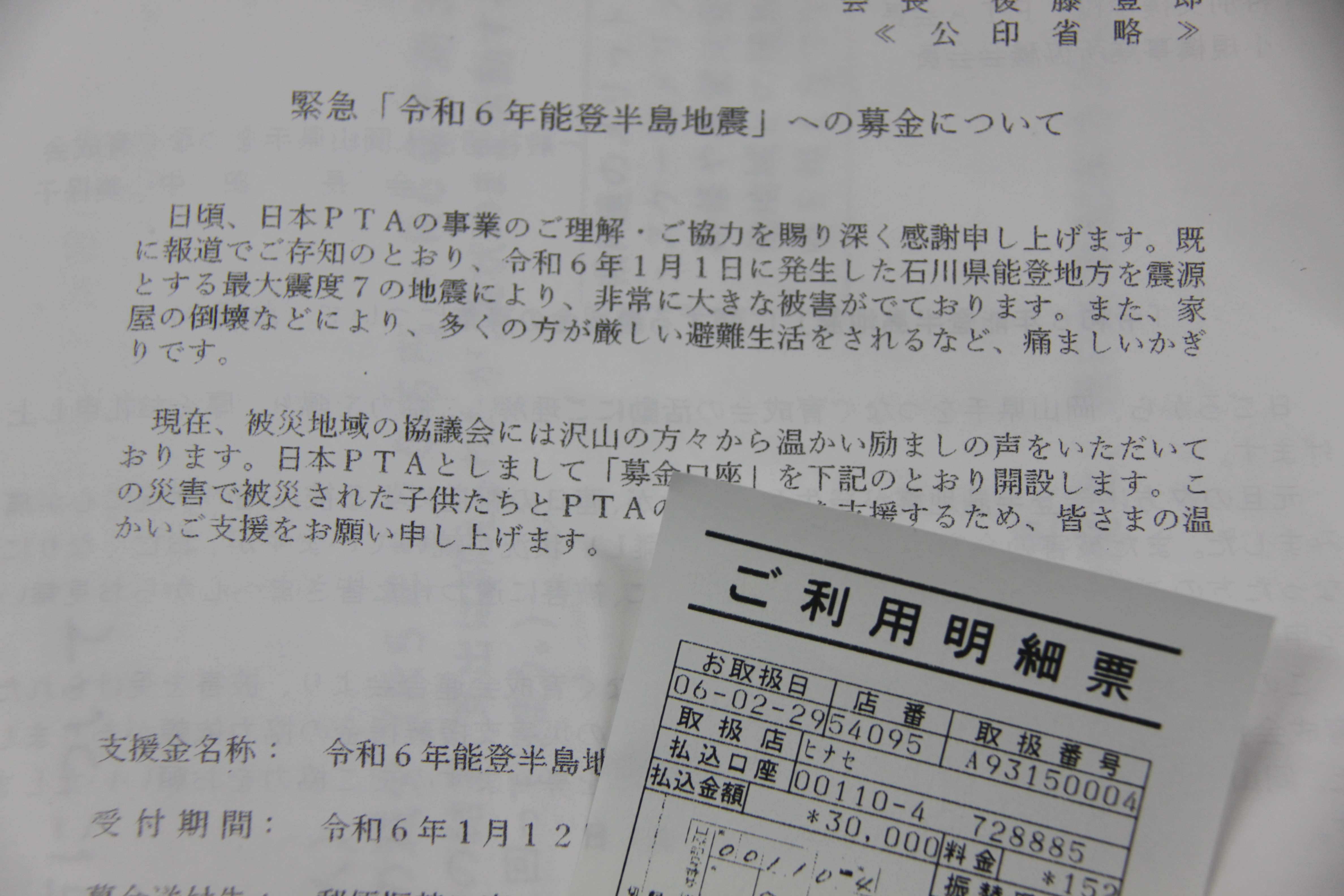
◎到達度確認テスト一日目(2/29)
ただそこに 言葉も無しに 月は居て 見上げる者に 全てをくれ
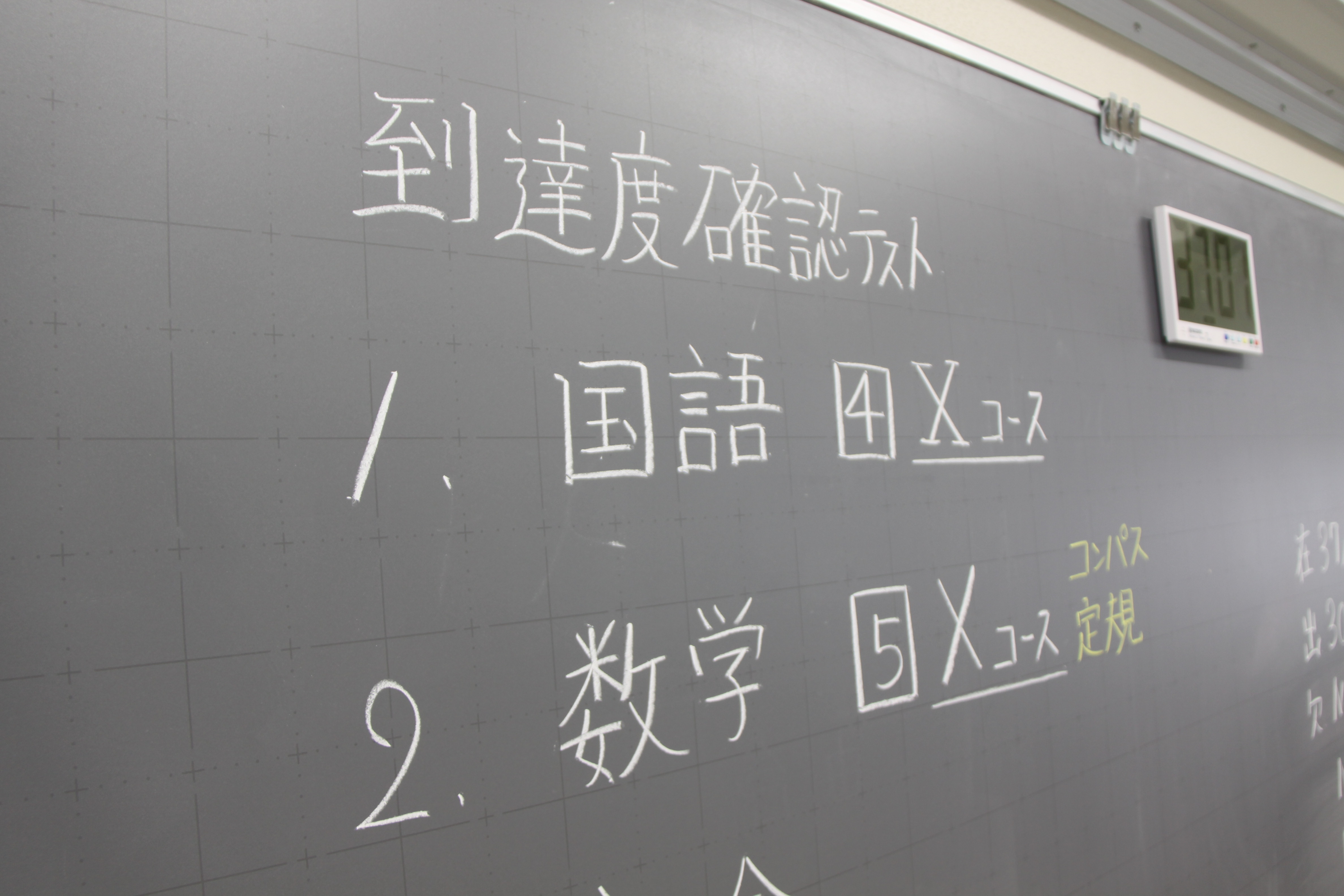
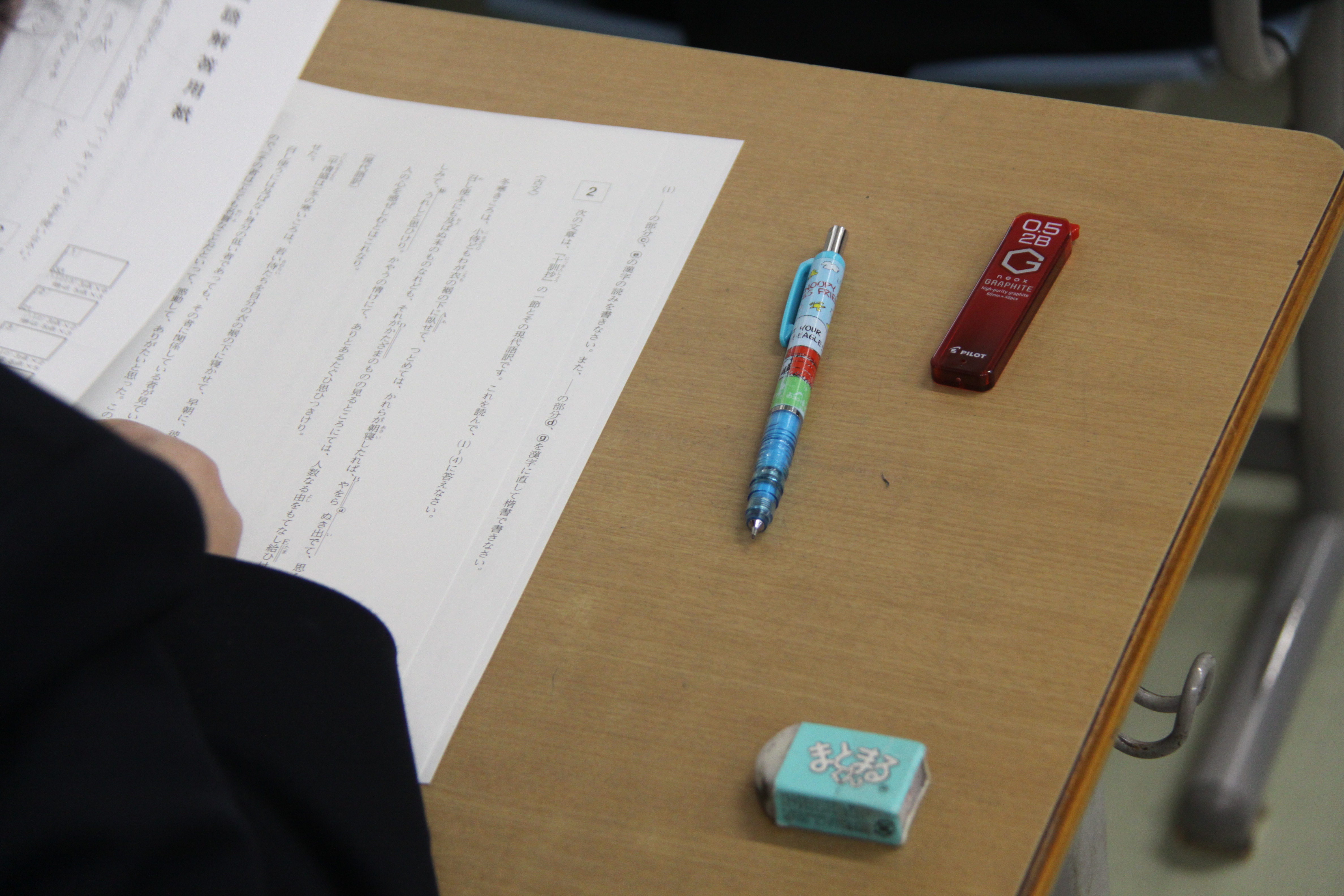
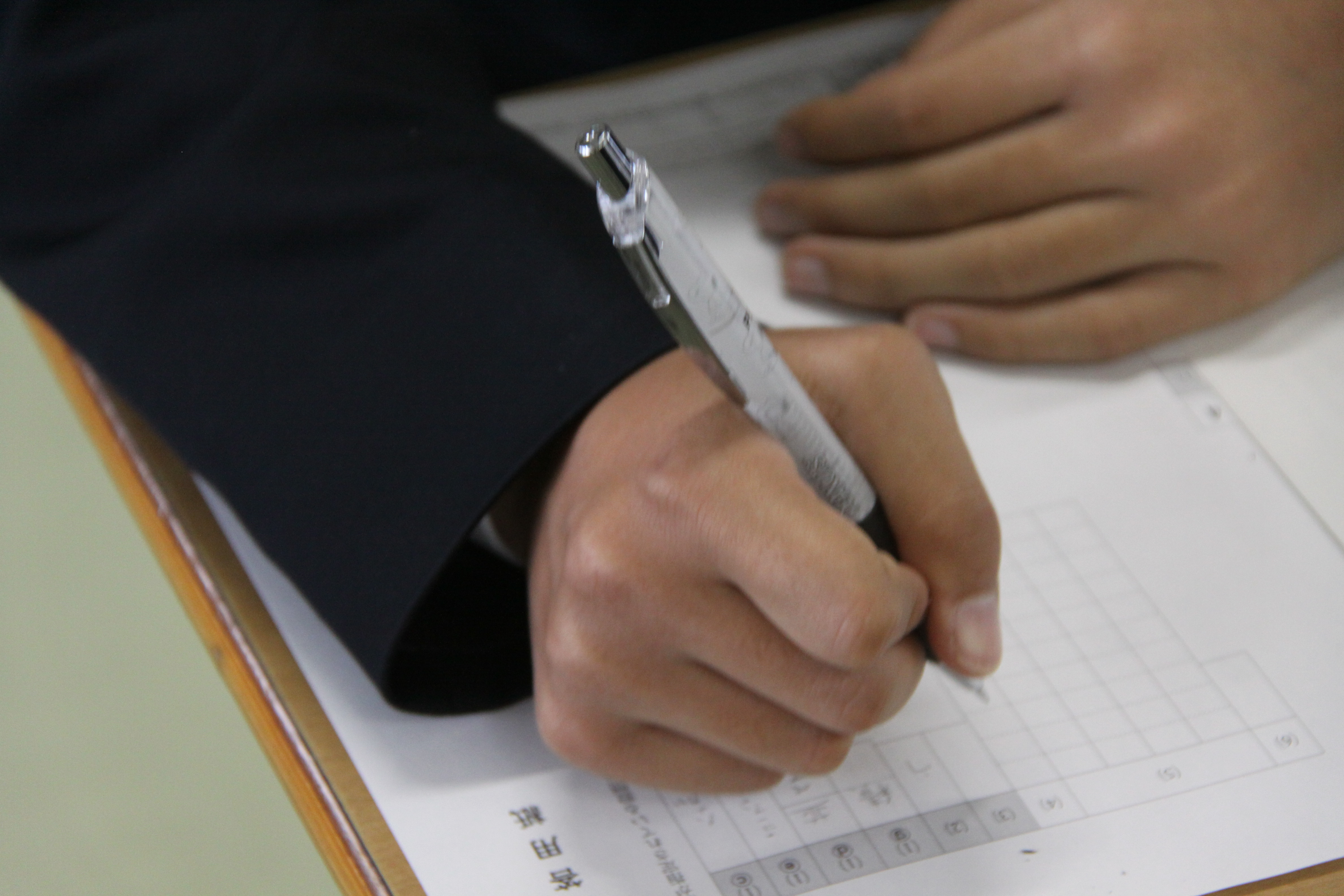
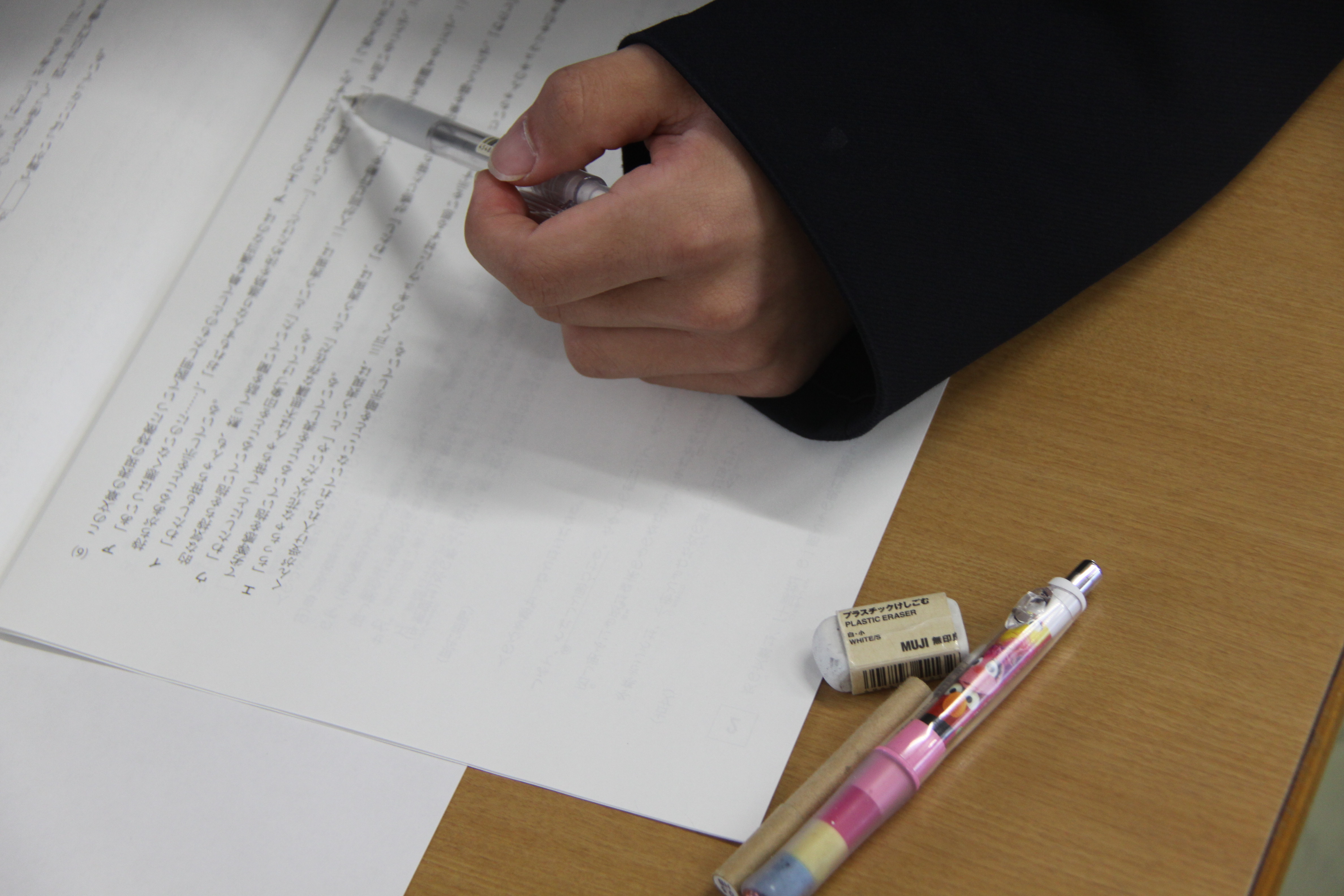

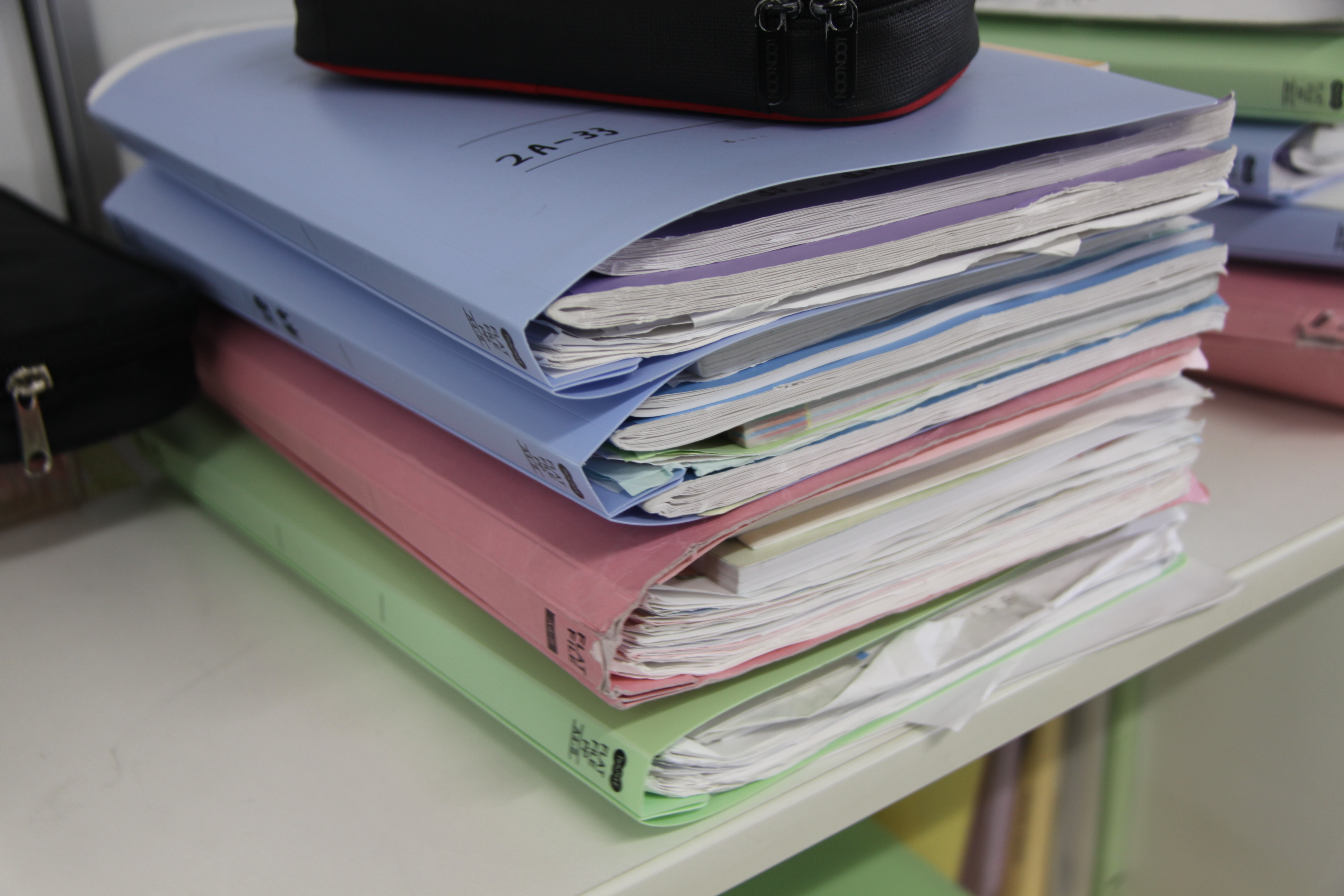

◎学年PTAあいさつ運動(2/29)


「なぜ、あいさつは大切?」すぐに答えられる人って少ないかもしれません。じっくりと考えたら、「相手の存在を認め、相手に対して心を開くこと」のようなこたえにたどり着くと思います。そうだと考えるなら、挨拶のできない組織は、「その組織の中の一人ひとりが、同じ組織のみんなに心を開いていない。」ということです。挨拶のできる組織なら、誰に対しても心を開いています。心を開いて人の話を聞くことができれば、「あ、なるほどそうか!それなら、ちゃんとやってみよう!」と思うことができます。心を閉じて人の話を聞いても「そんなこと言ったって、うまくいかないでしょ。」と思う人は、なかなか成長できません。それに、人に対して心を開けない人は、人からも心を開いてもらえません。逆に、いつも気持ちの良いあいさつをして、心を開ける人は、他の人も心を開いてくれます。心を開いてくれる友達に対しては、「何とかしてやりたい」という気持ちになります。心を開いてくれない友達に対しては「これ以上言っても無駄なのかも」と思ってしまうはずです。とても悲しいことです。自分が心を開かなければ、周りの人も心を開いてくれません。だから、大切なのは「あいさつは自分からする」ということです。周りの人が、心を開いてくれなかったら、自分が心を開いていないということ。周りの人が親切にしてくれなかったら、それは自分が周りの人に親切にしていないということ。周りの人が、あいさつをしてくれなかったら、自分が周りにあいさつをしていないというだけのこと。何でも「自分から」というのは勇気が必要です。しかし、その勇気がとっても大切です。あいさつとは「人が人として生きていくうえで、最も大切な流儀」なのです。あいさつの心を知り、「本物のあいさつ」ができる大人になっていってほしいと思います。
◎ひな中の風✨
明日はうるう年(2月29日)
2月は28日までですが、4年に一度だけ「29日」まである日があります。その「29日」まである年のことを閏年(うるうどし)または(じゅねん)というそうです。2024年の明日は、うるう年(2月29日まである年)です!
○なぜ、うるう年があるの?
地球は、太陽の周りを365日かけてまわっています(365日=1年)。でも、4年の間に、1日分だけズレが起こってしまうんだって。そのために、4年に1度、2月の日数を1日多くして29日にしたのだそう。
○うるう日が誕生日の人はどうするの?うるう年に誕生日を迎える人は、その前の日か、次の日にお誕生日を祝うことが多いのだそうです。うるう年でなく29日がない年でも、みんなと同じように一つずつ年を重ねています。
○何年がうるう年?・・・2024年、2028年、2032年、2036年、2040年…と、うるう年は4年ごとにおとずれます。
○太陽がプレゼントしてくれた一日。うるう年は、一年が一日だけ多くなります。4年に一度しかない日、太陽がプレゼントしてくれた日、どう楽しみます?

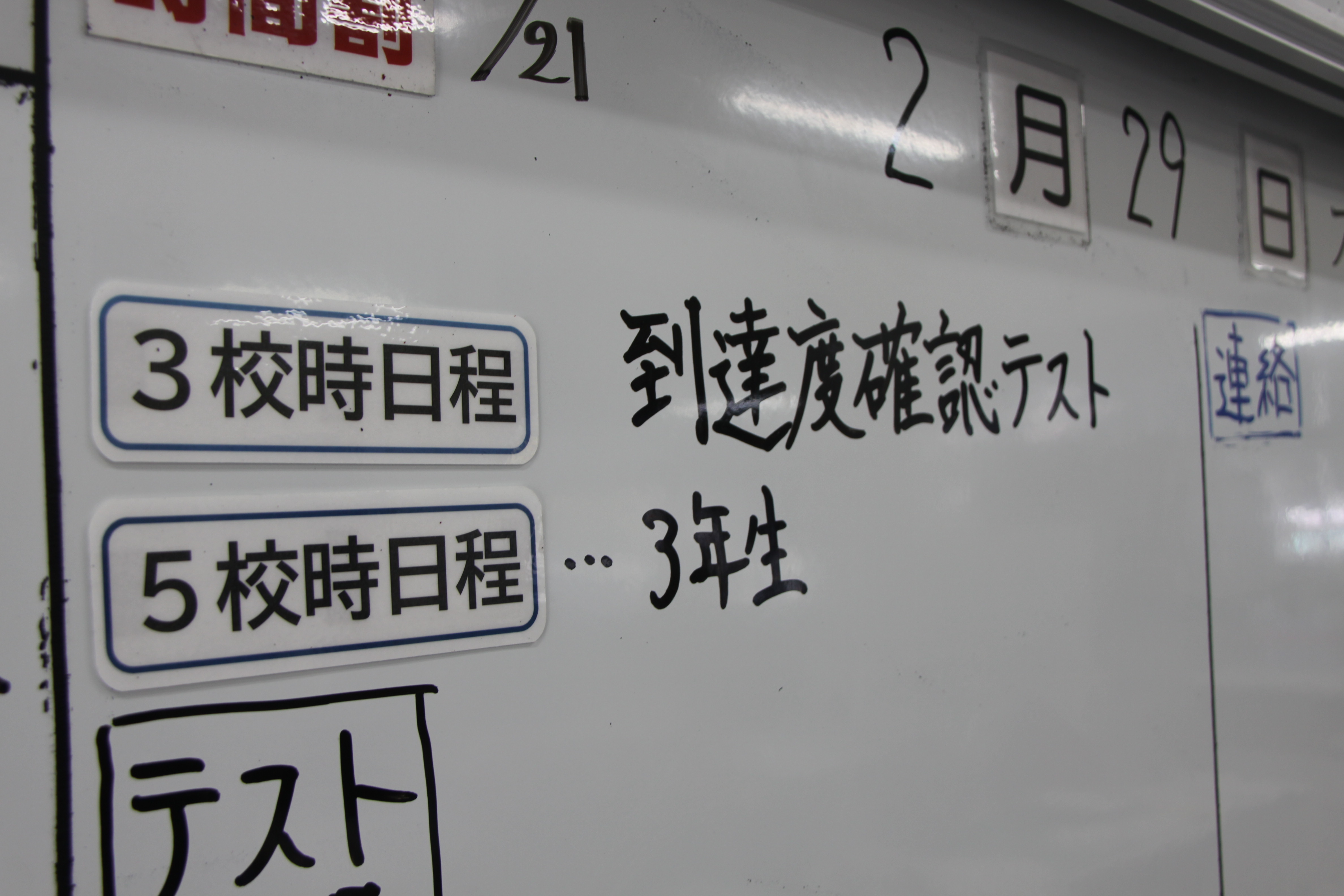


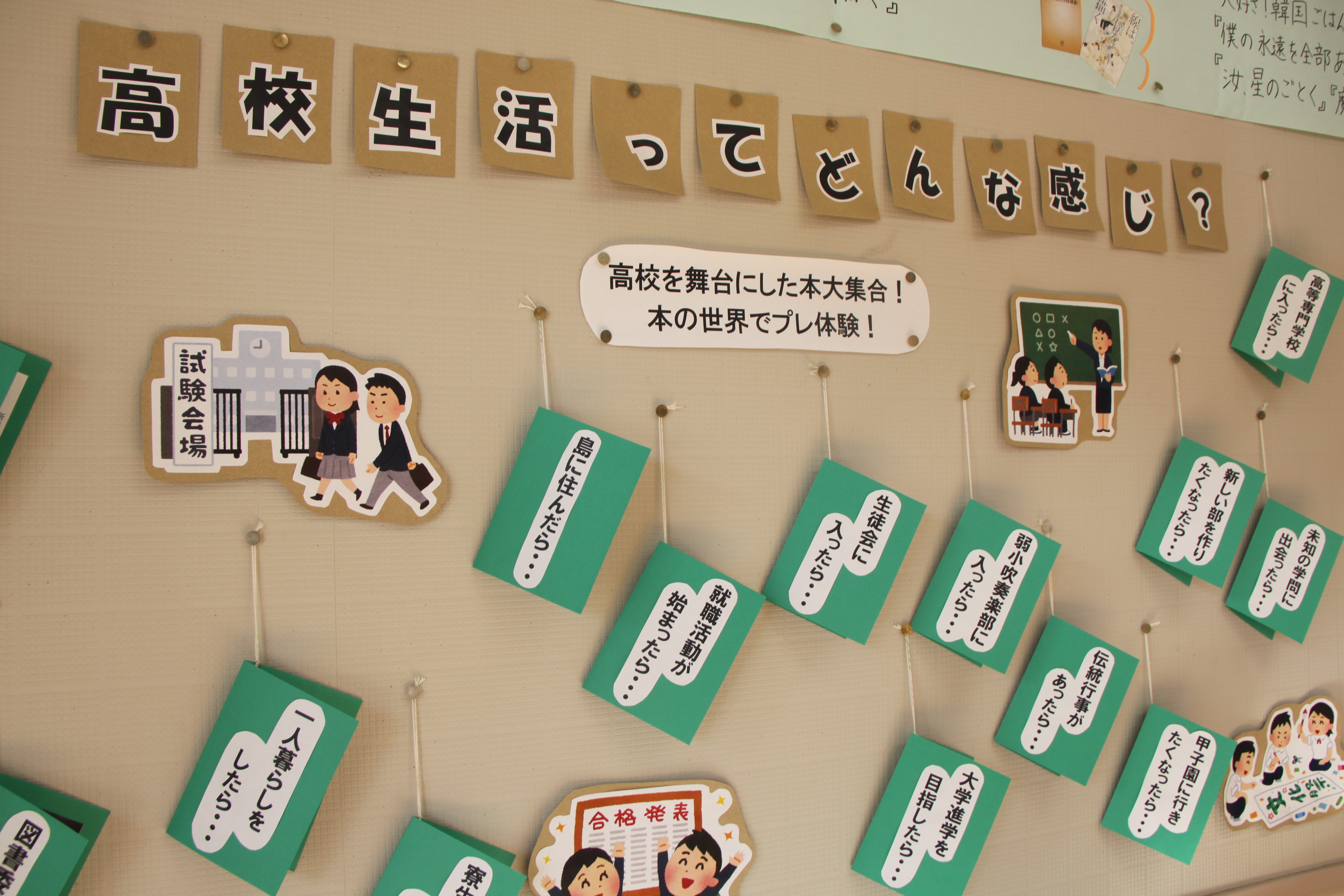

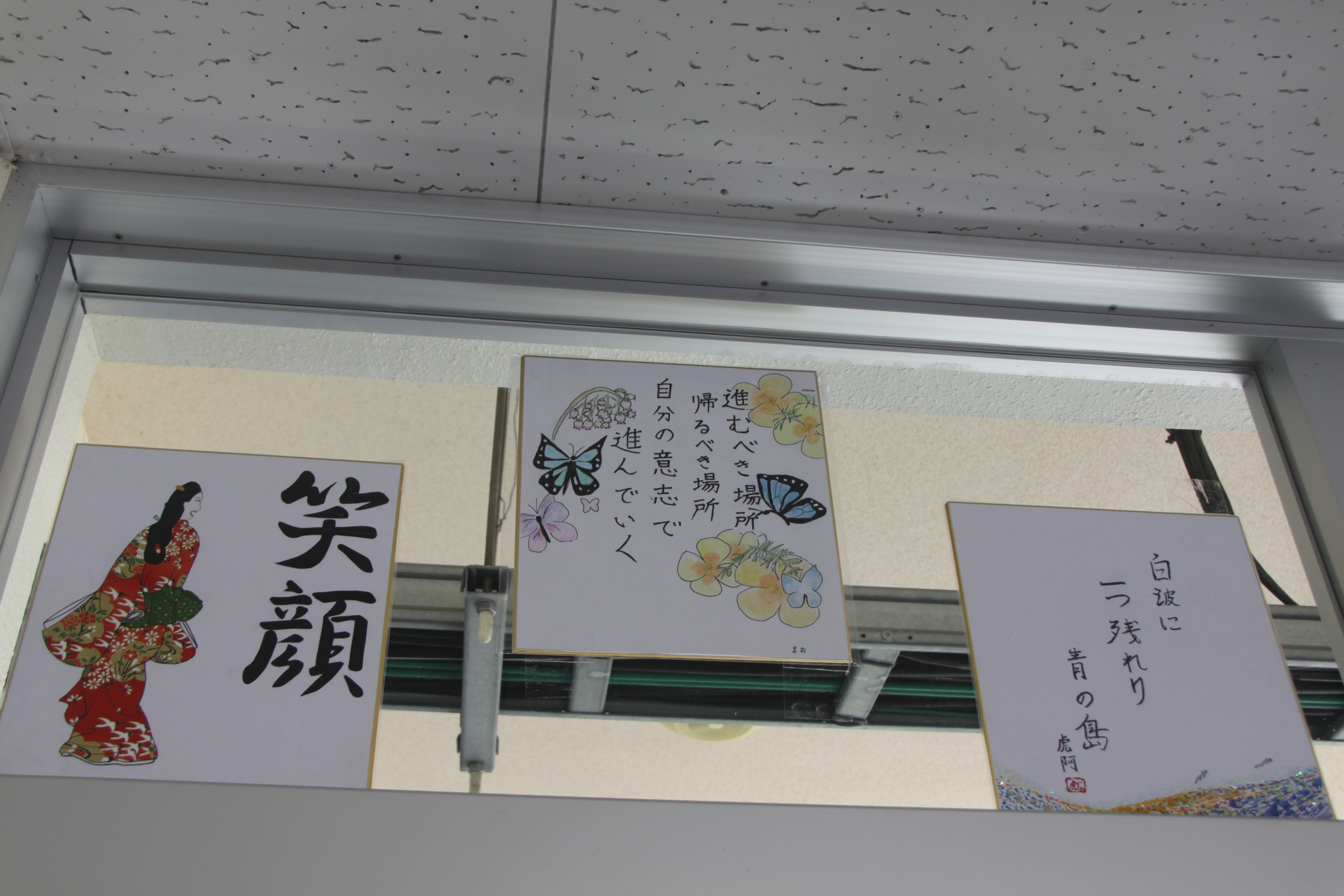


◎多くの人に支えられて
~栄養委員の朝食を食べよう大作戦(2/27~28)
備前市栄養委員さんと保健課管理栄養士さんらが来校され、給食時間中に「朝食の大切さ」についてお話をしていただきました。ありがとうございました。27日は3年生各クラスを回り、28日日は1.2年生、E・Dクラスでお話を聴きました。



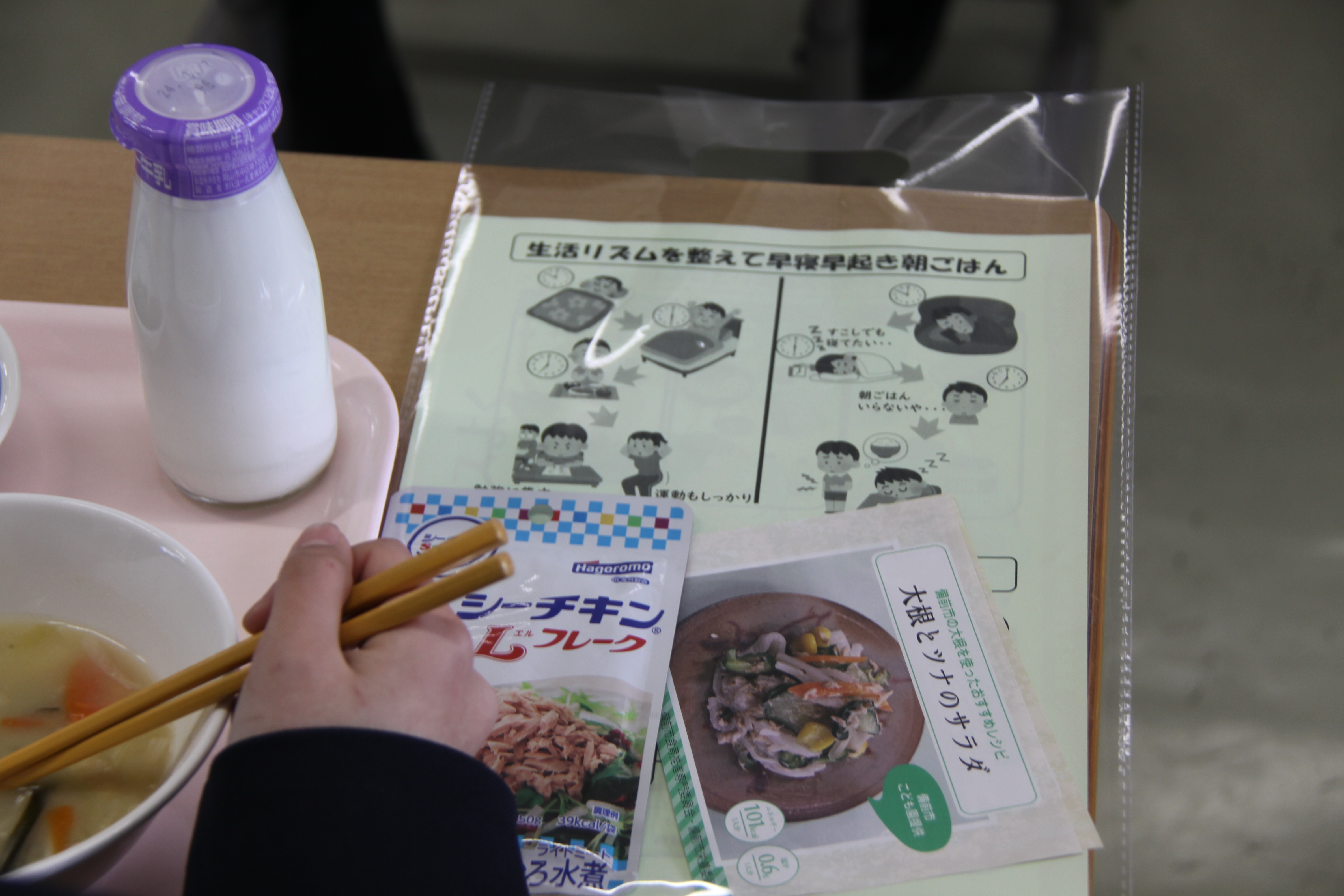
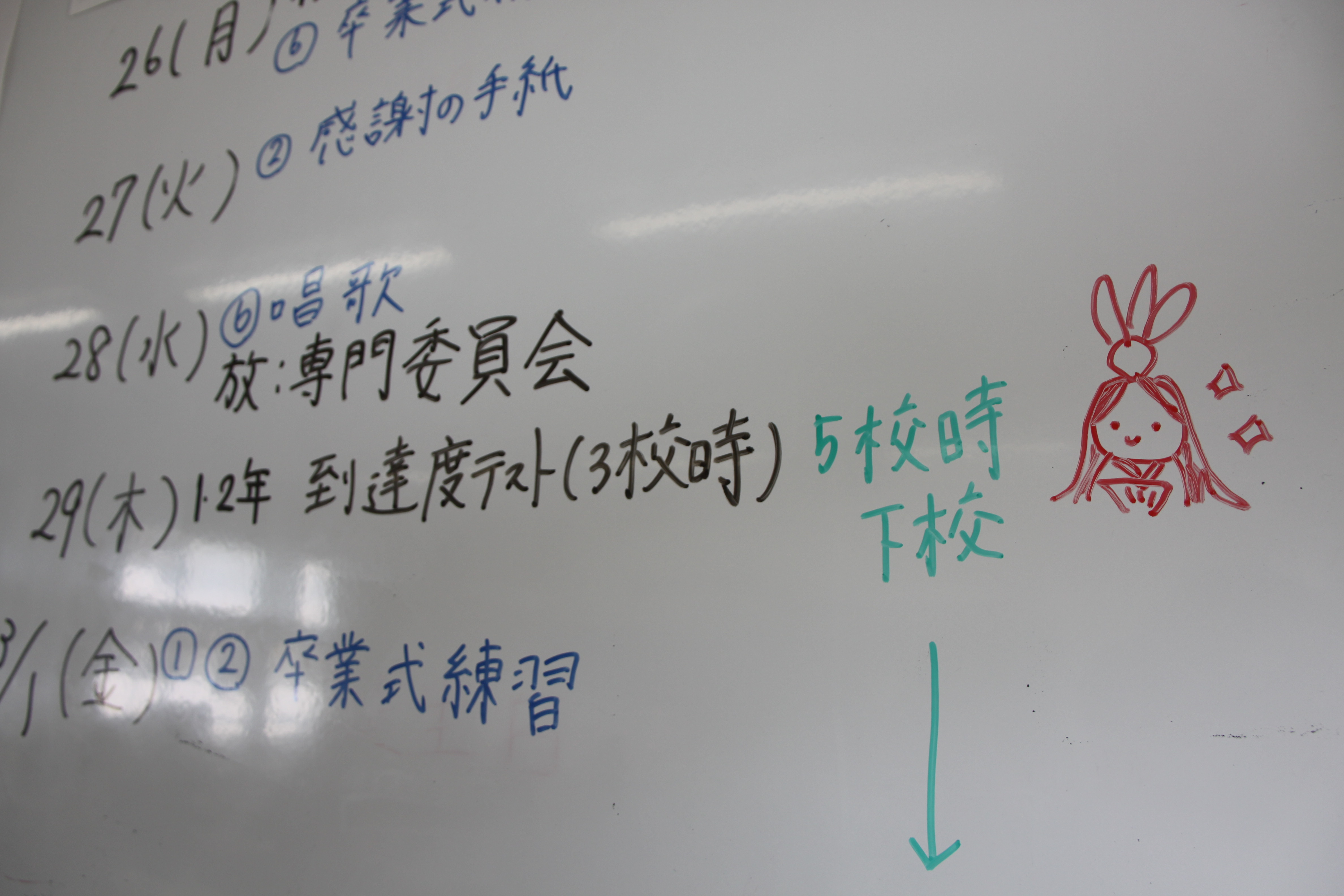




若い私たちには、とくに「朝食」は大切になってきますね。
◎ひな中の風✨〈いのちがたいせつ〉(2/26)
東備消防署さんをお招きして、2年生と教職員が応急手当講習会を受けました。






◎March:Spring has come~Jessica先生からのMessage(2/26)
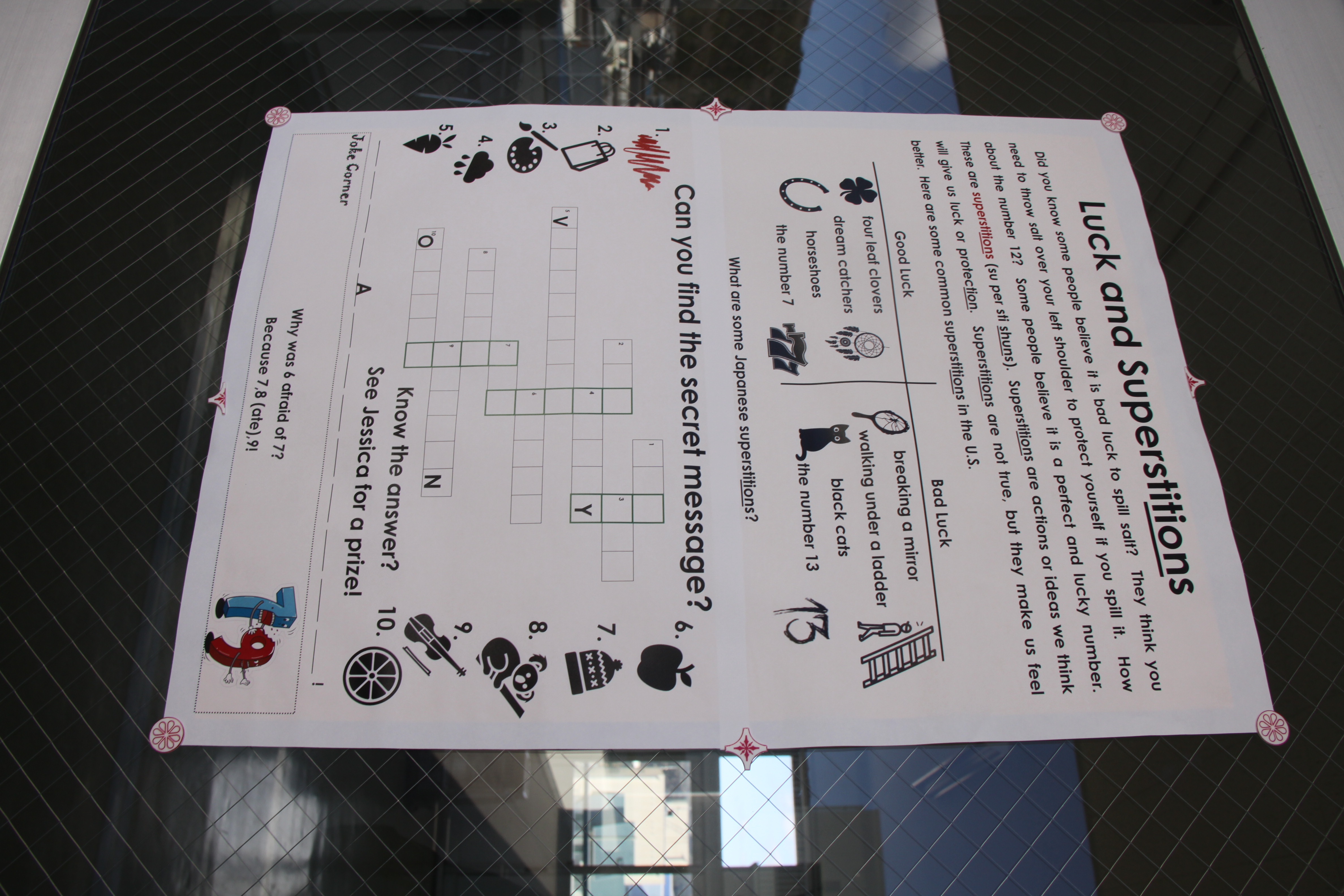
次週3/5は、今年度最後の英会話教室です∈^0^∋
◎正しく知り 正しく行動するための
学びの発信 (2/26~3/1)
日生地域公民館で開催していました3年生ハンセン病問題学習展示ですが、来会された方々が、「他のところでもぜひ開催してはどうか?」とご意見がたくさんあり、この度、市教委からお声かけいただき、3/1まで市役所一階ロビーでの展示を行います。
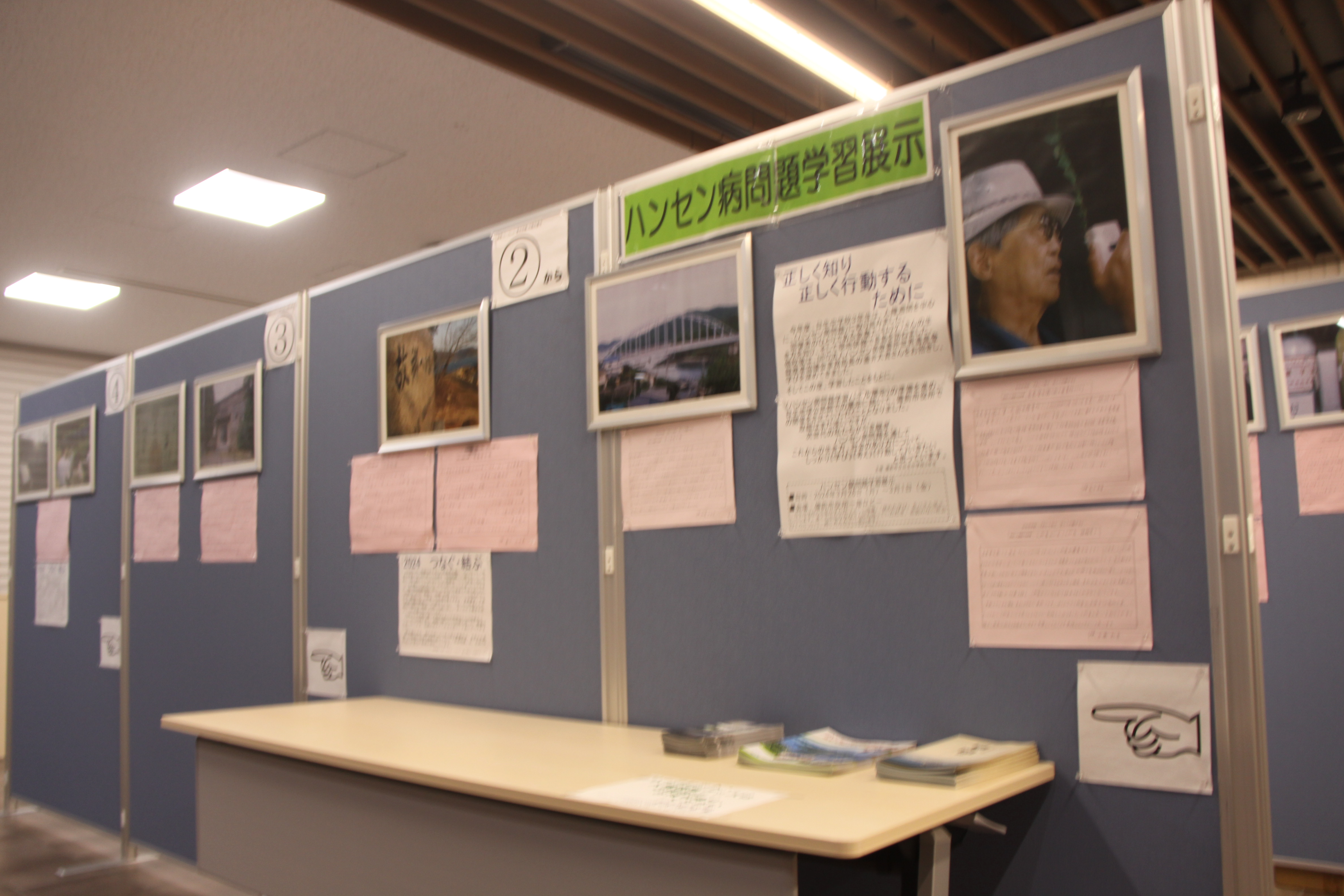

◎多くの人に支えられて(2/27~)
25日の日生かき祭りは、とても多くの人が来られ大盛況だったようです。駐車場となったグラウンドも丁寧に整備していただいています。
何事も多くの方々のみえない力で支えられているのですね。整備をありがとうございます。

◎2年生の豊かな学びの姿に、私たちも真摯に学び合います。
~事実と実践:校内授業公開&研修会(2/27)



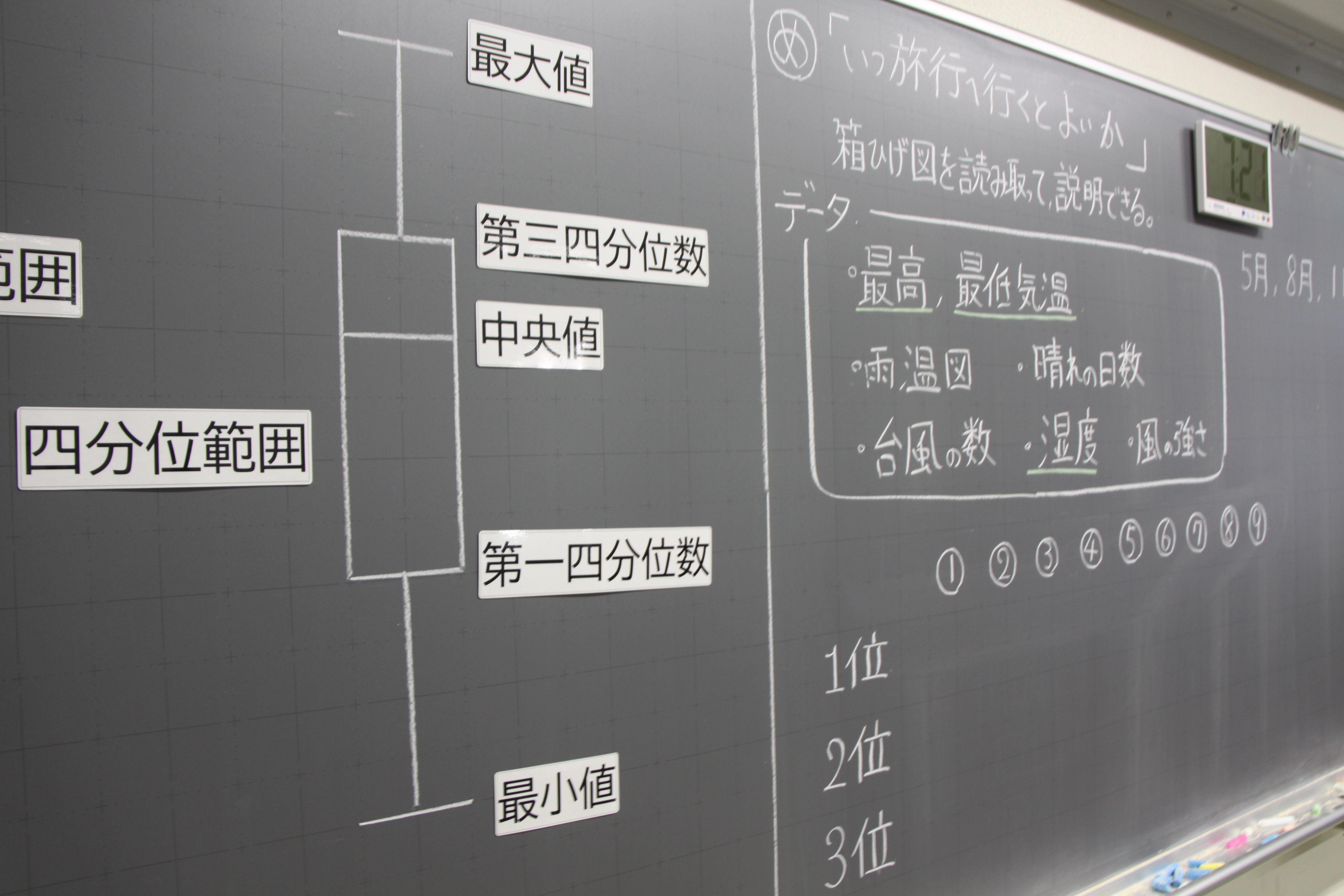

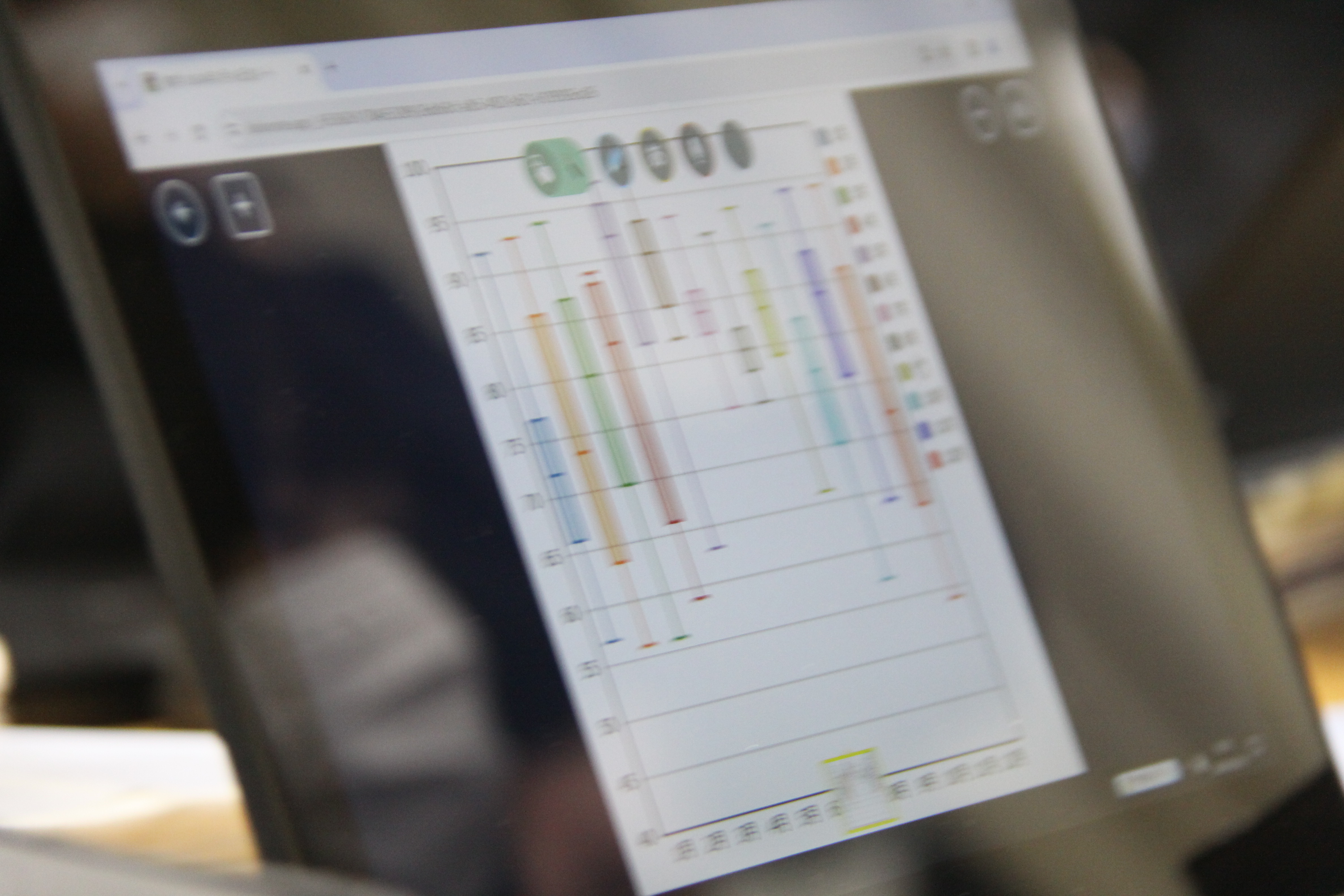

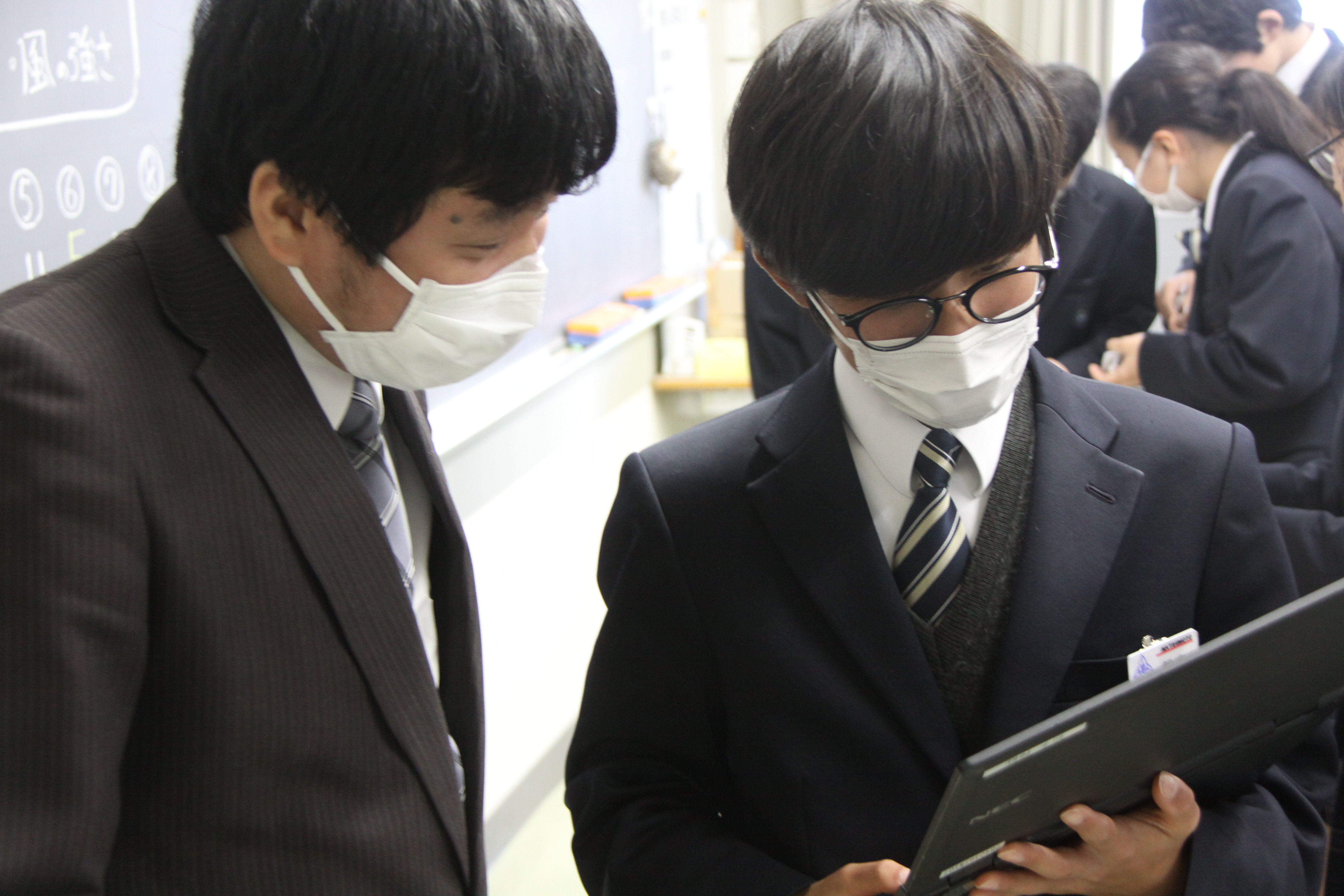




◎はじめにことばありき(2/26)
文化委員による読み語り

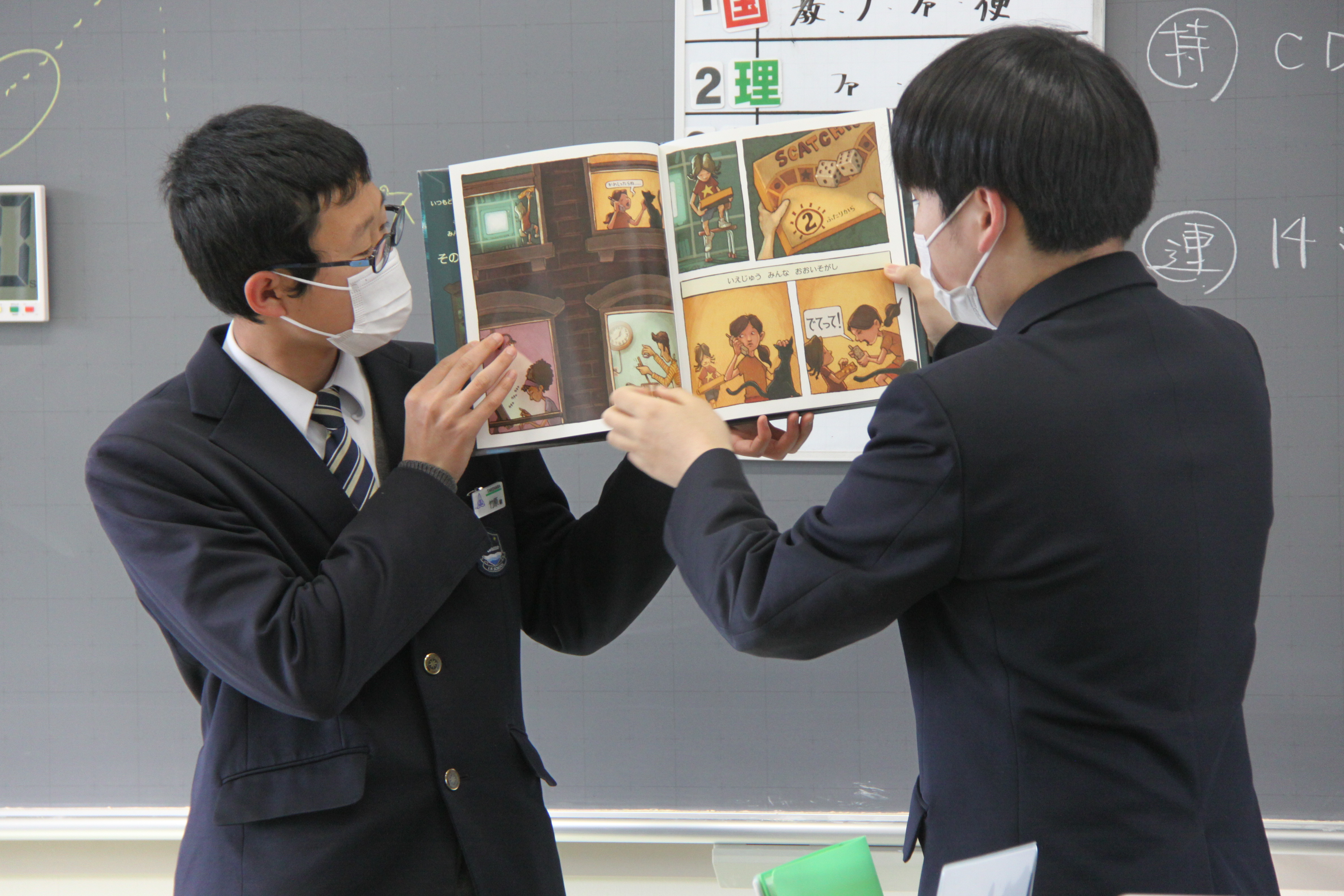
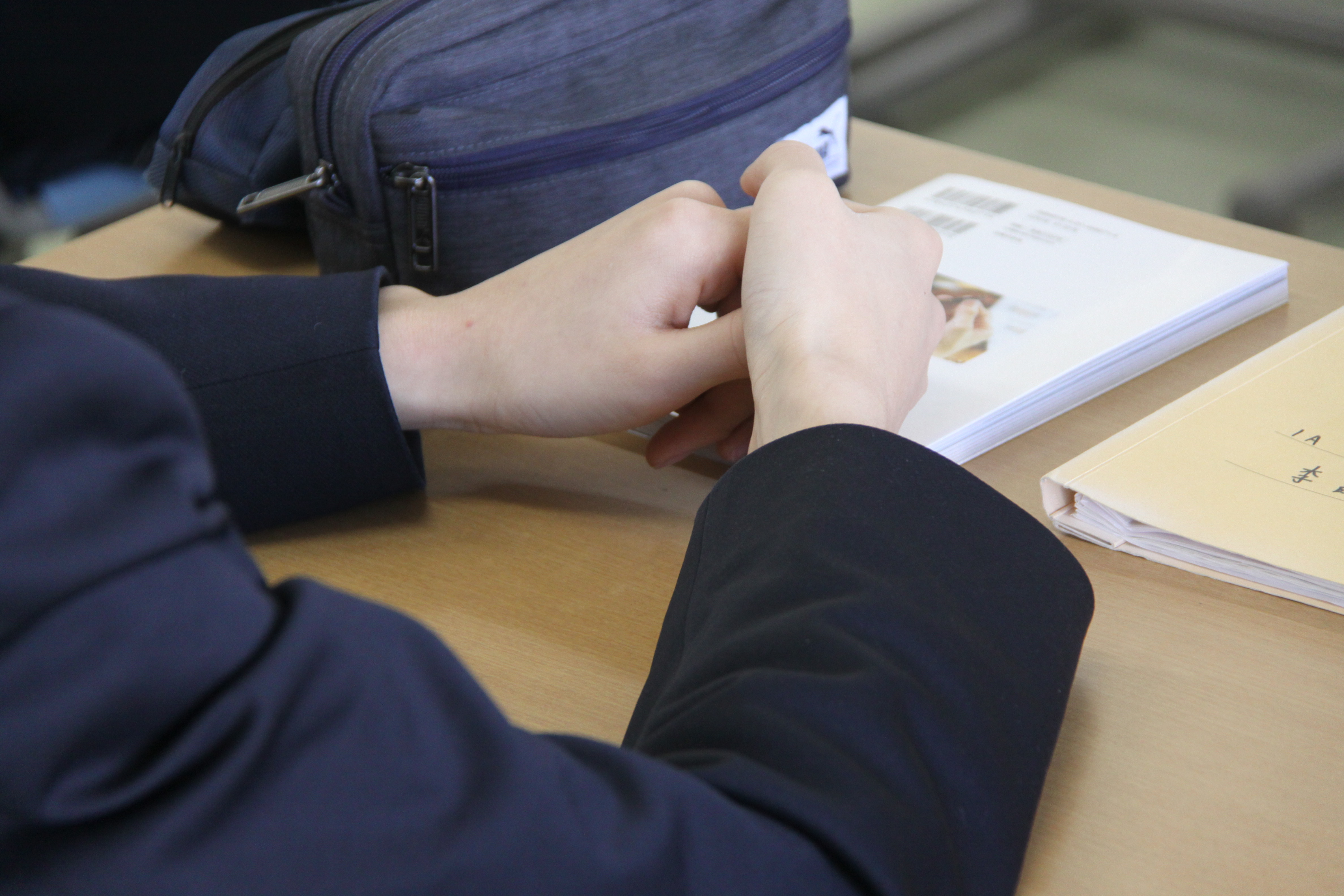

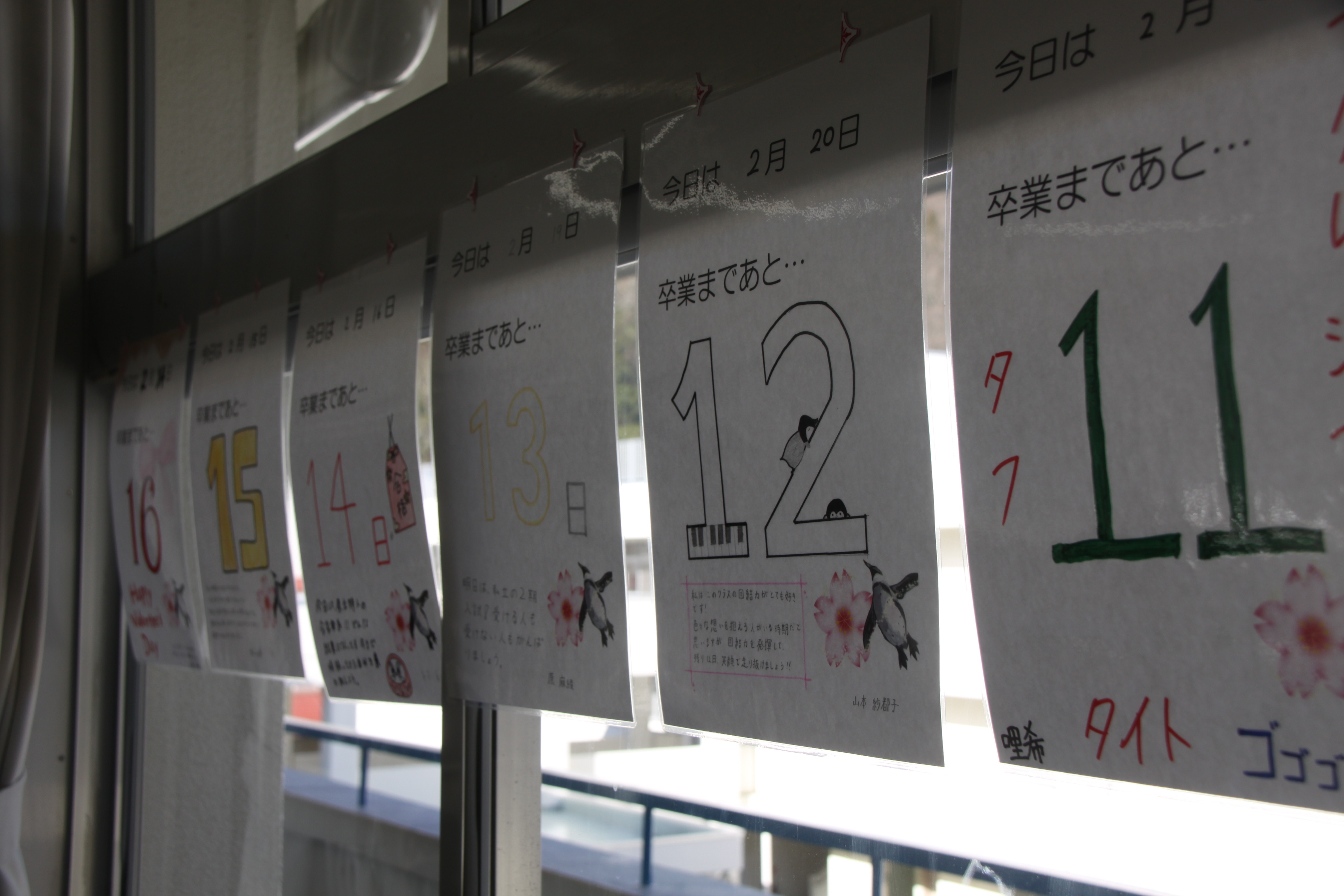




The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Helen Keller
(世界で最も素晴らしく、最も美しいものは、目で見たり手で触れたりすることはできません。それは、心で感じなければならないのです。)
◎未来の、子どもたち・学校・備前市のために
第2回備前市PTA連合会代議員会開催(2/22)
4年ぶりの市P連代議員会の開催でした。今年度の活動の進捗状況についての報告を行いました。その中で、今年度、取組のひとつとして、能登半島地震への支援活動について協議し、義援金の協力を行うことを決めました。また、会では、これからの活動に向けて、次年度の事務局(日生西小学校))と連携して、情報・意見交換も行いました。
3月9日(土)は、岡山県PTA連合会臨時常任委員会が開催されます。

◎2月22日=^_^=
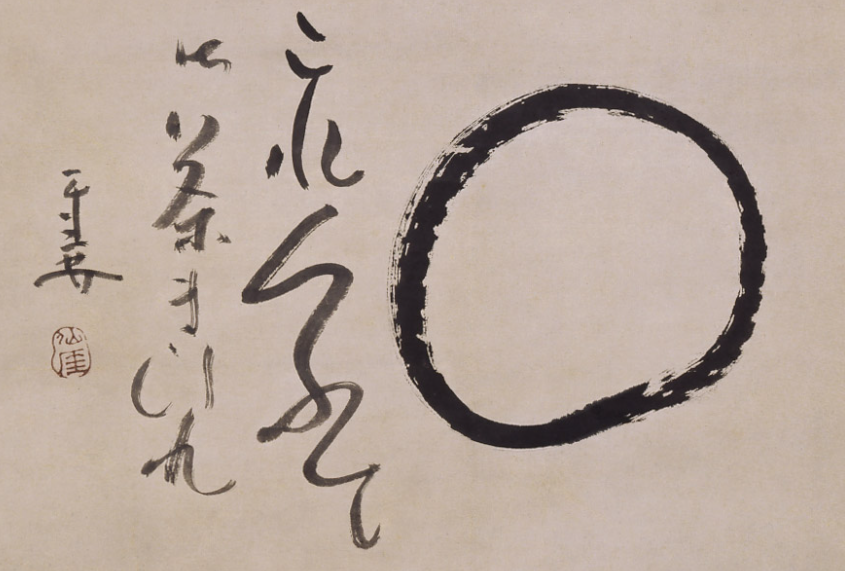
〈これでも食べて お茶飲まれ〉円相図 仙厓義梵
◎メディアコントロール週間~
わたし あなた 仲間と 家族と みんなで。
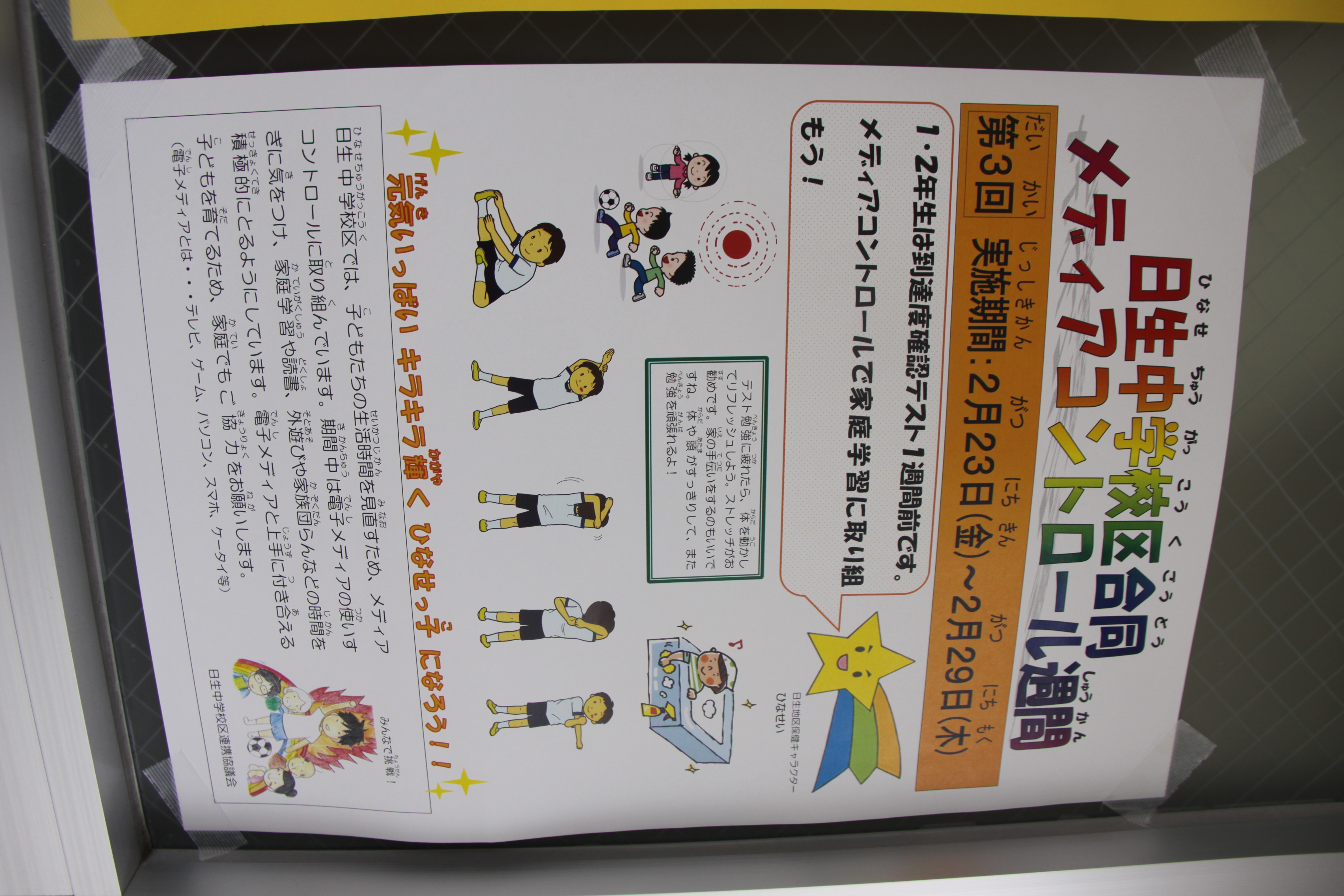

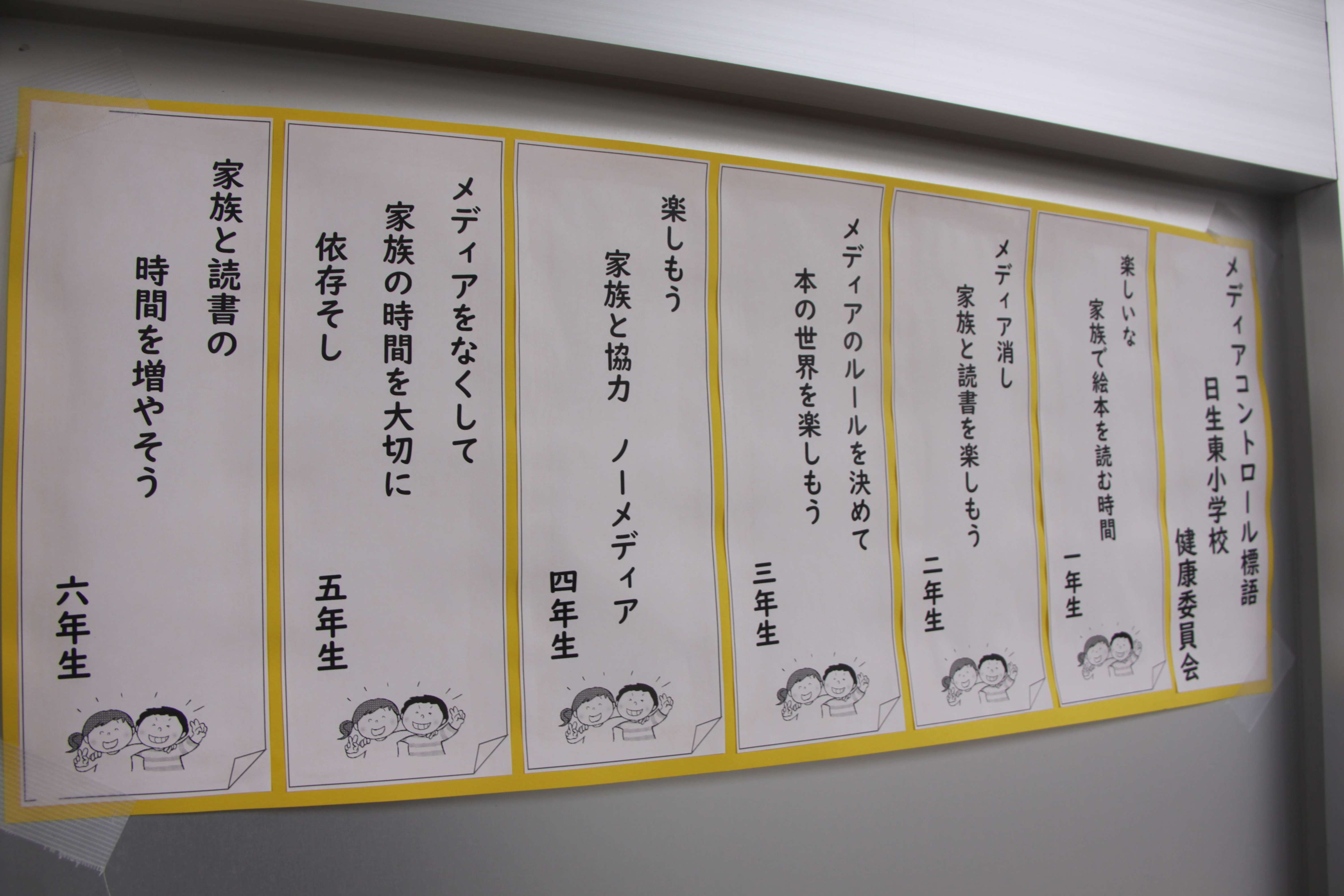

〈あなたがゆっくり歩くので わたしもゆっくり歩くすべを覚えました あなたがすぐに立ち止まるので わたしも立ち止まるすべを覚えました どんなに多くを 見落としていたか 聞き落としていたか なんば・みちこ〉
◎珍(?)日生百景!登録っ!👍👍👍(2/21)


◎多くの人に支えられて
~私たちのまち・私たちの母校(2/21)
昭和55年卒業同窓会様が来校され、生徒活動を支援するための寄付をいただきました。大切に使わせていただきます。ありがとうごいざいます。

◎〈3つの私って〉(^_^)(>_<)(O_O)
2年生が、山﨑スクールカウンセラーと「こころの授業」に取り組みました。(2/21)

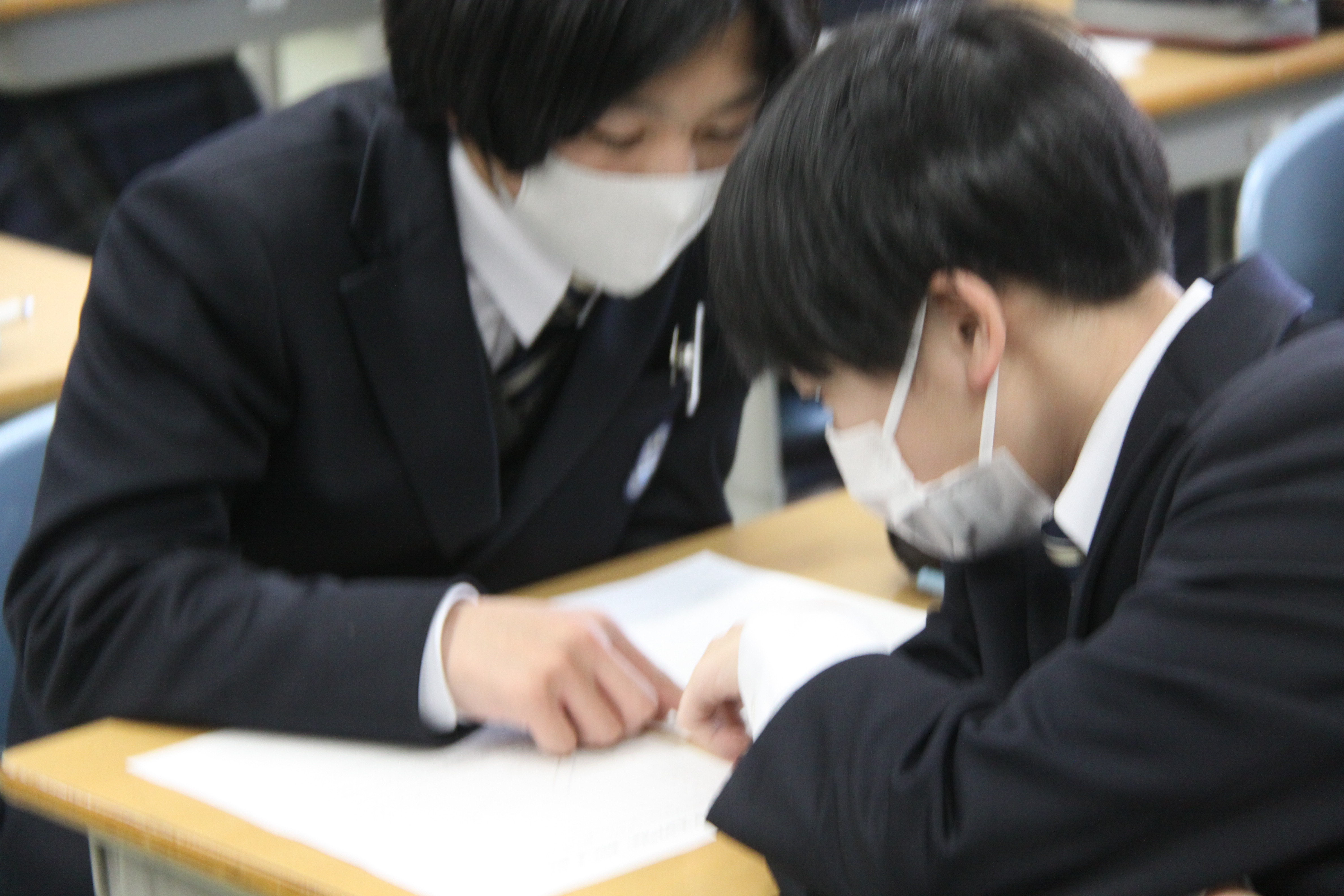
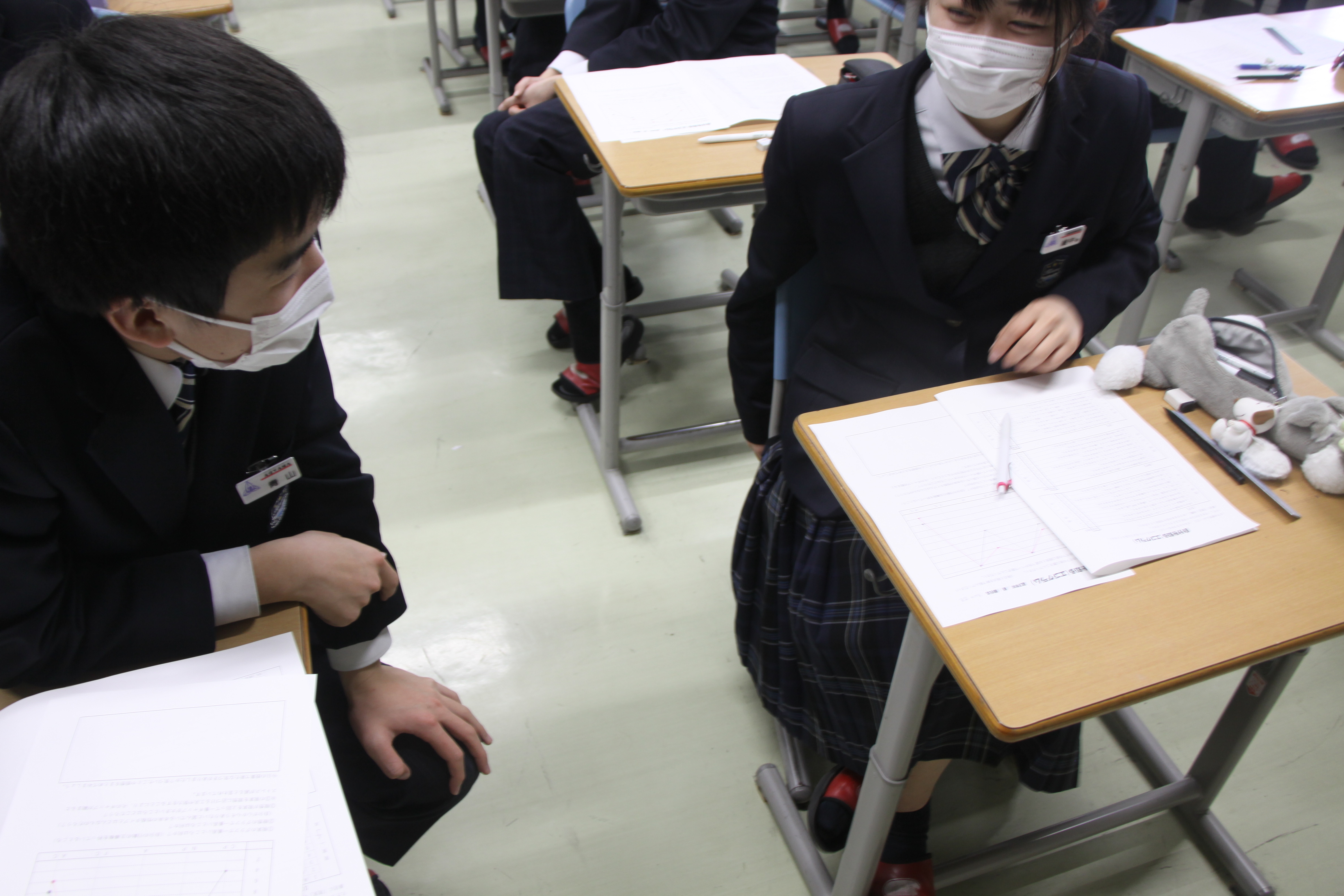

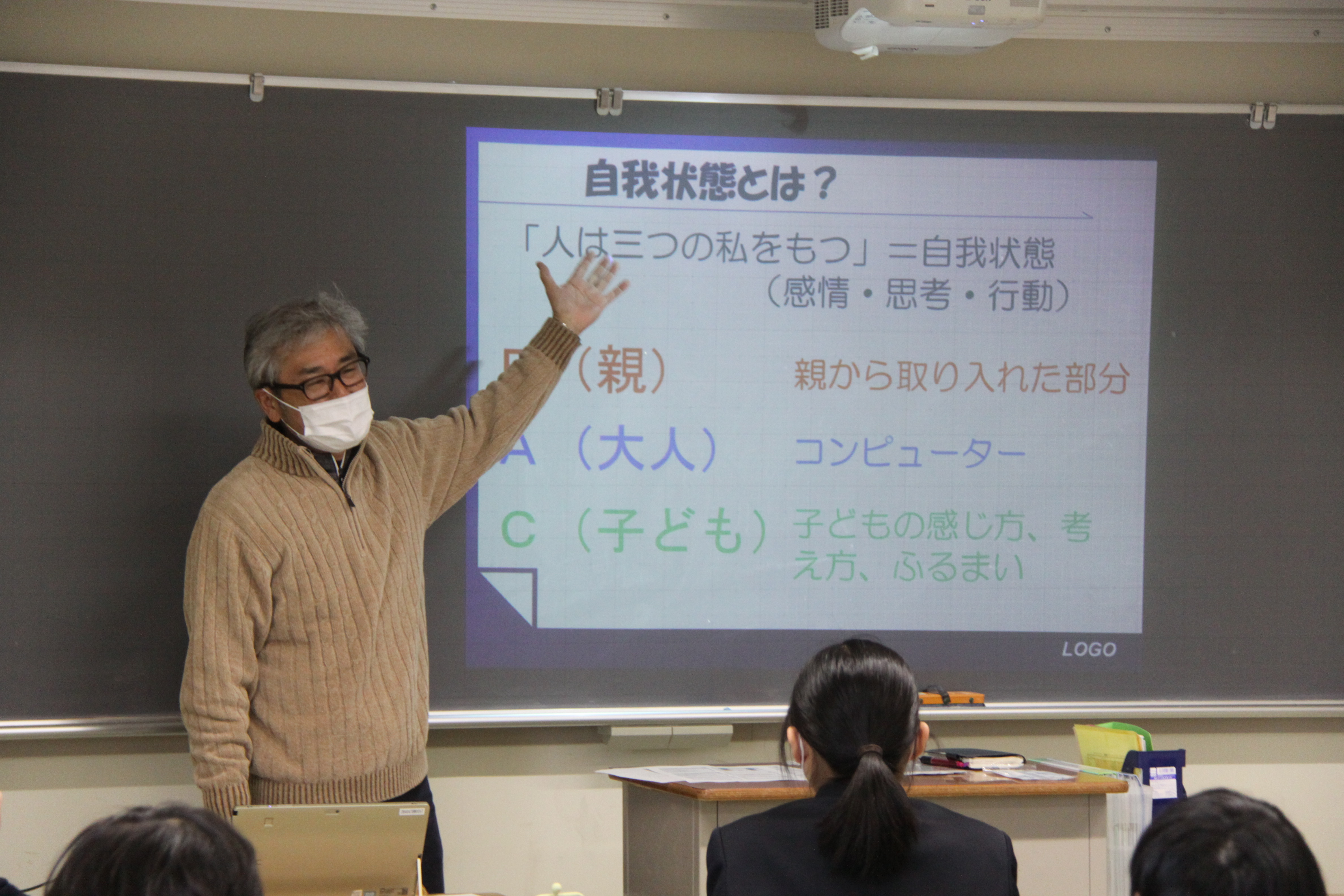



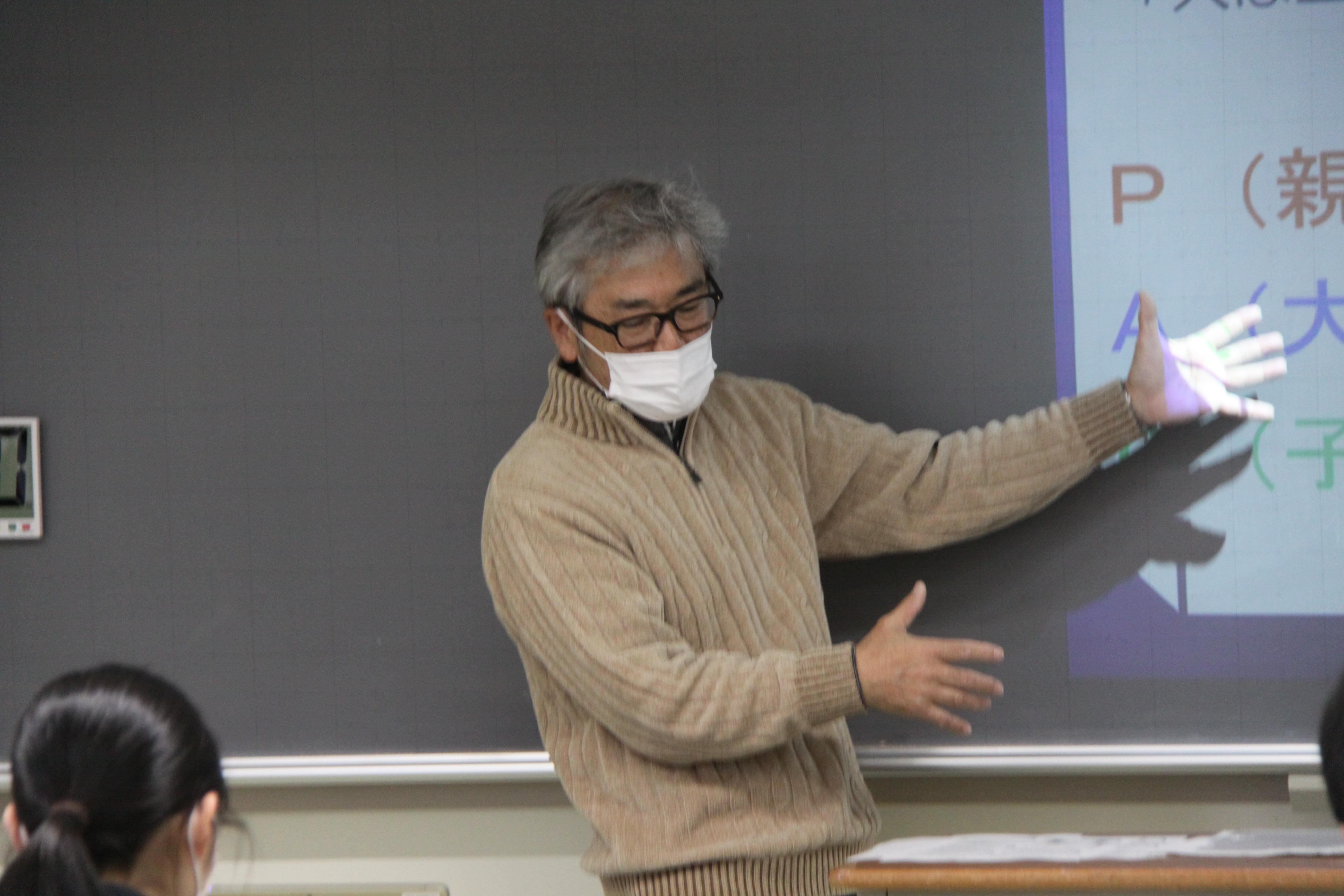
What matters is not the best but it is yourself. Jackie Chan (大事なのは最高ではなく自分らしさ。)
◎ゆたかな海の恵みを、ゆたかな地域のつながりの中で。
1年生が、カキの収穫体験学習に取り組みました。(2/21) 3年生はお家へ持って帰ります。




多くの方々に支えられた一年間の取組でした。
感謝して、みんなで美味しくいただきます。
◎Always‚ always‚ always believe in yourself‚ because if you don’t‚ then who will‚ Sweetie? Marilyn Monroe
(常に、常に、常に自分自身を信じなさい。あなたが信じないなら、誰があなたを信じるの?)
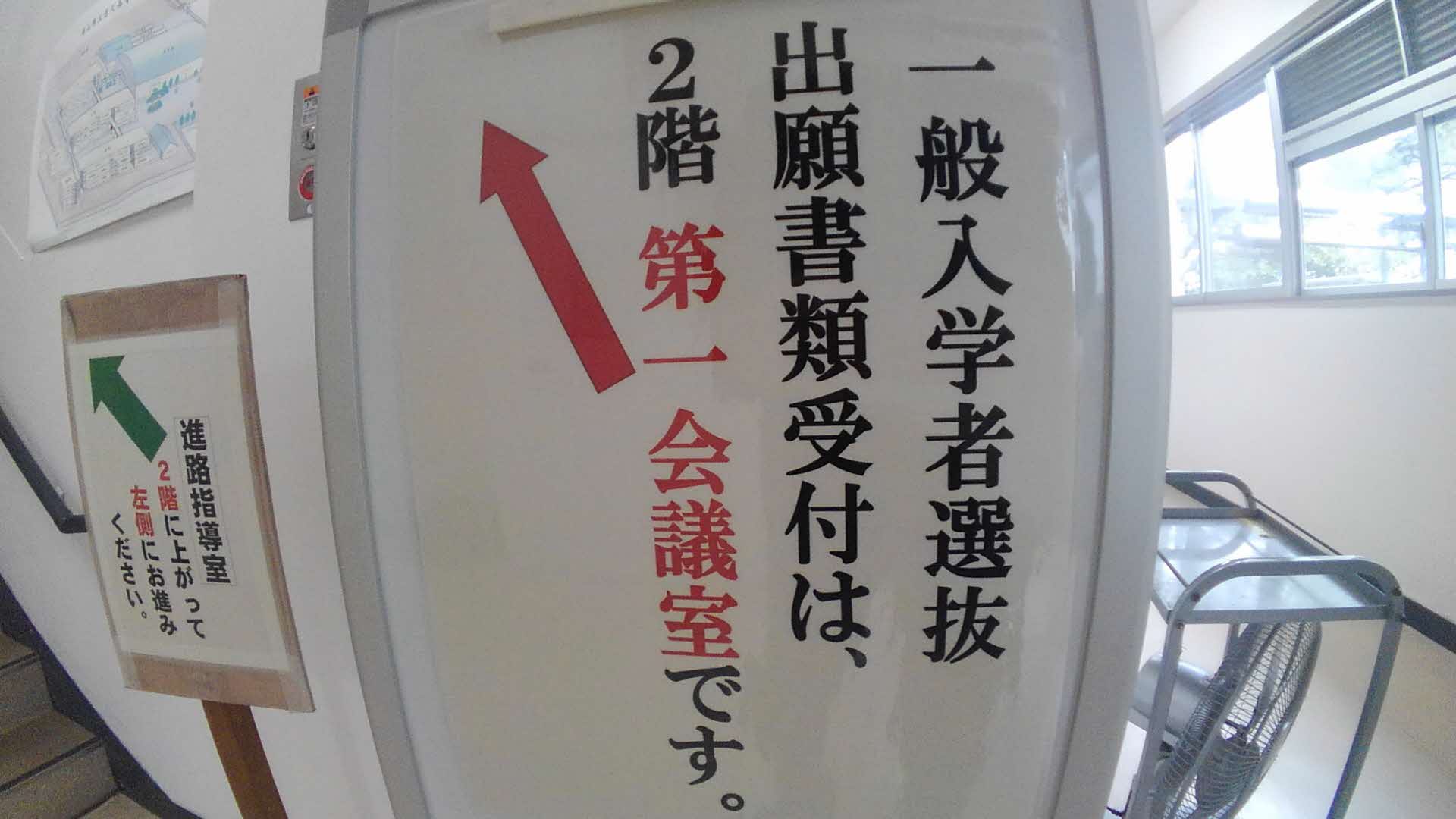
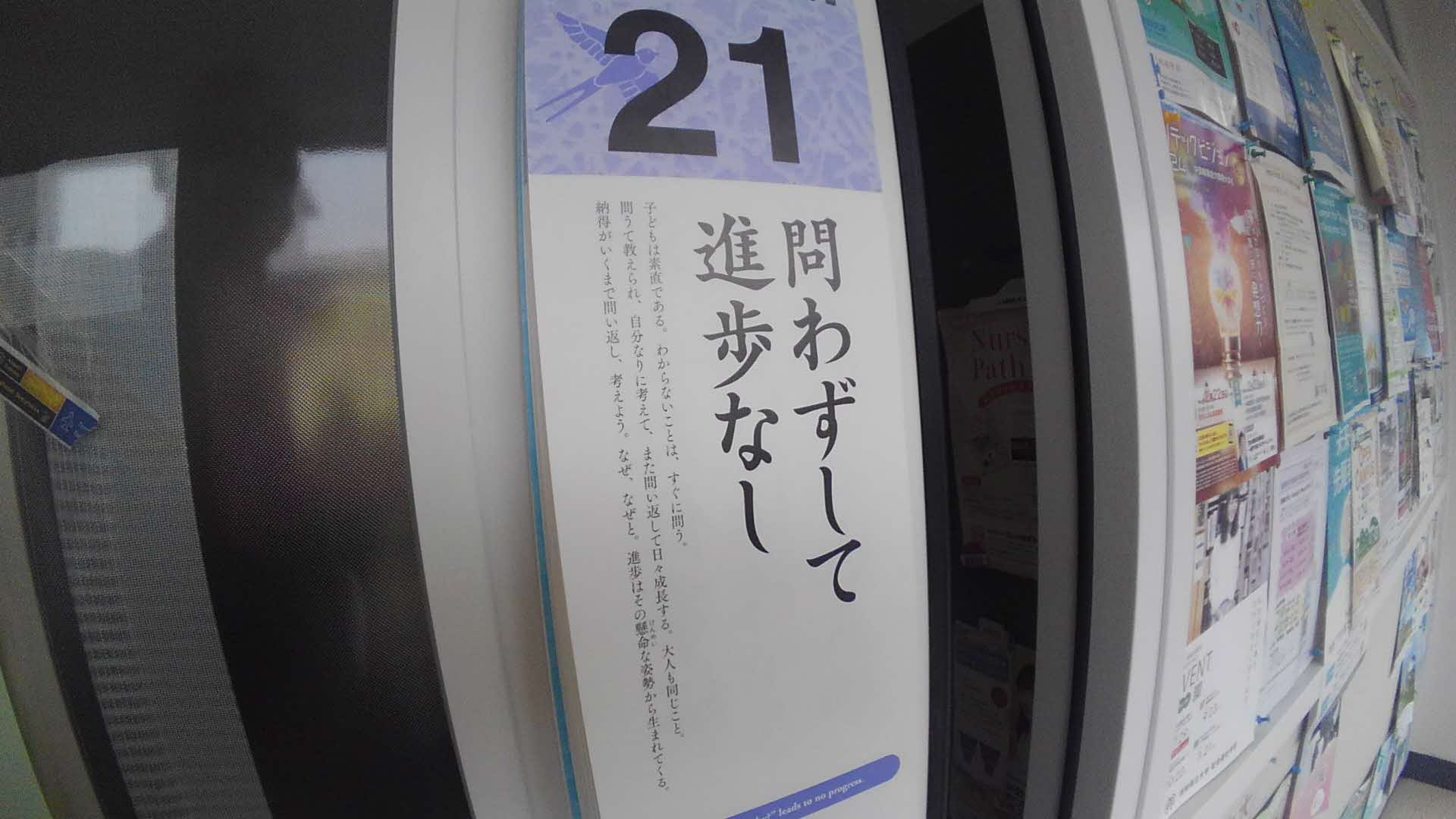
3月7.8日県立一般入試。18日合格発表。
◎あー、楽しいね、英語(2/20)
次回は2/27、3/5ですよ!
また、Jessica先生、よろしくお願いします。
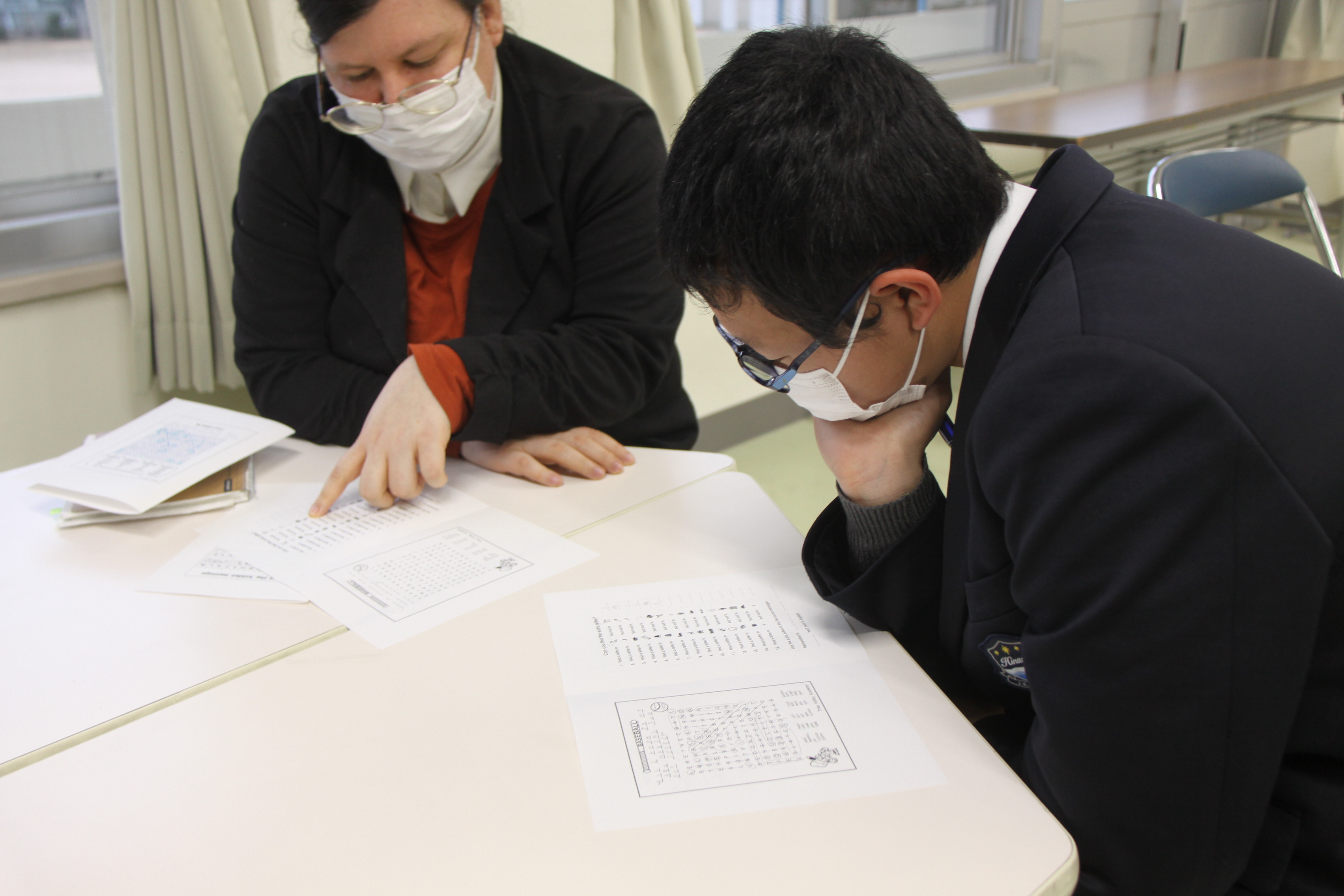
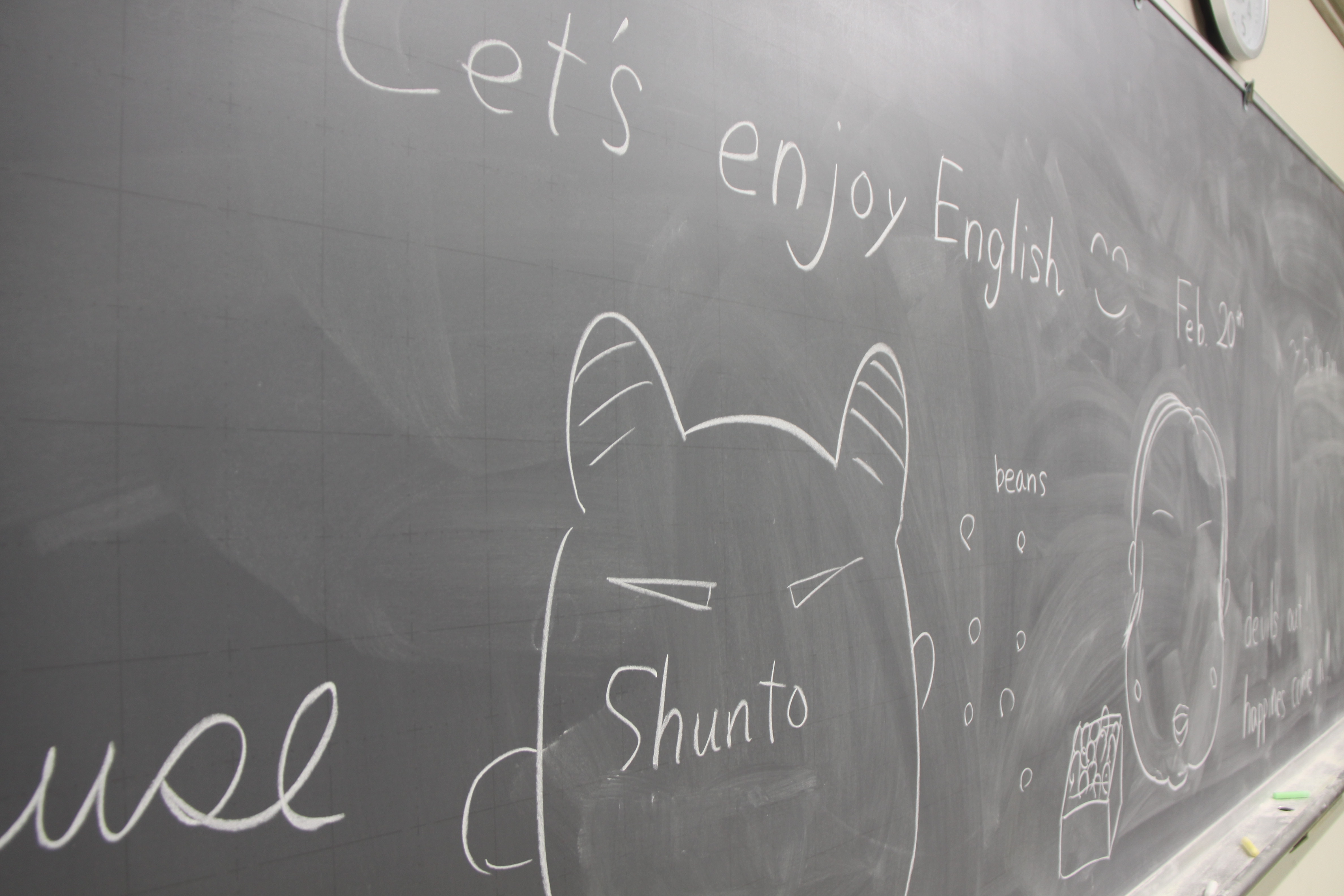
◎ねぇ、どっかに置いてきたような事が一つ二つ浮いているけど
ねぇ、ちゃんと拾っておこう はじけて忘れてしまう前に 「踊り子」作詞/曲:Vaundy
23日から29日まで、日生中学校区ではメディアコントロール週間が始まります。(日生中は、到達度確認テスト(3/1)に向けてテスト週間となります。)

2/20濃い霧の中を登校。
◎善き日のために
卒業証書授与式に向けて。



「まだ、ここにない、出会い。」
かさね られる わかれの ことばは
さよなら という いみ だけじゃない
もうすぐ かわされる
であいの ことばの ために
わかれの ことばは あるんだ
こんにちは さようなら こんにちは さようなら こんにちは さようなら
あつまって くる
それは わたしが わたしたちに なること
はなれて ゆく
それは わたしたちが わたしに いちど もどること
その くりかえしは
まだ ここには ない なにかに であう ために ある
その なにかが わたしを すこしだけ あたらしい わたしに して
もっともっと あたらしい わたしたちが はじまる
(佐倉康彦さんがつくられた「リクルート」の広告を紹介しました)
◎私たちのまち 私たちの日生
観光協会さんから「かき祭り」チラシをいただきました。
日生中は、21日に1年生が、総合的な学習の時間で、カキの洗浄・選別体験学習に取り組みます。「海洋学習」の一環として、地域の地場産業であるカキ養殖についての体験活動を通して日生の基幹産業について継続的に学んできましたが、今回は カキの洗浄作業・試食等を通して、養殖業の苦労とやりがいを感じ、勤労の大切さを学びます。様々な学習が、地域の方の指導や協力のおかげで行えることに感謝したいと思います。美味しくいただきます。∈^0^∋
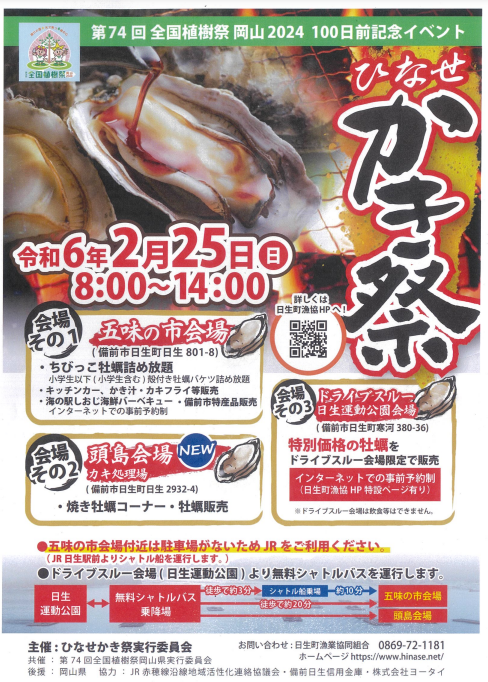
◎ひな中の風✨
残念な話なのですが、日生中学校の校門付近にいつも飲んだペットボトルを捨てている方がいるのです。朝の環境整備時に立川先生が回収してくださるのですが、いつまで経ってもポイ捨てはなくなりません。「気がついてくれたらなあ」とバケツを置いていても状況は変わらないのだけど、、、。しかし、最近、とてもうれしいことがありました。それは、立川先生が、ポイ捨てされたペットボトルを回収する前に、気がついた登校中の生徒の誰かがバケツにそっと入れているようなのです。さりげない行動ができるひな中生徒をとても誇りに思います。

◎ひな中の風✨
私たちが出来ること・伝えること(2/19)
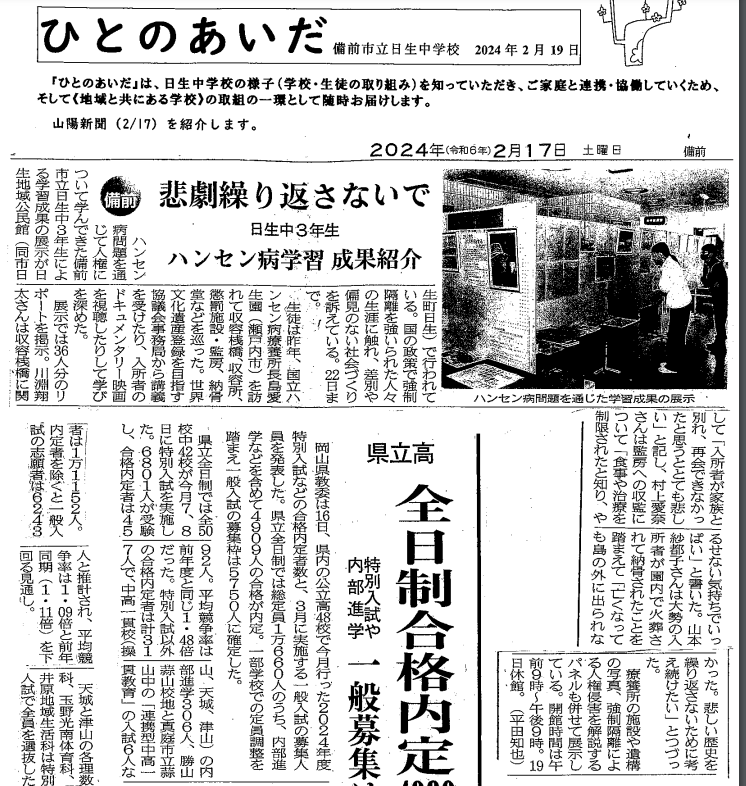
◎日生中パネル展は、2/26(月)13時~3/1(金)12時まで、備前市役所(1Fロビー)での展示を計画しています。
F
◎雨水(2/19)



二十四節気のひとつ「雨水」。雨水は「うすい」と読みます。雨水とは、雪が雨へと変わって降り注ぎ、降り積もった雪や氷もとけて水になる頃という意味。実際にはまだ雪深い地域もありますが、厳しい寒さが和らぎ暖かな雨が降ることで、雪解けが始まる頃です。凍っていた大地がゆるんで目覚め、草木が芽生える時期。雨水になると雪解け水で土が潤い始めるため、農耕の準備を始める目安とされました。
二十四節気では、雨水の前は暦のうえで春となる「立春」、雨水の次は、冬ごもりしていた生き物が活動し始める「啓蟄(けいちつ)」となります。の頃になると、寒い日が続いたかと思うと温かくなり……を繰り返すようになります。こうした様子を「三寒四温(さんかんしおん)」といいます。3日ほど寒い日が続いたあとに4日ほど暖かい日が続いてこれを繰り返す、という寒暖の周期を表しています。
「三寒四温」は、もともと中国北東部や朝鮮半島北部で使われていたことばで、本来は冬の気候を表しますが、気候の違う日本では寒暖の変化がはっきりと現れる早春に、冬から春へと季節が変わっていくニュアンスで使われることが多くなりました。また、立春から春分の間に初めて吹く南寄りの強風を「春一番」と呼びますが、春一番が吹くのもこの頃です。
◎ Imagine all the people living in class.
県立特別入試合否発表日(2/16)
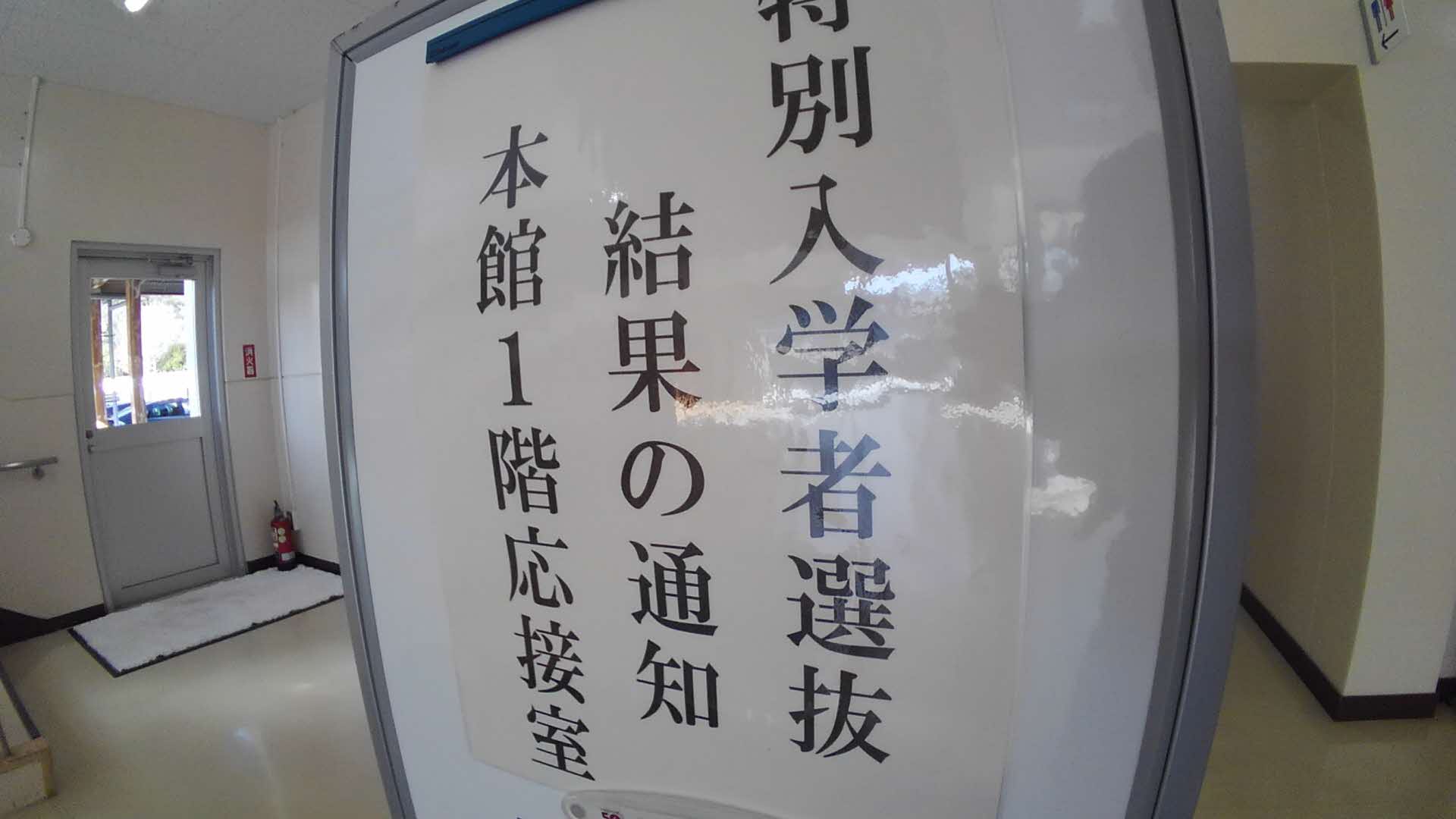

同じ不安や悩みをのりこえようとしている仲間だからこそ。
粘り強く、共に応えてきたクラスメートだからこそ。
私立入試で、1,2,3,4人の少し早く春がきた仲間たち。
そして今日、5,6,7,8人・・・と「内定合格」で、また「ほっ」とするひとが決まった。
これまでの中学校生活と準備が志望校に評価されたのだ。本当におめでとう。
だが、しかし、一緒に頑張ってきたのは「みんな」同じなのだ。にもかかわらず「受験制度」はこの日全員に「お疲れさん!」とは言ってくれなかった。
本当の最後の入試がこのあと待っている。
例えだが、電車は一本ではない。今日少しはやく乗れた人もいる。乗れんかった人もでてくる。だが、あせってはいけない。あわてててはいけない。あきらめてはいけない。チケットはちゃんとまだ用意されている。「これから」粘り強くあきらめず励もうと誓い、行動すれば‚かならず道は拓かれる。
そして‚少し先に電車に乗れた諸君は、あとから来るなかまを本気で応援してほしい。関わってほしい。
ひとり(孤独)にさせちゃあいけない。
ひとりになってはいけない。
だって、今まで一緒の悩みや不安を持って戦ってきたなかまなのだから。その気持ちは想像できるだろう。「想像力」…どれだけひとの気持ちをわかろうとできるか…とても大切なことだ)
「内定」を手にしても「一般入試に挑む」ことになっても、クラスの仲間どうし、声をかけ合って、「ともにがんばっていく覚悟」をいま決めよう。
そしてもうひとつ、どうか、卒業までの日々を、「なかま」を大切にしていくことをあらためて誓ってほしい。(S先生からいただいた資料を紹介しました)
◎子どもたちのために、PTAのちから(2/15)
~PTA幹事会
今年度の活動について振り返り、新年度の行事や新役員の引継や人選についても協議しました。来年度は、子どもたちのボランティア活動をさらにバックアップするための体制づくりや、星輝祭(体育の部)などの行事のサポート支援を強化する計画です。PTA会員の方々からのご意見やアイデアをお待ちしています。今年度さいごの委員総会は、3月4日(月)(18:30~19:00)を予定しています。役員の皆さん参会のほど、よろしくお願いします。

The best way to make your dreams come true is to wake up. Paul Valéry
(夢を現実にする一番いい方法は、目を覚ますことだ)
◎お魚はお任せっ!
私たちのちから ひな中のちから(2/15)
今日の調理実習(2年)も多くの人に支えられて、がんばることができました。ありがとうございました。
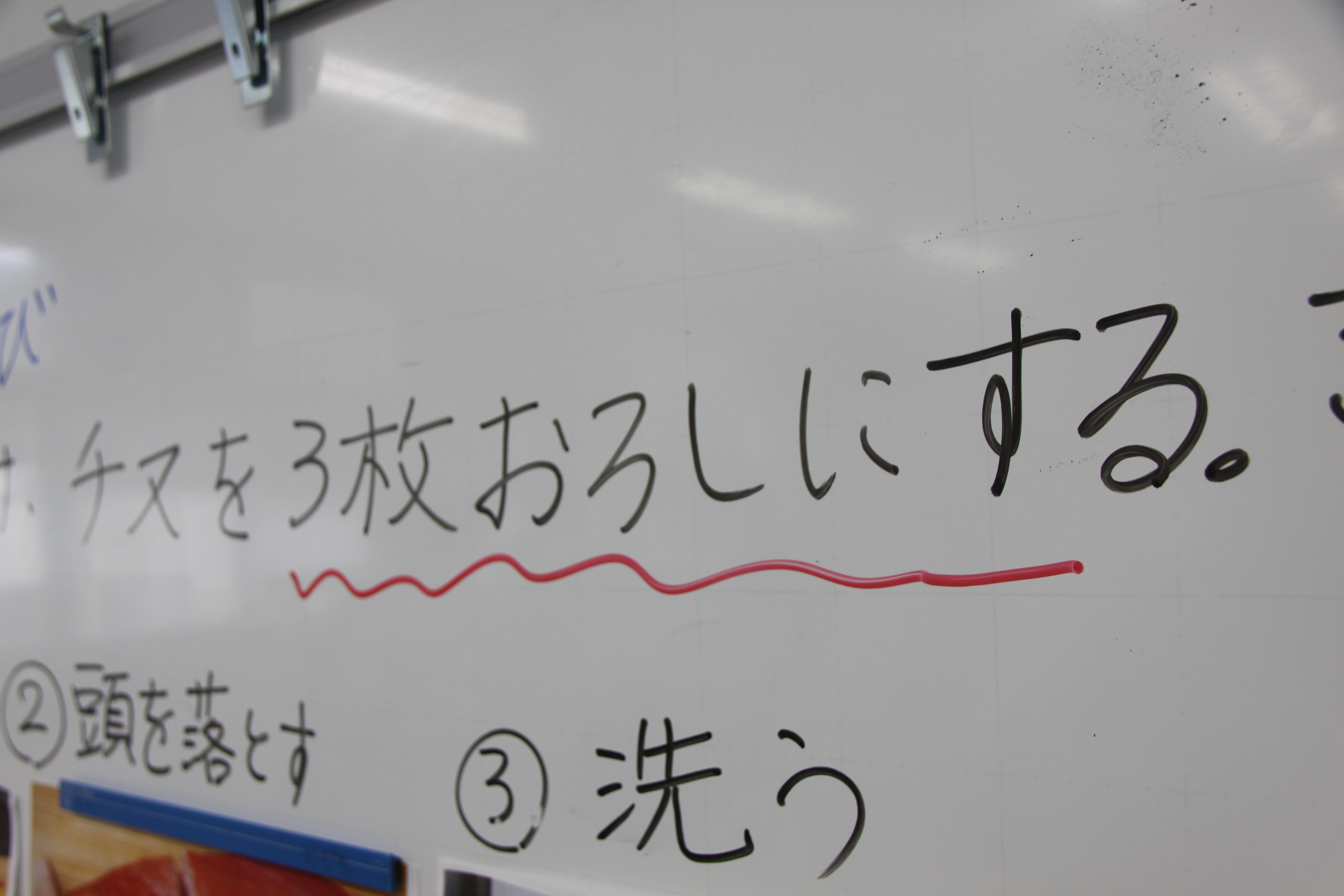










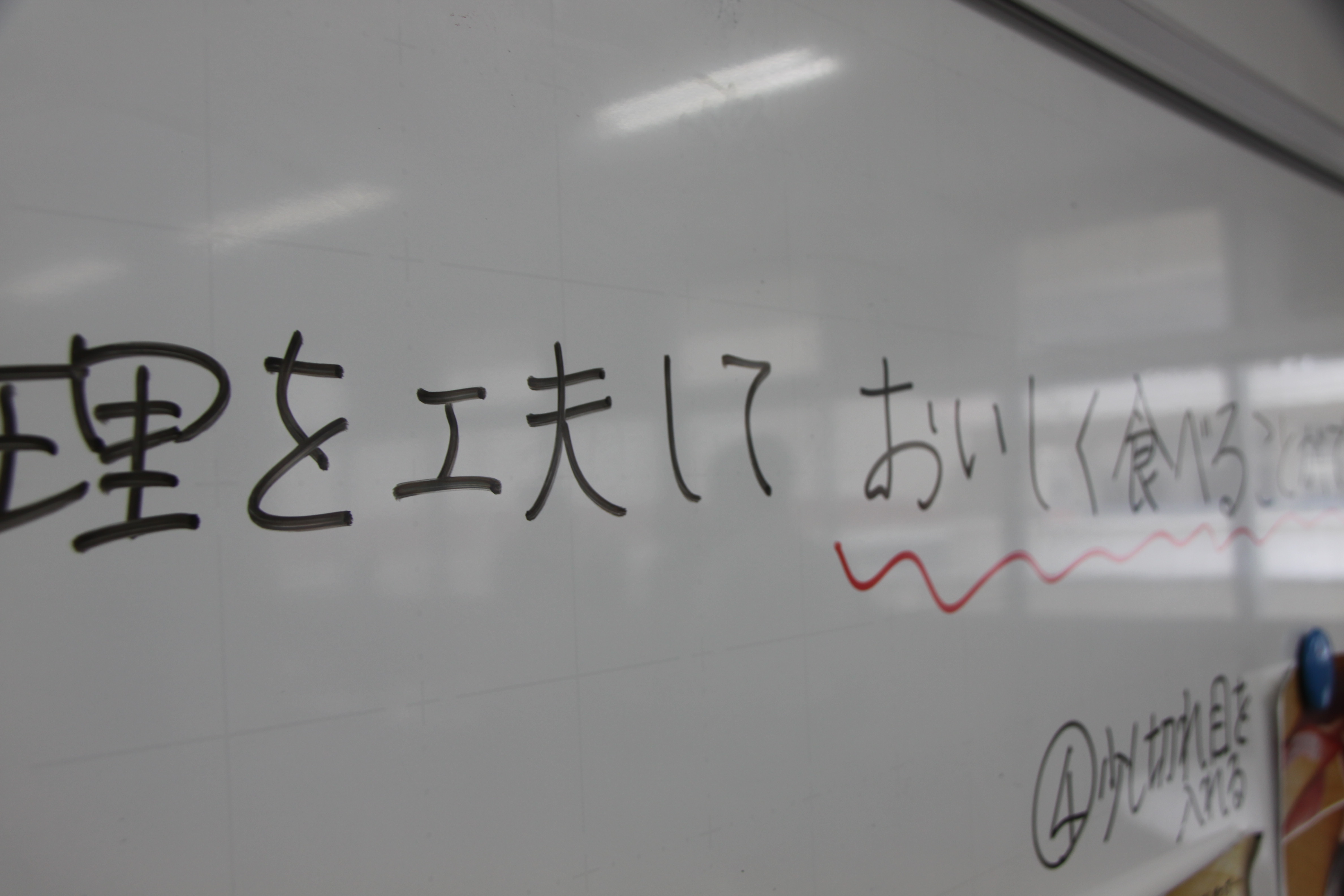
TO BE CONTINUE.
◎私たちのちから ひな中のちから
星輝祭(体育の部)にむけて実行委員会スタート!

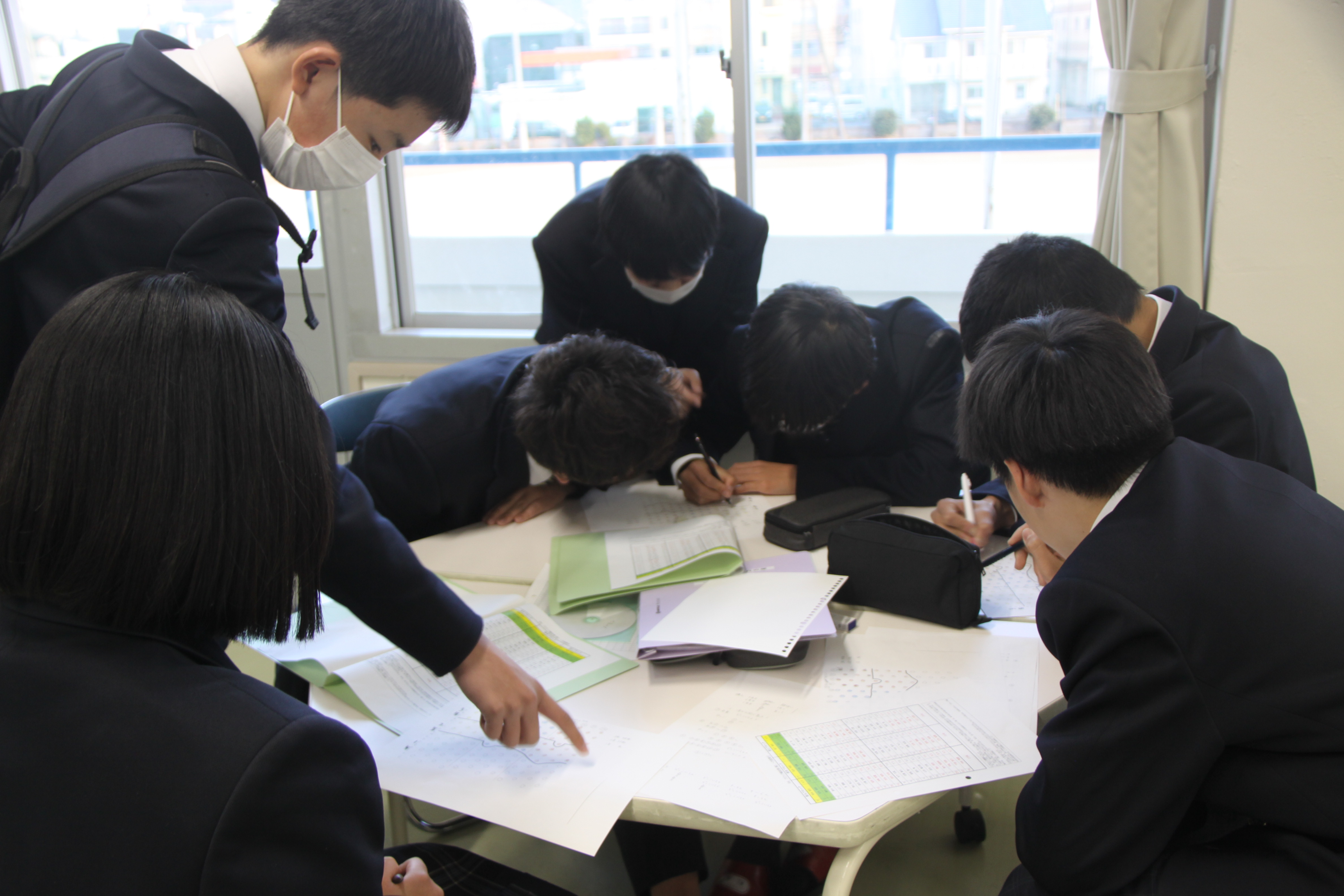
◎ダイバーシティ(多様性を認め合う)の学校へ。
第3回ひなせ親の会(2/14)を終えて
第3回ひなせ親の会(情報交流会)は特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。
14日の会では「どんとこい進級・進学」をテーマに、スクールソーシャルワーカー(SSW)、スクールカウンセラー(SC)、のアドバイスも受けながら、楽しく(笑いあり)共に深く考えることができました。新年度も参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会にしていきます。次回は4月8日(火)17:00~18:30で調整しています。また、中学校での学校・授業見学や進路相談などなど、お気軽にご相談ください。

2015(平成27年)年に、当時勤務していた中学校区の保護者の方々の願いと市・県の積極的な取組の中で、勤務校に新しく自閉症・情緒障害特別支援学級が開級されました。担任として私が、大切にせねばならないと思っていたことは、〈子どもと保護者の〈こえ〉をしっかり聴くこと〉でした。さらに、開級にあたっては、学習環境の整備(教室の構造化等)と、必要かつ具体的な合理的配慮の提供についても、保護者と市と学校がしっかり話し合いながら、綿密に準備を進めることができました。その流れの中で、入級する子どもの保護者の方々が、自主的・定期的に開催する「親の会」に自分自身も参加する機会を得ました。
親の会では、お茶を飲みながら、一人ひとりの子どもの日々の成長を喜び合ったり、「子育て」や「社会的自立」についての悩みや心配・不安なことを出し合ったりしましたが、いつも大きなテーマになっていたのは、中学校卒業後の「進路」でした。中学校では、子どもらは、一年時から計画的に進路・キャリア学習を進め、保護者もオープンスク-ルや高校説明会で進路情報を手にしていきますが、特別支援学級在籍の子どもたちの保護者が「自分の子どもの発達特性」等に合った進路情報を収集し、進路支援の見通しをもつ機会は少ない状況がありました。そして私自身も特別支援教育のニーズのある子どものための進路についての情報の少なさに、課題を抱えてました。そこで、親の会で話し合い、まずは勤務している中学校で高校を招き、「進路情報を自分たちで手に入れて、勉強をしていこう」と進路情報の学習会を始めることとしました。
今年度から、日生学区では、の小・中学校、地域と連携した親の会がはじまりました。保護者・当事者・学校・多くの支援の方々等、お互いの声を重ねながら、会の内実を創っていきたいと思います。
◎地域とのつながりは大切(2/15)
備前市手をつなぐ育成会研修会で、社会福祉法人閑谷福祉会 閑谷ワークセンター・ひなせに訪問させていただきました。高橋さんから、日生地域の中で、豊かなつながりを大切にして活動されているというお話を聴くことができました。また、寒河にある浜山作業所に移動して、資源物を分別する根気の要る作業の様子も見学させていただきました。近年、資源物のリサイクル等の意識は高まりましたが、搬出時にはより丁寧に分別する必要性をあらためて教えていただきました。ありがとうございました。備前市手をつなぐ育成会では、福祉や人権課題、特別支援教育等様々な研修を行っていきたいと思います。ご意見をおきかせください。
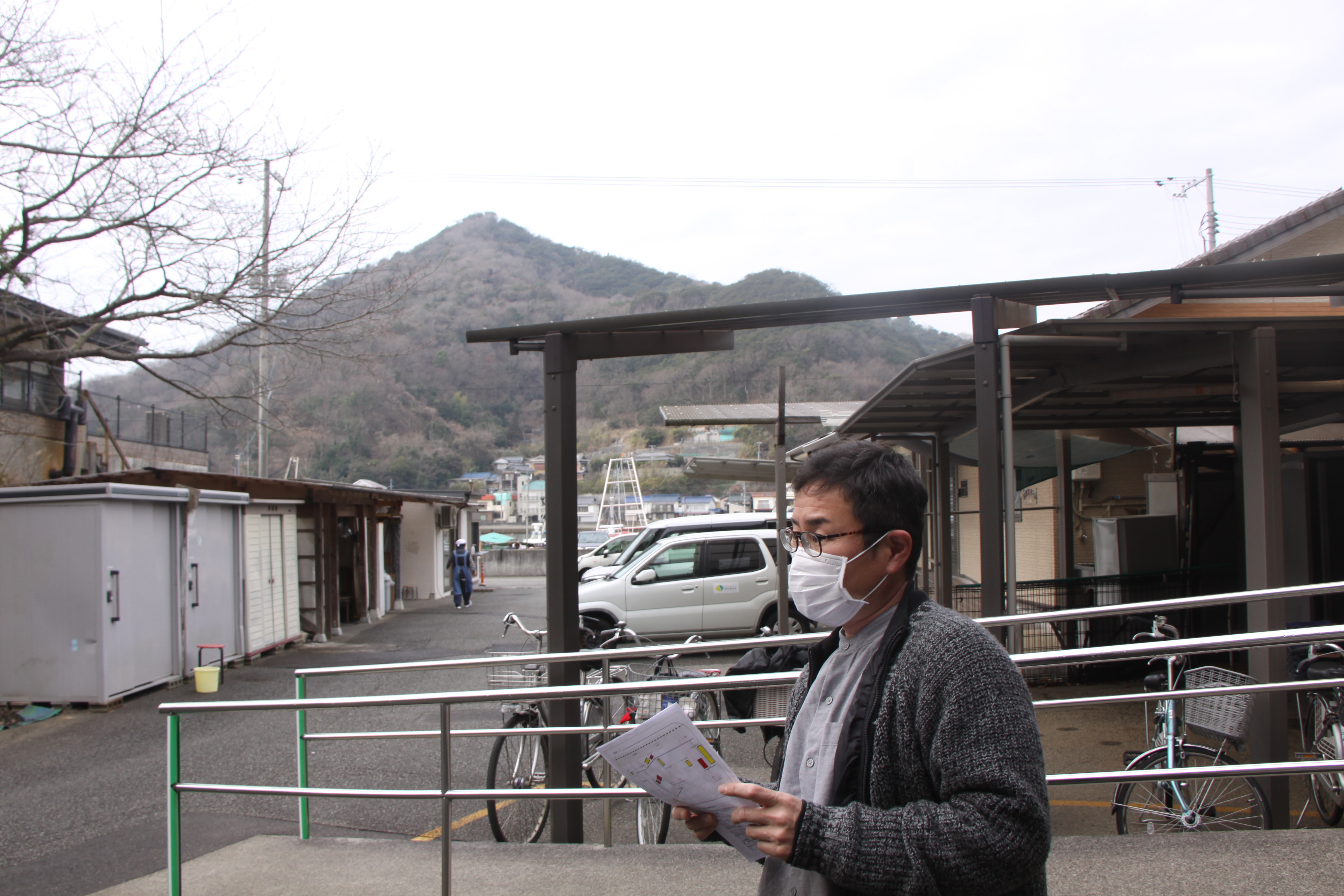





おいしいお弁当(なんと380円)は、大好評で販売中。
◎わたしたちのまち・ひなせ(2/14)
消防団操法訓練

◎澄める心をさながらに 映して永遠に育ちゆく♪(2/14)
6年生体験入学~夢や希望を実現していくための大切な三年間にしような。






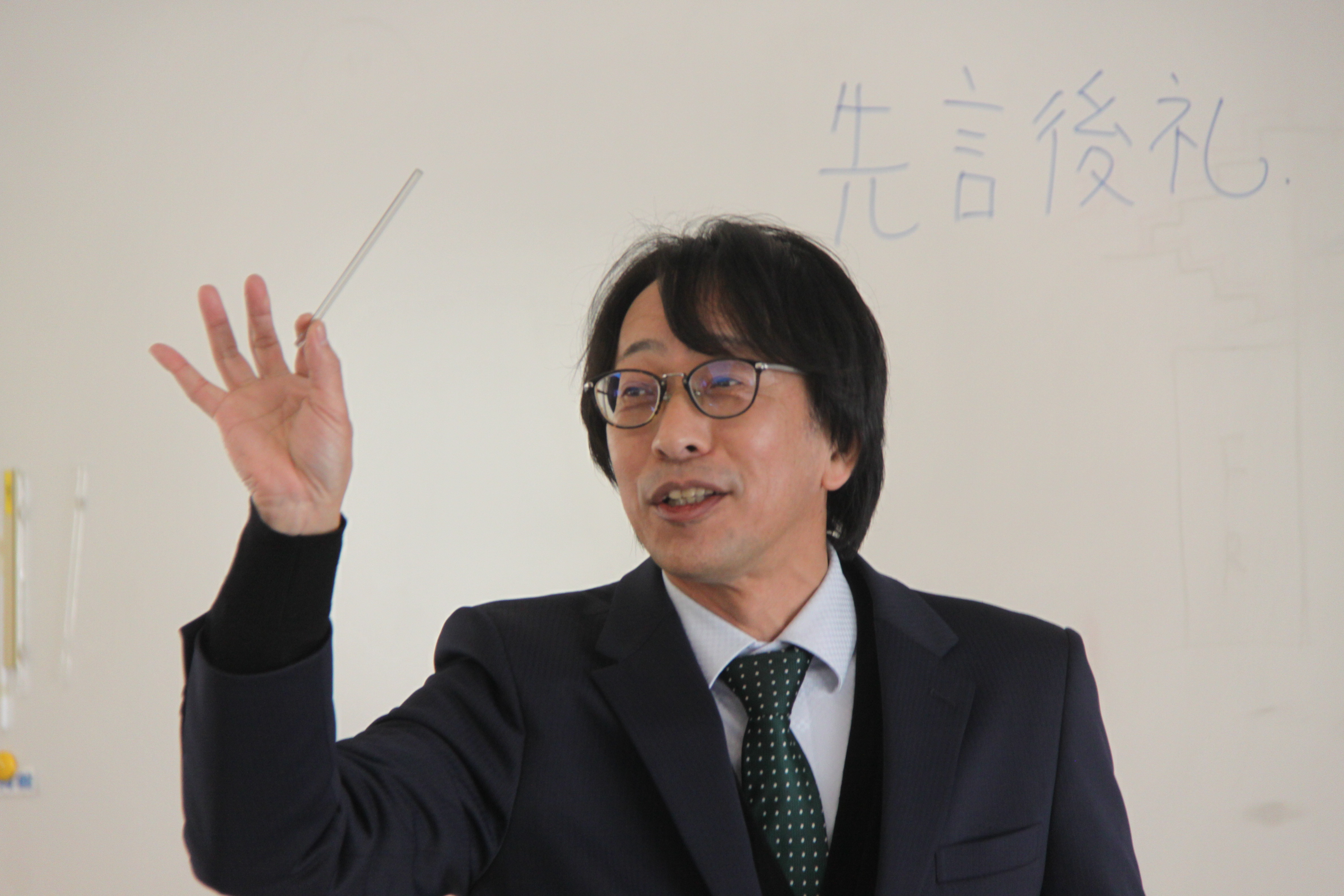




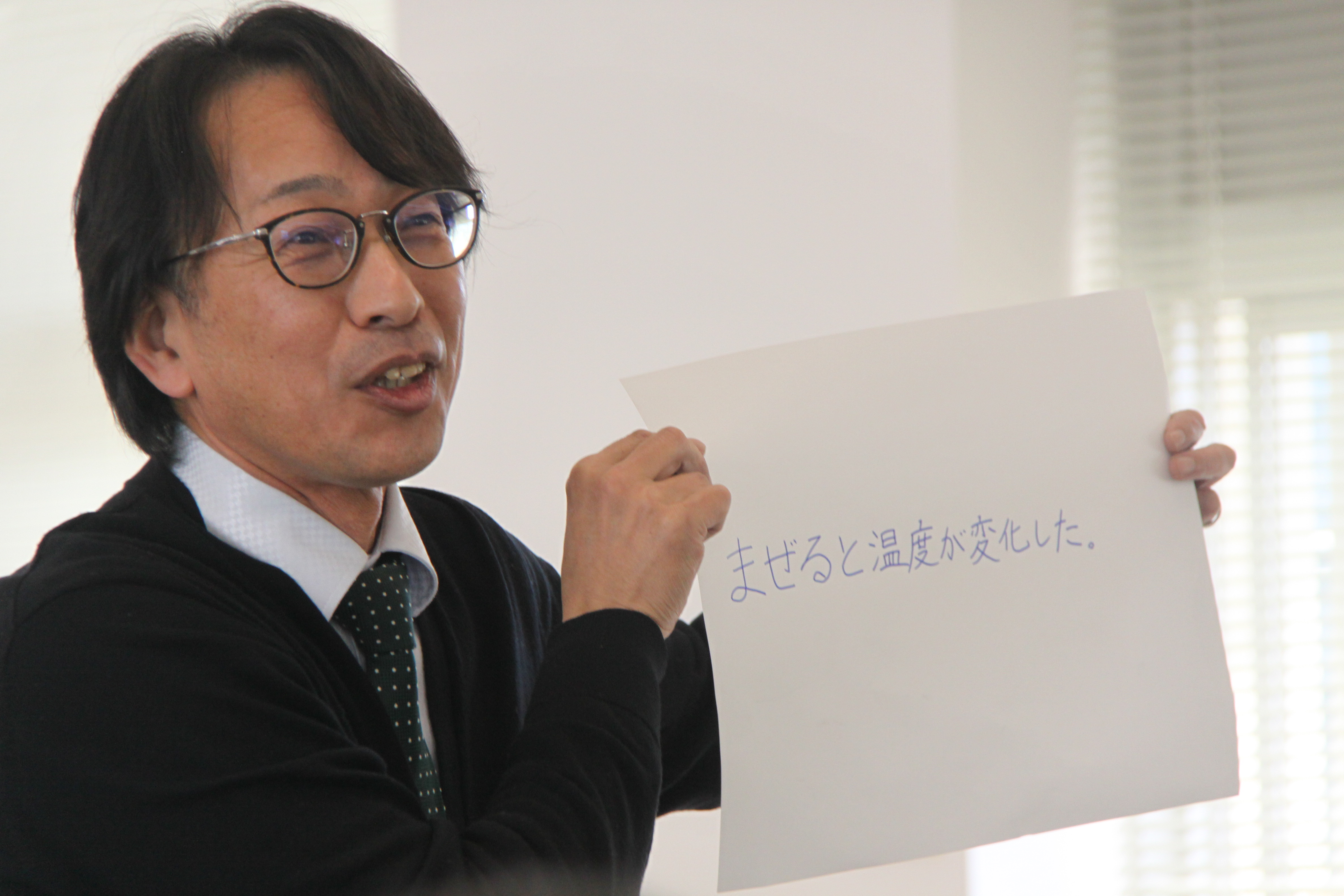
注意深く。
◎今日の日はなにもつけずに召し上がれこの世の甘い味がするから 盛田志保子
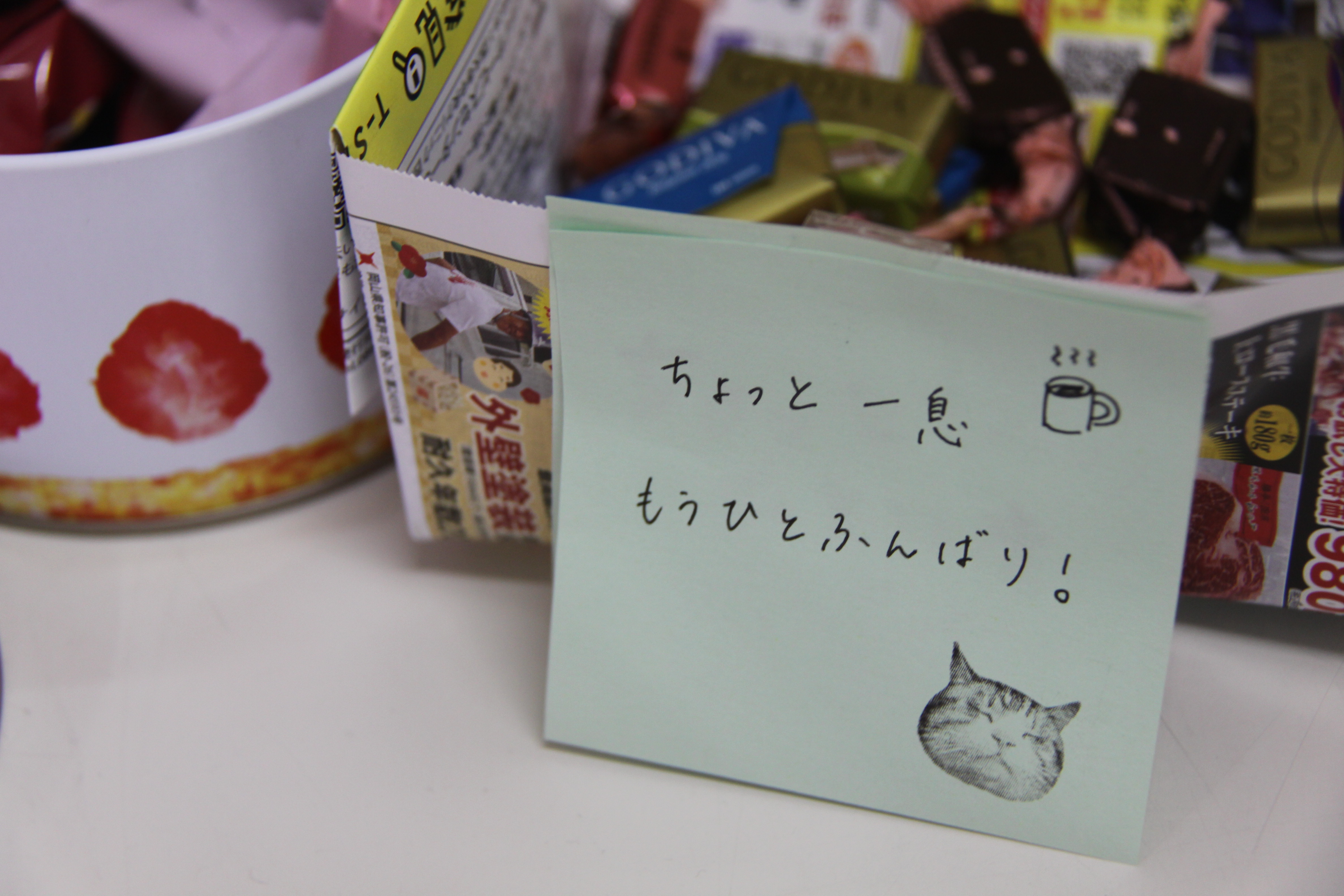
日生中は心理的安全性の高い職場を目指しています。
◎多くの人に支えられて~第8回英会話講座(2/13)
Thank you Jessica!

ちがいを豊かさに。
◎ひな中の風✨ 環境委員会が声かけしています。
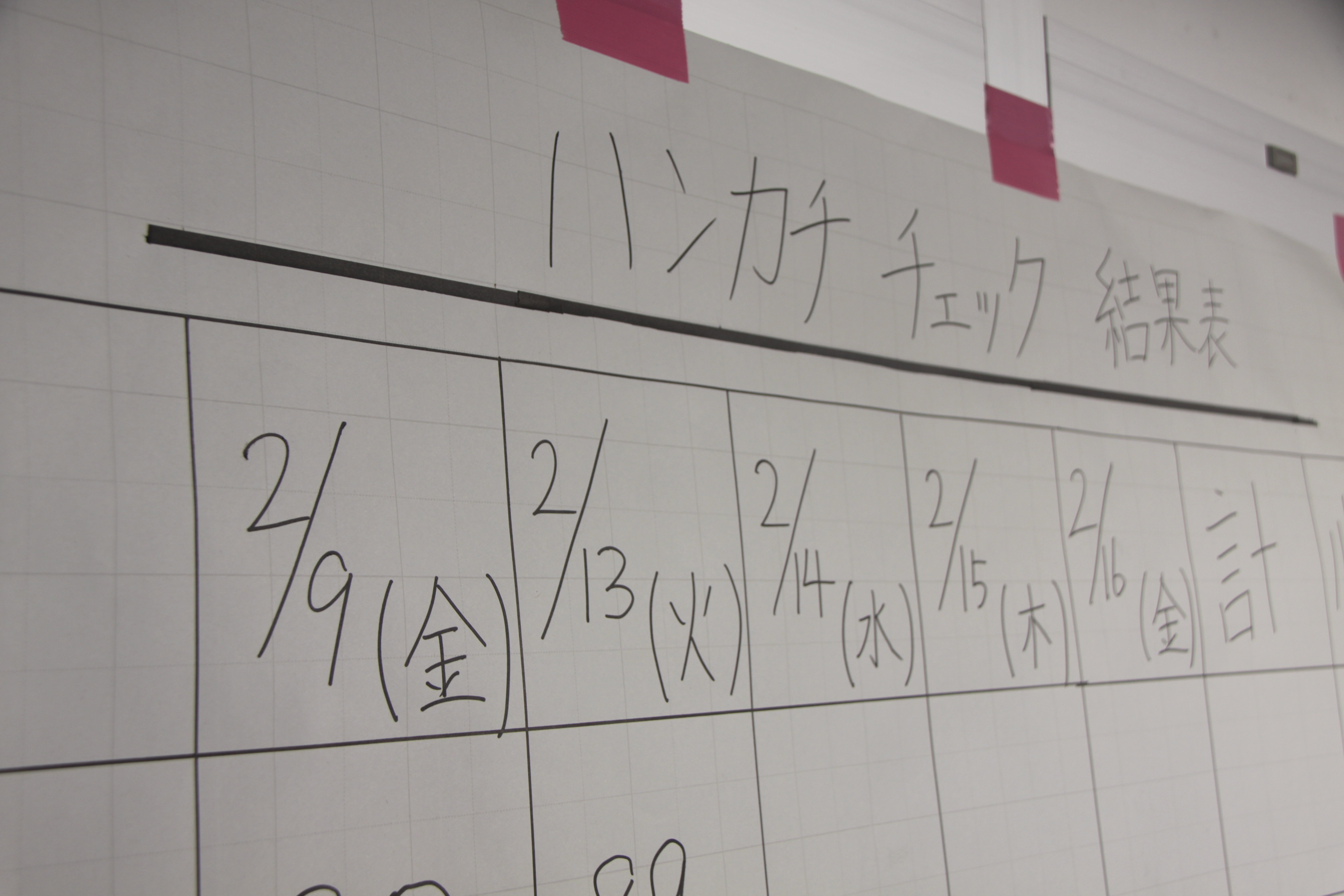
◎ようこそ日生中へ。ようこそ後輩たち。
共に学ぼう!共に進もう!
明日は6年生体験入学(^Д^)。(2/13)
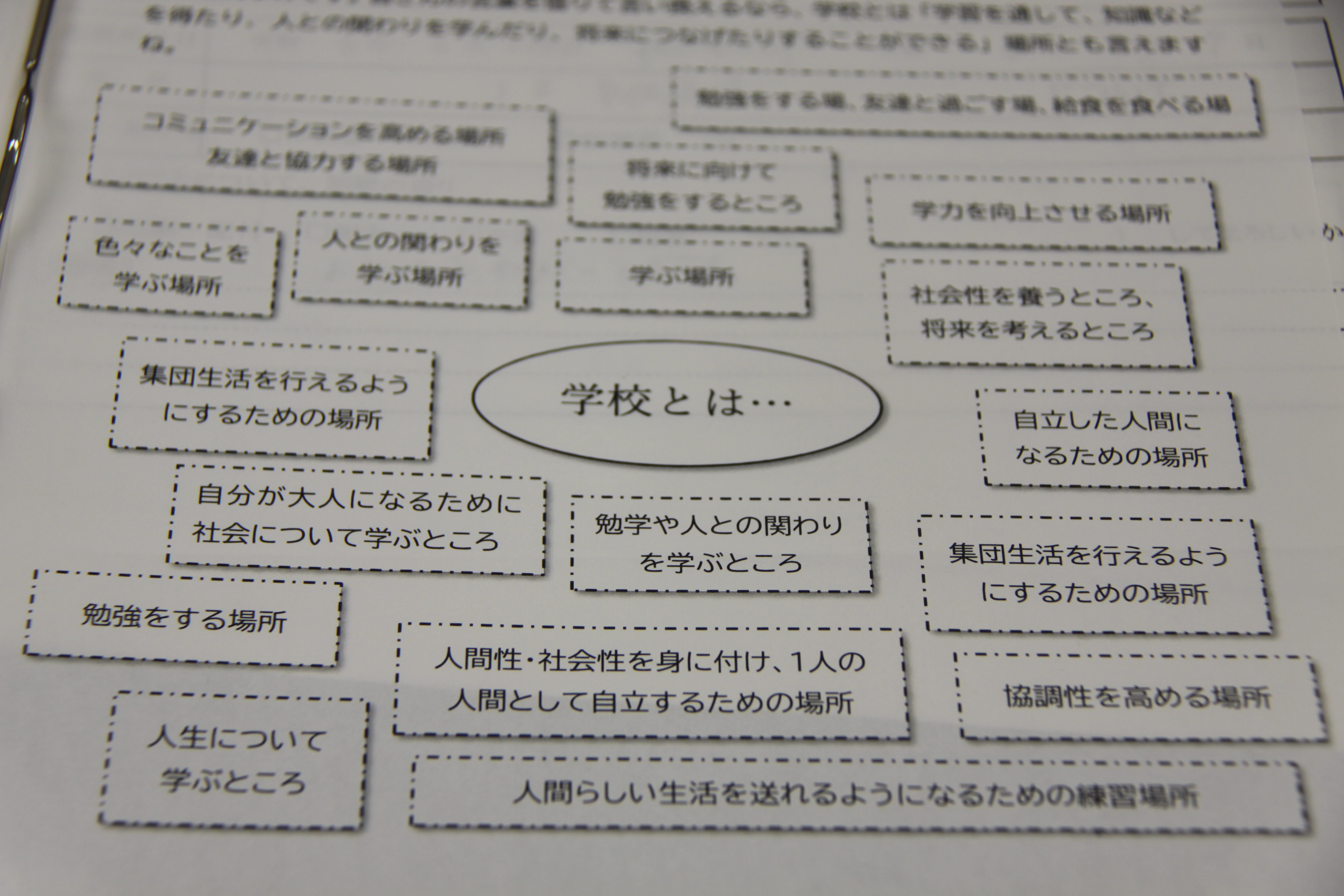

「三年生の学級通信」より。意味深いですね。
◎自分の「得意」なことをいかすことは大事。(2/13)
備前市手をつなぐ育成会研修会で、浦伊部にある社会福祉法人ひだすき ひだすき作業所へ見学に行ってきました。西岡さんから、施設の概要を聞き、所内での活動の見学をさせていただきました。備前焼の陶芸作業をはじめ、機器を分解し、レアメタルを取り出すための機器分解作業等など、利用者の方々一人ひとりが、特性を生かしながら、作業(しごと)に集中されて、真剣に取り組まれる姿をみさせていただきました。ありがとうございました。次回、備前市手をつなぐ育成会の研修会では、15日、ワークセンターひなせを訪ねます。





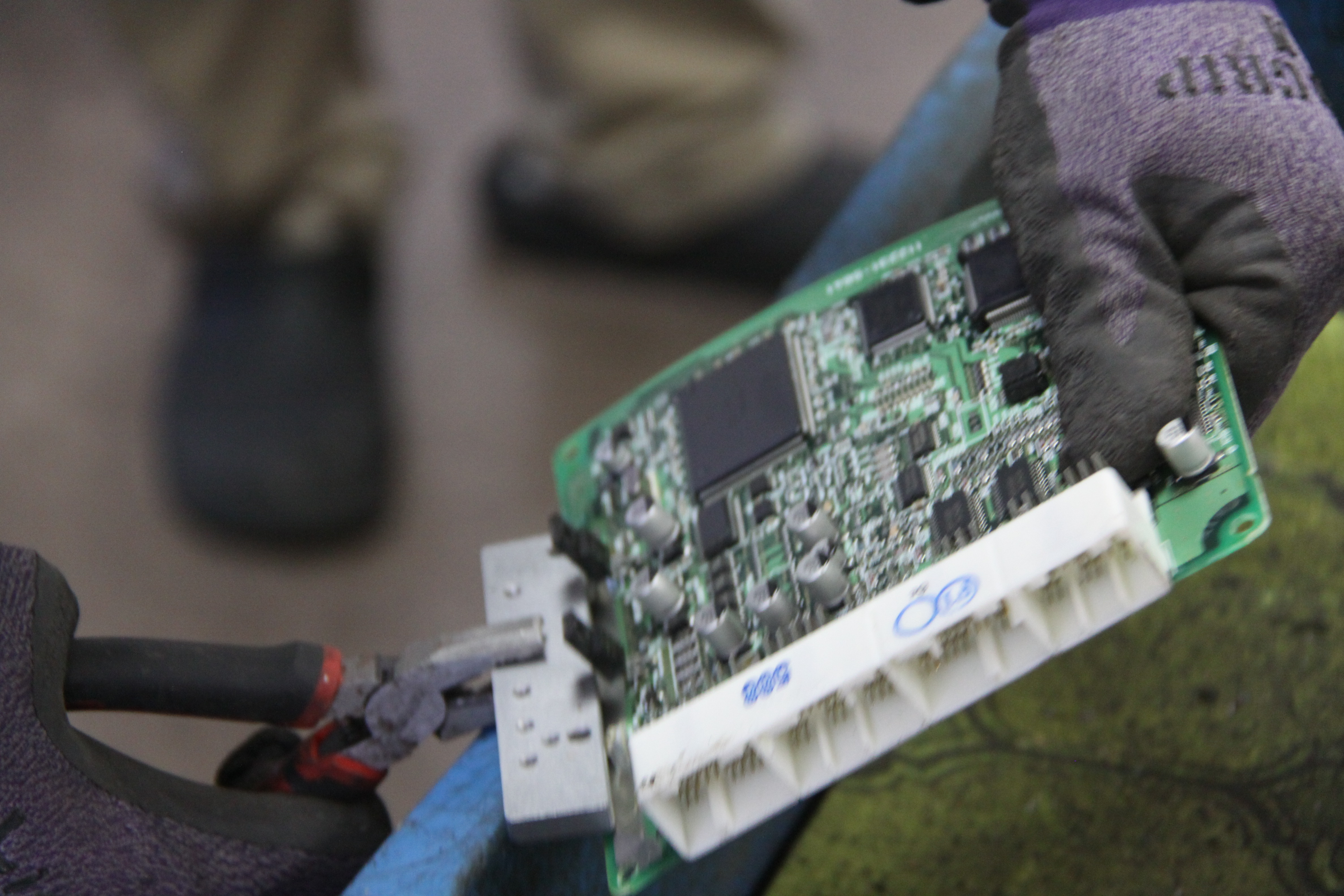



◎地域と共にある学校🎵(2/10)
備前、赤穂、上郡の2市1町から中学校吹奏楽部が集うジョイントコンサートが10日(土)、13時30分(開演)、赤穂市文化会館ハーモニーホールで行われます。6校、100人を越える生徒らが日頃の練習成果を発表します。
東備西播定住自立圏事業として赤穂市吹奏楽団が主催し、日生中も継続的に参加しています。日生中は伊里中・吉永中と合同で15時より、「OLA!」「おジャ魔女カーニバル」「アイドル」を演奏する予定です。ゲスト奏者はクラリネット奏者の上田浩子さんです。また、最後のプログラムは赤穂市吹奏楽団と共に「ジャンボリミッキー」「インビクタ」「学園天国」を合同演奏します。



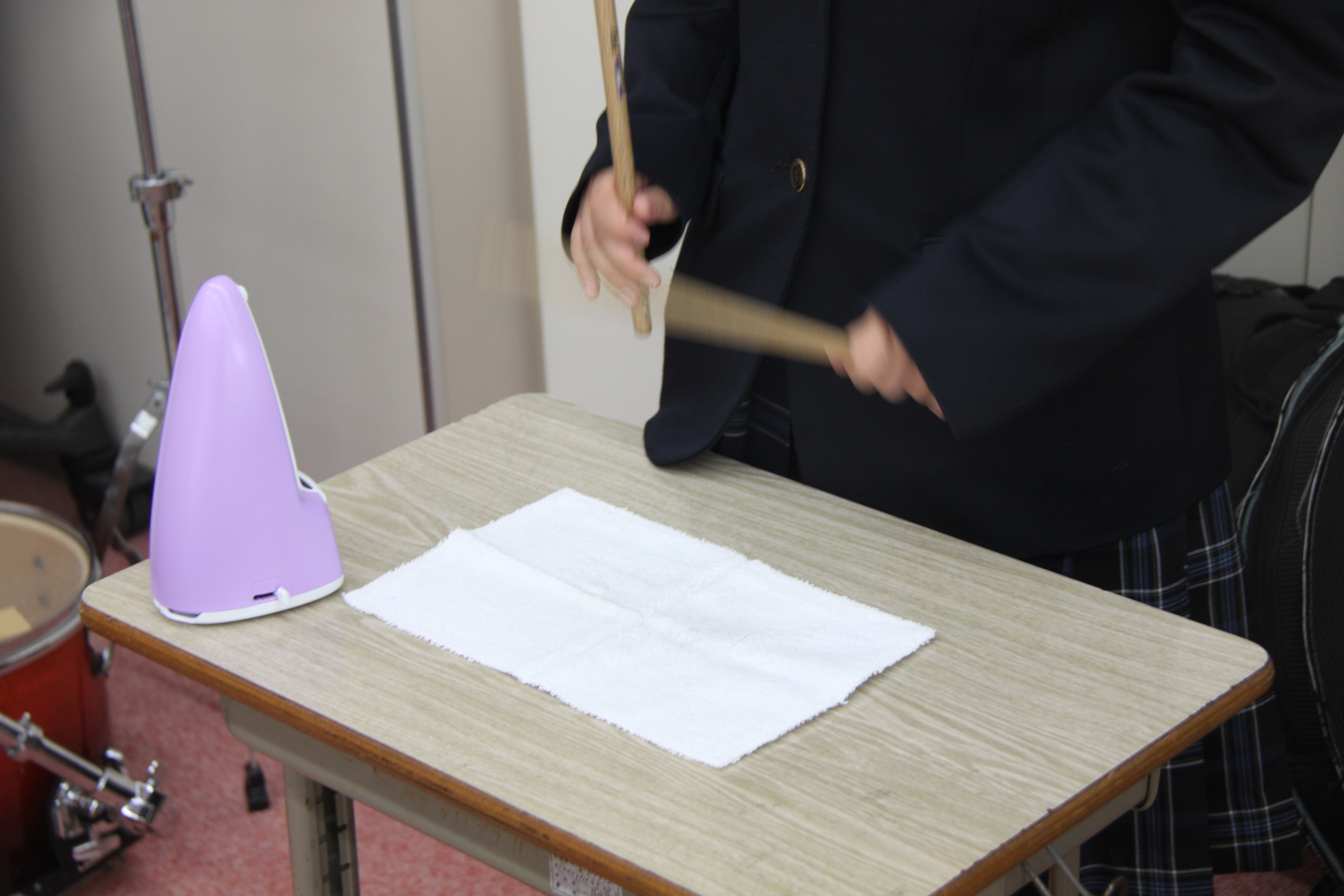

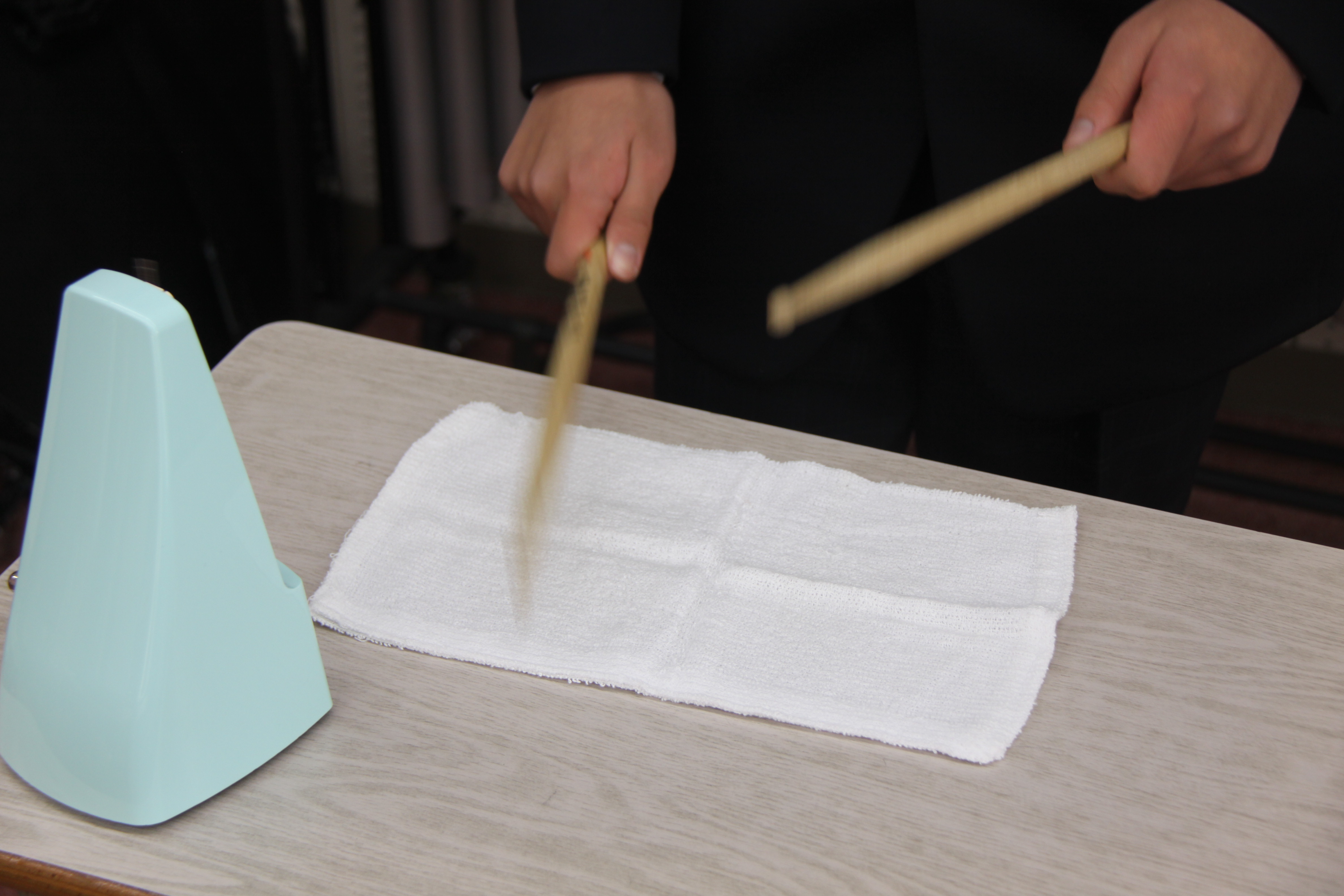
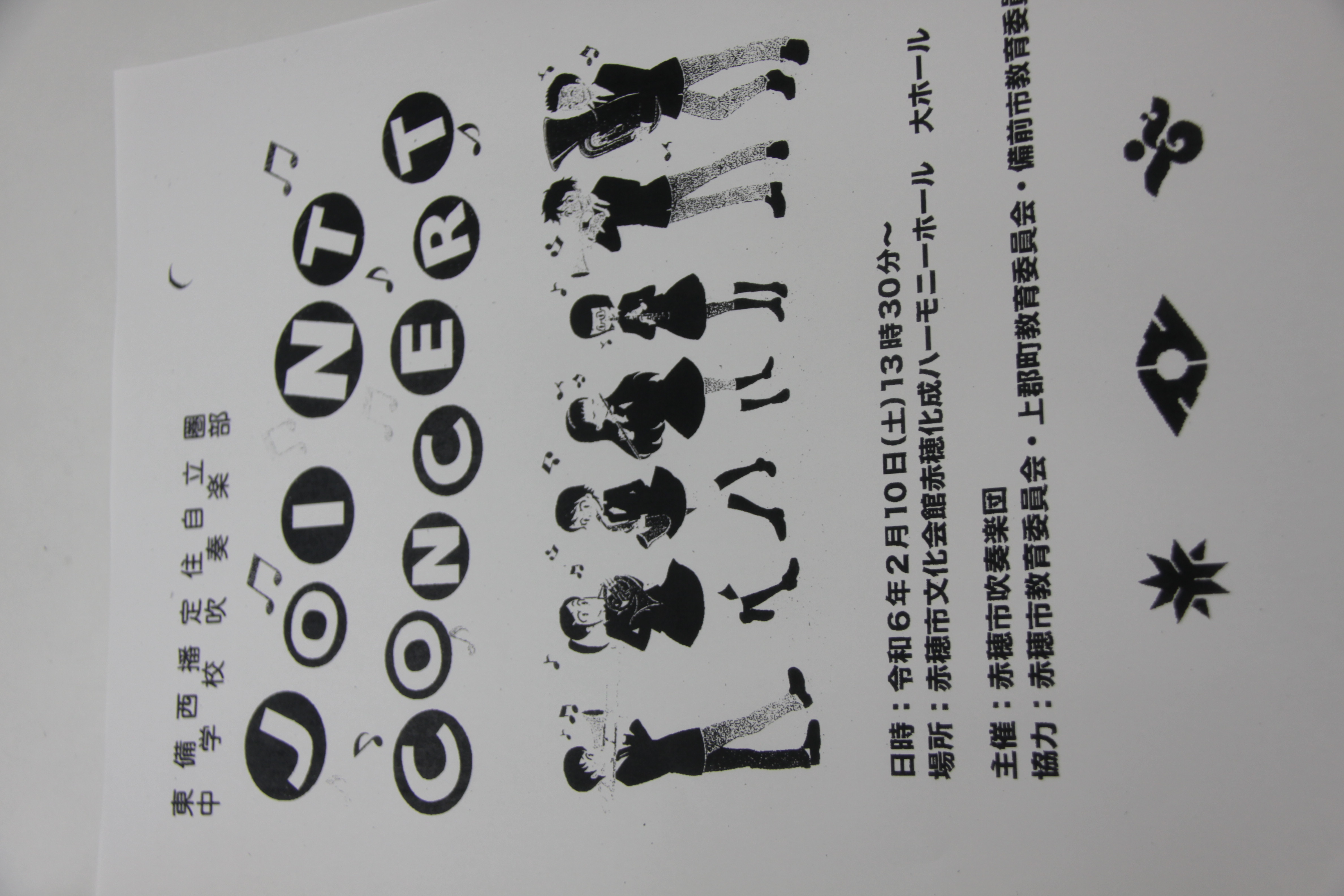
◎地域と共にある学校(2/9)
日生中は食育を大切にしています。先日の調理実習時の事前学習でいただいた資料です。ありがとうございます。

◎さくらさく さくらさききる さくらちる さくらちりきる またさくらさく 石川美南
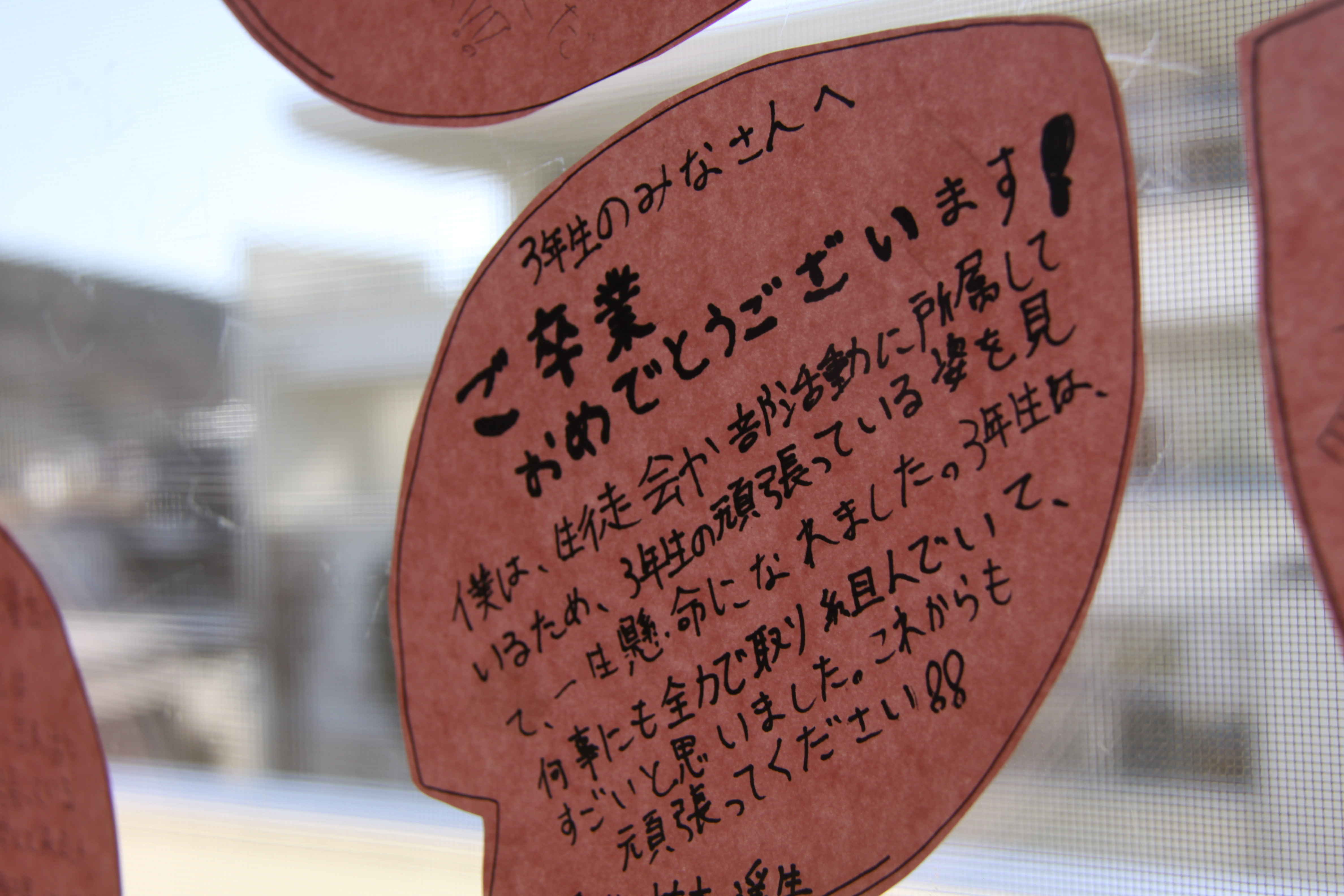

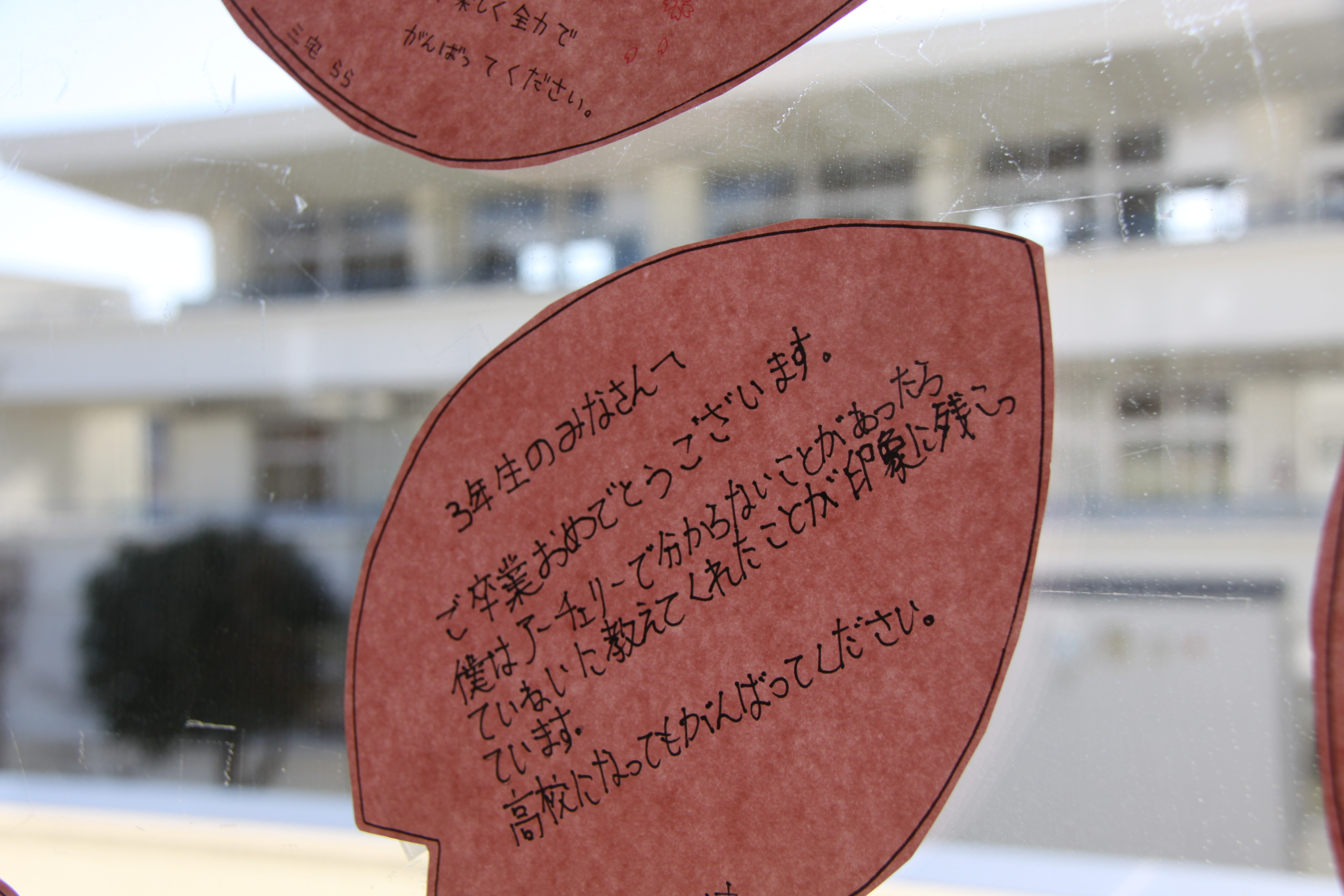

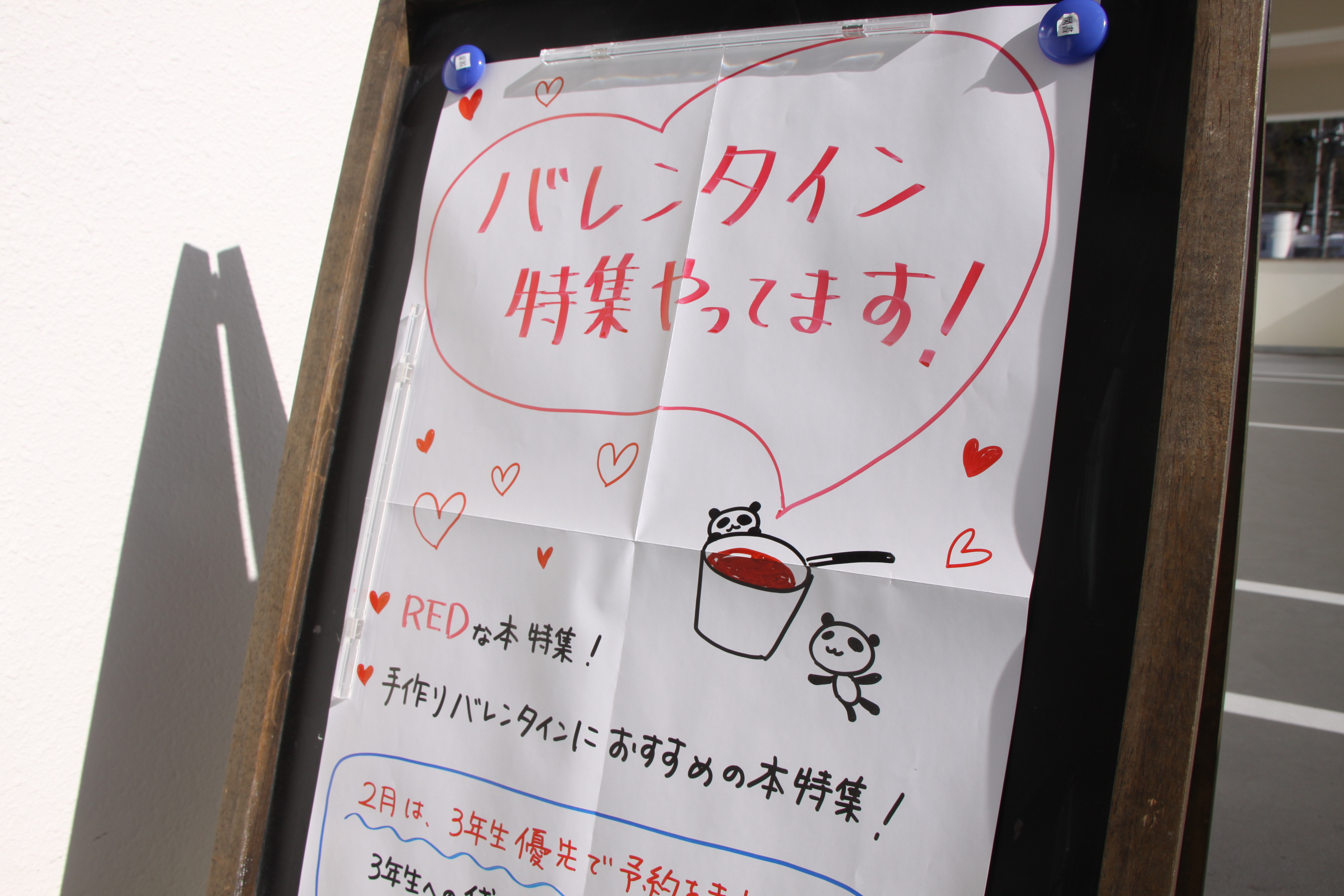

PTA事務局では「季節を感じるおひな様を玄関に飾れたら」と話があります。もし、現在、ご家庭でご使用されていないひな人形があり、中学校に飾ってもよいという方がおられまたら、中学校までご連絡ください。(_ _)

◎地域と共にある学校として(2/8・15)
チヌ(家庭科の調理実習でチヌ(クロダイ)の三枚おろしに挑戦し、また、おいしくいただく調理方法にトライしました。
チヌは、養殖カキや、アサリを食べ、食害が心配されていますが、 詳しい方によると、被害が増えている要因の一つは地球温暖化による海水温の上昇だそうです。チヌは水温が下がると活動量が低下し、冬場は動かなくなります。しかし「1月になっても活動しやすい水温になっていて、群れで生息しているので、1匹が、ノリやカキがエサになると学習すれば、食害が広がる可能性がある」と指摘しておられます。また、漁業関係者によると、人気が高いマダイの漁獲が増え、チヌ(クロダイ)を取る漁師が減ったことも背景に挙げられるそうです。そう考えると、一概に「悪い魚」ではなく、私たち人間社会の環境問題や経済活動も含めて考えていく認識が必要ですね。
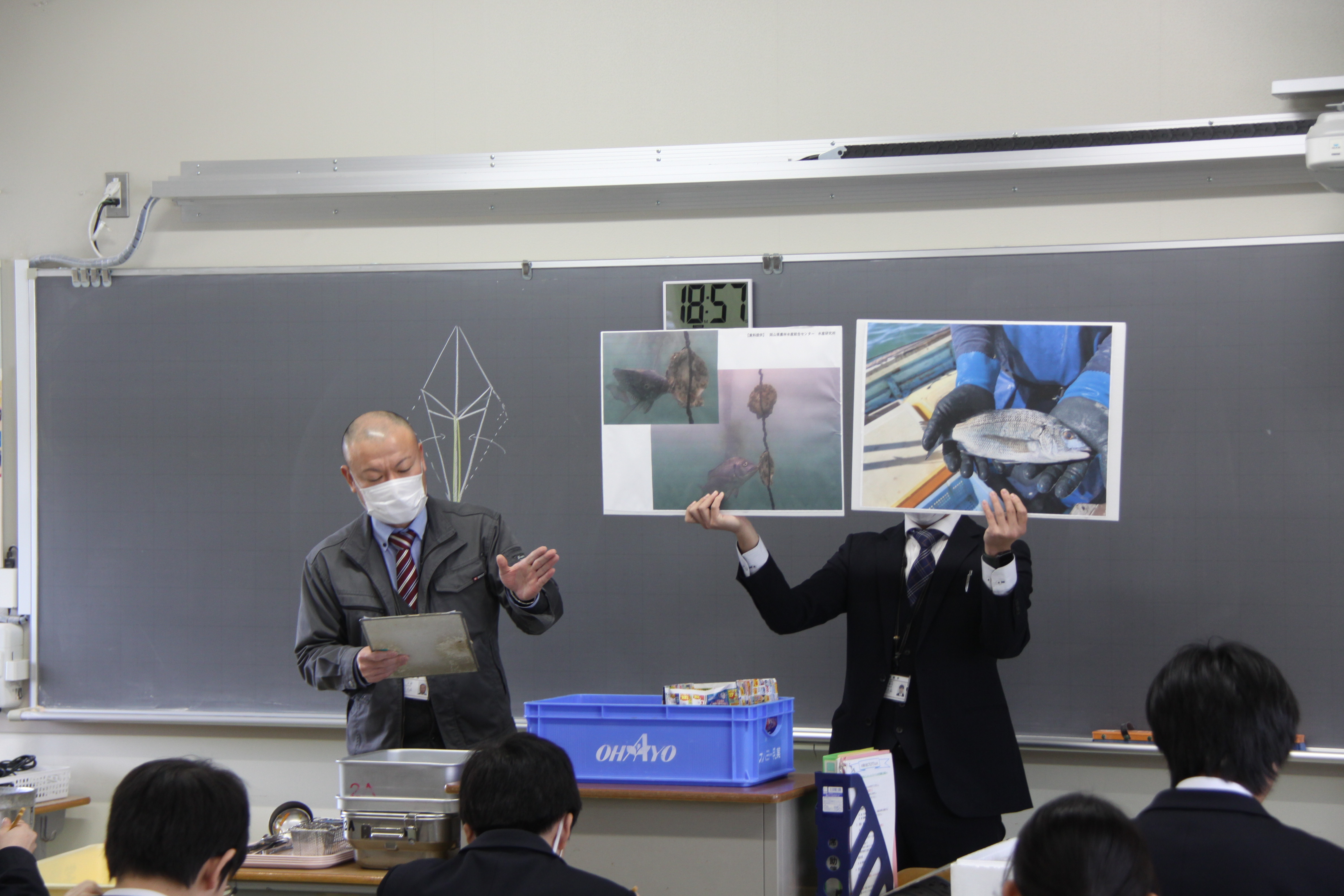











日生漁協さん、備前市農政水産課森田さん、頓宮さん、保健福祉部高山さん、調理場の北川さん、地域おこし協力隊の池上さん、子ども食堂の竹田さん、西日本放送さんをはじめ、多くの方々のご支援で取り組むことができました。ありがとうございました。15日には残りグループの生徒らも調理実週に挑戦します。
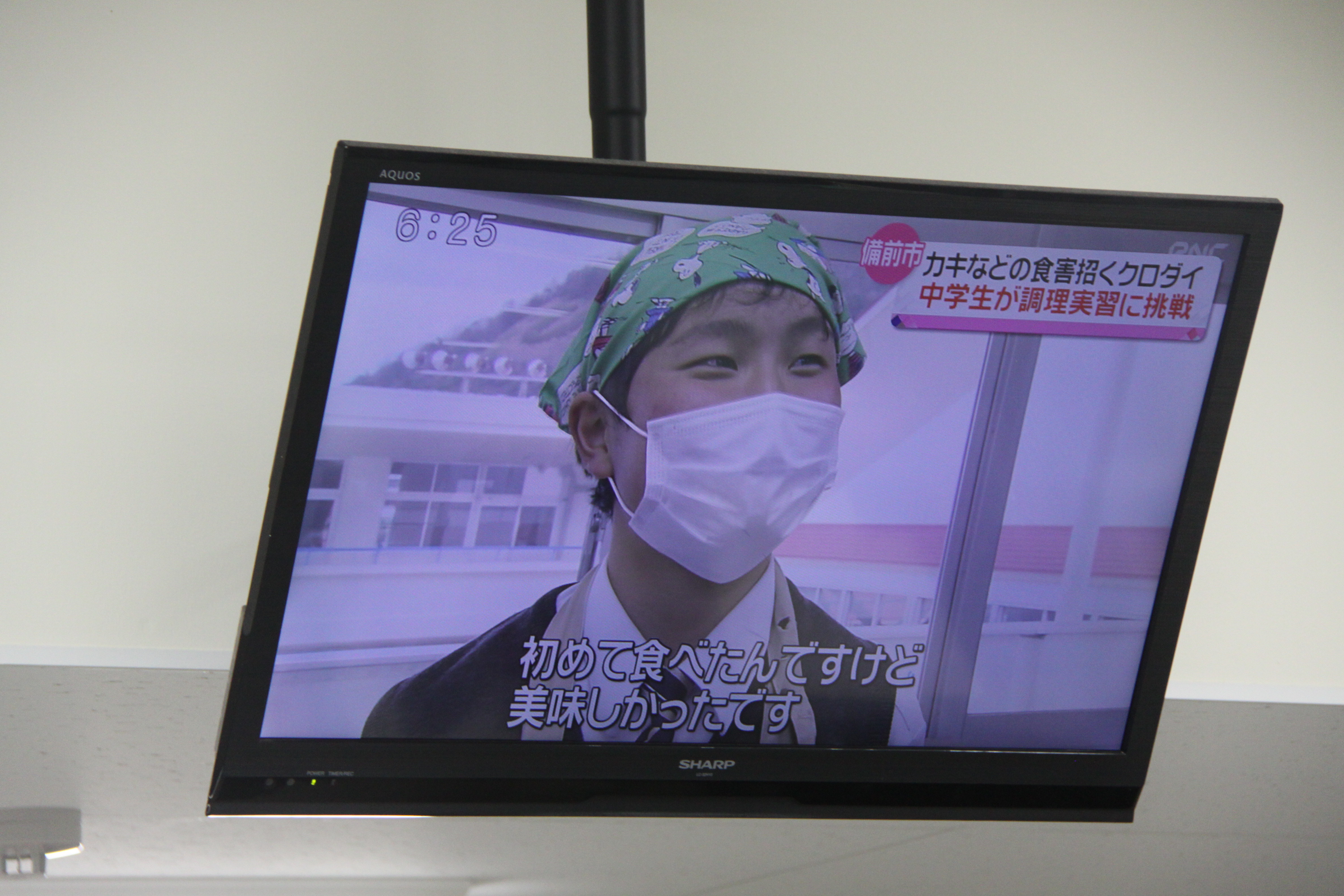

◎知る楽しさ 深める学び
~多文化共生社会へのいざない
Spring letter. Thanks Jessica ∈^0^∋(2/8)

◎道を拓(ひら)く。花は咲く。(2/7・8)
岡山県内の公立高校48校で7日、2024年度特別入試が2日間の日程で行われています。約7600人が出願しており、3月の一般入試に先立ち、共通の学力検査や面接、各校独自の作文などに挑んでいます。
興陽高(岡山市南区藤田)では農業、農業機械、造園デザインなどの5科で行い、特別入試の募集枠計160人に対して248人が受けました。担当者から注意事項の説明を受けた後、午前9時20分から国語、数学、英語の学力検査などに臨んだ。今日、8日は面接です。
生徒の多様な能力や適性をみて選抜する特別入試は14年度に導入され、県立43校と岡山、倉敷、玉野市立の5校で実施。今回は県教委が県立全日制普通科で募集枠の上限を引き上げたことを受けて9校が定員を拡大し、総定員の1万660人の43.9%に当たる4677人を特別入試で募っています。
合格内定者は16日に中学校を通じて通知します。一般入試は3月7、8日に行います。
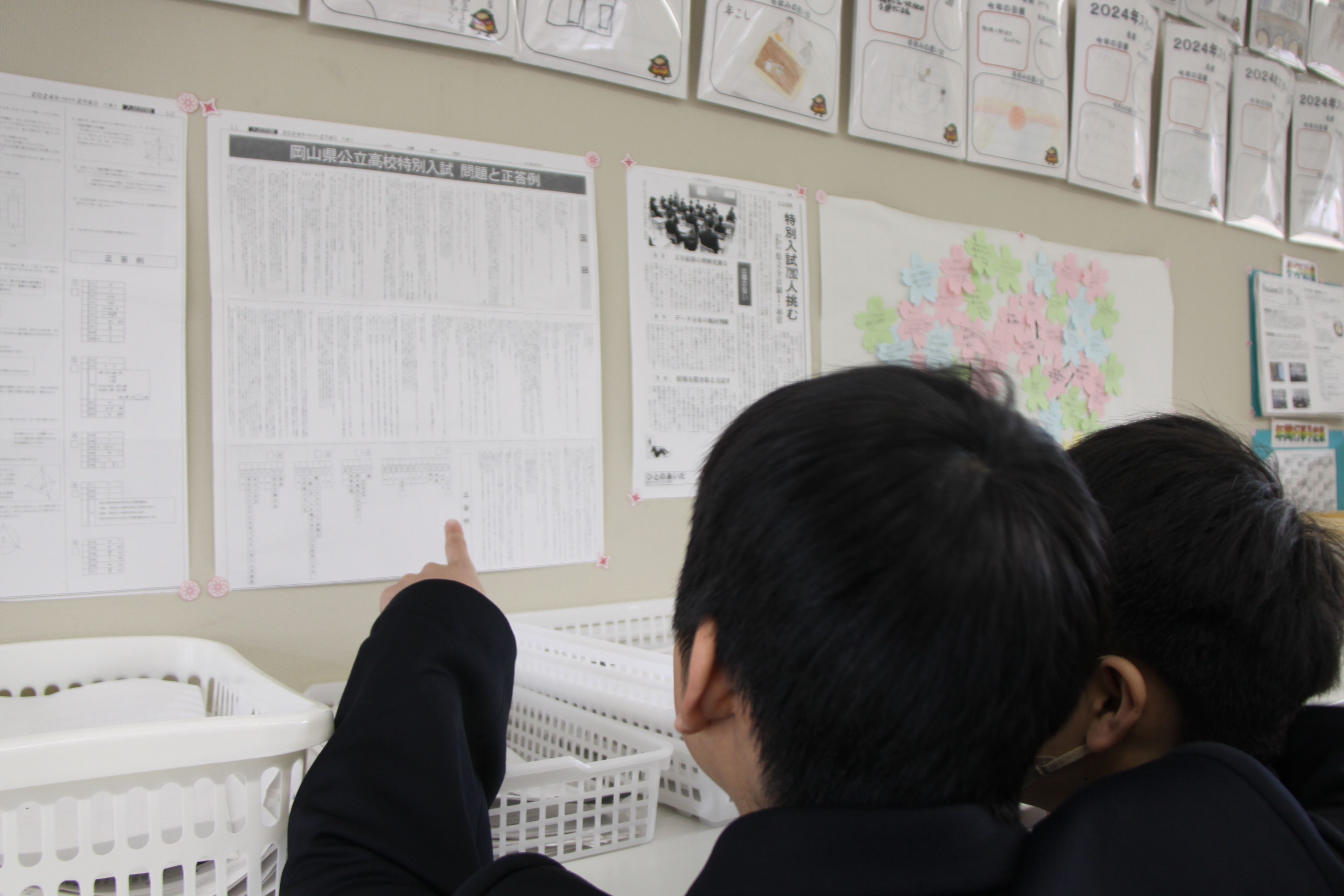
出題された問題を熱心にみる一年生。毎日を大事に、「仲間と共に道を拓いていこう!」
◎C6H12O6+6O2→6CO2+12H2O (2/8)
環境衛生検査のため学校薬剤士さんに来校していただきました。各教室の照度・騒音・CO2濃度を丁寧に測定をして、学習環境の点検をおこないました。気温が低いため換気が不十分のようで、教室の二酸化炭素濃度がとても高い教室がみられました。インフルエンザ・コロナ対策も合わせて、しっかり換気をしなくてはなりませんね。

◎正しく知る 正しく行動する(2/7)
岡山県警スクールサポーターの根木さんが定期的に来校され、子どもたちの地域安全に関する情報交換をおこなっています。この日は特殊詐欺のポスターを持ってきていただきましたので、玄関に掲示しています。詐欺は、大人、高齢者だけの話ではなく、中・高校生が加害者として巻き込まれるいわゆる「闇バイト」等の心配もあります。「正しく知る」学習の機会を大事にして、「正しく行動」出来るひな中生になってほしいと考えます。
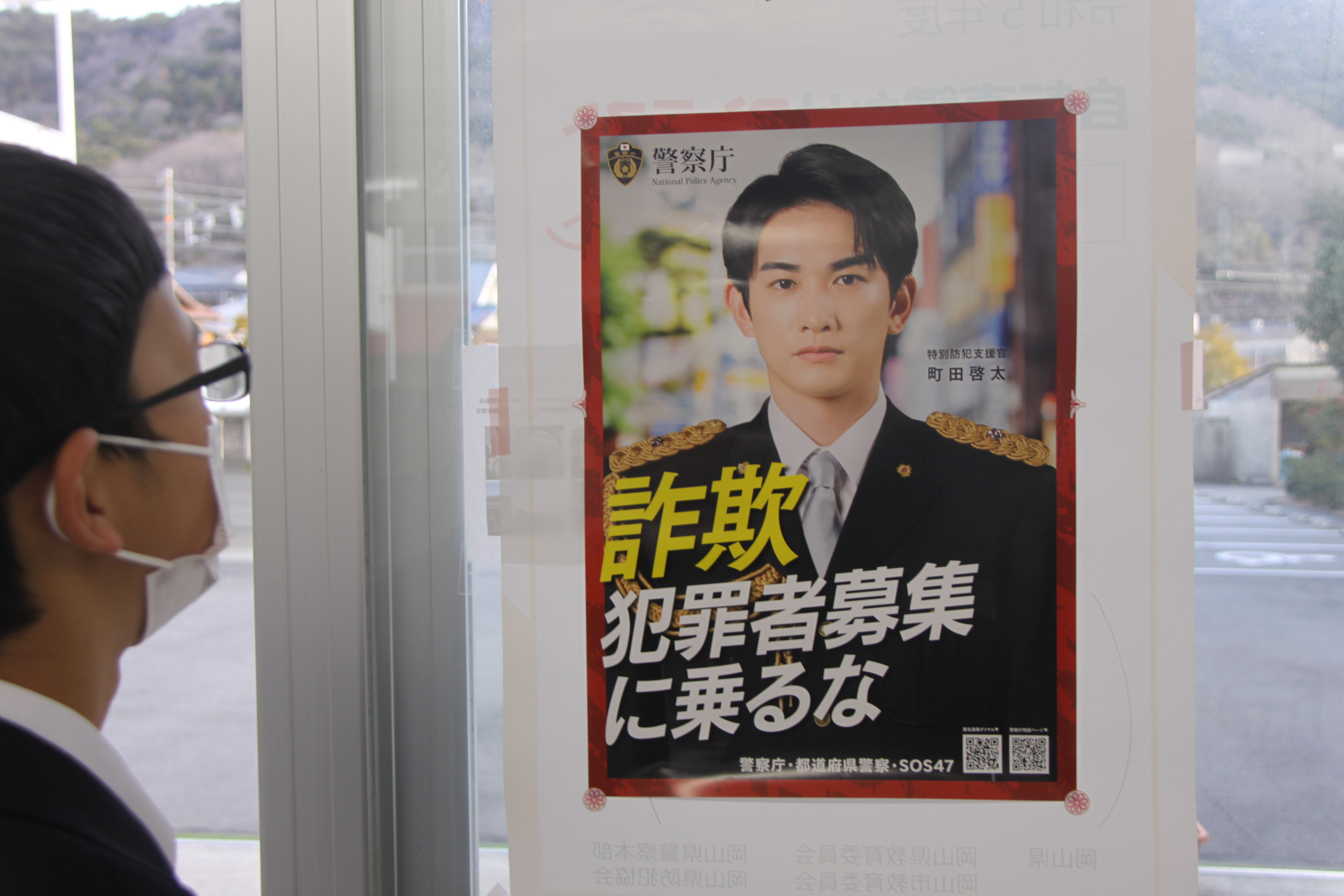
◎多くの人に支えられて(2/7)
週末の盛大な源平放水合戦が終わりました。多くの方の協力、サポートで行事やイベントは成り立ちます。この日、式典会場となった本校グラウンドも丁寧に整備していただきました。ありがとうございます。たくさんの方に支えられて、毎日の生活もあります。


◎〈ともにいきる いま これからの会〉
第3回ひなせ親の会(情報交流会)〈ご案内〉
◎特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。
◎これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。
◎お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。(カウンセリングや講座ではありません)
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)の小寺さんからアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。
ご案内が大変おそくなり、申し訳ありません。お気軽に、申し込み・ご参加ください。
1 日 時 2024年2月14日(水)17:45~19:00
2 場 所 日生中学校 E組教室(北棟1階)
3 内 容 「進級・進学どんとこい!? こころがまえと手立て」
「三年間、六年間を見通した成長をともに」をもとに意見交流
4 参加者 小・中学校の保護者 日生西・日生東小学校・日生中学校の先生
SC SSW 地域おこし協力隊
主催:日生中学校区連携協議会(特別支援教育部会)
ご相談があれば、日生中(久次)0869ー72-1365まで。
5 連 絡 会場準備の都合がありますので、参加の希望をお早めに
(2/9までに)各学校の担当までお知らせください。
◎なお、スクールカウンセラーの教育相談やSSWへのご相談も
各学校に問い合わせください。
6 予 定 新年度第1回:4月8日(火)17:00~18:30(予定)
◎私たちの生徒朝礼(2/6)
~自分から積極的に行動できる~
コロナ・インフルエンザ対策のため、今日の集会は、リモート開催としました。各委員会からの報告、備前市文芸展入賞者表彰等を行いました。


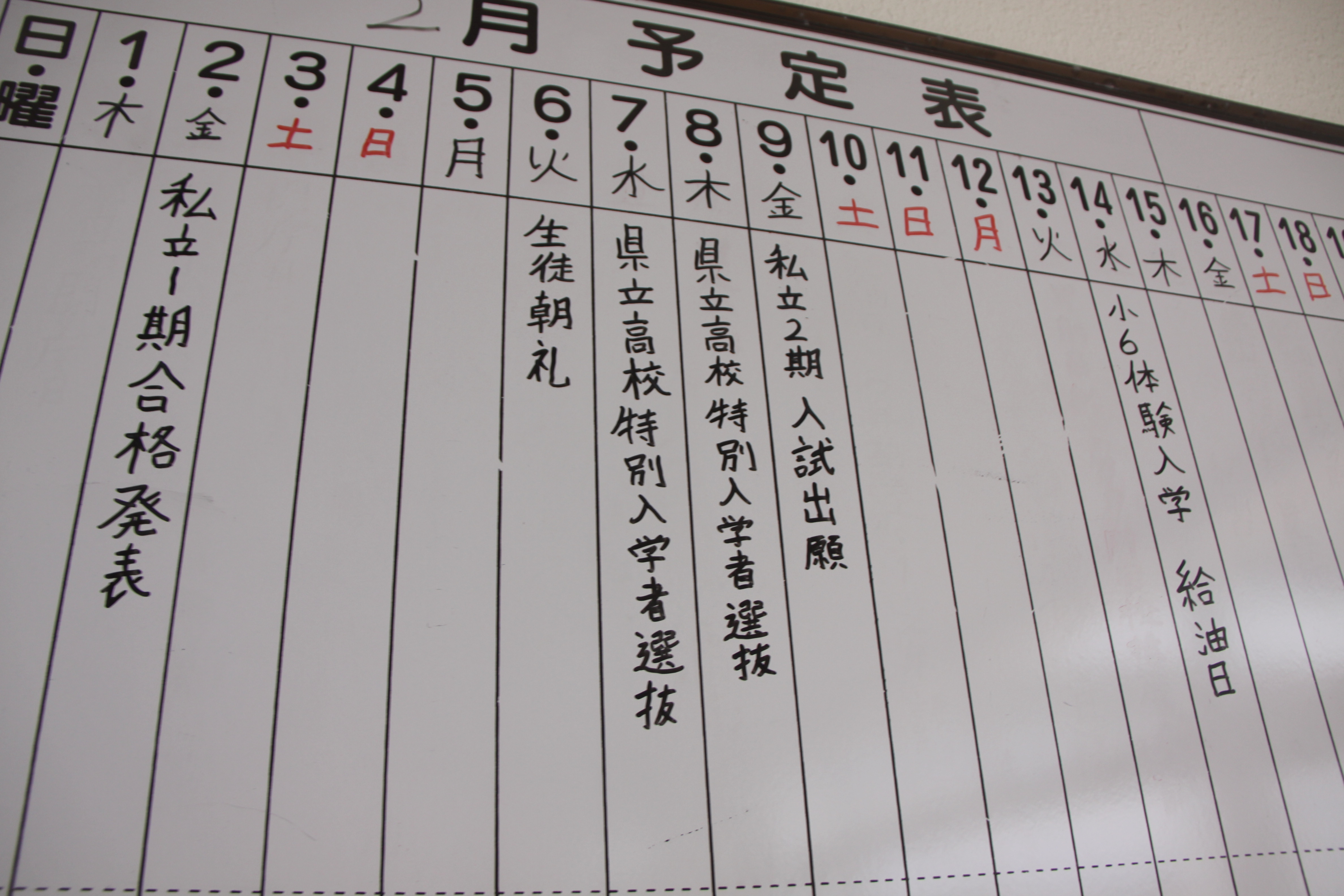

集会後に、生徒会役員たちは必ず「反省・振り返り会」をしています。大事なことですね。
◎多くの人に支えられて(2/6)
今日はリクエスト給食の日。ありがとう。いただきます。



◎ひな中の風
~交通安全第一の登下校を。安全確認OK? 並進してない?(2/6)



地域の方から、登下校について心配のお電話がありました。中学校でも、今一度、交通安全について確認をして、巡回指導、立哨をおこなっています。ご家庭でも、交通安全について話題にしていただければと思います。生活指導部より
◎今日は明日につながる(2/5~)
学年末となり、生徒たちも、授業で学習の振り返りやまとめをすることが多い時期です。先生たちも、自己目標シートをもとに、一年間の教育実践を振り返り、新年度にむけてがんばるための面談をおこなっています。また、教職員同士で学び合うOJT研修会も、研究テーマ「課題に向き合い、自ら学ぶ生徒の育成 ~個別最適化された学びを通して~」について、各チームに分かれて、今年度の実践を振り返っています。(右)。


岡山県市町村(組合)立学校教職員の「新しい教職員の評価システム」に関する実施要綱(趣旨)
第6条 目標管理は、次の各号に掲げる手順により実施する。
(1) 校長は、当該年度の4月の早い時期に、職員のうち目標管理の対象となるもの(以下「対象職員」という。)に対し学校経営目標を提示すること。
(2) 対象職員は、前号の学校経営目標を踏まえ、別表第2に定める職種ごとの職務分類の区分に従い自らの職務上の目標を自己目標シート(様式第1号)に記載し、校長が定める日までに校長に提出すること。
(4) 校長又は教頭(副校長を含む。以下同じ。)は、自己目標シートに関し、対象職員と当初面談を実施し、適切な目標を設定できるよう指導及び助言を行うこと。この場合において、対象職員は、必要に応じて目標の追加又は修正を行うこと。
(5) 校長及び教頭(以下「校長等」という。)は、対象職員の職務遂行状況の観察等を通して、目標の達成に向けての取組状況の把握に努め、適宜、適切な指導及び助言を行うこと。
(6) 対象職員は、設定した目標の達成状況について自己目標シートに記載し、当該年度の中途における校長が定める日までに校長に提出すること。
(7) 校長又は教頭は、自己目標シートその他必要な事項に関し、対象職員と中間面談を実施し、指導及び助言を行うこと。この場合において、対象職員は、必要に応じて目標の修正又は変更を行うこと。
(8) 対象職員は、設定した目標の達成状況についての自己評価を自己目標シートに記載し、当該年度末における校長が定める日までに校長に提出すること。なお、自己目標シートに記載する場合においては、別表第3に定める自己評価の段階評価の区分に従い評価を行うこと。
(9) 校長又は教頭は、自己目標シートその他必要な事項に関し、当該年度の3月末日までに対象職員と最終面談を実施し、目標の達成状況、自己評価及び次年度への課題等について、指導及び助言を行うこと。(一部)
◎わたしたちの日生
~春をみんなで迎えよう(2/4)

源平放水合戦は備前市消防団日生方面隊が消防団員の士気を高めようと出初式の日に毎年行っているものです。5つの分団の若者たちが源氏側と平家側に分かれ、船の上から放水合戦を行いました。この日は立春。日中は風も少なく比較的穏やかでしたが、さすがに、冬場の放水ですので消防団員さんはとても寒かったように見えました。約20分間続いた勇壮な放水合戦。最後は5色の水が空高く放水され、1年の無事を祈りました。会場の日生漁港には県の内外から多くの見物客が訪れ、勇ましい日生の消防団員の様子などを写真に撮るなどして楽しんでいました。とても大事にしている本行事を校長も参観させていただきました。ありがとうございました。
◎立春(2/4)

立春とは、二十四節気(にじゅうしせっき)において、春の始まりであり、1年の始まりとされる日です。
二十四節気は紀元前の中国で生まれた、太陽の動きに基づいたこよみです。1年を4つの季節に分け、さらにそれぞれの季節を6つに分割しています。
4×6=24なので、二十四節気…ということですね。四季の最初が、立春、立夏、立秋、立冬。この4つは「四立(しりゅう)」と呼ばれています。禅宗のお寺などでは「立春大吉」とかかれたお札を、家の入口に貼る風習があります。一年の始まりに、招運来福を願う意味があるとされ、門をくぐって家に入ってきた鬼もこのお札を見ると出ていくのだとか。
◆立春の頃の植物
「立春」があるのは2月のはじめ。寒さが厳しい時期ですが、少しずつでも春に近づいていることを教えてくれる植物はいくつかあります。このころに咲くのは、丸くて可愛らしい花を咲かせる「ヒナギク」や、明るい黄色の花を咲かせる「フクジュソウ」があります。「フクジュソウ」は漢字で書くと、「福寿草」。漢字がめでたく、縁起のいい植物です。
また、この時期に咲く植物で忘れてはいけないのが、「梅」。どこからか梅の華やかな香りを感じて、「もうすぐ春が来るなぁ」と感じたことのある方もいるのではないでしょうか?
◆立春に汲む若水
元旦の朝に井戸から汲んだ、一年で最初の水のことを「若水」と言います。この「若水」は、神棚に添えたり、食事の支度に使われますが、実は元々は「立春」に行う行事だったのです。一年の最初に汲んだ「若水」には、若返ったり、邪気をはらったりする力があると言われています。現在では正月の風習として浸透していますが、2022年の「立春」には、「若水」で淹れたお茶、「福茶」を飲んでみるのもオススメです。
◆立春の食べ物
「立春」に食べるものの中に、「立春朝生菓子」というものがあります。この「立春朝生菓子」というのは、「立春」の朝に作られて、その日のうちに食べられる生菓子のことです。主に桜餅やうぐいす餅など、春を感じられる生菓子が食べられます。また、小豆には穢れを払う力があるとされていることから、「立春」の朝に作られた大福も縁起がいいと言われていますよ。他にも、体を清める力があるとされている「豆腐」を食べる風習もあります。生菓子を作るのが難しい、という方は、その日に作られた大福や豆腐を買って食べるようにしてみてはいかがでしょうか。
◎多くの人に支えられて✨
今年も、ひな中チャレンジ企画
~ワクワク 仲間たちと 楽しく学ぶ~
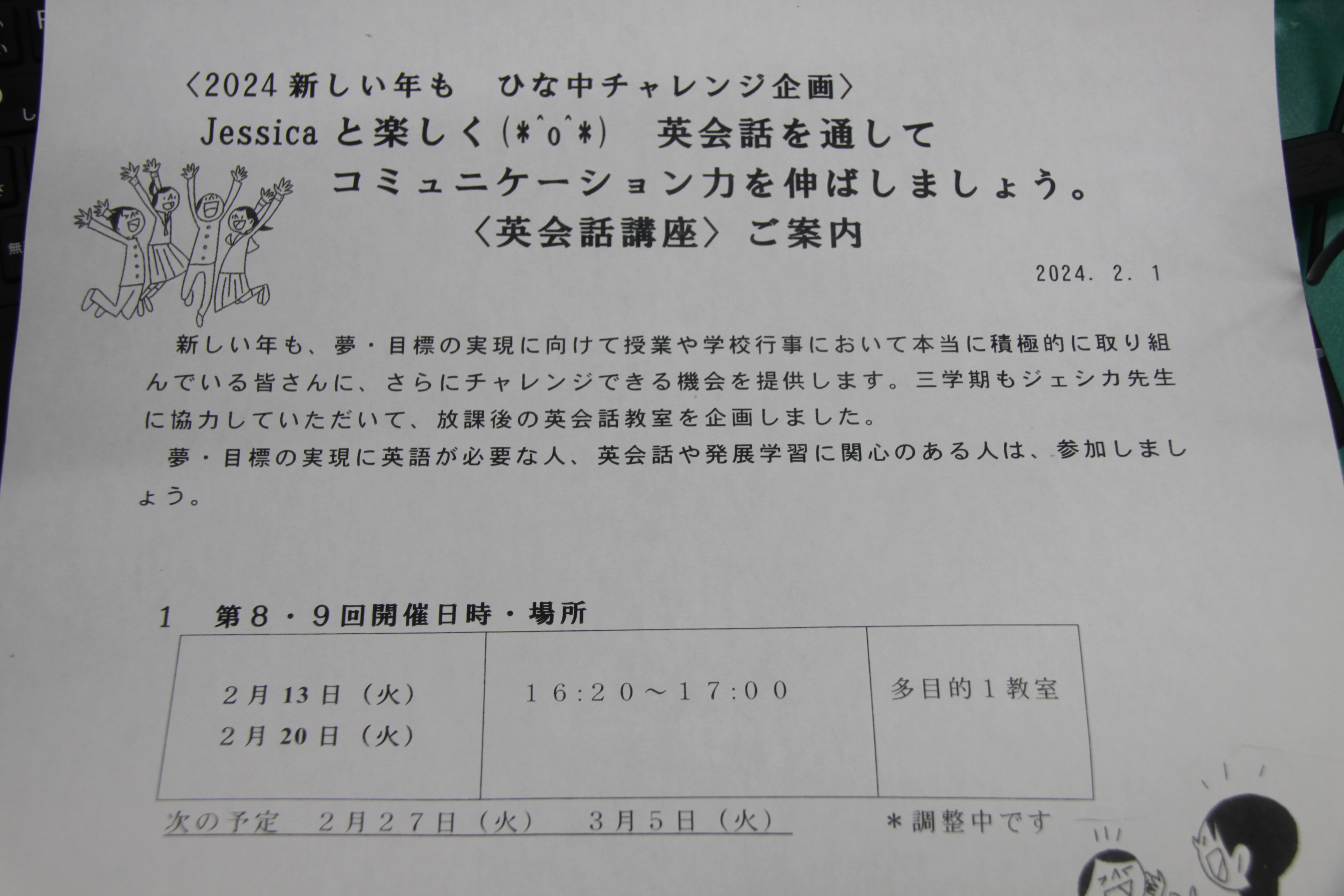
2/9〆切。Step by step. I can’t see any other way of accomplishing anything. Michael Jordan
(ステップ・バイ・ステップ。どんなことでも、何かを達成する場合にとるべき方法はただひとつ、一歩ずつ着実に立ち向かうことだ。これ以外に方法はない。)
◎差し入れのコーヒーは友のほっぺたにひゅるりと当ててから渡すのだ 千葉聡(改)
2月2日、私立一期入試結果発表日。専願受験で決定した人、第1志望校受験をこれから目指す人、再チャレンジする人、これからも共に歩いていくよ。






Today is your day! Your mountain is waiting. So… get on your way. Dr.Seuss
(今日という日は君のためにある!君の登るべき山が待っている。さあ、出発だ。)
◎メディアについて考える講演会開催(2/1)
備前市地域包括支援センターの岸本直子先生をお招きして、「子どもの姿勢・体力を見てみよう!~メディアが心と体に与える影響」についてお話を聴きました。この日は、日生西小学校6年生の子どもたちも一緒に学びました。本会は、毎年、日生町メディアコントロール連絡会が主催し、こ・小・中の連携を大切に継続的に進めています。また、PTA保護者の方で、一緒に学びたい内容やお話を聴かれたい講師等のご希望がありましたら、学校までご相談ください。

Our problems are man-made; therefore‚ they can be solved by man. Man’s reason and spirit have often solved the seemingly unsolvable. I believe they can do it again. John F. Kennedy
(私たちが抱える問題は、人間が作り出したものだ。したがって、人間が解決できる。人間の理知と精神は、解決不可能と思われることもしばしば解決してきた。これからもまたそうできると私は信じている。)
◎地域とともにある学校。(2/1)
日生の子ども食堂へ、サッカーボールを持っていきました。楽しくあそんでね。

We are all travelers in the wilderness of this world‚ and the best we can find in our travels is an honest friend. Robert Louis Stevenson
(私たちは、この世の荒野を旅する者であり、旅の途中で見つけることのできる最高のものは正直な友人である。)
◎ひな中の風✨(2/1)
~待ってるよ。2月14日は新入生体験入学(*^o^*)
生徒会中央役員を中心に、体験入学に向けて、部活動紹介VTRを作成しています。


◎ひな中の風✨
~チ・ヌ・サ・バ・キ・マ・ス〈2月8・15日〉
この日、家庭科での調理実習の2回目の打ち合わせに、備前市地域おこし協力隊の池上さん(調理師免許を持たれています!)が来校されました。8日と15日に2年生は、市農政水産課さんの協力をいただき、チヌを使った調理実習に取り組みます。

岡山では“チヌ”と呼ばれる「クロダイ」は、秋から春にかけてが旬の瀬戸内海を代表する魚です。かつては高級魚として扱われていましたが、近年は魚離れなどで消費量とともに漁獲量が減少しています。そして、海に生息する数が増加し、温暖化によって寒い時期の活動も活発になったため、岡山特産ののりやかきの稚貝を食べてしまう被害が増えています。このため県漁連などは、チヌの消費を拡大して、食害を減らそうと取り組みを進めています。
調理実習では、まずは三枚におろし、どんな調理方法がよいか、いくつかの味付けに挑戦する予定です。
◎2月・如月
今日から最終下校時刻は17:30(2/1~)
「きさらぎ」の由来には諸説ありますが、もっとも有力視されているのは、「衣更着」(=「衣を更に着る」)です。立春を迎えるとはいえまだまだ寒い日が多いため、重ね着をする月だという意味だそうです。一方でほかにも、徐々に暖かくなり木々が芽吹くことから「生更木」、次第に春の気配を感じ陽気になっていくことから「気更来」などの説もあります。いずれも、日差しが力強さを取り戻して、ただ単に寒いだけではない2月の特徴をよく言い表していますね。
他にも、小説や俳句、手紙などでは、如月の他にも様々な2月の異名が使われています。たとえば、「木芽月(このめづき)」や「梅見月(うめみづき)」、「雪消月(ゆききえづき・ゆきげつき)」など。立春以降、少しずつ春本番に向かっていく2月の変化をこまやかに捉えていて、まだまだ寒い日が多くて気持ちが落ち込みそうになる2月の気分を変えてくれそうな言葉たちです。
明日は私立一期入試の結果発表日です。

◎もう苛めないよと呼べば押入れからうつむきながら鬼が出てくる 石川美南

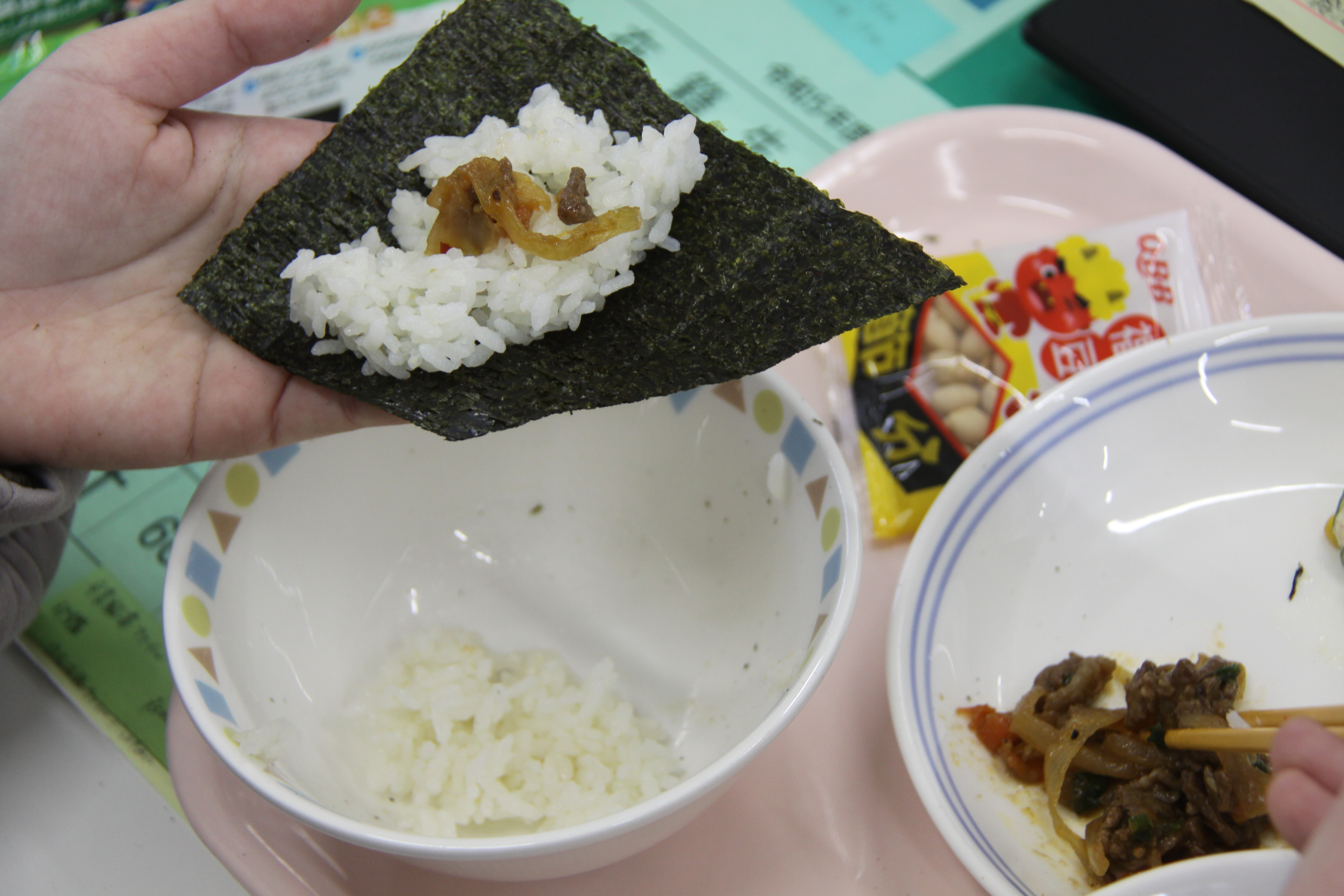
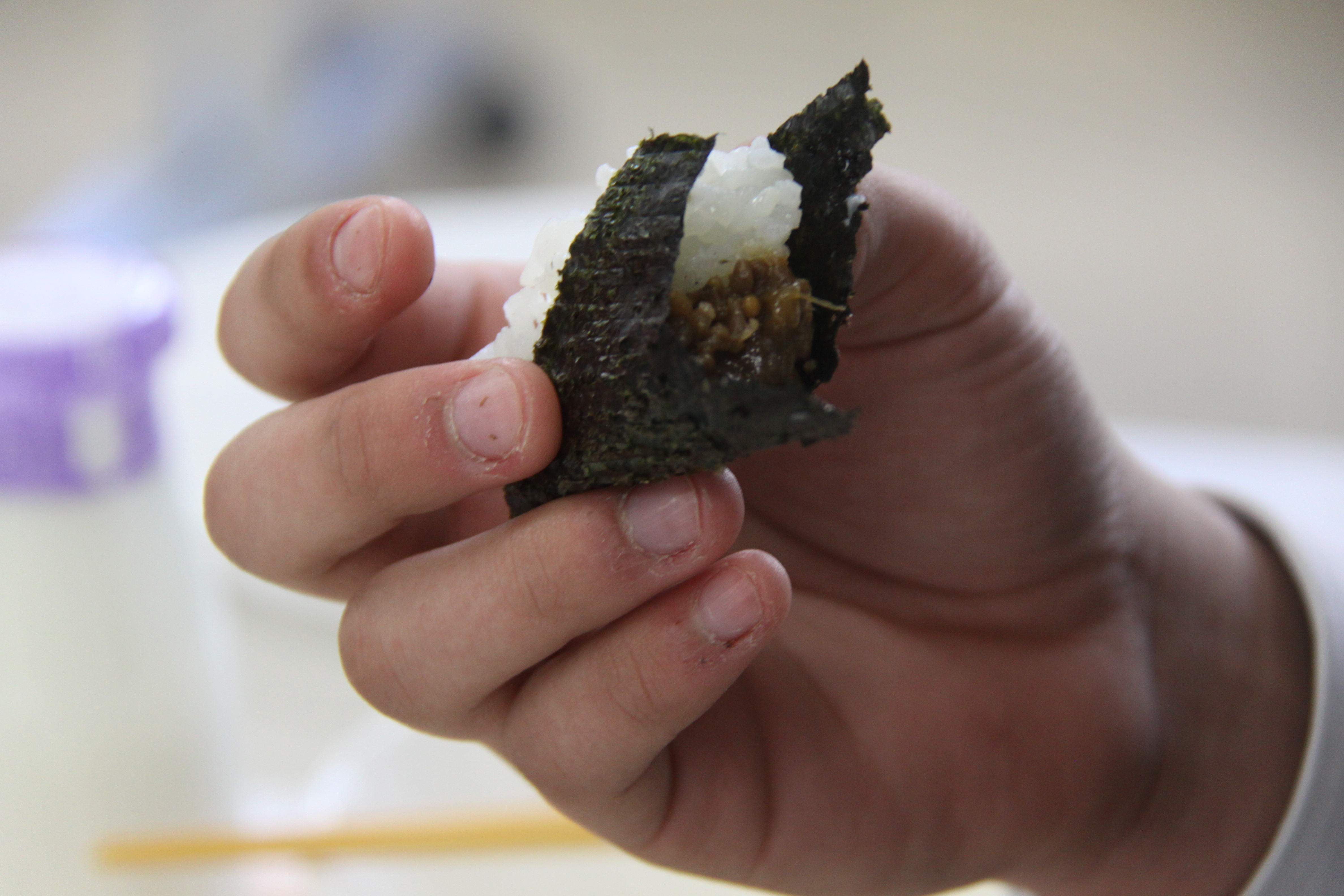
2月には、節分の行事がありますね。節分の鬼のとらえ方は社寺によって違うようです。
○仏立山真源寺(東京都台東区)→「福は内、悪魔外」
鬼子母神を御祭神としており、「恐れ入谷の鬼子母神」で有名。鬼子母神とは、他人の子供を襲って食べてしまう鬼神でしたが、見かねたお釈迦様が彼女の末子を隠し、子供を失う悲しみを諭します。それ以来仏教に帰依するようになり、子供の守り神となりました。
○鬼鎮神社(埼玉県比企郡嵐山町)→「福は内、鬼は内、悪魔外」
鎌倉時代の勇将・畠山重忠の館の鬼門除けとして建立したので「悪魔外」。また、金棒を持った鬼が奉納されているので「鬼は内」です。
○元興寺(奈良県奈良市)→「福は内、鬼は内」
寺に元興神(がごぜ)という鬼がいて、悪者を退治するという言い伝えがあります。
○天河神社(奈良県天川村)→「鬼は内、福は内」
鬼は全ての意識を超えて物事を正しく見るとされているため、前日に「鬼の宿」という鬼迎えの神事を行い、鬼を迎い入れてから節分会をします。
○大須観音(愛知県名古屋市)→「福は内」のみ
伊勢神宮の神様から授けられた鬼面を寺宝としているため「鬼は外」は禁句です。
【地域編】
○群馬県藤岡市鬼石地区→「福は内、鬼は内」
鬼が投げた石でできた町という伝説があり、鬼は町の守り神。全国各地から追い出された鬼を歓迎する「鬼恋節分祭」を開催しています。
○宮城県村田町→「鬼は内、福も内」
羅生門で鬼の腕を斬りとった男(渡辺綱)が、この地で乳母にばけた鬼に腕を取り返されてしまったため、鬼が逃げないよう「鬼は内」といいます。
○栃木県日光市鬼怒川温泉→「福は内、鬼も内」
鬼怒川温泉は邪気を払って開運をもたらす鬼がたくさんいる地とされているため、「鬼も内」と言う。
○茨城県つくば市鬼ケ窪→「あっちはあっち、こっちはこっち、鬼ヶ窪の年越しだ」
あちこちで追いやられ、逃げ込んできた鬼がかわいそうで追い払うことができないため「あっちはあっち、こっちはこっち」。節分の豆まきは新春(立春)を迎える前日の厄払いであり、昔は新年を迎える前日としてとらえていたので「鬼ヶ窪の年越しだ」と言っていたそうです。
◎多くの人に支えられて(2/1)
今日も防火設備点検をありがとうございました。停電時の対応やライト点灯時の処理方法も教えていただきました。さすがプロです。



◎わたしたちのひなせ ~源平放水合戦!【2/4】(日)※雨天決行
【 式典・訓練披露 】9:45~ 会場:日生中学校グラウンド
【 放水演習開始 】12:00~ 会場:日生港湾内・・・ 源平放水合戦は、備前市消防団日生方面隊による放水演習です。源平にわかれ、紅白の旗を上げた船に消防団員が乗り込み海上にて放水合戦を執り行います。岡山県備前市日生で開催される「源平放水合戦」は、毎年2月第一日曜に、日生港内で開催されます。 この行事は出初式の一環で1950年から70年以上前から行われてるものです。
放水合戦のフィナーレを飾る五色のカラー放水は空高くまでのぼり、ご覧いただく皆様の一年の安泰を祈願いたします。(どうぞ消防団員への温かい声援をお願いいたします。)新しい年のはじまりを告げる源平放水合戦をお見逃しなく!!(備前市観光協会より)
※見学に行く生徒諸君は、日生中学校生徒としての自覚を持って観覧しよう。

◎ひな中の風
~楽しい授業を。深い学びの授業を創る。(1/31)
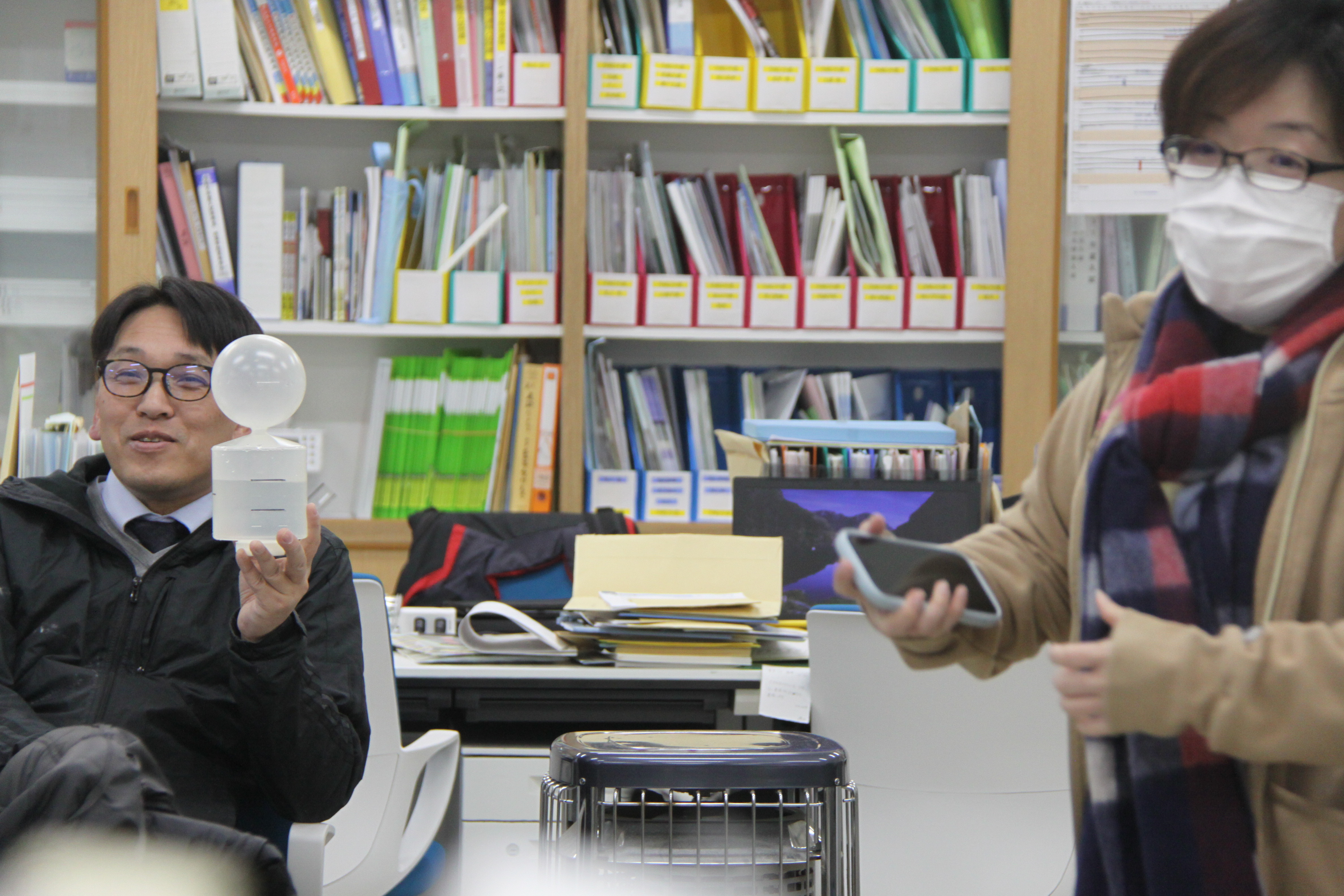
職員室では、子どもたちの「豊かな学び」のために、授業研究を日々おこなっています。この日は、球の体積と同半径の円柱の体積と比較する教具が、職員間で話題になりました。(^_^)
◎ひな中の風
~学び合うってこういうことさ✨


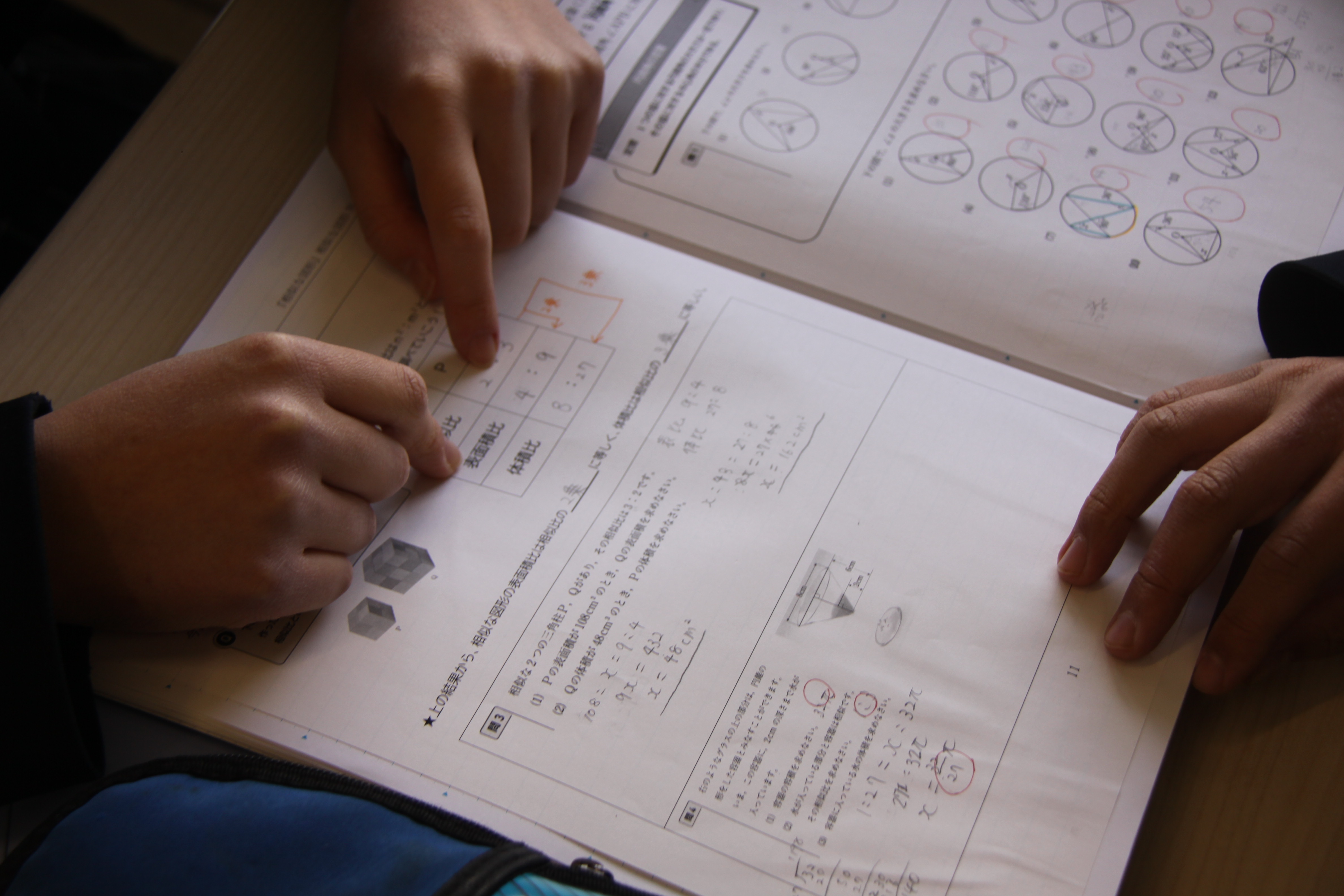

これってどうするん?に応える仲間として。
◎地域とともに・仲間と共に学ぶ学校(1/30)
開催中のハンセン病問題学習展示に行きました。参観の振り返りを一部紹介します。
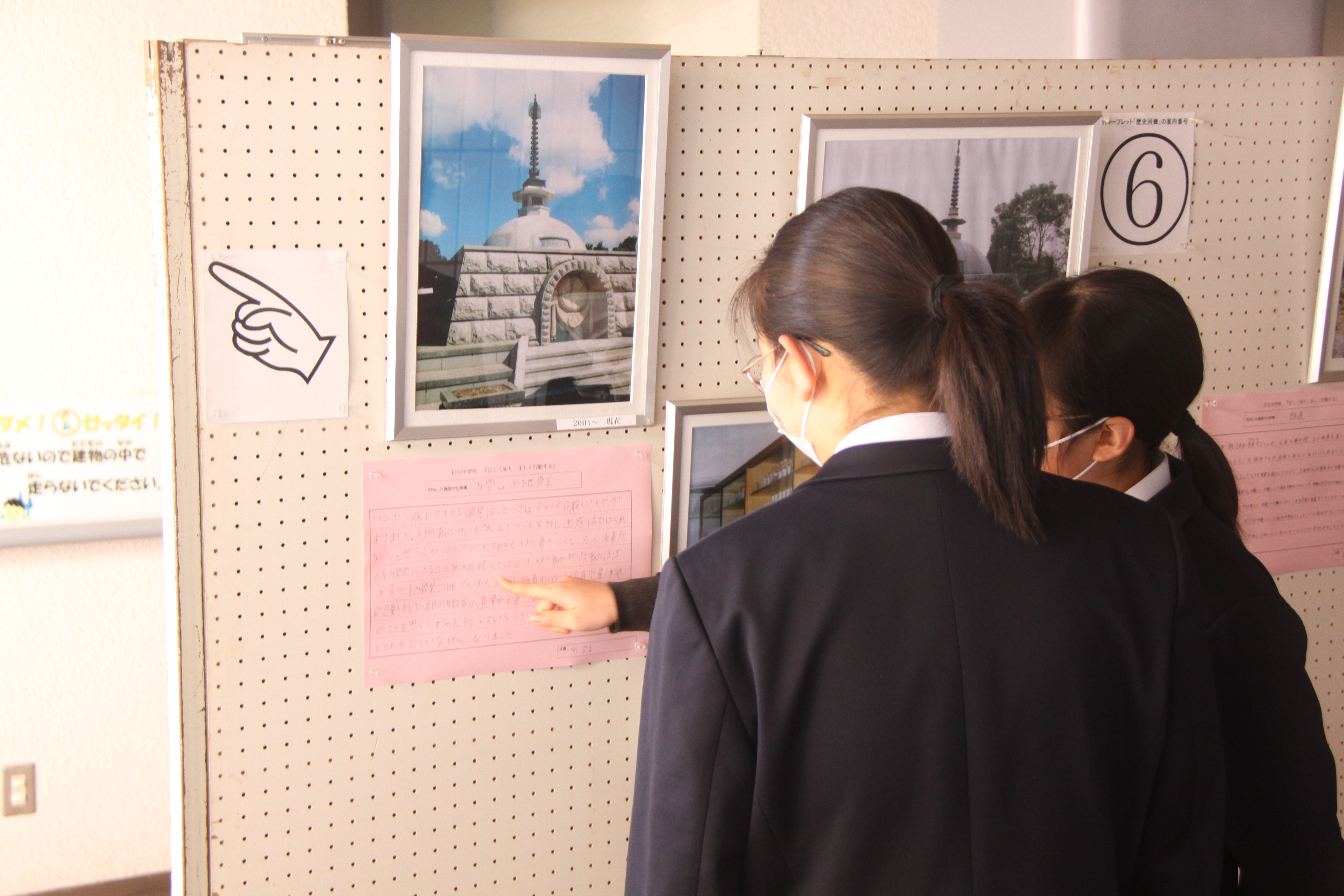


○友達と分担して、説明文をつくったのだけど、それぞれ書いた人の気持ちがどの説明文にもしっかりこもっていたので、ハンセン病の差別をなくしたいという心がとても伝わってきた。たくさんのパネルを見て、ハンセン病療養所へ行ったことがない人でも分かりやすいと思った。ぜひ多くの人に学んでもらいたいと思う。
○パネルでよりハンセン病について知れたと思うので良かったです。あまり知識がなかった邑久光明園についての展示もあり、学べました。
○自分以外のパネルは初めて見たけど、詳しいところまで書いていて知らない知識がたくさんあった。私たち、中学生がこのような活動をして、地域の人にも知ってもらうというのは大切なことなんだなと思った。差別・偏見をなくす第一歩として、まずは正しい知識を得ることが重要である。
○みんな調べたことと、調べたことに対して考えたことを詳しく書いていた。この展示によって、正しいハンセン病の知識を持つ人が増えるといいなと思った。
○ハンセン病についての漫画も見て、知らなかったことも知れた。伝えていこうと思った。
○みんなテーマごとに大切なことをまとめられていました。書いて、見て、終わり、ではなくて、次の世代に伝えていくことが大切だと思うので、どういった形でも大切なことを伝えていきたいと思う。
なお、展示は日生公民館にて、2月22日(木)までの予定です。是非一度足を運んでいただけると幸いです。
◎〈ひそやかに天動説は囁かれ
冷え極まれる1月の夜 石川美南〉
わたしたちのはじまりの風景8(1/30)

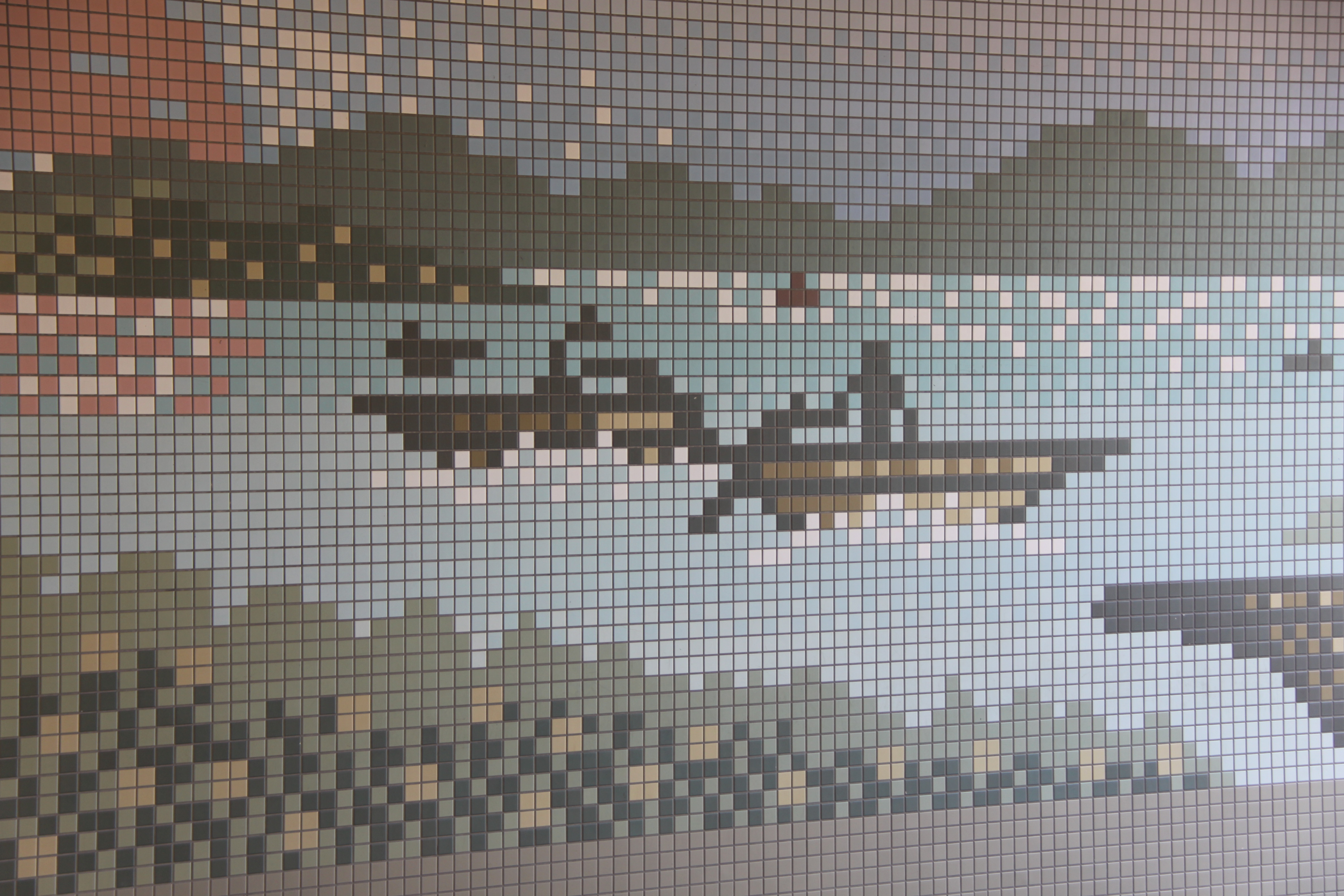







ここはどこでしょう?
◎私たちの大切な委員会活動(1/29)
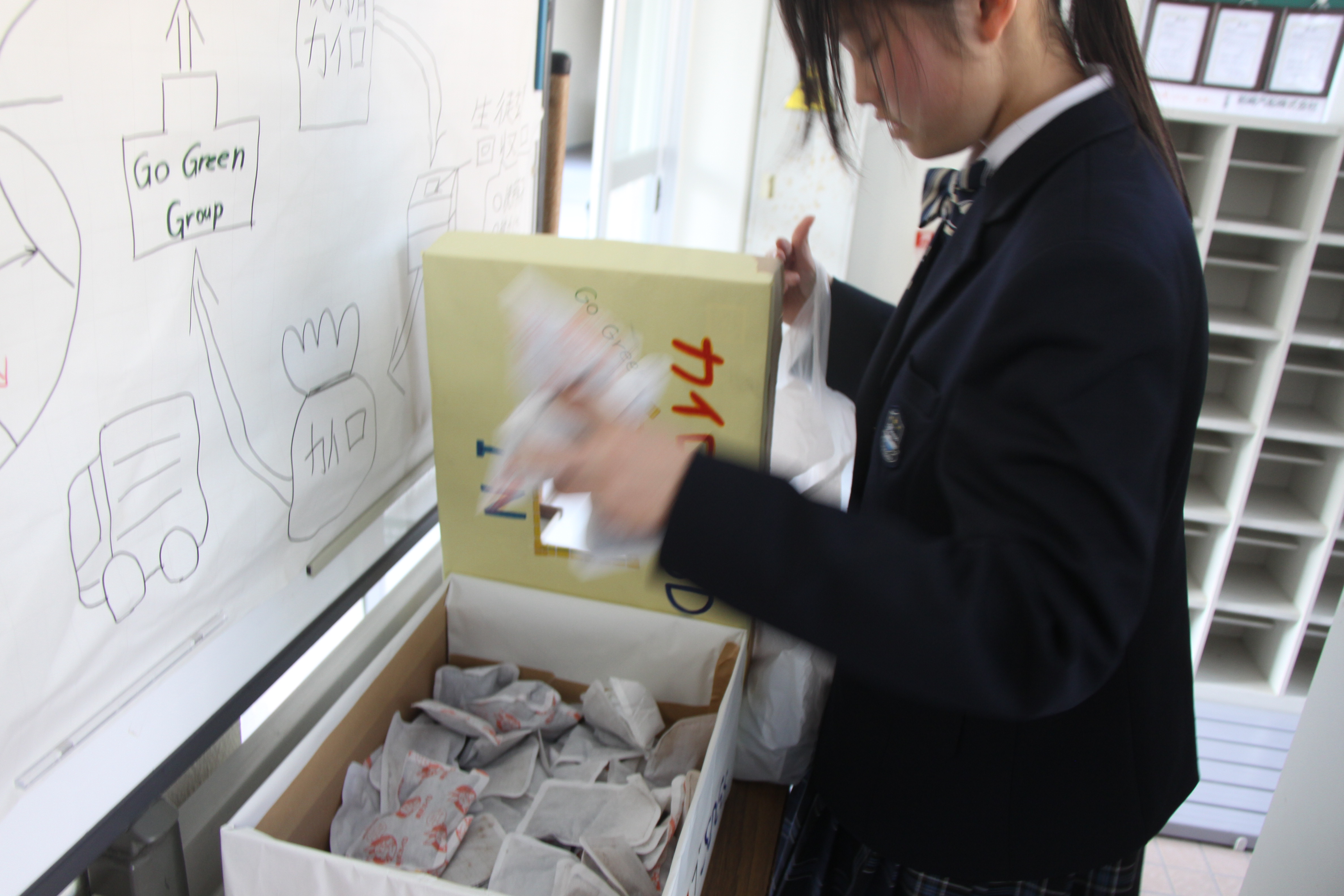
みんなありがとう。たくさんの使用済カイロが集まっています。
◎多くの人に支えられて(1/29)
寒い中、旧部室西側のフェンスの修繕をしていただきました。ありがとうございます。また、今日は学校評議員さんらが来校され、年度末に向け、学校評価について話し合いました。


学校関係者評価は、 保護者、 学校評議員、 地域住民、 青少年健全育成関係団体の関係者、 接続する学校(小学校に接続する中学校など) の教職員その他の学校関係者などにより構成された委員会等が、その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、 自己評価の結果について評価することを基本として行うものである。とあります。(学校評価ガイドライン(平成28年改訂) (抜粋)
また、 文部科学省は学校評価の必要性と目的について以下のように述べています。
○ 学校の裁量が拡大し、自主性・自律性が高まる上で、その教育活動等の成果を検証し、必要な支援・改善を行うことにより、児童生徒がより良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指し、教育の水準の向上と保証を図ることが重要である。また、学校運営の質に対する保護者等の関心が高まる中で、学校が適切に説明責任を果たすとともに、学校の状況に関する共通理解を持つことにより相互の連携協力の促進が図られることが期待される。これらのことから、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校及び設置者等が学校運営の改善を図ること、及び、評価結果等を広く保護者等に公表していくことが求められる。
○ このことから、学校評価は、以下の3つを目的として実施するものであり、これにより児童生徒がより良い教育活動等を享受できるよう学校運営の改善と発展を目指すための取組と整理する。
① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な改善を図ること。
② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明により、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。
③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。









◎「自分を大切に思える」子どもに育てねば。(1/29)
備前市手をつなぐ育成会研修会で、片上にある多機能型事業所ユートピアさんを訪問しました。管理者の大谷さんから、施設の見学・説明をしていただき、質疑応答・意見交流をさせていただきました。大谷さんは長年の経験に基づき、「自己肯定感」を小さな頃から育む大切さを感じておられ、貴重なお話をたくさん聴かせていただきました。ありがとうございました。
手をつなぐ育成会研修会は、引き続き、2月13日(火)ひだすき作業所、2月15日(木)閑谷ワークセンターひなせへ訪問させていただきます。参加希望の方がおられましたら、事務局(日生中)までご相談ください。



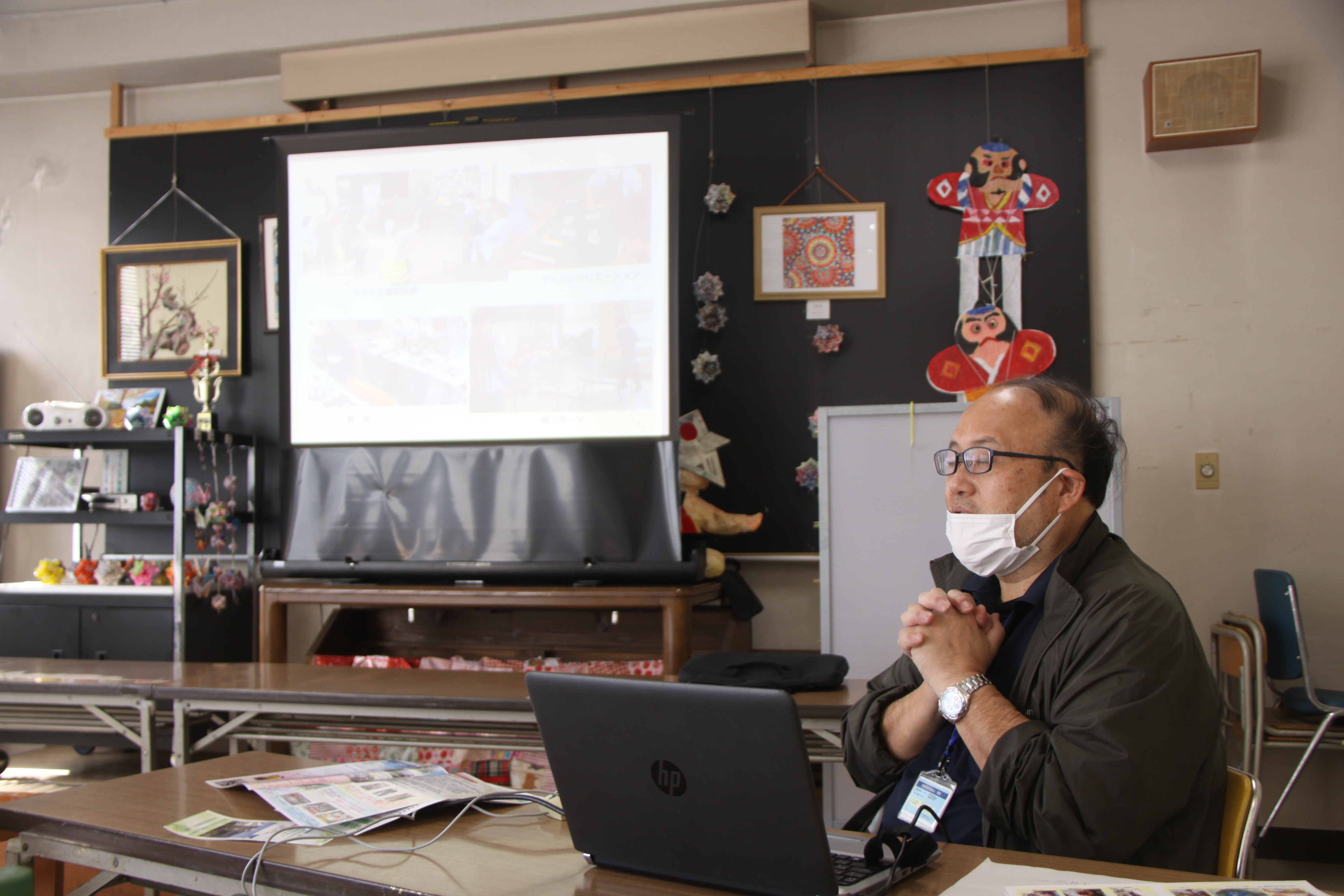
◎梅一輪 一輪ほどの 暖かさ 服部嵐雪 (1/29)



月曜日。今日もみんなと「おはよう」。中庭の梅が咲きました。
◎夜空の向こうには、もう明日が待っている♪(私立一期受験を越えて1/26)
月には月ごとに様々な呼び名があります。昔、人々は現代のようにカレンダーを見て生活するのではなく、月の満ち欠けとともに生活してきました。ネイティブアメリカンは、季節の移り変わりの満月を節目にして農作業や狩猟など生活の目安にし、そこから暦がつくられました。今日、1月26日はウルフムーンWolf Moon(狼月)とよばれています。真冬、食糧がなく飢えた狼の遠吠えにちなんだ名前を1月の満月に付けました。中世ヨーロッパでもネイティブアメリカンの人々もこの名前で呼んでいたようです。また他に、オールドムーンOld Moon(古月)やアイスムーンIce Moon(氷月)などとも呼ばれています。

◎ひな中の風✨~1.26、7:45、6℃

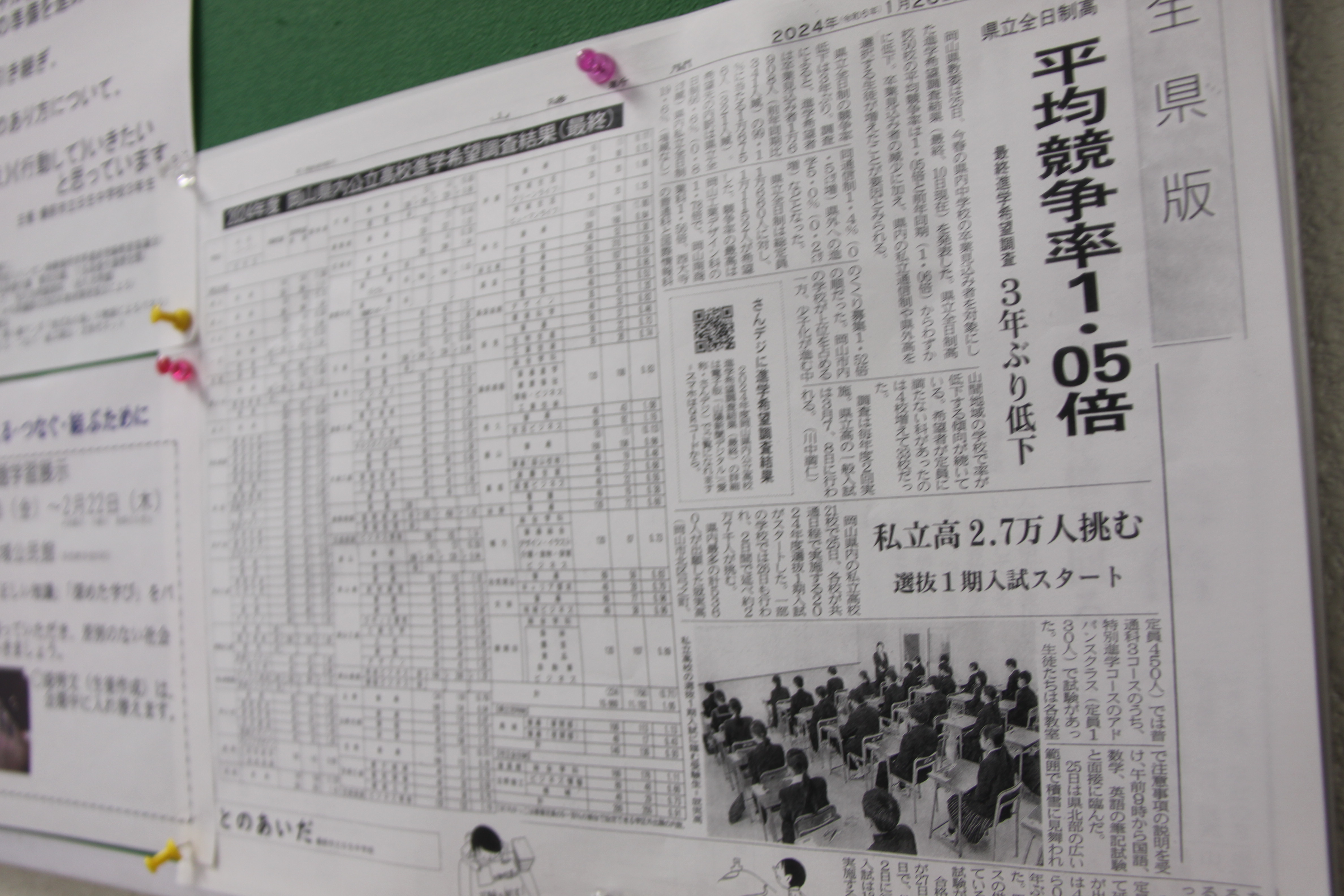




◎たしかな学力とは?(1/26)
26日、岡山県学力定着状況確認テスト(CBT)に取り組みました。
国では、子どもたちの学力状況を把握するため、文部科学省が実施している「全国学力・学習状況調査」を検証する「全国的な学力調査に関する専門家会議」の下で、紙ベースの調査からコンピューター使用型調査(以下、CBT:Computer Based Testing)への移行を検討したワーキンググループの最終まとめをもとに、順次導入を進めています。

◎「いただきます。∈^0^∋」
今日は、神根ねこめし。(給食週間・1/26)



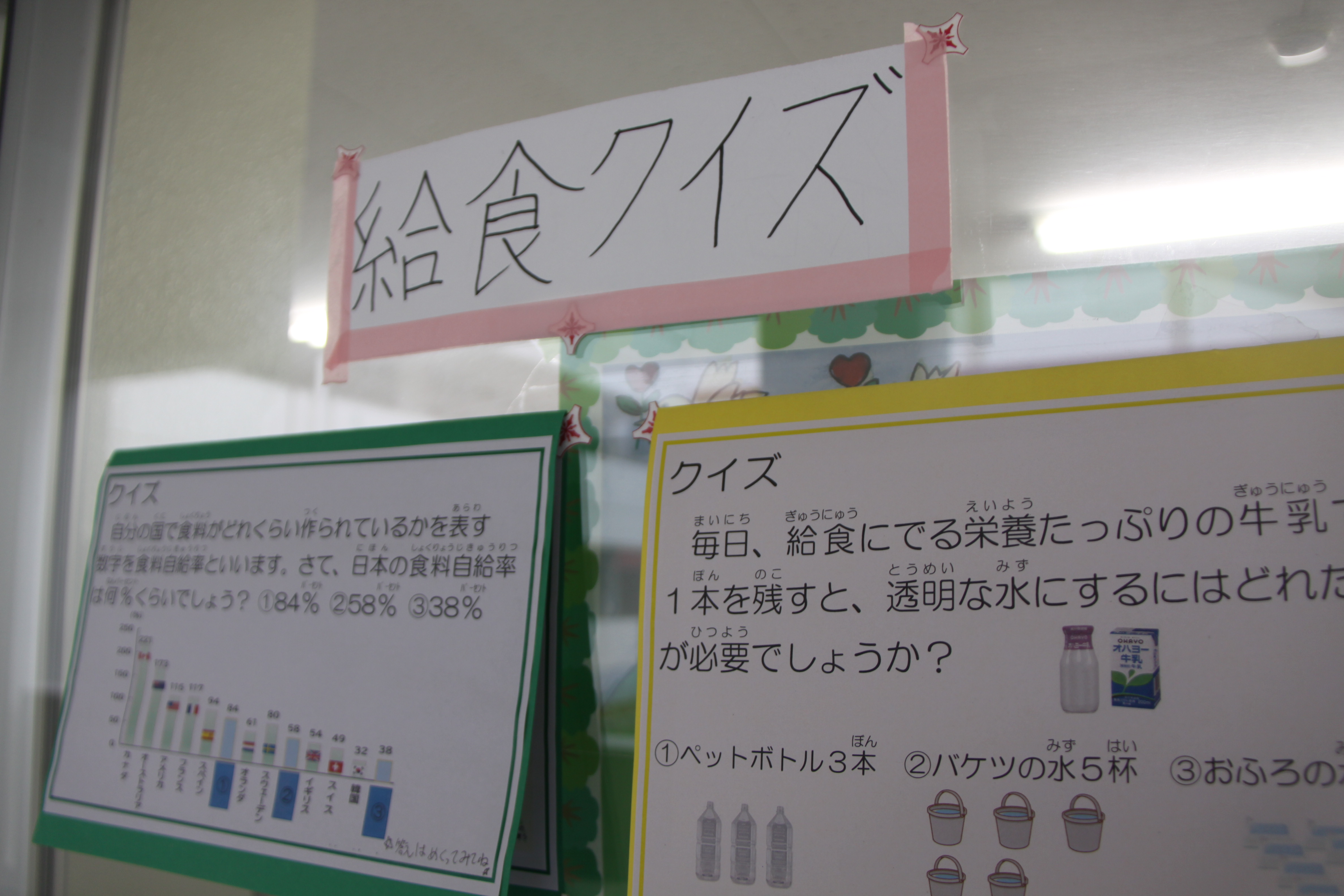

ねこめし??
◎私たちの学び・伝えたい思いをみんなへ。地域へ。(1/25)
3年ハンセン病問題学習展示に多くの方々が来会されています。アンケートを紹介します。
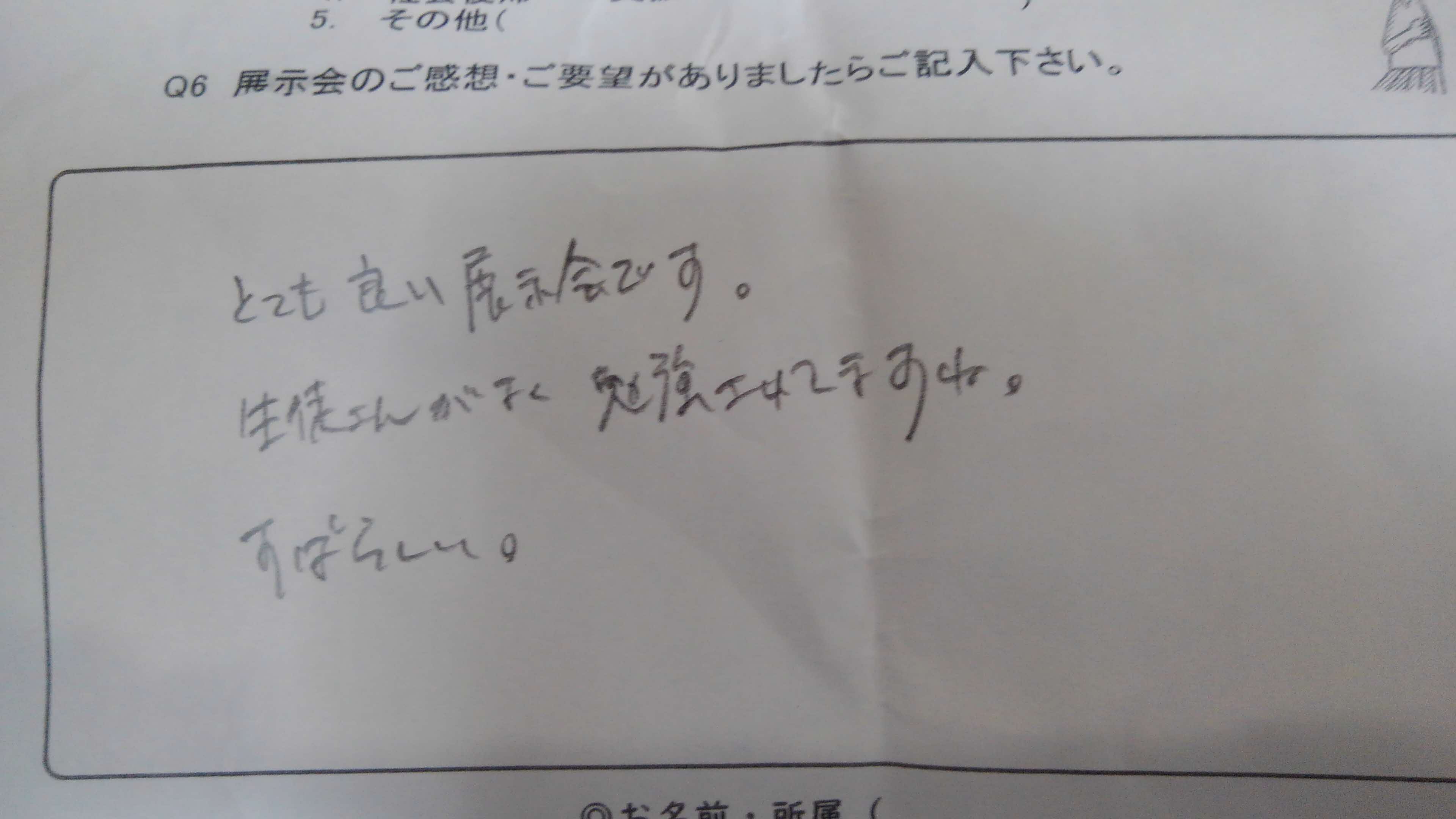
・日生地域公民館で2月22日まで
◎白い息追い越し過ぎる誰が背中
響く発車のベルファンファーレ(勉強短歌#023)
✨特別付録付き《ひなちゅううらない》
・・・直感でイラストを選んでください。☞🍎 🍊 🍍 🍇(どれにする?)
これまで、いくつかの学校でも入試があり、合格を手に入れた生徒もいますが、この日は、岡山県内の私立高校21校で25日、各校が共通日程で実施する2024年度選抜1期入試がスタートしました。一部の学校では26日も行われ、2日間で延べ約2万7千人が挑みます。生徒たちは受験校の各教室で注意事項の説明を受け、午前9時から国語、数学、英語の筆記試験と面接に臨みます。異なる学科・コースの併願受験を導入している13校では26日も試験がります。合格発表は岡山白陵が27日、金光学園が29日で、他の19校は2月2日。選抜2期入試は18校が同20日に実施します。
🍎・・・大吉。何をやってもうまくいく。だいじょう~ぶ!
🍊・・・強運日。強気でいこう。結果がついてくる。だいじょう~ぶ!
🍍・・・ラッキーデイ。たくさん福が舞い込む。だいじょう~ぶ!
🍇・・・これまでの取組が実を結ぶ。いいね。だいじょう~ぶ!
◎友よ!みんな がんばってこよう!〈入試事前打ち合わせ会にて:1/25・26〉


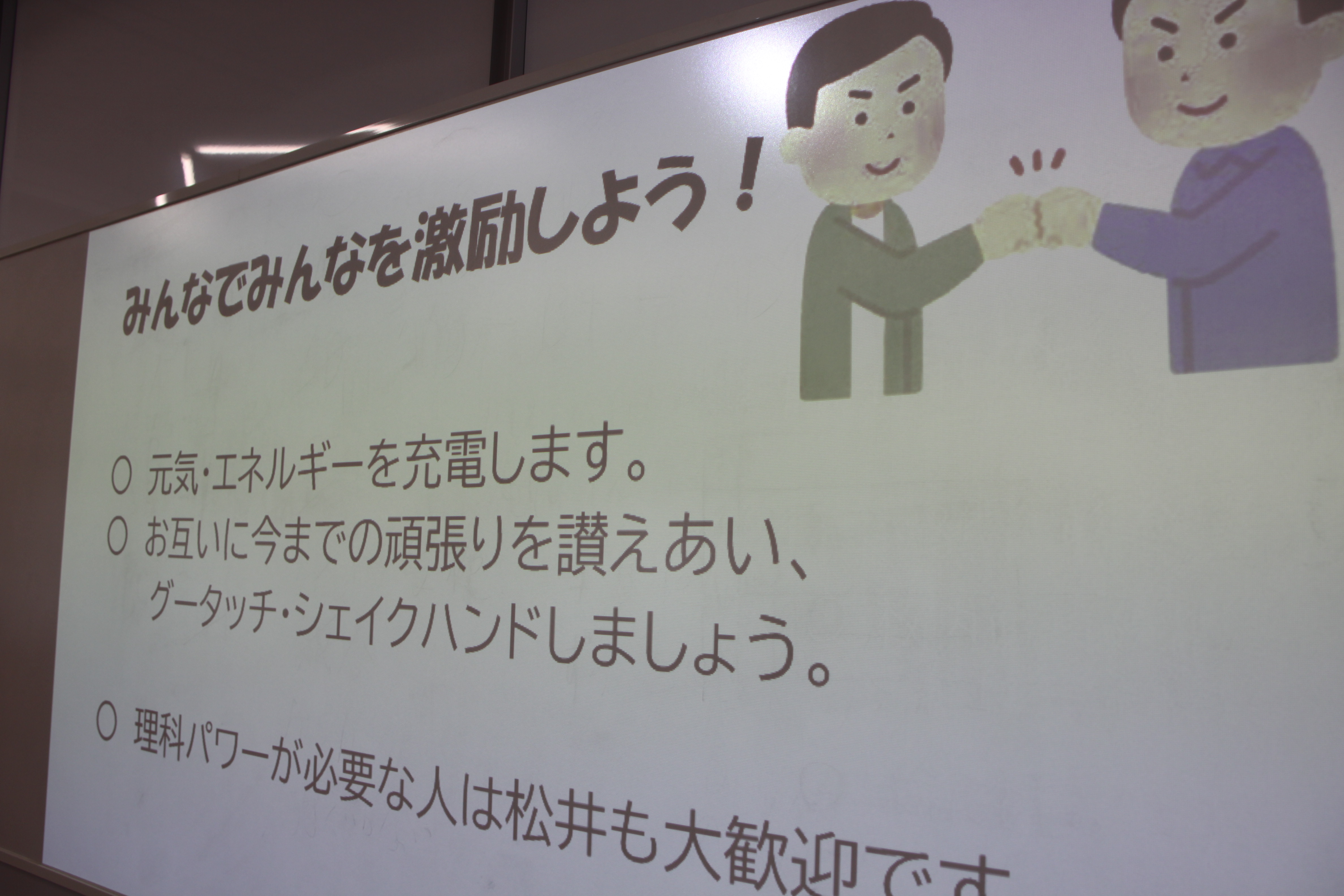
この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、 危ぶめば道はなし、踏み出せばその一歩が道となる、 迷わずゆけよ、ゆけばわかるよ。
◎三年生の先輩たちへ(1/24)
明日、私立高校の選抜1期入試が行われます。

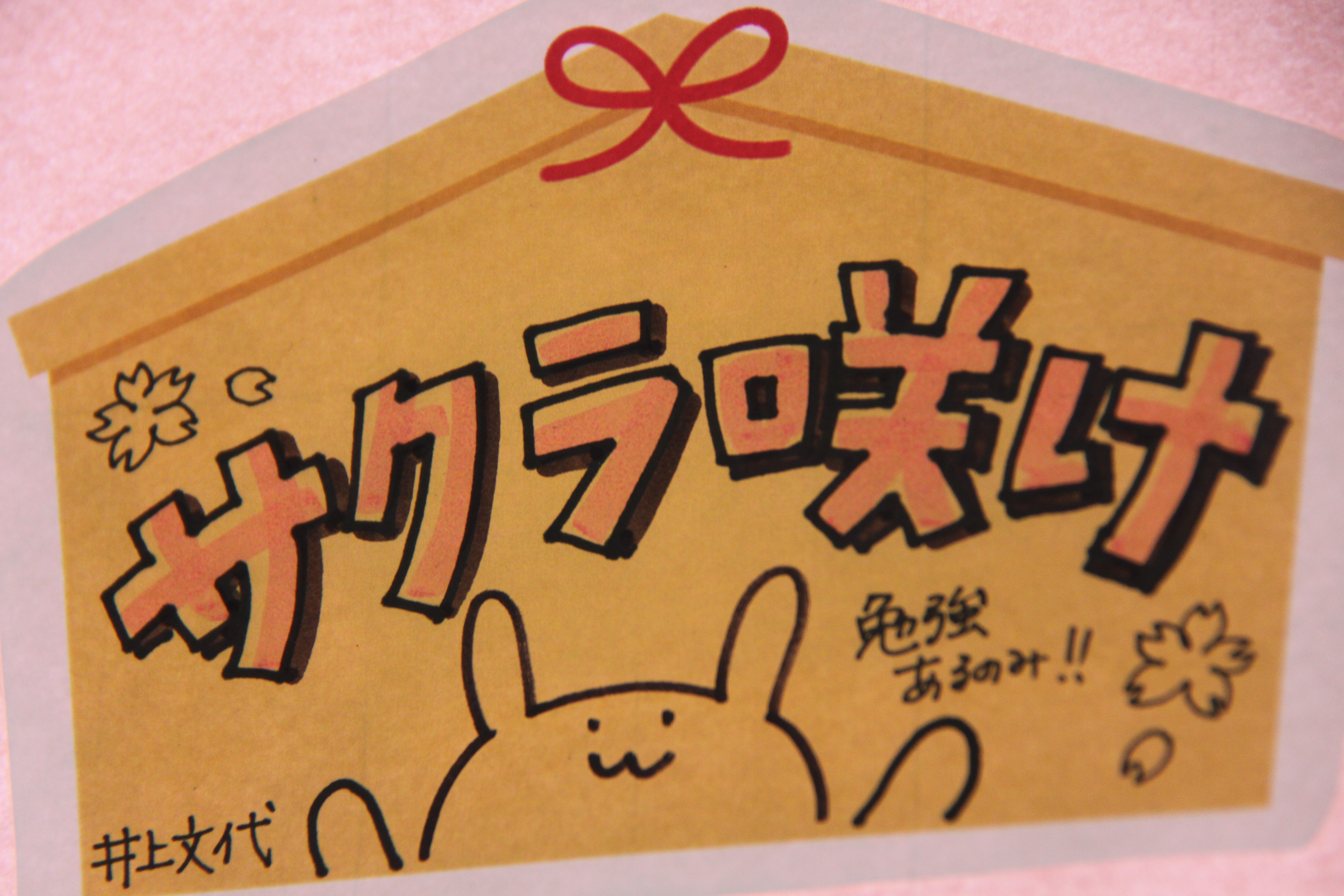
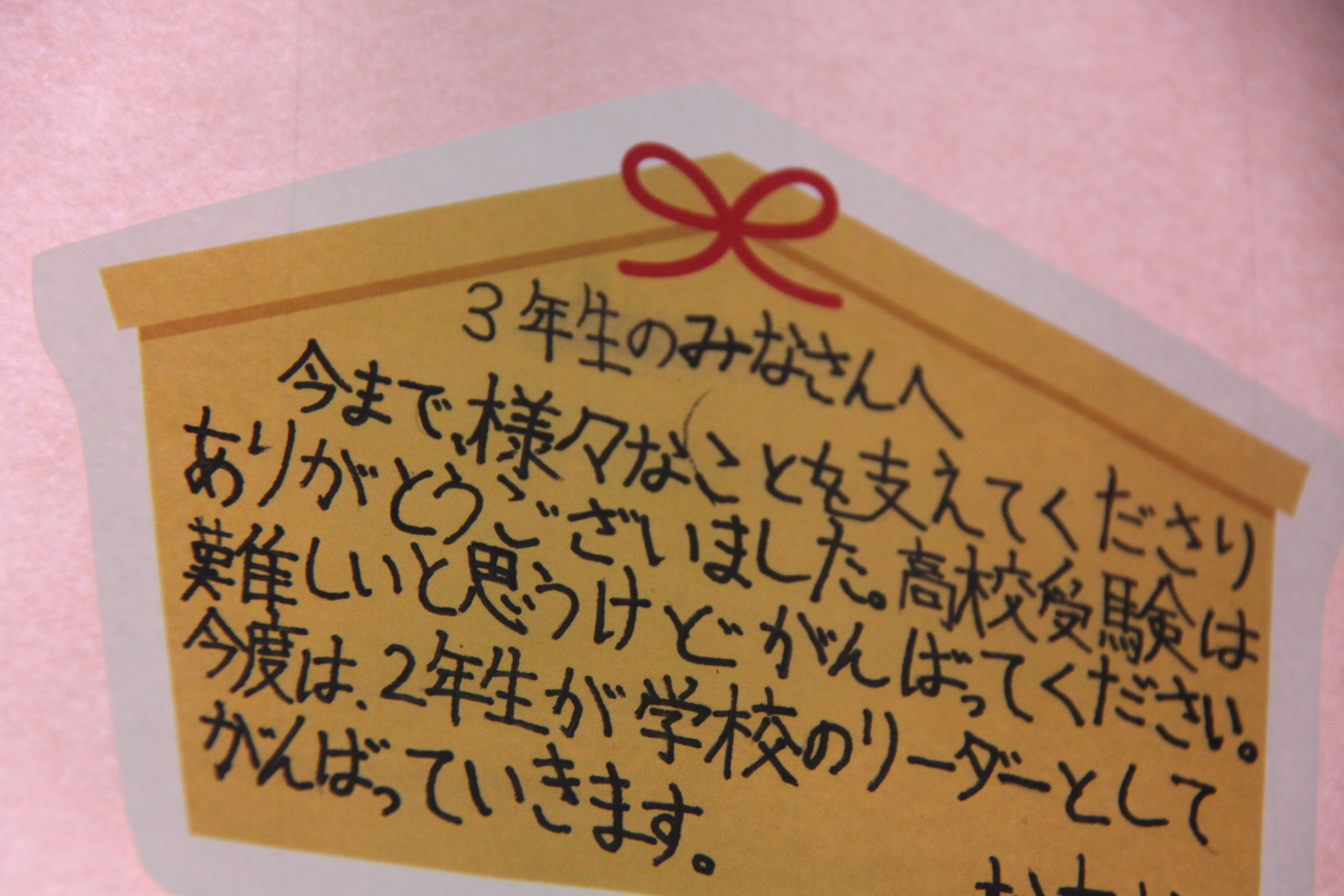
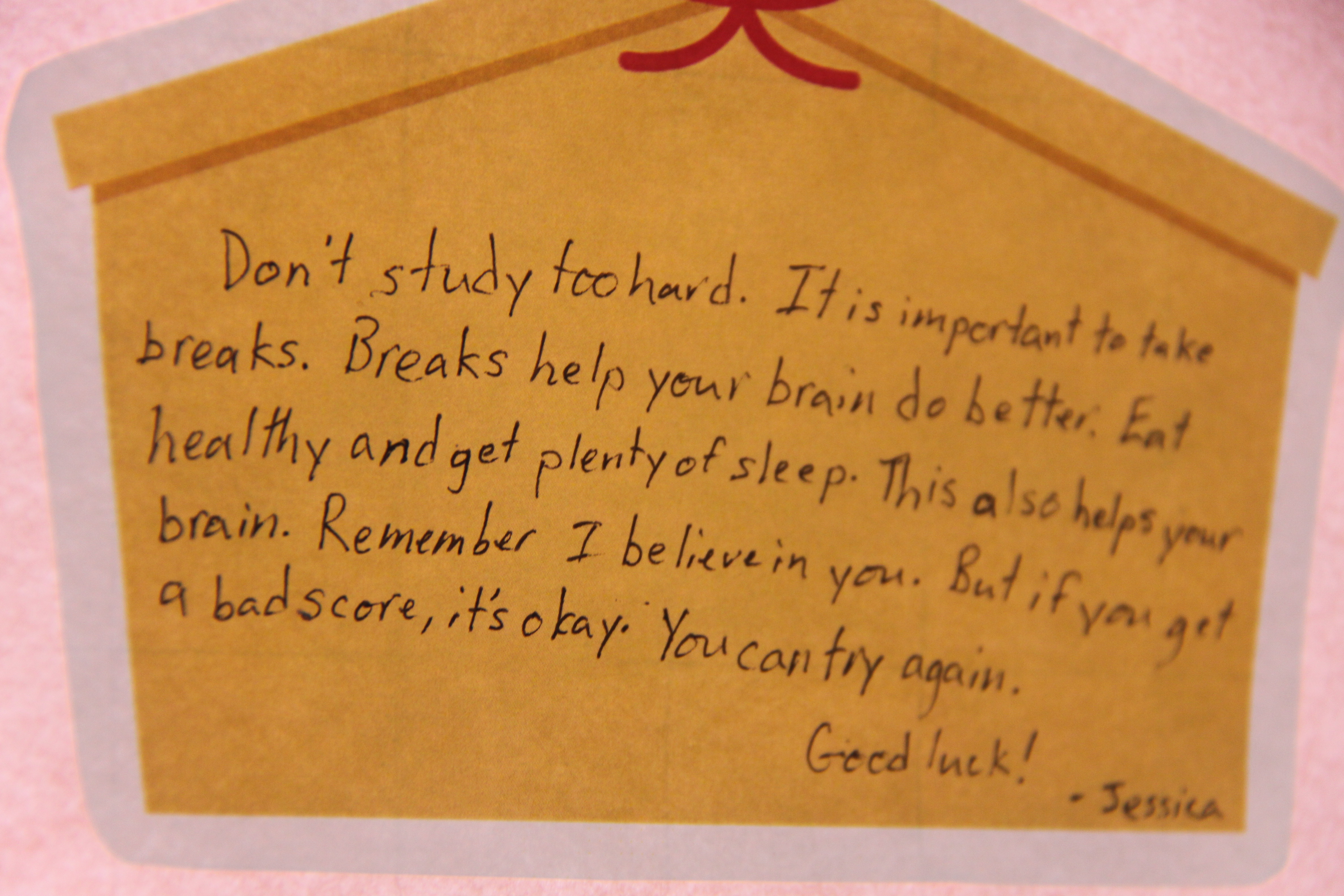
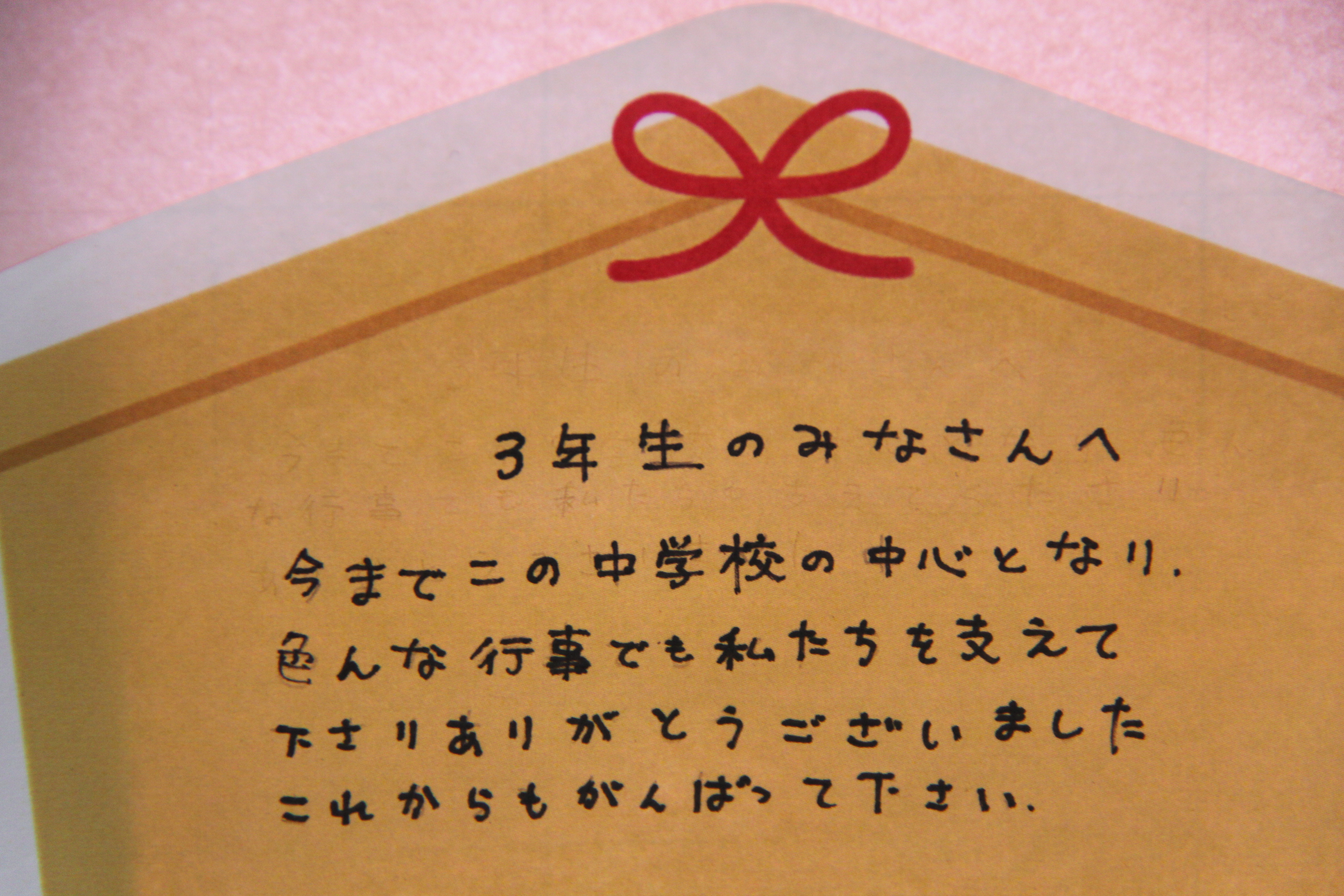
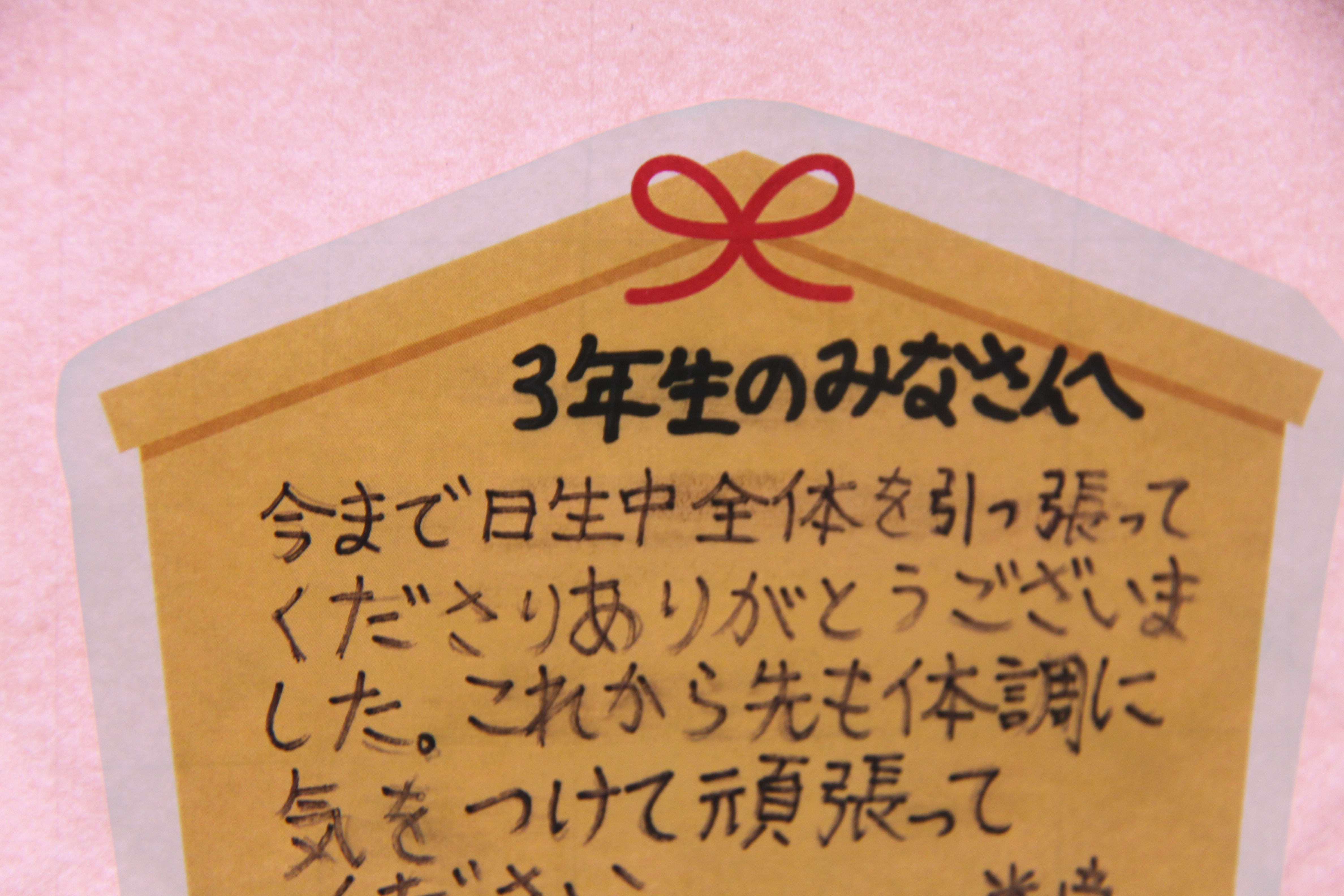
〈いざ挑めよ さらば開かれん〉岡山県内にある21の私立高校が共通の日程で行う選抜1期入試の出願状況をみると、平均倍率は4.95倍で2023年を下回っています。選抜1期入試に出願したのは5485人の募集定員に対し2万7142人で平均競争倍率は4.95倍となり2023年を0・06ポイント下回っています。最も倍率が高かったのは岡山市の就実高校の特別進学コースハイグレードクラスの53.65倍、次いで笠岡市の岡山龍谷高校の特別進学コースの35.9倍となっています。合格発表は今月27日から来月2日にかけて行われます。
◎ご参観ありがとうございました。新年度へ歩んでいきます(^_^)

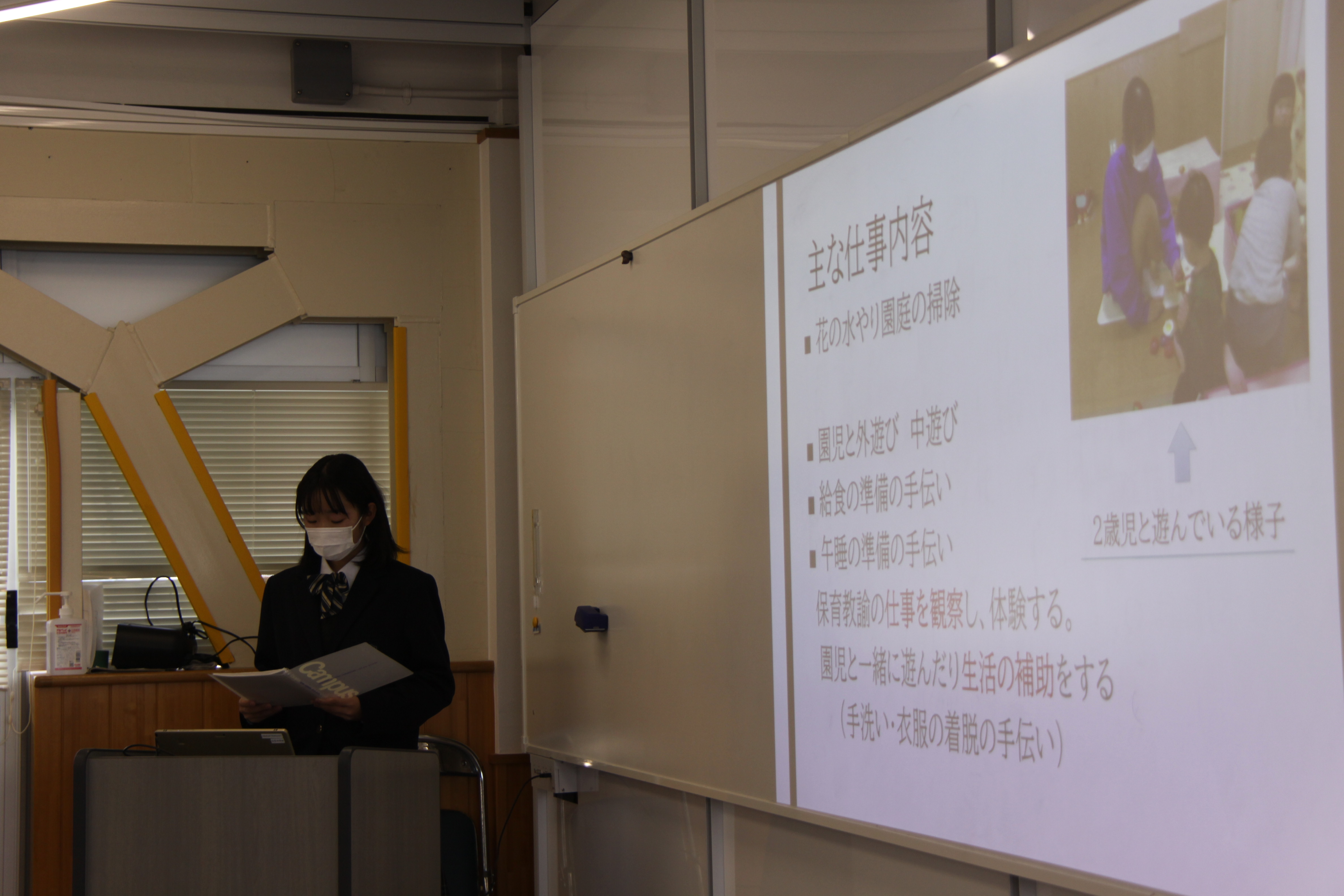


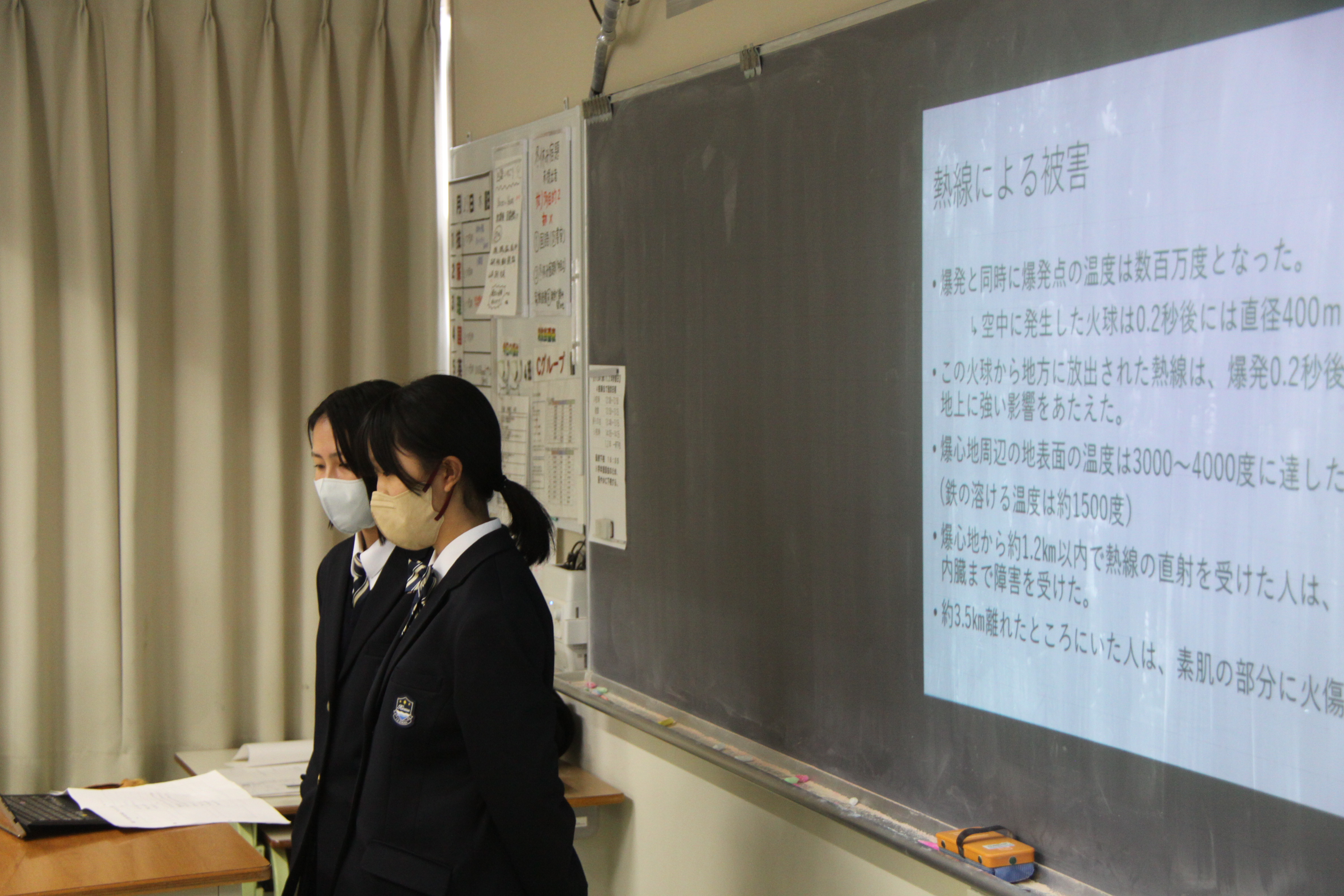




事を論ずるには、当に己れの地、己れの身より見を起すべし吉田松陰『丙辰幽室文稿』
◎To be what we are‚ and to become what we are capable of becoming‚ is the only end of life. Robert Louis Stevenson (ありのままの自分でいること、なりうるものになること、それが人生の唯一の目的です)
~さあ、公立高校特別入試出願(1/24)



岡山県内の公立高校48校で24日、2024年度特別入試の出願受け付けが始まりました。26日正午に締め切られ、2月7、8日に国語、数学、英語の学力検査や面接を行う。書類は各受験校へ持っていきましたが、今回の入試からインターネットによる出願手続きとなりました。特別入試は県立51校のうち43校、岡山、倉敷、玉野の市立5校が実施。これまで手書きを持参していた願書がデジタル端末で清書、ネットを通じて提出できるようになり、高校教員がパソコンで願書の確認作業を進めます。
生徒の多様な能力や適性をみて選抜する特別入試は、共通の学力検査と面接に加え、各校が独自に作文などを課す。定員枠は普通科が30~50%、専門学科と総合学科は50~80%の範囲内で各校が自由に設定。玉野光南体育科と井原地域生活科は全員を特別入試で選抜し、中高一貫校の天城と津山の理数科も内部進学者以外は特別入試で選びます。
出願状況は県教委が29日に公表。合格内定者には2月16日に中学校を通じて通知します。
◎地域にひらく学校・深める学校。
明日(1.24)は参観日・懇談会
1 目 的
| ○ | 本校の教育実践の実際を保護者に見ていただく中で,本校の教育への理解と信頼を得るとともに,保護者・家庭との連携を密にして学校教育の充実を図ります。 |
| ○ | 学年懇談では,保護者へ進級に向けての生活指導の依頼及び次年度の宿泊研修についての連絡の機会とします。 |
2 日 程
| 1・2年 | 3年 | ||
| 1~4校時 | 通常日程(50分×4) | ||
| 2:50~13:25 | 給 食 | ||
| 13:40~14:55 | 帰りの会 | ||
| 14:05~14:55 | 5時間目 参観授業(50分) | 通常授業 | |
| 15:05~15:55 | 1・2年生 一斉下校 |
15:00~15:40 学年懇談 |
6時間目 私立1期入試事前指導 ※ 終了後一斉下校 |
Judy Garland(夜の静寂の中で、私は何千人もの人々の拍手よりも、たった一人の人間の愛の言葉を願うことがよくあります。)
◎ひな中の風✨
~学び合う仲間たちと豊かな学びを。(1年生数学:1/24)

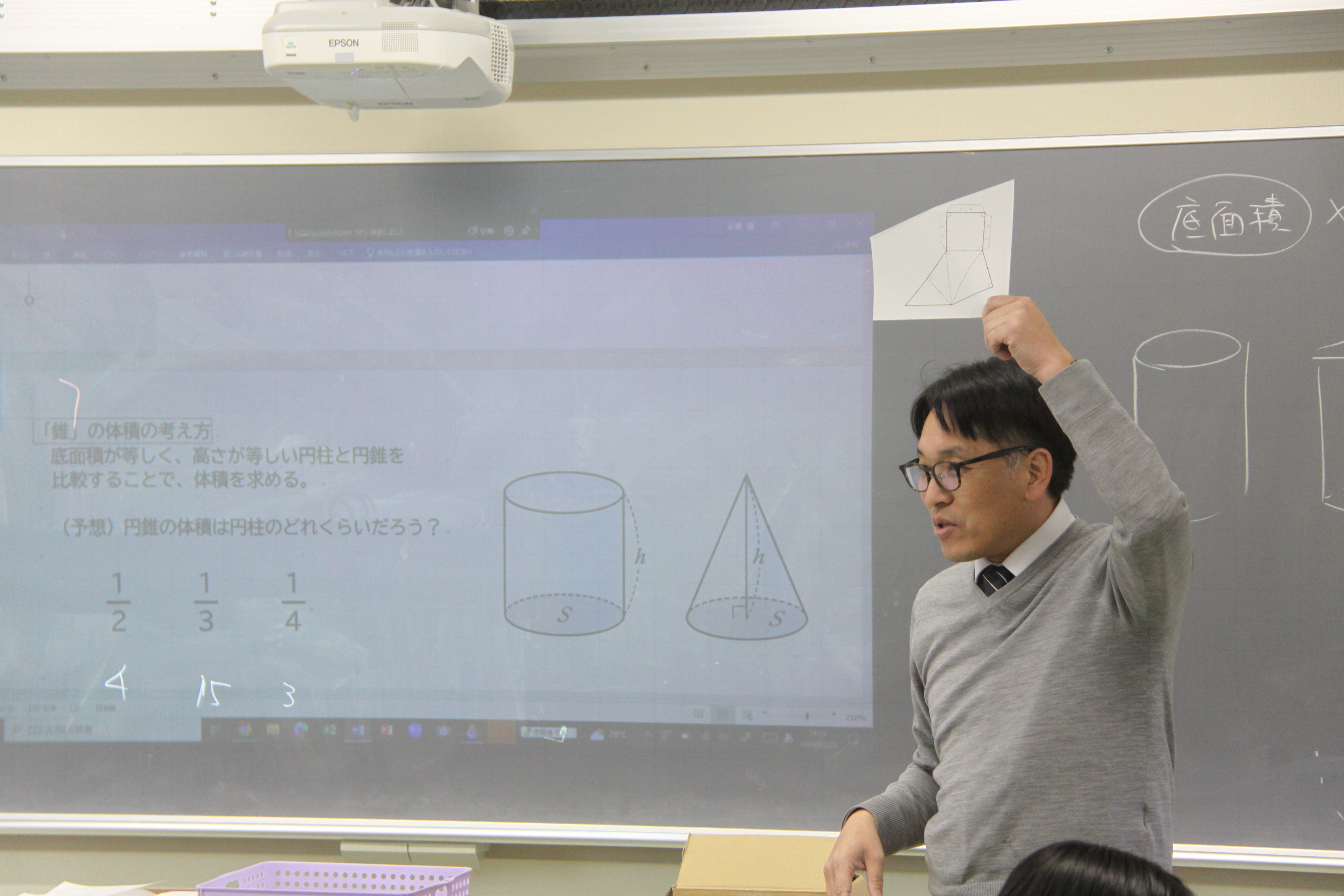
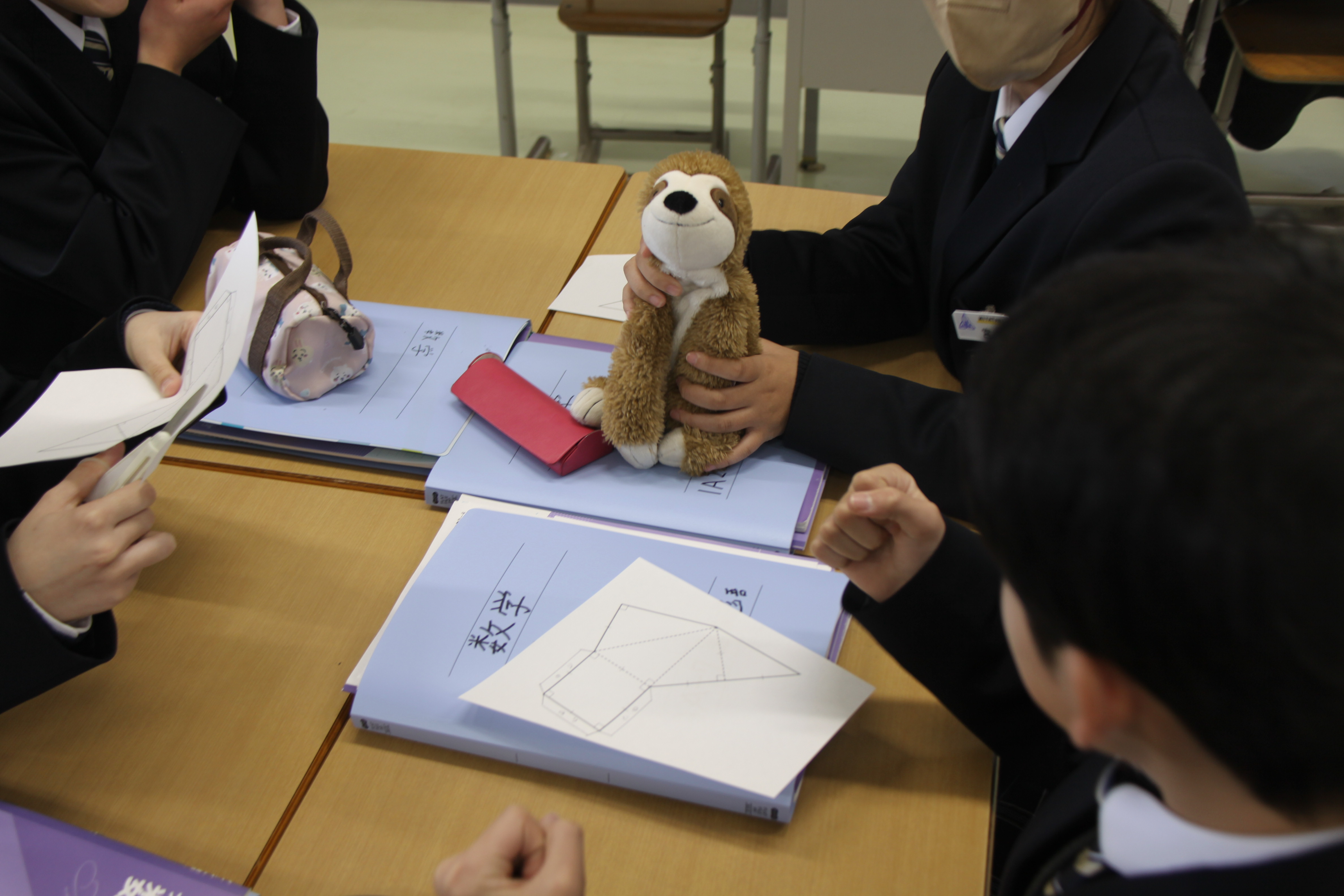
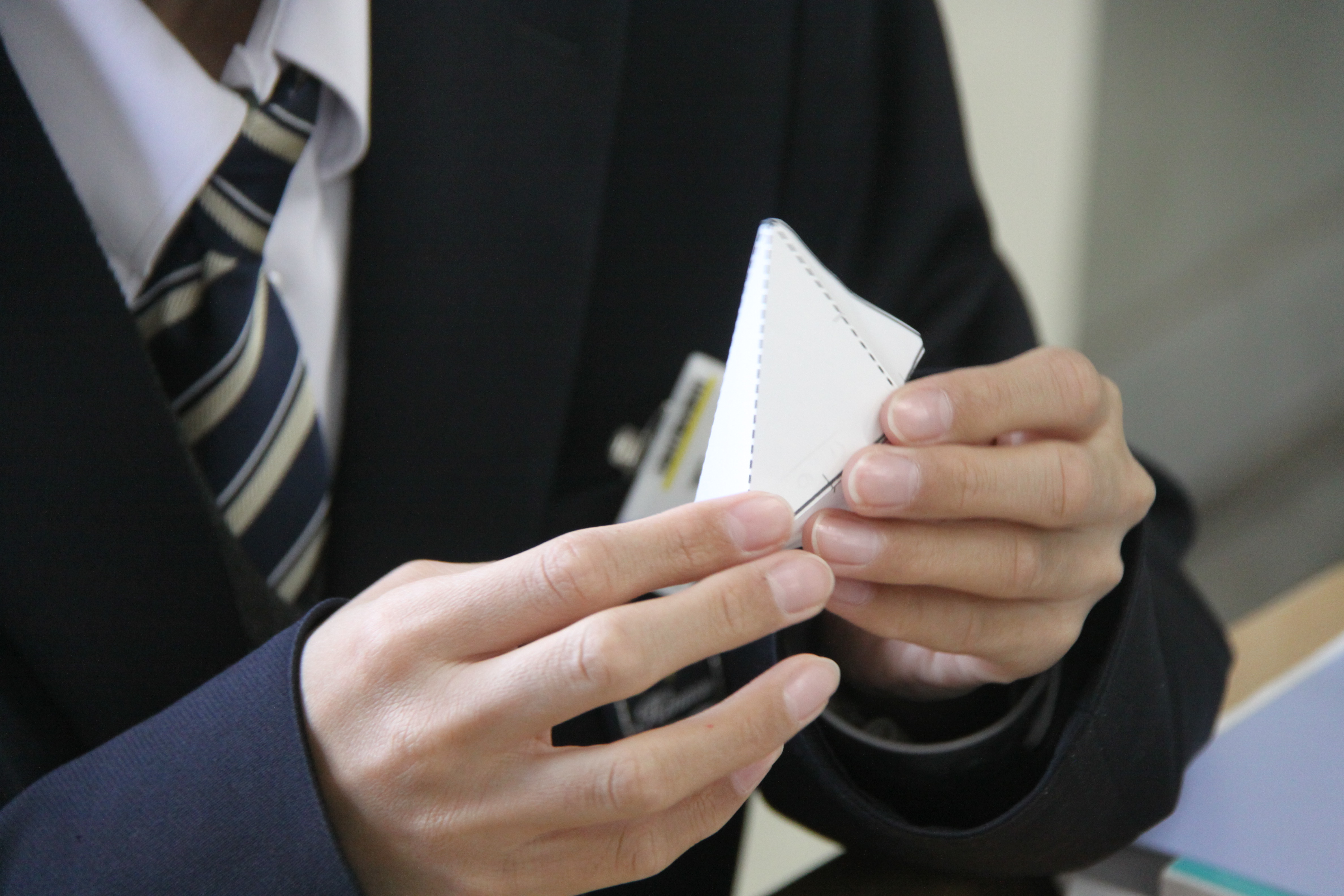

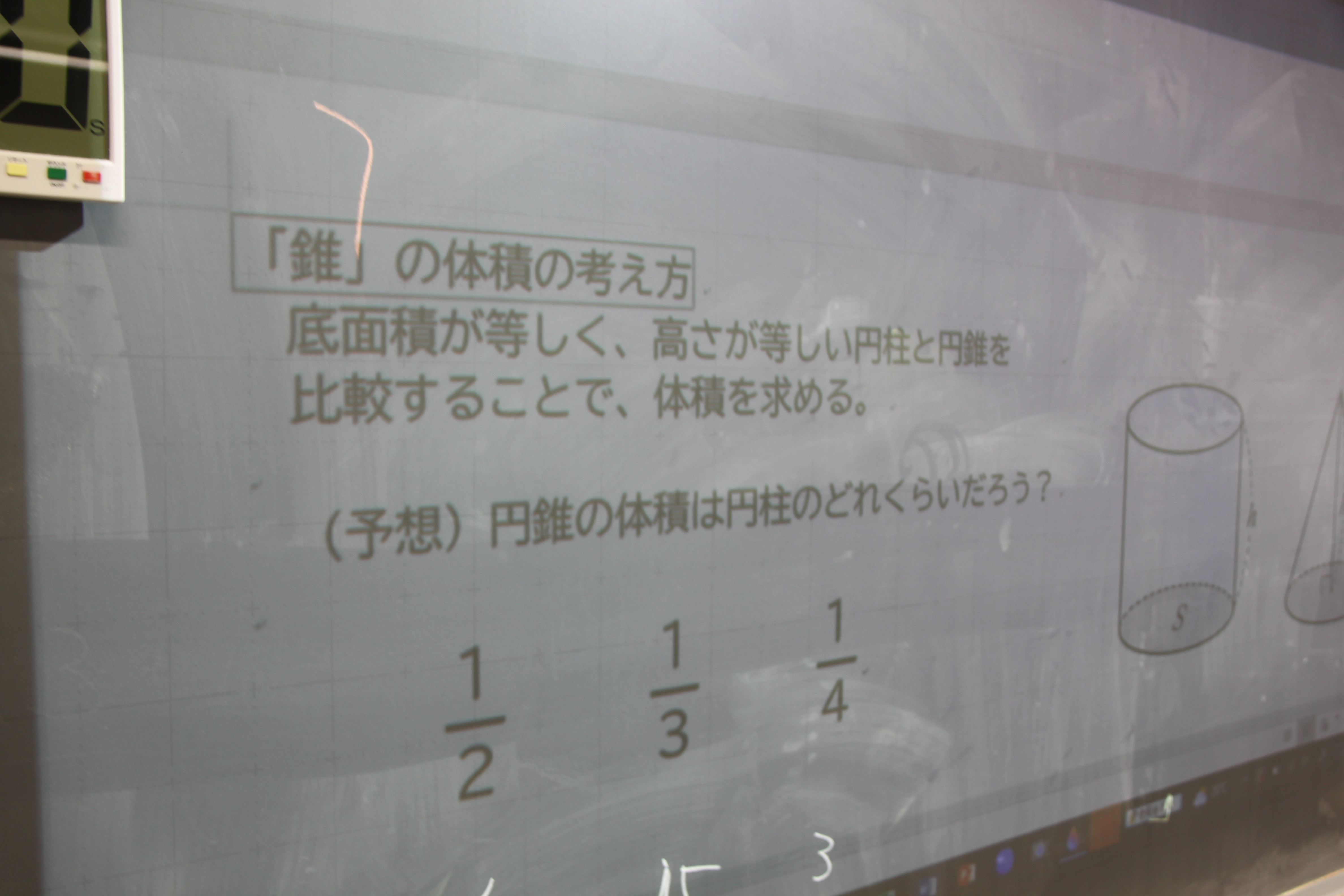
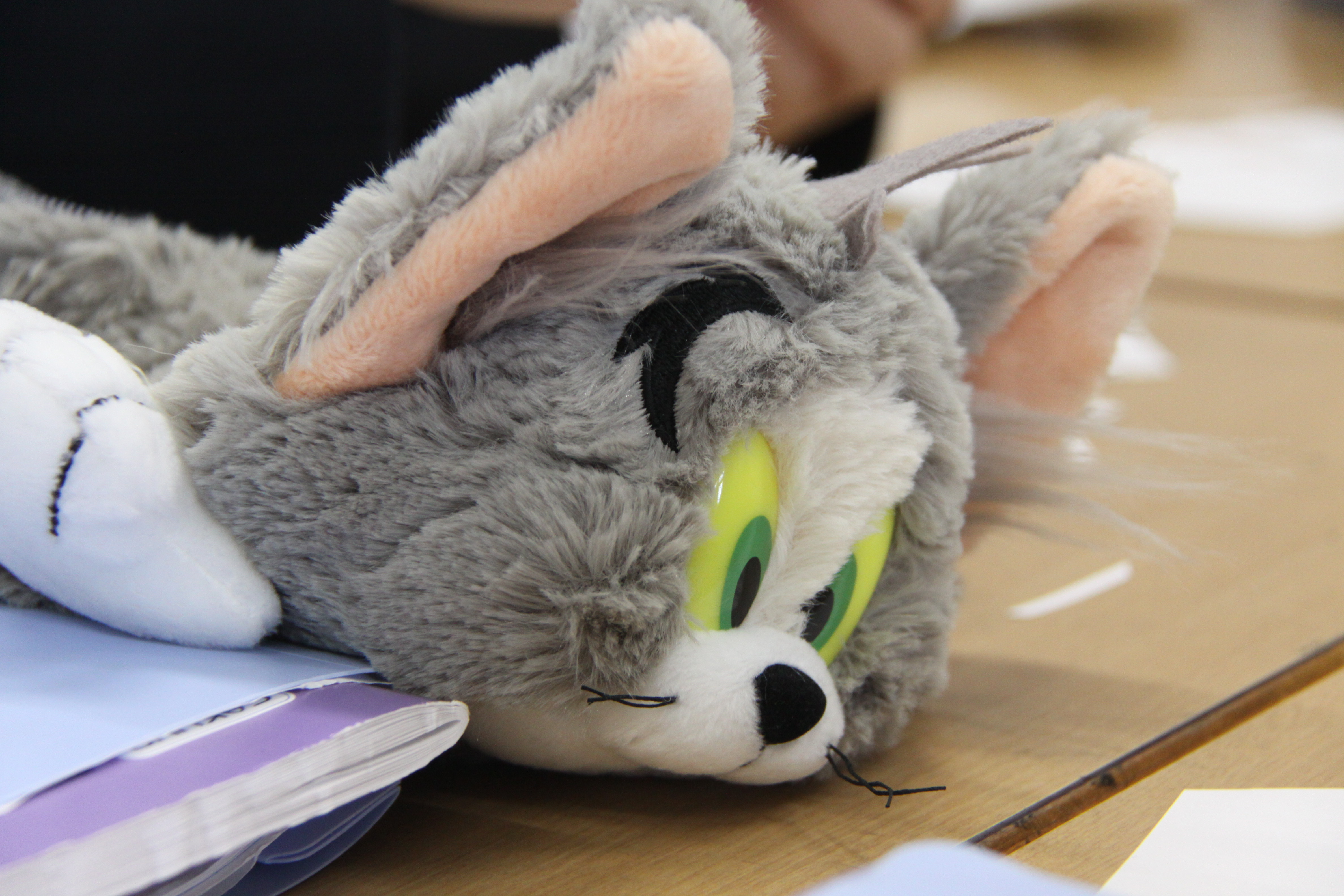
◎ひな中の風✨
「弱さやニガテ」も支え合える学級って素敵ですね。
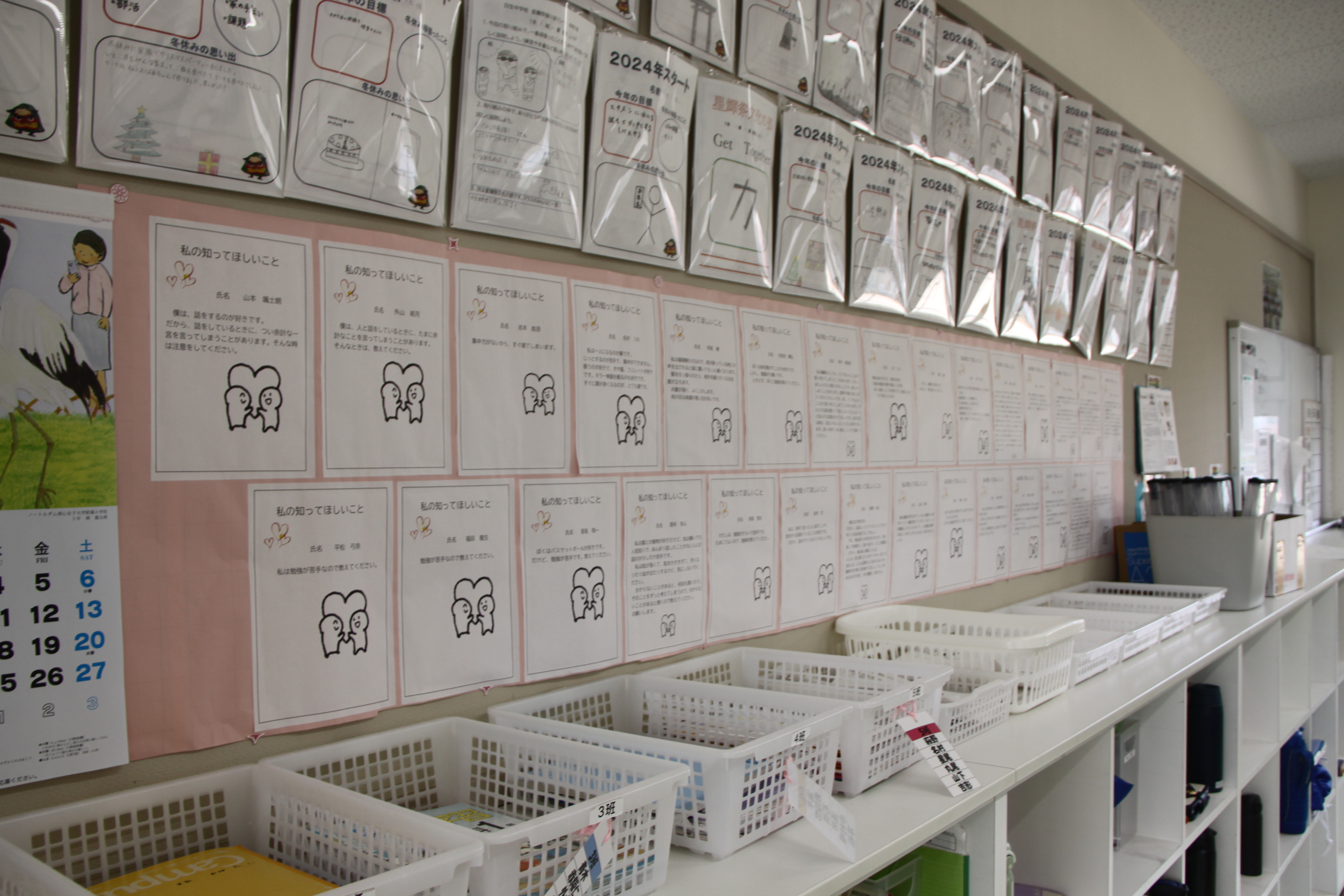
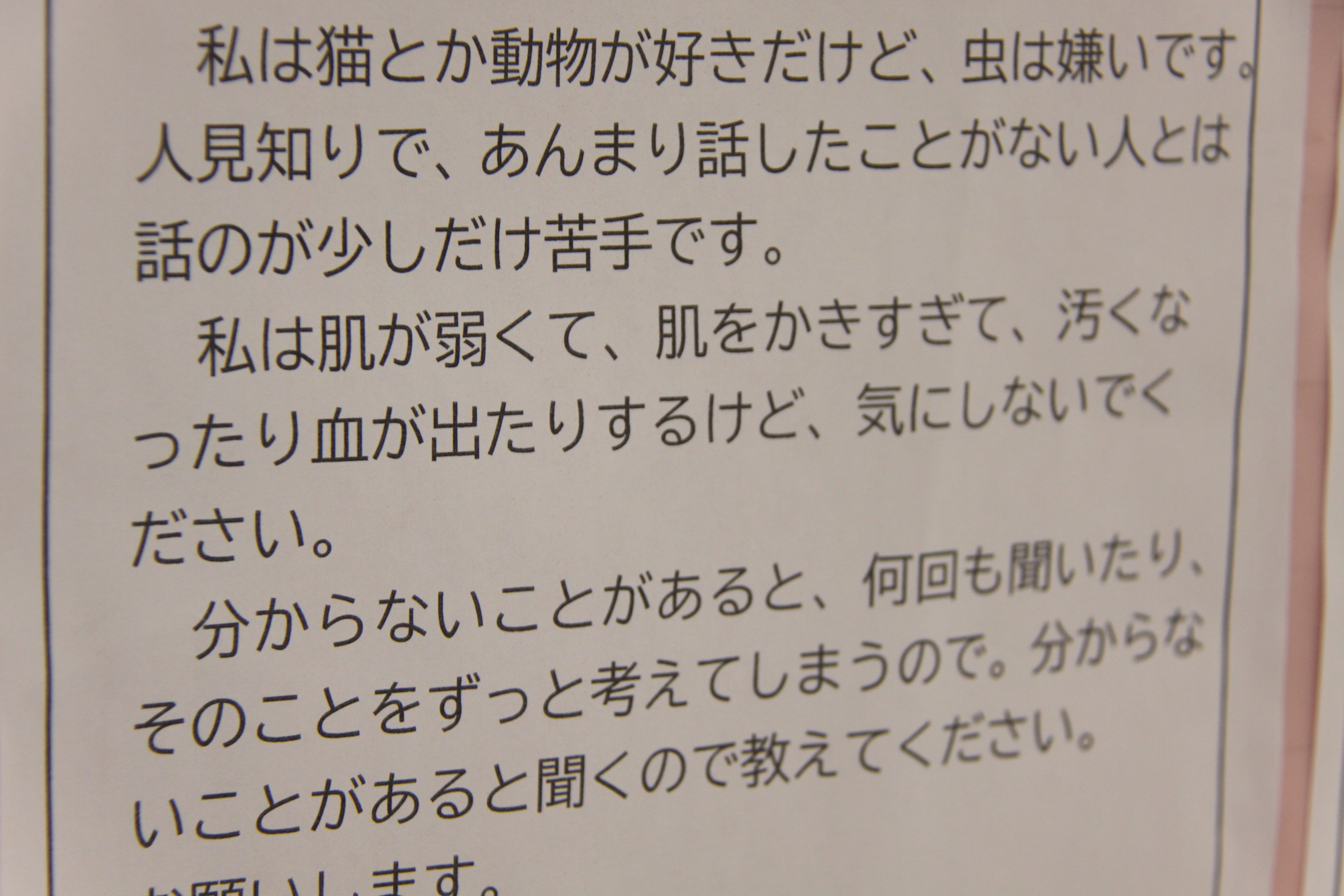
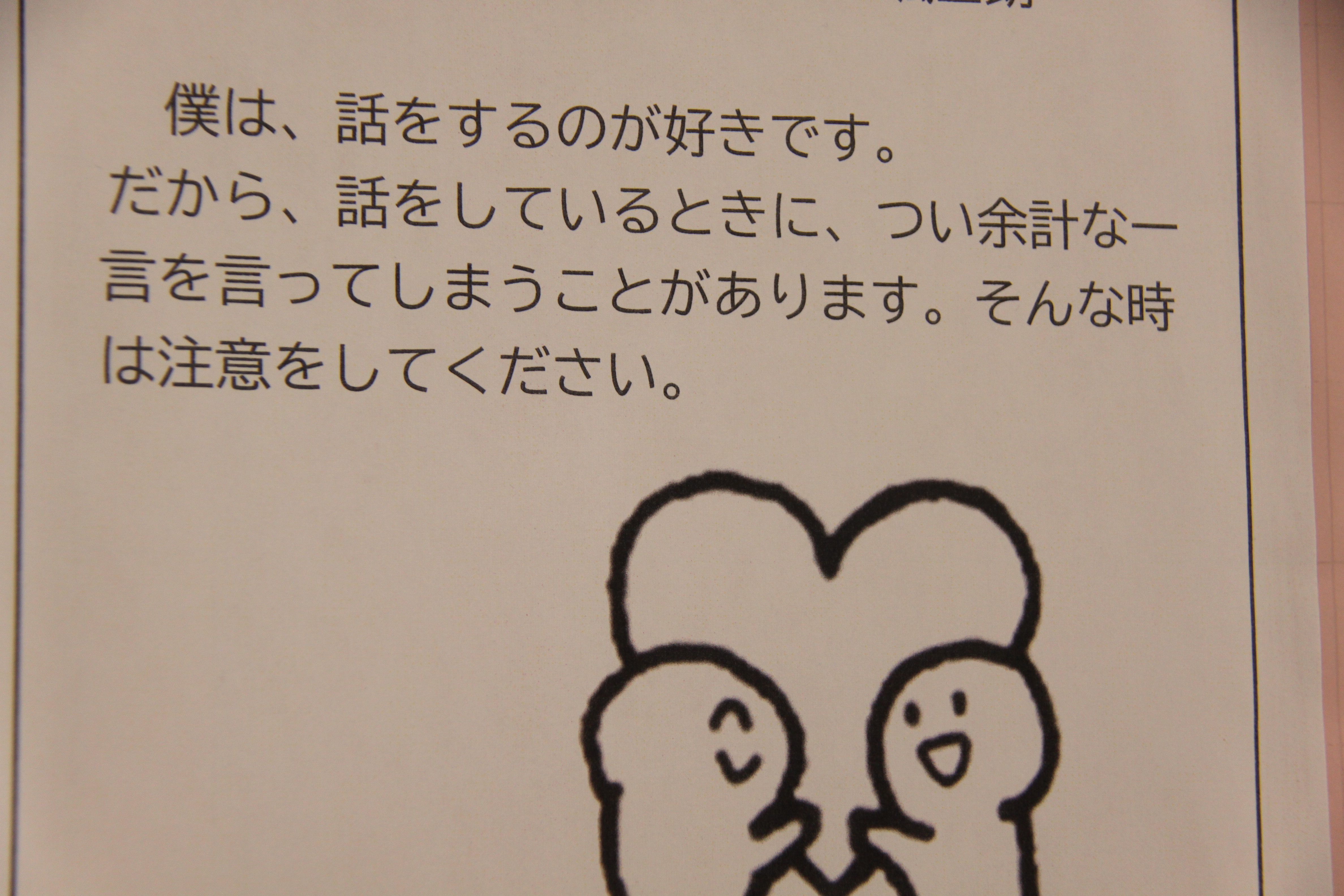
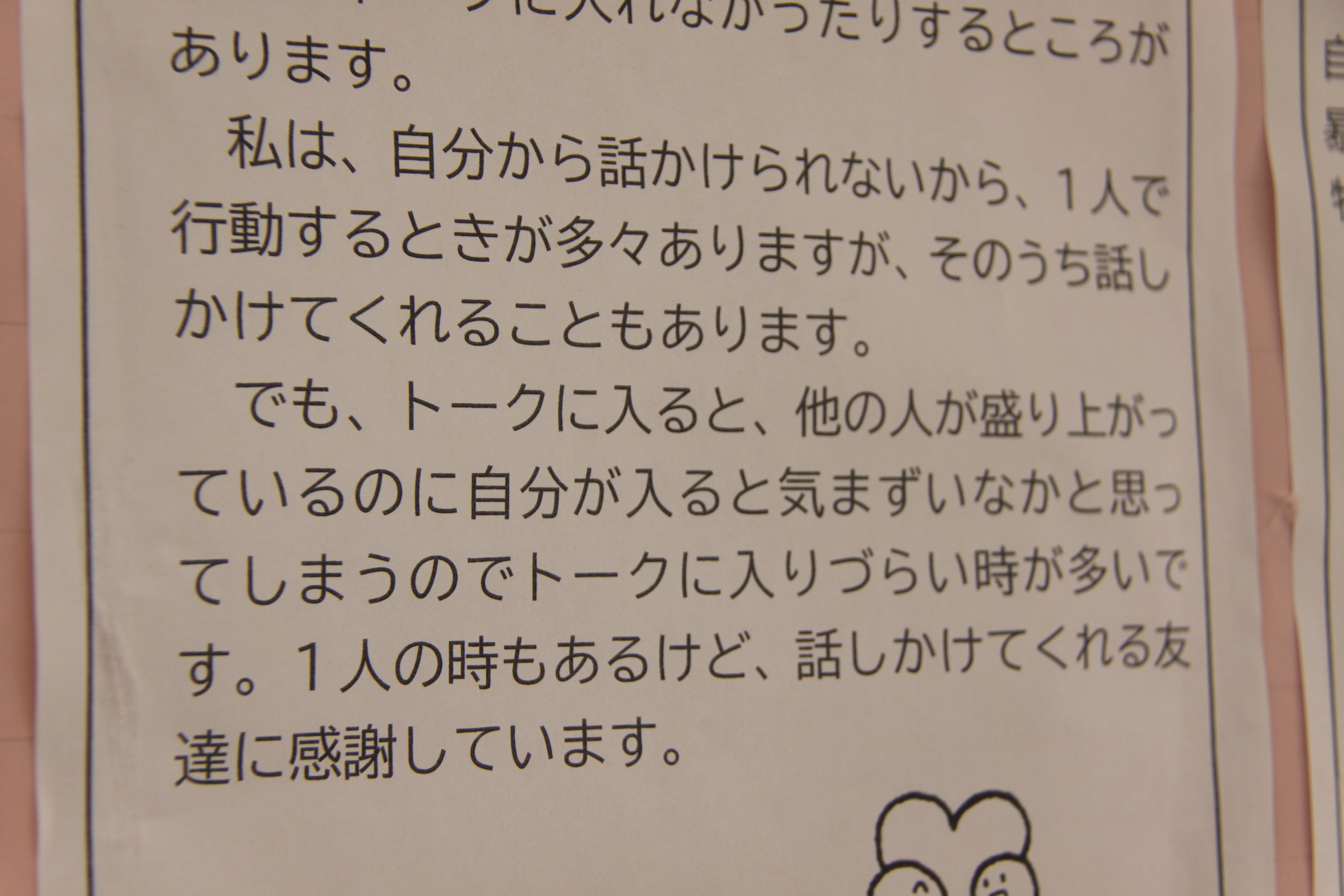


クラスでくらす、そして進級。
◎多くの人に支えられて(1/24~学校給食週間)
1月24~30日は「全国学校給食週間」です。この期間は、「学校給食の意義、役割等について生徒や教職員、保護者、地域住民等の理解と関心を高め、学校給食のより一層の充実発展を図ること」を目的としています。

〈学校給食はいつから始まったの?〉
今では当たり前となっている給食ですが、その始まりは明治22年。山形県鶴岡町の小学校でした。当時は貧しい状況の児童を対象に無料で提供され、その献立は「おにぎり・焼き鮭・漬物」のようなシンプルなものだったようです。その後、全国に広まり実施されるようになりましたが、戦争による食料不足により一時中断せざるを得なくなりました。やがて戦争が終わり、1946年(昭和21年)12月24日に東京・神奈川・千葉の3都県の学校で試験給食が実施されました。それ以来、12月24日を学校給食感謝の日と定めていましたが、冬休みと重なるため、1月24日から30日までの1週間が「全国学校給食週間」となりました。農林水産省は毎年1月を「食を考える月間」として各種取組を進めることとしています。備前市、調理場さんと連携して、給食委員会も、「食育」に関する取組を積極的に進めていきます。
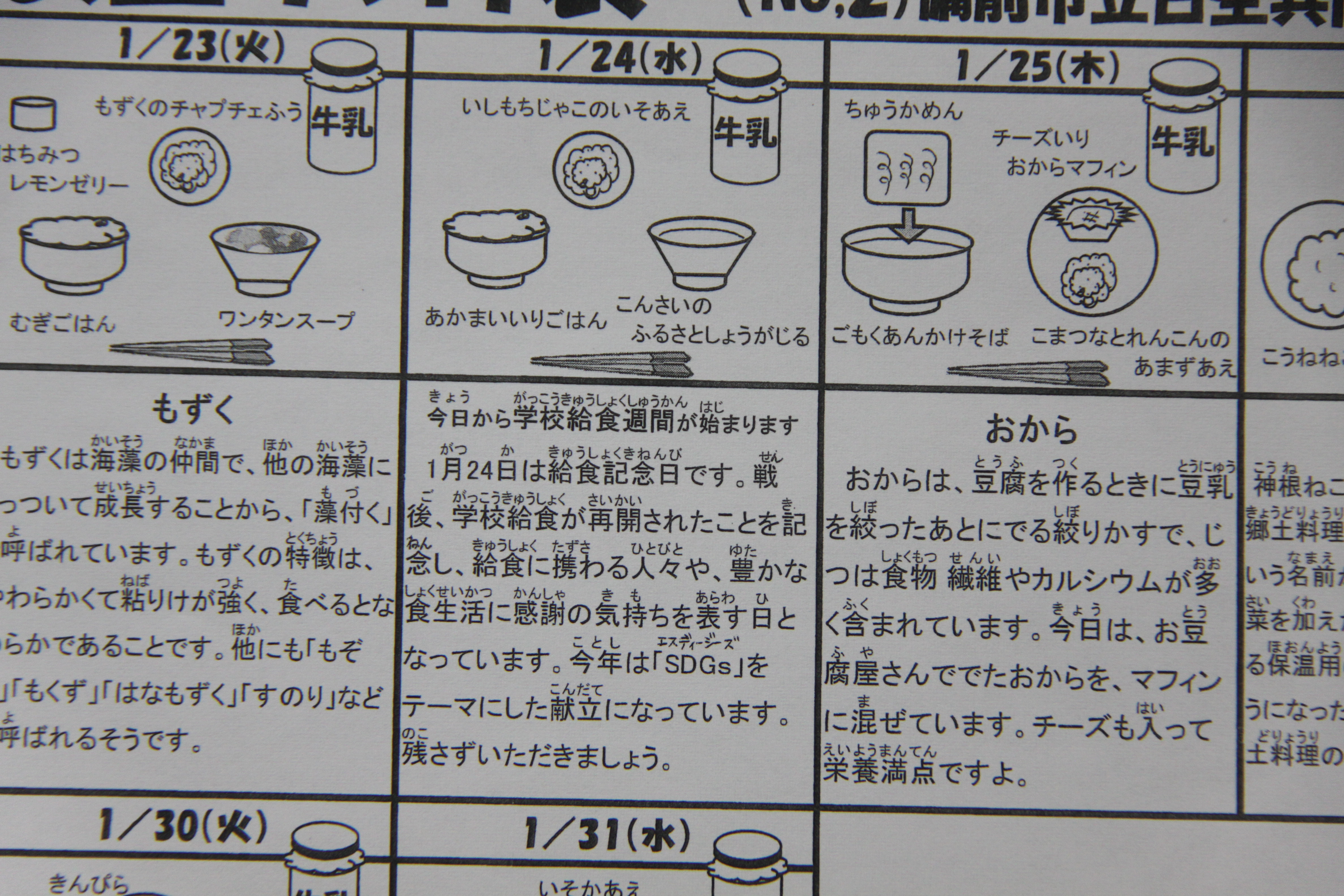
◎社会の中で、共に生きる・くらすために(1/23)
今日は、備前警察署を中心に学校とPTAも連携し、広域特別補導啓発活動(片上駅)を行いました。中学生になると電車を使う機会も増え、また中学校卒業後は、進学した高校に通うために電車を利用する人も多いと思います。この機会に、電車(公共交通機関)のマナー等を少し学びましょう。
【歩く】
○エスカレーターに乗るときは手すりをつかんで立ち止まりましょう。転ぶと危ないです。
○キャリーバックなど大きなカバンを持って歩くときは周囲に配慮しましょう。
○傘を持って歩くときは傘を下に向けて歩くと安心です。
【並ぶとき】
○電車を待つときは整列乗車を心がけましょう。
【乗るとき】
○発車間際の電車に駆け込むのは危ないので、余裕を持った乗車を心がけましょう。
○電車に乗ったら入口付近で立ち止まらず奥まで進みましょう。
【座るとき】
○座席を必要としている人に席を譲りましょう。
○荷物は座席の上に置かず、膝の上に置きましょう。
○多くの人が席を利用できるように足を広げたりせずに座りましょう。
【電車内での過ごし方】
○車内では会話は控えめに、飲食は周りの人への配慮を心がけましょう。
○イヤホンからの音漏れに気をつけましょう。
○濡れた傘を広げたまま持つと周りの人が濡れてしまいます。閉じて持ちましょう。
○車内で携帯電話やスマホを使うときは周りの人の迷惑になっていないか気をつけましょう。
【荷物を持つとき】
○車内ではリュックなどは自分の体の前にかかえましょう。
○荷物はドアの前に置かず荷物棚を利用しましょう。
【いつでも】
○困っている人を見かけたら声をかけて助け合いましょう。
〈追記〉校門近くを通るあなたへ。 臨時のゴミ入れを置きました。「ここに入れてね。というよりも持って帰ってね」

◎〈いま・現代・これから〉に生きる学び(1/23)
~2年生社会科・渋染一揆に学ぶ~
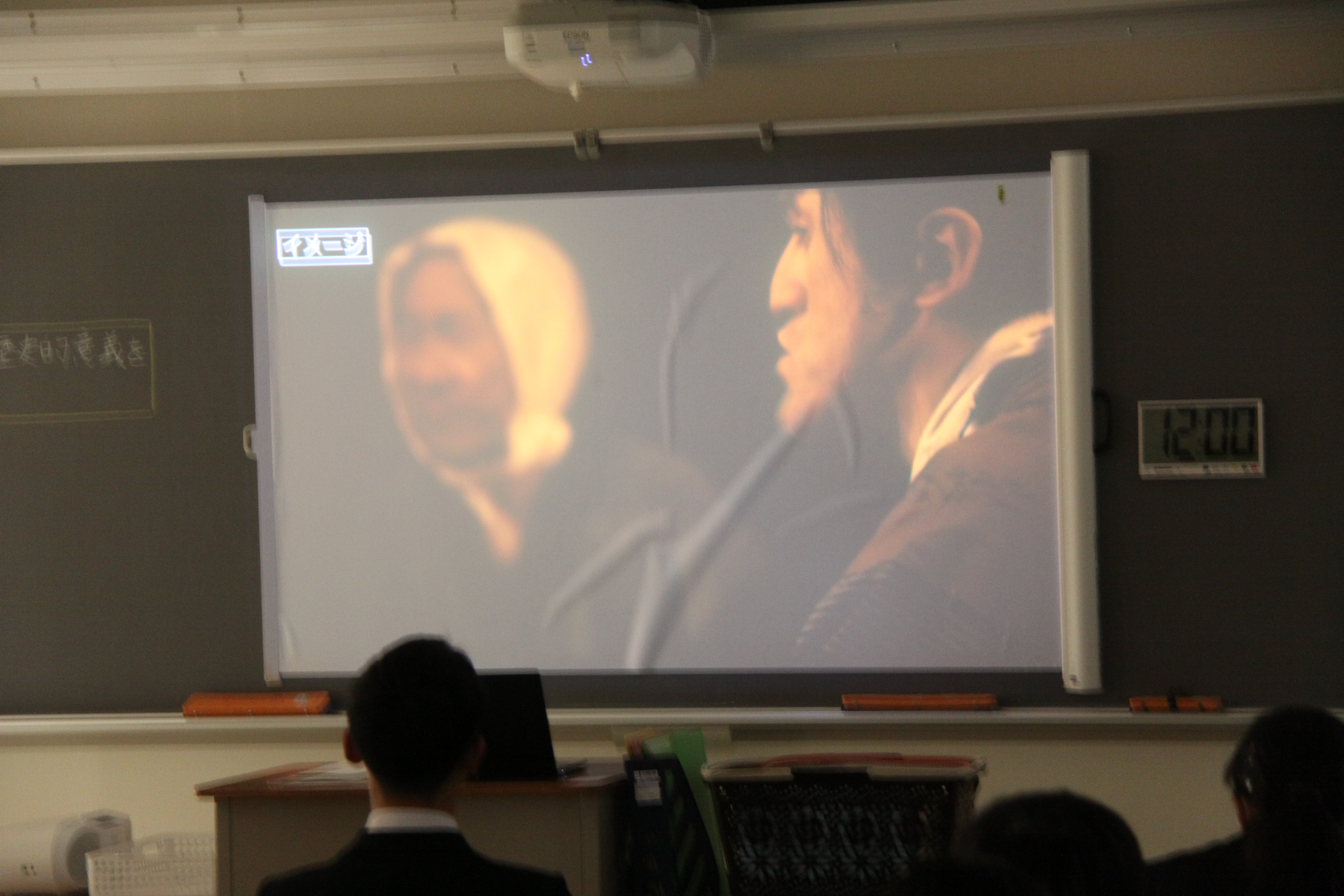
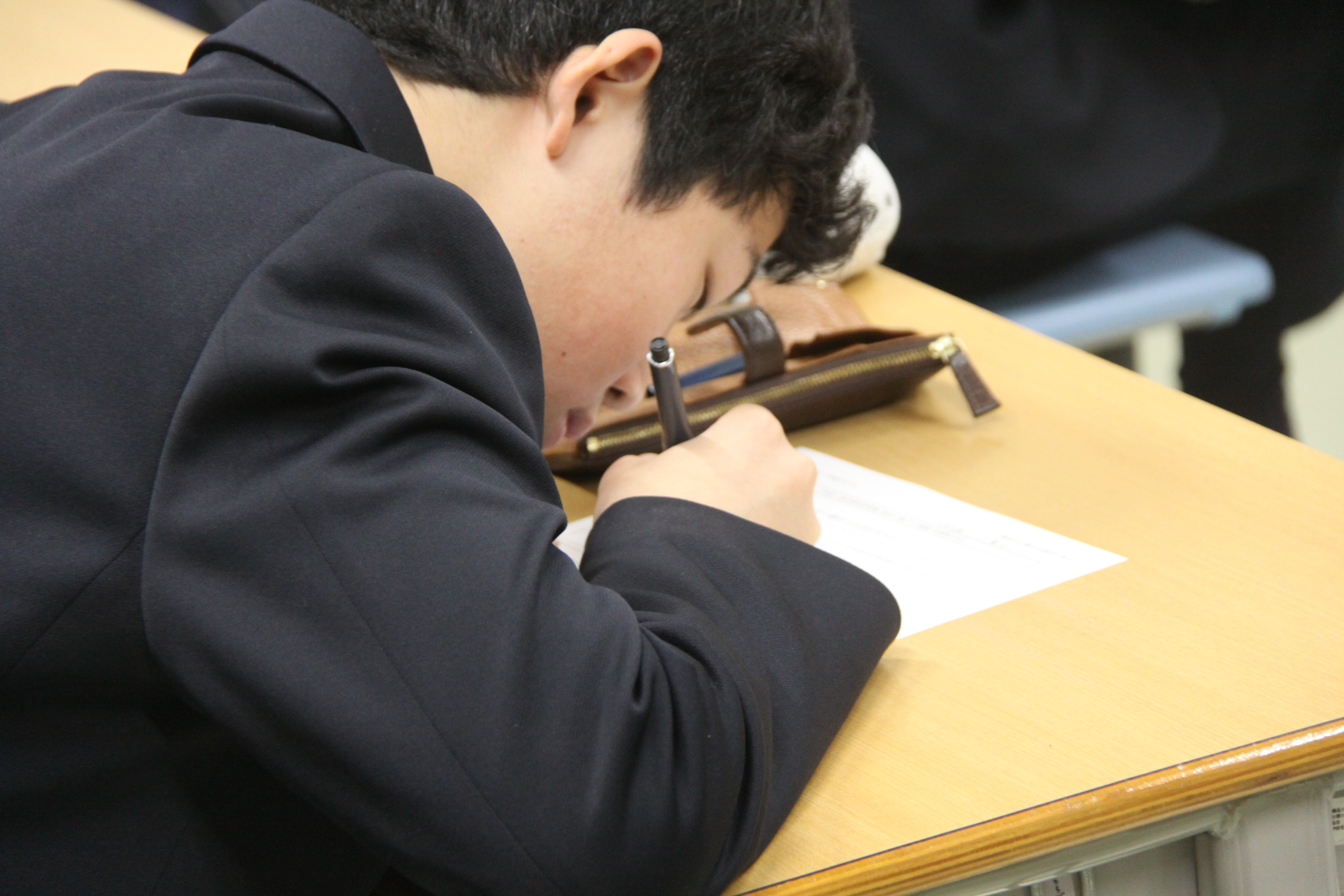

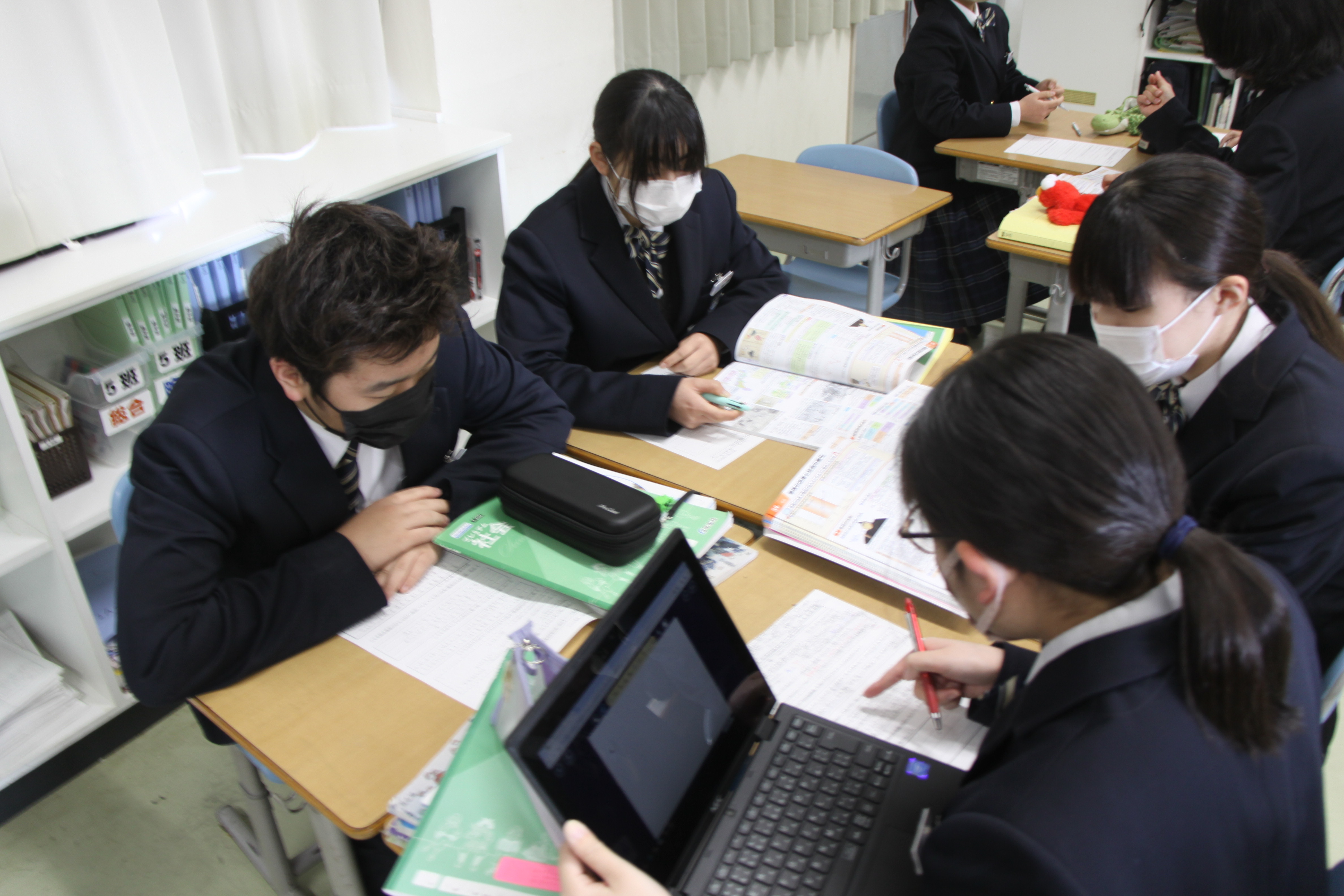
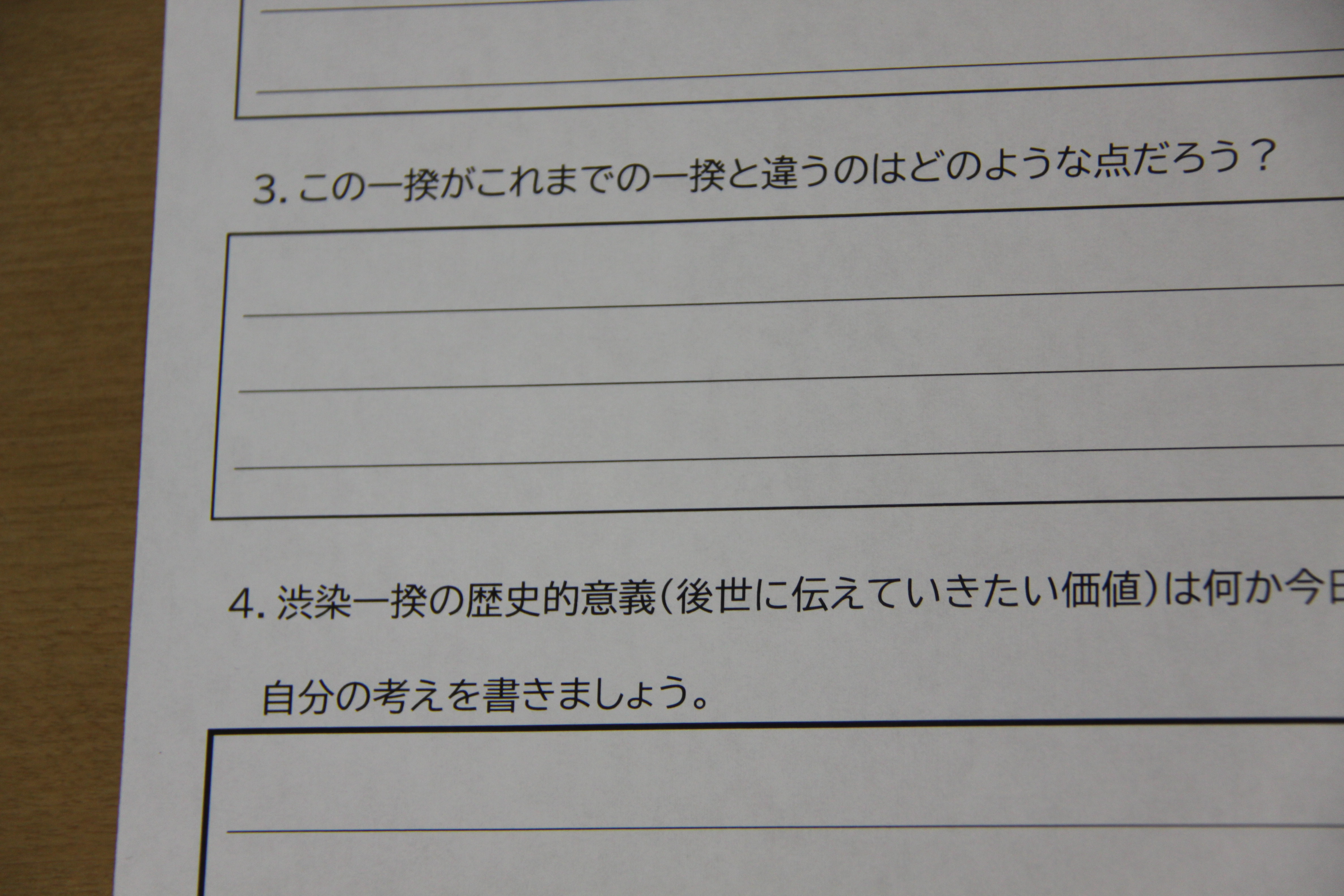
2年生が、社会科授業で「渋染一揆」に学びました。
私も、社会科歴史教科書に記述されている「渋染一揆」を大切に取り組んできました。また、最近では、「渋染一揆」を、社会科学習のみならず、特別活動においても、「いじめ問題」や、「望ましい人間関係の形成」や、「学ぶことや生きることの意義」等を考えていく授業実践が広がっています。そして今日、授業で活用した『渋染一揆を戦いぬいた人々』(DVD)について道徳で深めていくなら、「分け隔て」や「差別」の不当性をしっかりと見抜き、正義の実現に向けて、知恵を絞って行動した人々から「真理の探究」を学ぶことができます。また、子や孫のためにと撤回を求めて一揆に立ち上がった姿や入牢させられた仲間たちを助け出すために粘り強く闘い続けた人々の姿に注目したり、いまなお犠牲となった人々の功績と意志を受け継いで守り続けておられる方々の存在に注目したりすることで、「よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し、人間としての生きる喜びを感じる」道徳的価値に迫ることができます。さらには、〔信頼や友情〕や〔相互理解、寛容〕という項目でも、一揆に立ち上がった人々の強い絆だけではなく、差別を乗り越えて彼らを支持した百姓たちの姿に着目して学ぶことができます。
渋染一揆とは、1856年岡山(備前)藩五十三か村の被差別身分(かわた)の人々が差別法令(「別段御触書」)の差別性に気づき、民主的戦略をもとにこれを空文化させた闘いです。渋染一揆が成功した要因としては①「百姓」としての誇り(=人間としての誇り)、②かしこさ、したたかさ(=学問の重要性)、③自治力・団結力(=連帯の重要性)、④人間による、人間を取り返す行動(=行動の重要性)があげられます。渋染一揆の学習を通して、今を生きる私たち自身の課題に向き合い、差別に「気づく」、差別に「怒る」、差別解消に向けた「学習」を積み重ねる、ともに行動する「仲間」を増やす、そして「行動」する一連の≪解放のモデル≫を学び取ることができます。
また、「倹約御触書」と「別段御触書」を比較検討し、「別段御触書」が差別法令であることに気づかせます。「別段御触書」を出された人々の思いを考えます。経済・政治の面から封建体制が崩れだし、幕府や藩は身分制強化によってこれを乗り切ろうとします。部落だけではなく、武士も含めそれぞれの階層に規制の通達を繰り返します。身分制社会体制下にあっては、不満はあるものの仕方ないことだと大方はこれを受け入れます。ですが、岡山藩下五十三部落の人たちはこれを拒否します。身分制差別が当たり前の社会にあって、差別的扱いを否定する思想がどうして生まれたのか、考えてみることができます。
さらに、五回にわたる惣寄合:「渋染一揆」は特定の指導者の判断・指導というよりも、地域での話し合い、全体の話し合い(惣寄合)によって進められました。嘆願書も全員によって一言一句討議されました。民主主義的な手続き(討議)を経ています。このような民主的方法はどうして生まれたのかも考えてみる必要があります。(民主的合意形成 自治的組織)
多くの一揆の要求の大部分は年貢の引き下げや不正摘発(経済的不利益を受ける)であり、生活困窮のため止むにやまれぬものでした。これに比べて「渋染一揆」は、経済的要求ではありません。「同じに扱え」という今日でいえば「平等」を求める、その他の一揆にはみられない要求です。また他の一揆との違いは、武装をしなかったことです。一揆では威嚇や自衛のため、竹槍や鎌、ときには鉄砲も使われましたが、「渋染一揆」では何も持ちませんでした。徹底した話し合い(交渉)によって必ず勝利するという自信をもっていました。この確信のもとに一揆勢は佐山で代表による交渉にのぞみました。今でいう「行政交渉」の始まりともいえます。
当時「別器、別火、別食」が当然とされていた中で、百姓の茶屋万次郎が人を雇って水を振る舞ったことは、嘆願書を添削した目明かしや、助命嘆願を支援した百姓村の有力者とともに、百姓身分の人たちが一揆を支援していた証左として確認し、「差別することが当たり前」という間違った世の中は、「差別は絶対に許さない」と行動した人たちによって変わっていったことを学びたいと思います。(*「シリーズ映像で見る人権の歴史『渋染一揆を戦いぬいた人々』」資料より、久次)
◎ひな中のかぜ✨
~ひとのあいだ(^_^)~(1/22)
落ちていた小学生の帽子を、登校途中の2年生が見つけ、中学校へ届けてくれました。早速、小学校へ持っていきましたら、たいへん喜ばれていました。ありがとうね。



◎多くの人に支えられて(1/22)
先週末から本日まで、タカトリ(株)さんが来校し、グラウンドを整備していただきました。
子どもたちが取り組む学習内容も時代と共に変わっていきます。安全のため、老朽化が進む設備の撤去や整理が必要で、この日は、鉄棒付近の砂場あとを整備していただきました。ありがとうございました。

◎多くの人に支えられて(1/19)
備前市栄養委員会さんが来校され、朝食の大切さや、日生の郷土料理についてのお話を伺うことができました。そして、1月下旬には、中学生に向けても健康・食生活に関するお話をしてくださいます。ありがとうございます。
備前市栄養委員会さんは、長年、「健康びぜん21」「備前市食育推進計画」に基づき、乳幼児から高齢者までのすべての市民が健やかで心豊かに暮らせるまちを実現するために、地域の健康づくりリーダーとして、関係機関・団体などと協力しながら、市民が主体となった健康づくり活動をしておられます。

◎今をやめない やめない やめない
やめてしまえば 叶わないから
:SUPER BEAVER・突破口(1/19)
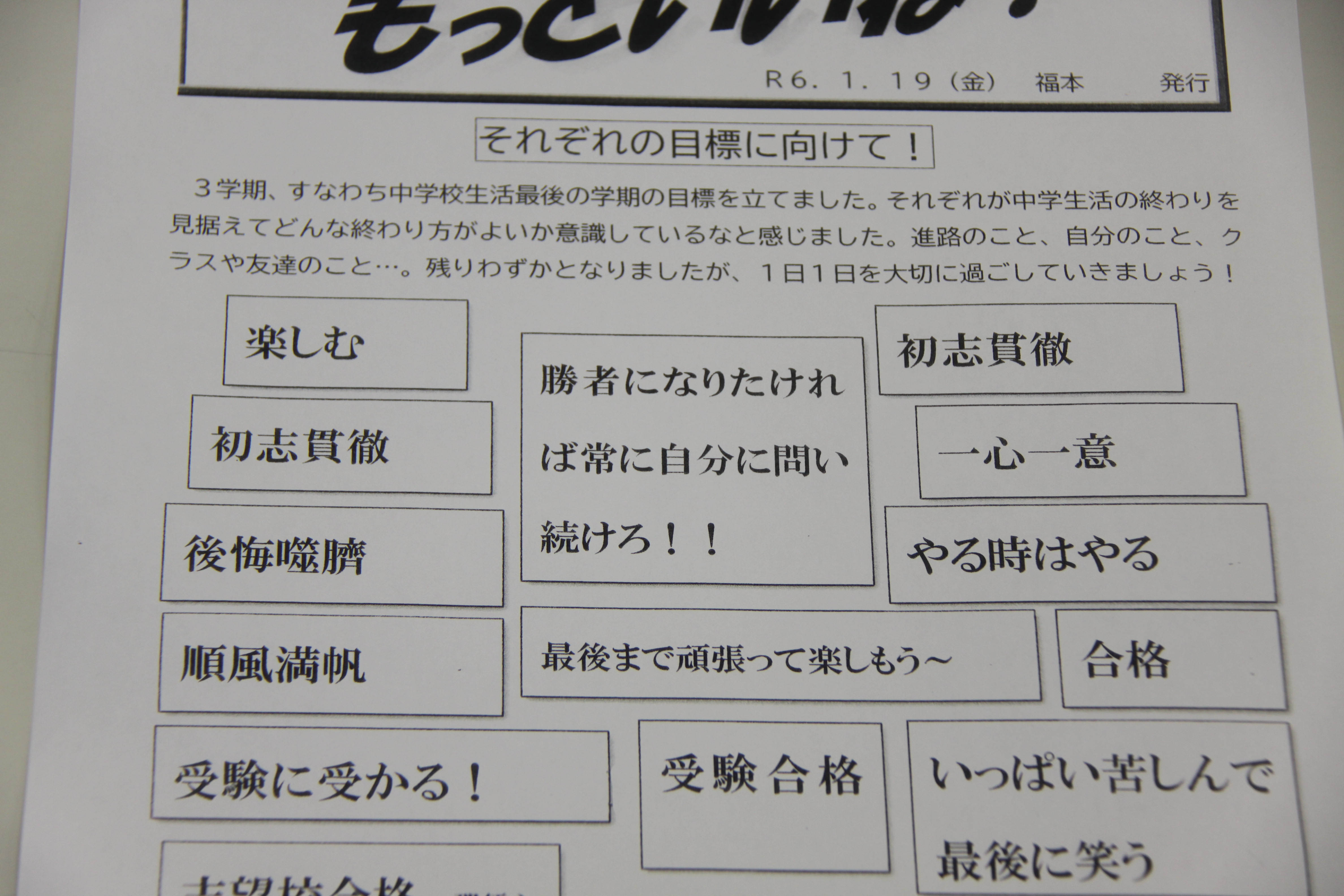
◎ひな中の風✨(1/18)


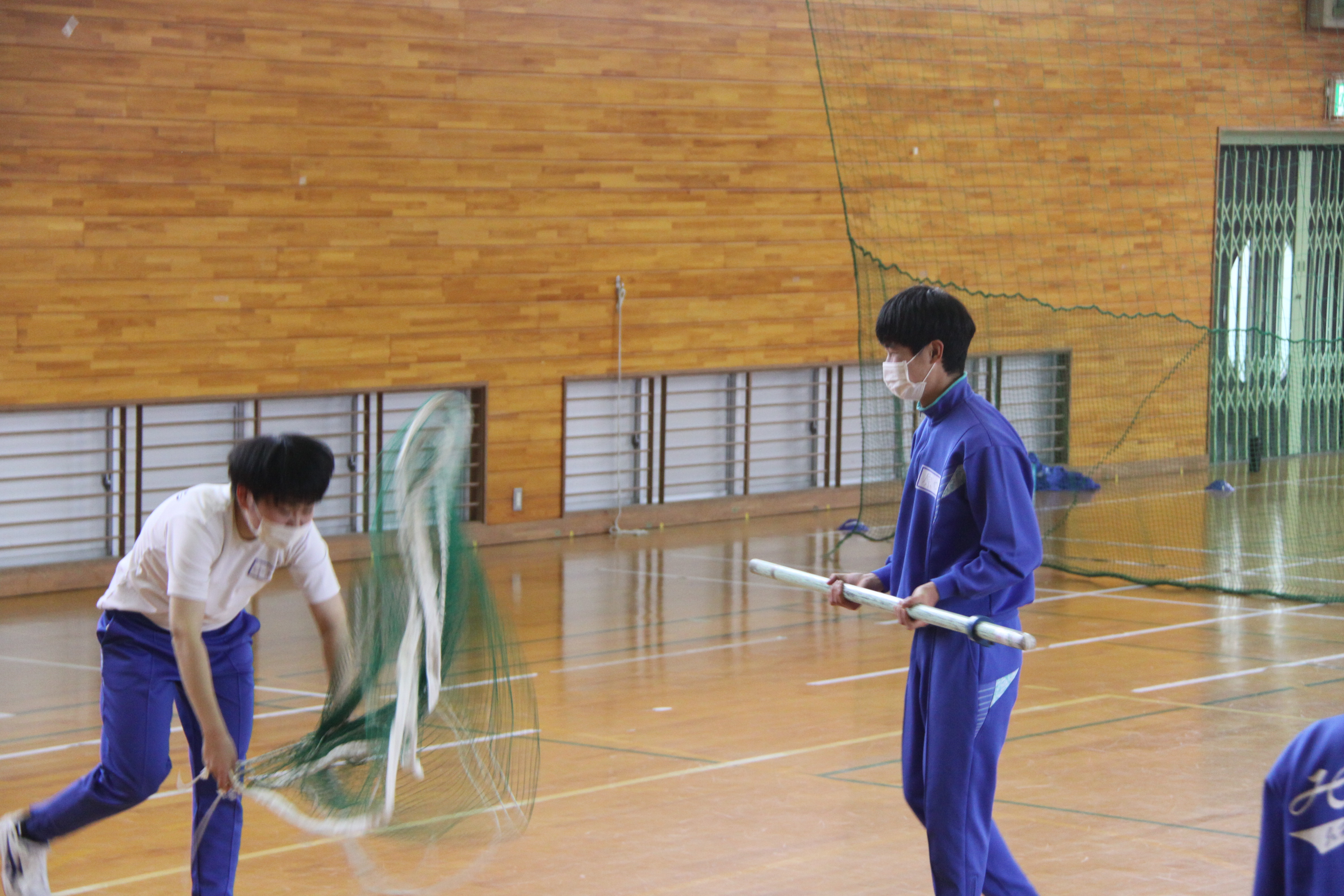
◎私たちのはじまりの風景7(1/17)
ここはどこでしょう?









子どもの頃に見た風景がずっと心の中に残ることがある。いつか大人になり、さまざまな人生の岐路に立った時、人の言葉ではなく、いつか見た風景に励まされたり勇気を与えられたりすることがきっとあるような気がする。『旅をする木』星野道夫より
◎1.17〈ともに〉
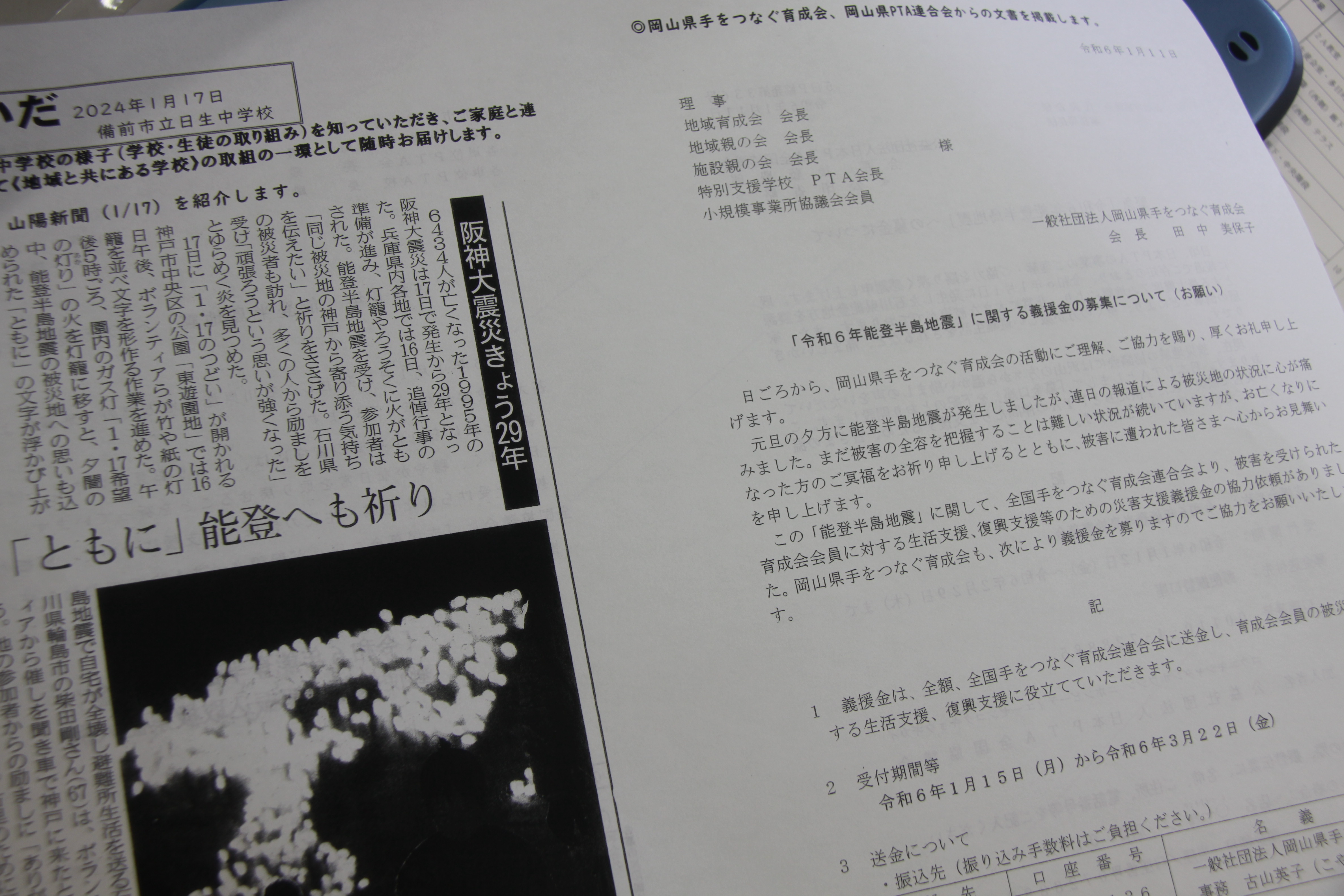
『ひとのあいだ』で、岡山県手をつなぐ育成会、岡山県PTA連合会の義援金等のご協力に関する文書を配布させていただきました。
◎寒中お見舞い申し上げます。
授業がんばっています。







今週末、1/20は大寒です。二十四節気において、「冬の最後を締めくくる約半月」が大寒です。毎年、だいたい1月20日~2月3日ごろです。
大寒の前の半月は「小寒(しょうかん)」。1月5日~19日ごろです。大寒と小寒を合わせて、「寒の内(かんのうち)」と呼びます。寒の内は、1年でもっとも寒い時期。各地で最低気温を記録するのもこのころです。寒の内は合計約30日間。小寒に入ることを「寒の入り(かんのいり)」、大寒が終わることを「寒の明け(かんのあけ)」と呼びます。大寒が終わると、春の始まり「立春」を迎えます。まだまだ寒いながら、冬の極みは過ぎ去り、春への準備が進む季節です。二十四節気においては、立春が1年の始まりなので、大寒の最終日は大みそか的な日でした。今も残る節分の豆まきなどの行事は、新年を迎えるための行事です。
◎ひろがる世界
~今日も、「読み語り」をありがとうございました(1/17)
本校の先生から紹介された本『幸福について』、ショーペンハウアーさんのコトバ。「自力でできる唯一のことは、「今の自分は何者であるか」を最大限に活かすことであり、したがってそれにふさわしい熱心な企てのみを追求し、それに合った修行の道にはげみ、わき目もふらず、ひいては、それにぴったりした地位や仕事や生き方を選ぶことである。」


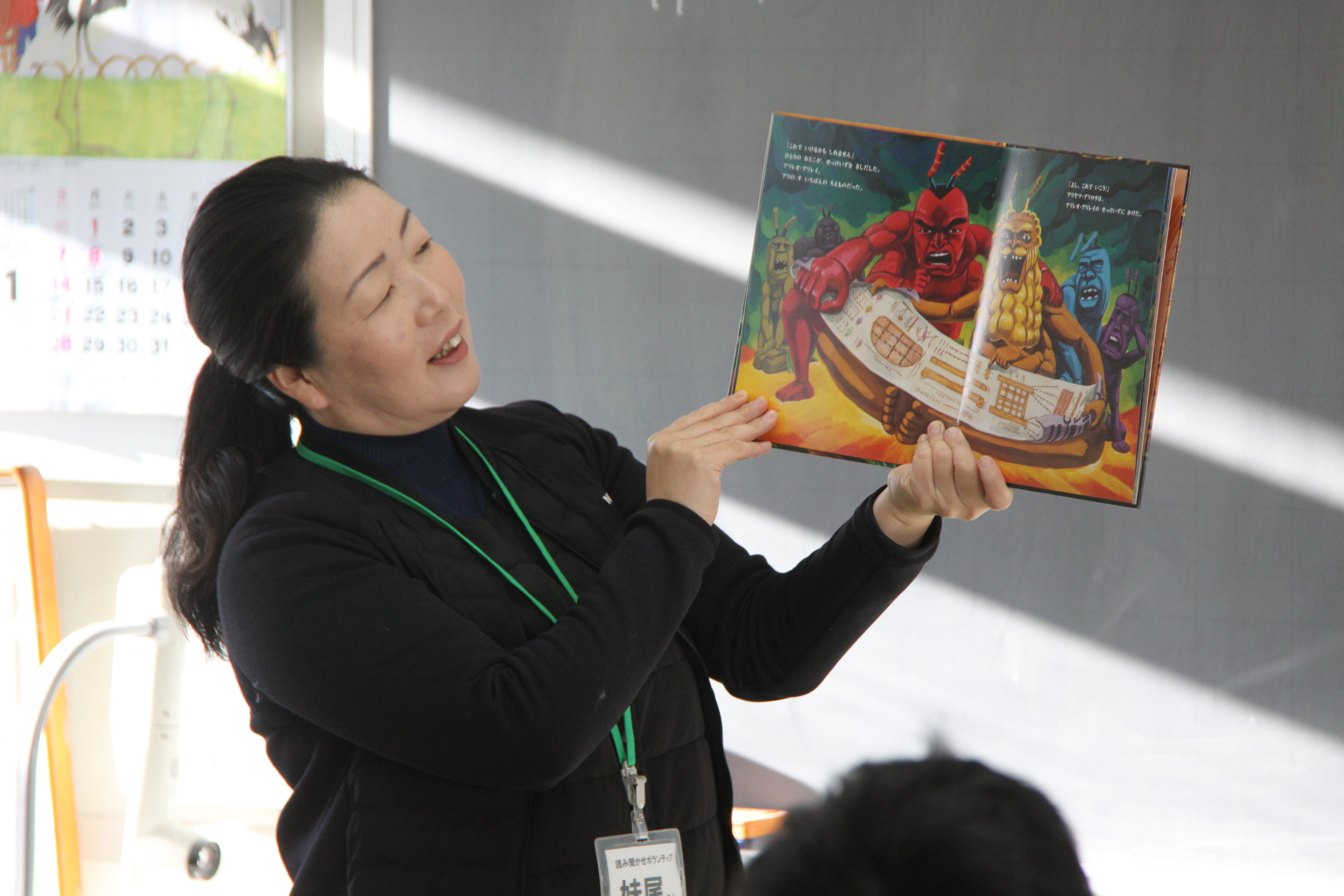
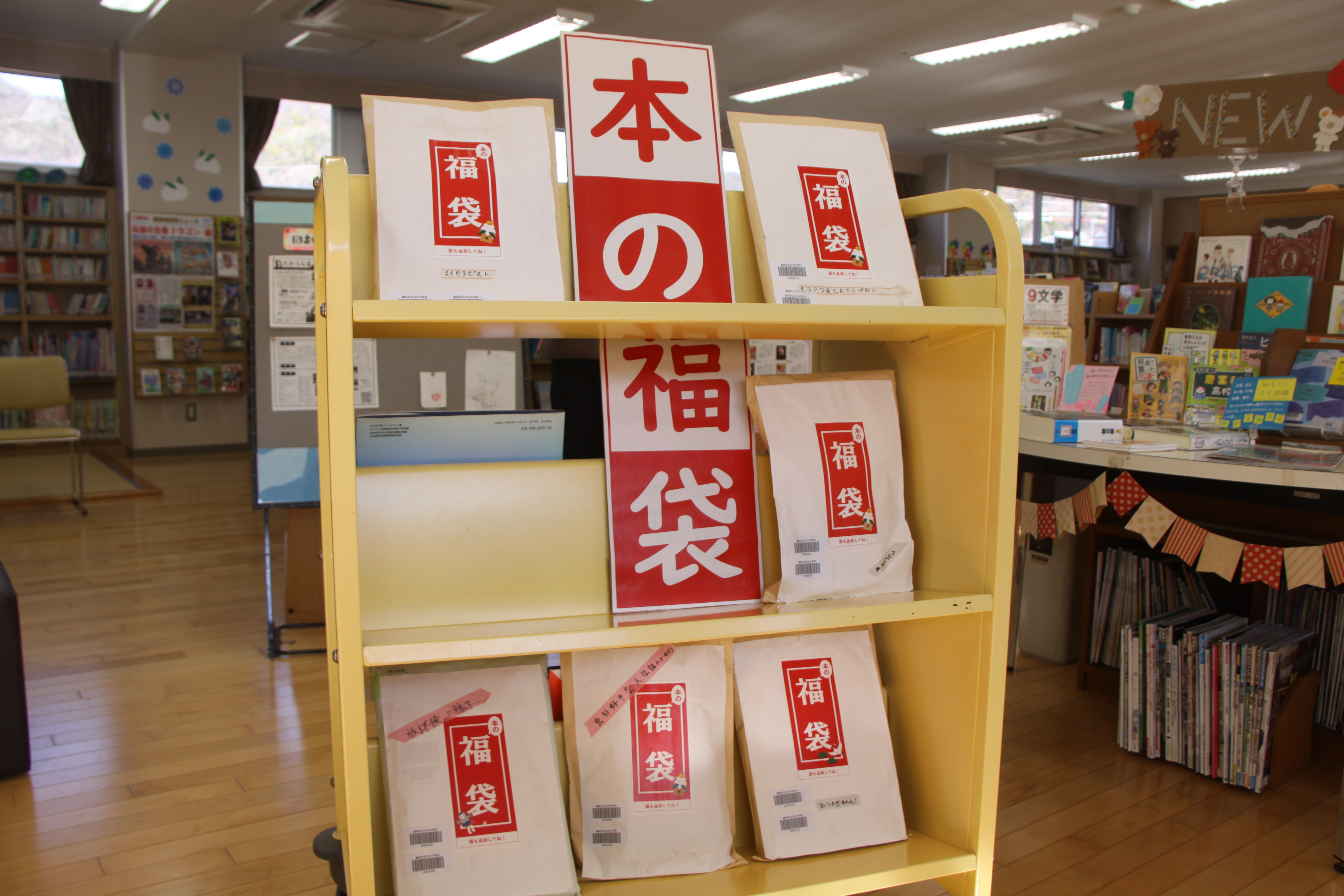
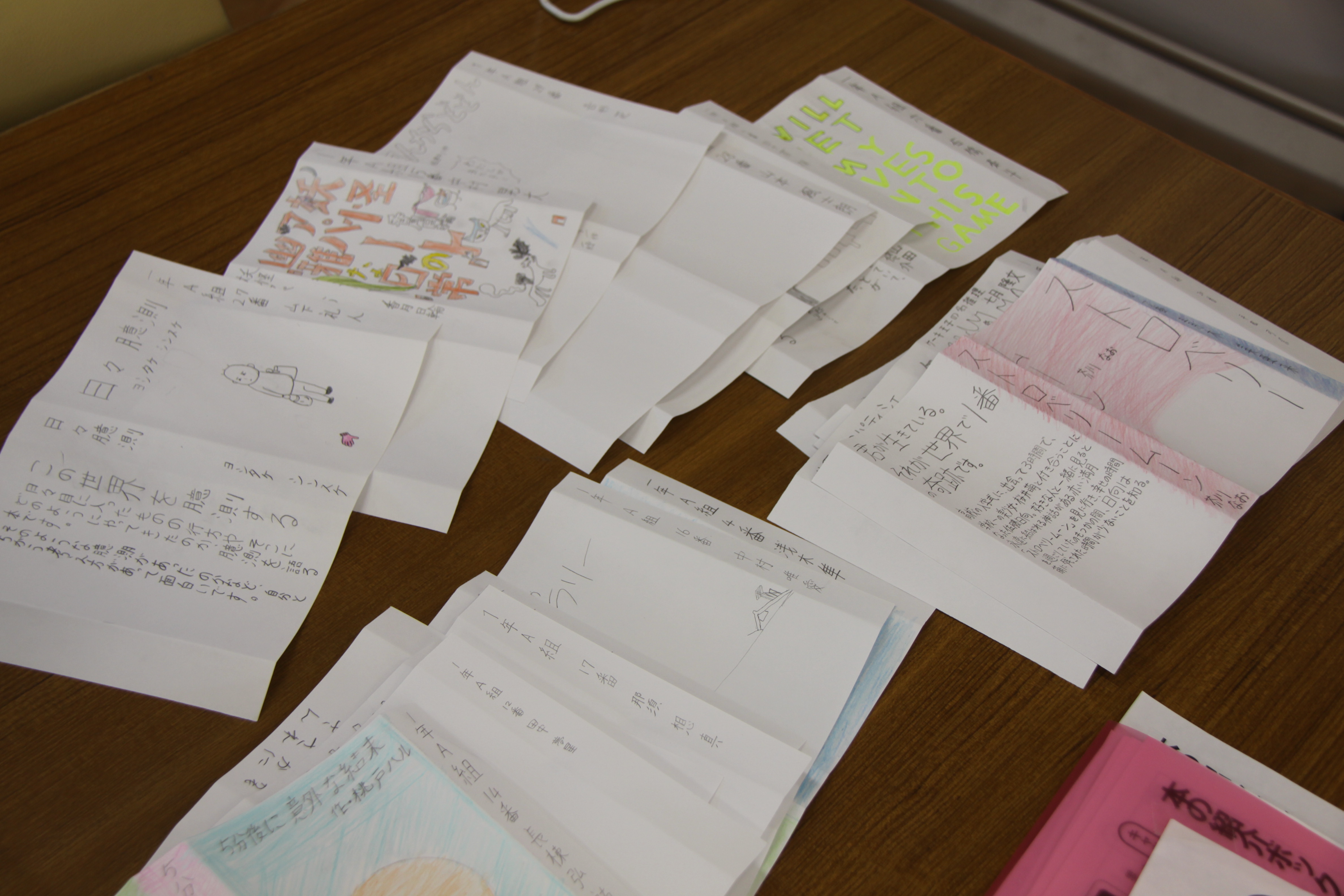

国語科と連携。1年生〈本の紹介ボックス〉、2年生〈ワタシの一行〉づくり
(*^o^*ポッキーを食べるのも宿題!?)
◎未来へ伝える・つなぐ・結ぶ
~たくさんの方が来場されています(1/16)
3年生のハンセン病問題学習展示(日生地域公民館)に、地域の方々が来場されています。


Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela
(教育は、世界を変えることができる、最も強力な武器である。)
◎生活を大切にする~防犯・規範意識を高める~
〈鍵かけコンテストを通して(1/16)〉
6月から11月に実施した自転車鍵かけコンテスト(岡山県警察本部主催)に、本校も体育委員会を中心に取り組み、この度、集計の結果(第2部:日生中平均施錠率99.11%)、知事表彰受賞校となった通知を受けました。ありがとうございます。これからも生活を大切にしていきます。

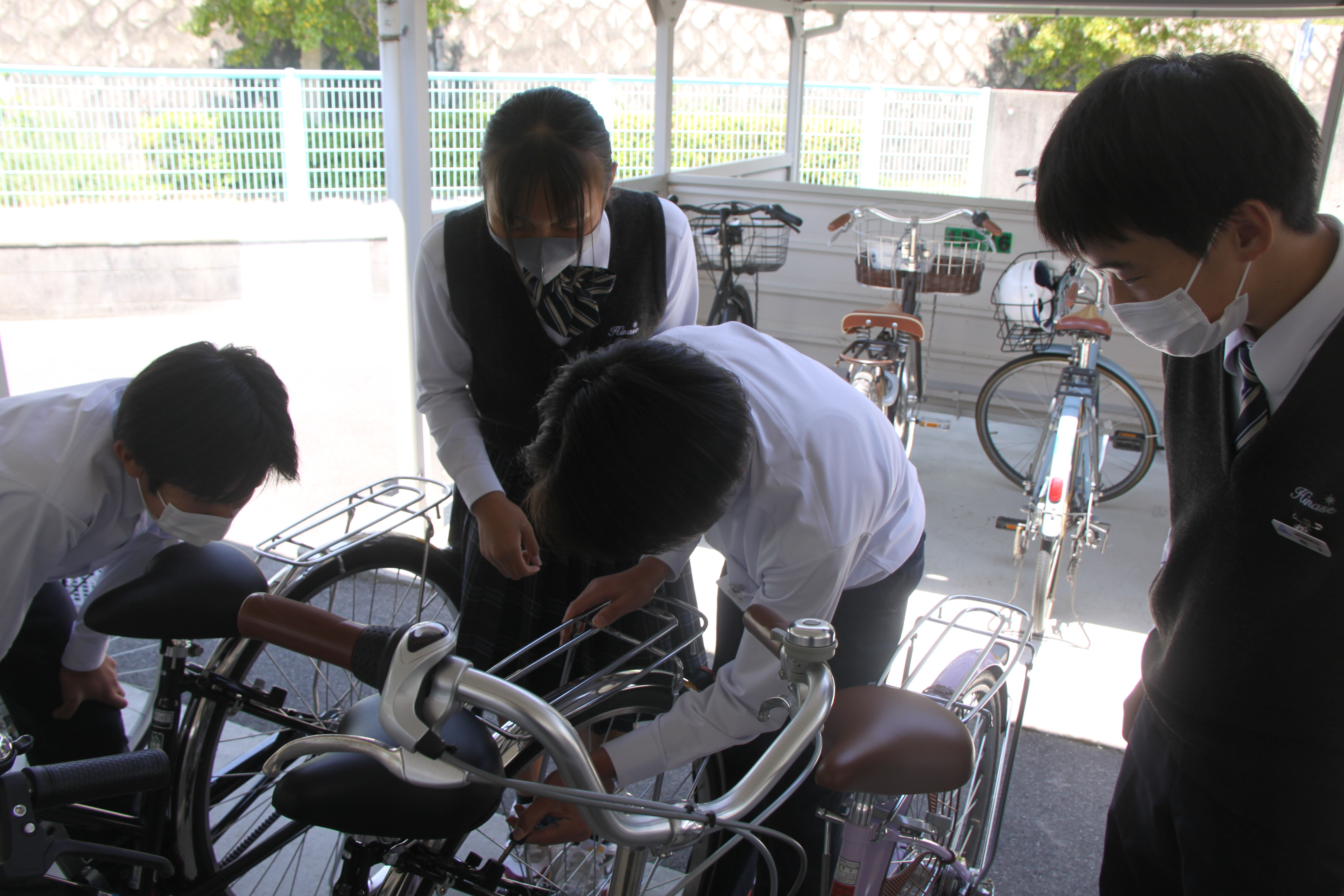




◎多くの人に支えられて
整った学習環境でがんばるために(1/16)
施設・備品を大切に使っています。老朽化して傷んだ箇所等(体育館前床タイル・テニスコートフェンス支柱撤去工事後・ソーラーシステムバッテリー交換)を学校で工夫して修繕しました。



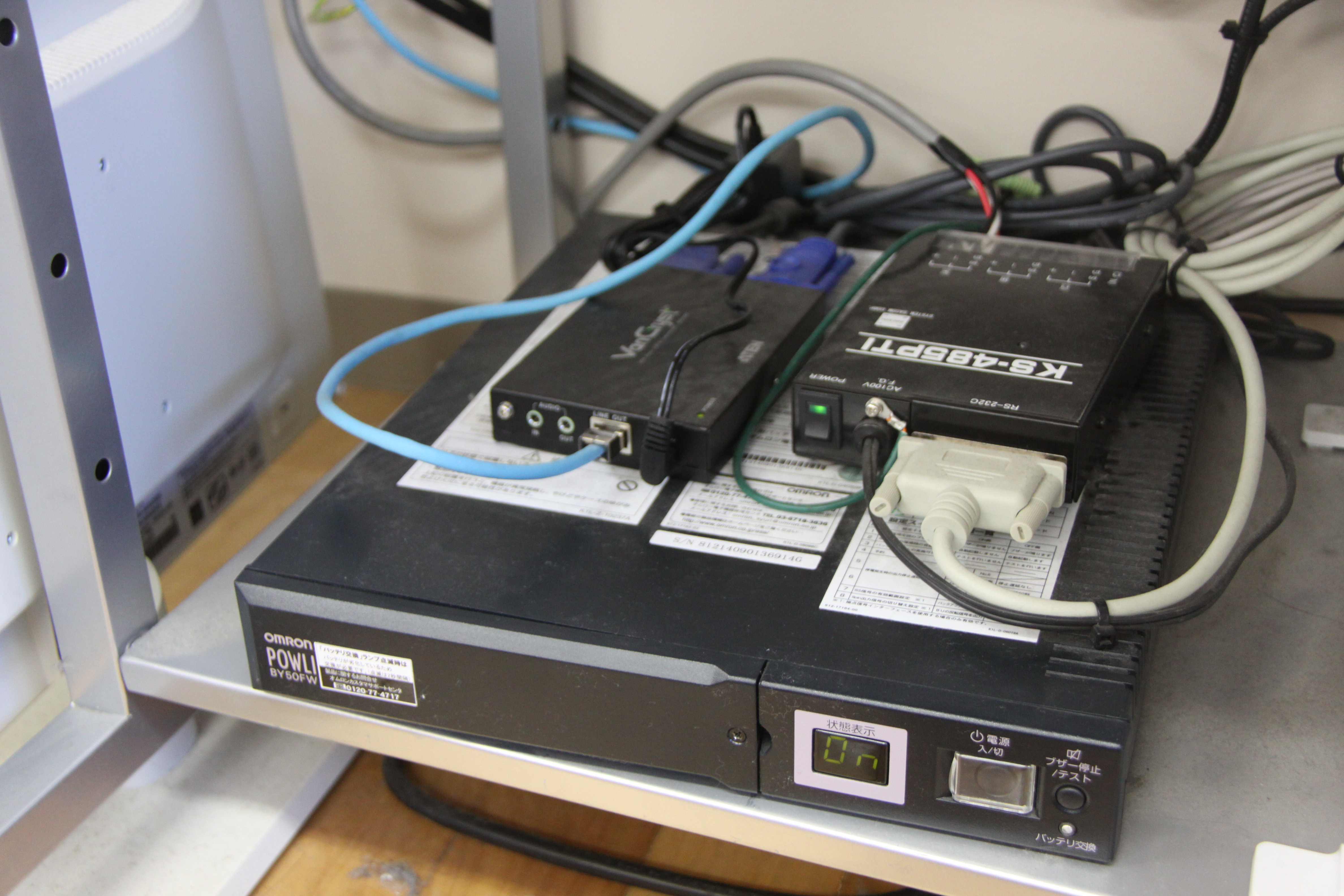
〈君のため用意されたる滑走路君は翼を手にすればいい〉 萩原慎一郎
◎29年目をむかえます。
気になった『まいどなニュース1/15配信』、山脇 未菜美記者の記事を紹介します。
地震で父さんと弟が死んだ―。1995年1月17日、兵庫県で起きた阪神・淡路大震災の直後、中学1年の少年は、学校の作文にこう書き始めた。あれから29年。少年は42歳になり、一人娘は小学6年になった。もうすぐ、自分は父が亡くなった年齢に、娘が当時の自分と同じ年齢になる。「気がかりだったやろうな、生きたかったやろうな」。そして、支えてくれた言葉の温もりを思う。
父の政明さん=当時(44)=と、小学校5年の弟・弘晃さん=同(10)=を亡くした藤本竜也さん。神戸市兵庫区の文化住宅2階に、家族4人で暮らしていた。優しく寡黙な父。一緒に少年野球をしていた弟は、藤本さんの後ろをついて歩いた。いつもは弟と同じ部屋で寝ていたのに…。あの日は、夜更かししていた弟を父が自分の部屋に呼び寄せた。
いつもは一緒に寝ていたのに…
突き上げるような揺れが収まり、布団をのけると屋根はない。隣の部屋にいた3人の姿は見えず、がれきの中から母の声がして助け出した。「うぅ」。弟のうめき声がしたが、いつしか聞こえなくなった。周囲は壊滅状態だった。がれきで埋まった路地を裸足で走り、大人を呼んだ。がれきの下から運び出された弟の体は冷たく、自衛隊に見つけられた父は即死だった。
「あの時、こっちで寝ようって言っていたら」「弟と取り合いになったスラムダンクの連載も、もう読まれへんやん」。一人になると、頭を巡った。大人を呼ぶために走った約5メートルの路地は、弟とボール遊びをした場所。見るとつらくなって、近寄れなくなった。明るく振る舞っていた母は、夜中に声を殺して泣いていた。
気持ちを和らげてくれたのが、友達だった。避難所になった学校の校庭で、家を失った友達とテント生活を送った。弟の友達の両親が営む寺にも居候させてもらった。ひと月ほど後に学校が再開すると、部活の友達と放課後や休みの日もずっと遊んだ。友達との何気ないやり取りが心地よかった。その思いを、作文につづった。
友達などが、「がんばれよ」と言ってくれた。この一言がこんなにうれしくなる事を知った。題名は「一言」とした。「家族を亡くした人に頑張れよと言うのって、難しい。でも、僕は、友達たちが何も聞かずにカラッと『頑張れよ』と言ってくれたことに救われたんです」
藤本さんはこの29年を「運が悪いけど、運がいい」と表現する。
高校卒業後、アルバイト先の整骨院の師匠が家計を心配して、専門学校の費用を出してくれた。結婚して娘が生まれ、幸せに満たされた。32歳、地元が好きで、被災した地域に整骨院を開いた。震災時に遊んだ友達は、飲み仲間になった。8年前、母が亡くなった時、そばに妻がいてくれた。幸せを実感するたびに、我が子の成長を見届けられなかった父と、未来を失った弟の無念が痛いくらいにこみ上げる。「いろんなものを失ったけど、震災後に得たものもありました。出会いがなければ、人生もっと違ったと思う」
今年1月1日、能登半島地震が起きた。映像やニュースに、路地を走ったあの時の記憶が、避難所に身を寄せた記憶が、それからの月日が、まざまざと甦る。
「自衛隊やボランティア、救護・救出してくれる人、家や道路を復旧してくれる人、声を掛けてくれる人、寄付してくれる人…。早いとか、遅いとか、やり方は関係なくて、人の優しい気持ち・行動の全てが生きる力になるはず。僕はなりました。今は先が見えないかもしれないけど、生きていれば、いいことはある。だから、伝えたいんです」
「がんばって」

わたしも、今、「一言」を大事に。
◎進路を切り拓く
~自分らしくせいいっぱい~全校面接練習日:1/15



1,2年生の諸君へ
受験の面接では、「いまの中学校生活」、そして「将来にむけての夢や希望」がとても大切です。よく聞かれる質問をいくつか紹介します
1.志望動機・志望理由は?
志望動機は、高校受験の面接で必ず聞かれる質問です。
高校側も特に知りたい項目になりますので、回答をしっかりと考えておきましょう。
そして、志望動機の回答では、「積極性」を感じさせることがまず重要です。「自分でも合格しそうだから」「家から近いから」といった積極性がないと受け取られる回答は避けましょう。また、志望理由は「具体的」であることも大切です。「楽しそうだから」「有名だから」といった漠然とした回答はあまり好ましくありませんね。
[例えば]
「私は高校でバスケットボールを思い切りやりたいので、バスケットボール部が強い貴校を志望しました」
・ちなみに、志望動機を伝える際はあまり長く説明しようとせずに、簡潔に結論を伝えましょう。例文のように「~ので」という理由を一緒に伝えると説得力と納得感が出るので良いでしょう。
2.高校に入学したらやりたいことは?
「高校に入学したらやりたいこと」も、高校受験の面接では質問されます。面接官は「高校でどの程度頑張れるのか」を見極めようとしていますので、「特にありません」などの消極的な回答はしないようにしましょう。
「高校に入学したらやりたいこと」への回答は、具体的であれば特別なものでなくても大丈夫です。自分が高校でやりたいと思うことを正直に答えましょう。
[例えば]
「私は海外の人や文化に興味があり、将来は国際的な仕事をしたいと思っています。そのために高校では英語の勉強を頑張りたいです」
3.中学校で頑張ったことは?
高校受験の面接では、「中学校で頑張ったこと」が質問されます。面接官がこの質問をする理由としては、ただ単に頑張った内容や結果を知りたいからではなく、その努力の過程であなたが何を学んだのかを知りたいからです。したがって努力の過程における工夫や学びを伝えると印象が良いでしょう。
[例えば]
「英語が話せるようになりたいと思い、毎日1時間英語の勉強に取り組みました。その結果、英検を受験し○級に合格しました。継続的な学習がしっかりと結果につながるということが分かったので、今後の学習のモチベーションも上がっています」
「部活と勉強の両立です。サッカー部の練習が休みの水曜日にまとめて勉強する時間をつくって授業の復習をしていました。忙しい中でも工夫をすることで時間が確保できることを学べました」
4.将来の夢・高校卒業後の進路は?
「将来の夢」も、高校受験の面接では質問されることが多いですね。自分が思っている夢を正直に答えれば問題ありません。また、その夢を実現させるために、いま頑張っていることも伝えるとアピール度が増します。
[例えば]
「将来は海外と関わりのある国際的な仕事がしたいです。そのために英語の勉強を頑張っています」
「将来は教育に携わる仕事に就きたいと考えています。目標に向かって好きなバスケットボールだけでなく教育関係の進路に必要な勉強にも力を入れています」
5.自分の長所・自己PRは?
「自分の長所」を問う質問は、高校受験の面接では大切な質問のひとつです。自分が長所と思うことについて、照れずに正直に答えましょう。長所の根拠となるエピソードを加えて話せると、面接官に対しての印象は良くなるでしょう。
[例えば]
「私の長所は素直なところです。部活でずっとレギュラーとして活躍できていたのも、監督やコーチのアドバイスや指導を素直に受け入れることができていたからだと思います」
「私の長所は、粘り強く頑張れるところです。そのおかげで、中学での部活も3年間休まずに続けることができました」
6.自分の短所は?
「自分の短所」も高校受験の面接では聞かれることが多いです。短所を答える際に注意が必要なのは、あまり否定的な答え方をしないことです。短所を改善するためにどのような努力をしているかを話し、前向きな回答になるように工夫しましょう。
[例えば]
「私の短所は、人が言うことに左右されやすいことです。しかし、それではいけないと思い、自分は何がやりたいのかをしっかりと考えるようにしています」
「私の短所は、熱中してしまうと人の言うことが耳に入りづらくなることです。そのため、アドバイスをしてもらったら、それが自分の考えと違っても最後まで聞いて考えるようにしています」
7.最近のニュースについて
「最近のニュースで気になったものは何か」「なぜそのニュースが気になったのか」という質問も、高校受験の面接ではよく聞かれます。ニュースについては、知識がないと答えることができません。普段から報道番組や新聞などを見て、自分の意見を持つ習慣をつけましょう。自分の関心のあること(将来の職業や趣味・特技に関連すること)が答えやすいでしょう。
[例えば]
「地球温暖化の問題について関心を持っています。日頃からゴミの分別や冷暖房の設定温度など自身でも貢献できる範囲では取り組んでいるのですが、私とあまり年も変わらない環境活動家の方が、各国の政治家に対し環境問題への意見を述べている姿を見て、すごいと感じました」
8.得意科目・苦手科目は?
「得意科目・苦手科目」も高校受験の面接で聞かれることがよくあります。答え方としては、科目をまず先に答え、次にその科目が得意な理由・苦手な理由を言えると良いです。苦手科目はどのように克服しようとしているのかを答えられるとさらに良くなります。
[例えば]
「得意科目は数学で、苦手科目は英語です。特に文法を覚えるのが苦手でしたが、参考書を使って毎日通学時間に覚えるようにしました。その結果、以前に比べて英語に対して苦手意識がなくなりました。」
Whatever you do‚ follow your conscience and work with one conviction. Jackie Chan
(何をするにしても自分の良心に従い、ひとつの信念を持って取り組むこと。)
◎第10回備前市文学賞表彰式(1/13)
備前市文学賞の開催趣旨は、「市民の文芸創作活動を奨励し、豊かな市民文化の振興を図ることを趣旨に実施します」とあります。今年度、本校生徒もたくさん入賞しました。おめでとうございます。
○短歌部門:小寺さん、森田さん
○俳句部門:山本さん、家嶋さん、竹原さん、田上さん、杉原さん、鎌田さん、村上さん、竹原駿さん、隅谷さん


〈単独者とはいかなる毒か幅深く被たる者はふりむかぬなり 渡辺松男〉
◎ひな中の風✨ 黙々と。(1/12:清掃時間)



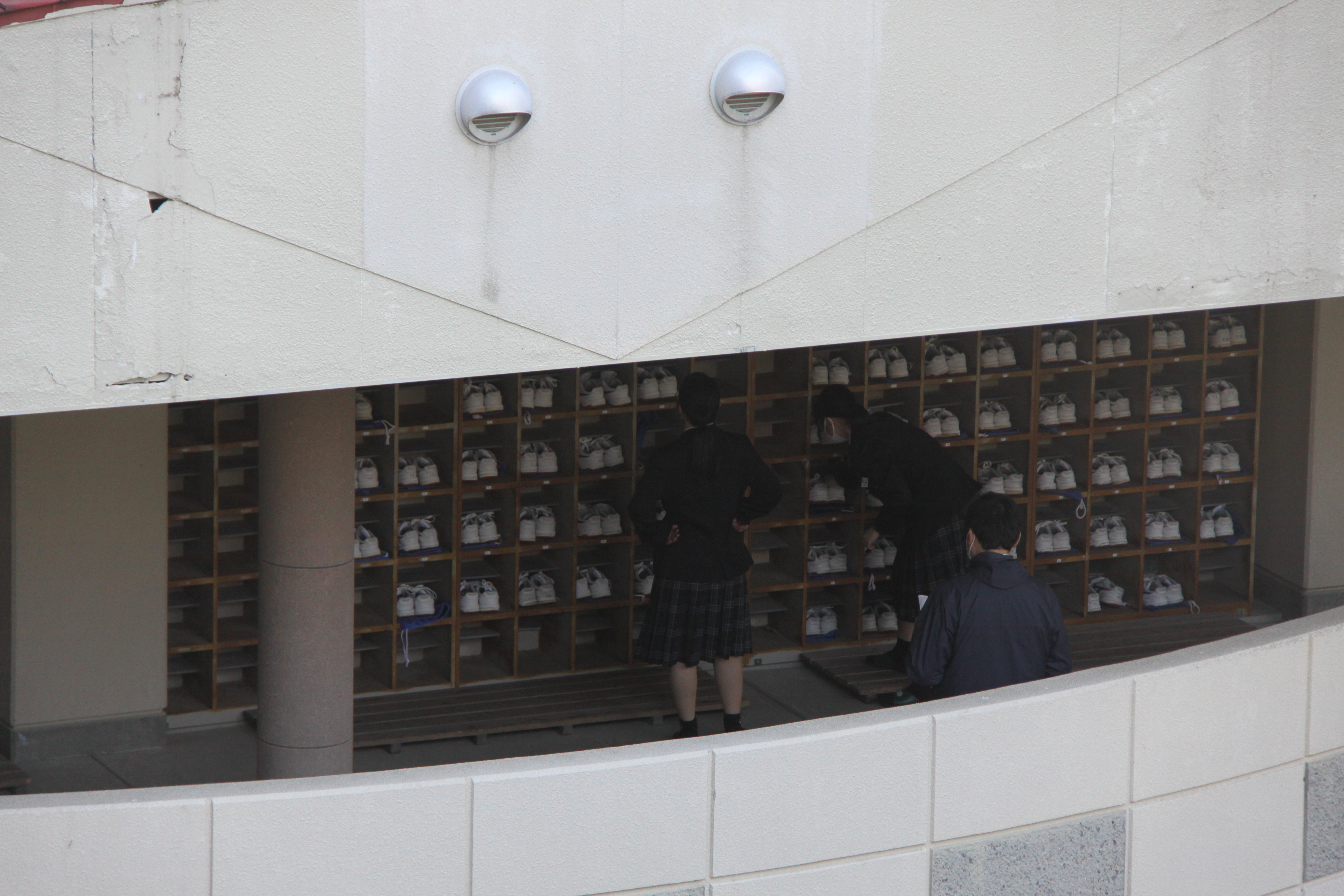





◎私の取り組んできたこと・伝えたいこと・知ってほしいことを。
~私らしくせいいっぱい 月曜日は、校内面接練習~

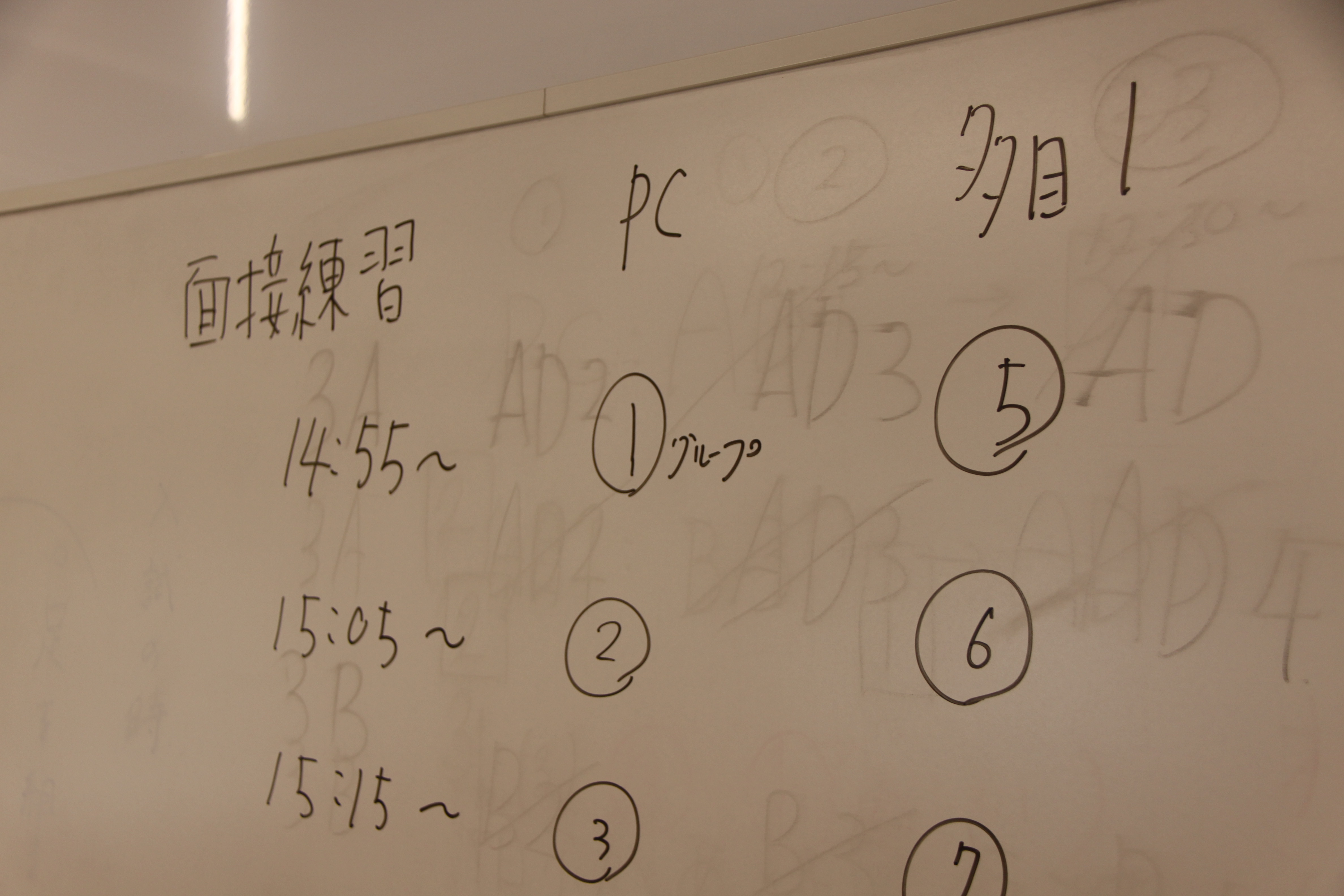
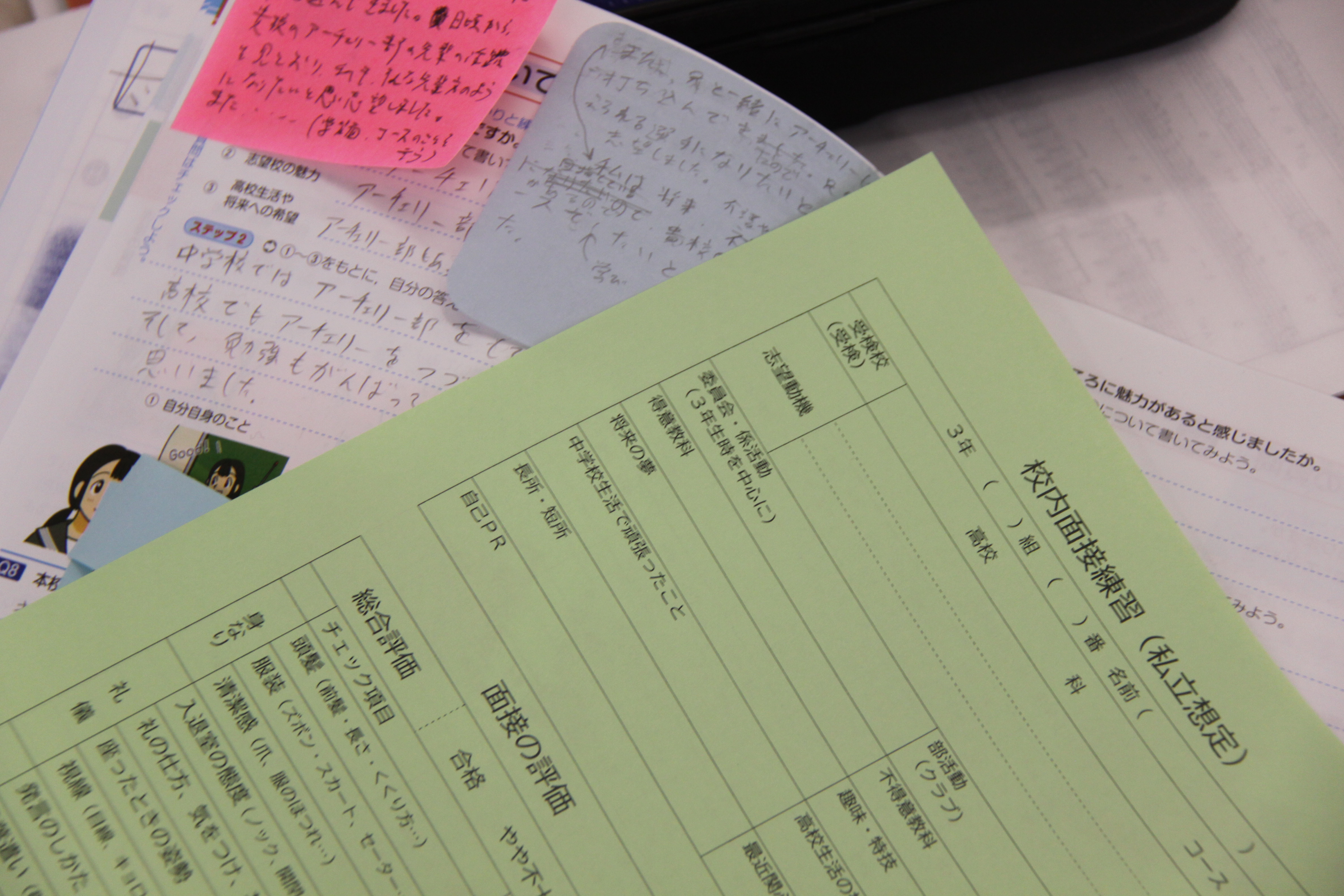
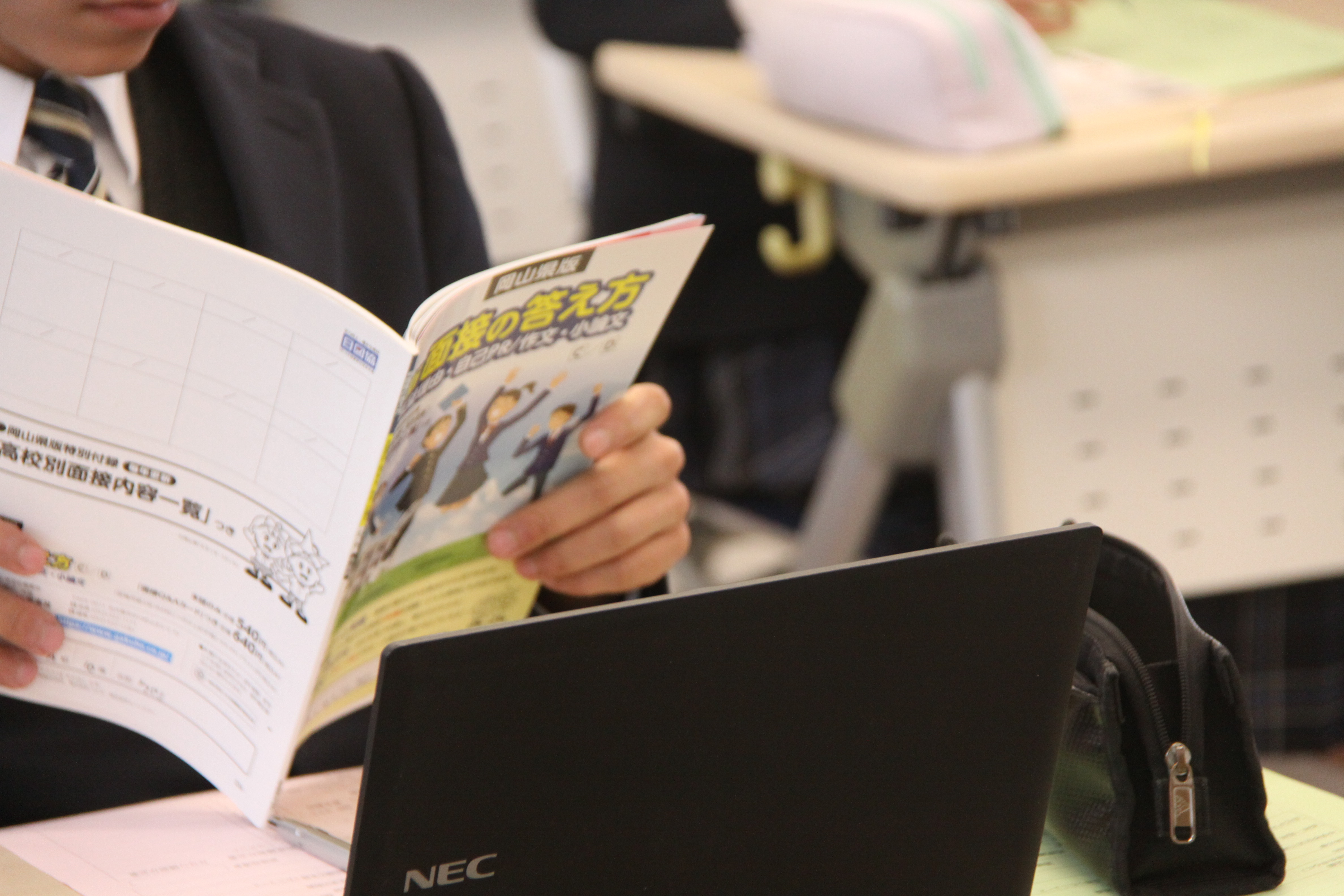


明日から大学入学共通テストも。!(^^)!
◎栄光に向かって走るあの列車に乗っていこう。(1/12)
本日、私立一期入試出願



○入試日程について
(1) 選抜1期
ア.出願期間:令和6年1月12日(金)~1月16日(火)
イ.入 試 日:令和6年1月25日(木)、1月26日(金)
ウ.合格発表:令和6年2月 2日(金)〔岡山白陵 1/27(土)・金光学園 1/29(月)〕
(2) 選抜2期
ア.出願期間:令和6年2月 9日(金)~2月14日(水)
イ.入 試 日:令和6年2月20日(火)
ウ.合格発表:令和6年2月22日(木)

◎学校生活を大切にしていくために(1/12)
(^_^)生活指導委員会を毎週おこなっています。
学校教育のなかで,教材を介して子どもの認識や技能を指導する学習指導にたいして,一人一人の子どもの生きかたをその子どもの生活現実に即して指導することをひろく生活指導とよびます。しかし,生活指導は,徳目主義的指導や管理主義的指導のように,特定の徳目体系や管理体制を子どもに強要して,特定の生きかたをうえつけるものではありません。また、それは,適応主義的指導のように,子どもの意識や行動を操作して,所与の集団体制に子どもを順応させようとするものでもありません。生活指導とは,子どもが自分の生活現実を知り,自分の生きかたをより価値あるものに高めていくことができるように指導する教育活動です。そこでは,子どもの生活現実を発展的に変革していくことと,子どもの人格,個性を発達させていくこととを統一してとらえています。
この日も、生徒一人ひとりの学校生活が充実するよう、学年担当の先生方を中心にていねいに協議を進めました。

◎正しく知り 正しく行動するために
〈3年生からの発信・1/12~2/22〉

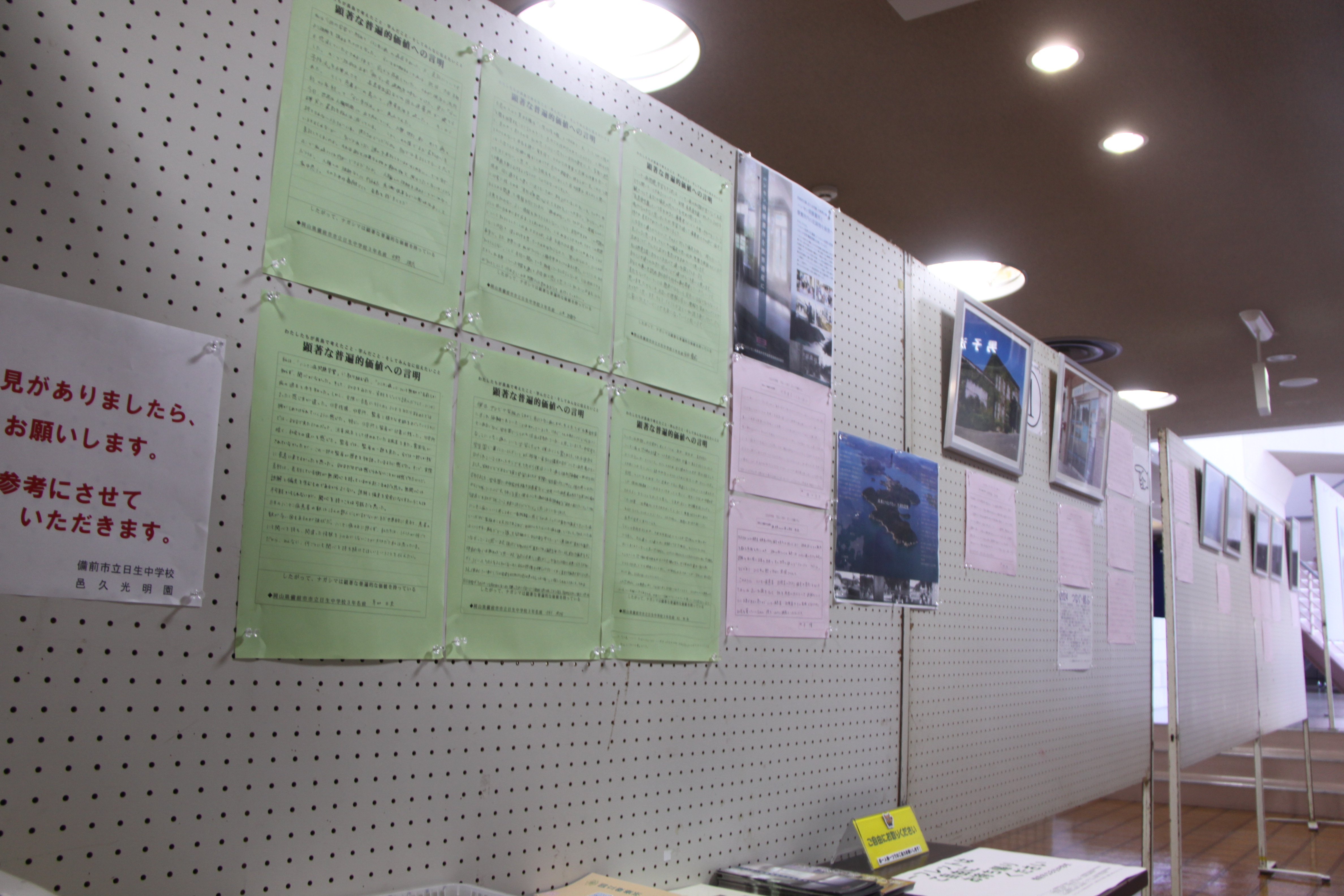
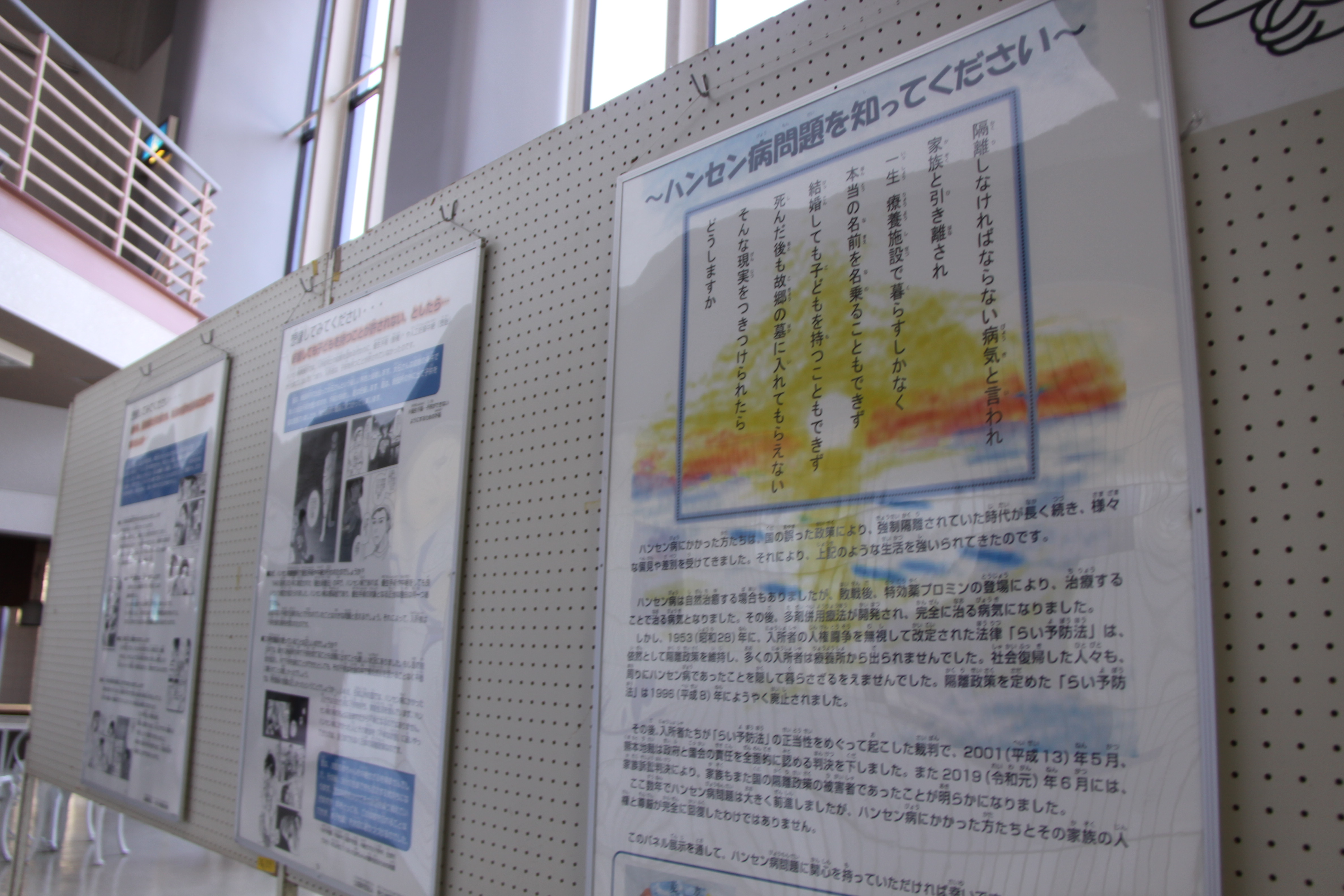

今年度、日生中学校3年生は、人権週間を中心に、〈ハンセン病学習学習〉に取り組みました。
回復者のひとりである金泰九(キムテグ)さんの生き方を知り、そして現地研修で長島を訪ねました。帰校後は、NPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会事務局長の釜井大資さんをお招きし、学びを深めてきました。
そしてこの度、学習したことをもとに、〈ハンセン病問題学習パネル展示〉の準備を進めてきました。取組はまだ浅いですが、次世代の私たちが引き継ぎ、
ハンセン病問題を通して、いま・これからの社会のあり方について、引き続き、しっかり《学び》《考え》《行動して》いきたいと思っています。
■備前市立日生中学校3年生
〈ハンセン病問題を未来へ伝える・つなぐ・結ぶために〉
■日時:2024年1月12日(金)~2月22日(木)
■会場:備前市立日生地域公民館(日生町日生630)
日生中学校の生徒が学んだ「正しい知識」「深めた学び」をパネル展示しています。多くの市民のみなさんにも知っていただき、差別のない社会づくりについて一緒に考えていきましょう。
■資料提供
リーフレット:「ハンセン病療養所を世界遺産に」(NPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会)
:「長島愛生園 歴史館」 「長島愛生園 歴史回廊」((長島愛生園歴史館)
:「邑久光明園資料」(邑久光明園)
写真パネル :岡山県人権教育研究協議会(*写真撮影は2003年教材開発部会による)
:公益財団法人邑久光明園友愛会(『麦ばあの島』の物語によるパネル)
:ハンセン病問題を未来へ伝える・つなぐ・結ぶ岡山・次世代ネット
説明文は会期中に入れ替える予定です。
〈療園の昔と今と将来を君に説きつつ声高くなる 谷川秋夫 歌集『祈る』より〉
◎私たちも学ぶびましょう。講演会のご案内〈来たる2/1〉
メディアが心と体に与える影響ディアが心と体に与える影響
「子どもの姿勢・体力を見てみよう!」 (*1/11保護者案内配布)
[ 日 時 ] 令和6年2月1日(木) 14:35~15:35
[ 会 場 ] 日生西小学校 フューチャールーム
[ 参加者 ] 日生中学校区(こども園・小・中)保護者、教職員、日生西小児童(6年生)
[ 内 容 ] 「子どもの姿勢・体力を見てみよう!」
○講師:備前市 地域包括支援センター 作業療法士 岸本 直子 先生 ★岸本先生の紹介・・・日頃は備前市地域包括支援センターの作業療法士としてご勤務されています。「生き粋びぜん体操」の先生としてもご活躍で、高齢の方を対象に運動機能の低下防止に向けて、いろいろな取り組みを行っておられます。
○お問い合わせ:日生中学校区連携協議会0869-72-0050 (担当:日生西小 岩本)


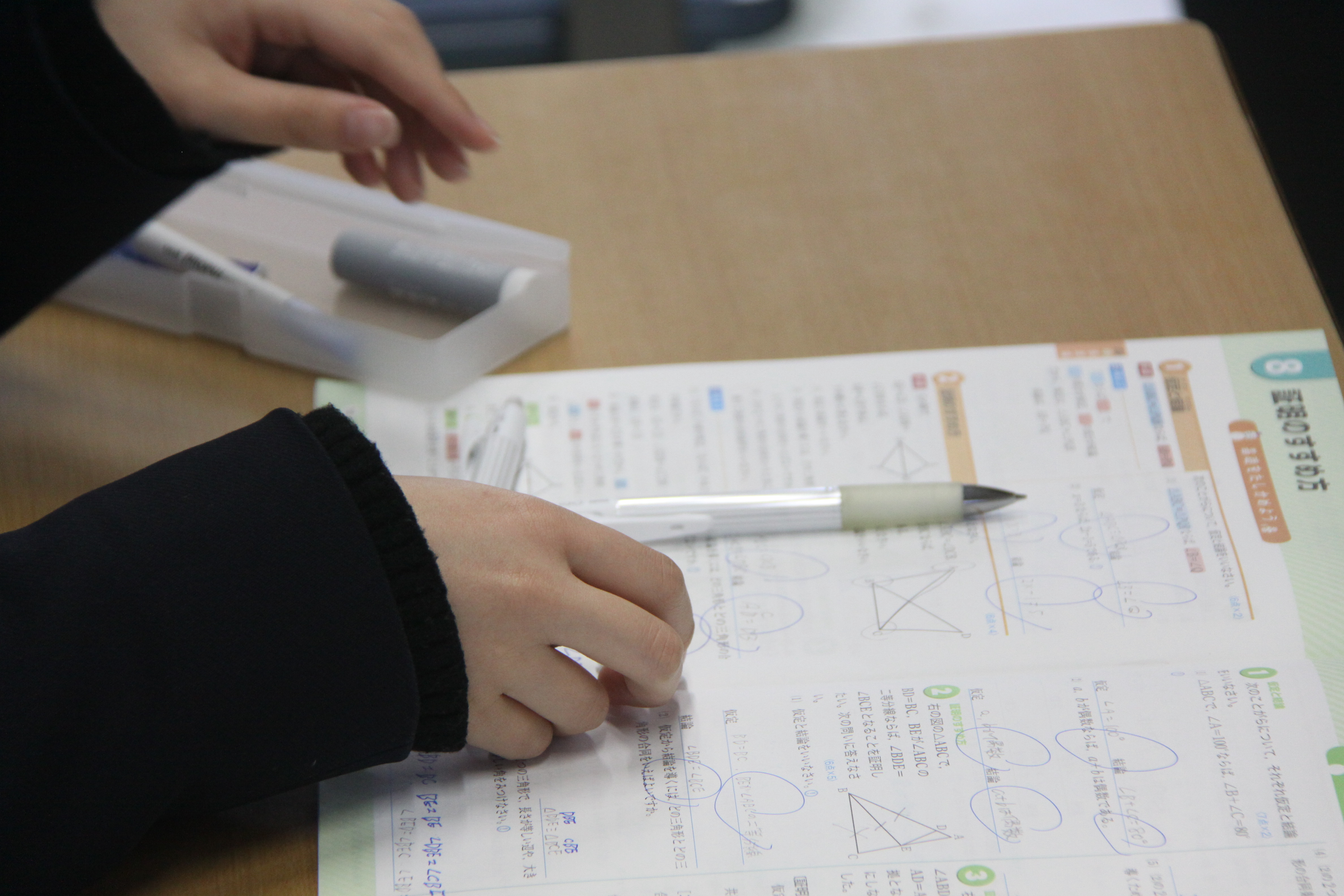
◎愛と感謝に生きよう♬
~今年も多くの人に支えられて~(1/11)
学校フェンス修繕のために事前の樹木伐採を、教育委員会総務課さんが来校し、寒い中で作業してくださいました。学習環境の整備をいつもありがとうございす。また、今月末はテニスコートの老朽化したポールの撤去工事を行います。
今日は、岡山県警根木スクールサポーターさんも来校されました。
今年も「感謝」の気持ちを大切にしたいですね。






◎あったかいんだから~今日も。(1/11)

◎Have a nice day ~頑張れ私 頑張れ今日も~♬(1/10)

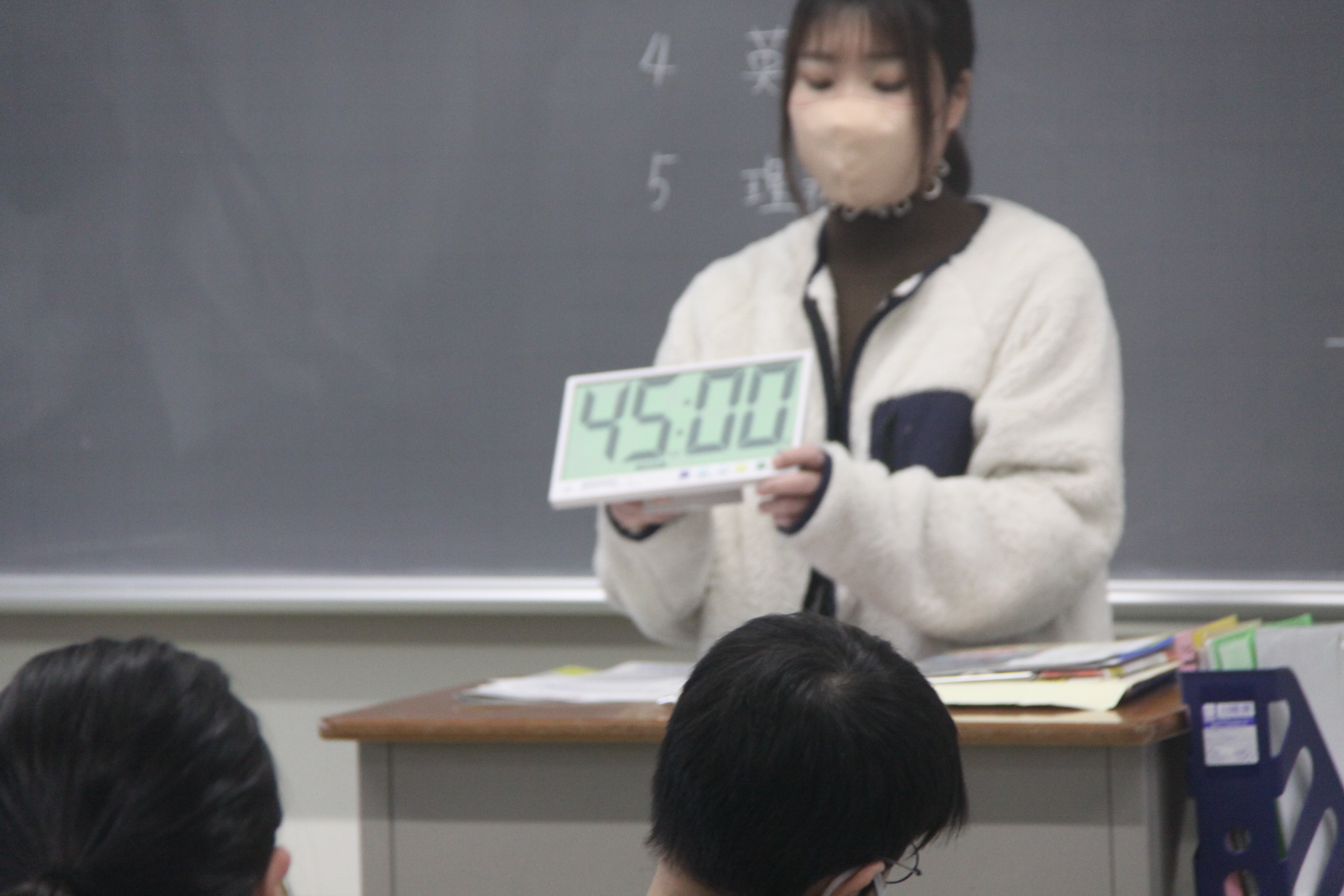

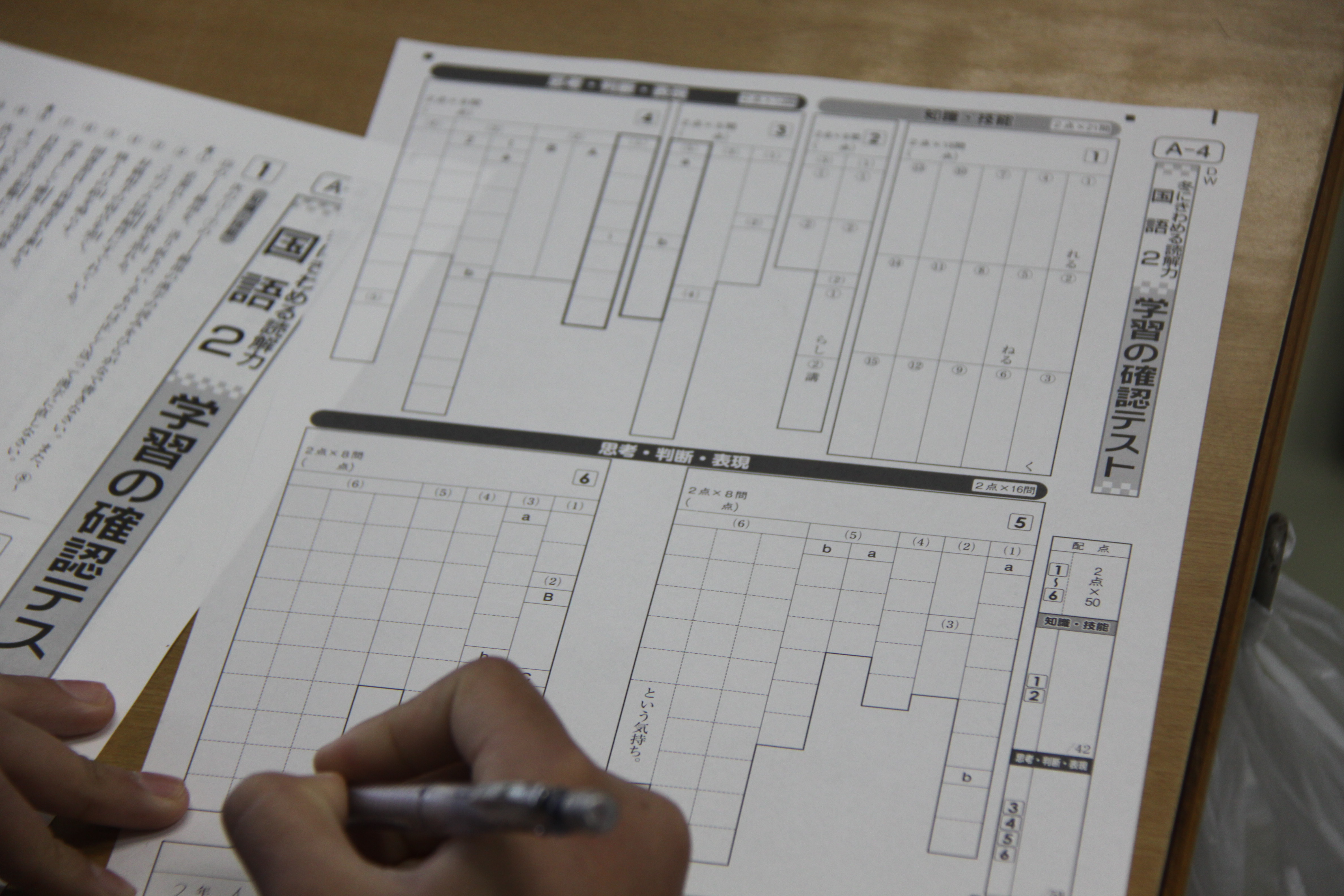

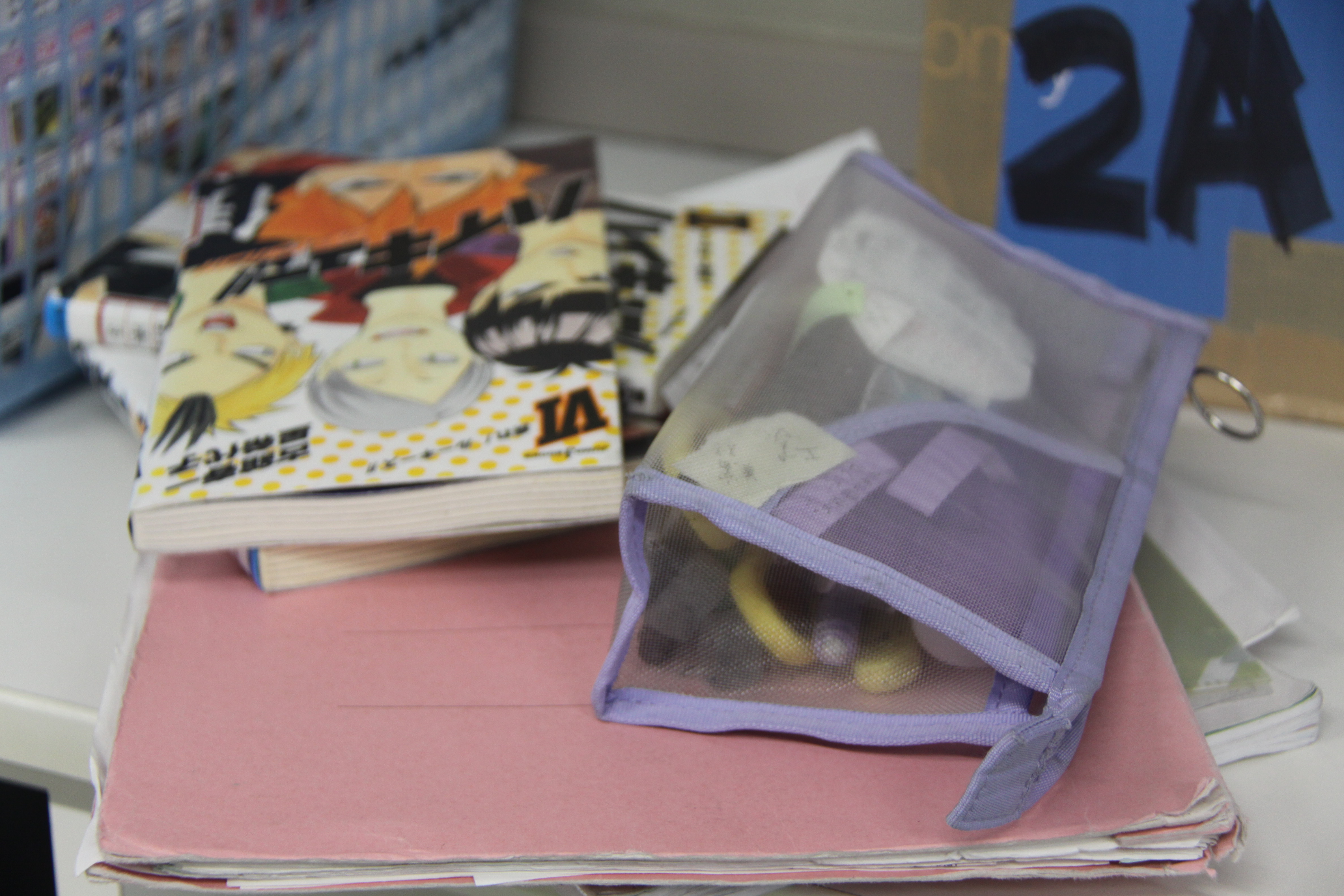
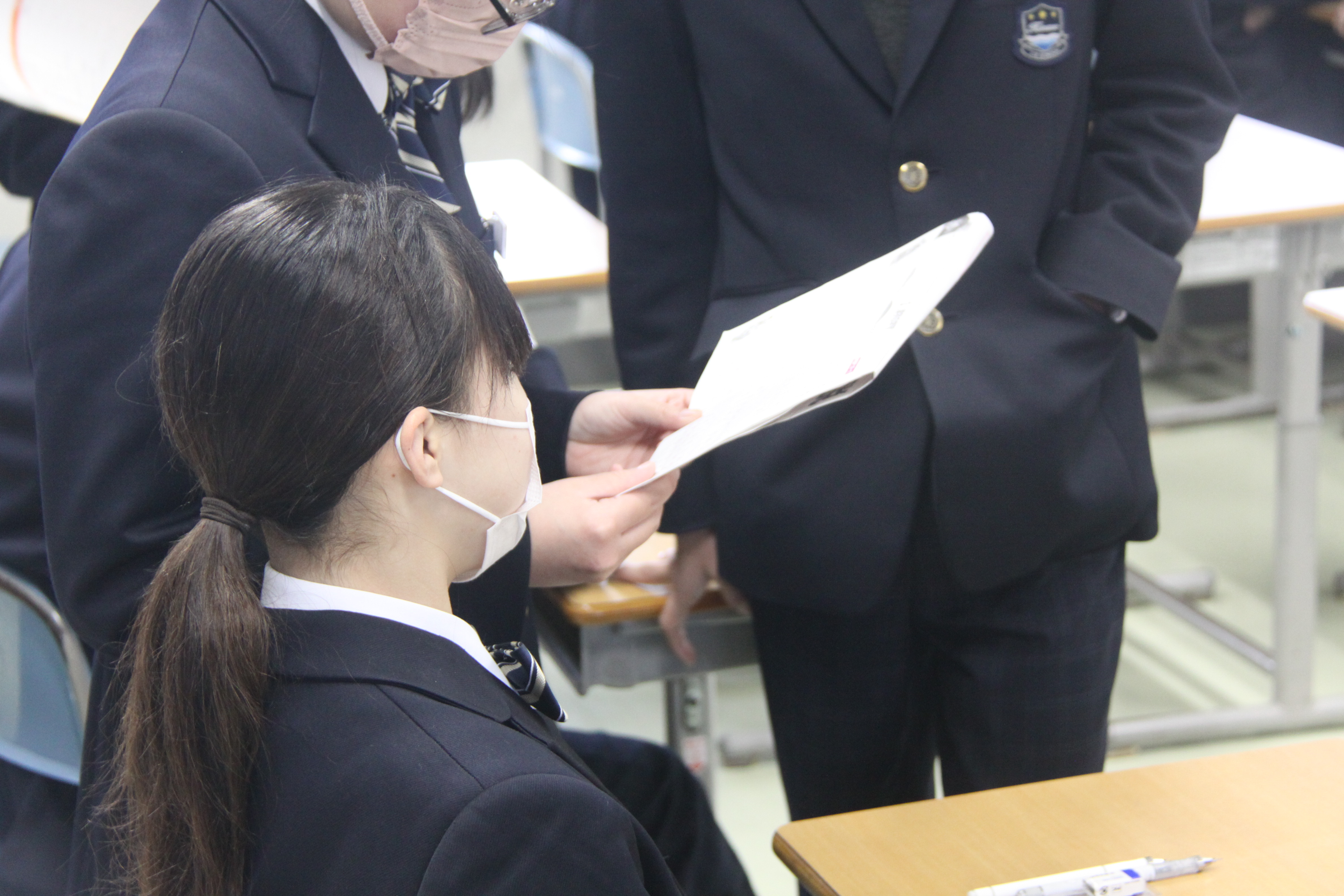


3年生到達度確認テスト 1.2年生課題テストを乗り越える。
◎3学期 わたしたちのはじめ(1/9:うったて)



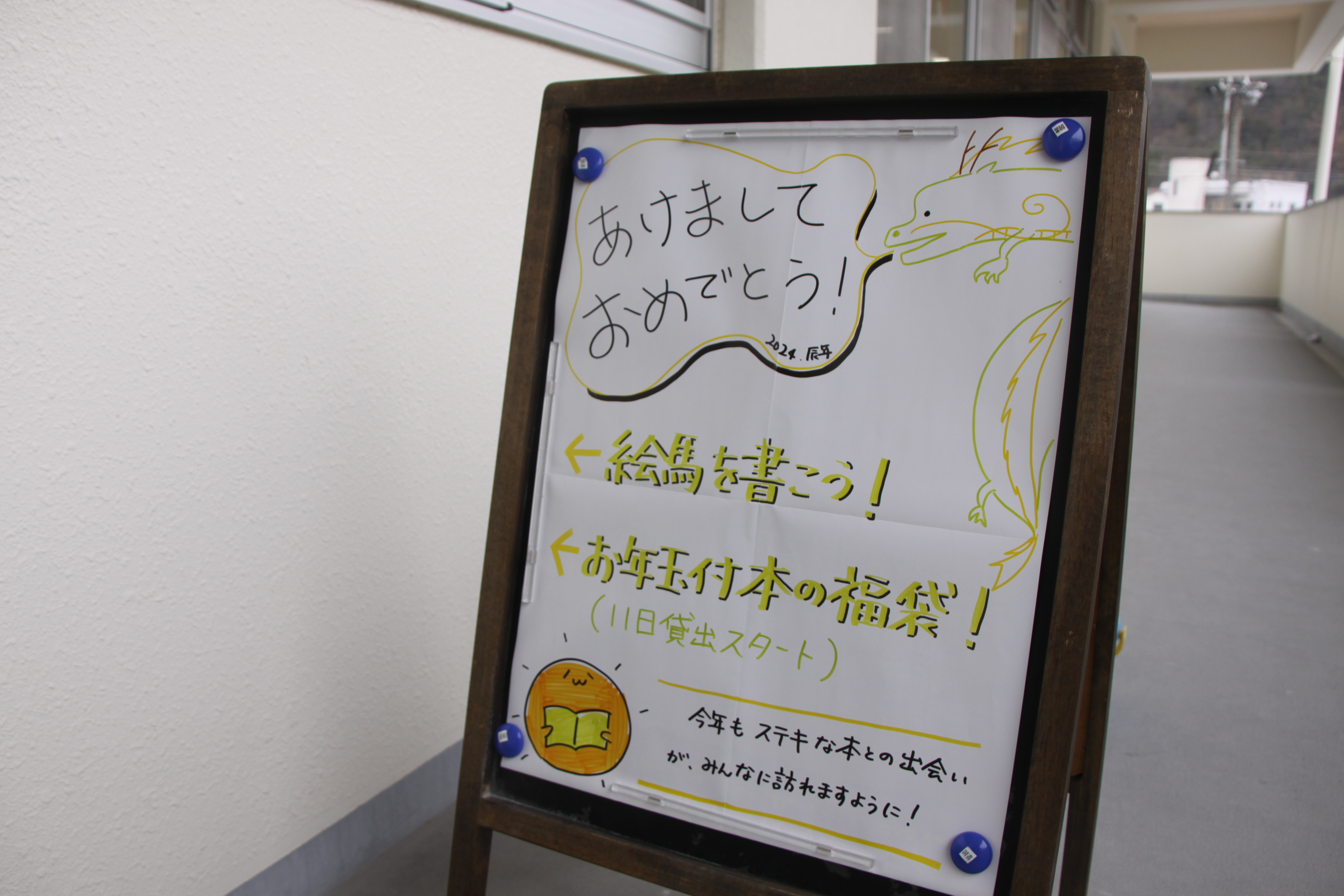
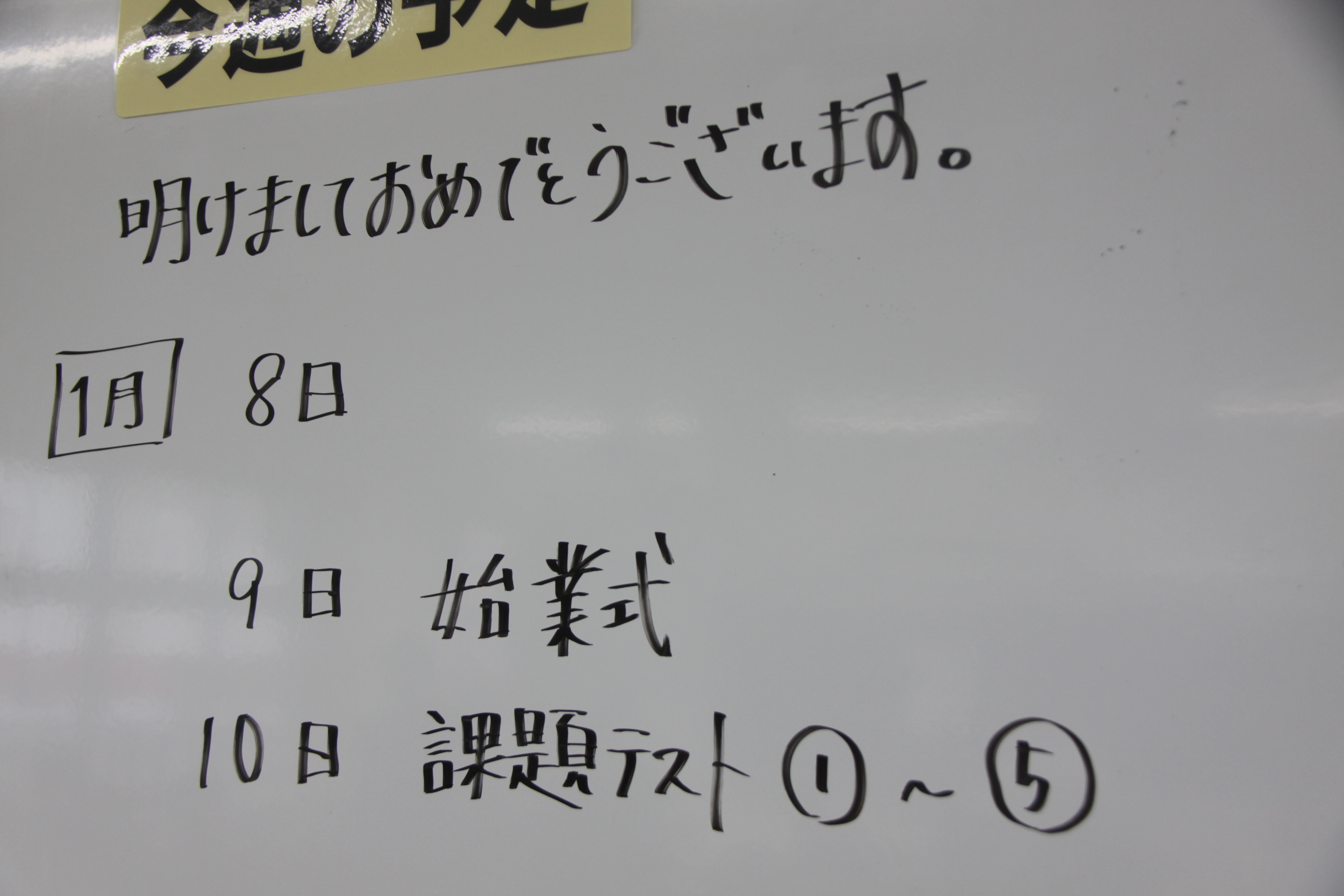




◎日生港町 どうしてこんなに 夜明けが早いのさ ♪


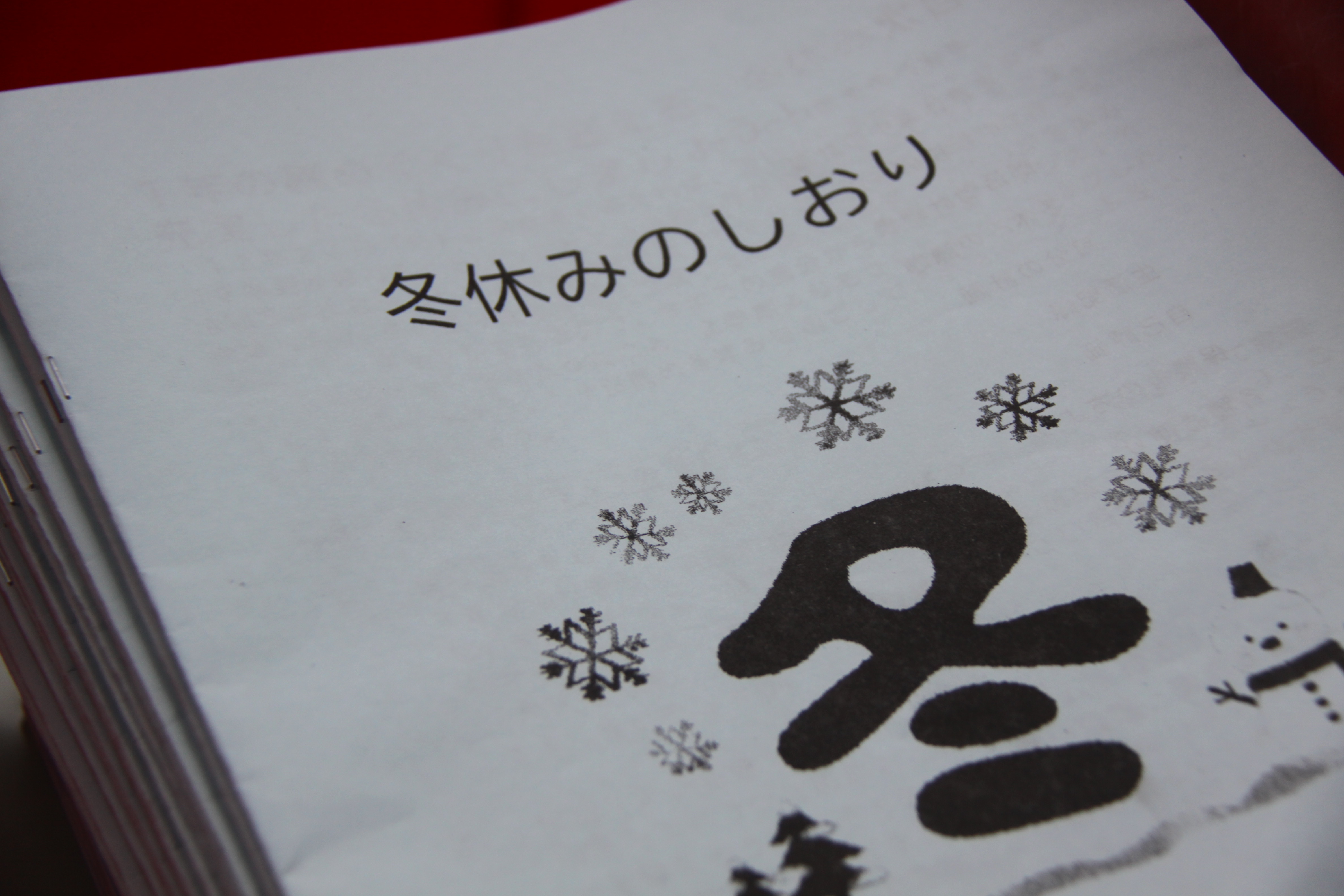




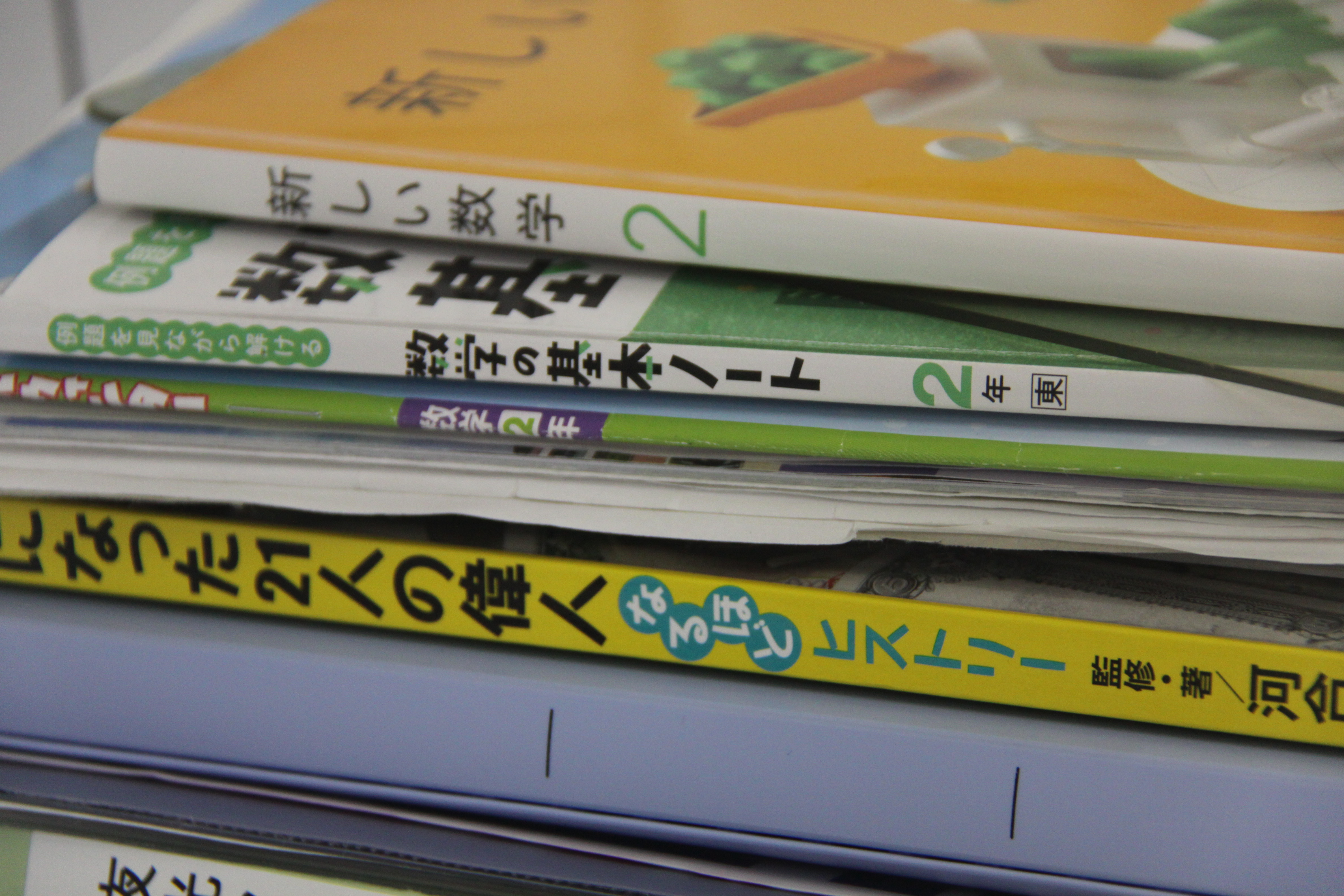

◎5年後のわたし ~1/8・成人の日~

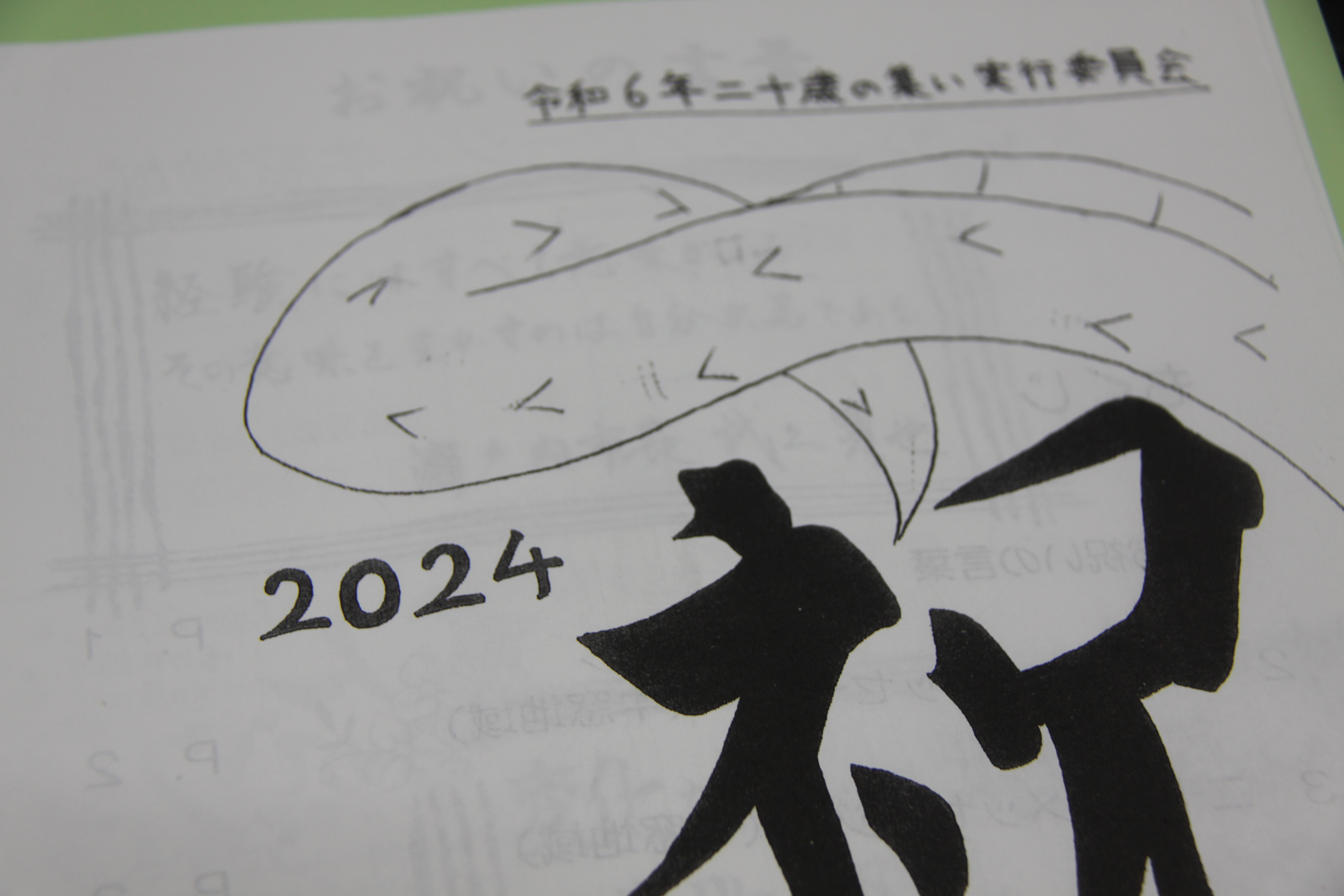
成人を祝う風習は古来から存在していました。男子の場合は、奈良時代以降より続く成人の儀式「元服(げんぷく)」。髪を結い、冠または烏帽子(えぼし)をつけ、服装も大人のものへと改めました。女子の場合は公家の女子が行った「裳着(もぎ)」。“裳”という腰から下にまとう衣服を身に付ける儀式、髪を結い上げる髪上げも行われ、大人の髪型へ変わります。そして、歯を黒く染める鉄漿付け(かねつけ)も成人の儀礼として行っていました。
一方、貴族のみに限らず、村人などの庶民が行う成人の儀式が各地で行われていました。「1日に60キロの柴を刈って12キロ売り歩けたら」「一人で鹿などの狩りができるようになったら」などの通過儀礼が存在していました。現在のように、「18歳になれば成人」といった年齢基準ではありませんでした。
成人式が初めて行われたのは埼玉県蕨市で、太平洋戦争が終わった後の昭和21年に、今後の時代を担っていく若者を励ます目的で「青年祭」が開催されました。その後、新成人が一堂に集う成人式が全国に広まり、1948年の国民の祝日に関する法律により「成人の日」は正式な祝日と定められました。
現在、成人の日は1月の第2月曜と制定されていますね。2000年に制定されたハッピーマンデー制度は、祝日と週休2日制をつなげ、3連休以上の期間を増やすため、国民の祝日の一部を従来の日付から特定の月曜日に移動させる制度。連休の日数を増やすことで観光業や運輸業などを活性化する目的で設けられ、成人の日も1月の第2月曜となりました。全国で地域ごとに差はあるものの、毎年1月の上旬から中旬にかけて成人式が行われています。
この日は、各自治体で行われる「二十歳の集い」の実行委員会に招かれた先生方もたくさんおられました。その中の先生が、いただいた記念冊子に掲載されていた「お祝いメッセージ」をひとつ紹介します。
あなたの知らないところに いろんな人生がある
あなたの人生がかけがえのないように
なかまの人生も またかけがえのないものだ。
人を愛するということは 知らない人生を知るということだ。
年にふさわしく 風にふさわしく
病気の時は病気のままに
元気な時は元気なままに 歩きつづけよう。
そしていつものあいさつですが
走る人にも歩く人にもまた、歩けない人にも
いつもいい風が吹きますように。
◎ひな中の風✨(1/5)


わたしはただ、人間に関わるあらゆることの上に友情を置くべきだと、君らに勧めることしかできない。これほど自然に適うもの、順境にも逆境にもこれほど役に立つものはないのだからな。
友情は順境をいっそう輝かせ、逆境を分かち担い合うことで軽減してくれる。(キケロ)
◎2024 〈初鴉「生きるに遠慮が要るものか」〉花田春兆句集『喜憂刻々』



◎花は咲く(12/27・自分らしく精一杯)
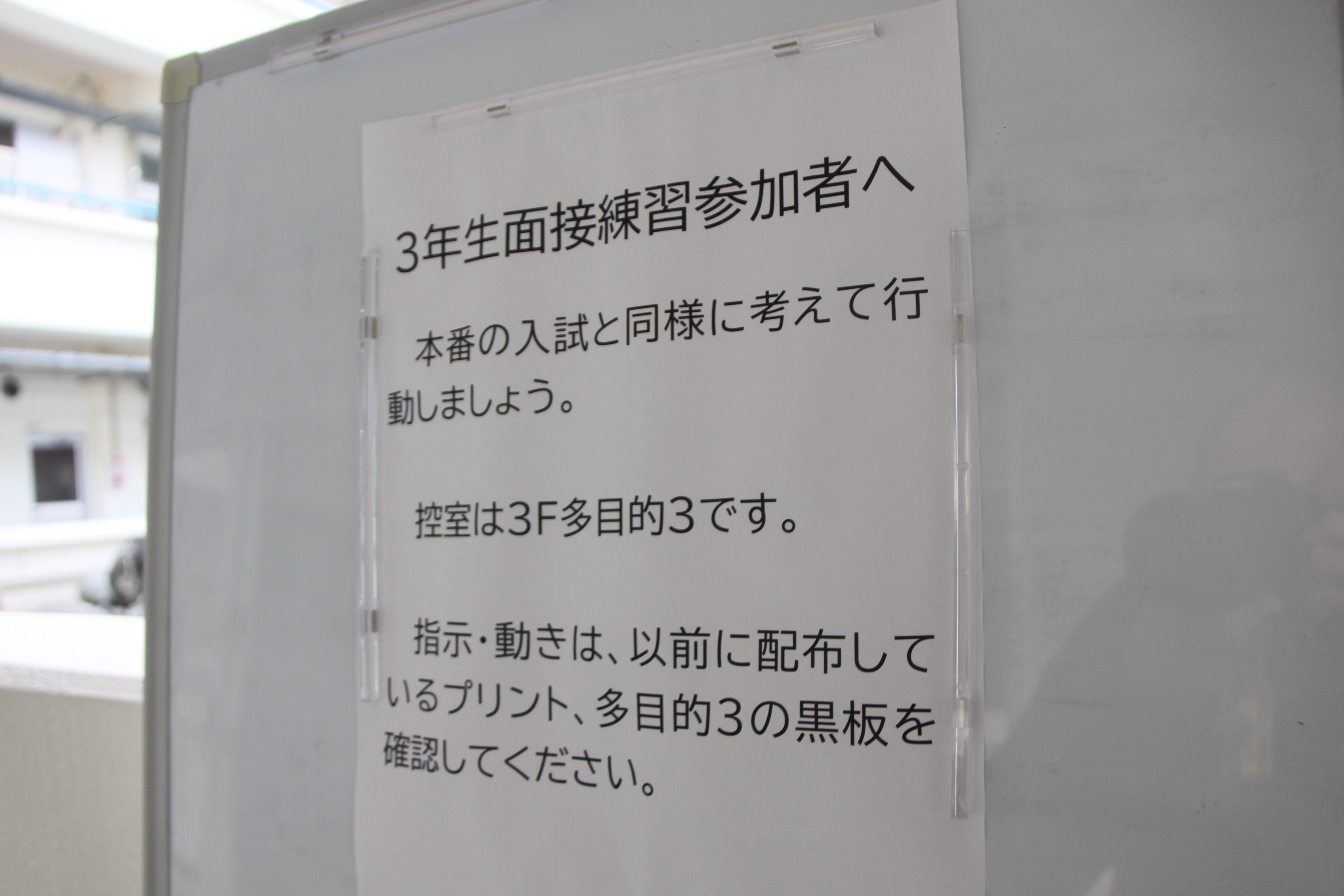





3学期、1月15日は、校内面接練習を行います。(1,2年生は13:55に下校となります。)
」
◎ひな中の風+私たちのはじまりの風景6(12/27)



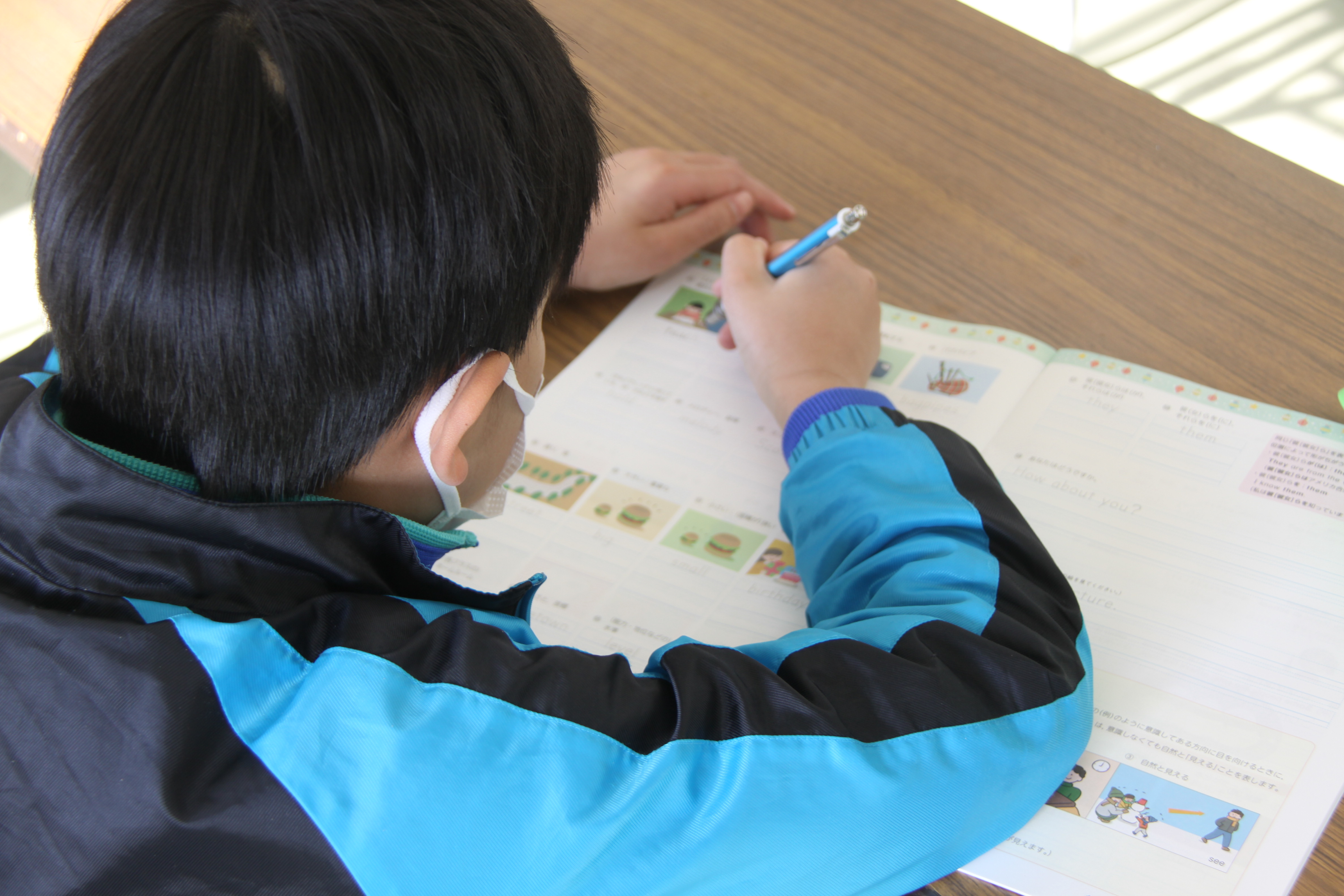



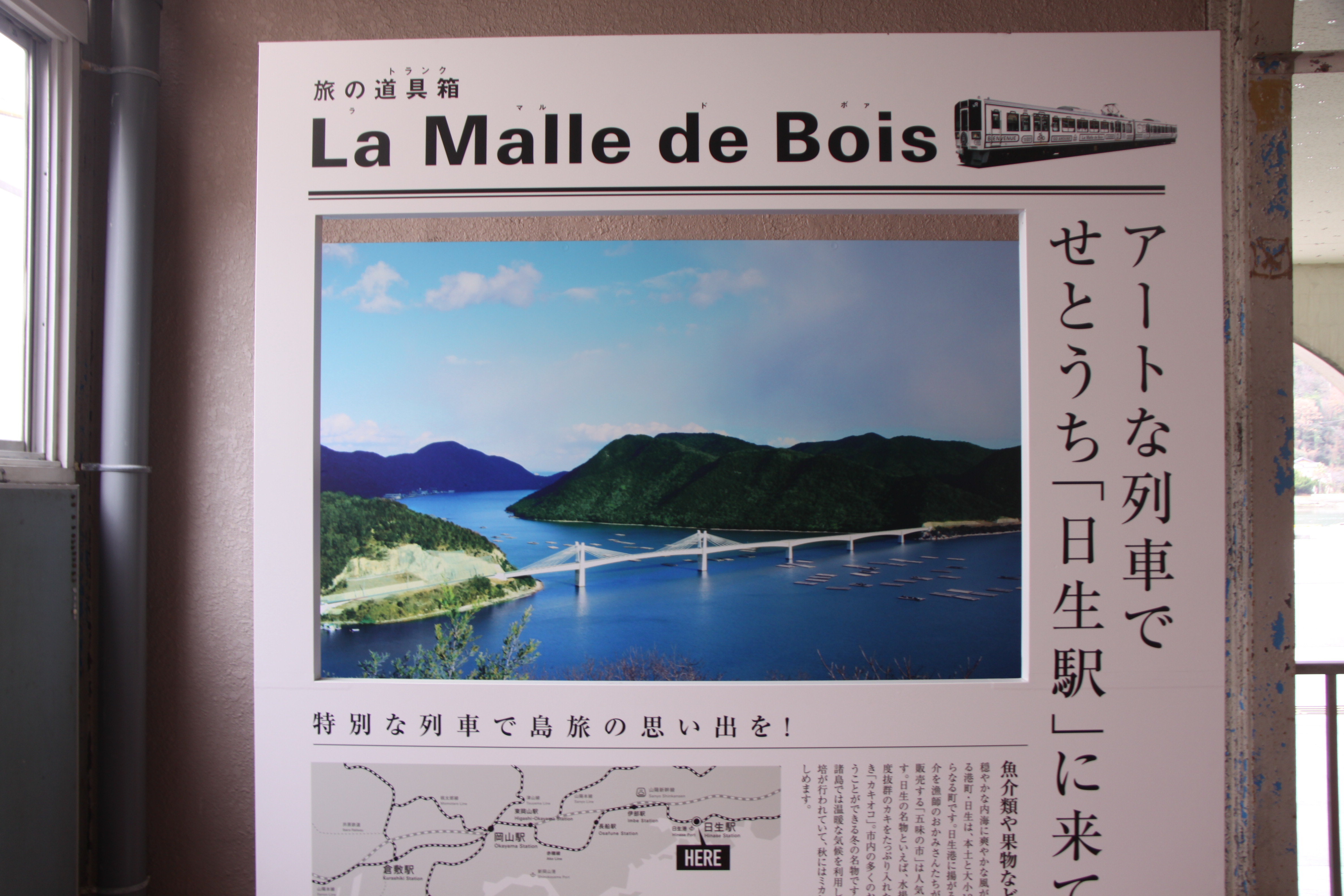

吹奏楽部のみんなと!Jamboree Mickey!(∈^0^∋)↗
◎多くの人に支えられて(12/27)
この日、岡山県学校生活協同組合(学生協)から三宅さんが来校され、サッカーボールを寄贈してくださいました。本校での贈呈式には、サッカー部の有吉君が代表として受け取りました。ありがとうございました。
学生協さんは、「学校生協グループ共済」引受会社である明治安田生命とともに、子どもの健全育成に資する地域・社会貢献活動として、学校教育関係機関にサッカーボールを寄贈されており、本年度、日生中学校へ3球くださりました。部活動や体育の授業で大切に活用させていただきます。当面は職員室前ロッカーに展示しております。


◎冬季休業に入りました。(12/23~2024.1.8)

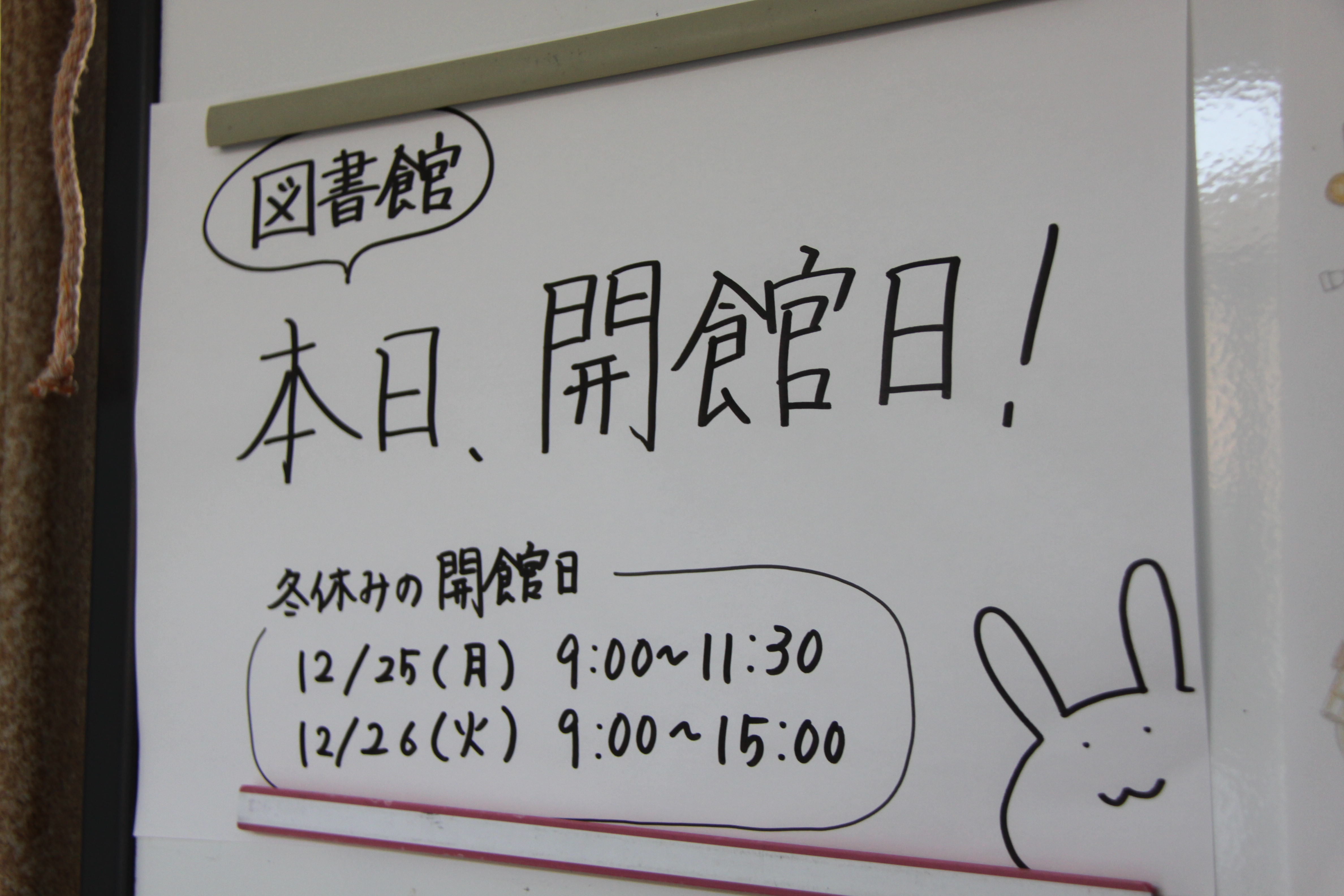

○12/28~1/3は学校閉庁日となります。
閉庁期間の緊急連絡先は、
備前市役所(0869)64ー3301、備前市教育庁小中一貫教育課(0869)64ー1858
◎年末・年始も信頼される教職員であるために。
現在、岡山県教育委員会では、庁内に不祥事防止対策チームを立ち上げ、心理学や犯罪抑止等の専門家をアドバイザーに迎えて、新たな研修プログラムやe-ラーニング、啓発資料等の作成を進めています。本校もそのような資料を継続的に活用し、不祥事防止やコンプライアンス意識の高揚に向けて校内研修に取り組んでいます。この日は、終業式を終え、午後から飲酒運転に関する長時間研修をおこないました。(コンプライアンス推進委員より)
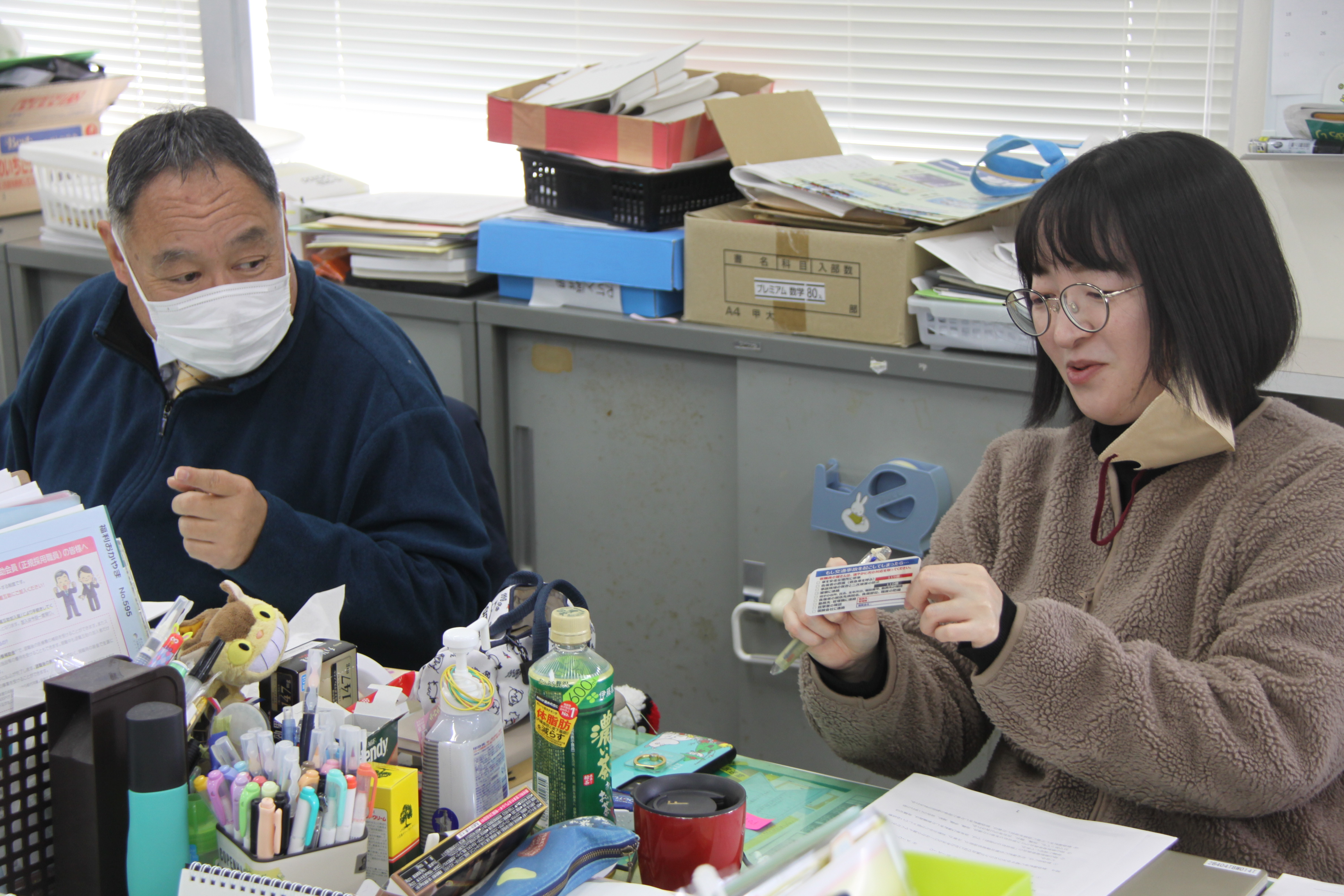
◎日生で輝く 日生が輝く✨(12/22)
7月に続き、生徒会が主催し、備前市社会福祉協議会日生支所さんと協力して、川東地区福祉協議会の方々と協働で、学校周辺、通学路、駅周辺の清掃活動に取り組みました。









集合時には、市社会福祉協議会日生支所の嶋村さんより、赤い羽根街頭募金(10/30、11/16)の報告書をいただきました。2日間の募金額は27‚914円となりました。たくさんの募金をありがとうございました。お声をかけてくださった皆様ありがとうございました。(_ _)

「荒井君、評価されようと思うなよ。人は自分の想像力の範囲内に収まるものしか評価しない。だから、誰かから評価されるというのは、その人の想像力の範囲内に収まることなんだよ。人の想像力を超えていきなさい」 (荒井祐樹『まとまらない言葉を生きる』より)
◎2学期のおわりに、冬休みの前に、2024年へ。
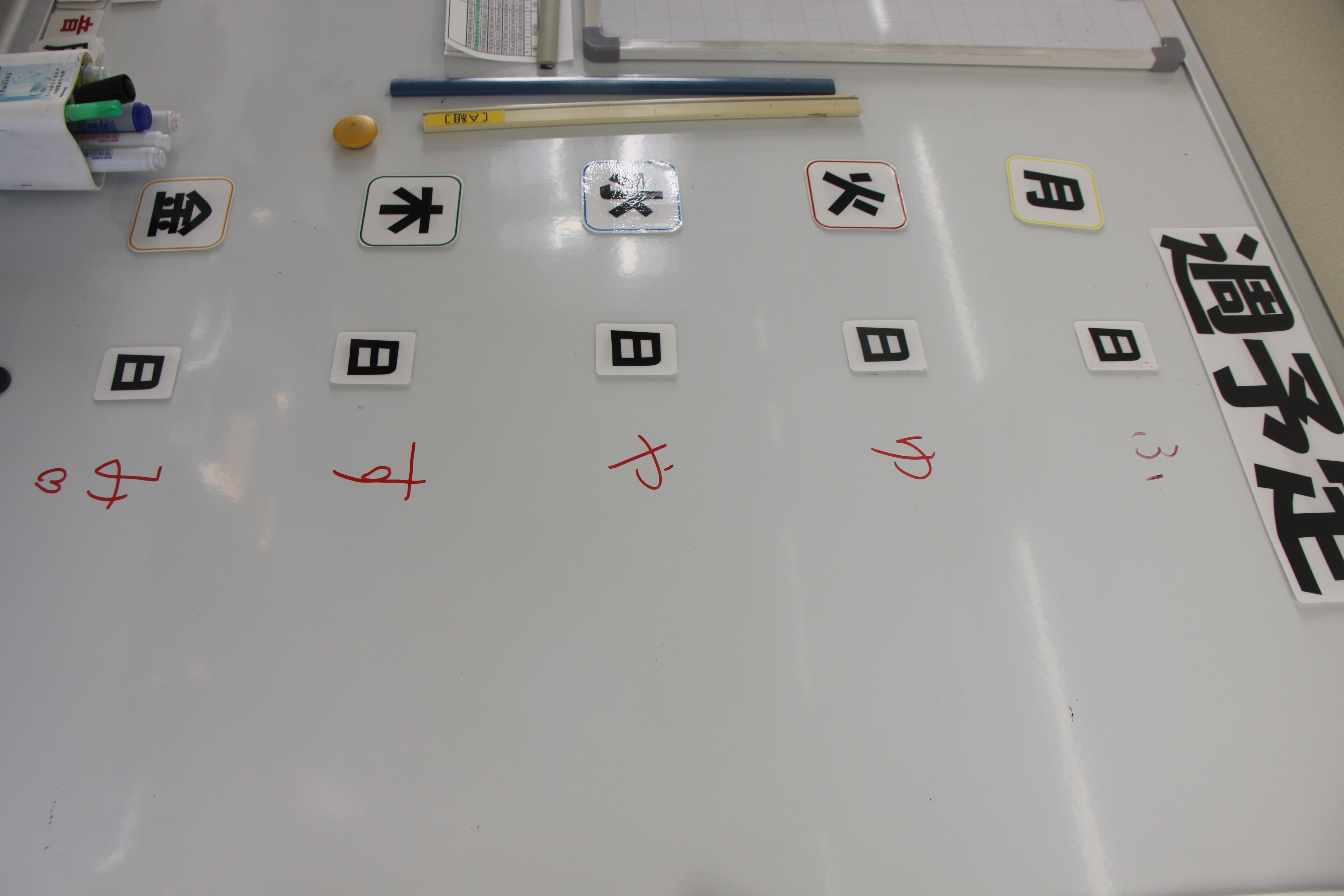
はじまりの日
きみが 手をのばせば
しあわせが とどきますように
きみのゆめが いつか
ほんとうに なりますように
まわりの人びとと
たすけあっていけますように
星空へのぼる
はしごを 見つけますように
毎日が きみの はじまりの日
きょうも あしたも
あたらしい きみの はじまりの日
やくそくを まもって
うそを きらいますように
このひろい 世界が
きみの目に 光りますように
背を まっすぐのばして
いつでも 勇気がもてますように
毎日が きみの はじまりの日
きょうも あしたも
あたらしい きみの はじまりの日
きみの手が ずっと
はたらきつづけますように
きみの足が とおくまで
走っていけますように
流されることなく
流れを つくりますように
きみの 心のうたが みんなに ひびきますように
毎日が きみの はじまりの日
きょうも あしたも
あたらしい きみの はじまりの日 ボブ・デュラン作 アーサー・ビナード訳
◎2学期終業式(12/22)

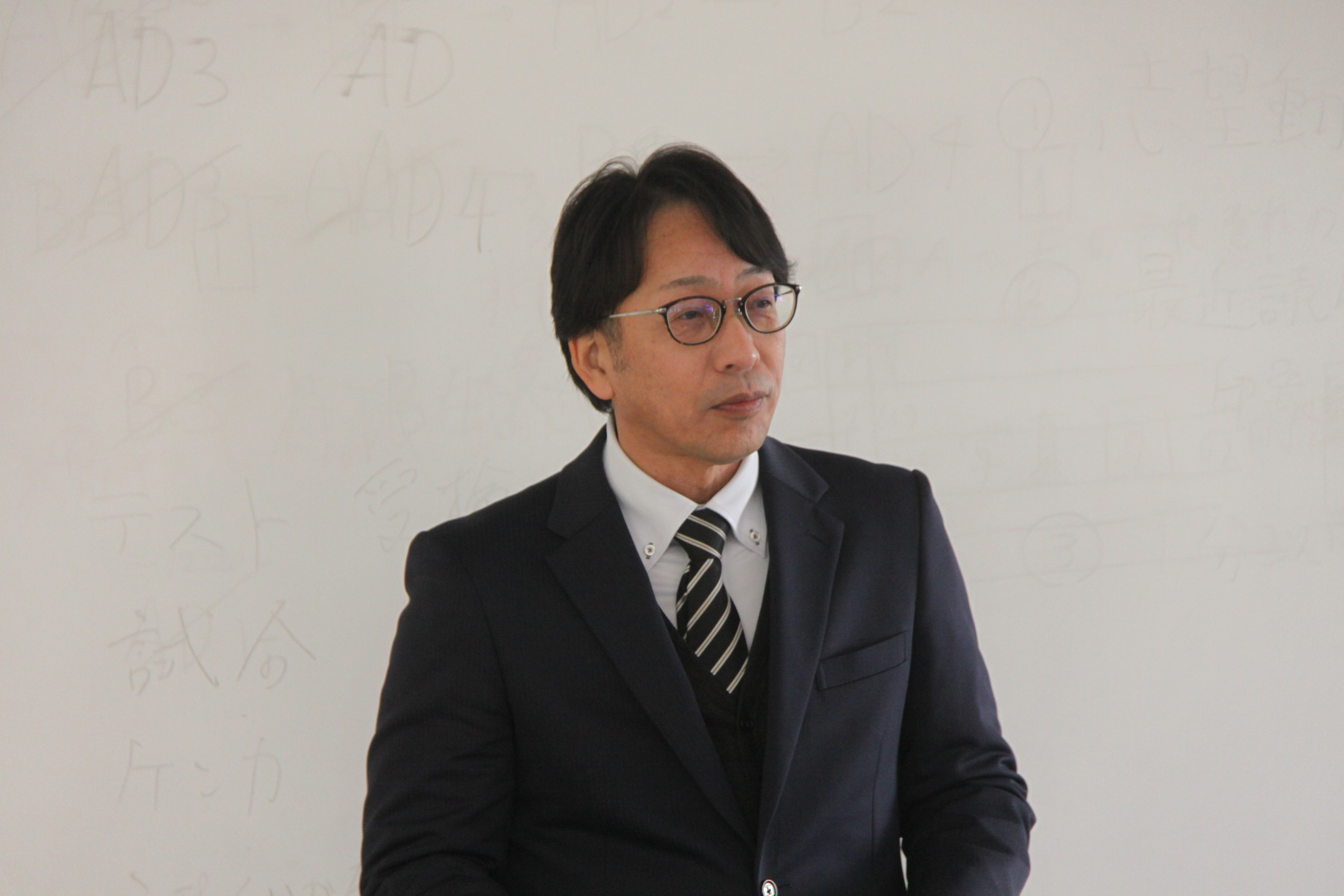



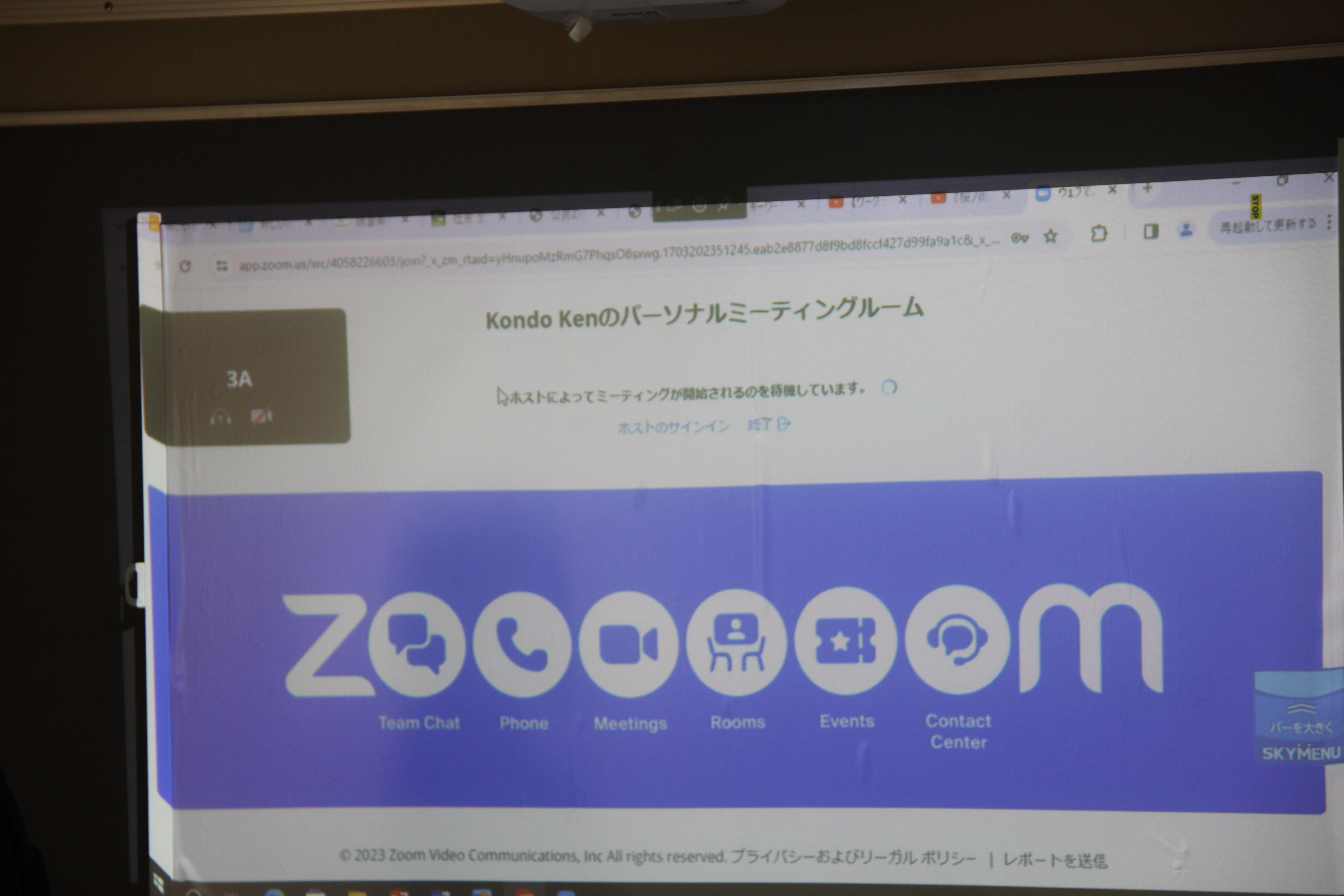


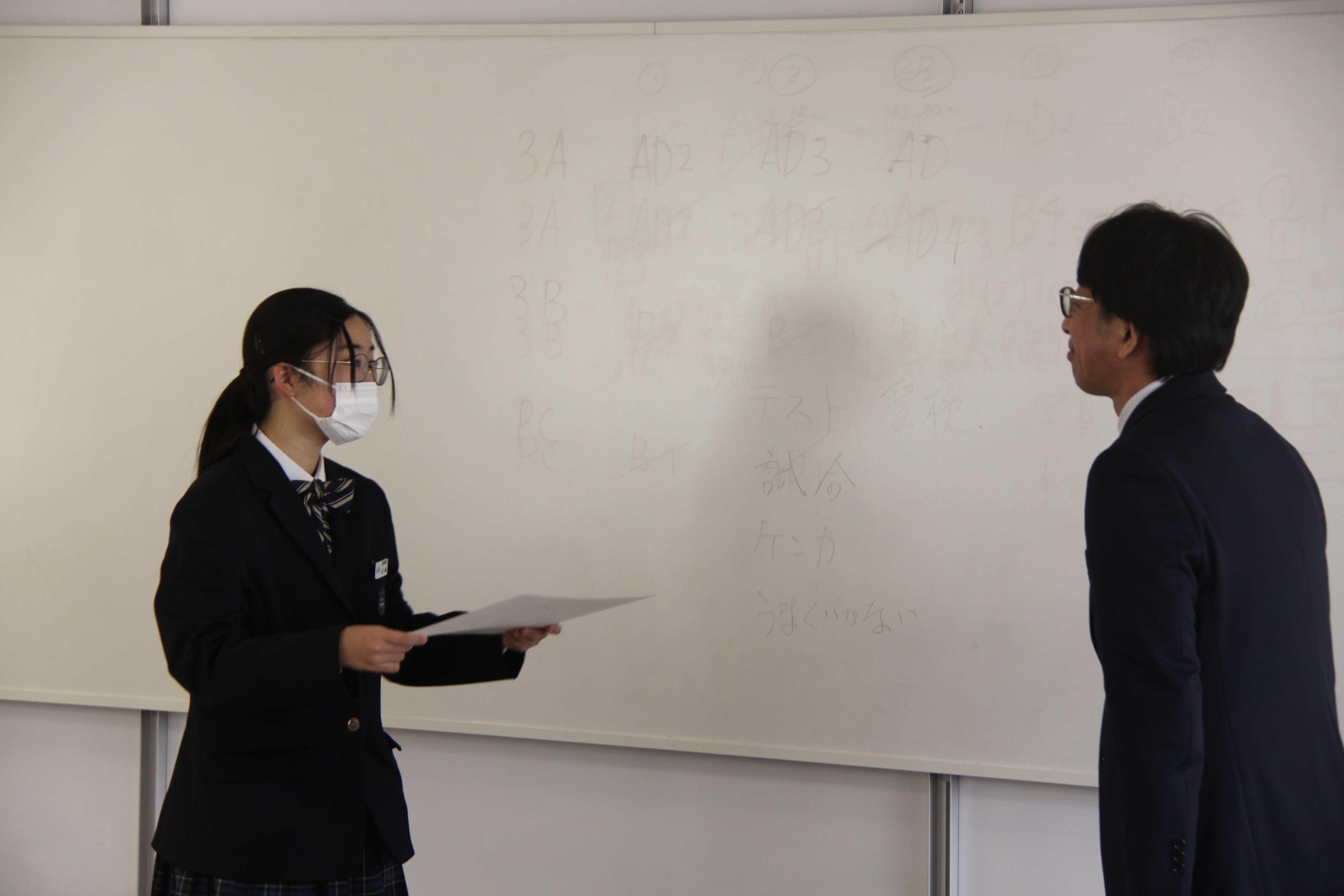

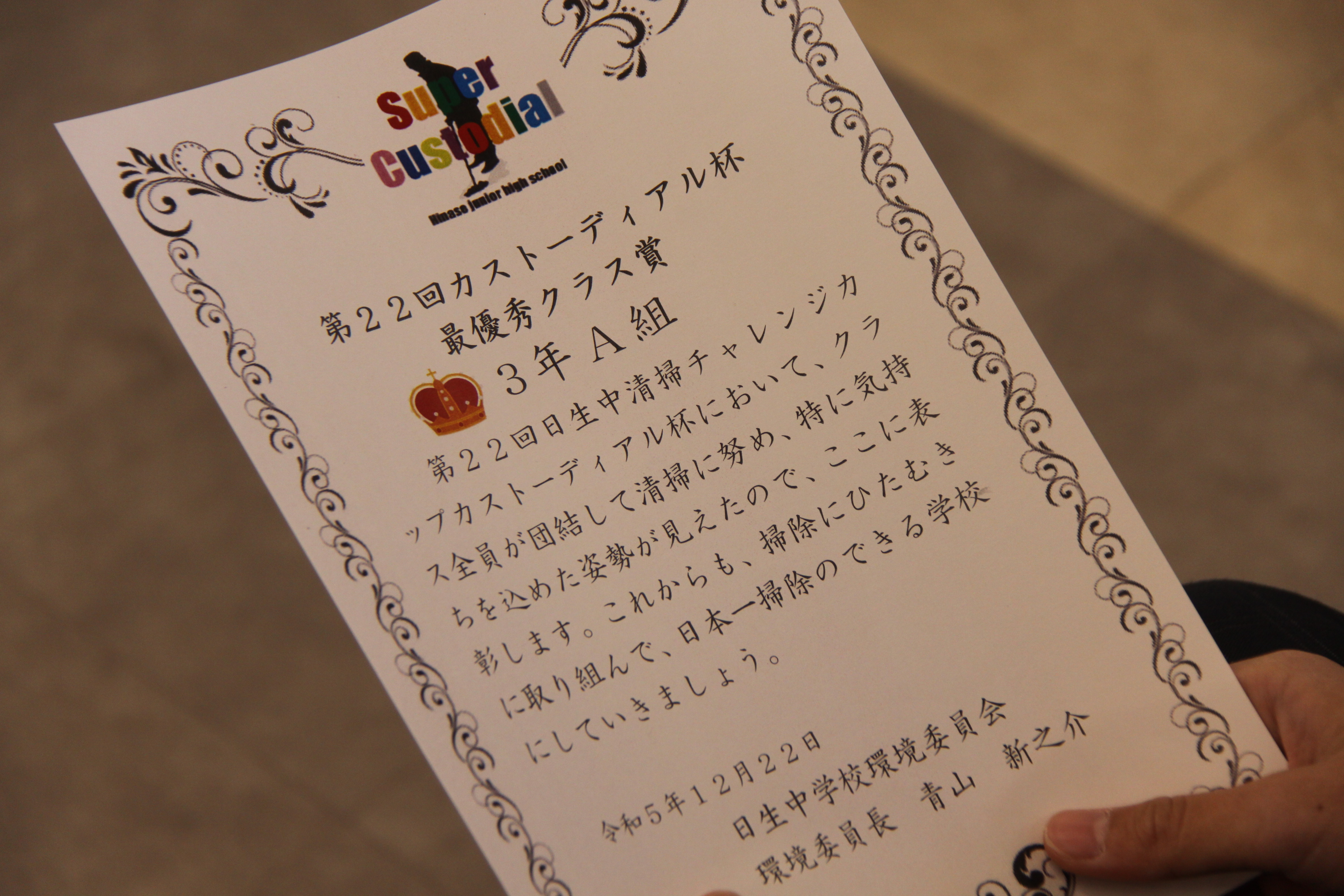
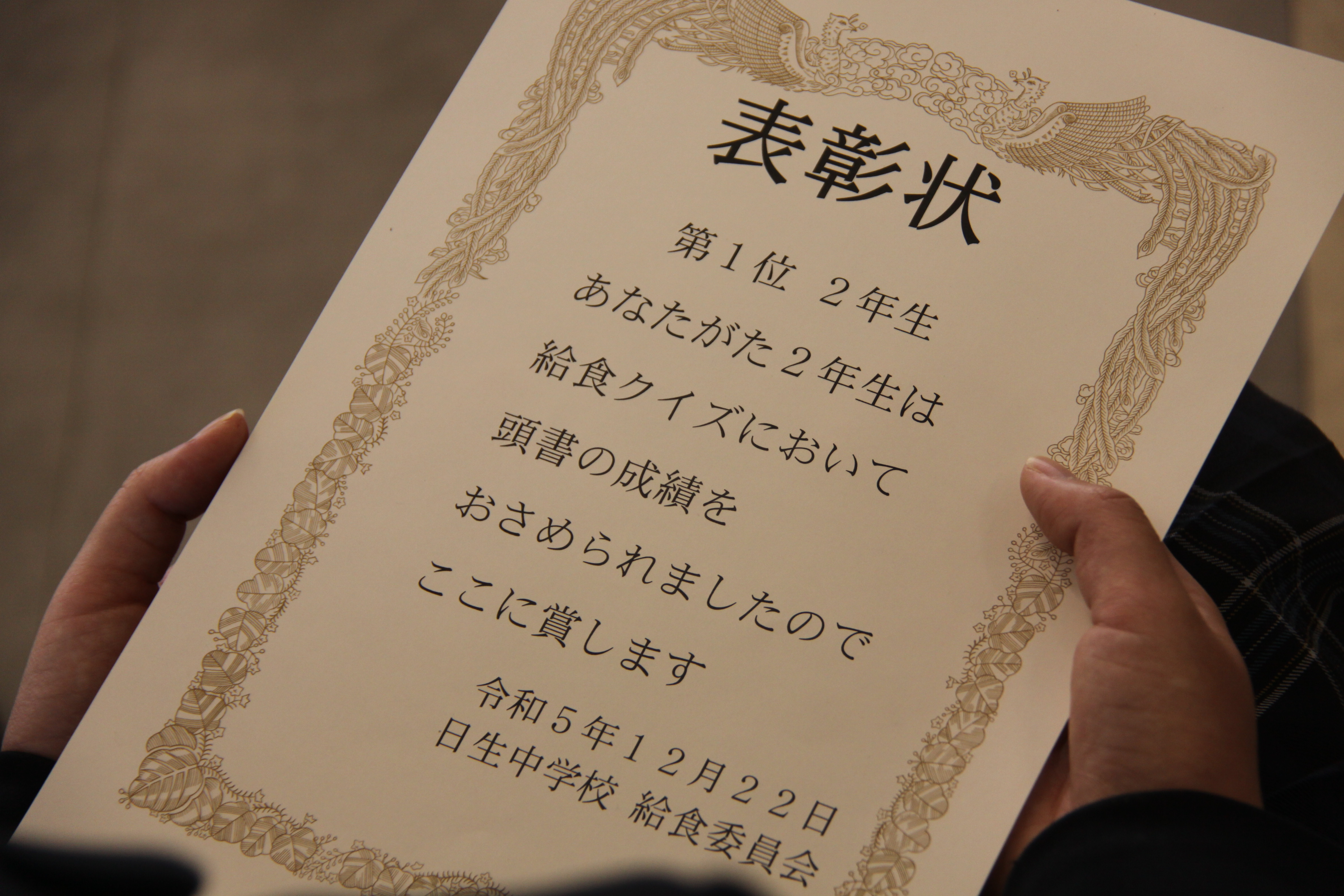



ぼくは ぼく からすえいぞう
ときどき ぼくは
ほんのすこし
いろつきの はねが ほしいな と
おもったりする
ほんのすこし
いいこえで うたえたらな と
おもったりもする
でも
これが ぼくだ と
とんでいく (工藤直子 のはらうた)
◎空は青く澄み渡り 海を目指して歩く 怖いものなんてない 僕らはもう一人じゃない 大切な何かが壊れたあの夜に 僕は星を探して一人で歩いていた ペルセウス座流星群 君も見てただろうか 僕は元気でやってるよ 君は今「ドコ」にいるの? 「方法」という悪魔にとり憑かれないで 「目的」という大事なものを思い出して は青く澄み渡り 海を目指して歩く 怖いものなんてない 僕らはもう一人じゃない(RPG SEKAI NO OWARIより)
(12.21吹奏楽部コンサート♬)











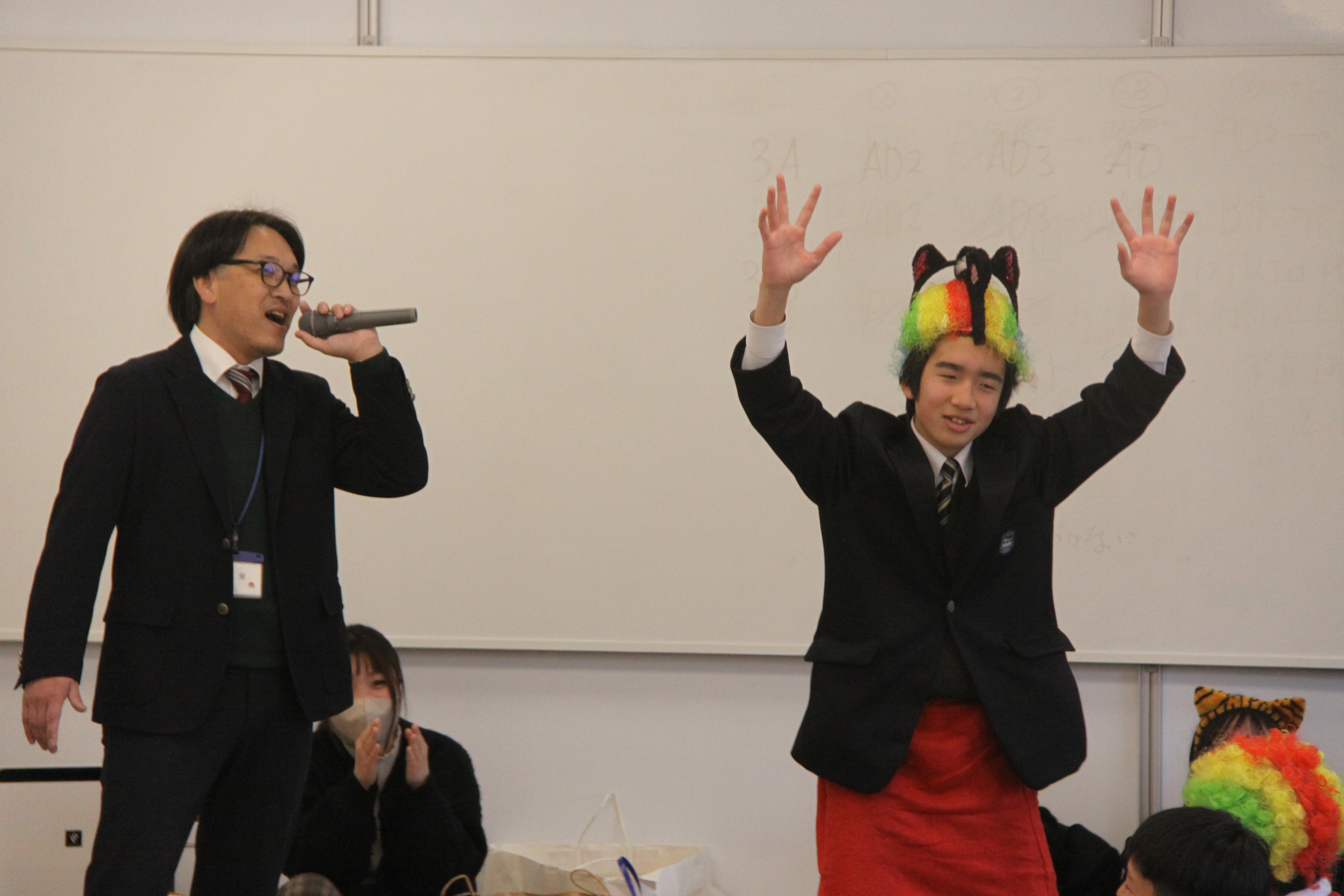
◎2学期もありがとう ありがとう、日生中。(学期末清掃:12/21)






◎私たちの学校をわたしたちが創る(12/21)
集まった意見を集約し、校則改定に関するアンケートを生徒会が実施。確かな一歩。




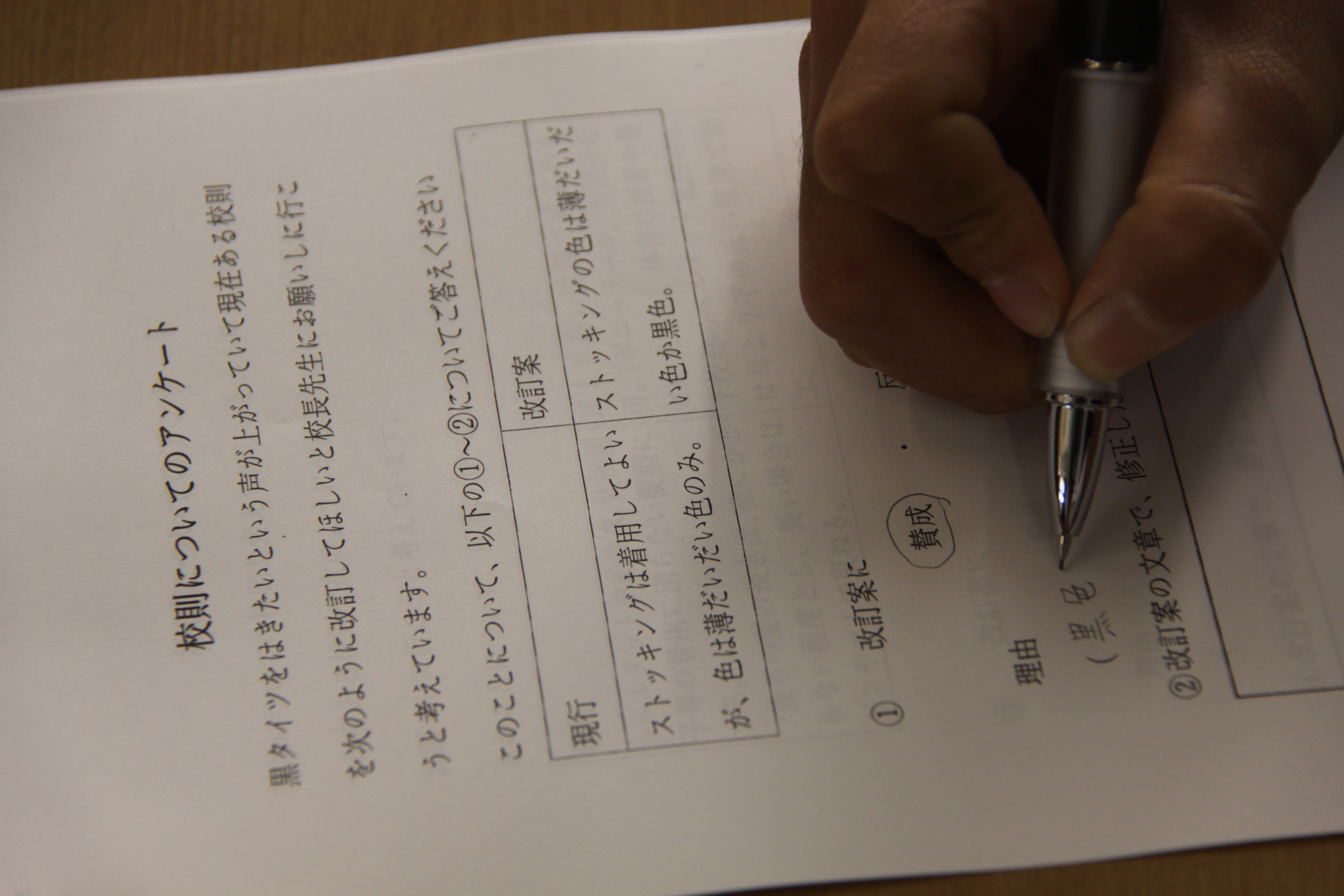
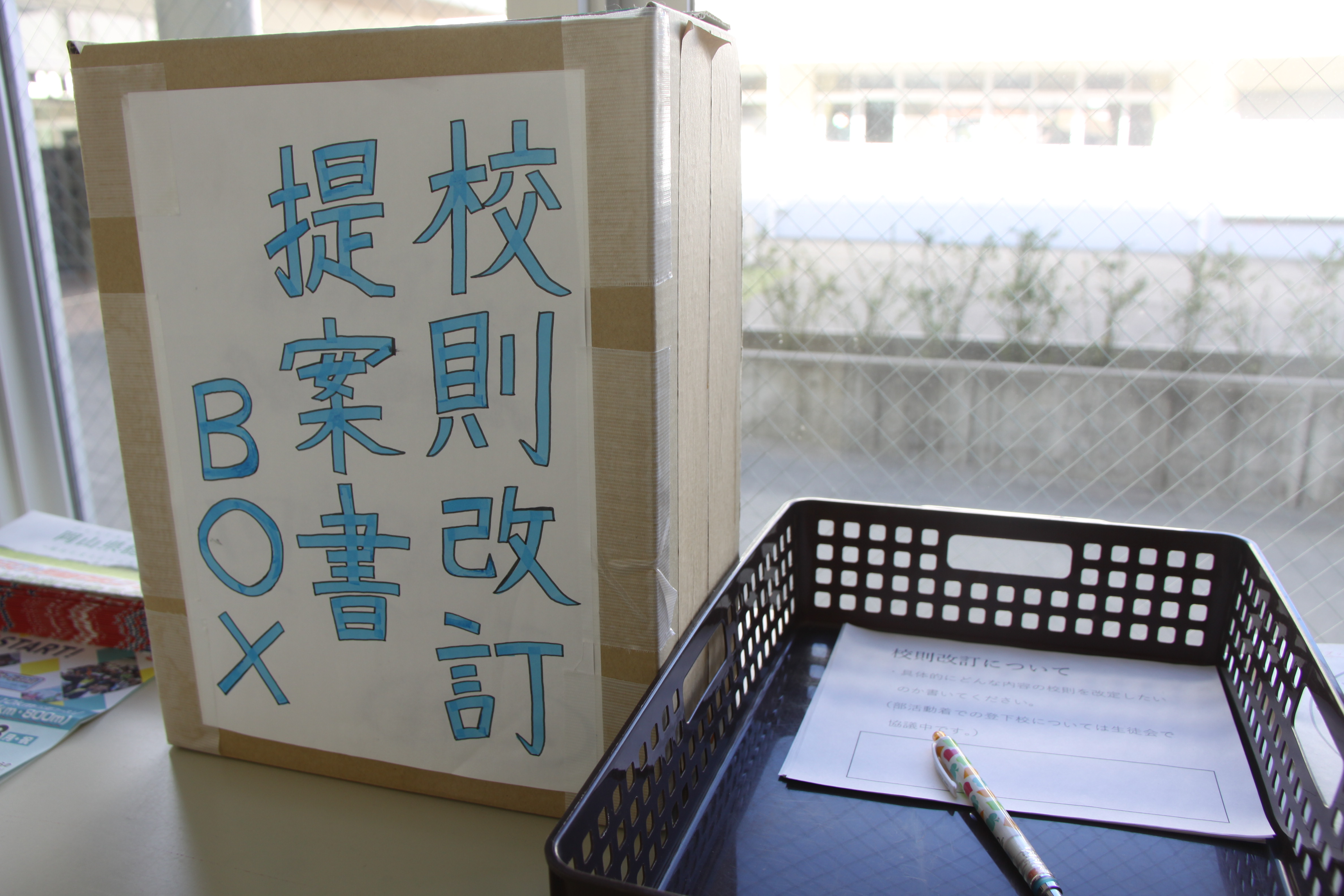
人間の勇気なるものは、天から降ったり、地から湧いたりするものではなく、勇気が出せる主体的、客観的条件が必要である。(森田竹次『偏見への挑戦』長島評論部会1972)
◎ひな中の風~✨(12/20)
「次代を担う中学生に、応募を機会に税について考え、税に関する正しい知識を身に付けてほしい」という趣旨で、毎年、納税貯蓄組合連合会は、県教育委員会などの後援を得て、税についての作文・書写を募集しています。令和5年度は、本校の清水さんが書写コンクールで入賞し、この日、瀬戸税務署総務課石村課長さん、備前東商工会の横山忠彦会長さん、横山康則事務局長さんが来校され、表彰の授与式をおこないました。おめでとう。

◎個別懇談最終日です。(^∧^)(12/20)
学期末を大切に、これからを大切に。
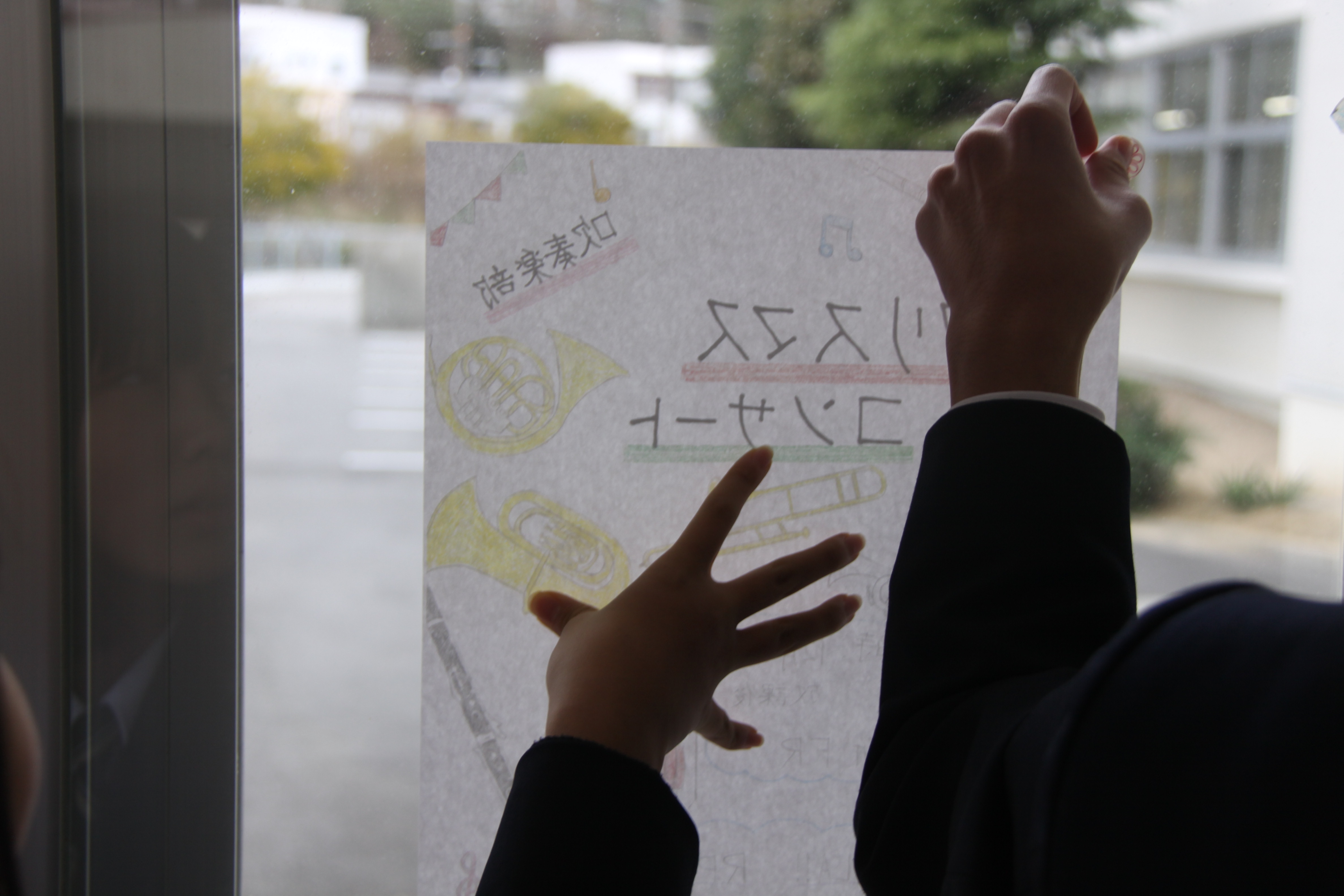
吹奏楽部クリスマスコンサートは22日。
「ええねん」:ウルフルズ 作詞:トータス松本 作曲:トータス松本
何も言わんでも ええねん 何もせんでも ええねん 笑いとばせば ええねん 好きにするのが ええねん 感じるだけで ええねん 気持ちよければ ええねん それでええねん それでええねん 後悔しても ええねん また始めたら ええねん 失敗しても ええねん もう一回やったら ええねん 前を向いたら ええねん 胸をはったら ええねん それでええねん それでええねん 僕はお前が ええねん 好きでいれたら ええねん 同じ夢を見れたら ええねん そんなステキなふたりが ええねん 心配せんで ええねん 僕を見てれば ええねん それでええねん それだけで アイディアなんか ええねん 別になくても ええねん ハッタリだけで ええねん 背伸びしたって ええねん カッときたって ええねん 終わりよければ ええねん それでええねん それでええねん つっぱって突っぱしる 転んで転げまわる 時々ドキドキする そんな自分が好きなら ええねん そんな日々が好きなら ええねん 情けなくても ええねん 叫んでみれば ええねん にがい涙も ええねん ポロリこぼれて ええねん ちょっと休めば ええねん フッと笑えば ええねん それでええねん それでええねん 何もなくても ええねん 信じていれば ええねん 意味がなくても ええねん 何かを感じていれば ええねん 他に何もいらんねん 他に何もいらんねん それでええねん それだけで ええねん
◎明日から寒波の予想アリ。降雪・低温・凍結にも注意し。(12/20)
「雪」の季節、いつも読み直す詩があります。岡山県赤磐市出身の永瀬清子さんの「降りつむ」を紹介します。

かなしみの国に 雪が降りつむ
かなしみを 糧として生きよと 雪が降りつむ
失いつくしたものの上に 雪が降りつむ
その山河の上に
そのうすき シャツの上に
そのみなし子の 乱れたる 頭髪の上に
四方の潮騒 いよよ高く 雪が降りつむ
夜も 昼もなく
長い かなしみの 音楽のごとく
哭きさけびの心を鎮めよと 雪が 降りつむ
ひよどりや狐の 巣に こもるごとく
かなしみに こもれと
地に強い草の葉の 冬を越すごとく
冬を 越せよと
その下から やがて よき春の立ちあがれと 雪が降りつむ
無限にふかい空から しずかに しずかに
非情の やさしさをもって 雪が降りつむ
かなしみの国に 雪が降りつむ
◎多くの人に支えられて(12/20)





二学期の給食は明日で終了となります。終了日前日の今日は、デザートにセレクト方式のケーキを出していただきました。事前に子どもたちが自分で選んだケーキをいただきます。今日を楽しみにしている生徒が多かったようです。
〈あなたはどっち派??〉
○いちごケーキ・・・スポンジといちごクリームを組み合わせ、スポンジのあいだにいちごジャムが入っています。酸味と甘さのバランスが絶妙です。※大豆を使用しています。
○チョコケーキ・・・チョコ味のスポンジとクリームを組み合わせ、スポンジのあいだにチョコソースが入っています。濃厚さにアクセントがありおいしいです。※大豆を使用しています。
◎ひな中の風~~




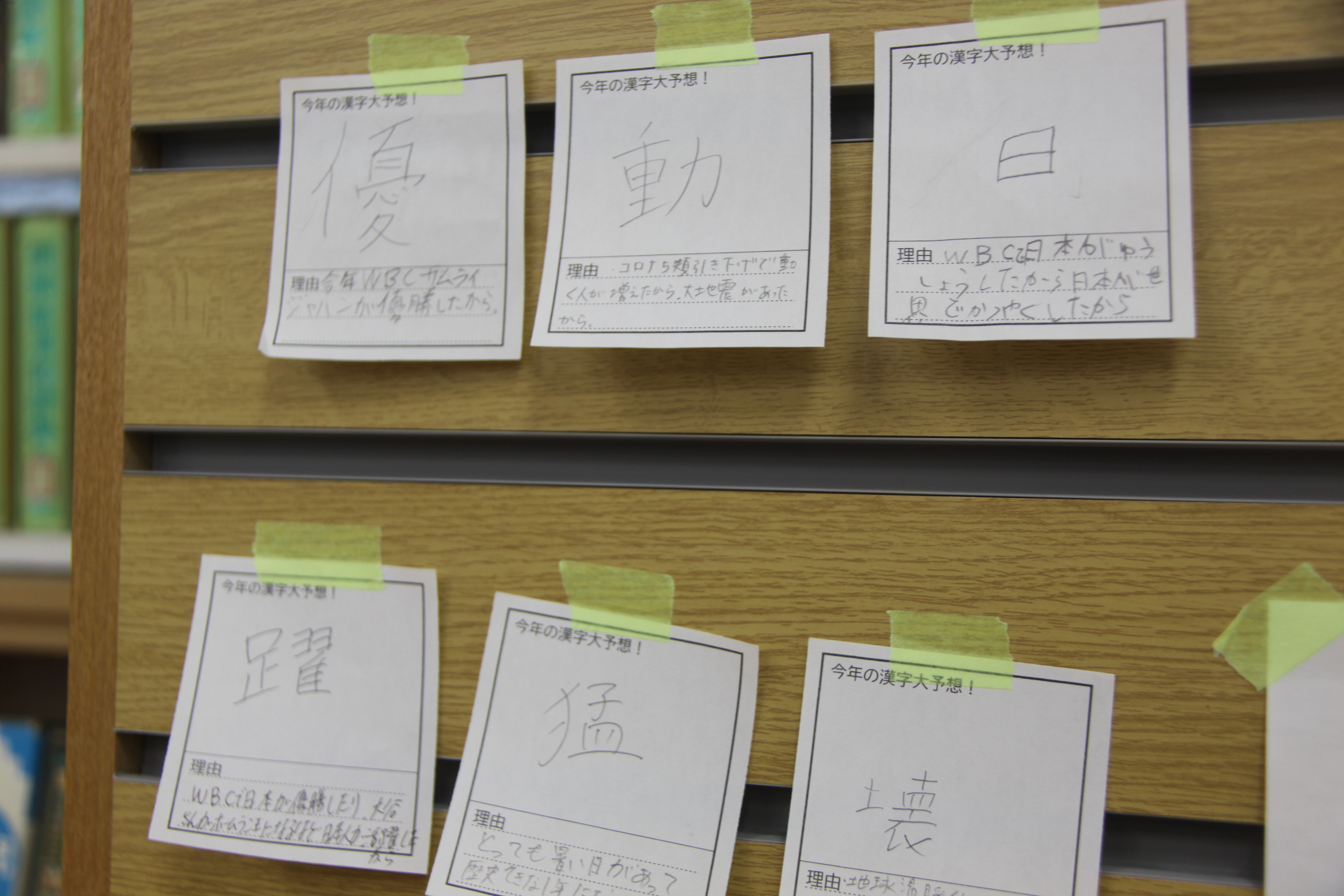




◎日生で輝く 日生が輝く よ。
日生中鑑札シール(過年度)が貼ってある自転車が、数台、駐輪場からはみ出して、交通の妨げになっていました。残念。


日生中生徒会は7月に続き、日生駅・中学校周辺の地域清掃ボランティアを22日、11時10分からおこないます。社会福祉協議会さんの協力を得て、川東地区福祉協議会の皆さんと協働して取り組みます。
◎ひな中の大切な〈時間〉(12/19・朝)
文化委員会による読み語りに耳を傾ける「しんしんタイム」。22日には、生徒会執行部による校則改定アンケートをおこないます。


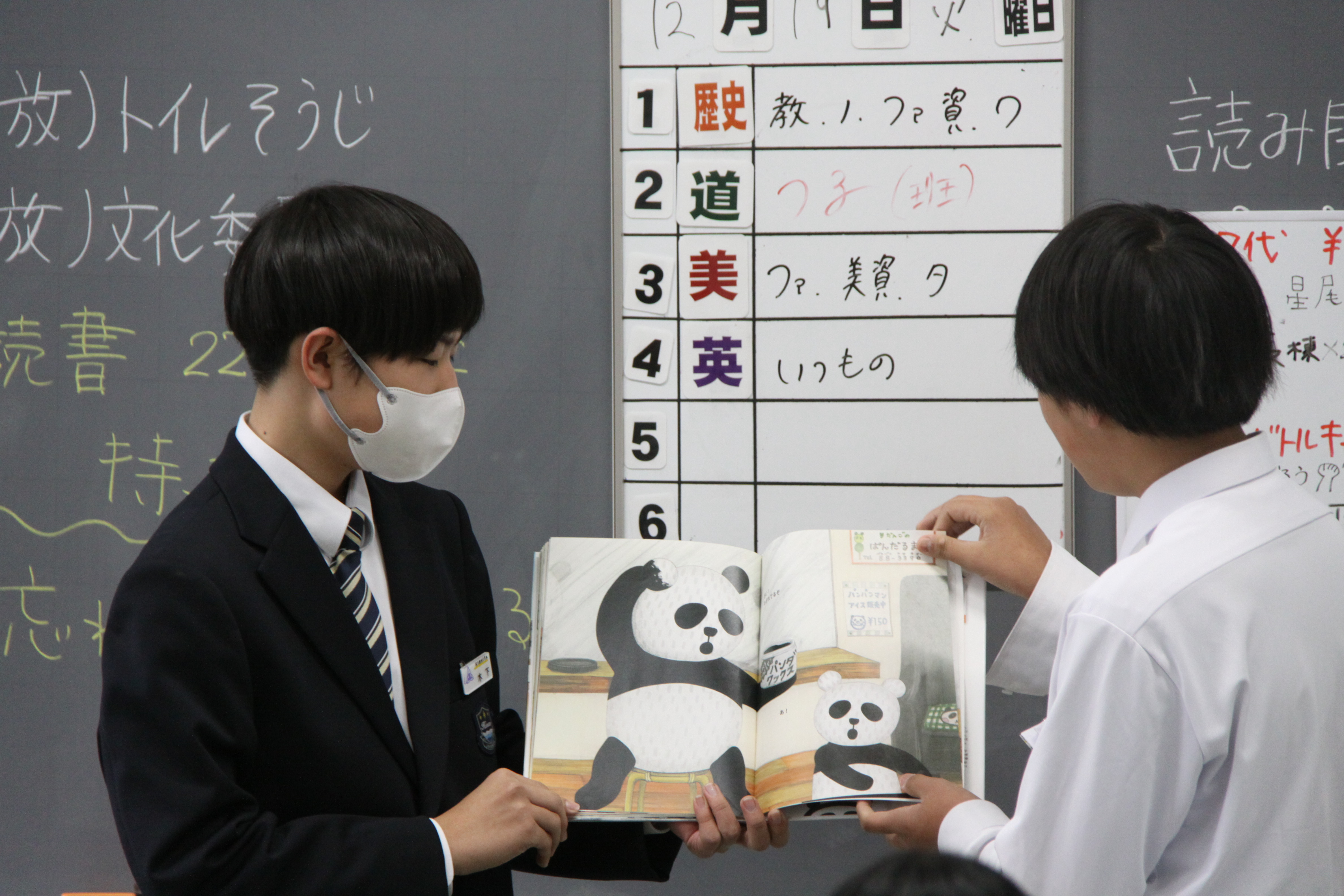


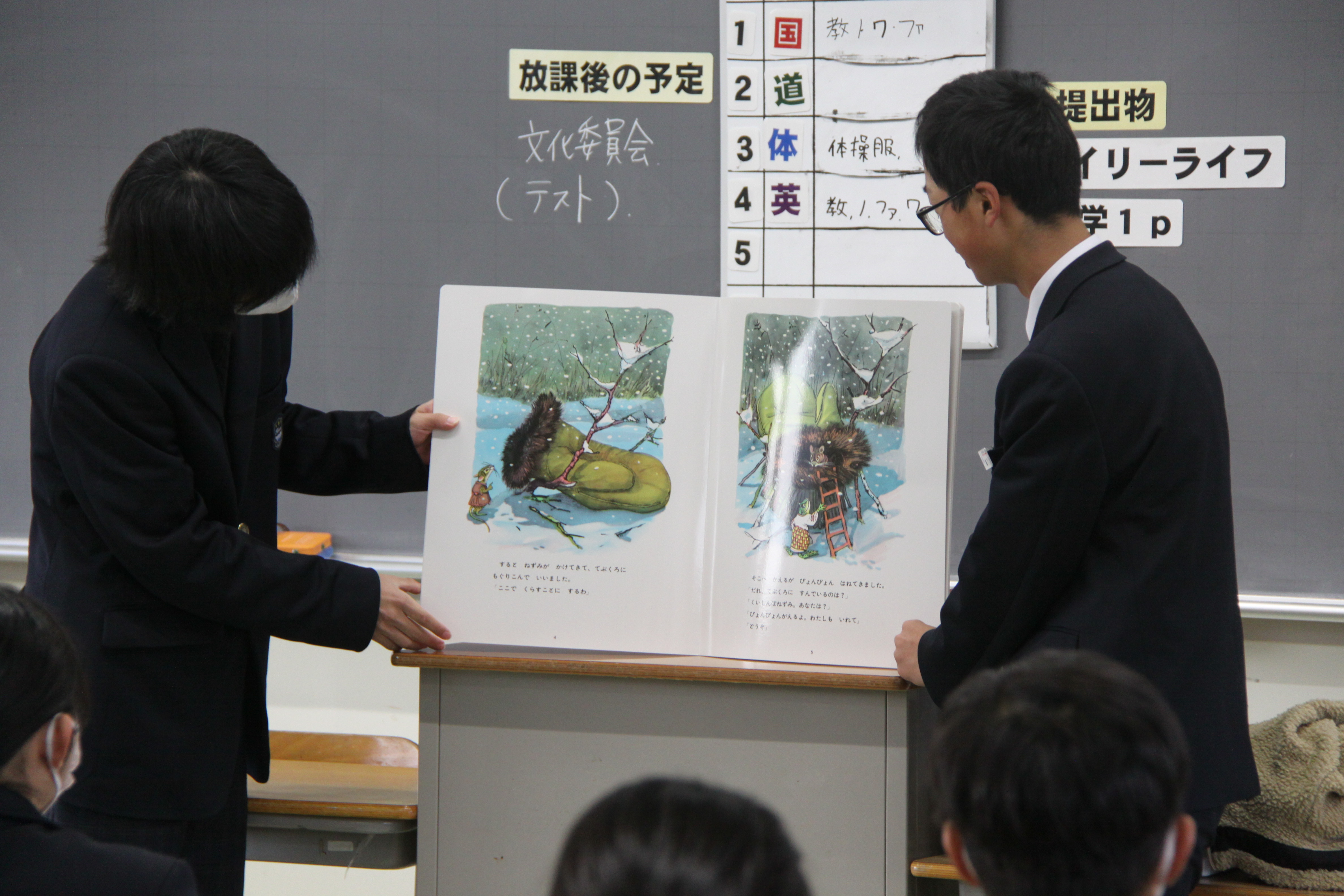
◎ひな中の風~~
~学ぶ仲間・学ぶ楽しさ・学ぶちからを~12/18
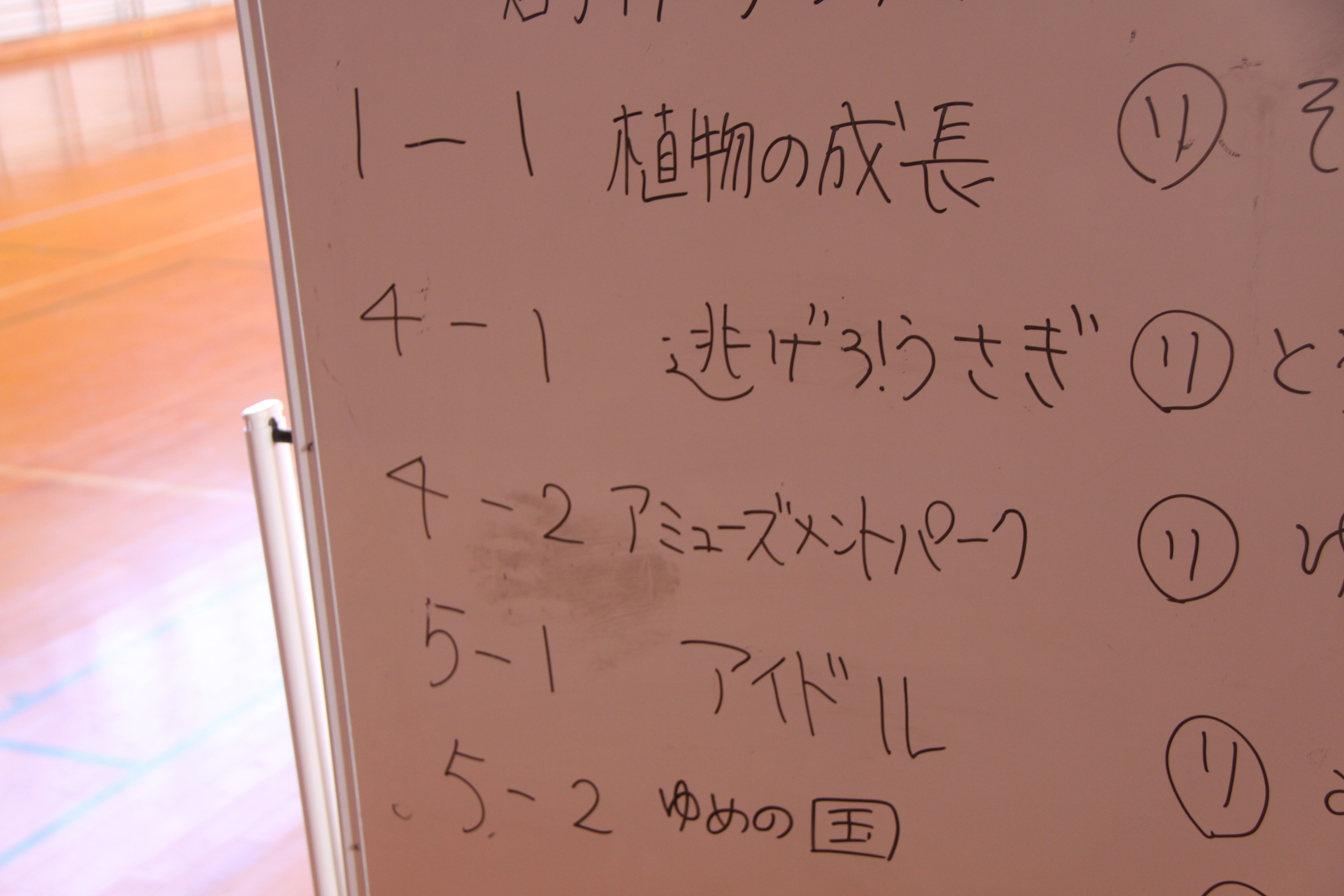




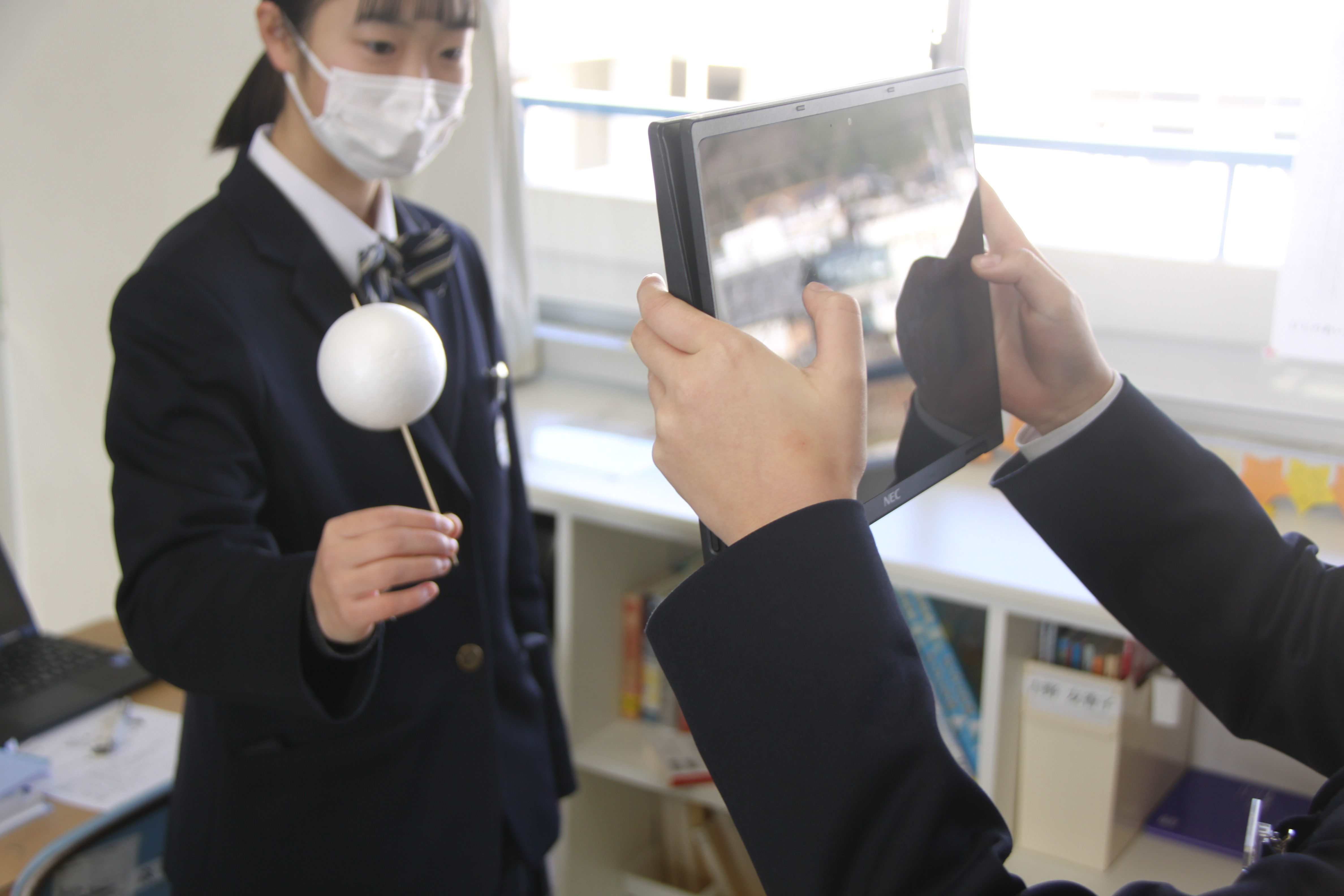
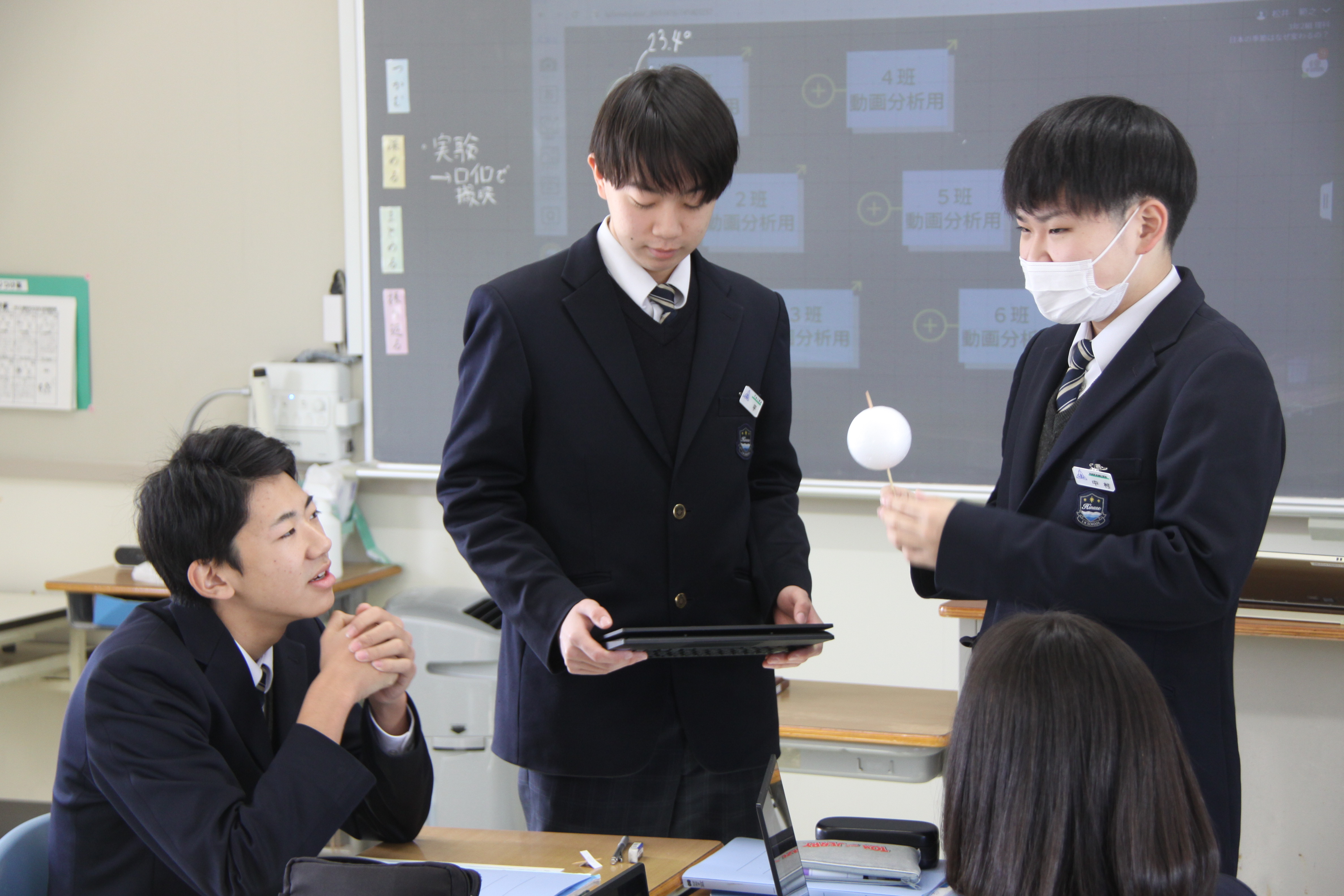
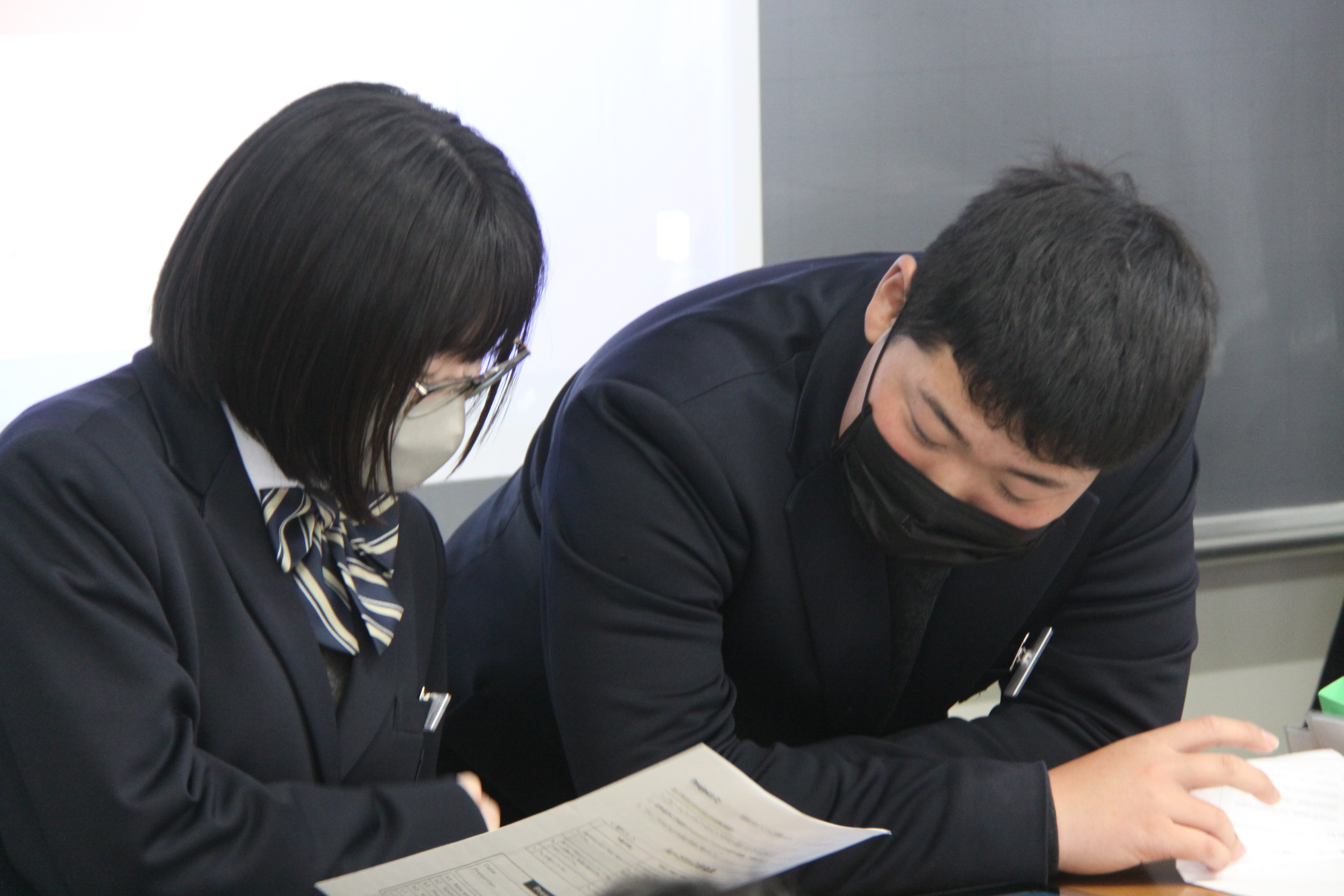

◎ASIAN EXPO 12.18
3年生英語科での取組。

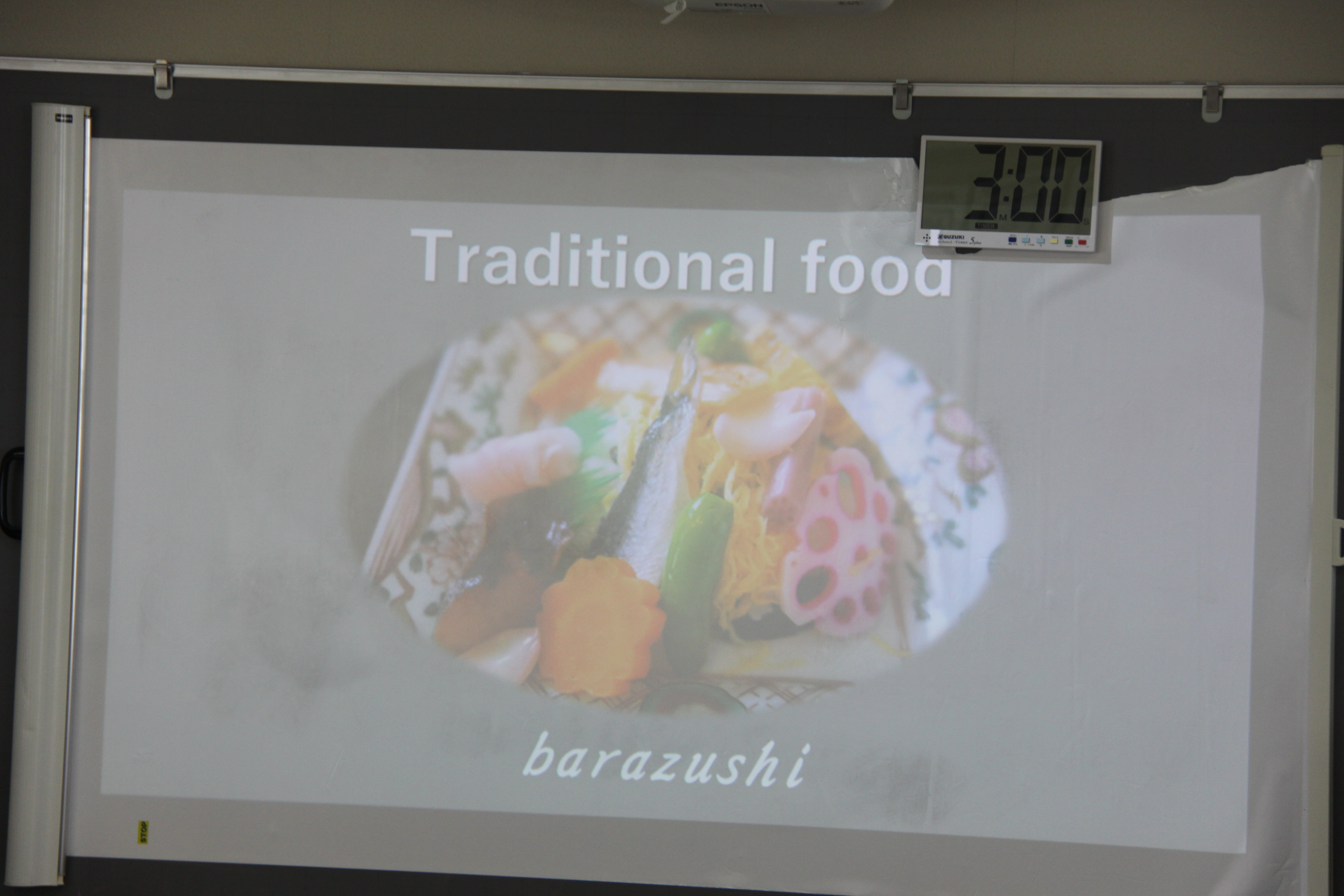
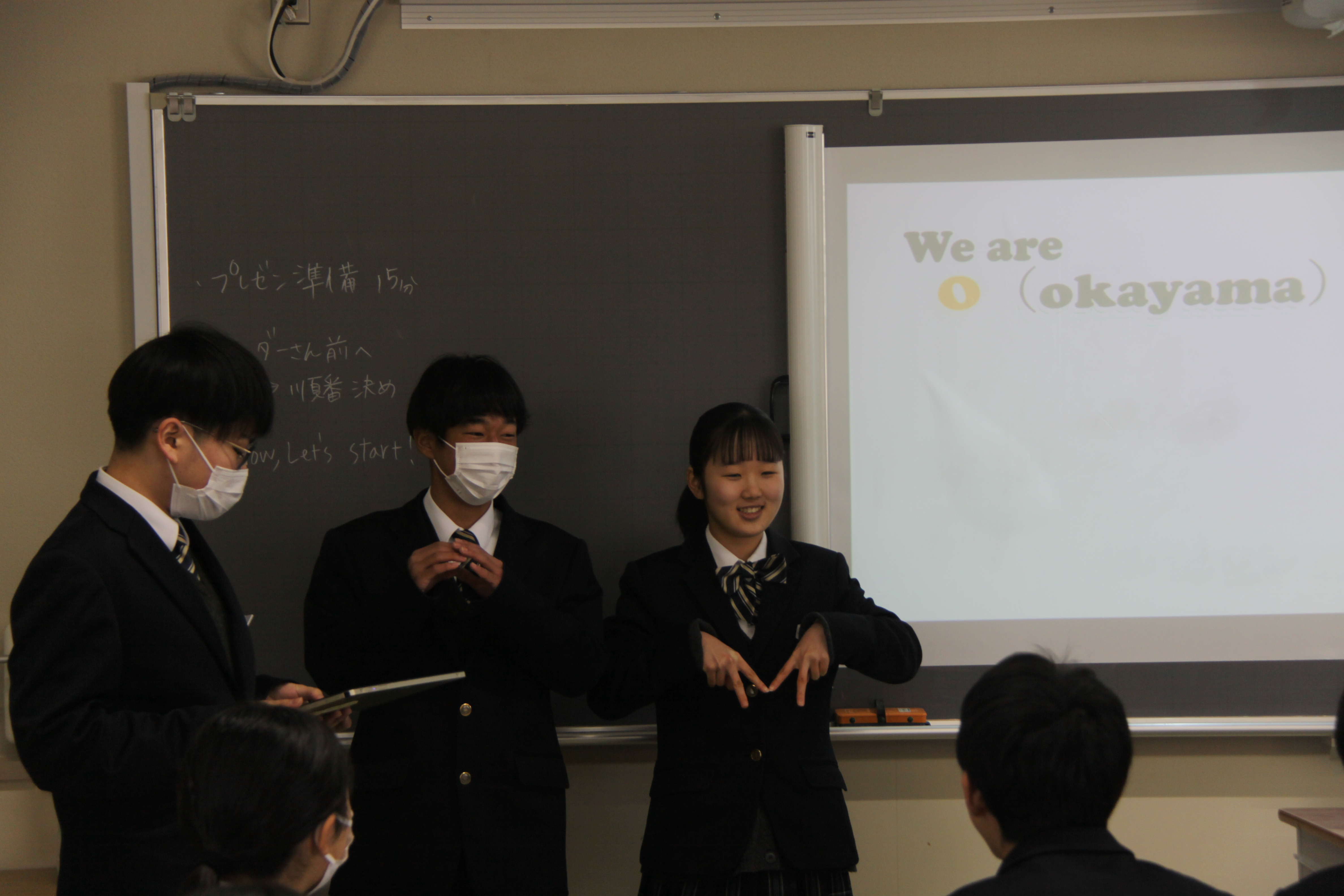





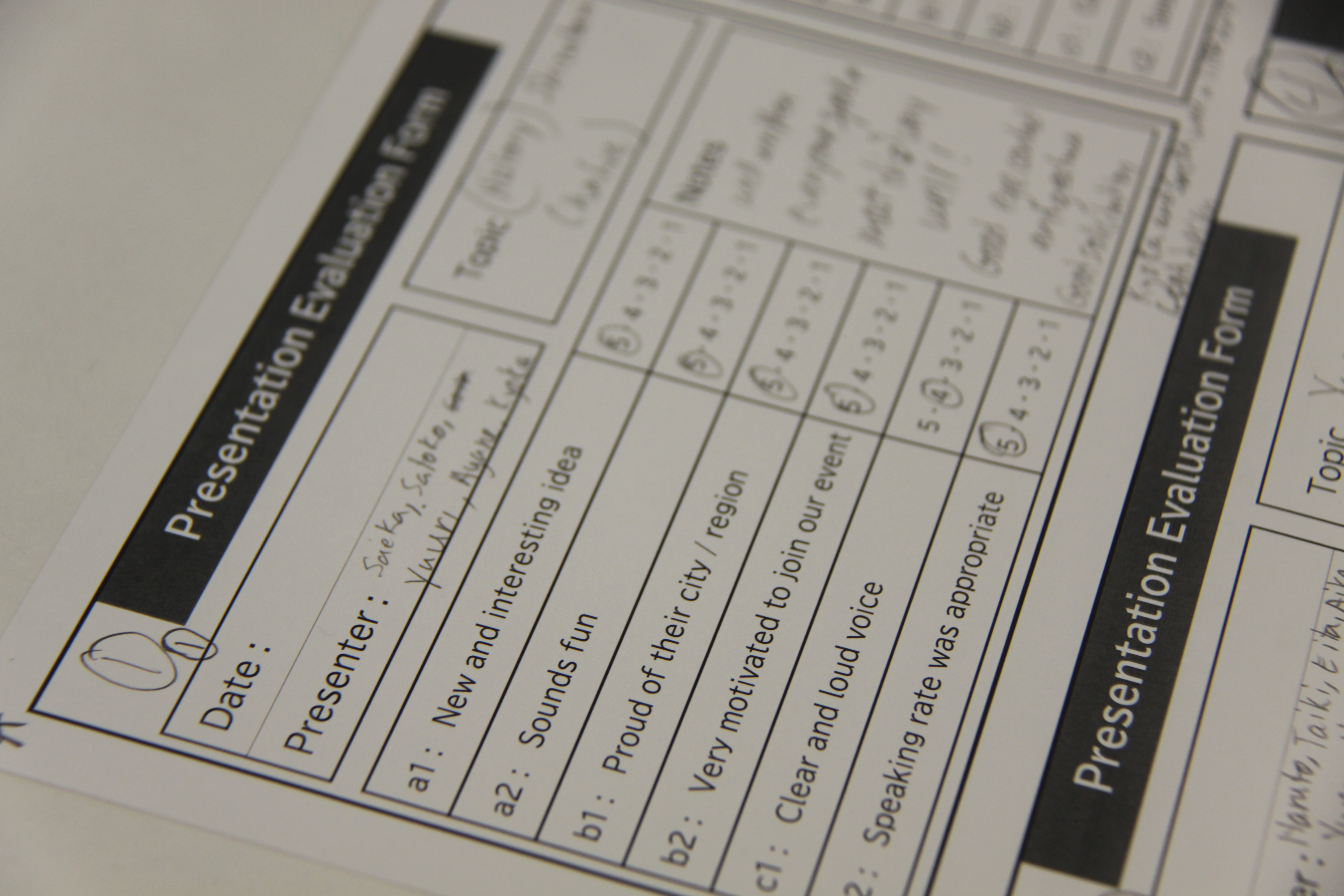
◎わたしの思いを創る。
第24回「未来に残そう青い海」海上保安庁図画コンクールにおいて、本校の竹原さん(3年生)が、第6管区海上保安本部長賞を受賞し、12月17日に玉野市での表彰式に参加しました。おめでとう(^_^)。
コンクールは、今年も6月から作品募集をはじめ、全国の小中学生から16,700点の応募がありました。22日の終業式で全校表彰伝達を行います。

◎ひな中の風~~

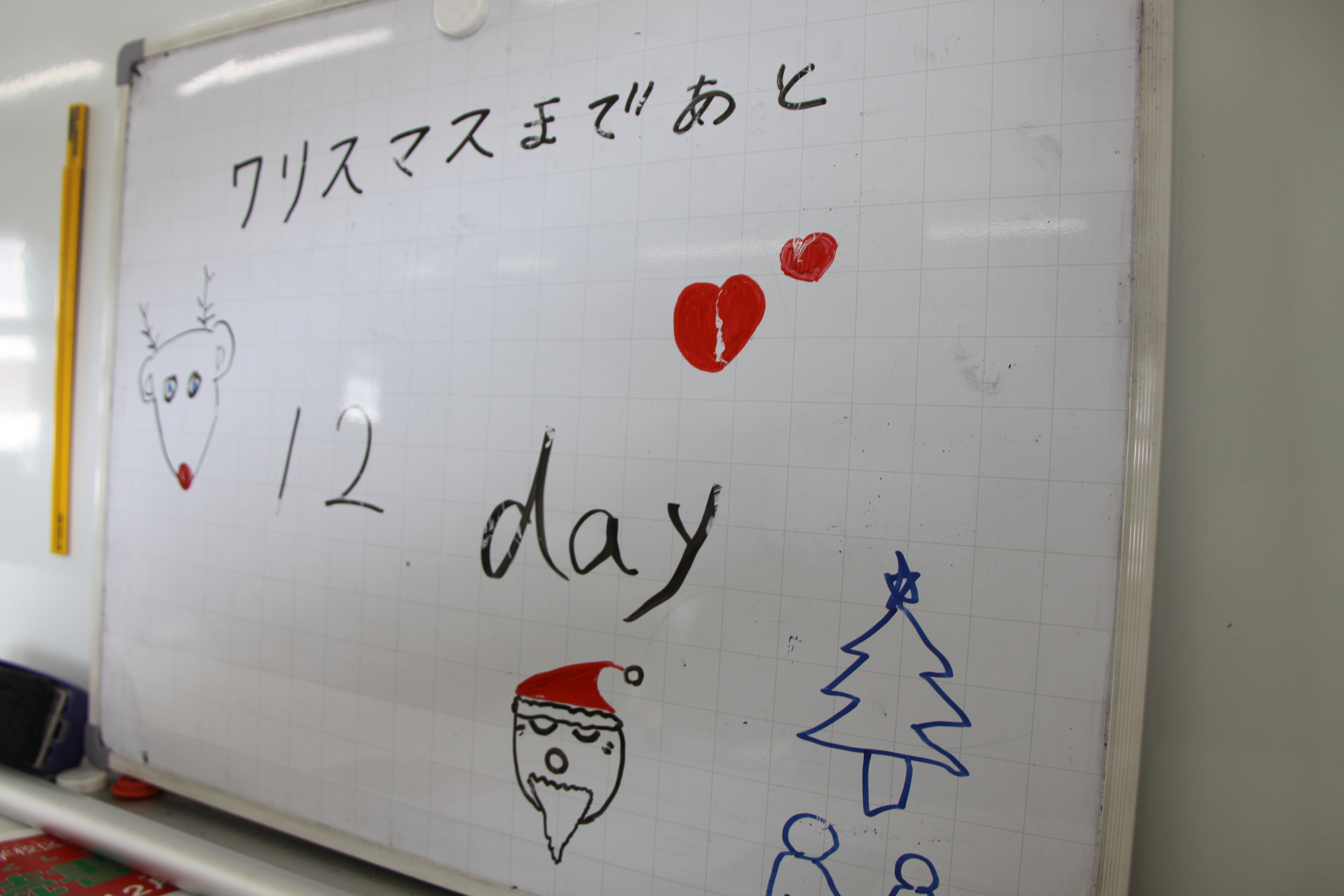

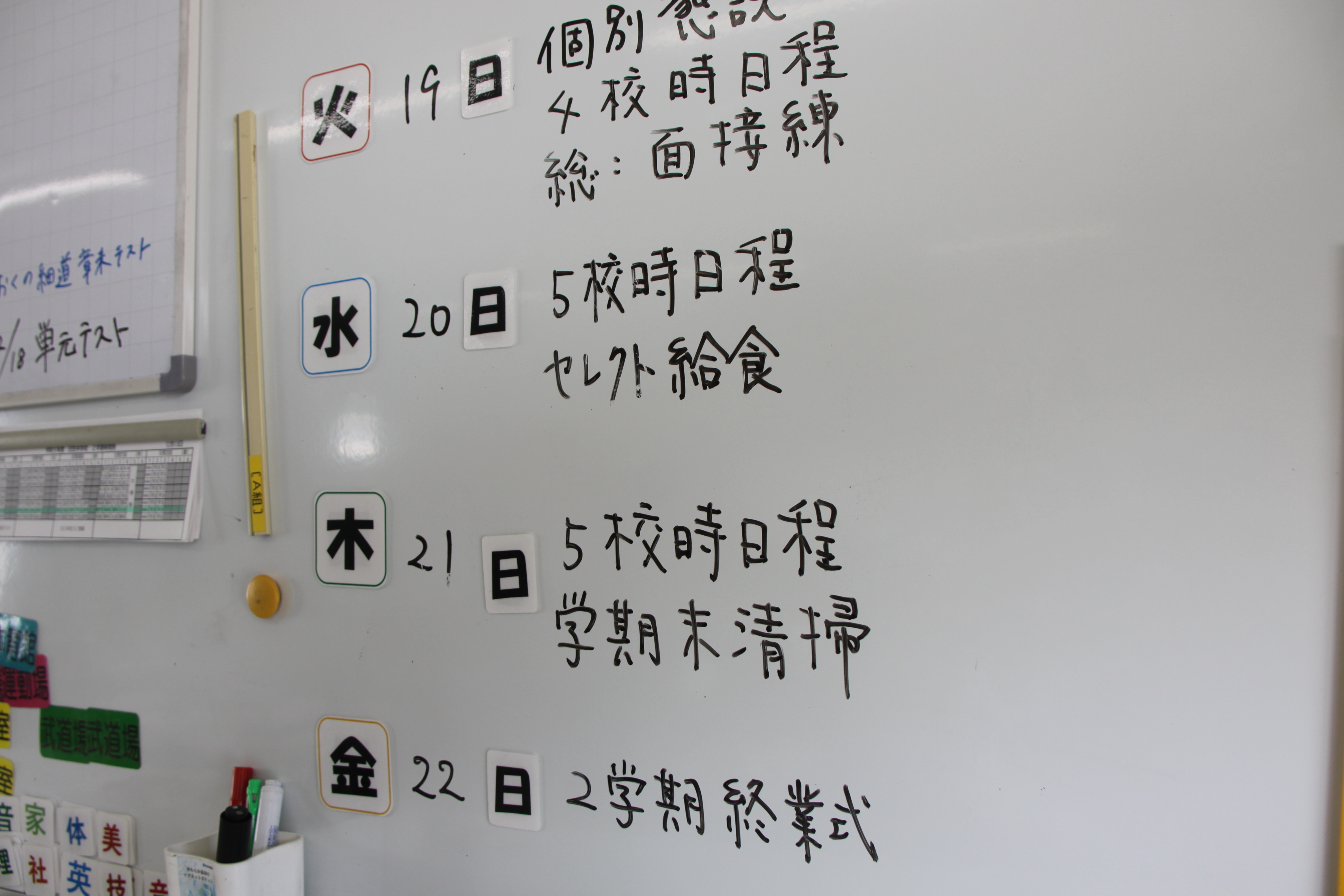

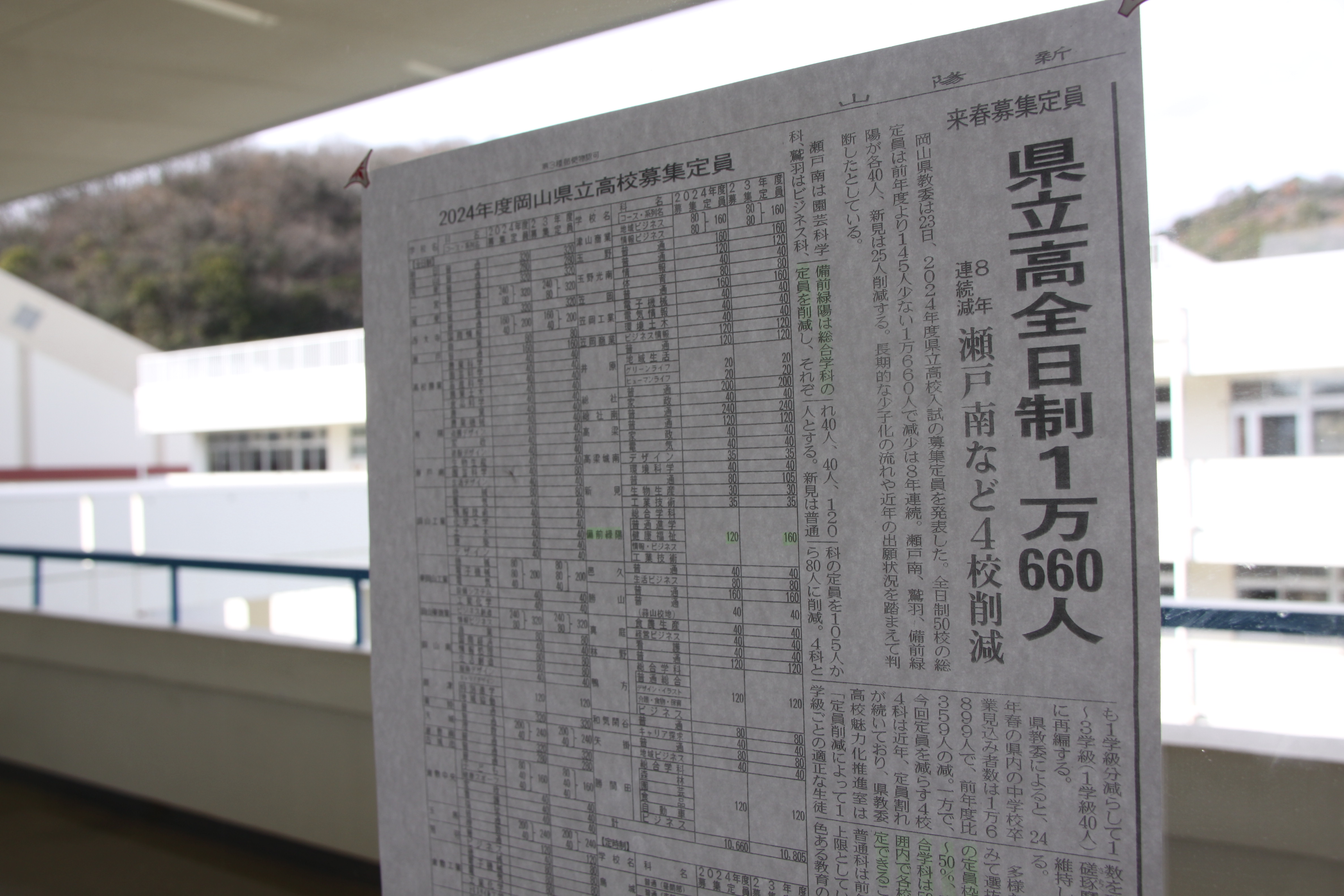


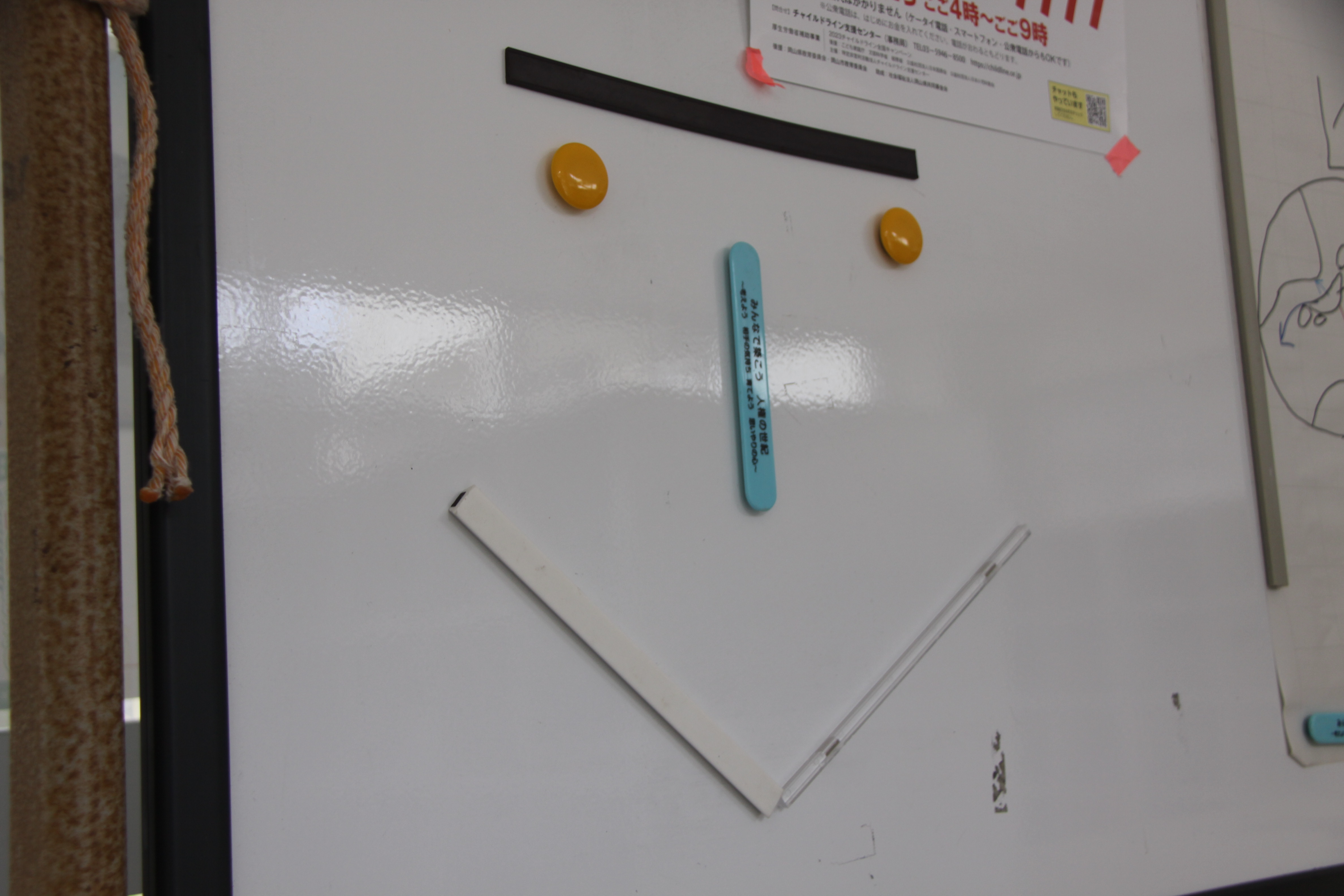
Be careful of your thoughts‚ for your thoughts become your words; Be careful of your words‚ for your words become your deeds; Be careful of your deeds‚ for your deeds become your habits;Be careful of your habits; for your habits become your character; Be careful of your character‚ for your character becomes your destiny. Mother Teresa
(思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。)
◎Merry Christmas!!
よい子のみんな!サンタさんはやってくるよ♬
一足早く、日生認定子ども園にサンタさんが来られていましたよ。(12/15)日生中のみんなも待っててね。(^_^)


◎ホンモノはどれだ?(1年生美術科からの挑戦12/15~)

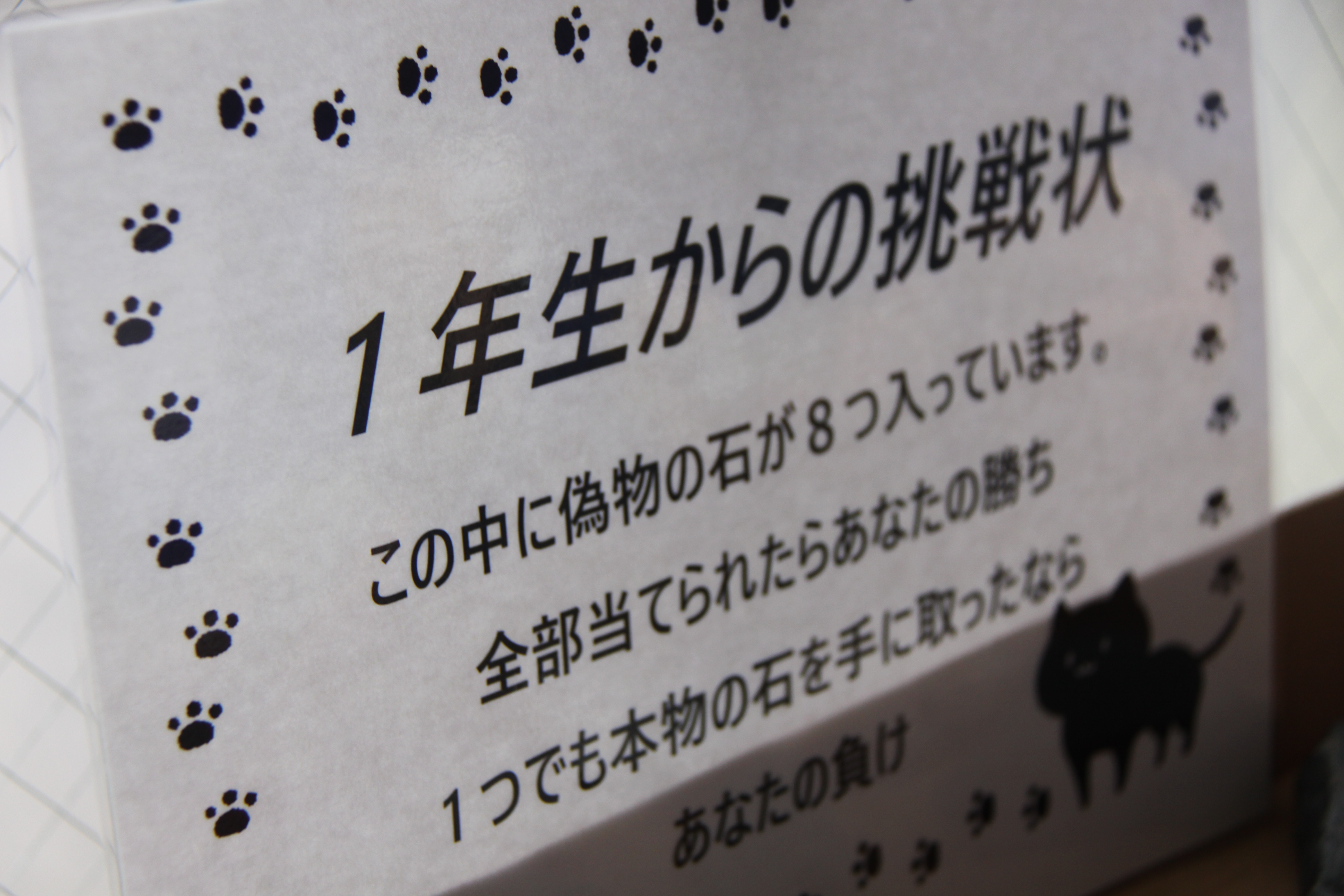


The search for truth begins with the doubt of all ‘truths’ in which one has previously believed. Nietzsche
(真実の追求は、誰かが以前に信じていた全ての”真実”の疑いから始まる。)
◎おのおのがた、12月14日でござる
ひな中の風~~



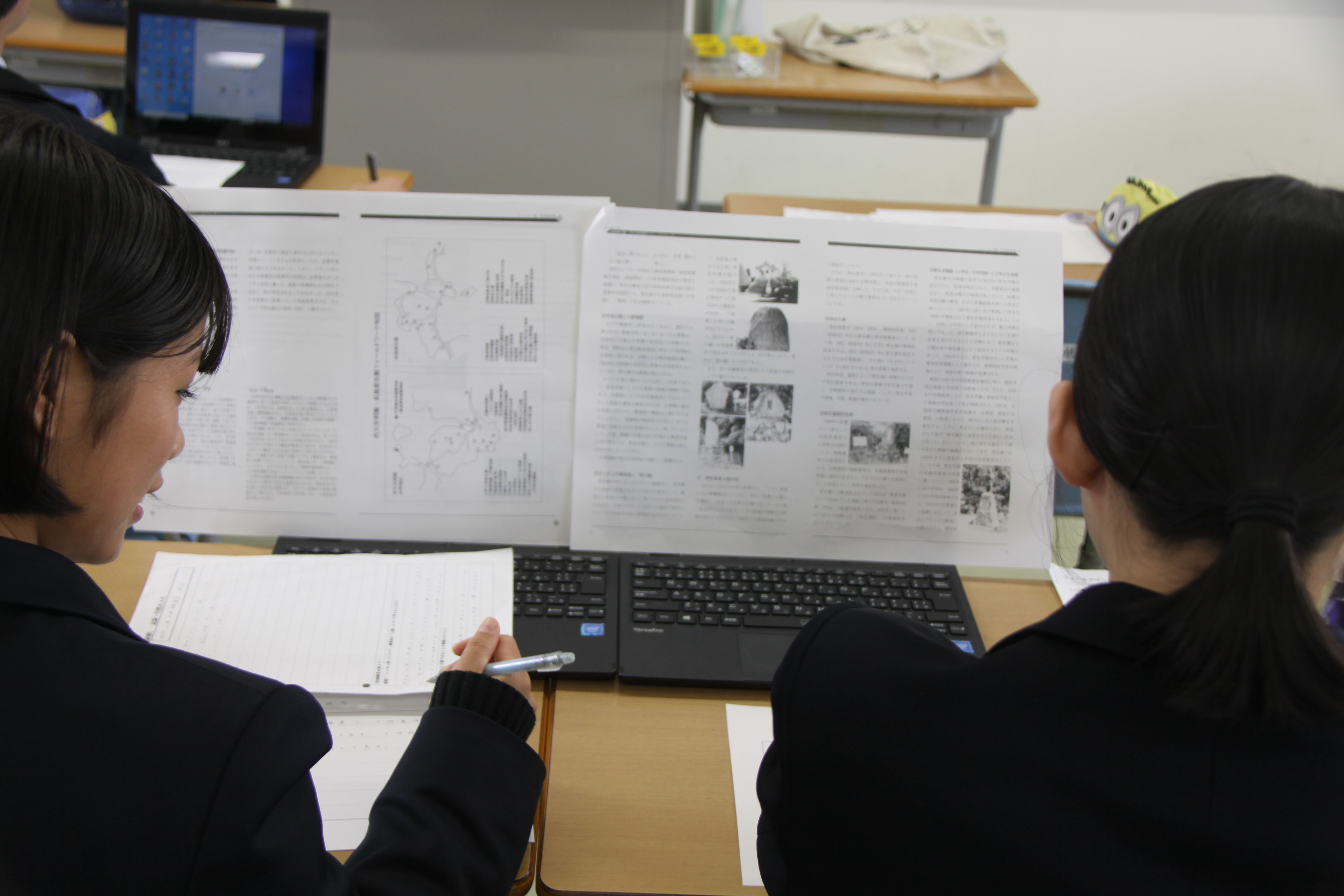


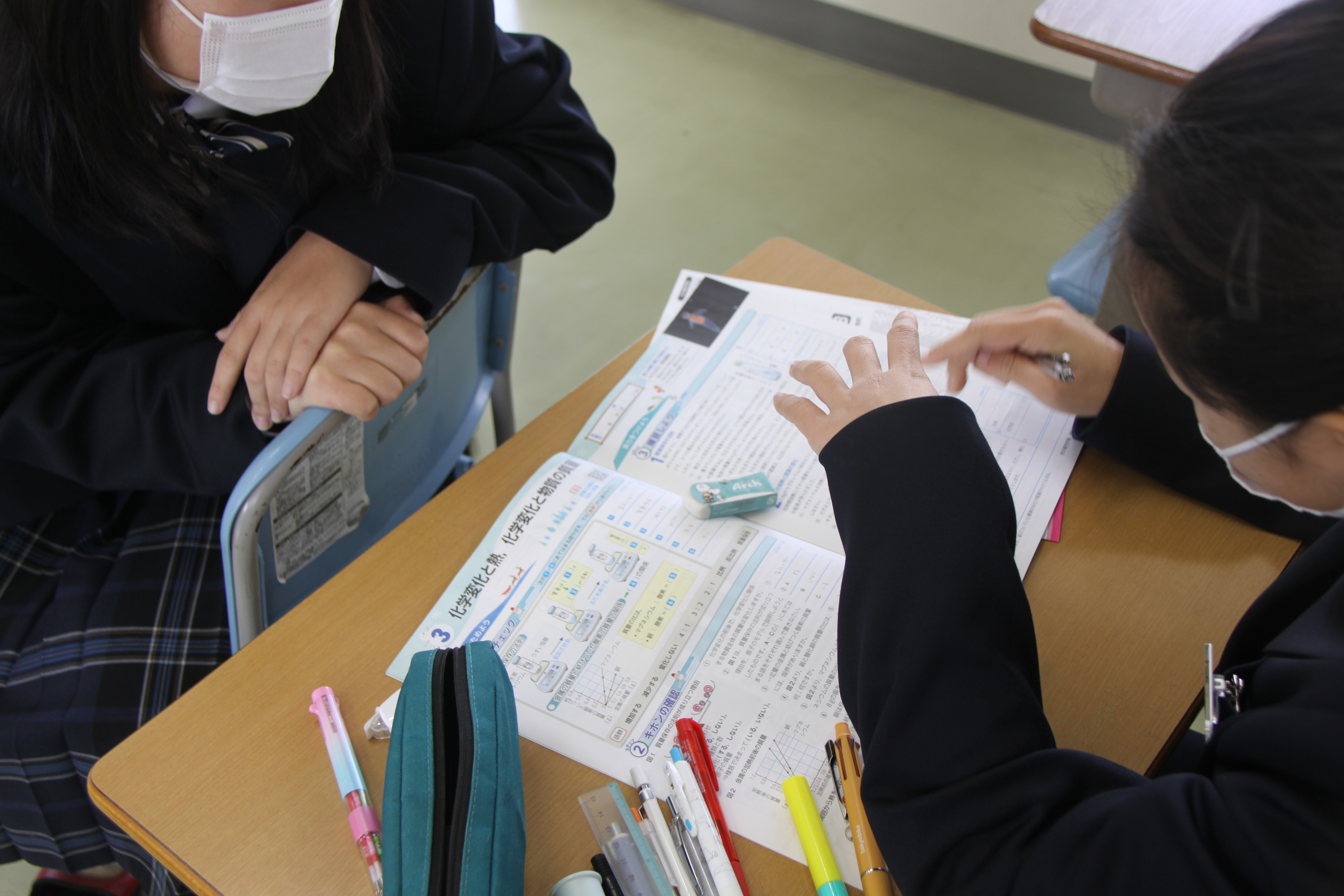
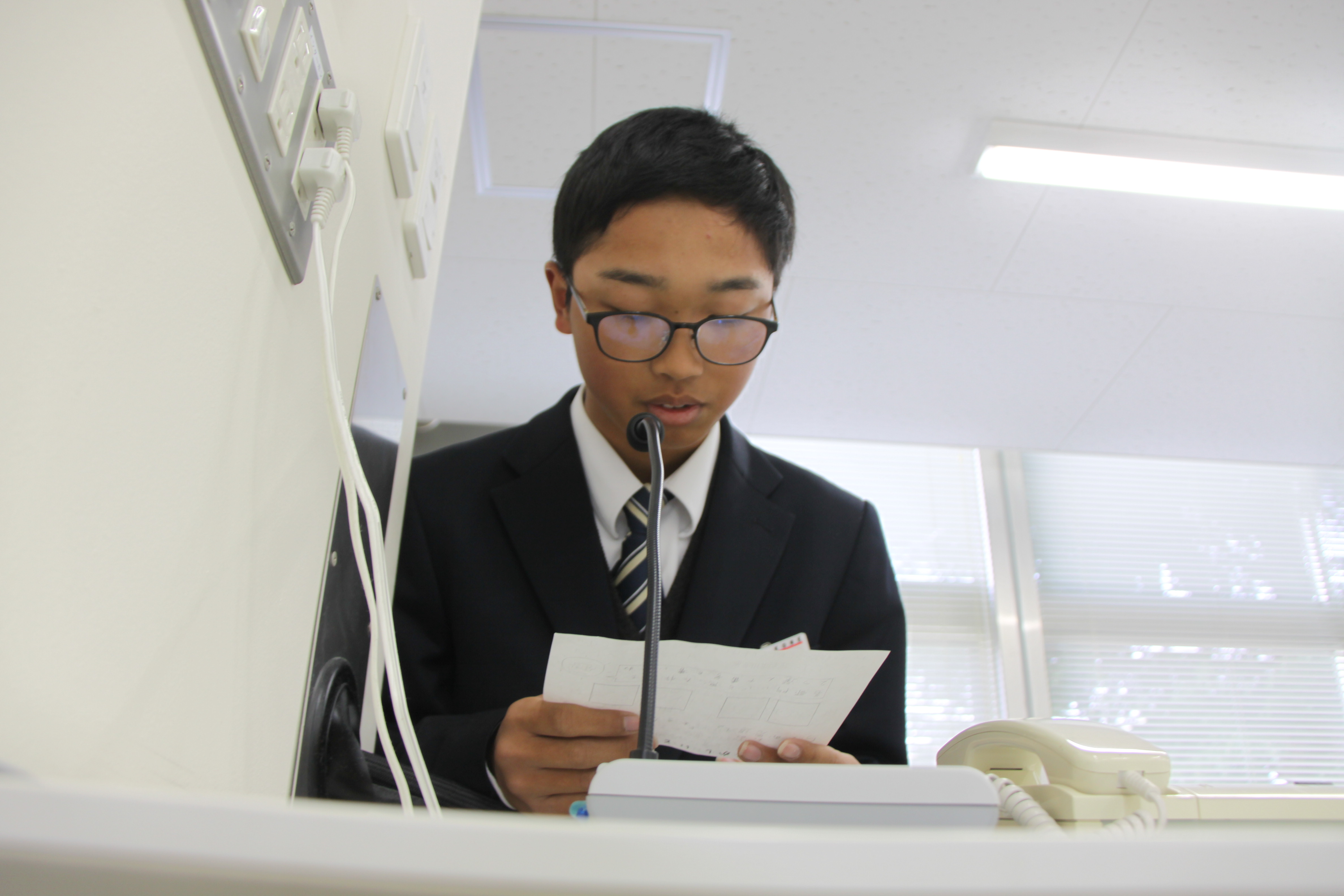
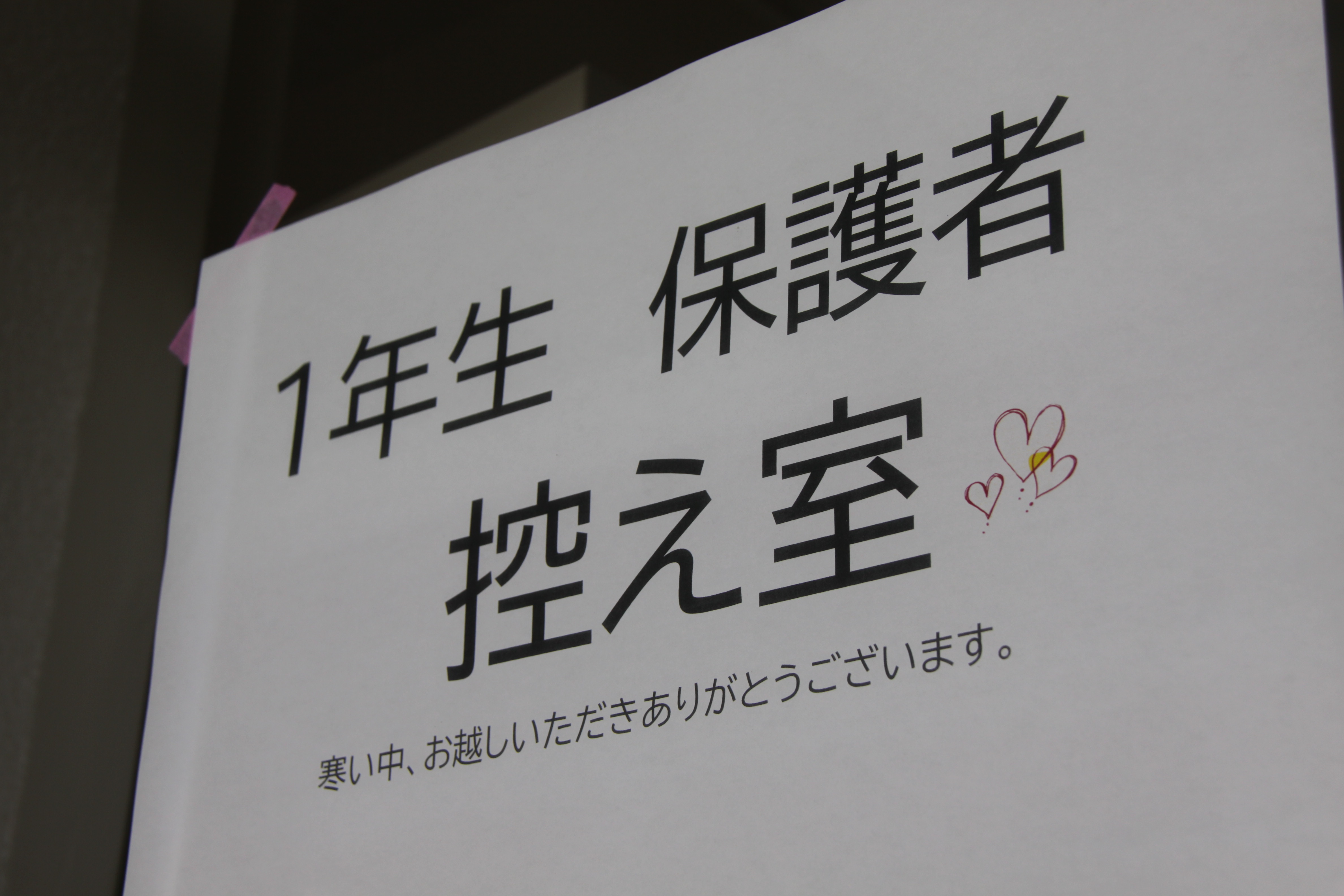
◎子どもを守るために「法律のルールを知ること」
今日からスタートする個別懇談で、法務省の資料を保護者の方に配布させていただきます。2023年6月に性犯罪についての法律が改正されました。お子さんと話し合ったり、ご家庭で話題にしてほしいと思います。
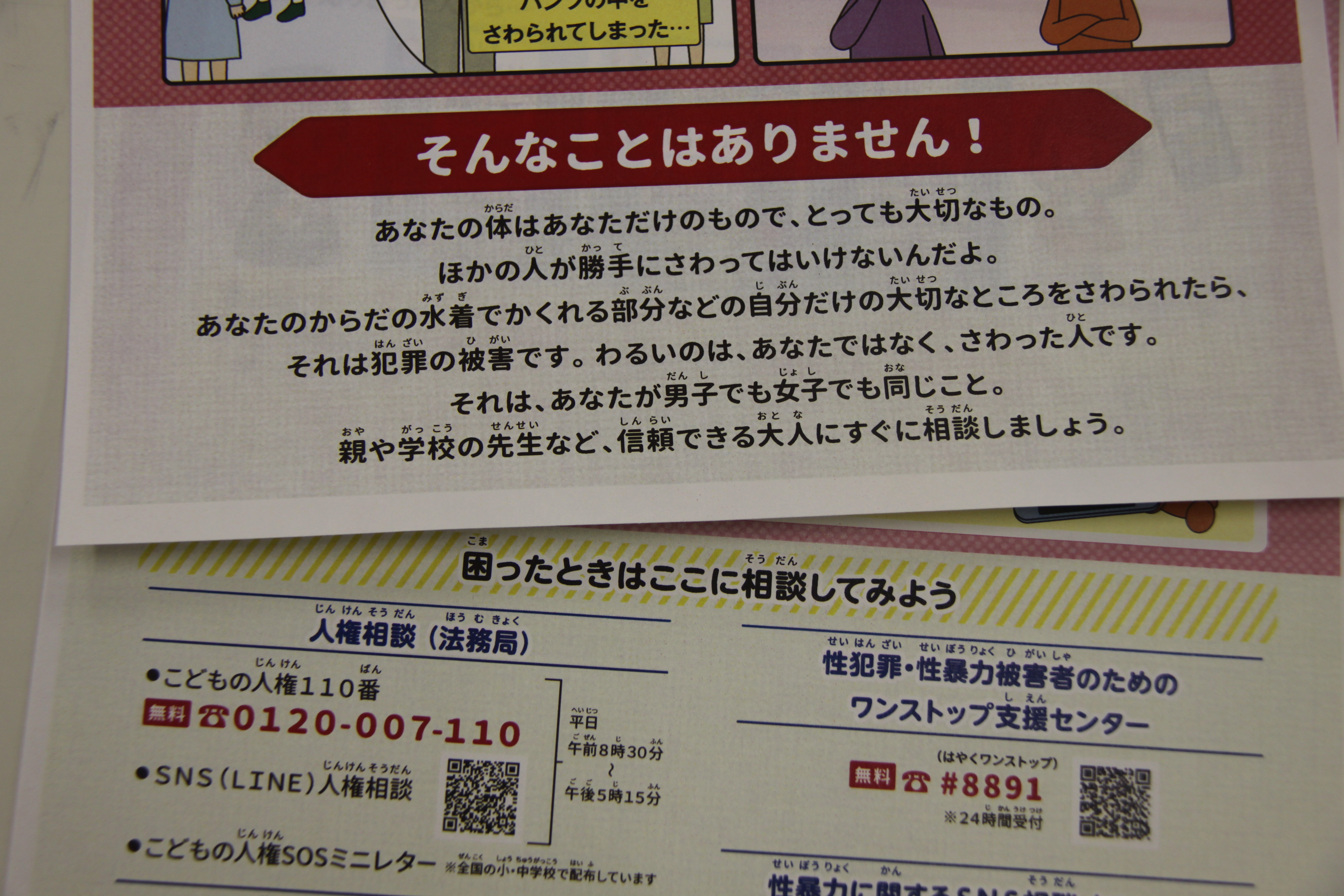
◎What a wonderful world(明日(14日)から個別懇談です)

The colors of the rainbow
虹の色は
So pretty in the sky
空を美しく彩っている
Are also on the faces of people going by
通り過ぎる人々の顔にも
虹の色が降り注いでる
I see friends shaking hands
友達同士が握手をしている
Saying‚ How do you do?
“ごきげんよう”って言いながらね
They’re really saying
心から言ってる
I love you
“君のことを愛してる”と
I hear babies cry
赤ん坊の泣き声が聞こえる
I watch them grow
彼らが大きくなるのを
見守るのさ
They’ll learn much more
彼らは沢山のことを学ぶだろう
Than I’ll never know
僕が知りえないこともね
And I think to myself
そして心の中で思うのさ
What a wonderful world
この世はなんて素晴らしいんだ
Yes‚ I think to myself
そう、僕は心の中で思うんだ
What a wonderful world
この世はなんて素晴らしいんだ
◎Power to the people‚right on (12/13)
環境委員会のよびかけによるボランティア活動!なんという参加者数だ!(*^▽^*)






Say we want a revolution We better get on right away Well you get on your feet And out on the street
◎ひな中の風~~
「ひとを大切にする社会」につながる学習Ⅱ(12/13)












◎たしかな進路保障をめざして(12/12)
日生中では、3年生の一人ひとりの進路実現のために、進路委員会や調査書作成委員会を開催し、全教職員で進路保障に取り組んでいます。この日は、成績や評価についての協議や、今後の進路事務についての確認をしました。


◎What a wonderful World
(今年ラストの英語教室12/12も楽しく・深く)
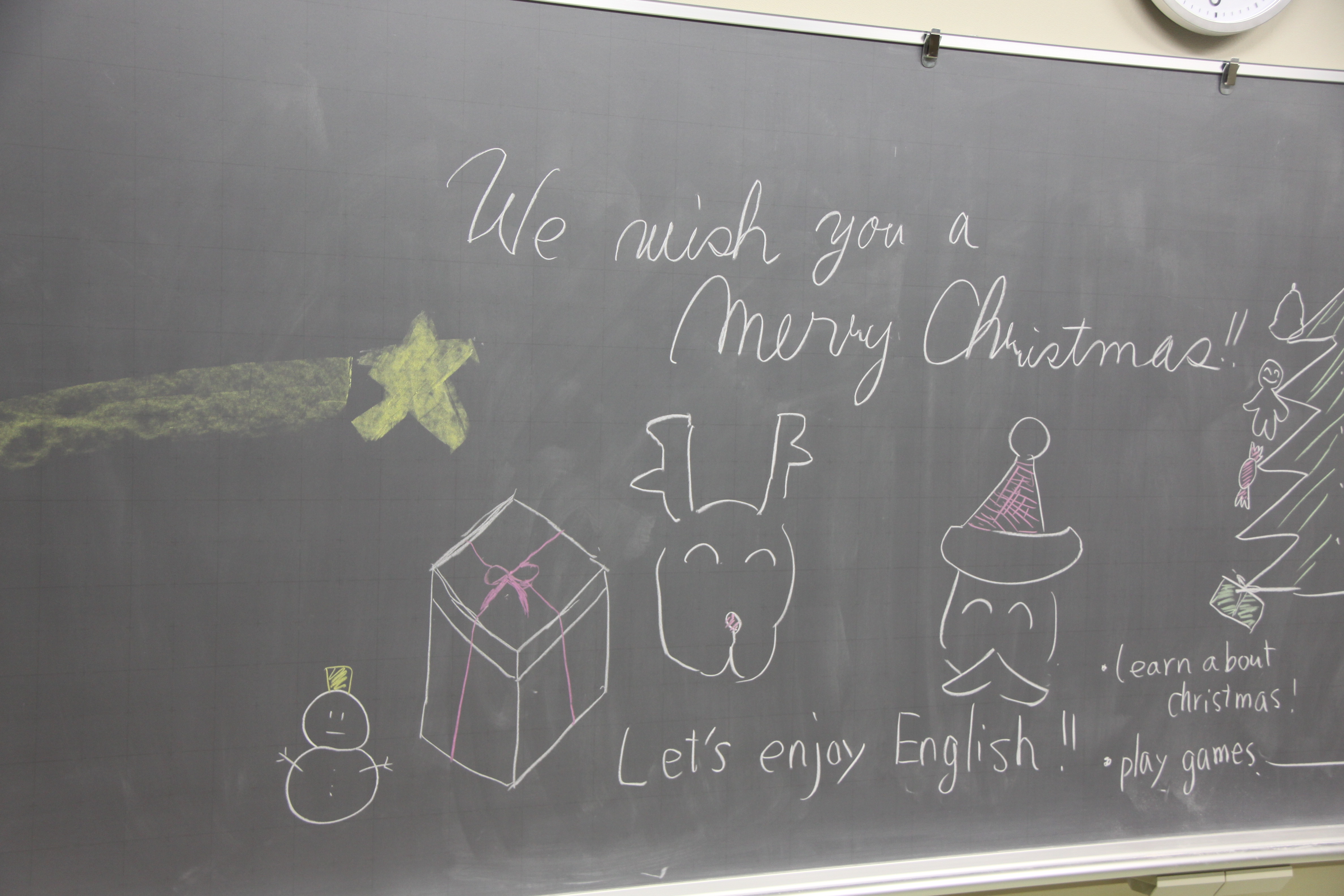
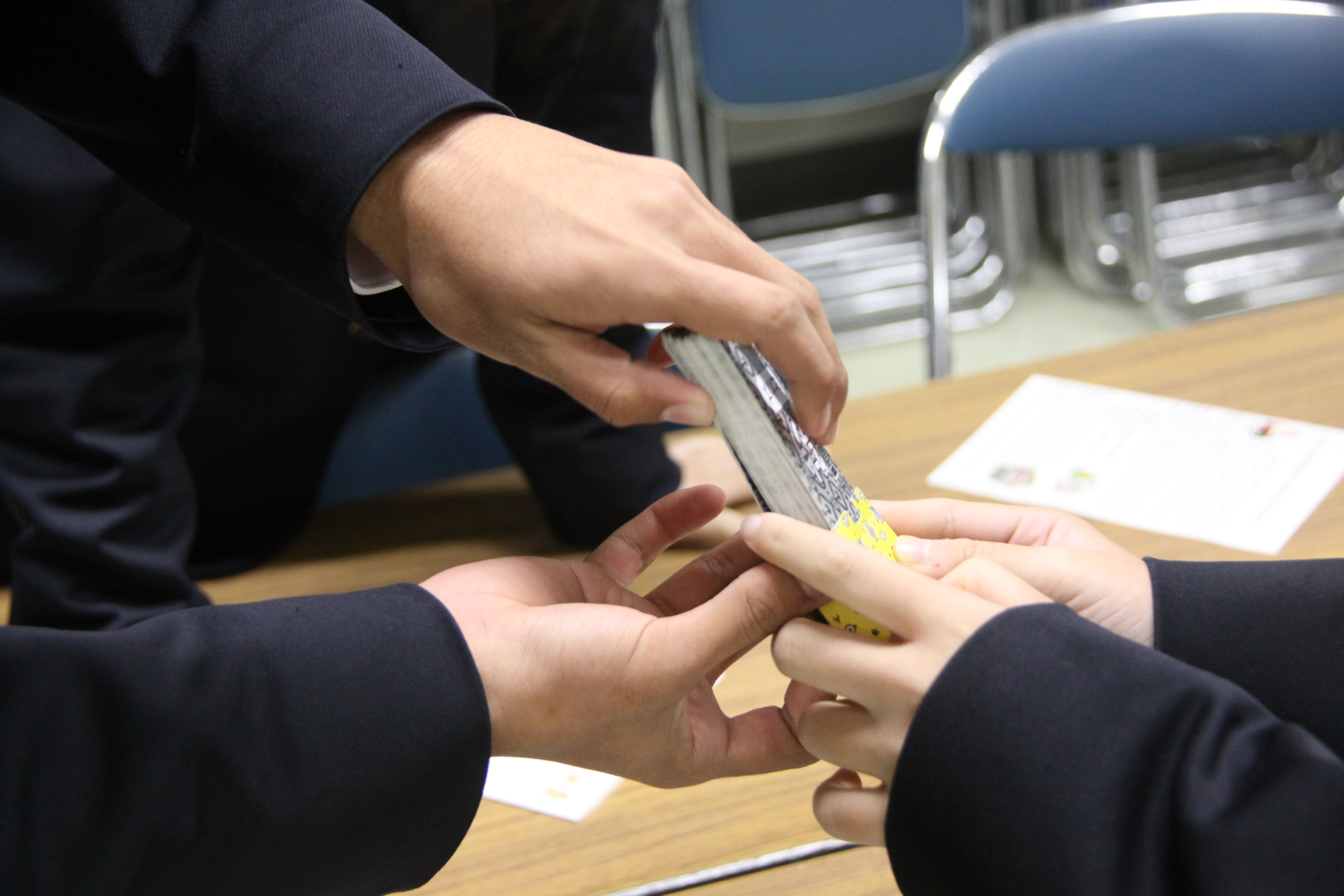
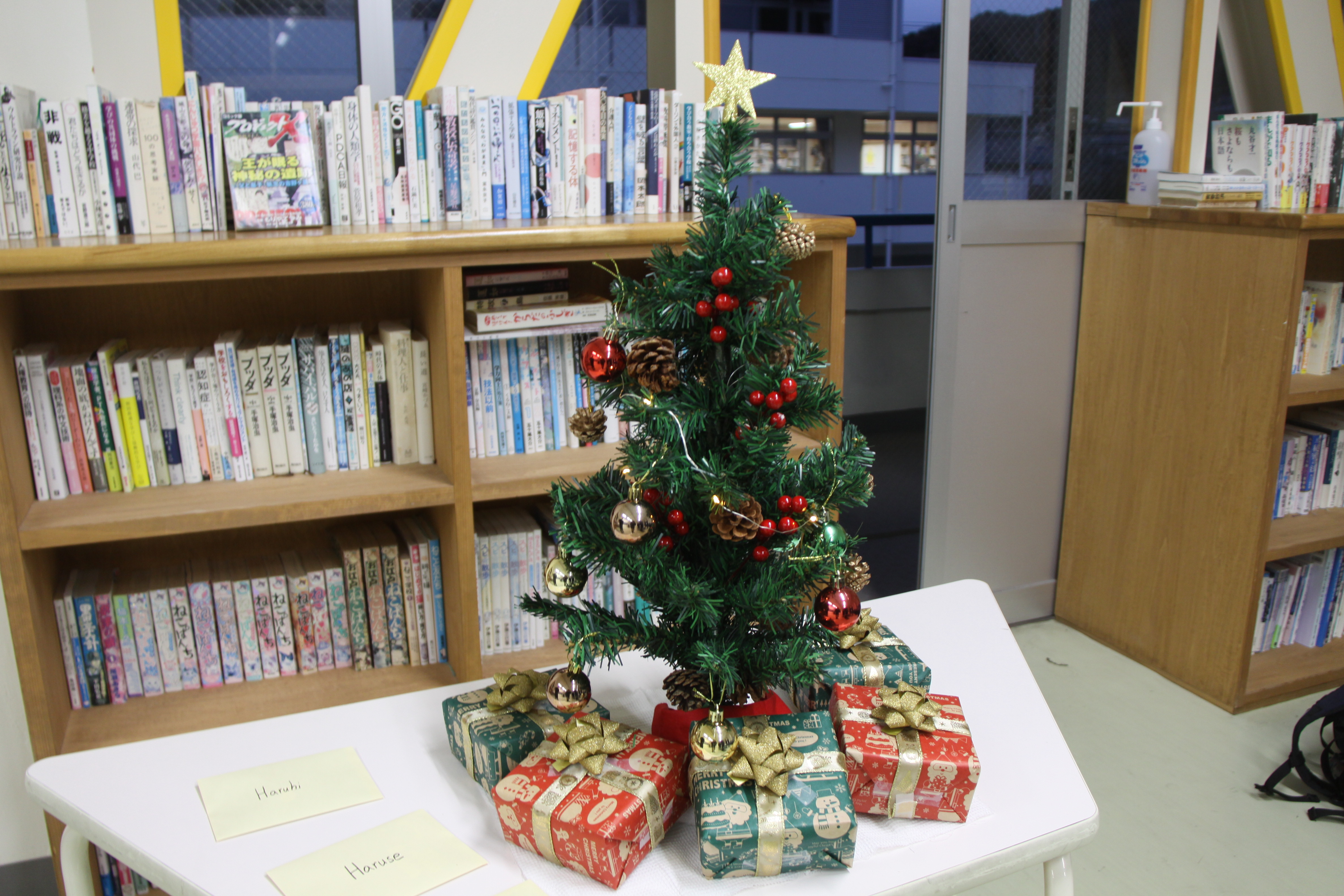

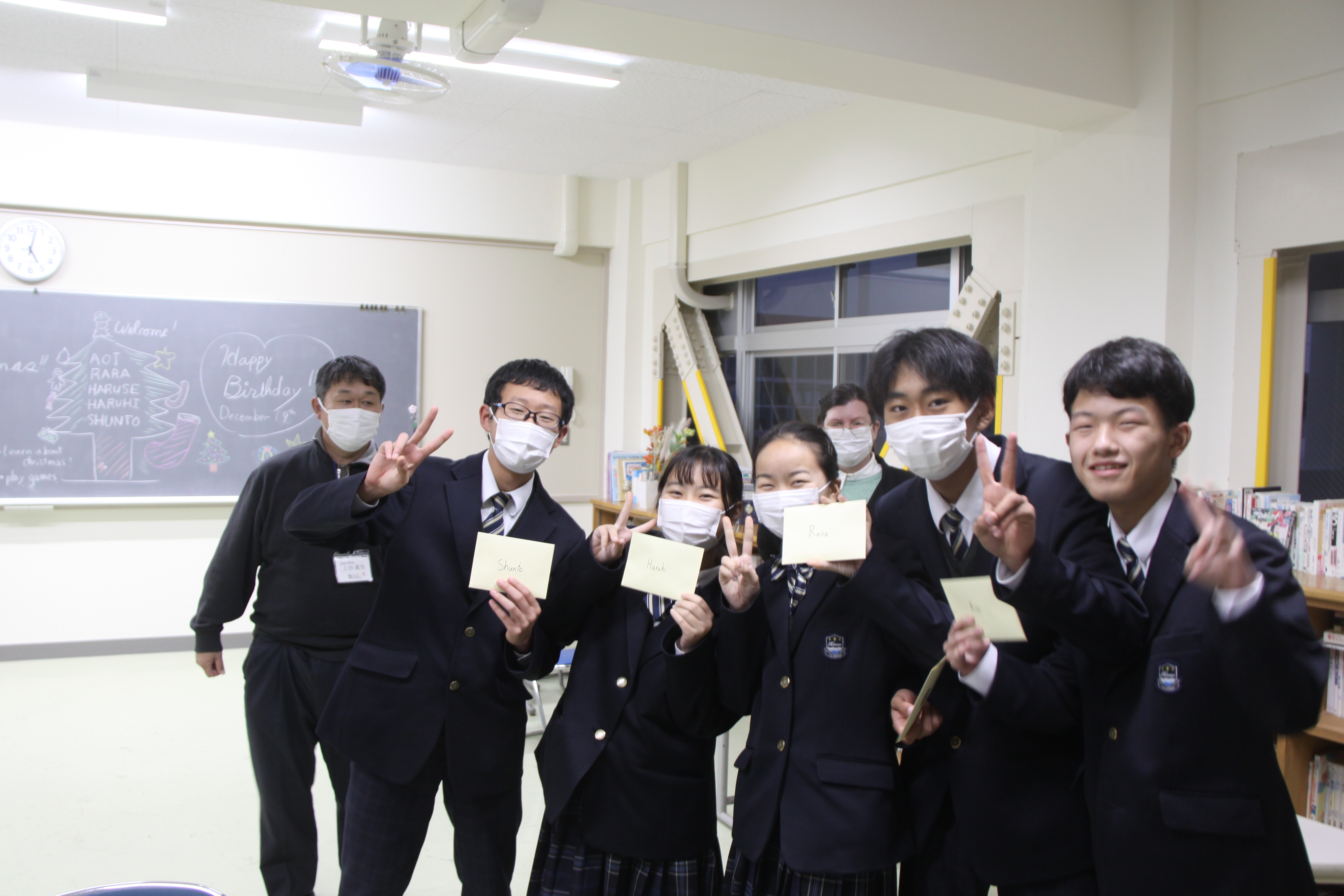
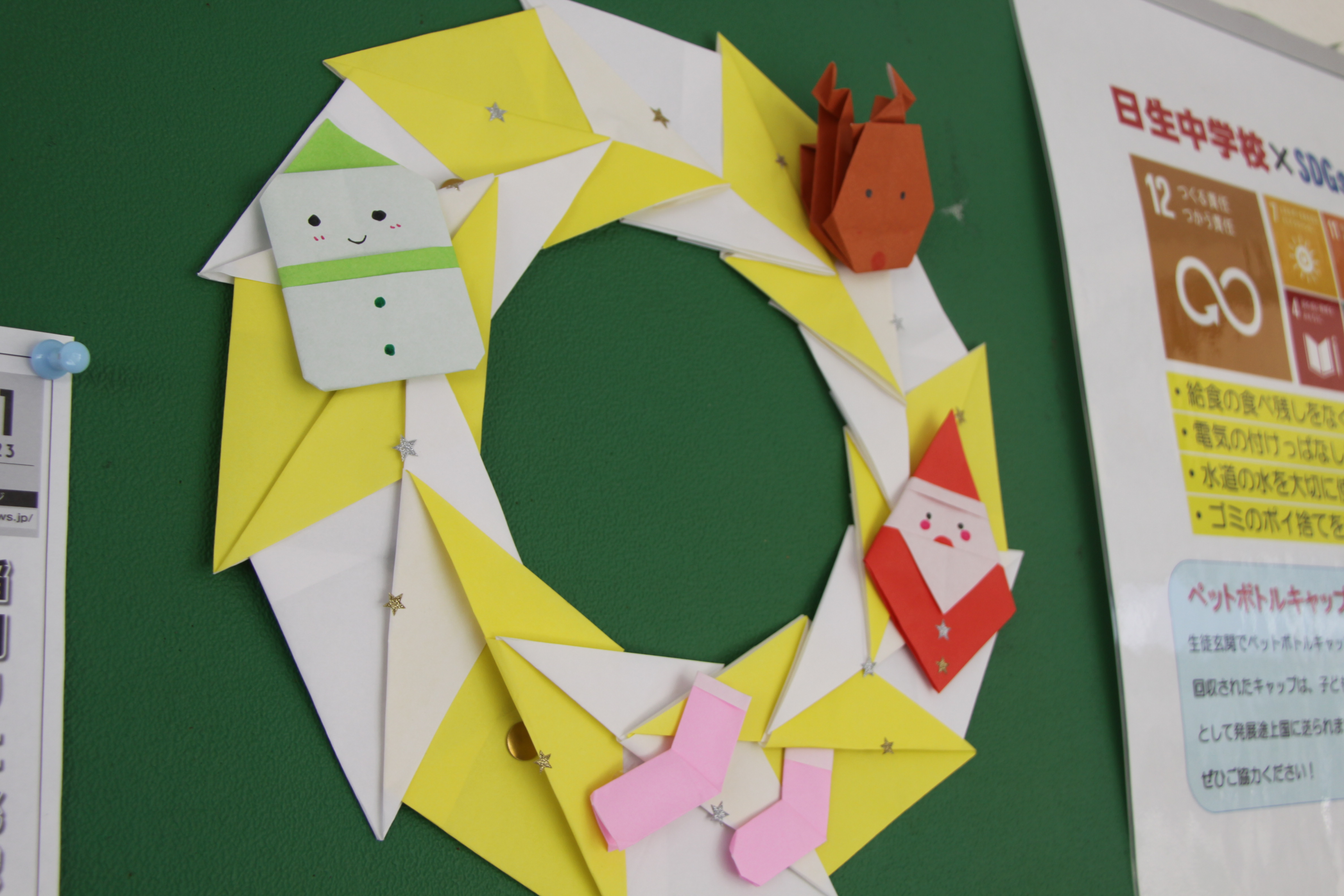
I see trees of green
緑の木々を
Red roses too
赤いバラを見ている
I see them bloom
花が咲いているよ
For me and you
僕と君のためにね
And I think to myself
僕は心の中で思う
What a wonderful world
この世はなんて素晴らしいんだ
I see skies of blue
青い空に浮かぶ
And clouds of white
白い雲を見てる
The bright blessed day
光り輝く祝福された日
The dark sacred night
神聖な真っ暗な夜
And I think to myself
僕は心の中で思う
What a wonderful world
この世はなんて素晴らしいんだ
◎私たちが、
〈いま〉、〈過去〉を〈未来〉につなげること(12/12)

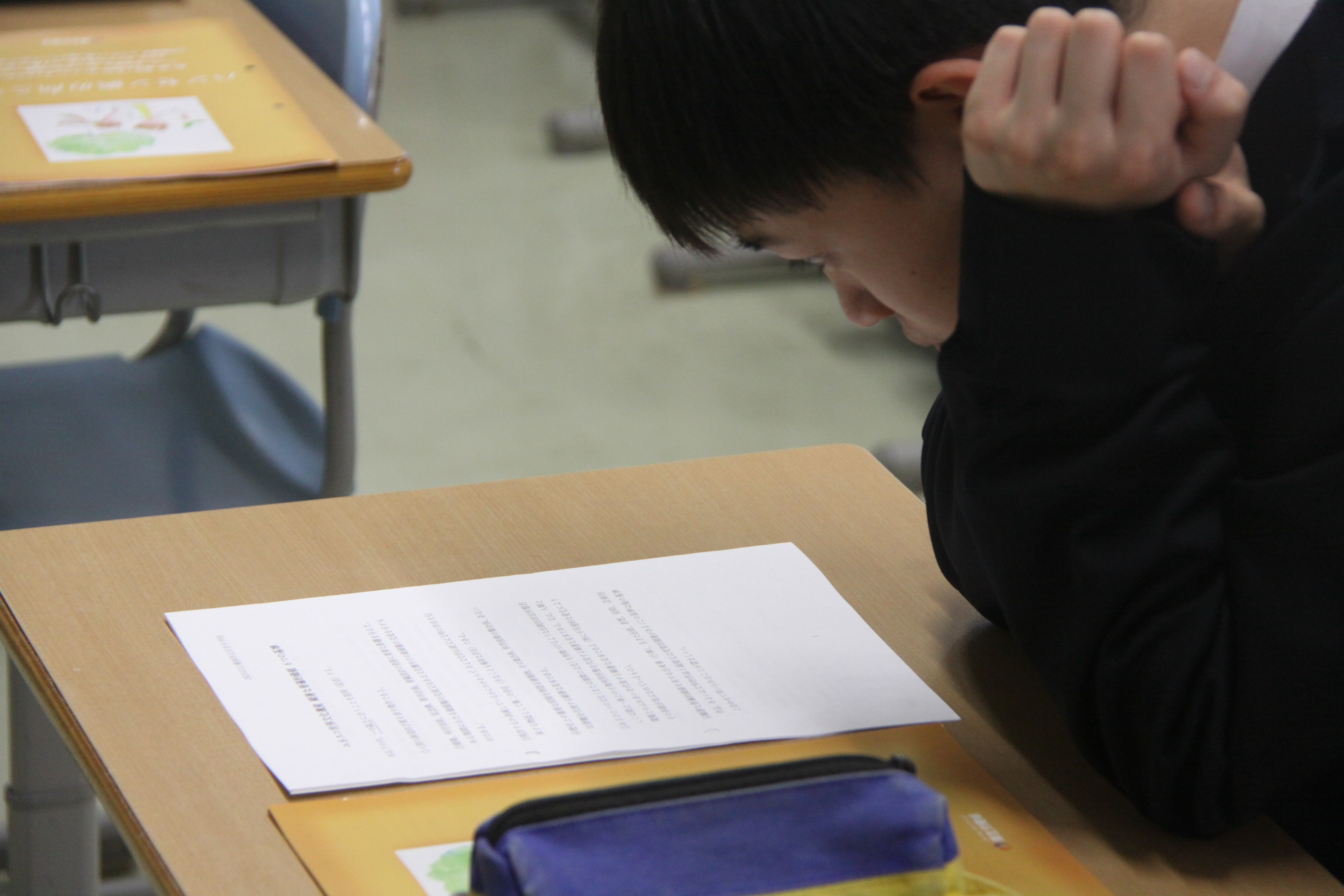
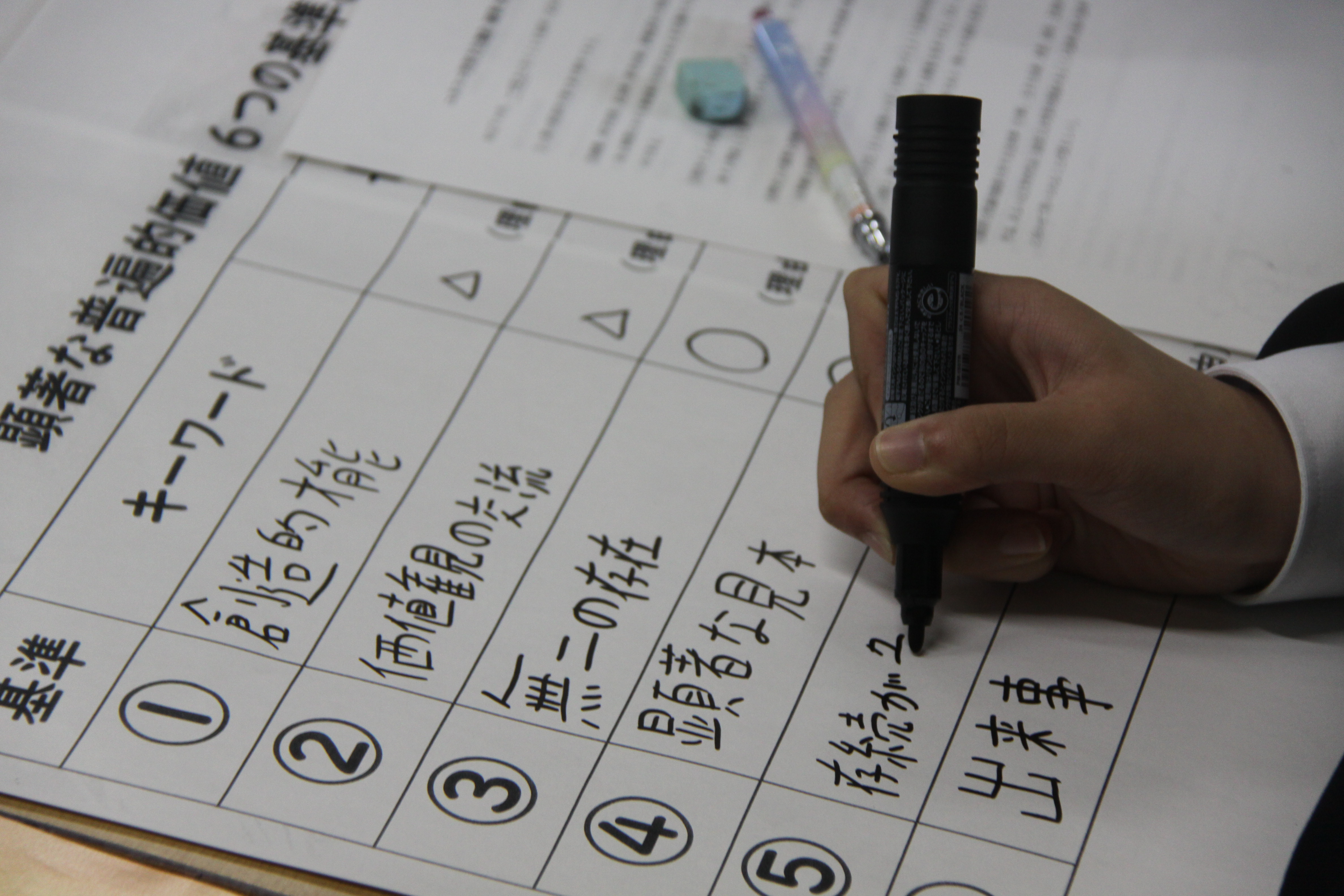

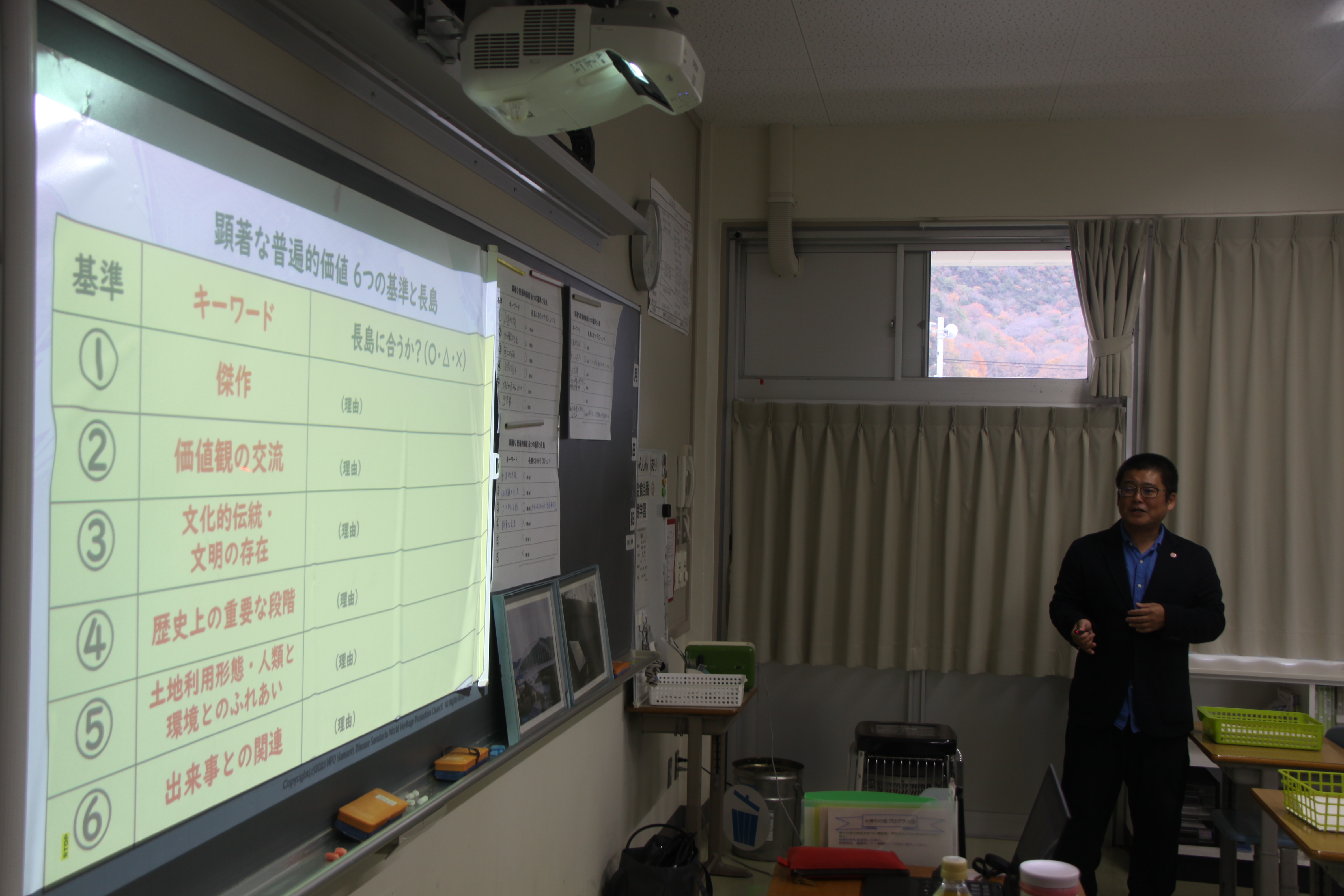

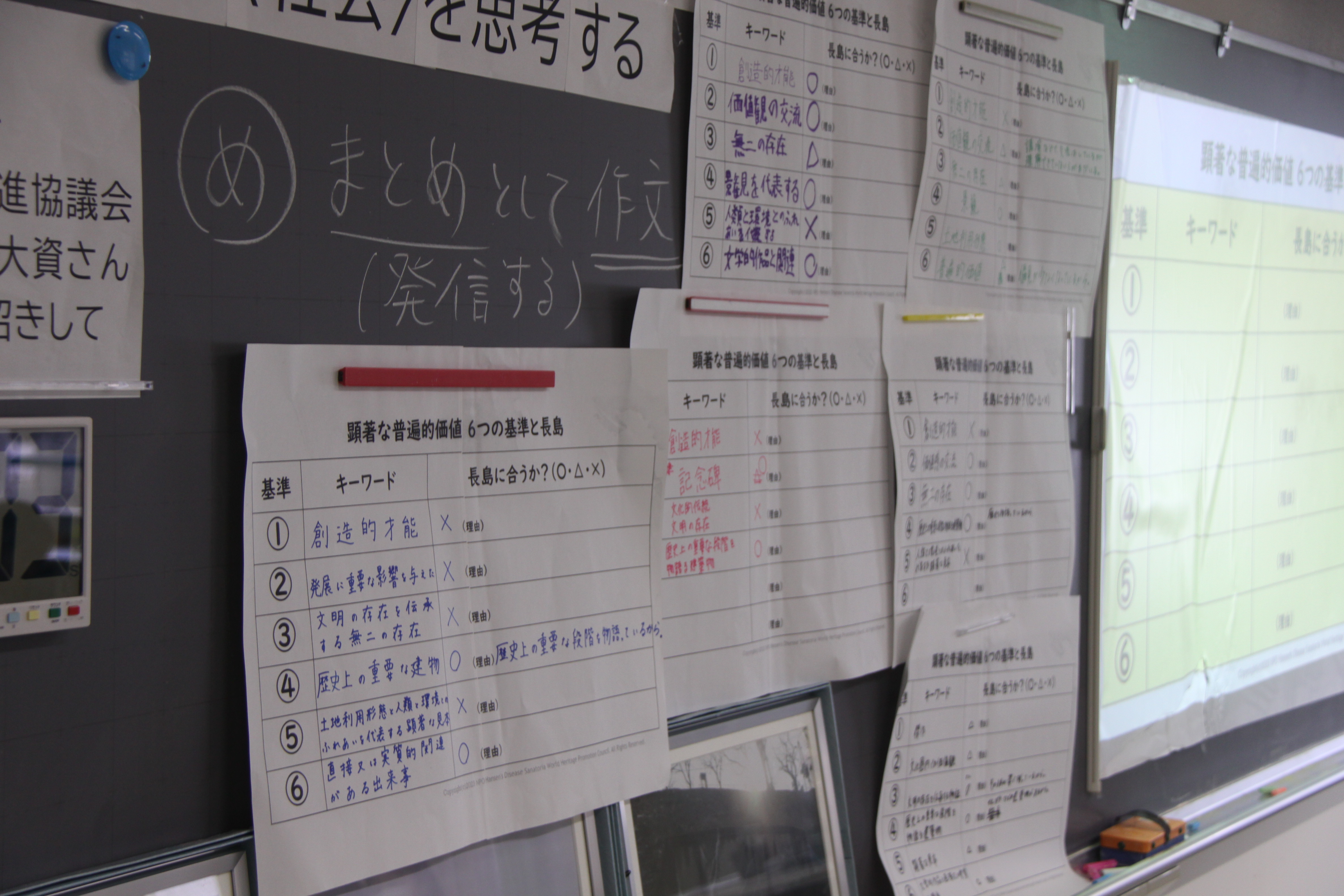
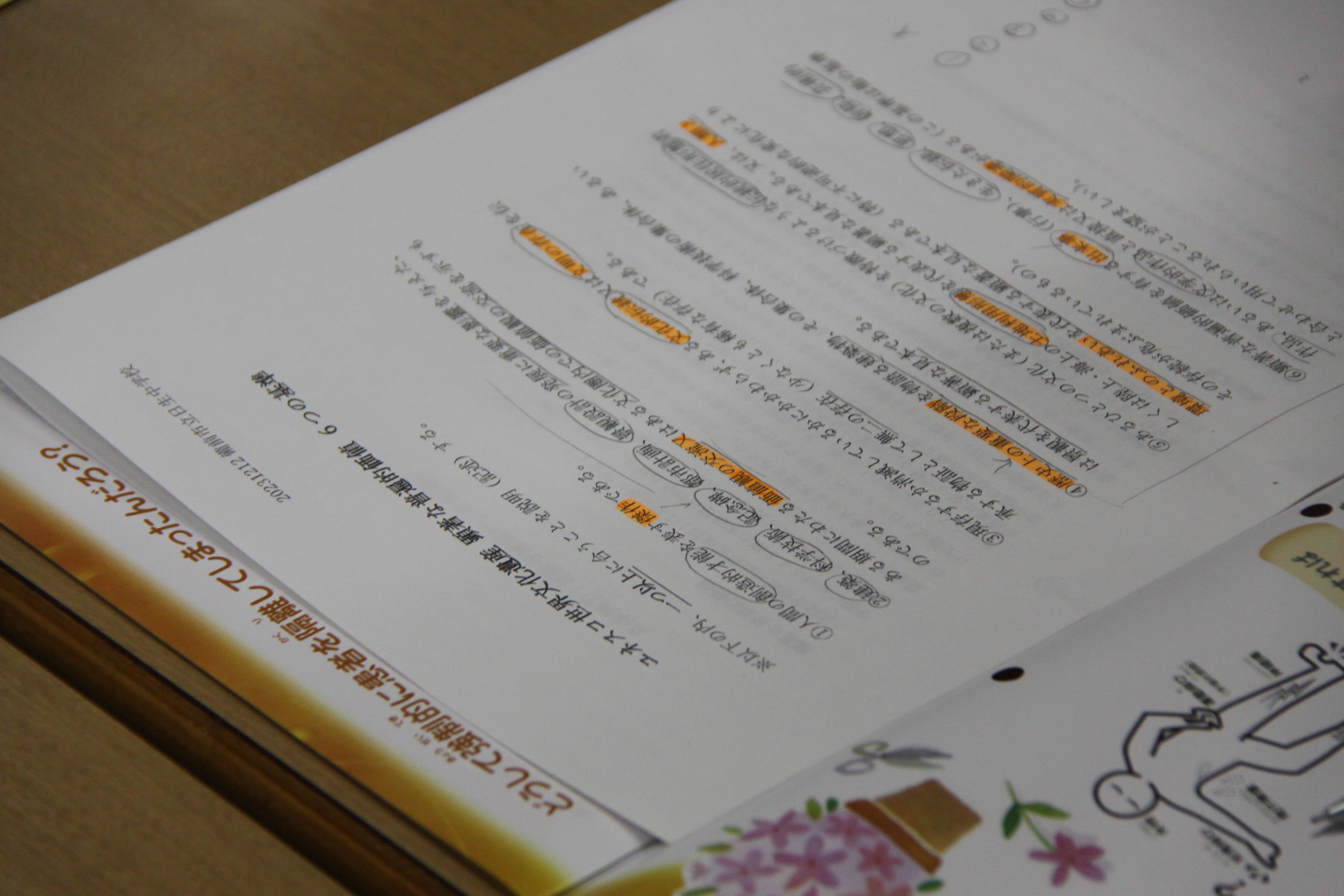
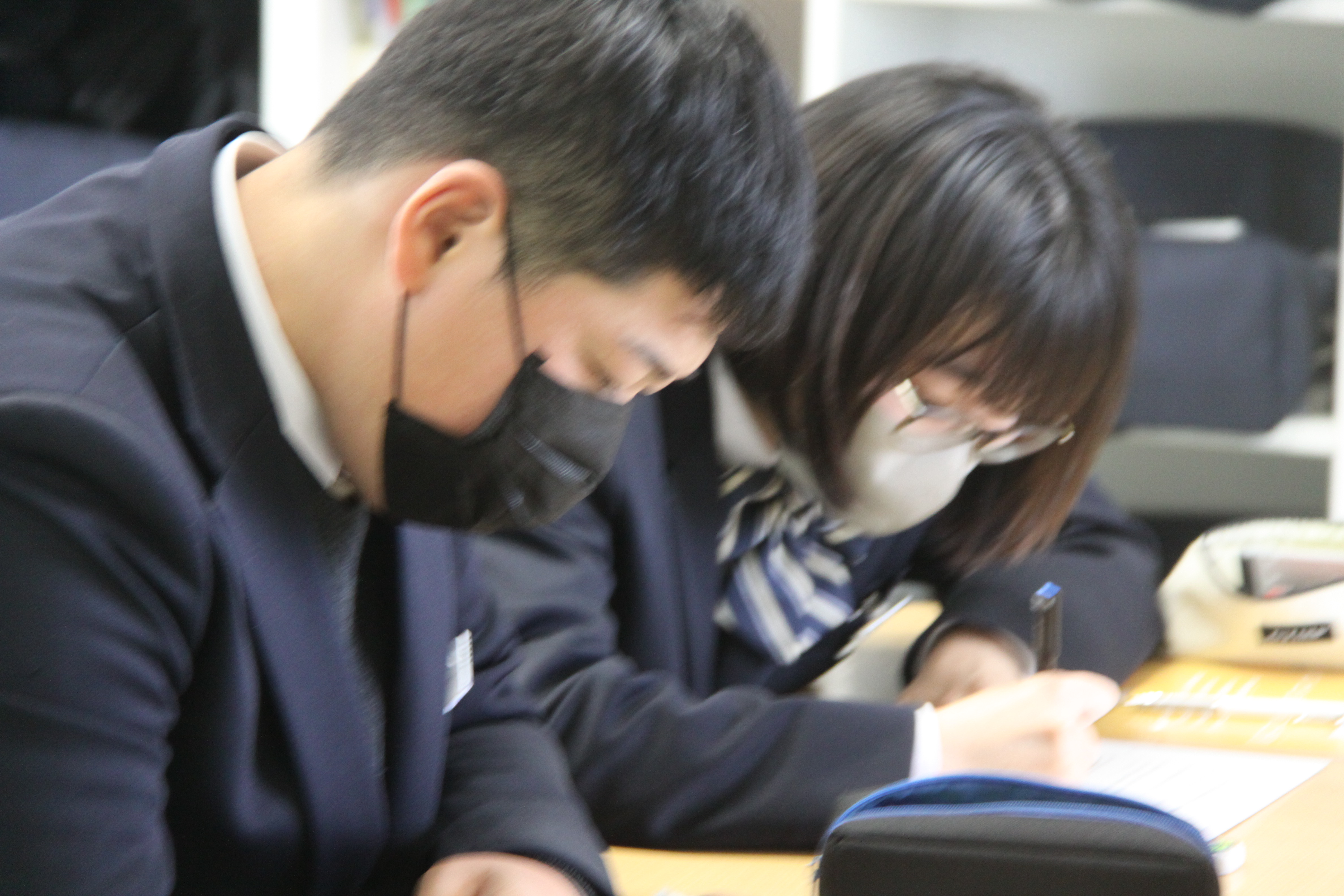
NPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会事務局長、釜井大資さんをエリアティチャーにお招きしました。授業では、ユネスコ世界文化遺産 顕著な普遍的価値 6つの基準について、ワークショップを中心に、長島がその基準が合うかを考え合い、学びを深めることができました。この後私たちは、地域学習のまとめのひとつとして、ハンセン病療養所の世界遺産登録申請時に必要となる「顕著な普遍的価値への言明(長島がどのように世界遺産の価値があるかについて作文)」にチャレンジします。
また、準備が遅くなっていますが、学習したことをもとにした「パネル展」にまとめ、を日生地域公民館をお借りして開催する予定です。ぜひ、私たちの〈学び〉の〈発信〉をご覧ください。
◆参考:NPOハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会のHPより一部紹介します。
○なぜこの課題に取り組むか
「未来につなげたい、大切な記憶」をモノで語り継ぐために
2001年「らい予防法違憲国家賠償訴訟」熊本地裁判決確定以降、ハンセン病問題への社会の関心は格段に高まりました。多くの方々がハンセン病療養所を訪れ、療養所内に存在する隔離の歴史を物語る歴史的建造物や資料に触れ、療養所入所者(元ハンセン病患者)の方々から直接、療養所内での過酷な生活や社会からの偏見・差別の体験を聞かれています。
しかしながら、ハンセン病療養所入所者の平均年齢は85歳を超え、近い将来、これらの歴史を直接的な体験者として証言できる方が存在しなくなることが予想されます。諸外国の中には元患者の子孫がこれらの歴史を語り継いでいる例がありますが、日本の隔離政策が療養所内で子どもを産み育てることを許さなかったため、このような第二世代・第三世代による歴史の承継は困難です。
-ハンセン病に対する偏見と差別を生み出した日本のハンセン病患者隔離政策と療養所の歴史を後世に正しく伝えたい、私たちの生きた証を残したい-
私たちはこのような国立療養所長島愛生園、邑久光明園(岡山県瀬戸内市)及び大島青松園(香川県高松市)入所者の方々の声を契機として、歴史的建造物や記録物というモノを通じてこれらの歴史を語り継ぐべく2018年1月に成立したNPO法人です。
○モノを残す意義
・歴史の証明を継承する
・モノに関わった、託された思いを伝承する
○具体的なモノ
・国策としてのハンセン病患者隔離政策の歴史
・療養所入所者の人間としての強さとレジリエンス(回復力)の証明
○モノの残し方
・ユネスコ世界文化遺産(建造物や土地が対象)
・ユネスコ世界の記憶(世界記憶遺産)(歴史的記録物が対象)
○モノを残す目的
・ハンセン病元患者の方々の真の名誉回復を図る
・継承されるモノを偏見と差別のない未来への礎(モニュメント)とする
ハンセン病に関するモノを世界遺産として継承し、世界中の人々が抱える様々な偏見・差別の解消につなげます。インクルーシブな未来を創造するために、忘れてはならない過去の教訓として。(詳細は同会のHPをぜひご覧ください)
◎多くの人に支えられて(12/11)

岡山県備前保健所東備支所、備前市保健福祉部保健課健康係さんが来校され、中学校卒業後の、支援やサポートを中心に、支援情報交換会を行いました。
ご参考に、厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトではひきこもりについて以下の内容がありました。
「様々な原因で長期間自宅などから出ず、自宅外での生活の場がない状態。特定の精神疾患を有するものとそうでないものがあり、社会問題化している。
厚生労働省の定義では、ひきこもりは単一の疾患や障害の概念ではなく、「さまざまな要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態」とされています。近年、ひきこもりの高齢化、長期化が鮮明になってきています。内閣府の調査によると、ひきこもりの数は15~39歳では推計54万1千人、40~64歳では推計61万3千人おり、7割以上が男性で、ひきこもりの期間は7年以上が半数を占めています。
ひきこもりには、統合失調症などの精神疾患や発達障害などにより周囲との摩擦が生じて引きこもる場合と、そういった疾患や障害などの生物学的な要因が原因とは考えにくい場合があります。後者は対人関係の問題などが引き金となり、社会参加が難しくなってしまったもので、「社会的ひきこもり」と呼ばれることもあります。
ひきこもりの人々の様相は多彩ですが、ひきこもりが長期化するのは、生物学的側面、心理的側面、社会的側面から複数の要因が混在しています。
厚生労働省では、「ひきこもり」を精神保健福祉の対象とし、平成15年に援助活動や福祉サービスの他NPOなど支援施設による様々な施策のための『「ひきこもり」対応ガイドライン』を策定しています。
さまざまなサポート機関とも連携・協働して、中学校では進路保障を進めていきます。心配なことや不安なことがあればいつでもご連絡・ご相談ください。72-1365(教頭)
◎おはよう おはよう (12/11)





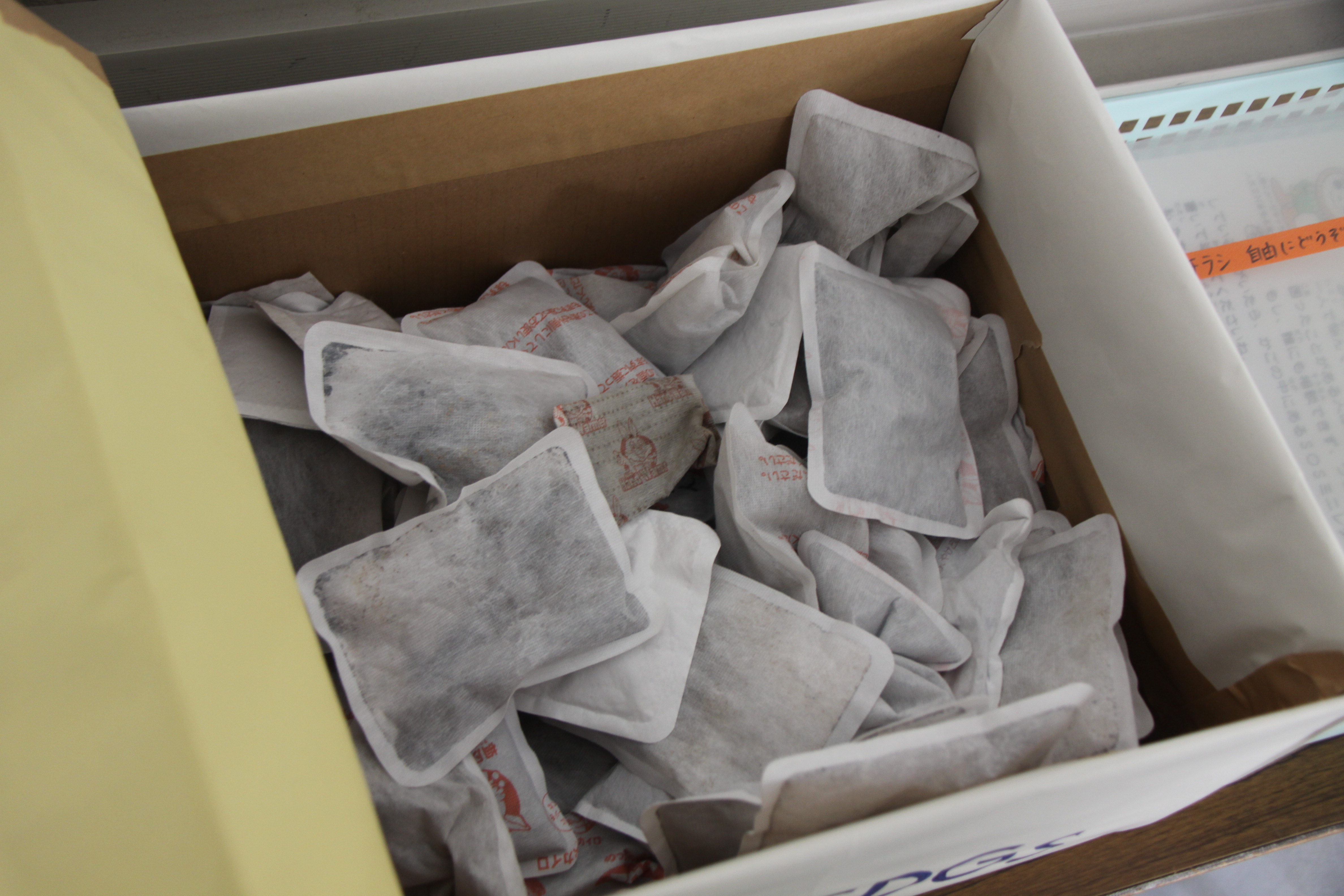

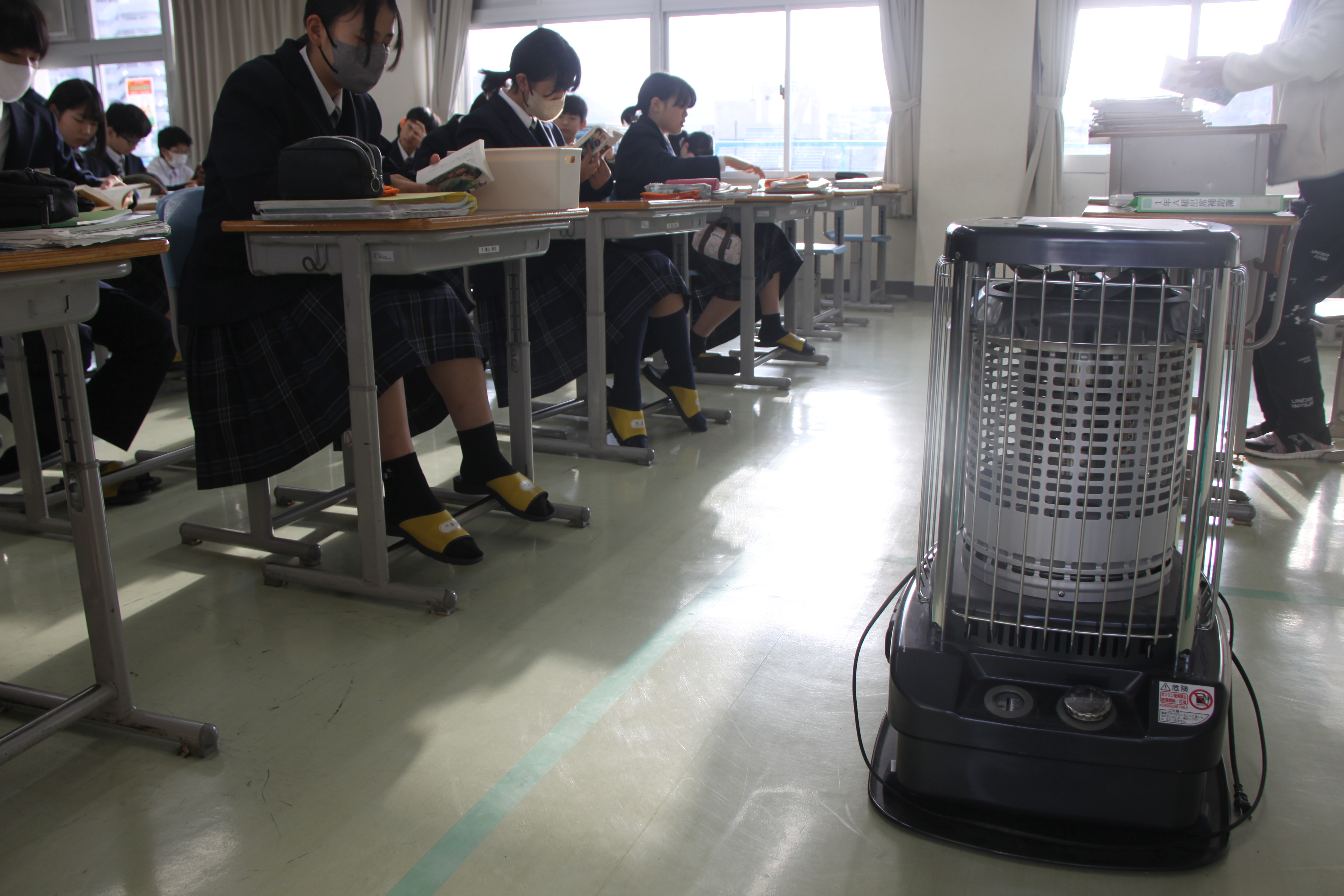

おはよう
こうしたろう
おひさま ぴかり
あさがきた!
すると のはらで
あさつゆ ぽちり
おがわが きらり
かげろう ゆらり
もぐらが もこり
とんぼが くるり
ことりは ひらり
そよかぜ そより
わたぐも ふわり
だから こうしは
うれしくて
にこり! 工藤直子 『のはらうた 「おはよう」』
◎3年生調理実習
たのしく おいしく ああたかく ありがとう(12/8)


◎12.8
〈お二人様ですかとピースで告げられてピースで返す世界が好きだ toron*〉

1941.12.8:太平洋戦争・なぜ開戦したの?
日中戦争が太平洋戦争へとつながり、日本人だけでおよそ310万人が亡くなった
太平洋戦争は、中国や東南アジアへ軍隊を進めた日本と、これに反対するアメリカ・イギリスなどの対立がきっかけで起きた戦争です。1941年12月8日(日本時間)、日本軍はイギリスの植民地であったマレー半島、アメリカ海軍の基地があるハワイの真珠湾を奇襲し、アジア・太平洋の広大な範囲を勢力圏に収めていきました。
この戦争を、当時の日本政府は「大東亜戦争」と呼びました(大東亜は、東アジアから東南アジアにかけての地域を指す)。戦後、日本を占領した連合国は「太平洋戦争」と呼び、その後、この名称が定着していきました。研究者の中には、中国や東南アジアも戦場になっていたことから、「アジア・太平洋戦争」が実態を反映した呼び方だと指摘する人もいます。
太平洋戦争へとつながった日中戦争の泥沼化
どのようにして太平洋戦争へと至ったのか、少し詳しく見ていきましょう。太平洋戦争開戦のちょうど10年前、日本軍は中国の東北部を占領し(満州事変)、その影響下のもと満州国を建国します。その後、中国側とたびたび武力衝突が起こり、1937年ついに中国との全面戦争へと発展しました。
こうした日本の動きに反対したのが、アメリカやイギリスです。両国は中国の国民政府に武器を供与するなどの支援を行い、日本軍の戦死者は増えていきました。日本政府や日本軍は、日中戦争(当時の呼び方は支那事変)が解決しないのは、中国を支えるアメリカ・イギリスのせいだと考えるようになりました。
第二次世界大戦がはじまり日米の対立が決定的に
その後、世界情勢が急変する中、事態はいっそう深刻化していきます。1939年、ヒトラー率いるドイツと、イギリス・フランスとの間で戦争が始まりました(第二次世界大戦)。日本はドイツ・イタリアと同盟を結び、東南アジアの資源を確保するためフランス領インドシナ北部(現在のベトナム)に軍を進めました(北部仏印進駐)。日独伊三国同盟と、イギリス・アメリカとの対立は決定的となりました。
アメリカの経済制裁 そして戦争へ
その後さらに日本がフランス領インドシナの南部にまで軍を進めると(南部仏印進駐)、アメリカは態度を硬化させます。日本に対しフランス領インドシナ、そして中国からの軍の撤退を強く要求し、石油やくず鉄の輸出を禁じる経済制裁を発動したのです。石油の7割をアメリカからの輸入に頼っていた日本にとっては、大変な衝撃でした。経済的な打撃と同時に、艦隊や軍用機が動かせなくなるため、軍事的にも大きな打撃を受けることになるからです。
海軍の作戦計画を担う軍令部のトップは、このまま石油がなくなれば艦隊を動かせなくなるとして「むしろこの際、打って出るのほかなし」と昭和天皇に伝えました。また、日中戦争では十数万の死者が出ていたことから、東條英機陸軍大臣(開戦時は総理大臣)は、「米国の主張にそのまま服したら支那事変の成果を壊滅するものだ」と、アメリカが求める中国からの撤兵に反対しました(参考:防衛庁防衛研修所『戦史叢書』)。
日本とアメリカは外交交渉をつづけていましたが、1941年11月、アメリカからさらに厳しい要求が出されると、日本側は交渉妥結の見込みはないと判断して、最終的に開戦を決定したのです。マレー半島上陸と真珠湾攻撃によって戦争を始めた日本軍は、石油を産出するオランダ領東インド(現在のインドネシア)を占領するなどして、“自給自足”の体制をつくりアメリカ・イギリスに対抗しようとしました。
勝利の見通しをもてないまま開戦した日本
戦争を始めた日本でしたが、アメリカ・イギリスの二大大国と戦って勝てるという明確な見通しをもっていませんでした。昭和天皇に「絶対に勝てるか」と問われた海軍軍令部のトップは「絶対とは申しかねます」と返答しています(参考:防衛庁防衛研修所『戦史叢書』)。多くの指導者たちは、日本軍が優勢を保っている間に、ドイツがイギリスに勝利すれば、有利な条件で講和できるだろう、と考えていたのです。
実際には、日本が戦端を開いたことにより、アメリカが全面的にヨーロッパ戦線にも参戦、1941年6月に始まっていたドイツとソビエト連邦の戦争でも、ソビエトが攻勢に転じるなど、日本のもくろみは崩れていきました。最終的には日中戦争も含めておよそ310万人の死者を出し、アメリカなどの連合国に降伏することになります。
多くの人が亡くなった戦争を避けることはできなかったのか。今にも通じる重い問いかけです。(NHK戦争を伝えるミュージアムより)
◎『未来の選択』佐藤久恵さんをお招きして(12・7)

「学習の振り返り」から一部を紹介します。
○体の成長について、正しく学び、自分の未来についてよく考え、健康で生活していきたいと思った。
○自分と相手の人生を守るために、避妊するときはしっかり話をする。子どものためにもお酒やたばこはしないようにしたいと思った。
○食生活をしっかりしたい。月経が2ヶ月とまっていた関係で、母親にとても心配をかけてしまった。自分自身もとても不安になっていたので、これからは栄養管理に気をつけたい。
○パートナーの身体のことについて深く知ることだ。わからないことは調べたり、相談していきたい。
○多様な「性」と、心の違いをしっかり理解して、関わり合えるようにしたいと思った。
○相談に産婦人科に行こうと思った。もちろん、パートナーと一緒に相談に。
○過度なダイエットをせず、健康な体をつくろうと思う。
◎2023人権週間にあたって~歩み新たに日に生せば~

(1)1948年12月10日
フランスのパリで開かれた国際連合総会において、第二次世界大戦の悲惨な結果を反省し、人権尊重が世界における自由・正義・平和の基礎であるとの『世界人権宣言』が採択されました。この宣言は「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」という人間の尊さを基本に、人間らしい暮らしをしていくための権利を宣言しています。
1950年の第5回国連総会で、毎年12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」として世界中で記念行事を行うことが決議されました。それを記念して、12月10日に至る1週間(12月4日から12月10日まで)が人権週間となっています。
日生中学校でもこの時期を中心に、「いじめや他人を傷つける言動がないか。友だちとともに、自分らしい生活をおくることができているか。」について、人権テーマを基に学習していく中で、あらためて考えることができました。
1年生は、備前市自立支援協議会の塚本さん・松下さん、小寺スクールソーシャルワーカーをお招きして、自分の特性を理解すると同時に、「クラスで暮らす」仲間をわかり合う学習に取り組みました。2年生は、職場体験学習の取組に重ねて、NPO法人きずなの川元さんと小坂さんをお招きして、「ホームレス問題」について学び、勤労観や福祉、社会のありようについて深く考えることができました。3年生は、ハンセン病回復者である金泰九さんの生き方や、長島愛生園フィールドワークから、「自分たちが生きるこれからの社会をどのように創っていくか」について探求しています。12日には、NPO法人ハンセン病世界遺産登録推進協議会の釜井事務局長を授業にお招きする予定です。
12月4日は、日生中人権集会を開催し、各学年ごとに取り組んできたことについて報告しました。
(2)あらためて大切にしたいこと。「いじめ」は人権侵害
ある友達と口をきかない、無視する、一緒に遊ばない、筆箱をかくす、机に落書きをする、カバンをかくす、などという「いじめ」の話は、テレビやインターネットで、残念ながら今も聞きます。
「いじめ」をする人たちが言う理由として「あいつはうざい」とか「背が低い」「女のようだ」「うっとうしい」「どんくさい」など聞くにたえない理由をあげるのです。
学校のなかまが、動作が遅かろうが丸顔であろうが、それはその人の「個性」・「ちがい」なのです。個性に干渉して、自分に合わせようとしたり、いじめたりすることは、なかまの〈人権〉を侵すことなのです。いじめるほうが、わがままで自分勝手で他人の人権がどれほど大切なものであるのかがわかっていないのです。「いじめ」は許すことのできない人権侵害の事件なのです。
(3)クラスの中の人権侵害
私たちの身近な人権とはどんなものがあるかな。
ひとには個性があるね。育ってきた家庭のちがい、男・女、LGBTQ+、生年月日、顔、身体がそれぞれ違うように、ひとは、それぞれ違った性格をもっている。考え方も感じ方もちがってくるね。すばやい動きのひともいれば、ゆっくりなひともいるし、ほがらかで友達とよく話ができるひともあれば、その反対で無口なひともいるね。それらのちがったひとたちの集まっているのが私たちの「社会」というわけ。それは学校でもクラスの中でも同じだね。
大切なことはそれら他の人・なかまの「ちがい」を認め合うことじゃないかな。ちがった性格やちがった生き方をするひとが、自分らしく、みんなと共に遊んだり、話し合ったり、喜びや悲しみを分かち合ってたりしていけたら。このことを〈人としての自由権〉と言うんだよ。もちろん、自由ということは、自分がわがままで勝手なこととはちがうよ。みんながそれぞれの自由を尊重しあうと同時に、学校やクラスではみんなが安心して遊んだり、勉強したりするために最低のきまりや規則が必要になってくるね。きまりや規則というのはみんなの自由を守るためにあるといえるんじゃないかな。
ひととしての自由権を守るためには、お互いの生き方やちがいを認めるだけでなく、積極的に尊重していく〈個人の尊厳〉を守るという強いものが必要だね。
みんなは安心して学校に登校し、自分の進路の実現に向かって学習できるという〈生存権〉をもっています。また一人ひとりがもっている「勉強する権利」を〈学習権〉と言うんだ。授業中に自分勝手にさわいだり、友達の発言をひやかしたり、ものを投げたりするのは、みんなの学習権を侵害することなんだ。
(4)個人の尊厳を守る
個人の尊厳を守るということは、自分を大切にするのと同じように、他人を大切にし、人を傷つけないことだね。
ひとの性格や行動、顔や身体のかたち、学校の成績などによって差別してはいけないね。もちろんその人の家の職業や出身や宗教、考え方、男女の性別、民族などによって人を差別してはいけないのはわかるよね。就職や結婚の際にそのことで差別することは許されないね。
以上のことをまとめていうと、『人間が人間らしく生きていくうえで、欠かすことのできない自由や権利のことを〈基本的人権〉というんだ。基本的人権が大事で、他のひとの人権を侵す差別がいけないことだということは、君たちはわかっているはず。
でも
「差別がなくなればいい」と考えているだけでは見当違いです。いくら差別が悪いことだとわかっていても、それだけで「差別をなくす力」にはならないからです。
みんなが安心して登校し、静かにゆったりした気持ちで勉強し、遊び、そしてスポーツや生徒会活動にうちこめるようにみんなで努力し合うことが、身近な人権尊重の一歩となります。
(5)江戸時代の末(1855)にあった『渋染一揆』に学ぶ
渋染一揆を成功させた人々のうごきを調べてみると、私たちが差別をなくし、共に生きる社会(クラス)をつくるための方法を知ることができます。簡単にまとめていますが、とても大事な視点です。人権週間にあたってみなさんに紹介します。
①差別がここに、こんなかたちであるという事実に気がつくこと!(高い人権感覚)
②その差別はどれほど私たちを苦しめているか、怒りをおぼえること!(相手の立場に立って、そのつらい気持ちをかんがえてみること)(正しい人権意識)
③その差別のなりたちや、しくみがどうなっているかを学び、差別をなくする道筋を明らかにすること!(仲間としっかり語り合う 冷静に状況を分析する)
④差別をなくするために、なかまと共に、どういう働きかけをしたらよいか、差別をなくする力(行動力)を身につけること!(みんなで正しく行動する うごかす(すべ)を整える)
3年生が取り組んでいる「ハンセン病問題学習」の中で出会った、金泰九(キムテグ)さんは、私たちに〈正しく知り 正しく行動する〉ことの大切さをいつも言われていました。人権週間を機に、よりよいクラス・個性豊かな、なかま・ともだちと共生する人権感覚・行動力をみがきましょう。
◎確かな学びを大切にする授業(12/7:3年理科)

参考:日周運動(にっしゅううんどう、英語: diurnal motion)とは、地球の自転によって、天球上の恒星やその他の天体が毎日地球の周りを回るように見える見かけの運動のことである。天体の日周運動は、天の北極と天の南極を結ぶ軸の周りを回るように見える。
地球が地軸の周りを1回自転するのには23時間56分4.09秒(1恒星日)かかるため、日周運動の周期はこの自転周期と等しい。
なお、地球の公転によって、天体が1年の周期で東から西へ回るように見える見かけの運動を年周運動という。年周視差および年周光行差は年周運動の一種である。
〈運動の方向〉
天の北極を中心とする、北半球での周極星の回転
天体の日周運動の方向は、北半球から観測した場合には以下のようになる。
・北の空を見た場合、天の北極より低い位置の天体は向かって左から右へ、すなわち西から東へ動く。
・北の空を見た場合、天の北極より高い位置の天体は向かって右から左へ、すなわち東から西へ動く。
・南の空を見た場合には、向かって左から右へ、すなわち東から西へ動く。
したがって、北天の周極星は天の北極の周りを反時計回りに動くことになる。北極星は、天の北極とほぼ同じ方向にあるため、あまり動かない。
地球上の北極点では北や東西の方角は存在しないため、天体の運動は単純に向かって左から右へ動く。天頂を見ると、全ての天体が天頂の周りを反時計回りに動くことになる。南半球での日周運動は、北半球での運動とは北と南、また左と右が入れ替わった動きになる。東と西は入れ替わらない。また、天の北極の代わりに天の南極が回転の中心となる。南半球では周極星は天の南極の周りを時計回りに動く。
赤道上では、二つの天の極は地平線上にあり、日周運動は北極星の周りを反時計回りに(左回りに)、また天の南極の周りを時計回りに(右回りに)動くように見える。二つの極を除いて全ての天体は東から西に動く。
◎夢にむかってたくましく生きる生徒の育成
それにしても、主体的に学ぼうとする姿がいっぱい!
(授業公開・OJT研修:12/7)
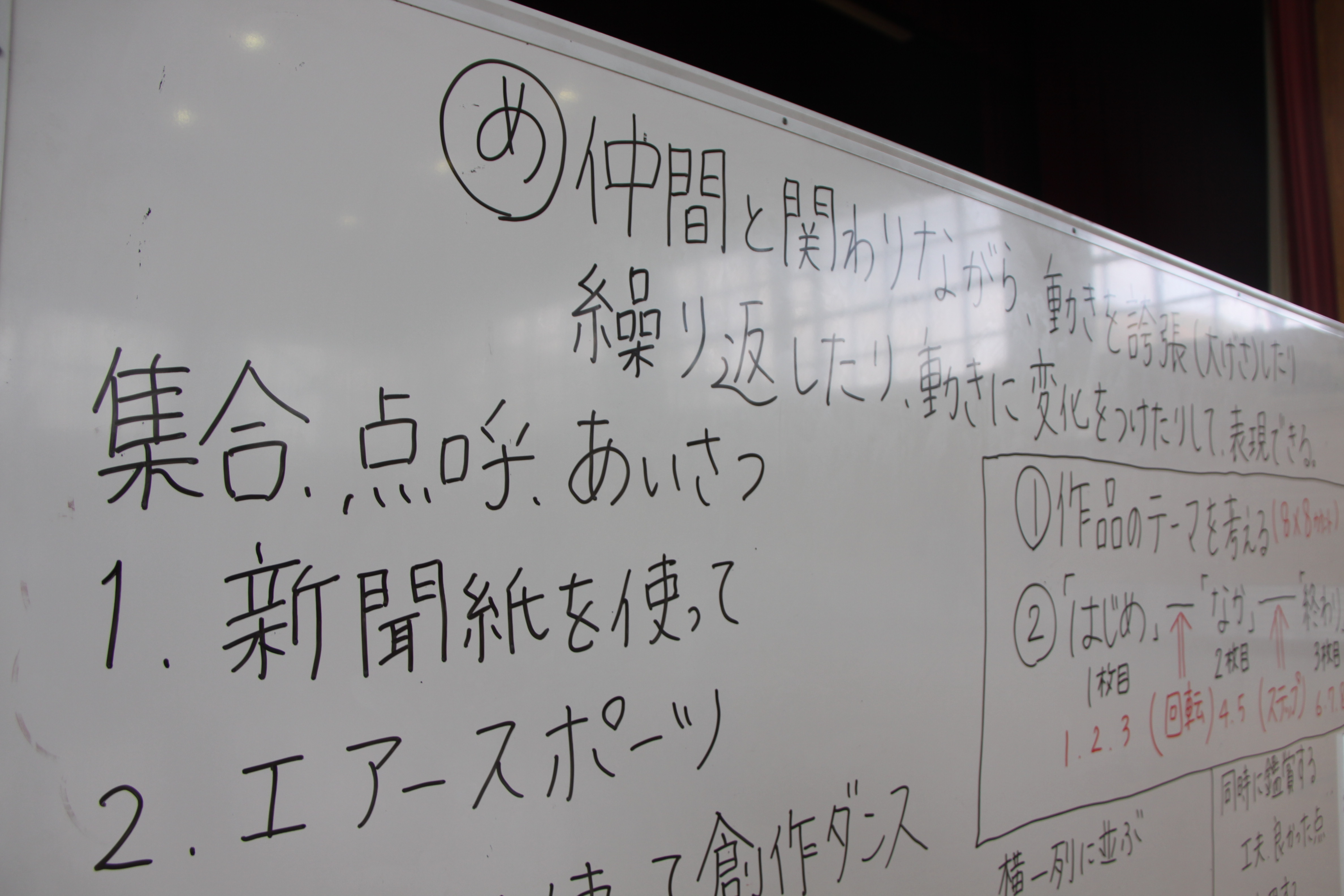

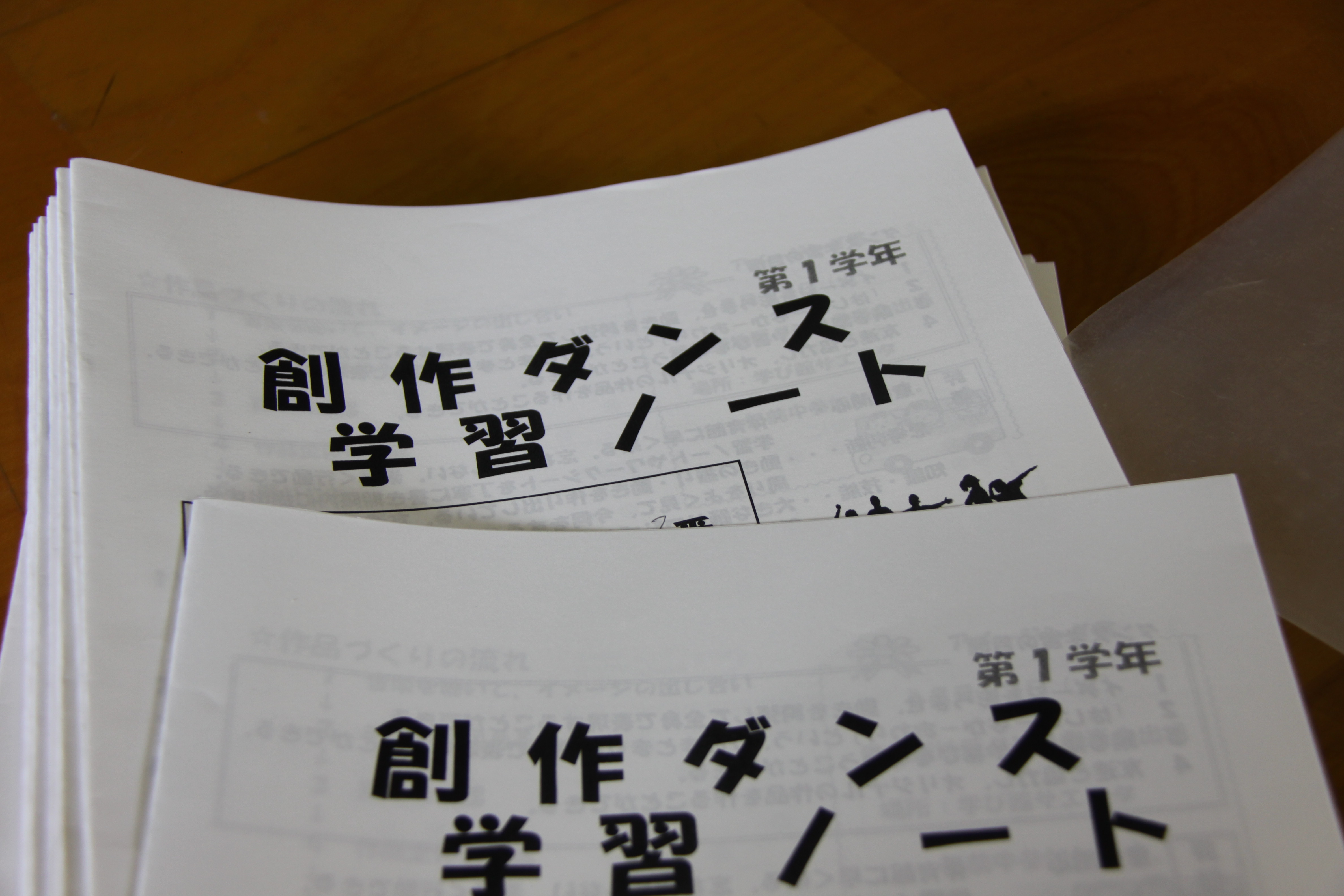








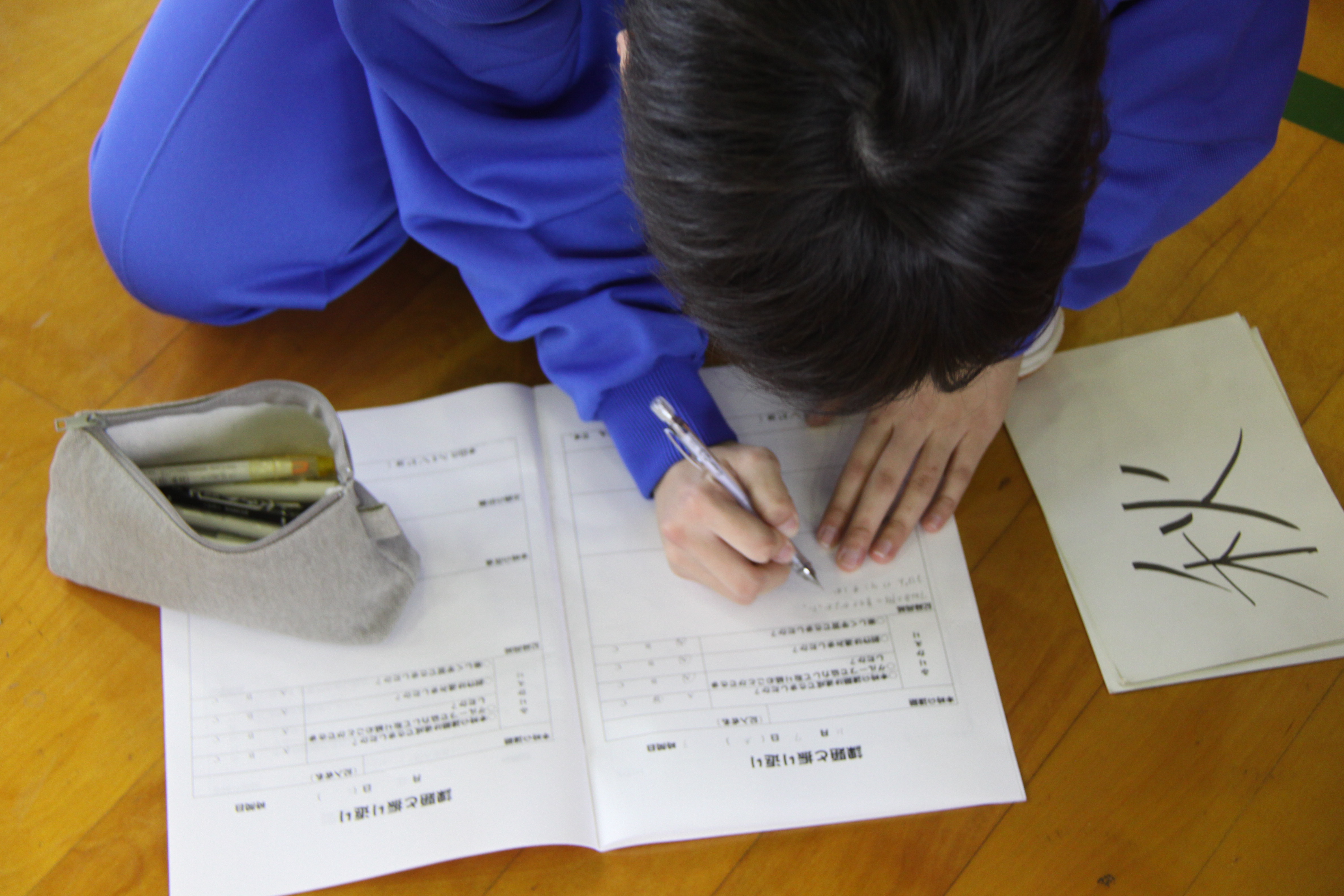
◎深く探究すればするほど、知らなくてはならないこと
が見つかる。人間の命が続く限り、常にそうだろうと
私は思う。アインシュタイン
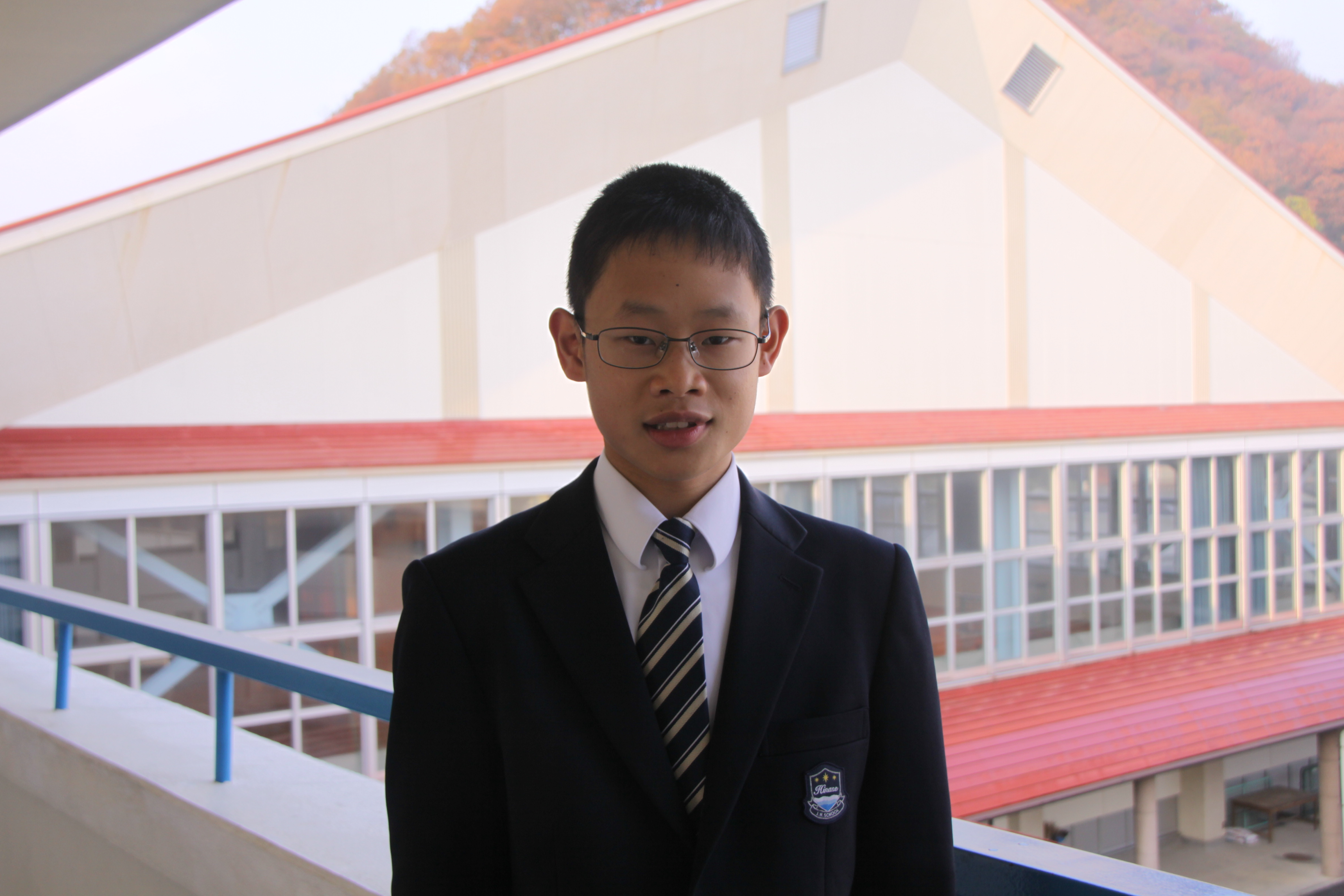
岡山県内の小中学生の自然科学に関する研究の中から選抜された優秀な研究を集めて「第73回岡山県児童生徒科学研究発表会」が12月3日、岡山理科大学で開催されました。小・中学生の個性的で、探求的な多くの研究発表がありました。備前市の代表として本校の奥原さんが、『日生の成り立ち』(地学)の研究を発表しました。
この会は、毎年、県科学教育研究会と県小学校・中学校教育研究会理科部会が主催し、研究発表は大学の教室を使って行われ、子どもたちが独自の視点で取り組んできた研究の成果を、制限時間内でプレゼンテーションします。発表が終わる度に、見守っていた保護者・小、中学校の教職員らから大きな拍手が沸き上がりました。(6日付けで大会報告が中学校に届きました。)
◎新しい学校のリーダーは、日生中。
いつものようにもくもくと清掃。(カストーディアル杯取組中12/6)












◎ひな中の風~~(12/6の風景)

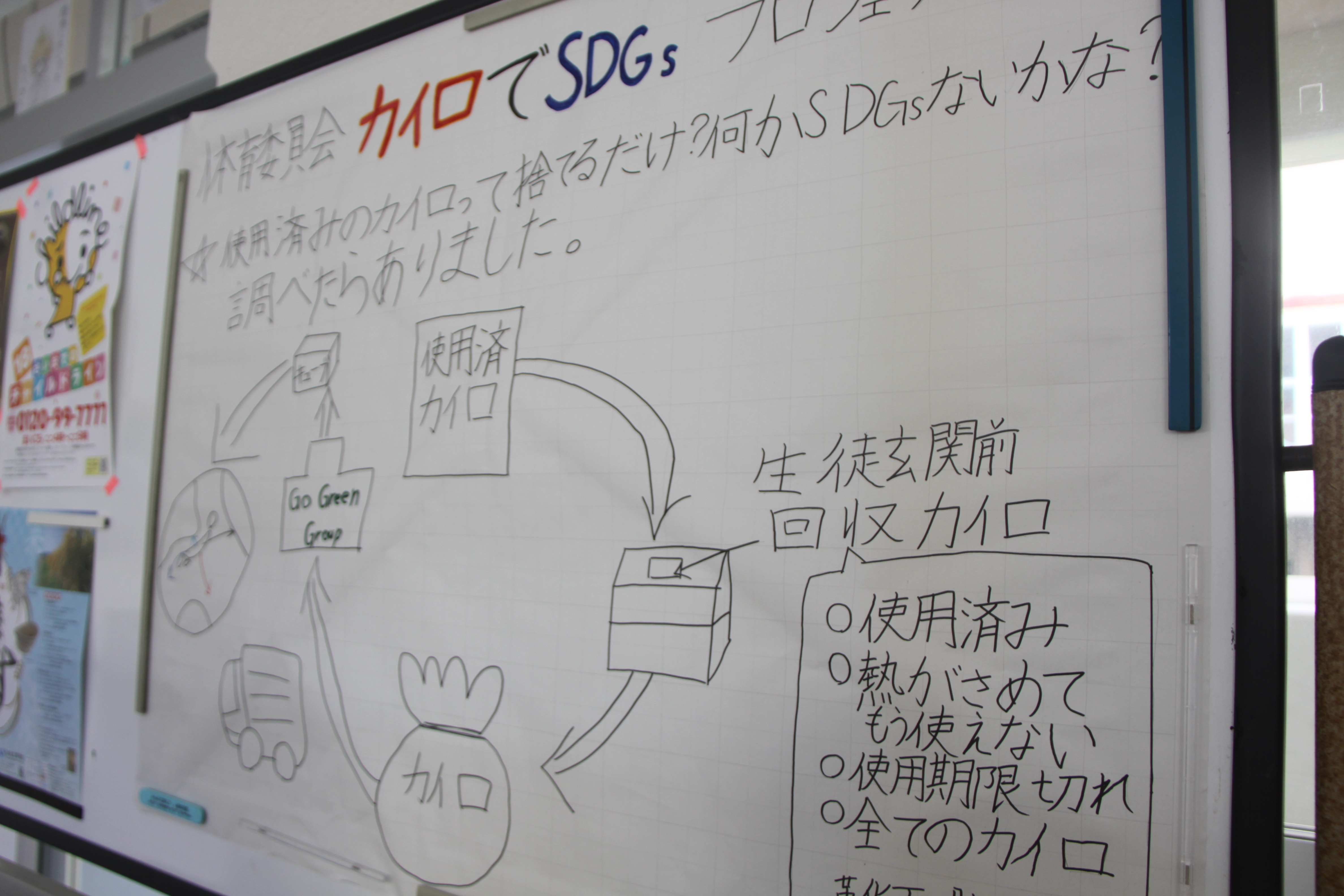




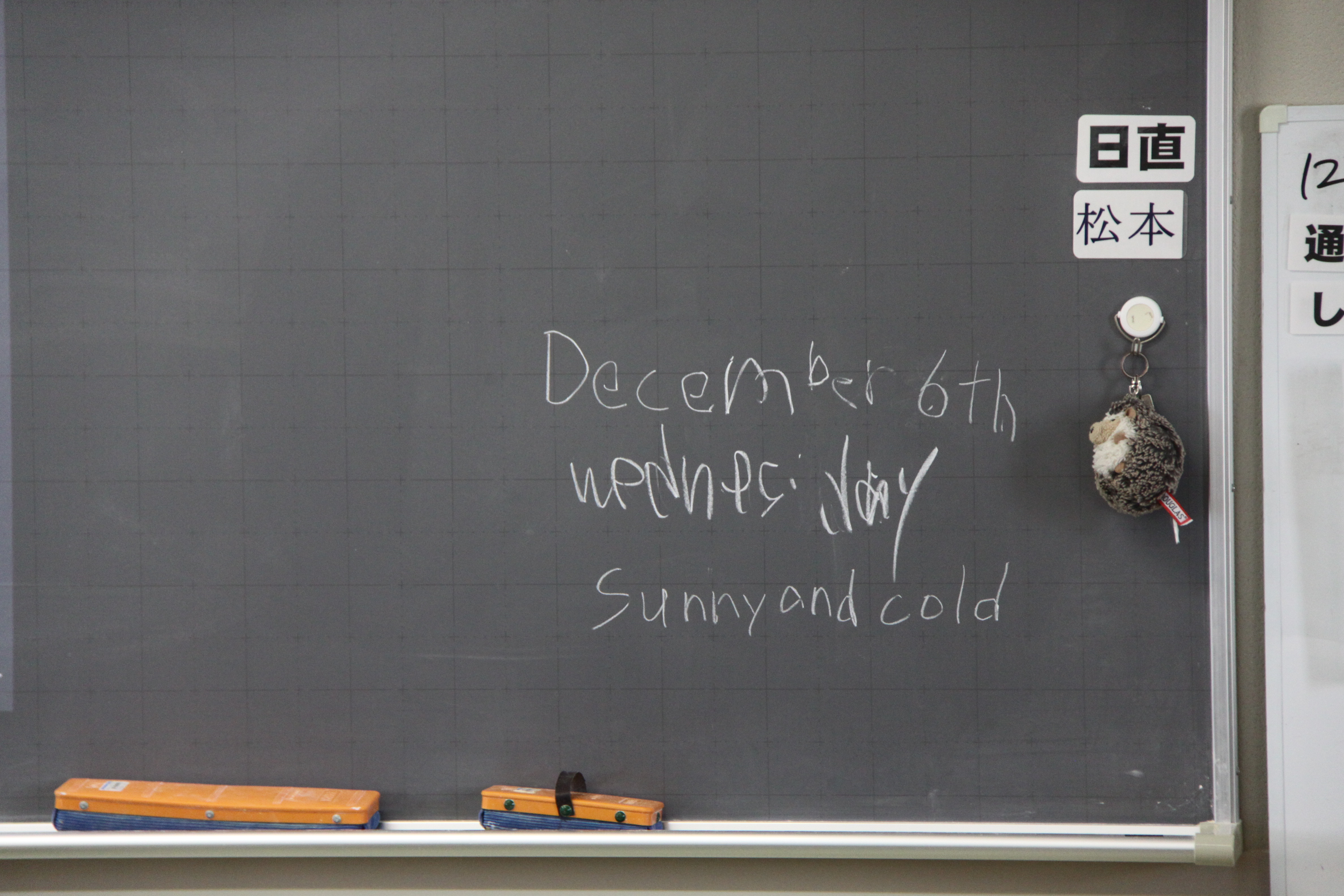

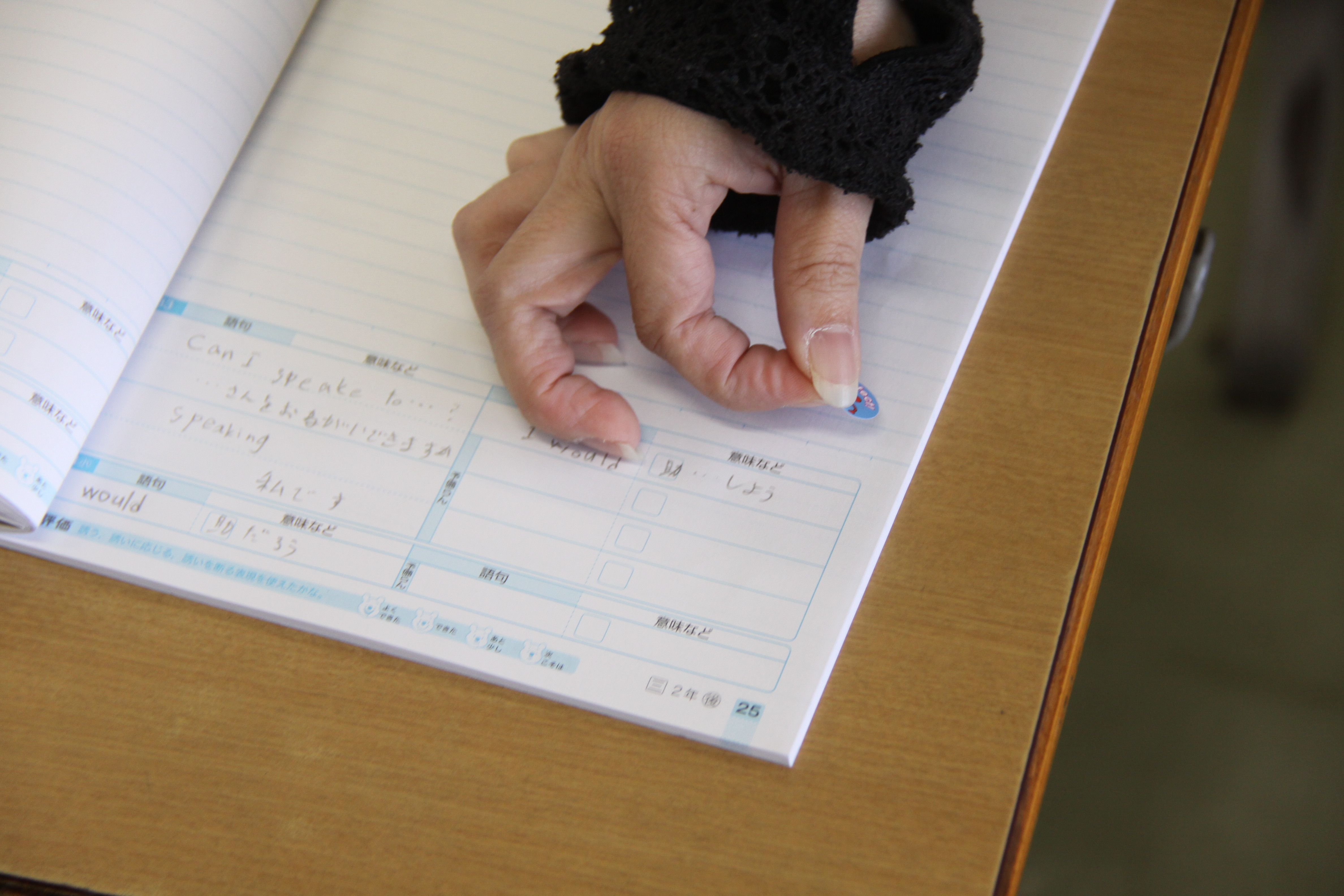

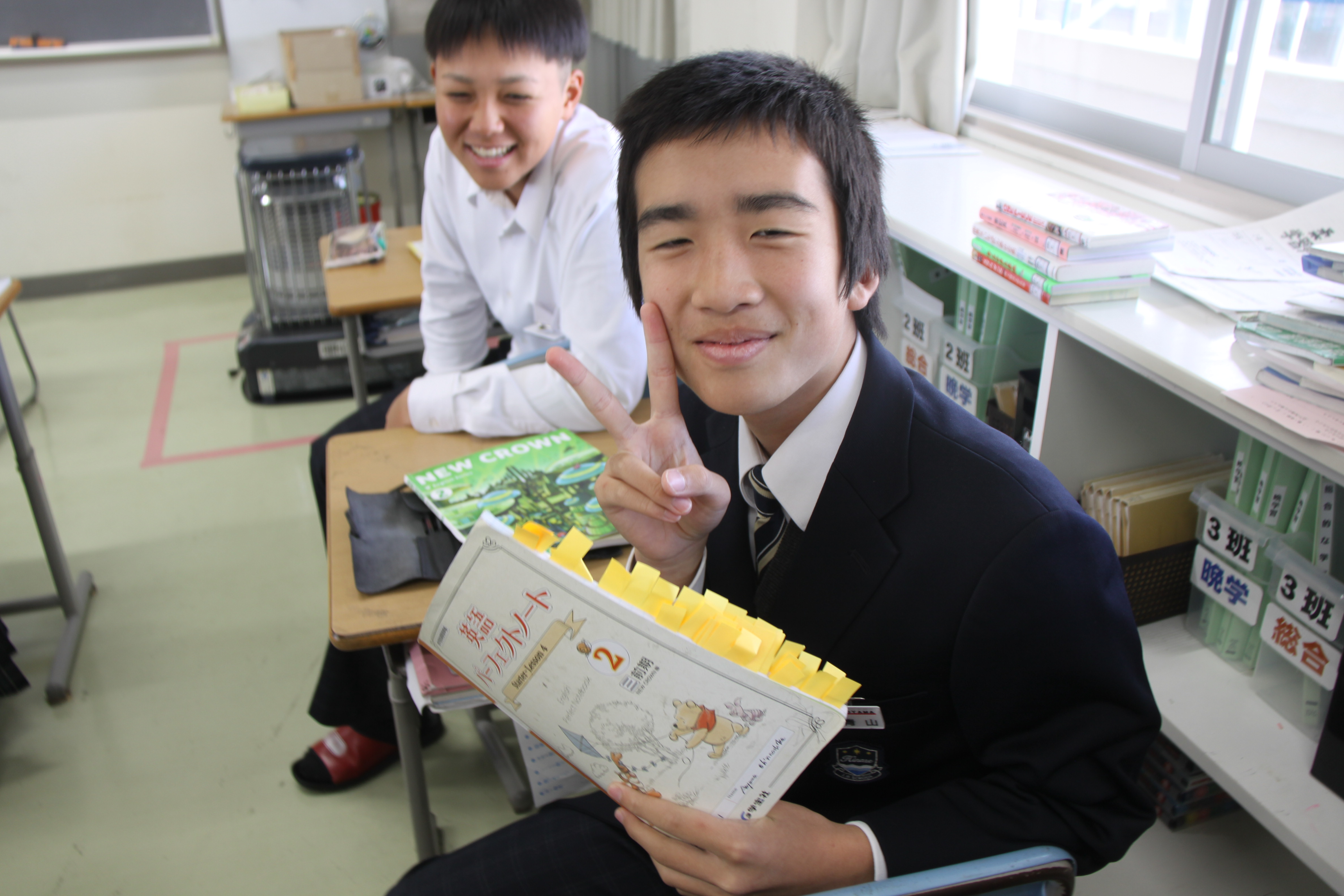

◎12月もアレ(A.R.E.)をお願いします。
学校評価アンケート(用紙版)は、5日に生徒便で配布しました。Googleフォームもしくは、紙媒体でご協力をお願いします。Googleフォームで回答された方は、用紙・封筒をそのままお返しくださいますようよろしくお願いします。18日(月)までにご回答・提出をお願いします。(_ _)
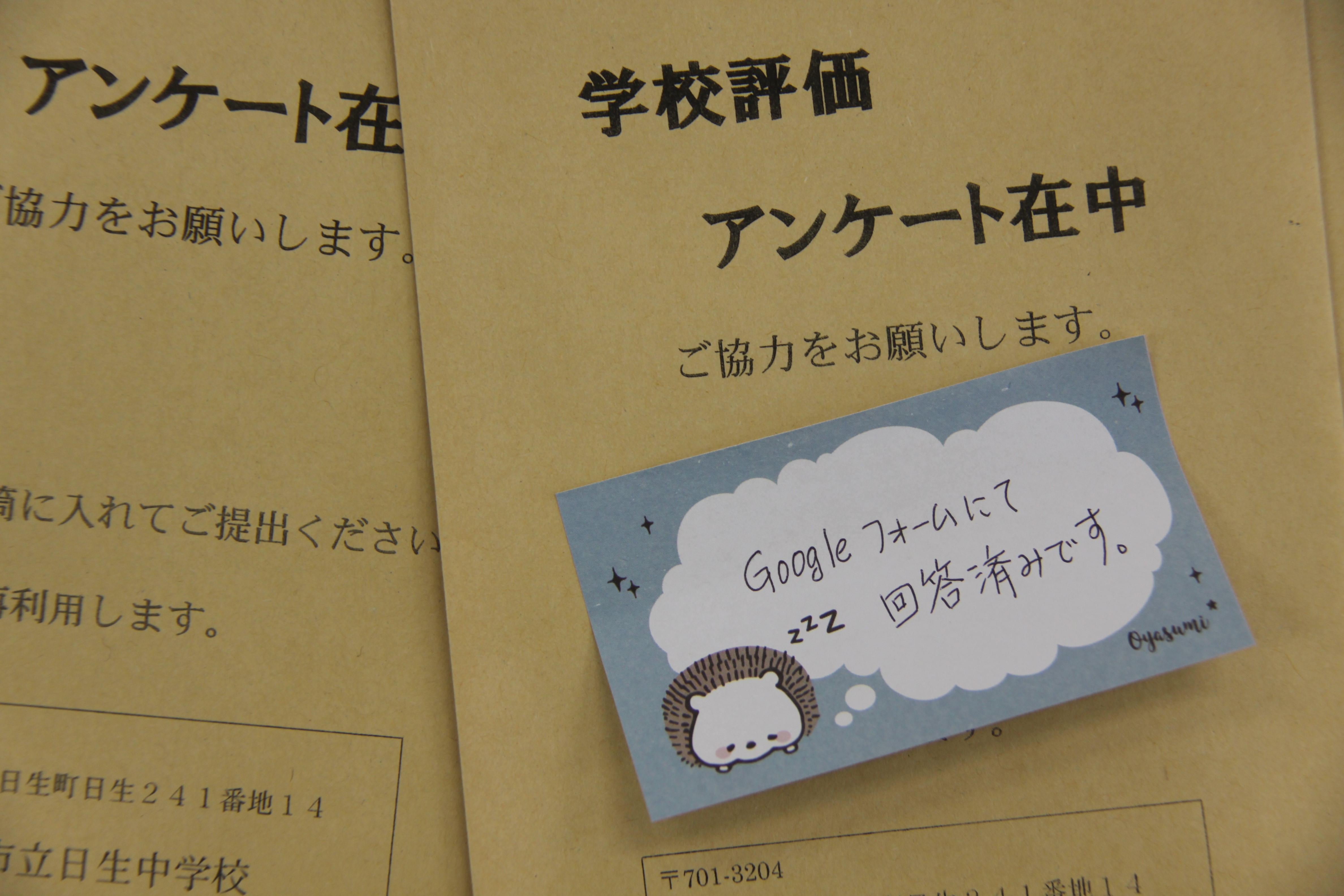
◎「俺は俺の仕事をする!この部室にごみは残さねえ」
キレイに使っているバスケ部更衣室です。 【『スラムダンク』池上亮二/19巻参照】

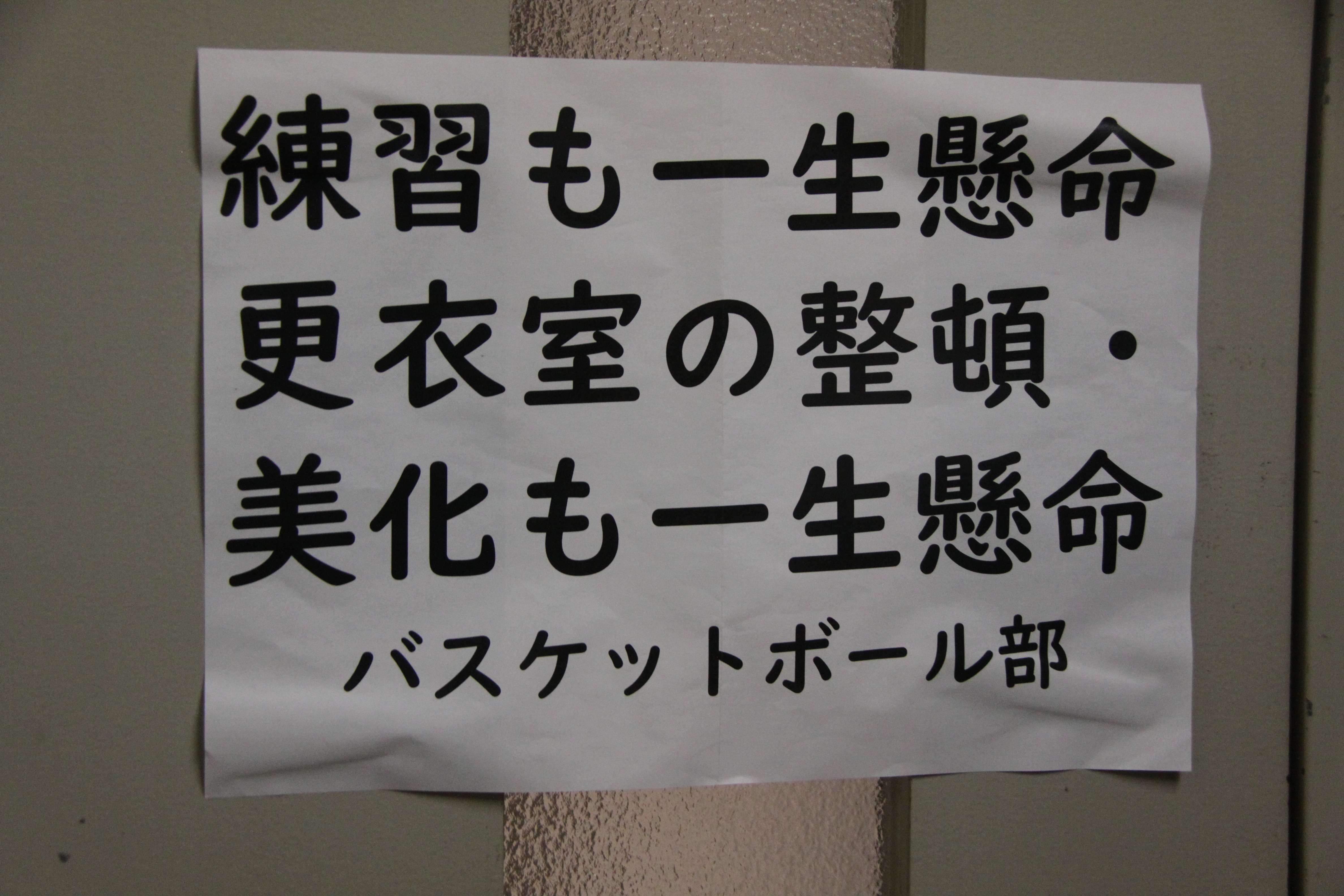

◎あー楽しっ。
Hard times arouse an instinctive
desire for authenticity. Coco Chanel
(厳しい時代だからこそ、本物を求める本能的な欲求が生まれる。)
チャレンジ企画・英会話教室を継続的に開催しています。(第6回:12/5‚第7回12/12)ちなみに、英語力のさらなる高みへ到達するための秘訣は、聞く・読むなどの英語に「触れる」インプットに加えて、話す・書くなどの英語を「使う」体験をしながら英語に触れることです。「使う」体験を頻繁に持ち、自分で間違いに気づき、正しく使ってみる機会を増やすことで「英語が使える」体験を積み重ねていけます。
Thank you Jessica!





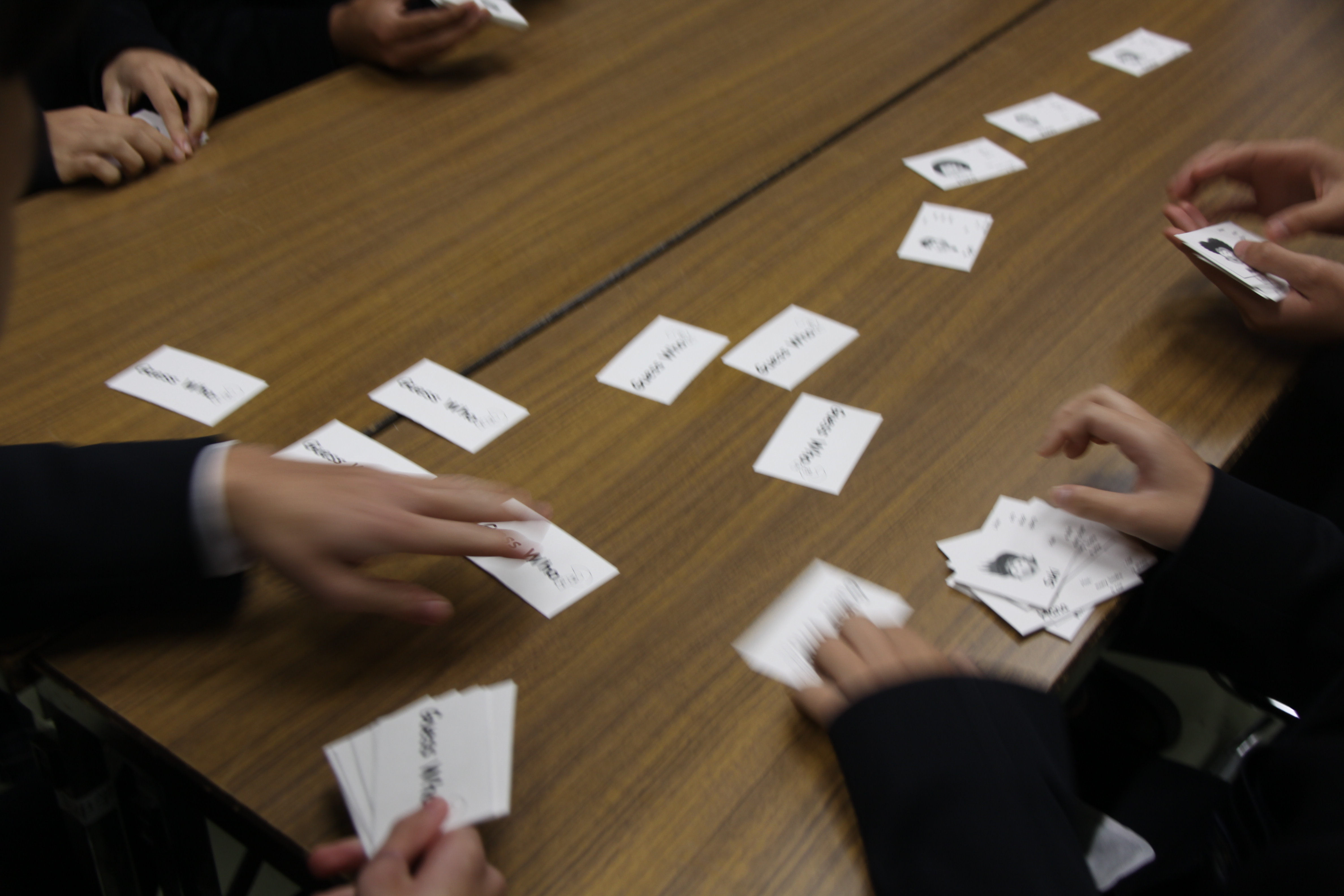
◎ひな中の流儀(12/5)
会場への静かな移動、大事な私たちの生徒集会、仲間の功績を讃え合う表彰式。



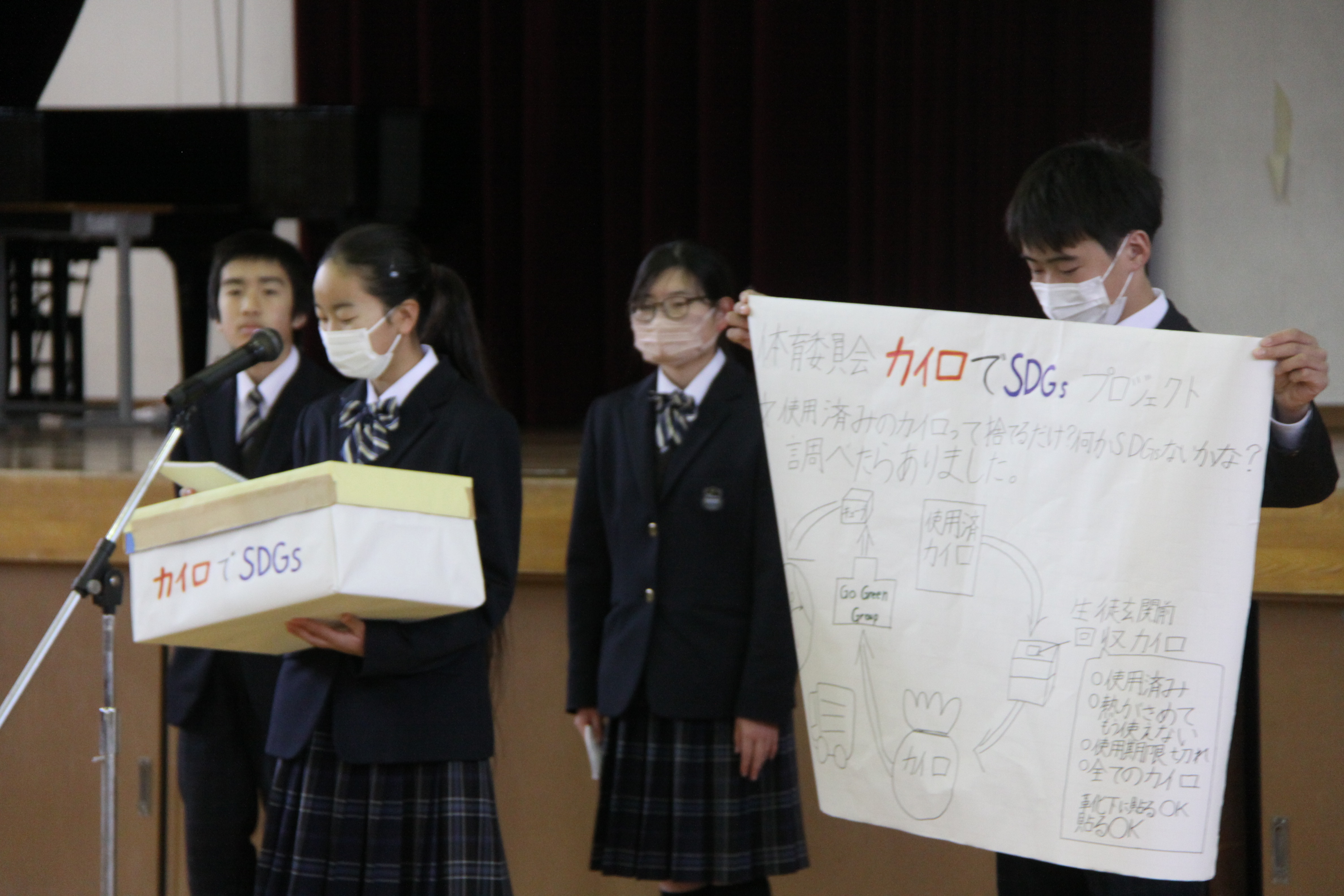




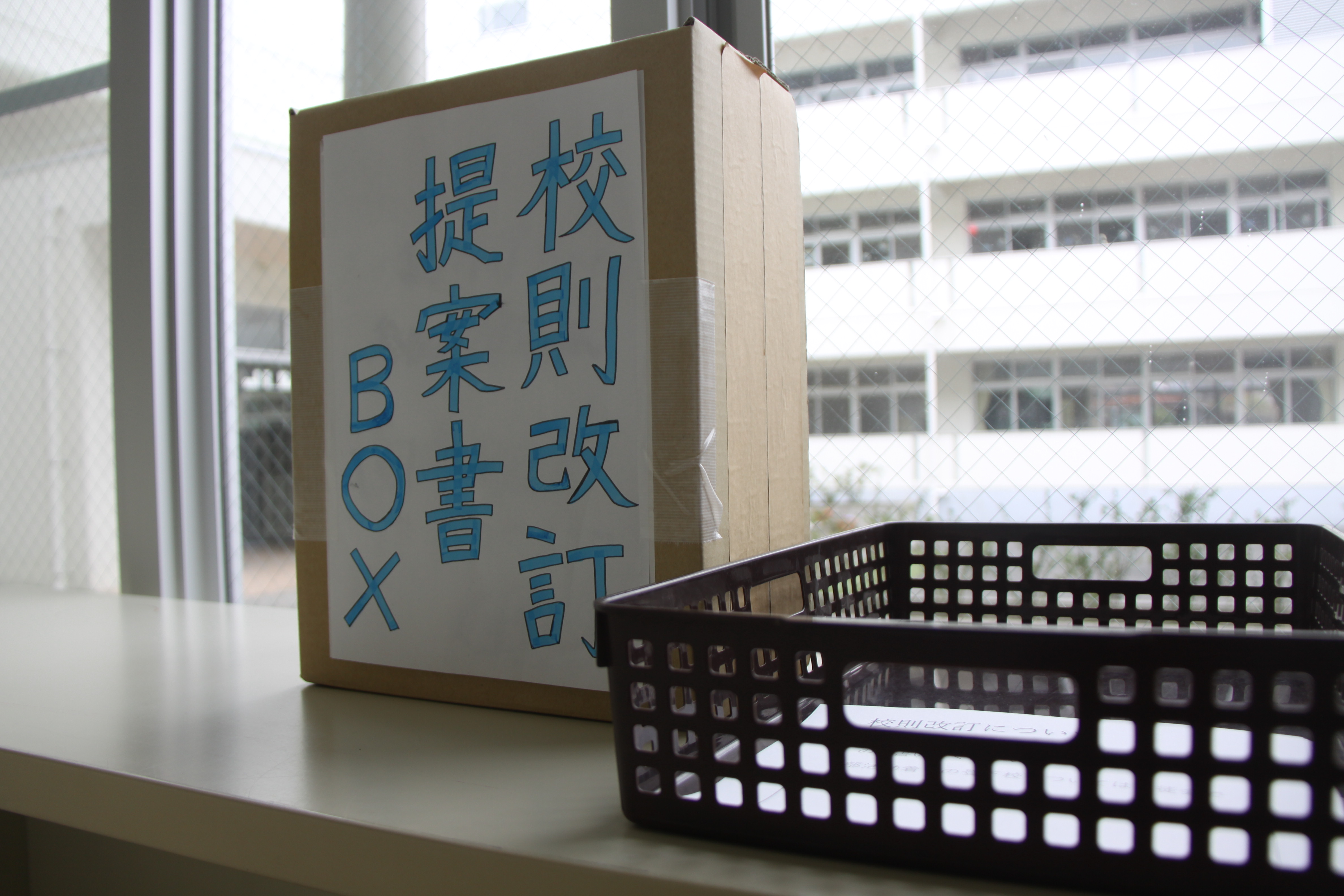
◎「ひとを大切にする社会」につながる学習










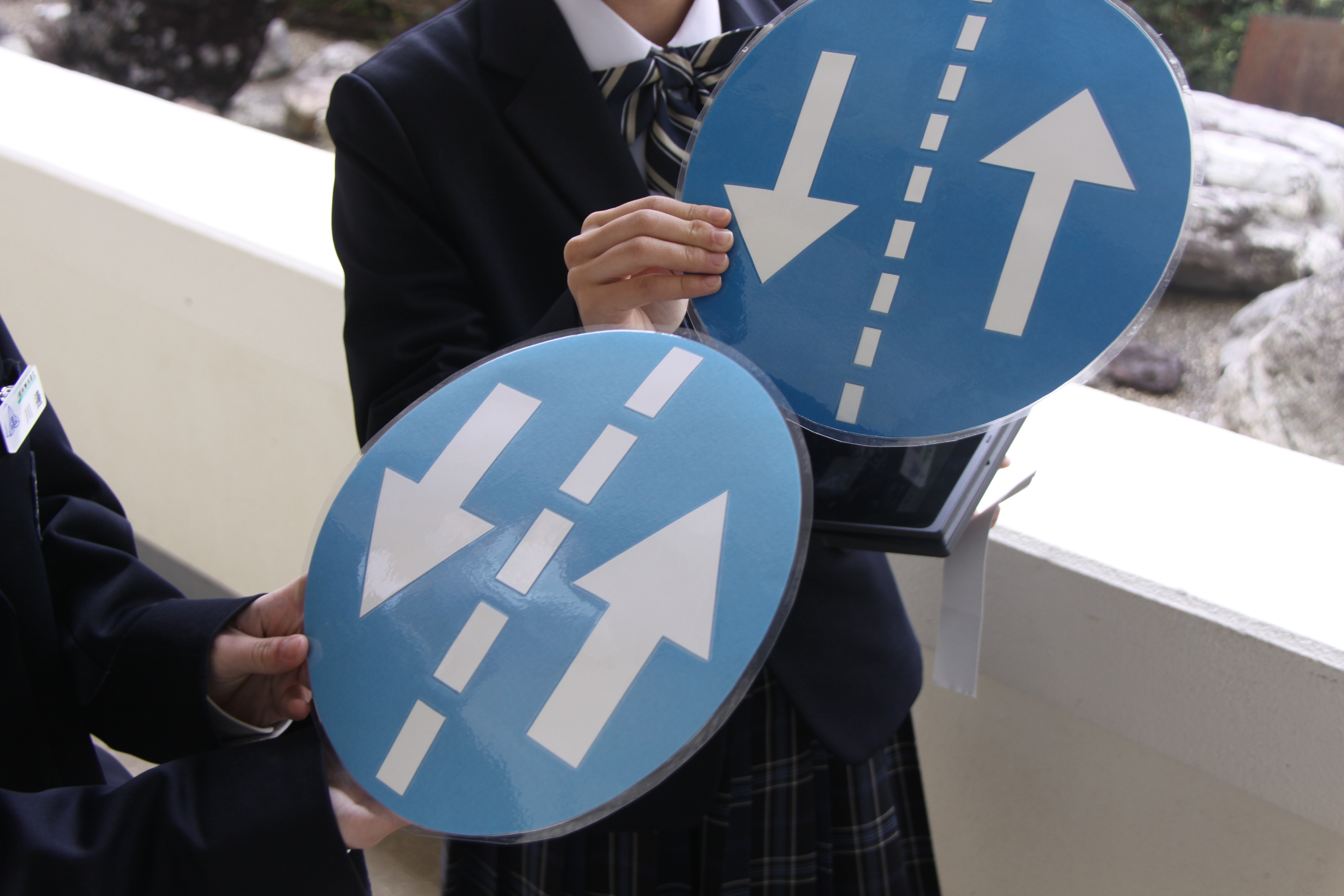

ユニバーサルデザインの中には、どんな人でもわかりやすく、一目で理解して正しく行動することができるよう促すピクトグラムという表示方法があります。
ピクトグラムは単なるイラストではなく、言葉に代わる伝達手段として、コミュニケーションツールの役割も担います。ピクトグラムは、情報の提示や注意の促しといった、情報伝達を図るための視覚表現です。古代までさかのぼれば、ものや人の形状を模して意味を伝える楔形(くさびがた)文字や、象形文字(ヒエログリフ)、甲骨文字などにも、ピクトグラムとの共通点を見ることができます。ピクトグラムを活用すると、文字の読み書きができない人でも意味を推察し、直感的に理解することができます。そのためピクトグラムは、街の案内板や、取扱説明書の警告表示などに、文字と併記される形で利用されています。図を用いた絵記号が、直感的な理解を促す伝達手段として国際的に注目を集めるようになるのは、1960年代に入ってからのことです。さらに1980年代以降になると公共施設を中心に広く普及していきました。
ピクトグラムは、単なるイラストや個人的なやりとりで用いる絵文字とは異なり、どんな条件下で誰が見ても、事前の学習なしに、一目で理解できる記号であることが求められます。そのため、視認性に優れ、意味の誤認識を起こしにくく、さらには案内板に長期間掲示されても目になじむ公共性に優れたデザインであることなどが、ピクトグラムの条件とされています。日本でも、大きな国際大会など外国人観光客が大勢訪日する機会のたびにピクトグラムの表記が改良され、JIS規格として整備されてきました。今では、公共施設や交通・商業施設、観光・スポーツ施設、安全や禁止・注意・災害防止に関係するものなど、さまざまなピクトグラムが規格となっています。
本校、美術科での授業では、それらの意義等を学習して、ひな中ピクトグラムを制作し、校内に掲示しています。来校時に視ていただければ幸いです。
◎ひな中の風~~
集(つど)う・深める・確かめる
4日、日生中学校人権集会をひらく
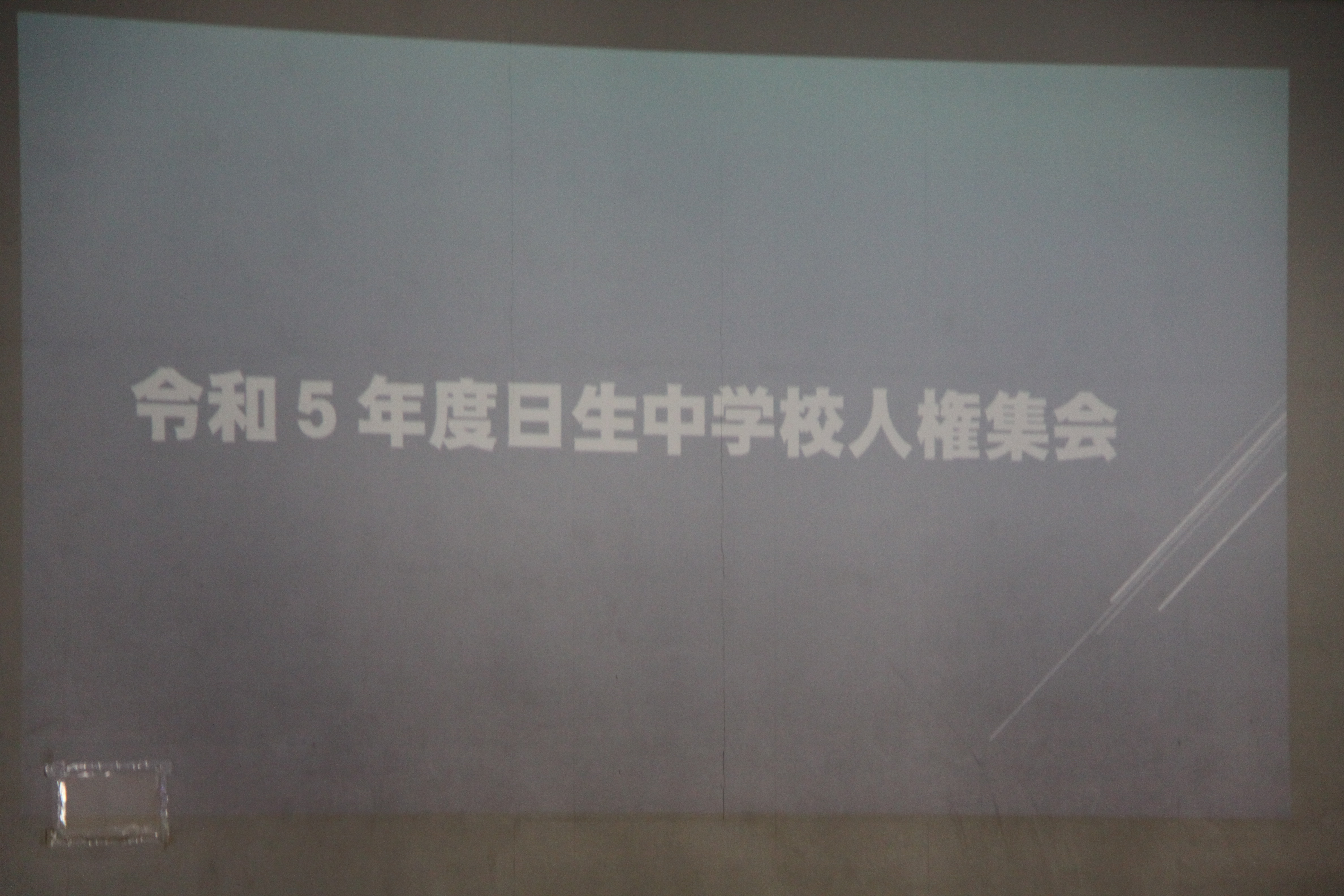



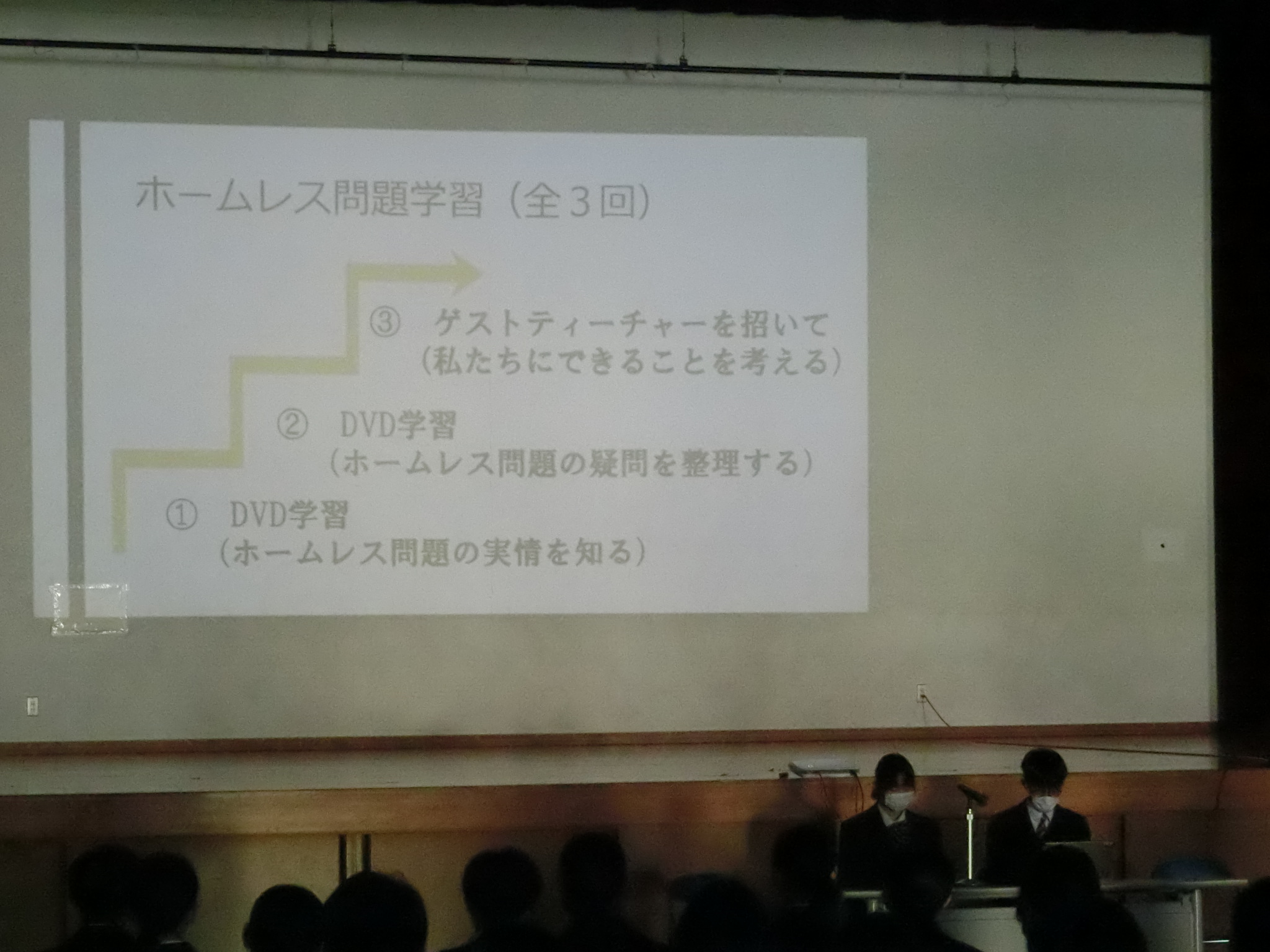
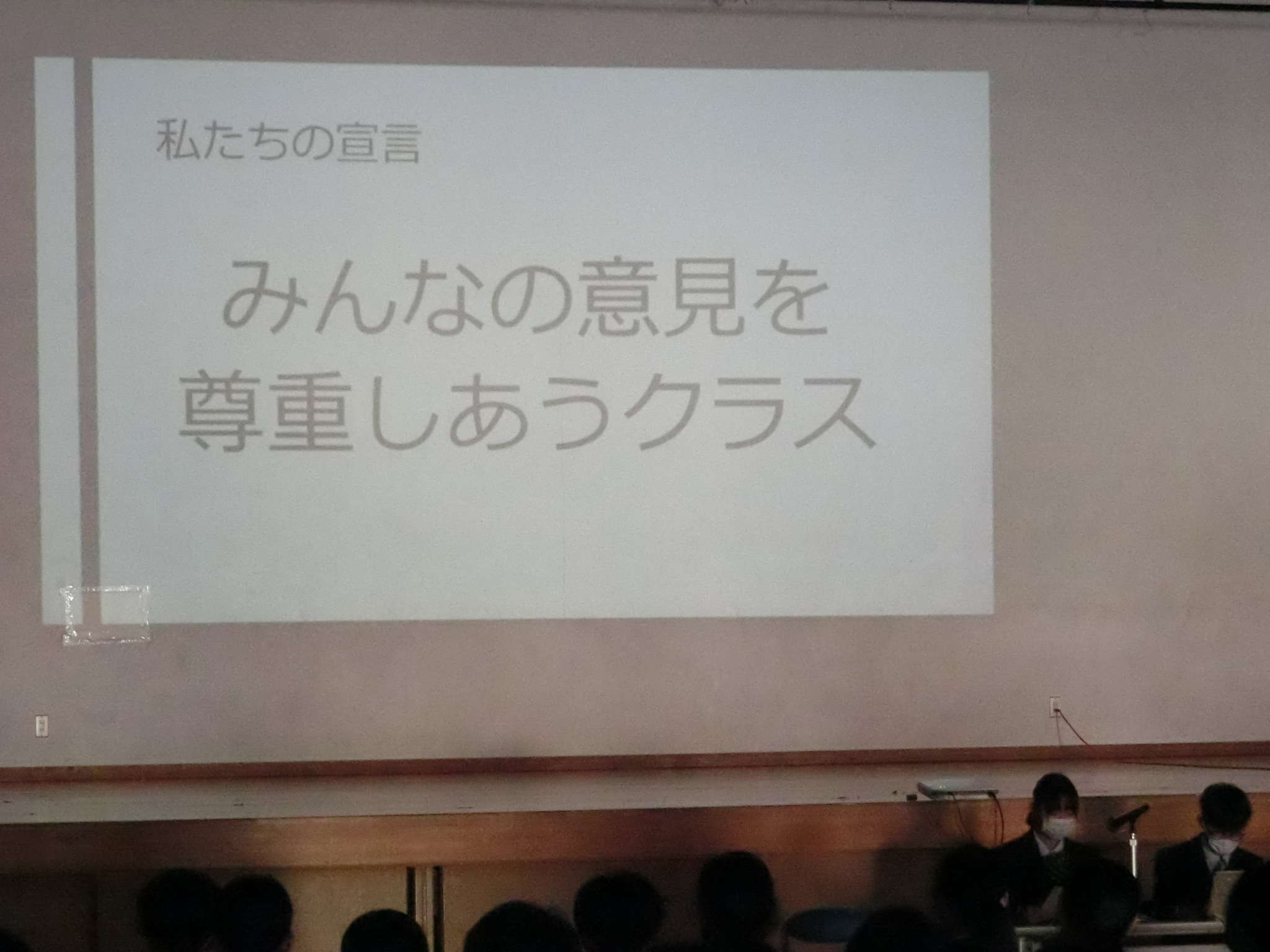
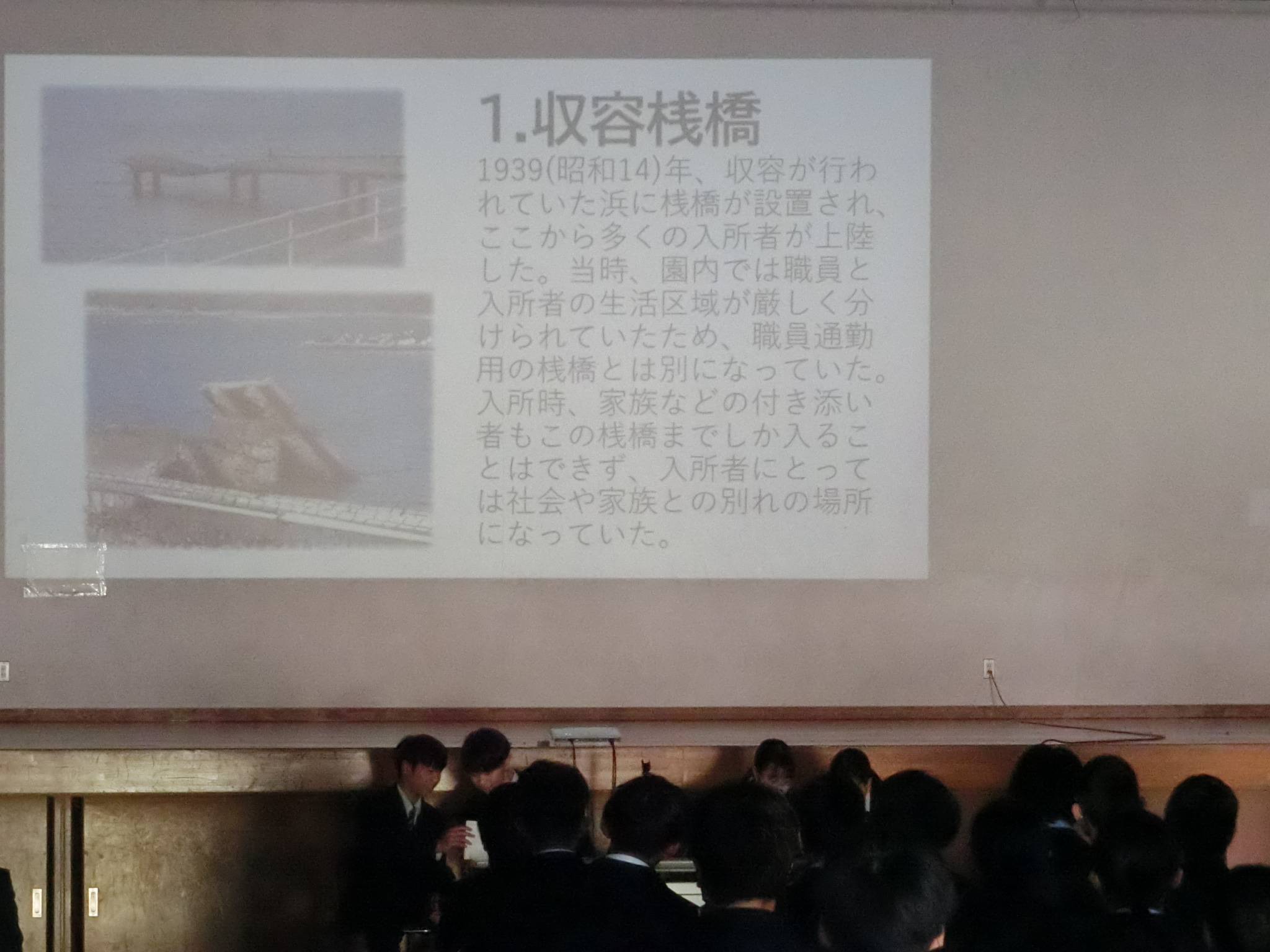


◎花は 花は 花は咲く(12/4 入学願書用写真撮影)



◎ひとのあいだ(集会の準備 1年生)






◎第22回カストーディアル杯スタートします。(12/4~)
「カストーディアル(custodial)」とは、英語で「維持する」を意味することば。ディズニーランド開園中、白いコスチュームを着た「カストーディアルキャスト」を目にした覚えがある方も多いのではないでしょうか。カストーディアルキャストはゲストのご案内をしながら、開園中のパークを綺麗に「維持する」役割を担っています。また、夜に活躍するナイトカストーディアルは、大きな機材を使ってパーク中を清掃したり、アトラクションの隅々を清掃したりと、役割が全く違います。彼らが『リセット清掃』と呼んでいるように、ナイトカストーディアルの役割は東京ディズニーリゾート®が誕生した1983年の状態に「リセット」し、その初々しい姿を維持することにあるのです。
4日からの日生中カストーディアル杯、いつものように清掃に一生懸命に取り組みます。
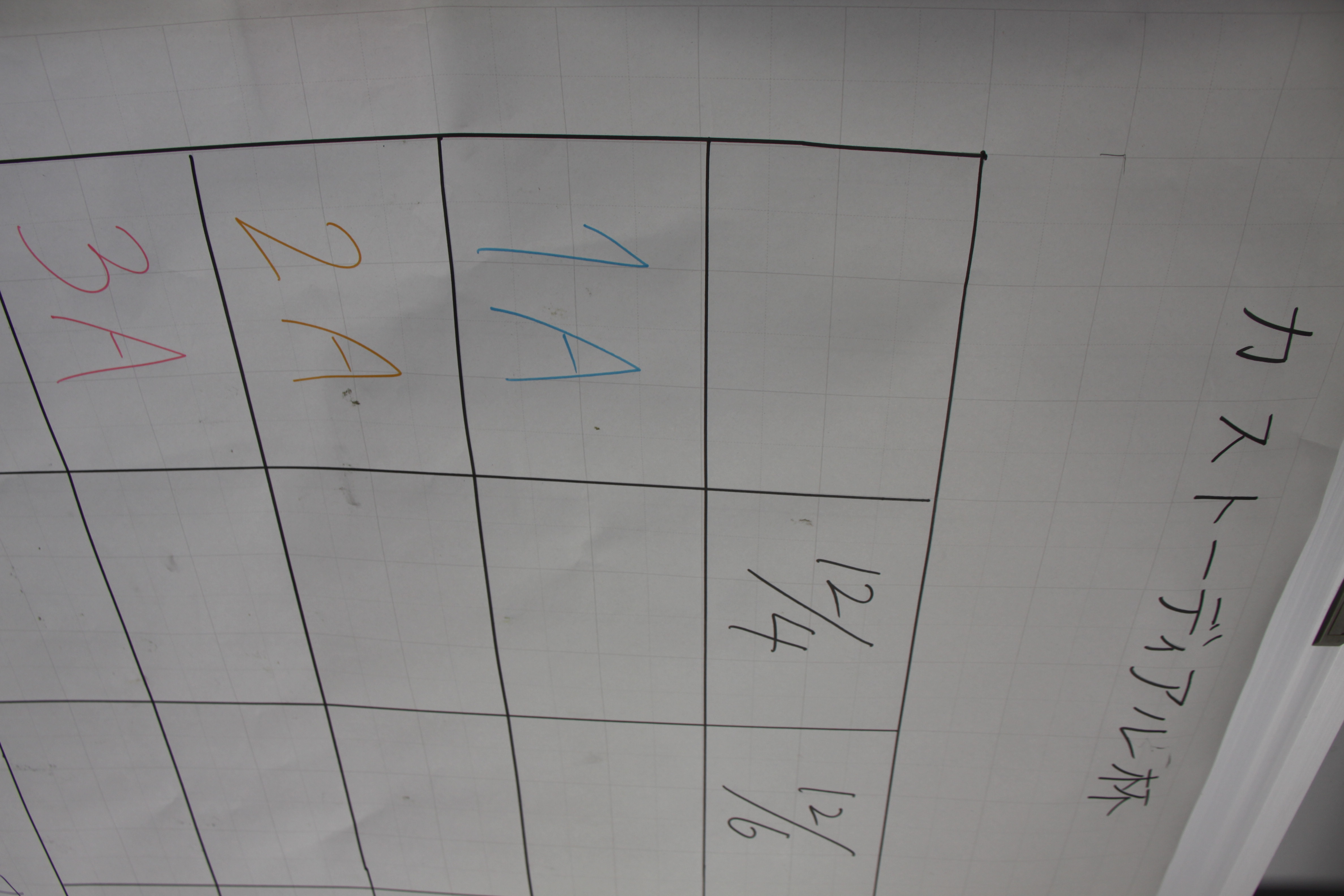
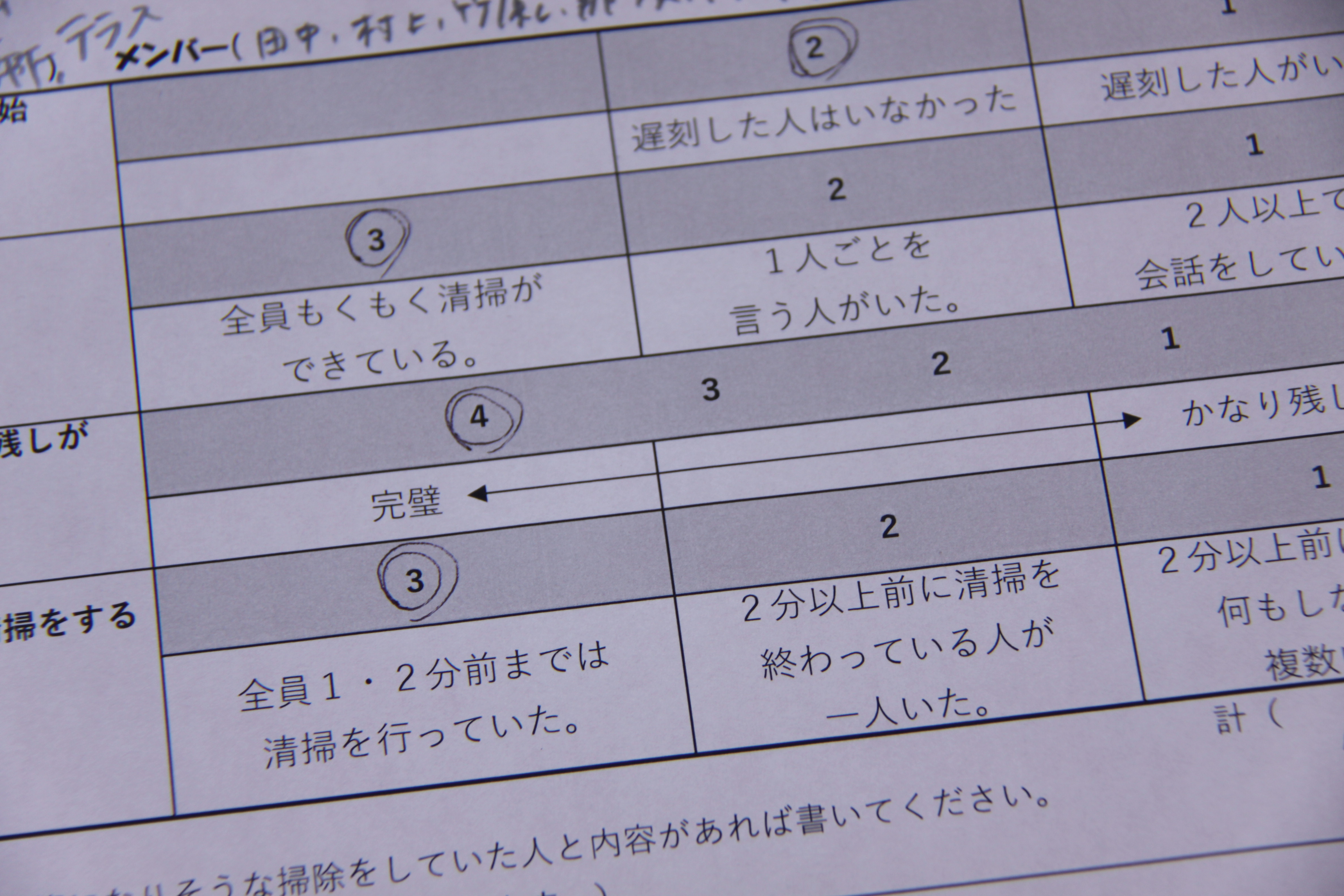
◎私たちのはじまりの風景5
~わかるかな?ここってどこでしょう。(12/2)









◎花は 花は 花は咲く
新入生保護者入学説明会・ひなせ親の会開催(12/1)

You have to be unique‚ and different‚ and shine in your own way. Lady GaGa
(あなたは、唯一無二で、人と違って、あなたの進む道で輝いていなければいけません。)
この日、第2回ひなせ親の会を開催しました。
第2回ひなせ親の会には、片上から備前市地域おこし隊もされている椙原さん、地域の子ども(大人)の居場所づくりに取り組む東さんを合わせて、8名の参加があり、「中学校入学についての素朴な質問」や「「発達の特性」を正しく自己受容していくために」を話題に、椙原さんの貴重な体験談に重ねて、参加者の方々と意見交流をおこなうことができました。次回(第3回:2月14日(水)17:45~19:00(*小6体験入学の日)も計画していますが、いつでも、中学校にお寄りください。お話しましょう。(教頭)
次回、第3回ひなせ「親の会」のご案内
特別支援教育について、(通常学級での特別支援・合理的配慮等ももちろん)保護者の方々と一緒に考えていく会です。◎これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。(カウンセリングや講座ではありませんけど)日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)からアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、次回も大切な時間にできたらと思います。お気軽に、申し込み・ご参加ください。
1 日 時:2024年2月14日(水)17:45~19:00 (*新入生体験入学の日)
2 場 所:日生中学校
3 内 容:「いっしょにガンバりたいね。学校・家庭・諸機関との協働」をもとに意見交流を予定
4 参加者:小・中学校の保護者、日生西・日生東小学校の先生、久次(日生中学校)、SSW
主 催:日生中学校区連携推進委員会(特別支援教育部会)
◎学校評価アンケートへのご協力をお願いします。(~12/10)
安心安全メールにて、12月学校評価アンケートを送信させていただました。学校評価は、児童生徒がより良い教育活動を享受できるように、学校が学校としての目標や取組等の達成状況を明らかにして、その結果をもとに学校運営のさらなる改善を図るために行っています。今回はGoogleフォームを活用して回答していただくようにしています。お手数をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。なお、紙媒体でのアンケートを希望される方は、来週に生徒便で配布しますのでしばらくおまちください。

◎自分らしくせいいっぱい 道を拓く
~進路実現へ 面接練習に取り組んでいます(12/1)

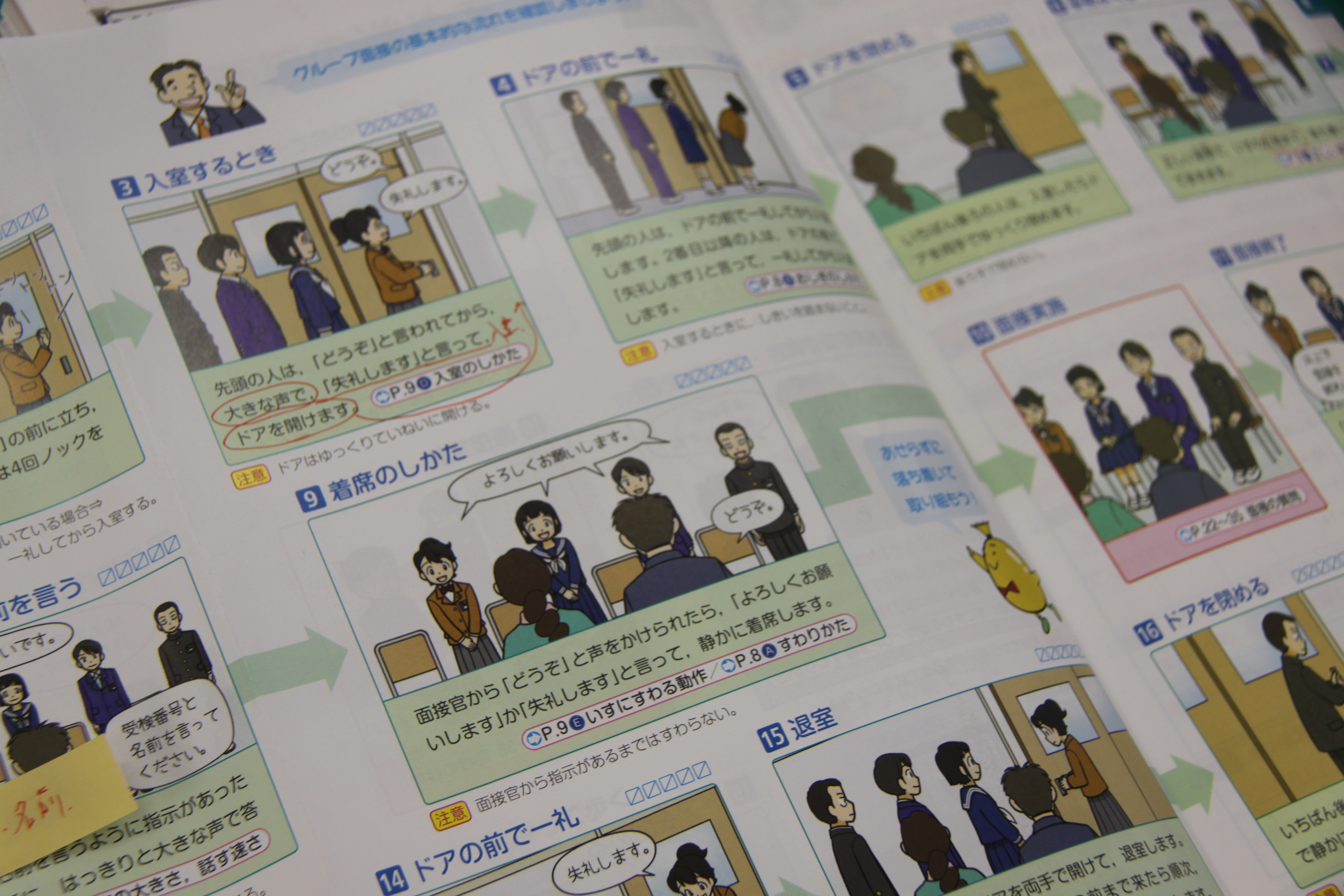
質問の具体例としていくらか挙げると、以下のような内容です。
「受験番号と氏名、出身学校を教えてください。」
「この高校(本校)を選んだ理由(志願理由)を教えてください。」
「あなたの長所と短所(性格)を教えてください。」
「中学校3年の生活の中で一番頑張ったことは何ですか。また得たものは何ですか。」
「この高校(本校)に入学したら(高校を卒業したら)したいことはありますか?その理由は?」
「あなたの得意(苦手)科目はなんですか?その理由は?」
「将来の夢は何ですか」
「あなたのがんばっていること、趣味や特技を教えてください。」
「最近のニュース(新聞)で印象に残ったものを教えてください。」
どの質問も、中学校3年間の生活を基にしたことです。言い換えれば、中学校生活を大事にしていくことが、面接試験を乗りこえる近道だと言えますね。3年生にも少しアドバイスです。1:焦らない。慌てない。落ち着いて。 2:しゃべるときは相手の目を見て、普段より少し大きな声で。3:受験校のことはしっかり調べておく。4 おおげさにいわない。ウソはつかない。5:思ったことを言うのではなく、面接官(高校)がどういう答えを求めているか考えて答える。 6:過去の質問を確認して、対応をしっかり考え、友達どうしで練習する(落ち着いて丁寧に説明する練習をしよう。) 7:椅子の座り方や服装などは本番と同様に練習しよう。8:敬語の訓練をしておこう。 9:質問や答え方を覚えるのではなく、よく考えておこう。必ず道は拓かれます。(^_^)
◎地域とともにある学校として
11月30日、特別養護老人ホームあおさぎ・ミドルステイあおさぎさんが開催している、地域密着型サービス運営推進会議に参加させていただきました。運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するもので、各事業所が自ら設置するものです。昨日の会議では、福祉体験学習や職場体験やボランティア活動などの推進など、福祉と教育の連携についても意見交換ができました。また、最新の介護用品の紹介やシニアカーへの試乗もさせていただきました。日生中も地域連携・協働をこれからも大事にしていきたいと想います。

◎時分の花を咲かそう(11/30:環境委員会活動)







◎なかまと学び合うということは
こういうことさ✨(2年生授業風景11/30)

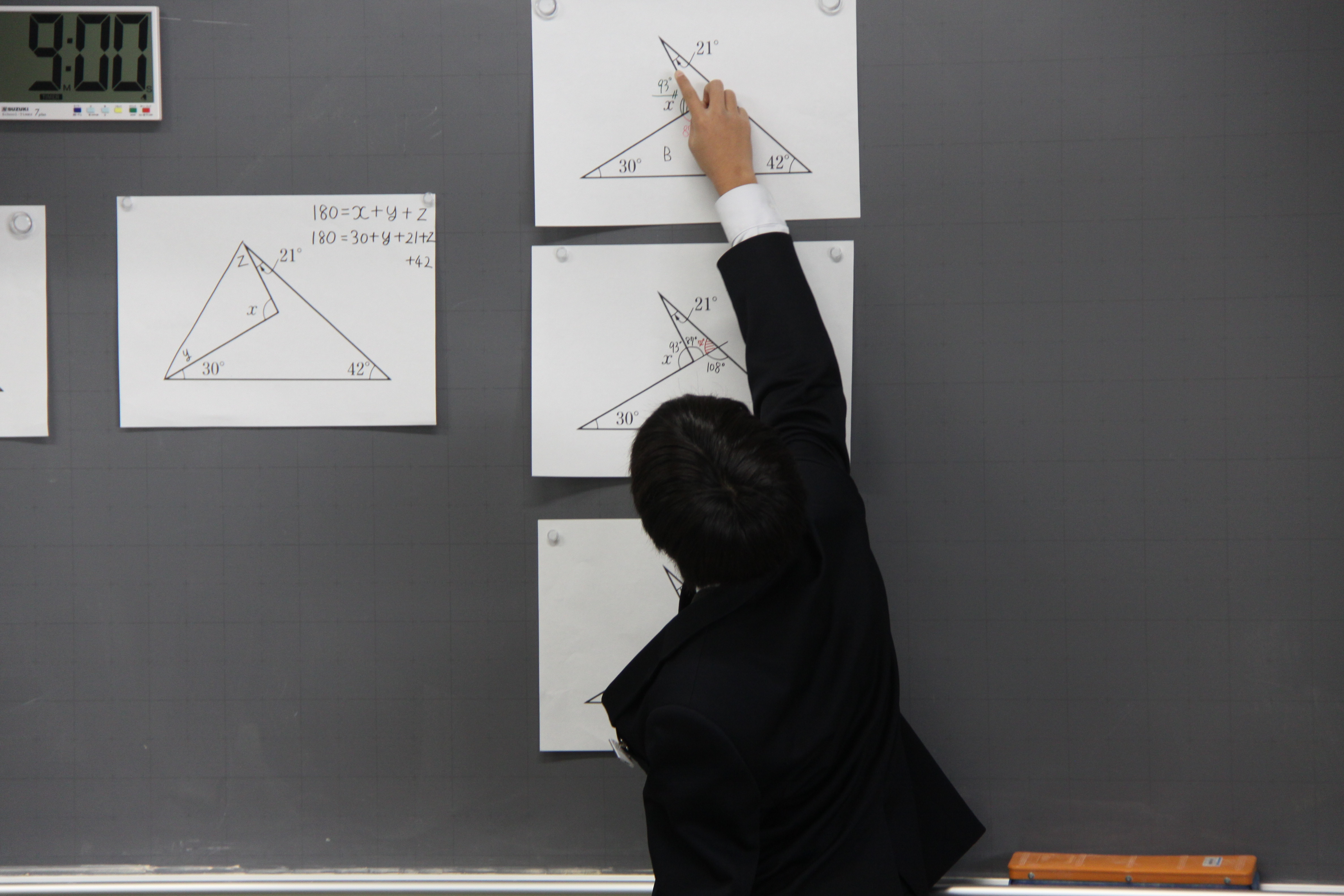




◎書を探そう まちに出よう
〈日生地域公民館で、今日から12/21まで∈^0^∋〉
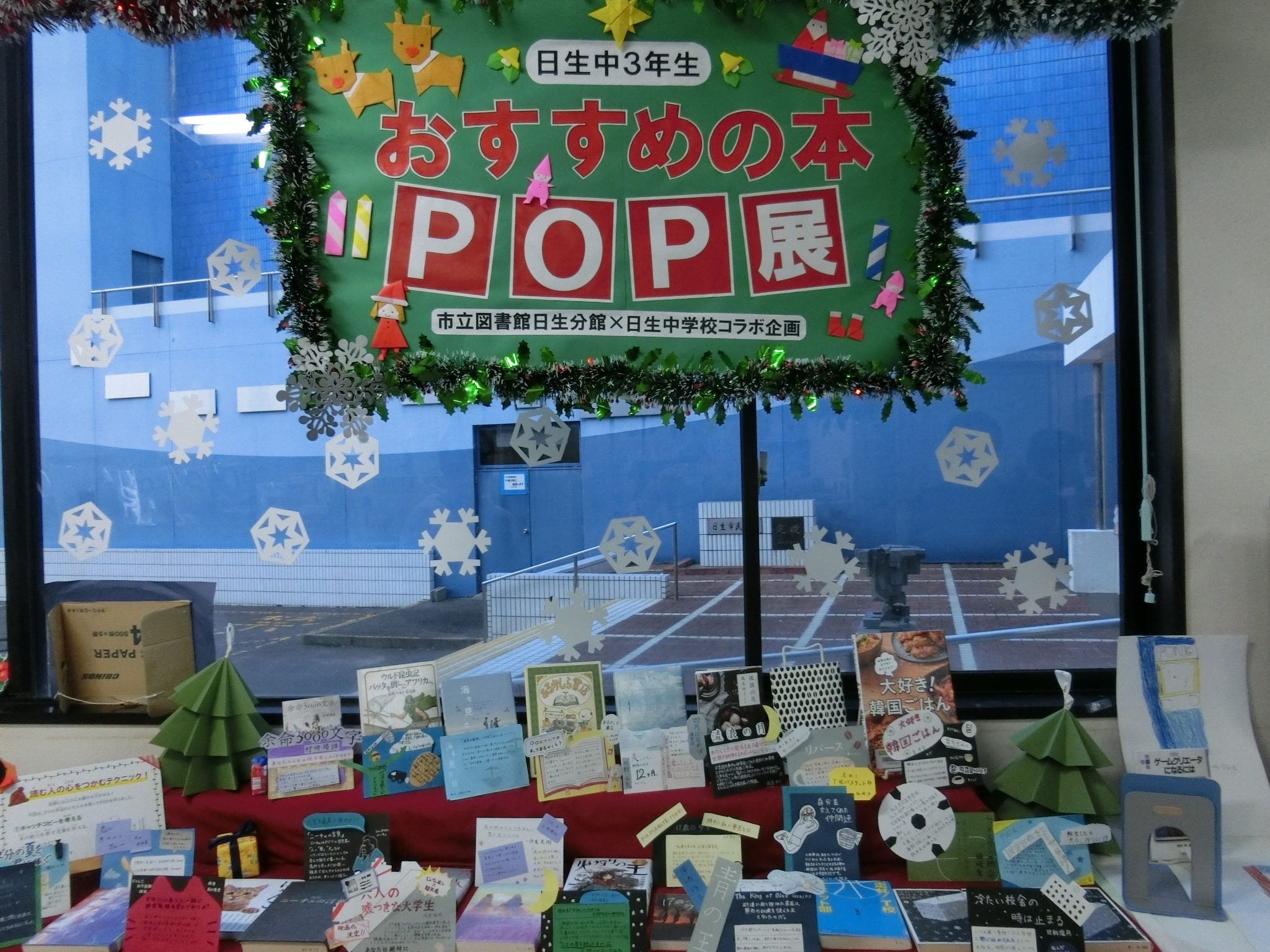
◎ひな中のアートセンスを味わって。
~地域とともにある学校へ(11/29)
日生地域図書館に、生徒たちがつくった本の紹介「ポップ」を展示しています。

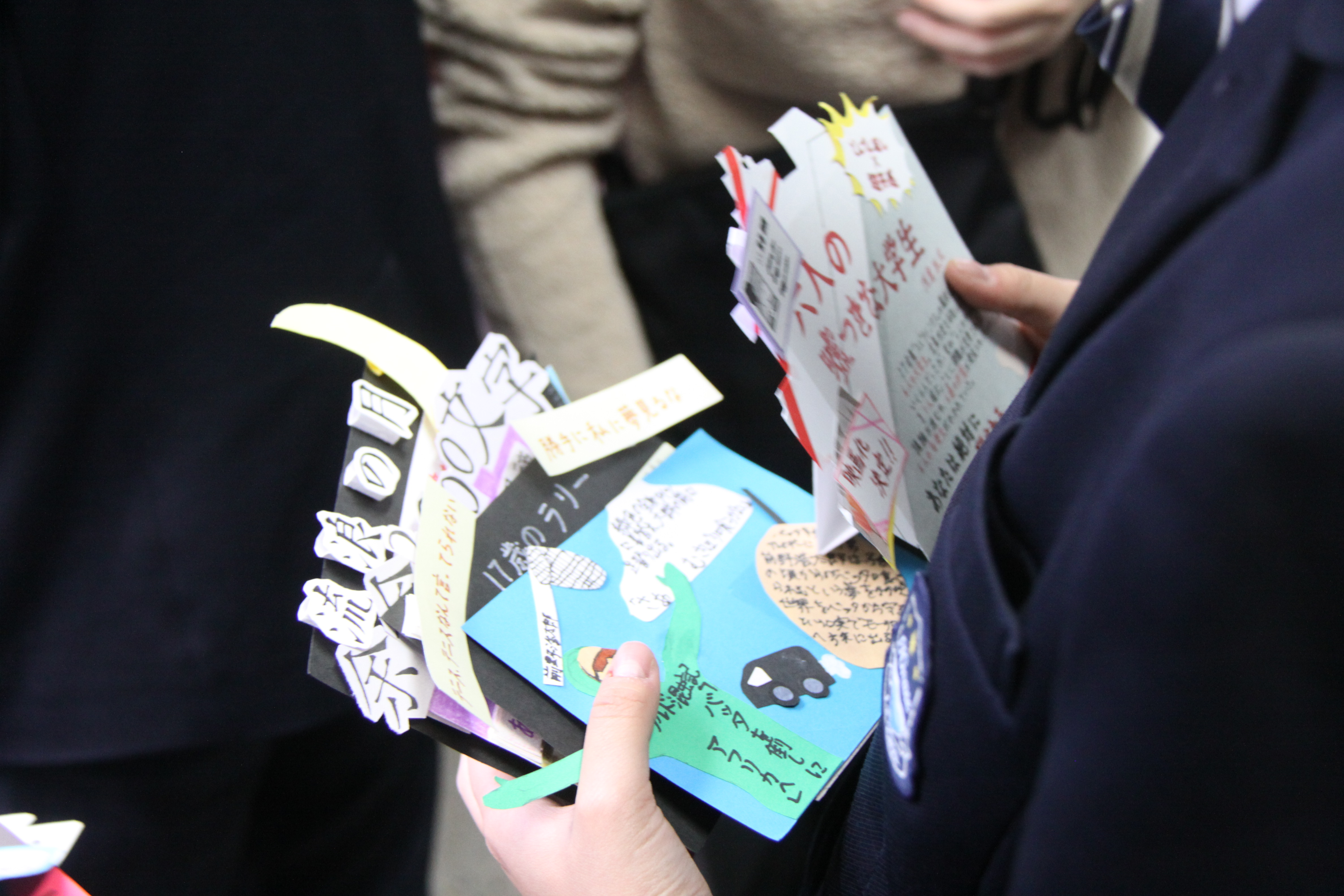




☆POPって?・・・読んだあなたが、その本を読んだことのない人に、 その本の「何」に「どう」心を動かされたかを短いフレーズに思いを込めて伝えるものです。
☆みなさんもつくってみてはどうですか?・・・①「伝えたい言葉」を探してみましょう:自分が伝えたい「感動」「面白さ」を、できるだけシンプルに(=むずかしい言葉を使わずに)表現できる言葉を探しましょう。自分はなぜその本を面白いと思っているのか、感じたことをたくさん書き出してみましょう。
つぎは「キャッチコピー」にしてみましょう。②ここからは、本を読んで感じ、書き出したいくつかの言葉の中から、自分がいちばん推したい言葉に行きつく作業です。思い浮かべ書き出した言葉を整理していくと、 一番自分の気持ちにピッタリくるフレーズがだんだん見えてくると思います。どんなフレーズにしたら、その本を読んだことのない人が興味を持ってくれるでしょうか。
③さあ、ポップを作ってみましょう:いちばん伝えたい言葉(キャッチコピー)は、思い切って「大きめに」書きましょう。目安としては、ポップの台紙の3分の1くらいのスペースを使うイメージです。字や絵の上手下手は関係ありません。ゆっくり丁寧に、がポイントです。自分の伝えたい気持ちに合う色やデザインを考えてみましょう。
④ぜひ、ひな中のPOPを参考にしてみてね。
◎師走へ

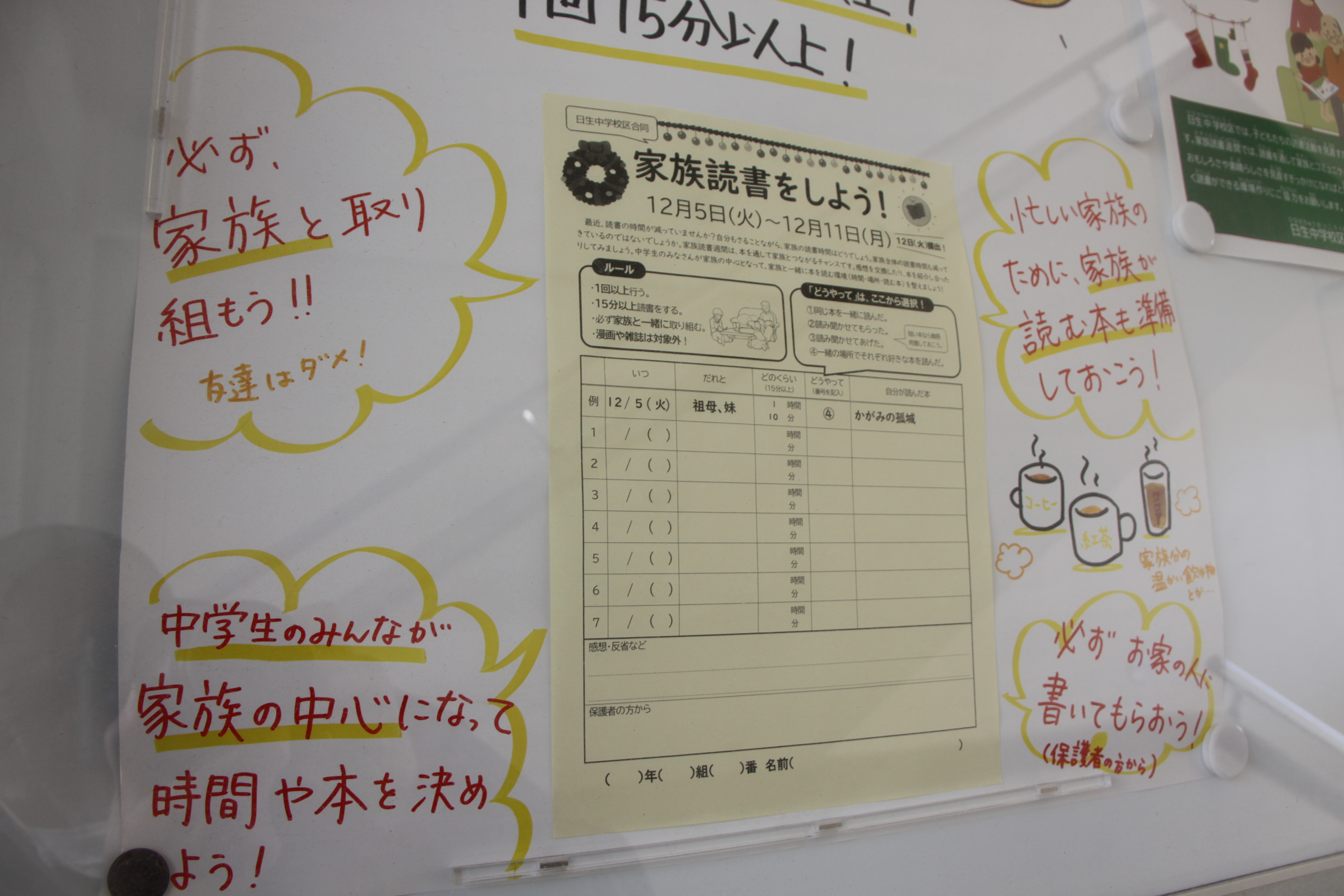
◎多くの人に支えられて(11/29)
今日から、市の規定に従って、地域の資源化物回収BOXを利用させていただいています。ありがとうございます。

◎インフルエンザシーズン到来??!予防 予防 予防 (^Д^)
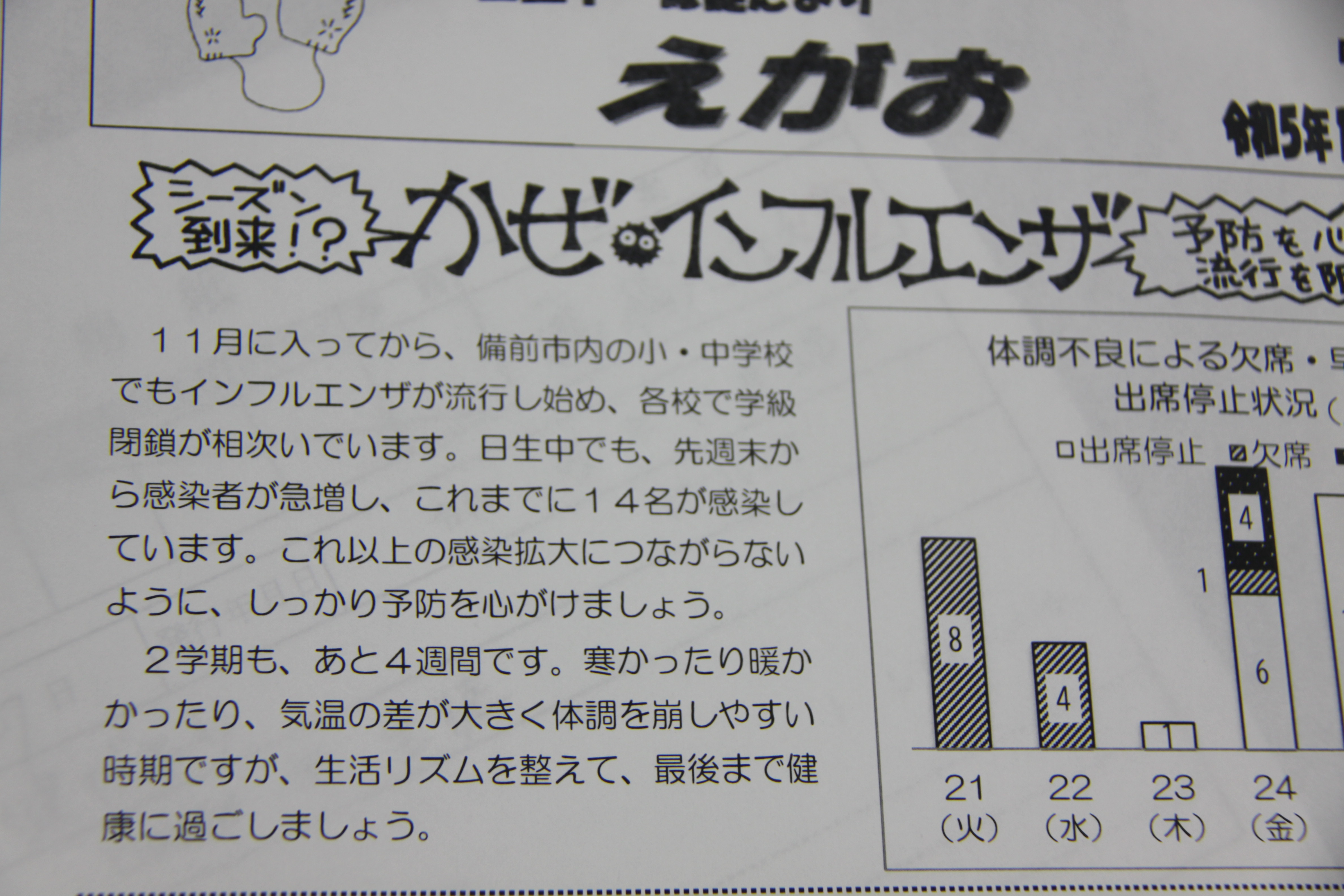
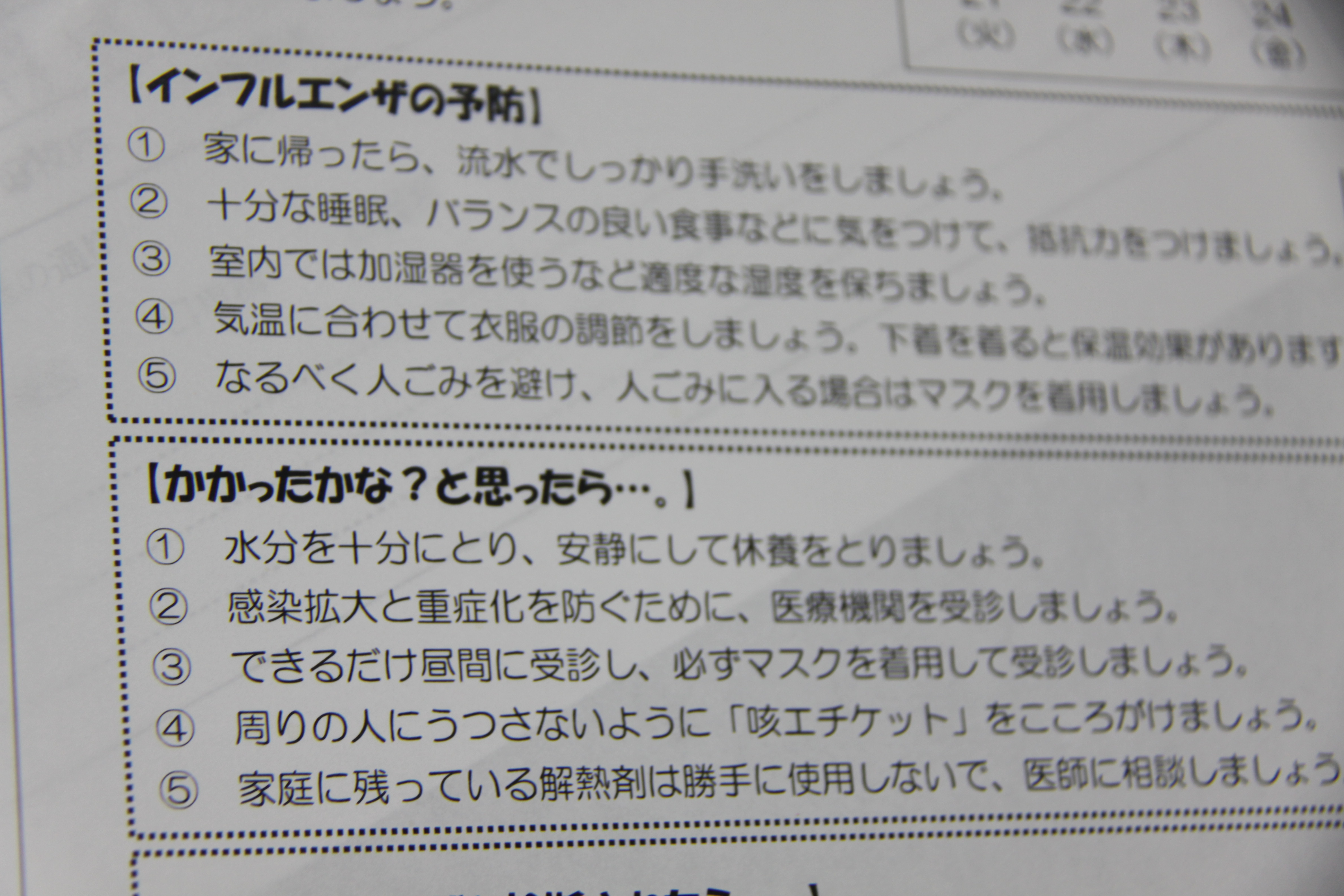
(保健だよりから)
◎学ぶもの 孤独を愛し 戯れよ 想い叶うは 静けさの先
(勉強短歌♯035 11/28・29到達度テスト)

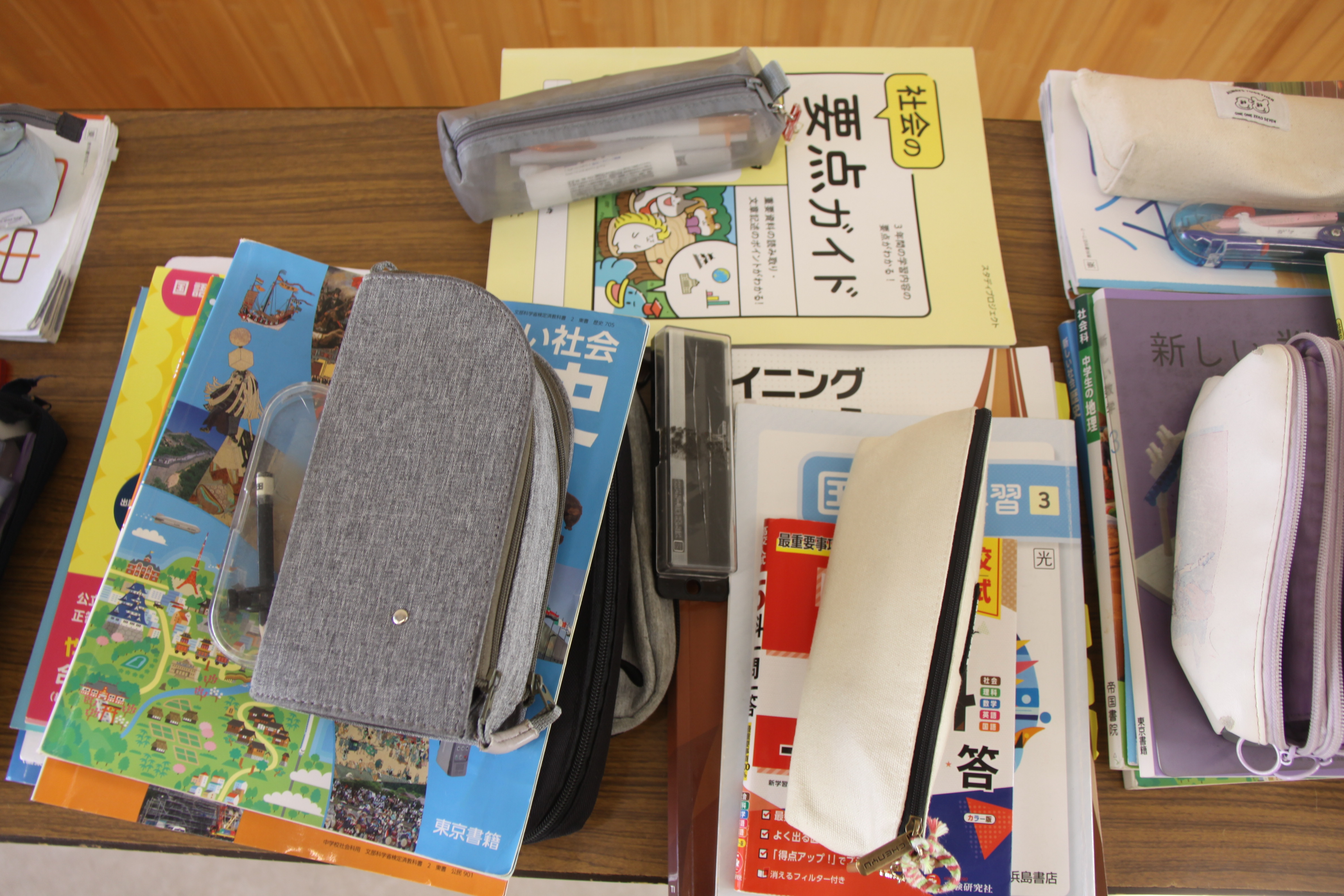

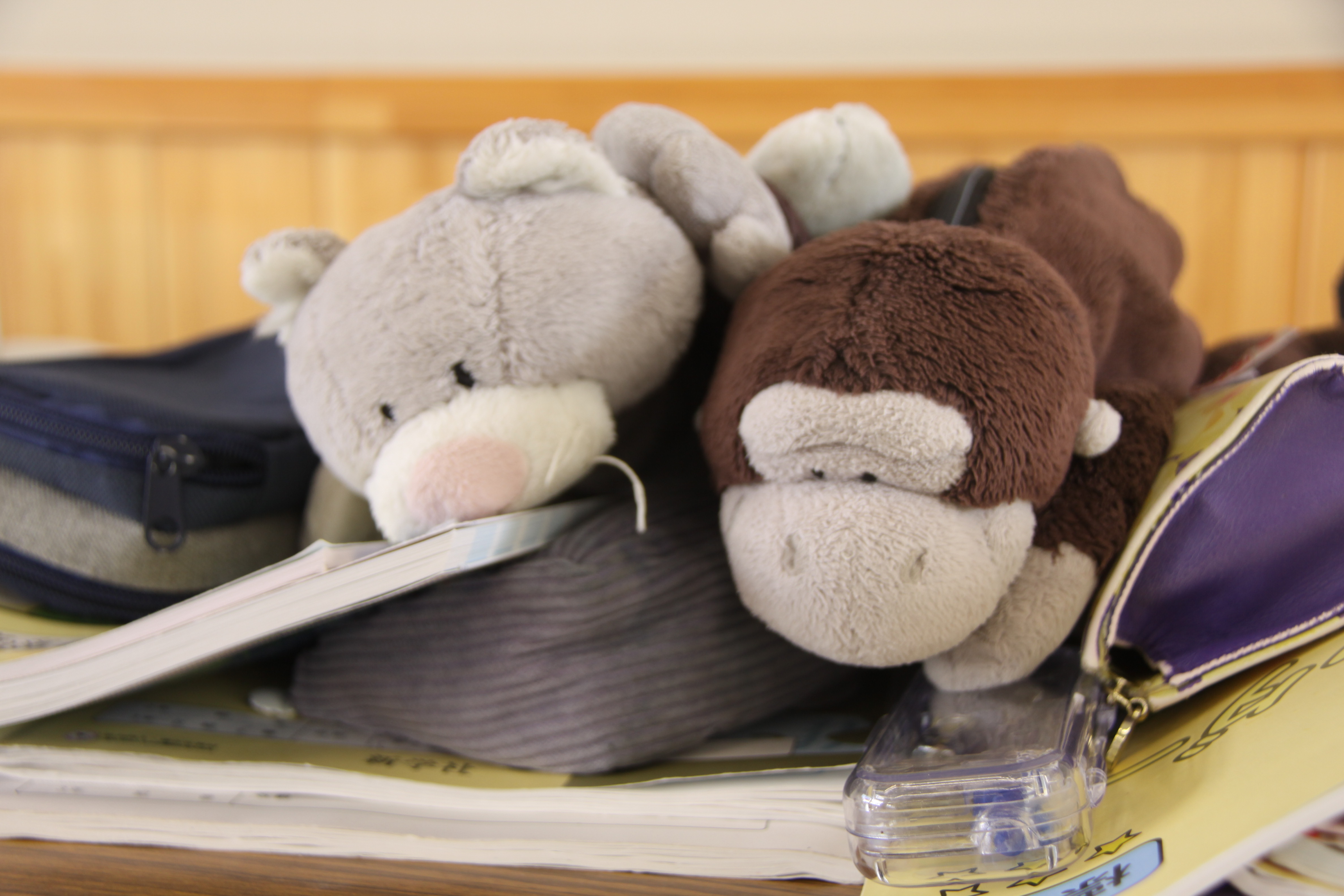
◎多くの人に支えられて(11/28:2学年PTAあいさつ運動)
「いってらっしゃい」「おはようございます」(^0^)






今日、下校時には、備前市青少年育成センターから末廣さん、今吉さんが来校され、あいさつ・声かけ運動、地域巡回指導をしてくださいました。ありがとうございました。
◎やっぱり、テストも仲間とならガンバレル。(11/28 07:49)
~今日から到達度テスト~

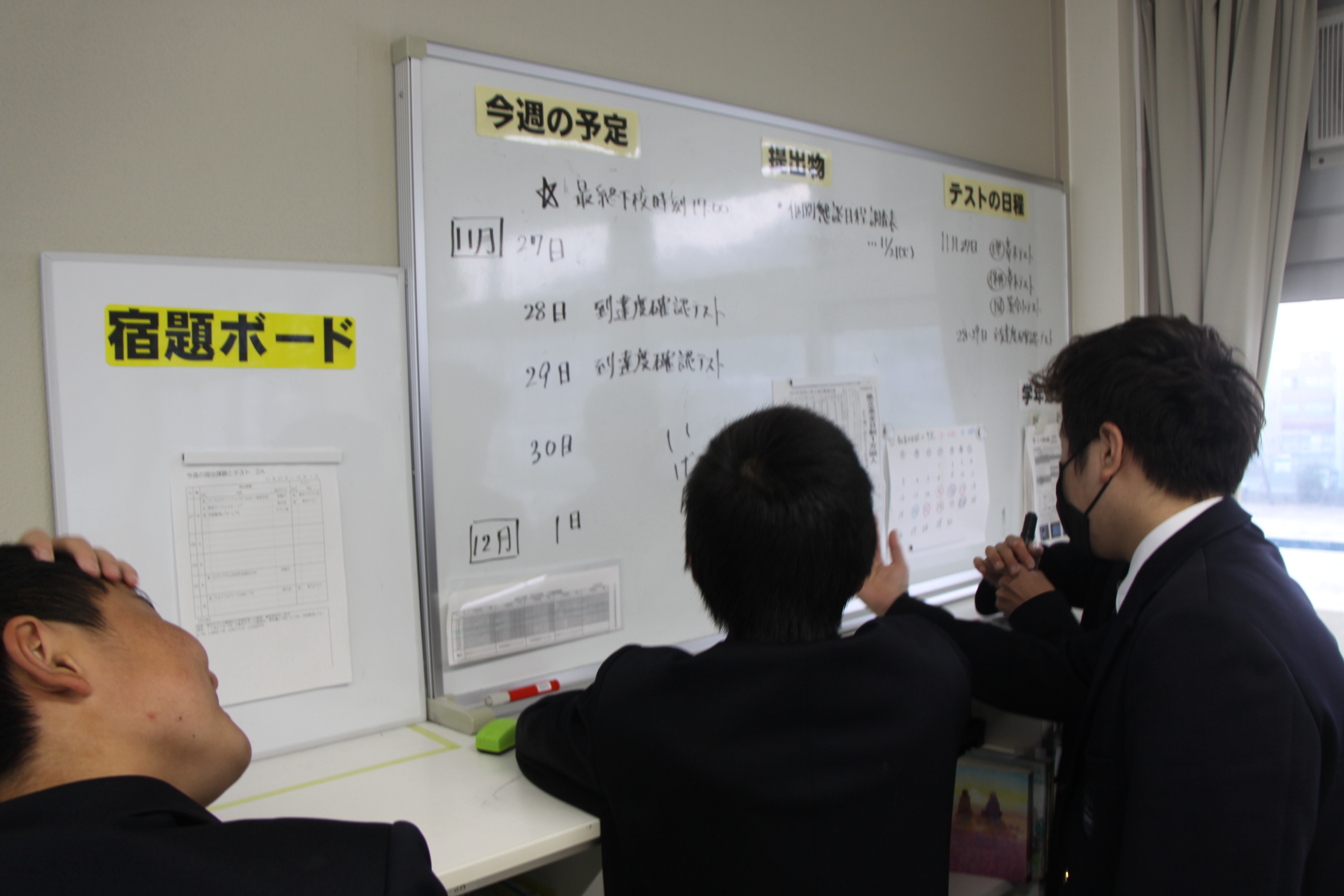
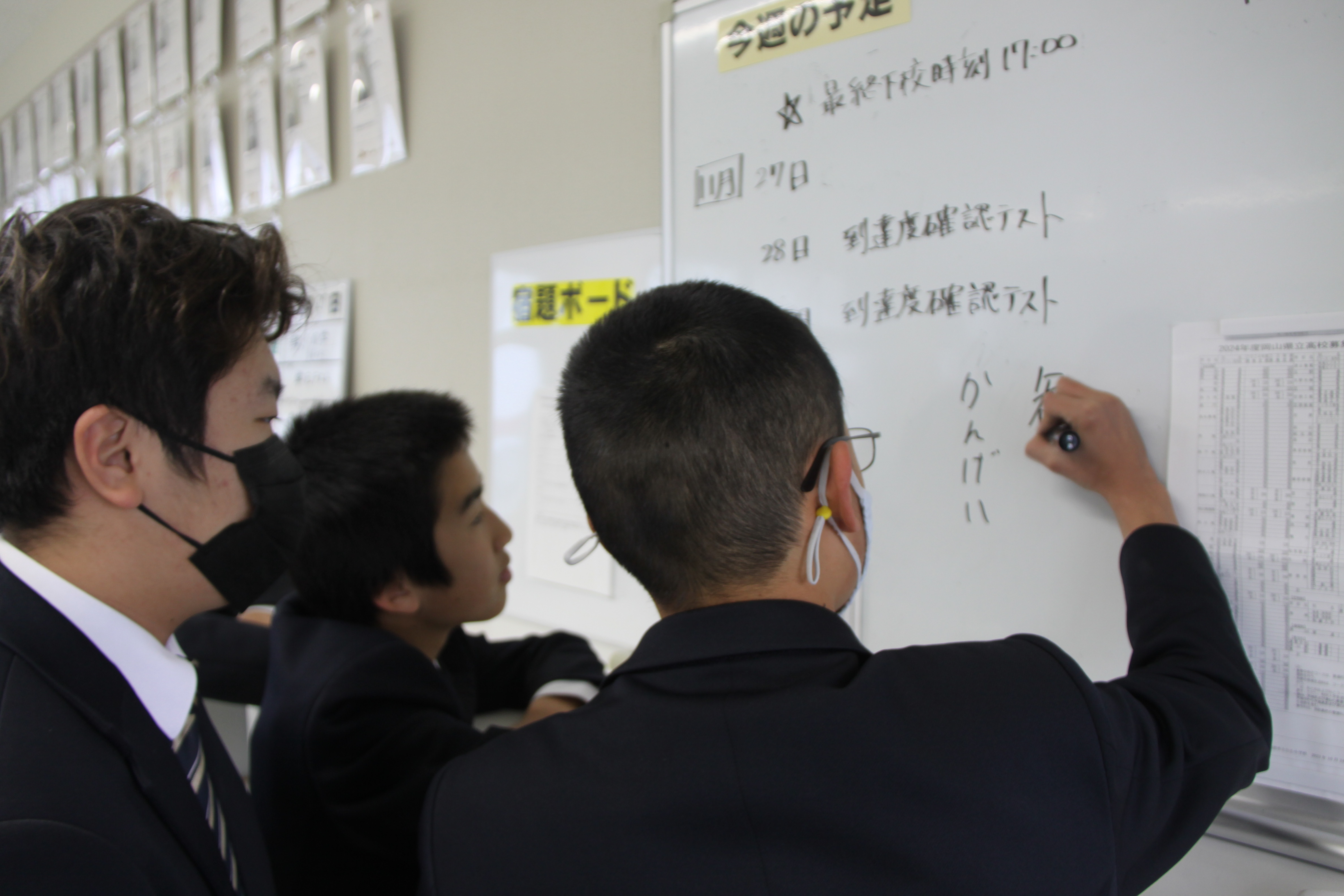
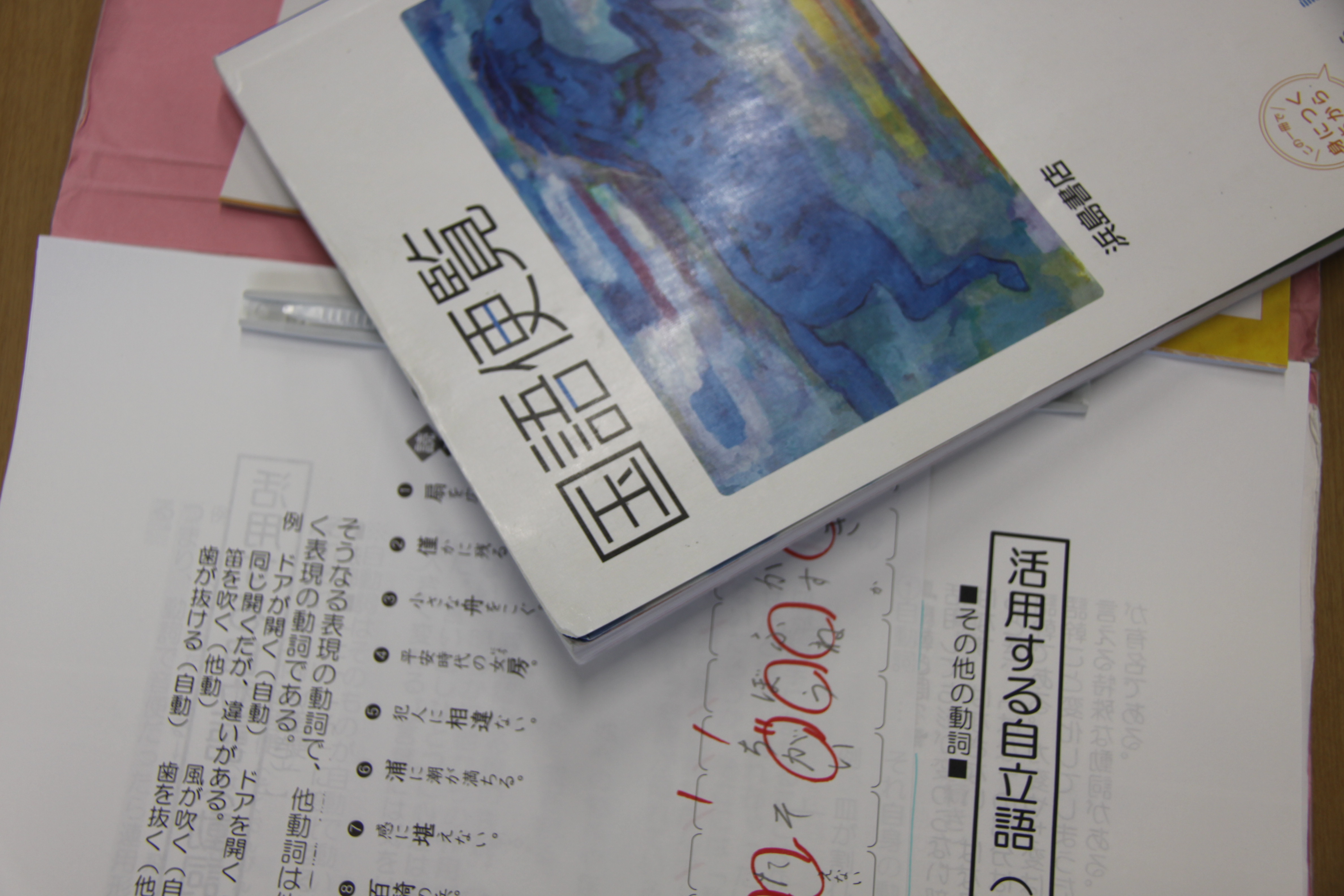
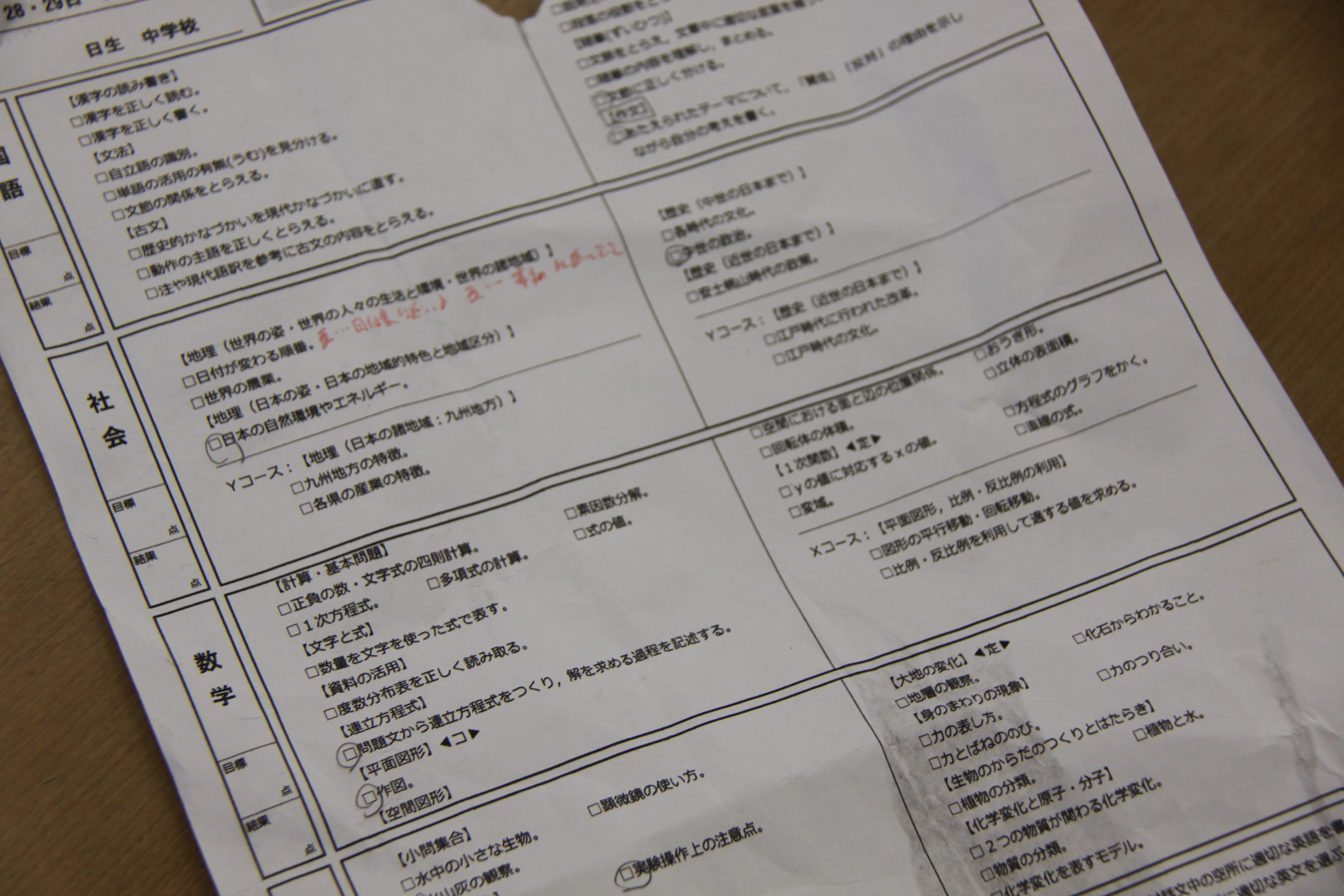

◎あたたかいなかまがいるからあたたかい。

◎みんなのためにえんやこら もひとつおまけにえんやこら
~11月27日、協力してストーブを設置しました。大切に使おうね。授業がんばろうね!そして、給油をありがとうありがとう。






◎師走、生徒会も今日・明日を大事に走ります(11/27)
専門委員会・生徒会執行部会開く

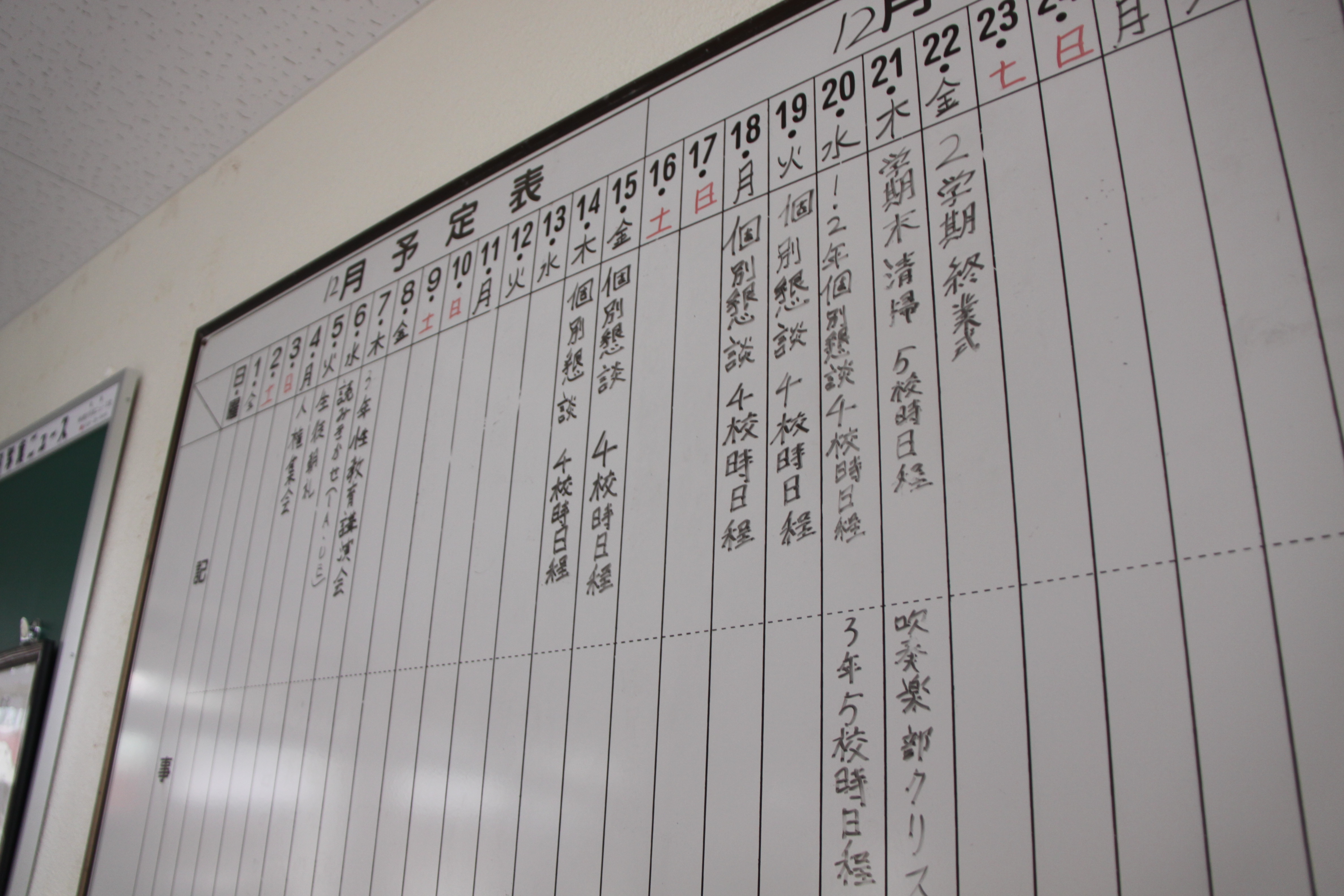
◎つなぐ かがやく ゆめひらく(11/25~26)
~だれ一人とり残さない社会の創造をめざして~
ステキな地元テーマですね!(*^o^*)
第74回全国人権・同和教育研究大会に教頭先生が参加されました。兵庫・京都・大阪を会場に、今年も全国からたくさんの人が集まり、実践報告をもとに語り合う2日間でした。大会は、4つの分科会をもとに21の分散会に分かれ、以下の討議課題に沿って討議していきました。第1分科会「人権確立をめざす教育の創造」では部落問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決をめざす教育をどう創造しているか。第2分科会「自主活動」では、子どもたちの自主的な活動と学習をどのように保障していくか。第3分科会「進路・学力保障」では、子どもたちの未来を拓く進路・学力保障をどう進めているか。第4分科会「人権確立をめざすまちづくり」では、〜地域の教育力・子ども会活動・啓発活動・学習活動・識字運動・文化創造〜部落問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決をめざすまちづくりをどう進めているか。・・・教頭先生が参加した第3分科会第3分散会には、京都府、京都市、熊本、大阪、三重からのレポート報告がありました。

◎多くの人に支えられて
令和5年度備前市立学校体育施設開放事業を活用して、グラウンド整備用の土を購入させていただきました。

◎教えの庭にも 早(はや)幾年(いくとせ)(11/22)

◎わたしたちのテスト週間はじまる(~29日)
到達度テストへ向けて取り組みます。
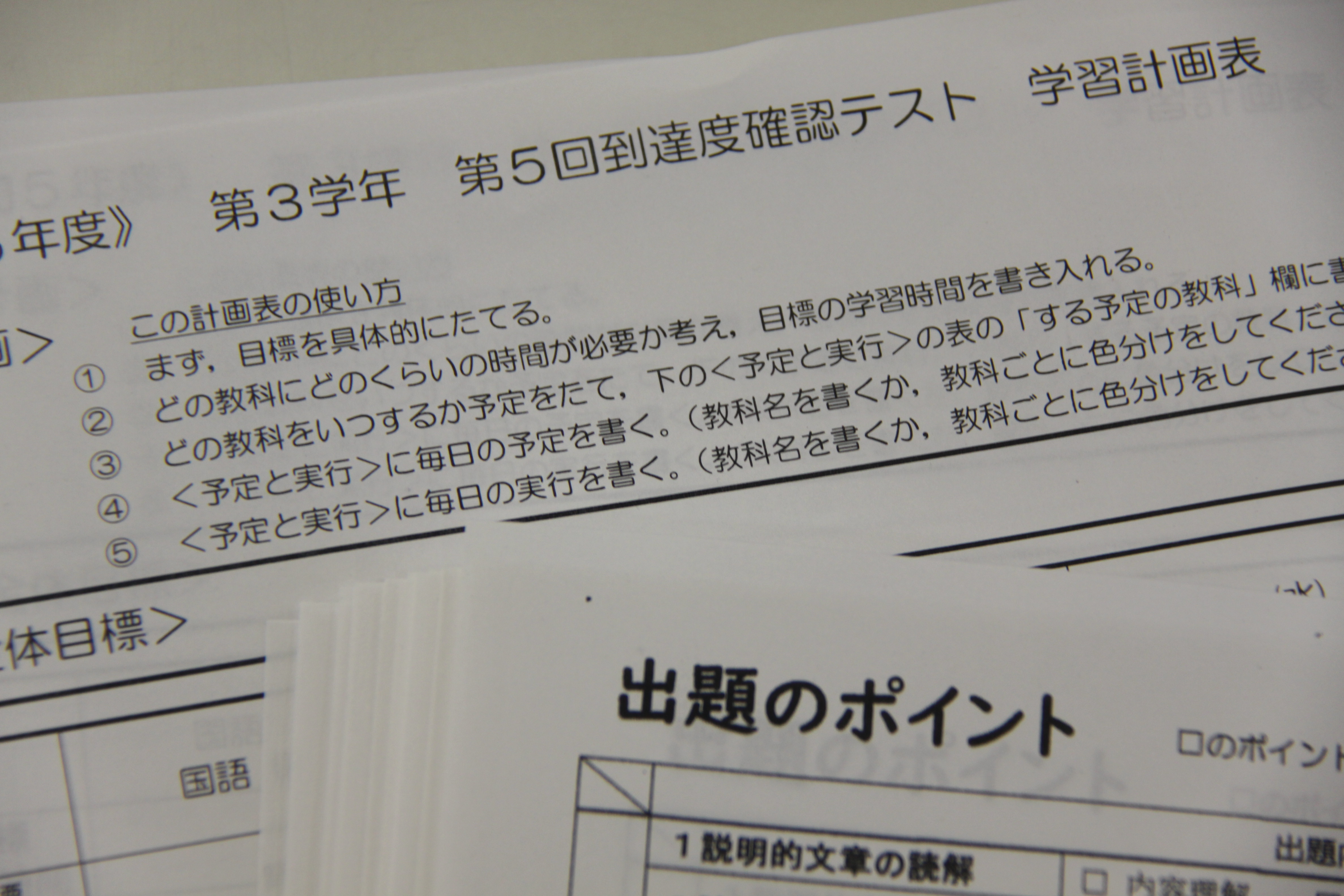
本番では一本の道を通るだけである。備えている時には想定されるすべての道を通る。本番では足はくたびれるだけである。足が丈夫になるのは、備えているときである。 むのたけじ
◎「正しく知り 正しく行動する」ための一歩(11/21)





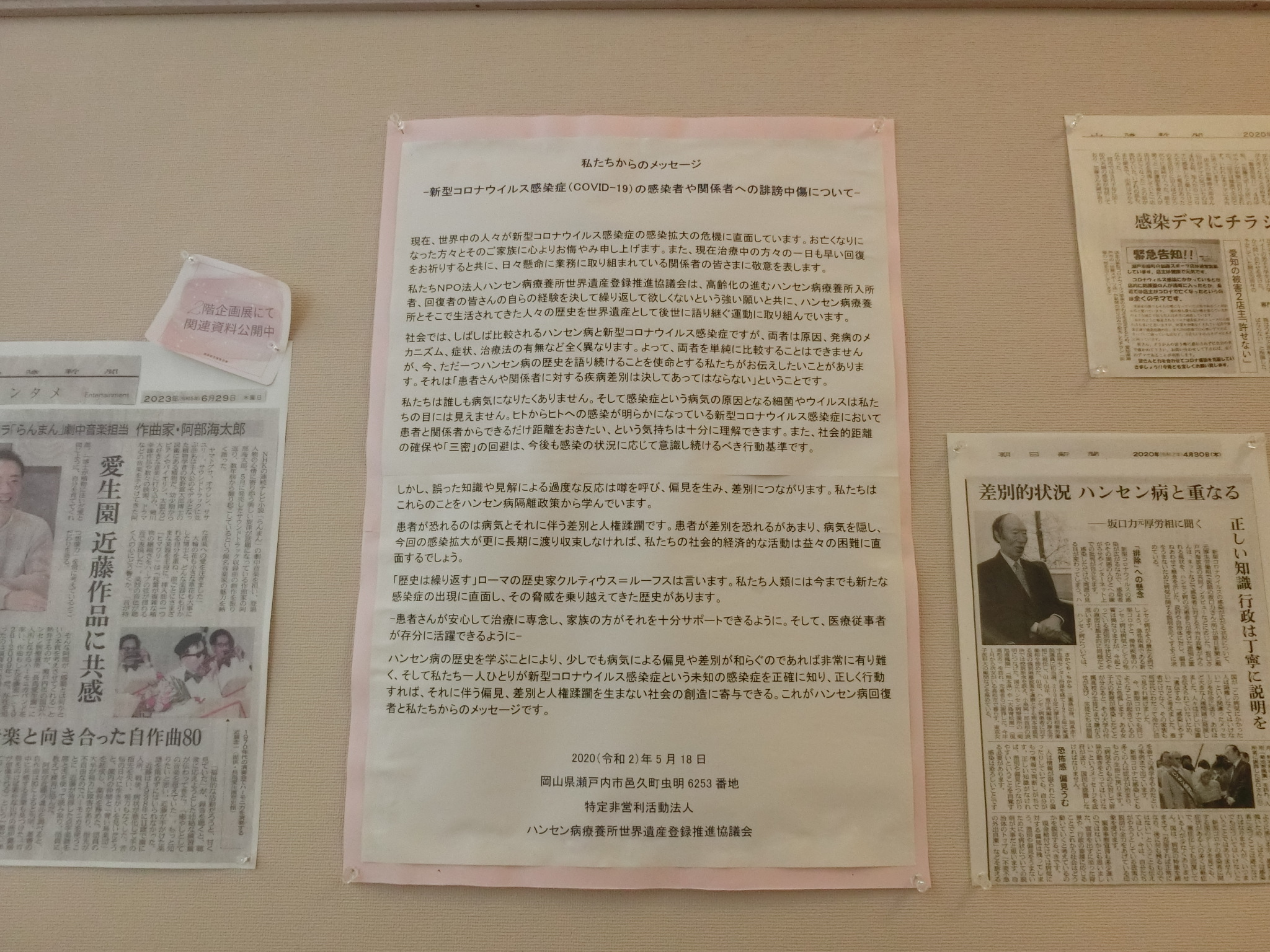
「また、おいで」
◎シン・ヒナセチュウ 2024年版 準備快調
11月20日の職員研修では、本年度の教育活動の反省をもとに、新年度の行事予定の検討を行いました。
また、保護者の方々には、今年度の教育活動を多面的・多角的に振り返るため,学校評価アンケート回答へのご協力をお願いします。今回は、12月初旬に、安心メール(連絡メール)で送付させていただき、そこから回答していただく形式へのご協力をお願いします。また、同様の文書を配布しますので,直接回答し,担任まで提出されても大丈夫です。ご多忙の中ではありますが,ご協力をお願いいたします。


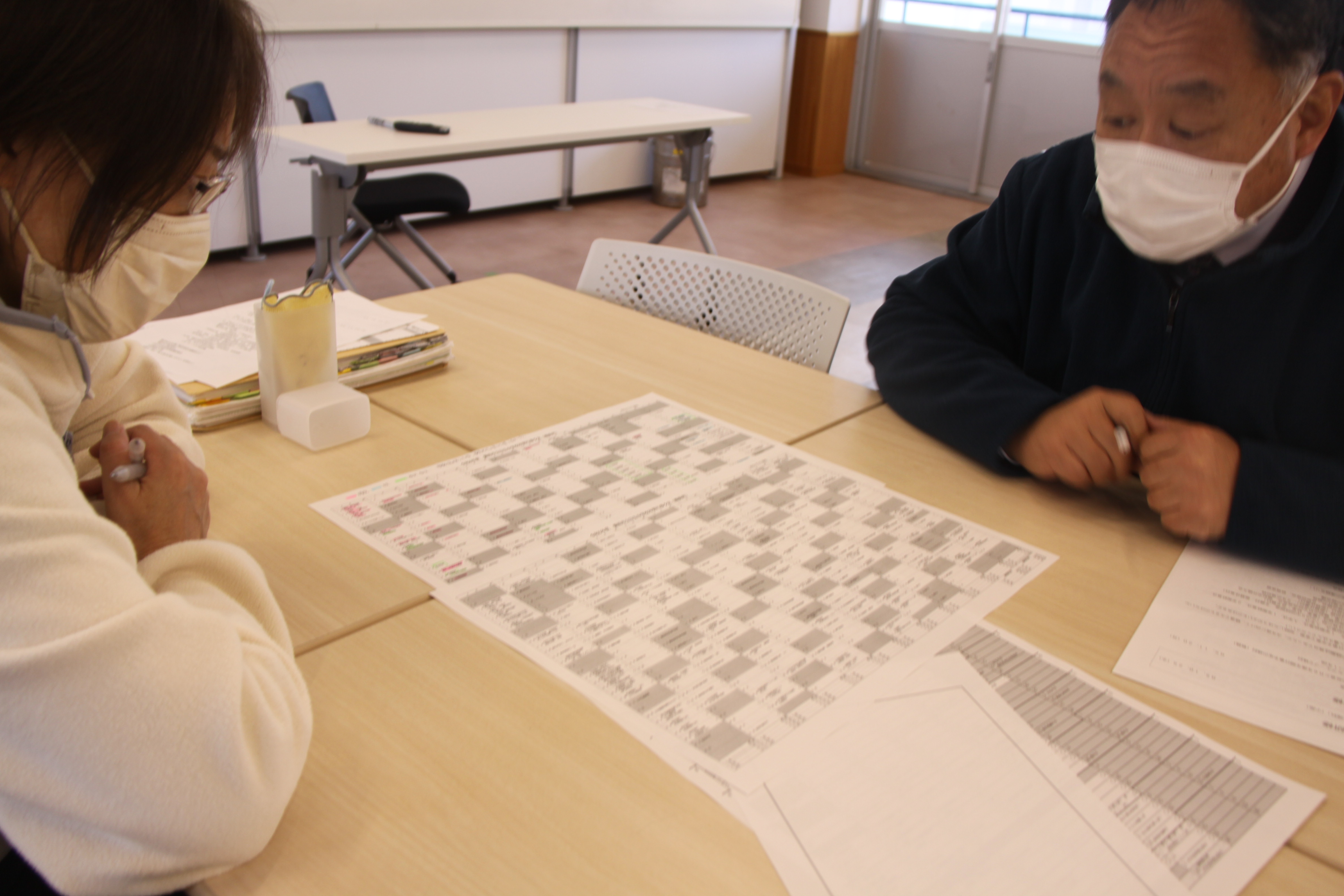
先生たちも同僚性を高めながら。
◎ワタシたちがつなぐナガシマ・ハンセン病問題の歴史
~確かな人権感覚を磨くフィールドワーク(11/20・21)
3年生は、総合的な学習の時間を活用し、PBLの取組のひとつとしてハンセン病問題学習に計画的に取り組んでいます。今日と明日、クラスで分かれて、園内12ヶ所の歴史的施設を巡りながら、学びを深めていきます。船着き場跡~収容所跡~監房跡~万霊山・納骨堂~恵みの鐘~世界遺産推進協議会事務局~一郎道~小川正子碑~恩賜記念館~(新良田教室(高校)跡)~歴史館見学と、約2時間フィールドワークを行います。









〈ひとのあいだ〉「人権と共生の時代」と言われる二十一世紀。しかしそれは与えられるものではありません。譲ることのできない“人権”と“共生社会”に実現のために、いま私たちは何をすべきなのか、どう生きていくのか、そのことが問われています。
ハンセン病は、昔は「らい」とか「らい病」と呼ばれ、人間にとって最も忌み嫌われてきた病気でした。現在日本には、ハンセン病治療のための国立療養所が13ヵ所、私立の療養所が2ヵ所あり、全国で927名(2022年)(*1333名(2018年)*2600名(2010年)が療養生活をおくっています。愛生園の入所者は2桁を切りました。そこで暮らす入園者の方々は、すでに病気が完治して何十年も経過している人ばかりです。国は、1907年からハンセン病患者を強制的に療養所に隔離する政策を続け、1996年に「らい予防法」が廃止されるまでの90年間、(2001年には、ハンセン病国賠訴訟で国の強制収容で違憲性が認められましたが)教育を受ける権利や社会生活を営む権利、結婚の自由など、人間としての基本的な権利を奪ってきたのです。
国の強制隔離政策とともに、「ハンセン病」問題についての正しい知識や理解がないために、さまざまな差別や偏見も生まれてきました。科学が進歩し、ハンセン病の適切な治療法が確立し、「不治の病」ではなくなった現在においても、ハンセン病に対する差別や偏見が根強く残ったままです。家族訴訟勝訴後のうごきをみてもまだまだ偏見や差別は厳しいと感じます。そうした厳しい社会状況の中を生き抜いてきた入園者を支えてきたのは、どのような思いであり、願いだったのでしょうか。家族や社会から隔絶され、非人間的な扱いを受けながらも捨て去ることがなかった家族への思いや人間回復への願いは…。入所者の方々の高齢化が進む中、次世代を生きる私たちは何をすべきか。私たちは、ハンセン病問題学習、入所者(回復者)であった金泰九さんの豊かな生き方にふれ、「自分たちの社会のありかた」を見つめ、「自分たちの社会をどうつくっていくか」を深く考え、行動することができるはずです。
学んだことを展示パネルにし、地域へ発信しようと思います。また、世界遺産登録推進協議会の釜井事務局長からお話を聴き、「顕著な普遍的価値の言明」にも取り組む予定です。
◎ワタシたちがよりよい社会をつくるために
備前市青少年健全育成大会開催
11月19日(日曜日)、吉永地域公民館で青少年健全育成大会を開催しました。
明るい家庭づくり作文最優秀作品の朗読発表や市内中学生弁論大会最優秀者の本校、石橋さんの発表、高校生による意見発表が行われました。また、青少年健全育成啓発ポスター最優秀賞受賞者の半田さん、山﨑さん、森下さん、木下さん、法師さん(5名中4名が本校生徒)が表彰されました。続いて劇団「花みずき」による青少年健全育成啓発劇が行われました。



◎読書月間~読み語り&本紹介(11/17先生Ver)
もっと楽しく もっと広く もっと深く 自分らしい本とのつきあい方を。








読書月間での先生からの読み語り&本紹介をしましたが、もう一冊だけ追加紹介です。(_ _)
『あん』:ドリアン助川さんの小説(仏訳は、2017年度 le Livre de Poche 読者大賞 Prix des Lecteurs を受賞)。映画にもなりました。
元ハンセン病患者の老女徳江、前科があり借金を背負ったどら焼き屋の店長千太郎、自分の生きる居場所を見つけかねている女子中学生ワカナの三者の交流を通じて、すべての人、いや、すべての生きものにとって生きることの意味とはなにかという普遍的な問いが、映画の中にも映しだされています。映画の終わりの方で、朝日に暖められ湯気を出している木に徳江が凭れている映像にかぶせて、徳江が死の直前に千太郎とワカナに宛てて残した録音メッセージが流れるシーンがあります。そのメッセージの中にこんな一言があります。
〈ねえ、店長さん。私たちはこの世を見るために、聞くために生まれて来た、だとすれば、何かになれなくても、私たちは、私たちには、生きる意味があるのよ。〉と。
ドリアン助川さんが、小説の発売記念イベントでこんなことを語っています。
『「人の役に立つこと」が生きる意味だ。「社会の役立つこと」が自分の生きてきた意味だ。そこに違和感があった。我々の生まれてきた意味が「社会・人の役に立つ」ことだけだとしたら、じゃあなんで人の役に立たないトンボはあんな綺麗な羽をしているの?とか蝶々の羽の模様はなんであんなに美しいの?とか、役に立つとか立たないとか全然違う次元で我々は生まれてきたのではないかと思う。生きる意味や価値も、人間が勝手に決めていること。幸や不幸さえも、人間が勝手に感じていることであって、自然の中では、幸や不幸はない。』
◎日生で輝く 日生が輝く(11/16)
赤い羽根共同募金活動を、前回に引き続き、社会福祉協議会さんのご支援をいただき、パオーネさんでさせていただきました。
声かけをさせていただく私たちを見て、募金と共に「がんばってね」「応援しているよ」とお声掛けしていただいた方がたくさんいらっしゃいました。
11月も中旬となり日暮れも早く、またここ最近、寒さも気になる中でしたが、この日もにたくさんの応援と募金をいただきました。皆様のお声掛けがあり、2日間、元気よく街頭募金活動をすることができました。この募金は、地域社会の高齢者、障がい者、災害時の時の支援などに使われます。募金期間は、令和6年3月末までです。引き続き、ご協力をお願いいたします。
2日間、本当にありがとうございました。 日生中学校生徒会執行部・ボランティア参加者 一同



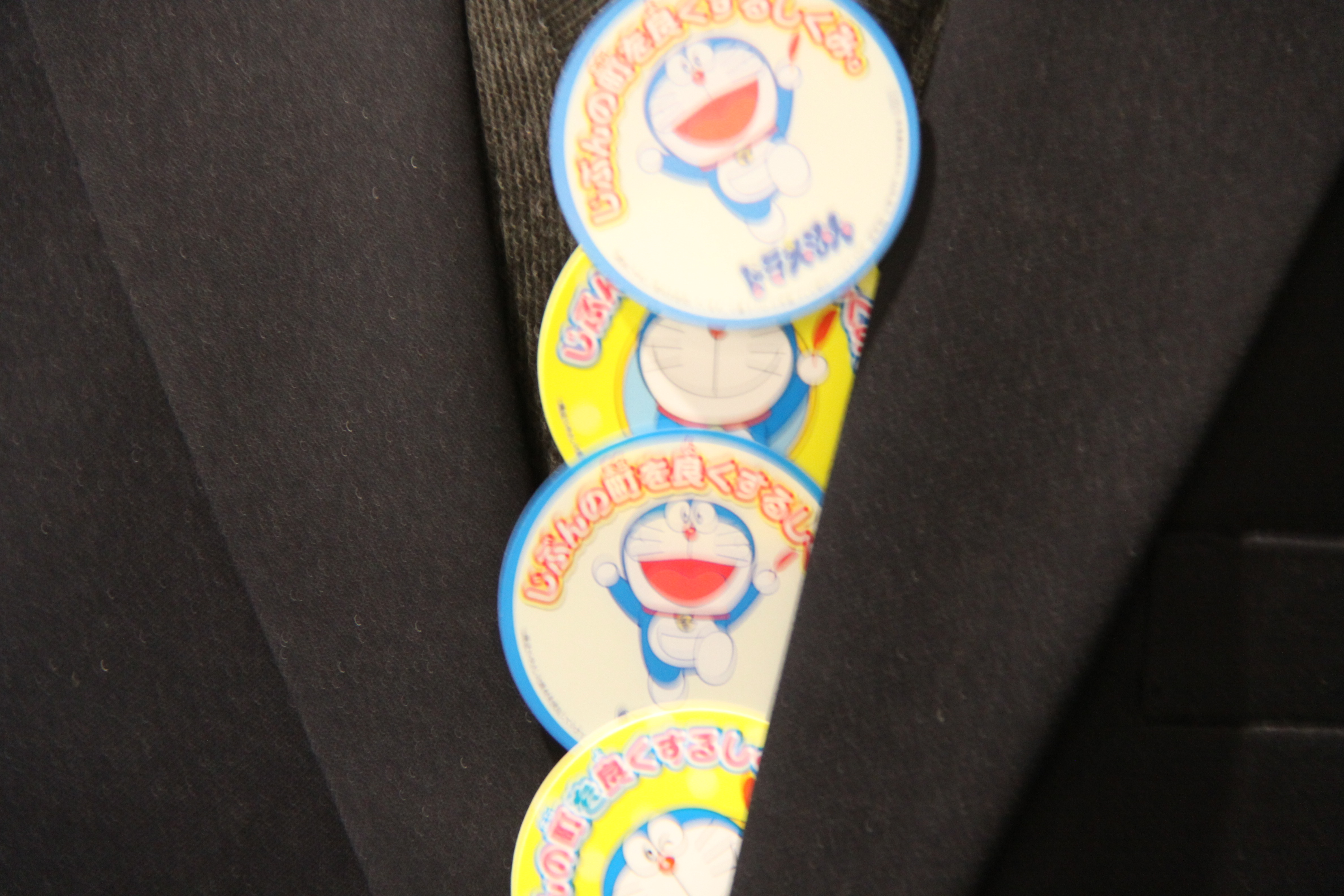


◎なかま・経験・チャレンジから確かな学びを手に。
2年生家庭科(11/15・16)
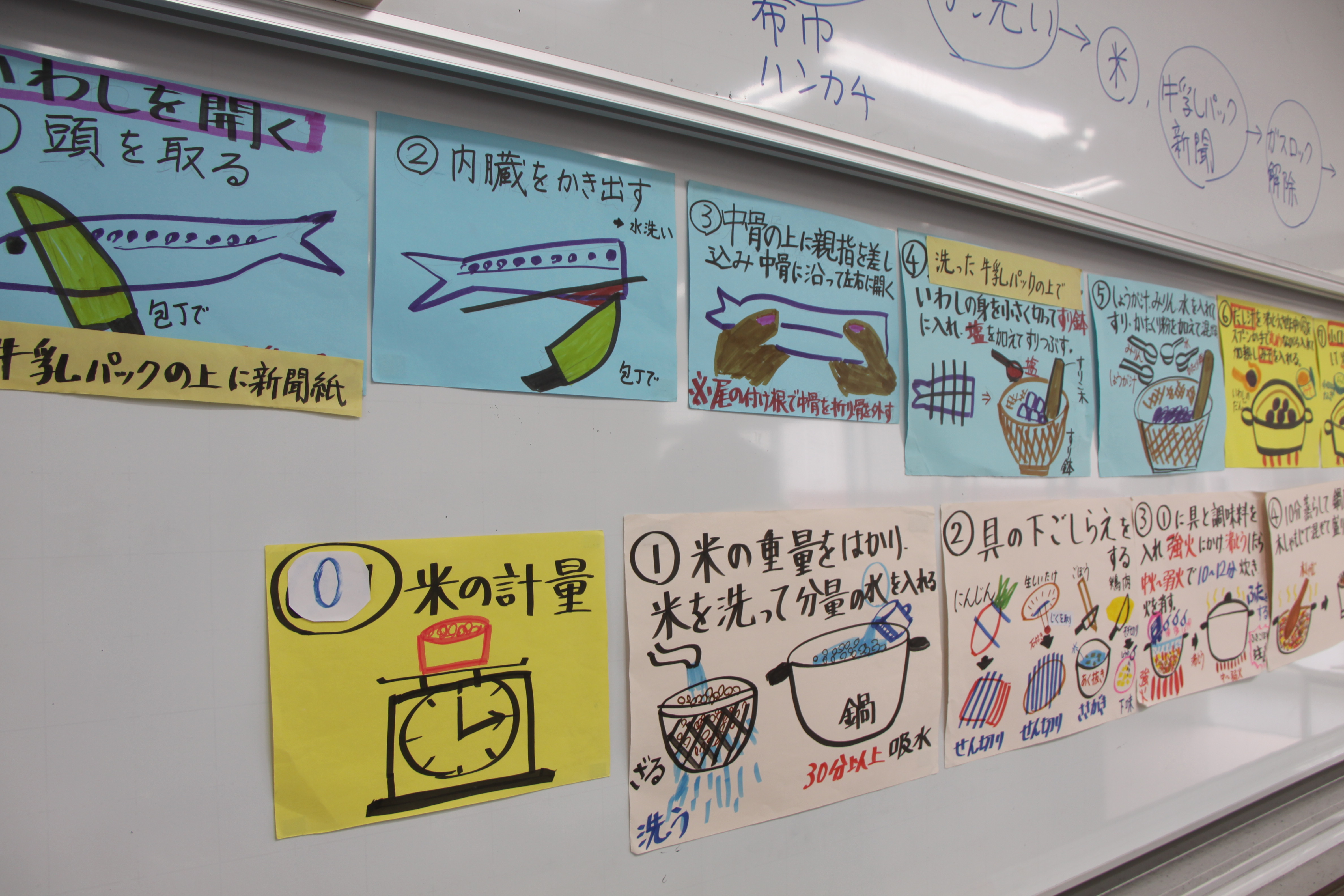











みんなでいただきましょう。ありがとう いただきます(^O^ 2年団)
◎服装検査!!ではなく、理科授業のために荷物を量っています。
~〈ゆたかな学習〉から〈たしかな学び〉を(11/16)

 5㎏!結構重い。
5㎏!結構重い。〈仕事と仕事の原理、仕事率〉仕事のF-sグラフ
理科では、物体に力を加えて、その力の向きに動かしたとき、仕事しごと(英語: work)をしたという。仕事は、力の大きさと力の向きに動いた距離との積のことである。
・仕事 = 力 × 力の向きに動いた距離
・仕事の単位は‚ 力の単位に距離の単位をかけたものである。力の単位としてN (ニュートン)を用い‚ 距離の単位としてm (メートル)を用いた場合の仕事の単位は N m となり‚ これはJ (ジュール)という名前がついている。単位時間あたりにする仕事を仕事率しごとりつ(英語: power)という。
・仕事率=仕事 ÷ かかった時間:仕事率の単位は‚ 仕事の単位を時間の単位で割ったものである。仕事の単位としてJ (ジュール)を用い‚ 時間の単位として秒を用いた場合の仕事率の単位は J/sとなり‚ これはW(ワット)という名前がついている・・・。
◎ひな中の風~~GROW UP WEEK
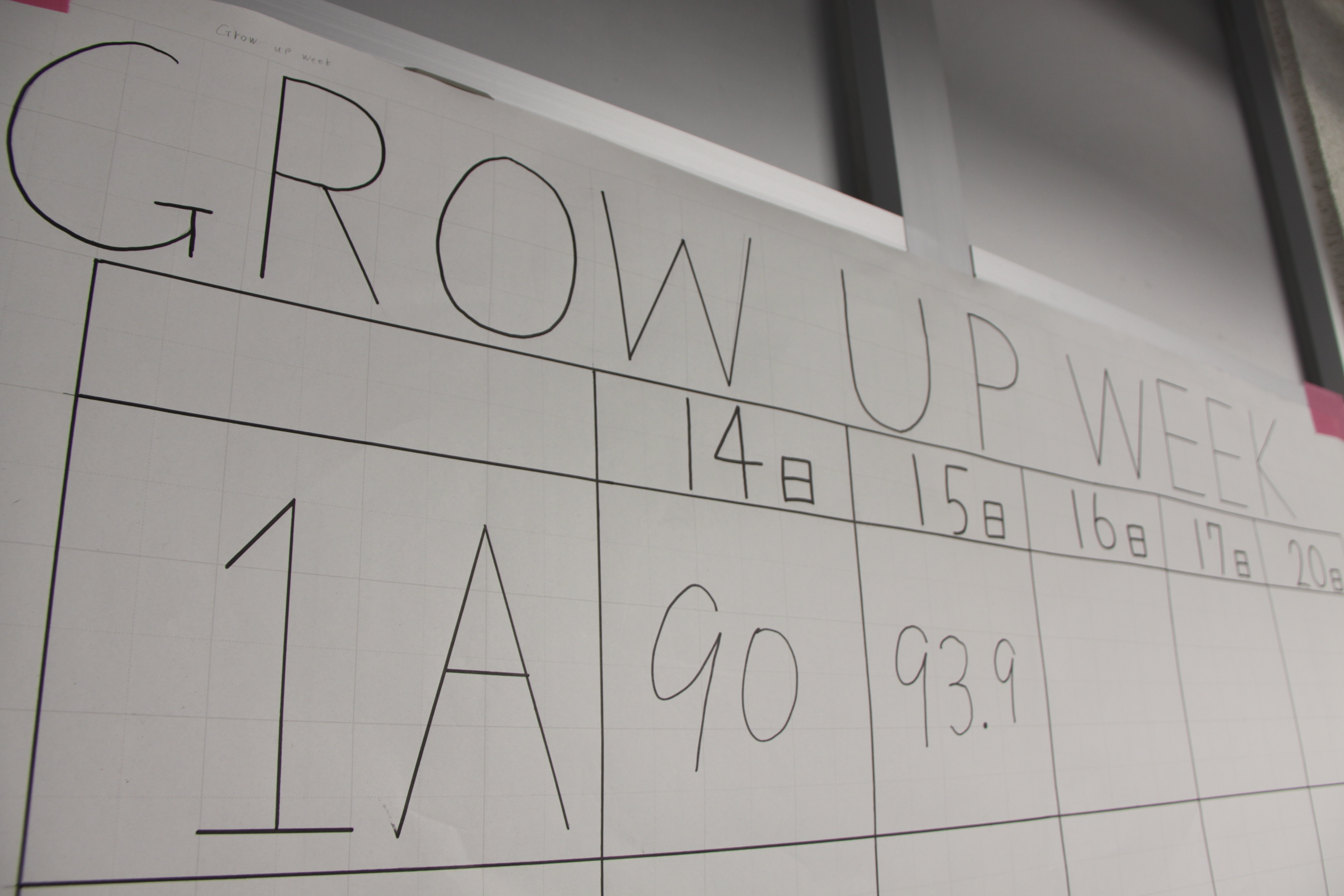
◎ともに学び続けるということ
第2回金泰九さんに学ぶ教育実践交流会に本校の教頭先生が参加されます。
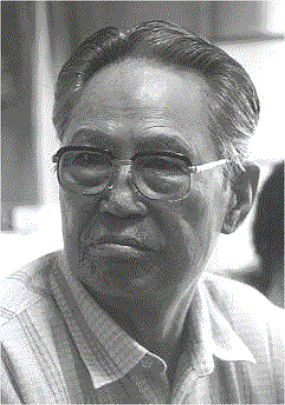
〈正しく知り 正しく行動する〉
金泰九(キムテグ)さんは、生前「ハンセン病問題」に関する学習会や講演会で小中学校へよく行かれていました。晩年には有志の方々と、ドキュメンタリー映画『虎ハ眠ラズ』が制作されました。本校3年生もこの映画を視聴し、映画の中の金さんに出会うことができました。この学習ののち、
3年生は、20・21日に愛生園に現地研修に訪問し、その後、世界遺産推進協議会事務局長の釜井さんをお招きしての授業を予定しています。
今週末(11/18)に開催される「金泰九さんに学ぶ教育実践交流会」の案内資料の一部を紹介します。
《~金さんの生き様から私たちの生き方をみつめること
想像を絶するような過酷な人生を歩んでこられたはずなのに、限りなく、やさしく、豊かで深く、そして勁(つよ)い。大らかな人柄と穏やかな語り口が醸しだす何とも言えぬ柔らかさに誰もが引きつけられ、全国各地に息子や娘が次々と生まれました。私たちの仲間たちもそのひとりだと自負しています。金泰九(Taegoo Kim)さんが亡くなり、はや8年が経とうとしています。その年の夏祭りでは花火が打ち上がる夜空を見上げ、江州音頭の太鼓の音に酔いました。10月には近しい仲間らと90歳のお祝いをし、コカコーラを飲み、アリランを一緒に歌い、楽しい時間を過ごさせていただきました。また来園することを約束して別れましたが、2016年11月19日早朝に逝去の知らせがありました。
金さんは1926年現在の韓国陜川(ハプチョン)生まれ、12歳で父を頼って日本に渡って来られました。1945年旧陸軍兵器学校卒業直前に日本の敗戦で復員します。1949年旧大阪市立商科大学(現大阪公立大学)在学中に発病し、1952年に強制隔離され、亡くなるまでの約60年間の大半を長島愛生園で暮らされました。原告に先頭となって加わった国賠訴訟は2001年、熊本地裁が国の強制隔離政策を違憲と判断し、勝訴します。その後は戦時中、日本の統治下で強制隔離政策が行われた韓国・台湾の元患者の補償問題も支援されました。2007年にまとめた自伝『我が八十歳に乾杯~在日朝鮮人ハンセン病回復者として生きた~』(牧歌舎)には金さんの生き様の一部が書かれています。
『…人権侵害のらい予防法を廃止するにおいて、法廃止に消極的態度をとっていた私は自分を恥じるのである。その理由なるものは、「功利的」な考えでしかなかったからである。それ以来私は「人権を」全てに優先して考えるようになった。「自他ともの人権を」である。全ての事象が人権と関わっている気もするのである。その場合、人権を最優先にして考えてみると、ことに理非が明瞭にみえてくる気がするのである』2022年11月19日は金さんが亡くなられて7年目にあたりました。在りし日を偲ぶとともに、教育に携わる者として、金さんからの学びや意志を引き継ぎながら、各地ですすめている実践を交流しました。そして今年、11月18日、第2回交流会を開催します。長年、金さんと交流を深めてこられて斉藤さん(毎日新聞記者)の記念講演、そして岡山と三重からの実践報告を通して、今年も学び合いましょう。》
◎多くの人に支えられて。(11/16)
たくさんのことを学ぶことができた避難訓練でした。消防本部から頂いた学習資料をご家庭に配布しました。


準備・片付けをありがとうございます。
◎正しく知り 正しく行動する(11/15)
第2回避難訓練。地震の発生を想定し、授業後の休憩時間間に実施しました。今回は、実施の時刻や内容等は事前に知らせず、緊急地震速報を受けての想定で訓練を実施しました。「災害はいつも起こる可能性がある」という意識を高めるために、今後も工夫及び改善を加えていきます。今回の訓練では、内容を知らせず実施しましたが、各クラスとも静かによく放送を聴き、地震の被害で使用不能な場所を迂回し、安全を確認しながら『正しい情報を手に入れ 正しく行動する』避難ができました。



〈ひとのあいだ〉ちょうど100年前の9月6日に「福田村事件」が起きました。 この出来事をもとに今年、『福田村事件』は映画となりました。
関東大震災直後、「朝鮮人が井戸に毒を投げた」といったデマが広がり、各地で、予備役といった在郷軍人や消防団などで結成された“自警団”によって、次々と朝鮮人の虐殺が行われました。当時を描いた絵巻には、刀などで朝鮮人が襲われる様子が描かれています。
こうした混乱の中、現在の千葉県野田市で日本人9人が殺害された「福田村事件」がありました。香川県から薬を売るために15人の日本人が村に来ていたところ、自警団の一部の人に朝鮮人だと疑われたことなどをきっかけに襲われ、子どもや妊婦を含む9人が亡くなりました。
それから、100年後の今年、9月6日、遺族など約80人が集まり、追悼式が行われました。事件を語り継ごうと追悼式を主催した市川さんは「無知からこの差別も生まれますから。差別の究極は人の命が奪われるってこと」と話しました。また、「福田村事件」の遺族の方は「当時の時代背景の中で、そうさせたことを直視するべきだと私は思います。デマをながした元が原因というか。ひょっとしたら家族や子どもを守るために(自分も)参加していたかもわからない」「(大切なのは)やっぱり差別をなくすこと。偏見・差別っていうのは人を狂わせるし、人を殺す。最大の人権侵害だと私は思います」(9月6日放送『news zero』より)抜粋
◎自分らしい学習方法を大切にしています。(晩学習)


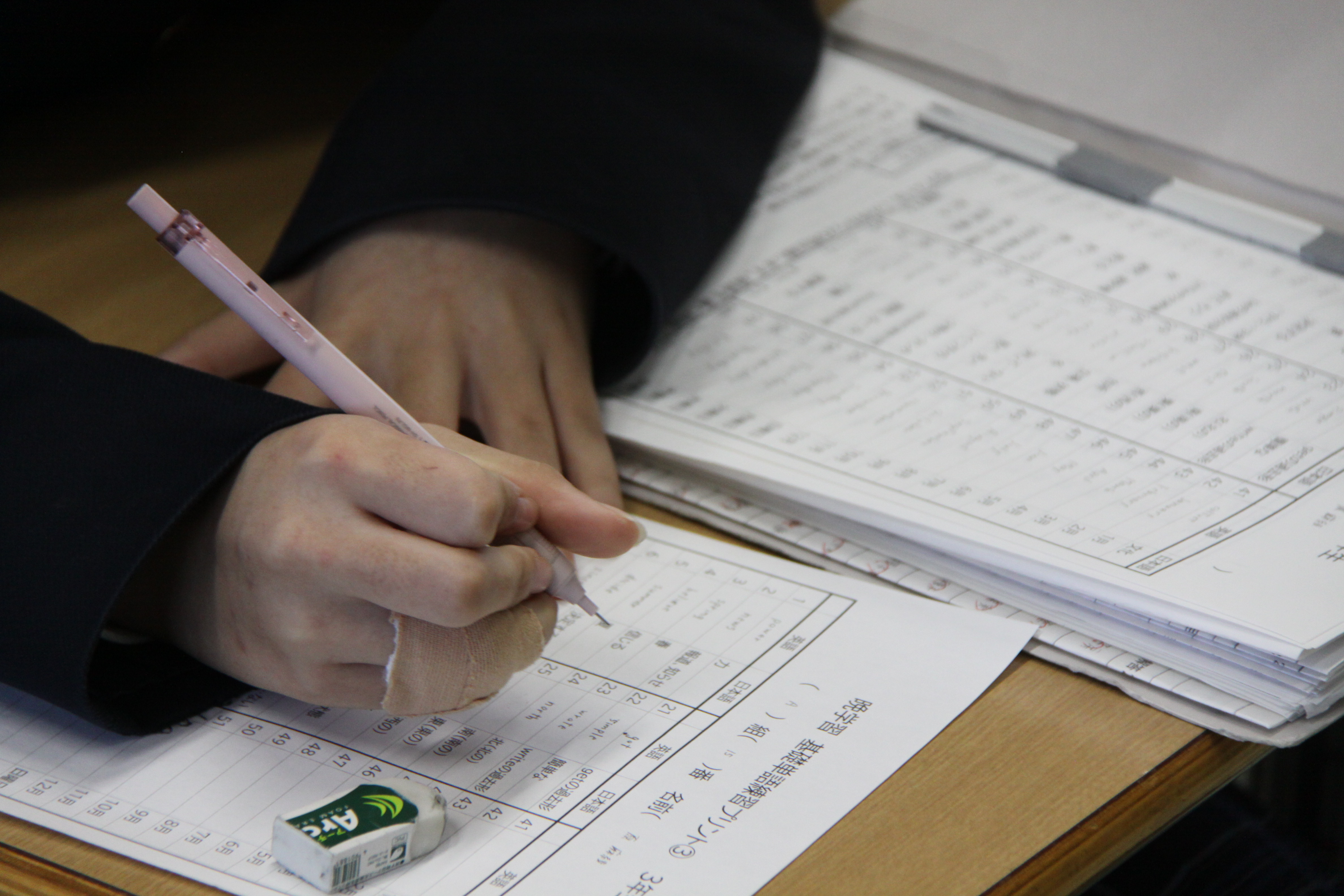

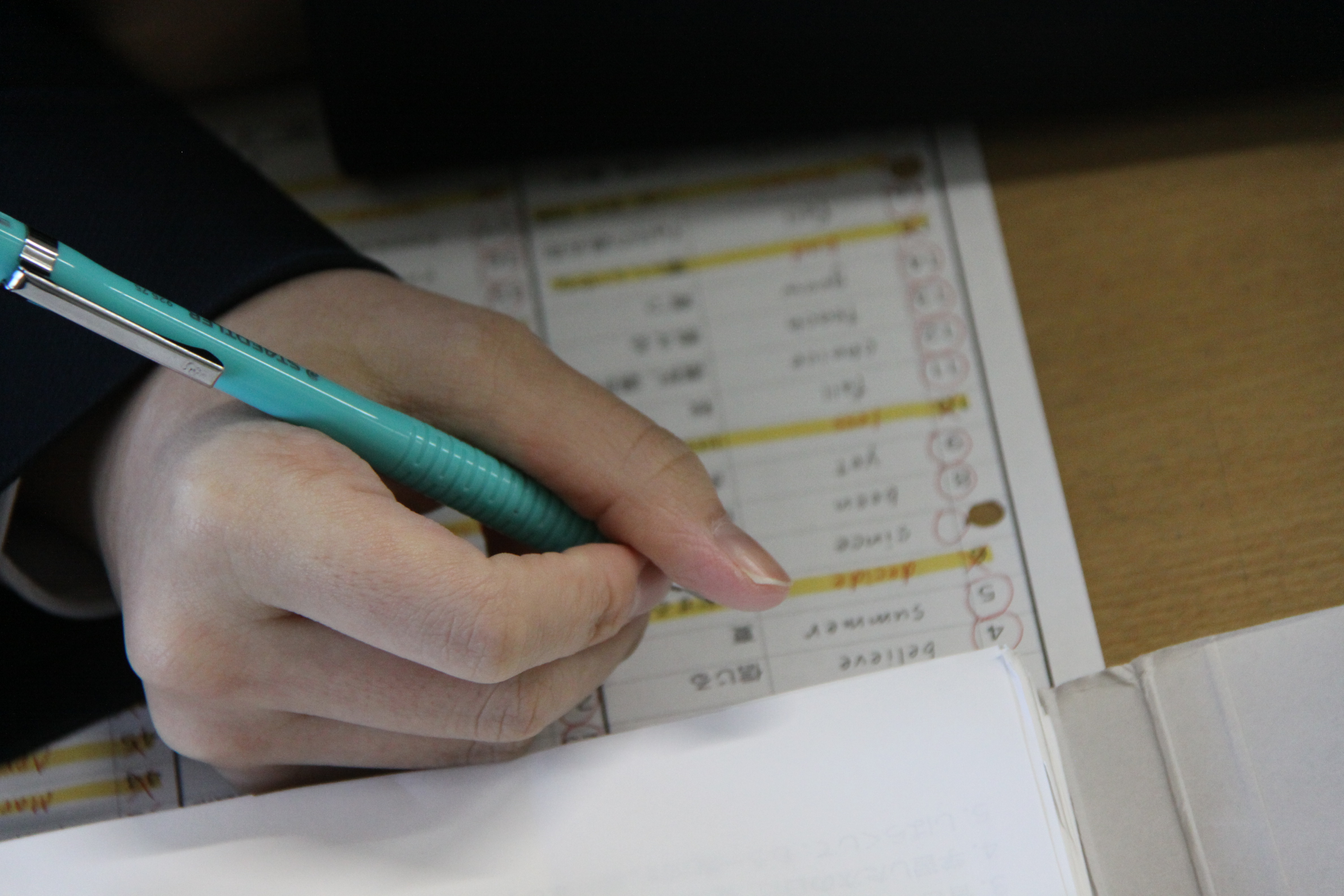
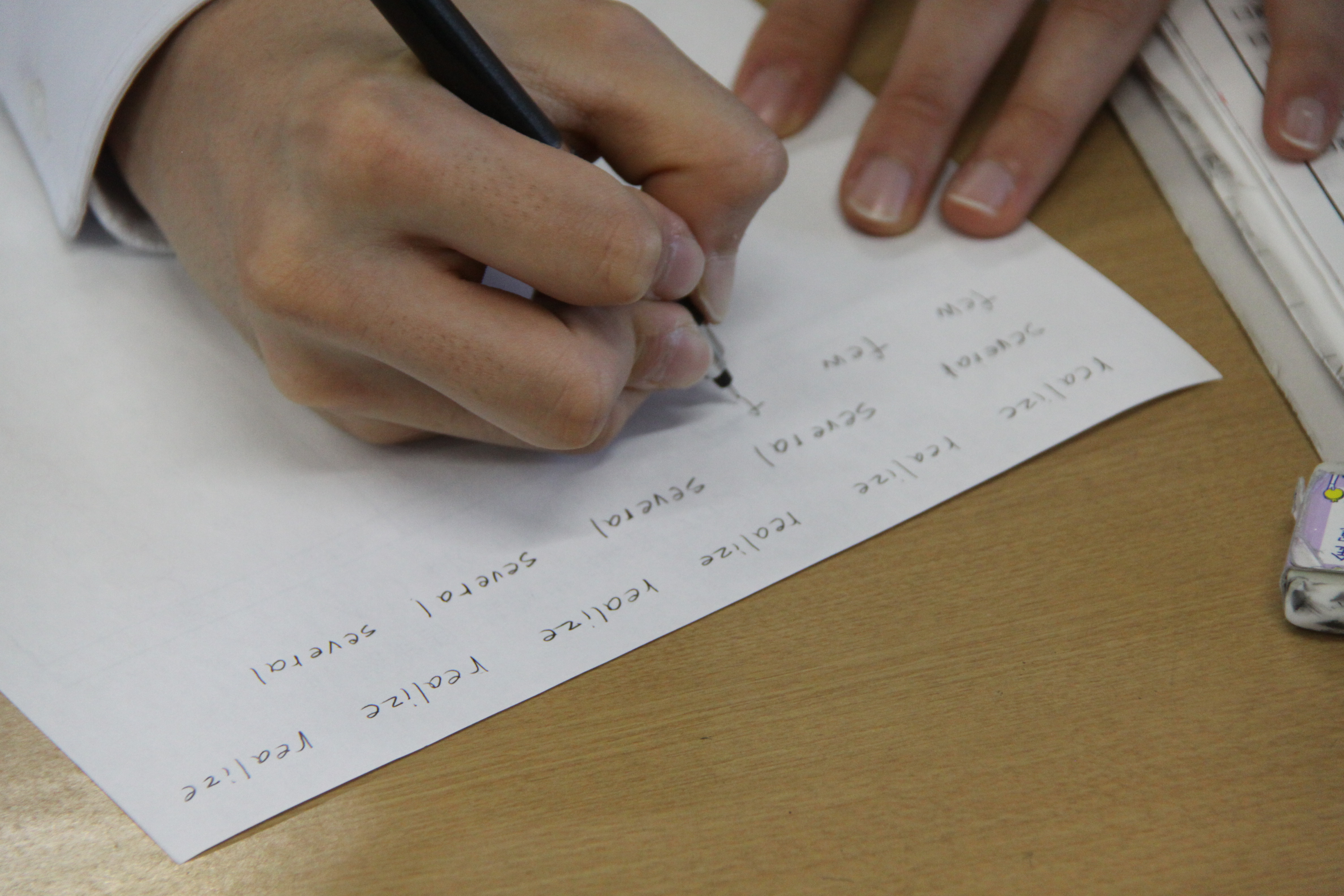
先日、1年生は、塚本さん、松下さんをお招きして、「自分の特性を正しく理解する」ことを学びました。昨日3年生の晩学習の様子を見ていると、一人ひとり勉強のしかたが違うのですね。繰り返し書いて覚える人、見直しをしながら解答用紙で確認する人、蛍光マーカーを利用する人・・・。脳のタイプも関係すると松下さんは言われていました。自己流勉強法で伸びている実感がない人、文字がたくさん書いてあると読む気がなくなってしまう人だったり、なにか自分で体験しながらだと覚えやすい人だったり、人それぞれ効果的なとらえ方は存在します。参考に認知特性を理解した6つの勉強方法を紹介します。
認知特性とは目で見たり、鼻で嗅いだり、耳で聴いたりと主に五感から入って来る様々な情報を脳で処理しどう表現するかのことを言います。これは人それぞれ違い、あなたがどのような方法が1番覚えやすいかを見極めることが大切です。ひとつの参考にしてみてください。(タイプは似たような部分もありますので、いろいろと自分らしい勉強方法を試してみてね)
◆視覚タイプ
□写真タイプ:文章単品で読よりも平面画像として捉えるのが得意な人。アニメのキャラクターなどを見なくても書くことが出来たり、絵を書くのが上手な方が多いです。〇おススメの勉強方法・・・図や表を使った視覚的に理解できるものを作成する。メモを取るくせをつけて常に見れるようにする。絵を書きながら勉強する。
□3D映像タイプ:断片的な画像よりもストーリー性がある映像で捉える傾向がある。例えば、四角よりも立体的な箱を想像したり、立体的に捉えることができるので、人の顔をよく覚えている方が多いです。〇おススメの勉強方法・・・Youtubeなどの動画で勉強する。映画などのストーリー性があるものを見る。何か思い出せない時は記憶を辿りながら思い出す。実際に行動して記憶として残す
◆聴覚タイプ
□聴覚言語タイプ:本を読んだり、文章を読んで理解するよりも音から聞いた方が情報処理が早い人。アニメやドラマ、映画で聞いたセリフを覚えるのが得意な人はこのタイプです。おすすめ勉強方法を使って、起床時や就寝時、通勤、通学時間を有効活用しましょう!〇おススメの勉強方法・・・Podcastsを聞く。習った単語や文章を自分で録音して聞く。映画やドラマを見る
□聴覚&音タイプ:一度聞いた音楽などを口ずさんだり音色や音階で理解する人です。モノマネや外国語の発音も良いと言われています。家事をしながら音楽を聴いたり、歌ってみたりすると覚えやすくなります。〇おススメの勉強方法・・・勉強したい語学の曲を聞く。オリジナルの曲を作り覚えたい単語を歌詞にする。口に出してアウトプットする。
◆言語タイプ
□言語映像タイプ:文章や文字を読んだあとにイメージして映像として理解する人。例えば旅行のブログを読んだらその現地で旅行してるのを想像できる人や本を読んで実際にその物語に入り込める人。〇おススメの勉強方法・・・覚えたい単語を実際に使う状況を想像して記憶させる。例えば覚えたい単語が「withdraw」(お金引き出す)だとします。そしたらあなたが実際に銀行に言って窓口で、「I would like to withdraw $50 from my bank account.」と言っているような状況を想像し記憶します。
□言語抽象タイプ:小説や本を読むと図式化して理解するのが得意な人で、登場人物の家系図や相関図などが頭に浮かんで理解する人です。〇おススメの勉強方法・・・エクセルなどを使ってわからない単語を表にする。図式を使って例文を英語で書いてみる。本を読んだ後にノートにまとめてみる。
◎ひな中は、食育を大切にしています。
~今週は地産地消週間(^O^)

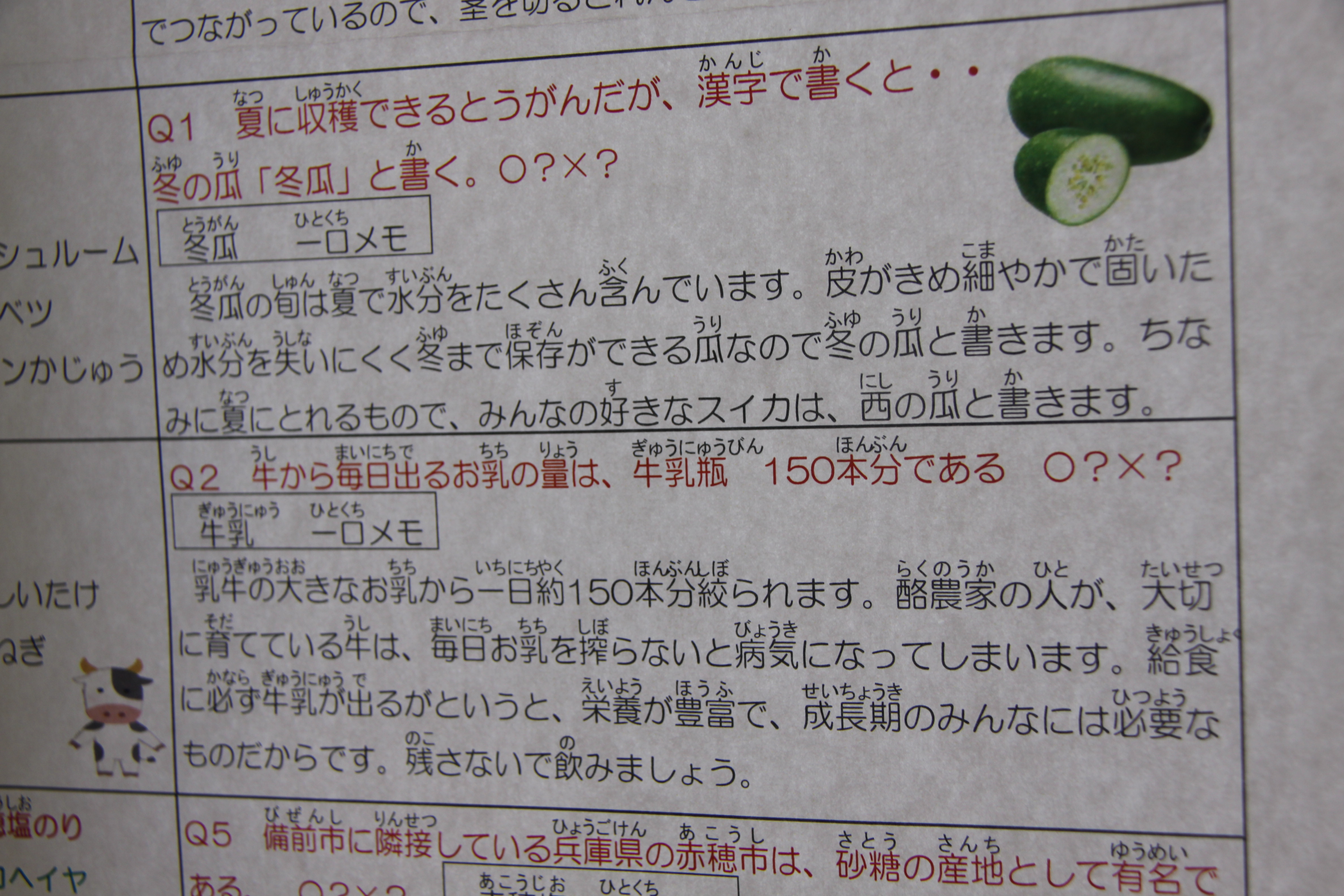
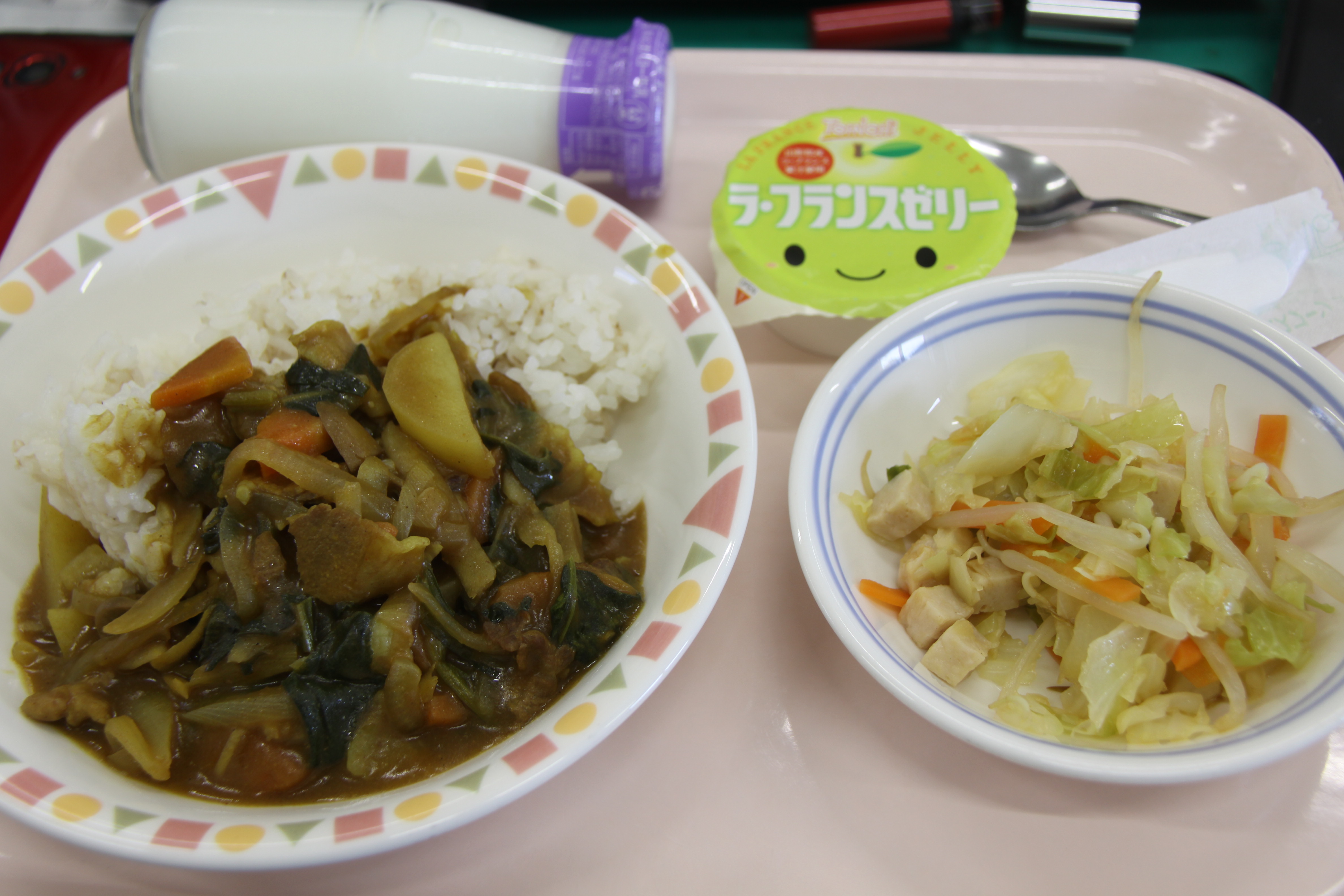
地産地消のメリットをいくつか紹介しますね。今週の献立の中で地場産物は何でしょうか?献立表で確認してみましょう。
新鮮で安価な農産物を食べられる
地産地消の農産物は輸送に時間やお金がかかりません。そのため、地元の消費者は鮮度が保たれたとれたてのものを、安価に手に入れることができます。鮮度が落ちてしまった農産物は、その分栄養価も下がってしまいます。同じ農作物を食べていたとしても鮮度の高いものを食べたほうが、栄養素を効率的にとることができます。
生産元や農作物に対して安心感がある
地産地消の農作物であれば、生産者や生産状況を確認できます。どこの誰が作っているのかもわからないものより、生産元を訪れたり、生産者と直接話ができたりする距離で作られた食材のほうが安心感を抱く方は多いのではないでしょうか。生産しているところを直にみることができれば、より安心して普段の食事を口にすることができるでしょう。
生産者の売上が増える
流通経費の節減により、生産者の手取りの増加、生産者の売上の向上が期待できます。生産者の収益が上がることで地域の農産物の質や量がさらに良くなる可能性があるのです。また、生産者の収益性が上がることで、地域が活性化し、魅力度がアップします。購入者は地域に貢献した気持ちになれるので、購入満足度が上がる効果もあるといえるでしょう。
エネルギー消費や温室効果ガスを削減できる
流通経路の長距離の輸送が必要ないため、ガソリンや電気を使わずに、消費者の元に食材を届けることができます。結果的に、エネルギー消費や温室効果ガスの削減につながります。エネルギー消費や温室効果ガスは、地球環境に悪影響を及ぼし、私達の住環境も悪化させます。地産地消を進めることで、自然と環境配慮に貢献することにつながるのです。
食料自給率が上がる
日本では、食料自給率の低下が問題視されています。日本のカロリーベースの食料自給率は約38%、生産額ベースの食料自給率は約66%と低い数値結果になっているためです。地産地消を行うことで、低下している食料自給率を上げることができます。輸入に頼りすぎると、世界情勢の影響を受けやすくなります。輸入食品が不足すると、各家庭に十分な食料が届かなくなるフードセキュリティ面のリスクがあります。リスクを回避するためには、地産地消を進め、食料自給率を上げる必要があるのです。
◎GROW UP WEEK(11/14~)
学級委員会を中心に、学級のみんなで、これまで以上に、集中して授業に臨むことができるようにすることを目的に取り組みます。
観点は、チャイム席(チャイムが鳴る前に授業の準備をして自分の席についている)、気持ちのよいあいさつ(先言後令)、授業態度(私語をせずに授業を受けることができている、授業中に不必要に横を向いたり後ろを向いたりしていない)、積極性(話し合いなどのグループ活動を活発に行っている、発表をしっかりしようとしている)です。ひな中らしさを磨いていきましょうね。

さあ みんなで 授業をがんばろう(1年生11/14 1時間目)
◎社会に開かれた学校として
~子どもたちの豊かな育ちのために
小中学校では、ケース会議を開催しています。ケース会議とは、学校での子どもの不安や心配事の解決のためには、生徒の生活全般に関する情報、家庭環境・生活に関する情報、成育や発達、心理・医療に関する情報など様々な側面から総合的に検討するための多くの情報が必要となります。それらの情報を円滑に共有し、合理的かつ効率的な対応ができるようにするための方法のひとつとしてケース会議があります。「ケースカンファレンス」とも言われ、解決すべき問題や課題のある事例を個別に深く検討することによって、その状況の理解を深め対策を考える方法です。子どもが抱える課題について、本人とその環境に関する様々な情報を収集・共有します。課題の背景や原因を分析し、その事案(ケース)の総合的な見立て(アセスメント)を行います。本校でも、対応の目標の設定、役割分担を内容とする援助・支援計画を具体的に協議・決定するために、ケース会議には、担任や生徒指導担当を中心に、校長、教頭、養護教諭、学年主任、スクールカウンセラーなど、状況やケースによって多くのメンバーが関わり、子どもの「育ち」を支援していきます。

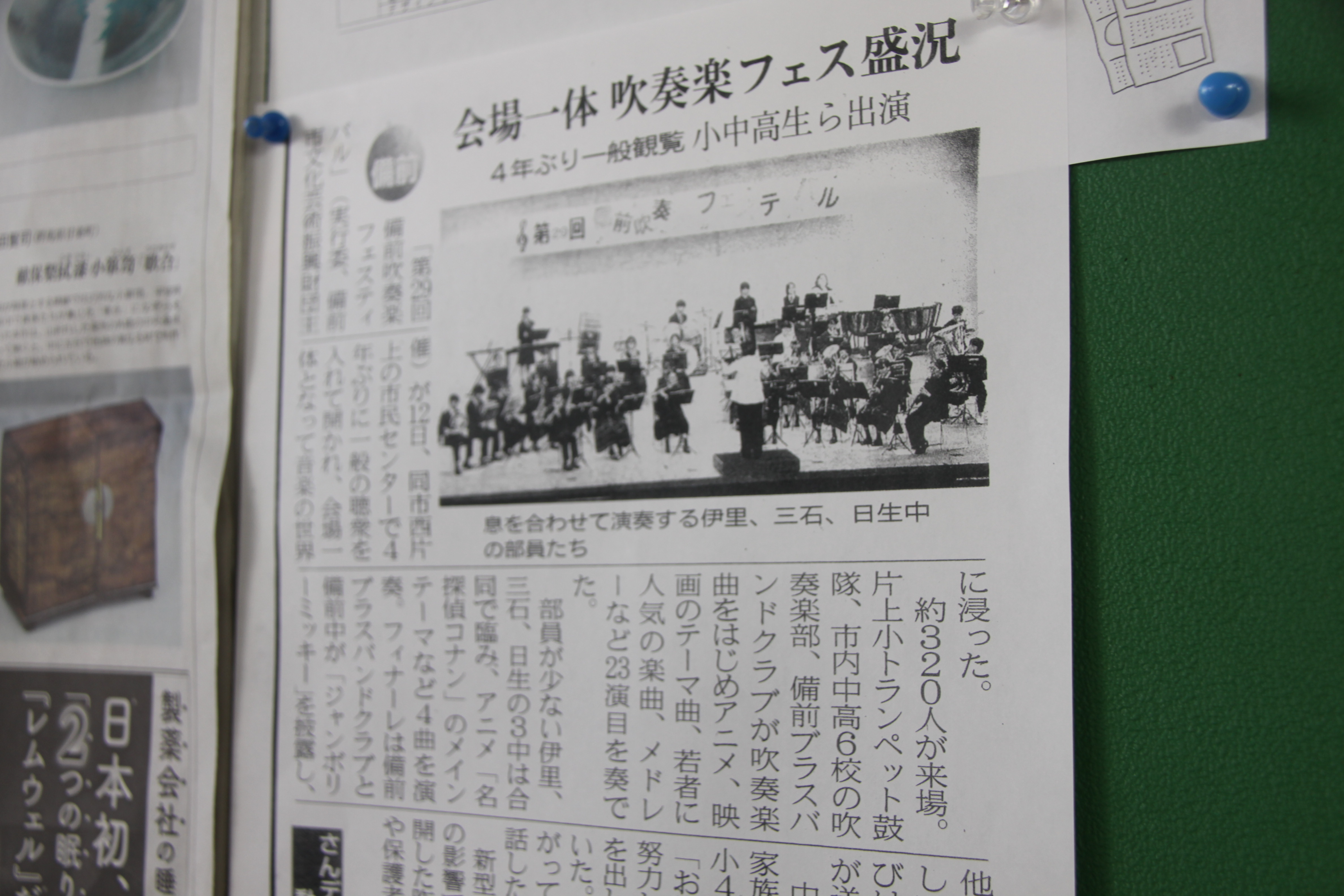

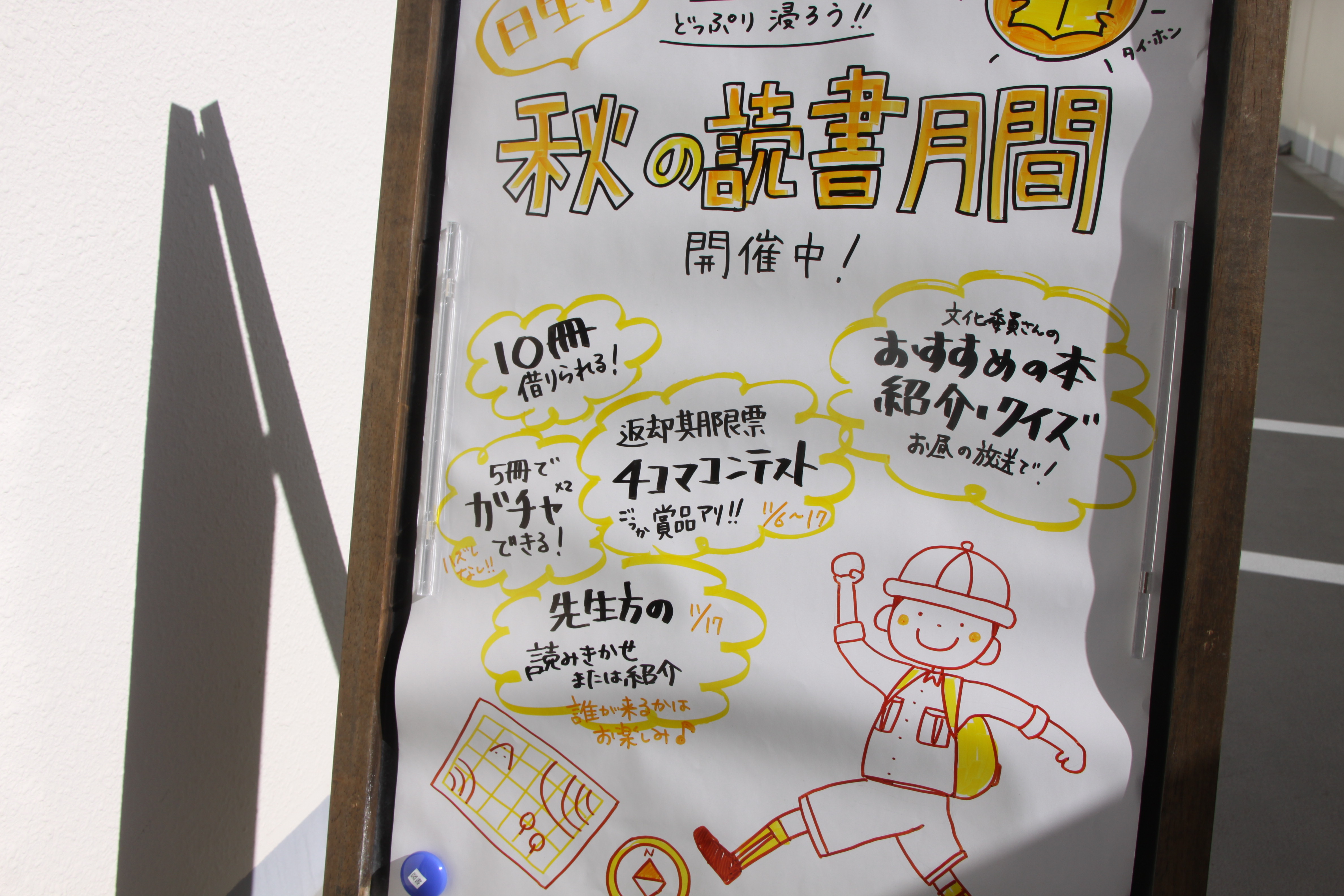



A man cannot be said to succeed in this life who does not satisfy one friend. Henry David Thoreau
たった一人の友達をも満足させることのできない人間が、この世の中で成功することができるなんて、とても考えられないことである。
◎〈「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ
俵万智〉(11/13)

◎がんばってます。これからもがんばります
ヽ(^。^)ノ(11/13)
岡山県では、令和2年度より学校経営アクションプランを各学校が作成し、学校全体で取り組んでいくための支援として、「管理職のビジョンと戦略を支援する学校訪問」を年2回実施しています。この日は石田先生、木村先生、谷口小中一貫教育課長らが学校訪問され、授業参観をされました。
近年、学校現場では若手教職員の育成、学校における働き方改革が課題となる中、生徒指導や特別支援教育など複雑化・多様化する様々な課題の解決を図るためには、教職員や学校内の多様な人材が目標に向かって組織的に取り組むことが不可欠になっています。このような時代にあって、学校組織マネジメントを機能させ、組織的課題解決力の向上を図ることで持続的・発展的な教育活動の実現を目指す「学校経営アクションプラン」の取組は、これまで取り組んできたことを大切にしながらも、学校経営の基本に据えて、今後も質を向上させていく必要があります。今後も教育活動を組織的・効率的に進め、よりよい学校づくりを進めていきます。そのためには、目標達成マネジメントと組織マネジメントを両輪とする学校経営マネジメントを基盤として、教職員の人材育成や働き方改革を進めつつ、教育課程の充実や「地域とともにある学校」として、家庭や地域との連携を図っていきたいと思います。



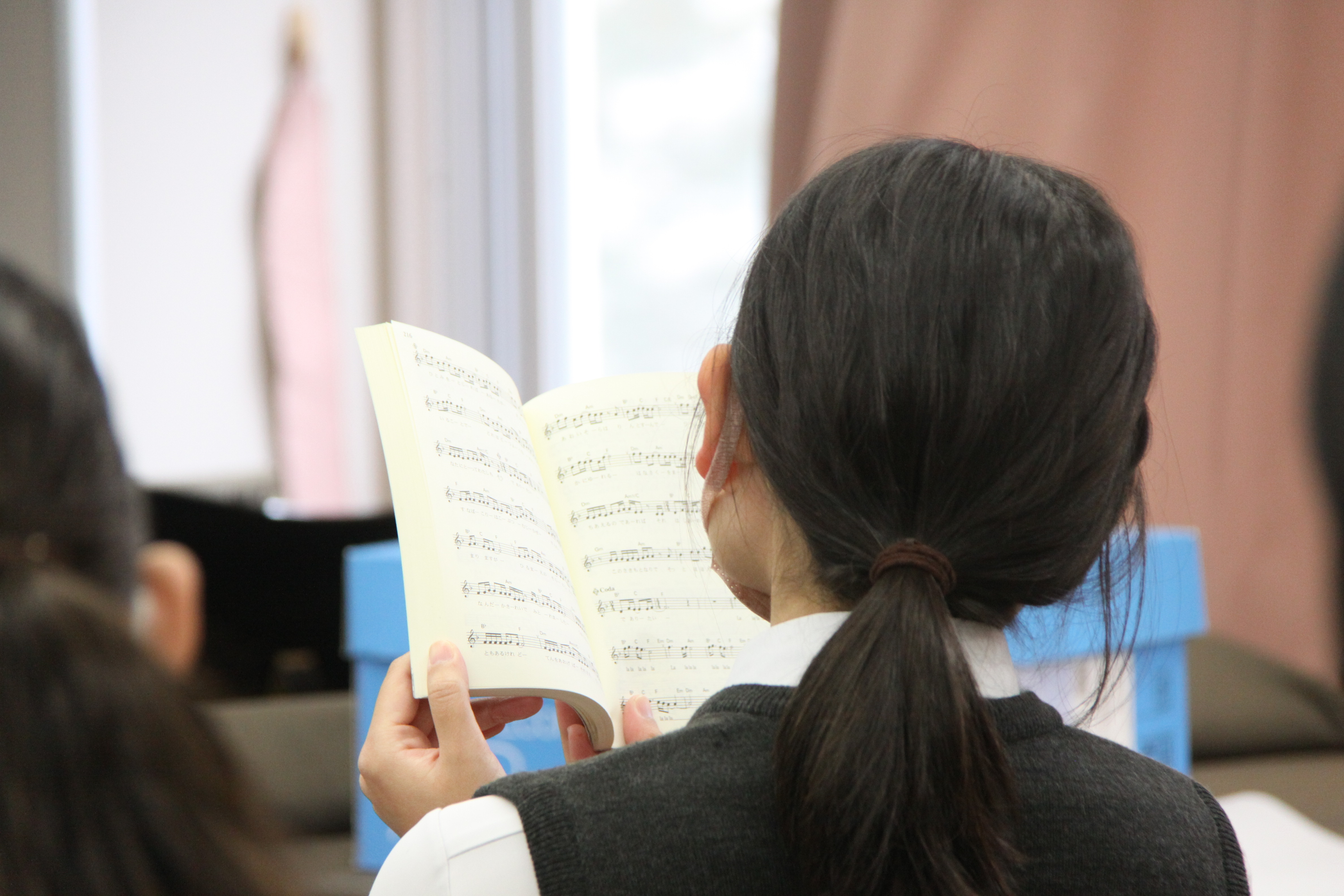
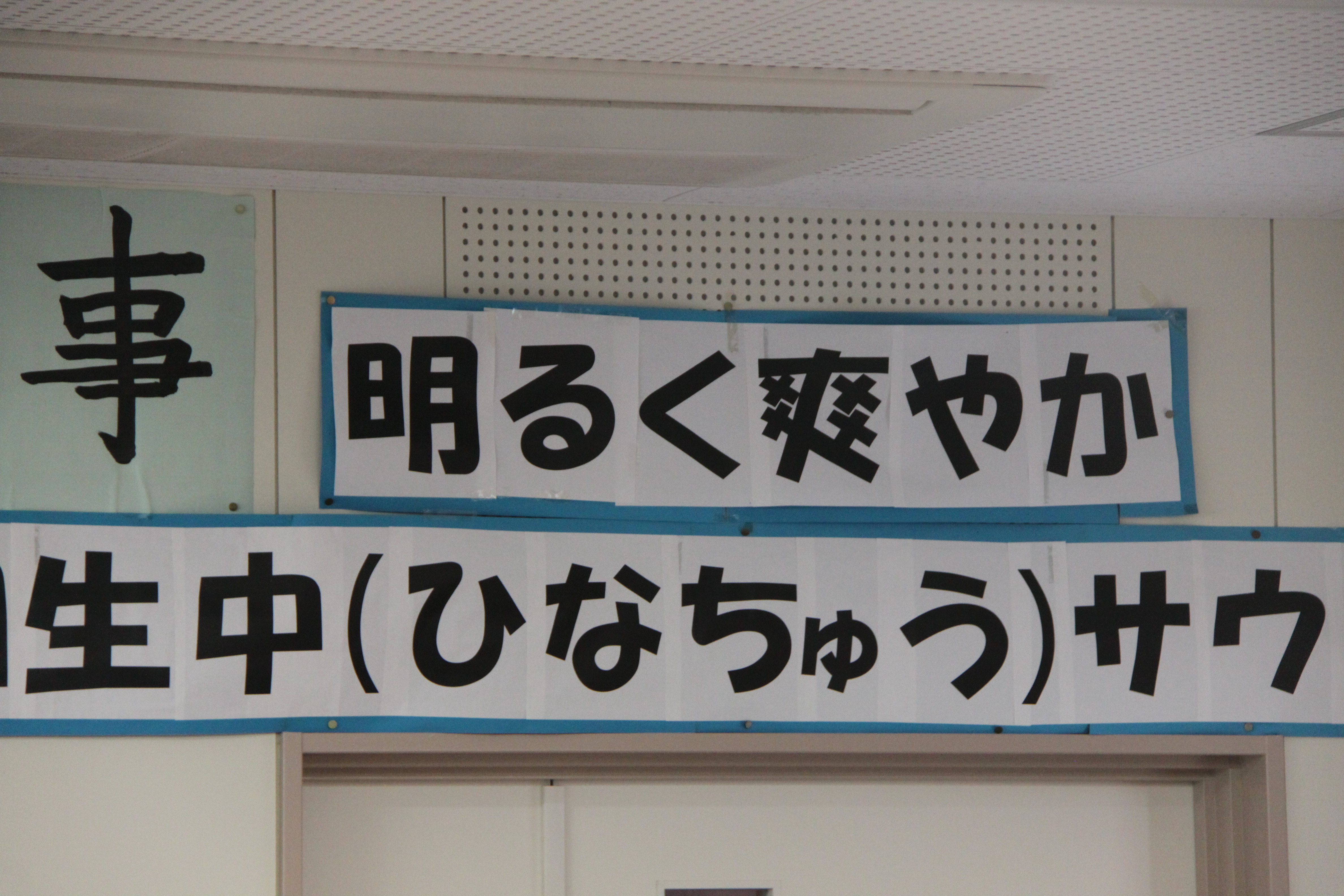

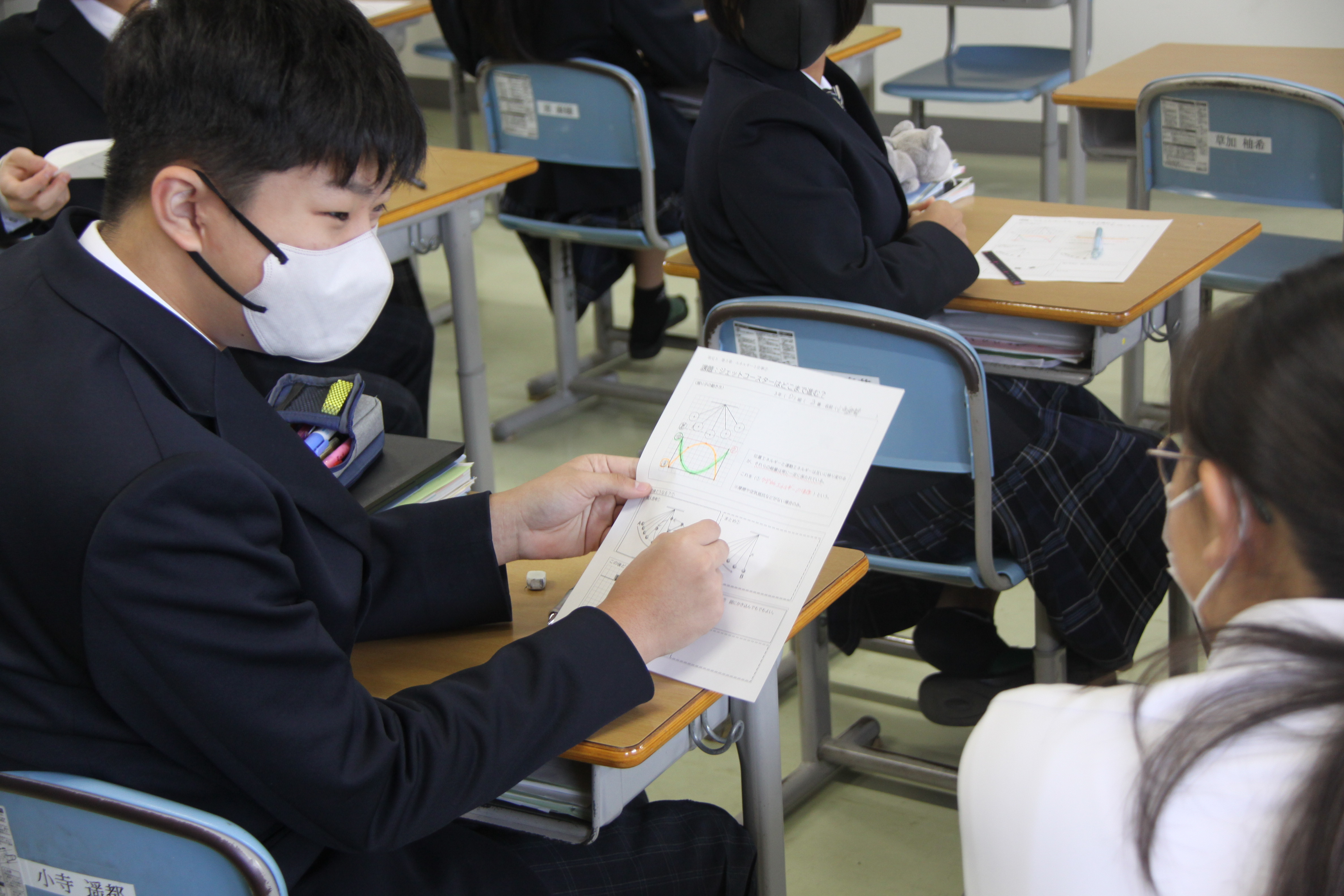
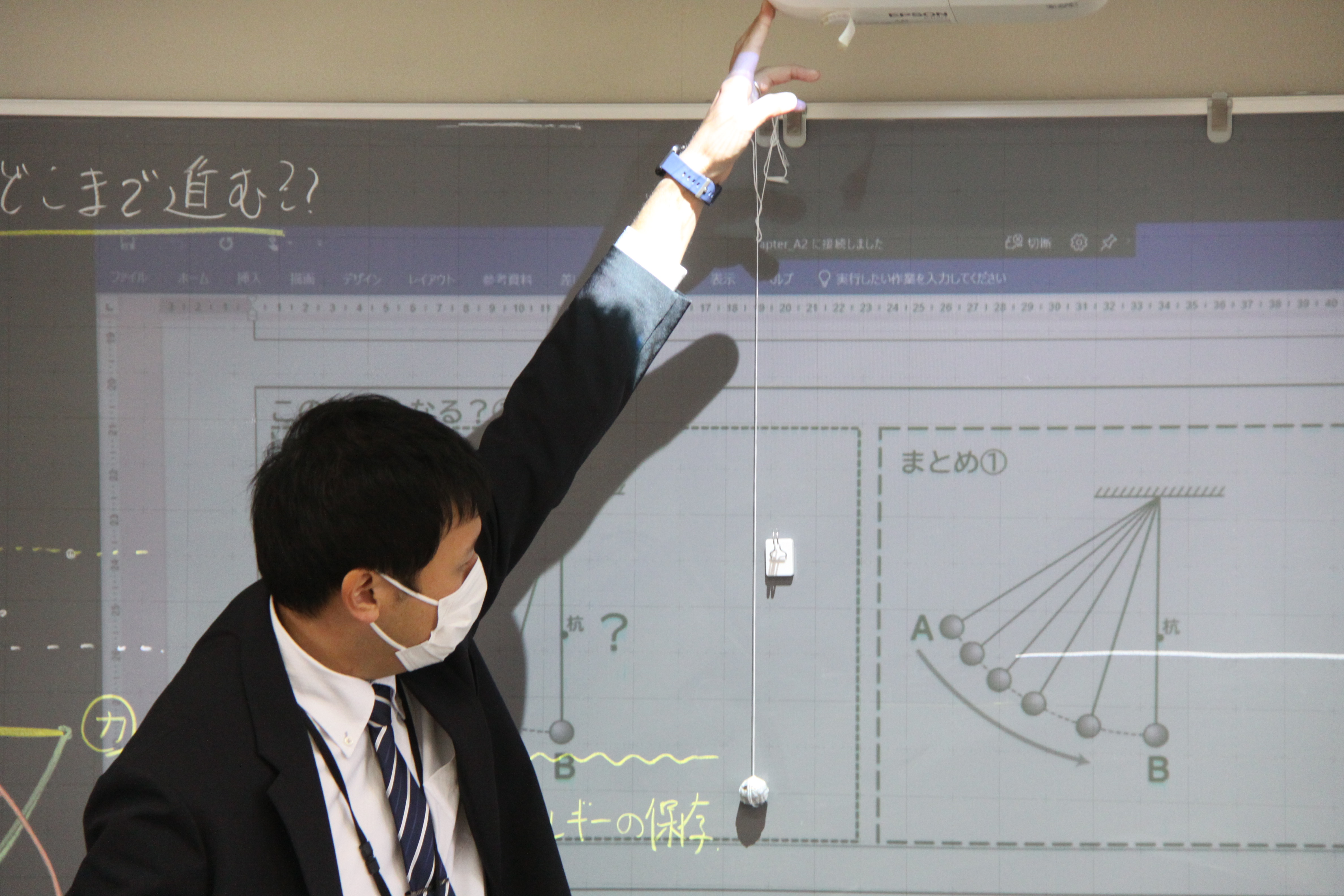




わたしたちらしくせいいっぱい
◎SHIGENKABUTSU KAISHU +1.0
11日(日)、多くの方々のご協力で資源化物回収が無事終わりました。ありがとうございました。また、勇盛商事の奥橋さんには今年度もサポートしていただき、大変助かりました。ありがとうございました。PTA保健部






◎チャレンジワーク4DAYS
ありがとう ありがとう
多くの方々に支えられ、ありがとうございました。(11/10)


2年生のみんなお疲れ様!(^^)!
◎小学生へ伝える・共に考える、海のこと、未来のこと。(11/10)
10日、1年生が西小学校を訪問し、アマモポットをつくりました。

自宅でつくられた方がいるようです。HPでの記事を少し紹介します。
アマモのススメ
○11月~12月は大切に選別したアマモの種を『アマモ育苗ポット』に蒔きます。
海底で育つものを、家庭でも育てることができます。
○小さな自分の海だと思ってみてください。ポットに人工海水と入れ砂を入れて、
○そこに種を蒔きます。(詳しいやり方があります)
○12月~1月海の季節が春になるころ、種から最初に白いひげのようなセンサーが生えます。センサーがポットの中の状態を感知します。水温・塩分濃度・光量のうち水温は大切で10℃くらいに下がる必要があります。条件がそろったらセンサーから緑の芽が出ます。とても可愛いです。
○ポットの容器が緑の葉っぱでいっぱいに育つのは3か月ほどかかります。(昆虫ケースを水槽にして育苗することもあります)
○2月~3月になればポットで育ったアマモの苗を移植します。
○引き潮の日、海に苗を植えに行きます。海に入りスコップで穴を掘りそっと苗を入れてあげます。
○大波にさらわれないように、アオサの陰にならないように、魚に食べられないように、育ってほしいと願います。
◎秋の読書月間続きます 文化委員会プレゼンツ
文化委員からのおすすめの本から、
クイズ:Q『その本は』を書いたのは、ヨシタケシンスケさんともうひとりは誰でしょう?
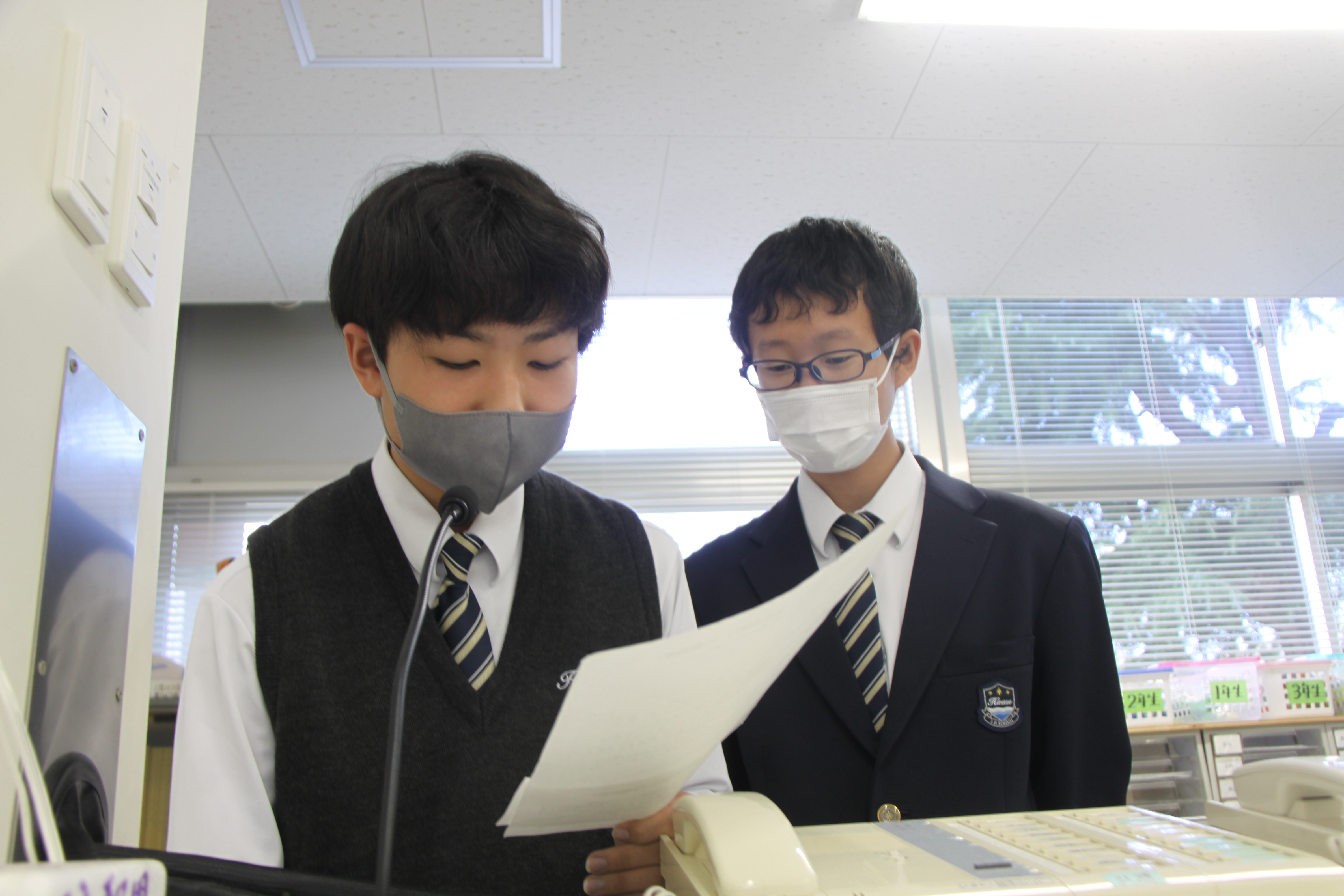
◎私のゆめはこのまちの夢だ
~職場体験まっただなか ご声援ありがとうございます。(一部紹介します)


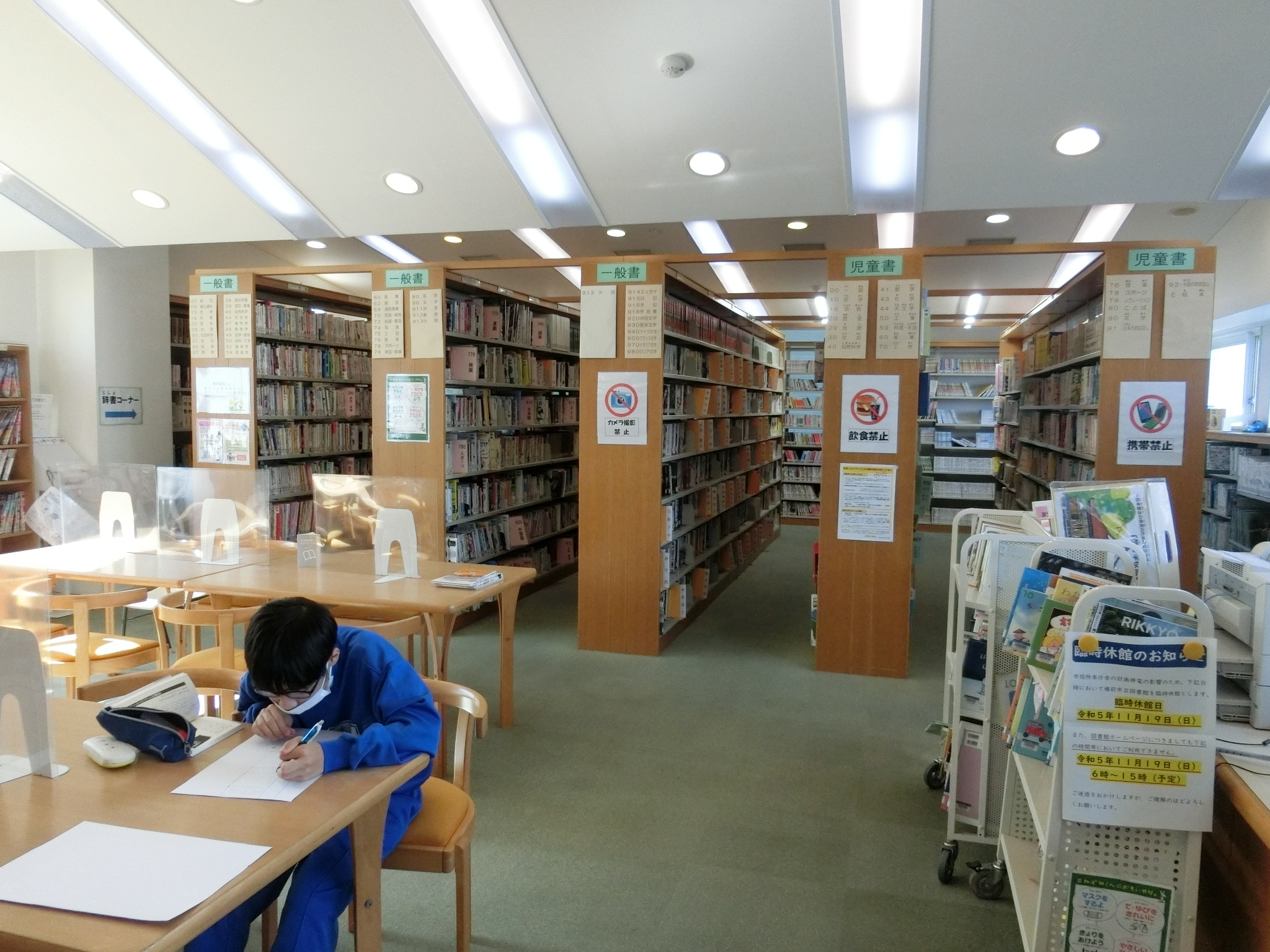

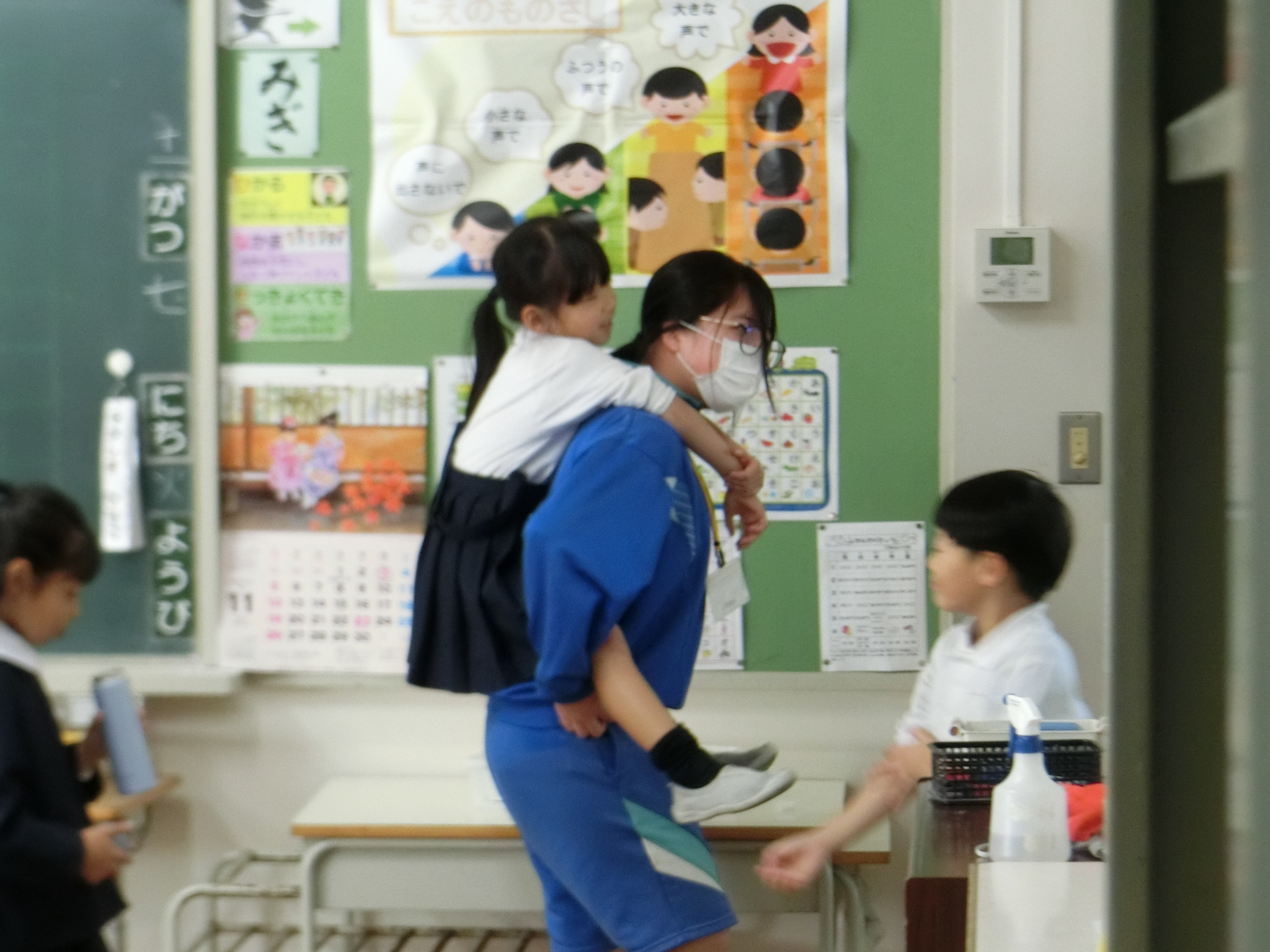



















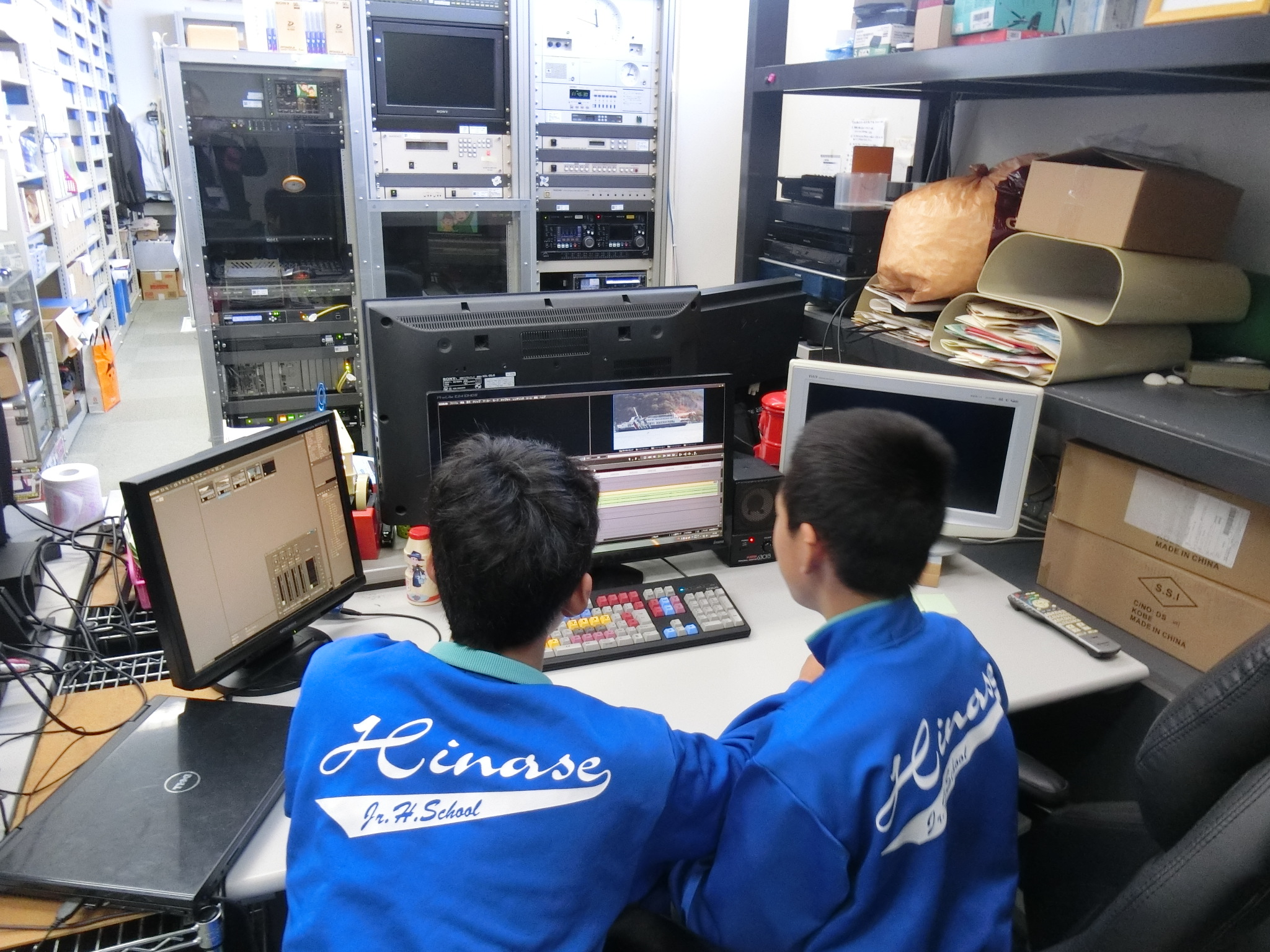
だれもかれもが力いっぱいにのびのびと生きてゆける世の中
だれもかれも「生まれて来てよかった」と思えるような世の中
じぶんを大切にすることが同時にひとを大切にすることになる世の中
そういう世の中を来させる仕事がきみたちの行くてにまっている
大きな大きな仕事
生きがいのある仕事
吉野源三郎
◎シン・シゲンカヴツカイシュウ 運動場版H(11.12)
平素は本校PTA活動に多大なるご協力をいただき、深く感謝いたします。
さて、PTA活動の一環として資源化物回収を次のとおり実施します。収益金は毎年のPTA活動に欠くことのできないものになっています。
つきましては、次のことをよくご理解のうえ、生徒全員、保護者全員のご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 PTA会長・保健部
●期 日:令和5年11月12日(日)8:30~9:00 雨天決行
●回収品:古新聞(広告が入っても構わない)・古雑誌・段ボール・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・鉄くず・金属類
●回収手順:各家庭で当日の8:30~9:00に回収品を直接回収場所まで持ってきましょう。※ 各地区のゴミステーションは使用しません。近所で声をかけあって、車で持って行けない家庭の回収品を一緒に持ってくるなど、ご協力をお願いします。※今年度も、ひなビジョンでのお知らせはしません。
●回収場所:日生中学校グラウンド(雨天時は、新駐車場)
●備 考:① 新聞紙は新聞紙のみ(広告が入っても構わない)、古雑誌は古雑誌のみというように、回収品は必ず分別し、ひもできつく縛って出してください。
・アルミ缶・スチール缶・牛乳パックはよく水洗いをして、それぞれ分別してください。
・鉄くず・金属類の例:自転車、フライパン等。(基本的に金属であれば可)
・リサイクル料金のかかる電化製品は不可。電気ストーブ、アイロン、パソコン、ファックス(業務用は不可)等は可。
・回収場所は一方通行とします。裏面の地図を参考に、スムーズに積みおろしができますよう、ご協力をよろしくお願い致します。


◎わたしは「ほしせいコース」。
あなたは、かきおこコース? それとも、鹿&いのししコース?
~ひな中も、メディアコントロール週間ガンバっています~
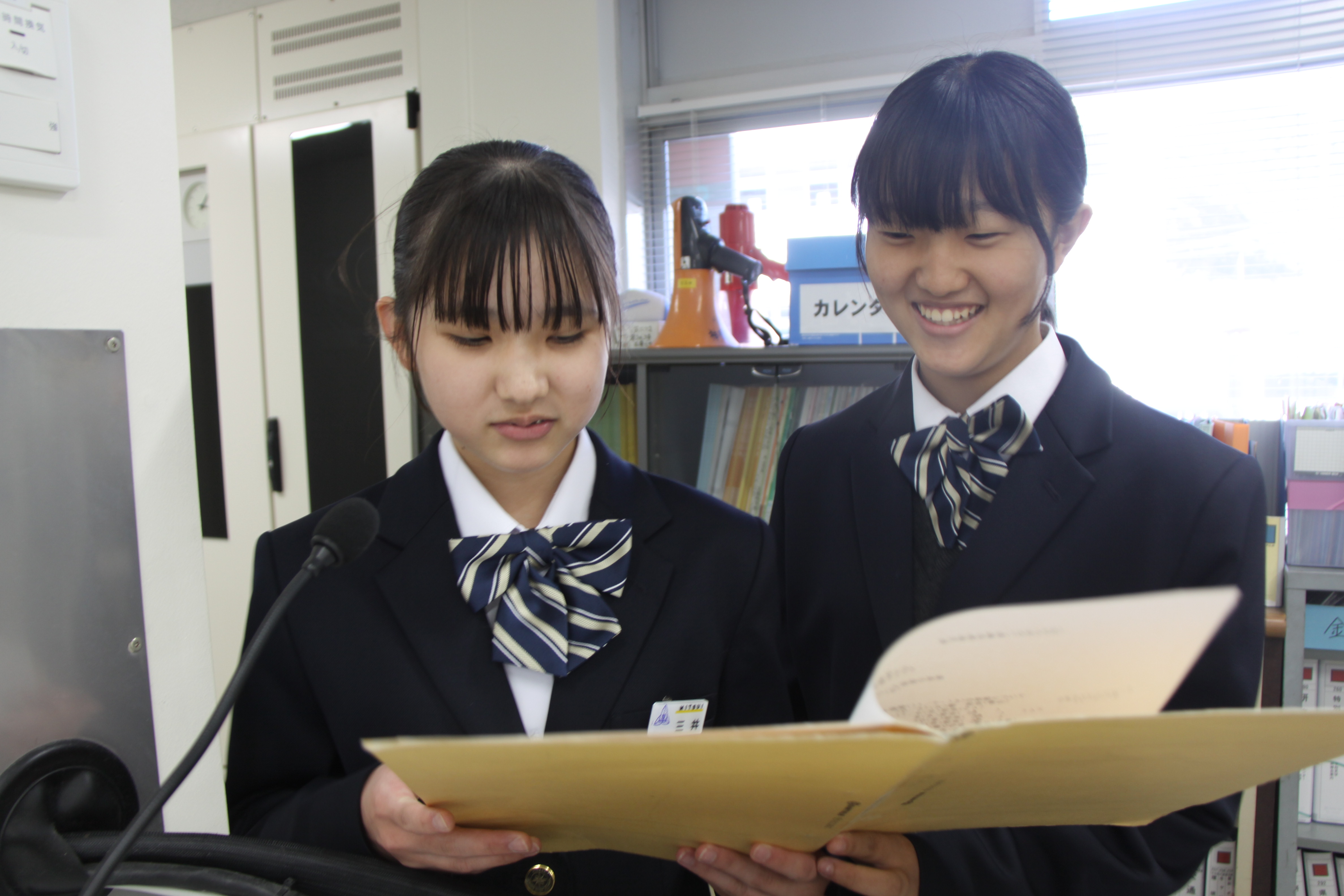
日生中学校区では、小・こども園と共に、メディアコントロール週間に様々な取組を進めています。この日も、環境委員会が全校に放送で働きかけました。
取組の参考に樋口進さんの記事を紹介します。
インターネットコンテンツの中でも依存性が高いとされているのが、若者が多く利用するソーシャルメディア、いわゆるSNSです。アメリカの調査では、18歳から22歳の45%が「自分はSNS依存かもしれない」と回答するなど、使いすぎを自覚する人は少なくありません。かつて依存に陥っていたという大学1年のエマ・レンキさん(ワシントン大学セントルイス校)に話を聞くことができました。レンキさんは小学校5年生でスマホを手に入れ、中学3年までSNSに没頭していました。当時は1日5~6時間をSNSに費やしていたといいます。不安や憂うつな状態が増え、通知音に条件反射してスマホに手を伸ばすといった重い依存症に苦しみました。やめられなかった大きな理由は、周りから取り残されることに恐怖を感じていたためでした。しかし一方でSNSを見るたびに、強烈な劣等感を覚えていたといいます。 「見逃すことが怖いんです。友達がどこへ行ったのか、彼らに何が起きているのか。SNSなしにどうやって知るのでしょう。でもSNSはハイライトを集めたもので、誰かのすごい体験をみんなが見る。特別な瞬間などない自分を常に意識させられるんです」(レンキさん)
レンキさんのように“置いていかれる恐怖”がSNSから離れられない理由になっている人も多いと樋口さんはいいます。
「仲間といろいろやり取りをしていて、自分だけ置いてきぼりになるというのを皆とても怖がるんです。患者さんたちには、見るのはいいけれども書き込むのはしばらくやめようよと言っています。書き込むと必ず反応を見たくなりますので」(樋口さん)
スタンフォード大学行動デザインラボ スティーブン・クレインさんは、
「ネットのサービスは、簡単に楽にそしてスムーズに使えるように考え抜かれた工夫が施されています。残念ながら過剰な利用は私たちユーザーの自己責任になっています。ですから自分でもう少し使いにくく、楽しめないようにする必要があるのです」と言います。
人間は『やりたい』『できる』『きっかけ』という3つの要素がそろった時に行動するというクレインさん。この3つの要素を減らすことでインターネットの過剰な利用を抑えることができるといいます。
◎クレインさんが提唱するスマートフォンの使い方です。
〈1「きっかけ」を減らす〉
スマホの“お休みモード”をONにして必要な通知以外来ないようにする。通知が来たことをきっかけに、ほかのアプリまでチェックしてしまう行動を減らせる。
〈2「できる」をなくす=やりにくくする〉
パスワードは保存せず、長いものを使う。指紋認証や顔認証など簡単にログインできるものは使わない。
〈3「やりたい」気持ちを抑える〉
人は本来色にひかれる。スマホの画面の色を赤一色などに変えると、色を見るときの興奮がなくなり、「使いたい」という気持ちが湧かなくなる。
・・・「簡単なことから始めて、頑張って一日それがやり通せたら「成功した!」と思うようにしてみてください」
樋口さんが患者に強く勧めているのは、家族全員でインターネットを使わない時間帯を作ることです。スマホを使わないことに抵抗する子どもも、親も一緒だと「やってみるか」という気持ちになることがあるといいます。こうすることで親子で会話をする時間が生まれるのもメリットです。また小さい時から親と楽しい活動をすることも大事だと樋口さんはいいます。ゲームに依存しても他の活動の楽しさを覚えていれば、ゲームから離れられるきっかけになるためです。
子どちの暮らしと切っても切り離せないインターネット。依存や脳への影響といったリスクに関して正しく知りながら、インターネットを「道具」として有効に活用していく方法を大人も子どもも身につけることが、真に豊かな生活を作る上で欠かせないのではないでしょうか。
[この記事はNHKサイエンスZERO 2022年4月10日(日)放送「インターネットと脳 見えてきた依存のメカニズム」を基に作成されています。]
◎きたえる・すすむ・みがく(7:48)

チームでの練習は、1つの練習メニューに費やせる時間や回数が限られているため、自分が「もう一回挑戦したい」と思っても次のメニューに移行してしまった、というようなことがあります。しかし、自主練習であれば練習内容も、費やす時間も自分で決められるため、納得がいくまで練習ができます。自分の苦手なことはもちろん、もう少しでできそうなことに絞って反復練習が可能なのです。また、動画などで見て「やってみたい!」と思った技にも挑戦できるため、自主練習は大事にしたいな。
◎私たちのはじまりの風景4(立冬)
さて、ここはどこでしょう?









◎私のゆめはこのまちの夢だ(11/7はじめます)
~職場体験 一人ひとりがせいいっぱい。

◎私のゆめはこのまちの夢だ
~職場体験スタート(11/7~10)

4日間、お世話になります。
日生東小学校 日生認定こども園 奥本生花店 山陽マルナカ穂浪店 ステラカフェ カフェ天goo きたろうお好み焼き 片上認定こども園 セブンイレブン岡山備前インター店 旬鮮食彩館パオーネ日生店 タイム備前店 ツヤ髪専門美容室ボヌール 夕立 日生運動公園 ひなビジョン THE COVECAFÉ 備前市立図書館日生分館 日生西小学校 伊部認定こども園 わくわくるーむ 海ラボ 山陽マルナカ備前店 カメイベーカリー 備前市立図書館 山下商事 ありがとうございます。(順不同・敬称略)
◎秋の読書月間 文化委員会プレゼンツ(11/7)
文化委員からのおすすめの本から、Qクイズ:咸臨丸の船長は誰でしょう?



◎♪♬♫(^^♪♩(11/7)
第21回おかやま県民文化祭参加事業
第29回備前吹奏楽フェスティバルへ
〇11月12日㈰ 13:00~(開場12:30) 会場:備前市市民センターホール 料金:無料 申込:不要
〇出演団体(予定) 日生中学校 片上小学校トランペット鼓隊、備前中学校、伊里中学校、三石中学校、吉永中学校吹奏楽部、備前緑陽高等学校吹奏楽部、備前ブラスバンドクラブ
〇駐車場:旧遊技場跡地(クラウン跡)、市民センター(中国銀行前)市役所本庁舎駐車場をご利用ください。
〇問い合わせ:備前吹奏楽フェスティバル実行委員会(備前市文化芸術振興財団)事務局 ☎0869-64-3302
〇小学生から大人まで、市内で活動する吹奏楽団がそろって出演いたします。流行の曲から懐かしい曲がたくさん。お楽しみください。









◎多くのひとに支えられて
この時期、岡山県広域特別補導協議会は、広域列車補導キャンペーンを行って、高校生を中心に啓発ティッシュを配布し,非行・万引き防止を呼びかけています。(県内JR倉敷駅,中庄駅,茶屋町駅,西阿知駅,児島駅,新倉敷駅,岡山駅,鴨方駅,総社駅,水島臨海鉄道:倉敷市駅,栄駅,井原鉄道:矢掛駅,清音駅等)東備支部(備前市青少年健全育成センター主催)でも17日に赤穂線で同キャンペーンを実施する予定でしたが、高校のインフルエンザ流行等により中止になりました。8日(水)は、ひなせっ子育成推進協議会が日生駅で街頭活動を予定しています。
日生中学校の卒業生も高校進学に伴い、鉄道を使って通学する子どもたちがたくさんいます。公共のマナー、規則やルールを守って高校生活を送ることはとても大切ですね。
現在、職場体験に取り組んでいる2年生たちは、各事業所で、社会人としてのルールやきまりなど大事なことをたくさん学ばせていただいています。

◎道を切り拓く
~3年生進路懇談はじまる(11/7~10)

進路懇談を、「有意義で良い時間にするために心がけたいこと」を以前に、先輩に教えていただいたことをひとつご紹介します。
進路懇談で「面談の場で子どもを否定しないこと〈子ども自身や、志望する進路を否定しない〉」そしてなにより「あなたの進路を全力で応援しているよ!」という気持ちを伝えることです。
反抗期真っただ中の子どもに対する愚痴をだれかに話したくなる気持ちは、どの母親でも持っているものです。しかし、三者面談の場では「先生に問題の解決策を教えてもらいたい」という気もちからの悩み相談であっても、隣で聞いている子どもから「悪口」と、捉えられてもおかしくありません。三者面談の場で大人が感情的になってしまうと、本当に必要な進路の話が建設的に行われることは難しくなります。(出来れば子どもについてのネガティブな情報は、三者面談の場ではなく、事前に手紙や電話で先生に伝えておくと良いかもしれません。)
面談後に子どものやる気とモチベーションをあげるために、参考にしてほしいことは「他者から期待されることで成績や成果が向上する現象」=「ピグマリオン効果」です。
教育心理学の用語の1つです。アメリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタールが行った実験で、あるクラスにテストを受験させ、その中から数人の生徒を適当に選び、教師に「〇さんと△さんと◇さんが成績が伸びるので注意してみていてください」と伝えたところ、本当にその生徒たちの成績が上がっていった、という結果に基づいたもので、別名「ローゼンタール効果」「教師期待効果」とも呼ばれています。
親から期待されることにより生徒のモチベーションが上がって努力をするようになり、成果をあげることができるといわれています。「期待しているよ」「これから伸びるはずだから大丈夫」「いい学校だね、いい青春時代を3年間つくろう」といったポジティブな声かけをすることで子どもが一層努力し、良い方向に向かうことも考えられます。
実際、「反抗期の子供に対し否定的なことを言わず褒めること」はなかなか難しいことかもしれませんが、進路相談の席では子どもの自尊心を尊重することは大事だと思います。また、限られた時間ですので、〇家族で子どもの進路についての事前のすり合わせを行っておく。〇受験制度や推薦などについてできる限り情報収集を行う。〇事前に担任にききたいことのポイントをまとめておく。〇面談を子どものモチベーションアップにつなげたる作戦を練る(先生の協力が必要な場合は事前に話しをしておく)こともよいかと思います。あくまでもご参考に。(久次)
◎おはよう おはよう。
いろいろあるけどいい日にしようね。(11/6 大風の中立つ)

○シアワセになるための23のことば
ひとつ、晴れを信じて、なるべく傘はもたないこと。
ひとつ、夢の中では、仕事をしないこと。
ひとつ、遅咲きでも、咲いておこう。
ひとつ、イエスかノーか迷ったら、ニャーと答えてみる。
ひとつ、そこに山があっても、のぼりたくなかったら、のぼらない。
ひとつ、たとえウソをついても、本当にすればウソツキじゃない。
ひとつ、天は人の上に青空をつくり、人の下に大地をつくった。
ひとつ、千里の道も、スキップしてゆこう。
ひとつ、隣の芝生が青かったら、遊びにいっちゃう。
ひとつ、ひとりが淋しいうちは、ふたりでも淋しいよ。
ひとつ、夢は近づき過ぎると見えなくなる。
ひとつ、カンちがいも才能だ。
ひとつ、雀の子、そこのけそこのけ、わたしが通る。
ひとつ、あきらめが早いって、切り替えが早いことでもある。
ひとつ、売られたケンカは、いまお金がないから、と言って買わないこと。
ひとつ、つまんない時は、つまんない顔しちゃえ。
ひとつ、時には家出をしてみる。ひとり暮らしでも…
ひとつ、総理大臣になったら、やりたいことが3つある。
ひとつ、努力も大事だけど、直感も重視する。
ひとつ、女の一年は男の十年。
ひとつ、よくばりは、幸福のはじまり。
ひとつ、人にやさしく、自分にいちばんやさしく。
ひとつ、後ろ向きも、後から見たら前向きだ!
(2009 / ファッション / 三井明子 / 広告コピーより)
◎多くの人に支えられて
~ひな中チャレンジワーク(11.7~11)
すべてを経験せよ 美も恐怖も 生き続けよ 絶望が最後ではない リルケ
職場体験の実施においては、学校の教育活動に対する受入事業所の賛同と協力が大変重要です。これは、地域との信頼関係を基盤とする学校と地域企業相互の役割を認識することにもつながります。受入事業所となる企業には、職場体験の意図を確認していただき、円滑な運営(教育活動)ができるよう、毎年ご協力をいただいています。ありがとうございます。

これから新たに職場体験受け入れを考えてくださる企業様へ
受入を検討していただく際に、事業所の皆様には以下のようなメリット(文部科学省資料)についても、ご理解をいただき積極的なご協力をお願いいたします。
〈受入事業所のメリット〉
○教育への参画を通しての社会貢献
○将来に向けた産業界を担う人材育成
○職場のさらなる活性化
○地域の子ども、中学生や学校教育への理解
○地域、学校との交流の深化
○指導に当たる社員の意識の向上
○地域における貴事業所の認知度の向上
〈職場体験を実施する生徒への事前・事後指導にも学校では力を入れています〉
(1)生徒が行う事前調査、事後活動などに積極的にご協力いただき、職場体験の意義と目的を確認しています。とくに、職場体験の事前訪問などの生徒との初めての出会いの場では、生徒の活動への意欲が高まるような激励や指導内容を明確にしていただき、より効果的な活動になっています。
(2)職場体験までの学校での事前指導として、入学当初から生徒は次のようなことを学んで、職場体験にのぞんでいます。
【職場体験までに学校で取り組む主な進路学習】
○身近な人々の職業調べ:家族など自分の身近な人の職業についてインタビューし、その仕事の内容、喜びや苦労について理解します。
○自分を知る:友達との話し合いや進路適性検査などの結果を参考に、自己の個性、能力適性などについて考えます。
○職業調べ:インターネットや書籍などを活用して、興味・関心のある職業の内容や就業過程について調査します。
〇職業人講話:実際に職業についている方をゲスト・ティーチャーとして招き、仕事に就くまでの体験や心構え、喜びや苦労などを交え
た「生き方」についての講話を聞きます。今年度は楠本さんをお招きしてマナー講座にも取り組みました。
〇人は、「何のために学ぶのか」「何のために働くのか」、「自分が暮らす社会のありかた」など、その意義や目的について考え、学ぶことや働くことの大切さについて学びます。今年度はNPO岡山きずなさんをお招きして、「ホームレス問題」学習にも取り組みました。
○自分の進路・将来設計:高校進学だけでなく、自分は、どんな職業について何のために働きたいかについて考え、将来の自己を想定した進路設計を作成します。
○職業の世界:多種多様な職業について調査したり、また、地域の企業について知ります。今年度も、日生漁協の方々からの「聞き書き」を行いました。
◎いま・未来のためには。学校と家庭とのさらなる連携から協働へ。
3年進学事務手続き説明会・学年懇談会(11/2)

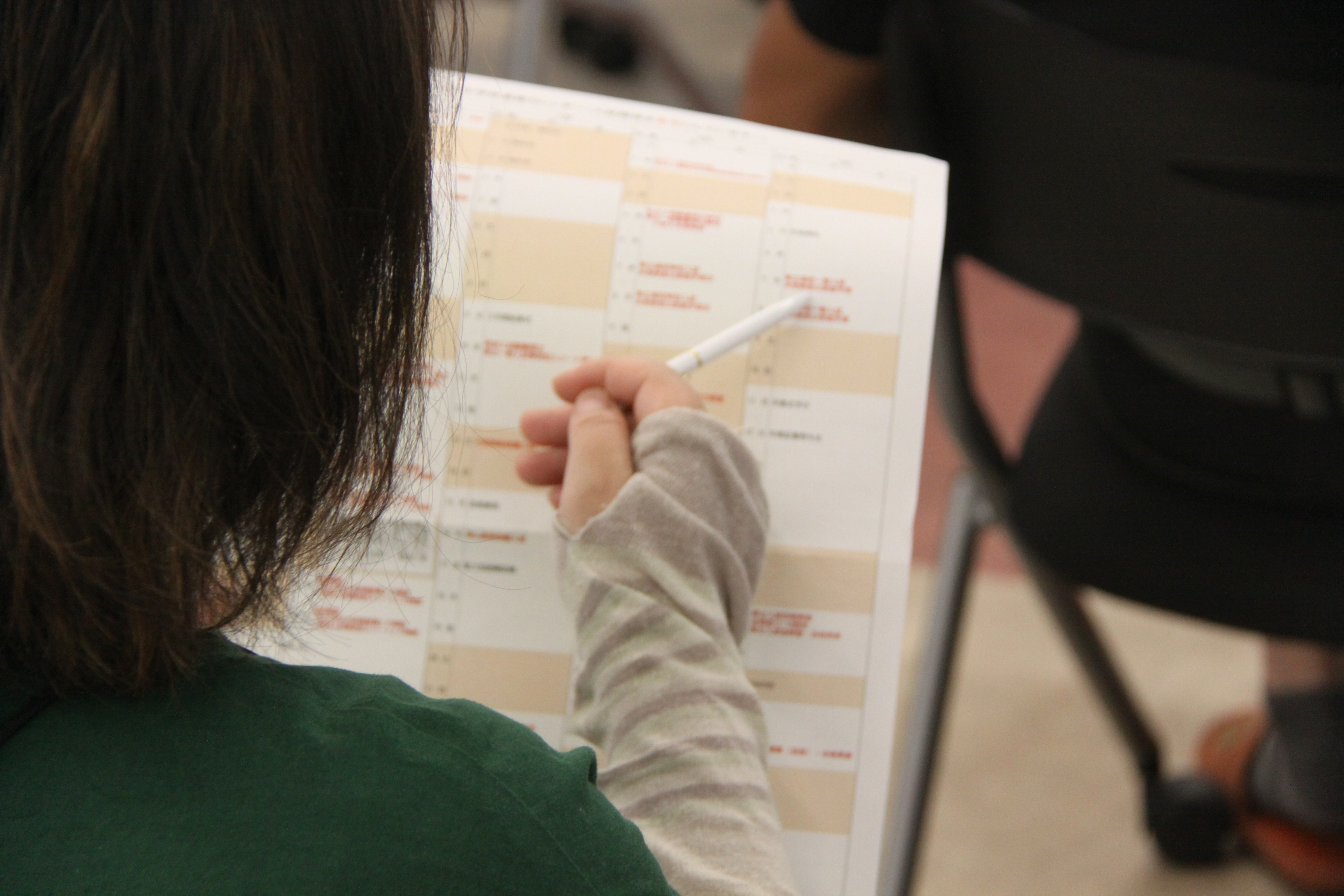


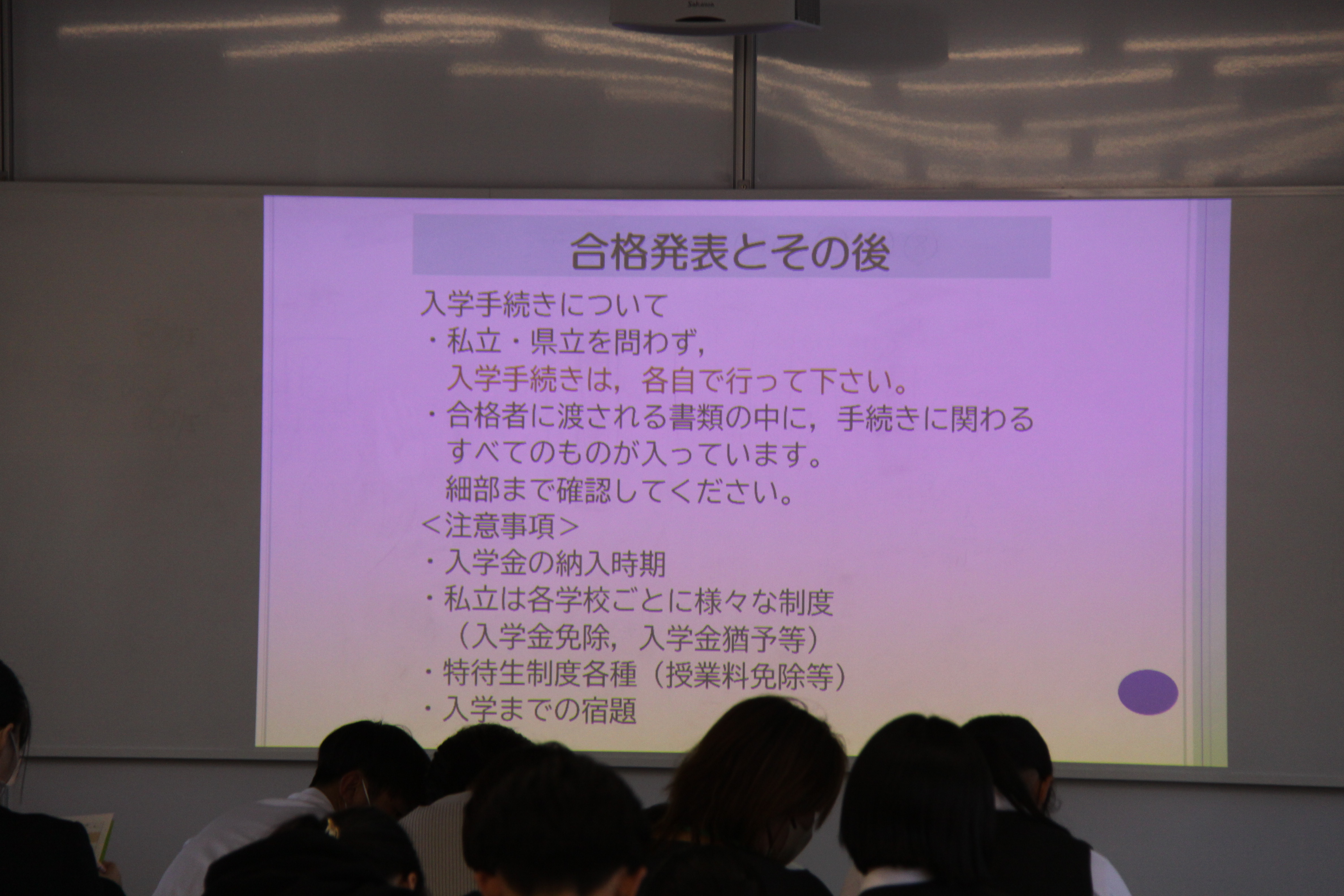



Listen‚ smile‚ agree‚ and then do whatever the fuck you were gonna do anyway. Robert Downey Jr.
(まず話を聞いて、にこっと笑って、うなずこう。それから、どんなことでも自分がやろうとしていた事をすればいいんだよ。)
進学事務がインターネット出願になっただけでなく、高校のスタイルや学び方も多様な時代となりました。一人ひとりが、自分らしい適性・能力を伸ばす中で、自分らしい進路の実現を図ることができます。進路や進学についてご相談がありましたら中学校にいつでもご相談ください。
◎豊かな学びを~人に出合う




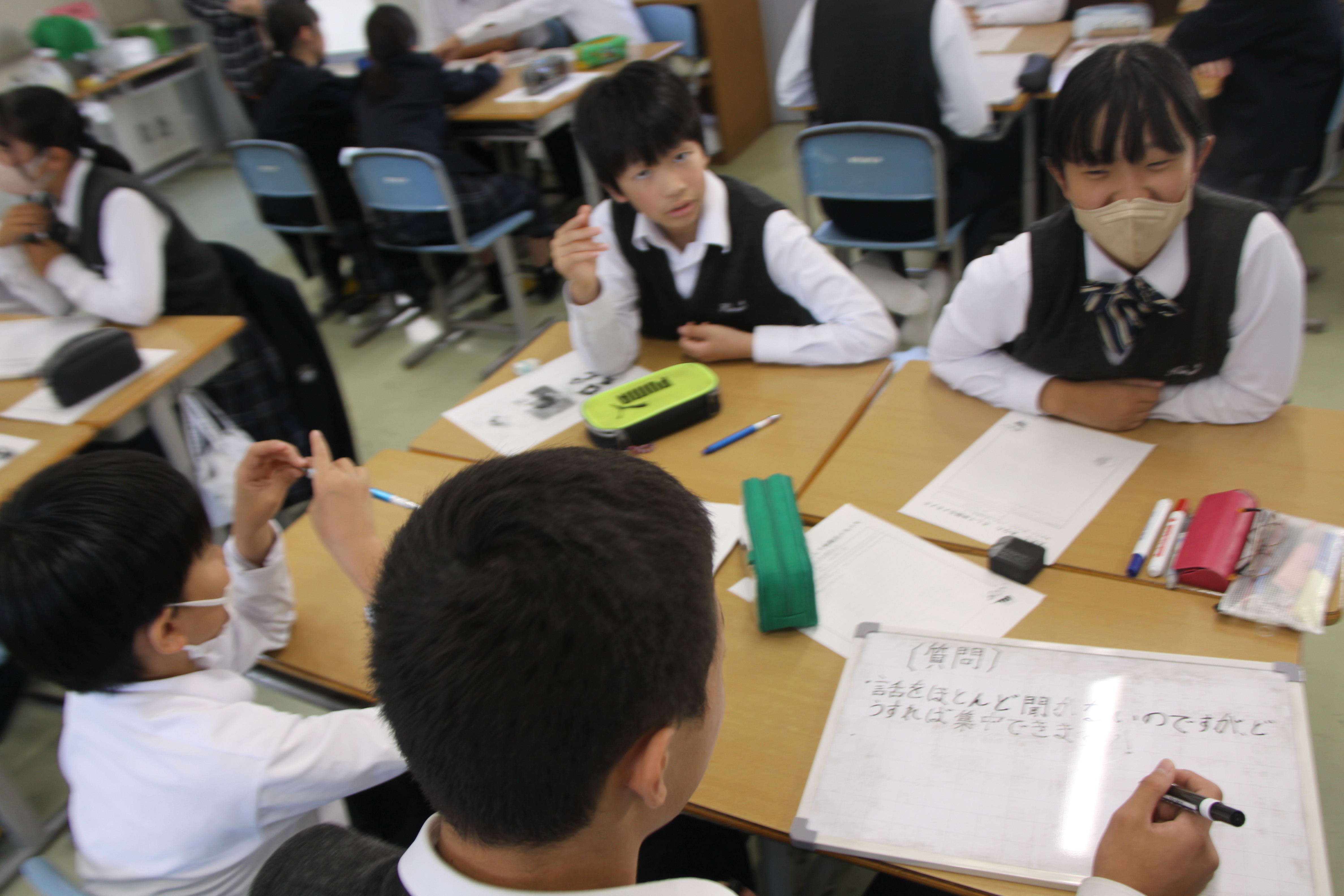



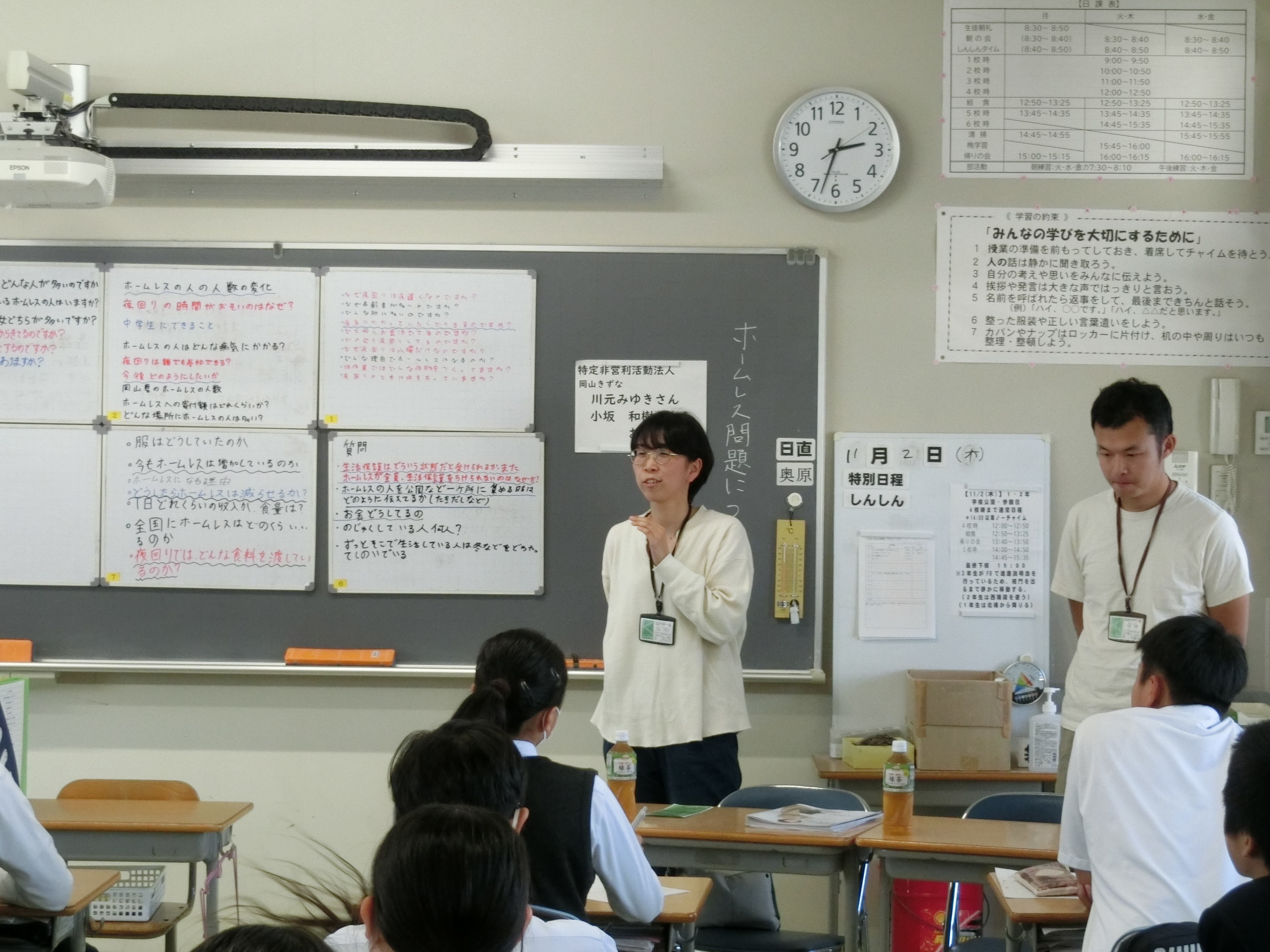
◎豊かな学びを~仲間と学ぶ

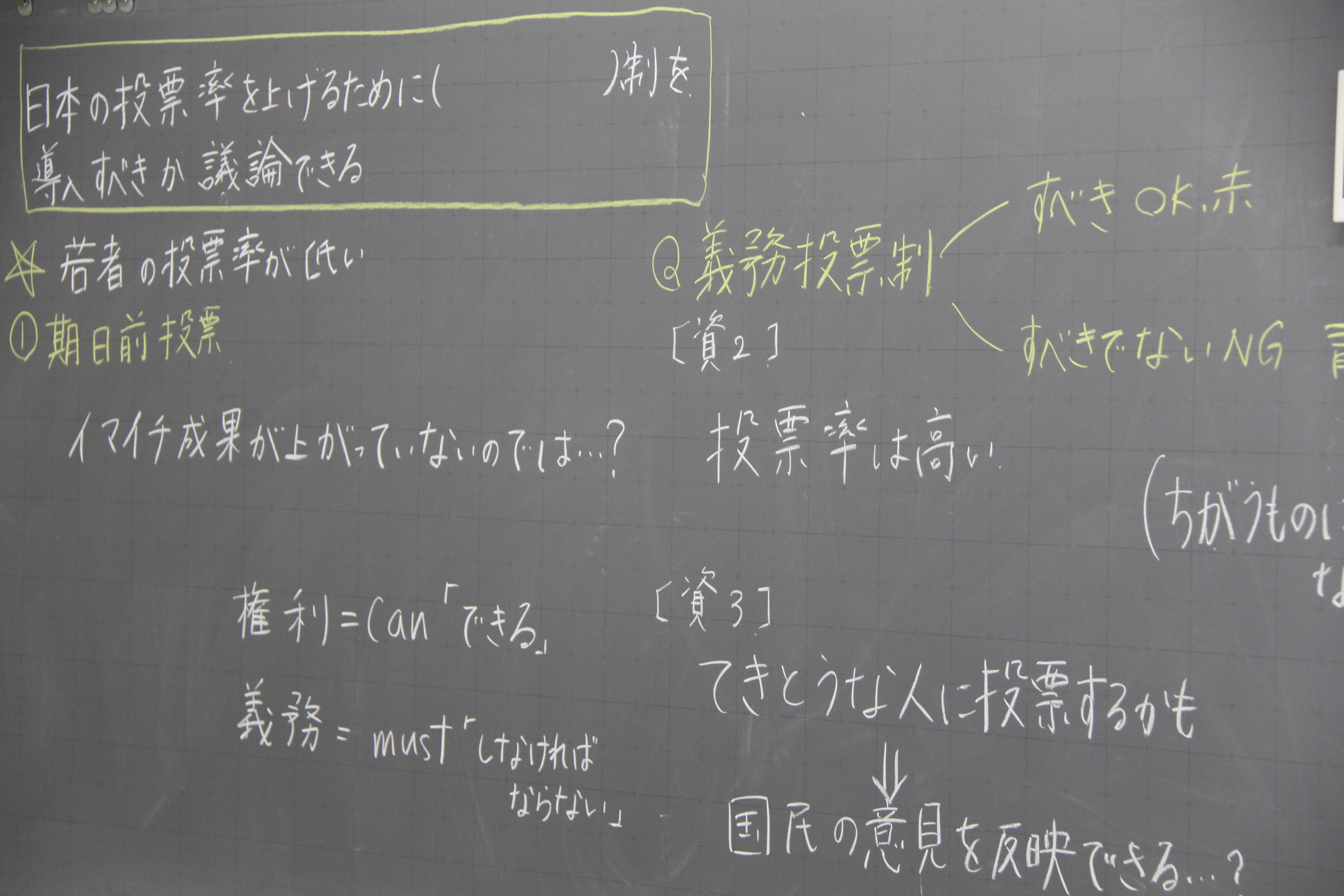


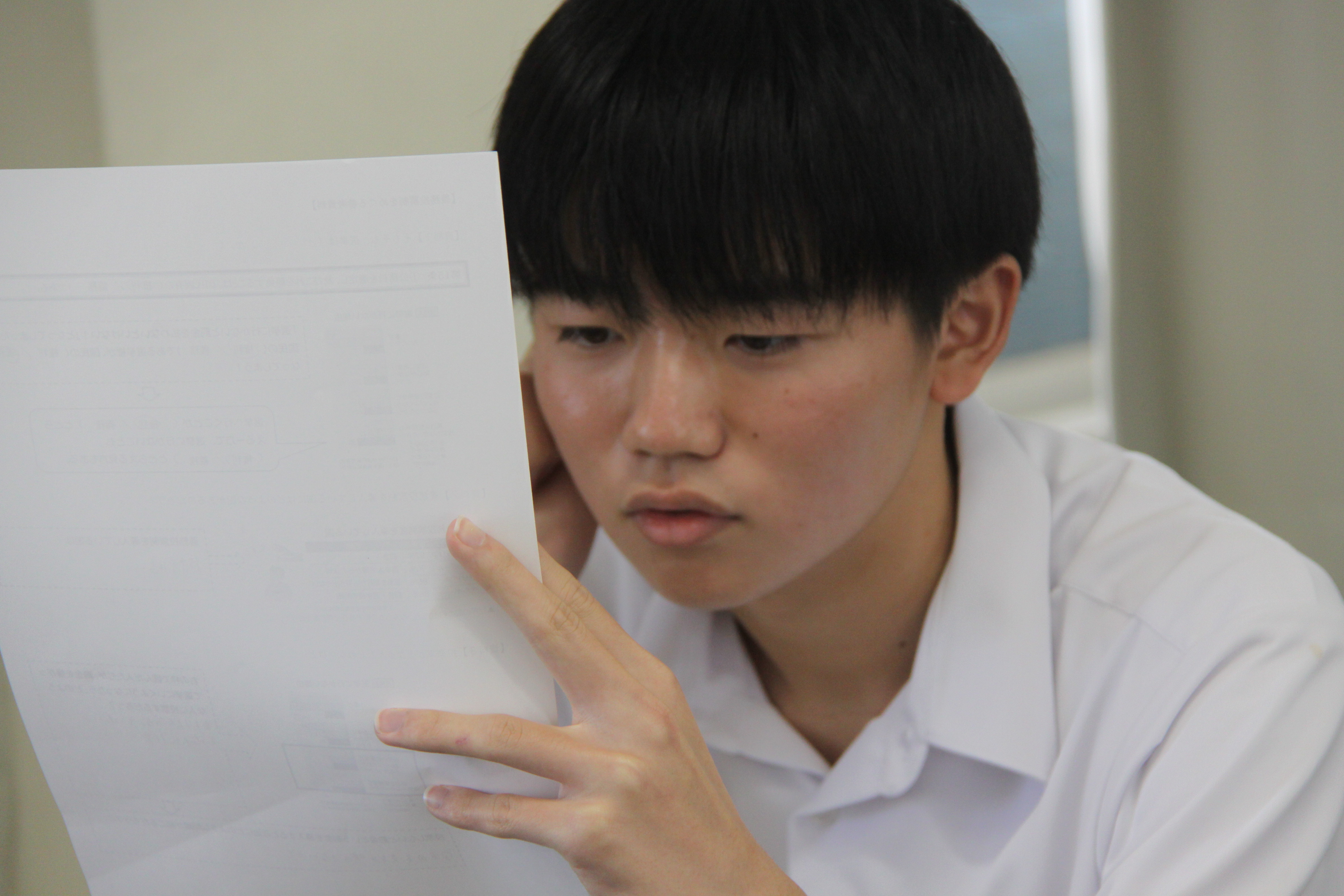

Alone we can do so little. Together we can do so much. Helen Keller
(私たちがひとりで出来ることはほとんど無い。私たちが一緒に出来ることはたくさんある。)
◎豊かな学びを~聞き書き
聞き書き」とは、対象となる人の話を「聞いて、書き記す」ことです。「聞き書き」は、聴くことを大事にコミュニケーションとしての「聴く力」で支えられ、その人のコトバとして書き記される「書く力」によってカタチとなります。「聞き書き」には、聞く力・書く力・それを語り手に「もどす」力が重要です。さらに「聞き書き」は、ひとりの語り手の人生(生きてきた)物語の記録であると同時に、その語り手の生きてきた地域の文化・歴史の伝承としての意味を待つといわれています。近年、医療や福祉の場でも「ナラティブ」への関心が高まり、「ライフヒストリー・インタビュー」や「聞き書き」の実践が多く報告されています。
地域独自の歴史や文化を見直し、それらを次世代につなぐことへの意識の高まりの中で、歴史や文化の保存・継承を目的とした取り組みとして、語りを通して地域の課題を具体的に捉え、地域理解を深める「地域学習」として、日生中でも継続的に「聞き書き」活動を行っています。
10月30日、2年生は日生漁協で行った聞き書きをまとめ、1年生にむけて発表しました。

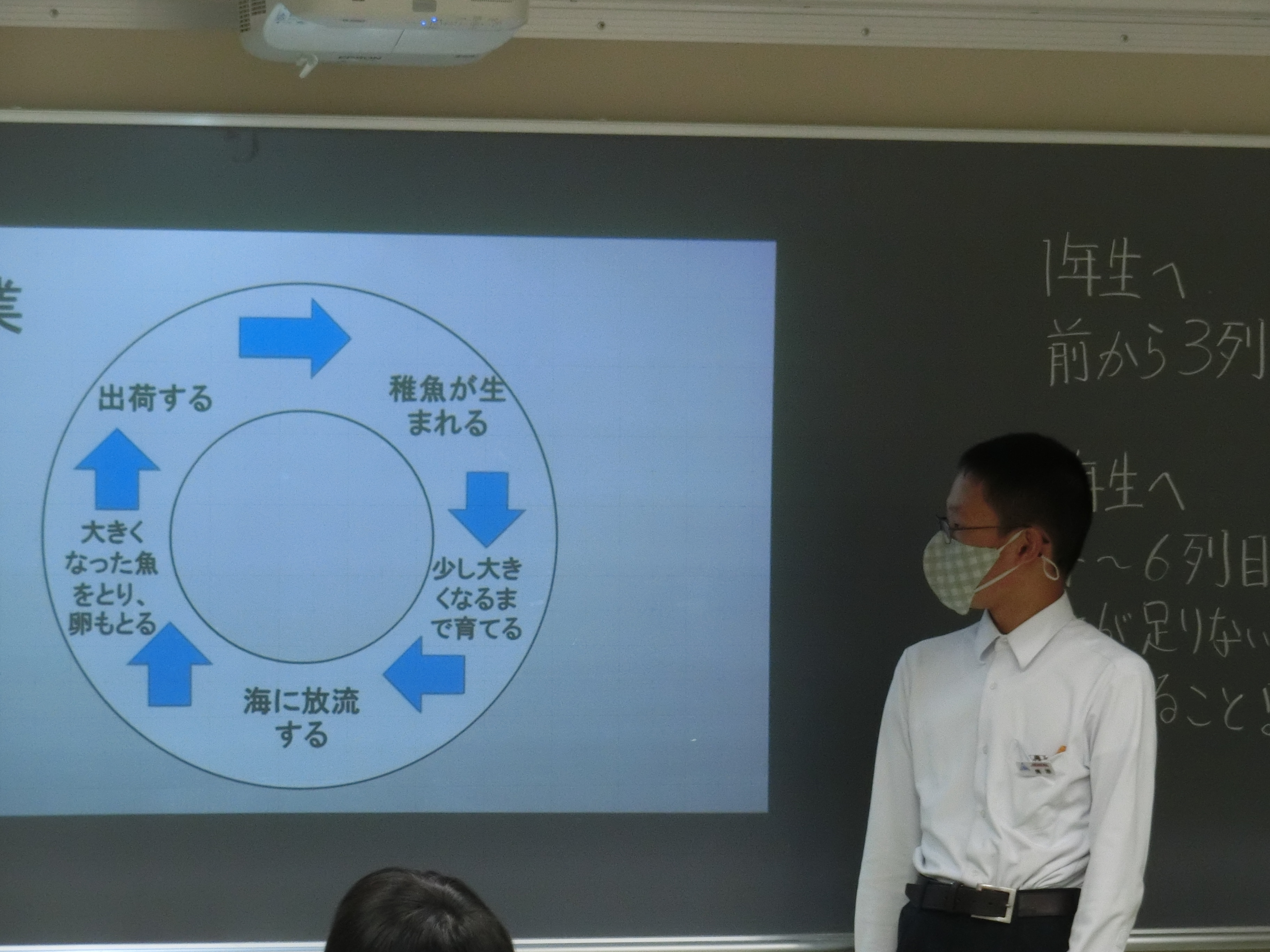

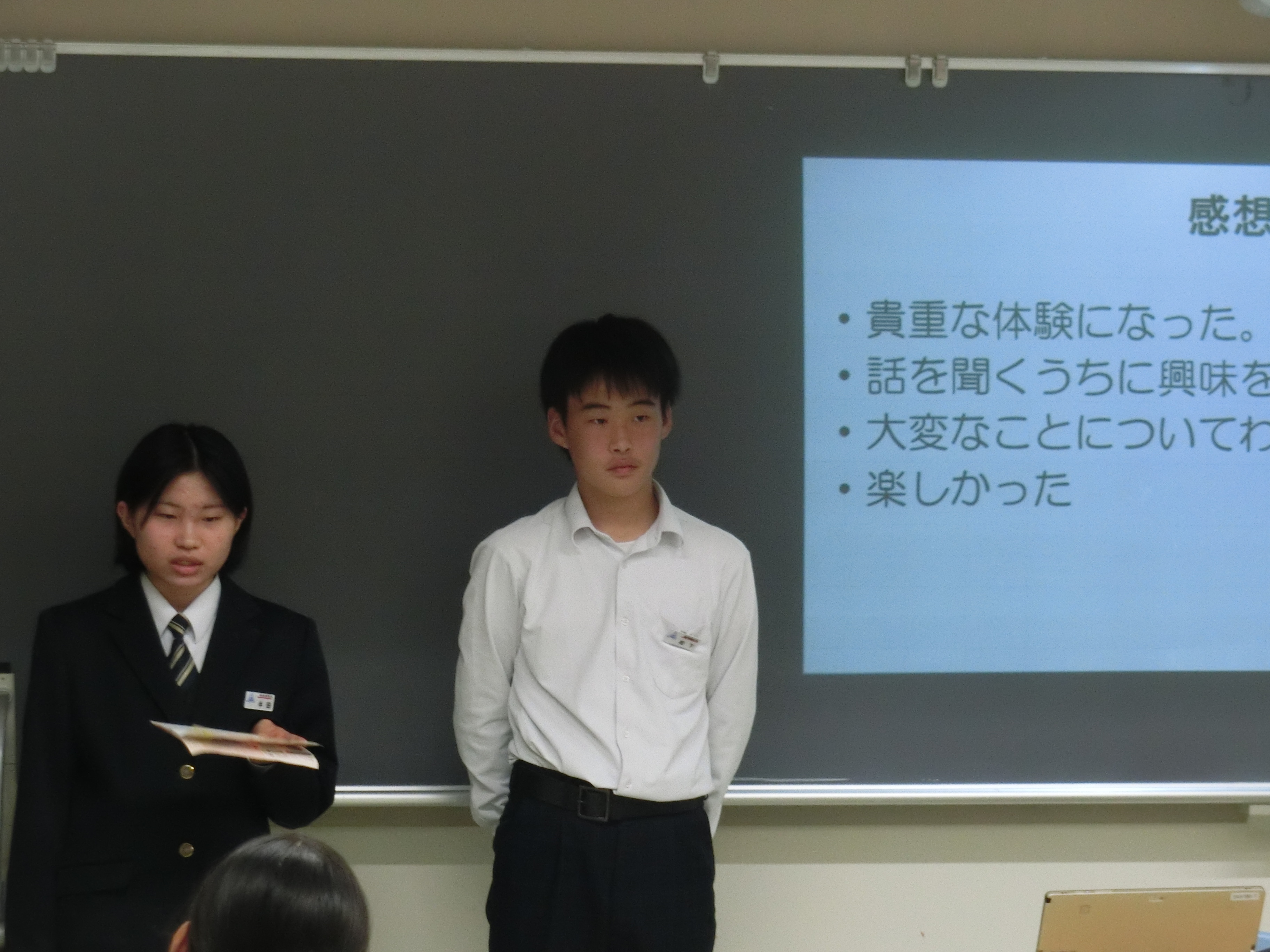
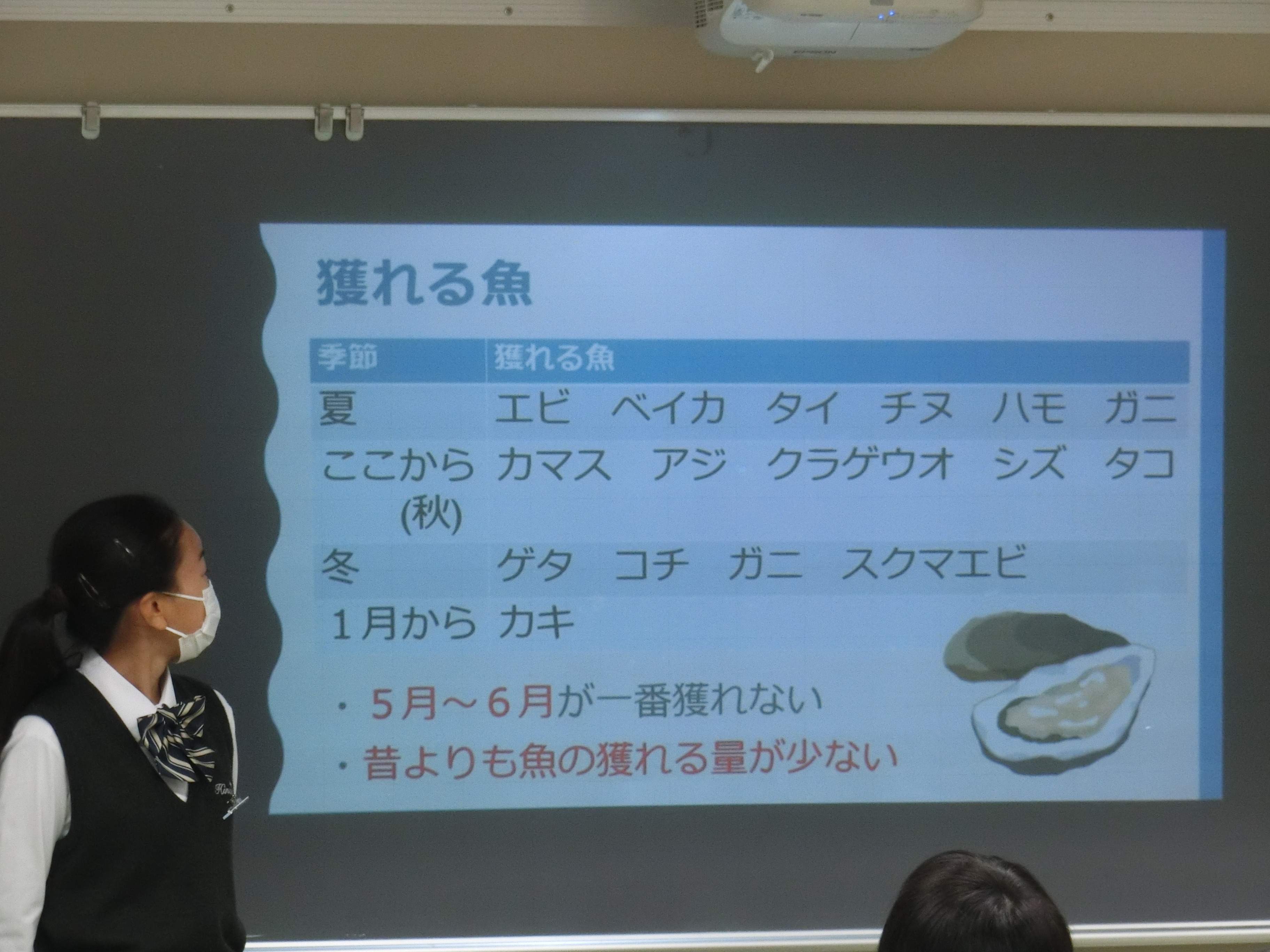
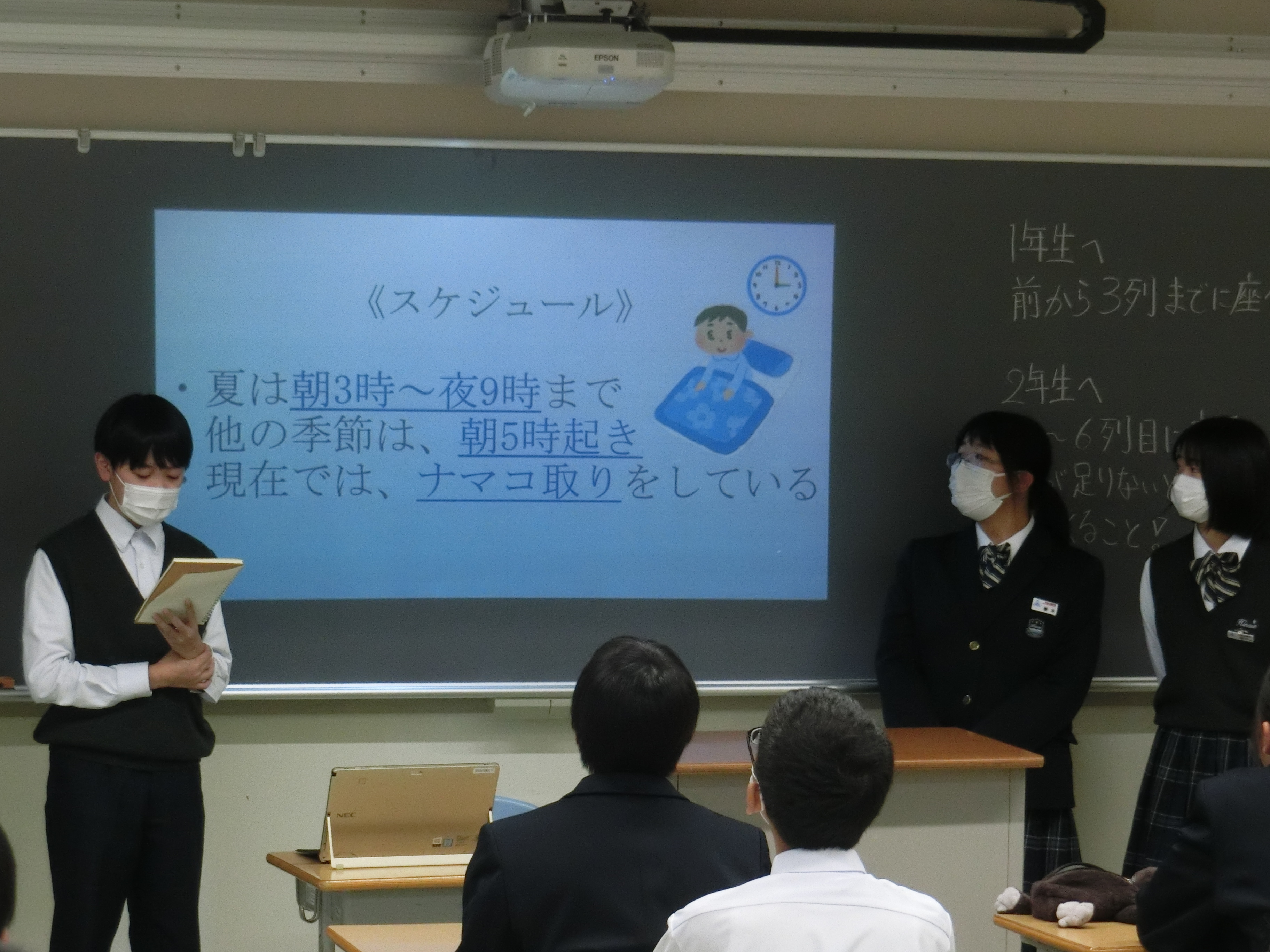
◎豊かな学びを ~人権教育から(11/2:学校公開日・参観日)
今日、2年生は、職場体験学習を前に、岡山きずなの川元さん、小坂さんをお招きして「ホームレス問題」について学びます。取組のねらいは、 ホームレス(ハウスレス)の人たちに対する偏見をなくすとともに、・不景気や格差の拡大を背景に、誰もが突然の事故、病気、解雇などで困窮状態に陥る可能性がある、社会問題であるということを学びます。また、自分自身を客観的にみたり、周りの仲間たちの背景を見つめていく中で、貧困の問題は自分たちも無関係ではないこと等を考えていきたいと思います。
1年生は、備前市自立支援協議会の松下さん、塚本さんをお招きして、本校の小寺SSWと共に、一人ひとりの発達特性やタイプなどお互いを理解し合う、よりよいクラスづくり(共生社会のあり方)を学びます。

日生中は、「人権を大切にすること」「自分とは違う他者と生きていくか」「自分とうまくつきあうこと(いまの自分を認めること)」、自分らしく、エンパワメント(自ら成長していくちから)する力を高めること」「他者に依存できる力をつける(本当の依存=自立・自律した生き方)こと」等を、道徳や学級活動等も活用して、これからも取り組んでいきたいと思います。
ご参考に、人権教育は、心がけや思いやりの教育、人権課題を知るだけの取組ではありません。人権教育には四つの側面があります。意義、内容、方法、目的です。
人権教育とは「人権として」の教育 Human Rights Education as human rights.
人権教育とは「人権について」の教育 Human Rights Education about human rights.
人権教育とは「人権を通して」の教育 Human Rights Education through human rights.
人権教育とは「人権のため」の教育 Human Rights Education for human rights.
◎多くの人に支えられて
市青少年健全育成センター来校(11/2)
この日早朝、備前市青少年健全育成センターから真鍋さんと、今吉さんが来校され、校門で生徒たちに声をかけてくださいました。いつもありがとうございます。
また、先日の地区会では、「西小学校前の信号付近(蕃山からの連絡道)で、通学時に、スピードが速く、交通安全上、とても心配な自動車があって危険だ」という意見が出てました。早速、学校から備前警察署へ連絡を入れ、巡回等の強化をお願いしました。生徒自身が、自分たちの安全を守ろうとする意識が高いことはとても大事なことです。本校でも交通の見回りを増やす予定ですが、自分を守る安全な自転車運転を心がけることも合わせて生徒らに話をしています。ご家庭でもどうぞサポートをどうぞよろしくお願いします。

◎創作の広場
第14回岡山県こども備前焼作品展において、岡山県教育委員会教育長賞を受賞した小寺くんの作品写真が『教育時報11月号』で紹介されました。
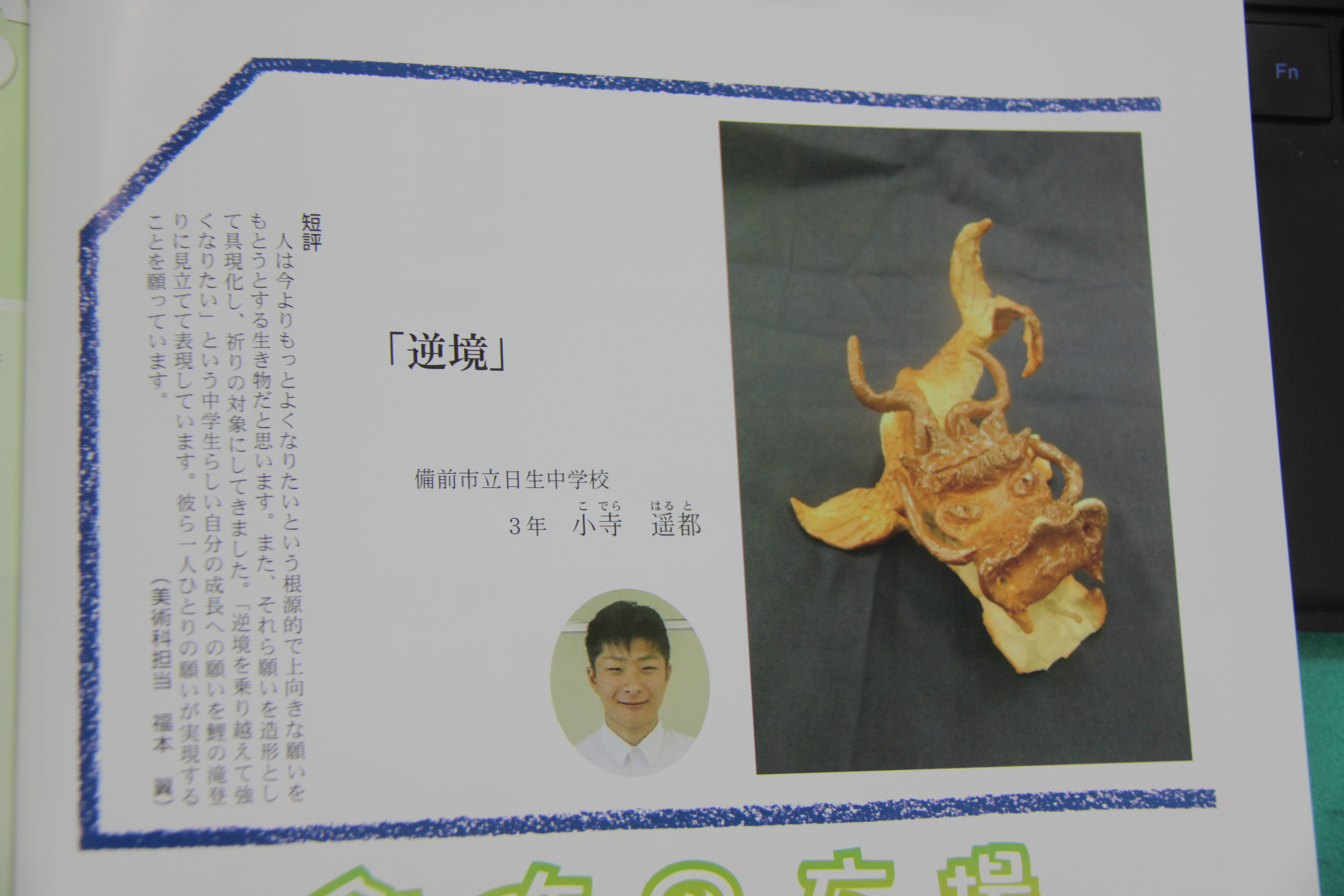
◎〈能あるきりんは首を隠す
んなわけねーだろ剝きだして生きていくんだ光の荒野 上篠 翔〉
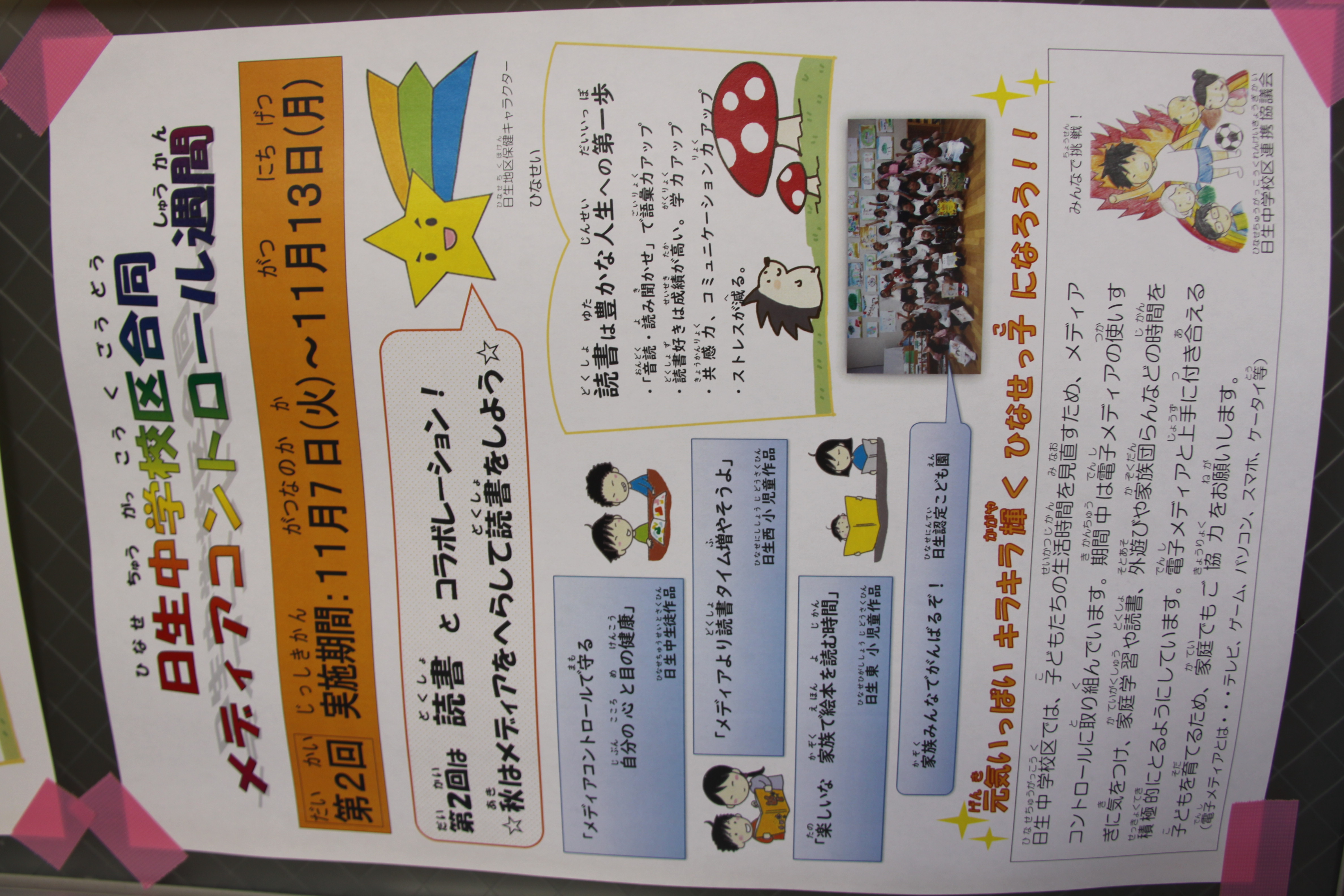
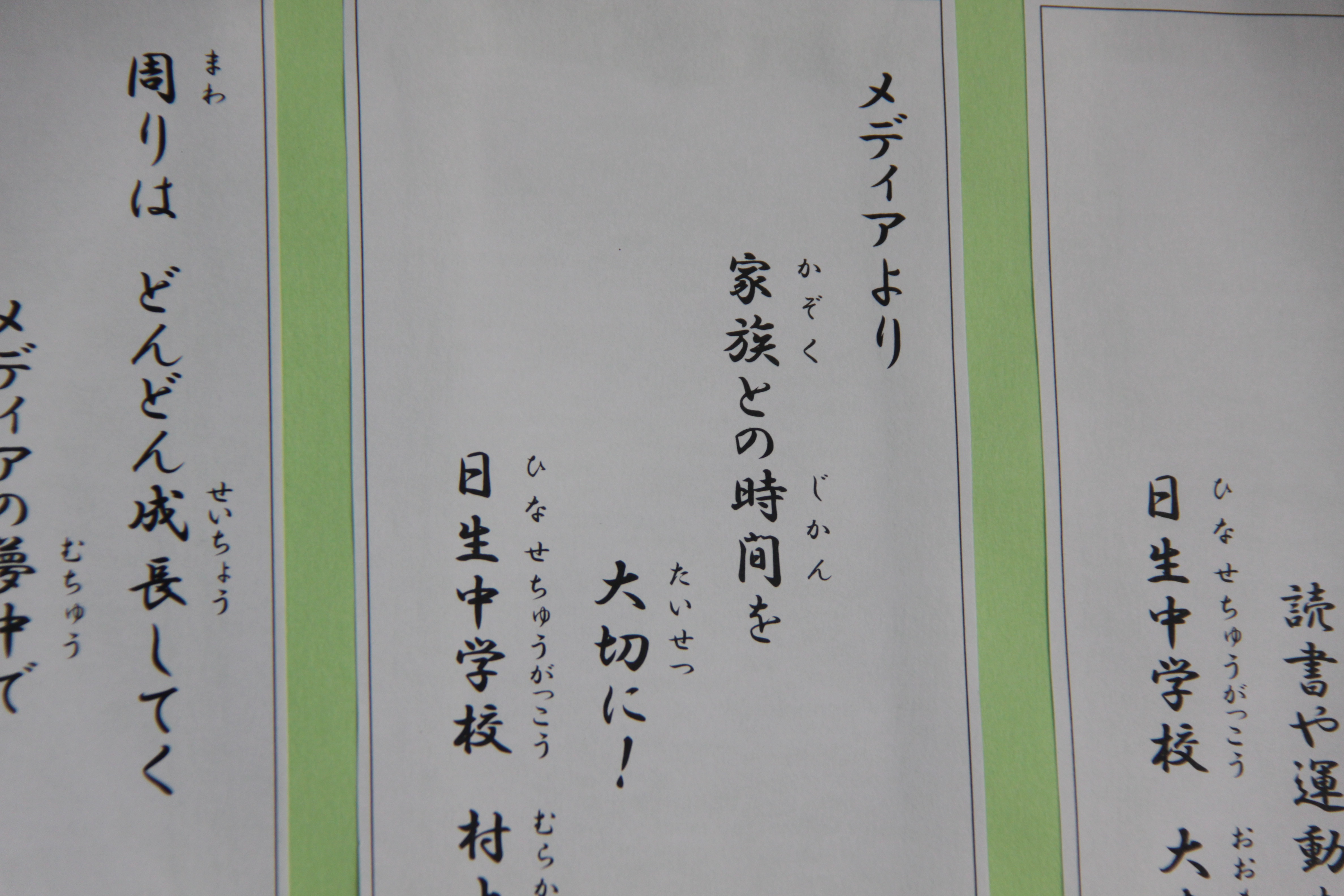
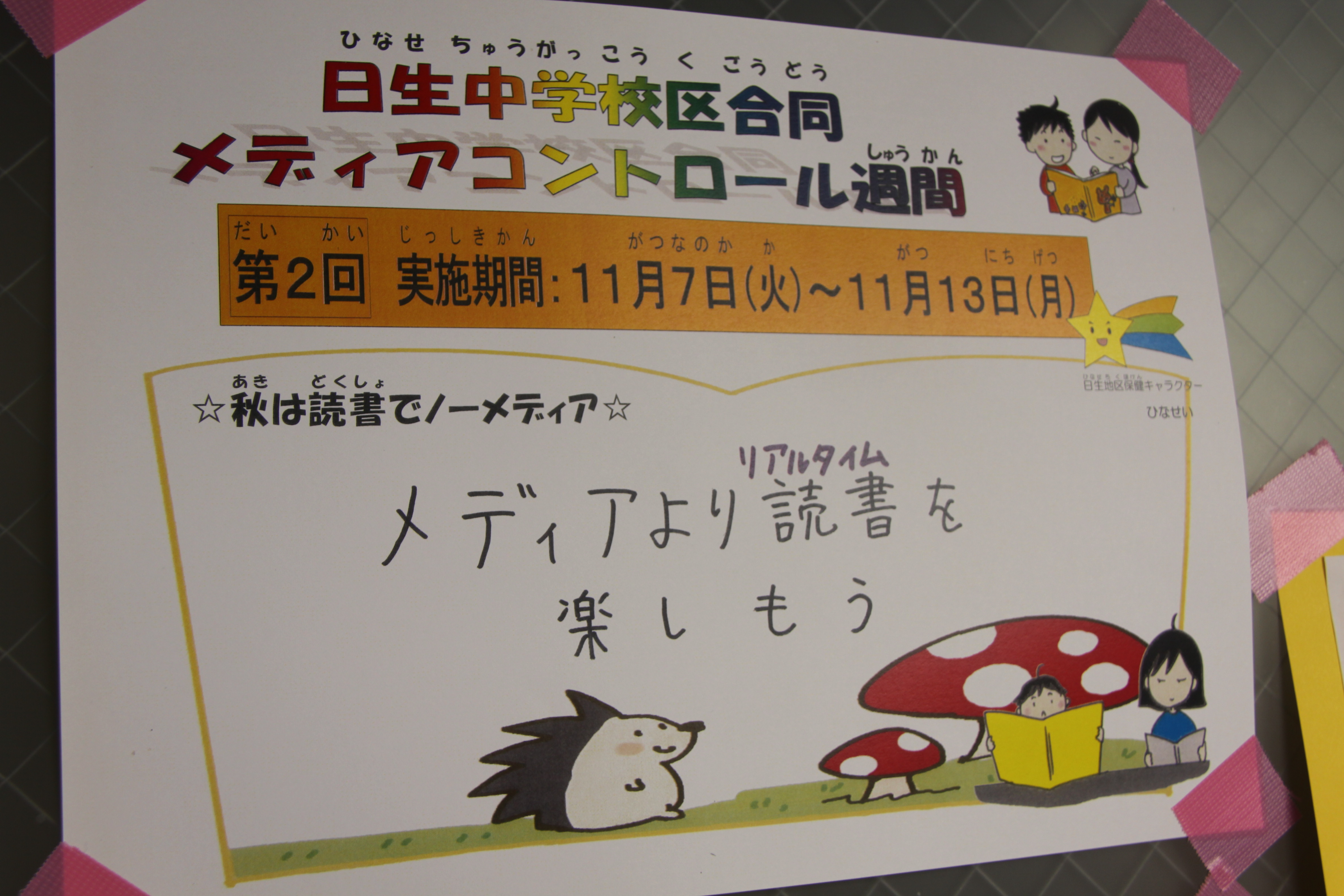

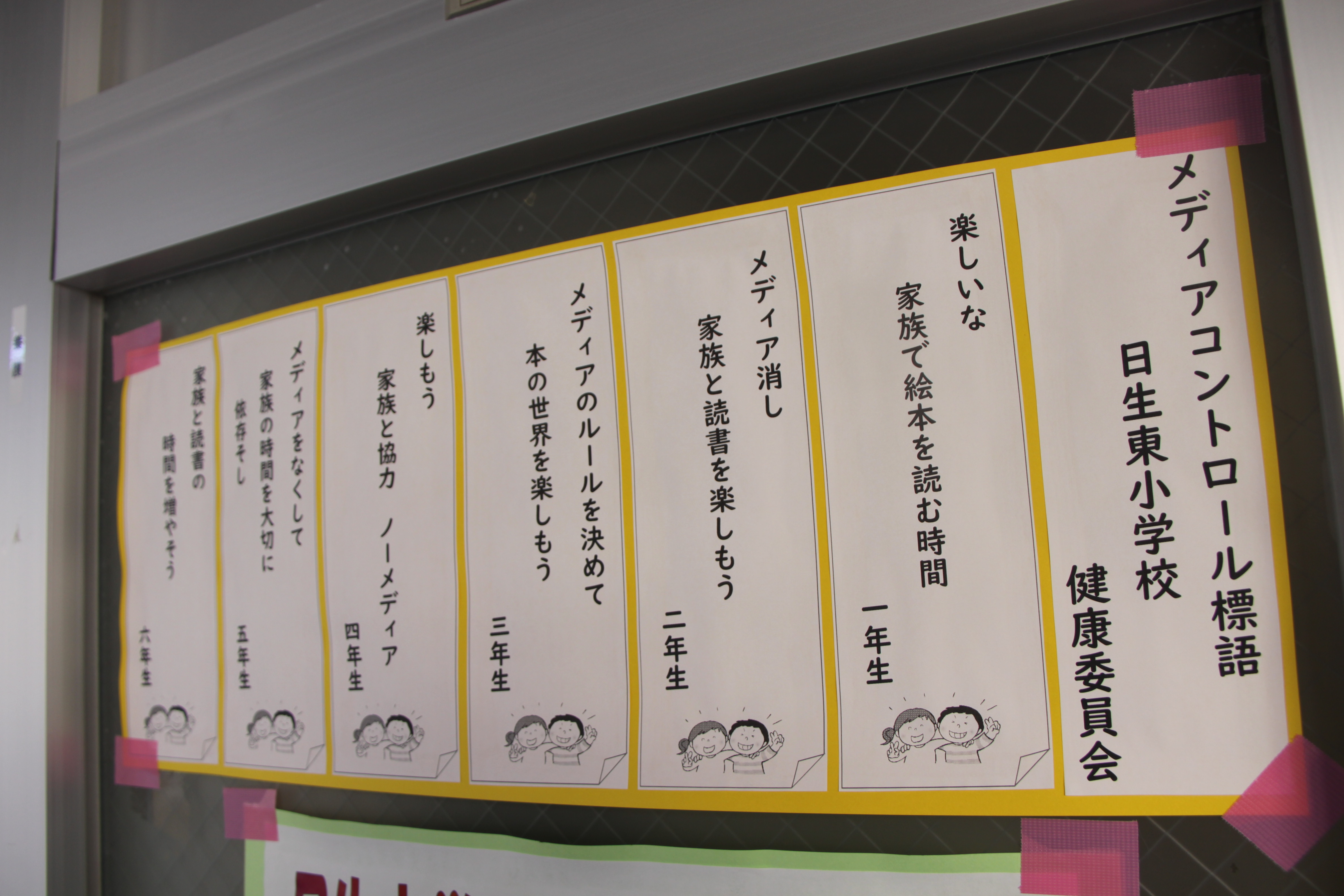

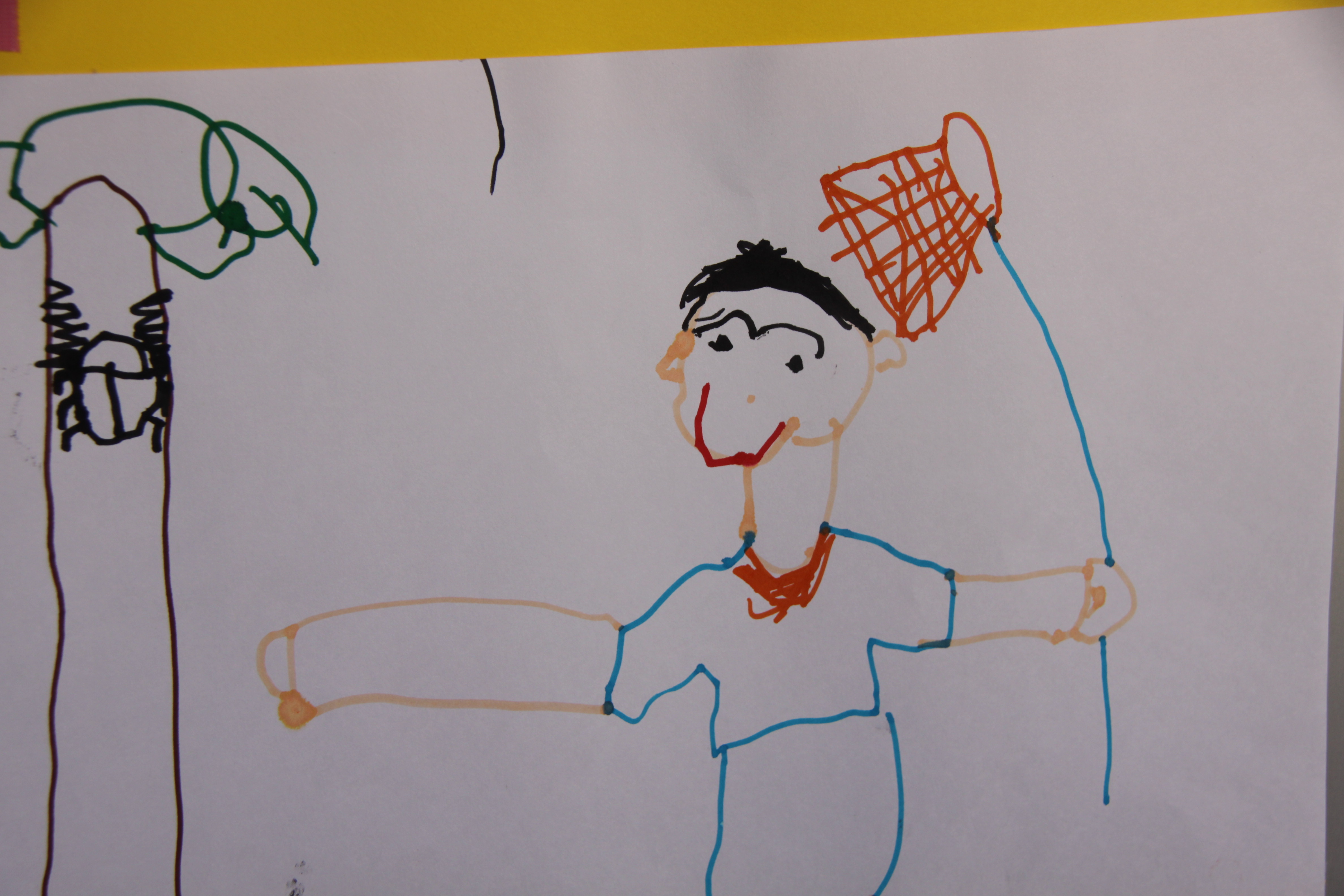

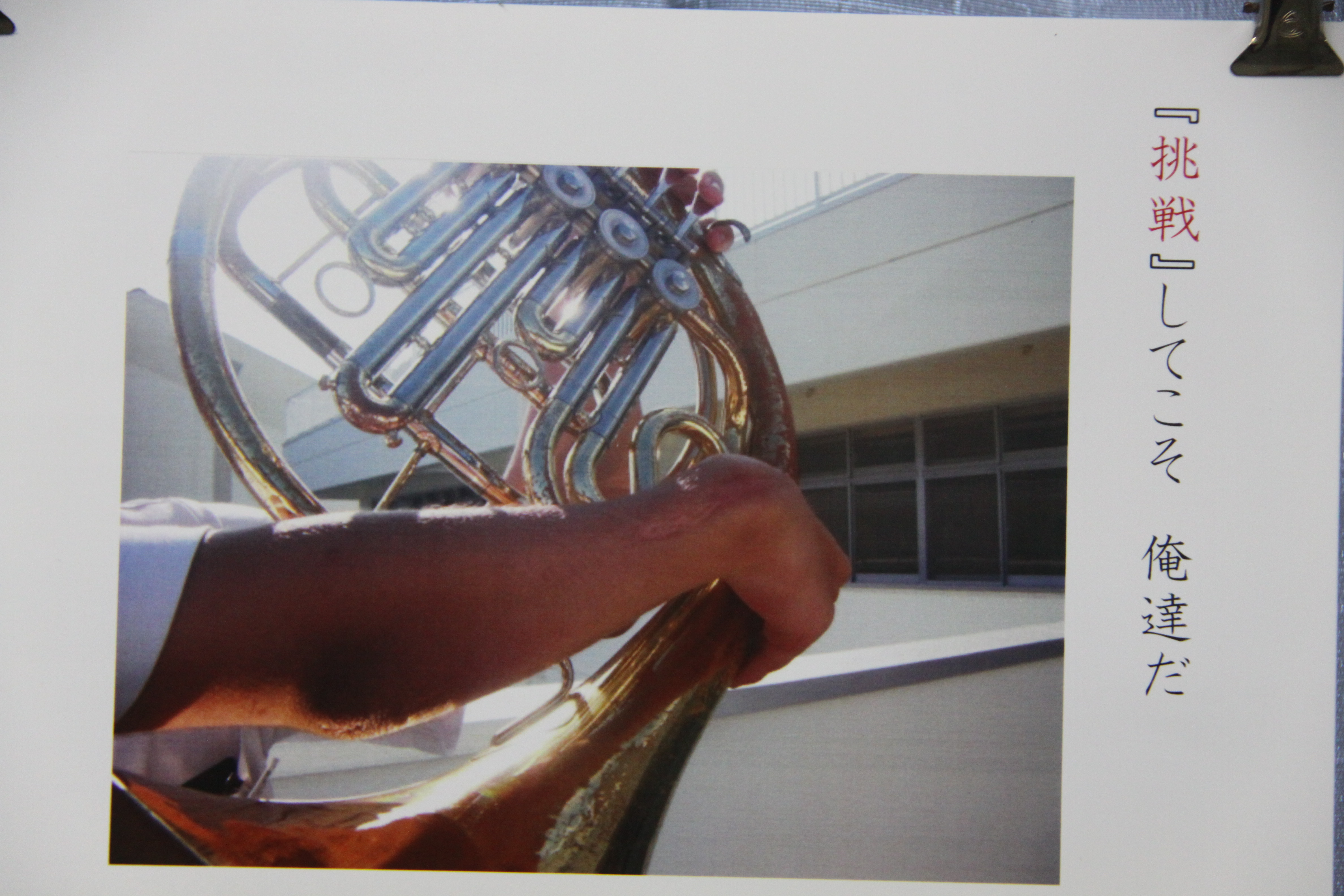

こどもえんのみなさん、げんきいっぱいの ぽすたーの えを ありがとう
◎わたしたちの学校はつくるのさ(10/31 生徒朝礼)



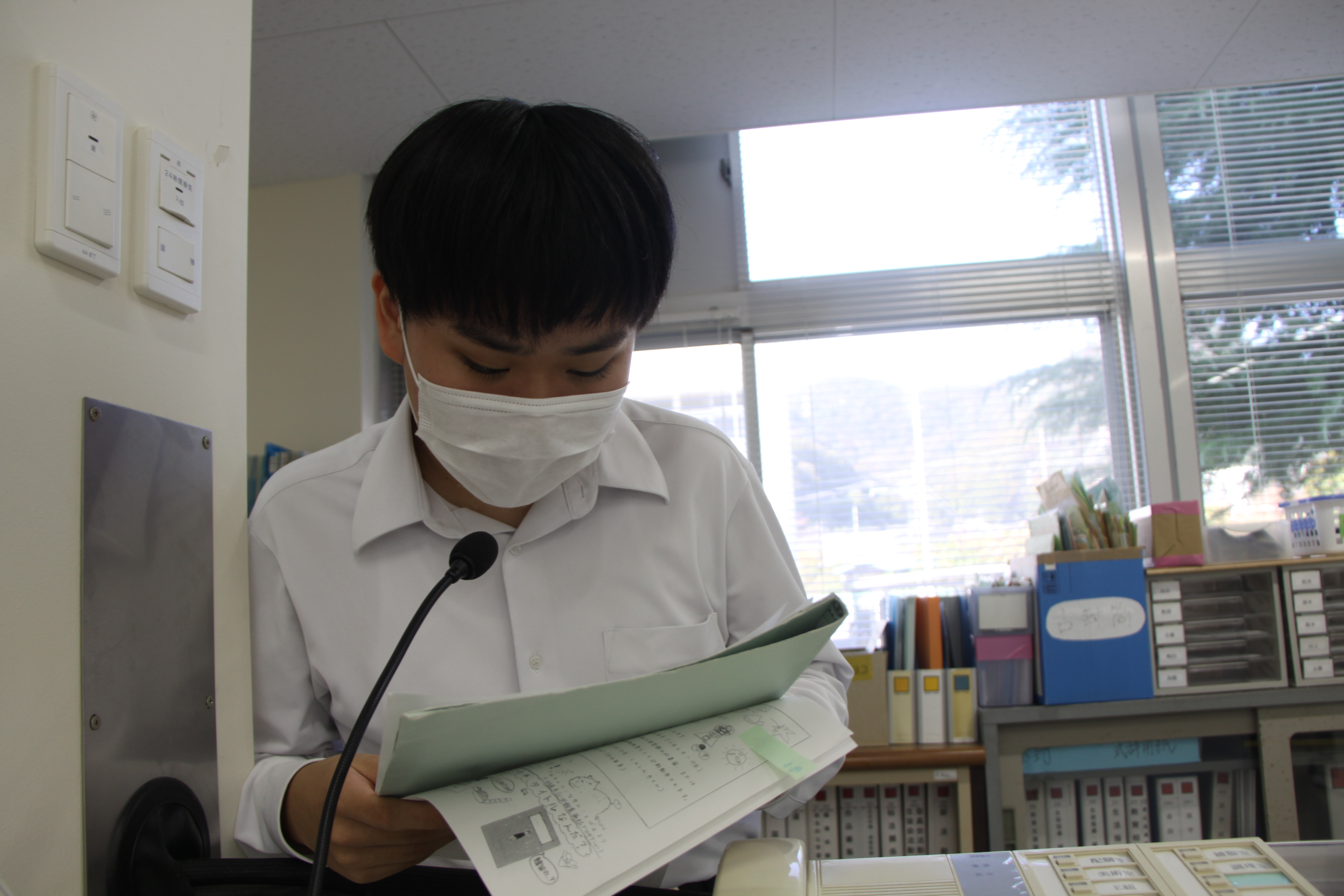
みんな!秋の読書月間スタートです。イベントするよ。(BY文化委員会 11/1~)
◎心に響く・考える・深める時間を共有できた幸せ(10/31)
10人の弁士のみなさんありがとう、ありがとう。素敵な時間でした。体験と知識が合わさり、説得力のある主張が多くありました。3年ぶりに市内各中学生の代表が一堂に会し、お互いに刺激し合った良い会でした。本校からは、3年生の杉原さんと石橋さんが、弁論を発表しました。2人とも、開催まで繰り返し練習した成果を発揮し、爽やかに堂々と主張しました。
そして、最優秀賞は、論題「戦争の記憶を風化させないように」を弁じた本校の石橋さんとなりました。おめでとう。石橋さんは11月24日開催の第48回岡山県中学校弁論大会(県中学校国語教育研究会、山陽新聞社主催 北区柳町の山陽新聞社会場)に備前市代表として出場します。
そして、聴衆であった生徒の皆さんの聴く姿勢や、しっかりした運営を行った文化委員会に、多くの方々からお褒めの言葉をいただきました。


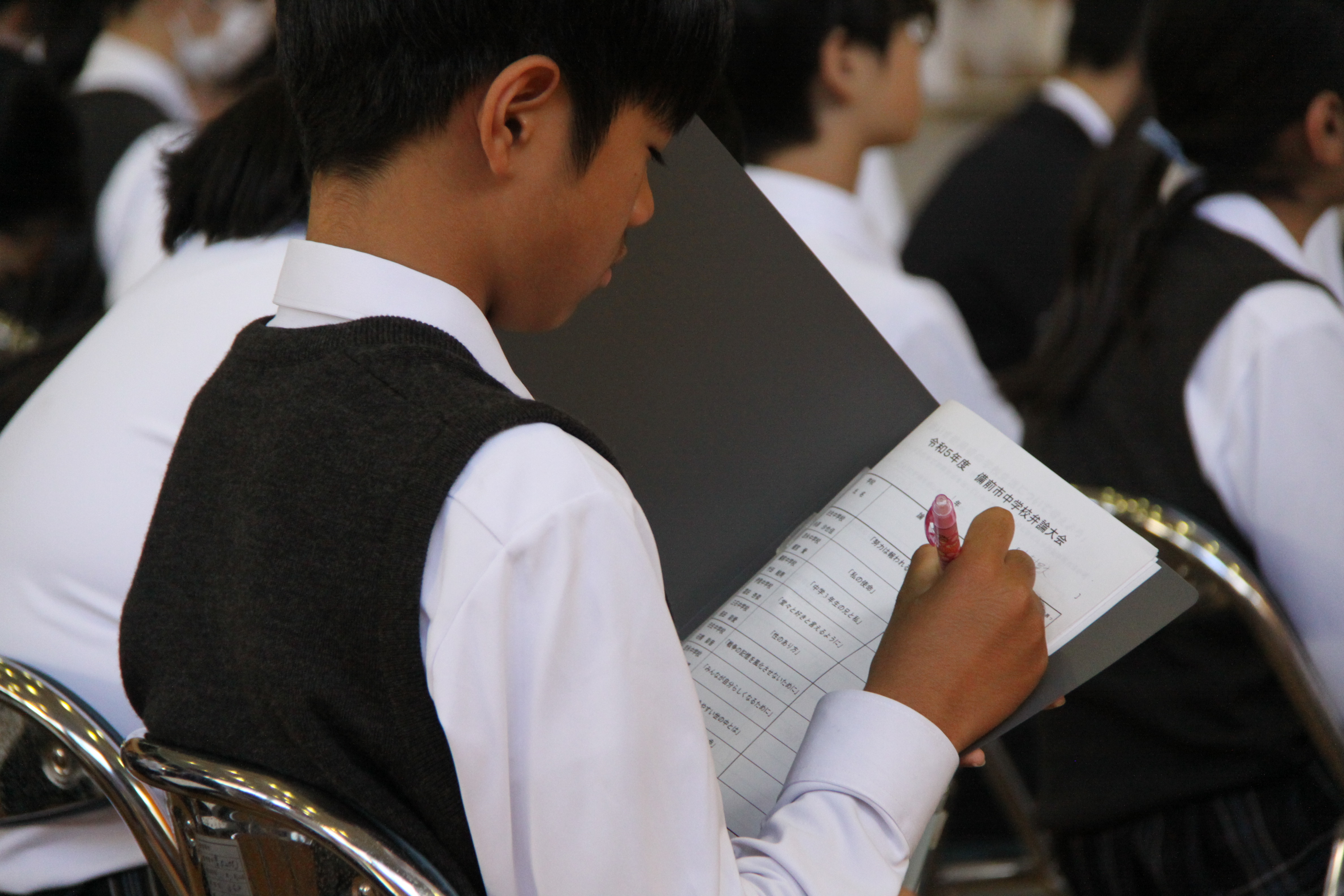



◎書くことは考えること 考えることは生きること
伝えること 聴くことは学ぶこと 学ぶことは生きること

日生中学校を会場にして、31日、今日、備前市中学校弁論大会が開催されます。市内各中学校代表生徒10名の弁論に耳を傾け、自分自身の考えを広げ・深めます。
論題は「努力は報われる?」「私の使命」「中学3年生の兄と私」「堂々と好きと言えるように」「性のあり方」「戦争の記憶を風化させないように」「みんなが自分らしくなるために」「生きやすい世の中とは」「ちいさな一歩」「自分を見つめる」です。
◎地域と共にある学校 ~私たちができること~
街頭募金へのご協力をありがとうございました。(10/30)
生徒会の新しい取組としての街頭募金活動を全校に呼びかけ、この日、社会福祉協議会の方々と一緒に、パオーネの入口で、「赤い羽根共同募金」への協力を呼びかけました。生徒たちの「御協力よろしくお願いします」の呼びかけに、多くの方々が次々と足を止めて募金に協力してくださいました。ありがとうございました。地域の方々の温かい善意に触れて、生徒たちもありがたさを感じ、活動の喜びを味わっていました。赤い羽根共同募金は、地域の福祉活動を支える募金として、10月1日から来年3月31日までの6か月間、全国各地で運動が展開されています。日生中学校では、校内にも募金箱を置いています。また、11月16日(木)にもう一度、街頭募金活動を行います。よろしくお願いします。









◎「お話に出合う」給食(#^.^#)(10/30)
日生中は食育に取り組んでいます。
絵本『こまったさん』(ご主人のヤマさんが、花屋のお仕事をそっちのけで鉄道の模型に夢中になっています。その鉄道模型の中に、こまったさんが入り込んでしまうというお話。いつの間にか食堂のキッチンで、ヤマさんがグラタンを作ることになって…貝柱のグラタンも、ほうれん草のグラタンも、ポテトのグラタンも、全部美味しそうで、食べたくなった人は多いはず。)の本の中にあるグラタンを献立にしてくださいました。ごちそうさまでした。
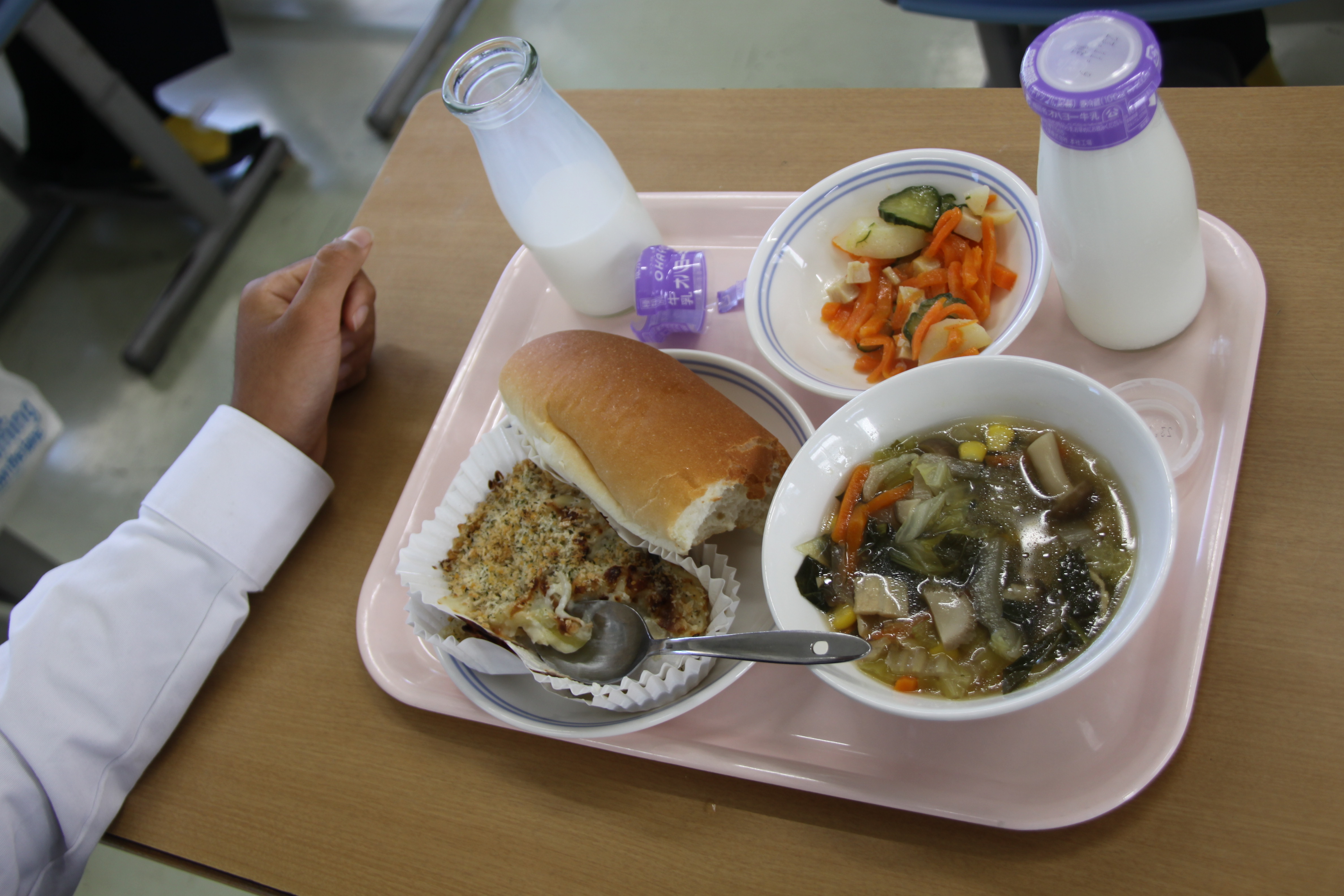

いつもありがとうございます
◎多くのコト・ヒトに支えられて
~〈暑かった夏、クーラーよ!助かったよ ありがとう〉(10/30)
酷暑の中お世話になったクーラー。ホコリいっぱいのフィルターを清掃していただきました。いつもありがとうございます。
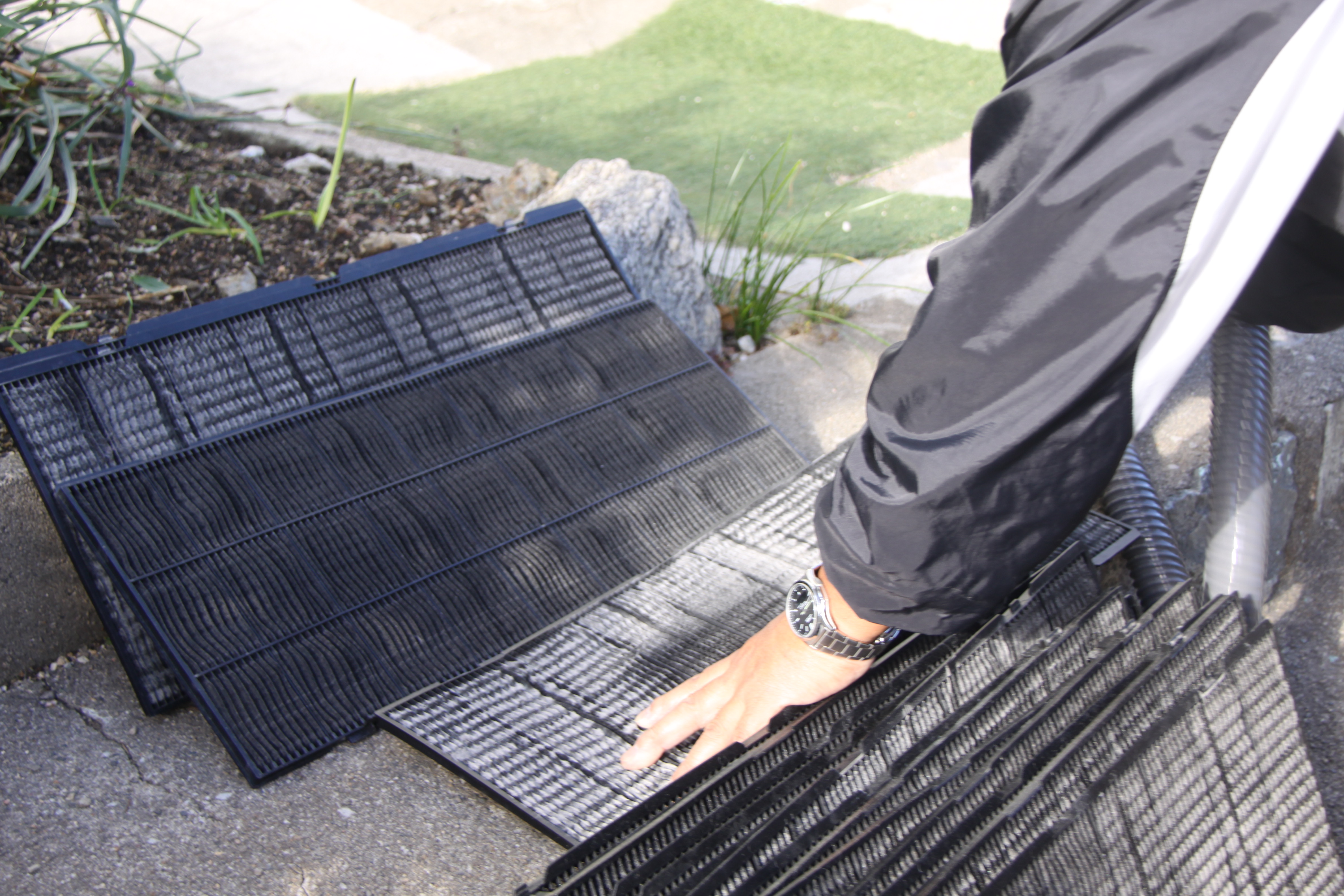
◎私のゆめはこのまちの夢だ
日生地域文化祭に、美術部、美術科、社会科で出展中です。

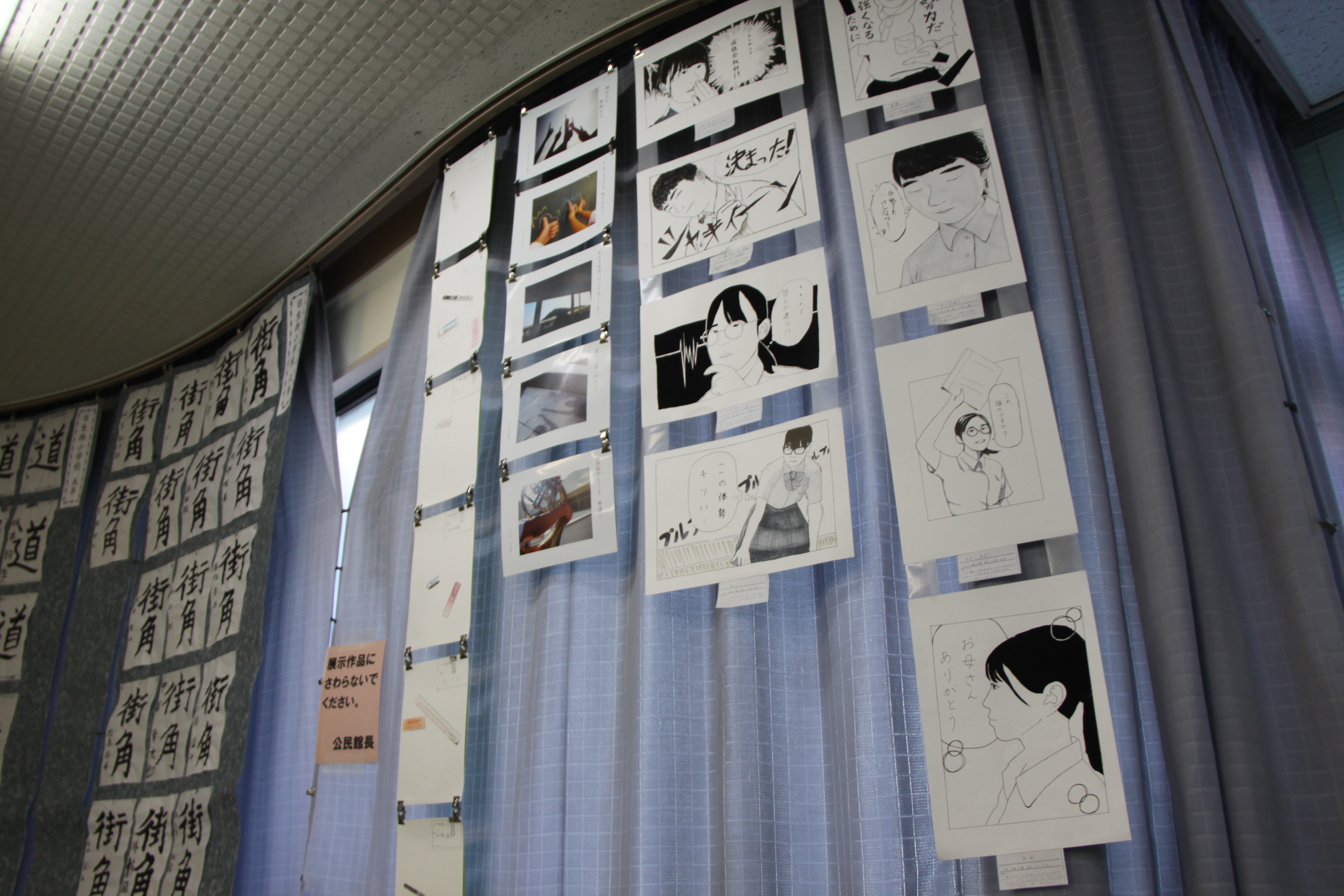



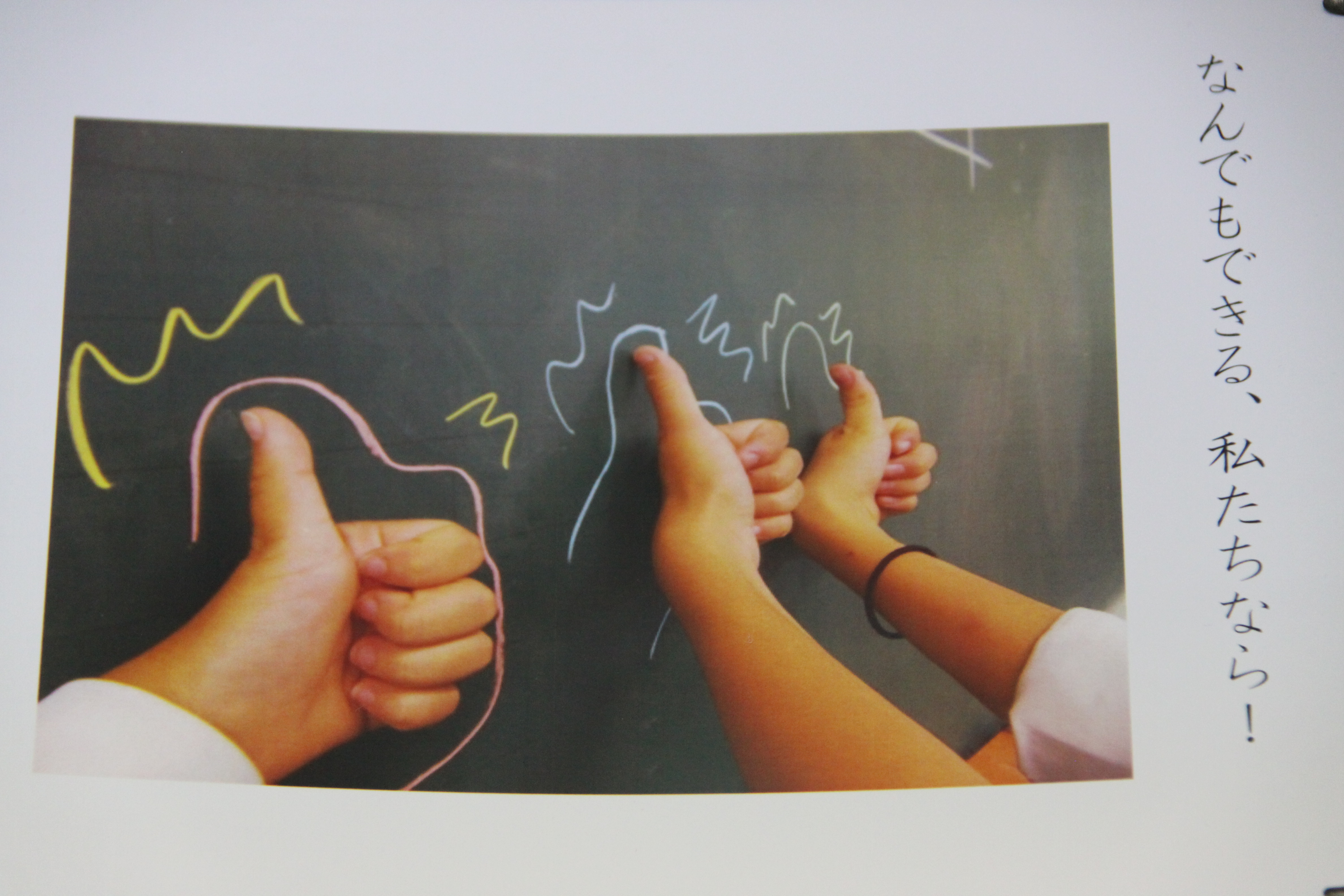


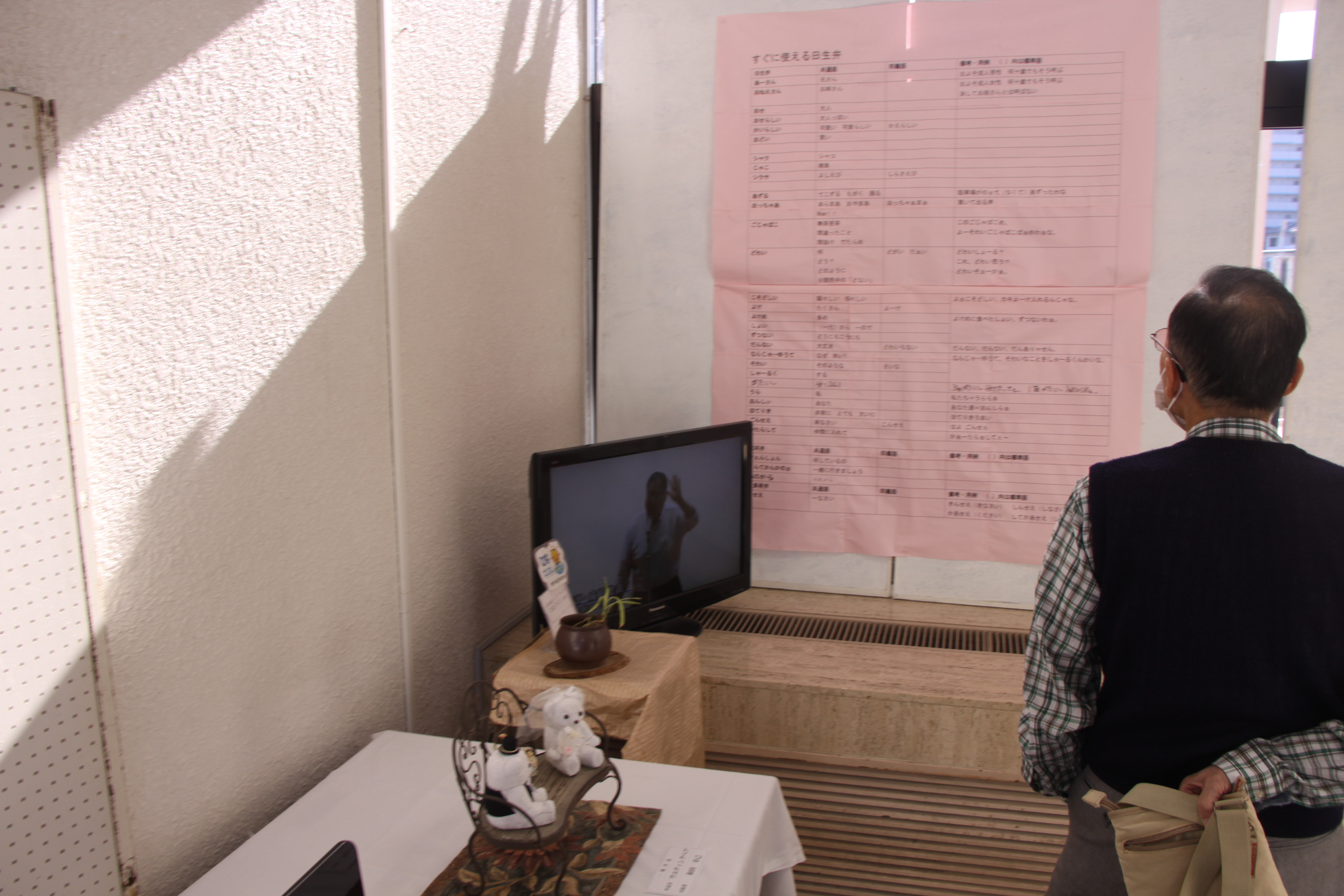
〇10月29日㈰~11月3日㈮ ※特別開館10月30日㈪ 9:00~18:00 (最終日は15:00まで)
〇発表 11月3日㈮ 10:00~会場 日生地域公民館 (日生市民会館)
〇備前市文化芸術振興財団ホームページ参照
〇会期中は、備前市民センターを中心に、日生市民会館、吉永地域公民館及び地区公民館において様々な展示や発表やイベントの開催を予定しています。11月3日は本校の吹奏楽部も舞台発表で参加いたします。皆さんのご来場を心よりお待ちしております。
◎カレーライスワークショップ(10/27)
「わたし あなた そして仲間」を理解する②
1年生は、人権学習に取り組む中で、お互いを深く知り、よりよいクラスを目指した活動を進めています。31日、そして参観日(11/2)にも継続的な取組を行います。

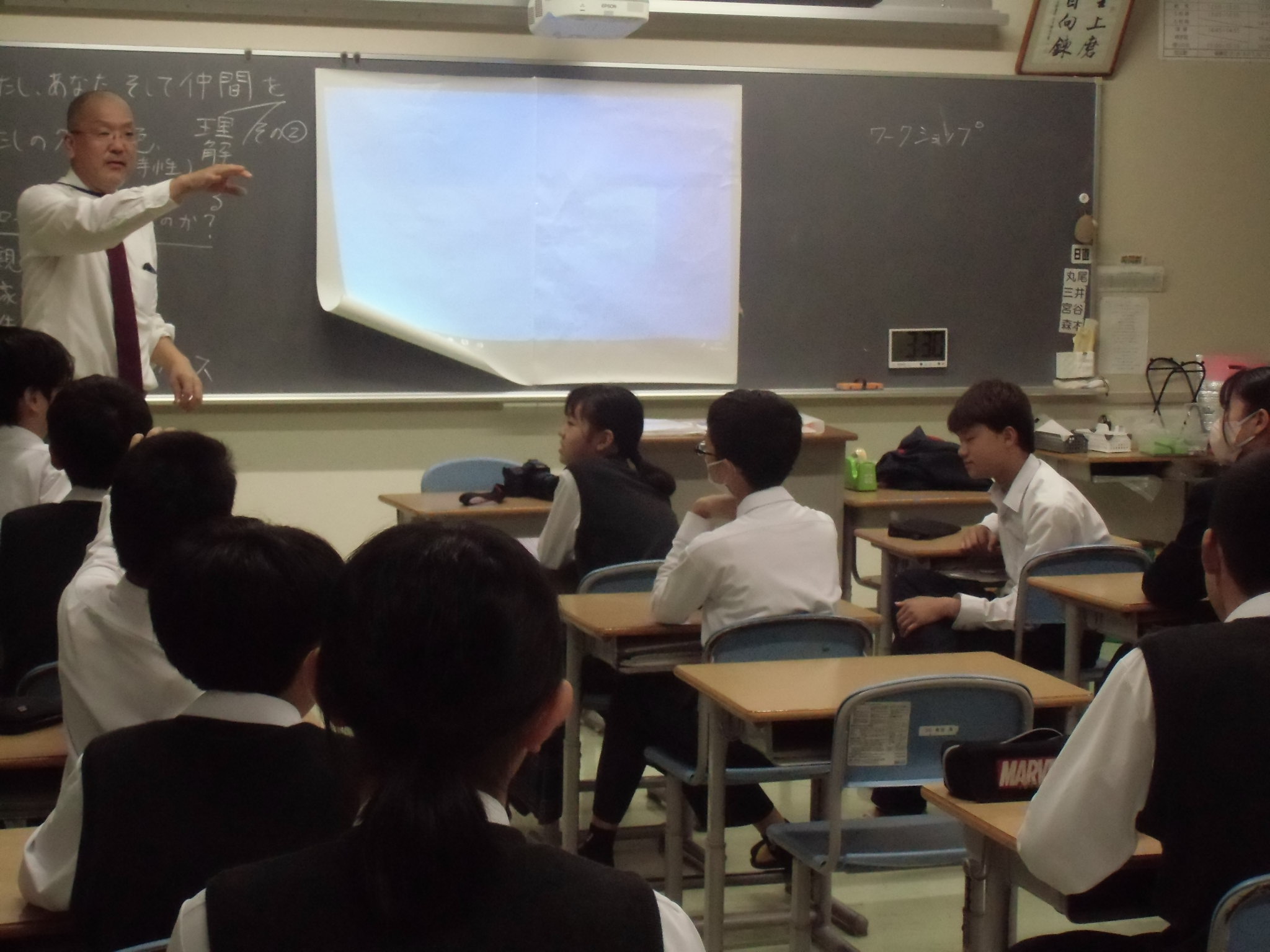

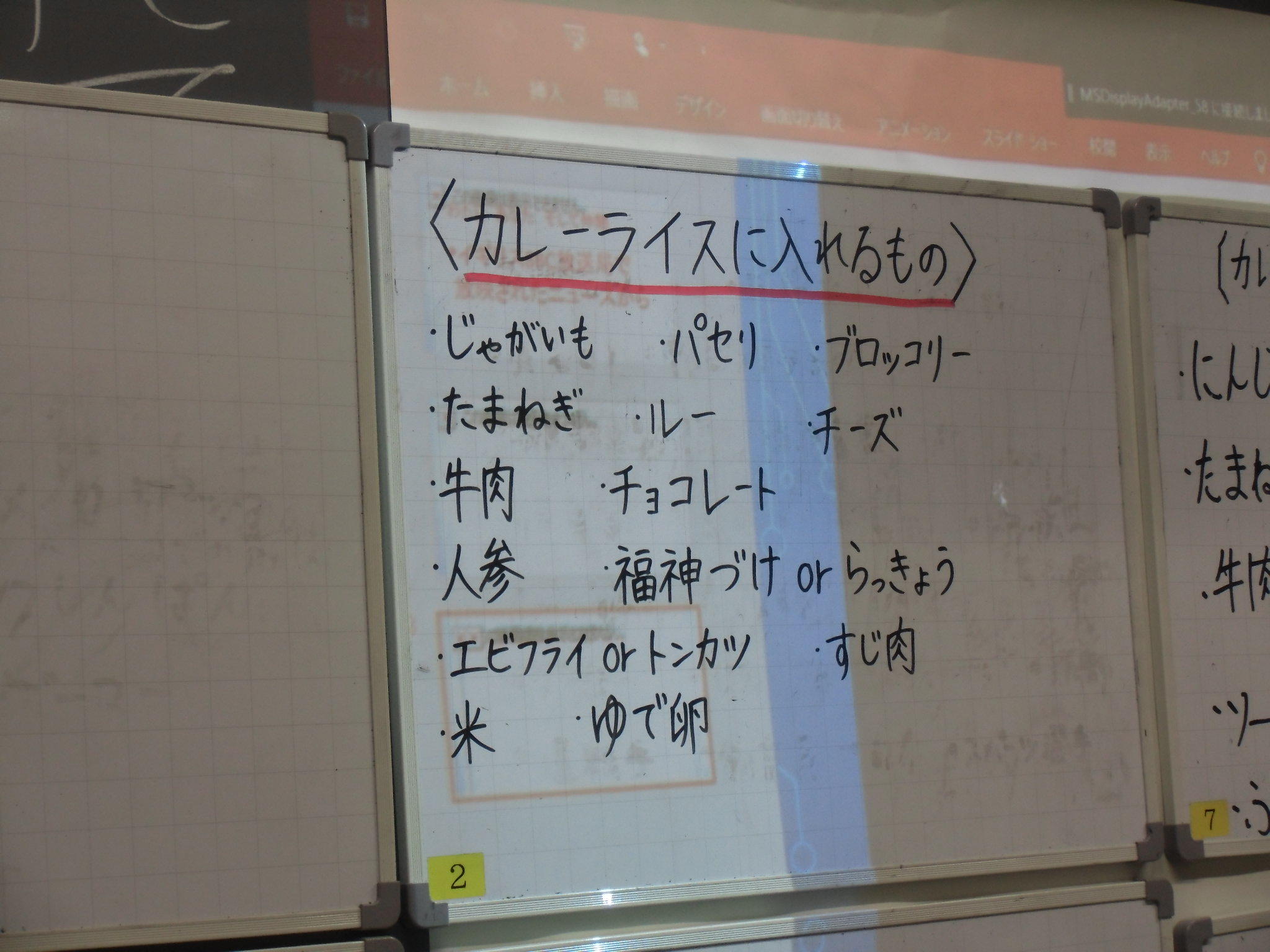
たくさん知って、もっとおいしいカレーにチャレンジできるね。
そして、「正しく知る」ちからを磨けたね。
◎私たちの生徒総会(10/27)
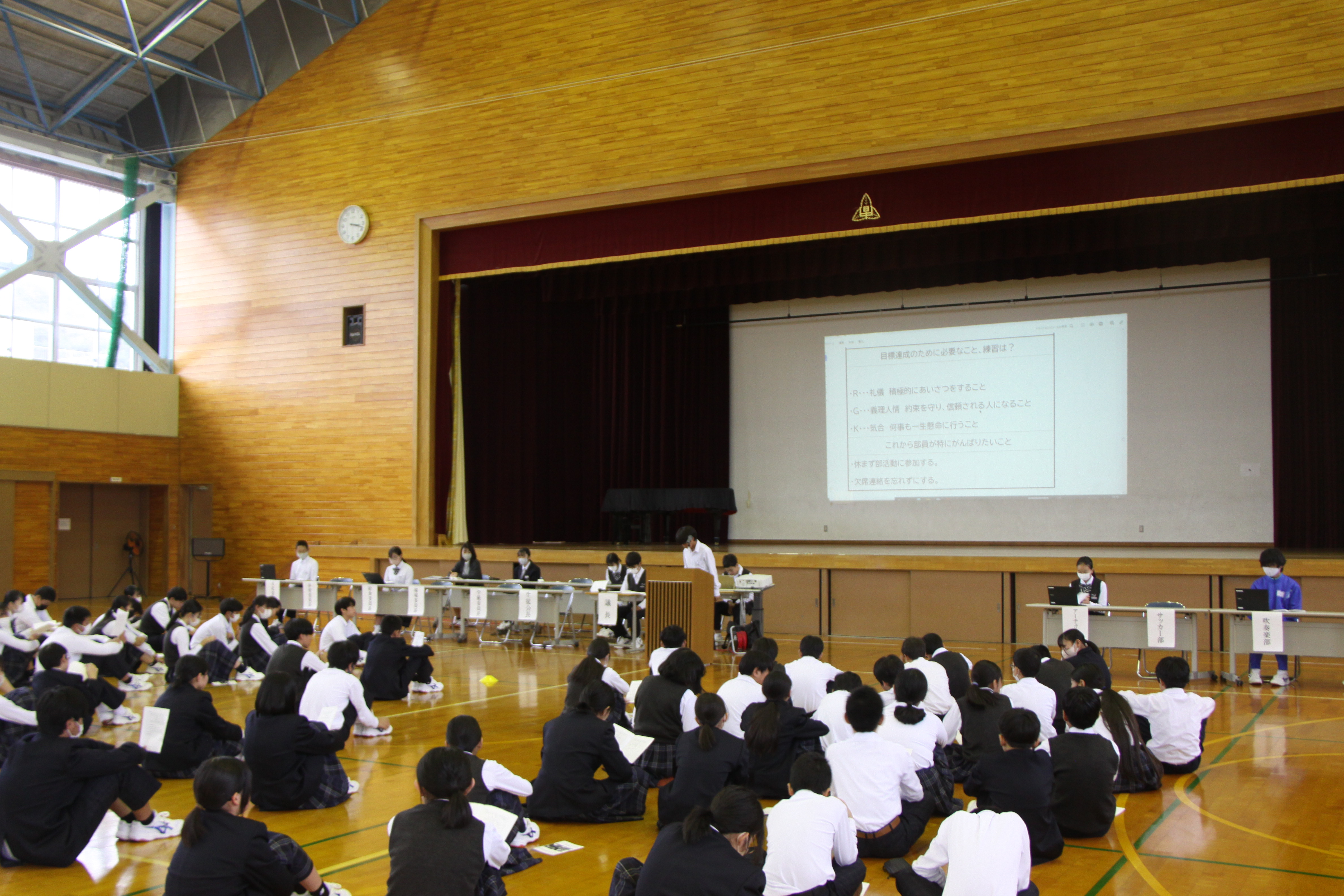


〈支配される/されない/させない 身につけるものには税関くらいのチェック 手塚美楽〉
◎日生で輝く 日生が輝く 地区会
I'll be back 11.12グラウンドで会おう ダダダダン


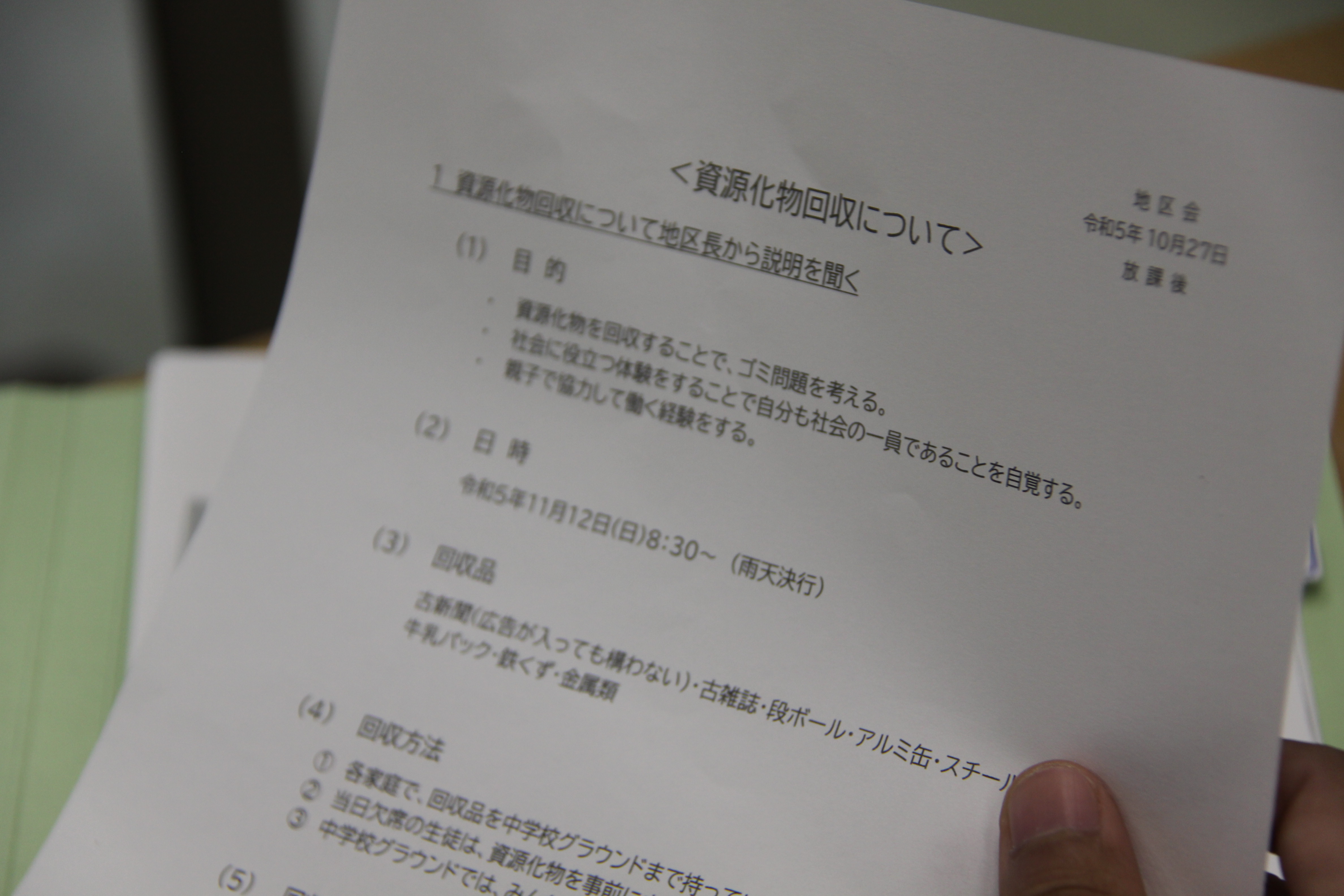
◎地区長会(10/27)
〈ワタシにまかせろ!11.12私たちの資源物回収〉
この取り組みは、私たちの学校生活を充実させるための活動費用になります。みんなで、11.12がんばりましょう。

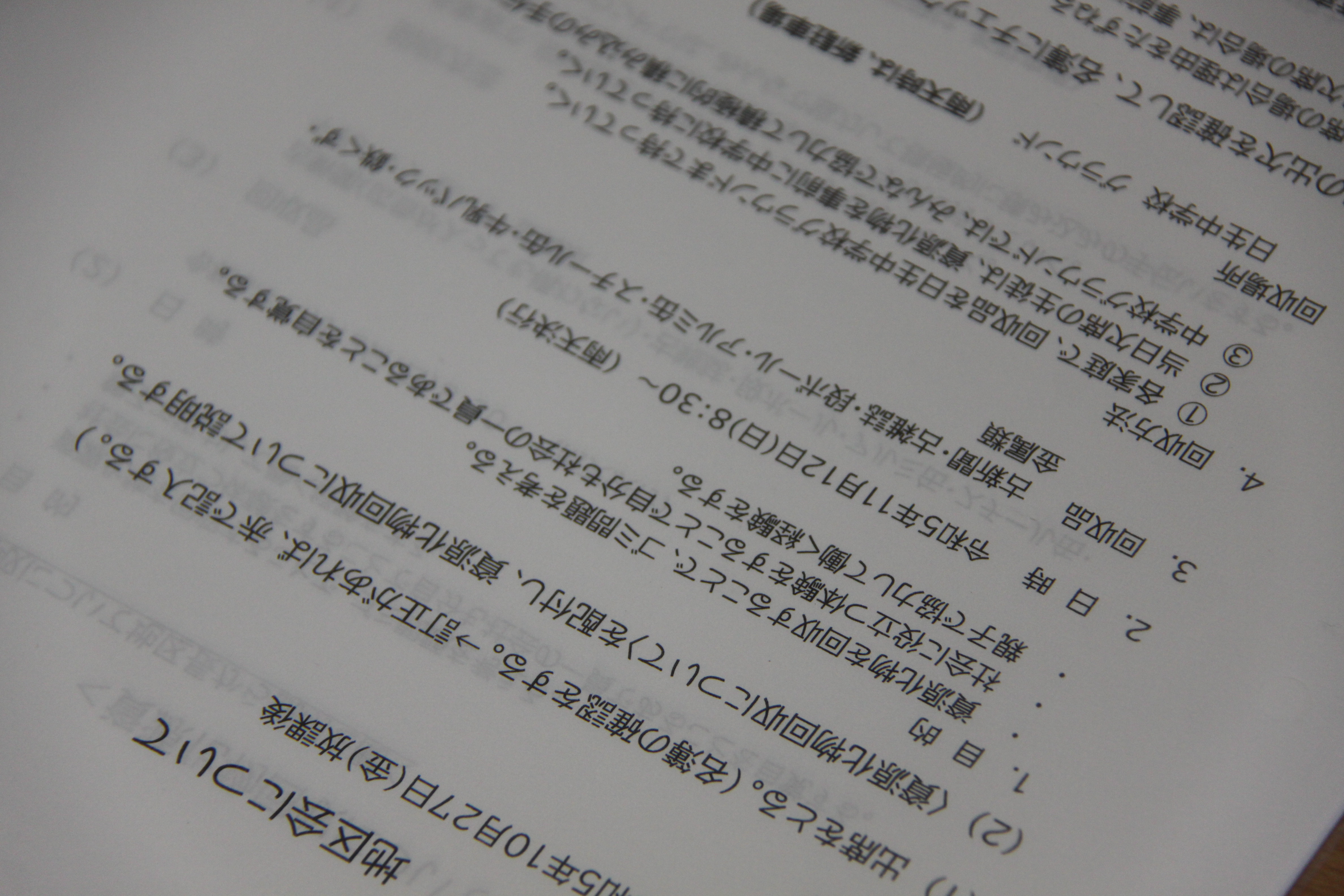

あらためて、資源物回収について考えるてみるよい機会となりましたね。リサイクルは資源を有効に使うために大きな役割を果たします。人間が何かを造るためには、必ず資源が必要です。このまま人間が自然から提供される資源を取り出し続けた場合、地球の資源は枯渇してしまう恐れがあります。しかし、私たち人間が排出するゴミも元はと言えば資源から作られています。だとしたら、ゴミから資源を取り出して、再び活用することができれば、資源の無駄遣いをできる限り抑えられるでしょう。資源を無駄にしないためにも、ゴミを有効活用することが、リサイクルをする理由の一つです。そして、自然環境への影響についても、サイクルをしなければ、ゴミが増え続け、環境に悪影響を与えてしまいます。ゴミを処分するために燃やすとしても、二酸化炭素や有害物質を排出し、それが大気汚染の原因となります。他にも水質汚染や土壌汚染など、ゴミによる環境への悪影響は数多く存在します。また、最終的にゴミを捨てる場所である最終処分場にも限りがあります。リサイクルをせずにゴミを捨て続けてしまうと、これも限界を迎え、ゴミで溢れかえることになってしまうでしょう。環境が悪くなることは、やがて人間の食べるものにも影響を与え、人間の健康に対しても害を与えてしまいます。そうならないためにも、極力ゴミを出さないようにリサイクルをする必要性があります。エネルギー使用量を抑える面からでも考える必要があります。人間が何か物を作る際には、エネルギーを消費します。石油や石炭、天然ガスのような自然界から得られたものを一次エネルギーと言い、それを使いやすいように加工したものを電気や都市ガス、ガソリンなどの二次エネルギーと言います。
何かを作るために必要なエネルギーは、資源を集めるところから始めるのと、ゴミをリサイクルして作るのとでは、消費量に圧倒的な差があるのです。リサイクルを行うことで、省エネルギーにも貢献できると言えるでしょう。そして温暖化の影響です。ゴミを燃やすことで、温暖化が加速すると言われています。なぜなら、ゴミを燃やすときに二酸化炭素などが排出されるからです。他にも、石炭や石油などを燃やして電気や熱エネルギーを得るために、二酸化炭素が排出されます。リサイクルをすることで、ゴミを燃やす機会が減り、エネルギーの使用も抑えるため、二酸化炭素の発生を防ぐことができます。リサイクルは温暖化を防ぐために大きな役割を持っていると言えるでしょう。日本におけるリサイクルも大切です。日本は国土が狭く、資源も限られています。だからこそ、積極的にリサイクルを行うことで、資源を有効に使う必要があります。また狭い国でありながら、日本は二酸化炭素の排出量は上位にランキングしています。国土が狭い故に焼却炉が多いことも原因ではありますが、日本はできる限り二酸化炭素の排出量を抑える必要があるでしょう。そのため、一人一人がリサイクルを意識した生活がこれからは求められるかもしれません。これからも継続的にリサイクルについて考える時間をもちたいですね。
◎多くの人に支えられて(10/26)
岡山県警察の学校警察連絡室さんが、スクールサポーターの根木さんと一緒に来校されました。熱心に取り組む授業の様子をみていただき、岡山の健全育成に関する情報交換をおこないました。学校警察連絡室は、岡山県の青少年の健全育成のため、平成26年度から県警少年課に置かれ、学校等と連携したサポート体制をつくっています。学校警察連絡室の任務は、学校周辺のパトロールによる厳正な補導措置と安心して学べる環境の確保、ルール・マナーの啓発活動、ボランティアとのあいさつ運動等規範意識向上のための各種活動を拡大・推進、暴力行為等に関する対応、学校からの相談受理等です。




〈きみのため 用意されたる滑走路 きみは翼を 手にすればいい 萩原慎一郎〉
◎なかまと一生懸命に勉強する、
1A公開授業・校内授業研究会(10/25)
〈どんな夢もかなえる 不思議なポッケでも 夕方の僕は 救えなかったよ 桝野 浩一〉
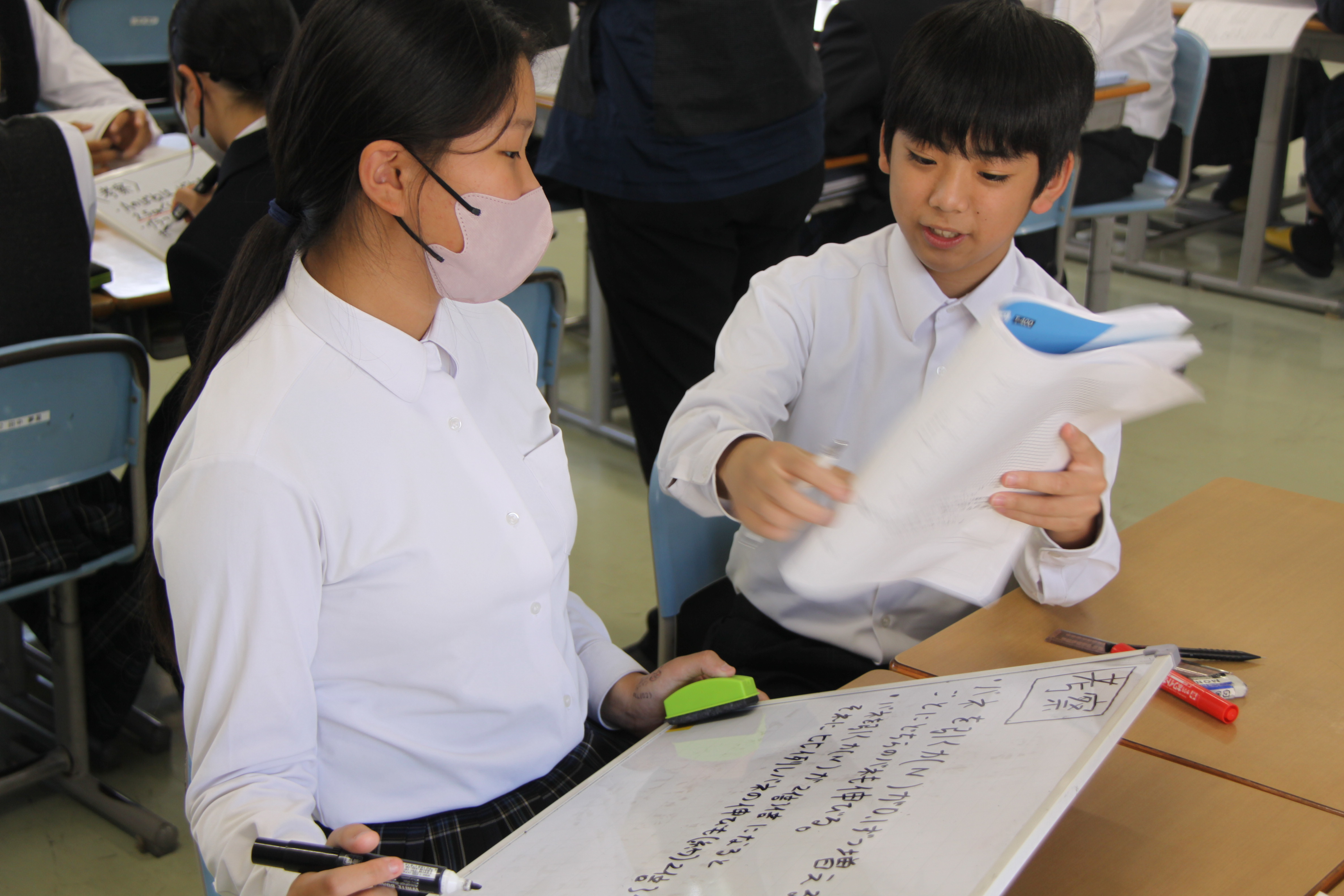

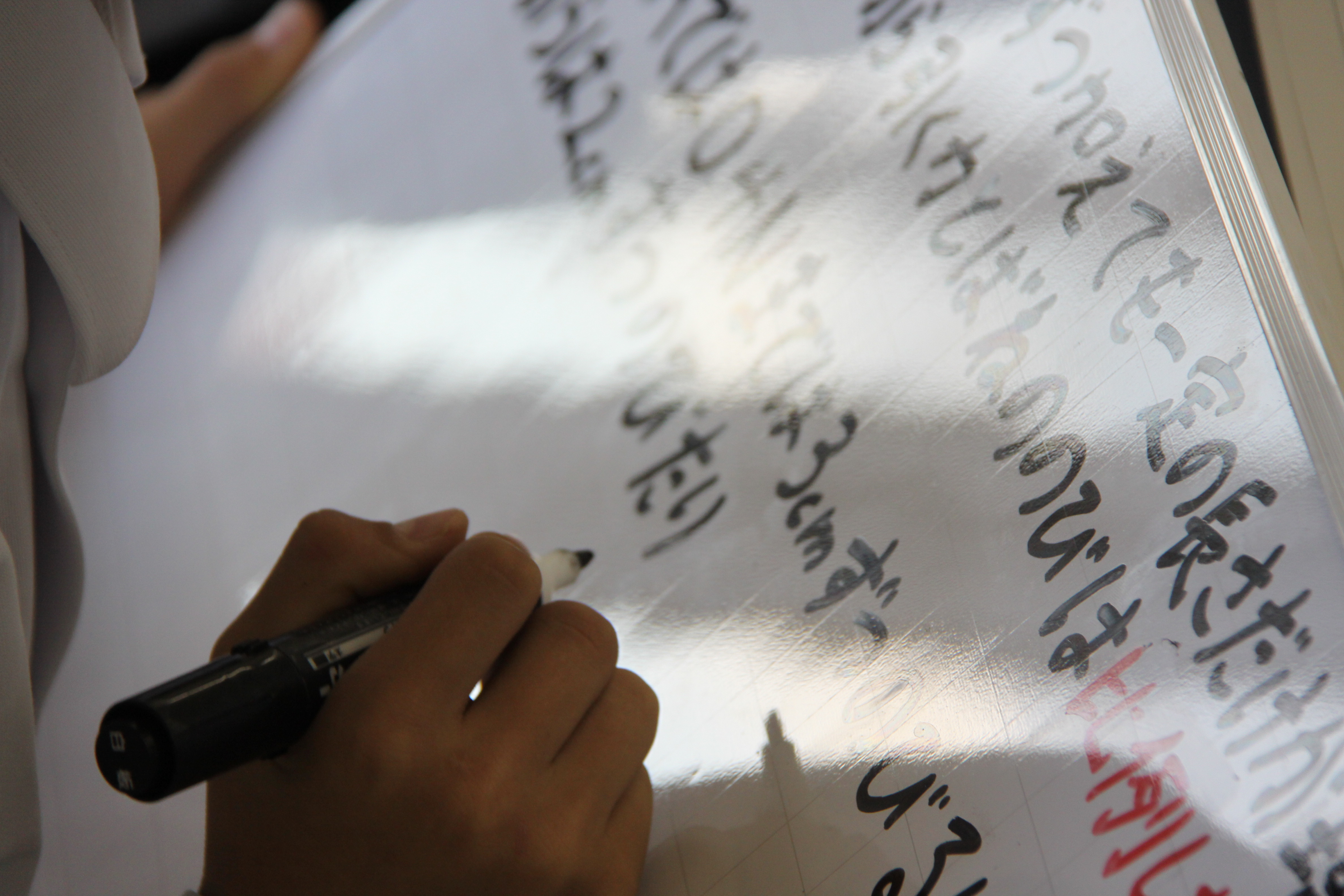


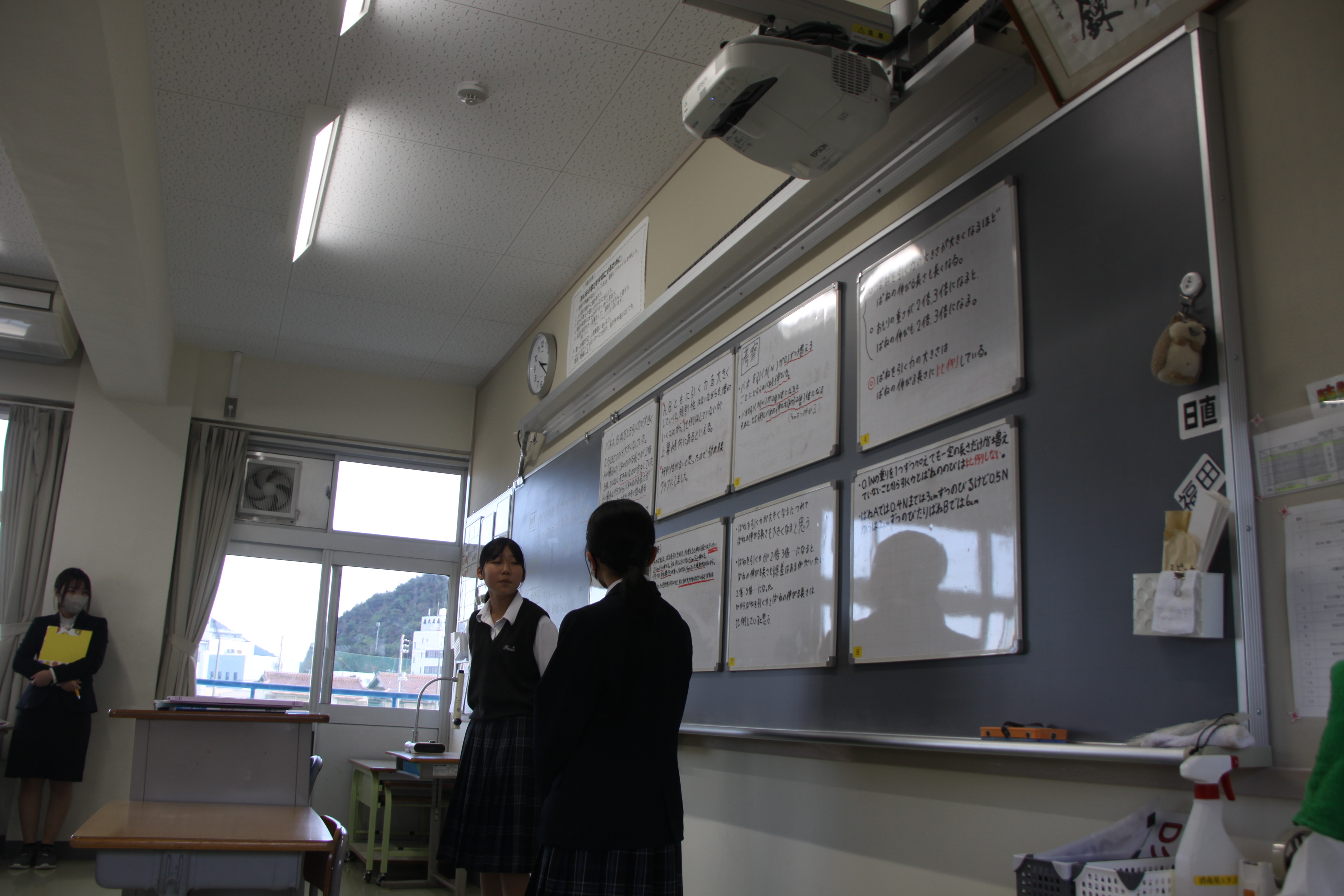



◎放課後2023年10月24日

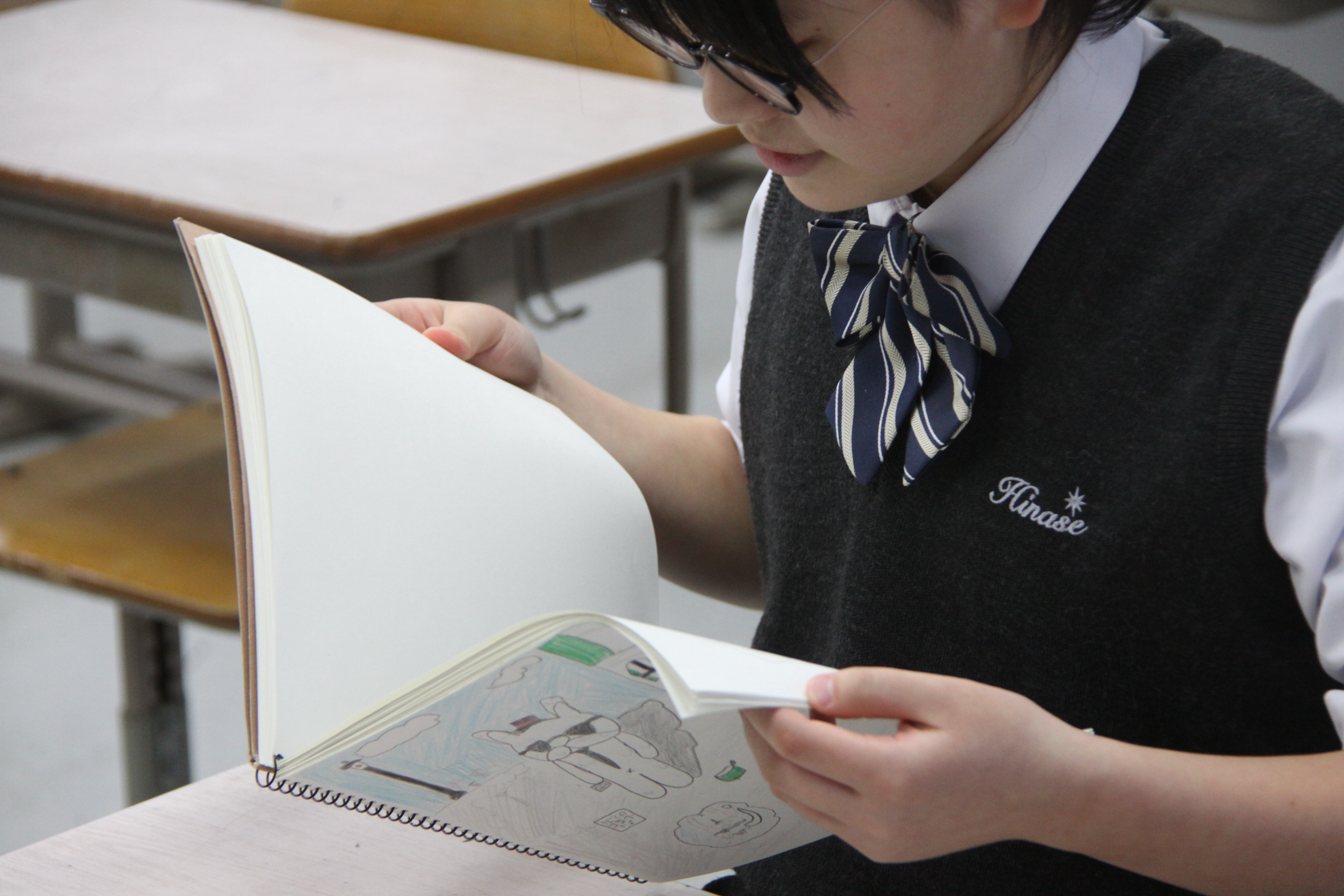







いのち短し 恋せよ少女(おとめ) 朱(あか)き唇 褪(あ)せぬ間に 熱き血潮の 冷えぬ間に 明日の月日は ないものを
◎「はたらくこと」を深く学ぶ(10/24)
職場体験学習の事前学習の教科横断的学習として、2年生では、キャリア教育(職場体験の趣旨に沿って、勤労観・職業観の育成並びに進路学習の一環として)として、人権課題のひとつである「ホームレス」問題を学習しています。
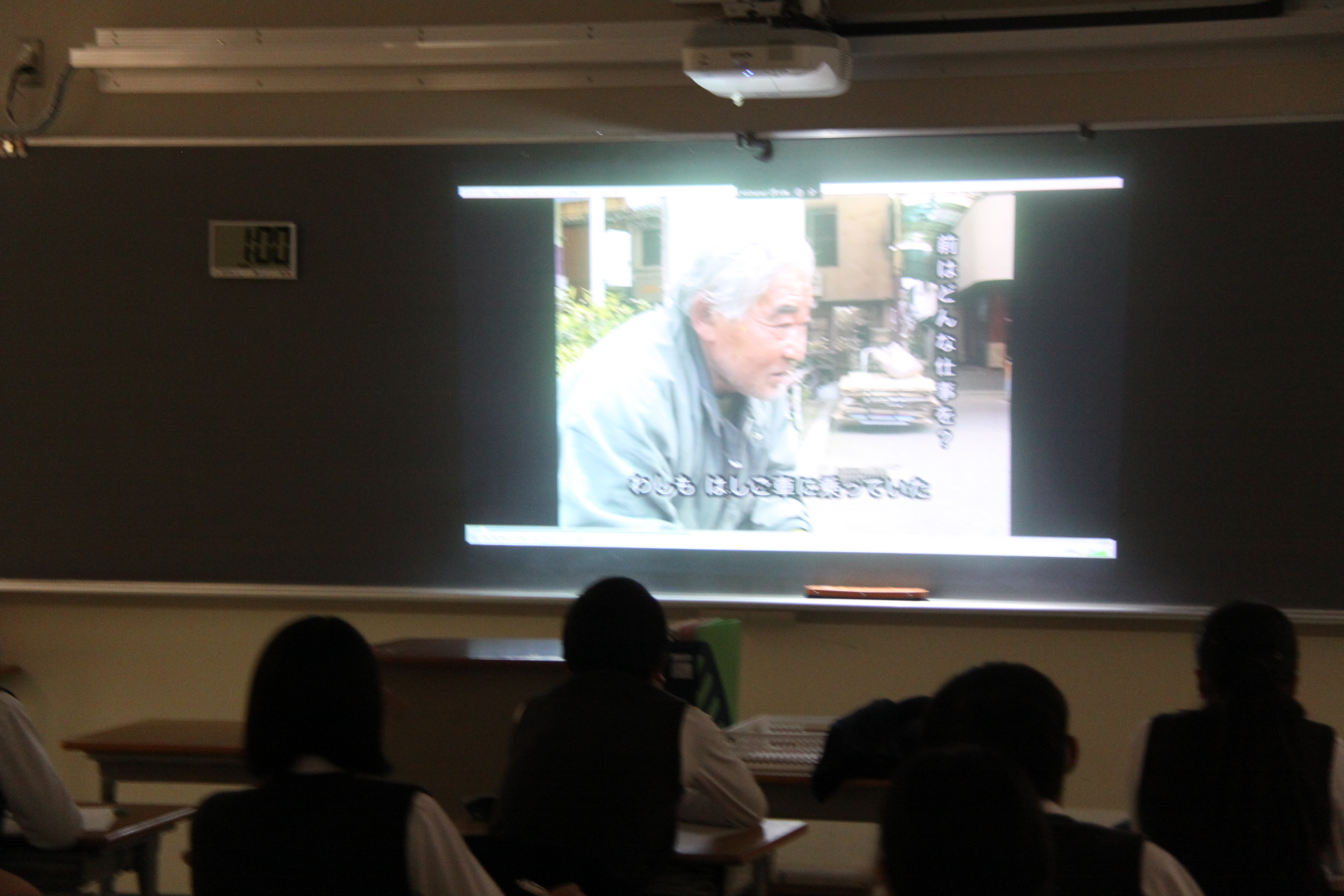
「ホームレス」=生きる寄りどころの喪失ととらえ、ホームレス問題を理解することだけが目的ではなく、「人権(社会)問題」に向き合う姿勢を培うことができる学習に取り組みます。さらに進路=生き方として捉えたときに、本取組は、日生中学校生徒の望ましい職業観や勤労観の育成、さらに社会問題へ関心を高めるために有意義であると考えられます。
取り組むにあたって、『「ホームレス」と出会う子どもたち』『身近なことから世界と私を考える授業(明石書店)』等を利用し、岡山のホームレス支援を進めている「NPOきずな」さんとの連携・支援をいただきながら進めていきます。数時間の学習で「ホームレス」問題の全てを理解することは難しいことも認識した上で、「社会や人に」関心を持ち続けていく「出会い」を紡いでいきます。学習の中で大切にしたいことをいくつかあげます〇路上生活者の生活と路上生活に至る原因について知り、無知からくる偏見と差別を減らす。〇「人」を人として、人の命を大切に出来る「生き方」(実践力)につながる一助とする。〇生徒一人ひとりが自分との関係を考える契機になる人権課題であると考える。今なお現代社会に強固な偏見・差別が存在し、若者による「ホームレス」襲撃事件が起きている状況を変えるための具体的な学習のひとつとする。④差別、偏見は「つくられる」が、また「なくすことができる」〇「ホームレス」とはいっときの生活の状態である。人をさす言葉ではない。〇路上生活という事実と「ハウスレス」「ホームレス」の人々を結びつけて判断する際に、社会における偏見があわさってしまうと、本人が望んだ、あるいは本人の責任だけで路上生活になったという自己責任論に基づく判断をしてしまうかもしれない。判断の際、照らしあわせるべき事実は、今まさに家に住んでいるという私たち自身の生活経験でだけであり、ホームレスの人々は「路上生活を望んでいない」という事実をとらえる中で、適切な判断力、正しい社会認識を育んでいきたい。
ヽ(^。^)ノお世話になる事業所(10/25現在:順不同・敬称略)
日生東小学校 日生認定こども園 奥本生花店 山陽マルナカ穂浪店 ステラカフェ カフェ天goo きたろうお好み焼き 片上認定こども園 セブンイレブン岡山備前インター店 旬鮮食彩館パオーネ日生店 タイム備前店 ツヤ髪専門美容室ボヌール 夕立 日生運動公園 ひなビジョン THE COVECAFÉ 備前市立図書館日生分館 日生西小学校 伊部認定こども園 ワわくわくるーむ 海ラボ 山陽マルナカ備前店 カメイベーカリー 備前市立図書館 山下商事
どうぞ(#^.^#)よろしくお願いします。
◎ひな中の風~授業が大切(10/24)
探求・協力・真正の学び。一年生理科実験中
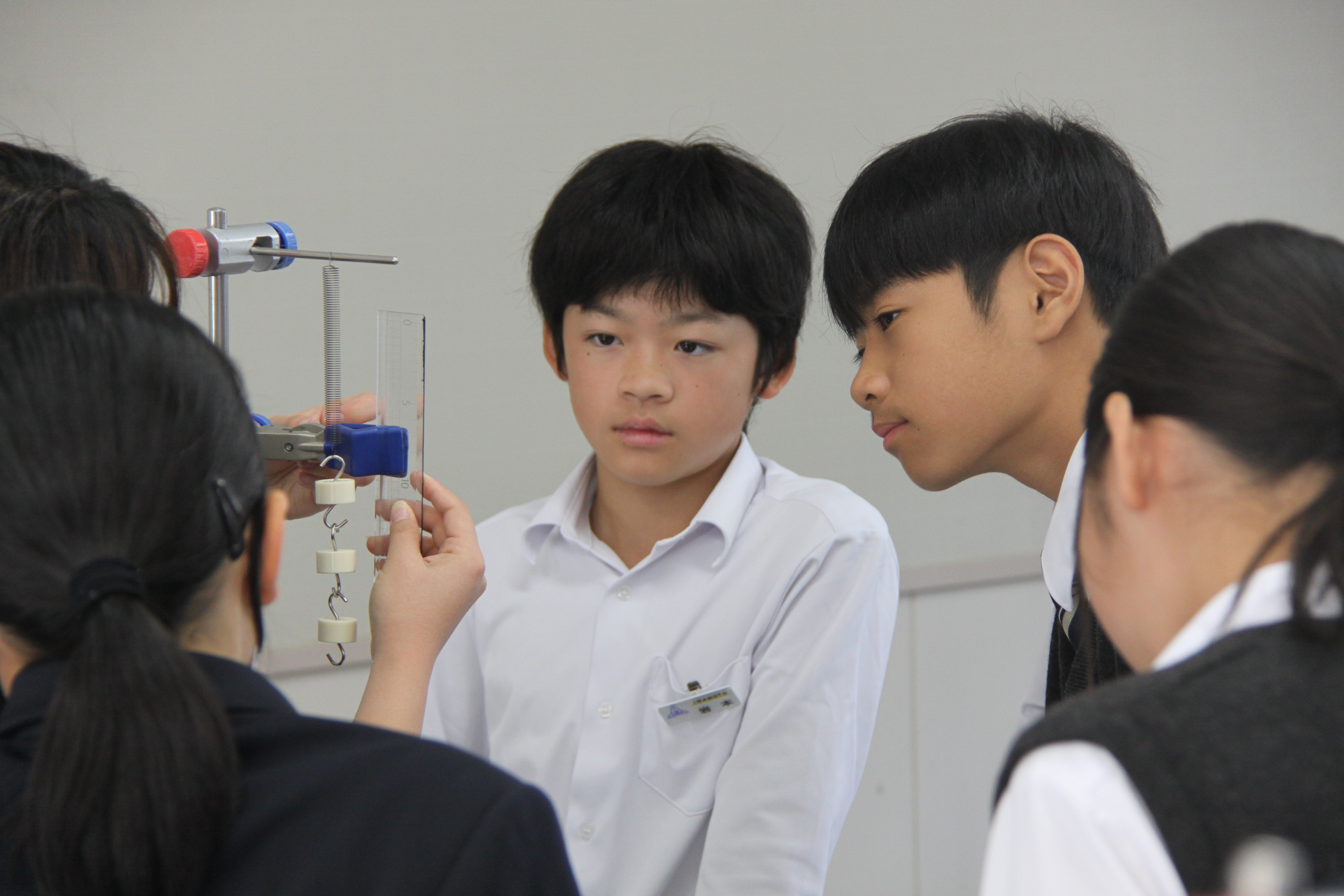
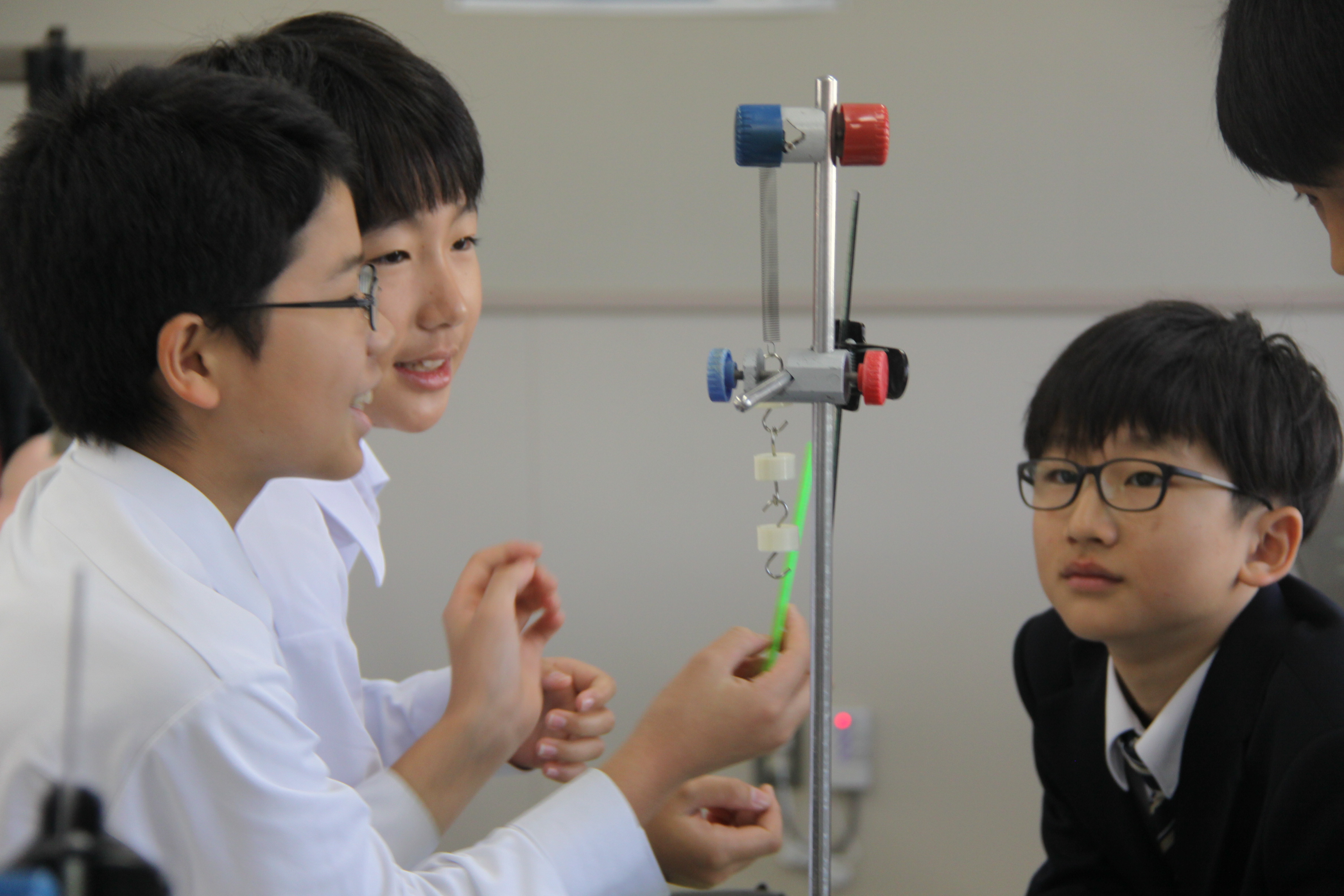
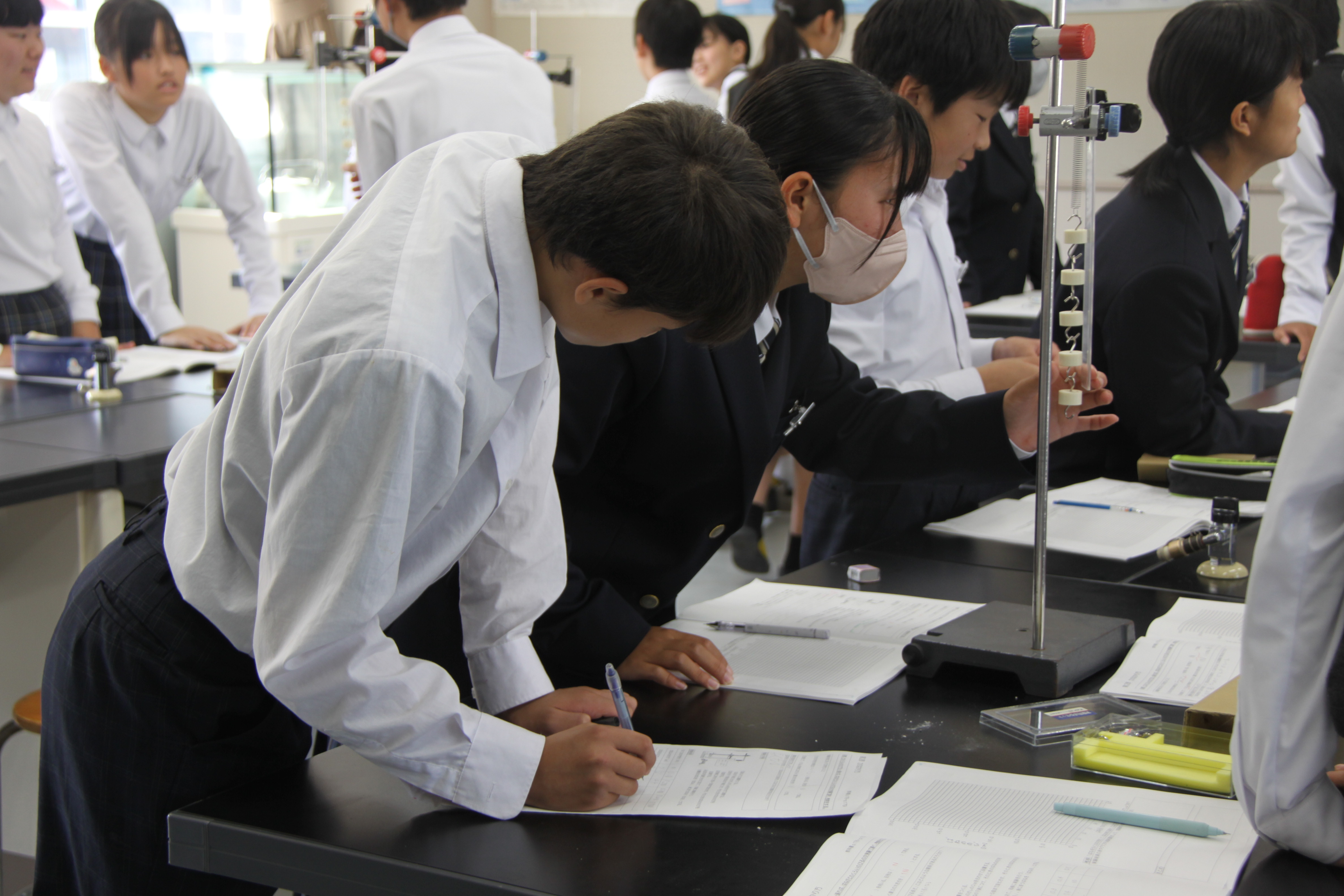




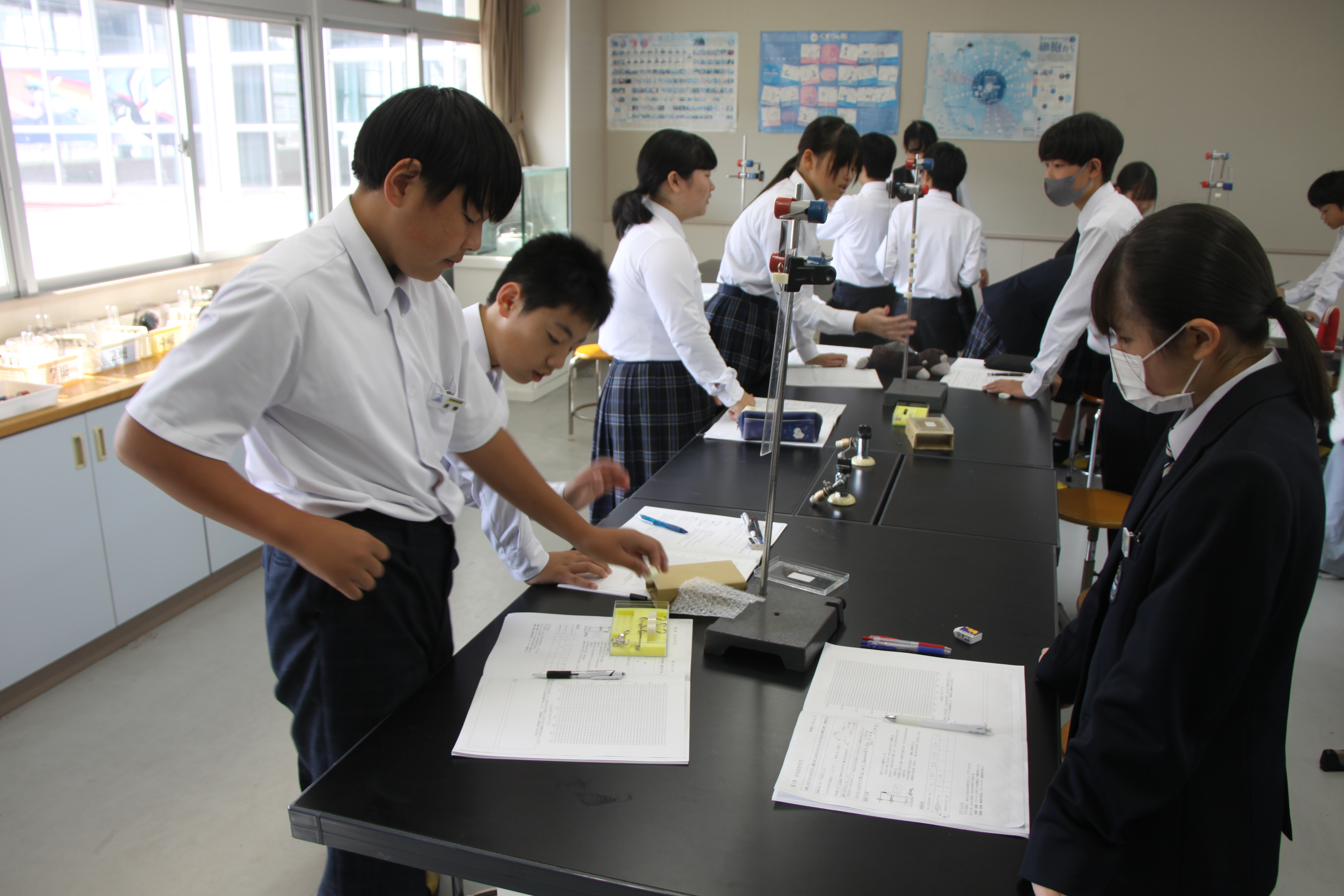
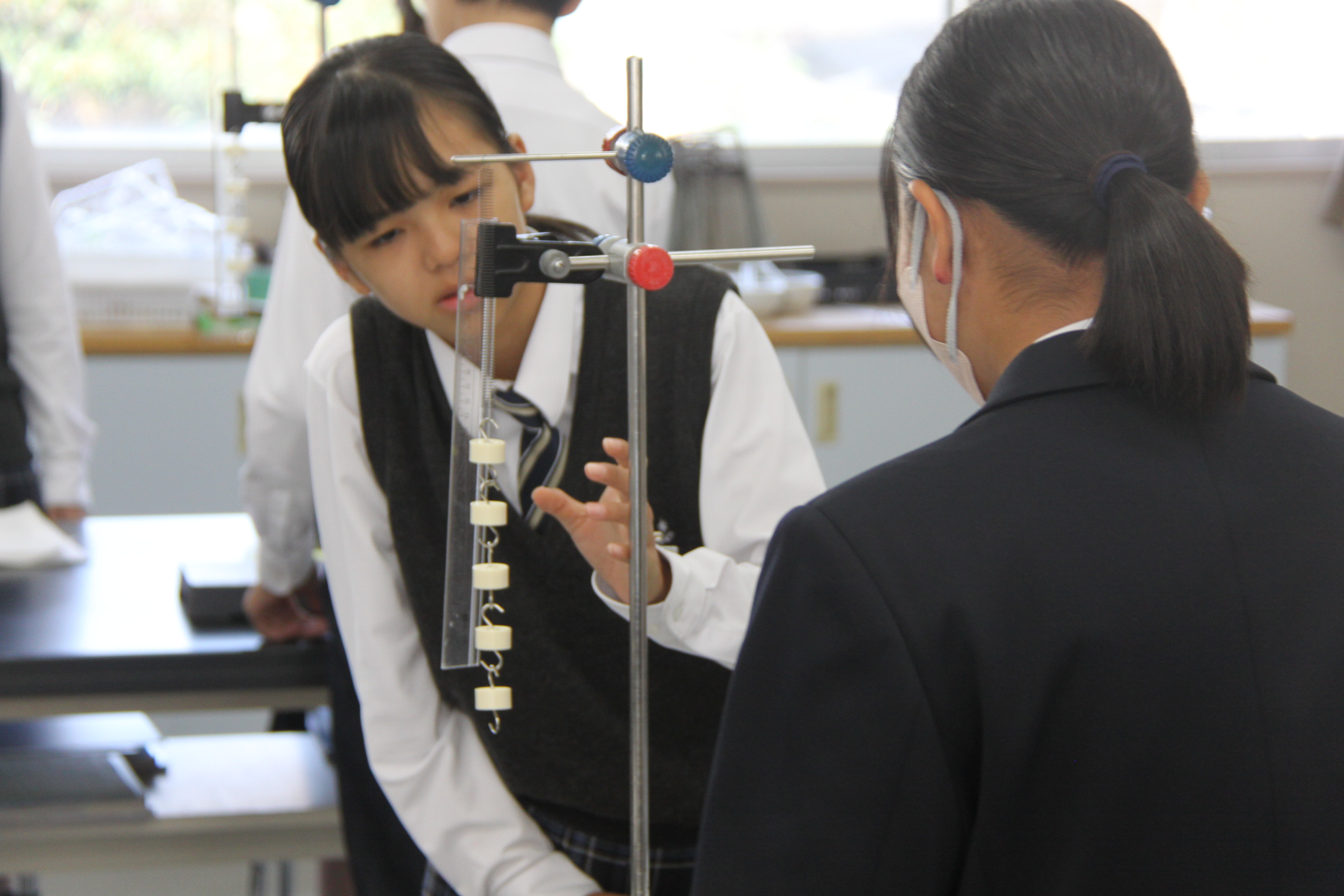
Healthy skepticism is the basis of all accurate observation. Conan Doyle
(健全な懐疑心は、すべての正確な観察の基礎となる。)
◎私たちのはじまりの風景3

消防操法大会は、各地域の消防団の皆さんが、迅速、確実かつ安全に行動するために定められた消防用機械器具の取扱い及び操作の基本について、その技術を競う大会です。
消防操法大会で競技される消防ポンプ操法は2種類。消防ポンプ自動車を使用した「ポンプ車操法」と、持ち運び可能な小型動力ポンプを使用した「小型ポンプ操法」があります。日生中グラウンドでも夕刻から地域の消防団さんが練習に取り組まれています。10月28日は日生操法大会が予定されています。
◎ひな中の風~~霜降の候
〈生まれたら、もう僕だった。水切りに向かない石の重さを思う 木下侑介〉

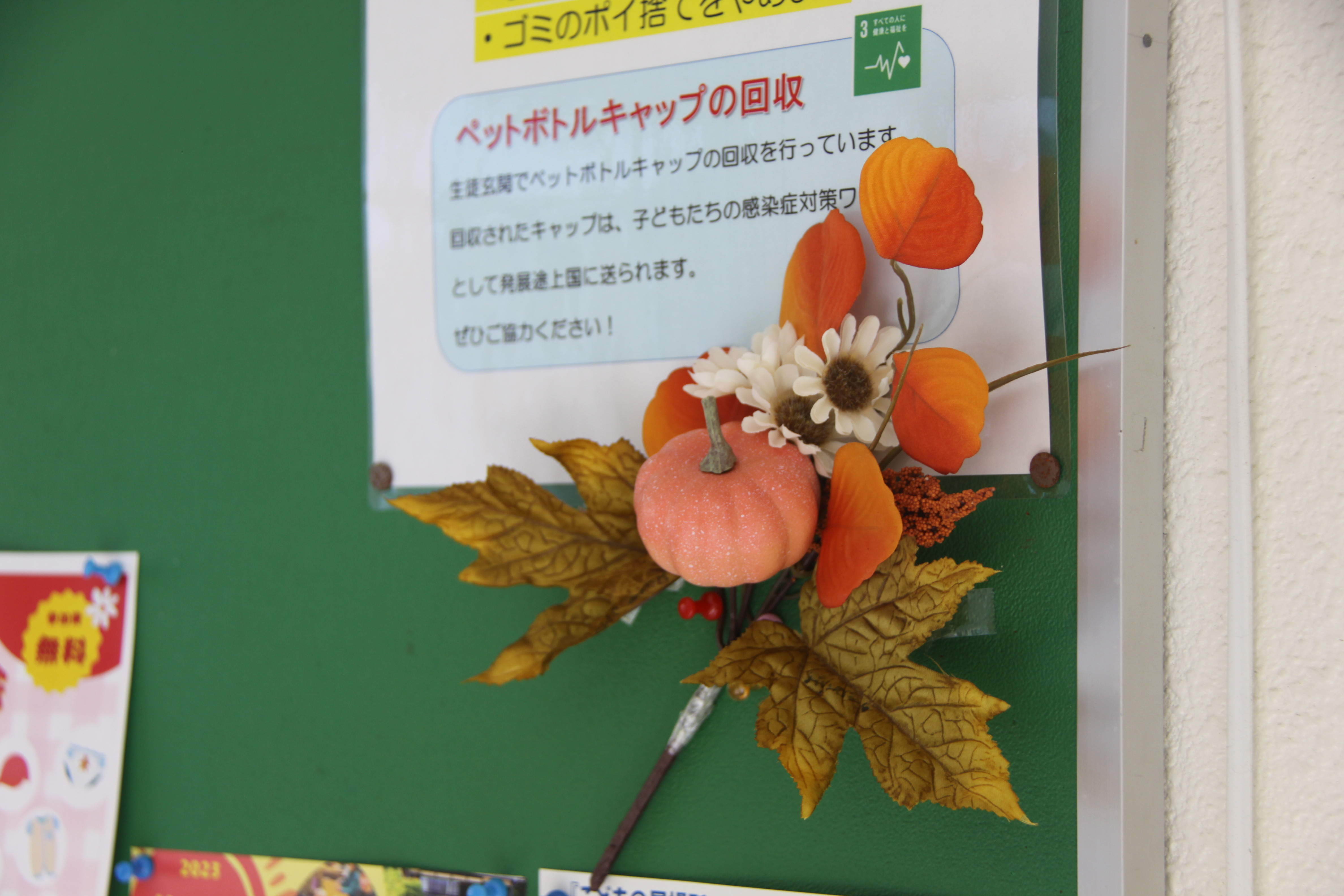

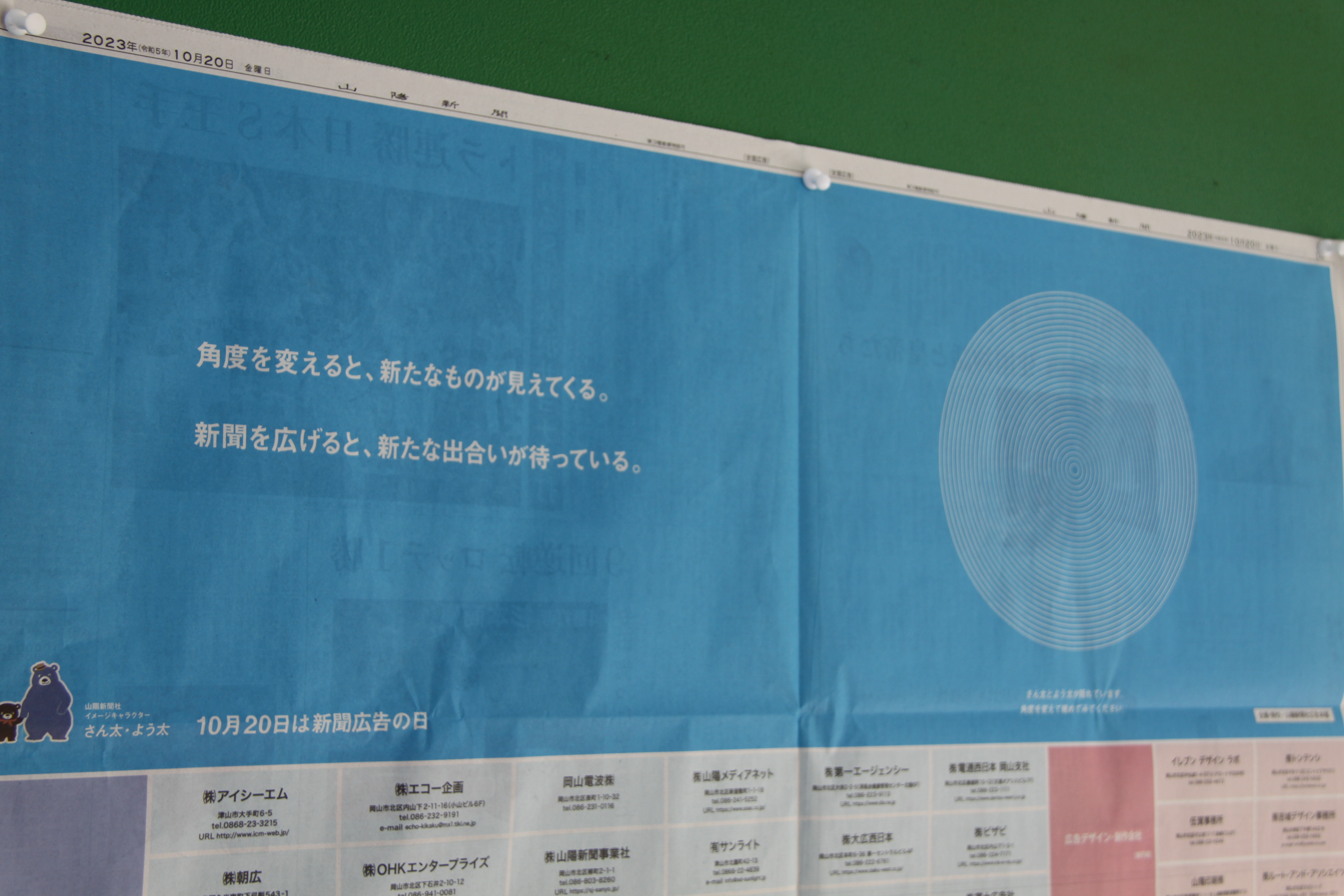





◎澄める心をさながらに 映して永遠(とわ)に育ちゆく♪(10/23)


◎さあ、職場体験学習の事前訪問に出発
私たちらしく ひな中らしく せいいっぱい(10/20~)


よろしくお願いします。 日生西小学校 日生東小学校 日生認定こども園 伊部認定こども園 片上認定こども園 奥本生花店 セブンイレブン岡山備前インター店 山陽マルナカ穂浪店 山陽マルナカ備前店 ホームセンター タイム備前店 ナフコ パオーネ THE COVE CAFÉ ステラカフェ きたろうお好み焼き 夕立 海ラボ 中元写真館 天gooカフェ パン工房むくむく 備前市立図書館 日生温水プール 備前消防署 日生図書館 日生町漁協 ひなビジョン(10/6現在・順不同・敬称略)
◎がんばりあえる仲間だよ
学習指導要領に評価の方法の工夫を求める記述があるように、目標に準じた評価方法を工夫するひとつの手立てとして、日生中では、定期考査を見直し、単元テストの取組を進めています。
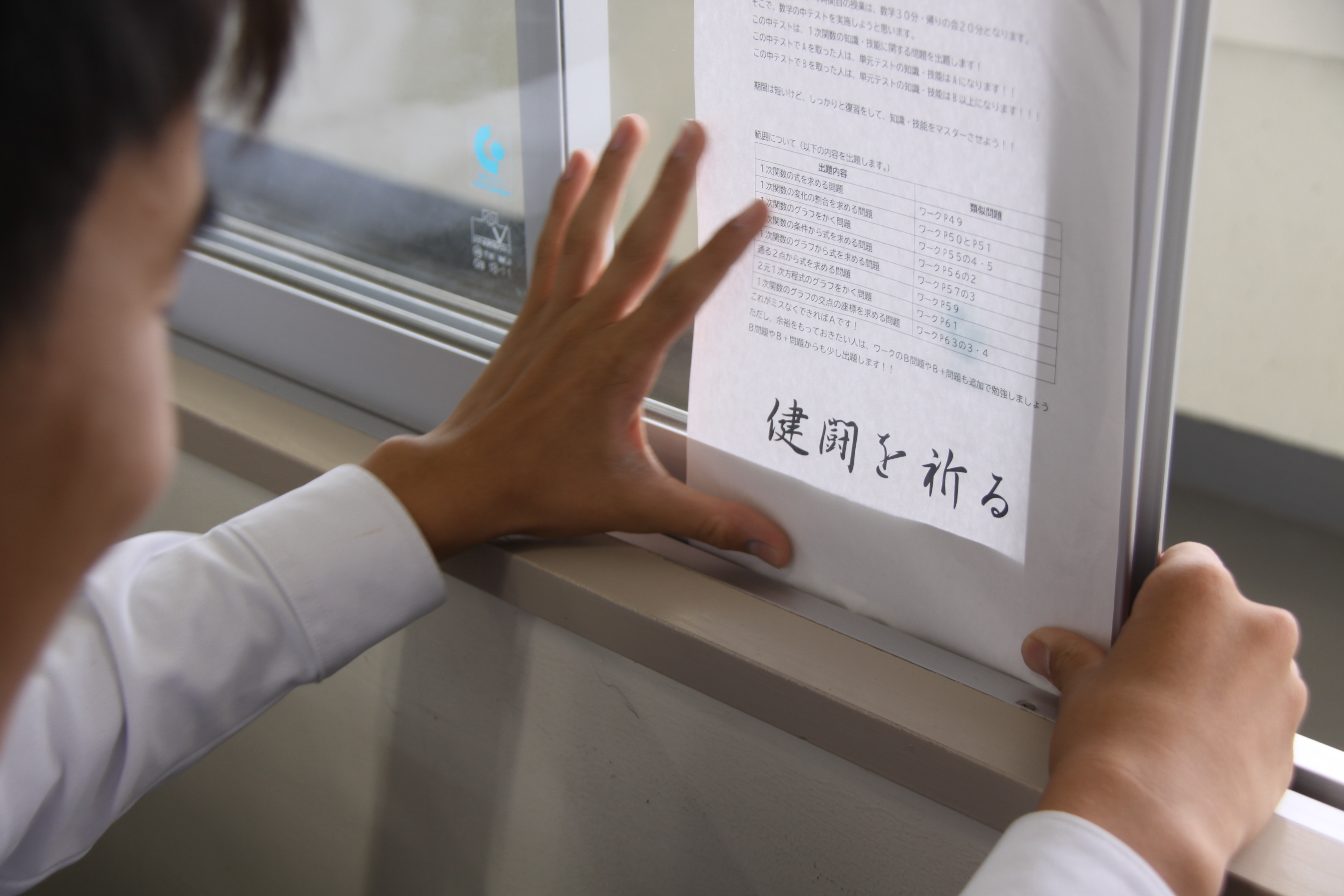


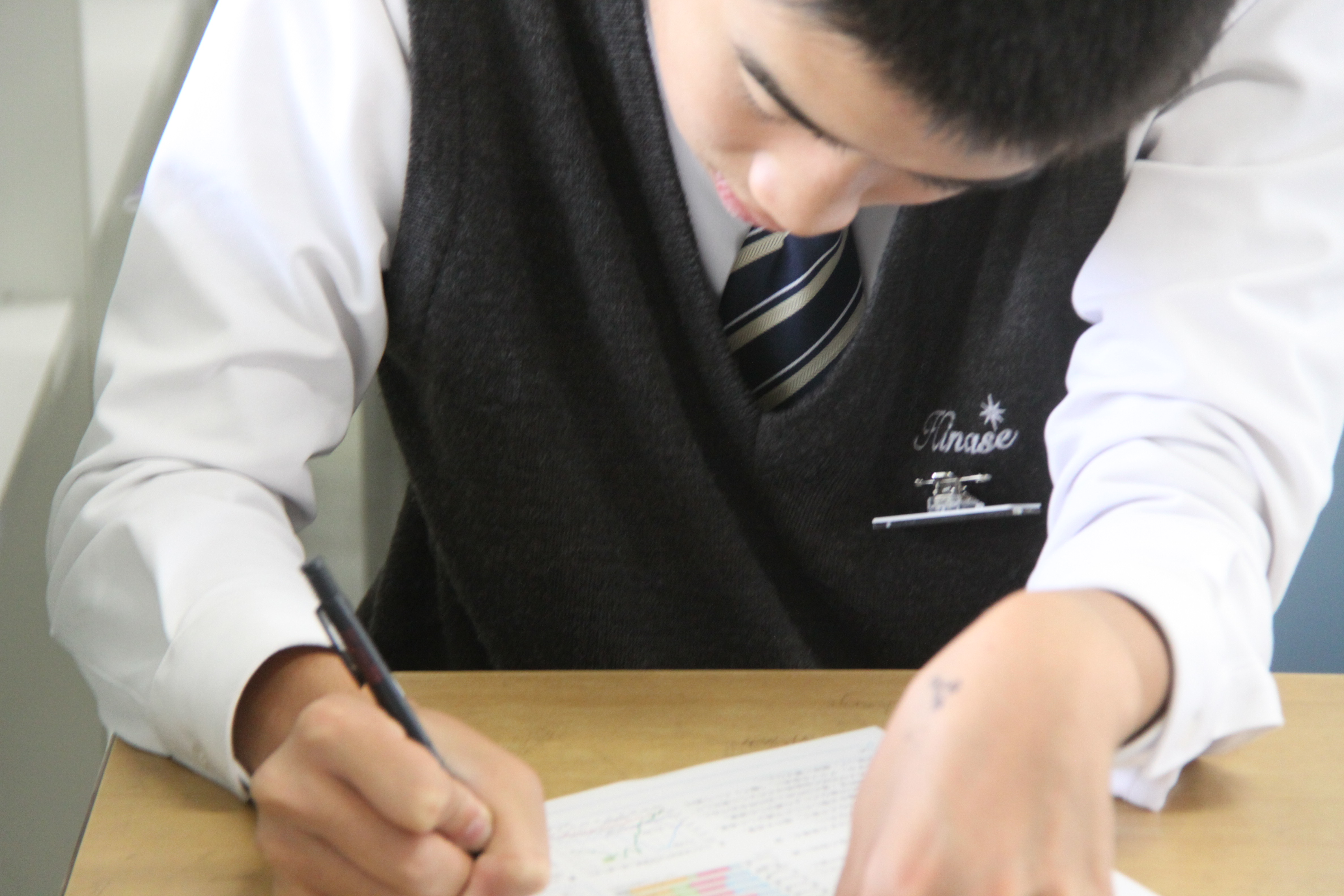


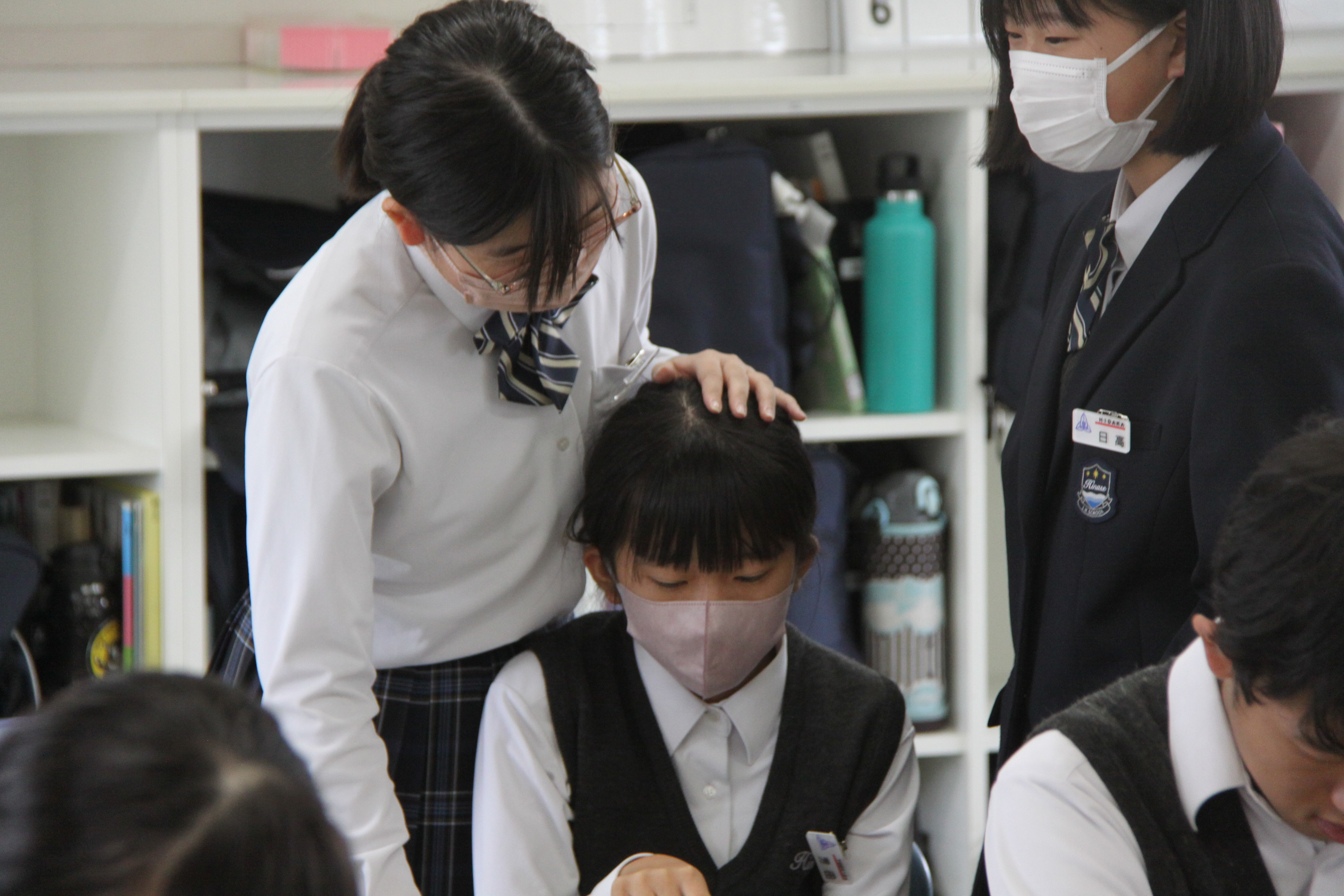


子曰、学而時習之、不亦説乎。有朋自遠方来、不亦楽乎。人不知而不溫、不亦君子乎。
(子曰わく、学びて時に之を習う、亦た説ばしからずや。朋遠方より来たる有り、亦た楽しからずや。人知らずして溫みず、亦た君子ならずや。)
孔先生がおっしゃった、学んだことをその時々で実践・経験を通して習熟していくこと、自分のものにしていくことは喜ばしいではないか。遠方から遙々訪れる朋と過ごし学びを深めるひとときは楽しいではないか。人に存在を認められなくても恨むことなく自分のやるべきことを粛々と行う人は、一廉(ひとかど)の人物なのではないか。|「論語」学而第一01
◎ようこそ ようこそ ひな中へ。
「えー未来を創ろうでっ」(赤ちゃん登校日:10/20)
人が、自分らしく、輝いて生きるには、人と関わり、人とつながることはとても大切です。家庭科では、まだ話すことがままならない赤ちゃんとその親に学校においでいただき、生徒と継続して関わり体験をもち、赤ちゃんの成長やいのちの尊さを実感しながら人間関係を構築するコミュニケーション(お互いの考えや気持ちを理解し合うこと)を学び人の愛情に気づくなど、子どもたちとともに赤ちゃん親子、参観する保護者、地域の方、教職員など、この授業に関わる人たちにたくさんの気づきや学びのある学習(赤ちゃん登校日)に取り組んでいます。
赤ちゃんや親との関わり体験にとどまらず、お互いが良い関係を構築するには、他者に自らが心開いて、『他者に「関心をもち」、「あいさつを交わし」、「みる」「知る」ことの大切さ、「きく」ことの大切さ、「伝える」「分かり合う」ことの大切さ』などのコミュニケーションの基礎を学ぶことがこの学習の大きな柱のひとつです。









〇貴重な学習に取り組んだ3年生に、吉野弘さんの詩を紹介します。
I was born 吉野弘
確か 英語を習い始めて間もない頃だ。
或(あ)る夏の宵(よい)。父と一緒に寺の境内を歩いてゆくと 青い夕靄(もや)の奥から浮き出るように 白い女がこちらへやってくる。物憂げに ゆっくりと。
女は身重らしかった。父に気兼ねをしながらも僕は女の腹から眼を離さなかった。頭を下にした胎児の 柔軟なうごめきを 腹のあたりに連想し それがやがて 世に生まれ出ることの不思議に打たれていた。
女はゆき過ぎた。
少年の思いは飛躍しやすい。 その時 僕は<生まれる>ということが まさしく<受身>である訳を ふと諒解(りょうかい)した。僕は興奮して父に話しかけた。
―やっぱり I was born なんだね―
父は怪訝(けげん)そうに僕の顔をのぞきこんだ。僕は繰り返した。
― I was born さ。受身形だよ。正しく言うと人間は生まれさせられるんだ。自分の意志ではないんだね―
その時 どんな驚きで 父は息子の言葉を聞いたか。僕の表情が単に無邪気として父の顔にうつり得たか。それを察するには 僕はまだ余りに幼なかった。僕にとってこの事は文法上の単純な発見に過ぎなかったのだから。
父は無言で暫(しばら)く歩いた後 思いがけない話をした。
―蜉蝣(かげろう)という虫はね。生まれてから二、三日で死ぬんだそうだが それなら一体 何の為(ため)に世の中へ出てくるのかと そんな事がひどく気になった頃があってね―
僕は父を見た。父は続けた。
―友人にその話をしたら 或(ある)日 これが蜉蝣(かげろう)の雌(めす)だといって拡大鏡で見せてくれた。説明によると 口は全く退化して食物を摂(と)るに適しない。胃の腑(ふ)を開いても 入っているのは空気ばかり。見ると その通りなんだ。ところが 卵だけは腹の中にぎっしり充満していて ほっそりした胸の方にまで及んでいる。それはまるで 目まぐるしく繰り返される生き死にの悲しみが 咽喉(のど)もとまで こみあげているように見えるのだ。淋(さみ)しい 光りの粒々(つぶつぶ)だったね。私が友人の方を振り向いて<卵>というと 彼も肯(うなず)いて答えた。<せつなげだね>。そんなことがあってから間もなくのことだったんだよ。お母さんがお前を生み落としてすぐに死なれたのは―。
父の話のそれからあとは もう覚えていない。ただひとつ痛みのように切なく 僕の脳裡(のうり)に灼(や)きついたものがあった。
―ほっそりした母の 胸の方まで 息苦しく ふさいでいた 白い僕の肉体― 詩集『消息』より
◎これからもひな中がんばろう!
みなさんよろしくお願いします。(≧▽≦)
〈11.12資源化物回収ご協力のお願い〉
平素は本校PTA活動に多大なるご協力をいただき、深く感謝いたします。
さて、PTA活動の一環として資源化物回収を以下のとおり実施します。収益金は毎年の日生中学校PTA活動に欠くことのできないものになっています。つきましては、以下のことをよくご理解のうえ、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。PTA会長 宮本研丞、保健部長 藤本麻美
1 期 日
・令和5年11月12日(日)8:30~雨天決行
2 回収品
・古新聞(広告が入っても構わない)・古雑誌・段ボール・アルミ缶・スチール缶・牛乳パック・鉄くず・金属類
3 回収手順
・各家庭で当日の8:30~9:00に回収品を直接回収場所(日生中グラウンド)まで持ってきてください。
※各地区のゴミステーションは使用しません。近所で声をかけあって、車で持って行けない家庭の回収品を一緒に持ってくるなど、ご協力をお願いします。
※今年度も、ひなビジョンでのお知らせはありません。
4 回収場所
・日生中学校 グラウンド(雨天時は、新駐車場)
5 備 考
・新聞紙は新聞紙のみ(広告が入ってもOK)、古雑誌は古雑誌のみというように、回収品は必ず分別し、ひもできつく縛って出してください。
・アルミ缶・スチール缶・牛乳パックはよく水洗いをして、それぞれ分別してください。
・鉄くず・金属類の例:自転車、フライパン等。(基本的に金属であれば可)
・リサイクル料金のかかる電化製品は不可。電気ストーブ、アイロン、パソコン、ファックス(業務用は不可)等は可。
・回収場所は一方通行とします。中学校南門から入っていただき東門から出るようお願いします。スムーズに積みおろしができますよう、ご協力をよろしくお願い致します。


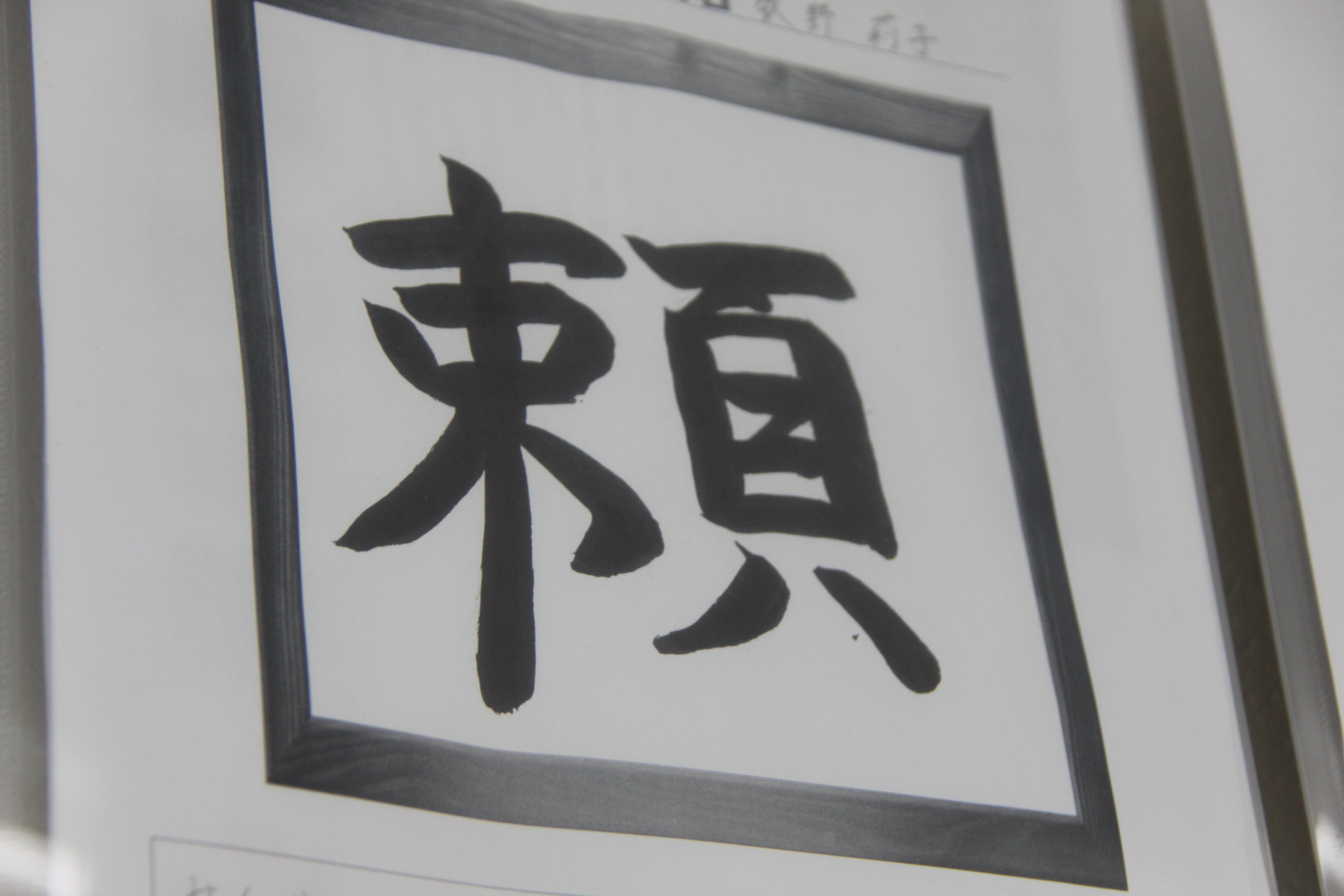

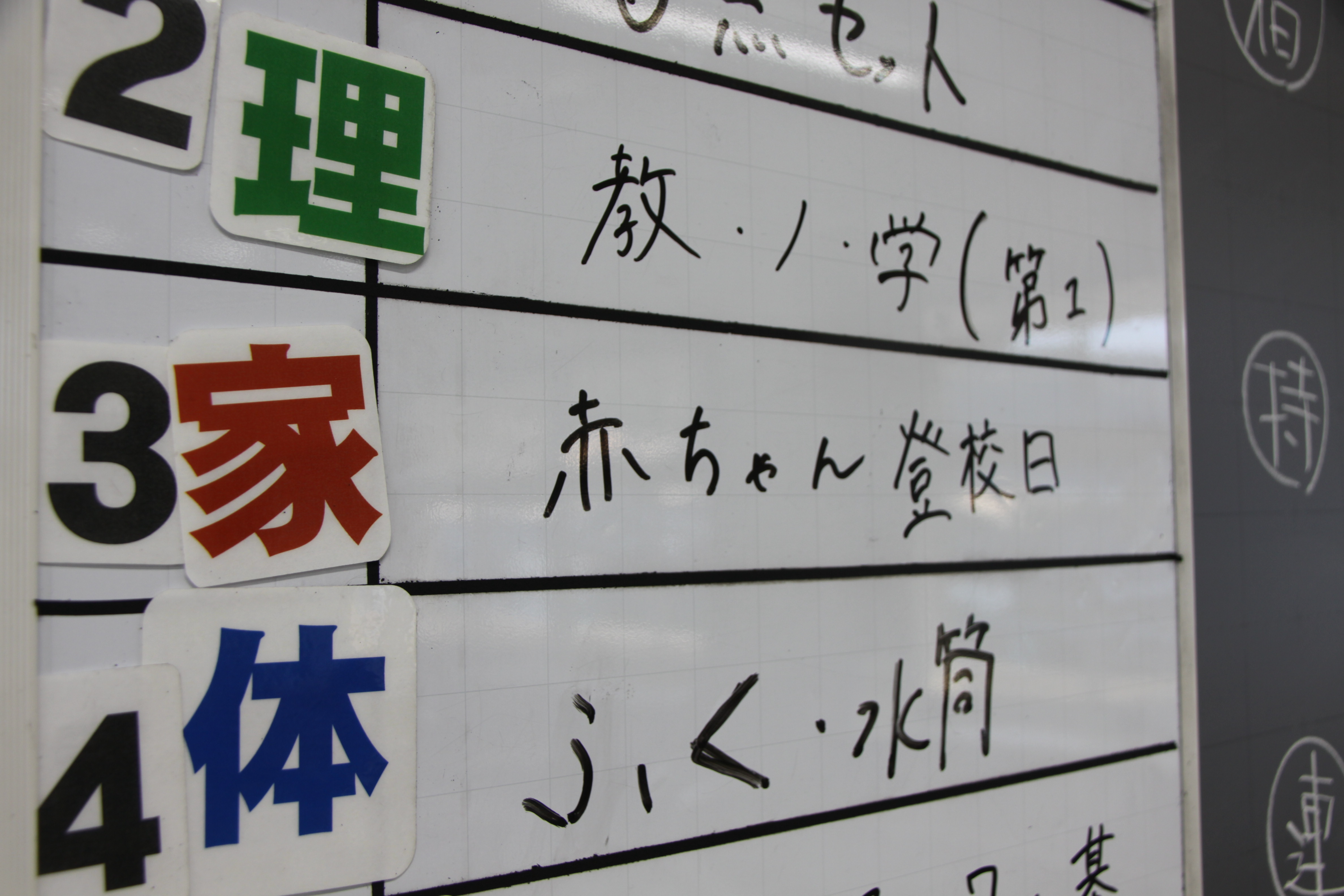




日生中は、多くの方々に支えられて、頑張っています。
◎HP訪問者数10000人を越えました。
これからもご支援よろしくお願いします。(10/19)
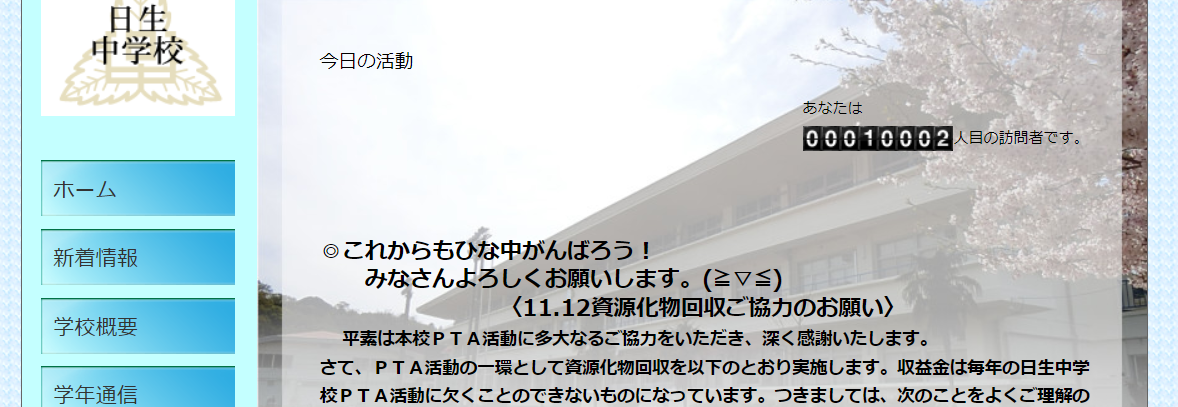
君子有九思ー(君子は九思あり) 論語 季氏第十六
孔子曰、君子有九思。
視思明、聽思聰、
色思温、 貌思恭、
言思忠、事思敬、
疑思問、忿思難、
(物はしっかりと見る、話は正確に聞く、表情はいつも穏やかに保つ、手厚く礼儀正しい姿勢、言葉は真心を持って偽らない、仕事は慎重にする、疑問には質問す
る、怒る時にはその後どうするか考えておく、道義を犯して利益を貪らない)
これからも日生中は、毎日、精進します。
◎地域と共にある学校の新しいカタチは。
日生中学区にある、カフェ天gooさんや、English schoolさんに行かれた先生から、「子どもたちを応援してくれるあたたかい場所ですねえ」とお話をききました。


現在、「子どもの居場所」については、国や地方公共団体でも議論されており、少しNHKのNEWSWAVE記事をご紹介します。
『学校や家庭以外で、いつでも安心して過ごせる場所をつくる必要があるとして、こども家庭庁は検討会での議論を始めています。「家と学校以外のこどもの居場所」、どんな場所なのでしょうか。東京、文京区では、中学生や高校生を対象にした交流スペース「b-lab(ビーラボ)」を8年前に設置、年間延べ2万5000人が利用しています。中には、談話スペースのほか、運動できるホールや楽器の練習ができるスペースなどが整備、ここで勉強したり、ゲームをして遊んだりと、自由に過ごせます。フロアには、スタッフのほかにボランティアの大学生などもいて、中学生や高校生が1人で来ても居心地良く過ごせるよう、さりげなく声をかけています。中には不登校など、学校や家庭で息苦しさを感じている生徒もいるということですが、スタッフはあえて聞き出すことはしません。会話の中から、やりたいことや、新たな関心や興味のきっかけをつかんでいくようにしているということです。また、ただ利用するだけでなく、みずからスタッフとして運営に関わる生徒もいます。ミーティングの際には企画したイベントの報告や、館内の掲示物のアイデアを出し合うなど主体的に活動しています。米田館長は、「こどもの居場所」の必要性について次のように話しています。「思春期まっただ中の中高生は、心も揺らぎやすく、葛藤も多いうえに、先の未来が見えない将来の不安も抱えています。一方で、昔のように見守ってくれる近所のお兄さん、お姉さんのような存在もなく、自分に目を向けてくれる居場所を意図的に作る必要があると感じています。安心できる居場所があれば、本当に好きなことややってみたいことを発見し、自己表現する可能性を持っていると思います。今後、国が政策として取り組むことで、多様な居場所が広がってほしいです」
こども家庭庁が昨年度、子どもや若者2036人を対象に行ったアンケート調査では、特に中高生以上の世代で「家や学校以外の居場所がほしい」にもかかわらず、そうした居場所が「ない」と回答する割合が高くなっています。アンケートで、「家や学校以外に『ここに居たい』と感じる居場所がほしい」と答えた人のうち、そうした居場所が「よりある」と答えた人と、「ない」と答えた人を見ると…。10~12歳 「ある」 81.7% 「ない」 18.3%。13~15歳 「ある」 73.3% 「ない」 26.7%。16~18歳 「ある」 73.1% 「ない」 26.9%と、年齢が上がるほど「ない」と答えた人の割合が高くなっています。
また、居場所がないと答えた人に、どのような場所なら行ってみたいか複数回答で尋ねたところ、▽15歳以下では、「いつでも行きたい時にいける」「好きなことをして自由に過ごせる」と回答した割合が50%前後と高い傾向にあり、16歳以上では、その2つに加えて、「1人で過ごせたり、何もせずのんびりできる」という回答の割合も約57%から64%と高くなりました。学校や家庭以外に、安心して過ごせる「こどもの居場所」について、こども家庭庁は引き続き有識者による検討会での議論を進めています。(NHK NEWSWAVE:2023年5月17日より一部)』
日生中学校でも、子どもの豊かな育ちを保障していくためには、これまでの地域連携・協働を踏まえて、さらによりよい学校づくりを進めていきたいと思っています。みなさんの一層のご協力・ご理解をいただき、また、ご意見やアイデア・エールをお聞かせ願えたら幸いです。
◎地域と共にある学校へ
〈おかやま教育週間にあたって〉(10/18)

~学校公開日・授業参観のご案内~
本校では11月2日(木)を学校公開日とし、授業はもちろんのこと、中学生の普段の学校生活などを自由にご覧頂く機会を設けております。ご多用とは存じますが、ご都合のよい時間にお越し下さいますよう、ご案内申し上げます。また、午後は参観授業として人権に関する道徳の公開授業を行います。(PTAの人権研修会を兼ねております。)
なお、地域の方々で参観希望の方はお手数ですが学校に事前にご連絡ください。
1 期 日
・令和5年11月2日(木) 9:00~12:50
2 場 所
・各教室 受付は1階渡り廊下
3 日 程
・学 校 公 開 : 9:00~12:50
・参 観 授 業 :14:00~14:50(PTA人権教育研修会)
・各学年懇談会:14:55~15:30
4 その他
・来校されましたら1階渡り廊下で受付をした際、保護者の名札をつけてください。
・上履き(スリッパ等)をご持参ください。
・公開授業の変更がある場合は、当日受付に掲示しておきますのでご確認ください。
・駐車場は、運動場南側をご利用下さい。
5 学校公開の時間割です。( )は教室です。すべて50分授業です。時刻は開始時刻です。
| 1A | 1D | 1E | 2E | 2A | 3AD | 3B | |
| 1校時 | 理科 | 英語 | 数学 | 技/家 | 道徳 | 道徳 | |
| 9:00 | (1A) | (1D) | (E) | (技術室/被服室) | (3A) | (3B) | |
| 2校時 | 英語 | 理科 | 理科 | 家/技 | 国語 | 美術 | |
| 10:00 | (1A) | (1D) | (E) | (被服室/技術室) | (3A) | (3B) | |
| 3校時 | 技/家 | 英語 | 国語 | 美術 | 社会 | ||
| 11:00 | (技術室/被服室) | (E) | (2A) | (3A) | (3B) | ||
| 4校時 | 家/技 | 国語 | 総合 | 社会 | 国語 | ||
| 12:00 | (被服室/技術室) | (E) | (2A/多目的4 /第2理科) |
(3A) | (3B) | ||
| 5校時 | 1年道徳 | 2年道徳 | 3年進路説明会 14:00~16:00 (フューチャールーム) |
||||
| 14:00 | (1A) | (2A) | |||||
◎令和5年度 人権教育研修会 について
※5校時「道徳」公開授業(PTA人権教育研修会)
| 1年生 ワタシ・アナタを認め合う 「お互いの特性について考える」 |
2年生 ホームレス問題学習から、 生き方・社会のあり方を考える (生き方・キャリア学習) |
2年 川元さん(NPO 岡山きずな)
◎わたし・私・ワタシ(10/18)
~古いアルバムの中に 隠れて想い出がいっぱい 無邪気な笑顔の下の 日付けは遥(はる)かなメモリー 時は無限のつながりで 終わりを思いもしないね~
…卒業アルバム用個人写真(^^)/と、入学願書に使う個人写真('_')を撮りました。中元さんありがとうございました。
~進路情報~令和6年度 岡山県立高等学校入学者選抜は、インターネット出願となります。私立高校はすでにインターネットによる出願を実施しています。岡山県のHPから出願に関する内容を少し紹介します。
〈令和6年度岡山県立高等学校入学者選抜では、全ての県立高等学校、全ての入試でインターネット出 願を実施します。本冊子ではインターネット出願を行うために必要なことを解説していますが、入試制度や学校別の実施内容等については、「令和6年度 岡山県立高等学校入学者選抜実施要項」や、パンフ レット「令和6年度 岡山県立高等学校へ入学を希望する皆さんへ」などで確認してください。 出願サイトで情報を入力し、中学校等の承認※を受けた後、入学選抜手数料を納付※すると、入学願書を印刷できるようになります。印刷した入学願書と、調査書等の出願書類は、中学校等を通じて志願する県立高等学校に提出し、受理されると出願完了となります。 受検票は出願サイト上で交付されるので、受検票の交付期間に各自でダウンロードして印刷し、切り取り線で切り取り、受検当日に持参してください。※県外の中学校等に在学中の生徒及び中学校等に在学していない場合は、中学校等の承認は不要です。※クレジットカードと、コンビニエンスストアでの支払いのどちらかを選択できます。〉高校進学についての仕組みや手続きは大きく変化しています。岡山県や各学校のホームページで確認してみてください。また、ご心配や不安のある方は、お気軽に学校へご相談くださいね。
~目や耳やからだで、ゆたかな生き方を~(10/18)
読み語りボランティアは、幼稚園や保育園、小学校で本の読み聞かせを無償で行うボランティア活動で、たくさんの学校が取り組んでいいます。日生中学校でも読み語りを通して、生徒らに、豊かな感性をもってほしい、たくさんの世界を知ってほしいという思いのもと、地域からボランティアさんが継続的に来校してくださっています。ありがとうございます。次回は11月22日です。
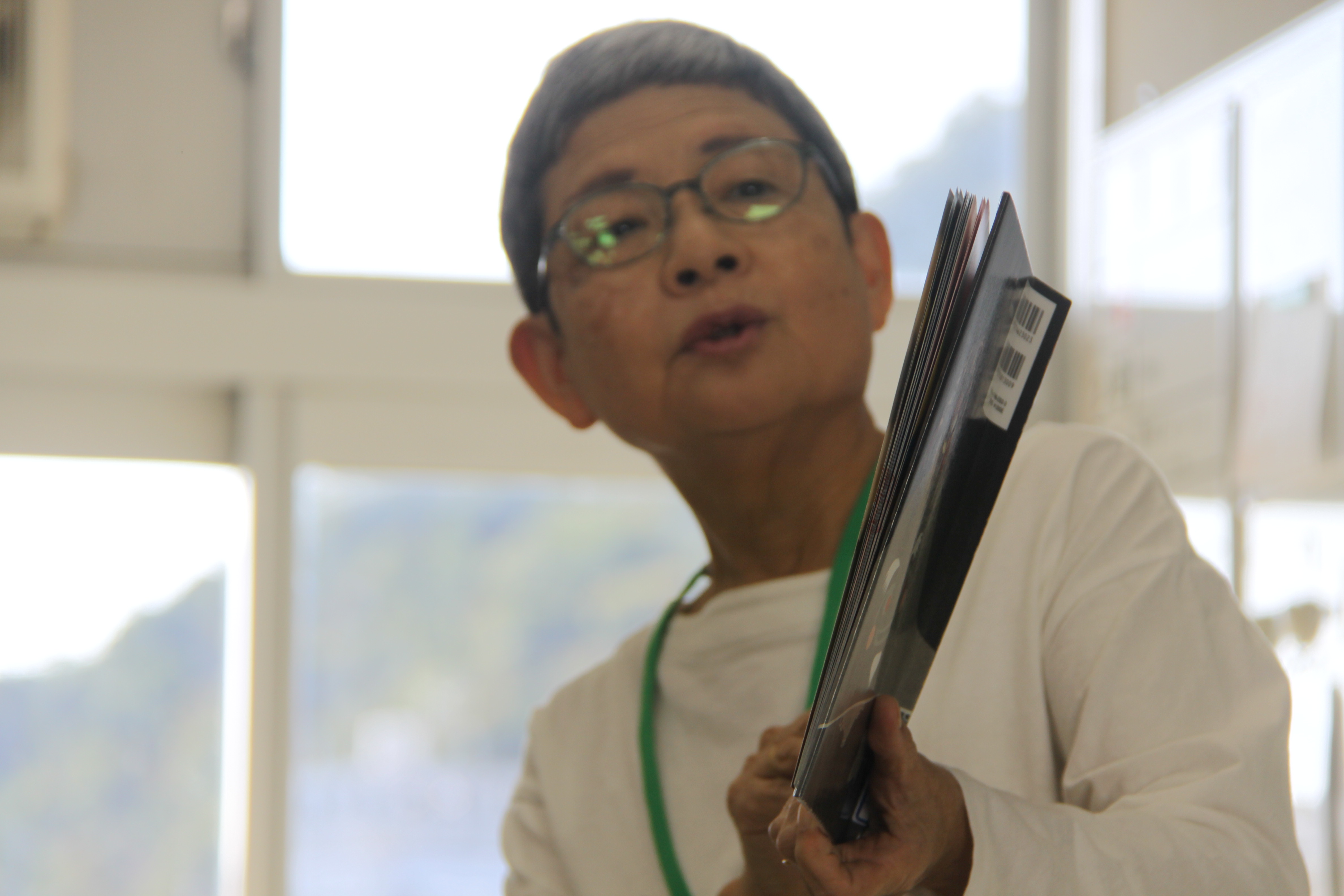


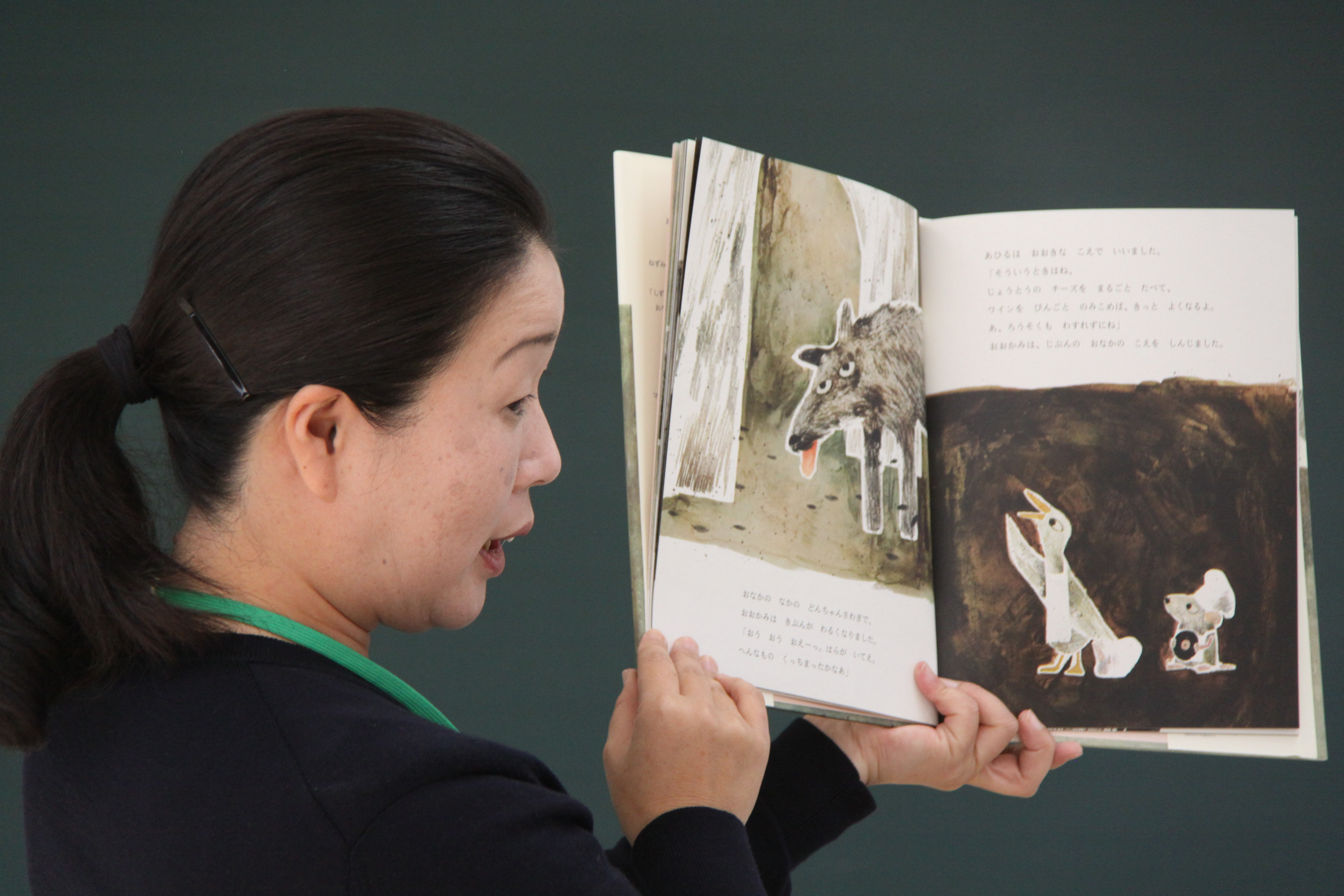


私からも、小学校の先生から教えていただいた、素敵な絵本(一部)を紹介します。
『へいわってすてきだね』安里有生/詩 長谷川義史/画
…
へいわってなにかな。
ぼくは、かんがえたよ。
ねこがわらう。
おなかがいっぱい。
やぎがのんびりあるいてる。
ちょうめいそうがたくさんはえ、よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。
みんなのこころから、へいわがうまれるんだね。
これからも、ずっとへいわがつづくように、ぼくも、ぼくのできることからがんばるよ。…
◎セイ ヤング(10/17)
委員会活動は、私たちの組織する生徒会において、学校における自分たちの生活の充実・発展や学校生活の改善・向上を目指すために、立場から自発的、自治的に行われる活動です。また、他学年の仲間同士で協力したり、よりよく交流したり、協働して目標の実現をしたりしようとする活動でもあります。
ひな中の学校生活上の諸問題から課題を見いだし、その解決に向けて取り組むためには私たち自ら活動の計画を立て、それぞれの役割を分担し、協力し合って集団活動を進められるようせねばなりません。今日も積極的に話し合っていきましょう。文化委員会・体育委員会・環境委員会に引き続き、明日は中央役員も集まります。球技会の計画や、SDGs等の取組としての使用済み簡易カイロ回収運動の企画など、準備しています。


Think left and think right and think low and think high. Oh‚ the thinks you can think up if only you try!
Dr.Seuss
(右を考え左を考え、それから下のことも上のことも考えよう。挑戦すれば、どれだけの考えを見つけ出すことができるか!)
◎チャレンジ 楽しむ 豊かなまなび(10/17)
ひな中チャレンジ企画として計画した〈第2回英会話講座〉を開催しました。引き続き10.24、10.31、11.14、12.5、12.12を予定しています。
夢・目標の実現に英語が必要な人、英会話や発展学習に関心のある人は、参加しましょう。Let‚s do it!(^^)/
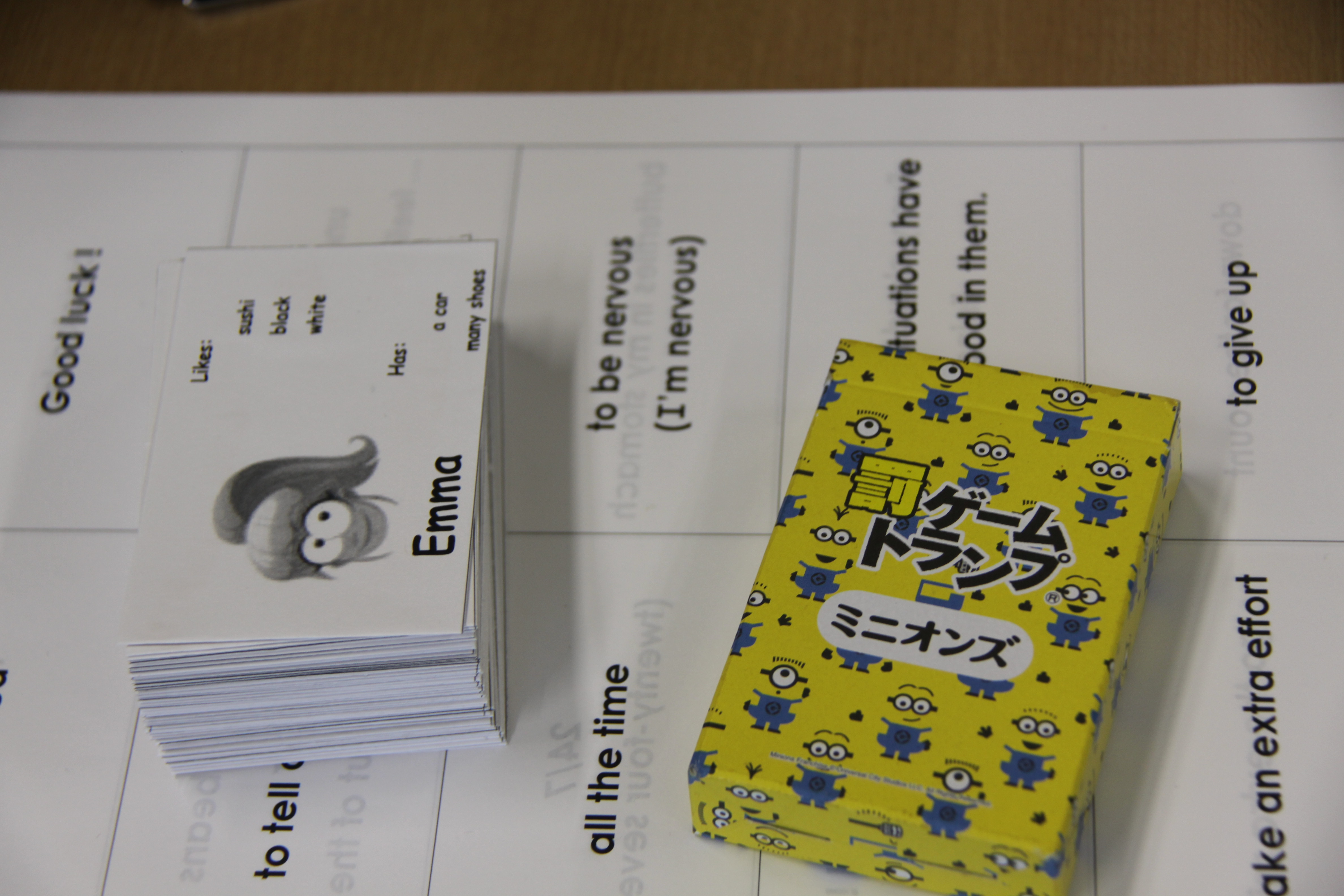

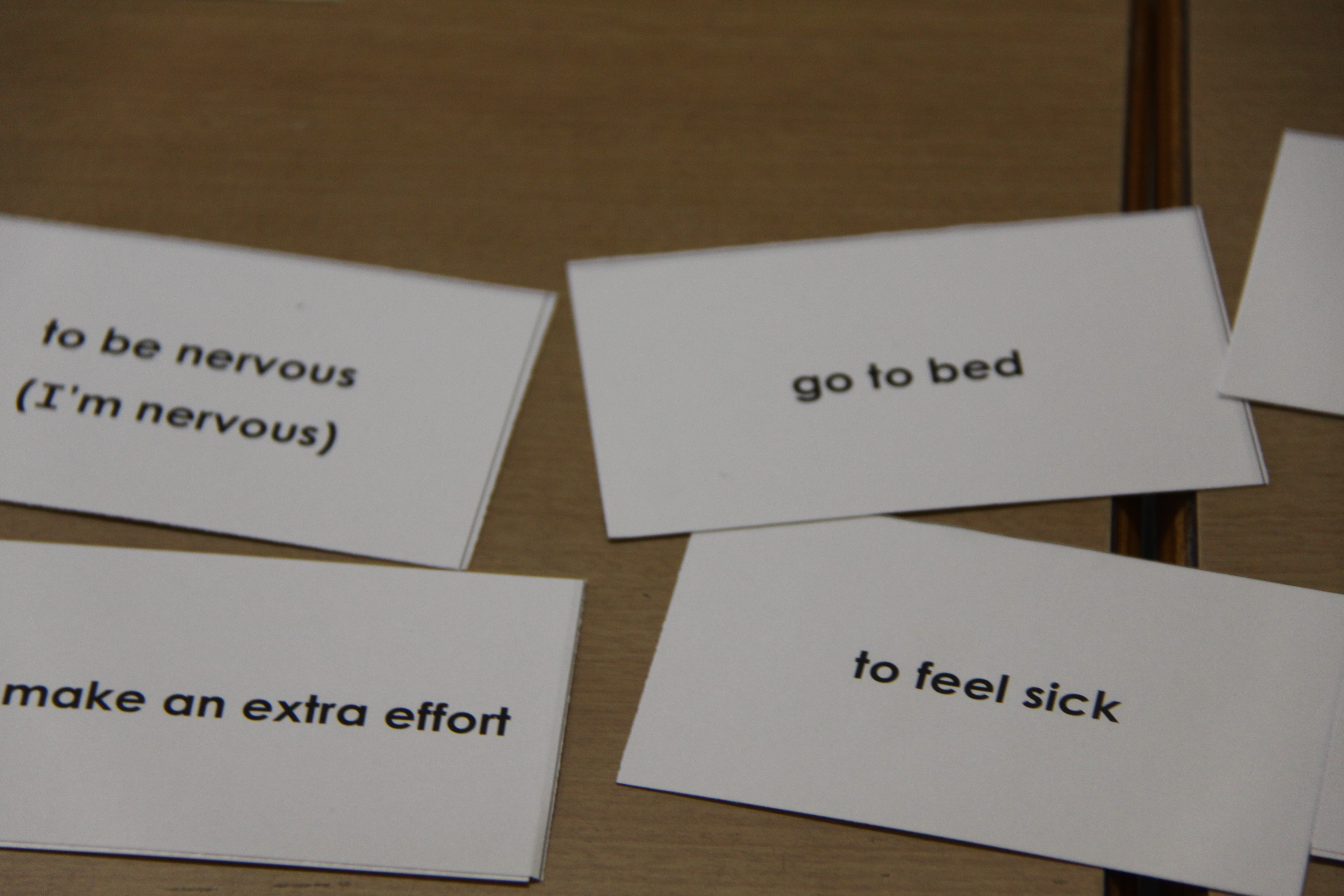
◎戦う時はいつだって一人だぞ
でも一人じゃない事もわかるだろ?UVERworld「Fight For Liberty」
〈10/17:三年生到達度テスト挑む〉

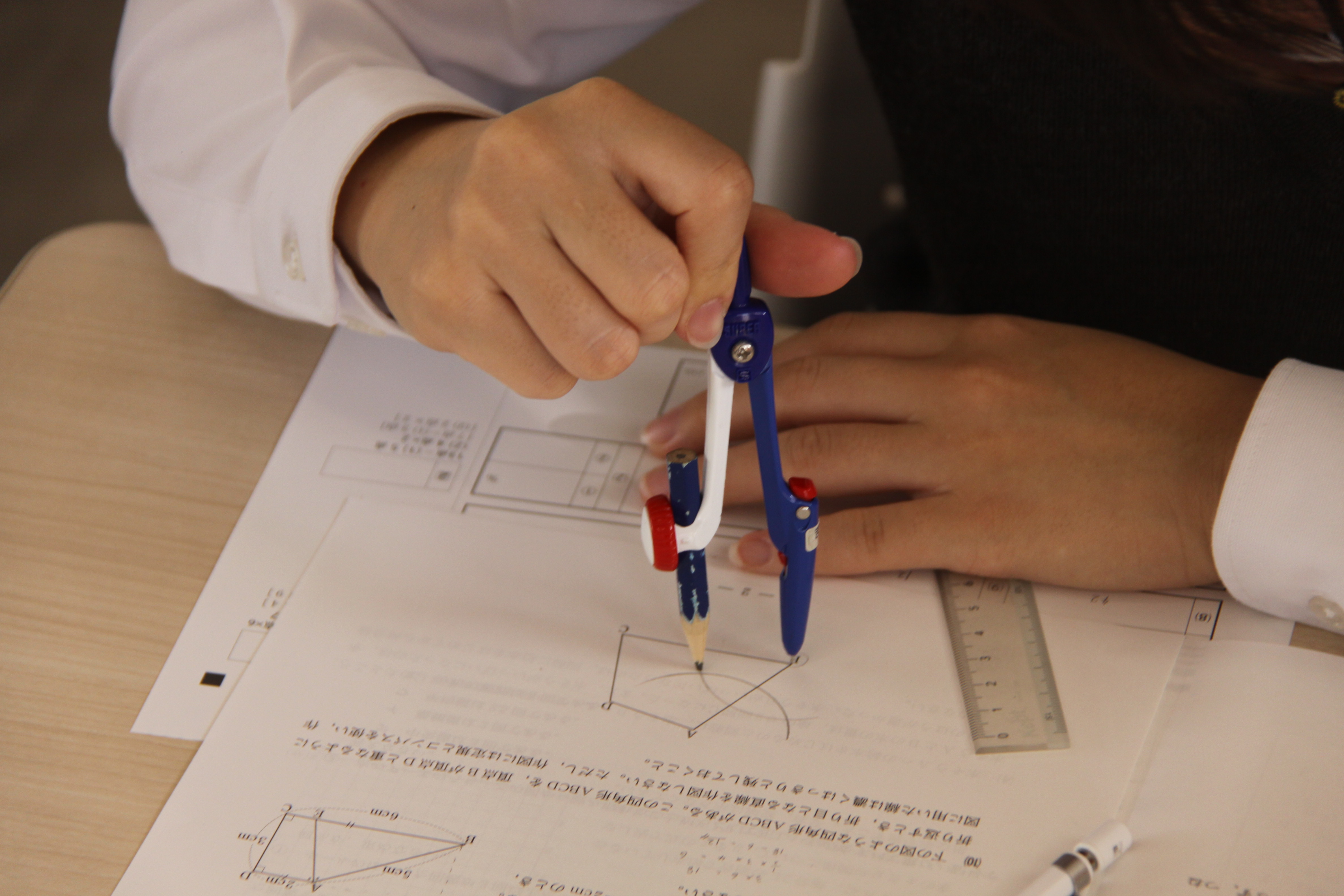
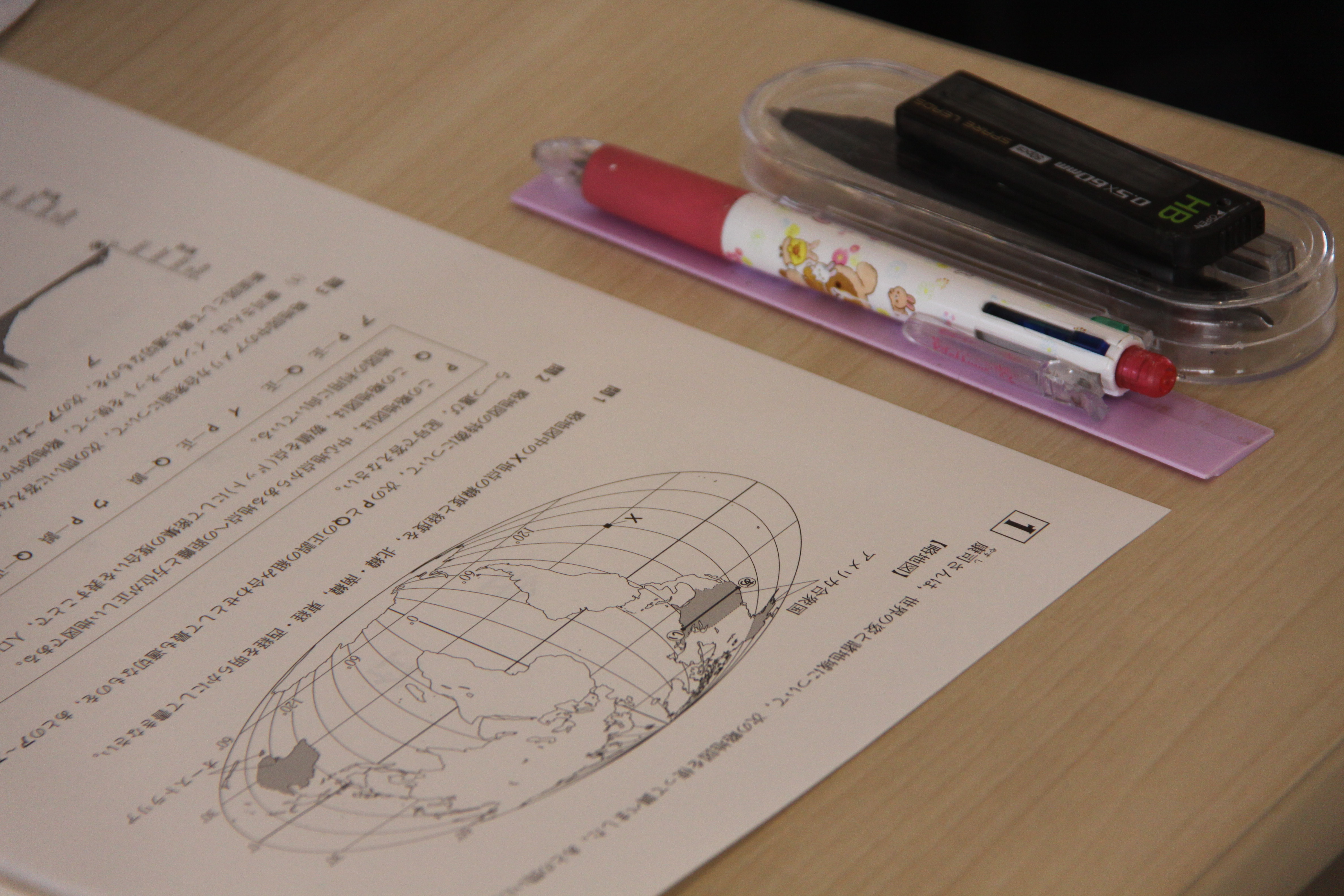
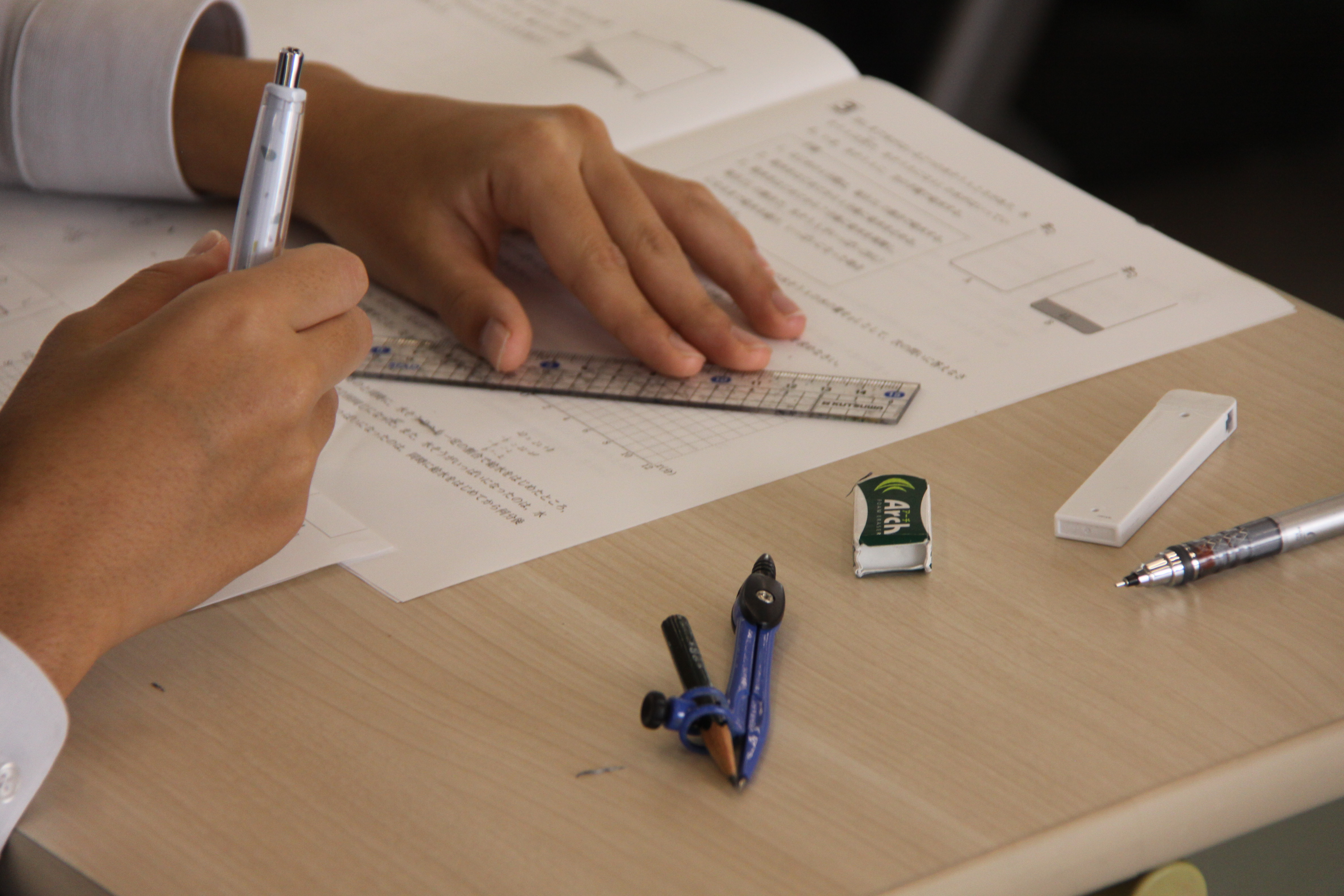

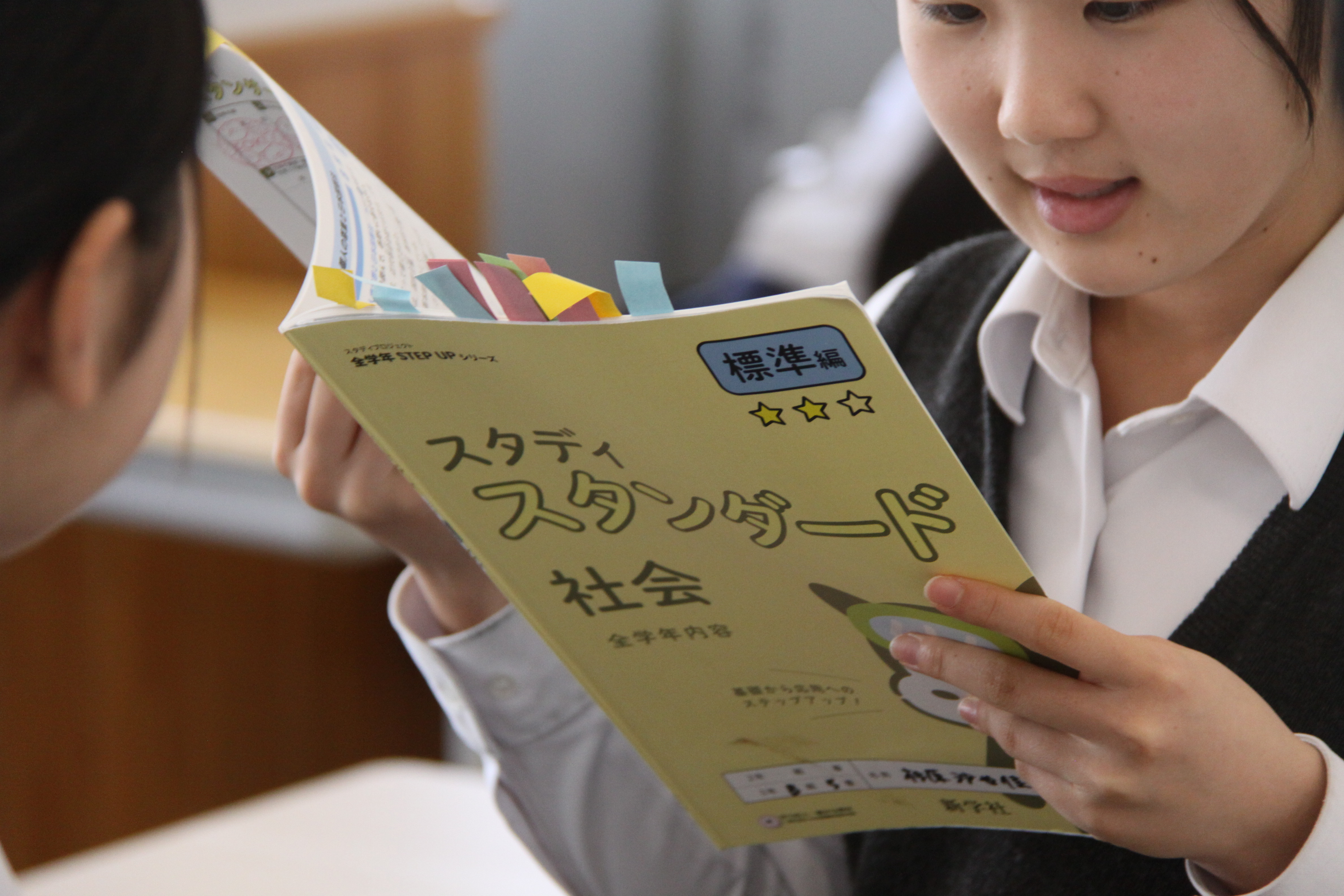



16日、岡山県私学協会は、県内私立高校の2024年度募集定員を発表しました。全23校の総定員は前年度と同じ5620人で、いずれの高校も定員を据え置いています。来春の県内中学校の卒業見込み者数が3年ぶりに減少に転じるものの、長期的な私学人気などを考慮したとみられます。
24年春の中学校卒業見込み者数は前年度比359人減の1万6899人で、25年春も減少が続くとみられます。県私学協会は「少子化の大きな流れは今後も変わらず、各校には一定の生徒数を確保することで教育の質を維持する狙いもあるのだろう」と推察しています。また、学校の特色を打ち出そうと、4校がコースの新設や改編を行いました。美作が不登校特例校(学びの多様化学校)に対応した「Bloom」を普通科に新設。創志学園は同じく普通科に「理数特別」を設けています。
試験は21校が共通日程で行い、選抜1期(学校で名称は異なる)は24年1月25日。うち13校は26日も続けます。選抜2期は18校が2月20日に予定しています。川崎医科大付属と吉備高原学園の2校は独自日程で実施します。インターネットによる出願は21校で受け付けます。23年度の選抜1期には同一校での併願受験を含めて延べ2万7476人が出願し、平均競争率は5・01倍でした。
◎共に生きよう 自分らしく生きよう(10/17:薬物乱用防止教室)
水島税関支署片上出張所から河内さん、中屋さんをお招きして「薬物乱用防止教室」を開催しました。また、小ワークショップを通して、秩序ある貿易を維持し、覚醒剤・麻薬をはじめとする不正物品の密輸取締りなどを行っている税関業務への理解を深めることもできました。



ひとのあいだ
隣の瀬戸内市には岡山ダルクという施設があります。ホームページには〈ダルクは覚せい剤、有機溶剤(シンナー)、市販薬(ブロン等) 、危険ドラック、その他の薬物から解放されるためのプログラムを持つ民間の薬物依存症リハビリ施設です。施設に入寮し、同じ悩み(病気)を持つ仲間とフェローシップ(分かち合い)の中で回復するため、場所の提供をし、12ステップによる今までとは違う生き方をする練習の場でもあります。(中略)薬物依存症はまず、“今日一日薬物を使わないで生きる”事からスタートします。そして、そのことを毎日続ける事によって薬を使わない(クリーンな)生き方をし、成長して行く事が回復につながります。 岡山ダルクでは、自助グループへの参加や、医療機関との連携も欠かせないプログラムの一環として行っています。〉とあります。そのダルクさんをお招きした学校での学習の「振り返り」を一部紹介させていただきます。本校での今日の学びを深めるために参考にしてほしいと思います。
○ダルクさんの話を聴いて,いろいろ辛い過去があって,薬物に手をつけてしまって,最後に言われたとおり,自分は薬物に手をつけたくないなと思いました。一人の方が言われていた「良いウソをついて,相手をこまらせないようにしていた」というの に少し共感しました。依存というのは怖いことだし,回復するのにも時間がかかることが分かりました。
○自分の気持ちを日常の中で言えるようにしたい。薬を使わなくても「人生,楽しいことばかりでではない」ことを頭に入れて,辛いことも乗り越えて,命を大切にしていきたい。
○辛い,悲しいと思うことを一人で抱え込む,それから自分の人生が変わっていったということを聴いて,人間って全部を一人で抱え込んでしまうと「間違った道」を歩んでしまうこともあるんだと感じました。今の自分の生活をふりかえってみて,「どう生きていくか」をお話してくださったことを頭に入れ,過ごしたいと思いました。
○薬物はよくないし,やりたいと思わない。でも,自分が病んでいるときに誘われた らしてしまうと思ってしまった。もしも,病んでいる人がいたら,一緒にご飯を食べに行って,話を聴こうと思います。
〇自分も断るのが少し苦手なので,本当に嫌な時はしっかり断り,自分のやりたいことをやっていきたいです。
○今は,自分は絶対に関わることがないだろうと思っていたけど,以外と身近にあるから,人ごとでは済まされないなと思った。「一度のあやまちが,人生を大きく変えてしまう依存をしてしまうと,一人では抜け出すことができない。周りの人がどんどん離れてしまう・・・。」この言葉に私は,薬物の怖さをあらためて感じ,すすめられても,断られるようになりたいと考えました。
○「ダルクにいても死んでしまう人がいる」というのを聴いて,びっくりした。薬物を一度やってしまうと,もう,後戻りができないことを知った。薬物で何もかも失うと聞いて衝撃的だった。薬物は絶対やらないと決めた。家族・友人を大切にしたいと思った。
○「他人事と思っている」という言葉を聞いて,もしかしたら,自分もそう思っているかもしれないと感じた。いつもの授業で習うのとは違い,言葉一つひとつに重みや現実味があり,その言葉が心に刻まれていくような気がした。孤立感などの負の感情が精神的な理由だと知り,自分も気をつけなくては・・・と思った。
○僕は絶対やらないし,依存もしないと思っていた自分が心のどこかに居たのだと思います。ですが,今回のお話を聴いて,「絶対」なんてないんだとあらためて思いました。僕の人生の中で,今回の防止教室は一生消えない大事な1ページになったと思います。身近にある危険から目をそむけず,相手も自分にも優しくなれるようにしたいです。
○自分を大切に思ってくれている人がいるかもしれないから,その人たちとずっとかかわっていけるように,「薬物」は使わないようにしようと思った。親戚や友達が困っていたら,しっかり相談にのろうと思う。もし,自分が悩みをかかえていたら 友達を頼ろうと思った。「薬物」が日本からなくなってほしいと思った。
◎「いっしょうけんめい」ってスバらしい
〈日生東小学校のみなさんと一緒に:10/17〉
本校の春名先生が、小学校4年生の総合的な学習の時間(以下、「総合的学習」と略する)にゲストティーチャーとして応援に行きました。海洋学習(アマモ)に関する内容についての質問に応じましたが、意欲的に取り組む姿勢、一生懸命にメモする学習態度にとても感心しました。
「総合的学習」は、知識教え込みの教育ではなく、子どもが自ら設定した課題などについて横断的・総合的な課題や学習を行う時間であり、情報を収集・整理・分析し、成果を発信する活動を通じて、これからの社会の中で自分の生き方を考えることのできる力を養うことを目指しています。学習指導要領改訂により、各学校の実態としては、むしろ主要教科の学力向上が重視され、「総合的学習」が軽視される傾向がないわけではないとの意見もありますが、「総合的学習」は、本来、自分の生き方を考え、自分たちの生活や社会を創造する力を育むという、教育の根本にも関わる重要な意義を有する活動です。そのような生き方をつくる学習、ひとを通して学ぶ学習など、中学校からも地域にどんどん出て行って、これからも子小中連携、地域連携をさらに進めていきます。!(^^)!
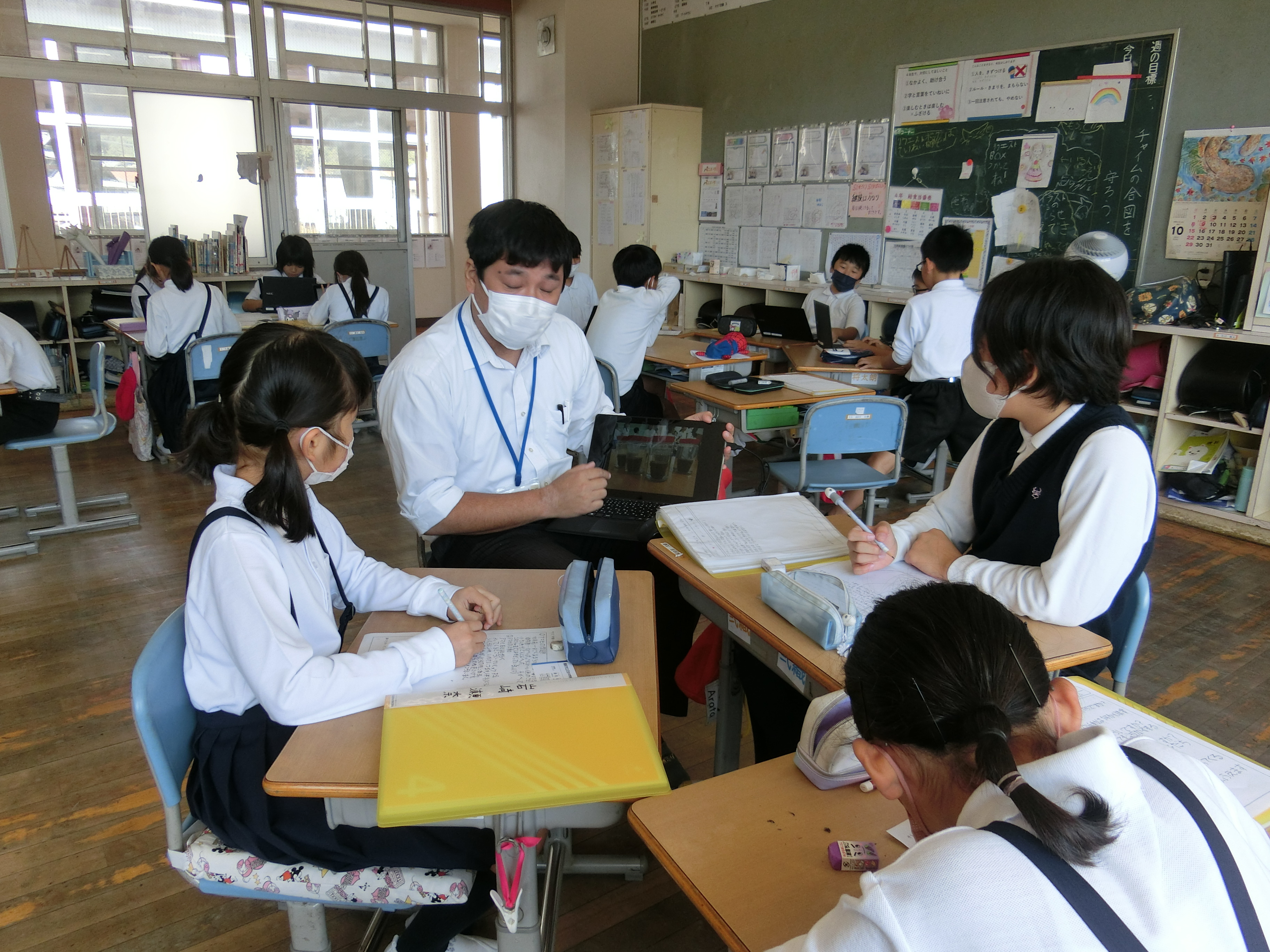
◎ひな中の風~~また明日ね!(#^.^#)
秋きぬと目にはさやかに見えねども風のおとにぞおどろかれぬる 藤原敏行
いつものように、先生と仲間たちと「さよなら」を交わしているひな中です。少し前に、中国語での「サヨナラ」を教えてもらいました。〈再見〉と書きます。「また会いましょう」という意味があることに感心して、他の国の「サヨナラ」も調べてみました。






中国語:再见 (ザイジェン) ベトナム語:Tạm biệt(タンビェッ) 韓国語:안녕히 가세요(アンニョンヒカセヨ) スペイン語:Adiós(アディオス) フランス語:Au revoir(オゥルヴォワー) アラビア語:مَعَ السَّلامَةِ (マアッサラァマ) ロシア語:до свидания(ダスヴィダーニャ) ポルトガル語:Adeus(アデウス) ドイツ語:Auf Wiedersehen(アゥフィーダーゼン) イタリア語:Arrivederci(アリヴェデルチ) ラテン語:Vale(ワレー) オランダ語:Tot ziens(トッツィーンズ) ヒンディー語:अलविदा(アルビダァ) トルコ語:Güle güle(ギュレ・ギュレ) タイ語:สวัสดี(サワディ) インドネシア語:Selamat Jalan(スラマッ・ジャラン) タガログ語: Paalam(パァラム) ギリシャ語:Αντίο(アンティオ) クメール語:ជម្រាបលា។(チョムリァリィァ) スウェーデン語:Hejdå(ヘイドァ) スワヒリ語:Kwa heri(クワヘェリ) チェコ語:Na shledanou(ナスレダノウ) フィンランド語:Näkemiin(ナケミィン) ペルシア語:خداحافظ (コダハフェズ) ポーランド語:Do widzenia(ド・ヴィゼニャ)…それぞれの国が大切にしている文字、文化、表現があるのですね。
では、また、明日は〈早上好!:zǎo shàng hǎo〉(^O^)/
◎出会いに心をこめて~(10/16)
楠原先生をお招きして
11月7日から行う日生中チャレンジワーク(職場体験学習)にむけて、楠本敦子さん(ブレイントレインおかやま)をお招きして、社会人としてのマナー・礼儀について演習しました。事前学習を深め、さらに意識を高め、充実した4日間にしたいと思います。講座のお礼に、「HEIWAの鐘」を聴いていただきました。
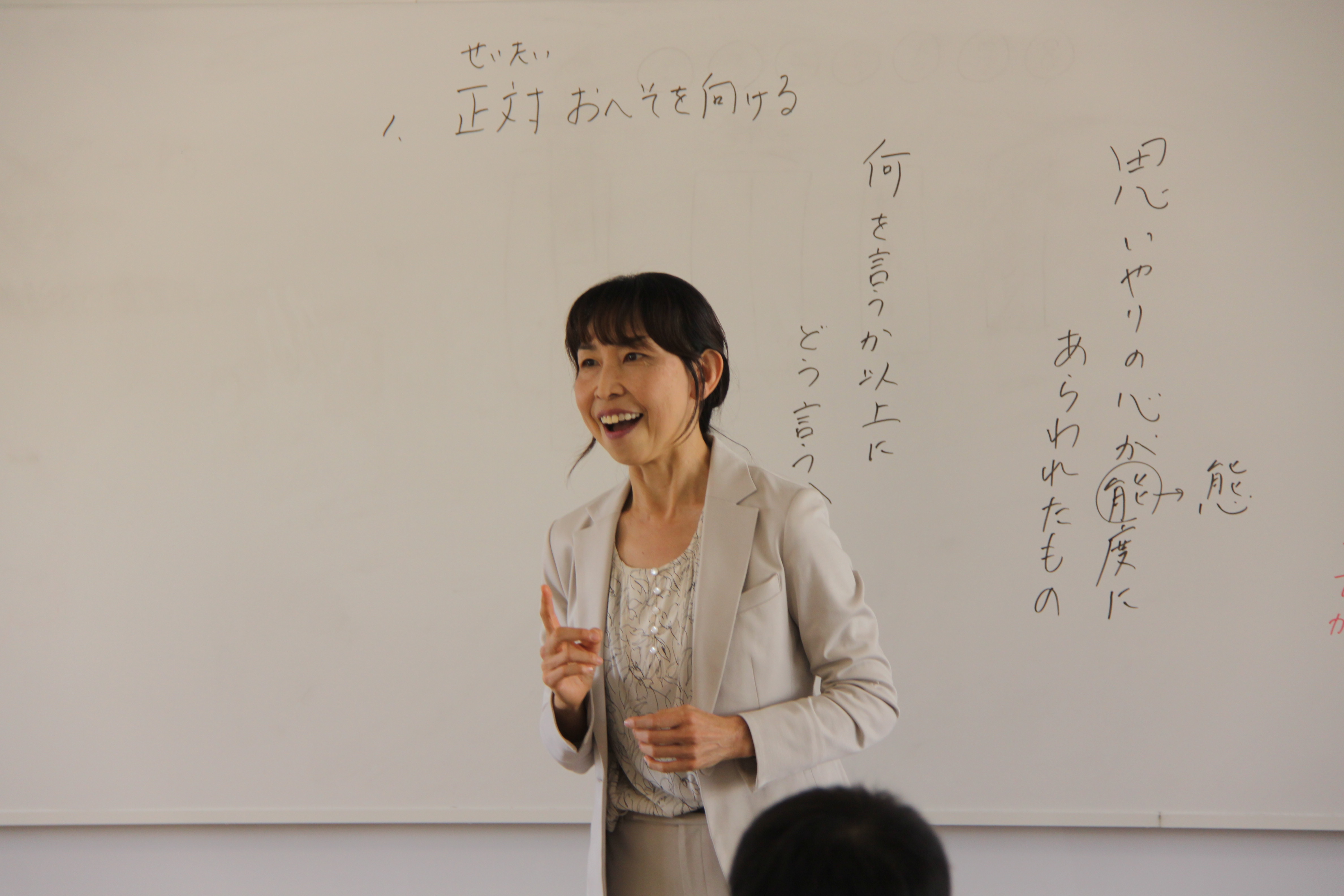
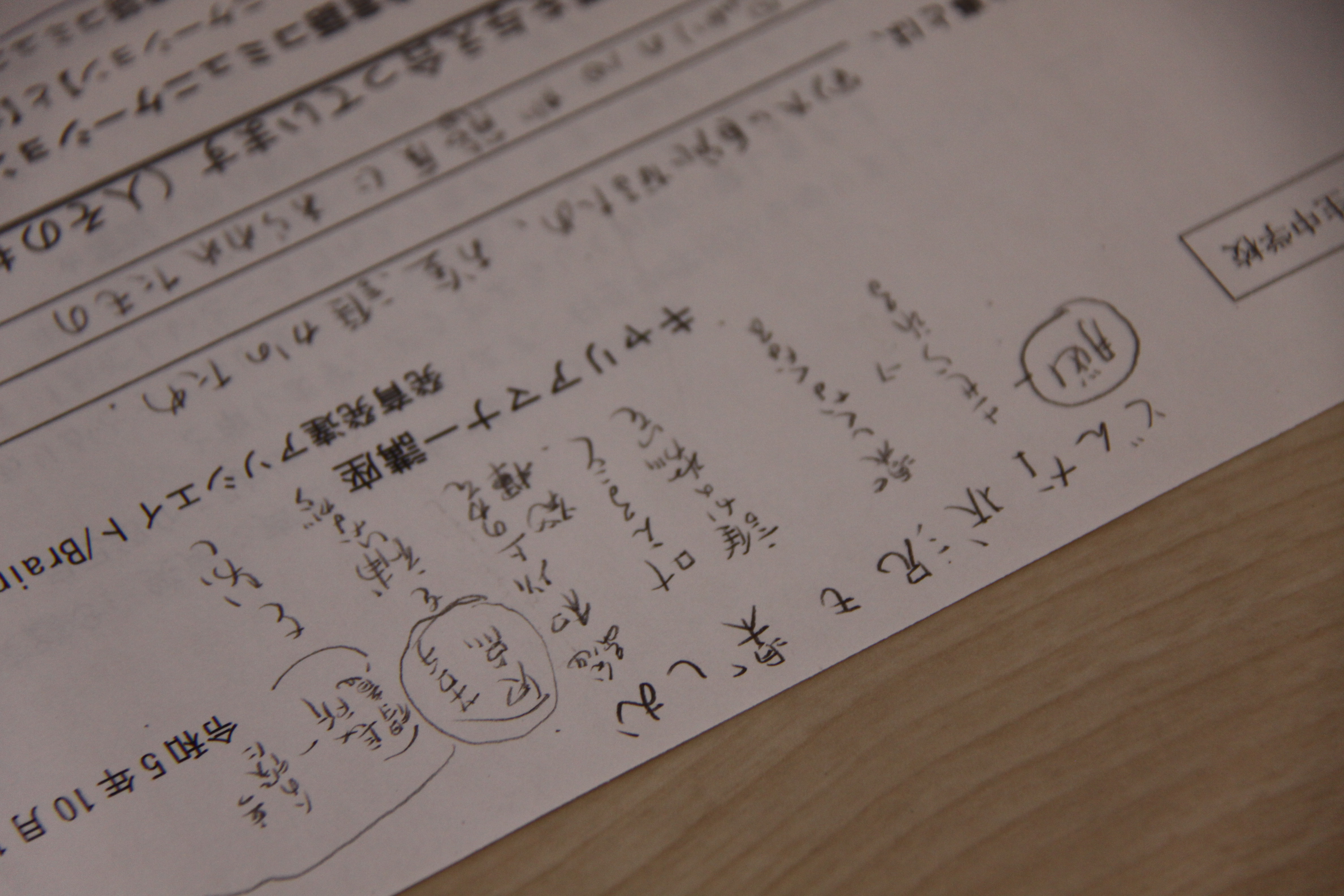







☆彡多くの人に支えられて
~頑張ります!よろしくお願いします。ヽ(^。^)ノ 〈お世話になる事業所〉
日生西小学校 日生東小学校 日生認定こども園 伊部認定こども園 片上認定こども園 奥本生花店 セブンイレブン岡山備前インター店 山陽マルナカ穂浪店 山陽マルナカ備前店 ホームセンター タイム備前店 ナフコ パオーネ THE COVE CAFÉ ステラカフェ きたろうお好み焼き 夕立 海ラボ 中元写真館 天gooカフェ パン工房むくむく 備前市立図書館 日生温水プール 備前消防署 日生図書館 日生町漁協 ひなビジョン
(10/6現在・順不同・敬称略)
◎ぜひ、職場体験(11/7(火)~10(金))に取り組むひな中生徒たちへ
エール・叱咤激励をお願いします。
◎ひな中は、あなたが大切。わたしが大切。
13日、たくさんの仲間たちと手すりをみがきました。私たちは落書きは許しません。仲間を大事にします。

◎〈ともに生きる社会〉へ。
~生徒会からみんなと。街頭募金ボラ募ります(10/13)

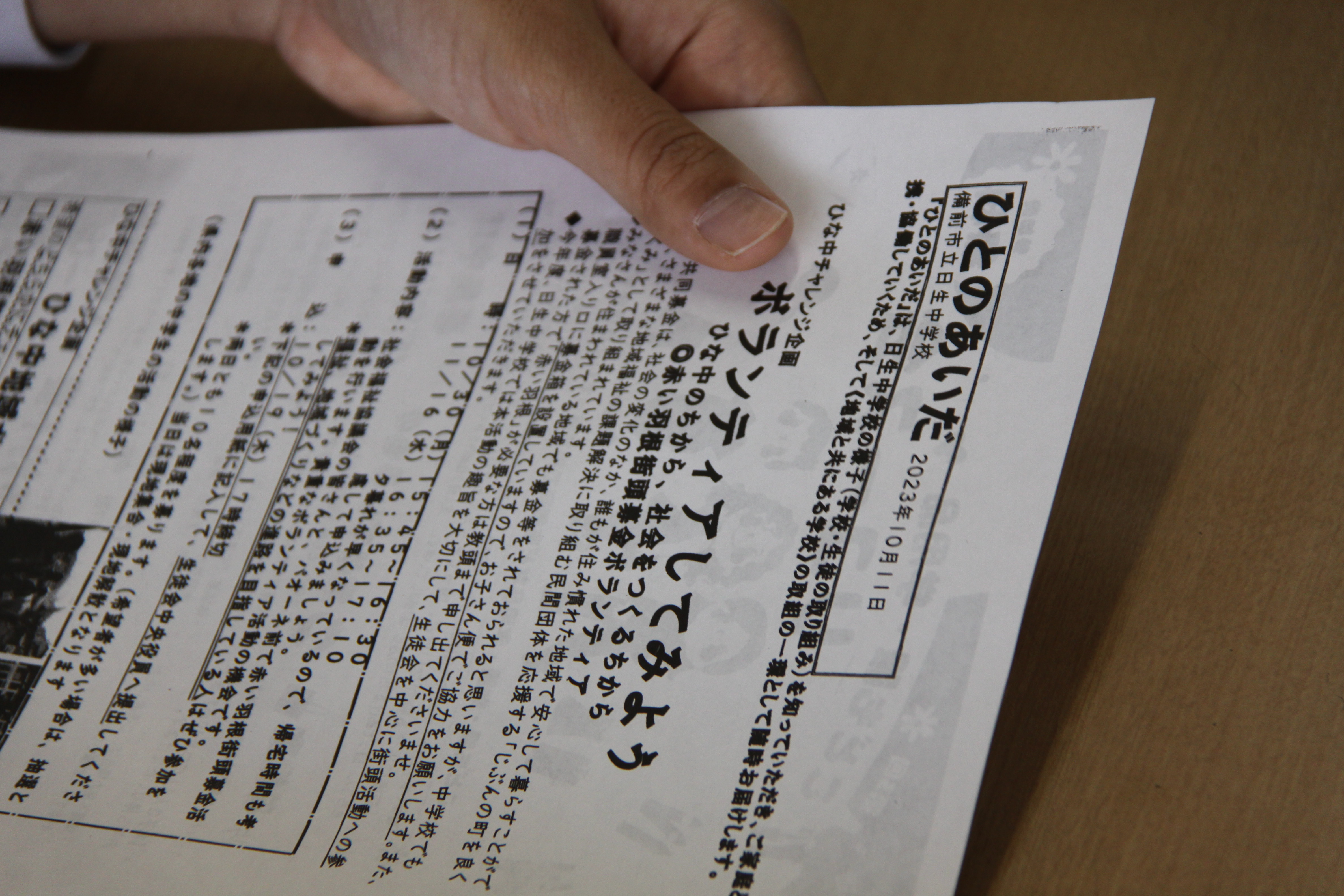
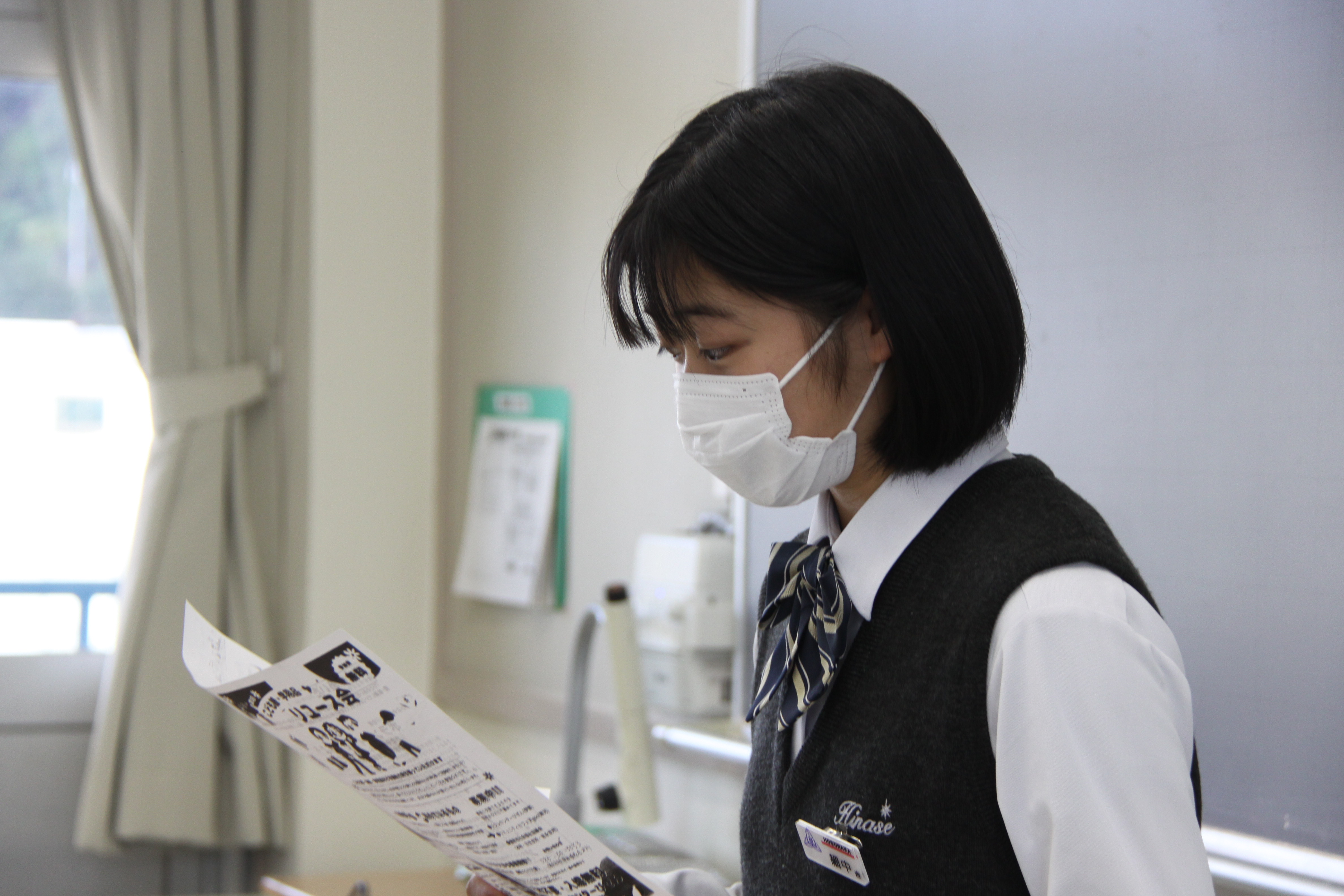


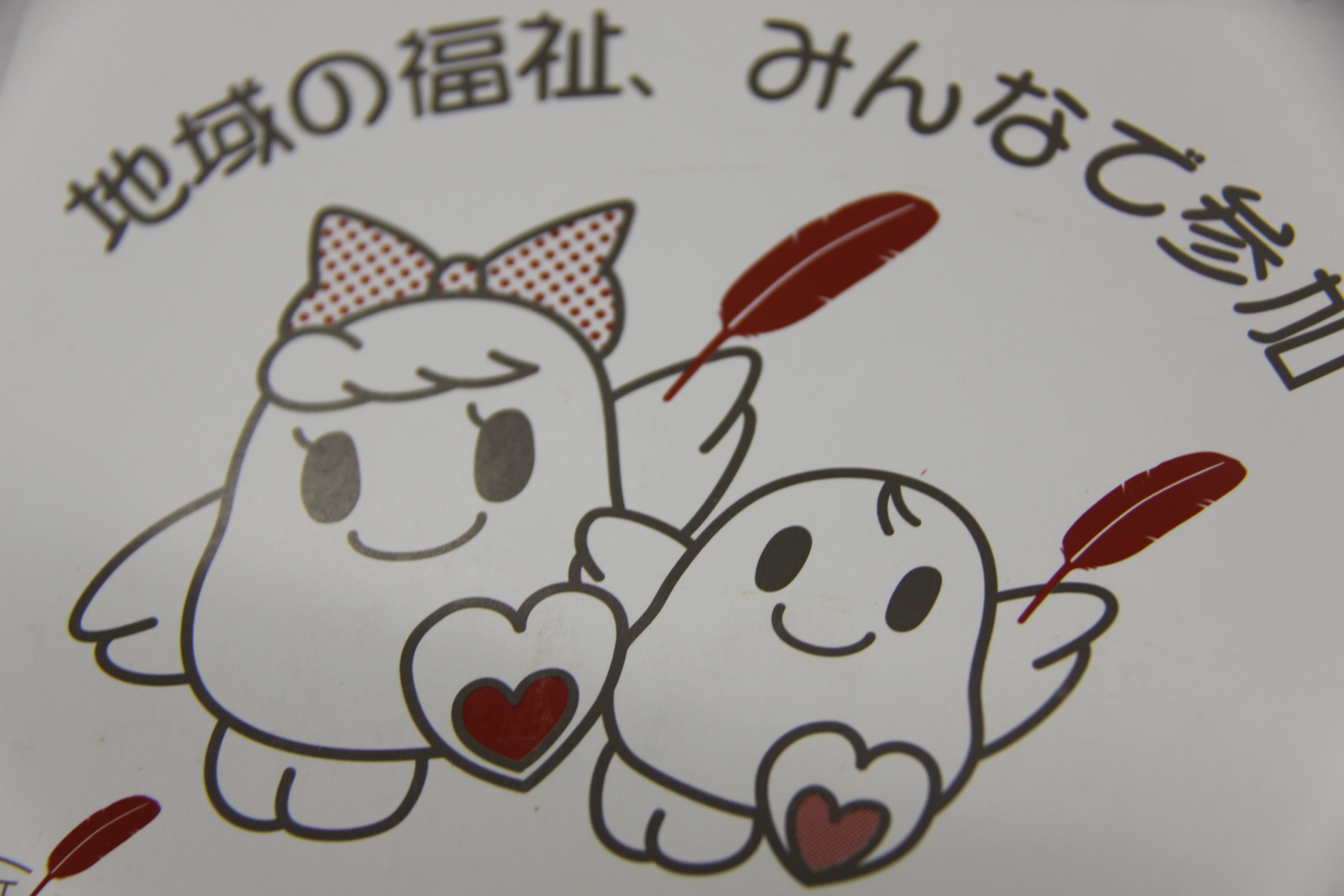
◎多くの人に支えられて
~今日のテーマは、「成長期に必要な栄養素」(10/13)
調理場から北川先生が食育の学習で来校されました。「成長期に必要な栄養素を意識した今日の献立はどれ?」…。正解は、10月の給食盛りつけ表(No2)で確認しましょうね。うふふ。


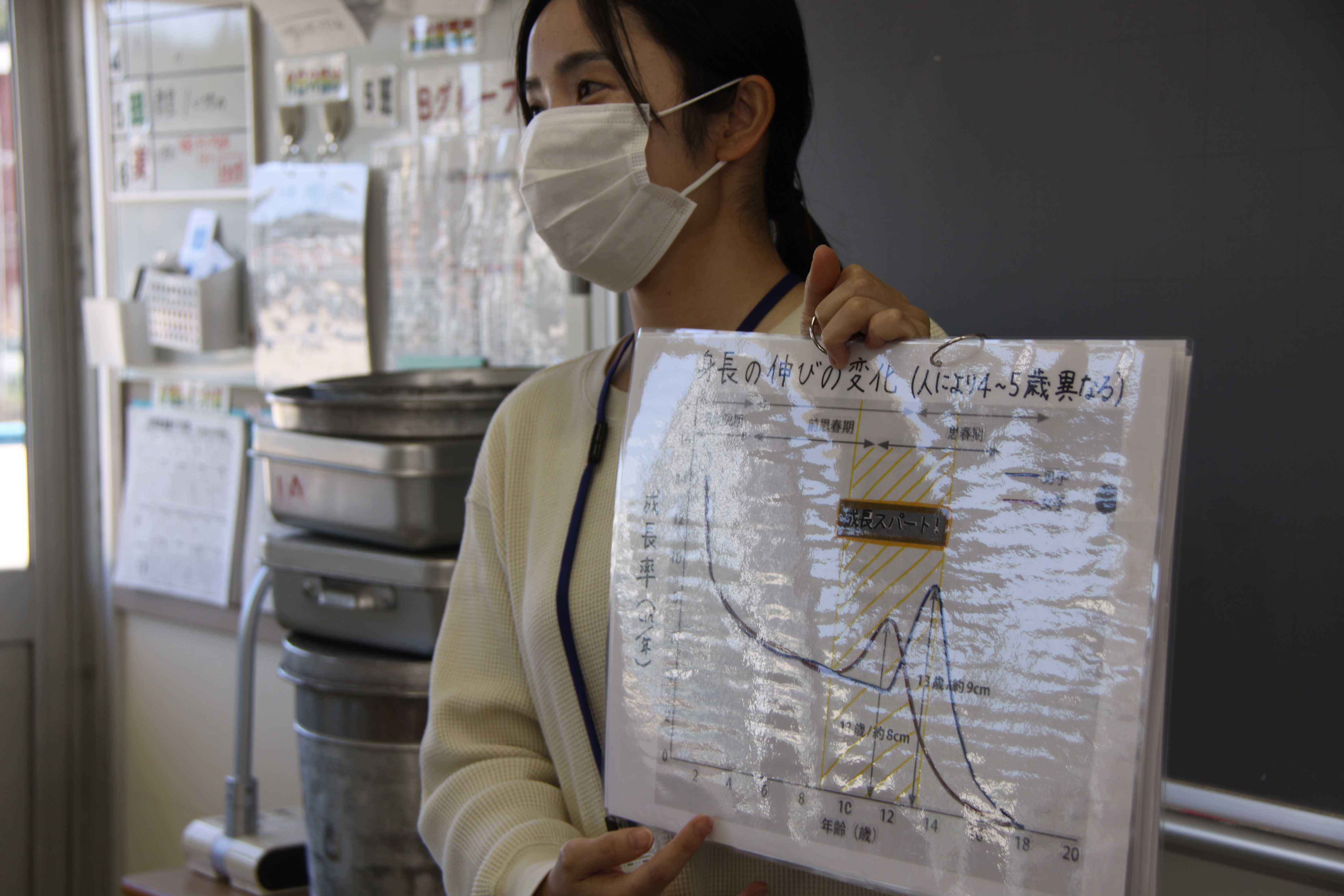

◎地域と共にある学校として
〈ともに生きるって〉(10/13:関西福祉大学へ)
日生中学校は、今年度も、関西福祉大学の「中学生体験学習」に参加しています。これは、大学と学生ボランティアが、地域の中学生に車いすやアイマスク体験や手話体験などの福祉体験学習や教育・看護の知識を提供し、広義ならびに狭義の福祉教育を実施しているものです。この日は、1年生が午前中に学習に取り組みました。3学期には、備前市社会福祉協議会日生支所さんと連携して、認知症サポーター養成講座に取り組む計画を進めています。










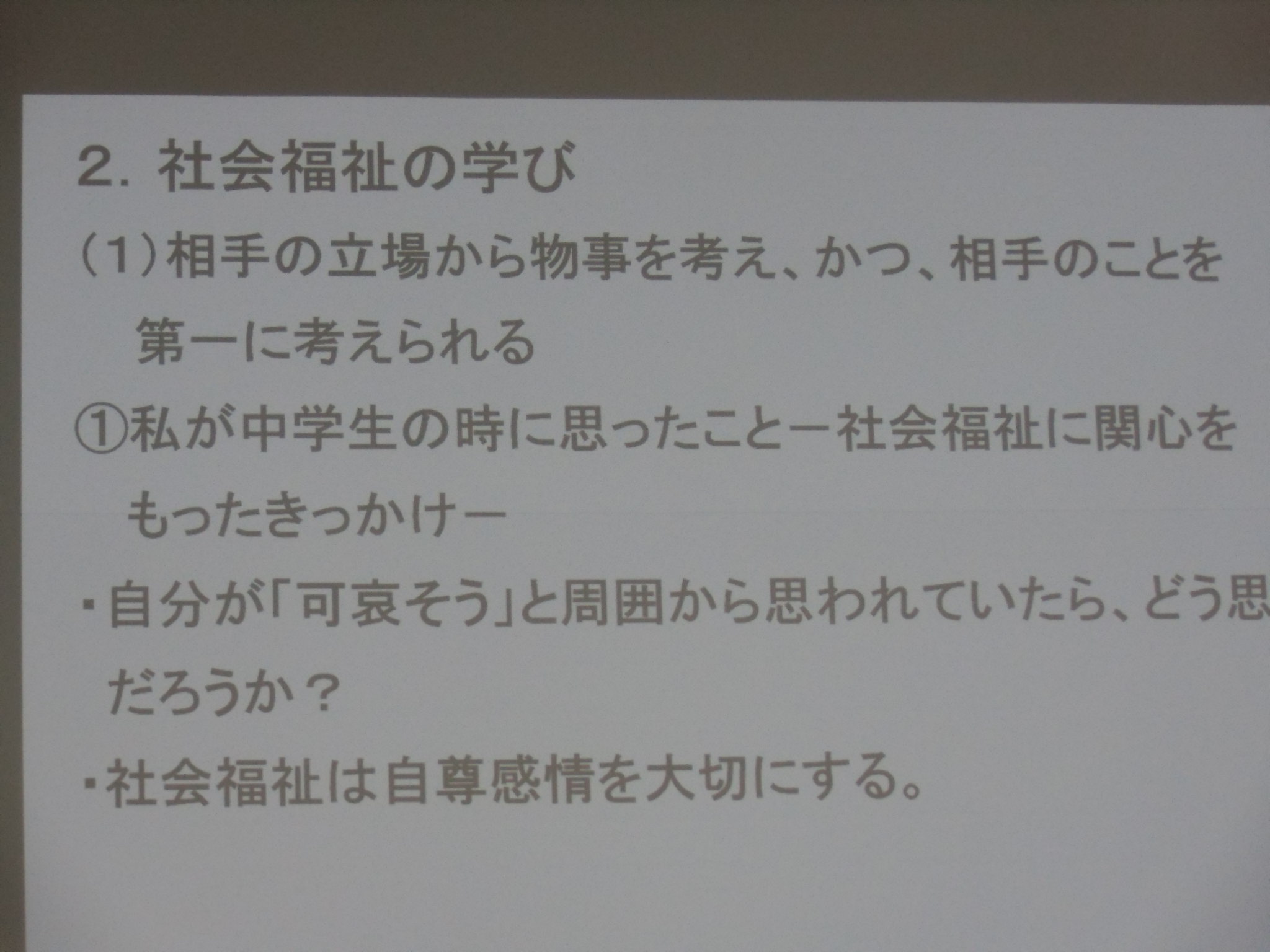

一年生の学習に重ねて…最近ご講演を聴かせていただいた奥田智志さんの記事(日本財団ジャーナルHP)の一部紹介します。
『目指すのは「助けて」と言える社会』NPO法人抱樸の奥田知志さんが奔走する「ひとりにしない」支援
…「厚生労働省の「令和元年版自殺対策白書」によると日本の10代の若者の自殺率は過去最高を記録した。「助けて」と言えない大人たちの姿を見て育つ子どもたちもまた「助けて」と声を上げることができずに、自らを追い詰めてしまっているのではないかと奥田さんは心配する。
そんな子どもや若者たちが少しでも生きやすくなるようにと、「生笑(いきわら)一座」を立ち上げ、全国行脚(学校訪問)を行う奥田さん。一座のメンバーはさまざまな事情でホームレスとなり、その後、抱樸と出会い自立した人たちで構成されている。過去の体験を伝えると共に、ワークショップや歌などを披露しながら、「苦しいときは助けてと言っていいんだよ」「生きてさえいえば、笑える日が来る」と伝え続けている。』
(追記:奥田さん著書『逃げ遅れた伴走者』も参考になります。久次)
◎遊びをせんとや生まれけむ『梁塵秘抄』
待っててね!!(;^ω^)(10/13)
これから、手作りおもちゃを持って、子ども園に家庭科での保育実習に行きます。



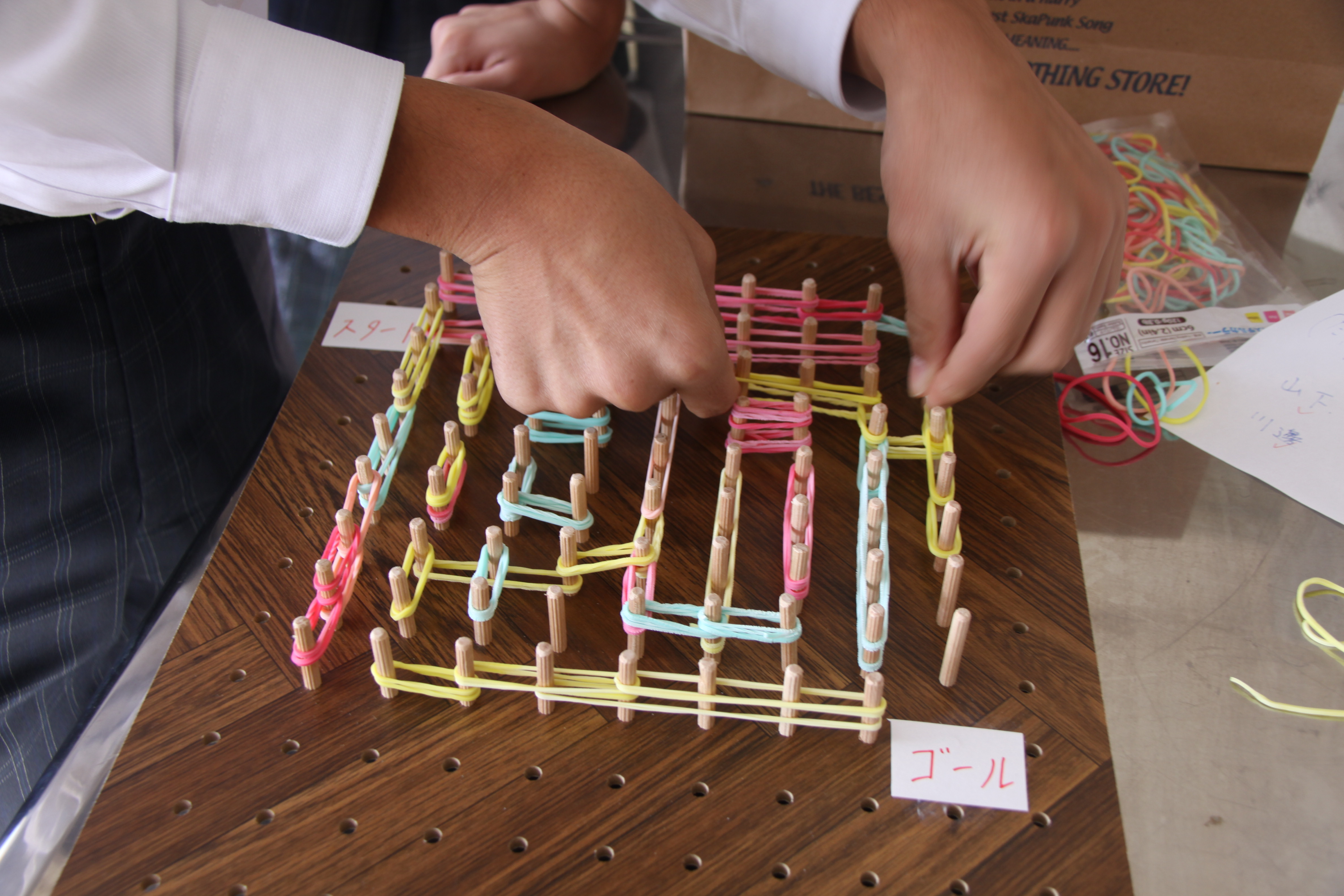


家庭科で…核家族化,少子化が進行する現在,中学生は家庭などの身近なところで幼児と触れ合う機会が少なくなってきています。そのために,幼児に対する関心をもちにくかったり,どのように接していいのか戸惑ったりすることも見受けられます。そこで,事前におもちゃの目的を考えさせ,心身の発達と関連付けて,対象児の年齢に適した製作計画を立て,創意工夫を加えて安全なおもちゃをつくりました。今回の保育実習では,自分たちのつくったおもちゃで幼児と一緒に遊び,触れ合うなかで,幼児に対する関心を高めていきます。また,育つ環境としての家族の役割について知り,さらには,自分の成長と家族や家庭生活とのかかわりについても考えていきます。
◎いのちをまもるひかり(10/12)
11日から、最終下校が17時となり、それに合わせて、夜行タスキ励行についても委員会を中心生徒らに働きかけています。反射タスキ等の反射材用品は、夜間における視認性を高めるものであり、夜間の歩行中や自転車乗用中の交通事故防止を図るうえで非常に効果的な手段です。歩行者や自転車利用者が薄暮や夜間に交通事故に遭わないようにするためには、反射材用品やLEDライト等を活用することが効果的です。反射材用品やLEDライトを活用すると、自動車のライトからの光を反射したり、自ら光ることで、自動車の運転者などに早めに自分の存在を知らせることができます。また、夜間歩くときは、運転者から見えやすいように、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴、衣服、カバンなどに反射材用品等を付けたりするようにしましょう。


◎多くの人に支えられて(10/12)
2004年(平成16年)の学校環境衛生基準の改定によりダニアレルゲン検査が新たに追加され、2009年には年1回定期的に検査することが義務づけられました。 そのため、学校薬剤師さんをと連携してアレルギーの原因となる”ダニ”の数を測定する検査があります。 近年、学校においてアレルギー疾患の児童生徒が増加しています。環境衛生上、ダニまたはダニアレルゲンは、アレルギーを引き起こす要因の一つとされています。快適な学習環境を維持するために、その対策は非常に重要ですので学校でも積極的に対策に取り組んでいます。



*学校薬剤師とは、学校環境衛生の維持・改善を目的として、大学を除く国立・公立・私立の学校すべてに委任委嘱されています。薬剤師が「薬学」を中心とした「専門的な知識」を発揮させ、法律に基づき活動します。ダニ検査は、正常で快適な学校の環境を維持し、児童生徒の学習意欲低下や健康被害を防ぐために行います。
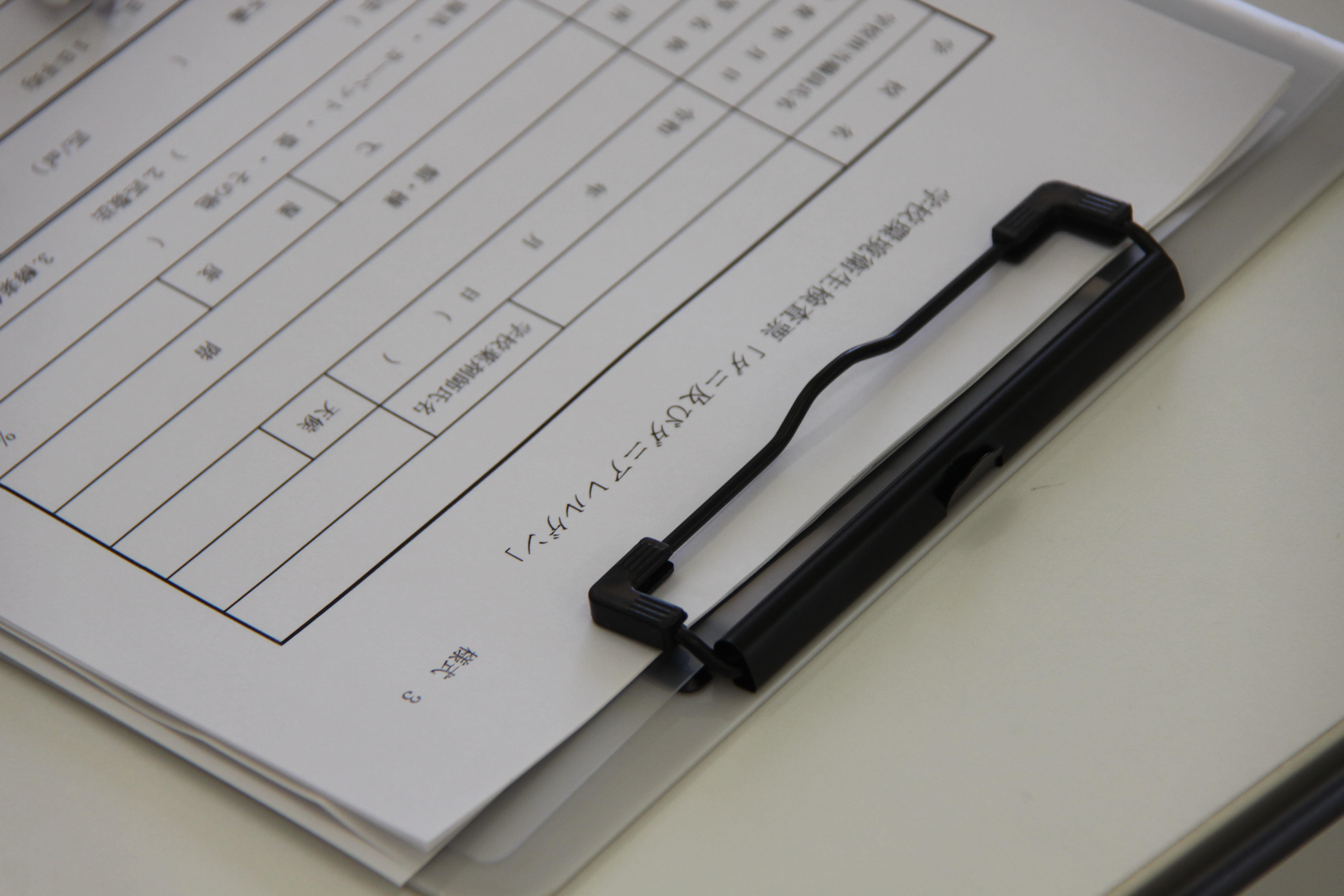
◎ひな中の風~~10月
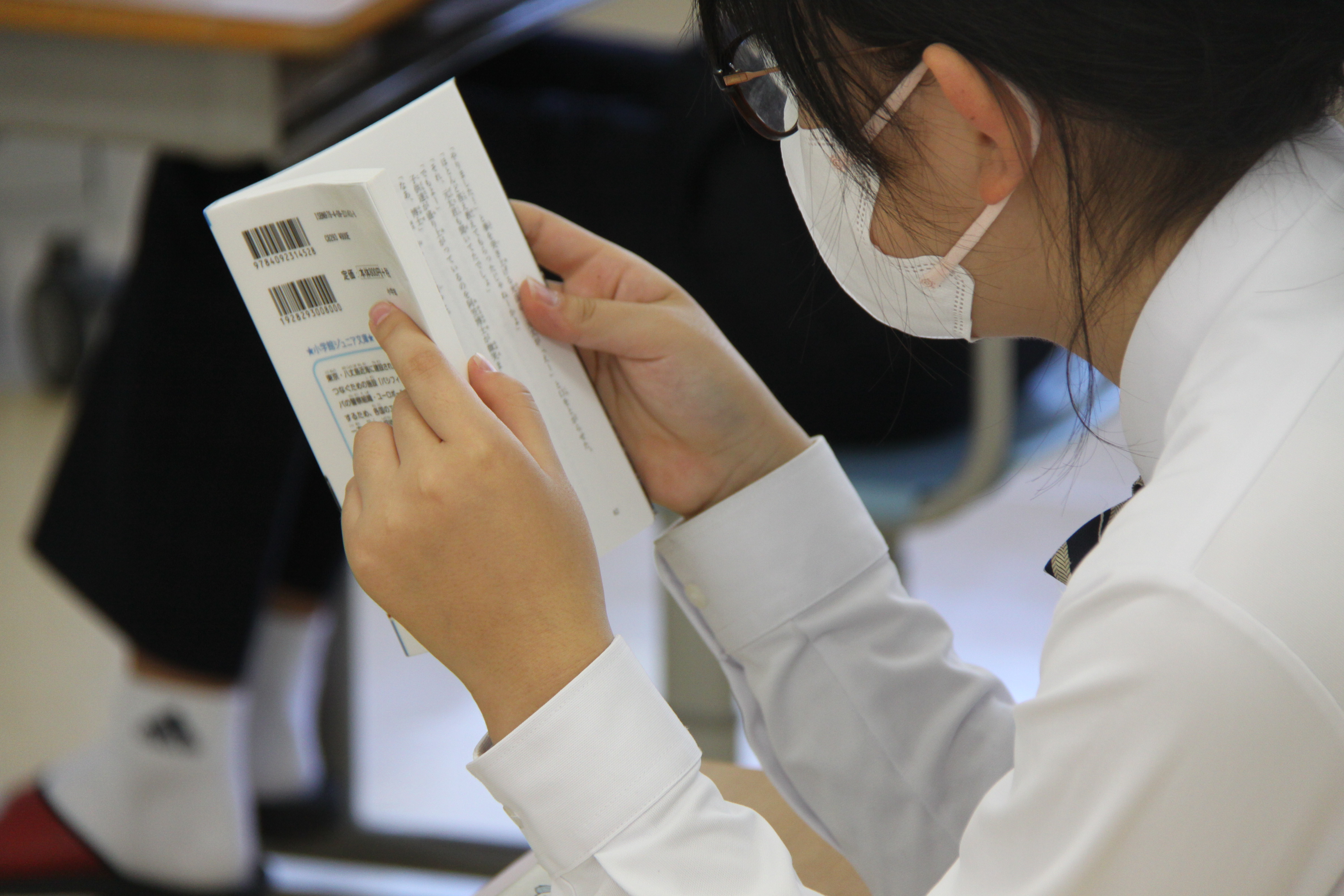




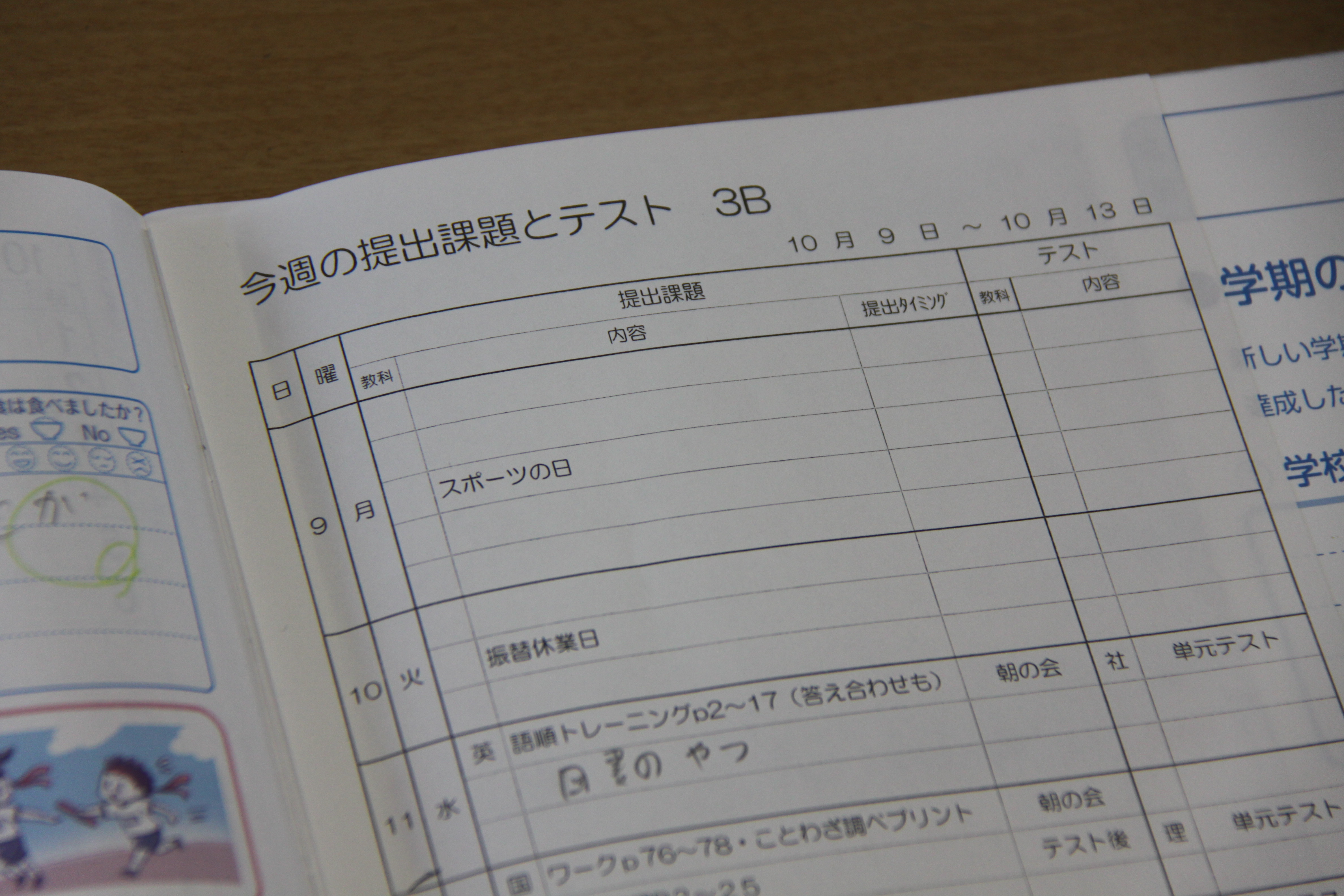

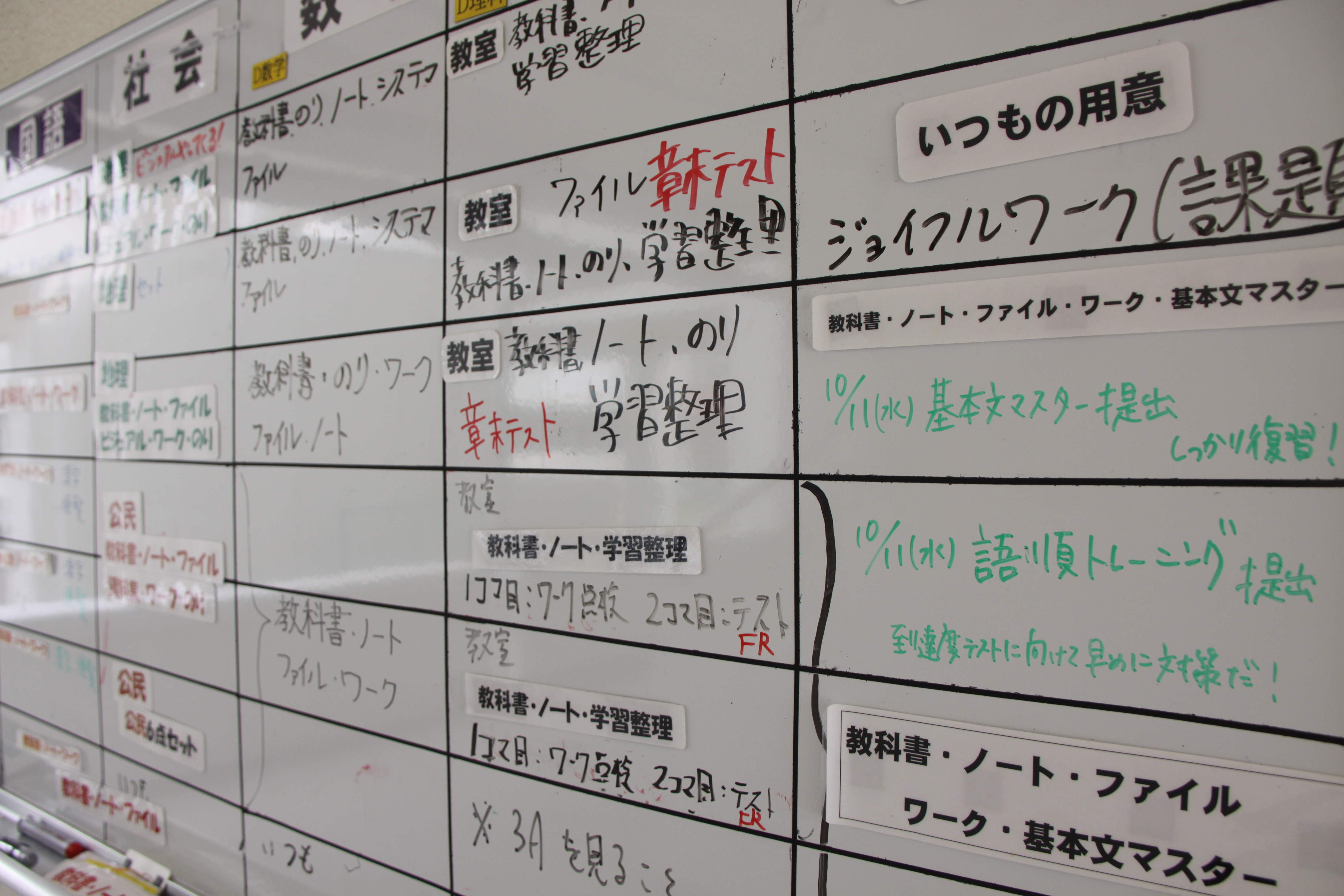
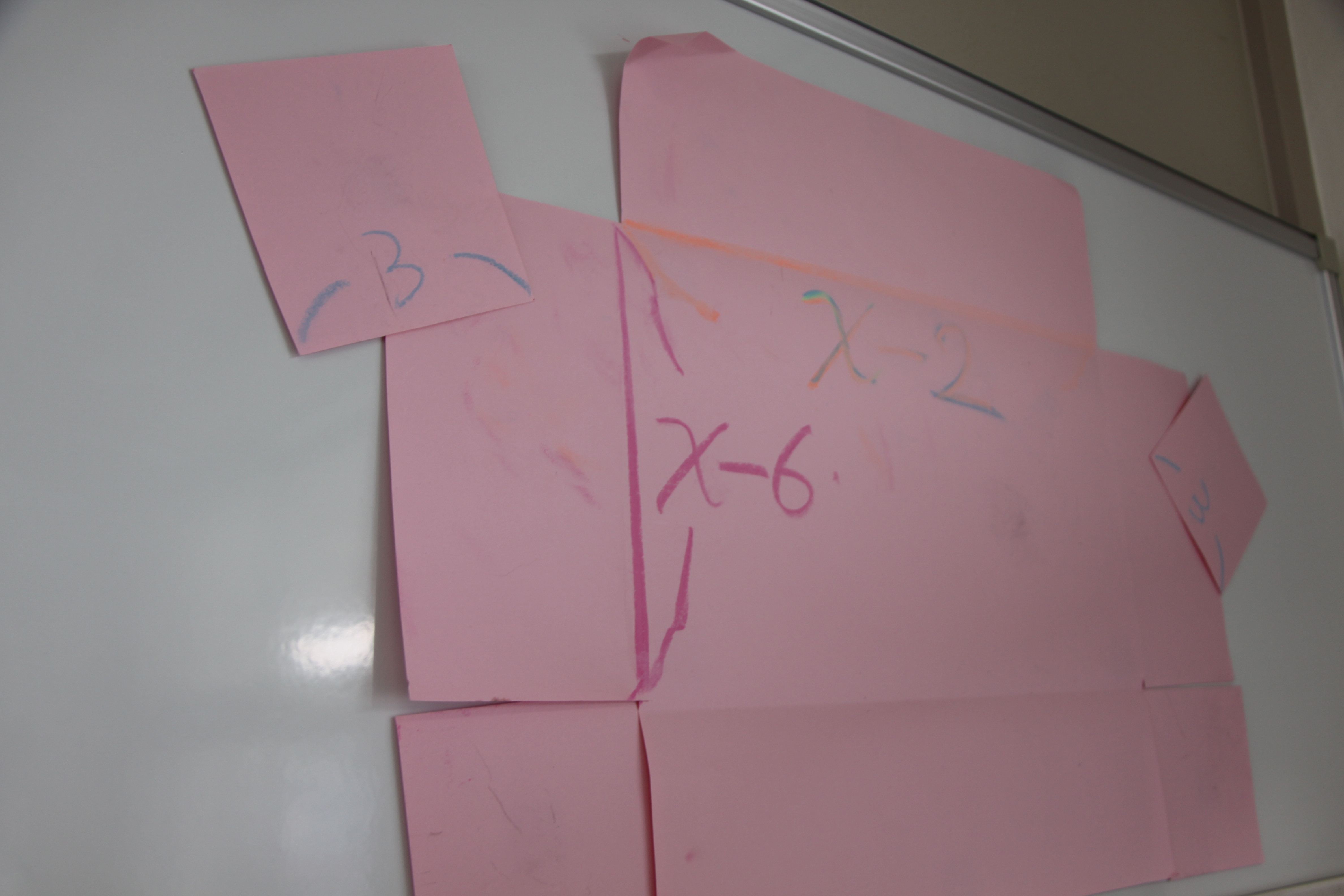
Just be yourself‚ there is no one better. TAYLOR SWIFT
(あなた自身でいるの、あなた自身よりも良い人なんていない)
◎ひとのあいだ(10/11)
連休中に観た映画について、3年生の生徒に少し話をしました。映画は、『虎ハ眠ラズ』『徘徊ママリン87歳の夏』『私と部落とハンセン病 林力99歳の遺言』『女になる』『福田村事件』です。差別や偏見、社会問題を扱ったものですが、映画の観方・とらえようは、人それぞれですが、ちなみに、僕は、「自分なら映画のどこにいるだろうか」と考えて観ることがあります。最近読んだ本の内容と重なるので少し紹介します。『少なくとも、通りいっぺんの「差別はなくなってほしいです。」とか、「平和な世の中が訪れるといいと思います」のような、自分は痛くもかゆくもないところからの意見を述べるよりは、はるかに意味のあることだと思う。そして「卑怯」でも「臆病」でもなく、むしろ勇気のいることだと思う。なぜなら、自分の身を切って、自分を射抜きながら考えているから。「もし自分がそこにいたら」を真剣に受けとめて、せいいっぱい想像して、いまの自分のありかたを正直に見つめているから。ふだん、ぼくらは、「自分のことは自分がいちばんわかっている」とぼんやり思っているけれど、こういうふうに少し深い問いをくぐりぬけると、あんがい自分って、自明の存在ではないかもしれないということに気づかされる。だから、自分のことを深く理解するためにも、自分に大事な問いを投げかけることが大事なんだと思う。そういう投げかけをしてはじめて、人はほかの人と「ともに生きる」用意ができるのではないだろうか。』(『ヘイトをのりこえる教室 ともに生きるためのレッスン 風巻浩・金迅野 著 より)

◎ひな中の風
~TA PATHEMATA MATHEMATA〈受苦せしものは学びたり〉



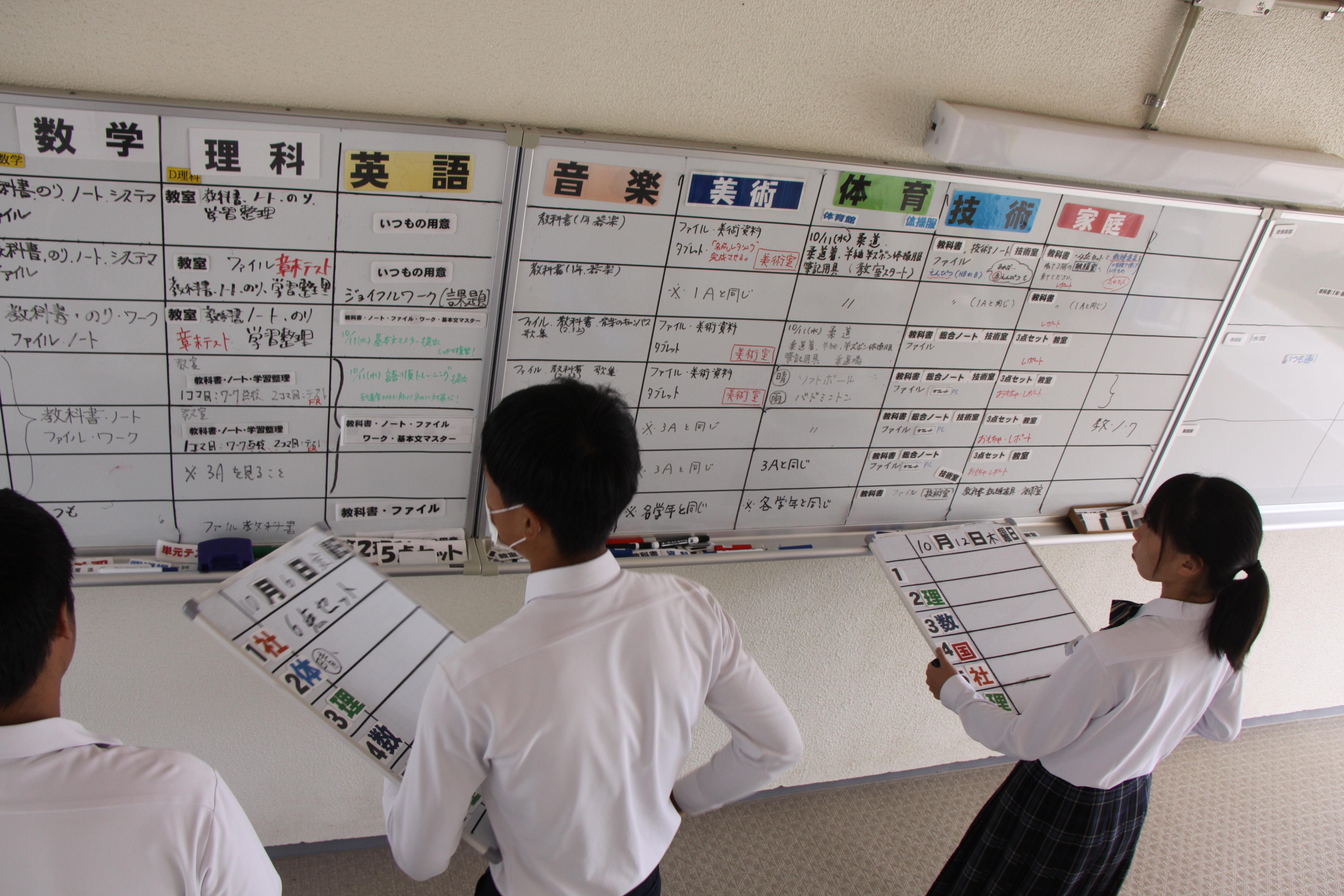

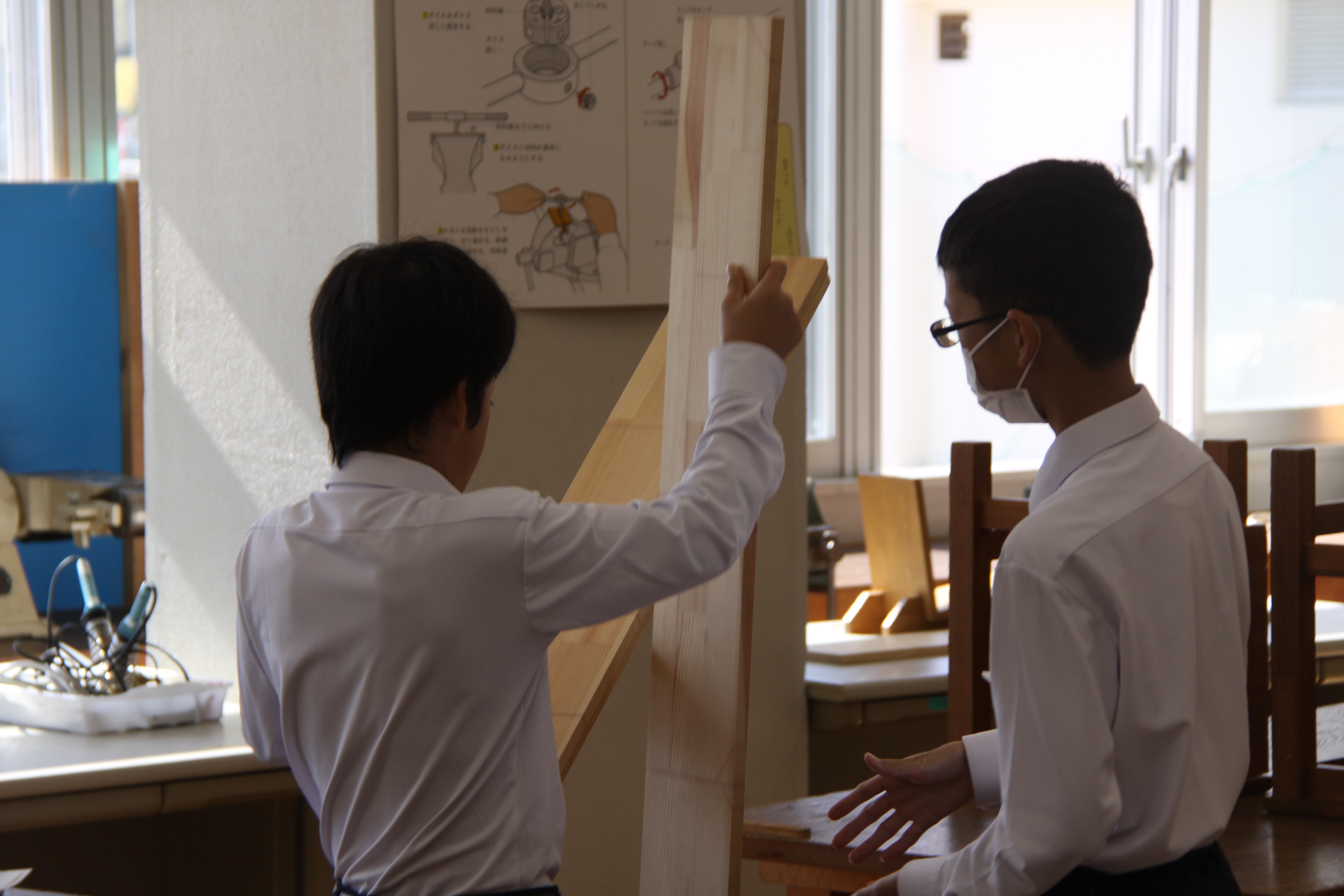



◎ひな中チャレンジ企画
ひな中のちからは、社会をつくるちから
赤い羽根街頭募金ボランティアを募る(10/11~)
赤い羽共同募金は、社会の変化のなか、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する「じぶんの町を良くするしくみ」として取り組まれています。
◆みなさんが住まわれている地域でも募金等をされておられると思いますが、中学校でも職員室入り口に募金箱を設置していますので、お子さん便でご協力をお願いします。ま
た、募金された方で「赤い羽根」が必要な方は教頭まで申し出てくださいませ。
◆今年度、日生中学校では本活動の趣旨を大切にして、生徒会を中心に街頭活動への参加をさせていただきます。
| (1)日 時:10/30(月)15:45~16:30 11/16(木)16:35~17:10 *夕暮れが早くなっているので、帰宅時間も考慮して申込みましょう。 (2)活動内容:社会福祉協議会の皆さんと、パオーネ前で赤い羽根街頭募金活動を行います。 貴重なボランティア活動の機会です。 *福祉、地域づくりなどの進路を目指している人はぜひ参加をしてみよう! (3)申 込:10/19(木)17時締切 *下記の申込用紙に記入して、生徒会中央役員へ提出してください。 *両日とも10名程度を募ります。(希望者が多い場合は、抽選とします。) *当日は現地集合・現地解散となります |
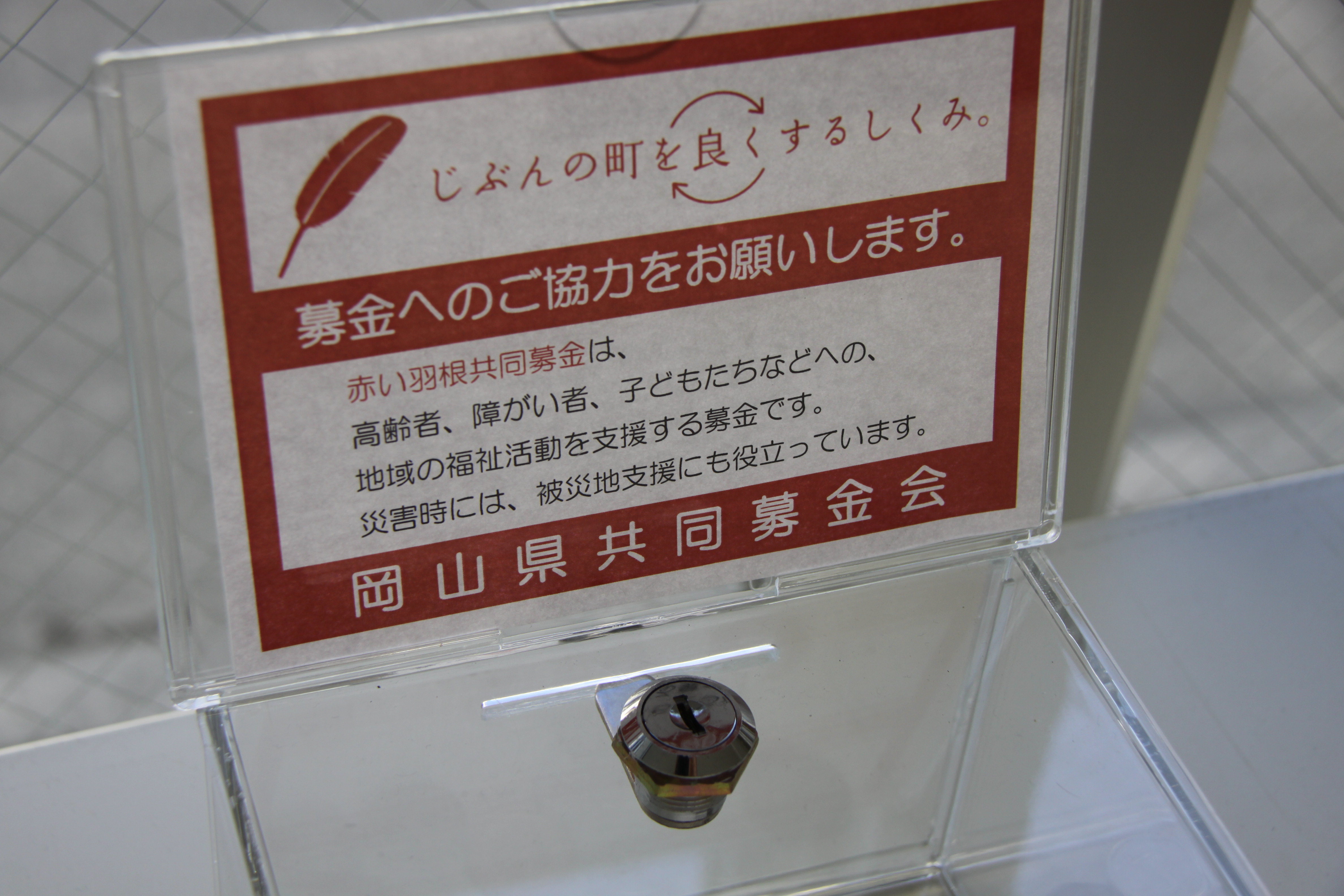
◎ひな中チャレンジ企画
楽しく(*^o^*) 英会話を通して コミュニケーション力を伸ばしましょう。
今、みなさんは、夢・目標の実現に向けて、授業や学校行事において本当に積極的に取り組めています。そんな皆さんに、さらにチャレンジできる機会を提供したいと思い、前回に引き続いて、放課後の英会話教室を企画しました。星輝祭文化の部を終え、放課後の時間を充実させましょう。
夢・目標の実現に英語が必要な人、英会話や発展学習に関心のある人は、参加しましょう。
1 第2・3回開催日時・場所(1日、両日でもOK)
| 10月17日(火) |
16:30~17:10 |
多目的1教室 |
| 10月24日(火) |
16:30~17:10 | 多目的1教室 |
2 申し込み・参加の注意事項: ○主体的に申し込みすること。〇継続的に参加することが望ましい。単日のみの参加でも可。〇申込書は10/16(月)〆
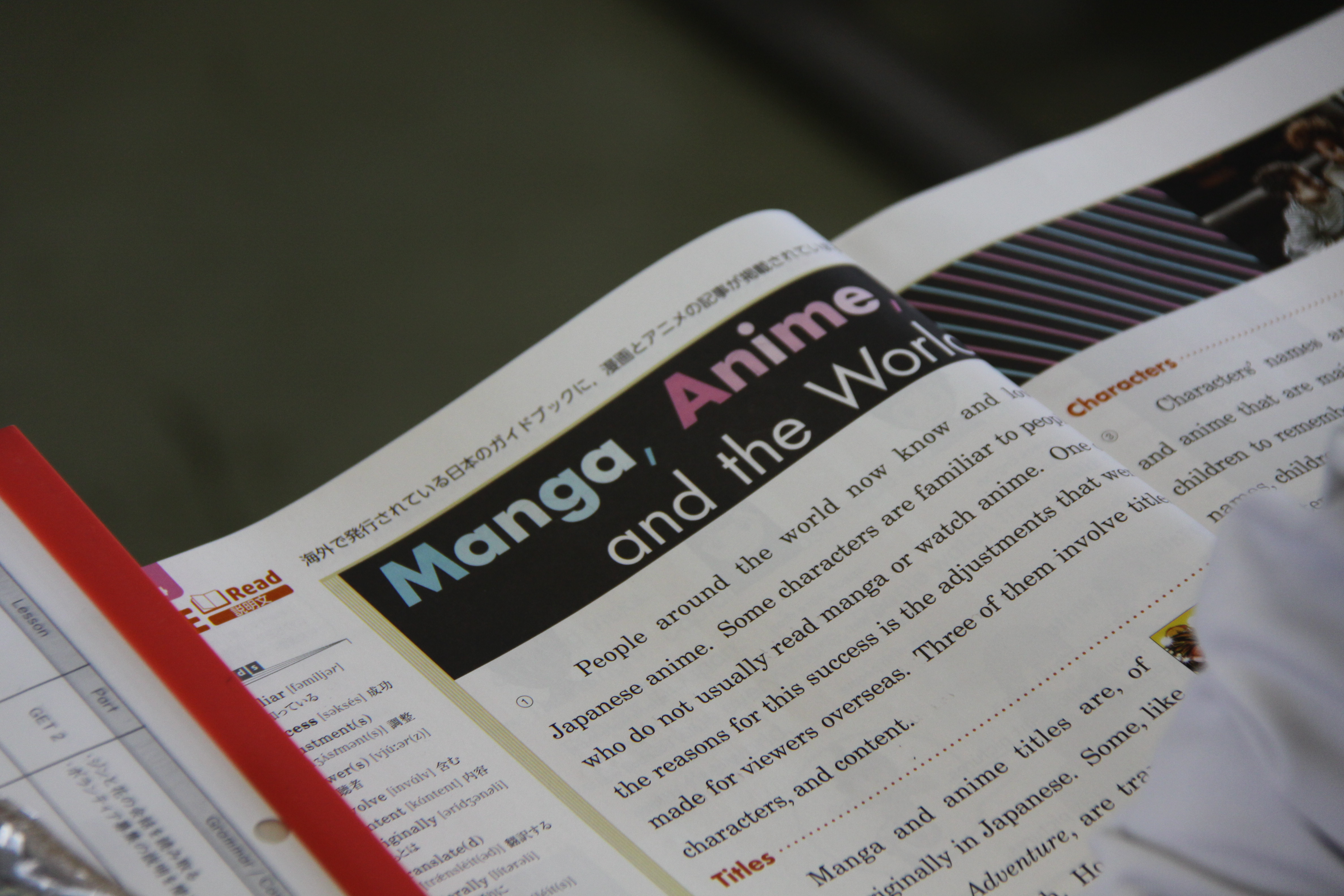


Let’s have fun and practice English!
◎私たちのはじまりの風景3
~わかるかな?ここってどこでしょう。(10/9)



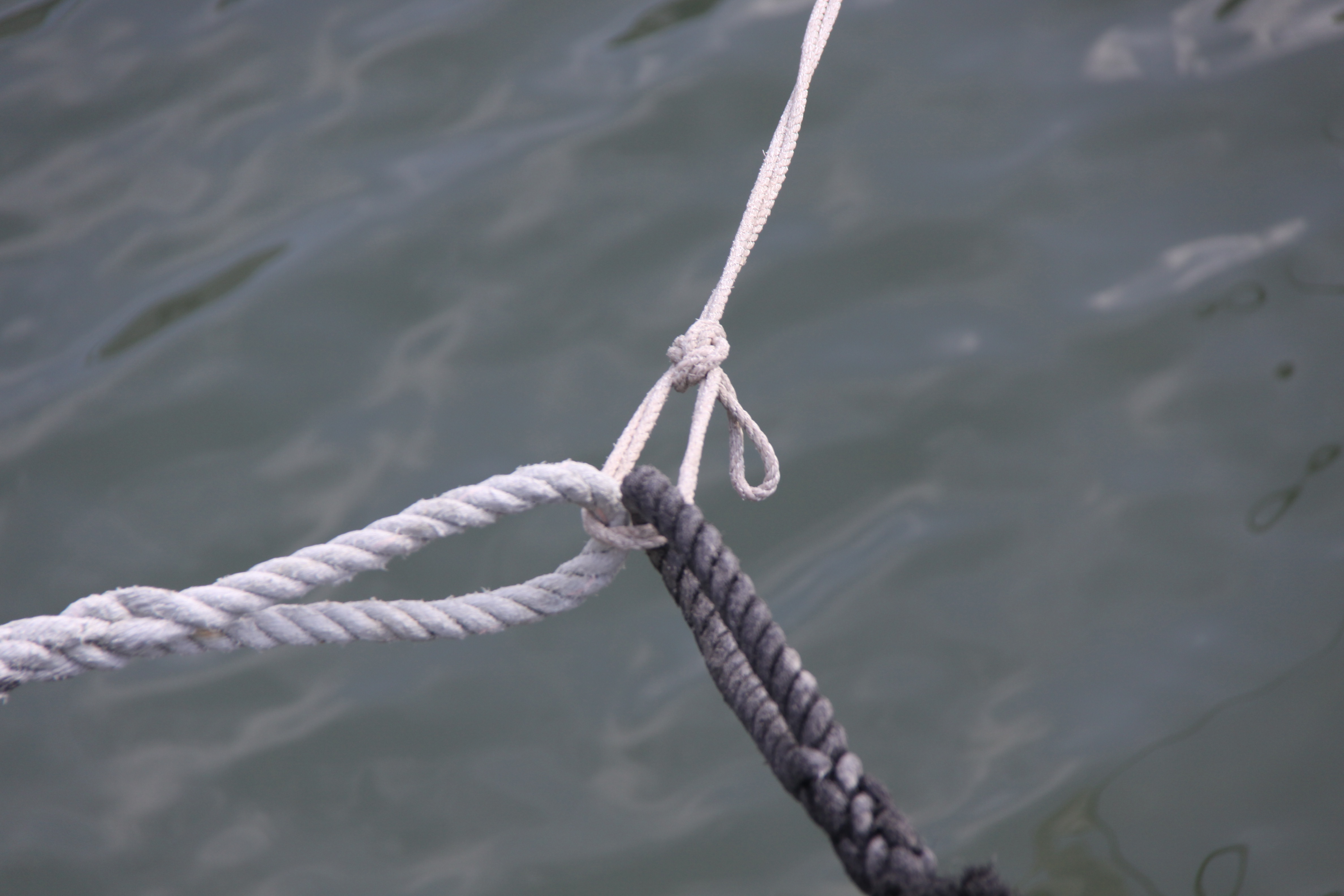





◎「ようい はじめ。」
問題:今から・これから・私たちのひな中

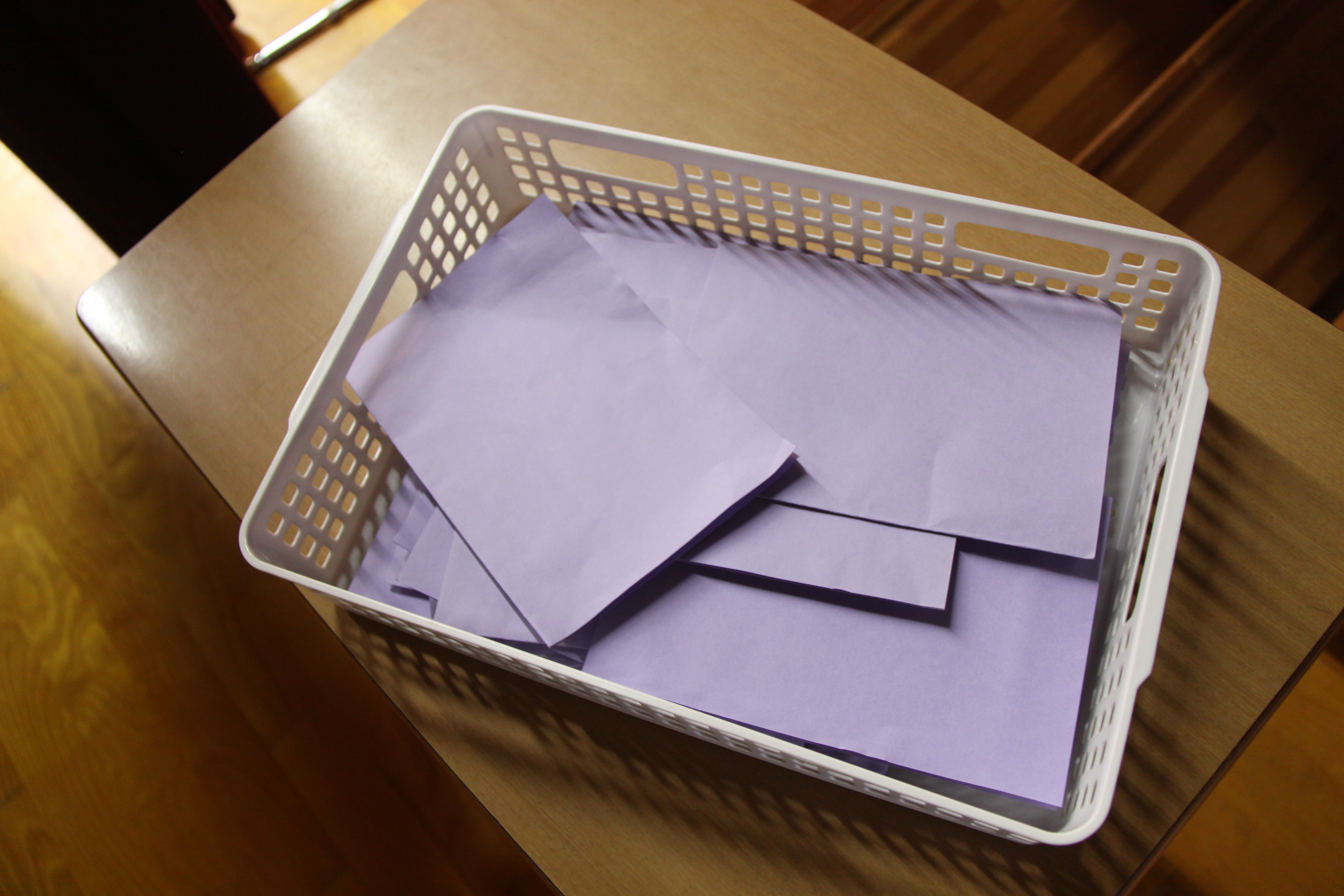


◎輪 ~星に輝け☆~
みんなの想い(10/7:2023星輝祭文化の部)






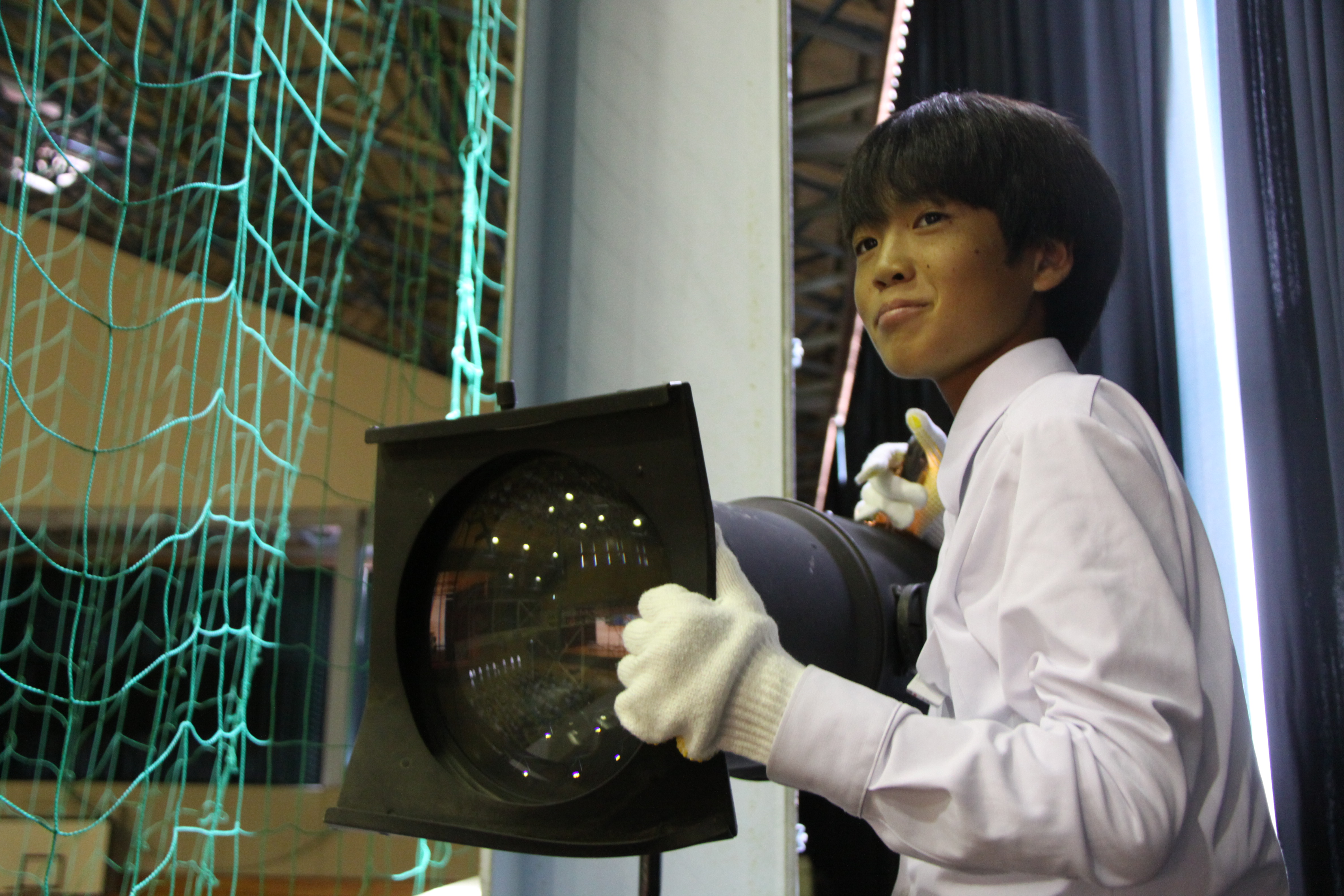








◎わたしが弱い時にこそ わたしは強い (明日は、星輝祭文化の部)
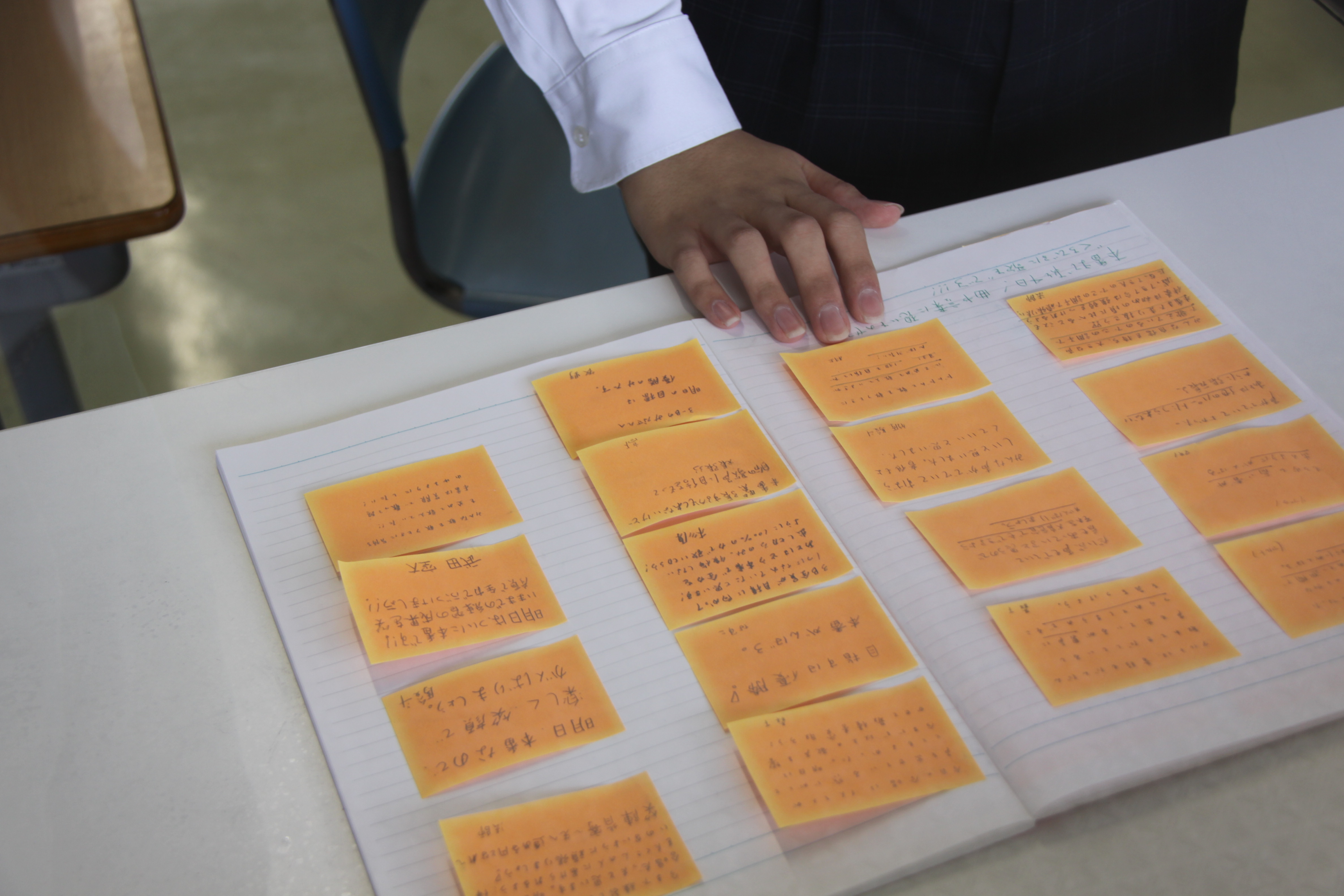
◎ひな中の風~~Everybody Loves Somebody(10/6)









◎生徒総会にむけて クラス議案検討(10/6)
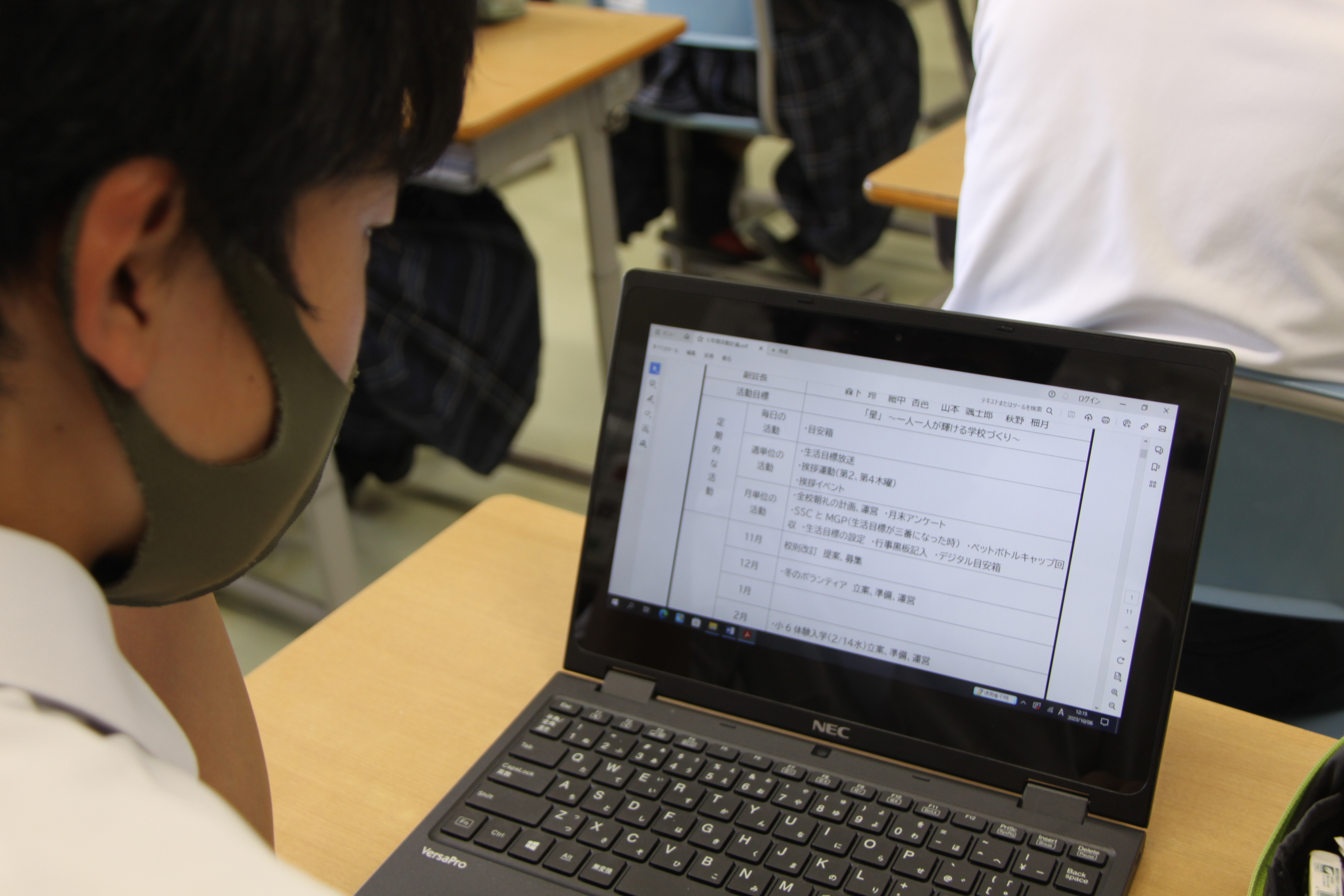
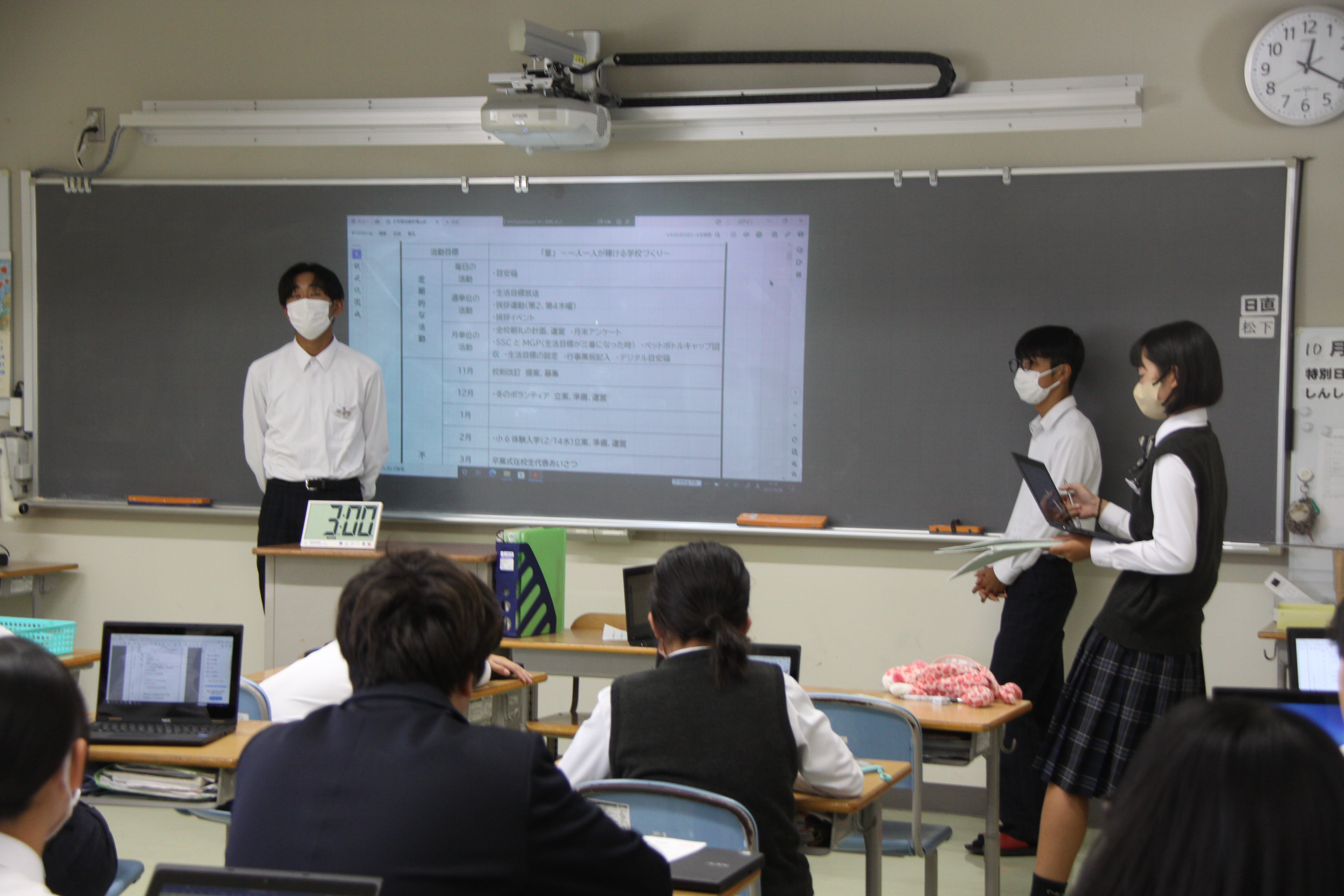

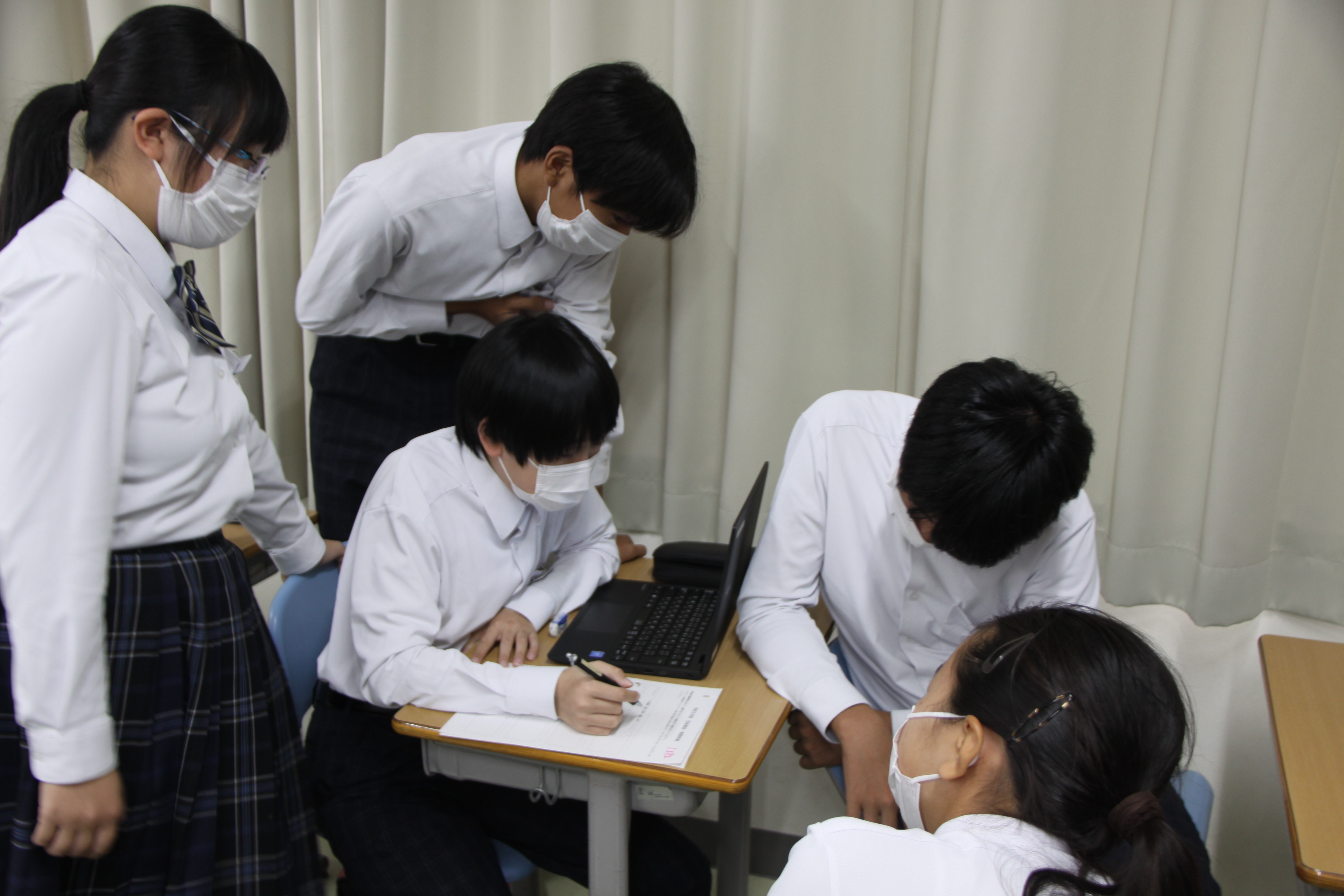

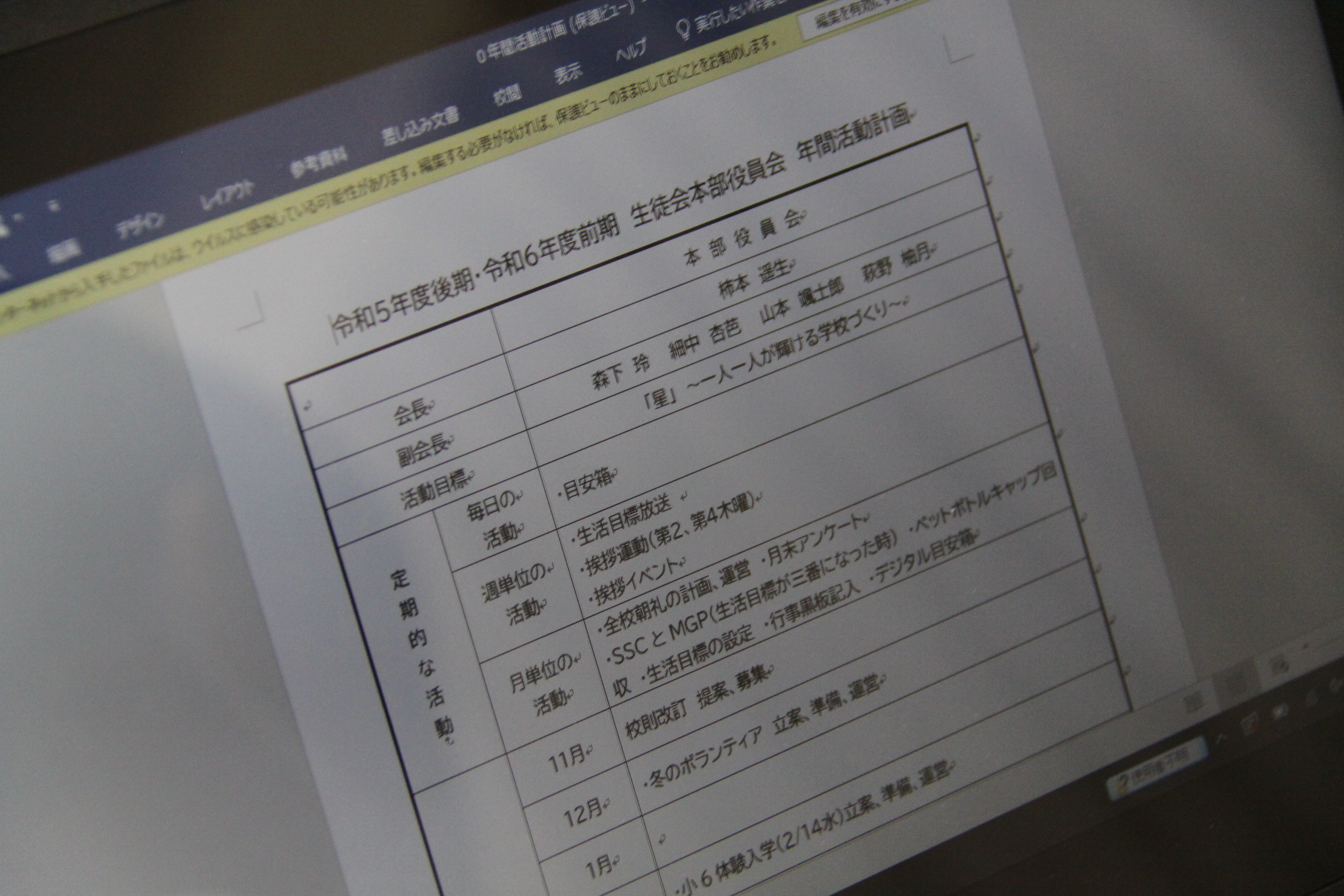
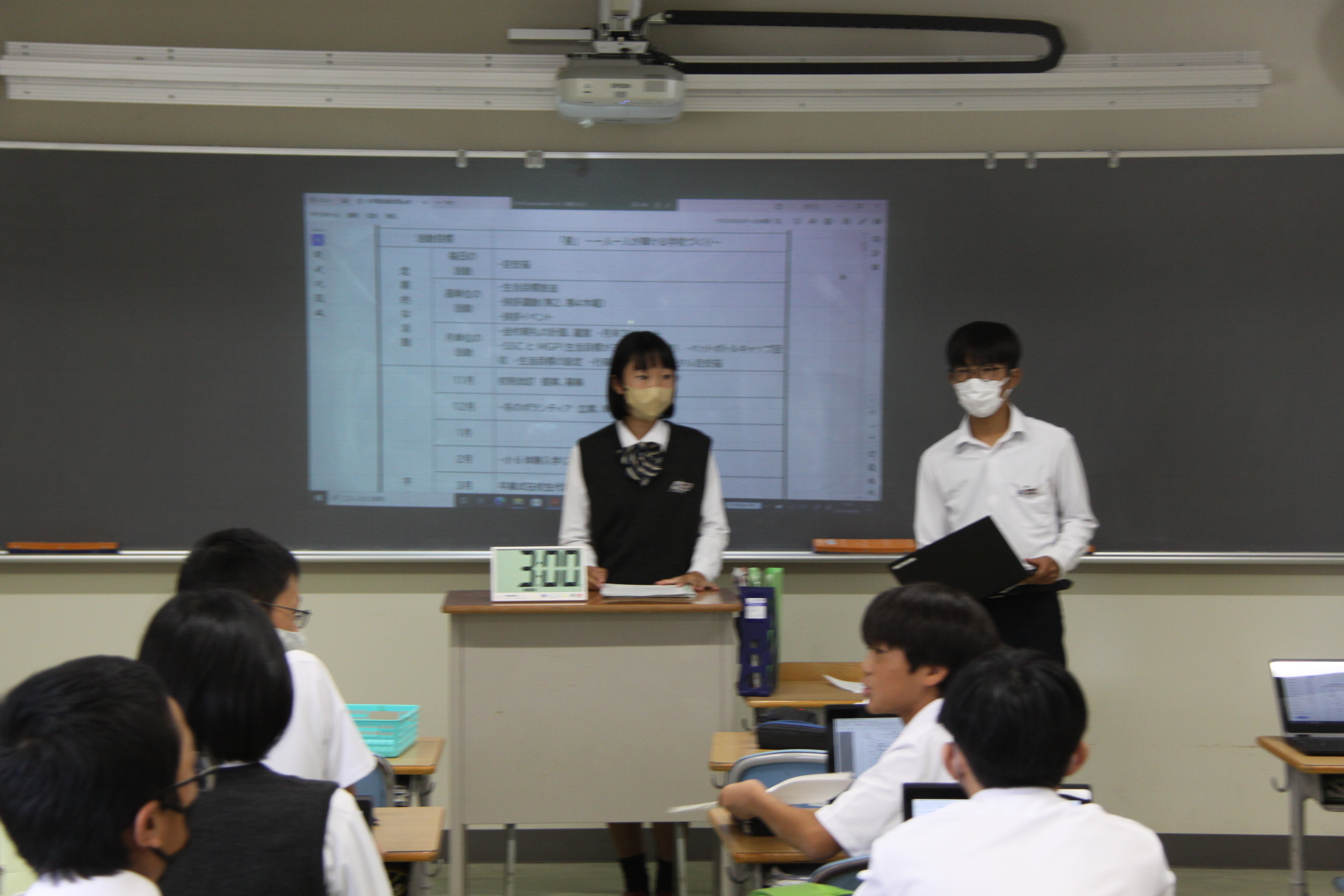
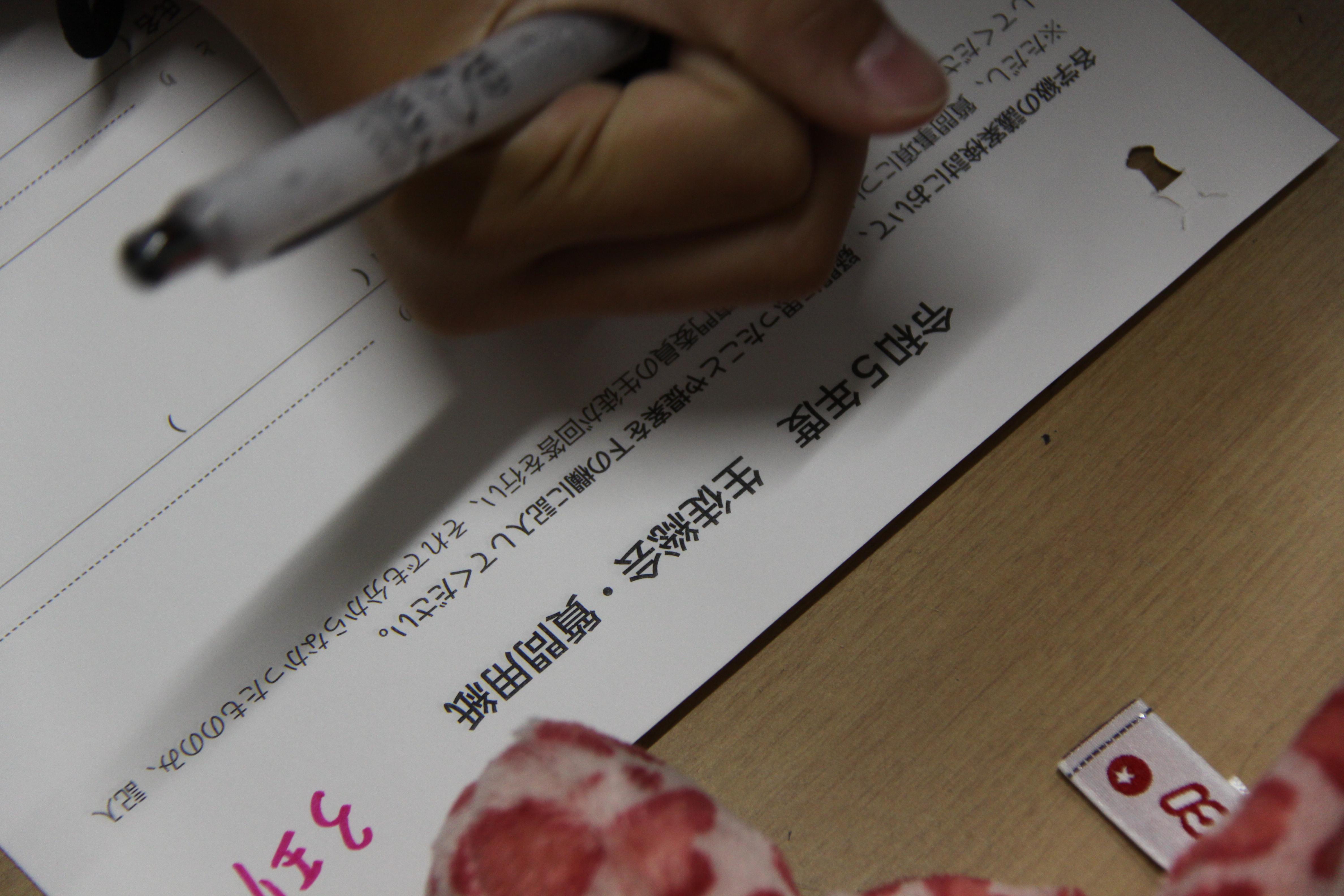

The era we are living in today is a dream coming true. Walt Disney
(今、私たちは夢が叶えられる世界に生きている。)
◎がむしゃらに生きて誰が笑う?
…一生懸命はかっこいい。(10/5)

◎声に身をまかせ 頭の中をからっぽにするだけ 目を閉じれば 胸の中に映る 懐かしい思い出や あなたとの毎日 本当のことは歌の中にある♪
(仲間と合唱練習 10/5)


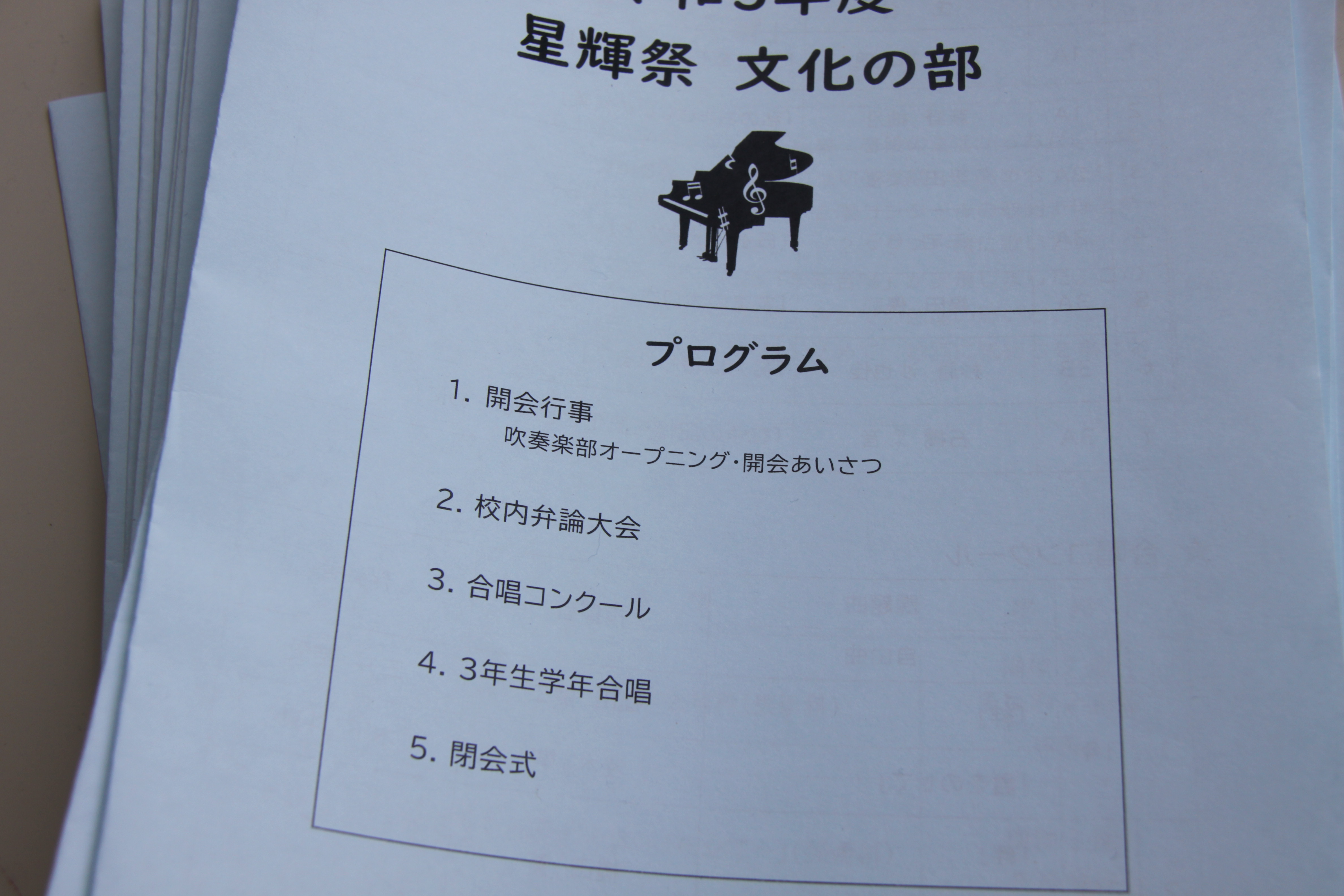






◎私たちのはじまりの風景2
~わかるかな?ここってどこでしょう。(10/5)









◎ひな中の風~~自律した学習者へ
〈学習する意味や楽しさを味わうということ〉






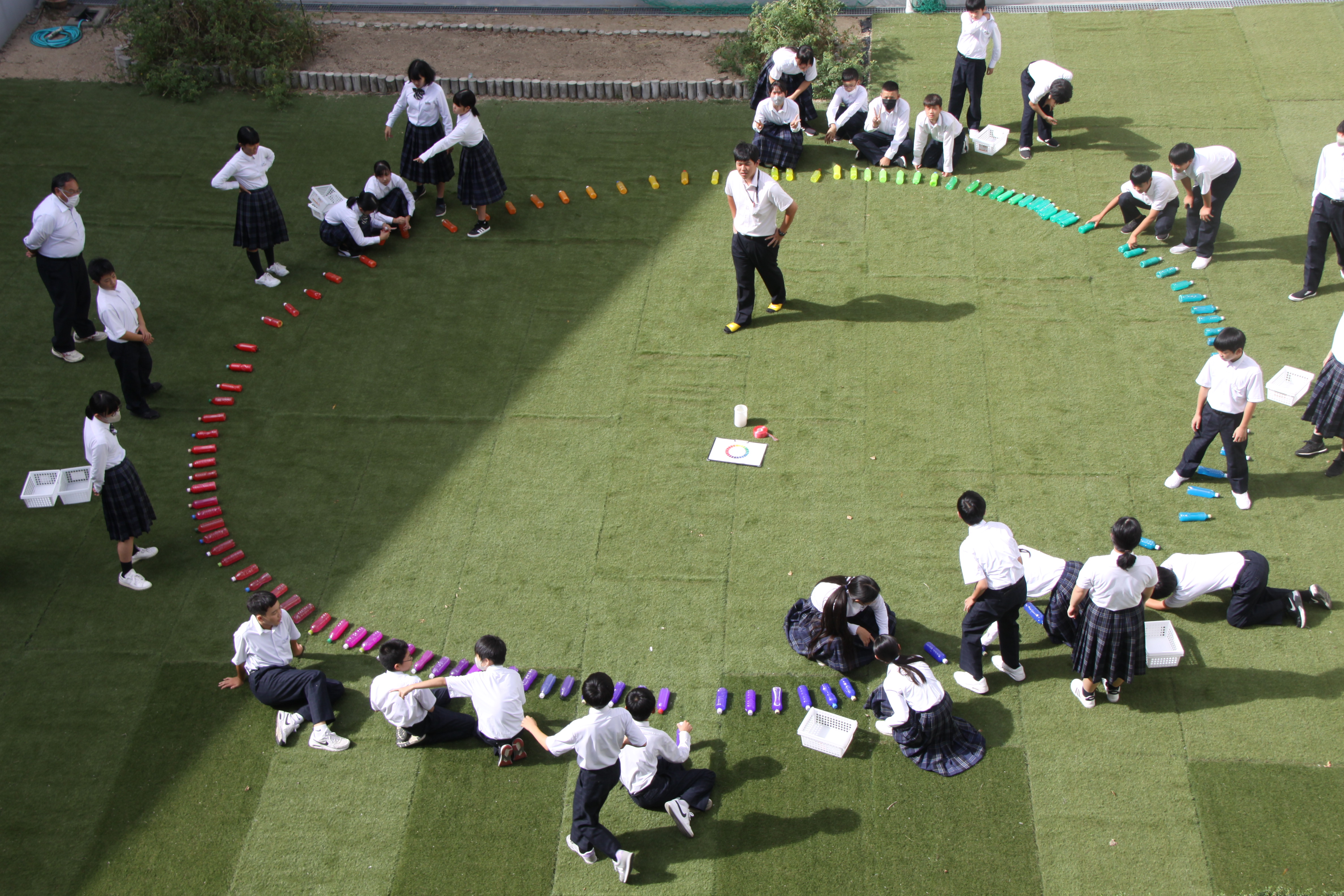
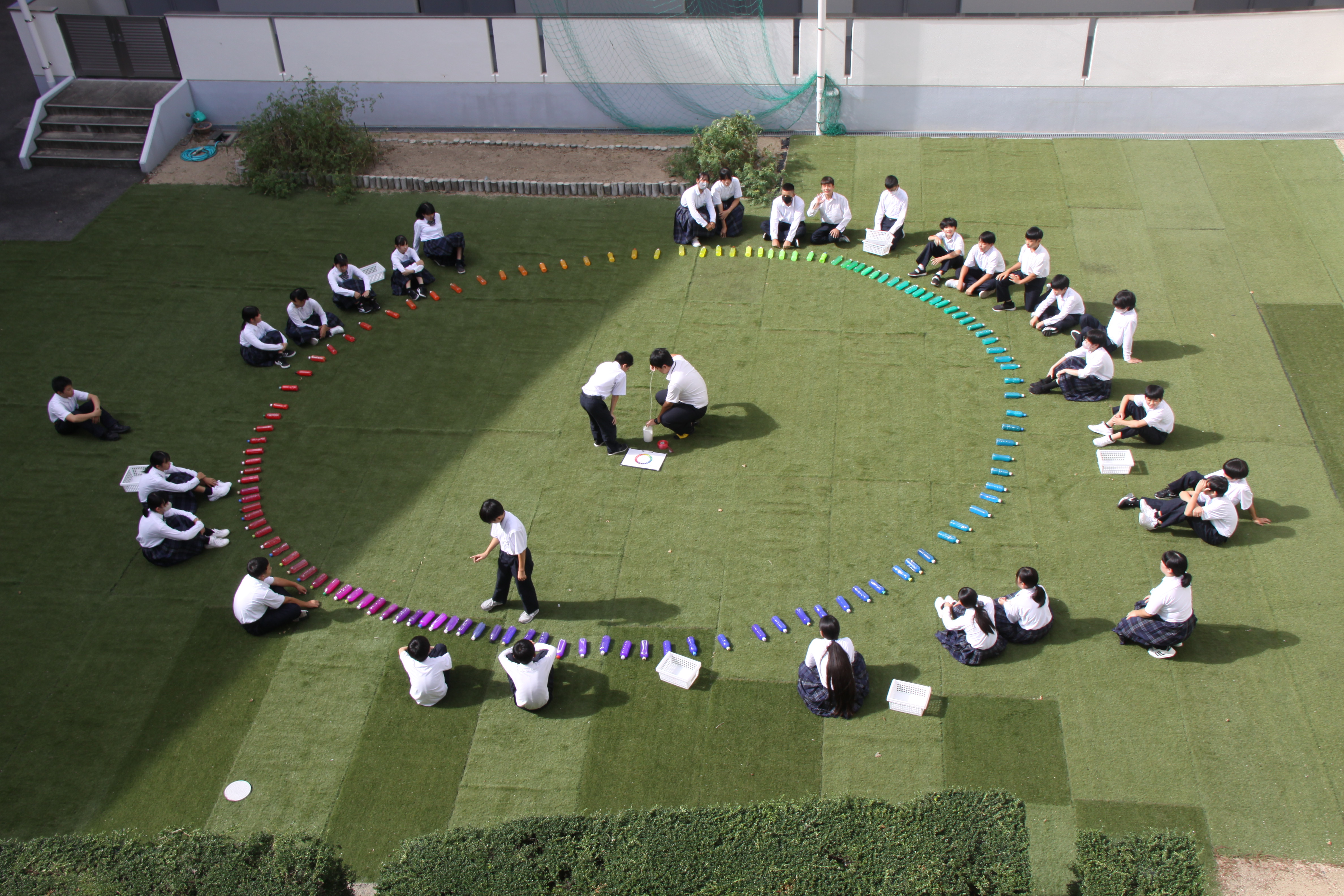

〈10/4 美術の様子〉
◎ひな中の風~~自律した学習者へ
〈ともに学び合う仲間として〉
グループ学習 は、授業者が生徒同士の時間時間・空間を意図的に設定することにより、子ども同士の学び合いの力を引き出すことをねらいます。 教育は、「自ら学んでいく子ども」を育てる営みですから、まさに日頃の 私たち授業者の働きかけの真価が問われる場とも言えます。グループワークで学べることは、①自分の意見を言ったり人の話を聞いたりするコミュニケーション能力が高まります。②論理的に思考し、説明する力が身につきます。③チームでの課題解決プロセスを学べます。④意見をわかりやすく伝えるプレゼン能力が高まります。(詳しくは、学びの共同体等を参照)


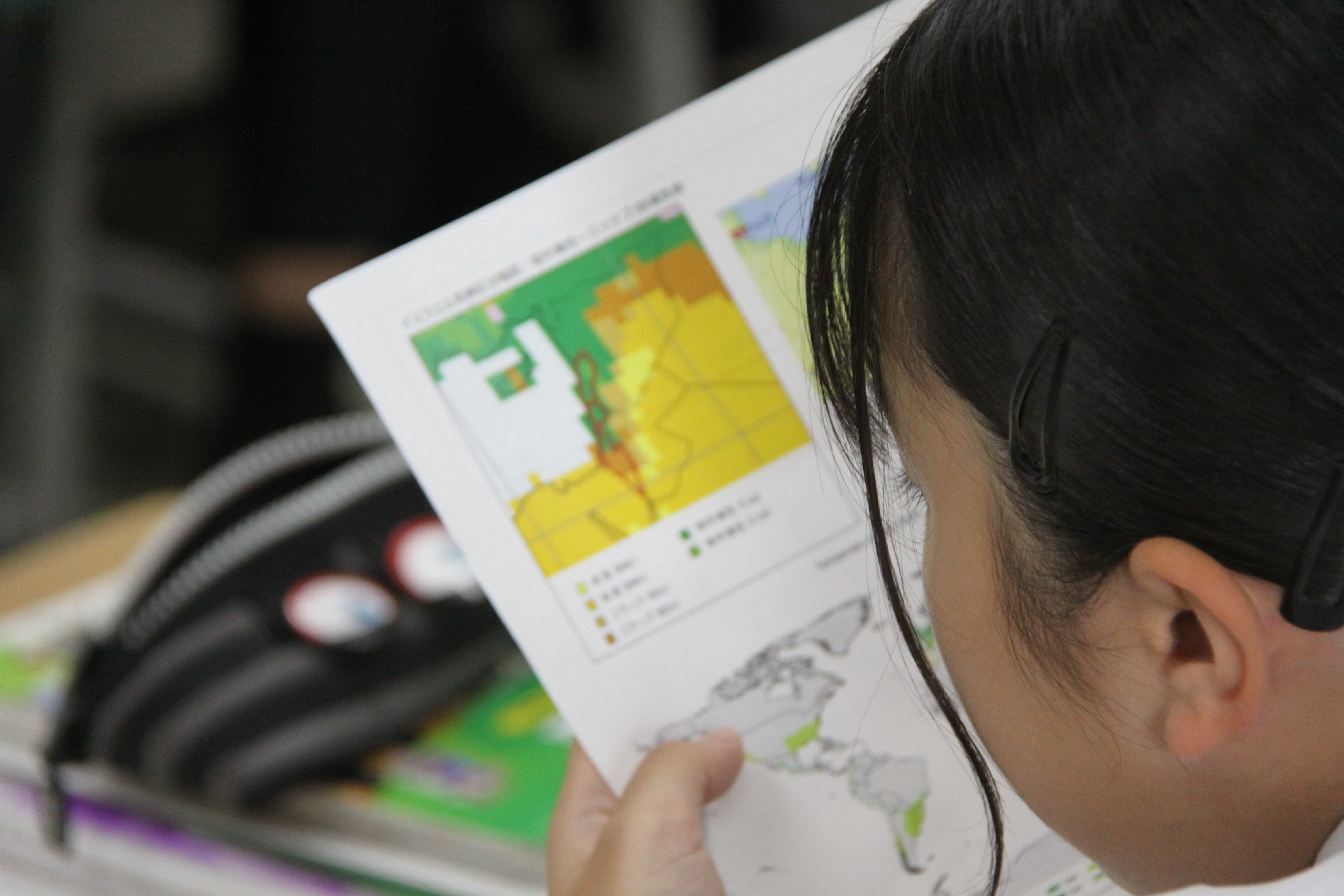


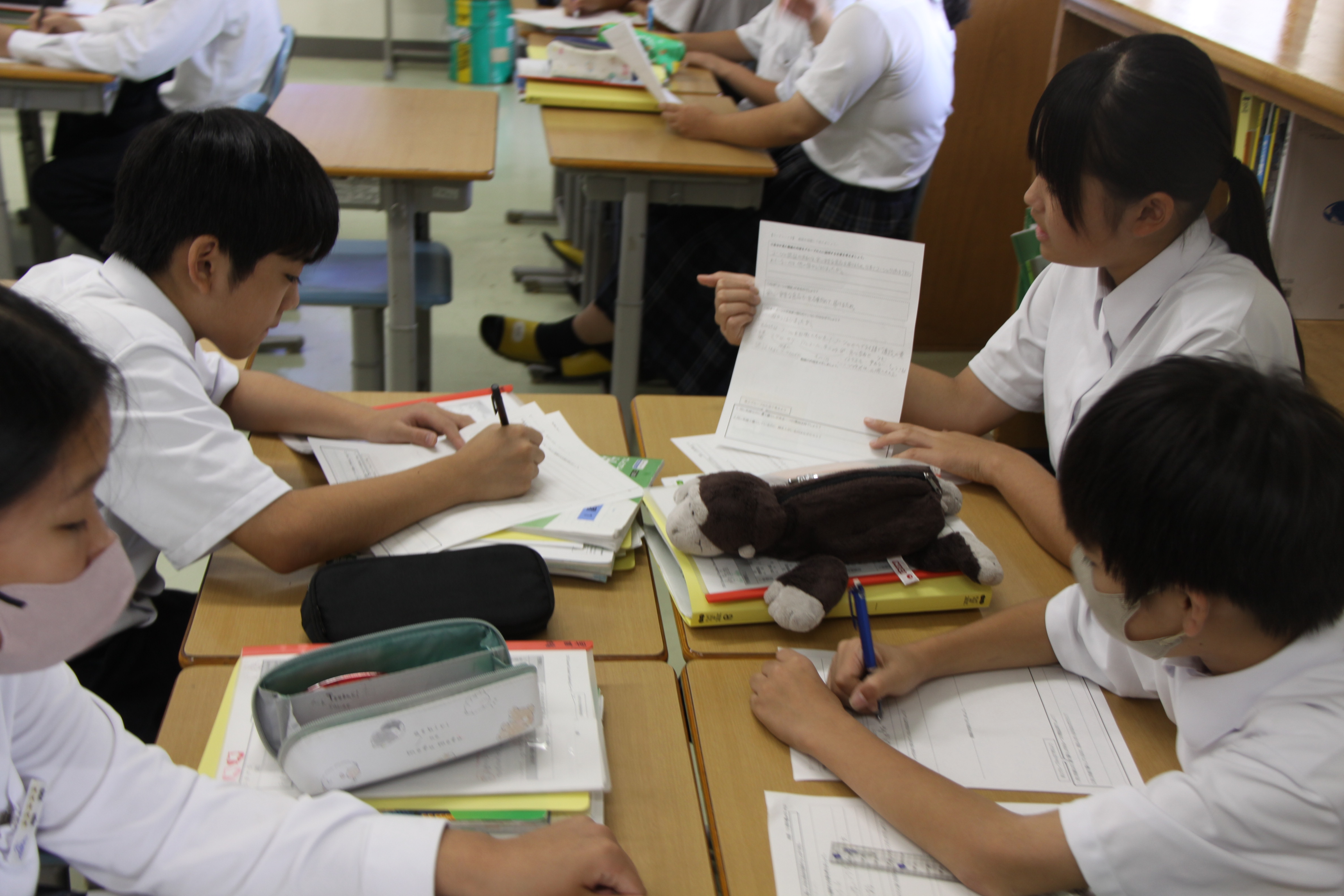
〈10/4 社会科の様子〉
I like friends who have independent minds because they tend to make you see problems from all angles.
Nelson Mandela (独立した考えを持つ友人は、問題をあらゆる角度から見ることができるようになる傾向があるので、私は好きです。)
◎ひな中の風~~「毎日のあたりまえ」を大切にする(10/4)
体育館で朝練習を終えたバスケットボール部。みんなを待って、係の生徒がしっかりと施錠。

A man does what he must – in spite of personal consequences‚ in spite of obstacles and dangers‚ and pressures – and that is the basis of all human morality. John F. Kennedy
(やらねばならないことをやる。個人的な不利益があろうとも、障害や危険や圧力があろうとも。そしてそれが人間倫理の基礎なのだ。)
◎出会いに心をこめて 書をすてよ 街に出よう
〈10/4 2年生チャレンジワーク事前学習〉
職場体験学習でお世話になる事業所へ、生徒自身が電話をかけさせていただきました。


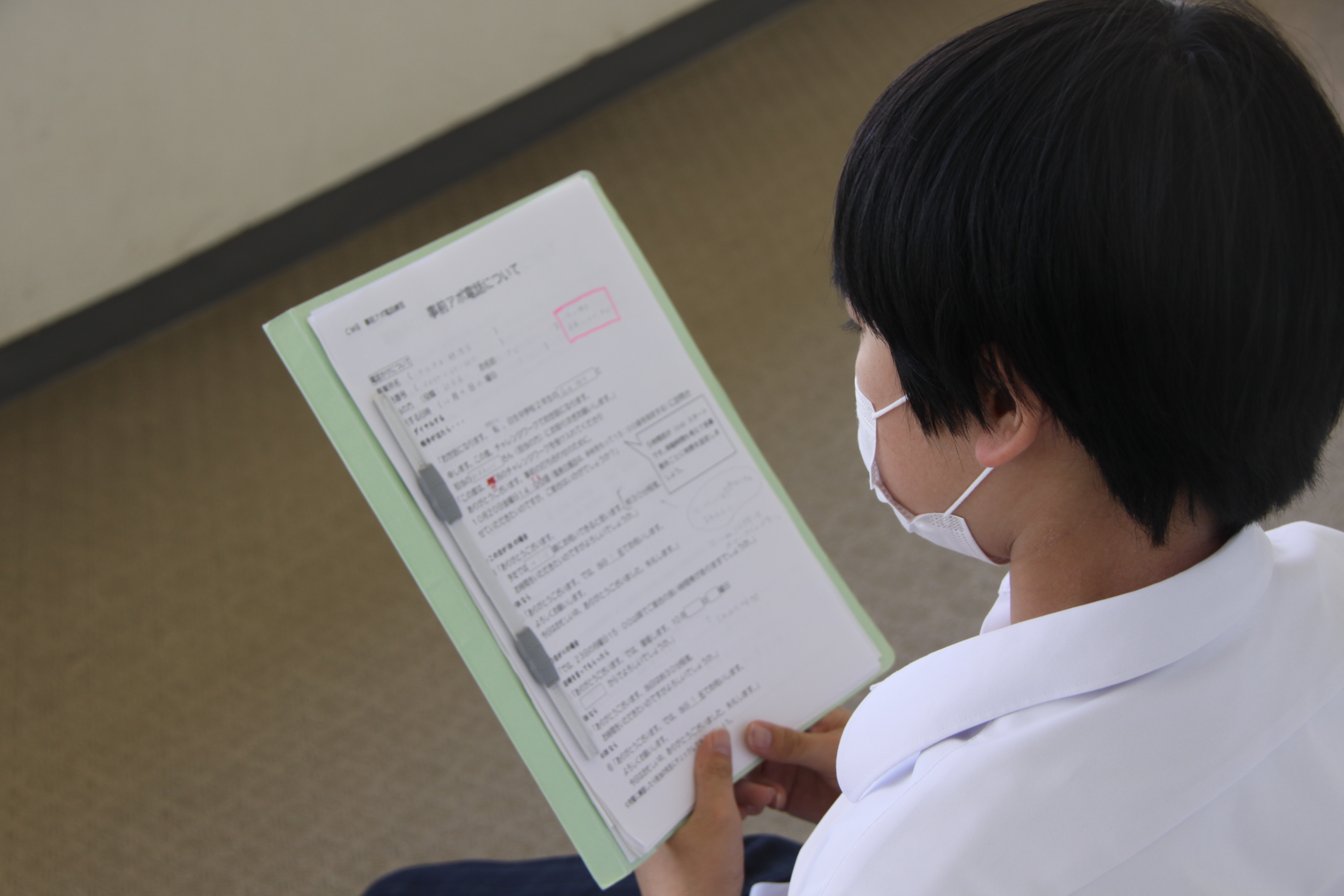
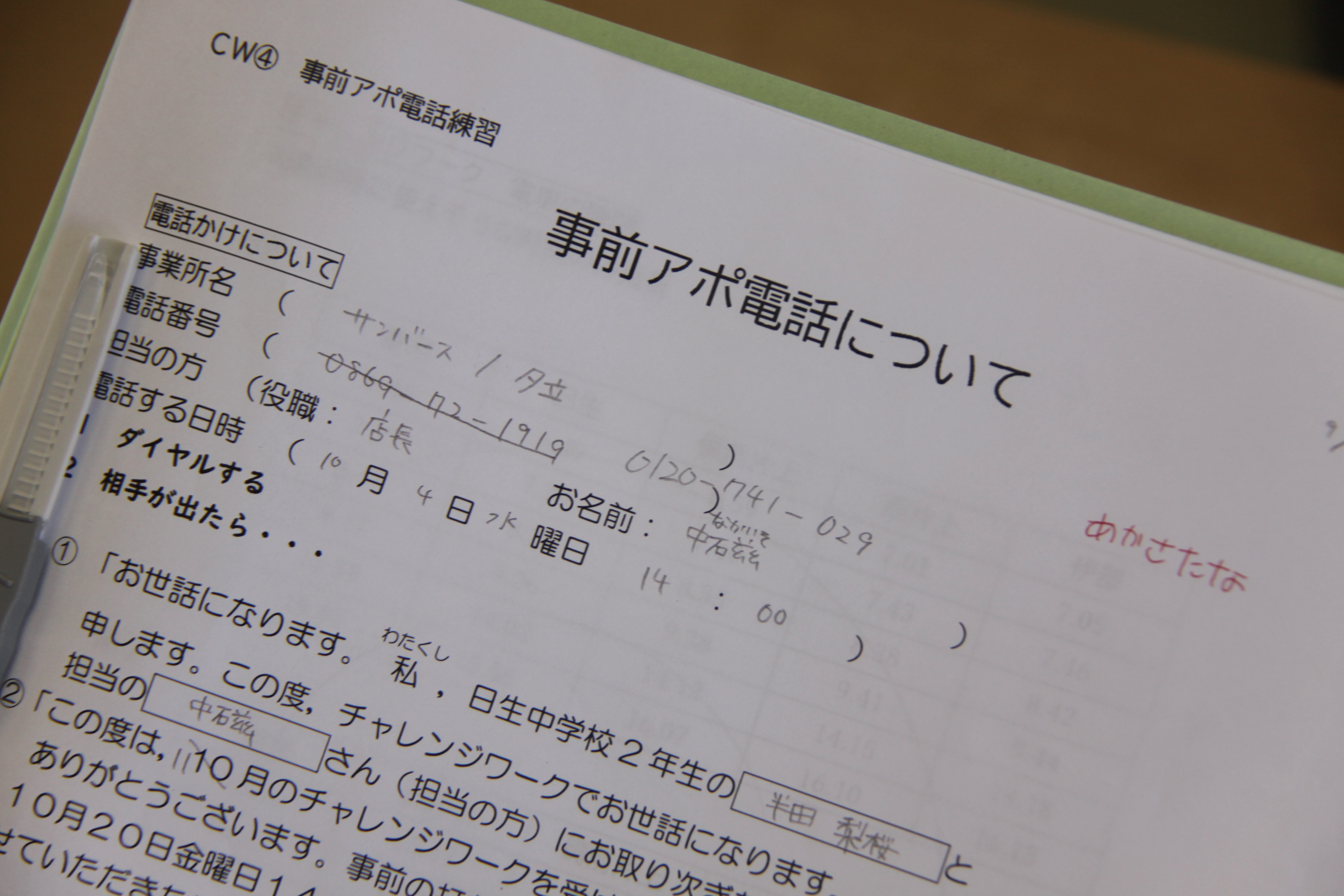



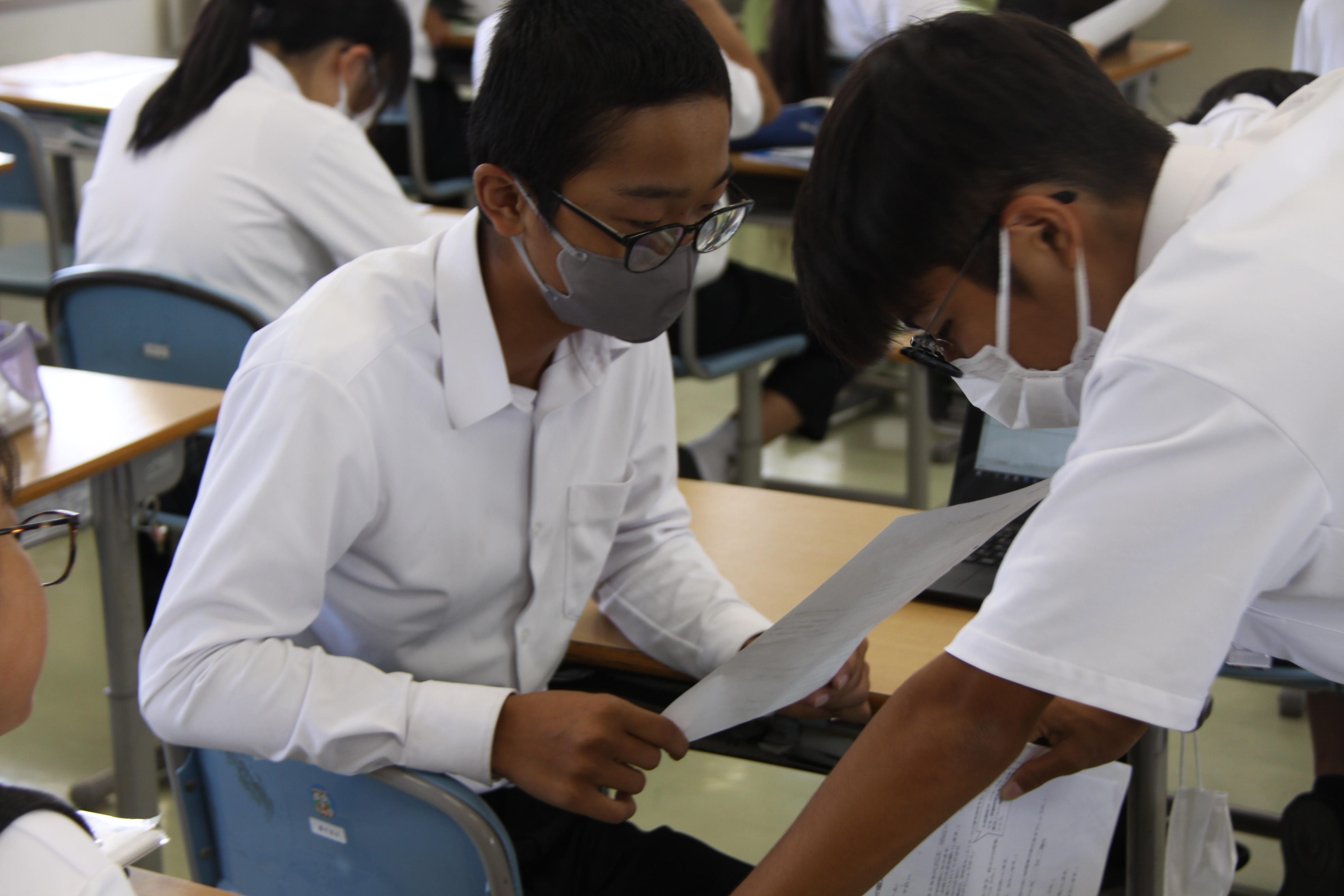
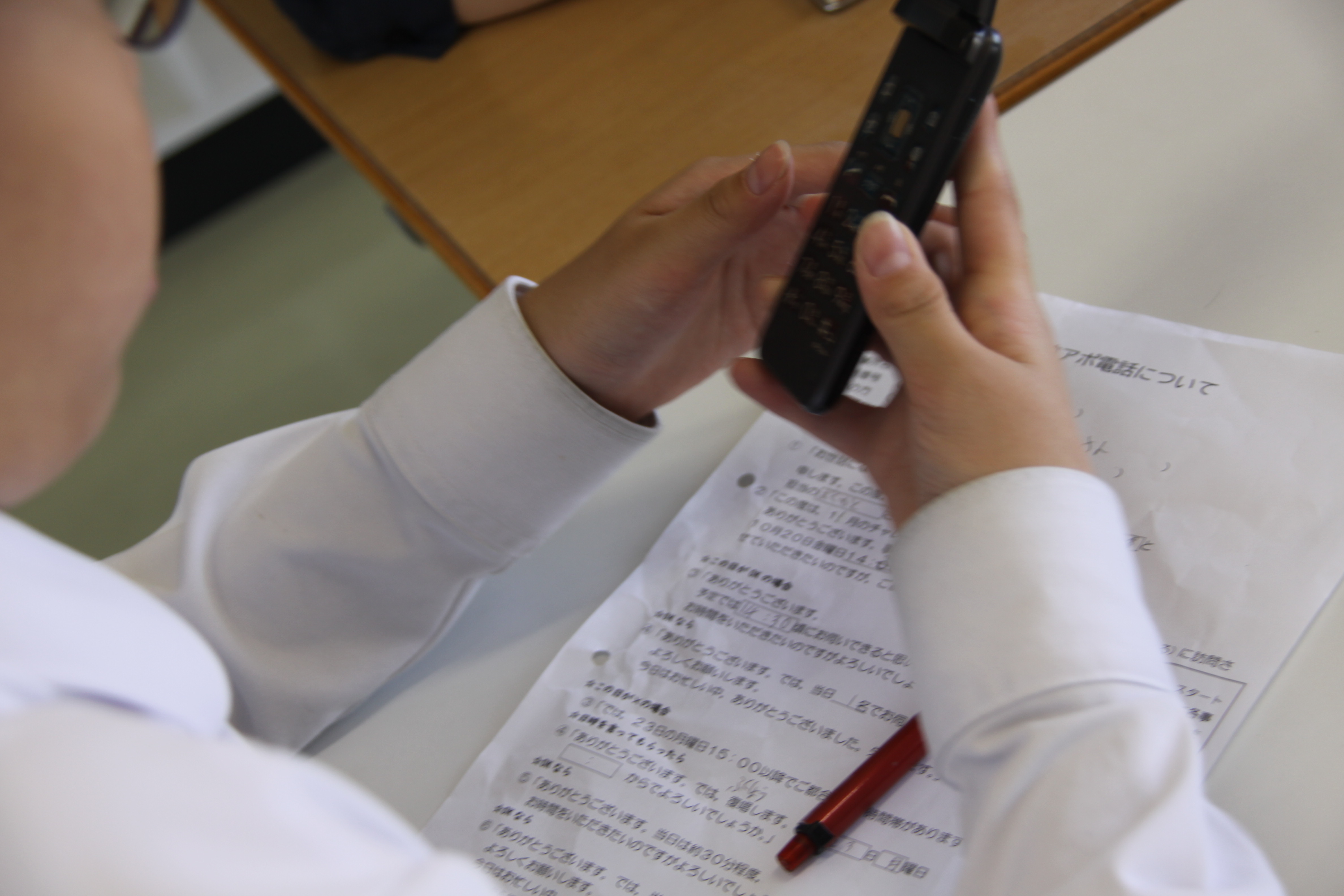
職場体験では、生徒が直接働く人と接することにより、また、実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義や働くことの意義を理解し、生きることの尊さを実感させることが求められています。また、生徒が主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など培うことのできる教育活動として、重要な意味を持っています。
望ましい勤労観、職業観の育成や、自己の将来に夢や希望を抱き、その実現を目指す意欲の高揚を図る教育は、これまでも様々な形で取り組んできましたが、より一層大切になってきています。職場体験は、こうした課題の解決に向けて、体験を重視した教育の改善・充実を図る取組の一環として大きな役割を担うものです。特に、生徒の進路意識の未成熟や勤労観、職業観の未発達が大きな課題となっている今日、生徒が実際的な知識や技術・技能に触れることを通して、学ぶことの意義を理解し主体的に進路を選択決定する態度や意志、意欲など、培うことのできる教育活動として重要な意味を持っています。
このような職業にかかわる体験は、ともすれば「働くこと」と疎遠になりがちであった学校教育の在り方を見直し、今、教育に求められている学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感させる具体的な実践の場でとなります。さらに、本校では、社会的問題である「ホームレス問題学習」にも取り組み、キャリア教育を積み重ねていきます。
また、中学校における職場体験は、小学校での街探検、職場見学等から、高等学校でのインターンシップ等へと体験活動を系統的につなげていく意味において、重要な役割を持っており、日生中学校チャレンジワークも、事業所や地域との深い連携・協力関係のもとに、生きた学びの場を構築していくという観点に立って、これからも地域と共にある学校の具現化に取り組んでいきたいと思います。
◎"In any project‚ I am ready to take on the thankless job‚ knowing well that every contribution matters for the overall success."(新旧生徒会中央役員)

◎確かな人権感覚が大切。(10/3)

日生中学校には、生徒会や専門委員会がつくって掲示物、ポスターや、みんなが授業で制作した作品がたくさん掲示されています。そのような学校で大切にしている展示物などの公共物について知っておいてほしいことがあります。小さなことかもしれないませんが、とても重要なことです。
自分が作ったり書いたりしたモノがいたずらされたりしたら、それは人の心を傷つける重大な人権侵害です。では、自分ではなく、芸能人やアイドルが写っているポスターでも、押しピンで鼻や目に穴を開けたり、落顔(らくがお)をしたら?どうでしょう。(アイドルが近くにいたらきっと怒り、悲しむでしょうが。近くにいないからよいという問題ではありませんね)。大きな問題があります。それを見た友達がいやな思いをしたり、落書きされたポスターをみて、笑ったりして新たな偏見やまちがった意識を植え付けられることで、差別を助長してしまうことにつながるからです。だから、お互いの人権を大切にするために、落書は決して許されるものではありません。日本でも「落書き」は、軽犯罪法や刑法(建造物等損壊罪、器物損壊罪)に基づき罰せられる犯罪です。また、落書きの内容が特定の個人を誹謗・中傷するものであれば、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。さらに公園や道路・学校にある物を傷つけたり汚したりしたりすると『刑法第261条(器物損壊罪)…3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料』『軽犯罪法第1条第33号…拘留又は科料』と規定されています。(科料とは『1、000円以上10、000円未満のお金を払うこと』です。払えなければ1日以上30日以下の期間、刑務所に留置される)
日生中学校では、多くの方に支えられて、豊かな掲示物があり、学校・学習環境を整えています。これからも、お互いの「人権」を尊重する学校生活を送っていきたいと思います。
◎ひな中のかぜ~~ 『軻親断機』こつこつこつこつ晩学習(10/3)
日生中学校は「晩学」を大切にしています。火・木曜日の帰りの会の前、15分間を利用して、基礎的な学習の定着を図るための自主学習に励んでいます。この日は、これまで取り組んでいた「四字熟語」の確認テストを行いました。

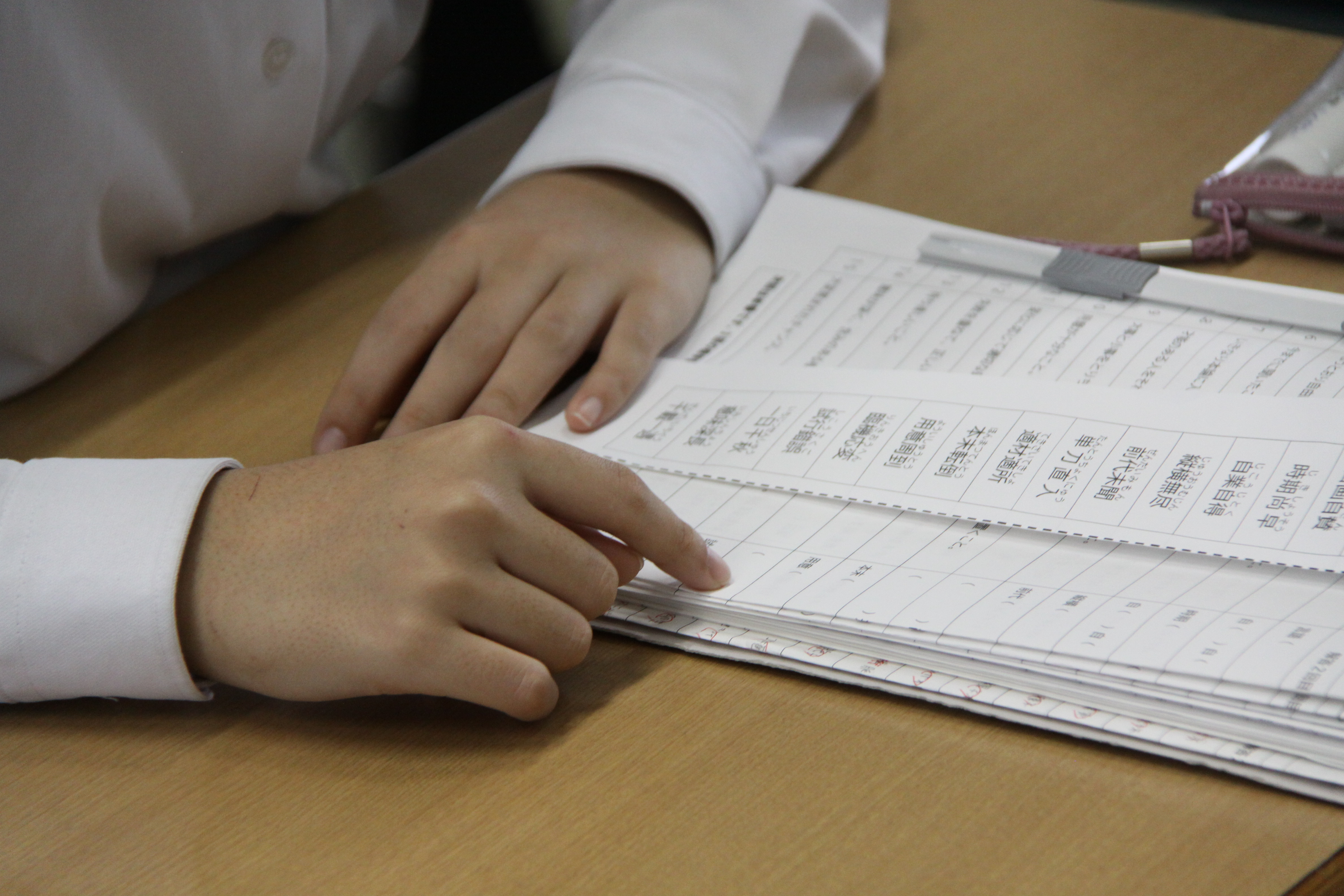
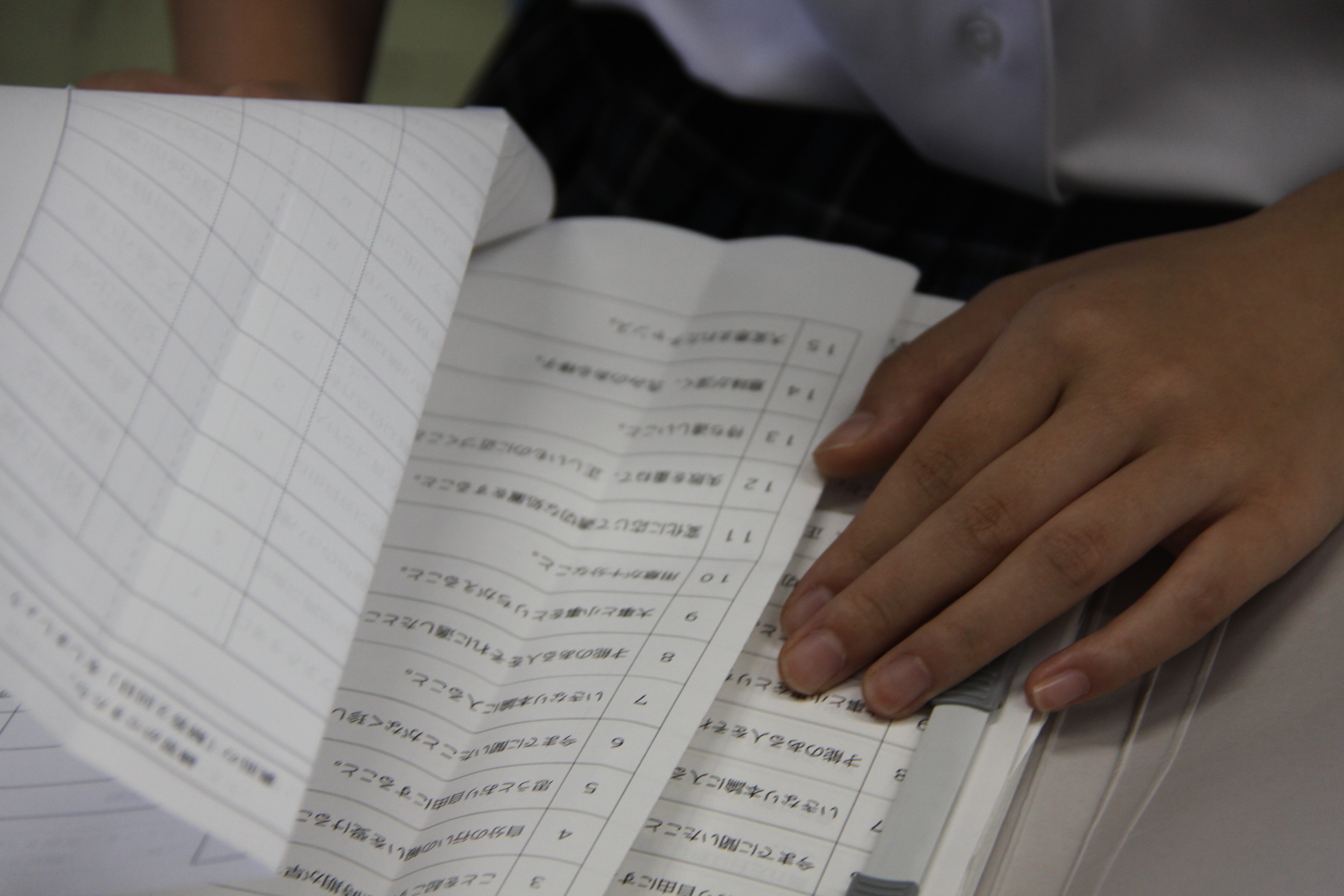
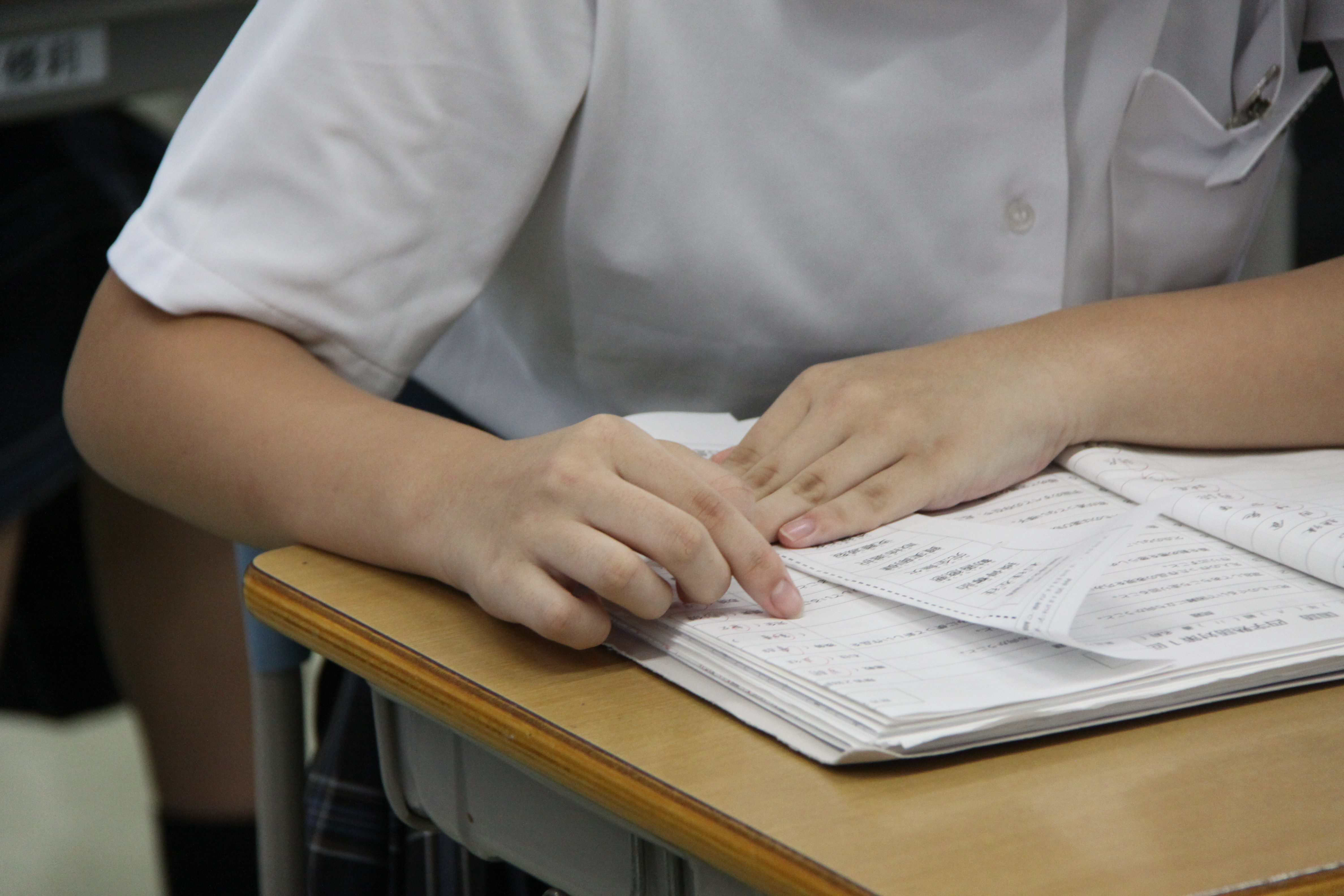
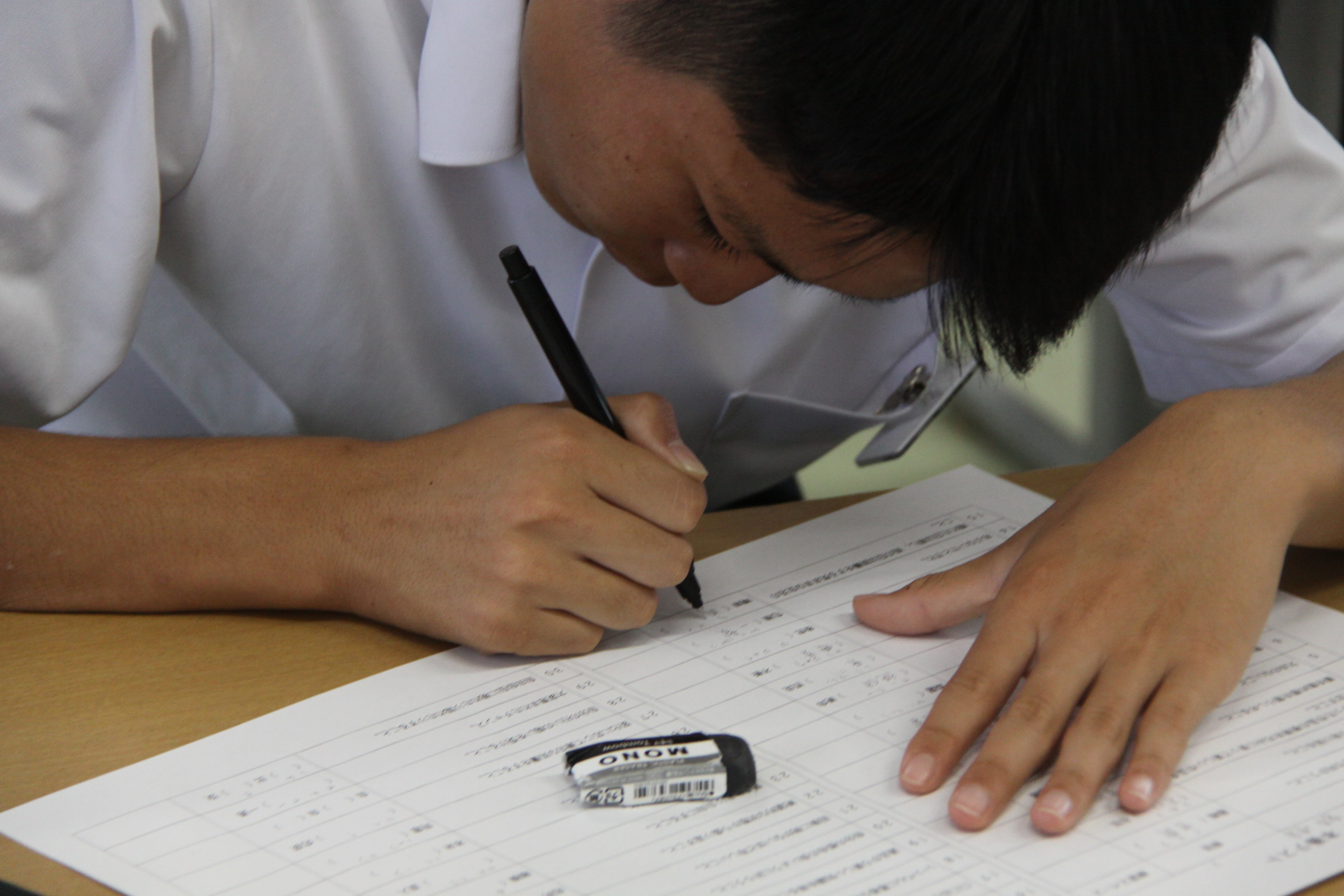

◎学力学習状況調査の返却(配付)(10/4)
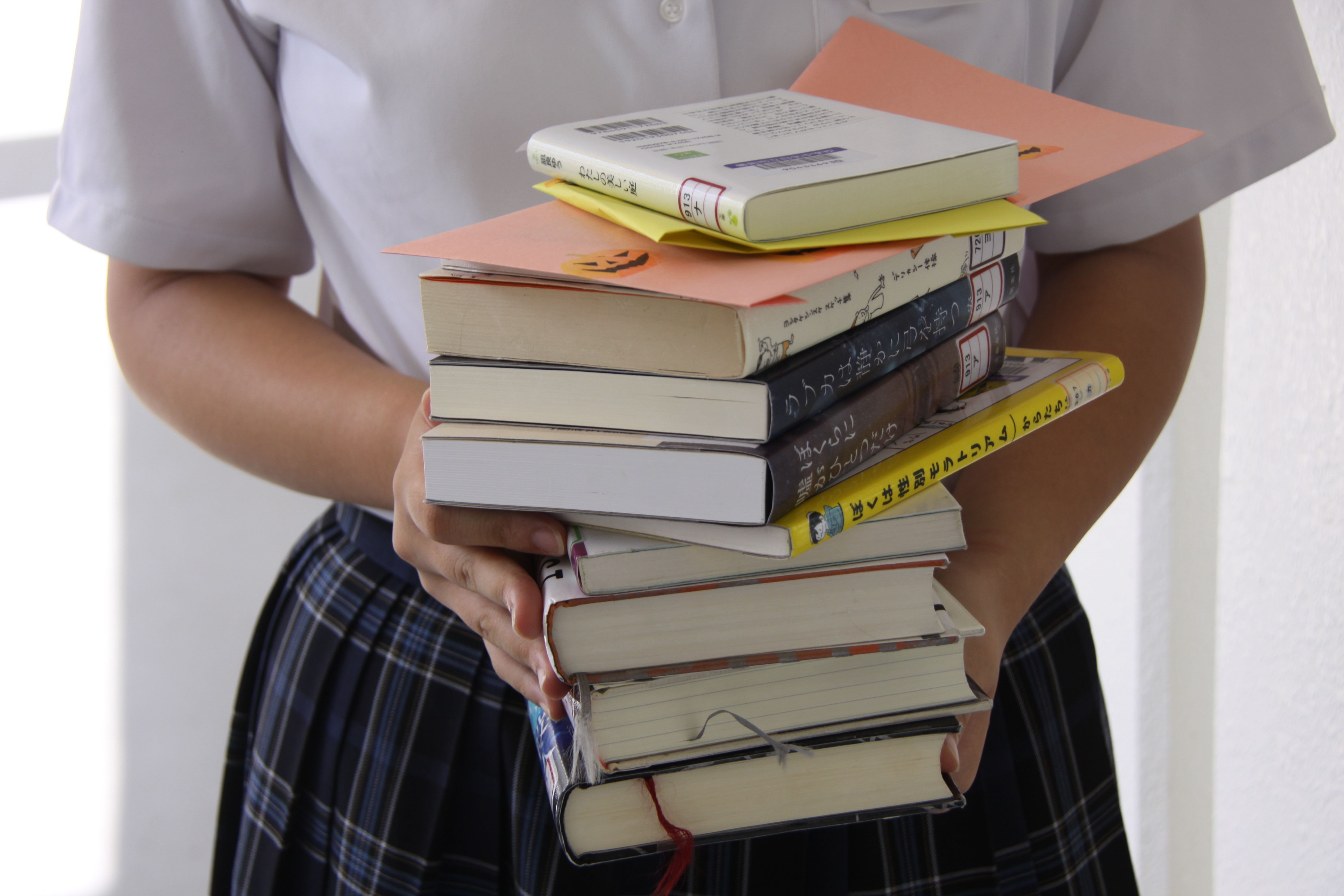
「新しい学力観」とは、自ら学ぶことの大切さや、自発的な思考力を重視した学力観のことを指しています。受け身ではなく、子ども自身が自分の力で考え、行動する能力を養うための教育法と言われています。激しく変化する社会の中では、自らの意思で行動することの大切さが問われる場面も数多く存在することから、改めて新しい学力観を持つことの重要性が注目されています。
縁あって、3年生へ調査結果を配付した際、「高い人権意識をもって、「その時、その場」で、自分自身がよりよい判断・行動できる生き方をしたいね」と話をさせていただきました(久次)。
◎わたしたちの学校・わたしたちの生活を高める
後期委員会活動も活発化しています。この日、体育委員会は、自転車の施錠点検と、「セーフティサイクル・ステップアップスクール(SSS)」に取り組みました。
SSSは、岡山県教育委員会及び岡山県警察との間で交通安全教育及び情報提供に関する協力体制の中で、児童生徒の交通ルールの遵守及び交通事故防止を目的とした交通安全教材「セーフティーサイクル・ステップアップ・スクール」です。この教材は、随時、学校だより『ひとのあいだ』でも紹介していますが、今回、体育委員会が活用して、交通安全に対する意識を高める取組を帰りの会で実施しました。(10/3)


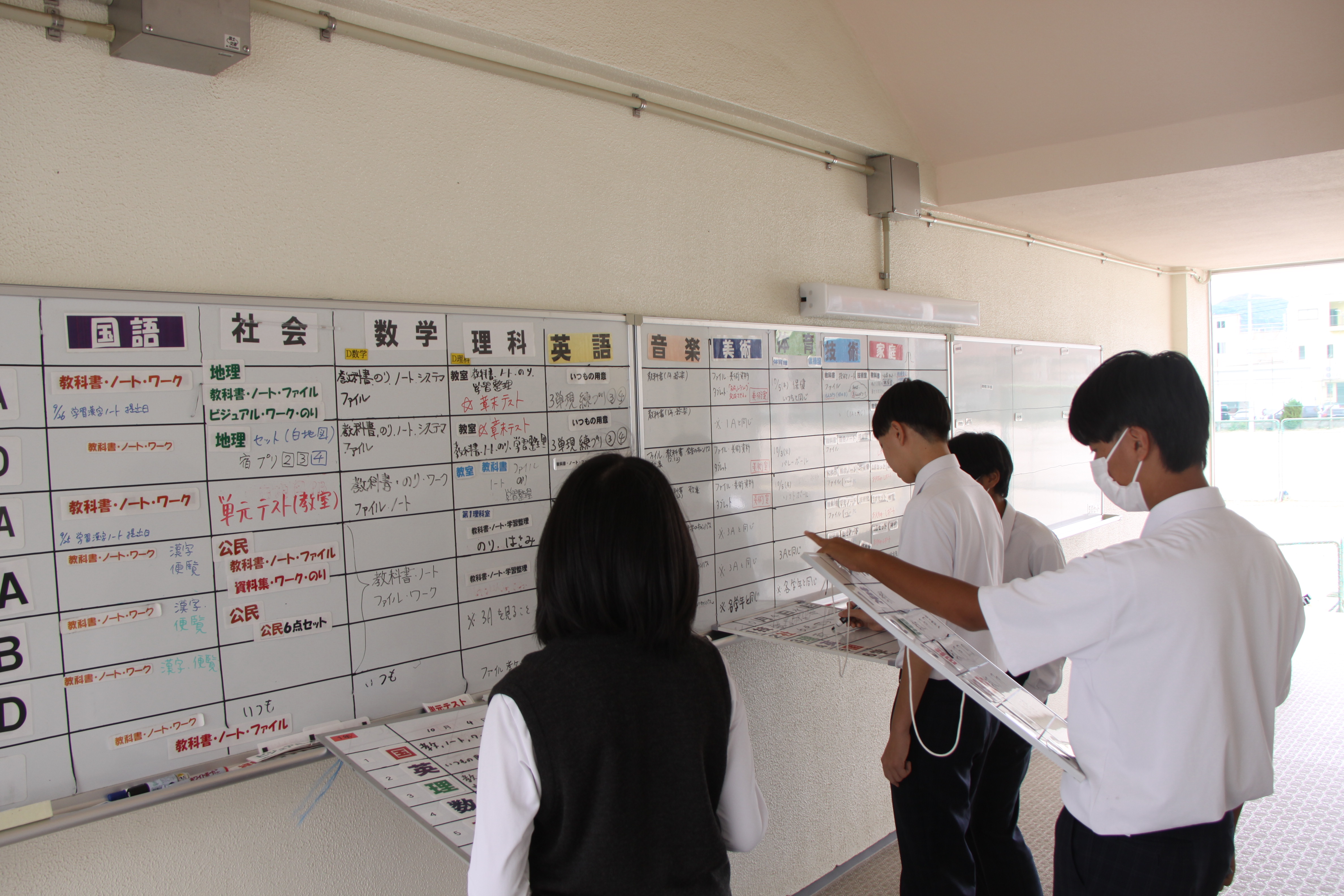

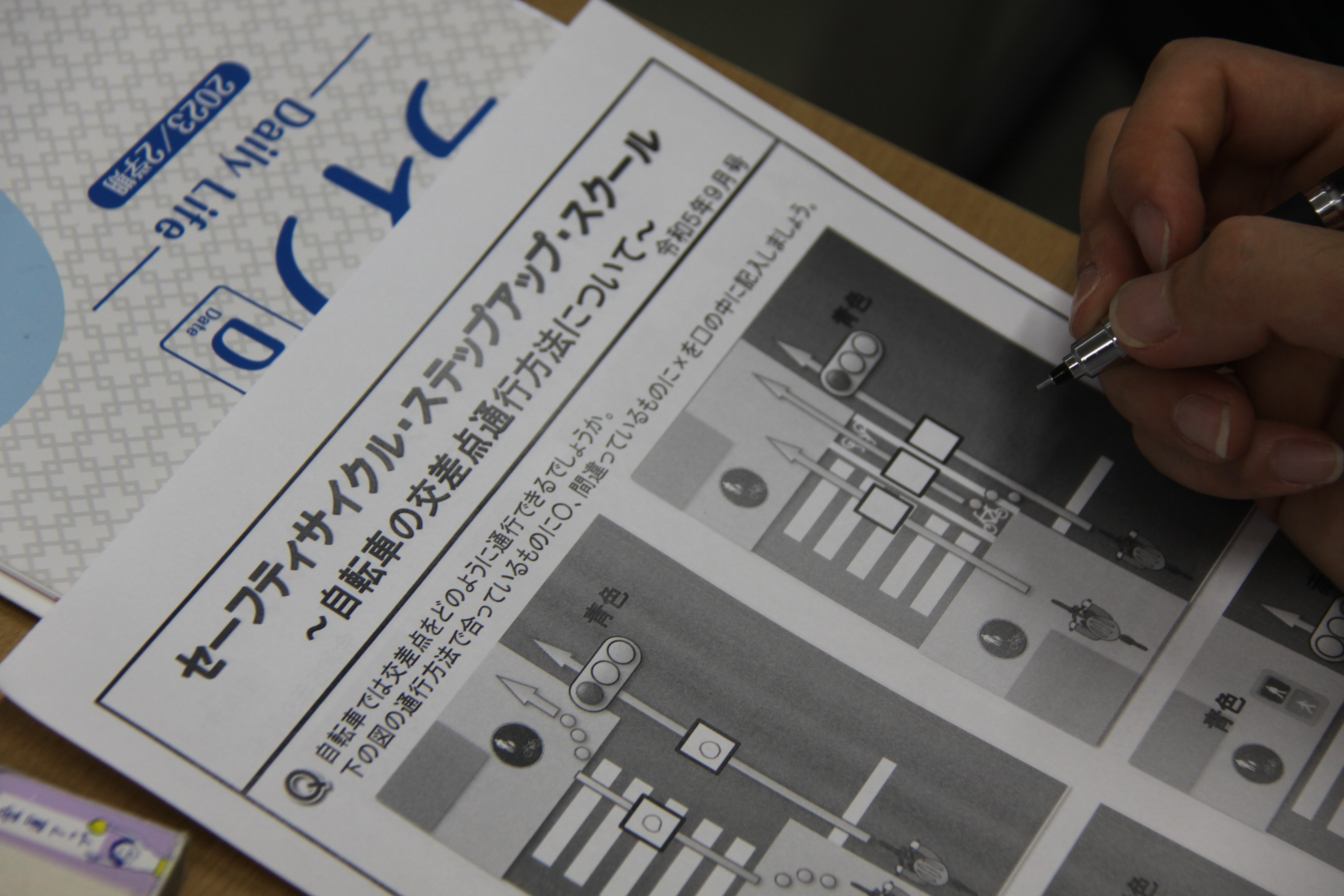
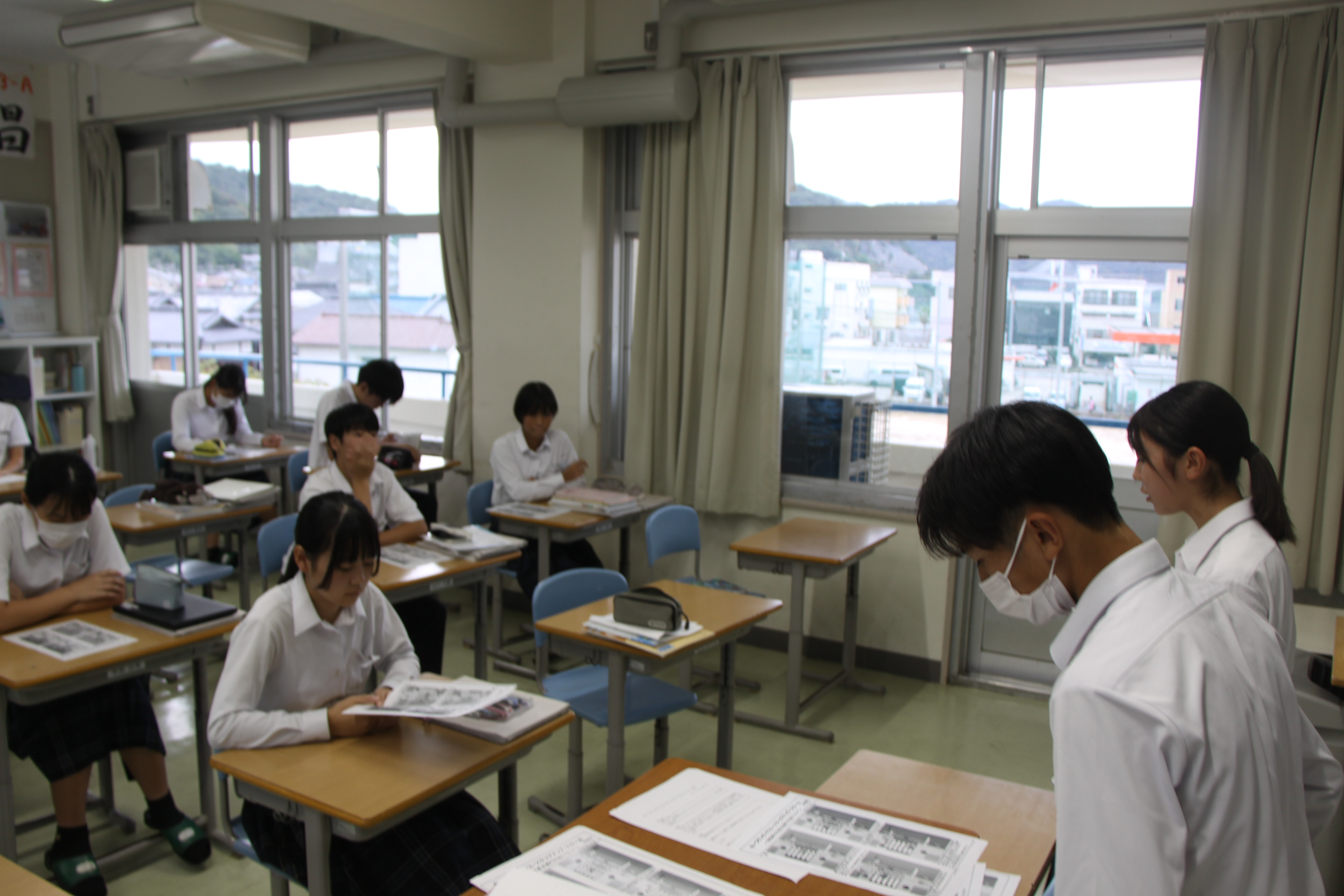
◎岡山県児童生徒科学研究発表会備前市大会開催(10/3)
奥原くん、寺地くんが日生中学校代表で出場
伊里中学校で備前市児童生徒科学研究発表会がありました。本校から寺地君と奥原君が日生中代表として参加し研究発表を行いました。二人とも落ち着いた態度で堂々と発表した様子は素晴らしかったです。審査の結果、奥原君は最優秀賞を受賞し、12月3日に行われる岡山県児童生徒科学研究発表会の備前市代表に選ばれました。

◎多くの人に支えられて
ICT支援員さんのちからをかりて
ICT支援員さんは、学校におけるICT関連業務を実現するために必要な専門スタッフです。 パソコン・タブレット端末・インターネット・動画・電子黒板などのICT機器を利用した学習をスムーズに行えるようにサポートし、生徒たちの情報を活用する能力を伸ばすための役割を担っています。10月2日から近藤先生が本校へ勤務されます。どうぞよろしくお願いします。(さっそく相談にのってもらう。(右が近藤先生です。))
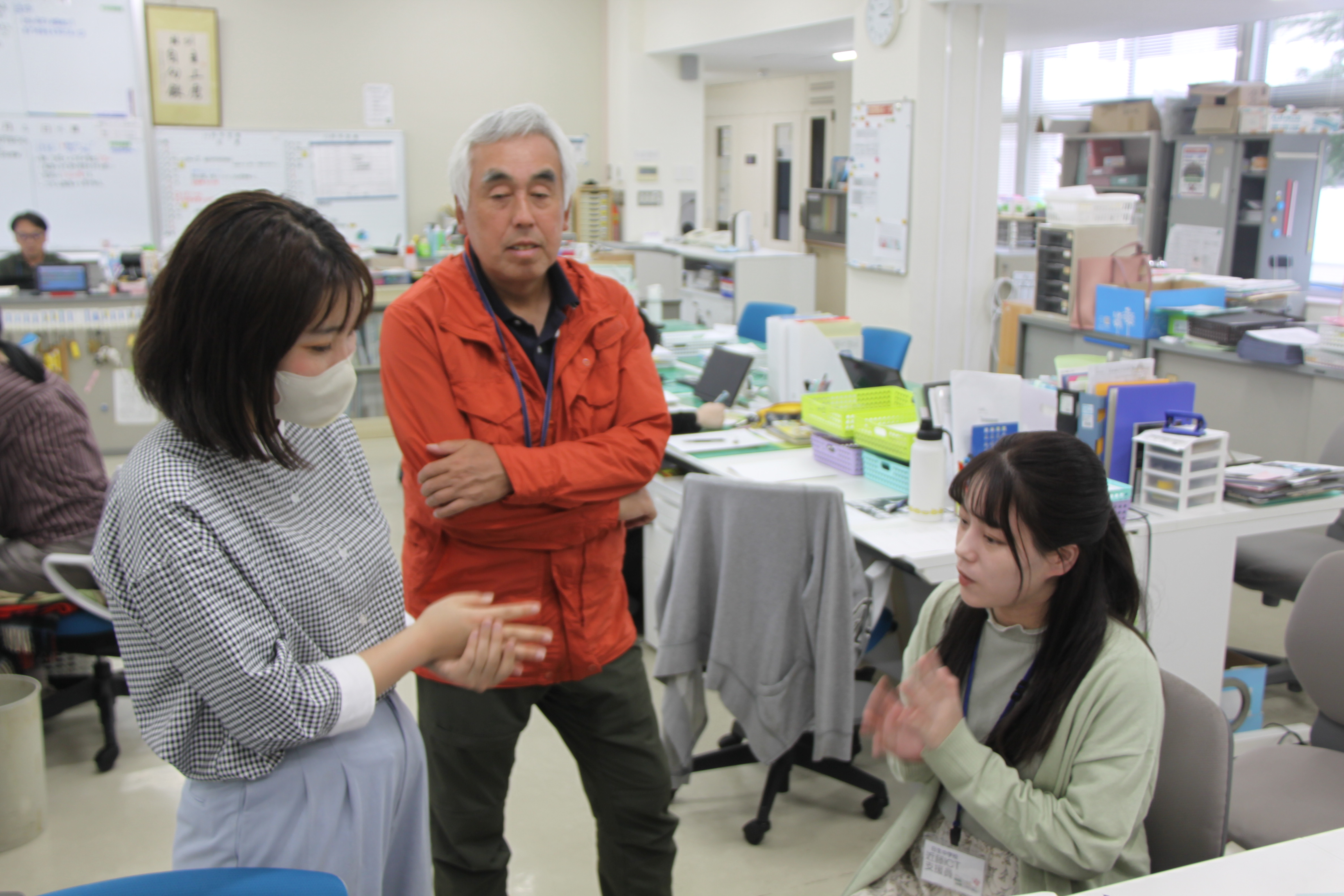
◎僕たちが知りたかったのは いつも正解など大人も知らない 喜びが溢れて止まらない夜の眠り方 悔しさで滲んだ心の傷の治し方 傷ついた友の 励まし方 あなたとはじめて怒鳴り合った日 あとで聞いたよ 君は笑っていたと 想いの伝え方がわからない 僕の心 君は無理矢理こじ開けたの あぁ 答えがある問いばかりを 教わってきたよ だけど明日からは 僕だけの正解をいざ 探しにゆくんだ♪(10/3)






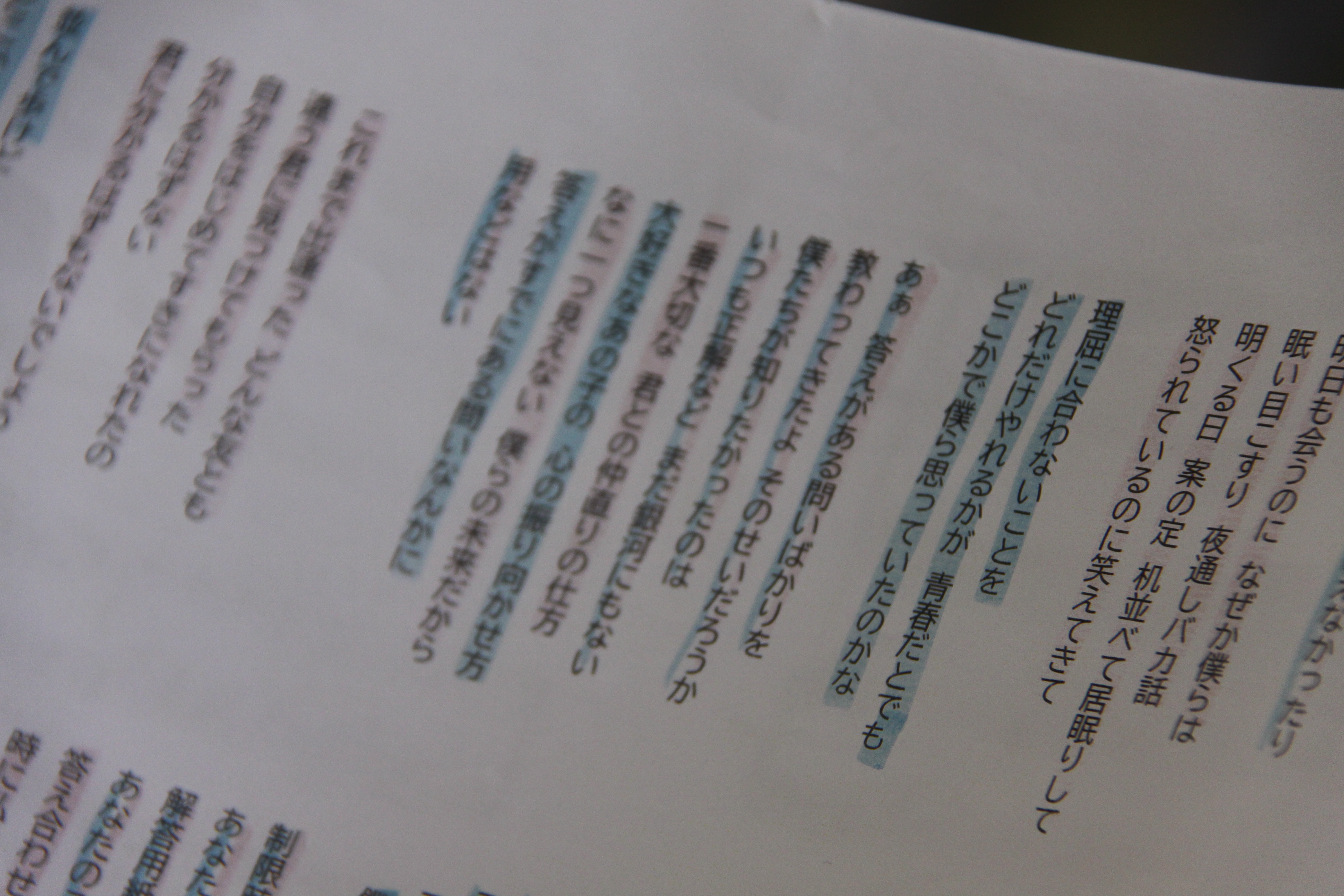


I dwell in possibility. Emily Dickinson (私は可能性の中に住んでいる。)
◎(10/2 第1回ひなせ親の会開催)
発達や特性について関心のある保護者たちが語り合う「親の会」を、赴任した学校で参加して、10年ぐらいになります。同じ経験をしてきたり、同じ立場であるからこそ、心を開き、言葉にできることがあります。保護者にとっては、互いに共感し、情報の交換もできる「居場所」の一つです。「中学校卒業後の進路についての情報がほしい」「充実した学校生活をおくってほしい」「誰かに聞いてほしかった」「ゲームばかりしていて大丈夫か」…などなど話題はいろいろ。集まった参加者が、考えていることや悩みや苦しさ、思いを一緒に語り合い、時には、親の会主催で、高校の先生をお招きして高校進学の学習会も開催したことがあります。
第1回ひなせ親の会には、地域の子ども(大人)の居場所づくりに取り組む東さんを合わせて、11名の参加があり、「中学校卒業後の進路情報」について意見交流をおこなうことができました。次回も計画していますが、12月を待たずとも、いつでも、中学校にお寄りください。お話しましょう。(教頭)
第2回ひなせ「親の会」のご案内 (調整中)
◎特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。◎これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。◎お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。(カウンセリングや講座ではありません)
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)からアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、次回も大切な時間にできたらと思います。お気軽に、申し込み・ご参加ください。
1 日 時 2023年12月1日(月)17:45~19:00 (*新入生説明会の日)
2 場 所 日生中学校
3 内 容 「「発達の特性」を正しく自己受容していくために」をもとに意見交流を予定
4 参加者 小・中学校の保護者 日生西・日生東小学校の先生 久次(日生中学校) SSW 主催:日生中学校区連携推進委員会(特別支援教育部会)
5 予 定 ・第3回:2月14日(水)17:45~19:00 (*小6体験入学の日)

◎地の塩 世の光 (10/2)


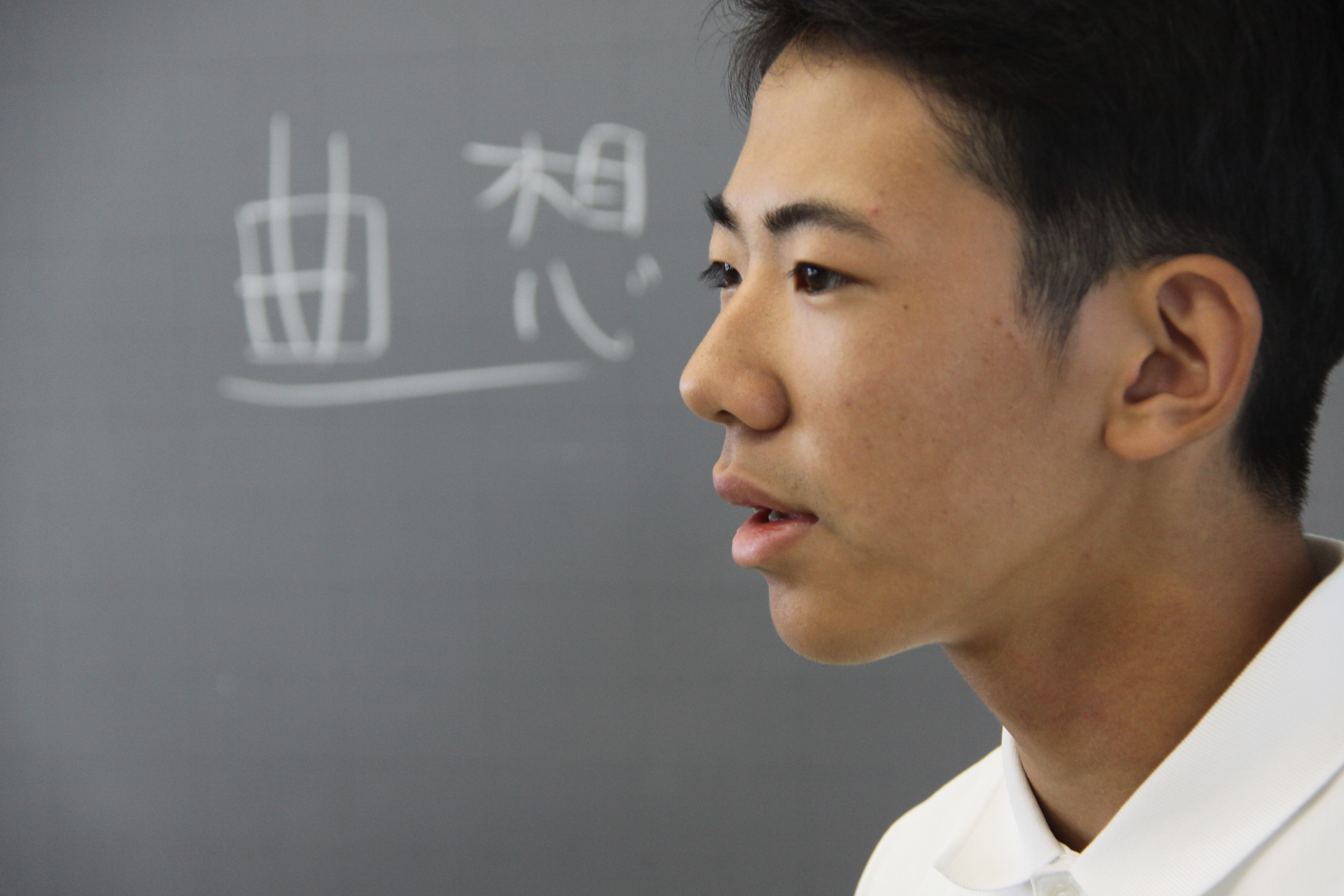






◎ひな中のかぜ~清秋の候








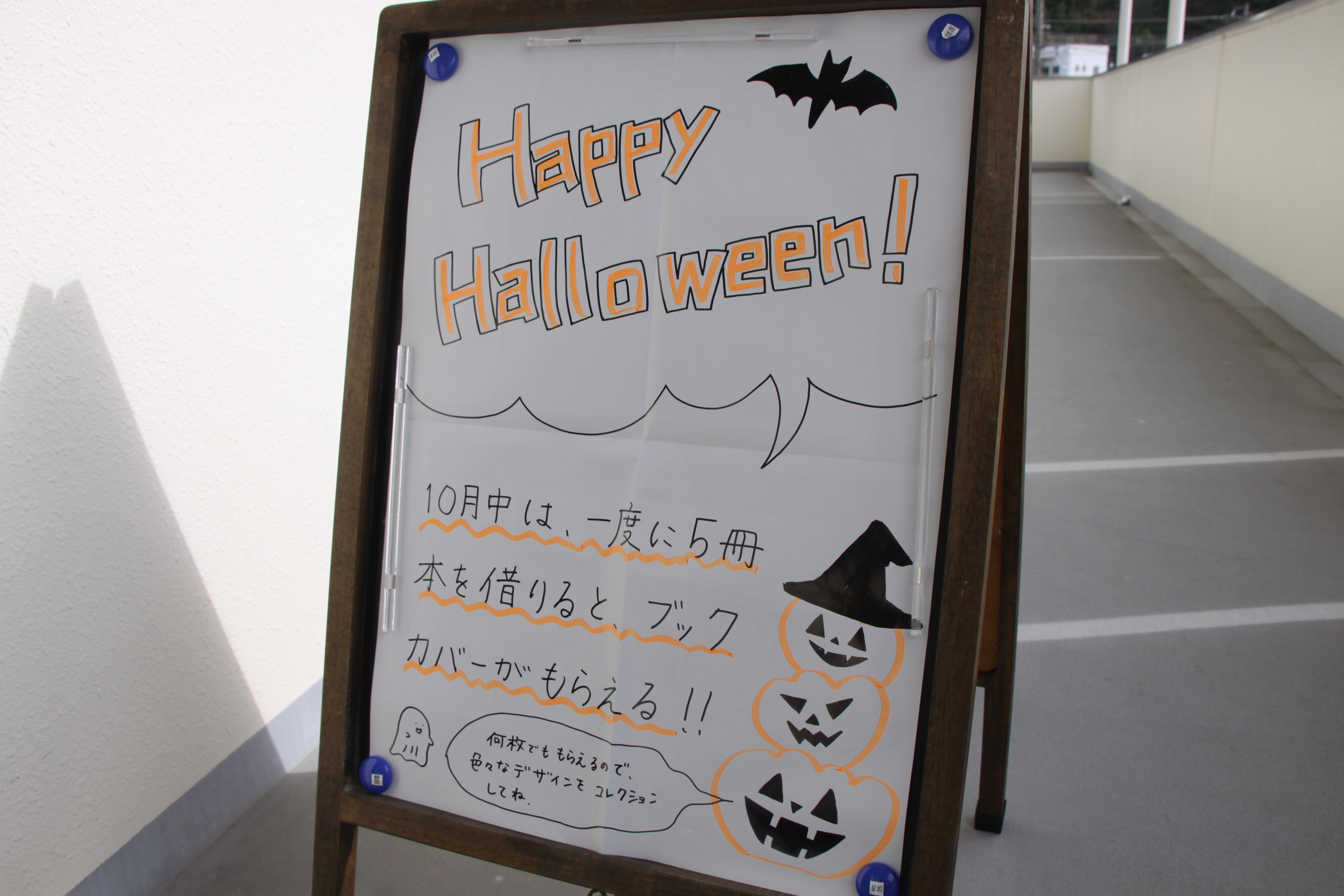
◎〈わたしの思い 届け〉
~校内弁論大会にあわせて(9/29)
学級弁論大会で選ばれた人代表の人が、いま、一生懸命に練習を重ねています。自分らしくせいいっぱい、論じてほしいと思います。この機会に少しだけ「伝える」ことについて。人に自分の考えを伝えるってけっこう難しいことです。伝え方・話し方のコツはいくらかあるようですがいくつか紹介します。参考にしてください。その1、〈話す「相手の存在」を意識する〉…発表は、話すことではありません。何が違うかというと、相手がいない状態で一方的に言葉を発していること。話をするということは、必ず聞く相手が存在します。大人になって行う発表はプレゼンテーションですが、よく見かけるのが目の前の聴衆を無視したような一方的な話し方です。どんなに内容が良くても聞きづらいと感じてしまいます。話すという行為は、必ず誰かに向っていることを意識するべきもの。会話しているときには目の前にいる相手を、そして人前で話すときには前にいる人たちに向かって話していることを心に留めておいてください。そう認識することで、話し方や伝え方を色々と工夫しようという気持ちになってきます。「理解してもらうには、どう構成したらいいか」「自分の気持ちを分かってもらう伝え方はどうしたらいいか」というように試行錯誤するでしょう。相手を意識すると確実に話し方が変わります。たとえば小学生の低学年の子に話すときには、目線を合わせてわかりやすい言葉を使うでしょう。高齢の方には、少し大きな声でゆっくりと話すはずです。このように相手の状況をわかろうとし、、相手のわかる言葉にすることはとても大切なことです。相手によって、わかりやすい(伝わりやすい)言葉、話すテンポ、例え話(比喩)が違います。日々、話している相手を意識すると相手に合わせた話し方が出来るようになります。相手の生活環境を考えてみると、どんな言葉で話すと一番伝わりやすいかが見つかります。これは通常の会話だけでなく、プレゼンテーションのような一対多数の場面でも同じ。話すときには、必ず聞く人がいることを忘れないでください。
もうひとつ、〈相手の話を「聞いて」話す〉…話すこと以上に大切なのが、聞くこと。よく言われることかもしれませんが、たしかに聞くことができる人は話が上手です。相手の話をしっかりと聞くということは、相手に興味を持って臨まないとできません。誰でも自分の話を熱心に興味深く聞いてもらえることは気持ちが良いもの。そうした行為は相手に好印象を与え、好感を持たれます。気持ちよく聞いてもらったあとは、相手の話を聞こうと思うものです。会話が楽しくなる雰囲気を作り出すためにも、いい聞き役になること。自分の話をする前に、相手がどんな人なのか、何に興味がある人なのかを知ることができると、相手に相応しい話し方が考えられます。自分が言いたいことを切り出す前に相手の話を聞くことで、相手はあなたの話を聞く用意ができてきます。上手に会話のシーンを作り出せれば、有意義なコミュニケーションの場になるはずです。
少し紹介しました。話す相手が誰であっても興味を持ち、思いやりの気持ちを持つこと。そうは言ってもなかなか難しいという人もいるでしょう。そんなときは、ひとつでも良いので相手の良いところを探しながら会話をします。その時間が、少しでも有意義になるはずです。


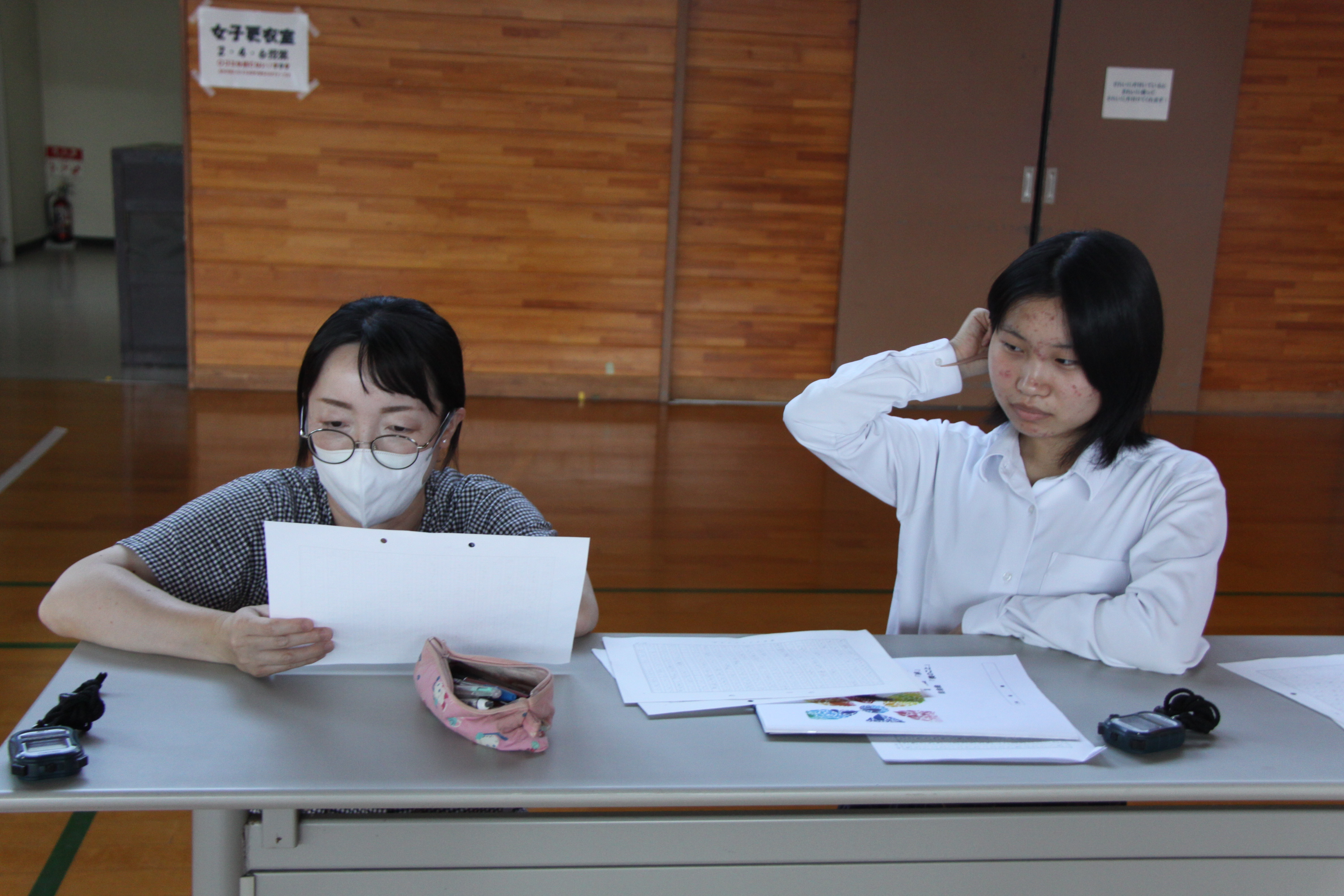

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Steve Jobs
(点と点を結ぶには、前を見てはいけない、後ろを見てはいけない。自分の未来で点と点がどうにかつながることを信じるしかない。)
◎明日のためにその1、左ジャブ。その2、右ストレート。(9/29)
全国(県・市)学力・学習状況調査結果の返却について
平素は、本校教育にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。さて、4月18日に実施した学力・学習状況調査の結果が返送されてきました。10月3日、お子さんの調査結果(個人票)を返却しますのでお知らせします。これまでの学習等の成果や取組状況について、お子様とともにあらためて確認する機会にしていただければと思います。子どもたちの「学ぶ力」、「進路を切り拓くちから」をさらに伸ばしていくための今後の手立てとして活用していきたいと考えています。今後とも、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

◎終わらない歌をうたおう(文化の部まで一週間 9/29)
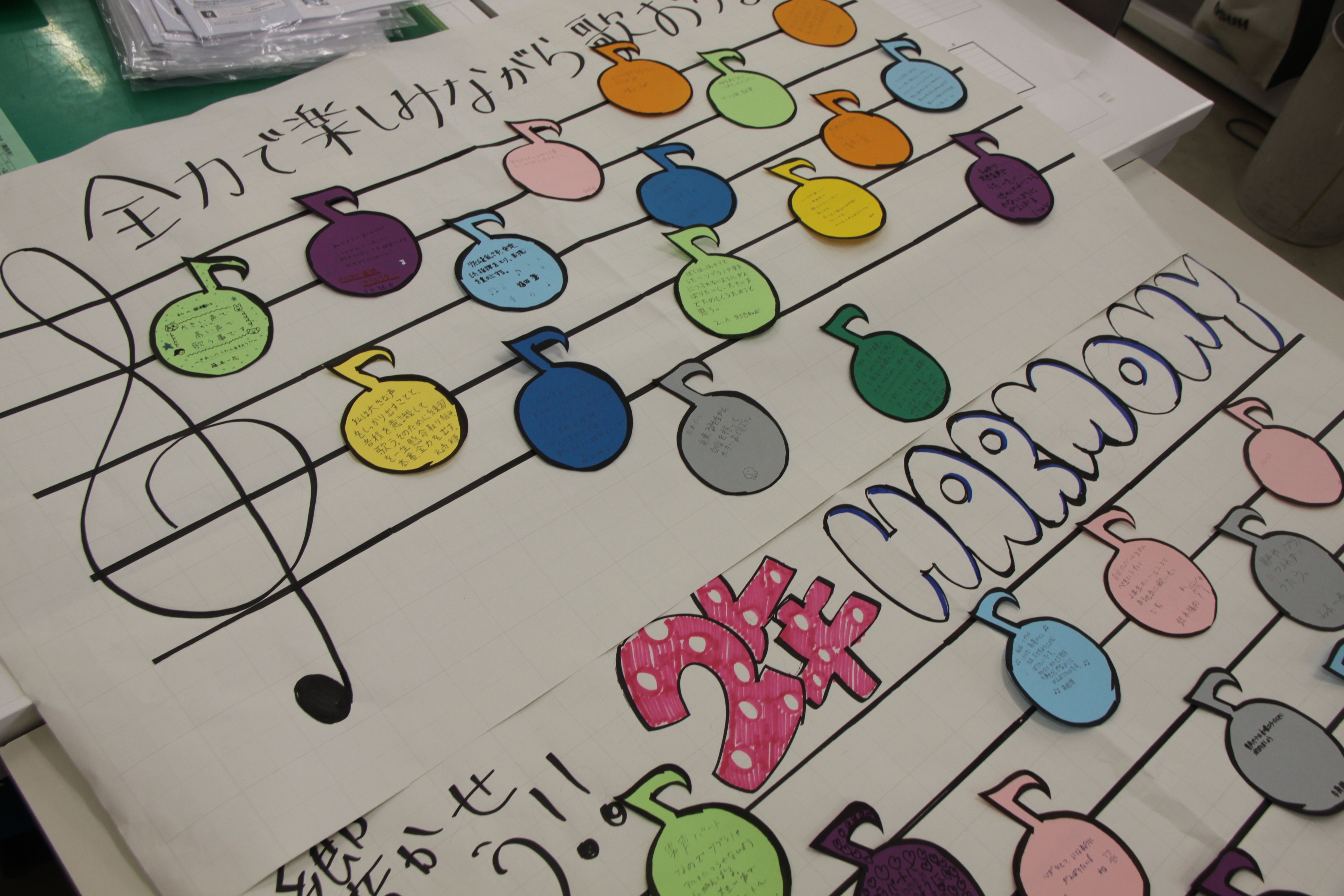
◎開かれた学校・地域と共にある学校へ
HP訪問者数9000人を越えました(9/29)
HP閲覧者数が多くなることだけがよいとは思いませんが、多くの方々のご理解・ご協力で生徒・中学校は歩みを進めていくことができます。これからも様々なご支援をよろしくお願いします。

9月29日(金)は「中秋の名月」です。中秋の名月をめでる習慣は、平安時代に中国から伝わったと言われています。日本では中秋の名月は農業の行事と結びつき、「芋名月」などとも呼ばれることもあります。今年の「中秋の名月」は満月です。満月の瞬間は18時58分で、夜に昇ってくる名月がちょうど満月ということになります。2021年、2022年、2023年と3年連続で満月の日付と一致しますが、次に中秋の名月と満月の日付が一致するのは2030年9月12日と7年も先になります。
「中秋の名月」というと満月を思い浮かべる方も多いと思いますが、毎年必ず満月の日になるわけではありません。これは、中秋の名月は太陰太陽暦の日付(新月からの日数)で決まりますが、満月(望)は、太陽、地球、月の位置関係で決まるからです。月の公転軌道は楕円形になっており、新月(朔)から満月(望)までにかかる日数は13.9日から15.6日と変化することが原因です。
◎Catch The Wind(9/28 1年生海洋学習)









◎Blowin' In The Wind(9/28 1年生海洋学習)









◎多くの人に支えられて(9/28 消防設備点検)
残暑厳しい中、授業に支障がないように、時間をかけて消防設備点検をしていただきました。また、専門家のてきぱきとした対応・効率のよい仕事の様子をみさせていただきました。さすが、プロフェショナルの仕事。ありがとうございました。






◎日生で輝く 日生が輝く (9/28 海洋学習)
アマモ場再生の取り組みは地道な作業の積み重ねです。毎年同じサイクルを繰り返し、少しずつアマモを増やしていきます。
私たち日生中学校での6月の海洋学習では、海に入ってアマモの種がついた枝「花枝(はなえだ)」を採取しました。そして採取した花枝はイカダに取り付けて育て、種子が放出される今月まで熟成されてきました。この種を海中に蒔きます。この作業を毎年繰り返し行うことで、「アマモ場の再生につなげよう」と、日生では長い間取り組んでこられました。
私たちも、大切な海洋学習として、このサイクルをきっちりと回すことの大切さを広めたり、継続的に参加したりすることで、活動を進めていきたいと思います。

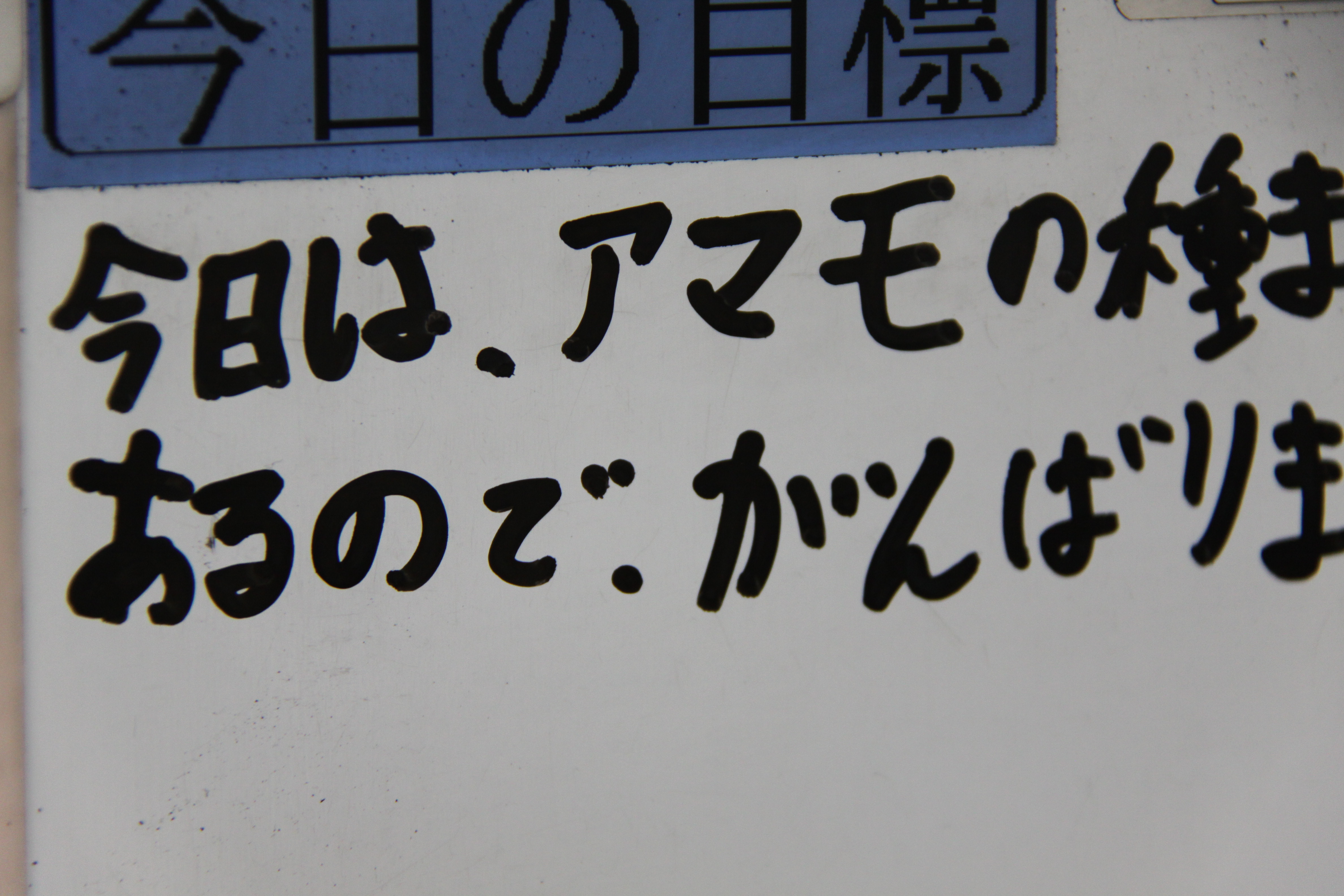
10月24日には、西小学校を訪問し、ポット法によるアマモの種苗生産の学習に小学生と共に取り組みます。アマモ場は,「海のゆりかご」と呼ばれ,魚類幼稚魚の保護育成場所としてとても重要です。近年は沿岸域の開発に伴い,アマモ場は少しずつ減少しています。その中で,日生漁協さん・研究者を中心に、ポット法によるアマモの種苗生産が進められ,海域へのアマモの移植の取組を行っています。
◎多くの人に支えられて~大切な学校生活のために(9/27)
昨年度のコロナ対応予算で購入していただいていた空気清浄器を、各教室・特別教室に整備しました。これから、インフルエンザやコロナの再流行も予想されます。ご家庭でも予防・対策を引き続きよろしくお願いします。

◎ひな中の風~~今年もみのりの秋へ(9/27)






先人のコトバ…We tend to be alive in the future‚ not now. We say‚ ”wait until I finish school and get my Ph.D. degree‚ and then I will be really alive.” When we have it‚ we say ‚ “I have to wait until I have a job in order to be really alive.” And then after the job‚ a car. After the car‚ a house. We are not capable of being alive in the presen Thich Nhat Hanh
(我々は今でなく、未来に生きてしまいがちです。例えば、「大学院を修了して博士号を取るまでは辛抱しよう、それから人生を楽しむんだ」そして、博士号を取ったら、「いい仕事に就くまでは、辛抱しよう、それから人生を楽しむんだ。」そして、仕事を手にしたら、次は車、その次は、家を手に入れるまで・・。このように、今この瞬間をめいいっぱい生きていない。)
◎日生で輝く 日生が輝く(9/26)
~3年生総合的な学習の時間発表 「確かな学び」は、街と後輩たちへ
観光協会の村上さんをお招きして、今年も〈日生への提言〉をおこないました。



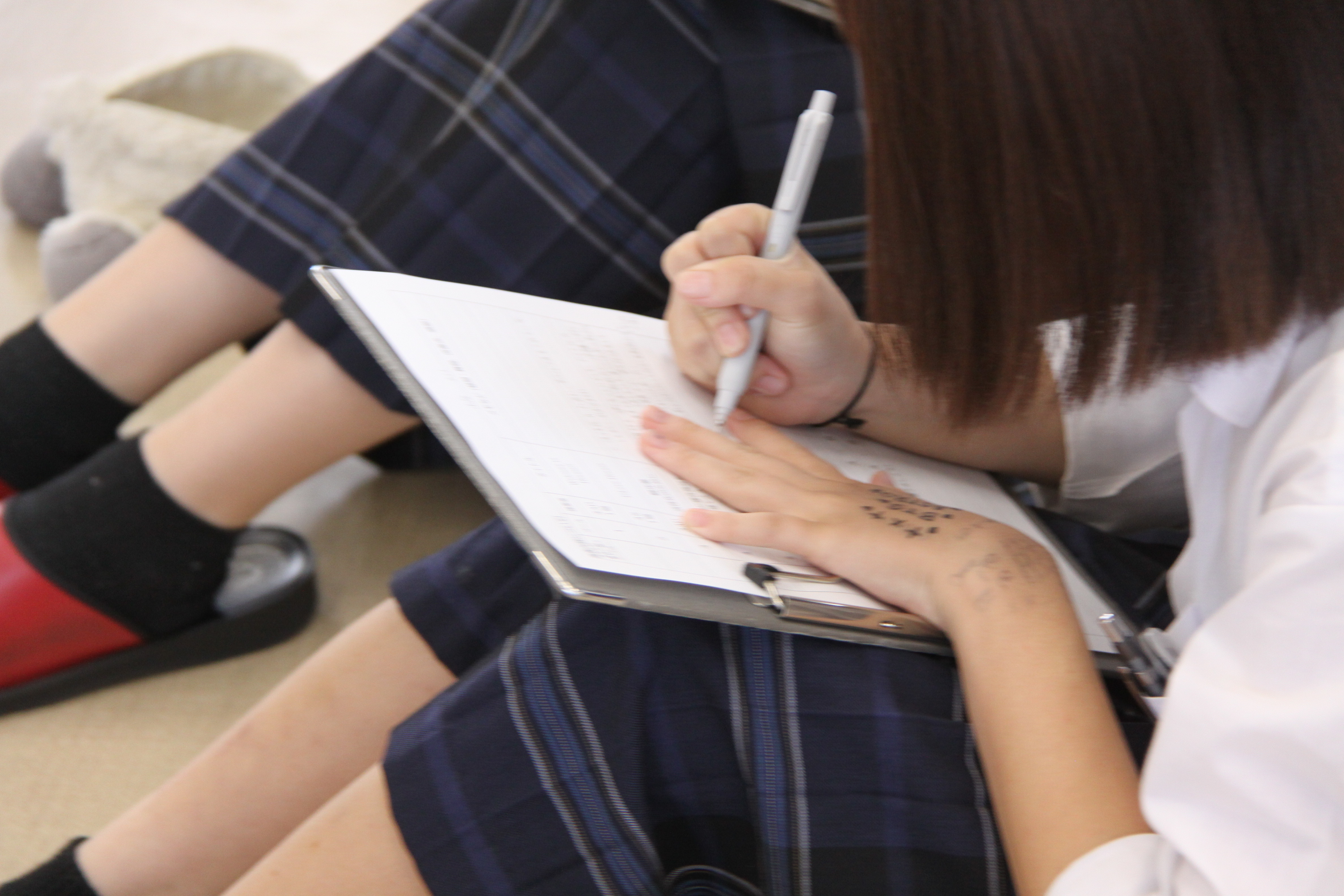
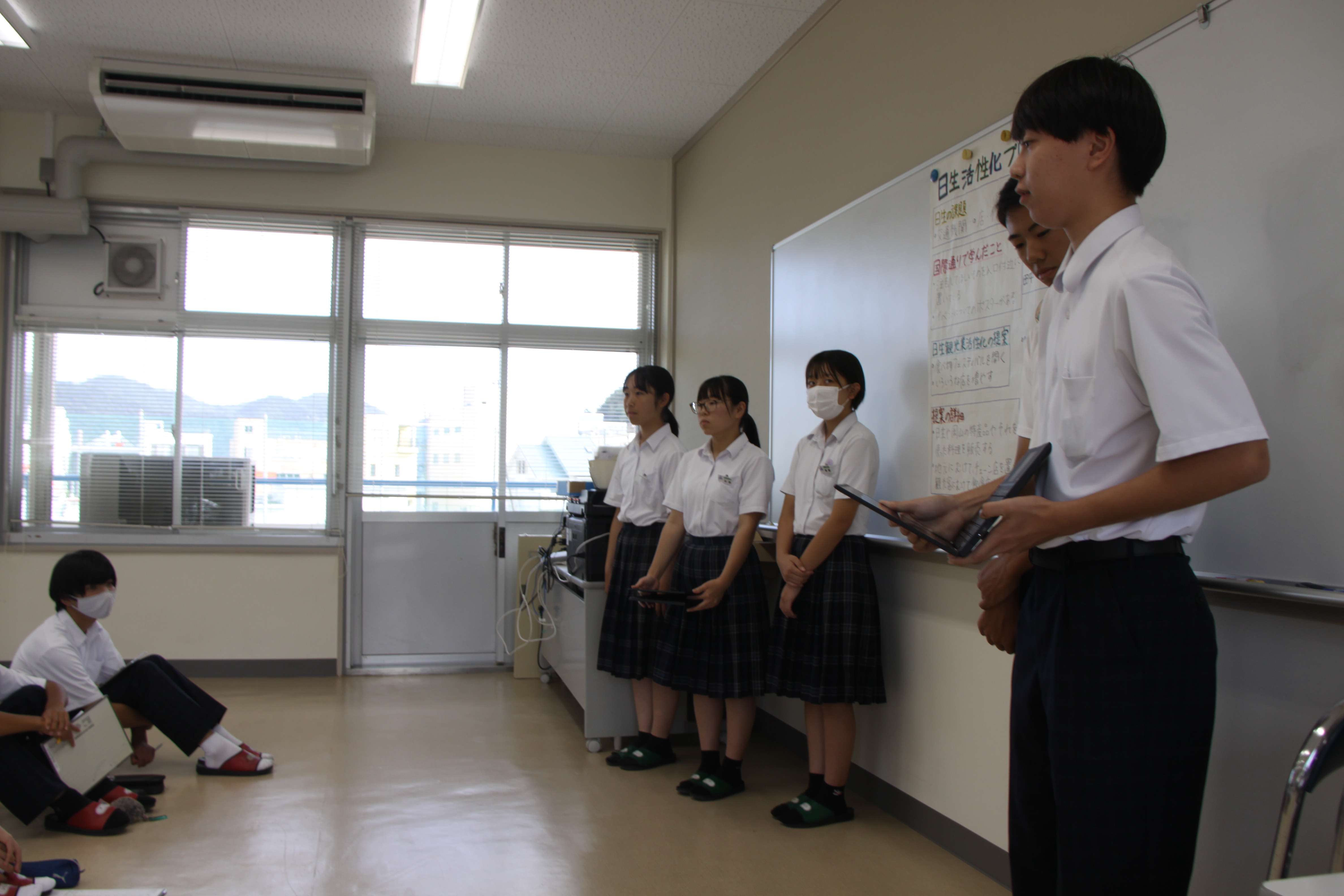

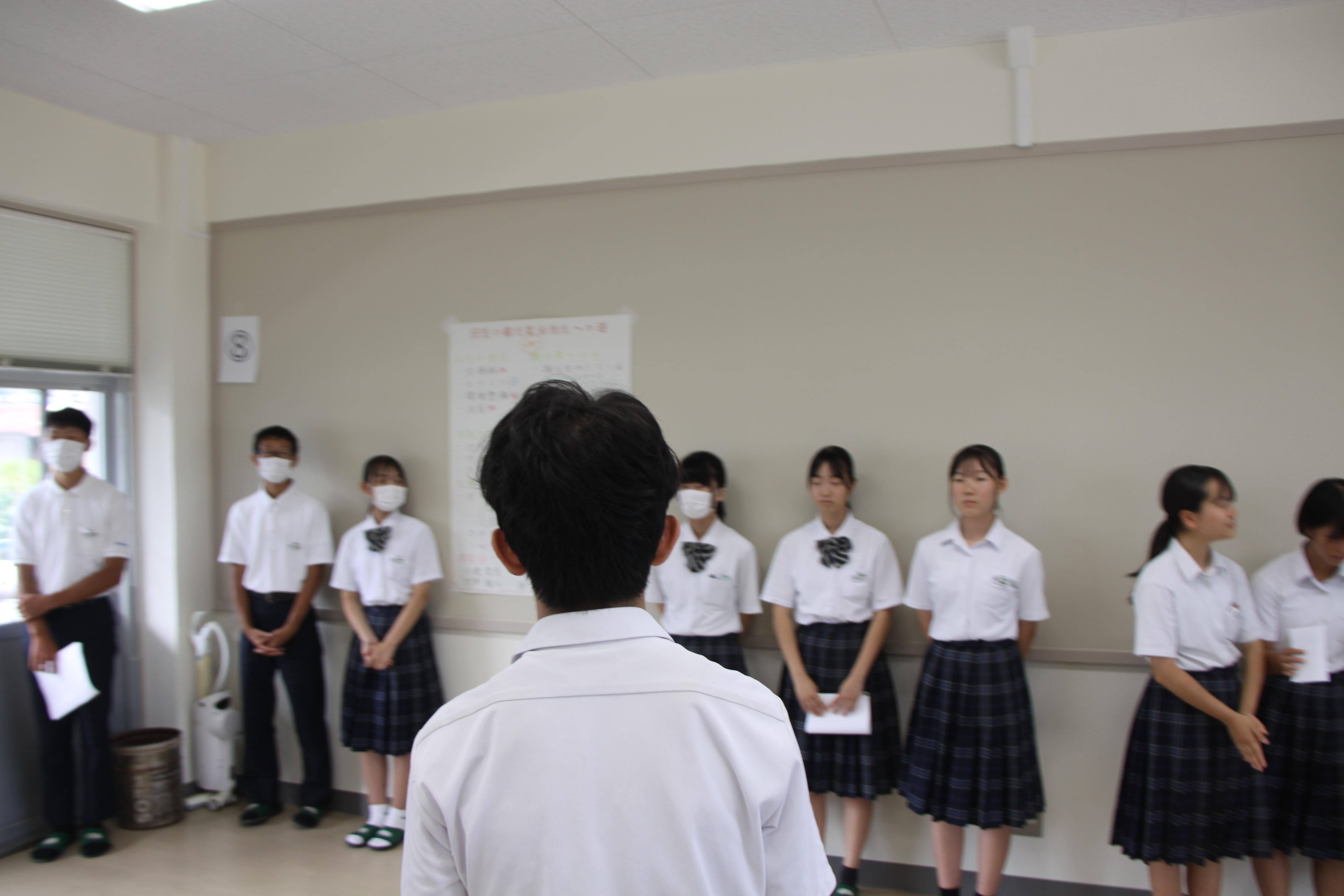


◎多くのひとに支えられて ~地域と共にある学校へ(9/26)
日生地区民生委員・児童委員協議会さんが来校されました。授業参観、給食試食会、情報交換を行い、これからの地域連携について協議を深めました。


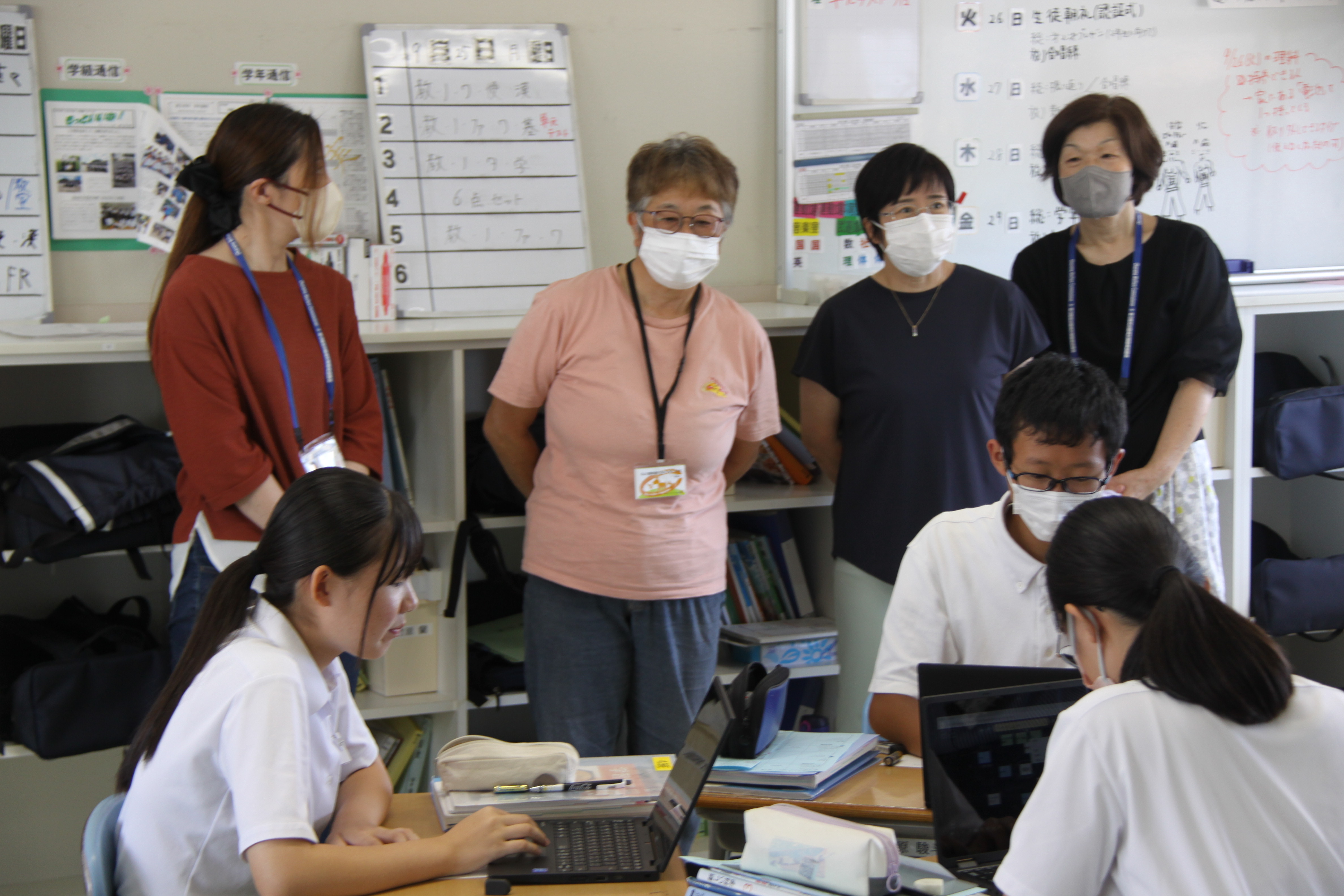






民生委員のしごとについて民生委員法第14条では次のように規定されています。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
もうちょっと、わかりやすく2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
民生委員さんってどんな人ひとなんだろう?
〇「民生委員」はみんなが安全に安心して生活できる地域をつくるボランティアだよ。みんなから困りごとや心配ごとをきいて、助けてくれる人や場所を紹介する「つなぎ役やく」なんだ。日本全国どこでも活動していて、まちのことをよく知っている。みんなのためによいことをしたい気持ちを強くもっている人から選ばれるんだよ。民生委員は子どもや子育ての困りごとの相談にのる、児童委員でもあるよ。だから正しい呼びかたは「民生委員・児童委員」というよ。なかには、とくに子どもたちの子育ての相談などを専門にする「主任児童委員」という役割をもつ人ひともいます。
〇民生委員・児童委員一人ひとりが担当する地域が決まっているのよ。私たちは地域で生活している住民のひとりだから、地域のいろいろな人たちとかかわりあいながら活動しているのよ。もちろん、相談してくれたみんなの秘密は必ず守ります。
民生委員は地域の推薦会で推薦され、国から依頼される地域の役割のひとつです。ボランティアなのでお給料はもらいません。一度選ばれると3年間続けます。これらのルールは法律で決まっています。
◎ひな中の風~~ 自主・向上・練磨 (9/26 後期生徒会認証式)

I like to see a man proud of the place in which he lives. Abraham Lincoln
(私は住んでいる場所を誇りに思っている人を見るのが好きだ。)
◎先生たちも日々、勉強です。(9/25 校内研修)
この日は、「評価・評定」についての学び合いました。


少しだけ学習指導要領について…。現在の学習指導要領は、目標及び内容が資質・能力の三つの柱で再整理されたことを踏まえ、観点別学習状況の評価については、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点に整理されました。各教科においてはこの3観点に基づき、学習指導要領で定められた資質・能力が、児童・生徒に確実に育成されているかを評価します。「児童・生徒にどのような力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教師の指導改善、児童・生徒の学習改善を図るために、指導と評価の一体化を実現する必要があります。
指導と評価の一体化に向けては、三つの資質・能力はそれぞれ別々に存在しているのではなく、相互に関連しており、一体的に育成することが求められます。例えば、「学びに向かう力、人間性等」については、「知識及び技能」及び「思考力、判断力、表現力等」の資質・能力を一体的に育成する過程を通して育成する必要があります。学習評価を行う際には、このことを十分に踏まえることが重要です。指導と評価の一体化を図るためには、「~できる」の形で単元の目標を設定し、その実現に向けて指導するとともに、「~できる」ようになったかどうかを評価する場面(「記録に残す評価」を行う場面)を設定する必要があります。「評価すること(「~できる」児童・生徒の姿)に向けて指導する「指導したことを評価する」 」 ことを常に意識することが重要です。なお、授業のねらいに即して児童・生徒の活動の状況を確実に見届けて指導に生かす、いわゆる「形成的評価」はとても大切になってきます。…先生たちも、生徒一人ひとりが、仲間と共に「学ぶちから」を高め、自分らしい進路を切り拓いていけるように、日々勉強していきますね。
◎歌は歌って初めてうたであり
鐘は叩いて初めて鐘であり 愛は与えて初めて愛である
(9/25~放課後練習スタート)


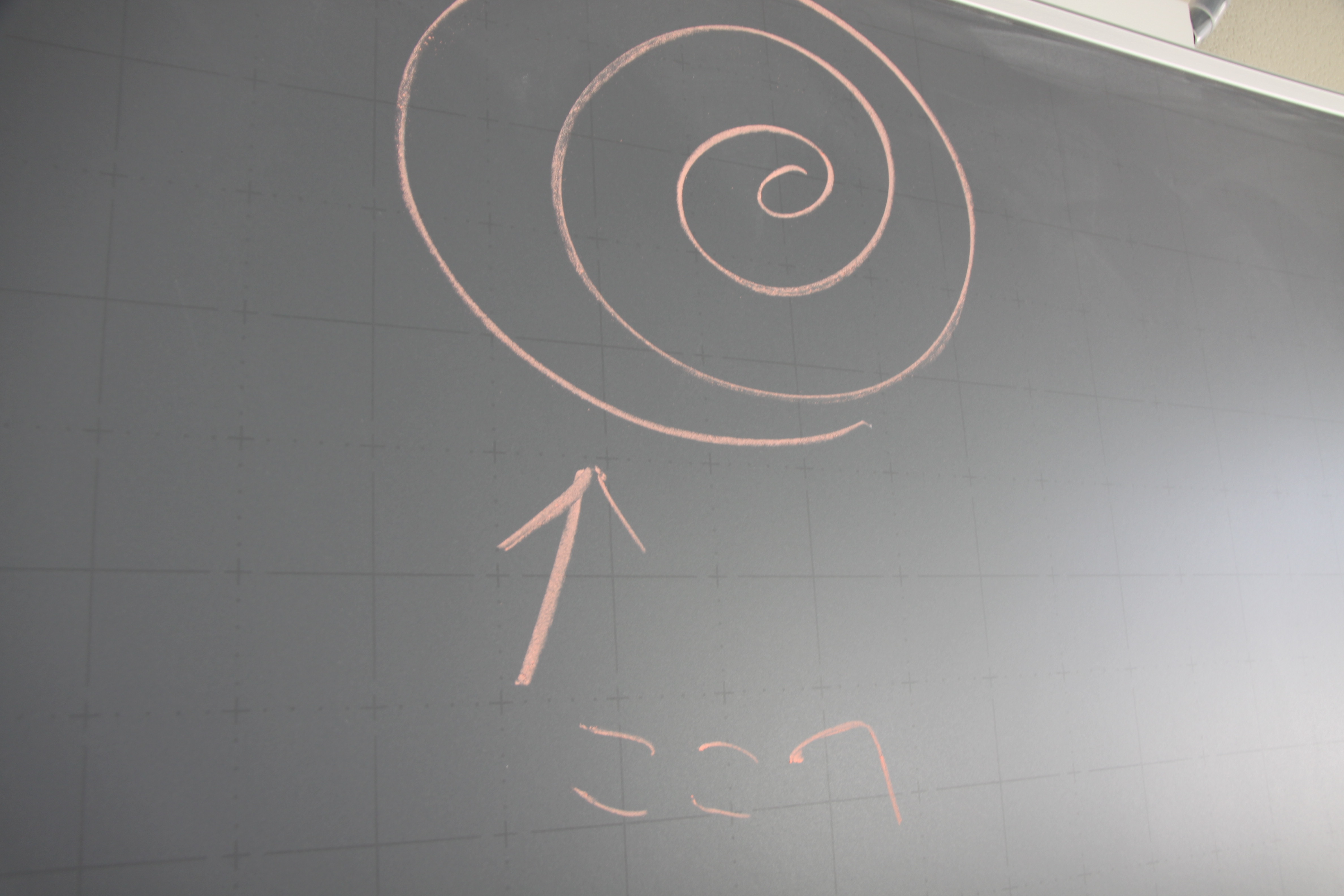
◎多くのひとに支えられて
~プロの「確かで」「きびしい」目で、安全を手にするということ。
自転車点検をありがとうございました。(9/25)
自転車事故は年々増加しており、単独事故や自転車同士の事故、歩行者との事故などさまざまなパターンがあります。自動車事故と比べると大きなものではない、と捉えられがちですが、自転車事故も一歩間違えれば多額の賠償金を支払うような大きなものになりかねません。事故の原因は運転技術や交通ルールだけではありません。自転車事故の原因の多くは、自転車の運転技術が未熟であること、交通ルールを守らないことですが、ほかにも、自転車の整備不良などが挙げられます。自転車も自動車と同じ車両ですので、整備がしっかりとされていなければ安全性が損なわれることも多いに考えられます。
安全に自転車に乗るには、日々の点検も大切です。日常的な点検とは、自転車に乗る人が日々行う点検です。自転車に乗る前には毎回必ず簡単なチェックをして、安全に乗れる状態かを確認します。ブレーキ、タイヤ、反射材、車体、ベルなど各部位をじっくりと点検し、ワイヤーのほつれや錆び、汚れなどがあれば、必要に応じて整備をする、専門店で修理をしてもらうようにしてください。また、日常的な点検に加え、車体を布で拭くなどのメンテナンスをすることで、安全面はもちろん見た目も美しく、長く自転車に乗ることができるでしょう。
今日は、自転車屋さんに来校していただき詳しくチェックしてもらいました。自転車整備カードをもらった人は、、近くの自転車さんに行き、部品の不備や各部位の劣化などをみてもらい、必要に応じて修理をしてもらい、ベストな状態の自転車に乗りましょう。
日頃から安全に自転車に乗ることを意識することは、事故を防ぐことにつながるだけでなく、自転車をベストな状態で維持することにもなります。



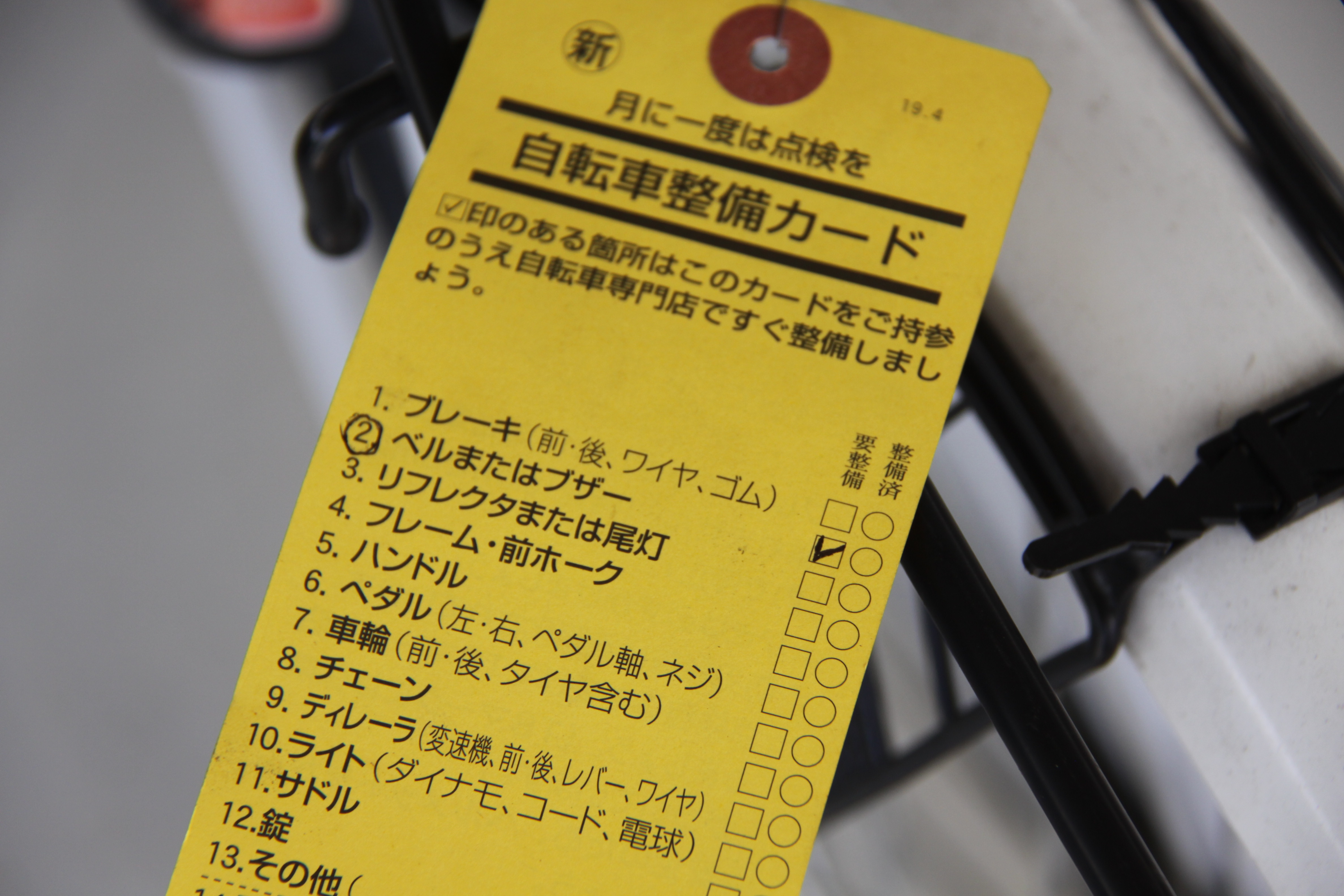





◎ひな中の風~~
たましいRevolution(9/25 歌声が響く朝 )


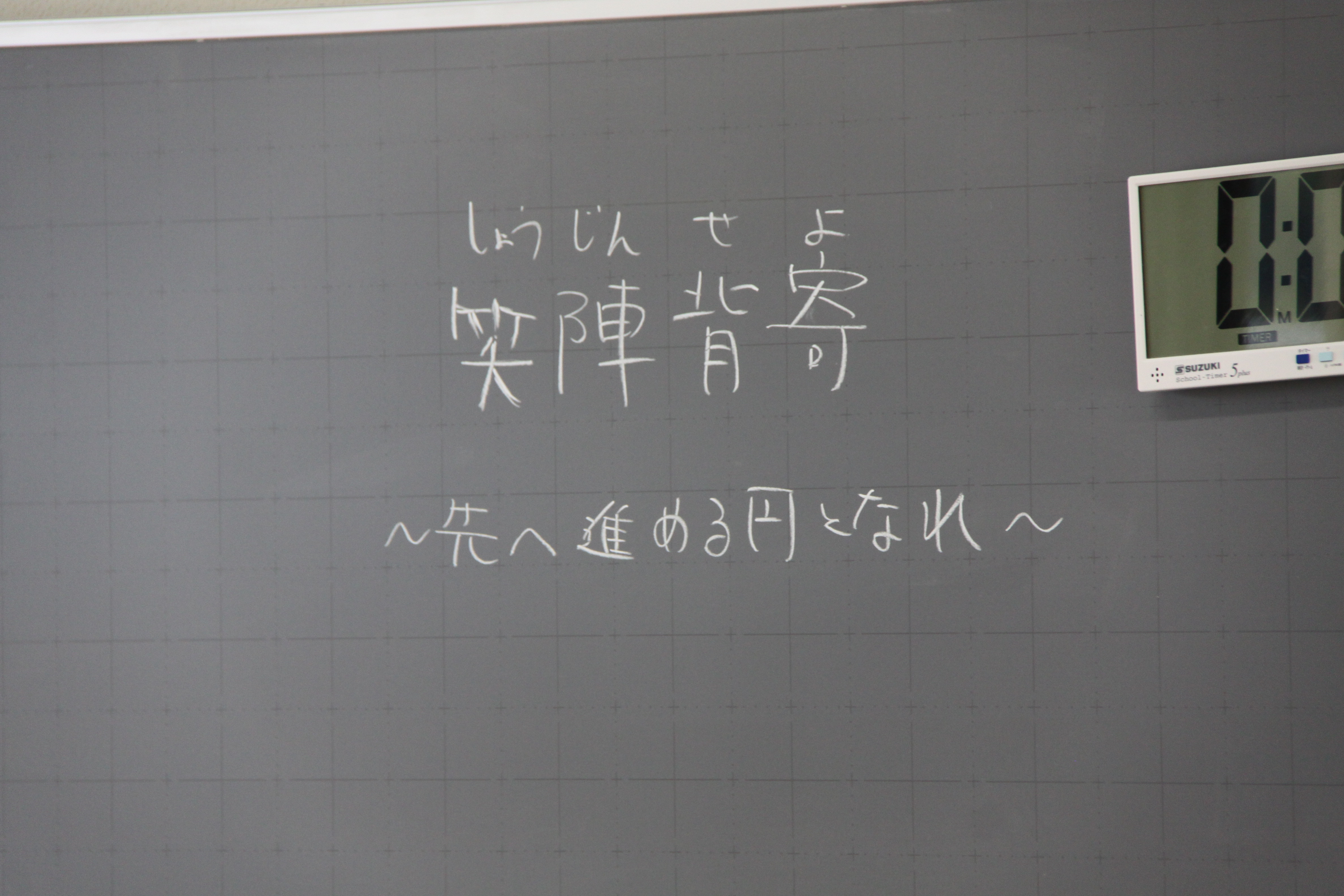

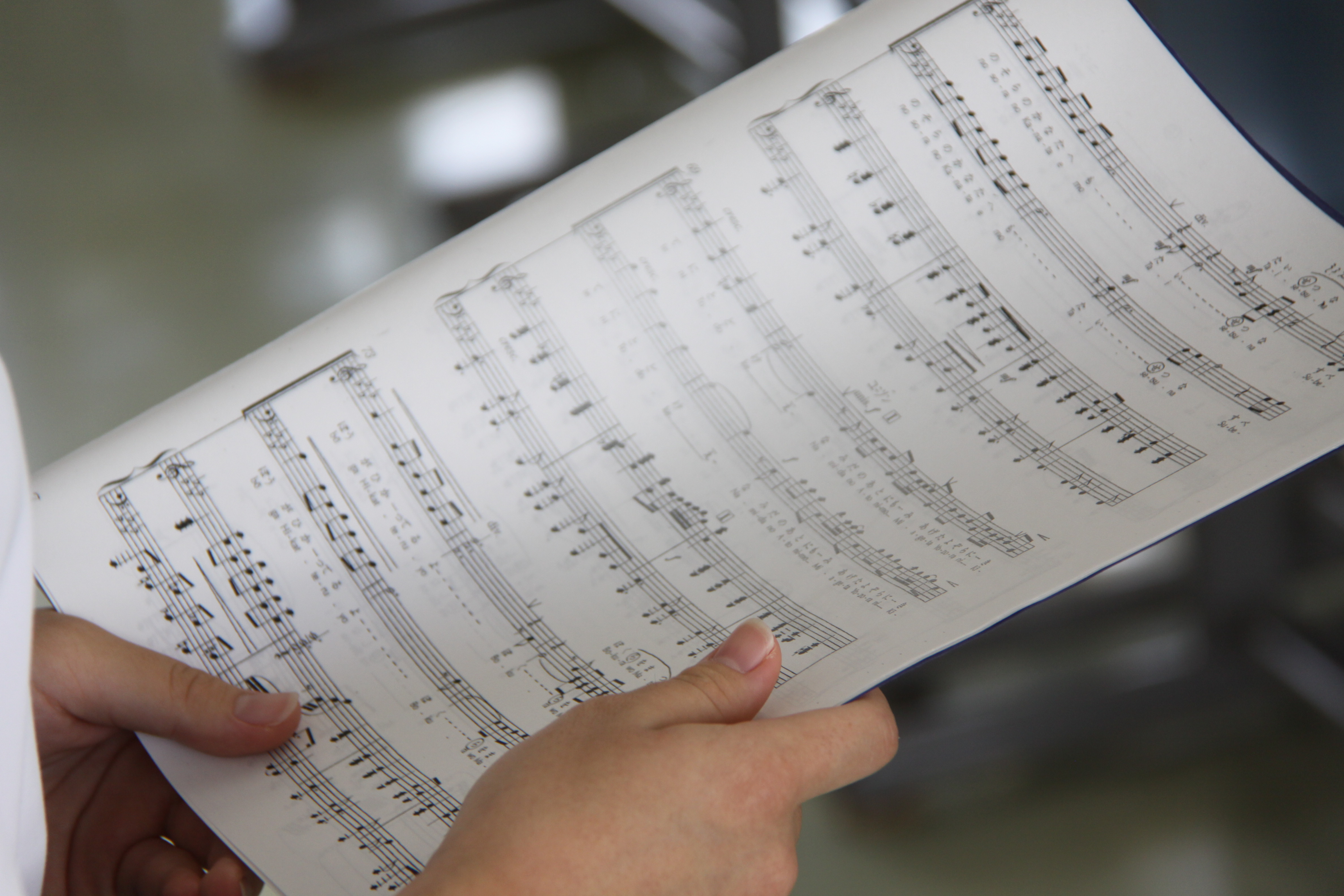

◎Don’t be afraid of new arenas. Elon Musk(9/22図書室)
(新しい舞台に立つことを恐れるな。)
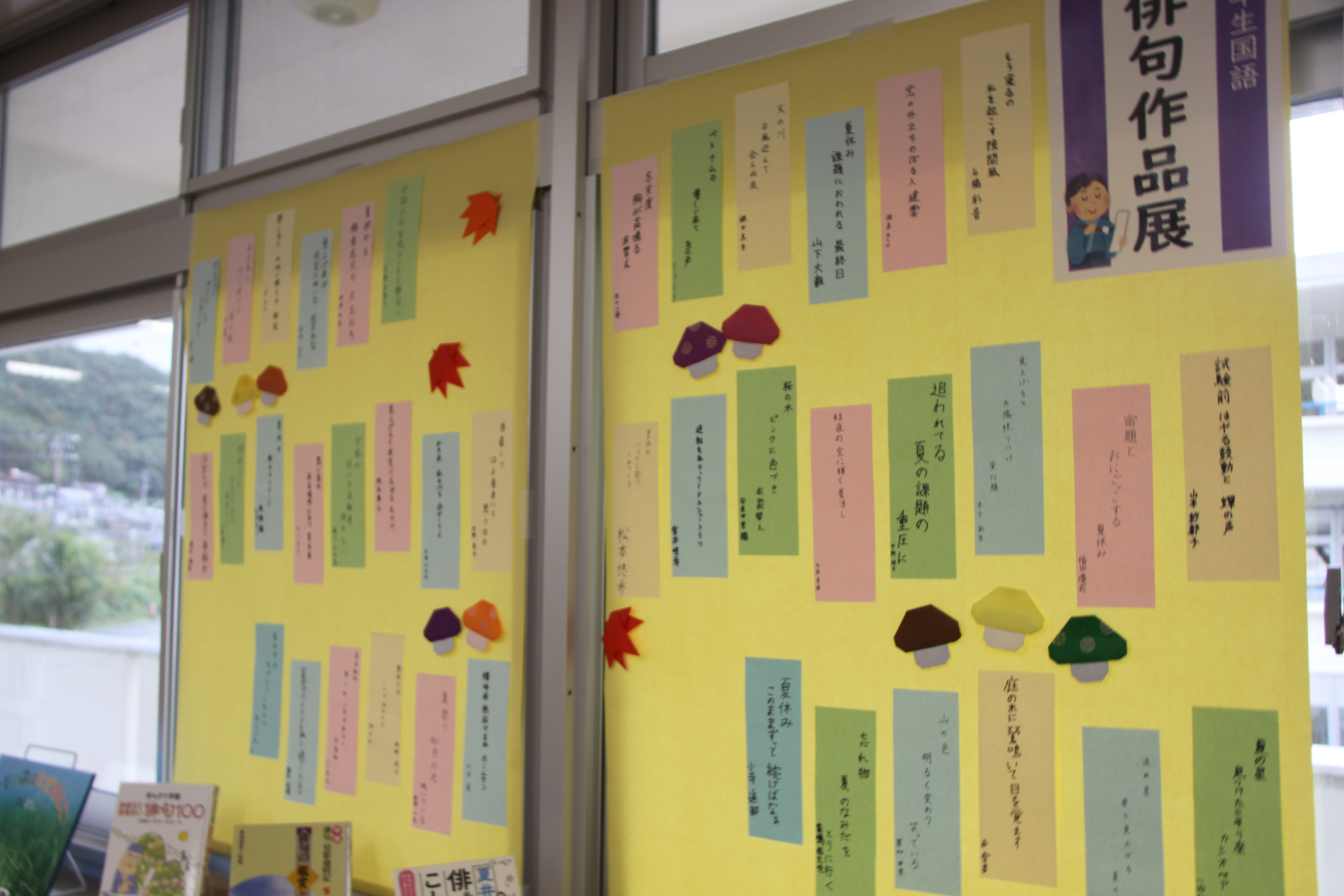
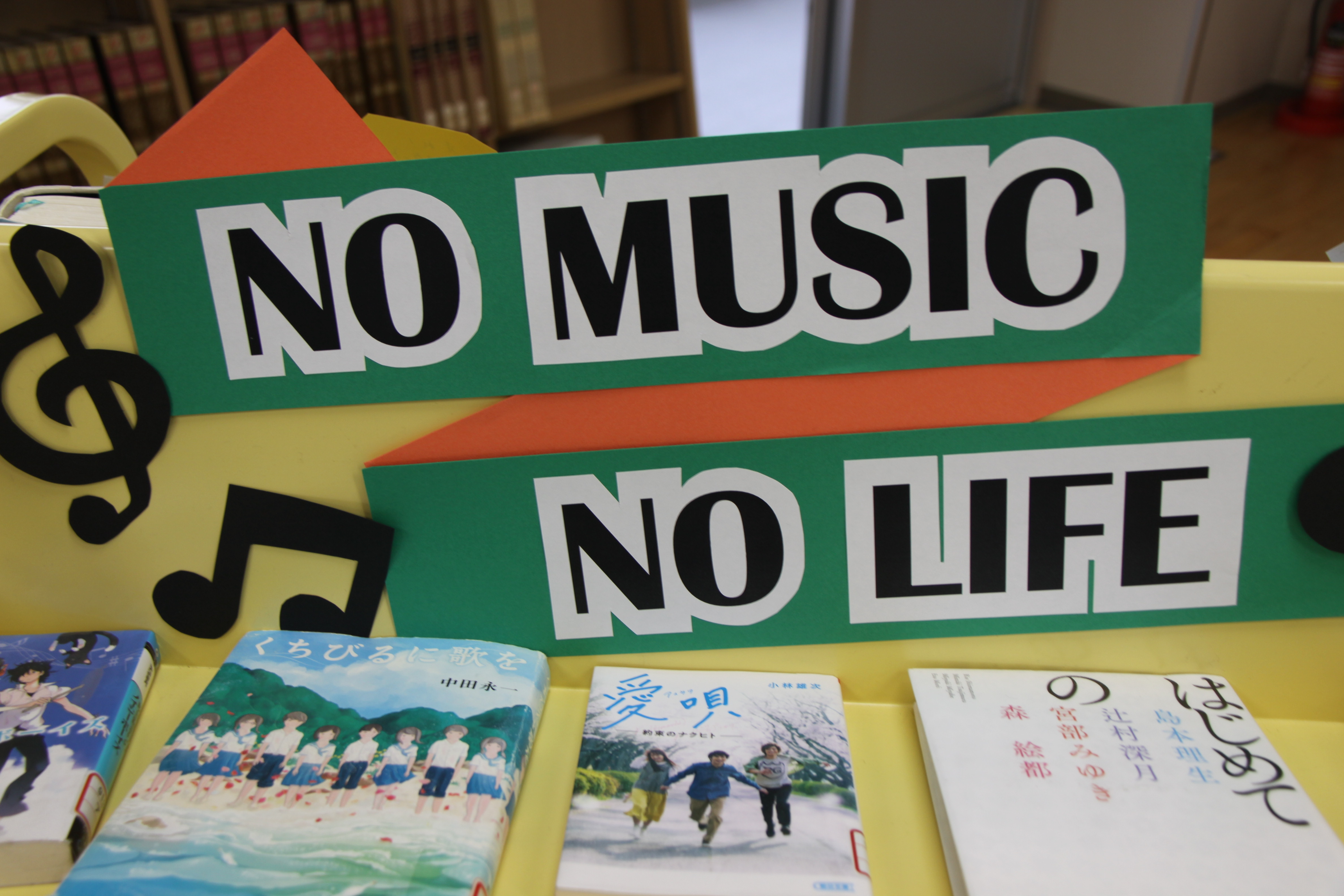

◎おいしくいただく(9/22)
調理場から北川先生が来校されました。気温差が大きいこの時期、体調に注意し、食生活を大切にしていくことについてお話をしてくださいました。





〈ちょっと食育〉脳は「情報」を食べている!?(NHKスペシャル「食の起源」より一部)
番組では、脳が感じるおいしさの不思議を実感するため、ある実験を行いました。20代から40代までの男女30人に集まってもらい、AとB、2つのグループに分けます。みなさん全員に、同じ食材を使ったポタージュスープとペペロンチーノを食べてもらいました。
すると、食べた料理は全く同じなのに、感想がまるで違いました!Aグループは「味が薄い」「クスリ的な味がする」と不人気。一方のBグループは「後味が良かった」「優しい味でした」と大好評だったんです。一体、なぜなんでしょう?
実は2つのグループ、食べるときに伝えられた「料理の名前」が違ったんです。例えば、スープは、Aグループには「低脂肪ごぼう健康スープ」、Bグループには「鳴門鯛のダシたっぷりポタージュ」。パスタは、Aグループには「パスタ風ズッキーニと大根の炒め物」、Bグループには「モチシャキ2色麺の創作ペペロンチーノ」と伝えられていました。どちらがおいしいそうかと聞かれたら、皆さんも、Bグループの方だと感じるのではないでしょうか。実際、料理の名前を「おいしそう」にするだけで、食事に満足する人の割合は、Aグループが60%なのに対し、Bグループは87%と上昇しました。私たちは、自分の舌や嗅覚より、人から与えられる情報でおいしさを感じるという、不思議な能力があるのです。
同じ料理でも名前が違うとおいしさが変わる!?
同じような社会実験がアメリカで行われていて、その成果が確かめられています。世界的な研究機関「better buying lab」では、世界有数の企業やホテルと手を組み、人気の薄いヘルシーな料理をどうにかしてお客さんに食べてもらおうとある試みを行いました。それは、「料理の名前を、美食をイメージさせるものに変える」だけ。
例えば「肉なしソーセージ」という料理名を、ソーセージ作りで有名な地域名をつけた「カンバーランド地方のスパイス野菜ソーセージ」にネーミングチェンジ。たったそれだけのことで、ヘルシーメニューの売り上げは76%もアップ!人は伝えられる情報だけで、簡単に感じる「おいしさ」が変わってしまうんです!
脳は結構ダマされやすい?
そのとき私たちの脳では何が起きているのか。最新研究で、実験からわかってきました。用意したのは、同じ苦さの2つの液体。ただし、一方は「強い苦味」、もう一方は「弱い苦味」だと被験者に伝えます。2つの液体を飲んだ時の脳の活動を調べると、興味深い結果が得られました。
注目したのは、苦味に対する嫌悪感を生み出す、「扁桃体」と呼ばれる脳の部分の反応です。「強い苦味」と伝えられた液体を飲むと、扁桃体は強い嫌悪感を示しました。ところが、同じ苦味の強さなのに「弱い苦味」だと伝えられた液体を飲んだ後は、嫌悪感が大きく弱まったのです。
あなたはどちらが苦そうに感じますか?
このとき脳全体の活動を見ると、もう一つ、活発に働いている場所が見つかりました。それは、「眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)」。眼窩前頭皮質は、味覚や嗅覚の情報だけでなく、体の五感全ての情報が集まる仕組みになっています。そのため、「苦くない」という情報を事前に伝えられると、眼窩前頭皮質はこれから口にする味を「苦くない」と予測。その後実際に苦い液体を口にしても、「苦くない」という判断を下すことが確かめられたのです。
苦手な食べ物がある人も、誰かに上手に料理してもらって、「これはおいしいよ!」と言われて口にしたら、脳が「おいしく」感じてくれるかもしれませんよ。
◎シン・日生中へ(9/21) 立ち合い演説会・投票


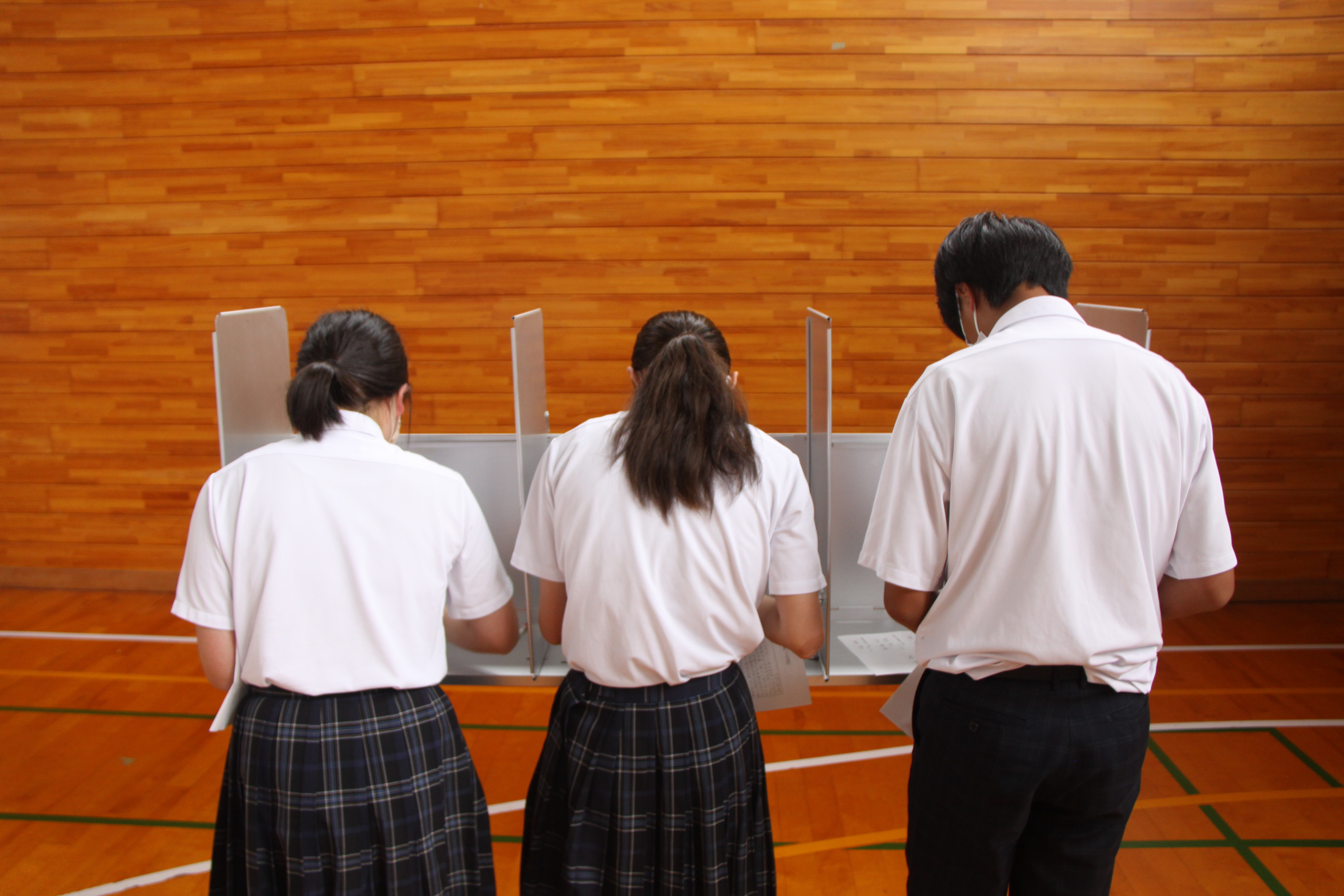

◎ひな中の風~~授業が大切(9/21 この日の美術科)








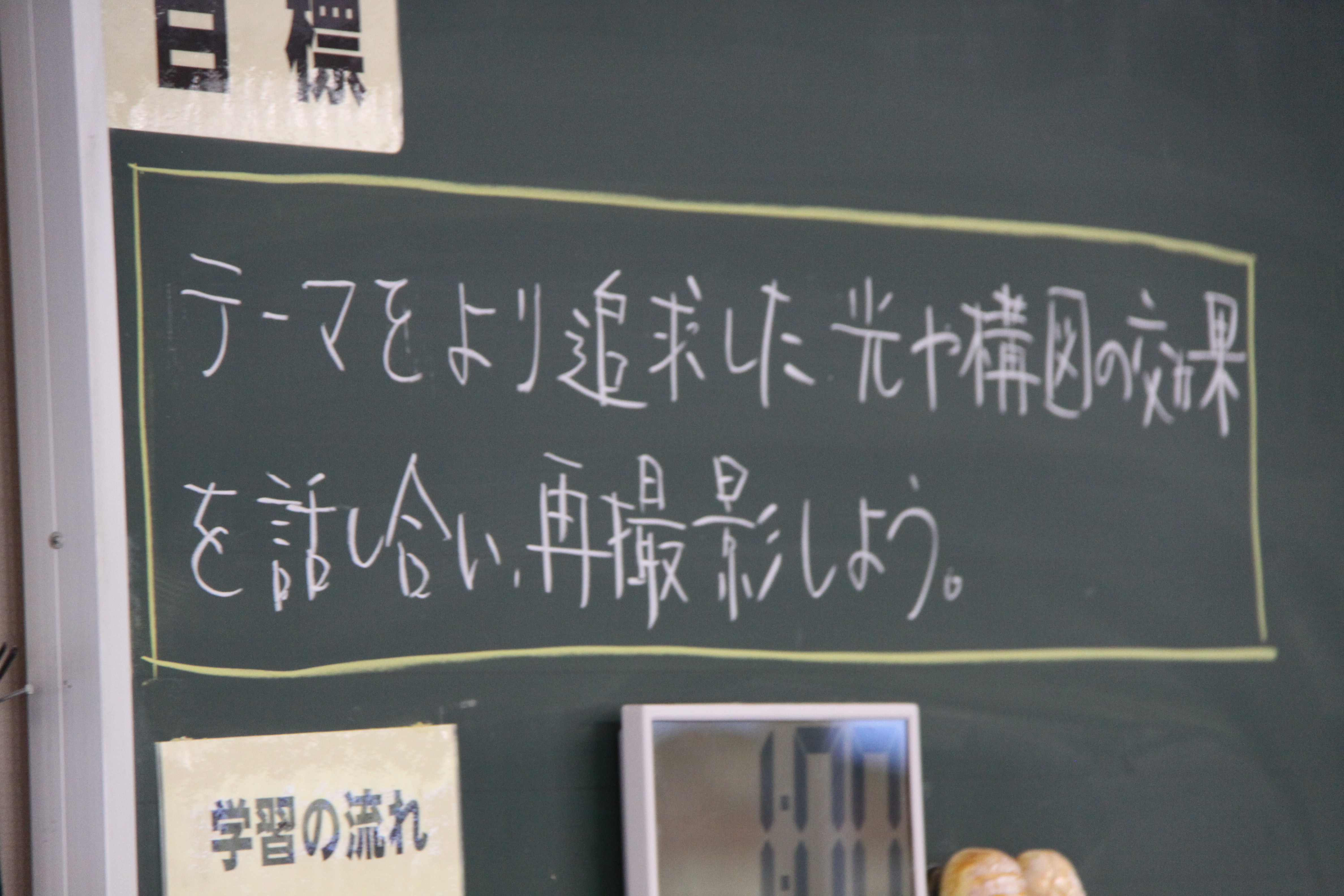
◎多くの人に支えられて
~「ありがとう」と感謝の意を伝えられるひな中の生徒たちです。
経年劣化等で汚れていた体育館の更衣室・トイレを、時間をかけて整備してもらいました。きれいになった更衣室に気づいた生徒らが、立川先生に「ありがとうございます」と言っている声を聞きました。きれいに、大切に施設を使おうね。



◎〈ついてってやれるのはその入り口まであとは一人でおやすみ坊や
俵万智〉

◎〈明日はどっちだ?〉選挙管理委員会
~立会演説会リハーサル・会場準備(9/20)




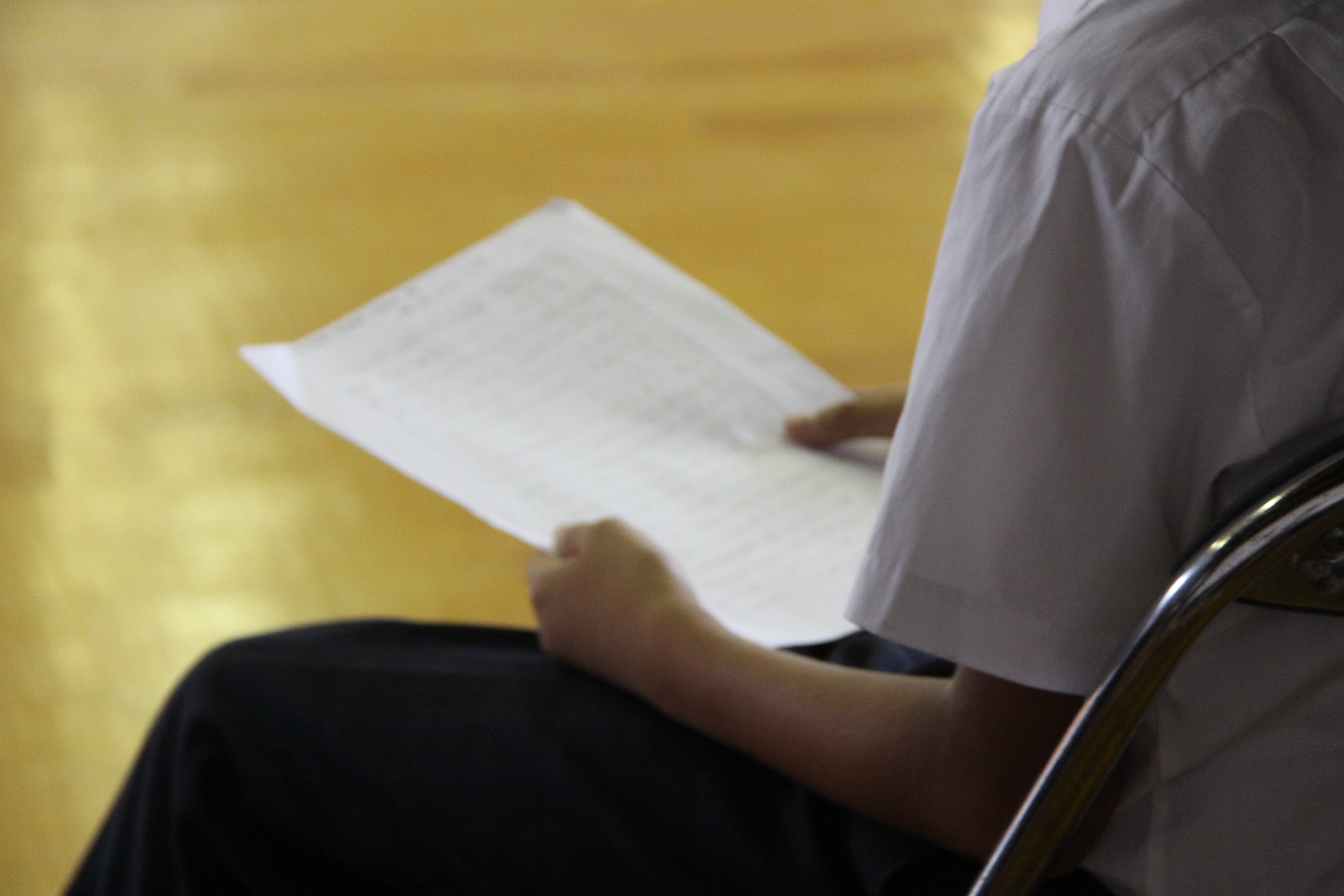
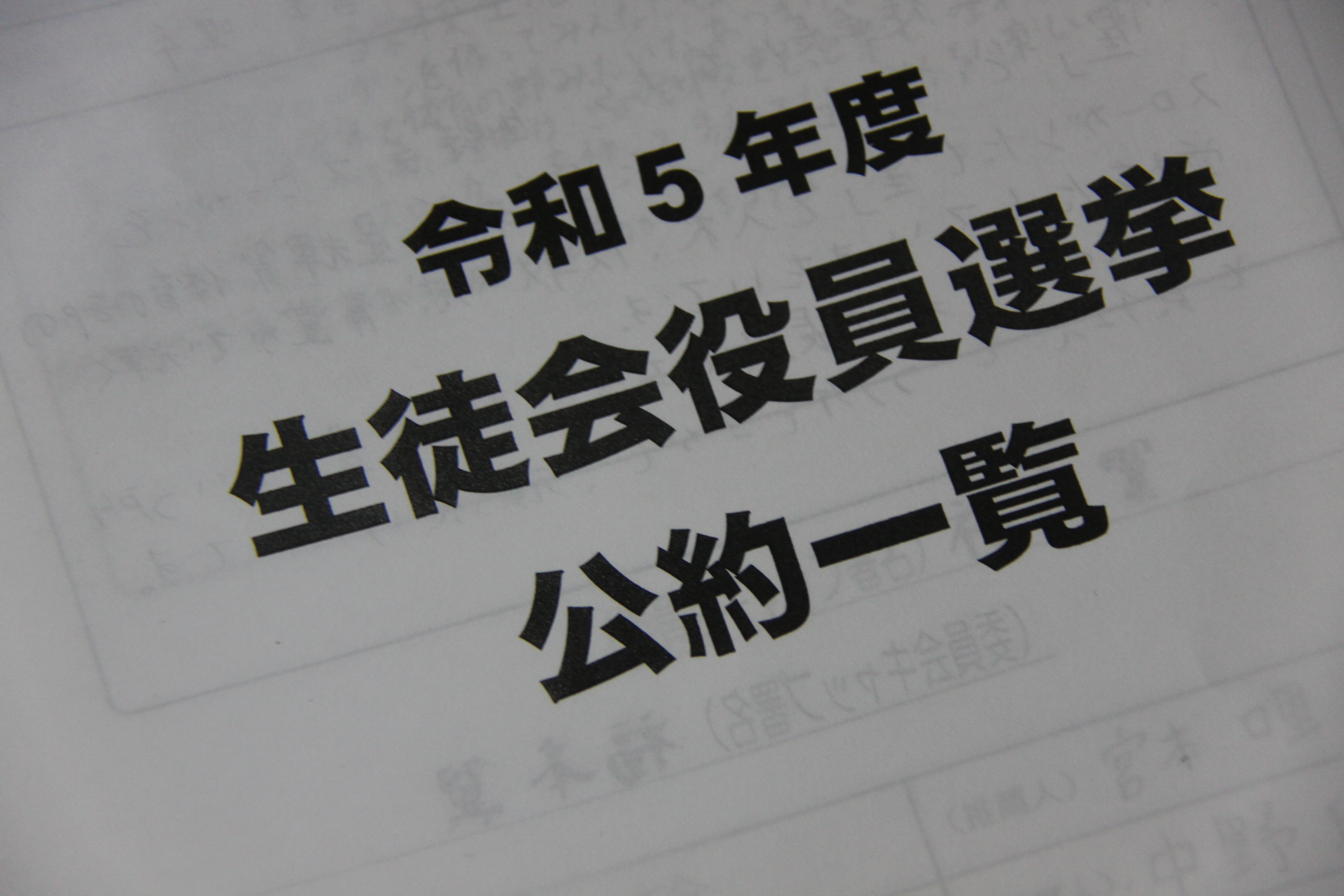
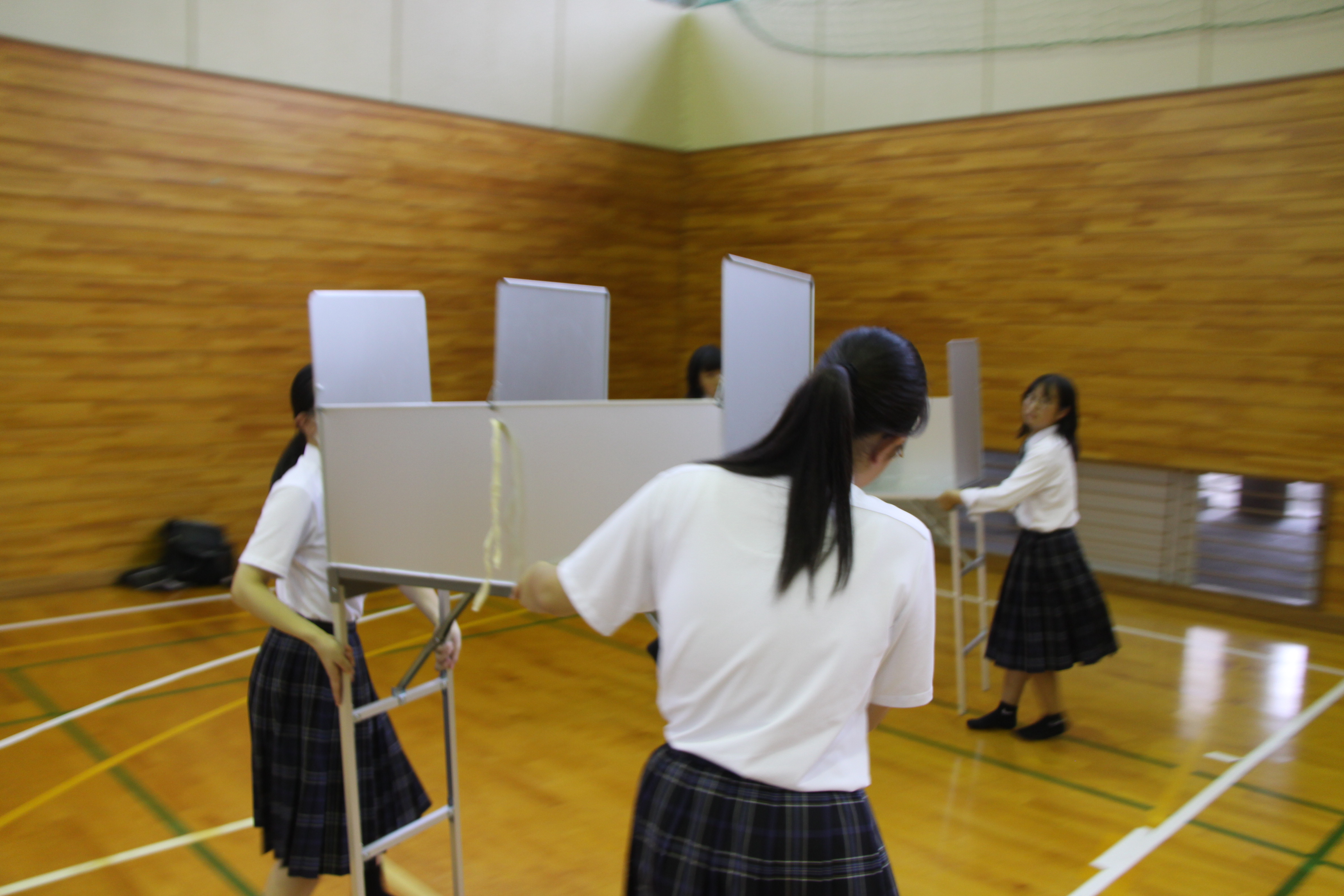


Some people want it to happen‚ some wish it would happen‚ others make it happen. Michael Jordan
(実現したいと願う人もいれば、実現してくれたらいいのにと夢想する人もいる。そして、みずから実現する人もいる。)
◎私たちのはじまりの風景 ~わかるかな?ここってどこでしょう。(9/20)






◎最初にコトバありき ~語る・聞く・知る学級弁論大会(9/19~)
〈論題〉友達 交通の危険性 友達の大切さ 兄の仕事 自殺防止~SNSの使い方~ 弁論はしたほうがよいのか 3年間の成長 リーダーとして 食事の大切さ 努力って何? 毎日の部活動 地球の温暖化 平和な世界の実現に向けて マイクロプラスチックの怖さ 家族と過ごすことの大切さ 星輝祭体育の部で得たもの 戦争がなくならない問題 平等 8年間野球をやって その努力は無駄ですか? 自殺防止について 時間の大切さ 訳を探る SNSの利点・欠点 日生の海から学んだこと ニュースを観て 地球の温暖化 スポーツについて 五教科を学ぶ理由 部活でがんばっていること 命の大切さについて 私たちにできること I‘m on a diet 税金と少子高齢化のかかわり 自分と戦った4年間 地球温暖化を防ぐには 将来の僕の夢 成功のカギは努力か運か スマホを持つようになって 今自分ができること ルールがあるのに 人の目消えていく動物 行動の前に考える 戦争の記憶を風化させないために コミュニケーションの大切さ ほっといても大丈夫? 地球温暖化の影響 中学生になってがんばりたいこと 大好きな野球をする中で 継続 あきらめずに努力することの大切さ さべつ 部活について 地球温暖化 ぼくは人がキライです けんかはいいこと 協力する大切さ 環境問題 海ゴミ問題への取り組みの重要性 ゴミのポイ捨てを見て考えたこと 私の誇り 日本に来て思うこと 選択の連続 コロナからの学び 自然を守るには 言葉の力、友達の大切さ 生命の素晴らしさ 私のおまじないの言葉 スマホでのトラブルについて いじめについて 部活動を通して 中国に行って 楽しむことの大切さ 礼儀正しく 「本気で向き合う」こと 「夢」について 動物の命について スマホとの関わり方 なぜ校則があるのか 部活に入ってから これからの世界 家族の大切さ 日生の伝統文化 時間の大切さ 健康のありがたさ 僕にとってのスポーツ 努力の成果 言葉のつかい方 言葉の力 部活について 平和について 想要世界和平 貧困を減らすためにできることは 中学校でがんばりたいこと 数学は日常に必要なのか 食費ロスについて考える コミュニケーションの大切さ 地球温暖化 部活動のけが SNSを正しく使うためには 得意と苦手 中学生になって ふつうの子って?
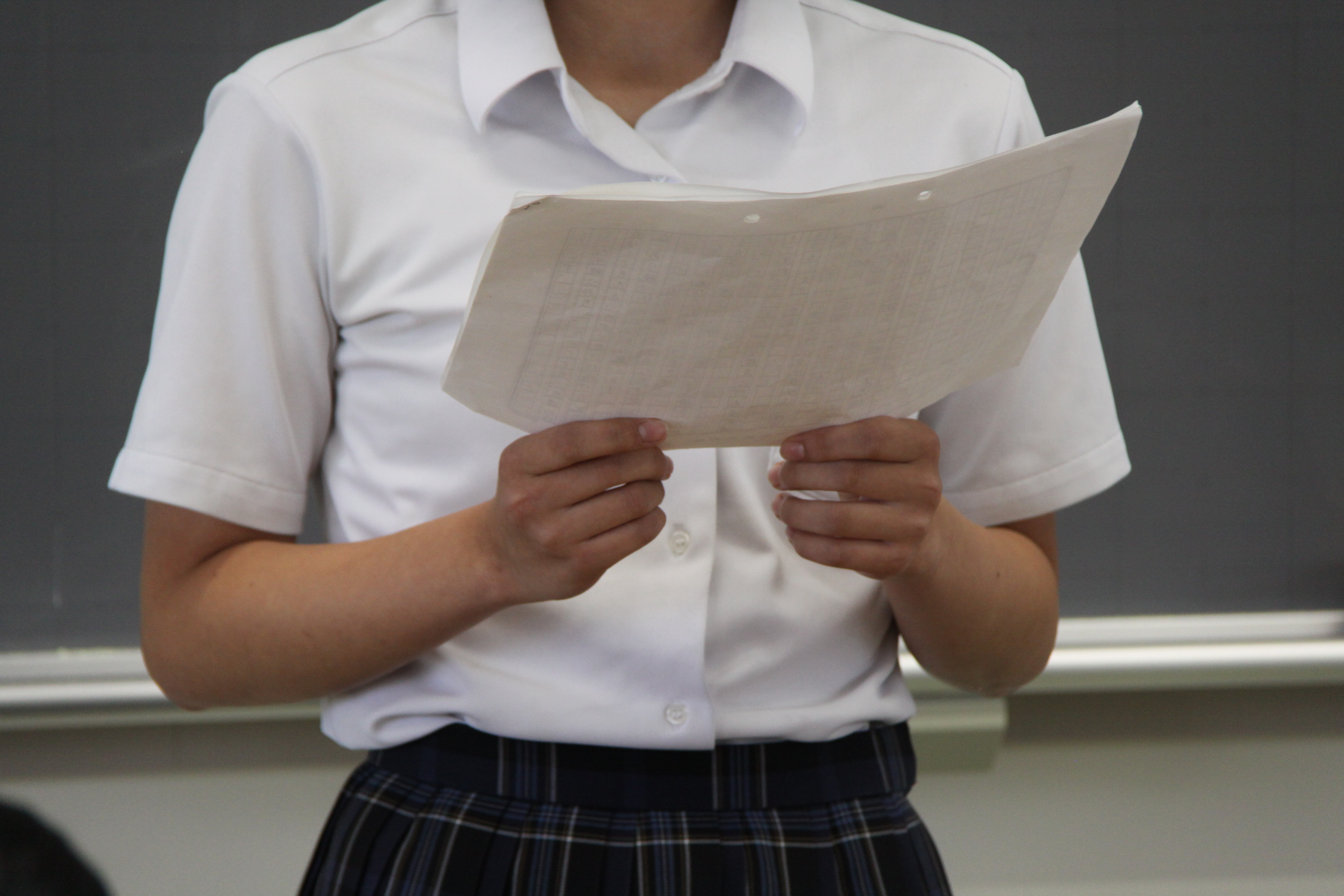




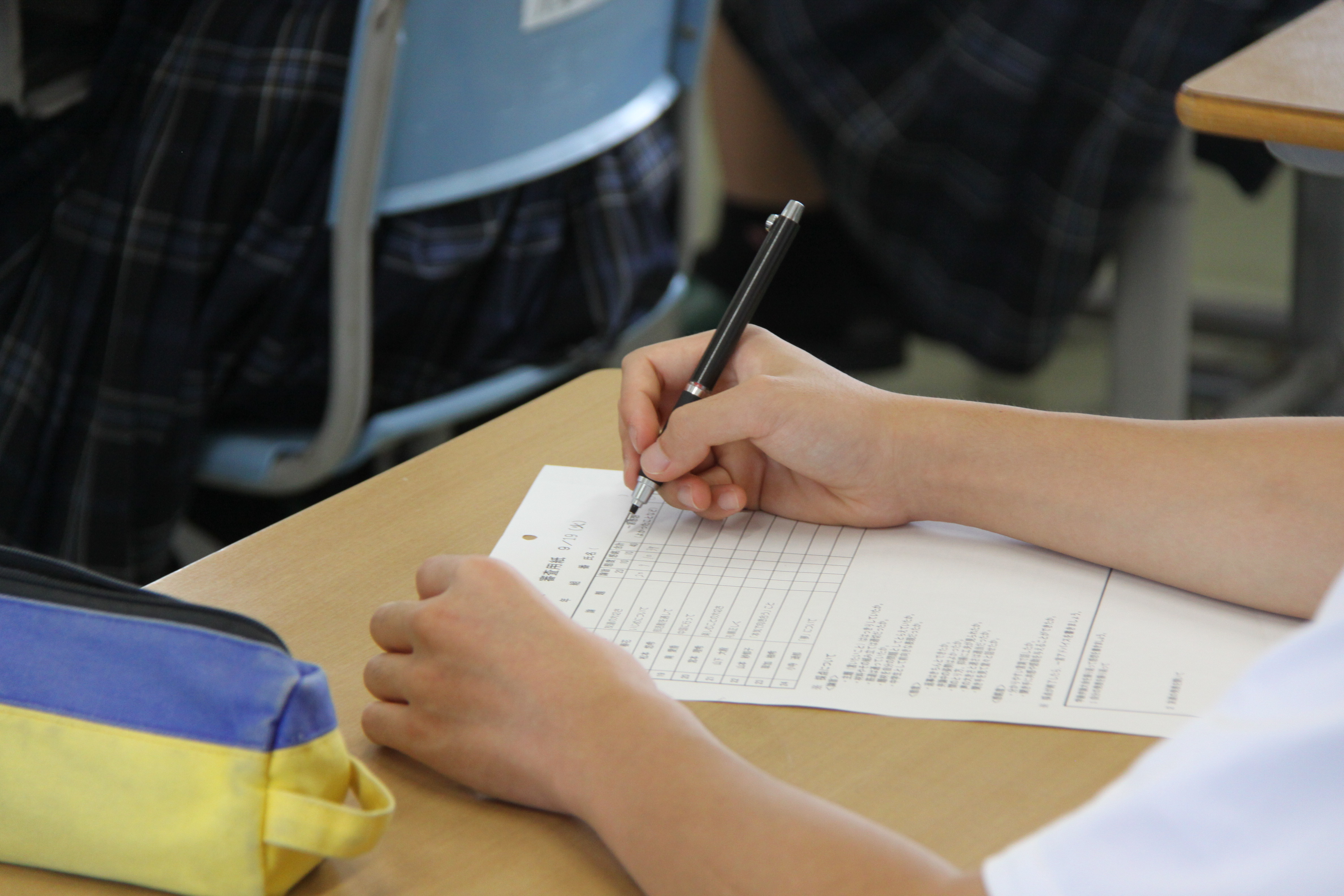

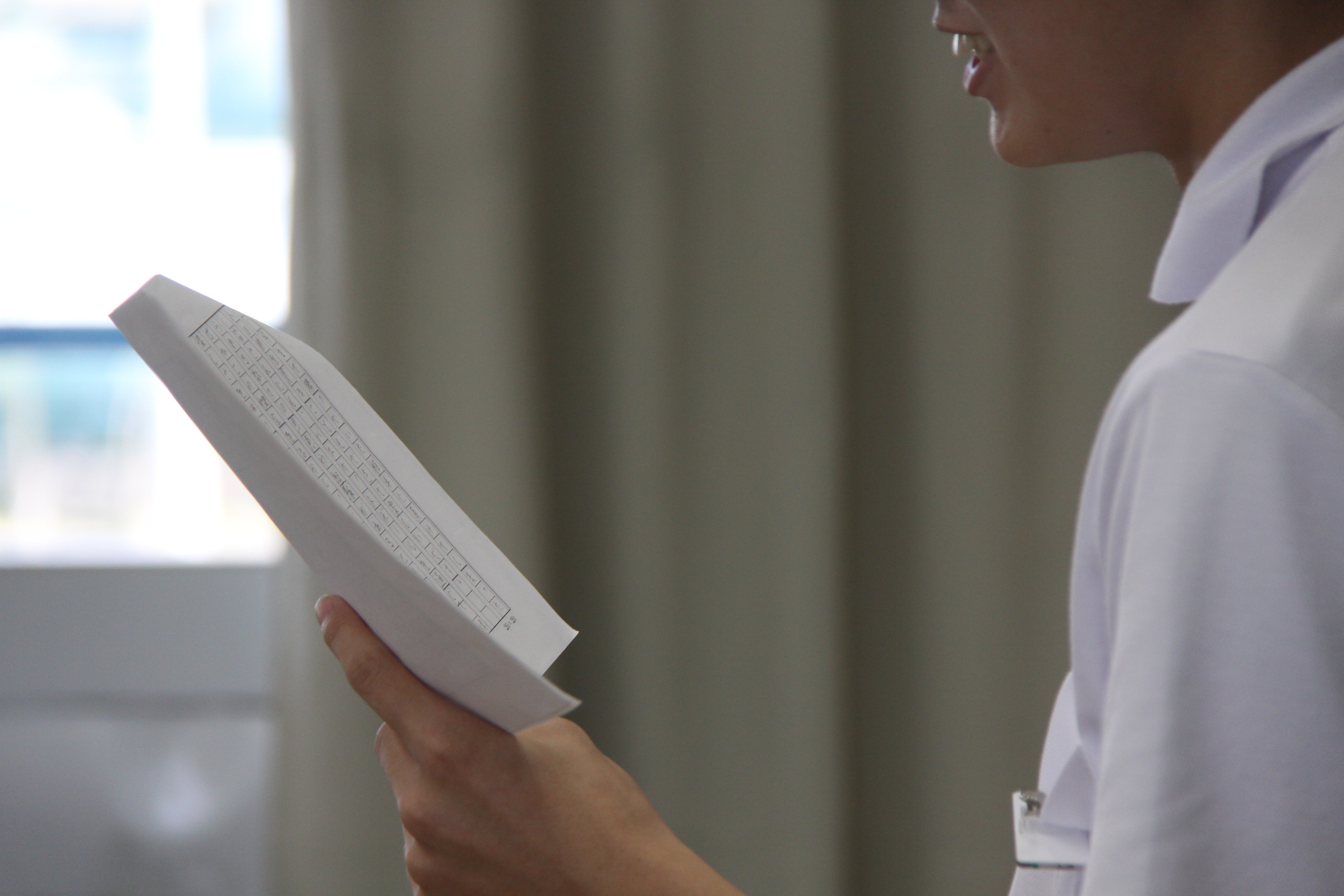
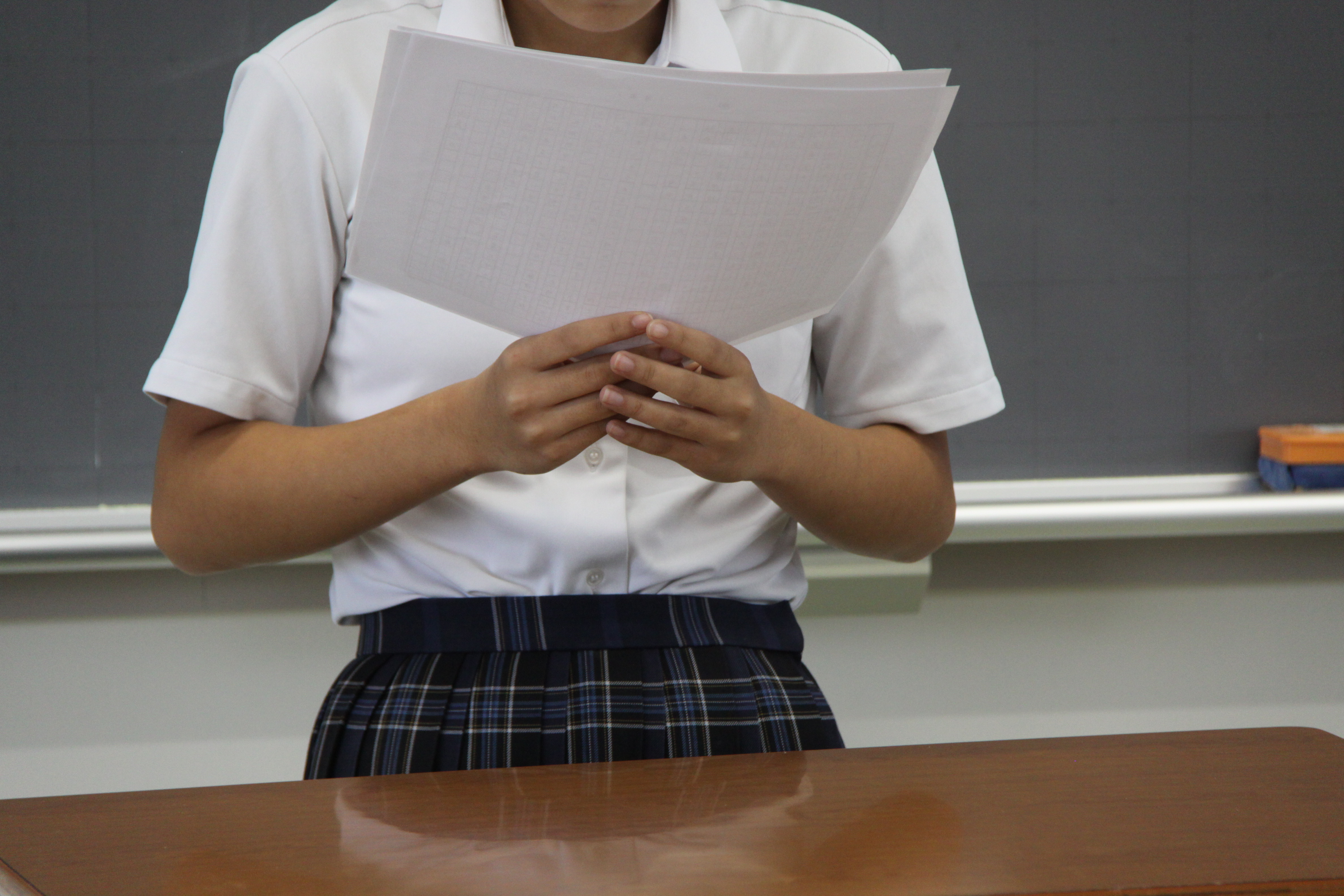
学級代表に選ばれた生徒は、10/7(土)星輝祭(文化の部)での校内弁論大会に出場します。
◎ひな中の風~~授業が大切
(9/19 この日の美術科。深く・アクティブな学びの追求)
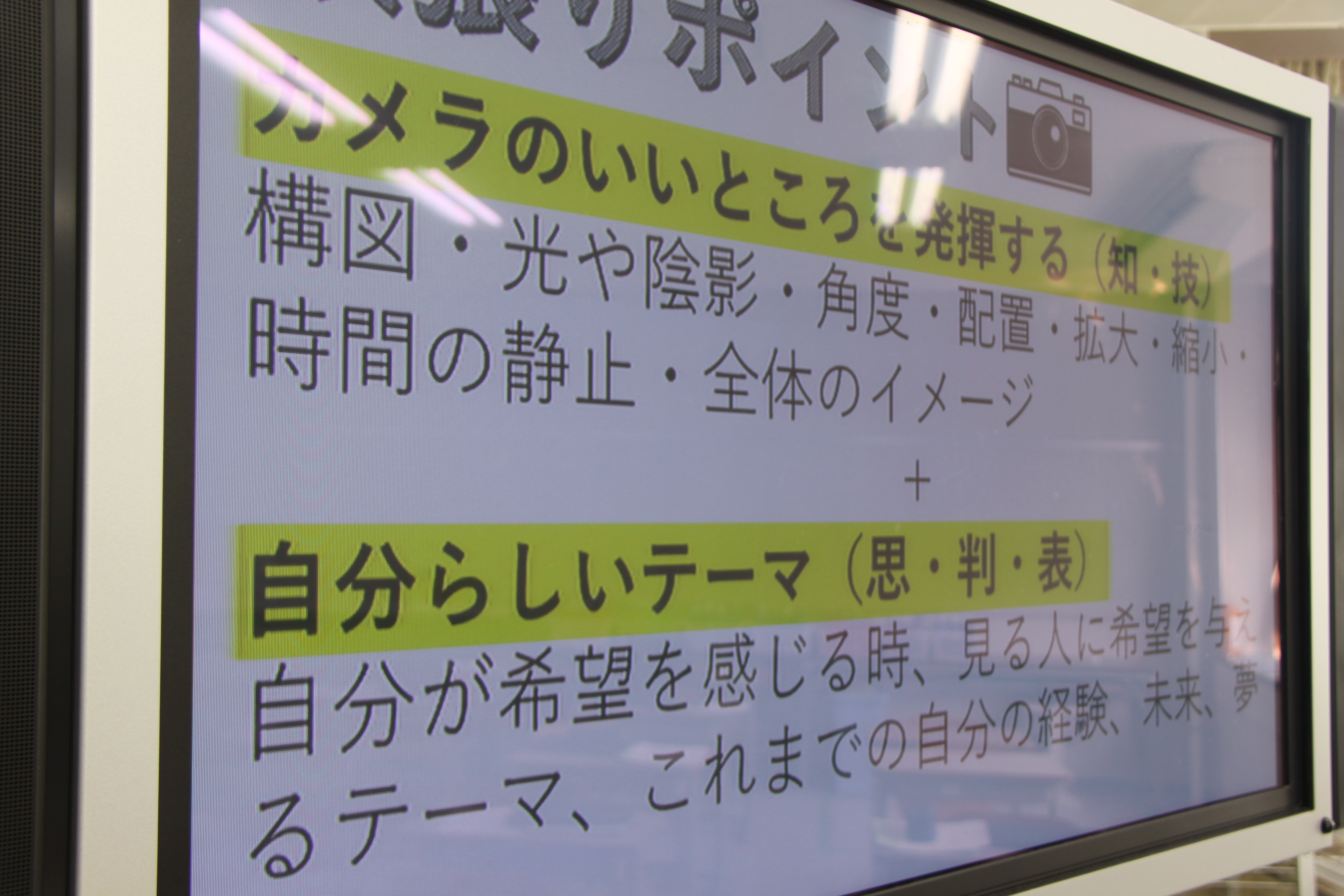







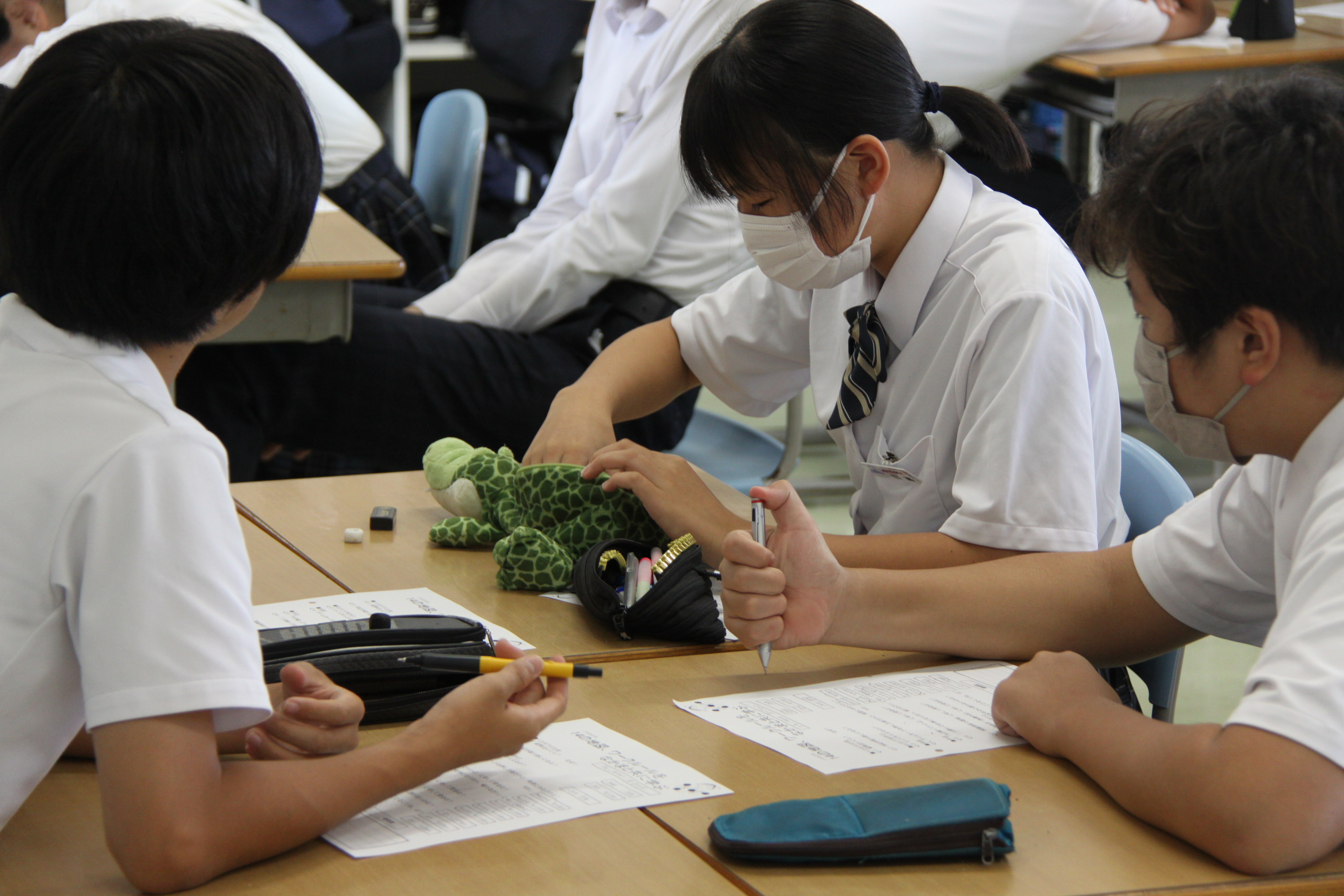
Individuals have to decide what is true and real for them. Tom Cruise
(人は、何が真実で何がリアルであるか選び定めなければならない。)
◎ひな中の風~~(9/19 8:12 選挙運動)
日生中未来予想図Ⅲ 「大切な一票がひな中を創る」

生徒会活動は、全校の生徒をもって組織する生徒会において、学校における自分たちの生活の充実・発展や学校生活の改善・向上を目指すために、生徒の立場から自発的、自治的に行われる活動である。また、異年齢の生徒同士で協力したり、よりよく交流したり、協働して目標の実現をしたりしようとする活動でもある。学校生活上の諸問題から課題を見いだし、その解決に向けて取り組む際に、生徒の自主性、自発性をできるだけ尊重し、生徒が自ら活動の計画を立て、生徒がそれぞれの役割を分担し、協力し合って日生中学校の生活を向上させていかなくてはならない。生徒会活動は、私たちが「どんな社会をつくっていくか」の基盤となる。
◎感謝。いま、また、ここから ~秋季大会・演奏会を終えて~
大会・会に向けて、準備や送迎等、そしてたくさんの応援、サポートをありがとうございました。この日の学びを新たな糧にして、また、仲間と共に支え、支えられ、がんばっていきます。(9/19より、最終下校は17:30となります)
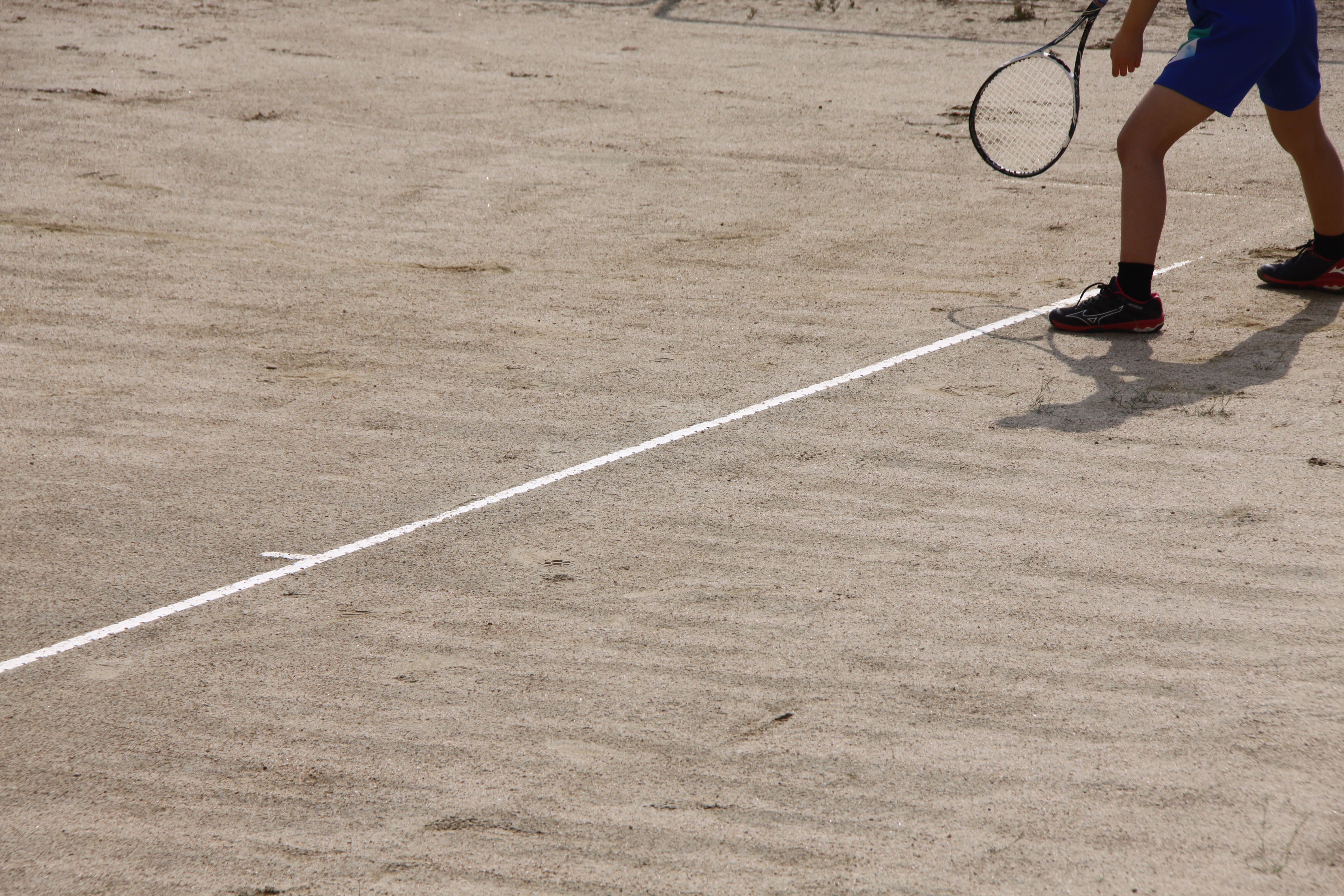
〈濁世の道俗、よくみづからおのれが能を思量せよとなり、知るべし 教行信証 親鸞〉
◎ひな中の風~~毎日がたいせつ

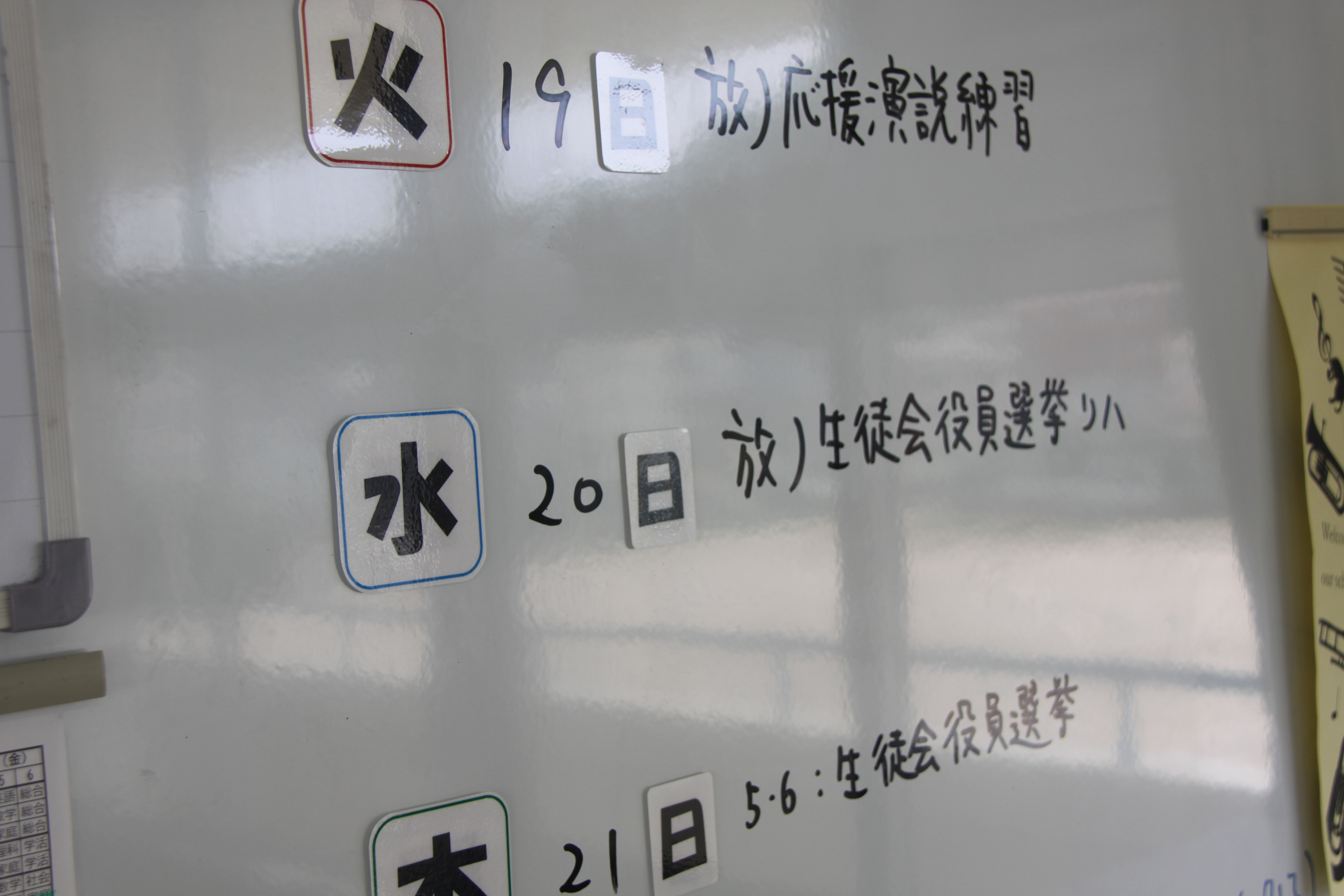
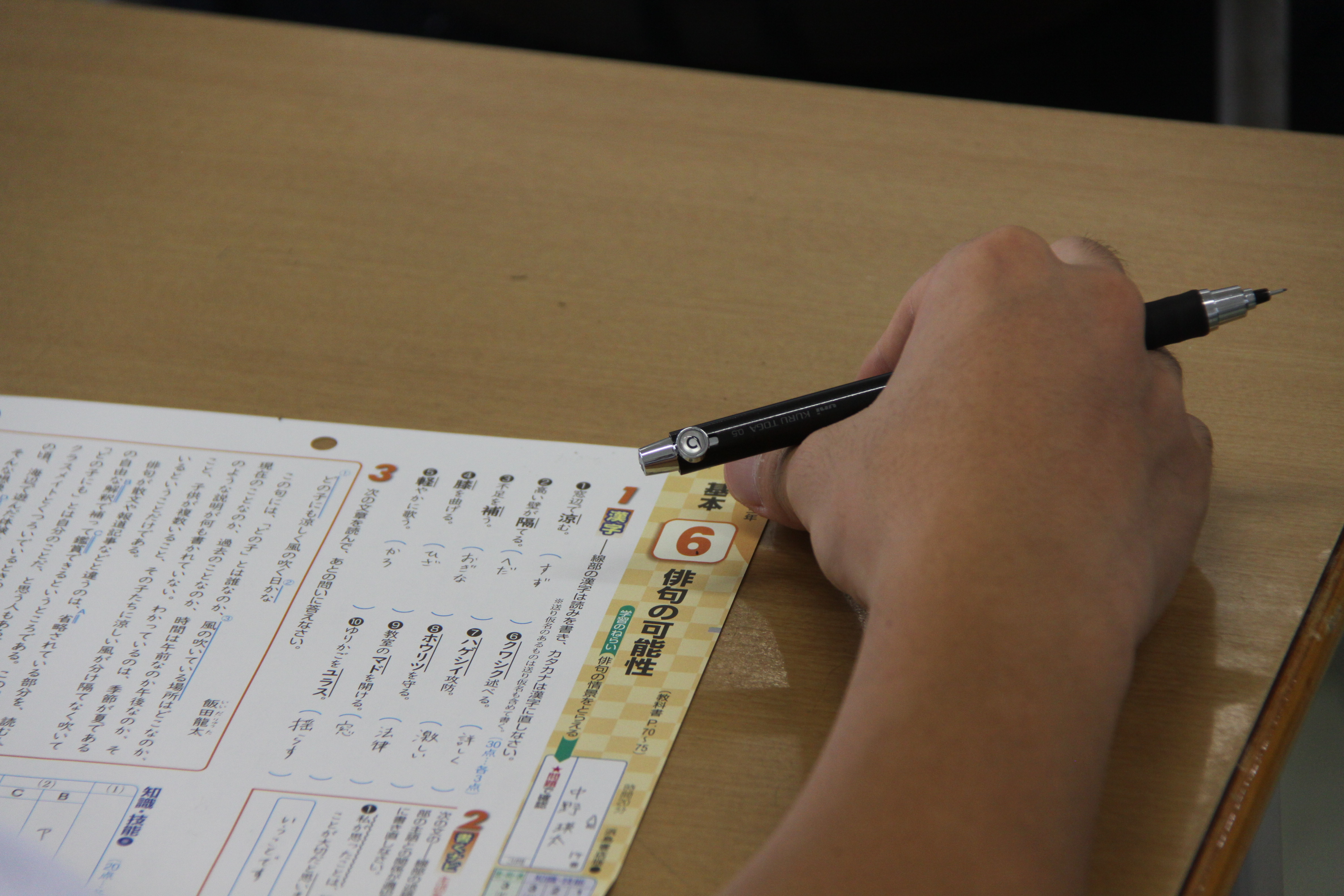
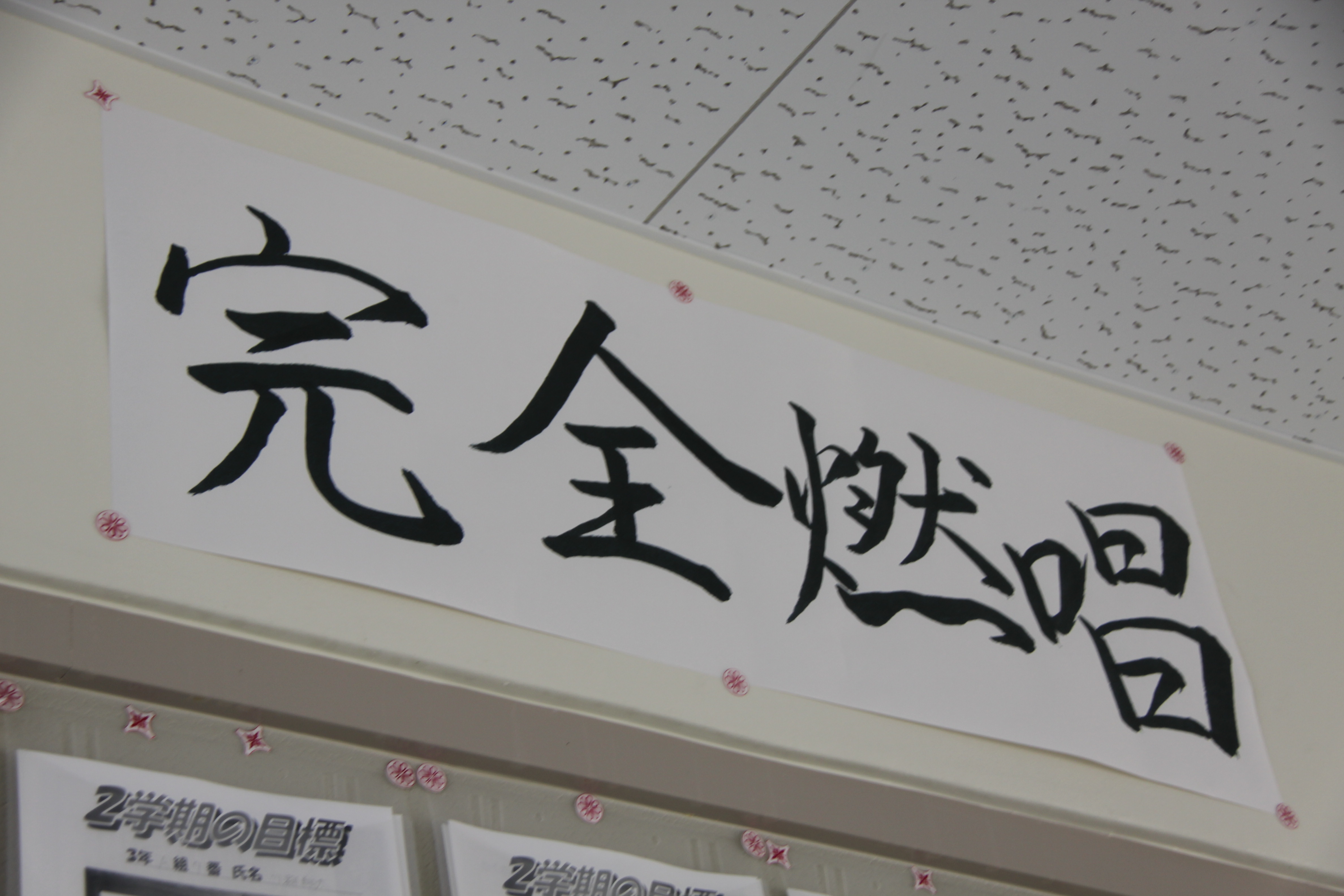
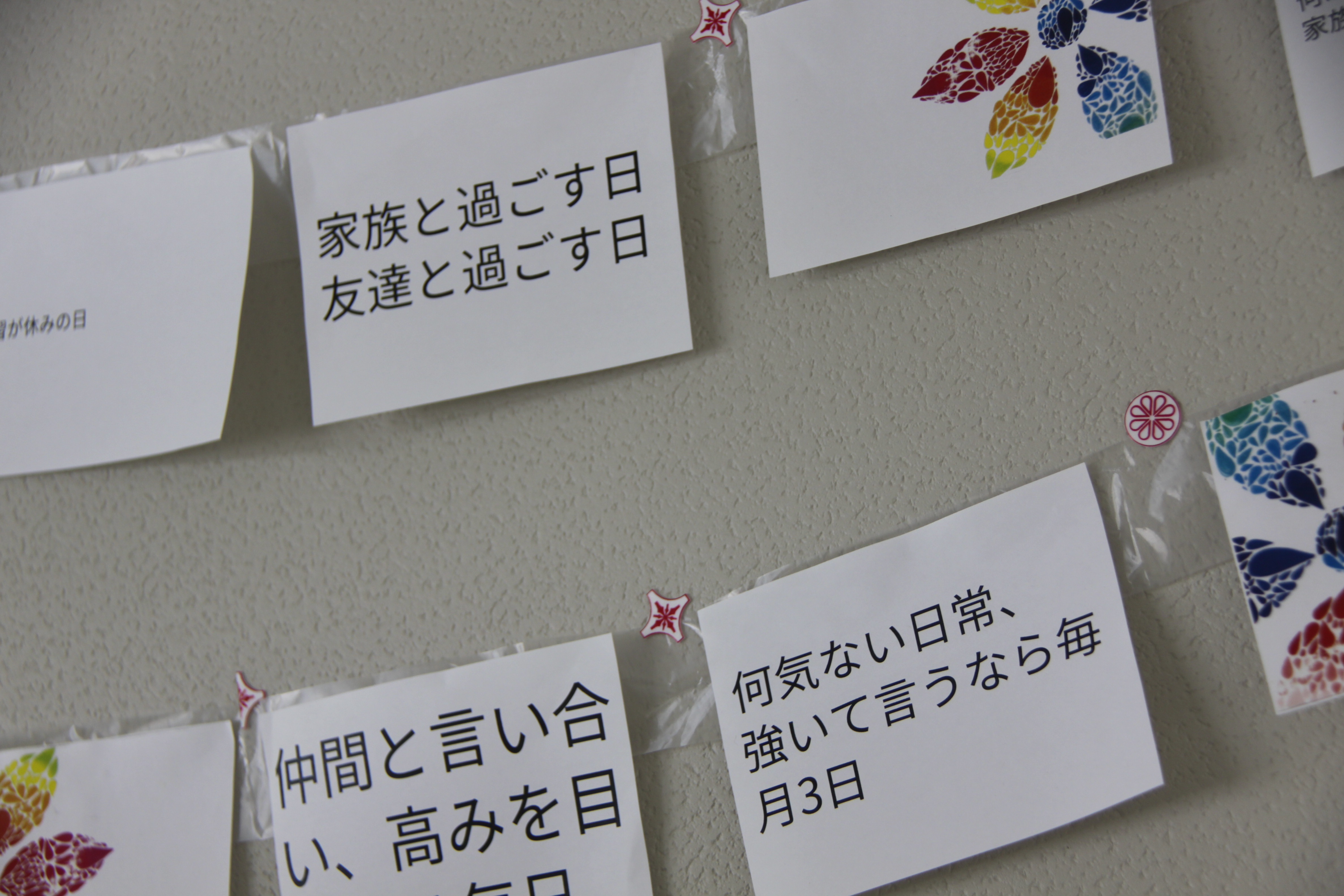
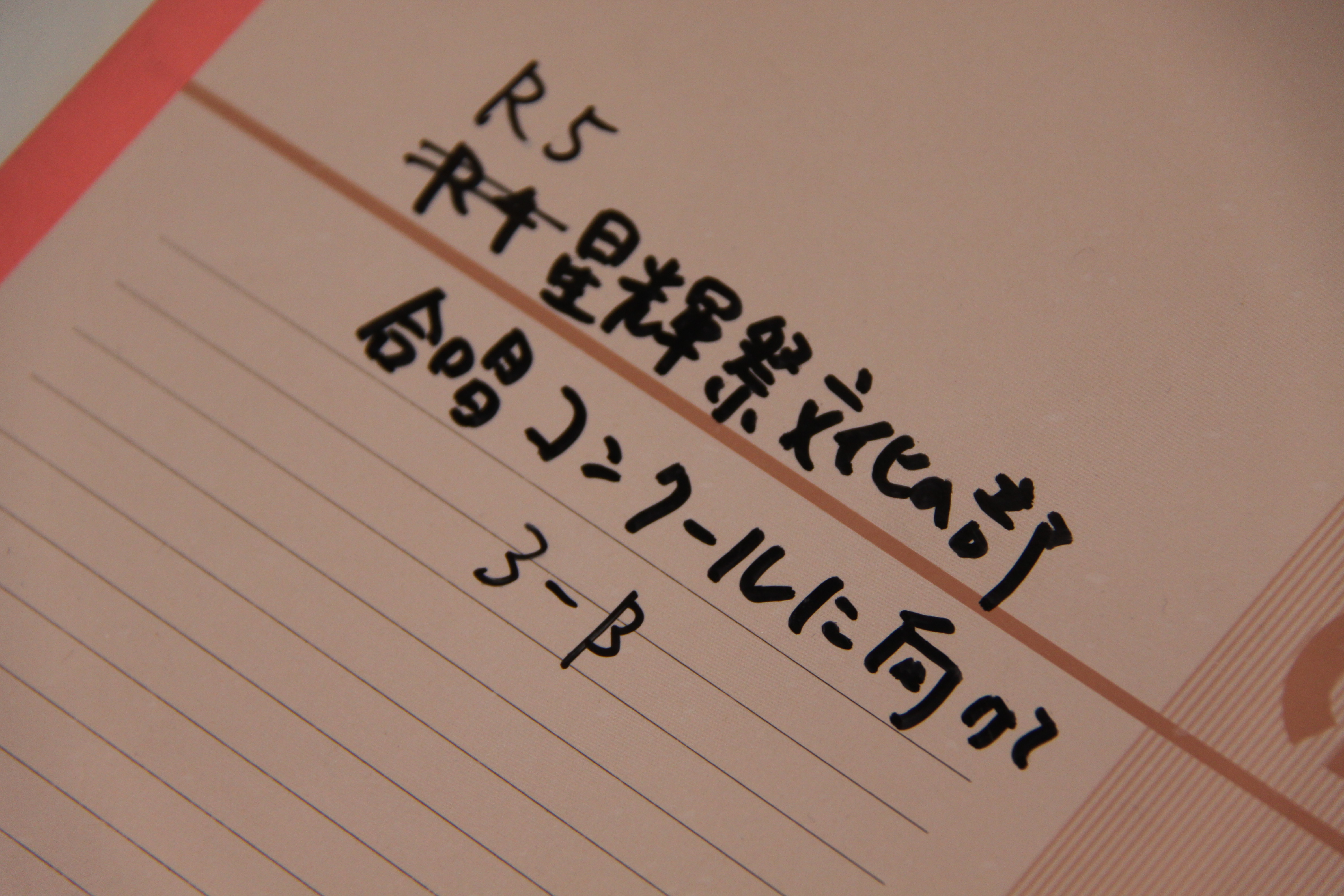



We must use time as a tool‚ not as a crutch. John F. Kennedy
(われわれは時間を道具のように使わねばいけない。すがりつく杖としてではなく。)
◎夢に向かってたくましく生きる生徒に(9/15)

〈ひな中チャレンジ企画〉
Jessicaと楽しく(*^o^*) 英会話を通してコミュニケーション力を伸ばしましょう。
〈英会話講座〉ご案内
今、みなさんは、夢・目標の実現に向けて、授業や学校行事において本当に積極的に取り組めています。そんな皆さんに、さらにチャレンジできる機会を提供したいと思い、ジェシカ先生に協力していただき、放課後の小人数での英会話教室を企画しました。夢・目標の実現に英語が必要な人、英会話や発展学習に関心のある人は、参加しましょう。
〇第1回 9月19日(火)
〇次の予定 10月17日(火) 24日(火) 31日(火) 11月14日(火) 12月 5日(火) 12日(火)
◎ひな中の風~~晩夏 重ねる日々(9/14)







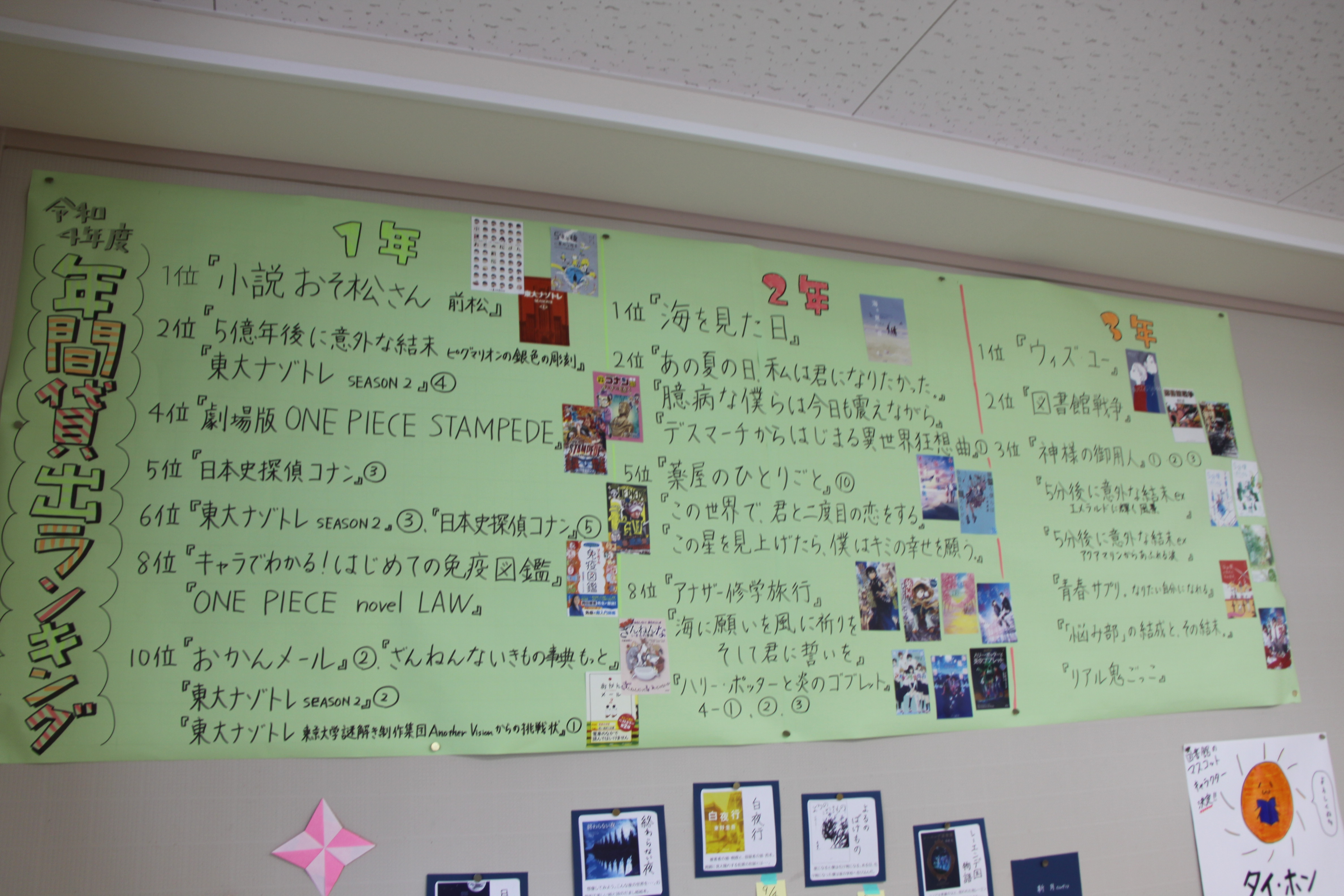

◎多くの人に支えられて
~ひなせっ子健全育成会下校見守り活動ありがとうございました(9/13)

 栄橋チームでの見守り活動
栄橋チームでの見守り活動◎大切なわたしの一票。~日生中生徒会選挙運動期間です~

◎ガンバロウ!一生懸命・ひたむきに・仲間とともに!
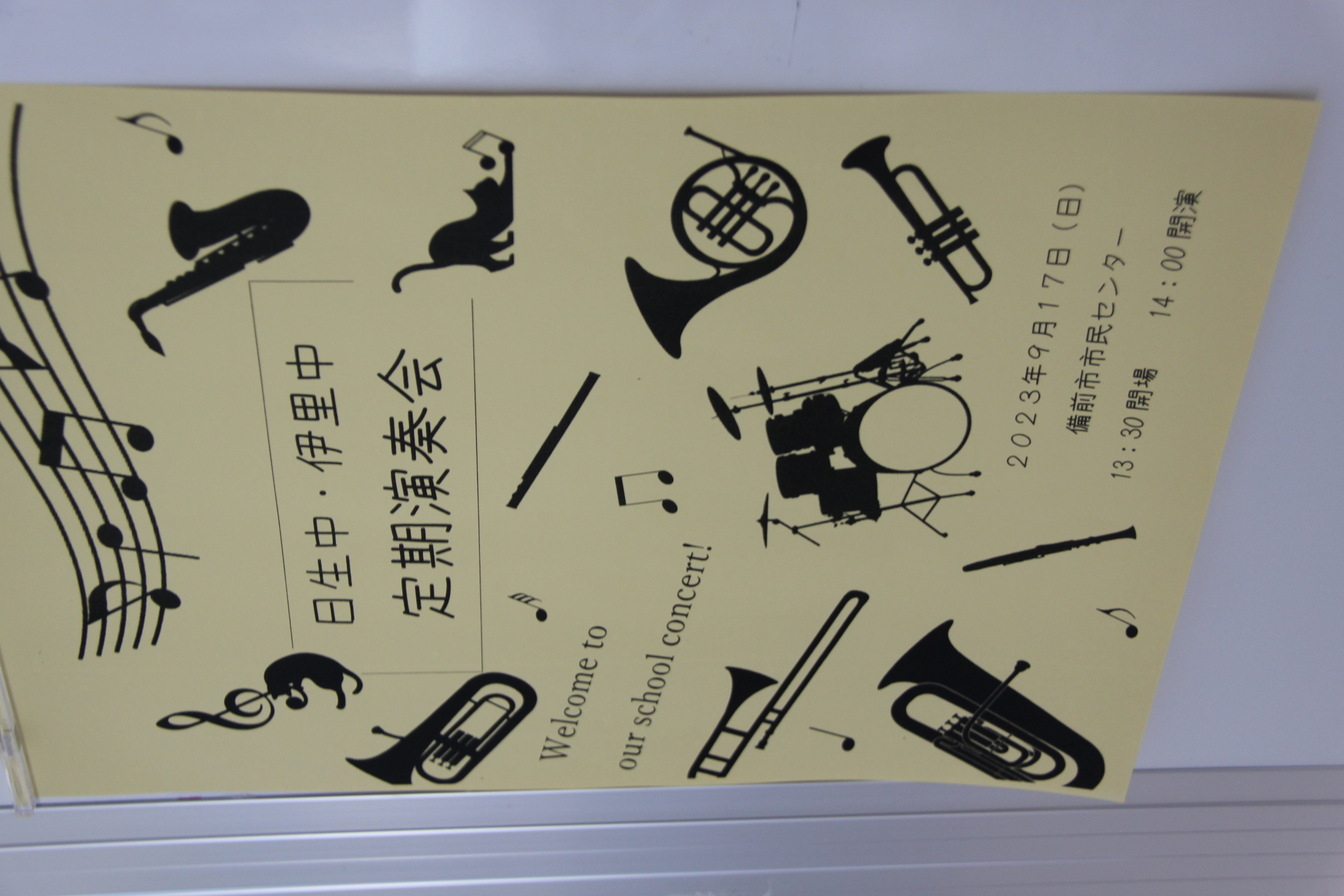
*備前東地区秋季総体(9/16.17)
□バスケットボール(会場:高陽中、伊里中)
□サッカー(会場:邑久スポーツ公園、高陽中)
□ソフトテニス(会場:吉井B&G、熊山運動公園、日生運動公園)
□水泳(*岡山県中学校秋季水泳競技大会(9/17)会場:岡山市立市民屋内温水プール)
□アーチェリー
(*岡山県アーチェリー選手権大会兼岡山県小中学生大会(9/24)会場:玉野スポーツセンター)
(*第18回西日本小中学生アーチェリー大会(10/29)会場:日生運動公園)
◎第1回ひなせ親の会(情報交流会)〈ご案内9・12〉

◎特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。
◎これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。
◎お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。
(カウンセリングや講座ではありません)
日生中学校区の小・中学校が連携し、この度、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行います。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)からアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。
お気軽に、申し込み・ご参加ください。
第1回ひなせ「親の会」のご案内
1 日 時 2023年10月2日(月)17:45~19:00
2 場 所 日生中学校 D組教室(北棟1階)
3 内 容 「中学校卒業後の多様な進路選択についての情報」をもとに意見交流
4 参加者 小・中学校の保護者 日生西・日生東小学校の先生 久次(日生中学校) SSW
主催:日生中学校区連携推進委員会(特別支援教育部会)
5 連 絡
会場準備の都合がありますので、参加の希望をお早めに(9/26までに)各学校の担当までお知らせください。なお、スクールカウンセラーの教育相談やSSWへのご相談も各学校に問い合わせください。
6 予 定 ・第2回:12月1日(金)17:45~19:00 (*新入生説明会の日)
・第3回:2月14日(水)17:45~19:00 (*小6体験入学の日)
◎〈学び〉を、自分から求めるということ。
〈学び〉のフィールドはいたるところに在るね。
(9/12:2年生水泳授業)
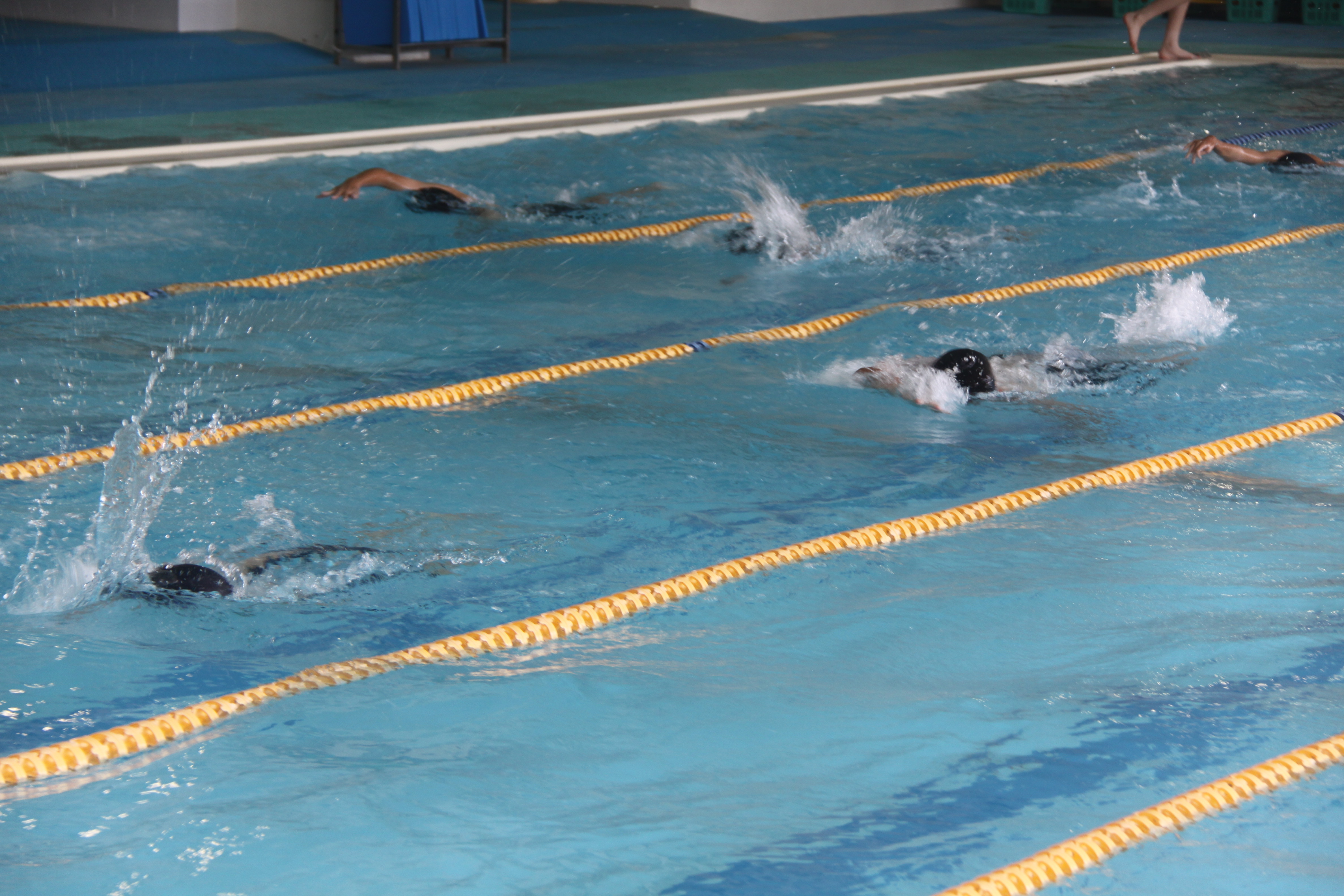


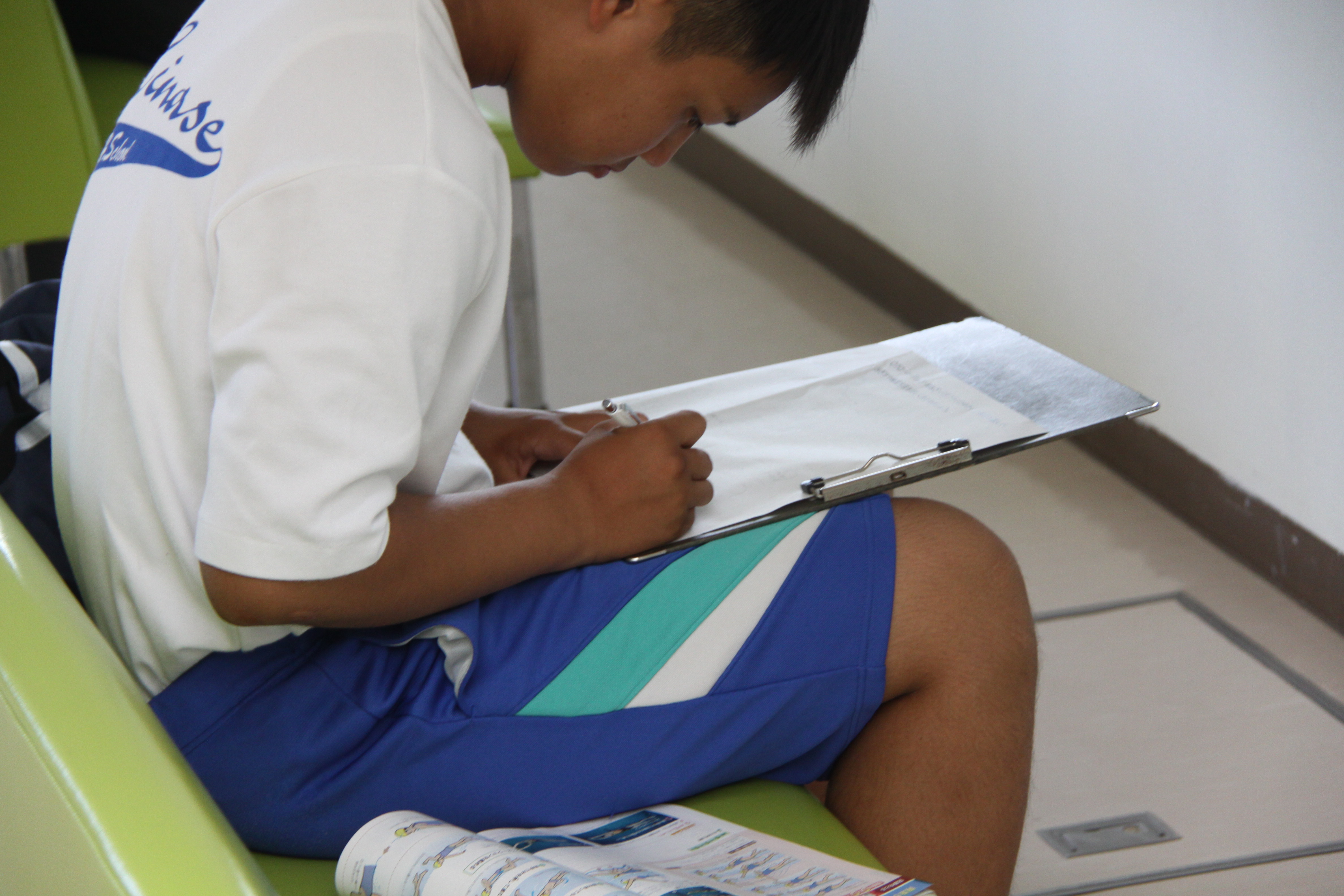





Any life‚ however long and complicated it may be‚ actually consists of a single moment — the moment when a man knows forever more who he is. Jorge Luis Borges
(どんな人生も、それがどんなに長く複雑なものであっても、実はたった一瞬の出来事で成り立っている)
◎子どもをまん中に、地域とともにある学校へ(9/11)
備前市文化スポーツ部地域移行課が来校され、学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方について、各部活動顧問と現在の状況や意見交流をおこないました。(明日も引き続いておこないます。)
国は方針について以下の文書を出しています。(R4.12)
学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する 総合的なガイドライン【概要】
〇 少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組 む必要。その際、生徒の自主的で多様な学びの場であった部活動の教育的意義を継承・発展させ、新しい価値が創出されるようにすることが重要。
〇 令和4年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、平成30年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的な ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的に改定。これにより、学校部活動の適正な運営や 効率的・効果的な活動の在り方とともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国の考え方を提示。
〇 部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、生徒の望ましい成長を保障できるよう、 地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備。地域の実情に応じ生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することが重要 (*詳細はスポーツ庁のHPで)

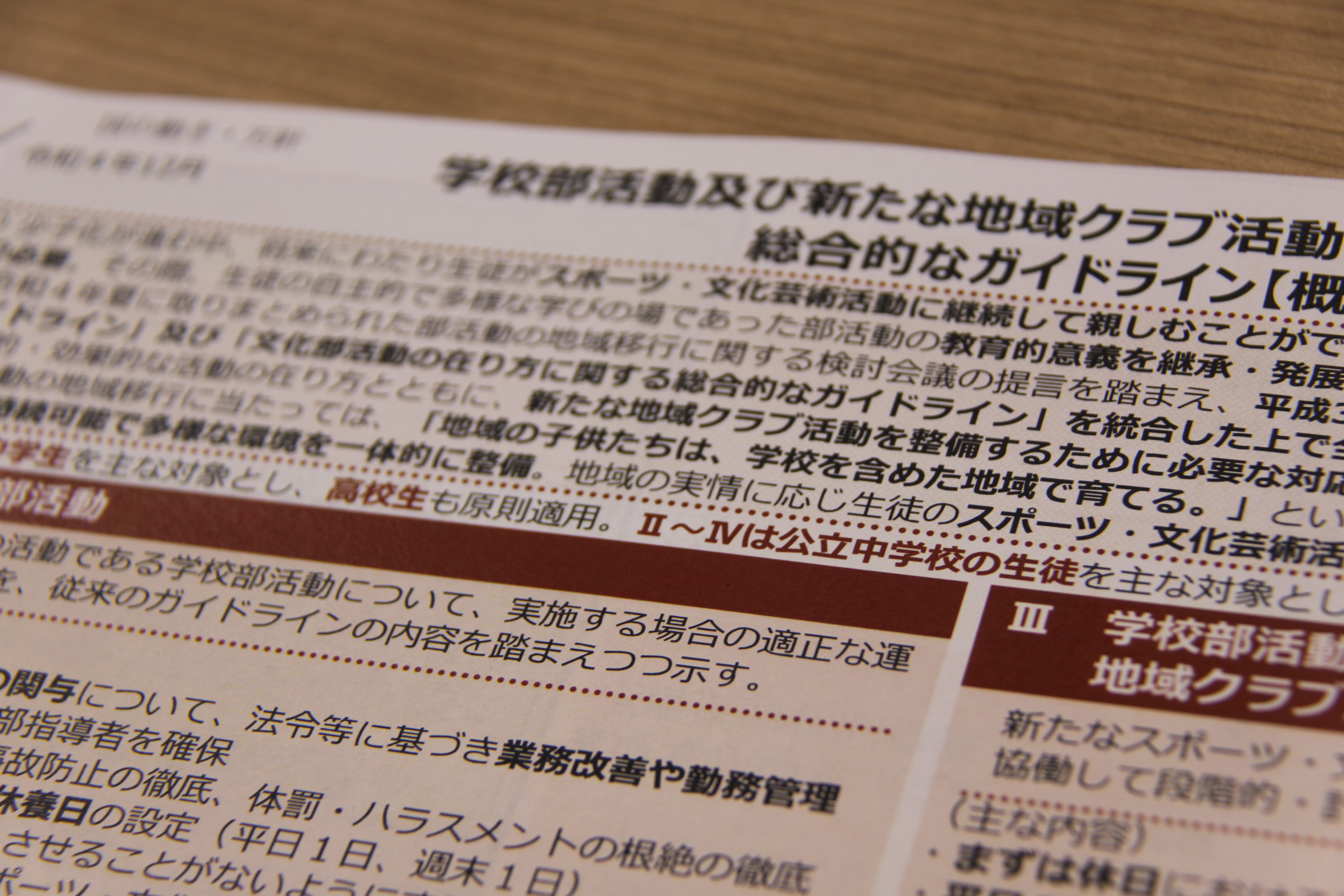

日生中では、地域クラブ活動について関心のある方々のご意見等を聴かせていただきたいと思っています。
◎十五の地図
ひな中の風~~日生中学校卒業アルバム写真撮影(9/8)

◎日生で輝く 日生が輝く 社会を創る
3年生総合的な学習の時間(日生への提言・中間報告)(9/8)
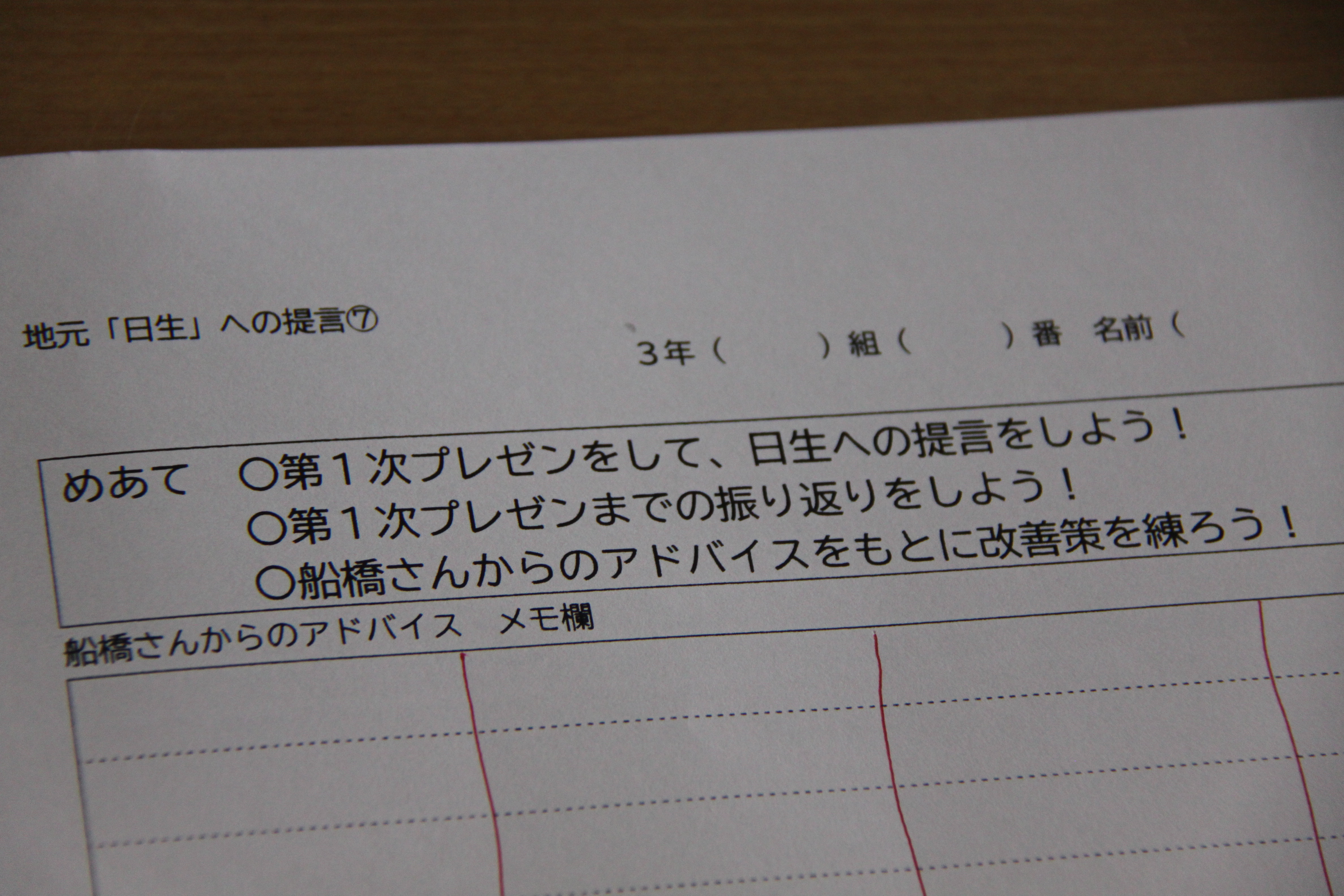

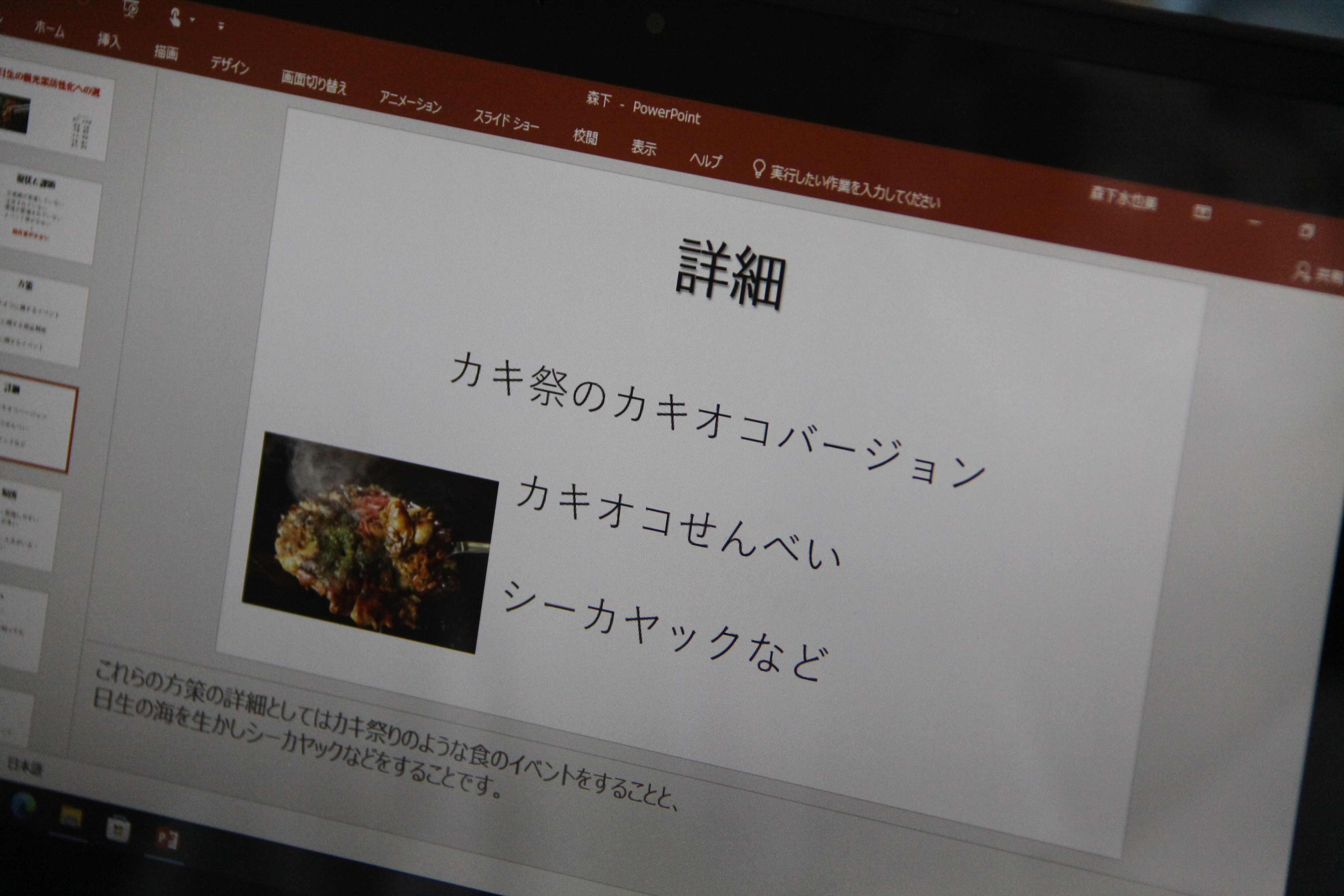

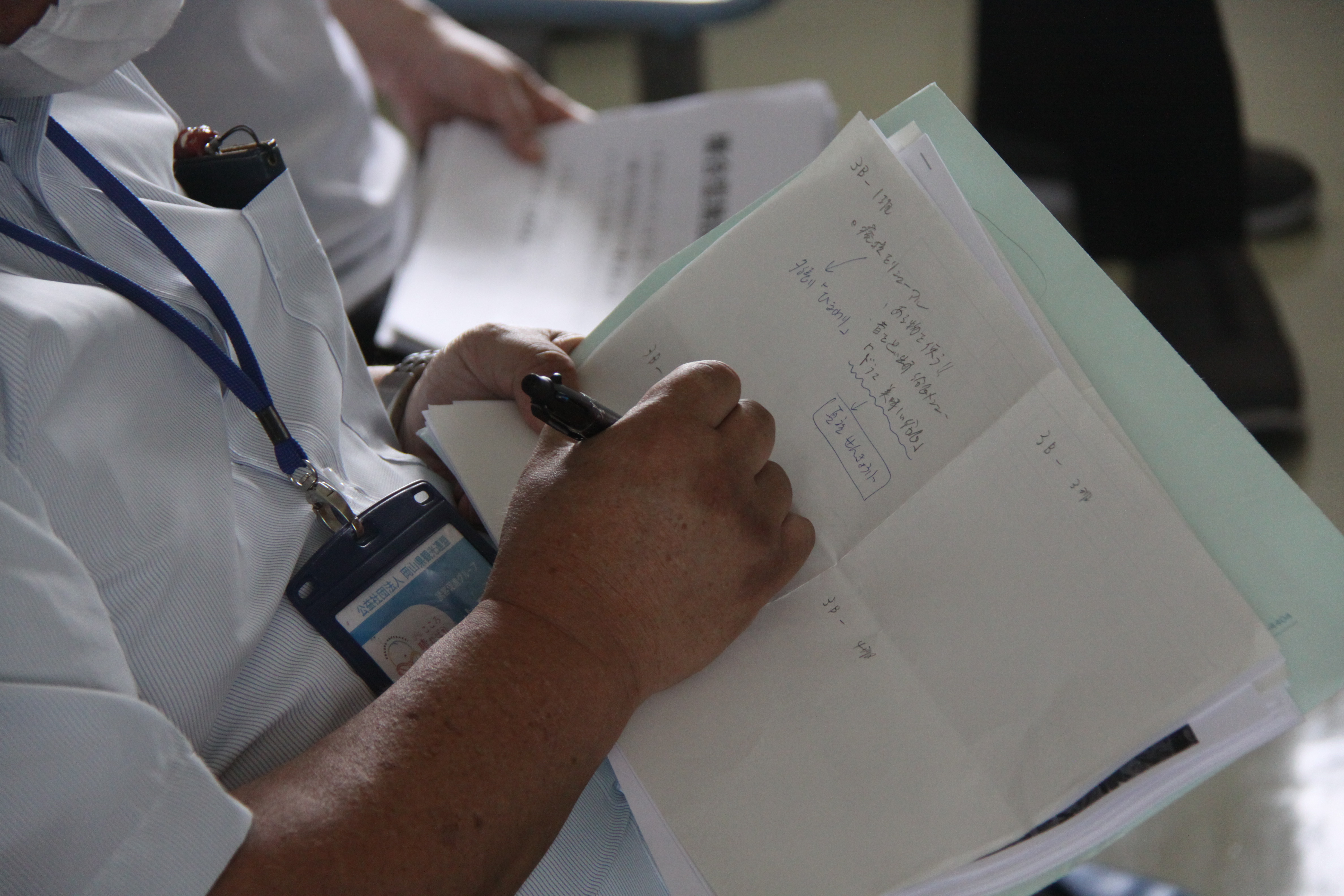
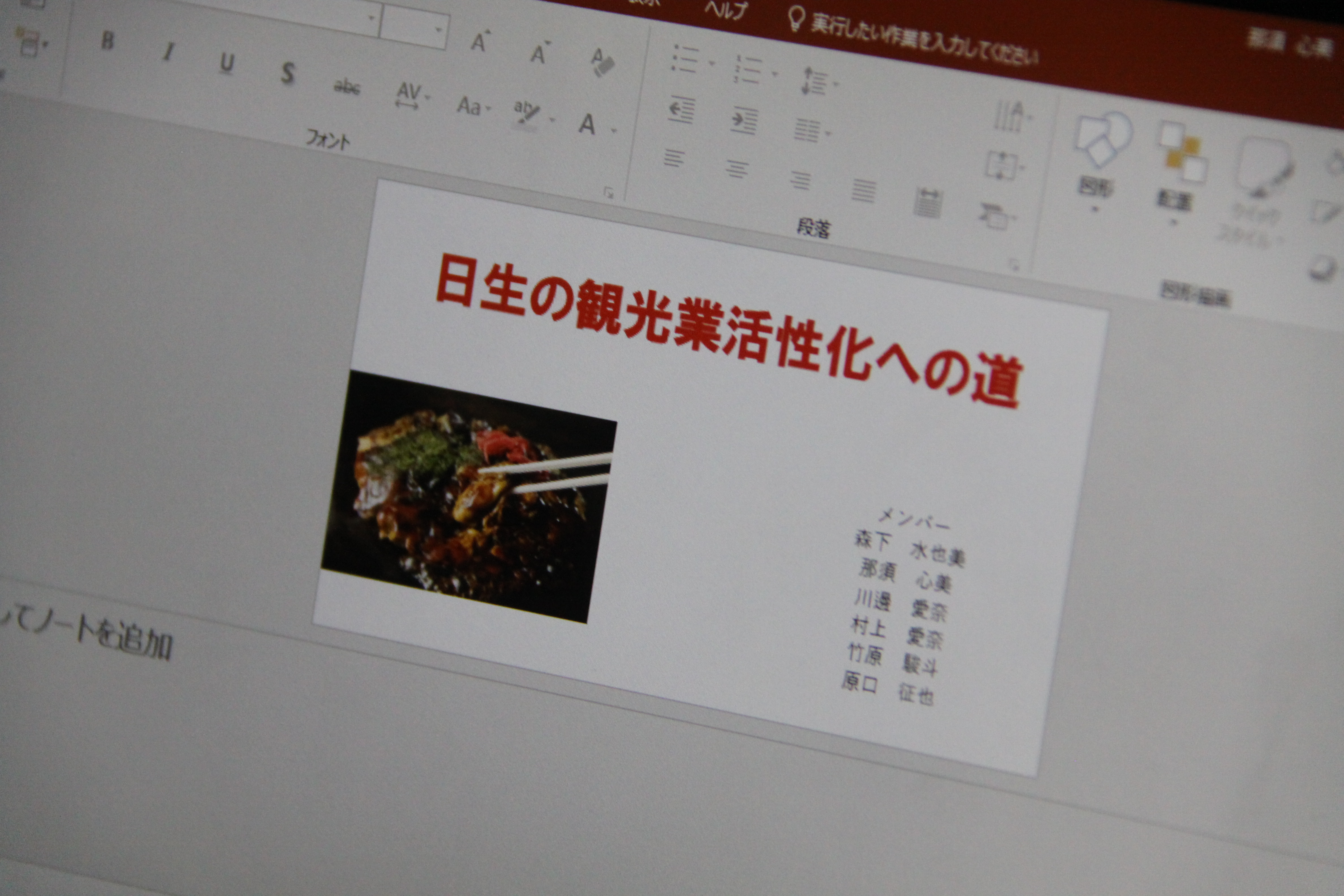
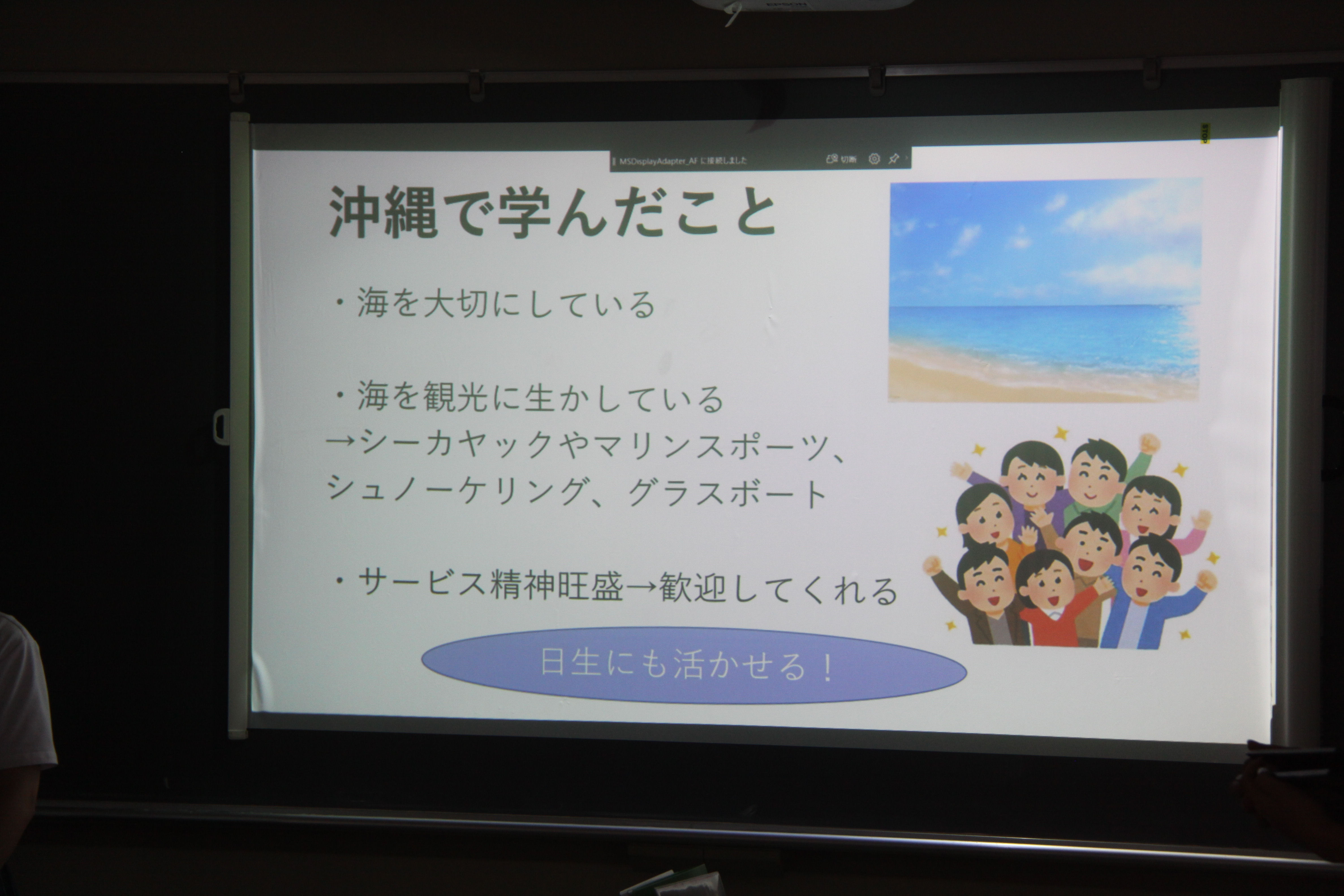


◎私たちの大切な委員会活動。自治的な学校生活へ(9/8)




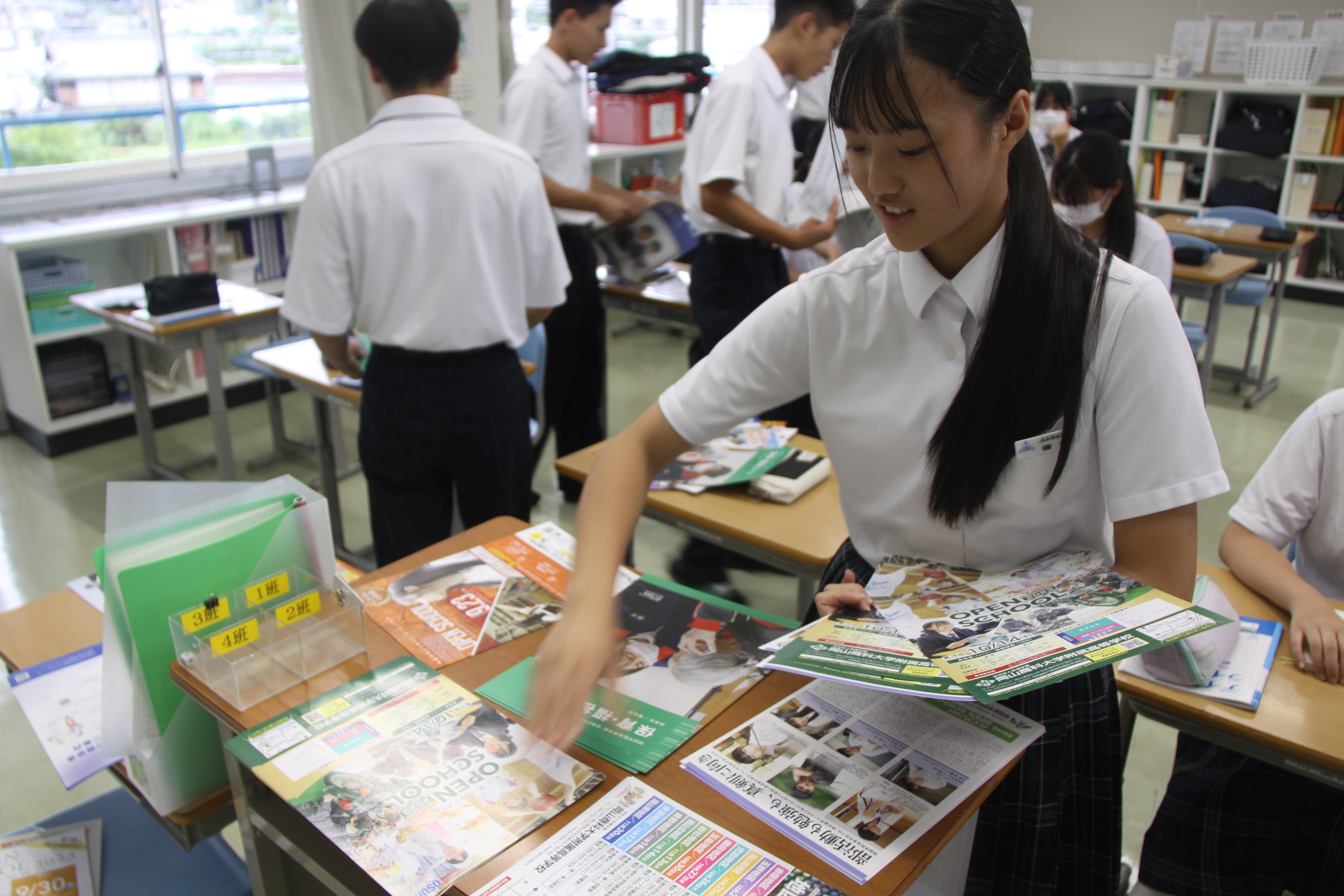

◎STOP THE SEASON IN THE SUN(9/7.8・12.13)
~水泳の授業に取り組んでいます~



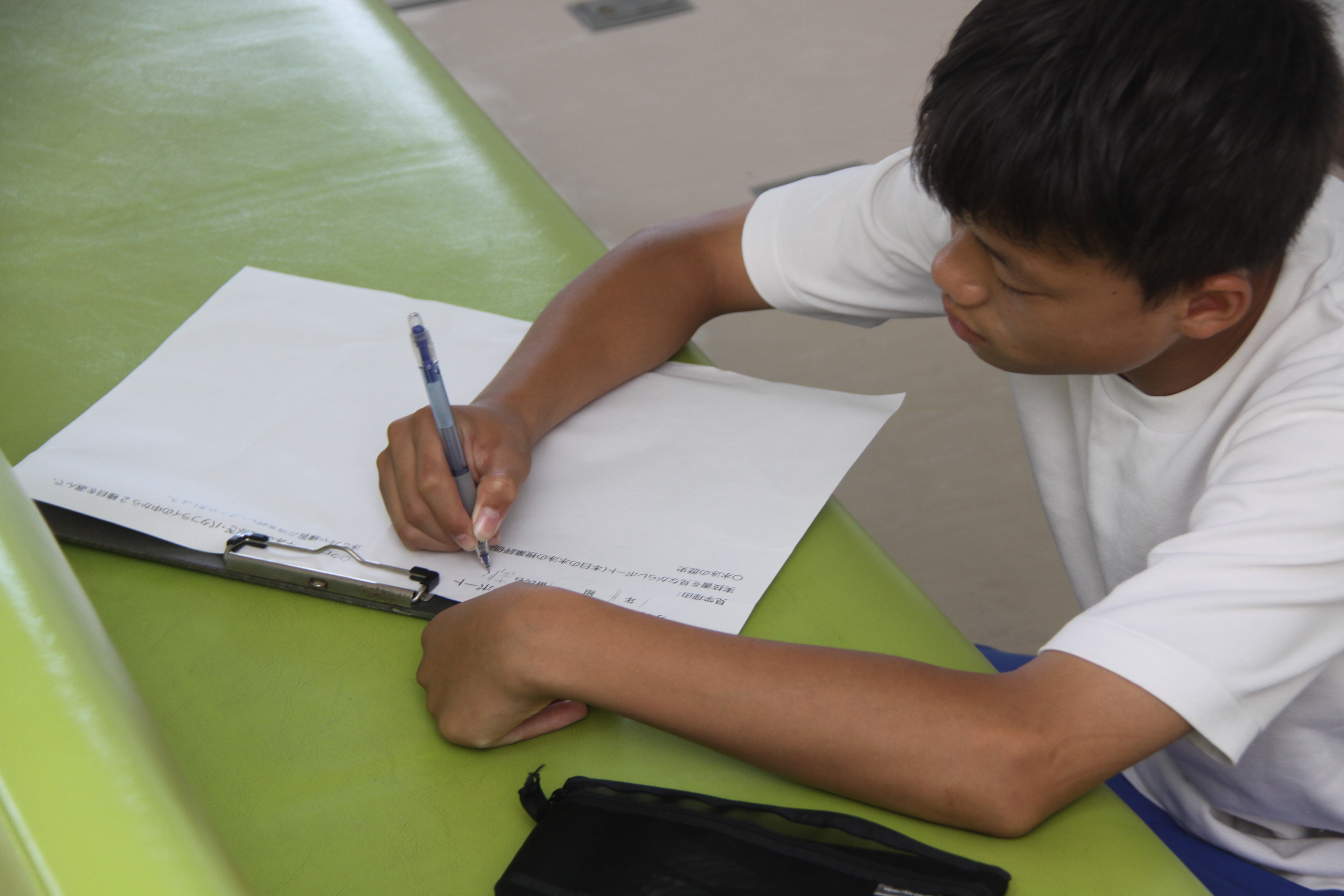


少し学校体育実技指導資料を読んでみました。
小学校から高等学校までを見通した体系体育の分野(小学校運動領域、中学校体育分野、高等学校科目体育)では、生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現に向けて、小学校から高等学校までを見通して、指導内容の改善が図られました。現行の学習指導要領では、従前のもので「基本の運動」の「内容」として示していたものが「領域」として示されました。「体つくり運動」については、すべての学年に位置付けられています。 また、「体つくり運動」の領域の内容のうち、すべての学年で「体ほぐしの運動」が位置付けられるとともに、小学校低学年及び中学年では、基本的な動きを身に付けることに重点を置いた「多様な動きをつくる運動(遊び)」が新たに位置付けられました。 「体つくり運動」と「体育理論」を除く、他の運動の領域では、小学校から中学校第2学年までは、従前の中学校学習指導要領で選択であった武道及びダンスを含めたすべての領域が必修となっています。中学校第3学年からは領域の選択がはじまります。中学校第3学年及び高等学校入学年次では、領域のまとまりからそれぞれ選択し、高等学校のその次の年次以降では、必修を除くすべての運動領域から選択することとしています。小学校から高等学校までを三つに分けた各段階では、次のような指導が期待されます。
【第1段階】
小学校低・中学年では、核となる易しい運動を幅広く行い、基本的な動きを身に付けていくことが大切で
す。また、児童は仲間とかかわったり、動きを工夫したりしながら運動遊びや運動の楽しさを味わうことが
求められます。一方、教師は、高学年以降につながる運動やスポーツの基本となる動き・意欲の育成に努め、
結果として体力の養成を目指します。
【第2段階】
小学校高学年、中学校の第1学年及び第2学年の段階は、中学校第3学年以降に始まる領域の選択に向け
て、次第にルール等を本格的な運動やスポーツに近づける段階です。全ての運動領域において、それぞれの
特性や魅力に触れさせることができる指導が大切です。小学校高学年と中学校第1学年では、校種の接続に
配慮した指導が求められます。
【第3段階】
中学校第3学年から高等学校卒業時までの最終段階です。運動の特性や魅力に応じた領域のまとまりから
自ら選択し(中学校3学年及び高等学校入学年次)、自己のスポーツの嗜好性を確認した後、高等学校その
次の年次以降においては、自らが取り組みたい領域を選択し、卒業後の豊かなスポーツライフの実現を図る
ため、主体的な取り組みを促す指導の工夫が求められます。
このように、小学校、中学校、高等学校の校種の接続を踏まえた指導によって、「生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現」を図ります
◎私たちが生きていくよりよい社会って‚
どう創っていくかなあ?
体育委員会は、継続的に自転車施錠の意識向上(安全意識)の取組を進めています。(9/6)
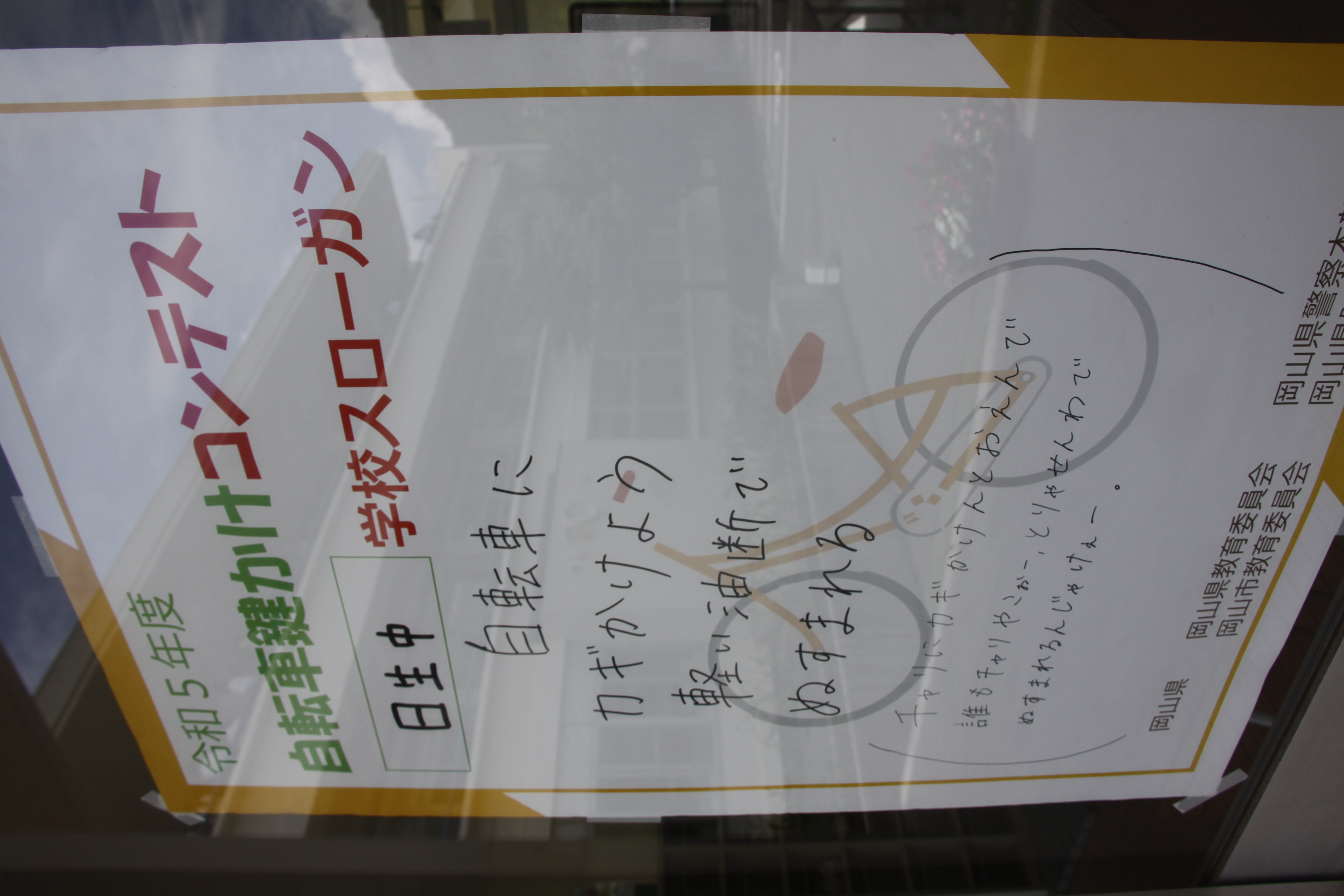
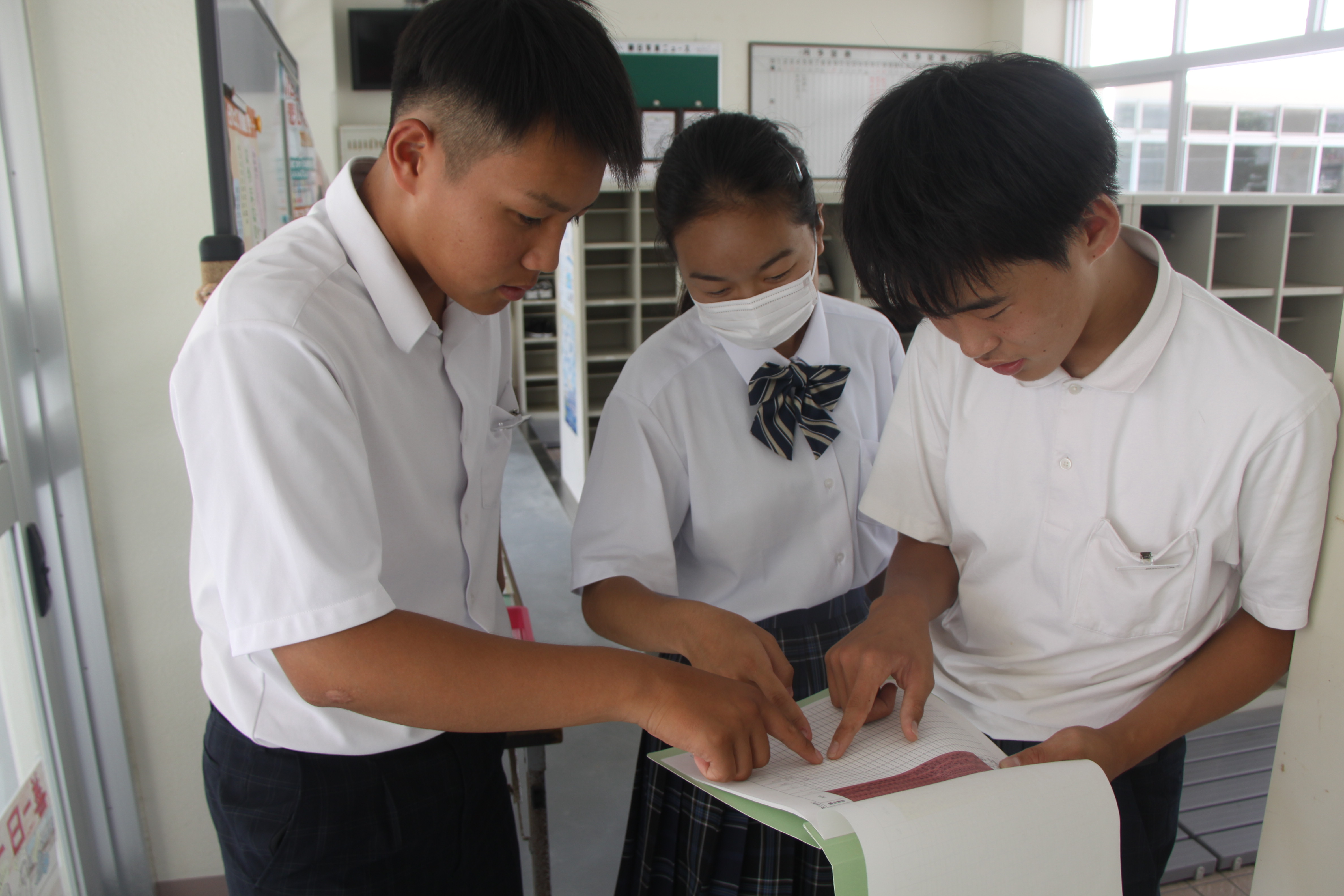
◎歩み新たに日に生せば 今日は昨日の我ならず
~日生中学校卒業アルバム写真撮影開始(9/5・8)~
悲しいことがあると 開く皮の表紙
卒業写真のあの人は やさしい目をしてる
町でみかけたとき 何も言えなかった
卒業写真の面影が そのままだったから
人ごみに流されて 変わってゆく私を
あなたはときどき 遠くでしかって

◎未来予想図日生中(9/5)~生徒集会



〈話す・伝えるって〉…ビジネス作家の臼井由妃氏によれば、「ゆっくり」「すっきり」「はっきり」の3つの「り」を意識して穏やかに話すと、相手への説得力がアップするのだそう。
取引先との商談や大勢の前でプレゼンを行なうときなど、緊張してつい早口になってしまいがちですよね。同氏は、「話を始める前に深呼吸し、口角を上げた笑顔をつくる習慣をつける」と、心が落ち着いて「ゆっくり」話せると言います。また、話す内容があまりに多すぎると相手側はうんざりしてしまうことも。そんなときは、本当に伝えなくてはならないことを優先して話すと言葉を「すっきり」させられるでしょう。
そして「はっきり」話すとは、声を張り上げることではなく、曖昧に聞こえる表現を避けること。たとえば、相手に納期を伝えるときは「早めに取りかかります」よりも「1週間以内に完成させます」と答えたほうが、聞き手にとってはわかりやすいはず。このように、3つの「り」を心に留めて話すようにしてみてると、大きな場・たくさんのひとと話すときのスキルがアップします。生徒会選挙21日、生徒総会27日、星輝祭10月7日、備前市弁論大会(日生中会場)10月31日を予定しています。
◎未来予想図日生中(9/4)~9月専門委員会
Life has meaning only if one barters it day by day for something other than itself.
Antoine de Saint-Exupery
(人生は、日々、自分以外の何かのために交換することで初めて意味を持つ。)

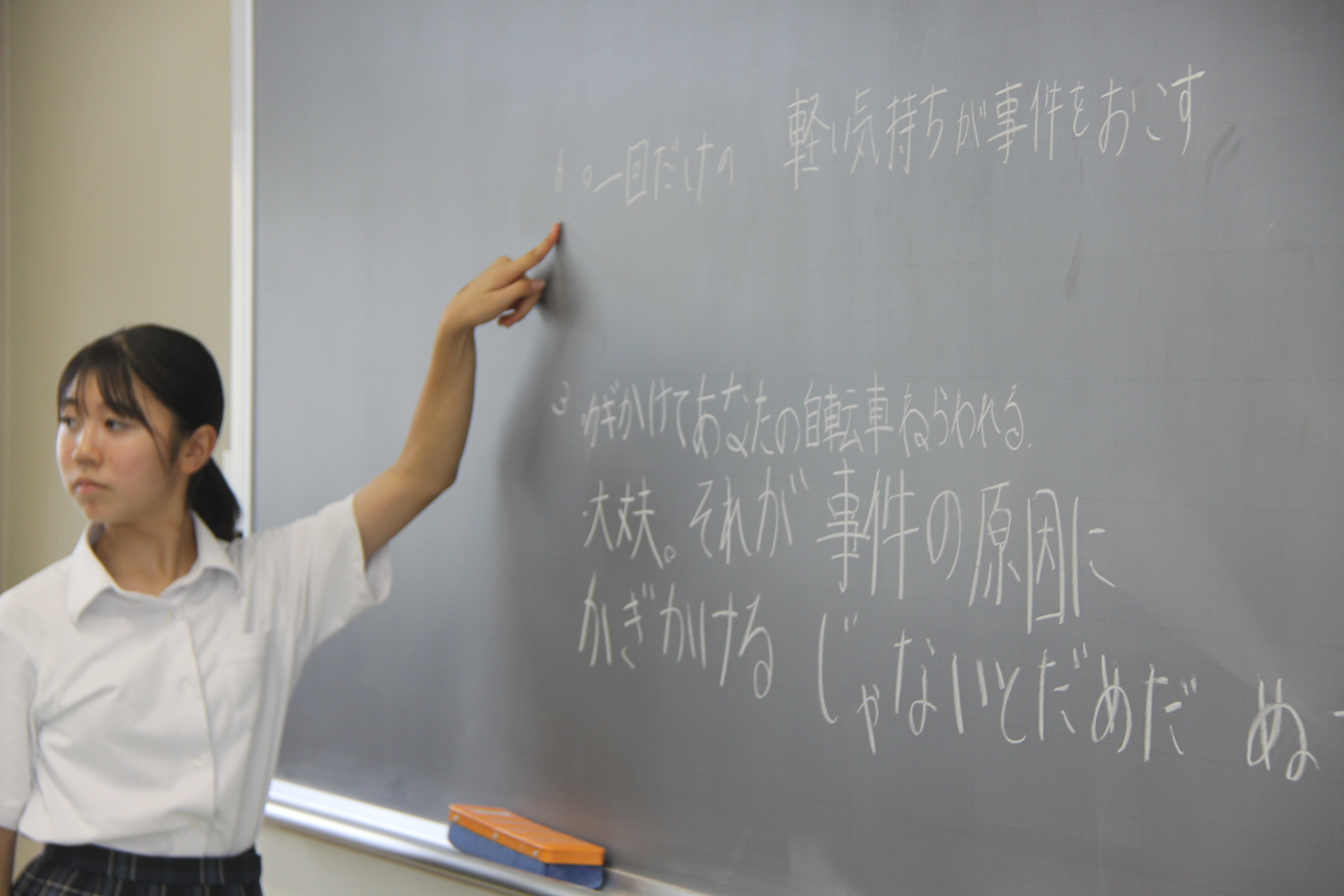

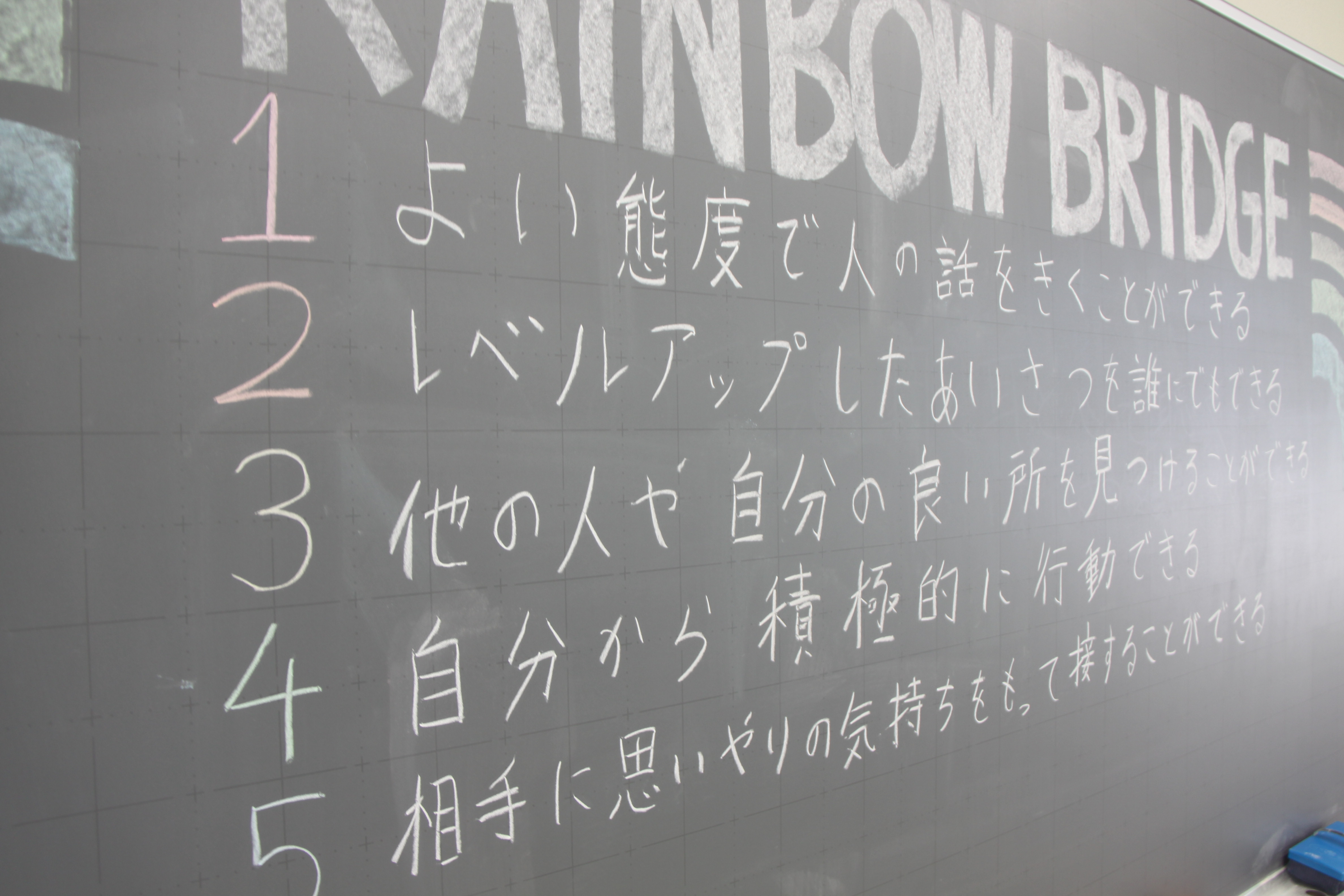

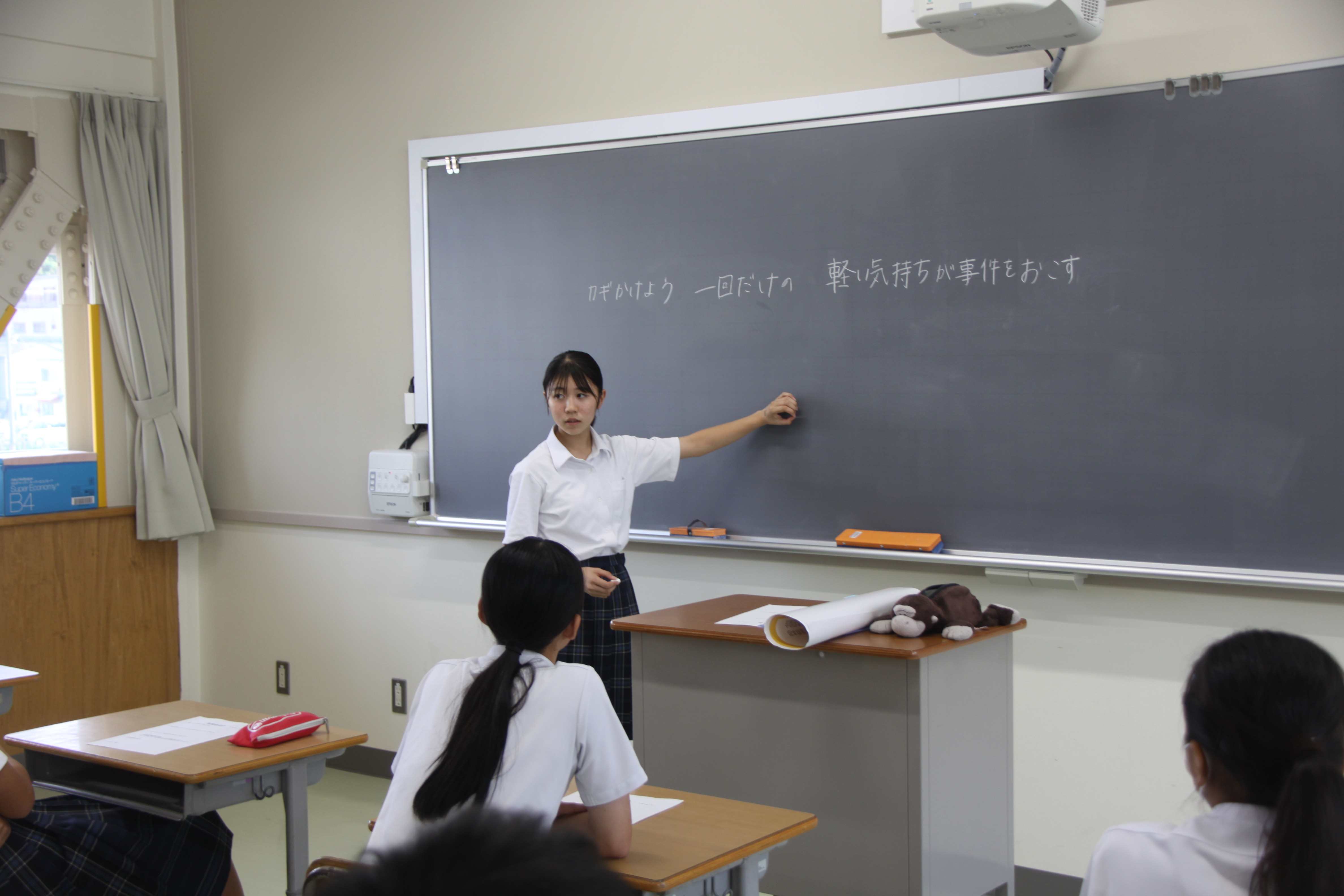
◎君は君らしくやりたいことをやるだけさ♬

◎多くのひとに支えられて(9/4)
From there to here‚ from here to there‚ funny things are everywhere! Dr.Seuss
(向こうからここまで、ここから向こうまで、面白いことはどこにでもある。)

◎日生中の明日はどっちだ(9/1)
第1回選挙管理委員会が開かれました。この後告示、立候補者受付、選挙運動等を経て、9月21日(木)に立会演説会及び選挙をおこないます。日生中学校のこれからを創る大切な委員会です。

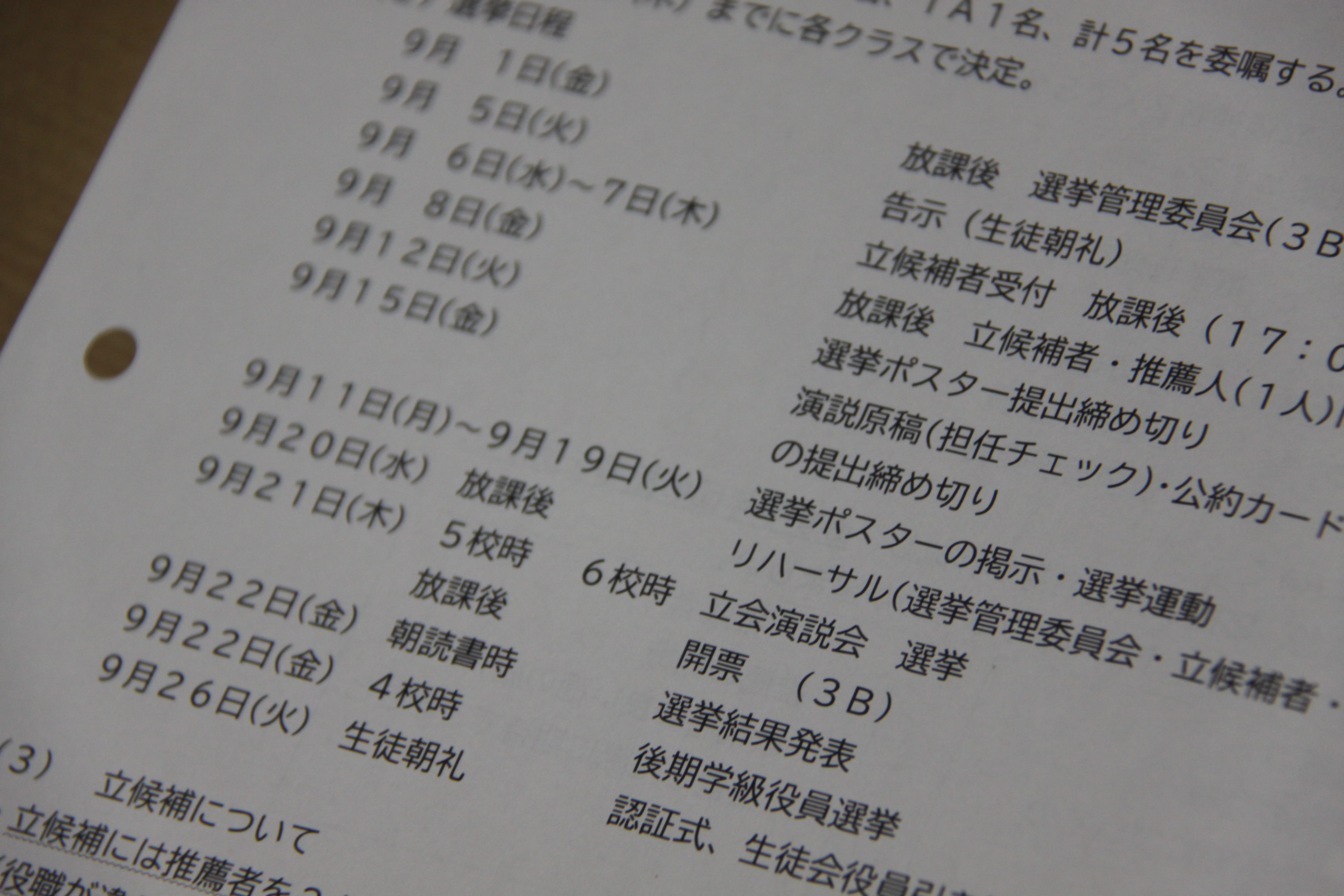

◎あの日、あの時を忘れない そして私と大切な人を守るために 防災週間~9.5
給食時間に実際に災害時の食事を想定し、防災用非常食を食べることで自然災害への理解を深めました。また、食育の一環としても取り組みました。(防災用非常食を食べる体験をしておくことで、災害時の不安を取り除き安心して食べることができます。)



◎だっぴしました🐛(8/31)
一人ひとりの若者が 人とのつながりの中で 自分らしく生きられる社会をつくる

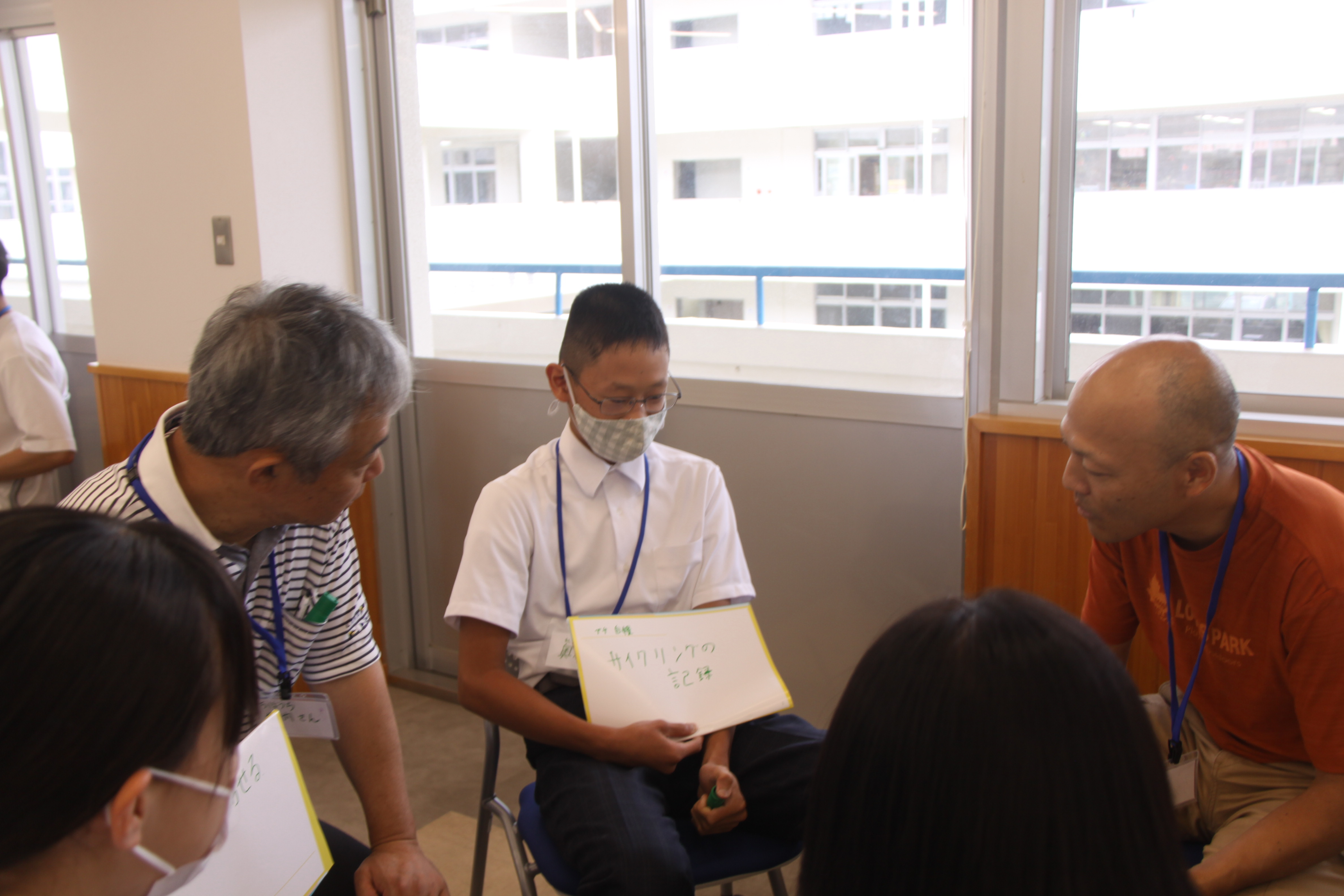






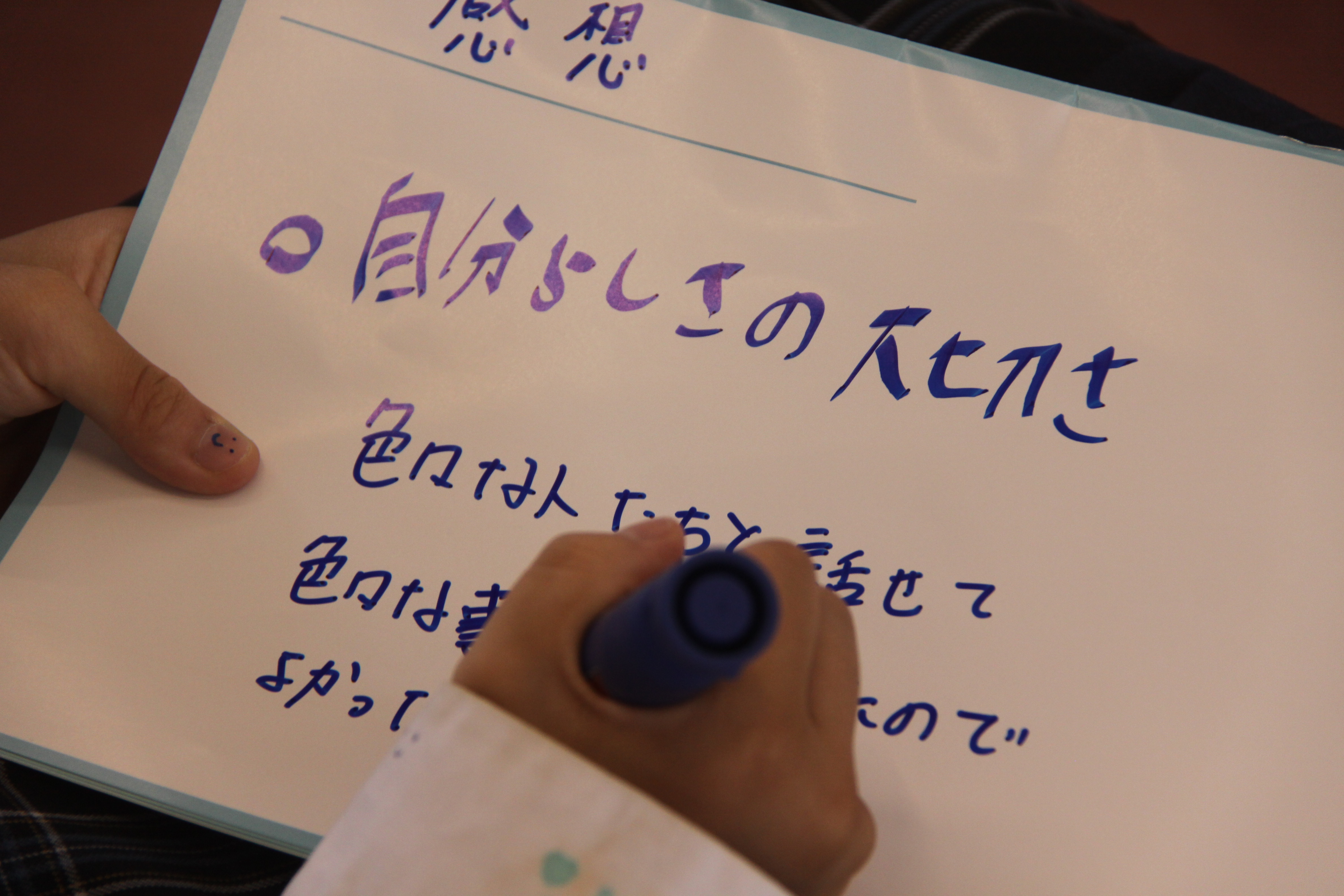
中学生だっぴとは、中学生4人〜5人・大学生2人・保護者など地域の大人2人の計8〜9人程度のグループを中学生の人数分つくり、 働き方や生き方などについてテーマに沿って自由に話し合うキャリア教育プログラムです。日生中学校2年生も毎年この取組を、地域の多くの方々のご支援・ご協力を頂き、実施しています。だっぴHPでは、以下の活動のポイントを掲載しています。
「地元や社会へ関心が高まる!」
自分たちの地域の人や知らない分野で生きる人の多様な価値観と出会うことで、社会のつながりに気づいたり、地元への興味関心を高めることができます。
「未来を考えるキッカケに!」
少し先の未来を生きる大学生や様々な経験を経て働くいろんな大人の話を聞き、自分のこれからをイメージしやすくなります。
「行動する勇気が育つ!」
地域の大人やお兄さんお姉さんが生き生きと真剣に話してくれた言葉、そして中学生自身が自分と向き合い話した言葉。その一つ一つが心を支えてくれる力になり、行動する勇気が育ちます。
「みんなで育てる地域に」
中学生と直接お話することで、子どもたちへの理解や関心が高まります。地域の力を学校に取り入れるキッカケにもなり、地域みんなで子どもを育てるつながりが生まれます。
…これからも日生中は〈地域とともにある学校〉としてがんばります
◎2学期始業~映して永遠に育ち行く♬(8/30)


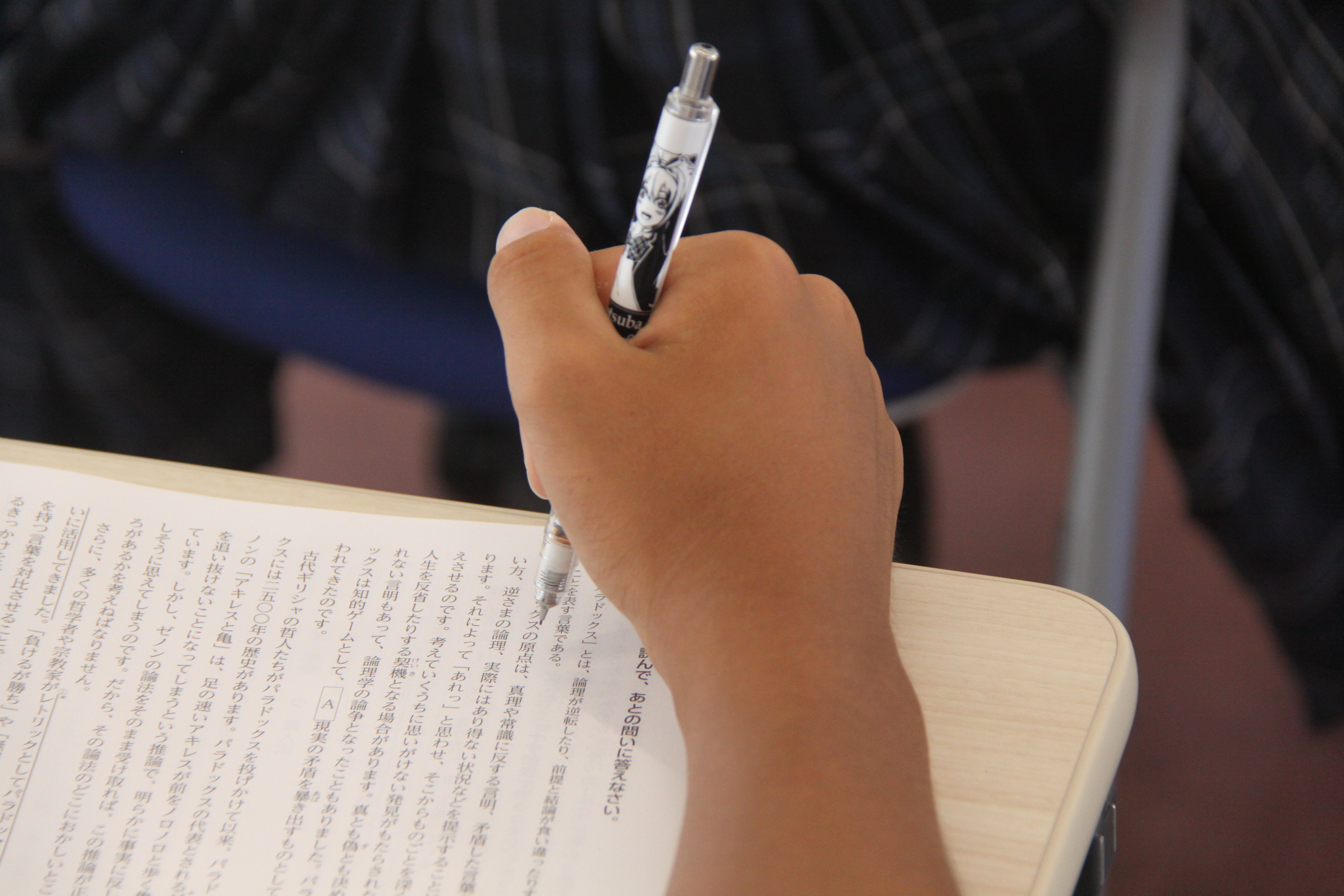
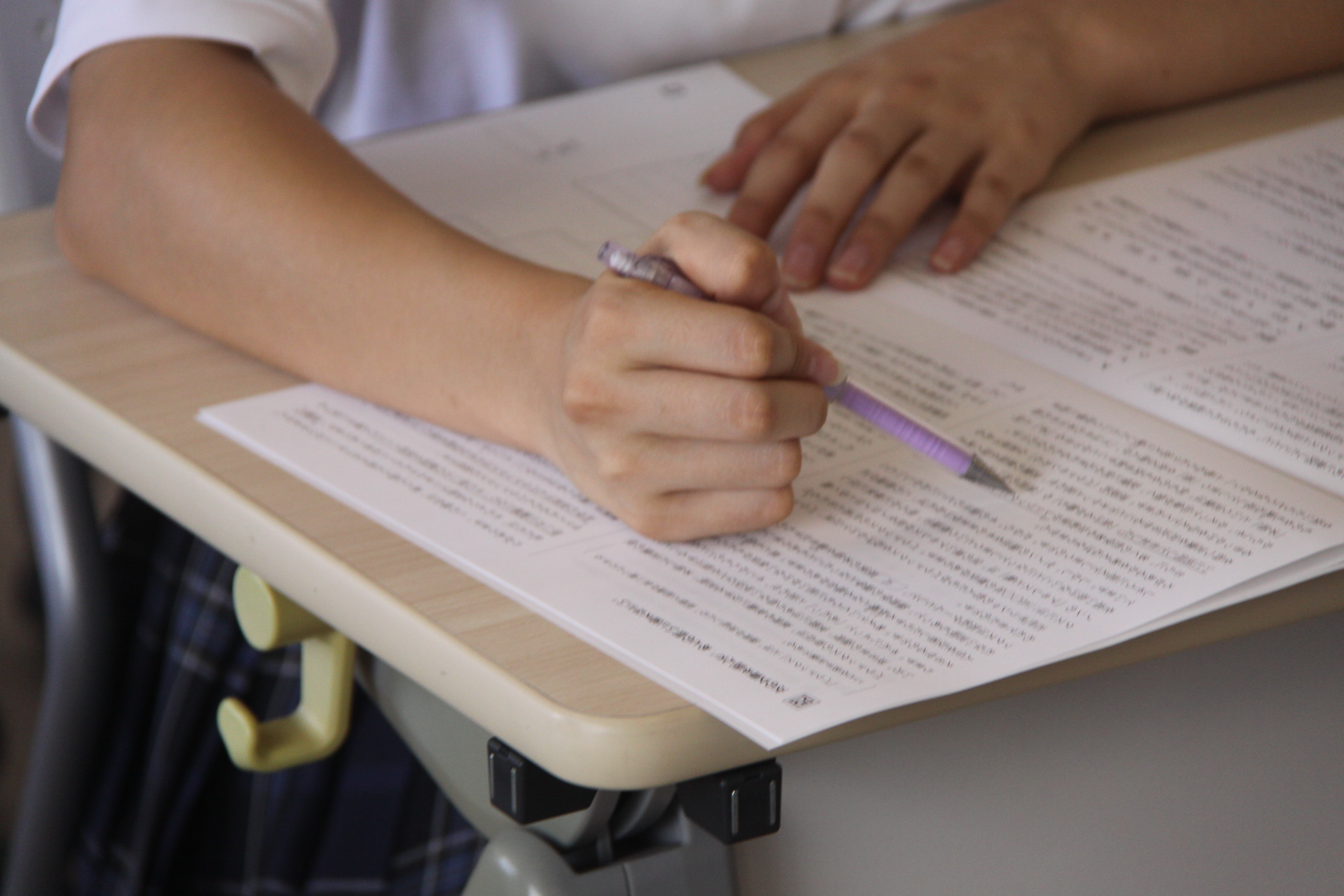
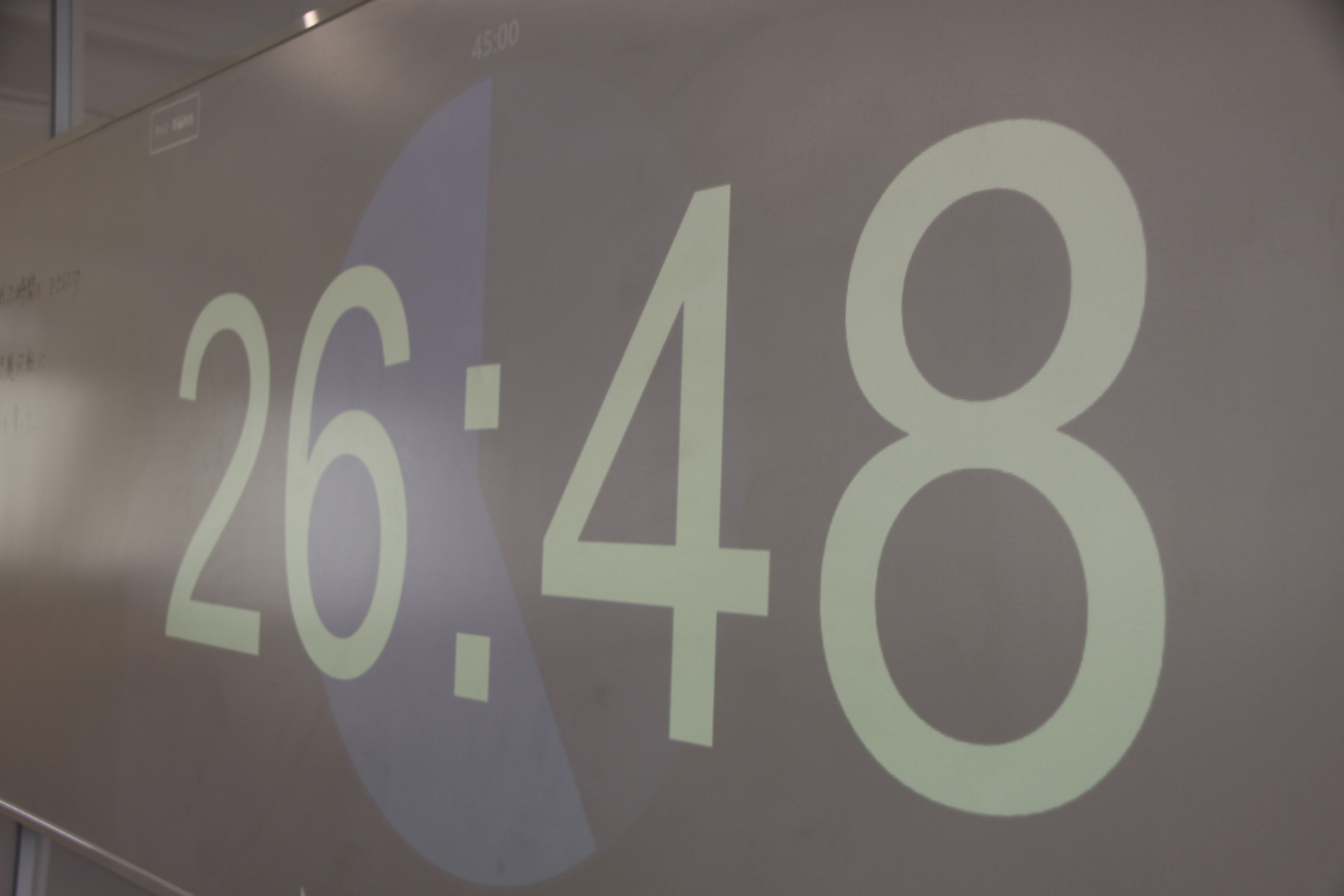
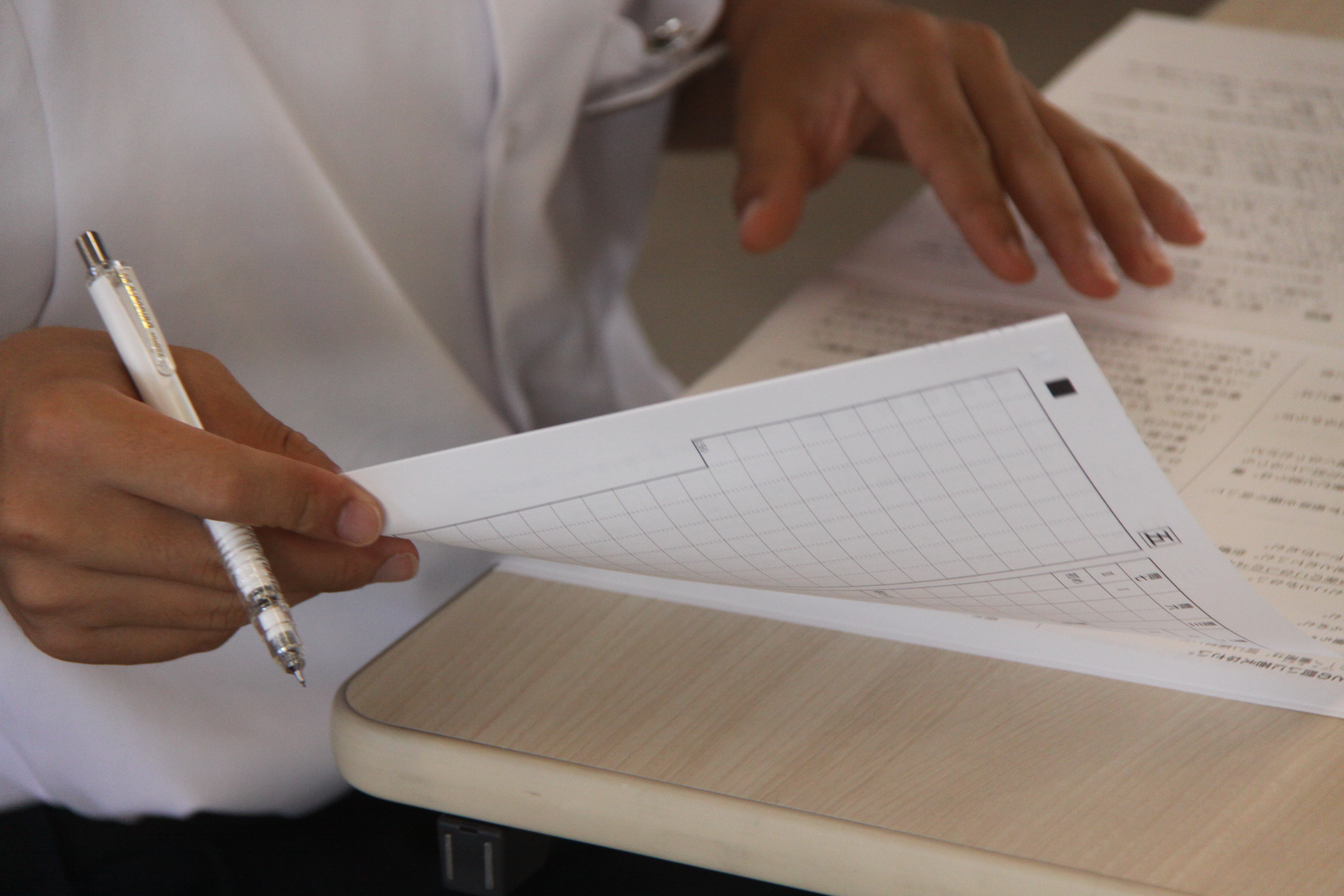


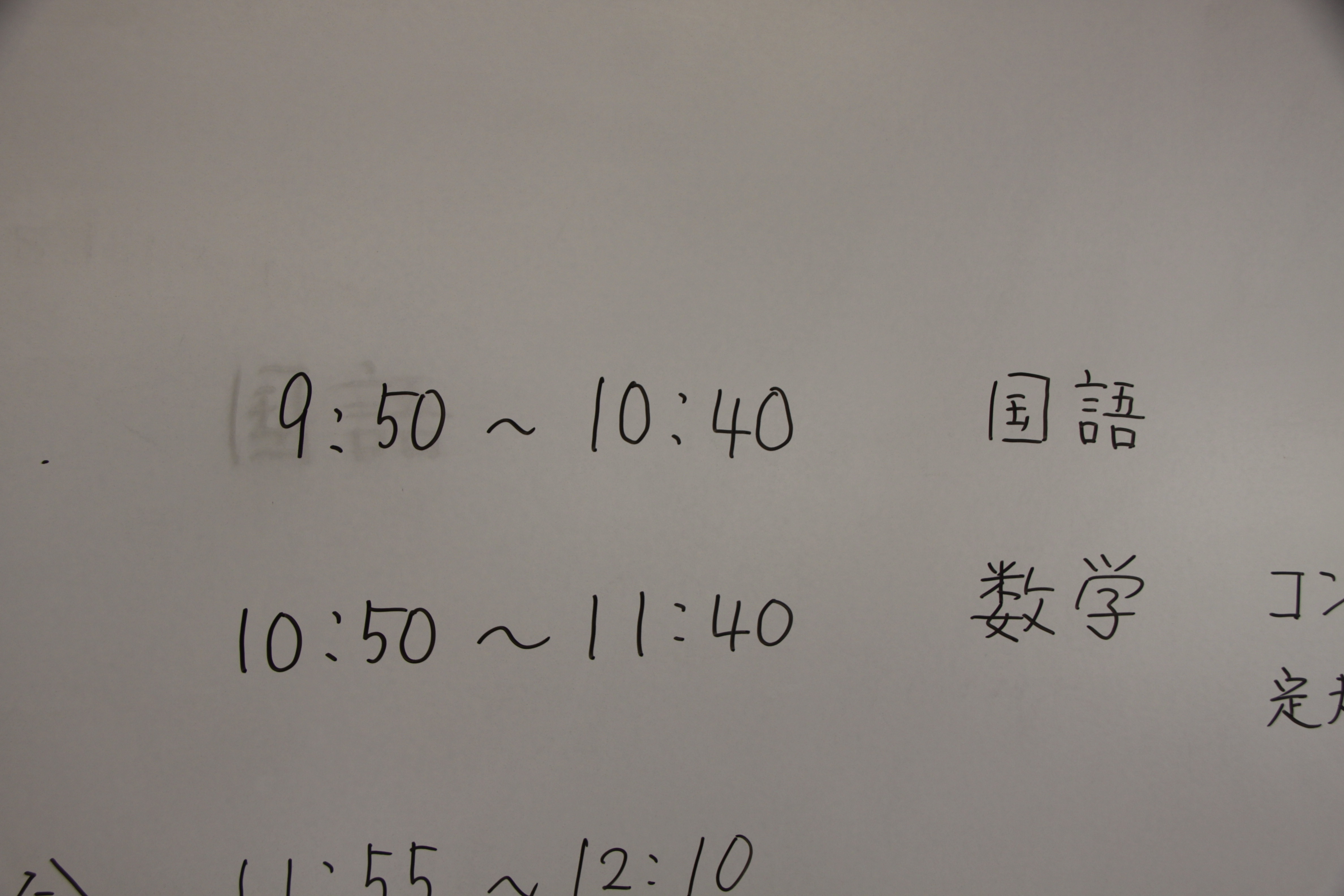
◎2学期始業~歩み新たに日に生せば♬(8/30)
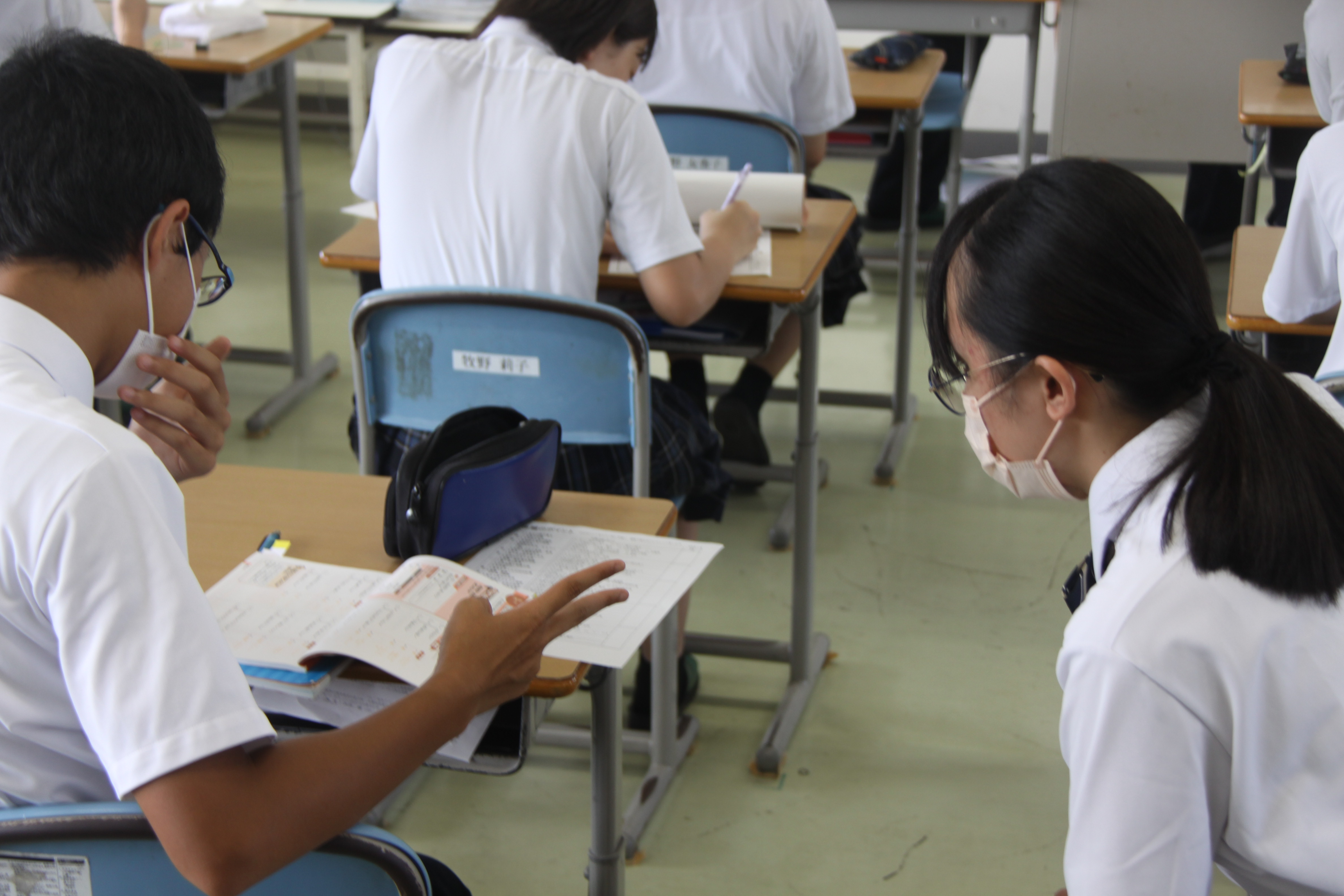

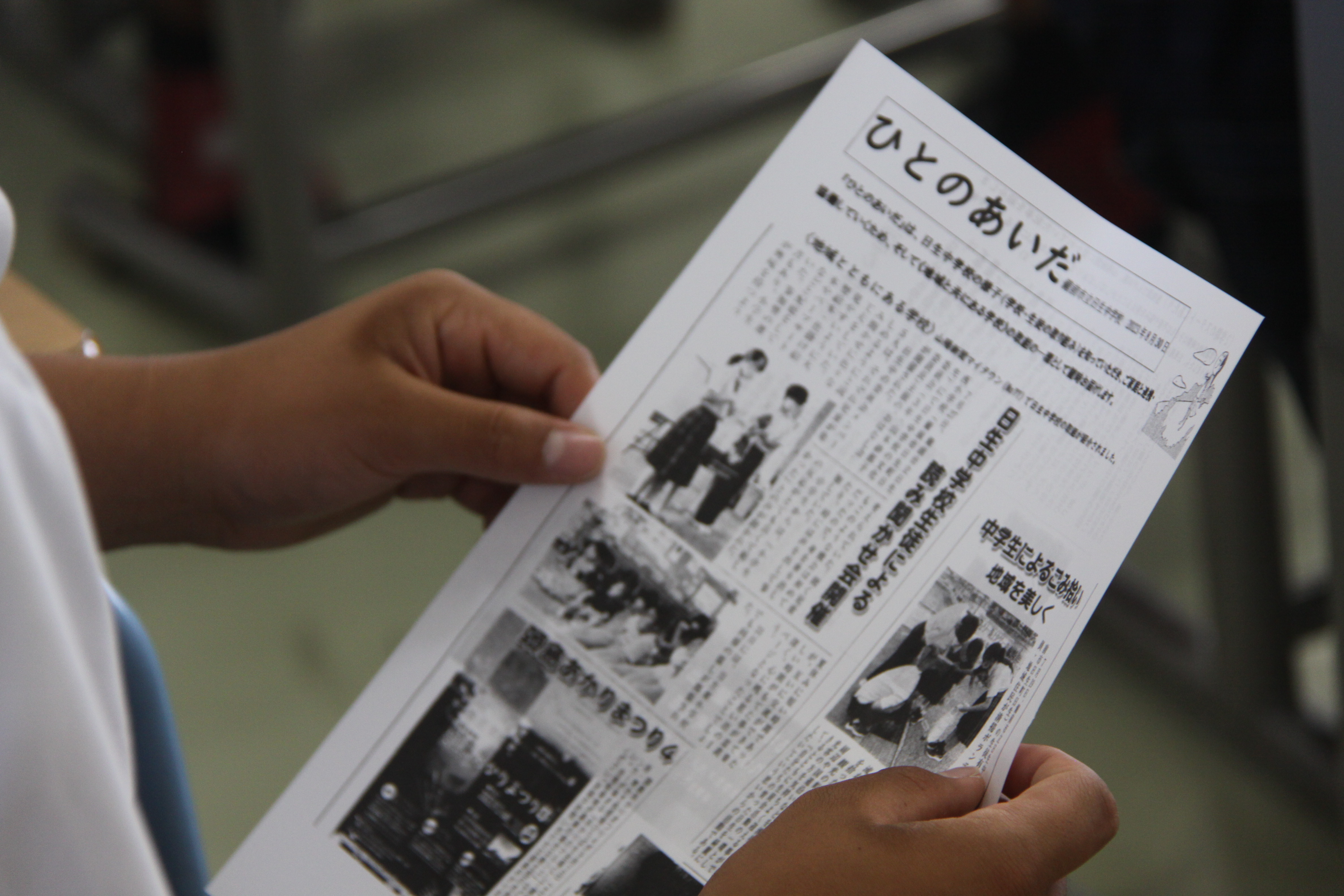

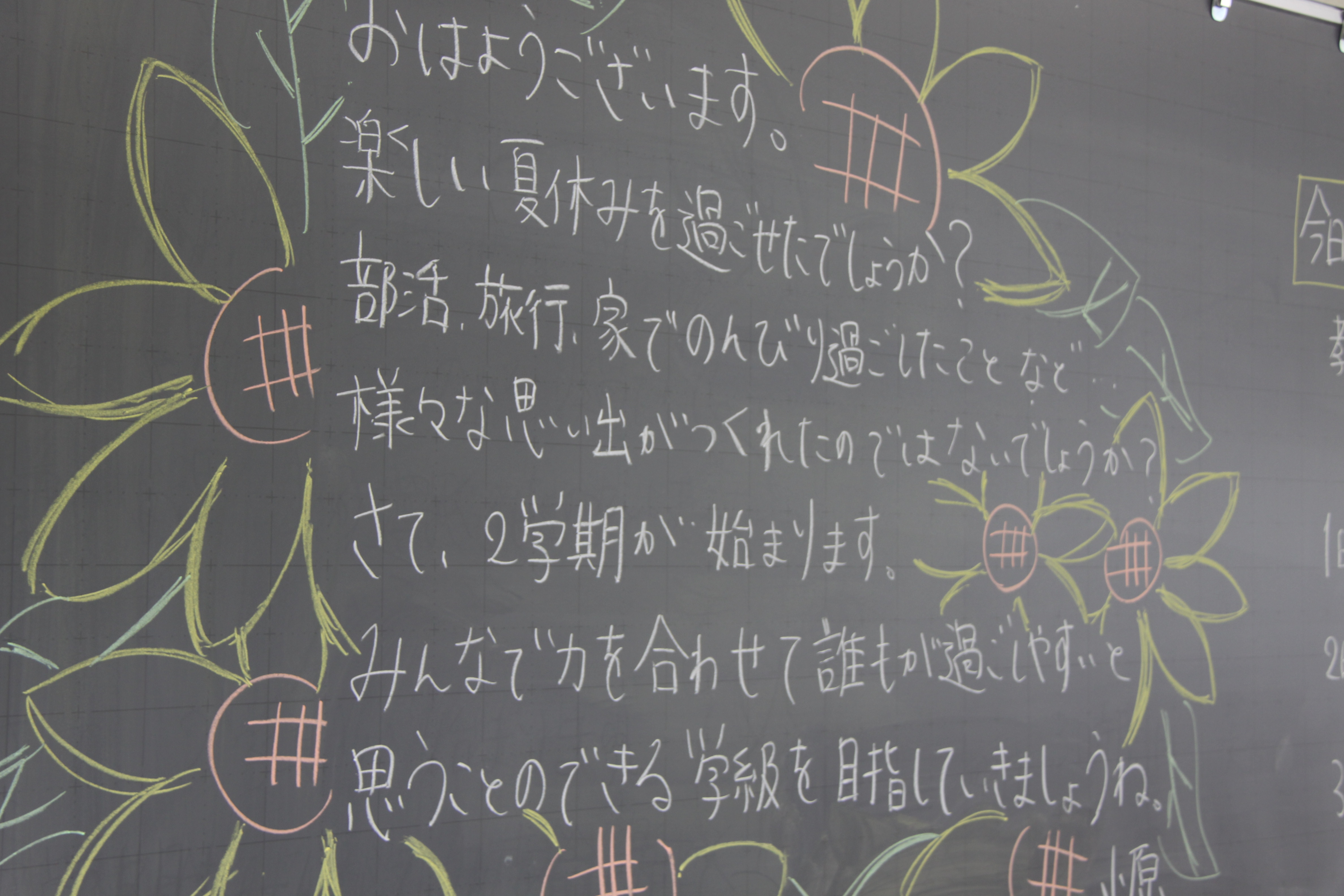



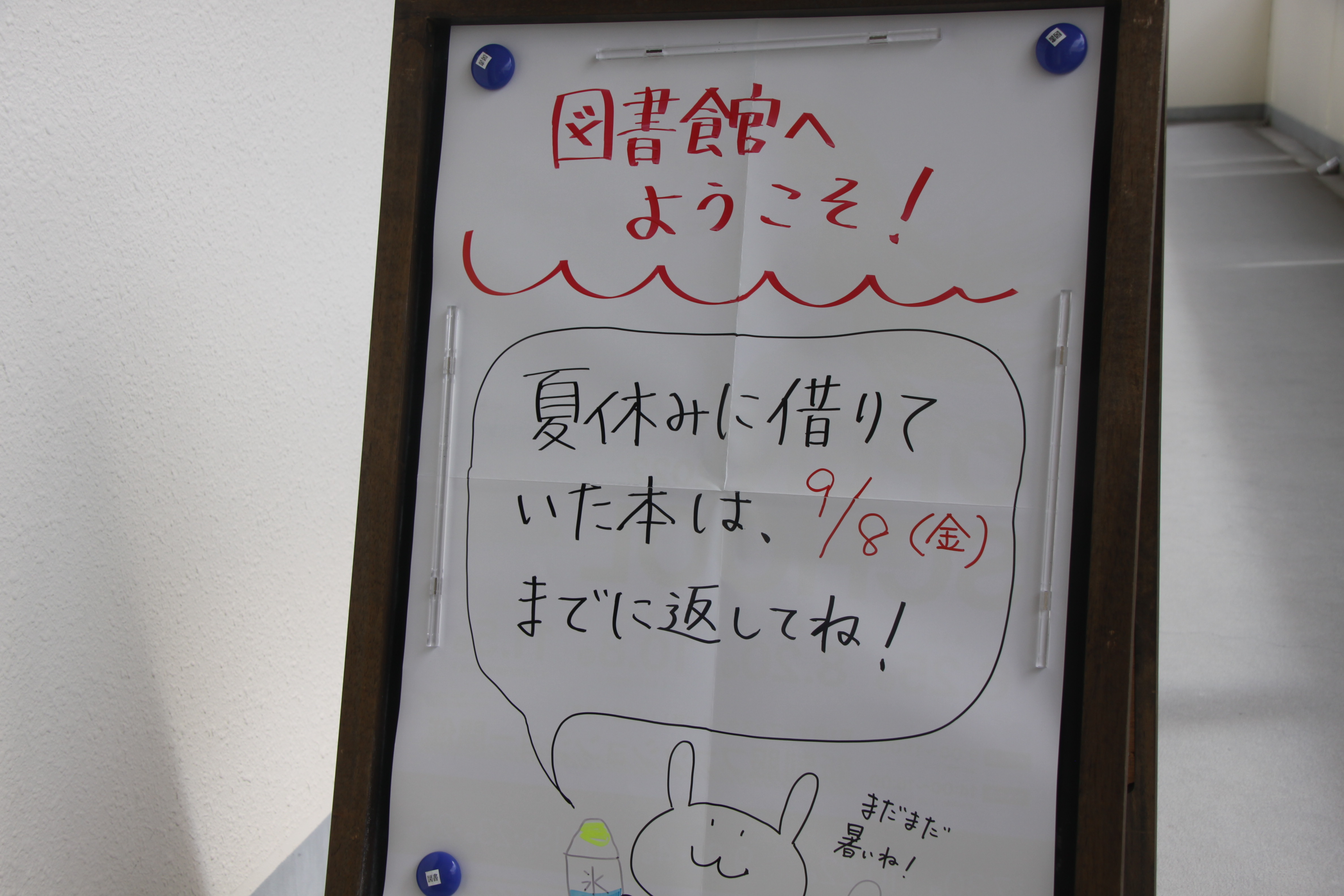
◎2学期始業の集い
~かいなを強く鍛えよと風に常盤の香を送る♪~(8/30)
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up Mark Twain
あなた自身を元気付けるための最良の方法は、誰か他の人を元気付けてみることだ。

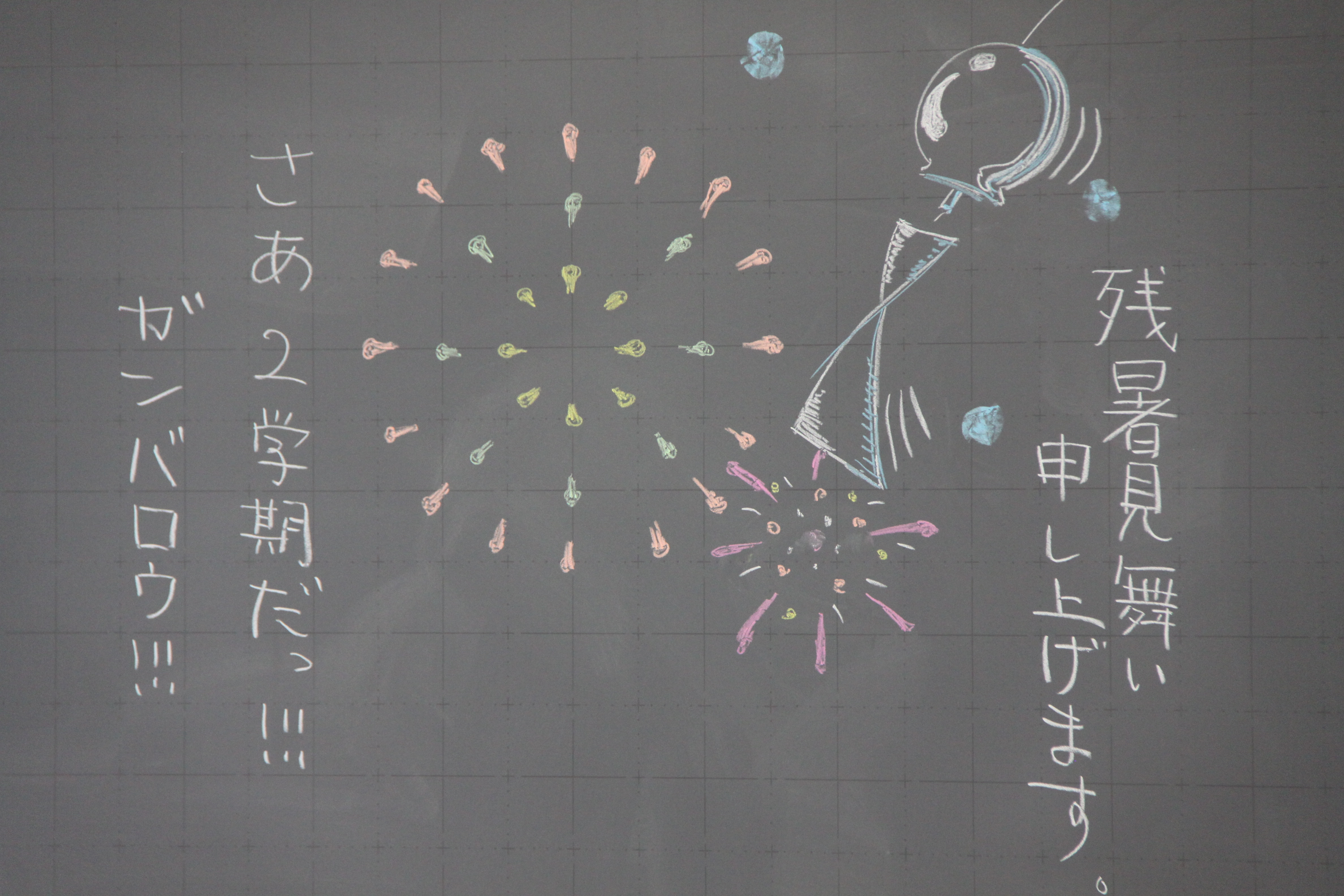







私のコトバを大事にしよう…「The words spoken determine the value of the person. Bernard Shaw」(話す言葉によって、その人の価値は決まる。)
◎〈 あの夏と呼ぶべき夏が皆にあり候うごかして氷みづ飲む〉
小島ゆかり(8/29)

◎夏便り~(8/29)






Imagination means nothing without doing. Charles Chaplin(行動を伴わない想像力は何の意味も持たない)
◎多くの人に支えられて(8/28)
二学期のスタートに向けて、教職員も校内の環境整備を進めています。今日は、長年残っていた窓枠の汚れや落書を、時間をかけて機械を使ってとり除きました。教室で使用しているプロジェクターの電球交換や、災害時の避難用食材・トイレの搬入等何かとある八月末の日々です。



◎先生たちもがんばっています。
~みんなの笑顔の学校生活のために~校内研修(8/28(月))
夏季休業中に一人ひとりが研修してきた内容を報告し合い、教育実践に役立てるための校内研修を行いました。

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela
(教育は、世界を変えることができる、最も強力な武器である。)
◎夏便り~春いちごの会へ参加して~(8/26(土))
特別支援教育のニーズのある子どもたちのための情報交流学習会のお手伝いをしてきました。たくさんの方が参加して、「自分らしい」進路実現にむけた〈元気が出るお話〉を聴きました。〈YouTube配信での進路情報は9月上旬まで無料視聴できます。赤磐市HPのトップページからアクセスできます。〉

◎『今日』
8月25日のお誕生を祝して伊藤 比呂美 (翻訳)さんの『今日』を。

Today I left some dishes dirty‚
The bed got made about two-thirty
The nappies soaked a little longer‚
The odour got a little stronger‚
The crumbs I spilt the day before
Were staring at me from the floor.
The art streaks on those window panes
Will still be there next time it rains.
“For shame‚oh‚lazy one‚”you say‚
And“just what did you do today?”
I nursed a baby till she slept‚
I held a toddler while he wept‚
I played a game of hide'n'seek.
I squeezed a toy so it would squeak.
I pushed a swing‚sang a song.
I taught a child what's right and wrong.
What did I do this whole day through?
Not much that shows‚ I guess it's true.
Unless you think that what I've done
Might be important to someone
With bright blue eyes‚ soft blonde hair.
If that is true‚ I've done my share.
今日、わたしはお皿を洗わなかった
ベッドはぐちゃぐちゃ
浸けといたおむつは
だんだんくさくなってきた
きのうこぼした食べかすが
床の上からわたしを見ている
窓ガラスはよごれすぎてアートみたい
雨が降るまでこのままだとおもう
人に見られたら
なんていわれるか
ひどいねえとか、だらしないとか
今日一日、何をしてたの? とか
わたしは、この子が眠るまで、おっぱいをやっていた
わたしは、この子が泣きやむまで、ずっとだっこしていた
わたしは、この子とかくれんぼした。
わたしは、この子のためにおもちゃを鳴らした、それはきゅうっと鳴った
わたしは、ぶらんこをゆすり、歌をうたった
わたしは、この子に、していいこととわるいことを、教えた
ほんとにいったい一日何をしていたのかな
たいしたことはしなかったね、たぶん、それはほんと
でもこう考えれば、
いいんじゃない?
今日一日、わたしは
澄んだ目をした、
髪のふわふわな、
この子のために
すごく大切なことを
していたんだって
そしてもし、
そっちのほうがほんとなら、
わたしはちゃーんとやったわけだ
The bed got made about two-thirty
The nappies soaked a little longer‚
The odour got a little stronger‚
The crumbs I spilt the day before
Were staring at me from the floor.
The art streaks on those window panes
Will still be there next time it rains.
“For shame‚oh‚lazy one‚”you say‚
And“just what did you do today?”
I nursed a baby till she slept‚
I held a toddler while he wept‚
I played a game of hide'n'seek.
I squeezed a toy so it would squeak.
I pushed a swing‚sang a song.
I taught a child what's right and wrong.
What did I do this whole day through?
Not much that shows‚ I guess it's true.
Unless you think that what I've done
Might be important to someone
With bright blue eyes‚ soft blonde hair.
If that is true‚ I've done my share.
今日、わたしはお皿を洗わなかった
ベッドはぐちゃぐちゃ
浸けといたおむつは
だんだんくさくなってきた
きのうこぼした食べかすが
床の上からわたしを見ている
窓ガラスはよごれすぎてアートみたい
雨が降るまでこのままだとおもう
人に見られたら
なんていわれるか
ひどいねえとか、だらしないとか
今日一日、何をしてたの? とか
わたしは、この子が眠るまで、おっぱいをやっていた
わたしは、この子が泣きやむまで、ずっとだっこしていた
わたしは、この子とかくれんぼした。
わたしは、この子のためにおもちゃを鳴らした、それはきゅうっと鳴った
わたしは、ぶらんこをゆすり、歌をうたった
わたしは、この子に、していいこととわるいことを、教えた
ほんとにいったい一日何をしていたのかな
たいしたことはしなかったね、たぶん、それはほんと
でもこう考えれば、
いいんじゃない?
今日一日、わたしは
澄んだ目をした、
髪のふわふわな、
この子のために
すごく大切なことを
していたんだって
そしてもし、
そっちのほうがほんとなら、
わたしはちゃーんとやったわけだ
◎多くのひとに支えられて(8/23)
酷暑の中、機器の整備作業をありがとうございました。

◎多くのひとに支えられて(8/22)
暑い中、今年も貯水槽の点検をしていただきました。ありがとうございました。また、明日は校内のICT機器の整備を行います。併せて、来年度の予算ヒアリングも行われます。学習環境を一層充実させ、教育活動の充実に努めます。






◎ひな中のかぜ~~心の痛みを想像して。(8/22)
重松清さんが、以前に山陽新聞に書かれた記事を『ひとのあいだ』で紹介します(8/30号)が、事前に読まれた先生から「HPでも読んでもらおうよ」とアドバイスをいただきました。2学期最初の時期は、子どもは不安や悩みを抱えることがしばしばあります。何か気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。(;^ω^)
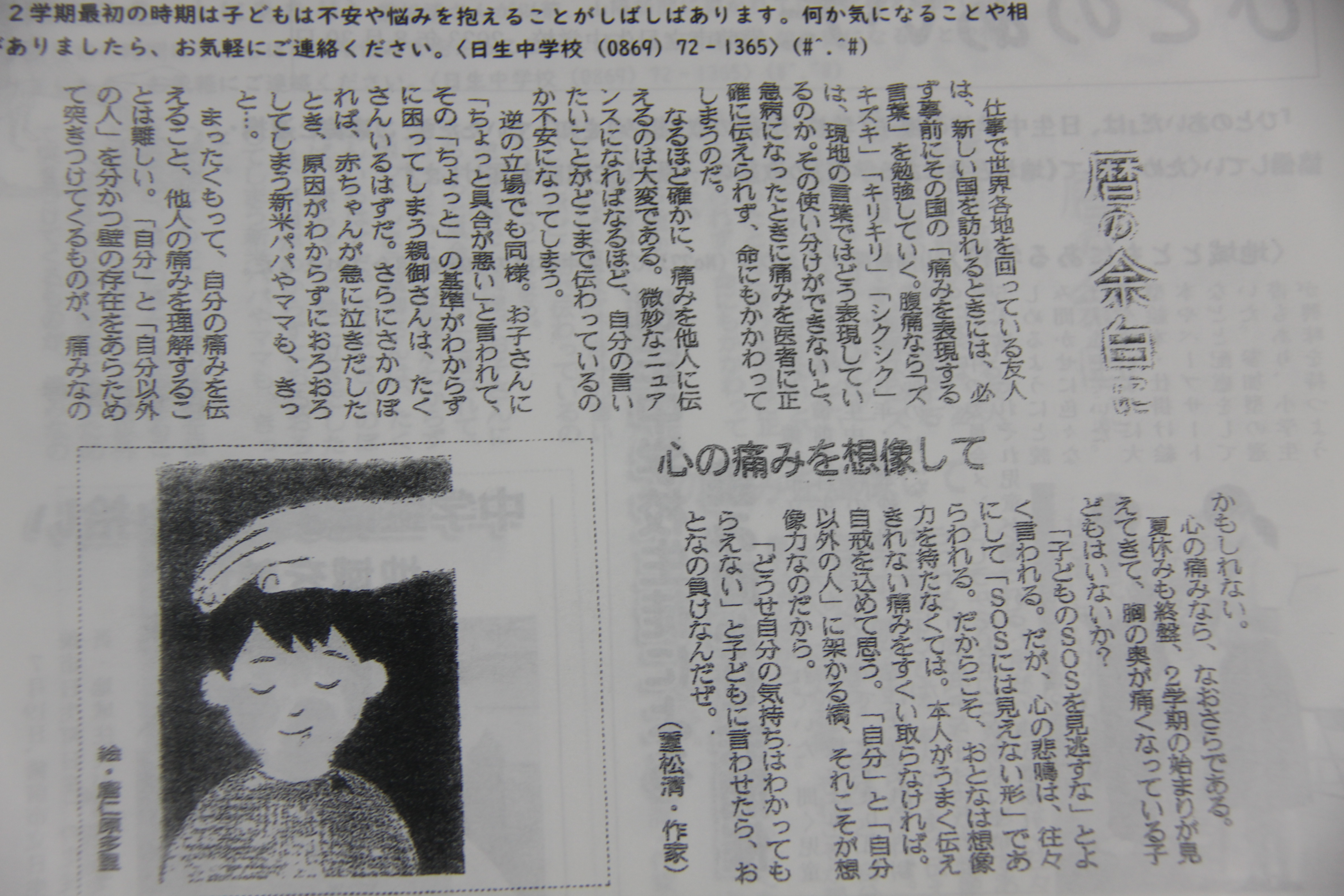
◎ひな中のかぜ~~今日は、明日につながっている。(8/22)
「一度も失敗しないことは自慢にならない。それは上手であるだけだ。10回失敗して11回立ち上がるなら、事はすでに成就している。:むのたけじ」
〇9月16日・17日 備前地区総合体育大会
〇9月17日 日生中学校吹奏楽部定期演奏会(伊里中合同)









◎ひな中のかぜ~~空に太陽がある限り♬
クラス菜園での夏の実り。子ども一人ひとりの夏の「経験・学び・成長」を大切にしていきたいものです。(8/17)

◎夏便り~~多くの方に支えられて
コミュニティカフェ天gooへ行かれた先生からの報告です。(8/18)

地域のこどもたち誰もが、地域の信頼できる大人たちの見守りの中で、安心して集える場所、「こどもの居場所」を開設している取組などなど、たくさんのお話を聴かせていただきました。楽しい、熱いひと時をありがとうございました。(詳細は天gooカフェのHPをぜひご覧ください)
夏ボラでも多くの生徒がお世話になりましたが、これからも〈地域とともにある日生中学校〉として、さらに連携・協働活動を進めていきたいと思います。
◎8月後半も、部活動、なかまとともに。
毎日、私らしくがんばろう。
残夏、宿題もせいいっぱい。



◎岡山県PTA連合会事務局長会へ参加(8/17)
この日、県内各地区の郡市PTA連合会の事務局長が集まり、今後の活動についての意見交換・情報共有を行いました。
岡山県PTA連合会について少しだけ紹介します。(詳しくは新HPで)
〈綱 領〉本会は教育を本旨とし、特定の政党や宗教に偏ることなく、小学校及び中学校におけるPTA活動を通して、わが国における社会教育及び家庭教育の充実に努めるとともに、家庭・学校・地域の連携を深め、子どもたちの健全育成と福祉の増進を図り、もって社会の発展に寄与する。
共に育もう やさしさと感謝の心を ~子どもたちの平和で豊かな未来のために~
〈基本方針〉岡山県PTA連合会は心豊かでたくましい子どもたちの育成を願い、会員一人ひとりが、魅力ある大人となるための学習や研修活動の充実と情報の提供に努め、また学校を支援し、学校・家庭・地域の絆を更に深める活動の推進を目指します。PTAは関係機関と協働して家庭や地域の教育力の向上に一層の努力をいたし、社会教育関係団体として率先して正しい教育世論の形成に努め、PTAに寄せられている期待に一層応えるよう努力をしてまいります。同時に各郡市PTA連合会との連携を密にし、活動の基本である単位PTAの活動を支援します。次に青少年の健全育成を阻害する社会環境の著しい悪化を背景として命の軽視や児童虐待等、多くの問題が発生し憂慮すべき事態に至っていますが、すべての大人がそれぞれの立場で命の大切さ物事の善悪の判断等、基本的倫理観や規範意識をしっかりと教え、身に付けさせるよう、家庭教育の重要性を協力に呼びかけ、積極的な活動を勧めてまいります。

これからの備前市PTA連合会の取組についても、新しい発想・ご意見・アイデア等随時聴かせていただけたら幸いです。(本年度事務局日生中へ)
◎夏便り~~
渋染一揆のフィールドワークへ参加された先生からの報告です。(8/16)
江戸時代も末期を迎えると幕府や藩の財政は苦しくなり、経済の引締めが相次いで行われました。岡山藩では、庶民に出した倹約令を徹底するため、被差別身分の人々に、「柄のない渋染めか藍染め以外の着物の着用を許さない」というさらに厳しい御触れを出します。あからさまなこの「分け隔て」の「差別」を認めるわけにはいかないと藩内53ケ村の人々は、のちに「渋染一揆」と呼ばれる大規模な抵抗運動を起こしました。
この渋染一揆に関連した歴史的な場所を実際に歩き、話を聴く中で、人としての尊厳をかけ、社会情勢を見抜き、知恵と力を合わせて闘った人々から、いま学ぶべきことは何かを深く考えました。

◎ひな中の風 ~台風一過、お見舞い申し上げます。
〈なにになったらわたしはさみしくないんだろう柑橘系の広場の中で 初谷むい〉
〇2学期始業の集い…8/30(水)から、またみんなでガンバロウ!
〇2年生だっぴ…8/31(木)
*時程は「夏休みのしおり」で各自確認を!
遅れんように、よいスタートをみんなで。!(^^)!

*〈だっぴ〉について…社会には、地域で生き、地域を作り、文化を継承してきたような魅力的な大人が多くいらっしゃいます。
その方たちは、様々な苦難を乗り越え、自身の価値観を形成し、地に足をつけて社会を作ってきた“先駆者”といえる魅力的な大人たちです。
もし、このような魅力的な大人と地域の未来を担う若者が顔を見ながら交流する機会や場が当たり前に地域社会にあるとしたら・・・
若者は、自分の夢や気持ちを諦めることなく、自分の意思で選択していく勇気を持つことが出来るのではないでしょうか。
【場の継続的な創出】
私たちは、このような場を地域に当たり前に作るために、“未来を模索する若者”と“地域の魅力的な大人”とがつながる場を創出し続けます。
未来を模索する若者と魅力的な大人の出会いは、それぞれの「実現力」を高めます。
《NPO法人だっぴHPより一部》
◎ひな中の風~~星輝祭(10.7文化の部)へ
たいせつな取り組み たいせつな仲間たちと 思いをこめて



ホリゾントの作製に各クラスで取り組んでいます。
◎8月15日がやってくる
21世紀の日本において、戦後とは、直近の戦争の第二次世界大戦終結後を指します。日本にとって精神的に大きな影響を与えた1945年(昭和20年)8月15日以降を戦後の始まりとし、「戦前・戦中」「戦後」として区分し、認識されている場合が多いです。この1945年(昭和20年)から「戦後」と表現され、今年は「戦後78年」に当たります。
宮柊二さんの歌をいくつか紹介します。
磧(かはら)より夜をまぎれ来(こ)し敵兵の三人(みたり)までを抑へて刺せり
ひきよせて寄り添ふごとく刺(さ)ししかば声も立てなくくづをれて伏す
石多き畑匍ひをれば身に添ひて跳弾の音しきりにすがふ
夏(なつ)衣(い)袴(こ)も靴も帽子も形なし簓(ささら)となりて阜平へ迫る
稲靑き水田見ゆとふささやきが潮(うしほ)となりて後尾(こうび)へ傳ふ
母よりの便り貰ふと兵隊がいたく優しき眼差(まなざ)しを見す
胡麻畑を踏みゆく若き戰(と)友(も)が云ふあはれ白胡麻は内地にて高しと
敵襲のあらぬ夜はなし斥けつつ五日に及べ月繊(ほそ)くなりぬ
手榴弾戰を演じし夜(よる)の朝(あした)にて青葦叢(むら)に向ひ佇(た)ちゐつ
護送途次ややによろしと傳へきて死亡を伝ふ二時間の後(のち)
女(め)童(わらは)を幸枝と言ふと羞(やさ)しみて告げけり若き父親にして
十二月二十六日入院
虔(つつし)みて吾等あれこそみんなみにいくさ戰ふときを病みつつ
病床(やみどこ)に臥(ふ)しつつ読むにあな羨(とも)しマニラへ迫る皇軍(みいくさ)のさま
再びをいくさにたたむ希(ねが)ひをばこもごも語る夜々集(よよつど)ひては
泥濘に小休止する一隊がすでに生きものの感じにあらず
麥の秀(ほ)を射ち薙ぎて弾丸(たま)の来るがゆゑ汗ながしつつ我等匐ひゆく
チヤルメラに似たりとおもふ支那軍の悲しき喇叭の音起りつつ
今日一日(ひとひ)暇(いとま)賜ひて麥畑に戰友(とも)らの屍(かばね)焼くと土掘る
昭和十七年七月「多磨」
戰死者をいたむ心理を議論して涙ながせし君も死にたり
◎〈エノラ・ゲイの火の翼 否死の翼 夕映えならば誰に触れなん 正岡 豊〉
(8/9)

◎〈ああ夏よ 長く思えど 実際は 風の速さで 過ぎゆくものよ〉
暑中お見舞い申し上げます。充実した夏休みが送れていますか?自分自身、また友達のことで何か気になることや心配なことがあればいつでも学校に相談してね。(学校閉庁日は8月10日~16日ですが…。)

◎夏便り~~人権研修に参加された先生から、ブルーハーツの歌を紹介していただきました。(8/8)
青空 歌 ブルーハーツ
作詞作曲 真島昌利
ブラウン管の向こう側 カッコつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した
ピカピカに光った銃で できれば僕の憂鬱を打ち倒してくれれば良かったのに
神様にワイロを送り 天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか
隠している その手を見せてみろよ
生まれたところや皮膚や目の色で 一体この僕の何が分かるというのだろう
運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないか
行き先ならどこでもいい
こんなはずじゃなかっただろ
歴史が僕を問い詰める
。
◎多くの人に支えられて(8/7)
備前警察署スクールサポーターの根木さんが来校され、自転車の施錠についてのサポートしてくれました。日生中学校は9月から県警察本部主催の鍵かけコンテストに参加します。いつも体育委員会が点検と声かけの取組をしていますが、この機会に、さらなる意識向上と施錠の徹底を進めましょう。
8月13日は、ひなせみなとまつりです。安全に十分気をつけて、楽しい時を過ごしましょう。日生中PTA生活指導部のメンバーは、備前市青少年育成センターと連携して会場を廻ります。

◎8月6日。日生中学校では、戦争・原爆・平和・ヒロシマについて継続的に学んでいます。
大平数子さん(1923-1986)の詩を紹介します。*広島の爆心地より2.2kmの地点で被爆。体内被曝の次男は、生後間もなく死去。夫も被爆により死亡。
『少年のひろしま』より
「あい」
逝ったひとはかえってこれないから
逝ったひとは叫ぶことが出来ないから
逝ったひとはなげくすべがないから
生きのこったひとはどうすればいい
生きのこったひとは何がわかればいい
生きのこったひとは悲しみをちぎってあるく
生きのこったひとは思い出を凍らせて歩く
生きのこったひとは固定した面(マスク)を抱いて歩く
(原爆より三日目に吾が家の焼けあとに呆然と立ちました)
めぐりめぐってたずねあてたら まだ灰があつうて
やかんをひろうてもどりました
でこぼこのやかんになっておりました
「やかん」
やかんよ
きかしてくれ
親しい人の消息を
やかんがかわゆうて
むしように
むしようにさすっておりました
坊さんが来てさ
くろいものを着てさ
かねをならしはじめると
母さんに見つめられて
あかるい灯明のむこうに
おまえたち
てれているのさ
ぽろ ぽろ
いとすいせんの匂う下で
母さんに叱られたとき
おまえたち
やったように
ちょっと泣き顔なのさ
「月夜」
もう寝たかい
もうねたかい
まだかい
もうねたろう
はよう
ねてくれよ
よんでいる
だれかよんでいる
むこうのほうでよんでいる
くずれながら
よせてきながら
母(ママン)ー
どこかでよんでいる
母(ママン)ー
沖の方でよんでいる
夕方
花やの前を通ると
花たちがいっせいにこっちを見る
チューリップも
アネモネも
スイートピーも
ヒヤシンスも
それからフリージアも
みいんな
手を出して
連れてかえってくれという
母さんに抱かれていたい言う
「失ったものに」
まちにあったかい灯がとぼるようになった
ふかふか ふかしたてのパンが
ちんれつだなにかざられるようになった
中学の帽子が似合うだろう
今宵かじるこのパンを
たべさしてやりたい
はらいっぱいたべさしてやりたい
女夜叉(おんなやしゃ)になって
おまえたちを殺したものを
憎んで、憎んで、憎み殺してやりたいが
今日は
母さんは空になって
おまえのための鳩を飛ばそう
まめつぶになって消えていくまで
とばしつづけよう
「慟哭」
しょうじ よう
やすし よう
しょうじ よう
やすし よう
しょうじ よおう
やすしい よおう
しょうじい よおう
やすしい よおう
しょうじい
しょうじい
しょうじいい *(しょうじ=次男)(やすし=長男)
◎生徒のみんな!学んでいますか?! 先生たちも校内研修で学んでいます。
夏季休業中は先生たちも大切な勉強の時間。2学期がさらに充実するよう計画的・主体的にみんなで研修に勤しんでいます。8月1日は備前市教育研修所人権教育研修会(備前市民センター)へ参加。8月2日は教育相談研修で「インデントプロセス法活用したケース会議の持ち方」について協議、教育課程の振り返りと次年度へ向けての検討会。8月3日はハイパーQUの活用と、2学期以降の人権教育プログラムの推進に向けて検討しました。8月28日は、各自が夏季休業中に取り組んだ研修について報告と情報共有を図ります。


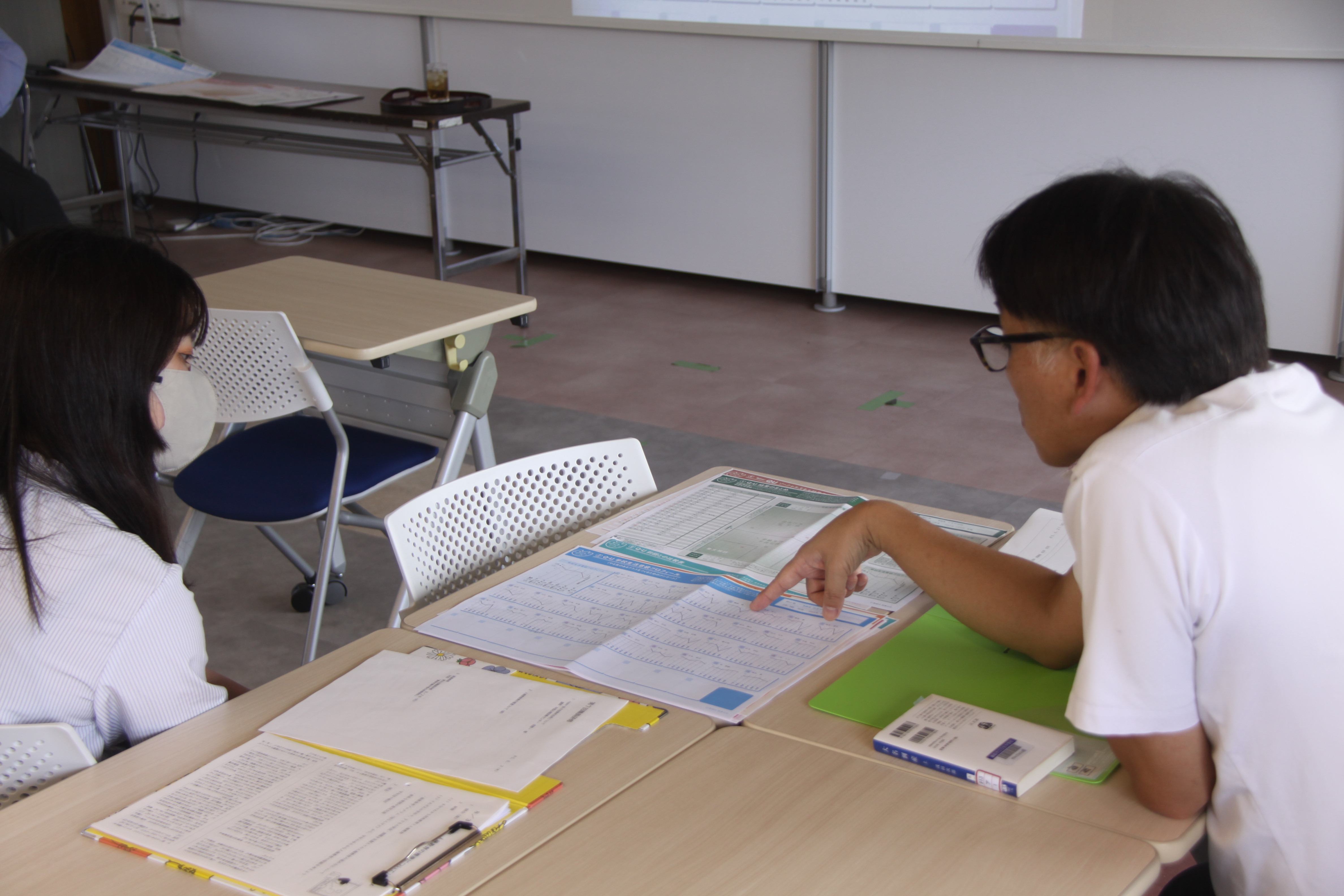
世阿弥『花鏡』より
…三箇条の口伝あり。
是非の初心忘るべからず。
時々の初心忘るべからず。
老後の初心忘るべからず
世阿弥は、“初心”をこのように3つに分けています。世阿弥の論ずる人生の中では、初心は何度もあるもの。「是非の初心忘るべからず」は、判断基準になる初心者時代の未熟さを忘れるべきでない。
「時々の初心」は、初心者から老年まで修行する中で、それぞれの時期における初心の段階を忘れるべきではない。そして「老後の初心」とは、年を取ったからと言って終わりではない、老年になってからも初めての事があるのでやはり初心を持って芸を極めるべきである。という事です。お能の世界で演者たちは、幼い子供時代や声変わりをする青年期など、各年齢にふさわしい芸を習得する必要があります。一度できたからと言って習得した芸を忘れてしまう事は、過去に習った事が全て身についていない事になります。獲得した芸を自分の物にするためには、復習を怠ってはいけません。いつまでも成長し続ける姿勢をもって、老後に至ってからも自分の未熟さを忘れないことが大事だということですね。
◎連携・協働を大切に、子どもたちの十五年間のゆたかな育ちを保障する教育を創りましょう。
日生中学校区連携協議会の研修会を日生西小学校で開催しました。総会後、学力向上部会・生徒指導部会・特別支援教育部会に分かれて部会協議を行いました。その後、スキルアップ研修会で学びを深めることができました。

◎ひな中の風~~
今年度も出張(。・ω・。)ノ♡文化委員によるお話し会
(日生西小7/27・日生東小7/31訪問)









◎公開保育にて(日生認定子ども園:7/27)
遊びをせむとや生まれけむ戯(たはぶ)れせむとや生まれけむ
遊ぶ子供の声聞けば我が身さへこそゆるがるれ (梁塵秘抄三五九より)






◎図書館開いてるよ ポンポンづくり(7/24)
明日と8/24もつくれるよ。ミサンガは8/23だよ。


◎地域とともにある学校
本校の生徒会主催のボランティア活動が山陽新聞(7/22)に紹介されました。
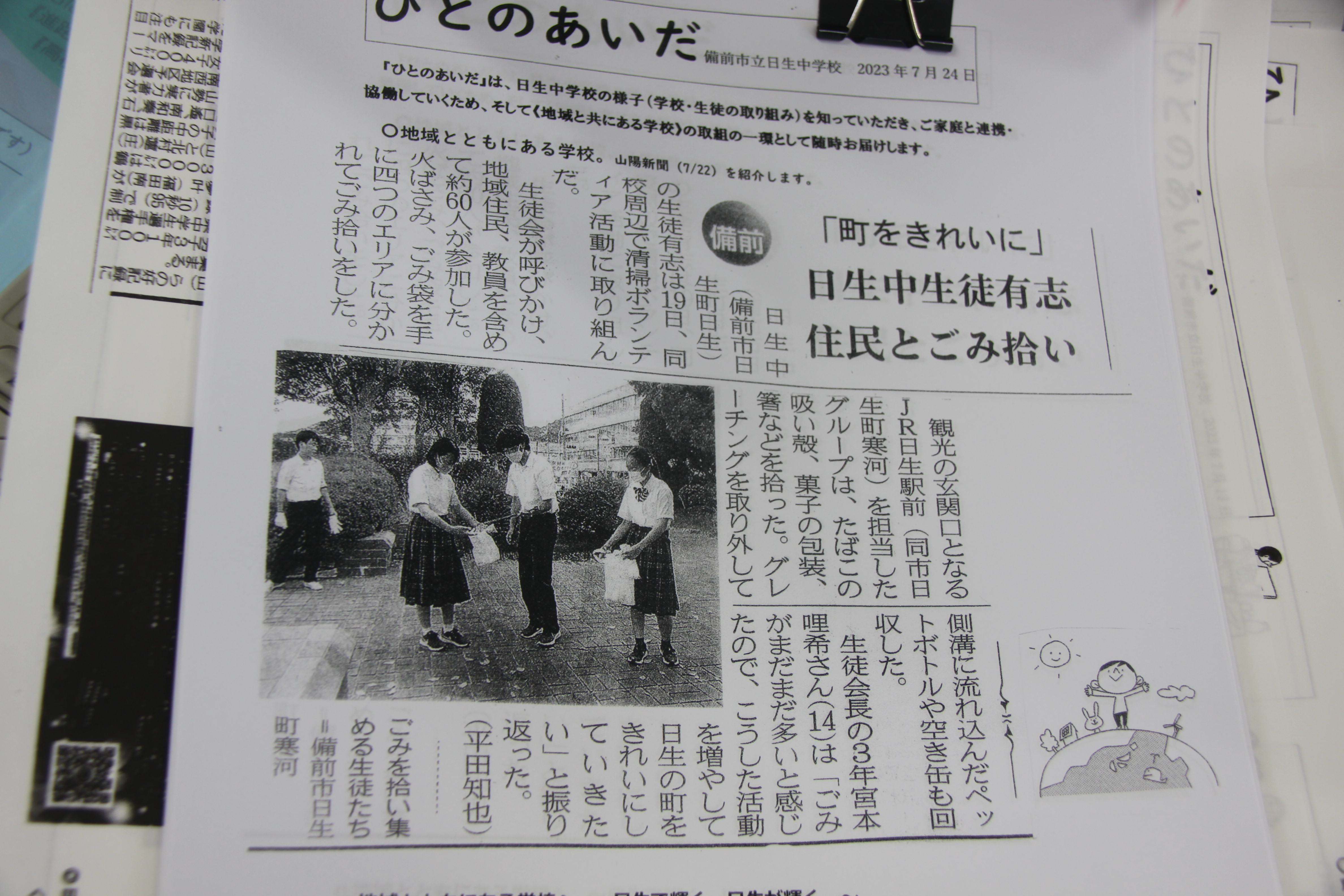
◎夏・ひな中 仲間とならガンバレル!~2年生補充学習中~


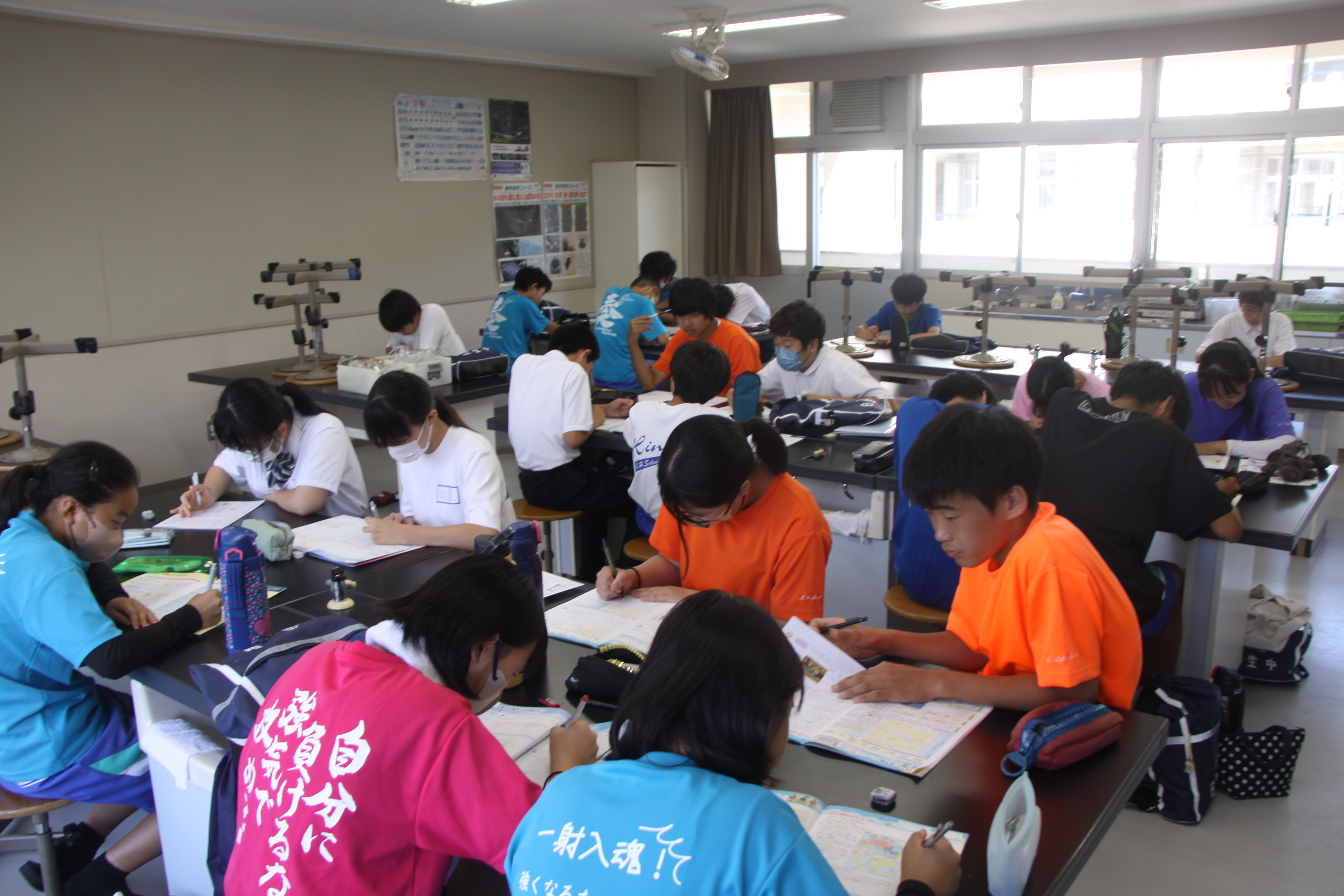
◎夏・ひな中 仲間と楽しむ ~図書館開館日を活用しよう~(7/20)
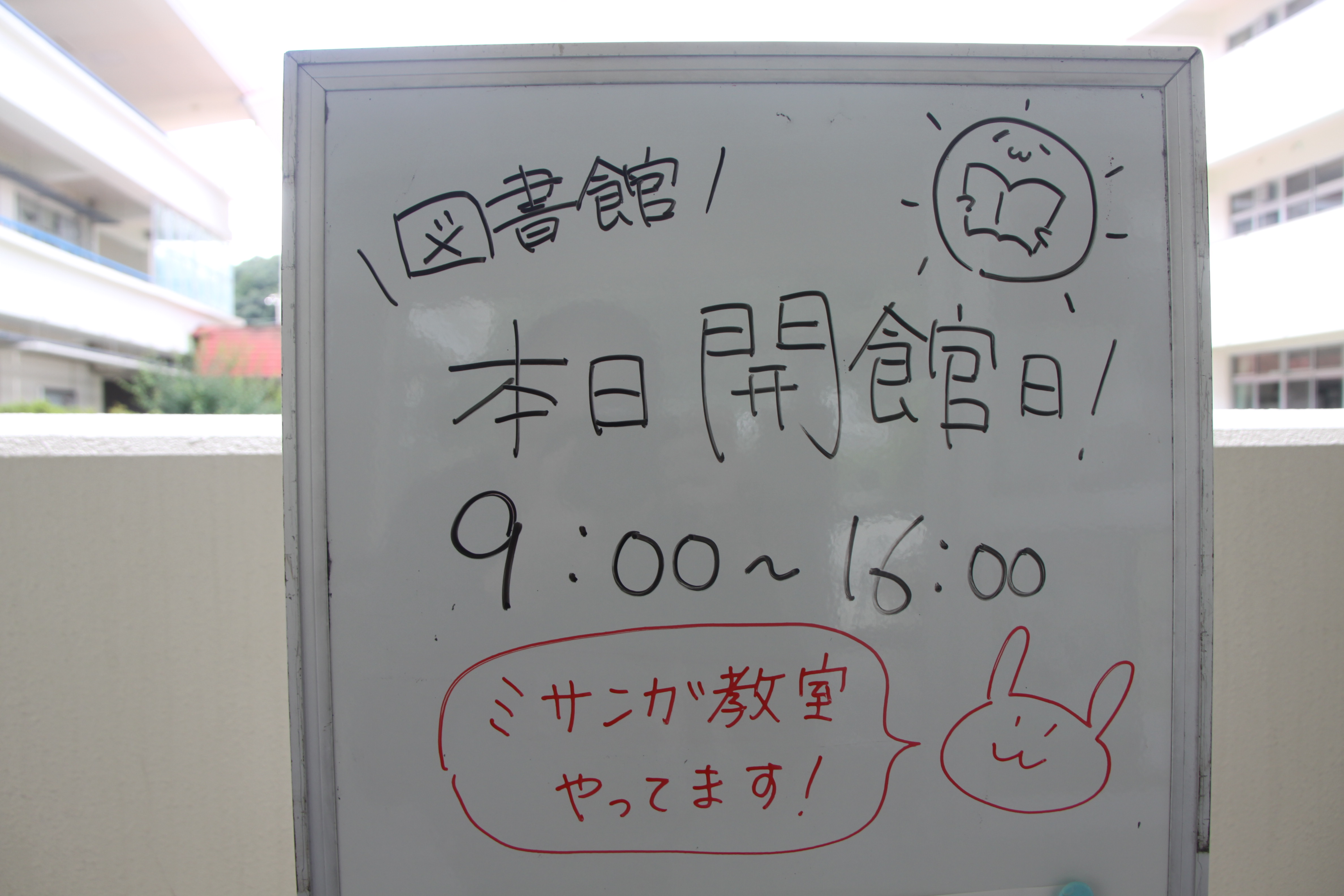
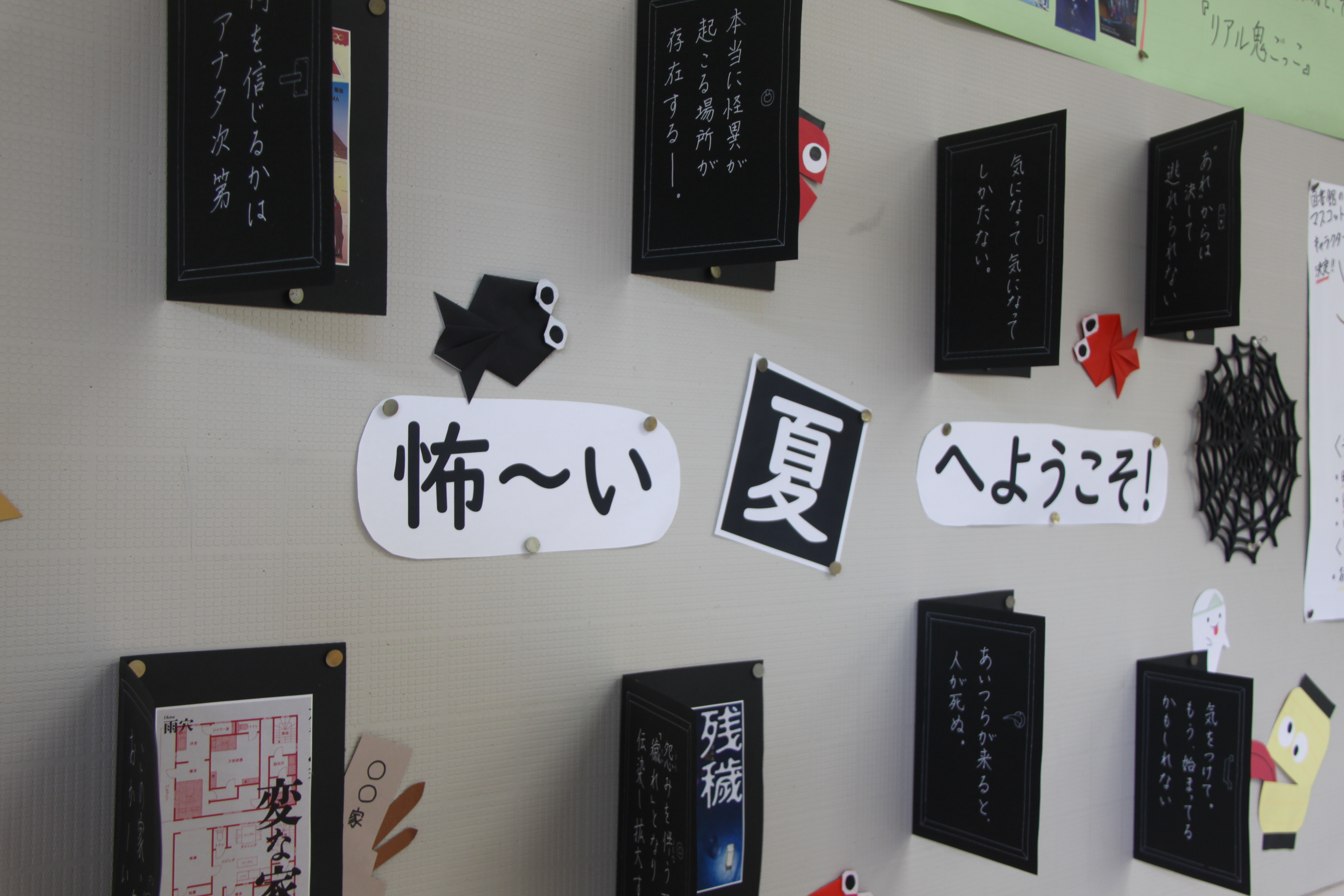


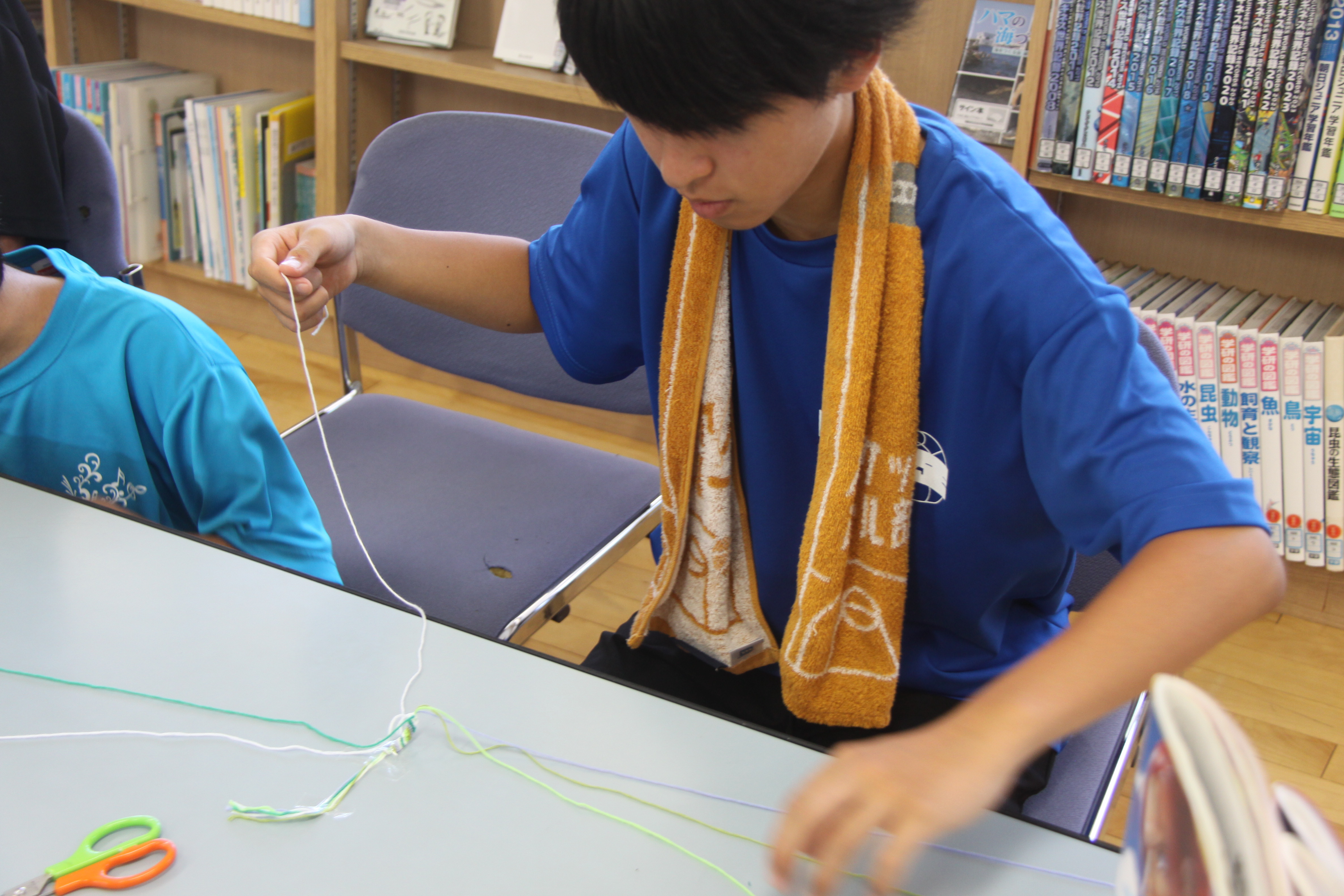
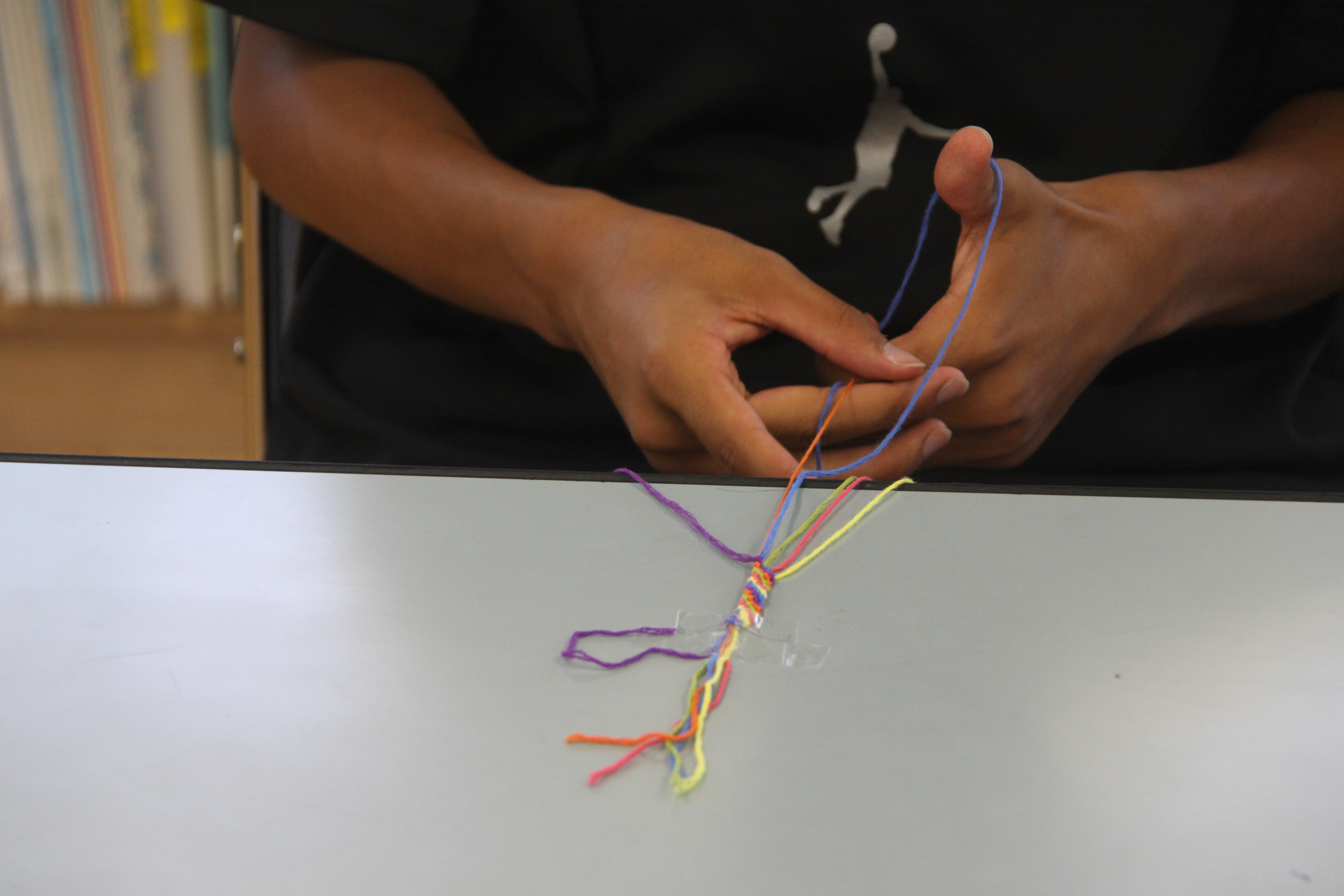
◎夏・ひな中にエール!
目標を達成するには、全力で取り組む以外に方法はない。
そこに近道はない。(7/20)
マイケル・ジョーダン (元バスケットボール選手)









7/22吹奏楽コンクール中学生小編成の部予選大会(マービーふれあい)
◎地域とともにある学校へ
~わたしたちがうごく まもる つくる わたしたちのまち~(7/19)
日生地域の夏祭りが計画されている中、生徒会が声かけして今年度も清掃ボランティアに取り組みました。地域の方々も参加してくださる予定でしたが、天候が不安定のために、生徒のみで行いました。活動には、60人以上の生徒が参加し、学校周辺、日生駅、日生西小、大通りを参加メンバーで手分けして環境美化に貢献することができたように思います。









◎地域とともにある学校へ ~日生で輝く 日生が輝く。~
頭島あかりまつり〈9.2〉へ、わたしたちもつながる!(^^)!
実行委員さんと社会福祉協議会日生支所さんをお招きして、3年生が行燈づくりに取り組みました(7/19)
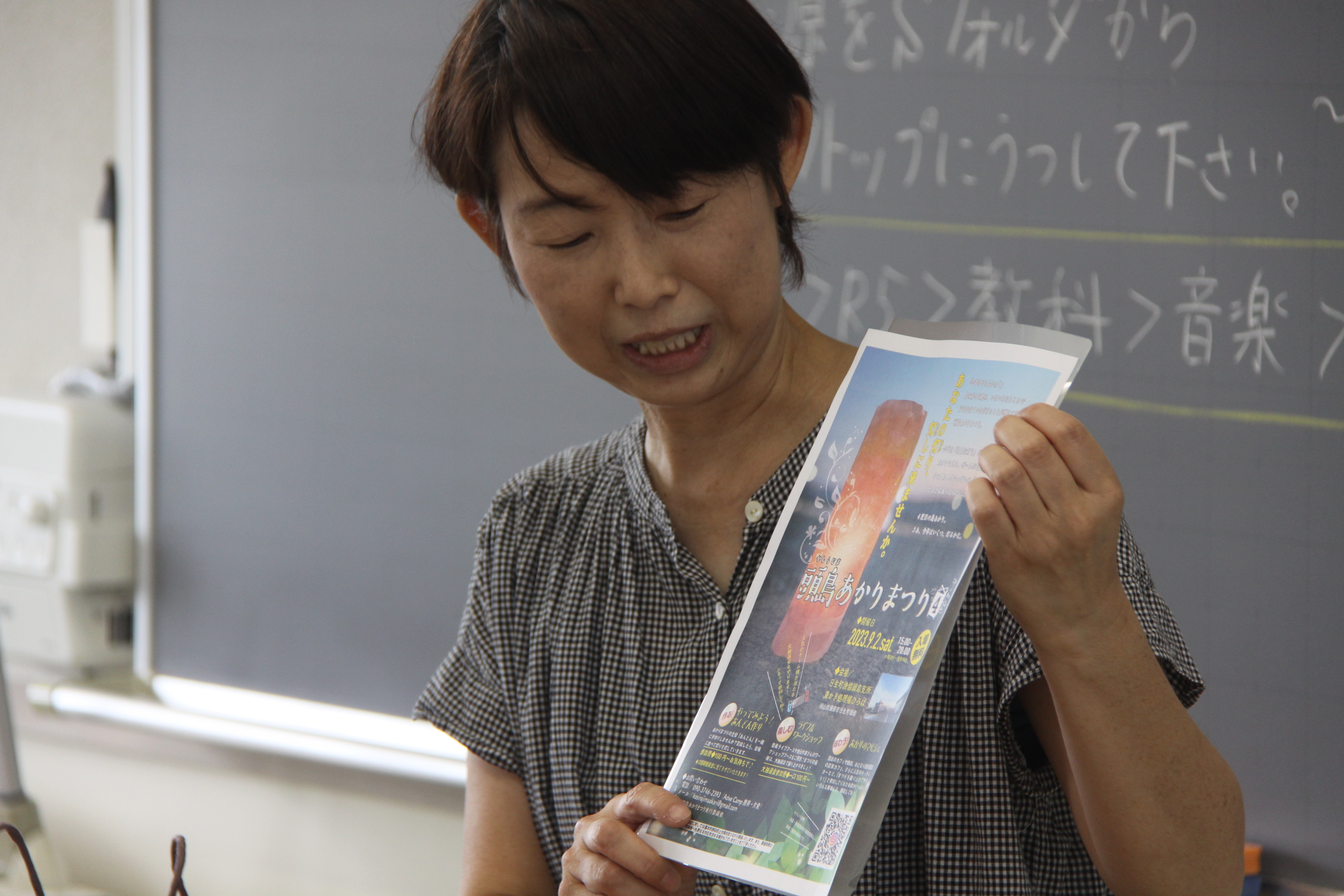





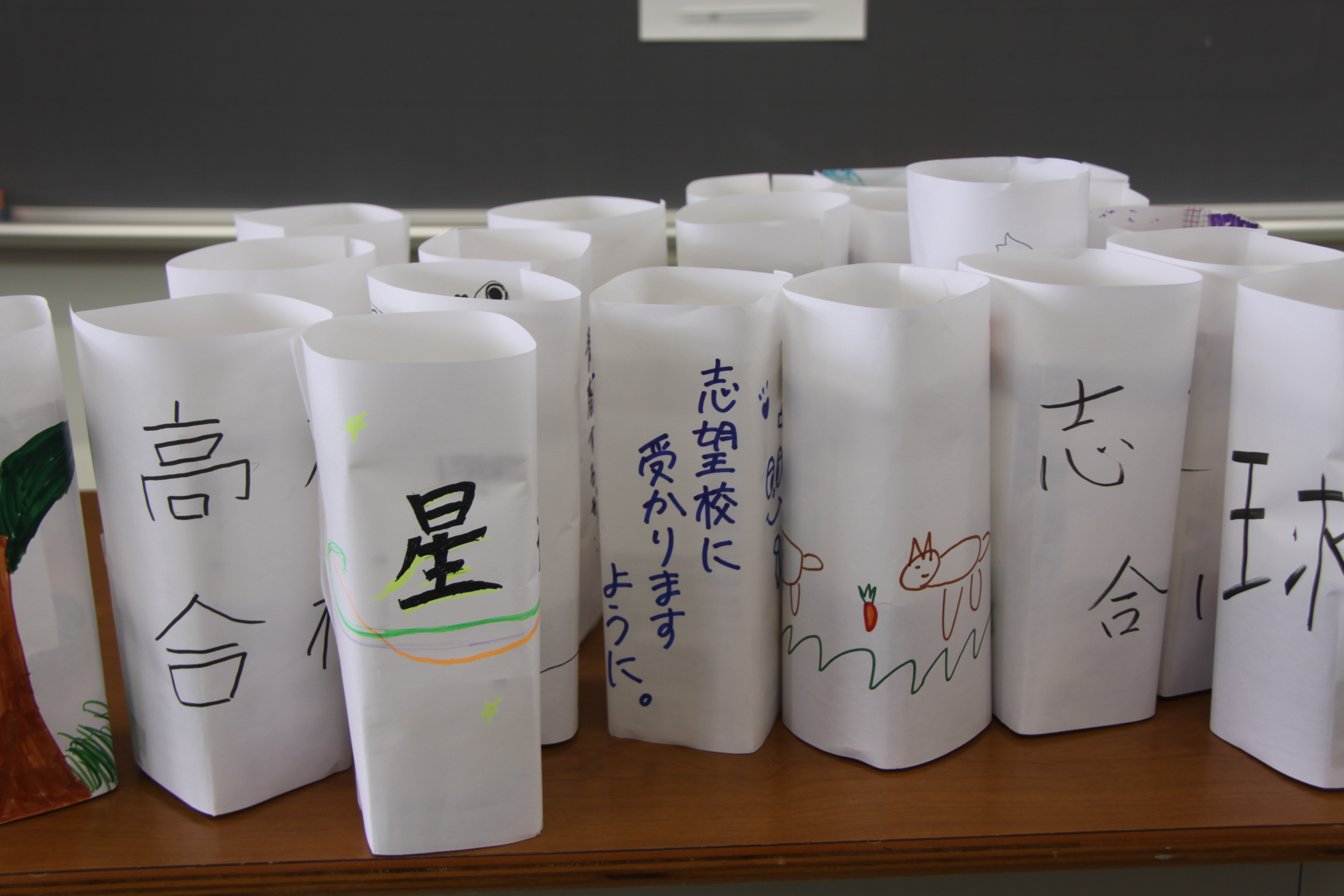


◎〈体育館の窓が切りとる青空は外でみるより夏だったこと 木下龍也〉
ステキな夏に、自分らしくせいいっぱい!




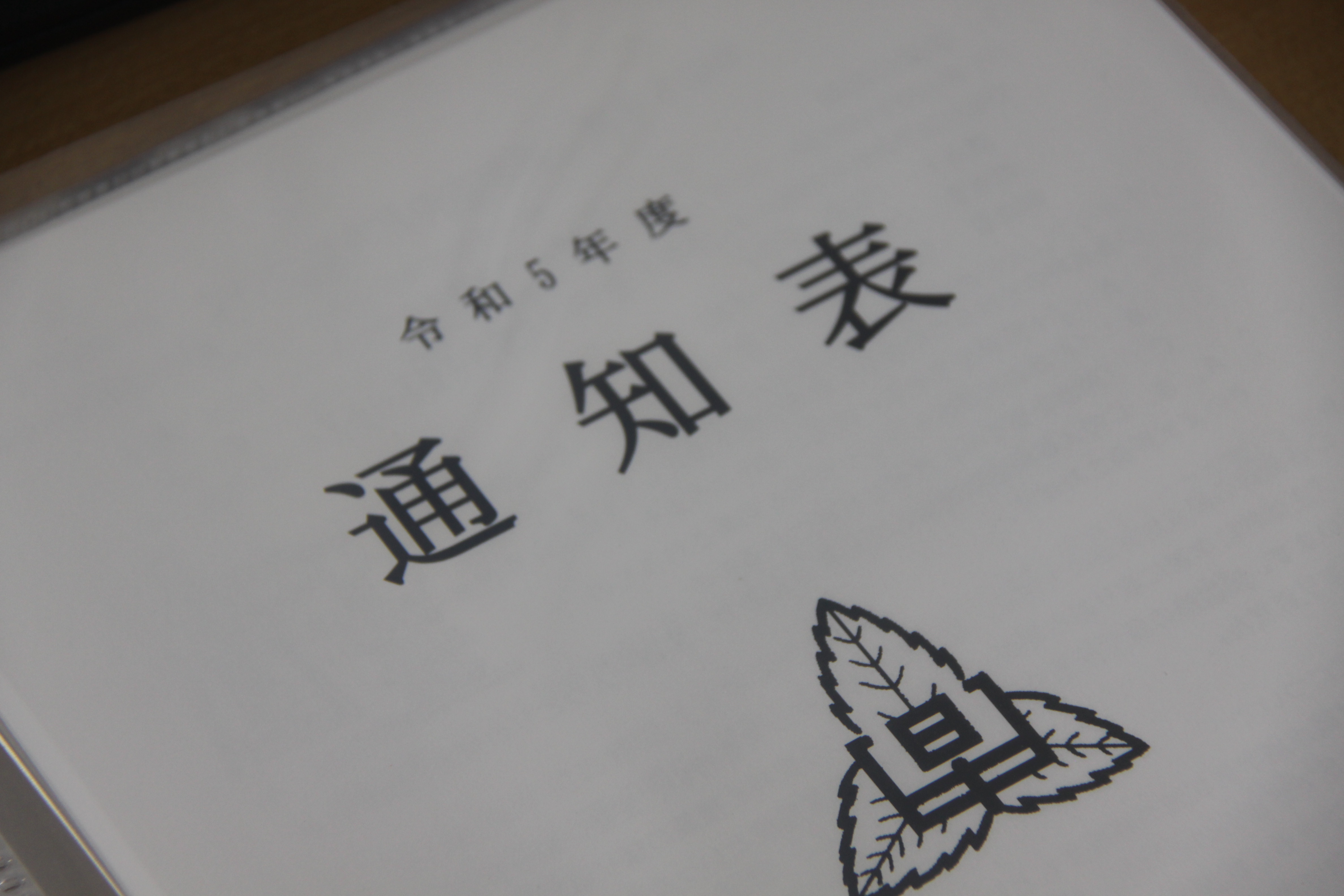
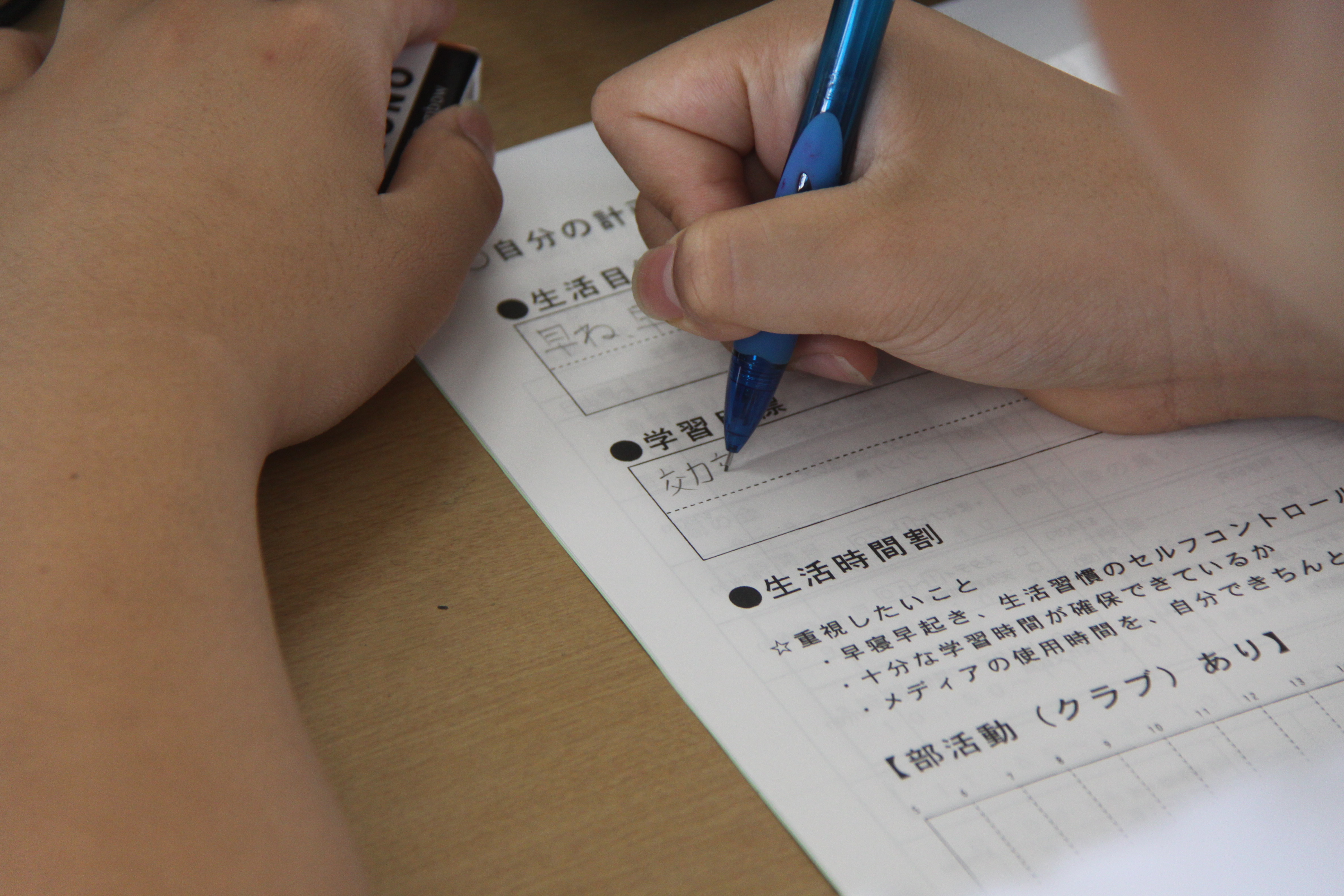

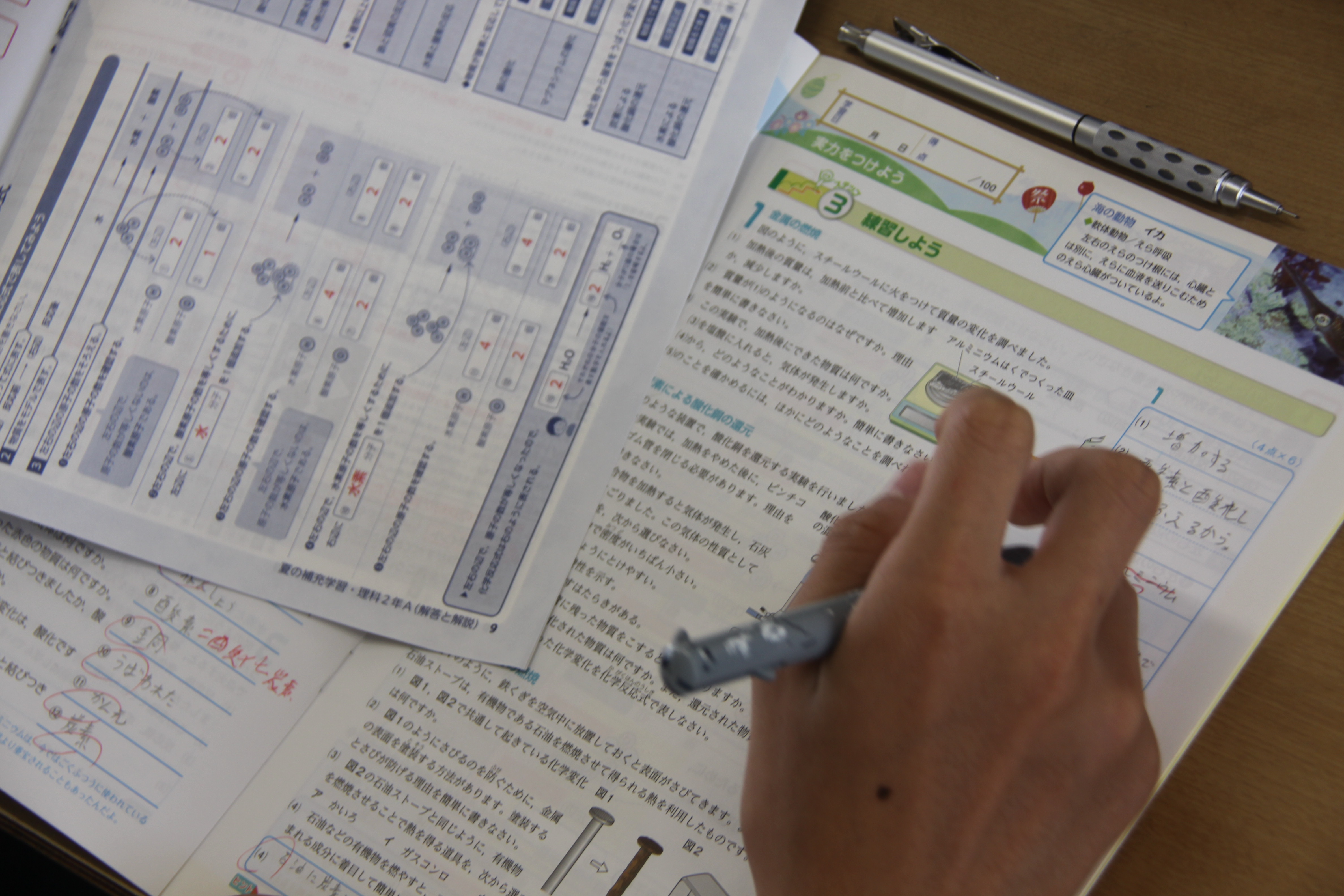

◎SUMMER TIME BLUES
~一学期終業式(7/19)に贈るコトバ。
「生きる」 谷川俊太郎
生きているということ
いま生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ
くしゃみすること
あなたと手をつなぐこと
生きているということ
いま生きているということ
それはミニスカート
それはプラネタリウム
それはヨハン・シュトラウス
それはピカソ
それはアルプス
すべての美しいものに出会うということ
そして
かくされた悪を注意深くこばむこと
生きているということ
いま生きているということ
泣けるということ
笑えるということ
怒れるということ
自由ということ
生きているということ
いま生きているということ
いま遠くで犬が吠えるということ
いま地球が廻っているということ
いまどこかで産声があがるということ
いまどこかで兵士が傷つくということ
いまぶらんこがゆれているということ
いまいまが過ぎてゆくこと
生きているということ
いま生きているということ
鳥ははばたくということ
海はとどろくということ
かたつむりははうということ
人は愛するということ
あなたの手のぬくみ
いのちということ (詩集『うつむく青年』1971年刊)





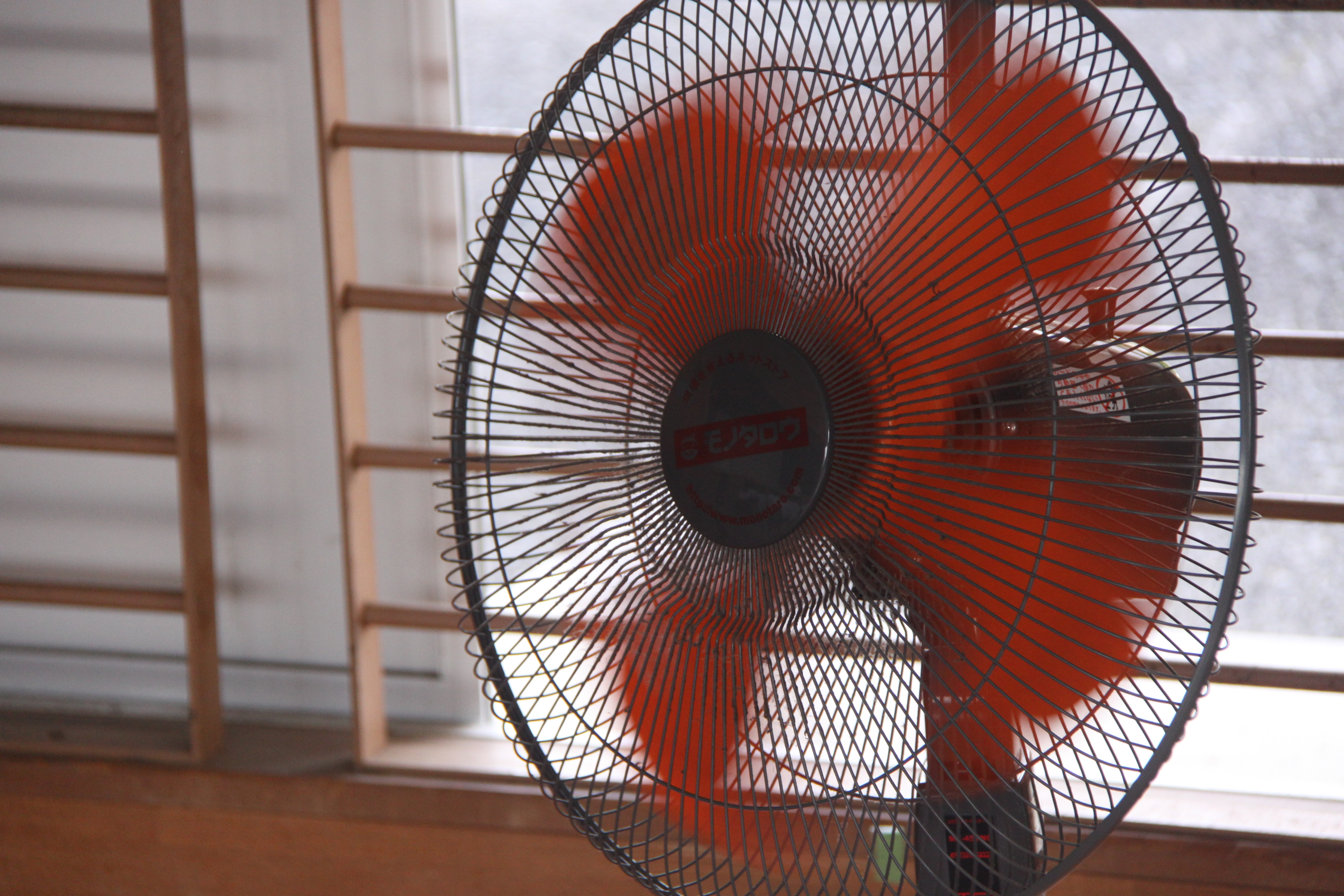


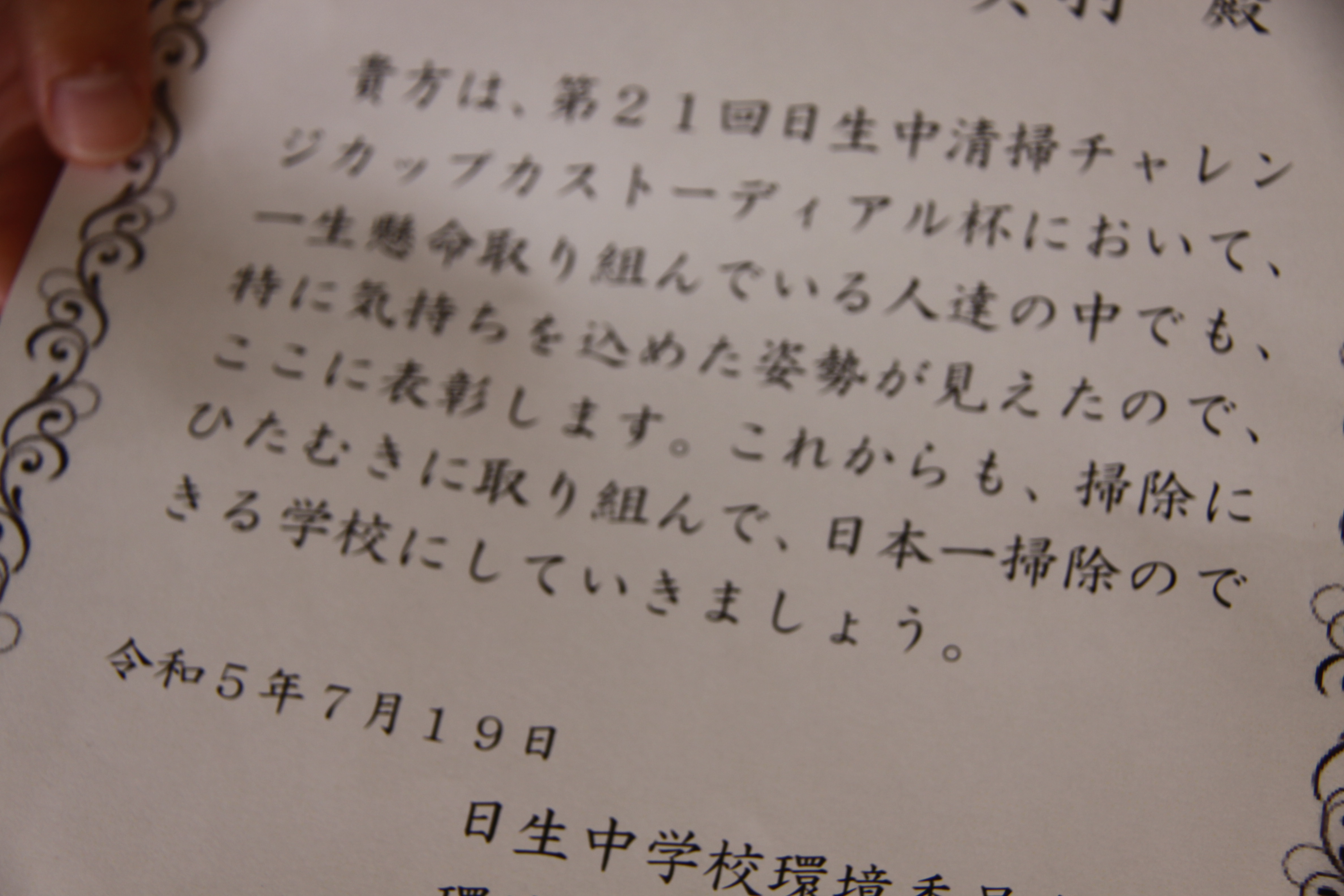



◎正しく知り 正しく行動できる日生中へ。
~生徒会本部役員からからみんなへ(7/19)









◎ありがとう1学期 ありがとう日生中 ありがとう仲間たち
~1学期大掃除(7/18)



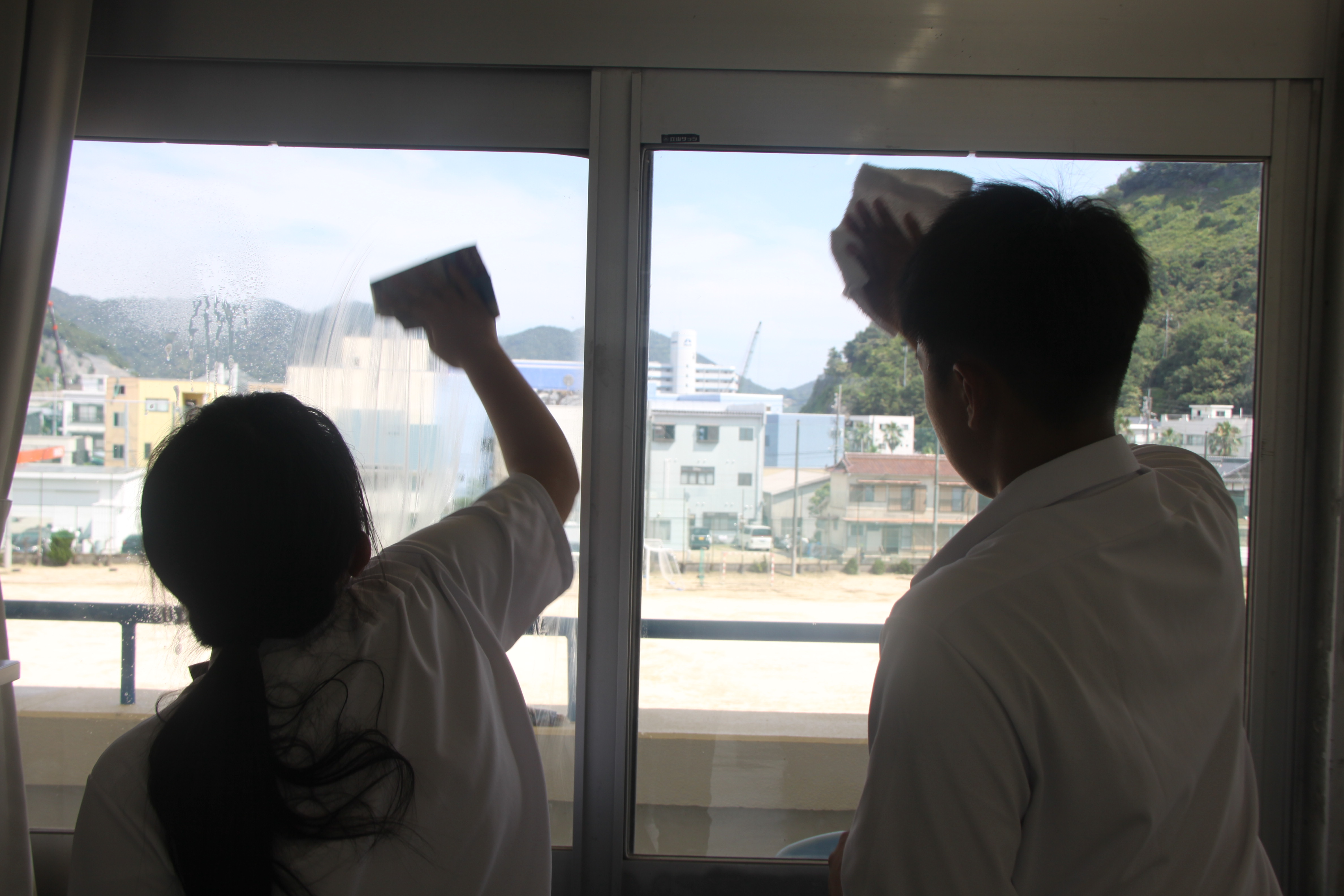

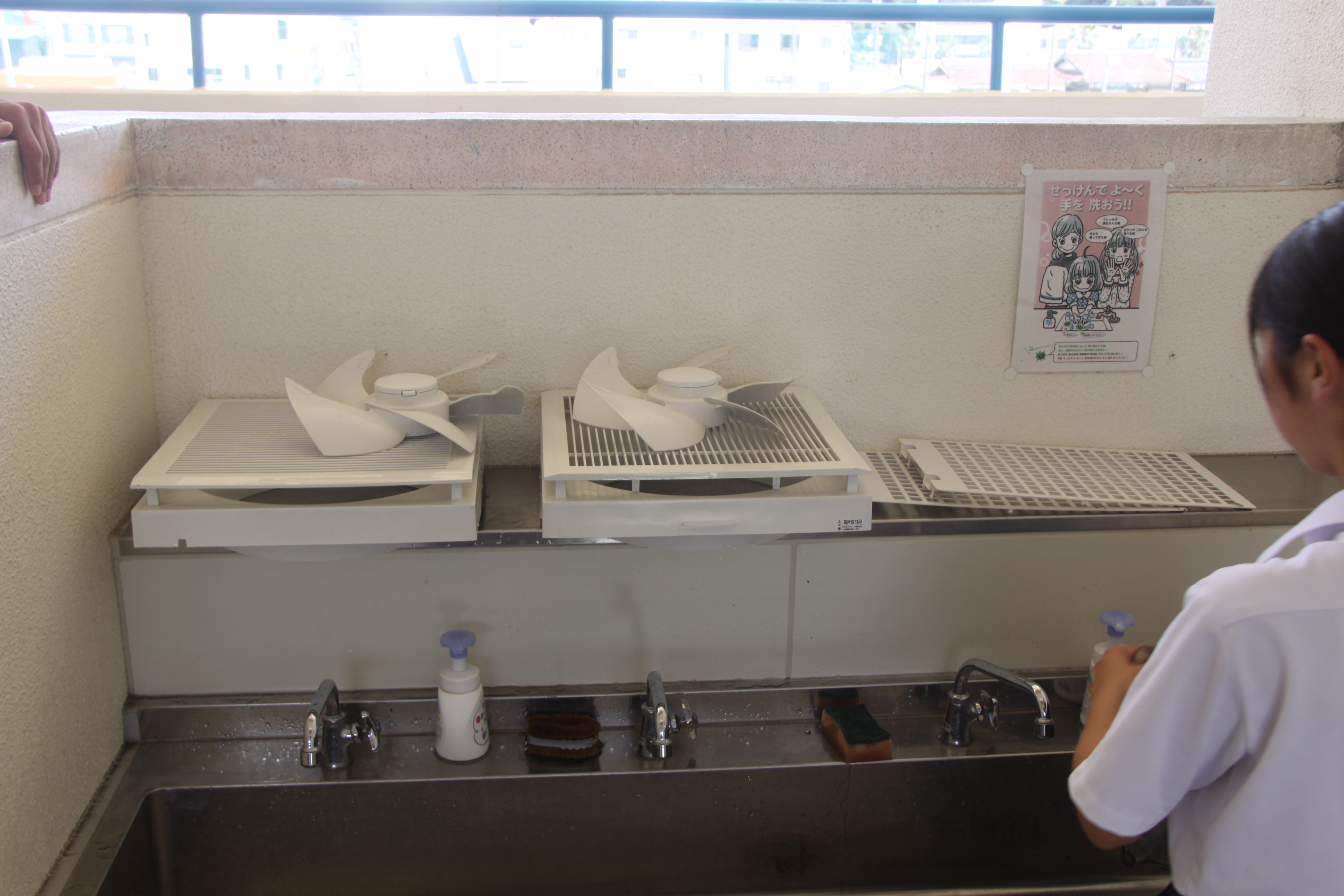
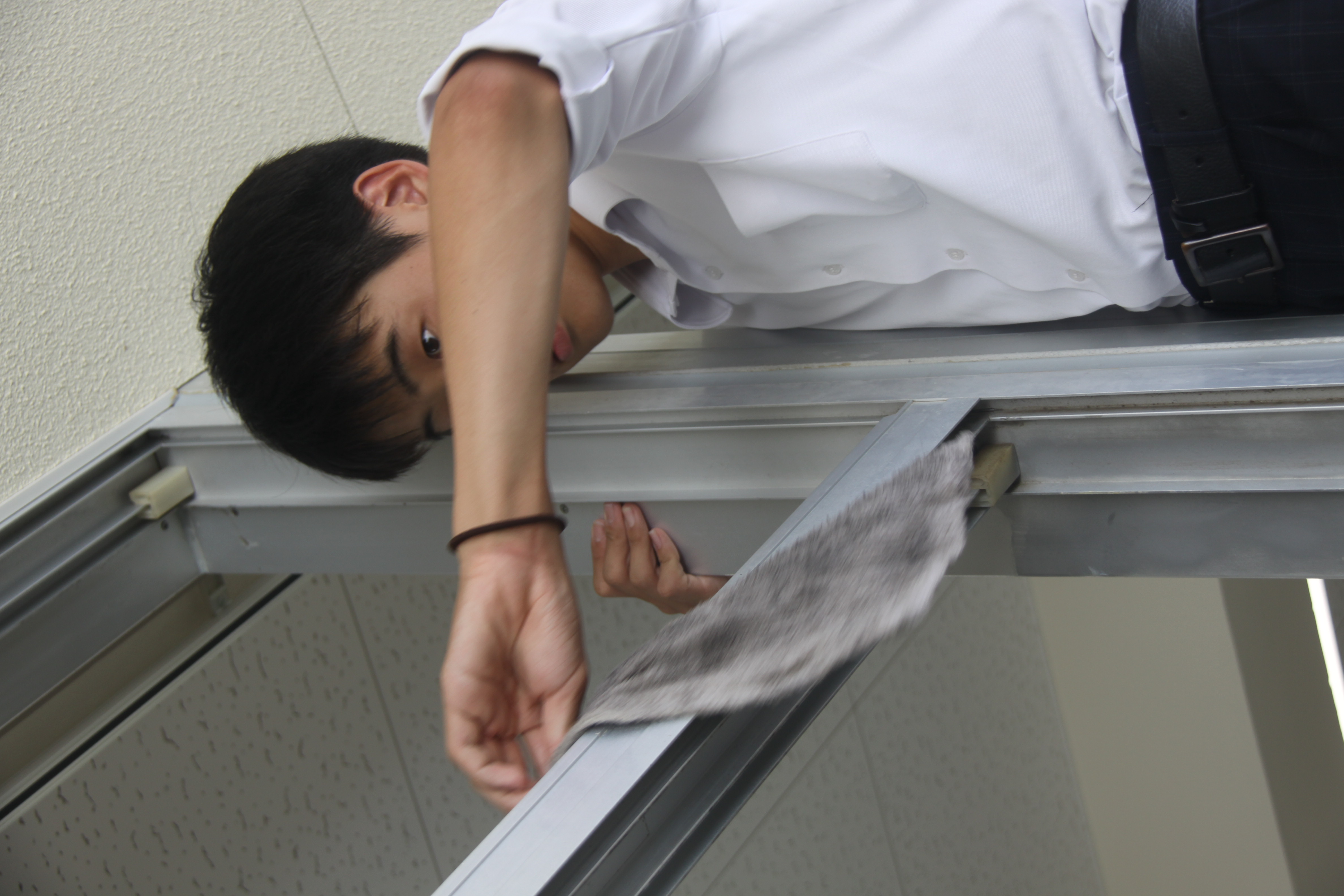
水洗トイレしか知らない人には、汲み取り式便所(落下式便所・ボットン便所)を使ったことがない人は、この詩にリアリティを感じないでしょうか。 しかし、とても考えさせられます。大掃除でがんばった生徒の皆さんに紹介します。
便所掃除 濱口國雄
扉をあけます
頭のしんまでくさくなります
まともに見ることが出来ません
神経までしびれる悲しいよごしかたです
澄んだ夜明けの空気もくさくします
掃除がいっぺんにいやになります
むかつくようなババ糞がかけてあります
どうして落着いてしてくれないのでしょう
けつの穴でも曲がっているのでしょう
それともよっぽどあわてたのでしょう
おこったところで美しくなりません
美しくするのが僕らの務めです
美しい世の中もこんな処から出発するのでしょう
くちびるを噛みしめ戸のさんに足をかけます
静かに水を流します
ババ糞におそるおそる箒をあてます
ポトンポトン便壺に落ちます
ガス弾が鼻の頭で破裂したほど苦しい空気が発散します
落とすたびに糞がはね上がって弱ります
かわいた糞はなかなかとれません
たわしに砂をつけます
手を突き入れて磨きます
汚水が顔にかかります
くちびるにもつきます
そんな事にかまっていられません
ゴリゴリ美しくするのが目的です
その手でエロ文ぬりつけた糞も落とします
大きな性器も落とします
朝風が壺から顔をなぜ上げます
心も糞になれて来ます
水を流します
心にしみた臭みを流すほど流します
雑巾でふきます
キンカクシのうらまで丁寧にふきます
社会悪をふきとる思いで力いっぱいふきます
もう一度水をかけます
雑巾で仕上げをいたします
クレゾール液をまきます
白い乳液から新鮮な一瞬が流れます
静かなうれしい気持ちですわってみます
朝の光が便器に反射します
クレゾール液が糞壺の中から七色の光で照らします
便所を美しくする娘は
美しい子供をうむといった母を思い出します
僕は男です
美しい妻に会えるかも知れません
*ジェンダーに関する記述がありますが、1950年代の時代状況をふまえてそのまま掲載しています。
◎ひな中の風 ~~7月の風景~
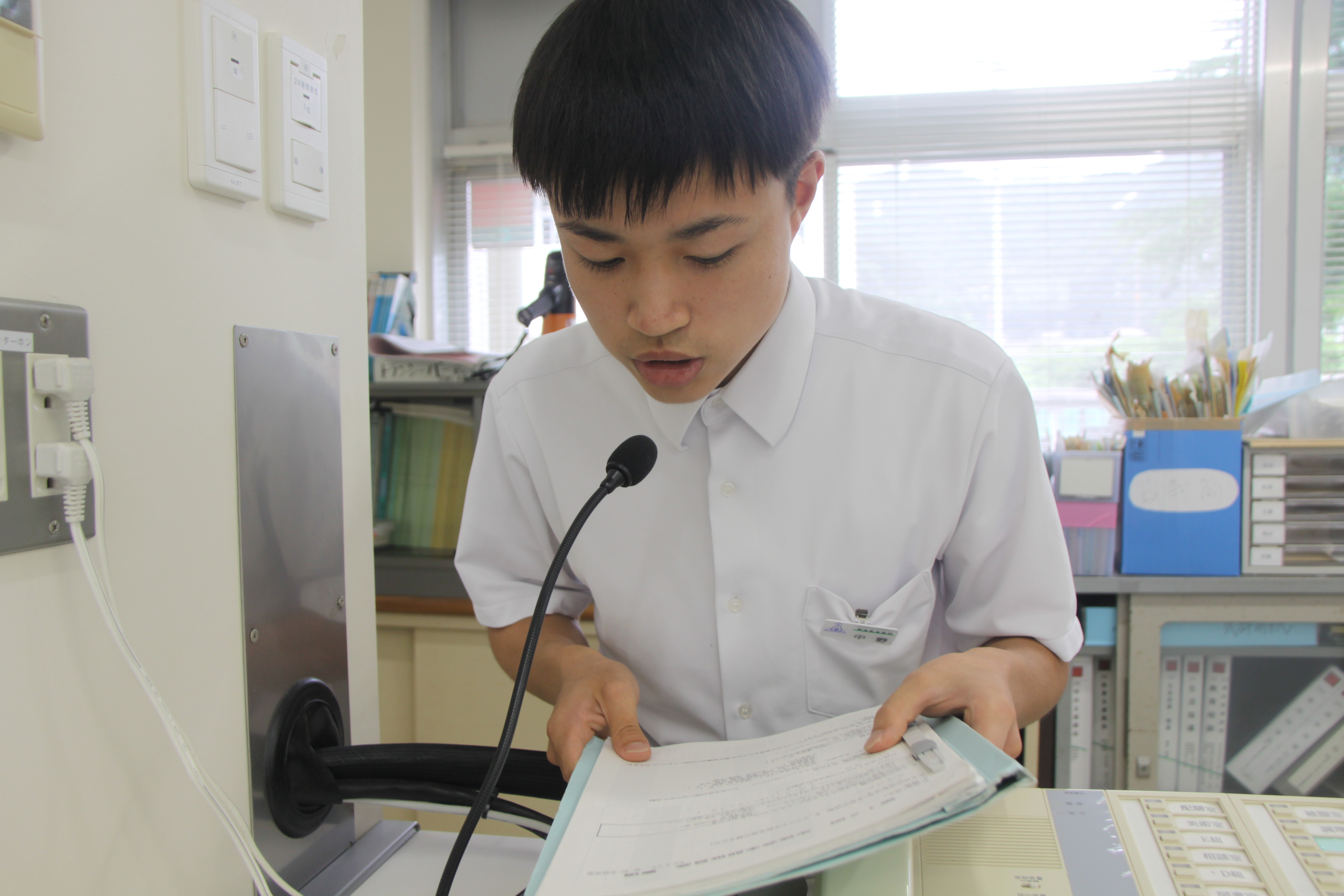









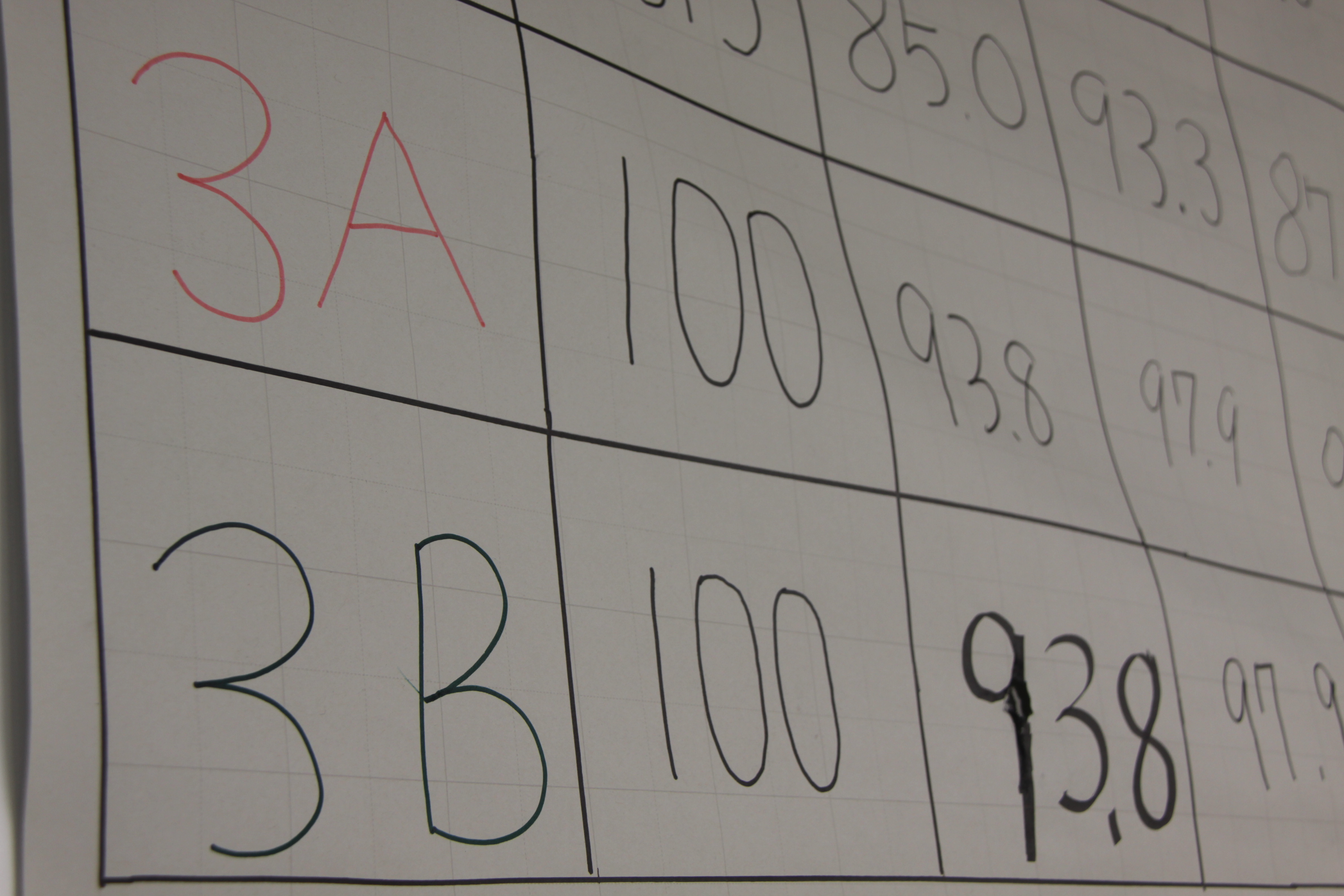

◎ひな中の風 ~授業がたいせつ~(7/14)
英語科では、オリジナルのアイスクリームについてのプレゼンテーションに取り組みました。「学び」は楽しく、深く、仲間と共に。

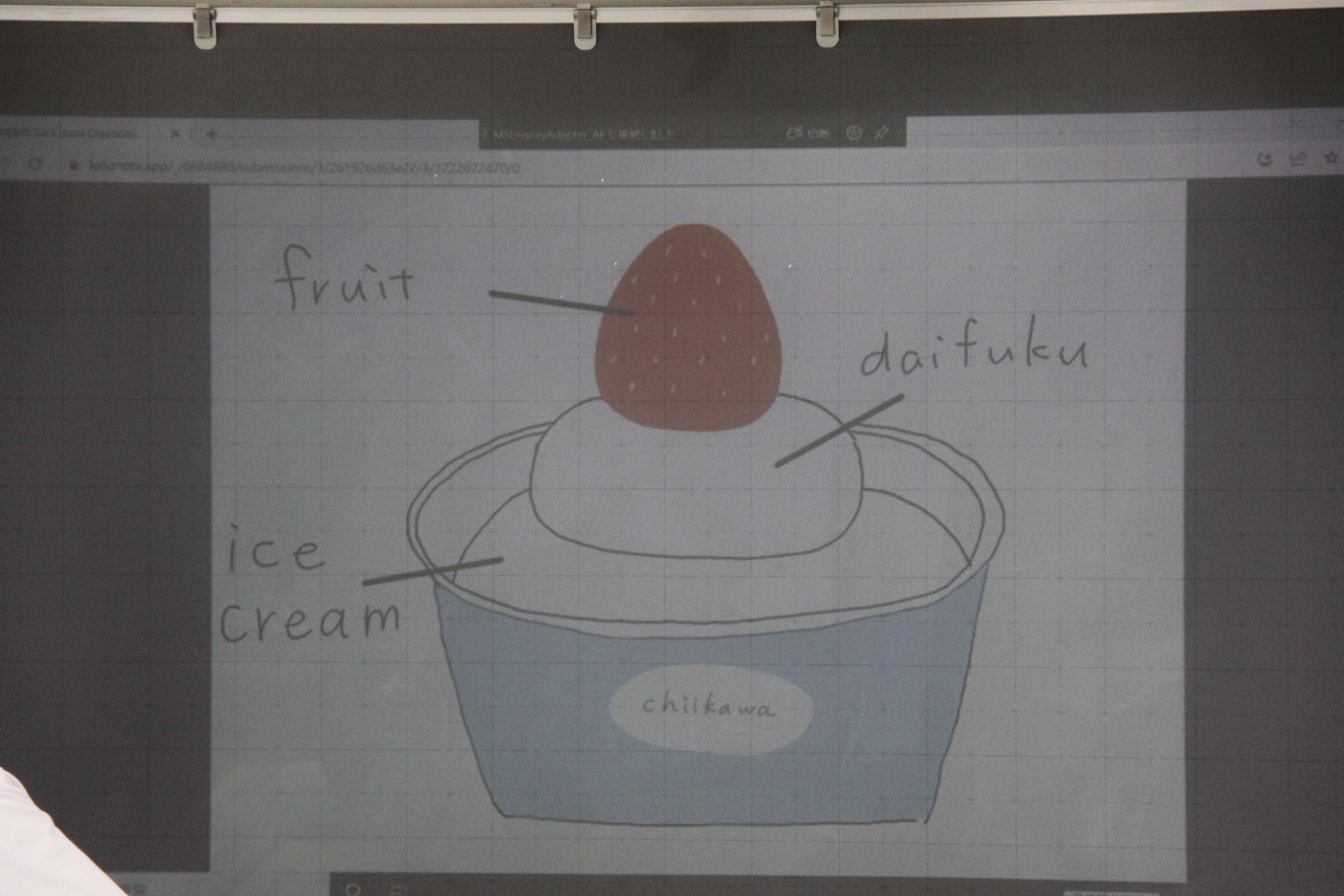

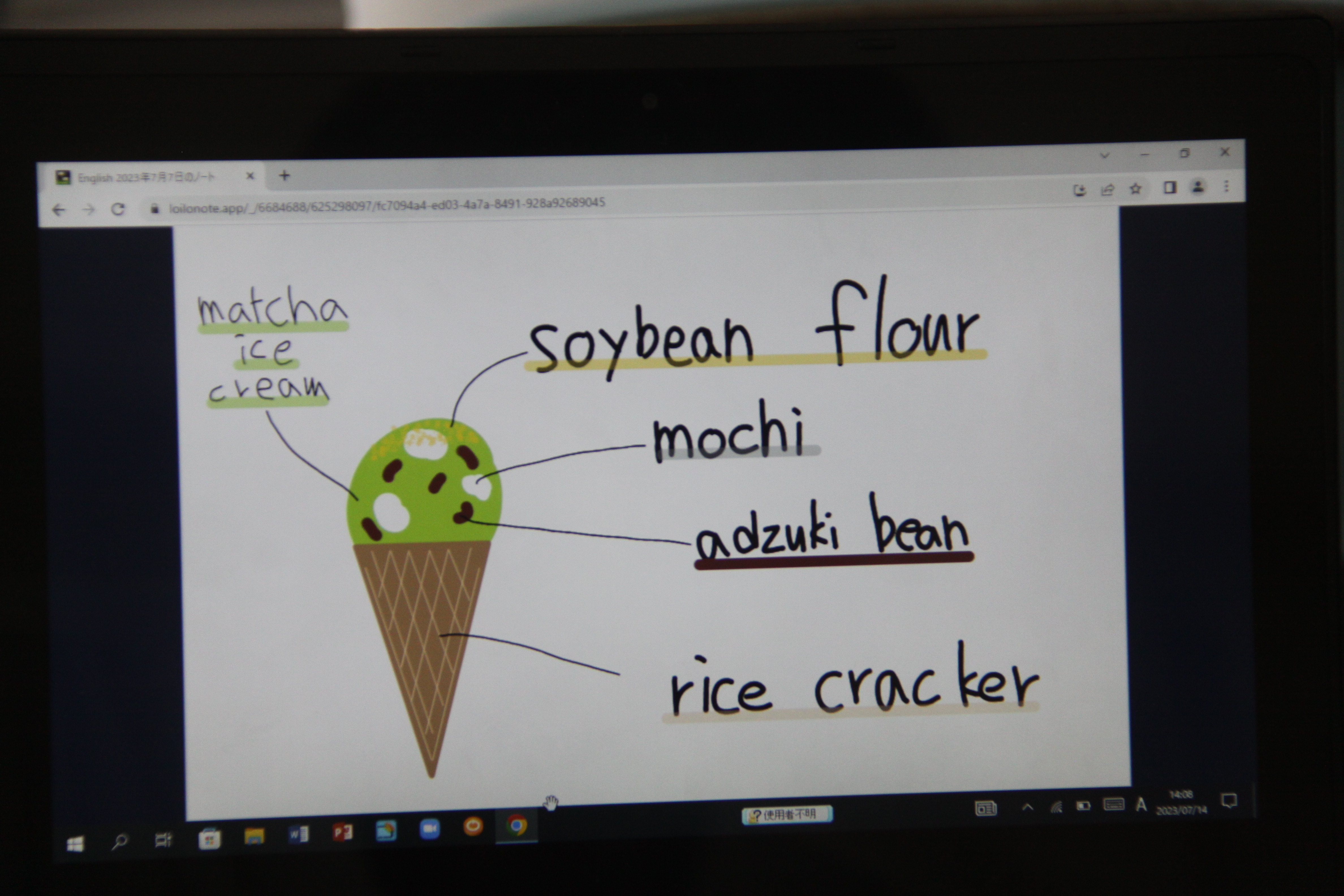
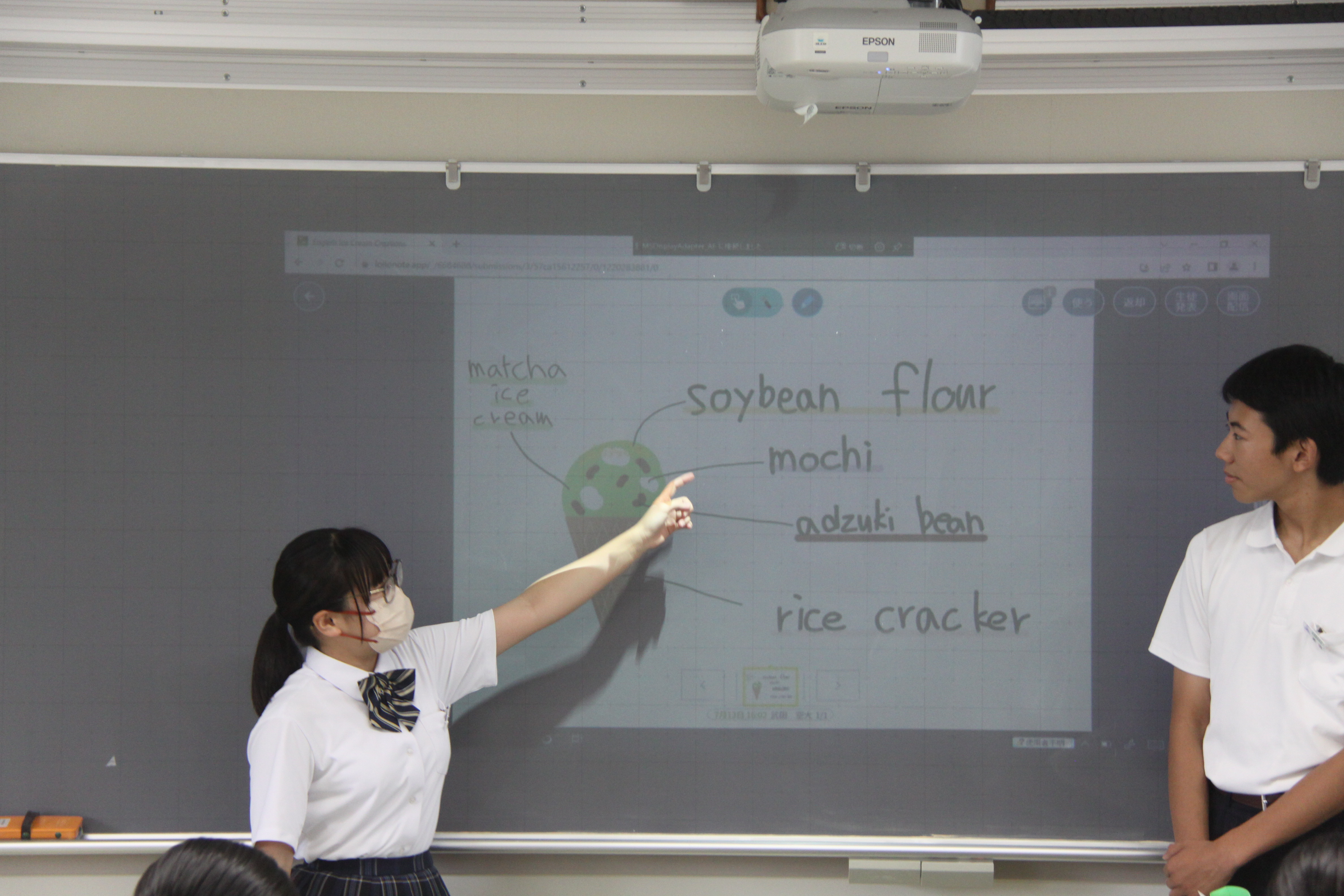

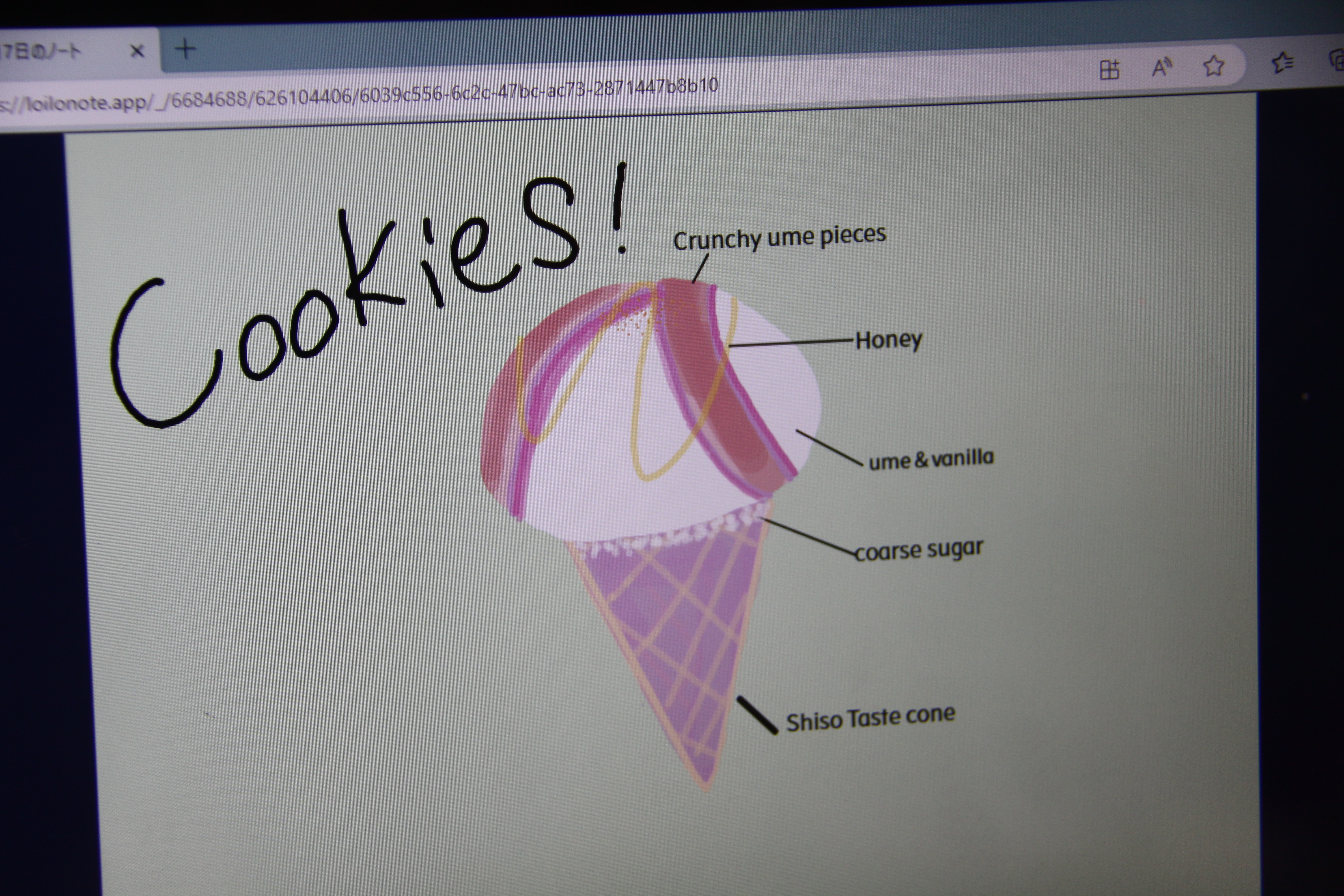

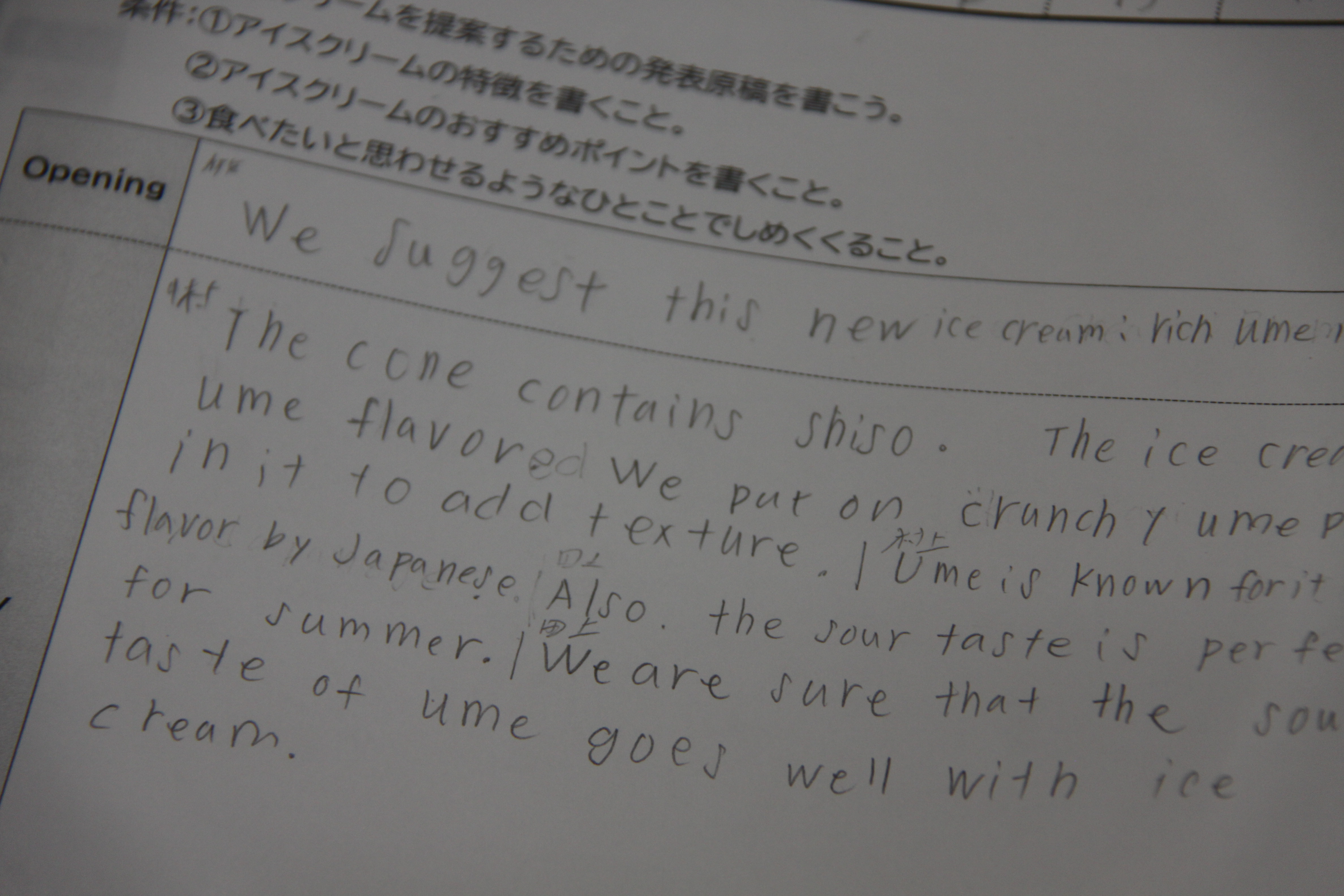
◎日生で輝く 日生が輝く。 地域と共にある学校
地域行事に参加したり、地域施設を利用することで、世代間の交流や地域とのつながりを作ることができます。夏休みには、お祭りや、集会など地域には季節ごとに楽しめる行事が多く開催されています。地域行事に参加することは、地域の人々とコミュニケーションをとる貴重な機会になります。また地域の大人の方を知っておくことは、万一の災害などの際に助け合いや、進路実現へのサポートなど社会で生きていくための大きなメリットがあります。「こんにちは」「お世話になります」「ありがとうございます」「手伝います」の気持ちを持って、地域のネットワークを築いてほしいと思います。
公民館では2年生が制作したハザードマップが展示されています。
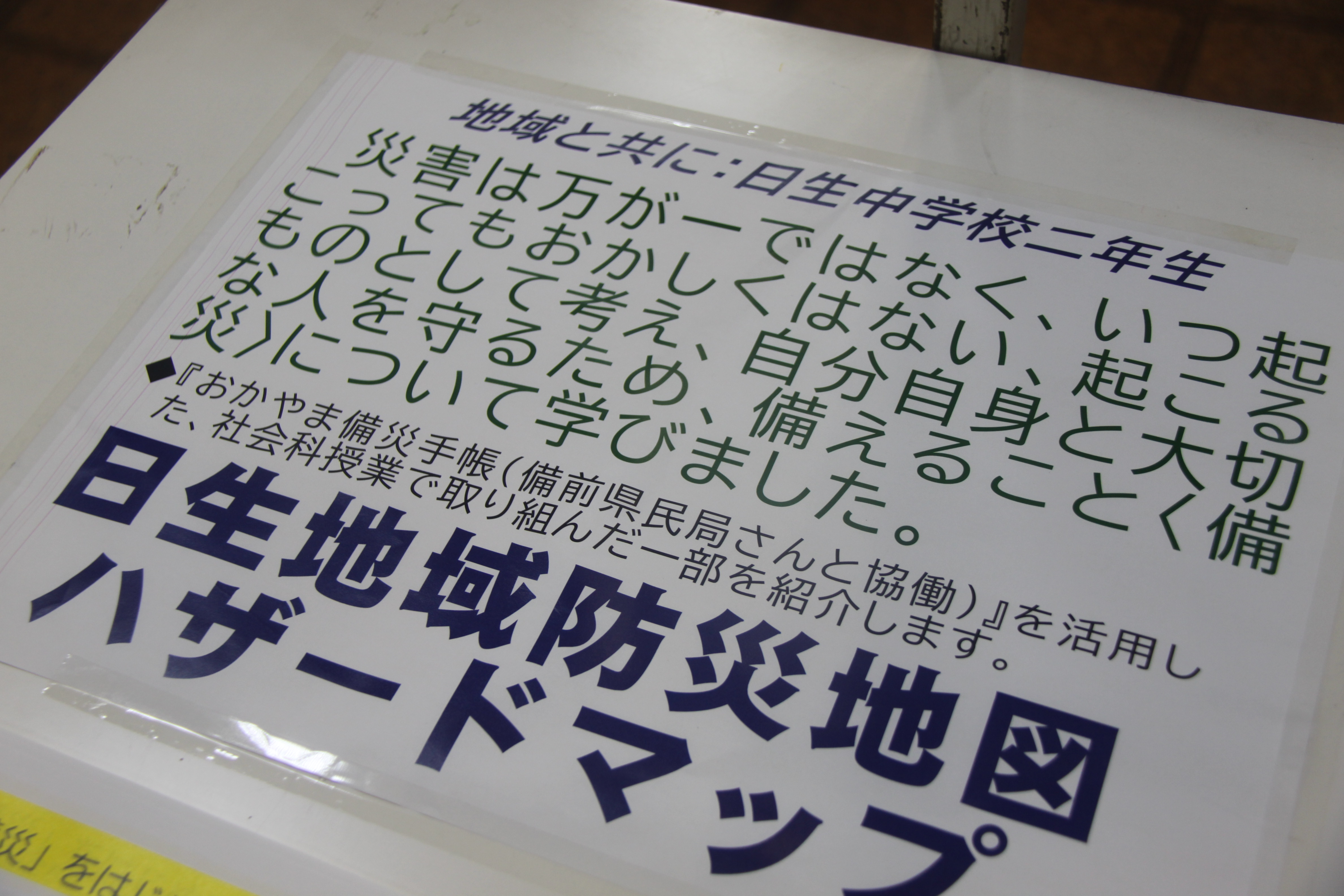

◎ 多くの人に支えられて 避難訓練開催(7/13)
スクールサポーターの根木さん、備前警察署と連携して、不審者が校地内に侵入した場合,生徒が安全に避難できるように教職員が組織的に適切かつ迅速 な対応できるように訓練を行いました。


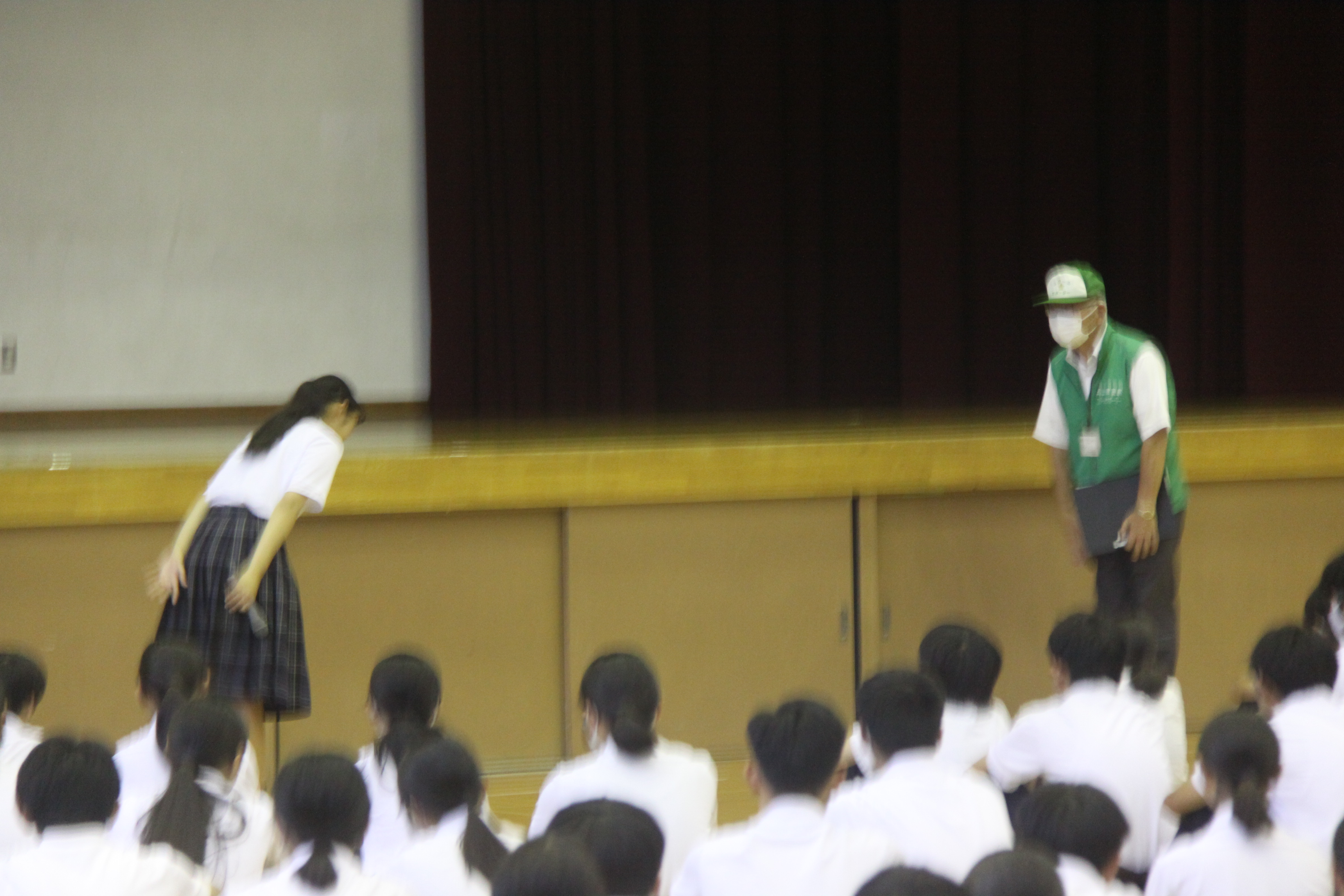
追記:
~子供を守るには、地域による見守りだけではなく、家庭での防犯教育を合わせて~
1 危険に遭わないように日頃から、親子で防犯について話し合いましょう。
例えば
〇外で一人にならない
〇110番の家のチェック、利用方法
〇 通学路を一緒に歩く、また、通学路だけではなく仲の良いお友達の家や習い事の所までなど、子供の行動範 囲も確認しましょう。
〇よく遊んでいる公園をチェックしましょう。
・草木が生い茂り、死角になっているところはないか?
・トイレは一人では入らない
〇防犯ブザーは大人になっても有効です。
※子供を狙っている大人もいるが、ほとんどの大人がみんなを見守っていることも最後に伝えてください。
女の子だけが狙われると思うのは間違いです。男の子も注意しましょう。
特に、商業施設のトイレ内における犯罪が発生しています。
2 もしもの時は・・・
〇あぶないと思ったらすぐ逃げること。
子供だけではありません。「あれ?この人不審者?違うかな?」何て悩んでいる間に連れさられてしまうかもしれません。
声を掛けられた時にしっかり断ることが大切です。
〇大きな声を出しましょう。
「キャー」とか「ワー」ではなく、「助けて-」と大きな声で叫びましょう。
3 被害に遭ってしまった時は・・・
〇あきらめずに逃げること。もうダメかも、と思わないことです。
〇被害に遭ったことをしっかり大人の人に知らせます。
出来るだけ早く110番通報しましょう。
学校に話してからとか、子供から話を 聞いたお母さんが「夫が帰宅してから」ではなくすぐにその場で110番通報です。
◎多くの人に支えられて
備前市青少年健全育成センターさん来校(7/12)
この日は、育成センターから、末廣さん、今吉さんが来校され学校と懇談・情報交換を行いました。センターは、青少年の非行防止と健全育成を図るために、街頭指導、青少年相談、連絡調整(地区指導員、学校)「育成のあゆみ」発行、青少年健全育成大会、研修会などを行っています。
電話相談(青少年問題):月曜から金曜 8時30分から17時(祝祭日、年末年始を除く) 電話:0869-64-4158 メール相談:bzikusei@city.bizen.lg.jp(市HPより)
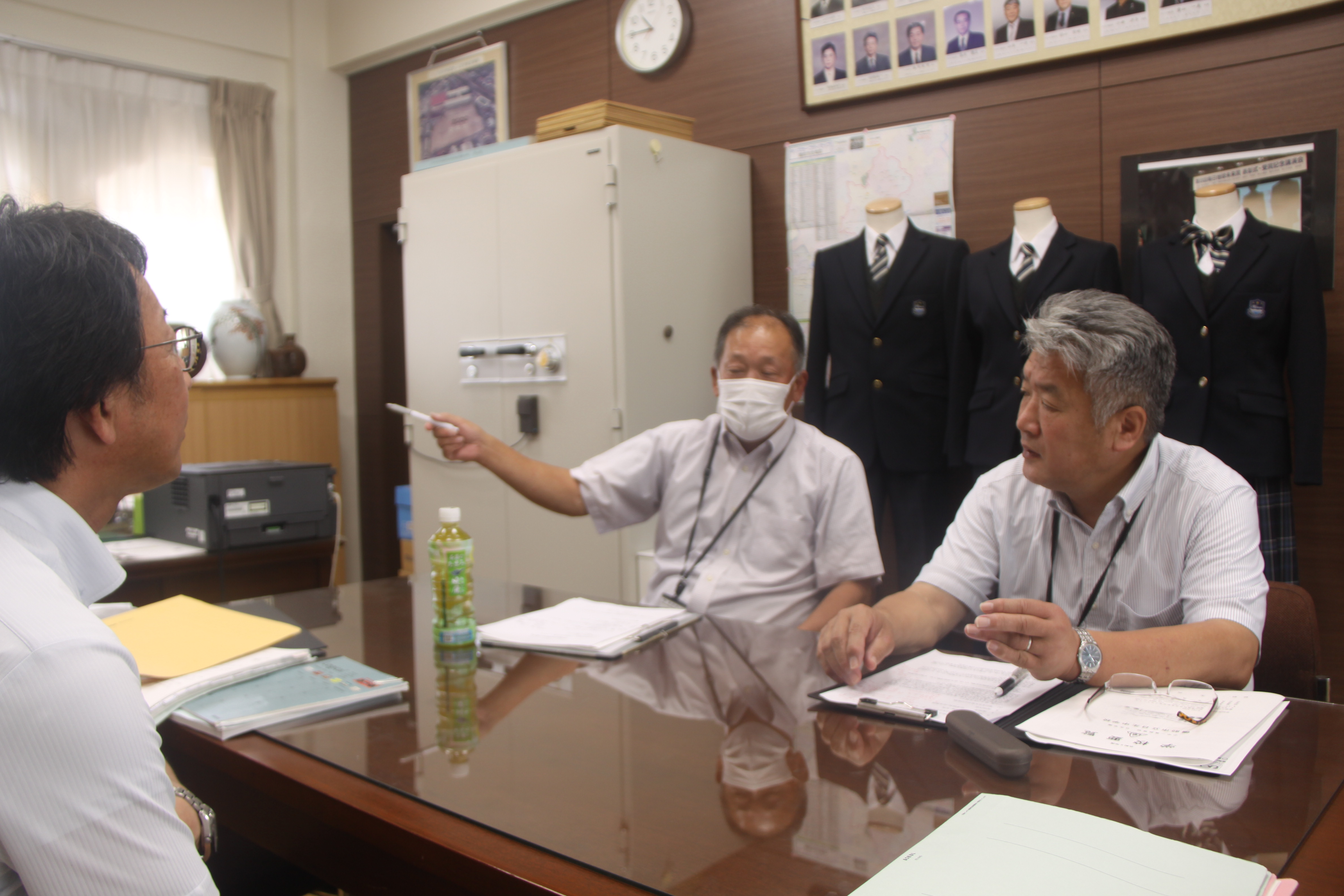
◎地域と共にある学校
日生地域 防災地図(ハザードマップ)
日生地域公民館で展示をします
災害は万が一ではなく、いつ起こってもおかしくはない、起こるものとして考え、自分自身と大切な人を守るため、備えること〈備災〉について学びました。『おかやま備災手帳(備前県民局さんと協働)』を活用した、社会科授業で取り組んだ一部を展示します。


◎正しく知り 正しく行動しよう
~ケータイ・スマホと上手につきあおう(7/11)
子どもたちが、安心・安全に携帯電話やスマートフォンを利用し、また、利用する際に守ってほしいルールやマナー、覚えておいてほしいトラブル事例から深く学び、生徒たちが自らの判断で、リスクを回避する能力を身に付けていくためのKDDIの出前講座を開設しました。本講座は、社会的責務と捉え、「スマホ・ケータイ安全教室」を全国で開催しているKDDIさんに依頼し、今年度も日生中学校区の全学校が連携して実施しました。
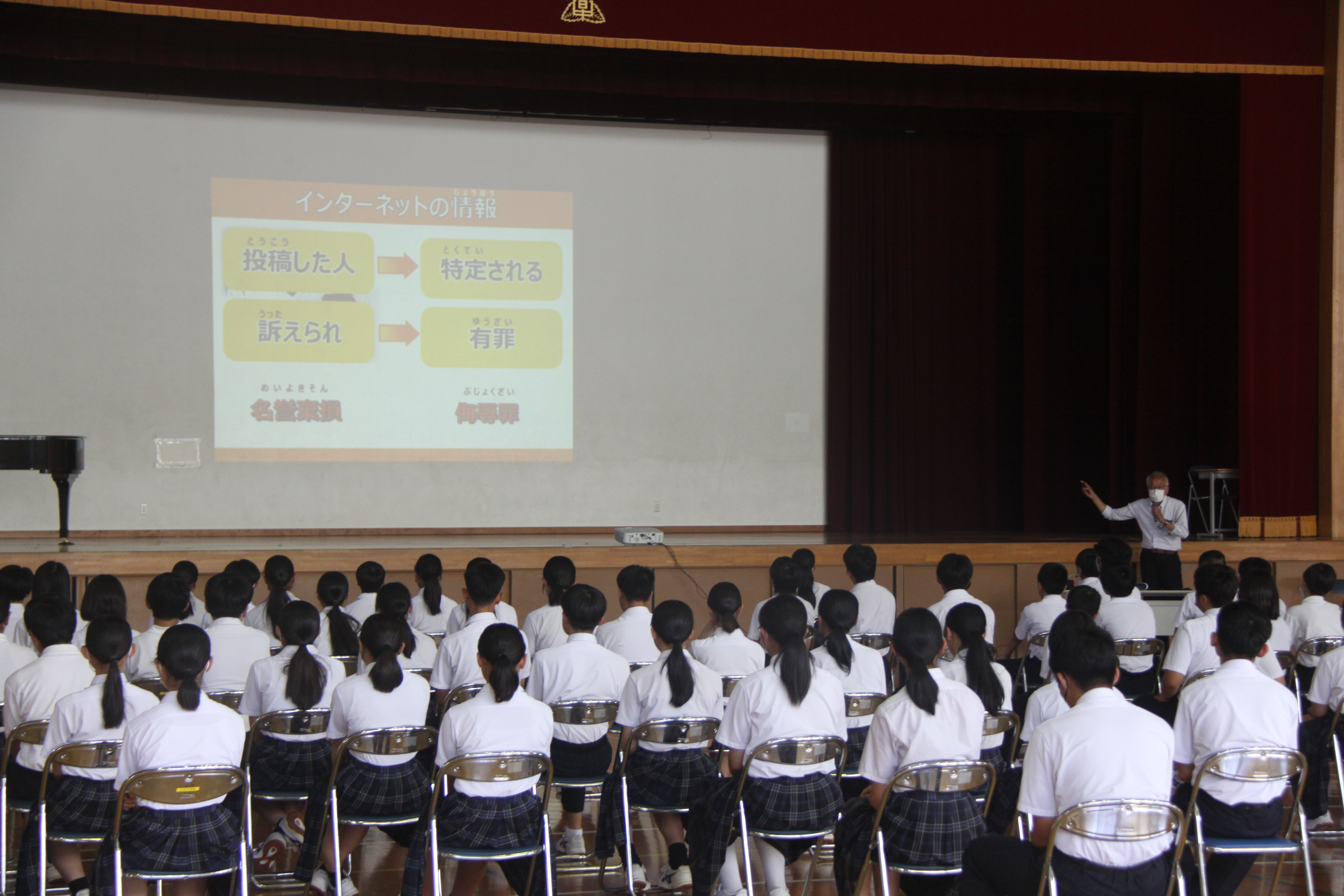
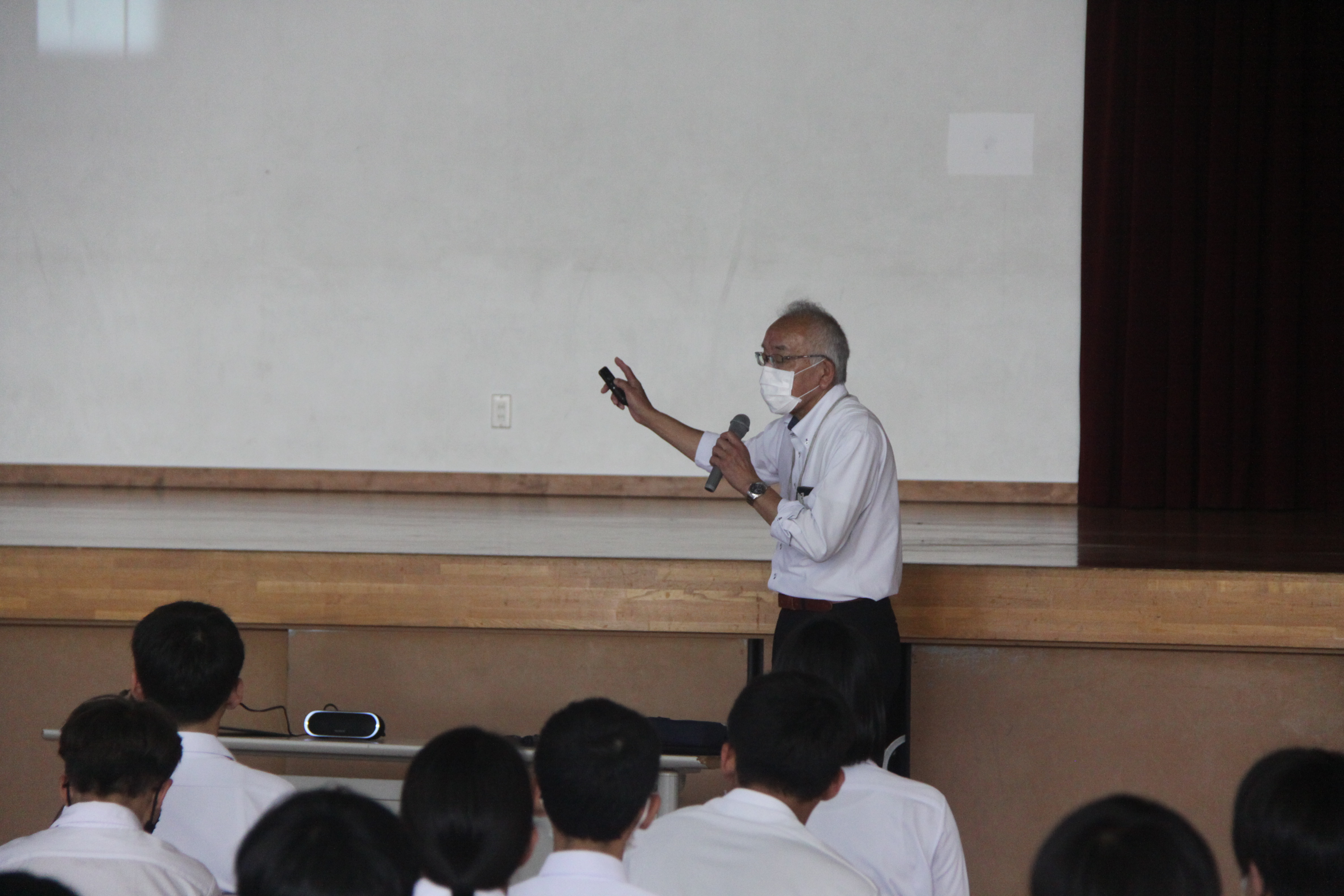
◎正しく知り 正しく行動しよう ~1年生「タバコの真実」授業(7/11)
夏休みを前に、本校教頭が、毎年取り組んでいる「薬物乱用防止教室」の一環としてタバコの授業を行いました。教頭先生は、友人が喫煙によるがんで亡くなったのを機にタバコについて調べはじめ、その内容を、これまでたくさんの小・中学校で話してこられたそうです。

◎夏へ みんなが 元気に。
茅の輪(ちのわ)の由来は、様々です。備後国(広島県東部)を旅していたスサノオノミコトは宿を探していました。そのとき、蘇民将来(そみんしょうらい)という人物は貧しい暮らしをしながらもスサノオを手厚くもてなしました。数年後、スサノオは再び蘇民将来のもとを訪れ、「病が流行ったら茅で輪を作り、腰につけて難を逃れなさい」と教えました。その後、教えを守った蘇民将来は難を逃れることができたそうです。それが茅の輪くぐりの由来とされています。昔は茅の輪を腰につけて無病息災を願いましたが、江戸時代初期ごろに、現在のように大きな輪をくぐるようになったとか。輪に茅が使われる理由には、茅に利尿作用があり、生薬として用いられ、夏の体調回復に使われていたから、あるいは茅は魔除けの力を持つと考えられていたから、などの説があります。校務員の立川先生が住んでおられる上郡の高嶺神社で祭事があり、つくられたものをひとつ飾っています。1学期もあとわずか。もうひとふんばり。みんな元気に夏を迎えましょう。

◎出会いに心をこめて ~どう生きていくか 一生懸命なひとに 一生懸命に聴く~(7/11)
2年生が、海洋学習の一環として、「海」にかかわる仕事に従事されている方々の思いや生き方について「聞き取り」をおこないました。




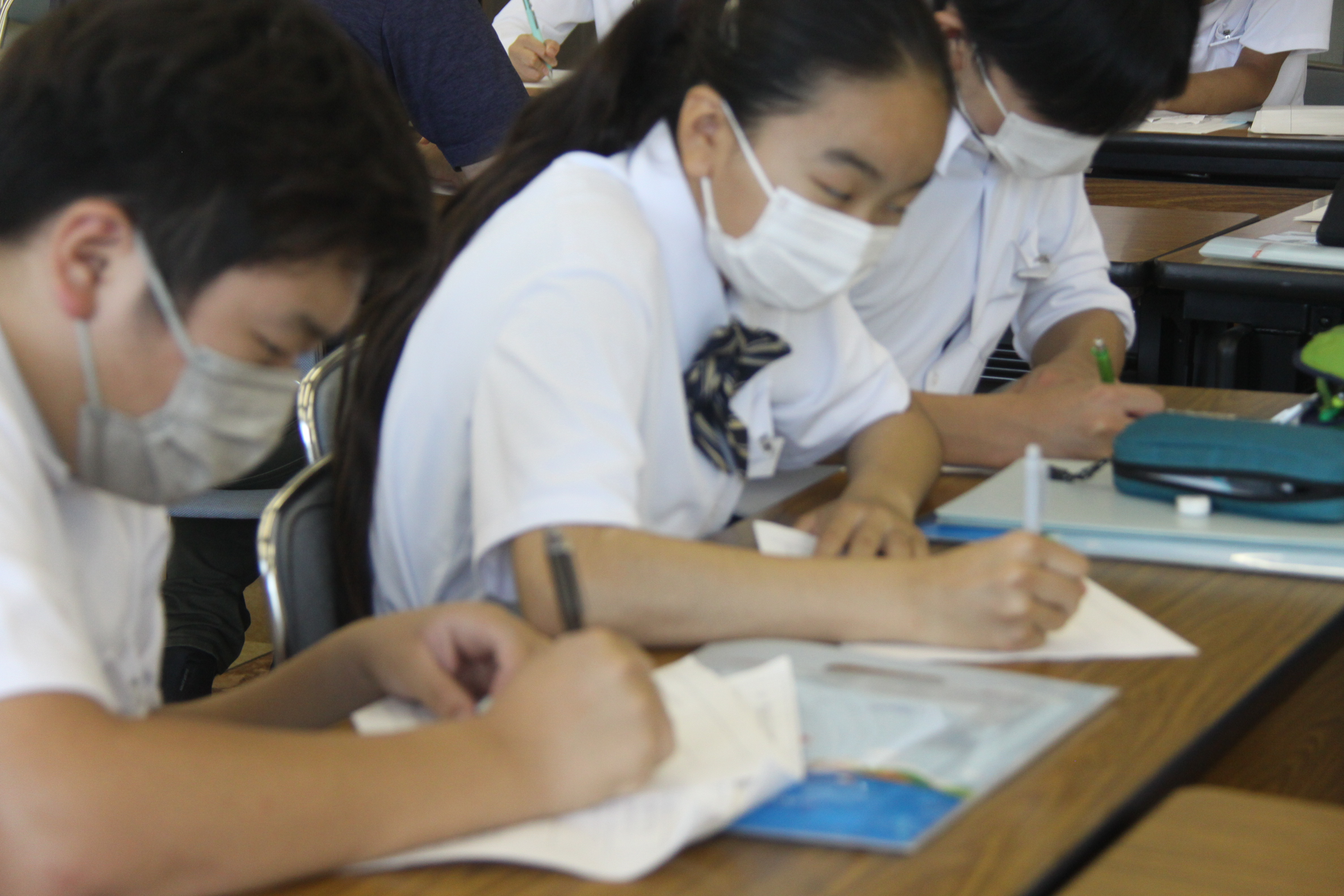

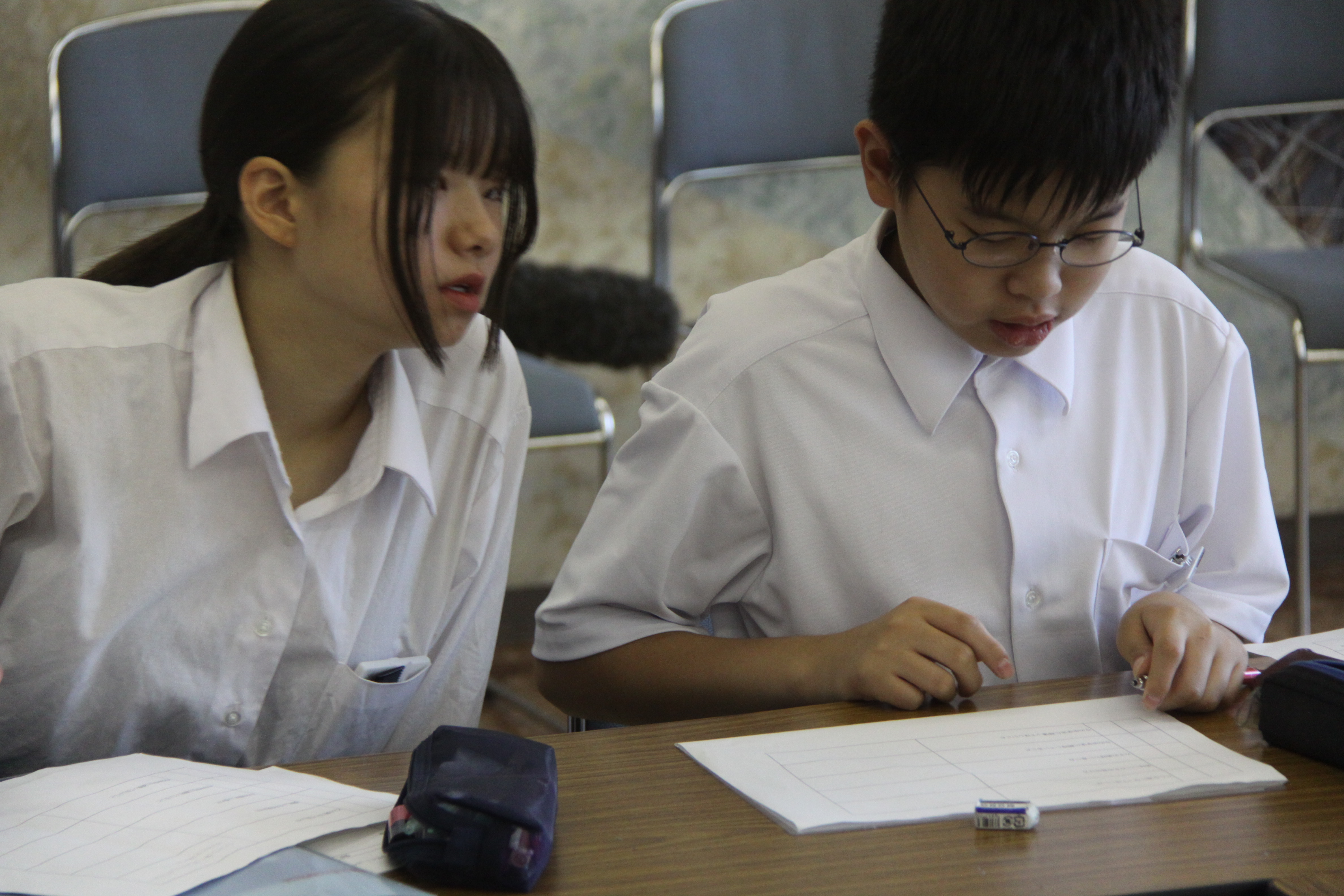





~地域と共にある学校~
生徒会が呼びかけている地域清掃ボランティア(7/19)には、日生地区川東地区福祉協議会の方々が参加してくださいます。ありがとうございます。
◎わたしたちのたいせつな夏・なかま・生活(1年生非行防止教室 7/7)
「中学生の最初の夏・これからの生活、仲間と一緒にがんばるために」をテーマに、備前警察署生活安全課から安藤さんをお招きして学習に取り組みました。
「振り返り」より一部を紹介します。
〇友達は大切。友達関係や、いい環境をつくっていくことで犯罪は防げることがわかりました。
〇クラスで問題がおこったら、みんなと話し合いたい。しっかり話して、友達が犯罪に巻き込まれないようにしたい。
〇自分の行動に責任をもって生きていきたいと思いました。
〇警察の方は怖いという印象だったんですが、安藤さんのお話を聴いて、悪いことをしてしまった人に、一生懸命に向き合っていてすごく優しくてすてきな方なんだと思いました。
〇この勉強を通して、今までの気持ちと変わったことがあります。それは、どんな小さい事件でも、将来が変わってしまうということです。なぜなら万引きなどの犯罪もだんだんエスカレートしていくからです。少しの「まあいいか」で自分の人生が変わっていくのは怖いことです。
〇僕が印象に残った話は、犯罪にかかわりかけた女の子は、家出やお母さんとの関係がうまくいってなかったけど、どんどん応援してくれるひとの話に耳を傾けていって、(お母さんと)どんどん仲良くなっていったことです。
〇…私もドラマやテレビにあこがれていました。(笑)。やっぱり警察官はかっこいいなと思いました。大変なこともあると思いますが、私たちは警察官に頼っています!これからもがんばってください。




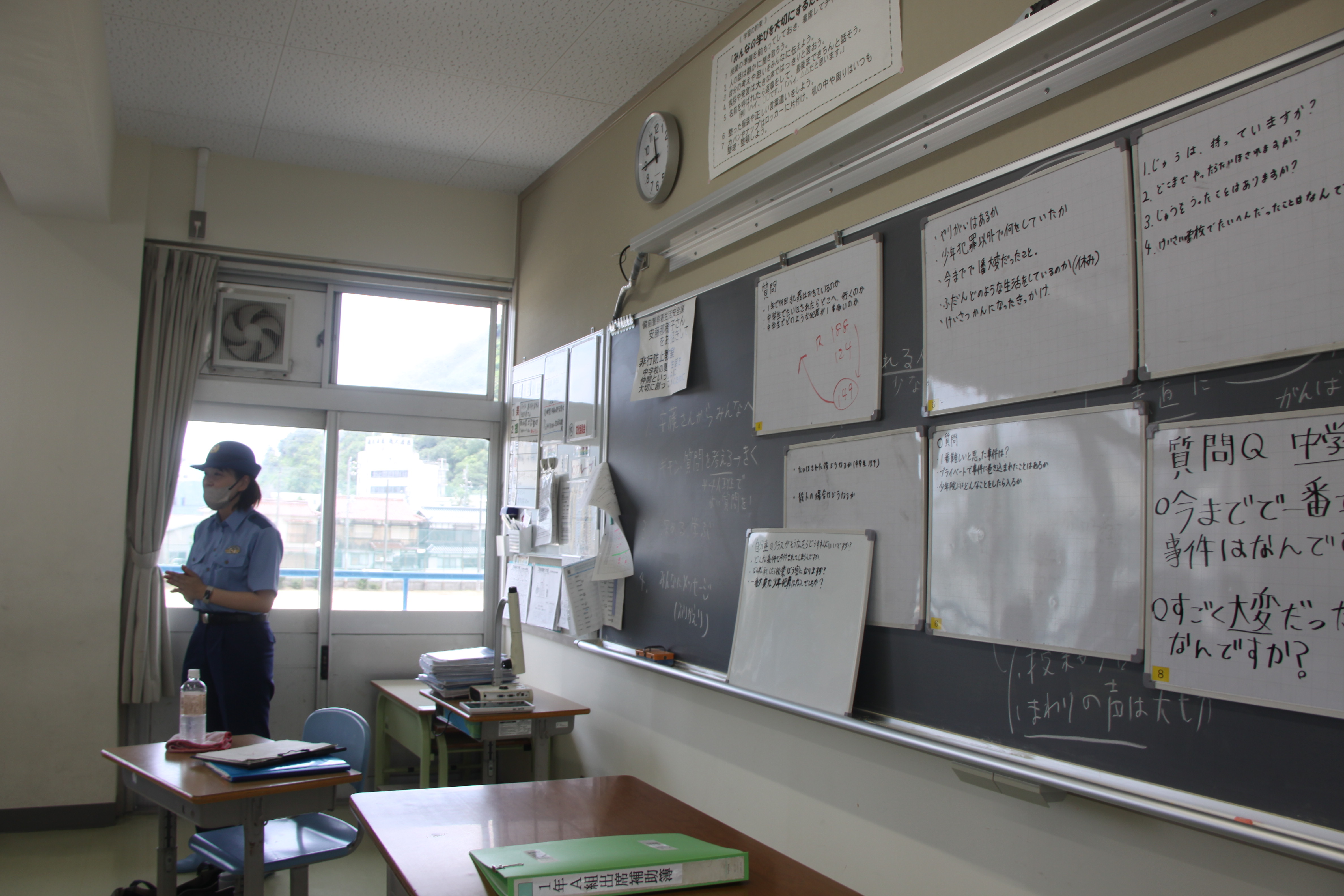

◎七夕のころ
風が吹ふき吹き笹藪ささやぶの
笹のささやきききました。
伸のびても、伸びても、まだ遠い、
夜の星ぞら、天の川、
いつになったら、届とどこうか。
風が吹き吹き外海の、
波のなげきをききました。
もう七夕もすんだのか、
天の川ともおわかれか。
さっき通って行ったのは、
五色きれいなたんざくの、
さめてさみしい、笹の枝えだ。 金子みすゞ

◎〈空を買う ついでに海も 買いました 水平線は 手に入らない 木下龍也〉(7/6ひな中の風景)









◎百花繚乱 ゆかた着付け体験学習(7/6)
2008年3月の学習指導要領では、国際社会で活躍する日本人の育成のため、我が国の郷土の伝統や文化を受け止め、それを継承、発展させるための伝統や文化に関する教育の充実を図ることが求められています。そして、中学校の技術・家庭科の衣生活分野では「和服の基本的な着装を扱うこともできること」が盛り込まれています。すなわち、日本の伝統文化である和服について着装も含めて理解するための教育、すなわち「きもの」 文化をどのように教育していくかについての検討、新しい教育デザインが必要となってきています。現代、情報のみならず、人やモノの移動を含むグローバル化が進み、外国人の日本文化への関心は高く、日本の文化を世界に発信する機会が増え、文化の相互交流はさらに大切だと考えられます。この日、NPO法人 和装教育国民推進会議岡山県支部の近藤さんらと、日生地域の森本さん、深谷さん、的野さんにサポートしていただき学習に取り組みました。貴重な体験学習をありがとうございました。

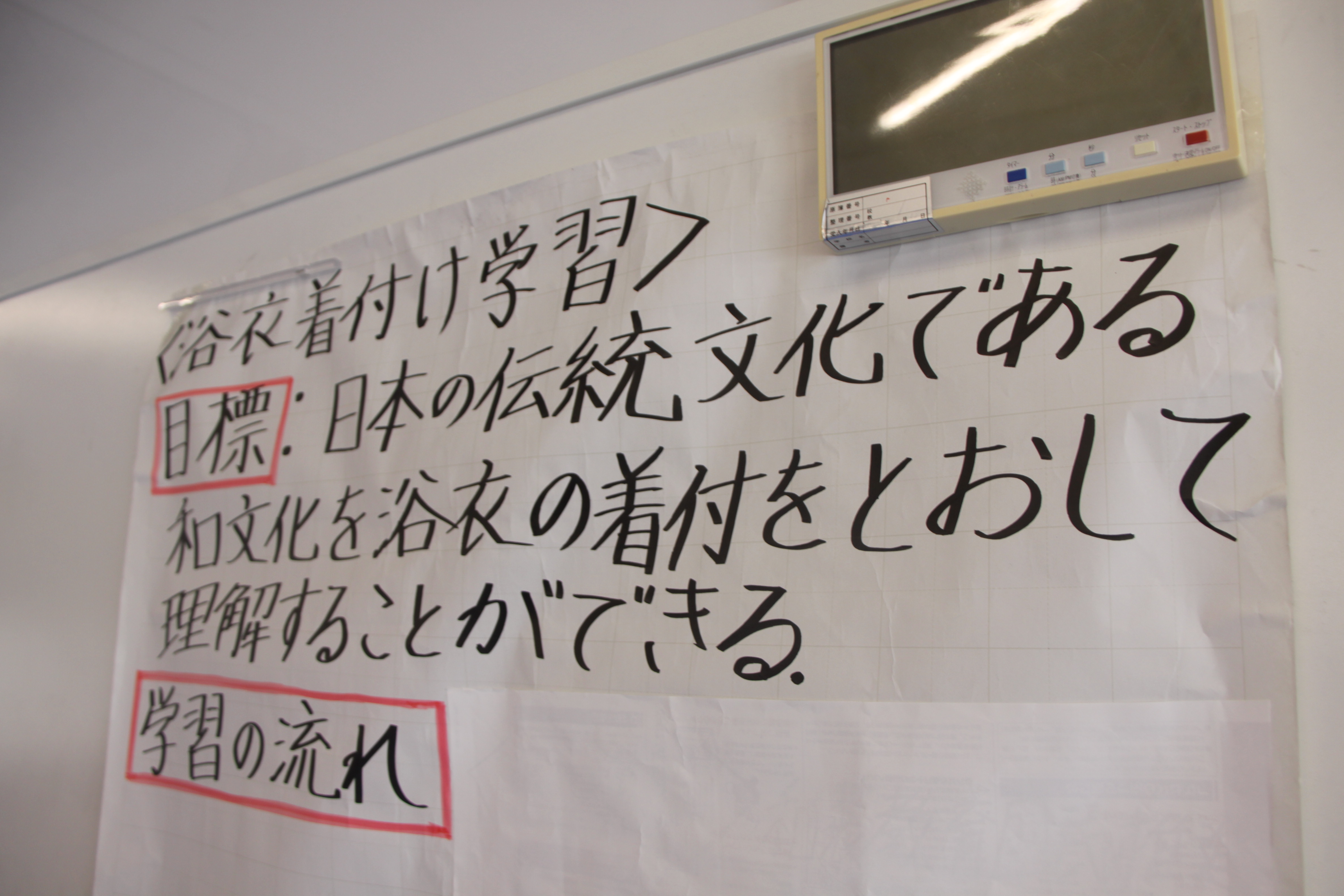







◎学び続ける者だけが教壇に立つことが出来る(7/5)
~OJT研修がんばっています。
学校が抱える教育課題が複雑化・多様化する中、教育課題に的確に対応し、活力ある学校づくりを進めるためには、教員一人ひとりの資質能力を一層高めるとともに、それらを最大限に発揮できる学校づくりが求められています。このため、日生中学校では、「組織的な学校運営による学校の総合力の向上」に向けた取組を推進しており、この取組の中で、日常の業務を通して相互の資質能力を高めていくOJT(On-the-Job-Training)に継続的に取り組んでいます。教員は、児童生徒とのふれあいや教員同士の協働した取組など、学校で行われる様々な教育活動を通して成長してきます。これからも、平素の教育活動を通じて教員相互が啓発しあう様々な取組を日常的に行っていきます。この日は数学の授業参観をもとにOJTをおこないました。

◎多くのひとに支えられて(7/5)~第1回学校保健委員会
子どもたちが、様々な健康問題に適切に対処したり、自分の生活行動をよりよく改善していく力を身につけたりするためには、家庭、地域社会の教育力を充実させる観点から、関係諸機関の協力の下に、日生中学校でも学校保健委員会を開催しています。
子どもの健康課題が複雑多様化、深刻化してきている状況にある中、これらの問題を解決するため、子どもたちが自分の生活行動をよりよく改善し、明るく健康で活力ある生活を送るための資質や能力を高める取組が求められています。このため、家庭や地域社会と連携を図る中核的な組織である学校保健委員会では、学校における健康の問題を研究協議し、家庭や地域社会等と連携して健康つくりを推進していきます。この日、山﨑スクールカウンセラー、日生東小前池養護教諭、北川栄養教諭、備前市福祉課綱島さんをお招きして、思春期の子どもをより深く理解するための研修を行いました。

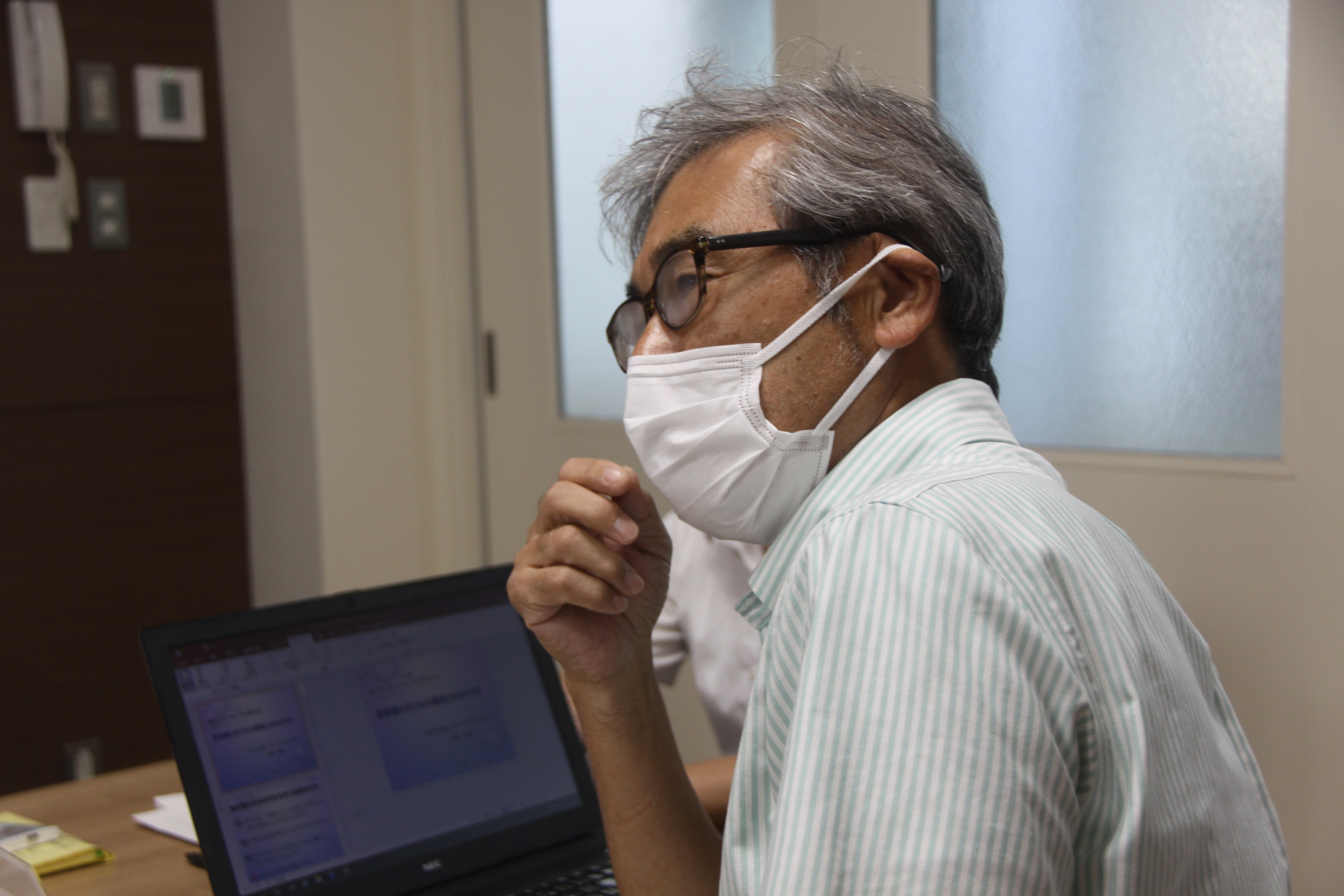
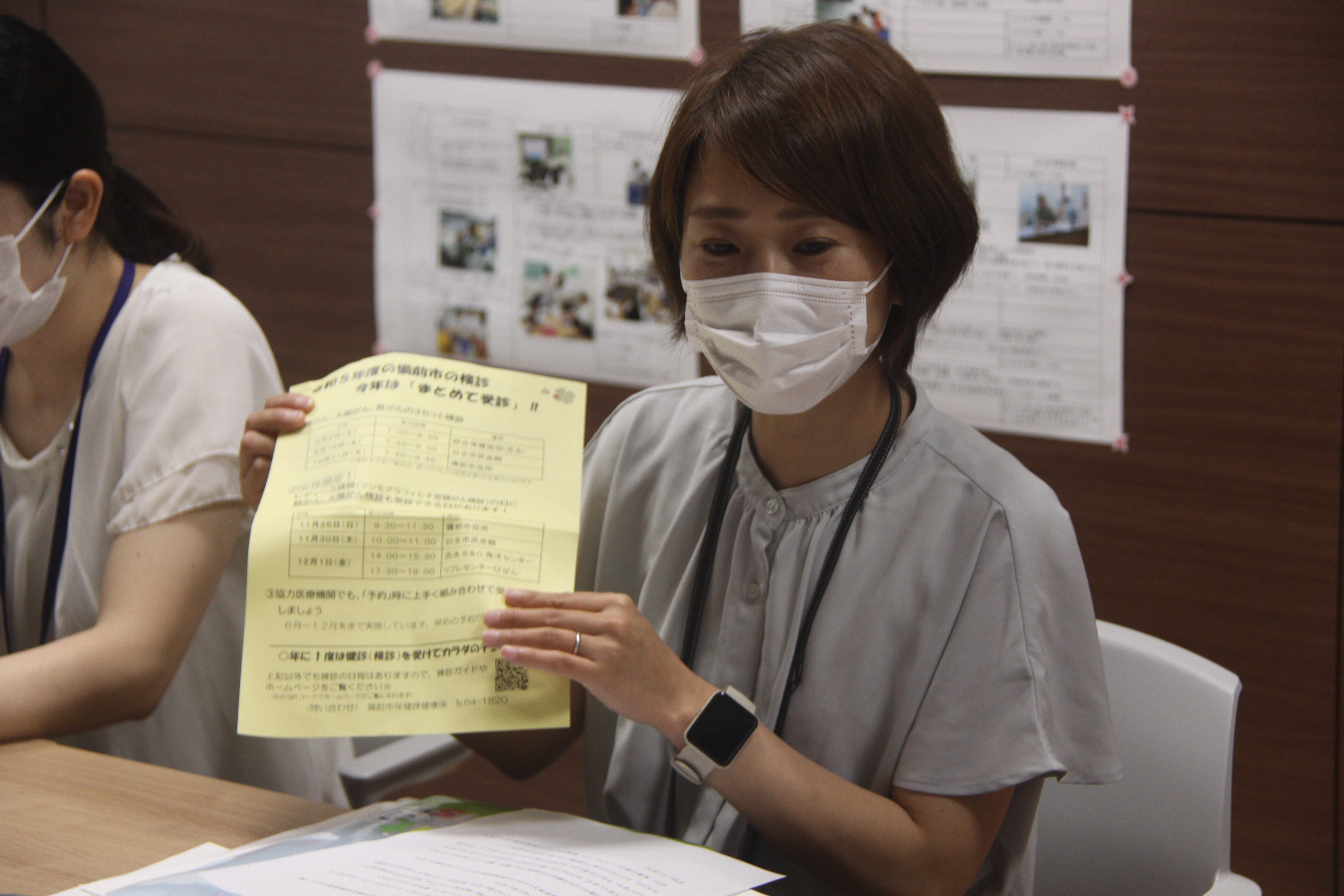
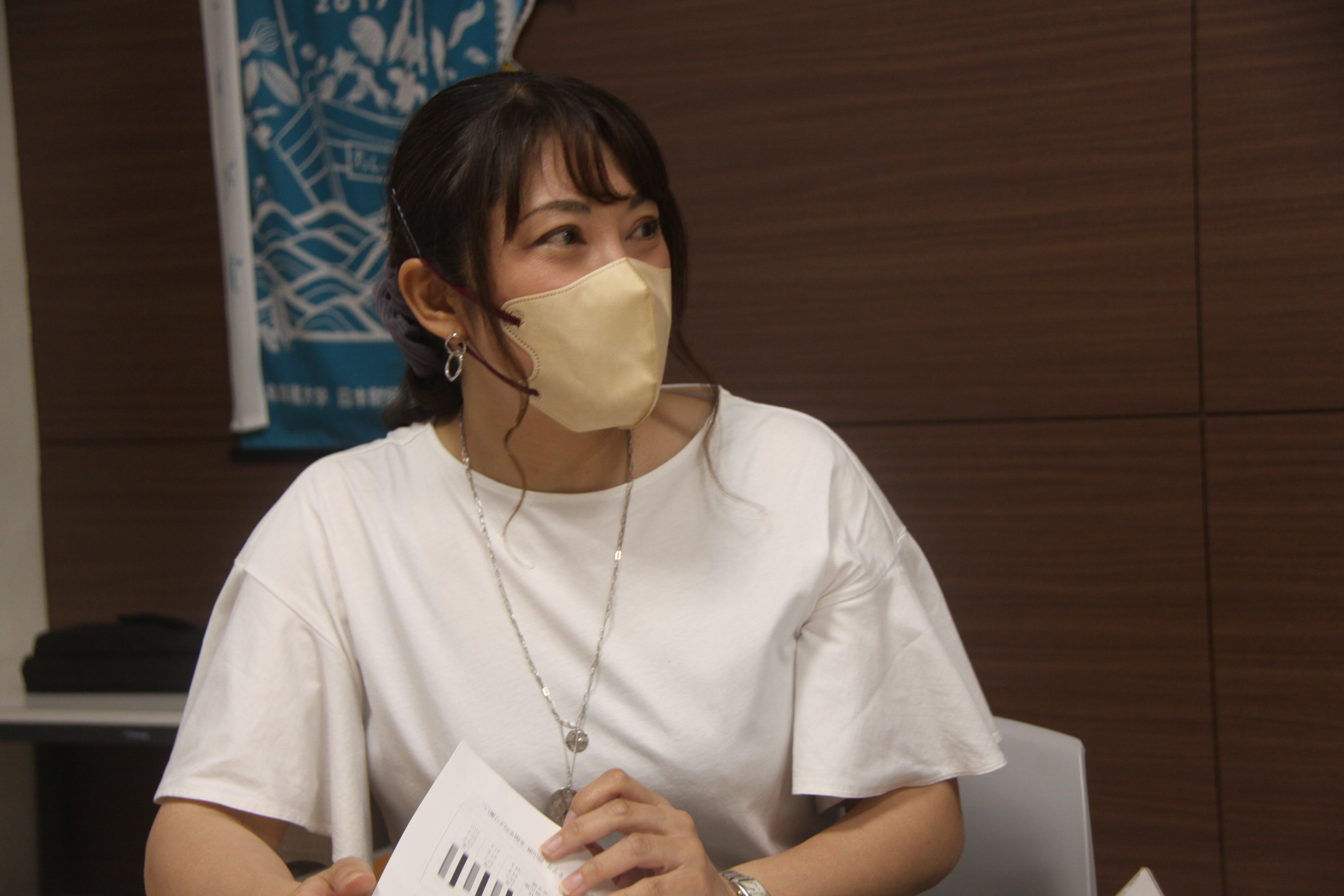
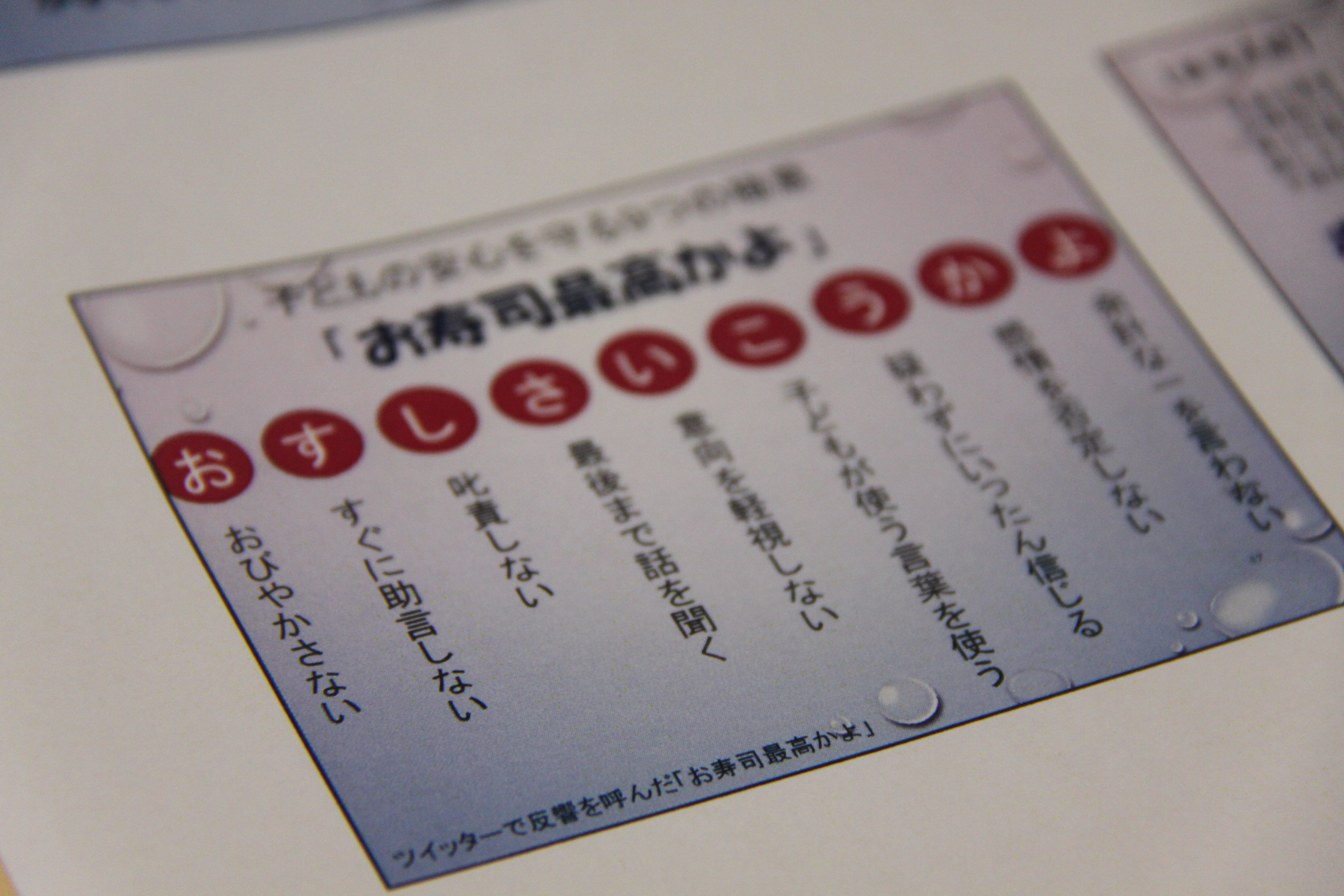
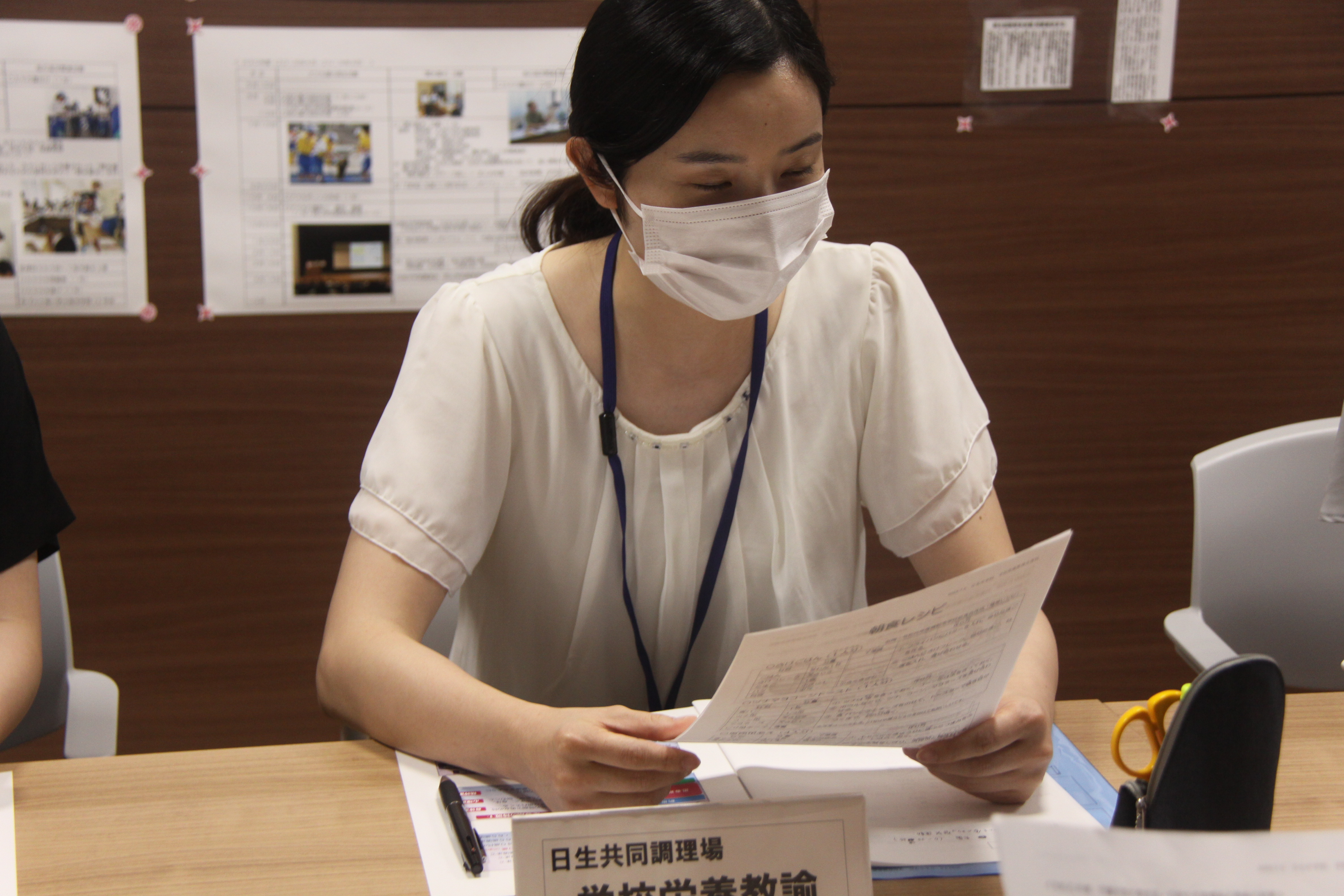
◎生徒朝礼(7/4)~わたしたちの学校 わたしたちの集い わたしたちは仲間
生徒朝礼では、備前東地区総合体育大会剣道競技の部・ソフトテニス競技の部での入賞者の表彰伝達をおこないました。




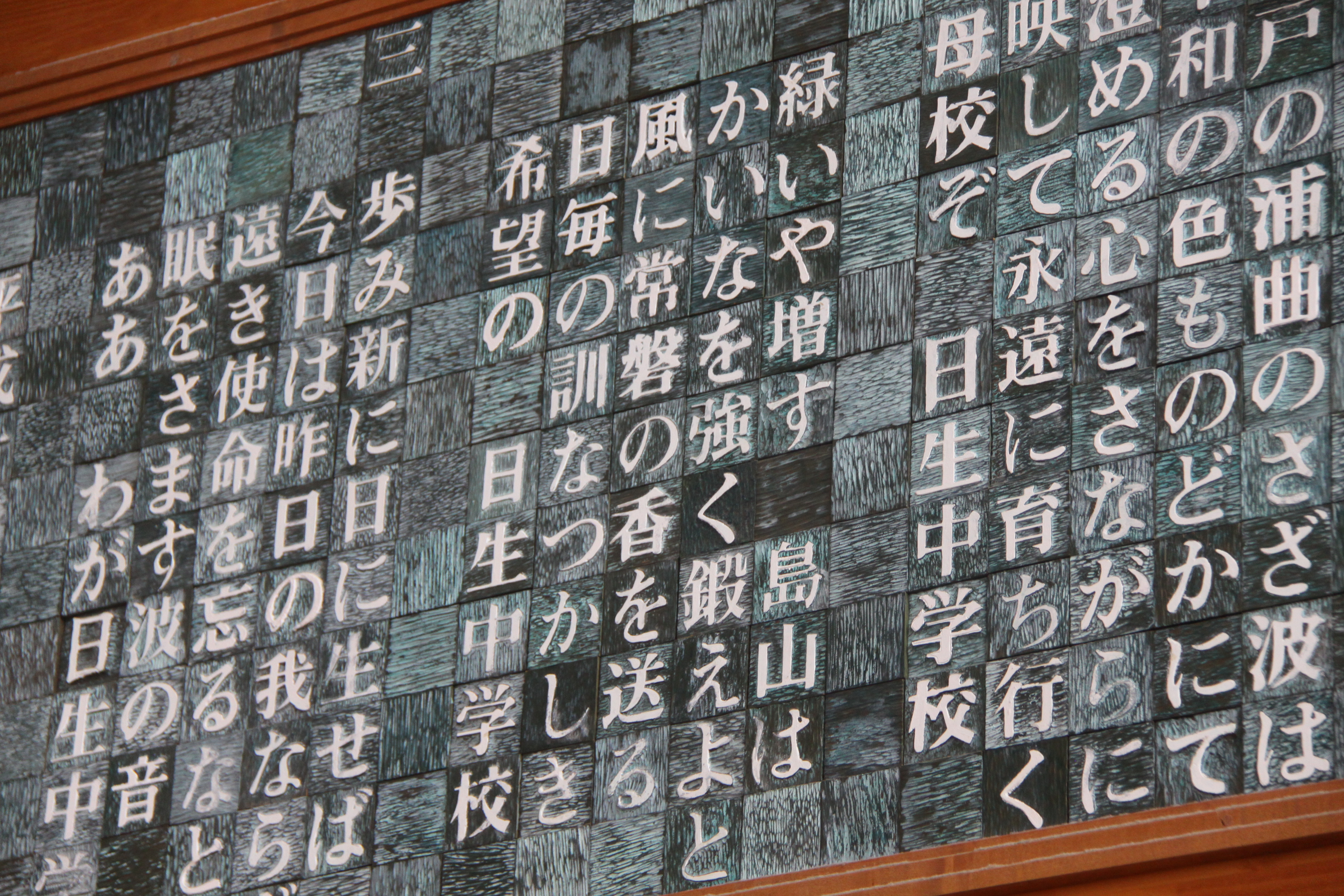




◎多くの人に支えられて 第1回学校評議員会開催(7/3)
第1回評議員会では、藪内さん、有吉さん、米本さん、星尾さん、三木さんに委嘱状をお渡し、その後、校長から学校経営計画・学校のグラウンドデザインについてお話をさせていただきました。授業参観ののち、意見交流を行い、とても充実した時間になりました。学校評議員は,学校が保護者や地域住民の意見を把握し,反映し,その協力を得るための方策について,校長の求めに応じて意見を述べ,学校の自主性・主体性の確立と,より一層地域に開かれた学校づくりのための支援を行うことを目的としています。また、会の役割として、校長は,学校運営に関し,自己の権限と責任に属する事項のうち,以下の4つの事項について学校評議員に助言や意見を求めることができます。①地域住民の学校運営への参画のあり方に関すること。②学校の教育活動の自己評価と地域への説明に関すること。③学校と保護者・地域の連携協力のあり方に関すること。④その他学校の運営の改善に関すること。
さらに、保護者の方々には第1回学校評価アンケートへ、ご協力(今年度よりQRコード版施行)をいただきました。ありがとうございました。データをまとめ、ご意見も合わせて今後のよりよい学校づくり・取組に役立たたせいただきます。



◎きのうえで こざるいさむ
ちいさい ころは かあさんの
おなかのかげから ながめてた
あおい おそらや しろいくも
ゆれる はっぱや えだのくさ
おおきく なって にいさんの
おしりの あとを くっついて
えだから えだへ いち・に・さん
ときどき ないて おちたっけ
いまでは ぼくも いちにんまえ
きのぼり じゃんぷ ちゅうがえり
ひらり あざやか めいじんだ
はっぱが ぱちぱち はくしゅする 『のはらうた』より
…日生認定子ども園のご協力で、技術家庭科(家庭分野)と総合的な学習の時間の一環として、三年生が、幼児とのふれ合い活動に取り組みました。(7/3)
また、7月6日には、浴衣着付け学習(家庭科)を、日生地域の方々のサポートもいただき実施します。







◎7月の風景




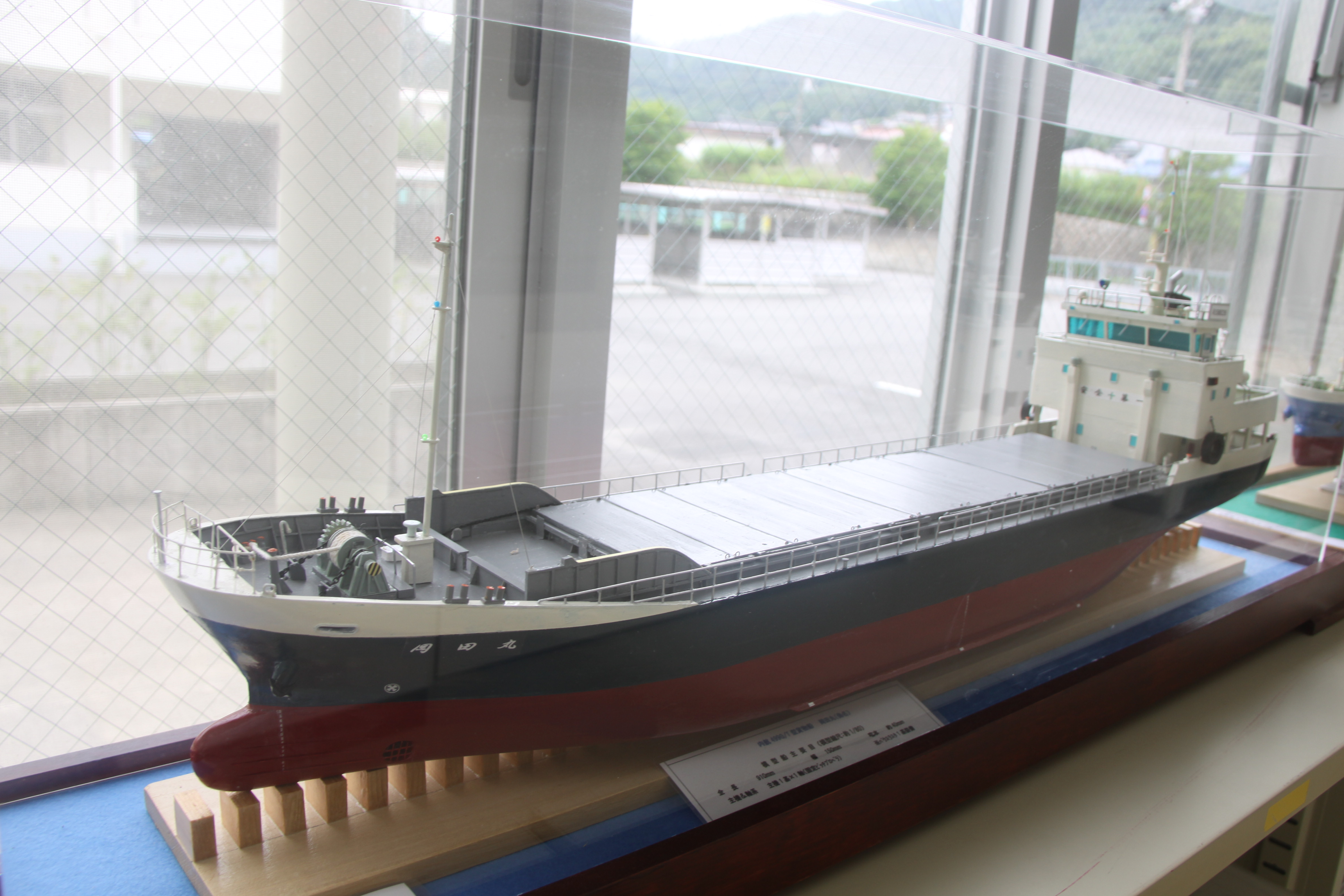

12日は弓削高専の実習船来港。ぜひ見学学習に。
◎ここ
どっかに行こうと私が言う
どこ行こうかとあなたが言う
ここもいいなと私が言う
ここでもいいねとあなたが言う
言ってるうちに日が暮れて
ここがどこかになっていく 谷川俊太郎
第1回小中連絡会開催。6/30)小学校の先生が一年生の授業の様子を参観され、一人ひとりのがんばりをみていただきました。日生中学区ではこども園・小学校・中学校との連携を深めて教育活動に取り組んでいます。本校の文化委員は、7月27日(木)に西小学校、7月31日(月)に東小学校へ「おはなし会(本の読み語り)」に出向きます。小学生のみんな楽しみにまっててね。(o^―^o)
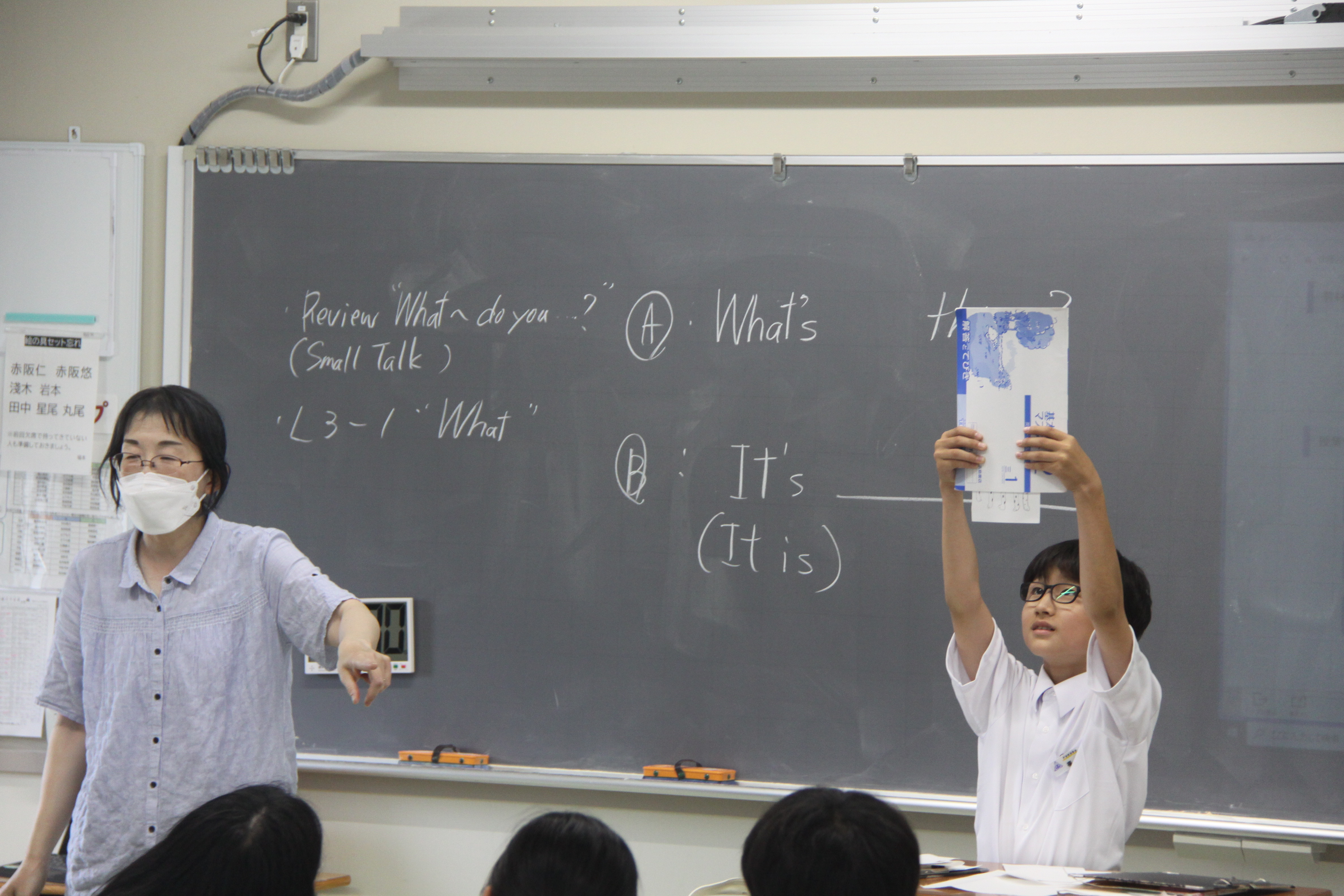



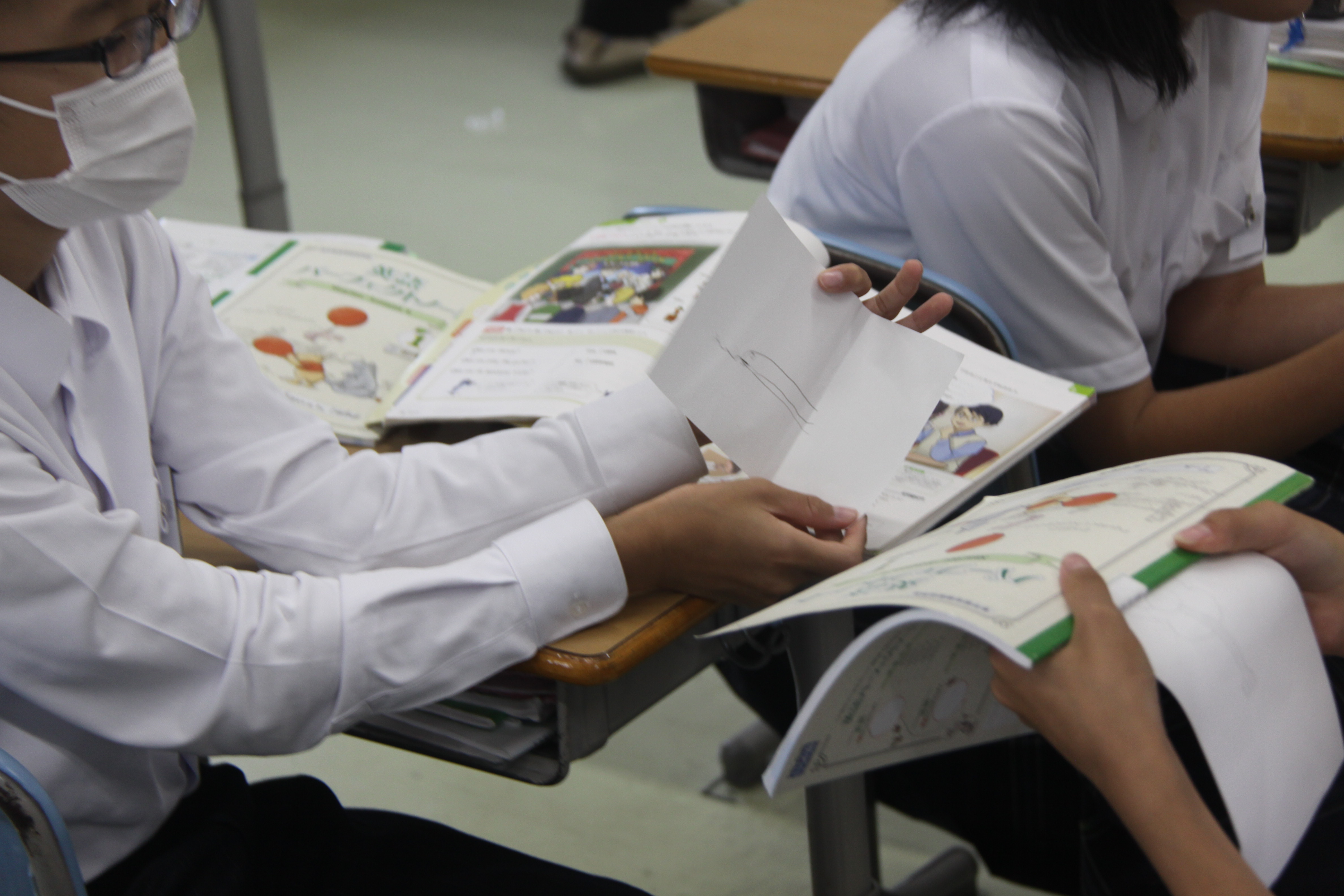

◎〈学ぶことの先に君の大好きな世界がちゃんとあるということ 勉強短歌♯027〉
到達度確認テスト乗り越える(6/29)
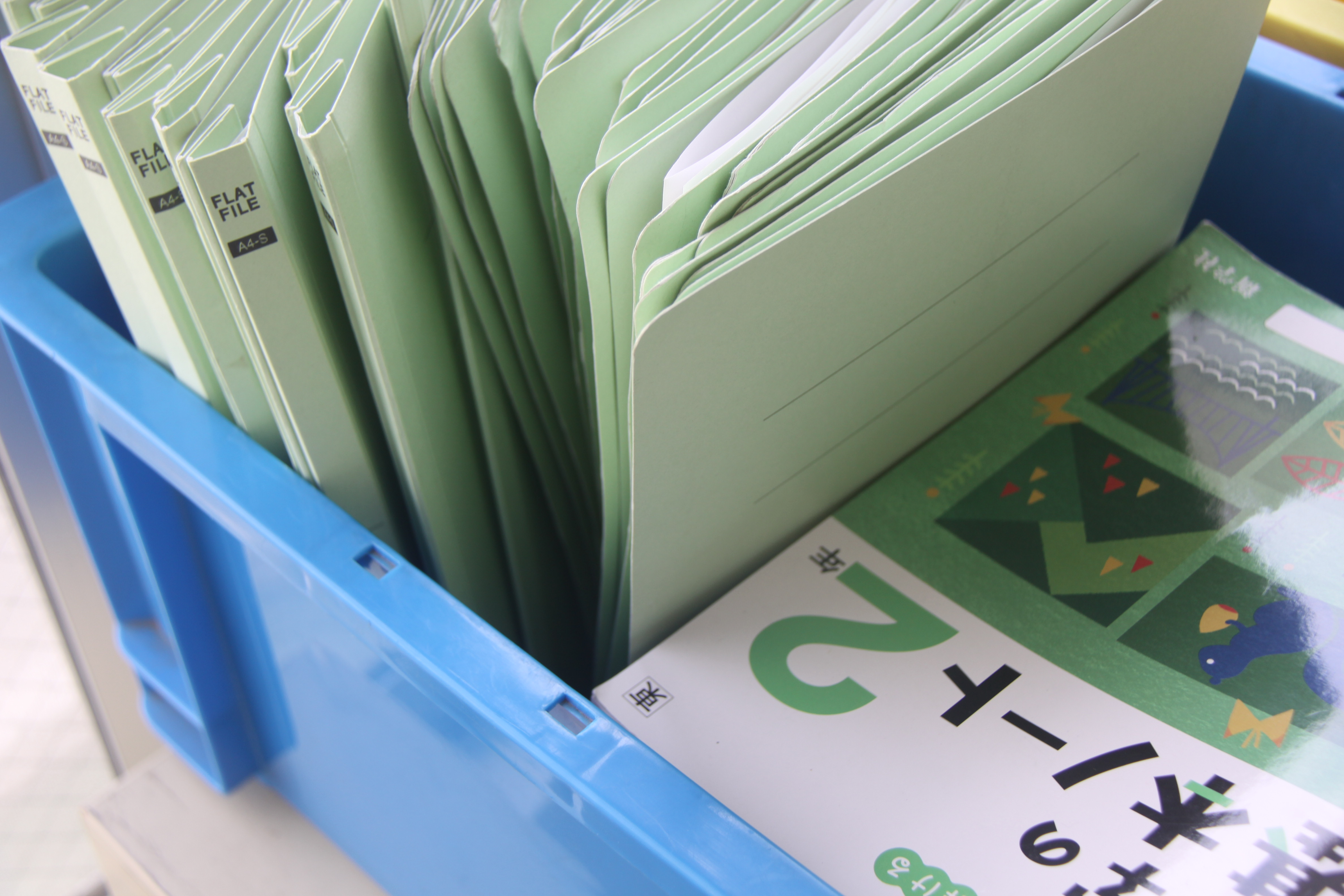
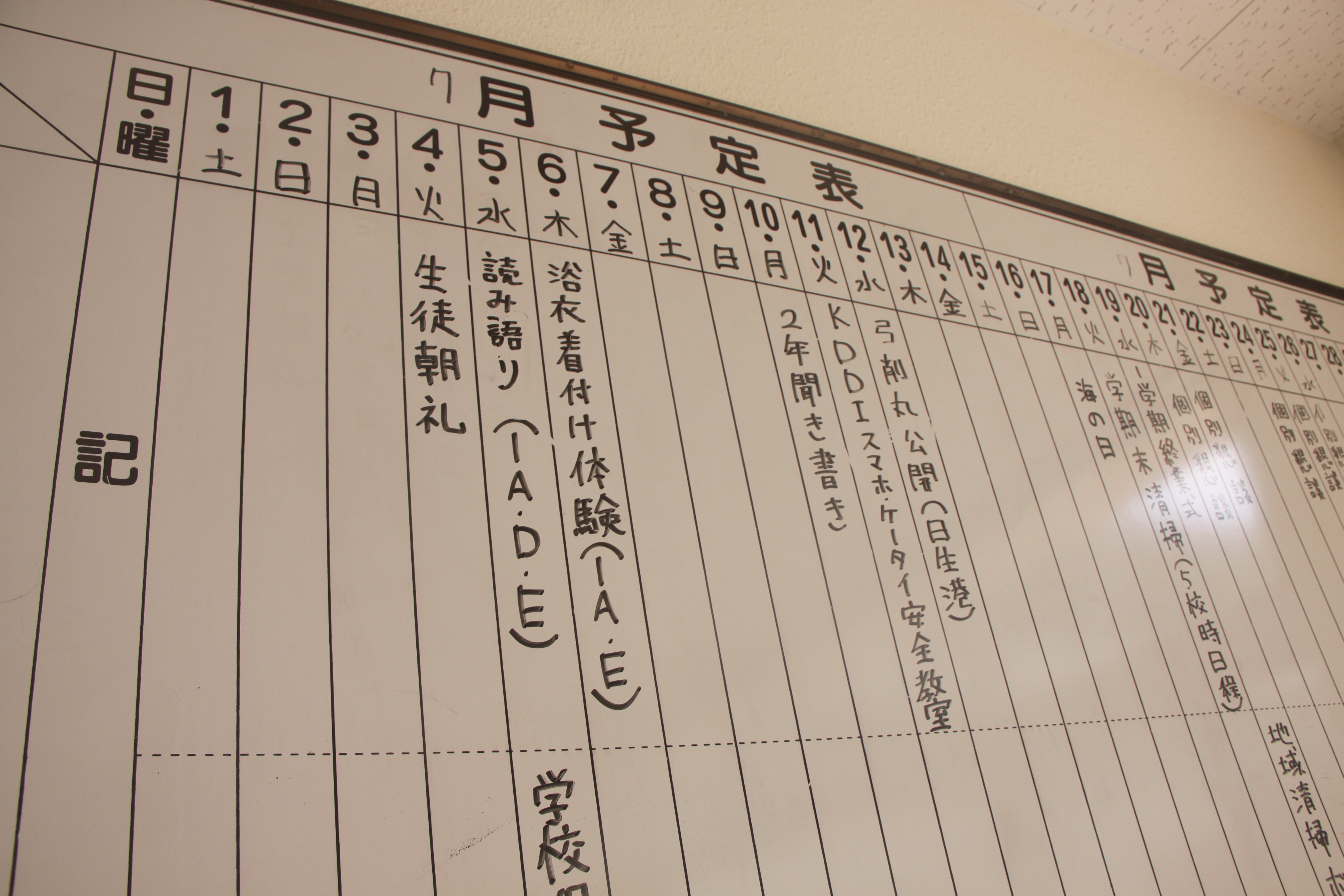
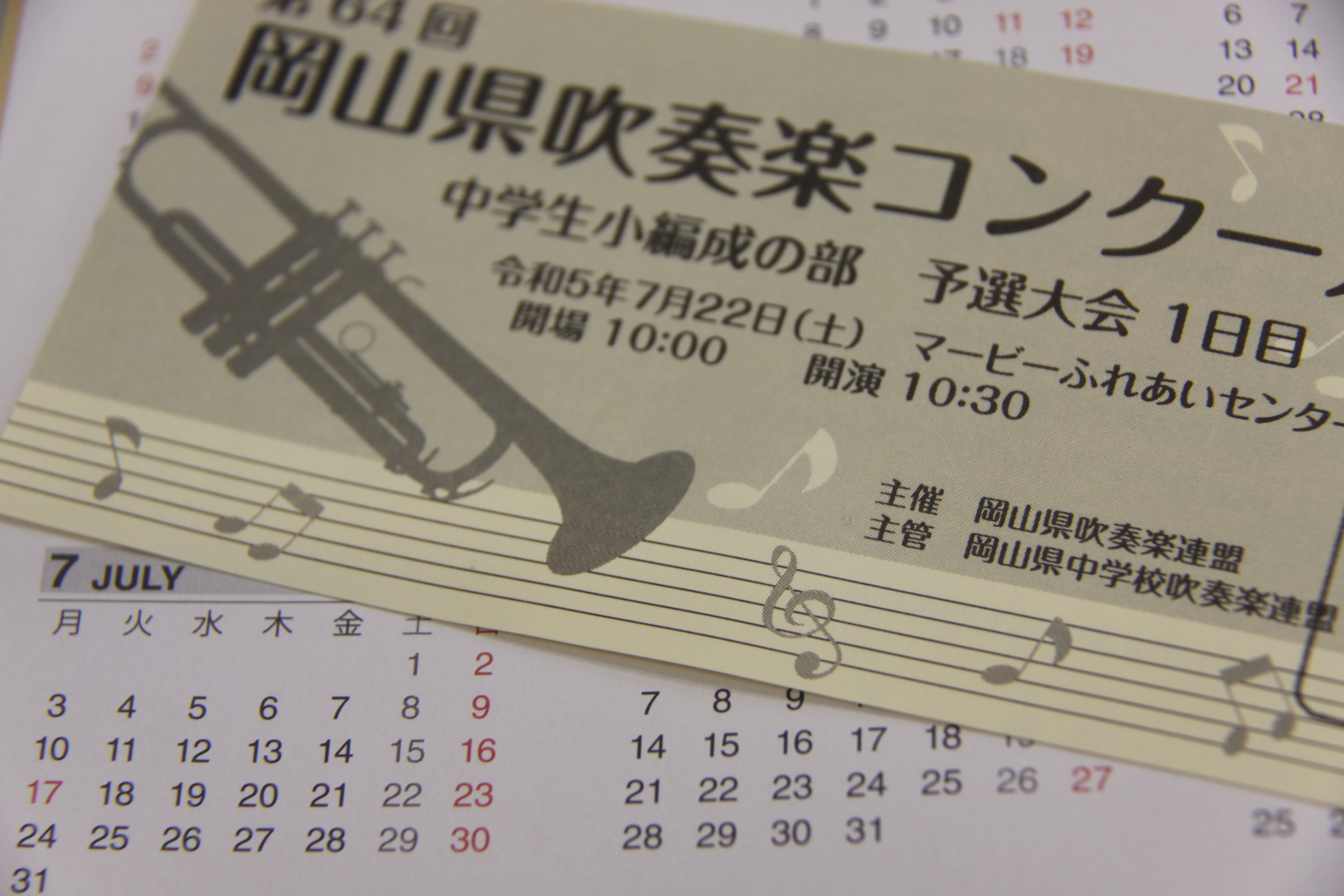
◎多くの人に支えられて(6/29)
地域で活動されているエコロジー東備の大橋さんが、グリーンカーテンの苗を持ってきてくださいました。ありがとうございます。グリーンカーテンは、地球温暖化防止国民運動(環境省)のひとつで、CO2削減・夏の節電対策として、ゴーヤやアサガオ などの植物を育てて作る取組です。


◎「おれは世界の海賊王になる」
進路を切り拓くOSD(オープンスクール)や、豊かな体験活動に取り組む中で
学期末期間となり、夏期休業中のOSDの案内や、地域での催し物の案内がたくさん配付・紹介されています。自分らしい進路実現のために積極的に参加・体験しましょう。
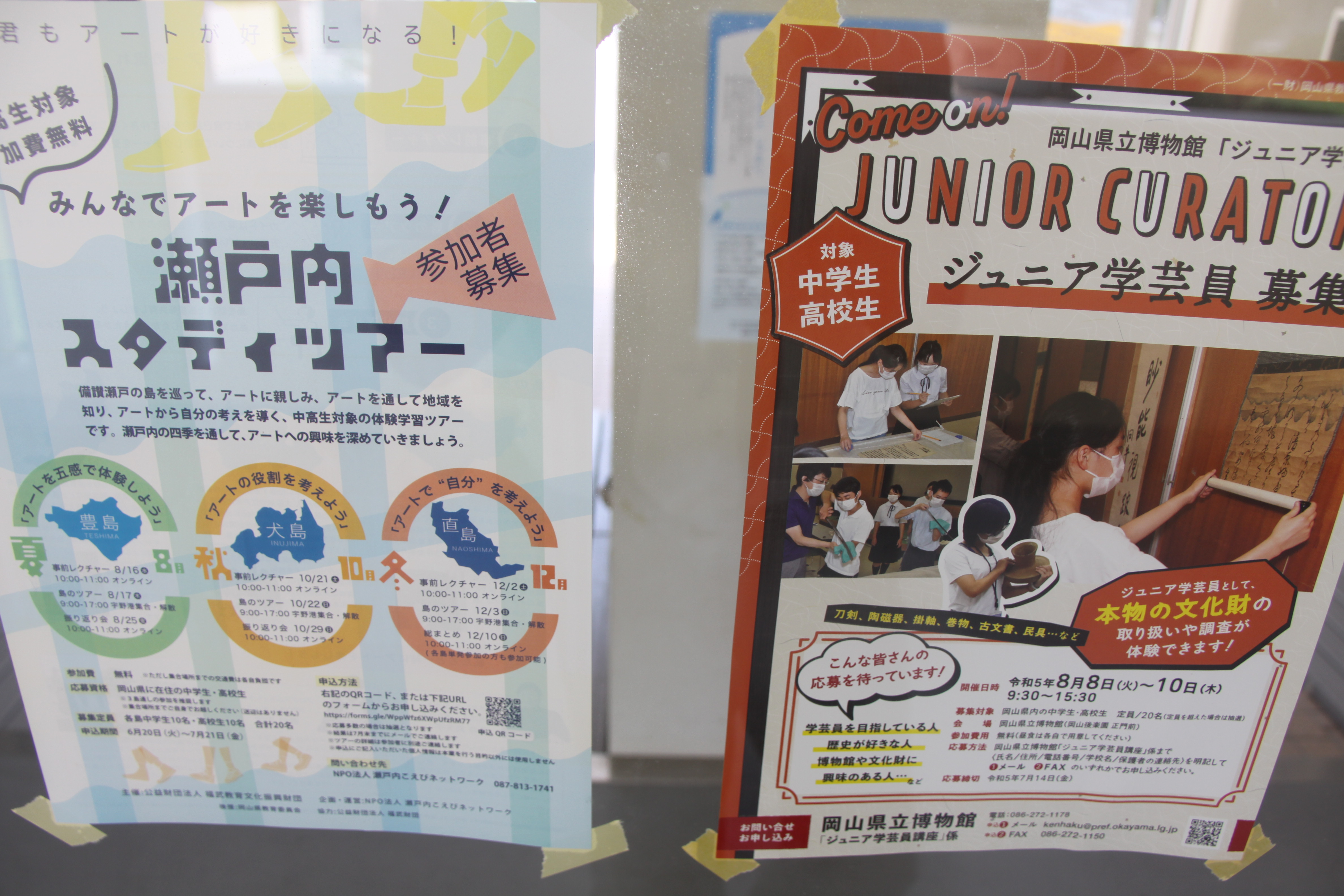
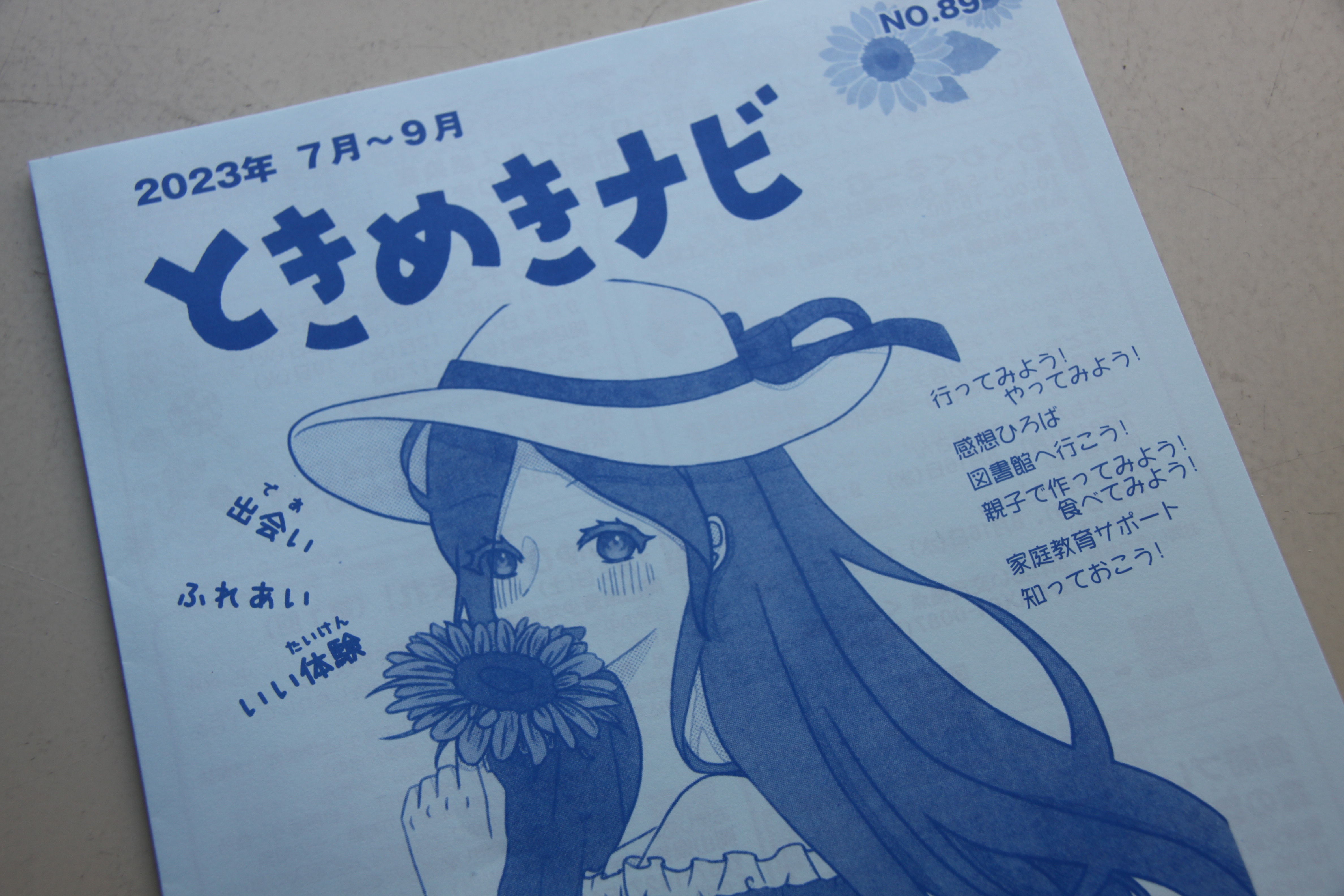
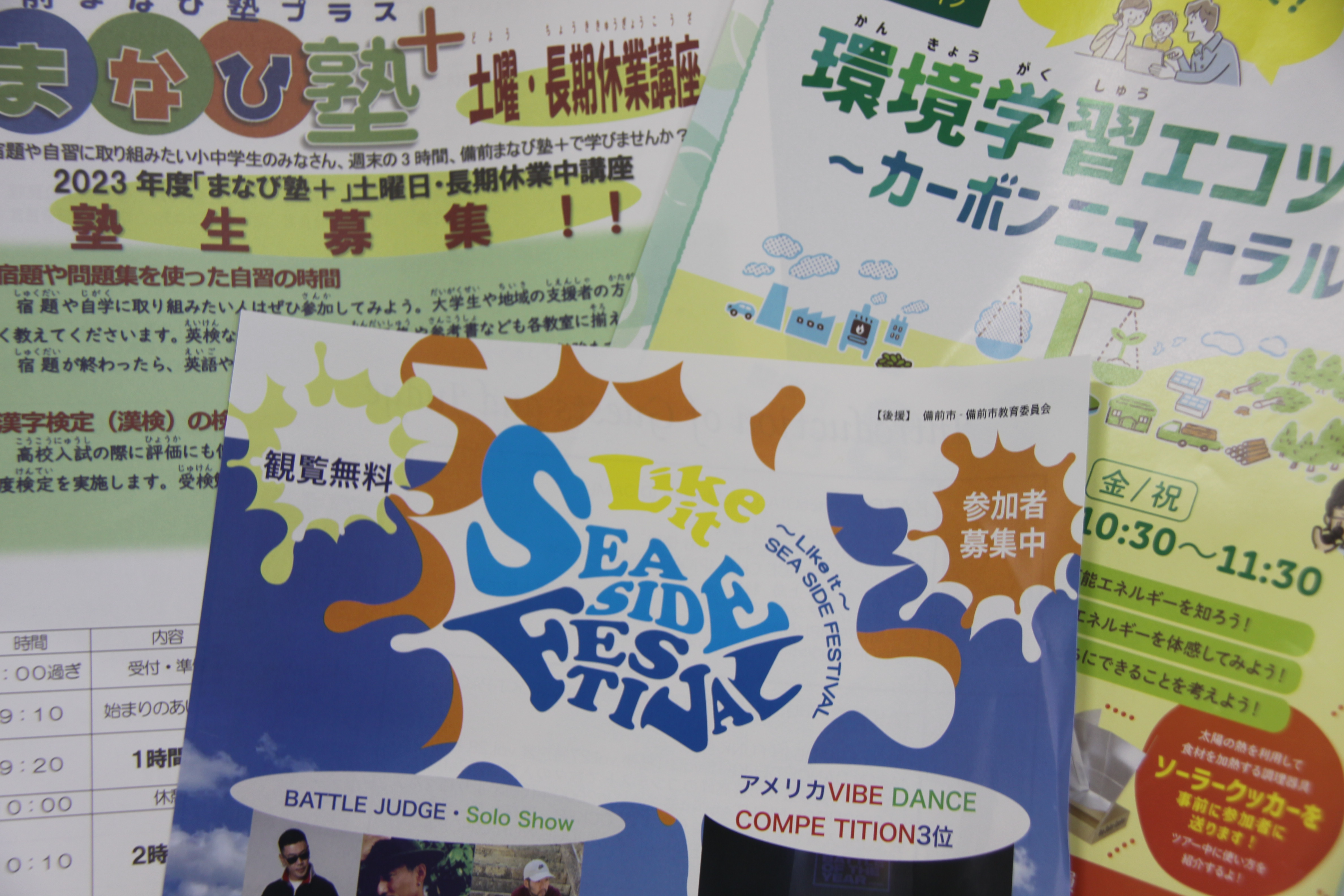
〇OSDについて
・高校等から送付されるパンフレット類を生徒に配付,あるいは教室掲示している情報を確認してください。
・ほとんどの高校等は生徒(保護者)が各自でWeb申込をするようになっています。
・保護者の方で参加をお願いします。学校からの引率はしません。
・参加に当たっては,公共のマナーに十分留意し,日生中学校の代表としてふさわしい態度がとれるようがんばりましょう。
〈申し込み〉
①参加校の情報を確認する。→②開催日,時間,内容などを,掲示物や配付物,Websiteから確認する。→③自分の日程と調整する。→④部活動,クラブ,家族旅行など
家族と話し合って,参加できるかどうかを確認する。→⑤各自でWeb申込をする。(体験講座や部見学など,希望内容を事前に申し込む必要がある場合は記入)
*中学校でとりまとめて申込をする高校については,各高校の〆切の1週間前を校内〆切とします。
*私立高校の場合→各自で申し込む。(インターネット,はがきなど) 原則として,高校への申し込み後は取り消せません。
*オープンスクール参加後にはレポートを記入・提出し、情報の整理と振り返りをしよう。
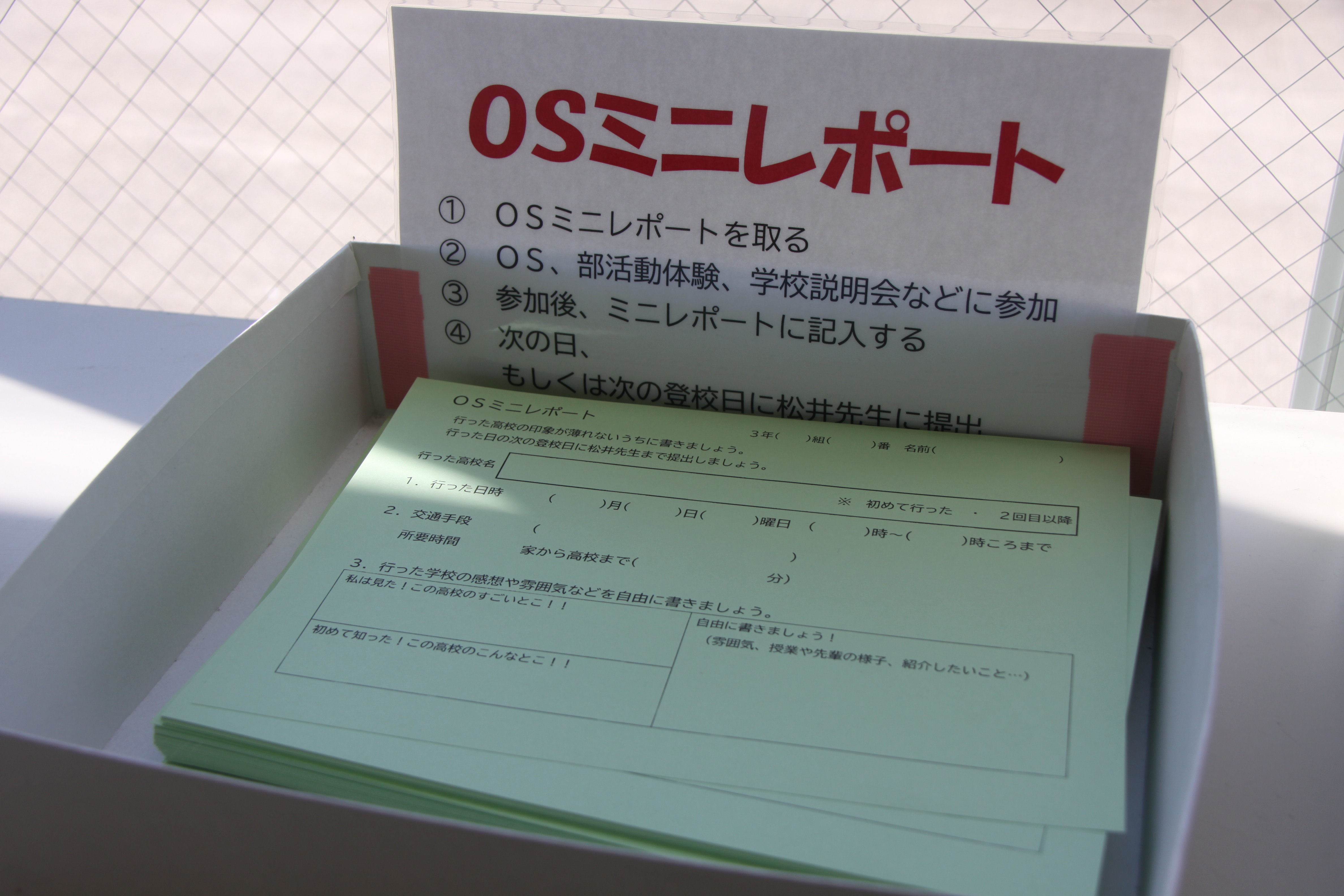
◎日生で輝く 日生が輝く
~第21回 日生中清掃チャレンジカップ(カストーディアル杯)
日生中学校を美しく清掃し,生徒,職員全員で,日本一清掃する学校を目指します。取組期間は6月30日(金)~7月 7日(金)、通常の清掃時間です。清掃活動の様子を審査員(先生ら)に4日間審査してもらい,活動場所ごとに観てもいらい、ベストクラス賞を決めます。この機会に、なかなか清掃できにくかった箇所や、長年の汚れが溜まっていた箇所の清掃にクラス全員で取り組み、1学期を締めくくりましょう。環境委員会より


◎多くの人に支えられて(6/28)
備前市青少年育成センターから末廣さん、今吉さん、大西さんが来校され、下校指導と地域の見回りをしてくださいました。ありがとうございました。青少年育成センターは、PTA等と連携して子どもたちの非行防止と健全育成活動に取り組んでいます。8月13日(日)のひなせ花火大会時にも補導・見守り活動をしてくださいます。


◎〈それぞれの 答案用紙が 一斉に 羽ばたく 試験開始のチャイム〉
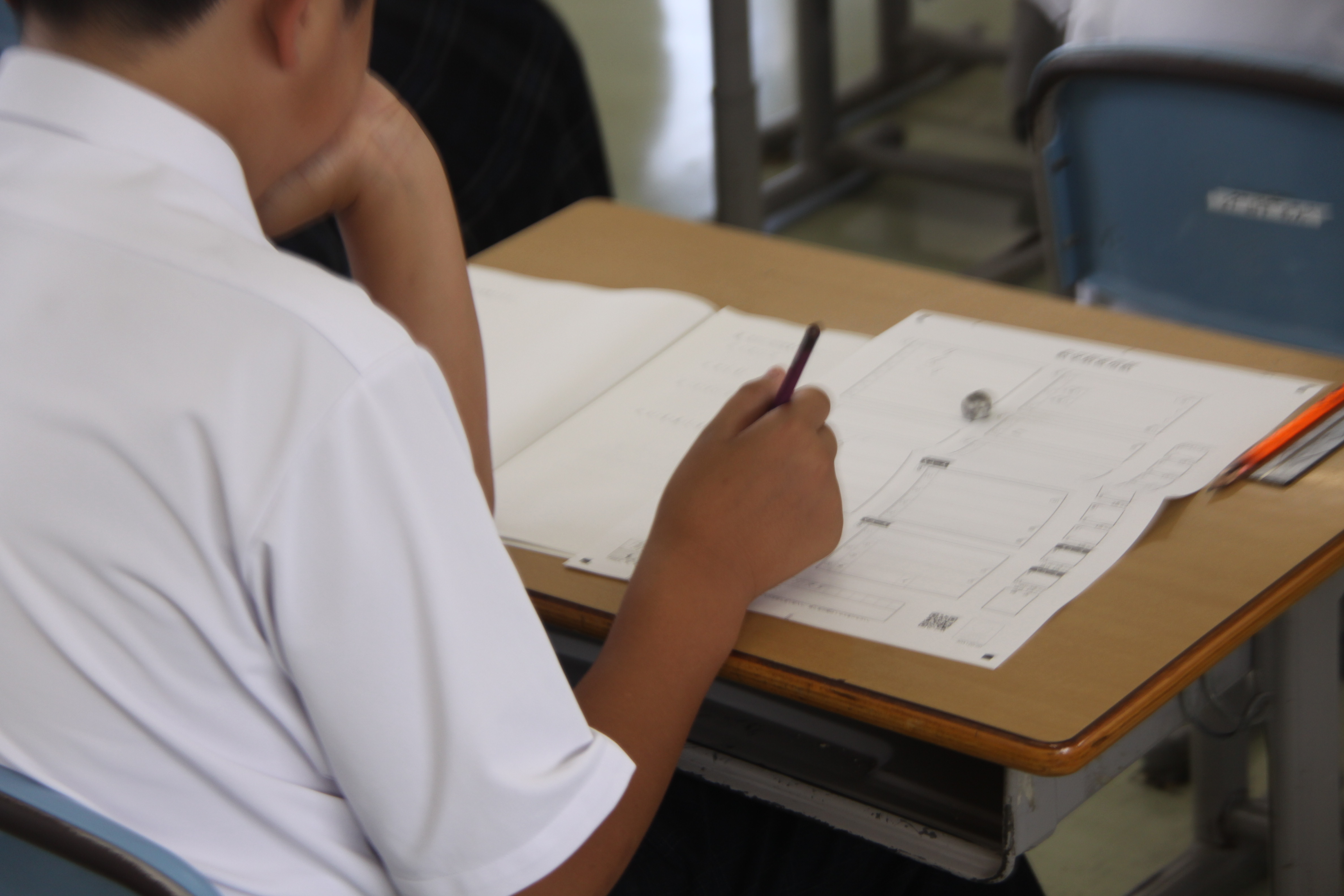
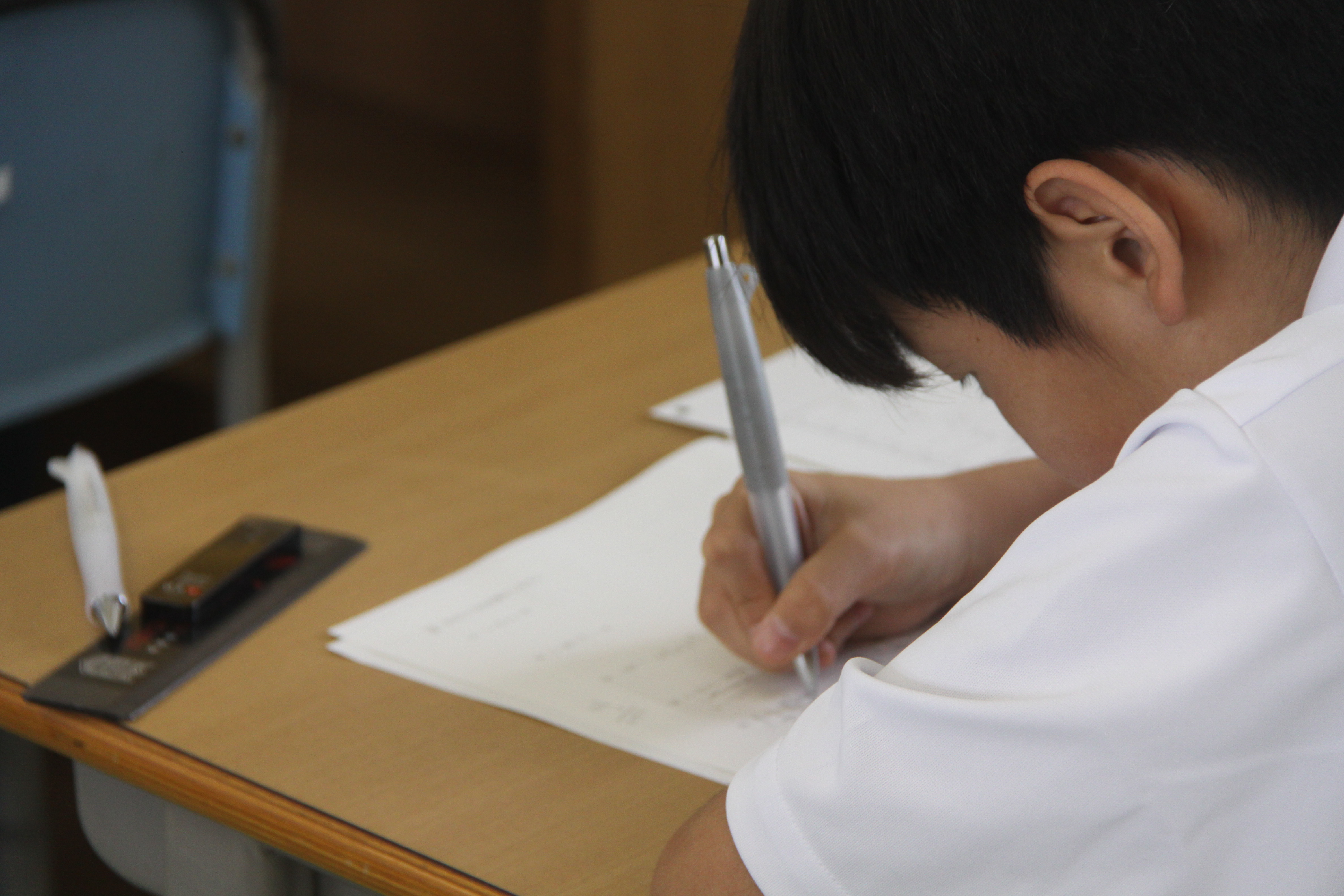

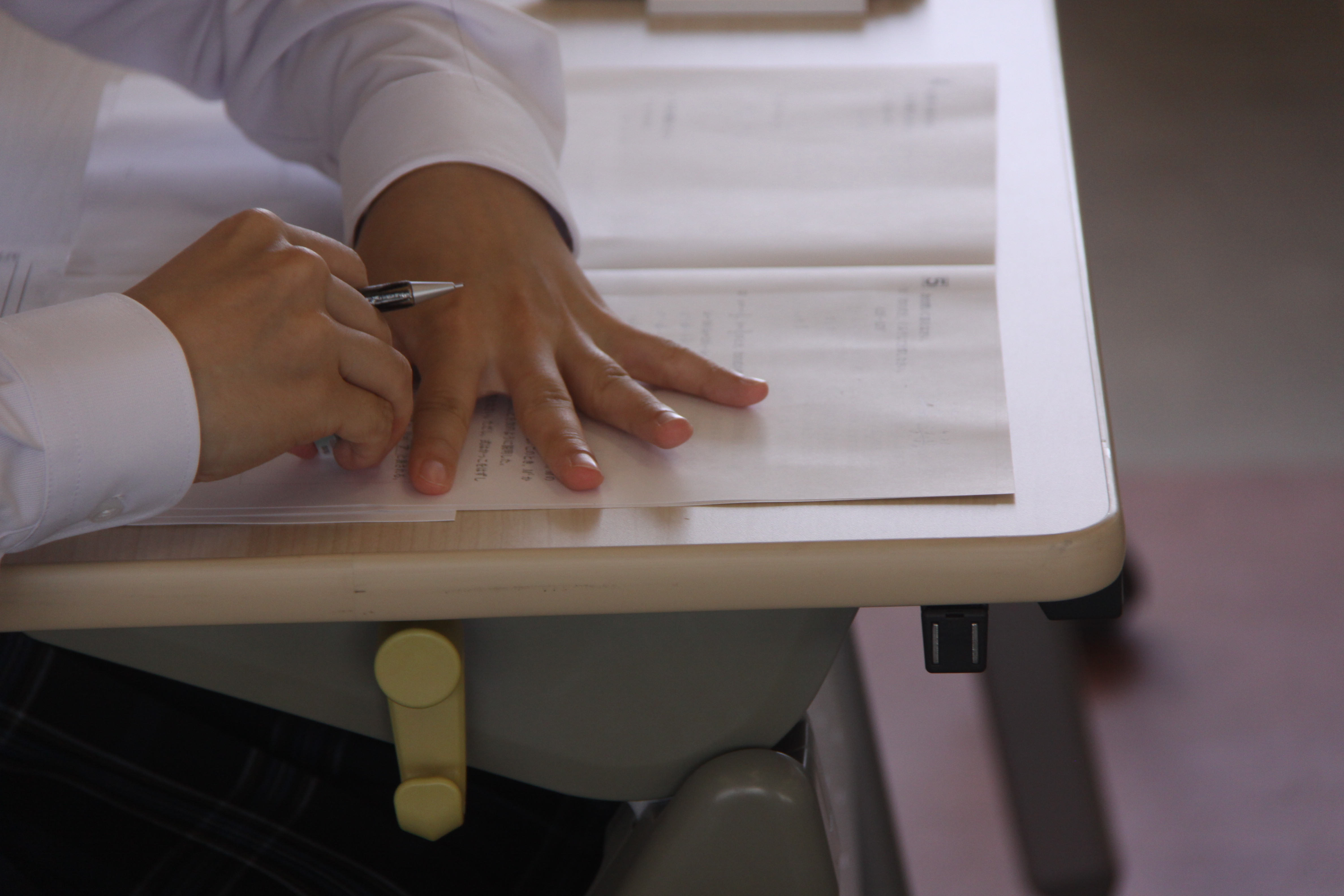
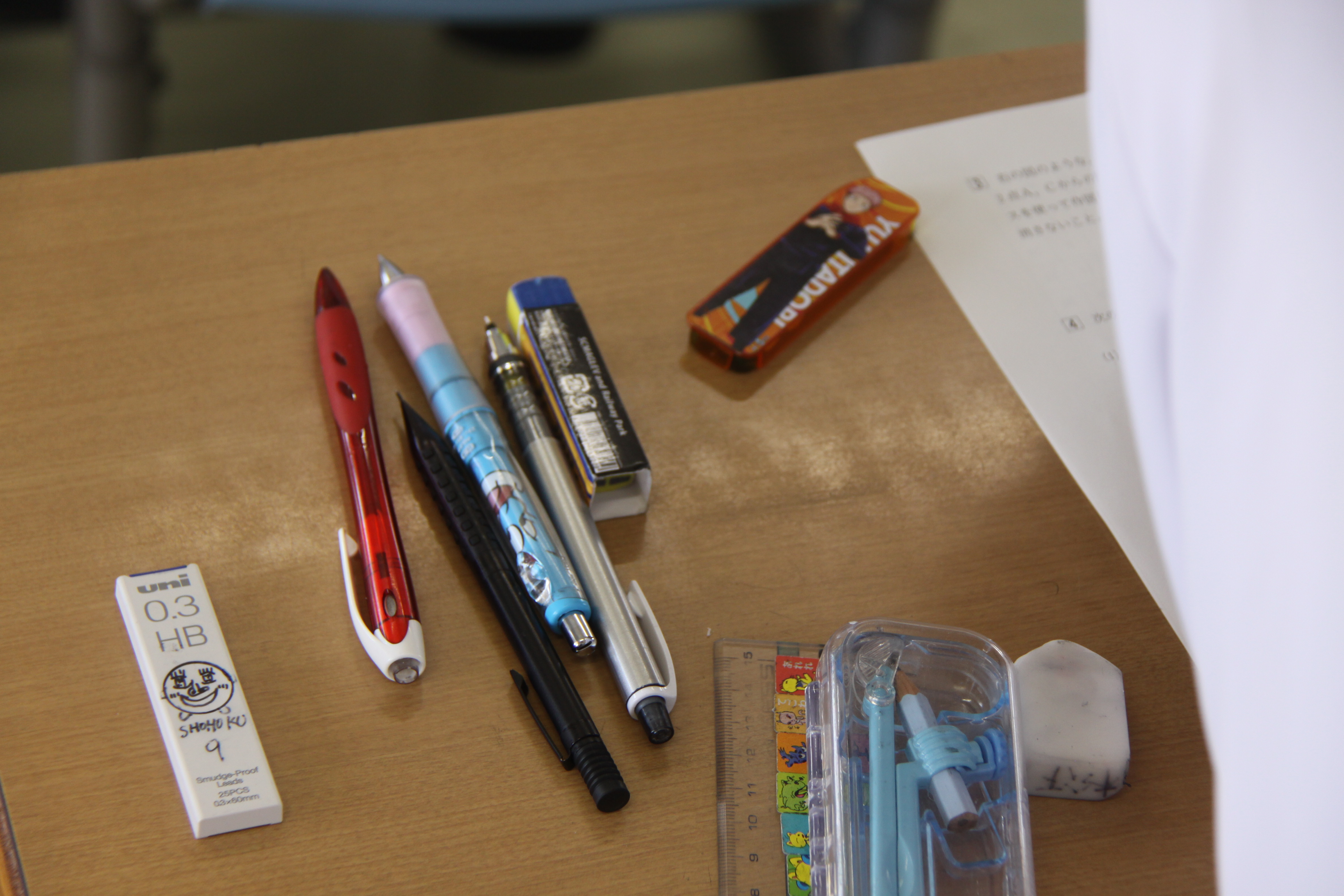
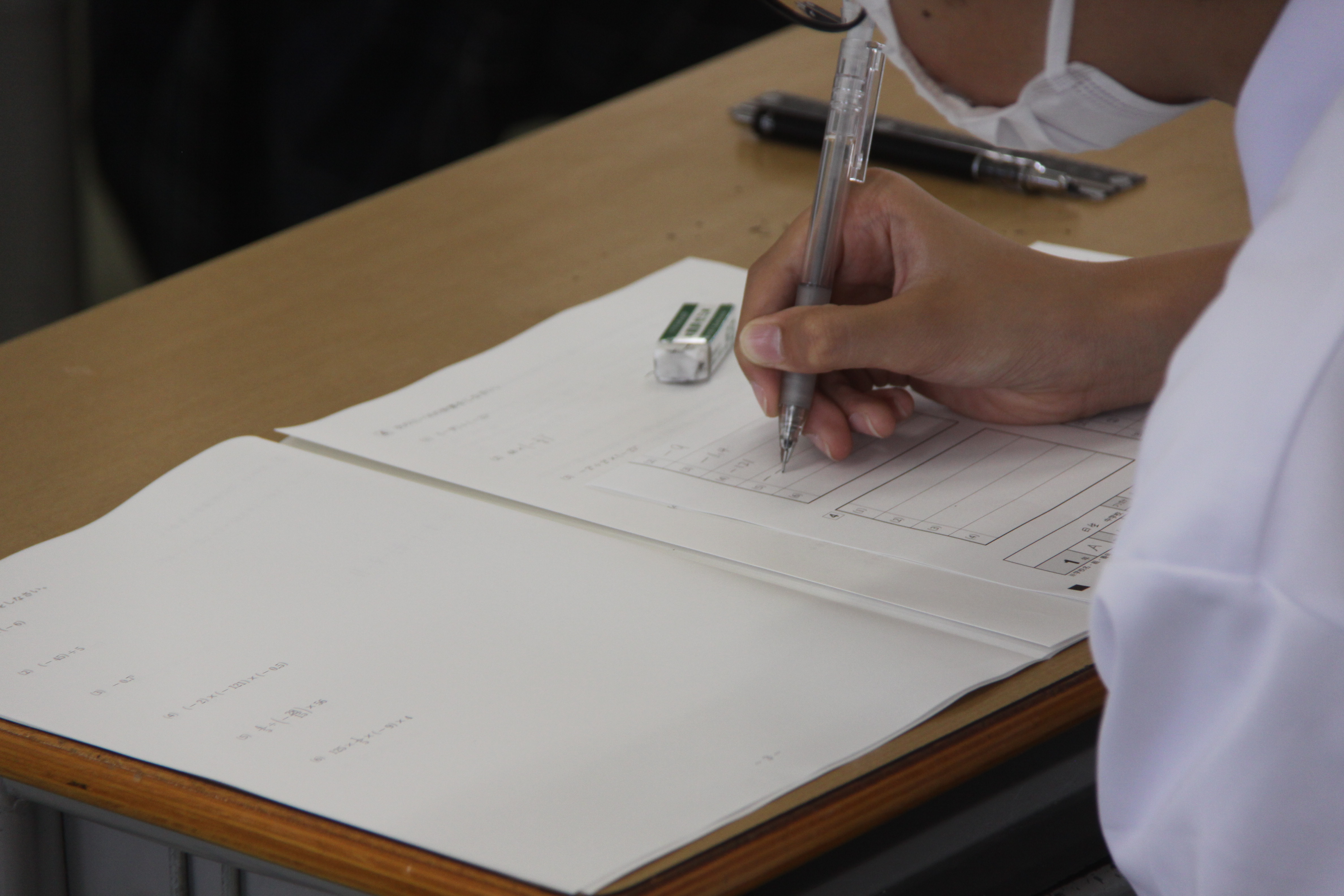

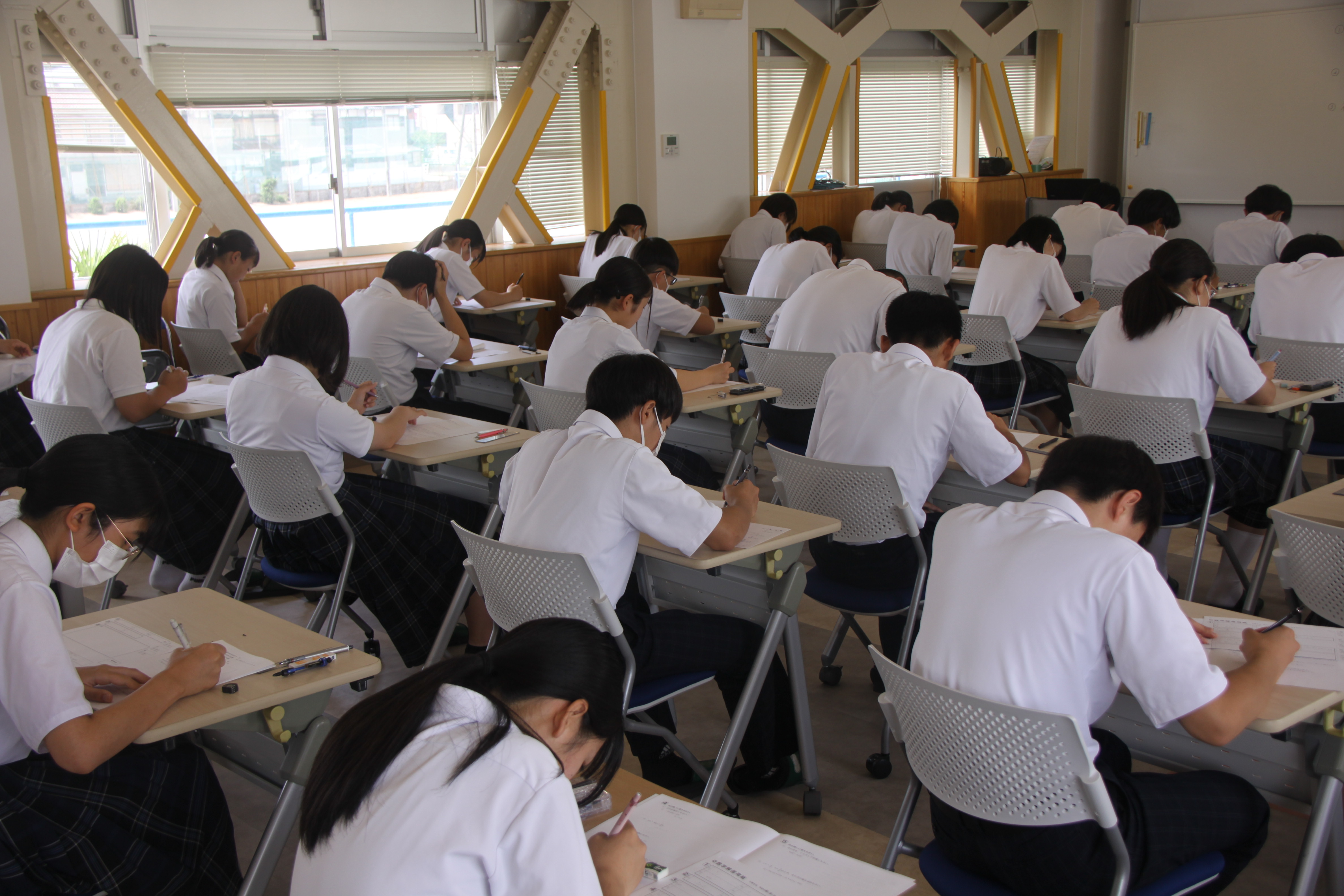

◎AM7:45 仲間とがんばれること(6/28)

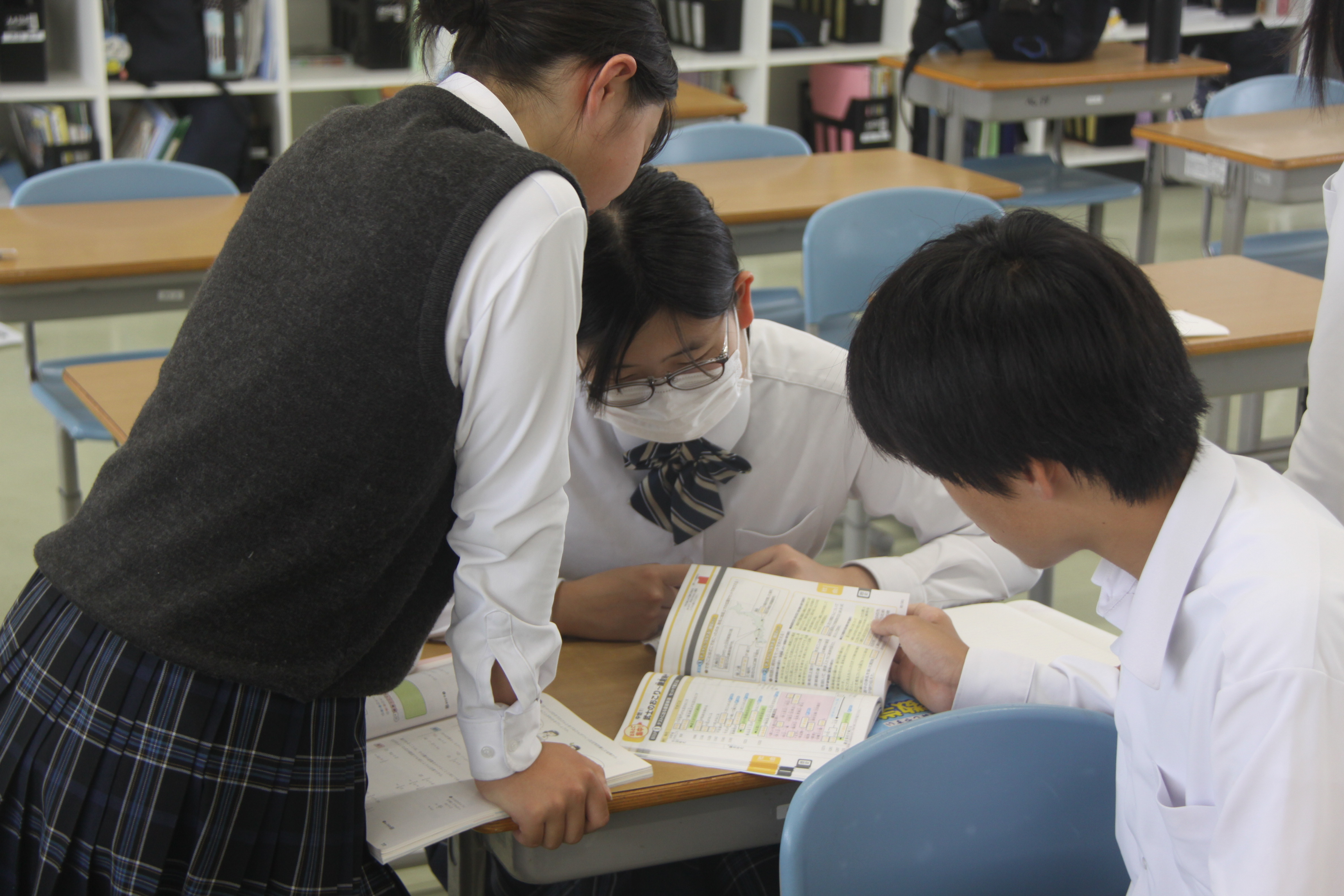
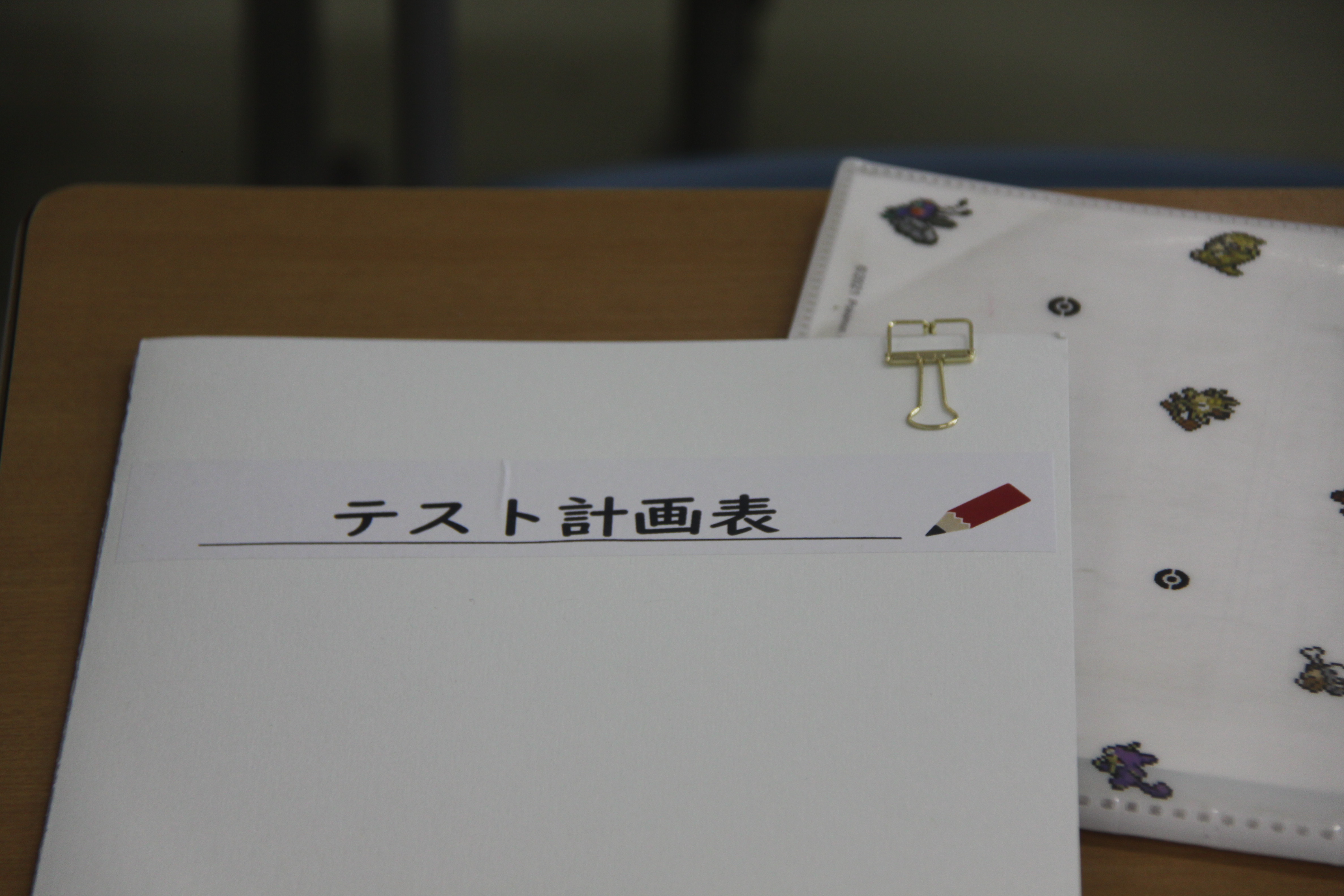

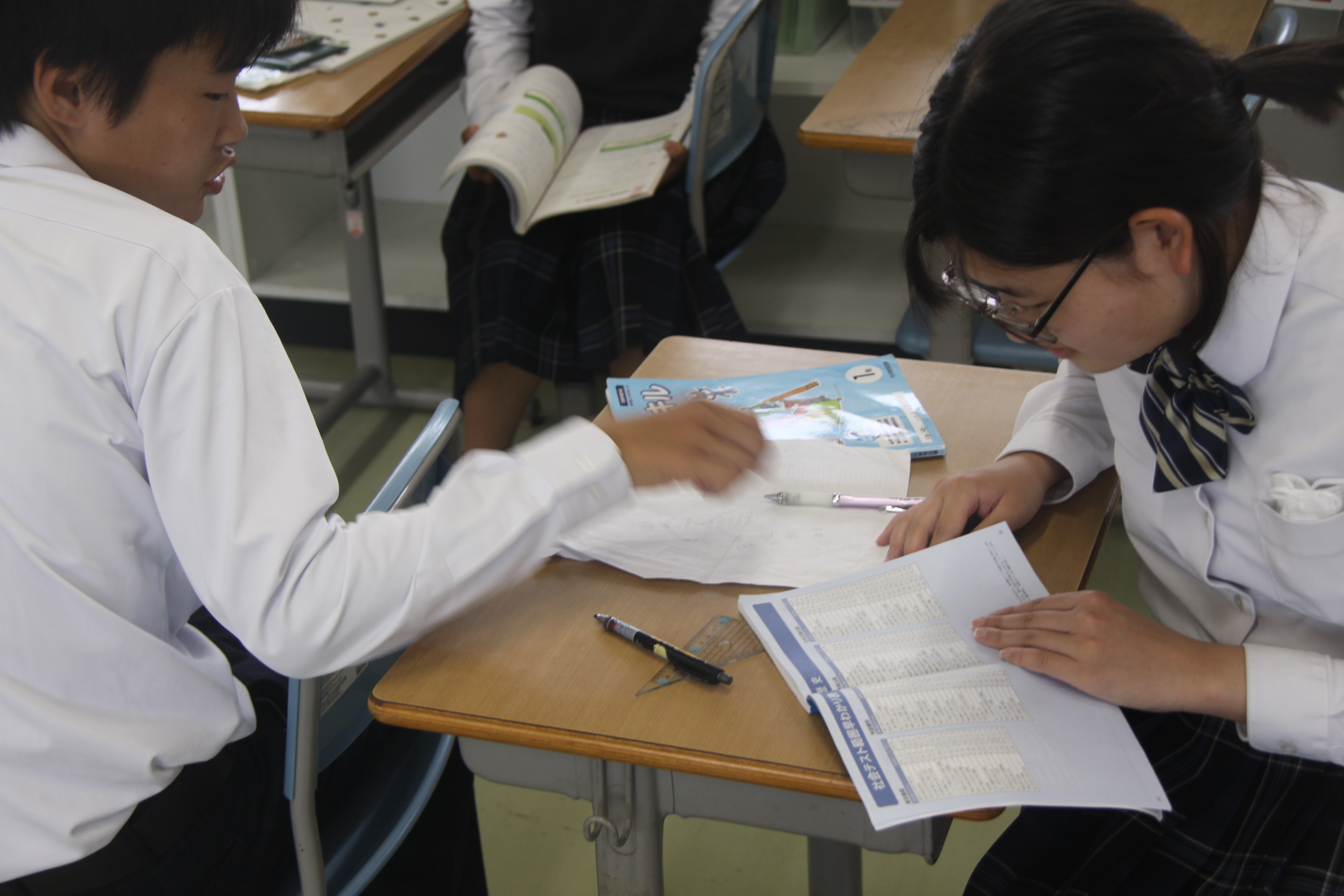
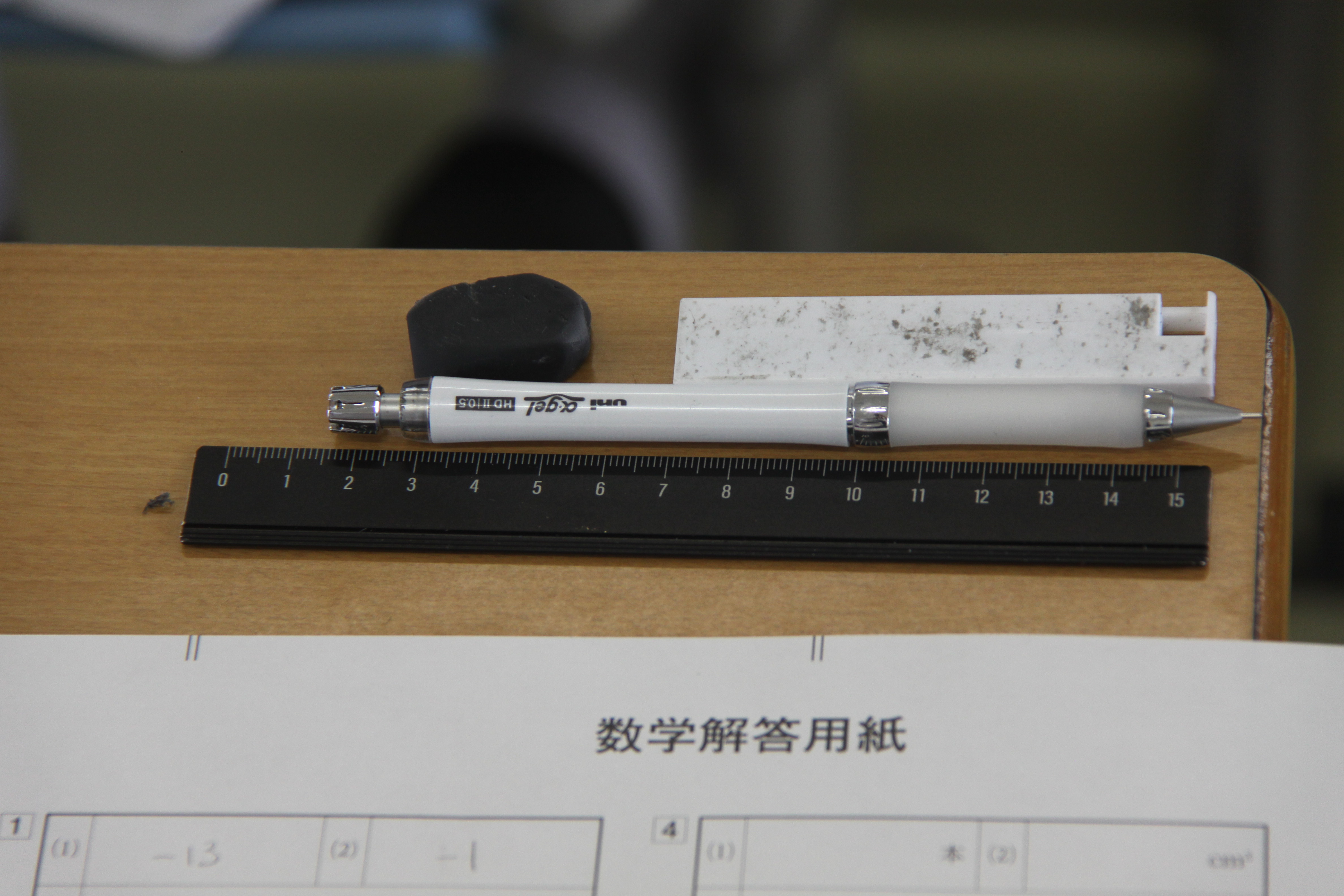
◎ひな中の風~~明日は到達度テスト。(6/27)
みんな 自分らしく精一杯!みんな乗り越えよう!


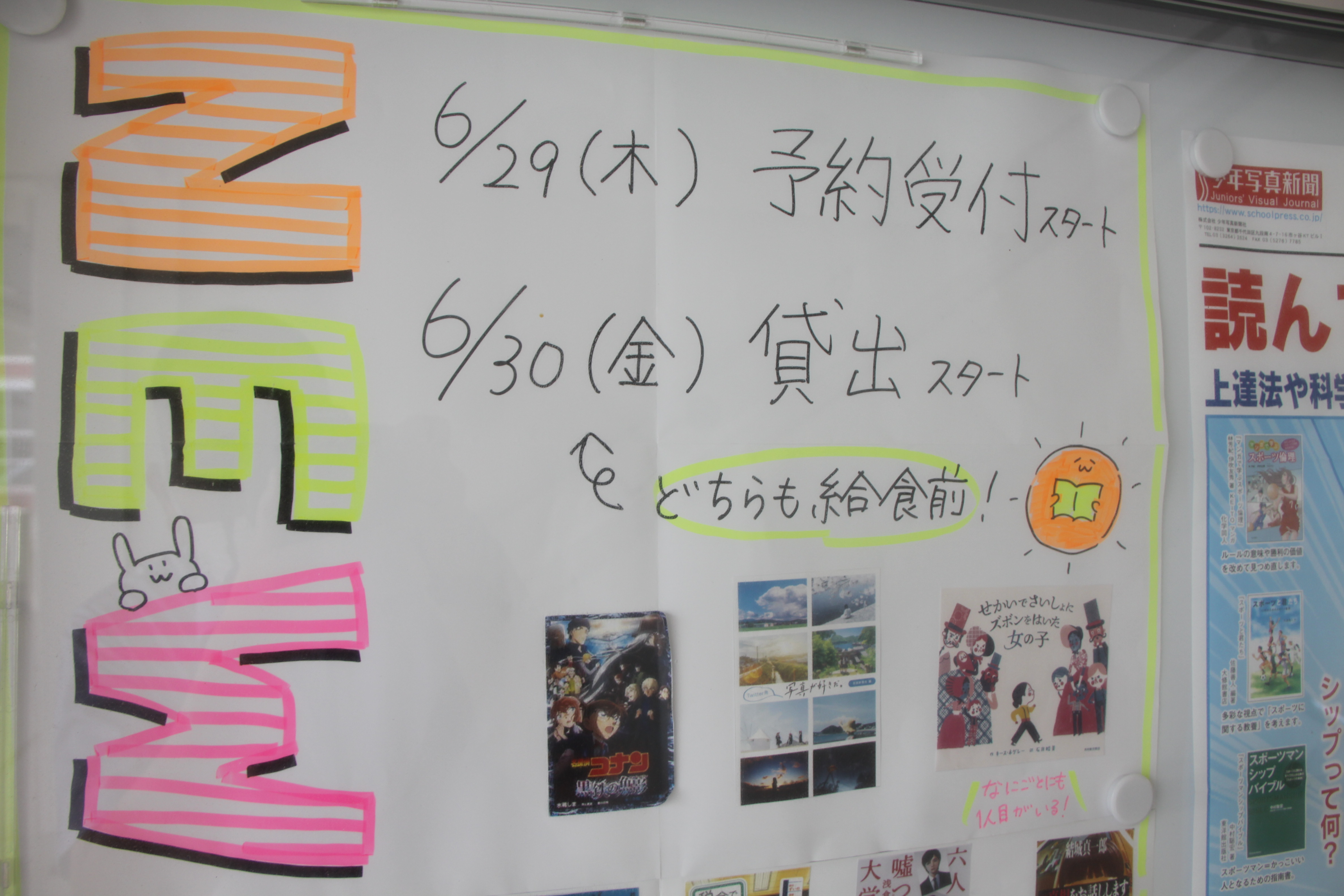


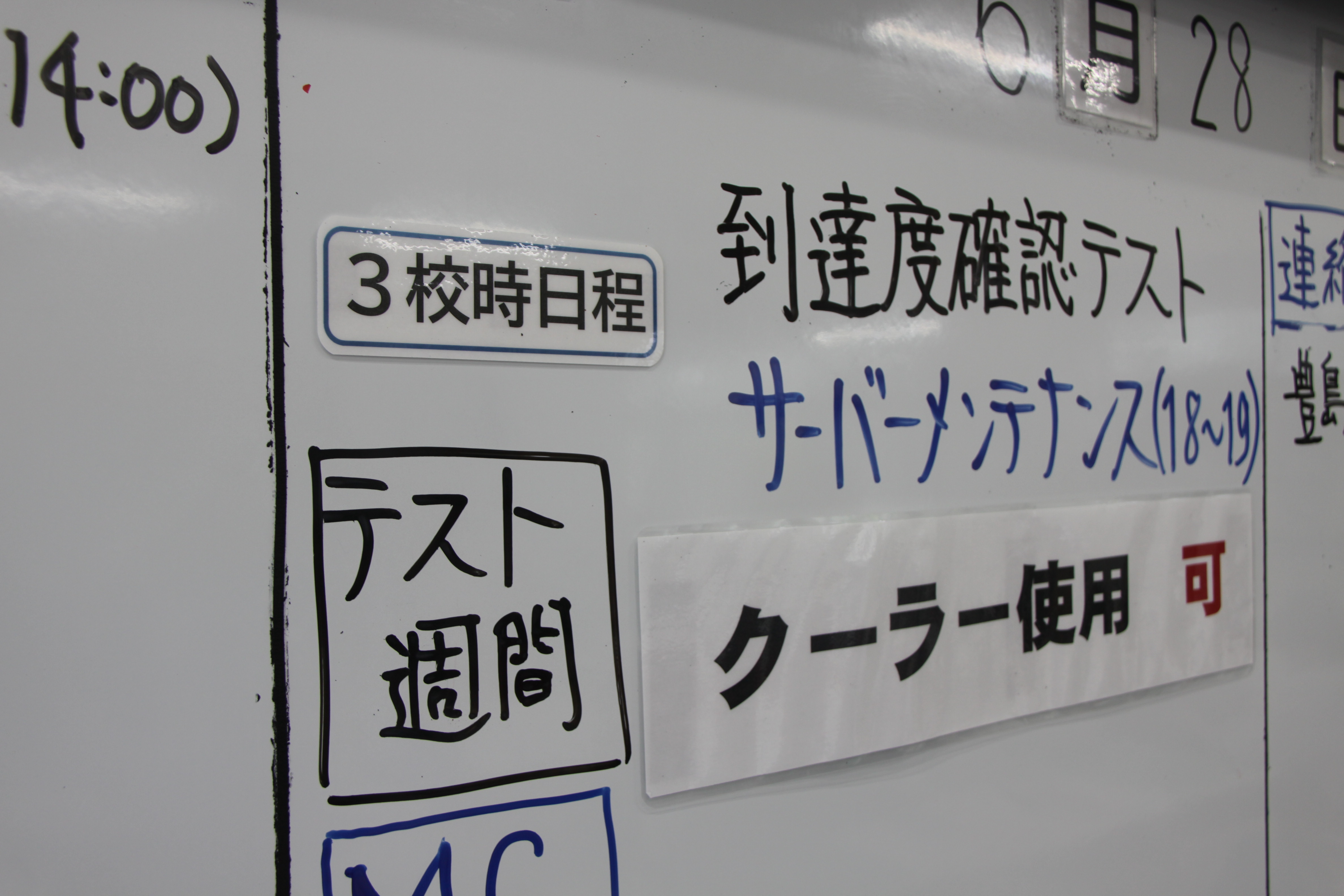
◎ひな中の風~~
「カギ忘れずにしようぜ!」
「安全・安心は自分の力で手にいれよ。」(6/27)
岡山県内中学・高校が校内駐輪場の自転車施錠率を競って防犯意識を高めることを目的とした県警主催の自転車鍵コンテストに今年度参加していますが、体育委員会は自転車の施錠チェックの取組(忘れている友達への声かけ等)を持続的におこなっています。
 頼りになる体育委員会
頼りになる体育委員会◎ひな中の風~~
「みんな おはよう!」 生徒会執行部 立つ(6/27)
明るい声で元気よく、気持ちのいいあいさつができることは重要。
たかがあいさつ、されどあいさつなのだ。
たった、これだけのことができるかできないかで人生は大きく変わる。特に、中学生や高校生ほど元気にあいさつをすることで印象は大きく変わる。先生の知っている企業で働いている営業担当を思い出すと…成果を上げている営業担当のNさんは、とても気持ちのよい挨拶をしている。逆に、成果が上がっていない営業担当さんはどうだろう。成果が上がっていない担当さんは、自信をなくし背筋が曲がっているはずだ。これでは悪循環だ。うまくいってないときほど声を出すこと(元気にあいさつをすること)で、自分の気持ちも高まる。積極的にあいさつをすることを意識してみよう。自分が変われば見える景色も変わる。生徒会執行部の朝の「あいさつ」声かけ、体育委員会のあいさつ運動で、ひな中の朝、そして「一日」は輝いている。

◎ひな中の風~~
わたしたちの学校を創る・よりよい生活を創る。(6/26)
専門委員会を開催し、活動の振り返りをしました。学級委員会では、これから利用するクーラーのルールの確認をしました。節電を意識して大事に使って、授業に取り組みます。生徒会執行部は皆さんからいただいたペットボトルキャップの集計をおこないました。体育委員会は球技大会に向けて準備を進めています。






◎一瞬の永遠
星輝祭体育の部の写真ネット閲覧注文ができます。ご利用ください。(~7/11(火)) *12日(水)に注文封筒(代金)を持参してください。

◎ひな中の風~~責任・誇り・絆 (6/23早朝)

◎ひな中の風~~
いっしょうけんめい いっしょうけんめい(単元テストに挑戦)(6/23)
この時期、各教科ごとで単元テストを実施しています。

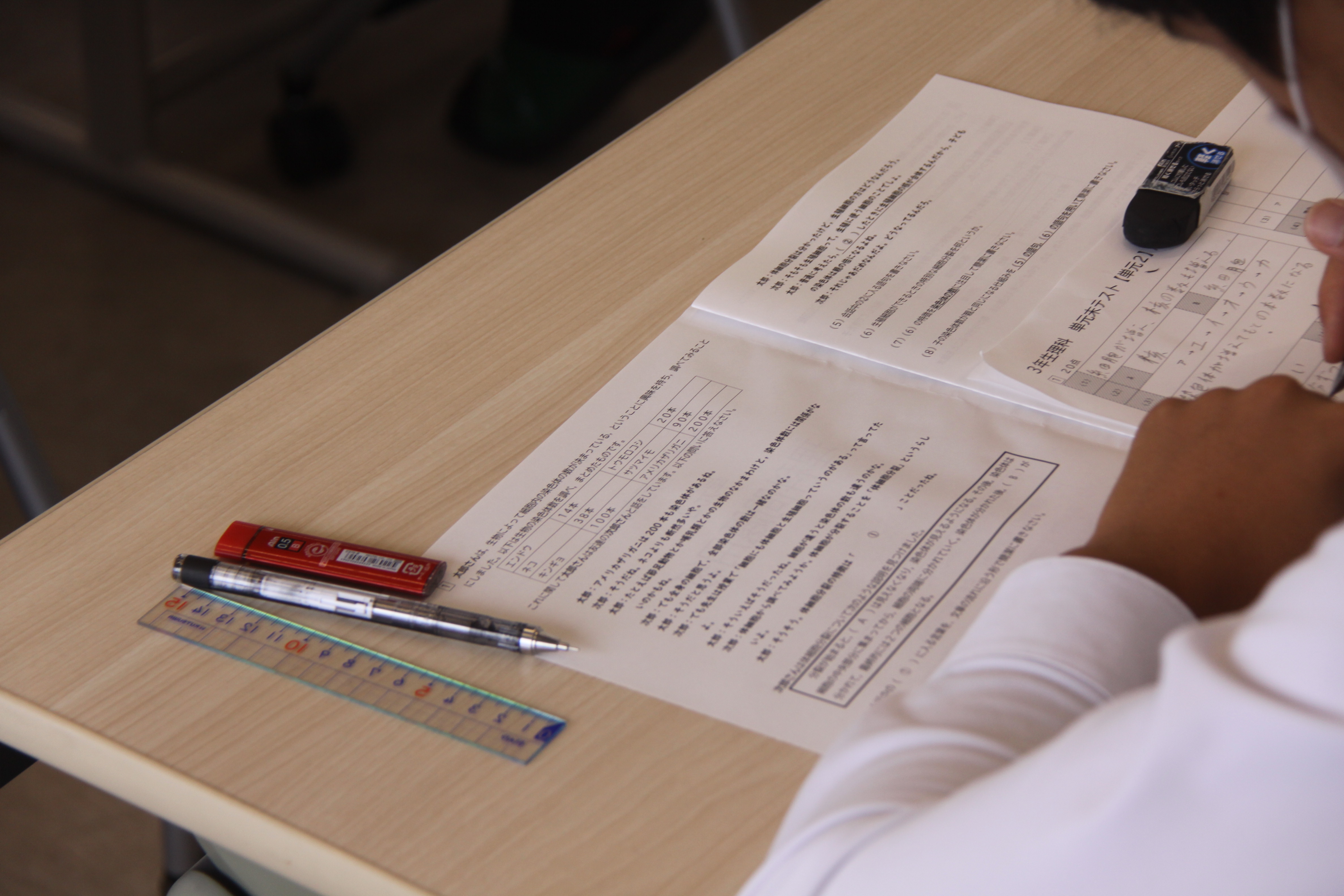
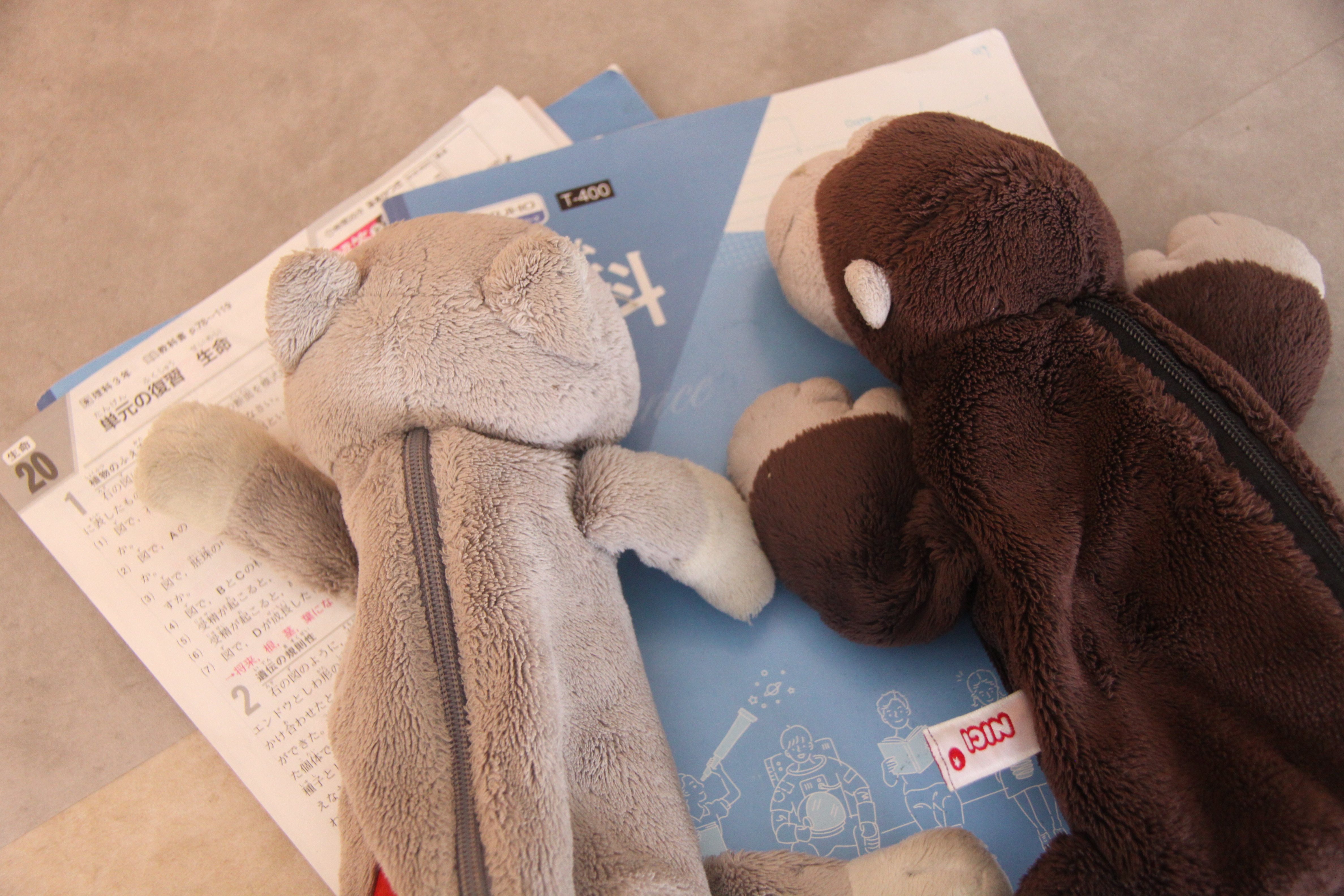
◎多くの人に支えられて(6/22)
学校薬剤師さんが来校され、学校環境衛生検査をしていただきました。ありがとうございました。
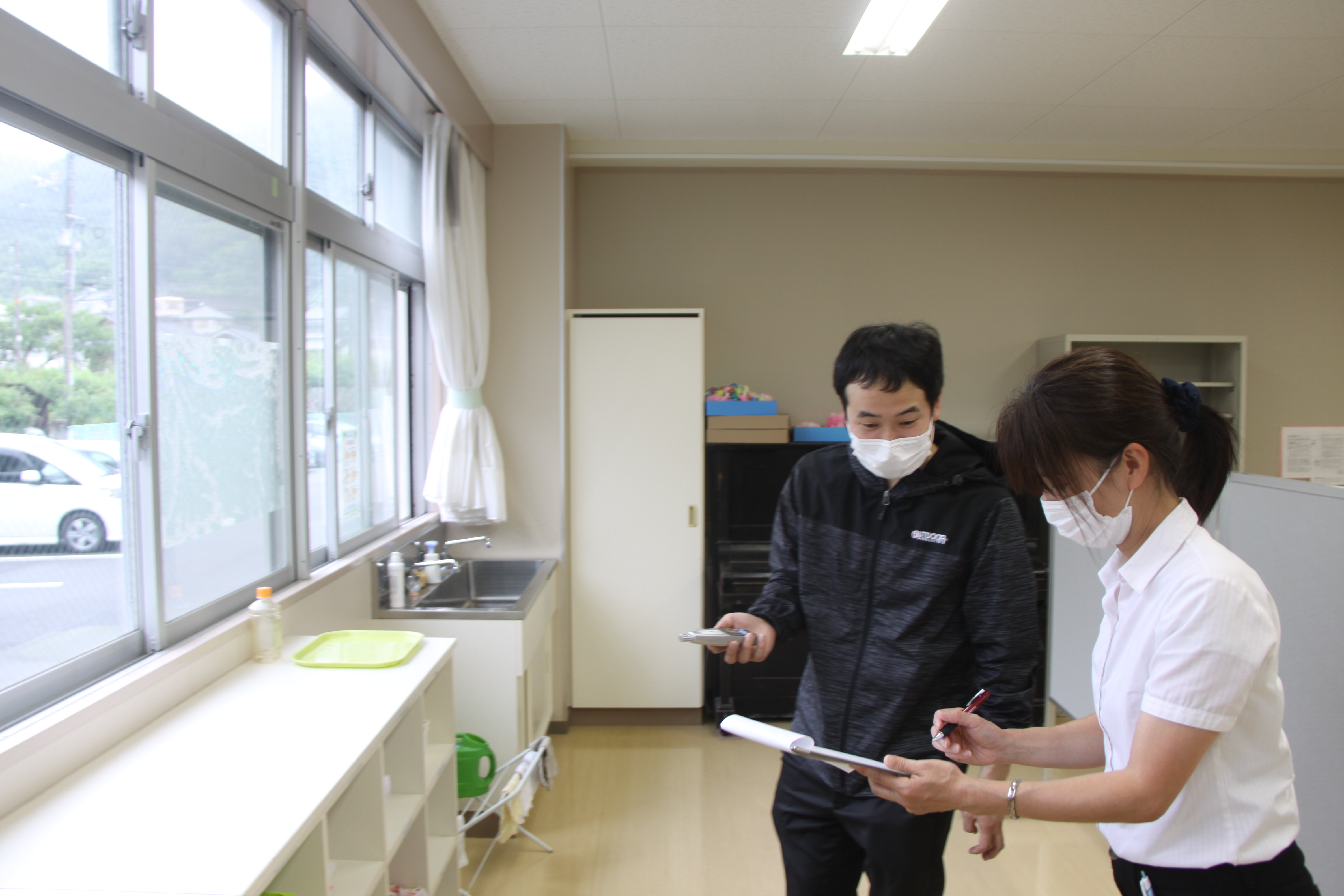
◎第1回学校評価アンケートを配付しました。(6/22)
よりよい学校づくりのためにご協力をお願いします。今年度はQRコードでの回答【推奨」ができるようにしました。〈写真は学校生活のようす〉
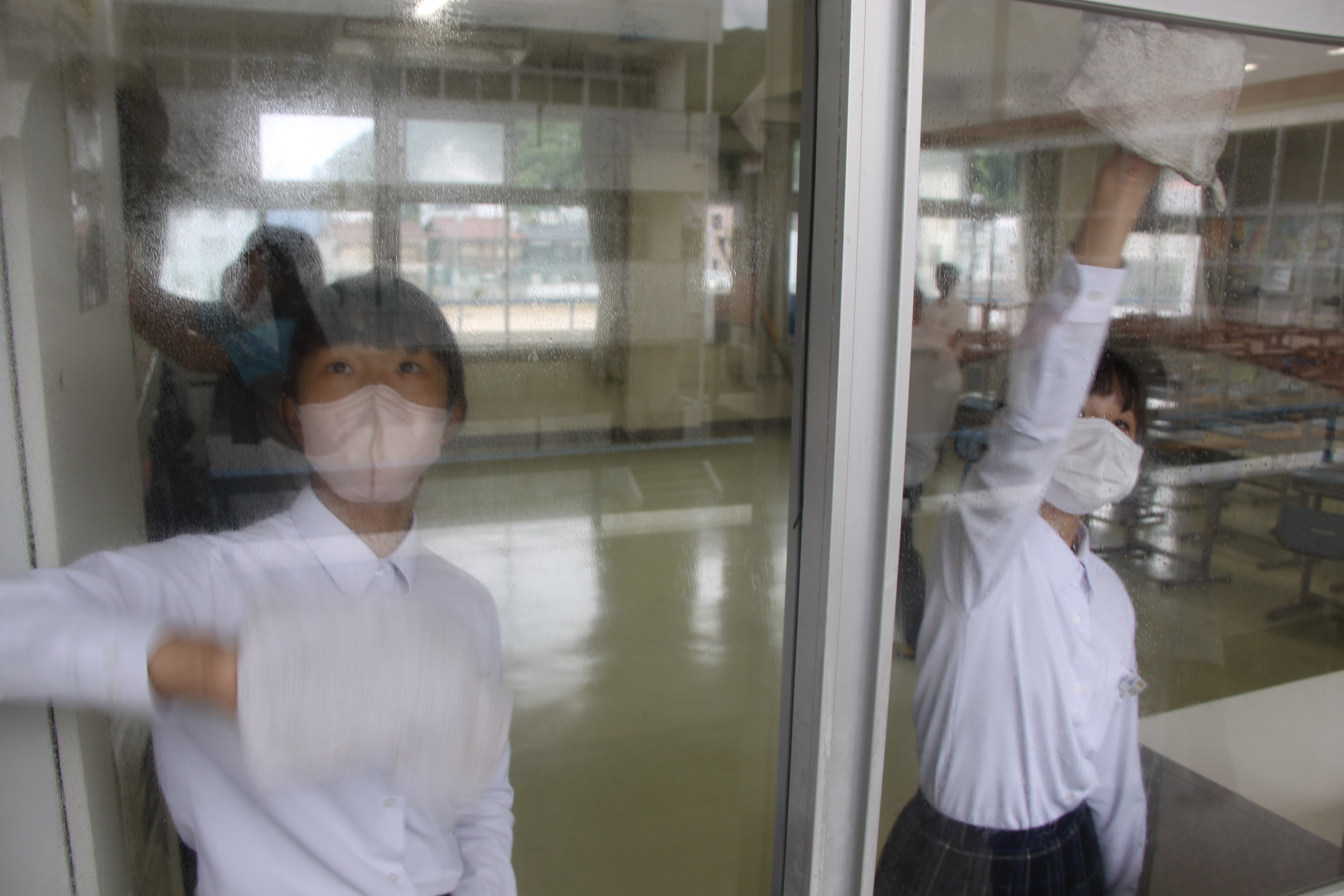




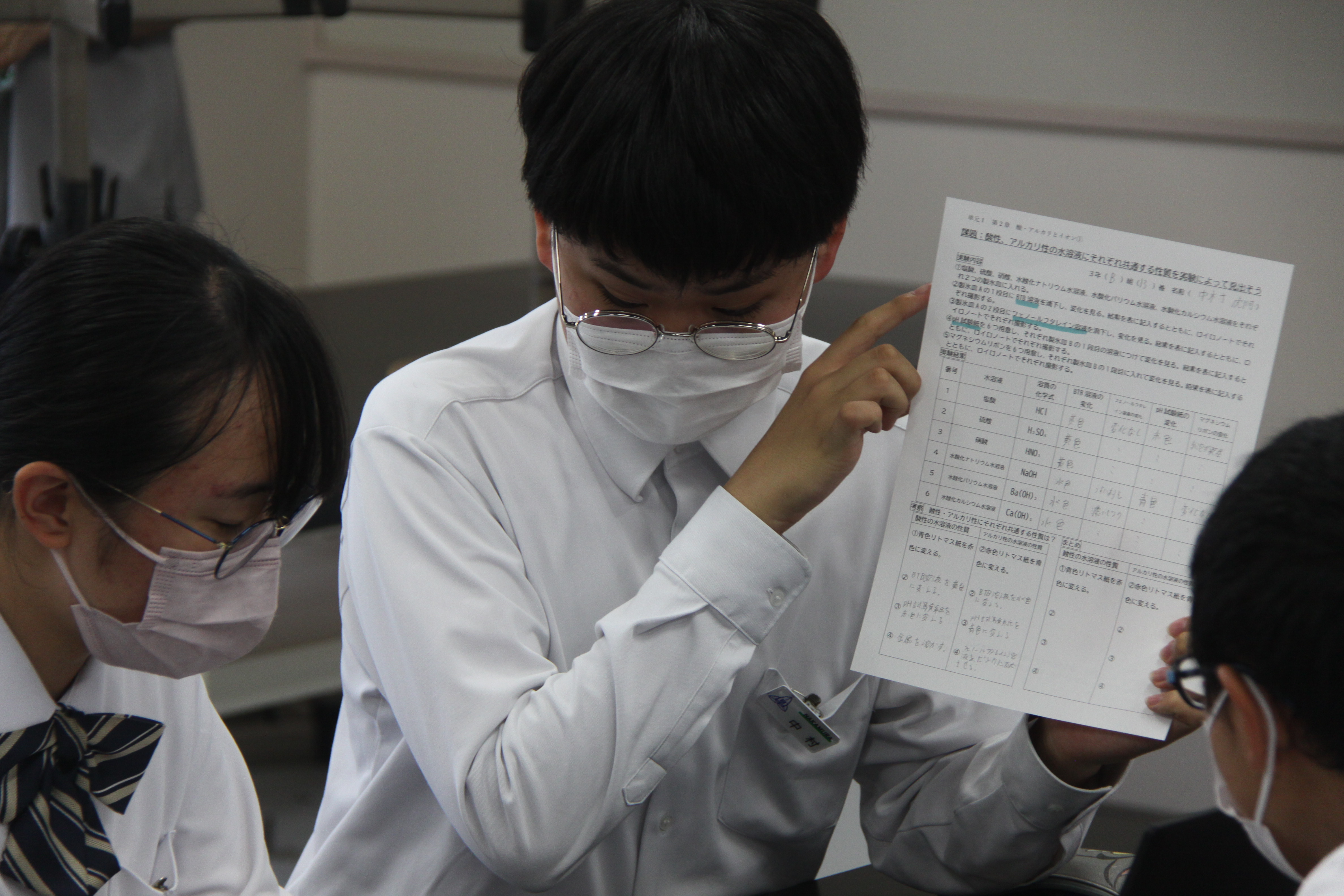


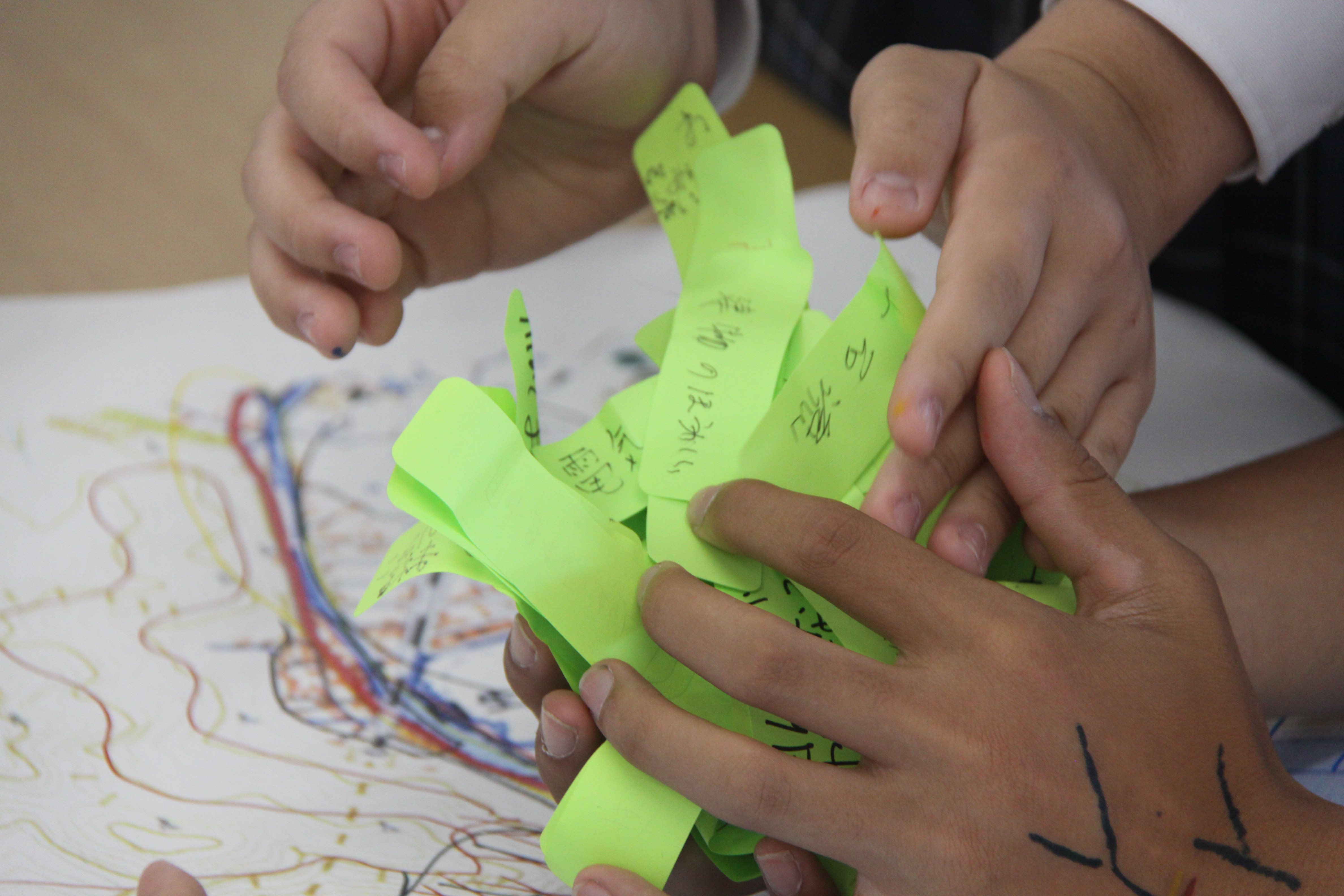
◎地域とともにある学校へ ~自分らしくせいいっぱい~(6/22)
継続的に、備前焼体験をもとにした学習に取り組んでいます。作品は第14回岡山県子ども備前焼作品展に出展します。





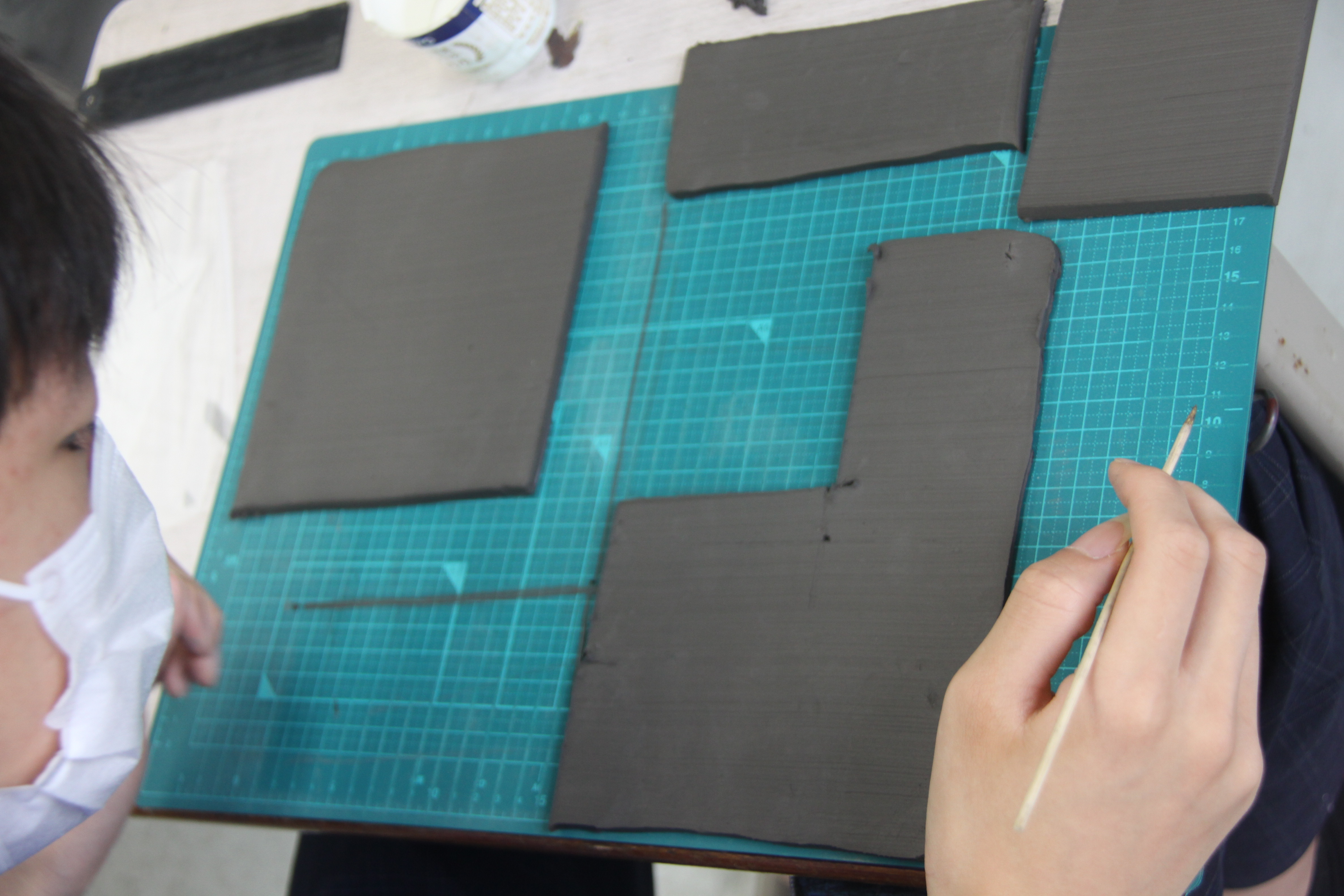
◎わたしたちのまち 生きる くらす つくる
~地域とともにある学校へ~
備前県民局さんをお招きした「備災」の授業(2年生社会科)をもとに、作成した日生地域ハザードマップを掲示しています。7月には、地域公民館に展示していただきます。
これからも地域の方をお招きしての学習や、地域に出かけて行っての活動に積極的に取り組んでいきます。地域での催し物やイベントなどの情報があれば学校にご一報ください。(o^―^o)



◎大切な時間を自分がつくる
到達度確認テストに向けてのテスト週間に合わせて、MC(メディアコントロール)週間に取り組んでいます。
また、学級委員会主催で「Grow UP Week」にもチャレンジ中です。(~6/28)
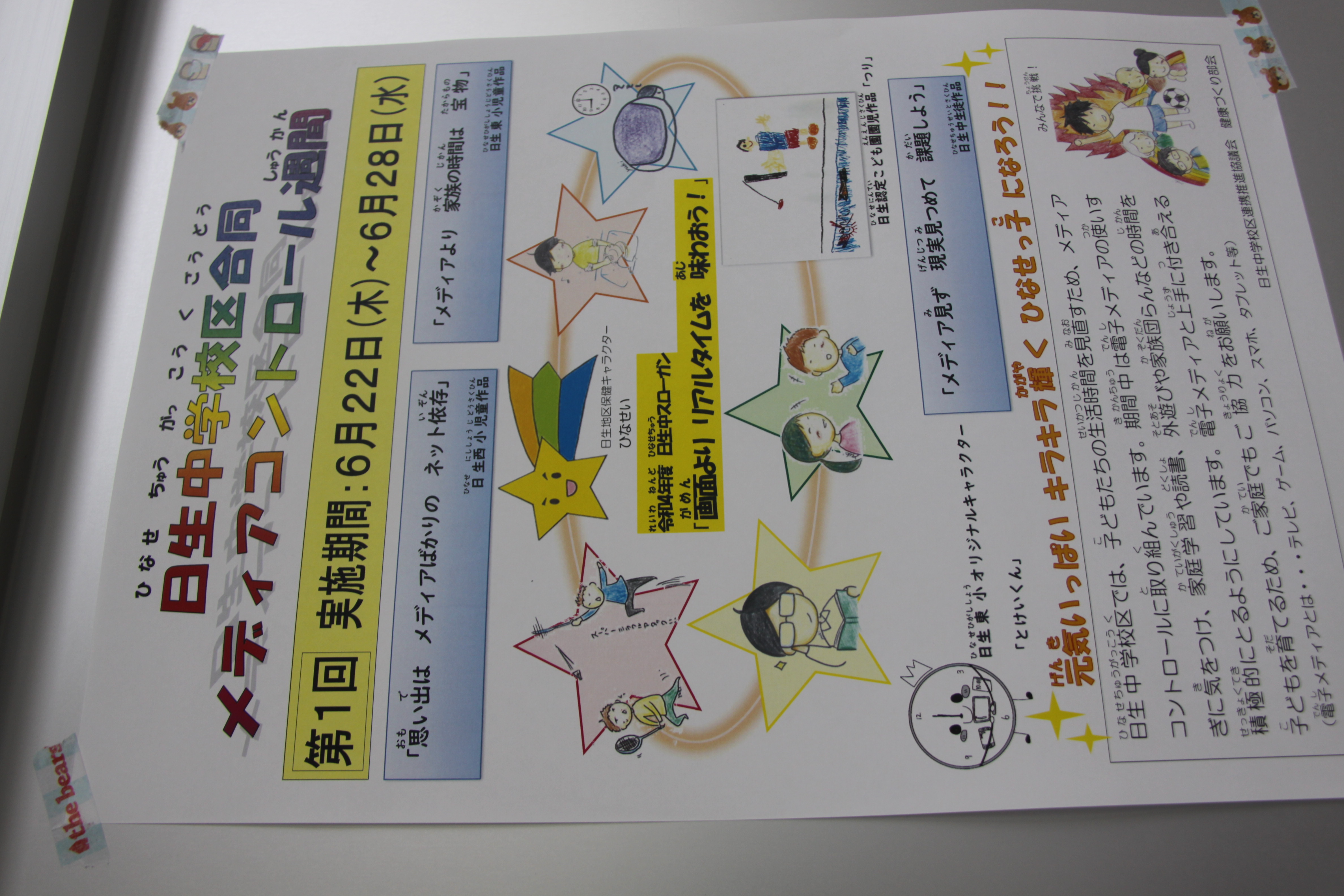
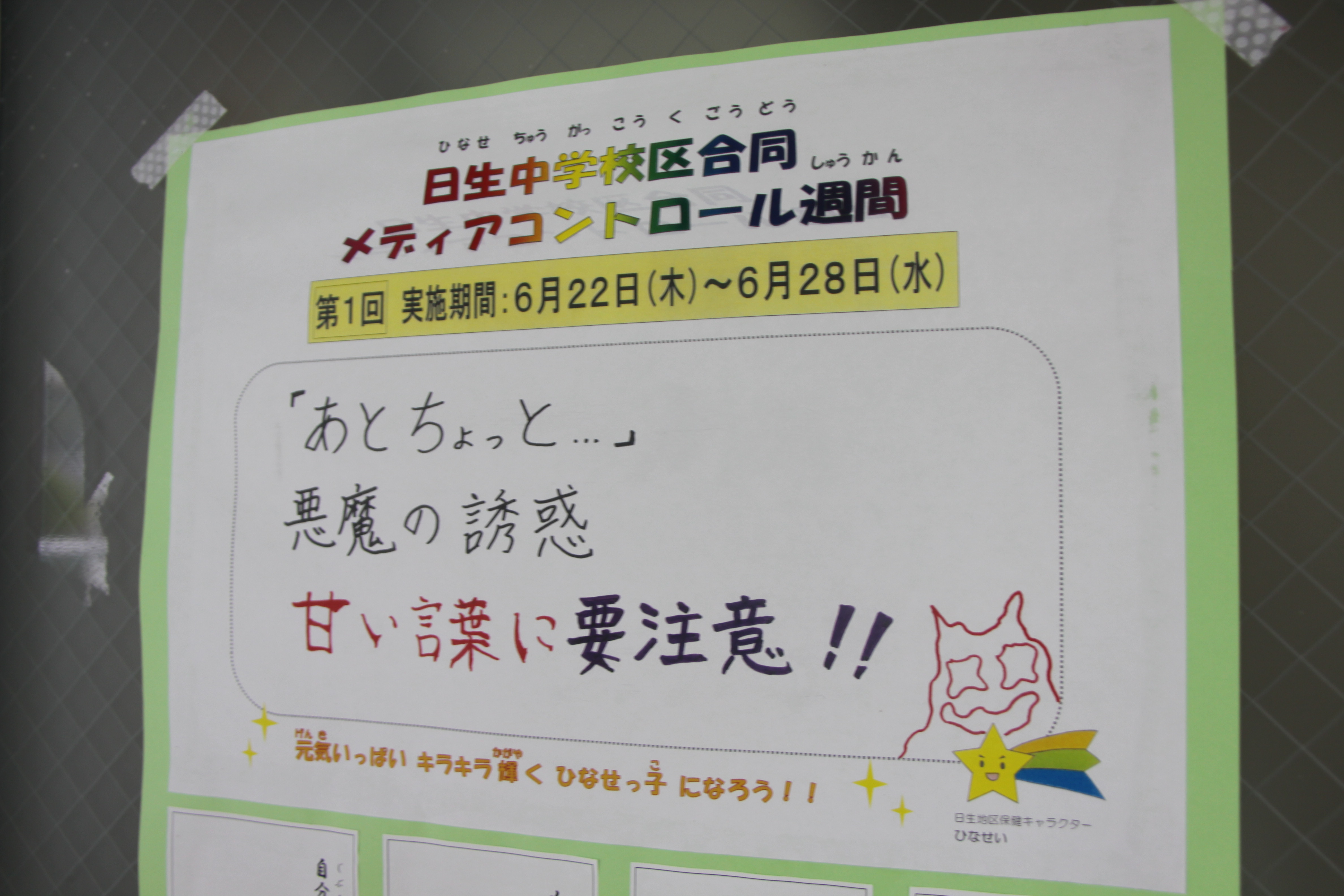
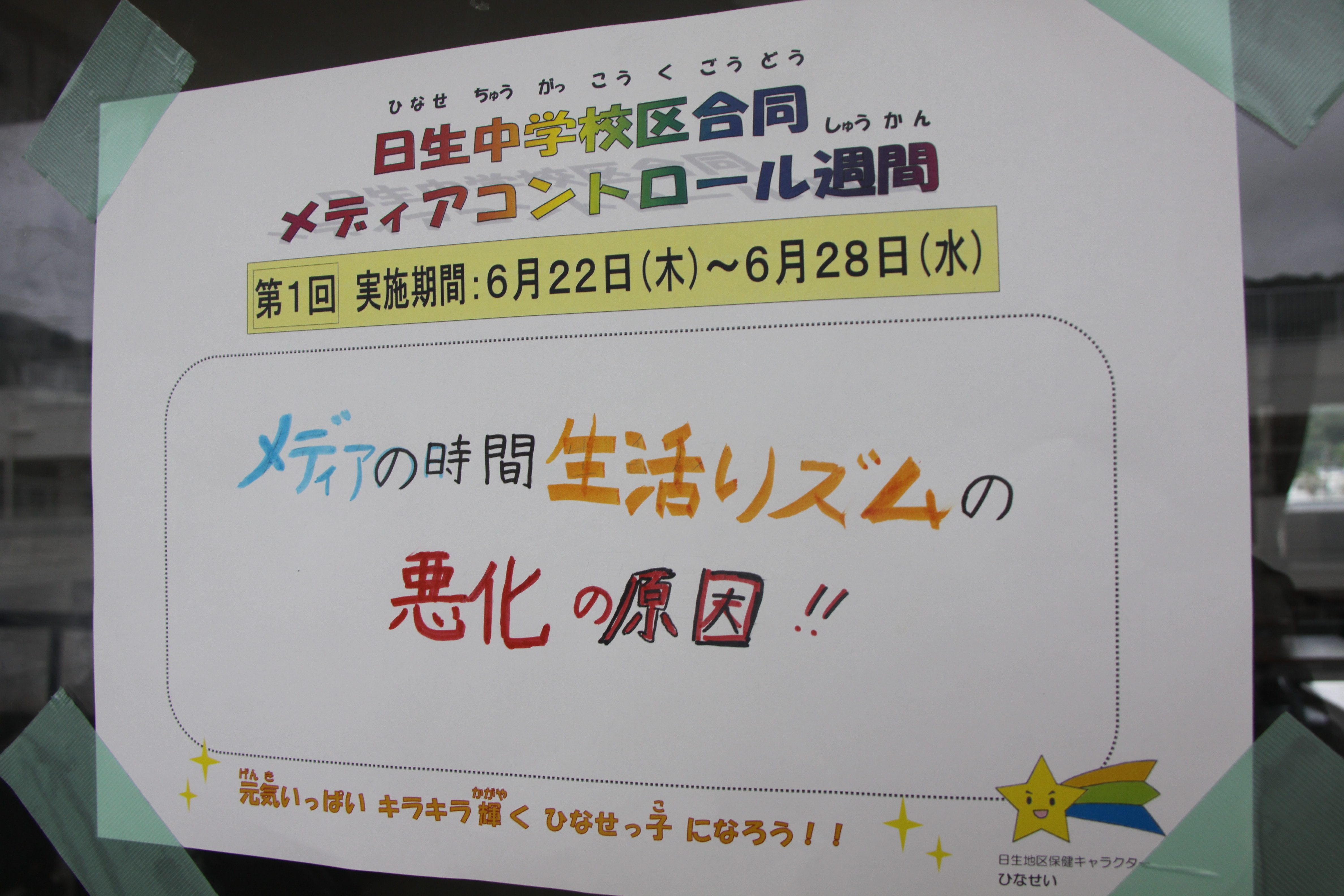
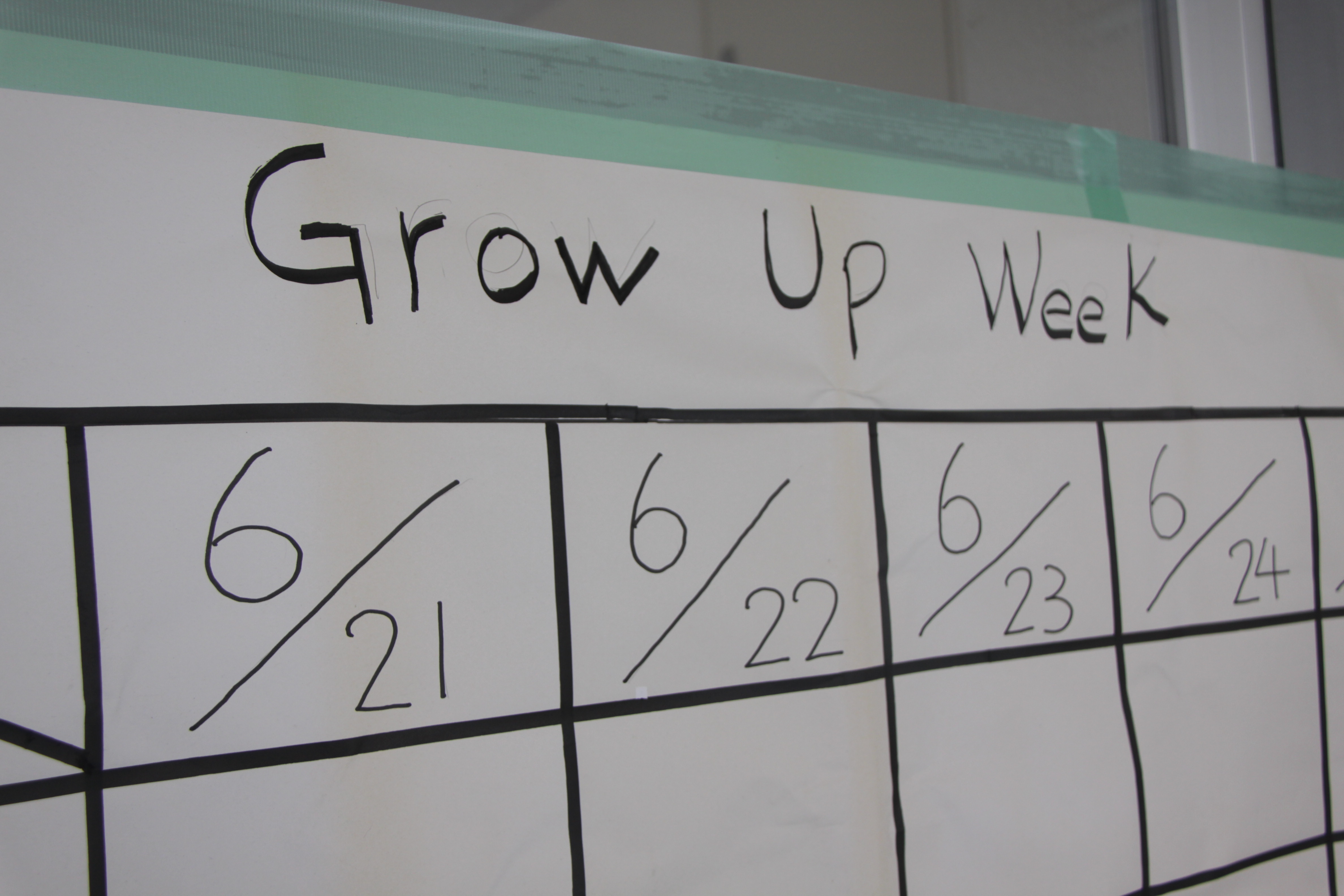
◎学び合う生徒に、先生たちも学び合います。園校内授業研修会(6/21)
研修会には、日生子ども園の先生も参加され、こ保小中連携についても話し合うことができました。
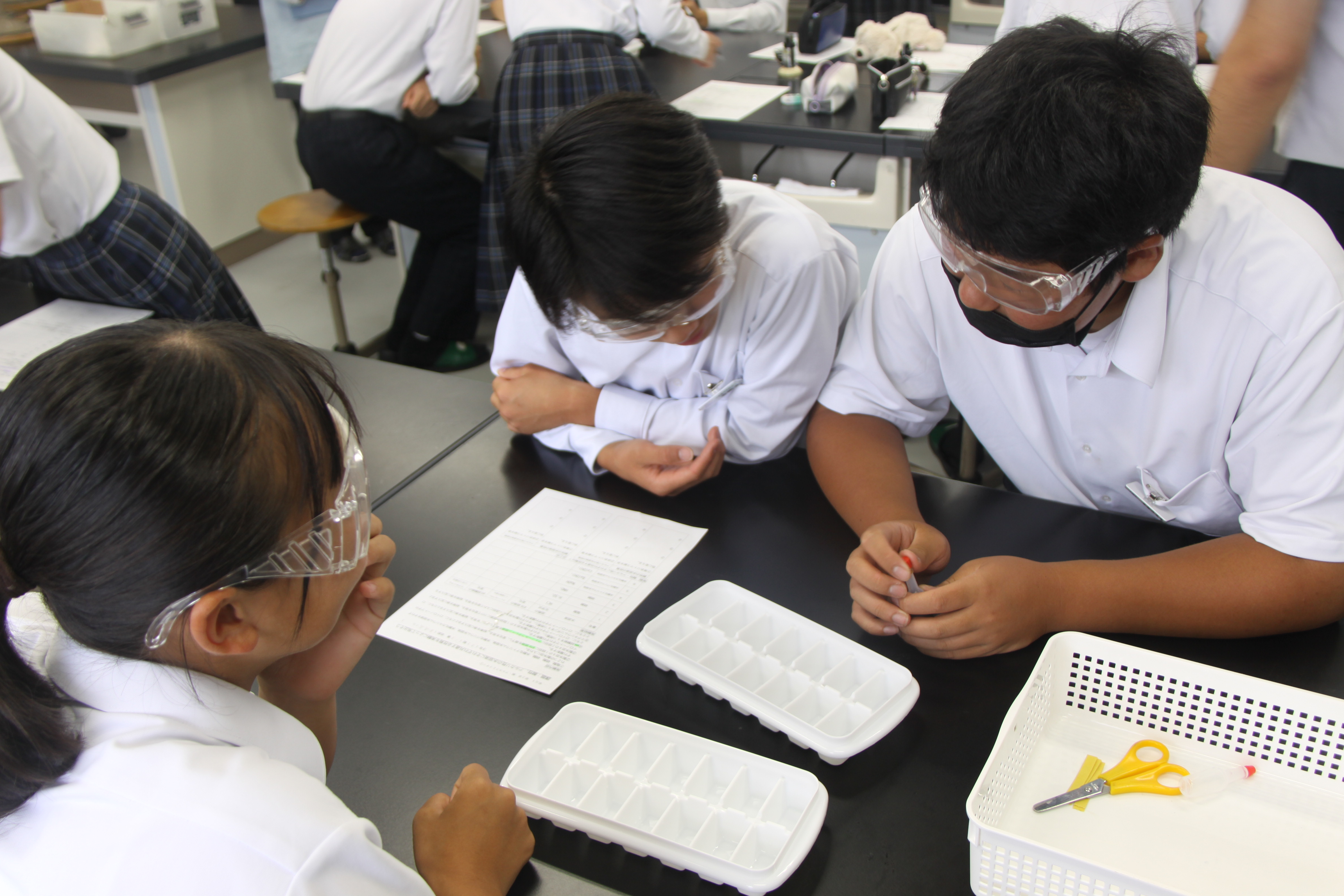


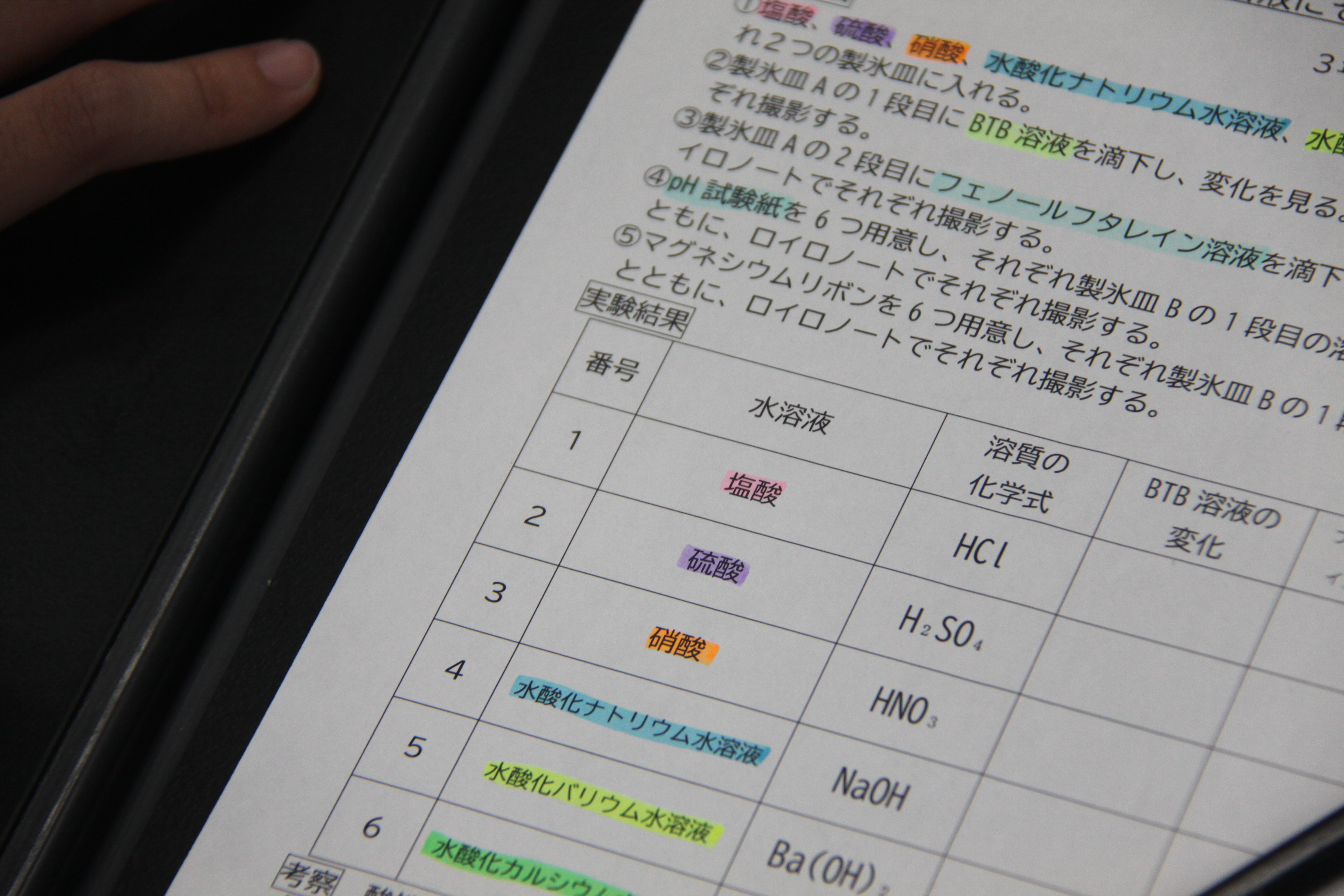
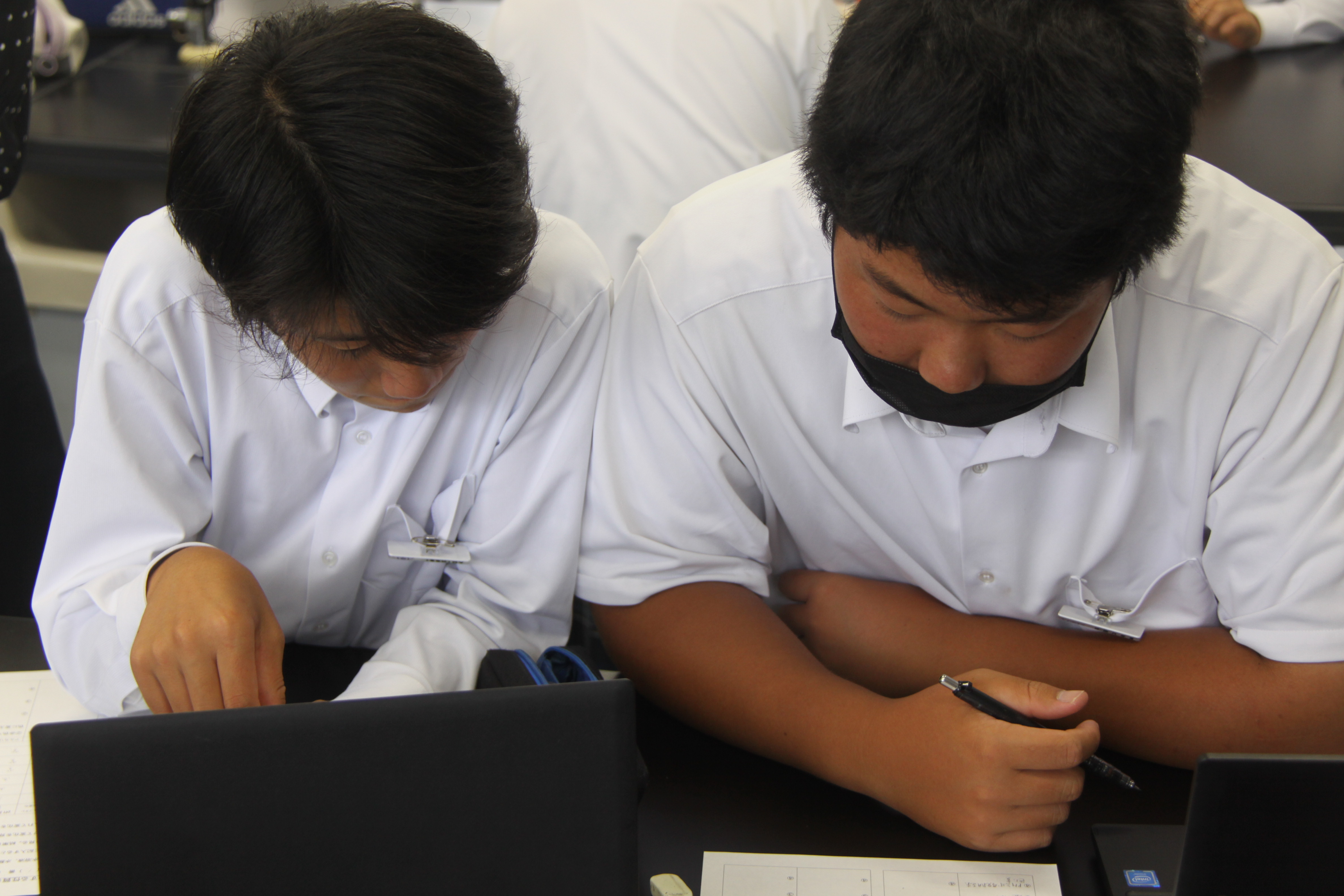
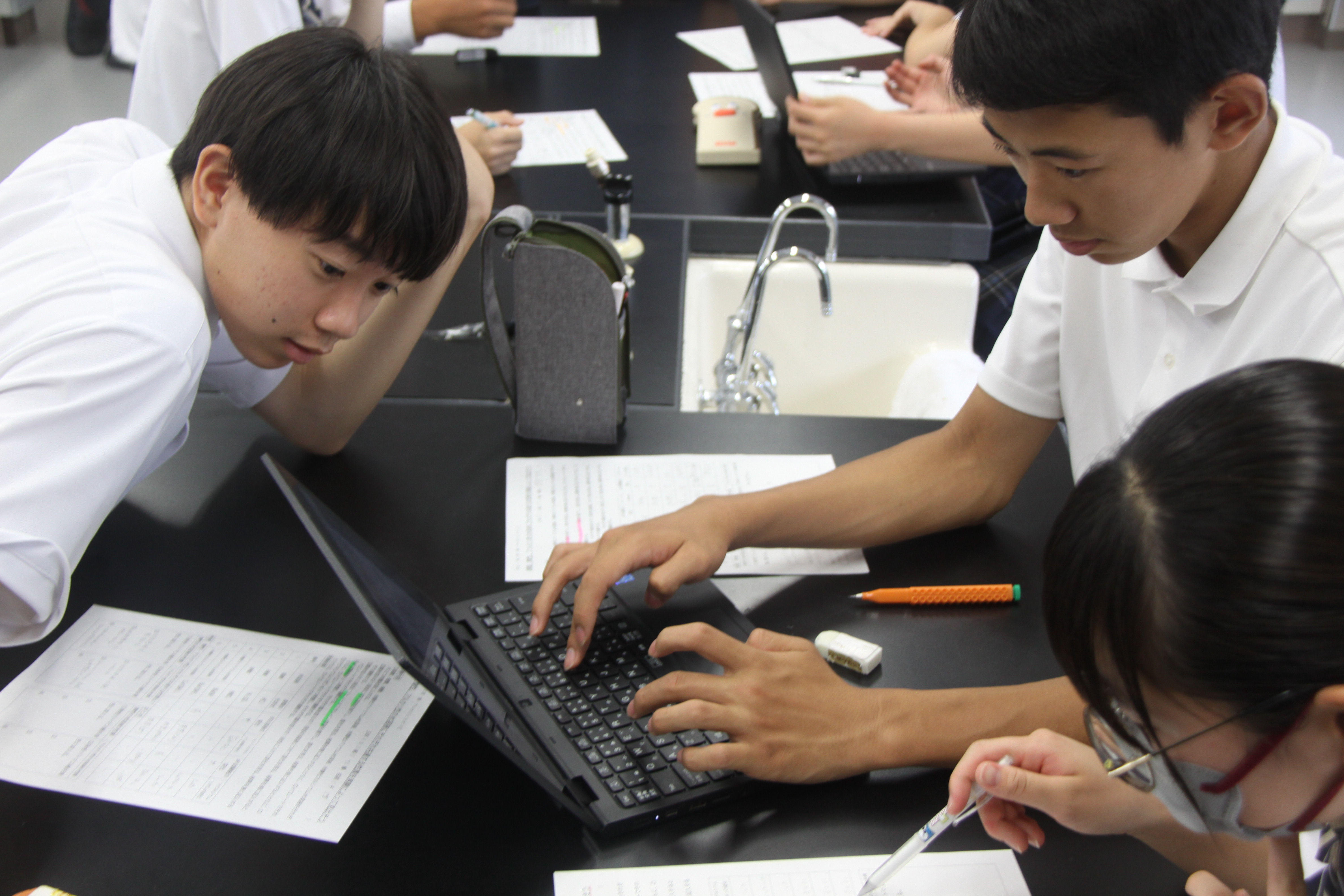



◎夢にむかってたくましく生きるために(6/20)
岡山教育事務所から石田・久戸瀬先生が、「管理職のビジョンと戦略を支援する学校訪問」に来校されました。学校経営アクションプランを中心に、多角的に協議することができました。(*アクションプランとは、学力向上のみならず、学校が抱える課 題の解決や特色ある学校づくりの実現に向けて、1年間を通した道しるべとなるプ ランです。 学校教育目標を達成させるために、現 状を把握し、課題が焦点化されています。本年度の日生中学校の重点目標は「自ら進んで学習に取り組む意欲と実践力を持つ生徒」と「社会と積極的に関わり、より良い社会を築こうとする生徒」になってほしいことを重点目標にあげています。)
両氏には、授業を参観をもとに、授業力向上に向けての貴重な意見をいただきました。前向きに授業に取り組むひな中の生徒の意欲をこれからも大切に、「主体的に学ぶことのできる」授業や取組を創っていきます。


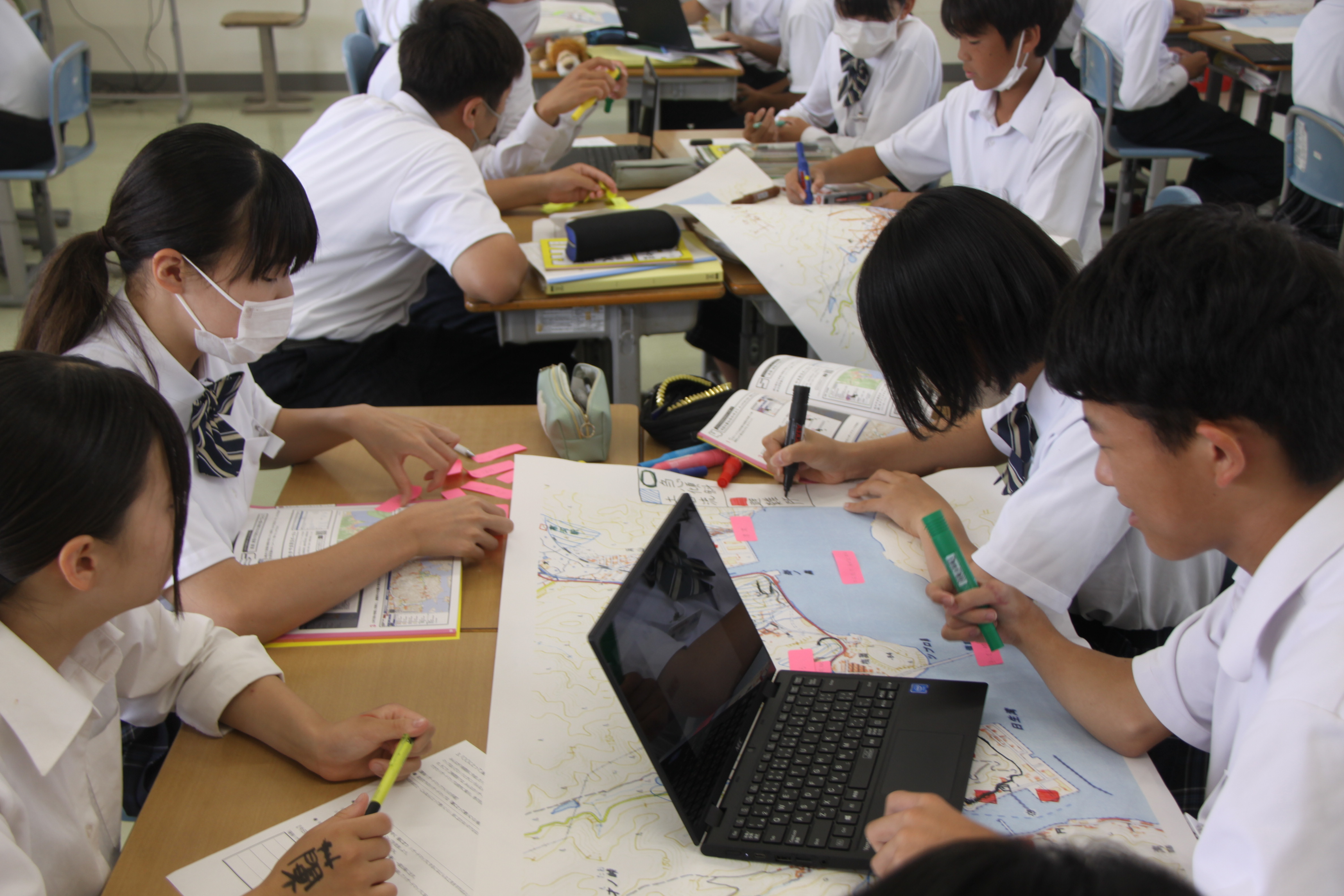

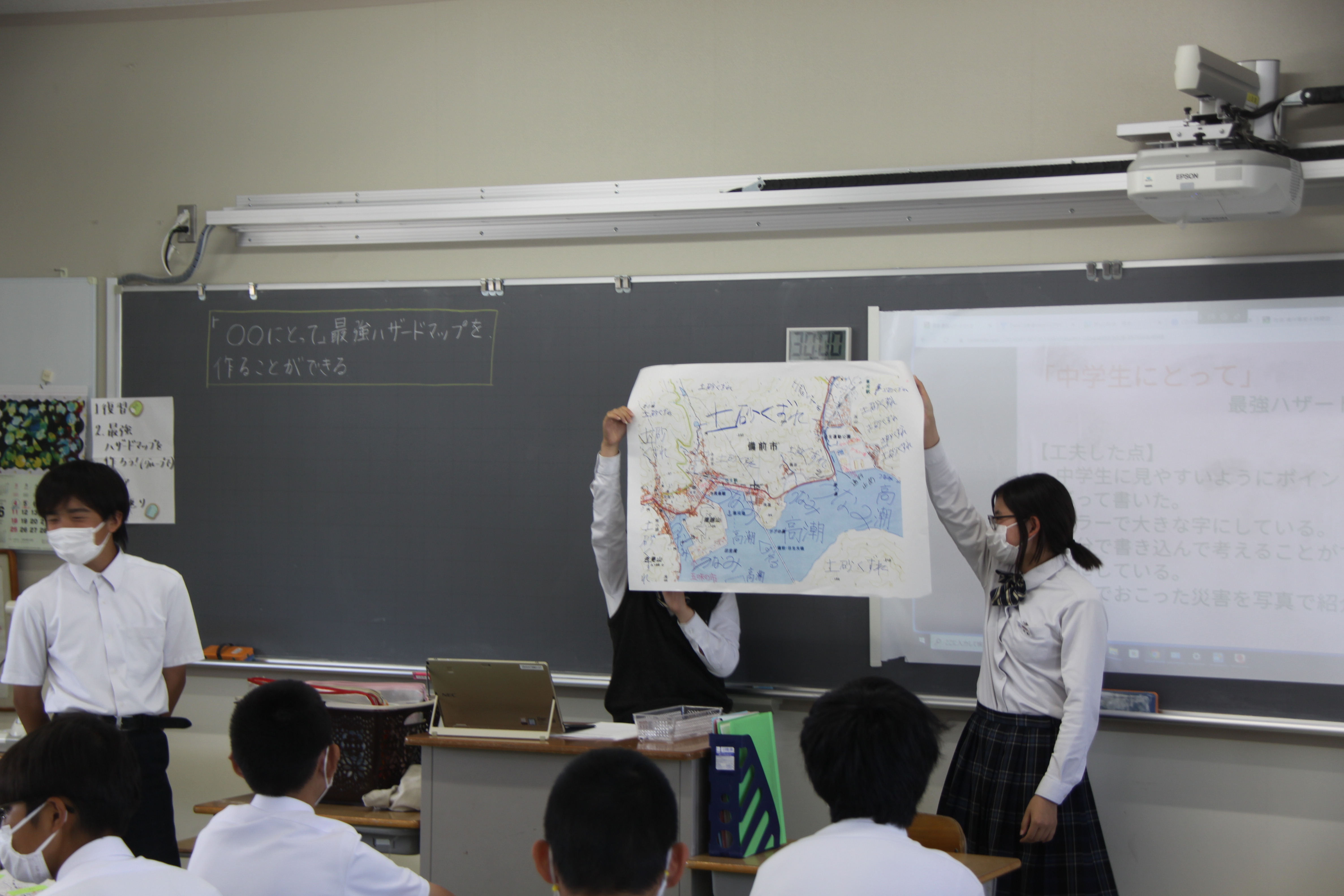


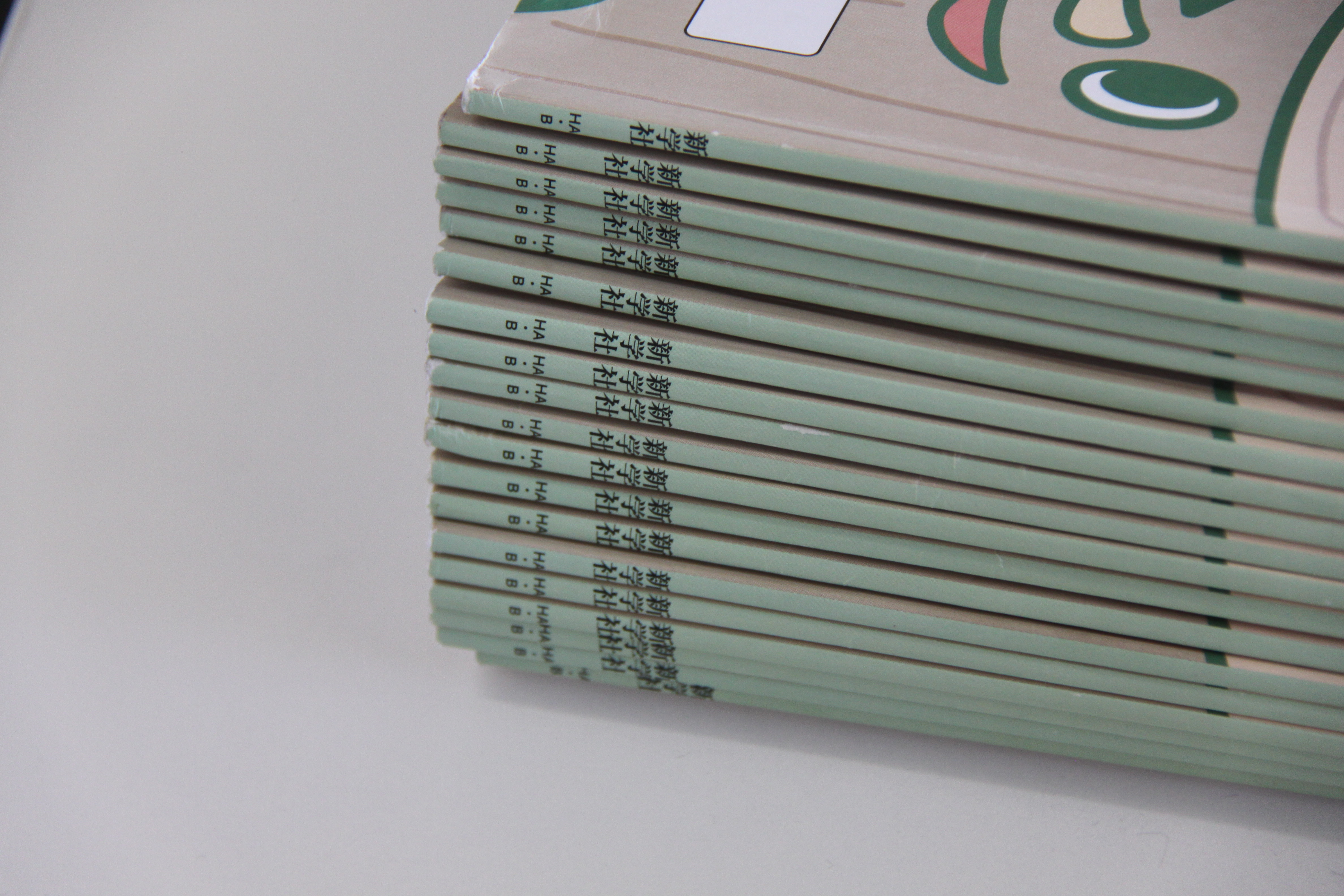

◎ひな中の風~~多くの人にささえられて
たくさんの応援・たくさんの激励・たくさんのサポートをありがとうございました。
これからも、ひとりひとりが、仲間とともに、一歩一歩進んでいきます。



◎ひな中の風~~
明日から備前東地区総合体育大会・岡山県中学校吹奏楽祭、それぞれの7月19日・20日。








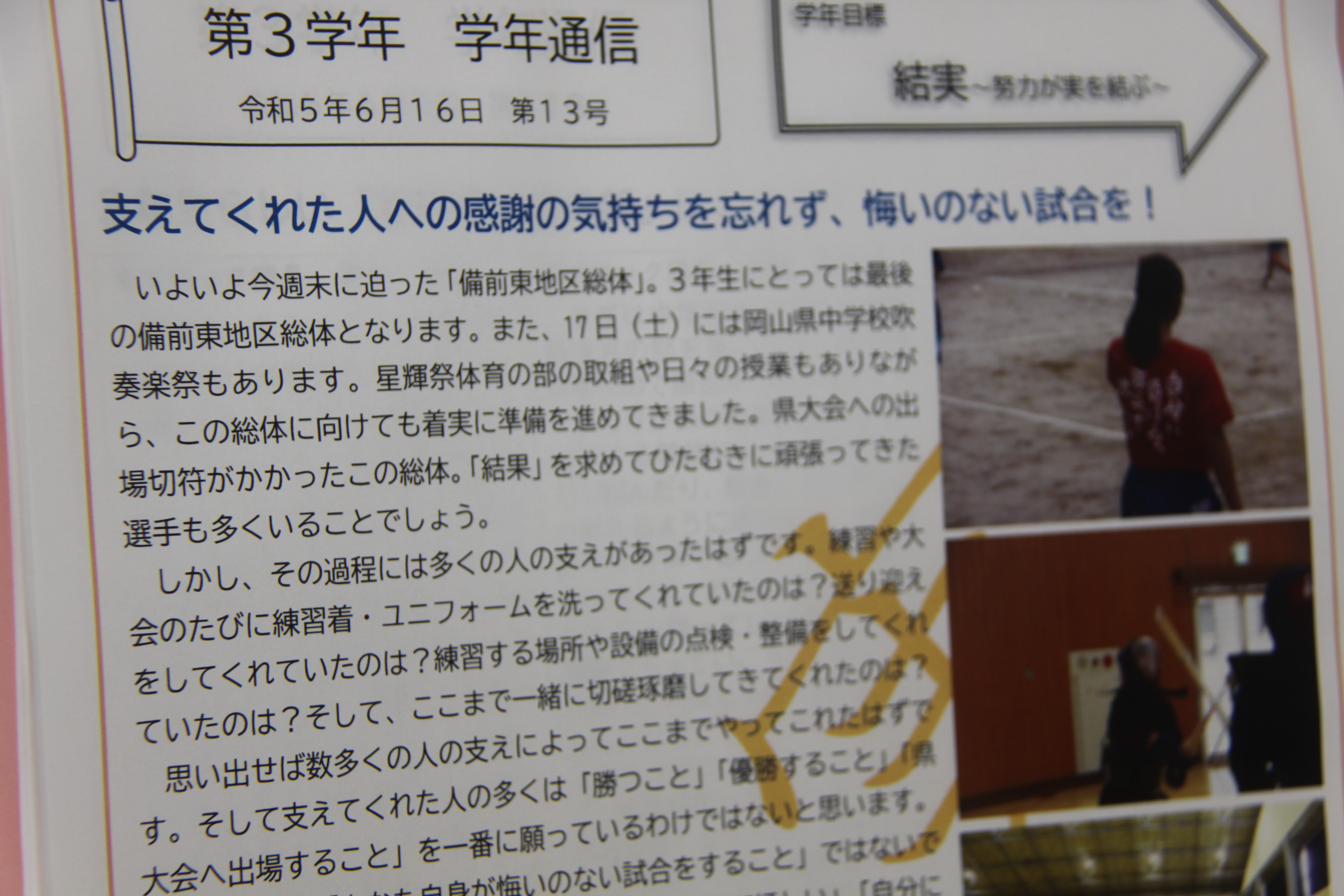
かまち、
おまえは 人に好かれるか好かれないかと言うことで、
生きているはずではなかったはずだ。
おまえは、生きる。
ただ、自分の生き方を貫く
それひとつだけのために、
おまえは裸
たったそれだけ、おまえの心しかこの世にはない
おまえの生き方を貫く
消えるまで、生命が消えるまで
すべての力を出し切って、生ききる
それがおまえの生き方だ。
おまえの生き方を貫け
それは意地ではない
美しさだ
今までは人の言うことを聞きすぎた
みじめな気持ちになり
仲間が欲しくなり
ろくでもないヤツを仲間だと思い込む
それからおまえが崩れていく
かまち
おまえを おまえは自分をもっと大切にしろ
激しく美しく生きろ
見せかけや、その時のいくじなしなみじめさは
激しい美しさ、真の叫びこそが美しい
くだらん連中に妥協するな
おまえにはおまえがある
人のことを考えず 自分の生き方を貫け
輝く激しさだけを信じろ
今を信じろ
自分を信じろ
ただ燃える一本の声明を信じろ
おまえは美しい
変わることのない偉大な真実だ
人に悲しまされるな
物事に悲しまされるな
おまえは生きることを生きろ
おまえは再び生きることをつかめ
おまえは眠っていた
それを揺り起こして
さあ、再びおまえを生きるんだ。
再びおまえを
妥協は敵だ
おまえはおまえしかないのだ
おまえがおまえでなくてどうする
おまえは生きることを生きろ
昔を思い出せ
この詩を書いたとき、作者山田かまちは17才でした。作者自身が自分に語りかけ 叫び続けた詩です。高校受験に失敗して中学浪人、失恋や仲間とのいさかい・・・。 自分が受け入れられない悶々とする思いを抱えながら、それでも自分自身を奮いたたせ、悩みや迷い、不安から立ち上がろうとする自分を鼓舞する詩です。若者には、誰にも困難を克服する力がある。
◎ひな中の風~~毎日がたいせつ
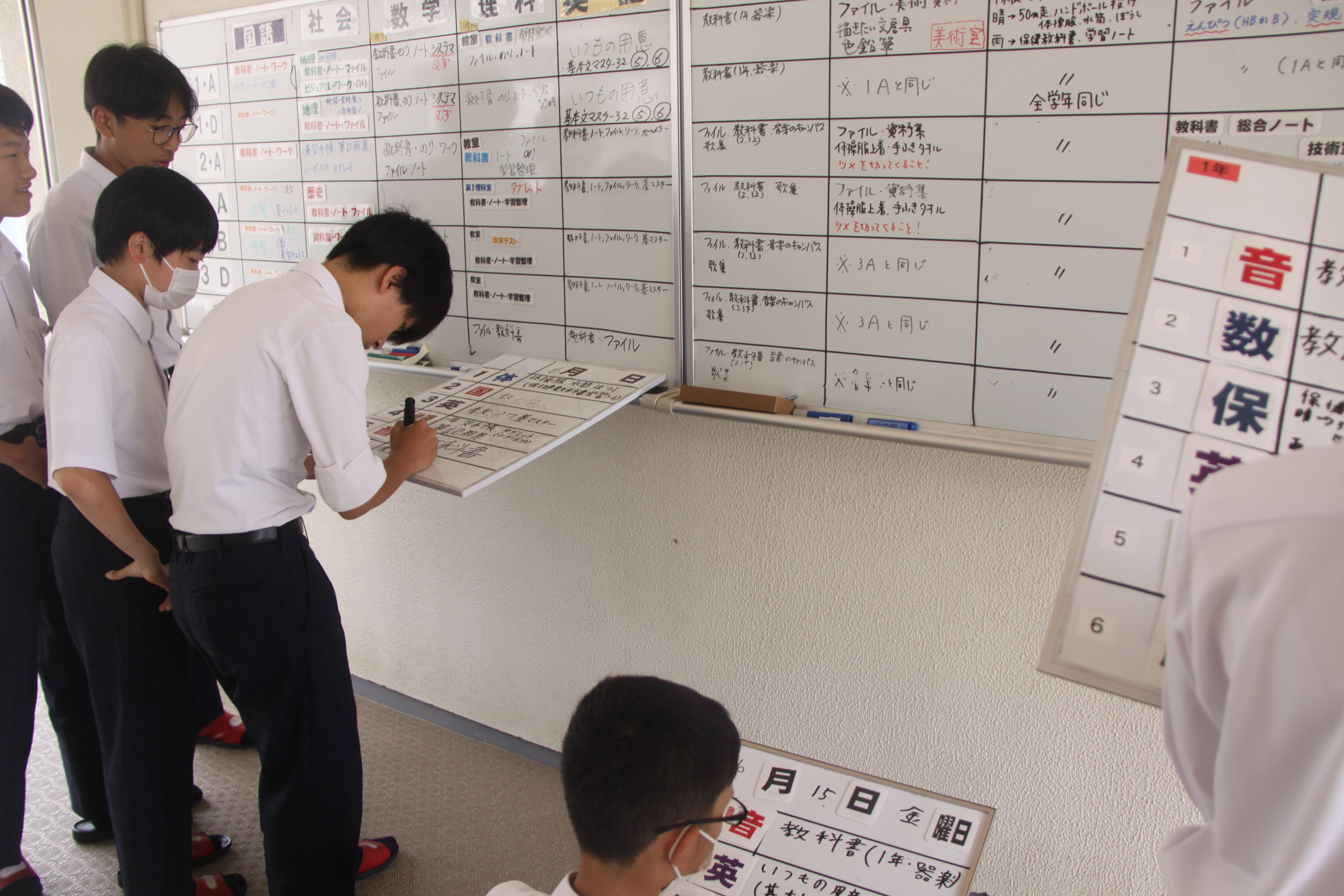
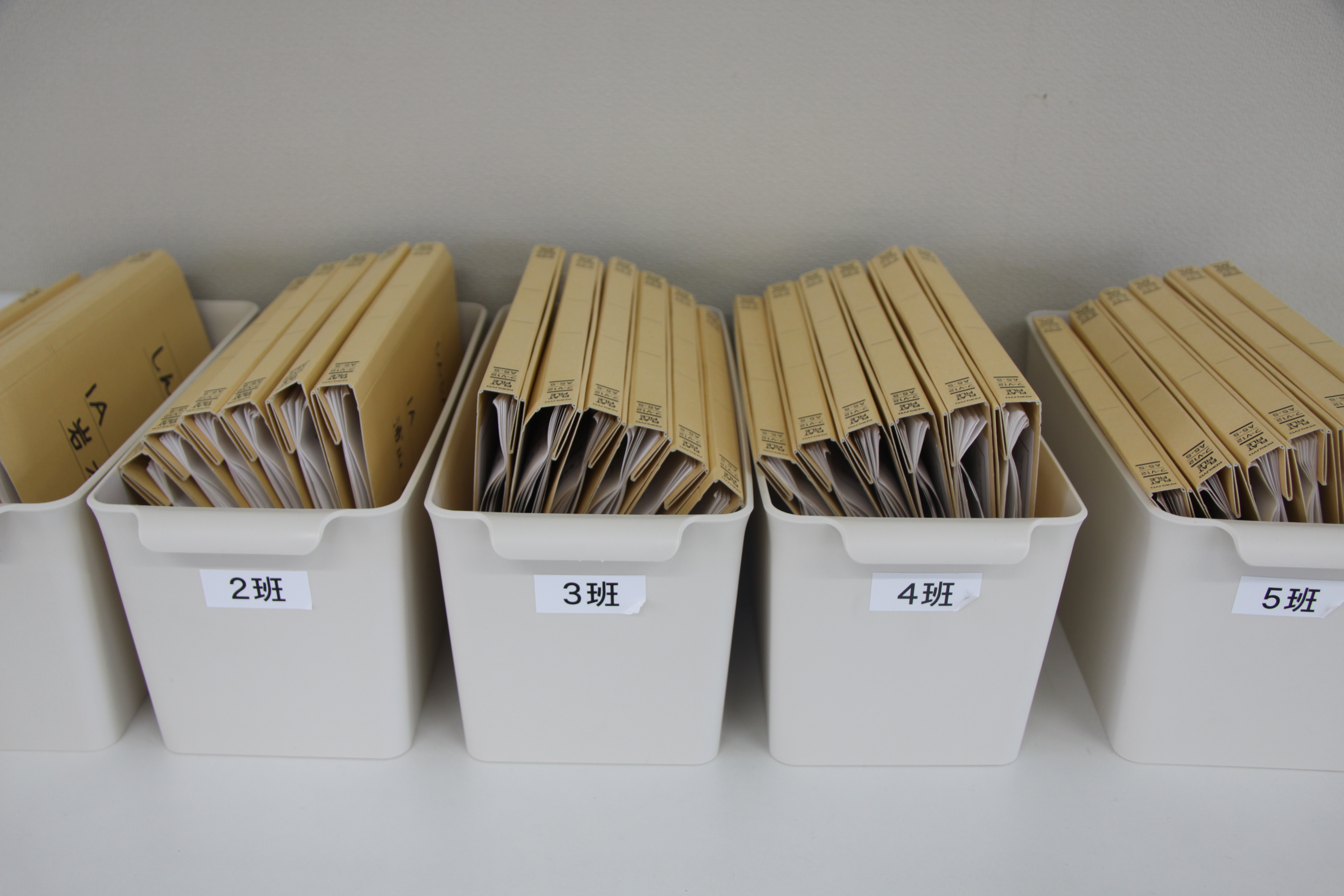

◎給食訪問(6/16)…「今日のお魚は?」「おいチヌ」(o^―^o)
「ごちそうさまでした」
共同調理場の北川先生が来校され、梅雨時期の食中毒の注意と、熱中症対策の水分補給についてお話をしてくださいました。





◎わたしたちのまち くらし みらい
防災 減災 備災 ~備前県民局八木さんをお招きして~(6/16)
2年生社会科(地理的分野)で、ハザードマップ作成をとおして、地域課題を見つめる学習に取り組んでいます。
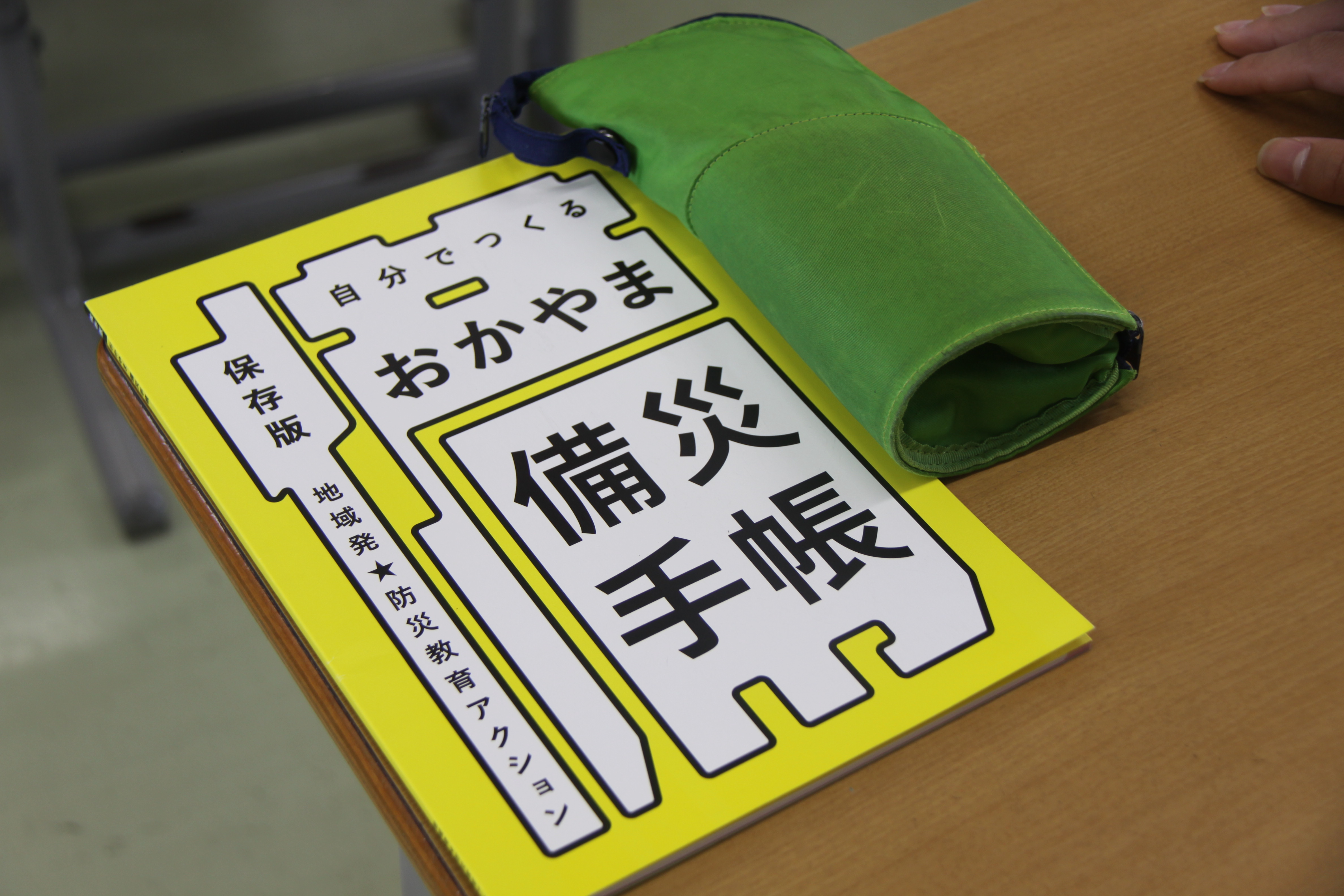

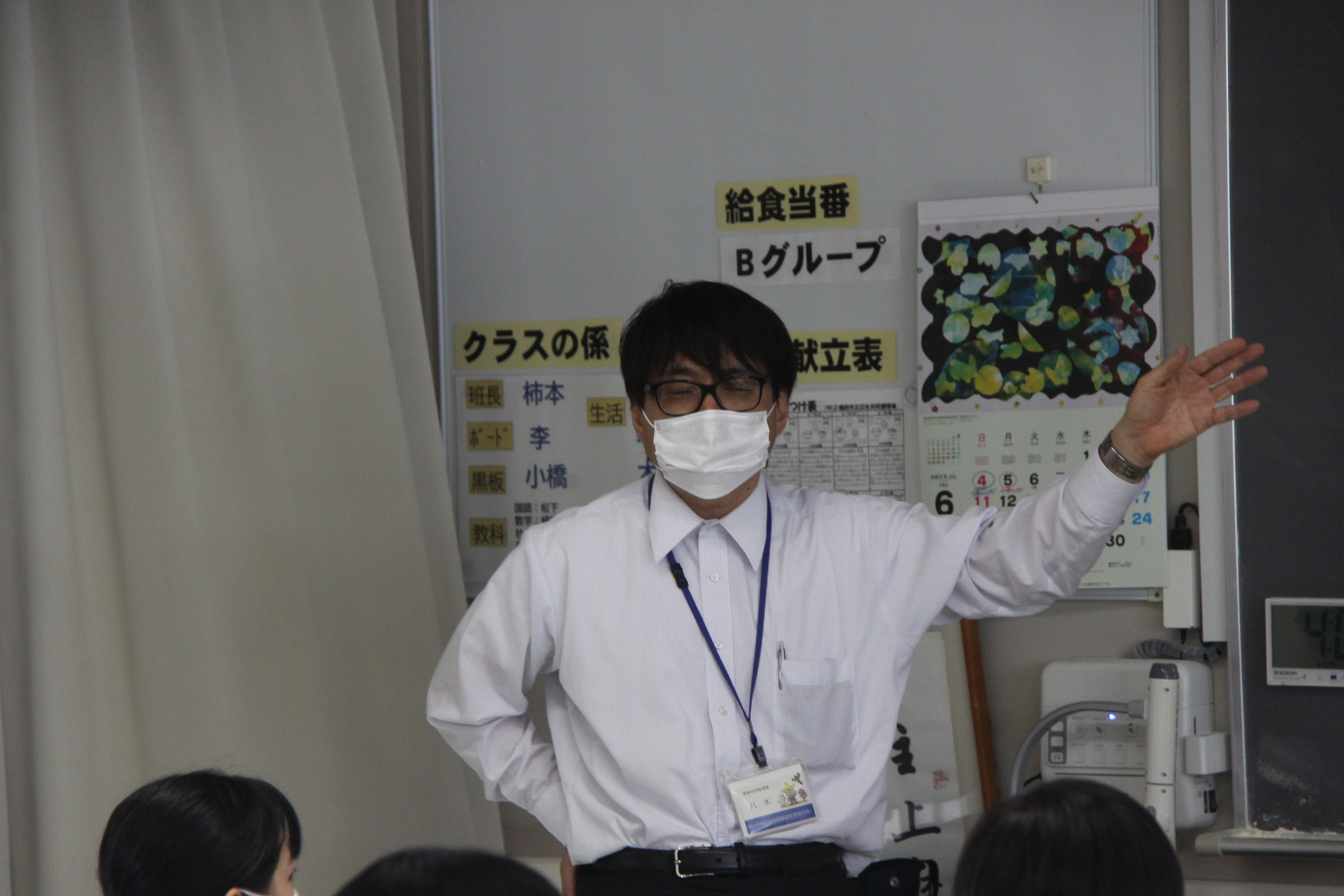
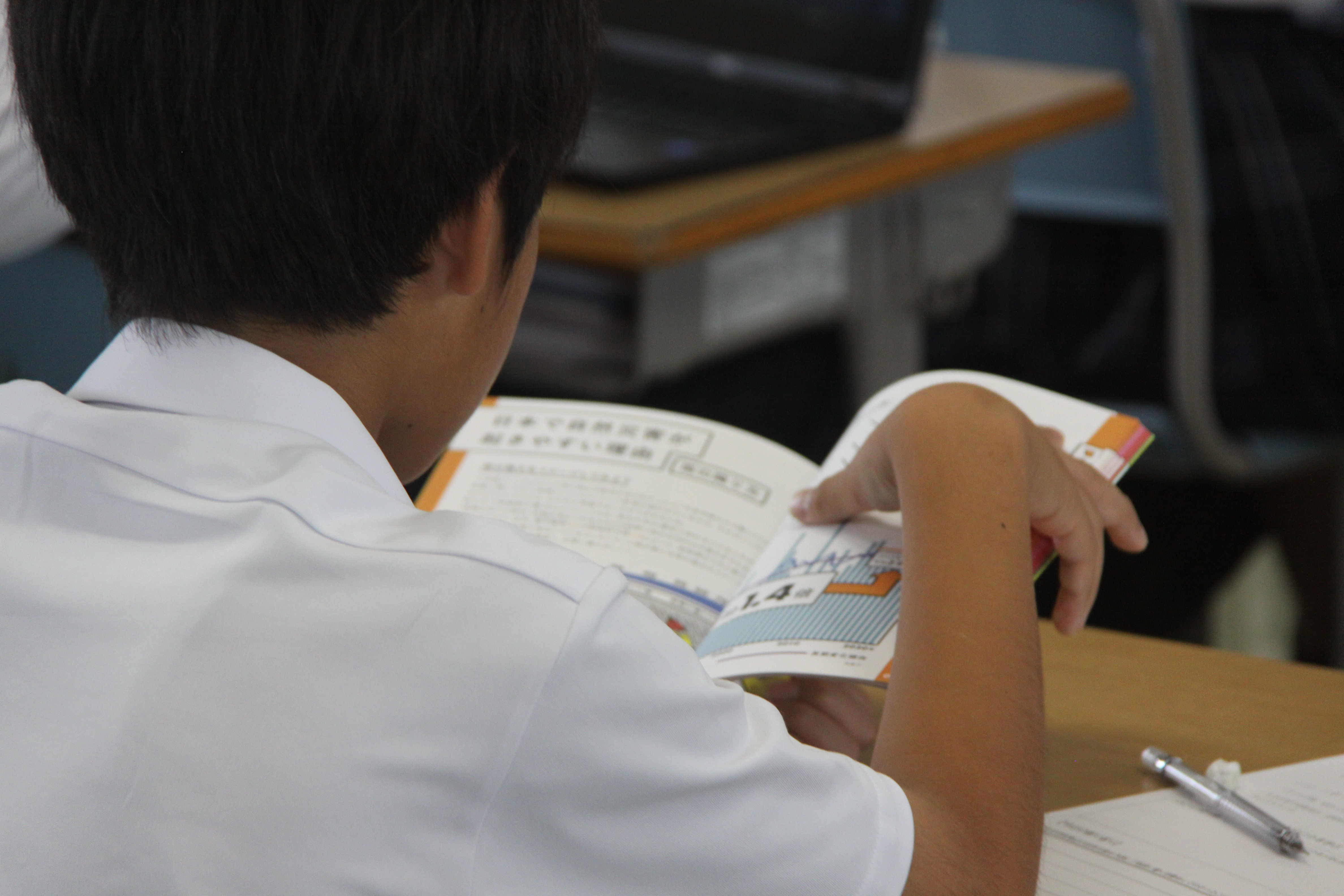
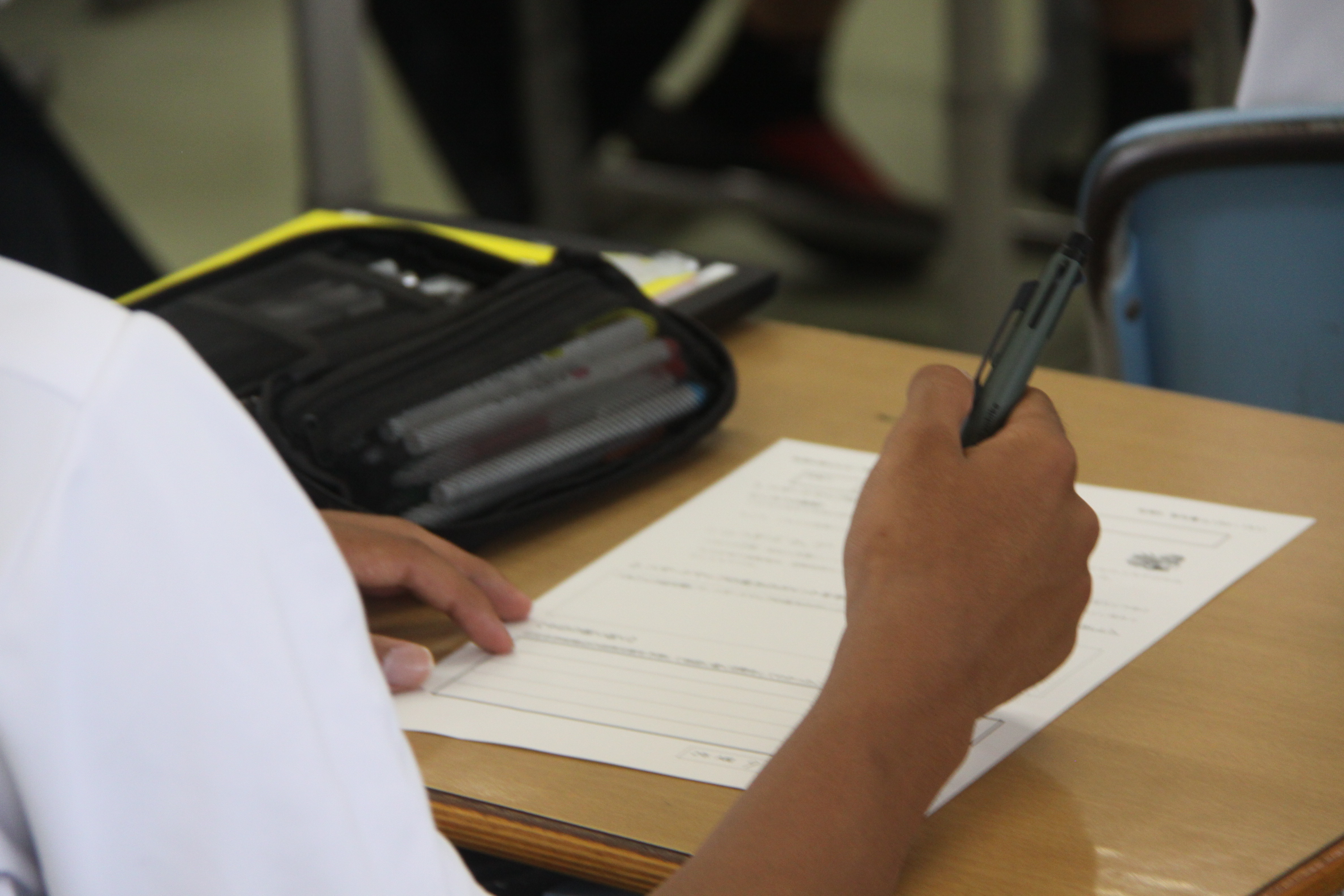
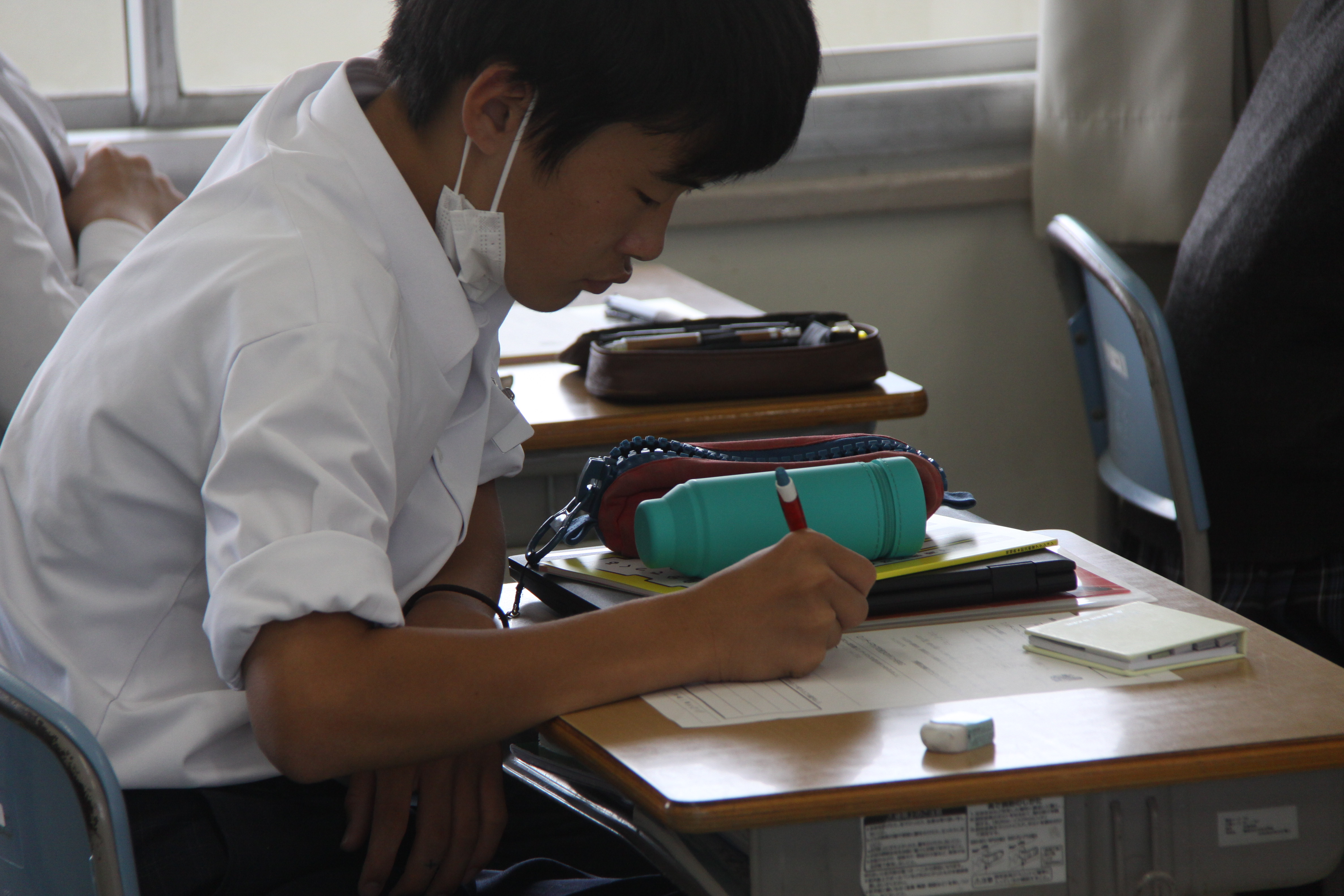
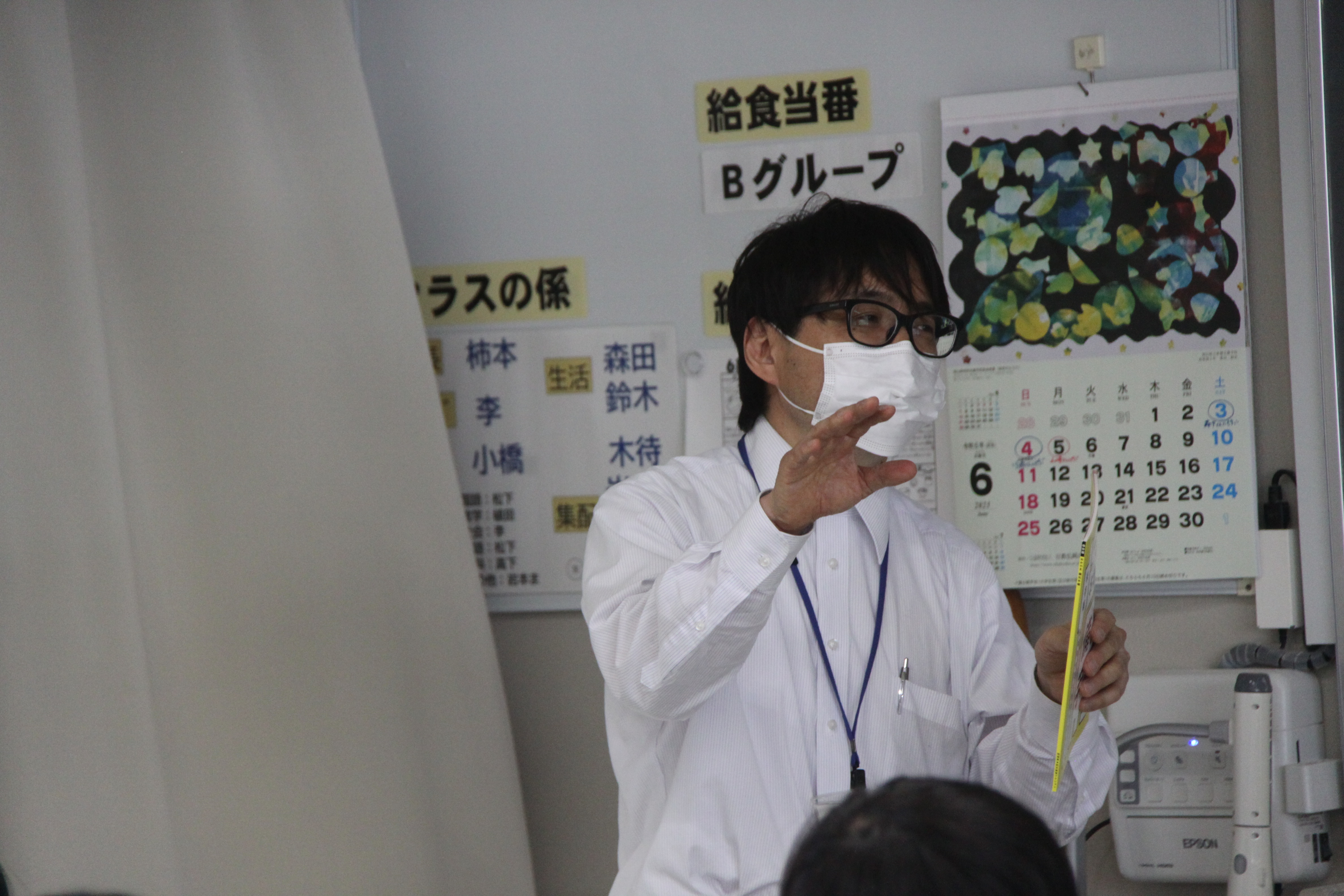
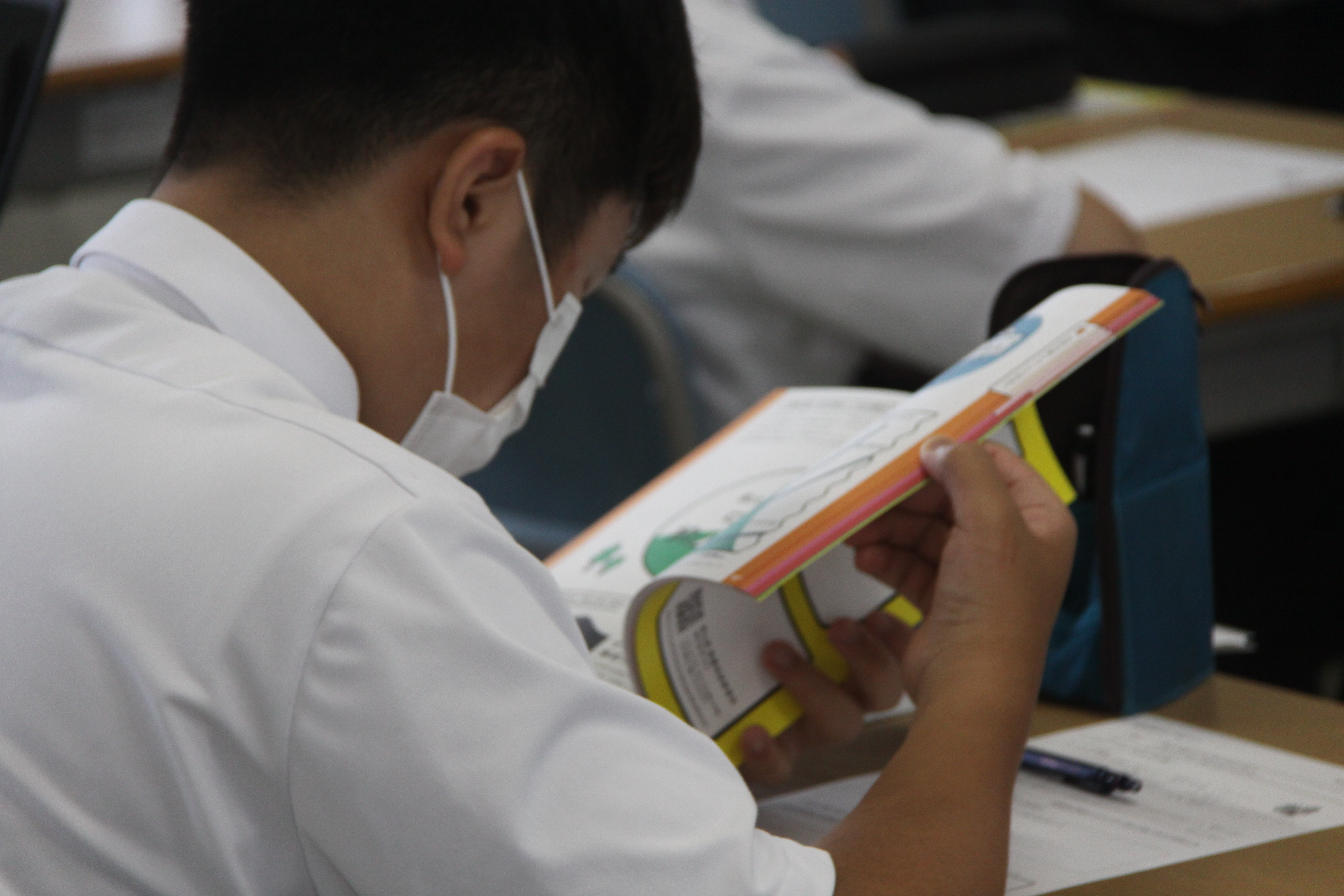
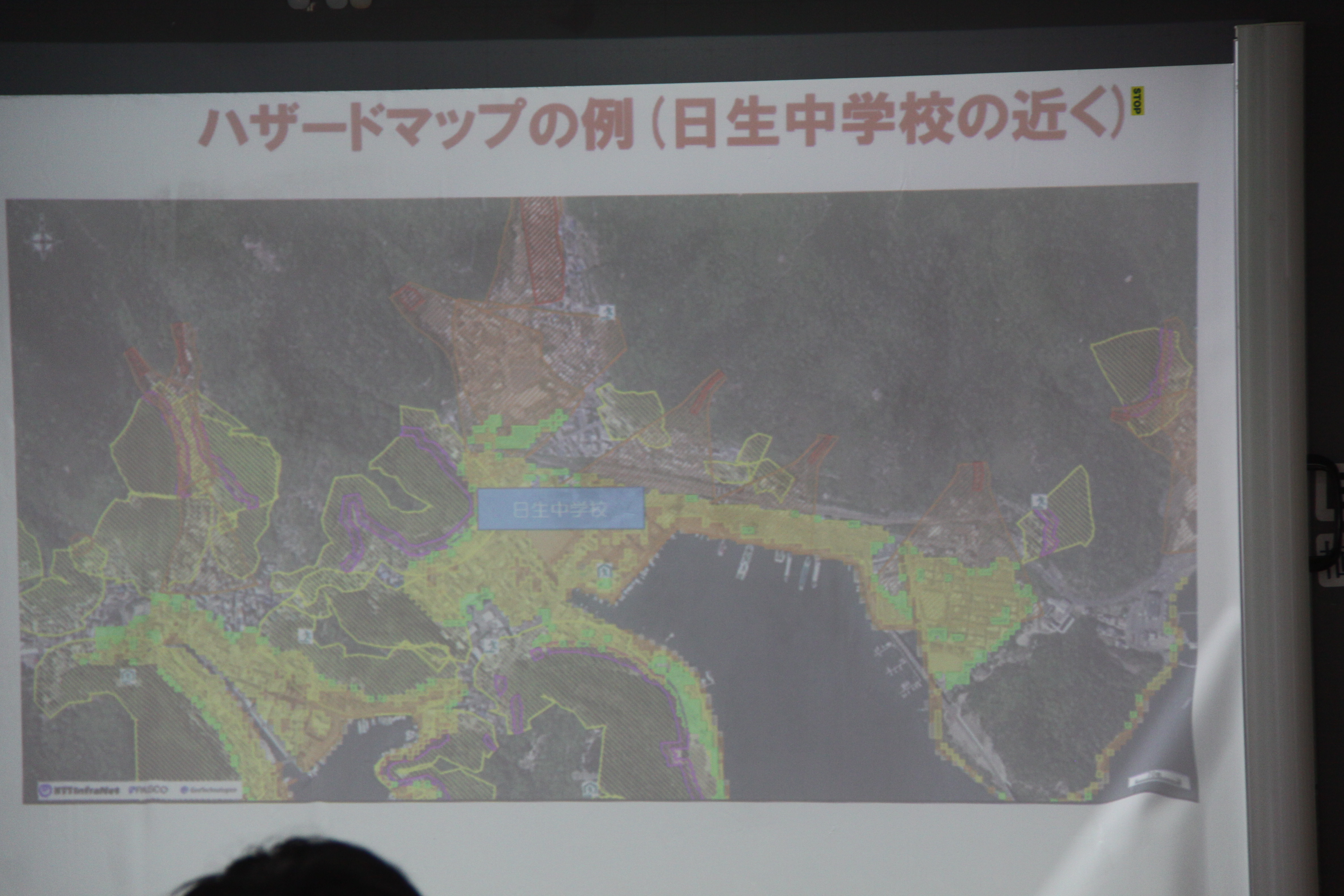
◎ひな中6月の風景
~わたしたちの学校 わたしたちのまち わたしたちの日々~
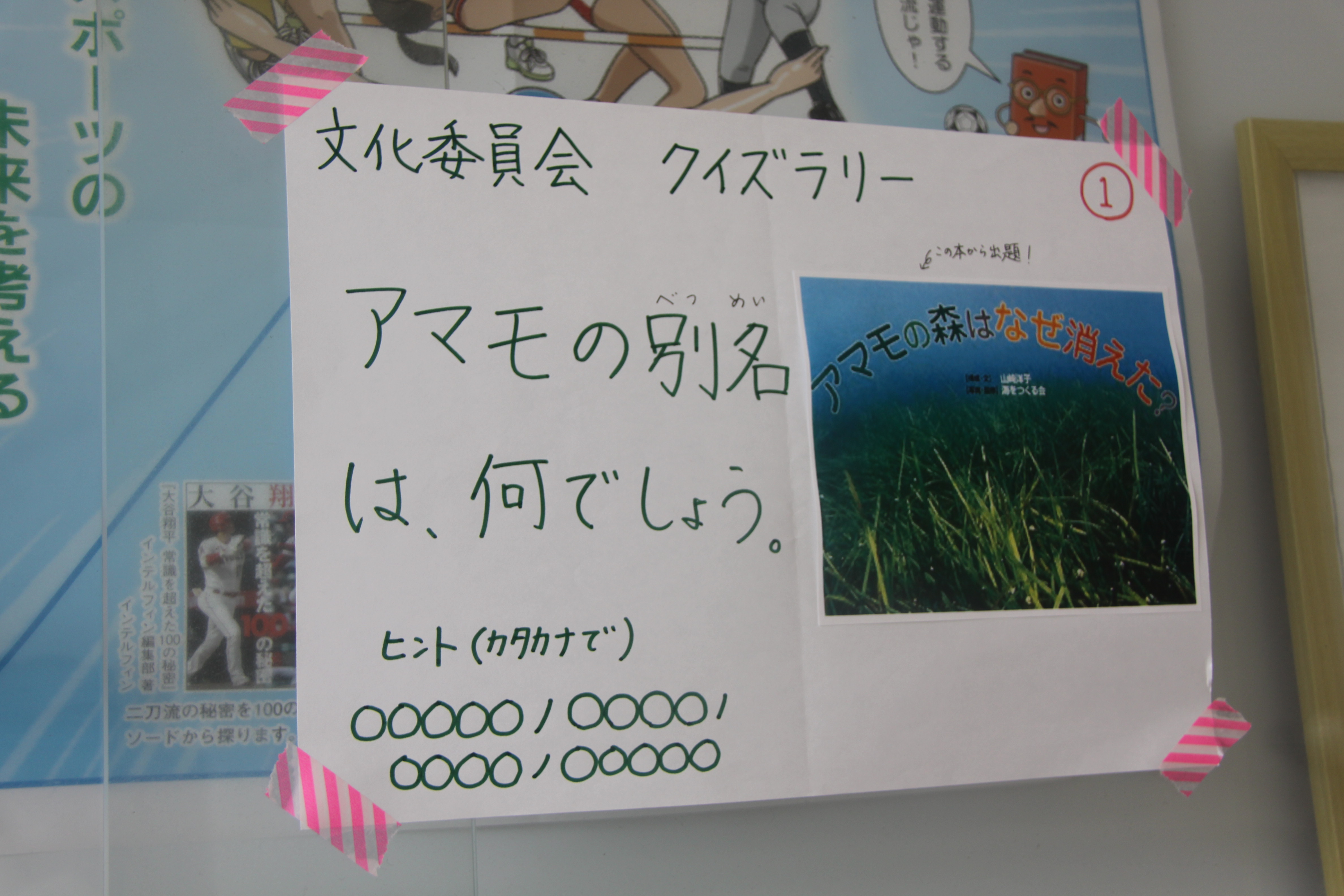






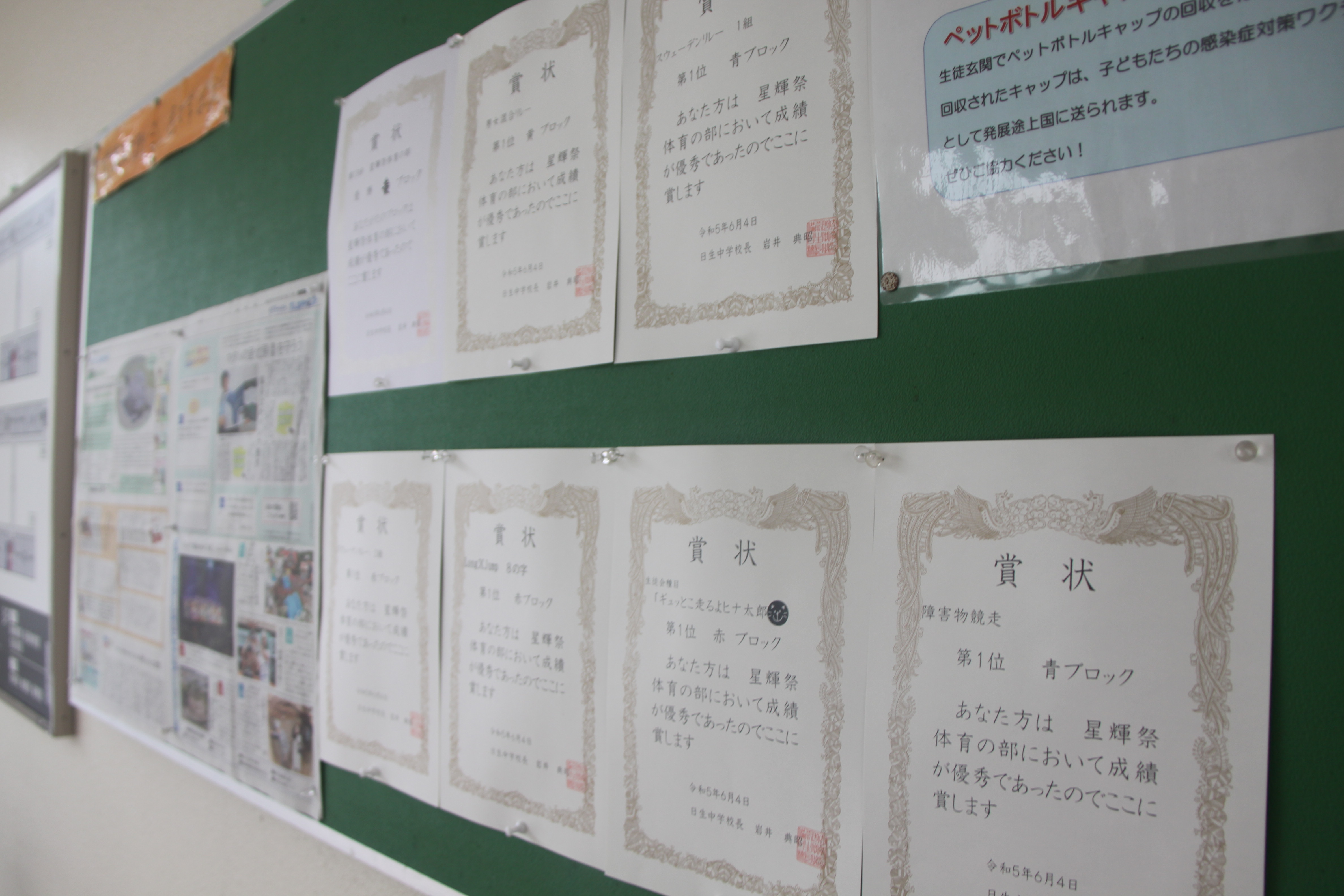

◎地域の中へ! 社会の中で! 夏のボランティアにチャレンジ
夏季休業中に活動する夏のボランティア体験にたくさんの生徒が申し込みました。(6/14)。同日、備前市社会福祉協議会日生支所さんが来校され、説明会をおこないました。ひな中のちからを地域・社会貢献のちからにしましょう。
夏ボラとは、県内の市町村社会福祉協議会が夏休み期間(主に7月~9月)等に実施しているボランティア体験プログラムです。ボランティア活動に関心のある生徒を対象に、県内の社会福祉施設や地域のボランティアグループ等でのボランティア体験を通じて社会福祉やボランティア活動についての理解を深めると同時に、さまざまな出会いの中から新しい発見や「ともに生きていく」視点を育むことを目的としています。この事業は、昭和57年から実施しており、これまで述べ12万人が参加しています。



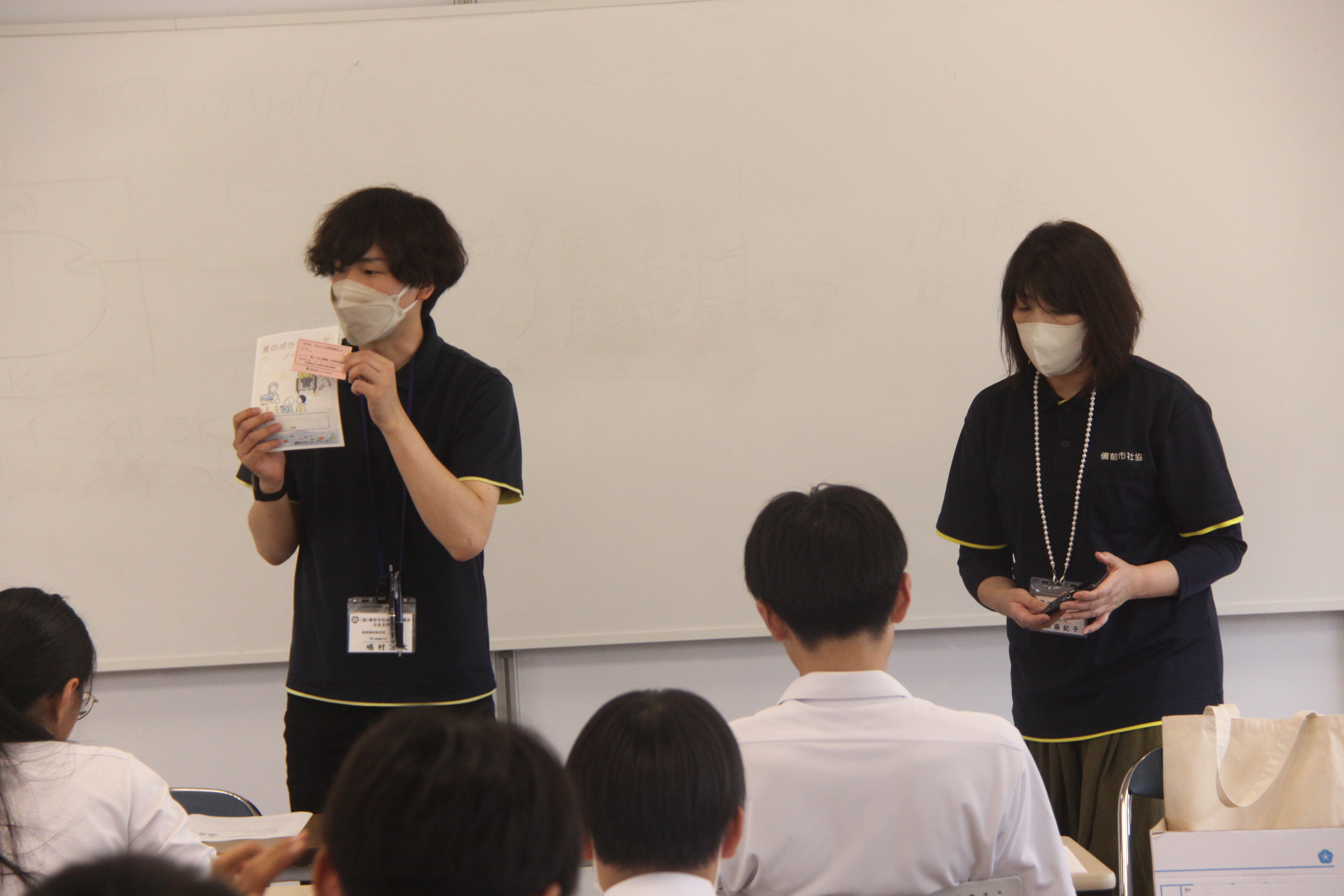
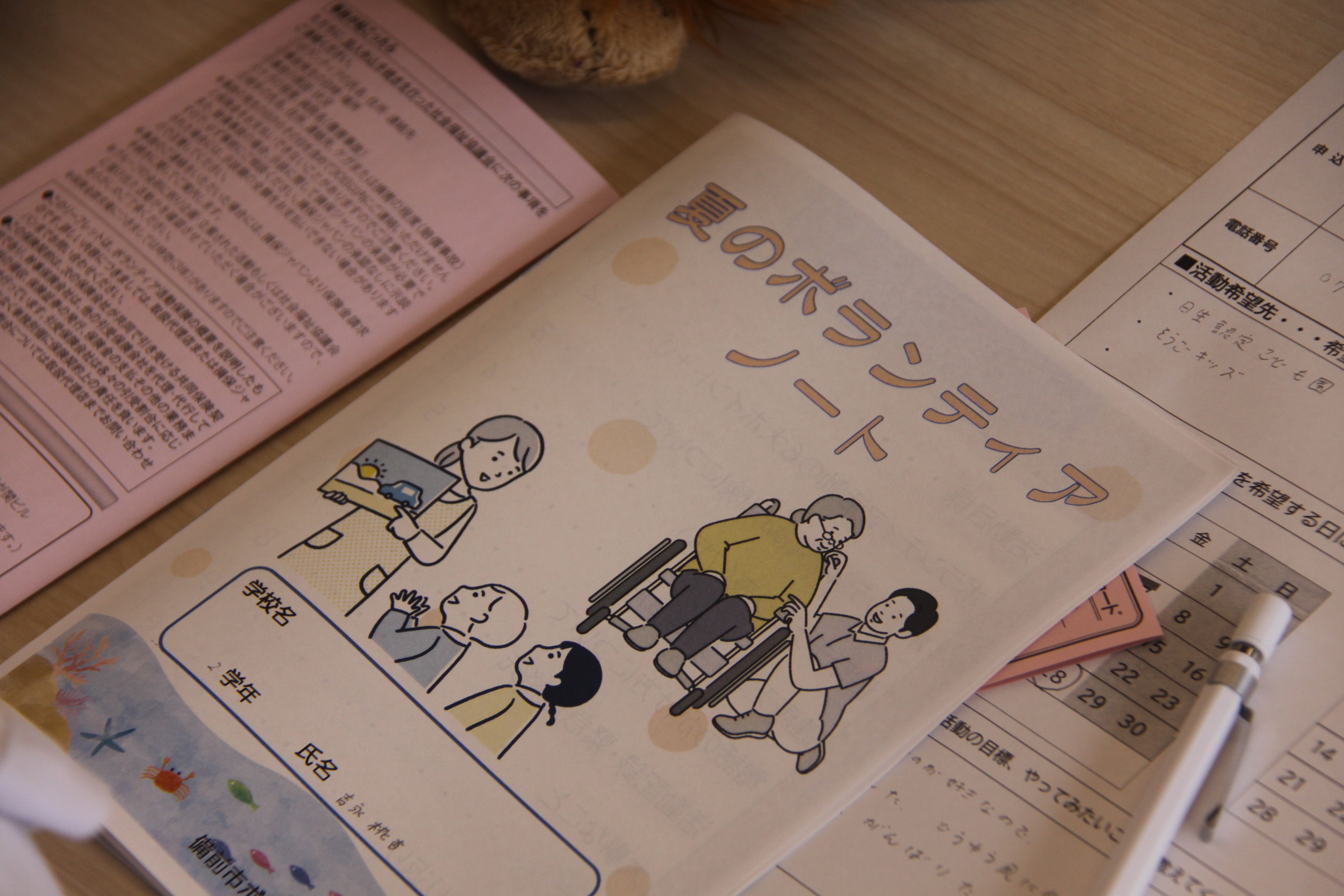
◎多くのひとに支えられて~
「困ったらひとを頼る」「声をだして伝える」って、
そして、ひとの「多様性を認める」って大切なことですね(6/14)
給食時間に、日生地区人権擁護委員さんが来校され、困ったときには助けをもとめることの大切さとSOSミニレターの利用方法について話をしてくださいました。
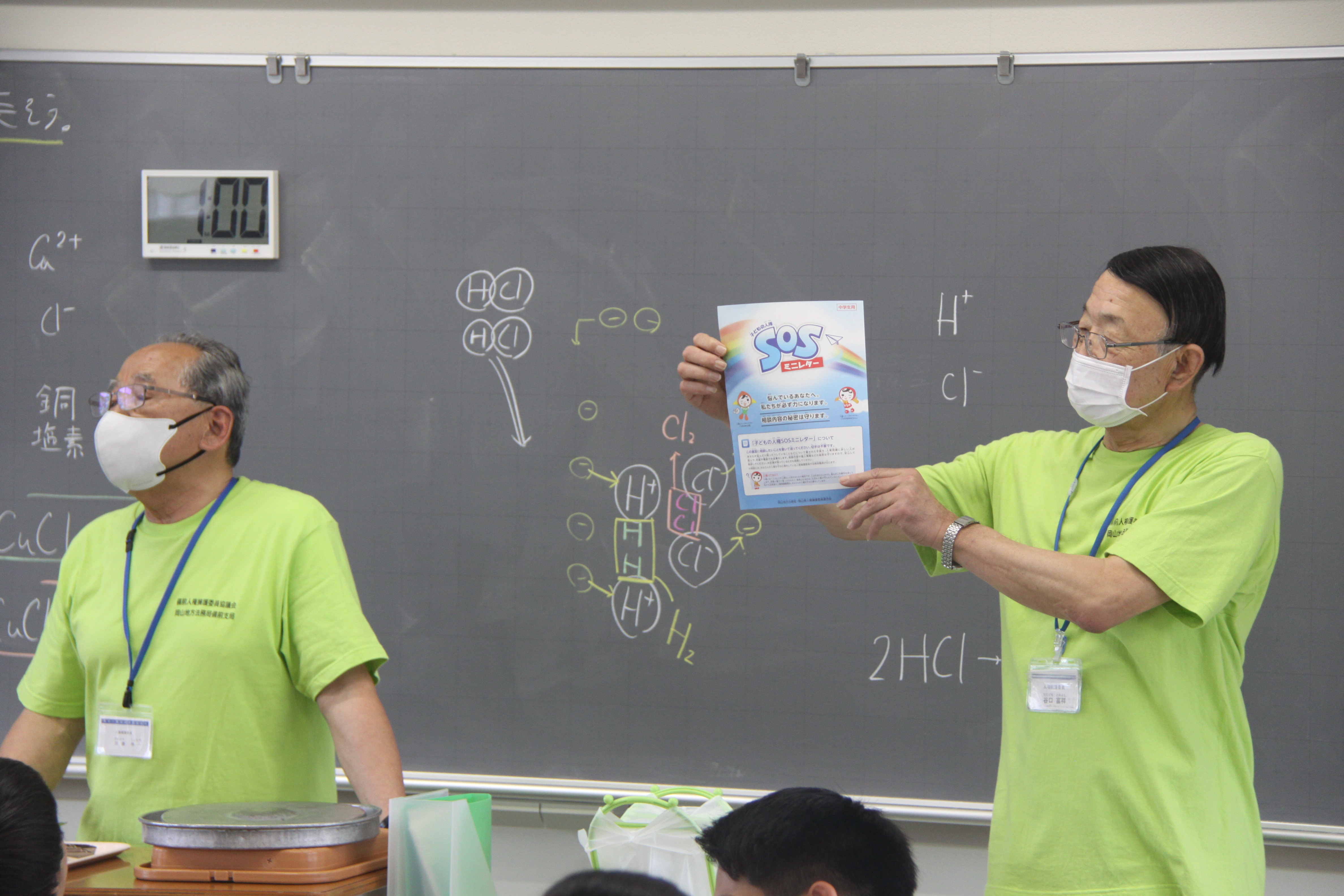
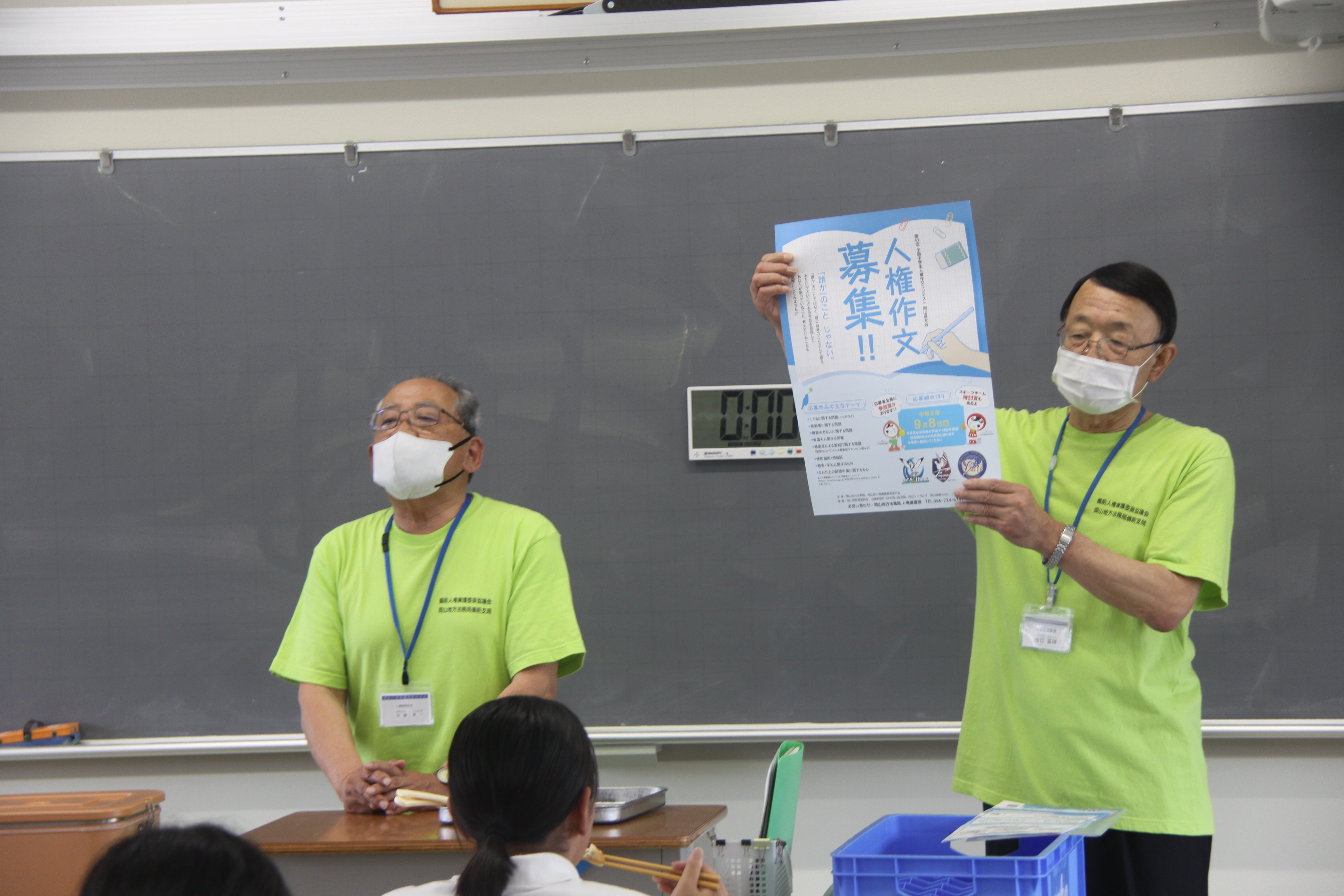

◎いくつになってもわくわくどきどき うれしい たのしい本の時間を。
多くのひとの支えられて ~今日も読み語りボランティアさんありがとう~(6/14)



◎わたしらしく せいいっぱい みんな!ガンバロウね!!(6/13)
| 種 目 | 日程 | 会 場 |
| ソフトテニス |
17日(土) 18日(日) |
日生運動公園 日生運動公園 |
| 剣 道 | 17日(土) | 個人戦 桜が丘中学校 |
| バスケットボール | 17日(土) 18日(日) |
高陽中学校・伊里中学校 高陽中学校 |
| サッカー |
17日(土) 18日(日) 19日(土) |
邑久スポーツ公園(vs白陵中 14:50~) 邑久スポーツ公園(11:30~) 邑久スポーツ公園 |
| 吹奏楽 | 17日(土) | 岡山県中学校吹奏楽部祭(倉敷市民会館)日生中12時 |
【生徒のみなさん】 総体に参加する生徒,保護者(応援者),観客など,全て の人が次のことを守り,素晴らしい大会にしましょう。
1 学 校代 表 と して の 自覚 と 誇 りを も って 参 加 しま し ょう 。
※ 態 度 や マ ナ ー 等 に 著 し く 反 す る 場 合 は,試合 出 場 停 止 処 分 の 対 象 と な る こ と が あ り ま す 。
2 生 徒は 大 会 参加 に 際し , 制 服・ 各 校規 定 の 体操 服 ・ユ ニ フ ォー ム で参 加 し まし ょ う。
3 水 分補 給 を しっ か りと 行 い ,体 調 管理 に 努 めま し ょう 。
4 ジ ュー ス ・ ガム な どの お 菓 子等 は ,持 っ て こな い よう に し まし ょ う。
5 ト イレ の 環 境美 化 に努 め 、 トイ レ のス リ ッ パは き ちん と 揃 える よ うに し ま しょ う 。
6 施 設・ 設 備 ・道 具 等を 大 切 に使 用 しま し ょ う。
※ 破 損 し た 場 合 は , 弁 償 の対 象と な りま す。
7 大 会会 場 で 出し た ゴミ は , 各自 で 持ち 帰 り まし ょ う。
8 携 帯 電 話 や ス マ ー ト フ ォ ン , 通 信 機 能 付 端 末 (ipodな ど )、 ミ ュ ー ジ ッ ク プ レ イ ヤ ー な ど は、 持 っ てこ な いよ う に しま し ょう 。
9 競 技 中 以 外 は マ ス ク を 着 用 し , 手 洗 い , う が い , 手 指 の 消 毒 な ど , こ ま め に 行 う よ う にしま しょう 。
10 大会 2週間 前からの検 温・健康 チェック を必ず行 い,参加 しましょう 。
【保護者のみなさん】
1 送迎の 際は ‚指定 された駐車場 等で ‚お願いいたします 。
2 保 護 者 ( 応 援 者 ) の 方 の 選 手 へ の 差 し 入 れ は , 直 接 , 顧 問 に 渡 し て い た だ く よ う ご 協 力く だ さい 。
3 撮 影 画 像 に つ い て は , 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら , 当 該 生 徒 及 び 関 係 者 等 の 許 可 な く イ ンタ ー ネッ ト 上 (動 画 サイ ト , 交流 サ イ ト, 掲 示板 等 ) へ公 開し な い でく だ さい 。
4 お子様 の健康状 態を把握 していた だき,参加 ・不参加 の判断を お願いい たします 。
※ 発 熱 や 風 邪 な ど の 症 状 ( ワ ク チ ン 接 種 に よ る 副 反 応 含 む ) が あ る 場 合 に は , 出 場 を 控 え て く だ さ い 。 ま た , 解 熱 後 は 医 師 の 指 示 の も と , 保 護 者 の 判 断 で 参 加 ・ 不 参加を判断ください。
◎わたしらしく せいいっぱい ~総体・吹奏楽祭へ~(6/12)









◎信頼される教職員であり続けるために
~コンプライアンス研修に取り組んでいます~(6/12)
令和5年度「県内統一の不祥事防止研修等の年間スケジュール等」をもとに、信頼される教職員であるために本校でもコンプライアンス意識の高揚に向け研修に取り組んでいます。この日は交通事故防止について意見交換をしながら研修を深めました。
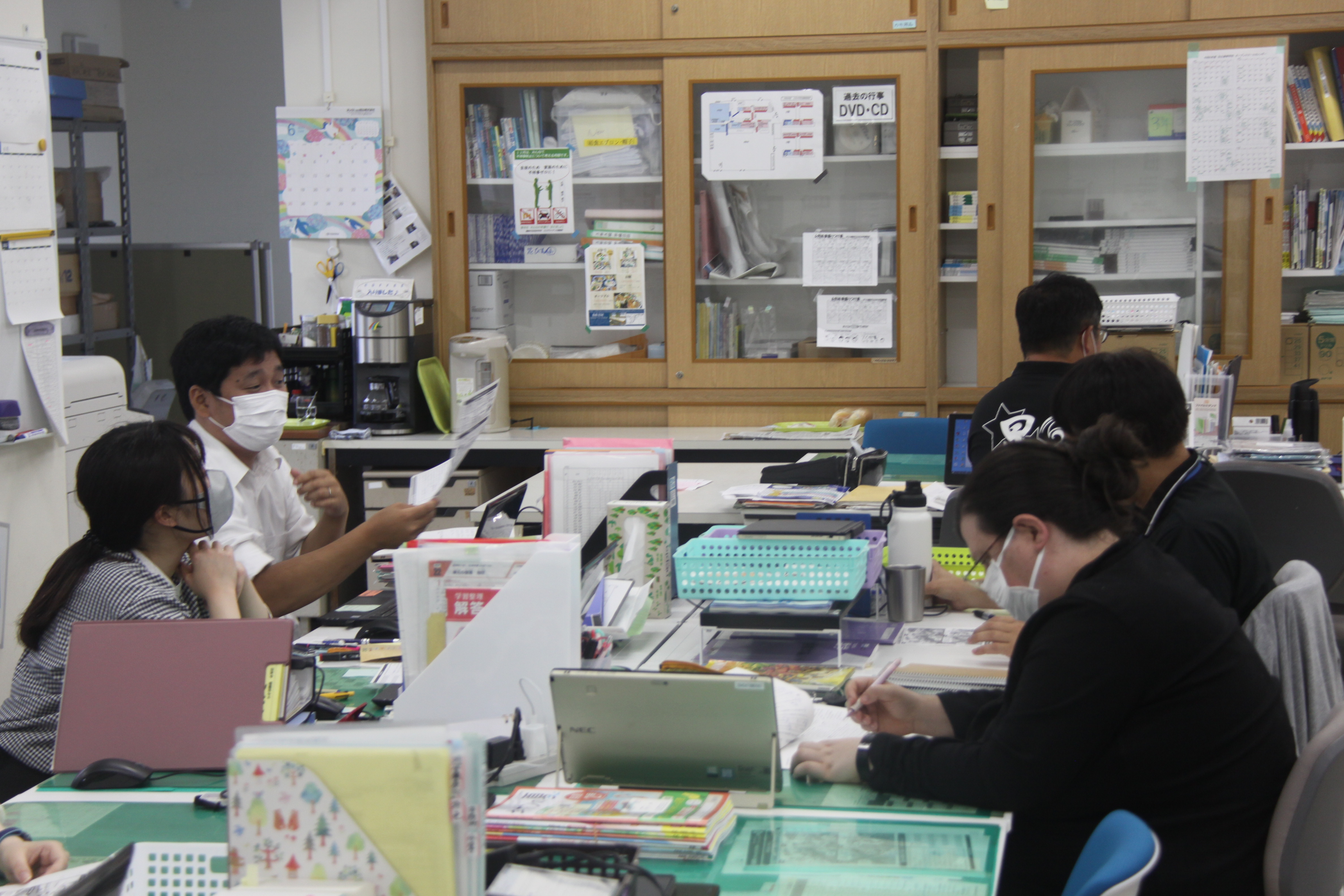

◎わたしたちの一生懸命 ~備前市教育委員会学校訪問~(6/8)
教育長をはじめ、備前市小中一貫教育課、教育振興課、国際教育課が来校され、生徒の授業の様子を参観されました。日生中は、真剣に、協同的に学ぶ姿、自ら進んで学習に取り組む姿を大切にしています。

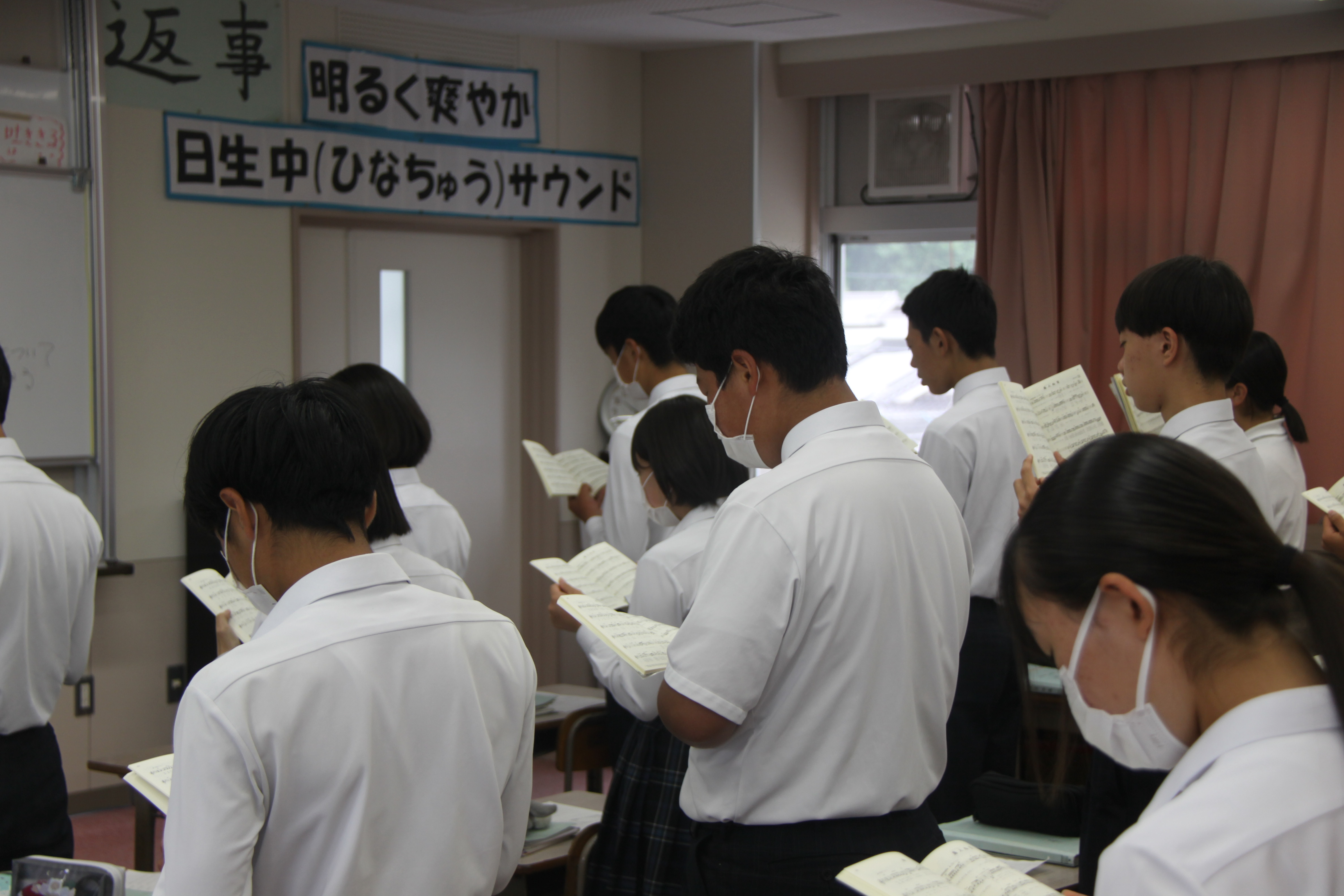



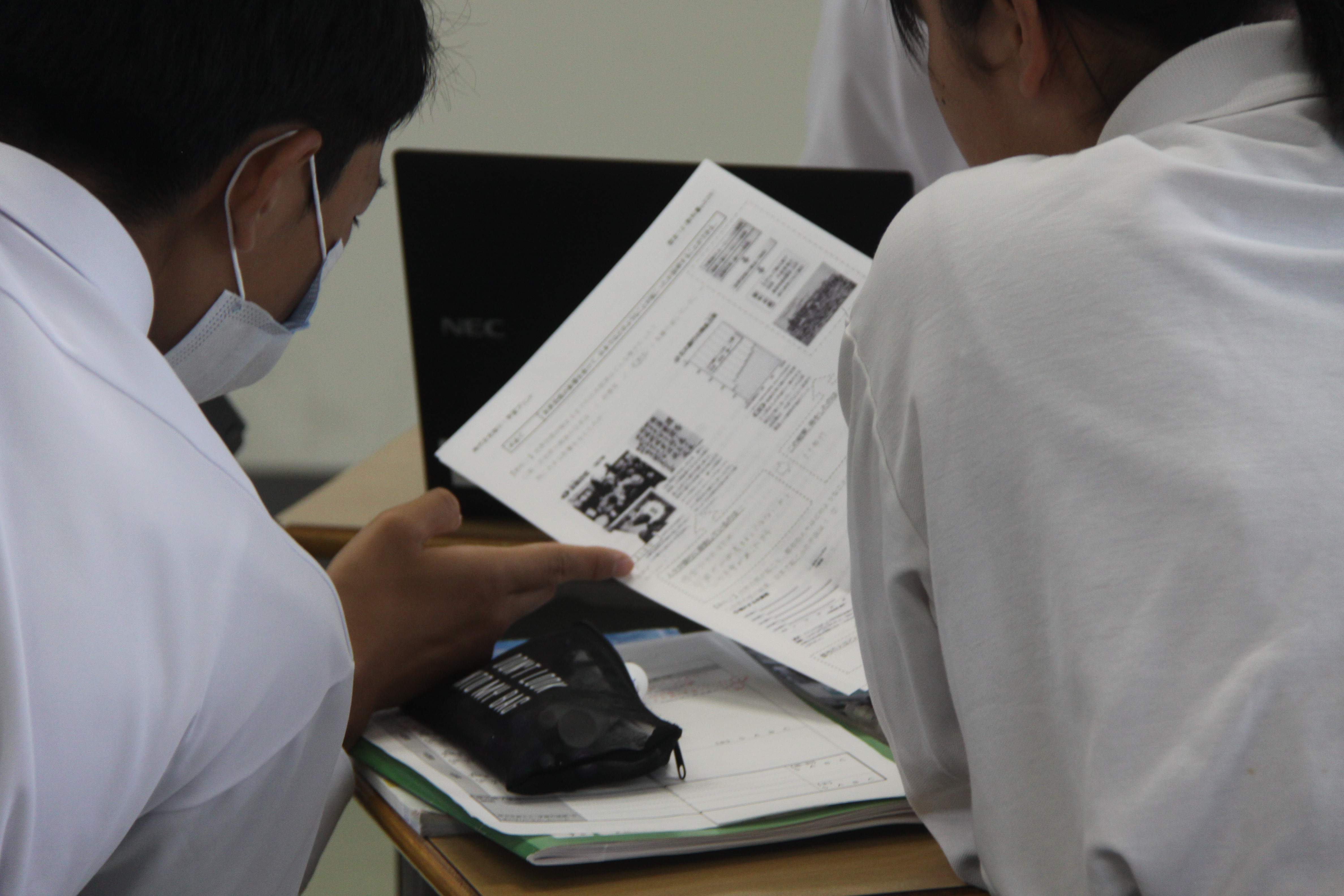



◎ありがとう ありがとう そしてこれからも みんな輝こう
~星輝祭体育の部ブロック会(6/7)~






◎Today is another day ~6.4を越えて~
わたしたちの生徒集会(6/7)


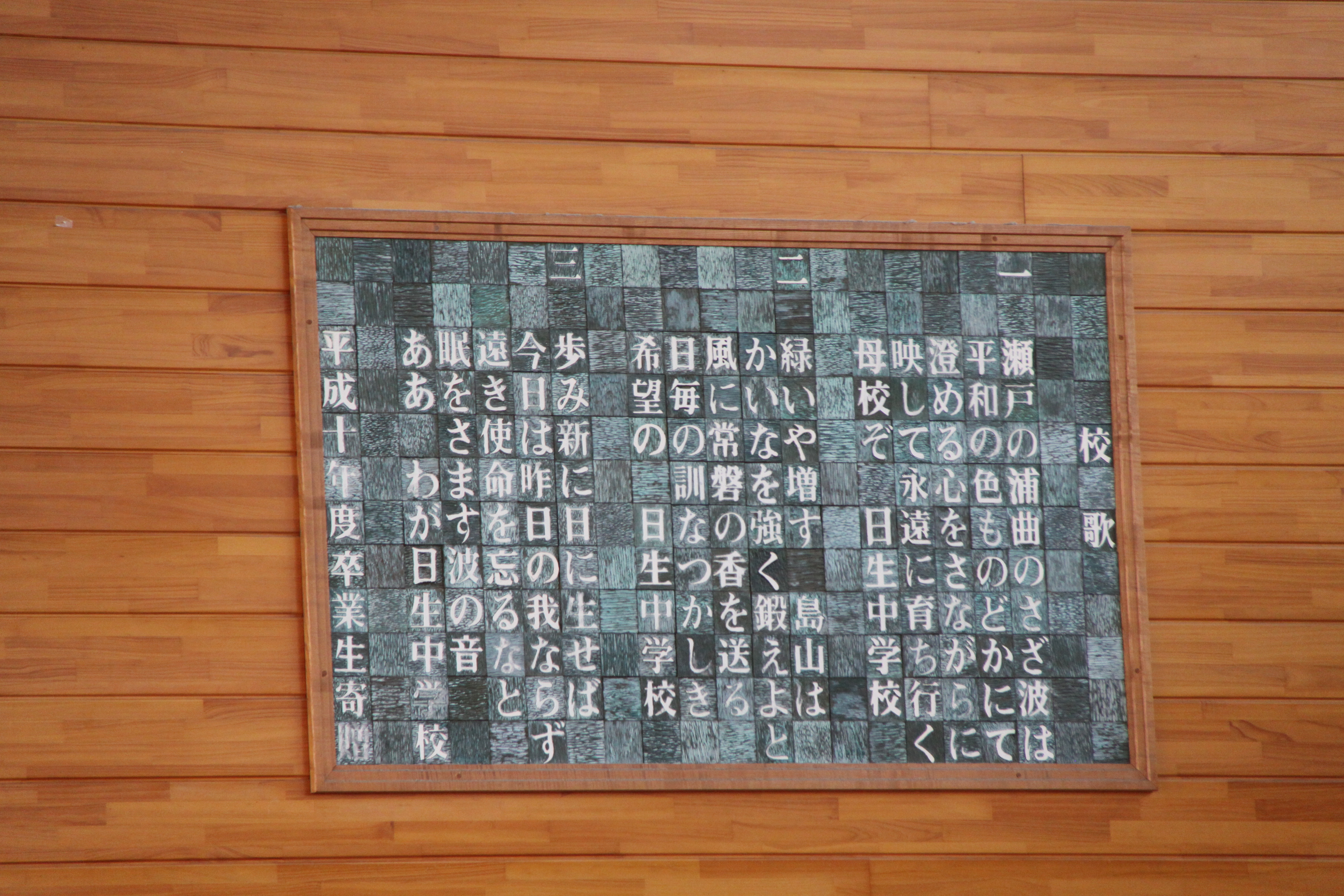

◎One for All All for Oneってこういうことさ。
自主・向上・練磨ってこういうことさ。
星輝祭体育の部開催(6/4(日))















◎星輝祭体育の部 日程変更のお知らせ(6/2(金))
(1)雨天のため、運動場のコンディションの回復と会場準備が必要となり、明日、3日(土)開催予定の星輝祭体育の部は、4日(日)に延期して開催いたします。
(2)明日、3日(土)は、通常通りの登校で、授業(最終の競技練習、会場準備)を行い、11時35分に帰りの会が終了します。(そのあと、各係会があります)
(3)4日は、8時30分から開会式となります。校舎2・3階のテラスでご観覧される方はスリッパをご準備ください。
(4)5日(月)・6日(火)は、振替休業日となります。
大きな変更となり、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

◎ひな中の風~~わたしたちの星輝祭

◎One for All All for One
〈青を抱くどこに行ってもきみの踏む土は土だよだいじょうぶだよ:初谷むい〉
(6/1(木))









◎ひな中の風~~6月の風景


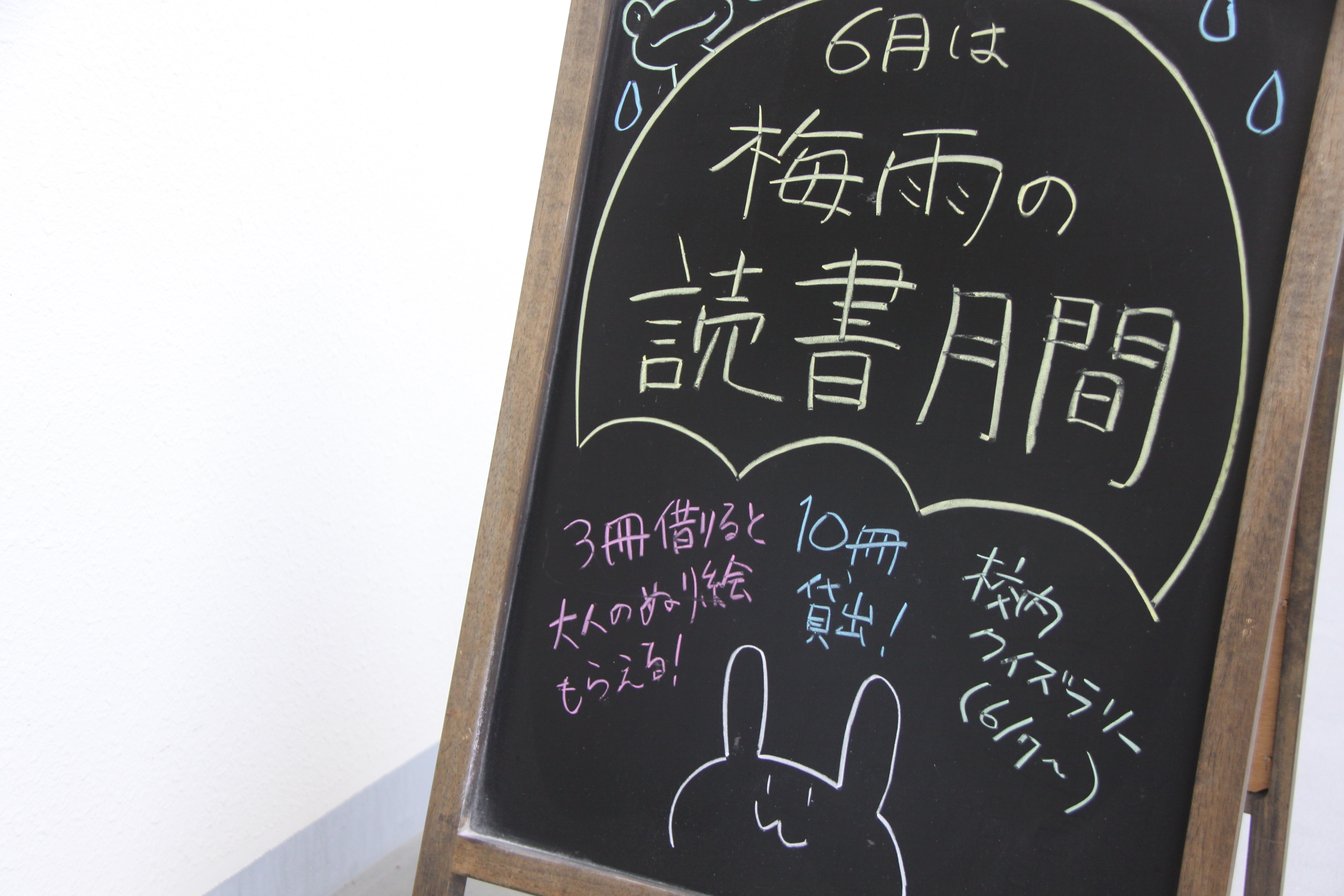

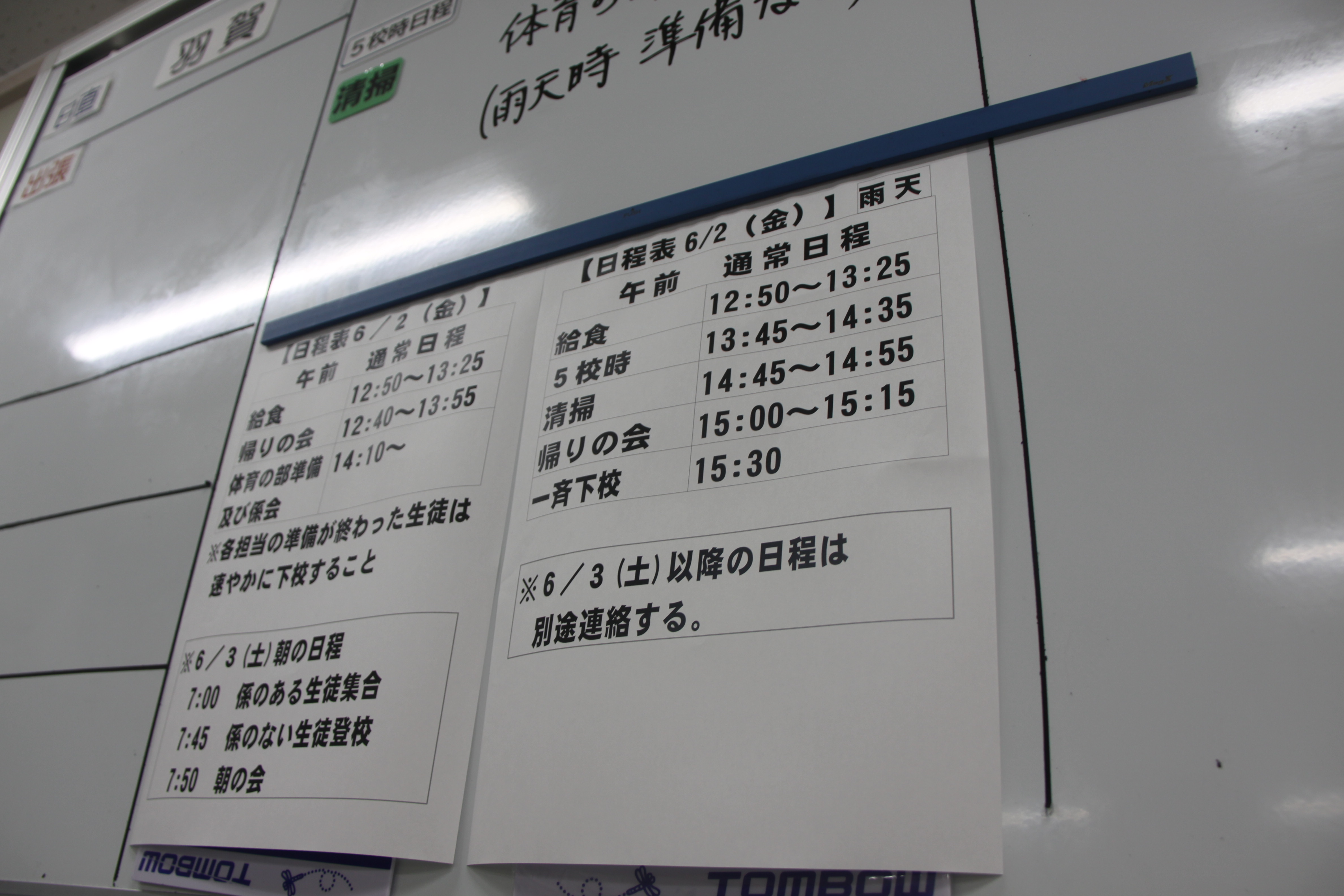

◎One for All All for One 雨ニモ負ケズ 梅雨ニモ負ケズ(5/31(火))
週末の天候が心配ですが、雨天時の登校についてご連絡します。
(1)雨天順延の連絡は、当日6:30頃に安心メールにてお伝えします。ただし事前に実施できないと判断する場合は前日までに連絡させていただく場合もあります。
(2)変更パターン
【3日(土)雨天延期時】は、3日は登校し、12時下校。4日(日)に体育の部を開催します。5日(月)6日(火)は休みで。7日(水)~登校。
【3日、4日とも雨天延期時】は、3日は登校し12時下校。4日(日)5日(月)と休み、6日(火)に体育の部を実施します。
【6日(火)登校時にはお弁当が必要です。よろしくお願いします】

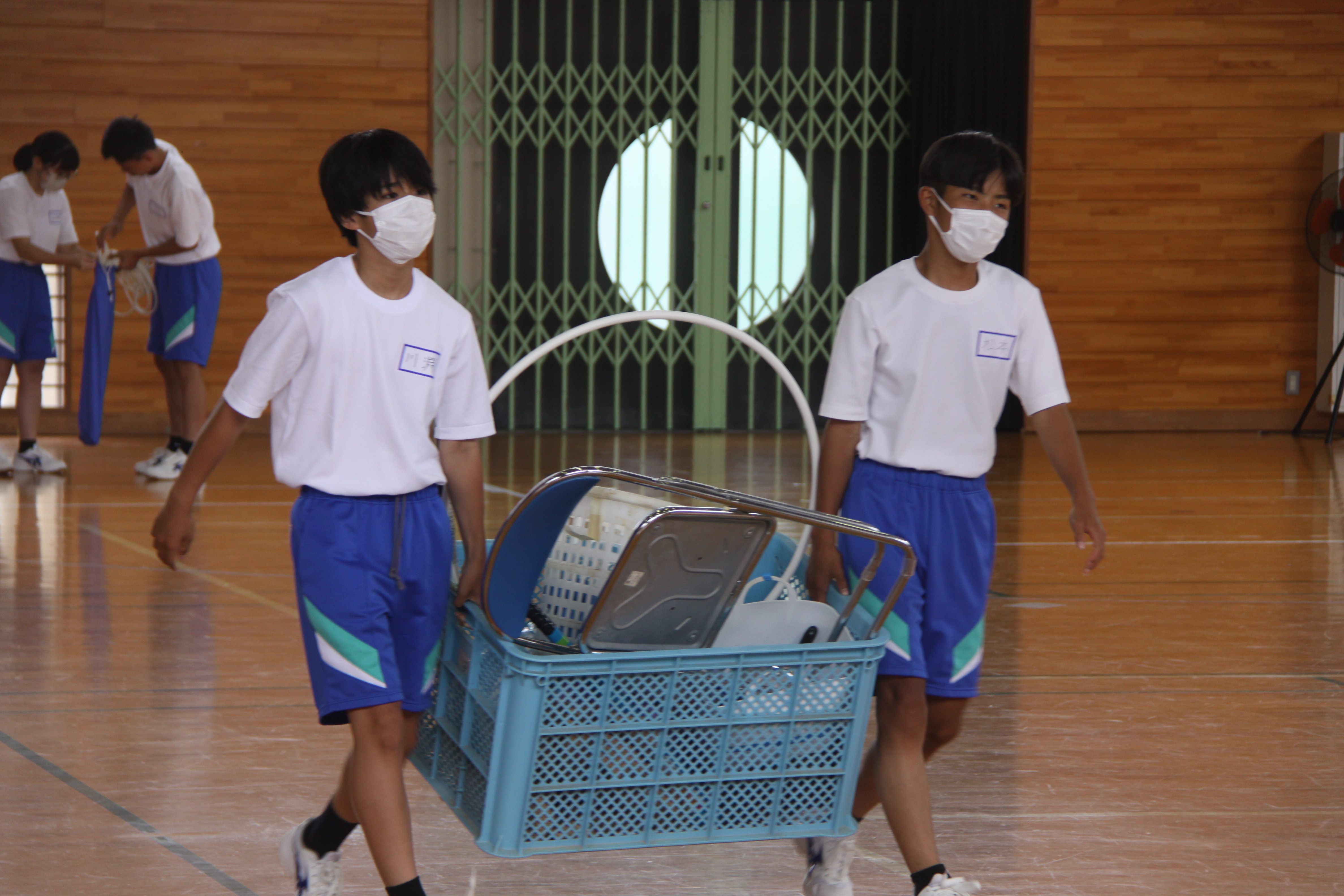







◎ひな中のかぜ~~「ありがとう」「行ってきます」
梅雨に入り、朝、お家の方の車で送ってもらう生徒も増えているようです。そんな中、とても多くの生徒が、「ありがとう」「行ってきます」と、笑顔で車から降りてきます。(そして、もちろん、登校を迎える教職員にも気持ちの良いあいさつをしてくれます)ひな中の生徒にとっては、日常のあたりまえのことかもしれませんが、とても感心しました。「ありがとう」「行ってきます」「さようなら」「また明日」「気をつけて」…私もコトバに心をこめて、これからも「登校・下校」を見守ろうと思います。

◎One for All All for One がんばったよ(5/26(金))

◎行ってきました。2年生 流れ藻の回収(5/26(金))
日生中は多くの方に支えられて海洋学習に取り組んでいます。皆さんも体験・参加したい方がおられましたら、「ひなせうみラボ」等を検索ください。〈ひなせうみラボHPより〉「…子どもから大人まですべての方々が楽しめるような海洋教育・体験プログラムを常時ご用意しております。アマモの再生体験は漁師さんの指導のもと、季節に合わせて年に数回行われます。初夏は流れ藻という海草の集まりを回収したあと、アマモの種を選別しやすい状態にするため約3ヶ月間寝かせます。秋には種を選別した後、種を海に撒いて新たなアマモの成長を見守ります。実際にアマモ場に行くと、そこを住処としている小魚たちの存在に子どもたちは目をキラキラさせて感動してくれます。」









◎多くの人に支えられて 日生共同調理場から北川先生来校(5/26(金))
食育の一環として、北川先生が来校され、朝食の大切さについて話をしてくださいました。
参考:人間のからだには体内時計と呼ばれるものがあるのを知っていますか?一日単位で、すいみんや体温、血圧やホルモン分泌などの変化をつかさどっている大切な機能です。人間が健康に過ごすために欠かすことのできない体内時計は、光と関係があり、太陽がのぼっている間は活動的に、しずんだら休息しなさい…と働きかけています。これを「体内リズム」といいます。「体内リズム」が自分の「生活リズム」とズレてしまうと、からだにとってはとても大きなストレス。ズレによってからだと心のバランスが保てなくなると、しっかり活動することができなくなったり、感情が不安定になってしまうことさえあるのです。
「体内リズム」と「生活リズム」のズレをなくすには、まず朝食をしっかりとることがとても大切。朝食を食べるためには、夕食の時間も大切です。夕食が遅いと朝ねぼうして時間がない、朝おなかが空いてなくて朝食を食べられないなどの悪いリズムができてしまいます。ですから、からだにとって、そして心にとって、快適なリズムを子どものうちにしっかり身体で覚えていくことが大事です。そのためにも、毎朝しっかりたべる「癖(くせ)」をつけましょう。〈農林水産省HPより〉

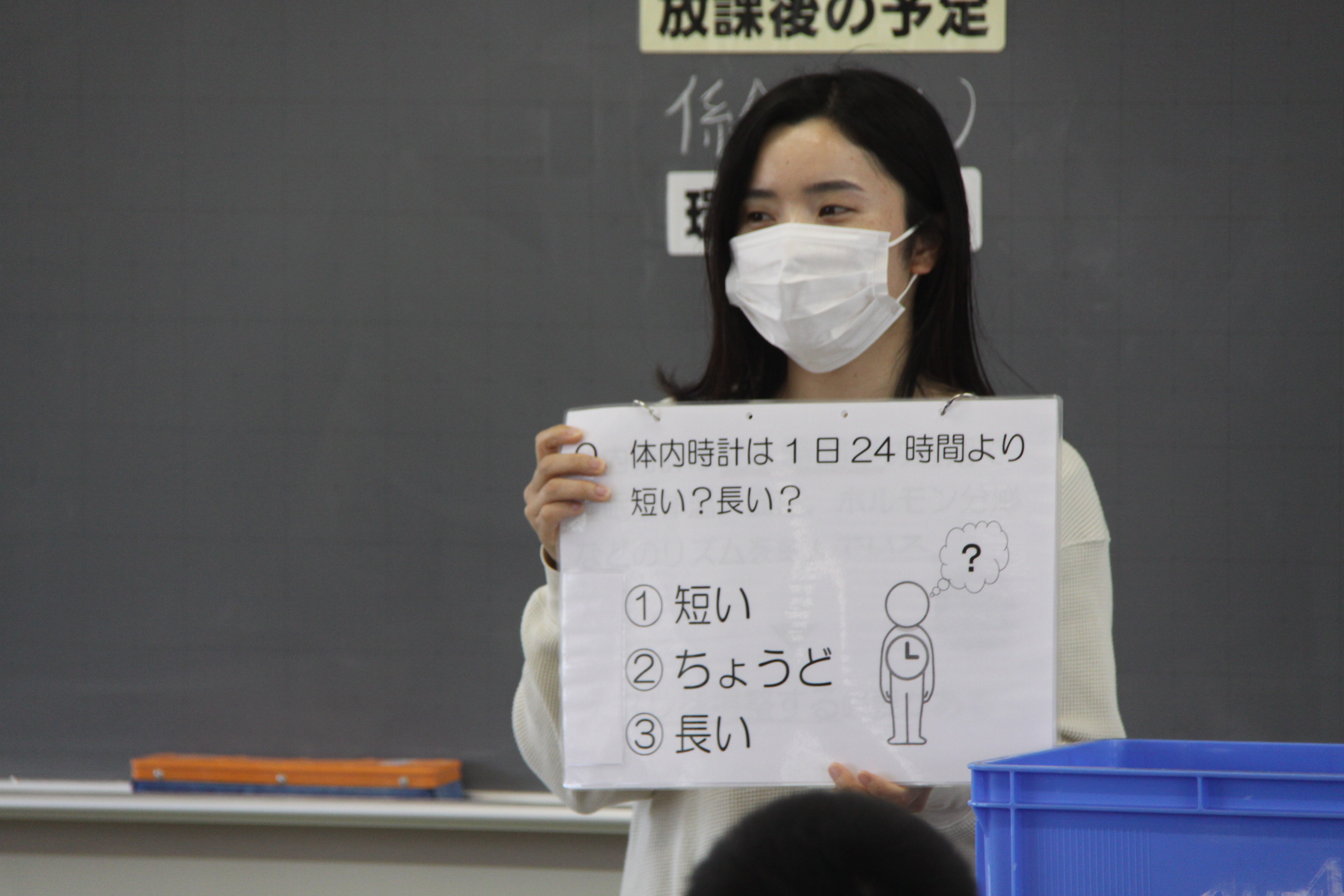




◎One for All All for One
~私らしく〈創る〉仲間とともに~(5/26(金))
来週の天候が不安定(予想)のため、日程を変更して、本日予行練習を実施しました。












◎さあ、今年も行こう!流れ藻の回収作業へ(5/24(水))
1・3年生が流れ藻の回収作業に取り組みました。2年生は金曜日に取り組みます(私(教頭)も一緒に参加します。楽しみです。)
アマモが生い茂るアマモ場は、多くの生き物の棲みかとしてだけではなく、海水の浄化と酸素の供給に大きな役割を果たしています。さらに枯れたアマモが堆積する有機物として分解され、再び栄養塩としての循環がはじまる場でもあります。最近ではブルーカーボンとしても、大きく注目されています。光合成によりCO2を吸収するだけでなく、アマモ場の海底の堆積物に取り込まれた炭素が数千年にわたって貯留されることから、地球温暖化対策のための、炭素の隔離・固定の場としての期待も大きくなっています。これからも、豊かな海を未来につなげていく取組を積極的に進めていきます。


長靴・手袋が、ひな中では必須なのです。
◎One for All All for One (5/24(水))






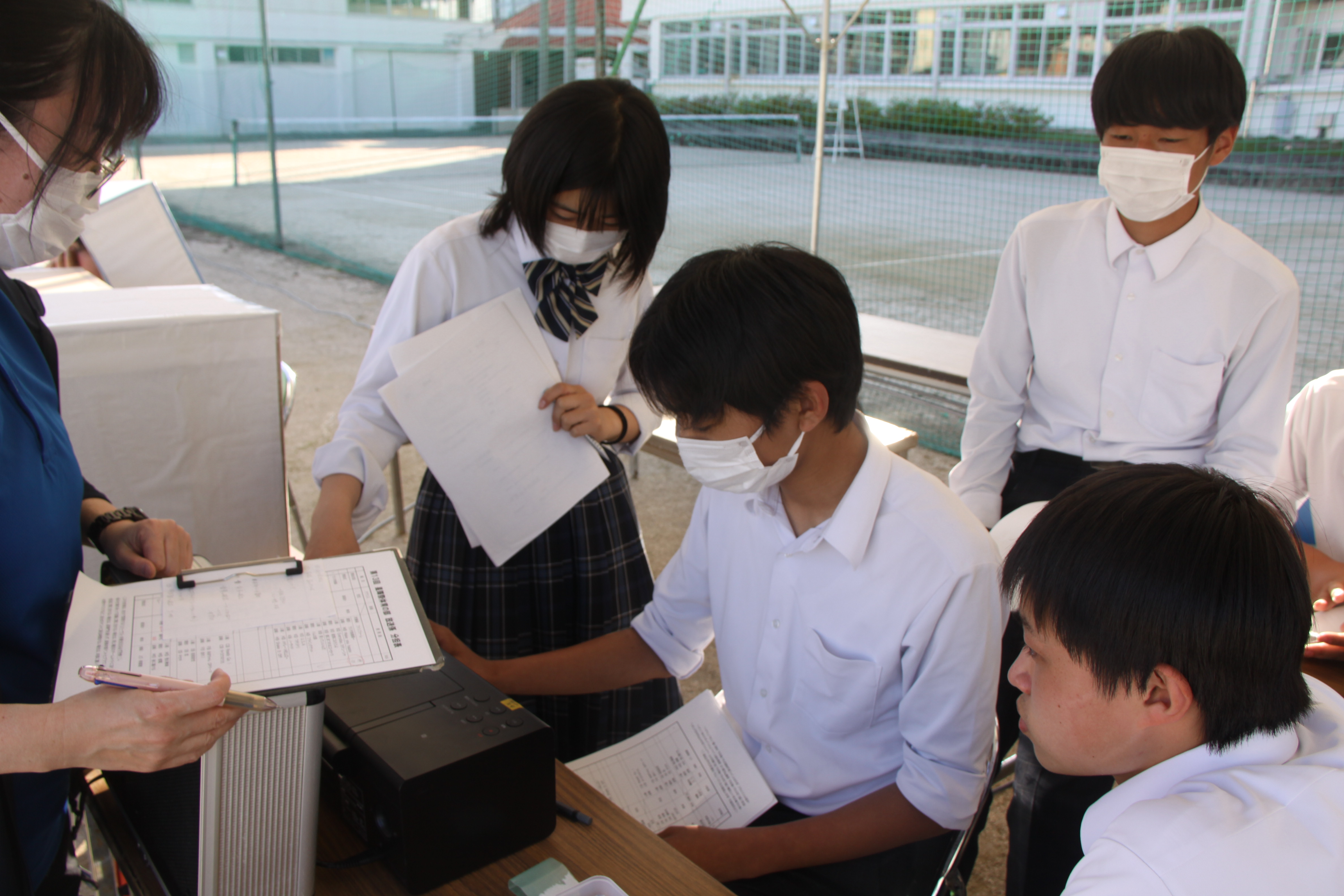


◎思いは同じ~クリーン大作戦(5/23(火))
環境委員会のよびかけで、なんとたくさんの仲間が集まったものだ。






◎我武者羅~仲間と共に練習・練習・練習(5/22(月))
本番は一本の道を通るだけだ。本番までの「いま」、この練習の繰り返しの中で、力がつき「磨かれ」「鍛えられる」のさ。









◎夢に向かって~教育実習スタート
(5/22(月)~6/9(金))
本校卒業生の石谷先生が3週間の教育実習をスタートさせました。「出会いに心をこめて」大切な時間にしましょう。

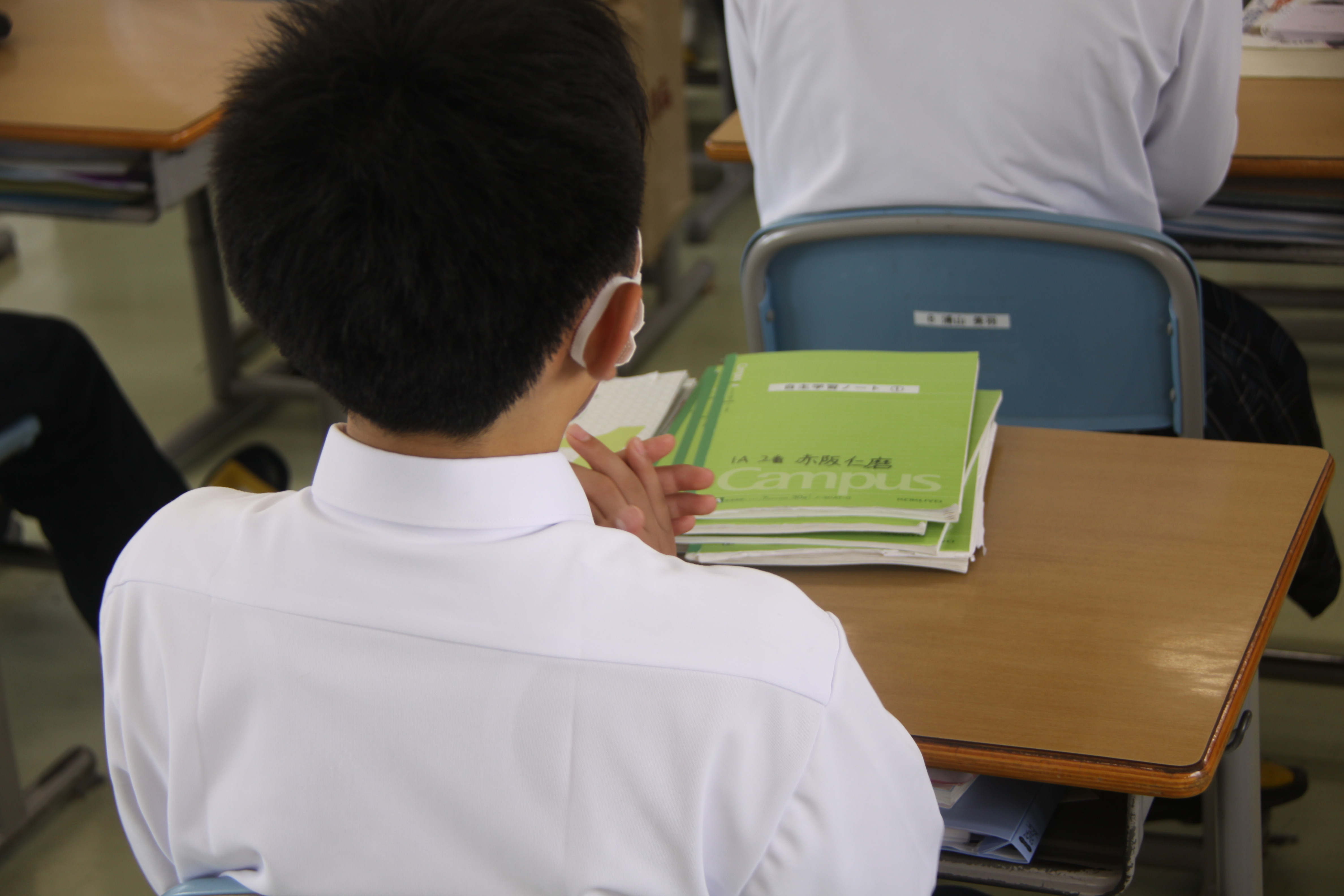
◎ひな中のかぜ~~優しさと行動と心強さを(5/18(金))
生徒のひとりが、下校途中に自転車のアクシデントで転倒し困った事がありました。帰宅途中だった仲間の一人は、息をきらして中学校に引き返して、連絡をしてくれました。また、たくさんの仲間は、ケガをしたその子に声をかけて応援がかけつけるまで勇気づけてくれました。通りかかった地域の方々も「お手伝いしましょうか」とたくさん声をかけてくれました。到着した家族の方は、生徒らの行動に大変感謝されていました。ありがとう みんな。ありがとう。



◎多くの人に支えられて~備前警察署スクールサポーター来校(5/18(金))
スクールサポーターさんは、警察官を退職された方等を警察署等に配置し、学校における少年の問題行動等へのサポート対応、巡回活動、相談活動、子どもの安全確保に関する助言などをおこなう学校を応援する制度のひとつです。この日、来校した根木スクールサポーターさんは、主体的・協同的な学習(授業)に取り組む生徒の様子に大変感心されていました。
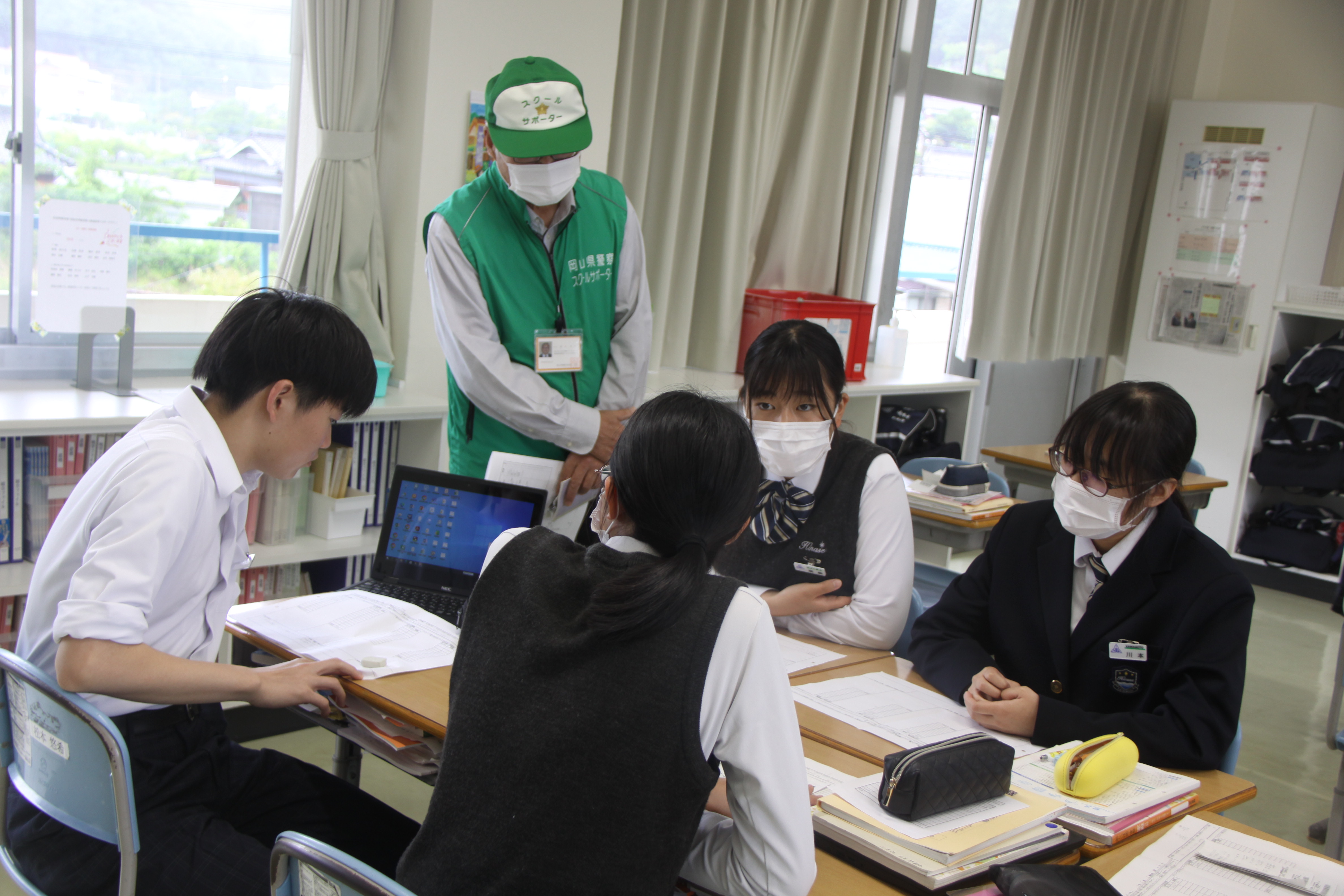
◎ひな中の風~~仲間と学ぶ

◎なかまを知るってステキ!~このメンバーで3年間がんばり合うための一歩~
(5/17(水))
山﨑スクールカウンセラー(やまちゃん先生)と共に、学年の仲間を知ることの大切さについて、ワークショップをしました。「盆栽が趣味?」「ハチュウ類を飼っている?」「日生諸島のうち3つ以上「サボテンを育てている?」「阪神ファン?」「ファジアーノの応援に行った?」「ポケモン図鑑を完成させた?」・・・。質問をし合う中で、仲間のことをもっと「知る」ことができました。(o^―^o)



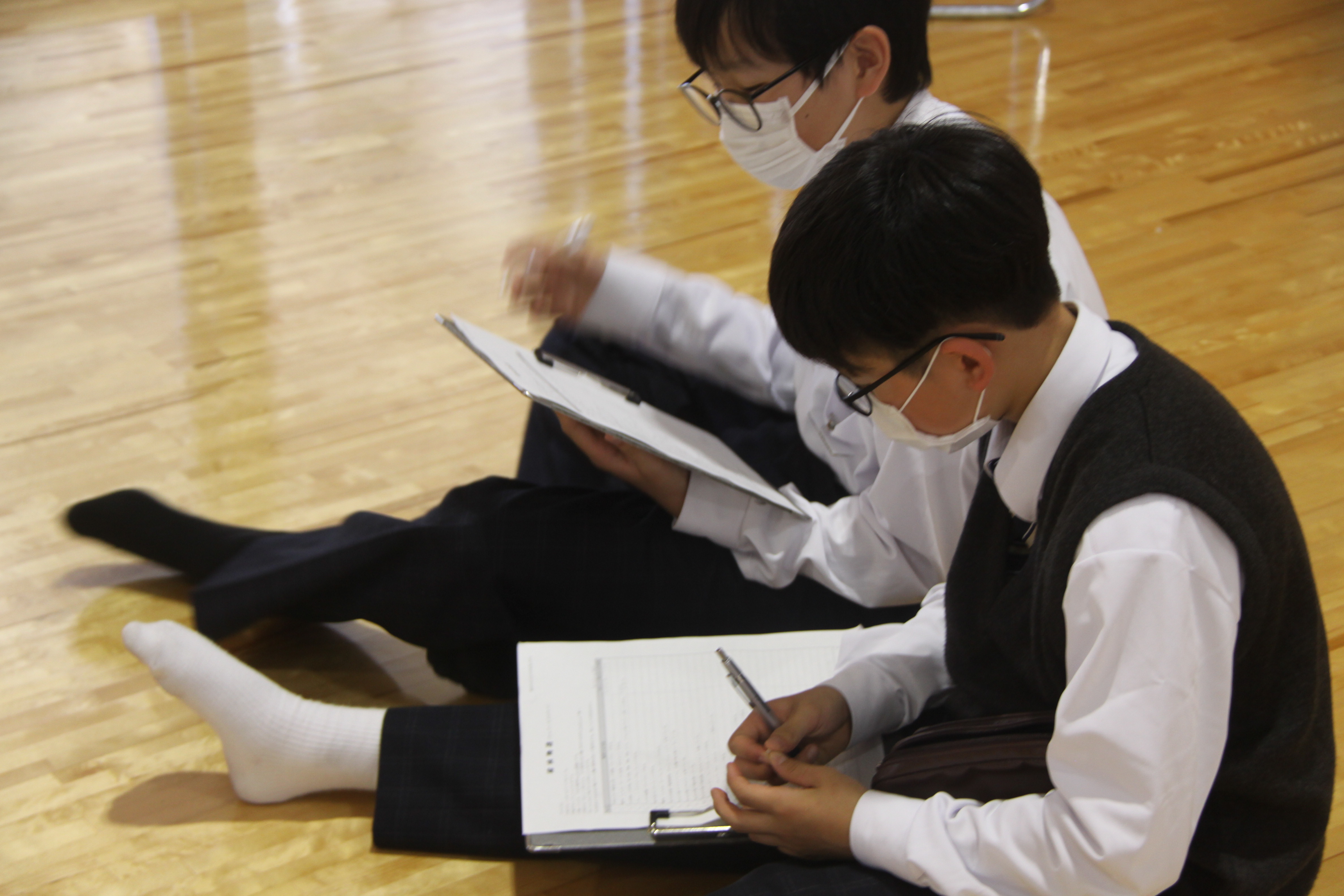
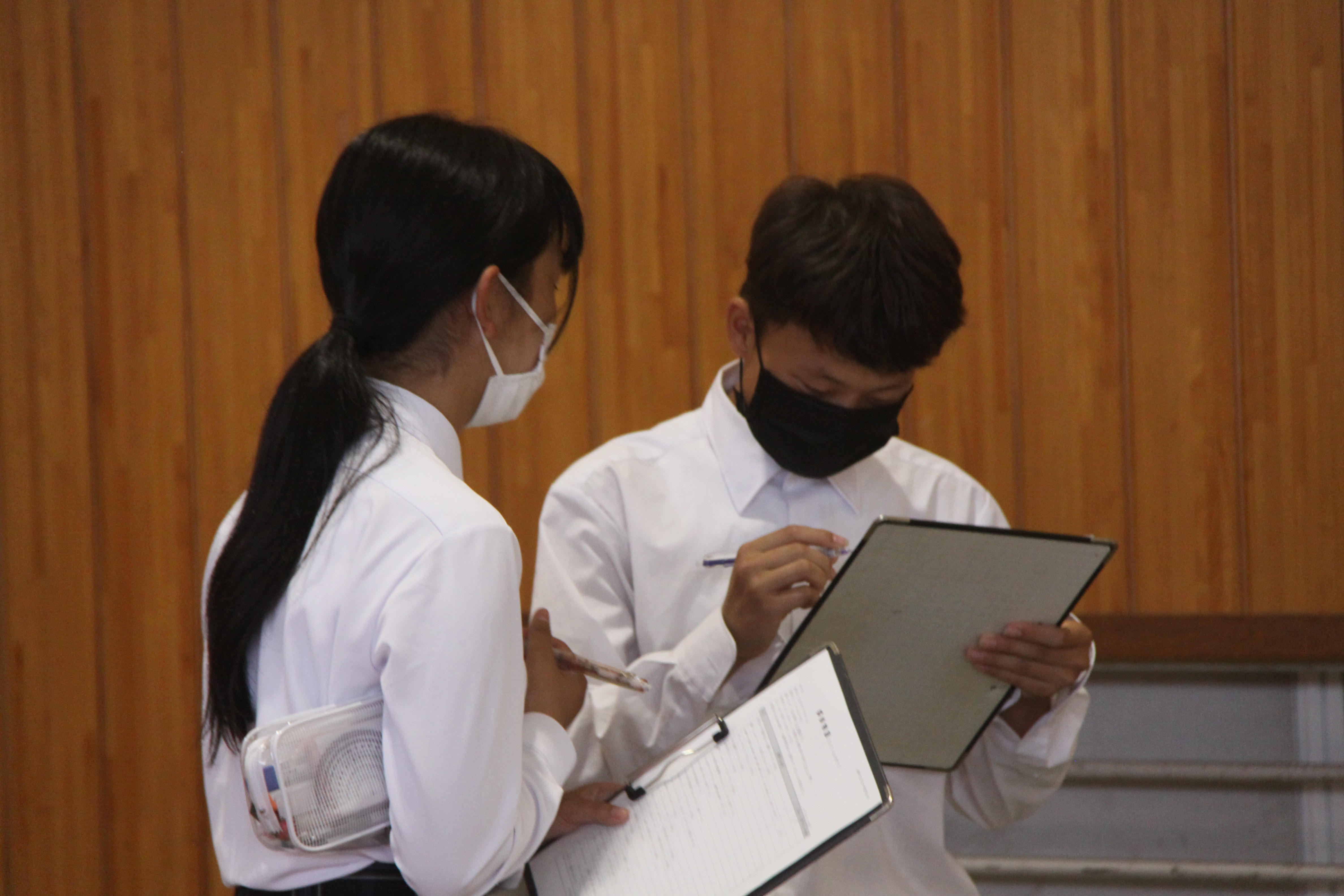


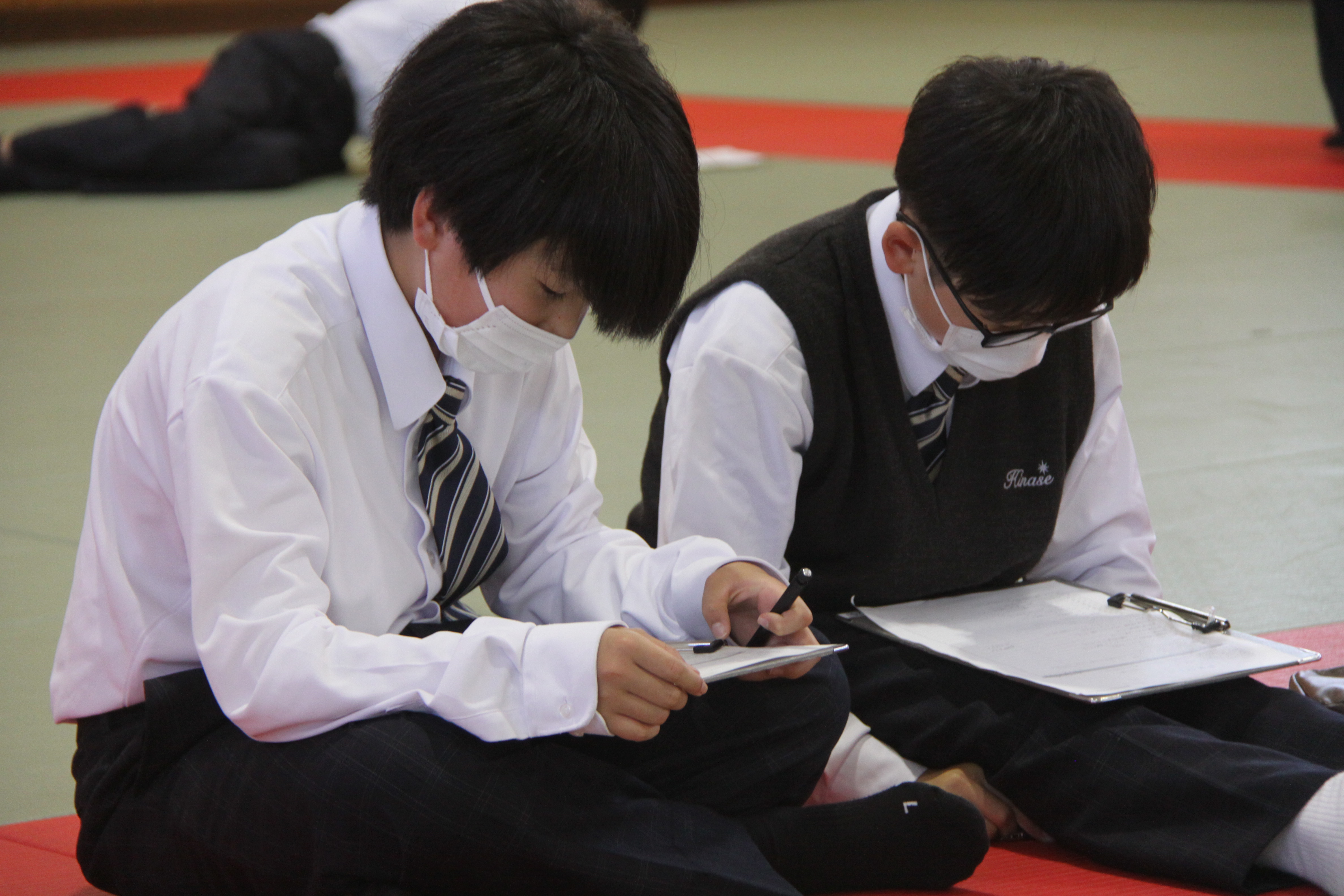




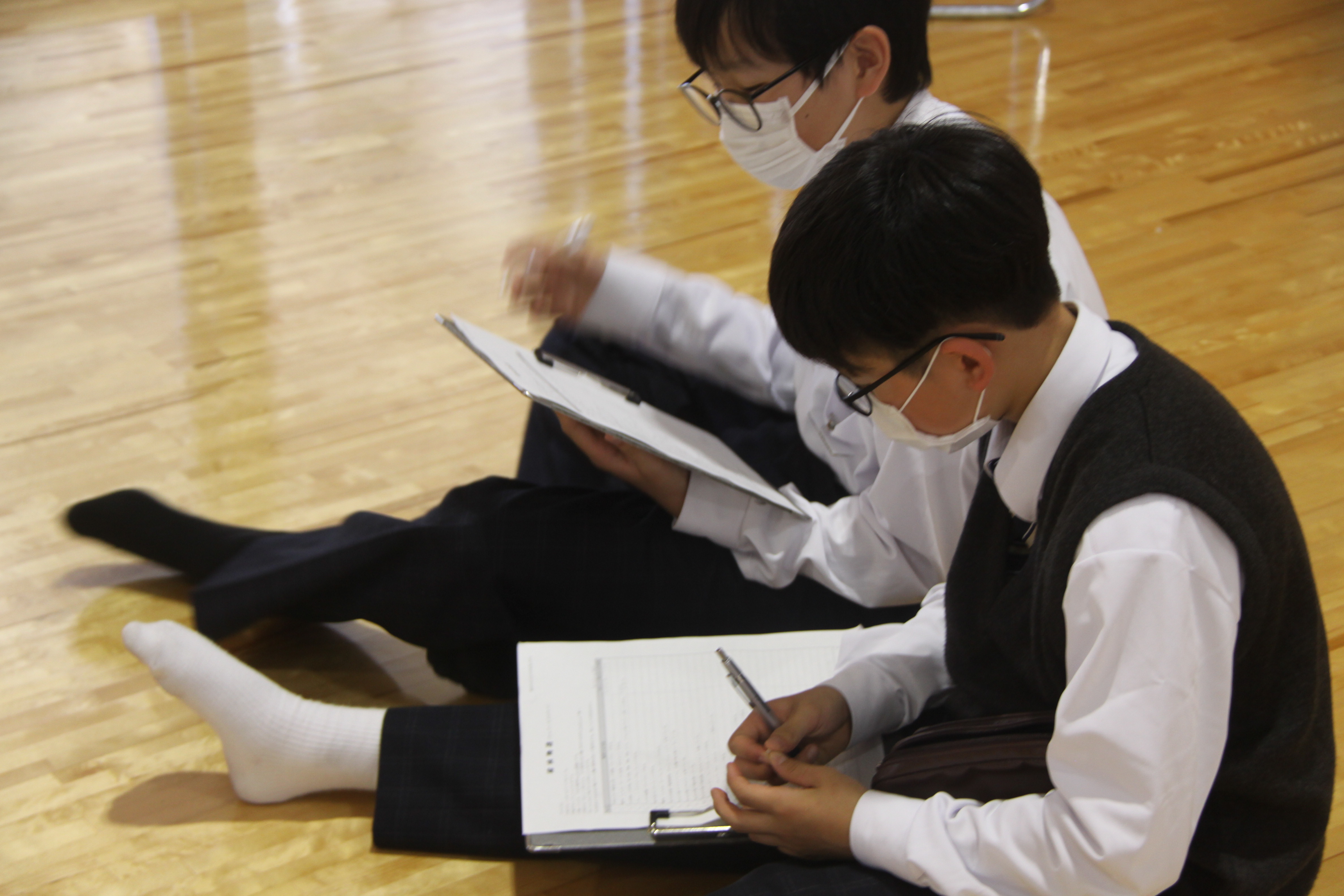
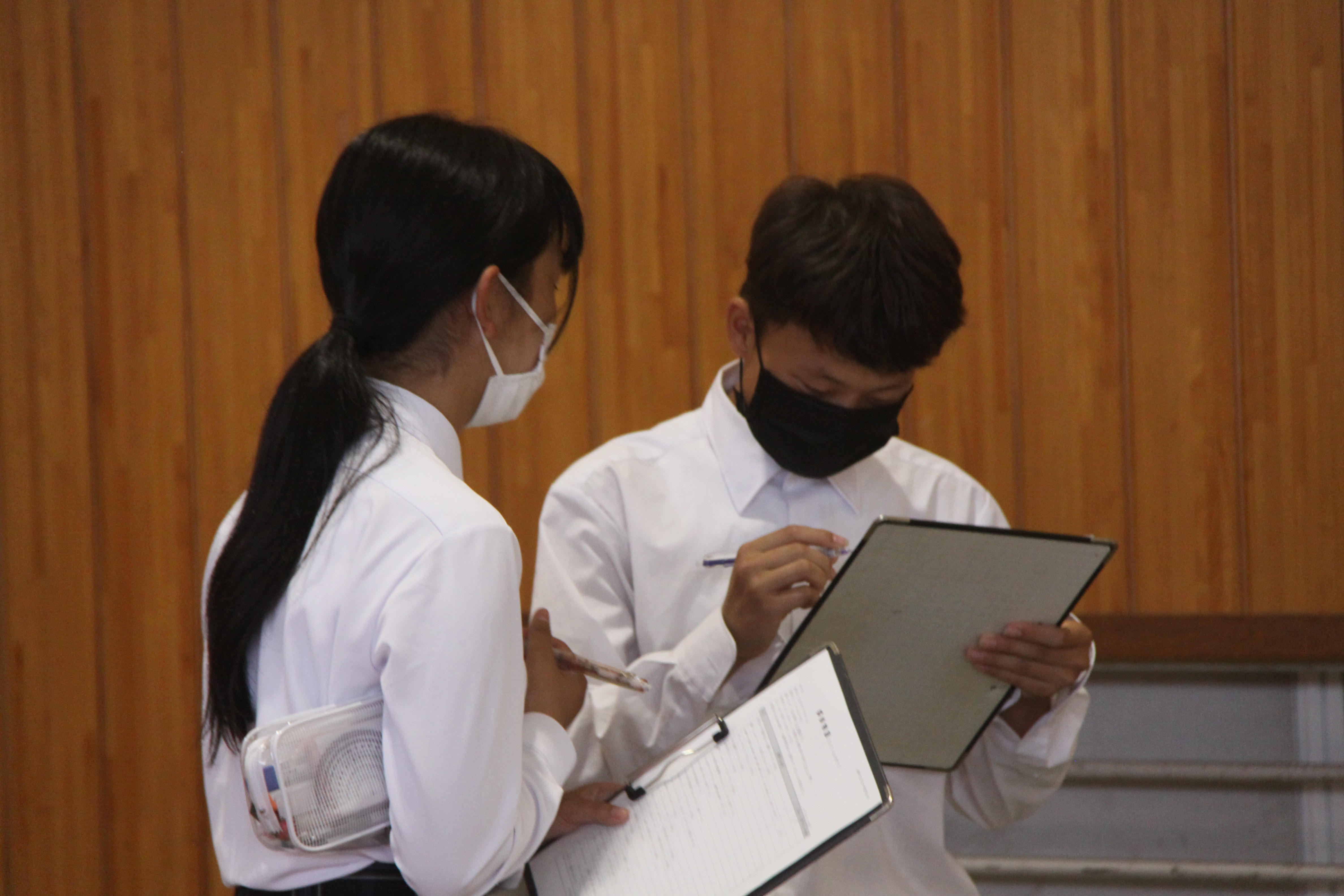


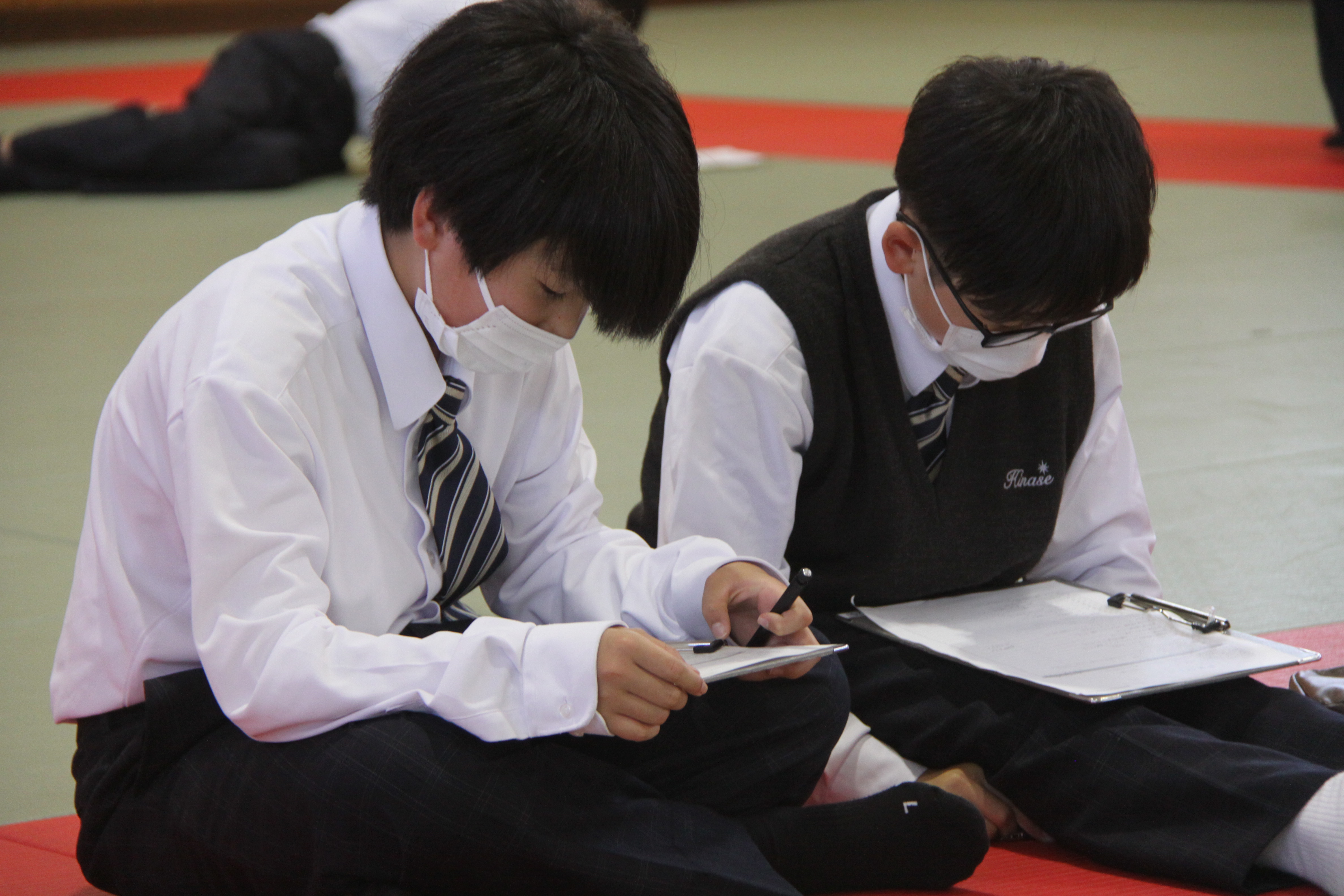

◎多くの人に支えられて 川渕・谷口人権擁護委員さん来校(5/17(水))
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている方々です。人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足しました。全国で、人権擁護委員は現在、約14,000人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村に配置されて、積極的な人権擁護活動を行っています。6月には人権SOSミニレターを持ってきてくだる予定です。

◎多くの人に支えられて
読み語りボランティアさんに誘(いざな)われて、自分の世界が広がる時間になっています。
(^▽^)/(5/17(水))
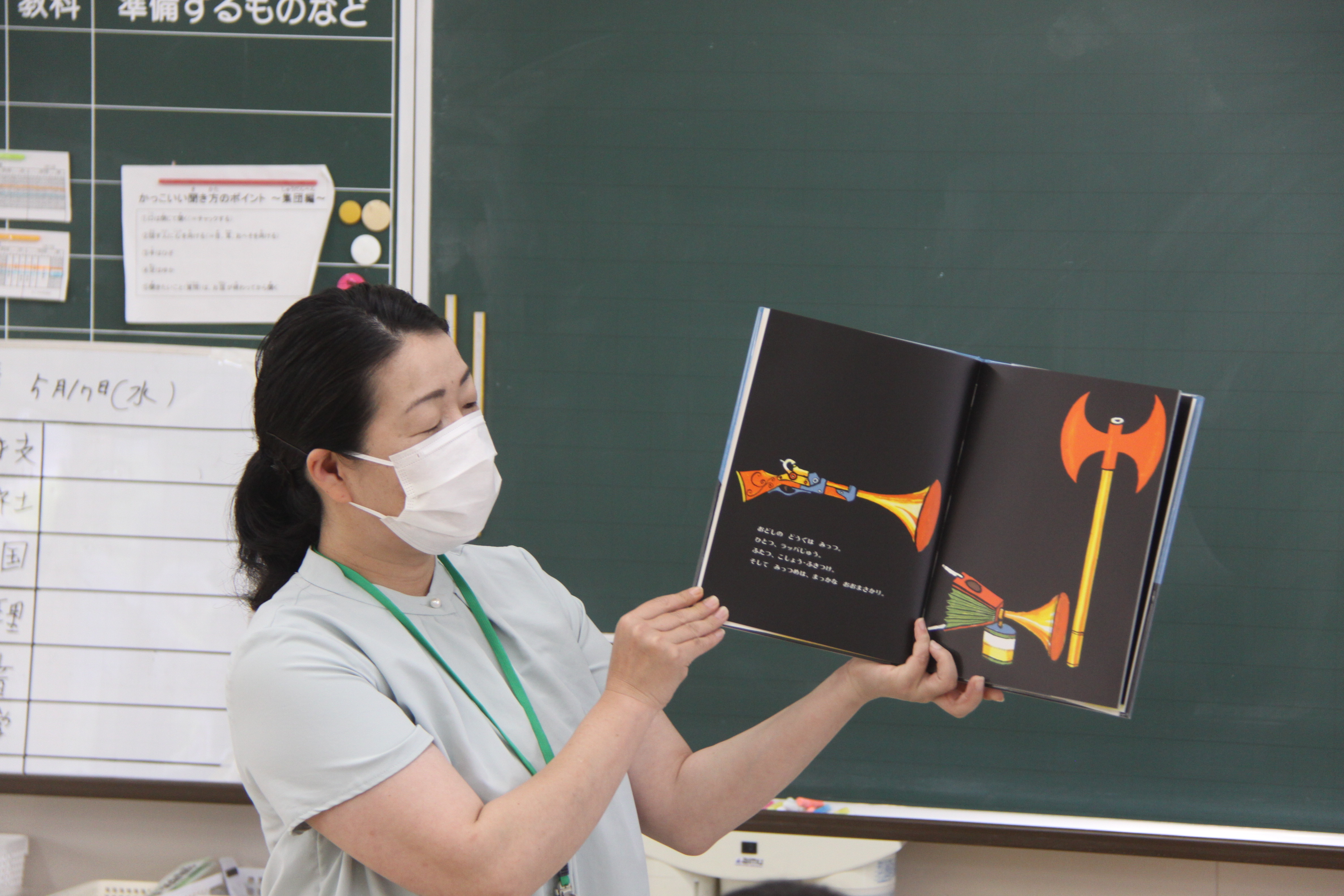





◎ひな中の風~~おおきくなあれ~ (5/17(水))

◎限りある時間を大事に、大切に。 ~部活動も自分らしくせいいっぱい~
日生中は、部の活動を通して心身の発達を促し,日常の生活を豊かにし,顧問の指導のもと,それぞれの部の特性やその正しい行い方・練習方法や正しい知識を身につけることを目的に、時間を大切にして朝練習と放課後の練習に取り組んでいます。朝の活動は7:30~8:10。午後部の最終下校時間は、4月~9月は18:00。10月・2~3月は17:30。11月~1月は17:00です。ただし、大会前2週間は30分間の延長を認めています。(中体連・中吹連主催の大会のみ)また、原則,6月・12月・3月に行われる,到達度確認テスト1週間前から終了までは活動しません。さらに、休養日として、月曜日は完全休止日、水曜日の午後部‚木曜日の朝部は休止としています。
現在、6月17日・18日の備前東地区夏季祖総合体育大会、第60回吹奏楽祭に向けてどの部も一生懸命取り組んでいます。これからもご支援をよろしくお願いします。
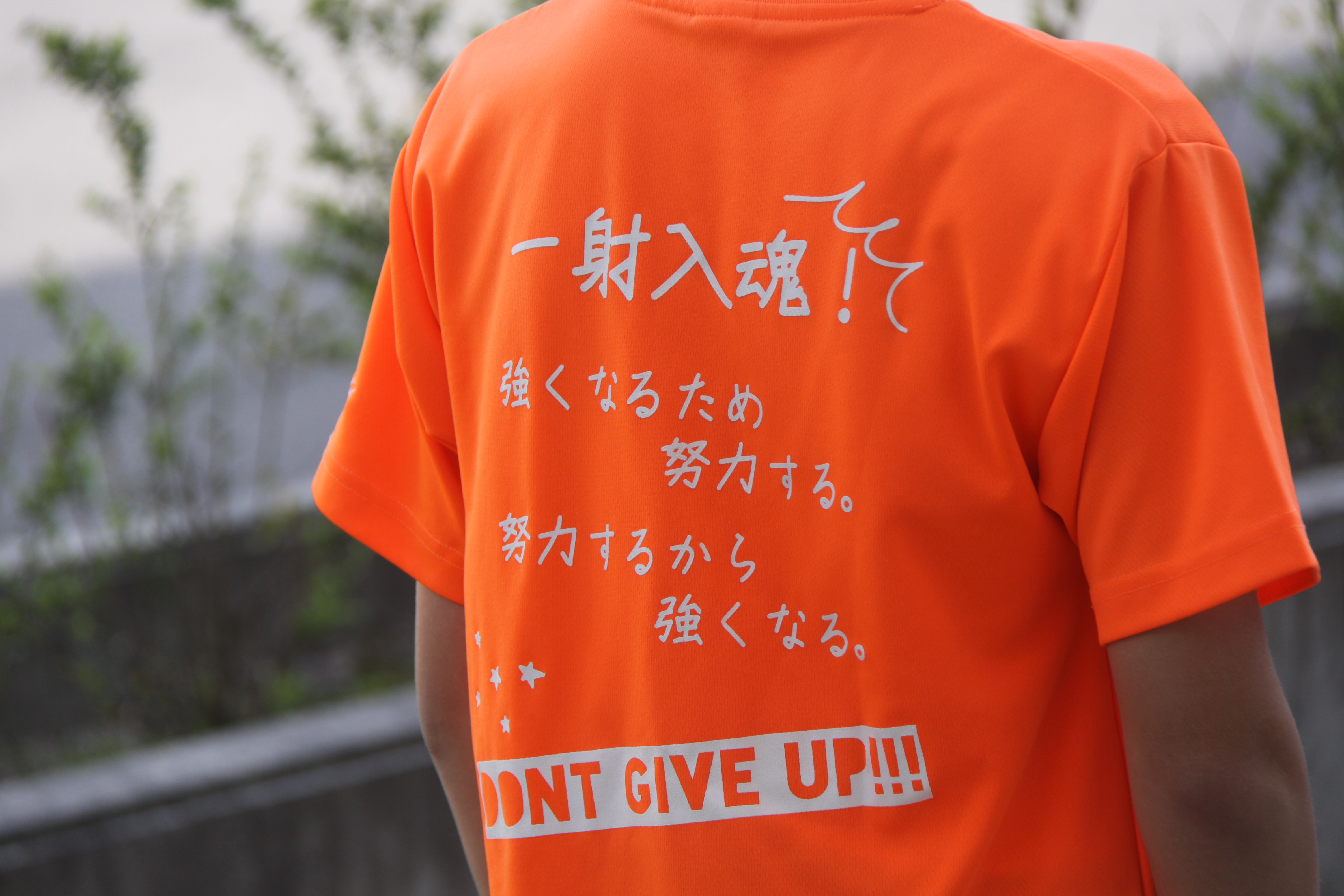





◎BLUE PERIOD ~自分らしくせいいっぱい~
『あなたが青く見えるなら りんごもうさぎの体も青くていいんだよ』




◎地域とともにある学校
~藤原さんをお招きして備前焼体験学習~(5/16(火))
私たちの「手・家事」を讃えた『手の知恵(藤原房子著)』を紹介した八塚実氏のコトバを紹介します。
「まぜる する きる きざむ ひく おろす むく さばく たたく はかる うつ こす ぬう く(絎)ける あむ むすぶ あらう すすぐ しぼる のばす たたむ はたく はく ふく みがく つつむ しめる かく とぐ はこぶ つかむ もつ…なんと日常生活はすごいね。私たちの手はたいしたものだね。もっともっとたくさんのことが出来るんだ」




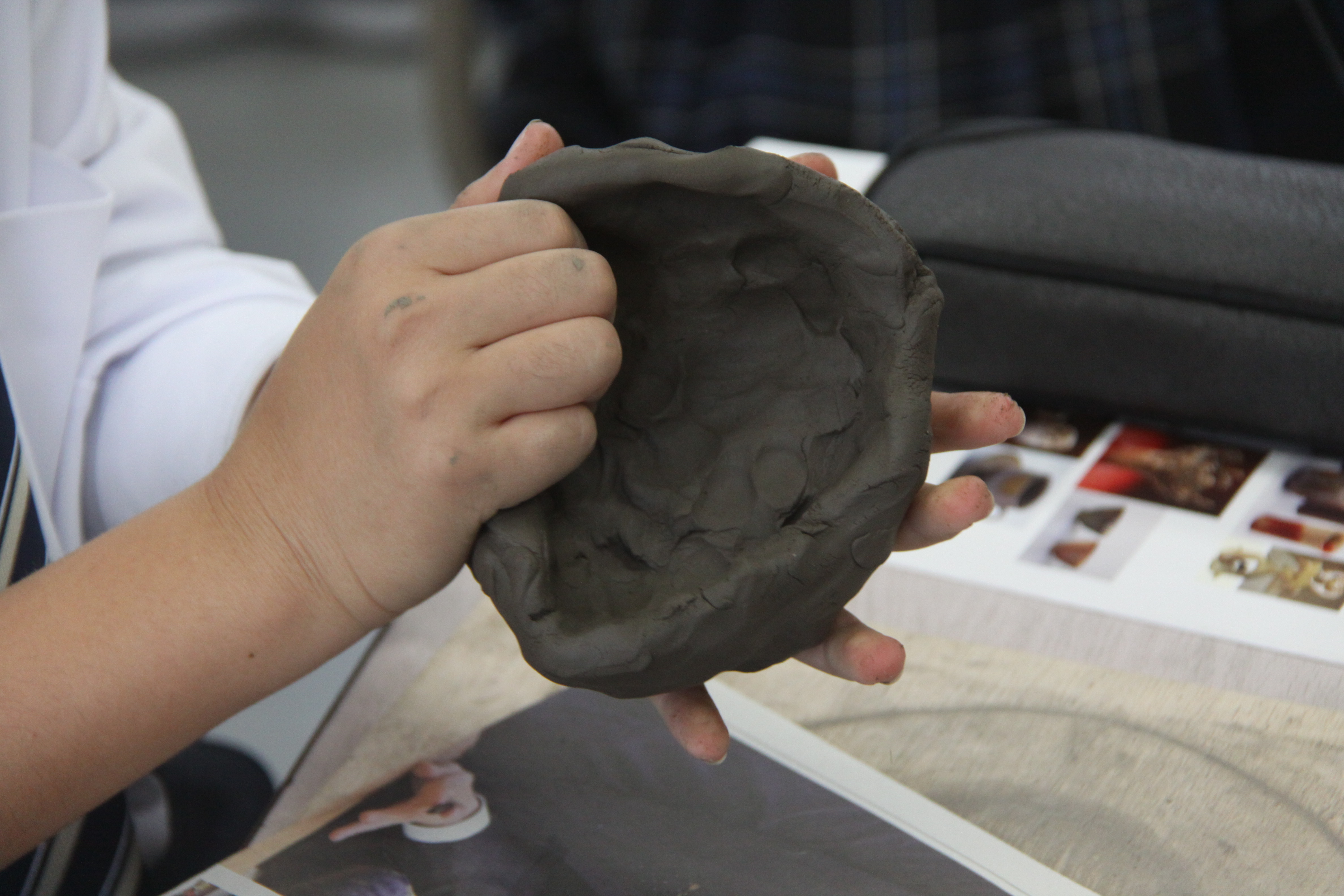




◎One for All All for One
~創り出すということ 練習を積み重ねるということ~ (5/16(火))



◎ひな中の風 ~~わたしたちの大切な時間 しんしんタイム~
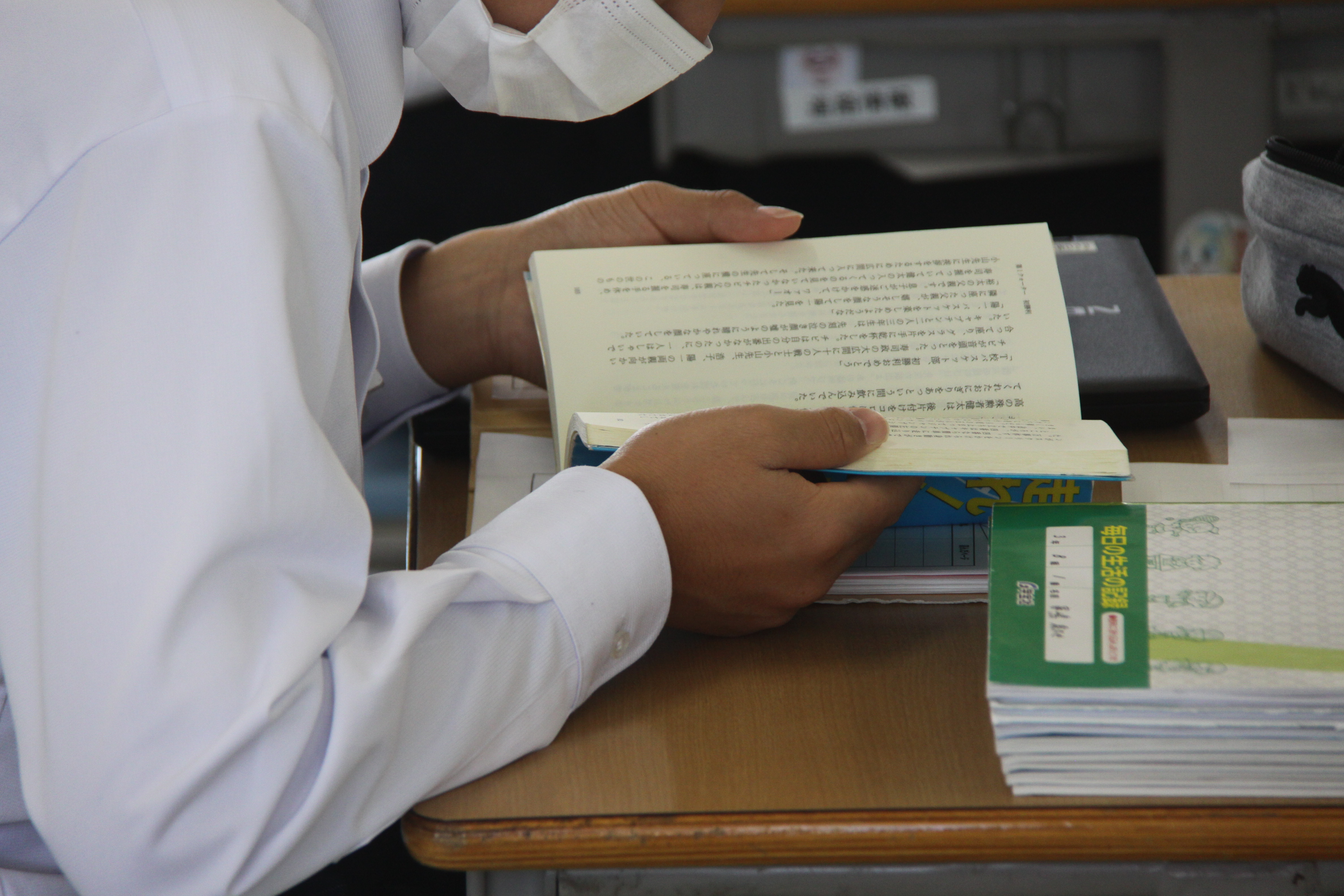


◎One for All All for One
~創り出すということ~星輝祭体育の部練習 (5/16(火))









お茶をいつもありがとうございます。(5/22からスポーツドリンクが可となります)
◎ひな中のかぜ~~こころよく、ちょっとした手伝いをしてくれるみんな。うれしいなあ。本の整理整頓、ありがとう。

◎歩み新たに日に生(な)せば♬
~今日もみんな一日を大切にしようね(5/15(月))~
体育委員会は毎週月曜日にあいさつ運動に取り組んでいます。



◎自分らしくせいいっぱい~第1回参観日~(5/13(土))
本年度最初の参観日、(授業参観、学年懇談会、部活動懇談会)を開催しました。お忙しい中ご参加をありがとうございました。(PTA総会は、活動精選の一環として書面開催(5/12配布)とさせていただきました)ご参加ありがとうございました。これからも≪生き方を考え、夢を育み、夢を実現させる力をつける学校づくり≫を進めてまいります。どうぞ、ご支援・ご協力を今後もよろしくお願いいたします。
大切にしたい詩をひとつ紹介します。
教室はまちがうところだ、 みんなどしどし手を上げて まちがった意見を いおうじゃない まちがった答えを いおうじゃないか まちがうことをおそれちゃいけない まちがった
ものをワラッちゃいけない まちがった意見を まちがった答えを ああじゃないか こうじゃないかと みんなで出し合い 言い合うなかでだんだん ほんとのものを 見つけていくのだ そうしてみんなで伸びていくのだ いつも正しくまちがいのない 答えをしなくちゃならんと思って そういうとこだと思っているから まちがうことがこわくてこわくて 手も上げられないで小さくなって 黙りこくって時間がすぎる しかたがないから先生だけが 勝手にしゃべって生徒はうわのそら それじゃあちっとも伸びてはいけない 神様でさえまちがう世の中 ましてこれから人間になろうと しているぼくらがまちがったって なにがおかしいあたりまえじゃないか うつむきうつむき そうっと上げた手 はじめて上げた手 先生がさした どきりと胸が大きく鳴って どっきどっきと体が燃えて 立ったとたんに忘れてしまった なんだかぼそぼそしゃべったけれども なにを言ったかちんぷんかんぷん 私はことりと座ってしまった 体がすうっと涼しくなって ああ言やあよかった こう言やあよかった あとでいいこと浮かんでくるのに それでいいのだ いくどもいくども おんなじことをくりかえすうちに それからだんだんどきりがやんで 言いたいことが言えてくるのだ はじめからうまいこと 言えるはずないんだ はじめから 答えがあたるはずないんだ なんどもなんども言ってるうちに まちがううちに 言いたいことの半分くらいは どうやらこうやら言えてくるのだ そうしてたまには答えも当たる まちがいだらけの僕らの教室 おそれちゃいけない ワラッちゃいけない 安心して手を上げ 安心してまちがえや まちがったってワラッたり ばかにしたりおこったり そんなものはおりゃあせん まちがったって誰かがよ なおしてくれるし教えてくれる 困ったときには先生が ない知恵しぼって教えるで そんな教室つくろうやあ おまえへんだと言われたって あんたちがうと言われたって そう思うだからしょうがない だれかがかりにもワラッたら まちがうことがなぜわるい まちがってることわかればよ 人が言おうが言うまいが おらあ自分であらためる わからなけりゃあそのかわり だれが言おうが こづこうが おらあ根性まげねえだ そんな教室つくろうやあ 出典:『教室はまちがうところだ』


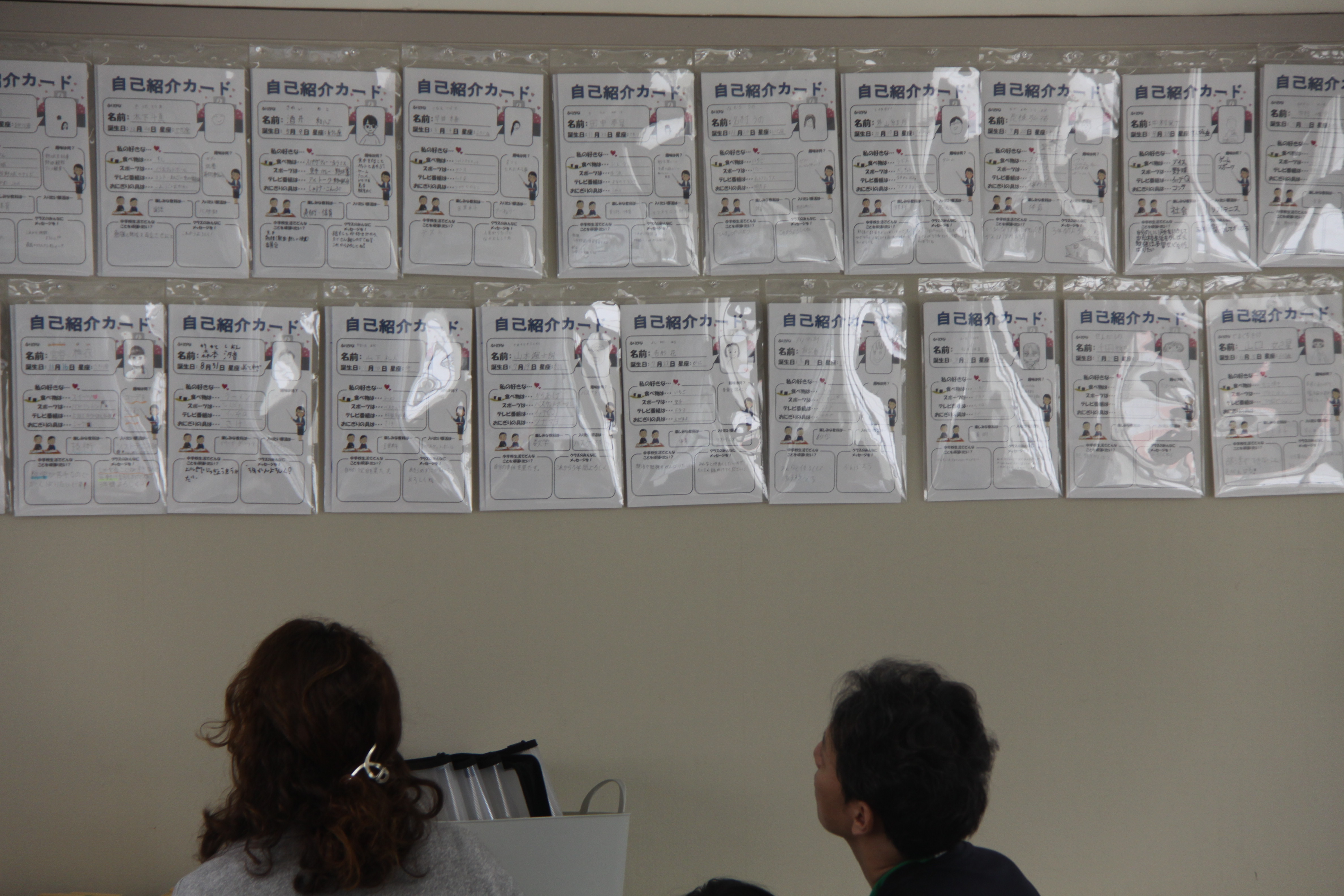
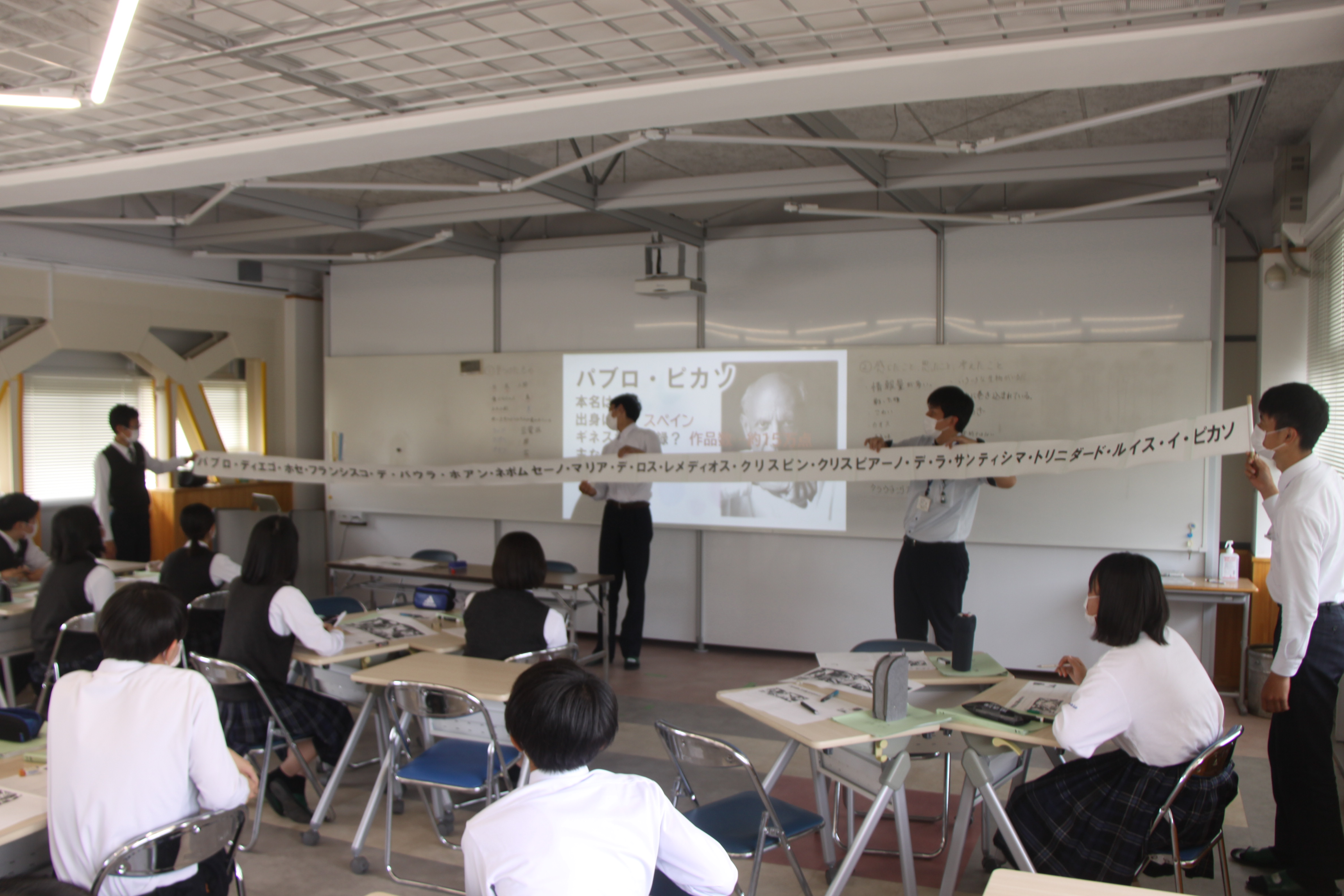


◎多くの人に支えられて(5/13(土))
学校近隣の方が校門付近の環境美化をしてくださっています。いつもありがとうございます。

◎夢に向かってたくましく生きる(5/12(金))
日生中は、自ら進んで学習に取り組む意欲と実践力をもてるよう、委員会活動や係・当番活動などを生徒の主体的な取り組みを大切にしています。(写真は、体育委員会の活動 学習係 給食当番 生徒会による放送)*体育委員会は自転車施錠の習慣化に向けて、呼びかけを行っています。参考までに、岡山県警少年課によると、県内の2022年の自転車盗難認知件数は2007件で前年比21%増、そのうち74%の自転車が鍵をかけていませんでした。

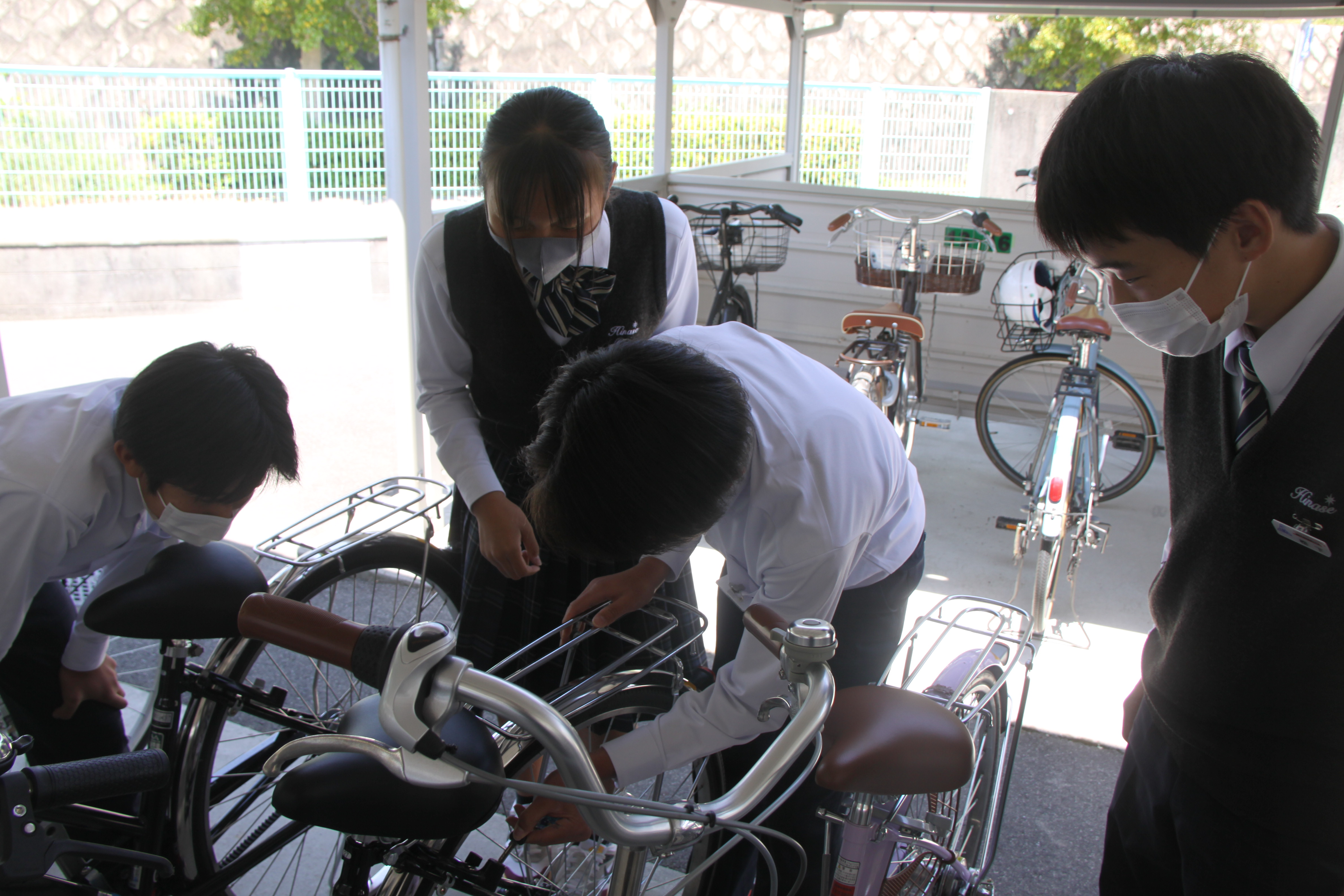

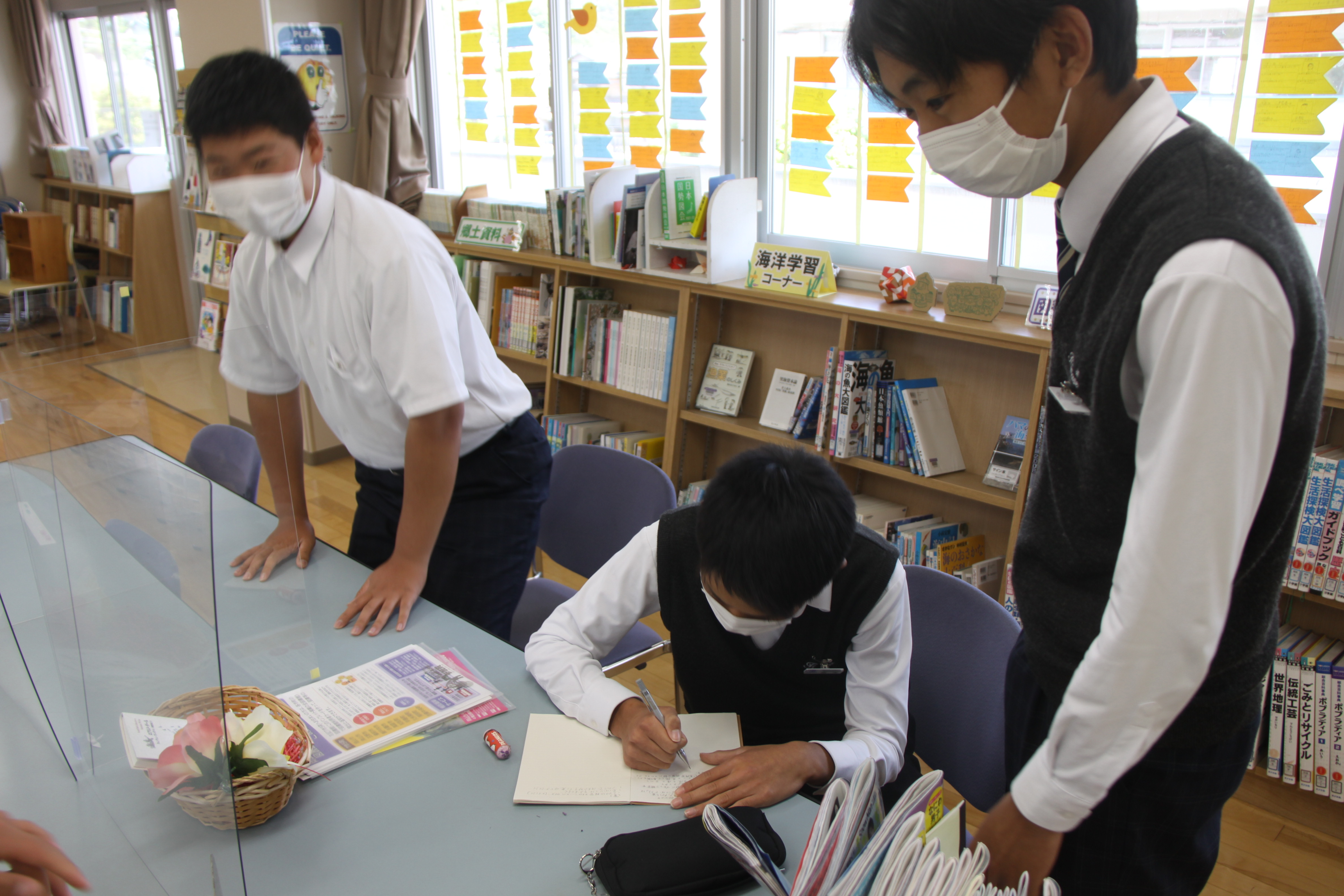





◎多くの人に支えられて(5/12(金))
備前市民生委員児童委員協議会日生地区の方々が、春の交通安全週間に合わせて、あいさつ運動に来校されました。子どもたちは、委員の皆さんととあいさつを交わし、気持ちのよい朝のスタートとなりました。
地域の民生委員さんは、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行っておられます。
交通安全週間に合わせて、本校教職員も街頭指導に立っています。地域・保護者の皆さんも、「行ってらっしゃい」「おはよう」「お帰り」など、これからも生徒へのあたたかい声かけをよろしくお願いします。
交通安全にお気をつけくださいませ。


◎豊かな学びを。2年生は何を育てているのかな。~~ひな中の風~~
多くの子どもたちにとって農業が身近に存在しなくなった生活環境の中で、作物の栽培に必要な基礎・基本を確認することは大切です。 日本・世界の農業の未来を支える農業観、生きる力につながる農業観、人格形成につながる農業觀・ 世界観を育てる大切な学習のひとつとして栽培学習に取り組んでいます。(5/11(木))
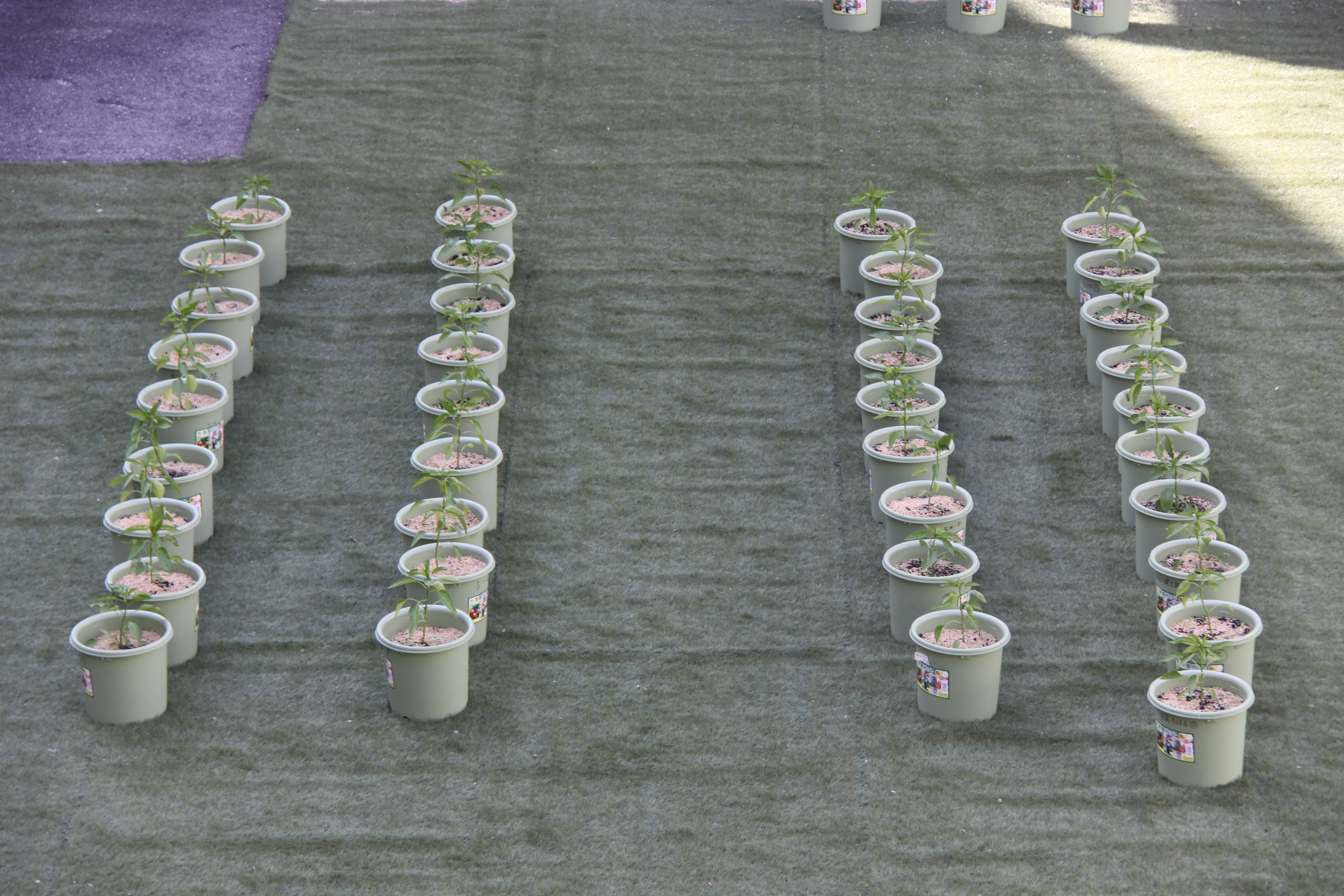
◎One for All All for One 一所懸命はカッコイイ。
(5/11(木)星輝祭・体育の部練習)






◎ひな中の風~~大切な時間として。もくもく清掃に取り組んでいます。
(5/10(水))

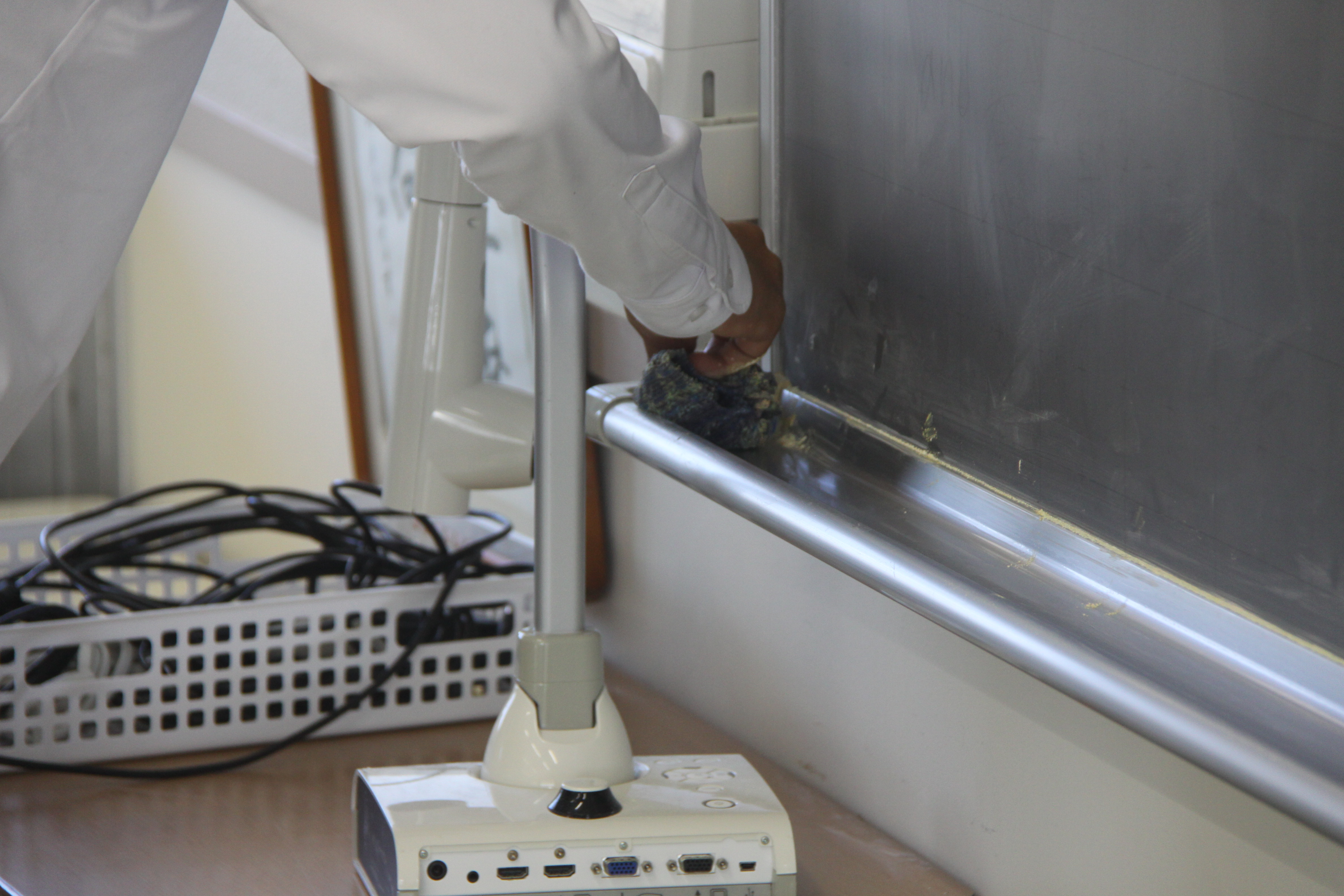

◎《ガンディーの左フックをかわしつつマザーテレサのビンタをくらう 西村曜》
日生中では積極的に委員会活動に取り組んでいます。文化委員会でも、一人ひとりのメッセージを書いた「こいのぼり」を図書室に掲示しています。足を運んで、世界が広がるたくさんの本に出会いましょうね。



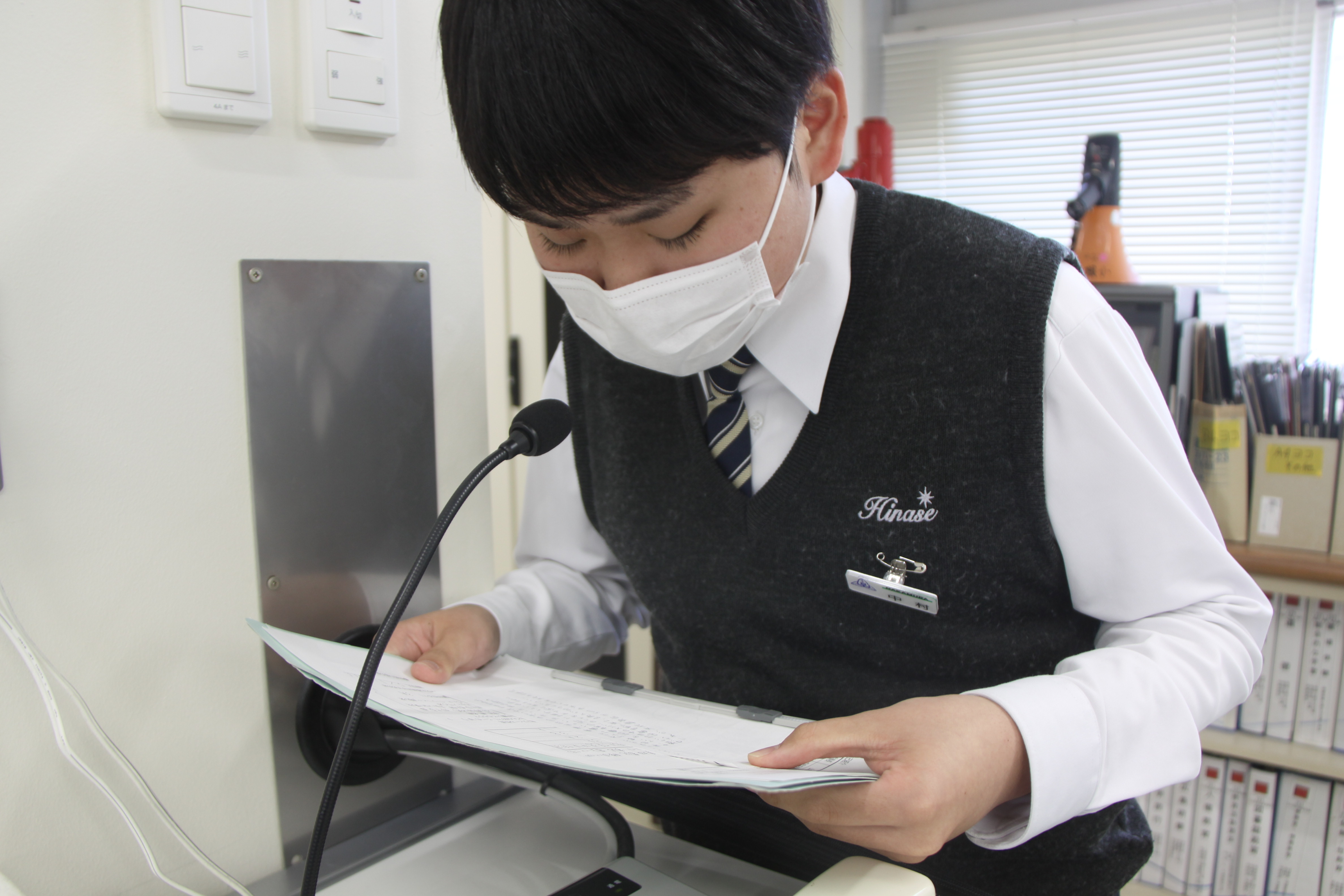
◎地域とともにある学校~カキの種つけ実習(海洋学習)(5/9(火))
今年度も1・3年生が種つけに参加しました。5月24・26日には流れ藻の回収に取り組みます。





◎ひな中の風 ~~本当にカッコいい着こなしをしよう~~
校内掲示している、先輩(制服検討委員会)から後輩たちへのメッセージを紹介します。
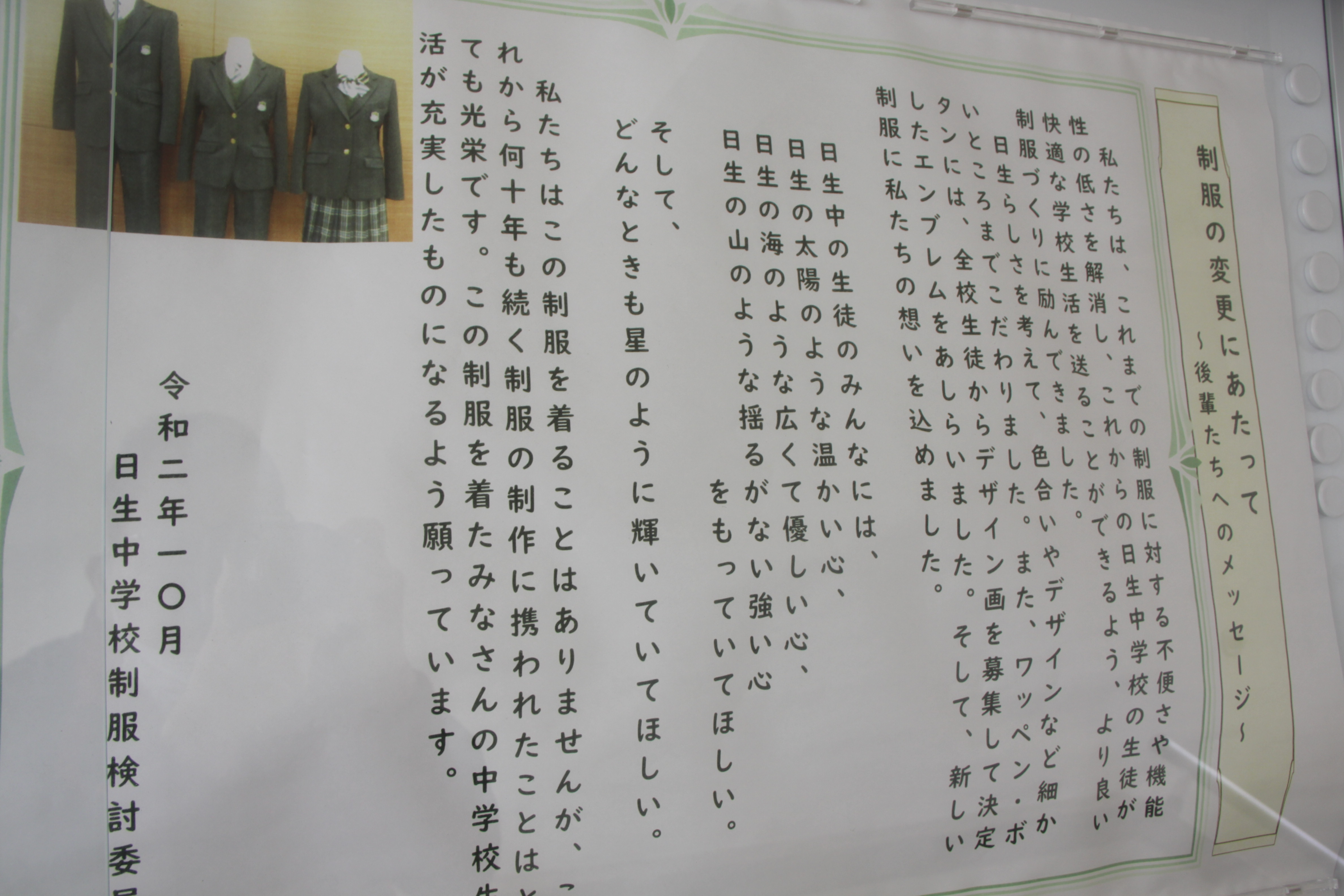
◎多くのひとにささえられて(5/3(火))
「生徒たちのためになるべくはやめに」と、大型連休中に、校門フェンスの修繕をしていただきました。ありがとうございました。

◎〈バンザイの姿勢で眠りいる吾子よ そうだバンザイ生まれてバンザイ 俵万智〉
5月。図書室にも、こいのぼりがたくさん泳いでいます。

◎仲間とともに学び合う~1年生閑谷研修(4/28(金))
「次の活動を考えて早めに行動する」「話をするひとの方へ向いて聞く」「仲間と協力して活動する」を目的に、閑谷研修に取り組みました。≪深い学び≫と≪反省≫を、これからの学校生活につなげていきましょうね。



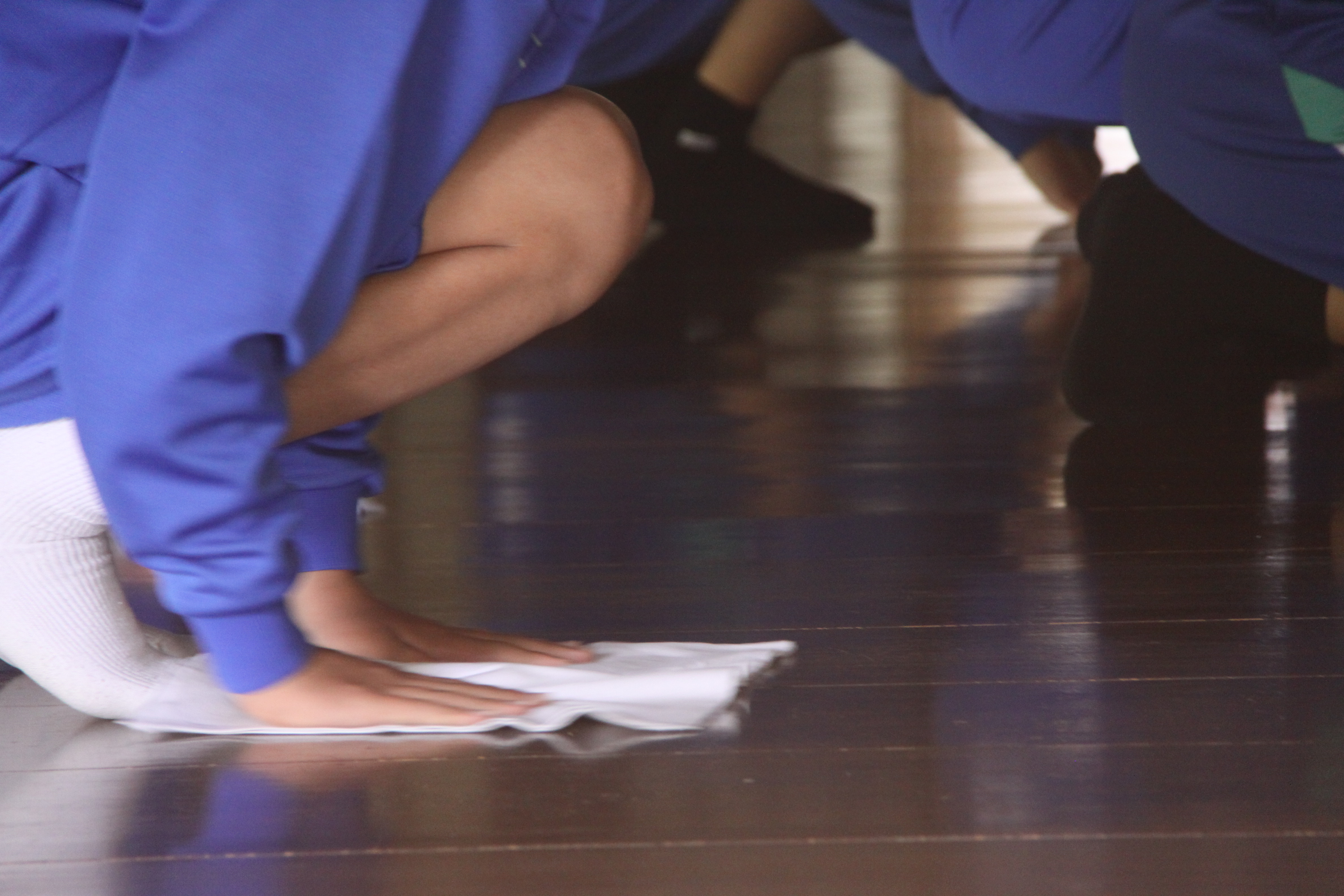


◎地域とともにある学校 ~ひなビジョン来校~(4/27(木))
4月に転勤して来られた先生方のインタビュー(撮影)にひなビジョンさんが来校されました。(カメラを前すると結構緊張しますね。)自分の思っていることを伝えることは大切ですね。…生徒諸君はインタビューは慣れているのでしょうか?

◎夢に向かってたくましく生きる
日生中は、困難なことがあってもあきらめないしなやかな心が育つよう、「授業」を大切にしています。
「これってどうするん?」に応える仲間として。(写真は、学びあう授業のようす4/27(木))


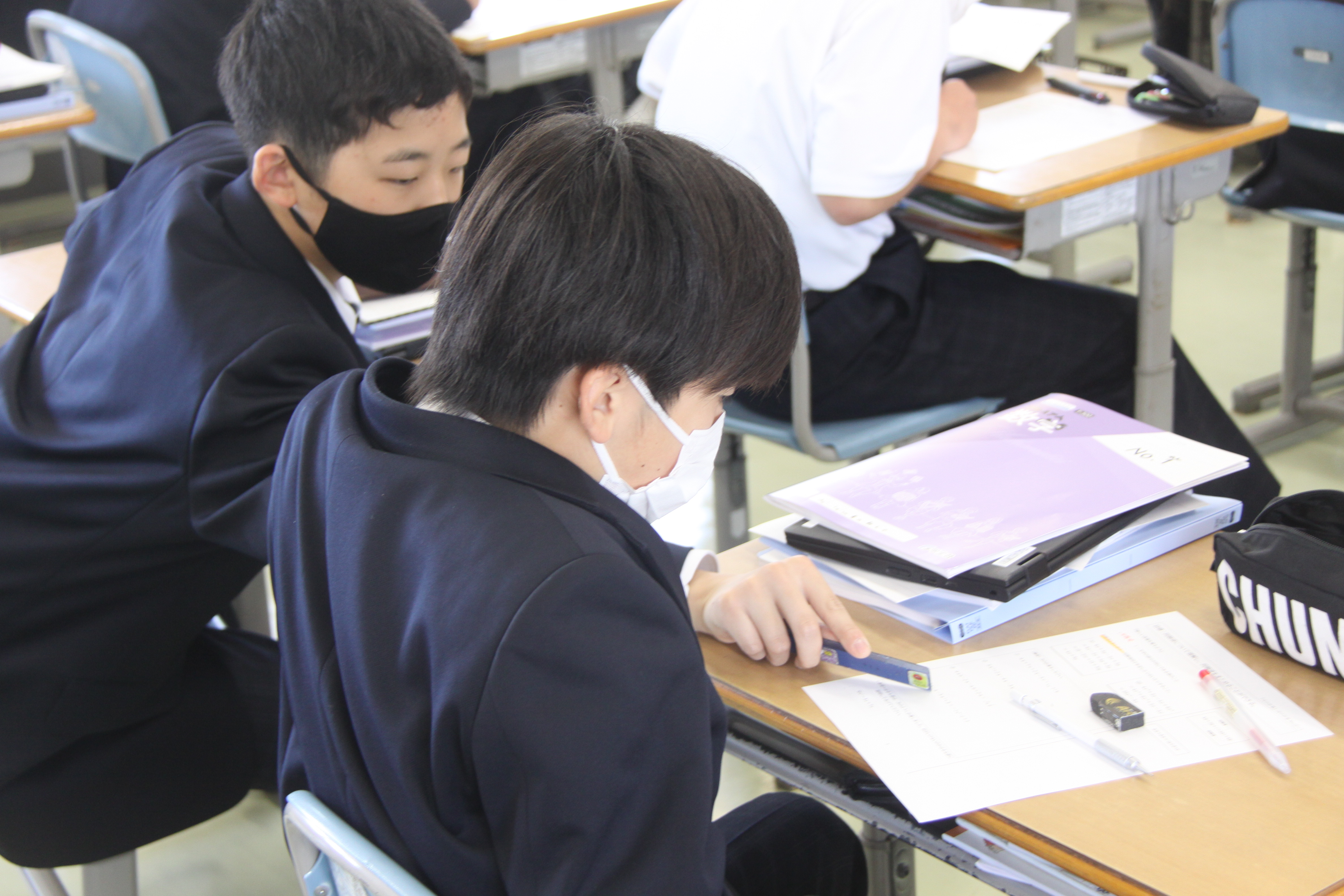
◎地域とともにある学校 ~海洋学習スタート~
日生漁業協同組合から天倉さんをお招きして、今年度も海洋学習の取組をスタートしました。
5/9は1,3年生はカキの種付け学習、5/24⑤⑥は、1,3年生が流れ藻の回収活動、5/26⑤⑥は、2年生が流れ藻の回収活動に取り組みます。

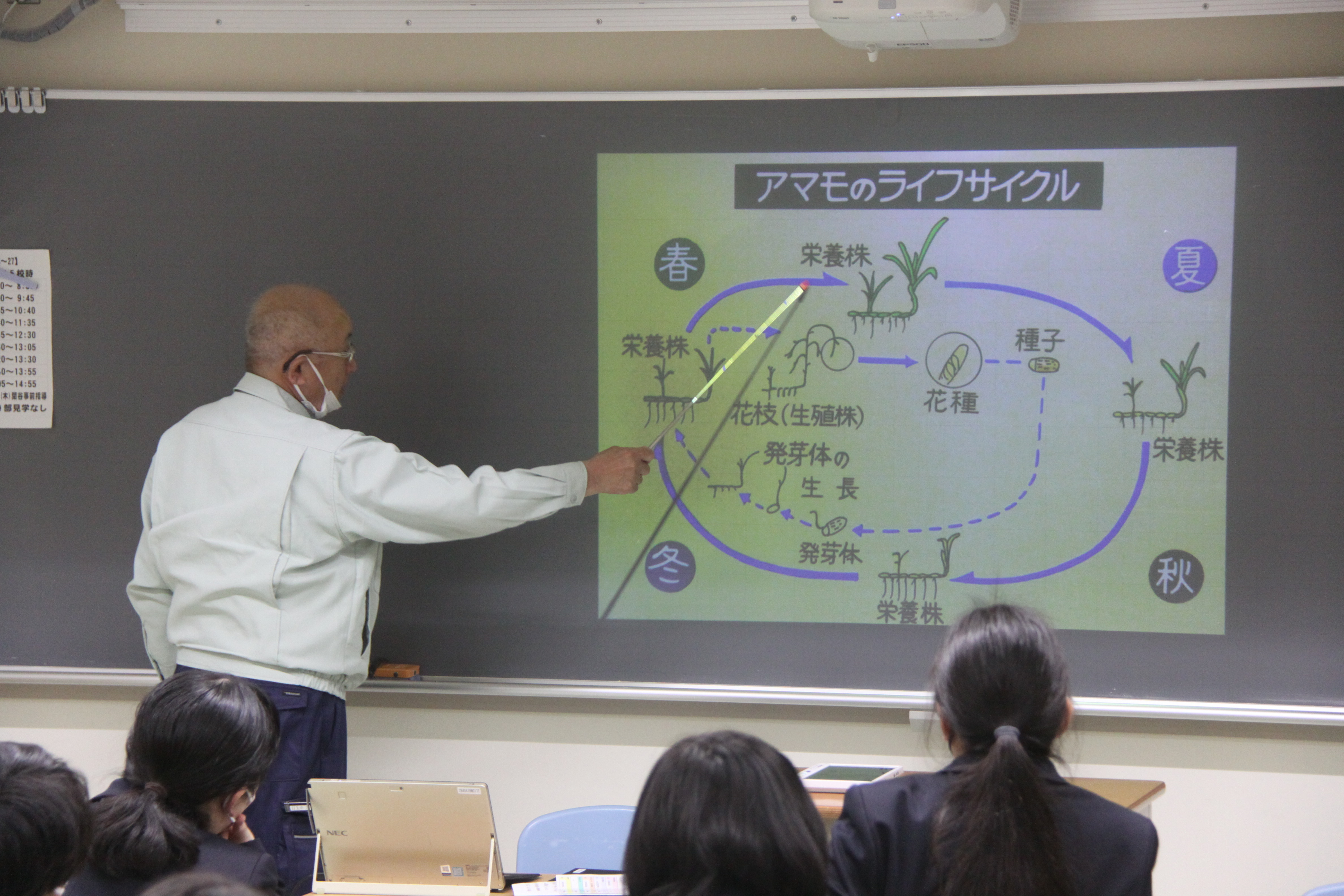
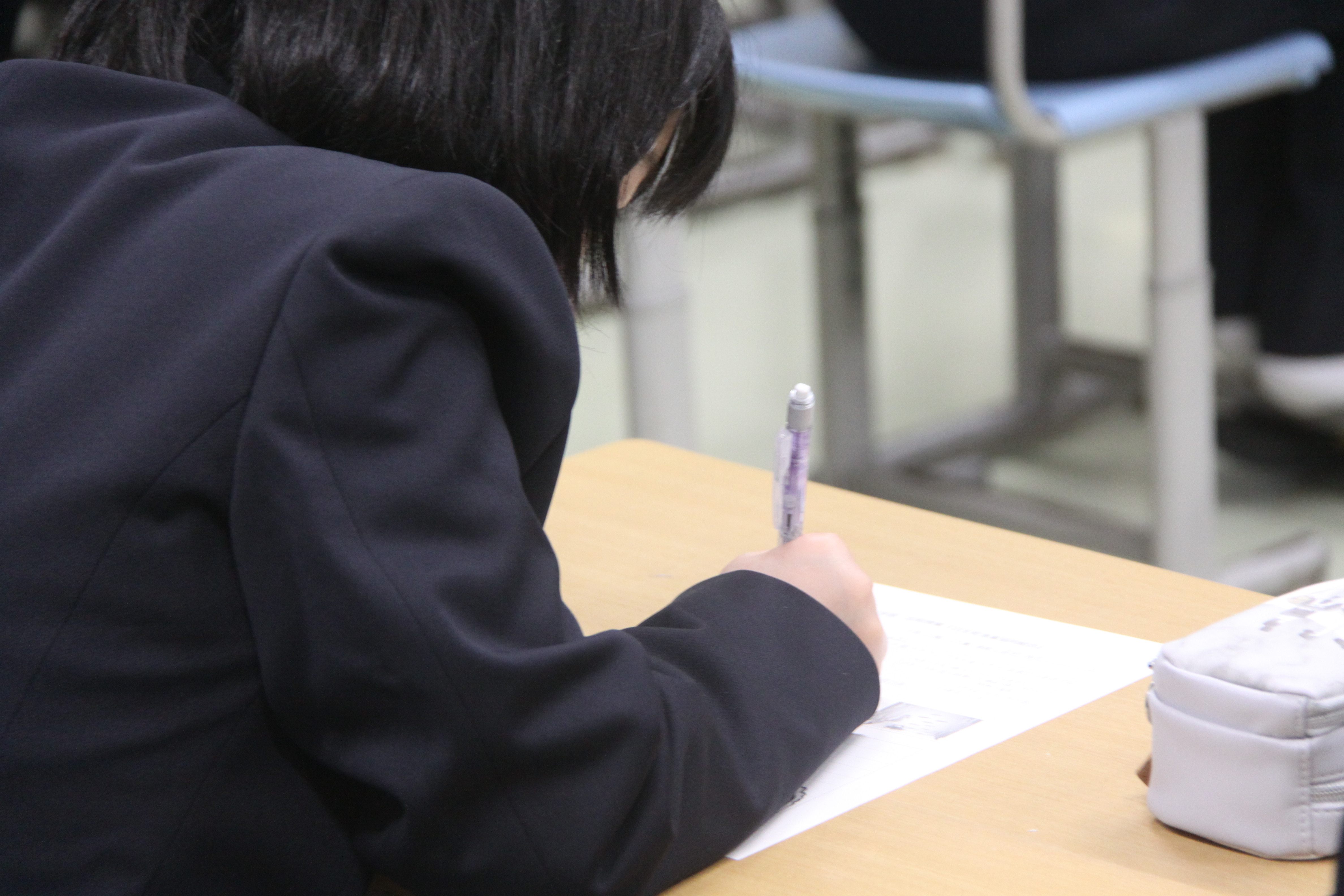
◎ひな中の風~~オキナワ修学旅行(4/26(水)~28(金))
Link Memories~沖縄からつなぐ おおきな輪~

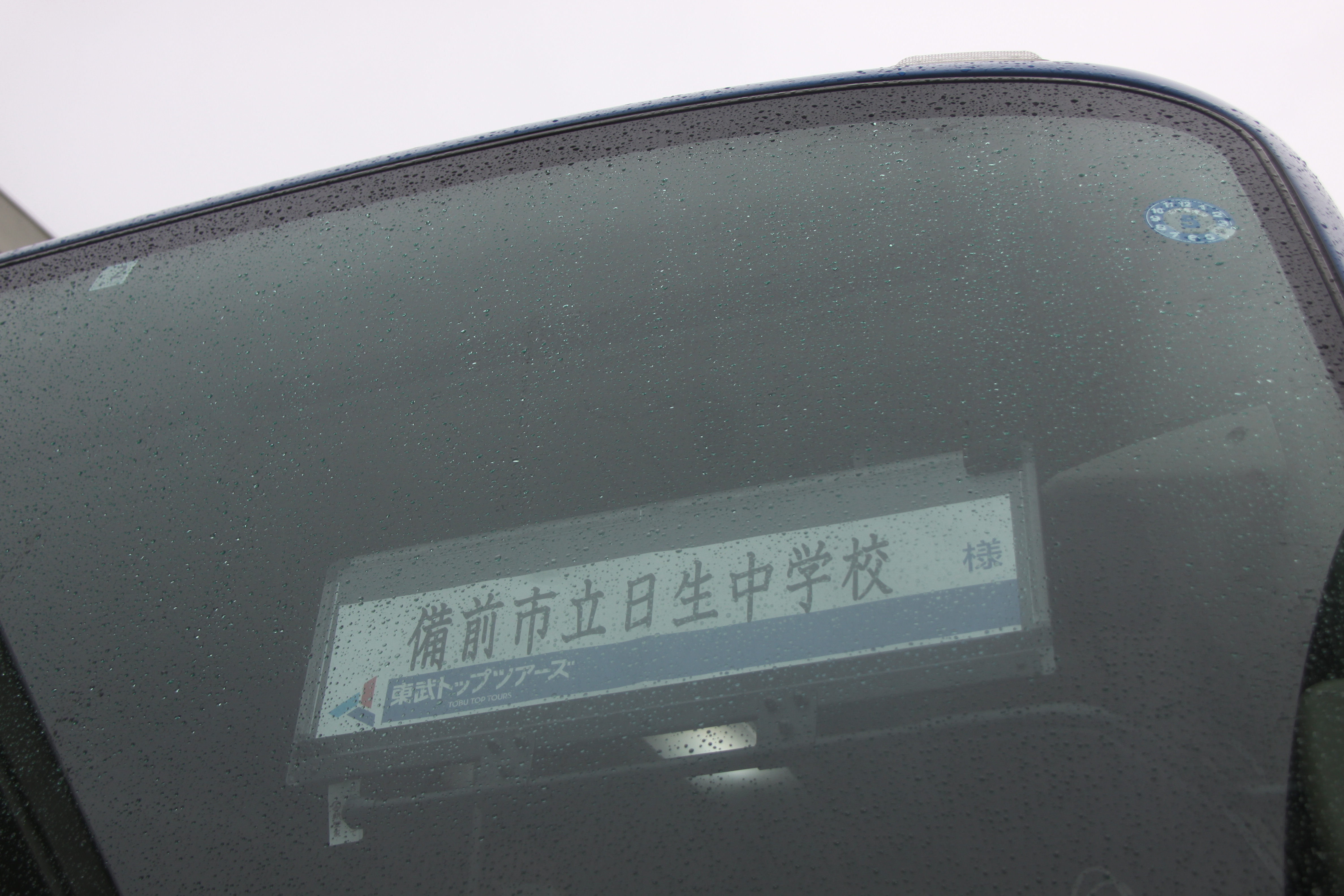

◎多くの人に支えられて ~いただきます ごちそうさま~
日生中は食育を大事にしています。この日も、自分の体調等に合わせて自分で量を調整している様子がみられました。感謝の気持ちを大切に「いただきます ごちそうさまでした」



◎わたしとあなたとたいせつな人を守るために
第1回避難訓練(4/24(火))避難訓練は、身の回りの危険を予測・回避し、安全な生活に対する理解を深めることにつながります。この日の訓練も、冷静に情報を聴き、速やかに対応・非難することができました。雨天のため、1年生を対象とした上山公園への土砂災害を想定した避難訓練は再調整中です。


◎夢に向かってたくましく生きる
日生中は、自ら進んで学習に取り組む意欲と実践力をもてるよう、「授業」を大切にしています。(写真は、学びあう授業のようす4/24)



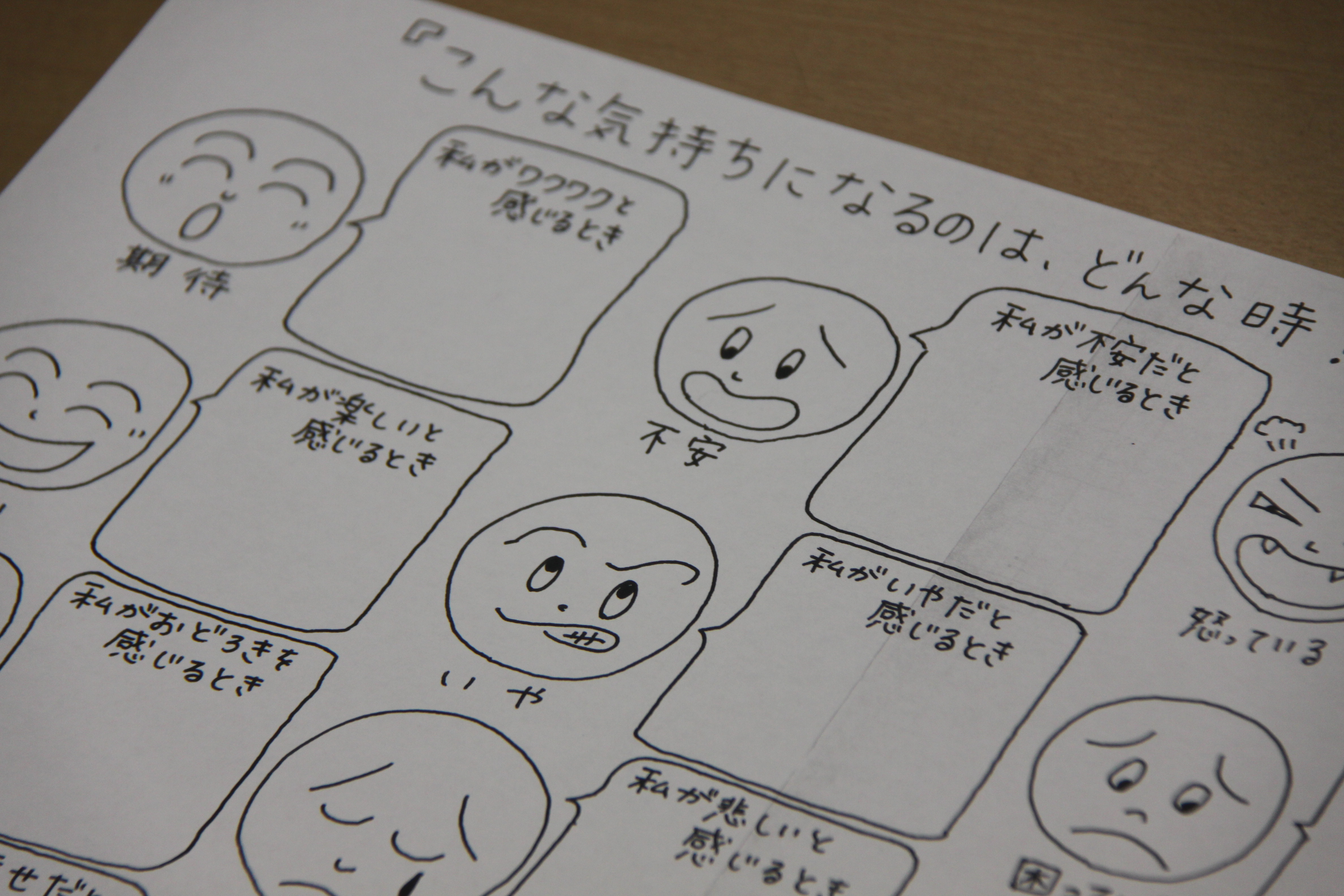
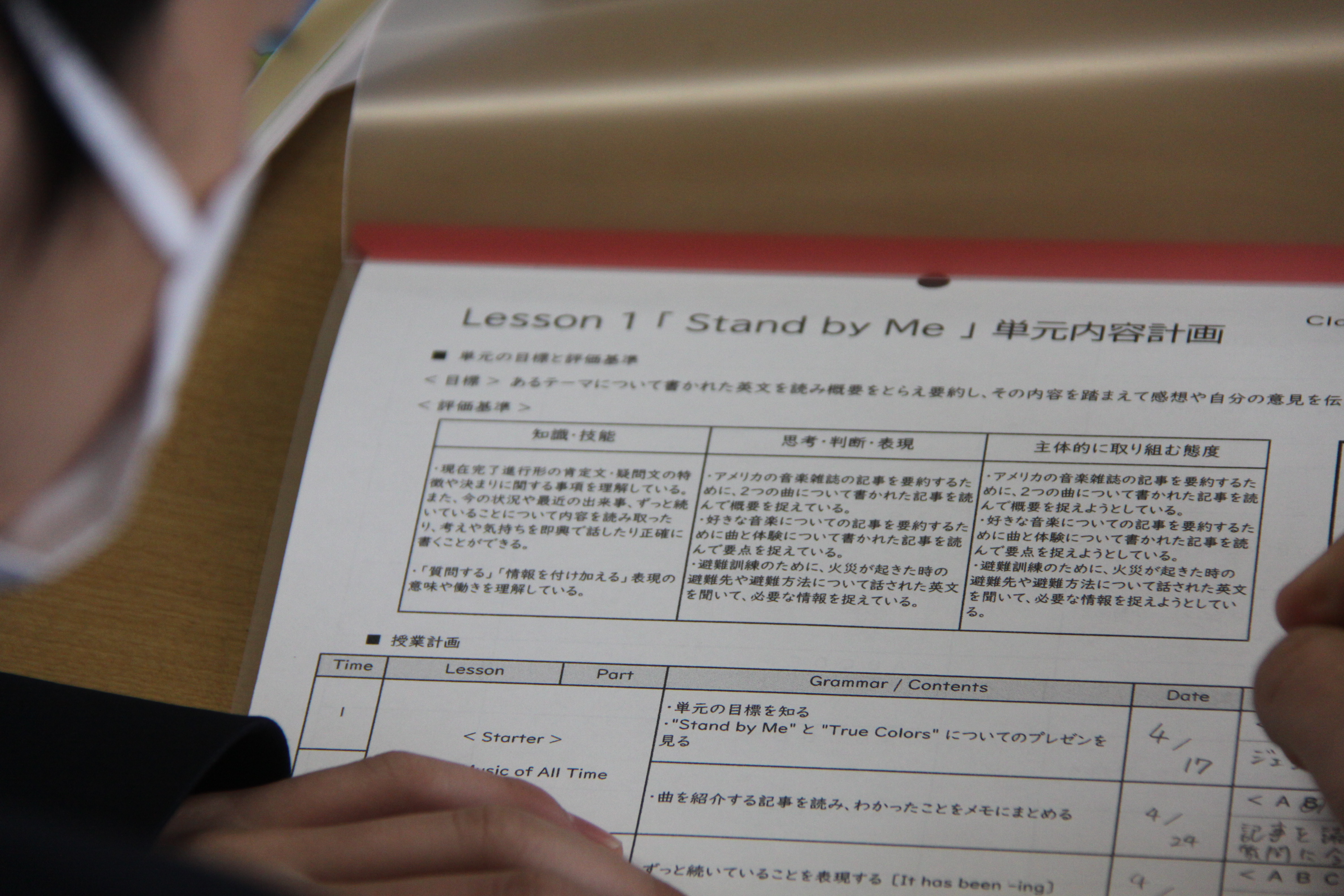

◎多くの人に支えられて(4/24(火))
急に故障した中央シャッターの修理・調整を業者さんにお願いしたところ、すばやく対応していただきました。さすがプロの技!ありがとうございました。

◎ひな中の風~~ヒロシマ研修へ(4/21(金)~22(土))
学びあう仲間、磨きあう、頑張りあう仲間と一緒に。


◎ひな中の風~~授業が大事~
閑谷研修、広島宿泊研修、修学旅行、専門委員会、部活動…、準備や活動で忙しい日々ですが、やっぱり授業が大事ですね。一生懸命に仲間とともに学びます。
写真は授業の様子です。(4/20(木))
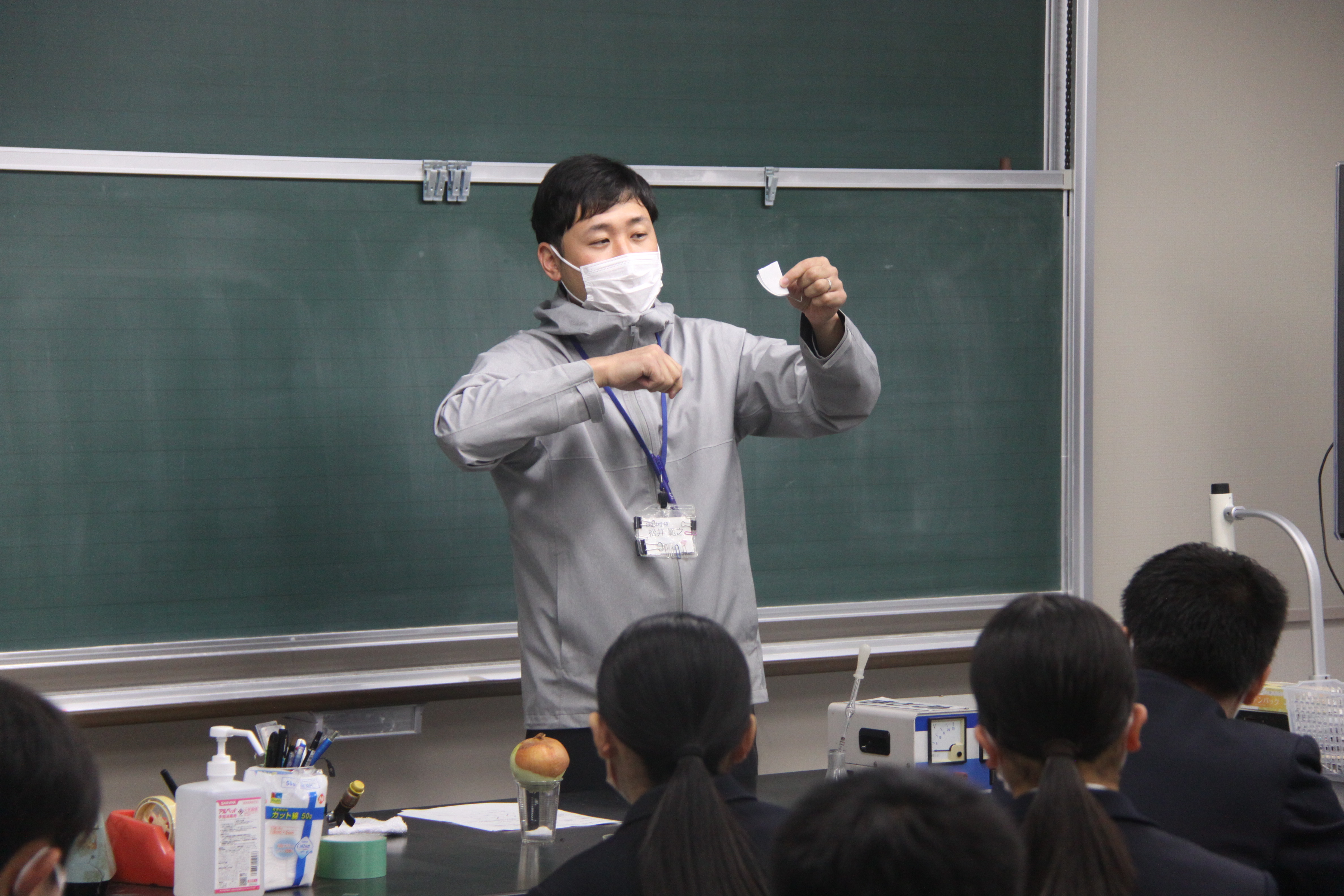


◎「子どもたちのために 日生中のために 私たちのこれからのために」
PTA委員総会開催(4/19(火))
宮本会長のあいさつの後、今年度の活動内容の確認、分担を行いました。議決事項はPTA総会(書面開催)資料を後日配布します。PTA事務局

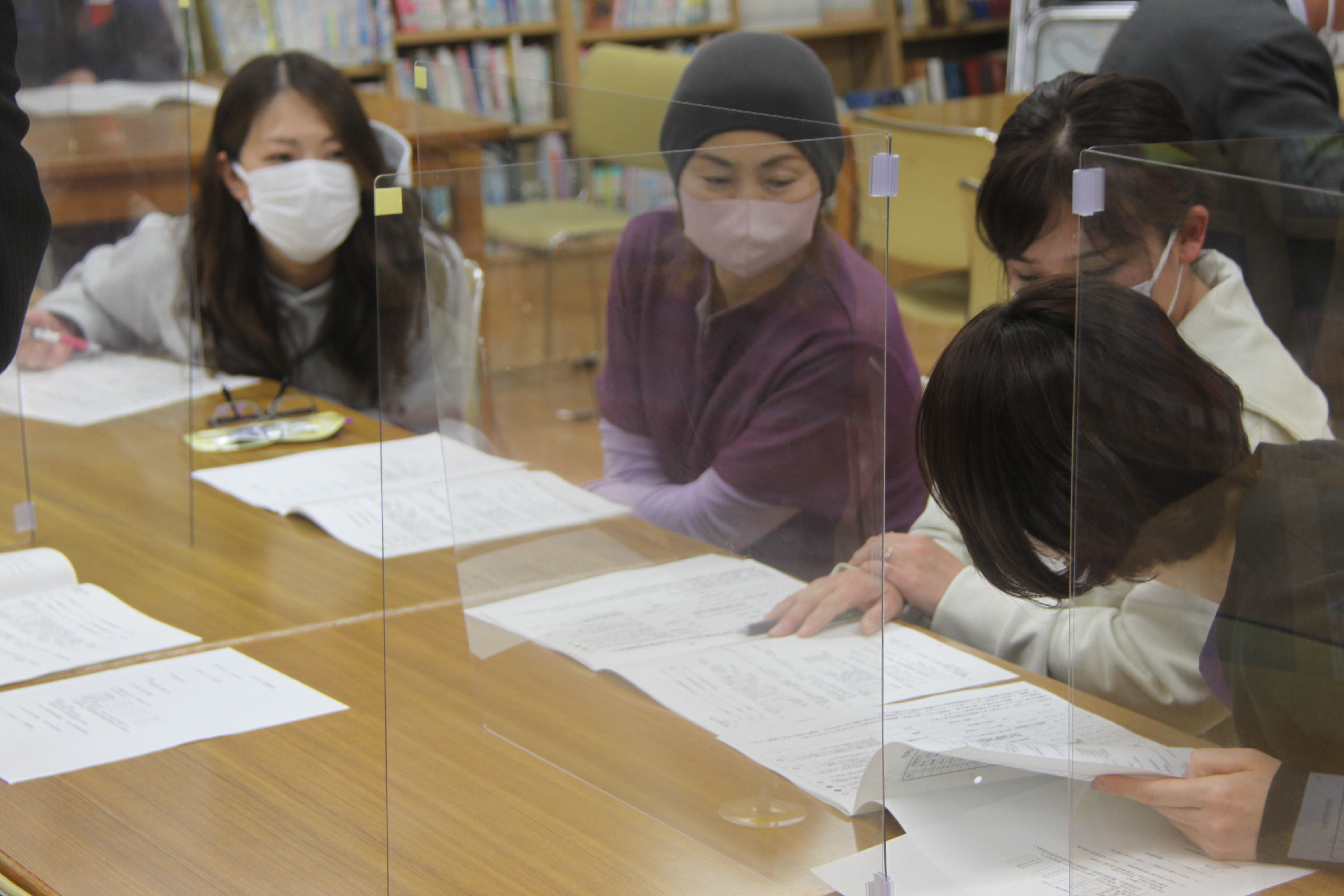

◎〈星輝祭って何や! 日生が輝く祭りや!〉
星輝祭(体育の部)ブロック会開催(4/19(水))
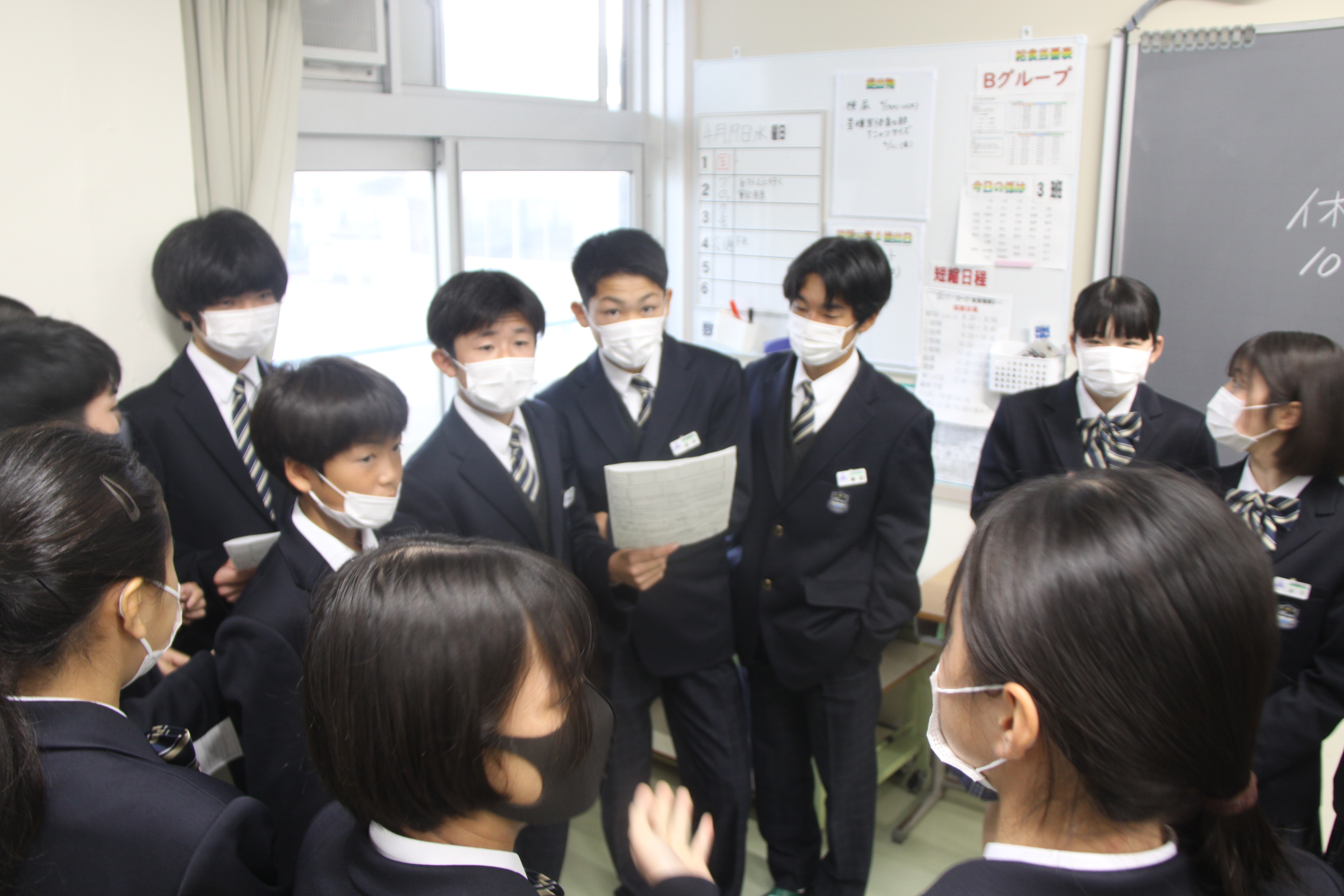

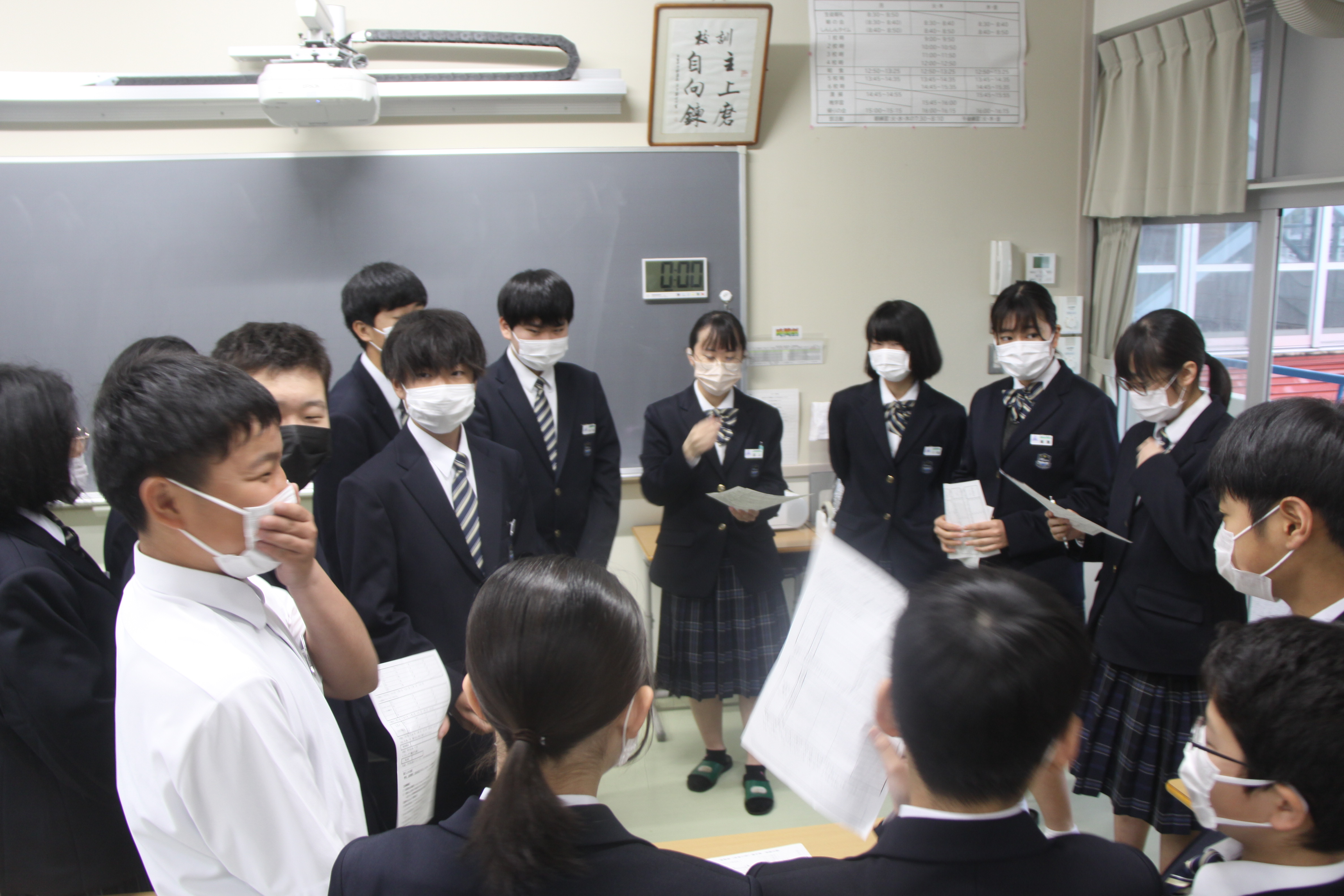
◎自分自身でいのちを守る運転・安全を~1年生交通安全教室(4/19(水))
備前警察署から神寶さん、橋本さんをお招きしました。お話を聴いた後は、「主体的に学ぶ」ことを大切にして、級友と質問・疑問を出し合い、積極的に神寶さんに質疑応答することができました。


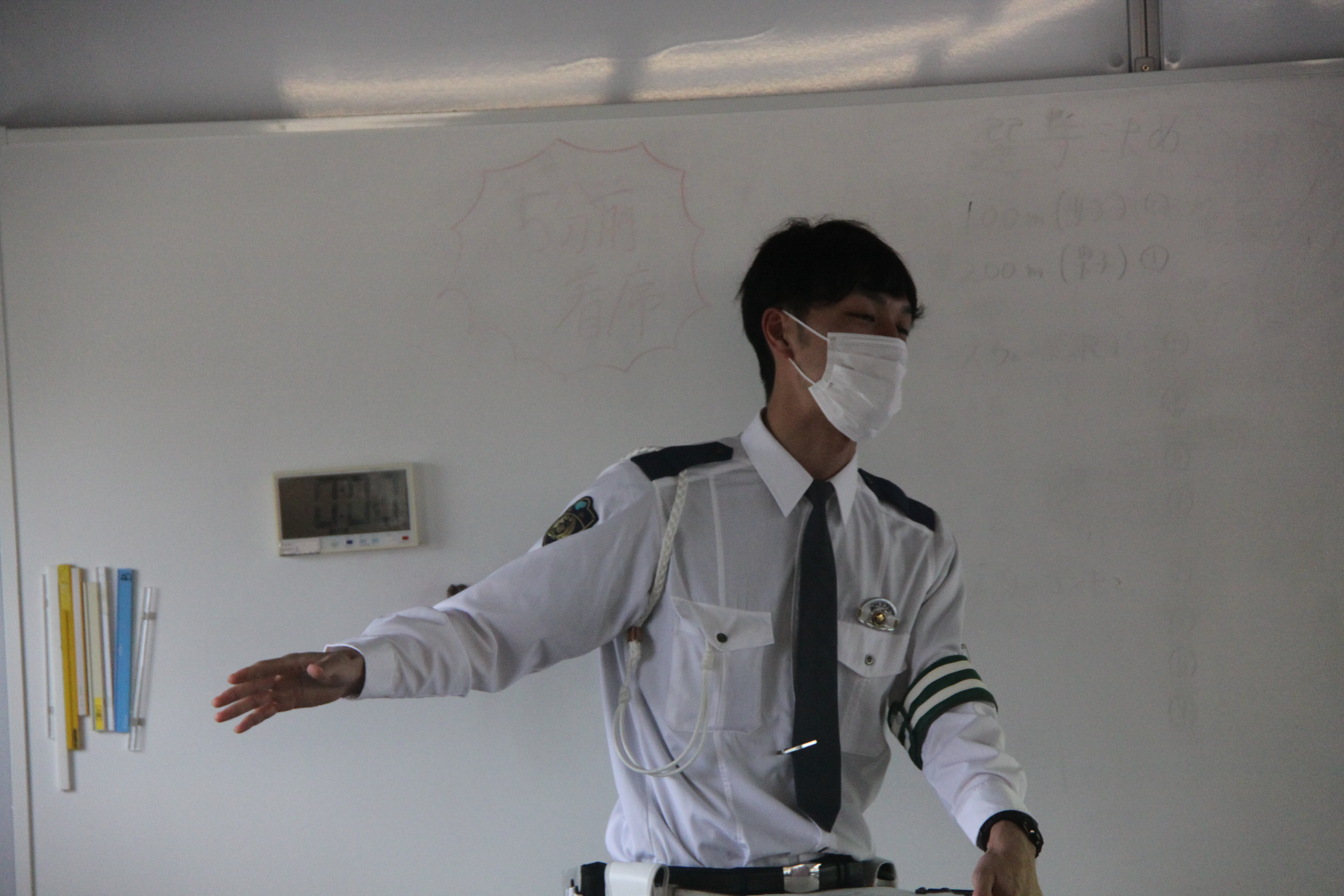
◎多くの人に支えられて(4/19(水))
この日、読み語りボランティアさんが来校され、今年度の打ち合わせを行いました。また、グラウンドバックネット跡の排水(下水)溝工事が始まりました。ありがとうございます。



◎自分らしく せいいっぱい
~山﨑スクールカウンセラーが今年度もみんなを応援します(4/19(水))~
この日、帰りの会で全クラスを回りました。ご相談があれば、お気軽に学校にご連絡ください。
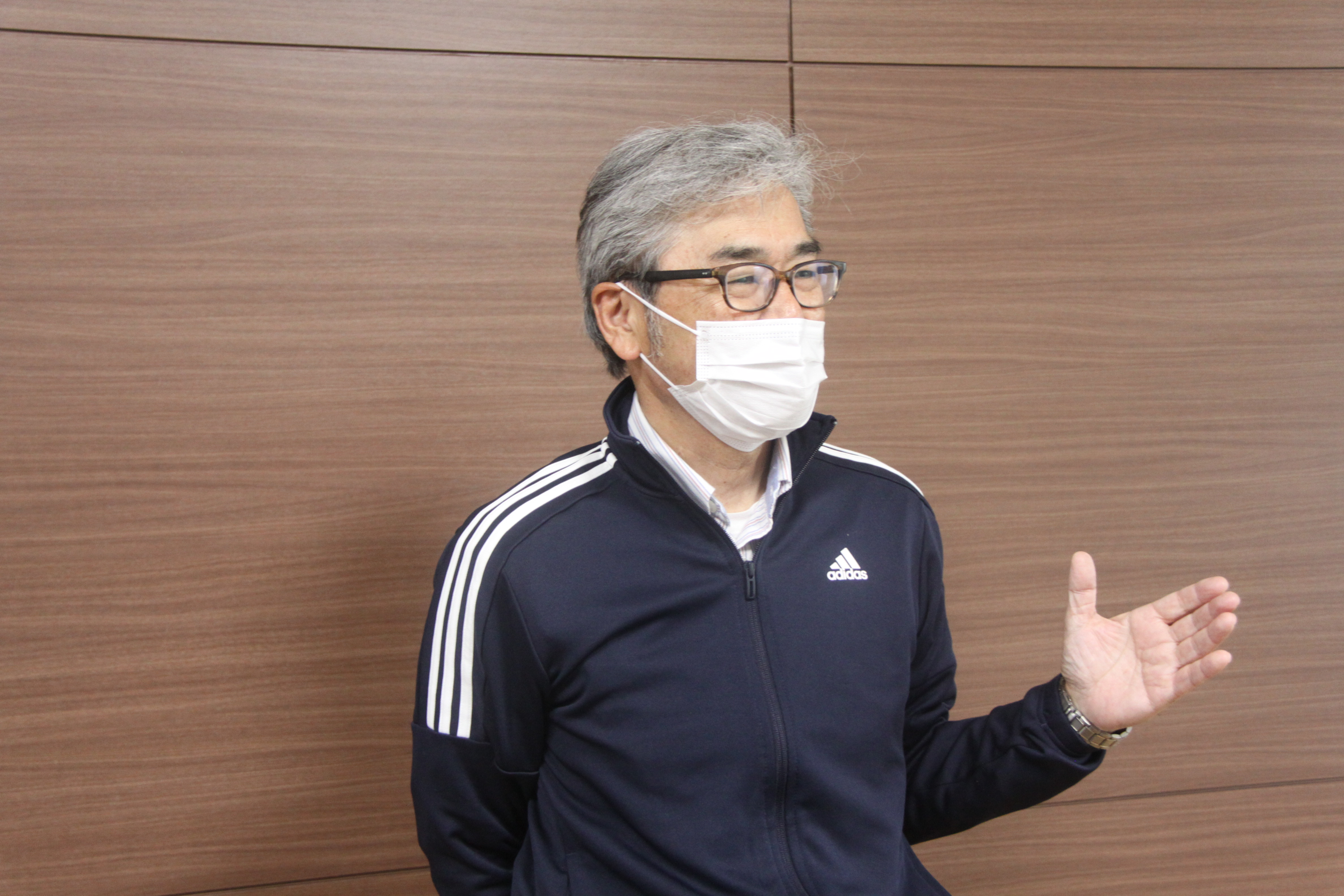
◎多くのひとに支えられて
~学習環境整備をありがとうございます。(4/18(火))

◎私たちの学校・生活をもっとよりよいものに
~第1回専門委員会開催(4/18(火))


◎自分らしくせいいっぱい
~全国(岡山県・備前市)学力状況調査乗り越える(4/18(火))

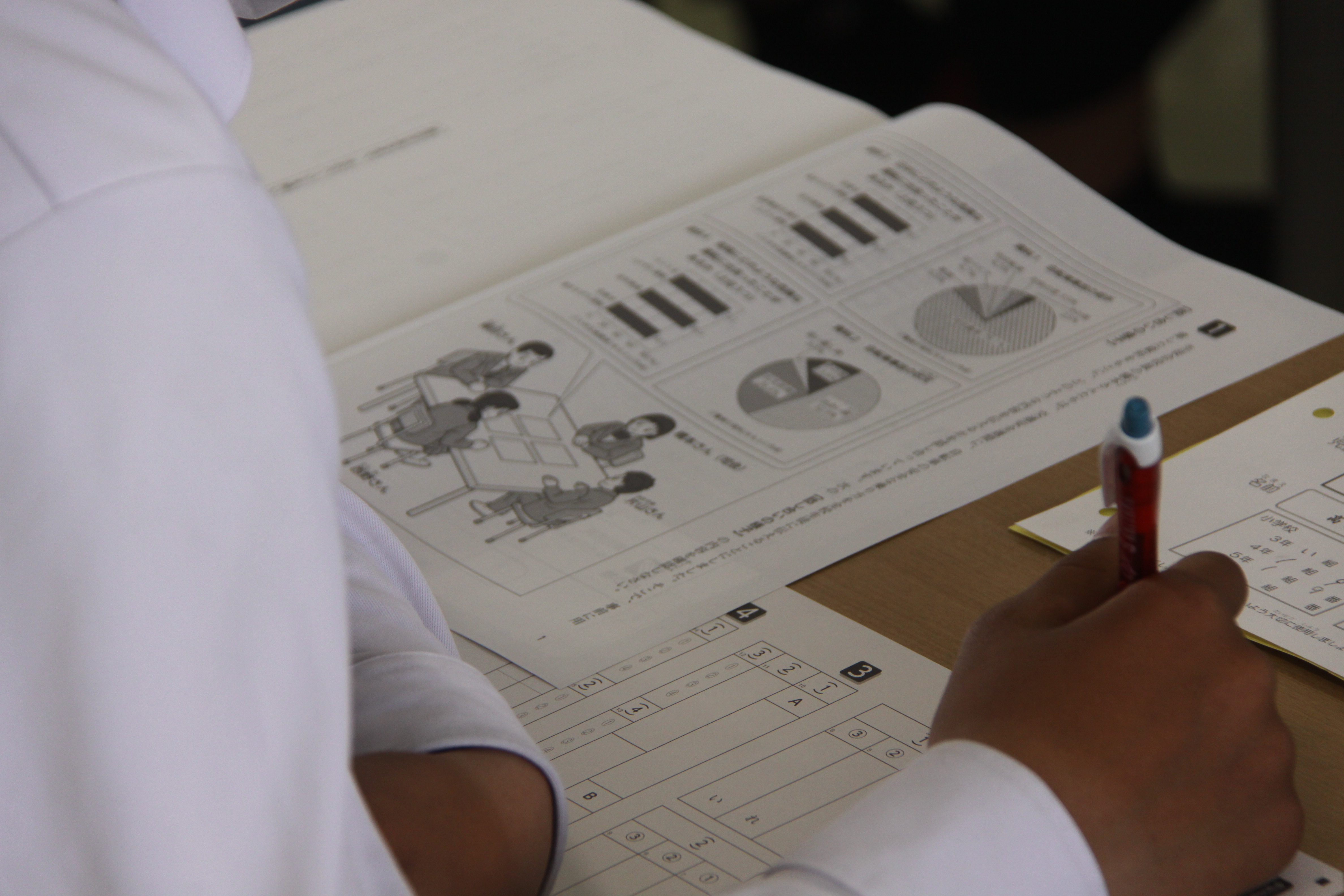
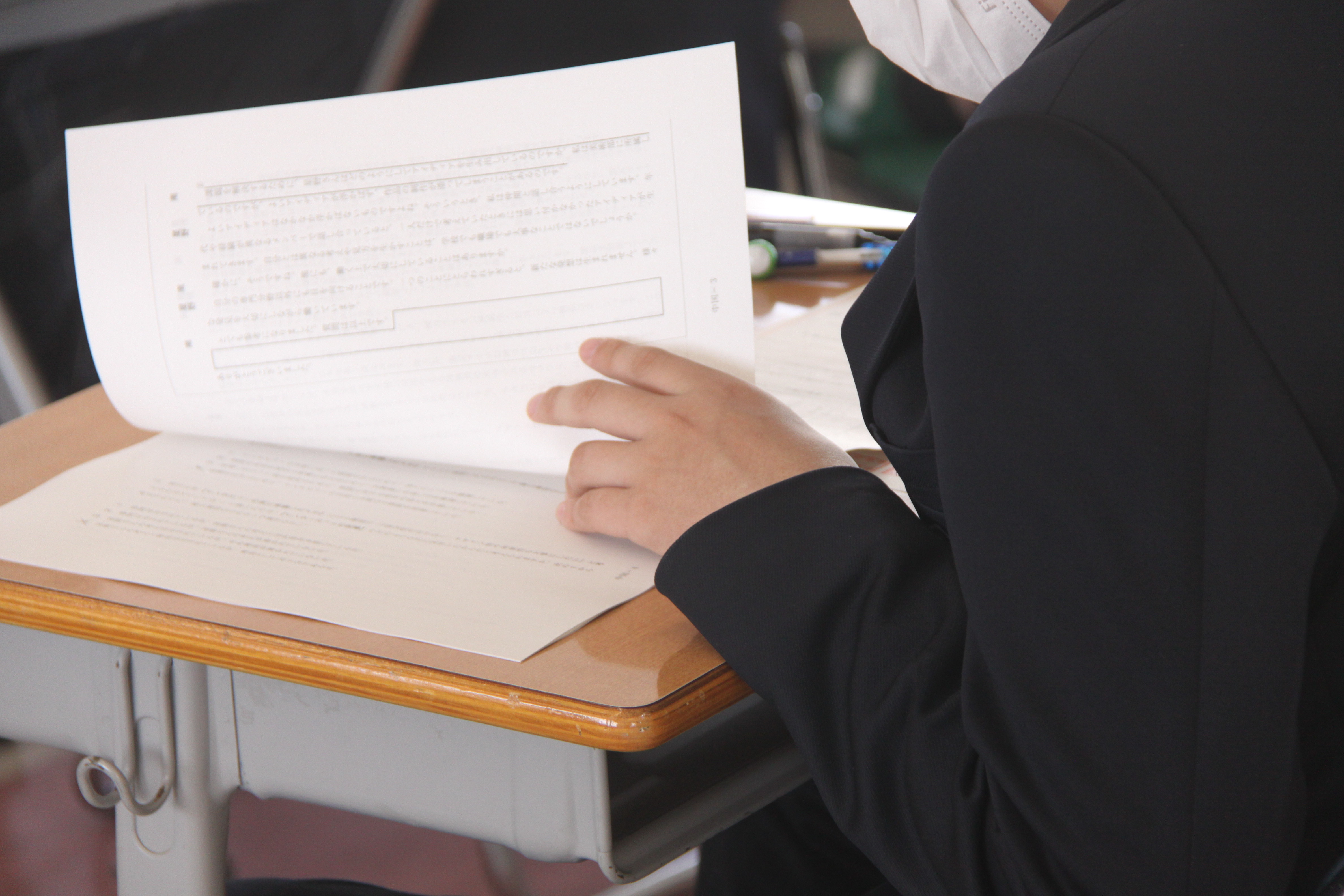
◎ひな中の風~~ひとの話を聴ける姿勢の大切さ

◎さあ、みんなのために、自分たちのために。
専門委員会認証式(4/17(月))

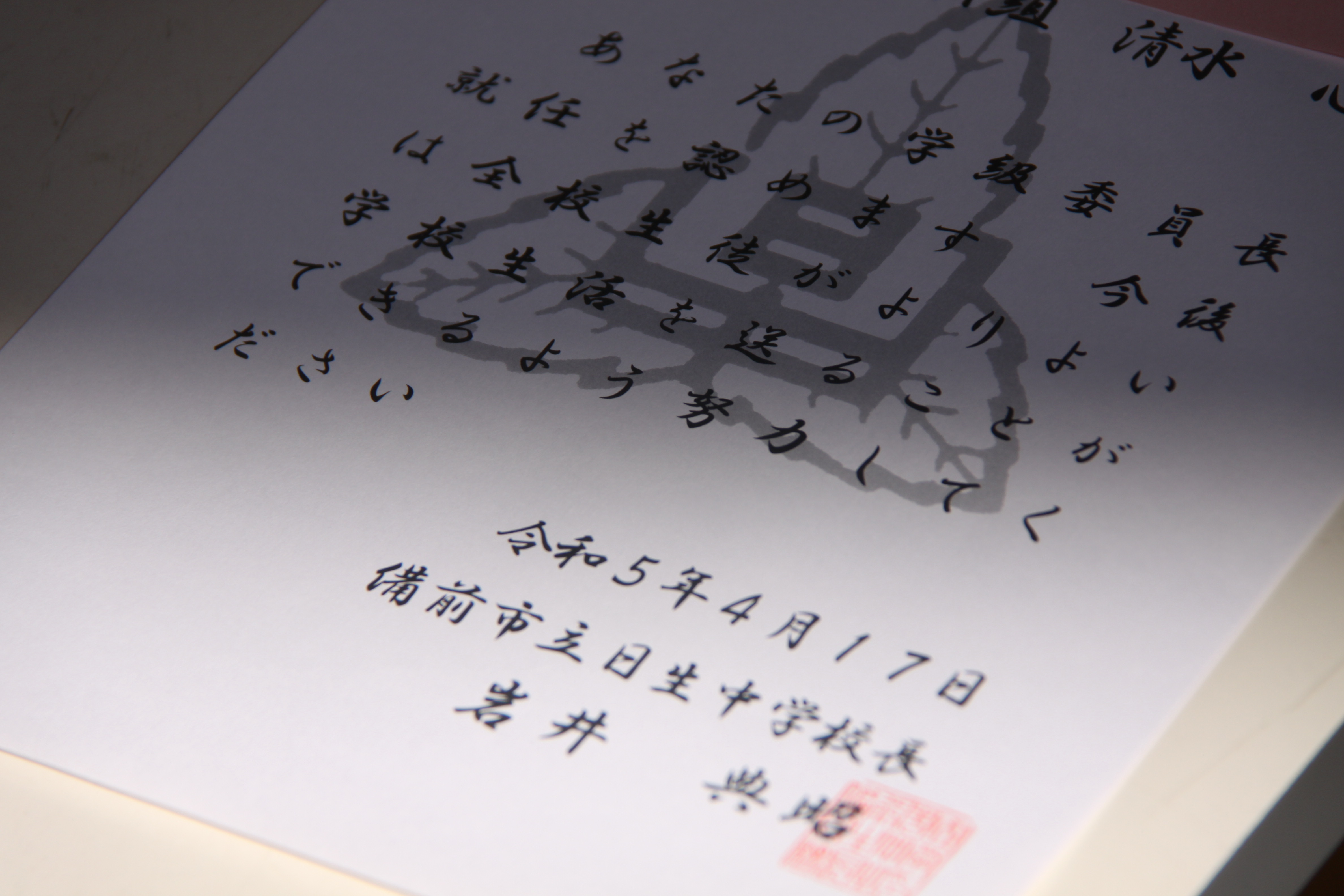

◎ひな中の風~~なかまとのあいさつではじまる月曜日~~(4/17(月))


◎想いよ届け 吹奏楽部新入生歓迎コンサート(4/14(金))




さようなら ありがとう (4/12(水))退任式
~日毎の訓 なつかしき 希望の日生中学校~




◎毎日が大切 ~授業スタート(4/12)~

ひな中の風~~一緒に毎日をがんばろう~~(4/11(木))

◎出会いにこころをこめて (4/11(火))
令和5年度入学式



◎≪自主 向上 練磨≫ ~新入生を迎えるために~(4/11(水))



2023年(令和5年)4月3日(月)始業式
〈一瞬の その一瞬の 一陣の 風のせなかを押して吹く風 西村曜〉

3月24日(金)
本日は、令和4年度の修了式でした。校長先生からは、「クラスの1年間を振り返ってほしい。そして、来年度は義務教育9年間で考えたとき、8年目・9年目になり、まとめの学年です。日生のそして学校の顔になってほしい。」というお話でした。その後、生徒会長、生徒指導主事からのお話がありました。また、今年度で退任される先生の退任式がありました。



3月11日(土)
卒業証書授与式がありました。今年度は在校生(2年生)も出席しての実施となりました。卒業する3年生にとっては一生忘れられない卒業式になったと思います。今日の感動を胸に新たな一歩を力強く踏み出してください。



3月9日(金)放課後
環境委員会によるクリーン作戦が放課後ありました。今回は生徒玄関や自転車置き場、フューチャールームなど明後日の卒業式に向けて3年生が気持ちよく卒業できるように掃除を行いました。ボランティアでの参加もたくさんあり、卒業式に向けてよい環境整備になりました。



3月9日(木)3校時
1年生でキャリア教育の一環として海運に関する出前授業を行いました。中国運輸局の方、日生海運組合の方に海運の役割や日生海運の歴史等についてお話をしていただきました。海運は、資源や食糧など物資の輸送になくてはならないもので私たちの生活を支えていること、日本の物資の輸送のうち船舶が99.6%を占めていることなどいろいろなことを教えていただきました。



3月7日(火)4校時
1、2年生合同でスマホ・ケータイ安全教室を実施しました。これは日生中学区全体で取り組んでいる活動で、KDDIの講師の方が日生東小、日生西小、日生中の3校それぞれで説明をしてくださいました。スマホに使われるのではなくスマホを上手に使えるよう、本日学んだことを実践していきましょう。

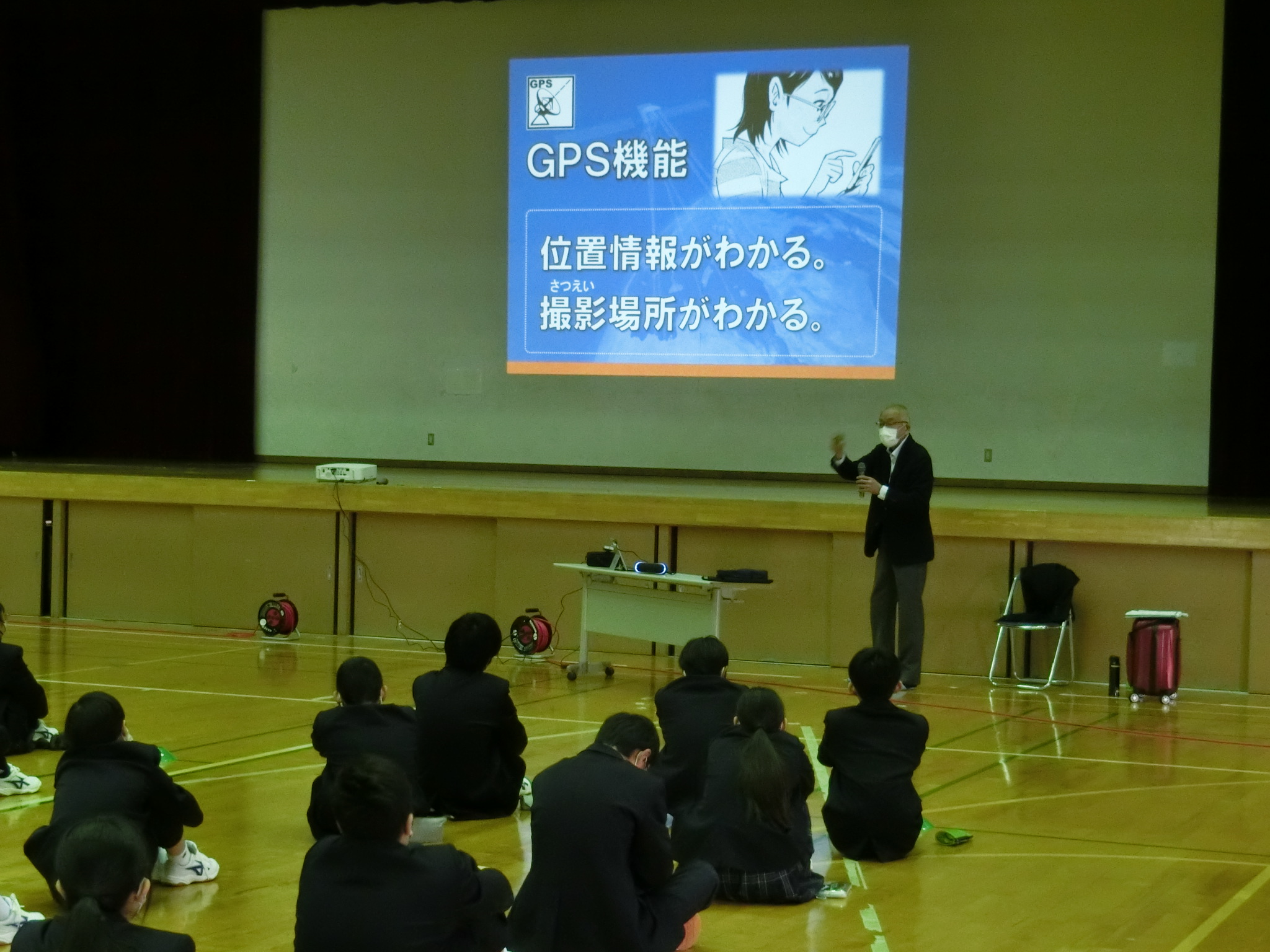

3月1日(水)放課後
日生中学校では、水曜日に放課後学習を行っています。希望する生徒が参加して学習を進めていきます。全職員と地域の支援員でサポート体制を組んで実施しています。今日が今年度の最終回でした。



3月1日(水)3,4校時
3校時に2AD、4校時に2Bが保健体育の授業で「救命法」の学習をしました。東備消防組合の方に来ていただき、心肺蘇生法の手順やAEDの使い方について説明をしていただきました。その後、マネキンを使って実際に心臓マッサージを体験しました。



2月1日(水)6校時
本日は、1・2年生の参観日でした。6校時の授業を参観していただいた後、各学年で懇談会を行いました。参観授業では、生徒の普段の様子を見ていただくことができたのではないかと思います。今年度最後の参観授業に多くの保護者の方に参加していただき、ありがとうございました。



1月19日(木)
本日は、不審者対応の避難訓練を行いました。警察の方が不審者になり、授業をしている教室に実際に侵入する形で実施しました。万が一自分たちの教室に侵入してきたらどのように行動するのかを考えて訓練に臨みました。その後、防犯教室をリモートで行いました。

1月10日(火)
本日は、3学期の始業式をリモートで行いました。校長先生の話のあと、生徒会長・生徒指導担当からの話や表彰伝達式がありました。その後、各クラスで学活を行い、宿題等の提出物を集めました。最後の締めくくりをする3学期、それぞれの目標に向かって悔いのない3学期にしてほしいと思います。

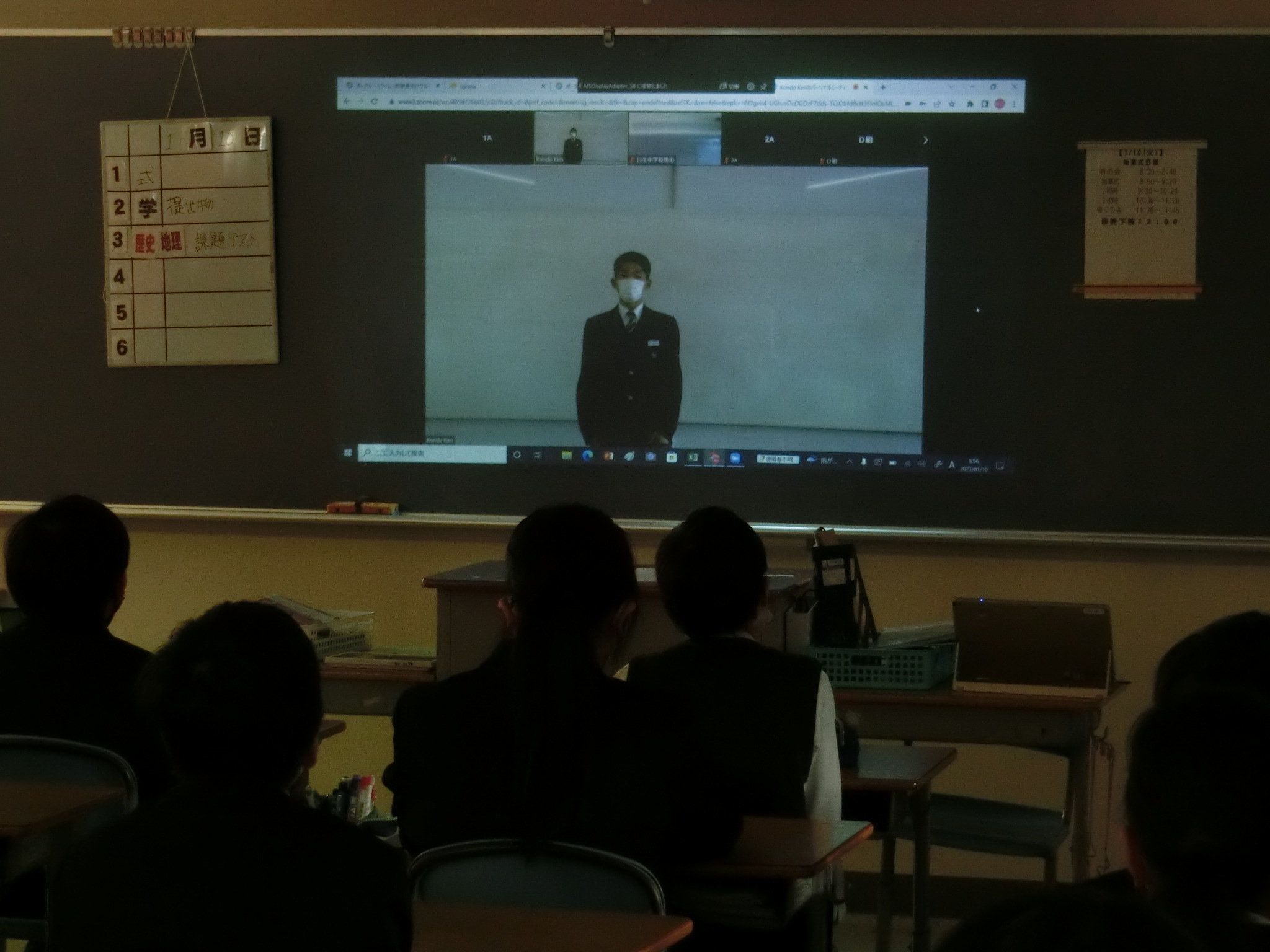

11月2日(水)
本日は、学校公開日並びに進路説明会、人権教育講演会でした。たくさんの保護者の方に参観していただき、ありがとうございました。1年生は総合的な学習の時間に自分が調べた職業についての発表会を、2年生は総合的な学習の時間にチャレンジワークの報告会を行いました。3年生は保護者の方と一緒に進路について学習をしました。また、午後にはPTA文化部の皆さんの協力のもと、人権教育講演会を開催しました。講師には、長島愛生園で学芸員をされている木下さんに来ていただき、「ハンセン病問題から学ぶ感染症の差別」と題して講演をしていただきました。






10月26日(水)
3年生の家庭科の授業で「幼児とのふれあい体験」を行いました。地域にある「わくわくるーむ」の協力のもと、赤ちゃんのお世話や一緒に遊ぶ活動を行いました。最初は緊張していた生徒も時間が経つにつれて少しずつ慣れていきました。今日の学習を通して、他者への思いやりや命の大切さについて改めて考える機会になったようです。



10月20日(木)
2年生は18(火)から4日間の日程でチャレンジワーク14(職場体験学習)を実施しています。備前市内や瀬戸内市内の事業所を中心に体験活動を行っています。コロナ禍の中、お引き受けていただいた事業所の皆様、ありがとうございました。生徒にとってはたいへん貴重な体験の場になっているようです。






10月12日(水)
3年生は、今日から2泊3日の修学旅行です。スローガン「平和の尊さを実感し、仲間との絆を深めよう」のもと、事前に学習したことを長崎・福岡の地で見て、聞いて、歩いて学んできてほしいと思います。

10月7日(金)5,6校時
1年生の総合的な学習の時間でアマモポットを作成しました。日生中学校ではアマモ場の再生活動に取り組んでおり、本日は流れ藻から回収した種をポットに入れる作業でした。この種からどのように芽を出し成長するのかしっかり観察していきます。ご協力いただきましたおかやまコープの皆様、ありがとうございました。


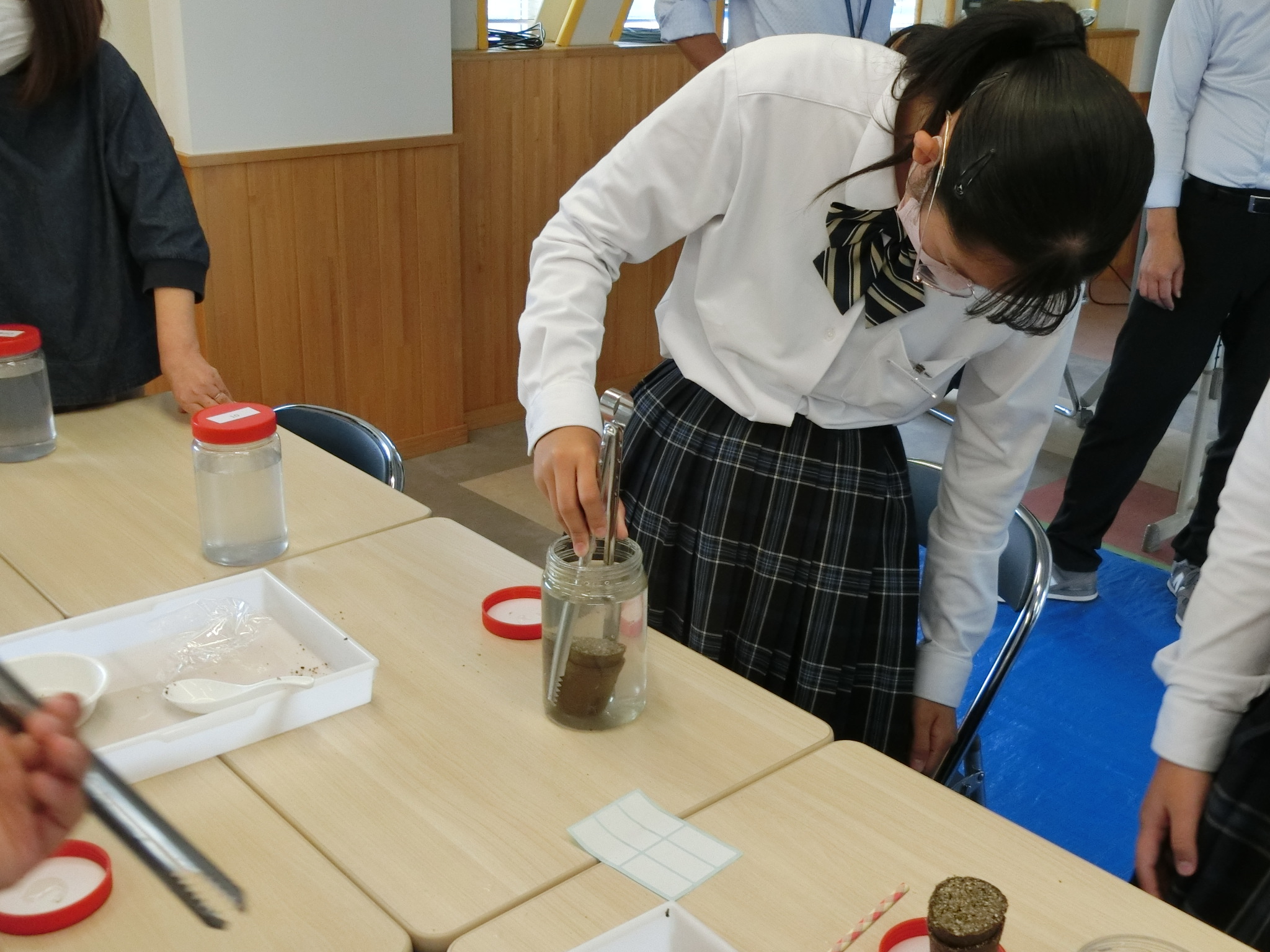
10月6日(木)6校時
学年の代表者による校内弁論大会がありました。7名の弁士は自分の経験をもとに堂々と発表することができました。学校代表の2名は、11月4日(金)に行われます備前市弁論大会に出場します。



10月1日(土)
本日は星輝祭(文化の部)。各クラスの合唱、そして3年生による舞台発表がありました。合唱は各クラスとも心をひとつにした歌声を、舞台発表は平和をテーマにした人権劇を保護者の方に届けることができました。






9月29日(木)放課後
明後日に行われる合唱コンクールに向けて、各学年・各クラスともに練習に熱が入っています。パートに分かれて練習をしたり、全体で合わせたりと30分の練習時間を計画的に使っていました。明後日の本番が楽しみです。




9月17日(土),18日(日)
備前東地区秋季総体がありました。日生中学校からは、ソフトテニス部・剣道部・バスケットボール部・サッカー部の生徒が参加しました。日頃の練習の成果を発揮して各部とも全力で頑張りました。その中でもソフトテニス部は団体戦優勝・個人戦2位、剣道部は個人戦ベスト8の成績を収め、県大会の切符を手にしました。



9月18日(日)
吹奏楽部の定期演奏会がありました。昨年はリモートでの開催であったため、久しぶりに対面での演奏会となりました。コロナ禍で発表の場が少なかった吹奏楽部員にとっては貴重な経験となりました。



9月16日(金)5,6校時
生徒会立会演説会がありました。感染対策のため、リモートで行いました。立候補者は、「こんな学校にしたい」という思いをそれぞれ伝えることができていました。その後、一人ひとりが貴重な1票を投票しました。みんなで協力してより良い学校をつくっていきましょう。



9月14日(水) 放課後
日生中学校では毎週水曜日に放課後学習を行っています。基礎や発展など7つのコースを開設し、希望した生徒が主体的に学習しています。



9月14日(水) 6校時
2年生の聞き書きのまとめとして、その成果をポスターセッションという形で1年生に発表しました。漁師さんなど漁業に関係する方の生き方から多くのことを学び、それを各グループで工夫を凝らして発表することができました。発表の後には1年生からの質問にしっかり答える姿が見られました。



9月14日(水)
備前市市民課の取り組みで自転車点検が行われました。皆さんが安全に登下校できるように、地域の業者の方が点検をしてくださいました。整備の必要な生徒には、黄色の札をつけています。ご家庭でも確認をお願いします。


9月14日(水) しんしんタイム
日生中学校では毎朝10分間の読書タイムを設けています。いつもは各自で読書を進めていますが、今日は文化委員による読み聞かせがありました。今日のためにしっかり準備をした文化委員が、クラスの仲間の前で堂々と読み聞かせを行うことができました。



9月13日(火) 5校時
2年生の総合的な学習の時間を利用して「ビジネスマナー」について学習しました。社会保険労務士をされている高橋先生に来ていただき、「職場体験学習前に知っておきたいこと」について学びました。2年生は11/18(火)から4日間の日程で職場体験学習を予定しています。今日の学びを職場体験に生かしてほしいと思います。


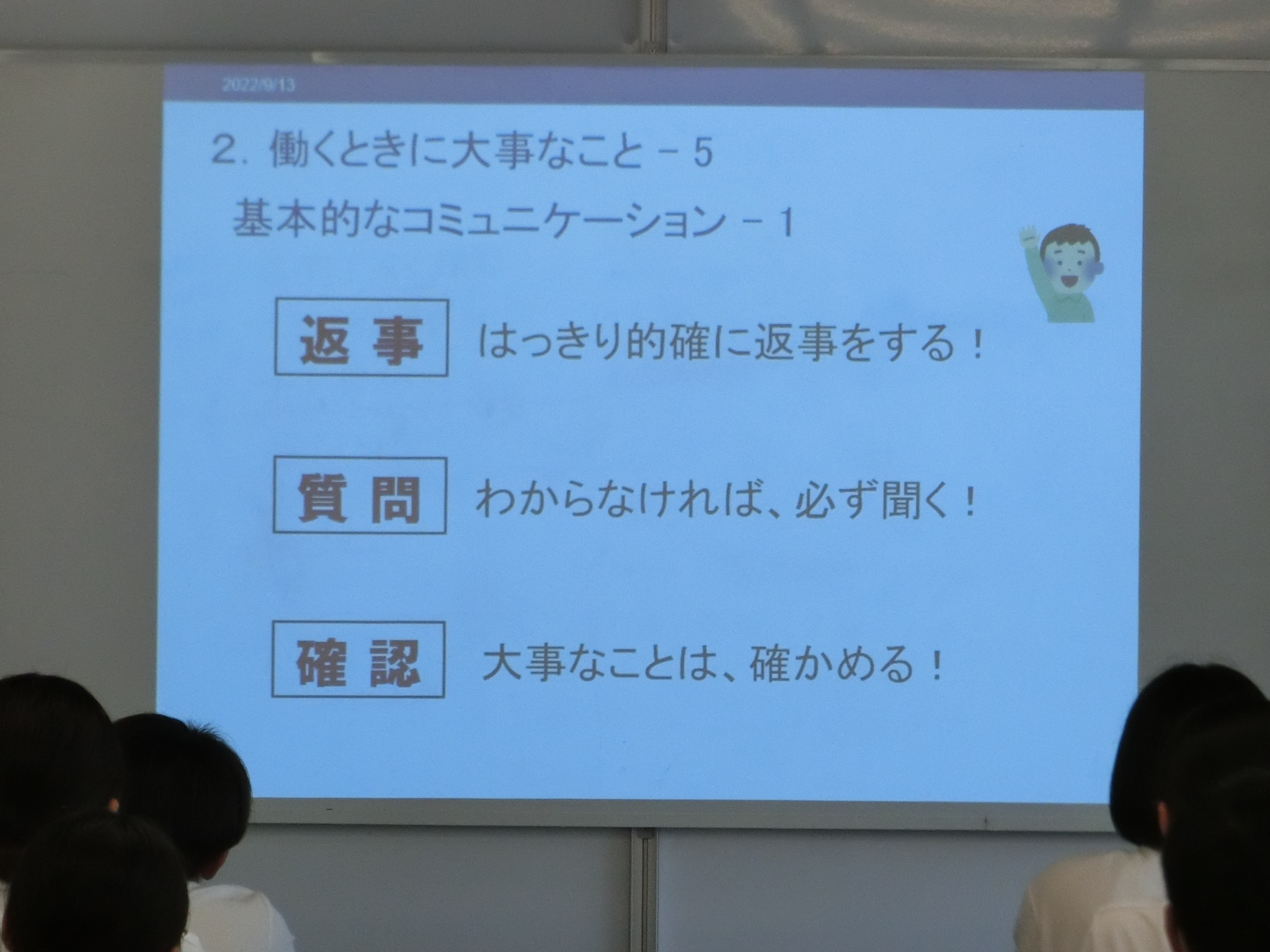
4月28日(木)1年生閑谷研修
1年生が閑谷研修を行いました。午前中は講堂で6つ論語を学びました。午後はスコアオリエンテーリングを行い、友情を深めました。



4月27日(水)2年生学活「PR大作戦」
2年生は、4月27日の学活で「PR大作戦~もっと友達のいいところをみつけよう~」という活動を行いました。唯一クラス替えのある学年で、新しいクラスになって1ヶ月がたちました。同じクラスになった人のいいところを旧クラスメートが紹介し、お互いの理解を深める目的で活動しました。
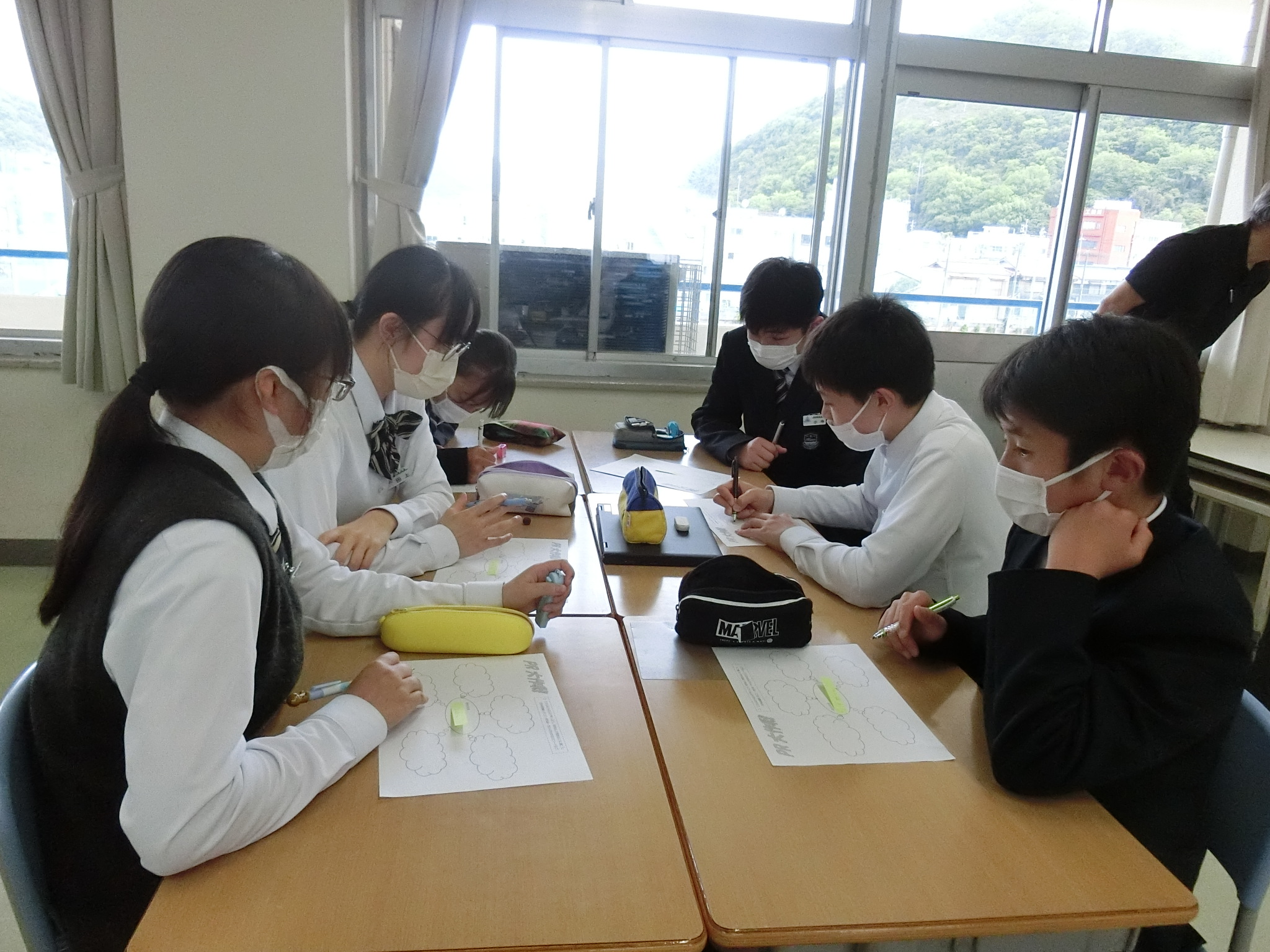
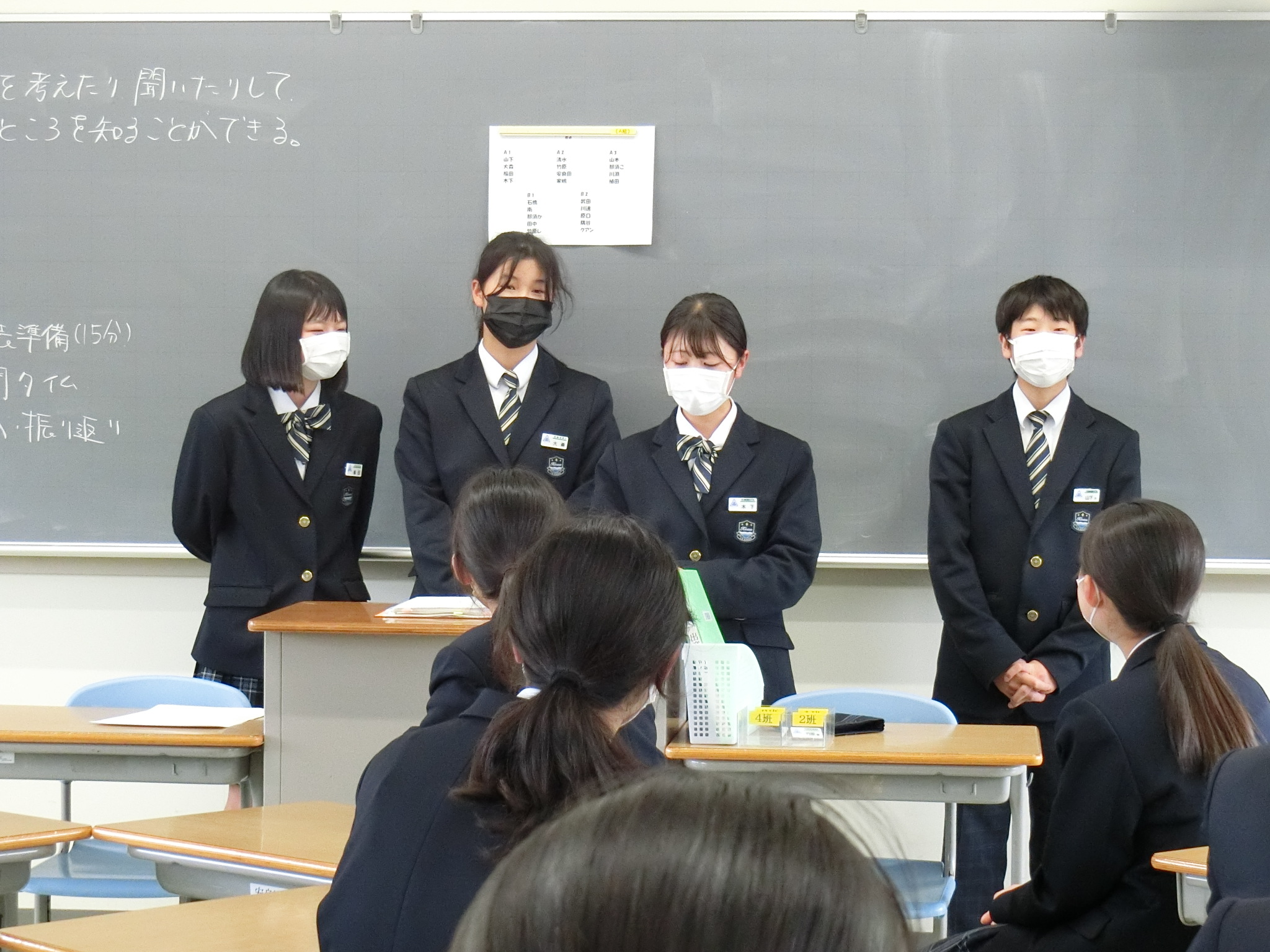

4月26日(火)吹奏楽部中庭コンサート
放課後に吹奏楽部が中庭コンサートを行いました。多くの手拍子に包まれて大盛況でした。


4月26日(火)1年生 6時間目
閑谷研修に向けて班活動を行いました。班対抗のレクも行い、友情を深めました。


4月26日(火)晩学習
社会科晩学習「目指せマゼラン☆世界周航マスター」が始まりました。4週間後の本番に向けて、暗記を頑張っています。

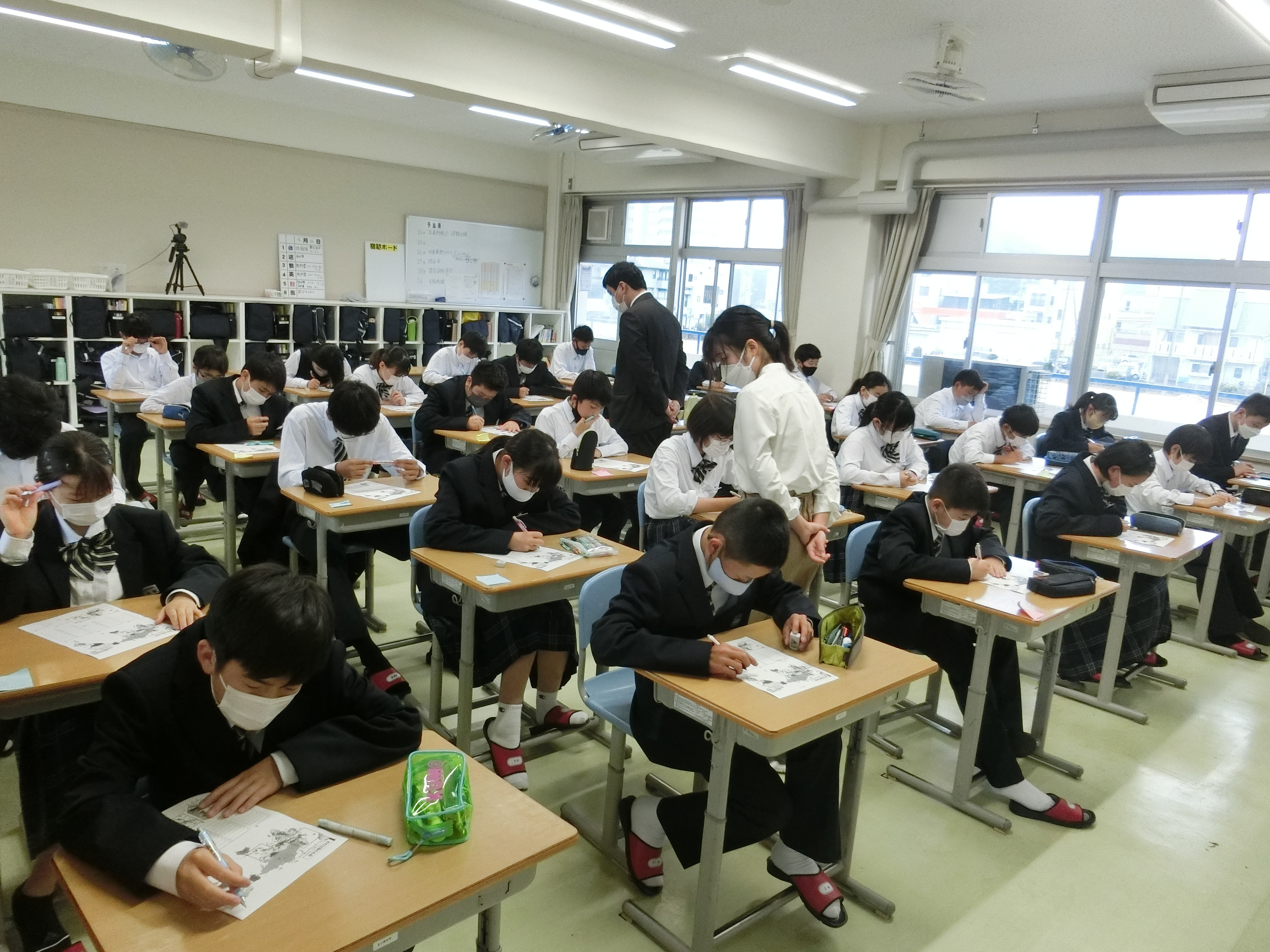
4月22日(金)避難訓練
火災を想定した避難訓練がありました。訓練の後、1年生は津波発生時に避難する上山公園まで歩いて行きました。



4月21日(木)3時間目 1年生学活
学級目標を決めました。学級委員長の2人が上手に話し合いをまとめていました。


4月20日(水)ブロック会
6月に実施する星輝祭体育の部のブロック会を行いました。ブロック長が所信表明を行い、その後出場種目を話し合いました。


4月18日(月)全校朝礼
前期専門委員会の認証式がありました。認証書授与のあと、代表の生徒が決意表明をしました。


4月15日(金)6校時
1年生対象交通安全教室を開催しました。備前警察署より2名来ていただき、自転車の通行に関する講話をしていただきました。


2023年(令和5年)4月3日(月)始業式
〈一瞬の その一瞬の 一陣の 風のせなかを押して吹く風 西村曜〉

3月24日(金)
本日は、令和4年度の修了式でした。校長先生からは、「クラスの1年間を振り返ってほしい。そして、来年度は義務教育9年間で考えたとき、8年目・9年目になり、まとめの学年です。日生のそして学校の顔になってほしい。」というお話でした。その後、生徒会長、生徒指導主事からのお話がありました。また、今年度で退任される先生の退任式がありました。



3月11日(土)
卒業証書授与式がありました。今年度は在校生(2年生)も出席しての実施となりました。卒業する3年生にとっては一生忘れられない卒業式になったと思います。今日の感動を胸に新たな一歩を力強く踏み出してください。



3月9日(金)放課後
環境委員会によるクリーン作戦が放課後ありました。今回は生徒玄関や自転車置き場、フューチャールームなど明後日の卒業式に向けて3年生が気持ちよく卒業できるように掃除を行いました。ボランティアでの参加もたくさんあり、卒業式に向けてよい環境整備になりました。



3月9日(木)3校時
1年生でキャリア教育の一環として海運に関する出前授業を行いました。中国運輸局の方、日生海運組合の方に海運の役割や日生海運の歴史等についてお話をしていただきました。海運は、資源や食糧など物資の輸送になくてはならないもので私たちの生活を支えていること、日本の物資の輸送のうち船舶が99.6%を占めていることなどいろいろなことを教えていただきました。



3月7日(火)4校時
1、2年生合同でスマホ・ケータイ安全教室を実施しました。これは日生中学区全体で取り組んでいる活動で、KDDIの講師の方が日生東小、日生西小、日生中の3校それぞれで説明をしてくださいました。スマホに使われるのではなくスマホを上手に使えるよう、本日学んだことを実践していきましょう。

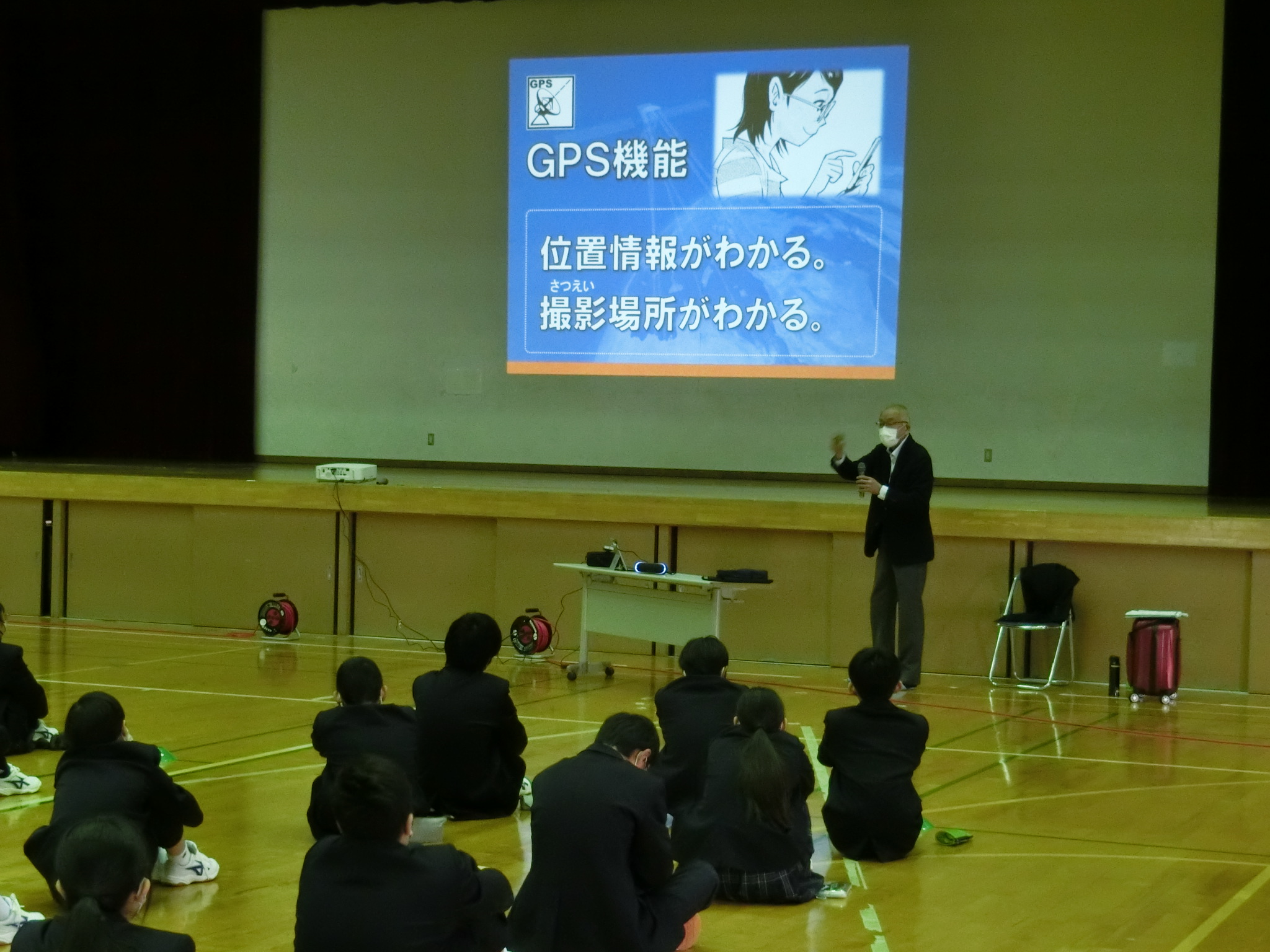

3月1日(水)放課後
日生中学校では、水曜日に放課後学習を行っています。希望する生徒が参加して学習を進めていきます。全職員と地域の支援員でサポート体制を組んで実施しています。今日が今年度の最終回でした。



3月1日(水)3,4校時
3校時に2AD、4校時に2Bが保健体育の授業で「救命法」の学習をしました。東備消防組合の方に来ていただき、心肺蘇生法の手順やAEDの使い方について説明をしていただきました。その後、マネキンを使って実際に心臓マッサージを体験しました。



2月1日(水)6校時
本日は、1・2年生の参観日でした。6校時の授業を参観していただいた後、各学年で懇談会を行いました。参観授業では、生徒の普段の様子を見ていただくことができたのではないかと思います。今年度最後の参観授業に多くの保護者の方に参加していただき、ありがとうございました。



1月19日(木)
本日は、不審者対応の避難訓練を行いました。警察の方が不審者になり、授業をしている教室に実際に侵入する形で実施しました。万が一自分たちの教室に侵入してきたらどのように行動するのかを考えて訓練に臨みました。その後、防犯教室をリモートで行いました。

1月10日(火)
本日は、3学期の始業式をリモートで行いました。校長先生の話のあと、生徒会長・生徒指導担当からの話や表彰伝達式がありました。その後、各クラスで学活を行い、宿題等の提出物を集めました。最後の締めくくりをする3学期、それぞれの目標に向かって悔いのない3学期にしてほしいと思います。

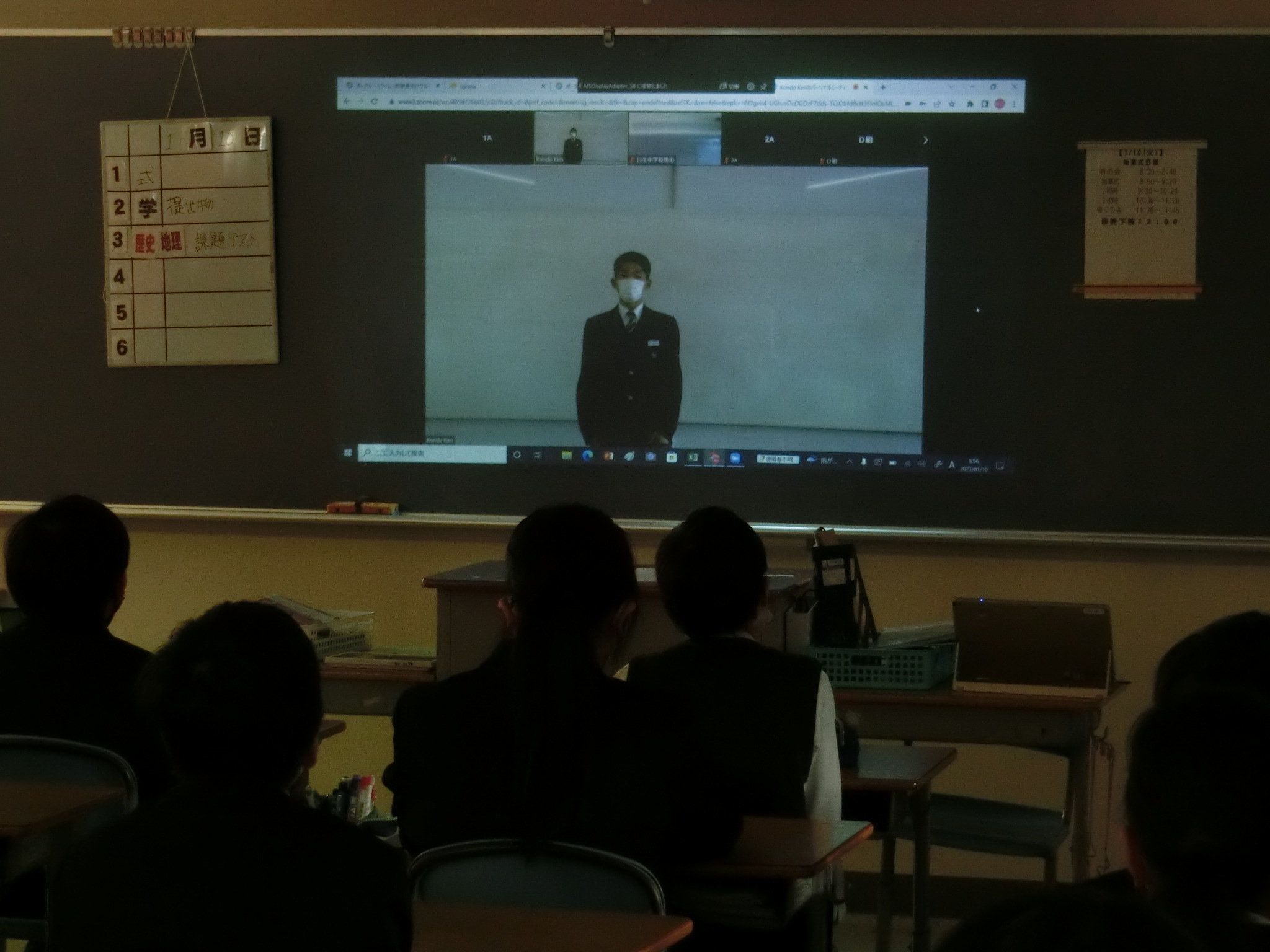

11月2日(水)
本日は、学校公開日並びに進路説明会、人権教育講演会でした。たくさんの保護者の方に参観していただき、ありがとうございました。1年生は総合的な学習の時間に自分が調べた職業についての発表会を、2年生は総合的な学習の時間にチャレンジワークの報告会を行いました。3年生は保護者の方と一緒に進路について学習をしました。また、午後にはPTA文化部の皆さんの協力のもと、人権教育講演会を開催しました。講師には、長島愛生園で学芸員をされている木下さんに来ていただき、「ハンセン病問題から学ぶ感染症の差別」と題して講演をしていただきました。






10月26日(水)
3年生の家庭科の授業で「幼児とのふれあい体験」を行いました。地域にある「わくわくるーむ」の協力のもと、赤ちゃんのお世話や一緒に遊ぶ活動を行いました。最初は緊張していた生徒も時間が経つにつれて少しずつ慣れていきました。今日の学習を通して、他者への思いやりや命の大切さについて改めて考える機会になったようです。



10月20日(木)
2年生は18(火)から4日間の日程でチャレンジワーク14(職場体験学習)を実施しています。備前市内や瀬戸内市内の事業所を中心に体験活動を行っています。コロナ禍の中、お引き受けていただいた事業所の皆様、ありがとうございました。生徒にとってはたいへん貴重な体験の場になっているようです。






10月12日(水)
3年生は、今日から2泊3日の修学旅行です。スローガン「平和の尊さを実感し、仲間との絆を深めよう」のもと、事前に学習したことを長崎・福岡の地で見て、聞いて、歩いて学んできてほしいと思います。

10月7日(金)5,6校時
1年生の総合的な学習の時間でアマモポットを作成しました。日生中学校ではアマモ場の再生活動に取り組んでおり、本日は流れ藻から回収した種をポットに入れる作業でした。この種からどのように芽を出し成長するのかしっかり観察していきます。ご協力いただきましたおかやまコープの皆様、ありがとうございました。


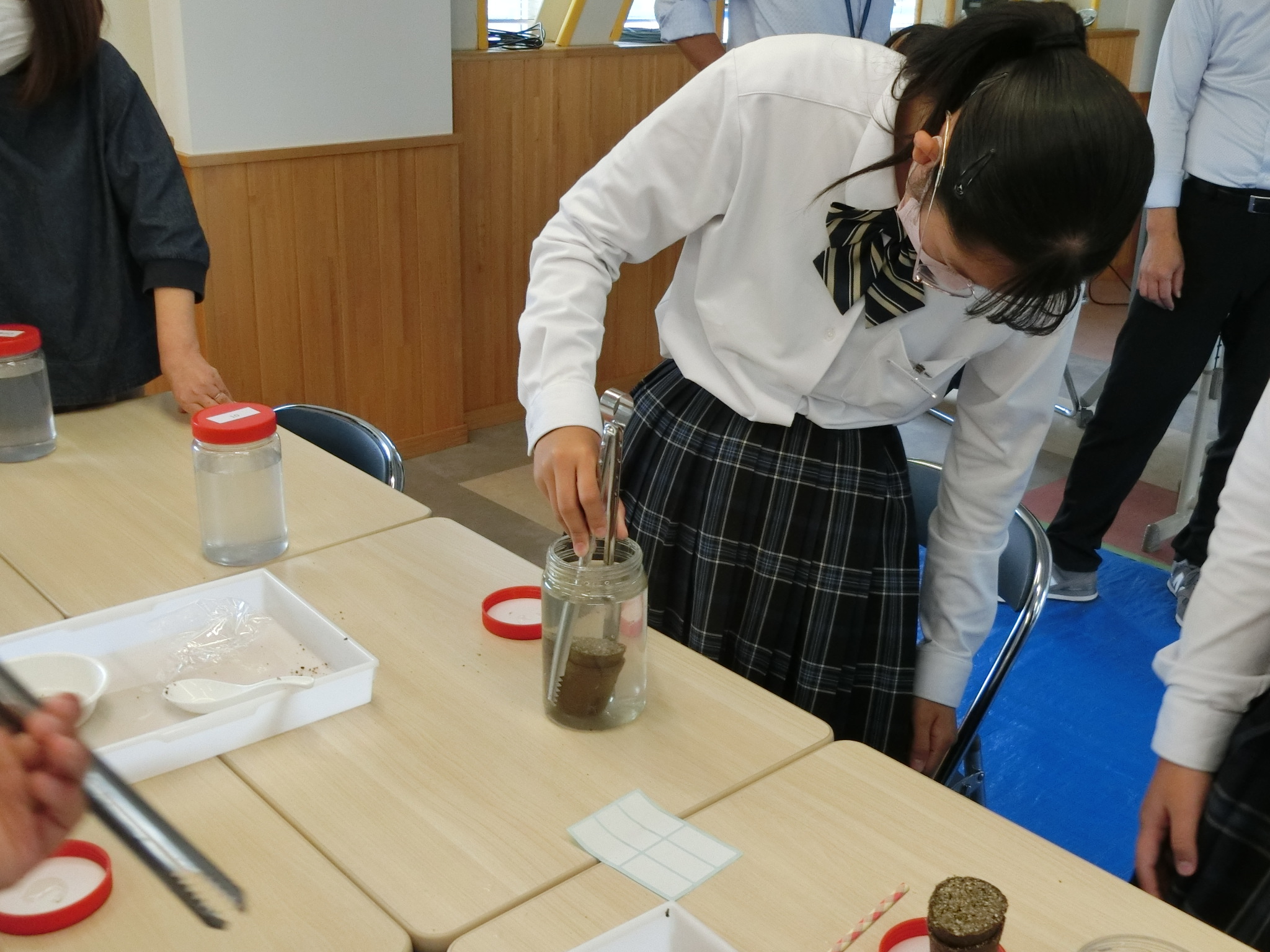
10月6日(木)6校時
学年の代表者による校内弁論大会がありました。7名の弁士は自分の経験をもとに堂々と発表することができました。学校代表の2名は、11月4日(金)に行われます備前市弁論大会に出場します。



10月1日(土)
本日は星輝祭(文化の部)。各クラスの合唱、そして3年生による舞台発表がありました。合唱は各クラスとも心をひとつにした歌声を、舞台発表は平和をテーマにした人権劇を保護者の方に届けることができました。






9月29日(木)放課後
明後日に行われる合唱コンクールに向けて、各学年・各クラスともに練習に熱が入っています。パートに分かれて練習をしたり、全体で合わせたりと30分の練習時間を計画的に使っていました。明後日の本番が楽しみです。




9月17日(土),18日(日)
備前東地区秋季総体がありました。日生中学校からは、ソフトテニス部・剣道部・バスケットボール部・サッカー部の生徒が参加しました。日頃の練習の成果を発揮して各部とも全力で頑張りました。その中でもソフトテニス部は団体戦優勝・個人戦2位、剣道部は個人戦ベスト8の成績を収め、県大会の切符を手にしました。



9月18日(日)
吹奏楽部の定期演奏会がありました。昨年はリモートでの開催であったため、久しぶりに対面での演奏会となりました。コロナ禍で発表の場が少なかった吹奏楽部員にとっては貴重な経験となりました。



9月16日(金)5,6校時
生徒会立会演説会がありました。感染対策のため、リモートで行いました。立候補者は、「こんな学校にしたい」という思いをそれぞれ伝えることができていました。その後、一人ひとりが貴重な1票を投票しました。みんなで協力してより良い学校をつくっていきましょう。



9月14日(水) 放課後
日生中学校では毎週水曜日に放課後学習を行っています。基礎や発展など7つのコースを開設し、希望した生徒が主体的に学習しています。



9月14日(水) 6校時
2年生の聞き書きのまとめとして、その成果をポスターセッションという形で1年生に発表しました。漁師さんなど漁業に関係する方の生き方から多くのことを学び、それを各グループで工夫を凝らして発表することができました。発表の後には1年生からの質問にしっかり答える姿が見られました。



9月14日(水)
備前市市民課の取り組みで自転車点検が行われました。皆さんが安全に登下校できるように、地域の業者の方が点検をしてくださいました。整備の必要な生徒には、黄色の札をつけています。ご家庭でも確認をお願いします。


9月14日(水) しんしんタイム
日生中学校では毎朝10分間の読書タイムを設けています。いつもは各自で読書を進めていますが、今日は文化委員による読み聞かせがありました。今日のためにしっかり準備をした文化委員が、クラスの仲間の前で堂々と読み聞かせを行うことができました。



9月13日(火) 5校時
2年生の総合的な学習の時間を利用して「ビジネスマナー」について学習しました。社会保険労務士をされている高橋先生に来ていただき、「職場体験学習前に知っておきたいこと」について学びました。2年生は11/18(火)から4日間の日程で職場体験学習を予定しています。今日の学びを職場体験に生かしてほしいと思います。


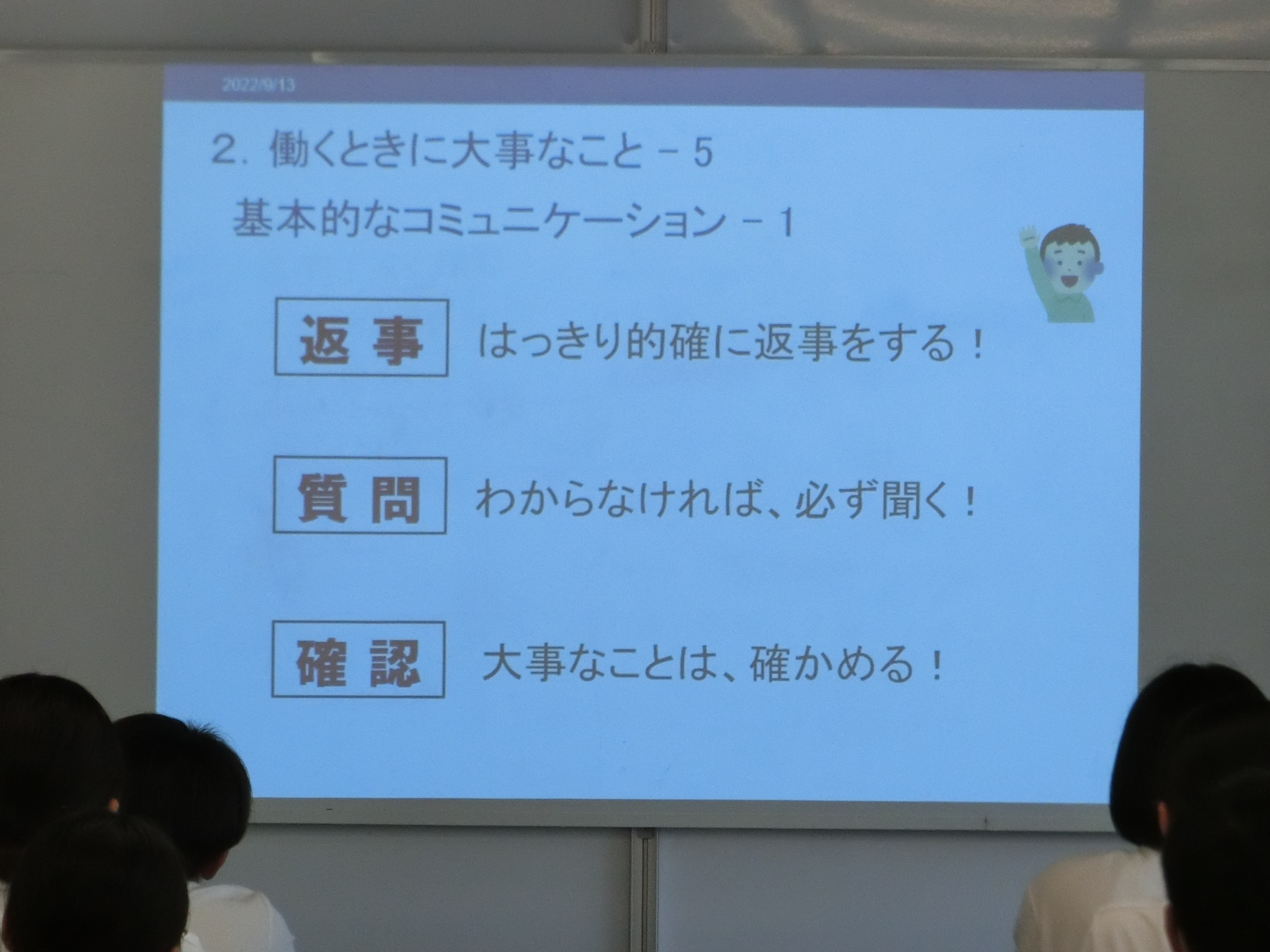
4月28日(木)1年生閑谷研修
1年生が閑谷研修を行いました。午前中は講堂で6つ論語を学びました。午後はスコアオリエンテーリングを行い、友情を深めました。



4月27日(水)2年生学活「PR大作戦」
2年生は、4月27日の学活で「PR大作戦~もっと友達のいいところをみつけよう~」という活動を行いました。唯一クラス替えのある学年で、新しいクラスになって1ヶ月がたちました。同じクラスになった人のいいところを旧クラスメートが紹介し、お互いの理解を深める目的で活動しました。
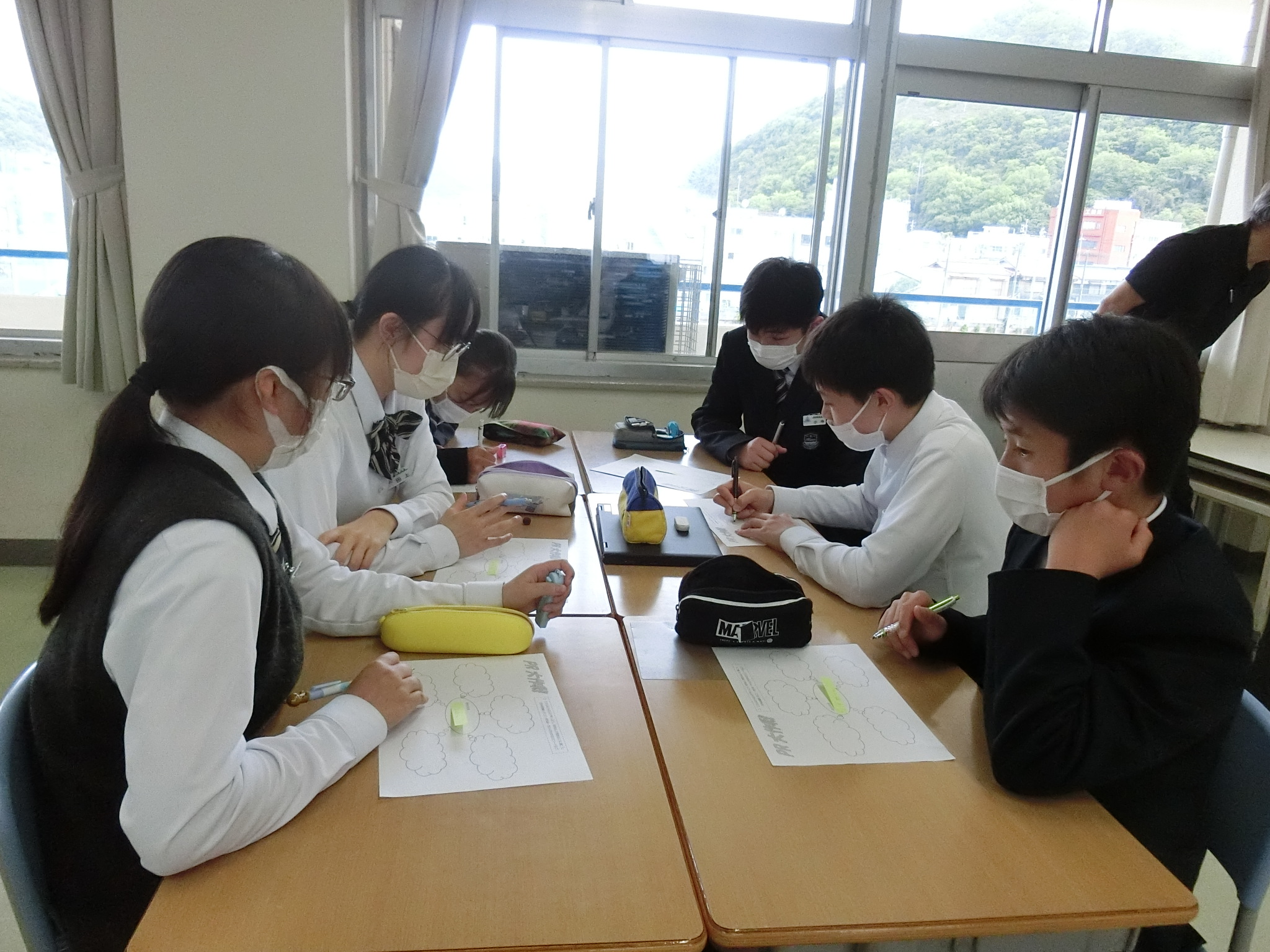
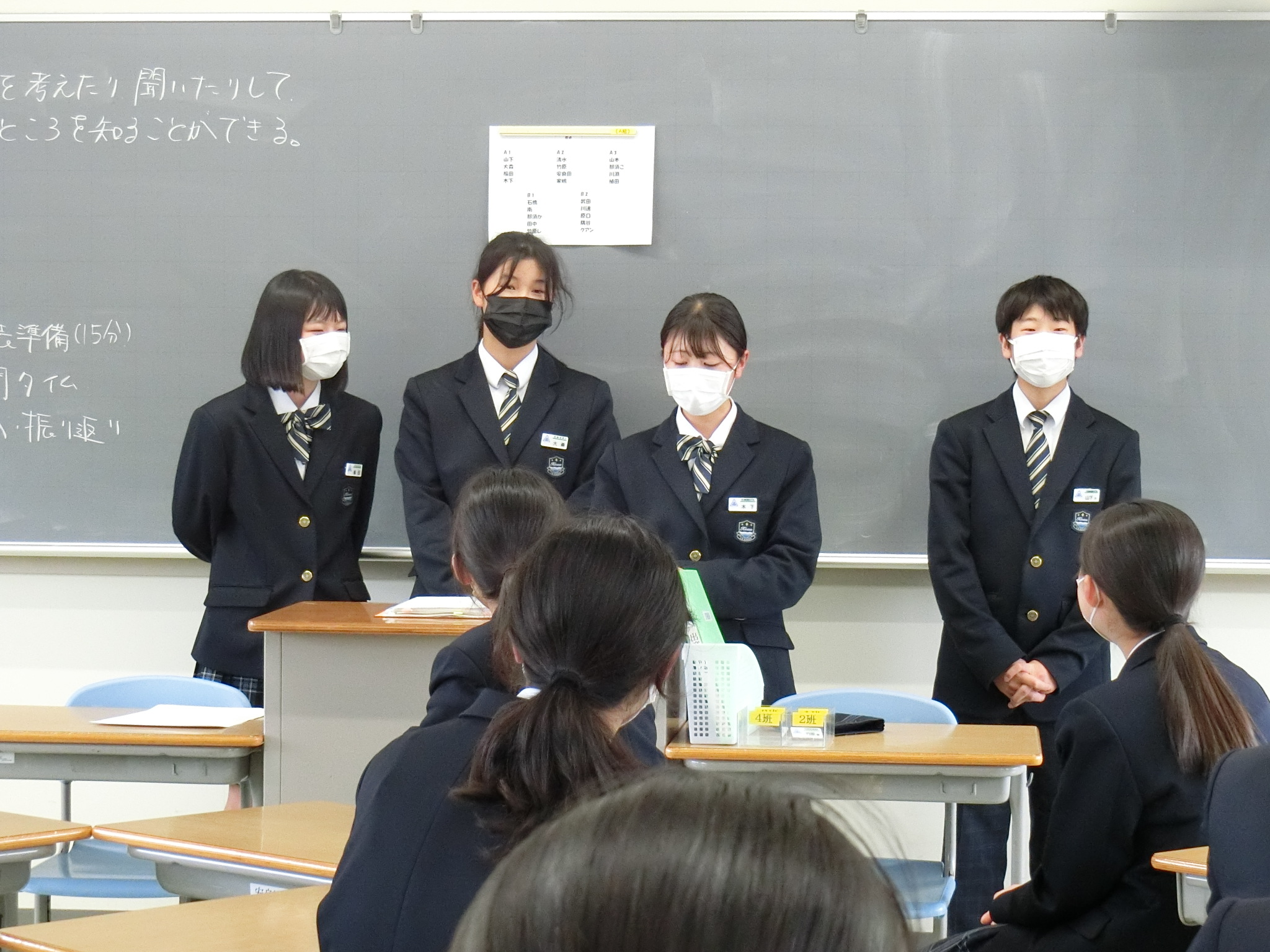

4月26日(火)吹奏楽部中庭コンサート
放課後に吹奏楽部が中庭コンサートを行いました。多くの手拍子に包まれて大盛況でした。


4月26日(火)1年生 6時間目
閑谷研修に向けて班活動を行いました。班対抗のレクも行い、友情を深めました。


4月26日(火)晩学習
社会科晩学習「目指せマゼラン☆世界周航マスター」が始まりました。4週間後の本番に向けて、暗記を頑張っています。

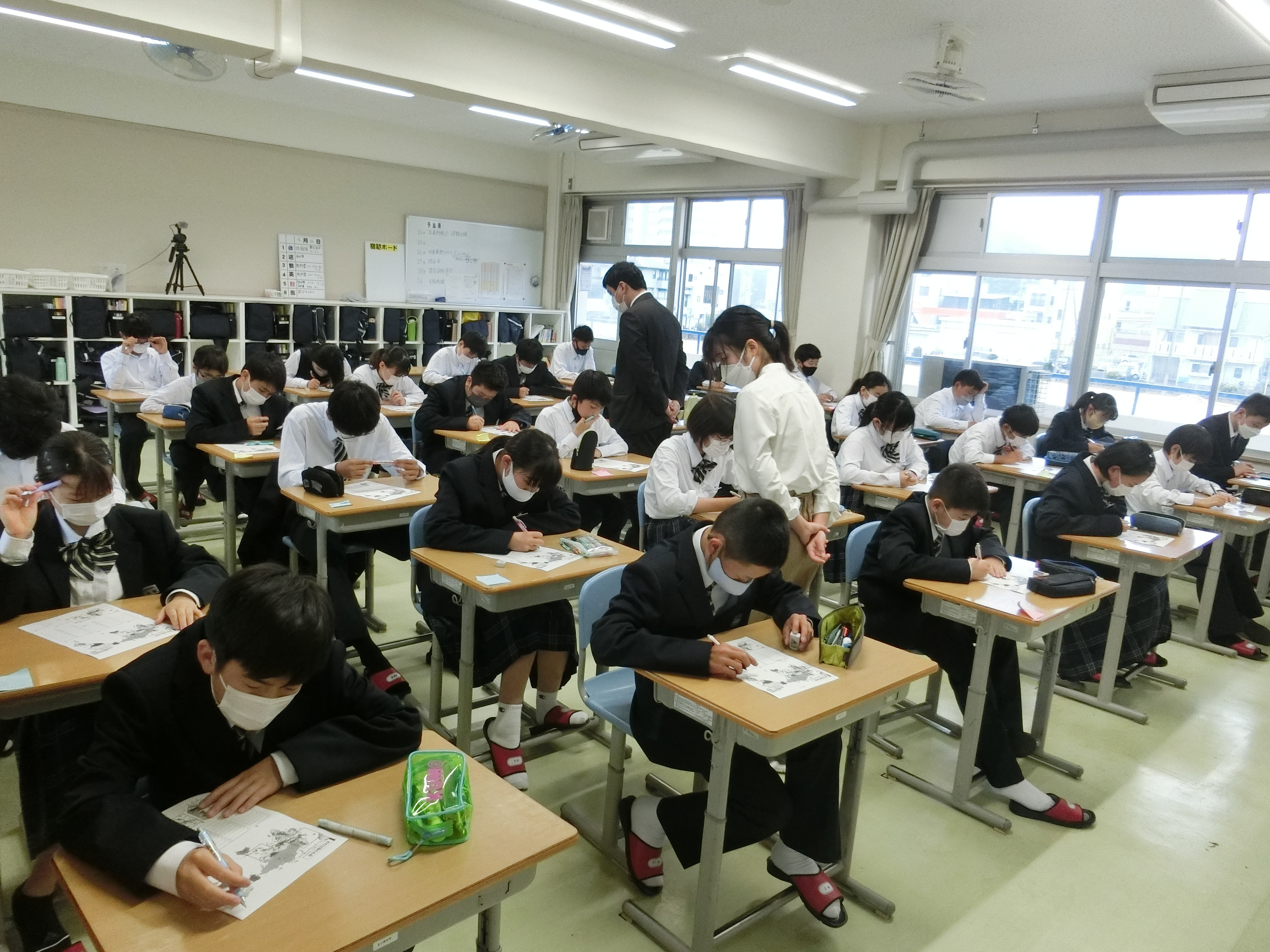
4月22日(金)避難訓練
火災を想定した避難訓練がありました。訓練の後、1年生は津波発生時に避難する上山公園まで歩いて行きました。



4月21日(木)3時間目 1年生学活
学級目標を決めました。学級委員長の2人が上手に話し合いをまとめていました。


4月20日(水)ブロック会
6月に実施する星輝祭体育の部のブロック会を行いました。ブロック長が所信表明を行い、その後出場種目を話し合いました。


4月18日(月)全校朝礼
前期専門委員会の認証式がありました。認証書授与のあと、代表の生徒が決意表明をしました。


4月15日(金)6校時


4月13日(水)5・6校時
1年生が校内巡りを行いました。初めて見る教室に、目を輝かせていました。


3月11日(金)
卒業証書授与式がありました。新型コロナウイルス感染症の影響で規模を縮小しての実施となりましたが、卒業する3年生にとっては一生忘れられない卒業式となりました。今日の感動を胸に新たな一歩を力強く踏み出してください。


3月10日(木)放課後
在校生と教職員で作成したモザイクアートを体育館に掲示しました。卒業する3年生へのサプライズイベントとして生徒会本部役員が中心となり計画しました。残念ながら在校生は卒業式に出席できませんが、在校生一人ひとりの思いはモザイクアートにつまっています。明日の卒業式に花を添える素晴らしい作品となりました。
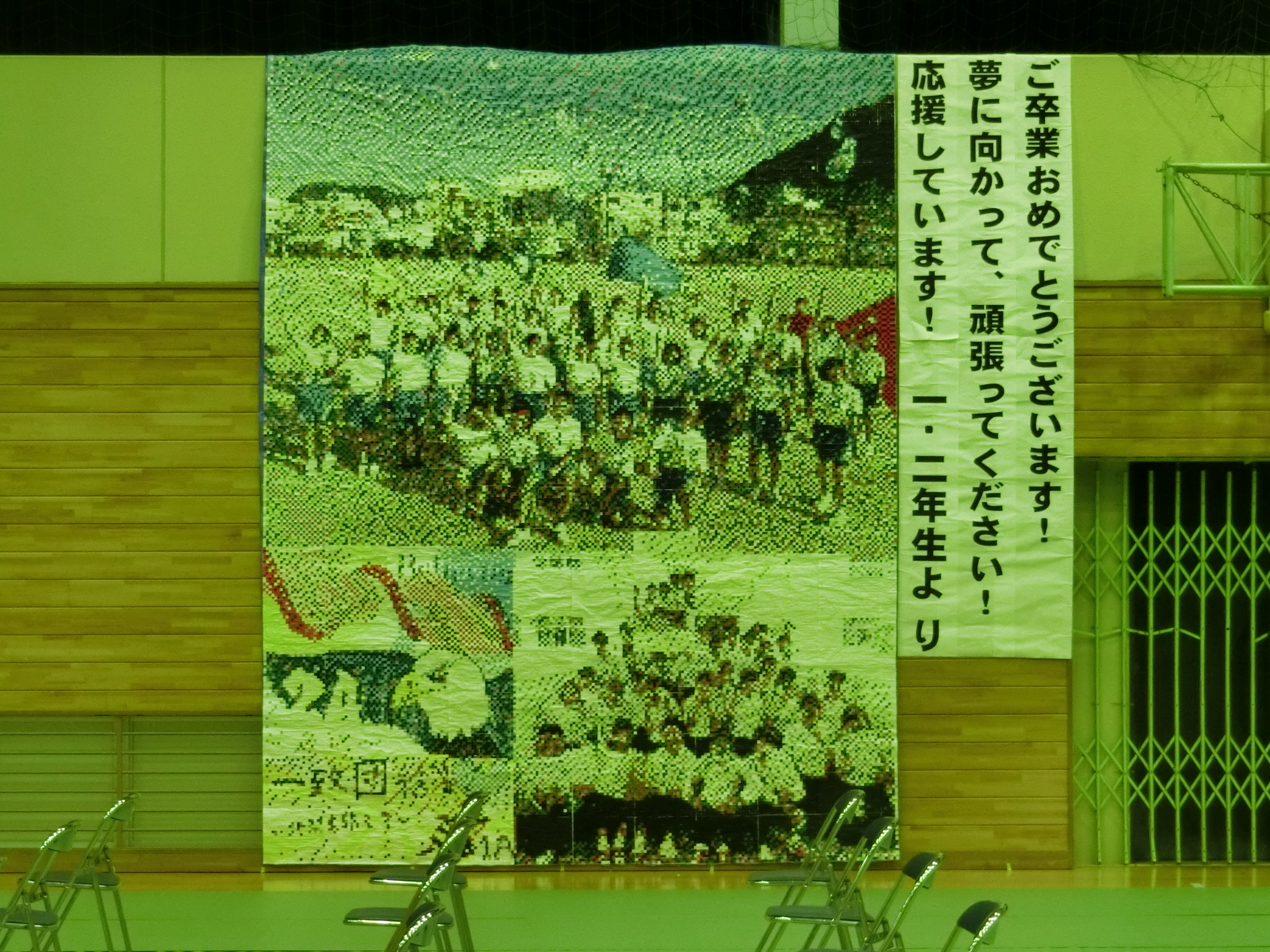
3月4日(金)放課後
環境委員会によるクリーン作戦が放課後ありました。今回は生徒玄関の掃除を環境委員と担当教員で行いました。丁寧に隅々まで掃除をしてくれており、来週にある卒業式に向けてもよい環境整備になりました。


3月2日(水)放課後
日生中学校では、水曜日に放課後学習を行っています。希望する生徒が参加して学習を進めていきます。全職員と地域の支援員でサポート体制を組んで実施しています。3年生は今日が最終回でした。来週にある入試に良い結果が出ることを願っています。




1月26日(水)5校時
2年生の美術の授業で大原美術館オンラインツアーを行いました。11月の岡山研修で見学できなかったため、本日のオンラインツアーとなりました。学芸員の方に施設の紹介や作品の説明をしていただきました。学校にいながら展示作品の説明が聞けるとても有意義な時間になりました。


1月25日(火)6校時
2年生でキャリア学習のまとめとして発表会を行いました。2年生になって行った「聞き書き活動」「チャレンジワーク」「企業訪問」をそれぞれの生徒がプレゼンテーションソフトを使ってまとめました。今回は、1年生の前で発表しましたが、一人一人が体験で得た学びを堂々と発表することができました。



1月25日(火)昼休み
24(月)から30(日)まで給食週間です。日頃からお世話になっている日生調理場の調理員さんや学校栄養職員の方へ全校生徒がお礼の手紙を書きました。その手紙と花かごを代表生徒が栄養職員さんに渡しました。


1月21日(金)6校時
本校スクールカウンセラーによる「こころの授業」が3年生でありました。受験期を前にストレスコントロールについて話をしていただきました。心をリラックスさせるためには身体をリラックスさせることが大切であること。そのための「呼吸を整える方法」「全身の力を抜く方法」について教えていただきました。



1月17日(月)5校時
防犯教室がありました。感染対策のため、リモートで行いました。備前警察署より2名来ていただき、講和とDVDを視聴しました。阪神淡路大震災から27年目の今日、一人一人が身を守るためにすべきことについて考えることができました。



12月24日(金)放課後
生徒会本部主催の冬のボランティア活動がありました。28名が参加してデイサービスセンター「こうら荘」の清掃活動を行いました。4グループに分かれて、落ち葉を集めたり草を抜いたりしました。短時間ではありましたが、みんなで協力してきれいにすることができました。



12月23日(木)放課後
吹奏楽部によるクリスマスコンサートが中庭でありました。「怪物」「夜に駆ける」「星影のエール」「クリスマスソングメドレー」「宿命」の5曲を演奏しました。新型コロナウイルス感染防止のため発表の場が少なくなっており、吹奏楽部員にとっては貴重な発表の場となりました。



12月20日(月)放課後
備前市の教育長さんの学校出前講座があり、中学校からは生徒会本部役員5名が参加しました。「将来の夢」「これから学校で取り組みたいこと」「読書や新聞記事、スポーツフェスティバルについて」「子ども学校運営協議会について」など、いろいろな話題で交流することができました。

12月16日(木)3,4校時
体育委員会主催のスポーツ大会がありました。1年生は各クラス1チーム、2、3年生は各学年2チームを編成し、合計6チームのトーナメント方式でキックベースボールを行いました。仲間への熱い声援、ミスをした時の声かけなどそれぞれのチームがひとつになって頑張っていました。


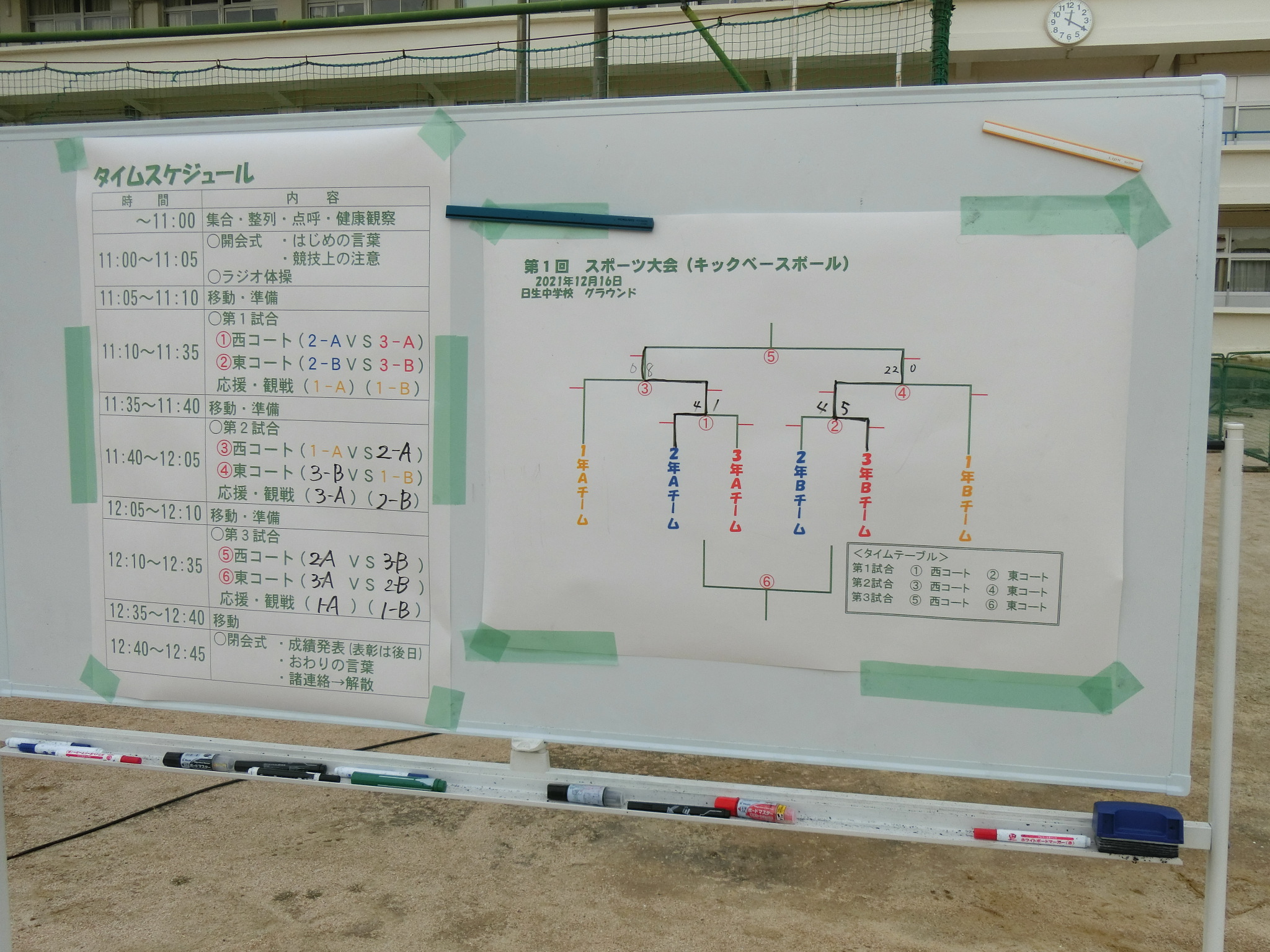
12月10日(金)3校時
3年生で性教育講演会を行いました。講師には、井上医院助産師の佐藤先生に来ていただき、講演をしていただきました。その人がその人らしく生きていくための学習で、からだの仕組みや出産、LGBTや性感染症など性に関する幅広い内容の話をしていただきました。特に先生が言われていた「みんな違っていてあたりまえ」、この言葉は先日の人権教育講演会の講演ともつながる内容でした。お互いの個性を大切にしながら学校生活を送っていきましょう。
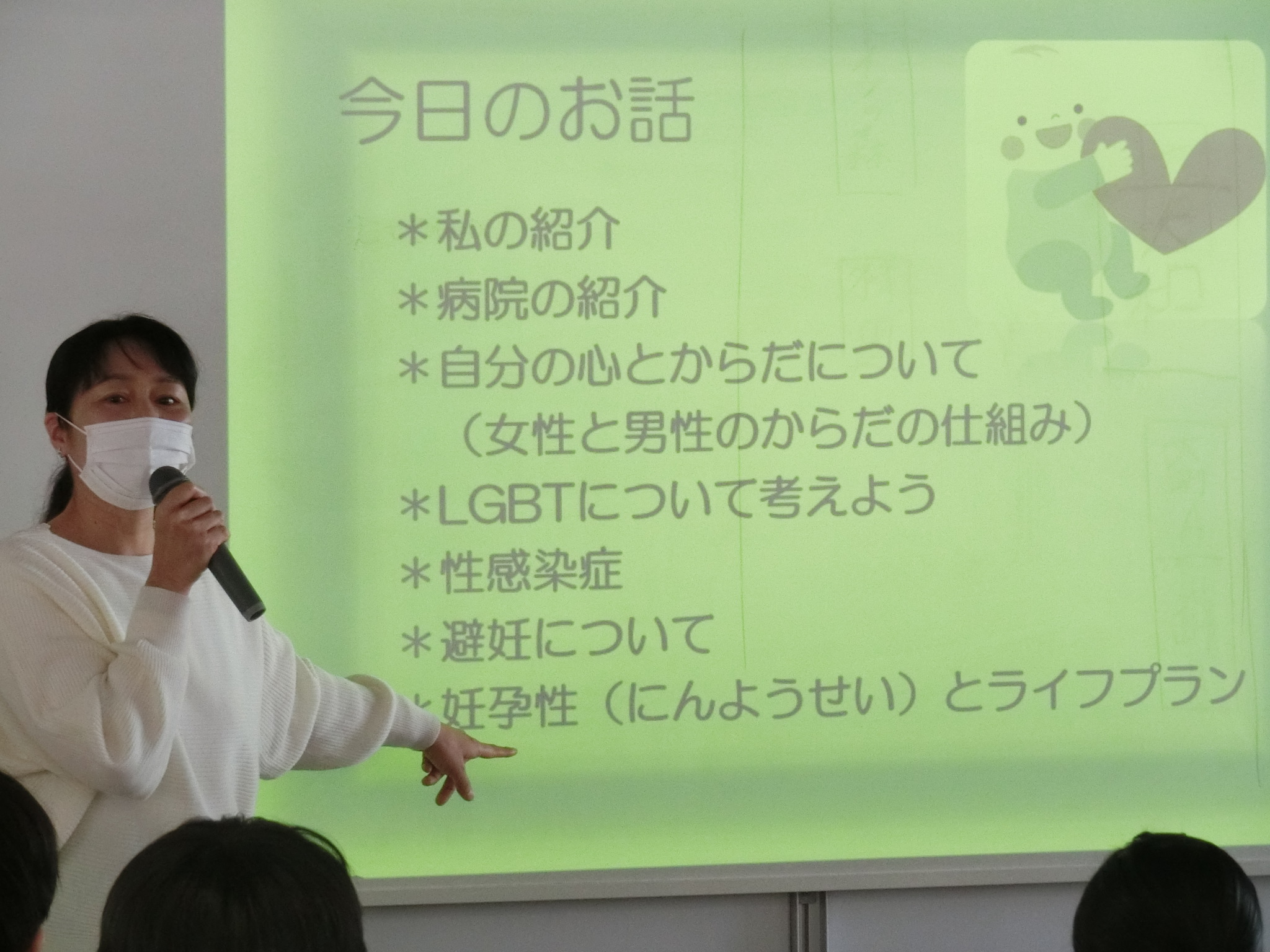

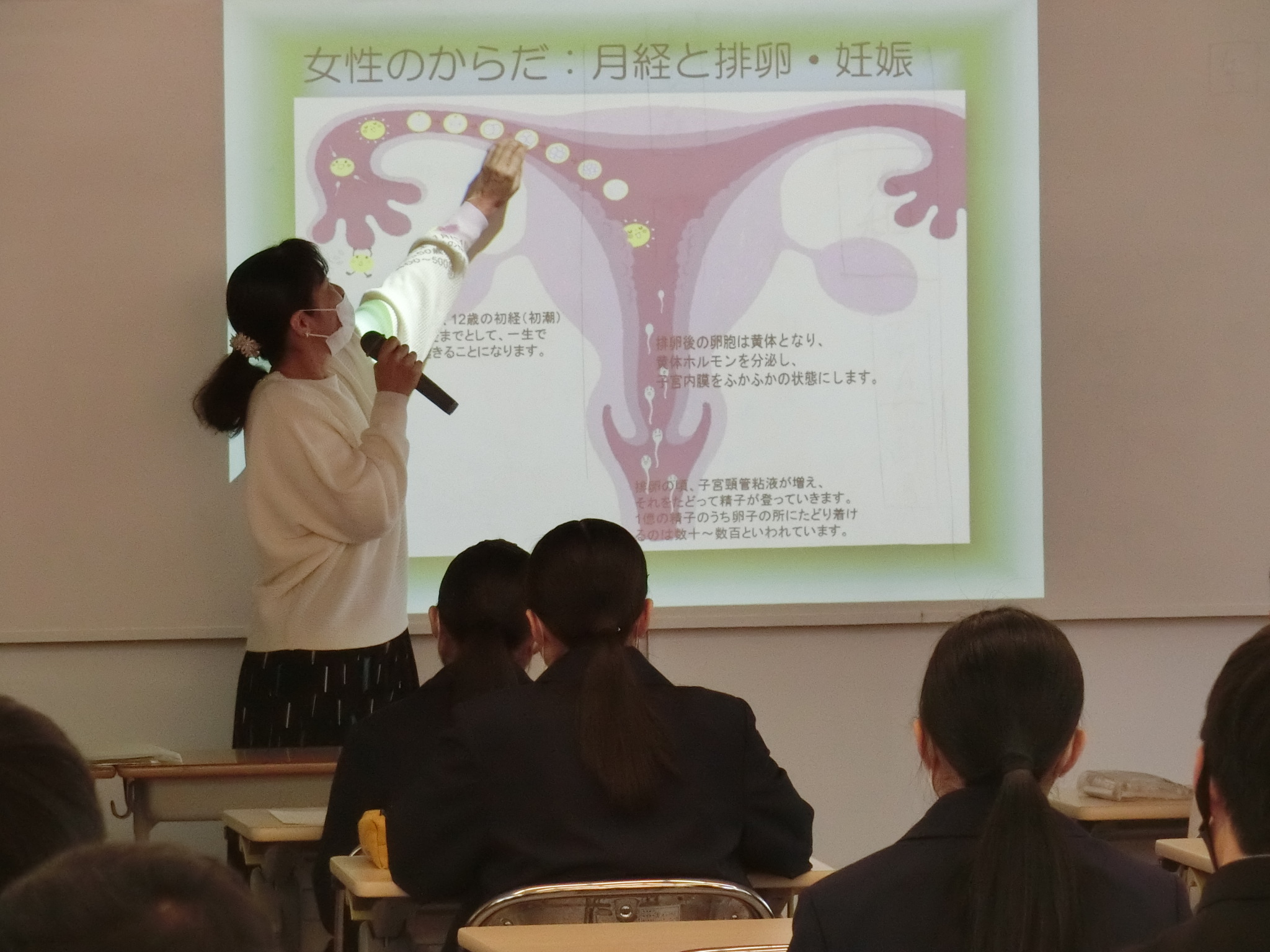
12月6日(月)5,6校時
PTA文化部保護者の皆さんの協力のもと、人権教育講演会を開催しました。講師には、岡山いのちの電話協会の牧野さんに来ていただき、「思春期・青年期の心の発達」と題して講演をしていただきました。「一人一人はかけがえのない存在で生きているだけで素晴らしい。みんな幸せになってほしい」と熱く語っておられました。講演は、事例をもとに思春期の発達課題について詳しく説明していただき、最後は、中学生に「悩みがあって当然、それが心を成長させる」「よき友、よき師を見つけよう」というメッセージをいただき、講演は終了しました。



12月2日(木)5,6校時
1年生は5校時、2年生は6校時に「こころの授業」がありました。本校の佐藤スクールカウンセラーが思春期の心について授業を行いました。思春期には、相手に合わせすぎてしんどくなったり、相手と比べて自分はダメだと思ったりすることがあるが、自分と相手は違っていい。お互いの個性を大切にすること、そして、違って当たり前のお互いの個性を合わせて協調性をつくり出していこうという内容でした。一人一人がなくてはならない存在です。一人一人が輝けるクラス・学年をつくっていきましょう。

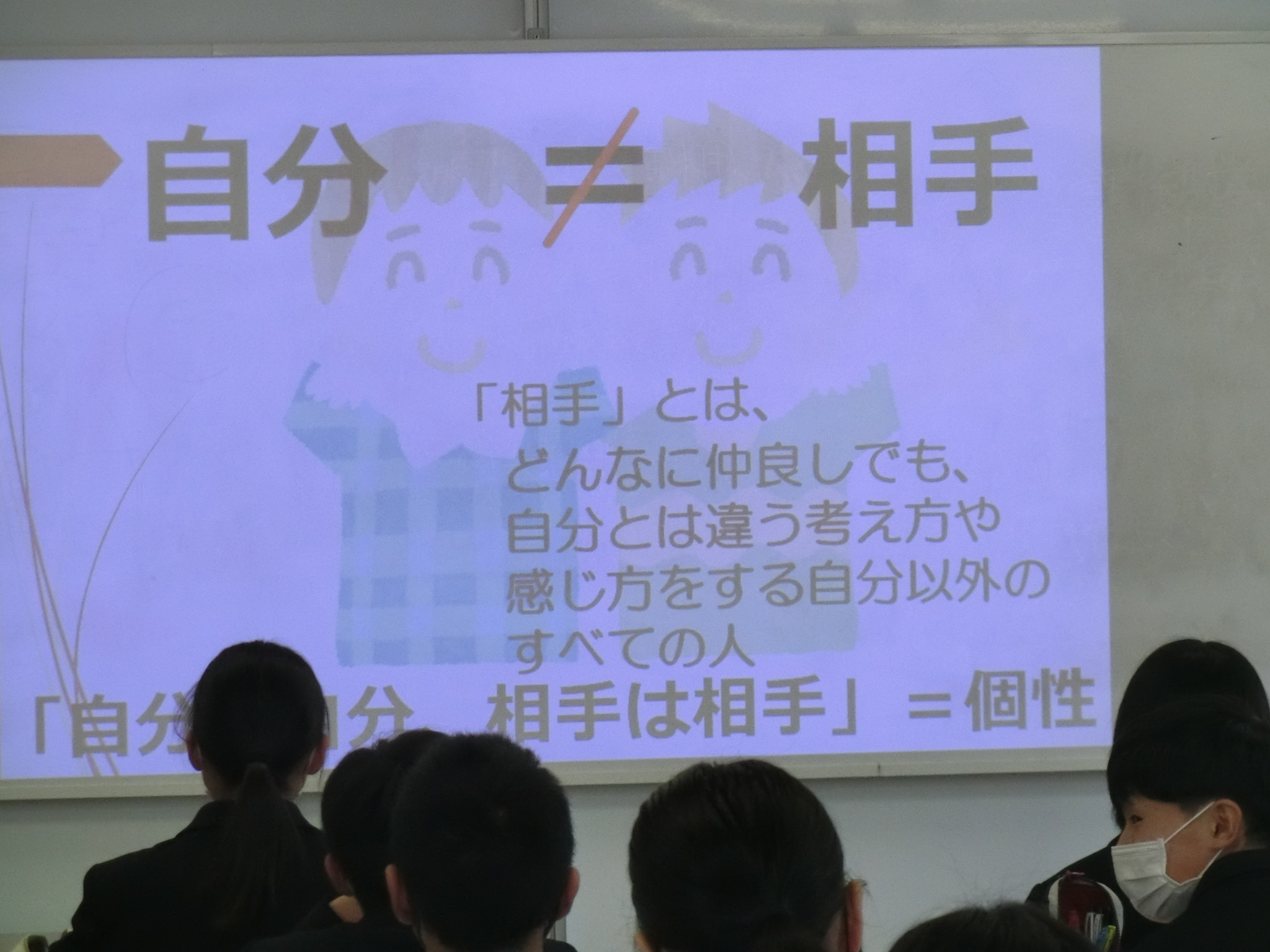
11月2日(火)
本日は、学校公開日並びに参観日、進路説明会でした。たくさんの保護者の方に参観していただき、ありがとうございました。3年生は4校時総合的な学習の時間に日生の将来について各グループで考え、提言を発表する活動でした。各グループとも地域資源を活用したいろいろなアイデアがあり、工夫を凝らした発表をすることができていました。

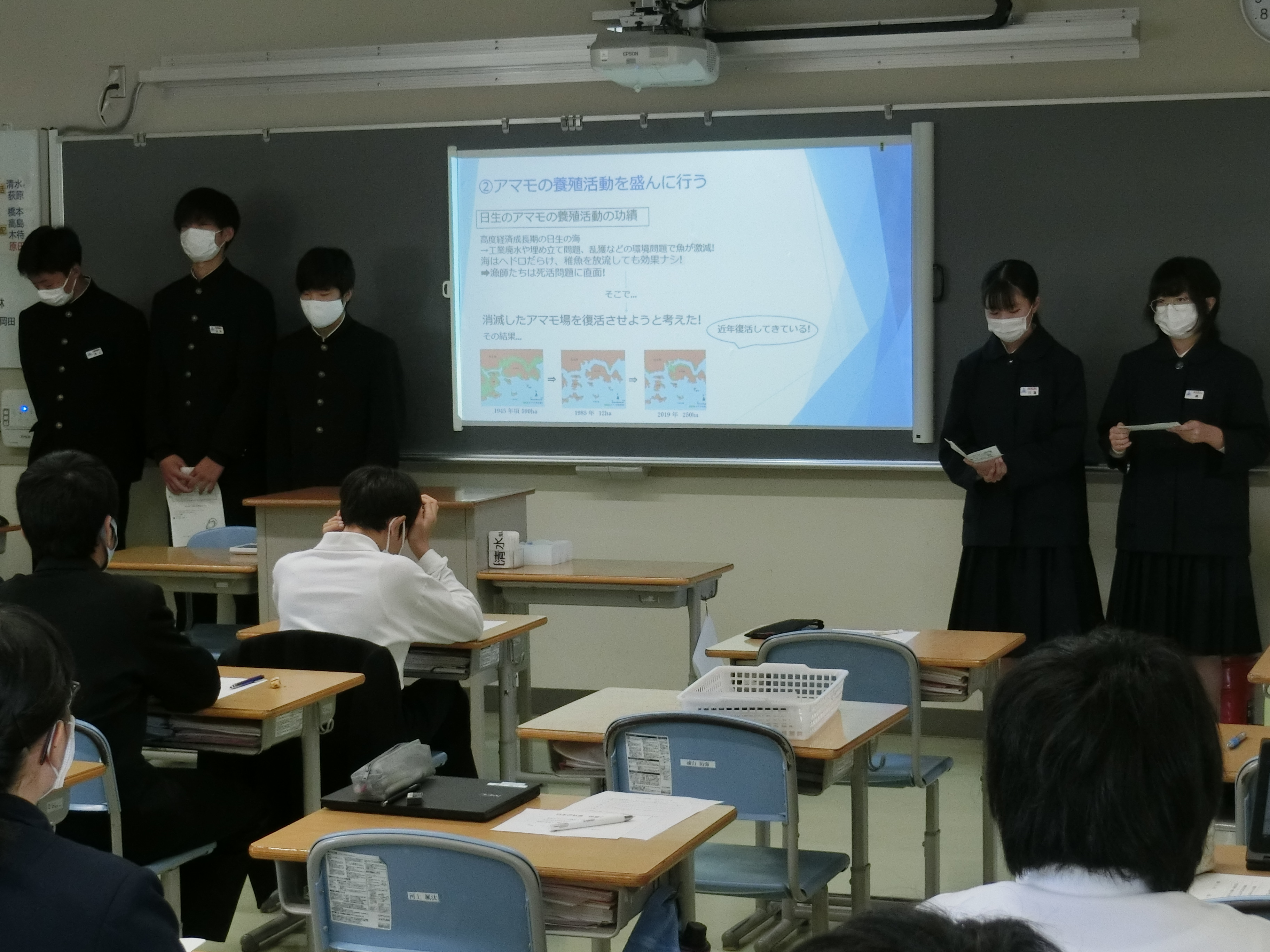

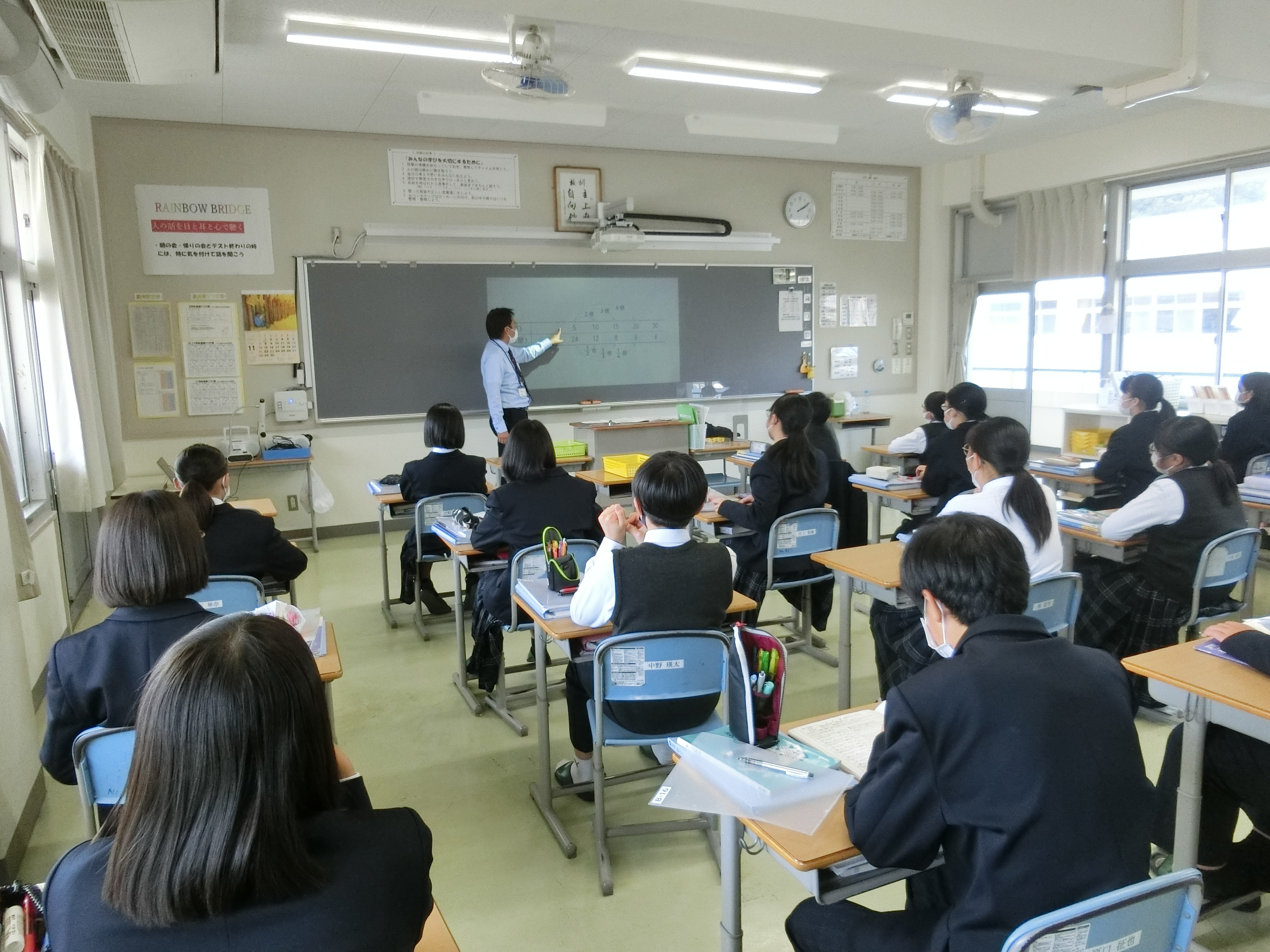


11月1日(月)
今朝の校門付近の様子です。体育委員会の生徒はあいさつ運動を、環境委員の生徒は落ち葉の掃除をしていました。体育委員による気持ちの良いあいさつ、環境委員による環境美化、朝からとても気持ちの良いスタートとなりました。


10月29日(金)2,3校時
3年生の家庭科の授業で保育体験を行いました。地域にある「わくわくるーむ」の協力のもと、赤ちゃんのお世話や一緒に遊ぶ活動を行いました。最初は緊張していた生徒も時間が経つにつれて少しずつ慣れていきました。今日の学習を通して、他者への思いやりや命の大切さについて改めて考える機会になったようです。



10月26日(火)6校時
各学級の代表者6名による校内弁論大会がありました。夢、受験、環境、言葉、自分を愛することなどをテーマにした内容でした。それぞれが自分の経験をもとに堂々と発表することができました。学校代表の2名は、11月5日(金)に行われます備前市弁論大会に出場します。

10月21日(木)
2年生は19(火)から4日間の日程でチャレンジワーク14(職場体験学習)を実施しています。備前市内や瀬戸内市内の事業所を中心に体験活動を行っています。コロナ禍の中、お引き受けていただいた事業所の皆様、ありがとうございました。生徒にとってはたいへん貴重な体験の場になっているようです。



10月15日(金)6校時
今年度2回目の生徒総会がありました。今日は、前期の活動報告と後期の活動計画、活動方針が決定されました。新しく役員になった専門委員長や生徒会本部役員を中心に充実した活動にしていきましょう。
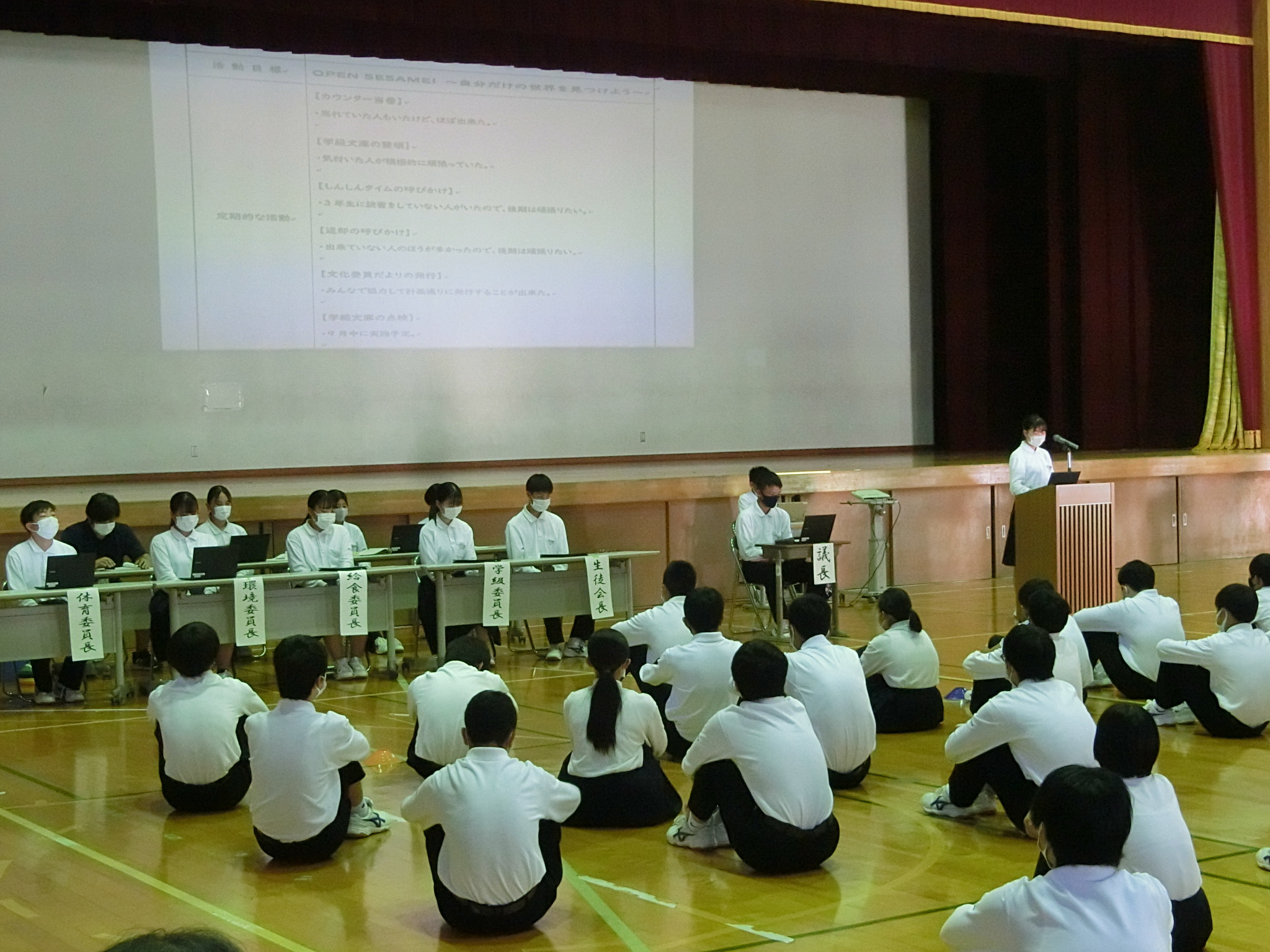
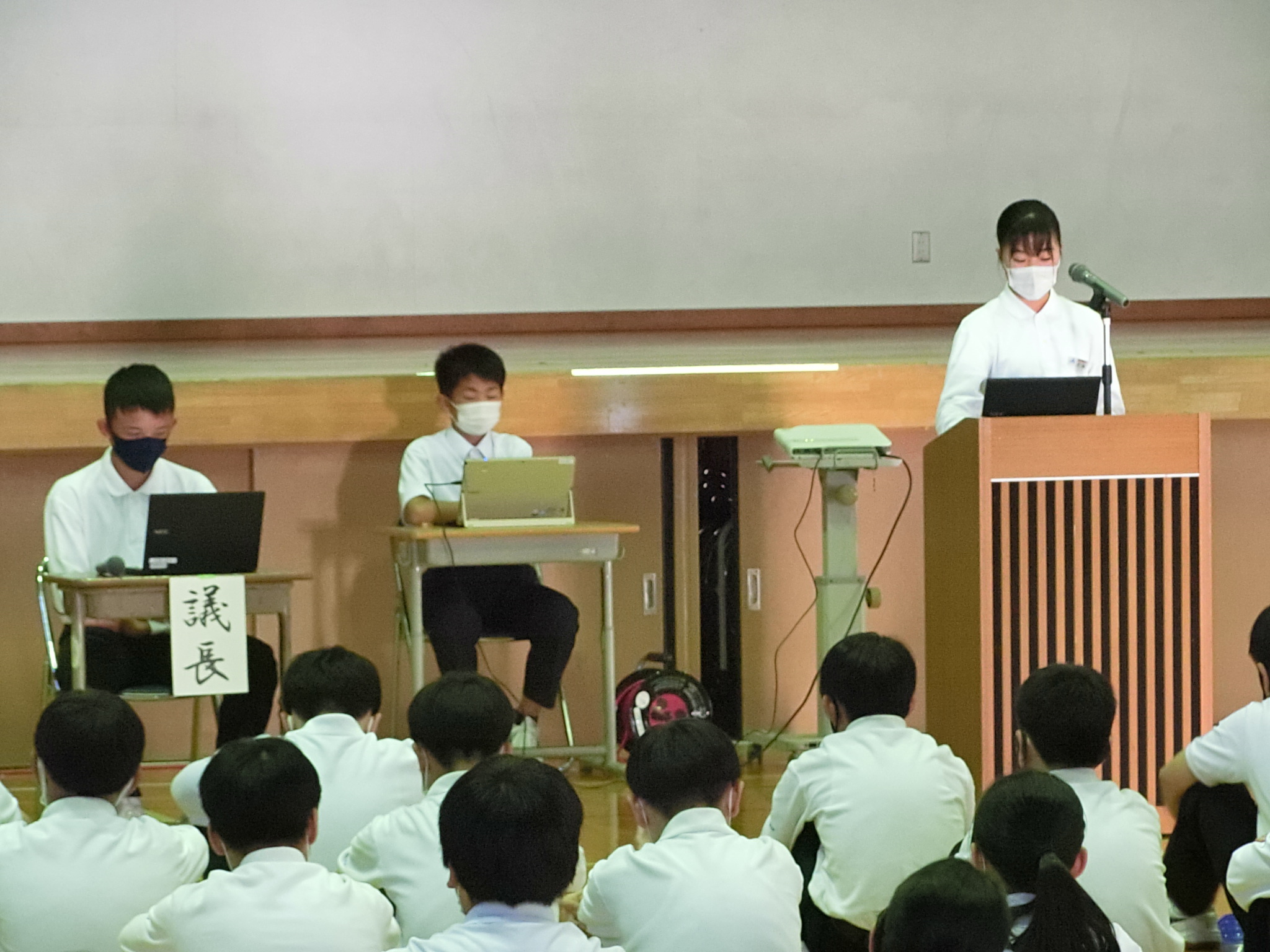

10月14日(木)5,6校時
2年生の総合的な学習の時間に「聞き書き」活動を行いました。この活動は、いろいろな職業の方に来ていただき、その人の生き方や職業観、その人の思いに触れることで自分自身の生き方を考える学習です。本日は8名の話者の方に来ていただき、岡山学芸館高校の生徒と一緒に活動を行いました。

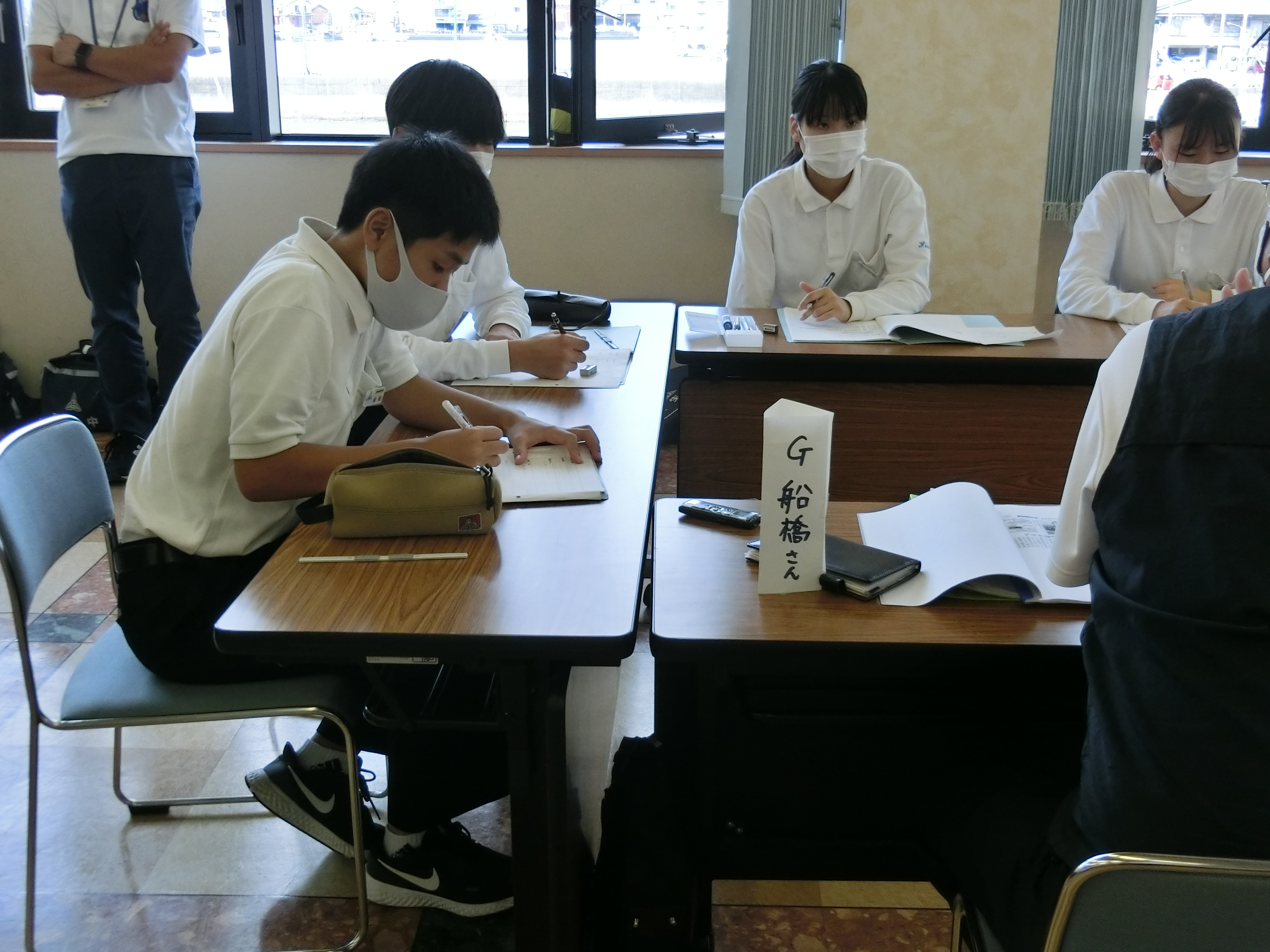

10月13日(水)5,6校時
5校時に2年生、6校時に3年生が保健体育の授業で「救命法」の学習をしました。東備消防組合の方に来ていただき、 心肺蘇生法の手順やAEDの使い方について説明をしていただきました。その後、マネキンを使って実際に心臓マッサージを体験しました。



10月8日(金)6校時
2年生の総合的な学習の時間に来週予定されている「聞き書き」の打合せを行いました。当日、一緒に活動する岡山学芸館高校の生徒とリモートで質問事項の確認を各グループで行いました。



10月8日(金)4校時
1、2年生合同でスマホ・ケータイ安全教室を実施しました。これは日生中学区全体で取り組んでいる活動で、KDDIの講師の方が日生東小、日生西小、日生中の3校それぞれで説明をしてくださいました。スマホに使われるのではなくスマホを上手に使えるよう、本日学んだことを実践していきましょう。
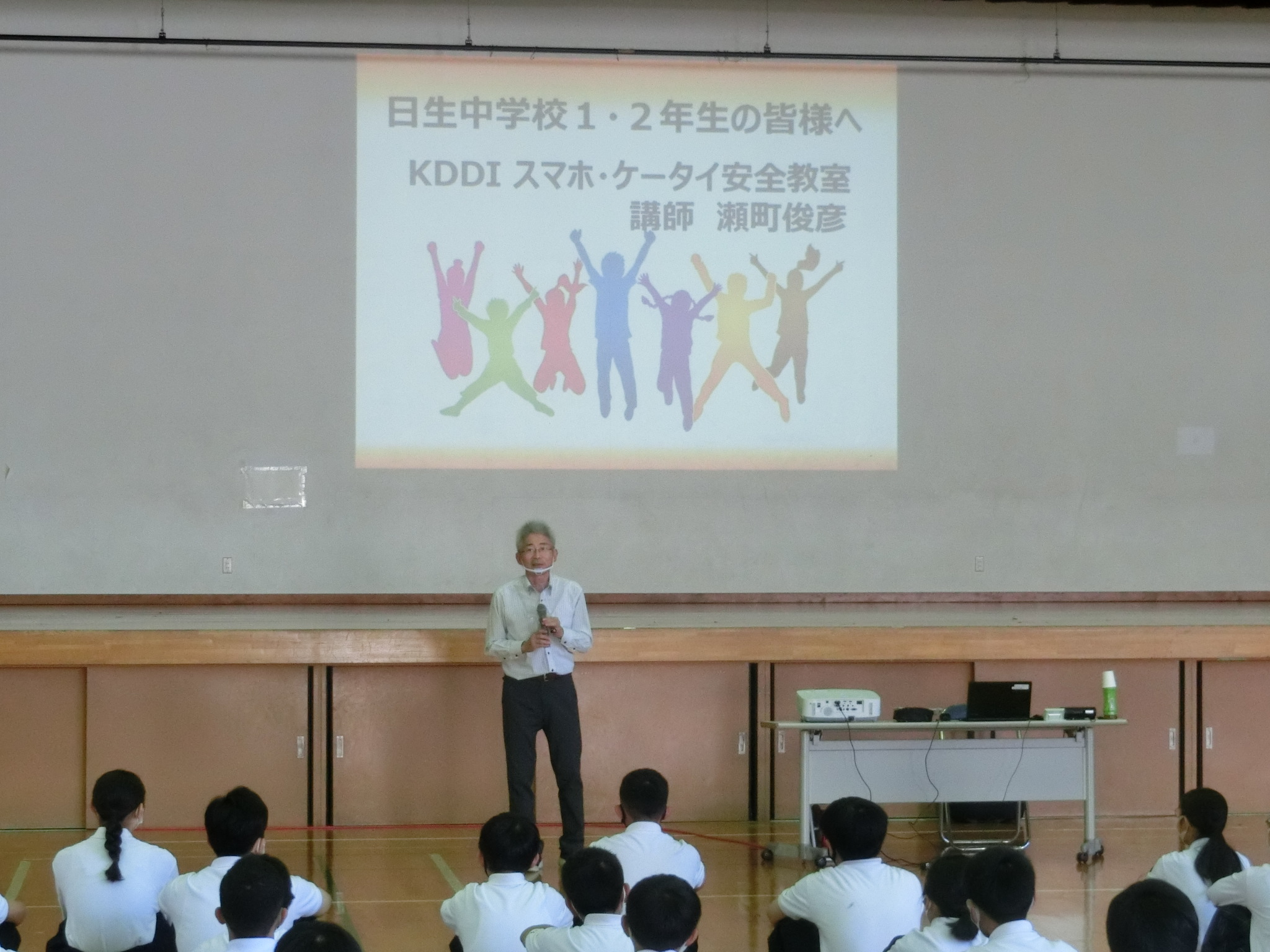

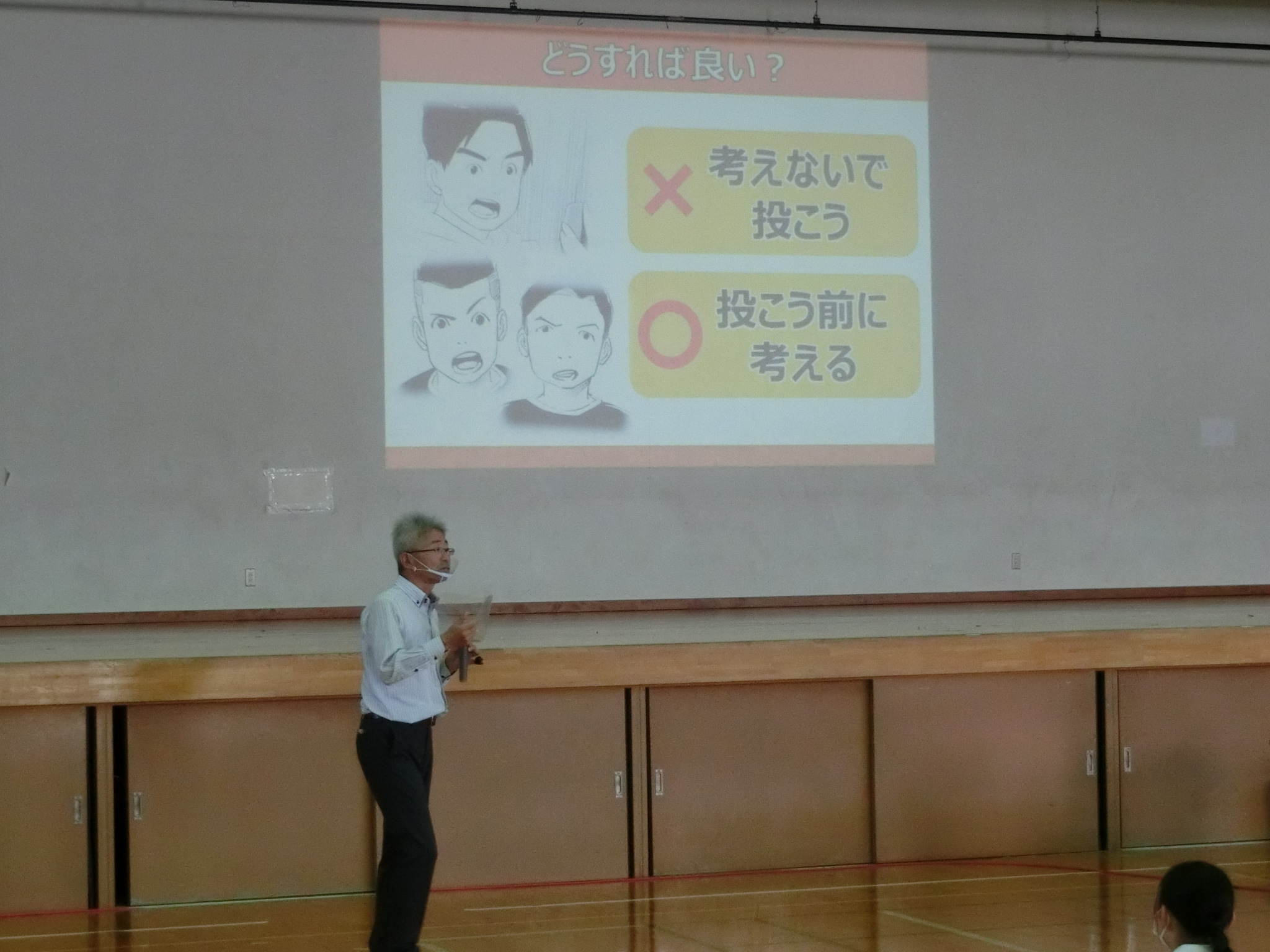
10月7日(木)
3年生は、今日から2泊3日の長崎修学旅行です。スローガン「ありがたし 思ひ出」のもと、事前に学習したことを長崎の地で見て、聞いて、歩いて学んできます。



10月6日(水)5,6校時
1年生の総合的な学習の時間でアマモポットを作成しました。日生中学校ではアマモ場の再生活動に取り組んでおり、本日は流れ藻から回収した種をポットに入れる作業でした。この種からどのように芽を出し成長するのかしっかり観察していきます。ご協力いただきましたおかやまコープの皆様、ありがとうございました。


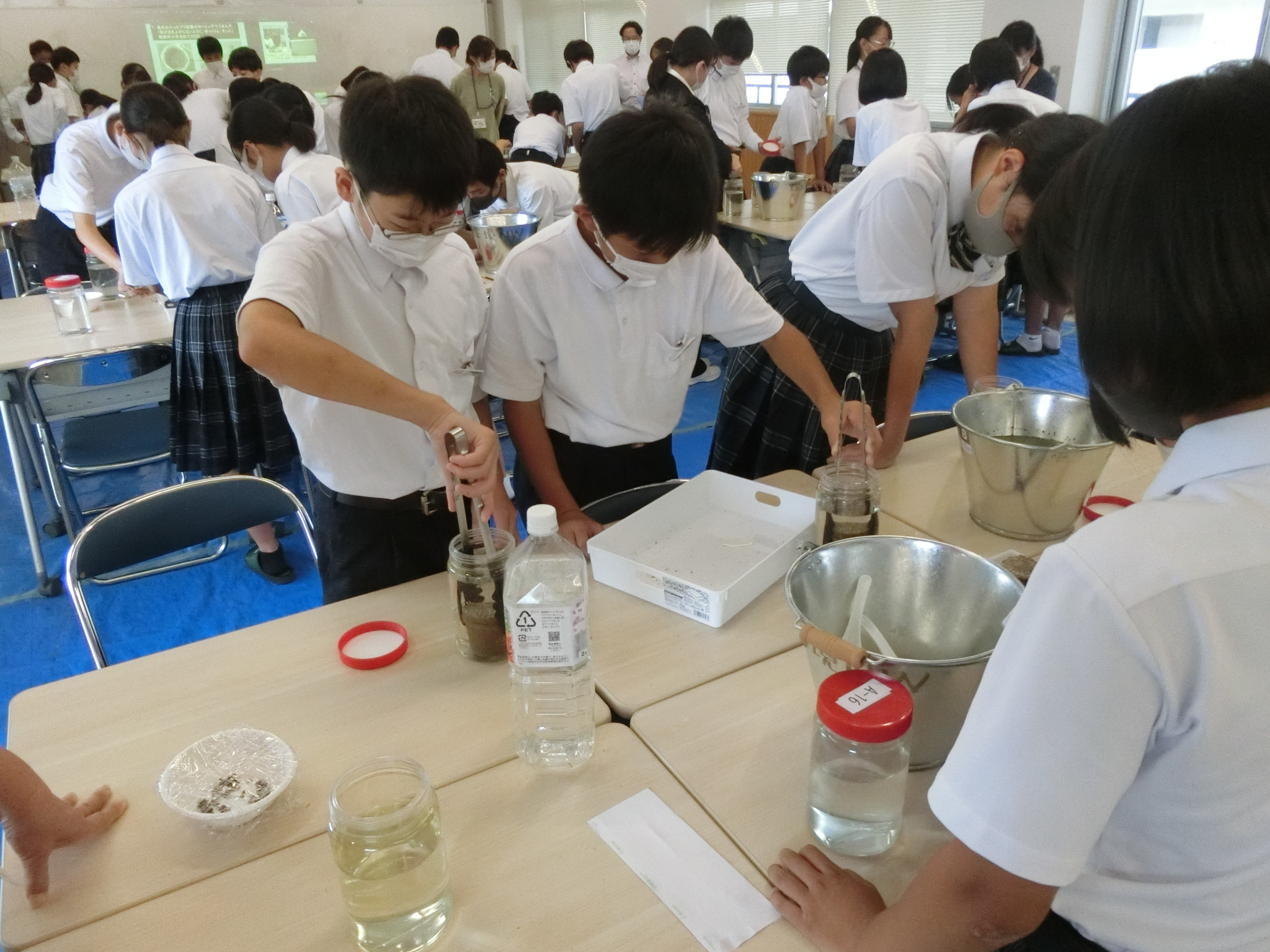
10月6日(水)2校時
3Aの国語の授業で、「お薦めの本のPOPづくり」を行いました。自分がこれまでに読んだ本の中で、ぜひ後輩たちに読んでもらいたい本を、思わず手に取ってみようと思えるようなPOPをつくって紹介するという授業です。生徒たちは、司書の井上先生の助言を受けながら、色とりどりの画用紙とペンを使って趣向を凝らしたPOPづくりに没頭していました。できあがった作品は、図書室と日生図書館に展示する予定です。


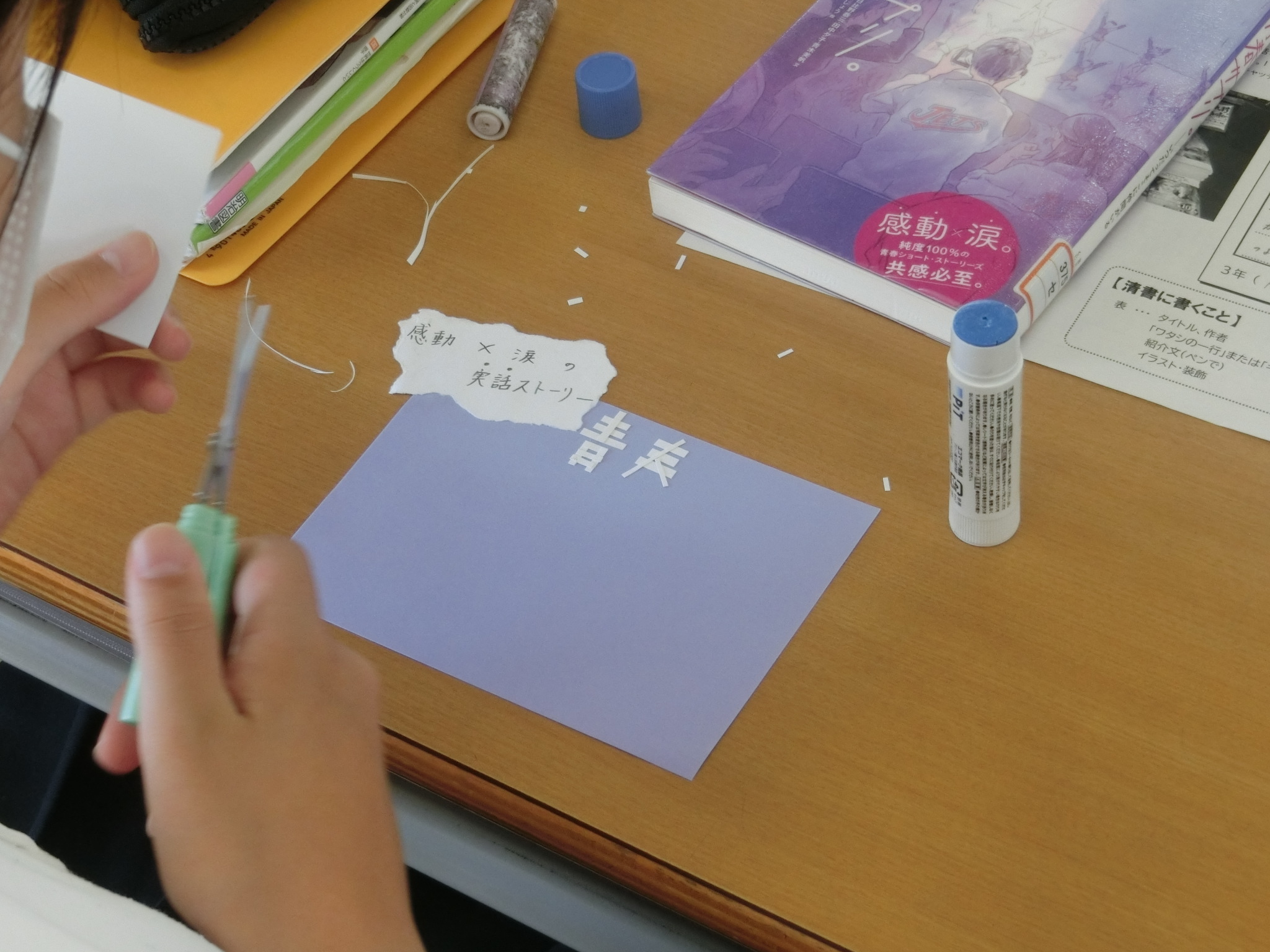
10月5日(火)2,3校時
2年生の総合的な学習の時間を利用して「ビジネスマナー」について学習しました。専門学校岡山ビジネスカレッジでキャリアコンサルタントをされている河原先生に来ていただいて「仕事とは」「働くとは」について学びました。2年生は10/19(火)から4日間の日程で職場体験学習(チャレンジワーク)を予定しています。今日の学びを職場体験に生かしてほしいと思います。


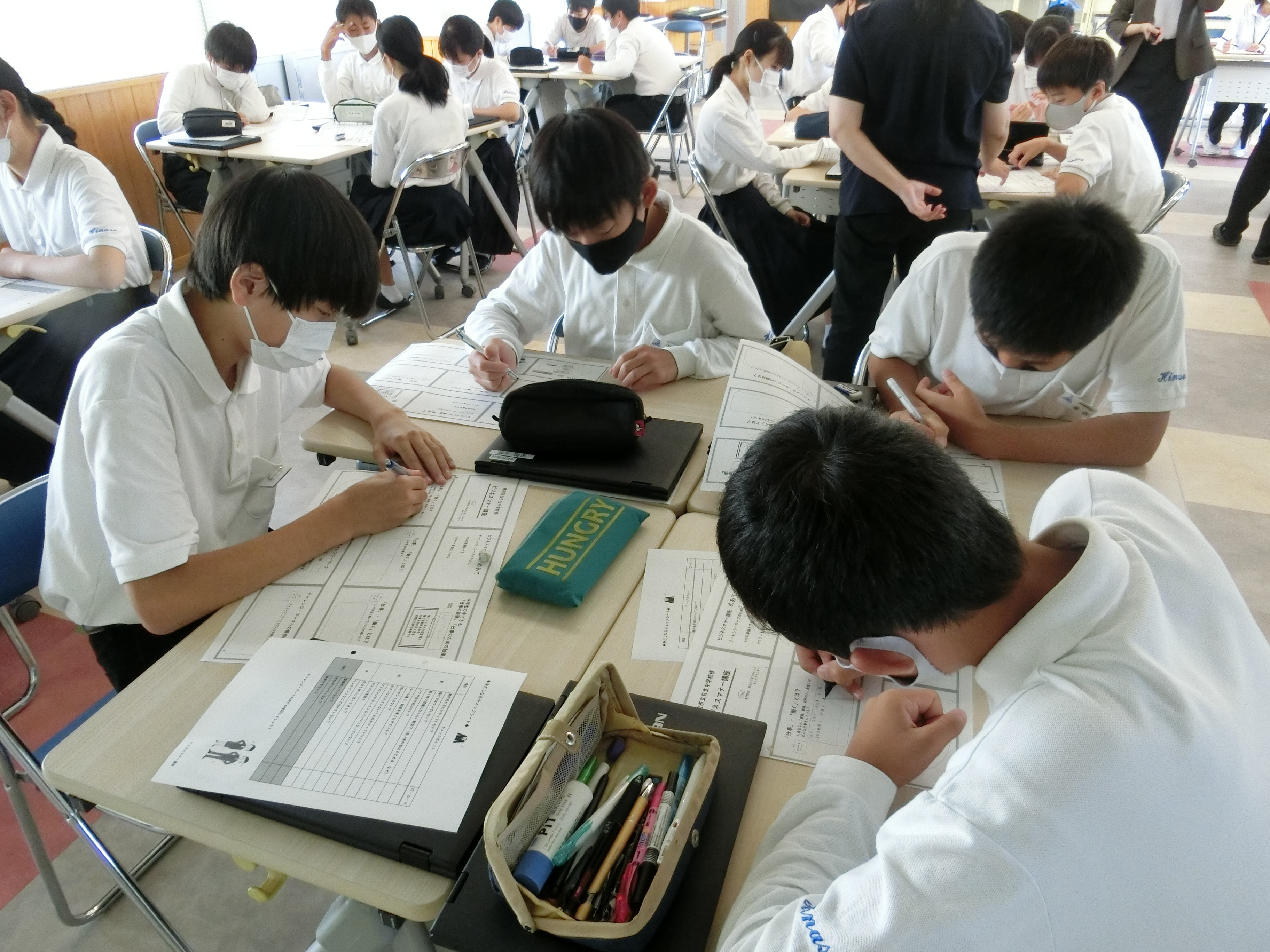
10月2日(土)
本日は星輝祭(文化の部)がありました。各クラスの合唱、3年生による舞台発表、そしてフィナーレは体育の部で発表できなかった星輝タイムでした。合唱は各クラスとも心をひとつにした歌声を、舞台発表は平和をテーマにした人権劇を保護者の方に届けることができました。フィナーレの星輝タイムはチーム日生中を全校生徒で体現することができました。












9月30日(木)放課後
明後日に近づいてきた合唱コンクールに向けて各クラスの練習が本気モードになってきました。今日は、体育館で3年生、武道場で2年生、フューチャールームで1年A組、音楽室で1年B・D組が練習をしていました。


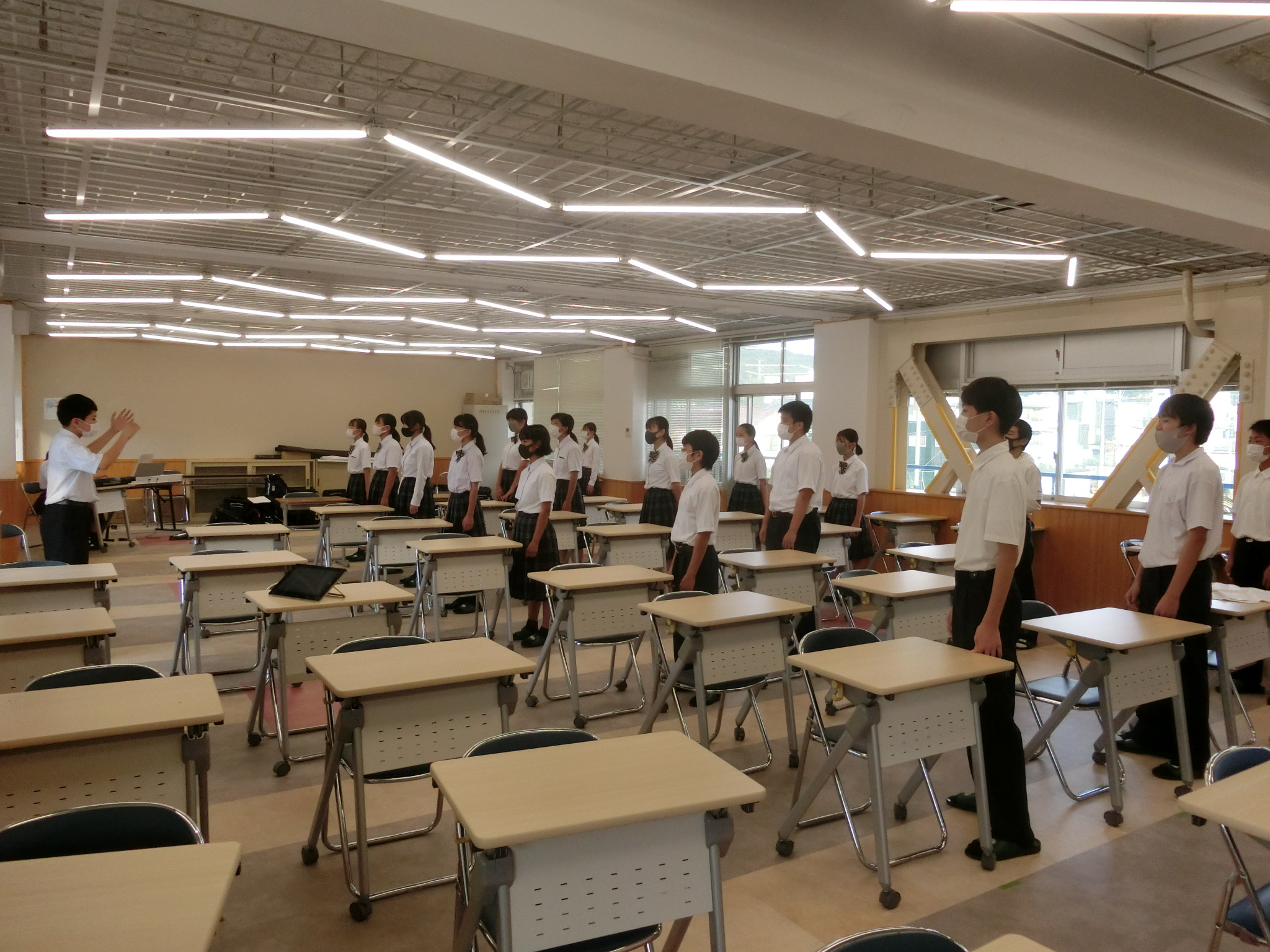

9月30日(木)4校時
星輝祭(文化の部)終了後に披露する星輝タイムの練習を全校体育の授業で行いました。グラウンドで練習するのはたいへん久しぶりでしたが、てきぱきと行動し、予定していた演技の確認をすべて行うことができました。



9月27日(月)全校朝礼
生徒会中央役員、専門委員長および後期専門委員の認証式がありました。新型コロナウイルス感染対策のため、リモートで実施しました。認証書授与のあと、代表の生徒が決意表明をしました。

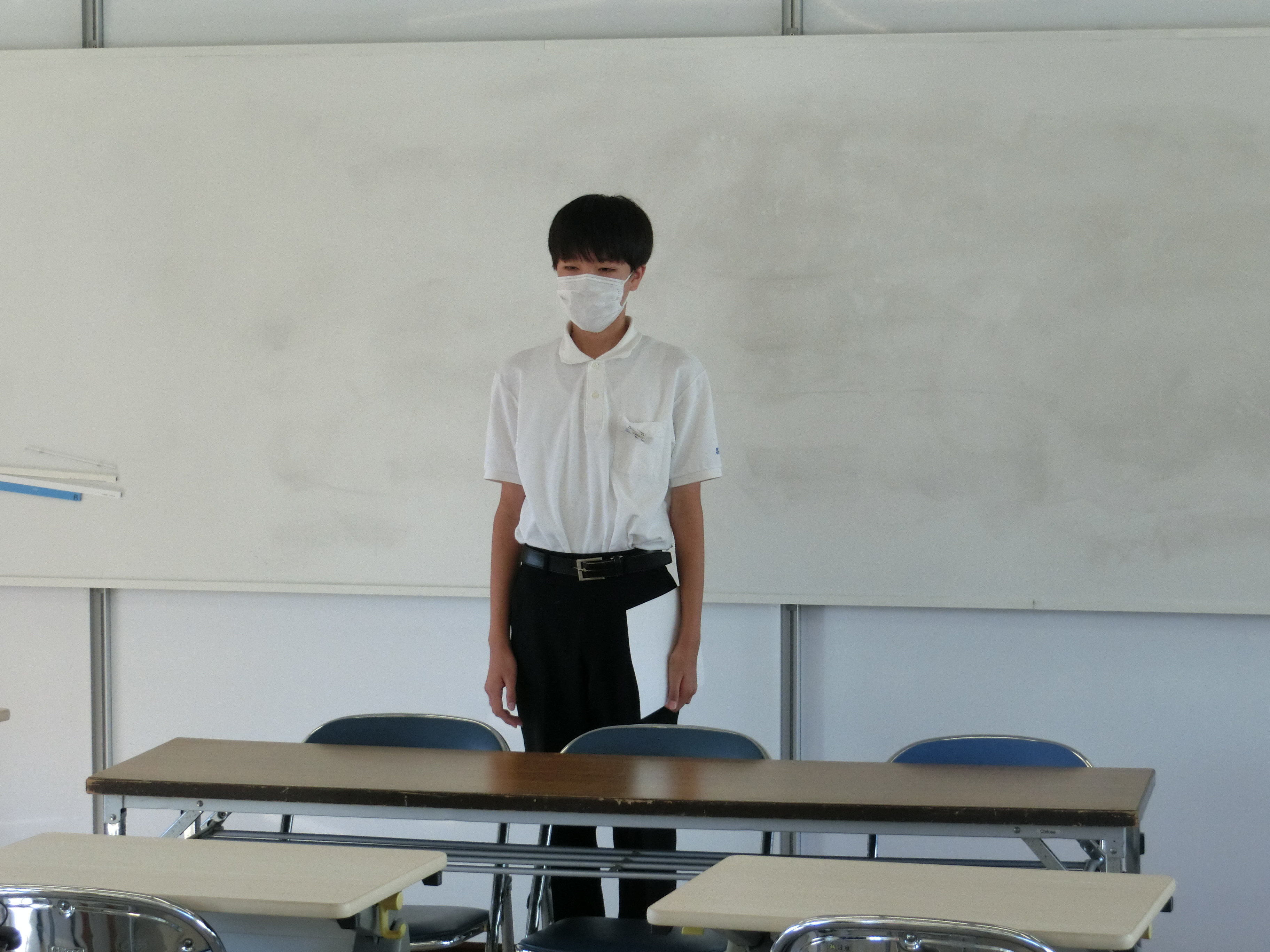

9月24日(金)5,6校時
全校体育の授業で、星輝祭(体育の部)代替行事2日目を行いました。Long × Jump (①全員跳び ②8の字跳び)と男女混合リレーがありました。どのブロックも声をかけ合い、最後の最後まで諦めずに頑張ることができました。









9月22日(水)5校時
生徒会役員選挙がありました。感染対策のため、リモートで実施しました。立候補者は、「こんな学校にしたい」という思いをそれぞれ伝えることができていました。みんなで協力してより良い学校をつくっていきましょう。



9月21日(火)5,6校時
延期になっていました星輝祭(体育の部)代替行事を全校体育の授業で実施しました。感染対策のため、入退場や観覧方法も変更になりましたが、生徒たちは自分たちで考え、素早く行動することができていました。各ブロックとも仲間のために一生懸命競技する姿が見られました。



9月19日(日)
吹奏楽部定期演奏会を行いました。まん延防止等重点措置の対象区域に備前市が指定されたため、リモートでの実施となりました。この1年間、新型コロナウイルス感染防止のため成果を発表する場がほとんどなく、3年生にとっては中学校生活最後の発表の場となりました。



9月10日(金)5,6校時
備前市や瀬戸内市、赤磐市の自治体と連携したキャリア学習を1年生で行いました。市の担当の方とリモートでつなぎ、各市の企業を紹介していただきました。生徒はタブレットを使いながら地元の企業の魅力をワークシートにまとめていました。


9月10日(金)1校時
星輝の大運動会に向けて全校体育の授業がありました。1学期から延期された行事ですが、来週の実施に向けて、感染対策をしながら各ブロックで練習を行いました。



9月1日(水)6校時
1年B組の理科の授業では、金属と非金属についての学習をしていました。タブレットを使いながら金属と非金属の分類方法について各グループで話し合い、次回の実験方法を決定していました。



9月1日(水)6校時
2年生の総合的な学習の時間で「聞き書き」について学習しました。今日は「聞き書き」学習の1時間目ということで、共存の森ネットワークの吉野奈保子さんに講話をしていただきました。緊急事態宣言の発出を受けてリモートでの開催となりました。吉野さんからは、「聞き書きで大切なこと」について話をしていただきました。
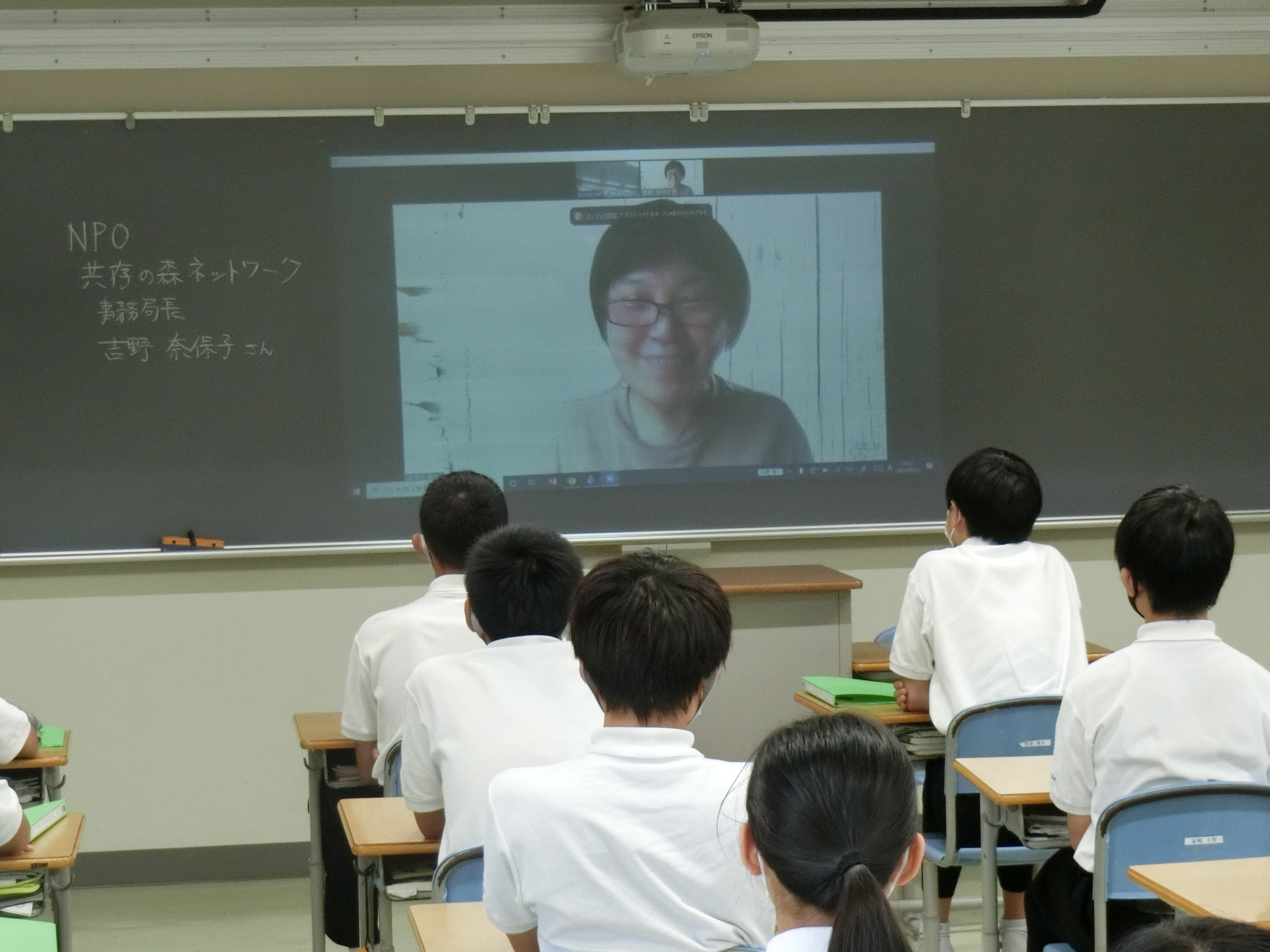
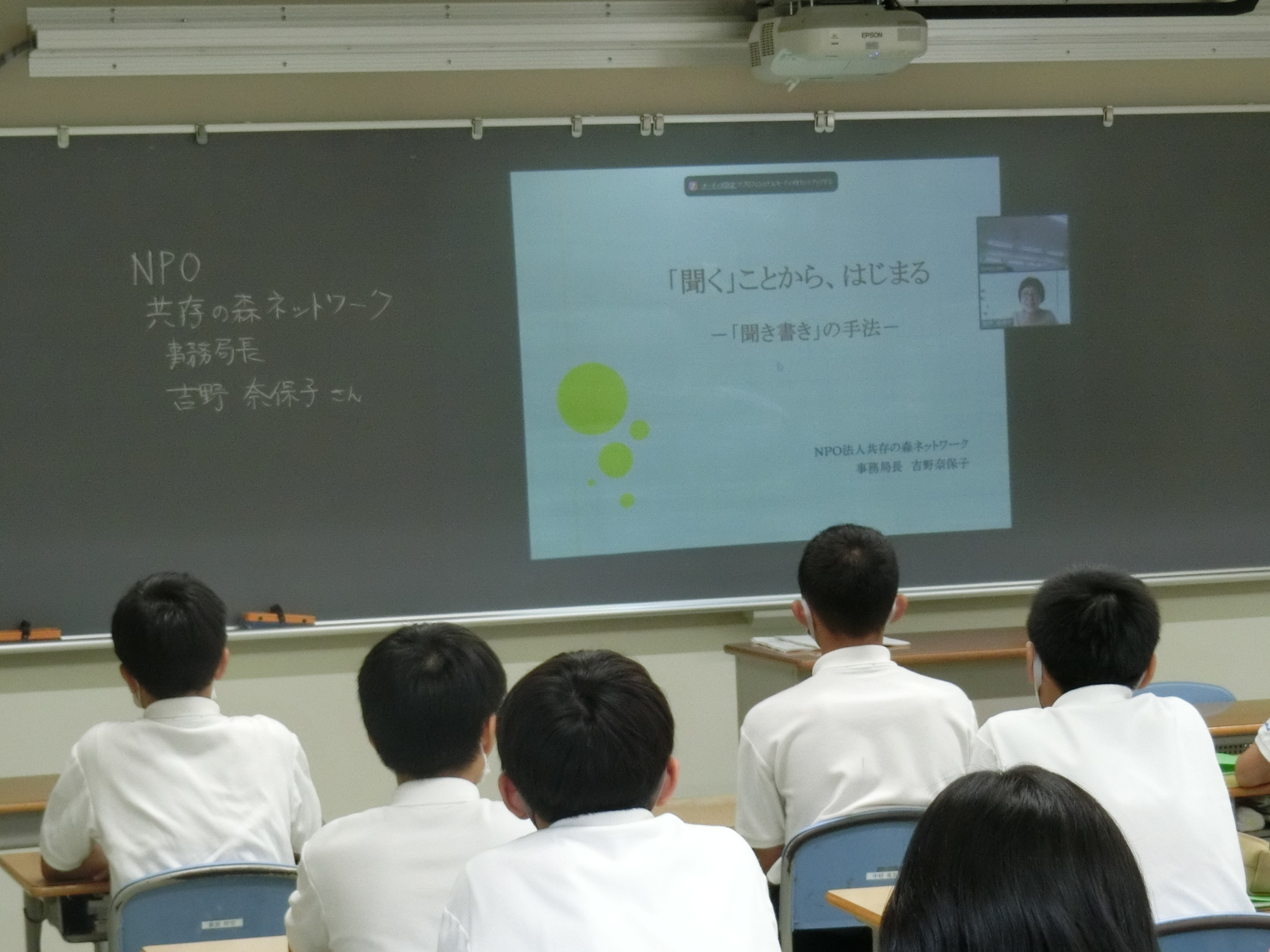

7月9日(金)放課後
本校の卒業生で瀬戸高校3年松原さんが、希望者を対象に授業をしてくれました。「自分の好きな言葉をテーマにプレゼンテーションを作る」という内容でした。参加した生徒はグループで楽しく活動することができ、他のグループに分かりやすく伝えることができました。

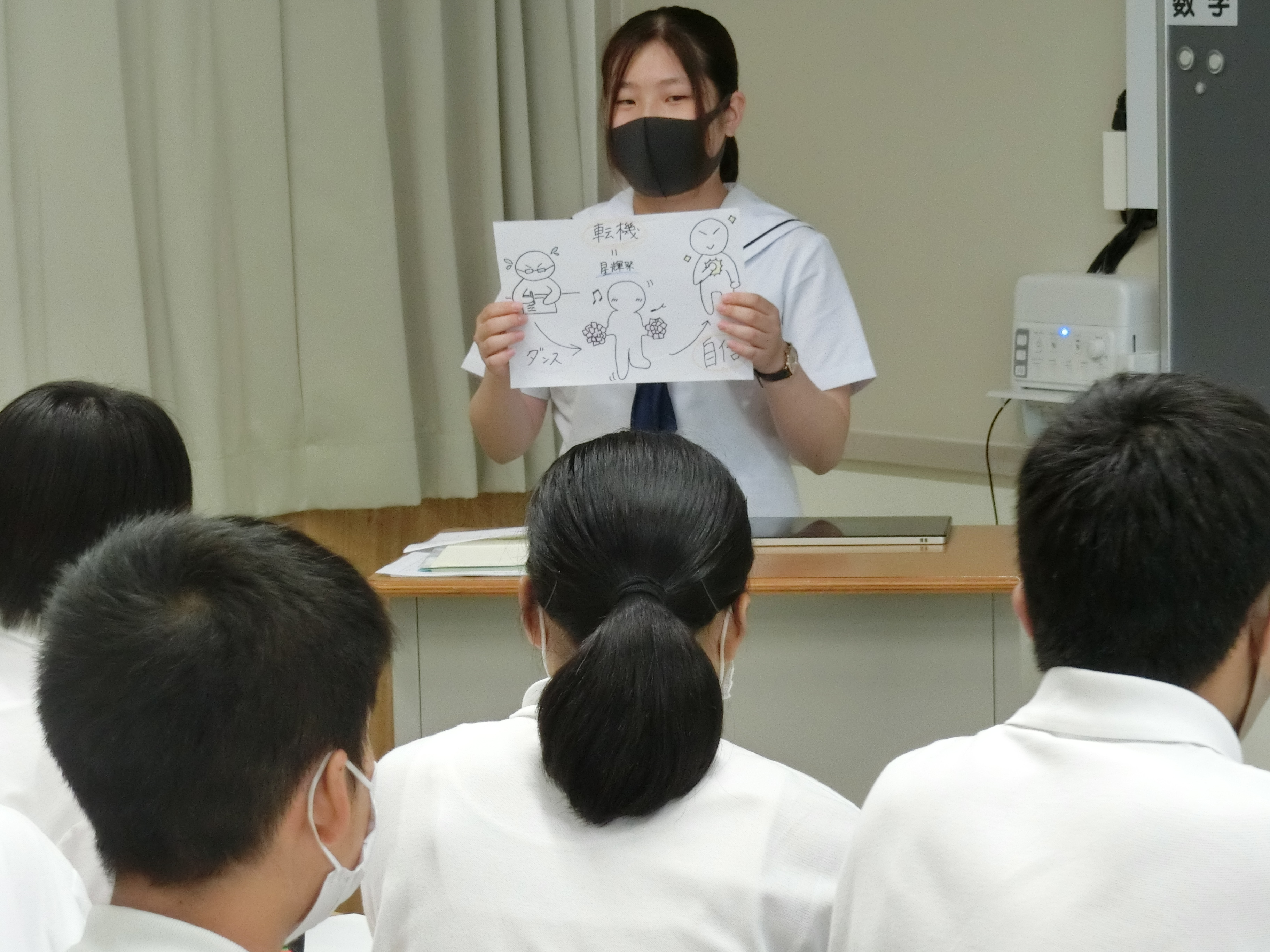
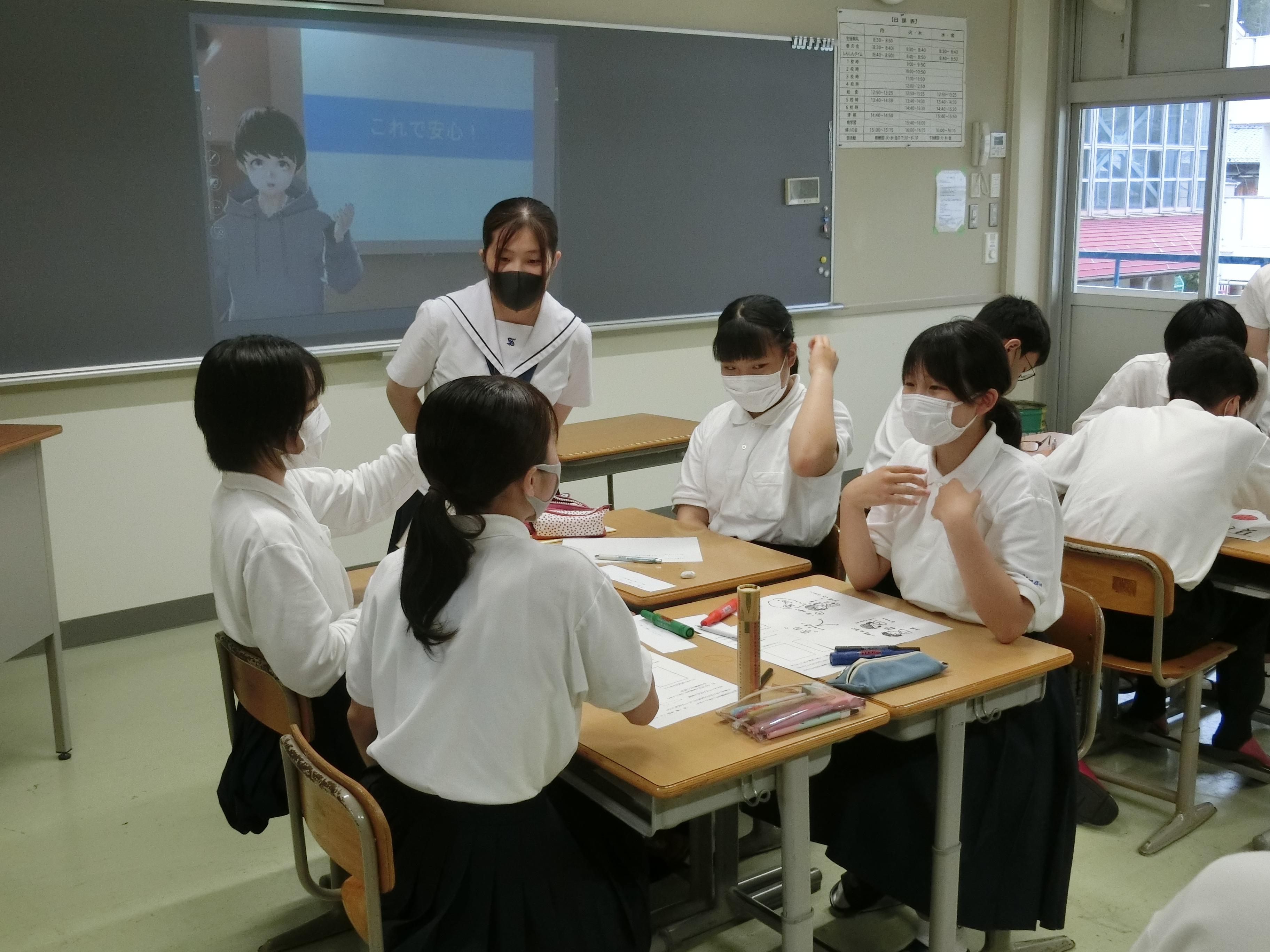


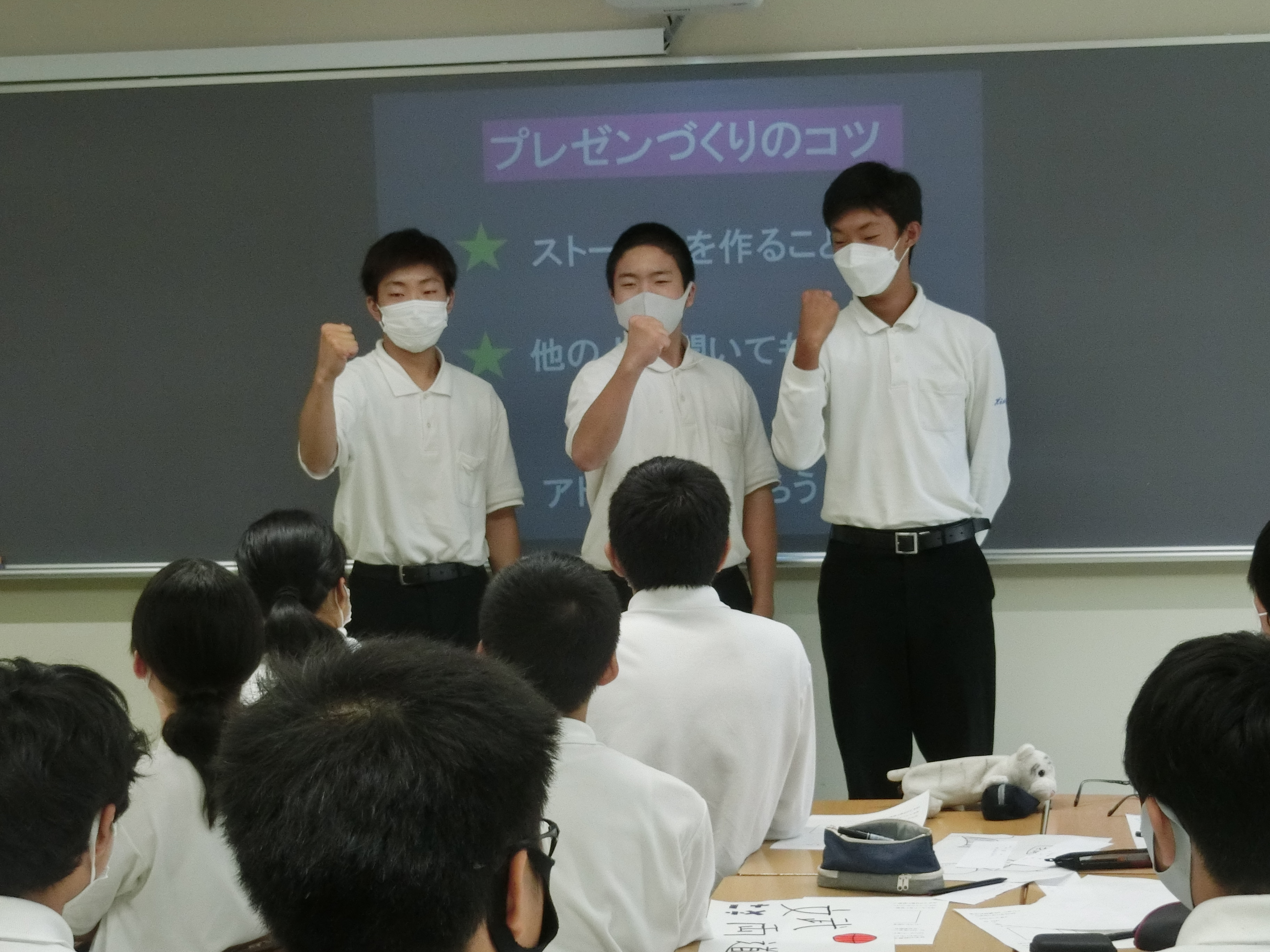
7月6日(火)5,6校時
全校体育の授業があり、星輝タイムや各競技の最終確認を行いました。短い練習期間の中で、実行委員を中心に今日まで頑張ってきました。いよいよ明日は「星輝の大運動会」です。



6月25日(金)3,4,5校時
広島県七尾中学校の原田先生を講師にお招きして、3年生で道徳の授業を行いました。日生中学校では、話し合いの手法として知識構成型ジグソー法の研究を進めており、その一環として授業をしていただきました。生徒たちは、話し合い活動を積極的に行い、自分たちの意見をわかりやすく仲間に伝えることができていました。5時間目にもジグソー法を取り入れた社会の授業があり、たくさんの先生方の前で意欲的に学習に取り組む姿がありました。
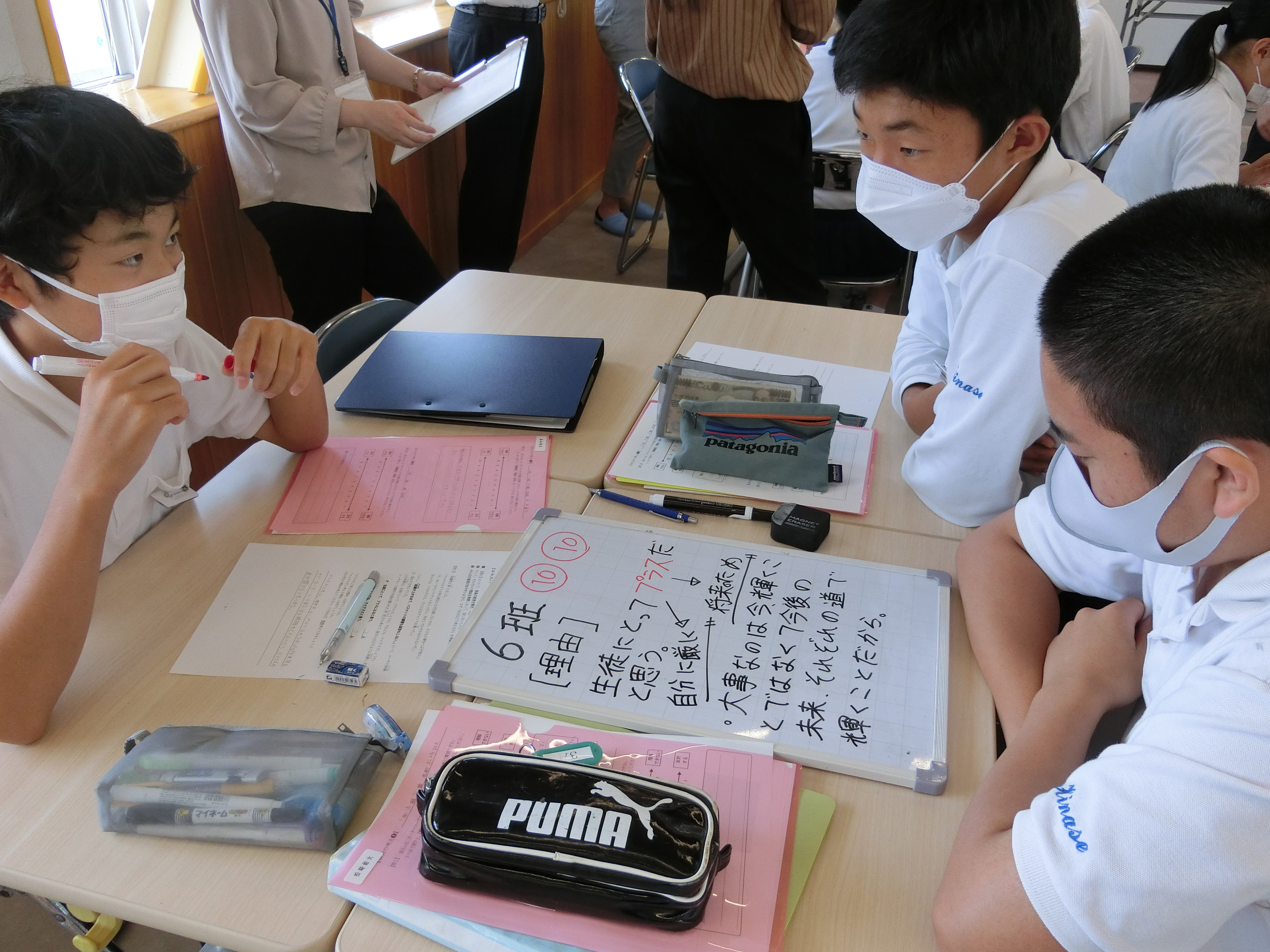

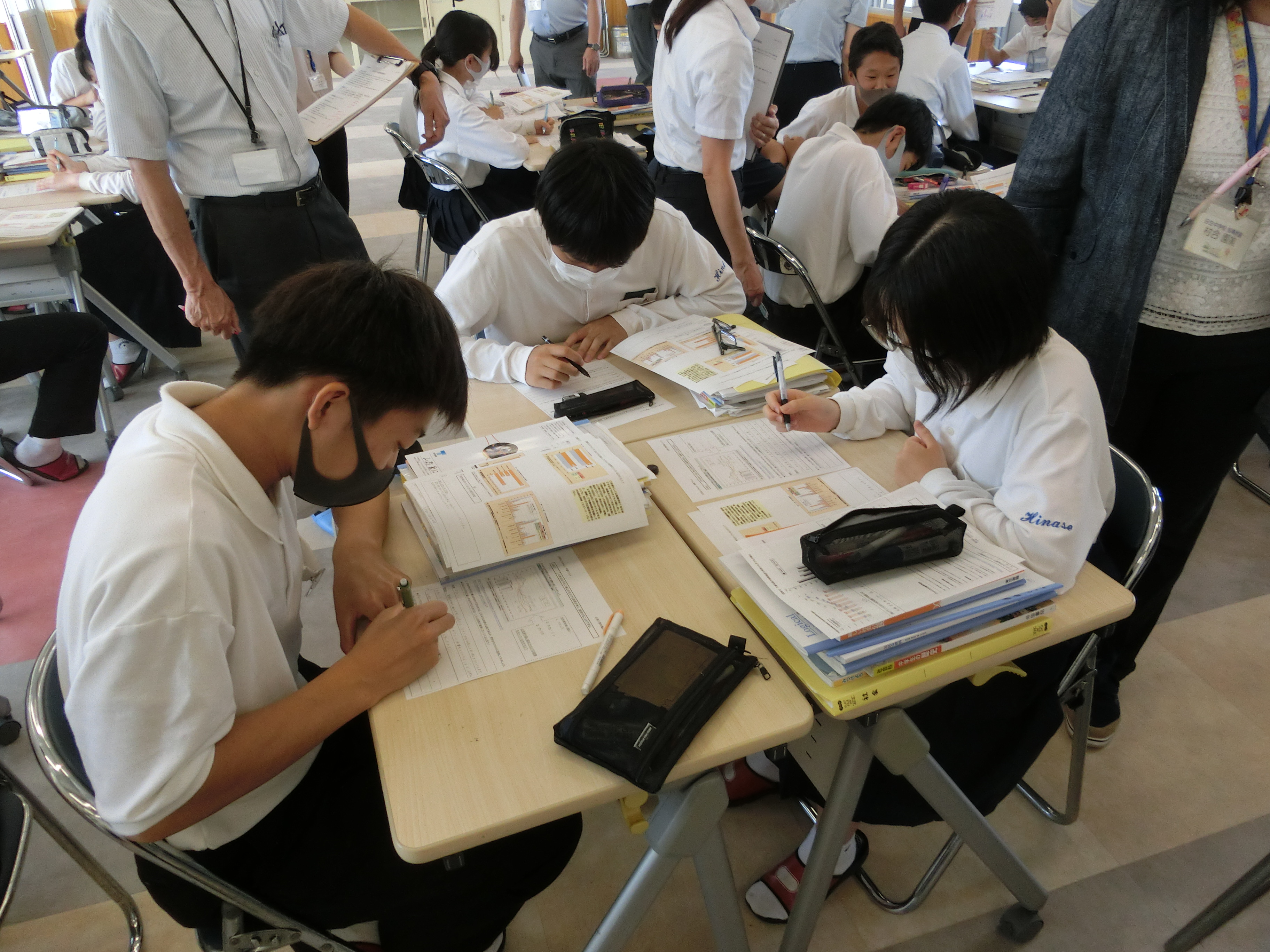
6月22日(火)5,6校時
(株)トンボとコラボしたキャリア学習の3時間目(最終回)がありました。各グループで提案する商品が手元に届き、その商品についてプレゼンを行いました。どのクループも工夫を凝らした素晴らしい発表でした。(株)トンボさんのご厚意で全てが商品化されることになり、生徒は大喜びでした。
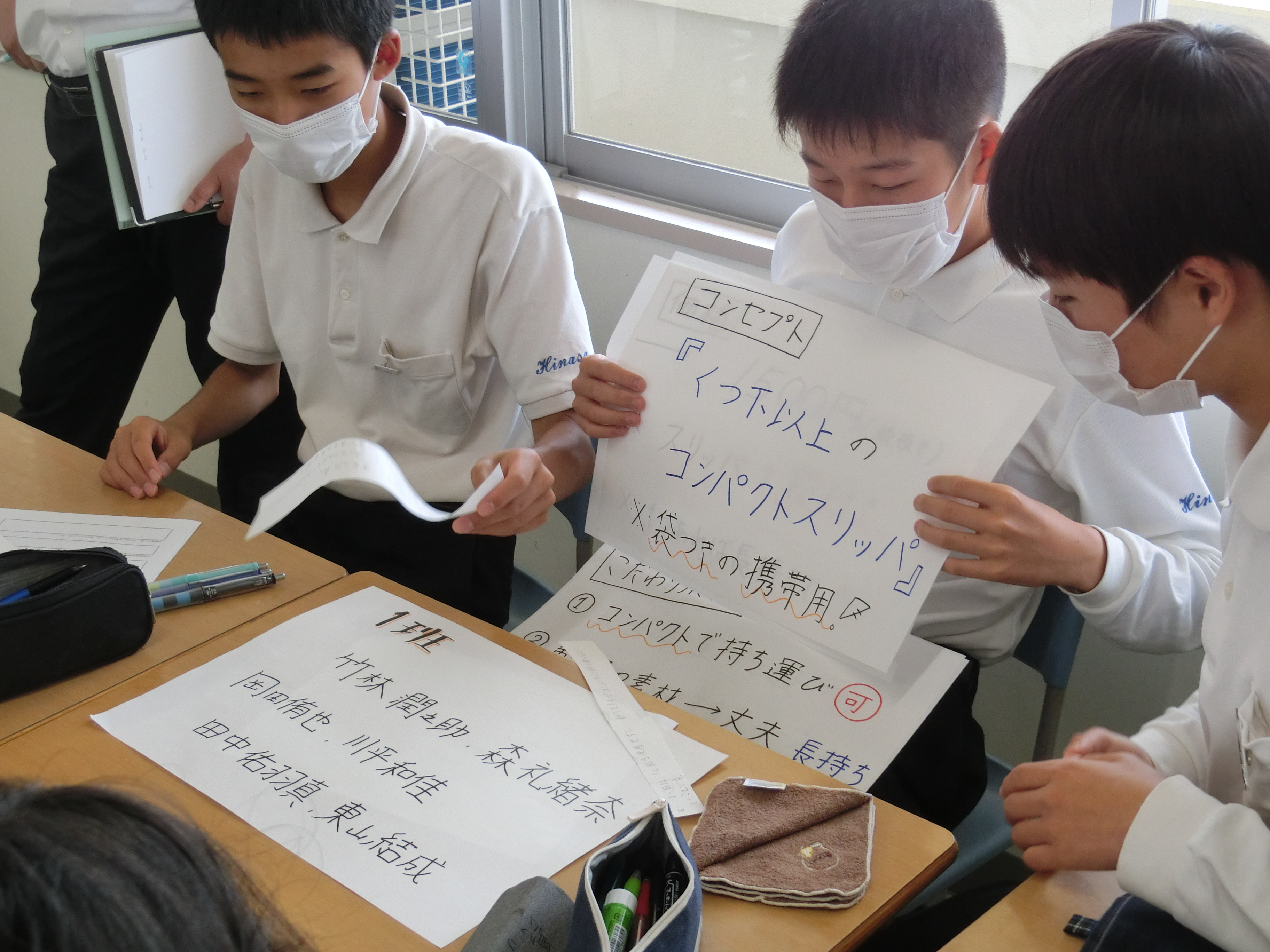


6月21日(月)3校時
緊急事態宣言が解除され、久しぶりに全校体育の授業がありました。星輝祭体育の部は中止となりましたが、その代替として行われる7月7日、8日の全校体育を「星輝の大運動会」と名付け、新たな気持ちで頑張っています。今日は星輝タイムの練習を頑張りました。



6月17日(木)晩学習
2年生の晩学習は「国語辞典を使ってことわざの意味を調べる」活動でした。制限時間は20分。チャイムと同時に国語辞典を使って一生懸命調べていました。今年度の晩学習は基礎学力の定着を目的に5教科を順番に実施しています。各教科の最終回はテストを行い、クラスごとに競い合っています。

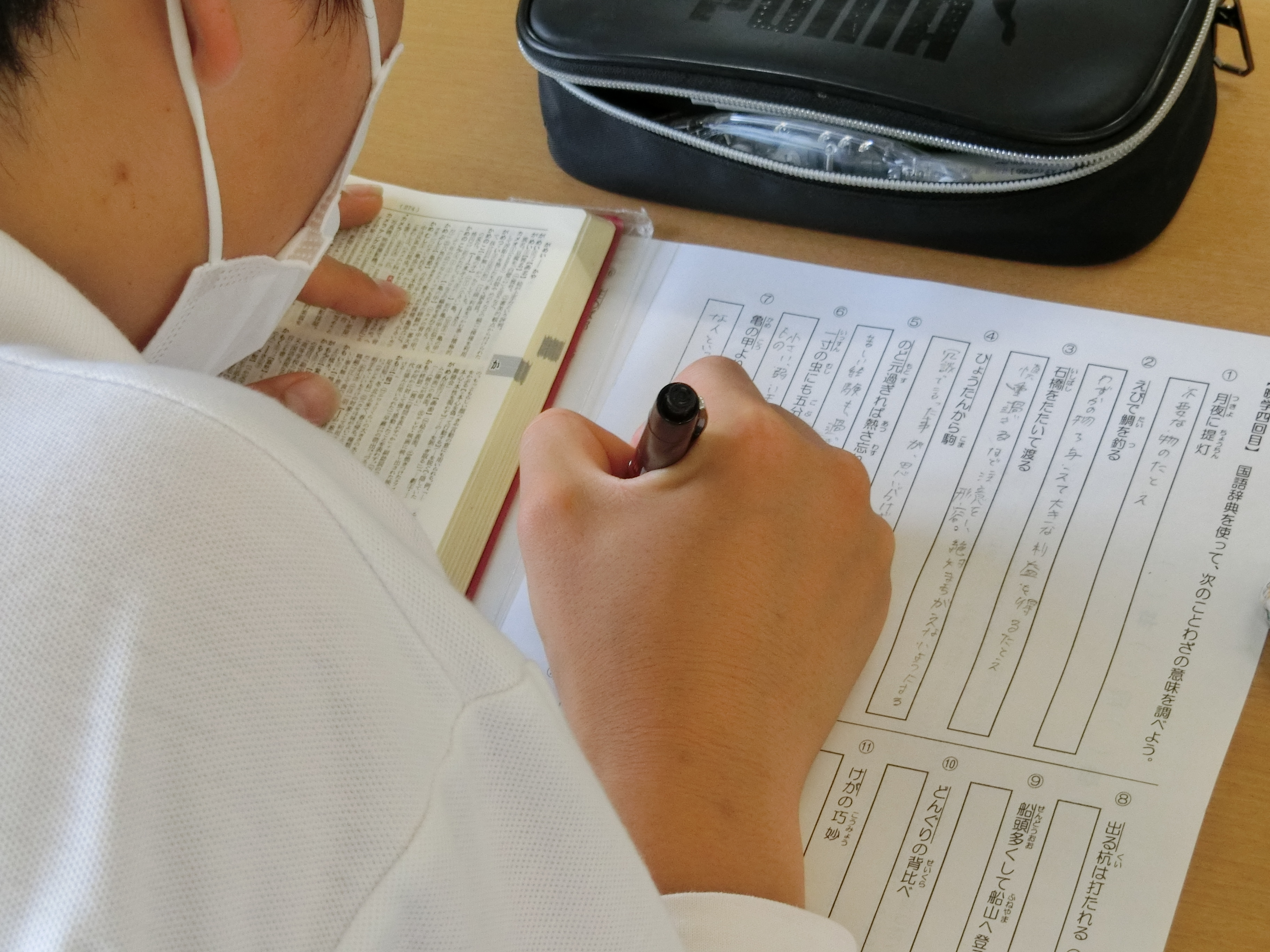
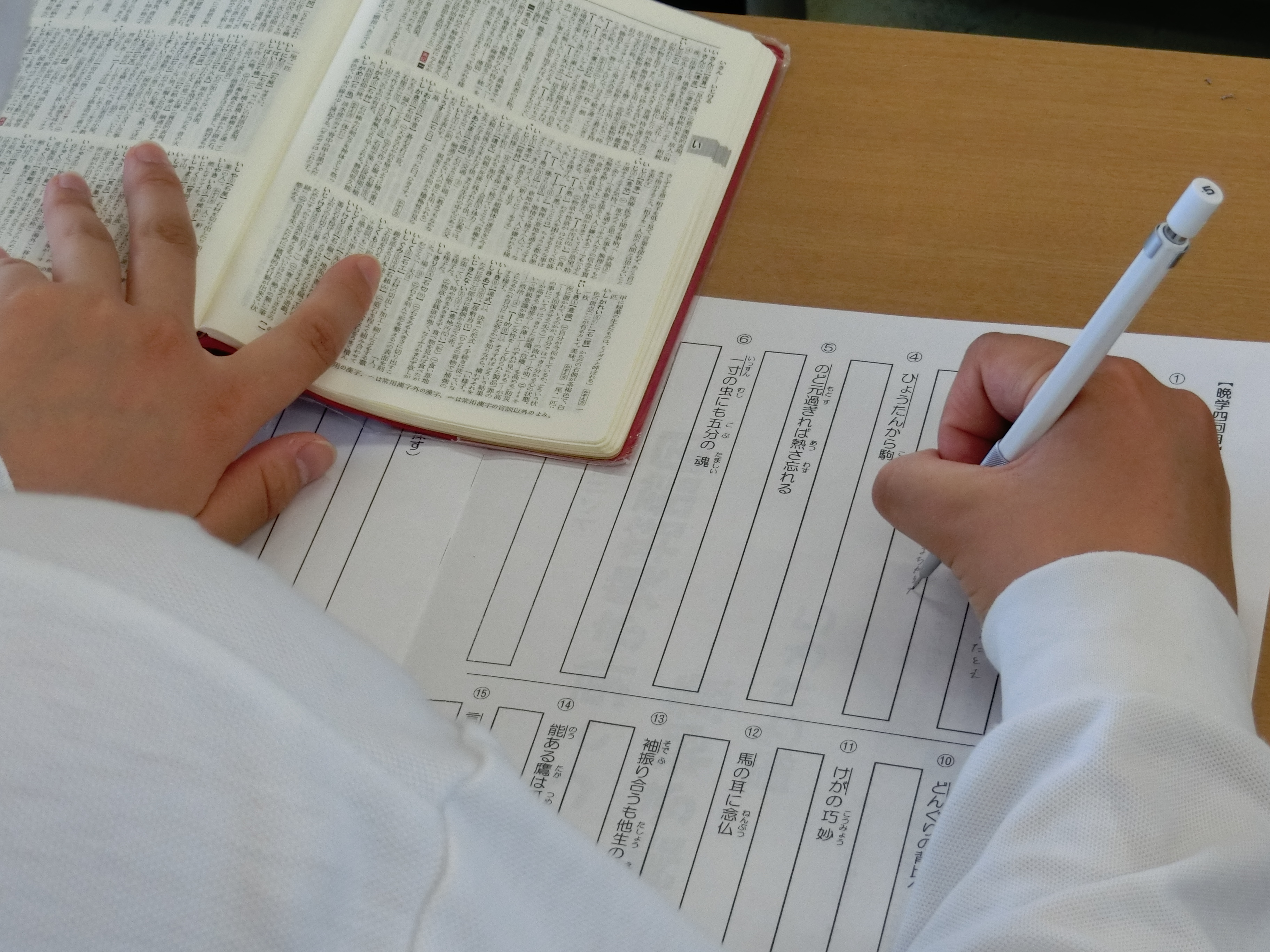
6月9日(水)放課後
今年度1回目の放課後学習会がありました。毎週水曜日の放課後を原則として、16時20分から17時20分までの1時間学習を進めていきます。今年度は、コース別(基礎・発展)に実施し、学力の定着・学力向上につなげていきます。

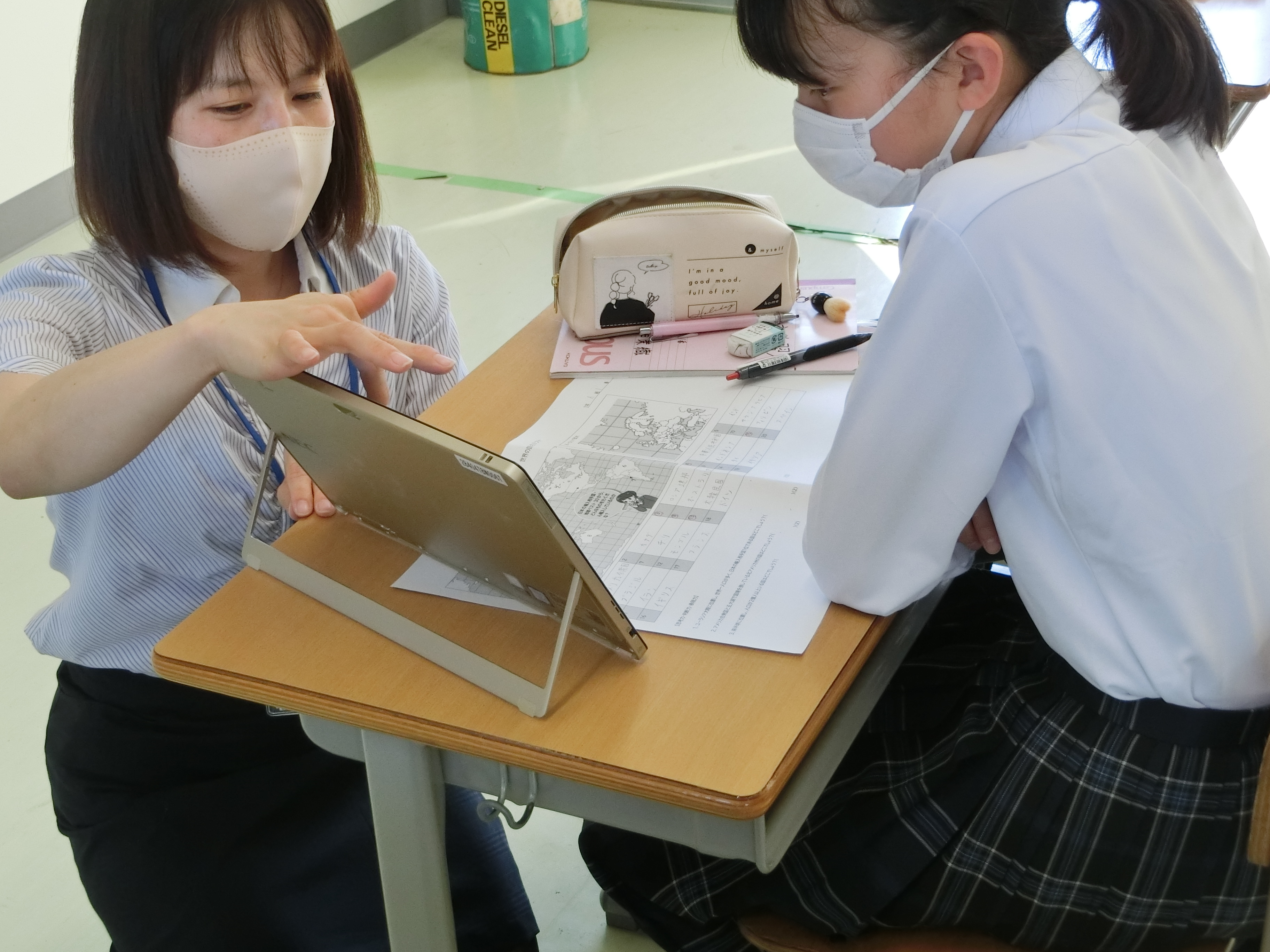

5月21日(金)5,6校時
3年生で(株)トンボとコラボしたキャリア学習の2時間目でした。緊急事態宣言を受けてリモートで行いました。各グループで提案する商品の「売りは何か」「価値を生み出すこだわり機能は?」「コンセプトテーマ」などについて検討しました。

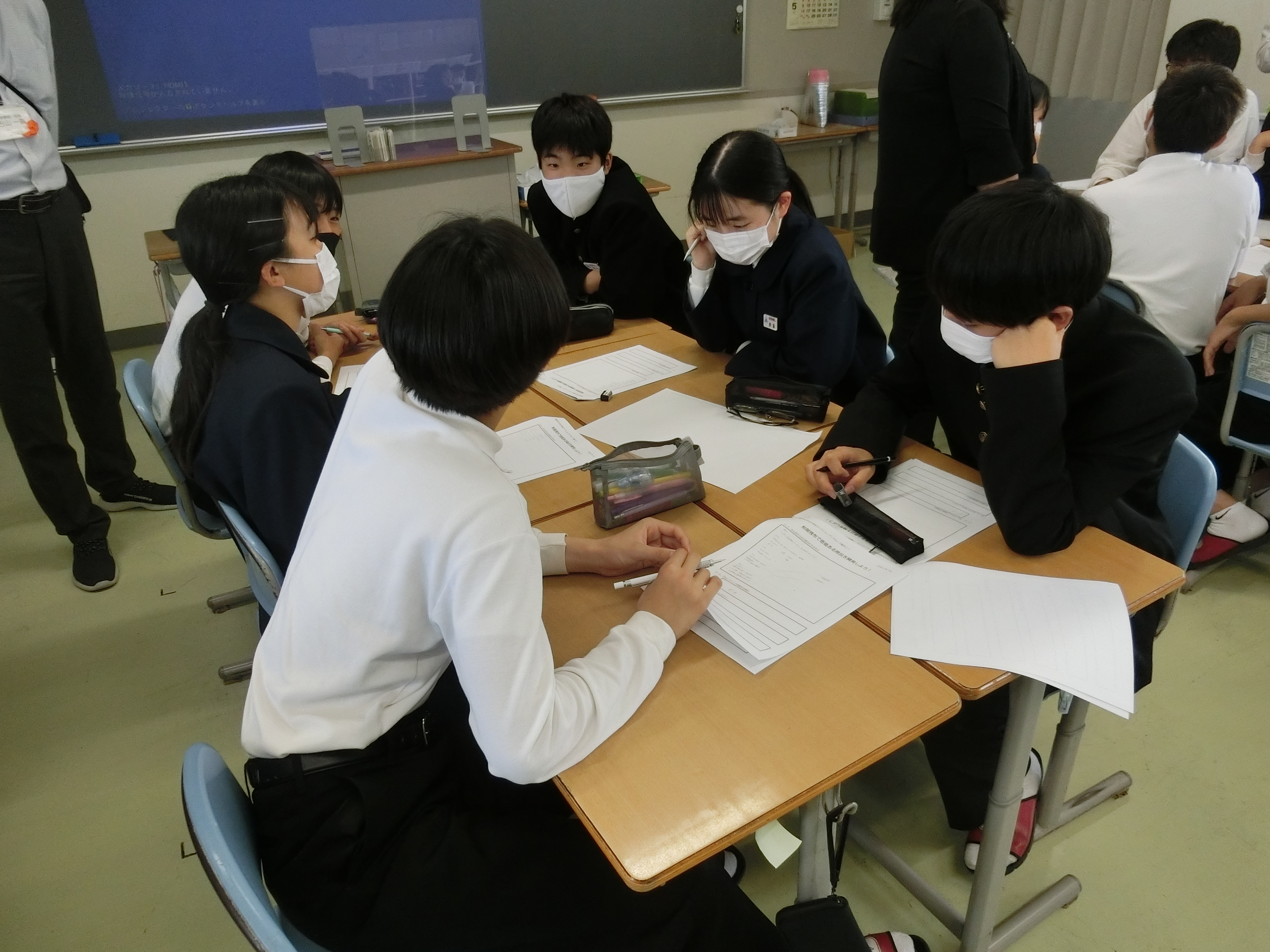

授業の途中にはトンボ岡山支店とリモートでつないで、経過報告や質問をしてアドバイスをいただきました。
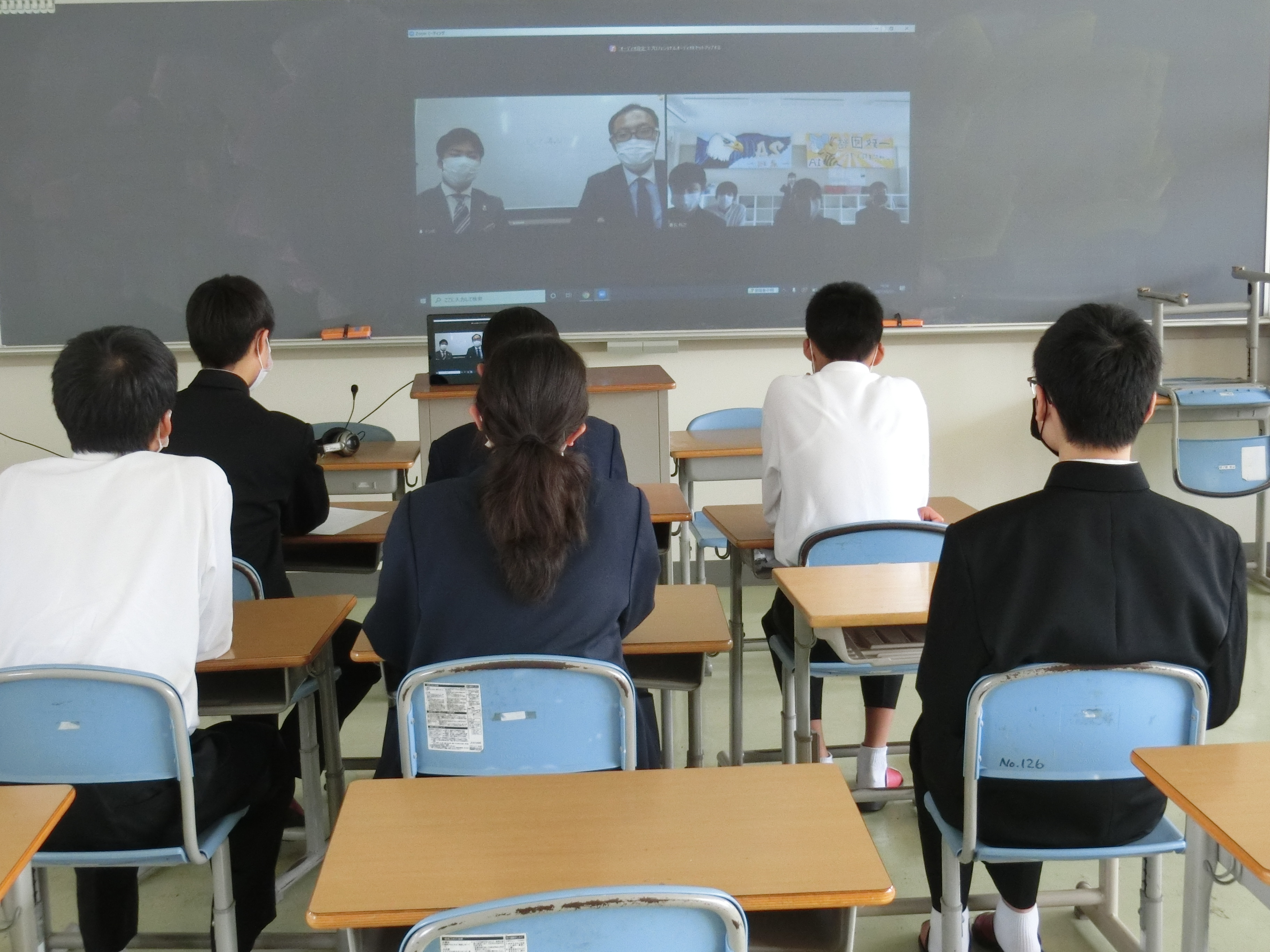


そのアドバイスをもとに商品の設計図を完成させました。
5月14日(金)2校時
全校体育の授業がありました。種目練習の3回目です。各ブロックとも場所と時間を有効に活用しながら練習に取り組んでいました。






5月14日(金)5,6校時
企業とコラボしたキャリア学習を3年生で実施しました。今回は株式会社トンボ様のご協力で、「制服残布で価値ある商品を開発しよう」というテーマで学習を進めていきます。今日の授業ではどんなものを商品化するか各グループで考えました。
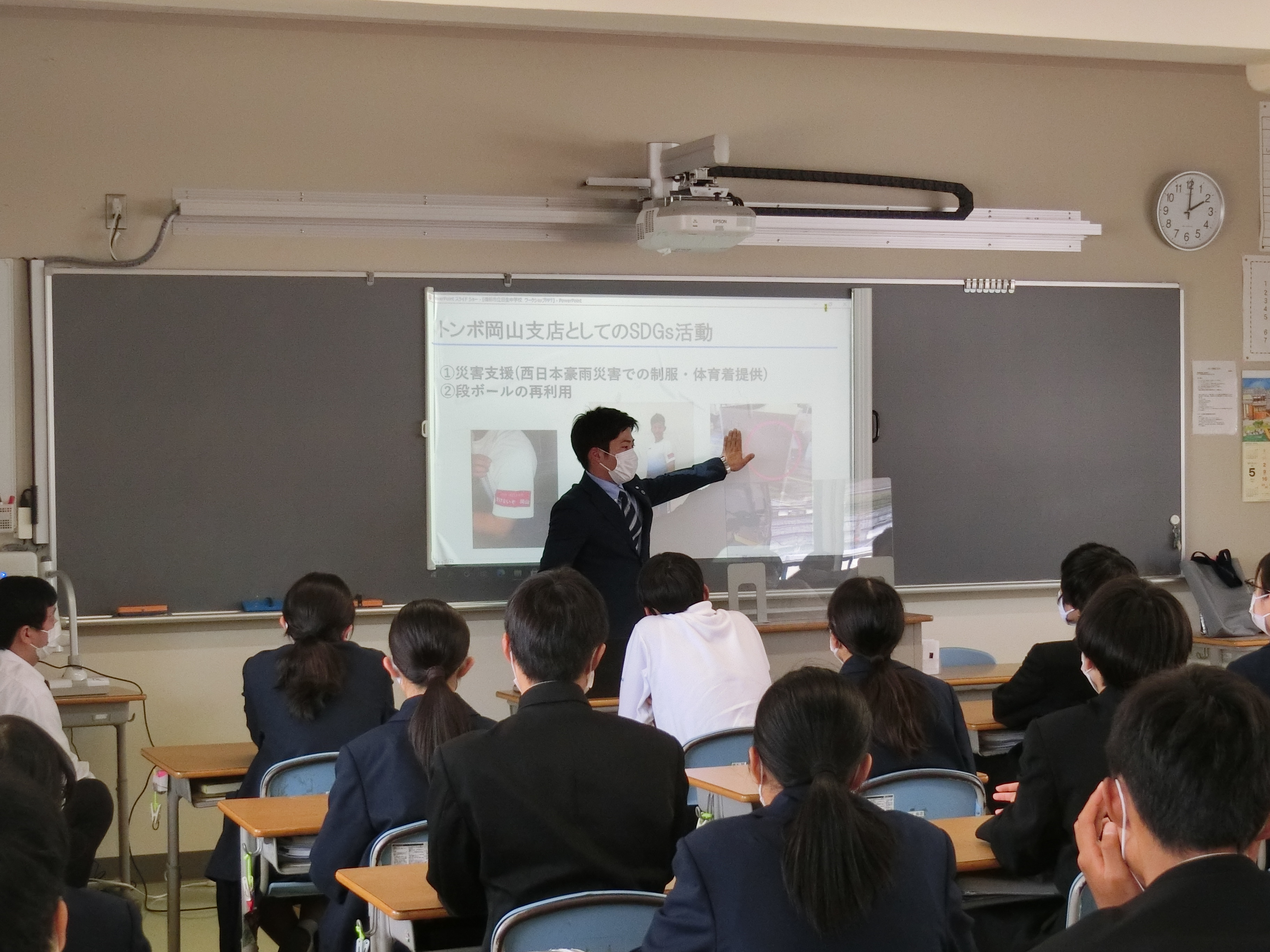


5月13日(木)3校時
全校体育がありました。今日は星輝タイムの練習です。昨年度までは各クラスで行っていましたが、今年度から全校演技を組み込んだ全校生徒による新しい形の星輝タイムです。今までの伝統を受け継ぎながら新しい形の星輝タイムをみんなで創り上げようと、実行委員を中心に頑張っています。


5月13日(木)5校時
1,2年生を対象にした海洋学習がありました。日生町漁協から天倉専務理事に来ていただき、話をしていただきました。日生の海について、日生漁協の取り組みについてのお話でした。「日生町漁協の歴史」「アマモ場再生活動」「日生中海洋学習の歴史」など、今までの活動について映像を見ながら紹介していただきました。今日が生徒にとっては海洋学習の始まりです。ふるさと日生をしっかり見つめ、将来につなげていきましょう。
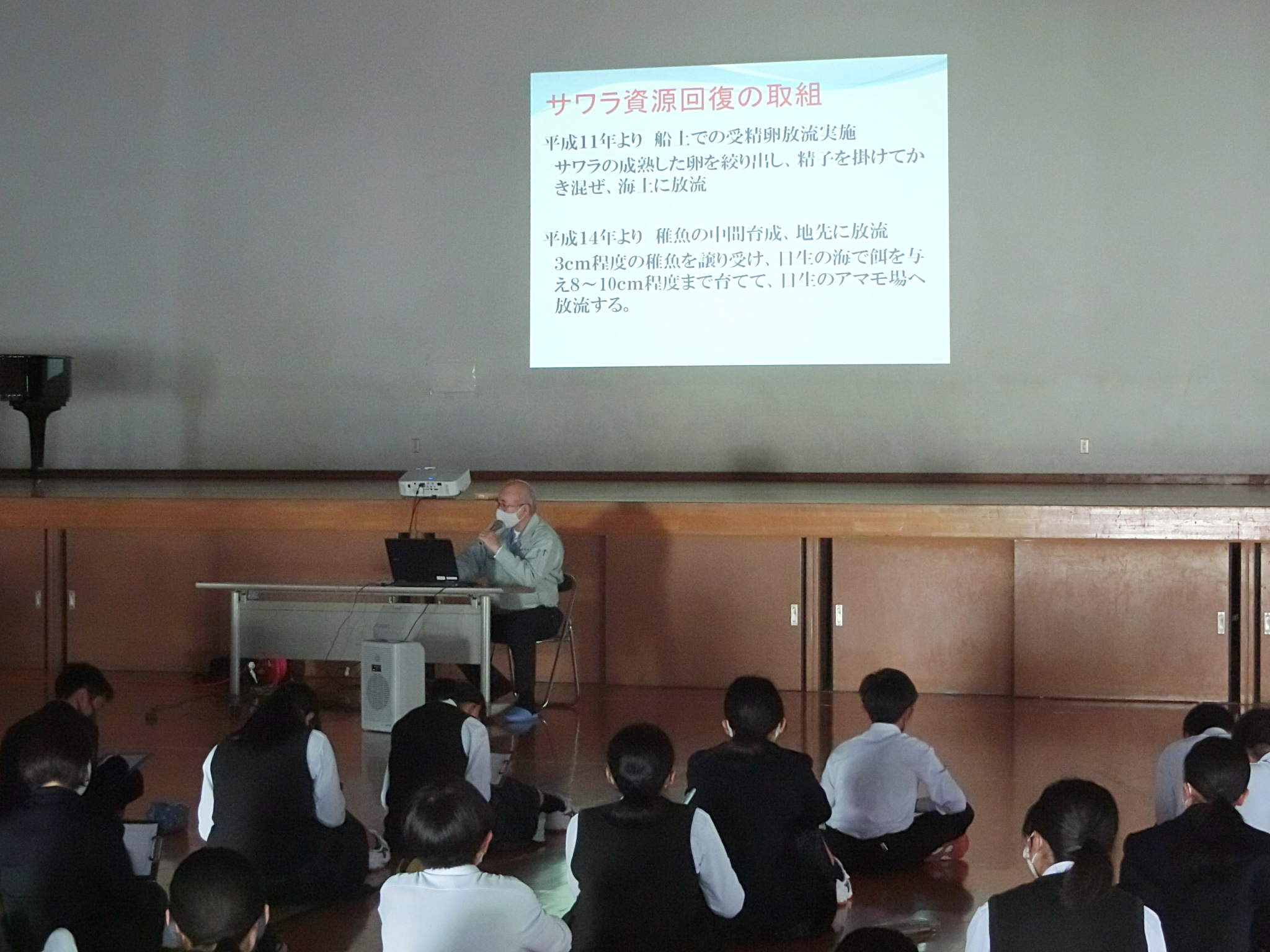
5月11日(火)6校時
生徒総会がありました。この総会は、令和3年度前期の活動計画や活動方針を決める大切な会です。しかし、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からリモートでの実施となりました。専門委員長や部長からは前期活動計画の発表があり、拍手で承認されました。今日の総会で決まったことが実行できるよう、生徒全員で取り組みを進めていきます。
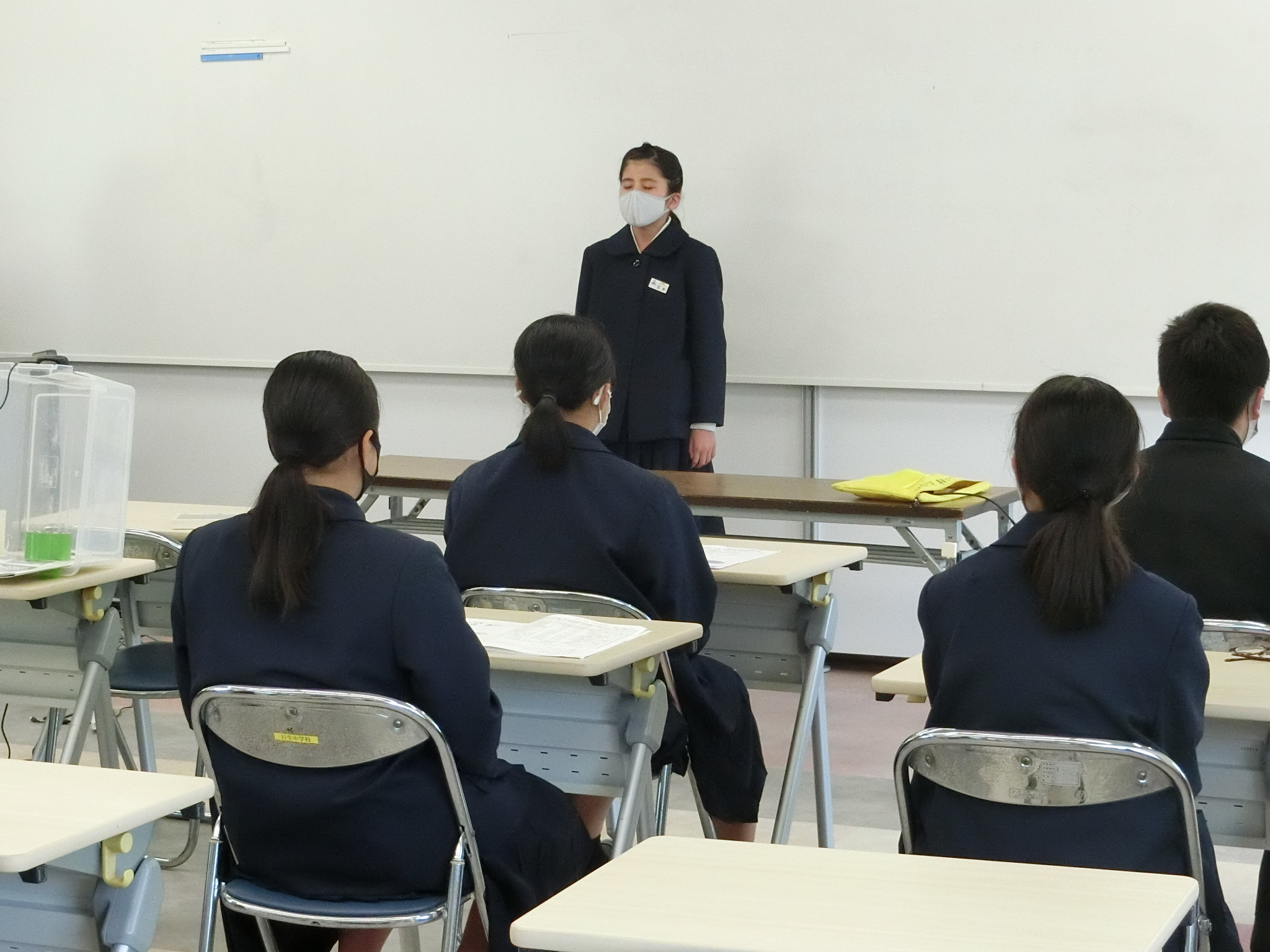

5月10日(月)
全校体育の授業がありました。星輝祭体育の部に向けての練習です。今日は種目練習の2回目ということで、各ブロックともブロック長を中心に時間を有効に活用しての練習でした。各ブロックとも生徒会種目を中心に練習に取り組んでいました。









5月8日(土)
授業参観、PTA総会、学年懇談、部活動懇談がありました。今年度、第1回目の参観日ということでたくさんの保護者の方に参観していただきました。ご参加いただいた保護者の皆さま、たいへんありがとうございました。
1校時の授業の様子
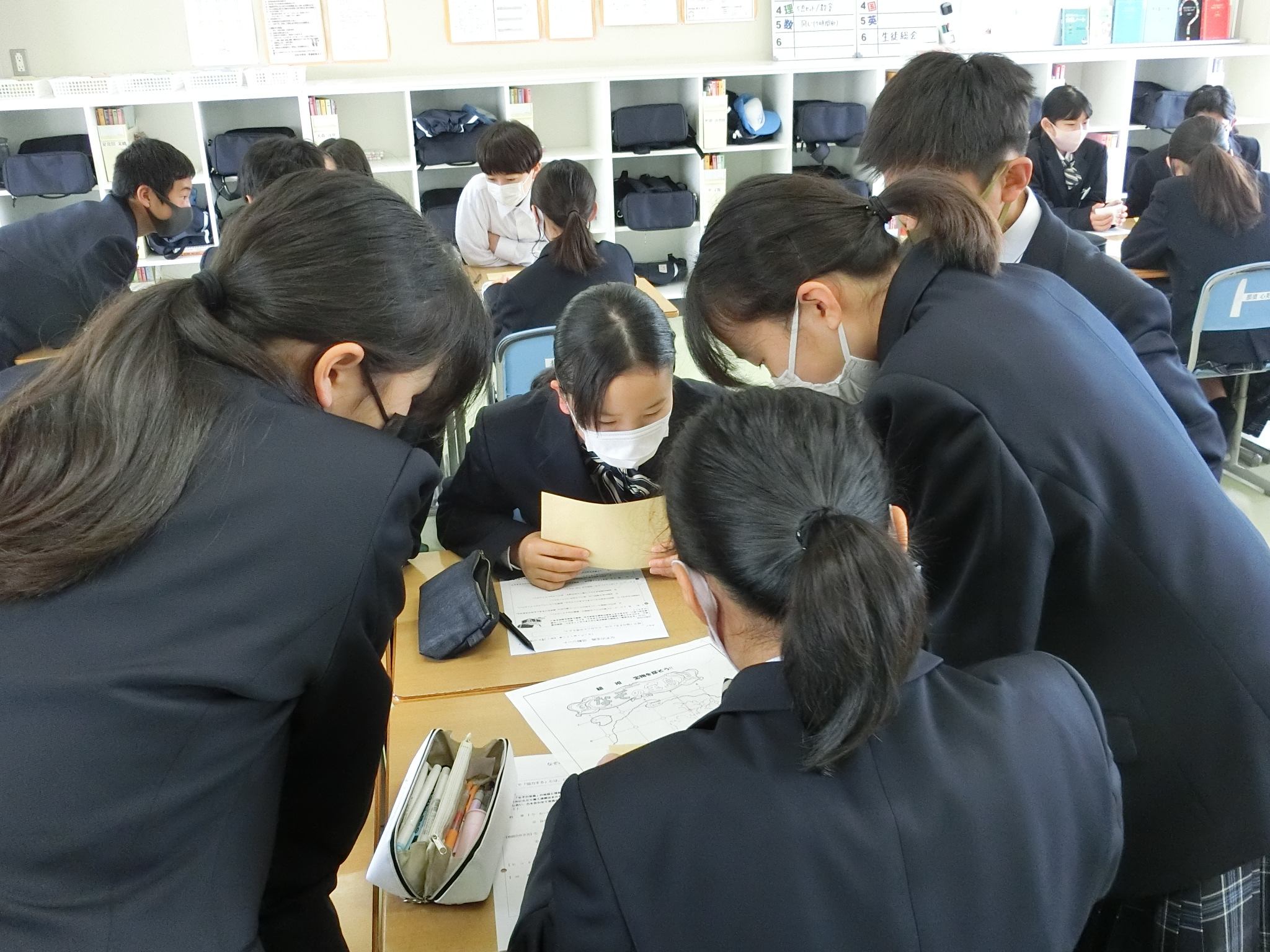



5月6日(木) 6校時
全校体育の授業がありました。星輝祭体育の部に向けて各ブロックでの種目練習でした。各ブロックともブロック長を中心に計画的に練習を行いました。
《青ブロック》…生徒会種目やリレーを中心に練習。


《赤ブロック》…Long X Jump(全員跳び、8の字跳び)や生徒会種目を中心に練習。全員跳びは10回、8の字跳びは233回を記録。


《黄ブロック》…Long X Jump(全員跳び、8の字跳び)を中心に練習。全員跳びでは16回を記録。


4月26日(月)5校時
