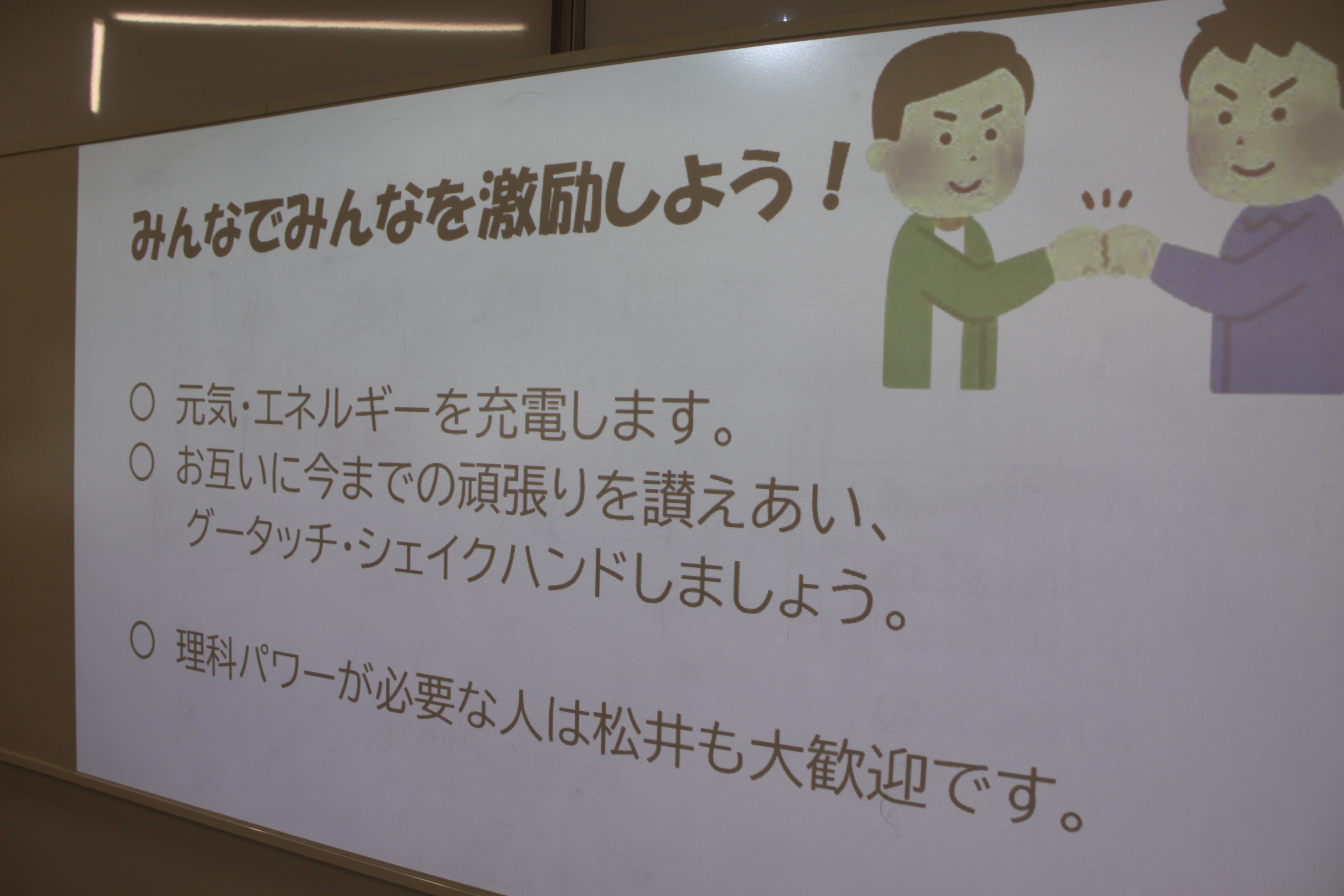先生のタネ
ひとのあいだ(ゆたかな教育実践のためのタネ) すべての学校教育の基盤となる、〈支え合う学級・つながる仲間〉づくりについて、先生たちと語りあったり、工夫や情報交換をしたりした内容や、本校で取り組んでいる実践を「ギュッ」」と記しています。
☆352日(7/28)春15の会の願い
山陽新聞の記事(7.23)を紹介します。
☆351日(7/25)事前学習シート(簡略版)
レポートに刺激されて、校外での自立活動計画のワークシートを考えてみました。
☆350日(7/24)「あつい壁」
先日視聴した「あつい壁」の上映会・学習会を仲間たちと準備をしている。映画の見方はそれぞれあり、感じ方も感想・意見もちがう中で、意見交流からハンセン病問題学習の内容を考えてみたい。映画を観ながらメモしたセリフをいくつか挙げる。「大学行って出世せよ」「虫のいどころがわるかっただけ 心配いらん」「学校は本当のことを教えるとです。科学を教えるとです」「親になってみんとわからんばい」「一生 上にあがれんでしょ」「怖か病気」「知っとって何もせんのはばかじゃなかいか。負けじゃあ!」「差別という荷物をなくしていかんと」…視たくなったでしょう。10月に上映学習会があるようです。
☆349日(7/23)鍵をあけはなつ
生徒らの日々の学校生活の中での、いわゆる生活指導、「○○は校則で禁止となっているよ」「確認してみたら、○○はだめです。」はよくある。先日、「それはいいんじゃない」と(自分なりに(勝手))に判断したら、他の先生との認識の共有を怠って、全教員による指導がズレて多大な迷惑をかけた。ごめんなさい。さて、本校は、近年の動きと同様に、生徒・保護者の意見を大切にして校則やルールのの見直しを積極的に進めている。そのことと直接的に関係があるわけではないが、山陽新聞(7/20)の読書欄で、『鍵をあけはなつ 村上靖彦著』について、細馬宏通氏が評者として書かれていた文が目にとまった。『多くの介護施設では玄関に鍵をかけ、開け閉めをスタッフが管理している。防犯のためだけではない。 用者が一人で外に出てしまうことを防ぐためだ。しかし、本書に登場する、あるグループホームのケアマネジャーは、こう考える。玄関の鍵が閉まり、外に出る自由がなくなると、 介護者は利用者の行動の意味を考えなくなる。逆に、玄関を開けておくと、利用者の行動にはさまざまな可能性が生まれる。介護者は忙しい。外出に付き添うのが難しいときもある。では、いつなら外出できるか。利用者とヘルパーは、次に外出できるときを「約束」をすることになる。こののように「約束」を交わし、果たすことが、介護では大事なのではないか。行動の可能性が広がることは、ときに介護を難しくする。しかしその 「難しさ」は、実は介護の「面白さ」 につながっているのではないか。・・・』
☆348日(7/22)発表と報告のちがい
岡山県人権教育研究大会(8/7)の実行委員会に教頭先生が参加され、分科会(研究協議)のあり方についての資料をいただいたそうです。その一部を紹介します。一読してみると、私自身も、みんなで集まって、研究協議、討議するちからのようなモノが弱まっているような気がしていました。これから、いろんな会の主催や、進行や司会をすることも増えてくると思いますが、対話して学びを深めるようなファシリテート?の意識を持ちたいと思いました。
『・・・「発表」とは、知識や技術の伝達が目的となる。 発表者は、自分のもつ知識や技術を普及伝達するために、相手に効果的に伝わる原稿考えることになる。また、発表を受ける場合は、知識や技術といった答えを求めているので、情報を受け取ろうと聞く。
対して、「報告」では対話そのものが目的の一つとなる。対話は、時間と空間を共有するところから始まる。報告者の語る姿や他の参加者のようす、他者の発言による気づき、その場に身を任せることで、自分のふだんの言動や実践を省みることにつながる。それは、言われたことをファイリングするのではなく、それぞれのなかにある考えを語り合う出会いの営みともいえる。報告者は、そのなかに、自分の実践を差し出す。そこには、わかりやすい成果物や大団円のストーリーはないのかもしれない。それは、教育実践に終わりがないことを意味している。 少し立ち止まって、一人では考えもしなかったことを、みんなで考える。教育実践記録はレポートとして残され、報告を通して広がり、また新たな実践へとつながっていく。』
生徒らの日々の学校生活の中での、いわゆる生活指導、「○○は校則で禁止となっているよ」「確認してみたら、○○はだめです。」はよくある。先日、「それはいいんじゃない」と(自分なりに(勝手))に判断したら、他の先生との認識の共有を怠って、全教員による指導がズレて多大な迷惑をかけた。ごめんなさい。さて、本校は、近年の動きと同様に、生徒・保護者の意見を大切にして校則やルールのの見直しを積極的に進めている。そのことと直接的に関係があるわけではないが、山陽新聞(7/20)の読書欄で、『鍵をあけはなつ 村上靖彦著』について、細馬宏通氏が評者として書かれていた文が目にとまった。『多くの介護施設では玄関に鍵をかけ、開け閉めをスタッフが管理している。防犯のためだけではない。 用者が一人で外に出てしまうことを防ぐためだ。しかし、本書に登場する、あるグループホームのケアマネジャーは、こう考える。玄関の鍵が閉まり、外に出る自由がなくなると、 介護者は利用者の行動の意味を考えなくなる。逆に、玄関を開けておくと、利用者の行動にはさまざまな可能性が生まれる。介護者は忙しい。外出に付き添うのが難しいときもある。では、いつなら外出できるか。利用者とヘルパーは、次に外出できるときを「約束」をすることになる。こののように「約束」を交わし、果たすことが、介護では大事なのではないか。行動の可能性が広がることは、ときに介護を難しくする。しかしその 「難しさ」は、実は介護の「面白さ」 につながっているのではないか。・・・』
☆348日(7/22)発表と報告のちがい
岡山県人権教育研究大会(8/7)の実行委員会に教頭先生が参加され、分科会(研究協議)のあり方についての資料をいただいたそうです。その一部を紹介します。一読してみると、私自身も、みんなで集まって、研究協議、討議するちからのようなモノが弱まっているような気がしていました。これから、いろんな会の主催や、進行や司会をすることも増えてくると思いますが、対話して学びを深めるようなファシリテート?の意識を持ちたいと思いました。
『・・・「発表」とは、知識や技術の伝達が目的となる。 発表者は、自分のもつ知識や技術を普及伝達するために、相手に効果的に伝わる原稿考えることになる。また、発表を受ける場合は、知識や技術といった答えを求めているので、情報を受け取ろうと聞く。
対して、「報告」では対話そのものが目的の一つとなる。対話は、時間と空間を共有するところから始まる。報告者の語る姿や他の参加者のようす、他者の発言による気づき、その場に身を任せることで、自分のふだんの言動や実践を省みることにつながる。それは、言われたことをファイリングするのではなく、それぞれのなかにある考えを語り合う出会いの営みともいえる。報告者は、そのなかに、自分の実践を差し出す。そこには、わかりやすい成果物や大団円のストーリーはないのかもしれない。それは、教育実践に終わりがないことを意味している。 少し立ち止まって、一人では考えもしなかったことを、みんなで考える。教育実践記録はレポートとして残され、報告を通して広がり、また新たな実践へとつながっていく。』
☆347日(7/18)自立と依存
自立活動のレポートを読んで、自立と依存についてちょっと考えている。レポートの中の3年生のひとりが、ある施設の見学に入る直前に「先生、くつひもをむすんで。」と言ってきたとのこと。(その時にどう声かけして、どのような支援・指導するのがよいか?は意見がわかれるところ、これもいろいろと話し合ってみたい)以前も同じような内容を記しましたが再掲します。
「自立」の意味を検索してみると、“自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと”と説明されています。(引用:Oxford Languages)つまり、自立とは「何にも依存しない状態」のようです。
たしかに、依存は英語で「dependence」、自立は 「independence 」で、否定を意味する「in」がついてるので、依存と自立は対立の概念とされています。しかし、何にも依存せずに生きている人なんて、一人もいません。例えば、社会人としての会社員も給料をその会社に依存していると言えます。当事者研究、べてるの家等で知られる熊谷先生は『「自立」とは、特定の依存先から支配されることなく、たくさんの依存先から自由に選択できる状態だと言います。』
学びの共同体の佐藤学さんは「子どもたちの小さなささやくような声が尊重されるべきである。「依存」と「自立」を対立的に考える のは誤りである。「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。』と言われます。うーん うーん。
☆346日(7/17)出会いを大切にできるか。
中国からの交流生を迎えて、授業案を国語科の先生と相談しました。
☆345日(7/16)国際交流とは何か
縁あって、市の国際交流事業で来岡する中国からの交流生が本校の見学(授業体験)に来られます。受け入れるにあたっては市ともいろいろと話をしました。時間と場所を提供するだけで、交流が成立するものではありませんね。関わる者どうしが「国際交流とは何か?」「今回の目的に重ねて出来ること」を共有し、多文化共生社会の意識を高めるものでなくてはいけないと考る機会になりました。事前に生徒たちが何にどのように出会うかも重要です。「学校便り」を全校生徒に事前学習資料として配りました。
☆344日(7/15)自立・社会参画の芽を
県内の自立活動の取組として、〈市内まで電車で行き、高校見学に行き、昼食を取り、家族に頼まれたモノを購入して、また電車に乗って帰宅する大作戦〉のレポートを読んだ。もちろん、しっかり事前学習で、時刻表を調べ、高校の場所を確認し、参加者で楽しめる昼食のお店を考えたそうだ。が、しかし当日。予想してなかった雨の中を慣れない傘をさしての行程。まさか高校が5Fにあるとは思わず、スマホを頼りにビルの周りをぐるぐる探し続けたり、昼食の場所は目視できるのに、地下街を通って遠回りしないといけなかったりとか、頼まれたモノを売っているお店が見つからなかったり、見つけたモノは、とても高価であることが分かり、購入すべきか悩んだり…。だけど、その度に、生徒らは(自分で、、時にはメンバーで)考え、判断し・決めて、その大作戦をやり遂げることができた。引率した教員は、これまでの学校での教育活動が、子どもたちの社会の中で生きていく力になっていると感じられる子どもたちの姿を看ることができたという。また、卒業までに取り組んでいかないといけない課題(子どもの課題ではなく、自立活動を中心とした教育活動の内容)も視えた。校外(社会)の学習がいつもできるわけではないが、社会参画を意識した確かな学習内容を創ってきたいとつくづく思ったなあ。
☆343日(7/14)やっぱり、仲間づくりの原点は
英語科で発表している子どもたちの姿をみていると、やっぱり、クラスの仲間に自分のことを知ってもらうことがとてもうれしく、そして仲間のことを知ることはとても大切だと思っているようにみえました。お互いを分かり合う場面を増やしてこそ、学び合う、支え合う仲間となっていくのではないか。

☆342日(7/11)聲をきく
親の会や様々な学習会を開催する中でいつも、参加される方々の「声」をきくことは大切だなあと思います。先日の会では、あるお父さんから「就労移行支援って何なの?」という疑問から、単に「特別支援学校か、通信制サポート校どっちがいい?」ではなく、子どものこれまでの「育ち」と、本人の願いや夢を大事にしながら、それぞれの歩幅でのこれからの「育ち」(社会的自立)に向けての伴走したいね」と話題になりました。教育に携わる私たちが、生徒の「発達」(特別支援教育)に係ることを保護者にどう伝え、どう長期的な連携を始めていくか?は重要だな。
☆341日(7/10)春15の会は必要なのか?
今年の活動の案内チラシが届きました。
☆340日(7/9)電話で聴く
先日、進学関係で聞きたいことがあり、関係機関にお電話させていただきました。最初の部署での電話応対してくださった方は、なぜか、電話内容をメモすることが一番らしく(それが分かる応対で)、要件が伝わっているのかどうか不安になりました。案の定?「分りかねる」と言われ、他の部署「名」だけを教えてくださり、通話を終えました。そのあと、その部署の電話番号を自分で調べて、かけ直したところ、今度の担当者はとても丁寧で、真摯に「聴いて」くださる中で、必要な情報を得ることができました。実はどちらも、不登校や発達障がい、そして高校進学について「何かあればお気軽にご連絡ください」というチラシや案内をたくさん配布している部署でした。「保護者が困って、やっとかけることのできた電話だったとしたら、どう思っただろうか?」…。わずかな時間の、ちょっとした電話だけども、大事な時間にしなくてはいけないなあと思いました。本市も、学校への欠席連絡については、連絡ツール(アプリ)を導入するそうです。
☆339日(7/8)
1学期の振り返りをしている時期かもしれません。「授業で静かにできた?」「友達に迷惑をかけなかった?」「黒板をきちんと写すことができた?」なんて質問項目はないと思いますが、子どもたちが日々の学校生活を振り返ると同時に、これは私たち教職員集団の教育実践がどうだったか問われることにもなりますね。どきどきしますな。そして、私たちの目指すことを明確化したものを質問項目にしないとね。「授業でわからないところを仲間に聞くことができた?」「聞かれたら、誠実に応えようとした?」「授業で自分の考えを話すことができた?」「仲間を意識して行動することができた?」「考えてながら板書を自分なりにまとめることができた?」なんてね。
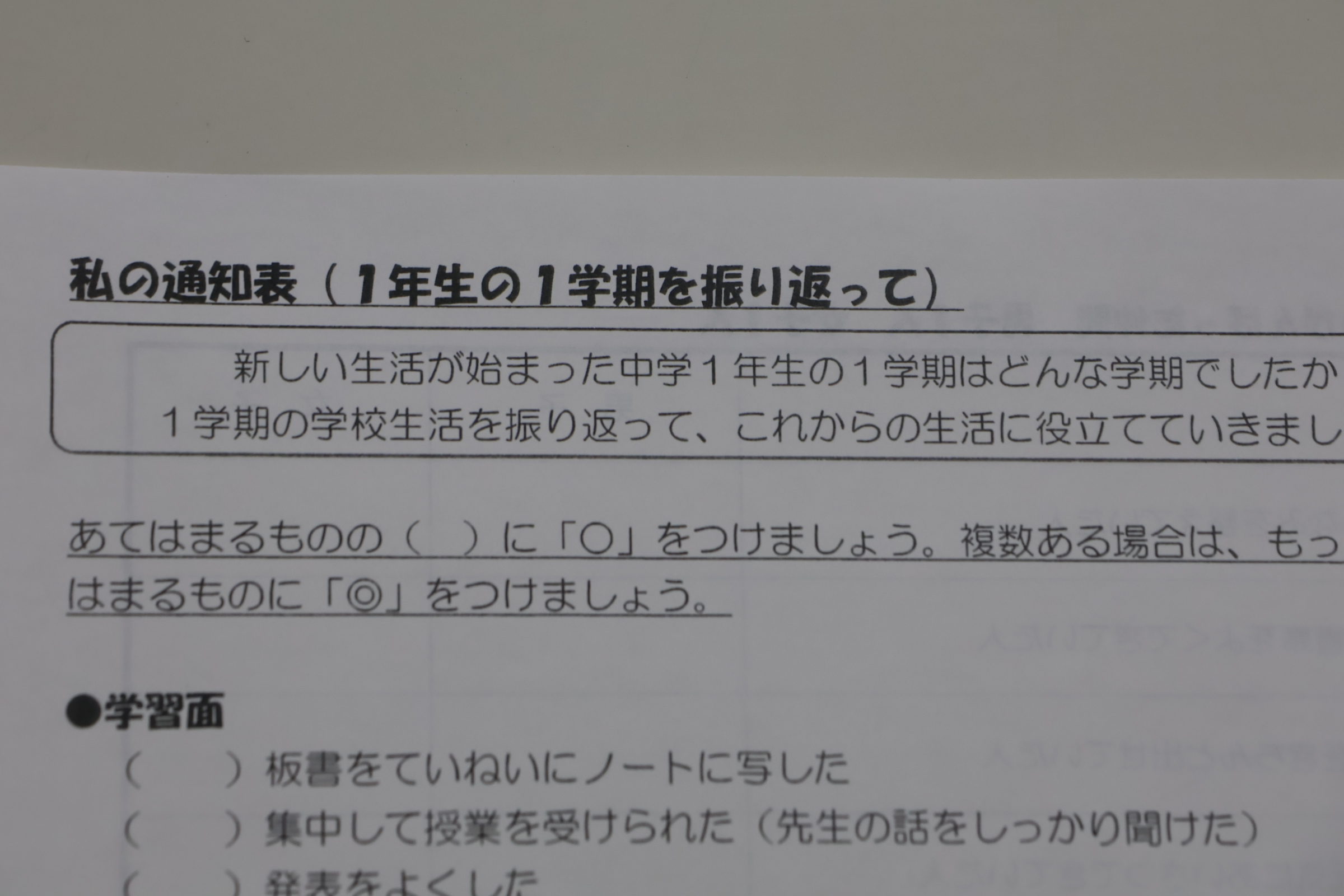
☆338日(7/7)第18回岡山県人権教育研究大会
研究大会の案内が届きました。東備のメンバーで第三分科会を運営します。実り多い会にしましょう。第3分科会での豊かな議論のために、若い参加者に向けて、同和教育(人権教育)のこれまでの実践から培ってきた子ども観や授業・教材観についての小学習会(基調提案)を行うことを考えています。
☆337日(7/4)私たちのしごと
ちょっと前、県北の生徒指導に長年取り組んでいる方とお話しを終え、そのあと偶然に読み直した、沢木耕太郎さんの著書『いのちの記憶 銀河を渡るⅡ『最初の人」が、印象に残りましたな。
☆336日(7/3)「事実と実践」とは。
小学校の実践から学び合う学習会(東備学ぶ会)を行います。
☆335日(7/2)つながりをつくる
前にも記しましたが、十五年間の豊かな育ちを目指して、今年度は中学校区で、こ小中の合同研修会を開催します。

☆334日(7/1)教育実践を振り返り、まとめること
第18回岡山県人権教育研究大会に向けて、報告者と共にレポートの三回の検討会を行い、ようやく原稿がまとまろうとしています。報告者は、これまでに、自分の教育実践をふりかえってレポートにまとめ、検討会での多角的な視点からの指摘やアドバイスや受けながら、さらに自分の実践をめくり(見つめ直す)作業、そして、もう一度コトバにして文章にするコトを繰り返してきました。とてもとても大変だったと思います。しかし、最後の検討会で報告者の顔には、深い学び感、やり終えた感(まだ報告はこれからですが笑)が表れておられたように思います。報告まで一緒にバックアップしていきます。がんばりましょう。報告者の分科会報告アピールの一部を紹介します。「赴任して・・・当初は、同和教育とはなんなのか、どのようにしたらよいのか何も分からないような状態でした。同和教育に対して不安でいっぱいだったように思います。しかし、町内の研修に参加したり、授業実践に取り組んだりすることで、少しずつですが理解が深まり、同和教育の大切さが分かってきたように思います。まだまだ学んでいる最中の私ですが、そんな経験や今の思いをお話しします。そして参加者の皆さんと同和教育について一緒に考えることができればと願っています。」
☆333日(6/30)『あつい壁』
28日に西宮市で開催された『あつい壁』上映会に参加しました。100人を超える多くの参加者の方々の熱意に圧倒されました。ハンセン病問題に、地域の中で継続的に取り組んでこられた市民グループも皆さんの活動の成果だと思います。
映画は60年前につくられたものですが、現代に生きる私たちがもう一度観るべき映画ではないかと思いました。一緒に観て、時代背景や課題を考察しながら、ハンセン病問題を深く考え、ハンセン病問題学習を創出するために意見を交わしたいなあ。上映しましょう。観ましょう。視ましょう。

☆332日(6/27)フィールドワークで学ぶ
小学校6年生と愛生園を歩きました。梅雨の合間の暑い日差しの中、収容桟橋-回春寮-内白間窯-監房跡-納骨堂-盲導響・柵-金さん住居跡-恵の鐘-スチーム施設-一朗道-小川正子碑-恩賜記念館-がけ―新良田教室跡展望-歴史館を、たっぷり2時間かけて廻りました。しっかりとした事前学習に裏付けされた「正しく知りたい気持ち」「学びたい真剣なまなざし」を感じた素敵な時間でした。

☆331日(6/26)子どもが語りあう集会へ
しばしば、生活指導上の課題があったときに、子どもたちを集めて話をする機会がありますが、教員の話を「しゃべる」だけでは、なかなか集団づくりは進みません。教員の話す願いや思い、あるいは事実を、生徒が受けとめ、生徒たちが自分のことばで語り合う集会を可能です。いくつかのスキルは準備しなくてはいけませんが、子どもを信頼しておれば、そんな意味ある集会にできます。
*写真は、全校集会での教員の話を受けて、マイクリレーで語る生徒。前日の全校集会を受けて、次日の生徒朝礼でショートストーリー劇をする生徒会メンバーら。


☆330日(6/25)みんなが幸せになる人権教育 土田光子さんをお招きして
23日、講演「みんなが幸せになるための人権学習~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~」として、土田 光子さんと熱い90分間を過ごすことができました。〈授業以前の、国語の授業を通しての「授業とはなんぞや」授業開き〉、〈これからの学校生活を貫いていくタコさん授業〉、〈どうしたん?へえそうなんか。それでどうする〉・・・(参加した方々とは共有できますが、何がなんだかわかりませんよね。お知りになりたい方はご連絡をお待ちしています。資料と共にお話をしましょう。)本当にあっという間の90分でしたが、参加者一人ひとりが、「自分のしごと」を見つめ、「今・ここから」の学校づくりの道標を再確認したような気がします。

次の日、職員室での朝の打ち合わせ時、「タコさんだった!確認しなくちゃ」とつぶやく先生の声があり、近くに居たもの同士で「うんうん」とうなずきあう場面がありました。(「タコさん知りたいでしょう( ´∀` ))
☆329日(6/24)扇蝶さんの人権落語から(^_^)



21日の東備学び会での人権落語を楽しみました。教職員のみならず、地域の方々がたくさん来会され、満員御礼となりました。「楽しかったあ」と、みなさん笑顔でお帰りになりました。扇蝶さんありがとうございました。
さて、その後、残った私たちと扇蝶さんと意見交流会をすることができ、感想や意見をたくさん交わし、さらに楽しい時間となりました。扇蝶さんは、小学校や地域での人権講演会にも喚ばれて、この人権落語をする機会も多いとのことですが、少しでも参加者同士で感想を語り合う時間は大切だなあとあらためて思いました。(落語噺自体を振り返っての意見交流なんてことは興ざめです笑)
この日、扇蝶さんは、扇蝶さん自身の持つ「落語」のちからで、会場全体をやわらかい雰囲気にしつつ、テーマである〈私らしさあなたらしさ・・・そしてつながり〉について、優しく(実は厳しく・鋭く)迫るために、自身の生き様(よう)を「開き」、語ってくれました。扇蝶さんの大事な生き様を、聴く者は大事に受けとめなくてはいけません。受けとめ方や感想は、それぞれですが、私は、「自分自身、学校、生徒たち、家族とどう向き合ってきたのか?」、「生徒たちにどう寄り添ってきたのか」、「デハ、オマエハ、「コレカラ」ナニヲシテイクノ?ドウイキテイク?」と問うこととなりました。会の冒頭で、「笑うのが、今日の会のルールです」と案内しましたが、私自身は泣いて聴いてました。素晴らしい人権落語でした。 人を動かす力のある人権落語でした。「楽しかったでいいんじゃない。難しく考えすぎ!」と言われそうですが、扇蝶さんの創作「噺」としての五十五分間の、その裏にある熟考、葛藤、練り上げた膨大な時間に敬意を表して、私も「これからも」「よっこらしょ」と、がんばっていこうと思います。二年越しの「人権漫才」をぜひ実現しましょう!
☆328日(6/23)
俳優の藤村志保さんが亡くなられました。ご冥福をお祈りします。20日の山陽新聞に記事がありました。『1961年、大映京都撮 「影所の研究所に入所し、翌 年、市川雷蔵さんの推薦で島崎藤村原作、市川崑監督の映画「破戒」のヒロイン ・志保役で映画デビューした。芸名は同作の原作者と役名から取った。大映時代劇に欠かせない存在となり、大スターの雷蔵さんとは「斬る」や「忍びの者」「眠狂四郎」シリーズなど、勝新太郎さんとは「破れ傘長庵」「座頭市喧嘩旅」などで共演した。他の主な出演映画は・・・』
☆327日(6/20)ひなせ親の会
今年度2回目のひなせ親の会を開催します。この日は、ひなせ認定こども園に寄らせていただき、人権講演会の時間に少しだけ会の紹介をします。15年間の豊かな育ちをめざした、こ小中連携をこれからも進めていきます。
☆326日(6/19)報告検討会で
報告レポート検討会で、「経済的にも、学習環境的にも「しんどい」子ども・家庭とどうつながっているのか?」が議論になった。子どもへの放課後の学習支援や、繰り返し家庭訪問を行い、丁寧に話し込む取り組みを進めていくことはもちろん大切だが、根っこの解決を図るための、福祉や行政、関係機関につなげるネットワーク・機能する体制を学校がきちんともっているか?が問われた。ややもすれば「福祉や行政につなげようとしたけど、保護者は拒否しているようで」で、働きかけがストップしてしまう場合がある。ここを越える、子どもと家庭の「つながり」を創りたい。「つながる」って簡単に使う言葉だけど、重くて、深い。
☆325日(6/18)報告をもとに語り合うって。
研究大会での報告やレポートは、発表会でも、お披露目の会でもありません。報告者が自分の教育実践をまとめ上げ、聞いた参加者が、それに自分の教育実践を重ね、これからの実践の糧にするための時間です。質問も少ない、意見交流もあまり出ない会とならないように、司会団はがんばらなくてななりません。岡山県人権教育研大会での進行に携わる時には、報告レポートの内容に合わせた分科会の基調提案(参考は2023年大会)をして、それをもとにして、話し合いを進めていきます。
☆324日(6/17)人権落語を楽しもう
ふじの舎扇蝶さんの、待ちに待った「人権落語」を楽しむ機会がきました。小中学校の人権教育の啓発講演会にも行かれる事も多いようです。一度、扇蝶さんの豊かな人権教育を味わってみましょう。
☆323日(6/16)◎実践を振り返ること
今週末に友人Tが、「研究大会のレポート案がやっとまとまった」と連絡があった。日々の実践をふりかえり、文書にまとめあげることのなんと大変なことか。Tの労をねぎらうと共に、明後日に行うレポート検討会では、実践と、週末を費やして作成したレポートに最大の敬意を払い、真剣に、本気で、全力で議論をしていこうと考えている。
1992年、初めて学級づくりについての自分の拙い教育実践のレポートを受けとめ、丁寧に論議してくれ、「実践から深く学ぶということはこういうことか!」と体感させてくれた先輩教員の顔と、分科会での協議の風景は今でも鮮明におぼえている。
また、年を経て「学級づくり」のレポートもあまり書かなくなった年齢になった頃、いつも、様々な研究会で、報告をしているN先輩教員から「自分の教育実践は年に一度はまとめて、誰かに聞いてもらわないと、教員としての感覚が鈍ってしまうぜ」と言われた。この教えも自分にとってはとても大きく、それ以降、年に一度は、自分の行っていることを必ず文書にして振り返ってみる。ちょっとした文書にするだけでも、この時間は、今もとても苦しい。自分の力量不足が明確になり、課題がたくさん表出し、自己嫌悪に陥ることも多々ある。しかしながら、ちょっとだけ、あたらしい気づきやヒントがに出会うことができる。そして「書き終えた!」時は、なんともいえない気持ちになる。さらに、まとめた内容を仲間や研修会の機会に話ることで、自分が持ちえていない視点からの指摘やアドバイスを受け、また、「がんばって取り組んでいこう!」と元気をもらえる。明後日のレポート検討では、Tもさらに学び、聴く私たち自身も学びが深まる会にせねばならない。語り合おう!
☆322目(6/13)願いと思いを共に
春15の会 第2回実行委員会


6月11日に、本校の教頭先生も参加してこられました。今年度の案内文書が少し変わりました。〈~特別支援教育のニーズのある子どもたちの進路・自立にむけて~〉です。進学に関する相談ブースだけでなく、学校(高校も含む)生活や、福祉、行政サービス、親の会など自己実現に向けての多ブースの開設も準備します。実施計画案を一部紹介します。
1 目的
(1)特別支援教育のニーズのある生徒の進路・進学や就職についての最新の情報を、本人・保護者や教育関係者、支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。
(2)動画配信や情報交流学習会を通じて高等学校生活を紹介し、進路に関する情報が収集できる会にする。
(3)視聴者が実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。
2 実行委員会の方針
(1)持続可能な会の開催ができるように積極的に工夫・改善を進める。
①目的が達成できるように有機的なヒト・組織・コトの協力(後援)や助言を仰ぐ。
②特別支援教育の推進のために、また本会の開催案内が必要とされる多くの方々に届くように、様々な組織と連携を図り、ネットワークを拡げる。
3 具体的実施計画(内容等)
◎動画配信 卒業後の進路について、申込者に対して高校・関係機関の紹介動画を期間限定で配信(東備地域自立支援協議会ホームページ上にて)する。
<期 間> 令和7年8月8日(金)~11月28日(金)
<内 容> 各校の作成動画には以下の内容を盛り込む。①別支援教育のニーズのある子どもの入学試験についての相談や受験時の配慮、サポート等②学校生活の様子(支援の実際)③卒業後の進路や就職の状況④相談窓口担当者 各校10分程度の動画とする。
◎参集方式(200人程度)
<内 容> 座談会、学校紹介、特設相談会(相談ブース)
<日 時> 令和7年8月23日(土)12:30~16:30
<場 所> 備前市立日生中学校(備前市日生町日生241-14)
(1)参加対象 小・中学校生徒 保護者 教職員 特別支援教育に関わる方
(2)主 催 春15(はるいちご)の会実行委員会
(3)共 催 赤磐市・瀬戸内市・備前市・和気町・東備地域自立支援協議会・備前県民局
(4)後 援 岡山県教育委員会・赤磐市教育委員会・瀬戸内市教育委員会・備前市教育委員会・和気町教育委員会・NPO法人岡山県自閉症児を育てる会・岡山県教職員組合・備前市PTA連合会・赤磐市障害者自立支援協議会・瀬戸内市自立支援協議会(申請予定) *ご案内(申し込み)チラシは、7月初旬に配布予定です!
☆321目(6/12)6.23校内研修が近くなりました
演題:みんなが幸せになるための人権教育
~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~
人権教育研修会の講師、土田光子さんより、レジュメを頂きました。一読するだけで魅力的で、とても楽しみです。一部をちょっと紹介します。
☆320目(6/11)縦割りチームで活躍の場は。
前回の続き。岡山市内でも、各学年を3チームに分け、1,2,3年生が協力しながら競技に取り組むスタイルの体育会が増えたとのこと。いつもはクラスや学年の中で、生徒の活動の姿をみることが多いですが、「このスタイルの体育会では、日頃とは違う子どもたちの姿がたくさん見ることができてびっくりした。(うれしかった)
)」と、若い先生が話してくれました。子どもたちが活躍できる場、子ども同士が活動する場をたくさん作ることが教職員の大事な役割かもしれません。



☆319目(6/10)目指すリーダーとは?
体育会を終えた岡山市の先生らと、「生徒のリーダーを育てる」ことについて話題になりました。私たちのリーダーイメージ・姿はどんなものでしょうか?
教員(教職員集団)の目指す方向に向かって、メンバーを力強く引っ張っていくリーダーをイメージしますか。教員の期待と指示を受け、いわゆる「ミニ先生」的な要素をもち(もたせ)ながら学級を仕切っていく(いかせる)。ややもすれば、小学校では、他の子どもも従順にリーダーに従う傾向があるために、そのような子どもをリーダーとして育て、時には学級運営や学級の問題解決すらリーダーに“丸投げ”することも場合もあるかもしれません。(でも、そのようなことを続けたら、誰もリーダーになりたがらなくなりますな。)
リーダーは進級、進学の経過とともにメンバーの信頼を増していかねばなりません。そのためには、「民主的なリーダー」を学級に育てて(同時に「仲間づくり」の取組は重要)いかねばならないよね。・・・という話になりました。
では、目指す「民主的なリーダー」ってどんな生徒なのか?について、いくつか意見を出してもらうと、『もちろん、目標に向けて集団をうまくリードしたり、活動や話し合いを積極的に進めることの他に、「集団の中で弱い立場の子の味方になれるリーダー」、『困っている子の立場を理解できるリーダー』、『仲間との協働意識を持てる(みんなで取り組める)リーダー』、『多様な仲間を認められるリーダー』、『仲間どうしのトラブルをうまく調整できる(おりあいをつける)リーダー』、『仲間はずしを絶対に出さない配慮を進んで行えるリーダー』などなど。『そんなリーダーおるんかい 笑 ?!』とう意見も含めて、〈リーダーの育成〉と〈反差別の仲間づくり〉を学級経営の両輪として考えたいと思います。目指すリーダーの育成には、教職員集団(学年団)がモデルになることはもちろんですが、日々の、小集団での活動を通して多くの経験を積み、「仕切らせ力」から、民主的な「高い人権意識」の醸成へのアプローチを進めたいと思います。民主的なリーダーは、意識して育てようとしなければ育ちません。集団を動かすためには、集団全体を相手にするのではなく、メンバー一人ひとりとの深い関係をどう築くか、などを具体的な活動の中で伝えていきたいと思います。
☆318目(6/6)国際交流って?多文化共生教育の中身?
国際交流事業として姉妹都市縁組などで来市した外国の生徒が、校区の小・中学校に「国際交流」という目的で、短時間で、書道や浴衣の着付け体験、スポーツ、給食試食等を一緒に行うことを聞きます。さて、それは、「国際交流となるのかなあ?」「国際交流の目的について、担当者とじっくり話をせねばならないね」「するなら、多文化共生社会の理念に基づいた継続的な取組の中でやらないといけんなあ」と、けっこう先生方と職員室で話題となりました。
少しだけ調べてみても、目的の明確化、丁寧な準備と、確かな実践をせねばなりませんね。(以下、参考)
外国人児童生徒にかかわる教育指針:多文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を図ることを支援するとともに、すべての児童生徒が互いを尊重し合い、多様な文化的背景をもつ外国人児童生徒と豊かに共生する真の国際化に向け、「人権教育基本方針」に基づき、外国人児童生徒の人権にかかわる課題の解決に取り組む。
〈基本的な考え方〉
1外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることができるよう支援する。
重点目標1 外国人児童生徒が誇りを持って過ごせる環境づくり
重点目標2 学習機会の提供と自尊感情の形成
重点目標3 学習指導及び進路指導の充実
2 すべての児童生徒に、外国人に対する偏見や差別の不当性について認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。
重点目標1 在日韓国・朝鮮人など日本に在留する外国人にかかわる歴史的経緯や社会的背景についての認識
重点目標2 日本語指導が必要な外国人児童生徒についての認識
重点目標3 差別や偏見の不当性についての認識
3 共生の心を育成することをめざし、すべての児童生徒に多様な文化を持った人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。
重点目標1 異なる文化の理解
重点目標2 自国の文化を尊重する態度と異文化間コミュニケーション能力の育成
4 外国人児童生徒にかかわる教育指導の充実に向け、教職員一人一人が人権意識の高揚に努めるとともに、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。
重点目標1 教職員の人権意識の高揚
重点目標2 教職員の研修の充実
重点目標3 家庭及び地域、関係機関・団体等とのネットワークの充実
①共生の心の育成…全ての子どもたちが、国籍や民族等の「違い」を認め合い、多様な文化的背景をもつ人々と豊かに共生する心、共に生きようとする意欲や態度を育むため、子ども・多文化共生センターなどの機関と連携し、異なる文化、民族、宗教、生活習慣、価値観に対する理解を図る。
②自己実現に向けた支援…全外国人幼児児童生徒等のアイデンティティの確立を図るため、子ども多文化共生サポーターや地域の人材等を活用し、母国の文化や言語、民族の歴史等の学習機会を充実する。また、進路など将来を見据えて、体系的・継続的な指導・支援を実施する。
③母語による支援の充実…学校生活への早期適応を促進するための心の安定や生活適応、学習支援が円滑にできるよう、子ども多文化共生サポーター等の母語支援員や多言語翻訳機・アプリケーション等のICTを活用し、外国人児童生徒等のコミュニケーションを図る。
④日本語指導の促進…日本語の習得や基礎学力の定着を図るため、各教科の指導等について児童生徒一人一人に応じて「特別の教育課程」を編成するなど、きめ細かな指導を行う。また、外国人児童生徒等の自己実現を支援するため、日本語指導が必要な外国人児童生徒等が在籍する学校間をオンラインでつなぎ、交流や学びの機会の充実を図る。
⑤帰国幼児児童生徒への支援 全帰国幼児児童生徒の円滑な就園・就学を図るため、家庭や地域と連携して、海外で培った特性を伸長するよう努めるとともに、温かく迎えられ、互いに理解し尊重し合えるよう配慮する
大切な「教育」の機会・場ですから、しっかりと目的を持って受け入れたいと思います。
☆317目(6/5)地域と共にある学校とは?
6/1のカキフェスに多くの生徒らが参加しました。変な言い方ですが、地域ボランティア活動を通して、その活動を「越える」営みにしていきたいと思っています。昨年度末に市の櫂の木賞応募時にまとめた文章を添付します。

☆316目(6/4)個人に返す、仲間の前で返す?
6/1に開催された、今年2回目のカキフェスには、本校からたくさんの生徒がボランティアとして参加することとなりした。参加日前までに、提出した申し込み用紙内容を確認し、生徒(保護者)へ返却しましたが、個人に返す(集配BOXに入れておく)のではなく、クラスの仲間の前で紹介し、エールも併せて、申し込み用紙を返却する場面をつくると、仲間を知り、仲間を認め合う大切な時間になるのではないかあと思います。本校の担任も、そんな小さな仲間づくりの時間の大事にしています。
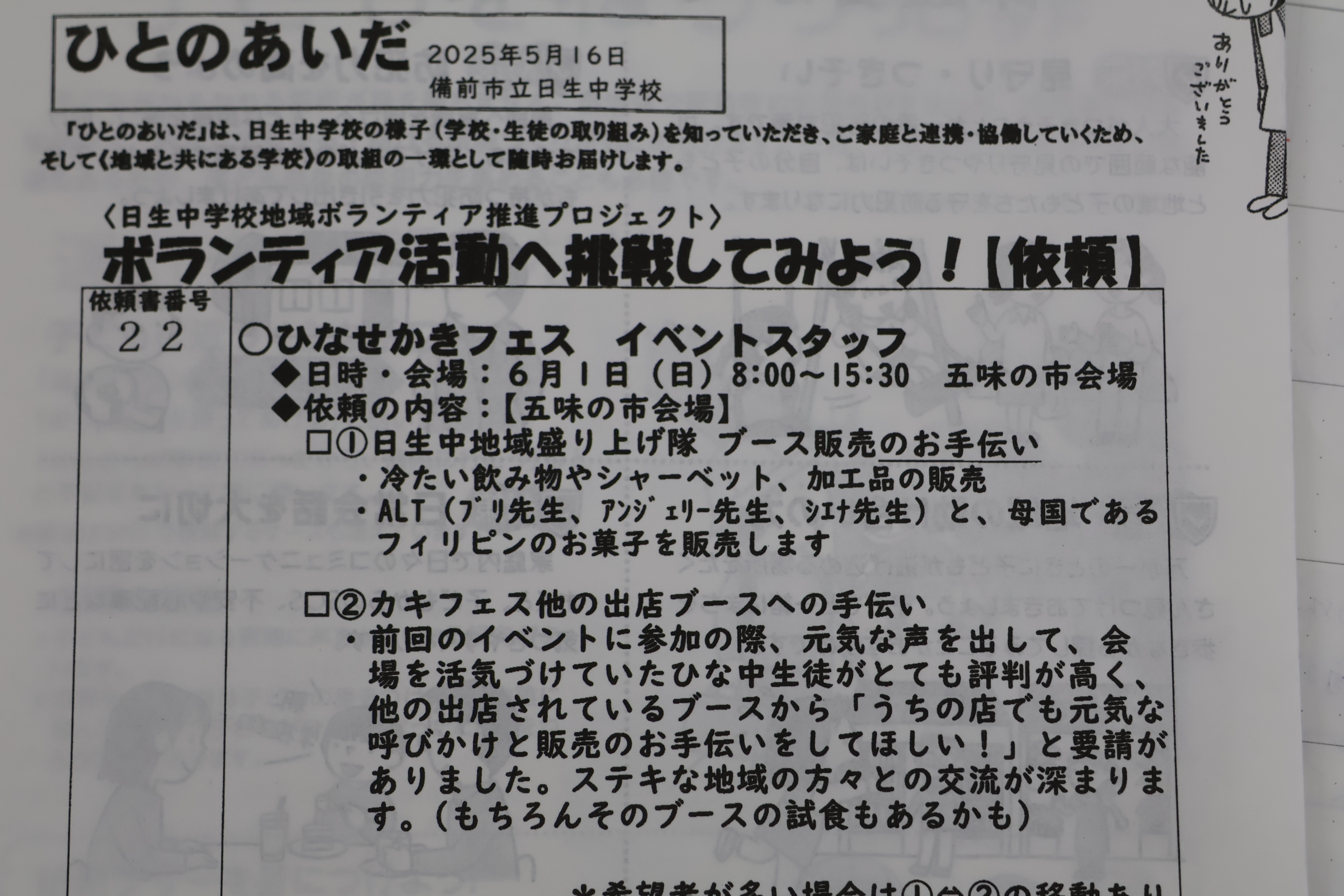
☆315日目(6/3)多文化共生社会へ、食文化を通して
6/1(日)のカキフェスにALTの先生方とブースで、母国フィリピンのお菓子を販売してきま~す。

☆314日目(6/2)多様な研修の機会を。
5/31(土)は「一次教研」が開催されました。「教研」を検索してみたら、〈教職員組合が他の労働組合と大きく異なる点として教育研究活動(通称、教研)が挙げられます。目の前の子どもの実態を出発点として「平和を守り、真実を貫く民主教育の確立」「わかる授業、楽しい学校」をめざして、全国の教職員と議論し、その成果を自らの日々の教育実践に生かす教研活動は世界的にも高く評価されています。この「子ども中心」の考え方は、組合活動全体にも見られ、少人数学級の推進を訴えていることも、子どもたちや学校を競争に駆り立てる全国学力・学習状況調査に反対していることも、子どもたちにゆとりあるゆたかな教育を実現したいという願いがあるからに他なりません。〉という文書がありました。私は、一推進委員としての参加でしたが、やっぱり、教職員がそれぞれの日々の「教育実践」と「思いや願い」を持ち寄り、お互いに「語り合う」ことを、これからも大切にしたいと思います。研修のイメージが教育センターでの研修や校内研修だけになっては、進歩がありません。東備地域での研修の機会としている「東備学ぶ会」や、「藤野会館学習講座」なども大事に活用しながら、教職員としての子ども観、授業観などを磨いていきたいと思います。
☆313日目(5/30)映画「あつい壁」って知っていますか?
西宮の知り合いから映画「あつい壁」(中山節夫監督)上映会のお知らせを頂きました。これまで何度も観る機会を逸していました。日程調整して参加しようと思います。
人権課題にかかわる映画は他にももたくさんありますね。、1948年につくられた「破戒」(木下恵介監督・池部良・高峯秀子さんが出演)はYouTubeで視聴できたのはびっくりしました。「破戒」は、2022年に間宮祥太朗さん・石井杏奈さんが出演で再映画化されています。2つの映画を見比べて観ると考えることもとても深くなります。もちろん、考えたことをじっくりと語り合う時間も持ちたいです。
☆312日目(5/29)人権教育と道徳教育の違いを確認しつつ。
修先日、人権教育担当者の研修に参加した際、報告の中で『人権教育(道徳教育)』という記述がありました。私たちは「違い」を明確にしながら、取り組まんといけんよなあと、小グループの中で話をしました。(研修会で、小グループでの話し合いを取り入れることが増えましたが、それに伴い、参加者全体で「一つ」のことを協議していく研修スタイルの会が減りました。みんなで一体感や共有感を味わうことはみはや過去の話?そんな会を作り出すファシリテーション技法を高めんたいな。)←それは置いといて、「違い」について
人権教育と道徳教育の関連
☆311日目(5/28)修学旅行を生徒主体な取組として。
修学旅行実行委員が旅行日程の中でどれだけ自主的に動くのか?を組み立てたいなあと思います。一見教員がしていることも、加納なら「これは子どもたちに任せたり、委ねたりできるのでは」という視点や、主体的な行動ができる学年集団づくり進めたい。以下の内容は、引率教員の仕事?添乗員さんの仕事?、子どもたちが動ける? □点呼 □航空券の配布 □お弁当・お茶配り □廊下の見守り □部屋の点検 □実行委員によるモーニングコール □注意事項や留意点
自立活動のレポートを読んで、自立と依存についてちょっと考えている。レポートの中の3年生のひとりが、ある施設の見学に入る直前に「先生、くつひもをむすんで。」と言ってきたとのこと。(その時にどう声かけして、どのような支援・指導するのがよいか?は意見がわかれるところ、これもいろいろと話し合ってみたい)以前も同じような内容を記しましたが再掲します。
「自立」の意味を検索してみると、“自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやって行くこと”と説明されています。(引用:Oxford Languages)つまり、自立とは「何にも依存しない状態」のようです。
たしかに、依存は英語で「dependence」、自立は 「independence 」で、否定を意味する「in」がついてるので、依存と自立は対立の概念とされています。しかし、何にも依存せずに生きている人なんて、一人もいません。例えば、社会人としての会社員も給料をその会社に依存していると言えます。当事者研究、べてるの家等で知られる熊谷先生は『「自立」とは、特定の依存先から支配されることなく、たくさんの依存先から自由に選択できる状態だと言います。』
学びの共同体の佐藤学さんは「子どもたちの小さなささやくような声が尊重されるべきである。「依存」と「自立」を対立的に考える のは誤りである。「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。』と言われます。うーん うーん。
☆346日(7/17)出会いを大切にできるか。
中国からの交流生を迎えて、授業案を国語科の先生と相談しました。
☆345日(7/16)国際交流とは何か
縁あって、市の国際交流事業で来岡する中国からの交流生が本校の見学(授業体験)に来られます。受け入れるにあたっては市ともいろいろと話をしました。時間と場所を提供するだけで、交流が成立するものではありませんね。関わる者どうしが「国際交流とは何か?」「今回の目的に重ねて出来ること」を共有し、多文化共生社会の意識を高めるものでなくてはいけないと考る機会になりました。事前に生徒たちが何にどのように出会うかも重要です。「学校便り」を全校生徒に事前学習資料として配りました。
☆344日(7/15)自立・社会参画の芽を
県内の自立活動の取組として、〈市内まで電車で行き、高校見学に行き、昼食を取り、家族に頼まれたモノを購入して、また電車に乗って帰宅する大作戦〉のレポートを読んだ。もちろん、しっかり事前学習で、時刻表を調べ、高校の場所を確認し、参加者で楽しめる昼食のお店を考えたそうだ。が、しかし当日。予想してなかった雨の中を慣れない傘をさしての行程。まさか高校が5Fにあるとは思わず、スマホを頼りにビルの周りをぐるぐる探し続けたり、昼食の場所は目視できるのに、地下街を通って遠回りしないといけなかったりとか、頼まれたモノを売っているお店が見つからなかったり、見つけたモノは、とても高価であることが分かり、購入すべきか悩んだり…。だけど、その度に、生徒らは(自分で、、時にはメンバーで)考え、判断し・決めて、その大作戦をやり遂げることができた。引率した教員は、これまでの学校での教育活動が、子どもたちの社会の中で生きていく力になっていると感じられる子どもたちの姿を看ることができたという。また、卒業までに取り組んでいかないといけない課題(子どもの課題ではなく、自立活動を中心とした教育活動の内容)も視えた。校外(社会)の学習がいつもできるわけではないが、社会参画を意識した確かな学習内容を創ってきたいとつくづく思ったなあ。
☆343日(7/14)やっぱり、仲間づくりの原点は
英語科で発表している子どもたちの姿をみていると、やっぱり、クラスの仲間に自分のことを知ってもらうことがとてもうれしく、そして仲間のことを知ることはとても大切だと思っているようにみえました。お互いを分かり合う場面を増やしてこそ、学び合う、支え合う仲間となっていくのではないか。

☆342日(7/11)聲をきく
親の会や様々な学習会を開催する中でいつも、参加される方々の「声」をきくことは大切だなあと思います。先日の会では、あるお父さんから「就労移行支援って何なの?」という疑問から、単に「特別支援学校か、通信制サポート校どっちがいい?」ではなく、子どものこれまでの「育ち」と、本人の願いや夢を大事にしながら、それぞれの歩幅でのこれからの「育ち」(社会的自立)に向けての伴走したいね」と話題になりました。教育に携わる私たちが、生徒の「発達」(特別支援教育)に係ることを保護者にどう伝え、どう長期的な連携を始めていくか?は重要だな。
☆341日(7/10)春15の会は必要なのか?
今年の活動の案内チラシが届きました。
☆340日(7/9)電話で聴く
先日、進学関係で聞きたいことがあり、関係機関にお電話させていただきました。最初の部署での電話応対してくださった方は、なぜか、電話内容をメモすることが一番らしく(それが分かる応対で)、要件が伝わっているのかどうか不安になりました。案の定?「分りかねる」と言われ、他の部署「名」だけを教えてくださり、通話を終えました。そのあと、その部署の電話番号を自分で調べて、かけ直したところ、今度の担当者はとても丁寧で、真摯に「聴いて」くださる中で、必要な情報を得ることができました。実はどちらも、不登校や発達障がい、そして高校進学について「何かあればお気軽にご連絡ください」というチラシや案内をたくさん配布している部署でした。「保護者が困って、やっとかけることのできた電話だったとしたら、どう思っただろうか?」…。わずかな時間の、ちょっとした電話だけども、大事な時間にしなくてはいけないなあと思いました。本市も、学校への欠席連絡については、連絡ツール(アプリ)を導入するそうです。
☆339日(7/8)
1学期の振り返りをしている時期かもしれません。「授業で静かにできた?」「友達に迷惑をかけなかった?」「黒板をきちんと写すことができた?」なんて質問項目はないと思いますが、子どもたちが日々の学校生活を振り返ると同時に、これは私たち教職員集団の教育実践がどうだったか問われることにもなりますね。どきどきしますな。そして、私たちの目指すことを明確化したものを質問項目にしないとね。「授業でわからないところを仲間に聞くことができた?」「聞かれたら、誠実に応えようとした?」「授業で自分の考えを話すことができた?」「仲間を意識して行動することができた?」「考えてながら板書を自分なりにまとめることができた?」なんてね。
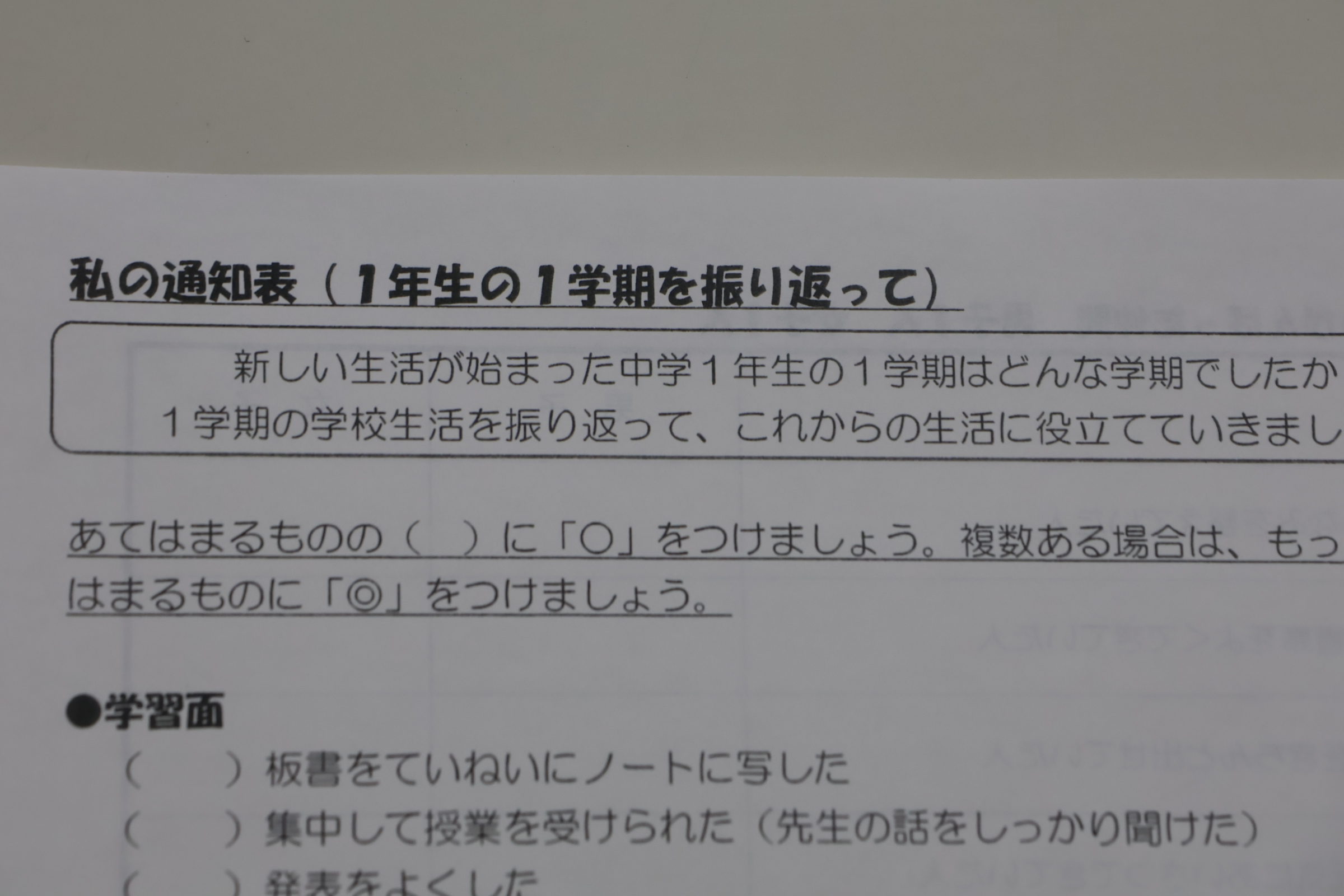
☆338日(7/7)第18回岡山県人権教育研究大会
研究大会の案内が届きました。東備のメンバーで第三分科会を運営します。実り多い会にしましょう。第3分科会での豊かな議論のために、若い参加者に向けて、同和教育(人権教育)のこれまでの実践から培ってきた子ども観や授業・教材観についての小学習会(基調提案)を行うことを考えています。
☆337日(7/4)私たちのしごと
ちょっと前、県北の生徒指導に長年取り組んでいる方とお話しを終え、そのあと偶然に読み直した、沢木耕太郎さんの著書『いのちの記憶 銀河を渡るⅡ『最初の人」が、印象に残りましたな。
☆336日(7/3)「事実と実践」とは。
小学校の実践から学び合う学習会(東備学ぶ会)を行います。
☆335日(7/2)つながりをつくる
前にも記しましたが、十五年間の豊かな育ちを目指して、今年度は中学校区で、こ小中の合同研修会を開催します。

☆334日(7/1)教育実践を振り返り、まとめること
第18回岡山県人権教育研究大会に向けて、報告者と共にレポートの三回の検討会を行い、ようやく原稿がまとまろうとしています。報告者は、これまでに、自分の教育実践をふりかえってレポートにまとめ、検討会での多角的な視点からの指摘やアドバイスや受けながら、さらに自分の実践をめくり(見つめ直す)作業、そして、もう一度コトバにして文章にするコトを繰り返してきました。とてもとても大変だったと思います。しかし、最後の検討会で報告者の顔には、深い学び感、やり終えた感(まだ報告はこれからですが笑)が表れておられたように思います。報告まで一緒にバックアップしていきます。がんばりましょう。報告者の分科会報告アピールの一部を紹介します。「赴任して・・・当初は、同和教育とはなんなのか、どのようにしたらよいのか何も分からないような状態でした。同和教育に対して不安でいっぱいだったように思います。しかし、町内の研修に参加したり、授業実践に取り組んだりすることで、少しずつですが理解が深まり、同和教育の大切さが分かってきたように思います。まだまだ学んでいる最中の私ですが、そんな経験や今の思いをお話しします。そして参加者の皆さんと同和教育について一緒に考えることができればと願っています。」
☆333日(6/30)『あつい壁』
28日に西宮市で開催された『あつい壁』上映会に参加しました。100人を超える多くの参加者の方々の熱意に圧倒されました。ハンセン病問題に、地域の中で継続的に取り組んでこられた市民グループも皆さんの活動の成果だと思います。
映画は60年前につくられたものですが、現代に生きる私たちがもう一度観るべき映画ではないかと思いました。一緒に観て、時代背景や課題を考察しながら、ハンセン病問題を深く考え、ハンセン病問題学習を創出するために意見を交わしたいなあ。上映しましょう。観ましょう。視ましょう。

☆332日(6/27)フィールドワークで学ぶ
小学校6年生と愛生園を歩きました。梅雨の合間の暑い日差しの中、収容桟橋-回春寮-内白間窯-監房跡-納骨堂-盲導響・柵-金さん住居跡-恵の鐘-スチーム施設-一朗道-小川正子碑-恩賜記念館-がけ―新良田教室跡展望-歴史館を、たっぷり2時間かけて廻りました。しっかりとした事前学習に裏付けされた「正しく知りたい気持ち」「学びたい真剣なまなざし」を感じた素敵な時間でした。

☆331日(6/26)子どもが語りあう集会へ
しばしば、生活指導上の課題があったときに、子どもたちを集めて話をする機会がありますが、教員の話を「しゃべる」だけでは、なかなか集団づくりは進みません。教員の話す願いや思い、あるいは事実を、生徒が受けとめ、生徒たちが自分のことばで語り合う集会を可能です。いくつかのスキルは準備しなくてはいけませんが、子どもを信頼しておれば、そんな意味ある集会にできます。
*写真は、全校集会での教員の話を受けて、マイクリレーで語る生徒。前日の全校集会を受けて、次日の生徒朝礼でショートストーリー劇をする生徒会メンバーら。


☆330日(6/25)みんなが幸せになる人権教育 土田光子さんをお招きして
23日、講演「みんなが幸せになるための人権学習~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~」として、土田 光子さんと熱い90分間を過ごすことができました。〈授業以前の、国語の授業を通しての「授業とはなんぞや」授業開き〉、〈これからの学校生活を貫いていくタコさん授業〉、〈どうしたん?へえそうなんか。それでどうする〉・・・(参加した方々とは共有できますが、何がなんだかわかりませんよね。お知りになりたい方はご連絡をお待ちしています。資料と共にお話をしましょう。)本当にあっという間の90分でしたが、参加者一人ひとりが、「自分のしごと」を見つめ、「今・ここから」の学校づくりの道標を再確認したような気がします。

次の日、職員室での朝の打ち合わせ時、「タコさんだった!確認しなくちゃ」とつぶやく先生の声があり、近くに居たもの同士で「うんうん」とうなずきあう場面がありました。(「タコさん知りたいでしょう( ´∀` ))
☆329日(6/24)扇蝶さんの人権落語から(^_^)



21日の東備学び会での人権落語を楽しみました。教職員のみならず、地域の方々がたくさん来会され、満員御礼となりました。「楽しかったあ」と、みなさん笑顔でお帰りになりました。扇蝶さんありがとうございました。
さて、その後、残った私たちと扇蝶さんと意見交流会をすることができ、感想や意見をたくさん交わし、さらに楽しい時間となりました。扇蝶さんは、小学校や地域での人権講演会にも喚ばれて、この人権落語をする機会も多いとのことですが、少しでも参加者同士で感想を語り合う時間は大切だなあとあらためて思いました。(落語噺自体を振り返っての意見交流なんてことは興ざめです笑)
この日、扇蝶さんは、扇蝶さん自身の持つ「落語」のちからで、会場全体をやわらかい雰囲気にしつつ、テーマである〈私らしさあなたらしさ・・・そしてつながり〉について、優しく(実は厳しく・鋭く)迫るために、自身の生き様(よう)を「開き」、語ってくれました。扇蝶さんの大事な生き様を、聴く者は大事に受けとめなくてはいけません。受けとめ方や感想は、それぞれですが、私は、「自分自身、学校、生徒たち、家族とどう向き合ってきたのか?」、「生徒たちにどう寄り添ってきたのか」、「デハ、オマエハ、「コレカラ」ナニヲシテイクノ?ドウイキテイク?」と問うこととなりました。会の冒頭で、「笑うのが、今日の会のルールです」と案内しましたが、私自身は泣いて聴いてました。素晴らしい人権落語でした。 人を動かす力のある人権落語でした。「楽しかったでいいんじゃない。難しく考えすぎ!」と言われそうですが、扇蝶さんの創作「噺」としての五十五分間の、その裏にある熟考、葛藤、練り上げた膨大な時間に敬意を表して、私も「これからも」「よっこらしょ」と、がんばっていこうと思います。二年越しの「人権漫才」をぜひ実現しましょう!
☆328日(6/23)
俳優の藤村志保さんが亡くなられました。ご冥福をお祈りします。20日の山陽新聞に記事がありました。『1961年、大映京都撮 「影所の研究所に入所し、翌 年、市川雷蔵さんの推薦で島崎藤村原作、市川崑監督の映画「破戒」のヒロイン ・志保役で映画デビューした。芸名は同作の原作者と役名から取った。大映時代劇に欠かせない存在となり、大スターの雷蔵さんとは「斬る」や「忍びの者」「眠狂四郎」シリーズなど、勝新太郎さんとは「破れ傘長庵」「座頭市喧嘩旅」などで共演した。他の主な出演映画は・・・』
☆327日(6/20)ひなせ親の会
今年度2回目のひなせ親の会を開催します。この日は、ひなせ認定こども園に寄らせていただき、人権講演会の時間に少しだけ会の紹介をします。15年間の豊かな育ちをめざした、こ小中連携をこれからも進めていきます。
☆326日(6/19)報告検討会で
報告レポート検討会で、「経済的にも、学習環境的にも「しんどい」子ども・家庭とどうつながっているのか?」が議論になった。子どもへの放課後の学習支援や、繰り返し家庭訪問を行い、丁寧に話し込む取り組みを進めていくことはもちろん大切だが、根っこの解決を図るための、福祉や行政、関係機関につなげるネットワーク・機能する体制を学校がきちんともっているか?が問われた。ややもすれば「福祉や行政につなげようとしたけど、保護者は拒否しているようで」で、働きかけがストップしてしまう場合がある。ここを越える、子どもと家庭の「つながり」を創りたい。「つながる」って簡単に使う言葉だけど、重くて、深い。
☆325日(6/18)報告をもとに語り合うって。
研究大会での報告やレポートは、発表会でも、お披露目の会でもありません。報告者が自分の教育実践をまとめ上げ、聞いた参加者が、それに自分の教育実践を重ね、これからの実践の糧にするための時間です。質問も少ない、意見交流もあまり出ない会とならないように、司会団はがんばらなくてななりません。岡山県人権教育研大会での進行に携わる時には、報告レポートの内容に合わせた分科会の基調提案(参考は2023年大会)をして、それをもとにして、話し合いを進めていきます。
☆324日(6/17)人権落語を楽しもう
ふじの舎扇蝶さんの、待ちに待った「人権落語」を楽しむ機会がきました。小中学校の人権教育の啓発講演会にも行かれる事も多いようです。一度、扇蝶さんの豊かな人権教育を味わってみましょう。
☆323日(6/16)◎実践を振り返ること
今週末に友人Tが、「研究大会のレポート案がやっとまとまった」と連絡があった。日々の実践をふりかえり、文書にまとめあげることのなんと大変なことか。Tの労をねぎらうと共に、明後日に行うレポート検討会では、実践と、週末を費やして作成したレポートに最大の敬意を払い、真剣に、本気で、全力で議論をしていこうと考えている。
1992年、初めて学級づくりについての自分の拙い教育実践のレポートを受けとめ、丁寧に論議してくれ、「実践から深く学ぶということはこういうことか!」と体感させてくれた先輩教員の顔と、分科会での協議の風景は今でも鮮明におぼえている。
また、年を経て「学級づくり」のレポートもあまり書かなくなった年齢になった頃、いつも、様々な研究会で、報告をしているN先輩教員から「自分の教育実践は年に一度はまとめて、誰かに聞いてもらわないと、教員としての感覚が鈍ってしまうぜ」と言われた。この教えも自分にとってはとても大きく、それ以降、年に一度は、自分の行っていることを必ず文書にして振り返ってみる。ちょっとした文書にするだけでも、この時間は、今もとても苦しい。自分の力量不足が明確になり、課題がたくさん表出し、自己嫌悪に陥ることも多々ある。しかしながら、ちょっとだけ、あたらしい気づきやヒントがに出会うことができる。そして「書き終えた!」時は、なんともいえない気持ちになる。さらに、まとめた内容を仲間や研修会の機会に話ることで、自分が持ちえていない視点からの指摘やアドバイスを受け、また、「がんばって取り組んでいこう!」と元気をもらえる。明後日のレポート検討では、Tもさらに学び、聴く私たち自身も学びが深まる会にせねばならない。語り合おう!
☆322目(6/13)願いと思いを共に
春15の会 第2回実行委員会


6月11日に、本校の教頭先生も参加してこられました。今年度の案内文書が少し変わりました。〈~特別支援教育のニーズのある子どもたちの進路・自立にむけて~〉です。進学に関する相談ブースだけでなく、学校(高校も含む)生活や、福祉、行政サービス、親の会など自己実現に向けての多ブースの開設も準備します。実施計画案を一部紹介します。
1 目的
(1)特別支援教育のニーズのある生徒の進路・進学や就職についての最新の情報を、本人・保護者や教育関係者、支援者自身が収集し、子どもの進路実現への見通しを立て、教育支援の充実に向けて見識を広げる会にする。
(2)動画配信や情報交流学習会を通じて高等学校生活を紹介し、進路に関する情報が収集できる会にする。
(3)視聴者が実際のオープンスクールへの参加や学校見学・学校相談等を積極的に行うための一助とする。
2 実行委員会の方針
(1)持続可能な会の開催ができるように積極的に工夫・改善を進める。
①目的が達成できるように有機的なヒト・組織・コトの協力(後援)や助言を仰ぐ。
②特別支援教育の推進のために、また本会の開催案内が必要とされる多くの方々に届くように、様々な組織と連携を図り、ネットワークを拡げる。
3 具体的実施計画(内容等)
◎動画配信 卒業後の進路について、申込者に対して高校・関係機関の紹介動画を期間限定で配信(東備地域自立支援協議会ホームページ上にて)する。
<期 間> 令和7年8月8日(金)~11月28日(金)
<内 容> 各校の作成動画には以下の内容を盛り込む。①別支援教育のニーズのある子どもの入学試験についての相談や受験時の配慮、サポート等②学校生活の様子(支援の実際)③卒業後の進路や就職の状況④相談窓口担当者 各校10分程度の動画とする。
◎参集方式(200人程度)
<内 容> 座談会、学校紹介、特設相談会(相談ブース)
<日 時> 令和7年8月23日(土)12:30~16:30
<場 所> 備前市立日生中学校(備前市日生町日生241-14)
(1)参加対象 小・中学校生徒 保護者 教職員 特別支援教育に関わる方
(2)主 催 春15(はるいちご)の会実行委員会
(3)共 催 赤磐市・瀬戸内市・備前市・和気町・東備地域自立支援協議会・備前県民局
(4)後 援 岡山県教育委員会・赤磐市教育委員会・瀬戸内市教育委員会・備前市教育委員会・和気町教育委員会・NPO法人岡山県自閉症児を育てる会・岡山県教職員組合・備前市PTA連合会・赤磐市障害者自立支援協議会・瀬戸内市自立支援協議会(申請予定) *ご案内(申し込み)チラシは、7月初旬に配布予定です!
☆321目(6/12)6.23校内研修が近くなりました
演題:みんなが幸せになるための人権教育
~人権学習・集団づくり・授業改革がつながってこそ~
人権教育研修会の講師、土田光子さんより、レジュメを頂きました。一読するだけで魅力的で、とても楽しみです。一部をちょっと紹介します。
☆320目(6/11)縦割りチームで活躍の場は。
前回の続き。岡山市内でも、各学年を3チームに分け、1,2,3年生が協力しながら競技に取り組むスタイルの体育会が増えたとのこと。いつもはクラスや学年の中で、生徒の活動の姿をみることが多いですが、「このスタイルの体育会では、日頃とは違う子どもたちの姿がたくさん見ることができてびっくりした。(うれしかった)
)」と、若い先生が話してくれました。子どもたちが活躍できる場、子ども同士が活動する場をたくさん作ることが教職員の大事な役割かもしれません。



☆319目(6/10)目指すリーダーとは?
体育会を終えた岡山市の先生らと、「生徒のリーダーを育てる」ことについて話題になりました。私たちのリーダーイメージ・姿はどんなものでしょうか?
教員(教職員集団)の目指す方向に向かって、メンバーを力強く引っ張っていくリーダーをイメージしますか。教員の期待と指示を受け、いわゆる「ミニ先生」的な要素をもち(もたせ)ながら学級を仕切っていく(いかせる)。ややもすれば、小学校では、他の子どもも従順にリーダーに従う傾向があるために、そのような子どもをリーダーとして育て、時には学級運営や学級の問題解決すらリーダーに“丸投げ”することも場合もあるかもしれません。(でも、そのようなことを続けたら、誰もリーダーになりたがらなくなりますな。)
リーダーは進級、進学の経過とともにメンバーの信頼を増していかねばなりません。そのためには、「民主的なリーダー」を学級に育てて(同時に「仲間づくり」の取組は重要)いかねばならないよね。・・・という話になりました。
では、目指す「民主的なリーダー」ってどんな生徒なのか?について、いくつか意見を出してもらうと、『もちろん、目標に向けて集団をうまくリードしたり、活動や話し合いを積極的に進めることの他に、「集団の中で弱い立場の子の味方になれるリーダー」、『困っている子の立場を理解できるリーダー』、『仲間との協働意識を持てる(みんなで取り組める)リーダー』、『多様な仲間を認められるリーダー』、『仲間どうしのトラブルをうまく調整できる(おりあいをつける)リーダー』、『仲間はずしを絶対に出さない配慮を進んで行えるリーダー』などなど。『そんなリーダーおるんかい 笑 ?!』とう意見も含めて、〈リーダーの育成〉と〈反差別の仲間づくり〉を学級経営の両輪として考えたいと思います。目指すリーダーの育成には、教職員集団(学年団)がモデルになることはもちろんですが、日々の、小集団での活動を通して多くの経験を積み、「仕切らせ力」から、民主的な「高い人権意識」の醸成へのアプローチを進めたいと思います。民主的なリーダーは、意識して育てようとしなければ育ちません。集団を動かすためには、集団全体を相手にするのではなく、メンバー一人ひとりとの深い関係をどう築くか、などを具体的な活動の中で伝えていきたいと思います。
☆318目(6/6)国際交流って?多文化共生教育の中身?
国際交流事業として姉妹都市縁組などで来市した外国の生徒が、校区の小・中学校に「国際交流」という目的で、短時間で、書道や浴衣の着付け体験、スポーツ、給食試食等を一緒に行うことを聞きます。さて、それは、「国際交流となるのかなあ?」「国際交流の目的について、担当者とじっくり話をせねばならないね」「するなら、多文化共生社会の理念に基づいた継続的な取組の中でやらないといけんなあ」と、けっこう先生方と職員室で話題となりました。
少しだけ調べてみても、目的の明確化、丁寧な準備と、確かな実践をせねばなりませんね。(以下、参考)
外国人児童生徒にかかわる教育指針:多文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を図ることを支援するとともに、すべての児童生徒が互いを尊重し合い、多様な文化的背景をもつ外国人児童生徒と豊かに共生する真の国際化に向け、「人権教育基本方針」に基づき、外国人児童生徒の人権にかかわる課題の解決に取り組む。
〈基本的な考え方〉
1外国人児童生徒が民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることができるよう支援する。
重点目標1 外国人児童生徒が誇りを持って過ごせる環境づくり
重点目標2 学習機会の提供と自尊感情の形成
重点目標3 学習指導及び進路指導の充実
2 すべての児童生徒に、外国人に対する偏見や差別の不当性について認識を深めさせるとともに、あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。
重点目標1 在日韓国・朝鮮人など日本に在留する外国人にかかわる歴史的経緯や社会的背景についての認識
重点目標2 日本語指導が必要な外国人児童生徒についての認識
重点目標3 差別や偏見の不当性についての認識
3 共生の心を育成することをめざし、すべての児童生徒に多様な文化を持った人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。
重点目標1 異なる文化の理解
重点目標2 自国の文化を尊重する態度と異文化間コミュニケーション能力の育成
4 外国人児童生徒にかかわる教育指導の充実に向け、教職員一人一人が人権意識の高揚に努めるとともに、実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。
重点目標1 教職員の人権意識の高揚
重点目標2 教職員の研修の充実
重点目標3 家庭及び地域、関係機関・団体等とのネットワークの充実
①共生の心の育成…全ての子どもたちが、国籍や民族等の「違い」を認め合い、多様な文化的背景をもつ人々と豊かに共生する心、共に生きようとする意欲や態度を育むため、子ども・多文化共生センターなどの機関と連携し、異なる文化、民族、宗教、生活習慣、価値観に対する理解を図る。
②自己実現に向けた支援…全外国人幼児児童生徒等のアイデンティティの確立を図るため、子ども多文化共生サポーターや地域の人材等を活用し、母国の文化や言語、民族の歴史等の学習機会を充実する。また、進路など将来を見据えて、体系的・継続的な指導・支援を実施する。
③母語による支援の充実…学校生活への早期適応を促進するための心の安定や生活適応、学習支援が円滑にできるよう、子ども多文化共生サポーター等の母語支援員や多言語翻訳機・アプリケーション等のICTを活用し、外国人児童生徒等のコミュニケーションを図る。
④日本語指導の促進…日本語の習得や基礎学力の定着を図るため、各教科の指導等について児童生徒一人一人に応じて「特別の教育課程」を編成するなど、きめ細かな指導を行う。また、外国人児童生徒等の自己実現を支援するため、日本語指導が必要な外国人児童生徒等が在籍する学校間をオンラインでつなぎ、交流や学びの機会の充実を図る。
⑤帰国幼児児童生徒への支援 全帰国幼児児童生徒の円滑な就園・就学を図るため、家庭や地域と連携して、海外で培った特性を伸長するよう努めるとともに、温かく迎えられ、互いに理解し尊重し合えるよう配慮する
大切な「教育」の機会・場ですから、しっかりと目的を持って受け入れたいと思います。
☆317目(6/5)地域と共にある学校とは?
6/1のカキフェスに多くの生徒らが参加しました。変な言い方ですが、地域ボランティア活動を通して、その活動を「越える」営みにしていきたいと思っています。昨年度末に市の櫂の木賞応募時にまとめた文章を添付します。

☆316目(6/4)個人に返す、仲間の前で返す?
6/1に開催された、今年2回目のカキフェスには、本校からたくさんの生徒がボランティアとして参加することとなりした。参加日前までに、提出した申し込み用紙内容を確認し、生徒(保護者)へ返却しましたが、個人に返す(集配BOXに入れておく)のではなく、クラスの仲間の前で紹介し、エールも併せて、申し込み用紙を返却する場面をつくると、仲間を知り、仲間を認め合う大切な時間になるのではないかあと思います。本校の担任も、そんな小さな仲間づくりの時間の大事にしています。
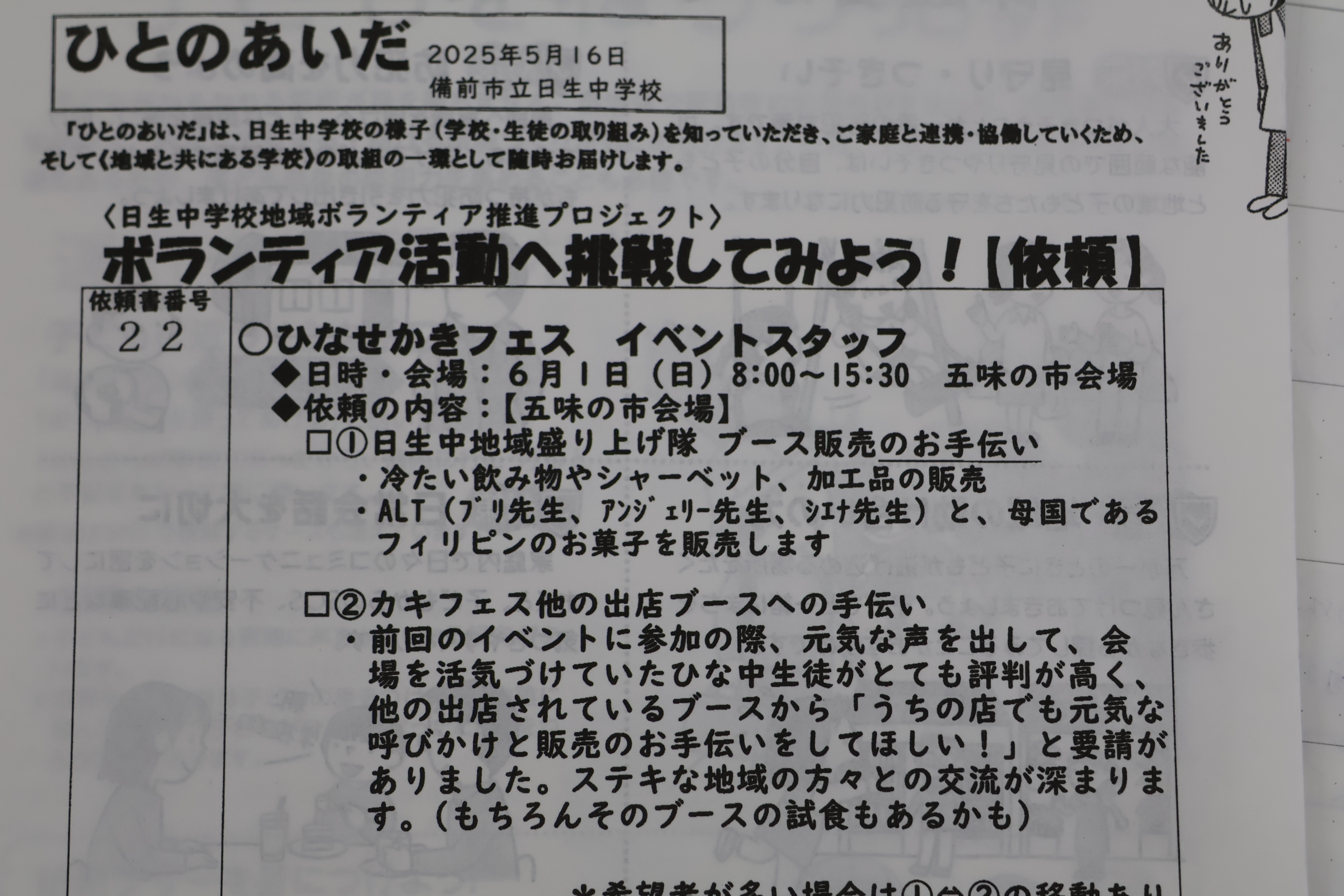
☆315日目(6/3)多文化共生社会へ、食文化を通して
6/1(日)のカキフェスにALTの先生方とブースで、母国フィリピンのお菓子を販売してきま~す。

☆314日目(6/2)多様な研修の機会を。
5/31(土)は「一次教研」が開催されました。「教研」を検索してみたら、〈教職員組合が他の労働組合と大きく異なる点として教育研究活動(通称、教研)が挙げられます。目の前の子どもの実態を出発点として「平和を守り、真実を貫く民主教育の確立」「わかる授業、楽しい学校」をめざして、全国の教職員と議論し、その成果を自らの日々の教育実践に生かす教研活動は世界的にも高く評価されています。この「子ども中心」の考え方は、組合活動全体にも見られ、少人数学級の推進を訴えていることも、子どもたちや学校を競争に駆り立てる全国学力・学習状況調査に反対していることも、子どもたちにゆとりあるゆたかな教育を実現したいという願いがあるからに他なりません。〉という文書がありました。私は、一推進委員としての参加でしたが、やっぱり、教職員がそれぞれの日々の「教育実践」と「思いや願い」を持ち寄り、お互いに「語り合う」ことを、これからも大切にしたいと思います。研修のイメージが教育センターでの研修や校内研修だけになっては、進歩がありません。東備地域での研修の機会としている「東備学ぶ会」や、「藤野会館学習講座」なども大事に活用しながら、教職員としての子ども観、授業観などを磨いていきたいと思います。
☆313日目(5/30)映画「あつい壁」って知っていますか?
西宮の知り合いから映画「あつい壁」(中山節夫監督)上映会のお知らせを頂きました。これまで何度も観る機会を逸していました。日程調整して参加しようと思います。
人権課題にかかわる映画は他にももたくさんありますね。、1948年につくられた「破戒」(木下恵介監督・池部良・高峯秀子さんが出演)はYouTubeで視聴できたのはびっくりしました。「破戒」は、2022年に間宮祥太朗さん・石井杏奈さんが出演で再映画化されています。2つの映画を見比べて観ると考えることもとても深くなります。もちろん、考えたことをじっくりと語り合う時間も持ちたいです。
☆312日目(5/29)人権教育と道徳教育の違いを確認しつつ。
修先日、人権教育担当者の研修に参加した際、報告の中で『人権教育(道徳教育)』という記述がありました。私たちは「違い」を明確にしながら、取り組まんといけんよなあと、小グループの中で話をしました。(研修会で、小グループでの話し合いを取り入れることが増えましたが、それに伴い、参加者全体で「一つ」のことを協議していく研修スタイルの会が減りました。みんなで一体感や共有感を味わうことはみはや過去の話?そんな会を作り出すファシリテーション技法を高めんたいな。)←それは置いといて、「違い」について
人権教育と道徳教育の関連
☆311日目(5/28)修学旅行を生徒主体な取組として。
修学旅行実行委員が旅行日程の中でどれだけ自主的に動くのか?を組み立てたいなあと思います。一見教員がしていることも、加納なら「これは子どもたちに任せたり、委ねたりできるのでは」という視点や、主体的な行動ができる学年集団づくり進めたい。以下の内容は、引率教員の仕事?添乗員さんの仕事?、子どもたちが動ける? □点呼 □航空券の配布 □お弁当・お茶配り □廊下の見守り □部屋の点検 □実行委員によるモーニングコール □注意事項や留意点
☆310日目(5/27)聴き取り?? 6/15の日
近くのスーパーに置いてありました。親と子の笑顔での会話が想像できたりしませんか。「聴き取り」学習は、余計なお節介の面もあるかも。でもそんな「つながる」取組をコーディネートすることが学校では大切だわ。
☆309日目(5/26)人との出会いを紡ぐ
304日目に記したが、家庭科でやはり修学旅行で「聴き取り」を課題にしている。3年生は保育分野を学習してるので、民泊先の方々に、「小さい頃の遊びや、食事、行事」と合わせ、「親の願いはどんなものだったのか?」を聴く。岡山と自然も文化も違い、しかも80年前に地上戦が行われた地である。子どもの頃の記憶や生い立ちから、戦争の実相を知り、ぐぐっと自分の身に近づけてくる子どもたちもいるだろう。
また、修学旅行の民泊先に、子どもたちは日生、岡山の観光パンフレットを持って行く。その取組についても日生観光協会の方が修学旅行の出発前日に来校されエールを贈ってくださる。さらに平和集会で歌う「島唄」の歌唱ワークショップで妹尾さんが来校される。多くの人々に支えていただき、修学旅行の内実が深まっていくように思える。帰校後の沖縄での学びのまとめが楽しみだなあ。
☆308日目(5/23)発達特性への支援
少し前(2023)に、関西地方の福祉関係の仕事をしている友人Sと、「学校の生活指導はもっと、「発達特性」の視点を大事にして、積極的に進めなければならないのでないか?」と責められたことがありました。専門機関や医療機関などと連携しながら、学校の支援体制を充実させることは、今とても重要になっています。その時に友人Sと交わしたメモを読み直しています。
☆307日目(5/22)「仲間と共に」の姿を、人権教育から拓く
土田光子さんをお招きしての校内研修会の案内ができました。限られた時間での講演(学習会)ですが、集って、聴いて、考えて、語って学び合いたいと思います。
☆306日目(5/21)ハンセン病問題学習を
山陽新聞(5・20)の記事を紹介します。
☆305日目(5/20)水平社宣言から学ぶ
社会科では、視聴覚教材も使って、深い学びにしていこうと授業研究を進めています。人権課題とのステキな出会いをどう紡ぐか。


☆304日目(5/19)民泊での学びをさらに深く
縁あって、家庭科の授業を一緒に検討する機会があり、昨年度の3年生が学習した内容を調べていると、「民泊先の方々に聞こう」というワークシートがあり、いいなあ!と思った。修学旅行の民泊は、よく考えてみれば民泊先の方々に丸投げ感が強いような気もする。岡山と異なる豊かな文化、風土をもつオキナワに生きてきた人々に直接話を聞ける貴重な機会と考えたら、多様な学習が考えられる。家庭科でのワークシートには、「子どものころの遊びや風土、季節の衣服や食文化」をそれぞれ聴き取らせてもらう欄があった。また、社会科や総合的な学習や課題探求学習として、オキナワ戦についてや戦後の沖縄復興や基地問題についての生の声を聴くことが可能だ。さらに、岡山や日生を紹介した自作パンフレットを持って行ったり、地元の観光協会から委ねられた観光パンフレットを渡すこともおもしろい。(そういえば、インターネットの性能がまだまだだった頃、「うちかび」とは言わず、それを生徒一人ひとりに配り、「どんな方法でもよいから調べて、社会科POINTを手に入れよう」と指示し、たくさんの生徒が、話題のひとつとして民泊先の方々に聞いて、社会科ポイントをゲットしていたことを思い出した。*ちなみに現在は、「黄色の紙 沖縄」だけで検索すると「うちかび」にヒットするので、沖縄で聞くまでもないことになってしまった)
人とひとがつながるしかけを、行程の中に入れこんでいくことができると、さらに「修学」旅行での学びは深くなる。
☆303日目(5/16)復習の小テストでもつながる
毎日の社会科授業での振り返り(復習)で使う小確認テストも、ちっちゃな「つながり」をつくることが出来るのではないかな。
☆302日目(5/15)参加している研修会はいくつある?
新年度になって最初の東備学ぶ会を5/10に開催しました。参加者がそれぞれ勤める学校でのクラス開き・授業開き、保護者との連携などについての具体的な報告をもとに、自分の実践を深く振り返ることができました。また、話題になったひとつに、〈研修会〉があります。それは、「自分は、研修や学習する機会をどれだけ持てているか?」です。若いN先生の「教育センターでの研修と校内研修しかないかも(東備学ぶ会に参加されてますが)」の発言に少しびっくりしたのととても残念に思いました。他の参加者の方々からは、この東備学ぶ会意外にも、岡山学び工房(学びの協同体についての学習会)、県教組夏季自主編成講座、渋染一揆現地研修会、教育運動推進センターの同和教育部会、金泰九さんに学ぶ教育実践交流会(今年度は11/22(土))、岡山県人権教育研究大会(今年度は8/7(木))や第一次教育研究集会(5/31(土))など、今も大事な研修(学習の)場にしていることが挙げらましたが、学校以外の研修会になかなか参加できてなく、また、「中・小教研の活動も「研修のさせられている」感をもったり、「報告や発表が目的化しているのではないか」という意見もでました。さらに、「学校現場は、自分から動かず、口を開けてエサを待っているひな鳥のような状況になっていないか?」との厳しい指摘もありました。
自らの足で、豊かで、確かな「学び」を手にいれないといけないなあと自省します。基本的に土曜の午後に開催する「東備学ぶ会」も、参加した方が「来てよかった~。明日からまたガンバロウと思う」時間になる内容をこれからも創っていきたいと思っています。
☆301日目(5/14)研修会の学びを深めたいなあ
以前にも記した内容と重なりますが、やっぱり最近の教職員の研修に参加すると、講義や視聴後に「近くの方、グループで感想をお話しください」という時間を取っている場合が多いなあと感じます。2000年頃に参加型の学習スタイルが導入され、講義形式の一方的でなく、双方向性を意識した研修会が増えました。自分の感想を話し、グループの方の意見を聴かせていただけるので、そのような相互に学び合う時間は自分にとってとても貴重です。しかし、研修でとり扱う人権課題の内容によっては、やはり、全体会で「質疑」「討議」「意見交流」「総括」「まとめ」などが必要な場合が多いと思います。
先日、人権啓発DVD『人権のすすめⅡ」を視聴した研修会も、全体会での意見共有ができたらよかったなあと思いました。と書きながら、自分がファシリテータとして全体会を進行することになると、なかなか不安もあり難しいなあと思いますが、「マイクロアグレッション」や「心理的安全性」などの新しい人権に関するキーワードを「知る」ことで終わらずに、人権意識や実践力を「深める」ための「全体会の」ファシリテートに少しずつ挑戦したいと思います。
☆300日目(5/13)ふれる?さわらない情報?
生徒との何気ない会話(情報)の中には、結構、家族や家庭のリアルな出来事が多い。時に、家庭での大きな出来事をさらっと(本当はそうでないけど)話すことがある。その話した内容(事案)は、〈聴いて、子どもと共有する〉だけでよいのか?、もしくは、〈本人のhelpとして受けとめ、きちんと還していく(または保護者と共有していく)」のか?と思考することはとても大切だと思う。子どもが話した内容は、虚と実(+無意識の思いなど)も含めて混沌としている場合もあるので、そんな時は、聴いた教員が一人で思考し、判断することは悩ましい。だから、仲間や学年団の教員から助言やアドバイスをもらったり、ケース会を持って共有することは必須だ。
聴いた(話の)内容が、ネグレクトや虐待、ヤングケアラーにつながる事案や、家庭や家族との学校連携の強化や、また、福祉や行政の支援につなげるきっかけにもなるかもしれない。「子どもの声」に誠実に「応えたい」と思う。
☆299日目(5/12)子どもの現実からスタート
週一回を基本に開催する生活指導委員会での報告がありました。それは道徳の授業で、「自分が入っているLineグループで、自分の仲の良い友達への誹謗があったらどうするか?」の発問に、予想していなかった発言があり、さらに多くの生徒が同じような意見を持っていことにとても驚いたということ。昨今、たくさんのスマホやケータイの危険性や付き合い方を学ぶ資料やプログラムは作られ、小・中学校で、継続的にそして繰り返し、学習に取り組んでいますが、「子どもたちの発言、〈思っている(思わされている)こと〉=現実」を見据えて、指導や支援、学習を展開していかないといけないなあと、再確認することができました。追記:生活指導委員会で、授業での子どもたちの様子(個人の名が出て)の報告をしてくれ、また、それを受けて、多面的な視野で支援、指導について協議できるメンバー(組織)はステキだなあと思っています。
☆298日目(5/9)「ありがとう」を書く
校外研修から帰った子どもたちは、それぞれ「ふりかえり」をしています。その「ふりかえり」に活用するワークシートに、「ありがとう」を書く枠(項目)があれば、その視点で研修を深く振り返ることができますね。また、クラスメートの何気ないひとことややさしさ、具体的な、(のぞましい)言動を、学級通信で共有することも大切ですね。
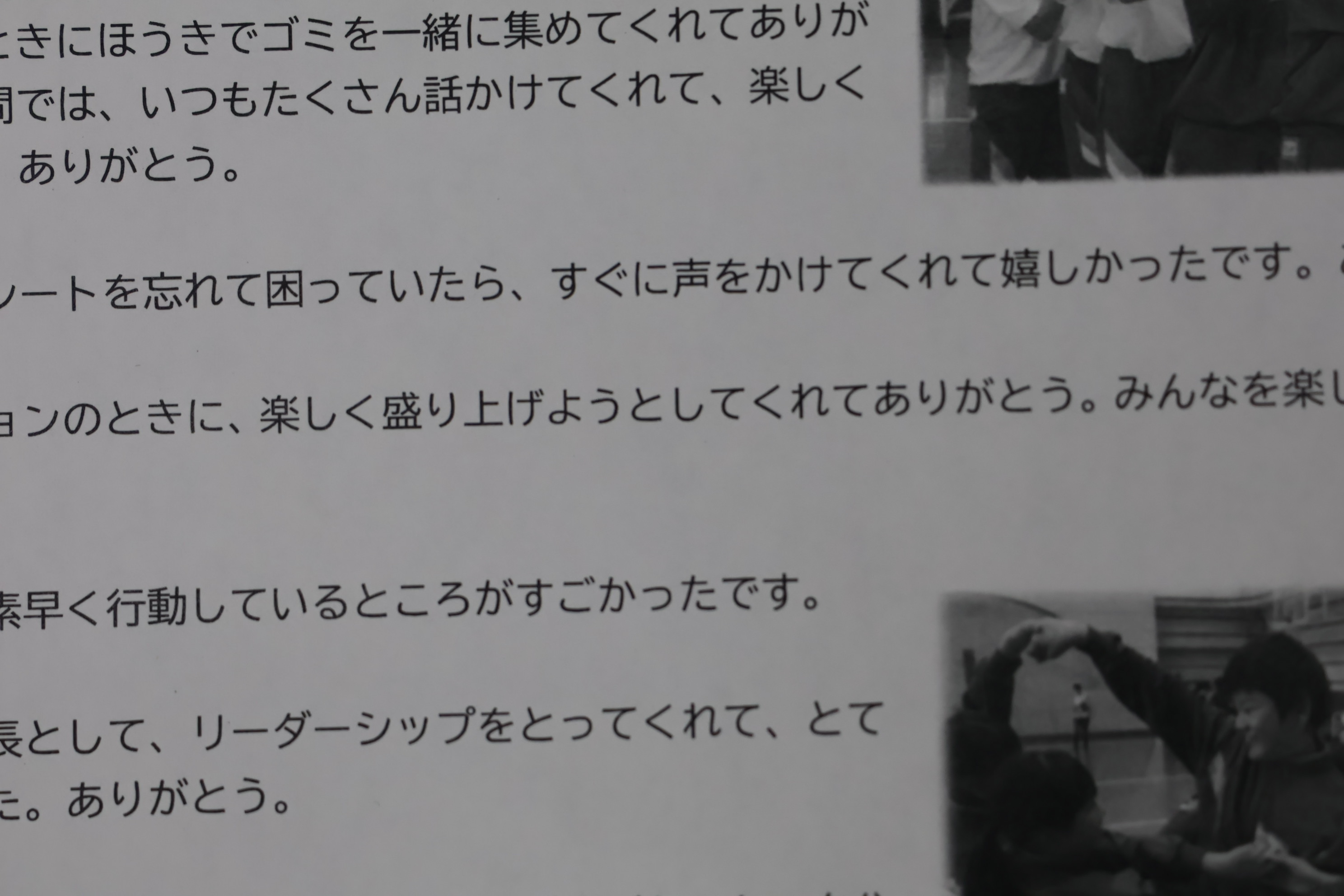
☆297日目(5/8)調整中ですが
『授業規律とは、一人ひとりが大切にされ、気にかけられているという信頼や、わからないことは支援の対象になっても、決して笑われることではないという安心と協働の文化を育む日々の学級経営を前提として、さらに授業そのものの工夫によって、結果として生まれるものであって、決してルールやしつけだけで成立するものではない。』と語られる土田さん。
本校の教育目標〈夢に向かって仲間とともに生きる生徒育成〉に向けて〈仲間ともに〉を、どのように進めていくか?~人権教育の視座から創る授業創造、学級・学校づくり~(仮題)をテーマに土田光子さんをお招きして講演学習会(校内研修会)〈6/23(月)14:50~〉を開催します。関心のある教職員の方々もご参加可能です。後日、ご案内させていただきます。
講師:土田 光子さん:1977年より中学校国語教諭として35年間教壇に立ち、子どもたちが教室で見せる事実の背景には一人ひとりが抱える生活があるという原則を大切に生活丸ごとでつながる集団づくりに取り組み続けてきました。2012年度より、9年間大阪教育大学で非常勤講師をされ、2021年より、大阪多様性教育ネットワーク共同代表をされています。著書に『私を創ったもの(明治図書)』、『格差をこえる学校づくり(大阪大学出版会)』、『子どもを見る眼』があります。
☆296日目(5/7) 春15(いちご)の会もあるよ
特別支援教育のニーズのある子どもたちのための進路情報交流学習会(春15の会)の実行委員会をおこないました。今年度も多様な進学先の情報をYouTube配信、また8月23日(土)12:30から、対面式での学校説明及び個別相談会を開催(会場:備前市立日生中学校)する予定です。準備をこれから進めていきます。春15の会のこれまで

☆295日目(5/2)学級活動通信に生徒名を載せる?
通信に子どもたちの名前を載せる?が話題になりました。
子どもたちが綴った学習のふりかえり・作文を学級通信に紹介し、学んだことをさらに深めたり共有していく取り組みはこれまでも大切にされてきました。私も通信で生徒の感想を載せる場合は、もちろん本人(保護者)に事前の承諾を得るのは前提として、自分の表明した内容(作文)には、誇りと自覚を持つべきとの考えから、表明する(生徒自身で決める)ことを基本としていました。(匿名性のデメリットを考える上でも。*ちなみに無記名で作文させる必要や価値がある場合もあることも最近では理解しつつ… 匿名と無記名は違いますね 匿名で書く内容と、無記名で記載することも意味が違うような?よくわからなくなってきました。)
実際には、名前を記載して紹介することを基盤として、時には内容に合わせて、生徒名を記入せず、口頭で紹介する場合もありました。でも、この、子どもの手を通して保護者に渡る通信の目的のひとつは、学校で子どもがどんなことを学び、子どもと一緒にいるクラスメートらとどんなことを考えたのか、を知ってもらえたらいいなあと考えていました。「学校を開く」ことの具現化というと、おおげさですが、学校・担任の大切な仕事だと思います。さらに、通信は、学級経営、学級活動の学習教材として考えているので、紙媒体のみの発行で、HP(デジタル化)等に紹介する(残す)必要はないと考えていました。
さて、通信のこれからを考えるに、参考に以下の文章を紹介します。…
個人情報保護法では,個人情報は「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」(個人情報保護法第2条第一号など)と定義されています。個人情報に該当するか否かは状況によって相対的に判断されます。そのため,掲載されたものが作文の一部であり,さらに名前が伏せられていたとしても,同じクラスの児童生徒や保護者には,誰の作文であるかが識別できる場合,個人情報に該当する可能性があります。作文が個人情報に該当するならば,原則として本人及び保護者の同意を得なければ学級通信に掲載することはできません。しかし,誰が書いた作文か識別できるかどうかは作文の内容に左右されるため,教員の判断だけでは難しい場合もあります。また,作文には児童生徒のプライベートな情報が記載されている場合があります。仮に,そこに児童生徒にとって他人(担任教員以外)に知られたくない情報が含まれていた場合,プライバシーの侵害に該当する可能性もあります。したがって,作文の一部でも学級通信に掲載するには,たとえ名前を伏せるとしても,個人情報やプライバシーの侵害に該当しないかどうかを慎重に判断する必要があるのです。
作文を学級通信に掲載することは,著作権の関係からも問題があります。作文も著作物である以上,児童生徒には著作者として公表するかしないかを自由に判断できる権利があります(著作者人格権としての公表権・著作権法第18 条)。そのため,著作者である児童生徒の同意なく作文を掲載することは,著作権法に違反する可能性があります。なお,著作権法第35 条第1項により,教員は授業の過程において著作物を著作権者の許諾なく複製することができますが,これは「公表された著作物」が対象なので,公表されていない児童生徒の作文は対象外であることに注意しなければなりません。
では,個人情報保護及び著作権の観点から,事前に児童生徒及び保護者の同意を得ておくには,どのような方法があるでしょうか。実務上は,入学直後や学年の開始時期などに,作文などを学級通信で掲載することにつき反対である児童生徒や保護者に対しては,あらかじめ同意しない旨の書面を提出してもらうことが行われています。学校の教育活動で個別の案件ごとに個人情報や著作権に関する同意を得るのは非常な手間であることを考えると,包括的な同意ないし不同意を得ておくことで対処する方法も違法とは言えないでしょう。(注*本校でも新年度に文書を配布・依頼しています)
しかし,たとえ保護者から包括的な同意を得ていたとしても,児童生徒本人が作文の掲載を希望しない場合にあえて掲載することは,子供の権利の観点から不適切と言えます。したがって,作文の場合は保護者から同意を得ていても児童生徒本人に掲載してもいいかどうかを確認する必要があります。一方,保護者から包括的な同意は得られていないが,児童生徒本人は掲載を希望する場合は,保護者と協議の上で掲載するとよいでしょう。(著・監修/神内 聡さんのHPより一部を紹介させていただきました)

☆294日目(5/1)閑谷の地で何をする?
郊外研修に出発する直前に、これからのスケジュールについては、「研修のしおり」の中に書いてあることを念押しし、「見て」「考えて」「行動」することを確認して学校を出ました。「生徒自身が考え・行動することを目的」としながらも、研修先に集まった時に、教員が再度、不必要に持ち物や注意事項をしゃべり、行程を語つたりすることが多かったなあ」と自らの実践を反省しました。自らしおりを見て、仲間に聴き、行動する姿はさすがでした。さらに、午後からのプレールームでの〈なかまづくり〉レク大会。笑顔と笑いと称賛に包まれた2時間半。ルールを守ることの中での楽しみの共有、仲間意識の高揚、また、ブーイングなど表現に対する適切なアドバイスがありましたね。学校に帰ってからの学びとしての「振り返り」が大切ですね。
子曰、学而不思則罔、思而不学則殆。子曰く、学びて思わざれば則ち罔し(くらし)、思いて学ばざれば則ち殆し(あやうし)

☆293日目(4/30)東備の先生たちと学び合う時間は
5月スタートします。
☆292日目(4/28)東備の先生たちと学び合う時間
自主的な学習会をしています。
☆291日目(4/25)教員が語るコトバ。
この時期、クラスでの新しい班づくりのために、班長さんらと担任は放課後、よりよい学級のために協議を重ねていることも多いかな。案が完成したら、学級活動資料に班長のひとりが書いてきて、次の日の朝、担任に印刷してもらい、6人の班長とともに、みんなのまえに立ち、班長としてのねがいや思いを語り、話し合いでの苦労したことを伝え、班案を提案・協議する。もしかすると却下されるかもしれない(ことも想定)。教員が説明したり、語らない班会議をめざしたい。すぐにはそんな生徒集団にはならないのはあたりまえだが、自主、自立、自律などの目標があるクラスや学校ならば、これこそ具現化しないといけないなあ。
☆290日目(4/24)教員が語るコトバ。
他県の友人Kとの会話。久しぶりに1年団の担当になったKさんは、うれしそうに「一生けん命に聴こうとする子どもたちを前にして、注意や小言、ましてや連絡ばっかりしてはいけんなあと。教員が発するコトバをもっともっと、磨きたいなあ。同時に、自分が「しゃべってしまう」内容を、子どもに委ねたり、子どもたちが語りあう時間をつくりたい」と熱く語った。朝夕の会のプログラムの紹介や生徒連絡票などの活用についてもお互いに実践について話しながら、長い長い長い電話を切った。
☆289日目(4/23)やっぱり、話しをしたら…
給食でのアレルギー相談などで来校された保護者が、相談が終わって帰られるときに、養護の先生は「〇〇さんが帰られます」と、私にも声をかけてくれます。それを受けて私は、保護者に声をかけて、学校での子どもさんのがんばっている様子を伝えたり、卒業したお姉ちゃんや兄ちゃんの話を聴いたり、たわいのない話をしながら玄関まで送っていきます。学校ではわからない、家庭での子どもの姿を教えてもらえたり、様々な家庭のようすを知ることができます。大事にしたいなあと思います。養護の先生との連携?と言うと変ですが、大切にした協働的な取り組みだと思うのです。
☆288日目(4/22)ここに書いてある内容って人権教育なの?
と、いう素朴な質問をうけました。「第4次岡山県人権教育推進プラン」を読んだらやっぱり、人権教育は教育活動のすべての基盤となる営みだと思います。前掲した内容ですが、あらためて、同和教育が育んできた人権教育について少しだけ確認します。同和教育」という名称が、「人権教育」と置き換えられ月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを、人権教育の取り組みの原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)などのかたちで問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ねて、今もその実践は多岐にわたる分野で生かされています。特に、確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教員・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、今日の教育課題を≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。また、同和教育で積み上げてきた豊かな教育内容と実践は、国際的な人権教育で提起されてきた内容と完全に一致していると確信をもっています。学年を中心に取り組む人権問題学習から日々のクラスでの出来事まで、どれも人権教育の視座に立つことができているか?を検証し、大切にしていきたいですね。
第4次岡山県人権教育推進プランから、
(3)人権教育の三つの視点
【視点1】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成 人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解と認識を深めるとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを共感的に受けとめるような感性や感覚を 育成する取組を進めます。 人権に関する知的理解を深めることと人権感覚を身に付けることによって、自分の人権と共に他の 人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度につながり、さらにそれらが、様々な場面や状況下で、問 題状況を変えていこうとする実践行動となって現れるようになることが大切です。
【視点2】自立支援 一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要とする人の自立支援に 取り組みます。 差別や人権侵害によって、個人のかけがえのない可能性が制約されている状況があれば、そのこと に自分自身が気付き、本来持っている個性や能力を伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、 それらの力を発揮して行動していくことができるように支援していくことが大切です。
【視点3】人権を尊重する環境づくり 視点1及び2の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような学校園や地域の雰囲 気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みます。 人権教育が効果を上げるためには、人間関係や全体的な雰囲気等も含め、学校園や地域の教育・学 習の場に人権を尊重する環境をつくることが大切です。また、違いを認め合い、多様性を受容する社 会を目指して、自他の人権を尊重し差別を許さない社会的風土を培うことも大切です
☆287日目(4/21)自分を開き、仲間を知る授業
1年生の家庭科では、生徒一人ひとりが宿題として、自分の私服をひとつ持って来てました。授業で学んだ「TPO」をもとに、自分の衣服について発表し、互いに聴き合いました。さらに、これが自己紹介も兼ており、個性豊かな、お互いを分かり合う楽しい授業となりました。
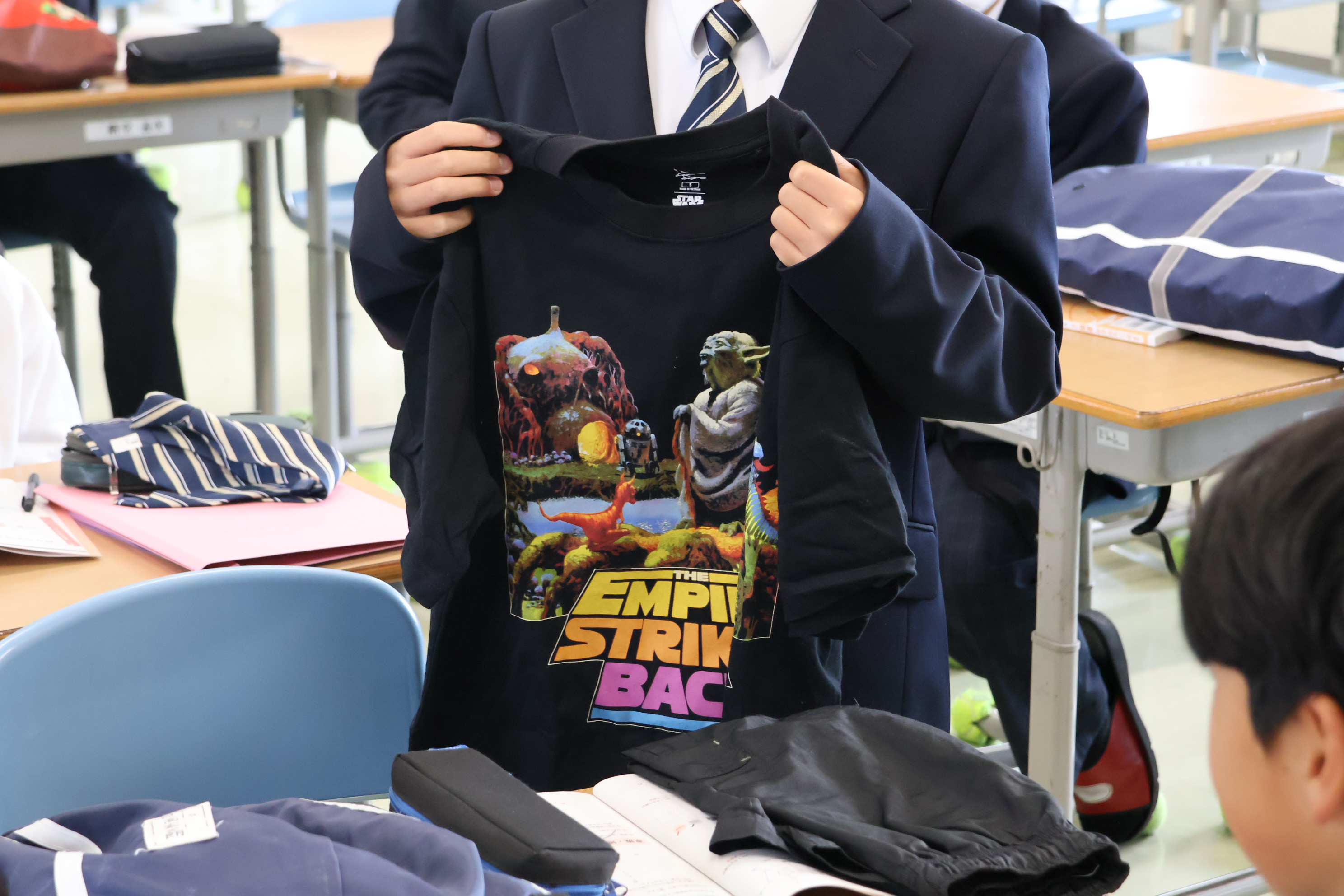
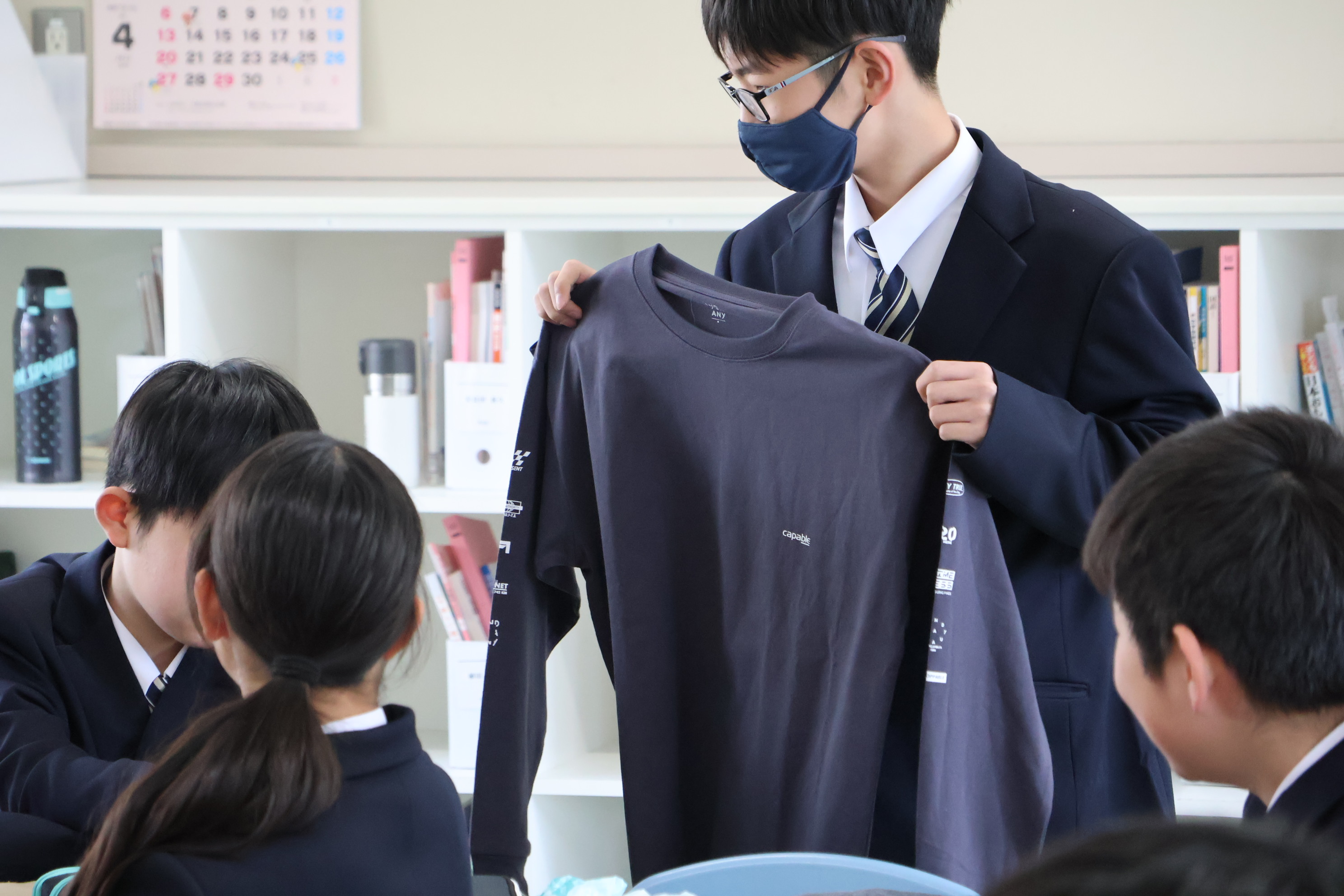

☆286日目(4/18)学級活動資料となかまづくり
学級役員の選出をする際に、学級通信を補助教材として作成している担任。時間も手間もかかるだろうけど、大切な時間にするための熱意が感じられ、「いいなあ」と思う。また、その学級通信は、家に持ち帰ることで、家族らと語るアイテムになることような願いも感じられて、さらに、「いいなあ」と思った。
そうだ!学級通信として発行するならめんどくさいいろいろな手続きがあるならば、学級活動資料として(もちろんロゴを入った学級活動資料)ワークシート形式にするのいいかもしれない。子どもたちは、新しく学級役員に決まった(決めた)仲間の名前を確認しながら記入して一覧表を完成させる。そして、その学級活動資料を家に持って帰るのだ。
担任がまとめた一覧表でなくてもよいかもね。記入する学級通信、いや学級活動資料の作成の発想はどうです?
☆285日目(4/17)入学式の準備・片付けから
新2・3年生諸君!入学式の会場準備では、とてもよく動いている姿がみえ、「さすが!すばらしい」と思いました。さて、会場準備ですが、もちろん、事前に、生徒のしごとの分担をしますが、これも、複数人であたり、子どもどうしで会話を交わしながら協力して取り組めるように進めていきます。そして、がんばった姿をカタチとして、ホームページで紹介する時には、協力しあう場面(二人で運ぶすのこ、みんなで整える白布机など)の写真が多いのはその性かしらん。

☆284日目(4/16)校外研修でOLしない?②
よりよい人間関係をつくるためには,「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる豊かな 人権感覚を育むことが特に重要です。 人権感覚は,言葉で説明するだけで身に付くものではな く,周囲の様々な人たちとの関わりの中で体験を通して育まれていくものです。子どもたちの人権感覚は,子ども自らが, 主体的に他の子どもたちとともに学習活動に参加し,協力的に活動し,体験することを通して身に付くと言えます。その 際,参加型の体験的学習が有効であることが指摘されています。 参加型学習は,子どもたちの主体的な活動とコミュニケーションを大切にし,単に知的理解にとどまらず,自分で「感じ, 考え,行動する」という主体的・実践的な学習です。参加型の体験学習は,「体験する」ことから始まり,「学んだことを日常生活に生かし」たり,「自らの変容につなげ」たりするところまで高める一連のサイクルで進めていくことが大切だと思います。 たくさんのあるアイスブレーキングやアクティビティの中から,人間関係づくりや人間関係の課題の解決につ ながることを意図し,〈自己肯定感の育成〉,〈友達との関係づくり〉,〈学級集団づくり〉の3つの観点で有効と考えられる活動を、限られた時間の中で取り組んでいきたいものです。
重ねて、「仲間づくり」の文言の前には、「反差別の仲間(づくり)」・「多文化共生の仲間(づくり)」などが、これまで取り組まれてきた人権(同和)教育の実践の中では掲げられていました。「どんな」仲間づくり(具体的な子どもたちの姿)に取り組むか?について、教職員みんなの認識を共有していきたいと思います。
☆283日目(4/15)校外研修でOLしない?
校外研修で定番のオリエンテーリングをせずに、体育館で「なかまづくり」の計画を進めている。何度もやっているOLを漫然と実施するのではなく、子どもたちの現状(持っている力や集団の課題(小学校からの引き継ぎ))を鑑み、学校を離れた立地条件を活かし、積極的に「仲間づくり」に挑むそうだ。大事なことですね。
以前からある「チームビルディング」、「何デジベル?校歌を歌う」「じゃんけん王」「誕生日チェーン」だけでなく、共同、協力、他者理解などの目的にした新しい、参加型体験学習、アイスブレーキング、ワークショップやアクティビティやコンテンツは、調べてみるとびっくりするほど他にもたくさんありますね。もちろん、どれをしてもよいわけでなく、「あー楽しかった」で終わらないように、「振り返り」をていねいに行おうや。事後(帰校後の取り組み)の学校生活につなげる見通しを持とう」と、一年団では確認をされていました。(続く)
☆282日目(4/14)お互いのくらし・生い立ちを知ることからの仲間づくり
家庭科で授業が楽しい!自分の一番最初の記憶をお互いに語ることからスタートして、幼い頃(乳幼児期・幼児期・児童期)の、「好きだったこと」、「嫌いだったこと」「楽しかったこと」などをクラスの仲間らと交流する授業展開。「なりたかったこと」で、〈どんぐり〉になりたかったと発表したり、日生の地でありながら、カキが苦手なクラスメートが結構多いこともお互いに知り得た。この授業をもとに、おうちの人(身近なひと)から、生まれた時の頃(前時の学習内容のつけたしと親の願いや思い)を聴き取り、クラスで発表するそうだ。思春期の子どもたちと親が向き合える大切な時間にもなるでしょうね。
☆281日目(4/11)出席簿
新入生のクラス出席簿について、新一年団の教員がアレコレと話している。「1番から(もちろん男女混合)、五十音順。もちろん支援級での授業を受ける生徒も含めて。(もちろん生徒・保護者の意向を聴いて)で印刷中でーす」「教員の都合や効率だけで名簿を分けたりしたらいけんな」と。
ステキな教職員集団です。この姿勢がみて子どもたちも育ちますよ。
☆280日目(4/10)写真の撮影隊形にならべ?!
新学期、郊外研修もあり、集団で写真を撮る機会やあります。撮影の隊形に、生徒は並ばされるのか?教員が並ばすのか?自主的に自分らで並ぶのか?って考えたことがありますか?校外研修や修学旅行先で、大きな声で教員が「並べ!」と叫んでいる学校を今でも観ることがあります。私は校外研修などでは、私自身が集合させることは少なく、実行委員が、クラスメートの前に立ち、集合場所や目的に応じてハンドサインを出して、①隊形、②隊形、写真隊形、バス隊形、「近くに寄るよ」隊形などなど、けっして大きな声を出さず(お互いが声をかけあって)に集まることができていました。
集団づくり、仲間づくり、学習集団づくり…それぞれどんな集団のイメージですかね。
☆279日目(4/9)深く、掲示・開示する
新学期・授業・クラスで、今年度の目標を考えて、ワークシートに、書かし掲示したり、発表させたりする機会も多いでしょう。そんな今、ちらっと寄ったクラスでは、単に「がんばる」と書かせるのではなく、自分の「がんばる」ことを、もう一度見つめさせ、具体的な目標や願いを綴る取り組みにしていました。すごいね。「書かせて、受けとる」ことは、生徒の自主性を尊重していることではありませんね。時には、ワークシートをつきかえし、「なぜそう思ったのか」「どうしてそれをがんばりたいのか?」「がんばるためには自分はどうしたいのか?」「クラスの仲間に願うことは何か?」など、深く思考する(自分をめくる)ことをきちんと促すことが大事だと思います。そして、そこで綴られた内容を級友らと開示し合う時間は、とても大きく変わるでしょうね。
☆278日目(4/8)学級づくりについて
桂 正孝さんが『いま「学級社会」をつくる意味』と題し、『部落解放838号(2023年5月号)』に書かれている小論をあらためて読んでいるところです。冒頭の部分を紹介します。
〈今日の公教育としての小中高校の学級担任教師の場合、教育実践の仕事の中心は、授業(教科指導) と学級づくり(生活指導)であるといえよう。本小論の表題に「学級づくり」に代えて「学級社会」づくりという用語を用いた意図は何か。いうまでもなく学級は、現代の学校制度にもとづいて編成される学校生活の単位集団であり、教師の指導によって真理や真実を追究し、子どもの個性的発達をめざす学習集団である。その際「学級社会」 づくりは、ホームルームという学級生活の場を中心に、教科指導と生活指導をとおして学習権保障を追究する教育実践の営為を意味している。いいかえれば、「学級社会」は、子どもたちが集団生活のなかで各自の学習体験をとおして「ものの見方・感じ方・考え方」を吟味しあい、民主主義のあり方を学ぶ場でもある。〉
新しく来られた家庭科の教員と相談して、学級社会を意識した、「聴き取り」「語り合うこと」「自己開示」などを通して、クラスの仲間たちと深く・確かに「分かり合あえるよう」な授業実践を考えています。
☆277日目(4/7)「わたしたちのしごと」について
先日、京都のお寺で、ある住職さんからお話を聴きました。
・・・檀家さんと一緒に食事をしていた時、対面に座られていたおばあさまから「とても、箸遣いがきれいじゃなあ」と言われたとのこと。「褒めていただきありがとうございます」、「きれいに遣えることを教えてくれた親に感謝しなさいね」とやりとりがあったそうな。その中で、自分がいま、「あたりまえのようにしていること」について、物心もつかない幼い頃ころに、親からていねいに、きちんと教えてもらっていたからこそなのだなあ。感謝したこともなかった、と振り返ることができたとのお話でした。
自分のことと重ねて・・・。毎日の、私たちの教職の仕事も、感謝されるものではないし、子どものへの指導や助言、声かけや取り組みがが、すぐに望んだ結果なるものではない。数値にそう簡単に表れない。しかしながら、子どもの現実から深く学びながら、「日々、日々」教え育てる営みを積み重ねていきたい(いくしかない)なあと思ったのでした。子どもたちの自己実現に向けて。今日から新学期!
☆276日目(4/3)〈みつめる・語る・知る〉ことで〈つながる〉子どもに
新学期の準備を学年団を中心に進めています。職員室では、わくわくする会話が職員室で聞こえます。「朝・夕の会で、子どもどうしが語り合う時間がもちたいね」「連絡票をつかって、ぼくたち(教員)が、しゃべることをできるだけ減らせんかな?教員は連絡係じゃないからね」「生活ノート(タブレット)をどう活用して、綴る?」、「綴った内容を、帰りの会で、学級通信(学級活動資料)にたくさん紹介したいなあ」「コロナ禍以降の、班のカタチでの給食時間のがんばろうか」「交通安全教室なんかも、一方的なレクチャースタイルの学習はやめて、双方向のやりとりで学ぶスタイルにしたいね」「掲示物をクラスのみんなでつくれないかなあ」などなど。今年度も、「仲間とともに」というキーワードに、教職員みんなで具現化(実践)していきます。
☆275日目(4/2)多文化共生社会のすてきな出会いを
ALTさんとともに、教室を整備中です。大切な学びの場所と機会、「人の出会い」と、「語り合う」ことを大切に新年度をスタートします。


☆274日目(4/1)当事者ぬきでことを決めない
山陽新聞(3/30)より『手足が不自由で電動車いすを使う香川県の公立中3 年の男子生徒(15)が、設備面などを理由に入学を断られた県内の私立高を腕試しで受験する際、交渉に当たった中学校長から「合格しても入学しない」との確約を求められていたことが30 日、分かった。生徒と保護者は約束の上で1月に受験し、合格通知を受け取った。 その後、公立高に合格した。文部科学省は改正障害者差別解消法に基づく対応指針で、正当な理由なく障害者だけに条件を付けるのは不当な差別に当たるとしており、保護者は中学校長の対応に不満を募らせている。中学校長は取材に「公立高の腕試しで受験することを私立高に示す意図があった。受験を認めてもらうためには致し方なかった」と話している。
文科省の指針は、障害者との対話を通じて相互理解を深め、対応策を検討することを求める。指針を知らなかった保護者は、私立高と直接対話する機会がないまま、中学校長の求めに応じて約束していた。指針を知らなかった保護者は、私立高こと直接対話する機会がないまま、中学校長の求めに応じて約束していた。「一方的に我慢を強いられ、中学校長からも『受けさせてもらえて良かったね』という雰囲気を感じた」と振り返る。』
この新聞記事を読みながら、福祉や人権など様々などの分野でも大切にされている、障害者権利条約の“私たちのことを私たち抜きで決めないで”(Nothing About us without us)というメッセージを思い出しました。新年度の学級開きをはじめるにあたって、大事なコトを再確認することができました。
また、もうひとつ。おそらく長年、「うでだめし」の入試、進路指導(進路保障でない!)がずっとあたりまえにように行われていたのかもしれませんね。「すべりどめ」の学校という言い方を久しく聞かなかったのだけど、学校観・進路観だけでなく、私たちの姿勢が問われているように感じました。
そうそう、転勤した方々は、新しい職場で「あれ?ここはどうなってるの?」と尋ねて、これまでの「あたりまえ」にある学校の取組などを見直す「風」を吹かすことが重要な役割かももしれません。追記、宝塚音楽学校の応募資格とされていた「容姿端麗」ということばは、今年度(2025年)の募集要項から削除されていました。
☆273日目(3.31)人権課題を取り上げること3
ハンセン病問題学習のこれからの参考に。
https://www.pref.okayama.jp/page/965554.html (3)中学校での授業実施例
☆272日目(3.28)人権課題を取り上げること2
地域により体制が整っていない状況もあるでしょうから、例えば、校区でなくても、差別をなくすために運動に粘り強く取り組んでこられた方々の思いや願い(歴史)を聴くことはどどうでしょう。問題なのは、地元が理解が難しいとか消極的だという理由で、フィールドワークや聴き取り学習、部落問題学習すべてをあきらめてしまうことではないでしょうか。多様な学び方やスタイル・新しい学習教材(視聴覚教材)が提起・製作されている中で、なかなか人権学習が進まないのは、もしかしたら、学校が地域との信頼関係がつくれていないからなのかもしれません。当事者の方々の「聲」から、自分たちの教育実践を問い直していきたいと思っています。
☆271日目(3.27)人権課題を取り上げること
身近にある人権課題を教材に
確かな人権感覚と実践・行動力を育むためには、身近にある部落差別や身近にある人権課題を教材化することが求められます。
部落問題学習は、ややもすると、自分の暮らしとは全く関係のない問題と感じられている例も多いようです。でも実際には、全国各地に被差別部落があります。また、政府の 2019 )年に行った意識調査(部落差別の実態に係る結果報告書) によれば、「部落差別」や「同和問題」ということばを聞いたことがある人は全国で77.7%、近畿・中国・四国地方では90%を越えます。ごく身近にある問題として部落問題学習をできるかどうかは、重要な要素だと思います。
教員が部落問題学習の実施をためらう理由の一つとして、「「どこに部落があるの?」などと子どもから尋ねられたときに答えられない」という意見があることも聞きます。これに対して、学校だけで学習を取り組もうすると、実施が進んでいかないのではないかと思うのです。学校だけでなく、部落問題に取り組んでいる仲間や、解放放運動に取り組んでいる地域の方々と協同で一緒に進めていく体制をつくれたらと思っています。子どもから「どこなん?」と質問がでたなら、「先生が知ってるから、先生と一緒に行ってみるか。クラス・友だちにも声かけてみんなで一緒にいこう」というのでよいではないかということです。そう返すことによって、質問した子どもの側もいろいろなことを考えることができます。友だちに声をかけてみて、どんな返答が返ってくるか。親に話したときに親はどう言うか。そういうことを通して自分自身の問題意識も振り返り、研ぎ澄ますことができるはずです。続く
☆270日目(3.26)今年度の授業をふりかえって
授業の中での仲間づくり
授業のなかでも仲間づくりは重要です。文部科学省も「主体的・対話的で深い学び」が大切なキーワードとなっています。そして、そのための一人学習、ペアでの学習、グループ学習(協同学習)、全体学習などを丁寧に組み合わせることの大切さもよく語られています。 (ちょっと追記:「グループで話してみて」「となりの人と相談して」と指示しても、その後の「見取り」がおろそかになり、対話的な学びが成立したかどうかを見届けようとする授業者の視座は必須です)
子ども同士の協同を育むうえで、同和教育が重視するのは、〈どのような子どもを中心に据えて〉授業を展開するのかという点です。社会的に不利な立場にある子ども、学習の面で困難をかかえている子ども、対人関係が得意ではない子どもなど、多面的な観点で〈弱い立場にある子どもたち〉に焦点を合わせて授業を組み立てるのです。このことは、その子たちを取りこぼさないようにするためだけではありません。主な目的は、その子たちのつまずきや問題意識をクラス全体で共有することによって、他の子どもたちの問題意識やスキルが高まるようになることです。
☆269日目(3.25)子ども観
ちょっと前、渋染一揆の現地研修についてきていた小学校2年生の子どもとあれこれ話をする機会があった。児童生徒と教員の関係ではないし、親戚関係でもない子どもの本当に、自由で、快活な言動、一挙手一投足は、とても新鮮だった。「集団づくり」においても、子どもたちをいかに見ていくかという「子ども観」や教師の 有り様は、取組内容とその効果に大きく影響する。大阪府松原市立布忍小学校 (以下「布忍小学校」)では、「良さの見えにくい子を学級集団の中心に据える」ことを実現する取組を大切にしている。 布忍小学校では、「集団づくり」を人と人がつながりをつくる「人間関係づくり」として だけではなく、人間のすばらしさや人間の痛みを共有できるつながりとして位置付け、「集団の質」を高めることをめざして、おもに5つの視点をキーワードにして取組を進めている。(1)子どもの「短所」や「できない」ところに目を向けるのではなく、一人ひとりの子どもの「良さ」を見付けようとする。 (2)教職員が、子どもから意識的・無意識的に発信される S0S の信号をキャッチし、「あれ? と感じたこと」を大切にする。 ③一人の教師が子どもを見るのではなく、一人ひとりの子どもをできるだけ大勢の教師 が見て、話し合うことで、多様な見方とらえ方を意識する。(4)「良さ」の見えにくい子どもを学級の中心に据え、その子どもの「良さ」とともに、 集団の「良さ」を伸ばそうとする。 (5)子ども同士の関係の中で、持ち物や特技等を武器として相手を迎合させる「ゆがんだ集団の関係」を見逃さないこと。 布忍小学校では、「いかに、子どもたち自身がつながろうとする(エンパワメントできる)仕掛けをするか」を課題と して位置付け、より質の高い集団づくりをめざしている。
☆268日目(3.24)コミュニケーション
岡本純子氏の講演会での要旨が山陽新聞に掲載されていました。要旨の要旨を紹介します《コミュニケーションは才能ではなくノウハウであり、誰でも上達する。その方法の一つは「相手が何を聞きたいか」・・・○人は自分が知りたい、聞きたい情報しか受け取らない。相手にとって価値ある情報とは、流行やニュースなどの聞き手が関心を持つこと○ 損得、困り事をはじめとする聞き手に関係のあること○聞き手の価値を認め、感謝や共感すること―の三つ。これらに自分が言いたいことを織り交ぜるとよい。2つめは「相手が何を感じるのか」・・・対話をしながら共感し、感情をかき立てる力がもとめられる。3つめは、「どのように言うのか」・・・コトバに体重と体温、思いや志を乗せることで印象は大きく変わる》とのこと。
一方的に自分の言いたいことをしゃべったり、自分の思い通りにするために相手を納得させたりすることがコミュニケーションではないことは誰もが承知していることだが、岡本さんが言われるように「対話しながら共感し」合う会話は、やはり意識しないと成立しないと思う。
「意識」といえば、先日も一生懸命に話さなければならない(変?)機会があった時に、「お互いの役職や先輩・後輩という関係、教員と生徒という関係性などは、コミュニケーションにどれくらい影響するのだろうか?」と思うことがあった。お互いの関係性を意識せねばならない時、関係性を利用する時、関係性をフラットで語り合い時などなど、そんな細かいことを計算したり、思考したりしてコミュニケーションを図ろうとすることは邪道なのであろうか?
ちなみにOpen Dialogueとは【「開かれた対話」を意味する。 この「対話」は、診察室で医師と患者が行う「会話」とは異なり、患者とその家族や友人、精神科医だけでなく臨床心理士や看護師といった関係者が1カ所に集まり、チームで繰り返し「対話」を重ねていくというものだ。】このオープンダイアローグは学校現場での「これから」をまさしく開いていくキーワードのひとつにしていきたいと思っている。
☆267日目(3.21)卒業式を終えて
本校の卒業式も無事終え、19日は市内小学校の卒業式でした。縁あって、小学校の卒業式の練習をみせていただく機会もあり、とても大事な行事だとあらためて感じました。さて、本校でも式に向けて、送辞・答辞や歌唱の指導に取り組みましたが、子どもたちの三年間の学びをもとに、「どのような式にしていくか?」をいつも考えます。前年度の内容を踏襲するべきこと(しないこと)、コロナ禍での見直しをした内容の再吟味、そして卒業を見据えたそれまでの教育活動のあり方にも言及しながら、今年度も、職員会議で協議することができました。代表答辞については、個人答辞の取り組みもあります(昨年度のタネを参照)が、少し意識したのは、祝辞と送辞と答辞がバラバラではなく、同じ内容のくりかえしではなく、つながっている、呼応しているイメージが持てたらいいなあと思っていました。そしてもうひとつは、本当にたくさんの取組を積み重ねてきた卒業生の「豊かな学び」が、在校生らに引き継がれていくように「コトバの精選」と、「表現」の練習に生徒会長は一生懸命取り組みました。本当に素晴らしいメッセージ(答辞)をありがとう。一部を記載します。
…「友」という歌はこんな言葉ではじまります。
友 今 君が見上げる空は どんな色に見えていますか
確かな答えなんて何一つ無い旅さ 心揺れて迷う時も
ためらう気持ち それでも 支えてくれる声が 気付けば いつもそばに
校長先生、来賓の方々、そして後輩たちのメッセージから、本当にいつでも 私たちのそばには
支えてくれる声が たくさんあったのだなあと感じています。
この佳き日、卒業を迎えた私たち三十八名のために、
このようにすばらしい卒業証書授与式を挙行してくださり、ありがとうございます。
また、ご多用の中、私たちのためにご臨席くださいました皆様、心より感謝申し上げます。
私たちは、たくさんの「学び」と「思い出」とともに、今日、日生中学校を旅立ちます。
三年前コロナ禍で、まだまだ何も先の見通せない中、私たちは、新しい生活への不安をかかえながらも、楽しみなことへの大きな期待をもって、中学校生活生活をスタートさせました。
一年生。閑谷研修では、講堂で息を合わせ大きな声で論語を読み、オリエンテーリングではグループごとでゴールを目指しました。そんな中で、個性豊かで楽しい仲間たちを知るともに、「クラスがひとつ」になることの難しさも学ぶことができました。
その後も、私たちは、「クラスがひとつになる」ことを大切にしてきました。
二年生に進級し、私たちは、自分のことだけはでなく、「生徒会のひとり」として、また、「後輩」のことも考えながら行動しなければならない難しさを知りました。
日生中学校には、これまで先輩たちも取り組んでこられた学習の機会がたくさんありました。
私たちはその一つひとつの学習に、一生懸命に取り組んでいくことが、先輩として、
新しい日生中学校の歴史を作っていくことになり、後輩たちに示すあるべき姿ではなかったか、と思います。
広島宿泊研修では、八十年前のできごとがあった地に立ちました。戦争の恐ろしさと悲惨さ、人々の生活の苦しさを再認識するだけでなく、「今ある日常」は当たり前ではないこと。先人の願いを受け継ぎ、平和を求め続けていくことを学びました。
職場体験や海洋学習は、私たちをさらに成長させてくれました。たくさんの方々との出会いの中で、「働くこと」の大変さ、大切さを学ぶとともに、ふるさと日生の素晴らしさと豊かさを確かめることができました。
そして、あっという間の三年生。
沖縄への修学旅行では、ひめゆりの塔、アブチラガマ洞窟を訪れ、日本唯一の地上戦があったことを学びました。また、民泊先の方々との、あたたかいふれあいは、どれも魅力的で、貴重な学習として、私たちの心に刻まれました。
総合的な学習の時間では、地域活性化プロジェクト「日生の応援団」と題し、地域の方たちの協力をいただき、「観光、福祉、お祭り、環境保全」などの分野について、それぞれ実践したことをまとめ、二年生や観光客に、自分たちの思いを伝えることができました。
三年生の僕たちにとって最後の星輝祭は、最高のものにしたいという思いで、前年度から計画を進めていきました。特に体育の部・星輝タイムでは、ダンスの振り付けや隊形を考える中、なかなかみんなの意見がまとまらず悩むこともたくさんありました。
しかし、「お互いが「できること」を探し出し、精一杯やろう!」と、みんなで協力して、前に、進んでいくことができました。
後輩からのメッセージの中にもありましたが、やはり、
「誰ひとり欠ける」ことなく、「全員でがんばる」ことは大事だと思います。僕たちはうまくアドバイスできたかどうかわかりませんが、それでもあきらめず、粘り強く、最後まで練習についてきてくれたおかげで、最高の体育の部になったと思っています。…
☆266日目(3.19)掲示物片づけた??③

そうそう、子どもたちと作っていました。
☆265日目(3.18)掲示物片づけた??②
『…実際に、私が持ち上がりで担任した2年生4月の学級開きの際には、教室に何も配置されておらず、壁には避難経路表示以外は何も貼っていない状態の教室からスタートした。のがらんとした教室をぐるりと見まわしながら、語った。
「見ての通り、教室の壁には何も貼っていませんし、何も置いていません。なぜでしょう?そう、この教室は、今日からあなたたちが過ごす新しい空間だからです。空いているところには何を貼りたいですか? 作品? 飾り? それとも何かのお知らせ? 今日から、自分たちの手でこの教室を作っていきましょう。」
こう宣言することによって、子どもたちが興味関心をもって見る掲示物が作られることになる。「見てもらえるかどうか」は掲示物にとって存在意義そのものである。係からの各種お知らせとしてのクイズ、学級子ども新聞や学級コンテストなど、これら自分たちで掲示したものに対しては、自分たちの手によって撤去したり更新したりといった責任が生じる。余白が埋まってくるにつれ、貼るスペースがなくなり、見てもらうための更新の必要が出るからである。
また余白は子どもたちの作った折り紙やイラストで飾りつけられ、それは掲示用の壁だけでは飽き足らず、天井や窓枠にまで広がり、これによりカラフルな教室が出来上がる。場合によっては、クラスや学年をまたいで見に来る。言うなれば「生きた掲示物」である。
こうなると、もっと見てもらいたい、楽しませたいという欲求が出て、自然と工夫を始める。 階段や靴箱といった場にも掲示したいと言い出す。創造性や主体性が、教室を飛び出るのである。 教室外の掲示になると、誰がいつまでに掲示してはがすかといった見通しや責任について学ぶ機会もできる。
冒頭の教師が作った掲示物に囲まれた教室では、教師の親切が裏目に出て、子どもの使えるスペースを先に潰してしまっている。これは教室の壁という物理的な余白を潰しているだけではなく、子どもの成長の可能性の余白を潰している行為ともいえる。
教室の壁に余白があれば、子どもたちは自然にそれを使おうと動き出す。その掲示物は教師の作ったものより美しく整ってはいないかもしれないし、教室は一見混沌として見えるかもしれないが、間違いなく子どもの成長が見える生き生きとしたものになっているはずである。』
☆264日目(3.17)掲示物片づけた??
『不親切教師のススメ』(松尾英明・著/さくら社)を紹介されました。実はパソコンで何もかも教員がやってしまう風潮もありますが、あらためて考えると大切なことです。
その中から少しだけ…『教師が作る美しく整った教主掲示:教室をぐるりと取り囲む色とりどりの掲示物。どれも美しく丁寧に書かれており、中には印刷されているものもある。よく見ると、全て学級担任が一生懸命に作ったものである。これまでの授業の学習の過程が書かれたものや、きれいに印刷された学級目標まで、担任の「いいクラスにしたい」という願いに対する努力の跡が見える。
だが残念ながら、これで「いいクラス」にしようというのは難しい。少なくとも、この美しく整然とした教室は、躍動感のある子ども文化を生み出せない仕組みになっている。教室の壁面や背面などの掲示場を、子どもたちが自分たちで創り上げていく場と捉えていないからである。美しくすること・伝えることには、教師のみ力が入り、肝心の子どもたちは、今何を伝えるべきか、 見てもらうにはどういう工夫をすべきかなどと、情報伝達に主体的に関わる力を育てる点が抜けてしまうのである。教室は子どもが最も長い時間過ごし、影響を受け続ける空間である。ここについて工夫の余地がないことの影響は大きい。学校の様々なことは全て教師によってお膳立てされて与えられるものであり、子どもは自分たちの過ごす環境について無力であるという無言のメッセージを与え続けることになる。つまり、大きな労力をかけて、マイナスにしかならない余計なお世話をしているのである。
掲示物に関して、教師は大いに不親切でよい。
子どものためを思って作るのかもしれないが、教師が作った掲示物というのは労力の割に実際に子どもは見ておらず、子どものためにもなっていないというのが現実である。
むしろ、教師のこのような「親切」を不要とし、自分たちの過ごす環境ぐらい自分たちで作らせてくれと言えるような主体性のある子どもを育てるのが理想である。
たとえ低学年でも、これはできる。むしろ低学年の早いうちからこそ、お世話される存在という誤認から脱却する必要がある。』続く
☆263日目(3.14)書を捨てまちにでよう
現地研修(フィールドワーク)から学ぶこと
渋染一揆やハンセン病問題学習でのフィールドワークのお手伝いをする機会をいただいていますが、先日、11月にご一緒させていただいた団体から、感想(振り返り)文が届きました。こちらこそありがとうございました。
・現地を自分の目で見て、自分で感じることができて、とてもよかったです。
・ハンセン病問題、差別のことなど考えさせられることばかりでした。新型コロナウイルス禍での対応もふり返れば、本当に適切だったのか?あらためて考えることができました。
・「自分の感情」も間違っていたのかなど考えました。ありがとうございました。
・「教員」として、「人として」の生き方を考える時間になりました。
・奥の奥の部分まで話していただけたと思います。ずっと学び続けていきたいです。
・初めて長島愛生園に来させていただきました。実際に目で見て空気を感じ、くわしくお話をきかせていただき、理解が深まりました。
・うつる病気の対応のしかたで、心が痛い瞬間がたくさんあり、考えること、ふりかえること、まわりの先輩や仲間と確認することを忘れないようにしたいと思います。
「正しく知って、正しく行動する」しっかり胸にとどめておきたいと思います。
(観光地の)ガイドでもなく、当事者でもなく、研究者でもない自分自身、いつも研修の地に赴く際には、身を正し、自分の立ち位置が問われているような気がします。歩いて・学び・考えて・語り合う学習スタイルを大事にしたいですね。
☆261日目(3.13)楽しく深く学ぶ場所はアルカ?
久しぶりに時間が合って、先週の金曜日、夕刻からの外川正明さんの学習会へ参加することができました。部落史学習というと、中世・近世の中の一部の出来事やとても専門的な分野かなあと思ってしまいそうですが、民衆の視座からの「日本の歴史」を見つめ直すと新たな発見や、深い学びがたくさんあり、あっという間に時間が過ぎてしまいす。この日のテーマは、「幕末維新と被差別民衆 DVD第4巻「明治維新と賤民廃止令」第1部を視聴」でした。参加された方の感想を紹介してしていただきましたが、読んで、まさしくその通りだと思います。以下。
〇〈目からうろこの話に巻き込まれました。世代も立場も違う人たちと学び合うのも新鮮です。歴史を動かしてきたのは、支配者だけではなくて、あらゆく人々の歴史を学ぶことが必要だと思いました。差別は差別する側の問題だということを伝えていきたい〉
〇〈人権教育を進めていく大きなヒントになっている。歴史を正しく知り、思いを知ることにより、本当に見方が変わってきます。だからこそ教員は、勉強して子どもたちの前に立つ必要があります。子どもたちに学んだことを伝え、地元に誇りを持ち、部落問題に立ち向かう一歩にならるようにがんばろうと思います。〉
新年度も予定されている学習会にぜひ行ってみようと思います。
☆260日目(3.12)家庭訪問の重要性(何度目??)
年度初めの家庭訪問がない学校も増えましたが、あらためて「家庭訪問の重要性」を本校でも再確認したいと思っています。また、「働き方改革」の課題やコロナ禍の残滓もあり、電話での連絡・対応が増えてきたりしているようにも感じます。しかし、電話や立ち話では見えてこなかったり、わからないこともたくさんあります。4月に行くのが家庭訪問ではありません。これまで勤務した学校で家庭訪問について確認しあったことは四つあります。
①生活指導上の課題も含め、保護者に伝える必要があるときに行く家庭訪問・・・「教育」は「今日行く」の原則を合言葉に。「今日行く」から指導になり、「明日行けば」言い訳になることもある
②子どもや保護者の気持ちや願いを聞き、先生の思いを伝え、信頼関係を築く家庭訪問
③子どもや保護者のくらしの現実をわかろうとするための家庭訪問
④出会った現実をもとに、教育活動として「生きる力」を獲得させることにつながる家庭訪問
このなかで、①や②については経験をしていただいたり、想像していただけるかと思いますが、人権教育を進めていくうえでは、③.④がとても大切になってきます。
☆259日目(3.11)「寄りそう」と「向き合う」②
続き〈・・・ぼくは焦っていた。「このまま通じ合えず卒業するのか」と。一方で、クラスの生徒たちは、進路H Rを深化させていた。「これからどんな生き方をするのか」「どの高校を選択するのか」などなど。時には授業を振り替えてでも話し合いが続けられていた。
「おれはいったい何をしてるんだ」「真摯に進路と向き合う生徒たちにどう応えたらいいのか」「Bにどう向き合えばいいのだ」。こんな思いに駆られて駆られていた卒業間近、ぼくはある行動に打って出ることに思いがいたった。それは、タバコを溶かした水を彼や生徒たちの前で飲み、自らの身体でタバコの害を彼に訴えようというものであった。
翌日の終わりの会で、ぼくは行動に出た。Bや生徒たちの面前でコップの水にタバコを溶かした。そのタバコ汁を飲もうとした矢先にBが飛び出してきて、「やめてくれ、オレもうタバコ吸わんから」と叫んだ。やっと、気持ちが通じた一瞬だった。そして、ぼくは子どもの「荒れ」に向き合うときの「本
気度」の重要性を悟ったのであった。
もちろん、これらの場面は、ぼくと彼、そしてクラスの生徒たちのあり様のなかで生み出されたものであり、だれが担任でも、どんな子どもにも、どのようなクラスの状況下でも実践できるというように一般化できるものではない。ぼく自身、それ以降もタバコを吸う生徒を何人も担任したが、同じ行動をとったというか、とれたことはなかった。そもそも学級づくりを含めて、教育実践とは、だれが、どの子を対象にしても、どのようなクラスでも同じようにできるとは限らないという性質のものである。だが、子どもたち、とりわけしんどい課題を背負わされている子どもの生活や思いに「向き合う」という姿勢は一般化できるし、学級担任ならだれにももってほしい教師としての基本姿勢だと思う。〉
・・・「子どもの現実」をもとに、「教育実践」を重ねていくことをやっぱり大事にしたい。そして自らの実践を真摯に振りかえり、教員として歩んでいかねばならないと思う。
☆258日目(3.10)受験事前指導
明日から県立一般入試となります。これまでも、私立・公立、すべての受験前日には、子どもたちへの指導をていねいに行ってきました。今日は、ここまでの長い道のりをがんばってきた子どもたちに、さいごのエールをおくる事前(指導)打ち合わせの会になります。
近年、県内の入試のしくみが大きく変わっていく中で、明日(3月11.12日)受験する生徒は大きく減ってきています。それに合わせて、これまでに内定合格を手に入れ、進路決定した生徒が増えました。そんな状況の変化の中で、進路先が決まった生徒から「打ち合わせの会に参加して、受験する仲間にエールを送りたい」と申し出があり、学年団で協議した結果、今日の打ち合わせの会に、受験生以外の子どもたち(有志)を参加させることとなりました。これまでのクラスづくりや仲間づくりの取り組みの延長にあるうごきではないかと思います。受験をともに乗り越える仲間、進路を切り拓く、頑張り合える仲間をやっぱり目指したいと思いました。
☆257日目(3.7)「寄りそう」と「向き合う」①
磯野雅治さんの「コロナ後の学級づくり再生に必要なこと(部落解放2023年5月号)」の『「寄りそう」から「向き合う」へ』の部分を少し紹介します。
〈…子どもと子どもをつなぐには、教師自身が担任として一人ひとりの子どもとつながることが欠かせない。というか子どもたちにその姿勢が視えなくては、子どもたちのなかに「みんなとつながろう」という意識は生まれがたい。なぜなら学級づくりは、 教師が高みから子どもたちに説くことではなく、教師と子ども、子どもと子どもとの生身のぶつかり合いのなかから生まれるものだからである。
これまでも担任が個々の子どもとつながるには、 「子どもをまるごと受け止める」「子どもの話を共感的に聴く」「子どもの言動の向こう側にあるものに思いを馳せる」ことが重要であり、ありのままの子どもに寄りそうことが大切だと思ってきた。しかし、最近それでは不十分ではないかと思うようになった。なぜなら寄りそうだけでは子どもとのかかわりが自分の学級づくり論や実践力の深化につながらないと思うようになったからだ。
ではいま、「寄りそう」ことからさらに何が必要なのか。それは、子どもの置かれている状況や思いに「向き合う」ということだと思う。そして、そこから自分の実践的課題を引き出すことだと思うようになった。
一九七六年、教師になって七年目、中学校三年生の担任をしたときのことである。クラスにBがいた。彼は、ブチ家出をして補導されたり、学校ではタバコを吸っては教師に見つかるということを繰り返していた。だが、ぼくの眼にはそう劣悪とも思えない生活環境のなかで、「なぜ彼が荒れるのか」という、彼の行動の向こう側にある思いが視えなかった。だからであろう、彼が喫煙を見つかり、ぼくが 「説教」をするということが何度となく繰り返されたが、当然、ぼくの話が彼の心を揺さぶるはずもなく、彼が変わることもないまま三学期を迎えることとなった・・・〉続ける
☆256日目(3.6)なかまづくりとは何か?
電子黒板の利活用の校内研修を予定している今日、「なかまづくり」の三つの視点について記します。
【視点】
(1)「教育的に不利な環境のもとにくらしている」子どもの姿が、取り組みの課題や成果を象徴的に現していること→このクラスが楽しいかを誰に聞くのか
(2)それぞれの子どもに個性があり、くらしがあり、様々な悩みももって生活していることをわかりあった上でのなかまであること
→「くらしの交流」をできるこそのなかま
→「しんどいこと」をやりとりできてこそのなかま
(3) なかまづくりは、教職員の意図的で継続的な取り組みの上に生み出されること
【取り組みの柱】
(1)生活をつづる、語る→日記(生活ノート・班ノート・学級通信・集会)を綴り、読みあい、互いの暮らしを交流する
(2)共同活動の組織化→生産的で文化的な活動を創りあげる
→互いの個性を知り合う
(3)人権学習や部落問題学習の実践→具体的な差別の問題(から)や、解決の手法や道筋を学ぶ
さあ、電子黒板を大いに活用しよう、と思う。
☆255日目(3.5)学年集会や学校集会を子どもの手で
先日本校で生徒集会がありました。生徒会執行部と専門委員長が中心に進行しました。校長が表彰状を渡した(伝達表彰)あと、、生徒会長と体育委員長にマイクを向けると、堂々と全校に向けてしっかりと自分のことばでメッセージを語りました。(事前にちょびっとだけ予告をしていただけなのに)せっかくの集会が、教員の説話や連絡事項で終わっては、生徒集会ではありませんね。できるだけ事前に打ち合わせはしておくのが大切ですが、その場の「ライブ感」ならではのプログラムから、生の声・双方向の会話が生まれるような集会にしたいものです。個別で起こった生活指導上の課題を生徒集団に投げかけ、それを受けた子どもらが互いに意見を交わす集会をいつもしていました。人権教育(同和教育)の視座からの集会を、一緒に組み立ててみましょう。
子ともたちの主体的・対話的で、深い学びには、「真正の学び」が必要だと思います。18歳を対象にした九ヵ国意識調査(日本財団2019)では、日本の18歳は「自分で国や社会を変えられると思う」が2・3%。異常に低い(平均30・9%)結果があります。これは大人社会の姿を見てそのような意識になっているという指摘もあるようですが、「原体験による確信」が皆無に等しいという点も背景にあるのではないか。小・中・高と学校社会を通過する際、自分が参加して何かを変えることができた、といえる「原体験」。これが圧倒的に不足している。学級・学校社会で「自分たちはここをこのように変えることができた。つくった」と、言い切れる大小の手応えある「社会づくり体験」を子ども時代から蓄積していくことが必要ではないか、と園田雅春さんは『部落解放2023 5月号』に書かれています。続けて園田さんは、「「こども参加」のあり方について、OECD(経済協力開発機構)は「共同エージェンシーの太陽モデル」(2018年・10カ国の生徒たちが作成)を提唱。参加の最終スタイルは「若者がプロジェクトを主導し、意思決定は若者と大人の協働で行われる。 プロジェクトの進行や運営は若者と大人の対等な立場で共有される」としている。また、この2023年4月1日施行の「こども基本法」の第三条には「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」と明記されている。学級という社会づくりにおいても、まず教師の持 「常識」を問い直して、子どもに委ねる領域を広げていく。こちらが身を引くところは引く。いま、これが必要な時代なのだ。』と言われています。
☆254日目(3.4)お互いを深く理解する授業を。
先日のひなせ親の会では、「療育」や支援についての学習会をおこないました。その中で相談支援員さんが、一人ひとりそれぞれの、発達の違いや物ごとの認知の違いを体感する小ワークショップをしてくださり、とても勉強になりました。本校では子ども同士が、互いの発達特性やそれぞれの得意・不得意(でこぼこ)なことを分かり合う授業から、〈反差別の仲間づくり〉を進めています。「この小ワークショップを参考にもっと授業を豊かにしていけるね」とSSWからもアドバイスもあり、これまでの取組をさらに深化させていこうと思いました。


「これは何?」から考える認識 「まず縦に半分、次に上から…」伝わるコト、わかることって。
☆253日目(3.3)朝・夕の帰りの会は何の時間?
前回の中で、新学期準備で、朝夕の会のプログラム、いやいやそもそも何を大事にして行うの?と質問がありました。ズバリ、もちろん諸連絡ではありませんね。その時間は「くらしを交流すること」ではないかと思うのです。生まれも育ちも生活環境もちがう子どもたちが、互いを理解しあうためには、 語る、つづることをとおして自分の暮らしを出し合う時間だと考えます。そのために、子どもたちには日々の暮らしを生活ノートに「書かせ」ることや「語らせる」ことを人権教育(同和教育)では大事にしてきました。とくに、学校やクラスでは見えない家庭や地域でのその子の姿が見えてくるものを大事にし、「書き」「語って」きました。もちろん、文章を書かせたからといって、子どもたちはすぐに家庭やくらしが投影している内容を書いてくるわけではありません。また、書いたからといって、その状況が変わるわけではありません。しかも、それが厳しいものであったり、人に知られたくないものであればなおさらです。しかし積み重ねることで、子どもたちは自分の暮らしに向きあうことになります。そして、まわりの子どもたちにとって、そのような友だちのくらしを知ることは、友だちの見方や理解を新たにさせます。励みになったり、その子の隣に座っている自分自身を見つめることにもつながります。個別の人権問題の理解にもつながることも多々あります。
そのためには、日常的で継続的な積み重ねが必要になります。よく人権学習で、「自分事として考えなさい」とか「自分に重ねて意見を言いなさい」と指示される場面を見ることがあります。しかし、子どもたちは考えることはできても、そのことを口に出せるかどうかは、日ごろの「自分事」を出し合える場面や経験を積み重ねているかどうかで決まってくると考えます。その経験を少しずつ重ねていくために朝夕の会があるのではないかと思うのです。(もちろん、日常の授業の中にも積み重ねていけるしくみ・手だてが必須です)
☆252日目(2.28)教員としてのシゴトをやっぱり磨かねば。
小・中学校の教育にかかわる仲間らと東備学ぶ会の名称で学習会をはじめて十三年目になります。三月になるので、新年度の学習会の内容や日程調整などの準備を進めているところです。学習内容については、昨今は、インターネットを利用しての多様な学び(情報・教材)が簡単に手に入りますが、やはり、互いに顔を合わせて、子どものことや自分の実践を語り合う中での学び(同和(人権)教育の視座からの参加者同士の意見交流による気づき)はとても大切です。ぜひ、対面で(この表記も、多様な学習形態が増えたということですよね)ゆったりと語り合いましょう。新年度の早い時期に、年間予定表をお届けします。
以下は、これまで東備学ぶ会で話題になった内容と、これから学習していきたいなあと思っている内容を併せて、いくつかランダムに記しています。開催未定の内容ですが、どれもワークショップをしたり、お互いの実践を語り合ったりして、深めていきたいですね。
○教壇に立つということ(教員の立ち位置 子どもが活躍できる教育環境 安全教育 服務 事務処理 指導要録・学籍簿 通知表)
○新学期準備(座席 呼名 教科書(無償化) 係・当番 連絡帳 家庭・保健調査表 ロッカー 掲示物)
○学級目標づくり(学級・学年通信 班ノート 生活ノート 自主学習ノート 綴る)
○授業(発問 発表方法 協働学習 語ること 聴くこと 板書 ICT ノート指導)
○教材理解と教材づくり(生徒理解 教科指導)
○総合的な学習の時間
○道徳教育と人権教育の違い
○学級づくり(日常の中の人権教育実践 生活が語られるクラス)
○特別活動(係活動と当番活動の意味 朝の会・終わりの会の運営方法 学級活動 自治活動)
○教員の学び(服装 言動 働き方改革の中で )
☆251日目(2.27)求められていること 教員としてのシゴト(2)
・・・これは実は、私たち大学教員も同じ。知識の伝達だけなら、パワーポイントを使って動画で講義を流せばいい。それに基づいて、どうその場で議論してもらうのかが重要です。まさに反転学習。でもそれが、大学教員にできるか、できているかと言えば、そうではないです。 だって、教員自身が一方通行の授業しか受けたことないから。
これは妄想も入っているかもしれないですけど・・・・・・結局、勅使川原さんの能力主義の解きほぐしが求められているのも、時代の価値転換期である今、何を指針にしていいかわからないという人が多いからだと思うんです。
教員の専門性の転換について補足しましょう。おそらく学校教育は、教科教育こそすべてと思い込まれている。でも、この生成 AI参入の転換期に先生に求められるのは、一つには、そういった標準化・規格化された学びにのれない子、落ちこぼれる子、しんどい子をひろい上げて、わかりやすく教えること。そしてもう一つ大事になってくるのは、それこそ一人ひとりの個別性だとか、主体性に見合った学びの場をどう提供していくかです。
でも、学校の先生は、教科教育をどううまくやるのかで査定されている現実がある。 その教授能力が評価対象なわけです。・・・』
☆250日目(2.26)求められていること 教員としてのシゴト(1)
先日少し紹介した『「これぐらいできないと困るのはきみだよ』?』(勅使河原真衣著 東洋館出版社)をもとに、知り合いの先生と話していると、終わりには、「学校の役割というか、教員のしごとに携わる一人ひとりとして、仲間らと一緒に、自分自身のしごとの中身を再確認したいね」と話が広がりました。そこで、同著での著者と竹端寛さんの対話の一部について少し長いですが紹介します。(P98.99)〈ぜひ著作を読んでください。〉
『…だから同じように、実は教師が求められている力も、スタディサプリ(リクルートが運営するオンライン学習サービス〕がある時代には変わってこないといけない。標準化・ 規格化した学びだったら、携帯やタブレットで動画を見たらいい。その上で、動画で再現できないものを先生が提供できるかどうか。それが問われている。
だから今、すごくしんどいのは、これまでも学校の先生は能力主義的に求められてきたけど、その中身がガラッと転換しているときだということです。(続く)
☆249日目(2.25)生活ノート再考 追記
「プライバシーは?」と、現代では疑問がある人もいるかもしれません。「教員がそんなに子どもの生活に立ち入ってもいいの?」と。けだし、プライバシー権とは、〈自分に関する情報は自分でコントロールできるという権利〉です。重要なのは、生徒たちが自分に関する情報を自分でコントロールできるということです。生徒たちは書いても書かなくてもよいのです。書いてみようかと思ったときに書ける状態をつくっておくことが大切です。書いてみて先生からそれに応じて、メッセージが来たらうれしいと思います。それで「また書いてみよう」となるかもしれないのです。現代のプライバシー権は、そういうときに書きたければ書く、書きたくなければ書くのをやめるという判断をできなければ行使できません。
私は、子どもたちが書いた内容を学級通信や学年通信に掲載したりしていました。そして、その内容を受けとめた他の仲間からメッセージが返ってくるような時間を創ることも大切です。クラスへ返す時には、本人に必ず、掲載してよいか聞かねばなりません。年度の初めに「このノートに書いたことは学級通信で紹介する場合があるよ。「それは困る」というときには、『これは載せないで』と言ってな」と生徒たちに伝えておくことで安心して書きやすくなります。学校だけでは見えなかった暮らし・生活が生徒同士で交流されるようになれば、生徒同士は必然的につながりやすくなります。
こういう活動を重ねることによって、子どもたちには自分で自分の情報をコントロールする力が育っていきます。少し自己開示をしたら、それを受けとめてさらに深いメッセージが返ってきた。そうすれば、またその人に自己開示をしてみたいと思うのではないでしょうか。どういうときに自分の情報を開示すれば良いのか、どういうときにはしない方がよいのか。そういう判断力が育つのです。これはプライバシー権を行使するための力を子どもたちに育む実践です。このことは、生活ノートやSNSでも基本的に同じです。生活ノートで判断できるようになった子どもたちなら、SNSでも判断できるようになりやすいはずです。自己開示の楽しみと気まずさ(危険性)を味わった人なら、SNSでも気をつけながら、必要に応じて自己開示するというスキルを身につけやすいはずです。逆に、ふだんは自己開示などぜんぜんする機会がないという人が、「匿名だから」とネット上で弱みをさらし、限度なく自己開示をする。そのあげくに誰かから攻撃されるなどの危険を避ける力を育むことにもなります。(たくさんの先輩の文章に加筆修正しました)
デジタル化にしてもよいコト、してはいけないコト、文章が残るコト、あえて残すコト、残さないコト、書く・綴るコトの価値などを細かいけども再考・再吟味し、今・これからの豊かな教育実践につなげていきたいと思います。
☆248日目(2.21)生活ノート再考
綴ること つながること 語ること 仲間づくりの中で
年度末になり、新年度の教育活動についても話す機会が増える時期です。本校でも、いわゆる「生活ノート」についても、どうするか?検討する予定です。
そこで、あまり実践したことがない方々とも・・・生活ノートでのやりとりとは、教員と子どもの間を行ったり来たりさせるノートです。ノートの中には、生徒たちの生活や、暮らしの中で考えたり感じたりしていることが書かれているというものです。教員は、子どもたちの書いてきたノートに返事を書いて返します。クラスの中にはたくさんの生徒たちがいますから、すべてに返信するというのは大変だと思う人が多いでしょう。しかし、いくつかのポイントで、継続させていく中で、生徒やクラスの「つながり」は確かなものになります。
ポイント1:90年代、関西地方の学校で、この実践に出会った当時は、特別に(絶対に)、暮らしや悩みを綴らなくてもよいノートとして設定されていました。自主学習ノートの取り組みと合わせて、家庭学習をするときに用いるノートにしていました。漢字の練習をしたり、因数分解の問題を解いたりするわけです。もちろん、暮らしや悩みを書いてもいい。こうすれば、悩みの多い生徒たちがどちらかと言えば暮らしや生活を綴る方向に傾きます。これには返事を書きます。少なくとも、生徒たちの書いた分量は返事として返します。学習が得意で、現在はあまり悩みがないという生徒は教科の問題を解いてくる方に傾くでしょう。教科の問題に取り組んだときは、「見たよ」という検印だけでもOKとのことでした。
ポイント2は、毎日出さなくてもいい、たとえば1週間に2回出すというやり方です。そうすれば、1日に出すのはクラスの半分ぐらいになります。その中から、返事を書く必要が出てくるのは、「暮らしや生活」を書いてきた残りの十人ほどになれば、継続しそうな気がしませんか。
そして、大切な3つめのポイントは、返信の書き方です。最初から「生活ノート」に、深刻な悩みを書いてくることはほとんどありません。アイドルのことやテレビドラマのこと、ゲームのことなどばかりかもしれません。これに付き合うのは、大人としてなかなかむずかしい。しかも、ガンバッテ付き合おうと努力してゲームについての返事を書いたりすると、生徒はさらに喜んでゲーム路線で書いてくるかもしれません。こういうときは、そのテレビドラマやゲーム・ネットを手がかりに、教員が自分の暮らしをさりげなく書いて返すことです。「その番組の時間帯には、先生の家ではご飯を食べていた…」「などと返すのです。そうすれば、「先生はこんな暮らしをしているんだ」と伝えられますし、「このノートにはこんなことを書いていいんだ」「暮らしを書くことって大切!」というメッセージを届けることにもなります。とはいえ、暮らしや生活を見つめて、生活を綴ることになる実践までには、なかなかたどりつくことが難しいと思います。教えてくださった関西の先生は、「そこは粘り強く、こだわっていかなくてはいけないよ」と言われてましたが、私は、生活ノート紙面でしりとりのやりとりのやりとりをしたり、シールを貼ったり(多種多様なモノがあります!)していました。要は、これも教員とのよりよい関係性(信頼によるつながり)の構築と、子どもと子どもをつなげる根幹になる取り組みだと思います。
☆247日目(2.20)進級にあたって 意識を高める取組として
3年生に進級する生徒らが、新入生に向けて新聞を製作する予定です。
☆246日目(2.19)私たちの立ち位置について
よくこの「タネ」の話題の中に出てくる教職員の「立ち位置」についてですが、川上康則さん著の「教室マルトリートメント(東洋館出版社)」に、そのあたりを考えるヒントとなる文章に出会いましたので、少し紹介します。(P30~31)『・・・職員室内の会話の中にも、特定の子どもや保護者を揶揄したり、嘲笑ったりするような場面に遭遇することがあります。関係する子どもをまるで自分の所有物であるかのごとく名前を呼び捨てにしたり、からかうようなあだ名をつけて笑いのネタにしたりするような不快極まりない会話を耳にすることがあります。特別支援教育の基本は「他者との違いを認め、相手をリスペクトする」ということです。
相手への敬意。
相手が見て感じたことへの敬意。
相手が考えて行動したことへの敬意。
相手が大切にしていることへの敬意。
相手が背負っているものへの敬意。
敬意を示せない教師の発言は、「他人の粗探し」にしか映りません。結局のところ、他人からも同じ視点で見つめ返されることになるように思います。反対に、相手への敬意にあふれた人から発せられた言葉には、人の心を支え、前向きにさせる力があります。指導を行う立場の前提として、「何を言うか」や「何をするか」よりも「どんな態度でその子の前にいるか」が大切だと思います。・・・』
☆245日目(2.18)進路公開ができる集団に
先日、小中合同のケース会に参加して、「自分を見つめ、綴り、語る」とりくみを粘り強くやっていかねばならないなあと思いました。
20代の頃に訪問した大阪の中学校では1年次は「自分」、2年次は「家族」、3年次が「進路公開」として、見つめ、綴り、語る取り組みを行っていました。3年生の進路公開につながる授業の中で、「***高校に進学したい。そして将来は**になりたい。だから今、自分は**したいと思っている。」と語るだけでなく、「自分の悩みや葛藤、親の思いや願い、家計や経済的なこと」を語り、クラスの仲間から熱くて真剣な応じ(返し)がありました。
「進路公開」というのは、自らの進路(多くは高校進学)をクラスの仲間の前で公開していくことです。しかしカタチを真似して、生徒どうしがつながりあっている集団だと思ってしまうのは危険だと思います。発表する子が、自分の暮らしをみつめ、自分をとりまく人々の願いを受けとめ、自分自身の可能性を高めるための進路を求めたことを語り、その発表を聞く側の子たちは、発表する子の暮らしに思いを馳せながら、強い声援を送る…ことが出来るためには、教職員集団が、クラスの日常の中で、自分を語り、聴き合う実践の積み重ねしかないと思います。ゆえに、「進路公開」というのは、お互いの暮らしや思いを知らない者どうしの学級集団では成立しない取り組みとも言えます。すなわち「進路公開」の時間が大事なんじゃなくて、それまですごしてきた日々で、どれだけ本気で隣に座っている仲間のことを知ってきたかが必要なのです。「クラスの仲間の語りに真剣に応じる文化」を作っていくことが「真のつながりのある学級集団づくり」ということです。
併せて、自分のことを語り、仲間のことを知ることのできる「朝・帰りの会」の時間がほとんどナイ、ある学校の教育課程表をみることがあり、とても気になっています。朝の会は「連絡」するだけの時間ではないのにねえ。「学級集団づくり」はどこでするのか?もう必要ないのか?と思ってしまいます。
☆242日目(2.17)「これくらいできないと困るのはきみだよ」?を教員としてどうとらえます?
『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(ISBN: 9784491055527:勅使川原 真衣/編著、野口 晃菜・竹端 寛・武田 緑・川上 康則/著)をS氏から「読め!」と言われて読んだ感想の一部です。・・・『教育現場(日本社会)に蔓延する(残滓?ではないか)能力主義について問題提起をしています。 「生徒・教師」という立場を置いといて、「人間である」という前提に立つと、安易に正論をぶちかまして学校現場を批判するのではなく、モヤモヤと葛藤する中で望む方向へ前進していくしかない(語り)対談になっているような気がしました。教育現場での変革は、トップダウンで一気に進むわけでなく、教育現場最前線の者が少しずつ、変えていくしかないとも思いました。(もちろん研究者や多様な方々と連携・協働は不可欠です)
また、日常的に子どものかかわる者のひとりとして、「子どもにかける言葉がいかに大切か」そして、その言葉を紡いでいくためには、「学校教育の中であたりまえ」と思っている言葉がけの内容をも見つめてみようと思ったのでした。社会や労働にある「能力主義」について、学校教育の中にある「望ましさ」(教職員の多くの場合は無自覚の指導・支援のカタチでの「望ましさ」)の背景にどんな傷つきや焦りがあるのかを探り、「能力主義」を捉え直すきっかけとなりました。』・・・まったくまとまらない文章なので、参考に、出版社の「本書からわかること」を記します。
環境や関係性を無視した能力観の果てに
社会では、日々さまざまな能力の必要性が訴えられていますが、それらは非常に移ろいやすいものです。労働の世界に目を向ければ、「新卒で必要な能力」が時代とともに移ろいますが、能力とは個人に宿るものではなく、その発揮は本来、環境との関係に左右されます。そして、労働の世界とは切っても切りはなせない関係である教育の現場でも、「コミュニケーション能力」「非認知能力」「指導力」という表現に、こうした一元的な能力主義の片鱗を見つけることは難しくありません。例えば、「これくらいできないと困るのはきみだよ」。言ったり、言われたりしたことのある人は多いでしょう。学校で相手や自分に「これくらいできないと困るのはきみだ」と言いたくなるときには、どのような社会で生きることが想定されているでしょうか。
「これくらい」が規定する社会は存在するのか
本書の編著者である勅使川原さんは、「能力とは個人に宿るものではなく、他者や環境との関係の中で発揮されるのではないか」と提案します。そして、一元的な能力主義を脱するためには、個人がすべての“能力”を身に付けて「強い個人」として生きることを目指すのではなく、強さと弱さ、とがりや特性を組み合わせて生きていくことを目指すほうが大切なのではないかとも考えます。本書では、「これくらいできないと」に表現される焦りが、昨今の学校をめぐる状況への合理化として表れているのではないかと仮定し、どうすれば一元的な能力主義という“自縄自縛”をほぐしていけるのかを議論します。
「学校だけが変わったって意味はない」?
「学校がいくら個性を大切にしても、その先で生きていく社会が変わらなければ、結局困るのは子どもたちではないか?」――こうした不安も生じるかもしれません。しかしながら、不登校児童生徒が30万人を超える今、このまま進んでいったとして、学校は子どもたちにとって、そして先生にとって、どんな場所になりうるでしょうか。私たちは、なに「から」始めていけそうでしょうか。4つの語り合いを通して、学校にある大人や子どもの傷つき・葛藤をつぶさに見つめながら、糸口をいっしょに考えていくための1冊です
追記(映画もそうですが、本も読み合って感想を語り合う「読書会」に、30年も前に連れて行ってもらったことを想いだしました。古そうで新しい「読書会」かもしれません。しましょう。)
☆241日目(2.14)働き方の改革の検証軸は??
授業公開ありがとう 研究協議ワクワクは大事
2019年に、文科省は、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方 改革に関する総合的な方策について(答申)【概要】 (平成31年1月25日中央教育審議会)で、学校における働き方改革の目的を4つあげています。
〇 これまでの我が国の学校教育の蓄積はSociety 5.0においても有効であり、浮足立つことなく充実を図る必要。これまで高い成果を挙げてきた我が国の学校教育を維持・向上させ、持続可能なものとするには、学校における働き方改革が急務。
〇 ❛子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする❜という働き方の中で、教師が疲弊していくのであれば、それは❛子供のため❜にはならない。学校における働き方改革の目的は、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること。
〇 志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、そのためにも、学校における働き方改革の実現が必要。
〇 学校における働き方改革を進めるに当たっては、地域と学校の連携・協働や家庭との連携強化により、学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化を図ることが大切。
どのように「目的」を読み取り、いま(2025年)どのように進めているか。検証軸としての〈私たちの教育活動・教育実践はどう高まっているのか?!を考えさせられる校内授業研究会でした。公開授業ありがとうございました。またみんなで、もっと語りましょうね。
☆240日目(2.13)授業公開ありがとう 研究協議わくわく
先日、第2回校内授業研究会を行い、授業や学級づくりについて協議しました。働き方改革で生み出した時間は、子どもたちに向き合うための授業研究や仲間づくりの創出につながらなくてはいけません。貴重な授業公開と研究協議の時間でした。学びあった内容を今後の学校(仲間)づくり、教育実践に生かしていきたいなあと思います。いくつか、人権教育での仲間づくりの視点でいくつか記します。
○グループ学習での学びが成立しているかどうかを、しっかりと見取っていきたい。
・見取りの基本は、協働学習をしているグループの机にしゃがみこんで、子どもたちのやりとりに耳を傾け、子どもたちの動きを目で追い、最初から最後まで聴き取ることだ。残念ながら最初から最後までくっついて聴くことは授業者は出来ないが、その代わりの自校の他教員がそれぞれのグループに分かれて入り、「学びが成立したか」どうかを丁寧に耳を傾けるしかない。参観授業で、生徒の机間を歩き、ノートやプリントをチラリと視ても分かることは少ないのではないかな。(授業参観者として何を視ようとしているのか)
○協働学習への道は険しいけれど一歩一歩。
・4人のグループにして、適切な課題を与えるだけですぐに協働学習が成立するわけでないことは誰もが知っている。グループでの協働学習を成立させるためには、複数人での会話(話し方)や聴き方、時間の管理や、声のトーンに至るまで、授業者のモデリングはもちろんだが、より、段階的・継続的な指導が必要だと思う。例えば、一人だけ話すのではなく順番に話すこと、時間内に話すことやまとめること、聴きあうことや話し合いの心地よさを味わうこと、表現技法(話法)を豊かにさせること等、全教科領域の強みを生かしながら、「多様な学び方」の指導や支援に力をいれたいと思う。(ちょっと次回に続く)
☆239日目(2.12)発表(表現)って、どう育む?続き
よくプレゼン力と一緒に語られこともありますが、もちろんプレゼンする力を高めること自身が目的ではありません。(プレゼンスキルとは、自分が伝えたい内容を相手に正しく伝えるためのスキルのひとつです。)しかしながら参考になります。プレゼンテーションでは、4つの力が必要だと言われています。
○自分で考える力:プレゼンテーションをする上で、物事を論理的に分かりやすく伝えることは必要不可欠です。一番伝えたい結論とその根拠を聞き手に分かりやすく伝えるためには自分の頭で内容を整理し、まとめあげる力が必要です。
○伝える力:プレゼンでは視覚と聴覚から情報を提供します。つまり、プレゼン資料と話す内容から伝えることを意識することで相手に伝えたい内容を十分に伝えることが可能です。例えば、プレゼン資料において、文字の大きさ・色使い・図形の使用によって重要箇所を目立たせたり直感的に伝えたい内容が分かるように工夫する必要があります。また、伝えたい相手に伝わる声量や抑揚をつけて話し、プレゼンを受ける側がスムーズに理解できるように務める必要があります。
○表現力:伝える相手にとって魅力的に伝わる表現力も大切です。態度や言葉のチョイスから話し手であるあなたの魅力を伝えることができれば、相手に人間性や信頼度を評価され交渉が上手くいくことがあります。例えば、具体例を伝えるときに共感を得られる表現ができる、ポジティブな雰囲気を出せる、応援したくなるような人柄が出せる、など、表現力があるだけで話を最後まで聞いてもらえます。内容を練るだけでなく、魅力的に伝える表現力を磨くことも重要なポイントです。
○ヒアリング力:プレゼンをする相手によっては、求められていることが変わることがあります。例えば、ジュースを売ろうとプレゼンするとき、Aさんは美味しいジュースが飲みたいと思っており、Bさんは冷たいジュースが欲しいと思っているとします。そこでAさんに冷たいジュースはいかがですかと伝えても、すぐには買おうと思いません。どんなジュースを求めているのか探ったうえで、美味しいジュースをプレゼンすれば効果的に相手に商品の良さを伝えることが可能です。相手が何を欲しており、どんな状況にあるのかを引き出すヒアリング力は、プレゼンを行う前に必要なスキルです。
☆238日目(2.10)発表(表現)って、どう育む?
岡山学び工房(学びの共同体についての有志の学習会)での、全国各地の授業実践記録を視ながらの意見交流では、いつも多くの気づきや学びがあります。少し前の勉強会では、中学生徒一人ひとりが学習でまとめた内容を、教壇の前に出てきて発表する映像を視聴しました。視ながら、自分の教育実践を振り返ると、生徒が〈話す、しゃべる〉だけで満足していたような気がして反省しました。発表は「表現」にひとつですが、自分と伝える相手を意識した、より豊かな表現力が高められるような支援や指導をあまりしてなかったような気がします。卒業式などの式典での生徒の答辞等の指導には「表現」の中身を意識した指導・助言をしていますが、日々の教育実践の中での「表現」力を高める支援やサポートをしっかり意識したいと思っています。表現力とは、自分の感情や思考を〈他者〉に分かりやすく伝える力です。文章や絵、声、表情、行動など、さまざまな方法で表現することができますが、必ず〈他者〉を意識させないといけませんね。表現力を高める指導・支援には、以下のようなポイントを押さえることが大切です。
○「書いてみたい」「書かなければならない」という動機づけをする。
○「私」に関わる身近なテーマを設定させる。
○読んでほしい、伝えたい相手を見つける(意識させる)。
○他人に読んでもらう(グループワークをくり返して、他者の目を内面化させる)。
○たくさん話す機会を増やす
今日あった出来事を家族や中学校の友達に話してみて、自分の考えがしっかり伝わるか練習させる
大勢の前で発表する際は、原稿を見ずに話すことや鏡の前で練習することを薦める。聞く側に回って自分の発表を客観視することで、より伝わる内容にブラッシュアップできることを実感させる。練習を重ねることで本番は自信をもって話せる。聴く側も気持ちが伝わりやすい発表に感じられます。
○本を読む・まねることの大切さを伝える
本を読むことで語彙力が増え、自分が伝えたい内容をスムーズに伝える言葉選びが簡単にできるようになります。本はテレビなどの媒体とは違って、難しい言葉や表現が使用されています。様々な本を読み語彙力を増やすことで表現力も上げることにつながります。さらに、話し方が上手いと思った人をまねることも効果的であることを教えましょう。まねはよくない事のように捉えがちですが、「仲間」から学ぶこと(まねぶこと)は学級dくりには必要な視点ですね。クラスの仲間にも伝えることが上手い人がいることを認識させ、自分が話すときにも使えそうな表現や言葉遣いをまねしてみる事で、自分の表現力を効率的に上げることが可能なことを共有できるクラスの「仲間」はステキですなあ。
○作った文章や資料を何度も推敲
資料作成の練習をすることも表現力を磨く1つのポイントです。PowerPointやGoogleスライドなど、生徒たちは、作成する機会はどんどん増えましたが、〈他者〉を意識し、教員の指導・支援や、仲間どうしのアドバイスが、よりよい資料作りにつながる体験をどんどん増やしましょう。続く
☆237日目(2.7)みんなで生徒を支える体制づくり③
まとめたものがみたいとリクエストがありましたので、提示します。
☆236日目(2.6)みんなで生徒を支える体制づくり②
前回に続き。
『対象の児童生徒と身近に接する支援員は、障害に関することや支援の仕方について質問を受けることがあります。こうした場合、当該児童生徒の発達の段階や、障害受容の状況等を踏まえた上で適切に答える必要があります。したがって、当初の打合せにおいて、どのように伝えるかについて、学級担任や特別支援教育コーディネーターと十分打ち合わせておく必要があります。同時に、支援の対象ではない児童生徒からの質問に対しても答えられるようにしておきます。対応の仕方を一概に言うことはできませんが、基本的には、
・対象となる児童生徒の個人情報の取扱いに十分留意する。
・対象となる児童生徒の自己評価が低下しないようにする。
・友達と差別・被差別の関係にならないようにインクルーシブの視点を大切にする。などのポイントを押さえ、一人一人の状態や学級の様子に応じた接し方をする。
年度当初の学年集会等を活用した取組(表明・発信)、日常的・持続的な発信を積極的に行いましょう。
☆235日目(2.5)みんなで生徒を支える体制づくり①
授業のサポートに入り、以前、文章にまとめた「支援さんとの協働」について一部を記します。
『支援員の役割は、対象となる児童生徒の支援が第一義的な役割であることは言うまでもありません。しかし、対象となる児童生徒への支援の形態は様々であり、他の児童生徒とかかわりを持つことも少なくありません。子どもと子どもを「つなげる」視点での支援が重要です。したがって、学校生活の様々な場面で支援員がどのように動いたらよいか、他の児童生徒への接し方・つなげ方も含めて、事前に学級担任と十分打合せておくことが大切です。また、障害のある児童生徒が通常の学級の中で必要な支援を受けて学校生活を送っていくためには、周囲の児童生徒の理解が不可欠です。一人ひとりの学び方が違うことや支援を必要とする人もいることなどを取り上げながら、児童生徒の発達段階を踏まえて、支援員が何のために教室に入っているのか、どのような役割を果たすのかなどについて説明し、支援を受ける本人以外の児童生徒も支援員について理解しておくことが大切です。』続く
☆234日目(2.4)綴る 書く まとめる って
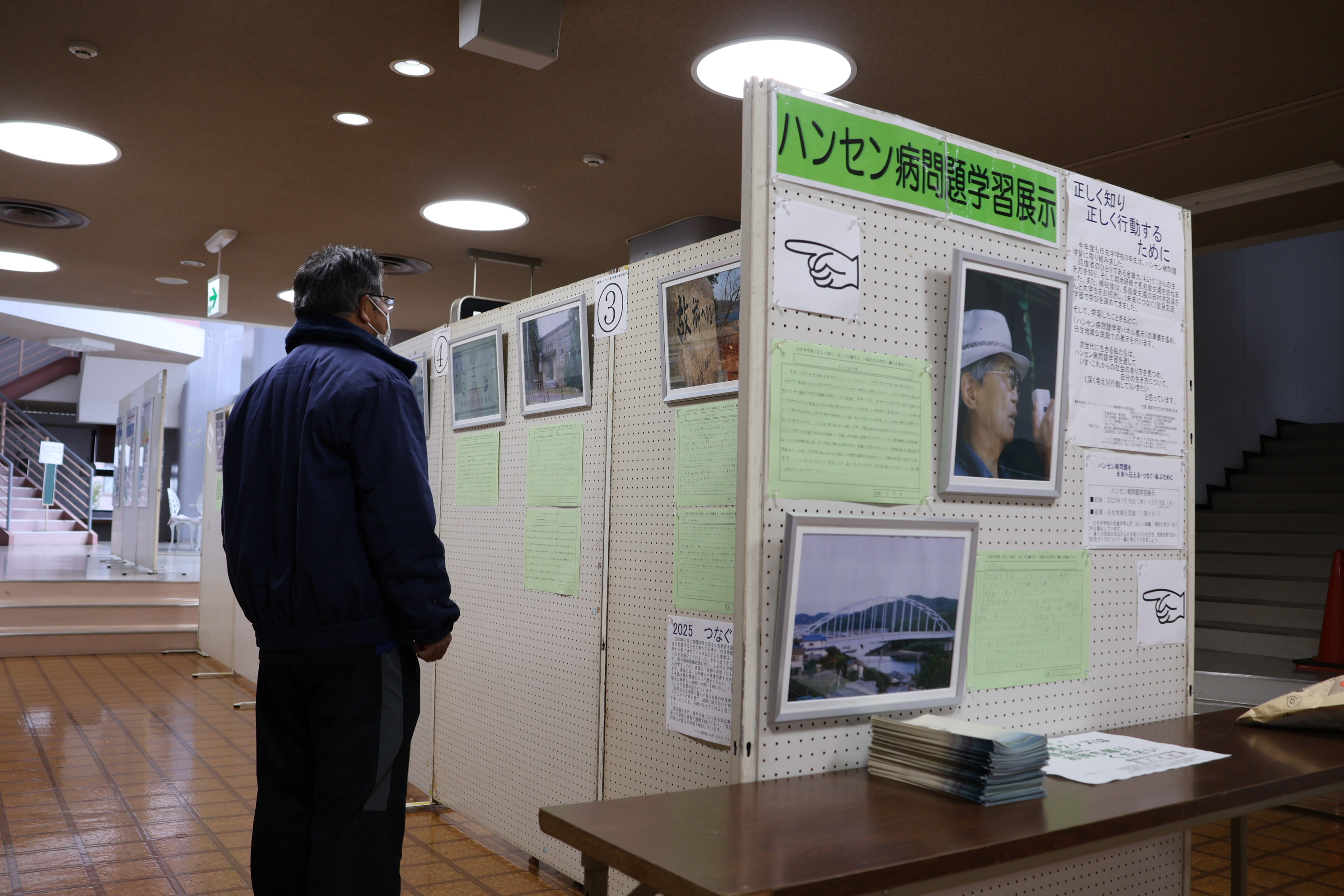
今年度も三年生は、ハンセン病問題に関する多様な学習の中で、まとめの1つとして、「パネル展示の説明文」づくりに取り組みました。 2月18日まで日生地域公民館で展示中です。
さて、生徒らは、金さんの生き様(よう)に出会い、視覚教材での学習に、フィールドワークで視たことや感じたこと、大学生との交流を重ねて、説明文を作成していきました。その中には施設の説明だけでなく、その中でもうひとつ大切にしていることは、パネル展示を観られる方々へ「伝えたい、私の願いや思い」を記することです。これがなければ、傍観的な第三者の視線に陥りやすくなり、批評家のような施設の説明で終わるおそれがあります。記することで、「自分の立ち位置が〈自分事(ごと)〉」にスライドすることになると思います。
子どもたちが思考して書くのは、〈学習者としての思い・伝えたいメッセージ〉なのか、単に〈感想〉なのかで、大きく変わってくるなあと感じています。私たちは「記す」ことに、より丁目的や意図を明確にして、望んでいかねばなりませんね。それが、子どもたちとってさらに深まりのある学びにつながっていくと思います。「感想を書きましょう」の指示だけでは、深化は起こりませんな。モデリングも併せて、ていねいにていねいに。
☆233日目(2.3)『こんにちは 愛生園」から考えたこと③
まったく私見です。他のマンガですが『この世の片隅に』は、同じ職場の方に薦められて読みました。第二次大戦中の呉のまちを中心に生きるスズさん(主人公)のお話ですが、読了後なぜか、スズさんが年を重ね八十歳ぐらいになっても凜として暮らしている姿が目に浮かんだのです。戦後80年となりますが、呉のまち、広島のまち、生きてきた人々が、今現在とつながっているような感覚をもった作品でした。ハンセン病問題もしかり、「過去と今・未来とをつなげる」ことが、様々なところでテーマとして掲げられて、様々な取組がされていますが・・・。ハンセン病問題に関する記録や写真を、ていねいに画として読み取りことばを重ねた本作品は、生きてきた人々を、「いま」につなげ、未来へもつなげるのではないかなと思いました。
☆232日目(1.31)『こんにちは 愛生園」から考えたこと②
6話の「綴り方」について。近年のデジタル化、GIGAスクール構想の中で、新しい学びのスタイルが進んでいます。(それはよいことですよ)しかし同時に、学校現場では、「書くこと自体」はどんどん減り、それに伴って「書く」意義や意味がとてもあいまいなものになっているような気もします。私は、91年に教員となり、同和教育(現在の人権教育)の中で「綴りかた」に出会うことができましたが、「綴り方」が育んできた優れた教育実践や、理念だけでなく、言葉自体の知らない若い方も多いのではないでしょうか。何が言いたいかというと、「綴る」ことをやっぱり大切にしきたいなあとマンガを読ませていただき、あらためて思うのです。GIGAスクール構想でもタブレット等を活用するスキルUPが目的となってはいけません。6話の中にもありましたが、学校教員の視座でみると、それは、単に文章を「書かせる」だけでなく、教員の視座、事象の捉え方についての助言・アドバイス、指導や支援のみならず、どのような言葉かけでその作品を本人に還すか、また、クラスや仲間に還していくか。受容(まるごと受けとめること)ができる仲間集団(反差別の集団づくり)をつくれているか、などなどを同時に考えなければならないよなと、改めて確認しました。教育改革の名のもとに、様々な手法やスキルやメソッド?などがもてはやされている感もありますが、「綴る」ことを通して、「見つめる」「語り合う」「つながる」教育の原点に立ち戻って考りたいとえようと思いました。
また、入所者の方々の「綴ったこと」は、その当時、社会や世の中を大きく動かすことはなかなか難しかった時代(正しい知識・理解不足)だったかもしれませんが、今現在、あらためてその価値は大きいと思います。私たちも小中学校の教員仲間らで、新たなハンセン病問題学習の授業ポログラムを考えています。もちろん、入所者の方々の生き様(よう)に学ぶハンセン病問題学習です。金泰九さん、『虎ハ眠ラズ』、『我が八十歳に乾杯』などを活用した教育実践はこれまでもたくさんありますが、「いま・これから」のためにあらためてつくりたいと考えています。そしてもう一つは、昨年度、徳田靖之弁護士(国賠訴訟の弁護団長)さんのお話を聴いて、黒川温泉での宿泊拒否の出来事をもとに、救らい思想(人の無意識の中にある、「かわいそう」な人たちへの救済、差別)をのり越える学習プログラムをつくりたいとも思っています。あれもこれもすぐには作れませんが、私の覚悟です。
☆231日目(1.30)
『こんにちは 愛生園」https://note.com › asanonoi
子どもたちと読みたい素敵なマンガを、知り合いから薦めていただいた、子どもたちと読みたい作品です。紹介してくれたIさんに返信した内容の一部です。(感想)
私は、2000年に初めて長島を訪れ、入所者の金泰九(kim teagoo)さんに出会い、縁あって、金さんの愛生園フィールドワークのお手伝いをさせてもらうようになりました。金さんが亡くなられた後も、小学生、中学生、保健の先生、様々な方々の現地研修に同伴して、園内を歩いて歴史的な場所や出来事、ハンセン病問題について話をしています。いつも現地研修のお手伝いを終えるとホッとしますが、同時に自己嫌悪というか、いつも同じ問いが頭の中をよぎります。それは、「当事者でない自分が、何を語れるのか?」です。療養所の歴史の中には、今の社会では想像もできない出来事(入所者のくらし・生き方)がたくさんありますが、そこから強烈なインパクトのある事象を、あたかも分かったかのように、「エピソード」として取り上げて、現地研修に来られる方々に話し(驚いてもらう)ようなことに自分はなっていないか?という猛省です。だから、減り続けている入所者数や平均年齢も軽々しく言うべきことではないかなあと思っています。現地研修に来られるグループの研修の目的や理解状況によっては伝えないこともあります。ハンセン病問題に関心を高めることを「煽って」はいけませんね。
ようやく、最近は、(二時間程度のフィールドワークのプログラムですが)、一緒に歩く時間には、自分自身のハンセン病問題への今現在の向き合い方と、金泰九さんが存命中に常日頃言われていたことや教えてもらったことを話すしかないなあと思っています。長島は観光地でもありません、観光ガイドでもなく、当事者の証言でもなく、自分の「立ち位置」をいつも確認しながら、今後も現地研修のお手伝いをしていこうと考えています。
例えば、現地研修の終わりには、「今日は、ハンセン病問題の歴史のほんの一端の学習でした。どうかまたいらしてください。金さんはいつも「またおいで」と笑顔でお別れしていました。そしてもうひとつ。ハンセン病問題を政治的・社会学的に論じた本もたくさんありますが、たくさんの入所者の方々が、自分の生き抜いてきた人生を本や記録で著しています。ぜひ、ハンセン病問題を「入所者が歩んで来られた生き様(よう)」から、深く、思考してほしいと思います。」と付け加えています。とても前置きが長くなりましたが、こんにちは 愛生園」のマンガの中に描かれた入所者一人ひとりが綴った(残した)「語り」「コトバ」から、私たちは、療養所でのリアルな生き様(よう)を丁寧に読み取り、学んでいくことがこれから益々重要になってくると感じています。世界遺産への登録の取組の中でも大きなキーワードになってくると思います。名もなき人々(大切な名前はもちろんあります)の聲を聴き、それを伝えていく活動を、私も私の方法で、微力ながら進めていこうと思います。
☆230日目(1.29)人権教育実践の中での仲間づくり(続き)
新しい教育要領や学習指導要領には、これまでなかった「前文」が加えられ、そのなかで、これからの学校には一人ひとりの子どもが、「自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と述べられています。
ここに示されている子どもたちに育みたい力は、これまで私たちが人権教育を通じて子どもたちに育んできた力と重なるものです。生まれ育った環境や障がいの有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもたちが意欲的に学び、夢や希望を実現できるようにしていくためには、学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの自尊感情を高め、多様な人と協働しながら、人権が尊重される社会づくりに主体的に参画する力を培う必要があります。そして、
その取組は、これまでの同和教育の理念や成果、手法を踏まえ、教育的に不利な環境のもとにある子どもを中心に据えた「仲間づくり」を基盤とすることが重要です。
あらためて
◆「仲間づくり」の目的
めざすべき「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある人権問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。
◆「仲間づくり」の視点
「仲間づくり」は、こうした目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。そのうえで、どのようなことを大切に取り組んでいけば良いか、これまでの成果などを踏まえ、ポイントを紹介します。
①子どもの生活背景をつかむこと
すべての教育活動は、子どもの姿、子どもを取り巻く現実から出発することが大切です。気になる言動を見せる子どもがどんなことを考え、どんな思いでいるのか、どんなくらしのなかで生活し、学校に通っているのか、保護者はどんな願いをかけて子育てをしているのか。そうしたことのなかに、その子どもが抱えさせられている課題を解決するための、取組のヒントがあります。子どもの生活背景をつかむためには、家庭訪問等の取組を通じて、くらしや思い・願いなどについて対話できる関係を、子どもや保護者と築くことが必要です。
②弱い立場に立たされている子どもを中心に据えて取り組むこと
「中心に据える」とは、決して集団のリーダーにするということではありません。取り組む教育活動が、子どもの自尊感情や学習意欲を高めたり、自他の人権を尊重し差別をなくそうとする意識を身につけたりすることにつながるものであるかを、その子どもの姿を通じて検証するということです。集団のなかで疎外されていたり、不安を感じながら生活していたりする子どもが学級で安心して過ごせるようにすることは、誰にとっても居心地の良い環境をつくることになります。また、弱い立場にある子どもの側に立ってまわりの子どもや集団を見ることで、他の子どもの課題や集団の課題が見えてきます。
③一人ひとりが生活のなかで感じている不安や悩みを共有し、ともに乗り越えようとする集団をめざすこと
「いいところ」「がんばっていること」を認め合うことは大切です。しかし、それだけではなく、一人ひとりが直面している課題を出し合うことが必要です。家庭や地域での生活、そのなかで抱えさせられている思いを知り合うためには、「聞いてもらえる」「知ってほしい」と思える集団であることが大切です。こうして知り合った一人ひとりの思いを共感することが、一人ひとりの課題の克服や、その背景にある人権問題の解決に向けて行動しようとする連帯感につながっていきます。
④個別的な人権問題についての学習と結びつけて取り組むこと
一人の子どもの生きづらさの背景に人権問題がある場合、その生きづらさは社会の問題であり、他の子どもにとっても共通の課題となります。友だちの思いを聞くなかで、「友だちを不安な思いにさせていたのは、社会の偏見や差別だった」「そのことに無自覚だった自分は、友だちを不安にさせていた」といった気づきが、人権問題の解決を「自分事」として引き寄せていきます。また、様々な人権問題について学習する際、自分が生活のなかで感じている不安や自分にとって身近な人権問題と重ねて考えを出し合うことによって、マジョリティを「普通」とする価値観やそれへの同調圧力など、それぞれ個別の問題に共通する社会の課題を見出し、自分自身とのつながりを見出すことができます。「仲間づくり」を基盤に、こうした学びを積み重ねることが、ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高めることにつながります。
◆「仲間づくり」の手法 〈テクニックか?!〉
これまでの取組において、有効性が確かめられてきたいくつかの手法があります。
①「つづる」「語る」・・・一人ひとりが自分を見つめる取組
「つづる」とは、過去の出来事を順番に思い出し、事実をありのままに書いていくことです。これを積み重ねることで、生活のなかにある自分自身の課題や不安、悩みを意識化し、これからの生き方や社会のあり様を考えることができるようになります。自分を見つめることは、つらいことや苦しいことも受けとめ、自分を否定することなく生きていく力を培っていきます。そうした力を身につけた子どもは、友だちの前で「語る」ことができるようにもなっていきます。また「語る」ことは、単に誰かに伝えるだけではなく、自尊感情や将来展望を確かなものにしていくことにもなります。
②「読み合う」「聴き合う」…知り合い、共感し合う取組
朝の会や帰りの会等で日常的に子どもがつづったものを読み合う取組や、人権学習・人権集会等で伝え合う取組が行われてきました。こうした取組によって、子どもは友だちの思いを知ったり、友だちに思いを返したりするなかで自分を深く掘り下げていきます。また、思いを伝える姿が、他の子どもにも「もっと自分のことを深く見つめたい」「自分もずっと避けていた課題と向き合いたい」という意欲を喚起することもあります。
「読み合う」「聴き合う」取組を進めるにあたっては、教職員が自分自身を語ること
を大切にしてきました。教職員が自分の不安や悩み、これまでの経験等を語ることは、子どもたちの「こういうことを話してもいいんだ」「自分のことを聴いてほしい」という安心感につながっていきます。
☆229日目(1.28)えっ!?仲間づくりの必要性はない?
学校には、教員に向けて様々な案内チラシが届きます。ふと気になったチラシの一文には「最も必要とされながらも、最も学ぶ機会が少なかったクラス担任の仕事。明日からすぐに使える実践的なテクニック〈担任学〉・・・」とありました。「学ぶ機会がない?」「テクニックなのか?」「担任ガク!?」と、いろいろと気になるコトはありますが、先日も仲間の教員と「もしかしたら〈学級づくりや仲間づくり〉への担任業の意識や目指すところが変わってきたのではないか。仲間づくりが必要とされていないのか?」と感じるところがあり話題になりました。『総合教育技術』2021年12/1月号でも関連した内容を取り上げていますので少し引用します。
以下[・・・学級経営それぞれこれまで多くの学校は、教科指導に比べ、学級経営にはあまり力を入れてこなかったと思うのです。しかし、その考え方を改めるべきときが来ています。これからの学校は、学級経営にもっと意図的に、計画的に取り組む必要があります。そう考える理由は、3つあります。
1つ目は、時代の要請です。令和3年1月26日の中教審の答申(「令和の日本型学校教育」の構築を目指して)の概要の中で、注目しているのは以下の部分です。
[一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要(文部科学省『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 』より)]
これは、世の中の変化を見据え、このような子どもたちを育てていくのだ、という文部科学省からの要請だといえます。ポイントは3点あります。1点目は「自分のよさや可能性を認識」、2点目は「あらゆる他者を価値のある存在として尊重」、3点目は「多様な人々と協働」です。これらのことを育成していくには、その前提として、学びの場としての学級経営の充実が求められるのではないかと考えます。
また、学習指導要領が改訂され、子どもたち一人一人に育成すべきものが「確かな学力」から、「3つの資質・能力」へと転換されました。現在の学習指導要領では、学級経営は「特別活動の資質・能力の実現によって深化していく」と書かれています。特別活動の資質・能力とは、協働の知識・技能を学び、話合い・合意形成・意思決定の能力を身につけ、そういった営みを通して人間関係を形成し自己実現していく、そのような子どもを育てることを意味します。それにより、学級経営が充実し、学びに向かう学習集団へと成長していく、そのように設計されているのです。
学級経営の目的も、新旧の学習指導要領を見比べてみると、大きく転換したことがわかります。旧学習指導要領でも学級経営の充実は求められてきましたが、それは「生徒指導の充実のため」でした。いじめ、校内暴力、学級崩壊、モンスターペアレンツなど、時代とともに様々な教育課題が山積するなかでは、学級集団を安定させるための学級経営をする必要があったからです。
新しい学習指導要領でも、その点は引き継がれていますが、それ以上に「主体的・対話的で深い学び」との関連が強く打ち出されています。授業改善をして「主体的・対話的で深い学び」という高度な学びを実現するためには、子どもたちの主体的で自治的な取り組みが不可欠であり、それは質の高い学級集団がなければできないことです。そのため、学級経営の充実の目的が「生徒指導の充実」から「授業改善」へと転換したのです。つまり、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、子どもたちが協働し、自ら問題解決していくような学級集団づくりが求められています。]
学級経営・学級集団づくり・仲間づくり、そして上記の中の「学習集団」・・・いろんなコトバがあり、捉えようも具体的な取組も教員一人ひとり様々でしょうが、テクニックだけではなく、時代の求めているモノやガクリョクコウジョウだけで「学級づくり」を語ることがないように自分自身肝に命じています。(続く)

☆228日目(1.27)「出来ない」をどう越えるか!②
森さんの文章の続き・・・
自分に引きつけながら考えられるように
その点とも関わりますが、部落問題学習の内容が、子どもたちが今直面している問題につながっているかどうかが問われます。つながる点は様々にあります。
情報化そのものが、子どもたちから縁遠い事柄ではありません。子どもたちの身近にスマホがあり、PCがあります。GIGAスクール構想が出ているいま、タブレットが子どもたちの身近な存在となっています。教員が知らない間に子どもたちが情報機器を使っていじめをしていたという事例を聞くことがあります。これは部落差別にもつながります。それら情報機器を使っての検索は、子どもたちにとって身近な行為です。「部落」や「部落差別」という言葉を知り、「部落」や「被差別部落」で検索すれば、残念ながら部落の所在地情報にゆきあたり、地域の映像が現れるのです。
部落差別と自己のつながりを考える手がかりひとつは、自己開示やカミングアウトに関わる問題です。自分のことをいつでもどこでもすべて明かして生きている人はほとんどいません。何かを言わないままに暮らしている人ばかりと言ってもよいほどです。
私の子どもの頃を振り返ってみると、小学校6年生の頃まで時々おねしょをしていました。これは当時の自分にとってたいへん恥ずかしいことで、誰にも知られたくないことでした。修学旅行はとりわけ心配な行事でした。一泊して、そのときにおねしょでもしたら、一生言われ続けるかもしれません。これは、おとなからすればたわいもないことに映るかもしれませんが、子ども本人にとってはけっこう深刻な問題です。もしも、このような問題とつないで部落差別が取り上げられれば、わたしにとって部落差別は身近な問題として映ったであろうと思います。
こう述べると、「おねしょと部落問題を一緒にするのか」という疑問や反論を出されるかもしれません。おねしょという問題はあえて出している面があります。そういう問題でも、部落差別と結びつきうると言いたいのです。ましてや、家族の中で対立やけんかがたえないとか、親のことを好きになれない、クラスでいじめられている、といったことがあれば、それは部落差別に直結するような問題です。そのようなことと結びつけて学習を組むことが求められるでしょう。
上の例は自分自身のこととして述べましたが、これを他の人のことにつなぐこともできます。できるというよりも、することが求められていると言うべきかと思います。部落問題学習を通して、自分の友だちが何かを苦にしているということを知ることができれば、部落問題学習が自分にとっても意味のあるものと感じられやすいでしょうし、部落差別も身近に感じやすいでしょう。》
さて、私たち(学年教職員集団)はどうしたでしょう。○部落問題学習に取り組む際の、不安や心配(イメージ)を明確にしよう。どうしたら前に進めるか考えていこう。→○中学校(教職員)だけで課題を抱え込まないようにする。課題や問題が出できた時が「真の学びのチャンス」と捉えよう。理解不足や差別意識からの発言をていねいに聴き取ろう。そこが大事。地域の方々や先輩たち、たくさんの力をかりて、豊かな学びを深めていこうと覚悟を決めよう。○私たち自身、まだまだ部落問題学習に関する勉強が足りないという自覚をしよう。○かっこつけずに、知っているフリをせず上から教えようとしない。○共に真摯に学び続ける姿を子どもたちにみせよう。○ムラの名前だけに拘泥するのではなく、中・長期的な部落問題学習を展開していこう。(差別されたムラでなく、たくましく生き抜いてきたムラ、差別に抗ってきたことを正しく認識することで、ムラに誇りを持てる)ということを共通認識して授業実践をおこないました。心配していたようなことは起こりませんでした。

☆227日目(1.24)受験に挑むとき
二日間の私立入試に多くの子どもたちが挑んでいます。どこの学校も事前指導では、教員からたくさんの諸注意や心構えなどが語られたでしょう。本校でも担任と共に学年団の先生がそれぞれ熱いエールを送りました。そして、その中で今年も、子どもたちは、これまでの労苦をねぎらい、「明日、がんばってこよう!」と堅い握手やハグなどをしながら、互いに受験への気持ちを新たにする取組を行いました。数十年前に先輩教員に教えてもらったこの実戦も、子どもたちの仲間感の熟育や集団意識の高まりの違いでうまくいかない場合もあります。子どもたちがかかわり合う、つながる(つなげる)日々の活動の延長線上に受験期のこの取組があります。受験は仲間をバラバラにすることが「ない」確かな仲間づくりを進めたいと思います。


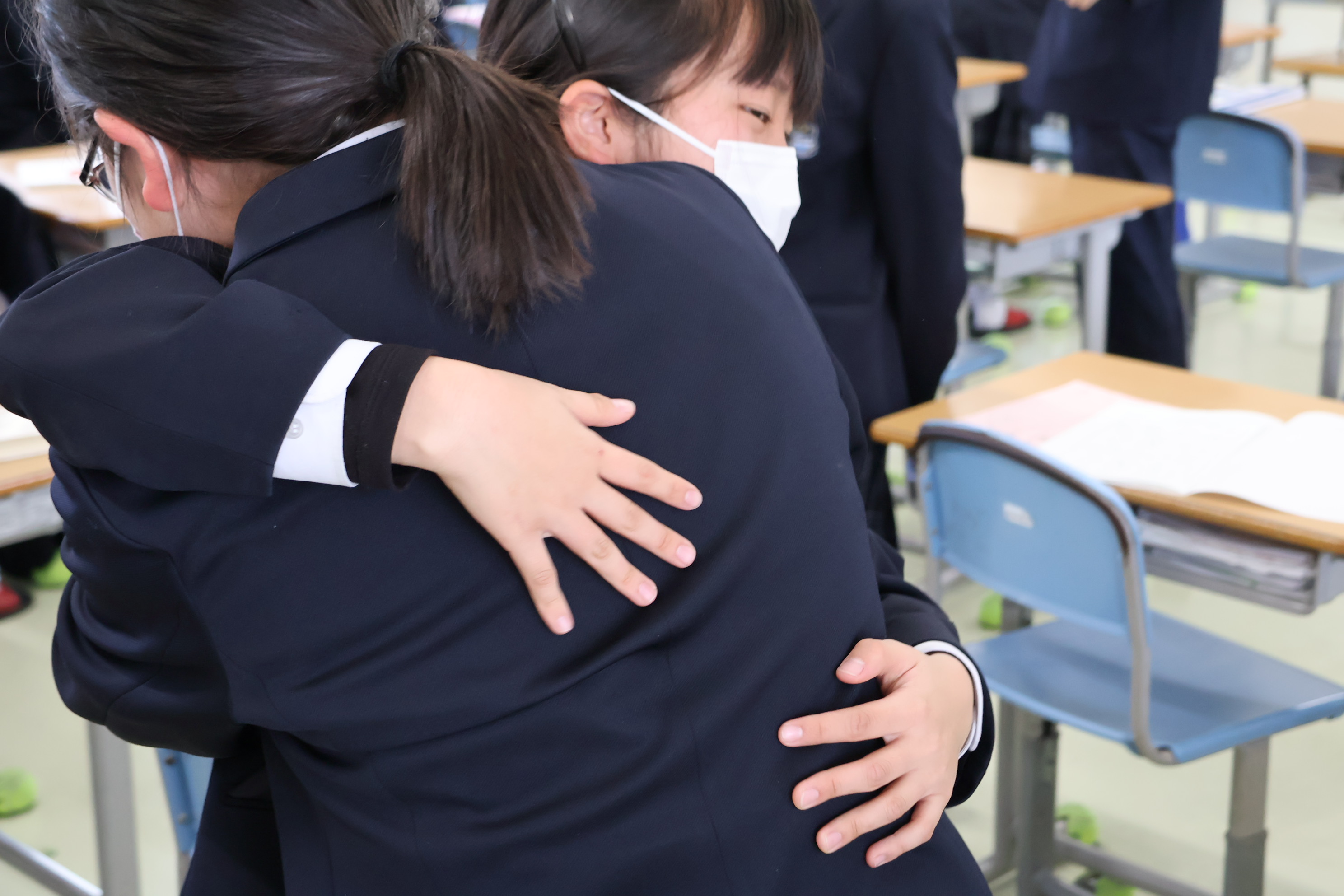
☆226日目(1.23)「出来ない」をどう越えるか!
外川さんが制作した優れたDVD「渋染一揆を闘いぬいた人々」の映像中には、入牢となった人々の村名が出ます。そのため以前に勤めた学校での授業検討時には、「ムラの名前が出ているので心配だ。DVDは使えないのではないか。」という意見が出てきたことがあります。
そこで、『日本文教出版HP(2022.01.05 学び!と人権 <Vol.08> 現代部落問題学習の課題 森 実』さんの文章を紹介します。
《・・・ただ、「どこが被差別部落かを授業で取り上げることはできない」という声もあります。私の住む自治体でも、そのことが話題になりました。学校の教員が部落問題学習の実施をためらう理由の一つとして、「『先生どこに部落があるの?』などと子どもから尋ねられたときに答えられない」という意見がありました。これに対して、市内の被差別部落で運動に取り組んでいる人から出たのは、「それやったら、うちにきてくれたらええやん」ということでした。フィールドワークなら、いつでも受け入れるよというわけです。このことを前提にすれば、子どもから「先生どこに部落があるの?」と尋ねられたときの答えは簡単です。「そうか。先生が知ってるから、先生と一緒に行ってみるか。友達にも声かけて一緒にいこか」というのでよいではないかということです。そう返すことによって、質問した子どもの側もいろいろなことを考えることができます。友達に声をかけてみて、どんな返答が返ってくるか。親に話したときに親はどう言うか。そういうことを通して自分自身の問題意識も振り返り、研ぎ澄ますことができるはずです。
そういう考え方をあちこちで紹介してみると、「いやそれはむずかしい」という声がしばしば返ってきます。「うちの自治体にある被差別部落は、そんな受け入れ体制がない」というわけです。地域によりいろいろな事情があることは分かります。そうであれば、同じ自治体の被差別部落ではないにせよ、見学を受け入れてくれるところを探してみることもできるのではないでしょうか。問題なのは、地元の被差別部落が消極的だという理由をもって、フィールドワークや部落問題学習すべてをあきらめてしまうことではないでしょうか。すぐ近くの被差別部落が無理でも、少し離れたところの被差別部落との信頼関係をつくることはできるかもしれません。また、地元の被差別部落が受け入れてくれないのは、学校が地域との信頼関係をつくれていないからなのかもしれません。部落の人たちの発言から、自分たちの教育実践を問い直すことも必要です。
身近な問題にという点で考えておきたいもう一つのことは、部落差別事象は、いろいろな場面に顔を出すということです。学校の近くで差別落書きが発生することもあります。親たちの発言の中に差別的な言動が含まれていることもあります。部落出身でなくても、部落問題に取り組んでいる人たちはいます。そういう事例や人物を取り上げることによって、子どもたちが自分にとって身近な問題として部落差別をとらえやすくなることは間違いありません。逆に、そういう面がないまま部落問題学習をすすめれば、偏見や思い込みを助長してしまいかねないのです。(長い引用でスイマセン)
差別をなくそうとする取り組みとあわせて
部落差別について学ぶときには、この差別をなくすための取り組みとあわせて学ぶ必要があります。どんな差別があるかを知るだけでは、力はわいてきません。悪くすると、無力感を広げるだけに終わります。そうではなくて、部落差別をなくすための取り組みや、取り組んでいる人の姿と合わせて学ぶことによって、力がわいてくる学習になり、展望を感じられる学習になります。
学校区をはじめ、差別をなくすために活動している人を招いて、自分の取り組みを紹介してもらうことが求められます。ある日突然に来て話してもらうのでは、子どもたちにとっては必然性のない話となり、せっかくの学習が実りに欠けます。一連の学習の流れに位置づけて、子どもたちが抱いた疑問に答え、子どもたちの思い込みを解いてもらうようにして出会いの場を設定することが重要です。
また、歴史学習でも、差別をなくそうとする取り組みが不可欠です。たとえば「水平社宣言」をきちんと位置づけることです。2022年は水平社が創立され「水平社宣言」が出されて100年です。「水平社宣言」は、つづめていえば<自分たちはこんな体験をし、悔しい思いを重ねてきた。だから自分たち自身で差別をなくしてすべての人が解放されることをめざして立ち上がるのだ>という文書です。子どもたちが自分自身の悔しかった体験を出し合い、その延長線上に「水平社宣言」を学ぶことによって、自分に引きつけて学習することができます。続く

☆225日目(1.22)体感する「学び」を創出したいね
少し前に外川正明氏の学習会へ参加しました。この日は、地元の歴史的な資料を丁寧に掘り起こされた研究と重ねて「渋染一揆」について、話を聞くことができました。会では、『シリーズ映像でみる人権の歴史DVD(第5巻)渋染一揆を闘いぬいた人々』を視聴し、参加者で意見交流を行いました。参考に、DVDの解説文を紹介します。「江戸時代も末期を迎えると幕府や藩の財政は苦しくなり、経済の引締めが相次いで行われました。「身分相応の暮らし」を命じる政策は、崩れかけていた身分制度を改めて強化することになりました。岡山藩では、庶民に出した倹約令を徹底するため、被差別身分の人々に、「柄のない渋染か藍染以外の着物の着用を許さない」というさらに厳しい御触れを出します。あからさまなこの「分け隔て」の「差別」を認めるわけにはいかないと藩内53ケ村の人々は、のちに「渋染一揆」と呼ばれる大規模な抵抗運動を起こしました。人々は、知恵を出し合って「嘆願書」を作成し抗議しますが、それが突き返されたことから1500名もの人々が「強訴」に立ち上がり、整然とした闘いでこの「特別の(別段)御触書き」を取り消させました。さらに、その責任者として入牢させられた12名を助け出すために「赦免」を求めて闘い続けました。
このDVDでは、地元の方々の協力を得て現地を取材し、原典資料を詳細に分析し、この渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。人としての尊厳をかけ、社会情勢を見抜き、知恵と力を合わせて戦った人々から、いま学ぶべきことは何かを問いかけます。」
外川さんのお話とDVDの視聴から、確かな学びを実現するためには、「時間と空間」を意識した学習プログラムや授業展開がとても大事だとあらためて感じました。それは、私が昨年度、何度か渋染一揆や長島愛生園でのフィールドワークの依頼を受けたのですが、研修される方々の時間の関係という理由で、資料館だけの見学研修で終わったり、研修コースを大きく省いたりすることがありました。そんなフィールドワークの手伝いを終えた時に心に残ったモヤモヤ感・・・。これは何なのか。これまで自分が参加したステキな現地研修やワークショップや研修会での、バラバラ、断片的な理解や知識の一つひとつ(点と点)が、時間軸でがつながり、空間軸で拡がり、「いま」と重なっていく感覚は「学び」の醍醐味、真性の「学び」ではないかと思うのです。そんな「学び」を今年度もしっかりと創出していきたいなあと思う学習会でした。参考にこのコースで廻りましょう。
◇渋染一揆:常福寺~岡山県水平社創立大会跡~(*岡崎良平の墓)~渋染一揆資料館見学(若宮神お参り)~八日市河原(結集の地)~虫明街道(稲荷山 万次郎茶屋)~備前市佐山(対峙の地)~(*伊木若狭陣屋跡)
◇愛生園:船着き場跡~収容所跡~監房跡~万霊山・納骨堂~平成公園~恵みの鐘~一郎道~小川正子碑~恩賜記念館~菴羅公園(*新良田教室(高校)跡)~歴史館見学~さざなみハウス(*むつみ交流館 しのび塚)*3/22も廻ります。一緒にどうですか?他の日もご希望に添います。

☆224日目(1.21)出来ることから
長野県の『チームで支援する特別支援学級」の資料(支援学級の担任の先生の立場から)の一部を紹介します。
以下、・・・特別支援学級担任のマツヤマ先生は,原学級の子どもたちにアユミさんのことをもっと知ってもらい,アユミさんが原学級でも自分らしく活動できるようになってほしいと願っています。
どのように原学級と連携していけばよいでしょうか。
●アユミさんが自分らしく活動することを願って
小学校に入学したころ,1年生の教室の隅にうずくまっていることが多かったアユミさん。4月の終わりに特別支援学級に入級しましたが,自分から話すことはほとんどありませんでした。特別支援学級担任のマツヤマ先生は,「アユミさんが自分の思いを話すことで,自分らしく活動し,楽しいことをたくさん経験できるのではないか」と考えました。そして,アユミさんが興味関心をもっている学習を通して,声を出したり話したりできるよう支援を続けました。また,行事の時には,アユミさんと一緒に原学級の活動に参加するようにしました。 3年生になり,アユミさんは特別支援学級の中では自分の思いを話せるようになり,自分らしさを出して伸び伸びと活動できるようになってきました。マツヤマ先生は,アユミさんが原学級とのかかわりを少しずつ増やし,原学級担任や子どもたちにも自分の思いを話せるようになってほしいと願いました。
●原学級の様子を知ろう
アユミさんと原学級のかかわりを増やすにはどうしたらよいか考え始めた時,マツヤマ先生は自分自身が原学級とのかかわりが少なく,原学級の活動についてほとんど知らないことに気づきました。
そこで,原学級の様子を知るための方法を考え,実践しました。そして,得た情報を基に,●アユミさんが参加しやすい活動を考えてみました。〈原学級でも自分らしさを~原学級とのかかわりを深めながら~ 〉
・・・こんなことからできそうです。
・原学級の時間割や週予定をもらおう。
・原学級と特別支援学級の学級通信を互いにやりとりしよう。
・原学級の担任と直接話をできない時もあるから,連絡帳を作ってアユミさんの様子を知らせたり,原学級の情報をもらったりしよう。
・学年会にも積極的に参加しよう。
・可能なときは,アユミさんと一緒に原学級の授業に参加しよう。学び方の現地研修
子どもと保護者の願いや思いを大切にして、「出来ない」ではなく、どうしたら「出来る」ようになるか!と思考を巡らしたいと思います。ちなみに保護者の意見を一方的に聞いて、学校だけで取り組んでいくものではありませんよね。子ども(クラス)の今の育ちや課題を保護者(もちろんチームとしての学校の仲間たちも)と共有しながら、共に「夢と希望」を語っていきましょう。出来ることはアル。
ユネスコ(国連教育科学文化機関)によると、インクルーシブ教育とは「すべての子どもを包摂する教育」のことで、障害がある、性的マイノリティである、外国にルーツがある、ヤングケアラーの子どもなど、多様な子どもがいることを前提として、すべての子どもの教育の保障を目指すものです。重要な点として、インクルーシブ教育は「結果」ではなく「プロセス」であることが挙げられます。多様なニーズを持つ全ての学習者が排除されず、学びに参加できるように取り組み、対応するプロセスそのものが、インクルーシブ教育ということです。そして、そのゴールには、多様なすべての子どもが共に学び、さらには人々が互いに、多様なあり方を認め合える全員参加型の「共生社会」の実現があります。
国際文書に初めてインクルーシブ教育が明記されたのが「サラマンカ宣言」です。1994年、スペインのサラマンカで開催された「特別ニーズ教育世界会議」において、ユネスコとスペイン政府によって採択されました。障害の有無に限定せず、「どんな特別な教育的ニーズを持つかにかかわらず、万人が教育を受けられるようにしないといけない」という「万人のための教育(Education for All)」を宣言している点で、国際標準としてのインクルーシブ教育の理念をよく表しています。
☆223日目(1.20)「出来ない」ではなく、「どうしたら出来るかなあ」
「なんでも相談・まんまるハート」の学習会へ参加してきました。東備地域自立支援協議会は、障がい者(児)の地域生活を支援し、自立と社会参画を促進するため、地域における障がい者等への支援体制の整備に関して中心的な役割を果たす場所であるとともに、障害者総合支援法の円滑な推進を図ることを目的として、備前市・和気町が共同して設置しています。同協議会は、4部会・2連絡会で構成されており、各種事業や啓発活動等に取り組んでいます。その中の子ども部会では発達等に関することについて、協議・企画運営を行っています。この日(1/9)は、「なんでも相談・まんまるハート」(子どもの発達が気になる保護者の方を対象とし、学習の場や相談会)があり、中学校での生活や進路・進学(入試制度)に関して情報交流を行いました。
さて、この会ではありませんが、いろんな学習会やの中やで、保護者から「原学級(←あえて。この意味合いが重要)での子どもの交流学習を希望しているんだけど、先生から、交流の時間はなかなか難しい(出来ない)。と言われて悩んでいる」と聞くことがあります。カリキュラム編成など学校の事情もあるのでしょうが、「出来ない」ではなく、「どうしたら出来るようになるか」と考えたいなあと本校ではいつも話しています。続く

☆222日目(1.17)1995.1.17を話す
たくさんの天災や人災、出来事や事件が起こりますが、その中から「どんなことを、どのように、朝の会や授業で語るのかは、とても大切なことだと思います。今年は、阪神淡路大震災から30年。「何を、なぜ、どうして自分は語るのか」確認しながら、語る機会を大事にします。
・阪神淡路大震災1.17のつどい実行委員会HPより
〈1995年1月17日 午前5時46分。
阪神淡路大震災が発生し、私たちの大切なものを数多く奪っていきました。
あの震災から、まもなく30年を迎えようとしています。
震災でお亡くなりになられた方を追悼するとともに、震災で培われた「きずな・支えあう心」「やさしさ・思いやり」の大切さを次世代へ語り継いでいくため、2025年1月17日(金)に「阪神淡路大震災1.17のつどい」を、神戸市中央区の東遊園地で行います。〉
この震災では、高層ビルや、高速道路までもが大きく倒壊し、現代の文明の脆弱さ思い知らされました。死者の数は6434人、負傷者は4万3792人。財産を多く失い、愛する我が家を失った人は、全壊、半壊合わせて24万9170棟で、全焼建物は7036棟でした。失ったのは数字に表れるものだけではありません。復興に際し、被災地域住民のそれまでのコミュニティも失われたとも言う人もたくさんいます。失ったことについていくら語っても切りがありませんが、想像を絶する痛みに耐え、この大震災 により私たちが未来に向けて得た、かけがえのないものは「多文化共生」と「ボランティア」といわれます。大震災が発生したこの年はボランティア元年ともされ、1月17日は「ボランティアの日」と定められました。実際に被災地に足を運んだ者は3ヶ月間で116万人、1日平均2万人を超えました。このボランティア文化が、後の東日本大震災にも、また、多くの海外の現場にもしっかり引き継がれるようになりました。教育現場では、小中高・大学などもボランティアが重要になり、本校でもボランティアは大切な取組となっています。
災害での被災者は何も日本人ばかりではありませんでした。多くの外国人も負傷し、200人の外国人が死亡しました。被災地となった兵庫県内の10市10町において被災時には8万人の外国人が居住していました。そのうちの4人に1人が日本語の読み書きが出来ませんでした。被災者を助けようとする情報がいくら被災地で行き交っても一向に恩恵を受けられない人がいること、日本社会の住人が日本語がわかる人ばかりではないということが震災で明らかになりました。そこから多言語での紙媒体やラジオ、インターネットコンテンツが日本で次々に生まれるようにもなりました。「言葉の壁」を取っはらう活動は、その延長線上に社会の壁は言葉の壁だけではなく「制度の壁」や「心の壁」に撤廃の取組につながっていきました。今、全国で、違う者同士が、〈共に生きる〉という目標に向かって、個として、組織的として、勢力的な取組が進んでいると感じます。たくさんのものを奪い去った震災ですが、1995年1月17日にうまれた「ボランティア」や「多文化共生」の樹を引き続き大切に育てて行けたらと思います。(にしゃんたさんの記事を編纂)
☆221日目(1.16)認知症サポーター養成講座から考える
昨年の11月に家庭科で、関係機関と協働で、中学生認知症サポーター養成講座の内容を基盤に、授業化を進め、2時間のプログラムを創って学習に取り組むことができました。
*認知症サポーターとは、〈認知症に対する正しい知識と寛容な理解のある、認知症の方やその家族らが暮らしやすい地域社会の実現を支援する方です。サポートといっても直接的な介護などをするわけではなく、認知症の人や家族の「よき理解者」としての活動がメインになっています。
役割や意義について、
(1)認知症に対して正しく理解し啓発する
誰もが認知症に対して偏見を持ってしまうものですが、とくに偏見の強い人は、認知症になると物事の判断がなにもできなくなってしまうと考える方もいます。しかし実際には、すべての物事を理解できなくなっているわけではなく、また感情やプライド、羞恥心があるのです。特に初期の認知症の方の理解力は、認知症でない方と同じようにできます。それにもかかわらず、必要以上に障害者扱いしたり、子ども扱いするとストレスがかかり、認知症の方の症状悪化を招く恐れがあります。正しい知識と寛容な理解を有したうえで、手助けの重要性を啓発することは認知症サポーターの大切な役割です。
(2)地域で協力体制を作り、認知症の方や家族を温かい目で見守る
一人歩きによって行方不明になったり、事故に遭ったりするケースが後を絶ちません。一人歩きによるトラブルを防ぐうえで重要なのが、相互扶助や助け合いのネットワークを構築し、地域全体で見守ることです。認知症の有無に関係なく、道に迷ったり、困っている様子がある方に対して声をかける、付き添うなどの親身になった振る舞いが認知症サポーターには求められます。
(3)すべての人が住みやすいまちづくりを担う地域のリーダーとして活躍する
多くの人は、認知症になると買い物や移動、趣味活動など地域の様々な場面で外出や交流の機会を減らしている傾向にあります。例えば、買い物に来た高齢者の様子から認知症が疑われる場合、まずは温かく見守り、必要に応じたサポートをすることは、認知症サポーターが率先して担うべき役割です。
さて、実際の授業では、知識偏重にならないように、ロールプレイを取り入れたり、小グループでのディスカッションを行ったりして多面的な学習の時間となり、豊かに学び合う時間となりました。
授業後の生徒の振り返りやメモに目を通すと、やはり、充実した学習内容であったことを確認できました。しかし、気になったことがひとつありました。それは、認知症にならない〈予防のための〉学習、(認知症になったらダメだという考え)にとどまってはいけないなあと思ったことです。授業プログラムづくりの時にも、「高齢による認知の衰えは誰にでもやってくること」を前提に、「自分たちはどんな社会をつくっていくか」の視座で、認知症の現実や、家族・地域社会の課題に迫っていこうと、学習内容の共通認識をもっていました。
新年度は、さらに、持続的な介護・福祉施設での体験学習(利用者、家族、スタッフなど多様な方々の聴き取り学習も)を地域協働の活動の中で進めていくことができればよいなあと思っています。
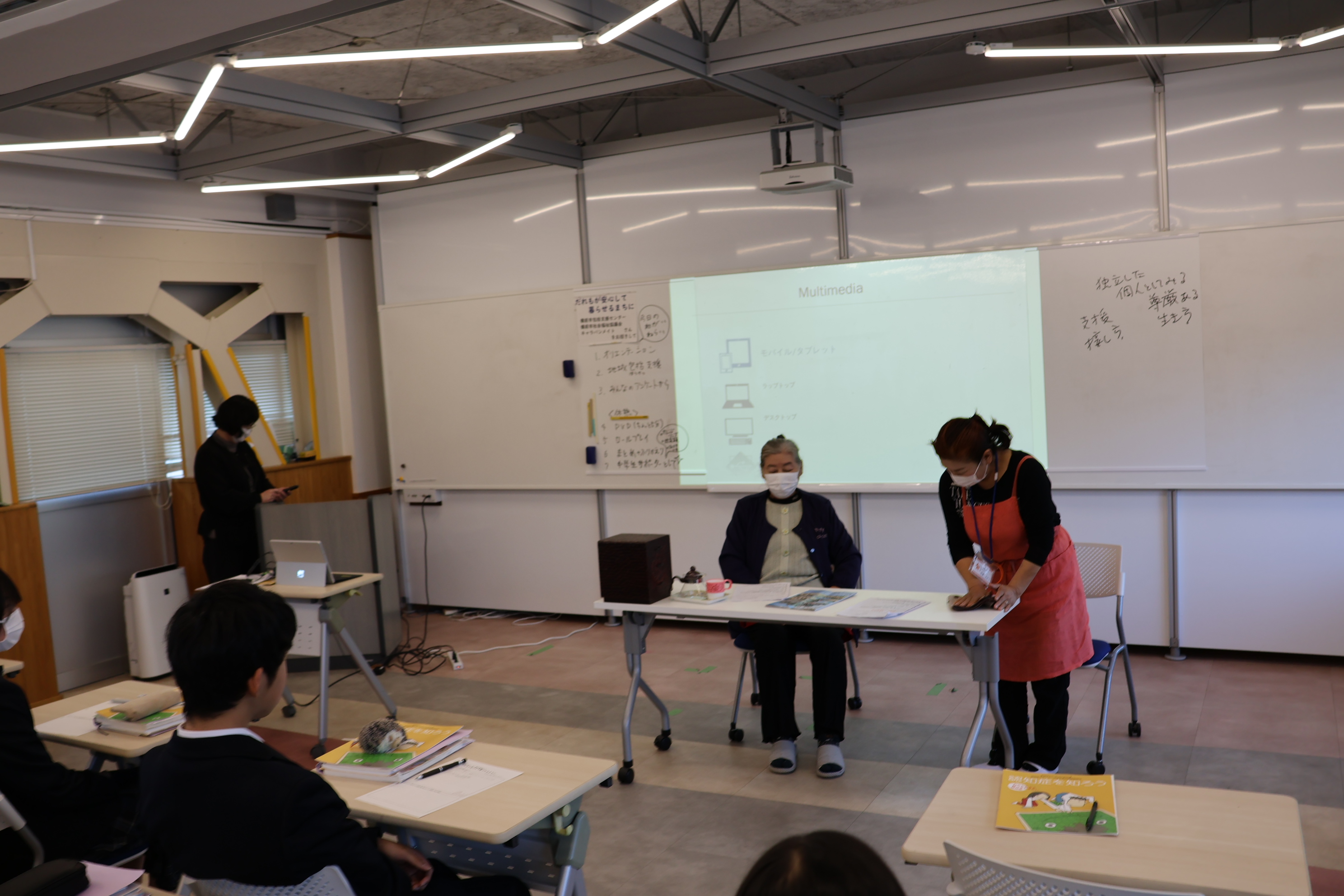
☆220日目(1.15)個人モデルと社会モデル
「個人モデル」とは、障害者が困難に直面するのは「その人に障害があるから」であり、克服するのはその人(と家族)の責任だとする考え方であるするのはその人(と家族)の責任だとする考え方である。それに対して「社会モデル」は、「社会こそが『障害(障壁)』をつくっており、それを取り除くのは社会の責務だ」と主張する。人間社会には身体や脳機能に損傷をもつ多様な人々がいるにもかかわらず、社会は少数者の存在やニーズを無視して成立している。学校や職場、街のつくり、慣習や制度、文化、情報など、どれをとっても健常者を基準にしたものであり、そうした社会のあり方こそが障害者に不利を強いている――と考えるのが「社会モデル」である。「障害があるから不便(差別される)」なのではなく、「障害とともに生きることを拒否する社会であるから不便」なのだ、と発想の転換を促すのである。
●なぜ社会モデルか
社会モデルは、さほど革新的な概念には見えない。社会に問題があるのは当然であり、今日よく聞かれる「バリアフリー」や「ノーマライゼーション」とどこが違うのか、と思われるかもしれない。だが「バリアフリー」という言葉の氾濫に比べて、多様な障害者にとって何がどう「バリア(障壁)」なのかに関心が高まっているだろうか。スロープのようなわかりやすいシンボルは別として、多くの障害者にとって切実なバリアは残ったままであるし、その理由も問われてはいない。また「ノーマライゼーション」のかけ声の一方で、なぜアブノーマルな生活を障害者が強いられてきたのかは必ずしも意識されていない。確かに「バリアフリー」や「ノーマライゼーション」は、社会モデルと重なる部分を持つが、そうでない部分もある。これらの概念は、現行社会の構成原理そのものを問うよりは、部分的改良で対処することを可とするものであるし、何より、社会モデルのように社会の全体像を捉えようとするものではないのだ。
社会モデルはものの捉え方を変える。例として「ろう者が講座に出たいが手話通訳がない」という状況を考えよう。「耳が聞こえないから参加できない」と考えるのが個人モデルであり、その場合、手話通訳の用意は「例外的、恩恵的な特別措置」となる。だが社会モデルではそもそも主催者が多様な参加者を想定していないことが問題なのだから、手話通訳は「本来、用意すべきこと」であり、ろう者が主催者にそれを求めるのは当然の権利だ。主張しづらいのが現実だが、「たった一人のために予算を使えない」といった多数派の論理に抵抗し、権利を求める根拠となるのが社会モデルなのである。
●社会モデルは別名「人権モデル」
社会モデルは「人権モデル」と言いかえられるほど、人権と親和性が高い概念である。当事者運動の過程で血肉化された社会モデルの考え方は、個々の障害者が直面する問題を、徹底して社会の文脈で捉える思想であり、運動における武器でもあった。駅の改良にせよ、
教育や就労をめぐる闘いにせよ、個人の努力や周囲の支援に頼るのではなく、社会の側の責任として解決すべきだと運動は主張してきたし、その認識を社会一般に広めようともしてきた。「社会モデル」という言葉を使わなくとも、日本で行われてきた障害当事者運動は社会モデルの視点を含んできた。障害者問題を人権の視点から捉えるならば、社会モデルは不可欠の視点なのである。(大阪府HPより)
219日目のイラスを、社会モデルとして考えてみると、だれの課題として捉えるかも重要になってきますね。
☆219日目(1.14)ちがいをどう説明するか?
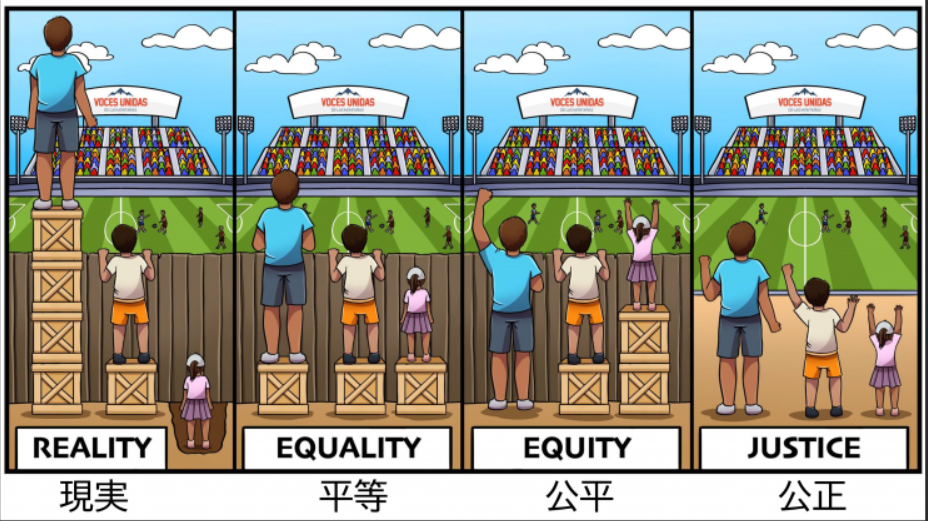
となりの席の先生と話題になりました。違いをどう説明しますかね。
☆218日目(1.10)子どもの姿・学び、実践からみる
全国人権・同和教育研究大会での分散会のまとめの一部に、働き方改革について少しだけ書きましたが、その続きです。知り合いが、先日テレビで、働き方改革の取り組んでいる学校のニュース報道を視聴したそうです。とても長時間労働の短縮を中心とした積極的な取組だったようですが、少し違和感というか物足りなさを感じたとのことです。その知り合いにいろいろと話をしてみると、岡山では、保護者に向けて、『働き方改革の目的 学校の働き方改革にご理解・ご協力をお願いします。』とし、続いて『この改革の目的は、学校のこれまでの働き方を見直し、教員の健康を守ることはもとより、教員が新しい知識や技能を学び続ける時間を確保し、自らの人間性や創造性を高めることで、子どもたちに対してより良い教育を提供することができるようにし、子どもたちの豊かな成長につなげることです』とあるのだから、長時間労働を短縮した具体的取組の紹介も必要だろうけど、その結果として、どのように授業研究・準備の質が高まり、仲間づくり(学級・学年経営)の内容が深まったかという実践をしっかりと示すことが大切だろう、とのこと。私はニュースを視てないので簡単には言えませんが、限られた番組の時間内で、「インパクトのある情報」としてニュース編集するには、時間が足りないこともわかりますが、この働き方改革の目的を鑑みると、「子どもたちはどう思っているのか」「子どもたちはどう変わったのか。」をじっくり聴いてみたいなあと思いました。
☆217日目(1.9)光あるうちに
先日、先輩から『光あるうちに―中世文化と部落問題を追って』横井 清著(阿吽社)を頂き、少しずつ読んでいます。読み応えがある本です。教育にかかわる者として、「謙虚」に、「誠実」に、「実直」に、あらためて部落問題に取り組まねばならないと思いました。(←抽象的ですが。)
阿吽社のHPでの本の紹介です。・・・〈ひたすらに内なる心音の伝え来る差別意識の波長に耳傾けてきた異色の中世史家が、ついにこの一書の中に佇み、中世文化・部落問題・故郷京都を取り結んで自らの軌跡を問う。〉
◆目次紹介
I 中世文化の探究
1 中世人と「やまい」
2 賤視と救済
3 「心理」と「時空」――『看聞日記』の世界
4 民衆文化の開花
II 部落史・部落差別への照射
5 部落史研究の到達点と課題(中世)
6 部落史研究と「私」
7 旅の人
8 私たちは、新鮮か――部落問題を富山県で考える
9 心理と思想の狭間から――藤田敬一著『同和はこわい考』を読む
別編 京都幻像――ある小宇宙
解題 中世文化と部落問題を追って
☆216日目(1.8)「かわいそう」?なんだかヘンな気持ち。
岡山シティミュージアムの特別展「ヨシタケシンスケ展かもしれない」に行ってきました。ヨシタケシンスケさん初の大規模個展となるそうです。作家の発想の源である小さなスケッチや絵本原画、展示会のためにヨシタケさんが考案した立体物や愛蔵のコレクションなどが展示され、作家の「頭のなか」がのぞけるそうで、〈発想の豊かさに支えられたヨシタケさんの「かもしれない」展示空間を、ぜひご体感ください。〉とありました。気になる展示がたくさんある中で、これもじっくいろんな人と語り合ってみたいなあと思ったのは『みえるとか みえないとか』という絵本です。持っている本なのですが、展示されているヨシタケさんのメモ・スケッチと併せて読んでみたら・・・。
この作品は、伊藤亜紗さんが光文社から2015年に出版した『目の見えない人は世界をどう見ているのか』をきっかけに、ヨシタケシンスケさんが伊藤さんに「そうだん」しながらつくった絵本です。本の紹介文はこうあります。
〈同じところを探しながら 違うところをお互いにおもしろがればいいんだね ぼくは宇宙飛行士。調査のために降り立ったのは、なんと目が3つあるひとの星。ぼくは普通にしているだけなのに、「うしろが見えないなんて不便そう」「かわいそう」って言われて、なんだかヘンな気持ち。そこで、目の見えない人に話しかけてみる。目の見えない人が「見る」世界は、ぼくとは大きく違っていた!(2018年7月発売/アリス館)〉
11月の読み語り(読み聞かせ)で選べばよかったかも。
☆215日目(1.7)新年を仲間と迎えること。
終業式の学級活動に、教室に入る機会がありました。通知表を渡す時間のウラで、子どもたちは、カードづくり(年賀・クリスマス)に取り組みました。自分自身の新年の抱負と、仲間へのメッセージと共にイラストを添えて、一人ひとりがステキなカードを作成しました。教室の窓に掲示して、お互いの見合っていました。冬休みの宿題(ワークブック)をコツコツと個々でするのもよいけれど、「この時間」に、「ここに居る仲間たち」と「共有できる活動」のなんとすばらしいことよ。そういえば、夏休み前の終業式では、暑中見舞い作成もできますね。仲間との意識が高まり、表現力の一助と。

☆214日目(12.24)聞き合う・話し合う、学び合う場を。
Si quid me fuerit humanitus‚ ut teneatis Quintus Ennius‚『Annaies』
今年11月29日~12月1日に参加した、全国人権・同和教育研究大会でのまとめ(総括)の一部です。
協力者として感じたことや考えたことを、皆さんといくつか共有したいと思います。
大会前に事前に送られてきたレポートを読む中で、「もっと聞きたい」ということがたくさんありました。この2日間の分散会の中で、しっかりと「聞き」「話す」ことがとても大事だということを再認識することができました。
2つめに、水俣事件で活動された川本輝夫さんは、「情熱とは、事あるごとに自分の意思を表明することである。」という言葉を残されています。私もこの言葉を大事にしていますが、本分散会の4本の報告では、「自分がどんな意思を持って取り組んでいるのか」、「私たちが大事にしていくことは何なのか」がしっかりと示されていたように思います。
「語ること」が、二日間を通して話題になりました。「しんどいことをいつまで語り続けなければならないのか」という大事な発言を受けとめながら、私は「語っていただきたい」と思っています。それは、語っていただいた事を、「聞いた」私たちの方がどう受けとめるのかということが大切ではないかと考えるからです。私の住んでいる地域でも、ハンセン病問題学習に取り組んでいて、回復者のお話を聴く学習を大切にしていますが、お話しをして下さる方が少なくなっている状況があります。ある時に回復者の方のお話しを聴く学習会を開催したら、先輩が「あなたは、どんな目的で話を聴こうとしているのか?あなたは、何を伝えたいのか、何を問いたいのか、自分がなぜハンセン病問題にかかわり続けるのか、そこを明確にしないと、被差別の立場の当事者を利用しているだけではないのか」と指摘されました。その出来事は、もう一度「自分の立ち位置をはっきりさせなくてはいけない」ということに気づかせてくれました。「語る」方の、思いや願いを受けとめる私自身の問題なのです。今日、討議の中にあった、〈「語り」を聴き、それを「返していく」やりとり(つながり)〉を、私も会場の皆さんと共に、大切にしていきたいと思います。
最後もう一つは、分散会の協議の中では出ませんでしたが、いわゆる「働き方改革」が学校現場ではすごい流れで進んでいます。しかし、子どもとの時間を創ることを目的としているはずなのに、時間外在校時間を短縮することが目的化しているのではないかと感じることがあります。その中で、先輩たち、私たちが培ってきた同和教育を基軸とした人権教育実践も形骸化が進んでいるようにも思えるのです。今年の進路保障分科会に参加する前に、30年前、全同教が出版した『学校同和教育実践講座LUMIERE 進路保障の課題と実践(1993 解放出版社)』を再読し、その本に実践報告が掲載されている先輩に会って「進路保障」についていろいろと話を聞きました。その話の中で、「今の働き方改革の中で、私たちが本来すべき大切なしごとをどんどん減らしているのではないか?」とたずねたら、「目の前に転んで足を擦りむいている子どもがいたら、ほっとけないだろう。絆創膏を貼ったり、頭をよしよししたりせん(しないと)と!。子どもたちの最前線にいるのは自分たちである。それをせずして、何のための学校なのか、何のための教員なのか。働き方改革はそこを抜きに考えたらおえまあ(いけない)」と言われました。そんな話を重ねながら、この2日間の分散会で再確認することができました。目の前の子どもたちのその最前線に居る覚悟というか、明日からも「やっていかないといけない」と思っています。また来年会いましょう。
☆213日目(12.23)語らせるのか?語るのか?
ファシリテートについてちょっと話題になりました。その意見の中のひとつ。「ファシリテーターは、語り手の話すことを、自分の進めたい方向に誘導する側面があるのではないか?」という内容についてどう考えますか?偶然に、映画『スープとイデオロギー』監督ヤンヨンヒ:2021年製作/118分/G/韓国・日本合作)を視聴しました。映画評でもありませんし、ネタバレではありませんが、その中で、監督として撮影しながら、娘であるヤンヨンヒが、母に「済州4.3事件」を〈語らせようとする〉ようにうつりました。その後監督(娘)は、母と共に、済州島に渡り、再度、事件のことを想いださせようと問いかけていくのですが、だんだんと話をしなくなる母親。そして〈何も語らない〉母の姿からとても大切なことに気がつき、娘として自分自身が語るシーンと、本題が重なりました。(抽象的な内容でごめんなさい。視聴してみてください。事前に『ディア・ピョンヤン』も)
参考:作品紹介:「ディア・ピョンヤン」などで自身の家族と北朝鮮の関係を描いてきた在日コリアン2世のヤン ヨンヒ監督が、韓国現代史最大のタブーとされる「済州4・3事件」を体験した母を主役に撮りあげたドキュメンタリー。朝鮮総連の熱心な活動家だったヤン監督の両親は、1970年代に「帰国事業」で3人の息子たちを北朝鮮へ送り出した。父の他界後も借金をしてまで息子たちへの仕送りを続ける母を、ヤン監督は心の中で責めてきた。年老いた母は、心の奥深くに秘めていた1948年の済州島での壮絶な体験について、初めて娘であるヤン監督に語り始める。アルツハイマー病の母から消えゆく記憶をすくいとるべく、ヤン監督は母を済州島へ連れて行くことを決意する。
☆212日目(12.20)子どもどうしをつなぐファシリテーションって。
「ファシリテーター」について聴かれました。以前、森田ゆりさんの『多様性トレーニングガイド』をもとにした、ファシリテーター養成講座の受講はとても貴重な体験で、以後の自分自身の授業づくりやワークショップや研修会などの基盤となっています。
facilitate=「促進することを容易にする」という意味で、主役である「参加者」が話し合いや会議などの参加型の場において,「何かをする」ことを促進したり,やりやすくするための手法です。(捉えようはたくさんあります)2000年代から拡がった参加型学習は、①自ら“主体的に参加”して,“体験”から学ぶ②“お互いから”学び合う③参加者自身の多様な経験が学習資源となることが特徴です。そして参加型学習は、現代的課題解決へのアプローチ、 “学び方”を学ぶ(“何を学ぶか”より“どのように学ぶか”を重視)、当事者意識を育むことができる学習スタイルのひとつです。私は会の進行をしながら以下のことも意識しています。
○本気で聴く傾聴(非言語メッセージ:身体・表情・視線・声や口調・姿勢,動作・距離感)
・参加者の多様性をありのまま,そのまま受けとめる
・うなずき,あいづち(聞いてもらっているという安心感)
・「聞いていますよ」というメッセージを伝えることが大切 「なるほど」,「○○さんはそう思うんですね」
○会をつくるための問いかけ
・開かれた質問(オープンクエスチョン)→ 広げ深める
・閉じられた質問(クローズドクエスチョン)→ 絞り込む
・問いかけ,待って,引き出す(プル)
・圧力(プッシュ)をかけて,促進する
☆211日目(12.19)子どもどうしをつなぐコトバは?
田村学芸員さんと大学生をお招きし、ハンセン病問題学習で取り組んでいる〈今〉、「どんなことを考えたのか?学んだか?」をクラスの中で意見交流を行う授業を行いました。子どもたちが仲間の意見に「重ね」ながら、自分の意見を語り、そこからまた、自分の考えが深まっていくことが出来ればよいなあと、ファシリテーションの意識をもって授業進行を心がけましたが、授業が終わってみれば、やはり、反省点がいっぱいありました。
先日読んだ『部落解放11月号 子ども・教育 自由ノート「128授業中の「禁句」』の園田雅春さんの文章をもう一度読み返しています。一部を紹介します。『・・・子どもAの発言を、「なるほど」と教師が先取りすれば、その授業場面は教師と子どもA、両者に限定された一対一の閉ざされた関係で終わってしまう。そもそも、子どもAは教師だけを相手に発言したのだろうか。もし、そうなら『みんなに対して発言してよ』とばかりに促すのが教師の役割ではないのか。それもせずに教師がAの発言をまっ先にキャッチし、「なるほど」と子どもたちに先んじて応答。これは横取り的な行為に当たらないか。「なるほど。」この一言は、Aの意見に納得する子どもや、肯定した子どもが自ら発する言葉なのだ。納得したことを子どもBが自分の言葉で発言。それを聴いた子どもCが補足したり、新たな自分の意見を表明したりする。このように子どもたちが主体的に展開する授業の「起点」を大切にしたい。学年があがるにつれて、教師からよりも、仲間からの「なるほど」に始まる応答の方が、よろこびが増すことも確かだ。子どもの自主的な発言が続かないために教師が「他にありませんか」と促す場面もよくある。しかし、「なるほど」「他に」という言葉は、子どもどうしの意見の連続性を断つ「切断語」。そう自覚し、教師の「禁句」としたい。』
人権教育実践の中で、「子どもどうしをつなげる」とはよく語られますが、日々の授業の中でどれだけ意識できているか・・・。校内でも議論したいと思います。

写真はハンセン病問題学習での田村さんからの提起
☆210日目(12.18)当事者研究となかまづくり
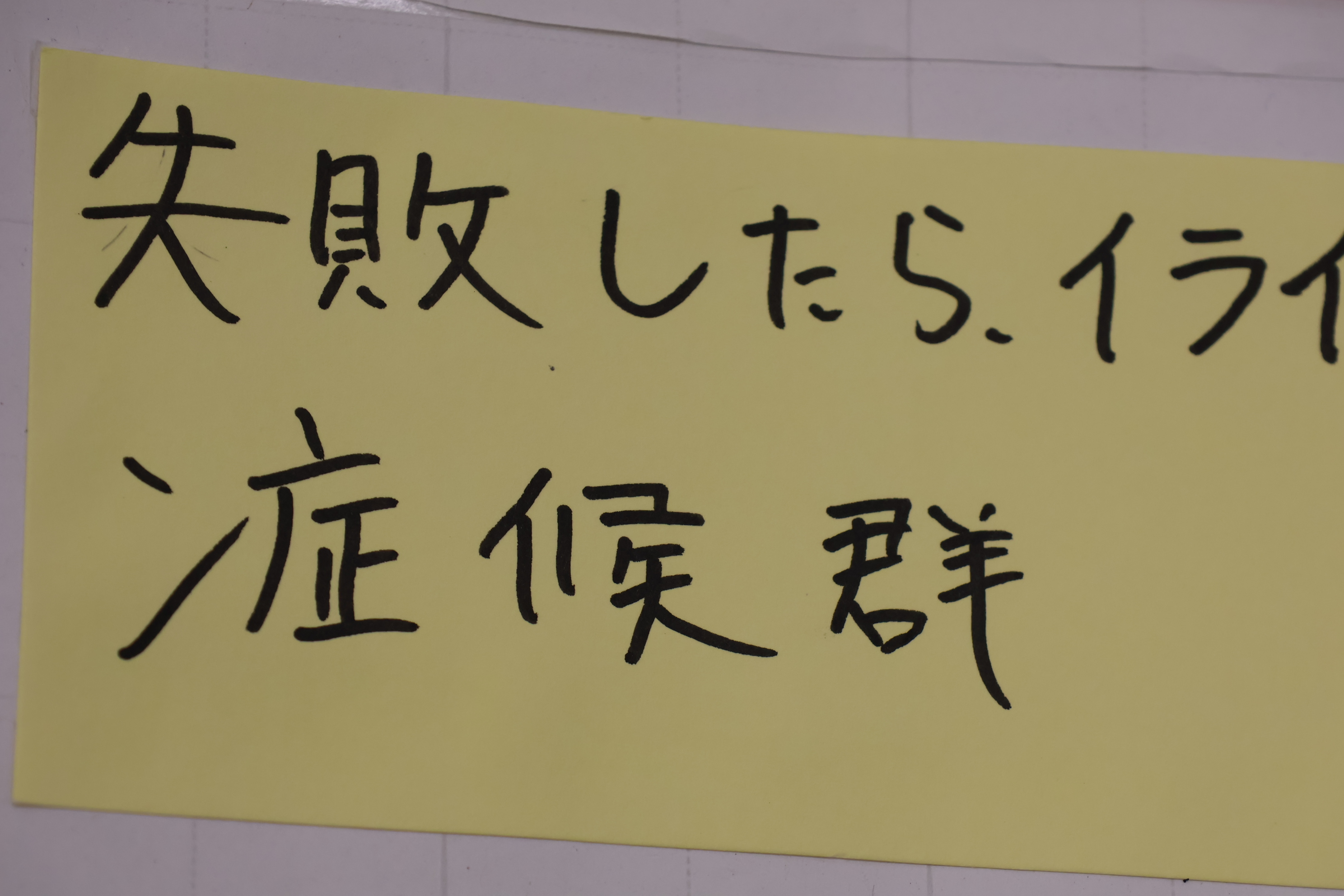
一年生全員が、それぞれの特性(ニガテ、くせ、持ち味)について、クラスメートに伝え、自分自身の付き合い方を話し、またクラスの仲間からのアドバイスを受けました。これは、べてるの家の当事者研究と、同和教育実践の仲間づくりを重ねたものです。
当事者研究については、『自分を助ける方法としての「当事者研究」とは(TOKYO人権 第97号(令和5年2月28日発行)』を、ご参考に転載します。
―「自分自身で、ともに」で社会とつながる
自らの生きづらさにアプローチする方法として、近年、「当事者研究※1」が注目を浴びています。「自分の苦労の研究者になってみる」というアイデアで、2001年に精神障害などを経験した当事者の自助活動の一つとして生まれました。現在では、病気や障害だけでなく、引きこもり、子育てなど幅広い分野で実践が広がり、2022年3月には『子ども当事者研究』として出版されるなど、子どもたちも取り組めるような内容として咀嚼(そしゃく)されてきました。「当事者研究」の魅力などについて、社会福祉法人浦河べてるの家※2理事でソーシャルワーカーの向谷地 生良(むかいやち・いくよし)さんにお話を伺いました。
自分ごととしての研究
当事者研究は、病気が原因で「爆発」を繰り返す青年に、向谷地さんが「一緒に研究してみない?」と提案したところから始まりました。以来、共通の悩みを抱えた人が、経験を共有しながら「自分の助け方」を見出す方法として全国で運用されてきました。困り事を研究対象として一旦自分から切り離して捉え、家族や仲間たちと語らいながら対処法を探るというスタイルが特徴で、実験感覚でワクワク感を持って取り組めることが魅力といわれています。
例えば、こんなエピソードがあります。自罰傾向が強く発作的に顔面を叩いてしまう人が浦河にやってきました。その人は、発作のたびに病院を受診して鎮静剤を打っていました。浦河に来て間もなく発作が起きたとき、そこにいた仲間が一緒に「発作の止め方」についてワイワイと研究をはじめ、一人のメンバーがその人の脇腹をくすぐると本人が大笑いして、発作が止まりました。その人は、「今まで専門家に任せきりにしていたけれど、自分のことだったんだ」と気づいたそうです。お互いに助け合い、新しい発見をし合う中で、自分の苦労を自分ごととして取り戻す、そんな作用を生む試みとして、当事者研究は知られるようになりました。
困難さは社会とつながっている
「自分自身で、ともに」をキーワードとする当事者研究には他に、「他者を助ける」という重要な作用があります。現在、困難を抱えていない人たちが、困難な状況を生きてきた人たちから学べることは大きいと向谷地さんは指摘します。「精神障害がある人たちの困難さと、一見何事もないように暮らしている人たちの日常は、つながっています。メンタルヘルスの危機というのは、個人的にたまたま不調になったというわけではありません。周囲や地域の事情とも関連していて、社会環境的に生み出されている部分があります。閉鎖された病棟の中で治療されるよりは、その人たちが発信することによって、多くの人にとって、回復の手がかりを得ることができます。社会の側が学ぶ、気づいていける部分がとても大きいのです」。
「人」と「出来事」を分けて考える
もう一つ、人権を考える上での重要な視点を、当事者研究に垣間見ることができます。「当事者研究では、『人』と『出来事』を分けて考える工夫をします。そうすることで、どんな問題や困難が起きても、その人が問題ではなく『問題が問題なのだ』と捉えることが可能になります。何か失敗したとき、自分自身を『ダメな人間だ』と思い込んだり、問題を起こした人を『問題な人』にすり替えて考えたりなど、人と問題を同一視する思考に陥りがちです。人間の存在価値は、本来、失敗や成功、問題の大小によって損なわれるものではありません。当事者研究で、多くの人たちと現実を共有することによって、その現実を生きている人たちをみんなで応援しようという社会の空気をつくっていく作業ができるようになったと思います」と向谷地さんは語ります。
「人づくり」「地域づくり」の可能性
実践の中でお互いの「弱さ」や「苦労」を持ち寄ることで、人と人が繋がり、その場に信頼と助け合いが生まれます。「当事者研究には『自分のことだけれども、みんなのことだ』という、共同性のような土俵をつくる力があります。対話を通じた『人づくり』であり『地域づくり』の活動の一つにもなる」と向谷地さんは考えています。
「当事者研究にマニュアルはない」と向谷地さん。「大切なのは、『ちょっと研究してみようかな』という思考を持ちながら暮らし、その考察を共有すること。一人で抱え込まないで、みんなで助け合って知恵を出し合い、身近なところで生かしていく。そうすることで、地域も社会も元気になるのでは」と呼びかけています。
・向谷地 生良(むかいやち・いくよし)
・インタビュー・執筆 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター専門員)
※1 参考になる情報:向谷地さん執筆の『レッツ!当事者研究』(べてるしあわせ研究所)のほか、メンタルヘルスマガジン『こころの元気+』で毎月、べてるの家の当事者研究を紹介しています。
たくさん本も医学書院さんから出ています。べてるの家には、〈三度の飯よりミーティング〉というコトバがあります。
☆209日目(12.17)「聴き取り」からの進路学習のススメ
学習所見を考えてみましたら。
・所見案1『「職業調べ」の学習では、●●の仕事について調査活動を行った。とくに仕事内容や必要
な資格、中学校卒業後の進路などについて調べた内容を取捨選択し、わかりやすくレポートにまとめることができた。これらの活動を通して、自分の将来について深く考えようとする意識を高めることができた。』
・所見案2『「身近な人からの聴き取り」では、親から若い頃から働いてきた仕事の苦労や、生きがい、そして親の進路に対する願いを聴き取ることができた。親の思いをしっかり受け取り、自分のこれまでの生活を見つめ直し、進路実現に向けての大きな指針となった。また、聴いた内容をまとめ、クラスで発表したことは、級友同士の理解がさらに深まると共に、進路を切り拓いていく学級の意識が高まった。クラスメートからの質問に応えたり、意見交流をしたりする姿は、確かな学びに裏打ちされた自信にあふれ、とても堂々としていた。』・・・これは所見ではないな。添削だらけの予想。
☆208日目(12.16)ハンセン病問題学習をどう進めるか 一考③
●まとめにむけて【準備】
*個人テーマの決定&分担テーマの分担(パネル説明書の分担)・これまでの学習をもとに ・「正しく知る 正しく行動する」を受けて
●【⑤⑥時間目】 「過去・現在・未来」をつなぐ学習内容を地域社会へ発信する
・学習してきたことをもとに、歴史的場所・施設の学習写真展示パネルの説明文をつくる
・掲示・啓発活動を日生中学校3年生として取り組む
・1月中旬→日生地域公民館、本校廊下へ掲示〔保護者・後輩へ) 表現/発信
・写真パネルは岡山県人権教育研究協議会から、啓発パネル「麦ばあの島」は邑久光明園から借りる
●【本学習以後の取組(調整中)】
○保護者(親子)希望者向けの長島現地研修〈東備まなぶ会主催など〉
○就職差別の撤廃の取り組みにつなげて「統一応募用紙の成立」についての学習
○3月卒業時の個人答辞づくり→代表の卒業生答辞づくり
○進路公開へ
☆207日目(12.13)ハンセン病問題学習をどう進めるか 一考②
~学ぶこと、考えること、そして生きること~
◎【4時間目】過去・現在・未来につなぐ 12月13日(金)⑥14:45~15:35
(1)めざしたいこと
・「未来へつなぐ」とはどういうことか?具体化できるようにする
・「これまでの自分の生き方・課題」を見つめて(重ねて)考え、語る
・個人モデルではなく、社会モデル(社会のありよう)の視座で考える
・「差別をなくそうとする主体者」としての立ち位置をつくる
・「人はなぜ差別するのか」を自分のコトバでまとまる
(2)エリアティチャー(AT) ・長島愛生園 田村学芸員さん ・岡山大学 学生4名 桑原さん
(3)授業のながれ(授業者(ファシリテーション))
テーマの共有『ハンセン病問題学習から何を学び、何を伝えていきたい(どう生きていく)?』(2分)
○AT紹介(3分)
○田村さんから提起
『ハンセン病問題にかかわって~君たちと共に、そして託したいこと(仮』【約15分】
・愛生園の「事実」から「課題」を知る ・未来へつなげるとは?必要性は?!・何を学び、何ができる? ・どんな社会をつくるか
○質疑応答(田村さんの提起をさらに深く理解するために *質疑の質も高める)
□生徒からの質問と田村さんの応答→場合によっては他の学習者にも聞く事アリ
□学生からのモデル質問と重ねて *関連質問 *これまでの自分の生き方に重ねる思考 *社会モデルの視座で【5分】
○討議・意見交流【20分】
□『自分はハンセン病問題学習から何を考えたか?何を学んだか?』について
・中学生の意見を中心に、大学生の学び(生き方)に関する意見を挟む
・生き方や具体的な活動に言及している発言者の意見を聞き、中学生がさらに学びを深めさせたい。
○まとめ
□田村さんから 大学生1名~2名) 今日の授業のまとめ
○日生中学校3年生へメッセージ【5分】
○授業終わり(あいさつ)
(3)留意点
○桑原先生と学生さんに、授業内容へのご意見をいただき、共通理解をお願いしたい
○中学生は本学習後に、展示の取組をします。その文書の中に「学び(伝えたいことやどう生きるか)」をまとめます。現時点では学習の途
中段階です。
☆206日目(12.12)ハンセン病問題学習で何をどう学んでいくか 一考①
先週末にフィールドワークに出かけた子どもたちは、今週、田村学芸員さんと、岡山大学で教職を学ぶ学生さんらをお招きして、意見交流学習を行います。〈過去・現在・未来をつなげる〉と私たちは簡単に言ってしまいますが、これまで学習したことを整理しながらカタチのある学びにしていかなければならないなあと思っています。
具体的な学習案(概略)
【社会科】公民分野「基本的人権の尊重」
【1時間目】
Q小学校での学習やニュースで知っていることや覚えていることはどんなことか?をもとに
・人はなぜ差別するのか(なぜ差別されたのかでなない視座で)・ハンセン病学習ではなく、ハンセン病問題学習として
・義務教育最終年度…人権を大切にできる人間として シチズンシップ(市民性)高めたいね。
・岡山(東備地域)からの発信者として
・資料・ワークシート配付、リーフレット『ハンセン病の向こう側』活用
QDVD『人間回復の橋、こころのかけ橋となれ』視聴学習【29分】
・ワークシートの6つの質問で復習(基礎的な学習)【10分】→まとめ【5分】
・素朴な質問や疑問に応えていく。関心をもって学んでいくことを具現化
・人間の思考(そう簡単ではない「自分事としてとらえること」へ!社会の在り方・自分の生き方と重なる授業の組み立てに)
Q次回・ナガシマで生きた「ひと」、金泰九さんから考えてみよう
【2時間目】〈授業のながれ GT久次同伴〉
Q前時の授業での疑問や質問をもとに
Qドキュメンタリー映画『虎ハ眠ラズ』視聴学習【43分版・30分版】振り返りの時間を確保する
Q金泰九さんに小感想を書く
・深くさらに学ぶために(疑問やさらなる問い)
【3時間目】長島愛生園現地研修(岡山県ハンセン病療養所入所者地域交流事業補助申請可 本校は備前市スクールバスの活用)
・学年PTA人権教育研修会と位置づけて、希望があれば保護者の参加も促す。風邪、インフルエンザ等の流行に留意
〈予定・調整〉12月6日(金)9:55中学校発~12:45中学校着
…FW(3年団 生徒)& 歴史館見学学習
・10:25~12:00フィールドワーク
・12:00~12:20歴史館見学(ワークシートとバインダー持参)
・12:20愛生園発 12:45中学校着→給食準備
☆205日目(12.11)生徒指導と人権教育
他校での人権教育実践を教えてもらいました。例えば、「教室のものを誤って壊した」時にどんな指導をするか?ということ。昨今は、個人への指導や注意で終わる場合が多いのでないでしょうか。その学校では、起こった出来事を、集団(クラス)にかえすことが出来るか(必要性があるか)?を考えて、多くの場合、クラスの問題として捉え、きちんと子どもから子どもへ話す(当事者がクラスの仲間に報告する)営みを大事にしているとのこと。あたりまえの視点だと思いますが、古い教育実践のようで、いま、必要な新しい教育実践だと思います。特別支援教育の「個々」の支援はもちろんですが、「クラス全体」への思考は、益々重要となっていますね。
☆204日目(12.10)人権週間にあたって②~世界人権デー
続きです。
(4)個人の尊厳を守る
個人の尊厳を守るということは、自分を大切にするのと同じように、他人を大切にし、人を傷つけないことだね。
ひとの性格や行動、顔や身体のかたち、学校の成績などによって差別してはいけないね。もちろんその人の家の職業や出身や宗教、考え方、男女の性別、民族などによって人を差別してはいけないのはわかるよね。就職や結婚の際にそのことで差別することは許されないね。
以上のことをまとめていうと、『人間が人間らしく生きていくうえで、欠かすことのできない自由や権利のことを〈基本的人権〉というんだ。基本的人権が大事で、他のひとの人権を侵す差別がいけないことだということは、君たちはわかっているはず。
でも
「差別がなくなればいい」と考えているだけでは見当違いです。いくら差別が悪いことだとわかっていても、それだけで「差別をなくす力」にはならないからです。
みんなが安心して登校し、静かにゆったりした気持ちで勉強し、遊び、そしてスポーツや生徒会活動にうちこめるようにみんなで努力し合うことが、身近な人権尊重の一歩となります。
(5)江戸時代の末(1855)にあった『渋染一揆』に学ぶ
つい先日、2年生が社会科で学習した「渋染一揆」。この一揆を成功させた人々のうごきを調べてみると、私たちが差別をなくし、共に生きる社会(クラス)をつくるための方法を知ることができます。簡単にまとめていますが、とても大事な視点です。人権週間にあたってみなさんに紹介します。
①差別がここに、こんなかたちであるという事実に気がつくこと!(高い人権感覚)
②その差別はどれほど私たちを苦しめているか、怒りをおぼえること!
(相手の立場に立って、そのつらい気持ちをかんがえてみること)(正しい人権意識)
③その差別のなりたちや、しくみがどうなっているかを学び、差別をなくする道筋を明らかにすること!
(仲間としっかり語り合う 冷静に状況を分析する)
④差別をなくするために、なかまと共に、どういう働きかけをしたらよいか、差別をなくする力(行動力)を身につけること!
(みんなで正しく行動する うごかす(すべ)を整える)
☆203日目(12.9)障害者の日ということですが
角岡伸彦さんの著書『カニは横に歩く 自立障害者たちの半世紀』を紹介します。
行動するCPたちの痛快・青春ノンフィクション! 「カニって横に歩いてるやん。誰も不思議に思わへんやん。障害者が健全者と違う歩き方をしてるのは当たり前のことちゃうの」行動するCPたちの痛快・青春ノンフィクション!「カニって横に歩いてるやん。誰も不思議に思わへんやん。障害者が健全者と違う歩き方をしてるのは当たり前のことちゃうの」1977年、川崎市でバスジャック事件を起こして、それまで顧みられなかった障害者のバス乗車に一石を投じた過激な障害者運動団体。それが「青い芝の会」である。著者の角岡伸彦氏は、ときに介助者として、またときには取材者として、過去27年間「青い芝」と深く長く対面してきた。本書の内容は、あまりにもひどい差別、どう考えてもやりすぎの闘争、真剣だけどユーモアを忘れない爆笑エピソードなど。障害があること。老いること。本書は「あるがままの生」という遠大なテーマに挑んだ本格ノンフィクションである。
●本文から「なんかの集会の時にね、福永が俺に『黙れ、健全者!』と言いよったんや。俺は言い返した。『お前、それはやめた方がええで。黙れ健全者言うんやったらな、健全者の方は黙れ障害者と言うで。君、それ反対できひんで。何々を言った健全者は黙れというのは、まだわかる。けど、健全者だから黙れというのは、そんなものはどこへ行っても通用せえへんで』」(第2章 宣言)仲間の自殺を知った関西青い芝は、緊急役員会を開いた。「私たちを殺す施設に用はない」、「なんちゅうこっちゃ、そんな施設(和歌山県立身体障害者福祉センター)はつぶさなあかん」。所長は「暴力障害者!」と叫び、所長室に鍵をかけたまま閉じこもってしまった。(第4章 炎)その頃、福永の活動を追いかけていたNHK大阪放送局が、阪神障害者解放センターと市側の交渉を映している。(『負けたらあかんでぇーー阪神大震災・ある障害者の闘い』九五年八月八日放映)。西宮市助役に対し、福永は声を上げた。「いっこもわかってないやんか! あんたら全然考えてないやんか! ちゃんと脳みそを働かせ、脳みそを!」(第9章 揺れ)
【著者略歴】角岡伸彦(かどおか・のぶひこ)1963年、兵庫県生まれ。関西学院大学社会学部卒。神戸新聞記者などを経てフリーに。著書に『被差別部落の青春』(講談社文庫)、『ホルモン奉行』(新潮文庫)、『はじめての部落問題』(文春新書)、『とことん!部落問題』(講談社)などがある。
☆202日目(12.6)人権週間にあたって①
もちろん、日々の生活の中での人権を意識した教育の営みが必要ですが、この週間にあらためて、子どもたちと話し合うことも大切だと思います。
 2024人権週間にあたって~歩み新たに日に生せば~
2024人権週間にあたって~歩み新たに日に生せば~
(1)1948年12月10日
フランスのパリで開かれた国際連合総会において、第二次世界大戦の悲惨な結果を反省し、人権尊重が世界における自由・正義・平和の基礎であるとの『世界人権宣言』が採択されました。この宣言は「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」という人間の尊さを基本に、人間らしい暮らしをしていくための権利を宣言しています。
1950年の第5回国連総会で、毎年12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」として世界中で記念行事を行うことが決議されました。それを記念して、12月10日に至る1週間(12月4日から12月10日まで)が人権週間となっています。
日生中学校でもこの時期を中心に、「いじめや他人を傷つける言動がないか。友だちとともに、自分らしい生活をおくることができているか。」について考え、3日の全校朝礼では、「ありがとう」「ごめんなさい」など、より人とのかかわりを大切にしようと、話し合いました。
1年生は、備前市自立支援協議会の椙原さん・森下さん、小寺スクールソーシャルワーカーをお招きして、自分自身の特性を理解すると同時に、「自分研究」をもとに「クラスで暮らす仲間」をお互いが理解し合う学習に取り組みました。2年生は、職場体験学習の取組に重ねて、NPO法人きずなの川元さんをお招きして、社会モデルとしての「ホームレス問題」について学び、勤労観や福祉、社会のありようについて深く考えることができました。3年生は、ハンセン病回復者である金泰九さんの生き方を視聴学習し、明日6日には、長島愛生園フィールドワークで、「自分たちが生きるこれからの社会をどのように創っていくか」について探求していきます。12日には、長島愛生園の田村学芸員さんをお招きし、シチズンシップ(市民性)の意識を高める学習を進めます。
(2)あらためて大切にしたいこと。「いじめ」は人権侵害
ある友達と口をきかない、無視する、一緒に遊ばない、筆箱をかくす、机に落書きをする、カバンをかくす、などという「いじめ」の話は、テレビやインターネットで、残念ながら今も聞きます。
「いじめ」をする人たちが言う理由として「あいつはうざい」とか「背が低い」「女、男のようだ」「うっとうしい」「どんくさい」など聞くにたえない理由をあげるのです。
学校のなかまが、動作が遅かろうが丸顔であろうが、それはその人の「個性」「ちがい」「持ち味」なのです。個性に干渉して、自分に合わせようとしたり、いじめたりすることは、なかまの〈人権〉を侵すことなのです。いじめるほうが、わがままで自分勝手で他人の人権がどれほど大切なものであるのかがわかっていないのです。「いじめ」は許すことのできない人権侵害の事件なのです。
(3)クラスの中の人権侵害
私たちの身近な人権とはどんなものがあるかな。
ひとには個性があるね。育ってきた家庭のちがい、男・女、LGBTQ+、生年月日、顔、身体がそれぞれ違うように、ひとは、それぞれ違った性格をもっている。考え方も感じ方もちがってくるね。すばやい動きのひともいれば、ゆっくりなひともいるし、ほがらかで友達とよく話ができるひともあれば、その反対で無口なひともいるね。それらのちがったひとたちの集まっているのが私たちの「社会」というわけ。それは学校でもクラスの中でも同じだね。
大切なことはそれら他の人・なかまの「ちがい」を認め合うことじゃないかな。ちがった性格やちがった生き方をするひとが、自分らしく、みんなと共に遊んだり、話し合ったり、喜びや悲しみを分かち合ってたりしていけたら。このことを〈人としての自由権〉と言うんだよ。もちろん、自由ということは、自分がわがままで勝手なこととはちがうよ。みんながそれぞれの自由を尊重しあうと同時に、学校やクラスではみんなが安心して遊んだり、勉強したりするために最低のきまりや規則が必要になってくるね。きまりや規則というのはみんなの自由を守るためにあるといえるんじゃないかな。
ひととしての自由権を守るためには、お互いの生き方やちがいを認めるだけでなく、積極的に尊重していく〈個人の尊厳〉を守るという強いものが必要だね。
みんなは安心して学校に登校し、自分の進路の実現に向かって学習できるという〈生存権〉をもっています。また一人ひとりがもっている「勉強する権利」を〈学習権〉と言うんだ。授業中に自分勝手にさわいだり、友達の発言をひやかしたり、ものを投げたりするのは、みんなの学習権を侵害することなんだ。
☆201日目(12.5)話し合うこと⑥

第75回全国人権・同和教育研究大会に参加して。
参加した分散会では、熊本・京都・大阪・福岡からの4本の報告をもとに、2日間、のべ8時間の研究協議を行いました。紙面での内容だけはわからない、子どもと教職員らと日々の営みや、うまくまとまらない願いや思いを丁寧に聴くことで、「実践」の内容が立ち上がってきます。さらに参加者自身の実践を重ねて語る発言には「事実」がみえてきます。 どんな「話し合い」にしたいのか?、「語る」ってことをどのように進めていくのか?に悩んでいる私にとっては、3日間の司会団の経験は大切な糧となりました。最終日、総括討論のまとめの中で、私は、水俣事件で取り組んでおられた故川本輝男さんの「情熱とは事あるごとに意思を表明すること」というコトバを紹介しました。話すこと・語る時には、「意思」が要りますなあ。
☆200日目(12.4)過去・現在・未来をつなぐハンセン病問題学習
三年団の先生方と授業研究と授業準備をおこないました。今年度の計画を進めていきます。
☆199日目(12.3)ひなせ親の会と重ねて
大阪の大先輩、土田光子さんのコトバを思い出しました。『授業規律とは、一人ひとりが大切にされ、気にかけられているという信頼や、わからないことは支援の対象になっても、決して笑われることではないという安心と協働の文化を育む日々の学級経営を前提として、さらに授業そのものの工夫によって、結果として生まれるものであって、決してルールやしつけだけで成立するものではない。』
☆198日目(12.2)人権教育の創造~コロナ禍を振り返って
フィールドワークで話した内容(徳田弁護士が書かれた内容)について、聞かれることが結構あったので、少しだけ紹介(p364~)します。詳細は『感染症と差別』をぜひお読みください。
☆197日目(11.29)現実から学ぶ
26日に、備前市教育研修所 学校運営部会と学校事務部会が合同で研修会を開催しました。岡山県備前県民局建設部東備地域管理課 中務課長を講師にお招きして、危機管理について見識を深めました。中務さんは、本校の避難訓練での講評や、社会科での授業でのアドバーザーとして来校され、リアルな現実をもとにしたアドバイスや指導・助言をしてくださいました。この日も、安全対策について、紙面だけの対策や、正論・理想だけの思考ではだめなことを改めて考えることができました。

今月末(11/30・12/1)は、全国人権・同和教育研究大会が開かれます。会のスローガンの冒頭には「差別の現実から深く学び・・・」とあります。子どもの現実を見つめ、課題や真実を見抜ける人権感覚を、不断に磨いていかねばなりません。
☆196日目(11.28)話し合うこと⑤
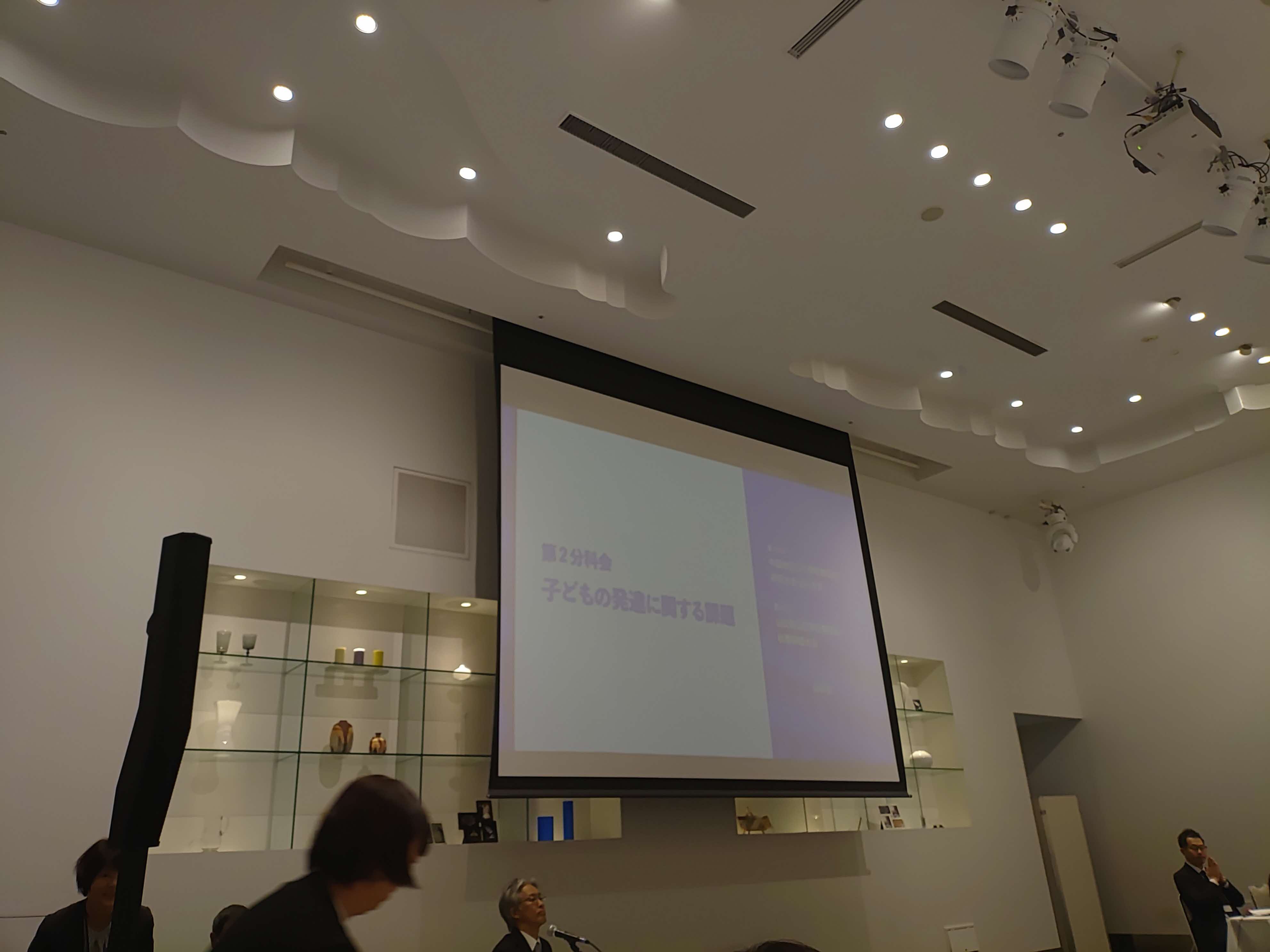
第44回中国地区公立学校教頭会研究大会(山口大会)があり、参加してきました。午後からは、「子どもの発達に関わる取組」の関する第2分科会で研究協議をおこないました。私のグループの中では、山口の先生から、生徒がとても少ない学校(さらに小中一貫校スタイル)で、地域協働活動を進めていく中で、子どもたちの関係が、学校の場だけでなく、地域社会や様々な人々と関わる場の中で、豊かになってきたことを聞きました。それは、本校でも進めている地域との協働活動の正しさを確信し、「またがんばっていこう!」と思えました。有意義に「話し合う」ことを、どのように会の中で設定(ファシテテート)していくか、大事ですねぇ。
☆195日目(11.27)話し合うこと④

縁あって、岡山の養護教諭の方々のフィールドワークのお手伝いをしました。長年に渡るハンセン病問題の反省を、教訓にしなければならない私たちですが、「コロナ禍で、どんなことが起こしてしまったか?」を、検証しなければならないと思います。そのことについて徳田弁護士が著書に書かれていたこと(①感染者・家族、医療従事者をウイルスを広げる悪者と見なしたこと。(旅客船の感染者への対応を私たちはどう見ていたか) ②感染したことは自己責任・自業自得だと考えたこと。(学校・施設などでも謝罪会見がありました。) ③多くの国民が自分や家族は感染しないと考えていたこと。(感染した人の立場に立つことができなかった。これは救らい思想での、「感染者を救う」という良いことをしている私たちを、感染者も「ありがたいと思っている」だろうと考えに通じる) ④差別や排除をしているコトを正義と信じたこと。(無らい県運動で積極的に報告をしたのは学校の先生でした)を、フィールドワークでも紹介しました。それに応えて、なんと!参加者の皆さんからは養護教諭の立場から本当にたくさんのお話を聴くことができたか。話し合う(語り合う)ことは、自分の視野をさらに拡げますね。お互いに語り合う時間を大事にしたいと思います。
☆194日目(11.26)話し合うこと③
今月末(11/31~12/1)は、全国人権・同和教育(全人教)研究大会が、熊本・福岡・鹿児島を会場に開催されます。私は、縁あって、進路保障をテーマにした分科会・分散会の進行のお手伝いをします。全国からの実践レポートをもとに2日間、様々な意見(事実と実践)を交わしながら研究協議をしていきます。学びを深めていく「研究協議」に向けて、今一度「進路保障」とは何か?を整理して、レポートを繰り返し読んで、会の進行準備を進めていきます。
「進路・学力保障」について ~ 子どもたちの未来を拓く進路・学力保障をどう進めているか(全人教の資料より)
私たちは、「進路保障は同和教育の総和である」ととらえてきました。進路保障は、単に進路を決定することではなく、子どもたちが、差別を許さず差別に負けない力、なかまとともに未来を切り拓いていく力などを獲得するための道すじや機会を保障する取組です。 その重要な柱として、学力保障の取組を進めてきました。学力保障では、子どもたちが自分自身を深く見つめること、「学ぶことの意義を実感しながら」学習や生活に意欲を持つこと、自己表現力を高めること、自尊感情を育むこと、自分の生き方を豊かに創りあげていくことをめざしてきました。そのためには子どもたちが多様な進路や生き方を選択できる力を身につけることをめざした授業や学校づくりに取り組むことが大切です。そうした取組を創る中で教職員自らが子どものくらしの現実や保護者の思いから学び、差別との関係や自分との関係を問うことが大切です。部落の子どもたちや障害のある子どもたち、在日外国人の子どもたちなど、被差別の子どもたちを中心に就学保障や就労保障に取り組んできました。その取組を、経済情勢悪化や貧困層の固定化などによって、被差別の子どもたちをはじめ特に厳しい状況におかれている子どもたちの進路保障の取組に普遍化させていくことが求められます。そして、地域や家庭と連携し、保・幼・こども園・小・中・高の一貫した取組の中で、生きて働く力や
その道すじを明らかにし、追求していきましょう。
一 被差別の子どもたちの進路をめぐる現実やその背景をとおして、私たちの課題を具体的に明らかにしよう。
二 「低学力傾向」「いじめ」「不登校」などの現実をみすえ、保・幼・こども園・小・中・高を通じて、子どもたちが生き生きと学び生活していくための授業や学校づくりを追求しよう。
三 すべての子どもたちが、学校や地域での活動をとおして、反差別の価値観でつながりあい、なかまとともに自らの生活・進路をどう切り拓いているかを明らかにしよう。
四 「統一応募用紙」制定の意義に深く学び、その趣旨の徹底とその精神をあらゆる場においてどのように具現化してきたかを明らかにしよう。
五 進路保障の態勢を確立していくために、被差別の子どもたちの現状を明らかにし、あるべき奨学金制度をめざすとともに、「権利としての奨学金」の学習を交流・討議しよう。
☆193日目(11.25)話し合うこと②
(引き続き)私たちの教職員の研修会では、ペアで協議することはあまりないですが、3~4人程度のグループで意見交流をすることがよくあります。(2000年初頭に人権ワークショップという学習スタイルや、協同学習のスタイルが拡がったのも理由のひとつかもしれません。)当たり前のように、いつものように、いろんな研修会でグループ協議をしていくのですが、自分自身、そのグループでの協議をする中での「深まりや気づき」が弱くなった気がしています。これはわたし自身の問題意識の低さや、積極的な姿勢の弱さなど私の課題だとは思いますが。同時に、もうひとつ、多い人数で協議するスタイルがとても減っているような気がします。「多人数では、意見がでないから、少人数のグループをつくって話す(意見交流だけ)」ことを続けていった結果、〈全員で侃々諤々とお互いの意見を語り合い、「目的」に向け意見を集約していき、みんなでひとつの結論を出して、実践していくことにつなげる協議スタイル〉が出来なくなっているのではないか??と考えたりしています。
この日(11/26)、私は、中国地区公立学校教頭会研究大会(山口)に参加します。分科会での協議に参加し、機会があれば、子ども学び方や私たちの学び方なぞも他の参加者とも一緒に考えてられてらいいなあと思っています。
☆192日目(11.22)話し合うこと①
授業や研修会でも、「近くの人と少し話をしてみてください」というスタイルが多いですね。私も、今週行った本校での「中学生認知症サポーター養成講座」でも前述のスタイルを用いて生徒らに「近くの人と話すことを」の促進したのですが、授業後の反省会で「ペア(複数人)になれず、一人だけの生徒がいた」ことが指摘され、思慮が足りず、みなければならない子どもたちを視てなかったと猛省しました。まだまだ「話し合い」に入ることが苦手な生徒らを含めて、話し合うペアやグループや明確に指示するべきだったと思います。そして、わいわいと話しができている全体の雰囲気をみるのではなく、ペアになれきれない子はいないかをみて、ペアリングの支援をするべきでした。そして、その上で、そのペアでの「学び」が成立しているか?を看取れねばなりませんね。話している・しゃべっている=学んでるではありませんものね。

☆190日目(11. 21)必要なことは何だ?
最近、特別支援教育の推進の中で、保護者や地域が求めていることは何だろう?課題は何だろう?そこから学習会や研修会を企画していかなければならないなあと、感じることが増えてきました。一方的な内容になっていないか、主体者不在ではないか?目的は何なのか。先に確実に進むために、ひなせ親の会の内容を今回このようなカタチにしました。一歩ずつ。
☆189日目(11. 20)金泰九さんと歩く
愛生園でのフィールドワーク(FW)のお手伝いをさせていただくことがありますが、金さんにくっついて廻った時に話されていた中身をもとにしています。大らかな人柄と穏やかな語り口が醸しだす何とも言えぬ柔らかさ、そして確かな人権感覚と行動力に引きつけられ、何度もFWとその後の学習会をご一緒させてもらいました。金さんになりかわって語ることは出来ませんが、自分自身が金さんに教えられたことや、学んだことは、生徒たちにしっかりと伝え続けなければならないと思っています。
今年も、生徒たちと、金さん(パネルと一緒に)と、12月6日は園内を廻り・学びます。
☆188日目(11. 19)ハンセン病の学習ではなく、ハンセン病問題学習を。
今年度も地域学習と連携させて、三年生はハンセン病問題学習に取り組みます。
三年生は、社会科公民分野において、日本国憲法の基本である「基本的人権の尊重」について学習しており、さらに具体的な姿として「ハンセン病問題」を取り上げ、正しく理解することは、生徒自身が暮らす県民として重要・不可欠であろうと考えます。また、義務教育最終年度にあたることも鑑み、中学校というフィールドから、「自らの学び」を社会・世界的視野に拡げていけるように、現地研修では、長島愛生園の歴史や、世界遺産登録推進のうごきを体感してきます。
言うに及ばず、私たちは、「ハンセン病について」の正しい知識習得だけではなく、「ハンセン病問題」に取り組んでいきます。ハンセン病問題とは、近代以降の国の間違ったハンセン病対策が原因で、患者、回復者およびその家族の方々の人権が侵害され、はなはだしい偏見差別にさらされた人権問題です。ハンセン病問題学習を通して、私たちの生きていくこれからの社会を主体的に創っていくという自覚(シチズンシップ)を高めたいと思います。
☆187日目(11. 18)
11/16・17に、第3回金泰九さんに学び教育実践交流会が開催されました。会の資料の一部と新聞記事を添付します。

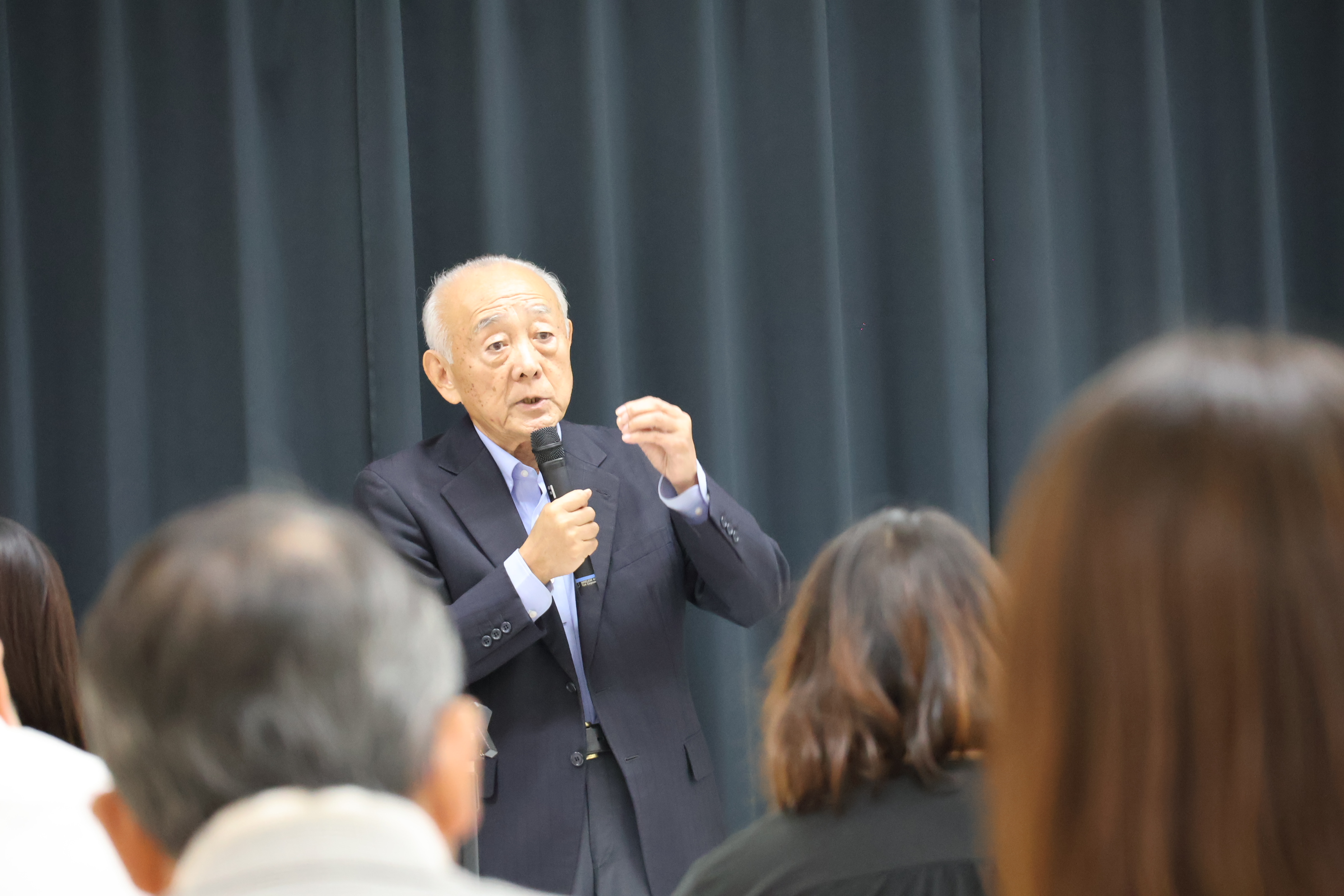
☆186日目(11.15)ハンセン病問題学習の内容について
多くの学校で実践が行われていますが、長年取り組んで大事にしたいなあと思っていることは、「ひと」との出会いを通してのハンセン病問題の学習です。毎年、子どもたちが出会っているのは、キムテグさん(金泰九)です。
金さんは1926年現在の韓国陜川(ハプチョン)生まれ、12歳で父を頼って日本に渡って来られました。1945年旧陸軍兵器学校卒業直前に日本の敗戦で復員します。1949年旧大阪市立商科大学(現大阪公立大学)在学中に発病し、1952年に強制隔離され、約60年間の大半を長島愛生園で暮らされました。原告に先頭となって加わった国賠訴訟は2001年、熊本地裁が国の強制隔離政策を違憲と判断し、勝訴します。その後は戦時中、日本の統治下で強制隔離政策が行われた韓国・台湾の元患者の補償問題も支援されました。2007年にまとめた自伝『我が八十歳に乾杯~在日朝鮮人ハンセン病回復者として生きた~』(牧歌舎)には金さんの生き様の一部が書かれています。『…人権侵害のらい予防法を廃止するにおいて、法廃止に消極的態度をとっていた私は自分を恥じるのである。その理由なるものは、「功利的」な考えでしかなかったからである。それ以来私は「人権を」全てに優先して考えるようになった。「自他ともの人権を」である。全ての事象が人権と関わっている気もするのである。その場合、人権を最優先にして考えてみると、ことに理非が明瞭にみえてくる気がするのである。』
すごい人でしょう。でも、実は、残念ながら9年前に亡くなられました。だから今、子どもたちが出会っているのは『虎ハ眠ラズ』というDVDの中の金さんです。
私は、これまでの授業の中で、ハンセン病に対する国の施策の問題や、裁判の経緯、療養所の歴史的施設の説明など、あれもこれも内容に入れて、授業者としての自分の立ち位置があやふやな時期もありました。が、今は一緒によりよい社会をつくるために学び続ける者の一人として?「ひとの生き方」からハンセン病問題を考えることを続けています。
DVD『虎ハ眠ラズ』の中の金さんとの出会いに、子どもたちは、毎年それぞれ違う反応を示します。そこから、その学年独自のハンセン病問題学習を進めていくこととなります。
声を聴く取組を。
(現在は、どの療養所の入所者(回復者)の方々が高齢となられ、直接お話しを聴く機会が難しくなりましたが、多くの入所者の方々の声が本や記録、証言集に残されています。私はもっともっと読まねばならないと痛感しています。合わせてそれをもとにした「ひと」を通してのハンセン病問題学習の内容をつくりたいと思っています。(一緒につくりませんか?))
明日、11月16日(土)第3回金泰九さんに学ぶ教育実践交流会があります。また追悼の集いでは、万霊山での納骨堂でのお参りができます。
☆185日目(11. 14)背景を知る2
一見分かりやすい文言なので、「多様性 個性重視」に集約されがちです。(インターネット上には侃々諤々、様々なご意見が多々ありますね)
以前、参加した人権学習会では、この詩を一人ひとりが鑑賞(解釈)し、意見交流をしましたが、その後、金子さんの歩んでこられた生き様(よう)や大正時代の女性の立ち位置や家族のありようを学習した上で、あらためて詩を読み返すと、詩の中の言葉の意味が深く迫ってくる体験をしました。それから、金子さんの「大漁」「星とたんぽぽ」など、他の詩を読んでみると以前とはまったく違う感想をもつことにもなりました。
鑑賞の授業でもそうですが、人権教育が大切にしている、人の背景(本当の思いや願い)を理解しようとする豊かな体験を日々の教育課程の中にきちんと組み込んでいきたいものです。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を参考に、彼女の生きてきた時代や、生い立ち、家族のことを学んでから、再度詩を読み返してみたいと思います。
○金子テル1903年4月11日生まれ 山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)1930年3月10日(26歳没)
金子 みすゞ(かねこ みすず、本名:金子 テル〈かねこ テル〉、1903年〈明治36年〉4月11日 - 1930年〈昭和5年〉3月10日)は、大正時代末期から昭和時代初期にかけて活躍した日本の童謡詩人。約500編の詩を遺した。没後半世紀はほぼ忘却されていたが、1980年代以降に脚光を浴び、再評価が進んだ西條八十に激賞された幻の童謡詩人とされている。遺稿集が発掘され、出版(1984年)、深く優しい世界観が広く知られた。代表作に「私と小鳥と鈴と」「大漁」など。
○生涯
山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)の生まれ。郡立深川高等女学校(現:山口県立大津緑洋高等学校)卒業。みすゞの母の妹の嫁ぎ先である下関の書店兼文房具店「上山文英堂」の清国の営口支店長だった父は、1906年(明治39年)2月10日、みすゞが3歳のときに清国で不慮の死[注 1]を遂げる。実弟は文藝春秋社の編集者や喜劇王・古川ロッパの脚本家などとして活躍し、子役の名門であった劇団若草の創始者である上山雅輔(本名:上山正祐)であるが、幼くして母の妹(みすゞにとっては叔母)の嫁ぎ先である上山家に養子に出されている。父の死後、母・祖母・兄とみすゞは仙崎ただ一つの本屋である「金子文英堂」を営んだ。みすゞは読書家で成績優秀、大津高等女学校を総代で卒業するほどだったが、教師の「卒業後は奈良女子高等師範へ進学し、教師になったら」という勧めを断ってのことだったという[3]。叔母の死後、実弟正祐の養父とみすゞの母が再婚したため、みすゞも下関に移り住む。
1923年(大正12年)、「金子みすゞ」というペンネームで童謡を書き始め、雑誌『童話』『婦人倶楽部』『婦人画報』『金の星』 に投稿した。この年、これら 4 誌全ての 9 月号にみすゞの投稿した 5 編の作品が一斉に掲載された。以降みすゞは次々と作品を投稿。雑誌『童話』を中心に 90 編 の作品を発表する。『童話』においては、推薦 16 編、入選 24 編、佳作 2 編の計 42 編が 掲載された。最後にみすゞが投稿し掲載された作品は『愛誦』1929年(昭和4年)5月号の「夕顔」である。1923年(大正12年)『婦人画報』9月号に掲載された「おとむらひ」は、翌年『現代抒情小曲選集』(西條八十編)におさめられた。1926年(大正15年)には、みすゞは「童謡詩人会」への入会をみとめられ、童謡詩人会編「日本童謡集」1926年版に「お魚」と「大漁」の詩が載った。童謡詩人会の会員は西條八十、泉鏡花、北原白秋、島崎藤村、野口雨情、三木露風、若山牧水など。女性では与謝野晶子と金子みすヾの二人だけだった。
1926年(大正15年)に叔父(義父)の経営する上山文英堂の番頭格で、芝居好きで酒は飲めないものの女癖の悪い宮本啓喜と結婚し、娘を1人もうける。しかし、夫はみすゞの実弟である正祐との不仲から、次第に叔父に冷遇されるようになり、女性問題を原因に上山文英堂を追われることとなる。みすゞは夫に従い、その後は子どもを連れて下関を転々とする。自暴自棄になった夫の放蕩は収まらず、後ろめたさからか、みすゞに詩の投稿、詩人仲間との文通を禁じた。
1927年(昭和2年)西條八十編『日本童謡集(上級用)小学生全集第48巻』および1928年(昭和3年)光風館編輯所 著『作文新編 巻1』に「お魚」が収載される。1929年(昭和4年)東亜学芸協会 編『全日本詩集』には「繭とお墓」(『愛誦』1927年(昭和2年)1月号が初出)が載る。1929年(昭和4年)、みすゞは「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」と 題した3冊の童謡集を二組制作し西條八十と正祐(当時上山雅輔の名前で文藝春秋社の編集者をしていた)にそれぞれ託した。(現存するものは同年秋に正祐に送られたもので1925年と1926年の博文館のポケットダイアリーの書店用見本に書かれている。1冊目の「美しい町」と2冊目の「空のかあさま」は清書。3冊目の「さみしい王女」の詩には校正した跡がある)
1927年に夫からうつされた淋病を発病。1928年には夫から創作や手紙のやり取りを禁じられる。1929年頃には病状が悪化し床に臥せることが多くなる。1930年(昭和5年)、夫と別居し、3歳の娘を連れて上山文英堂へ戻る。同年2月に正式な離婚が決まった(手続き上は成立していない)。みすゞは、せめて娘を手元で育てたいと要求し、夫も一度は受け入れたが、すぐに考えを翻し、娘の親権を強硬に要求。同年3月9日、みすゞは近くの写真店に行って写真を撮り、娘をふろに入れた後、寝付いたのを見届けてから、夜の内に服毒自殺を遂げ[注 2]、享年28(数え年)、26年の短い生涯を閉じた[3]。上山雅輔は回想録「年記」に「芥川龍之介の自殺が決定的な要因となった」と書いている。 遺書を3通残しており、そのうちの1通は元夫へ向けた「あなたがふうちゃんをどうしても連れていきたいというのなら,それは仕方ありません。でも,あなたがふうちゃんに与えられるものはお金であって,心の糧ではありません。私はふうちゃんを心の豊かな子に育てたいのです。だから,母ミチにあずけてほしいのです」という娘の養育を母ミチに託すよう求めるものだった[4]。法名は釈妙春信尼[5]。娘はそのまま母ミチの下で育てられている[3]。
金子みすゞの死後1930年(昭和5年)に創刊された西條八十が主宰する『蠟人形』(5月創刊号)には、みすゞの「象」と「四つ辻」の二作が載せられた。また、翌年の1931年(昭和6年)、西條八十は『蝋人形』9月号にみすゞの「繭と墓」を再掲載し「下ノ關の一夜 ── 亡き金子みすゞの追憶」と題した追悼文を残している。西條八十は、さらに1935年(昭和10年)にも『少女倶楽部』8月号と9月号に みすゞが送った童謡集のうちより「たもと」「女王さま」をそれぞれ掲載。また、9月号の方には「繭と墓」を彼女と下関で出逢った思い出の随筆をまじえて再度掲載した。戦後も1949年(昭和24年)、『蠟人形』5・6月号に西條八十選で「人形の木」が、1953年(昭和28年)の『少女クラブ』6月号には「木」と「先生」が掲載された。
☆185日目(11.13)背景を知る
ちょっと前に、「授業づくり」について、授業改革推進員さんと話題になったのは、「作品や音楽の鑑賞の際、その作者の背景(時代や作者自身の歩んできた生き様(よう))を事前(事後)学習することは必要なのか?」ということでした。もちろん、授業のねらいを明確にしていく中で、事前(事後)学習の内容も考えなくてはなりませんが、鑑賞させる作品や音楽〈だけ〉との出会いは、どこまで子どもたちの学びを深くすることができるのだろうか?と思いました。また、事前学習において、その作者についてのどのような情報を提供するかも、授業者の感性(授業観)に負うところが大きいような気がします。よく学校でも教材化する金子みすゞさんの『私と小鳥と鈴と』という詩があります。あらためて、どのように鑑賞しますか?
私が両手をひろげても、
お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のように、
地面を速く走れない。
私がからだをゆすっても、
きれいな音は出ないけど、
あの鳴る鈴は私のように、
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがって、みんないい。(次回へ続く)
☆184日目(11. 12)就職差別撤廃に向けた取組
3年生でハンセン病問題学習を行った後に、統一応募用紙の授業を進めたいと考えています。ハンセン病問題学習での学びが、「過去に大変なことがあった」とか、「差別しないように気をつけよう」と心がけや思いやりの涵養で終えないようにしたいと思います。もちろん、ハンセン病問題の解決に向けた様々な活動に取り組んできた人々の事実を学んでいきたいと思いますが、「願い」を「行動」で具現化していった「統一応募用紙」の成立経過を学ぶことは、人権を尊重する社会の実現のため、仲間と団結して行動する実践力を育む一助となります。
☆183日目(11. 11)就職差別撤廃に向けた取組
「面接報告書は、面接での質問内容をまとめ、後輩たちの面接対策のためだと思っていました。」と、話を聞いたり、「尊敬する人は誰ですか?と、なぜ質問するのはいけないのですか?」と尋ねられたことがあります。(残年ながら最近のことです。)また、「離職した子どもの事業所に課題があっても、高校側が把握し、申し入れ等の対応が弱い(ない)ようなこともある」とお母さんが語ってくれました。若い世代の先生方と共に、就職差別撤廃に向けた取組(たたかい)を学び直し、今現在の進路保障の取組を一層確かなものにしなければならないと思います。第75回全国人権・同和教育研究大会での報告レポートをもとに、それぞれのこれからの実践を研いていける場(分散会)になるように、準備を進めていきます。
☆182日目(11. 8)仲間って
「よくないことをしている友達に注意することができないといけない」「荒れは、自分が弱いからだ。自己責任だ」と、とても昔に、生活指導の場で聞いたことがあるフレーズですが、注意したり、監視したり(おおげさかも)する関係性は少し違うような気がします。「がんばり合える」というのか、お互いを解り合いながら、高め合うというのかな、うーん、うまく言えません。教育実践の一部を紹介します。ささえる合える仲間づくり(続ける)
☆181日目(11. 7)仲間づくりの中身
仲間づくり、集団づくり、人間関係づくり、学習集団づくり・・・たくさんの学級経営につながるキーワードがありますが、職場で、「仲間づくり」の思想を確かめ、共通認識・共通理解したいと思います。(続く)
☆180日目(11. 6)進路指導から進路保障へ
取り組みの中で、具体的な取り組みとしての、3つの柱(続く)
☆179日目(11.5)進路を保障する教育内容や学力とは何か
第75回全国同和教育・人権教育研究大会が今月末に九州で開催されます。縁あって実践報告協力者として、第3分科会(進路保障)での1分散会に参加します。そのために分散会でのレポート原稿をしっかり読み込んでいっているところです。
そんな折り、職場で進路保障や進路指導の意味や意義について話題になりました。ちょっと「進路保障」について、『リュミエール』学校同和教育実践講座11巻 進路保障の課題と実践(1993年学校同和教育実践講座刊行委員会編集)の本を引っ張り出してみました。30年前に著された内容を読み返しながら、今現在の課題に向けた解決や実践のありようを確認したいと思います。
進路保障とは単なる「進路先」の保障でなく、、、。(続く)
☆178日目(11. 1)「発達」特性について学ぶ、「クラスで暮らす」の学習案(ワークシート)
☆177日目(10.31)「発達」特性について学ぶ、「クラスで暮らす」の学習案
☆176日目(10.30)「ホームレス問題学習」の学習案(ワークシート)
☆175日目(10.29)「ホームレス問題学習」の学習案
☆174日目(10.28)「ホームレス問題学習」から考えること
打ち合わせメールより
おはようございます。授業日が近くなってきました。今年度は、私も一緒に授業の進行をさせていただきます。担任の先生と準備をしていますが、授業(きずなさんとで学んでいく方向性がまだ決まり切っていません。
双方向でのやりとりのひとつは、「ホームレス問題」についての素朴な質問や疑問についての、AT(エリアティチャー)さんとの対話が中心になるとおもうのですが、明日、事前学習(授業)の2回目をします。内容は教材DVDを使って、とくに「子ども夜廻り」に取り組んでる子どもたちの内容を中心にします。
2つめは、◎人と本気でかかわろとうする大切さ(しっかりと相手を理解しようとすること、本当に分かろうとすること)についてアプローチができたらと考えています。
それはなぜかというと、学級の中でお互いの関係性がよくなくて人間関係のトラブルがいくらかあり、一つの課題でした。そんな中で、昨年のこの時期に、東田直樹さんのDVDも活用し、「発達」にかかわるATの方々に来ていただいた授業の中で、自分の発達の特性、でこぼこ(自分の持っている特性・クセ・タイプとして、「発達障がい」という語句は使わず。)をお互いに知り合おう・理解しようという学習に授業で取り組みました。その学びの中で子どもたちはお互いを理解しようとする集団に変わっていったような気がします。そして今年度さらに、子ども同士が、相手を理解しながら、厳しく(優しく)迫ったり、励まし合ったり、ガンバリ合える関係性を持つクラスにできたらなあと思っています。
3つめは、この学習が終えて、子どもたちは4日間の職場体験学習へ行くのですが、職業感や勤労観について深まったらと思います。「助けて」とあたりまえに言える社会、共生の有り様を具現化していけたらとも考えています(そんなによくばりはできませんが)
本授業だけでそんな思考や構築できるわけはありませんが、学校での日々のアプローチも含め、この機会にATさんからのお話を大いに聴きたいと思うのです。子どもたちの質問に重ねる私の補助質問をいくつか挙げます。(いま現在です。月曜には変わるかもしれません。また連絡させていただきます)
授業の流れを含めて
①本授業のテーマの確認「ホームレス問題にかかわる川元さんとの質疑応答で、学びをふかめる」進行
②自己紹介(AT)
③質疑応答に向けて「提起」(AT)←いつも思いますが、けっこう、難しいですね
・きずなでの活動 ・(生徒たちに知ってほしいこと)基本的なことや
・課題 ・岡山状況や課題
④グループで質問を考えて、ホワイトボードで提示
⑤多くの質問からチョイス、質問内容を構成
・質疑応答の中で久次が重ねたいと思っていること
○「ホームレス問題」は私たちとどう関係しているか? ○政治や社会との関係性・きずなの役割 ○(「子ども夜廻り」から、)川元さんが取り組んでいるのは、どんな思いからなのか?○人を理解するには(声かけをする時に意識していること)○行政や福祉につなげる・支援するときに意識していること
○川元さんの思っている仕事観・勤労観、・ホームレス問題についての、世間や社会の偏見や差別意識に対して ○自分と違う、「ひと」をわかろうとすること
○「クラス」で「暮らす」にはどうするか?
⑥日生中学校2年生へメッセージ
⑦終わり
☆173日目(10.25)語り合うクラスへ、
前回の「聴き取り課題」のワークシート案です。
☆172日目(10.24)語り合うクラスへ、聴き合いたくなる課題を
構成的グループエンカウンターを、意図的・計画的にこれまでも活用してきましたが、いきつくところは、子ども自身が「背負っている生活」からの生の思いや願いの声を語り合う、聴き合うクラスの営みであろう。身近な(親)からの《仕事の聴き取り》と《聴き取りからの学びや思い》をまとめた《クラス報告》が出来たらいいなあ。
☆171日目(10.23)50年前の事実と願いから
趙博(チョウバク)さん(67)が創作した一人芝居「ヒロシマの母子像―四國五郎と弟・直登」の公演後、偶然に古本市で『原爆三十年 広島県の戦後史』を見つけて、やっと読み終えました。本のあとがきには「広島県は、被爆三〇周年にあたり、記念事業としていくつかの企画をもちました。その一つに、原爆問題を広島県の戦後の歴史の中に正しく位置づけ、二度と過ちをくり返さないことを願って、本書の刊行を計画しました。」とありました。発行は、昭和51年(1976年)。そしていま、2024年となり、戦後80年目を迎えようとしています。本書、第Ⅷ章 未来への志向の一部をもう一度読んでみます。
参照 趙博さんの芝居について再掲(*平和のための創作を続けた四國五郎(1924~2014年)の生き様をもとに構成された一人芝居です。四國が描いた広島の風景や反戦画を投影したスクリーンをバックに、詩や日記からの抜粋などを織り交ぜて公演されます。そして「あなたの隣にヒロシマの子はいませんか?」と私たちに問います。戦争への怒りと憎しみが生前の詩画人を創作に駆り立てた力だったことが伝わってきます。)
☆170日目(10.22)「なぜ」「どうして」なのかを考える
「なぜ、ウソをつく?」「そもそも、ウソなのか?」「なぜ、ウソをつかねばならないのか」そんなことを自問自答していたここ一週間が過ぎている。そんな時、10月20日山陽新聞9面、上間陽子さんの『論考2024』を読んだ。・・・やっぱり、「はなそう」「きこう」
☆169日目(10.21)「進路指導」について
19日、パブリック友の会第6回「&のつどい」に、岡山御津高校の末廣先生と共に、高校進学・進路についての「アドバイザー」役としてお手伝いをさせていただきました。本会の講演会(パネルディスカッション)は150名もの方が参加され、『障がいのある本人と家族の税・相続について』がテーマに、税理士、弁護士、社会保険労務士さんらのお話に熱心に耳を傾けておられました。講演会後に、精華学園や希望高校などの先生らの個別相談と同時進行で、保護者やお子さんから進路・進学についてのお話を聴かせていただきました。
会に参加して、あらためて「進路指導」について自分自身が考えさせられました。
・入学(受験学力を重視した)するだけの進路指導に向かっていないか。
・生徒の特性を深く、正しく、知ろうとしているか。
・保護者との本音・本気の連携ができる関係を築こうとしているか。保護者の願いや思いに寄り添った支援活動を行えているか。
・日々、新しくなっている、多様な進路(高校進学)の情報を更新しようとしているか?また、それを適正に生徒・保護者に提供できているか。
・高校間格差を助長するような進路指導をしていないか。
・進路、自己実現に向けた、中学校の授業や自立活動の中身は精選しているか。
・・・うーん。簡単に答(応)られそうにありませんが、身を引き締めて、今日もガンバロウ!と思います。
☆168日目(10.18)今だからこそ「しごと」の聴き取り
「見つめる」とは「自己洞察」である。自己の内面を見つめるだけでなく、他者との関係や社会との関係における自分の存在を見つめていくことである。
「語る」とは「自己開示」である。「語りたい」としたときに、ありのままの自分、赤裸々な自分を他者に伝える行為である。
「つながる」とは「人間関係づくり」である。日常の人間関係の中で、一人ひとりの「友だちになりたい」という気持ちを出し合い、より相手のことを知っていくことで、人間関係の絆を深めることである。地域の人々や親、人生のモデルとなるような他者、等の「語 り」を聞いて共感するなかで、自分の生活の現実や気持ちを見つめます。その気持ちを「語りたい」「分かってほしい」と欲したときに、自己を受容してくれる相手に語ります。「自分の気持ちを言えてすっきりした。」「みんなに分かってもらえてうれしかった。」という安心感は、強い自己肯定感に結びつきます。また、自己開示をし、自分を「語る」過程で新しい自分に気づき、自己洞察が一層深まります。「語ること」は、自己と他者の「つながり」を深めます。葛藤 や悩みを相互に「語る」機会が与えられることで、子どもたちは初めて信頼にもとづく人間関係を創出していくことができます。こうした日常の人間関係づくりのなかで、子どもたちは自己と他者との間のトラブルに対して問題解決能力をつけ、自他ともに対する信頼感を培っていくのです。同和教育は、単に部落問題をどう教えるかということだけでなく、「自分の生活を見つめ、語 り、仲間とつながること」を一貫して追求してきたのです。
(【参考文献】◇『子どもの心がひらく人権教育』松下一世著 解放出版社)
しごとや高校を調べ、発表する活動がありますが、その前後にやっぱり、親(身近なひと)からの「聴き取り」に取り組みたいと思う。夢や希望だけで、今の仕事に携わっているひとばかりはない。たくさんの「思い」や、子どもに対する強い「願い」をもちながら働いているひとから、学びとる「聴き取り」を進めたい。そして、聞き取った内容をもとに、自分がどう感じたか合わせて「語り」、クラスの中で、お互いの考えやを深く知る仲間として、「つながり」合うクラスの営みは、前述の松下さんが言われるような力や信頼感を培っていきます。
インターネットや本だけでの「しごと」「高校」調べを越えよう。
☆167日目(10.17)学習したことをふりかえる一考(続き②)
生徒が取り組んだ「顕著は普遍的価値の言明」を紹介します。顕著な普遍的価値とは、「その遺産の文化的意義が国境を越えるほど顕著であり、今日及び次世代のすべての人類にとって共通に重要であること」です。
◆タケミさん
『私が「ハンセン病問題」学習について考えたことは主に二つ。「国家の間違い」、「差別の意義」。「国家の間違い」、それは「らい予防法」を確立させたことだと私は考える。法律になれば全員逆らえない、全員が「らいは伝染病だ」と信じてしまう。もし、この法律がなければ尊い人権も、一生離れなかったであろう人々も守れていたはずだ。間違った偏見も差別も根強く残らなかったはずだ。次に「差別の意義」。このハンセン病においての差別は実に「無用」。家族との縁を切る、名前を捨てる、自由を奪われる。このような人権侵害の理由が「日本の見栄、世間体を守るため」。その程度で潰れる世間体ならたかが知れている。もっと早くハンセン病についての研究をすれば解決しただろう。後で思っても遅い。後悔はできるが事実を変えることはできない。これからの社会にも私たちにも言えることだ。その後悔の事実と、国家の罪の象徴・証拠がナガシマだと私は強く考えている。
したがって、ナガシマは顕著な普遍的な価値を持っている。』
◆ヒロミさん
『長島愛生園に行き、自分で見て、普通の島だなと思った。家が点々とし、普通の島にみえるが、収容桟橋→収容所→監房→納骨堂→恵の鐘→歴史館を見てまわり、暗い歴史が見えた。
収容桟橋では「ここから、すべてが始まったんだな」と思った。今は崩れて、もう外に出て行っていいよって呼びかけているように安心した。収容所では、実際に中に入ってベッドやお風呂を見たりして寒い雰囲気だった。皆で入っても間が空くぐらい広く、お風呂は狭かった。ここでDVDで見た消毒をかけられたり、検査されたりしたんだなと実感した。
監房はDVDにも出てきていなく、初めて見た。大きく、中に一人で入ると寂しいなと思った。納骨堂はこれまで見た中で、一番きれいで、白かった。何千人以上の人が家族にさようならを言えないまま亡くなって、しかも家族の元や、自分の居場所がないことを目の当たりにする切なさに心が痛んだ。
恵の鐘は唯一、患者さんの希望や怒りが見えた場所。そこからの眺めは良く、昔はどのように映っていたのかが気になった。
実際に長島愛生園に行き、分かったことや感じたことが多く、DVDでは語られなかったことが聞けて良かった。偏見や差別はだめだと分かっていても、やってしまう人間なのでその考えをどう変えていくかが大切だと改めて思った。ハンセン病の偏見は今ではもう少なくなってきているかもしれないが、自分の普通を貫くのではなく、違う角度や方向から見て、新しい考えをもっていきたいということを私は皆に伝えたい。したがって、ナガシマは顕著な普遍的な価値を持っている。』
☆161日目(10.16)学習したことをふりかえる一考(続き)
「感想」、「まとめ」だけでなく、様々な学習のふりかえりのスタイルを持っておきたいなあと思う。実践例として、ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会さんと連携して学習した際に、「顕著な普遍的価値の言明」の取組があります。
療養所が世界遺産として登録されるためには遺産(建物、構築物、土地、景観)に必要な「顕著な普遍的価値(Outstanding Universal Value)」を作成する必要があります。顕著は普遍的価値とは、「その遺産の文化的意義が国境を越えるほど顕著であり、今日及び次世代のすべての人類にとって共通に重要であること」をいいます。それを作成することを、「学習したことのふりかえり」のひとつにしました。
学習活動⑤【「今」ハンセン病問題に取り組むひとに出会う】
NPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会事務局長釜井大資さんをお招きして
・釜井さんからポスターを使ったワークショップ
◎釜井さんから生徒へ《顕著な普遍的価値の言明(A4)生徒版》の課題を提起》
生徒がつくった顕著な普遍的価値への言明の一部を紹介します。
◆ナナミさん
『ハンセン病問題は、ハンセン病にかかった人があれはうつるものだと決めつけられて、隔離されて、人としての正しい扱いを受けられず差別され続けられたことだけではなく、その長期に渡っての偏見は簡単には消えず、いつまでも残り続けてしまうので差別を受けて続けてきた人々の心も傷つき、社会復帰できる環境であってもすぐに戻ることはできなくなってしまうということが分かった。
人は誰もが言う「普通」と少しでも違う部分や、ある人が自分の勝手な判断で考えたこととかが広がると差別するし、差別につながるのだと思う。見た目であったり、その人が持っている病気のことであったり、その人の性格のことで、付き合い関わり方を変えてしまうのは違うと思う。
でも、私自身、今までに生まれつき病気を持った人に対して友達や普段みる人とは違う目で見てしまうことがあった。今回長島について、差別について学んで改めてこの世にいる人全てが大切な存在であり、全員普通であるんだ、違う目でみられる人なんていないと思った。生きていく中でも、その気持ちを常に持ち続けいくこと、持とうと思わなくてもそう思っていられる、そんな人が増えていくことで正しい考えを持つことができるし、違うことをただすこともできると思う。長島について考えることは、ハンセン病についての正しい知識を持つことにつながり、差別がどれだけ人を苦しめて間違ったことを生み出し続けるかを知ることにもつながる。今、私たちがこれらのことを学んだので、次はこれから生きる人たちに伝えていこうと思う。したがって、ナガシマは顕著な普遍的な価値を持っている。』
☆160日目(10.15)開示・協働のちからは高まっているか?
これまで、子どもたちの学力保障にとって大事なことは、「授業がわかること」、「自分を受け止めてくれる教師や地域の大人がいること」とともに、「心を通わせることの出来る友だちがいること」と様々な研究者は提言してきました。このことは、生きる力としての学力保障とは、単に学習内容が理解できることではなく、他者とつながりながら自己実現して社会の中で生き抜くための力を身につけることであるということを表しています。「自分を受け止めてくれる教師や地域の大人」や「心を通わせることの出来る友だち」とつながることによって、被差別の子どもが自分自身の存在を認め、自信を回復し、立ち上がる力をつけることをめざしているのです。そして「なかまづくり」は、子どもたちがこれら身の回りにいる人たちとつながるためのさまざまな取組を指しています。
「なかまづくり」を通して身に付けさせたい力の中で、最近気になることは「開示」や「協働」などの技能的側面です。相手に自分の意志や意見をはっきり主張することが大切だと思う気持ちが十分にもてていないことや、相手に自分の気持ちや考えをきちんと伝えるという行動に移せていないと捉えることができます。 「開示」の技能的側面は、困ったことや悩みを周りに相談することができていないと捉えることができます。 さらに、「協働」の技能的側面は、困っている人や集団の問題を解決するための行動ができていないと捉えることができます。
そこで、自分の考えや気持ちを相手に伝わるようにすることが良好な人間関係を築く為の基礎になるという実感や、同様に困ったことや悩みを周りに打ち明けられるような環境づくりの大切さを実感し、困っている人や集団のために解決する行動を起こすことが、学級の一員として、また社会の一員として良好な人間関係を築いていくことになると実感する経験が必要だと考えられます。
そのため、学級の中で自分の気持ちや考えを相手に伝わりやすいように工夫して伝える場面を仕組むことや、誰もが思いや悩みを打ち明けたときに受け止められるような雰囲気(場)をつくっていく手立てを講じることが必要となります。また、学級の中でさまざまな仕事を受けもち、友から頼られたり、自分がその仕事を達成したときの成就感を味わったりできるような手立てが必要です。また、全体的に技能的側面が低く現れていることから、道徳や学級活動等の取組において、日常の実践的行動力にいかにつなげるかという視点に着目した授業展開の工夫が必要と考えられます。
☆159日目(10.11)つづる・語る
再度、「仲間づくり」の有効性が確かめられてきたいくつかの手法をまとめました。
①「つづる」「語る」・・・一人ひとりが自分を見つめる取組
「つづる」とは、過去の出来事を順番に思い出し、事実をありのままに書いていくことです。これを積み重ねることで、生活のなかにある自分自身の課題や不安、悩みを意識化し、これからの生き方や社会のあり様を考えることができるようになります。自分を見つめることは、つらいことや苦しいことも受けとめ、自分を否定することなく生きていく力を培っていきます。そうした力を身につけた子どもは、友だちの前で「語る」ことができるようにもなっていきます。また「語る」ことは、単に誰かに伝えるだけではなく、自尊感情や将来展望を確かなものにしていくことにもなります。
②「読み合う」「聴き合う」…知り合い、共感し合う取組
朝の会や帰りの会等で日常的に子どもがつづったものを読み合う取組や、人権学習・人権集会等で伝え合う取組が行われてきました。こうした取組によって、子どもは友だちの思いを知ったり、友だちに思いを返したりするなかで自分を深く掘り下げていきます。また、思いを伝える姿が、他の子どもにも「もっと自分のことを深く見つめたい」「自分もずっと避けていた課題と向き合いたい」という意欲を喚起することもあります。
「読み合う」「聴き合う」取組を進めるにあたっては、私たち教職員が自分自身を語ることを大切にしてきました。教職員が自分の不安や悩み、これまでの経験等を語ることは、子どもたちの「こういうことを話してもいいんだ」「自分のことを聴いてほしい」という安心感につながっていきます。人権・同和教育の歴史の中で、「なかまづくり」とは、単に学級の子どもたち全員がなかよくなることをめざしたものではありません。部落差別をはじめとする、あらゆる差別を許さない反差別の集団づくりをめざしたものです。
わたしたちの先輩教師たちは、学校で気になる子どもたちの姿を見るにつけ、家庭にあしを運び、子どもたちの生活を知り、保護者の思いを受け止め、それを学級に返していくことで差別によって分断されてきた子どもたちをつなぐ地道な取組を続けてきました。
このような歴史の中で、「なかまづくり」は、それぞれ違った個性や生活背景をもった子どもたち一人ひとりが互いの存在を尊重し合い、集団の中でさまざまな個性を磨き、共に成長する関係を築く中で、一人ひとりの自立をめざす取組となっていったのです。
☆157日目(10.10)
「ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高める」人権教育
仲間づくりのポイント(続き)
④個別的な人権問題についての学習と結びつけて取り組むこと
一人の子どもの生きづらさの背景に人権問題がある場合、その生きづらさは社会の問題であり、他の子どもにとっても共通の課題となります。友だちの思いを聞くなかで、「友だちを不安な思いにさせていたのは、社会の偏見や差別だった」「そのことに無自覚だった自分は、友だちを不安にさせていた」といった気づきが、人権問題の解決を「自分事」として引き寄せていきます。また、様々な人権問題について学習する際、自分が生活のなかで感じている不安や自分にとって身近な人権問題と重ねて考えを出し合うことによって、マジョリティを「普通」とする価値観やそれへの同調圧力など、それぞれ個別の問題に共通する社会の課題を見出し、自分自身とのつながりを見出すことができます。「仲間づくり」を基盤に、こうした学びを積み重ねることが、ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高めることにつながります。
11月には、1年生は「仲間をもっと知ろう(発達特性)」、2年生は進路キャリア学習の一環として「ホームレス問題」について、3年生はハンセン病問題学習に取り組み、上記の「ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高めること」を進めていきたいと思います。(続ける)
☆156日目(10.9)思いを知り合う機会を・・・弁論大会、、、
幼稚園及び特別支援学校幼稚部、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教育要領や学習指導要領には、「前文」が加えられ、そのなかで、これからの学校には一人ひとりの子どもが、「自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と述べられて
います。ここに示されている子どもたちに育みたい力は、これまで私たちが人権教育を
通じて子どもたちに育んできた力と重なるものです。生まれ育った環境や障がいの有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもたちが意欲的に学び、夢や希望を実現できるようにしていくためには、学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの自尊感情を高め、多様な人と協働しながら、人権が尊重される社会づくりに主体的に参画する力を培う必要があります。そして、その取組は、これまでの同和教育の理念や成果、手法を踏まえ、教育的に不利な環境のもとにある子どもを中心に据えた「仲間づくり」を基盤とすることが重要です。
何度も繰り返しになりますが、「仲間づくり」について再掲します。
◆「仲間づくり」の目的
めざすべき「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある人権問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。
◆「仲間づくり」の視点
「仲間づくり」は、こうした目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。そのうえで、どのようなことを大切に取り組んでいけば良いか、これまでの教育実践の成果などを踏まえ、ポイントをいくつか挙げます。
①子どもの生活背景をつかむこと
すべての教育活動は、子どもの姿、子どもを取り巻く現実から出発することが大切です。気になる言動を見せる子どもがどんなことを考え、どんな思いでいるのか、どんなくらしのなかで生活し、学校に通っているのか、保護者はどんな願いをかけて子育てをしているのか。そうしたことのなかに、その子どもが抱えさせられている課題を解決するための、取組のヒントがあります。子どもの生活背景をつかむためには、家庭訪問等の取組を通じて、くらしや思い・願いなどについて対話できる関係を、子どもや保護者と築くことが必要です。
②弱い立場に立たされている子どもを中心に据えて取り組むこと
「中心に据える」とは、決して集団のリーダーにするということではありません。取り組む教育活動が、子どもの自尊感情や学習意欲を高めたり、自他の人権を尊重し差別をなくそうとする意識を身につけたりすることにつながるものであるかを、その子どもの姿を通じて検証するということです。集団のなかで疎外されていたり、不安を感じながら生活していたりする子どもが学級で安心して過ごせるようにすることは、誰にとっても居地の良い環境をつくることになります。また、弱い立場にある子どもの側に立ってまわりの子どもや集団を見ることで、他の子どもの課題や集団の課題が見えてきます。
③一人ひとりが生活のなかで感じている不安や悩みを共有し、ともに乗り越えようとする集団をめざすこと
「いいところ」「がんばっていること」を認め合うことは大切です。しかし、それだけではなく、一人ひとりが直面している課題を出し合うことが必要です。家庭や地域での生活、そのなかで抱えさせられている思いを知り合うためには、「聞いてもらえる」「知ってほしい」と思える集団であることが大切です。こうして知り合った一人ひとりの思いを共感することが、一人ひとりの課題の克服や、その背景にある人権問題の解決に向けて行動しようとする連帯感につながっていきます。
先日の校内弁論大会前の学級弁論大会だけでなく、1学期の課題を踏まえた2学期の目標の発表、夏季休業時の聴き取り課題の発表、生徒会・学級役員選挙演説会などなど、「思いを知り合う」機会を意図的に創りたいと思います。(続く)
☆155日目(10.8)サイードその2
『まず、「オリエンタリズム」の意味を調べると次のように書かれています。
【オリエンタリズム】
①オリエント世界(西アジア)へのあこがれに根ざす、西欧近代における文学・芸術上の風潮。東洋趣味。
②東洋の言語・文学・宗教などを研究する学問。東洋学。出典:デジタル大辞泉(小学館)
「オリエンタリズム」は、多くの辞書だと「東洋趣味」と書かれています。「東洋趣味」とは「西洋の人たちが東洋の文化に対してあこがれや好奇心を抱くこと」です。しかし、一般的にはこの意味で使われることはほとんどありません。「オリエンタリズム」は「西洋人が自分の都合のいいように西洋以外を見る見方」という意味で使われることが多いです。なぜこのような意味に変わってしまったのか、順を追って説明していきます。まず、「オリエンタリズム」は英語で「orientalism」と書き、「orient」はラテン語の「oriens」に由来します。「オリエンス(oriens)」とは「太陽が昇る方角」という意味です。つまり、「東側」ということです。この事から、「オリエント」は広い意味で「西洋以外の東側諸国全般」を指し、狭い意味で「西アジアやエジプト」を指すと言われています。ここで一つの疑問が浮かび上がります。それは「西とか東は何を基準に決めているのか?」ということです。考えてみれば、当たり前のことです。私たちの国、「日本」はアジアの東ということで「極東」と呼ばれています。また、アラビア半島やその周辺地域は「中近東」と呼ばれています。しかし、日本が極東にあるという基準は誰が何によって決めたのでしょうか?実はこれらの基準はすべてヨーロッパ人が決めたのです。日本が「極東」と呼ばれるのは、ヨーロッパから見て極めて東にあるからであり、アラビア周辺国が「中近東」と呼ばれるのは、ヨーロッパから見て近い東にあるからです。つまり、これらの言葉は「西洋中心主義」によって作り出されたものなのです。「西洋中心主義」とは「ヨーロッパ文明が世界の中心である」とする考え方のことです。そして、この考え方に異議を唱えたのがパレスチナ出身の批評家である「サイード(1935年~2003年)」と呼ばれる人物です。
サイードは著書『オリエンタリズム』の中で、西洋人のオリエント(東洋)に対する見方には、「西洋中心主義」が色濃く反映されていると主張しました。サイードによれば、西洋は東洋に対して、文学や絵画などを通じて「受動性・後進性・非合理性・幼児性・停滞」といった負のイメージを押し付けたと言います。その事で、西洋の優位性を確認してきたと言うのです。サイードが『オリエンタリズム』を発表してから、「東洋趣味」という概念が実は植民地主義的な考え方であったことが世に広まりました。実際に、西洋人は西洋と東洋を全く別の物とみなし、前者を発達した文明、後者を未開の文明とみなしていたのも事実です。「未開の文明」とは要するに「遅れていて野蛮な文明」ということです。そして、西洋人は東洋文明を遅れていると考えることにより、自分たちこそが世界の中心であるというアイデンティティを確立するようになりました。こうした西洋による身勝手な東洋のイメージを、サイードは「オリエンタリズム」と呼んだのです。つまり、「オリエンタリズム」というのは、西洋による東洋への見方を批判的に表した言葉だったということです。当時の世界は「帝国主義」と言い、強い国家が弱い国家を侵略するのが当たり前の時代でした。具体的に言うと、スペインやポルトガル、フランスなどのヨーロッパ諸国がアジアやアフリカなどの周辺国を次々と植民地にしていたのです。そして、西欧諸国はこの帝国主義的な植民地支配を正当化してきました。このような時代背景もあり、サイードは西洋中心主義の「オリエンタリズム」を強く批判したのです。』
☆154日目(10.5)「他者を語る際に存在する力関係」
ハンセン病問題を「伝え、理解や行動を求める活動」に、長年取り組んでおられる方から、エドワード・サイードの「他者を語る際に存在する力関係」という思想について教えていただきました。その方は、その思想から、ハンセン病問題に取り組む際に「他者の人生を利用しているという自覚をもつ:〈勝手なことを語らない。研究や業績のためになどに消費しない〉」ことを学んだということもお伺いしました。サイードさんが気になったので、少し調べてみました。
『*オリエンタリズムを超えて
「わかったようなふりをしない」「でも、わかろうとする」ということの逆は何だと思いますか。「わかった顔をする」「と同時に、わからないことを誇大化し、神秘化すること」です。これこそがサイードが批判したオリエンタリズムでした。
どういうことかといいますと、「オリエンタリズム」というのは、十八世紀の終わり頃から現代にかけて、西洋が、オリエント地域(中東と考えてください)を理解するときに駆使した学問的言説で、それは1)ヨーロッパ人のほうが、未開の中東の地域の人間よりも中東の人間のことを理解しているという「わかった顔」をすることです。いいかえると西洋の学問的な知は、オリエントは何か、その本質なり特質を立ち上げようとします。そしてそうすることで、オリエントの現実を構築します。現実を構築されてしまうと、それはオリエントの人たちにしてみれば植民地化とかわりありません。と同時に2)神秘的なオリエントをフェティシュ化する。絶対に理解不能ななにかがオリエントにはあるというかたちで、オリエントを徹底して神秘化します。ときには神秘と芸術の世界として称讃すらします。しかし、そうすることによって、オリエントの人間は自分たちと同類ではないというかたちで壁が立ち上げられ、分離の排除のメカニズムが働くのです。それはまた植民地化とかわりありません。
したがってオリエンタリズムとは切り分けのメカニズムなのです。西洋と東洋を分離する。分離することで一方が他方を支配するメカニズムが生まれる。そしてこれに貢献するのが、東洋とは何かという知の言説なのです。これに対するサイードからの批判は、西洋と東洋は、長い歴史の中で相互にまじりあってきた。現実に交流があったし、文化は絶えずまじりあってきたし、ハイブリッド性こそ、文化の本質ともいえるものということです。
☆153日目(10.4)教材づくり
研修会で、「教材づくり」が話題になりました。「子どもたちと一緒に読みたい!・学びたい!」と思った本や題材を教材化することですが、この時代でも若い先生方がそのような想いをもっていることをとてもうれしく思いました。そういえば、私もある本に感化され『命の授業』という教材では、科学的に人間の成分をお金に換算した「人間の価格」から、「いのち」の問題に迫ってみようとか、教材の文章プリントを4つに分けて配り、ストーリーを予想させる展開とか、バス停から離れてしまっているところでバスを待っている視覚障害者をみた自分はどうするのか?を4コマ漫画の最終コマで表現するとか、道徳で挑戦?実践?していた記憶がよみがえりました。それはさておき、ある小学校の先生が「子どもたちと読みたいのです」とオススメしてくれた本は、(TVドラマにもなったらしい)『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』岸田 奈美 (著)です。私も読み始めましたが、「子どもたち一緒に考えたいなあ」と!
☆152日目(10.3)行事での「振り返り」は何とつながっていくのか?〈学び・学級づくり〉
行事での取組の中で、「生徒が主体になるということ、教職員の支援はどうあるべきか」がいつも話題になります。卒業した子どもたちの「ふりかえり」からも考えたいと思います。
○クラスの皆ががんばっている中、ボクは結局最後まで練習に満足に出れませんでした。「大丈夫、明日がんばったらええが」と言ってくれた人たちにひどく申し訳なかったり。
ボクは、未だ自分に甘いようで、私事で練習に参加できなかったり…、でもそれをとがめもせず、「大丈夫」といってくれることに、毎回申し訳なく思いました。だから当日は心から歌いました「ありがとう、支えてくれて」と。届いたかどうかはわかりませんが、届け、届けとありったけの声で歌いました。なぜこのクラスに居たくなったのだろう。あんなに嫌いだったのに。その理由はまだわかりませんが、「楽しかった」。3 年間で一番心に残ると思います、歌っている間のことが。ステージに立った時、足が笑っていました。やばいふらふらすると思っている中、歌がはじまり、気づいたとき、「ありがとう。今まで出会った人たち、ボクをこの世に生んで育ててくれたひと、友人、大事な人、その皆を生んで育ててくれたひと、、皆に「ありがとう」と言いたくてたまらなくなりまた。「ありがとう 大好きです」そう伝わるように心から歌いました。そして同時に私は何度も人を裏切ったことに対して「ごめんなさい」と言いたくなりました。さてこれからもうひとつ大きくて苦しい壁が待っていますね。ボクもそれに向けて歩きださなきゃいけませんね。がんばります。ありがとう支えてくれて。ありがとう信じてくれて。ありがとう何度も裏切ったのにボクの側にいてくれて、きっかけがないと素直になれないような奴ですが、今後ともよろしくお願いします。T
○先生へ、いつも僕たちが歌の練習に、ありがとうございました。
そしてみんなへ、下手な指揮だったけど一生懸命歌ってくれてありがとう。俺たちの音楽会はまだ終わらないぞ!M
○日々の音楽会の練習を一番努力したのは2組だと思う。いろいろなトラブルもあったけど、最後はみんなで歌えてよかった。この団結が消えないように、苦しい受験もみんあで乗り越えていきたい。3-2 ってひとつになれば、こんな力がでるんだなあ。女子もみんな音楽会のために身だしなみに気をつけた。誰一人自分勝手なことをするひとがいなくて、団結してるった感じた。3-2 最高!Y
○3-2 のみんなありがとう!優勝はできんかったけどな…。俺は今までの行事の中でこんあにもみんなと団結してがんばったのははじめてじゃ。みんなで市の音楽会にいけたらええなー。もしいけたら優勝しようなー。みんなありがとう。先生もサポートやアドバイスありがとう。こんなに朝・昼・夜と歌ったのは初めて。のどが居たかった。でも楽しかった。音楽会というひとつの行事で、こんなにクラスが団結できるんじゃなって思えた。なんかクラスの雰囲気が変わったような気がした。最後に後輩たちへ、俺たちも2年生のころは音楽会なんてどーでもええとおもっとった。でも3-2 年になってからクラスで、みんなで、何かする楽しみを知った。じゃから今の1,2年生もクラスのみんなでないかする楽しみを見つけると、いい行事になっていくと思う。MA
○3-2のみんなで音楽会ができて楽しかった。優勝はできなかったけど、みんなで歌った合唱は最高だった。みんなありがとう。クラスみんなで相談して、朝練習をしたり、放課後練習をしたり、一生懸命がんばれた。みんなで放課後神社に行って歌をうたったのが一番楽しい練習だった。途中、いろいろあったけど、みんなが話を聴いてくれたり、いろいろ言ってくれたりでここまでがんばれたと思う。これからもみんなの団結でがんばっていきたい。後輩たちへ、来年もいい音楽会にしていってほしい。TO
○音楽会まで、練習の時いろいろあった。最初は朝練もいやで、「なんでやるのか」ずっと思っていたけど、ずっとやっているうちに本当に音楽会の練習を一生懸命やっている人たちの姿をみて、やっと本気で取り組むようになった。帰りの会が終わった後も、一回ずつ歌って練習したり、がつこうが使えないときは神社で練習したり、きつかったけど、みんなのかけ声のおかげで、練習に必死に取り組めた。歌っているとあごが痛くなったり、のどが痛くなったりしたけど、いろんな人が、どう歌えばいいのか教えてくれて良くなったりした。本当にこんなに音楽会で努力したのは初めてだった。音楽会は2位だったけどこんなに練習した成果が出せれた。本当に良かった。後輩たちも今回にような感動を味わえるような音楽会にしてほしいと思う。O
○3-2のみんなのおかげですごくいい思い出が出来ました。こんなに真剣に歌ったのははじめてで、優勝出来なかったけど、感動1位、団結力1位!だったと思います。どのクラスよりも2組は、まとまっていると思います。私は3-2 でよかったと思います。3-2 のみんなありがとう!どのクラスより練習する時間が多かった2組は、それだけみんなが「優勝したい!」という重いが大きかったんだなあと思います。神社での練習もすごくいい思い出になりました。楽しかったです。受験に向けても、みんなで励まし合いながらいけるといいです。後輩たちへ、みんながひとつにまとまれば、きっと最高の音楽会が出来るはず。さいごまであきらめずに!「ただの音楽会じゃけ どうでもいい」と思わず、音楽会にかけてみてください。O
☆151日目(10.2)教育と福祉の協働は可能か
「春15の会(特別支援教育のニーズのある子ども・保護者のための進路情報交流学習会)」実行委員会に参加しました。今年度は残念ながら、台風のために対面での情報交流学習会は中止となってしまいましたが、実行委員会では今年度の取組の総括を中心に話し合いました。その中で、「教育と福祉の連携・協働の重要性」について今回も話題になりました。
文科省も、連携について以下の内容があります。
「発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところです。
特に、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されています。こうした課題を踏まえ、各地方自治体の教育委員会や福祉部局が主導し、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、文部科学省と厚生労働省では、「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」を発足し、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討しました。」
また、福祉とは距離が遠いように思える教育と福祉分野の連携に関する「教育福祉」という内容があるようです。私自身は聞き慣れない言葉ですが、不登校や貧困、発達障がいなどの困難さを抱える現代の子どもたちの成長において非常に重要な概念となっているようです。『教育福祉とはどのような福祉のことなのか、その概念や具体例が解説された文章を少し紹介します。
[教育福祉の概念]教育学者である小川利夫によって1972年に提起されました。定義”教育福祉とは、教育と福祉が連携して、子ども・若者あるいは成人が安定した生活基盤のもとで豊かな人間発達を実現することをめざす概念である。”(辻 2017:1)
言い換えると、子どもと若者を取り巻く貧困や障がいなど様々な困難に対して、福祉と連携して支援することで成長や発達を支えるという考えになります。学校における児童生徒の環境調整や関係機関と連携した支援を行うスクールソーシャルワークは、まさに教育福祉の代表的な取組と言えます。教育福祉は、高度経済成長期に経済的な格差が広がる背景において生活基盤が不安定な層が増えたことや、夜間中学・養護施設の児童や勤労青年などの「教育と福祉の谷間」の問題に焦点が当てられたことで提起されました。この「教育と福祉の谷間」の問題は、子どもの貧困やヤングケアラー、不登校の児童生徒の増加など今日においても広い範囲にわたっており、支援の重要性は増してきている状況にあります。(ちなみによく似た言葉として、「福祉教育」がありますが、福祉教育は身の回りの福祉に関する課題や解決策を学ぶ教育になりますので、教育福祉とは全く異なるものになります。)
[教育福祉の例]
教育福祉には具体的にどのような取組があるのでしょうか。教育福祉は類型化すると、主に学校教育福祉と地域教育福祉の2つに分けられます。学校教育福祉はスクールソーシャルワークとも呼ばれていますが、主に学校教職員やスクールソーシャルワーカーなどが子どもや家庭に関わる取組が該当します。最近では、「地域に開かれた学校づくり」の取組においてコミュニティ・スクール[1]と地域学校協働活動[2]が一体的に推進されており、地域との連携により学習支援などの活動も行われるようになってきています。地域教育福祉は、学校に限らない公民館などの社会教育施設などで行われる取組が該当します。歴史的には、夜間中学や青年学級などの成人向けの取組が行われてきましたが、現在では、地域社会の希薄化や貧困などにより、子ども食堂などの子ども向けの取組も行われるようになりました。また、最近では、子どものサードプレイスとして「宿題カフェ」と呼ばれる放課後に子どもが集う場所づくりも行われています。地域教育福祉の取組には、地域に根差した活動や社会教育の実践が大きく関わっています。これらは必ずしも自治体によって行われているものだけでなく、NPOなどの民間団体によって取り組まれている活動もあります。
[教育福祉の視点]
教育福祉は、不登校、障がい児、外国人の子ども、子どもの貧困など多岐にわたる分野で重要な取組となっています。取組を行っていくためには、学校教職員と福祉関係者との連携や地域との連携が大切になります。様々な職種や立場の人たちが連携して、子どもたちにとってどのような支援が必要なのかを考えることが重要です。また教育福祉が重要視されるようになった背景には、制度の狭間に陥ってしまった当事者たちの問題がクローズアップされたことがあるため、既存の制度や支援では対応できない問題に注目することも重要です。特にヤングケアラーはその典型であり、これまで見過ごされてきた問題に焦点が当てられ、子どもの権利の視点から支援のあり方が考えられています。
教育福祉という言葉自体は馴染みが薄くても、その取組は意外とみなさんの身近にあるということです。教育福祉では、子どもや若者たちの育ちや学びにどのような支援が必要かを考えることが重要です。これからも子どもの最善の利益の視点に立って、教育福祉が一層推進される社会になることを願います。
[参考文献]辻 浩‚ 2017‚ 『現代教育福祉論—子ども・若者の自立支援と地域づくり』ミネルヴァ書房 山本理絵・望月彰、愛知県立大学「教育福祉学研究会」編‚ 2023‚ 『教育と福祉が出会う支援—子ども・教師・専門職がつながる学校・地域をめざして』溪水社
☆150日目(10.1)生徒会は、民主主義の学校
生徒会中央役員・専門委員会の認証式では、校長も「自分が投票した人が当選しなかった」「自分は不信任の意志表示」をした場合などについて言及されてましたが、私も《民主主義》のあり方を学ぶとても大切な機会であると思います。
『自分は何ができるか(自分は何をするか)』という視座が、次世代の担い手となるためにはとても大切だと思います。
「主権者」と「傍観者」の違いは,この「参画意識」の差だろうと思います。今回の選挙に立候補した生徒は,学校の課題を意識することができました。立候補者以外の生徒(不信任の意志表示をした生徒)も意識をすれば学校をさらによくする「主権者」になれます。
「地方自治は,民主主義の学校」と言われますが,身近な問題に意識を持てるか持てないかで,社会の見方は変わってきます。テレビ番組でも,回答者のタレントの中に,驚く
ほど社会問題に詳しかったり,問題意識が高かったりする人がいて,派手な外見とは別に,知性を感じたことがありました。意識は変えられます。意識が変わると,様々な情報が自分のアンテナに引っかかってくることになります。そうすると,ニュースが面白く見られるようになり,自分との関わりが少しずつ視えてきます。現状を知り,課題に対して,自分が参画していく意識を芽生えさせ,民主主義の主人公になっていける一助となるよう事後指導を積極的に進めていきたいと思いました。
☆149日目(9.30)SSWやSCとの連携・協働って大切。


柔軟な対応をありがとうございました。どんな連携・協働ができるか!これからもよろしくお願いします。
☆149日目(9.27)子どもの困り感をもとに、変えるのはワレラ
先日の校内研修でみんなと話し合ったことがもう1つあります。それはひとつの学年に対しての授業づくり(学習集団づくり)です。もちろん、教科指導は各教科担当が全精力をかけて授業研究・準備を進めるのが前提ですが、学習集団としての子どもたちを豊かに育てていくためには、チームとしてのアプローチが必要です。この日は、その学年の授業に関する取組や苦労していることを語ってもらいました。また、学年団の先生からも、その学年の生徒が成長してきた取組や強みについて話してもらい、今後の授業づくりにおおいに参考となりました。具体的実践に向けては、4人でのグループ学習時に声の大きさが気になり、話し合い活動に集中できにくい生徒がいることが共通の話題となり、意見の中で出た「グループ学習にふさわしい課題の提供」と「学びが成立しているか、授業者が意識的に、グループ学習を看取ること」、そして「4人でなく、2人のペアリング学習の活用」と「その際の声量の調整指導・支援」を進めていくこととなりました。みんなで授業づくりをがんばろう!

☆148日目(9.26)「人と食事をするのが苦手です」と。
山陽新聞(9/25)の子どもしんぶんさん太タイムズの記事に、「わたしは食べるのが下手(天川栄人作 小峰商店)」という書籍が紹介されていました。コロナ禍後の教育活動の内容の見直しだけではありませんが、「人と食事をするのが苦手」という子どもたちの存在も考えながら、先日の話も考えなければならないと思いました。読んでみようっと。
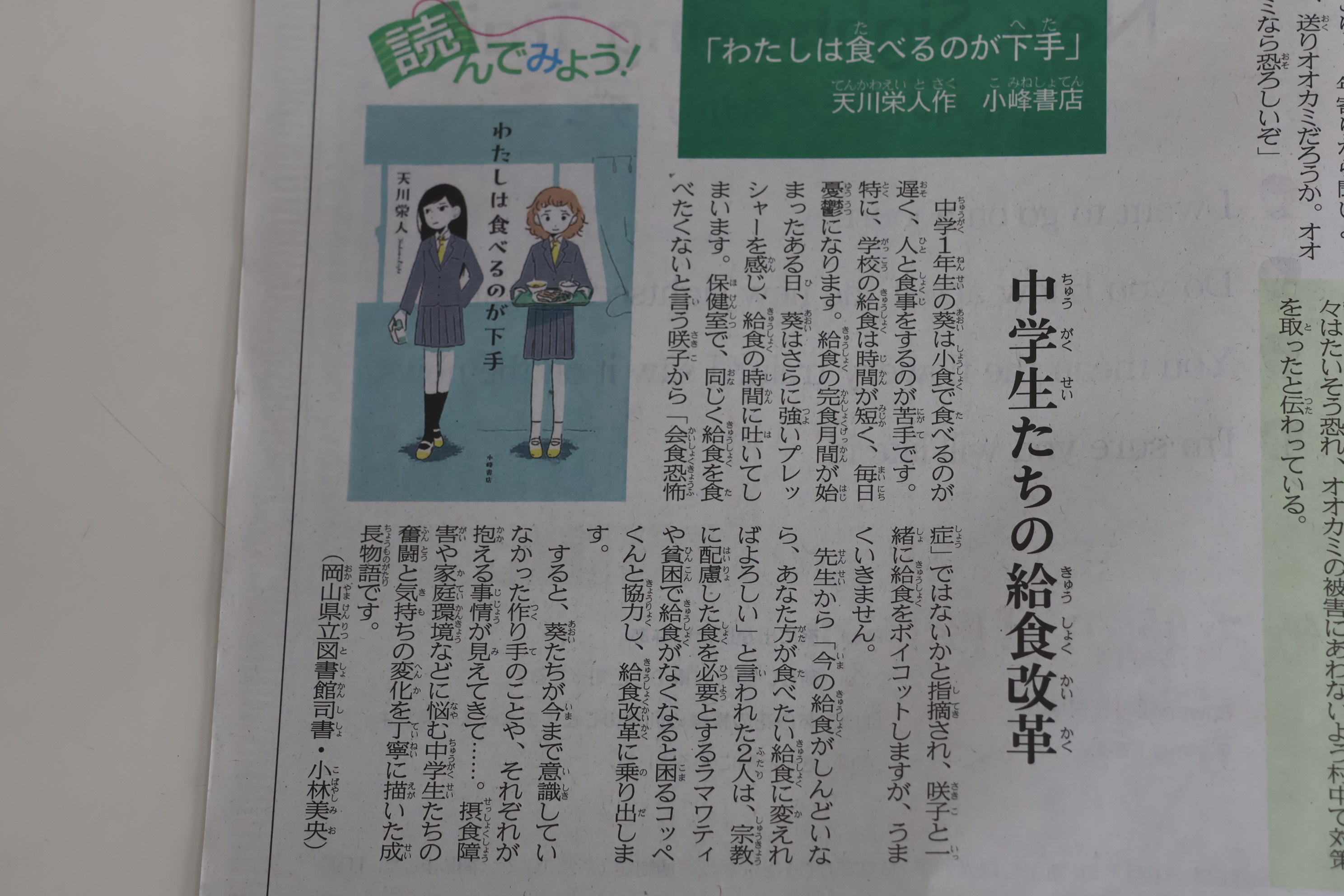
☆147日目(9.25)
先日の校内研修が終わっての立ち話。
生徒どうしが「かかわる」場の創出を考えたとき、「給食の生活班で食べること(会食)はとても大切だなあ」と確認しながら、まだコロナ禍の影響(?)で、一斉授業スタイルでの昼食になっている学校も多いとのこと。そうなっているのはどういうことなのか?を考えなければいけないなあと思いました。「やっぱり感染予防」「班にしたらウルサ過ぎる?「トラブル防止」「子どもたち自身が個食に慣れて、気まずそう」「給食の片付け時間が確保できない」・・・。話してみるといろいろと考えがありそうです。でも、それを越えて、やっぱり子どもどうしが「かかわり」、お互いが「そうなん。そうだったんか」と様々なコトをわかり合う場づくりを創出していきたいなあと思います。

☆146日目(9.24)今こそ「思想と行動を打ち鍛えたい」
~「ヒロシマの母子像ー四國五郎と弟・直登ー」から

大阪を拠点にシンガー・ソングライターや作家、俳優など多彩な表現活動を続ける趙博(チョウバク)さんが手がける一人芝居「ヒロシマの母子像―四國五郎と弟・直登―」の全国巡回公演に行ってきました。
今年は広島の反戦詩画人・四國五郎の生誕100年・没後10年。戦争を憎み、平和のために生きた四國に共鳴した趙さんは「反戦平和の思想と行動を今こそ打ち鍛えたい」と言われます。
絵本「おこりじぞう」の挿絵などで知られる四國五郎さん(1924~2014年)は徴兵先の旧満州(現中国東北部)でソ連軍との激戦を生き延びた後、三年間のシベリア抑留を経験します。そして広島に帰郷して弟の直登が原爆の犠牲になったと知り、弟が死の間際まで付けていた日記を母から受け取ります。その夜、自身の日記に「直登の死に対する悲しみを怒りと憎しみに転化させよ!」と書きました。
趙さんの一人芝居は、兄弟の絆を軸に、平和を希求する思いを語りや歌で構成されています。四國五郎さんが手がけた絵や詩、直登の日記などを織り交ぜ、母子のつながりを断ち切る戦争への怒り、それを許さない愛情。タイトルは四國が生前に発表した詩画集から発案されています。
趙さんは生前の四國五郎とは面識がありませんでしたが、19年に大阪大総合学術博物館であった回顧展で衝撃を受け「何としても伝えたい」との思いに駆られました。23年夏に大阪市内で初演し、その後台本を改訂しながら、今夏から関西を皮切りに全国巡回公演に臨んでおられます。
趙さんは「四國さんが生きていればウクライナやガザを見て何と言い、どんな作品を作っただろうか。被爆を体験したこの国で、反戦平和の思想がなぜ根付かなかったのか。芝居を通じて問いたい」と言われています。
岡山・オリエント美術館での本公演では、趙さんの深く、力強い、そしてあたたかい声での、語り・音楽、そして四國五郎さんの絵が大きく・厳しく自分の実践や活動に迫ってきました。
エンディング近く、趙さんが客席の間を通りながら「あなたの隣を見てください ひろしまの子がいませんか」という語りかけに、公演会場の一人ひとりが、思いを深くされていたように感じました。自分自身も、鈍った「思想と行動を打ち鍛え」、明日からの学校現場でガンバラネバなりません。
☆145日目(9.20)朝の会・帰りの会をどうする
今週の校内研修では、「朝の会・帰りの会についてどう考えるか?」について、これまでのクラス・仲間づくりの取組をもとに、和やかな雰囲気の中で、みんなで話し合いました。会自体は、とても短い時間ですが、一方的な連絡だけにならないような手立てや、「今日一日をがんばろう!」生徒らが元気で過ごせるような働きかけなど、具体的な取組内容を紹介し合うことができました。
また、生徒たちが「かかわる」場をつくる例として、「いまどんな気持ち」大阪府人権教育研究協議会(大人教)ホームページ (coocan.jp)の実践報告もありました。これはこの教材を利用して、生活班内で、自分の気持ちを表現(表出)し、他者に「関心をもち、かかわろうとする力を豊かにしていきたい」という視点からの実践報告でした。
「目ざす教育目標」に向けて、教職員それぞれの持ち味を生かしながら、学校のみんなで子どもたちを育てていこう!感じることができたよい研修会でした。

☆144日目(9.19)アンケートを考える 2
◆アンケート調査の計画では、次の項目を明確化することにより、実施方法を選択・決定していくことになりますね。 何のために調査をするか(調査目的) 何を収集するか(調査項目) 誰に聞くか(調査対象) 何人に調査するか(調査規模) いつ調査するか(調査時期) どのように調査するか(調査方法) どのように分析するか(分析方法) どのように報告するか(報告方法) 予算はいくらか(予算計画) いつまでに報告するか
と、話しながら、私もこれまで様々なアンケートを作成、実施、活用してきましたが、学校での取組では、あといくつかの要素が必要だと思います。ひとつめは、アンケート自体に、学習的な意味を持たせたい。アンケート内容に「学び」や、「新しい(正しい)知識」に触れることのできる内容を入れたり、アンケート実施後の学習時には、アンケート結果の「価値づけ」等をおこなうべきだと思います。ふたつめは、アンケートに向き合う一人ひとりの意思(コトバ)を尊重することです。
現在、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に合わせ、学校でのアンケートも実施されていると聞きましたが、もし本校が、実施にむけて検討するなら、「被害者がいるであろうことを前提」に、「あなたが悪いのではない、あなたが大切という強いメッセージ」と共に、「あなたの救済、相談へつながる道筋」を明記」し、とてもしんどい思いしたことを改めて憶いだせること」に寄り添う内容にしなければならないと思っています。
NHK“性暴力”実態調査アンケートについては、以下のような文章がありました。『…性被害についてのに遭ったという方やそのご家族を対象に、〇月〇日から〇月〇日まで実施した、NHK“性暴力”実態調査アンケート。一人ひとりのご経験や思いを、より大きな声として可視化して、社会全体に問いかけたいと回答を呼びかけました。
38‚383件。これが、私たちの元に届いた傷みの声です。
心から感謝するとともに、皆さんの思いを受け止め、それを伝えることの責任を感じております。
現在、アンケートの作成にご協力いただいた専門家の方々とともに分析を行っております。詳しい分析結果や専門家の見解は、こちらのページで6月以降に公開する予定ですが、今回は「被害の内容」や「加害者との関係性」など、一部を先行してお伝えします。
また下記の番組でも、アンケート結果とともに性暴力被害の実態に迫り、私たちの社会に求められることを考えます。ご覧いただけると幸いです。』
「今回、初めて自分の経験を人に伝えました」
「被害者ばかりが責められる社会を少しでも変える力になりたい」
「被害を思い出すのはきつかったけれど、当事者の実態を少しでも知ってほしいと回答しました」
被害について思い出したり、ことばにしたりすることは、大きなご負担をおかけしたことと思います。さらに自由記述欄には、被害の詳細やその後の苦しみ、アンケートに込めた思い、性暴力根絶への思いなど、本当に“命がけ”でつづってくださったことばがあふれていました。
アンケートや調査は、あたりまえですが、当事者を意識し、そのアンケートの重みを受けとめ、願いを実現できるよう取組につなげていくことが何より必要だと私は思います。
☆143日目(9.18)アンケートの意義1
最近、QRコードの普及にともない、アンケートが多くなったなあと思いがしています。さらに、実施したアンケート後どのように活用されたかが不明確で、多くの時間(「わずか5分です)と言われるけど)の浪費感が残るのは否めません。
そもそもアンケート調査とは、調査対象の意見や行動を把握するため、特定の期間内に様々な調査方法で様式化した質問で回答を求め、データを集める調査方法です。アンケート調査は調査対象に回答を求めなければ得られないデータを収集することが主な特徴であり、企業や行政サービスに対する顧客の満足度や、性別・年齢別の消費者の生活様式の把握が例としてあげられます。
アンケート調査の目的は、そのアンケート調査の位置づけにより異なり、計画を策定していくうえで目的を明確化する必要があります。事業活動を継続的に改善する手法として PDCA サイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Act:改善)がよく知られていますが、アンケート調査が PDCA サイクルのどの段階に位置づけられるかを照らし合わせることにより、アンケート調査の目的は定まりますね。
Plan(計画):問題の把握や仮説の設定を目的とした調査
(例)生活時間調査、家計調査 Do(実行):実態を詳細に把握することを目的とした調査
(例)サービスの利用状況調査、商品の利用実態調査
Check(評価):課題の原因分析や、事業効果の測定を目的とした調査(例)サービスの満足度調査、商品への要望調査
Act(改善):改善案を実施した場合の効果の検証や、事業の継続・改善案の実施を判断することを目的とした調査
(例)改善後サービスを例にとった要望調査、市場性調査
III. 実施方法
アンケート調査の実施では、アンケート調査の計画を立て、計画通りに実施し、収集したデータを分析し、分析結果を報告するという進め方となります。
☆142日目(9.17)児童・生徒をどう呼んでいるか?②
[男女で分ける]
男子生徒には姓名に「くん」、女子生徒には「さん(ちゃん)」を付けて呼ぶ方法は自然に聞こえる一方で、ジェンダーニュートラルへの配慮が欠けているとの意見もあります。性差をつけず全員を「さん」付けで呼ぶ指導の広がりがあるように、多様性を尊重する流れが強くなっているからですね。しかし現在でも、生物学的な性別で呼び方を変える方法は、教育現場でもよく見られます。たとえば「たなか さとし」という男子生徒がいれば、「たなかくん」「さとしくん」と呼ぶような感じです。また「たなか さとみ」という女子生徒がいれば、「たなかさん」「さとみさん」と呼んだり、低学年の児童であれば「さとみちゃん」という風に、意識的に「さん」と区別して呼んだりするケースもあるでしょう。
さらに苗字に「くん・さん」を付けるより、下の名前に「くん・さん(ちゃん)」を付けるほうが親近感を与えます。しかし異性の下の名前に「ちゃん」を付けて呼ぶのは、距離感が近すぎて、不快に思わせるリスクも…。異性を下の名前で呼ぶのは、極力避けることをおすすめします。
ちなみに現在は日本の多くの新聞でも、小学生男子に「君」、女子に「さん」を付けています。この一般例も、ジェンダーニュートラルの広がりで変わるかもしれませんね。
[呼び捨て]
呼び捨ては「さん・くん・ちゃん」を付けるより、相手に親近感を与える効果があります。しかし関係性によっては、少し乱暴な感じに聞こえるので注意が必要です。たとえば初対面で「たなか!」あるいは「さとし!」という感じで、いきなり自分の姓名が呼び捨てにされるのを想像してみてください。上から目線だと感じたりなれなれしい印象を受ける人は、一定数いることでしょう。また、男子生徒は呼び捨てで女子生徒は「さん」付けをすると、それは男女で差を付けていることになります。どのような呼び方であっても、全員統一するのが望ましいでしょう。親子や師弟のような親近感を感じるか、なれなれしさや荒っぽさを感じるかは、生徒の受け取り方次第です。呼び捨てで呼ぶ際には、生徒との関係性が大切になりそうです。
[あだ名]
あだ名で呼ぶことは、姓名の呼び捨てよりも、さらにフレンドリーな印象を生徒に与えるでしょう。ただし、いじめ防止の観点から生徒間ですらあだ名を付けることを禁止している学校もあります。自分に付けられたあだ名を、必ずしも全員が気に入るとは限りませんよね。そういう状況で、先生が生徒をあだ名で呼ぶことはあまりおすすめできません。
また特定の生徒だけをあだ名で呼ぶことは、その他の生徒から違和感を持たれるリスクがあります。よほどの信頼関係がない限り、生徒をあだ名で呼ぶのは避けた方がよいでしょう。
[代名詞]
生徒一人ひとりと心を通わせて話をするなら、「きみ」「あなた」といった代名詞ではなく生徒の名前を呼びましょう。その理由は、生徒を名前で呼ぶことで「ネームコーリング効果」が期待できるからです。「ネームコーリング効果」とは、自らの名前が呼ばれた際に、名前を呼んだ相手への好感度や信頼感が増す心理現象のことです。生徒を呼ぶときには「きみ」や「あなた」と呼ぶより、きちんと生徒の名前で呼んであげるといいでしょう。
しかし実際には、生徒の名前を呼べないケースもあるでしょう。代名詞を使う可能性のあるシーンは、以下のとおりです。
○慣れないクラスに入ったとき ○生徒の名前を忘れたとき
上記以外では、複数の生徒に話しかけるときに、全員まとめて「きみたち」「あなたたち」と呼ぶケースも考えられます。生徒を呼ぶときに代名詞を用いることは、そもそも好ましくありませんが、使わざるを得ない状況もあるでしょう。
〈どの生徒にも中立であるか。個々の生徒への配慮が足りているか〉
ここまで説明したジェンダーニュートラルを目指す動きやいじめ防止の対策など、数十年前までは問題視されていなかったことも、今は慎重に対応する必要があります。そういった時代の変遷を見逃さないこと、そして生徒一人ひとりに誠実に対応することが信頼関係を築くために大切なのではないでしょうか。
☆141日目(9.13)児童・生徒をどう呼んでいるか?①
他「児童・生徒をどう呼んでいるか」について、小学校に勤める連れ合いと話題になりました。(以前、自分の子どもが通っていた学校では、親のワタシが居る前でも、名字ではなく「名前」(いわゆる「呼び捨て))で、とても違和感を感じたことがありました。)
それぞれの学校が持っている学校風土や生徒観、小学校、中学校など校種の違いで呼び方はいろいろあるようですが、この時代、「学校」という場所で、どう呼ぶのがよいのでしょうか。たまたまインターネットで見つけた「まなびチップス」というサイトを読んでみました。
・・・「生徒をどう呼ぶべきか」という問いは、一見シンプルに見えて奥深いものです。相手の呼び方は、その人との関係性を形作る要因のひとつになり得るからですね。場合によっては、呼び方ひとつで教室の雰囲気まで変わる可能性もあります。
この記事では、そんな「生徒の呼び方問題」について考えてみましょう。
[生徒の呼び方とその印象]生徒の呼び方は、ざっくりと以下の5パターンに分類できます。□全員「さん」付け、□男女で分ける、□呼び捨て、□あだ名、□代名詞
厳密には「くん」「さん(ちゃん)」を付けたり、姓の呼び捨てか名の呼び捨てかなど、パターンは細かく分けられます。それぞれが与える印象など、生徒の呼び方について詳しく見ていきましょう。
[全員「さん」付け]
全生徒に対して「さん」付けをする呼び方は、ジェンダーニュートラル(性差に縛られない思考や行動、社会)の考えの浸透を目指す社会的背景が教育現場にも反映されたことで広まってきています。このジェンダーに関する問題意識は、日本では1980年代から徐々に広がって今に至りました。「さん」付けの呼び方は、生徒に次のような印象を与えます。
○どの生徒にも平等な印象 ○ジェンダーニュートラルな印象 ○生徒を個として尊重し、敬意を払っている印象 「さん」付けで統一して呼ぶことですべての生徒に対しても平等になり、男女の性差をつけない姿勢を生徒たちに示せます。また呼び捨てよりも「さん」付けのほうが、生徒に敬意を示せるでしょう。ただし全員「さん」付けの呼び方をすることに対して、心理的な距離を感じるなどの理由から否定的な意見を持つ人もいます。実践している現場でも、徹底度合いはまちまちで、デメリットを感じている先生も少なからずいるようです。ちなみに「さん」付けに限らずですが、下の名前で呼ぶことには、相手により強い親近感を与える効果があります。ただし名前呼びを嬉しく思う生徒がいる一方で、距離感の近さに抵抗感を持つ生徒もいることも事実です。「さん」付けで呼べば、授業中や会話でも自然と敬語が増えるでしょう。先生への親近感が薄れる可能性もありますが、線引きをしっかりすることで学習面ではプラスになることもあります。(続く)
☆140日目(9.12)本当の廃止や中止の理由は
他県の学校給食で、「フォークの扱いが危険だから」という意見が出て、「スパゲティをお箸を使って食べる?」という議論があった話を聞きました。そういえば先割れスプーンも使われなくなって久しいですが、周辺の先生に「廃止の理由」を聞くといろいろそれぞれでした。どうということはないのですが、Wikipediaを参考にいくつかをまとめました。
○学校給食の場で先割れスプーンが一頃盛んに用いられたが、今では『箸の使い方を知らない子供が増えたこと』の原因とされ廃止されつつある。
○1970年代から普及したランチプレートと呼ばれる総合食器の登場以降、逆に「ランチプレートに顔を近づけて食べる」という犬食いと呼ばれる食べ方を発生させる要因ともなった。器を置いたままで食べる洋食のスタイルとは異なり、日本では「食器を口元に持っていって食べる」という和食習慣を持つため、この食べ方はともすれば見苦しいとされる。
これは、先割れスプーンが汁物を食べるのには向かないという問題もあってのことである。こと当時の先割れスプーン先端部が「料理を絡めたり突き刺して食べる」という方法に向かない形状であることも問題視された。
先割れスプーンが多く使われていた時代には、「汁物の具材を先割れスプーンに詰め汁をすくう」という利用法が広まっていた。
○名前の由来であり最大の特徴として、先端が三つ又に割れており、スプーンでありながらフォークとしても使用できるいわゆる"spork "と、先端部に溝と穴とが穿たれ、特に果物の種を取り出しやすいことから、メロンやスイカを食べる際に使われる「先割れスプーン」が存在する。
sporkは、麻痺などにより箸が使えない人には、指先の力が無くても料理をすくったり引っ掛けたり突き刺して口に運べる便利な食器であることから、介護用品としても利用されている。また箸文化に不慣れな者がラーメンなど箸を使うことを前提とした麺料理を食べる際にも便利である。少々不器用に扱っても食事しやすいことから、幼児用食器としても利用される。
○日本の先割れスプーンは、比較的後になって登場したものである。 日本国内での初期の学校給食では、「突き刺して食べる」ことと「すくって食べる」という二通りに使えるという利便性を買われ、1950年代頃より先端部が「M」字状になっている「先割れスプーン」が用いられた。1990年代からは実用的なsporkが一般的となった。こちらは幼児や児童向けの食事風景や、コンビニエンスストアの弁当、また介護の場でも利用されている。
○先割れスプーンへの批判としてこのスプーンは、大衆の簡便な食事のために開発されたようなものであり、どっち付かずの食器とみなされる傾向がある。正式にテーブルマナーが問われるような場で使われることはない。
☆139日目(9.11)他の視座をもつ
前回に記した内容については、いま読み始めている『現代思想入門 千葉雅也著』から視座をいただいたことに依ります。著書の冒頭にはこう書かれています。
「大きく言って、現代では「きちんとする」方向へといろんな改革が進んでいます。これは僕の意見ですが、それによって生活がより窮屈になっていると感じます。(P12 )「現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。それが今、社会および自分自身を秩序化し、ノイズを排除して、純粋で正しいものを目指していくという道を歩んできました。そのなかで、二〇世紀の思想の特徴は、排除される余計なものをクリエイティブなものとして肯定したことです。」(P14)・・・この著書は、教育そのものについて言及しているわけではありません。しかし、自分たちがかかわっている教育現場をほかの視座や視点から、視つめてみることは大事かもしれません。読み手の勝手な解釈になりますが、引き続き読んでいこうと思います。
☆138日目(9.10)「はやい おそい」
職員研修で、「早く打つ」タイピングの体験をしました。たぶん、授業で実践してみたら、子どもたちは真剣に取り組むことが予想されますね。しかし、一見「盛り上がる」ようにもみえますが、タイピングの基本は、「速さ」ではなく、おのおのが自分のペースで「自己表現する文宇として」使用することであると考えます。自分が関わっていた、障害をもつ子どもたちは、一人ひとりの懸命な「意思表示・自己表現としてのタイピング」の姿をみていたら、「はやさ」の指導は必要があまりないように思いました。「はやい・おそい」をあおってはないと思いますが、子どもたちの感覚で「速い=よい」との認識が助長されてはいけません。研修では、ひとつの「指標」であることを言われましたが、(重々承知ですが)、子どもたちへの実施には、丁寧な指導・支援が不可欠です。どのような認識を子どもたちに提示するかは重要です。昨日研修に参加された方々は、各校で指導や実施する際には、そのようなことに言及されると思いますが、私も職員での校内研修時には大切にしたいと思いました。
☆137日目(9.9)
教師としての教える権利と教えることの願いと、子どもの成長と発展の願いを。
前述で、「(意味深いのです))」と書いたのは、K先生と話す中で、これまで取り組んだきた「学校づくり」や「保護者とのかかわりのありかた」について、この時代に、もう一度立ち戻る必要があるのではないかと思ったからです。1969年発行『双書 解放教育の実践2』(明治図書)の一部を紹介。どうでしょう?古いですかね?

☆136日目(9.6)僕らが自分らしくいられる学校へ
録りためていたTV番組「僕らが自分らしくいられる理由-54色の色鉛筆- 奈良のインクルーシブ中学校」(初回放送日:2021年7月17日)をじっくりと視聴し、「進路保障」についてあらためて考えました。
そんな折り、K先生(三年主任)と、「保護者と真に連携した(共に在る)教育活動はやっぱり大事だよなあ」と、昔話(教育実践)を交わす機会ががありました(←意味深いのです)。
大正中学校を舞台にした、番組の内容紹介です↓。
『僕の名前は、ゆうじ。今年3月に僕が卒業した中学校には、いろんな子がいた。重い知的障害のある子、パニックになりやすい子、家庭のことで悩む子。僕も読み書きが苦手。でも、自分らしく生きていくことを校長先生や担任の先生たち、そして地域の人たちが応援してくれた。文化祭や体育祭、1日かけて自分たちの気持ちを語りあった「集中ホームルーム」。そして進学受験。僕らが過ごした中学校の半年を見てください。#SDGs』
「僕らが自分らしくいられる理由-54色の色鉛筆- 奈良のインクルーシブ中学校」 - ETV特集 - NHK
☆135日目(9.5)当事者の話を聴いて
前田良さんのお話(備前市人権教職員人権教育研修会)から考えたことを‚やっとまとめることが出来ました。
○あらためて、人権教育は、いくつか挙げられている「人権課題を、知る学習」ではナイと思いました。過酷ではあるが、たくましく生きてこられてひとの生き方に出会い、「自分自身はこれまでどう生きてきたを問い直し、これからどんな生き方ができるのか?」を思考し、また、反差別・人権尊重の社会を創る(差別を許さないための法・政治・制度・学校、学級風土づくりへの行動力を意識した)教育を進めなければならないなあと思いました。
○当事者の話を聴くことは、学校に勤める者としてとても「しんどい」。それは、自分自身の「しごと」を振り返ることになるからです。
・学校現場の人権尊重の風土は貧しくないか?育っていく風土があるか?
・学校に、前田さんをサポートする人があまりにも少なかったのはなぜか?教職員が、子どもにとって「支援者」となっているか?
・当事者を支える「仲間づくり(学級集団づくり)」ができていたのか?
など、自分自身の、また、自校の取組を見直しになりました。
○講演でのお話を聴いて、「よかった。ためになった(知識)」だけでなく、教職員としての「立ち位置」を考えねばならないと思いました。
○日常の学校生活の中で、〈役立つ・生き抜く・闘える〉人権教育の内実をつくっていきたいと思います。前田さんが取り組んだ授業プログラムの作成にはなかなか多くの苦労があったと思います。学校外部からのアプローチには、とても慎重になる学校風土の中で、9年間を見通したプログラム作成はスゴイと思います。
本中学校区でも、子・小・中連携で、「特別支援」や「発達特性」についての学習プログラムをつくりたいなあと話題にしています。ただし、前田さんが講演の中で言われていた「性的マイノリティー(LGBTQ)の知識をわかる」のではなく、「一人ひとりの持ち味や、ニガテなこと、そして自分の悩みや不安」をクラスの仲間同士が知り、理解し合えるような内容&語り合える学級集団づくりを目的にしたプログラムになったらと思っています。

☆134日目(9.4)授業が「盛り上がる」って
2学期の授業の事前打ち合わせ会を関係するメンバーで行いました。その授業では、ロールプレイを多用しますが、演者の一人は学級担任が分担することとなりました。学級担任がすると「授業が盛り上がる」とのこと。私は、少し「?」となり「盛り上がる」とはどういうことなのか?気になりました。何でも話せて、協働活動を進めていくことができるメンバーなので、「子どもにとって、担任の演じる姿や言動を面白さだけで(滑稽さやギャップ)捉えて、学びの本質に迫るアプローチが弱まらないか?」「授業の雰囲気が和らいで、盛り上がった風に感じられるだけなら、担任は演者としてふさわしくないのではないか?」と素直に聞きました。これまでの経験(活動)から、「学びの質が低下することはない。一緒に学び合う主体者として、子どもたちは担任を捉えて、学びは深まると思います。(ファシリテーションの重要性)」とのこと。授業者共々、実践に向けてメンバー同士で共有認識をもつことができました。11月の授業は楽しみです。準備をがんばりましょう。
また、この「盛り上がる」授業の中身(質)を考えたい旨の話を、他学年団の先生にも話題にしましたが、「盛り上がり観や目指したい授業観や」が一緒だなあと感じることができて、でうれしいことでした。
「授業技術を高める」ことを言っているのではありません。子どもありきの授業づくりについて、これからも語り合いましょうねえ。(*^o^*)

☆133日目(9.3)「自分ごとってなんだ?その2」
特別な教科道徳や、総合的な学習や、もちろん人権教育の実践の中で〈「自分ごととして捉える」視点が重要である〉ということを結構聞きますし、論文やレポートにも文言が出てきます。まさか、人権課題として挙げられる17の項目、((1) 女性の人権を守ろう(2) 子どもの人権を守ろう(3) 高齢者の人権を守ろう(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう(5) 同和問題(部落差別)を解消しよう(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう(7) 外国人の人権を尊重しよう(8) HIV感染者等に対する偏見や差別をなくそう(9) ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう(10) 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう(11) 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう(12) インターネットによる人権侵害をなくそう(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう(15) 性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう(16) 人身取引をなくそう(17) 東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう)について、それぞれ「自分ごととして捉えるために」学習を展開しようということはしないと思うけど。
学習の結果、生徒のどんな姿が見られれば「自分ごと」として捉えたことになるのでしょうね。
本校でも、今年度の人権集会のあり方について検討を進めていきますが、「こころがけ」や「優しさ」を越える人権意識の高まりや行動力につながる、学びが深まる集会にしたいと思います。人権課題に出会わせるだけの取組では、「自分ごと」にはなりませんね。

☆131日目(9.2)「自分ごとってなんだ?」
私事ですが、様々なひとたちと、協働でイベントの運営を進めています。先日の打ち合わせ(会議)でのことですが、係分担が「なかなか決まらない」、というよりも、参加者メンバーが、自分からは手を挙げない。自分の意志表示をされない場面があり、とてもびっくり(ちょっとがっかり)してしまいました。学校現場でも、係や分担を「決める」ことはたくさんあり、その都度、苦労しながら子どもたちは決めていき、先へ進むのです。
・・・さてさて、ちなみに、HP『みんなの教育技術』、沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」の中で、沼田さんは以下の内容を書かれています。
・「自分ごと化」させれば意欲を引き出せる「自分からやる子に育てるにはどうしたらよいか。学習に対して子供のやる気を引き出すにはどうしたらよいか。」
これは、先生や保護者の方からよく寄せられる質問だ。確かに先生が宿題を出したり、授業中に時間を設けて無理やり子供たちに学習に取り組ませたりすることで、ある程度学びを習慣化させることはできるかもしれない。でも、意欲的に取り組んでいなければ、自分からやる子には育たないだろう。なぜ意欲的になれないのかと言えば、その勉強をいまやらなければならない理由がよくわからないし、やっていても楽しくないからだ。もし、教科書に書いていることが自分にとって大事だと感じたら、学びの効率はグッと上がるだろう。この学びが自分にとって役立つと分かれば、勉強は楽しくなり、自ら学び続けられようになる。つまり意欲を引き出すためには、その学びを自分ごと化できるかどうかにかかっていると思う。
・なぜ結婚式前のダイエットは成功しやすいのか
ただ、大人でも「自分ごと化」することは意外に難しいよね。
例えば、食事は栄養のバランスが大切ということは知っていても、独身で、太る心配もなく、病気になる心配もない、という時はあまり栄養バランスを考えず、ラーメンやパンばかり食べたり、偏ったメニューになってしまったりすることが多い。でも、自分に子供ができると自然に栄養のバランスを考え料理を作るようになることもあるよね。また病気になると、健康的な生活についてより真剣に考えるようになる。
つまり、「子供を育てる」「病気を治す」という目的があるから、バランスのよい食事や健康について自分ごと化し、自分でよく調べて深く学ぼうとするし、積極的に日々の生活に取り入れようとする。また、ダイエットが成功しないという人の場合、その主な原因は目的が曖昧だからだ。でも、結婚式前のダイエットは成功しやすいと言われるよね。
結婚式前のダイエットが成功する理由は、結婚式で、より美しい姿をみんなにお披露目し、その姿を写真に残すという目的があるから。そのために必死で努力するし、我慢することも厭わない。ボクも最近太ってきたなと気になるけれど瘦せられない。ただし、数か月後にエクササイズ本の表紙に上半身裸姿で掲載されると決まったら、今から死ぬ気でトレーニングしてバキバキの体にするだろう(笑)。
・学びの目的・ゴールを明確にすることが重要
つまり、自分ごと化させるためには、頑張る理由や目的がはっきりしていて、自分はこうなりたいとイメージさせることが重要。さらに、その目的に対する努力が、自分からやりたいと感じてやるのか、誰かにやらされているのかで、結果は全く違ってくる。だから、子供たちが「面白そうだな」とか「もっと頑張りたいな」と思わせるようなゴールを与えることが大切。子供たちに見せるゴールは、本来の目的とは違う「アナザーゴール」でもOK。本来の目的とは違うように見えても、まずは子供たちが面白そうだなと思うような「別のミッション」を与えてみる。それを自分ごと化して一生懸命取り組んでいるうちに、本来伸ばしたかった能力が身についているということもある。
・やる気を継続させるためには、ゲーム化するのがポイント
ゴールはあまりにも遠いところに設定してしまうと、最初からあきらめてしまったり、途中で疲れて意欲を失ってしまったりすることもあるから、スモールステップで段階的に設定しよう。すぐに達成しそうなアナザーゴールを追いかけていたら、気がついたらゴールをしていた、というのが理想だ。そして、子供たちのやる気を継続的に引き出すためには、「課題」「報酬」「制限」の3つを意識し、ゲーム化させることがポイント。ミッション(課題)を与え、それをクリアすると、どんな嬉しいことや楽しいことが待っているのかご褒美(報酬)を提示する。さらに、時間制限や守るべき条件(制限)を与えると、子供たちのやる気に火が付き夢中で取り組むようになる。「子供たちがワクワクすることは何だろう」と考え、子供たちが学びを自分ごと化し目標達成に向けて楽しみながら取り組めるシステムを考えてみよう。
・・・「自分ごと」って何なんでしょうね?生徒のどんな姿がみられたらよいのでしょうね?
☆130日目(8.30)木村氏の講演から
おおぞら高校のオンライン講演会を視聴した。木村泰子氏が「4つの力を軸に子どもたちと向き合ってきた」ことを聴くことができました。4つの力とは、
1「人を大切にする力」
・多様性にもつながることで、相手も自分も大切にすることを指す。この力が伸びるかどうか、周囲の大人が与える影響は大きい。「もし子どもに『人に迷惑をかけるな』と言って育てれば、迷惑をかける人を許せない人になってしまう。『役に立つ人になれ』と言い続ければ、役に立たない自分では駄目なのだと考えて、自尊心が保てなくなってしまう。大人でもこうした考えの人が多く、それは現在の生きづらい社会の一因にもなっているという。
2「自分の考えを持つ力」
3「自分を表現する力」は、新学習指導要領にも盛り込まれた「主体的・対話的で深い学び」にも通じるところがあるだろう。「旧来の教育では、先生の言うことを素直に聞く子ども、みんなと同じことができる子どもがいい子とされてきた。でもそうした時代はもう終わり、今はみんな違うことに価値がある時代になろうとしている。その子がその子らしく育つこと、自分の言葉で語りたいことを語れることが何より大切。
4「チャレンジする力」は、「失敗する力」と言い換えることができる。子どもは安心できる環境でこそ挑戦することができる。間違えたり失敗したりしたことを自覚し、やり直すことが成長につながる。木村氏は、大人は子どもが安心できる環境をつくるだけでいいという。
「大人が正解を教える必要はなく、失敗したときには『大丈夫?』と聞いて寄り添うだけでいい。『大丈夫なわけあれへん!』と助けを求めるのか、『うん、大丈夫やで』と自分で解決するのか。それも子ども自身が決めること」
こうした4つの力を伸ばすことで身に付くものを、木村氏は「見えない学力」だと説明する。これこそが、予想外の事態を自らクリアする力だ。大空小では4つの力を重視して子どもたちの「見えない学力」を高めたところ、「見える学力」である教科にも結果が表れたそうだ。その成果は大きく、全国学力状況調査で1位の県を上回った年もあるという。だがそれは「最上位の目的ではない」と木村氏は言う。
☆129日目(8.30)標語づくり その3
考えるためには、考える資料が要ります
消とても前の実践ですが、『防災について考える町づくり』に向けた消防署がさんが募集した『防災標語』です。消防署さんに用意していただいた資料担当で編集して配布し、「考えを深めて」応募しました。その中からいくつかを紹介します。
後でいい そう思うときに 起こっている
いつなのか 読めない未来に 防災を
火をつけて そのままどこかに 行かないで
家を出る時 火元確認 絶対に
生きる場所 避難場所を 再確認
家族で もしものために 備えよう
災害時 躊躇の時間は ありません
気をつけろ タコ足配線 危ないよ
日頃から 防火・防災 心がけ
探してみて 自分の家の 危険な場所
命以上 大事なものは ないんじゃない?
☆127日目(8.29)標語づくり その2
人権標語づくりについて。「仲間づくり(発達特性)」、「ホームレス問題」、「ハンセン病問題」学習を3年間重ねてきた子どもたち(3年時)がつくった標語を紹介します。
あの子、この子、全ての生徒の顔と名前を思い浮かぶことのできる、一人ひとりの学びをもとにしたオリジナルの標語だと思います。
個性を認め合うことで 絆がうまれる
正しい知識を 学び合おう
人のみためじゃなく 中身をみよう
人権というものを知り 自分たちで 差別をなくしていこう
どうするべきか ではなく どうあるべきか
人権は みんなを守る 盾となる
大切な事は 人と違う意見でも逃げず 正面から向き合うこと
人と人と 互いを認め 生きていく
近い距離 心の目では 遠い距離
「わかった」と 一言だけで 終わるのではなく 行動であらわそう
認め合い あなたの個性を 伸ばそうよ
仲間たちよ 正しい知識を学び 絆を深め
正しい行動は みんなの人権を 学び合う
一人ひとり 違うところがあるのは あたり前
あの人嫌い その差別 あなたは正しいと思いますか
僕たちは つながり生きる 命たち
なかまとは 学び合って 認め合う
このクラスは 絆を深めるためのクラス
花が咲き 色とりどりに 風にゆれる どれも美しく どれも違う
人を守り 人に守られる それが正しい つながりかた
勇気をもった行動が 反差別につながる
きもちわるい そんな理由じゃ バカバカしい
なかまとの絆 学び合う学校へ
あなたは知ってる? 正しい知識
僕たちは なかまと共に 助け合う
お互いの 人生変える そのいじめ
人とはみな 人とつながり 生きている
☆126日目(8.28)始業式の日、時間割
始業式(8月の登校日)の日には何(時間割)をしたらいいのでしょうか?
もちろん、しなければならないことはたくさんあります。宿題・提出物の提出、点検、課題テスト、2学期からの行事や授業についての伝達事項・注意事項・・・などなど。でも、やっぱり、40日間の一人ひとりの夏休みのくらしや体験を語り合う、共有する活動時間を捻出したいと思います。班別健康観察一覧表への記入するグループ活動や、夏休み報告書の作成(→掲示)や、1分間報告スピーチ(→1週間継続的に、全員が話す)など、計画的に「子どもたちが関わり合う」学習の時間をつくりたいですね。
また、始業式で教職員がスピーチする内容も、生徒会長のスピーチと合わせて、話者(担当者)どうしで、「意図的」「重厚」な構成化を進めたいものです。
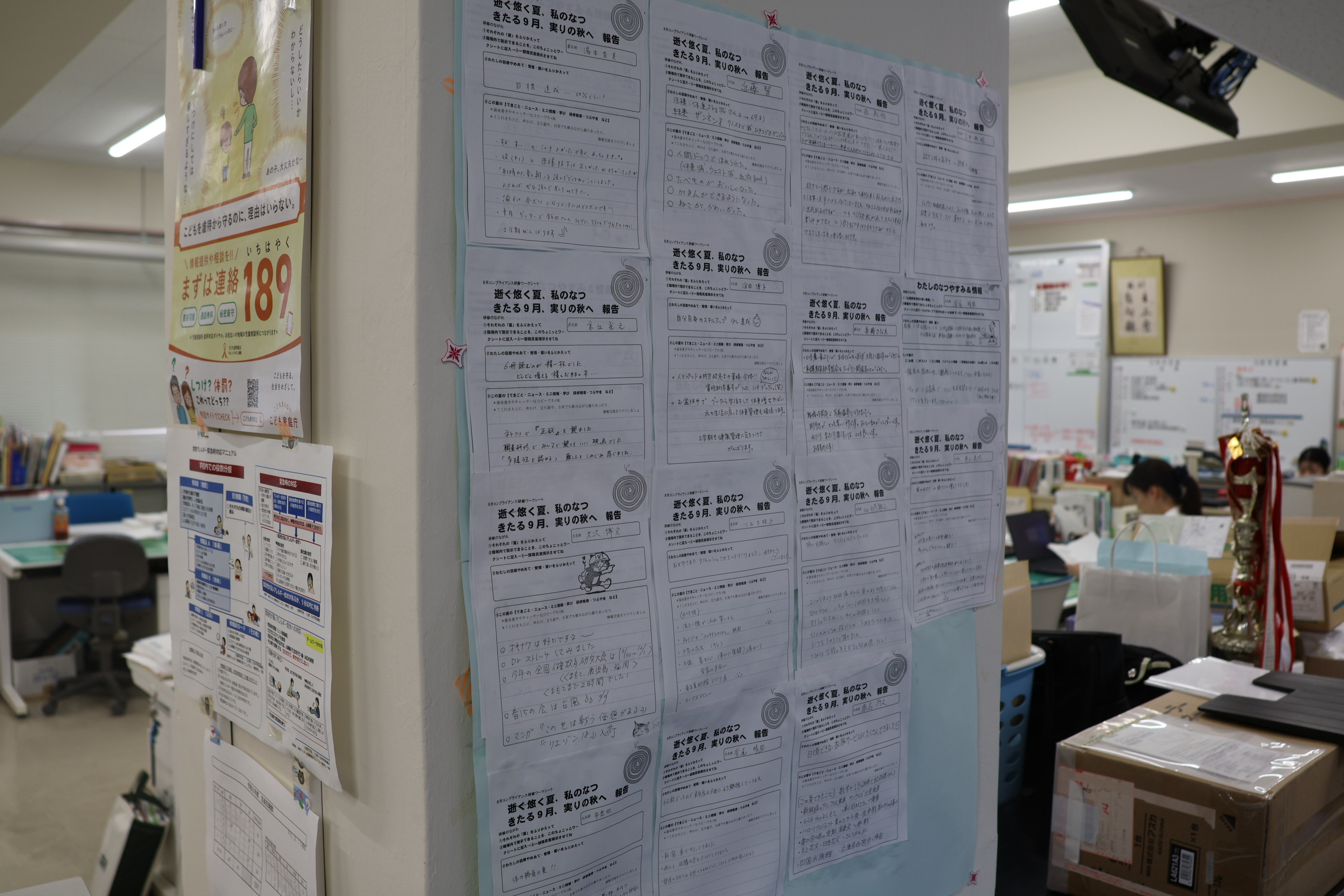
先生たちも、この夏を振り返り、取り組んだ「夏の報告」掲示しました。一人ひとりの夏の経験や体験のお話はステキです。
☆125日目(8.27)義務教育後の進路について、「春15の会」
取材記事が山陽新聞に記載されました。本当の課題解決の取組ではありませんが、すべての子どもたちの進路保障を進めるためのちっちゃい事ですが、多くの方々との協働による粘り強い活動です。

☆124日目(8.26)今日は人権宣言記念日です。
前日の話を受けて、標語づくりの資料として、『世界人権宣言』や『子どもの権利条約』に出会う機会にしてはどうでしょう?と意見をいただきました。
表面的な、誰に言っているかわかりにくい、呼びかけ文ではなく、自分自身が「大切にしたい事」「気になること」条項を選び、呼びかける文にすることで、自分の立ち位置が明確になると思います。さらに、「なぜそれを選んだか?」お互いに学級で意見交流することができたらステキですね。
【世界人権宣言】
第1条 みんな仲間だ
わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。
第2条 差別はいやだ
わたしたちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによって差別されるべきではありません。また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。
第3条 安心して暮らす
ちいさな子どもから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、わたしたちはみな自由に、安心して生きていける権利をもっています。
第4条 奴隷はいやだ
人はみな、奴隷のように働かされるべきではありません。人を物のように売り買いしてはいけません。
第5条 拷問はやめろ
人はみな、ひどい仕打ちによって、はずかしめられるべきではありません。
第6条 みんな人権をもっている
わたしたちはみな、だれでも、どこでも、法律に守られて、人として生きることができます。
第7条 法律は平等だ
法律はすべての人に平等でなければなりません。法律は差別をみとめてはなりません。
第8条 泣き寝入りはしない
わたしたちはみな、法律で守られている基本的な権利を、国によって奪われたら、裁判を起こし、その権利をとりもどすことができます。
第9条 簡単に捕まえないで
人はみな、法律によらないで、また好きかってに作られた法律によって、捕まったり、閉じこめたり、その国からむりやり追い出されたりするべきではありません。
第10条 裁判は公正に
わたしたちには、独立した、かたよらない裁判所で、大勢のまえで、うそのない裁判を受ける権利があります。
第11条 捕まっても罪があるとはかぎらない
うそのない裁判で決められるまでは、だれも罪があるとはみなされません。また人は、罪をおかした時の法律によってのみ、罰をうけます。あとから作られた法律で罰を受けることはありません。
第12条 ないしょの話
自分の暮らしや家族、手紙や秘密をかってにあばかれ、名誉や評判を傷つけられることはあってはなりません。そういう時は、法律によって守られます。
第13条 どこにでも住める
わたしたちはみな、いまいる国のどこへでも行けるし、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどることも自由にできます。
第14条 逃げるのも権利
だれでも、ひどい目にあったら、よその国に救いを求めて逃げていけます。しかし、その人が、だれが見ても罪をおかしている場合は、べつです。
第15条 どこの国がいい?
人には、ある国の国民になる権利があり、またよその国の国民になる権利もあります。その権利を好きかってにとりあげられることはありません。
第16条 ふたりで決める
おとなになったら、だれとでも好きな人と結婚し、家庭がもてます。結婚も、家庭生活も、離婚もだれにも口出しされずに、当人同士が決めることです。家族は社会と国によって、守られます。
第17条 財産をもつ
人はみな、ひとりで、またはほかの人といっしょに財産をもつことができます。自分の財産を好きかってに奪われることはありません。
第18条 考えるのは自由
人には、自分で自由に考える権利があります。この権利には、考えを変える自由や、ひとりで、またほかの人といっしょに考えをひろめる自由もふくまれます。
第19条 言いたい、知りたい、伝えたい
わたしたちには、自由に意見を言う権利があります。だれもその邪魔をすることはできません。人はみな、国をこえて、本、新聞、ラジオ、テレビなどを通じて、情報や意見を交換することができます。
第20条 集まる自由、集まらない自由
人には、平和のうちに集会を開いたり、仲間を集めて団体を作ったりする自由があります。しかし、いやがっている人を、むりやりそこに入れることはだれにもできません。
第21条 選ぶのはわたし
わたしたちはみな、直接にまたは、代表を選んで自分の国の政治に参加できます。また、だれでもその国の公務員になる権利があります。みんなの考えがはっきり反映されるように、選挙は定期的に、ただしく平等に行なわれなければなりません。その投票の秘密は守られます。
第22条 人間らしく生きる
人には、困った時に国から助けを受ける権利があります。また、人にはその国の力に応じて、豊かに生きていく権利があります。
第23条 安心して働けるように
人には、仕事を自由に選んで働く権利があり、同じ働きに対しては、同じお金をもらう権利があります。そのお金はちゃんと生活できるものでなければなりません。人はみな、仕事を失わないよう守られ、だれにも仲間と集まって組合をつくる権利があります。
第24条 大事な休み
人には、休む権利があります。そのためには、働く時間をきちんと決め、お金をもらえるまとまった休みがなければなりません。
第25条 幸せな生活
だれにでも、家族といっしょに健康で幸せな生活を送る権利があります。病気になったり、年をとったり、働き手が死んだりして、生活できなくなった時には、国に助けをもとめることができます。母と子はとくに大切にされなければいけません。
第26条 勉強したい?
だれにでも、教育を受ける権利があります。小、中学校はただで、だれもが行けます。大きくなったら、高校や専門学校、大学で好きなことを勉強できます。 教育は人がその能力をのばすこと、そして人としての権利と自由を大切にすることを目的とします。人はまた教育を通じて、世界中の人とともに平和に生きることを学ばなければなりません。
第27条 楽しい暮らし
だれにでも、絵や文学や音楽を楽しみ、科学の進歩とその恵みをわかちあう権利があります。また人には、自分の作ったものが生み出す利益を受ける権利があります。
第28条 この宣言がめざす社会
この宣言が、口先だけで終わらないような世界を作ろうとする権利もまた、わたしたちのものです。
第29条 権利と身勝手は違う
わたしたちはみな、すべての人の自由と権利を守り、住み良い世の中を作る為の義務を負っています。自分の自由と権利は、ほかの人々の自由と権利を守る時にのみ、制限されます。
第30条 権利を奪う「権利」はない
この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。
出典:わかりやすい谷川俊太郎訳 世界人権宣言
アムネスティ世界人権宣言 : アムネスティ・インターナショナル日本 AMNESTY
国連広報センターでも英語からの日本語訳を以下のページに紹介しています。
世界人権宣言テキスト | 国連広報センター (unic.or.jp)
【児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)】要約
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第2条 差別の禁止
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障害があるかないか、お金持ちであるかないか、などによって差別されません。
第3条 子どもにとってもっともよいこと
子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。
第4条 国の義務
国は、この条約に書かれた権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
第5条 親の指導を尊重
親(保護者)は、子どもの心やからだの発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。
国は、親の指導する権利を大切にしなければなりません。
第6条 生きる権利・育つ権利
すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
第7条 名前・国籍をもつ権利
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。
子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。
第8条 名前・国籍・家族関係を守る
国は、子どもの名前や国籍、家族の関係がむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。
もし、これがうばわれたときには、国はすぐにそれを元どおりにしなければなりません。
第9条 親と引き離されない権利
子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。
第10条 他の国にいる親と会える権利
国は、はなればなれになっている家族がお互いが会いたい、もう一度いっしょにくらしたい、と思うときには、できるだけ早く国を出たり入ったりすることができるように扱わなければなりません。親がちがう国に住んでいても、子どもはいつでも親と連絡をとることができます。
第11条 よその国に連れさられない権利
国は、子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにしなければなりません。
第12条 意見を表す権利
子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
第13条 表現の自由
子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
第14条 思想・良心・宗教の自由
子どもは、思想・良心および宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務をもっています。
第15条 結社・集会の自由
子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
第16条 プライバシー・名誉は守られる
子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。
第17条 適切な情報の入手
子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れることができます。国は、マスメディア(本・新聞・テレビなど)が、子どものためになる情報を多く提供するようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。
第18条 子どもの養育はまず親に責任
子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。
第19条 虐待・放任からの保護
親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。
第20条 家庭を奪われた子どもの保護
子どもは、家族といっしょにくらせなくなったときや、家族からはなれた方がその子どもにとってよいときには、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。
第21条 養子縁組
子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいことを考え、その子どもや新しい父母のことをしっかり調べたうえで、国や公の機関だけがそれを認めることができます。
第22条 難民の子ども
ちがう宗教を信じているため、自分の国の政府と違う考え方をしているため、また、戦争や災害がおこったために、よその国にのがれた子ども(難民の子ども)は、その国で守られ、援助を受けることができます。
第23条 障害のある子ども
心やからだに障害があっても、その子どもの個性やほこりが傷つけられてはなりません。国は障害のある子どもも充実してくらせるように、教育やトレーニング、保健サービスなどが受けられるようにしなければなりません。
第24条 健康・医療への権利
国は、子どもがいつも健康でいられるように、できるかぎりのことをしなければなりません。子どもは、病気になったときや、けがをしたときには、治療を受けることができます。
第25条 病院などの施設に入っている子ども
子どもは、心やからだの健康をとりもどすために病院などに入っているときに、その治療やそこでの扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらうことができます。
第26条 社会会保障を受ける権利
子どもやその家族が生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国がお金をはらうなどして、くらしを手助けしなければなりません。
第27条 生活水準の確保
子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。親(保護者)はそのための第一の責任者ですが、親の力だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します。
第28条 教育を受ける権利
子どもには教育を受ける権利があります。国はすべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、人はだれでも人間として大切にされるという考え方からはずれるものであってはなりません。
第29条 教育の目的
教育は、子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなとなかよくすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。
第30条 少数民族・先住民の子ども
少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもが、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利を、大切にしなければなりません。
第31条 休み、遊ぶ権利
子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤などからの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第35条 ゆうかい・売買からの保護
国は、子どもがゆうかいされたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
第37条 ごうもん・死刑の禁止
どんな子どもに対しても、ごうもんやむごい扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。もし、罪を犯してたいほされても、人間らしく年れいにあった扱いを受ける権利があります。
第38条 戦争からの保護
国は、15歳にならない子どもを兵士として戦場に連れていってはなりません。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてしなければなりません。
第39条 犠牲になった子どもを守る
子どもがほうっておかれたり、むごいしうちを受けたり、戦争にまきこまれたりしたら、国はそういう子どもの心やからだの傷をなおし、社会にもどれるようにしなければなりません。
第40条 子どもに関する司法
国は、罪を犯したとされた子どもが、人間の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになることを考えて、扱われなければなりません。
出典:財団法人日本ユニセフ協会ホームページ

☆123日目(8.26)「○○啓発標語、○○スローガン」募集にどう応えるのか?
法務局の「人権啓発標語コンテスト」の締切が近くなりました。子どもたちはどうやって標語を〈創って〉いますか?
「なかなか取り組む時間が取れなくて、応募用紙を配って、教師が少しだけ〈人権の話〉をして、〈書かせ〉、〈回収〉するだけになって、「せっかく人権について、クラスの仲間と人権を考える貴重な機会なのに、活かせることが出来ていない」という話もよく聴きます。
そのため、ここ数年間、ちょっと工夫して、子どもたちの豊かな発想で標語が創れるようにしています。それは、前年度の秋や人権週間の取組時に、まとめや、振り返りをするワークシートに、学んだ事を、短いコトバ(標語やスローガン)でまとめる記入枠を用意するのです。*これは、クラス掲示にも活用できます。この記入枠に書かれた、《活きた学びのコトバ》を次年度まで大切に保管しておき、啓発標語(=学習成果)として募集するのです。「ホームレス問題学習」に取り組んだ生徒の「標語・スローガン」例です。
○共に生きよう!
○認め合い 学び合える なかまをつくる
○一人ひとりの優しい行動が 絆につながる
○みんな 共に生きる仲間 認め合おう
○未来には ホームレスの人をなくそう
○反差別 正しい知識で 未来へ
○認め合う 学び合う 共に生きる社会を 正しい知識でつくろう
これまでの入賞作品を参考に10分程度で〈書かせ〉る取組は、生徒の「思考すること」「思いを馳せること」を軽んじていくように思えるのです。取り組むのなら、子どもたちがしっかり考えられる資料の〈提示〉をがんばって準備しましょうね!本校でも今年は、資料の準備を重視しています。『教室はまちがうところだ 蒔田 晋時』、詩『へいわってすてきだね 安里 有生くん(久部良小学校1年)』はどうでしょう?。

☆122日目(8.24)津山洋学資料館フィールドワーク
この夏も、津山洋学資料館(刑場跡・千人塚)や、長島愛生園、渋染一揆関係地に行ってきました。
フィールドワークとは、社会学や人類学から始まったリサーチの手法です。机上の書物を離れて、フィールド(学習対象の現地)を訪れ、フィールドの事情を直接視察したり、関係する方々や専門家から話を聴いたりしていく中で、問題点を明らかにして、学習を深めていきます。本や講義だけでは学べない知識や情報を直接現地で学ぶ、これがフィールドワークです。フィールドで、これまで当たり前に思っていた価値観や常識が自明のものではないことに行く度にいつも気付かされます。それは自分自身の生き方や、自分の生きている社会を見つめなおすことにもつながっていきます。こうしたフィールドワークは「社会づくり」につながります。現地の事情を調べ、人々と話しあっているうちに、現地の人たちにはかえって見えにくい問題点や課題に気付き、一緒になって解決策や新しい活動を考えられることも多々あります。フィールドワークはたんに学問的成果をあげるだけでなく、社会につながる取組であり、社会づくりやシチズンシップの醸成に寄与します。
2学期、3年生も長島愛生園でのフィールドワークを計画しています。



☆121日目(8.17)第75回全国人権・同和教育研究大会
第1回実践報告協力者会議に教頭先生が参加されました。今年度は、熊本・鹿児島・福岡会場に大会が開催されるとのことです。
「岡山からなんと熊本まで新幹線で約2時間ちょい、すぐだから、行こう!」と言われてましたが・・・。大会の概要を紹介します。
この大会は、第50回九州地区人権・同和教育夏期講座、第49回鹿児島県人権・同和教育研究大会、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす第52回熊本県人権教育研究大会を兼ねています。
《「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」このテーマのもと、全国各地で取り組まれている人権・同和教育の実践を交流し、学び合う。
全国人権教育研究協議会は、1953年、前身である全国同和教育研究協議会(全同教)結成以来、毎年全国人権 ・同和教育研究大会(研究大会)を開催してきました。一貫して、「教育の中にある差別をなくすため、地域・親や子どもたちを取り巻く現実から学ぶこと」を大切にしてきました。
熊本県人権教育研究協議会は、「たじろがず部落の子どもを中軸にすえて そこから新たな方向を見出してきた」先達の思いを受け継ぎ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、誰もが幸福に生きることのできる社会をつくり、「水平の佳き日」を実現するために取り組んできました。
私たちはもっと学びたい。同和対策事業特別措置法に始まる諸施策が2002年を境に一般施策に移行し、集会所の灯が消されていく中でもなお解放の火を掲げて学ぶなかまたちのことを…。
私たちはもっと学びたい。差別をなくすために、今日の社会の中で被差別の位置に立たされている子どもや親とともに歩き続けている人たちの姿に…。
学ぶことで私たちは、「たじろがず部落の子どもを中軸にすえて、そこから新たな方向を見出してきた」熊本の先達の思いを今一度自分のものにしたい。そして、これからの熊本や九州を担う人たちに、全国のなかまたちの強さ、厳しさ、優しさに出会って欲しい…。
このような現地の願いのもと、2011年鹿児島大会以来、13年ぶりに九州の地で研究大会を開催します。世界では、各地で戦争・紛争や武力衝突が起こり、暴力と差別・迫害が絶えません。また、人種・民族・宗教・政治体制等のちがいを理由に、分断と対立がすすみ、人権を無視する事態も発生しています。国内でも、部落問題をはじめさまざまな人権問題が解決されず、差別を温存する考え方も、未だ根強く存在しています。貧困等により人びとが生きづらくさせられている社会状況とも重なり、個人の尊厳と人権を否定する不寛容な風潮が広がり、さまざまな人権侵害が起こっています。また、情報技術の飛躍的な発展と並行し、ネット上には部落差別を煽る情報や在日韓国・朝鮮人へのヘイトスピーチをはじめ、社会的マイノリティや社会的弱者への攻撃があふれています。私たちは、このような状況に『たじろぐ』ことなく、人が人を思う「人の世の熱」を信じたいと思います。
そして、一人ひとりが持つ人を幸せにする力「にんげんの光」を結集し、「『事実と実践・創造』~であう つながる『ひと なかま まち』」の地元大会テーマのもと、すべての人が安心して生活できる「水平の佳き日」を、人権教育の事実と実践からともに創り、子どもたちに継承していきましょう。
ぜひとも、熊本、福岡、鹿児島の地にご参集いただき、研究大会を成功に導いてくださいますようお願いします。》(全人教HPより)
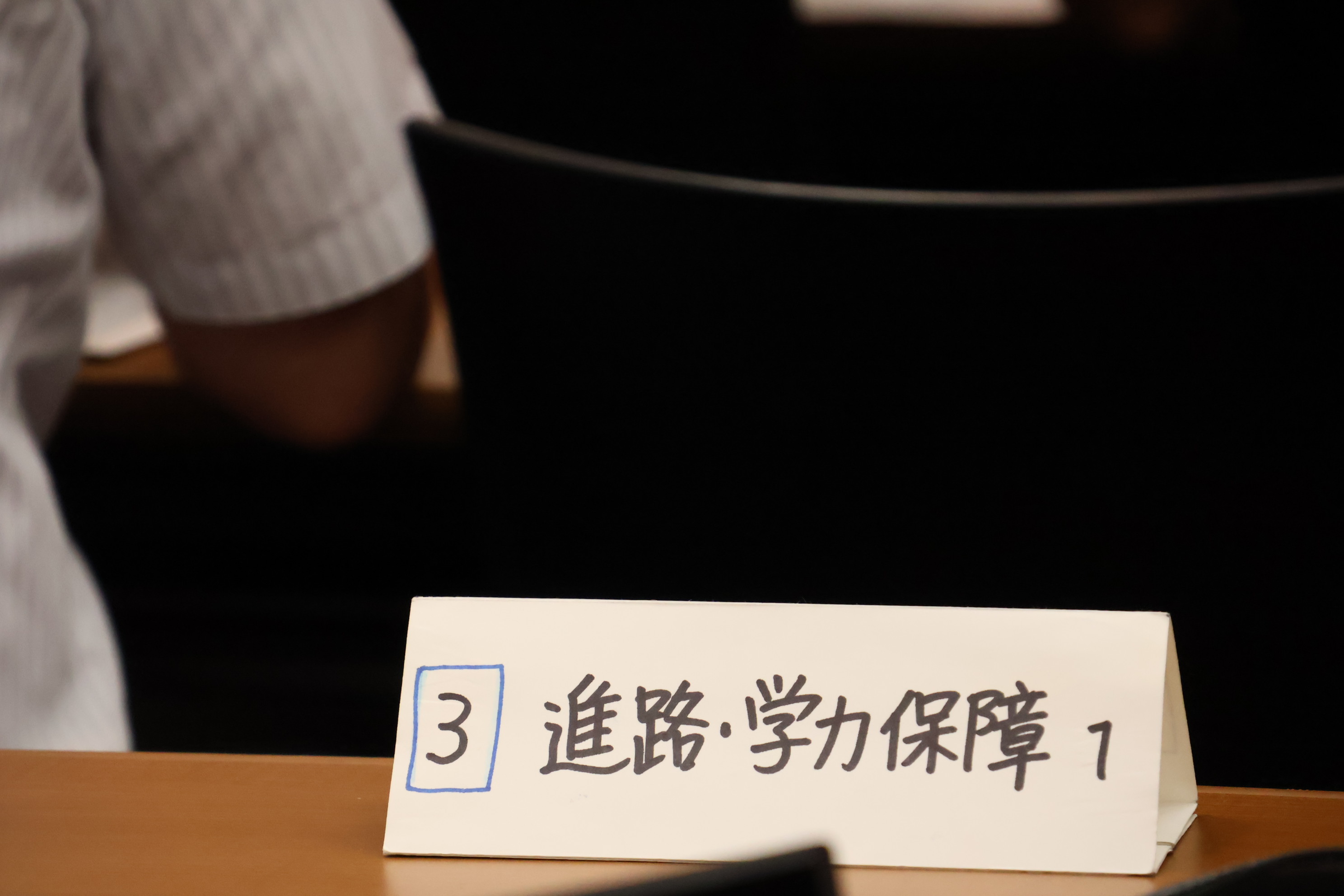
☆120日目(8.13)まちづくりにつながる教育内容の創造を。
8月13日、生徒と共に、ひなせみなとまつりへ参画(日生中ボランティア推進プロジェクト)。「中学生が出店しとんか!」「ひな中がんばっとるなあ」「参加してくれてうれしいなあ」などなど、準備期間から当日まで、たくさんの激励とエールのコトバや支援をいただきました。
住んでいる一人ひとりが自らの存在と人権が守られ、「生きがい」や「学びがい」や「働きがい」を実感できる豊かな生活を創り出すことを「人権のまちづくり」として、全同教(全国人権・同和教育研究協議会)は提案してきました。この「人権のまちづくり」のモデルは、これまでの同和教育、解放運動、そして人権教育の中で育まれてきました。住民の主体的な参加によって住民自治を育みながら地域共同体としての「まちづくり」が行われてきました。この運動の教訓が生かされて、各地で様々で豊かな取り組みがすすめられ、ムラから周辺地域へ「人権のまちづくり」がひろめられ、様々な立場の人との出会いや連帯が生まれ発展してきた歴史があります。そんな実践から導かれたキーワードとして「協働」と「参画」があります。一つの目標に向かってともに情報を共有し、ともに協力して活動に取り組む「協働」と、様々な活動に企画段階から参加していく「参画」です。2つのキーワードを核にして、職域や立場を乗り越えた活動が進められ、地域教育コミュニティが形づくられていくということです。
子どもたちをとりまく状況は、残念ながら、幼い子どもたちの命が奪われる痛ましい事件など、深刻さを増しています。もしかしたら、子どもたちを支え育てるまちづくりがあらゆるところで具体的に機能していれば避けられた事件もあったのではないかとも思われます。子どもの安全面や教育活動への支援、あるいは児童虐待防止に向けた支援など、子どもの命と人権を守り、育ちを支えるまちづくりの必要性は、ますます高まっています。(だからこそ、学校(こ・園・小・中)と家庭・地域、そして子どものために活動する様々な人々との協働といったボトムアップの手法とともに、行政的な支援も不可欠です。)「子ども(学校)を支え、育てるまちづくり」という目標にむけて様々な人々、関係機関等の協働と参画をどう構築していくのか、実践を重ねながら、確かなあり方を明らかにしていきたいと思います。

☆119日目(8.6)備前市教職員人権教育研修会会
『前田 良さん 講演会『パパは女子高生だった』に参加しました。(―女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ(←これは書籍の題))
学校現場では性の多様性や性的マイノリティについて学んだ経験がない教職員はまだまだ多いと言われています。当事者の教職員も存在しますが沈黙を強いられているのが現状です。性の多様性や性的マイノリティに関して学校で学ぶ機会があったという生徒も全体の9%に過ぎず、ほとんど学ばないまま社会に出て行くというのが実状です。学校では性的マイノリティは「いない」「見えない」存在とされる一方で、性的マイノリティをからかい傷つけ否定する言葉を聞いたことがある児童生徒は 74%に上ります(「NPO法人 ReBit の 2015 年調査」)。
性の多様性について学習に取り組み始めたものの、男女別の制服(標準服)やトイレ・更衣室、健康診断や修学旅行の部屋など性的マイノリティの子どもたちが直面している問題には無自覚なままという現実もあります。そうした実態の中で性的マイノリティの子どもたちは、部落や在日韓国・朝鮮人の子どもがそうしてきたように、息を潜めるように自分の存在を隠し、性的マイノリティとして生きることを諦めざるを得ないのが現実です。人生設計や進路・就職についても、書類の性別欄でつまずいたり不安を持たざるを得ない実態もあります。思春期には性的指向や性自認について揺らぎがあることも知らなければなりません。教職員が性的マイノリティについての理解を深めなければ子どもたちの悩みを受け止めることはできません。性的マイノリティの人たちが安心して自分の性を明らかにし、ありのままの自分で過ごせ学べる学校づくり、職場づくり、地域づくりに取り組んで行かなければなりません。まずは最低限の知識の共有から始めて、性的マイノリティであってもそうでなくても過ごしやすい環境をつくるために、各地の学校、職場、地域で研修・研究と実践に積極的に取り組むことが大切です。「いじめ防止対策推進法」(2013 年施行)に基づく国の基本方針に障害者や性的マイノリティが取り上げられ、教職員の理解促進と差別やいじめの防止に取り組むことが明記されています。性の多様性や性的マイノリティについて子どもたちと一緒に学習に取り組んでいきたいと思います。
☆118日目(8.3)知った気になったらいけませんね
もっともっともっと学ばなければいけません(自省)。この6月に縁あってから、徳田靖之のお話しを聴き、著書『感染症と差別』、ハンセン病市民学会年報(2020~2022)を読みました。「知った気になってはいけない」と思いながら、私自身が知った気になっていました(自省)。
かもがわ出版さんのHPの一部を紹介し、徳田靖之著『感染症と差別』の一読をお薦めします。
出版まで〜編集者が考えてきたこと
弁護士・徳田靖之さんによる著作『感染症と差別』。企画・編集された八木絹さん(フリーランス編集者、戸倉書院代表)に、刊行にいたるまでのエピソードを書いていただきました。全4回の第1回目です。
・第1回 コロナ禍で差別発言が溢れ出た
「感染者は、社会にとって迷惑な存在ではなく、社会を挙げて守るべき存在である」「ハンセン病やエイズにおいて繰り返された痛恨の過ちが、またもや繰り返されていることに我慢がならなかった」(「はじめに」4、5ページ、カッコ内のページはすべて本書)
・本書のコンセプトはこの言葉にすべてあらわされています。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団共同代表、薬害エイズ九州訴訟共同代表などとして、日本の大きな感染症の裁判を長年当事者とともにたたかい、人の心に潜む差別の問題を考え抜いてきた徳田靖之弁護士だからこそ書くことができた本だと思います。詳しい内容は本書をお読みいただくとして、ここでは本書の出版秘話といいますか、日ごろ読者と接する機会のない編集者が何を考え、どんな仕事をしているのか、お話ししたいと思います。
・感染者は不注意で不心得な者…か?
この本の企画を始めたのは2020年9月、新型コロナウイルスによる感染症への誹謗中傷が起こっていた最中のことです。前年暮れに中国武漢で始まった新型コロナウイルス感染症は、
2020年に入ると瞬く間に世界に広がりました。
日本では、ダイヤモンド・プリンセス号内での感染拡大を経て、一般市民にも広がっていきましたが、その過程で特筆すべきは、行政とメディアが「夜の街」などという言葉を使って、繁華街で酒を飲みながら騒ぐ人が感染を広げているという固定したイメージをつくり、感染者は不注意で不心得な者であるという認識を一般市民に広げたことです。県をまたぐ移動や飲食店の利用が規制されていく中で、他人の行動を監視する“自粛警察”なる言葉も発生。ネット空間などに感染者への誹謗中傷が蔓延していきました。
クラスターが発生した学校などに非難の電話が殺到し、感染して回復した人でも、学校や職場での非難の目に耐えかねて復帰できず、自死に至る例まで出ました。医療関係者の子どもを登園させない保育園が出たり、誹謗の言葉が投げかけられたりしました。
誰もがコロナウイルスに感染する可能性があるのに感染者を攻撃するとは、感染者のために献身的に働く医療従事者を追い詰めるとは、この国はいったいどうなってしまったのだろうと絶望的な気持ちになりました。同時に、これまで人権や平和、ジェンダーなど社会問題に関する書籍を編集してきた者として、この事態に一石を投じる本がつくれないかと考えるようになりました。その時心に浮かんだのは、数年前から関心を持ってきたハンセン病差別の問題です。
・ハンセン病差別の歴史に酷似している
ハンセン病の元患者の方たちが住む多磨全生園(東京都東村山市)は私の住まいから車で40分ほどの所にあります。2018年のある朝、NHKニュースで、元患者の方が偏見と差別に苦しんできた人生を語る「語り部の会」を続けていること、元患者の高齢化と社会の関心が薄れてきたことから、存続が難しいと報じているのを聞き、この会に参加することにしたのが、ハンセン病差別問題に関心を持ったきっかけです。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟(1998年提起、2001年判決=いわゆる熊本判決)での原告勝訴という快挙を知っていながら無関心だった私の、あまりにも遅すぎる学習の開始でした。
国立ハンセン病資料館(多磨全生園敷地内)での「語り部の会」で何人もの元患者の方の人生の物語を聞き、映画を見、関連の書籍を読んでいきました。群馬県草津の栗生楽泉園内にある重監房(*)跡と重監房資料館にも足を運びました。そうしたことを通じて、明治以降日本国家が欧米列強並みの「一等国」、つまり戦争に勝つ国になっていくために、「国辱」とさえいわれたハンセン病(当時は癩病と呼んでいました)の「撲滅」に血眼になった歴史があり、それが市民の中に強烈な差別意識を醸成したことを知りました。
*「特別病室」の名で1938年に設置され47年まで運用された懲罰施設。療養所長に与えられた懲戒拘束権をもって入所者を監禁した。9年間で93人が収監され、冬季には零下17度となる過酷な環境下で22人が死亡した(45、57ページなど)。
コロナ禍における感染者への偏見差別は、この歴史に酷似している、それを繰り返していると思いました。後で知りましたが、ハンセン病元患者のみなさんはこの事態に直面し、差別の歴史を繰り返すなと声を上げておられたそうです。
・語れるのはこの人しかいない
そんなとき、NHK(Eテレ)の「こころの時代」という主に宗教者が登場する番組に徳田靖之弁護士が出演した回(「光を求めてともに歩む」)の再放送を目にしました。
私(編集者)は、徳田弁護士がハンセン病家族国家賠償請求訴訟(2016年提起、2019年判決)のすぐ後に行った講演を聞いていました。熊本県の黒川温泉宿泊拒否事件の際に、菊池恵楓園(熊本県合志市)の入所者たちに全国から届いた誹謗中傷の手紙やはがき(*)(114ページ以降)を取り上げ、徳田弁護士は「元患者を自分より下に見て、気の毒な人だと同情している時には差別的なことを言わなかった人たちが、元患者が自分と同じ人間として人権を主張し始めると、とたんに『身の程を知れ』と激しく攻撃する」と語りました。これまで聞いたことがない見方で、これこそ差別の本質だと強い衝撃を受けました。差別者でないと自認している人ほどこうした心情に陥りがちなのではないか、これは厄介な問題だとも感じました。
*2003年9月、熊本県が里帰り事業として菊池恵楓園の入所者(熊本県出身者)を対象に黒川温泉一泊旅行を計画、同温泉内のホテルを予約したところ、ホテルが受け入れを拒否。県がこれを批判したことからホテルは拒否を撤回し、入所者に謝罪した。入所者がホテル支配人を批判する様子が報道されたテレビニュースなどを見た人から批判が寄せられた。
・「こころの時代」に戻りますと、徳田弁護士は、戦争で結核を発症した父親を幼くして亡くし、祖父母に育てられたこと、夫を失った若き母親が失意のあまり心を病んだことを語っていました。それが自らの弁護士としての原点だというお話は、私に二度目の衝撃を与えました。「感染症と差別の問題を語れるのは、この人しかいない」と確信し、私は番組が終わるとすぐに徳田弁護士に手紙を書き始めたのです。 https://note.com/kamogawa_syuppan/n/nde1399fe7374 かもがわ出版 から
・11月16日(土)「金泰九さんに学ぶ教育実践交流会」では、徳田さんの講演会を予定しています。
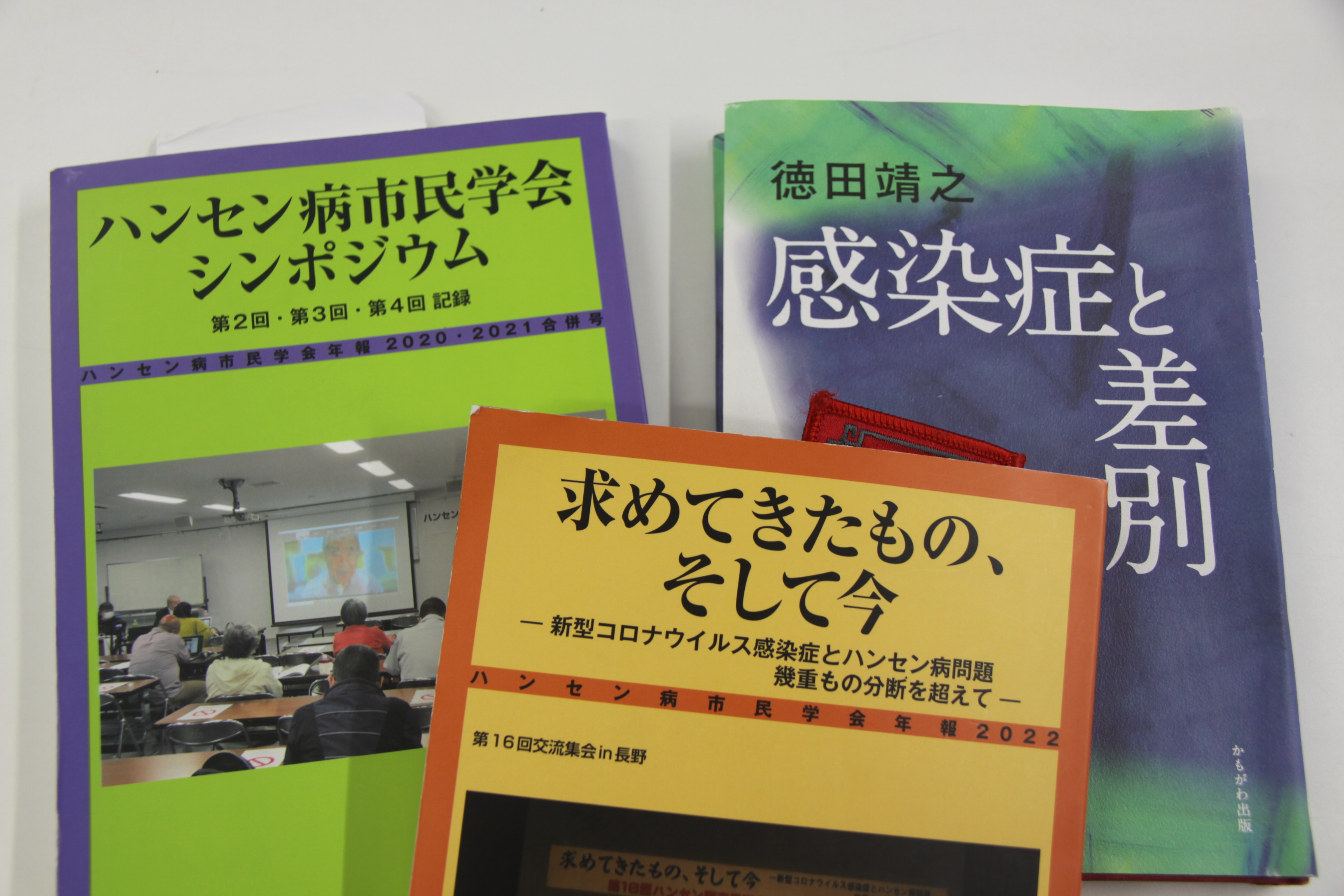
☆酷暑お見舞い申し上げます。一休み 一休み。

☆117日目(7.31)同和教育から引き継いでいくこと〈ご案内〉
〈シン・仲間づくりのための学級・学年通信〉を縁あって岡山県教職員組合夏季自主編成講座のひとつとして行います。『自分のめざす「クラスづくり」を進めたり、また、教育課題を解決したりするために、学級通信にひと工夫を加える(人権教育での仲間づくりの技)と、効く「通信」になります。子どもと子どもをつなぐとはどういうことか?、いじめや不登校を生まないクラスづくりのために「通信」はどう活用できるのか?5分で出来る通信の作成方法、年間200号を発行する方法など、その考え方を確認しながら、実際に作ってみよう』と働きかけています。8月6日(火)10:30~12:00を予定しています。都合がつく方はご参加していただきともに学びましょう。
☆116日目(7.30)同和教育から引き継いでいくこと
岡山県人権教育研究大会第2分科会での協議の中で、「進路保障」が話題となりました。同和教育から人権教育へ名称は変わりましたが、これまで先達らが教育実践から創りあげてきた豊かな「教育内容」があります。森実さんがまとめられた以下のHPで、同和教育の歩みが書かれています。ちなみに「統一応募用紙」(近畿高等学校統一応募用紙)は、高校生が就職試験を受験するために求人事業所に提出する用紙であり、紹介書、履歴書、調査書からなる。近畿高等学校統一応募用紙が昭和 46(1971)年2月に制定され使用されるまで、求人事業所は就職差別を温存助長する恐れのある思想、信条、宗教、尊敬する人物、支持政党、家族の資産、住居環境、家族の学歴などの記入項目のある独自の応募用紙<社用紙>の提出を求めていたが、そのことによって適性と能力以外のことで社会的差別を受けてきた多くの同和地区出身生徒等、被差別の状態におかれた生徒の苦しみは計り知れないものがありました。そこで、こうした差別を生み出す社用紙を撤廃する運動の中で制定されたのが近畿高等学校統一応募用紙です。 しかしながら、近畿高等学校統一応募用紙が制定されてから50年以上が経過し、制定の趣旨が教育関係者等に徹底されていない課題もあげられています。
部落差別と同和教育(その1)|学び!と人権|まなびと|Webマガジン|日本文教出版 (nichibun-g.co.jp)
☆115日目(7.29)
岡山県人権教育研究大会に参加しました。また、この日は、全国学力状況調査の結果公表日です。「同和教育の変容と今日的意義 ―解放教育の視点から』を紹介します(https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/85/4/85_420/_pdf)
☆114日目(7.27)
29日は、岡山県人権教育研究大会が開催されます。今年度は、2次案内チラシがなかなか届かない状況もあったのですが、どっこい今年も、東備地域から2本のレポートがあります。一つは、備前市立片上高校から「発達特性」や「支援」のありよう、そして進路保障に課する内容、もう一つは「社会科でのハンセン病問題学習」を学校の大切な取組に位置づけて継続的に取り組んでいる実践報告です。この研究大会は、「発表して、質疑応答をして終わる」スタイルではなく、報告を受け、質疑で報告内容の認識をさらに深めていきます。そして自分自身の実践や取組をもう一度見つめ直し、共に学び合う研究協議スタイルです。ぜひ第2分科会で、語り合いましょう。学びましょう。。
☆113日目(7.26)
昨日、7月25日は、長島愛生園で、「慰霊の花火大会」がありました。昨年度コロナ禍を越えて四年ぶりに開催され、今年2回となる「慰霊の花火大会」でした。一緒に行った、コロナ前の「夏祭り花火大会」を知っている友人は、「やぐらも組まれてなく、甲州音頭の歌声もなくて、少しさびしい感じがするね」とつぶやいていましたが・・・。友人に映ったこの日の愛生園の景色は、ハンセン病問題の「いまの状況」をみてとれる現実であることに間違いない。
明日は、愛生園で、フィールドワークのお手伝いをするのだが、「私はどこに立って(どんな立場で)、歴史的な遺物や建物・施設、そしてハンセン病問題についての歴史を語るべきなのか?入所者の方々から聴いた声を私は伝えることができるのか?」いつも案内しながら自問自答している。
再掲ですが、T先輩からいただいた私自身への戒めのコトバです。『何を伝えたい 何を問いかけたい そして、自分はなぜハンセン病問題にこだわるのかを明確にすることがもっとも大切なことだと思います。主旨、目的のない企画は「被差別の当事者を」利用するだけです。私はそんな企画には賛同できません。』

☆112日目(7.25)えー、あのー、えーと
昨日の内容について、以前に一緒に勤めたT先生と久しぶりに話をした。若い頃、自分の話し方のクセや特徴を気にしたり、改善することは難しいなあということになり、T先生と「話し方研究会」を立ち上げた(二人だけで)。その話し方研究会は、それぞれが授業や、学年集会や職員会議で話している内容を聞き合い、お互いに気になったことについて意見交換するのだ。「話すスピードが速いのではないか」「コトバが難しい。子どもにわかる内容で」「話すと伝えることは違うんで!」などなど、お互いに厳しく指摘し合うことで、〈語ること〉を鍛えることが出来たように思える。そして冒頭にある、「えー」「あのお」「えーと」と文章をつなぐ言葉がお互いにとても多いことにも気づかされた。「話し方研究会」を一緒にしませんか?
☆111日目(7.24)先生はいくつの、話し方・語り方・声をもっている?
ファシリテーション研修会で、M先生がそう私に尋ねられた。考えてみると、大きな声で生徒に「言う(聞かせる)」ことしか思ってなかった私は「ハッ」とした。あれから何年も経ち、どんな声で、どんな話し方がよいのか考えることが少しだけ出来るようになった。教室の後ろまでとどける声、大きな声ではなく「伝える」ことを意識した声、意思を伝える強い声、あえてクラスでひとりに語りかける声、つぶやく声、聴きながらうなずきながら発する声、時には沈黙すること、ずっと待つこと。いつも子どもたちとの向き合い方は真剣勝負だ。だからこそ声の大きさやトーン、内容は吟味したい。
☆110日目(7.23)私たち自身が豊かな発想をせねば。
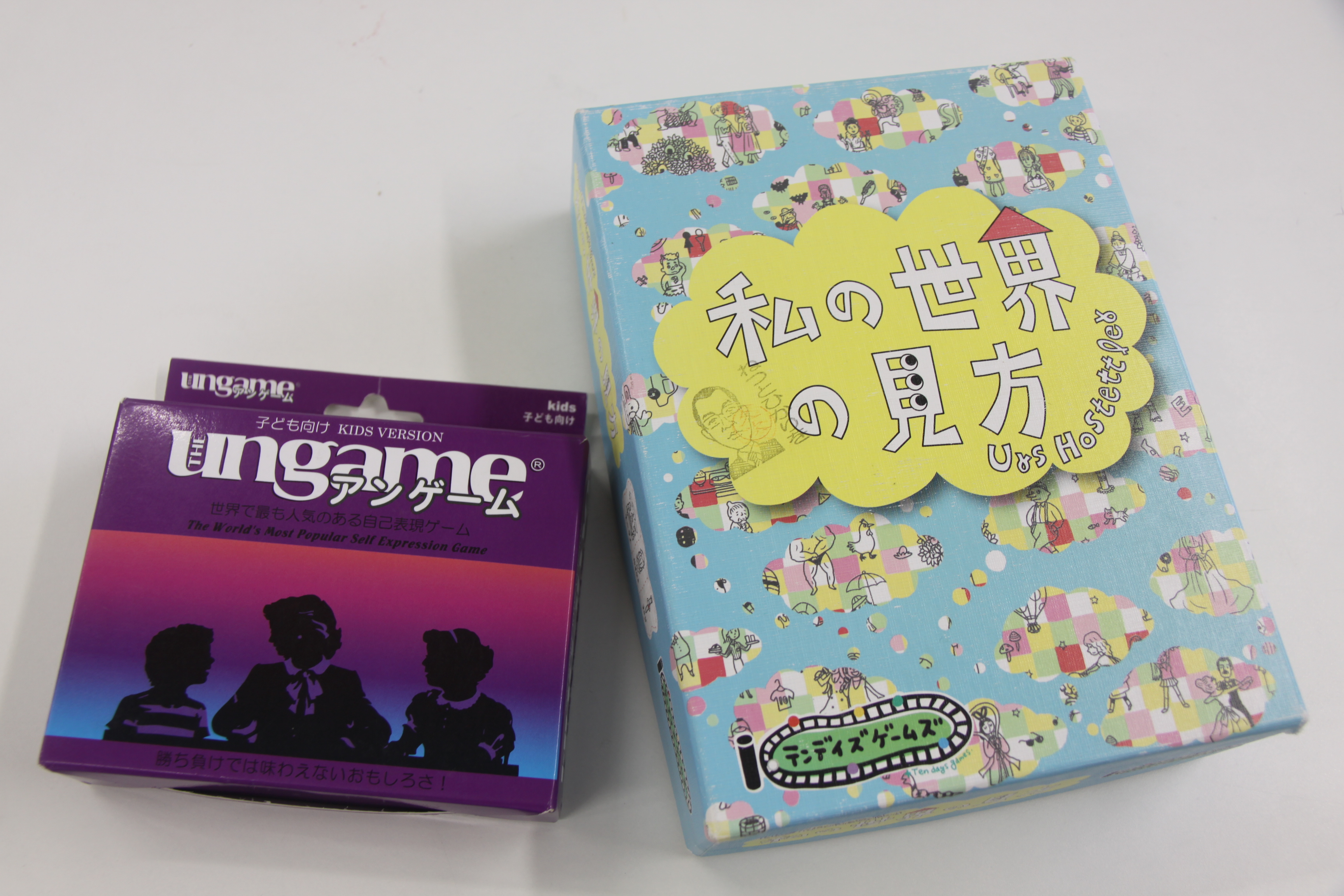
子どものたちとの活動で、SSTに積極的に取り組んむ中で、「内容が堅い、指導形式でおもしろくない、授業者だけがしゃべっている、生活につながっていない」など様々な教育現場で聞くことがありました。とある学校の友人に紹介してもらった「私の社会の見方」「アンゲーム」は、自分自身の視野を拡げてくれます。子どもたちの実態や課題に照らし合わせて運用方法やルールはアレンジして使ってみては。長期休業中に同僚と試しにしてみてください。ハズレなし。
☆109日目(7.22)自習時間で何を?
とても前の話です。急な授業変更となり、どうしても「自習」で課題プリントを用意して、教室に行くこととなりました。みなさんはどんな指示をしますか?プリントを配り、50分間黙々と取り組むこともできるのですが、学習グループのスタイルで、「「これってどうするん?」と聴き合うことをしよう」と指示しました。学年で〈共にがんばろう〉という目標をあげているのですから、具体的な場面を設定して、具体的な取組をせねばなりません。「自習」時間は、またそれまでのクラスづくりや取組・教育実践が試される時なのです。例えば「主体的に取り組むことができるようになっているクラスなのか?「わからない、教えて」と言える子どもたちが育っているか?そのつぶやきの応える仲間集団が出来ているか?」などをしっかりと看取りたいものです。また、50分の自習が終わる際には、「しっかりと仲間と大事な時間がおくれたか?」を、自習監督ではなく、授業者として、還す作業も必要となりますね。
☆108日目(7.19)長期休暇中ならではの宿題を。
以前にも紹介した「聴き取り学習」。例えば、一年生の夏には「中学校生活をたいせつにするために、仲間(友だち)に関すること」、冬には、「身近な平和について」。二年生の夏は「親(身近なひと)のしごとのついての生き様、願い」、二年生の冬は「高校時代」。そして三年生夏には「夢・未来に向けて、受験をどうこえたか(仲間と、親、自分)」を、思春期の子どもが、親と語り合うシチュエーションは結構大切な時間となります。また、聴き取りをまとめ、クラスで発表しあう時間をもつことで、より仲間を識ることができるのですな。
☆107日目(7.18)これからのハンセン病問題学習をどう進めるか
今年度の第3回金泰九さんに学ぶ教育実践交流会の案内ができました。
☆106日目(7.17)これからのハンセン病問題学習をどう進めるか
7/13に、ハンセン病市民学会「啓発資料調査部会」第4回学習会に参加してきました。弁護士の徳田靖之さんの講演「ハンセン病問題とどう向き合うべきか~司法の立場から」(主催者仮題)のお話を聴きました。これまでの取組を反省し、「もう一歩先に」進んでいくための人権教育の内実を創る「教材研究」を行い、実践をしていこうと思いました。そのいくつかは、「家族訴訟」、「黒川温泉宿泊拒否事件」、「救らい思想」、「当事者と支援者」についてです。徳田さんが、その日お話された内容が、頂いた資料にもありました。一部を紹介します。「大谷大学人権センター 人権センター叢書 VOL26『ハンセン病問題が私たちに問うもの』のP42~48」です。この内容について、ぜひ一緒に「教材化」していきましょう。
☆105日目(7.16)みんなの1777円
7/7の地域のイベントに参加した生徒たちは、しっかりと自立活動を振り返りました。また、時間をかけて精算し、お世話になった方々にお礼と会計報告をおこないました。
そして、自分たちが稼いだ「収益金をどう使うか?」これもまた大事な取組にせねばなりません。大事な1777円。
☆104日目(7.12)余計? 待ってる?
以前に勤めていた学校で、よく遅刻をしていたTくんは、職員室に寄って「遅刻手続き」して教室へ送っていました。
いつも、Tが「遅刻の手続き」をするために、職員室に入ってくると、いつも在室している教職員が気づき「おはようTくん」と寄って、そして、遅刻手続きの用紙と筆記具を用意して渡していました。 私がとても気になっていたのは、彼はこれまで「おはようございます」や「遅刻届をください」と言うことはないことですありませんでした。
とある日、同じように彼が遅刻して職員室に入ってきました。違っていたのは、(たまたま?偶然?)、在室していた教職員がTの存在に気がつかなったことでした。するとTは、当たり前のように「おはようございます」と気持ちのよいあいさつをしました。私は「おお!!!。いいあいさつだね」と声をかけ、そして、気になっていたことを素直に本人に話ました。そのあと、彼は遅刻手続きをして教室へ向かいました。
私は、学級担任にこれまでのいきさつと、今日の「いいあいさつ」だったことと、「クラスの中で」話をしてほしいことを伝えました。
・・・小さなことですが、何のために、いつ、どこまで、どのような「支援」、「サポート」「声かけ」するのか、そしてコトバを「待つ」のかなど、教育のプロとして自覚せねばならないことだなあと改めて考えたのです。
追記:その日の放課後、Tは、なぜなのか「投げキス」パフォーマンスをして下校していきました。
☆103日目(7.11)余計な指示はしない。不必要なことはしゃべらない
昨日の内容に関わって、やはり、担任からの「たくさんの」連絡事項を減らす校内体制をつくりたい。生徒連絡票に記入して、子どもから子どもへ伝えることを増やしましょう。ホワイトボードに掲示しましょう。行動の1から10までを説明する必要があるかないか?を、判断する力を磨いていきたいですね。と、言いながらこの内容も何度も繰り返しています。
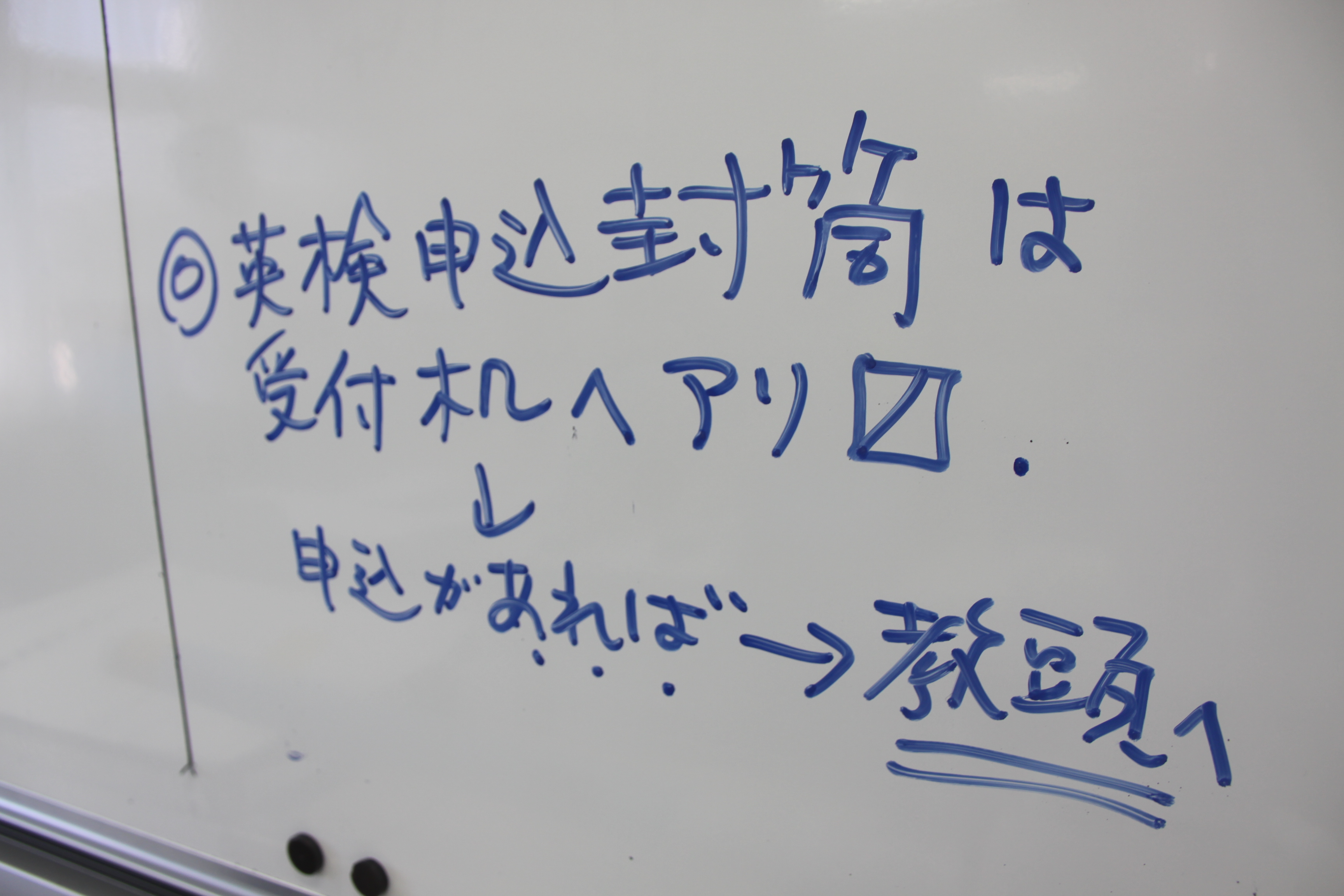
☆102日目(7.10)余計な指示はしない。不必要なことはしゃべらない
7月8日、三年英語科授業での〈アイスクリームプロジェクト〉で、生徒グループの発表は圧巻!「はい、授業始めるよ」「学級委員さん号令かけて」「じゃあ、次のグループは準備して」「はい、あいさつして、スタート」「誰が声をかけするの?○○さん、はい、どうぞ」「よかったよ。では、ワークシートに記入しましょう」、、、などの声かけが、まったくナイ素晴らしい授業指導でした。丁寧に指導、指示をしているつもりでも、子どもたちには要らない、自分たちで進めることができる」という確信をもてば、自ずから、不必要な「コトバ」は減り、教師の発するコトバの意味が変わってくるなあ。

☆101日目(7.9)地域協働と自立
7月7日の開催された「日生カキかきフェス」に参加してきました。多くの方々に支えられて、用意したフルーツアイスシャーベットは完売しました。事前に、販売する商品や種類、数量、値段を決めること、POPを作ること、お釣りの計算、呼びかけ、接客、当番シフト、そしてこの暑さの中での体調管理などなど・・・。学ぶことがたくさんありました。「振り返り」をしっかりして、本当の「生き抜く」力にしていきたいですね。


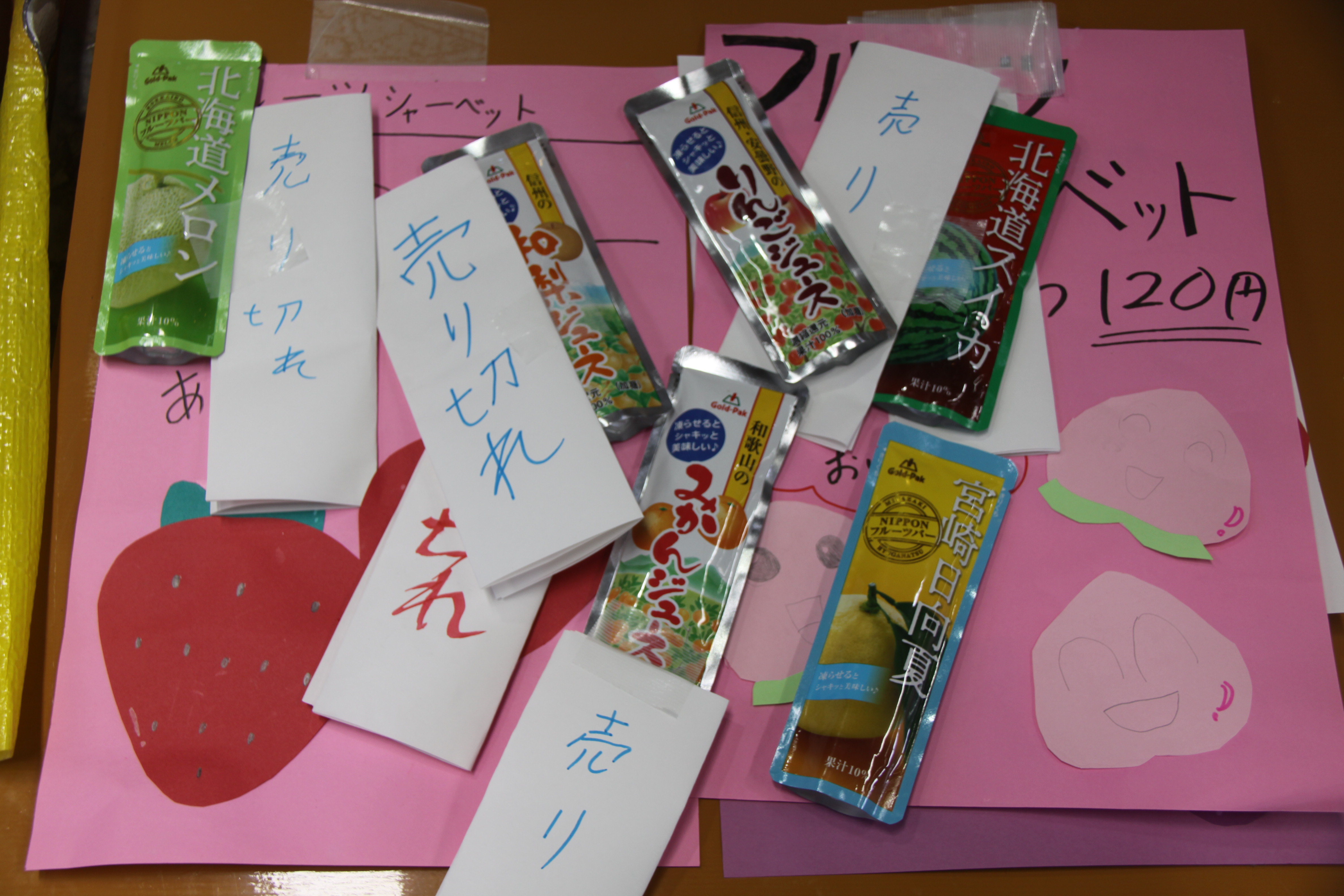
☆100日目(7.8)還すこと 友だちカウンセリング掲示
95日目に話題にしたピアサポートを参考にした「友だちカウンセリング」月に取り組んだ3年生の回答は、今回はサブ教室に掲示しました。掲示をしていると、「また、やりたい。もっとじっくり応えたかった。受験が近づいてきたときにもう一度したいなあ」と話してくれた生徒がいました。取組の振り返りを担任の先生と少し話しました。①質問数の精選が必要。グループの中で意見を出し合いじっくり「応える」時間をもちたい。全員分に応えるというのもポイントなのですがどうするかなあ。②掲示の方法や、掲示の準備も視野に入れてワークシートを工夫せねばならないこと。今回はA4両面のワークシートを用意しましたが、結局掲示する際には、A4両面をB4の2面に印刷しなおしました。39人分の質問を掲示するには、A4版かな。③質問に応える時間をしっかりとるために、グループの名前を一回ずつ書く時間と、質問項目は、事前に記載しておくような準備が必要だったのかも。いずれにせよ、子どもたちの状況や、目的・ねらいを明確にしていかないといけませんね。一生懸命に取り組む3年生諸君!ステキです!(掲示時期は夏休み終了まで。いつまでも貼っておきません。旬がありますからね。)

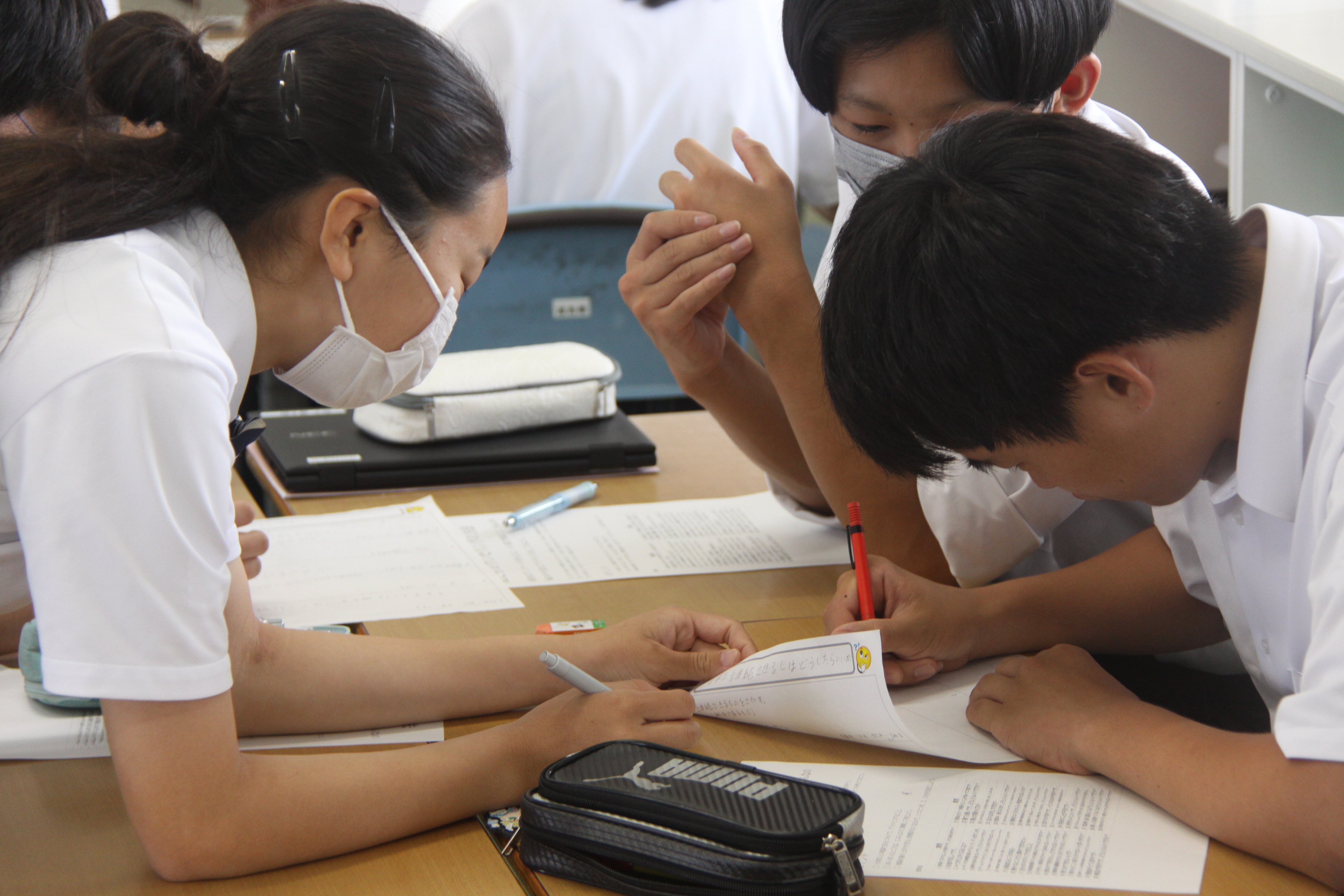
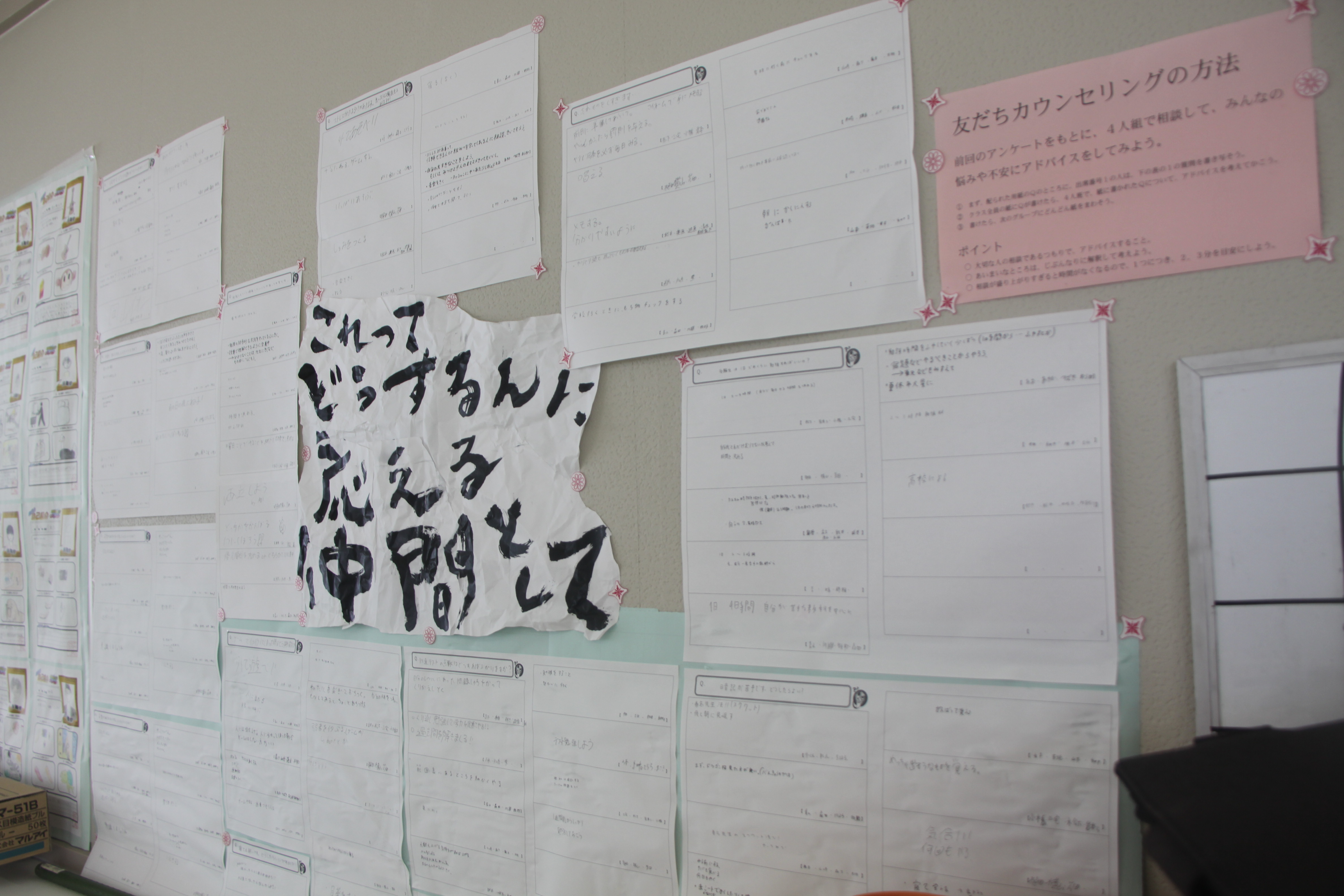
☆99日目(7.5)Nothing About us without us
これまでの「運動」を知った上で、障害者問題に取り組んでいきたいと思います。第1学習室にも置いていますので一読を。
・荒井 裕樹著『障害者差別を問いなおす』(ちくま新書)、『車椅子の横に立つ人──障害から見つめる「生きにくさ」』(青土社)、『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)、『差別されてる自覚はあるか: 横田弘と青い芝の会「行動綱領」』
・横塚晃一『障害者殺しの思想』
・横田弘著:『母よ!殺すな』
☆98日目(7.4)『生きることのはじまり』から
金満里さんの『生きることのはじまり』の中に、障害者解放運動の内容があります。岡山で障害者解放運動に長年携わっているNさんに、よく聴いていた「青い芝の会」。その綱領について提示します。
日本脳性マヒ者協会「全国青い芝の会」行動綱領
1.われらは、自らが脳性まひ者であることを自覚する。
われらは、現代社会にあって「本来あってはならない存在」とされつつある自らの位置を確認し、そこに一切の運動の原点を置かなければならないと信じ、且つ行動する。
1.われらは強烈な自己主張を行う。
われらが脳性マヒ者であることを自覚した時、そこに起るのは自らを守ろうとする意志である。
われらは強烈な自己主張こそ、それを成しうる唯一の路であると信じ、且つ行動をする。
1.われらは愛と正義を否定する
われらは愛と正義のもつエゴイズムを鋭く告発し、それを否定することによって生じる人間凝視に伴う相互理解こそ真の共生であると信じ、且つ行動する。
1.われらは健全者文明を否定する。
われらは健全者の作り出してきた現代文明が、われらの脳性まひ者を弾きだすことによってのみ成り立ってきたことを認識し、運動及び日常性生活の中からわれら独自の文化を創り出すことが現代文明への告発に通じることを信じ、且つ行動する。
1.われら問題解決の路を選ばない。
われらは安易に問題解決を図ろうとすることが、いかに危険な妥協への出発であるか、身をもって知ってきた。
われらは次々と問題提起を行うことのみが、われらの行いうる運動であると信じ、且つ行動する。
われらは以上五項目の行動綱領に基き、脳性まひ者の自立と解放を掲げつつ、すべての差別と闘う。
☆97日目(7.3)自立支援とは何か?
春いちごの会で、進路情報交流会の準備を進めている中で、人々舎から復刻された『生きることのはじまり』金 満里 著 を読んだ。あらためて「障害(がい)」「自立支援」などなどなどについて考えさせられた。読んだ方!お話をしましょう。本の紹介文は以下(在日の朝鮮古典芸能家の娘である著者が、重度身障者となり、施設生活・運動を経て自立、身体障害者だけの劇団「態変」を主宰し、一児の母となるまでの半生の記録。)職員室の「ひといきスペース」に置いておきますね。

☆96日目(7.2)春15(いちご)の会 〈声〉を訊く 開催案内
今年度の春15の会(特別支援教育のニーズのある子ども・保護者のための進路情報交流学習会)の案内です。これまで「学校の先生が開催するものではない。」と、言われる方が、たくさんおられました。しかし、必要としている「声」があり、進路情報のニーズがある事を大事にしたい。多くの方々に支えられて、東備地全域で開催します。もちろん多くの先生方も協力してくださっています。
☆95日目(7.1)ともだちカウンセリングの質問紙もポイント
ちなみに、質問は、クラス全員分がミソ。一人ひとりの「今」の質問に、クラスの仲間が真摯に応えていくことが大事ですね。
☆94日目(6.28)SSTやGWTを超えて
よく考えられたSSTやGWTの教材から、自分のことやクラスの問題を、学級全体で考える取組にならないと学びは「ホンモノ」になっていかない。以前に、教職員集団で創って実践した「ともだちカウンセリング」。本校でも、クラスの次なるステップアップのために、検討して取り組みます。
☆93日目(6.27)地域協働と「自立活動」
さあ、出発! みんなでがんばろう!
☆92日目(6.26)人権教育実践の会より。
前回に関連して、近々行われる学習会案内チラシからも、「拡がり」「深まり」が感じられますね。
① 「シン・仲間づくりのための学級・学年通信 ワークショップ」
日時 8月6日
あなたのめざす「クラスづくり」を進めたり、教育課題の解決のための、学級・学年通信(たより)にひと工夫を加え、スパイスの効いた「通信」になります。子どもと子どもをつなぐ、いじめや不登校を生まないクラスのための「通信」の手立てや、5分で出来る「通信」、年間200号発行する方法など、参加者同士で「学級づくり」の考え方を確認しながら、実際に作ってみましょう。人権教育の視野が拡がりますよ。
② 学級づくり、授業(PBL)づくりのためのフィールドワーク
「過去・いま・未来をつなぐハンセン病問題学習プログラムをつくろう」
日時 7月27日 (最終調整中)10時00分 ~ 11時30分
長島愛生園現地集合 愛生園内フィールドワーク…園内の歴史的な施設を歩きます。(船着き場跡~収容所跡~監房跡~万霊山・納骨堂~恵みの鐘~一郎道~旧資料館~歴史館)(約1.5時間)関心のある方、どなたでも参加できます。(お子さんも可能ですよ。)一緒に歩く中で「ハンセン病問題学習」の組み立てや学習プログラムなどを考えましょう。
☆91日目(6.25)拡がるなあ 深まるのよ 人権教育実践。
週末に、東備学ぶ会に参加してきました。小学校の先生から「ハンセン病問題学習」に取り組まれた実践報告でしたが、参加者同士で、様々な視点・視座からの意見交流では、わくわくする、学びの「拡がり」「深まり」を実感することができました。会で論議したいくつかの視点や意見を紹介します。
○「ハンセン病問題」という人権課題の知識を習得する学習ではなく、「ハンセン病問題学習」を通して、「どう自分たちは生きていくか?」「どんな社会・未来を創っていくのか」を考える取組(授業)でありたい。
○学習を通して「知ったこと」と「学んだ」ことは違うなあと思った。そこは明確にさせたいと思っています。そして、学習のまとめとして、「発信」もよくあるけど、「誰に伝えたいのか」「何を伝えるのか」もしっかり考えたいなあ。
○クラスの仲間づくりにつながっているし、つなげていかないといけないといつも思っている。
○子どもたちと一緒に「ハンセン病問題学習に取り組みたい、子どもたちに伝えたい!」と思ったのは、教師自身が何に出会って、どのように変わっていったことによるのか(教師自身の変わり目は何だったのか)?は大事だなあ。
○ハンセン病問題学習の目的は何か?クラスの子どもたちや教職員集団の課題は何なのかを明らかにして、取組を進めたいと思っています。ちなみに私は、「どう生きるか?」「クラスの仲間たちとどう暮らすのか」だな。
○子どもたちの感想や振り返りの中でも、とくに、教師自身が「クラス中で気になる子ども」の葛藤や学びの深まり、変化・成長をしっかりと見ていきたい。
○昨年度の実践の成果と課題をもとに、今年度のクラスづくりにどう生かしていけてるか?(いつも反省ばかりですが)
○クラスで完結しないように、学校全体(1~6年生)、中学校との連携した(継続的な)取組を構築したい。連携・継続は難しい。
90日目(6.24)学校行事を通した仲間づくり
文化祭・合唱コンクールに向けて、本校では実行委員会やパートリーダーの選出がはじまりました。テクニックや練習方法など参考になる動画はたくさんある時代となりましたが、「誰」が、「どのような働きかけ」の中で、視聴するのか。は考えたいものです。先生が「観よう」と言うのは簡単ですが、ある時は、実行委員メンバーと事前に視聴し、その中から、クラス全員で観るところを絞って、実行委員会メンバーのメッセージ入りの学級通信配布と合わせて、視聴しました。また、優れた映画もたくさんありますね。
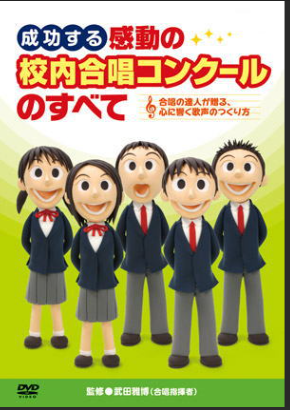
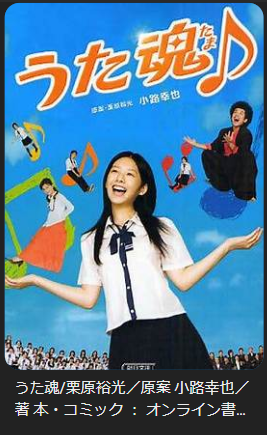

☆89日目(6.21)学年集会~仲間づくり~
学年集会は、子どもたちのもの。こんな学年集会もありました。
☆88日目(6.20)モノが教室でなくなったら~仲間づくり~
クラスで生徒のモノがなくなったらどんな手立てがかんがえられるでしょうか?それまでの学級内の教育課題や、生徒間の人間関係も充分把握した上で、学年団・学校全体で取り組まねばならないと思いますが、具体的な手立てを考えてみましょう。(一般的な生活指導の対応と重なることとまったく違うこともあると思いますが。)
○モノがなくなった子どものへの十分な支え(保護者との連携)の上に
○子どもたちへ還す取組(□その子へ近しい子らへ支える基盤・ □班長会 □クラスへ □学年・全校集会)*教職員だけが語らず、子どもた
ち自身が語る取組については前述済)
○問う(□クラスアンケート(情報提供) □声かけ相談 □叱る・・・だけでは解決にはなりませんが *何を問うかは重要ですね)
○探す(□すぐさま、放課後教職員全員で □クラス全員で(・放課後に時間をかかけて ・時には授業時間に) □全校で □何度も)
○示す(□なくなったモノの弁償・回復 □この出来事の重大性 □学年の課題として捉える )
○警察に被害届を出す・・・このぐらい・・・ですか。他にもあると思います。いろいろと話したいですね。
さて、人権教育実践で学んだ取組をひとつ。
もう、20年も前に、赴任していた学校で、「靴」がなくなったコト(盗った?)があり、上記の様々な取組をしましたが、靴は出てきませんでした。でもこのまま終わるといけないと思い、生徒会や学級委員会のメンバーらと話をして、つくったのは、大きな大きなメッセージボード。「私たちは絶対に許しません!」と大書して、全員が署名したものを玄関に掲示しました。そして、そのボードには、「こんなことを何度もするあなたは、何か悩みや心配ごとがあるのではないですか?相談にのります。ひとりで悩まないで」の旨の文書が書き添えました。これは、メッセージボードを作る際に、生徒会・学級委員メンバーから出た意見をもとに考えたことです。「したことは許されないことだけど、学年の仲間として一緒に生きていく」ことを体現した子どもたちでした。
☆87日目(6.19)掲示物の賞味期限はいつまで??
時間をかけて作成した掲示物や子どもたちが綴った願いや思いが書いている掲示物の掲示の期間はいつまででしょうか。本校でも星輝祭(体育の部)の取組のひとつとして、ステキな掲示物が展示されました。それから三週間あまりが経って、外す作業をおこないました。(ちょっとおそ過ぎたかも)。
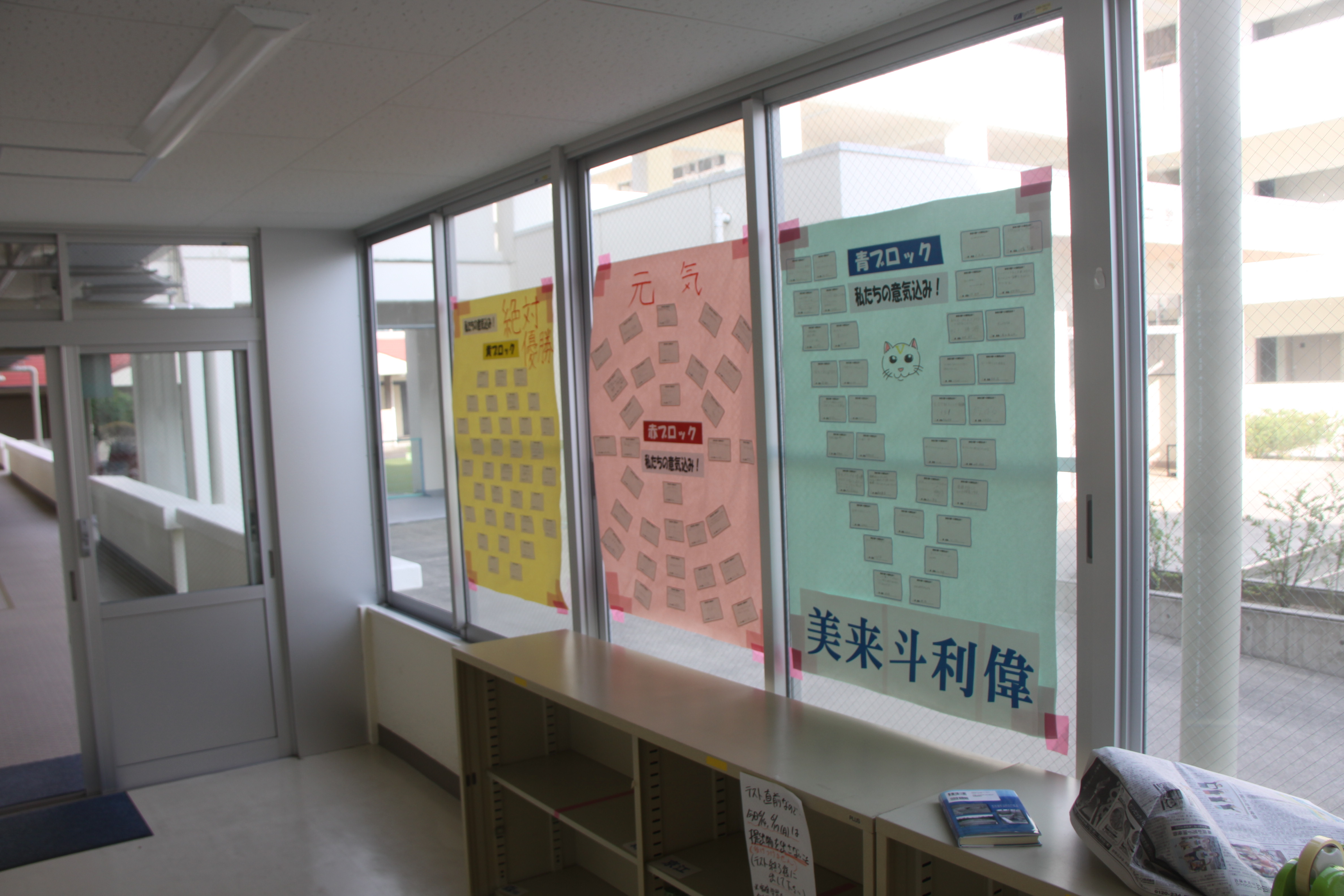
「何のために、どこに、いつまでに、誰が」掲示するか意図的に環境整備を進めたいですね。
ちなみに、ずっと(3月末まで)掲示する方法があります。
これです。学習室に移動させて、「あゆみ」として再掲示しました。クラスでも可能でしょう。
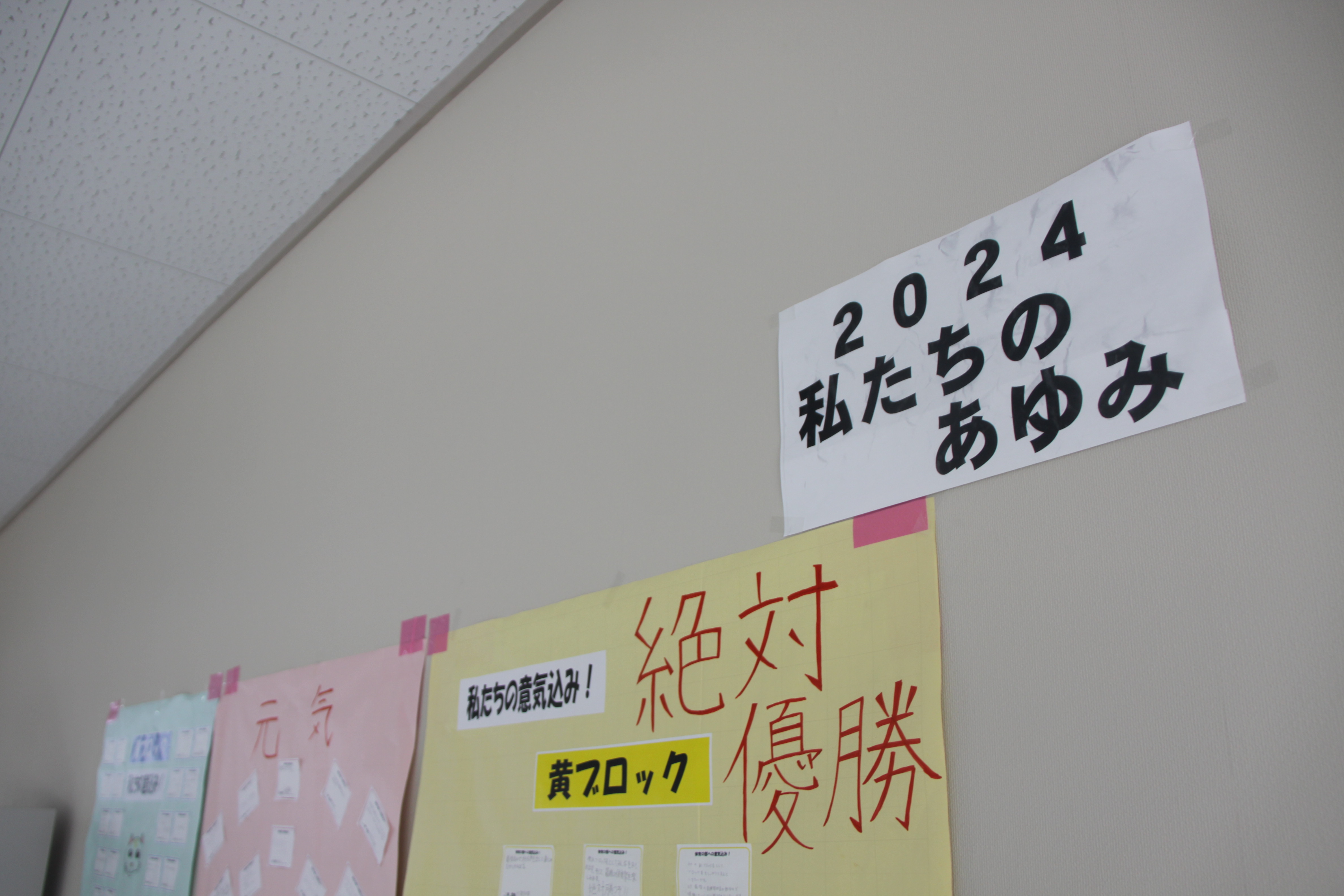
追記:2年生は広島研修時に乗ったバス(バスの運転集席の上の掲示物)さんから頂いた「日生中学校様 ○○バス」という用紙を、ヒロシマ研修の学びの証として、教室うしろにを貼っていますね。スバらしい。
☆86日目(6.18)何を話す(放つ?)月曜日の職員打ち合わせ会で
本校では、月曜日だけ全体での職員の打ち合わせがあります。他の日は学年団中心の打ち合わせ会のみで、全体での連絡事項は、前のホワイトボードやミライム等の連絡機能を活用しています。そうなると、あえて、一週間のはじまりである月曜日、限られた少ない時間に、「何を話し」「何を教職員どうしで共有するのか?」は大変重要になりますね。これまでもいろいろと考え、工夫はしてきたものの、自分なりに満足のいく「適切」な」や指示・連絡はなかなか出来ていません。この年になっても反省しきりです。
では、今日(6/16)は、どんな話が必要なのか?
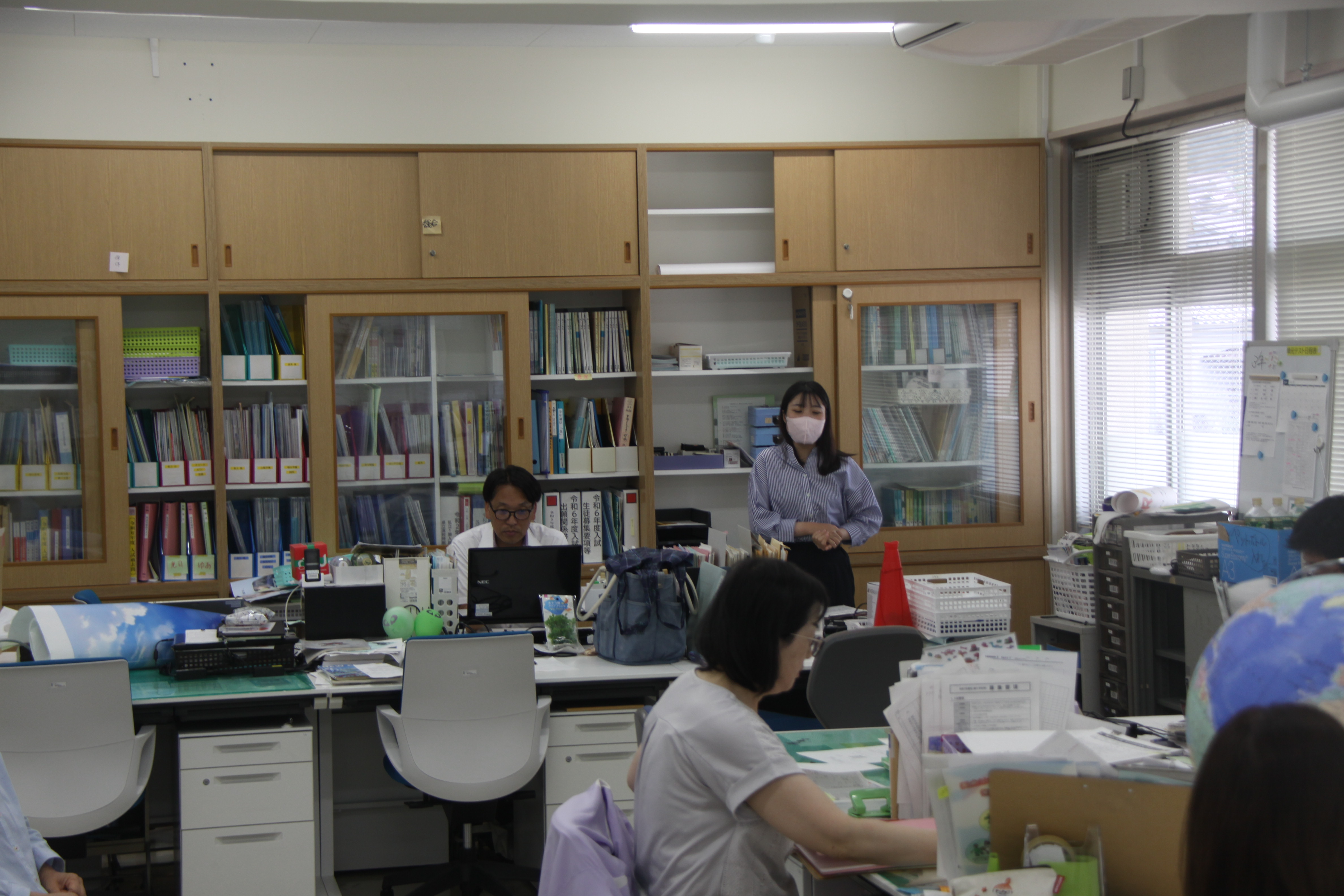
おりしも、週末には備前東地区大会と岡山県吹奏楽祭で生徒引率をした先生方がおられますので、大会の成績だけでなく、印象に残った出来事やストーリー、がんばった試合での子どもたちの状況、部活動を引退する3年生の様子などを話していただき、全職員で取組の情報を共有することができました。子どもたちのががんばっている姿や、一生懸命な取組の姿を共有して、一週間のスタートが切れてよかったと思います。
追記:時期が合えば、3年研修や、16年研修での学びのひとつを話して(還元)もらうことも大切にしています。
☆85日目(6.17)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
前回から、子どもたちの課題や実態をもとに取組をつくっていくタネでしたが、地域づくりと開かれた学校づくりについての「可能性」について話を広げることができました。あくまでも、「地域へ出かけていく入口」「地域との出会いの創出(きっかけ)」としての地域イベント参画ボランティアです。ヒントとなる出店案(実際に自立活動として出店した取組をもとに)を掲示します。
☆84日目(6.14)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
前々回のタネを受けて。地域のお祭りに参画するために、学年全体の気持ちを高め、みんなの「地域づくり」の意思を共有するために実践したワークシートです。
☆83日目(6.13)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
前回のタネを受けて、昨年度、警察署と連携した非行防止教室、薬物乱用防止教室につながるアンケートを実施したことがありました。とても、子どもたちの課題をもとに、有効的に授業づくりを進めることができました。
☆82日目(6.12)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
教育実習中の先生が、「授業づくりは大変だけど、楽しい」と言うのを聞くと、こちらもうれしくなります。一方的な知識の伝達ではなく、子どもたちの置かれている状況や、課題をもとにして、授業づくりを進めていきたいですね。「認知症」を学ぶ授業を福祉課さんと取り組んだ時にも、子どもたちへの事前アンケートを大切にしました。
☆81日目(6.11)朝の会、帰りの会で。
「子どもどうしをつなげる」か?の視点で。
一緒に学年をもった先生たちと実践した朝・帰りの会のメニュー表がありました。そういえば、帰りの会で、〈今週の歌〉を決めて、歌っていたこともありましたねえ。メニュー
☆80日目(6.10)いつでも「子どもどうしをつなげる」か?の視点で。
少し遅い当初面談の中で、先生たちと「子どもどうし」をつなげることについて話題になりました。様々な構成的グループエンカウンターやGWTなどの教材もありますが、日常的な場面の中から津創っていきたいですね。例えば、今日の生徒集会で、服装を整える場面があるとしたら、どうのように生徒らに声をかけますか?「服装を整えなさい」から、前後左右のペアにさせて、「お互いに身だしなみをチェックしてなあ。名札、ネクタイ、ボタン、服装、(緊張をほぐす意味で、寝癖直してもらえ。 鼻毛も出てないか?などなども)」もかかわりの場面を創ることができる。教室整備の意識を高めるには、帰りの会の終わりには、委員長が号令をかけて「さようなら」と言う場面が日常的だけど、「起立」の後に、「机を整えてください」、「窓際のひとは鍵の確認してください」と呼びかけをする、そしてみんなが応えるクラスをめざしたい。教職員が「している」ことを、子どもたちの係や役割に「委ねてみる」と、子どもたちはたくましく動き、主体的な学級になっていくと思います。
他にもないかなあ?「子どもどうしをつながる日常の中での取組は??」
☆79日目(6.6)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業5
教材の視点
(1) 禁服訟嘆難訴記
○ 生徒たちは、これまでの社会科での歴史学習の中で、江戸幕府による民衆支配政策として、「身分制度」が定められ、「武士」と「百姓」「町人」との間に、支配・被支配の関係が定められたことと、そうした社会の外に置かれて、「武士」から支配を受けるとともに、「排除の差別」を受けてきた人々がいたことを学んできた。さらに、そうした「差別された人々」は様々な役目や生業を通して、社会や文化を支えてきたこと、仕事に誇りをもって生き抜いてきたことも学習している。禁服訟嘆難訴記は、経済的、政治的に揺るぎだした幕藩体制が、民衆支配として差別を強化しようとしたことに対する闘いの記録として捉えたい。
○ 「禁服訟歎難訴記」は、一揆の中心となった神下村のある家に残されていた文書で和綴じの二分冊である。表紙は「穢多渋着物一件」と題された上に、貼紙をして「禁服訟歎難訴記」と題されている。改題されたのは、明治になって「賤民廃止令」が出された頃だろうと言われている。筆者は、一揆の指導者の一人で手習師匠をしていた豊五郎であったと考えられている。原文は五七調で書かれており、題名は「服装を禁じられて、嘆き訴え苦労して申し上げた記録」という意味と考える。
○ 「禁服訟歎難訴記」冒頭部分は、「太陽も月も明るく澄みわたっているといっても、雲がさまたげとなってその光をさえぎる。天は太陽・月・星の主、地は山・川・草木の主、人は天と地の間にあって禽獣の主である。狐や狸は死んで肉が腐っても皮を残して様々な御代の着物にする。人は死んでその遺骸が腐ると言っても、名前を天下に顕らかにする。この詞は本当にそのとおりであることよ」(『岡山部落解放研究所紀要』1988)とあり、教材では、「人は死んでも、名前を天下に残す」と端的な言葉にして、この部分をとりあげ、「人としての誇り」を意味する重要な学習の視点として提起されている。
(2) 分け隔てを許さないと立ち上がった人々
○ 渋染一揆がおこる要因となった岡山藩の御触の背景について
1800年前後から既に財政危機に陥っていた岡山藩は、幕府から房総半島警備を命じられたことで、百姓に対する24ヵ条の倹約令を出す。その内容は「衣類は木綿、襟・袖口にも絹類の使用禁止」「綿入れや目立つ染色も禁止」「華美で高価な髪飾りの禁止」「祭事の食事の制限」「雨具の制限」などまさに出費を抑えて倹約を命ずる内容であった。しかし、その一ヶ月後に、「差別された人々(えた身分とされた人々)」に対してのみ5ヵ条の「別段御触書」を出した。その内容は、「衣類は無紋の渋染藍染に限るが、新たな出費となるのでこれまでの衣類は着ていてもよい」「目明かしに就いている者は、これまで通りでよい」「雨天の時は栗下駄を履いてよいが百姓と出会った時は脱いでお辞儀をすること」「年貢を完納している家の女子は竹の柄の傘を用いてよい」「番役人はこれまでどおりでよいが絹類の着用は禁止」というものあった。一読してわかるように、これらは倹約につながるような命令ではなく、身分の違いを明確にするためにのみ出されたものであった。
○ 「別段御触書」を命じられた人々が、どのような思いに至ったのか、そしてどのように行動していくのかといった学習への意欲を喚起して、学習課題を明確にもたせたい。
(3) 知恵を集めた嘆願書
○ 別段御触書など受け入れることはできないと、人々が集まって嘆願書の作成に取り組む経過から考えさせたい。これまで「渋染一揆」については、「渋や藍」の色をめぐって論議があり、「渋色や藍色は人々の嫌がる色であった為に抗議した」という意見と「どちらも一般的な色であって問題は差別された人々にのみ無地無紋を命じ差別したことに抗議した」という意見であった。前者については、収監者の服が主に西日本では柿色(渋)一色であり、東日本では青色(藍)一色であったことなどから、その可能性は否定できない面がある。一方で、当時の浮世絵などには、鮮やかで様々な模様の藍色、赤色を来た人々の姿が描かれており、これらは当時の「おしゃれ」であったことから後者の意見も否定できない。では、人々はどのような理由で別段御触書に抗議したのかを改めて「禁服訟歎難訴記」ともうひとつの原典教材であり豊吉が書いたと言われている「屑者重宝記」を精読すると前者には、二種類の嘆願書が写されており、計三種類がそれぞれ微妙に異なっているのである。まず嘆願書作成の経過は、村々が持ち寄った嘆願書を豊吉がとりまとめ、それぞれが持ち帰った。その後、豊吉は、懇意にしていた目明かしに添削を受けて文章を整え、最終的に51カ村の代表の署名を得て提出している。それぞれの文書には、この連署のある嘆願書が掲載されている。加えて「難訴記」には、その後も村役人から御触書の承諾の押印を厳しく求められた村々がそれぞれに出した嘆願書が掲載されており、併せて三種類である。すべてに共通している訴えは、「百姓と同様に田を耕し年貢を納めているのになぜこのような衣類を命じられるのか」「役人として逮捕にあたる際にすぐにわかる衣類では逃げられてしまう」「年貢が納入できない時は衣類を質に入れて工面するがこれでは質草にならない」などと理論整然と衣服の制限の不当性を述べている。そこには、「服の色」のことについては全く書かれておらず、ひたすら「自分たちは百姓と同じだ」「分け隔ては許せない」という強い意志を読み取ることができる。そのような中で、受諾を迫られた村々が出した嘆願書には、「特別の差別を仰せつけられましては、もう一同気落ちしてしまい、正月・盆や季節の祭礼、神仏の参詣のしようもなく、若者たちは何の生き甲斐もないと、農業も放り出してしまうほどの難渋で、はなはだ歎かわしいことだと思います」という一文が記載されている。一連の経過から、この嘆願書はおそらく当初に村々から持ち寄ったひとつであり、まとめる際に、この部分は割愛されたものと考えられる。一方で、「重宝記」に掲載されている嘆願書には、「(隣国には)当国の百姓とはちがって、とりわけ強情の者が多くいるので、すでに、穢多たちの三人や五人打ち殺しても、お上は気にかけないだろうなどと、時には心得違いの者がいて、このようなことを言っています。(略)この度、別途お触れで、百姓と分け隔ての扱いをなされては、(略)厄介を掛けることが、ときどきでるのではないかと、重ね重ね歎かわしいことだと存じます」という一文がある。つまり、「ひと目でわかる衣服にされては神社仏閣の参拝もできない」は本音であり、人々は禁令を破って百姓たちと同じように参拝していた。しかし、これを書くと逆にとがめられるために「殺傷事件が起こり困ることになる」との藩にとっても不利益であるという論理で嘆願書をまとめたと考えられる。また、先に述べたように、藍色は今日も「Japan blue」と呼ばれるように人々に好まれ、高価なものもあったことから、これが差別された人々の色とつれることで、百姓たちが避けるようになることも、想定できたのではないかと思われる。
○ 「服の色」について言及するのではなく、御触書を撤回させるための理由を論理立てるために、どれだけ人々が知恵を絞って書きまとめたかを明らかにするために、教材中で語られる思い(根拠)の論理性、正当性、説得力などの面から読み取らせ、作成された「嘆願書」について深く考えさせる。
(4) 訴えるしかないと立ち上がったこと
○ 知恵を絞り、村々の合意のもとで提出された嘆願書であったが、何の論議もなく突き返されることになり、ここから人々は、いよいよ「強訴の闘い」に入っていく。ここでも、人々が社会状況を見抜いて勝つためにいかに闘うかを考え抜いた姿を見ることができる。当時の岡山藩には六人の家老がいて月番で藩政を統括しており、倹約令を出したのは財政再建を進めていた岡山城の近くに陣屋をおく日置忠尚であった。一方、虫明に陣屋をおいていた伊木若狭は、尊皇派に近く日置とは政策上必ずしも一致していなかった。人々は、伊木が筆頭家老であったことに加えて、こうした藩権力内部の状況をとらえて、虫明への強訴を決断したと考えられる。したがって、地理的に見ると、中心となった神下村などは岡山城下にあるため城や日置の陣屋までは西方向に数㎞の距離であるが結集地点の八日市河原は西方向に12㎞、そこから虫明までは、さらに西方向に16㎞もある。このような藩内の対立や陣屋の位置関係も理解させたい。
○ 八日市河原に結集して以降の強訴の様子については、非武装で整然と、また毅然として行動し、ひとりの怪我人も出さなかったことを確認する。
○ 当時「別器、別火、別食」が当然とされていた中で、百姓の茶屋万次郎が人を雇って水を振る舞ったことは、前述の嘆願書を添削した目明かし、後に登場する助命嘆願を支援した百姓村の有力者とともに、百姓身分の人たちが一揆を支援していた証左として確認したい。
(5) 投獄された仲間を助け出した人びと *本時は視聴をカットするが、学び合いでは重要な内容である。
○ 厳しい取り調べと投獄
渋染一揆のリーダーたちの読みの通り、伊木若狭が「なぜ嘆願書を審議することもなく突き返したのか」と日置の直属の部下であった奉行の影浦勘助を問いただし、日置がとりなすという場を経て、結果的に取り消された。人々の願いはかない、一揆としてはここで終結するが、この闘いは、この後の「助命嘆願」まで含めての一連のものであるからこそ、いまなお犠牲となった人々が「若宮神」として大切に祀られているのである。その重要性を踏まえて、投獄された仲間を助け出した人々についても学ぶ必要性が考えられる。
○ 差別を強化、固定化する御触は取り消されたが、強訴に及んだとして、暴行を加えた厳しい取り調べがなされる。原典教材には、互いに「誰が呼びかけたか知らない」「誰が書いたかわからない」など、曖昧な供述で互いに守りあったことが記されているが、最終的に12名が「首謀者」として入牢を命じられた。また、彼ら以外に閉門(軟禁)の処分を命じられ生計が立たなくなった人々の様子や、働き手を失い困窮した残された家族を人々が支えたことも記されている。「入牢した者は赦免がむつかしく、永牢か死罪かに違いないと世間の噂であった」と記載されているとおり、入牢から4ヶ月後、笹岡村の栄蔵(54歳)、神下村の権十郎(70歳)が病死する。続いて、翌年の1月から5月までに、神下村の助右衛門(55歳)、卯左衛門(26歳)、忠左衛門(23歳)、惣吉(42歳) が相次いで病死する。(一方で、稲坪村の友吉(35歳)は5ヶ月後に釈放されているが理由は不明である。)
(6) 助命嘆願の闘い
○ こうした状況を受けて、神下村の安次郎は、懇意にしていた隣村の百姓の八郎左衛門に依頼して、池田家の菩提寺である曹源寺に赦免への協力を求めた。この二人は囲碁仲間であったと言われており、ここにも身分を越えた信頼関係があったことが読みとれるし、「赦免、助命」を求める方法として、藩主の菩提寺に依頼したことにも巧みさを見ることができる。一方、獄死者が次々と出る中、残りの入牢者の様子について尋ねられた牢役人の「半死半生の躰」「同人等程恐入たる者なし(彼らほどきまりをしっかり守っている者はいない)」と答えを受けて、牢内で書き役を勤めていた良平と弥市が嘆願書を書きまとめて提出した。こうした牢内外の働きかけによって、5名が赦免となった。なお、「難訴記」には、良平と弥市の釈放を知った人々は、翌朝、駕を出して迎えに行き、帰村する道筋には、「四カ村の人々が続き、往来は人々であふれた」と記されている。
(7) 引き継がれている思い
○ 笹岡村の良平の墓碑と神下村の若宮神
良平の碑文を記した岡崎熊吉は甥にあたり、1902年8月(明治35年)三好伊平次らとともに中心となって「備作平民会」を創立し、その後は全国水平社創立大会にも参加するなど、部落差別の撤廃に向けて闘い続けた人物である。釈放されたものの歩くことも困難であった良平は、約一年後に亡くなるが、その43年後、「差別を許さない」と立ち上がった良平たちの意志は、熊吉たちに引き継がれ再び、岡山県での闘いへとつながっていった。
○ 若宮神は、最も多くの犠牲者を出した神下村の権十郎、助右衛門、卯左衛門、忠左衛門、惣吉を祀った碑で、区画整備で集められた地蔵尊、八幡宮の真ん中におかれている。いまもなお、「村の守り神」として大切にされている思いを地元の方が語ってくださっている。
○ 「禁服訟歎難訴記」の「人は死んでも名前を天下に残す」という文章の中の「人」は、個々人の固有名詞ではなく、「人としての尊厳をかけて差別と闘った人たち」であると捉えたい。その生き様を学んだ私たちはどうあるべきかを生徒と共に深めていきたい。
【参考とした資料】
渋染一揆を闘いぬいた人々(東映:シリーズ影像でみる人権の歴史第5巻)解説2017
岡山市『渋染一揆資料館研修資料』2014 版
外川正明『部落史に学ぶ』解放出版社 2001、『部落史に学ぶ2』解放出版社 2006
岡山県人権教育研究協議会『岡山からの人権教育 「渋染一揆」学習素材集』2012
柴田一『渋染一揆論』明石書店 1995
☆78日目(6.5)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業4
7 本時の展開
(続く)
☆77日目(6.4)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業3
4 準備物 パソコン モニター ワークシート
5 計画 第1時 社会科 幕府の政治改革 渋染一揆
(教材 渋染一揆に学ぼうワークシート 岡山県教職員組合教育運動推進センター)
第2時 道徳 本時
第3時 学級活動 渋染一揆から学んだこと~自分を見つめ、語り合う~
・渋染一揆の学習をとおして、もっとも印象に残った渋染一揆の場面(場景)をとりあげる。そしてその絵の中には自分の姿を描き、「何と言っているのか」を書き込む。
・同じ場面を選んだ者どうしで、グループをつくり、「なぜこの場面を描いたのか」をテーマに話し合う。話し合われた内容を学級で共有する。「なぜこの場面を描いたのか」を語ることは、渋染一揆そのものを語ることではなく、そこに重なる「わたし」を語ることとなる。「わたしをひらく」ことにより、互いに「仲間(学年)とつながっている」という実感をもたせる。
6 本時のねらい
渋染一揆の学習を通して、正義と公正さを重んじ、人権を守り、集団生活を充実させることで、差別や偏見のない社会の実現に努めようとする実践意欲を高める。
☆76日目(6.1)ふりかえりのシートと仲間づくり一考
指導案の紹介の途中ですが、本日、体育会を終えて時、どのようなふりかえりをするか?が話題になりました。作文用紙は用途がちがうので‚使わない方がよいですね。
子ども集団の4月からこれまでの「綴る」取組の中で、ふりかえる項目や、意識させる観点などを踏まえ、「綴る」時間をしっかりと確保せねばなりませんね。出来たら、週明け1時間目。しっかりと「うったて」をすると、生徒ら「綴り」ます。鉛筆の音だけが教室に響く時間となります。だって、「綴りたい」ことが一杯あり、伝えたいことが一杯あり、「綴る」ことは自分にとって有意義でることを体感していあるからね。
ワークシートで「振り返った」内容は、学級通信、学年通信、学年集会、ブロック会に「還す」ことも重要となります。(「還す」取組についてはまたの機会に。)
体育会振り返りシート1 体育会振り返りシート2 合唱祭振り返りシート 3年 2学期振り返りシート 1年 2学期振り返りシート
ヒロシマ研修振り返りシート
☆75日目(5.31)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業2
(4) 教材観
① 本教材の渋染一揆とは、1856年、岡山(備前)藩53か村の被差別身分(かわた)の人々が差別法令(「別段御触書」)の差別性に気づき、民主的戦略をもとにこれを空文化させた闘いである。渋染一揆が成功した要因としては〈ア〉「百姓」としての誇り(=人間としての誇り)、〈イ〉かしこさ、したたかさ(=学問の重要性)、〈ウ〉自治力・団結力(=連帯の重要性)、〈エ〉人間による、人間を取り返す行動(=行動の重要性)など多くの道徳的価値につながる事由があげられる。そして、渋染一揆を深く学ぶ学習を通して、今を生きる私たち自身の課題に向き合い、差別に「気づく」、差別に「怒る」、差別解消に向けた「学習」を積み重ねる、ともに行動する「仲間」を増やす、そして「行動」する一連の≪いじめ解消のモデル≫を学び取ることができる。渋染一揆の中に出てくる人々の願いと行動から、自分自身の課題を見つめ、自分たち自身でよりよい学校生活をつくっていくという意識を高めることに適した教材である。
② 本教材は、社会科での「武士政治の終わり」や「新しい時代への動き」あるいは「天保の改革」の学習を深めるものであるが、直接的には、小・中学校教科書で「武士の政治に苦しんできた人々が各地で一揆や打ち壊しを起こした」ことを具体的に学ぶ例として取り上げられている「渋染一揆」について学ぶ教材である。中学校社会科教科書(東京書籍)には「財政難に苦しんでいた岡山藩は、1855年、領内に29か条の倹約令を出しました。その中には、えた身分だけに出された命令があり、衣類を渋染か藍染に限るなど、百姓と別あつかいにするものでした。かれらは農業も行い、年貢も納めているのに、このような差別は我慢できないと、領内53か村が嘆願書を出しました。そのうち約半分の村から千数百人が立ち上がり、藩の役人と交渉し、ついに嘆願書を受理させました。このため、藩は倹約令を実施しませんでした。」と記されており、さらに倹約令の概要も記載されている。本教材では、こうした記載をさらに深めるために、「嘆願の闘い」「強訴の闘い」「助命の闘い」という一揆の経過からを丁寧に追っている。
また、本教材は、多様な学習の可能性が考えられ、道徳科の内容項目の指導の観点の中の、「A主として自分自身に関すること」の〔希望と勇気、克己と強い意志〕〔真理の探究、創造〕として示された項目や、「C主として集団や社会との関わりに関すること」の〔公平、公正、社会正義〕として示された項目、「D主として生命や自然や崇高なものとのかかわりに関すること」の〔生命の尊さ〕〔よりよく生きる喜び〕として示された項目、「B主として人との関わりに関すること」の〔信頼や友情〕や〔相互理解、寛容〕として示された項目において、その道徳的価値にせまることができると考えられる。その中から、本時は〔公平、公正、社会正義〕という道徳的価値に関わって、「中学校解説編」に、「よりよい社会を実現するためには正義と公正さを重んじる精神が不可欠であり、物事の是非を見極めて、誰に対しても公平に接し続けようとすることが必要となる。また、法やきまりに反すると同様に、自他の不公正に気付き、それを許さないという断固とした姿勢と力を合わせて積極的に差別や偏見をなくす努力が重要である」と述べられていることを鑑み学習を展開する。
③ 社会科における道徳教育との関連
「中学校学習指導要領社会科」の〔歴史的分野〕の4点の目標の中に示された内容項目の「(4)近世の日本」の「エ 社会の変動や欧米諸国の接近、幕府の政治改革、新しい学問・思想の動きなどを通して、幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを理解させる」に位置づけた学習であり、「同解説編」では、「この中項目のねらいは、幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを、次の各事項の学習を通して理解させることである」として、「社会の変動や欧米諸国の接近」「幕府の政治改革」「新しい学問・思想の動き」の三つに分け、「内容の取り扱い」として、「『幕府の政治改革』については、百姓一揆などに結び付く農村の変化や商業の発達などへの対応という観点から、代表的な事例を取り上げるようにすること」と記している。こうした社会科学習の目標に沿って、岡山藩で起こった『渋染一揆』を『代表的人物や事例』として取り上げ、「幕府の政治改革」について学び「幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを理解させる」ことと関連している。
④ 特別活動との関連
「中学校解説編」では、「イ自己及び他者の個性の理解と尊重」において、「自己の個性を見つめ、それを大切にしていくことは、自尊感情を高め、自己確立や自己実現を図るための基盤となる。また、他者の個性を理解し互いに尊重し合うことは、自己理解を一層深めるとともに、豊かな人間関係をはぐくんでいくことにつながる。」として、「自己及び他者の個性を理解し尊重していくことは重要な意味をもっている。」ことから、具体的な例として、「他者の生き方に学ばせるなどの活動」を指摘している。「人権を尊重する態度」や「学ぶことや生きることの意義」を考える上で、歴史上の人物の生き方を取りあげ、特に他者を尊重する姿勢や、学ぶことの意義について考える本学習は、指導の効果を高める。第2学年では進路学習として、「仕事」「生き方」についての聴き取り学習や、岡山チャレンジ・ワーク14『職場体験活動』の取り組みを通して、生徒自身が自分らしい生き方(進路実現)を目指して、働くことや職業について理解を深めてきた。
(5) 指導観
モデル・グループの学び合いを参考に、自分ができることは何かを「話し合う」場面において、そう考える理由を丁寧に語らせたい。モデル・グループ学習では授業者はファシリテーターとして、学習者の意見をつなぐことを重視する。意見をつなぐとは、授業者の発問に学習者が答えるだけでなく、その発言を他の学習者に広げ、深めていくことを指しており、本時においては、渋染一揆を多面的・多角的に捉えるので、たくさんの意見がでると考えられるが、他者の意見を聞き、その意見を取り入れ、思考しながら次の発言につながるような学び合いが進むように指導・支援していく。
第1時では、教材の内容(史実)をしっかり受けとめさせる。第2時(本時)で、その学習を深め、ねらいとする道徳的価値を自分たちの身近な生活の中に見いださせることで、生徒たちがより主体的な態度で、道徳的な問題を発見し、その解決策を考えていくことをファシリテートしていく。(続く)
☆74日目(5.30)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業
1 主題名 差別や偏見のない社会 公正、公平、社会正義
正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること
2 教材名 渋染一揆を闘いぬいた人々
(東映:シリーズ映像でみる人権の歴史第5巻)
(渋染一揆に学ぼうワークシート(岡山県教職員組合教育運動推進センター))
3 主題設定の理由
(1) 研究主題との関連について本校は本年度、研究主題「道徳のねらいを達成するための効果的で多様な授業実践」を設定し、協働学習を取り入れた授業実践を中心に研修を進めている。グループに分かれての協働学習では、主発問(テーマ・課題)設定が適切か、また発問に応じて学び合った内容が、主体的で対話的・深い学びになっているのかという課題について議論してきた。そこで、道徳の従来の形である教材を読み、主人公の心情やその変化に気づかせていくというパッシブ・ラーニング的な授業展開から離れ、モデル・グループ学習を取り入れることによって、協働的に学び合う議論が深まるのではないかと考えた。
(2) 主題観
「正義を重んじ」るということは、正しいと信じることを自ら積極的に実践できるように努めることであり、「公平さを重んじ」るということは、私心にとらわれたり偏見をもって事実をゆがめたりすることを避けるように努めることである。力を合わせて公正な、正義のとおるよりよい学年集団にしていこうという気持ちを持たせたい。
(3) 生徒観
本学年の生徒は、穏やかで仲間同士のトラブルも少ない。しかしながら、教育的課題を抱えている生徒(家庭)も少なくなく、困ったことを語り合える人間関係が育つまでには至っていない。社会的立場自覚(自己認知・社会的自立)を進めていく中で、自己肯定感(ありのままの自分)を高めていくには、きちんと語り合える学年集団づくりをさらに進める必要がある。そのためには、自己中心的な考え方から脱却して、公のことと自分のこととの関わりや社会の中における自分の立場に目を向け、社会をよりよくしていこうとする気持ちを大切にする必要がある。また、「見て見ぬふりをする」とか、「避けて通る」という消極的な立場ではなく、不正を憎み、不正な言動を断固として否定するほどの、たくましい態度が育つように指導することが大切である。さらに、この世の中から、あらゆる差別や偏見をなくすように努力し、望ましい社会の理想を掲げ、正義がとおり、公平で公正な社会の実現に積極的に努めることが大切だと認識させる必要がある。(続く)
☆73日目(5.29)仲間づくりをめざす「カレー」の授業 案1
《聴く つなぐ もどす》授業をめざした協同(グループでの学び)学習を取り入れた参考授業を自主公開します。(社会科授業デザインとして提示)
1 テーマ 歴史を学ぶ意義と、なかまと共に学ぶ大切さを学ぶ
2 ねらい
(1)これから授業をすすめていくにあたり、現在の子どもたちの「現実」、「学び」への意識や、集団としての「風土」を見立てる。それをもとに今後の授業展開の中での《つなぐ》ありかたを探る。
(2)「自己開示は楽しい」「共に学ぶことは意味がある」ことを実感させる。
(3)「会科は暗記の教科」という言い方も聞かれるが、決してそうではなく、これまでの私たちの生き方(歴史)を振り返り、これから私たちの生活・社会がどうあるべきかを考え、なかまと共に自己実現を図り、人権を守り、反差別・共生の社会(世の中)を創っていくという市民性を培う基礎となる教科と考える。そこで様々な学習活動を取り入れ経験・体験する中でその資質を育てていく一助とする。
3 材料
・カレーから戦後を考えてみよう(資料集ビジュアル公民2012) ホワイトボードペン 歴史資料集
4 指導の流れ
(1)確認テストの勉強→ 確認テスト
(2)授業の目標(歴史の見方について)の確認
(3)協同学習・カレーに何を入れる??
・カレーの歴史からワークシートで時代を読み取る 〈基礎〉
・現代のカレーについて考える〈ジャンプ課題?〉
5 教室の配置 4人グループを活用
6 宿泊研修に連動させる
☆72日目(5.28)仲間づくりとしての生活指導2
演習2・3については、これまで、いろんな人と話題にしましたが、多様で興味深いアプローチが考えられました。人権教育や仲間づくりの視座では、個別の支援にとどまらず、「誰のために」、「クラス」・「学年集団」への積極的なアプローチがポイントになりますね。以下の演習3はどうでしょう??
演習3
☆71日目(5.27)仲間づくりとしての生活指導
今日から教育実習生が、三週間、教育最前線で「教師としての学び」を深めていきます。私たちも全力で応援します。今日は、「教育公務員としての心得」について研修をしましたが、担任として、具体的な生活指導の場面を想定した演習を時間を持ちました。演習は以下の2つ。
○演習1
:手すりに落書きがあることを生徒が言ってきました。各クラスで担任が指導し、申し出るように呼びかけましたが、誰も出てきません。
○演習2
:不登校傾向の中学生のナナさん(1A)が病院を受診し、「起立性調節障害」と診断されました。お母さんとナナさん本人は、「クラスのみんなに、このことを知ってほしい」と担任に話しました。
☆70日目(5.24)学級通信の中の仲間づくり
体育会が近くなり、学級通信(学級活動資料)の活用もいろいろ考えられますね。若い先生方と話してみたら、たね(ねた)、アイデアがいっぱい出ます。
○体育会リーダーからクラスのみんなへメッセージ
○学級日誌の記録・つぶやき
○種目練習の工夫や作戦(インターネットでの結構あります。大縄跳び つなひき バトンパス 玉入れ・・・)クラスの㊙作戦用紙として。
○応援ボードの下書き案㊙
○小道具(応援グッズ)づくり募集のお知らせ→保護者やお家の人に協力してもらう。そして子どもたちが取り組んでいることを知ってもらえるアイテムですね。
○班ノートの一節
○体育会当日までの天気予想(気象庁&クラスの担当生徒)
○写真(黒板の作戦会議メモ、練習でこけたAくんの絆創膏、汚れたくつ)
☆69日目(5.23)自立支援?自立応援?適応指導の目的を。
・・・校内でのサードプレイスのあり方を検討しています。
サードプレイスという言葉は、アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した考え方である。著書『The Great Good Place』(1989)のなかで、「家庭や職場での役割から解放され、一個人としてくつろげる場」としてサードプレイスを位置づけました。利害関係のないコミュニティを謳歌し、様々なストレスを抱える現代社会のなかでも、ゆったりと過ごす時間を得ることが重要だとしています。
サードプレイスの基本的な定義
サードプレイスは、自由で開かれた「とびきり心地の良い場所(原題の通り“The Great Good Place”)」を指します。オルデンバーグは著書の中で「インフォーマルな公共生活の中核的環境」という定義もしています。義務や必要性に縛られることなくリラックスして過ごせる場所であり、後述するファーストプレイス・セカンドプレイスがある程度「役割」や「追うべき責務」が決められた組織であるのに対し、サードプレイスは気ままに自分の気持ちに応じて選択できる場所のことを言う。カフェや図書館、また地域活動等のコミュニティ(場所的な実態がないもの)も該当するとされています。
岡山御津高校で事業を進めている一般社団法人ぐるーん(岡山市北区下伊福西町 7-32-309)は、「~事業を始めるにあたって~」に以下の内容があります。
〈さまざまな家庭背景や課題を抱える生徒に対して、教員だけではなく、より多様な地域の大人による関わりやサポートが必要とされているというお話を高校の教員から聞いた。当団体はこれまで社会的養護の必要な子どもたちへの支援を中心に活動してきたが、社会的養護に至る前の段階で困難を抱える子どもと関わり、支援を届ける必要性を感じていたことから、他県で行われている居場所カフェを始めることにした。手作りの料理やワークショップの体験を提供し、健康面と精神面のサポート、安心できる空間、多様な体験の機会を提供することで、高校生の学校生活や大人への信頼感構築に寄与したいと考えた。〉
新見市立思誠小学校の学校だよりでは
〈ステップ教室(自立応援室)を開設しました
心の居場所推進プロジェクトが令和元年よりスタートし、今年度は県内の11小学校、33中学校が研究校として指定されて「自立応援室」を開設しています。本校におきましても、今年度の目標3本柱の一つ、不登校対策の取組の一つとして、第2学期から「ステップ教室」と命名し、自立応援室を開設することにしました。
自立応援室の目的は
・不登校から学校へのステップとして
・不登校にならないための一時避難の場所として
・教室に入るための心の準備を行う場所として
機能することです。特別教室棟の2階、旧パソコンルームが「ステップ教室」として生まれ変わりました。保護者の方からの希望をもとに、利用できるよう手続きを進めていきます。常に教員が1名待機して、指導支援にあたることができるようにし、児童一人一人の思いが反映される柔軟な教室運営を目指していきます
岡山K中学校自立応援室『Kルーム』については、
〈木之子中学校自立応援室『Kルーム』について、お知らせします。
〇自立応援室について
長期欠席・不登校対策の専用教室のことです。本校では、『きのこルーム』とよびます。専属教員により、個々の生徒の状況に応じた学習支援・生活支援を行い、学校(教室)への復帰を目指すと共に一時避難等により長期欠席・不登校の未然防止に努めます。
〇対応について
専属教員の本校での勤務を、月・水・金を基本とします。他の曜日は、兼務校での勤務となります。火・木は他の支援員等での対応となります。担任とも連携を図ります。
〇自立応援室『Kルーム』からのお知らせ
(別添)の自立応援室からのおしらせ「Kルームについて」をご覧いただき、ご相談等ありましたら、本校までご連絡ください。
子どもたちにとって、学校・地域にとって意味あるサードプレイスを考えていきたいと思いますが、もうひとつ、重要ことは、この取組が必要となってきた社会背景や社会的課題が何なのかを見定めて、根本解決に向けたうごきやアプローチも必要であることを忘れてはならないと思います。
☆68日目(5.22)人権学習の内実を確かなものに
2023年に教育運動推進センター「教育おかやま」でまとめたものの一部です。
私たちが生きていく社会を私たちがつくっていくために
⒈自分自身が学び合う仲間と場をもつこと
⒉「教育改革」渦の中、大切な根幹を見据えること
⒊社会とつながる教育運動をめざすこと
1 最初に
私は、互いの教育実践を語り合い、教育実践を高める職場を大事にしています。 同時に、学校外での学ぶ機会や場に参加して自分の取組を振り返り、授業改善に役立ててきました。例えば、それは、東備学ぶ会などです。その会でも、最近は上記の⒈~⒊のテーマが話題になります。その中で,私たちは、「出来ることを足元からやっていく」べく、いくつかの取組を進めてきました。
2 全ての教育実践の〈基盤となる人権教育〉の内実を豊かに するための〈東備学ぶ会〉は12年目に。
「思いやりの気持ちを高めたり、啓発映画を観させ、人権標語をつくる」「個別の人権問題をいくつか授業で教えること」「専門的な事なので分掌や社会科担当に任せる」等の、人権教育に対するありがちなイメージを払拭するために、「学び直し」しようと始めたのが〈東備学ぶ会〉です。きっかけは、2012年の第64回全国人権・同和教育研究大会(岡山大会)での教育実践に触れたミドル世代の先生たちの「熱」でした。「同和教育」という名称が、「人権教育」となって月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを会の原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)など問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ね、大きな成果をあげてきました。その中で確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教師・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、まさしく今日の教育課題の解決へ向けて≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。
例えば、[定例学習会〕の1月の案内文にはこうあります。
《「子ども・学校・担任」に必要な「仲間づくり」の力をみがこう!
・・・「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。「仲間づくり」は、このような目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。いくつかのポイントがあります。
ひとつは〈子どもの生活背景をつかむこと〉・・・すべての教育活動は、子どもの姿、子どもを取り巻く現実から出発することが大切です。気になる言動を見せる子どもがどんなことを考え、どんな思いでいるのか、どんなくらしのなかで生活し、学校に通っているのか、保護者はどんな願いをかけて子育てをしているのか。そうしたことの中に、その子どもが抱えさせられている課題を解決するための、取組のヒントがあります。子どもの生活背景をつかむためには、家庭訪問等の取組を通じて、くらしや思い・願いなどについて対話できる関係を、子どもや保護者と築くことが必要です。また、〈弱い立場に立たされている子どもを中心に据えて取り組むこと〉〈一人ひとりが生活のなかで感じている不安や悩みを共有し、ともに乗り越えようとする集団づくりをめざすこと〉〈個別的な人権(課題)問題についての学習と結びつけて取り組むこと〉などのポイントが挙げられます。
他にも、人権教育の取組において、有効性が確かめられてきたいくつかの手法(「つづる」「語る」「聴き合う」)もあります。(松下一世さん:『子どもの心がひらく人権教育』より参照)
このようなポイントや手法は、現在ちまたにあふれる新しい教育改革理論やスキル、メソッド等の中で語られる内容と重なっています。1960年代から教育現場の私たち教職員が生み出した人権(同和)教育は、実践力を磨きます。多忙な毎日ですが、子どもたちの〈豊かなそだち〉のために一緒に語り合いましょう。》と呼びかけています。
次回は6/22(土)13:30~16:00。「ハンセン病問題学習」の小学校実践報告です。
☆67日目(5.21)エリアティチャーとの出会いをどう創るか?
先週、津波を想定した避難訓練の一環として、裏山に避難した際に、お招きしたエリアティーチャー(以下AT)さんは「本当に避難が必要な時には、今日通った道路はおそらく通れないだろう」と話をされました。ドナーカードを扱った授業時にATして来校された臓器提供コーディネーターさんは、「ドナーカードを使わない人生を歩んでください」と話されました。豊かな経験から語られるコトバ(真性の学び)がもつ力は本当にすごいと思います。いつもATさんをお招きする時には、事前の打ち合わせ(授業者の願い、生徒の実態・課題、めざすこと、そしてATさんの想いをしっかり聞くこと)をして、授業のコーディネート、状況に応じてファシリテートの準備をします。
そして、ATからのお話や提起は、子どもたちにとって「衝撃的」なことや、「刺激的」なインパクトを与えようとするのは考えなくてはなりません。以前、先輩に以下のメッセージをいただきました。「何を伝えたい 何を問いかけたい そして、自分はなぜ、ハンセン病問題にこだ わるのかを明確にすることがもっとも大切なことだ。趣旨・目的のない企画は「被差別の当事者」を利用するだけです。私はそんな企画には賛同できません。」私の教育実践がそうだったのでしょう。自分の立ち位置が問われてきます。ATさんの想いや願いをまず、「私」がどうとらえて授業をつくっていくかを大切にしたいと思います。

☆66日目(5.20)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き④
13.終わりに
最後になりますけれども,偏見・差別,これから皆さんもまだまだ学習されると思いますけれども,さっきも言いましたように,日本にはまだまだいろんな差別があります。偏見もあります。でもね,偏見・差別というのは,本当のことを知らないためにおきる場合が非常に多いんですね。大方,そうじゃないでしょうか。偏見・差別があるような世の中なんて,不幸な社会,決して幸せな社会じゃないと私は思う。
自分らしく生きるためには,やはり,差別のない社会がいると思いますね。もし,皆さんが大きくなって,偏見・差別のような事例に遭遇した場合,その背景にあるもの,偏見・差別の実態と言うんでしょうか,本当のことを知るということ,そのことをちょっと考えてもらえば,「何だ,こういうことだったのか,大したことじゃないじゃないか。」というふうに思い当たることが多くあるんですね。だから,「正しく知る」ということ,このことこそ,偏見・差別をなくしていく近道だろうと思います。
どうか一つ皆さん,今日の皆さんにしたお話をどうか少し他の方にしていただいて,これから皆さん共々,偏見・差別のない,そういう社会作りに,お互い力を尽くしていきたいなあと思います。どうかよろしくお願いします。
どうも皆さん,長時間,本当にありがとうございました。
☆65日目(5.17)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き⑤
⑤ 長島愛生園では毎日どのようなことをしていたのか。
答 愛生園は国立療養所だから,炊事場 ~ 給食部 ~ から,食事が部屋に届けられる。朝7時10分頃に朝食が届けられる。今は自治会の仕事をやめているので,本を読んだり,ぶらぶらして時間を過ごす。医局に行くこともある。あっという間に時間が過ぎるが,退屈だと思ったことは今までない。12時が昼食。職員が5時に帰らないといけないので,4時30分頃に夕食が配食される。私も含め,大部分の人はこの時に食事をすます。
愛生園の入園者の半分は,不自由な生活をしている不自由者なので,職員が生活介護をして,食事の世話もしている。 後は自由時間。外へ行く場合もある。私も外に行くことが多い。パチンコに行く人もいれば,それぞれである。同じ国立療養所にいても,一人ひとりの生活パターンは違う。宗教に熱心な人もいるし,短歌・俳句・詩等の文芸に一生懸命になっている人もいる。
⑥ 愛生園に強制隔離されていた時に,うれしかったことや楽しかったことは一度もなかったのか。
答 悲しかったことは,先ほど話をしたように,妻が亡くなるときに出られなかったことだ。その他にも,園内で再婚した妻が今から15年前にあっという間に亡くなった。3月1日に心筋梗塞をおこして,3日で亡くなったこともつらかったことだ。つらかったことはたくさんあったと思うが,いつの間にか,つらかったことを忘れてしまった。その時々にはつらかったことはあったと思う。一晩で足が下がり,手が下がり,喉頭麻痺を起こした時は,本当に毎晩自殺をしようと思ったこともある。今はつらかったことが何か遠い昔のことのように思えて,忘れたというか,「浄化」されたというか,浄められてなくなったような感じである。うれしかったこともたくさんあったと思う。全部のうれしかったことの 中で橋が架かったこと,これはうれしかった。橋がかかって,まだ12年位 だが,架かる前
は船で通っていた。橋ができてから非常に便利になったこともあるが,精神的に自分の気持ちの上で,「島流しにされていない」という安心感があった。時間制でなく自由に帰れる。そういう利便性。それから,今まで島の中に閉じこめられての「島流し」というものが,今は,陸続きになってなくなった。いろんな人が,遠くから働きに来ている。橋がないときはあまり遠いところからは職員が来ていなかった。でも今は,橋があるので,一時間ぐらい自動車でかかっても,愛生園に働きに来ている。ということで,橋が架かったことも,大きな喜びだった。「予防法」が無くなった,このことも大きかったし,さっき言ったように裁判をして勝ったことも,忘れられない感動すべき事だ。
⑦ ハンセン病の人たちが病気がうつらないのがわかっていたのに,すぐに法律をなくさないで,数年たってから法律で隔離がなくなったことについてどう思っているか。
答 「予防法」がもっと早くになくなっていたら,たぶん社会復帰する人がたくさんいたことは間違いない。ところが,5年前に,「予防法」がなくなったときには,もう私たちは年をとりすぎていた。その頃,70歳位の平均年齢だったと思う。なぜ,「予防法」が長く続いていたかということだが,これは,国というのは一旦,法律を作るとなかなか廃止するということはない。部分的に直すことはあっても,廃止してしまうということは難しいことのようだ。たとえ,その「予防法」が現実に矛盾をはらんでいても,完全に廃止することはなかなか難しい。私たちも「廃止」という運動は実はしなかった。「改正」運動をずっとしてきた。強制収容できるような法律は,時代錯誤だ。時代に合わないことだから,「予防法」を「改正してくれ。」ということも何回も運動した。ところが,強制収容の条項は残したまま,国は言った。「強制収容をはずしてしまえば,『らい予防法』は体をなさない。」と。どこの国も,こんな「予防法」はなくなっていたが,日本だけが,明治40年に作られた「らい予防法」を90年近く堅持してきた。私たちも,もっともっと強く「廃止」の運動をしていたら,あるいはどうなっていたろうか,という思いもある。しかし,予防法を「廃止」というところまでは,踏み切れなかった。というのは,「予防法」をなくした後,いったいどうなるのか,療養所はどうなるのか。「予防法」という法律があるから,療養所があって,そこで療養できるのに「予防法」をなくした場合,その先が見えない。だから,「廃止」運動がなされなかったということも,あるいは原因かもしれない。でも,大谷藤郎という厚生省の元事務局長であった方が,「やはり,『予防法』はなくすべきだ。」という意見を出した。それで火がついて,かぜん私たちの全患協(全国ハンセン病患者協議会)という組織も「廃止」の方向に踏み切って運動をしてきた。そして,今から5年前,1996年4月1日から「予防法」はなくなった。もうちょっと,少なくとも30年前になくなっていたら,ずいぶん多くの人が社会復帰していたのではないか。「予防法」がなくなった時に,「さあ,皆さん『予防法』がなくなったから帰りなさい。」,こう言ったって,年をとっているし,外での生活ができないとなると,法がなくなったからといって,そうそう社会復帰した人はいない。それでも,全国で20人近くの人が社会復帰したが,だんだん年をとってきて一層社会復帰は難しい。「予防法」がなくなった時,新しい法律の中で,私たちは,従来通り療養所の中で引き続き療養を続けることになった。これから,ハンセン病療養所はいつまで存在するだろうか。まあ,そう長い間存在することはないと思う。平均年齢が75歳なので,あと20年もすれば,療養所の中,何人残るだろうか。そうはたくさん残らないと思う。もう,目の前にそういう時代が来ている。
☆64日目(5.16)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き④
あと残る時間が30分位しかありませんので,これからは,皆さんの質問を受けて,お話ししたいと思います。
12.質疑応答(質問者・金さん共にていねいな言葉遣いでしたが,常体で表記します。)
① 1960年に社会復帰したのに,1965年に愛生園に戻ったのはどうしてか。
答 療養所内で再婚をしていたが,二人で社会復帰することにはいろいろ困 難があったので,一人で社会復帰をしていた。小さな工場の事務員として まじめに仕事をしていたが,妻から早く帰ってきてくれと何回も言ってき たのも無視できなかった。それから,外にいて,けがが心配ということもあった。強いて言うならば,外の競争社会におけるいろいろな圧力に負けたのかな,とも思う。でも多くのことを学んだとても貴重な期間だった。
② 日本に来たときの気持ちが知りたい。
答 私は1926年に韓国で生まれたが,私が生まれたその当時は,私たちの国,朝鮮国は日本が支配していた。いわゆる植民地として統治されていた時代。私の故郷にあった小学校 ~ 小学校4年を終えて日本に来たが ~ 学校で教わる勉強は全部日本語の教科書。週に1時間だけ,自分たちの国の言葉,朝鮮語を習った。でも,家に帰れば,みんな朝鮮語。生活は朝鮮語だった。そのかわり,学校に一歩入ったら朝鮮語はいっさいだめ。日本語を使った。だから,日本に来た時は,子どもの言葉だけれども,言葉で苦労はしなかった。日本の子どもと同じくらいの言葉の力はあった。小学校5年生に入った。昭和13年1月に日本に来たが,その前年には,日本は中国大陸に侵略を開始して,中日戦争が始まっていた。その頃は,日本人は先勝ムードにあふれていた。提灯行列を毎晩のようにしていた。私も親に連れられて,参加したこともある。私も子どもだから,いつの間にか日本のいわゆる軍国主義にそまって,いつか日本の軍人になりたいと思うようになった。日本の少年よりも,もっと軍国少年になっていったような気がする。「俺は陸軍大将になるんだ。」という将来の夢を持っていた。ところが,大きくなると陸軍大将になれるはずがないとわかってきた。中学校に入ってから,学校でも軍事教練ばかりしていた時代だった。その後,友人に「神奈川の兵器学校だったら最前線に行かずに,兵站部隊で済む。退官したら,技師になることができる。だから一緒に行こう。」と誘われて,昭和19年,1944年に神奈川県の陸軍兵器学校に入った。これまで,この話,~ 日本の軍人になっていた ~ なんて話はあまりしたくなかった。しかし,数年前にどこかでこの話をした時に,話題性があったので,言ってもいいことかなと思い,自己紹介の文に書くようにした。日本に来たときに,日本の軍国時代のまっただ中だった。祖国の朝鮮は植民地であったが,提灯行列をするほどの軍国主義ではなかったから,びっくりした思いがある。
③ 「らい予防法」によって,商売をやめさせられたり,家族から引き離さ れたりした時にどんな気持ちだったか。
答 どの患者も共通だと思うが,病気になると,病気になった自分が悪いんだと思うところがある。そういうことから,ある種のあきらめ,しかたがないというふうにあきらめることがある。もちろん家族と引き離され,私の場合は妻が私が入っている間に死んでしまう。たいへんこれは,本当に悲しいことだけれども。私の場合で言うと,妻が亡くなってから自分を大分責めた。病気である自分と結婚していなければ,彼女は死ななかっんじゃないか。病気になった自分が悪いんだ,悪かったんだという自分を責める気持ちが,ずっとあった。本当に妻には申し訳ないことをしたということを今でも思っている。家族と引き離されることはつらい。ここで横道にそれるが,ハンセン病になったら,なった病人だけが社会におれなくなるように排除されたり,差別を受けたりしていることだけではない。病気になった本人だけではない。その家族,家族も非常に社会から排除された。偏見を受けたりもしている。家族にハンセン病が出た。そのために一家全員で心中したという例もある。そうしてみると,病気になった本人だけではなくて,家族もろとも,偏見・差別を受けた。被害を受けた。ここのところを覚えておいてほしいなと思う。なぜ,日本では,このようにただ病気になっただけなのに,それほど社会から排除されたり,いろんな偏見を受けなければならなかったのか。これは,おそらくどの国を見まわしても,日本ほどではない。日本は特に偏見が強い。これは,ハンセン病だけではない。いろんなことに対してある。 いつ,自分が偏見・差別を受ける立場になるかわからない。 質問からそれたが,今,愛生園でもどこでもそうだが,多くの方が自分の本名でない偽名を使っている。なぜ,偽名を使うか,愛生園でも半分以上が偽名を使っている。これは,外にいる自分の家族を守るためだ。もし,自分が長島愛生園に入っていることが知れて,家族に迷惑をかけてはいけない。そのために自分というものを押し殺して,名前を変えている。まだまだ,この状態は変わらない。「らい予防法」がなくなった今でも変わらない。でも,少しずつ,「らい予防法」がなくなったころから,自分たち自らが変わらなければいけないという空気も生まれているが,なかなか自分の本名を名乗るということがない。
④ 講演をしていてやりがいがあったと思ったできごとは何か。
答 私の今の「生きがいは」と問われれば,社会復帰は難しいけれども,こういうふうに,外へ出て皆さんと直接いろんな話ができる。私たちの側からすれば,啓発するための運動 ~ 啓発活動といってもいいと思うが ~をすることが,今の私の「生きがい」だと思っている。いろんな人と会って,またいろんな出会いがあって,そこからまた,いろんな始まりがおきる。ということで,講演活動は私にとって,「生きがい」のあることだと思っている。今から10年ほど前,神戸で校長先生の集まりで,「貧しい国ほどハンセン病は発生する。貧しいと子どもが栄養が足りないために,『菌』に対する免疫力がない。貧しい国ほど子どもたちに免疫力がない。私たちの国も当時非常に貧しかった。私は農家の生まれだが,特に農村地帯は疲弊していた。もし,私の国が貧しくなくて,植民地にされていなかったら,病気になってなかったんじゃないかという思いはある。私の父方にも母方にも誰もこの病気にかかった人はいない。なぜ,どこでこの病気になったのか,なかなかはっきりとわからないが,小さい時に,この病気の人が村に食事をもらいに来ていた。相当に病気の進ん方もいた。袋の中にごはんを入れるのだが,私の家の門の前に来たときには,私がその役目を長い間していた。はっきりはしないが,その時にうつったのかも知れない。だから,ハンセン病は貧困病であり,植民地病だと言ってもいいと思う。」と話をした。その後で,ある校長先生が私に「金さんは,もし日本が金さんの国を植民地にしなかったら,金さんはこの病気にかかってなかったと私は思います。」 と言ってくれた。これはとてもうれしいお言葉だった。私の話したことをよく聞いて下さり,理解して下さった方だった。そのように今日も,皆さんにお話をして,よく聞いてくれて,質問をしてくれる。これは,私にとって本当にうれしいことだ。だから,話に行っていやだと思うことはほとんどない。うれしい。
☆63日目(5.15)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き③
10.愛生園の中で
①入園者の強制作業
私は愛生園に入った時には,「もう,再び帰ることはなかろう。外へ帰ることはなかろう。」という思いだったんですが,入ってみたら,すごく園内は明るい空気をしていました。もうすでに,(ハンセン病は)治るっていう時代に入っていましたから。私も「真剣に治療して帰ろう。」という意欲や思いで,一生懸命,治療しました。
ところが,ある日,私に伝票が来ました。どういう伝票かというと,「何月何日から何月何日まで,不自由な人が住んでいる寮に付き添い作業に行ってくれ。」というものでした。園の中では,作業がたくさんあるんです。いろんな作業の仕事があるんです。私はその伝票を見て,「これはいったいどういうことか。」と聞いたら,「元気なものは,不自由な者を見なければならない。そういう制度になっているから,この付き添いの作業は行かないといけない。」と言われまして,私は,作業に行きました。これはね,強制作業なんですね。どうしても身体が悪くて,という時は,医師の証明を持っていかなくちゃならない。医師はなかなか証明を出しません。いちいち証明を出しておったら,作業が回らないってこともあったんでしょう。この強制作業にはびっくりしました。
②監房
私が入ったころには,愛生園の中に監房 ~ 監禁室,患者を捕まえて,監禁をして閉じこめる ~ コンクリート建ての見るからに頑丈な監房があったんですね。私が入園したのは,戦後7年目ですから監房に入れるという時代じゃなかったですけれども,それでも,その監房にびっくりしました。戦後は,昭和23年ぐらいまでは,入れておったようですけれども。園の中にいる人を監房に入れていたんです。どういう人を入れるか,無断で外出した者,慰めに博打をしたり,喧嘩をしたり,そういう人もそうですね。それから,恐いのがもう一つあるんですね。これは,職員に反抗する者,職員に反抗する者は罰せられるんですね。職員側にすれば,反抗するっていうふうに取るんだけれども,入園者からすれば,当たり前のことを言うわけでしょう。いろんな事をお願いする場合もあるわけですよね。それも職員からすれば,反抗するっていうことに結びつく。そういうふうなケースで入れられた人がたくさんいます。
一つ例を申し上げますと,戦時中,まだ特効薬のない時代ですから,いろんな試験薬があります。試薬といいますが,その試験薬をうかつに出して,多くの方が亡くなりました。モルモットですよ,早い話が。今でも生きてる私のある友だちが言うんですね。ある女の先生が,「あなた,この薬をやりなさい。」と言った。その薬は非常に副作用の強い危ない薬だったんです。その薬で亡くなった方がたくさんいる。だから,私の友だちは「いや,その薬はしません。」と言った。ところが,その先生は「あなた,ちょっと草津へいくか。」とこう言った。実は群馬県の草津に重監房というのがあったんです。その監房は,零下10度になる寒いところに作られて,せんべい布団1枚を与えて,麦飯のちいちゃな握り飯一つとコップ一杯の水を与えた。そういうふうに非常に虐待された監房です。そこに行けば,生きて帰ることがなかなか難しいと当時は思われていたんですね。確かに,22,3人はそこで凍死をしております。そこが,草津監房です。その先生は,彼を脅かしたわけですね。
③人権無視の「らい予防法」
そういうふうにして,ハンセン病療養所は,患者は治すというより,患者を無理矢理に入れて,そこで一生を飼い殺しにする。そうすることによって,社会から病気をなくすという,こういう考え方なんですね。だから,日本の「らい予防法」は,よその国に比べて,非常に人権をないがしろにした,人権を無視したそういう法律だったんです。一言で言えば,「らい予防法」は,「絶対隔離・絶滅政策」を盛り込んだ法律だったんです。これが「らい予防法」だったんです。
④ワゼクトミー(断種)
それから,皆さんには,新聞などの中で「断種」というのを聞く場合があると思います。これは,結婚をしたら子どもを産まないように,手術をするんですね。だから,愛生園の中で,子どもを産むってことは絶対にない。もし,子どもができても,堕胎をするということなんです。ほとんどもう,子どもが産まれる臨月に近いような場合も堕胎をするんです。堕胎をしたら,「おぎゃー」って泣いてたんです。どうしたかというと,ガーゼで息のできないように顔を押す。そして,その子どもを殺す。そういうことが,どの療養所でも平然と行われていたんですね。皆さん,どう思われますか。「らい予防法」というのは,本当に人権を無視した,ぞっとするような法律だったんですね。いったん療養所に入りますと,その法律をみんなが強いられます。私もさっき言いましたように,中に入ってからは,強制労働もさせられました。そして,なかなか帰してくれません。帰省はなかなかさせてくれないんですね。
⑤妻の死
私の例をお話ししますと,入って3年目に,妻の姉から手紙が来ました。「妹がたいへんな状態になっている。病気になっている。ぜひ,入院させたいから帰ってきてくれ。」このような手紙が何度も来ました。私はその手紙を持って,園の人事係に何度も帰省をお願いしました。
でも,ついに,私は帰してもらえなかったんです。もう逃げて帰ろうか,逃走しようかと,こうも思ったけれども,逃走する勇気もなくて,ついに,その年に帰れませんでした。その2年後の昭和32年には帰れましたけれども,もうすでに妻は亡くなっていたんですね。
ある会場で「金さんが一番辛いことは何だったか。」と質問されたことがあります。その質問を予期していなかったものですから,「何だったのかな。」と思った瞬間に,今言いましたように,昭和30年に帰省をさせてもらえなかったのが,やはり,一番辛かった,悲しかった,ということを言ったことがあります。今思いましても,もし,あの時帰っていたならば,たぶん二度と療養所には戻らなかったと思うんですね。もう,ほとんど身体も回復していたし,もちろん「菌」もないし,こういうふうに手足も悪くないし,若くて元気でしたから。それに第一,入って3年位ですから,そのころのいろいろなかかわりというのは消えていないでしょう。断絶がないですから,十分,まだ外で生きることができたと思うんです。ですから,もし,あの昭和30年に帰省を許されていたら,たぶん私は帰っていなかったと,こういうふうに思うんです。これ,やっぱり辛いことの一番にあげてもいいんじゃないんでしょうかね。
11.裁判について
皆さんの質問を楽しみにしてきているんですが,その前に一つだけ裁判のことがありますから,ちょっとだけ聞いて下さいね。それが済んで,質問をお受けしたいと思います。
①提訴
今から3年ほど前に熊本地方裁判所に「『らい予防法』違憲国賠訴訟」~ちょっと難しい用語なんですが ~ 「『らい予防法』は憲法に違反している,それに対して国は謝罪しなさい,また,損害賠償しなさい。」,そういうふうな裁判を提訴しました。私も,もちろん原告の一人です。そして,いろいろな証人を立てました。元厚生省の医務局長であった方,療養所の所長,現在,香川県の療養所の大島青松園の外科医長の方も証言しました。どの先生も,「『らい予防法』は憲法に違反している。行き過ぎだ。絶対隔離政策をする必要はなかったんだ。」と証言をしてくれました。そして,原告も自らいろんな被害状況を訴えました。
②熊本地裁判決 ~原告勝訴~
そういうことから,去る5月22日,判決が出るんですね。私も熊本地方裁判所に傍聴に行きました。そして,あの本当に日本の裁判史上,あるいは,人権史上と言ってもいいと思うんですが,本当に歴史的な判決,それは私たち原告勝訴の判決でした。「らい予防法」は違憲性の強い,違憲性のある法律だったと,だから厚生大臣は誤っていたという判決でした。
もう一つあるんです。もう一つ。ちょっと難しい話ですが,国会,法律を決めたりする国会。これは国権の最高機関といわれています。一番上に位置している。その国会が,そういう誤っている法律を何ら廃止もしない,手直しもしない,そのまま法律を見過ごしてきたというのは,これは,国会の誤りだ。「立法不作為」という難しい言葉があるんですが,この判決では,国会の誤りをも認めたんです。これは,大変なことなんです。今までの判決の中で,国会議員の誤りを指摘した,認めた裁判はかつてないんです。一度も。ところが,この裁判は国会の過失を認めました。控訴するか,しないか。一番問題になったのは,国会議員の「立法不作為」です。
もう一つ,判決の中で重要な点は,「除斥期間」というのがあるんですが,~ 提訴して20年前のものは,時効にかかって問題にならないんだということが民法に書かれているんですが ~ この除斥期間もこの判決の中ではまったく一蹴した。除斥期間なんてないんだ。早くから患者の被害はずっと今まで継続している。除斥期間は,「らい予防法」がなくなってからを基準にしているんですね。時効を認めなかった。大きくいってこの3つの,本当に私たちからすれば,輝かしい,すばらしい判決だったんですね。
③国側,控訴断念
ところが,あまりにも,すばらしい判決でしたから,絶対,国の方は高等裁判所に控訴する,みんなそう思っていました。原告の絶対勝利のすばらしい判決であるだけに,国は黙って認めないだろう。私もそう思いましたし,ほとんどのマスコミは控訴すると報道しました。それで,国に対して控訴してはいけないという運動をしました。
控訴する期間は判決から2週間以内なんですね。2週間の間に控訴するか,せんかが決まるわけですが,それで,私も5月21日,東京へ行きました。多くの人が集結したんです。一般の理解する人も,支援する人もたくさん,1000人近い人が,あの首相官邸前に集結したんです。私もマイクを持って,解説をしました。なかなか首相は会ってくれない。首相官邸の扉を叩いた。なかなか開かないんですね。「扉を開けろ」とシュプレヒコールをやっても開かない。私は,22日にいったん岡山に帰りました。
そして,テレビに出てましたように,23日の午後9時10分だと思うんですが,小泉首相が「例外的に控訴しません。」と言いましたね。控訴しなかった。控訴しないということは,熊本の一審判決が確定したわけですね。その後,目まぐるしく,国がいろいろなことをやってね,国会決議とか,内閣声明とか,厚生労働大臣の声明とかいろいろなものが出てくるんですが。
そういうふうにして,私は,自分が原告になって本当に良かったなとつくづく今でも思っております。「らい予防法」のことは,話せばいろいろありますけれども,憲法に違反する法律であったということを国も認めたわけですから,私はその点では,原告になって苦しかったけれども,闘ってきて良かったと思っております。
☆62日目(5.14)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演の続き②
7.なぜ,感染するのか。
それで,どうしてうつるのか,ということが一つ問題になりますね。うつる病気,感染する病気ですから。しかし,みんなうつるわけじゃないんですね。本当にうつる人は,ごくわずかな人なんです。いわゆる「らい菌」に対して,病原性を持っている,ちょっとむずかしい言葉ですね,まあ,うつりやすい体質の人もいるわけですね。そういう人が,ごくまれに,ハンセンの「らい菌」にたくさん襲われると,感染をするということです。しかし,ちっちゃい時,本当にまだお乳を飲んでいる乳幼児期にうつるというふうにいわれます。もう大人になってからは,身体に免疫力,菌に対する抵抗力ができますから,大人になってからは,絶対と言っていいほどうつることはありません。
これもよく例に出される話なんですが,療養所で働いている職員は何万といます。そういう何万の職員の中で,一人とて病気にかかった人はおらない。このことを考えてもね,成人になっては,なかなか病気がうつらないということを皆さんに知ってほしいなと思います。
だから,うつりやすい体質,いわゆる病原性を持っている人が,あまりに小さいときにうつる。それで,今の日本列島における子どもさんたち,皆さんも子どものうちに入るでしょうか,しかし,皆さんぐらいになるとうつるということはほとんどないんですね,中学生ですから。今の日本列島における乳幼児期の子どもというのは,非常に免疫力が高い。免疫力が高いということは,栄養がいいということなんですね。だから,今の子どもたちは,感染するということは,ほとんどない。
8.特効薬「プロミン」と「DDS」の副作用
それから,特効薬ができました。戦後,昭和24年,1949年から,どの療養所でも「プロミン」と言う特効薬が使われました。奇跡的にあの薬はハンセン病を治していったんですね。さっき,校長先生のお部屋でちょっと話をしたんですが,私もほとんど3年ぐらいで菌がおらない無菌になりました。長く治療していませんでした。
ところが,少し神経痛がするもんですから,ある日,先生に相談してDDSと言う薬,「ダプソン」といいますが,それを1錠ずつ1週間ほど飲んだら,その副作用から,私は,一晩で,たった一晩で足が下がったり,手が下がったり,喉頭麻痺を起こしたり,たいへんな副作用に見舞われました。その後遺症が今でも残っているんですが。ところが,今は,一種類だけの薬は使わないんですね。3つの薬を同時に併用するんです。多剤併用療法と言うんですが,3つの薬を一緒に併用するものですから,絶対に私のように副作用が起きたり,あるいは,後遺症をもたらしたり,そういうことはないんです。早く治る。そのような多剤併用療法で,3日も飲めば,いかにその人が菌をたくさん持っていても,その菌は感染力を失うっていうふうに大きく変わったんです。身体から菌が完全になくなるには,すこし間がかかるんですが。
そういう具合で,たいへん今は完治するいい薬ができましたから,病気になったからといって,ちっとも恐ろしい病気だとは,私は思いません。ハンセン病のことについては,少しおわかり願えたでしょうか。また,わからないことは,後ほど,質問をして下さい。
9.発病,そして「強制収容」
それから,去る5月11日,熊本地方裁判所で,私たちが起こしております「『らい予防法』違憲国家賠償請求訴訟」の判決がありました。その全面原告勝訴の判決があってから後,いろいろな新聞,あるいはテレビなどで放送もされていますから,皆さんも時に聞かれているんではないでしょうか。その中で「らい予防法」がどういうものであるかっていうことは,あんまり報道はされてないんですね。でも,憲法に違反するような良くない法律であったということは,何となくわかっていただけたと思うんですが,くわしくはわからないですよね。どうして,憲法に違反するような良くない法律だったか,このことについて少しお話をしてみたいと思います。
まず,私の体験からお話しをしましょうね。私は,1949年,昭和24年に,このハンセン病の告知を受けるんですね。そのころは,まだ自覚症状はあまりありませんでした。でも,背中の方に麻痺,-痛くない-,麻痺をしている部分があることがわかったんですね。それは,偶然,気がついたんです。
私を診察した医師が,長く私を診察している。本を繰って,長く考え込んで,いろいろしていました。「先生,私はなんの病気ですか。」と聞いたら,「レプラだと思う。」このようにおっしゃいました。今はあまり「レプラ」という用語は使われていませんけれども,そのころは,「レプラ」というのは「らい病」を指してる言葉だったんですね。これは,ギリシャ語です。私は「レプラ」と聞いてすぐ,「らい病」だなって思ったんです。先生からそう言われて,約1週間ほどしましたら,私は大阪に住んでいましたので,大阪府庁の衛生部予防課の大浜さんという女性が私の家に来まして,「あなたは病気だから,長島愛生園に行きなさい。」こういうふうに言われました。「どうして,僕が長島愛生園に行かなきゃならんのか。」ということで,何度か押し問答があったんですね。
私はついに,1952年,それから3年後に,強制収容で長島愛生園に収容されました。どうして僕が病気であるということが,すぐ府庁にわかったか。これはちゃんと「予防法」に書いてるんです。その時は,「予防法」があるのも知らずにいたんですけれども。どういうふうに書いているかというと,「ハンセン病を診察した医師は,必ず患者の所属する都道府県の知事に届け出をしなければいけない。」と,こうあるんですね。もし,その届け出を医師が怠ったら罰金があるんです。私を診察した医師はちゃんと知っていて,ハンセン病患者を診察したと大阪府の知事に届け出をしたんです。だから,大阪府から私の家に来た,こういうわけですね。
これもよく話をすることなんですが,実は,私は親を頼らずにいましたから,生活もあります。学生結婚もしていたもんですから,妻もいます。病気になっても生計を立てなければなりません。大阪の繁華街の新世界という所で友人の家を借りて食堂をしたことがあります。あまり大きな食堂ではありません。非常にうまくいっていました。その当時は,食料とか生活物資は全部国が統制していました。自由に売り買いしてはいけない,配給制度ですから。そういう時代に食堂は非常に繁盛するんですね。私の食堂も非常に繁盛しました。
ところが,何ヶ月かたって,さっき言いました大阪府の予防課の大浜さんが,私の店に来て,私は,もう,少し顔が腫れぼったくなっていましたから,店へ出てませんでしたが,「こういう商売をしてはいけない。」と言われるんですね。初め来た時には,私は会いませんでしたが,何回か来るうちに私と会って,やはり,「この病気の人は,こういう商売をしてはいけない。だから,やめなさい」と言いました。私は非常に腹が立ちました。私も生活をしなければならない。何かしなきゃならんのに,どうして,商売してはいけないのか。その後も何回か,来ました。
ある日,浪速署の制服の警察官を一緒に連れてきました。警察官は黙って立っていたままでしたけれども,やはり,それは威圧になるんですね。脅しになる。そうしますと,私も自然,商売する気持ちがだんだんなくなってしまって,ついに商売もやめるわけですね。これも「予防法」の中にちゃんと書いてるんですね。「従業禁止」という項目があるわけです。
そして私はついに,1952年,昭和27年7月22日,大阪駅から,いわゆる専用列車,私たちはこれを「お召し列車」と皮肉って言うんですけれども,私と大浜さんだけ,2人だけしか乗らない客車に乗せられて,岡山駅に送られました。私の場合は,本当に強制収容でした。それから,今日まで長く療養所で生活しています。数えますと49年になるんですね。
☆61日目(5.13)人権学習の内実を確かなものにしたい
人権教育の推進に取り組むときに、例に挙げられているいくつかの人権課題がありますが、その内容を知ること(理解する)からさらに一歩進んだ取組に出来たらいいなあと思っています。それには、「人との出会い」を学習の中にきちんと位置づけることが大切だと思います。ハンセン病問題学習に生徒たちと取り組む際に、私はいつも、金泰九(Kim teagoo)さんとの出会いを演出します。残念ながら亡くなられましたが、創られたドキュメンタリー映画『虎ハ眠ラズ』は秀逸で、今も教材として色あせていません。著書『我が八十歳に乾杯』もあります。人の生き方を通して、人権課題を見つめ、自分ごとにする学習を今年も学年団の先生たちと創っていきたいと思います。金さんの講演会(2003)の一部を何回かに分けて紹介します。
中学校の皆さん,こんにちは。(こんにちは)返事があってとてもうれしいです。ありがとう。ただ今,紹介をいただきましたように,岡山県邑久郡邑久町にあります,国立療養所長島愛生園から参りました金 泰九と申します。よろしくお願いします。
こんな格好で本当に皆さんに申し訳ないんですけど,実は,1週間程前に風呂場で滑っちゃって,骨折をしました。ギブスをまいているんですが,あと1月半ほどギブスをまかなきゃならんということで,こういう格好になりました。しかし,身体は至って元気ですから,皆さんご安心下さい。
これから約1時間半あまり,お話をさせていただきますが,今日は1年生から3年生までですから,やはり,やさしい言葉で話をした方がいいんじゃないかなと思っています。退屈して眠たい人もたぶんいるんじゃなかろうかと思います。どうぞ遠慮なく,こっくりこっくりして下さいね。
まず話の順序として,やはり,ハンセン病がどういう病気であるかということをみなさんに知ってもらう方がいいんじゃなかろうかと思って参りました。 それから,今,新聞その他,あるいはテレビ等で報道がされていますように,「らい予防法」の違憲性が強いあの裁判ですね。その「予防法」がどういうものであるかということも,みなさんあんまりは知らないだろうと思いますので,そのことも,私の得た体験をもとにして話をしたいと思います。
最後には,裁判にかかわるいろいろな問題もできれば話をしたいと思います。それがすんだ後,皆さんの方からいろいろ質問を受けて,そして,話をした方がいいんじゃないか,こう思いますから,質問の時間にはどうか,どんな質問でもけっこうですから,質問をして下さい。よろしくお願いします。
2.病名の由来とハンセン病の歴史
横田真智子先生の方からハンセン病についてのいろいろな学習はしたようですが,その復習と言う意味で,ハンセン病を病んだ私の方から,ハンセン病とはどういうものであるか,ということを少しお話をしてみたいと思います。 私は先ほどからハンセン病と言っていますが,以前はハンセン病のことを「らい病」あるいは「らい」と,そのような名前で呼んでいました。お年寄りの方は「らい」とか「らい病」と言う方がよくおわかりだと思います。でも今は,「らい」と言う用語は使いません。ハンセン病と言うようになりました。
ハンセン病の「ハンセン」は,今から約130年程前に,北欧のノルウェーのお医者さんでハンセンという方がこの菌を発見したことにちなんでいます。このハンセン病が地球上に現れたのは,ずいぶん古いんですね。たぶん,紀元前2,3世紀には,この地球上にはハンセン病があったと古文書を調査してわかります。日本でも日本書紀あたりでは,670年頃には「らい」と言う名称が書いてあります。奈良時代でもすでにハンセン病は日本にあったと思っていいと思います。「ハンセン病はうつる,伝染病だ」と。にもかかわらず,日本列島でハンセン病が現れてから1300年にもなるのに,あまりこの病気は蔓延,広がっていないんですね。伝染病だともっともっと広がっていいはずなのに,広がっていない。このことを見ても,この病気はそれほどうつらないっていうことが,皆さんおわかり願えるのではないでしょうか。
3.ハンセン病は「遺伝病」ではない。
この病気をちょっと難しい定義で言いますと,「らい菌」による「慢性感染症」,感染症なんです。そして,遺伝病ではありません。ずいぶん昔から病気があって,そして,どちらかというと同じ家族の中でこの病気が発生しているものですから,当時はうつっていく病気ではなくて遺伝する病気だ,と長い間思われてきたんですね。「遺伝病」,というふうに明治の初期あたりまでは日本でもそう思っていたようです。
ところが,さっき言いましたように,ノルウェーのハンセンさんが「らい菌」を発見した。菌を発見したんですから,これはとても「遺伝病」じゃないということがわかってきたんですね。だから,「感染症」なんです。
4.「らい菌」の特徴
「らい菌」は,「結核菌」とほぼ同じ時代に発見されるんですけれど,「結核菌」は培養器の中で培養できるんです。皆さん,培養っておわかりですね。菌を増やしていくことですね。でも,このハンセンの「らい菌」は未だに培養できないんです。なぜ,培養ができないか。早く,もし,培養ができたんだったら,もっと病気に効く薬が発見されたんでしょうけれども,培養ができなかったために,特効薬が早く作れなかったともいえるんです。
それほど「らい菌」は弱い菌なんですね。非常に弱い。形も抗酸性という性質も非常に似ているんだけれども,「結核菌」は人の体の中に入っても,肺とか腸とか,そういうところへ入って増えていくんだけれども,「らい菌」はね,身体の見える所,衣服で覆われていない見える部分にたくさん生息するんですね。それはなぜかというと,どうも「らい菌」は冷たい所を好むからと言う説があります。
5.「末梢神経」への影響
そして,体の中に入ったら,まず,どこに入るかというと,「末梢神経」,人間には「中枢神経」と「末梢神経」がありますよね。その「末梢神経」に「らい菌」が入る。「末梢神経」の中で菌が増えていくわけですが,そうすると,いろいろな「末梢神経」の「障害」が出てきます。「末梢神経」は「感覚神経」でもあるわけですよね。「痛い」とか,「熱い」,「冷たい」こういう感覚を司るところでもありますから,「末梢神経」がやられると,感覚がなくなるんですよ。痛いのもわからない。火にさわってもわからない。これが,ハンセン病の悪い特徴といえば特徴ですが。
そして,もう一つは,運動神経,私も今,指が曲がっていますが,このように萎縮してくるんですね。そして,身体が麻痺する。
私もね,ひじのここからはほとんど感覚がないんです。だから,火に触れても熱くないから,よく火傷します。釘を踏んでも,私の右足は前半分の感覚がありませんから,血が出ない限りわからない。そのように,ハンセン病の症状の特徴と言うのは,麻痺がまずおこることですね。
そして,少しそれが進むと,指が曲がってくる。これが,一番ハンセン病における悪い特徴だと私は思います。
6.「多菌型」と「少菌型」
しかしですね,ハンセン病でも「型」があるんです。いわゆる「タイプ」が。私は「多菌型」。非常に菌をたくさん持っている型,前は「らい腫型」といいました。それから,それに反して,菌を少なく持っている「少菌型」と言うのがあります。大きくわけて2つにわかれますが,実は「少菌型」の場合は,身体の末梢神経に確かに菌は入っているんだろうけれども,体の表面には菌が検出されないんです。いくら,どこをとっても菌の検出が見られないんです。
皆さん,ここでちょっと考えてほしいんですが,身体から菌が出ない人,もちろん,麻痺をしているわけです。あるいは手も曲がっている。そういう症状があるけれども,身体から,どこをとっても菌が出ないっていう人は,公衆衛生上何ら問題がない人でしょう。普通に皆さんと一緒に生活しても,何ら問題のない人だと思います。 そういう人も,今,療養所の中には3分の1以上おります。今はですね,特効薬で戦後,療養所の中でも治療されまして,もう菌を持っている人は,ほとんどいません。持っていても,感染力を保持しているような菌は一人もない。だから,療養所の中では,もう,まったく感染源になる人は一人もおらない。どこの療養所でもそうなんですね。
そういう意味では,外一般よりも療養所の中の方が,ハンセン病の感染と言う点から考えれば,全く安心できる場所なんです。
☆60日目(5.10)仲間とともに取り組む平和学習
今年度、久しぶりに広島研修に同行し、リニューアルした資料館を初めて見学しました。リニューアル中の時期に一度、生徒引率した際に、事前に学年団の先生らと下見に行き、「学習ノート」をつくりました。この学習ノートが必要なのか?、今あらためて話し合ってみたいと思いますがどうでしょう?
☆59日目(5.9)仲間とともに取り組む平和学習
学年集団の違いや、教師集団の取組の深化などで「群読(2014)」も変化していますね。
☆58日目(5.8)仲間とともに取り組む平和学習
昨日、3年生は沖縄修学旅行を前に、中庭で、平和集会リハーサルを行いました。しっかりとした「群読」、願いをこめた「歌」には、他の学年への強いメッセージも感じらた、とてみ素敵な取り組みでした。クラスで進める「群読」や「平和学習の内容」についても一考しましょう。少し前に生徒実行委員会が創出したオキナワ平和学習時の「群読」です。

☆57日目(5.7)学びの共同体とは?その③教科教育における「真性の学び」
○文学教育にとって「真正の学び」とはどういう学びなのか
文学の教育は「言葉」の教育である。「文学の言葉・詩の言葉」は、象徴性、多義性を特徴としている。文学は「アート」である。他のアートと同様、「もう一つの世界、もう一
人の他者、もう一人の私」と出会い、日常に隠された「もう一つの真実」を認識し表現する技法である。
文学・詩のテクストは一つの「作品」であり、比喩的に言えば「ごちそう」である。文学・詩の読みの目的は<わかる>ことではなく<味わう>ことにある。
文学・詩の学びは<テクストとの出会いと対話>である。協同的学びにおいても、<テクストとの対話>が中心にならなければならない。そのために<仲間との対話>があり<自己との対話>がある。逆ではない。
文学の授業・真正の学びを実現するための要件(文学の学びが成立するための教師の活動の要件。)①主題を追求しない。②「気持ち」を問わない。③「なぜ?」と問わな
い。文学の読みに「一義的な正解」はない。「多義性・多様性」に文学の本質がある。そのためにも虚心坦懐にテクストの言葉に寄り添って読むことが必要である。言葉に触れ、言葉に出合い、想像力によって言葉の<織物>を描き出すことが、読みの快楽である。具体的には、①12分程度の音読の保障、②3回はグループにもどす、③3回はテクストに戻すを基本として授業をデザインする。
○数学における真正の学び
①数学は「量と空間の科学」。数学的思考の本質は、「数学的推論」(現実(かず)→半抽象(量)→抽象(数))における「帰納と演繹」と「パターン認識」にある。
②しかし、近年、数学的推論(mathematical reasoning)の意味と論理よりも、問題の解法とスキルが重視される傾向がある。(純粋数学よりも応用(工学)数学が重視される傾向にある。)数学の理解は「量的意味」(半抽象)と「操作的意味」(アルゴリズム)とが合致した時に成立するが、最近の数学教科書は「量的意味」が軽視されている。(タイル、数直線、線分図など)。これでは、分数、比、割合で躓く可能性が大きい。「式ー答」ではなく「図-式ー答」の解答欄を実施しよう。③学年ごとに細切れになっている。(小数第一位=3年、小数第二位以上=4年、正方形・長方形の面積=4年、平行四辺形・台形の面積=4年など。)これでは、10進法の意味理解も、あるいは面積の求積の構造も理解されない。④数学的思考と自然や社会との結びつきが弱い。(数学的リテラシーが狭く認識されている。)
○社会科における真正の学び
社会科の目的は「民主的市民の形成(市民性の教育)」にある。社会科の学びは、史資料とデータによる思考と探究にある。(教科書で社会科は教えられない。)社会科の学びに正解はない。多元的な思考と探究が求められる。「社会と出会う」「社会を知る」「社会を生きる」、この三つが社会科の学びに保障される必要がある。社会的な事象は、因果関係において生じているのではない。複雑な要因の構造的な関係において生じている。
○理科における真正の学び
理科の授業における「予想」→「実験」→「検証・討論」という定番の授業は、根本的に見直す必要があるのではないか。「理解」中心から「探究」中心の授業への転換をはかる必要がある。科学的探究の本質は、「仮説→実験→検証」にあるのではない。日常の現象への「疑問(question)」が科学的探究の「問題(problem)」になるには何が必要か。これを教師は認識する必要がある(事例:NHKラジオ「子ども科学相談室」)。協同的学びの根拠はここにある。
科学的探究の本質は「モデルの構築」にある(数学も同様)。「詳細な観察(見える現象)」→「知識・情報の活用(考察)」→「理論モデル(見えない原理・法則)の構築」(言語化よりも図による提示が重要)
学びの共同体の実践では、<共有の学び(教科書知識の理解)>の探究的協同的学びと<ジャンプの学び(教科書レベルを超える課題)>による「理論モデルの構築」を実践している。
○アートの教育における真正の学び
・「アート」は「芸術」より広い。アートとは「生きる技法」そのものである。したがって、「アートの教育」は、「言葉の教育」と並んで、教育の中心である。
・アートとは、「もう一つの現実」「もう一つの真実」「もう一つの世界」「もう一つの私」「もう一つの他者」を見出し、それを表現する技法である。
・アートは、想像力と創造性によってもう一つの現実(内的真実)を生きる技法である。(「技とスタイル」の学び)したがって、アートは「世界の秘密」との対話であり、一人ひとりの「私の秘密」(内的リアリティ)に根差している。
○どう英語において「真正の学び」を実現するか。全教科のなかで最も混迷している。
<共有の学び>=教科書使用=教科書レベル
<ジャンプの学び>=authenticなテキストを活用。
小高学年、中1では、「スイミー・どろんこハリー・おてがみ・はらぺこあおむし」の絵本の翻訳、暗唱など。中2以上は、「アナと雪の女王」の脚本翻訳、ビデオ視聴、暗唱により高2~3のレベルへ。もう一つ、アジア諸国の英語教育の問題:「第二言語習得論」による弊害がある。アジア諸国にとって英語は「第二言語」ではない。「外国語」である。
○創造性の学びは「批判的思考」と「アートの学び」によって達成される。「アートの学び」(文学、詩、美術、音楽、演劇、舞踊など)が創造性の教育として、いっそう尊重
される必要がある。「批判的思考(critical thinking)」は、日本では誤解され混乱している。「批判的思考」は「異なる視点からの思考」つまり「多元的思考」である。「批判的思考による学び」は「探究と協同」、特に「高いレベルの学び」(ジャンプの学び)において有効に達成される。
☆56日目(5.2)学びの共同体とは?学習集団づくりとなかまづくりは違うのか?その②
探究と協同の学びのイノベーションをどう開始するか
① 授業と学び、学校改革のヴィジョンと哲学と理論の共有が最初に行うべき事柄である。あらゆる改革において<ヴィジョン>の共有は最優先課題である。どんな学校をつくり たいのか、どんな教育を求めるのか、どんな教室、どんな授業、どんな学びを希求しているのか。この<ヴィジョン>の共有は、すべての改革に先行する。『新版・学校を改革する』(岩波ブックレット)を活用する。
② 探究と協同の学びの学習(教室)環境を準備する。学習環境の改革が行われない限り、何も改革は進行しない。(小学1.2年生はコの字型+ペア学習、3年生以上、中学校、高校は男女混合4人グループの机の配置による協同学習。
③ すべての授業を<共有の学び>と<ジャンプの学び>で組織する。
④ すべての教師が教室を開いて学び合い、校内に同僚性と専門家の学びの共同体を構築する。
探究と協同の学びが成立する要件:探究と協同の学び(質の高い学び)の要件は三つ。
①<聴き合う関係>(話し合いではなく聴き合い、教え合いではなく学び合い、ケアの共同体)、②探究を促進する<ジャンプの学び>、③現実の文脈に則して教科の本質を追求する<真正の学び>の三つである。
① 探究と協同の学びにおいて有効なのは「発表的会話」ではなく「探索的会話」である。Douglass Barnes‚ Neil Mercer
② わからないときに隣の子に「ねえ、わからない、ここ教えて」という「援助要請(help seeking)」が、探究と協同の出発点を準備する。
③ 学びには、ある知識を学ぶ Learning I とその知識の学び方を学ぶ Learning II がある。Gregory Bateson 学びの共同体の「真正の学び」は、この Learning II の学びを実
現している。
真正の学びをデザインするー探究と協同の学びのイノベーションー
◎「真正の学び」は多義的な概念である。
①現実世界の学び、②探索的で探究的な学び、③現実的な課題で多様な知識を関連付け統合する学び、④高次の思考を追求する学び、⑤正解が定まらない探究的な学び、⑥反省的思考や熟考を促進する学び、⑦学びのプロセスで多様な他者と協同し真実性を追求する学び、などなどである。
◎学習者(表現者)の「内的真実」=ジャン・ジャック・ルソー
・モノ(対象)のホンモノと偽物を区別する意味=「外的真実」
・現実の文脈に則して教科の本質を追求する学び=AUTHENTIC LEARNING=ホンモノの学び
☆55日目(5.1)学びの共同体とは?学習集団づくりとなかまづくりは違うのか?
本校でも授業改革推進員の先生が来校され、中学校の取組・課題に合わせた授業づくりを進めています。授業参観後、授業についていろいろとお話できることが、「新しい学び」となっています。その中で、岡山で学びの共同体の話題もあがりました。岡山の研修会(岡山学び工房)の代表、秋山先生から提供してもらった資料の一部です。(パワーポイントなので項目的です。いろいろ意見交流を進めましょう)
「21世紀型の授業と学び」の世界標準と学びの共同体ー聴き合う関係による卓越性-
<21世紀型の授業と学び>
:1989年以降①学習者中心の授業、探究と協同の学び
②一斉授業の教室から、コの字型(小学校低学年)と4人グループの机の配置
③学びのファシリテーターとしての教師
④反省的実践家としての教師(教える専門家から学びの専門家へ)
⑤教師の専門的共同体(PLC)あるいは同僚性(collegiality)の構築
<学びの共同体>の独自性
:1992年以降①子どもの学びの権利の実現、学びの主人公としての子ども。
②一人も独りにしない「ケアの共同体」としての教室
③聴き合う関係の構築(民主主義は「話し合い」ではなく「聴き合い」)
④共有の学びとジャンプの学びー真正の学びの実現
⑤学びを中心とする授業研究による教師の専門家としての成長。教師が専門家として育ち合う同僚性。授業研究のイノベーション。
☆54日目(4.30)子どもたちが主体的に活動するオキナワ
広島研修の事前指導時に、「子どもたちが、実行委員会を中心に、〈主体的に活動する研修〉のあり方、組み立て方ってどうすればよいのだろう?」と話題になりました。コロナ禍前のオキナワ修学旅行の際に、同僚らと共に、子どもたち自身が運営する修学旅行を計画・実施することができました。日程のデータにもたくさんの意図した工夫があります。
☆53日目(4.26)T先輩から「おわりに」
「大阪大学の志水宏吉氏によると『社会学の領域では、「マイノリティー」は、次のように定義づけられている。「何らかの属性的要因(文化的・身体的等の特徴)を理由として、否定的に差異化され、社会的・政治的・経済的に弱い地位に置かれ、当人たちもそのことを意識している社会構成員。具体的には、「先住民や歴史的・地位的少数者も含まれ得るし、場合によっては女性・子ども・障害者なども含まれる可能性がある。」とされている。この定義から明らかなように、マイノリティーとは、ある社会の構成員のなかで相対的に弱い立場に置かれた「社会的弱者」のことである。』彼は、ニューカマーと呼ばれる新たに日本に来た外国人の問題を論じ、『彼らが日本の地域社会や学校・教室に提起する文化的異質性は、例えば、「在日」や「部落」の人々が示すそれよりもずっと可視的なものであるにもかかわらず、それに対する日本社会の側での対応は思いのほか鈍い。ニューカマーに対する教育支援の方途を実践的に探求することは、彼ら自身にとって有益であるのみならず、それが我が国の学校文化の体質自体の変革につながるという意味で、われわれマジョリティーたる日本人にとっても大きなメリットとなるに違いない』『「彼ら」の問題は、実は「私たち」の問題である。マイノリティー問題にこだわる意義は、その点にこそあるのである。』(『学校臨床社会学』~教育問題をどう考えるか~)と指摘している。長年、同和教育が『差別を生み出す学校を変革する』と主張してきたことと同じである。被差別部落の子どもたちの教育権を保障する取り組みは、その子たちだけでなくすべての子どもたちの教育権を保障する取り組みにとって力を発揮してきた。
しかし、同和教育の長年にわたる取り組みにも関わらず、いまだに部落問題を自分の問題と捉えられない人は多い。いまだに差別はしないまでも問題を忌避したり、問題から逃避したりする人は、少なくない。差別問題やマイノリティー問題への関わり方を切開すると、自分の意識や生活のありようを規定するものが見えてくる。偏見は持っていなくても差別意識は持っていたというのが、個人的な経験である。その差別意識から自分を解放したいというのが、「私の」問題としてこの問題に関わり続ける所以である。
ニューカマー問題が日本人としての意識や生活のあり方をも照射するように、日本固有の問題である部落問題はこの国のあり方を明らかにする。この国が国際社会で名誉ある地位を得るためにも、すべての人が各自の能力を発揮し社会のために貢献できるようになるためにも、マイノリティー問題など社会に存在する諸問題に無関心であってはならないのである。子どもたちがこれらの問題を自らの問題として認識し、具体的な取り組みを通じて、その解決を展望できる力を学校教育は保障することが大事な仕事となるのである。」
☆52日目(4.25)個に応じた学習
今から20年前の論文を前提に読むとこれも意味深いと思います。
「情報教育はコンピュータ活用教育の域をいまだ脱することができない現状にあるが、徐々に個別学習での成果も上げつつある。近年、「個に応じた学習」という研究がはやっている背景もある。たしかにコンピュータを活用すれば、個々の興味や関心・能力に応じた学習プログラムが可能である。これまでも一斉授業の中でも個に応じた指導はなされてきたが、コンピュータの登場は授業の画期的な変化を予想させた。学校は、問題解決的な学習にとって有力な手段を手に入れたといえよう。
しかし、最近は個に応じた学習というと、小集団学習であり、習熟度別学習であると捉えられているかのようである。ここにも学力向上問題が影を潜めているといえるかもしれない。習熟度別に小集団を組織してそれぞれに応じた課題をあたえるという発想は、効率主義の発想であって、個に応じたものとは言いがたい。小集団としての把握はなされても個としての存在は想定されていないからである。答えのはっきりした課題を確実にこなす学習や技能の獲得を目的とする授業にはこれが向いているのであろう。
情報教育で注目されるようになった個に応じた教育活動は、相互教授と呼ばれる。1台のコンピュータを二人で使うことにより、友達がアドバイザーとなることによって、知らず知らずのうちに技能を修得する学びである。友達が自分のモデルとなるのであり、自分よりも優れた者から学ぼうとする学びである。このようにして個々の得意分野を互いの学習に生かす、これは協同学習の一つの形態ともいえよう。赤堀侃司氏によると、これらは教育学者ビゴツキーによって発達の最近接領域理論として整理された。『すなわち、この発達の最近接領域では、学習者個人の問題解決能力は、大人である教師や一定のエキスパートなどの指導下ばかりでなく、より能力の高い仲間がいる場合にも高められ、より高次の発達水準へ導かれ、引き上げられるとする。』同じ集団の中に近似的に能力や技能の違う生徒がいることによって、相互の助け合いや教え合いが効果的に行われるというものである。
人権教育はその学習過程の中に相互に認め合い、協力し合う学習が必要になる。なぜなら、人権教育はその目的が重要であるだけではない。その学習過程そのものが民主的でなければならない。そのような意味でも小集団学習を取り入れるとしても、集団編成は均質な小集団であるよりは、できる限り多様な価値が交錯するような集団編成が目的意識的に追及される必要があるのである。」(続く)
☆51日目(4.24)協同学習
「日本では古くから班活動など集団を活用した指導がさまざまな面で見られてきた。したがって協同学習といってもさほど抵抗なく導入できるように思う。この協同学習の概念は情報教育の進展に伴って脚光を浴びるようになってきた新しい領域である。
従来、教師から一方的な新たな知識が与えられ、生徒はそれをいかに効率よく吸収し、自らのものにするかがこれまでの学習であったといってよいだろう。つまり、知識は個人の頭の中に個人の努力によって蓄積されるものだという知識観が横たわっていた。しかし、技術革新やあふれかえる情報のなかで、知識は絶えず陳腐化し更新される高度情報化社会にあっては、知識は個人の頭の中に蓄積するものではない。知識は状況や活動の中で生成され道具や他者との間に分かちもたれるものであるという考えに変わってきている。インターネットを想起すればこのことはよく分かる。誰も呼びかけたわけではないにもかかわらず、さまざまな能力を持った個人がそれぞれの能力を生かしてサイトを創作している。利用者はそれらの中から自分に必要な情報・知識を引き出し、活用する。そうした営みを通じて自然淘汰されながら、結果としてそれらの情報・知識は社会に広まり共有されていく。だから、教師に必要なのは、何か教える内容を先に決定するのではなく、状況に応じて生徒の必要とするものを見つける手助けをする力である。こうした中では教師と生徒の関係は、教え-教えられるといった固定的な関係ではありえない。これを意図的に構想したものが協同学習だといってよい。
東京工業大学の赤堀侃司氏の『情報教育論~教育工学のアプローチ~』によれば、コンピュータを道具として活用することによって、お互いの知識・考えを共有し、問題を解決していく学習を協同(協調)学習(Collaborative Learning)と呼んでいる。教室で取り扱う学習内容が人権問題や環境問題のように多面的な観点からの考察を必要とする内容であれば、情報・知識は必然的に教室の枠組みを越え、世界中の他者と結びついて獲得される形となり、学習は発展する。いわば問題解決を通じて学習共同体が出来上がっていくのである。そうなると、学習とは、このような学習共同体に参加することとなる。ここでは学習は主体的に展開されるのであって、教育ではなく学習が目的となっている。「低学力問題」を学びからの逃避としてとらえる東京大学の佐藤学氏の「学びの共同体」も同様の課題を提起している。学力は能力の一部であると同時に人格の一部である。佐藤氏は、協同的で反省的な学びとそれを支える同僚性の構築こそが今日の学校を再生する道であるという。これまで人権教育とは縁の薄いと考えられてきた領域に共通する課題が発見できるようになってきたといえよう。」(続く)
☆50日目(4.23)~学校を基礎としたカリキュラム開発
「地方分権が今後の政治の重点課題となっており、学校教育についても開かれた学校づくり、特色ある学校づくりという形で、地域にしっかりと根を下ろした学校づくりが始まっている。今後、校長に経営責任の強化とともに予算権や人事権が付与されるなど学校としての独自性が発揮される条件は拡大していくであろう。
放送大学の新井郁男氏の『教育経営論~生涯学習社会形成の観点から~』(放送大学)によると、1979年にOECD経済開発機構の教育研究革新センター(CERI)は、子どもたちをトータルに育てるための学校組織の改革に関する報告を行い、その中で学校が法的・行政的に自立性を持ち、専門性に基づいて独自の教育活動を創造することの重要性を説き、それを学校に基礎を置いたカリキュラム開発(School Based Curriculum Development)と名づけた。SBCDが可能なのは、①学校が関連するさまざまな組織と有機的な関連を持ちながら、独自のカリキュラムを編成する自由を持っていること ②教師と生徒が各自の経験を教育的な力として生かす自由な活動が保障されていること ③地方から中央にいたる種々の機関や団体など学校以外のレベルでのカリキュラム開発も容認されていること、だとされている。こうすることによって特色ある学校づくりが持続できるとしている。今後の教育改革が児童の権利を保障する国際的な流れを受けて、このように理解されていくか、先に指摘したような偏狭なナショナリズムに収斂されていくかは大きな分かれ目といえよう。しかし、いずれにせよ、子どもたちの現実・地域の環境を踏まえて教職員が独自にカリキュラムを創造できるような力量を身につけていかねばならないことに変わりはない。
「学力低下」問題を経て、今日ではあたかも「基礎学力か問題解決力か」という二者択一的な発想を押し付けるような問題の矮小化も進んでいる。当然のことだが、「学力も問題解決力も」でなくてはならない。カリキュラム開発としては、それをどう構造化していくかが課題である。基礎的な学力をつける学習には教師の指導は必ず必要だし、授業形態も一斉授業による指導も有効性をもつ。また、こうした学習では、目標―下位目標―行動目標―教材―教授―評価といった一連の流れが一般的である。しかし、創造的・発展的・問題解決的学習には教師は指導よりも支援が必要で、授業形態も協同学習が有効である。また、目標から支援までの間は学習者の反応に応じ、支援者の創意を生かしながら創造的な学びが展開されるという『羅生門的アプローチ』(注5)が注目されている。人権学習のような考え方や感じ方にかかわる教育内容は行動目標による評価にはそぐわないことから、目標の途中変更も可能な授業形態が望ましい。どちらが優れているかではなく、内容や活動に応じて、一つの単元でも組み合わせるような取り組みが必要となるのである。人権学習の場合は、協同的で問題解決的な学習が適していることは明らかである。」
☆49日目(4.22)「人権教育の歩みとこれからの取り組み(2004)」から考える
2004年当時、同和教育が「人権教育」へ変わろうとしていた時にT先輩がまとめられた論文がとても参考となります。また20年前に「これからも取組」として書かれた内容を2024年現在に読み返すととても考えることが多いと思います。
『人権教育の歩みとこれからの取り組み』から一部
「例えば、子どもたちの主体的な活動を組織する場合、生徒会組織や学級会組織をよりよいものにしようと工夫する学校は多い。しかし、その組織化の過程から生徒の主体的な参加を保障する学校はそれほど多いとはいえない。まして指導教員があれこれと枠組みを作ったりすると、生徒の意識は「活動は教師の許容する範囲のものでよい」とすることになりやすい、といったことである。この場合、指導方針や具体的な助言が子どもの主体形成に大きな影響を与えていることになる。同和教育についても同じことが言える。部落問題学習のときだけ民主的な授業をしても子どもたちからの信頼は得にくいものである。つまり、学校生活全般が授業であろうと生徒指導であろうと施設設備の利用や時間の区切り方であろうと、どこを切り取っても民主的であり、人権の姿が見えるようになっていることが必要なのである。部落問題を扱えそうな特定の教科・領域だけでなくすべての教科・領域で人権の観点で教職員と子どもの関係ができていなくてはならないといえる。そのことが了解できれば、自分は体育の教師だから教科としては同和教育にはあまり関われないなどということはないはずである。問題は、こうした観点で学校教育のあらゆる場面を眺めてきたかどうかということである。
そのような意味では、学校にいる教職員だけでなく、学校教育にかかわるすべての人が自らの人権感覚を持って、お互いの仕事やその進め方に対する“気づき”を大事にしながら、協働できる体制作り=学校経営への参画を担う必要がある。全同教加盟同教組織では、教科・領域の壁を打ち破るべく同和教育教材の作成に力を入れた時代があった。いわゆる人権学習の時間設定である。そして今、同和教育は、総合的な学習の時間に期待を寄せ、人権総合学習という形で進められていこうとしている。それは大事な取り組みだが、文字通りあらゆる場面での取り組みとはならない。むしろ、同和教育・人権教育は総合的な学習の時間の中でといった囲い込みに絡めとられていく道でもある。そうではなく、潜在的なカリキュラムを顕在化させ、その評価を学校教育の中に取り込む方法を研究すべきだと思う。学校の中の何が子どもたちの人権意識を磨いているのか、何がそれを阻害しているのかということである。この作業は、別の言い方をすれば、学校における人権文化を構築するための作業とも言える。これからのカリキュラム開発でぜひとも考慮してほしいものである。」(続く)
☆48日目(4.19)「綴る」ことから。
前掲で、90年代の本であることにびっくりしたと声もありましたが、引き続き北窓さんの本から一部を紹介します。
「子どもが綴る、教師も綴る」(P90~P92から)
私はこれまでに、いくつもの胸に熱いもののこみあげる感動的な実践報告に接する機会を得ました。そのすべてが、子どもたちの姿を丹念に伝えてくださったものでした。「子どもを綴る」ことの延長線上にそれは位置しています。
そんななかの一つにこのようなのがあります。
心閉ざすもの
大阪と京都の国境に、天王山がある。そして天王山のふもとに、大阪水上隣保館「はるか学園」は建っている。
一弘くんとゆかりちゃんは、ここから学校に通っている。一弘くんには母がいない。四歳のときに病気で亡くなったのだ。弟はまだ二歳だった。一弘くんの父は、「一家心中するよりはましだ」と考えて、身を切られる思いで二人を「はるか学園」に預ける決心をしたそうだ。
子煩悩なお父さんは、日曜日には面会に来られ、一弘くんも弟も、そんな父にとてもよくなついているようだった。
しかし、他の大人には人見知りのはげしい子だった。入学当初、どんなににこやかに話しかけても返事がなく、蚊のなくような声で「ウン」だけが言えた。
一方、ゆかりちゃんはといえば、笑顔を見せることがまったくなかった。教材「おらたちにゃ口はねえだに」のあの「もりい」のように、心を固く閉ざしたまま口を開くことがなかった。
抱きあげて笑いかけても、逃げるように腕をすりぬける……そんな子だった。
ゆかりちゃんには両親がいるのだが、面会もほとんどなく、兄と二人「はるか学園」での生活を続けている。
もの心つく頃に親の愛情を欲しいままにできなかったさびしさが、ゆかりちゃんの心の扉を閉ざし、さらに言葉をうばったにちがいない……、そう思った。
こだわり
それは、7月7日のことだった。子どもたちに短冊をわたし、願いごとを書かせた。楽しそうに無邪気に鉛筆を走らせる子どもたちのなかで、まったく手を動かさない子が二人だけいた。一弘くんとゆかりちゃんだ。二人をよんで話した。
「ねえ、何かお願いごとないの?」「書けない字があるの?」「何書いてもいいんだよ」
うなだれる二人に、私はたてつづけに言葉をあびせていた。
いま思えば、あまりにも冷たくひどい言葉だった。自分たちの願いごとが容易にかなわぬことを知っているからこそ、何も書かずにいたのかも知れないのだ。
さらに私はぬけぬけと続けていた。「おとうさんやお母さんと会いたいでしょう」と。
二人は、じっと私の目を見つめていた。私の心のなかを見透かそうとするかのように。
私は、そのときすでに二人に、「感性の鈍い教師」として見切りをつけられても仕方なかったのだ。しかし、その場は救われた。
二人は短冊を書いてくれたのだ。
おとうさん たなばたです おとうさん 一弘
おかあさんと あそぶように してください ゆかり
「ああ、書かせるんじゃなかった……」
私はもう後悔していた。それは、頭を鈍器で殴られたかのような衝撃だった。二人のすがりつくような思いをどうしてやることもできないくせに、無責任に書かせた自分がどうしようもなく惨めだった。
実は私は結婚するとき、親の承諾の得られないまま強引に己の道を貫いたのだが、その代償は大きく、私は親から半ば勘当されたような形になっていた。
親に会いたくて会いたくて会えぬつらさを、私は痛いほど思い知らされたのだ。だから、一弘くんやゆかりちゃんの心と重ねられるにちがいないと、勝手に思いこんでいた。
しかし、二人の短冊はあまりに重すぎた。私は、この重たい思いを真摯にうけとめねばならぬと思った。私自身はもちろんクラスの子どもたちと、その重さを分かちあいたいと思った。
この短冊にこだわり続けることから、学級の仲間づくりは始まった。 (『仲間をつなぐ人権学習』解放出版社P50~53より)
☆47日目(4.18)現実とつなげる学級づくり
◆北窓正明さん著書『仲間をつなぐ人権学習』 第2章「人権主義の生き方を求めて」(P85~86より抜粋)を紹介します。
・・・差別事象は実践の弱さの投影
たとえば、次に紹介しますのは、小学校二年生の「おてがみ」の学習のなかでのことです。この作品はアーノルド・ローベル作、三木卓訳で、大阪の解放教育読本『にんげん』にも載せられているものですが、友だちのいないガマくんのその寂しさを自分のことのように感じたカエルくんが、ガマくんにおてがみを出すといったストーリーのものです。
誰からもてがみのこないガマくんは、「とても不幸せな気もちで……」というところの「不幸せ」を、先生は子どもたちに聞きました。「みんなにとって、不幸せってどんなことかな?」と。その言葉にひとりの子がたった二行つづったのです。
「ぼくのふしあわせ。スブ、きのしたひでお、たかだひでお、ぼくはわからないです。」
担任の先生はこの子の書いた作文を私の前において、大粒の涙をボロボロと流されました。
「きのしたひでお」というのは、お父さんの通名です。「スブ」っていうのは朝鮮名、本名です。そして、「たかだひでお」はお母さんの姓です。「ぼくのふしあわせ」と題して書いた小学校二年生のこの子の頭のなかを、否、暮らしそのものが、この三つの名前をぐるぐると回っているのです。そのことが痛いほど担任の先生に見えているから、涙せざるを得ないのです。
通名を名のり、本名を名のり、時には父さんと母さんが別れて、母さんの姓を名のり……。そういう暮らしの現実がこの子のなかにあるのです。
子どもたちが現実にくらしのなかで抱く疑問、それにどうきちっと答えていくのか、それは何年生から部落問題を教えるのかということじゃないのです。就学前の子であろうと小学校低学年の子であろうと、生活のなかで持つ疑問やおかしいなと感じることがあります。それが自分なりに答えが出ない時に、子どもたちは日常的に引っかかりをもち、いらいらし、そして高学年になり体力がついてくると「荒れ」るのです。それぞれの年令なりに深い浅いはあれ、部落問題学習が子どもたちの生活現実、生活意識から出発してすすめられねばならないのです。(1990年発行)
☆46日目(4.17)自尊感情をキーワードに。
人権教育を核とした学級づくりのキーワードのひとつは、「セルフエスティーム」。ちなみに、キーワードはあとふたつあります。「コミュニケーション能力」「アサーティブネス(非攻撃的自己主張)」がそれです。(大阪府同和教育研究協議会の「わたし 出会い 発見」から引用。)
すでに、もうよく聞かれる概念ですが、あらためて「自尊感情(セルフエスティーム)」について。これは、「一生懸命生きているから自分が好きだ」という気持ちである。自分を否定するのではなく肯定的に認め、「自分らしさ」に自信をもち、自分を価値あるものとして思えるようになることである。そうして、自分の立場と自分の生き方に「誇り」がもてるようになると、これがアイデンティティの確立ということである。逆に言えば、自分のことを大切に思えないならば、人のことを大切にしようという気持ちも起こりにくいということである。
これは例えば、これまでも部落の子の「どうせオレなんかあかんねん」「高校行かれへんねん」「どうせ差別されるねん」という叫びに対して、その子を立たせようと必死の思いでかかわってきたことにつながるものである。
また、「いじめ」問題や差別事件の解決についても同様の問題に突き当たったはずである。原因をたどっていけば、加害者自身がつらかったり寂しかったりという生活体験の中で自分を大事にされず(「どうせオレなんか」)、自分も人も信じられなくなり、相手や被差別の者への共感がもてず、そうした恨み・つらみのはけ口としてねたみや反感を抱き(「なんでアイツばっかり」「オレだってしんどいのに」「あいつなんかどうなっても構わない」)、いじめや差別をしてしまうという深いいたみに出くわすケースが多かった。
これらに対しても、これまで同和教育の中で、生活を綴ったり生い立ちを語る中で、自分や親を見つめなおし、これまでのつらいことや反感・憤りを克服し、自分の立場に誇りを持って、差別やハンディに負けない生き方を見つけようとしてきた。これは、まさに自尊感情を育て、アイデンティティを確立することである。逆に言えば、自尊感情がしっかりしていることは、差別に対してしっかりと向きあい、世界の諸問題にも目を向けて行動できる基礎となるのである。
☆45日目(4.16)八ツ塚実さんの学級通信(3の3)
1983~1985学級の記録第3集より
□世の中が、どんなに急テンポで変わろうとも、教育の世界の方法や理念は、そう安直に変わるものではない。やっぱり、手間ひまかけてかかわりきらなくてはならない。 私はひたすらに「まじめ」作りに専念してきた。 「まじめ」さの欠落こそ、諸悪の根源だと考えている。まじめさを失った社会は、無礼・非礼の温床となる。人と人の間には、お互い暗黙のうちに守りあってきた「けじめ」というものがあった。これがあるがゆえに、わたしたちはささやかな平安を守ることが出来た。無礼・非礼は、この大切な「けじめ」を足げにしてしまう。
「けじめ」なき社会・・・それは「いじめ」社会にほかならない。
「まじめ」「けじめ」「いじめ」という語呂合わせめくが、私は今こそ、この部分に着目する必要があると考えている。(中略)教育の基本は「人権への覚め」をうながすことであると考えているし、「市民の作りあげる礼儀」こそ人権の形として現れたものと考えている。
□さあ、わたしたちがつくる学級通信はどんなものであるか。
☆44日目(4.15)八ツ塚実さんの学級通信(3の2)
1978~1980学級記録第2集より
□工夫もなく、愛もなく、努力をおしまぬ情熱もないから、当然そうなる。永年のアグラのツケがいまつくつけられている。
□それに加えて、世の中心となる考えは「経済的な効率」の論理だ。粗雑な人権感覚だ。さらに「家庭の崩壊」が追いうちかける。はびこる口先だけの評論が、この荒廃論議を一層まぜかえす。
□私はまゆをしかめない。「荒廃」の語もしり馬に乗って使うつもりはない。むしろ結構なことだと思っている。
□押さえ込んで統制をつくろうときではない。全く新しい理念を、いまこそ創造するときだからだ。私はえたいの知れない「教育の権威」をかさにきてこの仕事を続けるつもりはない。
□教育は荒廃しているのではない。いつの時も新生の模索の中にある。もし今の状況に「荒廃」の語を使うなら、日本の教育史のどの時代が荒廃してなかったというのだろう。それぞれの時代がそれぞれの時代を背景にして、それぞれ荒廃していたではないか。
□切り捨てられて、学校へもいけない子どもたちが沢山いた時代。
かわいい義勇軍や兵隊さんの養成所であった時代。
死ぬことが美徳とされ、「死ね」と教えられた時代。
個人的な立身出世の手助けに明け暮れた時代。
それぞれの時代がぬきさしならない課題を提示しながら、日本の教育の歴史の中にある。
□なぜ、いまことあらためて教育の荒廃なのか。
□今のままで流されれば、過去のあやまりを読み落としてしまう。そればかりか、美化さえしかねない。国をあげての教育批判は,他の一切の失策から目をそらす役割すら果たしている。
□もともと教育が、そこだけエアポケットのように荒廃するはずがない。いつからそんなお化けみたいな社会力学が横行しはじめたのだろう。
□このしごとにたずさわる全ての日々は、出発の日ばかりなのだ。結論を下したり、結果として評価できる日なんぞ、あるわけないんだ。
□「変わるためにこそ変えない部分が必要だ」ということと「変わらないためにこそ変える部分がある」という2つのことを「学級記録」の中から学んだ。
□「あたらしい憲法のはなし」を懐かしみ惜しむ人もある。それを文部省の変節のねたにする人もある。私はどちらもとりたくはない。惜しければ、変節も許さないのなら、自分の手でつくればよい。つくらなくてはならない。無いものねだりも、あてこすりも腹の足しにはならない。
□刻みつづけてきて、私はそこへ行き着いた。教職にあるあものの使命はまさにそれではなかろうか。
□あらためて考えてみると、私は民主主義について学んだことはないのだ。なんとなく選挙をし、正の字を連ねて開票し、話し合いもしないで多数決をやってきた。こんなことがなんで民主主義と呼べよう。
□きざなものいいとしてではなく、私は「共に学ぶ」という言葉がわが身にしみる。作りつづけ、学び続けることでのみ、ほの見えてくる民主主義。なんで私が、はなから指導者で有り得よう。歩みの中からつかまなくてはならないことにおいて、子どもとおとなの区別はない。
□日本中の教室の数だけ「民主主義の教科書」がほしい。そこでしかつくれない教科書が。このことを怠って、生きる心得をどんなに口数多く語っても、それは安っぽい人生訓でしかない。事実にうらうちされない薄汚れた授業活動は、ますます民主主義を遠いものとする。
□中学生たちと教科書をつくっていると、容赦なくわたしは教えられる。「正義のスケールの小ささ」だ。どんな小さな不正も許さない人たち」が、寄ってたかって小さな不正狩りにうつつをぬかしてきた。それが学校の輪郭となった。もともと未完成な存在である若者を、糾弾する学校や社会とは何だろう。
□あらためてはびこる教育批判なるものに耳を傾けてみよう。なんと多くのチマチマした正義による放言が混じりこんでいることか。大きい大きい不正義は、いつもふんぞりかえっている。栄光の中にある。
□「教育の荒廃」の語が、このような風土の中で使われている事実をこそ、私はおそれる。今、ポケットに手をつっこんで、マユをしかめているだけなら、それはまぎれもなく、教育の挽歌を奏でる手助けをしているのだ。
□私は、このてみやげを携えて、あなたと教育を語りたい。あなたのてみやげから、たくさんのことを教えてほしい。このプリントは、私が中学生に教えたことではない。私も共に学んだことの数々なのだ。1981
☆43日目(4.12)八ツ塚実さんの学級通信(3の1)
いま、学級通信をスタートする人は多い時期かも知れません。
八ツ塚実さんの「学級記録」に書かれていた内容の一部を紹介します。
2002年、尾道にある自宅を改造した資料館に行かせていただきた時に、八ツ塚さんのお連れ合いさんに頂いた3冊の本からの内容です。『学級記録第1集~3集(復刻)』1975~
□教育の仕事は、「継続」という時間の軸と「集団」という人間との掛け算でできる平面の上に、「営み」のすべてをつなげて素材とした建造物を構築することである。
□随所に使われる柱や板は、すべて「人権」と「平和」の素材であること。
□一時的な「投げ入れ」は教える側の自己満足でしかなく、日常化以外には、解放教育・人権教育の目的は達成されないということ。
□生徒にとって、ひとりの人間が自分の教師であり、わけても学級担任であるとは、何であるのか。学級編成と担任任命が教育側の手で一方的に行われている現状の中で、始業式の日に即「教師」でありえるのか。
□一人の人間が、一人の子どもにとっての教師になるためには、継続して呈示した行為の評価を通じるしかないのではないか。
□「一人を大切にする」とは、何をどうすることであるのか。そのことをオームにように口でとなえるだけで達成できるのか。
□子どもの意識のすこやかな変革を願うなら「ゆっくりと、ゆっくりと」「少しずつ、少しずつ」たゆまず語りかけ、はたらきかけるしかないこと。
□珠玉にような教材は、まさに日常の自分たちの生活そのものであるということ。
□自分の生活の教科書は、自分の手でしか作れないということ。
□学校が企画し実行する年間数十を越す「行事」は、切れてそこにあるのではなくすべてつながっている。「すべてつながっている」ことこそ教材の最もたるものであること。「行事」は日常生活の総括であるということ。
□感動・悲しみ・ためいき・に対してこの「学級記録」は着目しきれたであろうか。
□私たちの仕事は、途中やめが出来ない仕事だということ。
□学校では、その活動を開始するやいなや、ただちに教科の学習が有無をいわさずに行われる。
□国・社・数・理・音・美・保体・技家・英の各教科の教授活動。人類の文化遺産のさまざまな分野を受け継ぐのだから当然のことだ。がしかし、「その前に」ないしは「それと並行して」学んでおかなくてはならないことがある。それを怠ったり、軽視したりするから学習の電車に乗り遅れたり、乗れなかったりする人ができるのだ。
○なぜ勉強するんだろう
○どうやって勉強したらいいんだろう
○誰もが例外なく通る道筋
○学力とは何だろう
○学びの成果で、人からとやかく言われたりすることはないんだということ。
○ささやかな勇気と自信
○自分がやっていることの意味
□教師集団ということばを、あまりにも安易に使いすぎる。教師集団とは、何人かの教師が一ヵ所で仕事をする上で、時間ややり方などの一線をそろえるくらいのことをいうのではない。ましてや、線をそろえて仕事をしないでもすむような協定を結ぶことではない。一人ひとりの全力をてみやげにして、集団の質を高めることだ。
□「これが、わたしのささやかな自己に課した実験です。ここまでなら私でも出来ます。」事実に裏打ちされたこのことばを、だれもが持ち寄らなくてはならない。集団とは、なれあいの場をいうのではない。
□私の「学級記録」は私のロマンだ。最後の最後、私がたったひとりで教室に立って、彼らと学習活動するとき時の「私の教科書」であり「私の指導書」だ。
□卒業式 その後ろ姿を未ながら毎年自問します。「今年もひたむきに教師になろうと努力した1年だったろうか」と。
□「花はすぐ咲くもんじゃないんだ。月日をかけて咲くものだ。」目の前の花壇がそう教えてくれる。1978年3月24日
☆42日目(4.11)教科書無償化の取組について
入学式の中で、教科書授与時にこれまで「この教科書は これからに日本を担う皆さんへの期待を込め、国民の税金によって、無償で支給されています。大切に使いましょう」と話していましたが、今年度は、相談してアドバイスを受けながら「この教科書は、よりよい社会を造っていくために、高知県からはじまり、多くの人々の努力によって、義務教育を受ける小・中学生のみなさんに無償で支給されています。大切に使いましょう」としました。わずかな内容でしたが、「何を子どもたちに伝えるのか。伝えたいのか」を考えた大切な出来事でした。
以下の文章は高知市立長浜小学校のホームページの一部です。「子どもたちは,新学期をむかえるたびに,真新しい教科書を手にし,ページをめくりながら,これからはじまる勉強に期待をいだき,進級した喜びをかみしめることができます。
しかし,この教科書も今から50年ほど前までは,みんなが新しい教科書をただでもらえるというわけではありませんでした。
その頃,教科書は,毎年,新学期をむかえる前に各家庭でそろえることになっていました。3月になると保護者たちは,古い教科書をゆずってもらったり,古くて使えないものや,ないものだけを買いそろえたりして苦労していました。新しい教科書を全部そろえると小学校で700円,中学校で1200円ほどかかりました。一日働いても300円ほどの収入しかなかったのですから,子どもの数が今に比べて多かったその当時は教科書をそろえてやるだけでもたいへんな出費でした。
1960年(昭和35年)ごろになると,物価も値上がりをはじめ,教育費の保護者負担を軽くしようという動きも出はじめました。このころ,長浜地区の中でも,学校の先生たちや市民会館の館長さんといっしょにお母さんたちの読書会がはじまりました。2年ほどたつうちに,「わたしたちが習った歴史と今の子どもたちが習っている歴史は全然ちがう。わたしたちも子どもの教科書を使って勉強しなおそう。」という声が出はじめ,憲法の学習もはじまりました。
その中で,憲法26条に記されている「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。」という部分が問題になりました。「義務教育はこれを無償とするというのだから,教科書を買うのはおかしいのじゃないか。」「教科書はもともと政府が買いあたえるべきものだ。」「教科書がただでないということは,憲法で定められたことが守られていないということではないか。」ということが,話し合わされました。
そして,1961年(昭和36年)3月に,長浜地区で行われた会合の中で,「いくら請願しても効果はない。ただで配るまで買わずに頑張ろう。」という提案がなされ,校区のいろいろな団体が中心になって「長浜地区小中学校教科書をタダにする会」がつくられました。
この会は,各地で集会を開き,署名運動をはじめ,いっしょにたたかう団体もふやしていきました。教科書の無償要求は,憲法を守るための運動であるということに気づいた人々は,この運動をもりあげささえていきました。
その要求の正しさが理解され,1週間もたたないうちに長浜地区で1600名もの署名があつまりました。その要求を高知市の教育委員会にもちこみ,「憲法を守るために教科書を買わない。」というたたかいを始めました。運動は,新聞やテレビにもとりあげられ注目をあびました。
教育委員会は,「教科書をタダにする会」との交渉によって,無償の要求は正しいと認めましたが,全員に教科書を配るという約束は絶対にしませんでした。買える能力のある人は買ってほしいという教育委員会の要求をはねのけ,2000名の児童生徒のうち約8割にあたる1600名が,教科書を買わずに新学期がスタートしました。
学校では,教科書を持たない多くの子どもたちのために,先生たちはガリ版刷りのプリントを使って毎日授業を進めていきました。
その後,運動の正しさがたくさんの人々や団体・政党に支持され,全国的な運動に発展し,国会で大きな問題として取りあげられました。政府もついにこの要求の正しさを認め,1962年(昭37年)に法律をつくって,翌年から段階的に教科書が無償で子どもたちに配られることになりました。
私たちが,今なにげなく手にしている一冊一冊の教科書には,このような運動があったのです。
1961(昭和36)年からはじまった教科書無償の運動から今年で50年目を迎えました。この運動の歴史的な意義や当時のようすを,今の子どもたちや地域の方々など,たくさんの方々に知っていただきたく,教科書無償運動50周年記念パネル展を開催することになりました。
高知市立長浜小学校【教科書無償運動50周年記念パネル展資料より】

☆41日目(4.10)子どもにとっての特別支援学級②
2007年から、『特別支援教育』が学校教育法に位置づけられ、全国すべての学校において、障害のある子どもへの支援をより一層充実させていくことになりました。
もちろんそれまでも支援はしていたわけですが、一人一人のもっている力をさらに高め、より適切な支援をするために、このような名称となりました。
特別支援教育は英語でspecial needs educationまたはspecial supporteducationと表記されます。となると、説明の内容(草案)ですが、
・特別に助けが必要な時に、誰でも利用できる学級です。
・視力が見にくい人には、自分に合った「めがね」でサポートするように、たくさんの人と一緒の教室で学ぶのが苦手であったり、授業での進度がゆっくりがよかったり、静かな学習環境が落ち着いたりする人は、あなたに合う学習環境(教室)があります。
・あなたとおうちの人と学校の先生と一緒に教室利用について相談します。
・誰でも学習や学校生活の中で“助けてほしい”時があります。そんな時に解決するひとつとしての「特別支援学級」です。
特別支援学級の子たちの障害については説明する必要はありません。ただし、『接し方』については、子どもたちが疑問に思うことも出てくるでしょう。たとえば、『(特別支援学級の自閉症の)〇〇くんにあいさつをしても何も返ってこない。無視されているのかな?』と思う子が出てくるのも自然なことです。そういう時には『先生や支援員の先生ににどのようにしたらいいのか聞いてみてね』と話します。その子に合った接し方を具体的に教えてもらえることでしょう。
特別支援学級の子たちと交流することは、個々の違いを理解する上で大切なことです。早い段階で知ることにより、発達について偏見をもたずに接することができるようになるでしょう」障害イコールマイナスと考えているのは、以前の障害児教育の残滓かもしれません。
子どもたちの発達段階によって理解の仕方が変わってくるので、学年相応の働きかけの仕方があると思います。また、やはり子どもたちはまずは身近な大人の様子や考えに一番影響されると思います。
子どもたちの理解を深めるには実際に一緒に活動する「交流活動」が一番だと感じます。ただ、その際に大切なのは、その近くにいる大人が適宜適切な話しをすることだと思います。言葉を発することができない子はどんな思いをしてそれに取り組んでいるのか、なぜ彼はじっとそこに座ってられないのか・・・。そのためにも学校・教職員集団がもっともっと理解(更新)をすすめる必要があると思います。
ただ、やっぱり理解はすぐには深まりません。小学校1年生のその子が6年生のときに「あ~、私は1年生の頃あんなこと言っていたけど、あれは間違いだった。」と思えるように、豊かな出会い(正しい理解・ありのままをわかり合う相互の取組など)を少しずつ積み上げていくものだと思います。
☆40日目(4.9)子どもにとっての特別支援学級①
かなり以前、勤めていた学校での生徒総会議案検討時、いわゆる通常学級に在籍する生徒が「特別支援学級ってどんなところなのか知らない。説明してほしい」と発言した。そういえば、特別支援学級、特別支援教育について、生徒らの発達段階に応じて、正しい理解を深める学習や取組が出来てなかったことを反省した。私たち自身は、様々な書物や資料、研修から多文化共生社会やダイバーシティ、インクルーシブ教育などなどの内容を学んでいくが、子どもたちが理解できるような取組(伝え方)は、丁寧に考えていかねばいけないと思う。学校と教職員の特別支援教育観自体が問われることだと思う。
インターネットで検索すると、
[お母さんが、特別支援教育のニーズのある我が子にどう話すか?が多く記されています。]例えば
・支援学級の方が、先生が教えてくれる時間が長いんだよ。できること、今より増えそうだね!(本人のメリット)
・人数が少ない方が、話を上手に聞けるもんね。そっちの方が得意だもんね!(苦手の改善<得意を活かす)
・クラスの人数が少ない分、質問がしやすくて、すぐ教えてもらいやすいから。(本人の過ごしやすさ)
インターネットには、先生が本人のクラスメイトに話す例のNGな説明もありました。
①「Aさんは、支援学級に行って、みんなに追いつくために頑張っているよ」
『追いつくため』という言葉は避けたほうが良いです。支援学級の目的は、『その子に合った特別な支援を受けるため』です。
クラスの子に追くためのものではありません。
日本教育の歴史性からみると「みんなと同じ」がまだ根強いですが、ここの目的意識の違いは、お子さんの過ごしやすさを作る上で重要になります。
②「Aさんは、勉強が苦手だから、できるようになるために、支援学級に行っているんだよ。」
ポイントは『勉強が苦手だから』というところです。支援級は、欠点や苦手を改善するために行くところではありません。
「勉強ができない子の行くところ」という印象を子どもたちに与えてしまいます。
③「Aさんは、勉強をもっとできるようになるためだよ。応援してあげてね。」
『応援してあげてね』は、子どもの中で上下関係を作ってしまう可能性があります。
頑張っているのは、学校に来ている全ての子どもに当てはまり、そこに原(通常)学級や支援学級の違いはありません。
それぞれ、学びやすい場所や方法に違いがあり、別に支援学級に行くことが特別なことではなくて、自然と送り出す、迎える学級風土づくりが大切です。(続く)
☆39日目(2024.4.8)始業式 「綴ること」の意義
春休み中にも生活ノートについて協議し、新年度は「やりとり帳」というものを活用することとなりました。それに併せて、生徒(学校便り「ひとのあいだ」版にして保護者にも知っていただく形式)へ資料を配り、取組の説明を行います。参考に、補足説明文は以下の通りです。
「やりとり帳」へのねがい
長い間、担任をしていて、『やりとり帳』」などの〈ひとこと日記〉や〈生活の記録〉の取組には、いろいろな思いがあります。おもなねらいは,「君たちことをよく知り、しっかり応援したい」という思いが大きかったように思います。記入の様子や内容から,「君たちの学校生活が充実しているのか」、「悩んだり、困っていないか」などの変化を見逃さず、話を聞いたり、相談を受けたりするために大切にしてきた取組です。日記に書いてくれた内容を、時には、学級通信に掲載して、クラスへの提案や学級会での話し合いにもつなげたり、クラスのみんなに紹介したりして、学級をよくしていくための活動にも役立ててきました。
だから、皆さんが、学校生活での出来事や日常の暮らしを「綴る(つづる)」ことによって、自らの生活をしっかり観察し、自分たちの生活を認識し、たくましく生きていく力を高めてほしいと思うのです。
何か心配なことがあるのか、弱々しい文字でのつぶやきが書かれた生活ノート、うれしいことがあったのか、はずんだ文字の生活ノート、何度も消したり書いたりした跡が残る生活ノート、消しゴムの消しカスがはさがっている生活ノート、好きなキャラクターのイラスト・・・などなど、「やりとり帳」の記述を通して、しっかりと君たちの生活を知り、応援しようと思います。
「書くことは考えること、考えることは生きること」というコトバがあります。
「ひとこと」日記」を書くというのは、表現や伝達の手段であることは間違いなく、伝えるための技術をみにつけることは、将来社会に出てからとても役立ちます。しかし「綴る」ことにはもうひとつ、だいじな役割があります。それは「認識」といいます。残念ながら、最初から作文が好きな人は、あまりいないかもしれません。それは難しいからです。自分の前にある「人・もの・できごと」にぴったりな単語をみつけ、次には単語どうしを結びつけ文にし、さらに組み合わせていくという、頭をフル回転しなければならない作業です。時には、できごとをよいととらえるか、悪いととらえるかなどという、価値判断もしなければなりません。自分の視点で書いているので、うそはかけません。鉛筆を進めるのは、大変な仕事です。
小さい頃、君たちは「話しことば」の中で生活しています。相手が目の前にいて、視線やしぐさ・表情なども伝達の手助けとなるため、多少コトバや言い方や文法がまちがっていても、おおよそ通じてしまいます。しかし「書きことば」ではそうはいきません。目の前に相手はおらず、頼りになるのは文だけなのです。だからこそ、必然的に対象をしっかりみつめ、掴(つか)もうとし、価値判断をすることになります。家族・友達・社会・自然などを題材として「綴る」なかで、君たちはしだいに「認識」を深めていきます。こういった「認識」を獲得する学習を基盤とし(あるいは並行して)、プレゼン発表の原稿やレポートを書いていくなら実生活に根差した、重みのあるものとなるはずです。飛躍的に認識の幅が広がる中学校のこの時期なのですから。
もうひとつ、書くことの基本は、身の周りのことを、あったことを、あったように、自分のことばで、です。時間軸に沿って、「○○でした」「○○しました」というふうに、過去形で書いていきます(展開的過去形表現といいます)。これがある程度できるようになってはじめて、前述のさまざまな機能を持った文章を書けるようになっていきます。
新しい『自主学習ノート』と『やりとり帳』を使った取組にを大切に、チャレンジしてみましょう。
☆38日目 席替えではなく、なかまづくり2(生徒への配布資料)
席替えではない。班づくりである。
新班は、新しい級友と関わり、知り、
共にがんばり合う仲間になるための
取り組みなのだ
なぜ,班をつくるのか。
(1)この時期、これまでの先輩たちの学級を見ていると,
いくつかの仲良しなグループに分かれている様子が見られました。
もちろん気が合うという理由でグループが形成されるのは自然なことで,学校生活を楽しく過ごしていくには大切なグループです。
(2)しかしグループの中だけの友人関係にとどまり、クラスの中で自分の思いを語ることが少なくなってくる心配もありました。
さらには,人間関係の固定化により,「あの子は,いつもああだから」「きっと,あの子のせいにちがいない」といった決め付けや,「どうせ言っても変わらない」とあきらめて声をかけたりしない様子も見られることがありました。
(3)クラスはみんな一人一人にとって,お互いの人権が尊重され,安心して過ごせる場でないといけないことは言うまでもありません。
みんなが充実した学校生活を送るためには,
①「自分らしく生活していきたい」と思う気持ちをお互いが尊重して,
②係や当番活動、委員会活動に積極的に取り組み、
③「班のひとり、クラスのひとりである」という意識を持って協力、行動し,そして
④それをみんなで認め合うということが必要です。
(4)班活動は,授業中はもちろん,掃除や給食、係の仕事など学校生活の様々な場面で大切にしなければいけません。その班活動を継続して取り組むことで,自分の気持ちを伝え,仲間の思いを受け止め,がんばり合う仲間になっていくことを、○中学校では大事にしてきました。
(5)○中学校の班づくり(仲間づくり)は
①「約束を守らない」「何度注意しても言うことを聞いてくれない」「人に嫌なことを言う」など,話のやりとりの中で,様々な衝突やトラブルが起こることも予想されますが、その時は、自分をごまかしたり,人のせいにしたりしないように,「私」を主 語として,自分の気持ちを伝えよう。
②自分の気持ちを出せる班をめざそう。
③小さなことでも話し合おう。(言い合いなどが生じたときこそ,問題を解決していく 力を磨くチャンスと考えよう)
④相手の気持ちを深く聴こう。お互いを表面的な言動だけで判断するのではなく,納得がいかない友達の態度や様子に「何でなんだろう…」と疑問を持って終わるのではなく、粘り強くかかわる中で(班活動を行う中で),それまで抱え込んでいた不安や悩み・しんどさといったものを聞いたとき,「そうだったんだ」と,初めて友達の生活背景や言動に込められた思いを知ることはとても大切なことです。
そして,そのことに共感し,一緒になって考えてくれる仲間の存在を感じたとき,
「一緒にがんばり合っていこう」という学年の力はさらに深まっていきます。
☆37日目 通信のロゴづくりって何?
「通信のロゴ」って何ですか?に応えて。
生徒らの発想やセンスはすばらしいものがたくさんあります。ロゴを募集し、ストックして、発出する学級活動資料(通信)に添付します。書いてくれた枚数分全部使わないといけませんね。
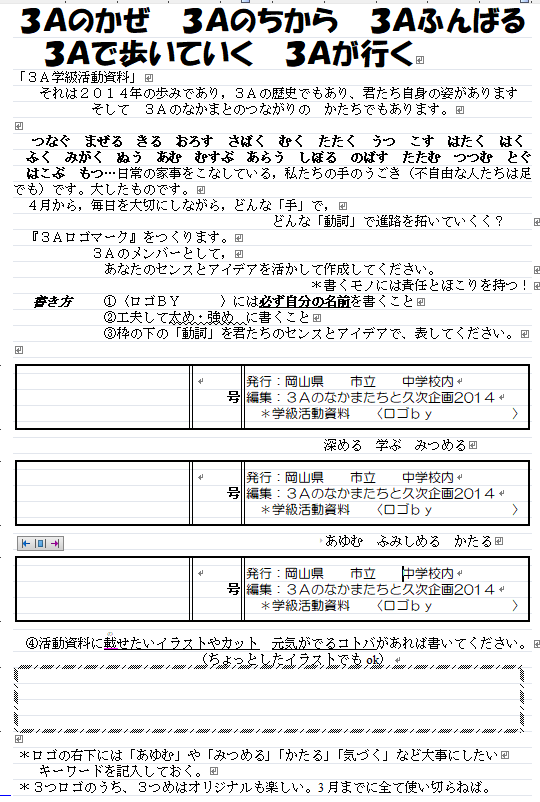
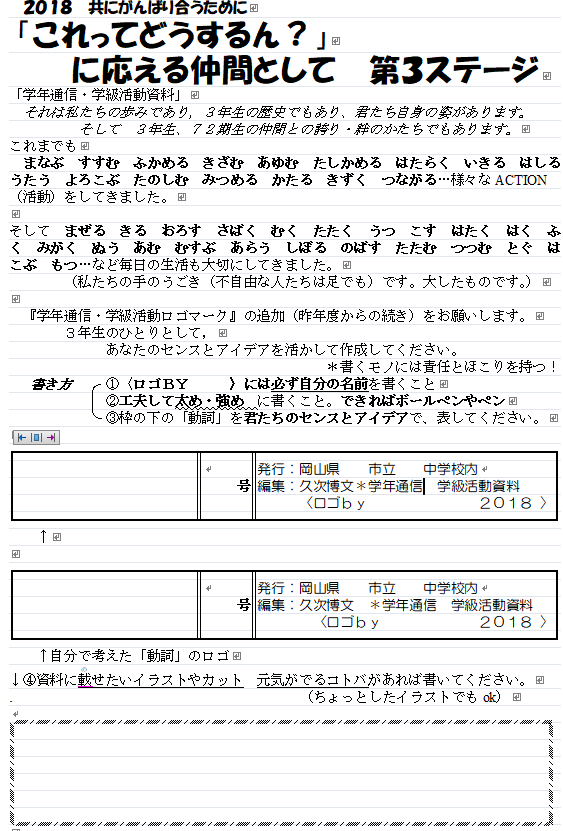
☆36日目 つらぬくこと こだわること
学級通信第一号については、年間・3年間をつらぬく指針がなくてはいけないと思います。また、通信の最終号でも、その内容に再掲示し「ふりかえり・まとめ」をせねばなりませんね。参照イメージのリクエストがありましたので、結構一方的なメッセージばかりで反省しますが、ご参考に。
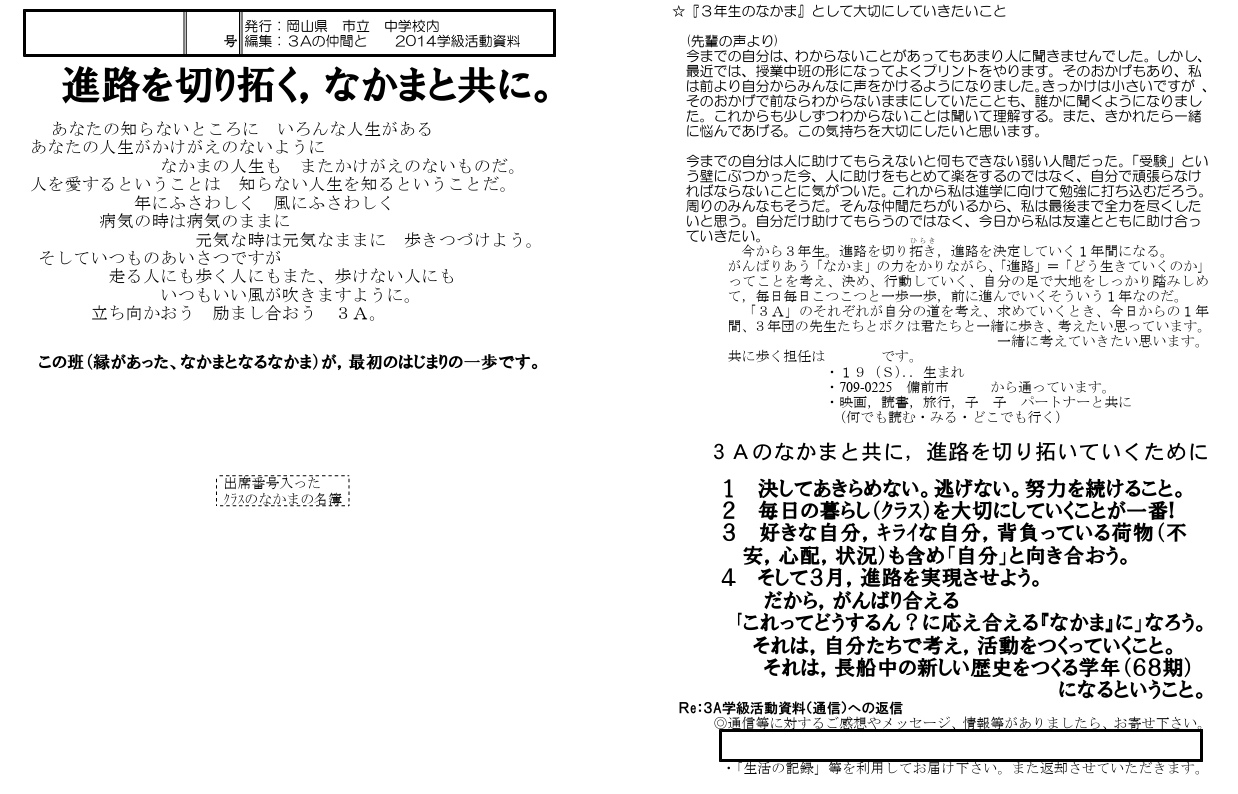
☆35日目 学級通信第1号の発行に向けて
子どもどうしが「しんどい」ことや「つらい」ことを語り合い、また「がんばり」合える集団になっていほしいと多くの教師が願っています。だからこそ、教師自身も自分自身の「生い立ち」や関わってる人権課題を「自己開示」しなければならないと思います。「4月最初から「暗い話」はちょっとしたくない」と聞いたことがありますが、人権問題は決して「暗い話」ではありません。真剣な生き方に関わる自「深い話」ならば中学生をきっと受け止めると思っています。またその語る内容によって、最初に書く「進級にあたって」などの作文の中身が大きく異なってきます。表面的な「進級して頑張ります~!」ではなく、やはり4月、自分自身の課題を深く見つめていくところからスタートしていけたらと思います。また子どもが開示した(取り組もうとしている課題)をしっかり受けとめ、寄り添い、覚悟をもって学級経営を進めていきたいと思っています。
新年度準備はいろいろありますね。
メモ
(1)学級通信1号 +当面の日程表
(2)学級通信「ロゴ」づくり
(3)生活班による春休み報告会
①単に点検にならぬように、班で春休みのできごとを話題にしながら、回収したいです
(4)朝の会、帰りの会改善①自主的な自治的活動の一助として
(5)提出物について 保護者とつながるために
・学校で子どもたちがおこなっている(取り組んでいること)を知ってもらう
(6)日直のしごと全
(7)班係活動一覧
(8)班長選出アンケート→班長会
(9)立候補(学級・専門委員)届
(10)道はいつもひらかれている色紙
(11)学級日誌(日直から日直へ)
(12)わたしはわたし(仲間を知るワークショップ)
(13)学級目標班会議WS
(14)最初の座席表
(15)自転車点検表 ①たかがされど
(16)誕生日原稿にお祝いメッセージ
☆34日目 今日は県立一般入試の結果発表の日。
残念な結果となった生徒らは、事前につくった「進路計画」表をもとに、新たな道を進んでいくことになるのですが、こころが揺れ動き、なかなか覚悟が決まらない場合も多々あります。そんな時、生徒(保護者)の気持ちをしっかり聴くことがやっぱり大切ですね。進路の決定は生徒たちにとって大変な作業です。特に、精神的、家庭的、経済的にハンディを負った生徒たちの気持ちを教員はどれだけ受け止められるかということ、それを受け止めた上で、的確に情報を伝え、考える場を提供することが重要です。そうすることで生徒は自ら選択し進路を決定していくことになります。
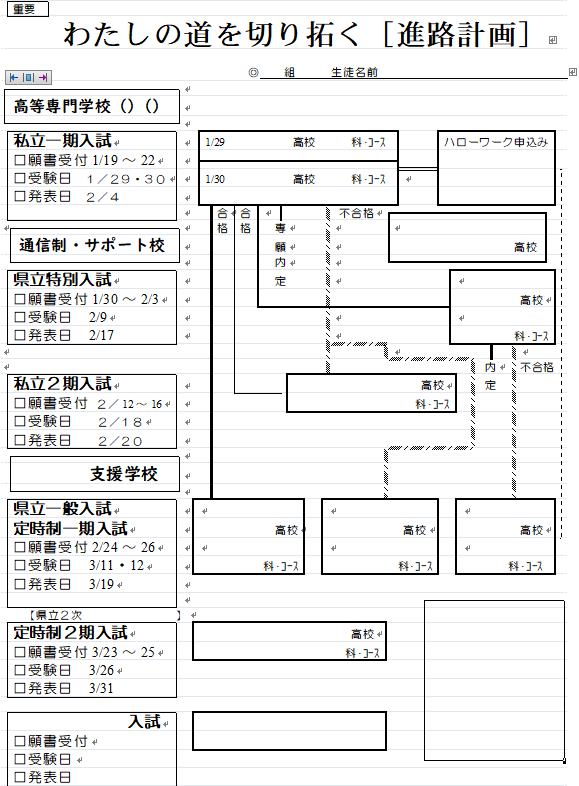
子どもたちにとって多種多様な進学先が増えました。進路指導には、私たちも謙虚に、正しい進路情報を更新していかねばなりませんね。
☆33日目 元気が出る行事(体育会・文化祭)へ
保護者から応援メッセージをいただく取組
おうちの方々からの子どもたちへのエールは、ちからがわいてきますね。当日より前に配布(お願い)し、2週間後くらいまで募り、「お便り」でかえします。
走り抜け!自分らしくせいいっぱい
体育会・「子どもたちへのがんばりメッセージ」をありがとうございました。
○中学校は、子どもの成長を軸として、保護者・地域と学校がパートナーとして連携・協働し、互いに意見を出し合い、学び合う中で、地域の将来を担う人財の育成を図るとともに、地域社会とのつながりを深めていく、「地域とともにある学校づくり」をめざしています。
いただいたメッセージの一部を紹介させていただきます。
○中学生ともなると、恥ずかしさから、なかなか本気を出しにくいものかと思っていましたが、皆、「真剣」に、「本気」を出し尽くしてる様子で胸が熱くなりました。(わが子も、筋肉痛に悩まされていま したが、それさえも「本気」「頑張り」の表れに感じられて、嬉しく思いました!)体育委員長の○○君の最後のコトバには本当に感激・感動しました。素晴らしい一日をありがとうございました。ここに 至るまでの先生方のご指導に感謝いたします。本当にありがとうございました。
○保護者観覧の体育会が開催できたことに感謝します。部活動で足の裏の皮が剥けてカットバンを貼った り、靴下を二枚履いたりして・・・、他の事はあまり言わないので、食事の時に「ポロッ」と言ってくれ る言葉で解ったり、「頑張っとるな~」と話したりしていました。中学校になりと、生徒がだんだんと 「主」になって動いて、成長を感じることができた初めての体育会でした。皆の一生懸命に頑張ってい て、親も頑張らんとな-と思いました。[みなさん頑張っておられますと思います。(_ _)PTA事務局)より]
○体育会に向けて、暑い中で先生方や子どもたちで毎日練習してきたことを聴いていました。「嵐の曲で体操をするんよ」って、少しネタばれしてくれたり、当日をとても楽しみにしていました。「リレーで 走るのが緊張する・・・」、「友だちが団長だから勝たせてあげたいんよ」って、早朝起きてランニングしたりまでしていました。子どものやる気と友だちを想う気持ちがとてもうれしかったです。最後の中学校の体育会は、私を幸せな気持ちにさせてくれました。暑い中、本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。
○中学生になって初めての体育会でしたが、とてもよくがんばっていたと思います。どの競技もほぼ全生 徒が出場する状況の中で、どの競技も白熱し、おもしろかったです。子どもは、自分の係の仕事も全うしていたようで、成長している姿にうれしくなりました。暑さのために、体調管理が難しい近年ですが、誰も大きなケガや体調不良になることなく遂行できて良かったです。
○久しぶりの中学校の体育会でした。子どもたちの人数も少なくなっており、寂しいかなと思いましたが、一人ひとりが頑張った様子もみることができ、何より、我が子がフル出場だったので、非常に充実 した、忙しい体育会を楽しませていただきました。毎日「足痛い」と、頑張ったかいもあり、この前まで小学生だった我が子も「ソーラン」を踊りきり、立派な○中生になったなあと嬉しく思いました。
中学3年間、走りぬけておくれ!!
☆32日目 何を綴るのか。何のための「振り返り」「感想」なのか?
ダルクさんとの出会い(例)
書くことは考えること 考えることは生きること
◎薬物乱用防止教室(人権集会「私らしく あなたらしく共に生きていくために」)の,生徒の「ふりかえり」を一部紹介します。
○お二人の話を聴いて,いろいろ辛い過去があって,薬物に手をつけてしまって,最後に言われたとおり,自分は薬物に手をつけたくないなと思いました。一人の方が 言われていた「良いウソをついて,相手をこまらせないようにしていた」というのに少し共感しました。依存というのは怖いことだし,回復するのにも時間がかかることが分かりました。
○自分の気持ちを日常の中で言えるようにしたい。薬を使わなくても「人生,楽しいことばかりでではない」ことを頭に入れて,辛いことも乗り越えて,命を大切にしていきたい。
○自分みたいに本音を言えない人がいたんだとびっくりした。一人ひとりに理由があって手を出しているんだと知り,僕は手をさしのべたくなった。今,お二人が,自分のことを素直に言えるのはすごいことだと思う。
○「自分みたいになるな」と自分を否定したことにとても驚いた。
○辛い,悲しいと思うことを一人で抱え込む,それから自分の人生が変わっていったということを聴いて,人間って全部を一人で抱え込んでしまうと「間違った道」を歩んでしまうこともあるんだと感じました。今の自分の生活をふりかえってみて,「どう生きていくか」をお話してくださったことを頭に入れ,過ごしたいと思いました。
○何か心配ごとや相談したいことがあれば,すぐに相談しようと思った。
○薬物はよくないし,やりたいと思わない。でも,自分が病んでいるときに誘われたらしてしまうと思ってしまった。もしも,病んでいる人がいたら,一緒にご飯を食べに行って,話を聴こうと思います。
○薬物以外でも,スマホなど普段いろんな人が使っているモノでも依存症になるから気をつけたい。
○自分も断るのが少し苦手なので,本当に嫌な時はしっかり断り,自分のやりたいことをやっていきたいです。
○今は,自分は絶対に関わることがないだろうと思っていたけど,以外と身近にあるから,人ごとでは済まされないなと思った。「一度のあやまちが,人生を大きく変 えてしまう依存をしてしまうと,一人では抜け出すことができない。周りの人がどんどん離れてしまう・・・。」この言葉に私は,薬物の怖さをあらためて感じ,すすめられても,断られるようになりたいと考えました。
○「ダルクにいても死んでしまう人がいる」というのを聴いて,びっくりした。薬物を一度やってしまうと,もう,後戻りができないことを知った。薬物で何もかも失うと聞いて衝撃的だった。薬物は絶対やらないと決めた。家族・友人を大切にしたいと思った。
○人に断れる自分になりたい。
○NOと言える人間関係をつくっていきたい。
○「他人事と思っている」という言葉を聞いて,もしかしたら,自分もそう思っているかもしれないと感じた。いつもの授業で習うのとは違い,言葉一つひとつに重み や現実味があり,その言葉が心に刻まれていくような気がした。孤立感などの負の 感情が精神的な理由だと知り,自分も気をつけなくては・・・と思った。
○僕は絶対やらないし,依存もしないと思っていた自分が心のどこかに居たのだと思います。ですが,今回のお話を聴いて,「絶対」なんてないんだとあらためて思いました。僕の人生の中で,今回の防止教室は一生消えない大事な1ページになった と思います。身近にある危険から目をそむけず,相手も自分にも優しくなれるようにしたいです。
○自分を大切に思ってくれている人がいるかもしれないから,その人たちとずっとか かわっていけるように,「薬物」は使わないようにしようと思った。親戚や友達が困っていたら,しっかり相談にのろうと思う。もし,自分が悩みをかかえていたら 友達を頼ろうと思った。「薬物」が日本からなくなってほしいと思った
☆31日目 何を綴るのか。何のための「振り返り」「感想」なのか?
「ホームレス問題」学習での学び(例)
◎川元さんとの出会い・「ホームレス問題学習」での「ふりかえり」の一部を紹介します。
○家があって,家族がいるのに帰れないし,頼れないのはすごく悲しいことだなと思った。岡山で実際にみたことがなくて,完全に他人ごとだと思っていた。本当にそういう人たちがいて,支援する人たちがいるのを学んで,自分でも何か出来ること があるかもしれないと思った。
○ホームレスの方に対する見方・考え方が変わった。いろんな苦労や恐怖がある中で 生きていて,僕たちよりもずっとすごいんだろうなと思った。安心して暮らせるよ うな,そしてホームレスの方がいない世界を作っていきたいと思った。僕は,ホームレスの人を下に見るようなことはせず,困っている時は助け,支えあうようになりたいです。
○私はあまりテレビや新聞などをみないので,今,社会にどんな問題があるのか余り 知りません。だから,これからはニュースや新聞で,今,どんな社会問題があるのか知っていこうと思います。ホームレスの人に出会っても,軽蔑するのではなく,周りの人と同じように接します。あと,生きる意味も考えていきたいです。
○生きる意味について考えた。僕は前から「人は死ぬものであり、死にたいと思うのなら死ぬのも別にいい」と考えている。それに加えて、「死んでもいい」という考え方が嫌いだ。生きたいのか死にたいのかはっきりしない、その考えを嫌悪している。しかし,今回のことを学び、生きる意味についての見解も少し変化があった。僕は今まで都会で生活に充実している人ばかりみて考えていた。しかし、孤立し、社会全体から否定されてきた人たちのことを学び、「人の生死は、その人たちが決めることだ」と思った。「死んでもいい」と思っている人たちが今も、生命活動をしているのは「生きたい」という本能があるからだと思う。その人たちはその本能に気づいていないだけではないかと思う。僕たちにできるのは、声をかけ、社会と結びつけることで、本能を感じさせることだけだと思う。人間は薄情だが、あたたかい心をもっていてほしいと思った。根本的に「死ぬのは自由」という考えは変化 していないが、その上にある「死にたいと思うなら死ねばいい」という考えが、「一度、生きたい気持ちがないか考えてみるほうがいい」という考えぐらいは変化した。
○今の僕はすごくめぐまれているのだと思いました。家族は優しいし、友だちと会話することが出来ている。だがいつか自分もホームレスになるかわからない今の世の中で、「これから僕はどう生きていけるのだろう」という考えがまた深まりました。何回かの授業では、自分にみえている明るい未来以外もみせてくれたことに感謝しています。大人は「君たちの未来は明るい」「社会は苦しいけどすばらしい場所だ」と言われますが、僕は社会にでるのは今は不安です。本当の幸せとは何なのだろう。僕たちは暗い世界を歩まなければいけないのか。大人が敷いたレールの上を走らなければならないのか。僕に分からないけど、一日、一日をがんばって生きていこうと思いました。
○ホームレスへの偏見がすごい中で支援活動をしているのはすごいと思った。ホームレスになる理由はそれぞれあった。ただ命をつなぐだけでなく、生きる上で大切な人間関係・信頼を創ろうとしている川元さんはすごいと思った。ボランティア活動に参加してみたいなと思った。
○信頼関係を築くこと,生きる意味について考えた。人数調査では,たとえ国が出した結果だとしても簡単に信じず,自分の目で,耳で,見たり聞いたりすることが大切だと思った。これから私は,周りの友人・家族・先生らと話し合いながら,生きる意味を見つけていきたいと思う。本当に困ったときは正直に「助けて」と言って,まわりの人に頼っていこうと決めた。
☆30日目 進路公開(28日目)へ、つながる3年間の進路・生き方学習
身近なひとに聴く(聞き取り)
1学期懇談資料
2024年7月20日~
1学年 保護者・生徒諸君へ
1年生総合的な学習の時間 夏休み聞き取り課題
身近なひとの「中学校時代」から学ぼう
~「進路」は「どう生きていくか」ということ。仲間と共に進路を切り拓こう~
への協力と子への励ましを!
保護者の皆様におかれましては、本校教育活動に対して多大なご支援をいただきありがとうございます。
さて、1年生は3年間の継続的な進路学習を進め、自分らしい能力や適性をもとにした進路実現をめざしていきたいと考えています。
そこで、夏休みには「身近なひとの中学校時代」についての聞き取りのご協力をお願いしたいと考えています。2学期には聞き取りの発表会を行い、生き方(進路)についての学習をさらに深め、そこから進路やしごとについての正しい認識や望ましい職業観について深く学んでいきたいと考えています。
これから自分の進路を切り拓いていく子どもに、身近な方から「生き方」についてさまざな経験を語ってもらいたいと思います。それによって進路に対する考え方や、職業観についての考えを学ぶことと思います。今回の「聞きとり」の協力をよろしくお願いします。
具体的内容
1 提出期日 ○年8月30日(2学期始業の集いの日)
2 内容 《身近な方からの「聞き取り」の内容は》
①中学校でがんばっていたこと(部活動、稽古事や勉強など)
②自分にとって苦手だったことや苦労したこと。そしてその問題にどう向き合ったか。
(克服しようとしたり、努力したり、折り合いをつけたことなど)
③自分を支えてくれた人々(身近なひとや友だちや仲間のこと)
④中学校時代を振り返って、中学生に応援メッセージ(願いや思い)
⑤聞き取りを終えての感想
・生徒自身が、身近なひとの中学校時代についての「聞き取り」をし、まとめる。
・文章化したものを見てあげてください。事実の確認とともに、さらに多くの内容が付け加えられるかもしれません。
・生徒自身が整理して、用紙に清書する。(完成)
・「聞き取り」をもとに、学級で報告発表会を行います。
◎そして、引き続いて、
1年生冬、「平和とは何だ~身近なところからの反戦・平和」
2年生夏、「はたらくって~身近なひとの生き様を知る~」、2年生冬「高校、進学、青春時代~ひたむきに・ひたすらに」
3年生夏、「進路決定にむけて、受験期をどうがんばったか」、3年生冬「個人答辞構想(案)」と、お家の方々と連携をしていきます。
☆30日目 3.11に、3.11を語る
その学年の全生徒たちの「総意」としての答辞の取組を以前に紹介しましたが、「いま・ここ」にあるコトについて、答辞や送辞では言及せねばならないと思います。折しも、13年前の出来事を過去の課題としてではなく、現在の課題としてそのことに触れ、そしてどう語るかはとても大切です。気仙沼市立階上中学校での梶原さんの卒業式答辞に触れるこはとても意味あることだと思います。
《 本日は未曽有の大震災の傷も癒えないさなか,私たちのために卒業式を挙行していただき,ありがとうございます。 ちょうど十日前の三月十二日。春を思わせる暖かな日でした。 私たちは,そのキラキラ光る日差しの中を,希望に胸を膨らませ,通い慣れたこの学 舎を,五十七名揃って巣立つはずでした。 前日の十一日。一足早く渡された思い出のたくさん詰まったアルバムを開き,十数時 間後の卒業式に思いを馳せた友もいたことでしょう。「東日本大震災」と名付けられる 天変地異が起こるとも知らずに…。 階上中学校といえば「防災教育」といわれ,内外から高く評価され,十分な訓練もし ていた私たちでした。しかし,自然の猛威の前には,人間の力はあまりにも無力で,私 たちから大切なものを容赦なく奪っていきました。天が与えた試練というには,むごす ぎるものでした。つらくて,悔しくてたまりません。 時計の針は十四時四十六分を指したままです。でも時は確実に流れています。生かさ れた者として,顔を上げ,常に思いやりの心を持ち,強く,正しく,たくましく生きて いかなければなりません。 命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし,苦境にあっても,天を恨まず, 運命に耐え,助け合って生きていくことが,これからの私たちの使命です。 私たちは今,それぞれの新しい人生の一歩を踏み出します。どこにいても,何をして いようとも,この地で,仲間と共有した時を忘れず,宝物として生きていきます。 後輩の皆さん,階上中学校で過ごす「あたりまえ」に思える日々や友達が,いかに貴 重なものかを考え,いとおしんで過ごしてください。先生方,親身のご指導,ありがと うございました。先生方が,いかに私たちを思ってくださっていたか,今になってよく 分かります。地域の皆さん,これまで様々なご支援をいただき,ありがとうございまし た。これからもよろしくお願いいたします。 お父さん,お母さん,家族の皆さん,これから私たちが歩んでいく姿を見守っていて ください。必ず,よき社会人になります。 私は,この階上中学校の生徒でいられたことを誇りに思います。 最後に,本当に,本当に,ありがとうございました。 平成二十三年三月二十二日 第六十四回卒業生代表 梶原 裕太》

☆29日目 「落書きや掲示物のいたずら」をどう受けとめる?
もちろん、してしまった本人を特定して指導することが前提ですが、学年集団(仲間)全体の課題として捉えて、学年集会、または全校集会を行う視座が必要だと思います。(集会には学級委員や生徒会役員が語る場面をつくることが大切ですね)
少し古い資料ですが、学年通信として配布し、クラスの指導で参考した文書を紹介します。
【◎「人権と共生の時代」の中で。
それは与えられるものではありません。譲ることのできない“人権”と“共生社会”をつくるために、私たちは中学校生活の中で、一人ひとりを「大切」にして、「どう生きていくのか」考えていかなければなりません。今週は、残念ながら掲示物への侵害がありました。そのことについてあらためて一緒に考えてほしいと思います。
「掲示物の「目に穴をあける」という行為。例え、それが新聞やポスターだとしても、とても嫌な行為です。穴があいた人物の目が私に訴えてきます。「同じようにされたら、あなたはどうする?」と。『自分だったらどうする?』を心の中にいつも持ち続けることが、お互いの「人権」を大切にすることになるのです。やる人は、軽い気持ちかもしれません。でも「軽い気持ちだから許される」…ということはありません。いや、軽い気持ちでやるようになってしまった…ということは、とても大変なことなのです。初めての時、「やろう」とする時、心の片隅にある良心がブレーキをかけたはず。ほんのちょっとでも「ためらい」があったはずなのです。そして、何度も繰り返すうちに、平気になるのです。「良心、一人ひとりが大切」というブレーキを大切にしてほしいと思います。初めての時、ためらうようなことは、きっと「してはいけないこと」なのです。】
様々な指導をしても、本人が名乗ってこない場合、落書きはどのようにして消しますか?教職員が消さなくても、必ずその取組を大切に受けとめてくれる生徒たちはいます。本校でも5月頃に廊下の手すりに落書きがあり、その落書きを消す作業に参加してくれた生徒はなんと10人以上。次の日はクラスでその旨を報告。「落書きを許さない学級風土」が育まれていきます。

☆28日目 卒業を前に「進路公開」
今日と明日は、県立一般入学者選抜の日。卒業を目の前に最後の学級活動の準備をしている担任の先生らとの会話の中で・・・。
「進路公開」というのは、自らの進路(多くは高校進学や将来の夢や目標)をクラスの仲間の前で公開していくことです。
発表する子が、自分の暮らしをみつめ、自分をとりまく人々の願いを受けとめ、自分自身の可能性を高めるための進路を求めたことを語り、その発表を聞く側の子たちは、発表した子の暮らしに思いを馳せながら、強い声援を送る」そんな時間を、卒業式前にしっかりと取りたいですね。
だから、「進路公開」はお互いの暮らしを知らない者どうしの学級集団では成立しないとりくみとも言えます。すなわち「進路公開」の時間が大事なんじゃなくて、それまですごしてきた日々で、どれだけ本気で隣に座っている仲間のことを知ってきたかが必要なのです。
「仲間の語りを聴く・返す学級風土」とは、言い換えれば「クラスの仲間の語りに一生懸命に真剣に返していく文化」を作っていくことが「真のつながりのある学級集団づくり」ということです。本校でも「聞き取り課題の報告会」や、発達特性について考え、ゲストティーチャーからの提案で、自分の苦手なことや応援してほしいことを語り合う活動をおこないました。
「自分を見つめ、綴り、語る」取組は実はますます重要だと考えます。
☆27日目 東備学ぶ会で何をしている?
人権教育実践を中心に様々な教育課題について学習しています。2024年2月の学習会の内容を紹介します。
□特別支援教育と人権教育2「十八歳への進路保障」
障害者の権利条約の第14条では、「『障害に基づく差別』とは、障害に基づくあらゆる区別、排除は制限であり、『障害に基づく差別』には、合理的配慮を行わないこと」とあります。「共に学ぶ」「自立」とはどういうことか。
◎1/20は、通常学級の在籍する児童にかかわって小学校の先生からの報告をもとに、共生・合理的配慮について具体的な実践から考えていくことができました。
◎2/17は、地元の定時制高校の先生から、卒業生徒の進路保障に関する報告をもとに、小・中・高の連携や自立支援のあり方について考えたいと思います。
これまでも東備学ぶ会では、特別支援教育についてたくさん論議してきました。例えば、「子どもにとって、多人数の教室で、静かに座っているだけで子どもどうしのつながりが弱いような気がする。居ることが「共生」なのか悩む」「教室の秩序を乱してしまう子どもを「特別な場に連れ出す」ことは、合理的配慮なのかなあ」という声。また、クールダウンする部屋や、個別学習を要求する子どもに応えることは、合理的配慮か分離なのか。子どもがいじめや差別に合うことを心配して、保護者が特別支援学校や普通学級を希望する状況があるかを学校は把握できているか。発達特性が早期に発見され、早期治療が受けてもらうことが学校の役割なのか・・・などなど。日々の葛藤を受けて、今回の学習会は精神論や理念でなく、合理的配慮や共生について、具体的な日々の教育実践(現在の私たちの学校教育の内実)を問いながら、教育の本質に深くかかわる問題、「子どもの成長、学校の使命とは何か」という、この古くて新しい問いに対して、一緒に考えていけたらと思っています。
☆26日目 「地域を歩く・知る・学ぶ」取組は、東備地域で学び合う先生たちの会で開催しました。
「東備学ぶ会」の学習会の案内にある文書を紹介します。
東備学ぶ会は12年目を迎えました。本会は、2012年の第64回全国人権・同和教育研究大会/岡山大会開催を機に、≪人権教育の内実をつくり≫さらに、「豊かな」教育実践を創るために、「同和教育の財産」を大切にした学習会(研修会)を行なっています。
「同和教育」という名称が、「人権教育」と置き換えられ月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを活動の原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)などのかたちで問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ね、大きな成果をあげてきました。そしてその中で確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教師・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、今日の教育課題を≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。同和教育と人権教育の関係は対立的ものでもなく、同和教育が人権教育に変わったわけでもありません。「普遍から個別へ」「個別から普遍へ」という不可分の関係として考えることが大切だと思います。同和教育で積み上げてきた豊かな教育内容と実践は、国際的な人権教育で提起されてきた内容と完全に一致していると確信をもっています。
多忙な毎日ですが、私たち自身が〈学び合うちから〉を高めることは、子どもたちの〈豊かなそだち〉へつながっていきます。一緒に語り合いましょう。学び合いましょう。
☆25日目 地域を歩く・知る・学ぶ
鶴島フィールドワークへ、日生、東備地域の先生方と一緒に行ってきました。この島は浦上四番崩れで大弾圧を受け捕らえられた3400人のうち117人が流刑され開拓を強制されながら改宗を迫られ、禁教が解かれるまでの三年半の間に、死者18名、改宗者55名を出す過酷な仕打ちを受けた地です。その後、私有地となり、ご家族がいなくなってから長い間、無人島となっていたため、日生港から、釣船に乗せていただき、島に着くことができました。伸び放題の木々の間を案内していただき、井戸の跡や石碑を見て、その後、18人の方のお墓と慰霊碑、そして真っ白なマリア像がある島の南側の丘陵地へたどり着きました。また、高台の上には改宗を迫った祠、そこに続く長い石段(強制労働で作らさられたものでしょう)を歩いて桟橋へ帰り、岐路につきました。地域の文化や人々にどもたちが出会う豊かな機会を創っていくことは、これからますます大切になっていきますね。教材化したなあ。

追記:日生諸島(岡山県備前市)の鶴(つる)島にキリシタン遺跡
明冶政府の外来思想排斥政策は、多くのキリスト教信者を心身ともに苦しめました。岡山城下から約50km離れた無人島「鶴島」に送られたキリシタンたち(長崎県浦上キリシタン教徒117名)は、自由な身になるまでの3ヶ年半をこの島で過ごしましましたが、すしづめ状態の長屋、土地の開墾、説教聴問などに耐えかね、改宗せざるえない人もいたといいます。この島は、草地で開墾するには適しており、大豆、麦、さつま芋などが作られていましたが、それらの作物を口にすることは許されていませんでした。この島で亡くなった18名のキリシタンたちは、島の南東の丘斜面に葬られています。
また、この島には、浦上の「四番崩れ」で、長崎から流された岩永マキさんがいました。彼女は、浦上に帰ったあと、神父をたすけ、看護婦、孤児院、十字会など社会奉仕の中心人物となりました。
1969年、岡山市のカトリック教徒により、殉教百年祭が盛大に行われ、殉教者碑・十字架などの建立とともに、めい福が祈られ、「殉教の島」となっています。
☆24日目 授業での複数指導(TTや支援員との協働連携)支援体制での効果的な取組は??
1 複数指導・支援の多様な活動例を参考に,効果的なさらなる授業づくりを。
(1)授業準備
①個々の生徒の実態や課題(個別の指導計画)を加味した授業づくり
②アイデアを出し合いながら、共同での授業計画の練り合い
③個々の教師の個性・特性を生かした担当や役割分担
④教材・教具の準備
(2)授業の中で
①教え合い・学び合いの実践(★1~★6参考)
・学習活動への意欲付け ・個人やグループ別指導場面での役割分担
・発達特性を踏まえた上での、課題への理解を支援するための補足や手本の提示、手立て、モデリング
②事前に検討した個別(抽出)指導の実施
③定性的評価・・・授業中の抽出生徒への指導・支援・見取り
・評価対象者を分担し細かく見取り、多面的な視点からの評価
④状況に応じた生徒の抽出指導 けがへの対応、事故の防止の確認
⑤教材・教具の出し入れ(提示)
⑥小テストの採点や提出物の確認
(3)授業後
①話し合いによる授業全体への客観的評価
②多面的な視点から、生徒一人一人についての情報交換と評価
③授業計画の見直しなどの協力
2 実践していくために
校内研修の中で
(1)これまで取り組んできた 「教え合い・学び合い」の授業とは子ども同士が学習課題を媒介にしてつながり,「聞き合い」「伝え合い」等の互恵的な人間関係の中で「学び」を深めていく学習方法である。ペアやグループの形で活動することが多いが,子ども同士の関わり合いの中で個々の「学び」を深めていくことが大切となる。学び合いの授業で教師は,学び合いの場を設定したり,子ども同士の学び合いが促進するような援助的な関わりを重視し,直接「教える」という行為を控え,子どもの「学び」の実態に合わせて授業を展開することとなる。
(2) 聴き合う場としてのデザイン
学び合いでは,「聴く」ことが重視されており,3から4人のグループでの指導や話し合いで行われる。子どもだけでなく教師を含めた集団の誰もが,顔を上げるだけで 誰かと視線を合わせて話を聴くことができる。教師は子ども一人一人の表情をつぶさに見て,非言語の情報を読んだりつぶやきを拾ったりする。
2 授業づくり
(1)教師は,落ち着いた声の大きさや調子で,授業を始める。その教師の穏やかな態度やしぐさに合わせて,子どもの気持ちの高ぶりが収まり,休み時間と学習時間の区別が自然と付けられる。
(2)教師は,終始,声の大きさを抑え,柔らかな口調で授業を展開していく。教室には,落ち着いた雰囲気ができ,その中で生まれる子どものつぶやきを教師が捉える。教師 自身が「聴くこと」を大切にする姿勢がモデルとなり,子どもも「聴くこと」のよさを意識し,友達のつぶやきにも耳を傾ける「聴き合う」関係がつくられる。
(3) 学び合いは,グループで行われる。しかし,必ずしも,意見をまとめ合ったり話しあったりすることが目的のグループ学習ではない。一人一人が自分の学びを進める時 にも机を付ける。分からない時,困った時,「分からない」「教えて」という言葉を自 然に口に出すことができる。そしてそれを受け止められる距離,その中でそれぞれの 学びを進め,互いに学び合うのである。2人組では,学びに広がりを生み出しにくい。3人では,2人と1人に分かれがちである。5人以上になると,頭を突き合わせるこ とが難しくなる。4人組は,ある程度の意見の多様さをもちつつ,机を付け合うことで,関わり合いが自然に生まれ,親密な距離感の中で,それぞれの学びを進行させる ことができる人数である。人間関係がまだ十分につくられていない時期や学級の実態によっては,簡単な意見や感想をペアで交換することもある。
(4) 子どもを学びに引き込む魅力のある課題は,課題を媒介とした関わり合いを自然に生み,子どもと子どもをつなぐ役割も果たす。「どう思う?」「分かる?」そんなつぶや きから自然と子どもがつながり始める。子どもの実生活につながる魅力的な課題づくりや子どもと学習課題を結び付ける具体物の提示等で課題の設定を工夫し,子どもを 学びへと引き込む。
佐藤(2009)の「トランポリンモデル」
*子どもを学びのステージに乗せることを「トランポリンに乗せる」と表現する。学びに入りにくい子どもの多くは学力が低位で,トランポリンに乗りにくい子どもである。同じトランポリンに乗っていれば学力の高位の子どもの跳躍によって,トランポリンの揺れが起き,低位の子どもも一緒に高い学びへの跳躍を始める。授業前半で「最低限学ばせたいレベル」まで低位の子どもを引き上げ,その上で,後半はさらに高い課題の設定をして高位の子どもの跳躍を大きくさせ,全体の子どもの学習レベルを引き上げる。
3 複数指導の役割・多様性
(1)子どもと子どもをつなぐために【実践例】
① 安心感のある場としてのデザイン
・突っ伏したままで机を動かす気配のない子どもがいると,教師は机をそっとグループの形へと動かす。突っ伏していても学級の一員として子どもを尊重しているという教 師のメッセージは重要。
・教室に居ない子どもの机を隣の席の子どもがグループの形に動かす。突っ伏している子どもをそっと起こして仲間に入れる。そんな関わりが子どもの中にも見える。
・子どもを学びへとつなげる教師の関わりは,教室の中だけではない。廊下には,常に教師がいて,教室に入れない子どもが教室へと足を向けるまで見守ったり,必要に応 じて教室に入って子どもの援助をしたりする。
・遅刻生徒に対しては職員室で手続きを促し、教室(授業)まで送っていく。
② 自由な学びの場としてのデザイン
・突っ伏したままで授業に参加していないと見える子どもが,実は,友達の発言を聴き,発言者の方を見ていることが多い。子どもは教室に居さえすれば学びに入るきっかけ
を自分でつかむ。「全ての子どもの学びを保障する」ために授業規律がある。学びに参加できていない子どもの姿を丸ごと受け止めることで,個の学びを保障している。 学びに入らせるために働きかけたり促したりすることはあっても,教師が押し付ける指導はない。反面,人と距離を置くことが学び合いを妨げることにつながると考え, 机と机はきちんと付ける,壁をつくらないように筆箱や教科書を人と人の間に置かない,といった指導・支援を進める。
(2) 指導能力の育成につながる生徒指導の三つの留意点に重なること
ア 子どもに自己存在感を与えること
聴き合うことを重視した場づくりは,子ども同士が,目を見合わせ,表情を読み合い,言葉を交わし合い,互いの存在を感じ合うことを可能にする。人との関わり合いの中で,自分の存在を確認できる場である。また,一人一人の「そうせざるを得ない」気持ちに寄り添い,子どもの姿を丸ごと受け止めようとする教師の姿は,自分たちが大切にされていて,価値のある存在であることを子どもに伝えている。
イ 共感的な人間関係を育成すること
学び合いでは,親密な距離感の中で,「分からない」と言って支え合うことが許され,一緒に学び合える仲間がいる。そこでは,「分からない」と言える学級の雰囲気をつくるのは,教師ではなく子どもである。共に学ぶ仲間に対する共感的な気持ちや態度は,仲間との関わりの中で,自分自身が実感して繰り返し経験していくことで育っている。
ウ 自己決定の場を与え自己の可能性の開発を援助すること
学び合いのグループは,一人一人の学びを進めつつ,課題という媒介を通して関わり合いが生まれる場である。だからこそ,教師が話題を焦点化したり効率的な学びを進めたりするために行う「発問」よりも,子どもの学び合いを自然に引き起こす「課題の設定」が重要になってくる。そして,グループで課題の解決に向けて取り組む中で,自分の学びを進めたり,つながりを求めたりする自由がある。このことは,学び合いの場が自由な場であり,自己決定のできる場として保障されていることを意味している。
(3)子どもの関わり合いを促進するために
「居場所」となる場がデザインされた子どもの間には,自然と関わり合いが生まれる。 しかし,この関わり合いは,子どもなりの関わり合い方である。そもそも,人と関わ ることを苦手としている子ども同士の関わり合いが更に進むための手だては?
★1 分からない子どもへ寄り添う
多くの学校では,グループ活動している時に学んでいない子どもに対して,グループに入って他の子どもと同じように学ぶことを指示する。しかし,これまでの実践研究 校では,学びに入ろうとしない子どもには,その気持ちを理解することから始める。教師は学びに入ろうとしない子どもは,学習面でのつまずきがあり,困っている子どもと捉えているからである。そこで教師は,授業が分からないという気持ちに寄り添い,受け止めながら,「分からないから,教えて」と他の子どもに聞くことを教える。
安心して「分からないから,教えて」と言えるようにするために,実践校には学校全体で決められた授業の声かけ(ルール例)がある。この声かけによって,子どもは自 分から学びに入ることができるようになっている。例えば,一人で困っている子どもは,「分からないから,教えて」とグループのメンバーに頼るように教師が教える。
「これってどうするん?」「分からないから教えて」を言えるための声かけルール
○ 人の話をよく聴くこと
○ 分からないことは「分からない」と言うこと
○ 困った時は「どうするん」と自分から言うこと
○ 頼られた時はしっかり対応(誠実)に応えること課題が分からずに学びに入れない子どもには,そっと寄り添って課題を具体的に伝え,まず課題を理解させ,それから,課題という媒介を通してグループのメンバーに頼ることを教える。こうした教師の関わりによって,子どもは,困った時には他の子を頼るることを覚え,自分から依存できる力を育もてると考えられる。その結果,学力が低位な子どもでも,グループのメンバーに依存することで,メンバーが援助する関わりが生まれている。そして,教師は本当に個別の援助が必要な子どもに関わることが可能になる。
★2 子どもの状態を丁寧に見取る
教師は授業中,常に子どもの状態を丁寧に見取る。見取るポイントは三つある。一つ目は身体からの見取りである。子どもの状態を目の動きや表情,手の動き,仕草な どから見取っている。二つ目は,つまずきやつぶやきからの見取りである。つまずいている様子はないか,分からないことを声に出してつぶやいていないかを見取っている。三つ目は子どものつながりからの見取りである。子どもは,課題とつながっているか,子ども同士がつながっているか,子どもと教師がつながっているか,さらに,一人一人の子どもと集団がつながっているかを見取っている。こうした見取りは,子どもがグループで活動している時だけでなく,教師が全体の場で発問している時や子どもの発言を聞く時などにおいて常に行われている。そして,見取りの結果から,教師は,次に何をすればよいか判断している。
★3 子どもを信じて待つ
学びに入っていない子どもがいても,丁寧な見取りの結果,学びに入りそうな時には,あえて声をかけずに,子どもが自分から学びに入るのを待つ。一見すると,教師は何もせず,子どもが偶然学びに入ったようにも見えるが,それまでの教師の見取りを追っていくと,そこには,あえて何もせずに待っている教師の姿がある。ある教科の授業中におけるグループでの活動で,学びに入らず,突っ伏していた子どもがいた。教師は見取りを行った結果,直接その子どもに声をかけず,学びに入るのを待つ方を選択した。その後,グループでの学び合いが進む中で,その子どもは身体を起こして自分から学びに入っていった。教師が「待つ」ことは,他にも様々な場面で重要である。グループで活動している時,子ども同士の学び合いがすぐに進まなくても,あえて声をかけずに待つ。子どもが学びに入り,学び合いが起きるまでの時間を保障しているのである。また,学び合いが始まっている時は,学び合いが十分に進むまで待つ。学び合いが始まっているにも関わらず,時間を理由に学び合いを止めるようなことはしない。むしろ,子どもの学び合いの状態に合わせて,柔軟に授業の進め方を調整している。こうした教師の「待つ」姿勢によって,子ども同士の学び合いが起き,関わり合いが主体的に行われる。さらに,全体の場で子どもを指名する時にも,教師は,その子どもが発言するまで待っている。どんなに時間がかかっても,子どもの発言を待ち続ける。ここで教師が望んでいるのは,正答や素晴らしい意見ではない。その子どもが自分から発言することである。教師は,子どもの発言をうなずきながら聞き,受け止める。
★4 学び合いが起きない時は,戻す
教師は授業中,常に子どもの状態や子どもと集団の関わりを見取り,関わりが起きそうなら待つことをしているが,子どもの学びが進まなかったり,学び合いが起きないない時には,一旦グループでの活動を止めて,課題を全体に戻す。そして,課題を丁寧に確認したり,課題の提示の仕方を工夫したりして,改めてグループでの活動を始める。学び合いが起きず進まない状態を見取り,素早く戻すことで,子どもが新たな学びに入れるようにしている。
★5 子ども同士をつなぐ
学びに入っている子どもが,教師に質問した時,教師は答えるのではなく,グループの他の子どもにその質問をつなぐ。教師は子どもAからの質問に対して,正解を伝えることも,ヒントを出すこともせず,同じグループの子どもB,子どもCにつなげる。子どもAの最初の質問を教師がつなげることにより,学び合いが起きた場面である。こうした教師のつなぐという関わりの中で,子ども同士がつながり,子ども同士の関わり合いが生まれてくる。また,教師がつなぐ先を変えて見せることで,子どもは誰とでもつながる機会を与えられるとともに,それぞれの子どもとのつながり方が分かり,次回から誰と,どうつながるかを自己決定するようになる。
さらに,子ども同士をつなぐことは全体の場でも行われている。多くの学校では,一斉授業の中で教師が発問し,子どもから何らかの回答があると,「そうだね」「よく分かったね」と返すことが多い。しかし,実践では,教師が発問し,子どもから発言があった時,その子どもに返さず,他の子どもに「今の発言についてどう思った」「もう一度,話してみて」とつないでいく。このように,教師が子どもの発言を直接他の子どもにつなぐことで,グループで活動していない時も,子ども同士の学び合いを意図的に起こしている。この「教師が,子どもへ発問し,子どもから返ってきた発言を他の子どもへつないでいく」ことを,実践校では「一往復半」と呼んでいる。
ここで,子どもの発言が他の子どもに聞こえなかった場合は,もう一度発言させるが,教師自身は復唱をしない。発言する子どもに「もう少し大きな声で」という指示もしない。学級全体に対して「聴くこと」に集中するように指示する。子どもが互いの発言を集中して聴くことで,子ども同士が自然につながり,他の子どもの発言を尊重するようになる。
★5 教師は「教える」ことに終始せず,常に子どもの「学び」を援助する立場
授業での教師の子どもに対する関わりの大部分は,教師が学習を「指導する」視点でなく,子どもの個の学びや集団による学び合いを「援助する」視点を大切にしたい。丁寧に子どもの状態や子ども同士の関わりの状態を見取り,分からなくても依存すれば学び合いに入れることを教え,学び合いに入るのを待ち,学び合いが起きないようなら「戻す」ことをしている。そして,学び合いがさらに促進するように,「つなぐ」ことを丁寧に行っている。こうした教師の関わりは,子どもの授業における学び合いを促進すると同時に,人間関係の希薄化が問題視される子どもをつなぎ,関わり合いを生む機会を提供している。この関わり合いの中で,子どもは,依存してもよいということ,誰とどうつながるかを自由に決められるということを知りながら人と関わる力を身に付けている。このことは,共感的な人間関係を育むとともに,選択の自由などの自己決定のできる場が保障されていると言える。よって,子どもの関わり合いを促進することは,よりよい人間関係づくりやコミュニケーション能力を育成する生徒指導を行うことであり,子どもの自己実現の基礎となる自己指導能力を育んでいく生徒指導となっている。
★6 授業者(複数指導者)の振り返り〈見取り〉
○分からない子どもが「分からないから,教えて」と周りに援助を求めていたか?○援助の求めに応じてくれる雰囲気がグループ・学級全体にあったのか?その状況 はどうであったのか?
○「訊かれた(援助を求められた)子どきもが,訊いた子どもの分からなさに寄り添って丁寧に説明できていたか?
○教師は,学びから逃避しようとする子どもをグループにつないでいく関わりができていたのか?
○子ども同士の学び合いの時間は十分に確保されていたのか?
○教師のグループの学び合いを見取る立ち位置は適切であったか?
○グループでの学び合いにするタイミングやねらいは適切であったか?
○グループでの学び合いを終えるタイミングはどうであったか?
○それを促進する教師の援助者としての関わりが有効であったか?
引用・参考文献
・平成22・23年度岡山県総合教育センター所員研究(共同研究;生徒指導)「学び合いを促進する教師の関わりについての研究-なぜ,あの子が学びに入れたのかを探る-」
・ 文部科学省(2011)『平成22年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」』
・文部科学省(2010)『生徒指導提要』,p.1
・佐藤曉(2009)『子どもも教師も元気が出る授業づくりの実践ライブ』学研,p.178
・佐藤曉・守田暁美(2009)『子どもをつなぐ学級づくり』東洋館出版
・新学習指導要領・生きる力:文部科学省(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.html)
☆23日目 新年度教育課程の編成の中で家庭訪問の意義をあらためて
家庭生活と学校をつなぐために同和教育において一貫して大切にされてきたものです。1つの方法であるだけでなく、そこに同和教育の精神が集約されています。
子どもを理解するためには保護者を理解することが必要です。家庭での親との関係が子どもの精神状態やものの考え方や感じ方をかたちづくっていきます。教師は教室にいる子どもを相手に教科指導や生活指導をしていますが、家庭での親と子どもの関係を把握したときに、その指導にこもる思いは強くなると思います。子どもと対するとき、教員が保護者から信頼を得ているかどうかは決定的に重要です。保護者はどんなふうに働き、どんな思いや期待をもって子どもを育てているのか。生活が厳しければ厳しいほど、保護者が誇りを失っていればいるほど、心を開いて教員と話すのは難しくなりやすいです。家庭訪問も回数を重ねてることとなります。保護者自身が自らの生き方に問題を感じていたり、乗り越えられない問題をかかえていたりする場合には、その保護者の精神状態は子どもにさまざまな影響を与えます。そのような保護者のかかえている問題を聞き取るという行為は、教師にとって、自らの生き方を省みる機会を提供するものです。「差別の現実から深く学ぶ」というスローガンのもとに、同和教育では家庭訪問による教師と保護者とつながりを教育実践の重要な過程とみなしてきたのです。
子どもの言動が落ち着かなかったり、荒れたりしているとき、その原因や理由を本人に聞いてもわからない場合もあります。そんな時は行くのです。電話ではありません。家庭を訪問し保護者と語り合いましょう。その際、できごとだけを伝えるのではなく、指導の内容やそのときの教員の願いやおもいをしっかり伝えましょう。問題行動を起こしてしまった子どもの保護者の多くは、子どもの教育について深く悩んだり不安をもったりしている場合があります。そんな保護者に「家庭でよく話をしてください」という一方的な気持ちで連絡しても保護者との距離は縮まりません。だから問題を伝えるだけでなく、良いところやがんばっているところも伝えましょう。「一緒に手を取り合って子どもを育てていきましょう」というメッセージを保護者に伝え続けていくことで保護者との関係は変化していきます。つい子どもにあたってしまうしかない親のしんどさ、悩みを誰にも言えず一人で悩む親の姿など、だんだんと語っていく中で子どもや保護者のくらしや願いが見えてきます。「今の親の感覚はどうなっとるん」「あたりまえの親ならこうじゃろ」と保護者と距離を置くのではなく、しんどさをありのままに語り合える関係をつくりましょう。「この先生は子どものことを一緒に考えてくれる」ということが伝われば、少しずつ保護者とのつながり、子どもとのつながりが深まっていきます。
☆22日目 コの字の席学習スタイル
先日の校内公開授業で、2年生の深い学びを創出したひとつである、コの字型の席について、「学びの共同体」に関する佐藤学さんの著書からいくつか挙げてみます。


○授業改革って
(1)教職員自身が非力であることを自覚すること。自分の非力を見せ合う中で謙虚に授業 改革に取り組もう。
(2)研修は他人のためにおこなうのではなく、教職員である自分自身のためにおこなう。 ひいては生徒たちのためになるという考えに立つこと。
(3)いわゆる「うまい授業」をしようと思わないこと。たとえ「ぶざまな授業」であって も生徒たちと誠実に向き合う授業を志向しよう。指導案どおりに進行する授業がよい のではなく、生徒が自分で考え、おおいに戸惑いながら進行する授業をめざそう。
○授業改革のための研究授業の改革
(1)一般的に従来の研究授業(授業の研修)の反省点として、①形式性を重視することで 研究授業としておこなうことが、一人ひとりの日常の授業にいきてこないこと。②授業 を見る視点が、所定の「仮説」に限定され、それ以外の授業の見方が制約されてしまう 点があげられる事がある。そこで本校の研究授業を以下の方法・方向性を検討しながら 取り組んでいきたい。
①授業をみて気づいたこと・考えたこと・学んだことを対等に、自由に発言する。一般論 や理論の紹介ではなく事実に即してコメントを出しあう。
②授業のコメントにおいて正答は無い。正否、優劣を評定することが目的ではない。授業 という複合的な事実を見る目を広げ、深めていくことが目的であり、自分と異なった意 見に触れ、その根拠を確かめつつ、自分の理解を深め、授業という複雑で奥行きのある 実体への理解へ近づいていく終わりなき課程であることを自覚する。
③教材の是非や教え方の是非は100とおりの正解がある。しかしその授業の進展における教職員の姿勢・願いや、生徒の発するメッセージの受け止め方はおそらく1とおりし かない。生徒一人ひとりを注意深く観察しながら,具体的な作業を提起して学びの展開 を触発し,多様な発見や意見の交流を組織し,学びの活動が豊かで深い経験になるよう に様々な働きかけを行うのである。「交わり」「つながり」を生み出す活動を,教職員 の仕事の中軸に構成する。
(2)研究授業の推進に向けて
①授業の上手下手は問わない。授業の巧拙は「生まれつき」であることを自覚し、「自分らしいいい授業」をめざす。
②授業公開にあたっては、事前に形式的な内容に多くのエネルギーを注がない。事後の研究会(校内研修)を充実させる。「やって」「おわった」という充実感だけを求めるも のになりがちだった研究授業。事前に時間をかける必要性はない。事後の検討にたっぷり時間をかける。授業の良し悪しを議論するのではなく、授業の「難しさ」と「おもし ろさ」を共有することこそが授業の研修の目的である。いつも生徒の学びの具体的な姿を話し合いの中で浮き上がらせることを研修で求めていく。
③教職員の発問や教材の解釈についてよりも生徒の学 びの具体的な様相と教職員のそれへの対応を中心に話し合う。
④多様な教育の考え方と多様な経験を備えた教職員たちが、同じ授業の事例と観察と批評を通して、教職員としての証を探索しあい、実践的なディスコース(実践を創造し反省 する言語)とそのディスコースで結ばれた実践者の共同体を育てあう営みが授業の研修である。
⑦研究資料による報告でも口頭による報告でも,固有名の生徒が登場して,自分の言葉で 表現するように心がけること。その研究を通して教職員一人ひとりが何を感じ何に挑戦 してきたのか,教室の生徒たちはどう学び,何につまずき,どう克服してきたのか等, リアルに語られる必要がある。
○生徒の自立性と自律性を促す授業のあり方を進めるために
(1)生徒(観)について
・生徒個々人がそれぞれ自主的に学ぶ授業に移行させない。
・一時間単位の検討ではなく、長い時間軸の中で一人ひとりの学びと成長を見据えなが ら日常の授業を検討していく。
・子ども一人ひとりの自然な言葉と身体による授業への参加を基盤として、具体的な事実を対象とする多様なイメージの交流を実現させる。
・「一人ひとりの生徒の思考そのものを参照にする意志決定の授業」をめざす。教職員は授業の絶え間ないデザインとその修正(授業の展開の選択や方針の修正)をおこなう。(授業デザインの作成)
・子ども一人ひとりの自然な言葉と身体による授業への参加を基盤として、具体的な事実を対象とする多様なイメージの交流を実現させる。
・個と個が摺り合わせられる授業→ディスコースコミニティ(議論しあう共同体)としての学級づくりを進めていく。また、発言しなくても一生懸命考えている生徒がいる 授業や、たどたどしい言葉が他の生徒の心に深く届き確かな説得力を持つような風土がある学級づくりを進めていく。
・級友の言葉をひとつひとつ味わって聴ける「学び上手」の生徒を育成する。
・どんな誤答の中にも、その答えを導き出した「理の世界」がある。必要なことは答えの当否を裁断することではなく、「理の世界」を洞察し、その省察を教室で共有し摺 り合わせて、真実へと至る筋道を共同で探索する。
(2)私たち教職員(観)について
・生徒だけが一方的に発達し成長することはありえない。学び成長し続ける者のみが教 えることを可能にする。《よく学ぶ者だけが教壇という舞台に立つ資格を持つ》
・教室に聴きあう関わりを築くことは、教職員の豊かな経験を基礎とする見識と粘り強 い取り組みを必要とする。
・ハンドサイン・起立礼・付け足し等、児童生徒を一方的な操作対象にしている授業, 教室の話し合いと切り離して人為的なゲームをしている授業,「虚偽」の主体性を演 じさせられている教室が見られる場合がある。生徒とじっくり「良い時間を過ごそう」 という意識で教室に立つことが,解決の確かな糸口を準備してくれる。発言を「引き 出し」たり「組織」したりする前に,生徒一人ひとりの言葉を「聞くこと」や「味わ うこと」へと教職員の意識をシフトさせる。求めるべきは「よく発言する教室」では なく「よく聴きあう教室」が発言を通して多様な思考や感情を交流しあえる教室を準 備する。この関係は逆ではない。
・教職員が一人ひとりの生徒の言葉に耳をすまして敏感に対応し,一人ひとりの生徒に ていねいに届く言葉を発すること(生徒一人ひとりの胸に届く言葉をていねいに選び ながら語りかける教職員の話し方)ができるようになって,はじめて生徒たちのなか に聴きあう関わりが生まれ,しっとりとことばを深く吟味しながら交換しあう関わり が教室に築かれることになる。
(3)教材(観)について
・「主体性」が理念として考えられる授業においては「自学自習」を理想化し,自己実 現や自己決定を理想化する傾向を生みだしている。しかし自学学習や自己実現や自己決定は独学の理想ではあっても,教材や仲間や教職員が介在する授業場面において理想化してはならない。
・生徒と集団(固有名としての生徒の存在)の実態や教育課題に即して、「生徒の状態」 「生徒にとっての意味」を考えて、特定の教材を選ぶ。何のためになぜこの教材を選ぶのかとその教材の意味を考えつつ教材を選ぶ。そしてその指導・支援にあたっては、その学習が生徒自身の課題となり、生徒が学習の主体となるために、どのような方法 で指導・支援するかが教職員の重要な課題となる。
参考文献 『授業研究入門』/『教育改革をデザインする』/『教育方法学』/『学力を問い直す』(岩波書店) 『授業を変える学校が変わる』/『学校を創る』(小学館)
『学び その死と再生』(太郎次郎社)から久次がまとめたもの。
☆21日目 生活ノートとICT・デジタル化 考察その2
「綴ることは認識すること」
―ひとむかし前までは、作文といえば、いわゆる生活文…くらしを題材とし、人のかかわりを綴ったもの…が定番でしたが、現在の教科書では、(小学校)2~3年生で生活文は「卒業」となり、あとは、ここでも表現活動の技術を習得する単元が中心となっています。手紙文・礼状・発表原稿・レポートなど、多様にとりあげ、最後はやはりプレゼンテーションをめざしていたるのでしょうか。
作文は、表現や伝達の手段であることは間違いなく、伝えるための技術をみにつけることは、将来社会に出てから役立ちます。しかし綴ることにはもうひとつ、だいじな役割があります。僕たちはこれを「認識」とよんでいます。残念ながら、最初から作文が好きなこどもは、あまりいません。難しいからです。自分の前にある人・もの・できごとにぴったりな単語をみつけ、次には単語どうしを結びつけ文にし、さらに組み合わせていくという、語彙論、文法論を総動員しなければならない作業です。時には、できごとをよいととらえるか、悪いととらえるかなどという、価値判断もしなければなりません。自分の視点で書いているので、うそはかけません。鉛筆を進めるのは、大変な仕事です。就学前の子どもたちは、「話しことば」の中で生活しています。相手が目の前にいて、視線やしぐさ・表情なども伝達の手助けとなるため、多少語彙や文法がまちがっていても、おおよそ通じてしまいます。しかし「書きことば」ではそうはいきません。目の前に相手はおらず、頼りになるのは文だけなのです。だからこそ、必然的に対象をしっかりみつめ、掴もうとし、価値判断をすることになります。家族・友達・社会・自然などを題材として綴るなかで、子どもたちはしだいに「認識」を深めていきます。こういった「認識」を獲得する学習を基盤とし(あるいは並行して)、発表原稿やレポートを書くのなら実生活に根差した、重みのあるものとなるはずです。現行の教科書が、中・高学年での生活文指導を放棄しているのは残念です。飛躍的に認識の幅が広がる時期なのですから。もうひとつ、書くことの基本は、みのまわりのことを、あったことを、あったように、自分のことばで、です。時間軸に沿って、「○○でした」「○○しました」というふうに、過去形で書いていきます(展開的過去形表現といいます)。これがある程度できるようになってはじめて、前述のさまざまな機能を持った文章を書けるようになるはずです。くらしを書きなれてないと、いくら技術を教えても、いきなり手紙やレポートは書けないのは、昔から言われてきたことです。(『教育 おかやま(2014年3月発行)』より 日本語教育を考える P2~P3 岡山県教職員組合教育運動推進センター:学力保障「日本語」研究部会
☆20日目 教室掲示物は片付ける?
毎年3月、学級の掲示物はもう処分してしまいますか?最近では、「学級通信」「学年通信」「保健だより」「クラス目標」「班メンバー表」「清掃分担表」「朝夕のめにゅー表」などの多くは先生たちがコンピュータで作成しているようですが。
残しておいて、新学期にも必要なモノ(例えば学級通信を掲示していた枠だけでなく、1年間を通して子どもがつくったモノを掲示する学級文化を構築したいですね)は新しいクラスの生徒が制作する(生徒一人ひとりひとつの掲示物を作る!(用意できます))のはどうでしょう。このときに前年度の掲示物を参考資料として、班に道具と一緒に渡します。必ず「これより(前年度の掲示物より)よいやつをつくるぞ!」とがんばります。作ったことがない生徒や苦手な男の子も、例示があると班のなかまと一緒につくることができます。子どもが班の仲間と楽しく語りながらつくる時間は貴重です。
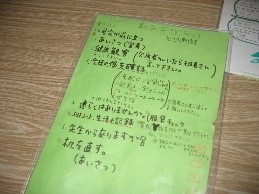
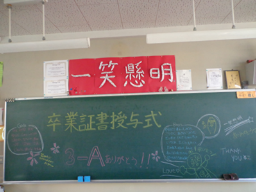
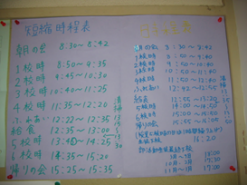
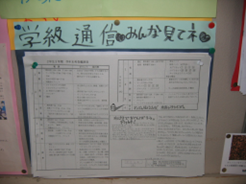
☆19 カウントダウンカレンダー」で、
クラスのつながりを確かめられる仕掛けをたくさん入れたいですね。
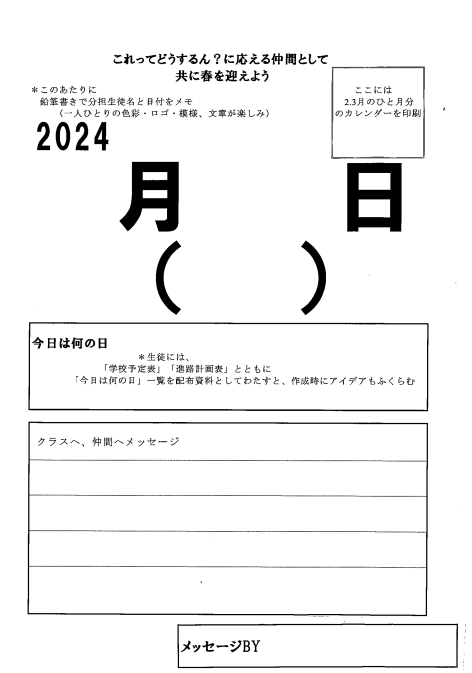
☆18 新入生歓迎新聞づくり(新3年生全員で!)
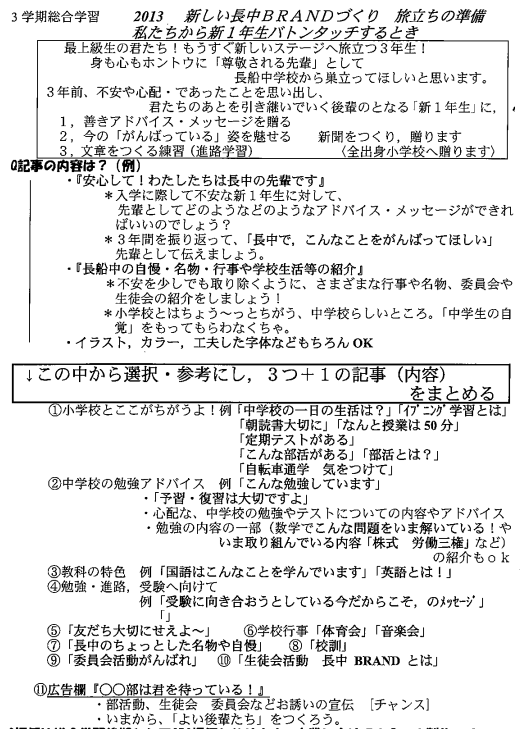
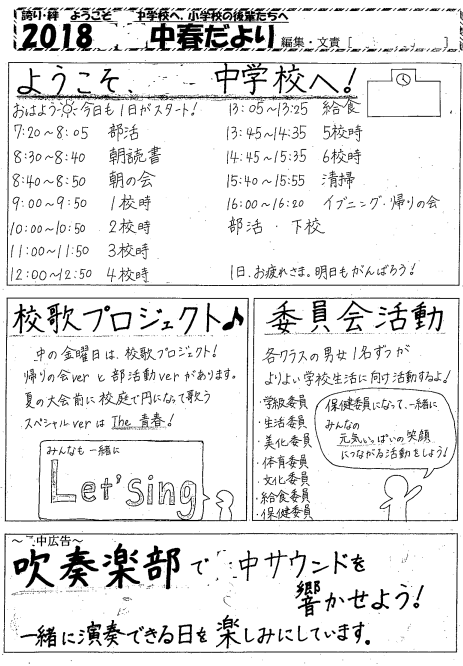
☆17 個人答辞をもとに、卒業答辞に。
代表生徒だけが考える「答辞」から、一人ひとりが三年間を振り返って個人答辞を綴り、それを集約したかたちで卒業生答辞を作成する取組をこれまでおこなってきました。子どもたちが取り組むワークシート文書を少し紹介します。
2024旅立ちの時にあたってー個人答辞ー 道をひらいていく
~私・わたしたちの○○中~
この時期、3年生のみんなは中学校での生活をふと振り返ってみたりすることもあるのではないでしょうか。一人ひとりが、いろんなことを経験し学んできたと思います。良かったことも、そして悔やんでいることがあったとしても、その一つ一つは、あなた達がこれから生きていくになっていくことだろうと思います。大切にしていかねばなりません。
もうすぐ旅立ちの時がやってきます。出発するためには、今の一人ひとりの姿勢が問われます。時の流れにまかせて、卒業式を迎え、そして進路先へ行く…そんな、ただなんとなくといった生き方をしないでください。自分の道を切り拓いていくためには、「いまの自分」がやっぱり大切です。
なかまたちと共に過ごす時間をどれだけ大切にできるか?
どう中学校生活を締めくくるかは、4月からの生活の土台となります。
そしてもうひとつは
これから自分がどんなことを大切にしていくのか?という生き方を決意することが大切になります。
この中学校で経験したこと、学んだこと、これからの生き方や夢を「思いをこめて」個人答辞としてまとめましょう。
①中学校生活の思い出、行事となかま(修学旅行・文化祭・体育大会・部活など)
②三年間を通して、なかまから学んだこと (中学校入学時の自分と現在の自分を比 べて、心の成長や今の自分のつくったできごと・学級活動・生徒会・総合学習(職場体験、ヒロシマ・オキナワ研修、渋染一揆、閑谷、協同学習、ガンバリ合う、支え合うな かま、ハンセン病問題学 習、進路学習など)
③進路についての課題と決意、様々な進路
(進路や自分の夢・抱えている課題にどう立ち向かい、どうがんばっていくのか)
④自分たちの反省、課題及び決意(後輩たちや在校生に伝えたいこと)
⑤お礼のことば(今まで自分たちを支えてくれた人々に伝えたいこと)
⑥締めくくり
*○○期三年生として
・各クラスで書かれた、全員の個人答辞を集約する。
・集約したものをもとにして、3学年の答辞の全体像を考える。
・答辞代表を3年生全員で支える。3年生全員でよい卒業式を創る。
・卒業式を成功させるために、一人ひとりが大切にする意識を高め、声をかけ合い、あらためて団結する。
☆16 自立と依存は相反する?
「依存」と「自立」を対立的に考えるのは誤りである。「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。『授業を変える学校が変わる』/『学校を創る』(小学館)等で佐藤学さんが書かれていた内容を初めて読んだ時には衝撃を受けました。それからずっと「自立」の中身について考えていますが、先日、車いすユーザーである東京大学の熊谷晋一郎さんは「自立とは依存先を増やすこと」と言われた文章に出会うことができました。
自立とは「依存先を増やすこと」
親は、「社会というのは障害者に厳しい。障害を持ったままの状態で一人で社会に出したら、息子はのたれ死んでしまうのではないか」と心配していたようです。でも、実際に一人暮らしを始めて私が感じたのは、「社会は案外やさしい場所なんだ」ということでした。
大学の近くに下宿していたのですが、部屋に戻ると必ず友達が2〜3人いて、「お帰り」と迎えてくれました。いつの間にか合い鍵が8個も作られていて、みんなが代わる代わるやってきては好き勝手にご飯を作って食べていく。その代わり、私をお風呂に入れてくれたり、失禁した時は介助してくれたりしました。
また、外出時に見ず知らずの人にトイレの介助を頼んだこともあります。たくさんの人が助けてくれました。こうした経験から次第に人や社会に関心を持つようになり、入学当初目指していた数学者ではなく、医学の道を志すことを決めたのです。
それまで私が依存できる先は親だけでした。だから、親を失えば生きていけないのでは、という不安がぬぐえなかった。でも、一人暮らしをしたことで、友達や社会など、依存できる先を増やしていけば、自分は生きていける、自立できるんだということがわかったのです。
「自立」とは、依存しなくなることだと思われがちです。でも、そうではありません。「依存先を増やしていくこと」こそが、自立なのです。これは障害の有無にかかわらず、すべての人に通じる普遍的なことだと、私は思います。(全国大学生活共同組合連合会インタビューより)
☆15 面接で不適切な質問? どう答えるの?
今日は、特別入試の結果発表でした。
生徒らは、教科の試験とともに、多くの子が初めて「面接」を体験したと思います。そして中学校では、「どんな質問が出たか」を報告書にまとめる取組をしています。それを受験校ごとにまとめ、「過去出題例」として蓄積し、次の年の三年生らが、それを参考に面接練習を行います。ここ数年は、業者の『面接ガイド』を活用しているようですが、やはり、自分たちが受けた質問をまとめることはとても大切だと思います。それは、後輩たちに「こんな質問内容がでたから、参考にしてガンバレ」という目的だけではありません。
就職試験は、応募者の適性・能力に基づいた採用基準とすることになっています。それは、応募者のもつ適性・能力が求人職種の職務を遂行できるかどうかを基準として採用選考を行わなければなりません。就職の機会均等とは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、このためには、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。だから、面接での「これは、就職差別につながるおそれのある不適切な質問か」見定める力を生徒自身が持てる指導を進めていかねばならないと思います。合わせて、私たち教職員もそのようなことがないように、「面接での質問事項」をチェックし、子どもたちの進路保障を確かなものにしないといけないと思います。
家族、住んでいるところ、資産などに関する質問・・・応募者の適性・能力を中心とした選考を行うのではなく、本人の責任でないことがらで判断しようとしていることです。このことは、前近代的な身分制により形成された部落差別により、教育や就職の機会均等の権利を侵害されてきた人たちを排除することにもつながるものです。住宅環境や家庭環境の状況を聞くことは、地域の生活水準等を判断することになり、主観的判断に属する事柄です。これらは本人の努力によって解決できない問題を採否決定の基準とすることになり、そこに予断と偏見が働くおそれがあります。
思想・信条、宗教、尊敬する人物などに関する質問・・・思想・信条や宗教、支持する政党、人生観などは、信教の自由、思想・信条の自由など、憲法で保障されている個人の自由権に属することがらです。それを採用選考に持ち込むことは、基本的人権を侵すことであり、厳に慎むべきことです。思想・信条、宗教などについて直接質問する場合のほか、形を変えた質問を行い、これらのことを把握しようとする企業がありますが、絶対に行うべきではありません。
性別・男女雇用機会均等法に関する質問・・・性別を理由(または前提、背景)とした質問は、男女雇用機会均等法の趣旨に違反する採用選考につながります。また、男女共に同じ質問をしていても、一方の性については採用、不採用の判断に影響がなく、他方の性についてはその返答が採用、不採用の判断要素となるような場合は、採用において性別を理由として差別していることになります。
☆14 ひとに出会う授業のありようや、
学習のまとめについて、「はっ!」とした本。
知識を学んだり、当事者の語りを聴くことについて。『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育 誰のことばにも同じだけ価値がある』(野口晃菜 喜多一馬編著・学事出版)の星野俊樹(P115)には・・・《知識を学んでも当事者に心を寄せる経験がなければ(情動的共感なしの認知的共感)、子どもの反応は、政治的正しさに囚われたままで終わり、自分の発言に用心深くはなりますが、行動は型にはまった人目を気にしたものになりがちで、洞察や分析はできても当事者に冷たいものとなってしまうでしょう。逆に、知識を十分に学ばず、当事者のライフヒストリーを聞いて「感銘を受ける」だけでは、(認知的共感のない情動的共感)、当事者に対する、上から目線の「哀れみ」や「善意」が子どもたちに広がってしまうおそれがあります。そのため、「異質な他者に共感しよう」と子どもたちの心情にただ訴えかけるのではなく、情動的共感と認知的共感の両方を子どもたちが得られる機会を保障する必要があります。多様性や社会的公正を効果的に教えるためには、感性と知性の両方に働きかけることが重要です。》(*ダイアン・J.グッドマン『真のダイバーシティを目指して 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育』上智大学出版、2017年等を参照のこと)とありました。
「ひとに出会う授業」をもっともっと丁寧につくっていきたいと思います。
☆13特別支援教育と仲間づくり
『関係支援を核とした学級づくり 「特別でない」特別支援教育をめざして』拝野佳生さんは、小学校と特別支援学校の教員経験をもとに、「関係支援」をキーワードとする学級集団づくりを提案し、「学び合い支え合う仲間づくり」という日々の教育活動から生み出した方法論を著者の実践を通じて具体的に提起されています。
2007年4月、学校教育法の一部改正で「特別支援教育」が正式に実施されることとなりました。「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。私も、前任校で(2012(平成24年))特別支援コーディネーターとなり、校内の支援体制の確立に取り組んだ中で、自立や社会参画するという視点に立った支援には十五年間の育ちを見据えて進めることの大切さを認識しました。それと同時に特性のあるその子への「個別支援の手立て」について語られることが多いけど、その子が所属する「クラスや学年集団のありようや関係性の構築」についてしっかりと実践を進めることが重要だと議論した覚えがあります。現在も同様で、当事者(特別支援教育のニーズの必要な生徒)を包括する「認め合う集団づくり」に果敢にアプローチしていかねばならないと思います。前述の拝野氏の著書をもとにしっかりと語り合いたいですね。
☆12 生活ノートと「効率化、働き方改革」
「自主学習ノート」を初めて取り組んだ時期には、生活ノートと併せて2冊の点検に多くの時間が必要となりました。思い切って、生活ノートの提出をやめました。一日中、自分で持っていて、授業中には、教科担当からの宿題や提出物などの連絡事項をいつでもメモする、帰りの会には、教科係が書いた明日の教科や準備物を書く「生活ノート」としました。(大人が持っている手帳と一緒です。現在はそのようなマネジメント手帳がたくさんつくられていますが、生活ノートを朝の会で提出し、帰りの会までに担任がコメントして返すシステムを廃止することに、職場ではとても抵抗がありましたが。)「自主学習ノートに思ったことや生活のふりかえりなどなど綴っていいよ(自主的に)」とし、担任団は、「文章があってもなくても、しっかりと自主学習ノートにコメントする」ことを共通理解し、三年間取り組みました。今年、二十歳の集いで久しぶりに会った彼らはステキな大人になっていたなあ。
☆11 生活ノートのデジタル化
担任生活を振り返ってみて、これまでの「生活記録ノート」の主なねらいは,「生徒指導の視点による生徒理解」の要素が大きかったように思う。記入の様子や内容から,普段の生徒の変化を見逃さず、対話を通した学級担任との信頼関係構築ための大切な手立てのひとつだった。また、同和教育実践が大事にしてきた生活綴り方教育の視点での記入指導、支援をおこない、学級通信に掲載し、クラスへの提案や学級会での話し合いにもつなげる実践を進めてきた。生活綴り方教育とは、社会の現実のなかで厳しい環境に置かれた子どもたちが、実生活を綴ることにより、自らの生活を観察し、自分たちの生活の事実を認識し、 それに働きかけて、たくましく生きていくように育てるという立場に立った教育実践の方法であ る。
何度も消したり書いたりした跡が残る生活ノート、消しゴムの消しカスがはさがっている生活ノート、採点ではないからと、青ペンでコメントを長年書いていた生活ノート・・・は、やはり生徒の「くらし」を知り、教育につなげる大切なアイテムであった。何かと「振り返り」が重要視される現在、「生活やものごとを見つめ、つづれる力」を育みたいと思う。また、私たち自身も表現の中の「子どもの真実を読む」力を鍛えなくちゃいけませんけど。
『さみしい夜にはペンを持て』(古賀史健 氏:ポプラ社 2023)を読み終えて、「書くことは考えること、考えることは生きること」という、かつて作文指導で教えてもらったコトバを思い出しました。この本をもとに「書くこと」について授業化をしてみたいと考えています。
☆10 生徒の作品展示・学級通信掲載の
生徒名は〈明らかにする?〉〈匿名にする?〉(2/8)
インターネット場の匿名のコトバを使って、誹謗中傷、ヘイトスピーチなど人を差別する状況があります。そんな中で、学校ではやっぱり、自分の書いた文章、発したコトバ、つくった作品には、誇りと責任をもってほしいと思います。「えーはずかしい」「みんなにみせるのいやだ」を越える指導、支援を行い、「お互いに相手の考えや指向などをわかり合える「仲間づくり」を進めていきたいものです。(仲間の文章や作品を受けとめる集団意識の涵養)さて、そのためには、発表した生徒の発言を教員自身が受けとめることは大前提ですが、まずは、教師自身もせいいっぱい「自分のことを語る」ことが大切ですね。ありきたりのことではなく、「こんなことも話してくれるんだ。自分も話していいんだ」と思える内容を吟味し「子どもたちのモデル」に先生自身がなることです。」
☆9 聲をきく(2/7)
2015(平成27年)年に、当時勤務していた中学校区の保護者の方々の願いと市・県の積極的な取組の中で、勤務校に新しく自閉症・情緒障害特別支援学級が開級された。担任として私が、大切にせねばならないと思っていたことは、〈子どもと保護者の〈こえ〉をしっかり聴くこと〉だった。さらに、開級にあたっては、学習環境の整備(教室の構造化等)と、必要かつ具体的な合理的配慮の提供についても、保護者と市と学校がしっかり話し合いながら、綿密に準備を進めた。その流れの中で、入級する子どもの保護者の方々が、自主的定期的に開催する「親の会」に自分自身も参加した。
親の会では、お茶を飲みながら、一人ひとりの子どもの日々の成長を喜び合ったり、「子育て」や「社会的自立」についての悩みや心配・不安なことを出し合ったりしたが、いつも大きなテーマになっていたのは、中学校卒業後の「進路」であった。中学校では、子どもらは、一年時から計画的に進路・キャリア学習を進め、保護者もオープンスク-ルや高校説明会で進路情報を手にしていくが、特別支援学級在籍の子どもたちの保護者が「自分の子どもの発達特性」等に合った進路情報を収集し、進路支援の見通しをもつ機会はほとんどなかった。そして私自身も特別支援教育のニーズのある子どものための進路についての情報の少なさに、課題を抱えていた。
そこで、親の会で話し合い、まずは勤務している中学校で高校を招き、「進路情報を自分たちで手に入れて、勉強をしていこう」と取組を始めることとした。今年度は、学区の小学校とも連携して親の会を開催している。
第3回ひなせ親の会(情報交流会)〈ご案内〉
◎特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。◎これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。◎お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。(カウンセリングや講座ではありません)
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)の小寺さんからアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。
ご案内が大変おそくなり、申し訳ありません。お気軽に、申し込み・ご参加ください。
第3回ひなせ「親の会」のご案内
1 日 時 2024年2月14日(水)17:45~19:00
2 場 所 日生中学校 E組教室(北棟1階)
3 内 容 「進級・進学どんとこい!? こころがまえと手立て」
「三年間、六年間を見通した成長をともに」をもとに意見交流
4 参加者 小・中学校の保護者
日生西・日生東小学校 日生中学校の先生
SC SSW 備前市地域おこし協力隊さんなど
主催:日生中学校区連携協議会(特別支援教育部会)
5 連 絡 会場準備の都合がありますので、参加の希望をお早めに
(2/9までに)各学校の担当までお知らせください。
◎なお、スクールカウンセラーの教育相談やSSWへのご相談
も各学校に問い合わせください。
6 予 定 新年度第1回:4月8日(火)17:00~18:30(予定)
☆8 班活動の可能性(2/6)
『ザ・席替え(家本芳郎著)』を読んでいると、「替え替えではなくて、班替えという視点で考えんといけんよ」とアドバイスを受けた。支え合う・がんばり合う仲間(集団)づくりが課題であった学校にいた頃、その先輩先生は、「出来るのなら、子ども同士が関わる環境や状況をなるべく多く創出できるかを考えたいと思う。その取組・活動は、「個人でできること」、「個人でせねばならないことなのか」、「班の仲間とせねばならないことなのか」、「班の仲間とでできることなのか」とも言う。
さて、個人でもできるけど、班活動でできること(ゆだねること)は例えば? □健康観察 □宿題・生活点検 □提出物あつめ(列の後ろから集めるのではなく) □班ノート □班に1枚(大きくコピー)だけ資料を配る □班紹介ポスター □新教科書への名前書き作業(始業式・入学式学活) □自転車整備点検 □長期休業明けの思い出語り合い □新入生歓迎新聞づくり □学級通信ロゴ作成・・・・関わる=わかり合うチャンスをどんだけ創れるかなあ。 そして、給食時間(コロナ禍からの、本当の脱却を!)あの、班の仲間と、たわいのない話をしながら、様々なことを知り合いなんと大事な時間だったか。(もしかししたら、コロナ禍で、一番、非認知能力等の育成を阻んでいたかもしれない時間)本校の1年団は復活させました。それも、子どもたちの「班のみんなと一緒に食べたいという要望」をカタチにしました。なんと楽しい豊かな時間だったか(*^o^*)。
☆7 受験期のなかまづくり(2/5)
クラスのみんなで、「それぞれの進路実現に向けてがんばっていこう」と、あらためて仲間意識を強めるクラス(学年)イベントはどうでしょう。内定合格を手に入れた生徒、これから第1志望校の受験にチャレンジする生徒、「受験でクラスがバラバラにならないよう」に楽しく、深く、豊かな、がんばり合える学級活動を創造したいですね。
1イベント名:「ほっと一息、お茶を飲んで、みんなで受験を乗り越えよう」学級活動
2事前準備:(内定合格の生徒がひとくちクッキーを焼いてくるだんどり) 実行委員による、飲み物アンケート
3用意するもの:飲み物を入れるカップ 飲みたい(お気に入りの)粉末のもと(お茶やココア、ミルクティーなど)一人分 お湯を沸かすポット
4当日:生活班隊形・円形
5式次第:①学級委員開会あいさつ (②クッキーありがとう披露) ③飲み物にお湯を入れる ④がんばろう乾杯 ⑤歓談・お代わり ⑥ひとりずつ、思いや願いを語る・聴き合う。⑦お招きしたゲストからのエール(先生等)(⑧歌やパフォーマンス))⑨閉会・かたづけ
☆6 今日は合格発表。(2/2)
合格発表とはいいますが、全員が合格を手にするわけではありません。合否発表の日です。
もう、あまり使われないコトバですが、それは「すべりどめ(受験校)」。若い頃、気軽に使ったワタシに、先輩先生がピシリと言われました。「ある生徒にとっては「すべりどめ」かもしれないが、ある子にとっては「第一志望校」なんよ。高校間格差を助長するような言い方(意識)はいけんな。本人が第1志望校が不合格で「すべりどめ」に行くこともあるよな。「すべりどめ」の高校で青春を送るという意識を子どもに持たせてええんか?あるいは、友達が、「すべりどめ」の高校に第1志望で入学する場合もある。お互いが違う学校を受験するんだけど、受験を乗り越える、ともにがんばりあう「クラス・学園集団」をつくるなら、とことんコトバは大事にせい。第一志望校、第二志望校と言わんとね。」
☆5 学校から地域・社会へ発信(2/1)
○三年生は、計画的に取り組んだハンセン病問題学習での「学び」を、邑久光明園さんや次世代ネットさんに協力いただき、「啓発パネル展」を開催しています。学習内容をプレゼンしたり、提言したりする取組が各校で行われていると思いますが、に発信・協働する「立ち位置」に生徒自身が立つこと(人権を大切にすることを他者に伝えようとする立ち位置)は「自分ごと」の意識が高まると考えられます。自身の展示会を観覧した生徒の振り返り(一部)。
○書いた人の気持ちがどの説明文にもしっかりこもっていたので、ハンセン病の差別をなくしたいという心がとても伝わってきた。たくさんのパネルを見て、ハンセン病療養所へ行ったことがない人でも分かりやすいと思った。
○パネルでよりハンセン病について知れたと思うので良かったです。あまり知識がなかった邑久光明園についての展示もあり、学べました。
○自分以外のパネルは初めて見たけど、詳しいところまで書いていて知らない知識がたくさんあった。中学生がこのような活動をして、地域の人にも知ってもらうというのは大切なことなんだなと思った。差別・偏見をなくす第一歩として、まずは正しい知識を得ることが重要である。
○みんな調べたことと、調べたことに対して考えたことを詳しく書いていた。この展示によって、正しいハンセン病の知識を持つ人が増えるといいなと思った。
○ハンセン病についての漫画も見て、知らなかったことも知れた。伝えていこうと思った。
○パネルの内容によって数字が割り振られていたり、内容への理解を深めることができるような写真も一緒に展示されたりしていたため、とても見やすかった。実際に行われてきたことをただ単に述べるのではなく、そこから考えたことも書かれていたため、読むことが楽しくなった。
○みんなテーマごとに大切なことをまとめられていました。書いて、見て、終わり、ではなくて、次の世代に伝えていくことが大切だと思うので、どういった形でも大切なことを伝えていきたいと思う。

☆4 先生は連絡係ではなああい(1/31)
少し前の、ある人権教育の研修会で、担任の先生が「朝・夕の会で私は連絡事項ばかり〈しゃべって〉いて、本当に大切なことを〈話して〉なかった。」という実践報告を聴いたことがあります。生徒へ伝えなくてはならないたくさんの事は、本当に、「担任」が言うことなのか?あらためて考えることができました。学級委員、係、日直、給食時間、ホワイトボードなど、子どもがこどもたちへ一生懸命に伝える場面や場所を、知恵をしぼってつくりたいなあと思います。係の子から仲間たちへ伝える「連絡票」にはしっかりと集中して耳を傾ける生徒が多いです。
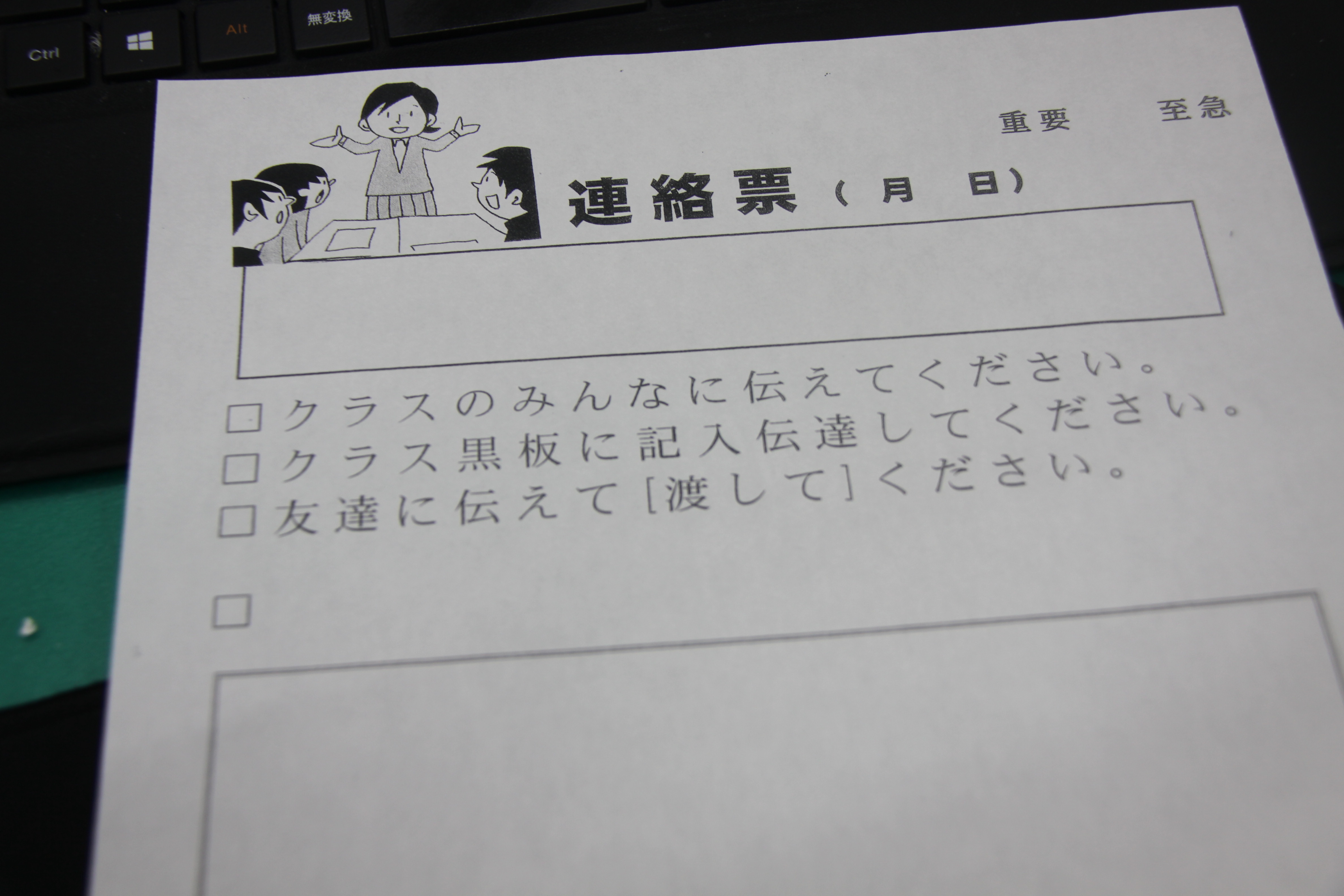
☆3 学級・クラス通信でのキャッチーな見出しは?
「私立一期入試」を終えて、どんな記事の見出しにするか?(1/30)
○〈私立一期入試 お疲れ様〉〈一期入試終える〉と無難な見出しになりそうなワタシですが、「誰」を意識して、「誰」のために、「何」のために(支えあうクラスづくり)の中での「こだわり」を大事にする」と考えると〈私立一期、みんなで乗り越えたぜ!〉〈共に乗り切った!またこれからも一歩一歩〉と、いうのもよいかも。〈がんばれ〉ではなく〈一緒にがんばろう!〉とすると、自分の立ち位置が変わりますね。
☆2 「弱さやニガテ」もわかり合えるクラスってステキ(1/29)
○得意なことや、趣味・特技を知り合う取組は多いが、自分の特性や、苦手なことを語り、共にわかり合い、支え合うクラス集団づくりはとても大事です。1年生は計画的な取組の中で、そんなことをお互いに語り合い、教室にも掲示しています。
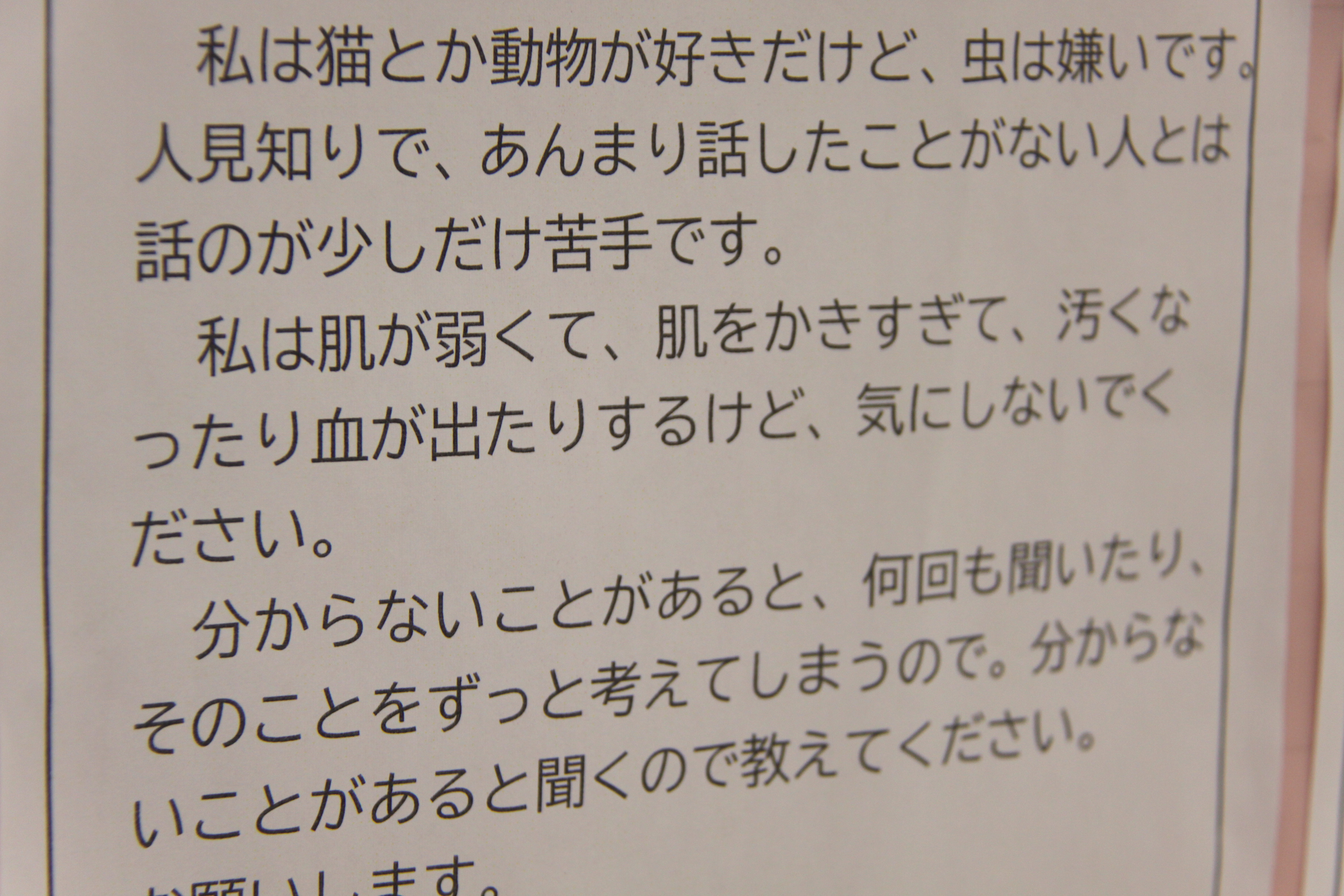
学習計画
【1時間目】『DVD君が僕の息子について教えてくれたこと』より
【2時間目】クラスでクラス わたし あなた なかまを〈よく〉しるために
・カレーライスワークショップ(トレーニング)、真実を見抜トレーニング2(BBCニュースから)
【3時間目】『わたしあなたそしてみんな」
・特徴や持ち味(動物)だけのヒントで、それが誰なのか当てるワークショップ
【4時間目】ワタシとワタシのとなりの「あなた」と共に生きていくために
・エリアテーチャー:東備地域自立支援協議会子ども部会 塚本さん、備前市役所障がい者福祉係 松下さんをお招きして~5時間目への提起
【5時間目】ここだけのみんなに知ってもらいたいこと。わかってほしいこと」ひとつ報告会
・これからがんばる「進路実現」や「学校生活」にむけて、クラスの仲間に知ってほしいことをまとめ、語る。報告を受けとめる。
☆1 受験事前指導(1/24)
○入試への心構えや注意事項、持ち物の確認などはとても大切です。そしてもうひとつ、生徒たち自身がお互いに、これまでの努力を讃え合い、「明日はがんばろうね!」と声をかけあう時間をとりたいものです。グータッチや握手、ハグをしながら、健闘を誓い合うことは、学年仲間の絆が一層強まるのではないでしょうか。学年の先生の一人は「先生の専門教科(理科)の知識を全部インストールするよ」と、希望生徒と握手で送電(?)してました。

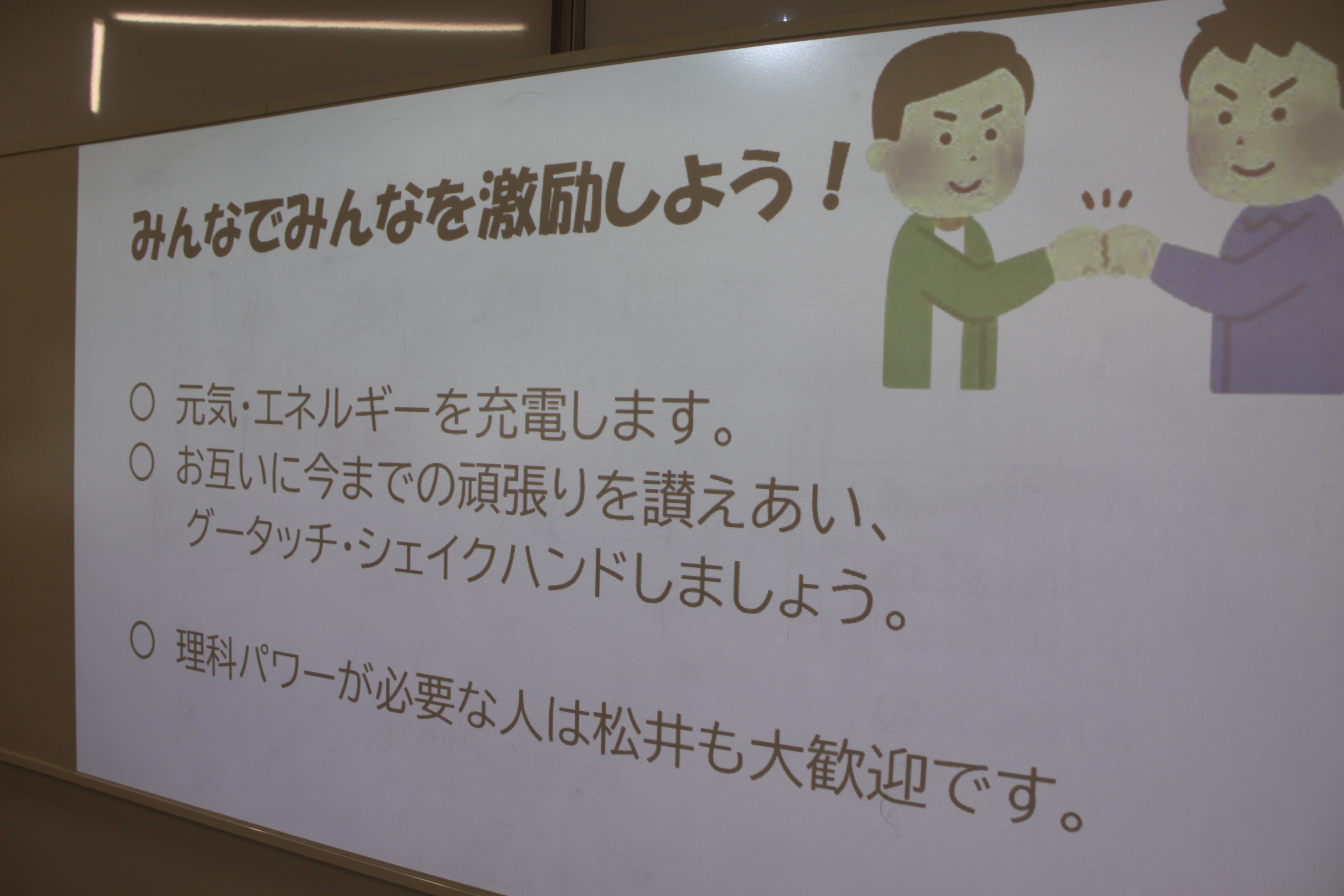

☆310日目(5/27)聴き取り?? 6/15の日
近くのスーパーに置いてありました。親と子の笑顔での会話が想像できたりしませんか。「聴き取り」学習は、余計なお節介の面もあるかも。でもそんな「つながる」取組をコーディネートすることが学校では大切だわ。
☆309日目(5/26)人との出会いを紡ぐ
304日目に記したが、家庭科でやはり修学旅行で「聴き取り」を課題にしている。3年生は保育分野を学習してるので、民泊先の方々に、「小さい頃の遊びや、食事、行事」と合わせ、「親の願いはどんなものだったのか?」を聴く。岡山と自然も文化も違い、しかも80年前に地上戦が行われた地である。子どもの頃の記憶や生い立ちから、戦争の実相を知り、ぐぐっと自分の身に近づけてくる子どもたちもいるだろう。
また、修学旅行の民泊先に、子どもたちは日生、岡山の観光パンフレットを持って行く。その取組についても日生観光協会の方が修学旅行の出発前日に来校されエールを贈ってくださる。さらに平和集会で歌う「島唄」の歌唱ワークショップで妹尾さんが来校される。多くの人々に支えていただき、修学旅行の内実が深まっていくように思える。帰校後の沖縄での学びのまとめが楽しみだなあ。
☆308日目(5/23)発達特性への支援
少し前(2023)に、関西地方の福祉関係の仕事をしている友人Sと、「学校の生活指導はもっと、「発達特性」の視点を大事にして、積極的に進めなければならないのでないか?」と責められたことがありました。専門機関や医療機関などと連携しながら、学校の支援体制を充実させることは、今とても重要になっています。その時に友人Sと交わしたメモを読み直しています。
☆307日目(5/22)「仲間と共に」の姿を、人権教育から拓く
土田光子さんをお招きしての校内研修会の案内ができました。限られた時間での講演(学習会)ですが、集って、聴いて、考えて、語って学び合いたいと思います。
☆306日目(5/21)ハンセン病問題学習を
山陽新聞(5・20)の記事を紹介します。
☆305日目(5/20)水平社宣言から学ぶ
社会科では、視聴覚教材も使って、深い学びにしていこうと授業研究を進めています。人権課題とのステキな出会いをどう紡ぐか。


☆304日目(5/19)民泊での学びをさらに深く
縁あって、家庭科の授業を一緒に検討する機会があり、昨年度の3年生が学習した内容を調べていると、「民泊先の方々に聞こう」というワークシートがあり、いいなあ!と思った。修学旅行の民泊は、よく考えてみれば民泊先の方々に丸投げ感が強いような気もする。岡山と異なる豊かな文化、風土をもつオキナワに生きてきた人々に直接話を聞ける貴重な機会と考えたら、多様な学習が考えられる。家庭科でのワークシートには、「子どものころの遊びや風土、季節の衣服や食文化」をそれぞれ聴き取らせてもらう欄があった。また、社会科や総合的な学習や課題探求学習として、オキナワ戦についてや戦後の沖縄復興や基地問題についての生の声を聴くことが可能だ。さらに、岡山や日生を紹介した自作パンフレットを持って行ったり、地元の観光協会から委ねられた観光パンフレットを渡すこともおもしろい。(そういえば、インターネットの性能がまだまだだった頃、「うちかび」とは言わず、それを生徒一人ひとりに配り、「どんな方法でもよいから調べて、社会科POINTを手に入れよう」と指示し、たくさんの生徒が、話題のひとつとして民泊先の方々に聞いて、社会科ポイントをゲットしていたことを思い出した。*ちなみに現在は、「黄色の紙 沖縄」だけで検索すると「うちかび」にヒットするので、沖縄で聞くまでもないことになってしまった)
人とひとがつながるしかけを、行程の中に入れこんでいくことができると、さらに「修学」旅行での学びは深くなる。
☆303日目(5/16)復習の小テストでもつながる
毎日の社会科授業での振り返り(復習)で使う小確認テストも、ちっちゃな「つながり」をつくることが出来るのではないかな。
☆302日目(5/15)参加している研修会はいくつある?
新年度になって最初の東備学ぶ会を5/10に開催しました。参加者がそれぞれ勤める学校でのクラス開き・授業開き、保護者との連携などについての具体的な報告をもとに、自分の実践を深く振り返ることができました。また、話題になったひとつに、〈研修会〉があります。それは、「自分は、研修や学習する機会をどれだけ持てているか?」です。若いN先生の「教育センターでの研修と校内研修しかないかも(東備学ぶ会に参加されてますが)」の発言に少しびっくりしたのととても残念に思いました。他の参加者の方々からは、この東備学ぶ会意外にも、岡山学び工房(学びの協同体についての学習会)、県教組夏季自主編成講座、渋染一揆現地研修会、教育運動推進センターの同和教育部会、金泰九さんに学ぶ教育実践交流会(今年度は11/22(土))、岡山県人権教育研究大会(今年度は8/7(木))や第一次教育研究集会(5/31(土))など、今も大事な研修(学習の)場にしていることが挙げらましたが、学校以外の研修会になかなか参加できてなく、また、「中・小教研の活動も「研修のさせられている」感をもったり、「報告や発表が目的化しているのではないか」という意見もでました。さらに、「学校現場は、自分から動かず、口を開けてエサを待っているひな鳥のような状況になっていないか?」との厳しい指摘もありました。
自らの足で、豊かで、確かな「学び」を手にいれないといけないなあと自省します。基本的に土曜の午後に開催する「東備学ぶ会」も、参加した方が「来てよかった~。明日からまたガンバロウと思う」時間になる内容をこれからも創っていきたいと思っています。
☆301日目(5/14)研修会の学びを深めたいなあ
以前にも記した内容と重なりますが、やっぱり最近の教職員の研修に参加すると、講義や視聴後に「近くの方、グループで感想をお話しください」という時間を取っている場合が多いなあと感じます。2000年頃に参加型の学習スタイルが導入され、講義形式の一方的でなく、双方向性を意識した研修会が増えました。自分の感想を話し、グループの方の意見を聴かせていただけるので、そのような相互に学び合う時間は自分にとってとても貴重です。しかし、研修でとり扱う人権課題の内容によっては、やはり、全体会で「質疑」「討議」「意見交流」「総括」「まとめ」などが必要な場合が多いと思います。
先日、人権啓発DVD『人権のすすめⅡ」を視聴した研修会も、全体会での意見共有ができたらよかったなあと思いました。と書きながら、自分がファシリテータとして全体会を進行することになると、なかなか不安もあり難しいなあと思いますが、「マイクロアグレッション」や「心理的安全性」などの新しい人権に関するキーワードを「知る」ことで終わらずに、人権意識や実践力を「深める」ための「全体会の」ファシリテートに少しずつ挑戦したいと思います。
☆300日目(5/13)ふれる?さわらない情報?
生徒との何気ない会話(情報)の中には、結構、家族や家庭のリアルな出来事が多い。時に、家庭での大きな出来事をさらっと(本当はそうでないけど)話すことがある。その話した内容(事案)は、〈聴いて、子どもと共有する〉だけでよいのか?、もしくは、〈本人のhelpとして受けとめ、きちんと還していく(または保護者と共有していく)」のか?と思考することはとても大切だと思う。子どもが話した内容は、虚と実(+無意識の思いなど)も含めて混沌としている場合もあるので、そんな時は、聴いた教員が一人で思考し、判断することは悩ましい。だから、仲間や学年団の教員から助言やアドバイスをもらったり、ケース会を持って共有することは必須だ。
聴いた(話の)内容が、ネグレクトや虐待、ヤングケアラーにつながる事案や、家庭や家族との学校連携の強化や、また、福祉や行政の支援につなげるきっかけにもなるかもしれない。「子どもの声」に誠実に「応えたい」と思う。
☆299日目(5/12)子どもの現実からスタート
週一回を基本に開催する生活指導委員会での報告がありました。それは道徳の授業で、「自分が入っているLineグループで、自分の仲の良い友達への誹謗があったらどうするか?」の発問に、予想していなかった発言があり、さらに多くの生徒が同じような意見を持っていことにとても驚いたということ。昨今、たくさんのスマホやケータイの危険性や付き合い方を学ぶ資料やプログラムは作られ、小・中学校で、継続的にそして繰り返し、学習に取り組んでいますが、「子どもたちの発言、〈思っている(思わされている)こと〉=現実」を見据えて、指導や支援、学習を展開していかないといけないなあと、再確認することができました。追記:生活指導委員会で、授業での子どもたちの様子(個人の名が出て)の報告をしてくれ、また、それを受けて、多面的な視野で支援、指導について協議できるメンバー(組織)はステキだなあと思っています。
☆298日目(5/9)「ありがとう」を書く
校外研修から帰った子どもたちは、それぞれ「ふりかえり」をしています。その「ふりかえり」に活用するワークシートに、「ありがとう」を書く枠(項目)があれば、その視点で研修を深く振り返ることができますね。また、クラスメートの何気ないひとことややさしさ、具体的な、(のぞましい)言動を、学級通信で共有することも大切ですね。
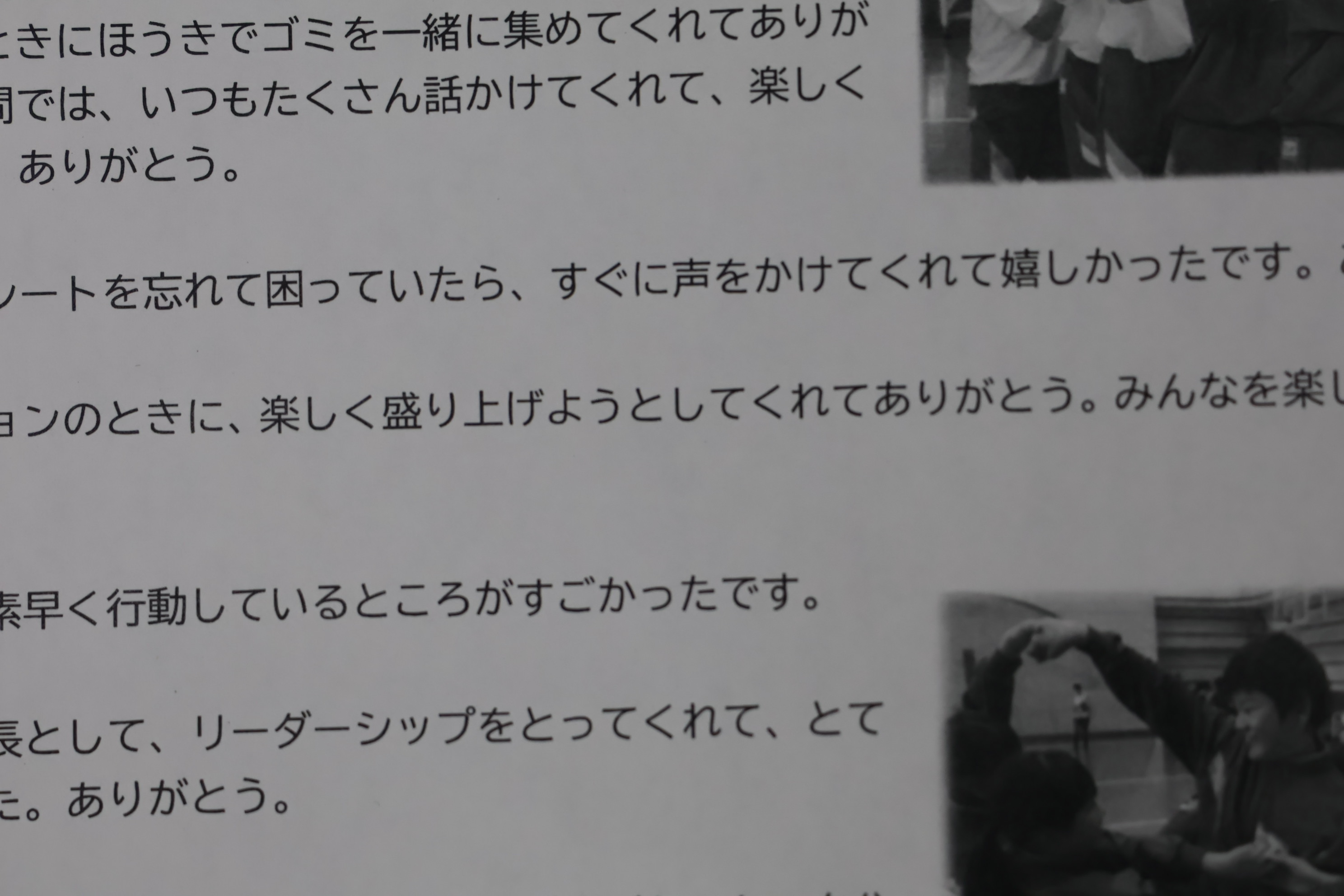
☆297日目(5/8)調整中ですが
『授業規律とは、一人ひとりが大切にされ、気にかけられているという信頼や、わからないことは支援の対象になっても、決して笑われることではないという安心と協働の文化を育む日々の学級経営を前提として、さらに授業そのものの工夫によって、結果として生まれるものであって、決してルールやしつけだけで成立するものではない。』と語られる土田さん。
本校の教育目標〈夢に向かって仲間とともに生きる生徒育成〉に向けて〈仲間ともに〉を、どのように進めていくか?~人権教育の視座から創る授業創造、学級・学校づくり~(仮題)をテーマに土田光子さんをお招きして講演学習会(校内研修会)〈6/23(月)14:50~〉を開催します。関心のある教職員の方々もご参加可能です。後日、ご案内させていただきます。
講師:土田 光子さん:1977年より中学校国語教諭として35年間教壇に立ち、子どもたちが教室で見せる事実の背景には一人ひとりが抱える生活があるという原則を大切に生活丸ごとでつながる集団づくりに取り組み続けてきました。2012年度より、9年間大阪教育大学で非常勤講師をされ、2021年より、大阪多様性教育ネットワーク共同代表をされています。著書に『私を創ったもの(明治図書)』、『格差をこえる学校づくり(大阪大学出版会)』、『子どもを見る眼』があります。
☆296日目(5/7) 春15(いちご)の会もあるよ
特別支援教育のニーズのある子どもたちのための進路情報交流学習会(春15の会)の実行委員会をおこないました。今年度も多様な進学先の情報をYouTube配信、また8月23日(土)12:30から、対面式での学校説明及び個別相談会を開催(会場:備前市立日生中学校)する予定です。準備をこれから進めていきます。春15の会のこれまで

☆295日目(5/2)学級活動通信に生徒名を載せる?
通信に子どもたちの名前を載せる?が話題になりました。
子どもたちが綴った学習のふりかえり・作文を学級通信に紹介し、学んだことをさらに深めたり共有していく取り組みはこれまでも大切にされてきました。私も通信で生徒の感想を載せる場合は、もちろん本人(保護者)に事前の承諾を得るのは前提として、自分の表明した内容(作文)には、誇りと自覚を持つべきとの考えから、表明する(生徒自身で決める)ことを基本としていました。(匿名性のデメリットを考える上でも。*ちなみに無記名で作文させる必要や価値がある場合もあることも最近では理解しつつ… 匿名と無記名は違いますね 匿名で書く内容と、無記名で記載することも意味が違うような?よくわからなくなってきました。)
実際には、名前を記載して紹介することを基盤として、時には内容に合わせて、生徒名を記入せず、口頭で紹介する場合もありました。でも、この、子どもの手を通して保護者に渡る通信の目的のひとつは、学校で子どもがどんなことを学び、子どもと一緒にいるクラスメートらとどんなことを考えたのか、を知ってもらえたらいいなあと考えていました。「学校を開く」ことの具現化というと、おおげさですが、学校・担任の大切な仕事だと思います。さらに、通信は、学級経営、学級活動の学習教材として考えているので、紙媒体のみの発行で、HP(デジタル化)等に紹介する(残す)必要はないと考えていました。
さて、通信のこれからを考えるに、参考に以下の文章を紹介します。…
個人情報保護法では,個人情報は「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」(個人情報保護法第2条第一号など)と定義されています。個人情報に該当するか否かは状況によって相対的に判断されます。そのため,掲載されたものが作文の一部であり,さらに名前が伏せられていたとしても,同じクラスの児童生徒や保護者には,誰の作文であるかが識別できる場合,個人情報に該当する可能性があります。作文が個人情報に該当するならば,原則として本人及び保護者の同意を得なければ学級通信に掲載することはできません。しかし,誰が書いた作文か識別できるかどうかは作文の内容に左右されるため,教員の判断だけでは難しい場合もあります。また,作文には児童生徒のプライベートな情報が記載されている場合があります。仮に,そこに児童生徒にとって他人(担任教員以外)に知られたくない情報が含まれていた場合,プライバシーの侵害に該当する可能性もあります。したがって,作文の一部でも学級通信に掲載するには,たとえ名前を伏せるとしても,個人情報やプライバシーの侵害に該当しないかどうかを慎重に判断する必要があるのです。
作文を学級通信に掲載することは,著作権の関係からも問題があります。作文も著作物である以上,児童生徒には著作者として公表するかしないかを自由に判断できる権利があります(著作者人格権としての公表権・著作権法第18 条)。そのため,著作者である児童生徒の同意なく作文を掲載することは,著作権法に違反する可能性があります。なお,著作権法第35 条第1項により,教員は授業の過程において著作物を著作権者の許諾なく複製することができますが,これは「公表された著作物」が対象なので,公表されていない児童生徒の作文は対象外であることに注意しなければなりません。
では,個人情報保護及び著作権の観点から,事前に児童生徒及び保護者の同意を得ておくには,どのような方法があるでしょうか。実務上は,入学直後や学年の開始時期などに,作文などを学級通信で掲載することにつき反対である児童生徒や保護者に対しては,あらかじめ同意しない旨の書面を提出してもらうことが行われています。学校の教育活動で個別の案件ごとに個人情報や著作権に関する同意を得るのは非常な手間であることを考えると,包括的な同意ないし不同意を得ておくことで対処する方法も違法とは言えないでしょう。(注*本校でも新年度に文書を配布・依頼しています)
しかし,たとえ保護者から包括的な同意を得ていたとしても,児童生徒本人が作文の掲載を希望しない場合にあえて掲載することは,子供の権利の観点から不適切と言えます。したがって,作文の場合は保護者から同意を得ていても児童生徒本人に掲載してもいいかどうかを確認する必要があります。一方,保護者から包括的な同意は得られていないが,児童生徒本人は掲載を希望する場合は,保護者と協議の上で掲載するとよいでしょう。(著・監修/神内 聡さんのHPより一部を紹介させていただきました)

☆294日目(5/1)閑谷の地で何をする?
郊外研修に出発する直前に、これからのスケジュールについては、「研修のしおり」の中に書いてあることを念押しし、「見て」「考えて」「行動」することを確認して学校を出ました。「生徒自身が考え・行動することを目的」としながらも、研修先に集まった時に、教員が再度、不必要に持ち物や注意事項をしゃべり、行程を語つたりすることが多かったなあ」と自らの実践を反省しました。自らしおりを見て、仲間に聴き、行動する姿はさすがでした。さらに、午後からのプレールームでの〈なかまづくり〉レク大会。笑顔と笑いと称賛に包まれた2時間半。ルールを守ることの中での楽しみの共有、仲間意識の高揚、また、ブーイングなど表現に対する適切なアドバイスがありましたね。学校に帰ってからの学びとしての「振り返り」が大切ですね。
子曰、学而不思則罔、思而不学則殆。子曰く、学びて思わざれば則ち罔し(くらし)、思いて学ばざれば則ち殆し(あやうし)

☆293日目(4/30)東備の先生たちと学び合う時間は
5月スタートします。
☆292日目(4/28)東備の先生たちと学び合う時間
自主的な学習会をしています。
☆291日目(4/25)教員が語るコトバ。
この時期、クラスでの新しい班づくりのために、班長さんらと担任は放課後、よりよい学級のために協議を重ねていることも多いかな。案が完成したら、学級活動資料に班長のひとりが書いてきて、次の日の朝、担任に印刷してもらい、6人の班長とともに、みんなのまえに立ち、班長としてのねがいや思いを語り、話し合いでの苦労したことを伝え、班案を提案・協議する。もしかすると却下されるかもしれない(ことも想定)。教員が説明したり、語らない班会議をめざしたい。すぐにはそんな生徒集団にはならないのはあたりまえだが、自主、自立、自律などの目標があるクラスや学校ならば、これこそ具現化しないといけないなあ。
☆290日目(4/24)教員が語るコトバ。
他県の友人Kとの会話。久しぶりに1年団の担当になったKさんは、うれしそうに「一生けん命に聴こうとする子どもたちを前にして、注意や小言、ましてや連絡ばっかりしてはいけんなあと。教員が発するコトバをもっともっと、磨きたいなあ。同時に、自分が「しゃべってしまう」内容を、子どもに委ねたり、子どもたちが語りあう時間をつくりたい」と熱く語った。朝夕の会のプログラムの紹介や生徒連絡票などの活用についてもお互いに実践について話しながら、長い長い長い電話を切った。
☆289日目(4/23)やっぱり、話しをしたら…
給食でのアレルギー相談などで来校された保護者が、相談が終わって帰られるときに、養護の先生は「〇〇さんが帰られます」と、私にも声をかけてくれます。それを受けて私は、保護者に声をかけて、学校での子どもさんのがんばっている様子を伝えたり、卒業したお姉ちゃんや兄ちゃんの話を聴いたり、たわいのない話をしながら玄関まで送っていきます。学校ではわからない、家庭での子どもの姿を教えてもらえたり、様々な家庭のようすを知ることができます。大事にしたいなあと思います。養護の先生との連携?と言うと変ですが、大切にした協働的な取り組みだと思うのです。
☆288日目(4/22)ここに書いてある内容って人権教育なの?
と、いう素朴な質問をうけました。「第4次岡山県人権教育推進プラン」を読んだらやっぱり、人権教育は教育活動のすべての基盤となる営みだと思います。前掲した内容ですが、あらためて、同和教育が育んできた人権教育について少しだけ確認します。同和教育」という名称が、「人権教育」と置き換えられ月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを、人権教育の取り組みの原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)などのかたちで問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ねて、今もその実践は多岐にわたる分野で生かされています。特に、確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教員・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、今日の教育課題を≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。また、同和教育で積み上げてきた豊かな教育内容と実践は、国際的な人権教育で提起されてきた内容と完全に一致していると確信をもっています。学年を中心に取り組む人権問題学習から日々のクラスでの出来事まで、どれも人権教育の視座に立つことができているか?を検証し、大切にしていきたいですね。
第4次岡山県人権教育推進プランから、
(3)人権教育の三つの視点
【視点1】人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成 人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と意義についての理解と認識を深めるとともに、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それらを共感的に受けとめるような感性や感覚を 育成する取組を進めます。 人権に関する知的理解を深めることと人権感覚を身に付けることによって、自分の人権と共に他の 人の人権を守ろうとする意識・意欲・態度につながり、さらにそれらが、様々な場面や状況下で、問 題状況を変えていこうとする実践行動となって現れるようになることが大切です。
【視点2】自立支援 一人一人を大切にするという観点から、人権問題に関わり教育上配慮を必要とする人の自立支援に 取り組みます。 差別や人権侵害によって、個人のかけがえのない可能性が制約されている状況があれば、そのこと に自分自身が気付き、本来持っている個性や能力を伸ばし、自己決定力を高め、自律的な力を付け、 それらの力を発揮して行動していくことができるように支援していくことが大切です。
【視点3】人権を尊重する環境づくり 視点1及び2の取組の基盤となる、自分や他の人の大切さを認め合えるような学校園や地域の雰囲 気づくり、そのための条件整備等の環境づくりに取り組みます。 人権教育が効果を上げるためには、人間関係や全体的な雰囲気等も含め、学校園や地域の教育・学 習の場に人権を尊重する環境をつくることが大切です。また、違いを認め合い、多様性を受容する社 会を目指して、自他の人権を尊重し差別を許さない社会的風土を培うことも大切です
☆287日目(4/21)自分を開き、仲間を知る授業
1年生の家庭科では、生徒一人ひとりが宿題として、自分の私服をひとつ持って来てました。授業で学んだ「TPO」をもとに、自分の衣服について発表し、互いに聴き合いました。さらに、これが自己紹介も兼ており、個性豊かな、お互いを分かり合う楽しい授業となりました。
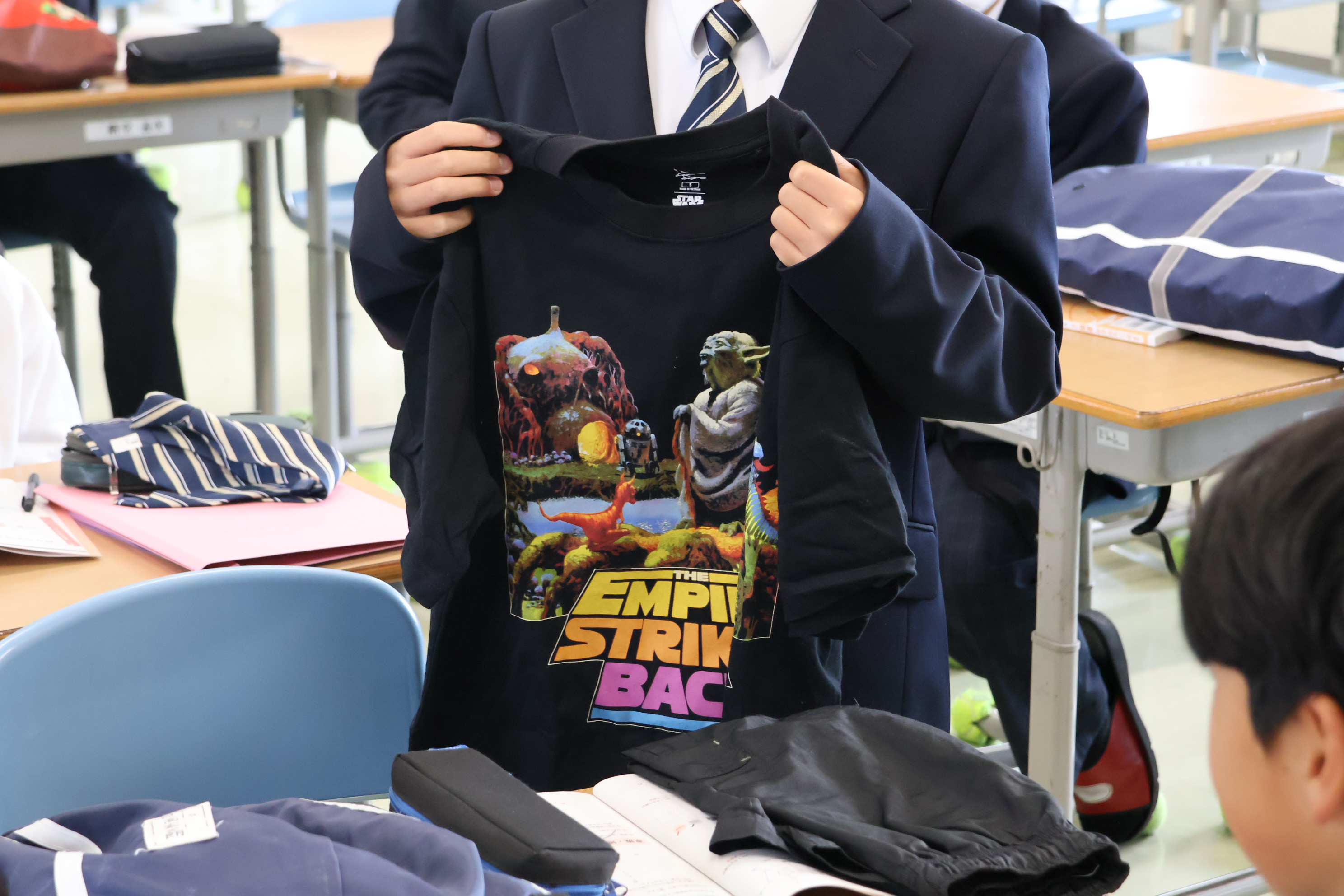
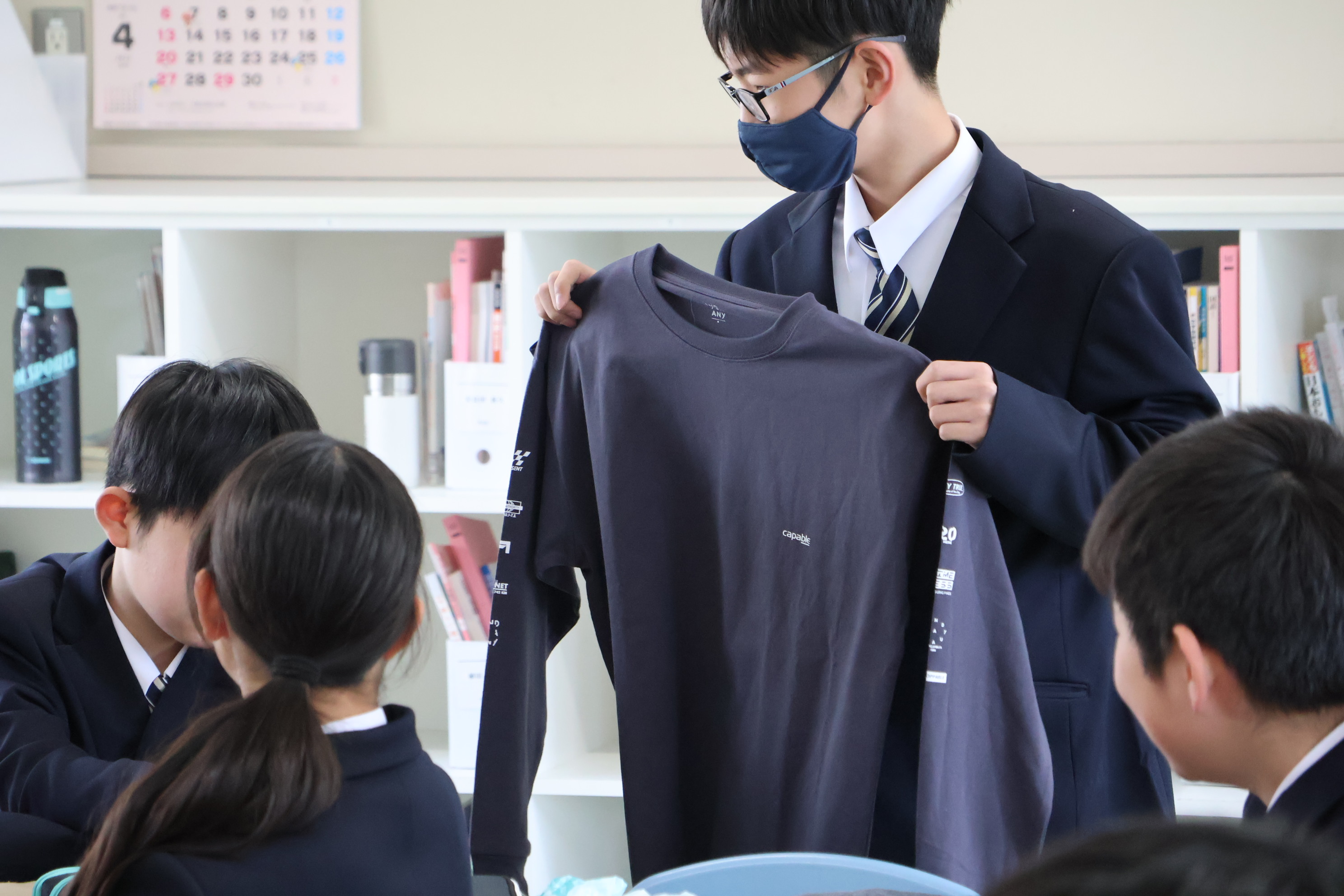

☆286日目(4/18)学級活動資料となかまづくり
学級役員の選出をする際に、学級通信を補助教材として作成している担任。時間も手間もかかるだろうけど、大切な時間にするための熱意が感じられ、「いいなあ」と思う。また、その学級通信は、家に持ち帰ることで、家族らと語るアイテムになることような願いも感じられて、さらに、「いいなあ」と思った。
そうだ!学級通信として発行するならめんどくさいいろいろな手続きがあるならば、学級活動資料として(もちろんロゴを入った学級活動資料)ワークシート形式にするのいいかもしれない。子どもたちは、新しく学級役員に決まった(決めた)仲間の名前を確認しながら記入して一覧表を完成させる。そして、その学級活動資料を家に持って帰るのだ。
担任がまとめた一覧表でなくてもよいかもね。記入する学級通信、いや学級活動資料の作成の発想はどうです?
☆285日目(4/17)入学式の準備・片付けから
新2・3年生諸君!入学式の会場準備では、とてもよく動いている姿がみえ、「さすが!すばらしい」と思いました。さて、会場準備ですが、もちろん、事前に、生徒のしごとの分担をしますが、これも、複数人であたり、子どもどうしで会話を交わしながら協力して取り組めるように進めていきます。そして、がんばった姿をカタチとして、ホームページで紹介する時には、協力しあう場面(二人で運ぶすのこ、みんなで整える白布机など)の写真が多いのはその性かしらん。

☆284日目(4/16)校外研修でOLしない?②
よりよい人間関係をつくるためには,「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる豊かな 人権感覚を育むことが特に重要です。 人権感覚は,言葉で説明するだけで身に付くものではな く,周囲の様々な人たちとの関わりの中で体験を通して育まれていくものです。子どもたちの人権感覚は,子ども自らが, 主体的に他の子どもたちとともに学習活動に参加し,協力的に活動し,体験することを通して身に付くと言えます。その 際,参加型の体験的学習が有効であることが指摘されています。 参加型学習は,子どもたちの主体的な活動とコミュニケーションを大切にし,単に知的理解にとどまらず,自分で「感じ, 考え,行動する」という主体的・実践的な学習です。参加型の体験学習は,「体験する」ことから始まり,「学んだことを日常生活に生かし」たり,「自らの変容につなげ」たりするところまで高める一連のサイクルで進めていくことが大切だと思います。 たくさんのあるアイスブレーキングやアクティビティの中から,人間関係づくりや人間関係の課題の解決につ ながることを意図し,〈自己肯定感の育成〉,〈友達との関係づくり〉,〈学級集団づくり〉の3つの観点で有効と考えられる活動を、限られた時間の中で取り組んでいきたいものです。
重ねて、「仲間づくり」の文言の前には、「反差別の仲間(づくり)」・「多文化共生の仲間(づくり)」などが、これまで取り組まれてきた人権(同和)教育の実践の中では掲げられていました。「どんな」仲間づくり(具体的な子どもたちの姿)に取り組むか?について、教職員みんなの認識を共有していきたいと思います。
☆283日目(4/15)校外研修でOLしない?
校外研修で定番のオリエンテーリングをせずに、体育館で「なかまづくり」の計画を進めている。何度もやっているOLを漫然と実施するのではなく、子どもたちの現状(持っている力や集団の課題(小学校からの引き継ぎ))を鑑み、学校を離れた立地条件を活かし、積極的に「仲間づくり」に挑むそうだ。大事なことですね。
以前からある「チームビルディング」、「何デジベル?校歌を歌う」「じゃんけん王」「誕生日チェーン」だけでなく、共同、協力、他者理解などの目的にした新しい、参加型体験学習、アイスブレーキング、ワークショップやアクティビティやコンテンツは、調べてみるとびっくりするほど他にもたくさんありますね。もちろん、どれをしてもよいわけでなく、「あー楽しかった」で終わらないように、「振り返り」をていねいに行おうや。事後(帰校後の取り組み)の学校生活につなげる見通しを持とう」と、一年団では確認をされていました。(続く)
☆282日目(4/14)お互いのくらし・生い立ちを知ることからの仲間づくり
家庭科で授業が楽しい!自分の一番最初の記憶をお互いに語ることからスタートして、幼い頃(乳幼児期・幼児期・児童期)の、「好きだったこと」、「嫌いだったこと」「楽しかったこと」などをクラスの仲間らと交流する授業展開。「なりたかったこと」で、〈どんぐり〉になりたかったと発表したり、日生の地でありながら、カキが苦手なクラスメートが結構多いこともお互いに知り得た。この授業をもとに、おうちの人(身近なひと)から、生まれた時の頃(前時の学習内容のつけたしと親の願いや思い)を聴き取り、クラスで発表するそうだ。思春期の子どもたちと親が向き合える大切な時間にもなるでしょうね。
☆281日目(4/11)出席簿
新入生のクラス出席簿について、新一年団の教員がアレコレと話している。「1番から(もちろん男女混合)、五十音順。もちろん支援級での授業を受ける生徒も含めて。(もちろん生徒・保護者の意向を聴いて)で印刷中でーす」「教員の都合や効率だけで名簿を分けたりしたらいけんな」と。
ステキな教職員集団です。この姿勢がみて子どもたちも育ちますよ。
☆280日目(4/10)写真の撮影隊形にならべ?!
新学期、郊外研修もあり、集団で写真を撮る機会やあります。撮影の隊形に、生徒は並ばされるのか?教員が並ばすのか?自主的に自分らで並ぶのか?って考えたことがありますか?校外研修や修学旅行先で、大きな声で教員が「並べ!」と叫んでいる学校を今でも観ることがあります。私は校外研修などでは、私自身が集合させることは少なく、実行委員が、クラスメートの前に立ち、集合場所や目的に応じてハンドサインを出して、①隊形、②隊形、写真隊形、バス隊形、「近くに寄るよ」隊形などなど、けっして大きな声を出さず(お互いが声をかけあって)に集まることができていました。
集団づくり、仲間づくり、学習集団づくり…それぞれどんな集団のイメージですかね。
☆279日目(4/9)深く、掲示・開示する
新学期・授業・クラスで、今年度の目標を考えて、ワークシートに、書かし掲示したり、発表させたりする機会も多いでしょう。そんな今、ちらっと寄ったクラスでは、単に「がんばる」と書かせるのではなく、自分の「がんばる」ことを、もう一度見つめさせ、具体的な目標や願いを綴る取り組みにしていました。すごいね。「書かせて、受けとる」ことは、生徒の自主性を尊重していることではありませんね。時には、ワークシートをつきかえし、「なぜそう思ったのか」「どうしてそれをがんばりたいのか?」「がんばるためには自分はどうしたいのか?」「クラスの仲間に願うことは何か?」など、深く思考する(自分をめくる)ことをきちんと促すことが大事だと思います。そして、そこで綴られた内容を級友らと開示し合う時間は、とても大きく変わるでしょうね。
☆278日目(4/8)学級づくりについて
桂 正孝さんが『いま「学級社会」をつくる意味』と題し、『部落解放838号(2023年5月号)』に書かれている小論をあらためて読んでいるところです。冒頭の部分を紹介します。
〈今日の公教育としての小中高校の学級担任教師の場合、教育実践の仕事の中心は、授業(教科指導) と学級づくり(生活指導)であるといえよう。本小論の表題に「学級づくり」に代えて「学級社会」づくりという用語を用いた意図は何か。いうまでもなく学級は、現代の学校制度にもとづいて編成される学校生活の単位集団であり、教師の指導によって真理や真実を追究し、子どもの個性的発達をめざす学習集団である。その際「学級社会」 づくりは、ホームルームという学級生活の場を中心に、教科指導と生活指導をとおして学習権保障を追究する教育実践の営為を意味している。いいかえれば、「学級社会」は、子どもたちが集団生活のなかで各自の学習体験をとおして「ものの見方・感じ方・考え方」を吟味しあい、民主主義のあり方を学ぶ場でもある。〉
新しく来られた家庭科の教員と相談して、学級社会を意識した、「聴き取り」「語り合うこと」「自己開示」などを通して、クラスの仲間たちと深く・確かに「分かり合あえるよう」な授業実践を考えています。
☆277日目(4/7)「わたしたちのしごと」について
先日、京都のお寺で、ある住職さんからお話を聴きました。
・・・檀家さんと一緒に食事をしていた時、対面に座られていたおばあさまから「とても、箸遣いがきれいじゃなあ」と言われたとのこと。「褒めていただきありがとうございます」、「きれいに遣えることを教えてくれた親に感謝しなさいね」とやりとりがあったそうな。その中で、自分がいま、「あたりまえのようにしていること」について、物心もつかない幼い頃ころに、親からていねいに、きちんと教えてもらっていたからこそなのだなあ。感謝したこともなかった、と振り返ることができたとのお話でした。
自分のことと重ねて・・・。毎日の、私たちの教職の仕事も、感謝されるものではないし、子どものへの指導や助言、声かけや取り組みがが、すぐに望んだ結果なるものではない。数値にそう簡単に表れない。しかしながら、子どもの現実から深く学びながら、「日々、日々」教え育てる営みを積み重ねていきたい(いくしかない)なあと思ったのでした。子どもたちの自己実現に向けて。今日から新学期!
☆276日目(4/3)〈みつめる・語る・知る〉ことで〈つながる〉子どもに
新学期の準備を学年団を中心に進めています。職員室では、わくわくする会話が職員室で聞こえます。「朝・夕の会で、子どもどうしが語り合う時間がもちたいね」「連絡票をつかって、ぼくたち(教員)が、しゃべることをできるだけ減らせんかな?教員は連絡係じゃないからね」「生活ノート(タブレット)をどう活用して、綴る?」、「綴った内容を、帰りの会で、学級通信(学級活動資料)にたくさん紹介したいなあ」「コロナ禍以降の、班のカタチでの給食時間のがんばろうか」「交通安全教室なんかも、一方的なレクチャースタイルの学習はやめて、双方向のやりとりで学ぶスタイルにしたいね」「掲示物をクラスのみんなでつくれないかなあ」などなど。今年度も、「仲間とともに」というキーワードに、教職員みんなで具現化(実践)していきます。
☆275日目(4/2)多文化共生社会のすてきな出会いを
ALTさんとともに、教室を整備中です。大切な学びの場所と機会、「人の出会い」と、「語り合う」ことを大切に新年度をスタートします。


☆274日目(4/1)当事者ぬきでことを決めない
山陽新聞(3/30)より『手足が不自由で電動車いすを使う香川県の公立中3 年の男子生徒(15)が、設備面などを理由に入学を断られた県内の私立高を腕試しで受験する際、交渉に当たった中学校長から「合格しても入学しない」との確約を求められていたことが30 日、分かった。生徒と保護者は約束の上で1月に受験し、合格通知を受け取った。 その後、公立高に合格した。文部科学省は改正障害者差別解消法に基づく対応指針で、正当な理由なく障害者だけに条件を付けるのは不当な差別に当たるとしており、保護者は中学校長の対応に不満を募らせている。中学校長は取材に「公立高の腕試しで受験することを私立高に示す意図があった。受験を認めてもらうためには致し方なかった」と話している。
文科省の指針は、障害者との対話を通じて相互理解を深め、対応策を検討することを求める。指針を知らなかった保護者は、私立高と直接対話する機会がないまま、中学校長の求めに応じて約束していた。指針を知らなかった保護者は、私立高こと直接対話する機会がないまま、中学校長の求めに応じて約束していた。「一方的に我慢を強いられ、中学校長からも『受けさせてもらえて良かったね』という雰囲気を感じた」と振り返る。』
この新聞記事を読みながら、福祉や人権など様々などの分野でも大切にされている、障害者権利条約の“私たちのことを私たち抜きで決めないで”(Nothing About us without us)というメッセージを思い出しました。新年度の学級開きをはじめるにあたって、大事なコトを再確認することができました。
また、もうひとつ。おそらく長年、「うでだめし」の入試、進路指導(進路保障でない!)がずっとあたりまえにように行われていたのかもしれませんね。「すべりどめ」の学校という言い方を久しく聞かなかったのだけど、学校観・進路観だけでなく、私たちの姿勢が問われているように感じました。
そうそう、転勤した方々は、新しい職場で「あれ?ここはどうなってるの?」と尋ねて、これまでの「あたりまえ」にある学校の取組などを見直す「風」を吹かすことが重要な役割かももしれません。追記、宝塚音楽学校の応募資格とされていた「容姿端麗」ということばは、今年度(2025年)の募集要項から削除されていました。
☆273日目(3.31)人権課題を取り上げること3
ハンセン病問題学習のこれからの参考に。
https://www.pref.okayama.jp/page/965554.html (3)中学校での授業実施例
☆272日目(3.28)人権課題を取り上げること2
地域により体制が整っていない状況もあるでしょうから、例えば、校区でなくても、差別をなくすために運動に粘り強く取り組んでこられた方々の思いや願い(歴史)を聴くことはどどうでしょう。問題なのは、地元が理解が難しいとか消極的だという理由で、フィールドワークや聴き取り学習、部落問題学習すべてをあきらめてしまうことではないでしょうか。多様な学び方やスタイル・新しい学習教材(視聴覚教材)が提起・製作されている中で、なかなか人権学習が進まないのは、もしかしたら、学校が地域との信頼関係がつくれていないからなのかもしれません。当事者の方々の「聲」から、自分たちの教育実践を問い直していきたいと思っています。
☆271日目(3.27)人権課題を取り上げること
身近にある人権課題を教材に
確かな人権感覚と実践・行動力を育むためには、身近にある部落差別や身近にある人権課題を教材化することが求められます。
部落問題学習は、ややもすると、自分の暮らしとは全く関係のない問題と感じられている例も多いようです。でも実際には、全国各地に被差別部落があります。また、政府の 2019 )年に行った意識調査(部落差別の実態に係る結果報告書) によれば、「部落差別」や「同和問題」ということばを聞いたことがある人は全国で77.7%、近畿・中国・四国地方では90%を越えます。ごく身近にある問題として部落問題学習をできるかどうかは、重要な要素だと思います。
教員が部落問題学習の実施をためらう理由の一つとして、「「どこに部落があるの?」などと子どもから尋ねられたときに答えられない」という意見があることも聞きます。これに対して、学校だけで学習を取り組もうすると、実施が進んでいかないのではないかと思うのです。学校だけでなく、部落問題に取り組んでいる仲間や、解放放運動に取り組んでいる地域の方々と協同で一緒に進めていく体制をつくれたらと思っています。子どもから「どこなん?」と質問がでたなら、「先生が知ってるから、先生と一緒に行ってみるか。クラス・友だちにも声かけてみんなで一緒にいこう」というのでよいではないかということです。そう返すことによって、質問した子どもの側もいろいろなことを考えることができます。友だちに声をかけてみて、どんな返答が返ってくるか。親に話したときに親はどう言うか。そういうことを通して自分自身の問題意識も振り返り、研ぎ澄ますことができるはずです。続く
☆270日目(3.26)今年度の授業をふりかえって
授業の中での仲間づくり
授業のなかでも仲間づくりは重要です。文部科学省も「主体的・対話的で深い学び」が大切なキーワードとなっています。そして、そのための一人学習、ペアでの学習、グループ学習(協同学習)、全体学習などを丁寧に組み合わせることの大切さもよく語られています。 (ちょっと追記:「グループで話してみて」「となりの人と相談して」と指示しても、その後の「見取り」がおろそかになり、対話的な学びが成立したかどうかを見届けようとする授業者の視座は必須です)
子ども同士の協同を育むうえで、同和教育が重視するのは、〈どのような子どもを中心に据えて〉授業を展開するのかという点です。社会的に不利な立場にある子ども、学習の面で困難をかかえている子ども、対人関係が得意ではない子どもなど、多面的な観点で〈弱い立場にある子どもたち〉に焦点を合わせて授業を組み立てるのです。このことは、その子たちを取りこぼさないようにするためだけではありません。主な目的は、その子たちのつまずきや問題意識をクラス全体で共有することによって、他の子どもたちの問題意識やスキルが高まるようになることです。
☆269日目(3.25)子ども観
ちょっと前、渋染一揆の現地研修についてきていた小学校2年生の子どもとあれこれ話をする機会があった。児童生徒と教員の関係ではないし、親戚関係でもない子どもの本当に、自由で、快活な言動、一挙手一投足は、とても新鮮だった。「集団づくり」においても、子どもたちをいかに見ていくかという「子ども観」や教師の 有り様は、取組内容とその効果に大きく影響する。大阪府松原市立布忍小学校 (以下「布忍小学校」)では、「良さの見えにくい子を学級集団の中心に据える」ことを実現する取組を大切にしている。 布忍小学校では、「集団づくり」を人と人がつながりをつくる「人間関係づくり」として だけではなく、人間のすばらしさや人間の痛みを共有できるつながりとして位置付け、「集団の質」を高めることをめざして、おもに5つの視点をキーワードにして取組を進めている。(1)子どもの「短所」や「できない」ところに目を向けるのではなく、一人ひとりの子どもの「良さ」を見付けようとする。 (2)教職員が、子どもから意識的・無意識的に発信される S0S の信号をキャッチし、「あれ? と感じたこと」を大切にする。 ③一人の教師が子どもを見るのではなく、一人ひとりの子どもをできるだけ大勢の教師 が見て、話し合うことで、多様な見方とらえ方を意識する。(4)「良さ」の見えにくい子どもを学級の中心に据え、その子どもの「良さ」とともに、 集団の「良さ」を伸ばそうとする。 (5)子ども同士の関係の中で、持ち物や特技等を武器として相手を迎合させる「ゆがんだ集団の関係」を見逃さないこと。 布忍小学校では、「いかに、子どもたち自身がつながろうとする(エンパワメントできる)仕掛けをするか」を課題と して位置付け、より質の高い集団づくりをめざしている。
☆268日目(3.24)コミュニケーション
岡本純子氏の講演会での要旨が山陽新聞に掲載されていました。要旨の要旨を紹介します《コミュニケーションは才能ではなくノウハウであり、誰でも上達する。その方法の一つは「相手が何を聞きたいか」・・・○人は自分が知りたい、聞きたい情報しか受け取らない。相手にとって価値ある情報とは、流行やニュースなどの聞き手が関心を持つこと○ 損得、困り事をはじめとする聞き手に関係のあること○聞き手の価値を認め、感謝や共感すること―の三つ。これらに自分が言いたいことを織り交ぜるとよい。2つめは「相手が何を感じるのか」・・・対話をしながら共感し、感情をかき立てる力がもとめられる。3つめは、「どのように言うのか」・・・コトバに体重と体温、思いや志を乗せることで印象は大きく変わる》とのこと。
一方的に自分の言いたいことをしゃべったり、自分の思い通りにするために相手を納得させたりすることがコミュニケーションではないことは誰もが承知していることだが、岡本さんが言われるように「対話しながら共感し」合う会話は、やはり意識しないと成立しないと思う。
「意識」といえば、先日も一生懸命に話さなければならない(変?)機会があった時に、「お互いの役職や先輩・後輩という関係、教員と生徒という関係性などは、コミュニケーションにどれくらい影響するのだろうか?」と思うことがあった。お互いの関係性を意識せねばならない時、関係性を利用する時、関係性をフラットで語り合い時などなど、そんな細かいことを計算したり、思考したりしてコミュニケーションを図ろうとすることは邪道なのであろうか?
ちなみにOpen Dialogueとは【「開かれた対話」を意味する。 この「対話」は、診察室で医師と患者が行う「会話」とは異なり、患者とその家族や友人、精神科医だけでなく臨床心理士や看護師といった関係者が1カ所に集まり、チームで繰り返し「対話」を重ねていくというものだ。】このオープンダイアローグは学校現場での「これから」をまさしく開いていくキーワードのひとつにしていきたいと思っている。
☆267日目(3.21)卒業式を終えて
本校の卒業式も無事終え、19日は市内小学校の卒業式でした。縁あって、小学校の卒業式の練習をみせていただく機会もあり、とても大事な行事だとあらためて感じました。さて、本校でも式に向けて、送辞・答辞や歌唱の指導に取り組みましたが、子どもたちの三年間の学びをもとに、「どのような式にしていくか?」をいつも考えます。前年度の内容を踏襲するべきこと(しないこと)、コロナ禍での見直しをした内容の再吟味、そして卒業を見据えたそれまでの教育活動のあり方にも言及しながら、今年度も、職員会議で協議することができました。代表答辞については、個人答辞の取り組みもあります(昨年度のタネを参照)が、少し意識したのは、祝辞と送辞と答辞がバラバラではなく、同じ内容のくりかえしではなく、つながっている、呼応しているイメージが持てたらいいなあと思っていました。そしてもうひとつは、本当にたくさんの取組を積み重ねてきた卒業生の「豊かな学び」が、在校生らに引き継がれていくように「コトバの精選」と、「表現」の練習に生徒会長は一生懸命取り組みました。本当に素晴らしいメッセージ(答辞)をありがとう。一部を記載します。
…「友」という歌はこんな言葉ではじまります。
友 今 君が見上げる空は どんな色に見えていますか
確かな答えなんて何一つ無い旅さ 心揺れて迷う時も
ためらう気持ち それでも 支えてくれる声が 気付けば いつもそばに
校長先生、来賓の方々、そして後輩たちのメッセージから、本当にいつでも 私たちのそばには
支えてくれる声が たくさんあったのだなあと感じています。
この佳き日、卒業を迎えた私たち三十八名のために、
このようにすばらしい卒業証書授与式を挙行してくださり、ありがとうございます。
また、ご多用の中、私たちのためにご臨席くださいました皆様、心より感謝申し上げます。
私たちは、たくさんの「学び」と「思い出」とともに、今日、日生中学校を旅立ちます。
三年前コロナ禍で、まだまだ何も先の見通せない中、私たちは、新しい生活への不安をかかえながらも、楽しみなことへの大きな期待をもって、中学校生活生活をスタートさせました。
一年生。閑谷研修では、講堂で息を合わせ大きな声で論語を読み、オリエンテーリングではグループごとでゴールを目指しました。そんな中で、個性豊かで楽しい仲間たちを知るともに、「クラスがひとつ」になることの難しさも学ぶことができました。
その後も、私たちは、「クラスがひとつになる」ことを大切にしてきました。
二年生に進級し、私たちは、自分のことだけはでなく、「生徒会のひとり」として、また、「後輩」のことも考えながら行動しなければならない難しさを知りました。
日生中学校には、これまで先輩たちも取り組んでこられた学習の機会がたくさんありました。
私たちはその一つひとつの学習に、一生懸命に取り組んでいくことが、先輩として、
新しい日生中学校の歴史を作っていくことになり、後輩たちに示すあるべき姿ではなかったか、と思います。
広島宿泊研修では、八十年前のできごとがあった地に立ちました。戦争の恐ろしさと悲惨さ、人々の生活の苦しさを再認識するだけでなく、「今ある日常」は当たり前ではないこと。先人の願いを受け継ぎ、平和を求め続けていくことを学びました。
職場体験や海洋学習は、私たちをさらに成長させてくれました。たくさんの方々との出会いの中で、「働くこと」の大変さ、大切さを学ぶとともに、ふるさと日生の素晴らしさと豊かさを確かめることができました。
そして、あっという間の三年生。
沖縄への修学旅行では、ひめゆりの塔、アブチラガマ洞窟を訪れ、日本唯一の地上戦があったことを学びました。また、民泊先の方々との、あたたかいふれあいは、どれも魅力的で、貴重な学習として、私たちの心に刻まれました。
総合的な学習の時間では、地域活性化プロジェクト「日生の応援団」と題し、地域の方たちの協力をいただき、「観光、福祉、お祭り、環境保全」などの分野について、それぞれ実践したことをまとめ、二年生や観光客に、自分たちの思いを伝えることができました。
三年生の僕たちにとって最後の星輝祭は、最高のものにしたいという思いで、前年度から計画を進めていきました。特に体育の部・星輝タイムでは、ダンスの振り付けや隊形を考える中、なかなかみんなの意見がまとまらず悩むこともたくさんありました。
しかし、「お互いが「できること」を探し出し、精一杯やろう!」と、みんなで協力して、前に、進んでいくことができました。
後輩からのメッセージの中にもありましたが、やはり、
「誰ひとり欠ける」ことなく、「全員でがんばる」ことは大事だと思います。僕たちはうまくアドバイスできたかどうかわかりませんが、それでもあきらめず、粘り強く、最後まで練習についてきてくれたおかげで、最高の体育の部になったと思っています。…
☆266日目(3.19)掲示物片づけた??③

そうそう、子どもたちと作っていました。
☆265日目(3.18)掲示物片づけた??②
『…実際に、私が持ち上がりで担任した2年生4月の学級開きの際には、教室に何も配置されておらず、壁には避難経路表示以外は何も貼っていない状態の教室からスタートした。のがらんとした教室をぐるりと見まわしながら、語った。
「見ての通り、教室の壁には何も貼っていませんし、何も置いていません。なぜでしょう?そう、この教室は、今日からあなたたちが過ごす新しい空間だからです。空いているところには何を貼りたいですか? 作品? 飾り? それとも何かのお知らせ? 今日から、自分たちの手でこの教室を作っていきましょう。」
こう宣言することによって、子どもたちが興味関心をもって見る掲示物が作られることになる。「見てもらえるかどうか」は掲示物にとって存在意義そのものである。係からの各種お知らせとしてのクイズ、学級子ども新聞や学級コンテストなど、これら自分たちで掲示したものに対しては、自分たちの手によって撤去したり更新したりといった責任が生じる。余白が埋まってくるにつれ、貼るスペースがなくなり、見てもらうための更新の必要が出るからである。
また余白は子どもたちの作った折り紙やイラストで飾りつけられ、それは掲示用の壁だけでは飽き足らず、天井や窓枠にまで広がり、これによりカラフルな教室が出来上がる。場合によっては、クラスや学年をまたいで見に来る。言うなれば「生きた掲示物」である。
こうなると、もっと見てもらいたい、楽しませたいという欲求が出て、自然と工夫を始める。 階段や靴箱といった場にも掲示したいと言い出す。創造性や主体性が、教室を飛び出るのである。 教室外の掲示になると、誰がいつまでに掲示してはがすかといった見通しや責任について学ぶ機会もできる。
冒頭の教師が作った掲示物に囲まれた教室では、教師の親切が裏目に出て、子どもの使えるスペースを先に潰してしまっている。これは教室の壁という物理的な余白を潰しているだけではなく、子どもの成長の可能性の余白を潰している行為ともいえる。
教室の壁に余白があれば、子どもたちは自然にそれを使おうと動き出す。その掲示物は教師の作ったものより美しく整ってはいないかもしれないし、教室は一見混沌として見えるかもしれないが、間違いなく子どもの成長が見える生き生きとしたものになっているはずである。』
☆264日目(3.17)掲示物片づけた??
『不親切教師のススメ』(松尾英明・著/さくら社)を紹介されました。実はパソコンで何もかも教員がやってしまう風潮もありますが、あらためて考えると大切なことです。
その中から少しだけ…『教師が作る美しく整った教主掲示:教室をぐるりと取り囲む色とりどりの掲示物。どれも美しく丁寧に書かれており、中には印刷されているものもある。よく見ると、全て学級担任が一生懸命に作ったものである。これまでの授業の学習の過程が書かれたものや、きれいに印刷された学級目標まで、担任の「いいクラスにしたい」という願いに対する努力の跡が見える。
だが残念ながら、これで「いいクラス」にしようというのは難しい。少なくとも、この美しく整然とした教室は、躍動感のある子ども文化を生み出せない仕組みになっている。教室の壁面や背面などの掲示場を、子どもたちが自分たちで創り上げていく場と捉えていないからである。美しくすること・伝えることには、教師のみ力が入り、肝心の子どもたちは、今何を伝えるべきか、 見てもらうにはどういう工夫をすべきかなどと、情報伝達に主体的に関わる力を育てる点が抜けてしまうのである。教室は子どもが最も長い時間過ごし、影響を受け続ける空間である。ここについて工夫の余地がないことの影響は大きい。学校の様々なことは全て教師によってお膳立てされて与えられるものであり、子どもは自分たちの過ごす環境について無力であるという無言のメッセージを与え続けることになる。つまり、大きな労力をかけて、マイナスにしかならない余計なお世話をしているのである。
掲示物に関して、教師は大いに不親切でよい。
子どものためを思って作るのかもしれないが、教師が作った掲示物というのは労力の割に実際に子どもは見ておらず、子どものためにもなっていないというのが現実である。
むしろ、教師のこのような「親切」を不要とし、自分たちの過ごす環境ぐらい自分たちで作らせてくれと言えるような主体性のある子どもを育てるのが理想である。
たとえ低学年でも、これはできる。むしろ低学年の早いうちからこそ、お世話される存在という誤認から脱却する必要がある。』続く
☆263日目(3.14)書を捨てまちにでよう
現地研修(フィールドワーク)から学ぶこと
渋染一揆やハンセン病問題学習でのフィールドワークのお手伝いをする機会をいただいていますが、先日、11月にご一緒させていただいた団体から、感想(振り返り)文が届きました。こちらこそありがとうございました。
・現地を自分の目で見て、自分で感じることができて、とてもよかったです。
・ハンセン病問題、差別のことなど考えさせられることばかりでした。新型コロナウイルス禍での対応もふり返れば、本当に適切だったのか?あらためて考えることができました。
・「自分の感情」も間違っていたのかなど考えました。ありがとうございました。
・「教員」として、「人として」の生き方を考える時間になりました。
・奥の奥の部分まで話していただけたと思います。ずっと学び続けていきたいです。
・初めて長島愛生園に来させていただきました。実際に目で見て空気を感じ、くわしくお話をきかせていただき、理解が深まりました。
・うつる病気の対応のしかたで、心が痛い瞬間がたくさんあり、考えること、ふりかえること、まわりの先輩や仲間と確認することを忘れないようにしたいと思います。
「正しく知って、正しく行動する」しっかり胸にとどめておきたいと思います。
(観光地の)ガイドでもなく、当事者でもなく、研究者でもない自分自身、いつも研修の地に赴く際には、身を正し、自分の立ち位置が問われているような気がします。歩いて・学び・考えて・語り合う学習スタイルを大事にしたいですね。
☆261日目(3.13)楽しく深く学ぶ場所はアルカ?
久しぶりに時間が合って、先週の金曜日、夕刻からの外川正明さんの学習会へ参加することができました。部落史学習というと、中世・近世の中の一部の出来事やとても専門的な分野かなあと思ってしまいそうですが、民衆の視座からの「日本の歴史」を見つめ直すと新たな発見や、深い学びがたくさんあり、あっという間に時間が過ぎてしまいす。この日のテーマは、「幕末維新と被差別民衆 DVD第4巻「明治維新と賤民廃止令」第1部を視聴」でした。参加された方の感想を紹介してしていただきましたが、読んで、まさしくその通りだと思います。以下。
〇〈目からうろこの話に巻き込まれました。世代も立場も違う人たちと学び合うのも新鮮です。歴史を動かしてきたのは、支配者だけではなくて、あらゆく人々の歴史を学ぶことが必要だと思いました。差別は差別する側の問題だということを伝えていきたい〉
〇〈人権教育を進めていく大きなヒントになっている。歴史を正しく知り、思いを知ることにより、本当に見方が変わってきます。だからこそ教員は、勉強して子どもたちの前に立つ必要があります。子どもたちに学んだことを伝え、地元に誇りを持ち、部落問題に立ち向かう一歩にならるようにがんばろうと思います。〉
新年度も予定されている学習会にぜひ行ってみようと思います。
☆260日目(3.12)家庭訪問の重要性(何度目??)
年度初めの家庭訪問がない学校も増えましたが、あらためて「家庭訪問の重要性」を本校でも再確認したいと思っています。また、「働き方改革」の課題やコロナ禍の残滓もあり、電話での連絡・対応が増えてきたりしているようにも感じます。しかし、電話や立ち話では見えてこなかったり、わからないこともたくさんあります。4月に行くのが家庭訪問ではありません。これまで勤務した学校で家庭訪問について確認しあったことは四つあります。
①生活指導上の課題も含め、保護者に伝える必要があるときに行く家庭訪問・・・「教育」は「今日行く」の原則を合言葉に。「今日行く」から指導になり、「明日行けば」言い訳になることもある
②子どもや保護者の気持ちや願いを聞き、先生の思いを伝え、信頼関係を築く家庭訪問
③子どもや保護者のくらしの現実をわかろうとするための家庭訪問
④出会った現実をもとに、教育活動として「生きる力」を獲得させることにつながる家庭訪問
このなかで、①や②については経験をしていただいたり、想像していただけるかと思いますが、人権教育を進めていくうえでは、③.④がとても大切になってきます。
☆259日目(3.11)「寄りそう」と「向き合う」②
続き〈・・・ぼくは焦っていた。「このまま通じ合えず卒業するのか」と。一方で、クラスの生徒たちは、進路H Rを深化させていた。「これからどんな生き方をするのか」「どの高校を選択するのか」などなど。時には授業を振り替えてでも話し合いが続けられていた。
「おれはいったい何をしてるんだ」「真摯に進路と向き合う生徒たちにどう応えたらいいのか」「Bにどう向き合えばいいのだ」。こんな思いに駆られて駆られていた卒業間近、ぼくはある行動に打って出ることに思いがいたった。それは、タバコを溶かした水を彼や生徒たちの前で飲み、自らの身体でタバコの害を彼に訴えようというものであった。
翌日の終わりの会で、ぼくは行動に出た。Bや生徒たちの面前でコップの水にタバコを溶かした。そのタバコ汁を飲もうとした矢先にBが飛び出してきて、「やめてくれ、オレもうタバコ吸わんから」と叫んだ。やっと、気持ちが通じた一瞬だった。そして、ぼくは子どもの「荒れ」に向き合うときの「本
気度」の重要性を悟ったのであった。
もちろん、これらの場面は、ぼくと彼、そしてクラスの生徒たちのあり様のなかで生み出されたものであり、だれが担任でも、どんな子どもにも、どのようなクラスの状況下でも実践できるというように一般化できるものではない。ぼく自身、それ以降もタバコを吸う生徒を何人も担任したが、同じ行動をとったというか、とれたことはなかった。そもそも学級づくりを含めて、教育実践とは、だれが、どの子を対象にしても、どのようなクラスでも同じようにできるとは限らないという性質のものである。だが、子どもたち、とりわけしんどい課題を背負わされている子どもの生活や思いに「向き合う」という姿勢は一般化できるし、学級担任ならだれにももってほしい教師としての基本姿勢だと思う。〉
・・・「子どもの現実」をもとに、「教育実践」を重ねていくことをやっぱり大事にしたい。そして自らの実践を真摯に振りかえり、教員として歩んでいかねばならないと思う。
☆258日目(3.10)受験事前指導
明日から県立一般入試となります。これまでも、私立・公立、すべての受験前日には、子どもたちへの指導をていねいに行ってきました。今日は、ここまでの長い道のりをがんばってきた子どもたちに、さいごのエールをおくる事前(指導)打ち合わせの会になります。
近年、県内の入試のしくみが大きく変わっていく中で、明日(3月11.12日)受験する生徒は大きく減ってきています。それに合わせて、これまでに内定合格を手に入れ、進路決定した生徒が増えました。そんな状況の変化の中で、進路先が決まった生徒から「打ち合わせの会に参加して、受験する仲間にエールを送りたい」と申し出があり、学年団で協議した結果、今日の打ち合わせの会に、受験生以外の子どもたち(有志)を参加させることとなりました。これまでのクラスづくりや仲間づくりの取り組みの延長にあるうごきではないかと思います。受験をともに乗り越える仲間、進路を切り拓く、頑張り合える仲間をやっぱり目指したいと思いました。
☆257日目(3.7)「寄りそう」と「向き合う」①
磯野雅治さんの「コロナ後の学級づくり再生に必要なこと(部落解放2023年5月号)」の『「寄りそう」から「向き合う」へ』の部分を少し紹介します。
〈…子どもと子どもをつなぐには、教師自身が担任として一人ひとりの子どもとつながることが欠かせない。というか子どもたちにその姿勢が視えなくては、子どもたちのなかに「みんなとつながろう」という意識は生まれがたい。なぜなら学級づくりは、 教師が高みから子どもたちに説くことではなく、教師と子ども、子どもと子どもとの生身のぶつかり合いのなかから生まれるものだからである。
これまでも担任が個々の子どもとつながるには、 「子どもをまるごと受け止める」「子どもの話を共感的に聴く」「子どもの言動の向こう側にあるものに思いを馳せる」ことが重要であり、ありのままの子どもに寄りそうことが大切だと思ってきた。しかし、最近それでは不十分ではないかと思うようになった。なぜなら寄りそうだけでは子どもとのかかわりが自分の学級づくり論や実践力の深化につながらないと思うようになったからだ。
ではいま、「寄りそう」ことからさらに何が必要なのか。それは、子どもの置かれている状況や思いに「向き合う」ということだと思う。そして、そこから自分の実践的課題を引き出すことだと思うようになった。
一九七六年、教師になって七年目、中学校三年生の担任をしたときのことである。クラスにBがいた。彼は、ブチ家出をして補導されたり、学校ではタバコを吸っては教師に見つかるということを繰り返していた。だが、ぼくの眼にはそう劣悪とも思えない生活環境のなかで、「なぜ彼が荒れるのか」という、彼の行動の向こう側にある思いが視えなかった。だからであろう、彼が喫煙を見つかり、ぼくが 「説教」をするということが何度となく繰り返されたが、当然、ぼくの話が彼の心を揺さぶるはずもなく、彼が変わることもないまま三学期を迎えることとなった・・・〉続ける
☆256日目(3.6)なかまづくりとは何か?
電子黒板の利活用の校内研修を予定している今日、「なかまづくり」の三つの視点について記します。
【視点】
(1)「教育的に不利な環境のもとにくらしている」子どもの姿が、取り組みの課題や成果を象徴的に現していること→このクラスが楽しいかを誰に聞くのか
(2)それぞれの子どもに個性があり、くらしがあり、様々な悩みももって生活していることをわかりあった上でのなかまであること
→「くらしの交流」をできるこそのなかま
→「しんどいこと」をやりとりできてこそのなかま
(3) なかまづくりは、教職員の意図的で継続的な取り組みの上に生み出されること
【取り組みの柱】
(1)生活をつづる、語る→日記(生活ノート・班ノート・学級通信・集会)を綴り、読みあい、互いの暮らしを交流する
(2)共同活動の組織化→生産的で文化的な活動を創りあげる
→互いの個性を知り合う
(3)人権学習や部落問題学習の実践→具体的な差別の問題(から)や、解決の手法や道筋を学ぶ
さあ、電子黒板を大いに活用しよう、と思う。
☆255日目(3.5)学年集会や学校集会を子どもの手で
先日本校で生徒集会がありました。生徒会執行部と専門委員長が中心に進行しました。校長が表彰状を渡した(伝達表彰)あと、、生徒会長と体育委員長にマイクを向けると、堂々と全校に向けてしっかりと自分のことばでメッセージを語りました。(事前にちょびっとだけ予告をしていただけなのに)せっかくの集会が、教員の説話や連絡事項で終わっては、生徒集会ではありませんね。できるだけ事前に打ち合わせはしておくのが大切ですが、その場の「ライブ感」ならではのプログラムから、生の声・双方向の会話が生まれるような集会にしたいものです。個別で起こった生活指導上の課題を生徒集団に投げかけ、それを受けた子どもらが互いに意見を交わす集会をいつもしていました。人権教育(同和教育)の視座からの集会を、一緒に組み立ててみましょう。
子ともたちの主体的・対話的で、深い学びには、「真正の学び」が必要だと思います。18歳を対象にした九ヵ国意識調査(日本財団2019)では、日本の18歳は「自分で国や社会を変えられると思う」が2・3%。異常に低い(平均30・9%)結果があります。これは大人社会の姿を見てそのような意識になっているという指摘もあるようですが、「原体験による確信」が皆無に等しいという点も背景にあるのではないか。小・中・高と学校社会を通過する際、自分が参加して何かを変えることができた、といえる「原体験」。これが圧倒的に不足している。学級・学校社会で「自分たちはここをこのように変えることができた。つくった」と、言い切れる大小の手応えある「社会づくり体験」を子ども時代から蓄積していくことが必要ではないか、と園田雅春さんは『部落解放2023 5月号』に書かれています。続けて園田さんは、「「こども参加」のあり方について、OECD(経済協力開発機構)は「共同エージェンシーの太陽モデル」(2018年・10カ国の生徒たちが作成)を提唱。参加の最終スタイルは「若者がプロジェクトを主導し、意思決定は若者と大人の協働で行われる。 プロジェクトの進行や運営は若者と大人の対等な立場で共有される」としている。また、この2023年4月1日施行の「こども基本法」の第三条には「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」と明記されている。学級という社会づくりにおいても、まず教師の持 「常識」を問い直して、子どもに委ねる領域を広げていく。こちらが身を引くところは引く。いま、これが必要な時代なのだ。』と言われています。
☆254日目(3.4)お互いを深く理解する授業を。
先日のひなせ親の会では、「療育」や支援についての学習会をおこないました。その中で相談支援員さんが、一人ひとりそれぞれの、発達の違いや物ごとの認知の違いを体感する小ワークショップをしてくださり、とても勉強になりました。本校では子ども同士が、互いの発達特性やそれぞれの得意・不得意(でこぼこ)なことを分かり合う授業から、〈反差別の仲間づくり〉を進めています。「この小ワークショップを参考にもっと授業を豊かにしていけるね」とSSWからもアドバイスもあり、これまでの取組をさらに深化させていこうと思いました。
「これは何?」から考える認識 「まず縦に半分、次に上から…」伝わるコト、わかることって。
☆253日目(3.3)朝・夕の帰りの会は何の時間?
前回の中で、新学期準備で、朝夕の会のプログラム、いやいやそもそも何を大事にして行うの?と質問がありました。ズバリ、もちろん諸連絡ではありませんね。その時間は「くらしを交流すること」ではないかと思うのです。生まれも育ちも生活環境もちがう子どもたちが、互いを理解しあうためには、 語る、つづることをとおして自分の暮らしを出し合う時間だと考えます。そのために、子どもたちには日々の暮らしを生活ノートに「書かせ」ることや「語らせる」ことを人権教育(同和教育)では大事にしてきました。とくに、学校やクラスでは見えない家庭や地域でのその子の姿が見えてくるものを大事にし、「書き」「語って」きました。もちろん、文章を書かせたからといって、子どもたちはすぐに家庭やくらしが投影している内容を書いてくるわけではありません。また、書いたからといって、その状況が変わるわけではありません。しかも、それが厳しいものであったり、人に知られたくないものであればなおさらです。しかし積み重ねることで、子どもたちは自分の暮らしに向きあうことになります。そして、まわりの子どもたちにとって、そのような友だちのくらしを知ることは、友だちの見方や理解を新たにさせます。励みになったり、その子の隣に座っている自分自身を見つめることにもつながります。個別の人権問題の理解にもつながることも多々あります。
そのためには、日常的で継続的な積み重ねが必要になります。よく人権学習で、「自分事として考えなさい」とか「自分に重ねて意見を言いなさい」と指示される場面を見ることがあります。しかし、子どもたちは考えることはできても、そのことを口に出せるかどうかは、日ごろの「自分事」を出し合える場面や経験を積み重ねているかどうかで決まってくると考えます。その経験を少しずつ重ねていくために朝夕の会があるのではないかと思うのです。(もちろん、日常の授業の中にも積み重ねていけるしくみ・手だてが必須です)
☆252日目(2.28)教員としてのシゴトをやっぱり磨かねば。
小・中学校の教育にかかわる仲間らと東備学ぶ会の名称で学習会をはじめて十三年目になります。三月になるので、新年度の学習会の内容や日程調整などの準備を進めているところです。学習内容については、昨今は、インターネットを利用しての多様な学び(情報・教材)が簡単に手に入りますが、やはり、互いに顔を合わせて、子どものことや自分の実践を語り合う中での学び(同和(人権)教育の視座からの参加者同士の意見交流による気づき)はとても大切です。ぜひ、対面で(この表記も、多様な学習形態が増えたということですよね)ゆったりと語り合いましょう。新年度の早い時期に、年間予定表をお届けします。
以下は、これまで東備学ぶ会で話題になった内容と、これから学習していきたいなあと思っている内容を併せて、いくつかランダムに記しています。開催未定の内容ですが、どれもワークショップをしたり、お互いの実践を語り合ったりして、深めていきたいですね。
○教壇に立つということ(教員の立ち位置 子どもが活躍できる教育環境 安全教育 服務 事務処理 指導要録・学籍簿 通知表)
○新学期準備(座席 呼名 教科書(無償化) 係・当番 連絡帳 家庭・保健調査表 ロッカー 掲示物)
○学級目標づくり(学級・学年通信 班ノート 生活ノート 自主学習ノート 綴る)
○授業(発問 発表方法 協働学習 語ること 聴くこと 板書 ICT ノート指導)
○教材理解と教材づくり(生徒理解 教科指導)
○総合的な学習の時間
○道徳教育と人権教育の違い
○学級づくり(日常の中の人権教育実践 生活が語られるクラス)
○特別活動(係活動と当番活動の意味 朝の会・終わりの会の運営方法 学級活動 自治活動)
○教員の学び(服装 言動 働き方改革の中で )
☆251日目(2.27)求められていること 教員としてのシゴト(2)
・・・これは実は、私たち大学教員も同じ。知識の伝達だけなら、パワーポイントを使って動画で講義を流せばいい。それに基づいて、どうその場で議論してもらうのかが重要です。まさに反転学習。でもそれが、大学教員にできるか、できているかと言えば、そうではないです。 だって、教員自身が一方通行の授業しか受けたことないから。
これは妄想も入っているかもしれないですけど・・・・・・結局、勅使川原さんの能力主義の解きほぐしが求められているのも、時代の価値転換期である今、何を指針にしていいかわからないという人が多いからだと思うんです。
教員の専門性の転換について補足しましょう。おそらく学校教育は、教科教育こそすべてと思い込まれている。でも、この生成 AI参入の転換期に先生に求められるのは、一つには、そういった標準化・規格化された学びにのれない子、落ちこぼれる子、しんどい子をひろい上げて、わかりやすく教えること。そしてもう一つ大事になってくるのは、それこそ一人ひとりの個別性だとか、主体性に見合った学びの場をどう提供していくかです。
でも、学校の先生は、教科教育をどううまくやるのかで査定されている現実がある。 その教授能力が評価対象なわけです。・・・』
☆250日目(2.26)求められていること 教員としてのシゴト(1)
先日少し紹介した『「これぐらいできないと困るのはきみだよ』?』(勅使河原真衣著 東洋館出版社)をもとに、知り合いの先生と話していると、終わりには、「学校の役割というか、教員のしごとに携わる一人ひとりとして、仲間らと一緒に、自分自身のしごとの中身を再確認したいね」と話が広がりました。そこで、同著での著者と竹端寛さんの対話の一部について少し長いですが紹介します。(P98.99)〈ぜひ著作を読んでください。〉
『…だから同じように、実は教師が求められている力も、スタディサプリ(リクルートが運営するオンライン学習サービス〕がある時代には変わってこないといけない。標準化・ 規格化した学びだったら、携帯やタブレットで動画を見たらいい。その上で、動画で再現できないものを先生が提供できるかどうか。それが問われている。
だから今、すごくしんどいのは、これまでも学校の先生は能力主義的に求められてきたけど、その中身がガラッと転換しているときだということです。(続く)
☆249日目(2.25)生活ノート再考 追記
「プライバシーは?」と、現代では疑問がある人もいるかもしれません。「教員がそんなに子どもの生活に立ち入ってもいいの?」と。けだし、プライバシー権とは、〈自分に関する情報は自分でコントロールできるという権利〉です。重要なのは、生徒たちが自分に関する情報を自分でコントロールできるということです。生徒たちは書いても書かなくてもよいのです。書いてみようかと思ったときに書ける状態をつくっておくことが大切です。書いてみて先生からそれに応じて、メッセージが来たらうれしいと思います。それで「また書いてみよう」となるかもしれないのです。現代のプライバシー権は、そういうときに書きたければ書く、書きたくなければ書くのをやめるという判断をできなければ行使できません。
私は、子どもたちが書いた内容を学級通信や学年通信に掲載したりしていました。そして、その内容を受けとめた他の仲間からメッセージが返ってくるような時間を創ることも大切です。クラスへ返す時には、本人に必ず、掲載してよいか聞かねばなりません。年度の初めに「このノートに書いたことは学級通信で紹介する場合があるよ。「それは困る」というときには、『これは載せないで』と言ってな」と生徒たちに伝えておくことで安心して書きやすくなります。学校だけでは見えなかった暮らし・生活が生徒同士で交流されるようになれば、生徒同士は必然的につながりやすくなります。
こういう活動を重ねることによって、子どもたちには自分で自分の情報をコントロールする力が育っていきます。少し自己開示をしたら、それを受けとめてさらに深いメッセージが返ってきた。そうすれば、またその人に自己開示をしてみたいと思うのではないでしょうか。どういうときに自分の情報を開示すれば良いのか、どういうときにはしない方がよいのか。そういう判断力が育つのです。これはプライバシー権を行使するための力を子どもたちに育む実践です。このことは、生活ノートやSNSでも基本的に同じです。生活ノートで判断できるようになった子どもたちなら、SNSでも判断できるようになりやすいはずです。自己開示の楽しみと気まずさ(危険性)を味わった人なら、SNSでも気をつけながら、必要に応じて自己開示するというスキルを身につけやすいはずです。逆に、ふだんは自己開示などぜんぜんする機会がないという人が、「匿名だから」とネット上で弱みをさらし、限度なく自己開示をする。そのあげくに誰かから攻撃されるなどの危険を避ける力を育むことにもなります。(たくさんの先輩の文章に加筆修正しました)
デジタル化にしてもよいコト、してはいけないコト、文章が残るコト、あえて残すコト、残さないコト、書く・綴るコトの価値などを細かいけども再考・再吟味し、今・これからの豊かな教育実践につなげていきたいと思います。
☆248日目(2.21)生活ノート再考
綴ること つながること 語ること 仲間づくりの中で
年度末になり、新年度の教育活動についても話す機会が増える時期です。本校でも、いわゆる「生活ノート」についても、どうするか?検討する予定です。
そこで、あまり実践したことがない方々とも・・・生活ノートでのやりとりとは、教員と子どもの間を行ったり来たりさせるノートです。ノートの中には、生徒たちの生活や、暮らしの中で考えたり感じたりしていることが書かれているというものです。教員は、子どもたちの書いてきたノートに返事を書いて返します。クラスの中にはたくさんの生徒たちがいますから、すべてに返信するというのは大変だと思う人が多いでしょう。しかし、いくつかのポイントで、継続させていく中で、生徒やクラスの「つながり」は確かなものになります。
ポイント1:90年代、関西地方の学校で、この実践に出会った当時は、特別に(絶対に)、暮らしや悩みを綴らなくてもよいノートとして設定されていました。自主学習ノートの取り組みと合わせて、家庭学習をするときに用いるノートにしていました。漢字の練習をしたり、因数分解の問題を解いたりするわけです。もちろん、暮らしや悩みを書いてもいい。こうすれば、悩みの多い生徒たちがどちらかと言えば暮らしや生活を綴る方向に傾きます。これには返事を書きます。少なくとも、生徒たちの書いた分量は返事として返します。学習が得意で、現在はあまり悩みがないという生徒は教科の問題を解いてくる方に傾くでしょう。教科の問題に取り組んだときは、「見たよ」という検印だけでもOKとのことでした。
ポイント2は、毎日出さなくてもいい、たとえば1週間に2回出すというやり方です。そうすれば、1日に出すのはクラスの半分ぐらいになります。その中から、返事を書く必要が出てくるのは、「暮らしや生活」を書いてきた残りの十人ほどになれば、継続しそうな気がしませんか。
そして、大切な3つめのポイントは、返信の書き方です。最初から「生活ノート」に、深刻な悩みを書いてくることはほとんどありません。アイドルのことやテレビドラマのこと、ゲームのことなどばかりかもしれません。これに付き合うのは、大人としてなかなかむずかしい。しかも、ガンバッテ付き合おうと努力してゲームについての返事を書いたりすると、生徒はさらに喜んでゲーム路線で書いてくるかもしれません。こういうときは、そのテレビドラマやゲーム・ネットを手がかりに、教員が自分の暮らしをさりげなく書いて返すことです。「その番組の時間帯には、先生の家ではご飯を食べていた…」「などと返すのです。そうすれば、「先生はこんな暮らしをしているんだ」と伝えられますし、「このノートにはこんなことを書いていいんだ」「暮らしを書くことって大切!」というメッセージを届けることにもなります。とはいえ、暮らしや生活を見つめて、生活を綴ることになる実践までには、なかなかたどりつくことが難しいと思います。教えてくださった関西の先生は、「そこは粘り強く、こだわっていかなくてはいけないよ」と言われてましたが、私は、生活ノート紙面でしりとりのやりとりのやりとりをしたり、シールを貼ったり(多種多様なモノがあります!)していました。要は、これも教員とのよりよい関係性(信頼によるつながり)の構築と、子どもと子どもをつなげる根幹になる取り組みだと思います。
☆247日目(2.20)進級にあたって 意識を高める取組として
3年生に進級する生徒らが、新入生に向けて新聞を製作する予定です。
☆246日目(2.19)私たちの立ち位置について
よくこの「タネ」の話題の中に出てくる教職員の「立ち位置」についてですが、川上康則さん著の「教室マルトリートメント(東洋館出版社)」に、そのあたりを考えるヒントとなる文章に出会いましたので、少し紹介します。(P30~31)『・・・職員室内の会話の中にも、特定の子どもや保護者を揶揄したり、嘲笑ったりするような場面に遭遇することがあります。関係する子どもをまるで自分の所有物であるかのごとく名前を呼び捨てにしたり、からかうようなあだ名をつけて笑いのネタにしたりするような不快極まりない会話を耳にすることがあります。特別支援教育の基本は「他者との違いを認め、相手をリスペクトする」ということです。
相手への敬意。
相手が見て感じたことへの敬意。
相手が考えて行動したことへの敬意。
相手が大切にしていることへの敬意。
相手が背負っているものへの敬意。
敬意を示せない教師の発言は、「他人の粗探し」にしか映りません。結局のところ、他人からも同じ視点で見つめ返されることになるように思います。反対に、相手への敬意にあふれた人から発せられた言葉には、人の心を支え、前向きにさせる力があります。指導を行う立場の前提として、「何を言うか」や「何をするか」よりも「どんな態度でその子の前にいるか」が大切だと思います。・・・』
☆245日目(2.18)進路公開ができる集団に
先日、小中合同のケース会に参加して、「自分を見つめ、綴り、語る」とりくみを粘り強くやっていかねばならないなあと思いました。
20代の頃に訪問した大阪の中学校では1年次は「自分」、2年次は「家族」、3年次が「進路公開」として、見つめ、綴り、語る取り組みを行っていました。3年生の進路公開につながる授業の中で、「***高校に進学したい。そして将来は**になりたい。だから今、自分は**したいと思っている。」と語るだけでなく、「自分の悩みや葛藤、親の思いや願い、家計や経済的なこと」を語り、クラスの仲間から熱くて真剣な応じ(返し)がありました。
「進路公開」というのは、自らの進路(多くは高校進学)をクラスの仲間の前で公開していくことです。しかしカタチを真似して、生徒どうしがつながりあっている集団だと思ってしまうのは危険だと思います。発表する子が、自分の暮らしをみつめ、自分をとりまく人々の願いを受けとめ、自分自身の可能性を高めるための進路を求めたことを語り、その発表を聞く側の子たちは、発表する子の暮らしに思いを馳せながら、強い声援を送る…ことが出来るためには、教職員集団が、クラスの日常の中で、自分を語り、聴き合う実践の積み重ねしかないと思います。ゆえに、「進路公開」というのは、お互いの暮らしや思いを知らない者どうしの学級集団では成立しない取り組みとも言えます。すなわち「進路公開」の時間が大事なんじゃなくて、それまですごしてきた日々で、どれだけ本気で隣に座っている仲間のことを知ってきたかが必要なのです。「クラスの仲間の語りに真剣に応じる文化」を作っていくことが「真のつながりのある学級集団づくり」ということです。
併せて、自分のことを語り、仲間のことを知ることのできる「朝・帰りの会」の時間がほとんどナイ、ある学校の教育課程表をみることがあり、とても気になっています。朝の会は「連絡」するだけの時間ではないのにねえ。「学級集団づくり」はどこでするのか?もう必要ないのか?と思ってしまいます。
☆242日目(2.17)「これくらいできないと困るのはきみだよ」?を教員としてどうとらえます?
『「これくらいできないと困るのはきみだよ」?』(ISBN: 9784491055527:勅使川原 真衣/編著、野口 晃菜・竹端 寛・武田 緑・川上 康則/著)をS氏から「読め!」と言われて読んだ感想の一部です。・・・『教育現場(日本社会)に蔓延する(残滓?ではないか)能力主義について問題提起をしています。 「生徒・教師」という立場を置いといて、「人間である」という前提に立つと、安易に正論をぶちかまして学校現場を批判するのではなく、モヤモヤと葛藤する中で望む方向へ前進していくしかない(語り)対談になっているような気がしました。教育現場での変革は、トップダウンで一気に進むわけでなく、教育現場最前線の者が少しずつ、変えていくしかないとも思いました。(もちろん研究者や多様な方々と連携・協働は不可欠です)
また、日常的に子どものかかわる者のひとりとして、「子どもにかける言葉がいかに大切か」そして、その言葉を紡いでいくためには、「学校教育の中であたりまえ」と思っている言葉がけの内容をも見つめてみようと思ったのでした。社会や労働にある「能力主義」について、学校教育の中にある「望ましさ」(教職員の多くの場合は無自覚の指導・支援のカタチでの「望ましさ」)の背景にどんな傷つきや焦りがあるのかを探り、「能力主義」を捉え直すきっかけとなりました。』・・・まったくまとまらない文章なので、参考に、出版社の「本書からわかること」を記します。
環境や関係性を無視した能力観の果てに
社会では、日々さまざまな能力の必要性が訴えられていますが、それらは非常に移ろいやすいものです。労働の世界に目を向ければ、「新卒で必要な能力」が時代とともに移ろいますが、能力とは個人に宿るものではなく、その発揮は本来、環境との関係に左右されます。そして、労働の世界とは切っても切りはなせない関係である教育の現場でも、「コミュニケーション能力」「非認知能力」「指導力」という表現に、こうした一元的な能力主義の片鱗を見つけることは難しくありません。例えば、「これくらいできないと困るのはきみだよ」。言ったり、言われたりしたことのある人は多いでしょう。学校で相手や自分に「これくらいできないと困るのはきみだ」と言いたくなるときには、どのような社会で生きることが想定されているでしょうか。
「これくらい」が規定する社会は存在するのか
本書の編著者である勅使川原さんは、「能力とは個人に宿るものではなく、他者や環境との関係の中で発揮されるのではないか」と提案します。そして、一元的な能力主義を脱するためには、個人がすべての“能力”を身に付けて「強い個人」として生きることを目指すのではなく、強さと弱さ、とがりや特性を組み合わせて生きていくことを目指すほうが大切なのではないかとも考えます。本書では、「これくらいできないと」に表現される焦りが、昨今の学校をめぐる状況への合理化として表れているのではないかと仮定し、どうすれば一元的な能力主義という“自縄自縛”をほぐしていけるのかを議論します。
「学校だけが変わったって意味はない」?
「学校がいくら個性を大切にしても、その先で生きていく社会が変わらなければ、結局困るのは子どもたちではないか?」――こうした不安も生じるかもしれません。しかしながら、不登校児童生徒が30万人を超える今、このまま進んでいったとして、学校は子どもたちにとって、そして先生にとって、どんな場所になりうるでしょうか。私たちは、なに「から」始めていけそうでしょうか。4つの語り合いを通して、学校にある大人や子どもの傷つき・葛藤をつぶさに見つめながら、糸口をいっしょに考えていくための1冊です
追記(映画もそうですが、本も読み合って感想を語り合う「読書会」に、30年も前に連れて行ってもらったことを想いだしました。古そうで新しい「読書会」かもしれません。しましょう。)
☆241日目(2.14)働き方の改革の検証軸は??
授業公開ありがとう 研究協議ワクワクは大事
2019年に、文科省は、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方 改革に関する総合的な方策について(答申)【概要】 (平成31年1月25日中央教育審議会)で、学校における働き方改革の目的を4つあげています。
〇 これまでの我が国の学校教育の蓄積はSociety 5.0においても有効であり、浮足立つことなく充実を図る必要。これまで高い成果を挙げてきた我が国の学校教育を維持・向上させ、持続可能なものとするには、学校における働き方改革が急務。
〇 ❛子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする❜という働き方の中で、教師が疲弊していくのであれば、それは❛子供のため❜にはならない。学校における働き方改革の目的は、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること。
〇 志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、そのためにも、学校における働き方改革の実現が必要。
〇 学校における働き方改革を進めるに当たっては、地域と学校の連携・協働や家庭との連携強化により、学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化を図ることが大切。
どのように「目的」を読み取り、いま(2025年)どのように進めているか。検証軸としての〈私たちの教育活動・教育実践はどう高まっているのか?!を考えさせられる校内授業研究会でした。公開授業ありがとうございました。またみんなで、もっと語りましょうね。
☆240日目(2.13)授業公開ありがとう 研究協議わくわく
先日、第2回校内授業研究会を行い、授業や学級づくりについて協議しました。働き方改革で生み出した時間は、子どもたちに向き合うための授業研究や仲間づくりの創出につながらなくてはいけません。貴重な授業公開と研究協議の時間でした。学びあった内容を今後の学校(仲間)づくり、教育実践に生かしていきたいなあと思います。いくつか、人権教育での仲間づくりの視点でいくつか記します。
○グループ学習での学びが成立しているかどうかを、しっかりと見取っていきたい。
・見取りの基本は、協働学習をしているグループの机にしゃがみこんで、子どもたちのやりとりに耳を傾け、子どもたちの動きを目で追い、最初から最後まで聴き取ることだ。残念ながら最初から最後までくっついて聴くことは授業者は出来ないが、その代わりの自校の他教員がそれぞれのグループに分かれて入り、「学びが成立したか」どうかを丁寧に耳を傾けるしかない。参観授業で、生徒の机間を歩き、ノートやプリントをチラリと視ても分かることは少ないのではないかな。(授業参観者として何を視ようとしているのか)
○協働学習への道は険しいけれど一歩一歩。
・4人のグループにして、適切な課題を与えるだけですぐに協働学習が成立するわけでないことは誰もが知っている。グループでの協働学習を成立させるためには、複数人での会話(話し方)や聴き方、時間の管理や、声のトーンに至るまで、授業者のモデリングはもちろんだが、より、段階的・継続的な指導が必要だと思う。例えば、一人だけ話すのではなく順番に話すこと、時間内に話すことやまとめること、聴きあうことや話し合いの心地よさを味わうこと、表現技法(話法)を豊かにさせること等、全教科領域の強みを生かしながら、「多様な学び方」の指導や支援に力をいれたいと思う。(ちょっと次回に続く)
☆239日目(2.12)発表(表現)って、どう育む?続き
よくプレゼン力と一緒に語られこともありますが、もちろんプレゼンする力を高めること自身が目的ではありません。(プレゼンスキルとは、自分が伝えたい内容を相手に正しく伝えるためのスキルのひとつです。)しかしながら参考になります。プレゼンテーションでは、4つの力が必要だと言われています。
○自分で考える力:プレゼンテーションをする上で、物事を論理的に分かりやすく伝えることは必要不可欠です。一番伝えたい結論とその根拠を聞き手に分かりやすく伝えるためには自分の頭で内容を整理し、まとめあげる力が必要です。
○伝える力:プレゼンでは視覚と聴覚から情報を提供します。つまり、プレゼン資料と話す内容から伝えることを意識することで相手に伝えたい内容を十分に伝えることが可能です。例えば、プレゼン資料において、文字の大きさ・色使い・図形の使用によって重要箇所を目立たせたり直感的に伝えたい内容が分かるように工夫する必要があります。また、伝えたい相手に伝わる声量や抑揚をつけて話し、プレゼンを受ける側がスムーズに理解できるように務める必要があります。
○表現力:伝える相手にとって魅力的に伝わる表現力も大切です。態度や言葉のチョイスから話し手であるあなたの魅力を伝えることができれば、相手に人間性や信頼度を評価され交渉が上手くいくことがあります。例えば、具体例を伝えるときに共感を得られる表現ができる、ポジティブな雰囲気を出せる、応援したくなるような人柄が出せる、など、表現力があるだけで話を最後まで聞いてもらえます。内容を練るだけでなく、魅力的に伝える表現力を磨くことも重要なポイントです。
○ヒアリング力:プレゼンをする相手によっては、求められていることが変わることがあります。例えば、ジュースを売ろうとプレゼンするとき、Aさんは美味しいジュースが飲みたいと思っており、Bさんは冷たいジュースが欲しいと思っているとします。そこでAさんに冷たいジュースはいかがですかと伝えても、すぐには買おうと思いません。どんなジュースを求めているのか探ったうえで、美味しいジュースをプレゼンすれば効果的に相手に商品の良さを伝えることが可能です。相手が何を欲しており、どんな状況にあるのかを引き出すヒアリング力は、プレゼンを行う前に必要なスキルです。
☆238日目(2.10)発表(表現)って、どう育む?
岡山学び工房(学びの共同体についての有志の学習会)での、全国各地の授業実践記録を視ながらの意見交流では、いつも多くの気づきや学びがあります。少し前の勉強会では、中学生徒一人ひとりが学習でまとめた内容を、教壇の前に出てきて発表する映像を視聴しました。視ながら、自分の教育実践を振り返ると、生徒が〈話す、しゃべる〉だけで満足していたような気がして反省しました。発表は「表現」にひとつですが、自分と伝える相手を意識した、より豊かな表現力が高められるような支援や指導をあまりしてなかったような気がします。卒業式などの式典での生徒の答辞等の指導には「表現」の中身を意識した指導・助言をしていますが、日々の教育実践の中での「表現」力を高める支援やサポートをしっかり意識したいと思っています。表現力とは、自分の感情や思考を〈他者〉に分かりやすく伝える力です。文章や絵、声、表情、行動など、さまざまな方法で表現することができますが、必ず〈他者〉を意識させないといけませんね。表現力を高める指導・支援には、以下のようなポイントを押さえることが大切です。
○「書いてみたい」「書かなければならない」という動機づけをする。
○「私」に関わる身近なテーマを設定させる。
○読んでほしい、伝えたい相手を見つける(意識させる)。
○他人に読んでもらう(グループワークをくり返して、他者の目を内面化させる)。
○たくさん話す機会を増やす
今日あった出来事を家族や中学校の友達に話してみて、自分の考えがしっかり伝わるか練習させる
大勢の前で発表する際は、原稿を見ずに話すことや鏡の前で練習することを薦める。聞く側に回って自分の発表を客観視することで、より伝わる内容にブラッシュアップできることを実感させる。練習を重ねることで本番は自信をもって話せる。聴く側も気持ちが伝わりやすい発表に感じられます。
○本を読む・まねることの大切さを伝える
本を読むことで語彙力が増え、自分が伝えたい内容をスムーズに伝える言葉選びが簡単にできるようになります。本はテレビなどの媒体とは違って、難しい言葉や表現が使用されています。様々な本を読み語彙力を増やすことで表現力も上げることにつながります。さらに、話し方が上手いと思った人をまねることも効果的であることを教えましょう。まねはよくない事のように捉えがちですが、「仲間」から学ぶこと(まねぶこと)は学級dくりには必要な視点ですね。クラスの仲間にも伝えることが上手い人がいることを認識させ、自分が話すときにも使えそうな表現や言葉遣いをまねしてみる事で、自分の表現力を効率的に上げることが可能なことを共有できるクラスの「仲間」はステキですなあ。
○作った文章や資料を何度も推敲
資料作成の練習をすることも表現力を磨く1つのポイントです。PowerPointやGoogleスライドなど、生徒たちは、作成する機会はどんどん増えましたが、〈他者〉を意識し、教員の指導・支援や、仲間どうしのアドバイスが、よりよい資料作りにつながる体験をどんどん増やしましょう。続く
☆237日目(2.7)みんなで生徒を支える体制づくり③
まとめたものがみたいとリクエストがありましたので、提示します。
☆236日目(2.6)みんなで生徒を支える体制づくり②
前回に続き。
『対象の児童生徒と身近に接する支援員は、障害に関することや支援の仕方について質問を受けることがあります。こうした場合、当該児童生徒の発達の段階や、障害受容の状況等を踏まえた上で適切に答える必要があります。したがって、当初の打合せにおいて、どのように伝えるかについて、学級担任や特別支援教育コーディネーターと十分打ち合わせておく必要があります。同時に、支援の対象ではない児童生徒からの質問に対しても答えられるようにしておきます。対応の仕方を一概に言うことはできませんが、基本的には、
・対象となる児童生徒の個人情報の取扱いに十分留意する。
・対象となる児童生徒の自己評価が低下しないようにする。
・友達と差別・被差別の関係にならないようにインクルーシブの視点を大切にする。などのポイントを押さえ、一人一人の状態や学級の様子に応じた接し方をする。
年度当初の学年集会等を活用した取組(表明・発信)、日常的・持続的な発信を積極的に行いましょう。
☆235日目(2.5)みんなで生徒を支える体制づくり①
授業のサポートに入り、以前、文章にまとめた「支援さんとの協働」について一部を記します。
『支援員の役割は、対象となる児童生徒の支援が第一義的な役割であることは言うまでもありません。しかし、対象となる児童生徒への支援の形態は様々であり、他の児童生徒とかかわりを持つことも少なくありません。子どもと子どもを「つなげる」視点での支援が重要です。したがって、学校生活の様々な場面で支援員がどのように動いたらよいか、他の児童生徒への接し方・つなげ方も含めて、事前に学級担任と十分打合せておくことが大切です。また、障害のある児童生徒が通常の学級の中で必要な支援を受けて学校生活を送っていくためには、周囲の児童生徒の理解が不可欠です。一人ひとりの学び方が違うことや支援を必要とする人もいることなどを取り上げながら、児童生徒の発達段階を踏まえて、支援員が何のために教室に入っているのか、どのような役割を果たすのかなどについて説明し、支援を受ける本人以外の児童生徒も支援員について理解しておくことが大切です。』続く
☆234日目(2.4)綴る 書く まとめる って
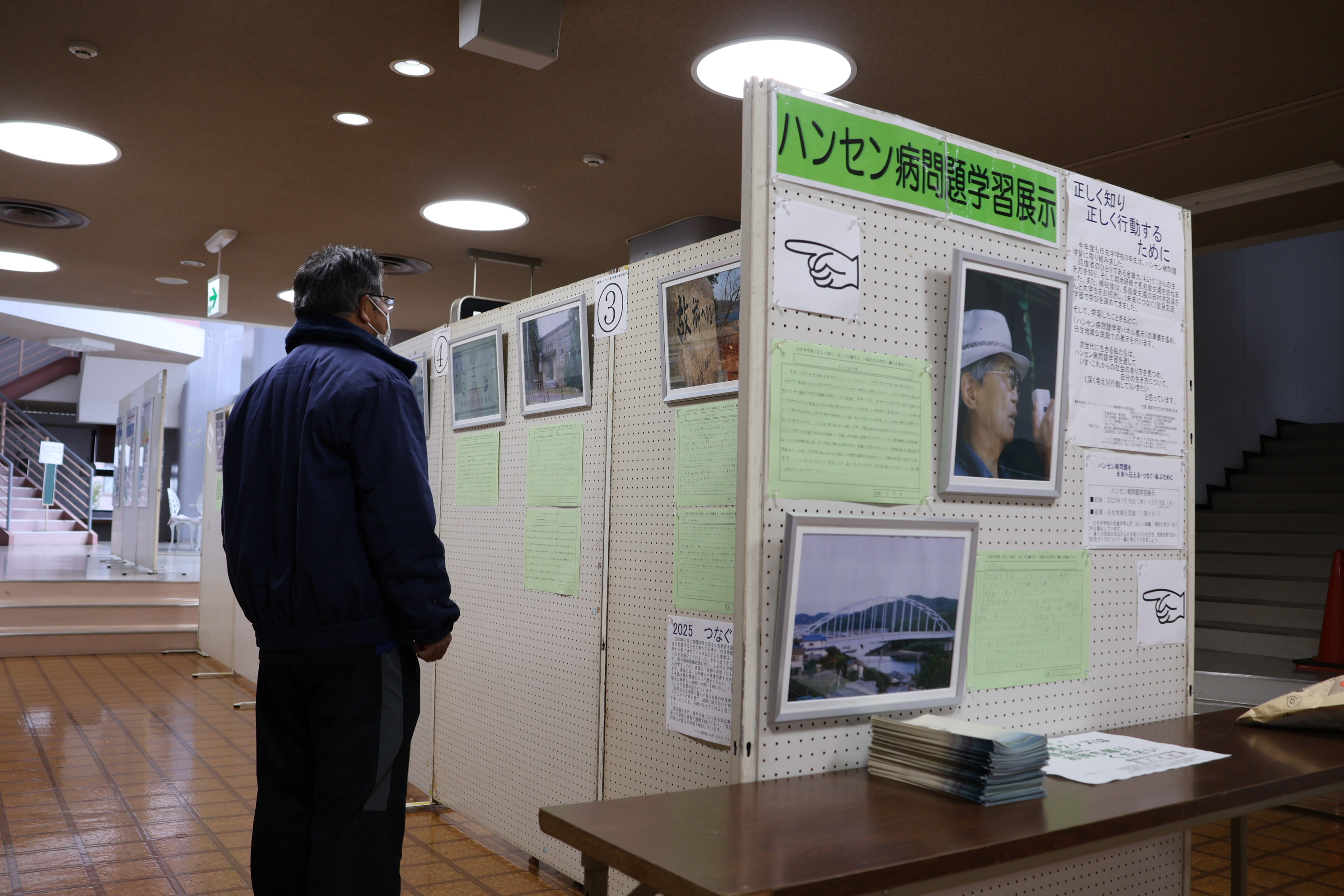
今年度も三年生は、ハンセン病問題に関する多様な学習の中で、まとめの1つとして、「パネル展示の説明文」づくりに取り組みました。 2月18日まで日生地域公民館で展示中です。
さて、生徒らは、金さんの生き様(よう)に出会い、視覚教材での学習に、フィールドワークで視たことや感じたこと、大学生との交流を重ねて、説明文を作成していきました。その中には施設の説明だけでなく、その中でもうひとつ大切にしていることは、パネル展示を観られる方々へ「伝えたい、私の願いや思い」を記することです。これがなければ、傍観的な第三者の視線に陥りやすくなり、批評家のような施設の説明で終わるおそれがあります。記することで、「自分の立ち位置が〈自分事(ごと)〉」にスライドすることになると思います。
子どもたちが思考して書くのは、〈学習者としての思い・伝えたいメッセージ〉なのか、単に〈感想〉なのかで、大きく変わってくるなあと感じています。私たちは「記す」ことに、より丁目的や意図を明確にして、望んでいかねばなりませんね。それが、子どもたちとってさらに深まりのある学びにつながっていくと思います。「感想を書きましょう」の指示だけでは、深化は起こりませんな。モデリングも併せて、ていねいにていねいに。
☆233日目(2.3)『こんにちは 愛生園」から考えたこと③
まったく私見です。他のマンガですが『この世の片隅に』は、同じ職場の方に薦められて読みました。第二次大戦中の呉のまちを中心に生きるスズさん(主人公)のお話ですが、読了後なぜか、スズさんが年を重ね八十歳ぐらいになっても凜として暮らしている姿が目に浮かんだのです。戦後80年となりますが、呉のまち、広島のまち、生きてきた人々が、今現在とつながっているような感覚をもった作品でした。ハンセン病問題もしかり、「過去と今・未来とをつなげる」ことが、様々なところでテーマとして掲げられて、様々な取組がされていますが・・・。ハンセン病問題に関する記録や写真を、ていねいに画として読み取りことばを重ねた本作品は、生きてきた人々を、「いま」につなげ、未来へもつなげるのではないかなと思いました。
☆232日目(1.31)『こんにちは 愛生園」から考えたこと②
6話の「綴り方」について。近年のデジタル化、GIGAスクール構想の中で、新しい学びのスタイルが進んでいます。(それはよいことですよ)しかし同時に、学校現場では、「書くこと自体」はどんどん減り、それに伴って「書く」意義や意味がとてもあいまいなものになっているような気もします。私は、91年に教員となり、同和教育(現在の人権教育)の中で「綴りかた」に出会うことができましたが、「綴り方」が育んできた優れた教育実践や、理念だけでなく、言葉自体の知らない若い方も多いのではないでしょうか。何が言いたいかというと、「綴る」ことをやっぱり大切にしきたいなあとマンガを読ませていただき、あらためて思うのです。GIGAスクール構想でもタブレット等を活用するスキルUPが目的となってはいけません。6話の中にもありましたが、学校教員の視座でみると、それは、単に文章を「書かせる」だけでなく、教員の視座、事象の捉え方についての助言・アドバイス、指導や支援のみならず、どのような言葉かけでその作品を本人に還すか、また、クラスや仲間に還していくか。受容(まるごと受けとめること)ができる仲間集団(反差別の集団づくり)をつくれているか、などなどを同時に考えなければならないよなと、改めて確認しました。教育改革の名のもとに、様々な手法やスキルやメソッド?などがもてはやされている感もありますが、「綴る」ことを通して、「見つめる」「語り合う」「つながる」教育の原点に立ち戻って考りたいとえようと思いました。
また、入所者の方々の「綴ったこと」は、その当時、社会や世の中を大きく動かすことはなかなか難しかった時代(正しい知識・理解不足)だったかもしれませんが、今現在、あらためてその価値は大きいと思います。私たちも小中学校の教員仲間らで、新たなハンセン病問題学習の授業ポログラムを考えています。もちろん、入所者の方々の生き様(よう)に学ぶハンセン病問題学習です。金泰九さん、『虎ハ眠ラズ』、『我が八十歳に乾杯』などを活用した教育実践はこれまでもたくさんありますが、「いま・これから」のためにあらためてつくりたいと考えています。そしてもう一つは、昨年度、徳田靖之弁護士(国賠訴訟の弁護団長)さんのお話を聴いて、黒川温泉での宿泊拒否の出来事をもとに、救らい思想(人の無意識の中にある、「かわいそう」な人たちへの救済、差別)をのり越える学習プログラムをつくりたいとも思っています。あれもこれもすぐには作れませんが、私の覚悟です。
☆231日目(1.30)
『こんにちは 愛生園」https://note.com › asanonoi
子どもたちと読みたい素敵なマンガを、知り合いから薦めていただいた、子どもたちと読みたい作品です。紹介してくれたIさんに返信した内容の一部です。(感想)
私は、2000年に初めて長島を訪れ、入所者の金泰九(kim teagoo)さんに出会い、縁あって、金さんの愛生園フィールドワークのお手伝いをさせてもらうようになりました。金さんが亡くなられた後も、小学生、中学生、保健の先生、様々な方々の現地研修に同伴して、園内を歩いて歴史的な場所や出来事、ハンセン病問題について話をしています。いつも現地研修のお手伝いを終えるとホッとしますが、同時に自己嫌悪というか、いつも同じ問いが頭の中をよぎります。それは、「当事者でない自分が、何を語れるのか?」です。療養所の歴史の中には、今の社会では想像もできない出来事(入所者のくらし・生き方)がたくさんありますが、そこから強烈なインパクトのある事象を、あたかも分かったかのように、「エピソード」として取り上げて、現地研修に来られる方々に話し(驚いてもらう)ようなことに自分はなっていないか?という猛省です。だから、減り続けている入所者数や平均年齢も軽々しく言うべきことではないかなあと思っています。現地研修に来られるグループの研修の目的や理解状況によっては伝えないこともあります。ハンセン病問題に関心を高めることを「煽って」はいけませんね。
ようやく、最近は、(二時間程度のフィールドワークのプログラムですが)、一緒に歩く時間には、自分自身のハンセン病問題への今現在の向き合い方と、金泰九さんが存命中に常日頃言われていたことや教えてもらったことを話すしかないなあと思っています。長島は観光地でもありません、観光ガイドでもなく、当事者の証言でもなく、自分の「立ち位置」をいつも確認しながら、今後も現地研修のお手伝いをしていこうと考えています。
例えば、現地研修の終わりには、「今日は、ハンセン病問題の歴史のほんの一端の学習でした。どうかまたいらしてください。金さんはいつも「またおいで」と笑顔でお別れしていました。そしてもうひとつ。ハンセン病問題を政治的・社会学的に論じた本もたくさんありますが、たくさんの入所者の方々が、自分の生き抜いてきた人生を本や記録で著しています。ぜひ、ハンセン病問題を「入所者が歩んで来られた生き様(よう)」から、深く、思考してほしいと思います。」と付け加えています。とても前置きが長くなりましたが、こんにちは 愛生園」のマンガの中に描かれた入所者一人ひとりが綴った(残した)「語り」「コトバ」から、私たちは、療養所でのリアルな生き様(よう)を丁寧に読み取り、学んでいくことがこれから益々重要になってくると感じています。世界遺産への登録の取組の中でも大きなキーワードになってくると思います。名もなき人々(大切な名前はもちろんあります)の聲を聴き、それを伝えていく活動を、私も私の方法で、微力ながら進めていこうと思います。
☆230日目(1.29)人権教育実践の中での仲間づくり(続き)
新しい教育要領や学習指導要領には、これまでなかった「前文」が加えられ、そのなかで、これからの学校には一人ひとりの子どもが、「自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と述べられています。
ここに示されている子どもたちに育みたい力は、これまで私たちが人権教育を通じて子どもたちに育んできた力と重なるものです。生まれ育った環境や障がいの有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもたちが意欲的に学び、夢や希望を実現できるようにしていくためには、学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの自尊感情を高め、多様な人と協働しながら、人権が尊重される社会づくりに主体的に参画する力を培う必要があります。そして、
その取組は、これまでの同和教育の理念や成果、手法を踏まえ、教育的に不利な環境のもとにある子どもを中心に据えた「仲間づくり」を基盤とすることが重要です。
あらためて
◆「仲間づくり」の目的
めざすべき「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある人権問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。
◆「仲間づくり」の視点
「仲間づくり」は、こうした目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。そのうえで、どのようなことを大切に取り組んでいけば良いか、これまでの成果などを踏まえ、ポイントを紹介します。
①子どもの生活背景をつかむこと
すべての教育活動は、子どもの姿、子どもを取り巻く現実から出発することが大切です。気になる言動を見せる子どもがどんなことを考え、どんな思いでいるのか、どんなくらしのなかで生活し、学校に通っているのか、保護者はどんな願いをかけて子育てをしているのか。そうしたことのなかに、その子どもが抱えさせられている課題を解決するための、取組のヒントがあります。子どもの生活背景をつかむためには、家庭訪問等の取組を通じて、くらしや思い・願いなどについて対話できる関係を、子どもや保護者と築くことが必要です。
②弱い立場に立たされている子どもを中心に据えて取り組むこと
「中心に据える」とは、決して集団のリーダーにするということではありません。取り組む教育活動が、子どもの自尊感情や学習意欲を高めたり、自他の人権を尊重し差別をなくそうとする意識を身につけたりすることにつながるものであるかを、その子どもの姿を通じて検証するということです。集団のなかで疎外されていたり、不安を感じながら生活していたりする子どもが学級で安心して過ごせるようにすることは、誰にとっても居心地の良い環境をつくることになります。また、弱い立場にある子どもの側に立ってまわりの子どもや集団を見ることで、他の子どもの課題や集団の課題が見えてきます。
③一人ひとりが生活のなかで感じている不安や悩みを共有し、ともに乗り越えようとする集団をめざすこと
「いいところ」「がんばっていること」を認め合うことは大切です。しかし、それだけではなく、一人ひとりが直面している課題を出し合うことが必要です。家庭や地域での生活、そのなかで抱えさせられている思いを知り合うためには、「聞いてもらえる」「知ってほしい」と思える集団であることが大切です。こうして知り合った一人ひとりの思いを共感することが、一人ひとりの課題の克服や、その背景にある人権問題の解決に向けて行動しようとする連帯感につながっていきます。
④個別的な人権問題についての学習と結びつけて取り組むこと
一人の子どもの生きづらさの背景に人権問題がある場合、その生きづらさは社会の問題であり、他の子どもにとっても共通の課題となります。友だちの思いを聞くなかで、「友だちを不安な思いにさせていたのは、社会の偏見や差別だった」「そのことに無自覚だった自分は、友だちを不安にさせていた」といった気づきが、人権問題の解決を「自分事」として引き寄せていきます。また、様々な人権問題について学習する際、自分が生活のなかで感じている不安や自分にとって身近な人権問題と重ねて考えを出し合うことによって、マジョリティを「普通」とする価値観やそれへの同調圧力など、それぞれ個別の問題に共通する社会の課題を見出し、自分自身とのつながりを見出すことができます。「仲間づくり」を基盤に、こうした学びを積み重ねることが、ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高めることにつながります。
◆「仲間づくり」の手法 〈テクニックか?!〉
これまでの取組において、有効性が確かめられてきたいくつかの手法があります。
①「つづる」「語る」・・・一人ひとりが自分を見つめる取組
「つづる」とは、過去の出来事を順番に思い出し、事実をありのままに書いていくことです。これを積み重ねることで、生活のなかにある自分自身の課題や不安、悩みを意識化し、これからの生き方や社会のあり様を考えることができるようになります。自分を見つめることは、つらいことや苦しいことも受けとめ、自分を否定することなく生きていく力を培っていきます。そうした力を身につけた子どもは、友だちの前で「語る」ことができるようにもなっていきます。また「語る」ことは、単に誰かに伝えるだけではなく、自尊感情や将来展望を確かなものにしていくことにもなります。
②「読み合う」「聴き合う」…知り合い、共感し合う取組
朝の会や帰りの会等で日常的に子どもがつづったものを読み合う取組や、人権学習・人権集会等で伝え合う取組が行われてきました。こうした取組によって、子どもは友だちの思いを知ったり、友だちに思いを返したりするなかで自分を深く掘り下げていきます。また、思いを伝える姿が、他の子どもにも「もっと自分のことを深く見つめたい」「自分もずっと避けていた課題と向き合いたい」という意欲を喚起することもあります。
「読み合う」「聴き合う」取組を進めるにあたっては、教職員が自分自身を語ること
を大切にしてきました。教職員が自分の不安や悩み、これまでの経験等を語ることは、子どもたちの「こういうことを話してもいいんだ」「自分のことを聴いてほしい」という安心感につながっていきます。
☆229日目(1.28)えっ!?仲間づくりの必要性はない?
学校には、教員に向けて様々な案内チラシが届きます。ふと気になったチラシの一文には「最も必要とされながらも、最も学ぶ機会が少なかったクラス担任の仕事。明日からすぐに使える実践的なテクニック〈担任学〉・・・」とありました。「学ぶ機会がない?」「テクニックなのか?」「担任ガク!?」と、いろいろと気になるコトはありますが、先日も仲間の教員と「もしかしたら〈学級づくりや仲間づくり〉への担任業の意識や目指すところが変わってきたのではないか。仲間づくりが必要とされていないのか?」と感じるところがあり話題になりました。『総合教育技術』2021年12/1月号でも関連した内容を取り上げていますので少し引用します。
以下[・・・学級経営それぞれこれまで多くの学校は、教科指導に比べ、学級経営にはあまり力を入れてこなかったと思うのです。しかし、その考え方を改めるべきときが来ています。これからの学校は、学級経営にもっと意図的に、計画的に取り組む必要があります。そう考える理由は、3つあります。
1つ目は、時代の要請です。令和3年1月26日の中教審の答申(「令和の日本型学校教育」の構築を目指して)の概要の中で、注目しているのは以下の部分です。
[一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが必要(文部科学省『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 』より)]
これは、世の中の変化を見据え、このような子どもたちを育てていくのだ、という文部科学省からの要請だといえます。ポイントは3点あります。1点目は「自分のよさや可能性を認識」、2点目は「あらゆる他者を価値のある存在として尊重」、3点目は「多様な人々と協働」です。これらのことを育成していくには、その前提として、学びの場としての学級経営の充実が求められるのではないかと考えます。
また、学習指導要領が改訂され、子どもたち一人一人に育成すべきものが「確かな学力」から、「3つの資質・能力」へと転換されました。現在の学習指導要領では、学級経営は「特別活動の資質・能力の実現によって深化していく」と書かれています。特別活動の資質・能力とは、協働の知識・技能を学び、話合い・合意形成・意思決定の能力を身につけ、そういった営みを通して人間関係を形成し自己実現していく、そのような子どもを育てることを意味します。それにより、学級経営が充実し、学びに向かう学習集団へと成長していく、そのように設計されているのです。
学級経営の目的も、新旧の学習指導要領を見比べてみると、大きく転換したことがわかります。旧学習指導要領でも学級経営の充実は求められてきましたが、それは「生徒指導の充実のため」でした。いじめ、校内暴力、学級崩壊、モンスターペアレンツなど、時代とともに様々な教育課題が山積するなかでは、学級集団を安定させるための学級経営をする必要があったからです。
新しい学習指導要領でも、その点は引き継がれていますが、それ以上に「主体的・対話的で深い学び」との関連が強く打ち出されています。授業改善をして「主体的・対話的で深い学び」という高度な学びを実現するためには、子どもたちの主体的で自治的な取り組みが不可欠であり、それは質の高い学級集団がなければできないことです。そのため、学級経営の充実の目的が「生徒指導の充実」から「授業改善」へと転換したのです。つまり、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、子どもたちが協働し、自ら問題解決していくような学級集団づくりが求められています。]
学級経営・学級集団づくり・仲間づくり、そして上記の中の「学習集団」・・・いろんなコトバがあり、捉えようも具体的な取組も教員一人ひとり様々でしょうが、テクニックだけではなく、時代の求めているモノやガクリョクコウジョウだけで「学級づくり」を語ることがないように自分自身肝に命じています。(続く)

☆228日目(1.27)「出来ない」をどう越えるか!②
森さんの文章の続き・・・
自分に引きつけながら考えられるように
その点とも関わりますが、部落問題学習の内容が、子どもたちが今直面している問題につながっているかどうかが問われます。つながる点は様々にあります。
情報化そのものが、子どもたちから縁遠い事柄ではありません。子どもたちの身近にスマホがあり、PCがあります。GIGAスクール構想が出ているいま、タブレットが子どもたちの身近な存在となっています。教員が知らない間に子どもたちが情報機器を使っていじめをしていたという事例を聞くことがあります。これは部落差別にもつながります。それら情報機器を使っての検索は、子どもたちにとって身近な行為です。「部落」や「部落差別」という言葉を知り、「部落」や「被差別部落」で検索すれば、残念ながら部落の所在地情報にゆきあたり、地域の映像が現れるのです。
部落差別と自己のつながりを考える手がかりひとつは、自己開示やカミングアウトに関わる問題です。自分のことをいつでもどこでもすべて明かして生きている人はほとんどいません。何かを言わないままに暮らしている人ばかりと言ってもよいほどです。
私の子どもの頃を振り返ってみると、小学校6年生の頃まで時々おねしょをしていました。これは当時の自分にとってたいへん恥ずかしいことで、誰にも知られたくないことでした。修学旅行はとりわけ心配な行事でした。一泊して、そのときにおねしょでもしたら、一生言われ続けるかもしれません。これは、おとなからすればたわいもないことに映るかもしれませんが、子ども本人にとってはけっこう深刻な問題です。もしも、このような問題とつないで部落差別が取り上げられれば、わたしにとって部落差別は身近な問題として映ったであろうと思います。
こう述べると、「おねしょと部落問題を一緒にするのか」という疑問や反論を出されるかもしれません。おねしょという問題はあえて出している面があります。そういう問題でも、部落差別と結びつきうると言いたいのです。ましてや、家族の中で対立やけんかがたえないとか、親のことを好きになれない、クラスでいじめられている、といったことがあれば、それは部落差別に直結するような問題です。そのようなことと結びつけて学習を組むことが求められるでしょう。
上の例は自分自身のこととして述べましたが、これを他の人のことにつなぐこともできます。できるというよりも、することが求められていると言うべきかと思います。部落問題学習を通して、自分の友だちが何かを苦にしているということを知ることができれば、部落問題学習が自分にとっても意味のあるものと感じられやすいでしょうし、部落差別も身近に感じやすいでしょう。》
さて、私たち(学年教職員集団)はどうしたでしょう。○部落問題学習に取り組む際の、不安や心配(イメージ)を明確にしよう。どうしたら前に進めるか考えていこう。→○中学校(教職員)だけで課題を抱え込まないようにする。課題や問題が出できた時が「真の学びのチャンス」と捉えよう。理解不足や差別意識からの発言をていねいに聴き取ろう。そこが大事。地域の方々や先輩たち、たくさんの力をかりて、豊かな学びを深めていこうと覚悟を決めよう。○私たち自身、まだまだ部落問題学習に関する勉強が足りないという自覚をしよう。○かっこつけずに、知っているフリをせず上から教えようとしない。○共に真摯に学び続ける姿を子どもたちにみせよう。○ムラの名前だけに拘泥するのではなく、中・長期的な部落問題学習を展開していこう。(差別されたムラでなく、たくましく生き抜いてきたムラ、差別に抗ってきたことを正しく認識することで、ムラに誇りを持てる)ということを共通認識して授業実践をおこないました。心配していたようなことは起こりませんでした。

☆227日目(1.24)受験に挑むとき
二日間の私立入試に多くの子どもたちが挑んでいます。どこの学校も事前指導では、教員からたくさんの諸注意や心構えなどが語られたでしょう。本校でも担任と共に学年団の先生がそれぞれ熱いエールを送りました。そして、その中で今年も、子どもたちは、これまでの労苦をねぎらい、「明日、がんばってこよう!」と堅い握手やハグなどをしながら、互いに受験への気持ちを新たにする取組を行いました。数十年前に先輩教員に教えてもらったこの実戦も、子どもたちの仲間感の熟育や集団意識の高まりの違いでうまくいかない場合もあります。子どもたちがかかわり合う、つながる(つなげる)日々の活動の延長線上に受験期のこの取組があります。受験は仲間をバラバラにすることが「ない」確かな仲間づくりを進めたいと思います。


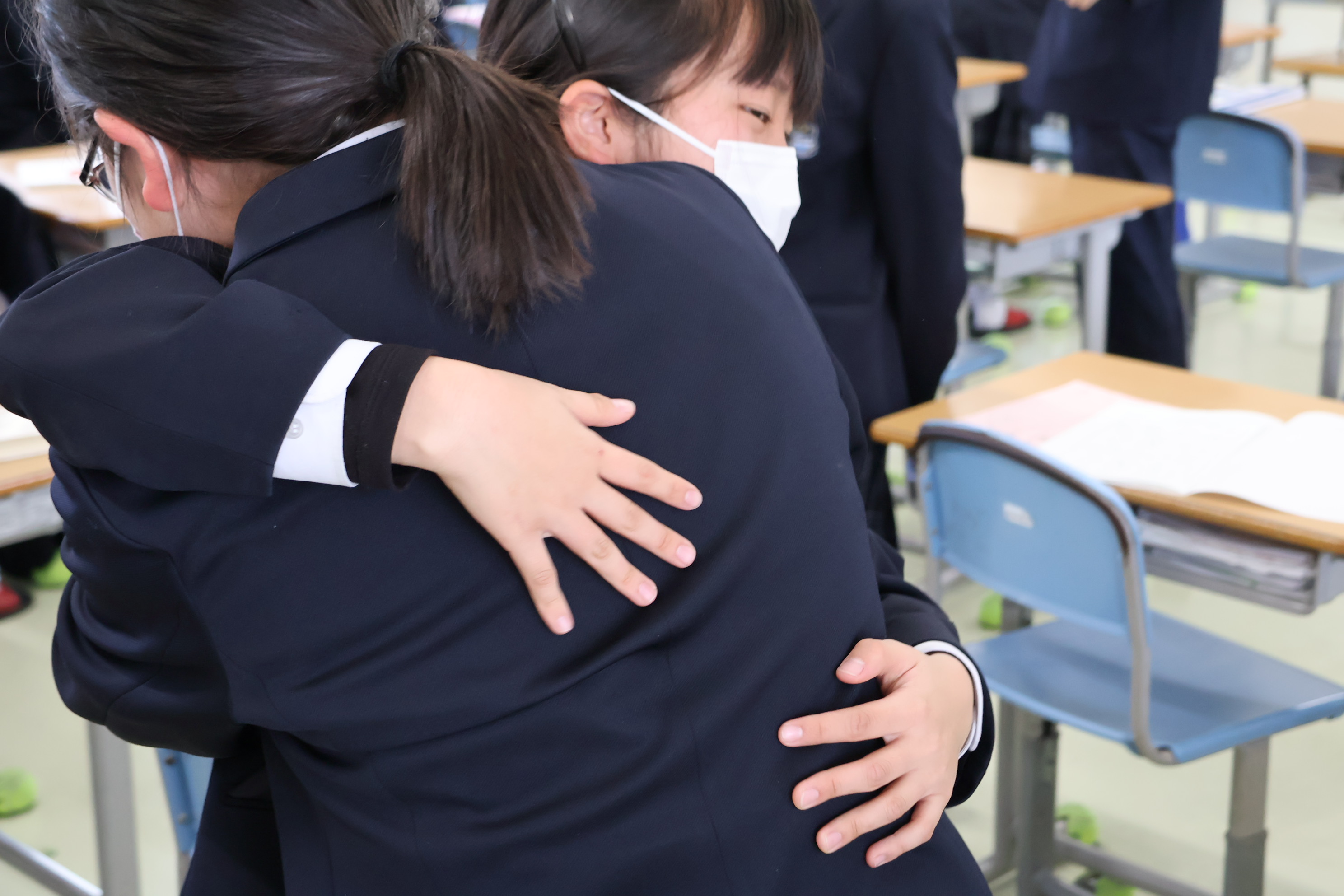
☆226日目(1.23)「出来ない」をどう越えるか!
外川さんが制作した優れたDVD「渋染一揆を闘いぬいた人々」の映像中には、入牢となった人々の村名が出ます。そのため以前に勤めた学校での授業検討時には、「ムラの名前が出ているので心配だ。DVDは使えないのではないか。」という意見が出てきたことがあります。
そこで、『日本文教出版HP(2022.01.05 学び!と人権 <Vol.08> 現代部落問題学習の課題 森 実』さんの文章を紹介します。
《・・・ただ、「どこが被差別部落かを授業で取り上げることはできない」という声もあります。私の住む自治体でも、そのことが話題になりました。学校の教員が部落問題学習の実施をためらう理由の一つとして、「『先生どこに部落があるの?』などと子どもから尋ねられたときに答えられない」という意見がありました。これに対して、市内の被差別部落で運動に取り組んでいる人から出たのは、「それやったら、うちにきてくれたらええやん」ということでした。フィールドワークなら、いつでも受け入れるよというわけです。このことを前提にすれば、子どもから「先生どこに部落があるの?」と尋ねられたときの答えは簡単です。「そうか。先生が知ってるから、先生と一緒に行ってみるか。友達にも声かけて一緒にいこか」というのでよいではないかということです。そう返すことによって、質問した子どもの側もいろいろなことを考えることができます。友達に声をかけてみて、どんな返答が返ってくるか。親に話したときに親はどう言うか。そういうことを通して自分自身の問題意識も振り返り、研ぎ澄ますことができるはずです。
そういう考え方をあちこちで紹介してみると、「いやそれはむずかしい」という声がしばしば返ってきます。「うちの自治体にある被差別部落は、そんな受け入れ体制がない」というわけです。地域によりいろいろな事情があることは分かります。そうであれば、同じ自治体の被差別部落ではないにせよ、見学を受け入れてくれるところを探してみることもできるのではないでしょうか。問題なのは、地元の被差別部落が消極的だという理由をもって、フィールドワークや部落問題学習すべてをあきらめてしまうことではないでしょうか。すぐ近くの被差別部落が無理でも、少し離れたところの被差別部落との信頼関係をつくることはできるかもしれません。また、地元の被差別部落が受け入れてくれないのは、学校が地域との信頼関係をつくれていないからなのかもしれません。部落の人たちの発言から、自分たちの教育実践を問い直すことも必要です。
身近な問題にという点で考えておきたいもう一つのことは、部落差別事象は、いろいろな場面に顔を出すということです。学校の近くで差別落書きが発生することもあります。親たちの発言の中に差別的な言動が含まれていることもあります。部落出身でなくても、部落問題に取り組んでいる人たちはいます。そういう事例や人物を取り上げることによって、子どもたちが自分にとって身近な問題として部落差別をとらえやすくなることは間違いありません。逆に、そういう面がないまま部落問題学習をすすめれば、偏見や思い込みを助長してしまいかねないのです。(長い引用でスイマセン)
差別をなくそうとする取り組みとあわせて
部落差別について学ぶときには、この差別をなくすための取り組みとあわせて学ぶ必要があります。どんな差別があるかを知るだけでは、力はわいてきません。悪くすると、無力感を広げるだけに終わります。そうではなくて、部落差別をなくすための取り組みや、取り組んでいる人の姿と合わせて学ぶことによって、力がわいてくる学習になり、展望を感じられる学習になります。
学校区をはじめ、差別をなくすために活動している人を招いて、自分の取り組みを紹介してもらうことが求められます。ある日突然に来て話してもらうのでは、子どもたちにとっては必然性のない話となり、せっかくの学習が実りに欠けます。一連の学習の流れに位置づけて、子どもたちが抱いた疑問に答え、子どもたちの思い込みを解いてもらうようにして出会いの場を設定することが重要です。
また、歴史学習でも、差別をなくそうとする取り組みが不可欠です。たとえば「水平社宣言」をきちんと位置づけることです。2022年は水平社が創立され「水平社宣言」が出されて100年です。「水平社宣言」は、つづめていえば<自分たちはこんな体験をし、悔しい思いを重ねてきた。だから自分たち自身で差別をなくしてすべての人が解放されることをめざして立ち上がるのだ>という文書です。子どもたちが自分自身の悔しかった体験を出し合い、その延長線上に「水平社宣言」を学ぶことによって、自分に引きつけて学習することができます。続く

☆225日目(1.22)体感する「学び」を創出したいね
少し前に外川正明氏の学習会へ参加しました。この日は、地元の歴史的な資料を丁寧に掘り起こされた研究と重ねて「渋染一揆」について、話を聞くことができました。会では、『シリーズ映像でみる人権の歴史DVD(第5巻)渋染一揆を闘いぬいた人々』を視聴し、参加者で意見交流を行いました。参考に、DVDの解説文を紹介します。「江戸時代も末期を迎えると幕府や藩の財政は苦しくなり、経済の引締めが相次いで行われました。「身分相応の暮らし」を命じる政策は、崩れかけていた身分制度を改めて強化することになりました。岡山藩では、庶民に出した倹約令を徹底するため、被差別身分の人々に、「柄のない渋染か藍染以外の着物の着用を許さない」というさらに厳しい御触れを出します。あからさまなこの「分け隔て」の「差別」を認めるわけにはいかないと藩内53ケ村の人々は、のちに「渋染一揆」と呼ばれる大規模な抵抗運動を起こしました。人々は、知恵を出し合って「嘆願書」を作成し抗議しますが、それが突き返されたことから1500名もの人々が「強訴」に立ち上がり、整然とした闘いでこの「特別の(別段)御触書き」を取り消させました。さらに、その責任者として入牢させられた12名を助け出すために「赦免」を求めて闘い続けました。
このDVDでは、地元の方々の協力を得て現地を取材し、原典資料を詳細に分析し、この渋染一揆の経過を丁寧に追いかけました。人としての尊厳をかけ、社会情勢を見抜き、知恵と力を合わせて戦った人々から、いま学ぶべきことは何かを問いかけます。」
外川さんのお話とDVDの視聴から、確かな学びを実現するためには、「時間と空間」を意識した学習プログラムや授業展開がとても大事だとあらためて感じました。それは、私が昨年度、何度か渋染一揆や長島愛生園でのフィールドワークの依頼を受けたのですが、研修される方々の時間の関係という理由で、資料館だけの見学研修で終わったり、研修コースを大きく省いたりすることがありました。そんなフィールドワークの手伝いを終えた時に心に残ったモヤモヤ感・・・。これは何なのか。これまで自分が参加したステキな現地研修やワークショップや研修会での、バラバラ、断片的な理解や知識の一つひとつ(点と点)が、時間軸でがつながり、空間軸で拡がり、「いま」と重なっていく感覚は「学び」の醍醐味、真性の「学び」ではないかと思うのです。そんな「学び」を今年度もしっかりと創出していきたいなあと思う学習会でした。参考にこのコースで廻りましょう。
◇渋染一揆:常福寺~岡山県水平社創立大会跡~(*岡崎良平の墓)~渋染一揆資料館見学(若宮神お参り)~八日市河原(結集の地)~虫明街道(稲荷山 万次郎茶屋)~備前市佐山(対峙の地)~(*伊木若狭陣屋跡)
◇愛生園:船着き場跡~収容所跡~監房跡~万霊山・納骨堂~平成公園~恵みの鐘~一郎道~小川正子碑~恩賜記念館~菴羅公園(*新良田教室(高校)跡)~歴史館見学~さざなみハウス(*むつみ交流館 しのび塚)*3/22も廻ります。一緒にどうですか?他の日もご希望に添います。

☆224日目(1.21)出来ることから
長野県の『チームで支援する特別支援学級」の資料(支援学級の担任の先生の立場から)の一部を紹介します。
以下、・・・特別支援学級担任のマツヤマ先生は,原学級の子どもたちにアユミさんのことをもっと知ってもらい,アユミさんが原学級でも自分らしく活動できるようになってほしいと願っています。
どのように原学級と連携していけばよいでしょうか。
●アユミさんが自分らしく活動することを願って
小学校に入学したころ,1年生の教室の隅にうずくまっていることが多かったアユミさん。4月の終わりに特別支援学級に入級しましたが,自分から話すことはほとんどありませんでした。特別支援学級担任のマツヤマ先生は,「アユミさんが自分の思いを話すことで,自分らしく活動し,楽しいことをたくさん経験できるのではないか」と考えました。そして,アユミさんが興味関心をもっている学習を通して,声を出したり話したりできるよう支援を続けました。また,行事の時には,アユミさんと一緒に原学級の活動に参加するようにしました。 3年生になり,アユミさんは特別支援学級の中では自分の思いを話せるようになり,自分らしさを出して伸び伸びと活動できるようになってきました。マツヤマ先生は,アユミさんが原学級とのかかわりを少しずつ増やし,原学級担任や子どもたちにも自分の思いを話せるようになってほしいと願いました。
●原学級の様子を知ろう
アユミさんと原学級のかかわりを増やすにはどうしたらよいか考え始めた時,マツヤマ先生は自分自身が原学級とのかかわりが少なく,原学級の活動についてほとんど知らないことに気づきました。
そこで,原学級の様子を知るための方法を考え,実践しました。そして,得た情報を基に,●アユミさんが参加しやすい活動を考えてみました。〈原学級でも自分らしさを~原学級とのかかわりを深めながら~ 〉
・・・こんなことからできそうです。
・原学級の時間割や週予定をもらおう。
・原学級と特別支援学級の学級通信を互いにやりとりしよう。
・原学級の担任と直接話をできない時もあるから,連絡帳を作ってアユミさんの様子を知らせたり,原学級の情報をもらったりしよう。
・学年会にも積極的に参加しよう。
・可能なときは,アユミさんと一緒に原学級の授業に参加しよう。学び方の現地研修
子どもと保護者の願いや思いを大切にして、「出来ない」ではなく、どうしたら「出来る」ようになるか!と思考を巡らしたいと思います。ちなみに保護者の意見を一方的に聞いて、学校だけで取り組んでいくものではありませんよね。子ども(クラス)の今の育ちや課題を保護者(もちろんチームとしての学校の仲間たちも)と共有しながら、共に「夢と希望」を語っていきましょう。出来ることはアル。
ユネスコ(国連教育科学文化機関)によると、インクルーシブ教育とは「すべての子どもを包摂する教育」のことで、障害がある、性的マイノリティである、外国にルーツがある、ヤングケアラーの子どもなど、多様な子どもがいることを前提として、すべての子どもの教育の保障を目指すものです。重要な点として、インクルーシブ教育は「結果」ではなく「プロセス」であることが挙げられます。多様なニーズを持つ全ての学習者が排除されず、学びに参加できるように取り組み、対応するプロセスそのものが、インクルーシブ教育ということです。そして、そのゴールには、多様なすべての子どもが共に学び、さらには人々が互いに、多様なあり方を認め合える全員参加型の「共生社会」の実現があります。
国際文書に初めてインクルーシブ教育が明記されたのが「サラマンカ宣言」です。1994年、スペインのサラマンカで開催された「特別ニーズ教育世界会議」において、ユネスコとスペイン政府によって採択されました。障害の有無に限定せず、「どんな特別な教育的ニーズを持つかにかかわらず、万人が教育を受けられるようにしないといけない」という「万人のための教育(Education for All)」を宣言している点で、国際標準としてのインクルーシブ教育の理念をよく表しています。
☆223日目(1.20)「出来ない」ではなく、「どうしたら出来るかなあ」
「なんでも相談・まんまるハート」の学習会へ参加してきました。東備地域自立支援協議会は、障がい者(児)の地域生活を支援し、自立と社会参画を促進するため、地域における障がい者等への支援体制の整備に関して中心的な役割を果たす場所であるとともに、障害者総合支援法の円滑な推進を図ることを目的として、備前市・和気町が共同して設置しています。同協議会は、4部会・2連絡会で構成されており、各種事業や啓発活動等に取り組んでいます。その中の子ども部会では発達等に関することについて、協議・企画運営を行っています。この日(1/9)は、「なんでも相談・まんまるハート」(子どもの発達が気になる保護者の方を対象とし、学習の場や相談会)があり、中学校での生活や進路・進学(入試制度)に関して情報交流を行いました。
さて、この会ではありませんが、いろんな学習会やの中やで、保護者から「原学級(←あえて。この意味合いが重要)での子どもの交流学習を希望しているんだけど、先生から、交流の時間はなかなか難しい(出来ない)。と言われて悩んでいる」と聞くことがあります。カリキュラム編成など学校の事情もあるのでしょうが、「出来ない」ではなく、「どうしたら出来るようになるか」と考えたいなあと本校ではいつも話しています。続く

☆222日目(1.17)1995.1.17を話す
たくさんの天災や人災、出来事や事件が起こりますが、その中から「どんなことを、どのように、朝の会や授業で語るのかは、とても大切なことだと思います。今年は、阪神淡路大震災から30年。「何を、なぜ、どうして自分は語るのか」確認しながら、語る機会を大事にします。
・阪神淡路大震災1.17のつどい実行委員会HPより
〈1995年1月17日 午前5時46分。
阪神淡路大震災が発生し、私たちの大切なものを数多く奪っていきました。
あの震災から、まもなく30年を迎えようとしています。
震災でお亡くなりになられた方を追悼するとともに、震災で培われた「きずな・支えあう心」「やさしさ・思いやり」の大切さを次世代へ語り継いでいくため、2025年1月17日(金)に「阪神淡路大震災1.17のつどい」を、神戸市中央区の東遊園地で行います。〉
この震災では、高層ビルや、高速道路までもが大きく倒壊し、現代の文明の脆弱さ思い知らされました。死者の数は6434人、負傷者は4万3792人。財産を多く失い、愛する我が家を失った人は、全壊、半壊合わせて24万9170棟で、全焼建物は7036棟でした。失ったのは数字に表れるものだけではありません。復興に際し、被災地域住民のそれまでのコミュニティも失われたとも言う人もたくさんいます。失ったことについていくら語っても切りがありませんが、想像を絶する痛みに耐え、この大震災 により私たちが未来に向けて得た、かけがえのないものは「多文化共生」と「ボランティア」といわれます。大震災が発生したこの年はボランティア元年ともされ、1月17日は「ボランティアの日」と定められました。実際に被災地に足を運んだ者は3ヶ月間で116万人、1日平均2万人を超えました。このボランティア文化が、後の東日本大震災にも、また、多くの海外の現場にもしっかり引き継がれるようになりました。教育現場では、小中高・大学などもボランティアが重要になり、本校でもボランティアは大切な取組となっています。
災害での被災者は何も日本人ばかりではありませんでした。多くの外国人も負傷し、200人の外国人が死亡しました。被災地となった兵庫県内の10市10町において被災時には8万人の外国人が居住していました。そのうちの4人に1人が日本語の読み書きが出来ませんでした。被災者を助けようとする情報がいくら被災地で行き交っても一向に恩恵を受けられない人がいること、日本社会の住人が日本語がわかる人ばかりではないということが震災で明らかになりました。そこから多言語での紙媒体やラジオ、インターネットコンテンツが日本で次々に生まれるようにもなりました。「言葉の壁」を取っはらう活動は、その延長線上に社会の壁は言葉の壁だけではなく「制度の壁」や「心の壁」に撤廃の取組につながっていきました。今、全国で、違う者同士が、〈共に生きる〉という目標に向かって、個として、組織的として、勢力的な取組が進んでいると感じます。たくさんのものを奪い去った震災ですが、1995年1月17日にうまれた「ボランティア」や「多文化共生」の樹を引き続き大切に育てて行けたらと思います。(にしゃんたさんの記事を編纂)
☆221日目(1.16)認知症サポーター養成講座から考える
昨年の11月に家庭科で、関係機関と協働で、中学生認知症サポーター養成講座の内容を基盤に、授業化を進め、2時間のプログラムを創って学習に取り組むことができました。
*認知症サポーターとは、〈認知症に対する正しい知識と寛容な理解のある、認知症の方やその家族らが暮らしやすい地域社会の実現を支援する方です。サポートといっても直接的な介護などをするわけではなく、認知症の人や家族の「よき理解者」としての活動がメインになっています。
役割や意義について、
(1)認知症に対して正しく理解し啓発する
誰もが認知症に対して偏見を持ってしまうものですが、とくに偏見の強い人は、認知症になると物事の判断がなにもできなくなってしまうと考える方もいます。しかし実際には、すべての物事を理解できなくなっているわけではなく、また感情やプライド、羞恥心があるのです。特に初期の認知症の方の理解力は、認知症でない方と同じようにできます。それにもかかわらず、必要以上に障害者扱いしたり、子ども扱いするとストレスがかかり、認知症の方の症状悪化を招く恐れがあります。正しい知識と寛容な理解を有したうえで、手助けの重要性を啓発することは認知症サポーターの大切な役割です。
(2)地域で協力体制を作り、認知症の方や家族を温かい目で見守る
一人歩きによって行方不明になったり、事故に遭ったりするケースが後を絶ちません。一人歩きによるトラブルを防ぐうえで重要なのが、相互扶助や助け合いのネットワークを構築し、地域全体で見守ることです。認知症の有無に関係なく、道に迷ったり、困っている様子がある方に対して声をかける、付き添うなどの親身になった振る舞いが認知症サポーターには求められます。
(3)すべての人が住みやすいまちづくりを担う地域のリーダーとして活躍する
多くの人は、認知症になると買い物や移動、趣味活動など地域の様々な場面で外出や交流の機会を減らしている傾向にあります。例えば、買い物に来た高齢者の様子から認知症が疑われる場合、まずは温かく見守り、必要に応じたサポートをすることは、認知症サポーターが率先して担うべき役割です。
さて、実際の授業では、知識偏重にならないように、ロールプレイを取り入れたり、小グループでのディスカッションを行ったりして多面的な学習の時間となり、豊かに学び合う時間となりました。
授業後の生徒の振り返りやメモに目を通すと、やはり、充実した学習内容であったことを確認できました。しかし、気になったことがひとつありました。それは、認知症にならない〈予防のための〉学習、(認知症になったらダメだという考え)にとどまってはいけないなあと思ったことです。授業プログラムづくりの時にも、「高齢による認知の衰えは誰にでもやってくること」を前提に、「自分たちはどんな社会をつくっていくか」の視座で、認知症の現実や、家族・地域社会の課題に迫っていこうと、学習内容の共通認識をもっていました。
新年度は、さらに、持続的な介護・福祉施設での体験学習(利用者、家族、スタッフなど多様な方々の聴き取り学習も)を地域協働の活動の中で進めていくことができればよいなあと思っています。
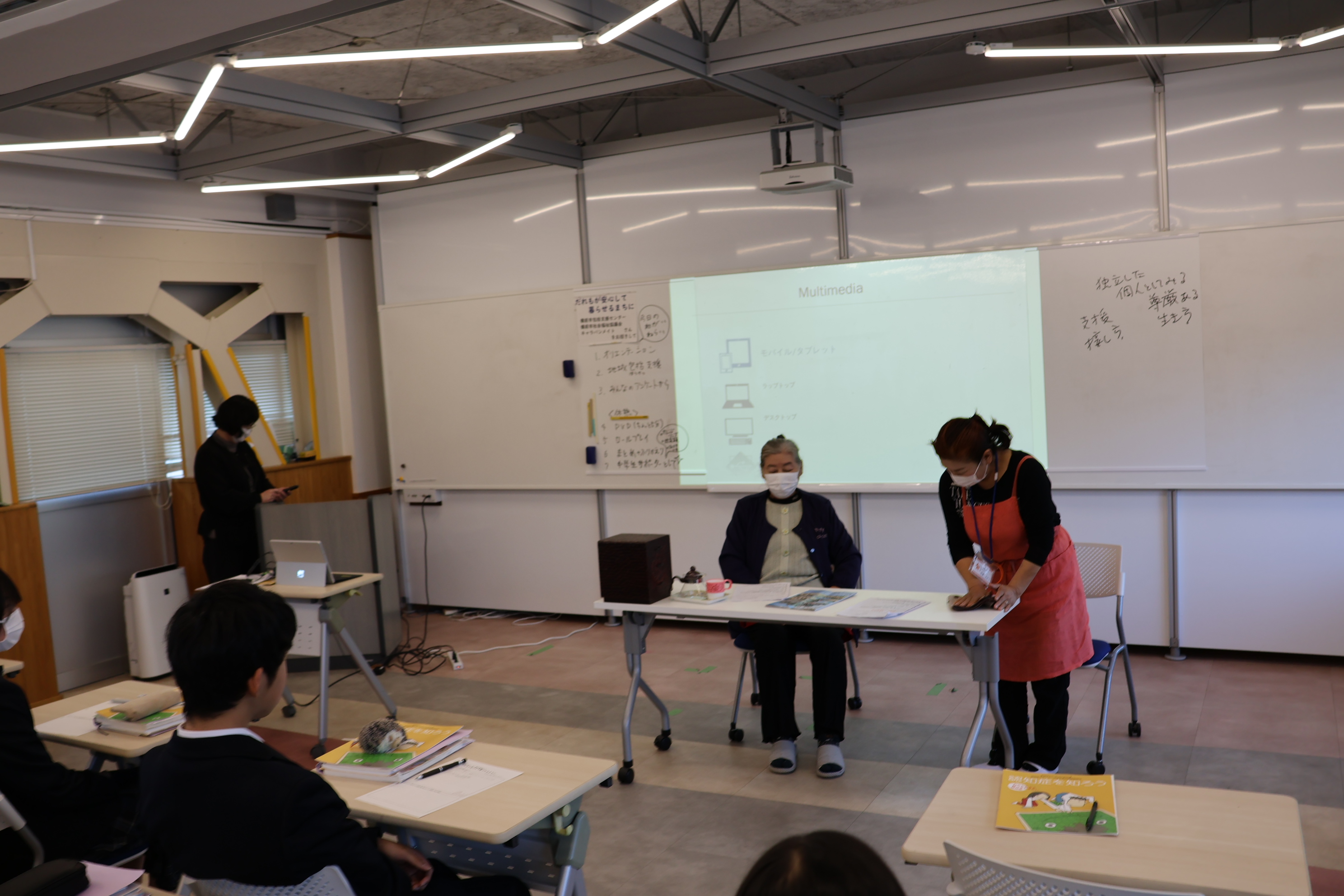
☆220日目(1.15)個人モデルと社会モデル
「個人モデル」とは、障害者が困難に直面するのは「その人に障害があるから」であり、克服するのはその人(と家族)の責任だとする考え方であるするのはその人(と家族)の責任だとする考え方である。それに対して「社会モデル」は、「社会こそが『障害(障壁)』をつくっており、それを取り除くのは社会の責務だ」と主張する。人間社会には身体や脳機能に損傷をもつ多様な人々がいるにもかかわらず、社会は少数者の存在やニーズを無視して成立している。学校や職場、街のつくり、慣習や制度、文化、情報など、どれをとっても健常者を基準にしたものであり、そうした社会のあり方こそが障害者に不利を強いている――と考えるのが「社会モデル」である。「障害があるから不便(差別される)」なのではなく、「障害とともに生きることを拒否する社会であるから不便」なのだ、と発想の転換を促すのである。
●なぜ社会モデルか
社会モデルは、さほど革新的な概念には見えない。社会に問題があるのは当然であり、今日よく聞かれる「バリアフリー」や「ノーマライゼーション」とどこが違うのか、と思われるかもしれない。だが「バリアフリー」という言葉の氾濫に比べて、多様な障害者にとって何がどう「バリア(障壁)」なのかに関心が高まっているだろうか。スロープのようなわかりやすいシンボルは別として、多くの障害者にとって切実なバリアは残ったままであるし、その理由も問われてはいない。また「ノーマライゼーション」のかけ声の一方で、なぜアブノーマルな生活を障害者が強いられてきたのかは必ずしも意識されていない。確かに「バリアフリー」や「ノーマライゼーション」は、社会モデルと重なる部分を持つが、そうでない部分もある。これらの概念は、現行社会の構成原理そのものを問うよりは、部分的改良で対処することを可とするものであるし、何より、社会モデルのように社会の全体像を捉えようとするものではないのだ。
社会モデルはものの捉え方を変える。例として「ろう者が講座に出たいが手話通訳がない」という状況を考えよう。「耳が聞こえないから参加できない」と考えるのが個人モデルであり、その場合、手話通訳の用意は「例外的、恩恵的な特別措置」となる。だが社会モデルではそもそも主催者が多様な参加者を想定していないことが問題なのだから、手話通訳は「本来、用意すべきこと」であり、ろう者が主催者にそれを求めるのは当然の権利だ。主張しづらいのが現実だが、「たった一人のために予算を使えない」といった多数派の論理に抵抗し、権利を求める根拠となるのが社会モデルなのである。
●社会モデルは別名「人権モデル」
社会モデルは「人権モデル」と言いかえられるほど、人権と親和性が高い概念である。当事者運動の過程で血肉化された社会モデルの考え方は、個々の障害者が直面する問題を、徹底して社会の文脈で捉える思想であり、運動における武器でもあった。駅の改良にせよ、
教育や就労をめぐる闘いにせよ、個人の努力や周囲の支援に頼るのではなく、社会の側の責任として解決すべきだと運動は主張してきたし、その認識を社会一般に広めようともしてきた。「社会モデル」という言葉を使わなくとも、日本で行われてきた障害当事者運動は社会モデルの視点を含んできた。障害者問題を人権の視点から捉えるならば、社会モデルは不可欠の視点なのである。(大阪府HPより)
219日目のイラスを、社会モデルとして考えてみると、だれの課題として捉えるかも重要になってきますね。
☆219日目(1.14)ちがいをどう説明するか?
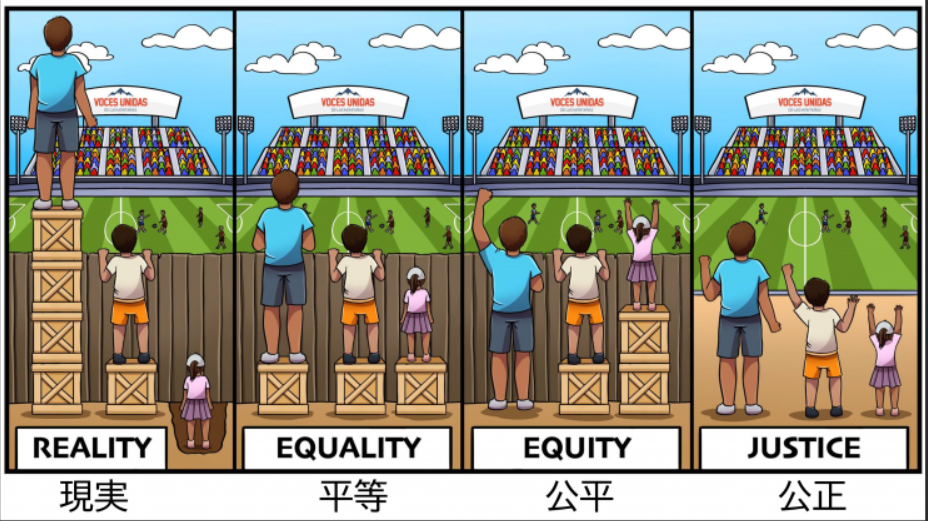
となりの席の先生と話題になりました。違いをどう説明しますかね。
☆218日目(1.10)子どもの姿・学び、実践からみる
全国人権・同和教育研究大会での分散会のまとめの一部に、働き方改革について少しだけ書きましたが、その続きです。知り合いが、先日テレビで、働き方改革の取り組んでいる学校のニュース報道を視聴したそうです。とても長時間労働の短縮を中心とした積極的な取組だったようですが、少し違和感というか物足りなさを感じたとのことです。その知り合いにいろいろと話をしてみると、岡山では、保護者に向けて、『働き方改革の目的 学校の働き方改革にご理解・ご協力をお願いします。』とし、続いて『この改革の目的は、学校のこれまでの働き方を見直し、教員の健康を守ることはもとより、教員が新しい知識や技能を学び続ける時間を確保し、自らの人間性や創造性を高めることで、子どもたちに対してより良い教育を提供することができるようにし、子どもたちの豊かな成長につなげることです』とあるのだから、長時間労働を短縮した具体的取組の紹介も必要だろうけど、その結果として、どのように授業研究・準備の質が高まり、仲間づくり(学級・学年経営)の内容が深まったかという実践をしっかりと示すことが大切だろう、とのこと。私はニュースを視てないので簡単には言えませんが、限られた番組の時間内で、「インパクトのある情報」としてニュース編集するには、時間が足りないこともわかりますが、この働き方改革の目的を鑑みると、「子どもたちはどう思っているのか」「子どもたちはどう変わったのか。」をじっくり聴いてみたいなあと思いました。
☆217日目(1.9)光あるうちに
先日、先輩から『光あるうちに―中世文化と部落問題を追って』横井 清著(阿吽社)を頂き、少しずつ読んでいます。読み応えがある本です。教育にかかわる者として、「謙虚」に、「誠実」に、「実直」に、あらためて部落問題に取り組まねばならないと思いました。(←抽象的ですが。)
阿吽社のHPでの本の紹介です。・・・〈ひたすらに内なる心音の伝え来る差別意識の波長に耳傾けてきた異色の中世史家が、ついにこの一書の中に佇み、中世文化・部落問題・故郷京都を取り結んで自らの軌跡を問う。〉
◆目次紹介
I 中世文化の探究
1 中世人と「やまい」
2 賤視と救済
3 「心理」と「時空」――『看聞日記』の世界
4 民衆文化の開花
II 部落史・部落差別への照射
5 部落史研究の到達点と課題(中世)
6 部落史研究と「私」
7 旅の人
8 私たちは、新鮮か――部落問題を富山県で考える
9 心理と思想の狭間から――藤田敬一著『同和はこわい考』を読む
別編 京都幻像――ある小宇宙
解題 中世文化と部落問題を追って
☆216日目(1.8)「かわいそう」?なんだかヘンな気持ち。
岡山シティミュージアムの特別展「ヨシタケシンスケ展かもしれない」に行ってきました。ヨシタケシンスケさん初の大規模個展となるそうです。作家の発想の源である小さなスケッチや絵本原画、展示会のためにヨシタケさんが考案した立体物や愛蔵のコレクションなどが展示され、作家の「頭のなか」がのぞけるそうで、〈発想の豊かさに支えられたヨシタケさんの「かもしれない」展示空間を、ぜひご体感ください。〉とありました。気になる展示がたくさんある中で、これもじっくいろんな人と語り合ってみたいなあと思ったのは『みえるとか みえないとか』という絵本です。持っている本なのですが、展示されているヨシタケさんのメモ・スケッチと併せて読んでみたら・・・。
この作品は、伊藤亜紗さんが光文社から2015年に出版した『目の見えない人は世界をどう見ているのか』をきっかけに、ヨシタケシンスケさんが伊藤さんに「そうだん」しながらつくった絵本です。本の紹介文はこうあります。
〈同じところを探しながら 違うところをお互いにおもしろがればいいんだね ぼくは宇宙飛行士。調査のために降り立ったのは、なんと目が3つあるひとの星。ぼくは普通にしているだけなのに、「うしろが見えないなんて不便そう」「かわいそう」って言われて、なんだかヘンな気持ち。そこで、目の見えない人に話しかけてみる。目の見えない人が「見る」世界は、ぼくとは大きく違っていた!(2018年7月発売/アリス館)〉
11月の読み語り(読み聞かせ)で選べばよかったかも。
☆215日目(1.7)新年を仲間と迎えること。
終業式の学級活動に、教室に入る機会がありました。通知表を渡す時間のウラで、子どもたちは、カードづくり(年賀・クリスマス)に取り組みました。自分自身の新年の抱負と、仲間へのメッセージと共にイラストを添えて、一人ひとりがステキなカードを作成しました。教室の窓に掲示して、お互いの見合っていました。冬休みの宿題(ワークブック)をコツコツと個々でするのもよいけれど、「この時間」に、「ここに居る仲間たち」と「共有できる活動」のなんとすばらしいことよ。そういえば、夏休み前の終業式では、暑中見舞い作成もできますね。仲間との意識が高まり、表現力の一助と。

☆214日目(12.24)聞き合う・話し合う、学び合う場を。
Si quid me fuerit humanitus‚ ut teneatis Quintus Ennius‚『Annaies』
今年11月29日~12月1日に参加した、全国人権・同和教育研究大会でのまとめ(総括)の一部です。
協力者として感じたことや考えたことを、皆さんといくつか共有したいと思います。
大会前に事前に送られてきたレポートを読む中で、「もっと聞きたい」ということがたくさんありました。この2日間の分散会の中で、しっかりと「聞き」「話す」ことがとても大事だということを再認識することができました。
2つめに、水俣事件で活動された川本輝夫さんは、「情熱とは、事あるごとに自分の意思を表明することである。」という言葉を残されています。私もこの言葉を大事にしていますが、本分散会の4本の報告では、「自分がどんな意思を持って取り組んでいるのか」、「私たちが大事にしていくことは何なのか」がしっかりと示されていたように思います。
「語ること」が、二日間を通して話題になりました。「しんどいことをいつまで語り続けなければならないのか」という大事な発言を受けとめながら、私は「語っていただきたい」と思っています。それは、語っていただいた事を、「聞いた」私たちの方がどう受けとめるのかということが大切ではないかと考えるからです。私の住んでいる地域でも、ハンセン病問題学習に取り組んでいて、回復者のお話を聴く学習を大切にしていますが、お話しをして下さる方が少なくなっている状況があります。ある時に回復者の方のお話しを聴く学習会を開催したら、先輩が「あなたは、どんな目的で話を聴こうとしているのか?あなたは、何を伝えたいのか、何を問いたいのか、自分がなぜハンセン病問題にかかわり続けるのか、そこを明確にしないと、被差別の立場の当事者を利用しているだけではないのか」と指摘されました。その出来事は、もう一度「自分の立ち位置をはっきりさせなくてはいけない」ということに気づかせてくれました。「語る」方の、思いや願いを受けとめる私自身の問題なのです。今日、討議の中にあった、〈「語り」を聴き、それを「返していく」やりとり(つながり)〉を、私も会場の皆さんと共に、大切にしていきたいと思います。
最後もう一つは、分散会の協議の中では出ませんでしたが、いわゆる「働き方改革」が学校現場ではすごい流れで進んでいます。しかし、子どもとの時間を創ることを目的としているはずなのに、時間外在校時間を短縮することが目的化しているのではないかと感じることがあります。その中で、先輩たち、私たちが培ってきた同和教育を基軸とした人権教育実践も形骸化が進んでいるようにも思えるのです。今年の進路保障分科会に参加する前に、30年前、全同教が出版した『学校同和教育実践講座LUMIERE 進路保障の課題と実践(1993 解放出版社)』を再読し、その本に実践報告が掲載されている先輩に会って「進路保障」についていろいろと話を聞きました。その話の中で、「今の働き方改革の中で、私たちが本来すべき大切なしごとをどんどん減らしているのではないか?」とたずねたら、「目の前に転んで足を擦りむいている子どもがいたら、ほっとけないだろう。絆創膏を貼ったり、頭をよしよししたりせん(しないと)と!。子どもたちの最前線にいるのは自分たちである。それをせずして、何のための学校なのか、何のための教員なのか。働き方改革はそこを抜きに考えたらおえまあ(いけない)」と言われました。そんな話を重ねながら、この2日間の分散会で再確認することができました。目の前の子どもたちのその最前線に居る覚悟というか、明日からも「やっていかないといけない」と思っています。また来年会いましょう。
☆213日目(12.23)語らせるのか?語るのか?
ファシリテートについてちょっと話題になりました。その意見の中のひとつ。「ファシリテーターは、語り手の話すことを、自分の進めたい方向に誘導する側面があるのではないか?」という内容についてどう考えますか?偶然に、映画『スープとイデオロギー』監督ヤンヨンヒ:2021年製作/118分/G/韓国・日本合作)を視聴しました。映画評でもありませんし、ネタバレではありませんが、その中で、監督として撮影しながら、娘であるヤンヨンヒが、母に「済州4.3事件」を〈語らせようとする〉ようにうつりました。その後監督(娘)は、母と共に、済州島に渡り、再度、事件のことを想いださせようと問いかけていくのですが、だんだんと話をしなくなる母親。そして〈何も語らない〉母の姿からとても大切なことに気がつき、娘として自分自身が語るシーンと、本題が重なりました。(抽象的な内容でごめんなさい。視聴してみてください。事前に『ディア・ピョンヤン』も)
参考:作品紹介:「ディア・ピョンヤン」などで自身の家族と北朝鮮の関係を描いてきた在日コリアン2世のヤン ヨンヒ監督が、韓国現代史最大のタブーとされる「済州4・3事件」を体験した母を主役に撮りあげたドキュメンタリー。朝鮮総連の熱心な活動家だったヤン監督の両親は、1970年代に「帰国事業」で3人の息子たちを北朝鮮へ送り出した。父の他界後も借金をしてまで息子たちへの仕送りを続ける母を、ヤン監督は心の中で責めてきた。年老いた母は、心の奥深くに秘めていた1948年の済州島での壮絶な体験について、初めて娘であるヤン監督に語り始める。アルツハイマー病の母から消えゆく記憶をすくいとるべく、ヤン監督は母を済州島へ連れて行くことを決意する。
☆212日目(12.20)子どもどうしをつなぐファシリテーションって。
「ファシリテーター」について聴かれました。以前、森田ゆりさんの『多様性トレーニングガイド』をもとにした、ファシリテーター養成講座の受講はとても貴重な体験で、以後の自分自身の授業づくりやワークショップや研修会などの基盤となっています。
facilitate=「促進することを容易にする」という意味で、主役である「参加者」が話し合いや会議などの参加型の場において,「何かをする」ことを促進したり,やりやすくするための手法です。(捉えようはたくさんあります)2000年代から拡がった参加型学習は、①自ら“主体的に参加”して,“体験”から学ぶ②“お互いから”学び合う③参加者自身の多様な経験が学習資源となることが特徴です。そして参加型学習は、現代的課題解決へのアプローチ、 “学び方”を学ぶ(“何を学ぶか”より“どのように学ぶか”を重視)、当事者意識を育むことができる学習スタイルのひとつです。私は会の進行をしながら以下のことも意識しています。
○本気で聴く傾聴(非言語メッセージ:身体・表情・視線・声や口調・姿勢,動作・距離感)
・参加者の多様性をありのまま,そのまま受けとめる
・うなずき,あいづち(聞いてもらっているという安心感)
・「聞いていますよ」というメッセージを伝えることが大切 「なるほど」,「○○さんはそう思うんですね」
○会をつくるための問いかけ
・開かれた質問(オープンクエスチョン)→ 広げ深める
・閉じられた質問(クローズドクエスチョン)→ 絞り込む
・問いかけ,待って,引き出す(プル)
・圧力(プッシュ)をかけて,促進する
☆211日目(12.19)子どもどうしをつなぐコトバは?
田村学芸員さんと大学生をお招きし、ハンセン病問題学習で取り組んでいる〈今〉、「どんなことを考えたのか?学んだか?」をクラスの中で意見交流を行う授業を行いました。子どもたちが仲間の意見に「重ね」ながら、自分の意見を語り、そこからまた、自分の考えが深まっていくことが出来ればよいなあと、ファシリテーションの意識をもって授業進行を心がけましたが、授業が終わってみれば、やはり、反省点がいっぱいありました。
先日読んだ『部落解放11月号 子ども・教育 自由ノート「128授業中の「禁句」』の園田雅春さんの文章をもう一度読み返しています。一部を紹介します。『・・・子どもAの発言を、「なるほど」と教師が先取りすれば、その授業場面は教師と子どもA、両者に限定された一対一の閉ざされた関係で終わってしまう。そもそも、子どもAは教師だけを相手に発言したのだろうか。もし、そうなら『みんなに対して発言してよ』とばかりに促すのが教師の役割ではないのか。それもせずに教師がAの発言をまっ先にキャッチし、「なるほど」と子どもたちに先んじて応答。これは横取り的な行為に当たらないか。「なるほど。」この一言は、Aの意見に納得する子どもや、肯定した子どもが自ら発する言葉なのだ。納得したことを子どもBが自分の言葉で発言。それを聴いた子どもCが補足したり、新たな自分の意見を表明したりする。このように子どもたちが主体的に展開する授業の「起点」を大切にしたい。学年があがるにつれて、教師からよりも、仲間からの「なるほど」に始まる応答の方が、よろこびが増すことも確かだ。子どもの自主的な発言が続かないために教師が「他にありませんか」と促す場面もよくある。しかし、「なるほど」「他に」という言葉は、子どもどうしの意見の連続性を断つ「切断語」。そう自覚し、教師の「禁句」としたい。』
人権教育実践の中で、「子どもどうしをつなげる」とはよく語られますが、日々の授業の中でどれだけ意識できているか・・・。校内でも議論したいと思います。

写真はハンセン病問題学習での田村さんからの提起
☆210日目(12.18)当事者研究となかまづくり
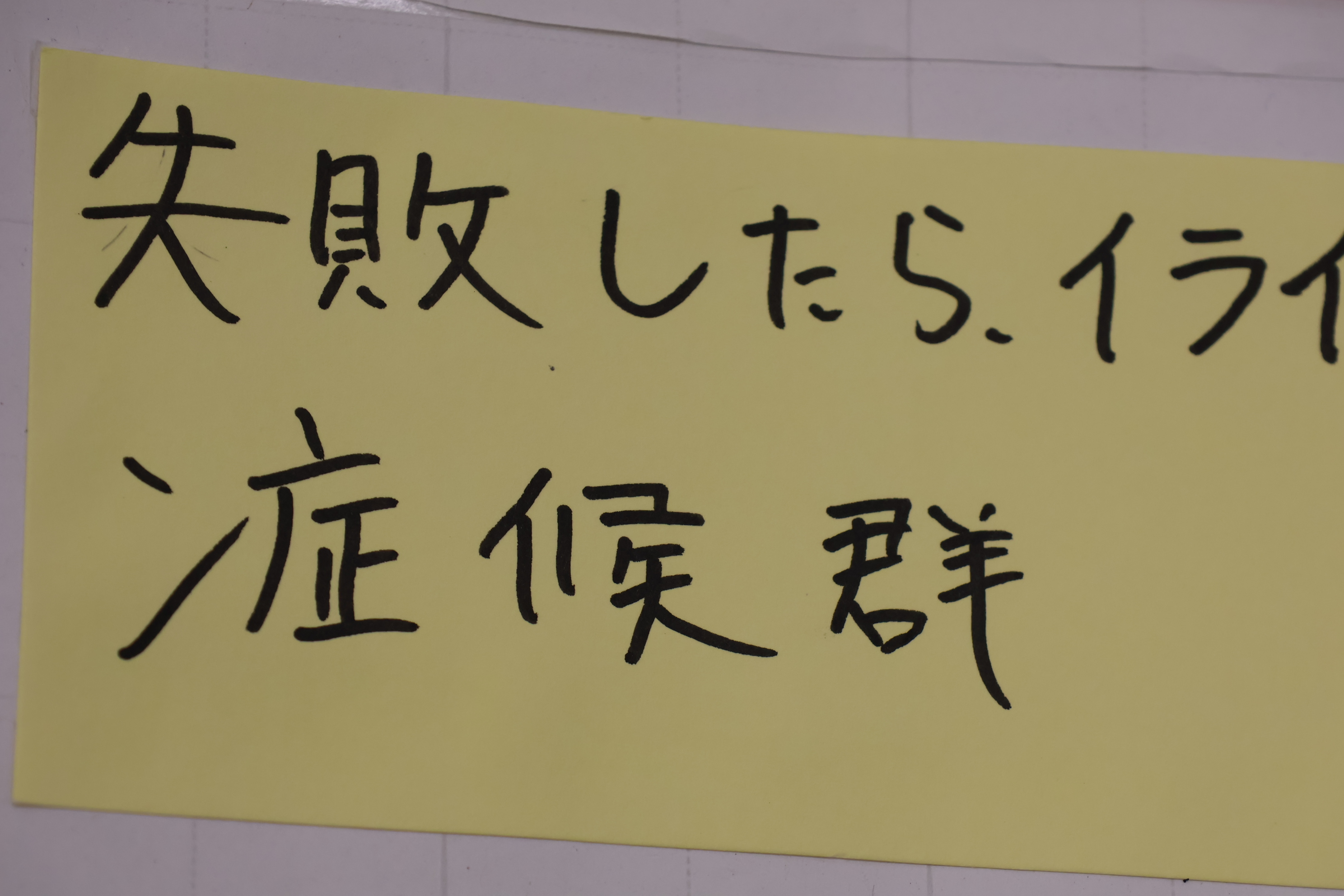
一年生全員が、それぞれの特性(ニガテ、くせ、持ち味)について、クラスメートに伝え、自分自身の付き合い方を話し、またクラスの仲間からのアドバイスを受けました。これは、べてるの家の当事者研究と、同和教育実践の仲間づくりを重ねたものです。
当事者研究については、『自分を助ける方法としての「当事者研究」とは(TOKYO人権 第97号(令和5年2月28日発行)』を、ご参考に転載します。
―「自分自身で、ともに」で社会とつながる
自らの生きづらさにアプローチする方法として、近年、「当事者研究※1」が注目を浴びています。「自分の苦労の研究者になってみる」というアイデアで、2001年に精神障害などを経験した当事者の自助活動の一つとして生まれました。現在では、病気や障害だけでなく、引きこもり、子育てなど幅広い分野で実践が広がり、2022年3月には『子ども当事者研究』として出版されるなど、子どもたちも取り組めるような内容として咀嚼(そしゃく)されてきました。「当事者研究」の魅力などについて、社会福祉法人浦河べてるの家※2理事でソーシャルワーカーの向谷地 生良(むかいやち・いくよし)さんにお話を伺いました。
自分ごととしての研究
当事者研究は、病気が原因で「爆発」を繰り返す青年に、向谷地さんが「一緒に研究してみない?」と提案したところから始まりました。以来、共通の悩みを抱えた人が、経験を共有しながら「自分の助け方」を見出す方法として全国で運用されてきました。困り事を研究対象として一旦自分から切り離して捉え、家族や仲間たちと語らいながら対処法を探るというスタイルが特徴で、実験感覚でワクワク感を持って取り組めることが魅力といわれています。
例えば、こんなエピソードがあります。自罰傾向が強く発作的に顔面を叩いてしまう人が浦河にやってきました。その人は、発作のたびに病院を受診して鎮静剤を打っていました。浦河に来て間もなく発作が起きたとき、そこにいた仲間が一緒に「発作の止め方」についてワイワイと研究をはじめ、一人のメンバーがその人の脇腹をくすぐると本人が大笑いして、発作が止まりました。その人は、「今まで専門家に任せきりにしていたけれど、自分のことだったんだ」と気づいたそうです。お互いに助け合い、新しい発見をし合う中で、自分の苦労を自分ごととして取り戻す、そんな作用を生む試みとして、当事者研究は知られるようになりました。
困難さは社会とつながっている
「自分自身で、ともに」をキーワードとする当事者研究には他に、「他者を助ける」という重要な作用があります。現在、困難を抱えていない人たちが、困難な状況を生きてきた人たちから学べることは大きいと向谷地さんは指摘します。「精神障害がある人たちの困難さと、一見何事もないように暮らしている人たちの日常は、つながっています。メンタルヘルスの危機というのは、個人的にたまたま不調になったというわけではありません。周囲や地域の事情とも関連していて、社会環境的に生み出されている部分があります。閉鎖された病棟の中で治療されるよりは、その人たちが発信することによって、多くの人にとって、回復の手がかりを得ることができます。社会の側が学ぶ、気づいていける部分がとても大きいのです」。
「人」と「出来事」を分けて考える
もう一つ、人権を考える上での重要な視点を、当事者研究に垣間見ることができます。「当事者研究では、『人』と『出来事』を分けて考える工夫をします。そうすることで、どんな問題や困難が起きても、その人が問題ではなく『問題が問題なのだ』と捉えることが可能になります。何か失敗したとき、自分自身を『ダメな人間だ』と思い込んだり、問題を起こした人を『問題な人』にすり替えて考えたりなど、人と問題を同一視する思考に陥りがちです。人間の存在価値は、本来、失敗や成功、問題の大小によって損なわれるものではありません。当事者研究で、多くの人たちと現実を共有することによって、その現実を生きている人たちをみんなで応援しようという社会の空気をつくっていく作業ができるようになったと思います」と向谷地さんは語ります。
「人づくり」「地域づくり」の可能性
実践の中でお互いの「弱さ」や「苦労」を持ち寄ることで、人と人が繋がり、その場に信頼と助け合いが生まれます。「当事者研究には『自分のことだけれども、みんなのことだ』という、共同性のような土俵をつくる力があります。対話を通じた『人づくり』であり『地域づくり』の活動の一つにもなる」と向谷地さんは考えています。
「当事者研究にマニュアルはない」と向谷地さん。「大切なのは、『ちょっと研究してみようかな』という思考を持ちながら暮らし、その考察を共有すること。一人で抱え込まないで、みんなで助け合って知恵を出し合い、身近なところで生かしていく。そうすることで、地域も社会も元気になるのでは」と呼びかけています。
・向谷地 生良(むかいやち・いくよし)
・インタビュー・執筆 吉田 加奈子(東京都人権啓発センター専門員)
※1 参考になる情報:向谷地さん執筆の『レッツ!当事者研究』(べてるしあわせ研究所)のほか、メンタルヘルスマガジン『こころの元気+』で毎月、べてるの家の当事者研究を紹介しています。
たくさん本も医学書院さんから出ています。べてるの家には、〈三度の飯よりミーティング〉というコトバがあります。
☆209日目(12.17)「聴き取り」からの進路学習のススメ
学習所見を考えてみましたら。
・所見案1『「職業調べ」の学習では、●●の仕事について調査活動を行った。とくに仕事内容や必要
な資格、中学校卒業後の進路などについて調べた内容を取捨選択し、わかりやすくレポートにまとめることができた。これらの活動を通して、自分の将来について深く考えようとする意識を高めることができた。』
・所見案2『「身近な人からの聴き取り」では、親から若い頃から働いてきた仕事の苦労や、生きがい、そして親の進路に対する願いを聴き取ることができた。親の思いをしっかり受け取り、自分のこれまでの生活を見つめ直し、進路実現に向けての大きな指針となった。また、聴いた内容をまとめ、クラスで発表したことは、級友同士の理解がさらに深まると共に、進路を切り拓いていく学級の意識が高まった。クラスメートからの質問に応えたり、意見交流をしたりする姿は、確かな学びに裏打ちされた自信にあふれ、とても堂々としていた。』・・・これは所見ではないな。添削だらけの予想。
☆208日目(12.16)ハンセン病問題学習をどう進めるか 一考③
●まとめにむけて【準備】
*個人テーマの決定&分担テーマの分担(パネル説明書の分担)・これまでの学習をもとに ・「正しく知る 正しく行動する」を受けて
●【⑤⑥時間目】 「過去・現在・未来」をつなぐ学習内容を地域社会へ発信する
・学習してきたことをもとに、歴史的場所・施設の学習写真展示パネルの説明文をつくる
・掲示・啓発活動を日生中学校3年生として取り組む
・1月中旬→日生地域公民館、本校廊下へ掲示〔保護者・後輩へ) 表現/発信
・写真パネルは岡山県人権教育研究協議会から、啓発パネル「麦ばあの島」は邑久光明園から借りる
●【本学習以後の取組(調整中)】
○保護者(親子)希望者向けの長島現地研修〈東備まなぶ会主催など〉
○就職差別の撤廃の取り組みにつなげて「統一応募用紙の成立」についての学習
○3月卒業時の個人答辞づくり→代表の卒業生答辞づくり
○進路公開へ
☆207日目(12.13)ハンセン病問題学習をどう進めるか 一考②
~学ぶこと、考えること、そして生きること~
◎【4時間目】過去・現在・未来につなぐ 12月13日(金)⑥14:45~15:35
(1)めざしたいこと
・「未来へつなぐ」とはどういうことか?具体化できるようにする
・「これまでの自分の生き方・課題」を見つめて(重ねて)考え、語る
・個人モデルではなく、社会モデル(社会のありよう)の視座で考える
・「差別をなくそうとする主体者」としての立ち位置をつくる
・「人はなぜ差別するのか」を自分のコトバでまとまる
(2)エリアティチャー(AT) ・長島愛生園 田村学芸員さん ・岡山大学 学生4名 桑原さん
(3)授業のながれ(授業者(ファシリテーション))
テーマの共有『ハンセン病問題学習から何を学び、何を伝えていきたい(どう生きていく)?』(2分)
○AT紹介(3分)
○田村さんから提起
『ハンセン病問題にかかわって~君たちと共に、そして託したいこと(仮』【約15分】
・愛生園の「事実」から「課題」を知る ・未来へつなげるとは?必要性は?!・何を学び、何ができる? ・どんな社会をつくるか
○質疑応答(田村さんの提起をさらに深く理解するために *質疑の質も高める)
□生徒からの質問と田村さんの応答→場合によっては他の学習者にも聞く事アリ
□学生からのモデル質問と重ねて *関連質問 *これまでの自分の生き方に重ねる思考 *社会モデルの視座で【5分】
○討議・意見交流【20分】
□『自分はハンセン病問題学習から何を考えたか?何を学んだか?』について
・中学生の意見を中心に、大学生の学び(生き方)に関する意見を挟む
・生き方や具体的な活動に言及している発言者の意見を聞き、中学生がさらに学びを深めさせたい。
○まとめ
□田村さんから 大学生1名~2名) 今日の授業のまとめ
○日生中学校3年生へメッセージ【5分】
○授業終わり(あいさつ)
(3)留意点
○桑原先生と学生さんに、授業内容へのご意見をいただき、共通理解をお願いしたい
○中学生は本学習後に、展示の取組をします。その文書の中に「学び(伝えたいことやどう生きるか)」をまとめます。現時点では学習の途
中段階です。
☆206日目(12.12)ハンセン病問題学習で何をどう学んでいくか 一考①
先週末にフィールドワークに出かけた子どもたちは、今週、田村学芸員さんと、岡山大学で教職を学ぶ学生さんらをお招きして、意見交流学習を行います。〈過去・現在・未来をつなげる〉と私たちは簡単に言ってしまいますが、これまで学習したことを整理しながらカタチのある学びにしていかなければならないなあと思っています。
具体的な学習案(概略)
【社会科】公民分野「基本的人権の尊重」
【1時間目】
Q小学校での学習やニュースで知っていることや覚えていることはどんなことか?をもとに
・人はなぜ差別するのか(なぜ差別されたのかでなない視座で)・ハンセン病学習ではなく、ハンセン病問題学習として
・義務教育最終年度…人権を大切にできる人間として シチズンシップ(市民性)高めたいね。
・岡山(東備地域)からの発信者として
・資料・ワークシート配付、リーフレット『ハンセン病の向こう側』活用
QDVD『人間回復の橋、こころのかけ橋となれ』視聴学習【29分】
・ワークシートの6つの質問で復習(基礎的な学習)【10分】→まとめ【5分】
・素朴な質問や疑問に応えていく。関心をもって学んでいくことを具現化
・人間の思考(そう簡単ではない「自分事としてとらえること」へ!社会の在り方・自分の生き方と重なる授業の組み立てに)
Q次回・ナガシマで生きた「ひと」、金泰九さんから考えてみよう
【2時間目】〈授業のながれ GT久次同伴〉
Q前時の授業での疑問や質問をもとに
Qドキュメンタリー映画『虎ハ眠ラズ』視聴学習【43分版・30分版】振り返りの時間を確保する
Q金泰九さんに小感想を書く
・深くさらに学ぶために(疑問やさらなる問い)
【3時間目】長島愛生園現地研修(岡山県ハンセン病療養所入所者地域交流事業補助申請可 本校は備前市スクールバスの活用)
・学年PTA人権教育研修会と位置づけて、希望があれば保護者の参加も促す。風邪、インフルエンザ等の流行に留意
〈予定・調整〉12月6日(金)9:55中学校発~12:45中学校着
…FW(3年団 生徒)& 歴史館見学学習
・10:25~12:00フィールドワーク
・12:00~12:20歴史館見学(ワークシートとバインダー持参)
・12:20愛生園発 12:45中学校着→給食準備
☆205日目(12.11)生徒指導と人権教育
他校での人権教育実践を教えてもらいました。例えば、「教室のものを誤って壊した」時にどんな指導をするか?ということ。昨今は、個人への指導や注意で終わる場合が多いのでないでしょうか。その学校では、起こった出来事を、集団(クラス)にかえすことが出来るか(必要性があるか)?を考えて、多くの場合、クラスの問題として捉え、きちんと子どもから子どもへ話す(当事者がクラスの仲間に報告する)営みを大事にしているとのこと。あたりまえの視点だと思いますが、古い教育実践のようで、いま、必要な新しい教育実践だと思います。特別支援教育の「個々」の支援はもちろんですが、「クラス全体」への思考は、益々重要となっていますね。
☆204日目(12.10)人権週間にあたって②~世界人権デー
続きです。
(4)個人の尊厳を守る
個人の尊厳を守るということは、自分を大切にするのと同じように、他人を大切にし、人を傷つけないことだね。
ひとの性格や行動、顔や身体のかたち、学校の成績などによって差別してはいけないね。もちろんその人の家の職業や出身や宗教、考え方、男女の性別、民族などによって人を差別してはいけないのはわかるよね。就職や結婚の際にそのことで差別することは許されないね。
以上のことをまとめていうと、『人間が人間らしく生きていくうえで、欠かすことのできない自由や権利のことを〈基本的人権〉というんだ。基本的人権が大事で、他のひとの人権を侵す差別がいけないことだということは、君たちはわかっているはず。
でも
「差別がなくなればいい」と考えているだけでは見当違いです。いくら差別が悪いことだとわかっていても、それだけで「差別をなくす力」にはならないからです。
みんなが安心して登校し、静かにゆったりした気持ちで勉強し、遊び、そしてスポーツや生徒会活動にうちこめるようにみんなで努力し合うことが、身近な人権尊重の一歩となります。
(5)江戸時代の末(1855)にあった『渋染一揆』に学ぶ
つい先日、2年生が社会科で学習した「渋染一揆」。この一揆を成功させた人々のうごきを調べてみると、私たちが差別をなくし、共に生きる社会(クラス)をつくるための方法を知ることができます。簡単にまとめていますが、とても大事な視点です。人権週間にあたってみなさんに紹介します。
①差別がここに、こんなかたちであるという事実に気がつくこと!(高い人権感覚)
②その差別はどれほど私たちを苦しめているか、怒りをおぼえること!
(相手の立場に立って、そのつらい気持ちをかんがえてみること)(正しい人権意識)
③その差別のなりたちや、しくみがどうなっているかを学び、差別をなくする道筋を明らかにすること!
(仲間としっかり語り合う 冷静に状況を分析する)
④差別をなくするために、なかまと共に、どういう働きかけをしたらよいか、差別をなくする力(行動力)を身につけること!
(みんなで正しく行動する うごかす(すべ)を整える)
☆203日目(12.9)障害者の日ということですが
角岡伸彦さんの著書『カニは横に歩く 自立障害者たちの半世紀』を紹介します。
行動するCPたちの痛快・青春ノンフィクション! 「カニって横に歩いてるやん。誰も不思議に思わへんやん。障害者が健全者と違う歩き方をしてるのは当たり前のことちゃうの」行動するCPたちの痛快・青春ノンフィクション!「カニって横に歩いてるやん。誰も不思議に思わへんやん。障害者が健全者と違う歩き方をしてるのは当たり前のことちゃうの」1977年、川崎市でバスジャック事件を起こして、それまで顧みられなかった障害者のバス乗車に一石を投じた過激な障害者運動団体。それが「青い芝の会」である。著者の角岡伸彦氏は、ときに介助者として、またときには取材者として、過去27年間「青い芝」と深く長く対面してきた。本書の内容は、あまりにもひどい差別、どう考えてもやりすぎの闘争、真剣だけどユーモアを忘れない爆笑エピソードなど。障害があること。老いること。本書は「あるがままの生」という遠大なテーマに挑んだ本格ノンフィクションである。
●本文から「なんかの集会の時にね、福永が俺に『黙れ、健全者!』と言いよったんや。俺は言い返した。『お前、それはやめた方がええで。黙れ健全者言うんやったらな、健全者の方は黙れ障害者と言うで。君、それ反対できひんで。何々を言った健全者は黙れというのは、まだわかる。けど、健全者だから黙れというのは、そんなものはどこへ行っても通用せえへんで』」(第2章 宣言)仲間の自殺を知った関西青い芝は、緊急役員会を開いた。「私たちを殺す施設に用はない」、「なんちゅうこっちゃ、そんな施設(和歌山県立身体障害者福祉センター)はつぶさなあかん」。所長は「暴力障害者!」と叫び、所長室に鍵をかけたまま閉じこもってしまった。(第4章 炎)その頃、福永の活動を追いかけていたNHK大阪放送局が、阪神障害者解放センターと市側の交渉を映している。(『負けたらあかんでぇーー阪神大震災・ある障害者の闘い』九五年八月八日放映)。西宮市助役に対し、福永は声を上げた。「いっこもわかってないやんか! あんたら全然考えてないやんか! ちゃんと脳みそを働かせ、脳みそを!」(第9章 揺れ)
【著者略歴】角岡伸彦(かどおか・のぶひこ)1963年、兵庫県生まれ。関西学院大学社会学部卒。神戸新聞記者などを経てフリーに。著書に『被差別部落の青春』(講談社文庫)、『ホルモン奉行』(新潮文庫)、『はじめての部落問題』(文春新書)、『とことん!部落問題』(講談社)などがある。
☆202日目(12.6)人権週間にあたって①
もちろん、日々の生活の中での人権を意識した教育の営みが必要ですが、この週間にあらためて、子どもたちと話し合うことも大切だと思います。
 2024人権週間にあたって~歩み新たに日に生せば~
2024人権週間にあたって~歩み新たに日に生せば~(1)1948年12月10日
フランスのパリで開かれた国際連合総会において、第二次世界大戦の悲惨な結果を反省し、人権尊重が世界における自由・正義・平和の基礎であるとの『世界人権宣言』が採択されました。この宣言は「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」という人間の尊さを基本に、人間らしい暮らしをしていくための権利を宣言しています。
1950年の第5回国連総会で、毎年12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」として世界中で記念行事を行うことが決議されました。それを記念して、12月10日に至る1週間(12月4日から12月10日まで)が人権週間となっています。
日生中学校でもこの時期を中心に、「いじめや他人を傷つける言動がないか。友だちとともに、自分らしい生活をおくることができているか。」について考え、3日の全校朝礼では、「ありがとう」「ごめんなさい」など、より人とのかかわりを大切にしようと、話し合いました。
1年生は、備前市自立支援協議会の椙原さん・森下さん、小寺スクールソーシャルワーカーをお招きして、自分自身の特性を理解すると同時に、「自分研究」をもとに「クラスで暮らす仲間」をお互いが理解し合う学習に取り組みました。2年生は、職場体験学習の取組に重ねて、NPO法人きずなの川元さんをお招きして、社会モデルとしての「ホームレス問題」について学び、勤労観や福祉、社会のありようについて深く考えることができました。3年生は、ハンセン病回復者である金泰九さんの生き方を視聴学習し、明日6日には、長島愛生園フィールドワークで、「自分たちが生きるこれからの社会をどのように創っていくか」について探求していきます。12日には、長島愛生園の田村学芸員さんをお招きし、シチズンシップ(市民性)の意識を高める学習を進めます。
(2)あらためて大切にしたいこと。「いじめ」は人権侵害
ある友達と口をきかない、無視する、一緒に遊ばない、筆箱をかくす、机に落書きをする、カバンをかくす、などという「いじめ」の話は、テレビやインターネットで、残念ながら今も聞きます。
「いじめ」をする人たちが言う理由として「あいつはうざい」とか「背が低い」「女、男のようだ」「うっとうしい」「どんくさい」など聞くにたえない理由をあげるのです。
学校のなかまが、動作が遅かろうが丸顔であろうが、それはその人の「個性」「ちがい」「持ち味」なのです。個性に干渉して、自分に合わせようとしたり、いじめたりすることは、なかまの〈人権〉を侵すことなのです。いじめるほうが、わがままで自分勝手で他人の人権がどれほど大切なものであるのかがわかっていないのです。「いじめ」は許すことのできない人権侵害の事件なのです。
(3)クラスの中の人権侵害
私たちの身近な人権とはどんなものがあるかな。
ひとには個性があるね。育ってきた家庭のちがい、男・女、LGBTQ+、生年月日、顔、身体がそれぞれ違うように、ひとは、それぞれ違った性格をもっている。考え方も感じ方もちがってくるね。すばやい動きのひともいれば、ゆっくりなひともいるし、ほがらかで友達とよく話ができるひともあれば、その反対で無口なひともいるね。それらのちがったひとたちの集まっているのが私たちの「社会」というわけ。それは学校でもクラスの中でも同じだね。
大切なことはそれら他の人・なかまの「ちがい」を認め合うことじゃないかな。ちがった性格やちがった生き方をするひとが、自分らしく、みんなと共に遊んだり、話し合ったり、喜びや悲しみを分かち合ってたりしていけたら。このことを〈人としての自由権〉と言うんだよ。もちろん、自由ということは、自分がわがままで勝手なこととはちがうよ。みんながそれぞれの自由を尊重しあうと同時に、学校やクラスではみんなが安心して遊んだり、勉強したりするために最低のきまりや規則が必要になってくるね。きまりや規則というのはみんなの自由を守るためにあるといえるんじゃないかな。
ひととしての自由権を守るためには、お互いの生き方やちがいを認めるだけでなく、積極的に尊重していく〈個人の尊厳〉を守るという強いものが必要だね。
みんなは安心して学校に登校し、自分の進路の実現に向かって学習できるという〈生存権〉をもっています。また一人ひとりがもっている「勉強する権利」を〈学習権〉と言うんだ。授業中に自分勝手にさわいだり、友達の発言をひやかしたり、ものを投げたりするのは、みんなの学習権を侵害することなんだ。
☆201日目(12.5)話し合うこと⑥

第75回全国人権・同和教育研究大会に参加して。
参加した分散会では、熊本・京都・大阪・福岡からの4本の報告をもとに、2日間、のべ8時間の研究協議を行いました。紙面での内容だけはわからない、子どもと教職員らと日々の営みや、うまくまとまらない願いや思いを丁寧に聴くことで、「実践」の内容が立ち上がってきます。さらに参加者自身の実践を重ねて語る発言には「事実」がみえてきます。 どんな「話し合い」にしたいのか?、「語る」ってことをどのように進めていくのか?に悩んでいる私にとっては、3日間の司会団の経験は大切な糧となりました。最終日、総括討論のまとめの中で、私は、水俣事件で取り組んでおられた故川本輝男さんの「情熱とは事あるごとに意思を表明すること」というコトバを紹介しました。話すこと・語る時には、「意思」が要りますなあ。
☆200日目(12.4)過去・現在・未来をつなぐハンセン病問題学習
三年団の先生方と授業研究と授業準備をおこないました。今年度の計画を進めていきます。
☆199日目(12.3)ひなせ親の会と重ねて
大阪の大先輩、土田光子さんのコトバを思い出しました。『授業規律とは、一人ひとりが大切にされ、気にかけられているという信頼や、わからないことは支援の対象になっても、決して笑われることではないという安心と協働の文化を育む日々の学級経営を前提として、さらに授業そのものの工夫によって、結果として生まれるものであって、決してルールやしつけだけで成立するものではない。』
☆198日目(12.2)人権教育の創造~コロナ禍を振り返って
フィールドワークで話した内容(徳田弁護士が書かれた内容)について、聞かれることが結構あったので、少しだけ紹介(p364~)します。詳細は『感染症と差別』をぜひお読みください。
☆197日目(11.29)現実から学ぶ
26日に、備前市教育研修所 学校運営部会と学校事務部会が合同で研修会を開催しました。岡山県備前県民局建設部東備地域管理課 中務課長を講師にお招きして、危機管理について見識を深めました。中務さんは、本校の避難訓練での講評や、社会科での授業でのアドバーザーとして来校され、リアルな現実をもとにしたアドバイスや指導・助言をしてくださいました。この日も、安全対策について、紙面だけの対策や、正論・理想だけの思考ではだめなことを改めて考えることができました。

今月末(11/30・12/1)は、全国人権・同和教育研究大会が開かれます。会のスローガンの冒頭には「差別の現実から深く学び・・・」とあります。子どもの現実を見つめ、課題や真実を見抜ける人権感覚を、不断に磨いていかねばなりません。
☆196日目(11.28)話し合うこと⑤
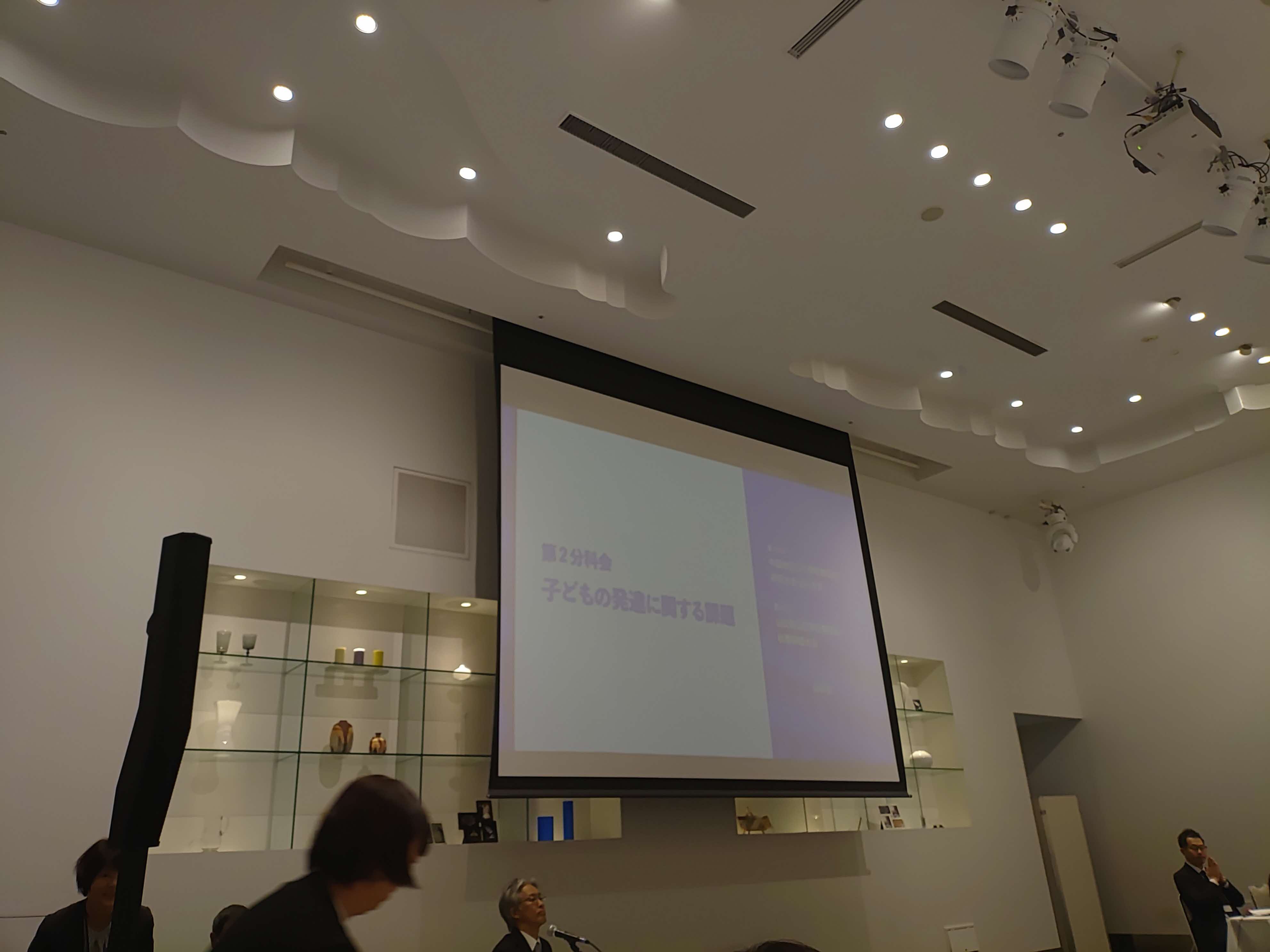
第44回中国地区公立学校教頭会研究大会(山口大会)があり、参加してきました。午後からは、「子どもの発達に関わる取組」の関する第2分科会で研究協議をおこないました。私のグループの中では、山口の先生から、生徒がとても少ない学校(さらに小中一貫校スタイル)で、地域協働活動を進めていく中で、子どもたちの関係が、学校の場だけでなく、地域社会や様々な人々と関わる場の中で、豊かになってきたことを聞きました。それは、本校でも進めている地域との協働活動の正しさを確信し、「またがんばっていこう!」と思えました。有意義に「話し合う」ことを、どのように会の中で設定(ファシテテート)していくか、大事ですねぇ。
☆195日目(11.27)話し合うこと④

縁あって、岡山の養護教諭の方々のフィールドワークのお手伝いをしました。長年に渡るハンセン病問題の反省を、教訓にしなければならない私たちですが、「コロナ禍で、どんなことが起こしてしまったか?」を、検証しなければならないと思います。そのことについて徳田弁護士が著書に書かれていたこと(①感染者・家族、医療従事者をウイルスを広げる悪者と見なしたこと。(旅客船の感染者への対応を私たちはどう見ていたか) ②感染したことは自己責任・自業自得だと考えたこと。(学校・施設などでも謝罪会見がありました。) ③多くの国民が自分や家族は感染しないと考えていたこと。(感染した人の立場に立つことができなかった。これは救らい思想での、「感染者を救う」という良いことをしている私たちを、感染者も「ありがたいと思っている」だろうと考えに通じる) ④差別や排除をしているコトを正義と信じたこと。(無らい県運動で積極的に報告をしたのは学校の先生でした)を、フィールドワークでも紹介しました。それに応えて、なんと!参加者の皆さんからは養護教諭の立場から本当にたくさんのお話を聴くことができたか。話し合う(語り合う)ことは、自分の視野をさらに拡げますね。お互いに語り合う時間を大事にしたいと思います。
☆194日目(11.26)話し合うこと③
今月末(11/31~12/1)は、全国人権・同和教育(全人教)研究大会が、熊本・福岡・鹿児島を会場に開催されます。私は、縁あって、進路保障をテーマにした分科会・分散会の進行のお手伝いをします。全国からの実践レポートをもとに2日間、様々な意見(事実と実践)を交わしながら研究協議をしていきます。学びを深めていく「研究協議」に向けて、今一度「進路保障」とは何か?を整理して、レポートを繰り返し読んで、会の進行準備を進めていきます。
「進路・学力保障」について ~ 子どもたちの未来を拓く進路・学力保障をどう進めているか(全人教の資料より)
私たちは、「進路保障は同和教育の総和である」ととらえてきました。進路保障は、単に進路を決定することではなく、子どもたちが、差別を許さず差別に負けない力、なかまとともに未来を切り拓いていく力などを獲得するための道すじや機会を保障する取組です。 その重要な柱として、学力保障の取組を進めてきました。学力保障では、子どもたちが自分自身を深く見つめること、「学ぶことの意義を実感しながら」学習や生活に意欲を持つこと、自己表現力を高めること、自尊感情を育むこと、自分の生き方を豊かに創りあげていくことをめざしてきました。そのためには子どもたちが多様な進路や生き方を選択できる力を身につけることをめざした授業や学校づくりに取り組むことが大切です。そうした取組を創る中で教職員自らが子どものくらしの現実や保護者の思いから学び、差別との関係や自分との関係を問うことが大切です。部落の子どもたちや障害のある子どもたち、在日外国人の子どもたちなど、被差別の子どもたちを中心に就学保障や就労保障に取り組んできました。その取組を、経済情勢悪化や貧困層の固定化などによって、被差別の子どもたちをはじめ特に厳しい状況におかれている子どもたちの進路保障の取組に普遍化させていくことが求められます。そして、地域や家庭と連携し、保・幼・こども園・小・中・高の一貫した取組の中で、生きて働く力や
その道すじを明らかにし、追求していきましょう。
一 被差別の子どもたちの進路をめぐる現実やその背景をとおして、私たちの課題を具体的に明らかにしよう。
二 「低学力傾向」「いじめ」「不登校」などの現実をみすえ、保・幼・こども園・小・中・高を通じて、子どもたちが生き生きと学び生活していくための授業や学校づくりを追求しよう。
三 すべての子どもたちが、学校や地域での活動をとおして、反差別の価値観でつながりあい、なかまとともに自らの生活・進路をどう切り拓いているかを明らかにしよう。
四 「統一応募用紙」制定の意義に深く学び、その趣旨の徹底とその精神をあらゆる場においてどのように具現化してきたかを明らかにしよう。
五 進路保障の態勢を確立していくために、被差別の子どもたちの現状を明らかにし、あるべき奨学金制度をめざすとともに、「権利としての奨学金」の学習を交流・討議しよう。
☆193日目(11.25)話し合うこと②
(引き続き)私たちの教職員の研修会では、ペアで協議することはあまりないですが、3~4人程度のグループで意見交流をすることがよくあります。(2000年初頭に人権ワークショップという学習スタイルや、協同学習のスタイルが拡がったのも理由のひとつかもしれません。)当たり前のように、いつものように、いろんな研修会でグループ協議をしていくのですが、自分自身、そのグループでの協議をする中での「深まりや気づき」が弱くなった気がしています。これはわたし自身の問題意識の低さや、積極的な姿勢の弱さなど私の課題だとは思いますが。同時に、もうひとつ、多い人数で協議するスタイルがとても減っているような気がします。「多人数では、意見がでないから、少人数のグループをつくって話す(意見交流だけ)」ことを続けていった結果、〈全員で侃々諤々とお互いの意見を語り合い、「目的」に向け意見を集約していき、みんなでひとつの結論を出して、実践していくことにつなげる協議スタイル〉が出来なくなっているのではないか??と考えたりしています。
この日(11/26)、私は、中国地区公立学校教頭会研究大会(山口)に参加します。分科会での協議に参加し、機会があれば、子ども学び方や私たちの学び方なぞも他の参加者とも一緒に考えてられてらいいなあと思っています。
☆192日目(11.22)話し合うこと①
授業や研修会でも、「近くの人と少し話をしてみてください」というスタイルが多いですね。私も、今週行った本校での「中学生認知症サポーター養成講座」でも前述のスタイルを用いて生徒らに「近くの人と話すことを」の促進したのですが、授業後の反省会で「ペア(複数人)になれず、一人だけの生徒がいた」ことが指摘され、思慮が足りず、みなければならない子どもたちを視てなかったと猛省しました。まだまだ「話し合い」に入ることが苦手な生徒らを含めて、話し合うペアやグループや明確に指示するべきだったと思います。そして、わいわいと話しができている全体の雰囲気をみるのではなく、ペアになれきれない子はいないかをみて、ペアリングの支援をするべきでした。そして、その上で、そのペアでの「学び」が成立しているか?を看取れねばなりませんね。話している・しゃべっている=学んでるではありませんものね。

☆190日目(11. 21)必要なことは何だ?
最近、特別支援教育の推進の中で、保護者や地域が求めていることは何だろう?課題は何だろう?そこから学習会や研修会を企画していかなければならないなあと、感じることが増えてきました。一方的な内容になっていないか、主体者不在ではないか?目的は何なのか。先に確実に進むために、ひなせ親の会の内容を今回このようなカタチにしました。一歩ずつ。
☆189日目(11. 20)金泰九さんと歩く
愛生園でのフィールドワーク(FW)のお手伝いをさせていただくことがありますが、金さんにくっついて廻った時に話されていた中身をもとにしています。大らかな人柄と穏やかな語り口が醸しだす何とも言えぬ柔らかさ、そして確かな人権感覚と行動力に引きつけられ、何度もFWとその後の学習会をご一緒させてもらいました。金さんになりかわって語ることは出来ませんが、自分自身が金さんに教えられたことや、学んだことは、生徒たちにしっかりと伝え続けなければならないと思っています。
今年も、生徒たちと、金さん(パネルと一緒に)と、12月6日は園内を廻り・学びます。
☆188日目(11. 19)ハンセン病の学習ではなく、ハンセン病問題学習を。
今年度も地域学習と連携させて、三年生はハンセン病問題学習に取り組みます。
三年生は、社会科公民分野において、日本国憲法の基本である「基本的人権の尊重」について学習しており、さらに具体的な姿として「ハンセン病問題」を取り上げ、正しく理解することは、生徒自身が暮らす県民として重要・不可欠であろうと考えます。また、義務教育最終年度にあたることも鑑み、中学校というフィールドから、「自らの学び」を社会・世界的視野に拡げていけるように、現地研修では、長島愛生園の歴史や、世界遺産登録推進のうごきを体感してきます。
言うに及ばず、私たちは、「ハンセン病について」の正しい知識習得だけではなく、「ハンセン病問題」に取り組んでいきます。ハンセン病問題とは、近代以降の国の間違ったハンセン病対策が原因で、患者、回復者およびその家族の方々の人権が侵害され、はなはだしい偏見差別にさらされた人権問題です。ハンセン病問題学習を通して、私たちの生きていくこれからの社会を主体的に創っていくという自覚(シチズンシップ)を高めたいと思います。
☆187日目(11. 18)
11/16・17に、第3回金泰九さんに学び教育実践交流会が開催されました。会の資料の一部と新聞記事を添付します。

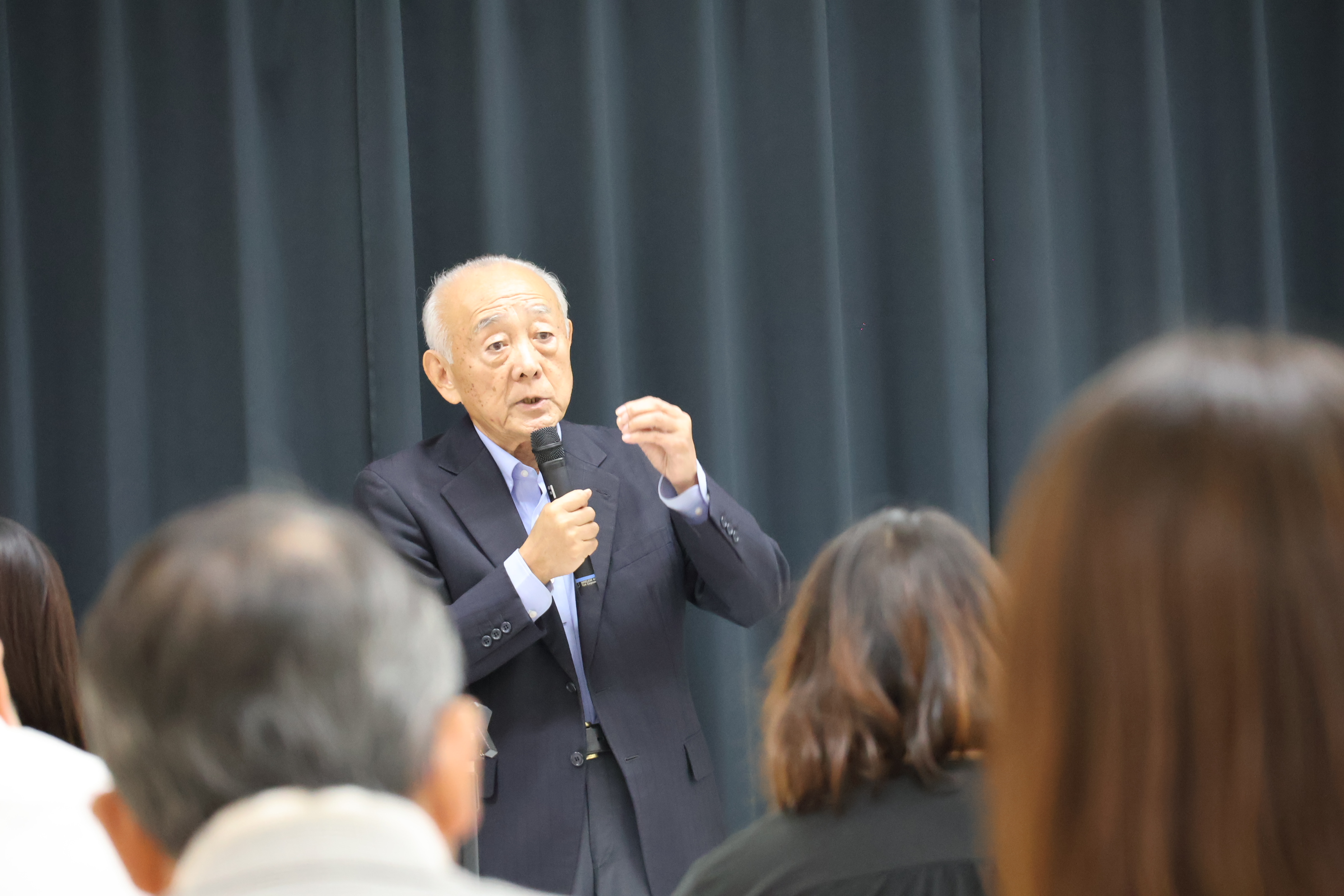
☆186日目(11.15)ハンセン病問題学習の内容について
多くの学校で実践が行われていますが、長年取り組んで大事にしたいなあと思っていることは、「ひと」との出会いを通してのハンセン病問題の学習です。毎年、子どもたちが出会っているのは、キムテグさん(金泰九)です。
金さんは1926年現在の韓国陜川(ハプチョン)生まれ、12歳で父を頼って日本に渡って来られました。1945年旧陸軍兵器学校卒業直前に日本の敗戦で復員します。1949年旧大阪市立商科大学(現大阪公立大学)在学中に発病し、1952年に強制隔離され、約60年間の大半を長島愛生園で暮らされました。原告に先頭となって加わった国賠訴訟は2001年、熊本地裁が国の強制隔離政策を違憲と判断し、勝訴します。その後は戦時中、日本の統治下で強制隔離政策が行われた韓国・台湾の元患者の補償問題も支援されました。2007年にまとめた自伝『我が八十歳に乾杯~在日朝鮮人ハンセン病回復者として生きた~』(牧歌舎)には金さんの生き様の一部が書かれています。『…人権侵害のらい予防法を廃止するにおいて、法廃止に消極的態度をとっていた私は自分を恥じるのである。その理由なるものは、「功利的」な考えでしかなかったからである。それ以来私は「人権を」全てに優先して考えるようになった。「自他ともの人権を」である。全ての事象が人権と関わっている気もするのである。その場合、人権を最優先にして考えてみると、ことに理非が明瞭にみえてくる気がするのである。』
すごい人でしょう。でも、実は、残念ながら9年前に亡くなられました。だから今、子どもたちが出会っているのは『虎ハ眠ラズ』というDVDの中の金さんです。
私は、これまでの授業の中で、ハンセン病に対する国の施策の問題や、裁判の経緯、療養所の歴史的施設の説明など、あれもこれも内容に入れて、授業者としての自分の立ち位置があやふやな時期もありました。が、今は一緒によりよい社会をつくるために学び続ける者の一人として?「ひとの生き方」からハンセン病問題を考えることを続けています。
DVD『虎ハ眠ラズ』の中の金さんとの出会いに、子どもたちは、毎年それぞれ違う反応を示します。そこから、その学年独自のハンセン病問題学習を進めていくこととなります。
声を聴く取組を。
(現在は、どの療養所の入所者(回復者)の方々が高齢となられ、直接お話しを聴く機会が難しくなりましたが、多くの入所者の方々の声が本や記録、証言集に残されています。私はもっともっと読まねばならないと痛感しています。合わせてそれをもとにした「ひと」を通してのハンセン病問題学習の内容をつくりたいと思っています。(一緒につくりませんか?))
明日、11月16日(土)第3回金泰九さんに学ぶ教育実践交流会があります。また追悼の集いでは、万霊山での納骨堂でのお参りができます。
☆185日目(11. 14)背景を知る2
一見分かりやすい文言なので、「多様性 個性重視」に集約されがちです。(インターネット上には侃々諤々、様々なご意見が多々ありますね)
以前、参加した人権学習会では、この詩を一人ひとりが鑑賞(解釈)し、意見交流をしましたが、その後、金子さんの歩んでこられた生き様(よう)や大正時代の女性の立ち位置や家族のありようを学習した上で、あらためて詩を読み返すと、詩の中の言葉の意味が深く迫ってくる体験をしました。それから、金子さんの「大漁」「星とたんぽぽ」など、他の詩を読んでみると以前とはまったく違う感想をもつことにもなりました。
鑑賞の授業でもそうですが、人権教育が大切にしている、人の背景(本当の思いや願い)を理解しようとする豊かな体験を日々の教育課程の中にきちんと組み込んでいきたいものです。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』を参考に、彼女の生きてきた時代や、生い立ち、家族のことを学んでから、再度詩を読み返してみたいと思います。
○金子テル1903年4月11日生まれ 山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)1930年3月10日(26歳没)
金子 みすゞ(かねこ みすず、本名:金子 テル〈かねこ テル〉、1903年〈明治36年〉4月11日 - 1930年〈昭和5年〉3月10日)は、大正時代末期から昭和時代初期にかけて活躍した日本の童謡詩人。約500編の詩を遺した。没後半世紀はほぼ忘却されていたが、1980年代以降に脚光を浴び、再評価が進んだ西條八十に激賞された幻の童謡詩人とされている。遺稿集が発掘され、出版(1984年)、深く優しい世界観が広く知られた。代表作に「私と小鳥と鈴と」「大漁」など。
○生涯
山口県大津郡仙崎村(現:長門市仙崎)の生まれ。郡立深川高等女学校(現:山口県立大津緑洋高等学校)卒業。みすゞの母の妹の嫁ぎ先である下関の書店兼文房具店「上山文英堂」の清国の営口支店長だった父は、1906年(明治39年)2月10日、みすゞが3歳のときに清国で不慮の死[注 1]を遂げる。実弟は文藝春秋社の編集者や喜劇王・古川ロッパの脚本家などとして活躍し、子役の名門であった劇団若草の創始者である上山雅輔(本名:上山正祐)であるが、幼くして母の妹(みすゞにとっては叔母)の嫁ぎ先である上山家に養子に出されている。父の死後、母・祖母・兄とみすゞは仙崎ただ一つの本屋である「金子文英堂」を営んだ。みすゞは読書家で成績優秀、大津高等女学校を総代で卒業するほどだったが、教師の「卒業後は奈良女子高等師範へ進学し、教師になったら」という勧めを断ってのことだったという[3]。叔母の死後、実弟正祐の養父とみすゞの母が再婚したため、みすゞも下関に移り住む。
1923年(大正12年)、「金子みすゞ」というペンネームで童謡を書き始め、雑誌『童話』『婦人倶楽部』『婦人画報』『金の星』 に投稿した。この年、これら 4 誌全ての 9 月号にみすゞの投稿した 5 編の作品が一斉に掲載された。以降みすゞは次々と作品を投稿。雑誌『童話』を中心に 90 編 の作品を発表する。『童話』においては、推薦 16 編、入選 24 編、佳作 2 編の計 42 編が 掲載された。最後にみすゞが投稿し掲載された作品は『愛誦』1929年(昭和4年)5月号の「夕顔」である。1923年(大正12年)『婦人画報』9月号に掲載された「おとむらひ」は、翌年『現代抒情小曲選集』(西條八十編)におさめられた。1926年(大正15年)には、みすゞは「童謡詩人会」への入会をみとめられ、童謡詩人会編「日本童謡集」1926年版に「お魚」と「大漁」の詩が載った。童謡詩人会の会員は西條八十、泉鏡花、北原白秋、島崎藤村、野口雨情、三木露風、若山牧水など。女性では与謝野晶子と金子みすヾの二人だけだった。
1926年(大正15年)に叔父(義父)の経営する上山文英堂の番頭格で、芝居好きで酒は飲めないものの女癖の悪い宮本啓喜と結婚し、娘を1人もうける。しかし、夫はみすゞの実弟である正祐との不仲から、次第に叔父に冷遇されるようになり、女性問題を原因に上山文英堂を追われることとなる。みすゞは夫に従い、その後は子どもを連れて下関を転々とする。自暴自棄になった夫の放蕩は収まらず、後ろめたさからか、みすゞに詩の投稿、詩人仲間との文通を禁じた。
1927年(昭和2年)西條八十編『日本童謡集(上級用)小学生全集第48巻』および1928年(昭和3年)光風館編輯所 著『作文新編 巻1』に「お魚」が収載される。1929年(昭和4年)東亜学芸協会 編『全日本詩集』には「繭とお墓」(『愛誦』1927年(昭和2年)1月号が初出)が載る。1929年(昭和4年)、みすゞは「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」と 題した3冊の童謡集を二組制作し西條八十と正祐(当時上山雅輔の名前で文藝春秋社の編集者をしていた)にそれぞれ託した。(現存するものは同年秋に正祐に送られたもので1925年と1926年の博文館のポケットダイアリーの書店用見本に書かれている。1冊目の「美しい町」と2冊目の「空のかあさま」は清書。3冊目の「さみしい王女」の詩には校正した跡がある)
1927年に夫からうつされた淋病を発病。1928年には夫から創作や手紙のやり取りを禁じられる。1929年頃には病状が悪化し床に臥せることが多くなる。1930年(昭和5年)、夫と別居し、3歳の娘を連れて上山文英堂へ戻る。同年2月に正式な離婚が決まった(手続き上は成立していない)。みすゞは、せめて娘を手元で育てたいと要求し、夫も一度は受け入れたが、すぐに考えを翻し、娘の親権を強硬に要求。同年3月9日、みすゞは近くの写真店に行って写真を撮り、娘をふろに入れた後、寝付いたのを見届けてから、夜の内に服毒自殺を遂げ[注 2]、享年28(数え年)、26年の短い生涯を閉じた[3]。上山雅輔は回想録「年記」に「芥川龍之介の自殺が決定的な要因となった」と書いている。 遺書を3通残しており、そのうちの1通は元夫へ向けた「あなたがふうちゃんをどうしても連れていきたいというのなら,それは仕方ありません。でも,あなたがふうちゃんに与えられるものはお金であって,心の糧ではありません。私はふうちゃんを心の豊かな子に育てたいのです。だから,母ミチにあずけてほしいのです」という娘の養育を母ミチに託すよう求めるものだった[4]。法名は釈妙春信尼[5]。娘はそのまま母ミチの下で育てられている[3]。
金子みすゞの死後1930年(昭和5年)に創刊された西條八十が主宰する『蠟人形』(5月創刊号)には、みすゞの「象」と「四つ辻」の二作が載せられた。また、翌年の1931年(昭和6年)、西條八十は『蝋人形』9月号にみすゞの「繭と墓」を再掲載し「下ノ關の一夜 ── 亡き金子みすゞの追憶」と題した追悼文を残している。西條八十は、さらに1935年(昭和10年)にも『少女倶楽部』8月号と9月号に みすゞが送った童謡集のうちより「たもと」「女王さま」をそれぞれ掲載。また、9月号の方には「繭と墓」を彼女と下関で出逢った思い出の随筆をまじえて再度掲載した。戦後も1949年(昭和24年)、『蠟人形』5・6月号に西條八十選で「人形の木」が、1953年(昭和28年)の『少女クラブ』6月号には「木」と「先生」が掲載された。
☆185日目(11.13)背景を知る
ちょっと前に、「授業づくり」について、授業改革推進員さんと話題になったのは、「作品や音楽の鑑賞の際、その作者の背景(時代や作者自身の歩んできた生き様(よう))を事前(事後)学習することは必要なのか?」ということでした。もちろん、授業のねらいを明確にしていく中で、事前(事後)学習の内容も考えなくてはなりませんが、鑑賞させる作品や音楽〈だけ〉との出会いは、どこまで子どもたちの学びを深くすることができるのだろうか?と思いました。また、事前学習において、その作者についてのどのような情報を提供するかも、授業者の感性(授業観)に負うところが大きいような気がします。よく学校でも教材化する金子みすゞさんの『私と小鳥と鈴と』という詩があります。あらためて、どのように鑑賞しますか?
私が両手をひろげても、
お空はちっとも飛べないが、
飛べる小鳥は私のように、
地面を速く走れない。
私がからだをゆすっても、
きれいな音は出ないけど、
あの鳴る鈴は私のように、
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私、
みんなちがって、みんないい。(次回へ続く)
☆184日目(11. 12)就職差別撤廃に向けた取組
3年生でハンセン病問題学習を行った後に、統一応募用紙の授業を進めたいと考えています。ハンセン病問題学習での学びが、「過去に大変なことがあった」とか、「差別しないように気をつけよう」と心がけや思いやりの涵養で終えないようにしたいと思います。もちろん、ハンセン病問題の解決に向けた様々な活動に取り組んできた人々の事実を学んでいきたいと思いますが、「願い」を「行動」で具現化していった「統一応募用紙」の成立経過を学ぶことは、人権を尊重する社会の実現のため、仲間と団結して行動する実践力を育む一助となります。
☆183日目(11. 11)就職差別撤廃に向けた取組
「面接報告書は、面接での質問内容をまとめ、後輩たちの面接対策のためだと思っていました。」と、話を聞いたり、「尊敬する人は誰ですか?と、なぜ質問するのはいけないのですか?」と尋ねられたことがあります。(残年ながら最近のことです。)また、「離職した子どもの事業所に課題があっても、高校側が把握し、申し入れ等の対応が弱い(ない)ようなこともある」とお母さんが語ってくれました。若い世代の先生方と共に、就職差別撤廃に向けた取組(たたかい)を学び直し、今現在の進路保障の取組を一層確かなものにしなければならないと思います。第75回全国人権・同和教育研究大会での報告レポートをもとに、それぞれのこれからの実践を研いていける場(分散会)になるように、準備を進めていきます。
☆182日目(11. 8)仲間って
「よくないことをしている友達に注意することができないといけない」「荒れは、自分が弱いからだ。自己責任だ」と、とても昔に、生活指導の場で聞いたことがあるフレーズですが、注意したり、監視したり(おおげさかも)する関係性は少し違うような気がします。「がんばり合える」というのか、お互いを解り合いながら、高め合うというのかな、うーん、うまく言えません。教育実践の一部を紹介します。ささえる合える仲間づくり(続ける)
☆181日目(11. 7)仲間づくりの中身
仲間づくり、集団づくり、人間関係づくり、学習集団づくり・・・たくさんの学級経営につながるキーワードがありますが、職場で、「仲間づくり」の思想を確かめ、共通認識・共通理解したいと思います。(続く)
☆180日目(11. 6)進路指導から進路保障へ
取り組みの中で、具体的な取り組みとしての、3つの柱(続く)
☆179日目(11.5)進路を保障する教育内容や学力とは何か
第75回全国同和教育・人権教育研究大会が今月末に九州で開催されます。縁あって実践報告協力者として、第3分科会(進路保障)での1分散会に参加します。そのために分散会でのレポート原稿をしっかり読み込んでいっているところです。
そんな折り、職場で進路保障や進路指導の意味や意義について話題になりました。ちょっと「進路保障」について、『リュミエール』学校同和教育実践講座11巻 進路保障の課題と実践(1993年学校同和教育実践講座刊行委員会編集)の本を引っ張り出してみました。30年前に著された内容を読み返しながら、今現在の課題に向けた解決や実践のありようを確認したいと思います。
進路保障とは単なる「進路先」の保障でなく、、、。(続く)
☆178日目(11. 1)「発達」特性について学ぶ、「クラスで暮らす」の学習案(ワークシート)
☆177日目(10.31)「発達」特性について学ぶ、「クラスで暮らす」の学習案
☆176日目(10.30)「ホームレス問題学習」の学習案(ワークシート)
☆175日目(10.29)「ホームレス問題学習」の学習案
☆174日目(10.28)「ホームレス問題学習」から考えること
打ち合わせメールより
おはようございます。授業日が近くなってきました。今年度は、私も一緒に授業の進行をさせていただきます。担任の先生と準備をしていますが、授業(きずなさんとで学んでいく方向性がまだ決まり切っていません。
双方向でのやりとりのひとつは、「ホームレス問題」についての素朴な質問や疑問についての、AT(エリアティチャー)さんとの対話が中心になるとおもうのですが、明日、事前学習(授業)の2回目をします。内容は教材DVDを使って、とくに「子ども夜廻り」に取り組んでる子どもたちの内容を中心にします。
2つめは、◎人と本気でかかわろとうする大切さ(しっかりと相手を理解しようとすること、本当に分かろうとすること)についてアプローチができたらと考えています。
それはなぜかというと、学級の中でお互いの関係性がよくなくて人間関係のトラブルがいくらかあり、一つの課題でした。そんな中で、昨年のこの時期に、東田直樹さんのDVDも活用し、「発達」にかかわるATの方々に来ていただいた授業の中で、自分の発達の特性、でこぼこ(自分の持っている特性・クセ・タイプとして、「発達障がい」という語句は使わず。)をお互いに知り合おう・理解しようという学習に授業で取り組みました。その学びの中で子どもたちはお互いを理解しようとする集団に変わっていったような気がします。そして今年度さらに、子ども同士が、相手を理解しながら、厳しく(優しく)迫ったり、励まし合ったり、ガンバリ合える関係性を持つクラスにできたらなあと思っています。
3つめは、この学習が終えて、子どもたちは4日間の職場体験学習へ行くのですが、職業感や勤労観について深まったらと思います。「助けて」とあたりまえに言える社会、共生の有り様を具現化していけたらとも考えています(そんなによくばりはできませんが)
本授業だけでそんな思考や構築できるわけはありませんが、学校での日々のアプローチも含め、この機会にATさんからのお話を大いに聴きたいと思うのです。子どもたちの質問に重ねる私の補助質問をいくつか挙げます。(いま現在です。月曜には変わるかもしれません。また連絡させていただきます)
授業の流れを含めて
①本授業のテーマの確認「ホームレス問題にかかわる川元さんとの質疑応答で、学びをふかめる」進行
②自己紹介(AT)
③質疑応答に向けて「提起」(AT)←いつも思いますが、けっこう、難しいですね
・きずなでの活動 ・(生徒たちに知ってほしいこと)基本的なことや
・課題 ・岡山状況や課題
④グループで質問を考えて、ホワイトボードで提示
⑤多くの質問からチョイス、質問内容を構成
・質疑応答の中で久次が重ねたいと思っていること
○「ホームレス問題」は私たちとどう関係しているか? ○政治や社会との関係性・きずなの役割 ○(「子ども夜廻り」から、)川元さんが取り組んでいるのは、どんな思いからなのか?○人を理解するには(声かけをする時に意識していること)○行政や福祉につなげる・支援するときに意識していること
○川元さんの思っている仕事観・勤労観、・ホームレス問題についての、世間や社会の偏見や差別意識に対して ○自分と違う、「ひと」をわかろうとすること
○「クラス」で「暮らす」にはどうするか?
⑥日生中学校2年生へメッセージ
⑦終わり
☆173日目(10.25)語り合うクラスへ、
前回の「聴き取り課題」のワークシート案です。
☆172日目(10.24)語り合うクラスへ、聴き合いたくなる課題を
構成的グループエンカウンターを、意図的・計画的にこれまでも活用してきましたが、いきつくところは、子ども自身が「背負っている生活」からの生の思いや願いの声を語り合う、聴き合うクラスの営みであろう。身近な(親)からの《仕事の聴き取り》と《聴き取りからの学びや思い》をまとめた《クラス報告》が出来たらいいなあ。
☆171日目(10.23)50年前の事実と願いから
趙博(チョウバク)さん(67)が創作した一人芝居「ヒロシマの母子像―四國五郎と弟・直登」の公演後、偶然に古本市で『原爆三十年 広島県の戦後史』を見つけて、やっと読み終えました。本のあとがきには「広島県は、被爆三〇周年にあたり、記念事業としていくつかの企画をもちました。その一つに、原爆問題を広島県の戦後の歴史の中に正しく位置づけ、二度と過ちをくり返さないことを願って、本書の刊行を計画しました。」とありました。発行は、昭和51年(1976年)。そしていま、2024年となり、戦後80年目を迎えようとしています。本書、第Ⅷ章 未来への志向の一部をもう一度読んでみます。
参照 趙博さんの芝居について再掲(*平和のための創作を続けた四國五郎(1924~2014年)の生き様をもとに構成された一人芝居です。四國が描いた広島の風景や反戦画を投影したスクリーンをバックに、詩や日記からの抜粋などを織り交ぜて公演されます。そして「あなたの隣にヒロシマの子はいませんか?」と私たちに問います。戦争への怒りと憎しみが生前の詩画人を創作に駆り立てた力だったことが伝わってきます。)
☆170日目(10.22)「なぜ」「どうして」なのかを考える
「なぜ、ウソをつく?」「そもそも、ウソなのか?」「なぜ、ウソをつかねばならないのか」そんなことを自問自答していたここ一週間が過ぎている。そんな時、10月20日山陽新聞9面、上間陽子さんの『論考2024』を読んだ。・・・やっぱり、「はなそう」「きこう」
☆169日目(10.21)「進路指導」について
19日、パブリック友の会第6回「&のつどい」に、岡山御津高校の末廣先生と共に、高校進学・進路についての「アドバイザー」役としてお手伝いをさせていただきました。本会の講演会(パネルディスカッション)は150名もの方が参加され、『障がいのある本人と家族の税・相続について』がテーマに、税理士、弁護士、社会保険労務士さんらのお話に熱心に耳を傾けておられました。講演会後に、精華学園や希望高校などの先生らの個別相談と同時進行で、保護者やお子さんから進路・進学についてのお話を聴かせていただきました。
会に参加して、あらためて「進路指導」について自分自身が考えさせられました。
・入学(受験学力を重視した)するだけの進路指導に向かっていないか。
・生徒の特性を深く、正しく、知ろうとしているか。
・保護者との本音・本気の連携ができる関係を築こうとしているか。保護者の願いや思いに寄り添った支援活動を行えているか。
・日々、新しくなっている、多様な進路(高校進学)の情報を更新しようとしているか?また、それを適正に生徒・保護者に提供できているか。
・高校間格差を助長するような進路指導をしていないか。
・進路、自己実現に向けた、中学校の授業や自立活動の中身は精選しているか。
・・・うーん。簡単に答(応)られそうにありませんが、身を引き締めて、今日もガンバロウ!と思います。
☆168日目(10.18)今だからこそ「しごと」の聴き取り
「見つめる」とは「自己洞察」である。自己の内面を見つめるだけでなく、他者との関係や社会との関係における自分の存在を見つめていくことである。
「語る」とは「自己開示」である。「語りたい」としたときに、ありのままの自分、赤裸々な自分を他者に伝える行為である。
「つながる」とは「人間関係づくり」である。日常の人間関係の中で、一人ひとりの「友だちになりたい」という気持ちを出し合い、より相手のことを知っていくことで、人間関係の絆を深めることである。地域の人々や親、人生のモデルとなるような他者、等の「語 り」を聞いて共感するなかで、自分の生活の現実や気持ちを見つめます。その気持ちを「語りたい」「分かってほしい」と欲したときに、自己を受容してくれる相手に語ります。「自分の気持ちを言えてすっきりした。」「みんなに分かってもらえてうれしかった。」という安心感は、強い自己肯定感に結びつきます。また、自己開示をし、自分を「語る」過程で新しい自分に気づき、自己洞察が一層深まります。「語ること」は、自己と他者の「つながり」を深めます。葛藤 や悩みを相互に「語る」機会が与えられることで、子どもたちは初めて信頼にもとづく人間関係を創出していくことができます。こうした日常の人間関係づくりのなかで、子どもたちは自己と他者との間のトラブルに対して問題解決能力をつけ、自他ともに対する信頼感を培っていくのです。同和教育は、単に部落問題をどう教えるかということだけでなく、「自分の生活を見つめ、語 り、仲間とつながること」を一貫して追求してきたのです。
(【参考文献】◇『子どもの心がひらく人権教育』松下一世著 解放出版社)
しごとや高校を調べ、発表する活動がありますが、その前後にやっぱり、親(身近なひと)からの「聴き取り」に取り組みたいと思う。夢や希望だけで、今の仕事に携わっているひとばかりはない。たくさんの「思い」や、子どもに対する強い「願い」をもちながら働いているひとから、学びとる「聴き取り」を進めたい。そして、聞き取った内容をもとに、自分がどう感じたか合わせて「語り」、クラスの中で、お互いの考えやを深く知る仲間として、「つながり」合うクラスの営みは、前述の松下さんが言われるような力や信頼感を培っていきます。
インターネットや本だけでの「しごと」「高校」調べを越えよう。
☆167日目(10.17)学習したことをふりかえる一考(続き②)
生徒が取り組んだ「顕著は普遍的価値の言明」を紹介します。顕著な普遍的価値とは、「その遺産の文化的意義が国境を越えるほど顕著であり、今日及び次世代のすべての人類にとって共通に重要であること」です。
◆タケミさん
『私が「ハンセン病問題」学習について考えたことは主に二つ。「国家の間違い」、「差別の意義」。「国家の間違い」、それは「らい予防法」を確立させたことだと私は考える。法律になれば全員逆らえない、全員が「らいは伝染病だ」と信じてしまう。もし、この法律がなければ尊い人権も、一生離れなかったであろう人々も守れていたはずだ。間違った偏見も差別も根強く残らなかったはずだ。次に「差別の意義」。このハンセン病においての差別は実に「無用」。家族との縁を切る、名前を捨てる、自由を奪われる。このような人権侵害の理由が「日本の見栄、世間体を守るため」。その程度で潰れる世間体ならたかが知れている。もっと早くハンセン病についての研究をすれば解決しただろう。後で思っても遅い。後悔はできるが事実を変えることはできない。これからの社会にも私たちにも言えることだ。その後悔の事実と、国家の罪の象徴・証拠がナガシマだと私は強く考えている。
したがって、ナガシマは顕著な普遍的な価値を持っている。』
◆ヒロミさん
『長島愛生園に行き、自分で見て、普通の島だなと思った。家が点々とし、普通の島にみえるが、収容桟橋→収容所→監房→納骨堂→恵の鐘→歴史館を見てまわり、暗い歴史が見えた。
収容桟橋では「ここから、すべてが始まったんだな」と思った。今は崩れて、もう外に出て行っていいよって呼びかけているように安心した。収容所では、実際に中に入ってベッドやお風呂を見たりして寒い雰囲気だった。皆で入っても間が空くぐらい広く、お風呂は狭かった。ここでDVDで見た消毒をかけられたり、検査されたりしたんだなと実感した。
監房はDVDにも出てきていなく、初めて見た。大きく、中に一人で入ると寂しいなと思った。納骨堂はこれまで見た中で、一番きれいで、白かった。何千人以上の人が家族にさようならを言えないまま亡くなって、しかも家族の元や、自分の居場所がないことを目の当たりにする切なさに心が痛んだ。
恵の鐘は唯一、患者さんの希望や怒りが見えた場所。そこからの眺めは良く、昔はどのように映っていたのかが気になった。
実際に長島愛生園に行き、分かったことや感じたことが多く、DVDでは語られなかったことが聞けて良かった。偏見や差別はだめだと分かっていても、やってしまう人間なのでその考えをどう変えていくかが大切だと改めて思った。ハンセン病の偏見は今ではもう少なくなってきているかもしれないが、自分の普通を貫くのではなく、違う角度や方向から見て、新しい考えをもっていきたいということを私は皆に伝えたい。したがって、ナガシマは顕著な普遍的な価値を持っている。』
☆161日目(10.16)学習したことをふりかえる一考(続き)
「感想」、「まとめ」だけでなく、様々な学習のふりかえりのスタイルを持っておきたいなあと思う。実践例として、ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会さんと連携して学習した際に、「顕著な普遍的価値の言明」の取組があります。
療養所が世界遺産として登録されるためには遺産(建物、構築物、土地、景観)に必要な「顕著な普遍的価値(Outstanding Universal Value)」を作成する必要があります。顕著は普遍的価値とは、「その遺産の文化的意義が国境を越えるほど顕著であり、今日及び次世代のすべての人類にとって共通に重要であること」をいいます。それを作成することを、「学習したことのふりかえり」のひとつにしました。
学習活動⑤【「今」ハンセン病問題に取り組むひとに出会う】
NPO法人ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会事務局長釜井大資さんをお招きして
・釜井さんからポスターを使ったワークショップ
◎釜井さんから生徒へ《顕著な普遍的価値の言明(A4)生徒版》の課題を提起》
生徒がつくった顕著な普遍的価値への言明の一部を紹介します。
◆ナナミさん
『ハンセン病問題は、ハンセン病にかかった人があれはうつるものだと決めつけられて、隔離されて、人としての正しい扱いを受けられず差別され続けられたことだけではなく、その長期に渡っての偏見は簡単には消えず、いつまでも残り続けてしまうので差別を受けて続けてきた人々の心も傷つき、社会復帰できる環境であってもすぐに戻ることはできなくなってしまうということが分かった。
人は誰もが言う「普通」と少しでも違う部分や、ある人が自分の勝手な判断で考えたこととかが広がると差別するし、差別につながるのだと思う。見た目であったり、その人が持っている病気のことであったり、その人の性格のことで、付き合い関わり方を変えてしまうのは違うと思う。
でも、私自身、今までに生まれつき病気を持った人に対して友達や普段みる人とは違う目で見てしまうことがあった。今回長島について、差別について学んで改めてこの世にいる人全てが大切な存在であり、全員普通であるんだ、違う目でみられる人なんていないと思った。生きていく中でも、その気持ちを常に持ち続けいくこと、持とうと思わなくてもそう思っていられる、そんな人が増えていくことで正しい考えを持つことができるし、違うことをただすこともできると思う。長島について考えることは、ハンセン病についての正しい知識を持つことにつながり、差別がどれだけ人を苦しめて間違ったことを生み出し続けるかを知ることにもつながる。今、私たちがこれらのことを学んだので、次はこれから生きる人たちに伝えていこうと思う。したがって、ナガシマは顕著な普遍的な価値を持っている。』
☆160日目(10.15)開示・協働のちからは高まっているか?
これまで、子どもたちの学力保障にとって大事なことは、「授業がわかること」、「自分を受け止めてくれる教師や地域の大人がいること」とともに、「心を通わせることの出来る友だちがいること」と様々な研究者は提言してきました。このことは、生きる力としての学力保障とは、単に学習内容が理解できることではなく、他者とつながりながら自己実現して社会の中で生き抜くための力を身につけることであるということを表しています。「自分を受け止めてくれる教師や地域の大人」や「心を通わせることの出来る友だち」とつながることによって、被差別の子どもが自分自身の存在を認め、自信を回復し、立ち上がる力をつけることをめざしているのです。そして「なかまづくり」は、子どもたちがこれら身の回りにいる人たちとつながるためのさまざまな取組を指しています。
「なかまづくり」を通して身に付けさせたい力の中で、最近気になることは「開示」や「協働」などの技能的側面です。相手に自分の意志や意見をはっきり主張することが大切だと思う気持ちが十分にもてていないことや、相手に自分の気持ちや考えをきちんと伝えるという行動に移せていないと捉えることができます。 「開示」の技能的側面は、困ったことや悩みを周りに相談することができていないと捉えることができます。 さらに、「協働」の技能的側面は、困っている人や集団の問題を解決するための行動ができていないと捉えることができます。
そこで、自分の考えや気持ちを相手に伝わるようにすることが良好な人間関係を築く為の基礎になるという実感や、同様に困ったことや悩みを周りに打ち明けられるような環境づくりの大切さを実感し、困っている人や集団のために解決する行動を起こすことが、学級の一員として、また社会の一員として良好な人間関係を築いていくことになると実感する経験が必要だと考えられます。
そのため、学級の中で自分の気持ちや考えを相手に伝わりやすいように工夫して伝える場面を仕組むことや、誰もが思いや悩みを打ち明けたときに受け止められるような雰囲気(場)をつくっていく手立てを講じることが必要となります。また、学級の中でさまざまな仕事を受けもち、友から頼られたり、自分がその仕事を達成したときの成就感を味わったりできるような手立てが必要です。また、全体的に技能的側面が低く現れていることから、道徳や学級活動等の取組において、日常の実践的行動力にいかにつなげるかという視点に着目した授業展開の工夫が必要と考えられます。
☆159日目(10.11)つづる・語る
再度、「仲間づくり」の有効性が確かめられてきたいくつかの手法をまとめました。
①「つづる」「語る」・・・一人ひとりが自分を見つめる取組
「つづる」とは、過去の出来事を順番に思い出し、事実をありのままに書いていくことです。これを積み重ねることで、生活のなかにある自分自身の課題や不安、悩みを意識化し、これからの生き方や社会のあり様を考えることができるようになります。自分を見つめることは、つらいことや苦しいことも受けとめ、自分を否定することなく生きていく力を培っていきます。そうした力を身につけた子どもは、友だちの前で「語る」ことができるようにもなっていきます。また「語る」ことは、単に誰かに伝えるだけではなく、自尊感情や将来展望を確かなものにしていくことにもなります。
②「読み合う」「聴き合う」…知り合い、共感し合う取組
朝の会や帰りの会等で日常的に子どもがつづったものを読み合う取組や、人権学習・人権集会等で伝え合う取組が行われてきました。こうした取組によって、子どもは友だちの思いを知ったり、友だちに思いを返したりするなかで自分を深く掘り下げていきます。また、思いを伝える姿が、他の子どもにも「もっと自分のことを深く見つめたい」「自分もずっと避けていた課題と向き合いたい」という意欲を喚起することもあります。
「読み合う」「聴き合う」取組を進めるにあたっては、私たち教職員が自分自身を語ることを大切にしてきました。教職員が自分の不安や悩み、これまでの経験等を語ることは、子どもたちの「こういうことを話してもいいんだ」「自分のことを聴いてほしい」という安心感につながっていきます。人権・同和教育の歴史の中で、「なかまづくり」とは、単に学級の子どもたち全員がなかよくなることをめざしたものではありません。部落差別をはじめとする、あらゆる差別を許さない反差別の集団づくりをめざしたものです。
わたしたちの先輩教師たちは、学校で気になる子どもたちの姿を見るにつけ、家庭にあしを運び、子どもたちの生活を知り、保護者の思いを受け止め、それを学級に返していくことで差別によって分断されてきた子どもたちをつなぐ地道な取組を続けてきました。
このような歴史の中で、「なかまづくり」は、それぞれ違った個性や生活背景をもった子どもたち一人ひとりが互いの存在を尊重し合い、集団の中でさまざまな個性を磨き、共に成長する関係を築く中で、一人ひとりの自立をめざす取組となっていったのです。
☆157日目(10.10)
「ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高める」人権教育
仲間づくりのポイント(続き)
④個別的な人権問題についての学習と結びつけて取り組むこと
一人の子どもの生きづらさの背景に人権問題がある場合、その生きづらさは社会の問題であり、他の子どもにとっても共通の課題となります。友だちの思いを聞くなかで、「友だちを不安な思いにさせていたのは、社会の偏見や差別だった」「そのことに無自覚だった自分は、友だちを不安にさせていた」といった気づきが、人権問題の解決を「自分事」として引き寄せていきます。また、様々な人権問題について学習する際、自分が生活のなかで感じている不安や自分にとって身近な人権問題と重ねて考えを出し合うことによって、マジョリティを「普通」とする価値観やそれへの同調圧力など、それぞれ個別の問題に共通する社会の課題を見出し、自分自身とのつながりを見出すことができます。「仲間づくり」を基盤に、こうした学びを積み重ねることが、ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高めることにつながります。
11月には、1年生は「仲間をもっと知ろう(発達特性)」、2年生は進路キャリア学習の一環として「ホームレス問題」について、3年生はハンセン病問題学習に取り組み、上記の「ともに生活や社会をよりよくしようとする意欲や行動力を高めること」を進めていきたいと思います。(続ける)
☆156日目(10.9)思いを知り合う機会を・・・弁論大会、、、
幼稚園及び特別支援学校幼稚部、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の教育要領や学習指導要領には、「前文」が加えられ、そのなかで、これからの学校には一人ひとりの子どもが、「自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」と述べられて
います。ここに示されている子どもたちに育みたい力は、これまで私たちが人権教育を
通じて子どもたちに育んできた力と重なるものです。生まれ育った環境や障がいの有無、国籍等にかかわらず、すべての子どもたちが意欲的に学び、夢や希望を実現できるようにしていくためには、学校の教育活動全体を通じて、子どもたちの自尊感情を高め、多様な人と協働しながら、人権が尊重される社会づくりに主体的に参画する力を培う必要があります。そして、その取組は、これまでの同和教育の理念や成果、手法を踏まえ、教育的に不利な環境のもとにある子どもを中心に据えた「仲間づくり」を基盤とすることが重要です。
何度も繰り返しになりますが、「仲間づくり」について再掲します。
◆「仲間づくり」の目的
めざすべき「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある人権問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。
◆「仲間づくり」の視点
「仲間づくり」は、こうした目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。そのうえで、どのようなことを大切に取り組んでいけば良いか、これまでの教育実践の成果などを踏まえ、ポイントをいくつか挙げます。
①子どもの生活背景をつかむこと
すべての教育活動は、子どもの姿、子どもを取り巻く現実から出発することが大切です。気になる言動を見せる子どもがどんなことを考え、どんな思いでいるのか、どんなくらしのなかで生活し、学校に通っているのか、保護者はどんな願いをかけて子育てをしているのか。そうしたことのなかに、その子どもが抱えさせられている課題を解決するための、取組のヒントがあります。子どもの生活背景をつかむためには、家庭訪問等の取組を通じて、くらしや思い・願いなどについて対話できる関係を、子どもや保護者と築くことが必要です。
②弱い立場に立たされている子どもを中心に据えて取り組むこと
「中心に据える」とは、決して集団のリーダーにするということではありません。取り組む教育活動が、子どもの自尊感情や学習意欲を高めたり、自他の人権を尊重し差別をなくそうとする意識を身につけたりすることにつながるものであるかを、その子どもの姿を通じて検証するということです。集団のなかで疎外されていたり、不安を感じながら生活していたりする子どもが学級で安心して過ごせるようにすることは、誰にとっても居地の良い環境をつくることになります。また、弱い立場にある子どもの側に立ってまわりの子どもや集団を見ることで、他の子どもの課題や集団の課題が見えてきます。
③一人ひとりが生活のなかで感じている不安や悩みを共有し、ともに乗り越えようとする集団をめざすこと
「いいところ」「がんばっていること」を認め合うことは大切です。しかし、それだけではなく、一人ひとりが直面している課題を出し合うことが必要です。家庭や地域での生活、そのなかで抱えさせられている思いを知り合うためには、「聞いてもらえる」「知ってほしい」と思える集団であることが大切です。こうして知り合った一人ひとりの思いを共感することが、一人ひとりの課題の克服や、その背景にある人権問題の解決に向けて行動しようとする連帯感につながっていきます。
先日の校内弁論大会前の学級弁論大会だけでなく、1学期の課題を踏まえた2学期の目標の発表、夏季休業時の聴き取り課題の発表、生徒会・学級役員選挙演説会などなど、「思いを知り合う」機会を意図的に創りたいと思います。(続く)
☆155日目(10.8)サイードその2
『まず、「オリエンタリズム」の意味を調べると次のように書かれています。
【オリエンタリズム】
①オリエント世界(西アジア)へのあこがれに根ざす、西欧近代における文学・芸術上の風潮。東洋趣味。
②東洋の言語・文学・宗教などを研究する学問。東洋学。出典:デジタル大辞泉(小学館)
「オリエンタリズム」は、多くの辞書だと「東洋趣味」と書かれています。「東洋趣味」とは「西洋の人たちが東洋の文化に対してあこがれや好奇心を抱くこと」です。しかし、一般的にはこの意味で使われることはほとんどありません。「オリエンタリズム」は「西洋人が自分の都合のいいように西洋以外を見る見方」という意味で使われることが多いです。なぜこのような意味に変わってしまったのか、順を追って説明していきます。まず、「オリエンタリズム」は英語で「orientalism」と書き、「orient」はラテン語の「oriens」に由来します。「オリエンス(oriens)」とは「太陽が昇る方角」という意味です。つまり、「東側」ということです。この事から、「オリエント」は広い意味で「西洋以外の東側諸国全般」を指し、狭い意味で「西アジアやエジプト」を指すと言われています。ここで一つの疑問が浮かび上がります。それは「西とか東は何を基準に決めているのか?」ということです。考えてみれば、当たり前のことです。私たちの国、「日本」はアジアの東ということで「極東」と呼ばれています。また、アラビア半島やその周辺地域は「中近東」と呼ばれています。しかし、日本が極東にあるという基準は誰が何によって決めたのでしょうか?実はこれらの基準はすべてヨーロッパ人が決めたのです。日本が「極東」と呼ばれるのは、ヨーロッパから見て極めて東にあるからであり、アラビア周辺国が「中近東」と呼ばれるのは、ヨーロッパから見て近い東にあるからです。つまり、これらの言葉は「西洋中心主義」によって作り出されたものなのです。「西洋中心主義」とは「ヨーロッパ文明が世界の中心である」とする考え方のことです。そして、この考え方に異議を唱えたのがパレスチナ出身の批評家である「サイード(1935年~2003年)」と呼ばれる人物です。
サイードは著書『オリエンタリズム』の中で、西洋人のオリエント(東洋)に対する見方には、「西洋中心主義」が色濃く反映されていると主張しました。サイードによれば、西洋は東洋に対して、文学や絵画などを通じて「受動性・後進性・非合理性・幼児性・停滞」といった負のイメージを押し付けたと言います。その事で、西洋の優位性を確認してきたと言うのです。サイードが『オリエンタリズム』を発表してから、「東洋趣味」という概念が実は植民地主義的な考え方であったことが世に広まりました。実際に、西洋人は西洋と東洋を全く別の物とみなし、前者を発達した文明、後者を未開の文明とみなしていたのも事実です。「未開の文明」とは要するに「遅れていて野蛮な文明」ということです。そして、西洋人は東洋文明を遅れていると考えることにより、自分たちこそが世界の中心であるというアイデンティティを確立するようになりました。こうした西洋による身勝手な東洋のイメージを、サイードは「オリエンタリズム」と呼んだのです。つまり、「オリエンタリズム」というのは、西洋による東洋への見方を批判的に表した言葉だったということです。当時の世界は「帝国主義」と言い、強い国家が弱い国家を侵略するのが当たり前の時代でした。具体的に言うと、スペインやポルトガル、フランスなどのヨーロッパ諸国がアジアやアフリカなどの周辺国を次々と植民地にしていたのです。そして、西欧諸国はこの帝国主義的な植民地支配を正当化してきました。このような時代背景もあり、サイードは西洋中心主義の「オリエンタリズム」を強く批判したのです。』
☆154日目(10.5)「他者を語る際に存在する力関係」
ハンセン病問題を「伝え、理解や行動を求める活動」に、長年取り組んでおられる方から、エドワード・サイードの「他者を語る際に存在する力関係」という思想について教えていただきました。その方は、その思想から、ハンセン病問題に取り組む際に「他者の人生を利用しているという自覚をもつ:〈勝手なことを語らない。研究や業績のためになどに消費しない〉」ことを学んだということもお伺いしました。サイードさんが気になったので、少し調べてみました。
『*オリエンタリズムを超えて
「わかったようなふりをしない」「でも、わかろうとする」ということの逆は何だと思いますか。「わかった顔をする」「と同時に、わからないことを誇大化し、神秘化すること」です。これこそがサイードが批判したオリエンタリズムでした。
どういうことかといいますと、「オリエンタリズム」というのは、十八世紀の終わり頃から現代にかけて、西洋が、オリエント地域(中東と考えてください)を理解するときに駆使した学問的言説で、それは1)ヨーロッパ人のほうが、未開の中東の地域の人間よりも中東の人間のことを理解しているという「わかった顔」をすることです。いいかえると西洋の学問的な知は、オリエントは何か、その本質なり特質を立ち上げようとします。そしてそうすることで、オリエントの現実を構築します。現実を構築されてしまうと、それはオリエントの人たちにしてみれば植民地化とかわりありません。と同時に2)神秘的なオリエントをフェティシュ化する。絶対に理解不能ななにかがオリエントにはあるというかたちで、オリエントを徹底して神秘化します。ときには神秘と芸術の世界として称讃すらします。しかし、そうすることによって、オリエントの人間は自分たちと同類ではないというかたちで壁が立ち上げられ、分離の排除のメカニズムが働くのです。それはまた植民地化とかわりありません。
したがってオリエンタリズムとは切り分けのメカニズムなのです。西洋と東洋を分離する。分離することで一方が他方を支配するメカニズムが生まれる。そしてこれに貢献するのが、東洋とは何かという知の言説なのです。これに対するサイードからの批判は、西洋と東洋は、長い歴史の中で相互にまじりあってきた。現実に交流があったし、文化は絶えずまじりあってきたし、ハイブリッド性こそ、文化の本質ともいえるものということです。
☆153日目(10.4)教材づくり
研修会で、「教材づくり」が話題になりました。「子どもたちと一緒に読みたい!・学びたい!」と思った本や題材を教材化することですが、この時代でも若い先生方がそのような想いをもっていることをとてもうれしく思いました。そういえば、私もある本に感化され『命の授業』という教材では、科学的に人間の成分をお金に換算した「人間の価格」から、「いのち」の問題に迫ってみようとか、教材の文章プリントを4つに分けて配り、ストーリーを予想させる展開とか、バス停から離れてしまっているところでバスを待っている視覚障害者をみた自分はどうするのか?を4コマ漫画の最終コマで表現するとか、道徳で挑戦?実践?していた記憶がよみがえりました。それはさておき、ある小学校の先生が「子どもたちと読みたいのです」とオススメしてくれた本は、(TVドラマにもなったらしい)『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』岸田 奈美 (著)です。私も読み始めましたが、「子どもたち一緒に考えたいなあ」と!
☆152日目(10.3)行事での「振り返り」は何とつながっていくのか?〈学び・学級づくり〉
行事での取組の中で、「生徒が主体になるということ、教職員の支援はどうあるべきか」がいつも話題になります。卒業した子どもたちの「ふりかえり」からも考えたいと思います。
○クラスの皆ががんばっている中、ボクは結局最後まで練習に満足に出れませんでした。「大丈夫、明日がんばったらええが」と言ってくれた人たちにひどく申し訳なかったり。
ボクは、未だ自分に甘いようで、私事で練習に参加できなかったり…、でもそれをとがめもせず、「大丈夫」といってくれることに、毎回申し訳なく思いました。だから当日は心から歌いました「ありがとう、支えてくれて」と。届いたかどうかはわかりませんが、届け、届けとありったけの声で歌いました。なぜこのクラスに居たくなったのだろう。あんなに嫌いだったのに。その理由はまだわかりませんが、「楽しかった」。3 年間で一番心に残ると思います、歌っている間のことが。ステージに立った時、足が笑っていました。やばいふらふらすると思っている中、歌がはじまり、気づいたとき、「ありがとう。今まで出会った人たち、ボクをこの世に生んで育ててくれたひと、友人、大事な人、その皆を生んで育ててくれたひと、、皆に「ありがとう」と言いたくてたまらなくなりまた。「ありがとう 大好きです」そう伝わるように心から歌いました。そして同時に私は何度も人を裏切ったことに対して「ごめんなさい」と言いたくなりました。さてこれからもうひとつ大きくて苦しい壁が待っていますね。ボクもそれに向けて歩きださなきゃいけませんね。がんばります。ありがとう支えてくれて。ありがとう信じてくれて。ありがとう何度も裏切ったのにボクの側にいてくれて、きっかけがないと素直になれないような奴ですが、今後ともよろしくお願いします。T
○先生へ、いつも僕たちが歌の練習に、ありがとうございました。
そしてみんなへ、下手な指揮だったけど一生懸命歌ってくれてありがとう。俺たちの音楽会はまだ終わらないぞ!M
○日々の音楽会の練習を一番努力したのは2組だと思う。いろいろなトラブルもあったけど、最後はみんなで歌えてよかった。この団結が消えないように、苦しい受験もみんあで乗り越えていきたい。3-2 ってひとつになれば、こんな力がでるんだなあ。女子もみんな音楽会のために身だしなみに気をつけた。誰一人自分勝手なことをするひとがいなくて、団結してるった感じた。3-2 最高!Y
○3-2 のみんなありがとう!優勝はできんかったけどな…。俺は今までの行事の中でこんあにもみんなと団結してがんばったのははじめてじゃ。みんなで市の音楽会にいけたらええなー。もしいけたら優勝しようなー。みんなありがとう。先生もサポートやアドバイスありがとう。こんなに朝・昼・夜と歌ったのは初めて。のどが居たかった。でも楽しかった。音楽会というひとつの行事で、こんなにクラスが団結できるんじゃなって思えた。なんかクラスの雰囲気が変わったような気がした。最後に後輩たちへ、俺たちも2年生のころは音楽会なんてどーでもええとおもっとった。でも3-2 年になってからクラスで、みんなで、何かする楽しみを知った。じゃから今の1,2年生もクラスのみんなでないかする楽しみを見つけると、いい行事になっていくと思う。MA
○3-2のみんなで音楽会ができて楽しかった。優勝はできなかったけど、みんなで歌った合唱は最高だった。みんなありがとう。クラスみんなで相談して、朝練習をしたり、放課後練習をしたり、一生懸命がんばれた。みんなで放課後神社に行って歌をうたったのが一番楽しい練習だった。途中、いろいろあったけど、みんなが話を聴いてくれたり、いろいろ言ってくれたりでここまでがんばれたと思う。これからもみんなの団結でがんばっていきたい。後輩たちへ、来年もいい音楽会にしていってほしい。TO
○音楽会まで、練習の時いろいろあった。最初は朝練もいやで、「なんでやるのか」ずっと思っていたけど、ずっとやっているうちに本当に音楽会の練習を一生懸命やっている人たちの姿をみて、やっと本気で取り組むようになった。帰りの会が終わった後も、一回ずつ歌って練習したり、がつこうが使えないときは神社で練習したり、きつかったけど、みんなのかけ声のおかげで、練習に必死に取り組めた。歌っているとあごが痛くなったり、のどが痛くなったりしたけど、いろんな人が、どう歌えばいいのか教えてくれて良くなったりした。本当にこんなに音楽会で努力したのは初めてだった。音楽会は2位だったけどこんなに練習した成果が出せれた。本当に良かった。後輩たちも今回にような感動を味わえるような音楽会にしてほしいと思う。O
○3-2のみんなのおかげですごくいい思い出が出来ました。こんなに真剣に歌ったのははじめてで、優勝出来なかったけど、感動1位、団結力1位!だったと思います。どのクラスよりも2組は、まとまっていると思います。私は3-2 でよかったと思います。3-2 のみんなありがとう!どのクラスより練習する時間が多かった2組は、それだけみんなが「優勝したい!」という重いが大きかったんだなあと思います。神社での練習もすごくいい思い出になりました。楽しかったです。受験に向けても、みんなで励まし合いながらいけるといいです。後輩たちへ、みんながひとつにまとまれば、きっと最高の音楽会が出来るはず。さいごまであきらめずに!「ただの音楽会じゃけ どうでもいい」と思わず、音楽会にかけてみてください。O
☆151日目(10.2)教育と福祉の協働は可能か
「春15の会(特別支援教育のニーズのある子ども・保護者のための進路情報交流学習会)」実行委員会に参加しました。今年度は残念ながら、台風のために対面での情報交流学習会は中止となってしまいましたが、実行委員会では今年度の取組の総括を中心に話し合いました。その中で、「教育と福祉の連携・協働の重要性」について今回も話題になりました。
文科省も、連携について以下の内容があります。
「発達障害をはじめ障害のある子供たちへの支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であり、一層の推進が求められているところです。
特に、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されています。こうした課題を踏まえ、各地方自治体の教育委員会や福祉部局が主導し、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域で切れ目なく支援が受けられるよう、文部科学省と厚生労働省では、「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」を発足し、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討しました。」
また、福祉とは距離が遠いように思える教育と福祉分野の連携に関する「教育福祉」という内容があるようです。私自身は聞き慣れない言葉ですが、不登校や貧困、発達障がいなどの困難さを抱える現代の子どもたちの成長において非常に重要な概念となっているようです。『教育福祉とはどのような福祉のことなのか、その概念や具体例が解説された文章を少し紹介します。
[教育福祉の概念]教育学者である小川利夫によって1972年に提起されました。定義”教育福祉とは、教育と福祉が連携して、子ども・若者あるいは成人が安定した生活基盤のもとで豊かな人間発達を実現することをめざす概念である。”(辻 2017:1)
言い換えると、子どもと若者を取り巻く貧困や障がいなど様々な困難に対して、福祉と連携して支援することで成長や発達を支えるという考えになります。学校における児童生徒の環境調整や関係機関と連携した支援を行うスクールソーシャルワークは、まさに教育福祉の代表的な取組と言えます。教育福祉は、高度経済成長期に経済的な格差が広がる背景において生活基盤が不安定な層が増えたことや、夜間中学・養護施設の児童や勤労青年などの「教育と福祉の谷間」の問題に焦点が当てられたことで提起されました。この「教育と福祉の谷間」の問題は、子どもの貧困やヤングケアラー、不登校の児童生徒の増加など今日においても広い範囲にわたっており、支援の重要性は増してきている状況にあります。(ちなみによく似た言葉として、「福祉教育」がありますが、福祉教育は身の回りの福祉に関する課題や解決策を学ぶ教育になりますので、教育福祉とは全く異なるものになります。)
[教育福祉の例]
教育福祉には具体的にどのような取組があるのでしょうか。教育福祉は類型化すると、主に学校教育福祉と地域教育福祉の2つに分けられます。学校教育福祉はスクールソーシャルワークとも呼ばれていますが、主に学校教職員やスクールソーシャルワーカーなどが子どもや家庭に関わる取組が該当します。最近では、「地域に開かれた学校づくり」の取組においてコミュニティ・スクール[1]と地域学校協働活動[2]が一体的に推進されており、地域との連携により学習支援などの活動も行われるようになってきています。地域教育福祉は、学校に限らない公民館などの社会教育施設などで行われる取組が該当します。歴史的には、夜間中学や青年学級などの成人向けの取組が行われてきましたが、現在では、地域社会の希薄化や貧困などにより、子ども食堂などの子ども向けの取組も行われるようになりました。また、最近では、子どものサードプレイスとして「宿題カフェ」と呼ばれる放課後に子どもが集う場所づくりも行われています。地域教育福祉の取組には、地域に根差した活動や社会教育の実践が大きく関わっています。これらは必ずしも自治体によって行われているものだけでなく、NPOなどの民間団体によって取り組まれている活動もあります。
[教育福祉の視点]
教育福祉は、不登校、障がい児、外国人の子ども、子どもの貧困など多岐にわたる分野で重要な取組となっています。取組を行っていくためには、学校教職員と福祉関係者との連携や地域との連携が大切になります。様々な職種や立場の人たちが連携して、子どもたちにとってどのような支援が必要なのかを考えることが重要です。また教育福祉が重要視されるようになった背景には、制度の狭間に陥ってしまった当事者たちの問題がクローズアップされたことがあるため、既存の制度や支援では対応できない問題に注目することも重要です。特にヤングケアラーはその典型であり、これまで見過ごされてきた問題に焦点が当てられ、子どもの権利の視点から支援のあり方が考えられています。
教育福祉という言葉自体は馴染みが薄くても、その取組は意外とみなさんの身近にあるということです。教育福祉では、子どもや若者たちの育ちや学びにどのような支援が必要かを考えることが重要です。これからも子どもの最善の利益の視点に立って、教育福祉が一層推進される社会になることを願います。
[参考文献]辻 浩‚ 2017‚ 『現代教育福祉論—子ども・若者の自立支援と地域づくり』ミネルヴァ書房 山本理絵・望月彰、愛知県立大学「教育福祉学研究会」編‚ 2023‚ 『教育と福祉が出会う支援—子ども・教師・専門職がつながる学校・地域をめざして』溪水社
☆150日目(10.1)生徒会は、民主主義の学校
生徒会中央役員・専門委員会の認証式では、校長も「自分が投票した人が当選しなかった」「自分は不信任の意志表示」をした場合などについて言及されてましたが、私も《民主主義》のあり方を学ぶとても大切な機会であると思います。
『自分は何ができるか(自分は何をするか)』という視座が、次世代の担い手となるためにはとても大切だと思います。
「主権者」と「傍観者」の違いは,この「参画意識」の差だろうと思います。今回の選挙に立候補した生徒は,学校の課題を意識することができました。立候補者以外の生徒(不信任の意志表示をした生徒)も意識をすれば学校をさらによくする「主権者」になれます。
「地方自治は,民主主義の学校」と言われますが,身近な問題に意識を持てるか持てないかで,社会の見方は変わってきます。テレビ番組でも,回答者のタレントの中に,驚く
ほど社会問題に詳しかったり,問題意識が高かったりする人がいて,派手な外見とは別に,知性を感じたことがありました。意識は変えられます。意識が変わると,様々な情報が自分のアンテナに引っかかってくることになります。そうすると,ニュースが面白く見られるようになり,自分との関わりが少しずつ視えてきます。現状を知り,課題に対して,自分が参画していく意識を芽生えさせ,民主主義の主人公になっていける一助となるよう事後指導を積極的に進めていきたいと思いました。
☆149日目(9.30)SSWやSCとの連携・協働って大切。


柔軟な対応をありがとうございました。どんな連携・協働ができるか!これからもよろしくお願いします。
☆149日目(9.27)子どもの困り感をもとに、変えるのはワレラ
先日の校内研修でみんなと話し合ったことがもう1つあります。それはひとつの学年に対しての授業づくり(学習集団づくり)です。もちろん、教科指導は各教科担当が全精力をかけて授業研究・準備を進めるのが前提ですが、学習集団としての子どもたちを豊かに育てていくためには、チームとしてのアプローチが必要です。この日は、その学年の授業に関する取組や苦労していることを語ってもらいました。また、学年団の先生からも、その学年の生徒が成長してきた取組や強みについて話してもらい、今後の授業づくりにおおいに参考となりました。具体的実践に向けては、4人でのグループ学習時に声の大きさが気になり、話し合い活動に集中できにくい生徒がいることが共通の話題となり、意見の中で出た「グループ学習にふさわしい課題の提供」と「学びが成立しているか、授業者が意識的に、グループ学習を看取ること」、そして「4人でなく、2人のペアリング学習の活用」と「その際の声量の調整指導・支援」を進めていくこととなりました。みんなで授業づくりをがんばろう!

☆148日目(9.26)「人と食事をするのが苦手です」と。
山陽新聞(9/25)の子どもしんぶんさん太タイムズの記事に、「わたしは食べるのが下手(天川栄人作 小峰商店)」という書籍が紹介されていました。コロナ禍後の教育活動の内容の見直しだけではありませんが、「人と食事をするのが苦手」という子どもたちの存在も考えながら、先日の話も考えなければならないと思いました。読んでみようっと。
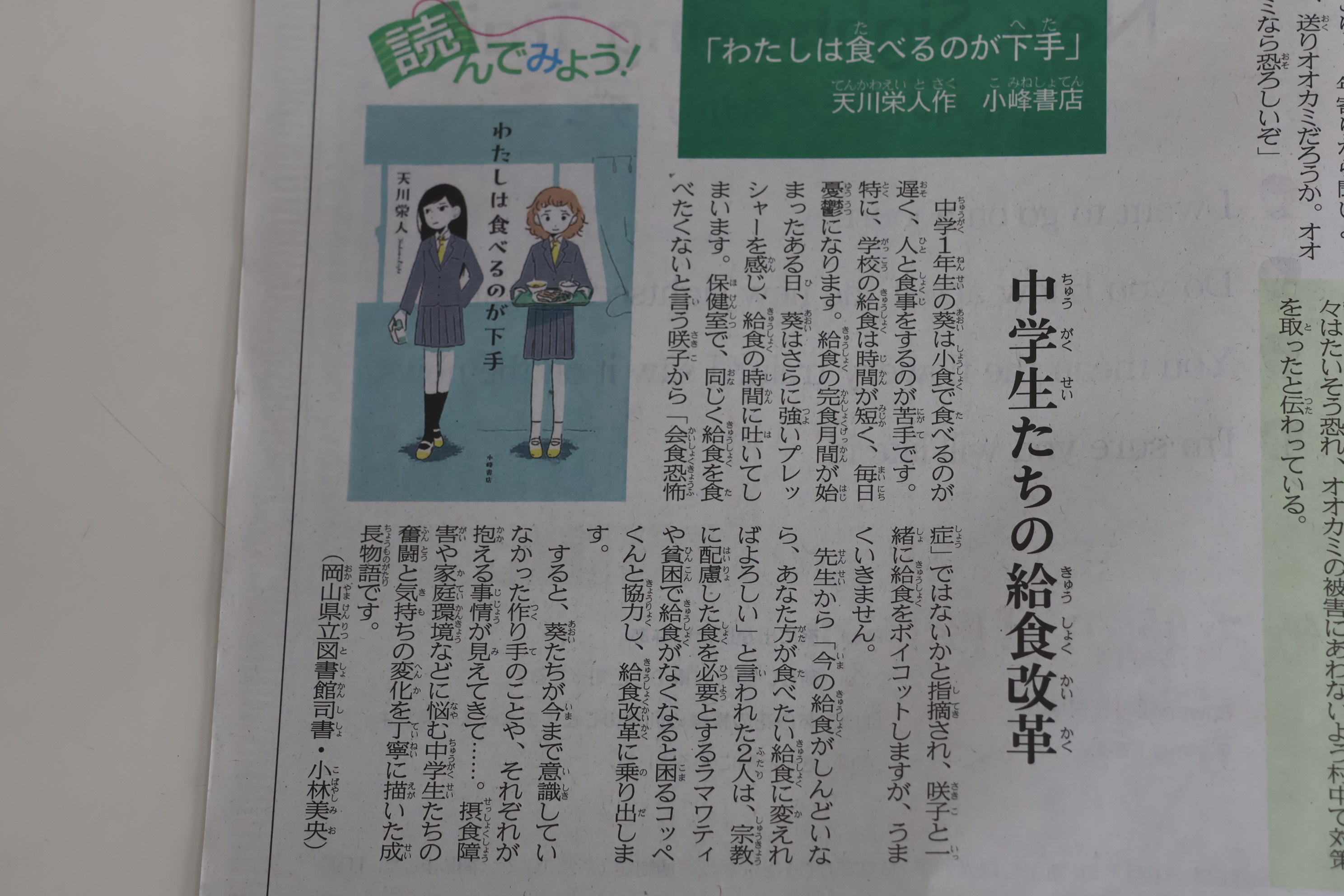
☆147日目(9.25)
先日の校内研修が終わっての立ち話。
生徒どうしが「かかわる」場の創出を考えたとき、「給食の生活班で食べること(会食)はとても大切だなあ」と確認しながら、まだコロナ禍の影響(?)で、一斉授業スタイルでの昼食になっている学校も多いとのこと。そうなっているのはどういうことなのか?を考えなければいけないなあと思いました。「やっぱり感染予防」「班にしたらウルサ過ぎる?「トラブル防止」「子どもたち自身が個食に慣れて、気まずそう」「給食の片付け時間が確保できない」・・・。話してみるといろいろと考えがありそうです。でも、それを越えて、やっぱり子どもどうしが「かかわり」、お互いが「そうなん。そうだったんか」と様々なコトをわかり合う場づくりを創出していきたいなあと思います。

☆146日目(9.24)今こそ「思想と行動を打ち鍛えたい」
~「ヒロシマの母子像ー四國五郎と弟・直登ー」から

大阪を拠点にシンガー・ソングライターや作家、俳優など多彩な表現活動を続ける趙博(チョウバク)さんが手がける一人芝居「ヒロシマの母子像―四國五郎と弟・直登―」の全国巡回公演に行ってきました。
今年は広島の反戦詩画人・四國五郎の生誕100年・没後10年。戦争を憎み、平和のために生きた四國に共鳴した趙さんは「反戦平和の思想と行動を今こそ打ち鍛えたい」と言われます。
絵本「おこりじぞう」の挿絵などで知られる四國五郎さん(1924~2014年)は徴兵先の旧満州(現中国東北部)でソ連軍との激戦を生き延びた後、三年間のシベリア抑留を経験します。そして広島に帰郷して弟の直登が原爆の犠牲になったと知り、弟が死の間際まで付けていた日記を母から受け取ります。その夜、自身の日記に「直登の死に対する悲しみを怒りと憎しみに転化させよ!」と書きました。
趙さんの一人芝居は、兄弟の絆を軸に、平和を希求する思いを語りや歌で構成されています。四國五郎さんが手がけた絵や詩、直登の日記などを織り交ぜ、母子のつながりを断ち切る戦争への怒り、それを許さない愛情。タイトルは四國が生前に発表した詩画集から発案されています。
趙さんは生前の四國五郎とは面識がありませんでしたが、19年に大阪大総合学術博物館であった回顧展で衝撃を受け「何としても伝えたい」との思いに駆られました。23年夏に大阪市内で初演し、その後台本を改訂しながら、今夏から関西を皮切りに全国巡回公演に臨んでおられます。
趙さんは「四國さんが生きていればウクライナやガザを見て何と言い、どんな作品を作っただろうか。被爆を体験したこの国で、反戦平和の思想がなぜ根付かなかったのか。芝居を通じて問いたい」と言われています。
岡山・オリエント美術館での本公演では、趙さんの深く、力強い、そしてあたたかい声での、語り・音楽、そして四國五郎さんの絵が大きく・厳しく自分の実践や活動に迫ってきました。
エンディング近く、趙さんが客席の間を通りながら「あなたの隣を見てください ひろしまの子がいませんか」という語りかけに、公演会場の一人ひとりが、思いを深くされていたように感じました。自分自身も、鈍った「思想と行動を打ち鍛え」、明日からの学校現場でガンバラネバなりません。
☆145日目(9.20)朝の会・帰りの会をどうする
今週の校内研修では、「朝の会・帰りの会についてどう考えるか?」について、これまでのクラス・仲間づくりの取組をもとに、和やかな雰囲気の中で、みんなで話し合いました。会自体は、とても短い時間ですが、一方的な連絡だけにならないような手立てや、「今日一日をがんばろう!」生徒らが元気で過ごせるような働きかけなど、具体的な取組内容を紹介し合うことができました。
また、生徒たちが「かかわる」場をつくる例として、「いまどんな気持ち」大阪府人権教育研究協議会(大人教)ホームページ (coocan.jp)の実践報告もありました。これはこの教材を利用して、生活班内で、自分の気持ちを表現(表出)し、他者に「関心をもち、かかわろうとする力を豊かにしていきたい」という視点からの実践報告でした。
「目ざす教育目標」に向けて、教職員それぞれの持ち味を生かしながら、学校のみんなで子どもたちを育てていこう!感じることができたよい研修会でした。

☆144日目(9.19)アンケートを考える 2
◆アンケート調査の計画では、次の項目を明確化することにより、実施方法を選択・決定していくことになりますね。 何のために調査をするか(調査目的) 何を収集するか(調査項目) 誰に聞くか(調査対象) 何人に調査するか(調査規模) いつ調査するか(調査時期) どのように調査するか(調査方法) どのように分析するか(分析方法) どのように報告するか(報告方法) 予算はいくらか(予算計画) いつまでに報告するか
と、話しながら、私もこれまで様々なアンケートを作成、実施、活用してきましたが、学校での取組では、あといくつかの要素が必要だと思います。ひとつめは、アンケート自体に、学習的な意味を持たせたい。アンケート内容に「学び」や、「新しい(正しい)知識」に触れることのできる内容を入れたり、アンケート実施後の学習時には、アンケート結果の「価値づけ」等をおこなうべきだと思います。ふたつめは、アンケートに向き合う一人ひとりの意思(コトバ)を尊重することです。
現在、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に合わせ、学校でのアンケートも実施されていると聞きましたが、もし本校が、実施にむけて検討するなら、「被害者がいるであろうことを前提」に、「あなたが悪いのではない、あなたが大切という強いメッセージ」と共に、「あなたの救済、相談へつながる道筋」を明記」し、とてもしんどい思いしたことを改めて憶いだせること」に寄り添う内容にしなければならないと思っています。
NHK“性暴力”実態調査アンケートについては、以下のような文章がありました。『…性被害についてのに遭ったという方やそのご家族を対象に、〇月〇日から〇月〇日まで実施した、NHK“性暴力”実態調査アンケート。一人ひとりのご経験や思いを、より大きな声として可視化して、社会全体に問いかけたいと回答を呼びかけました。
38‚383件。これが、私たちの元に届いた傷みの声です。
心から感謝するとともに、皆さんの思いを受け止め、それを伝えることの責任を感じております。
現在、アンケートの作成にご協力いただいた専門家の方々とともに分析を行っております。詳しい分析結果や専門家の見解は、こちらのページで6月以降に公開する予定ですが、今回は「被害の内容」や「加害者との関係性」など、一部を先行してお伝えします。
また下記の番組でも、アンケート結果とともに性暴力被害の実態に迫り、私たちの社会に求められることを考えます。ご覧いただけると幸いです。』
「今回、初めて自分の経験を人に伝えました」
「被害者ばかりが責められる社会を少しでも変える力になりたい」
「被害を思い出すのはきつかったけれど、当事者の実態を少しでも知ってほしいと回答しました」
被害について思い出したり、ことばにしたりすることは、大きなご負担をおかけしたことと思います。さらに自由記述欄には、被害の詳細やその後の苦しみ、アンケートに込めた思い、性暴力根絶への思いなど、本当に“命がけ”でつづってくださったことばがあふれていました。
アンケートや調査は、あたりまえですが、当事者を意識し、そのアンケートの重みを受けとめ、願いを実現できるよう取組につなげていくことが何より必要だと私は思います。
☆143日目(9.18)アンケートの意義1
最近、QRコードの普及にともない、アンケートが多くなったなあと思いがしています。さらに、実施したアンケート後どのように活用されたかが不明確で、多くの時間(「わずか5分です)と言われるけど)の浪費感が残るのは否めません。
そもそもアンケート調査とは、調査対象の意見や行動を把握するため、特定の期間内に様々な調査方法で様式化した質問で回答を求め、データを集める調査方法です。アンケート調査は調査対象に回答を求めなければ得られないデータを収集することが主な特徴であり、企業や行政サービスに対する顧客の満足度や、性別・年齢別の消費者の生活様式の把握が例としてあげられます。
アンケート調査の目的は、そのアンケート調査の位置づけにより異なり、計画を策定していくうえで目的を明確化する必要があります。事業活動を継続的に改善する手法として PDCA サイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Act:改善)がよく知られていますが、アンケート調査が PDCA サイクルのどの段階に位置づけられるかを照らし合わせることにより、アンケート調査の目的は定まりますね。
Plan(計画):問題の把握や仮説の設定を目的とした調査
(例)生活時間調査、家計調査 Do(実行):実態を詳細に把握することを目的とした調査
(例)サービスの利用状況調査、商品の利用実態調査
Check(評価):課題の原因分析や、事業効果の測定を目的とした調査(例)サービスの満足度調査、商品への要望調査
Act(改善):改善案を実施した場合の効果の検証や、事業の継続・改善案の実施を判断することを目的とした調査
(例)改善後サービスを例にとった要望調査、市場性調査
III. 実施方法
アンケート調査の実施では、アンケート調査の計画を立て、計画通りに実施し、収集したデータを分析し、分析結果を報告するという進め方となります。
☆142日目(9.17)児童・生徒をどう呼んでいるか?②
[男女で分ける]
男子生徒には姓名に「くん」、女子生徒には「さん(ちゃん)」を付けて呼ぶ方法は自然に聞こえる一方で、ジェンダーニュートラルへの配慮が欠けているとの意見もあります。性差をつけず全員を「さん」付けで呼ぶ指導の広がりがあるように、多様性を尊重する流れが強くなっているからですね。しかし現在でも、生物学的な性別で呼び方を変える方法は、教育現場でもよく見られます。たとえば「たなか さとし」という男子生徒がいれば、「たなかくん」「さとしくん」と呼ぶような感じです。また「たなか さとみ」という女子生徒がいれば、「たなかさん」「さとみさん」と呼んだり、低学年の児童であれば「さとみちゃん」という風に、意識的に「さん」と区別して呼んだりするケースもあるでしょう。
さらに苗字に「くん・さん」を付けるより、下の名前に「くん・さん(ちゃん)」を付けるほうが親近感を与えます。しかし異性の下の名前に「ちゃん」を付けて呼ぶのは、距離感が近すぎて、不快に思わせるリスクも…。異性を下の名前で呼ぶのは、極力避けることをおすすめします。
ちなみに現在は日本の多くの新聞でも、小学生男子に「君」、女子に「さん」を付けています。この一般例も、ジェンダーニュートラルの広がりで変わるかもしれませんね。
[呼び捨て]
呼び捨ては「さん・くん・ちゃん」を付けるより、相手に親近感を与える効果があります。しかし関係性によっては、少し乱暴な感じに聞こえるので注意が必要です。たとえば初対面で「たなか!」あるいは「さとし!」という感じで、いきなり自分の姓名が呼び捨てにされるのを想像してみてください。上から目線だと感じたりなれなれしい印象を受ける人は、一定数いることでしょう。また、男子生徒は呼び捨てで女子生徒は「さん」付けをすると、それは男女で差を付けていることになります。どのような呼び方であっても、全員統一するのが望ましいでしょう。親子や師弟のような親近感を感じるか、なれなれしさや荒っぽさを感じるかは、生徒の受け取り方次第です。呼び捨てで呼ぶ際には、生徒との関係性が大切になりそうです。
[あだ名]
あだ名で呼ぶことは、姓名の呼び捨てよりも、さらにフレンドリーな印象を生徒に与えるでしょう。ただし、いじめ防止の観点から生徒間ですらあだ名を付けることを禁止している学校もあります。自分に付けられたあだ名を、必ずしも全員が気に入るとは限りませんよね。そういう状況で、先生が生徒をあだ名で呼ぶことはあまりおすすめできません。
また特定の生徒だけをあだ名で呼ぶことは、その他の生徒から違和感を持たれるリスクがあります。よほどの信頼関係がない限り、生徒をあだ名で呼ぶのは避けた方がよいでしょう。
[代名詞]
生徒一人ひとりと心を通わせて話をするなら、「きみ」「あなた」といった代名詞ではなく生徒の名前を呼びましょう。その理由は、生徒を名前で呼ぶことで「ネームコーリング効果」が期待できるからです。「ネームコーリング効果」とは、自らの名前が呼ばれた際に、名前を呼んだ相手への好感度や信頼感が増す心理現象のことです。生徒を呼ぶときには「きみ」や「あなた」と呼ぶより、きちんと生徒の名前で呼んであげるといいでしょう。
しかし実際には、生徒の名前を呼べないケースもあるでしょう。代名詞を使う可能性のあるシーンは、以下のとおりです。
○慣れないクラスに入ったとき ○生徒の名前を忘れたとき
上記以外では、複数の生徒に話しかけるときに、全員まとめて「きみたち」「あなたたち」と呼ぶケースも考えられます。生徒を呼ぶときに代名詞を用いることは、そもそも好ましくありませんが、使わざるを得ない状況もあるでしょう。
〈どの生徒にも中立であるか。個々の生徒への配慮が足りているか〉
ここまで説明したジェンダーニュートラルを目指す動きやいじめ防止の対策など、数十年前までは問題視されていなかったことも、今は慎重に対応する必要があります。そういった時代の変遷を見逃さないこと、そして生徒一人ひとりに誠実に対応することが信頼関係を築くために大切なのではないでしょうか。
☆141日目(9.13)児童・生徒をどう呼んでいるか?①
他「児童・生徒をどう呼んでいるか」について、小学校に勤める連れ合いと話題になりました。(以前、自分の子どもが通っていた学校では、親のワタシが居る前でも、名字ではなく「名前」(いわゆる「呼び捨て))で、とても違和感を感じたことがありました。)
それぞれの学校が持っている学校風土や生徒観、小学校、中学校など校種の違いで呼び方はいろいろあるようですが、この時代、「学校」という場所で、どう呼ぶのがよいのでしょうか。たまたまインターネットで見つけた「まなびチップス」というサイトを読んでみました。
・・・「生徒をどう呼ぶべきか」という問いは、一見シンプルに見えて奥深いものです。相手の呼び方は、その人との関係性を形作る要因のひとつになり得るからですね。場合によっては、呼び方ひとつで教室の雰囲気まで変わる可能性もあります。
この記事では、そんな「生徒の呼び方問題」について考えてみましょう。
[生徒の呼び方とその印象]生徒の呼び方は、ざっくりと以下の5パターンに分類できます。□全員「さん」付け、□男女で分ける、□呼び捨て、□あだ名、□代名詞
厳密には「くん」「さん(ちゃん)」を付けたり、姓の呼び捨てか名の呼び捨てかなど、パターンは細かく分けられます。それぞれが与える印象など、生徒の呼び方について詳しく見ていきましょう。
[全員「さん」付け]
全生徒に対して「さん」付けをする呼び方は、ジェンダーニュートラル(性差に縛られない思考や行動、社会)の考えの浸透を目指す社会的背景が教育現場にも反映されたことで広まってきています。このジェンダーに関する問題意識は、日本では1980年代から徐々に広がって今に至りました。「さん」付けの呼び方は、生徒に次のような印象を与えます。
○どの生徒にも平等な印象 ○ジェンダーニュートラルな印象 ○生徒を個として尊重し、敬意を払っている印象 「さん」付けで統一して呼ぶことですべての生徒に対しても平等になり、男女の性差をつけない姿勢を生徒たちに示せます。また呼び捨てよりも「さん」付けのほうが、生徒に敬意を示せるでしょう。ただし全員「さん」付けの呼び方をすることに対して、心理的な距離を感じるなどの理由から否定的な意見を持つ人もいます。実践している現場でも、徹底度合いはまちまちで、デメリットを感じている先生も少なからずいるようです。ちなみに「さん」付けに限らずですが、下の名前で呼ぶことには、相手により強い親近感を与える効果があります。ただし名前呼びを嬉しく思う生徒がいる一方で、距離感の近さに抵抗感を持つ生徒もいることも事実です。「さん」付けで呼べば、授業中や会話でも自然と敬語が増えるでしょう。先生への親近感が薄れる可能性もありますが、線引きをしっかりすることで学習面ではプラスになることもあります。(続く)
☆140日目(9.12)本当の廃止や中止の理由は
他県の学校給食で、「フォークの扱いが危険だから」という意見が出て、「スパゲティをお箸を使って食べる?」という議論があった話を聞きました。そういえば先割れスプーンも使われなくなって久しいですが、周辺の先生に「廃止の理由」を聞くといろいろそれぞれでした。どうということはないのですが、Wikipediaを参考にいくつかをまとめました。
○学校給食の場で先割れスプーンが一頃盛んに用いられたが、今では『箸の使い方を知らない子供が増えたこと』の原因とされ廃止されつつある。
○1970年代から普及したランチプレートと呼ばれる総合食器の登場以降、逆に「ランチプレートに顔を近づけて食べる」という犬食いと呼ばれる食べ方を発生させる要因ともなった。器を置いたままで食べる洋食のスタイルとは異なり、日本では「食器を口元に持っていって食べる」という和食習慣を持つため、この食べ方はともすれば見苦しいとされる。
これは、先割れスプーンが汁物を食べるのには向かないという問題もあってのことである。こと当時の先割れスプーン先端部が「料理を絡めたり突き刺して食べる」という方法に向かない形状であることも問題視された。
先割れスプーンが多く使われていた時代には、「汁物の具材を先割れスプーンに詰め汁をすくう」という利用法が広まっていた。
○名前の由来であり最大の特徴として、先端が三つ又に割れており、スプーンでありながらフォークとしても使用できるいわゆる"spork "と、先端部に溝と穴とが穿たれ、特に果物の種を取り出しやすいことから、メロンやスイカを食べる際に使われる「先割れスプーン」が存在する。
sporkは、麻痺などにより箸が使えない人には、指先の力が無くても料理をすくったり引っ掛けたり突き刺して口に運べる便利な食器であることから、介護用品としても利用されている。また箸文化に不慣れな者がラーメンなど箸を使うことを前提とした麺料理を食べる際にも便利である。少々不器用に扱っても食事しやすいことから、幼児用食器としても利用される。
○日本の先割れスプーンは、比較的後になって登場したものである。 日本国内での初期の学校給食では、「突き刺して食べる」ことと「すくって食べる」という二通りに使えるという利便性を買われ、1950年代頃より先端部が「M」字状になっている「先割れスプーン」が用いられた。1990年代からは実用的なsporkが一般的となった。こちらは幼児や児童向けの食事風景や、コンビニエンスストアの弁当、また介護の場でも利用されている。
○先割れスプーンへの批判としてこのスプーンは、大衆の簡便な食事のために開発されたようなものであり、どっち付かずの食器とみなされる傾向がある。正式にテーブルマナーが問われるような場で使われることはない。
☆139日目(9.11)他の視座をもつ
前回に記した内容については、いま読み始めている『現代思想入門 千葉雅也著』から視座をいただいたことに依ります。著書の冒頭にはこう書かれています。
「大きく言って、現代では「きちんとする」方向へといろんな改革が進んでいます。これは僕の意見ですが、それによって生活がより窮屈になっていると感じます。(P12 )「現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。それが今、社会および自分自身を秩序化し、ノイズを排除して、純粋で正しいものを目指していくという道を歩んできました。そのなかで、二〇世紀の思想の特徴は、排除される余計なものをクリエイティブなものとして肯定したことです。」(P14)・・・この著書は、教育そのものについて言及しているわけではありません。しかし、自分たちがかかわっている教育現場をほかの視座や視点から、視つめてみることは大事かもしれません。読み手の勝手な解釈になりますが、引き続き読んでいこうと思います。
☆138日目(9.10)「はやい おそい」
職員研修で、「早く打つ」タイピングの体験をしました。たぶん、授業で実践してみたら、子どもたちは真剣に取り組むことが予想されますね。しかし、一見「盛り上がる」ようにもみえますが、タイピングの基本は、「速さ」ではなく、おのおのが自分のペースで「自己表現する文宇として」使用することであると考えます。自分が関わっていた、障害をもつ子どもたちは、一人ひとりの懸命な「意思表示・自己表現としてのタイピング」の姿をみていたら、「はやさ」の指導は必要があまりないように思いました。「はやい・おそい」をあおってはないと思いますが、子どもたちの感覚で「速い=よい」との認識が助長されてはいけません。研修では、ひとつの「指標」であることを言われましたが、(重々承知ですが)、子どもたちへの実施には、丁寧な指導・支援が不可欠です。どのような認識を子どもたちに提示するかは重要です。昨日研修に参加された方々は、各校で指導や実施する際には、そのようなことに言及されると思いますが、私も職員での校内研修時には大切にしたいと思いました。
☆137日目(9.9)
教師としての教える権利と教えることの願いと、子どもの成長と発展の願いを。
前述で、「(意味深いのです))」と書いたのは、K先生と話す中で、これまで取り組んだきた「学校づくり」や「保護者とのかかわりのありかた」について、この時代に、もう一度立ち戻る必要があるのではないかと思ったからです。1969年発行『双書 解放教育の実践2』(明治図書)の一部を紹介。どうでしょう?古いですかね?

☆136日目(9.6)僕らが自分らしくいられる学校へ
録りためていたTV番組「僕らが自分らしくいられる理由-54色の色鉛筆- 奈良のインクルーシブ中学校」(初回放送日:2021年7月17日)をじっくりと視聴し、「進路保障」についてあらためて考えました。
そんな折り、K先生(三年主任)と、「保護者と真に連携した(共に在る)教育活動はやっぱり大事だよなあ」と、昔話(教育実践)を交わす機会ががありました(←意味深いのです)。
大正中学校を舞台にした、番組の内容紹介です↓。
『僕の名前は、ゆうじ。今年3月に僕が卒業した中学校には、いろんな子がいた。重い知的障害のある子、パニックになりやすい子、家庭のことで悩む子。僕も読み書きが苦手。でも、自分らしく生きていくことを校長先生や担任の先生たち、そして地域の人たちが応援してくれた。文化祭や体育祭、1日かけて自分たちの気持ちを語りあった「集中ホームルーム」。そして進学受験。僕らが過ごした中学校の半年を見てください。#SDGs』
「僕らが自分らしくいられる理由-54色の色鉛筆- 奈良のインクルーシブ中学校」 - ETV特集 - NHK
☆135日目(9.5)当事者の話を聴いて
前田良さんのお話(備前市人権教職員人権教育研修会)から考えたことを‚やっとまとめることが出来ました。
○あらためて、人権教育は、いくつか挙げられている「人権課題を、知る学習」ではナイと思いました。過酷ではあるが、たくましく生きてこられてひとの生き方に出会い、「自分自身はこれまでどう生きてきたを問い直し、これからどんな生き方ができるのか?」を思考し、また、反差別・人権尊重の社会を創る(差別を許さないための法・政治・制度・学校、学級風土づくりへの行動力を意識した)教育を進めなければならないなあと思いました。
○当事者の話を聴くことは、学校に勤める者としてとても「しんどい」。それは、自分自身の「しごと」を振り返ることになるからです。
・学校現場の人権尊重の風土は貧しくないか?育っていく風土があるか?
・学校に、前田さんをサポートする人があまりにも少なかったのはなぜか?教職員が、子どもにとって「支援者」となっているか?
・当事者を支える「仲間づくり(学級集団づくり)」ができていたのか?
など、自分自身の、また、自校の取組を見直しになりました。
○講演でのお話を聴いて、「よかった。ためになった(知識)」だけでなく、教職員としての「立ち位置」を考えねばならないと思いました。
○日常の学校生活の中で、〈役立つ・生き抜く・闘える〉人権教育の内実をつくっていきたいと思います。前田さんが取り組んだ授業プログラムの作成にはなかなか多くの苦労があったと思います。学校外部からのアプローチには、とても慎重になる学校風土の中で、9年間を見通したプログラム作成はスゴイと思います。
本中学校区でも、子・小・中連携で、「特別支援」や「発達特性」についての学習プログラムをつくりたいなあと話題にしています。ただし、前田さんが講演の中で言われていた「性的マイノリティー(LGBTQ)の知識をわかる」のではなく、「一人ひとりの持ち味や、ニガテなこと、そして自分の悩みや不安」をクラスの仲間同士が知り、理解し合えるような内容&語り合える学級集団づくりを目的にしたプログラムになったらと思っています。

☆134日目(9.4)授業が「盛り上がる」って
2学期の授業の事前打ち合わせ会を関係するメンバーで行いました。その授業では、ロールプレイを多用しますが、演者の一人は学級担任が分担することとなりました。学級担任がすると「授業が盛り上がる」とのこと。私は、少し「?」となり「盛り上がる」とはどういうことなのか?気になりました。何でも話せて、協働活動を進めていくことができるメンバーなので、「子どもにとって、担任の演じる姿や言動を面白さだけで(滑稽さやギャップ)捉えて、学びの本質に迫るアプローチが弱まらないか?」「授業の雰囲気が和らいで、盛り上がった風に感じられるだけなら、担任は演者としてふさわしくないのではないか?」と素直に聞きました。これまでの経験(活動)から、「学びの質が低下することはない。一緒に学び合う主体者として、子どもたちは担任を捉えて、学びは深まると思います。(ファシリテーションの重要性)」とのこと。授業者共々、実践に向けてメンバー同士で共有認識をもつことができました。11月の授業は楽しみです。準備をがんばりましょう。
また、この「盛り上がる」授業の中身(質)を考えたい旨の話を、他学年団の先生にも話題にしましたが、「盛り上がり観や目指したい授業観や」が一緒だなあと感じることができて、でうれしいことでした。
「授業技術を高める」ことを言っているのではありません。子どもありきの授業づくりについて、これからも語り合いましょうねえ。(*^o^*)

☆133日目(9.3)「自分ごとってなんだ?その2」
特別な教科道徳や、総合的な学習や、もちろん人権教育の実践の中で〈「自分ごととして捉える」視点が重要である〉ということを結構聞きますし、論文やレポートにも文言が出てきます。まさか、人権課題として挙げられる17の項目、((1) 女性の人権を守ろう(2) 子どもの人権を守ろう(3) 高齢者の人権を守ろう(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう(5) 同和問題(部落差別)を解消しよう(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう(7) 外国人の人権を尊重しよう(8) HIV感染者等に対する偏見や差別をなくそう(9) ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう(10) 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう(11) 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう(12) インターネットによる人権侵害をなくそう(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう(15) 性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう(16) 人身取引をなくそう(17) 東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう)について、それぞれ「自分ごととして捉えるために」学習を展開しようということはしないと思うけど。
学習の結果、生徒のどんな姿が見られれば「自分ごと」として捉えたことになるのでしょうね。
本校でも、今年度の人権集会のあり方について検討を進めていきますが、「こころがけ」や「優しさ」を越える人権意識の高まりや行動力につながる、学びが深まる集会にしたいと思います。人権課題に出会わせるだけの取組では、「自分ごと」にはなりませんね。

☆131日目(9.2)「自分ごとってなんだ?」
私事ですが、様々なひとたちと、協働でイベントの運営を進めています。先日の打ち合わせ(会議)でのことですが、係分担が「なかなか決まらない」、というよりも、参加者メンバーが、自分からは手を挙げない。自分の意志表示をされない場面があり、とてもびっくり(ちょっとがっかり)してしまいました。学校現場でも、係や分担を「決める」ことはたくさんあり、その都度、苦労しながら子どもたちは決めていき、先へ進むのです。
・・・さてさて、ちなみに、HP『みんなの教育技術』、沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」の中で、沼田さんは以下の内容を書かれています。
・「自分ごと化」させれば意欲を引き出せる「自分からやる子に育てるにはどうしたらよいか。学習に対して子供のやる気を引き出すにはどうしたらよいか。」
これは、先生や保護者の方からよく寄せられる質問だ。確かに先生が宿題を出したり、授業中に時間を設けて無理やり子供たちに学習に取り組ませたりすることで、ある程度学びを習慣化させることはできるかもしれない。でも、意欲的に取り組んでいなければ、自分からやる子には育たないだろう。なぜ意欲的になれないのかと言えば、その勉強をいまやらなければならない理由がよくわからないし、やっていても楽しくないからだ。もし、教科書に書いていることが自分にとって大事だと感じたら、学びの効率はグッと上がるだろう。この学びが自分にとって役立つと分かれば、勉強は楽しくなり、自ら学び続けられようになる。つまり意欲を引き出すためには、その学びを自分ごと化できるかどうかにかかっていると思う。
・なぜ結婚式前のダイエットは成功しやすいのか
ただ、大人でも「自分ごと化」することは意外に難しいよね。
例えば、食事は栄養のバランスが大切ということは知っていても、独身で、太る心配もなく、病気になる心配もない、という時はあまり栄養バランスを考えず、ラーメンやパンばかり食べたり、偏ったメニューになってしまったりすることが多い。でも、自分に子供ができると自然に栄養のバランスを考え料理を作るようになることもあるよね。また病気になると、健康的な生活についてより真剣に考えるようになる。
つまり、「子供を育てる」「病気を治す」という目的があるから、バランスのよい食事や健康について自分ごと化し、自分でよく調べて深く学ぼうとするし、積極的に日々の生活に取り入れようとする。また、ダイエットが成功しないという人の場合、その主な原因は目的が曖昧だからだ。でも、結婚式前のダイエットは成功しやすいと言われるよね。
結婚式前のダイエットが成功する理由は、結婚式で、より美しい姿をみんなにお披露目し、その姿を写真に残すという目的があるから。そのために必死で努力するし、我慢することも厭わない。ボクも最近太ってきたなと気になるけれど瘦せられない。ただし、数か月後にエクササイズ本の表紙に上半身裸姿で掲載されると決まったら、今から死ぬ気でトレーニングしてバキバキの体にするだろう(笑)。
・学びの目的・ゴールを明確にすることが重要
つまり、自分ごと化させるためには、頑張る理由や目的がはっきりしていて、自分はこうなりたいとイメージさせることが重要。さらに、その目的に対する努力が、自分からやりたいと感じてやるのか、誰かにやらされているのかで、結果は全く違ってくる。だから、子供たちが「面白そうだな」とか「もっと頑張りたいな」と思わせるようなゴールを与えることが大切。子供たちに見せるゴールは、本来の目的とは違う「アナザーゴール」でもOK。本来の目的とは違うように見えても、まずは子供たちが面白そうだなと思うような「別のミッション」を与えてみる。それを自分ごと化して一生懸命取り組んでいるうちに、本来伸ばしたかった能力が身についているということもある。
・やる気を継続させるためには、ゲーム化するのがポイント
ゴールはあまりにも遠いところに設定してしまうと、最初からあきらめてしまったり、途中で疲れて意欲を失ってしまったりすることもあるから、スモールステップで段階的に設定しよう。すぐに達成しそうなアナザーゴールを追いかけていたら、気がついたらゴールをしていた、というのが理想だ。そして、子供たちのやる気を継続的に引き出すためには、「課題」「報酬」「制限」の3つを意識し、ゲーム化させることがポイント。ミッション(課題)を与え、それをクリアすると、どんな嬉しいことや楽しいことが待っているのかご褒美(報酬)を提示する。さらに、時間制限や守るべき条件(制限)を与えると、子供たちのやる気に火が付き夢中で取り組むようになる。「子供たちがワクワクすることは何だろう」と考え、子供たちが学びを自分ごと化し目標達成に向けて楽しみながら取り組めるシステムを考えてみよう。
・・・「自分ごと」って何なんでしょうね?生徒のどんな姿がみられたらよいのでしょうね?
☆130日目(8.30)木村氏の講演から
おおぞら高校のオンライン講演会を視聴した。木村泰子氏が「4つの力を軸に子どもたちと向き合ってきた」ことを聴くことができました。4つの力とは、
1「人を大切にする力」
・多様性にもつながることで、相手も自分も大切にすることを指す。この力が伸びるかどうか、周囲の大人が与える影響は大きい。「もし子どもに『人に迷惑をかけるな』と言って育てれば、迷惑をかける人を許せない人になってしまう。『役に立つ人になれ』と言い続ければ、役に立たない自分では駄目なのだと考えて、自尊心が保てなくなってしまう。大人でもこうした考えの人が多く、それは現在の生きづらい社会の一因にもなっているという。
2「自分の考えを持つ力」
3「自分を表現する力」は、新学習指導要領にも盛り込まれた「主体的・対話的で深い学び」にも通じるところがあるだろう。「旧来の教育では、先生の言うことを素直に聞く子ども、みんなと同じことができる子どもがいい子とされてきた。でもそうした時代はもう終わり、今はみんな違うことに価値がある時代になろうとしている。その子がその子らしく育つこと、自分の言葉で語りたいことを語れることが何より大切。
4「チャレンジする力」は、「失敗する力」と言い換えることができる。子どもは安心できる環境でこそ挑戦することができる。間違えたり失敗したりしたことを自覚し、やり直すことが成長につながる。木村氏は、大人は子どもが安心できる環境をつくるだけでいいという。
「大人が正解を教える必要はなく、失敗したときには『大丈夫?』と聞いて寄り添うだけでいい。『大丈夫なわけあれへん!』と助けを求めるのか、『うん、大丈夫やで』と自分で解決するのか。それも子ども自身が決めること」
こうした4つの力を伸ばすことで身に付くものを、木村氏は「見えない学力」だと説明する。これこそが、予想外の事態を自らクリアする力だ。大空小では4つの力を重視して子どもたちの「見えない学力」を高めたところ、「見える学力」である教科にも結果が表れたそうだ。その成果は大きく、全国学力状況調査で1位の県を上回った年もあるという。だがそれは「最上位の目的ではない」と木村氏は言う。
☆129日目(8.30)標語づくり その3
考えるためには、考える資料が要ります
消とても前の実践ですが、『防災について考える町づくり』に向けた消防署がさんが募集した『防災標語』です。消防署さんに用意していただいた資料担当で編集して配布し、「考えを深めて」応募しました。その中からいくつかを紹介します。
後でいい そう思うときに 起こっている
いつなのか 読めない未来に 防災を
火をつけて そのままどこかに 行かないで
家を出る時 火元確認 絶対に
生きる場所 避難場所を 再確認
家族で もしものために 備えよう
災害時 躊躇の時間は ありません
気をつけろ タコ足配線 危ないよ
日頃から 防火・防災 心がけ
探してみて 自分の家の 危険な場所
命以上 大事なものは ないんじゃない?
☆127日目(8.29)標語づくり その2
人権標語づくりについて。「仲間づくり(発達特性)」、「ホームレス問題」、「ハンセン病問題」学習を3年間重ねてきた子どもたち(3年時)がつくった標語を紹介します。
あの子、この子、全ての生徒の顔と名前を思い浮かぶことのできる、一人ひとりの学びをもとにしたオリジナルの標語だと思います。
個性を認め合うことで 絆がうまれる
正しい知識を 学び合おう
人のみためじゃなく 中身をみよう
人権というものを知り 自分たちで 差別をなくしていこう
どうするべきか ではなく どうあるべきか
人権は みんなを守る 盾となる
大切な事は 人と違う意見でも逃げず 正面から向き合うこと
人と人と 互いを認め 生きていく
近い距離 心の目では 遠い距離
「わかった」と 一言だけで 終わるのではなく 行動であらわそう
認め合い あなたの個性を 伸ばそうよ
仲間たちよ 正しい知識を学び 絆を深め
正しい行動は みんなの人権を 学び合う
一人ひとり 違うところがあるのは あたり前
あの人嫌い その差別 あなたは正しいと思いますか
僕たちは つながり生きる 命たち
なかまとは 学び合って 認め合う
このクラスは 絆を深めるためのクラス
花が咲き 色とりどりに 風にゆれる どれも美しく どれも違う
人を守り 人に守られる それが正しい つながりかた
勇気をもった行動が 反差別につながる
きもちわるい そんな理由じゃ バカバカしい
なかまとの絆 学び合う学校へ
あなたは知ってる? 正しい知識
僕たちは なかまと共に 助け合う
お互いの 人生変える そのいじめ
人とはみな 人とつながり 生きている
☆126日目(8.28)始業式の日、時間割
始業式(8月の登校日)の日には何(時間割)をしたらいいのでしょうか?
もちろん、しなければならないことはたくさんあります。宿題・提出物の提出、点検、課題テスト、2学期からの行事や授業についての伝達事項・注意事項・・・などなど。でも、やっぱり、40日間の一人ひとりの夏休みのくらしや体験を語り合う、共有する活動時間を捻出したいと思います。班別健康観察一覧表への記入するグループ活動や、夏休み報告書の作成(→掲示)や、1分間報告スピーチ(→1週間継続的に、全員が話す)など、計画的に「子どもたちが関わり合う」学習の時間をつくりたいですね。
また、始業式で教職員がスピーチする内容も、生徒会長のスピーチと合わせて、話者(担当者)どうしで、「意図的」「重厚」な構成化を進めたいものです。
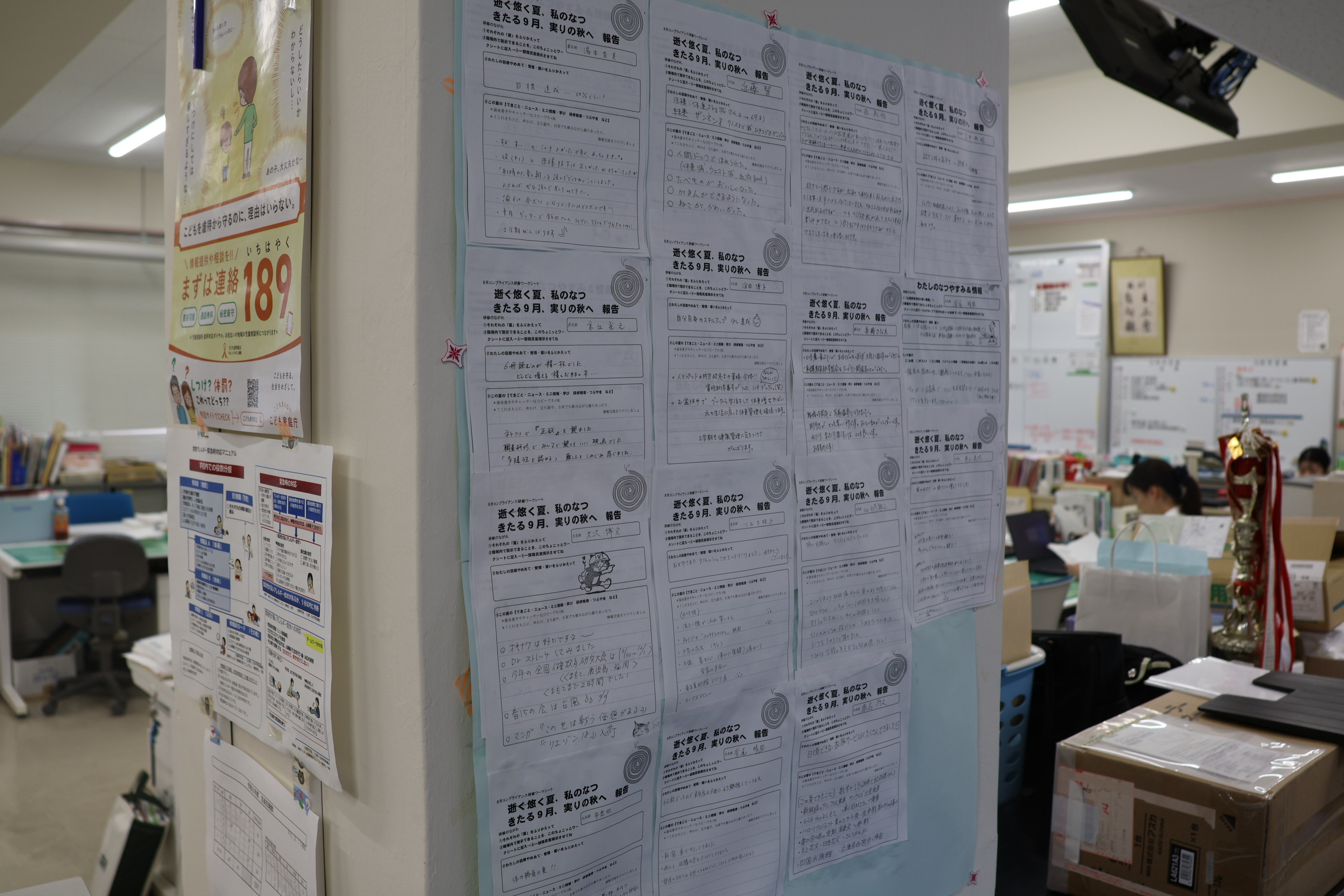
先生たちも、この夏を振り返り、取り組んだ「夏の報告」掲示しました。一人ひとりの夏の経験や体験のお話はステキです。
☆125日目(8.27)義務教育後の進路について、「春15の会」
取材記事が山陽新聞に記載されました。本当の課題解決の取組ではありませんが、すべての子どもたちの進路保障を進めるためのちっちゃい事ですが、多くの方々との協働による粘り強い活動です。

☆124日目(8.26)今日は人権宣言記念日です。
前日の話を受けて、標語づくりの資料として、『世界人権宣言』や『子どもの権利条約』に出会う機会にしてはどうでしょう?と意見をいただきました。
表面的な、誰に言っているかわかりにくい、呼びかけ文ではなく、自分自身が「大切にしたい事」「気になること」条項を選び、呼びかける文にすることで、自分の立ち位置が明確になると思います。さらに、「なぜそれを選んだか?」お互いに学級で意見交流することができたらステキですね。
【世界人権宣言】
第1条 みんな仲間だ
わたしたちはみな、生まれながらにして自由です。ひとりひとりがかけがえのない人間であり、その値打ちも同じです。だからたがいによく考え、助けあわねばなりません。
第2条 差別はいやだ
わたしたちはみな、意見の違いや、生まれ、男、女、宗教、人種、ことば、皮膚の色の違いによって差別されるべきではありません。また、どんな国に生きていようと、その権利にかわりはありません。
第3条 安心して暮らす
ちいさな子どもから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、わたしたちはみな自由に、安心して生きていける権利をもっています。
第4条 奴隷はいやだ
人はみな、奴隷のように働かされるべきではありません。人を物のように売り買いしてはいけません。
第5条 拷問はやめろ
人はみな、ひどい仕打ちによって、はずかしめられるべきではありません。
第6条 みんな人権をもっている
わたしたちはみな、だれでも、どこでも、法律に守られて、人として生きることができます。
第7条 法律は平等だ
法律はすべての人に平等でなければなりません。法律は差別をみとめてはなりません。
第8条 泣き寝入りはしない
わたしたちはみな、法律で守られている基本的な権利を、国によって奪われたら、裁判を起こし、その権利をとりもどすことができます。
第9条 簡単に捕まえないで
人はみな、法律によらないで、また好きかってに作られた法律によって、捕まったり、閉じこめたり、その国からむりやり追い出されたりするべきではありません。
第10条 裁判は公正に
わたしたちには、独立した、かたよらない裁判所で、大勢のまえで、うそのない裁判を受ける権利があります。
第11条 捕まっても罪があるとはかぎらない
うそのない裁判で決められるまでは、だれも罪があるとはみなされません。また人は、罪をおかした時の法律によってのみ、罰をうけます。あとから作られた法律で罰を受けることはありません。
第12条 ないしょの話
自分の暮らしや家族、手紙や秘密をかってにあばかれ、名誉や評判を傷つけられることはあってはなりません。そういう時は、法律によって守られます。
第13条 どこにでも住める
わたしたちはみな、いまいる国のどこへでも行けるし、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどることも自由にできます。
第14条 逃げるのも権利
だれでも、ひどい目にあったら、よその国に救いを求めて逃げていけます。しかし、その人が、だれが見ても罪をおかしている場合は、べつです。
第15条 どこの国がいい?
人には、ある国の国民になる権利があり、またよその国の国民になる権利もあります。その権利を好きかってにとりあげられることはありません。
第16条 ふたりで決める
おとなになったら、だれとでも好きな人と結婚し、家庭がもてます。結婚も、家庭生活も、離婚もだれにも口出しされずに、当人同士が決めることです。家族は社会と国によって、守られます。
第17条 財産をもつ
人はみな、ひとりで、またはほかの人といっしょに財産をもつことができます。自分の財産を好きかってに奪われることはありません。
第18条 考えるのは自由
人には、自分で自由に考える権利があります。この権利には、考えを変える自由や、ひとりで、またほかの人といっしょに考えをひろめる自由もふくまれます。
第19条 言いたい、知りたい、伝えたい
わたしたちには、自由に意見を言う権利があります。だれもその邪魔をすることはできません。人はみな、国をこえて、本、新聞、ラジオ、テレビなどを通じて、情報や意見を交換することができます。
第20条 集まる自由、集まらない自由
人には、平和のうちに集会を開いたり、仲間を集めて団体を作ったりする自由があります。しかし、いやがっている人を、むりやりそこに入れることはだれにもできません。
第21条 選ぶのはわたし
わたしたちはみな、直接にまたは、代表を選んで自分の国の政治に参加できます。また、だれでもその国の公務員になる権利があります。みんなの考えがはっきり反映されるように、選挙は定期的に、ただしく平等に行なわれなければなりません。その投票の秘密は守られます。
第22条 人間らしく生きる
人には、困った時に国から助けを受ける権利があります。また、人にはその国の力に応じて、豊かに生きていく権利があります。
第23条 安心して働けるように
人には、仕事を自由に選んで働く権利があり、同じ働きに対しては、同じお金をもらう権利があります。そのお金はちゃんと生活できるものでなければなりません。人はみな、仕事を失わないよう守られ、だれにも仲間と集まって組合をつくる権利があります。
第24条 大事な休み
人には、休む権利があります。そのためには、働く時間をきちんと決め、お金をもらえるまとまった休みがなければなりません。
第25条 幸せな生活
だれにでも、家族といっしょに健康で幸せな生活を送る権利があります。病気になったり、年をとったり、働き手が死んだりして、生活できなくなった時には、国に助けをもとめることができます。母と子はとくに大切にされなければいけません。
第26条 勉強したい?
だれにでも、教育を受ける権利があります。小、中学校はただで、だれもが行けます。大きくなったら、高校や専門学校、大学で好きなことを勉強できます。 教育は人がその能力をのばすこと、そして人としての権利と自由を大切にすることを目的とします。人はまた教育を通じて、世界中の人とともに平和に生きることを学ばなければなりません。
第27条 楽しい暮らし
だれにでも、絵や文学や音楽を楽しみ、科学の進歩とその恵みをわかちあう権利があります。また人には、自分の作ったものが生み出す利益を受ける権利があります。
第28条 この宣言がめざす社会
この宣言が、口先だけで終わらないような世界を作ろうとする権利もまた、わたしたちのものです。
第29条 権利と身勝手は違う
わたしたちはみな、すべての人の自由と権利を守り、住み良い世の中を作る為の義務を負っています。自分の自由と権利は、ほかの人々の自由と権利を守る時にのみ、制限されます。
第30条 権利を奪う「権利」はない
この宣言でうたわれている自由と権利を、ほかの人の自由と権利をこわすために使ってはなりません。どんな国にも、集団にも、人にも、そのような権利はないのです。
出典:わかりやすい谷川俊太郎訳 世界人権宣言
アムネスティ世界人権宣言 : アムネスティ・インターナショナル日本 AMNESTY
国連広報センターでも英語からの日本語訳を以下のページに紹介しています。
世界人権宣言テキスト | 国連広報センター (unic.or.jp)
【児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)】要約
第1条 子どもの定義
18歳になっていない人を子どもとします。
第2条 差別の禁止
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障害があるかないか、お金持ちであるかないか、などによって差別されません。
第3条 子どもにとってもっともよいこと
子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。
第4条 国の義務
国は、この条約に書かれた権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
第5条 親の指導を尊重
親(保護者)は、子どもの心やからだの発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。
国は、親の指導する権利を大切にしなければなりません。
第6条 生きる権利・育つ権利
すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。
第7条 名前・国籍をもつ権利
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。
子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。
第8条 名前・国籍・家族関係を守る
国は、子どもの名前や国籍、家族の関係がむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。
もし、これがうばわれたときには、国はすぐにそれを元どおりにしなければなりません。
第9条 親と引き離されない権利
子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。
第10条 他の国にいる親と会える権利
国は、はなればなれになっている家族がお互いが会いたい、もう一度いっしょにくらしたい、と思うときには、できるだけ早く国を出たり入ったりすることができるように扱わなければなりません。親がちがう国に住んでいても、子どもはいつでも親と連絡をとることができます。
第11条 よその国に連れさられない権利
国は、子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにしなければなりません。
第12条 意見を表す権利
子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
第13条 表現の自由
子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
第14条 思想・良心・宗教の自由
子どもは、思想・良心および宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務をもっています。
第15条 結社・集会の自由
子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
第16条 プライバシー・名誉は守られる
子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。
第17条 適切な情報の入手
子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れることができます。国は、マスメディア(本・新聞・テレビなど)が、子どものためになる情報を多く提供するようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。
第18条 子どもの養育はまず親に責任
子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。
第19条 虐待・放任からの保護
親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。
第20条 家庭を奪われた子どもの保護
子どもは、家族といっしょにくらせなくなったときや、家族からはなれた方がその子どもにとってよいときには、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。
第21条 養子縁組
子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいことを考え、その子どもや新しい父母のことをしっかり調べたうえで、国や公の機関だけがそれを認めることができます。
第22条 難民の子ども
ちがう宗教を信じているため、自分の国の政府と違う考え方をしているため、また、戦争や災害がおこったために、よその国にのがれた子ども(難民の子ども)は、その国で守られ、援助を受けることができます。
第23条 障害のある子ども
心やからだに障害があっても、その子どもの個性やほこりが傷つけられてはなりません。国は障害のある子どもも充実してくらせるように、教育やトレーニング、保健サービスなどが受けられるようにしなければなりません。
第24条 健康・医療への権利
国は、子どもがいつも健康でいられるように、できるかぎりのことをしなければなりません。子どもは、病気になったときや、けがをしたときには、治療を受けることができます。
第25条 病院などの施設に入っている子ども
子どもは、心やからだの健康をとりもどすために病院などに入っているときに、その治療やそこでの扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらうことができます。
第26条 社会会保障を受ける権利
子どもやその家族が生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、国がお金をはらうなどして、くらしを手助けしなければなりません。
第27条 生活水準の確保
子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な生活を送る権利をもっています。親(保護者)はそのための第一の責任者ですが、親の力だけで子どものくらしが守れないときは、国も協力します。
第28条 教育を受ける権利
子どもには教育を受ける権利があります。国はすべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、人はだれでも人間として大切にされるという考え方からはずれるものであってはなりません。
第29条 教育の目的
教育は、子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなとなかよくすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。
第30条 少数民族・先住民の子ども
少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもが、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利を、大切にしなければなりません。
第31条 休み、遊ぶ権利
子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。
第32条 経済的搾取・有害な労働からの保護
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利があります。
第33条 麻薬・覚せい剤などからの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条 性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第35条 ゆうかい・売買からの保護
国は、子どもがゆうかいされたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。
第36条 あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
第37条 ごうもん・死刑の禁止
どんな子どもに対しても、ごうもんやむごい扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。もし、罪を犯してたいほされても、人間らしく年れいにあった扱いを受ける権利があります。
第38条 戦争からの保護
国は、15歳にならない子どもを兵士として戦場に連れていってはなりません。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてしなければなりません。
第39条 犠牲になった子どもを守る
子どもがほうっておかれたり、むごいしうちを受けたり、戦争にまきこまれたりしたら、国はそういう子どもの心やからだの傷をなおし、社会にもどれるようにしなければなりません。
第40条 子どもに関する司法
国は、罪を犯したとされた子どもが、人間の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになることを考えて、扱われなければなりません。
出典:財団法人日本ユニセフ協会ホームページ

☆123日目(8.26)「○○啓発標語、○○スローガン」募集にどう応えるのか?
法務局の「人権啓発標語コンテスト」の締切が近くなりました。子どもたちはどうやって標語を〈創って〉いますか?
「なかなか取り組む時間が取れなくて、応募用紙を配って、教師が少しだけ〈人権の話〉をして、〈書かせ〉、〈回収〉するだけになって、「せっかく人権について、クラスの仲間と人権を考える貴重な機会なのに、活かせることが出来ていない」という話もよく聴きます。
そのため、ここ数年間、ちょっと工夫して、子どもたちの豊かな発想で標語が創れるようにしています。それは、前年度の秋や人権週間の取組時に、まとめや、振り返りをするワークシートに、学んだ事を、短いコトバ(標語やスローガン)でまとめる記入枠を用意するのです。*これは、クラス掲示にも活用できます。この記入枠に書かれた、《活きた学びのコトバ》を次年度まで大切に保管しておき、啓発標語(=学習成果)として募集するのです。「ホームレス問題学習」に取り組んだ生徒の「標語・スローガン」例です。
○共に生きよう!
○認め合い 学び合える なかまをつくる
○一人ひとりの優しい行動が 絆につながる
○みんな 共に生きる仲間 認め合おう
○未来には ホームレスの人をなくそう
○反差別 正しい知識で 未来へ
○認め合う 学び合う 共に生きる社会を 正しい知識でつくろう
これまでの入賞作品を参考に10分程度で〈書かせ〉る取組は、生徒の「思考すること」「思いを馳せること」を軽んじていくように思えるのです。取り組むのなら、子どもたちがしっかり考えられる資料の〈提示〉をがんばって準備しましょうね!本校でも今年は、資料の準備を重視しています。『教室はまちがうところだ 蒔田 晋時』、詩『へいわってすてきだね 安里 有生くん(久部良小学校1年)』はどうでしょう?。

☆122日目(8.24)津山洋学資料館フィールドワーク
この夏も、津山洋学資料館(刑場跡・千人塚)や、長島愛生園、渋染一揆関係地に行ってきました。
フィールドワークとは、社会学や人類学から始まったリサーチの手法です。机上の書物を離れて、フィールド(学習対象の現地)を訪れ、フィールドの事情を直接視察したり、関係する方々や専門家から話を聴いたりしていく中で、問題点を明らかにして、学習を深めていきます。本や講義だけでは学べない知識や情報を直接現地で学ぶ、これがフィールドワークです。フィールドで、これまで当たり前に思っていた価値観や常識が自明のものではないことに行く度にいつも気付かされます。それは自分自身の生き方や、自分の生きている社会を見つめなおすことにもつながっていきます。こうしたフィールドワークは「社会づくり」につながります。現地の事情を調べ、人々と話しあっているうちに、現地の人たちにはかえって見えにくい問題点や課題に気付き、一緒になって解決策や新しい活動を考えられることも多々あります。フィールドワークはたんに学問的成果をあげるだけでなく、社会につながる取組であり、社会づくりやシチズンシップの醸成に寄与します。
2学期、3年生も長島愛生園でのフィールドワークを計画しています。



☆121日目(8.17)第75回全国人権・同和教育研究大会
第1回実践報告協力者会議に教頭先生が参加されました。今年度は、熊本・鹿児島・福岡会場に大会が開催されるとのことです。
「岡山からなんと熊本まで新幹線で約2時間ちょい、すぐだから、行こう!」と言われてましたが・・・。大会の概要を紹介します。
この大会は、第50回九州地区人権・同和教育夏期講座、第49回鹿児島県人権・同和教育研究大会、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす第52回熊本県人権教育研究大会を兼ねています。
《「差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」このテーマのもと、全国各地で取り組まれている人権・同和教育の実践を交流し、学び合う。
全国人権教育研究協議会は、1953年、前身である全国同和教育研究協議会(全同教)結成以来、毎年全国人権 ・同和教育研究大会(研究大会)を開催してきました。一貫して、「教育の中にある差別をなくすため、地域・親や子どもたちを取り巻く現実から学ぶこと」を大切にしてきました。
熊本県人権教育研究協議会は、「たじろがず部落の子どもを中軸にすえて そこから新たな方向を見出してきた」先達の思いを受け継ぎ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、誰もが幸福に生きることのできる社会をつくり、「水平の佳き日」を実現するために取り組んできました。
私たちはもっと学びたい。同和対策事業特別措置法に始まる諸施策が2002年を境に一般施策に移行し、集会所の灯が消されていく中でもなお解放の火を掲げて学ぶなかまたちのことを…。
私たちはもっと学びたい。差別をなくすために、今日の社会の中で被差別の位置に立たされている子どもや親とともに歩き続けている人たちの姿に…。
学ぶことで私たちは、「たじろがず部落の子どもを中軸にすえて、そこから新たな方向を見出してきた」熊本の先達の思いを今一度自分のものにしたい。そして、これからの熊本や九州を担う人たちに、全国のなかまたちの強さ、厳しさ、優しさに出会って欲しい…。
このような現地の願いのもと、2011年鹿児島大会以来、13年ぶりに九州の地で研究大会を開催します。世界では、各地で戦争・紛争や武力衝突が起こり、暴力と差別・迫害が絶えません。また、人種・民族・宗教・政治体制等のちがいを理由に、分断と対立がすすみ、人権を無視する事態も発生しています。国内でも、部落問題をはじめさまざまな人権問題が解決されず、差別を温存する考え方も、未だ根強く存在しています。貧困等により人びとが生きづらくさせられている社会状況とも重なり、個人の尊厳と人権を否定する不寛容な風潮が広がり、さまざまな人権侵害が起こっています。また、情報技術の飛躍的な発展と並行し、ネット上には部落差別を煽る情報や在日韓国・朝鮮人へのヘイトスピーチをはじめ、社会的マイノリティや社会的弱者への攻撃があふれています。私たちは、このような状況に『たじろぐ』ことなく、人が人を思う「人の世の熱」を信じたいと思います。
そして、一人ひとりが持つ人を幸せにする力「にんげんの光」を結集し、「『事実と実践・創造』~であう つながる『ひと なかま まち』」の地元大会テーマのもと、すべての人が安心して生活できる「水平の佳き日」を、人権教育の事実と実践からともに創り、子どもたちに継承していきましょう。
ぜひとも、熊本、福岡、鹿児島の地にご参集いただき、研究大会を成功に導いてくださいますようお願いします。》(全人教HPより)
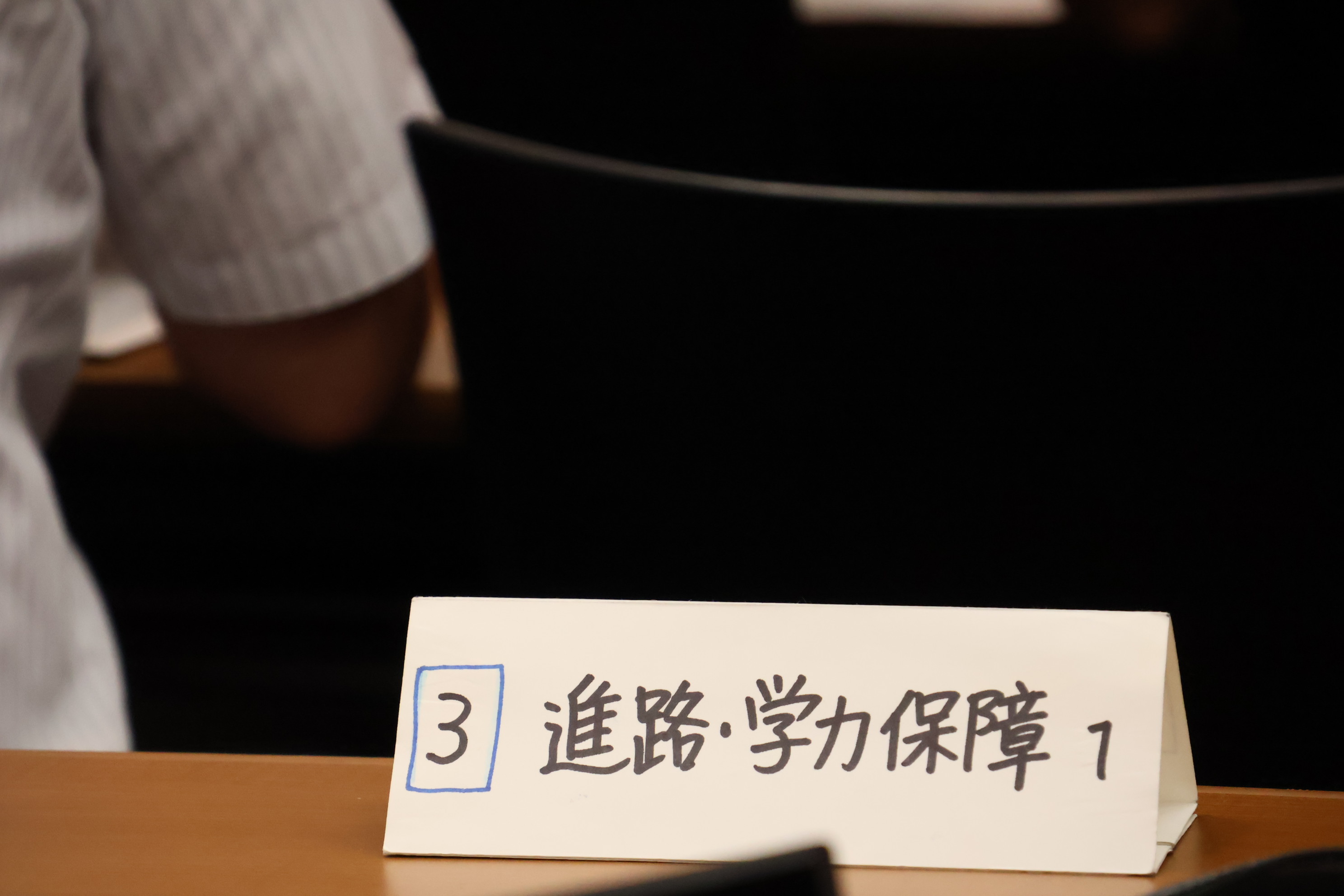
☆120日目(8.13)まちづくりにつながる教育内容の創造を。
8月13日、生徒と共に、ひなせみなとまつりへ参画(日生中ボランティア推進プロジェクト)。「中学生が出店しとんか!」「ひな中がんばっとるなあ」「参加してくれてうれしいなあ」などなど、準備期間から当日まで、たくさんの激励とエールのコトバや支援をいただきました。
住んでいる一人ひとりが自らの存在と人権が守られ、「生きがい」や「学びがい」や「働きがい」を実感できる豊かな生活を創り出すことを「人権のまちづくり」として、全同教(全国人権・同和教育研究協議会)は提案してきました。この「人権のまちづくり」のモデルは、これまでの同和教育、解放運動、そして人権教育の中で育まれてきました。住民の主体的な参加によって住民自治を育みながら地域共同体としての「まちづくり」が行われてきました。この運動の教訓が生かされて、各地で様々で豊かな取り組みがすすめられ、ムラから周辺地域へ「人権のまちづくり」がひろめられ、様々な立場の人との出会いや連帯が生まれ発展してきた歴史があります。そんな実践から導かれたキーワードとして「協働」と「参画」があります。一つの目標に向かってともに情報を共有し、ともに協力して活動に取り組む「協働」と、様々な活動に企画段階から参加していく「参画」です。2つのキーワードを核にして、職域や立場を乗り越えた活動が進められ、地域教育コミュニティが形づくられていくということです。
子どもたちをとりまく状況は、残念ながら、幼い子どもたちの命が奪われる痛ましい事件など、深刻さを増しています。もしかしたら、子どもたちを支え育てるまちづくりがあらゆるところで具体的に機能していれば避けられた事件もあったのではないかとも思われます。子どもの安全面や教育活動への支援、あるいは児童虐待防止に向けた支援など、子どもの命と人権を守り、育ちを支えるまちづくりの必要性は、ますます高まっています。(だからこそ、学校(こ・園・小・中)と家庭・地域、そして子どものために活動する様々な人々との協働といったボトムアップの手法とともに、行政的な支援も不可欠です。)「子ども(学校)を支え、育てるまちづくり」という目標にむけて様々な人々、関係機関等の協働と参画をどう構築していくのか、実践を重ねながら、確かなあり方を明らかにしていきたいと思います。

☆119日目(8.6)備前市教職員人権教育研修会会
『前田 良さん 講演会『パパは女子高生だった』に参加しました。(―女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ(←これは書籍の題))
学校現場では性の多様性や性的マイノリティについて学んだ経験がない教職員はまだまだ多いと言われています。当事者の教職員も存在しますが沈黙を強いられているのが現状です。性の多様性や性的マイノリティに関して学校で学ぶ機会があったという生徒も全体の9%に過ぎず、ほとんど学ばないまま社会に出て行くというのが実状です。学校では性的マイノリティは「いない」「見えない」存在とされる一方で、性的マイノリティをからかい傷つけ否定する言葉を聞いたことがある児童生徒は 74%に上ります(「NPO法人 ReBit の 2015 年調査」)。
性の多様性について学習に取り組み始めたものの、男女別の制服(標準服)やトイレ・更衣室、健康診断や修学旅行の部屋など性的マイノリティの子どもたちが直面している問題には無自覚なままという現実もあります。そうした実態の中で性的マイノリティの子どもたちは、部落や在日韓国・朝鮮人の子どもがそうしてきたように、息を潜めるように自分の存在を隠し、性的マイノリティとして生きることを諦めざるを得ないのが現実です。人生設計や進路・就職についても、書類の性別欄でつまずいたり不安を持たざるを得ない実態もあります。思春期には性的指向や性自認について揺らぎがあることも知らなければなりません。教職員が性的マイノリティについての理解を深めなければ子どもたちの悩みを受け止めることはできません。性的マイノリティの人たちが安心して自分の性を明らかにし、ありのままの自分で過ごせ学べる学校づくり、職場づくり、地域づくりに取り組んで行かなければなりません。まずは最低限の知識の共有から始めて、性的マイノリティであってもそうでなくても過ごしやすい環境をつくるために、各地の学校、職場、地域で研修・研究と実践に積極的に取り組むことが大切です。「いじめ防止対策推進法」(2013 年施行)に基づく国の基本方針に障害者や性的マイノリティが取り上げられ、教職員の理解促進と差別やいじめの防止に取り組むことが明記されています。性の多様性や性的マイノリティについて子どもたちと一緒に学習に取り組んでいきたいと思います。
☆118日目(8.3)知った気になったらいけませんね
もっともっともっと学ばなければいけません(自省)。この6月に縁あってから、徳田靖之のお話しを聴き、著書『感染症と差別』、ハンセン病市民学会年報(2020~2022)を読みました。「知った気になってはいけない」と思いながら、私自身が知った気になっていました(自省)。
かもがわ出版さんのHPの一部を紹介し、徳田靖之著『感染症と差別』の一読をお薦めします。
出版まで〜編集者が考えてきたこと
弁護士・徳田靖之さんによる著作『感染症と差別』。企画・編集された八木絹さん(フリーランス編集者、戸倉書院代表)に、刊行にいたるまでのエピソードを書いていただきました。全4回の第1回目です。
・第1回 コロナ禍で差別発言が溢れ出た
「感染者は、社会にとって迷惑な存在ではなく、社会を挙げて守るべき存在である」「ハンセン病やエイズにおいて繰り返された痛恨の過ちが、またもや繰り返されていることに我慢がならなかった」(「はじめに」4、5ページ、カッコ内のページはすべて本書)
・本書のコンセプトはこの言葉にすべてあらわされています。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団共同代表、薬害エイズ九州訴訟共同代表などとして、日本の大きな感染症の裁判を長年当事者とともにたたかい、人の心に潜む差別の問題を考え抜いてきた徳田靖之弁護士だからこそ書くことができた本だと思います。詳しい内容は本書をお読みいただくとして、ここでは本書の出版秘話といいますか、日ごろ読者と接する機会のない編集者が何を考え、どんな仕事をしているのか、お話ししたいと思います。
・感染者は不注意で不心得な者…か?
この本の企画を始めたのは2020年9月、新型コロナウイルスによる感染症への誹謗中傷が起こっていた最中のことです。前年暮れに中国武漢で始まった新型コロナウイルス感染症は、
2020年に入ると瞬く間に世界に広がりました。
日本では、ダイヤモンド・プリンセス号内での感染拡大を経て、一般市民にも広がっていきましたが、その過程で特筆すべきは、行政とメディアが「夜の街」などという言葉を使って、繁華街で酒を飲みながら騒ぐ人が感染を広げているという固定したイメージをつくり、感染者は不注意で不心得な者であるという認識を一般市民に広げたことです。県をまたぐ移動や飲食店の利用が規制されていく中で、他人の行動を監視する“自粛警察”なる言葉も発生。ネット空間などに感染者への誹謗中傷が蔓延していきました。
クラスターが発生した学校などに非難の電話が殺到し、感染して回復した人でも、学校や職場での非難の目に耐えかねて復帰できず、自死に至る例まで出ました。医療関係者の子どもを登園させない保育園が出たり、誹謗の言葉が投げかけられたりしました。
誰もがコロナウイルスに感染する可能性があるのに感染者を攻撃するとは、感染者のために献身的に働く医療従事者を追い詰めるとは、この国はいったいどうなってしまったのだろうと絶望的な気持ちになりました。同時に、これまで人権や平和、ジェンダーなど社会問題に関する書籍を編集してきた者として、この事態に一石を投じる本がつくれないかと考えるようになりました。その時心に浮かんだのは、数年前から関心を持ってきたハンセン病差別の問題です。
・ハンセン病差別の歴史に酷似している
ハンセン病の元患者の方たちが住む多磨全生園(東京都東村山市)は私の住まいから車で40分ほどの所にあります。2018年のある朝、NHKニュースで、元患者の方が偏見と差別に苦しんできた人生を語る「語り部の会」を続けていること、元患者の高齢化と社会の関心が薄れてきたことから、存続が難しいと報じているのを聞き、この会に参加することにしたのが、ハンセン病差別問題に関心を持ったきっかけです。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟(1998年提起、2001年判決=いわゆる熊本判決)での原告勝訴という快挙を知っていながら無関心だった私の、あまりにも遅すぎる学習の開始でした。
国立ハンセン病資料館(多磨全生園敷地内)での「語り部の会」で何人もの元患者の方の人生の物語を聞き、映画を見、関連の書籍を読んでいきました。群馬県草津の栗生楽泉園内にある重監房(*)跡と重監房資料館にも足を運びました。そうしたことを通じて、明治以降日本国家が欧米列強並みの「一等国」、つまり戦争に勝つ国になっていくために、「国辱」とさえいわれたハンセン病(当時は癩病と呼んでいました)の「撲滅」に血眼になった歴史があり、それが市民の中に強烈な差別意識を醸成したことを知りました。
*「特別病室」の名で1938年に設置され47年まで運用された懲罰施設。療養所長に与えられた懲戒拘束権をもって入所者を監禁した。9年間で93人が収監され、冬季には零下17度となる過酷な環境下で22人が死亡した(45、57ページなど)。
コロナ禍における感染者への偏見差別は、この歴史に酷似している、それを繰り返していると思いました。後で知りましたが、ハンセン病元患者のみなさんはこの事態に直面し、差別の歴史を繰り返すなと声を上げておられたそうです。
・語れるのはこの人しかいない
そんなとき、NHK(Eテレ)の「こころの時代」という主に宗教者が登場する番組に徳田靖之弁護士が出演した回(「光を求めてともに歩む」)の再放送を目にしました。
私(編集者)は、徳田弁護士がハンセン病家族国家賠償請求訴訟(2016年提起、2019年判決)のすぐ後に行った講演を聞いていました。熊本県の黒川温泉宿泊拒否事件の際に、菊池恵楓園(熊本県合志市)の入所者たちに全国から届いた誹謗中傷の手紙やはがき(*)(114ページ以降)を取り上げ、徳田弁護士は「元患者を自分より下に見て、気の毒な人だと同情している時には差別的なことを言わなかった人たちが、元患者が自分と同じ人間として人権を主張し始めると、とたんに『身の程を知れ』と激しく攻撃する」と語りました。これまで聞いたことがない見方で、これこそ差別の本質だと強い衝撃を受けました。差別者でないと自認している人ほどこうした心情に陥りがちなのではないか、これは厄介な問題だとも感じました。
*2003年9月、熊本県が里帰り事業として菊池恵楓園の入所者(熊本県出身者)を対象に黒川温泉一泊旅行を計画、同温泉内のホテルを予約したところ、ホテルが受け入れを拒否。県がこれを批判したことからホテルは拒否を撤回し、入所者に謝罪した。入所者がホテル支配人を批判する様子が報道されたテレビニュースなどを見た人から批判が寄せられた。
・「こころの時代」に戻りますと、徳田弁護士は、戦争で結核を発症した父親を幼くして亡くし、祖父母に育てられたこと、夫を失った若き母親が失意のあまり心を病んだことを語っていました。それが自らの弁護士としての原点だというお話は、私に二度目の衝撃を与えました。「感染症と差別の問題を語れるのは、この人しかいない」と確信し、私は番組が終わるとすぐに徳田弁護士に手紙を書き始めたのです。 https://note.com/kamogawa_syuppan/n/nde1399fe7374 かもがわ出版 から
・11月16日(土)「金泰九さんに学ぶ教育実践交流会」では、徳田さんの講演会を予定しています。
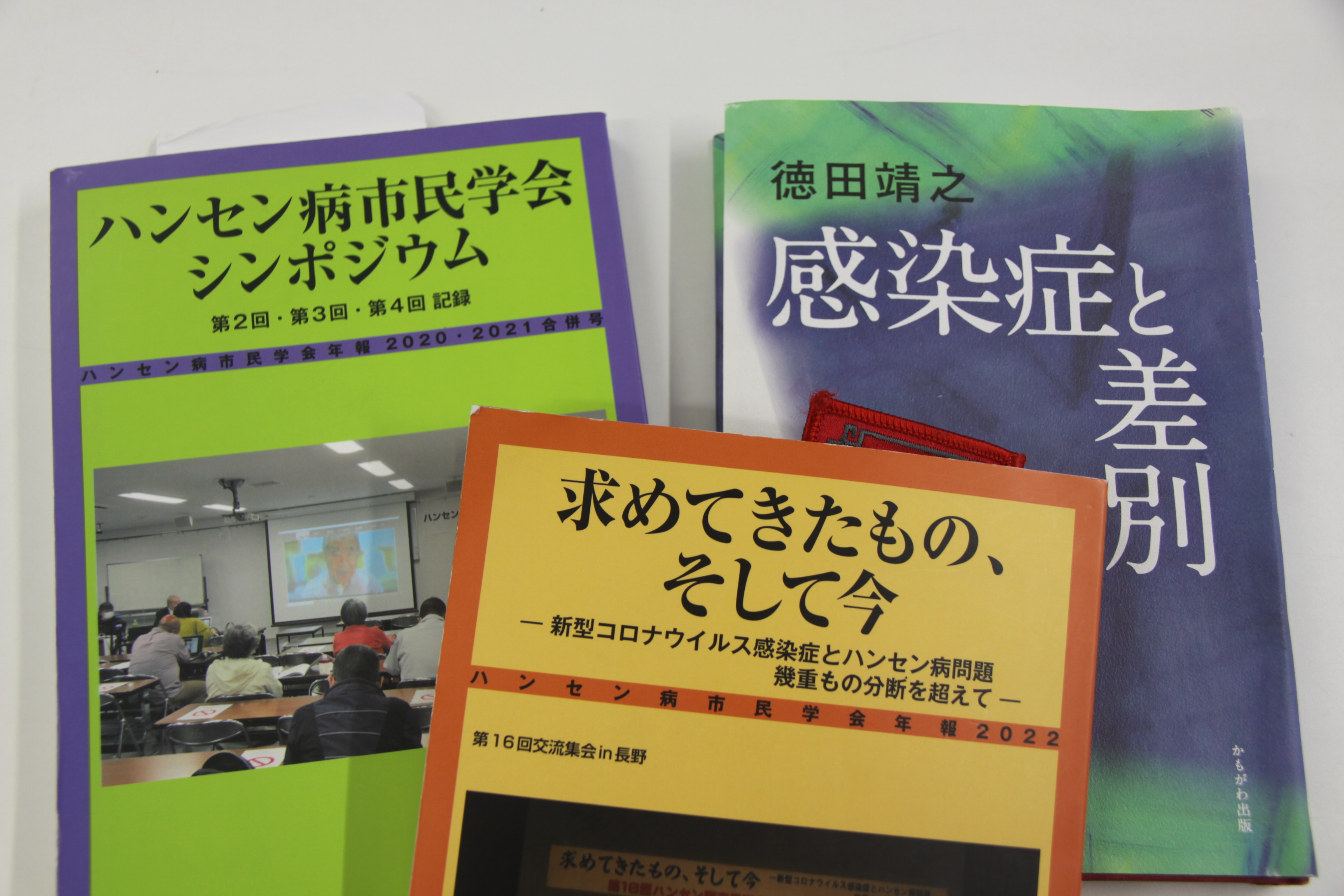
☆酷暑お見舞い申し上げます。一休み 一休み。

☆117日目(7.31)同和教育から引き継いでいくこと〈ご案内〉
〈シン・仲間づくりのための学級・学年通信〉を縁あって岡山県教職員組合夏季自主編成講座のひとつとして行います。『自分のめざす「クラスづくり」を進めたり、また、教育課題を解決したりするために、学級通信にひと工夫を加える(人権教育での仲間づくりの技)と、効く「通信」になります。子どもと子どもをつなぐとはどういうことか?、いじめや不登校を生まないクラスづくりのために「通信」はどう活用できるのか?5分で出来る通信の作成方法、年間200号を発行する方法など、その考え方を確認しながら、実際に作ってみよう』と働きかけています。8月6日(火)10:30~12:00を予定しています。都合がつく方はご参加していただきともに学びましょう。
☆116日目(7.30)同和教育から引き継いでいくこと
岡山県人権教育研究大会第2分科会での協議の中で、「進路保障」が話題となりました。同和教育から人権教育へ名称は変わりましたが、これまで先達らが教育実践から創りあげてきた豊かな「教育内容」があります。森実さんがまとめられた以下のHPで、同和教育の歩みが書かれています。ちなみに「統一応募用紙」(近畿高等学校統一応募用紙)は、高校生が就職試験を受験するために求人事業所に提出する用紙であり、紹介書、履歴書、調査書からなる。近畿高等学校統一応募用紙が昭和 46(1971)年2月に制定され使用されるまで、求人事業所は就職差別を温存助長する恐れのある思想、信条、宗教、尊敬する人物、支持政党、家族の資産、住居環境、家族の学歴などの記入項目のある独自の応募用紙<社用紙>の提出を求めていたが、そのことによって適性と能力以外のことで社会的差別を受けてきた多くの同和地区出身生徒等、被差別の状態におかれた生徒の苦しみは計り知れないものがありました。そこで、こうした差別を生み出す社用紙を撤廃する運動の中で制定されたのが近畿高等学校統一応募用紙です。 しかしながら、近畿高等学校統一応募用紙が制定されてから50年以上が経過し、制定の趣旨が教育関係者等に徹底されていない課題もあげられています。
部落差別と同和教育(その1)|学び!と人権|まなびと|Webマガジン|日本文教出版 (nichibun-g.co.jp)
☆115日目(7.29)
岡山県人権教育研究大会に参加しました。また、この日は、全国学力状況調査の結果公表日です。「同和教育の変容と今日的意義 ―解放教育の視点から』を紹介します(https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku/85/4/85_420/_pdf)
☆114日目(7.27)
29日は、岡山県人権教育研究大会が開催されます。今年度は、2次案内チラシがなかなか届かない状況もあったのですが、どっこい今年も、東備地域から2本のレポートがあります。一つは、備前市立片上高校から「発達特性」や「支援」のありよう、そして進路保障に課する内容、もう一つは「社会科でのハンセン病問題学習」を学校の大切な取組に位置づけて継続的に取り組んでいる実践報告です。この研究大会は、「発表して、質疑応答をして終わる」スタイルではなく、報告を受け、質疑で報告内容の認識をさらに深めていきます。そして自分自身の実践や取組をもう一度見つめ直し、共に学び合う研究協議スタイルです。ぜひ第2分科会で、語り合いましょう。学びましょう。。
☆113日目(7.26)
昨日、7月25日は、長島愛生園で、「慰霊の花火大会」がありました。昨年度コロナ禍を越えて四年ぶりに開催され、今年2回となる「慰霊の花火大会」でした。一緒に行った、コロナ前の「夏祭り花火大会」を知っている友人は、「やぐらも組まれてなく、甲州音頭の歌声もなくて、少しさびしい感じがするね」とつぶやいていましたが・・・。友人に映ったこの日の愛生園の景色は、ハンセン病問題の「いまの状況」をみてとれる現実であることに間違いない。
明日は、愛生園で、フィールドワークのお手伝いをするのだが、「私はどこに立って(どんな立場で)、歴史的な遺物や建物・施設、そしてハンセン病問題についての歴史を語るべきなのか?入所者の方々から聴いた声を私は伝えることができるのか?」いつも案内しながら自問自答している。
再掲ですが、T先輩からいただいた私自身への戒めのコトバです。『何を伝えたい 何を問いかけたい そして、自分はなぜハンセン病問題にこだわるのかを明確にすることがもっとも大切なことだと思います。主旨、目的のない企画は「被差別の当事者を」利用するだけです。私はそんな企画には賛同できません。』

☆112日目(7.25)えー、あのー、えーと
昨日の内容について、以前に一緒に勤めたT先生と久しぶりに話をした。若い頃、自分の話し方のクセや特徴を気にしたり、改善することは難しいなあということになり、T先生と「話し方研究会」を立ち上げた(二人だけで)。その話し方研究会は、それぞれが授業や、学年集会や職員会議で話している内容を聞き合い、お互いに気になったことについて意見交換するのだ。「話すスピードが速いのではないか」「コトバが難しい。子どもにわかる内容で」「話すと伝えることは違うんで!」などなど、お互いに厳しく指摘し合うことで、〈語ること〉を鍛えることが出来たように思える。そして冒頭にある、「えー」「あのお」「えーと」と文章をつなぐ言葉がお互いにとても多いことにも気づかされた。「話し方研究会」を一緒にしませんか?
☆111日目(7.24)先生はいくつの、話し方・語り方・声をもっている?
ファシリテーション研修会で、M先生がそう私に尋ねられた。考えてみると、大きな声で生徒に「言う(聞かせる)」ことしか思ってなかった私は「ハッ」とした。あれから何年も経ち、どんな声で、どんな話し方がよいのか考えることが少しだけ出来るようになった。教室の後ろまでとどける声、大きな声ではなく「伝える」ことを意識した声、意思を伝える強い声、あえてクラスでひとりに語りかける声、つぶやく声、聴きながらうなずきながら発する声、時には沈黙すること、ずっと待つこと。いつも子どもたちとの向き合い方は真剣勝負だ。だからこそ声の大きさやトーン、内容は吟味したい。
☆110日目(7.23)私たち自身が豊かな発想をせねば。
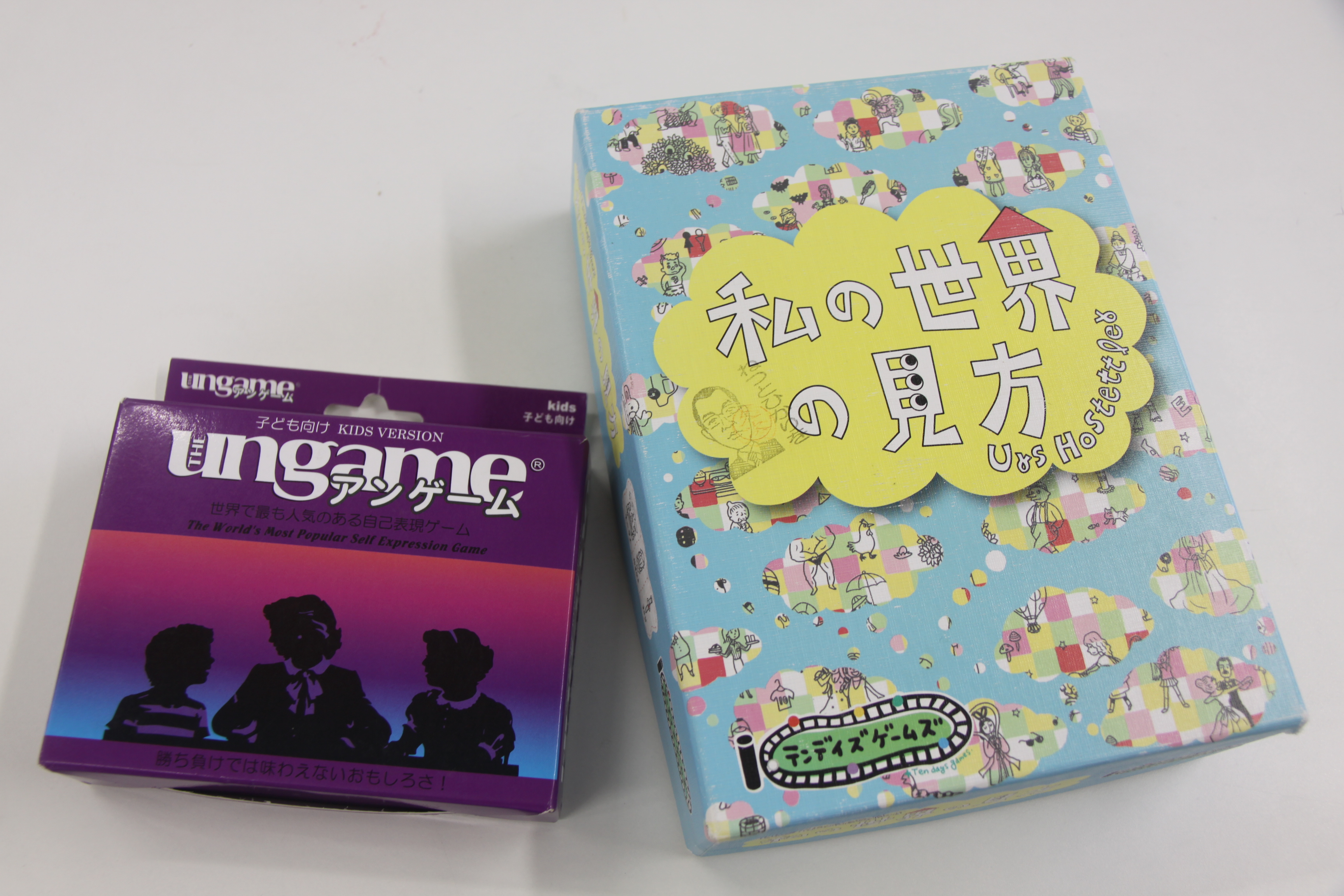
子どものたちとの活動で、SSTに積極的に取り組んむ中で、「内容が堅い、指導形式でおもしろくない、授業者だけがしゃべっている、生活につながっていない」など様々な教育現場で聞くことがありました。とある学校の友人に紹介してもらった「私の社会の見方」「アンゲーム」は、自分自身の視野を拡げてくれます。子どもたちの実態や課題に照らし合わせて運用方法やルールはアレンジして使ってみては。長期休業中に同僚と試しにしてみてください。ハズレなし。
☆109日目(7.22)自習時間で何を?
とても前の話です。急な授業変更となり、どうしても「自習」で課題プリントを用意して、教室に行くこととなりました。みなさんはどんな指示をしますか?プリントを配り、50分間黙々と取り組むこともできるのですが、学習グループのスタイルで、「「これってどうするん?」と聴き合うことをしよう」と指示しました。学年で〈共にがんばろう〉という目標をあげているのですから、具体的な場面を設定して、具体的な取組をせねばなりません。「自習」時間は、またそれまでのクラスづくりや取組・教育実践が試される時なのです。例えば「主体的に取り組むことができるようになっているクラスなのか?「わからない、教えて」と言える子どもたちが育っているか?そのつぶやきの応える仲間集団が出来ているか?」などをしっかりと看取りたいものです。また、50分の自習が終わる際には、「しっかりと仲間と大事な時間がおくれたか?」を、自習監督ではなく、授業者として、還す作業も必要となりますね。
☆108日目(7.19)長期休暇中ならではの宿題を。
以前にも紹介した「聴き取り学習」。例えば、一年生の夏には「中学校生活をたいせつにするために、仲間(友だち)に関すること」、冬には、「身近な平和について」。二年生の夏は「親(身近なひと)のしごとのついての生き様、願い」、二年生の冬は「高校時代」。そして三年生夏には「夢・未来に向けて、受験をどうこえたか(仲間と、親、自分)」を、思春期の子どもが、親と語り合うシチュエーションは結構大切な時間となります。また、聴き取りをまとめ、クラスで発表しあう時間をもつことで、より仲間を識ることができるのですな。
☆107日目(7.18)これからのハンセン病問題学習をどう進めるか
今年度の第3回金泰九さんに学ぶ教育実践交流会の案内ができました。
☆106日目(7.17)これからのハンセン病問題学習をどう進めるか
7/13に、ハンセン病市民学会「啓発資料調査部会」第4回学習会に参加してきました。弁護士の徳田靖之さんの講演「ハンセン病問題とどう向き合うべきか~司法の立場から」(主催者仮題)のお話を聴きました。これまでの取組を反省し、「もう一歩先に」進んでいくための人権教育の内実を創る「教材研究」を行い、実践をしていこうと思いました。そのいくつかは、「家族訴訟」、「黒川温泉宿泊拒否事件」、「救らい思想」、「当事者と支援者」についてです。徳田さんが、その日お話された内容が、頂いた資料にもありました。一部を紹介します。「大谷大学人権センター 人権センター叢書 VOL26『ハンセン病問題が私たちに問うもの』のP42~48」です。この内容について、ぜひ一緒に「教材化」していきましょう。
☆105日目(7.16)みんなの1777円
7/7の地域のイベントに参加した生徒たちは、しっかりと自立活動を振り返りました。また、時間をかけて精算し、お世話になった方々にお礼と会計報告をおこないました。
そして、自分たちが稼いだ「収益金をどう使うか?」これもまた大事な取組にせねばなりません。大事な1777円。
☆104日目(7.12)余計? 待ってる?
以前に勤めていた学校で、よく遅刻をしていたTくんは、職員室に寄って「遅刻手続き」して教室へ送っていました。
いつも、Tが「遅刻の手続き」をするために、職員室に入ってくると、いつも在室している教職員が気づき「おはようTくん」と寄って、そして、遅刻手続きの用紙と筆記具を用意して渡していました。 私がとても気になっていたのは、彼はこれまで「おはようございます」や「遅刻届をください」と言うことはないことですありませんでした。
とある日、同じように彼が遅刻して職員室に入ってきました。違っていたのは、(たまたま?偶然?)、在室していた教職員がTの存在に気がつかなったことでした。するとTは、当たり前のように「おはようございます」と気持ちのよいあいさつをしました。私は「おお!!!。いいあいさつだね」と声をかけ、そして、気になっていたことを素直に本人に話ました。そのあと、彼は遅刻手続きをして教室へ向かいました。
私は、学級担任にこれまでのいきさつと、今日の「いいあいさつ」だったことと、「クラスの中で」話をしてほしいことを伝えました。
・・・小さなことですが、何のために、いつ、どこまで、どのような「支援」、「サポート」「声かけ」するのか、そしてコトバを「待つ」のかなど、教育のプロとして自覚せねばならないことだなあと改めて考えたのです。
追記:その日の放課後、Tは、なぜなのか「投げキス」パフォーマンスをして下校していきました。
☆103日目(7.11)余計な指示はしない。不必要なことはしゃべらない
昨日の内容に関わって、やはり、担任からの「たくさんの」連絡事項を減らす校内体制をつくりたい。生徒連絡票に記入して、子どもから子どもへ伝えることを増やしましょう。ホワイトボードに掲示しましょう。行動の1から10までを説明する必要があるかないか?を、判断する力を磨いていきたいですね。と、言いながらこの内容も何度も繰り返しています。
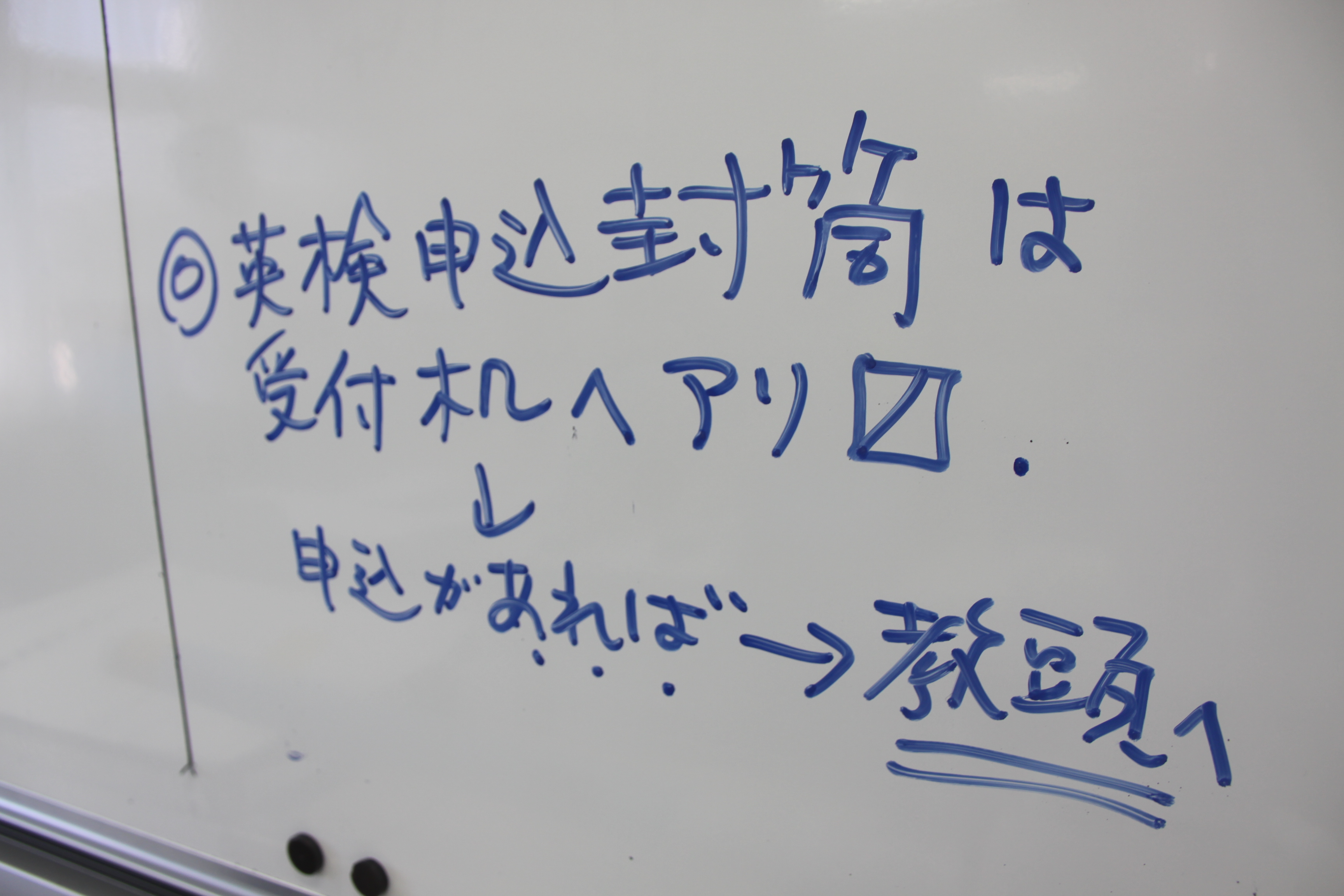
☆102日目(7.10)余計な指示はしない。不必要なことはしゃべらない
7月8日、三年英語科授業での〈アイスクリームプロジェクト〉で、生徒グループの発表は圧巻!「はい、授業始めるよ」「学級委員さん号令かけて」「じゃあ、次のグループは準備して」「はい、あいさつして、スタート」「誰が声をかけするの?○○さん、はい、どうぞ」「よかったよ。では、ワークシートに記入しましょう」、、、などの声かけが、まったくナイ素晴らしい授業指導でした。丁寧に指導、指示をしているつもりでも、子どもたちには要らない、自分たちで進めることができる」という確信をもてば、自ずから、不必要な「コトバ」は減り、教師の発するコトバの意味が変わってくるなあ。

☆101日目(7.9)地域協働と自立
7月7日の開催された「日生カキかきフェス」に参加してきました。多くの方々に支えられて、用意したフルーツアイスシャーベットは完売しました。事前に、販売する商品や種類、数量、値段を決めること、POPを作ること、お釣りの計算、呼びかけ、接客、当番シフト、そしてこの暑さの中での体調管理などなど・・・。学ぶことがたくさんありました。「振り返り」をしっかりして、本当の「生き抜く」力にしていきたいですね。


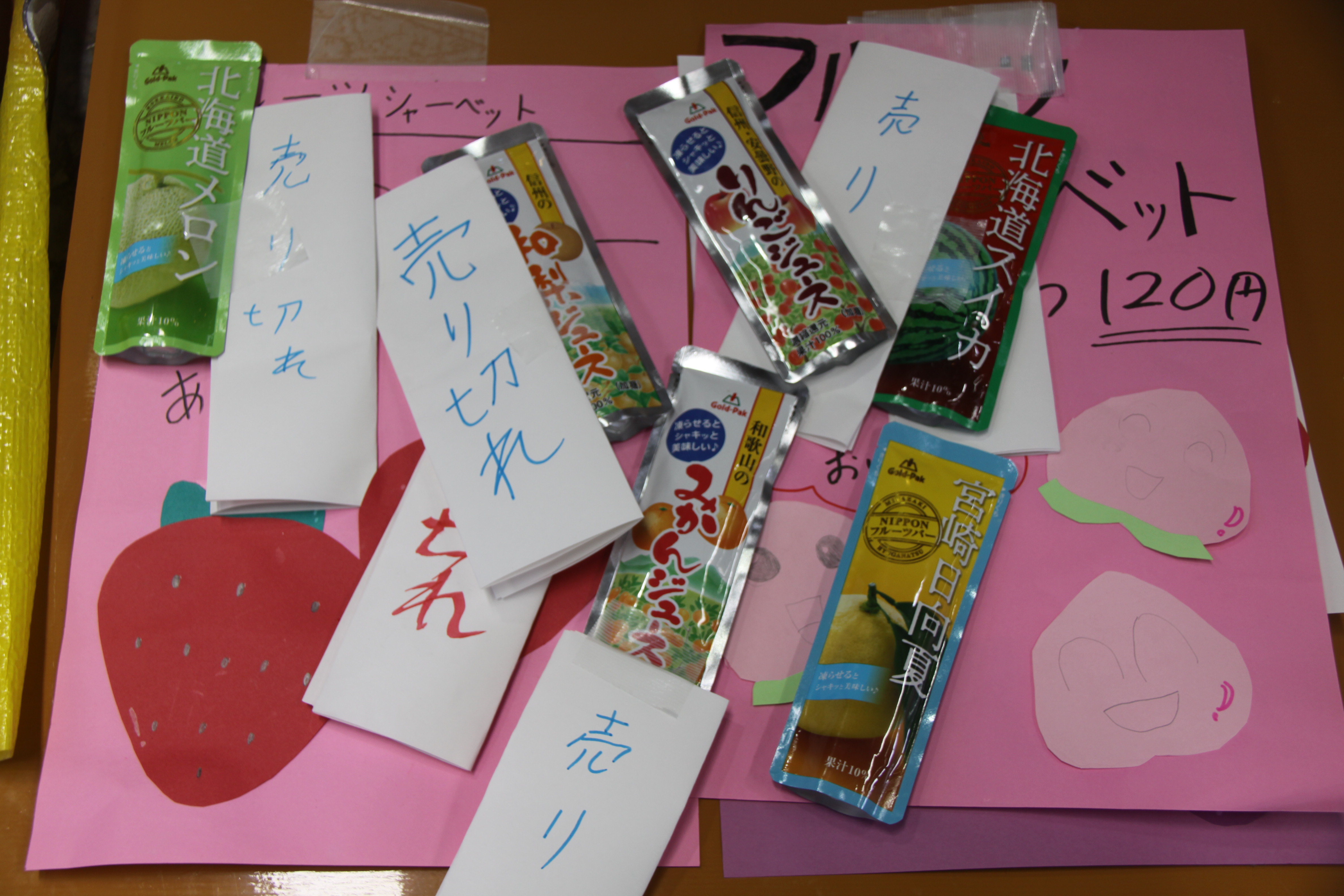
☆100日目(7.8)還すこと 友だちカウンセリング掲示
95日目に話題にしたピアサポートを参考にした「友だちカウンセリング」月に取り組んだ3年生の回答は、今回はサブ教室に掲示しました。掲示をしていると、「また、やりたい。もっとじっくり応えたかった。受験が近づいてきたときにもう一度したいなあ」と話してくれた生徒がいました。取組の振り返りを担任の先生と少し話しました。①質問数の精選が必要。グループの中で意見を出し合いじっくり「応える」時間をもちたい。全員分に応えるというのもポイントなのですがどうするかなあ。②掲示の方法や、掲示の準備も視野に入れてワークシートを工夫せねばならないこと。今回はA4両面のワークシートを用意しましたが、結局掲示する際には、A4両面をB4の2面に印刷しなおしました。39人分の質問を掲示するには、A4版かな。③質問に応える時間をしっかりとるために、グループの名前を一回ずつ書く時間と、質問項目は、事前に記載しておくような準備が必要だったのかも。いずれにせよ、子どもたちの状況や、目的・ねらいを明確にしていかないといけませんね。一生懸命に取り組む3年生諸君!ステキです!(掲示時期は夏休み終了まで。いつまでも貼っておきません。旬がありますからね。)

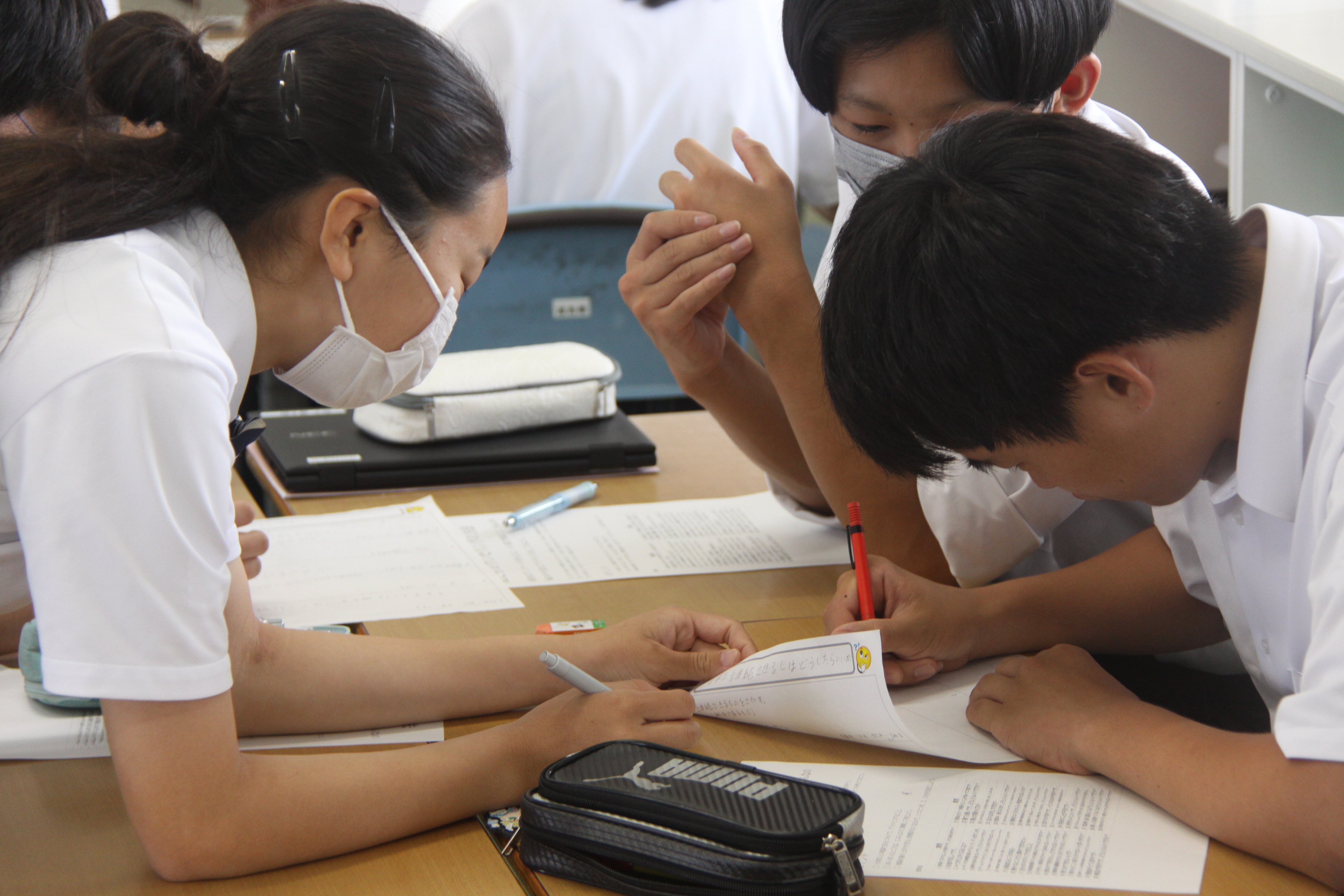
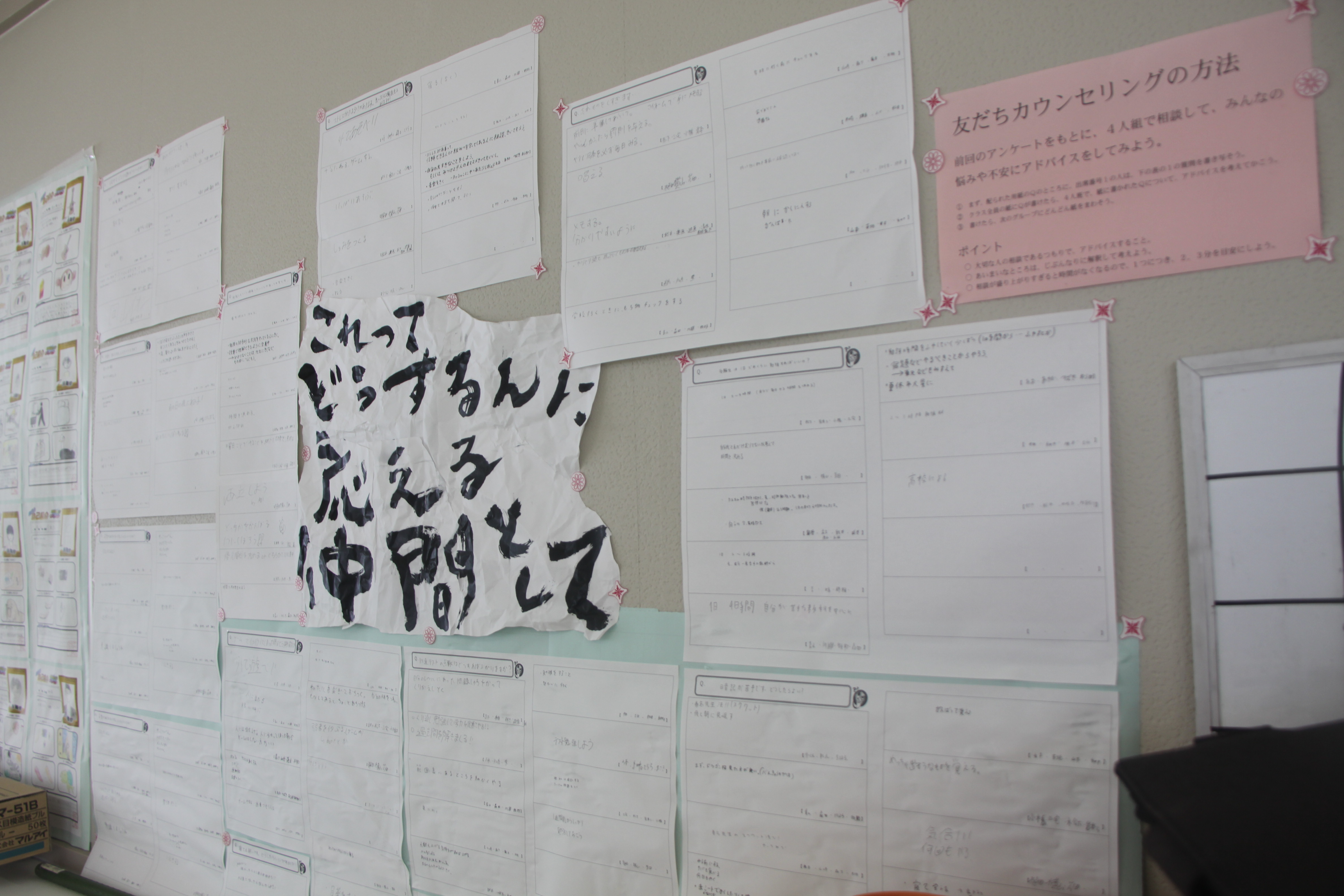
☆99日目(7.5)Nothing About us without us
これまでの「運動」を知った上で、障害者問題に取り組んでいきたいと思います。第1学習室にも置いていますので一読を。
・荒井 裕樹著『障害者差別を問いなおす』(ちくま新書)、『車椅子の横に立つ人──障害から見つめる「生きにくさ」』(青土社)、『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)、『差別されてる自覚はあるか: 横田弘と青い芝の会「行動綱領」』
・横塚晃一『障害者殺しの思想』
・横田弘著:『母よ!殺すな』
☆98日目(7.4)『生きることのはじまり』から
金満里さんの『生きることのはじまり』の中に、障害者解放運動の内容があります。岡山で障害者解放運動に長年携わっているNさんに、よく聴いていた「青い芝の会」。その綱領について提示します。
日本脳性マヒ者協会「全国青い芝の会」行動綱領
1.われらは、自らが脳性まひ者であることを自覚する。
われらは、現代社会にあって「本来あってはならない存在」とされつつある自らの位置を確認し、そこに一切の運動の原点を置かなければならないと信じ、且つ行動する。
1.われらは強烈な自己主張を行う。
われらが脳性マヒ者であることを自覚した時、そこに起るのは自らを守ろうとする意志である。
われらは強烈な自己主張こそ、それを成しうる唯一の路であると信じ、且つ行動をする。
1.われらは愛と正義を否定する
われらは愛と正義のもつエゴイズムを鋭く告発し、それを否定することによって生じる人間凝視に伴う相互理解こそ真の共生であると信じ、且つ行動する。
1.われらは健全者文明を否定する。
われらは健全者の作り出してきた現代文明が、われらの脳性まひ者を弾きだすことによってのみ成り立ってきたことを認識し、運動及び日常性生活の中からわれら独自の文化を創り出すことが現代文明への告発に通じることを信じ、且つ行動する。
1.われら問題解決の路を選ばない。
われらは安易に問題解決を図ろうとすることが、いかに危険な妥協への出発であるか、身をもって知ってきた。
われらは次々と問題提起を行うことのみが、われらの行いうる運動であると信じ、且つ行動する。
われらは以上五項目の行動綱領に基き、脳性まひ者の自立と解放を掲げつつ、すべての差別と闘う。
☆97日目(7.3)自立支援とは何か?
春いちごの会で、進路情報交流会の準備を進めている中で、人々舎から復刻された『生きることのはじまり』金 満里 著 を読んだ。あらためて「障害(がい)」「自立支援」などなどなどについて考えさせられた。読んだ方!お話をしましょう。本の紹介文は以下(在日の朝鮮古典芸能家の娘である著者が、重度身障者となり、施設生活・運動を経て自立、身体障害者だけの劇団「態変」を主宰し、一児の母となるまでの半生の記録。)職員室の「ひといきスペース」に置いておきますね。

☆96日目(7.2)春15(いちご)の会 〈声〉を訊く 開催案内
今年度の春15の会(特別支援教育のニーズのある子ども・保護者のための進路情報交流学習会)の案内です。これまで「学校の先生が開催するものではない。」と、言われる方が、たくさんおられました。しかし、必要としている「声」があり、進路情報のニーズがある事を大事にしたい。多くの方々に支えられて、東備地全域で開催します。もちろん多くの先生方も協力してくださっています。
☆95日目(7.1)ともだちカウンセリングの質問紙もポイント
ちなみに、質問は、クラス全員分がミソ。一人ひとりの「今」の質問に、クラスの仲間が真摯に応えていくことが大事ですね。
☆94日目(6.28)SSTやGWTを超えて
よく考えられたSSTやGWTの教材から、自分のことやクラスの問題を、学級全体で考える取組にならないと学びは「ホンモノ」になっていかない。以前に、教職員集団で創って実践した「ともだちカウンセリング」。本校でも、クラスの次なるステップアップのために、検討して取り組みます。
☆93日目(6.27)地域協働と「自立活動」
さあ、出発! みんなでがんばろう!
☆92日目(6.26)人権教育実践の会より。
前回に関連して、近々行われる学習会案内チラシからも、「拡がり」「深まり」が感じられますね。
① 「シン・仲間づくりのための学級・学年通信 ワークショップ」
日時 8月6日
あなたのめざす「クラスづくり」を進めたり、教育課題の解決のための、学級・学年通信(たより)にひと工夫を加え、スパイスの効いた「通信」になります。子どもと子どもをつなぐ、いじめや不登校を生まないクラスのための「通信」の手立てや、5分で出来る「通信」、年間200号発行する方法など、参加者同士で「学級づくり」の考え方を確認しながら、実際に作ってみましょう。人権教育の視野が拡がりますよ。
② 学級づくり、授業(PBL)づくりのためのフィールドワーク
「過去・いま・未来をつなぐハンセン病問題学習プログラムをつくろう」
日時 7月27日 (最終調整中)10時00分 ~ 11時30分
長島愛生園現地集合 愛生園内フィールドワーク…園内の歴史的な施設を歩きます。(船着き場跡~収容所跡~監房跡~万霊山・納骨堂~恵みの鐘~一郎道~旧資料館~歴史館)(約1.5時間)関心のある方、どなたでも参加できます。(お子さんも可能ですよ。)一緒に歩く中で「ハンセン病問題学習」の組み立てや学習プログラムなどを考えましょう。
☆91日目(6.25)拡がるなあ 深まるのよ 人権教育実践。
週末に、東備学ぶ会に参加してきました。小学校の先生から「ハンセン病問題学習」に取り組まれた実践報告でしたが、参加者同士で、様々な視点・視座からの意見交流では、わくわくする、学びの「拡がり」「深まり」を実感することができました。会で論議したいくつかの視点や意見を紹介します。
○「ハンセン病問題」という人権課題の知識を習得する学習ではなく、「ハンセン病問題学習」を通して、「どう自分たちは生きていくか?」「どんな社会・未来を創っていくのか」を考える取組(授業)でありたい。
○学習を通して「知ったこと」と「学んだ」ことは違うなあと思った。そこは明確にさせたいと思っています。そして、学習のまとめとして、「発信」もよくあるけど、「誰に伝えたいのか」「何を伝えるのか」もしっかり考えたいなあ。
○クラスの仲間づくりにつながっているし、つなげていかないといけないといつも思っている。
○子どもたちと一緒に「ハンセン病問題学習に取り組みたい、子どもたちに伝えたい!」と思ったのは、教師自身が何に出会って、どのように変わっていったことによるのか(教師自身の変わり目は何だったのか)?は大事だなあ。
○ハンセン病問題学習の目的は何か?クラスの子どもたちや教職員集団の課題は何なのかを明らかにして、取組を進めたいと思っています。ちなみに私は、「どう生きるか?」「クラスの仲間たちとどう暮らすのか」だな。
○子どもたちの感想や振り返りの中でも、とくに、教師自身が「クラス中で気になる子ども」の葛藤や学びの深まり、変化・成長をしっかりと見ていきたい。
○昨年度の実践の成果と課題をもとに、今年度のクラスづくりにどう生かしていけてるか?(いつも反省ばかりですが)
○クラスで完結しないように、学校全体(1~6年生)、中学校との連携した(継続的な)取組を構築したい。連携・継続は難しい。
90日目(6.24)学校行事を通した仲間づくり
文化祭・合唱コンクールに向けて、本校では実行委員会やパートリーダーの選出がはじまりました。テクニックや練習方法など参考になる動画はたくさんある時代となりましたが、「誰」が、「どのような働きかけ」の中で、視聴するのか。は考えたいものです。先生が「観よう」と言うのは簡単ですが、ある時は、実行委員メンバーと事前に視聴し、その中から、クラス全員で観るところを絞って、実行委員会メンバーのメッセージ入りの学級通信配布と合わせて、視聴しました。また、優れた映画もたくさんありますね。
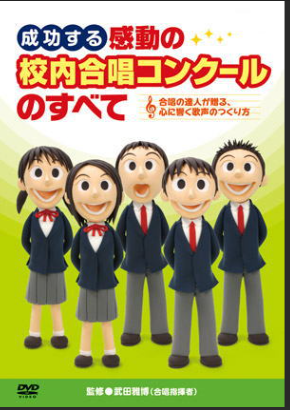
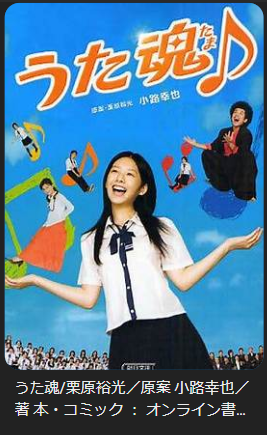

☆89日目(6.21)学年集会~仲間づくり~
学年集会は、子どもたちのもの。こんな学年集会もありました。
☆88日目(6.20)モノが教室でなくなったら~仲間づくり~
クラスで生徒のモノがなくなったらどんな手立てがかんがえられるでしょうか?それまでの学級内の教育課題や、生徒間の人間関係も充分把握した上で、学年団・学校全体で取り組まねばならないと思いますが、具体的な手立てを考えてみましょう。(一般的な生活指導の対応と重なることとまったく違うこともあると思いますが。)
○モノがなくなった子どものへの十分な支え(保護者との連携)の上に
○子どもたちへ還す取組(□その子へ近しい子らへ支える基盤・ □班長会 □クラスへ □学年・全校集会)*教職員だけが語らず、子どもた
ち自身が語る取組については前述済)
○問う(□クラスアンケート(情報提供) □声かけ相談 □叱る・・・だけでは解決にはなりませんが *何を問うかは重要ですね)
○探す(□すぐさま、放課後教職員全員で □クラス全員で(・放課後に時間をかかけて ・時には授業時間に) □全校で □何度も)
○示す(□なくなったモノの弁償・回復 □この出来事の重大性 □学年の課題として捉える )
○警察に被害届を出す・・・このぐらい・・・ですか。他にもあると思います。いろいろと話したいですね。
さて、人権教育実践で学んだ取組をひとつ。
もう、20年も前に、赴任していた学校で、「靴」がなくなったコト(盗った?)があり、上記の様々な取組をしましたが、靴は出てきませんでした。でもこのまま終わるといけないと思い、生徒会や学級委員会のメンバーらと話をして、つくったのは、大きな大きなメッセージボード。「私たちは絶対に許しません!」と大書して、全員が署名したものを玄関に掲示しました。そして、そのボードには、「こんなことを何度もするあなたは、何か悩みや心配ごとがあるのではないですか?相談にのります。ひとりで悩まないで」の旨の文書が書き添えました。これは、メッセージボードを作る際に、生徒会・学級委員メンバーから出た意見をもとに考えたことです。「したことは許されないことだけど、学年の仲間として一緒に生きていく」ことを体現した子どもたちでした。
☆87日目(6.19)掲示物の賞味期限はいつまで??
時間をかけて作成した掲示物や子どもたちが綴った願いや思いが書いている掲示物の掲示の期間はいつまででしょうか。本校でも星輝祭(体育の部)の取組のひとつとして、ステキな掲示物が展示されました。それから三週間あまりが経って、外す作業をおこないました。(ちょっとおそ過ぎたかも)。
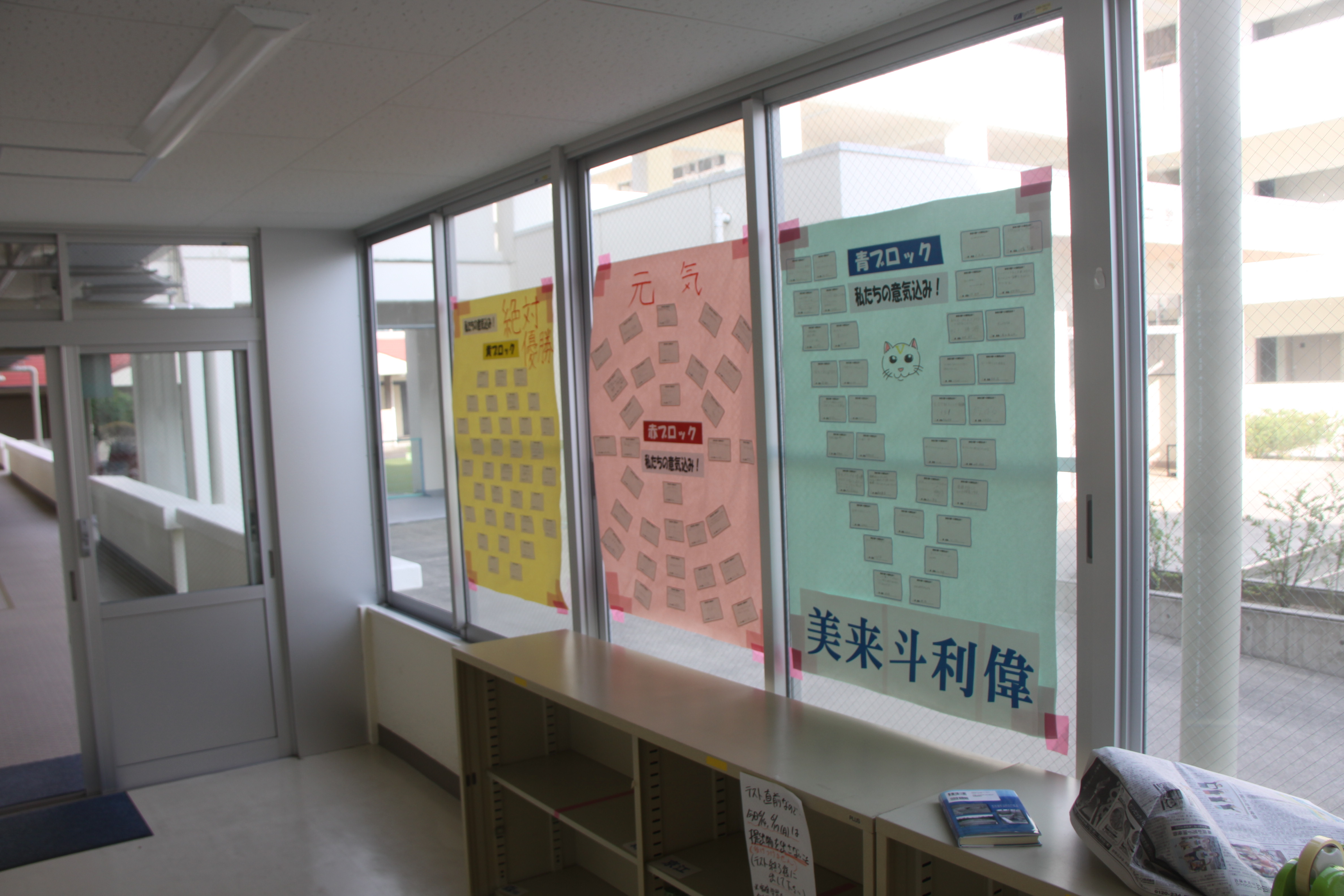
「何のために、どこに、いつまでに、誰が」掲示するか意図的に環境整備を進めたいですね。
ちなみに、ずっと(3月末まで)掲示する方法があります。
これです。学習室に移動させて、「あゆみ」として再掲示しました。クラスでも可能でしょう。
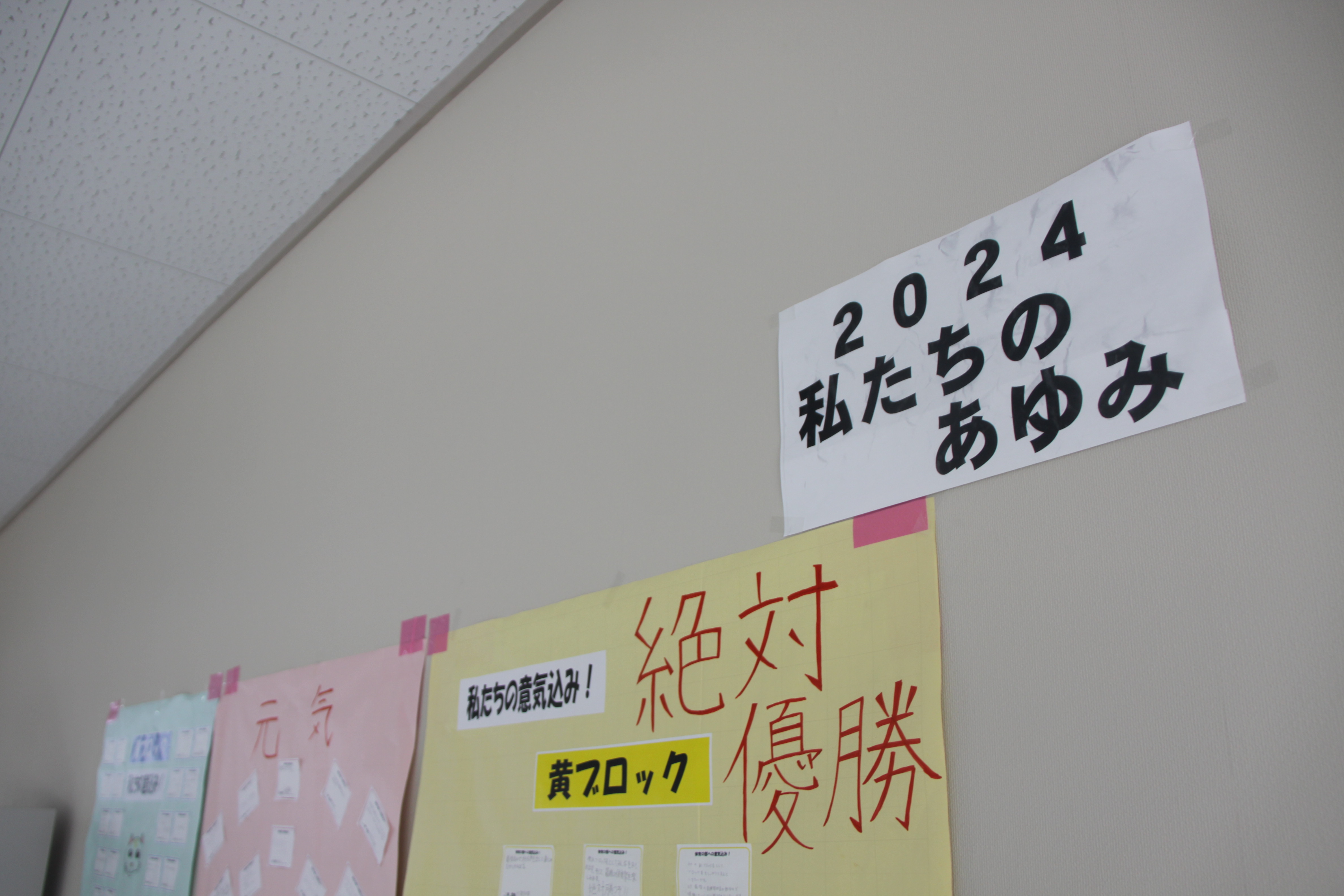
追記:2年生は広島研修時に乗ったバス(バスの運転集席の上の掲示物)さんから頂いた「日生中学校様 ○○バス」という用紙を、ヒロシマ研修の学びの証として、教室うしろにを貼っていますね。スバらしい。
☆86日目(6.18)何を話す(放つ?)月曜日の職員打ち合わせ会で
本校では、月曜日だけ全体での職員の打ち合わせがあります。他の日は学年団中心の打ち合わせ会のみで、全体での連絡事項は、前のホワイトボードやミライム等の連絡機能を活用しています。そうなると、あえて、一週間のはじまりである月曜日、限られた少ない時間に、「何を話し」「何を教職員どうしで共有するのか?」は大変重要になりますね。これまでもいろいろと考え、工夫はしてきたものの、自分なりに満足のいく「適切」な」や指示・連絡はなかなか出来ていません。この年になっても反省しきりです。
では、今日(6/16)は、どんな話が必要なのか?
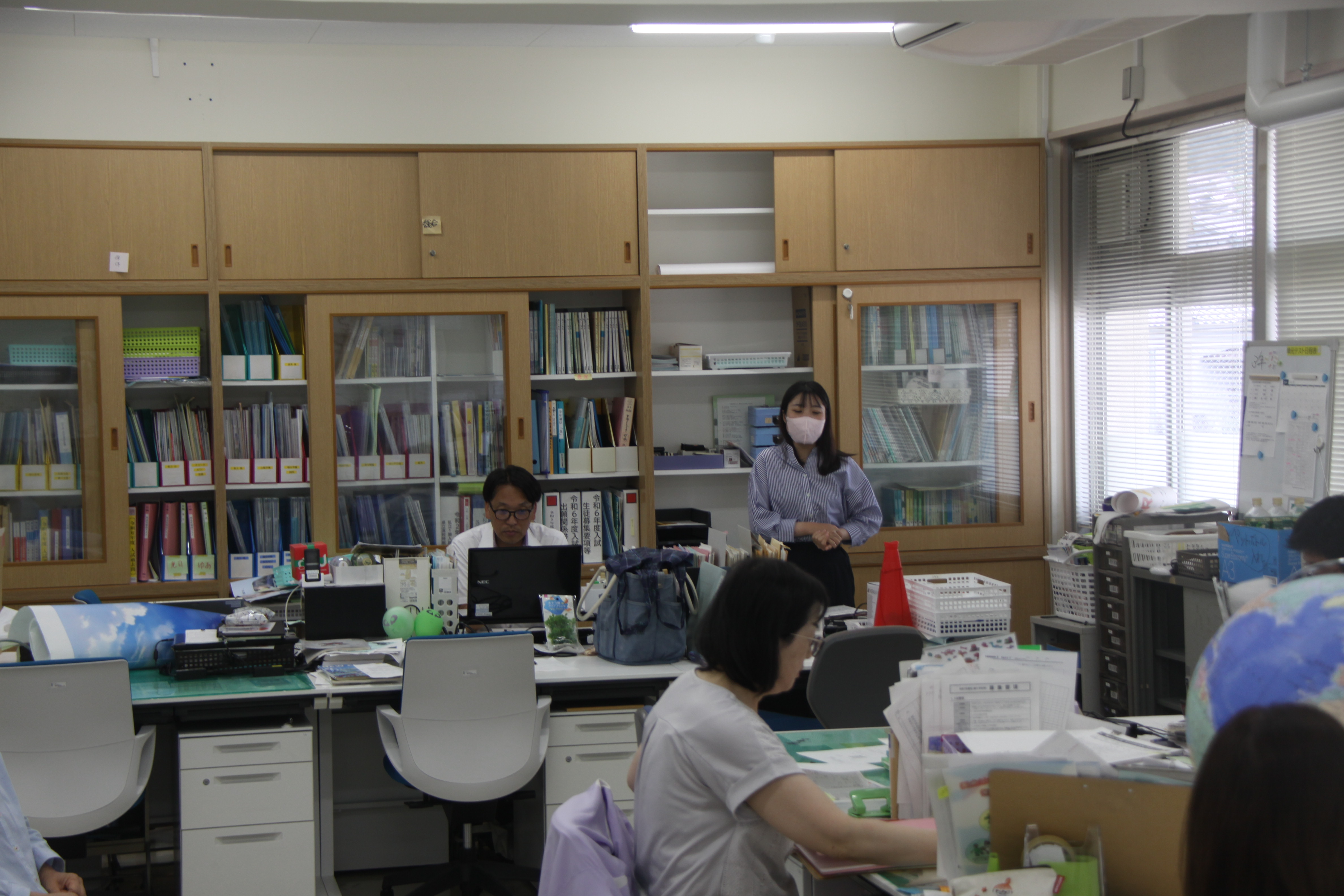
おりしも、週末には備前東地区大会と岡山県吹奏楽祭で生徒引率をした先生方がおられますので、大会の成績だけでなく、印象に残った出来事やストーリー、がんばった試合での子どもたちの状況、部活動を引退する3年生の様子などを話していただき、全職員で取組の情報を共有することができました。子どもたちのががんばっている姿や、一生懸命な取組の姿を共有して、一週間のスタートが切れてよかったと思います。
追記:時期が合えば、3年研修や、16年研修での学びのひとつを話して(還元)もらうことも大切にしています。
☆85日目(6.17)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
前回から、子どもたちの課題や実態をもとに取組をつくっていくタネでしたが、地域づくりと開かれた学校づくりについての「可能性」について話を広げることができました。あくまでも、「地域へ出かけていく入口」「地域との出会いの創出(きっかけ)」としての地域イベント参画ボランティアです。ヒントとなる出店案(実際に自立活動として出店した取組をもとに)を掲示します。
☆84日目(6.14)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
前々回のタネを受けて。地域のお祭りに参画するために、学年全体の気持ちを高め、みんなの「地域づくり」の意思を共有するために実践したワークシートです。
☆83日目(6.13)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
前回のタネを受けて、昨年度、警察署と連携した非行防止教室、薬物乱用防止教室につながるアンケートを実施したことがありました。とても、子どもたちの課題をもとに、有効的に授業づくりを進めることができました。
☆82日目(6.12)授業づくりには子どもたちの実態を知らねばならないよね。
教育実習中の先生が、「授業づくりは大変だけど、楽しい」と言うのを聞くと、こちらもうれしくなります。一方的な知識の伝達ではなく、子どもたちの置かれている状況や、課題をもとにして、授業づくりを進めていきたいですね。「認知症」を学ぶ授業を福祉課さんと取り組んだ時にも、子どもたちへの事前アンケートを大切にしました。
☆81日目(6.11)朝の会、帰りの会で。
「子どもどうしをつなげる」か?の視点で。
一緒に学年をもった先生たちと実践した朝・帰りの会のメニュー表がありました。そういえば、帰りの会で、〈今週の歌〉を決めて、歌っていたこともありましたねえ。メニュー
☆80日目(6.10)いつでも「子どもどうしをつなげる」か?の視点で。
少し遅い当初面談の中で、先生たちと「子どもどうし」をつなげることについて話題になりました。様々な構成的グループエンカウンターやGWTなどの教材もありますが、日常的な場面の中から津創っていきたいですね。例えば、今日の生徒集会で、服装を整える場面があるとしたら、どうのように生徒らに声をかけますか?「服装を整えなさい」から、前後左右のペアにさせて、「お互いに身だしなみをチェックしてなあ。名札、ネクタイ、ボタン、服装、(緊張をほぐす意味で、寝癖直してもらえ。 鼻毛も出てないか?などなども)」もかかわりの場面を創ることができる。教室整備の意識を高めるには、帰りの会の終わりには、委員長が号令をかけて「さようなら」と言う場面が日常的だけど、「起立」の後に、「机を整えてください」、「窓際のひとは鍵の確認してください」と呼びかけをする、そしてみんなが応えるクラスをめざしたい。教職員が「している」ことを、子どもたちの係や役割に「委ねてみる」と、子どもたちはたくましく動き、主体的な学級になっていくと思います。
他にもないかなあ?「子どもどうしをつながる日常の中での取組は??」
☆79日目(6.6)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業5
教材の視点
(1) 禁服訟嘆難訴記
○ 生徒たちは、これまでの社会科での歴史学習の中で、江戸幕府による民衆支配政策として、「身分制度」が定められ、「武士」と「百姓」「町人」との間に、支配・被支配の関係が定められたことと、そうした社会の外に置かれて、「武士」から支配を受けるとともに、「排除の差別」を受けてきた人々がいたことを学んできた。さらに、そうした「差別された人々」は様々な役目や生業を通して、社会や文化を支えてきたこと、仕事に誇りをもって生き抜いてきたことも学習している。禁服訟嘆難訴記は、経済的、政治的に揺るぎだした幕藩体制が、民衆支配として差別を強化しようとしたことに対する闘いの記録として捉えたい。
○ 「禁服訟歎難訴記」は、一揆の中心となった神下村のある家に残されていた文書で和綴じの二分冊である。表紙は「穢多渋着物一件」と題された上に、貼紙をして「禁服訟歎難訴記」と題されている。改題されたのは、明治になって「賤民廃止令」が出された頃だろうと言われている。筆者は、一揆の指導者の一人で手習師匠をしていた豊五郎であったと考えられている。原文は五七調で書かれており、題名は「服装を禁じられて、嘆き訴え苦労して申し上げた記録」という意味と考える。
○ 「禁服訟歎難訴記」冒頭部分は、「太陽も月も明るく澄みわたっているといっても、雲がさまたげとなってその光をさえぎる。天は太陽・月・星の主、地は山・川・草木の主、人は天と地の間にあって禽獣の主である。狐や狸は死んで肉が腐っても皮を残して様々な御代の着物にする。人は死んでその遺骸が腐ると言っても、名前を天下に顕らかにする。この詞は本当にそのとおりであることよ」(『岡山部落解放研究所紀要』1988)とあり、教材では、「人は死んでも、名前を天下に残す」と端的な言葉にして、この部分をとりあげ、「人としての誇り」を意味する重要な学習の視点として提起されている。
(2) 分け隔てを許さないと立ち上がった人々
○ 渋染一揆がおこる要因となった岡山藩の御触の背景について
1800年前後から既に財政危機に陥っていた岡山藩は、幕府から房総半島警備を命じられたことで、百姓に対する24ヵ条の倹約令を出す。その内容は「衣類は木綿、襟・袖口にも絹類の使用禁止」「綿入れや目立つ染色も禁止」「華美で高価な髪飾りの禁止」「祭事の食事の制限」「雨具の制限」などまさに出費を抑えて倹約を命ずる内容であった。しかし、その一ヶ月後に、「差別された人々(えた身分とされた人々)」に対してのみ5ヵ条の「別段御触書」を出した。その内容は、「衣類は無紋の渋染藍染に限るが、新たな出費となるのでこれまでの衣類は着ていてもよい」「目明かしに就いている者は、これまで通りでよい」「雨天の時は栗下駄を履いてよいが百姓と出会った時は脱いでお辞儀をすること」「年貢を完納している家の女子は竹の柄の傘を用いてよい」「番役人はこれまでどおりでよいが絹類の着用は禁止」というものあった。一読してわかるように、これらは倹約につながるような命令ではなく、身分の違いを明確にするためにのみ出されたものであった。
○ 「別段御触書」を命じられた人々が、どのような思いに至ったのか、そしてどのように行動していくのかといった学習への意欲を喚起して、学習課題を明確にもたせたい。
(3) 知恵を集めた嘆願書
○ 別段御触書など受け入れることはできないと、人々が集まって嘆願書の作成に取り組む経過から考えさせたい。これまで「渋染一揆」については、「渋や藍」の色をめぐって論議があり、「渋色や藍色は人々の嫌がる色であった為に抗議した」という意見と「どちらも一般的な色であって問題は差別された人々にのみ無地無紋を命じ差別したことに抗議した」という意見であった。前者については、収監者の服が主に西日本では柿色(渋)一色であり、東日本では青色(藍)一色であったことなどから、その可能性は否定できない面がある。一方で、当時の浮世絵などには、鮮やかで様々な模様の藍色、赤色を来た人々の姿が描かれており、これらは当時の「おしゃれ」であったことから後者の意見も否定できない。では、人々はどのような理由で別段御触書に抗議したのかを改めて「禁服訟歎難訴記」ともうひとつの原典教材であり豊吉が書いたと言われている「屑者重宝記」を精読すると前者には、二種類の嘆願書が写されており、計三種類がそれぞれ微妙に異なっているのである。まず嘆願書作成の経過は、村々が持ち寄った嘆願書を豊吉がとりまとめ、それぞれが持ち帰った。その後、豊吉は、懇意にしていた目明かしに添削を受けて文章を整え、最終的に51カ村の代表の署名を得て提出している。それぞれの文書には、この連署のある嘆願書が掲載されている。加えて「難訴記」には、その後も村役人から御触書の承諾の押印を厳しく求められた村々がそれぞれに出した嘆願書が掲載されており、併せて三種類である。すべてに共通している訴えは、「百姓と同様に田を耕し年貢を納めているのになぜこのような衣類を命じられるのか」「役人として逮捕にあたる際にすぐにわかる衣類では逃げられてしまう」「年貢が納入できない時は衣類を質に入れて工面するがこれでは質草にならない」などと理論整然と衣服の制限の不当性を述べている。そこには、「服の色」のことについては全く書かれておらず、ひたすら「自分たちは百姓と同じだ」「分け隔ては許せない」という強い意志を読み取ることができる。そのような中で、受諾を迫られた村々が出した嘆願書には、「特別の差別を仰せつけられましては、もう一同気落ちしてしまい、正月・盆や季節の祭礼、神仏の参詣のしようもなく、若者たちは何の生き甲斐もないと、農業も放り出してしまうほどの難渋で、はなはだ歎かわしいことだと思います」という一文が記載されている。一連の経過から、この嘆願書はおそらく当初に村々から持ち寄ったひとつであり、まとめる際に、この部分は割愛されたものと考えられる。一方で、「重宝記」に掲載されている嘆願書には、「(隣国には)当国の百姓とはちがって、とりわけ強情の者が多くいるので、すでに、穢多たちの三人や五人打ち殺しても、お上は気にかけないだろうなどと、時には心得違いの者がいて、このようなことを言っています。(略)この度、別途お触れで、百姓と分け隔ての扱いをなされては、(略)厄介を掛けることが、ときどきでるのではないかと、重ね重ね歎かわしいことだと存じます」という一文がある。つまり、「ひと目でわかる衣服にされては神社仏閣の参拝もできない」は本音であり、人々は禁令を破って百姓たちと同じように参拝していた。しかし、これを書くと逆にとがめられるために「殺傷事件が起こり困ることになる」との藩にとっても不利益であるという論理で嘆願書をまとめたと考えられる。また、先に述べたように、藍色は今日も「Japan blue」と呼ばれるように人々に好まれ、高価なものもあったことから、これが差別された人々の色とつれることで、百姓たちが避けるようになることも、想定できたのではないかと思われる。
○ 「服の色」について言及するのではなく、御触書を撤回させるための理由を論理立てるために、どれだけ人々が知恵を絞って書きまとめたかを明らかにするために、教材中で語られる思い(根拠)の論理性、正当性、説得力などの面から読み取らせ、作成された「嘆願書」について深く考えさせる。
(4) 訴えるしかないと立ち上がったこと
○ 知恵を絞り、村々の合意のもとで提出された嘆願書であったが、何の論議もなく突き返されることになり、ここから人々は、いよいよ「強訴の闘い」に入っていく。ここでも、人々が社会状況を見抜いて勝つためにいかに闘うかを考え抜いた姿を見ることができる。当時の岡山藩には六人の家老がいて月番で藩政を統括しており、倹約令を出したのは財政再建を進めていた岡山城の近くに陣屋をおく日置忠尚であった。一方、虫明に陣屋をおいていた伊木若狭は、尊皇派に近く日置とは政策上必ずしも一致していなかった。人々は、伊木が筆頭家老であったことに加えて、こうした藩権力内部の状況をとらえて、虫明への強訴を決断したと考えられる。したがって、地理的に見ると、中心となった神下村などは岡山城下にあるため城や日置の陣屋までは西方向に数㎞の距離であるが結集地点の八日市河原は西方向に12㎞、そこから虫明までは、さらに西方向に16㎞もある。このような藩内の対立や陣屋の位置関係も理解させたい。
○ 八日市河原に結集して以降の強訴の様子については、非武装で整然と、また毅然として行動し、ひとりの怪我人も出さなかったことを確認する。
○ 当時「別器、別火、別食」が当然とされていた中で、百姓の茶屋万次郎が人を雇って水を振る舞ったことは、前述の嘆願書を添削した目明かし、後に登場する助命嘆願を支援した百姓村の有力者とともに、百姓身分の人たちが一揆を支援していた証左として確認したい。
(5) 投獄された仲間を助け出した人びと *本時は視聴をカットするが、学び合いでは重要な内容である。
○ 厳しい取り調べと投獄
渋染一揆のリーダーたちの読みの通り、伊木若狭が「なぜ嘆願書を審議することもなく突き返したのか」と日置の直属の部下であった奉行の影浦勘助を問いただし、日置がとりなすという場を経て、結果的に取り消された。人々の願いはかない、一揆としてはここで終結するが、この闘いは、この後の「助命嘆願」まで含めての一連のものであるからこそ、いまなお犠牲となった人々が「若宮神」として大切に祀られているのである。その重要性を踏まえて、投獄された仲間を助け出した人々についても学ぶ必要性が考えられる。
○ 差別を強化、固定化する御触は取り消されたが、強訴に及んだとして、暴行を加えた厳しい取り調べがなされる。原典教材には、互いに「誰が呼びかけたか知らない」「誰が書いたかわからない」など、曖昧な供述で互いに守りあったことが記されているが、最終的に12名が「首謀者」として入牢を命じられた。また、彼ら以外に閉門(軟禁)の処分を命じられ生計が立たなくなった人々の様子や、働き手を失い困窮した残された家族を人々が支えたことも記されている。「入牢した者は赦免がむつかしく、永牢か死罪かに違いないと世間の噂であった」と記載されているとおり、入牢から4ヶ月後、笹岡村の栄蔵(54歳)、神下村の権十郎(70歳)が病死する。続いて、翌年の1月から5月までに、神下村の助右衛門(55歳)、卯左衛門(26歳)、忠左衛門(23歳)、惣吉(42歳) が相次いで病死する。(一方で、稲坪村の友吉(35歳)は5ヶ月後に釈放されているが理由は不明である。)
(6) 助命嘆願の闘い
○ こうした状況を受けて、神下村の安次郎は、懇意にしていた隣村の百姓の八郎左衛門に依頼して、池田家の菩提寺である曹源寺に赦免への協力を求めた。この二人は囲碁仲間であったと言われており、ここにも身分を越えた信頼関係があったことが読みとれるし、「赦免、助命」を求める方法として、藩主の菩提寺に依頼したことにも巧みさを見ることができる。一方、獄死者が次々と出る中、残りの入牢者の様子について尋ねられた牢役人の「半死半生の躰」「同人等程恐入たる者なし(彼らほどきまりをしっかり守っている者はいない)」と答えを受けて、牢内で書き役を勤めていた良平と弥市が嘆願書を書きまとめて提出した。こうした牢内外の働きかけによって、5名が赦免となった。なお、「難訴記」には、良平と弥市の釈放を知った人々は、翌朝、駕を出して迎えに行き、帰村する道筋には、「四カ村の人々が続き、往来は人々であふれた」と記されている。
(7) 引き継がれている思い
○ 笹岡村の良平の墓碑と神下村の若宮神
良平の碑文を記した岡崎熊吉は甥にあたり、1902年8月(明治35年)三好伊平次らとともに中心となって「備作平民会」を創立し、その後は全国水平社創立大会にも参加するなど、部落差別の撤廃に向けて闘い続けた人物である。釈放されたものの歩くことも困難であった良平は、約一年後に亡くなるが、その43年後、「差別を許さない」と立ち上がった良平たちの意志は、熊吉たちに引き継がれ再び、岡山県での闘いへとつながっていった。
○ 若宮神は、最も多くの犠牲者を出した神下村の権十郎、助右衛門、卯左衛門、忠左衛門、惣吉を祀った碑で、区画整備で集められた地蔵尊、八幡宮の真ん中におかれている。いまもなお、「村の守り神」として大切にされている思いを地元の方が語ってくださっている。
○ 「禁服訟歎難訴記」の「人は死んでも名前を天下に残す」という文章の中の「人」は、個々人の固有名詞ではなく、「人としての尊厳をかけて差別と闘った人たち」であると捉えたい。その生き様を学んだ私たちはどうあるべきかを生徒と共に深めていきたい。
【参考とした資料】
渋染一揆を闘いぬいた人々(東映:シリーズ影像でみる人権の歴史第5巻)解説2017
岡山市『渋染一揆資料館研修資料』2014 版
外川正明『部落史に学ぶ』解放出版社 2001、『部落史に学ぶ2』解放出版社 2006
岡山県人権教育研究協議会『岡山からの人権教育 「渋染一揆」学習素材集』2012
柴田一『渋染一揆論』明石書店 1995
☆78日目(6.5)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業4
7 本時の展開
| |
主な学習活動と予想される生徒の心の動き |
支援(◎)と評価(★) |
||
| 導 入 |
1 学年集団のイメージを交流する。 |
◎ 事前アンケートを実施し、その結果をパ ワーポイントで提示することで、2年生の 良いところを共感させるとともに、集団生 活の課題について課題認識をもたせる。 |
||
| |
2年生の良いところはどのようなことだと思いますか。 |
|
||
| ・みんなの仲がよい ・行事に熱心に取り組む |
||||
| 展 開 |
2 『渋染一揆を闘いぬいた人々(第1章~12:49)』を 視聴して考える。 (1) 第一次で学習したワークシートを参考に、渋染 一揆の中から課題解決の方法を見つける。 |
◎ なぜそのような気持ちをもったのか、具体的な理由(根拠)を考えさせる。 ◎ 茶屋万次郎の行動、助命に協力した百姓 等、一揆に立ち上がった人々の強い絆だけ ではなく、差別を乗り越えて彼らを支持し た百姓たちの姿にも着目させたい。 ◎ 自分の考え方やこれまでの生活(葛 藤 や悩み)に照らし合わせて話すこと(主体 性)や、グループで出た意見について、 分の意見を重ねていくこと(対話性)で、 自分なりの考えがより深まっていくこと (深い学び)を、モデル・グループによる 学び合いで示す。 ◎ モデル・グループ学習から、学び合い (人の意見を聴き、自分の考えを深めてい くこと)の内容を高めることが大切である という認識をもたせる。 |
||
| |
よりよい学年にするために、渋染一揆から自分が活かせることはどんなことだろうか。 |
|
||
| ・御触書がおかしいと見抜く力 *学問の重要性 ・正しいことを主張し書き表す力 ・みんなで話し合い、考える力 *連帯の重要性 ・どうしたら勝てるか(交渉力) ・世の中を見つめる力 ・勇気を出して仲間と行動する力 *行動の重要性 ・怒るだけでなく正しく行動する力 ・百姓の視点から ・差別された人々の行動力はすごい。 ・いままで差別していたことが、間違っていた。 ・差別しないで協力しなければならない。 ・自分たちも生活をよくするために力をあわせよう。 ・公正でない世の中は変えなければならない。 (2) 教員のモデル・グループでの学び合いをみることで、 「学び合う」ことについて考える。 ・自分と同じようにみんなにも悩みや不安があるんだな。 ・悩みや不安を仲間と一緒に解決したい。 ・自分のことだけでなく、よりよい学年にしたいと、誰もが しっかり考えているんだな。 ・グループの仲間の話を聴いて、自分の考えが深まった。 ・自分の意見を聞いてもらえてうれしい。 ・もっと話し合いたい。 |
||||
| 終 末 |
3 グループで交流しながら自分の考えを深める。 | ◎ 教員が各グループに付き、学び合いを見 取る。学び合いが進んでない場合は声かけ をする。 また、部落差別に関わる不適切な発言等 があった場合はしっかりと発言の趣旨や状 況を把握し、適切な指導・助言を行う。 ◎ 「禁服訟歎難訴記」の「人は死んでも名 前を天下に残す」という文章の中の「人」 は、個々人の固有名詞ではなく、「人とし ての尊厳をかけて、差別と闘った人たち」 であり、その生き様を学んだ私たちはどう あるべきかをさらに深く学び合うことを予 告(次時)する。 ★ 正義と公正さを重んじ、人権を守り、 集団生活を充実させようと、意欲をもって 学習(学び合い)に取り組むことができた か。〈ワークシート〉 |
||
| |
モデル・グループの学び合いを参考(つなげて)に、よりよい学年にするためにあなたができることは何だろうか。 |
|
||
| ・おかしい、不公正だと思ったことはそのままにしない。解 決のためにみんなで話し合いたい。 ・好き嫌いはあるけど、偏見をもたないように努力する。 ・いじめや不正な行動を止めれない時は、助けを求めたり相 談したりする。 ・自己中心的な考え方を改めて、学年全体の立場からも考え られるようにしたい。 ・相手に気持ちをきちんと伝えるためにコミニュケーション の方法を豊かにしたい。 ・もっと勉強をして差別や偏見に気づく感性を磨きたい。 |
||||
☆77日目(6.4)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業3
4 準備物 パソコン モニター ワークシート
5 計画 第1時 社会科 幕府の政治改革 渋染一揆
(教材 渋染一揆に学ぼうワークシート 岡山県教職員組合教育運動推進センター)
第2時 道徳 本時
第3時 学級活動 渋染一揆から学んだこと~自分を見つめ、語り合う~
・渋染一揆の学習をとおして、もっとも印象に残った渋染一揆の場面(場景)をとりあげる。そしてその絵の中には自分の姿を描き、「何と言っているのか」を書き込む。
・同じ場面を選んだ者どうしで、グループをつくり、「なぜこの場面を描いたのか」をテーマに話し合う。話し合われた内容を学級で共有する。「なぜこの場面を描いたのか」を語ることは、渋染一揆そのものを語ることではなく、そこに重なる「わたし」を語ることとなる。「わたしをひらく」ことにより、互いに「仲間(学年)とつながっている」という実感をもたせる。
6 本時のねらい
渋染一揆の学習を通して、正義と公正さを重んじ、人権を守り、集団生活を充実させることで、差別や偏見のない社会の実現に努めようとする実践意欲を高める。
☆76日目(6.1)ふりかえりのシートと仲間づくり一考
指導案の紹介の途中ですが、本日、体育会を終えて時、どのようなふりかえりをするか?が話題になりました。作文用紙は用途がちがうので‚使わない方がよいですね。
子ども集団の4月からこれまでの「綴る」取組の中で、ふりかえる項目や、意識させる観点などを踏まえ、「綴る」時間をしっかりと確保せねばなりませんね。出来たら、週明け1時間目。しっかりと「うったて」をすると、生徒ら「綴り」ます。鉛筆の音だけが教室に響く時間となります。だって、「綴りたい」ことが一杯あり、伝えたいことが一杯あり、「綴る」ことは自分にとって有意義でることを体感していあるからね。
ワークシートで「振り返った」内容は、学級通信、学年通信、学年集会、ブロック会に「還す」ことも重要となります。(「還す」取組についてはまたの機会に。)
体育会振り返りシート1 体育会振り返りシート2 合唱祭振り返りシート 3年 2学期振り返りシート 1年 2学期振り返りシート
ヒロシマ研修振り返りシート
☆75日目(5.31)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業2
(4) 教材観
① 本教材の渋染一揆とは、1856年、岡山(備前)藩53か村の被差別身分(かわた)の人々が差別法令(「別段御触書」)の差別性に気づき、民主的戦略をもとにこれを空文化させた闘いである。渋染一揆が成功した要因としては〈ア〉「百姓」としての誇り(=人間としての誇り)、〈イ〉かしこさ、したたかさ(=学問の重要性)、〈ウ〉自治力・団結力(=連帯の重要性)、〈エ〉人間による、人間を取り返す行動(=行動の重要性)など多くの道徳的価値につながる事由があげられる。そして、渋染一揆を深く学ぶ学習を通して、今を生きる私たち自身の課題に向き合い、差別に「気づく」、差別に「怒る」、差別解消に向けた「学習」を積み重ねる、ともに行動する「仲間」を増やす、そして「行動」する一連の≪いじめ解消のモデル≫を学び取ることができる。渋染一揆の中に出てくる人々の願いと行動から、自分自身の課題を見つめ、自分たち自身でよりよい学校生活をつくっていくという意識を高めることに適した教材である。
② 本教材は、社会科での「武士政治の終わり」や「新しい時代への動き」あるいは「天保の改革」の学習を深めるものであるが、直接的には、小・中学校教科書で「武士の政治に苦しんできた人々が各地で一揆や打ち壊しを起こした」ことを具体的に学ぶ例として取り上げられている「渋染一揆」について学ぶ教材である。中学校社会科教科書(東京書籍)には「財政難に苦しんでいた岡山藩は、1855年、領内に29か条の倹約令を出しました。その中には、えた身分だけに出された命令があり、衣類を渋染か藍染に限るなど、百姓と別あつかいにするものでした。かれらは農業も行い、年貢も納めているのに、このような差別は我慢できないと、領内53か村が嘆願書を出しました。そのうち約半分の村から千数百人が立ち上がり、藩の役人と交渉し、ついに嘆願書を受理させました。このため、藩は倹約令を実施しませんでした。」と記されており、さらに倹約令の概要も記載されている。本教材では、こうした記載をさらに深めるために、「嘆願の闘い」「強訴の闘い」「助命の闘い」という一揆の経過からを丁寧に追っている。
また、本教材は、多様な学習の可能性が考えられ、道徳科の内容項目の指導の観点の中の、「A主として自分自身に関すること」の〔希望と勇気、克己と強い意志〕〔真理の探究、創造〕として示された項目や、「C主として集団や社会との関わりに関すること」の〔公平、公正、社会正義〕として示された項目、「D主として生命や自然や崇高なものとのかかわりに関すること」の〔生命の尊さ〕〔よりよく生きる喜び〕として示された項目、「B主として人との関わりに関すること」の〔信頼や友情〕や〔相互理解、寛容〕として示された項目において、その道徳的価値にせまることができると考えられる。その中から、本時は〔公平、公正、社会正義〕という道徳的価値に関わって、「中学校解説編」に、「よりよい社会を実現するためには正義と公正さを重んじる精神が不可欠であり、物事の是非を見極めて、誰に対しても公平に接し続けようとすることが必要となる。また、法やきまりに反すると同様に、自他の不公正に気付き、それを許さないという断固とした姿勢と力を合わせて積極的に差別や偏見をなくす努力が重要である」と述べられていることを鑑み学習を展開する。
③ 社会科における道徳教育との関連
「中学校学習指導要領社会科」の〔歴史的分野〕の4点の目標の中に示された内容項目の「(4)近世の日本」の「エ 社会の変動や欧米諸国の接近、幕府の政治改革、新しい学問・思想の動きなどを通して、幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを理解させる」に位置づけた学習であり、「同解説編」では、「この中項目のねらいは、幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを、次の各事項の学習を通して理解させることである」として、「社会の変動や欧米諸国の接近」「幕府の政治改革」「新しい学問・思想の動き」の三つに分け、「内容の取り扱い」として、「『幕府の政治改革』については、百姓一揆などに結び付く農村の変化や商業の発達などへの対応という観点から、代表的な事例を取り上げるようにすること」と記している。こうした社会科学習の目標に沿って、岡山藩で起こった『渋染一揆』を『代表的人物や事例』として取り上げ、「幕府の政治改革」について学び「幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを理解させる」ことと関連している。
④ 特別活動との関連
「中学校解説編」では、「イ自己及び他者の個性の理解と尊重」において、「自己の個性を見つめ、それを大切にしていくことは、自尊感情を高め、自己確立や自己実現を図るための基盤となる。また、他者の個性を理解し互いに尊重し合うことは、自己理解を一層深めるとともに、豊かな人間関係をはぐくんでいくことにつながる。」として、「自己及び他者の個性を理解し尊重していくことは重要な意味をもっている。」ことから、具体的な例として、「他者の生き方に学ばせるなどの活動」を指摘している。「人権を尊重する態度」や「学ぶことや生きることの意義」を考える上で、歴史上の人物の生き方を取りあげ、特に他者を尊重する姿勢や、学ぶことの意義について考える本学習は、指導の効果を高める。第2学年では進路学習として、「仕事」「生き方」についての聴き取り学習や、岡山チャレンジ・ワーク14『職場体験活動』の取り組みを通して、生徒自身が自分らしい生き方(進路実現)を目指して、働くことや職業について理解を深めてきた。
(5) 指導観
モデル・グループの学び合いを参考に、自分ができることは何かを「話し合う」場面において、そう考える理由を丁寧に語らせたい。モデル・グループ学習では授業者はファシリテーターとして、学習者の意見をつなぐことを重視する。意見をつなぐとは、授業者の発問に学習者が答えるだけでなく、その発言を他の学習者に広げ、深めていくことを指しており、本時においては、渋染一揆を多面的・多角的に捉えるので、たくさんの意見がでると考えられるが、他者の意見を聞き、その意見を取り入れ、思考しながら次の発言につながるような学び合いが進むように指導・支援していく。
第1時では、教材の内容(史実)をしっかり受けとめさせる。第2時(本時)で、その学習を深め、ねらいとする道徳的価値を自分たちの身近な生活の中に見いださせることで、生徒たちがより主体的な態度で、道徳的な問題を発見し、その解決策を考えていくことをファシリテートしていく。(続く)
☆74日目(5.30)渋染一揆授業指導案~反差別の仲間づくりをめざす~
若い先生たちと学ぶモデルグループ学習を取り入れた「道徳」での授業
1 主題名 差別や偏見のない社会 公正、公平、社会正義
正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること
2 教材名 渋染一揆を闘いぬいた人々
(東映:シリーズ映像でみる人権の歴史第5巻)
(渋染一揆に学ぼうワークシート(岡山県教職員組合教育運動推進センター))
3 主題設定の理由
(1) 研究主題との関連について本校は本年度、研究主題「道徳のねらいを達成するための効果的で多様な授業実践」を設定し、協働学習を取り入れた授業実践を中心に研修を進めている。グループに分かれての協働学習では、主発問(テーマ・課題)設定が適切か、また発問に応じて学び合った内容が、主体的で対話的・深い学びになっているのかという課題について議論してきた。そこで、道徳の従来の形である教材を読み、主人公の心情やその変化に気づかせていくというパッシブ・ラーニング的な授業展開から離れ、モデル・グループ学習を取り入れることによって、協働的に学び合う議論が深まるのではないかと考えた。
(2) 主題観
「正義を重んじ」るということは、正しいと信じることを自ら積極的に実践できるように努めることであり、「公平さを重んじ」るということは、私心にとらわれたり偏見をもって事実をゆがめたりすることを避けるように努めることである。力を合わせて公正な、正義のとおるよりよい学年集団にしていこうという気持ちを持たせたい。
(3) 生徒観
本学年の生徒は、穏やかで仲間同士のトラブルも少ない。しかしながら、教育的課題を抱えている生徒(家庭)も少なくなく、困ったことを語り合える人間関係が育つまでには至っていない。社会的立場自覚(自己認知・社会的自立)を進めていく中で、自己肯定感(ありのままの自分)を高めていくには、きちんと語り合える学年集団づくりをさらに進める必要がある。そのためには、自己中心的な考え方から脱却して、公のことと自分のこととの関わりや社会の中における自分の立場に目を向け、社会をよりよくしていこうとする気持ちを大切にする必要がある。また、「見て見ぬふりをする」とか、「避けて通る」という消極的な立場ではなく、不正を憎み、不正な言動を断固として否定するほどの、たくましい態度が育つように指導することが大切である。さらに、この世の中から、あらゆる差別や偏見をなくすように努力し、望ましい社会の理想を掲げ、正義がとおり、公平で公正な社会の実現に積極的に努めることが大切だと認識させる必要がある。(続く)
☆73日目(5.29)仲間づくりをめざす「カレー」の授業 案1
《聴く つなぐ もどす》授業をめざした協同(グループでの学び)学習を取り入れた参考授業を自主公開します。(社会科授業デザインとして提示)
1 テーマ 歴史を学ぶ意義と、なかまと共に学ぶ大切さを学ぶ
2 ねらい
(1)これから授業をすすめていくにあたり、現在の子どもたちの「現実」、「学び」への意識や、集団としての「風土」を見立てる。それをもとに今後の授業展開の中での《つなぐ》ありかたを探る。
(2)「自己開示は楽しい」「共に学ぶことは意味がある」ことを実感させる。
(3)「会科は暗記の教科」という言い方も聞かれるが、決してそうではなく、これまでの私たちの生き方(歴史)を振り返り、これから私たちの生活・社会がどうあるべきかを考え、なかまと共に自己実現を図り、人権を守り、反差別・共生の社会(世の中)を創っていくという市民性を培う基礎となる教科と考える。そこで様々な学習活動を取り入れ経験・体験する中でその資質を育てていく一助とする。
3 材料
・カレーから戦後を考えてみよう(資料集ビジュアル公民2012) ホワイトボードペン 歴史資料集
4 指導の流れ
(1)確認テストの勉強→ 確認テスト
(2)授業の目標(歴史の見方について)の確認
(3)協同学習・カレーに何を入れる??
・カレーの歴史からワークシートで時代を読み取る 〈基礎〉
・現代のカレーについて考える〈ジャンプ課題?〉
5 教室の配置 4人グループを活用
6 宿泊研修に連動させる
☆72日目(5.28)仲間づくりとしての生活指導2
演習2・3については、これまで、いろんな人と話題にしましたが、多様で興味深いアプローチが考えられました。人権教育や仲間づくりの視座では、個別の支援にとどまらず、「誰のために」、「クラス」・「学年集団」への積極的なアプローチがポイントになりますね。以下の演習3はどうでしょう??
演習3
| 給食終了後、中学生のタケさん(3A)の下足箱に入れていた体育館シューズがなくなったと担任から連絡がありました。「日頃の状況から生徒ヒロ(3B)が怪しい」と学年団は思いますが、証拠はありません。 |
☆71日目(5.27)仲間づくりとしての生活指導
今日から教育実習生が、三週間、教育最前線で「教師としての学び」を深めていきます。私たちも全力で応援します。今日は、「教育公務員としての心得」について研修をしましたが、担任として、具体的な生活指導の場面を想定した演習を時間を持ちました。演習は以下の2つ。
○演習1
:手すりに落書きがあることを生徒が言ってきました。各クラスで担任が指導し、申し出るように呼びかけましたが、誰も出てきません。
○演習2
:不登校傾向の中学生のナナさん(1A)が病院を受診し、「起立性調節障害」と診断されました。お母さんとナナさん本人は、「クラスのみんなに、このことを知ってほしい」と担任に話しました。
☆70日目(5.24)学級通信の中の仲間づくり
体育会が近くなり、学級通信(学級活動資料)の活用もいろいろ考えられますね。若い先生方と話してみたら、たね(ねた)、アイデアがいっぱい出ます。
○体育会リーダーからクラスのみんなへメッセージ
○学級日誌の記録・つぶやき
○種目練習の工夫や作戦(インターネットでの結構あります。大縄跳び つなひき バトンパス 玉入れ・・・)クラスの㊙作戦用紙として。
○応援ボードの下書き案㊙
○小道具(応援グッズ)づくり募集のお知らせ→保護者やお家の人に協力してもらう。そして子どもたちが取り組んでいることを知ってもらえるアイテムですね。
○班ノートの一節
○体育会当日までの天気予想(気象庁&クラスの担当生徒)
○写真(黒板の作戦会議メモ、練習でこけたAくんの絆創膏、汚れたくつ)
☆69日目(5.23)自立支援?自立応援?適応指導の目的を。
・・・校内でのサードプレイスのあり方を検討しています。
サードプレイスという言葉は、アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した考え方である。著書『The Great Good Place』(1989)のなかで、「家庭や職場での役割から解放され、一個人としてくつろげる場」としてサードプレイスを位置づけました。利害関係のないコミュニティを謳歌し、様々なストレスを抱える現代社会のなかでも、ゆったりと過ごす時間を得ることが重要だとしています。
サードプレイスの基本的な定義
サードプレイスは、自由で開かれた「とびきり心地の良い場所(原題の通り“The Great Good Place”)」を指します。オルデンバーグは著書の中で「インフォーマルな公共生活の中核的環境」という定義もしています。義務や必要性に縛られることなくリラックスして過ごせる場所であり、後述するファーストプレイス・セカンドプレイスがある程度「役割」や「追うべき責務」が決められた組織であるのに対し、サードプレイスは気ままに自分の気持ちに応じて選択できる場所のことを言う。カフェや図書館、また地域活動等のコミュニティ(場所的な実態がないもの)も該当するとされています。
岡山御津高校で事業を進めている一般社団法人ぐるーん(岡山市北区下伊福西町 7-32-309)は、「~事業を始めるにあたって~」に以下の内容があります。
〈さまざまな家庭背景や課題を抱える生徒に対して、教員だけではなく、より多様な地域の大人による関わりやサポートが必要とされているというお話を高校の教員から聞いた。当団体はこれまで社会的養護の必要な子どもたちへの支援を中心に活動してきたが、社会的養護に至る前の段階で困難を抱える子どもと関わり、支援を届ける必要性を感じていたことから、他県で行われている居場所カフェを始めることにした。手作りの料理やワークショップの体験を提供し、健康面と精神面のサポート、安心できる空間、多様な体験の機会を提供することで、高校生の学校生活や大人への信頼感構築に寄与したいと考えた。〉
新見市立思誠小学校の学校だよりでは
〈ステップ教室(自立応援室)を開設しました
心の居場所推進プロジェクトが令和元年よりスタートし、今年度は県内の11小学校、33中学校が研究校として指定されて「自立応援室」を開設しています。本校におきましても、今年度の目標3本柱の一つ、不登校対策の取組の一つとして、第2学期から「ステップ教室」と命名し、自立応援室を開設することにしました。
自立応援室の目的は
・不登校から学校へのステップとして
・不登校にならないための一時避難の場所として
・教室に入るための心の準備を行う場所として
機能することです。特別教室棟の2階、旧パソコンルームが「ステップ教室」として生まれ変わりました。保護者の方からの希望をもとに、利用できるよう手続きを進めていきます。常に教員が1名待機して、指導支援にあたることができるようにし、児童一人一人の思いが反映される柔軟な教室運営を目指していきます
岡山K中学校自立応援室『Kルーム』については、
〈木之子中学校自立応援室『Kルーム』について、お知らせします。
〇自立応援室について
長期欠席・不登校対策の専用教室のことです。本校では、『きのこルーム』とよびます。専属教員により、個々の生徒の状況に応じた学習支援・生活支援を行い、学校(教室)への復帰を目指すと共に一時避難等により長期欠席・不登校の未然防止に努めます。
〇対応について
専属教員の本校での勤務を、月・水・金を基本とします。他の曜日は、兼務校での勤務となります。火・木は他の支援員等での対応となります。担任とも連携を図ります。
〇自立応援室『Kルーム』からのお知らせ
(別添)の自立応援室からのおしらせ「Kルームについて」をご覧いただき、ご相談等ありましたら、本校までご連絡ください。
子どもたちにとって、学校・地域にとって意味あるサードプレイスを考えていきたいと思いますが、もうひとつ、重要ことは、この取組が必要となってきた社会背景や社会的課題が何なのかを見定めて、根本解決に向けたうごきやアプローチも必要であることを忘れてはならないと思います。
☆68日目(5.22)人権学習の内実を確かなものに
2023年に教育運動推進センター「教育おかやま」でまとめたものの一部です。
私たちが生きていく社会を私たちがつくっていくために
⒈自分自身が学び合う仲間と場をもつこと
⒉「教育改革」渦の中、大切な根幹を見据えること
⒊社会とつながる教育運動をめざすこと
1 最初に
私は、互いの教育実践を語り合い、教育実践を高める職場を大事にしています。 同時に、学校外での学ぶ機会や場に参加して自分の取組を振り返り、授業改善に役立ててきました。例えば、それは、東備学ぶ会などです。その会でも、最近は上記の⒈~⒊のテーマが話題になります。その中で,私たちは、「出来ることを足元からやっていく」べく、いくつかの取組を進めてきました。
2 全ての教育実践の〈基盤となる人権教育〉の内実を豊かに するための〈東備学ぶ会〉は12年目に。
「思いやりの気持ちを高めたり、啓発映画を観させ、人権標語をつくる」「個別の人権問題をいくつか授業で教えること」「専門的な事なので分掌や社会科担当に任せる」等の、人権教育に対するありがちなイメージを払拭するために、「学び直し」しようと始めたのが〈東備学ぶ会〉です。きっかけは、2012年の第64回全国人権・同和教育研究大会(岡山大会)での教育実践に触れたミドル世代の先生たちの「熱」でした。「同和教育」という名称が、「人権教育」となって月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを会の原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)など問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ね、大きな成果をあげてきました。その中で確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教師・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、まさしく今日の教育課題の解決へ向けて≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。
例えば、[定例学習会〕の1月の案内文にはこうあります。
《「子ども・学校・担任」に必要な「仲間づくり」の力をみがこう!
・・・「仲間づくり」の取組は、一人ひとりの子どもが抱えさせられている互いの生きづらさを共有し、それぞれの課題をともに克服しようとしたり、生きづらさの背景にある問題を解決していこうとしたりする意欲や行動力を身につけることです。「仲間づくり」は、このような目的を達成するために意図的に取り組むものです。そのためには、子どもの学校での表面的な姿だけでなく、家庭での生活やそのなかで感じている不安や悩み、保護者の思いや願い等をつかむことが、その出発点となります。いくつかのポイントがあります。
ひとつは〈子どもの生活背景をつかむこと〉・・・すべての教育活動は、子どもの姿、子どもを取り巻く現実から出発することが大切です。気になる言動を見せる子どもがどんなことを考え、どんな思いでいるのか、どんなくらしのなかで生活し、学校に通っているのか、保護者はどんな願いをかけて子育てをしているのか。そうしたことの中に、その子どもが抱えさせられている課題を解決するための、取組のヒントがあります。子どもの生活背景をつかむためには、家庭訪問等の取組を通じて、くらしや思い・願いなどについて対話できる関係を、子どもや保護者と築くことが必要です。また、〈弱い立場に立たされている子どもを中心に据えて取り組むこと〉〈一人ひとりが生活のなかで感じている不安や悩みを共有し、ともに乗り越えようとする集団づくりをめざすこと〉〈個別的な人権(課題)問題についての学習と結びつけて取り組むこと〉などのポイントが挙げられます。
他にも、人権教育の取組において、有効性が確かめられてきたいくつかの手法(「つづる」「語る」「聴き合う」)もあります。(松下一世さん:『子どもの心がひらく人権教育』より参照)
このようなポイントや手法は、現在ちまたにあふれる新しい教育改革理論やスキル、メソッド等の中で語られる内容と重なっています。1960年代から教育現場の私たち教職員が生み出した人権(同和)教育は、実践力を磨きます。多忙な毎日ですが、子どもたちの〈豊かなそだち〉のために一緒に語り合いましょう。》と呼びかけています。
次回は6/22(土)13:30~16:00。「ハンセン病問題学習」の小学校実践報告です。
☆67日目(5.21)エリアティチャーとの出会いをどう創るか?
先週、津波を想定した避難訓練の一環として、裏山に避難した際に、お招きしたエリアティーチャー(以下AT)さんは「本当に避難が必要な時には、今日通った道路はおそらく通れないだろう」と話をされました。ドナーカードを扱った授業時にATして来校された臓器提供コーディネーターさんは、「ドナーカードを使わない人生を歩んでください」と話されました。豊かな経験から語られるコトバ(真性の学び)がもつ力は本当にすごいと思います。いつもATさんをお招きする時には、事前の打ち合わせ(授業者の願い、生徒の実態・課題、めざすこと、そしてATさんの想いをしっかり聞くこと)をして、授業のコーディネート、状況に応じてファシリテートの準備をします。
そして、ATからのお話や提起は、子どもたちにとって「衝撃的」なことや、「刺激的」なインパクトを与えようとするのは考えなくてはなりません。以前、先輩に以下のメッセージをいただきました。「何を伝えたい 何を問いかけたい そして、自分はなぜ、ハンセン病問題にこだ わるのかを明確にすることがもっとも大切なことだ。趣旨・目的のない企画は「被差別の当事者」を利用するだけです。私はそんな企画には賛同できません。」私の教育実践がそうだったのでしょう。自分の立ち位置が問われてきます。ATさんの想いや願いをまず、「私」がどうとらえて授業をつくっていくかを大切にしたいと思います。

☆66日目(5.20)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き④
13.終わりに
最後になりますけれども,偏見・差別,これから皆さんもまだまだ学習されると思いますけれども,さっきも言いましたように,日本にはまだまだいろんな差別があります。偏見もあります。でもね,偏見・差別というのは,本当のことを知らないためにおきる場合が非常に多いんですね。大方,そうじゃないでしょうか。偏見・差別があるような世の中なんて,不幸な社会,決して幸せな社会じゃないと私は思う。
自分らしく生きるためには,やはり,差別のない社会がいると思いますね。もし,皆さんが大きくなって,偏見・差別のような事例に遭遇した場合,その背景にあるもの,偏見・差別の実態と言うんでしょうか,本当のことを知るということ,そのことをちょっと考えてもらえば,「何だ,こういうことだったのか,大したことじゃないじゃないか。」というふうに思い当たることが多くあるんですね。だから,「正しく知る」ということ,このことこそ,偏見・差別をなくしていく近道だろうと思います。
どうか一つ皆さん,今日の皆さんにしたお話をどうか少し他の方にしていただいて,これから皆さん共々,偏見・差別のない,そういう社会作りに,お互い力を尽くしていきたいなあと思います。どうかよろしくお願いします。
どうも皆さん,長時間,本当にありがとうございました。
☆65日目(5.17)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き⑤
⑤ 長島愛生園では毎日どのようなことをしていたのか。
答 愛生園は国立療養所だから,炊事場 ~ 給食部 ~ から,食事が部屋に届けられる。朝7時10分頃に朝食が届けられる。今は自治会の仕事をやめているので,本を読んだり,ぶらぶらして時間を過ごす。医局に行くこともある。あっという間に時間が過ぎるが,退屈だと思ったことは今までない。12時が昼食。職員が5時に帰らないといけないので,4時30分頃に夕食が配食される。私も含め,大部分の人はこの時に食事をすます。
愛生園の入園者の半分は,不自由な生活をしている不自由者なので,職員が生活介護をして,食事の世話もしている。 後は自由時間。外へ行く場合もある。私も外に行くことが多い。パチンコに行く人もいれば,それぞれである。同じ国立療養所にいても,一人ひとりの生活パターンは違う。宗教に熱心な人もいるし,短歌・俳句・詩等の文芸に一生懸命になっている人もいる。
⑥ 愛生園に強制隔離されていた時に,うれしかったことや楽しかったことは一度もなかったのか。
答 悲しかったことは,先ほど話をしたように,妻が亡くなるときに出られなかったことだ。その他にも,園内で再婚した妻が今から15年前にあっという間に亡くなった。3月1日に心筋梗塞をおこして,3日で亡くなったこともつらかったことだ。つらかったことはたくさんあったと思うが,いつの間にか,つらかったことを忘れてしまった。その時々にはつらかったことはあったと思う。一晩で足が下がり,手が下がり,喉頭麻痺を起こした時は,本当に毎晩自殺をしようと思ったこともある。今はつらかったことが何か遠い昔のことのように思えて,忘れたというか,「浄化」されたというか,浄められてなくなったような感じである。うれしかったこともたくさんあったと思う。全部のうれしかったことの 中で橋が架かったこと,これはうれしかった。橋がかかって,まだ12年位 だが,架かる前
は船で通っていた。橋ができてから非常に便利になったこともあるが,精神的に自分の気持ちの上で,「島流しにされていない」という安心感があった。時間制でなく自由に帰れる。そういう利便性。それから,今まで島の中に閉じこめられての「島流し」というものが,今は,陸続きになってなくなった。いろんな人が,遠くから働きに来ている。橋がないときはあまり遠いところからは職員が来ていなかった。でも今は,橋があるので,一時間ぐらい自動車でかかっても,愛生園に働きに来ている。ということで,橋が架かったことも,大きな喜びだった。「予防法」が無くなった,このことも大きかったし,さっき言ったように裁判をして勝ったことも,忘れられない感動すべき事だ。
⑦ ハンセン病の人たちが病気がうつらないのがわかっていたのに,すぐに法律をなくさないで,数年たってから法律で隔離がなくなったことについてどう思っているか。
答 「予防法」がもっと早くになくなっていたら,たぶん社会復帰する人がたくさんいたことは間違いない。ところが,5年前に,「予防法」がなくなったときには,もう私たちは年をとりすぎていた。その頃,70歳位の平均年齢だったと思う。なぜ,「予防法」が長く続いていたかということだが,これは,国というのは一旦,法律を作るとなかなか廃止するということはない。部分的に直すことはあっても,廃止してしまうということは難しいことのようだ。たとえ,その「予防法」が現実に矛盾をはらんでいても,完全に廃止することはなかなか難しい。私たちも「廃止」という運動は実はしなかった。「改正」運動をずっとしてきた。強制収容できるような法律は,時代錯誤だ。時代に合わないことだから,「予防法」を「改正してくれ。」ということも何回も運動した。ところが,強制収容の条項は残したまま,国は言った。「強制収容をはずしてしまえば,『らい予防法』は体をなさない。」と。どこの国も,こんな「予防法」はなくなっていたが,日本だけが,明治40年に作られた「らい予防法」を90年近く堅持してきた。私たちも,もっともっと強く「廃止」の運動をしていたら,あるいはどうなっていたろうか,という思いもある。しかし,予防法を「廃止」というところまでは,踏み切れなかった。というのは,「予防法」をなくした後,いったいどうなるのか,療養所はどうなるのか。「予防法」という法律があるから,療養所があって,そこで療養できるのに「予防法」をなくした場合,その先が見えない。だから,「廃止」運動がなされなかったということも,あるいは原因かもしれない。でも,大谷藤郎という厚生省の元事務局長であった方が,「やはり,『予防法』はなくすべきだ。」という意見を出した。それで火がついて,かぜん私たちの全患協(全国ハンセン病患者協議会)という組織も「廃止」の方向に踏み切って運動をしてきた。そして,今から5年前,1996年4月1日から「予防法」はなくなった。もうちょっと,少なくとも30年前になくなっていたら,ずいぶん多くの人が社会復帰していたのではないか。「予防法」がなくなった時に,「さあ,皆さん『予防法』がなくなったから帰りなさい。」,こう言ったって,年をとっているし,外での生活ができないとなると,法がなくなったからといって,そうそう社会復帰した人はいない。それでも,全国で20人近くの人が社会復帰したが,だんだん年をとってきて一層社会復帰は難しい。「予防法」がなくなった時,新しい法律の中で,私たちは,従来通り療養所の中で引き続き療養を続けることになった。これから,ハンセン病療養所はいつまで存在するだろうか。まあ,そう長い間存在することはないと思う。平均年齢が75歳なので,あと20年もすれば,療養所の中,何人残るだろうか。そうはたくさん残らないと思う。もう,目の前にそういう時代が来ている。
☆64日目(5.16)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き④
あと残る時間が30分位しかありませんので,これからは,皆さんの質問を受けて,お話ししたいと思います。
12.質疑応答(質問者・金さん共にていねいな言葉遣いでしたが,常体で表記します。)
① 1960年に社会復帰したのに,1965年に愛生園に戻ったのはどうしてか。
答 療養所内で再婚をしていたが,二人で社会復帰することにはいろいろ困 難があったので,一人で社会復帰をしていた。小さな工場の事務員として まじめに仕事をしていたが,妻から早く帰ってきてくれと何回も言ってき たのも無視できなかった。それから,外にいて,けがが心配ということもあった。強いて言うならば,外の競争社会におけるいろいろな圧力に負けたのかな,とも思う。でも多くのことを学んだとても貴重な期間だった。
② 日本に来たときの気持ちが知りたい。
答 私は1926年に韓国で生まれたが,私が生まれたその当時は,私たちの国,朝鮮国は日本が支配していた。いわゆる植民地として統治されていた時代。私の故郷にあった小学校 ~ 小学校4年を終えて日本に来たが ~ 学校で教わる勉強は全部日本語の教科書。週に1時間だけ,自分たちの国の言葉,朝鮮語を習った。でも,家に帰れば,みんな朝鮮語。生活は朝鮮語だった。そのかわり,学校に一歩入ったら朝鮮語はいっさいだめ。日本語を使った。だから,日本に来た時は,子どもの言葉だけれども,言葉で苦労はしなかった。日本の子どもと同じくらいの言葉の力はあった。小学校5年生に入った。昭和13年1月に日本に来たが,その前年には,日本は中国大陸に侵略を開始して,中日戦争が始まっていた。その頃は,日本人は先勝ムードにあふれていた。提灯行列を毎晩のようにしていた。私も親に連れられて,参加したこともある。私も子どもだから,いつの間にか日本のいわゆる軍国主義にそまって,いつか日本の軍人になりたいと思うようになった。日本の少年よりも,もっと軍国少年になっていったような気がする。「俺は陸軍大将になるんだ。」という将来の夢を持っていた。ところが,大きくなると陸軍大将になれるはずがないとわかってきた。中学校に入ってから,学校でも軍事教練ばかりしていた時代だった。その後,友人に「神奈川の兵器学校だったら最前線に行かずに,兵站部隊で済む。退官したら,技師になることができる。だから一緒に行こう。」と誘われて,昭和19年,1944年に神奈川県の陸軍兵器学校に入った。これまで,この話,~ 日本の軍人になっていた ~ なんて話はあまりしたくなかった。しかし,数年前にどこかでこの話をした時に,話題性があったので,言ってもいいことかなと思い,自己紹介の文に書くようにした。日本に来たときに,日本の軍国時代のまっただ中だった。祖国の朝鮮は植民地であったが,提灯行列をするほどの軍国主義ではなかったから,びっくりした思いがある。
③ 「らい予防法」によって,商売をやめさせられたり,家族から引き離さ れたりした時にどんな気持ちだったか。
答 どの患者も共通だと思うが,病気になると,病気になった自分が悪いんだと思うところがある。そういうことから,ある種のあきらめ,しかたがないというふうにあきらめることがある。もちろん家族と引き離され,私の場合は妻が私が入っている間に死んでしまう。たいへんこれは,本当に悲しいことだけれども。私の場合で言うと,妻が亡くなってから自分を大分責めた。病気である自分と結婚していなければ,彼女は死ななかっんじゃないか。病気になった自分が悪いんだ,悪かったんだという自分を責める気持ちが,ずっとあった。本当に妻には申し訳ないことをしたということを今でも思っている。家族と引き離されることはつらい。ここで横道にそれるが,ハンセン病になったら,なった病人だけが社会におれなくなるように排除されたり,差別を受けたりしていることだけではない。病気になった本人だけではない。その家族,家族も非常に社会から排除された。偏見を受けたりもしている。家族にハンセン病が出た。そのために一家全員で心中したという例もある。そうしてみると,病気になった本人だけではなくて,家族もろとも,偏見・差別を受けた。被害を受けた。ここのところを覚えておいてほしいなと思う。なぜ,日本では,このようにただ病気になっただけなのに,それほど社会から排除されたり,いろんな偏見を受けなければならなかったのか。これは,おそらくどの国を見まわしても,日本ほどではない。日本は特に偏見が強い。これは,ハンセン病だけではない。いろんなことに対してある。 いつ,自分が偏見・差別を受ける立場になるかわからない。 質問からそれたが,今,愛生園でもどこでもそうだが,多くの方が自分の本名でない偽名を使っている。なぜ,偽名を使うか,愛生園でも半分以上が偽名を使っている。これは,外にいる自分の家族を守るためだ。もし,自分が長島愛生園に入っていることが知れて,家族に迷惑をかけてはいけない。そのために自分というものを押し殺して,名前を変えている。まだまだ,この状態は変わらない。「らい予防法」がなくなった今でも変わらない。でも,少しずつ,「らい予防法」がなくなったころから,自分たち自らが変わらなければいけないという空気も生まれているが,なかなか自分の本名を名乗るということがない。
④ 講演をしていてやりがいがあったと思ったできごとは何か。
答 私の今の「生きがいは」と問われれば,社会復帰は難しいけれども,こういうふうに,外へ出て皆さんと直接いろんな話ができる。私たちの側からすれば,啓発するための運動 ~ 啓発活動といってもいいと思うが ~をすることが,今の私の「生きがい」だと思っている。いろんな人と会って,またいろんな出会いがあって,そこからまた,いろんな始まりがおきる。ということで,講演活動は私にとって,「生きがい」のあることだと思っている。今から10年ほど前,神戸で校長先生の集まりで,「貧しい国ほどハンセン病は発生する。貧しいと子どもが栄養が足りないために,『菌』に対する免疫力がない。貧しい国ほど子どもたちに免疫力がない。私たちの国も当時非常に貧しかった。私は農家の生まれだが,特に農村地帯は疲弊していた。もし,私の国が貧しくなくて,植民地にされていなかったら,病気になってなかったんじゃないかという思いはある。私の父方にも母方にも誰もこの病気にかかった人はいない。なぜ,どこでこの病気になったのか,なかなかはっきりとわからないが,小さい時に,この病気の人が村に食事をもらいに来ていた。相当に病気の進ん方もいた。袋の中にごはんを入れるのだが,私の家の門の前に来たときには,私がその役目を長い間していた。はっきりはしないが,その時にうつったのかも知れない。だから,ハンセン病は貧困病であり,植民地病だと言ってもいいと思う。」と話をした。その後で,ある校長先生が私に「金さんは,もし日本が金さんの国を植民地にしなかったら,金さんはこの病気にかかってなかったと私は思います。」 と言ってくれた。これはとてもうれしいお言葉だった。私の話したことをよく聞いて下さり,理解して下さった方だった。そのように今日も,皆さんにお話をして,よく聞いてくれて,質問をしてくれる。これは,私にとって本当にうれしいことだ。だから,話に行っていやだと思うことはほとんどない。うれしい。
☆63日目(5.15)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演会の続き③
10.愛生園の中で
①入園者の強制作業
私は愛生園に入った時には,「もう,再び帰ることはなかろう。外へ帰ることはなかろう。」という思いだったんですが,入ってみたら,すごく園内は明るい空気をしていました。もうすでに,(ハンセン病は)治るっていう時代に入っていましたから。私も「真剣に治療して帰ろう。」という意欲や思いで,一生懸命,治療しました。
ところが,ある日,私に伝票が来ました。どういう伝票かというと,「何月何日から何月何日まで,不自由な人が住んでいる寮に付き添い作業に行ってくれ。」というものでした。園の中では,作業がたくさんあるんです。いろんな作業の仕事があるんです。私はその伝票を見て,「これはいったいどういうことか。」と聞いたら,「元気なものは,不自由な者を見なければならない。そういう制度になっているから,この付き添いの作業は行かないといけない。」と言われまして,私は,作業に行きました。これはね,強制作業なんですね。どうしても身体が悪くて,という時は,医師の証明を持っていかなくちゃならない。医師はなかなか証明を出しません。いちいち証明を出しておったら,作業が回らないってこともあったんでしょう。この強制作業にはびっくりしました。
②監房
私が入ったころには,愛生園の中に監房 ~ 監禁室,患者を捕まえて,監禁をして閉じこめる ~ コンクリート建ての見るからに頑丈な監房があったんですね。私が入園したのは,戦後7年目ですから監房に入れるという時代じゃなかったですけれども,それでも,その監房にびっくりしました。戦後は,昭和23年ぐらいまでは,入れておったようですけれども。園の中にいる人を監房に入れていたんです。どういう人を入れるか,無断で外出した者,慰めに博打をしたり,喧嘩をしたり,そういう人もそうですね。それから,恐いのがもう一つあるんですね。これは,職員に反抗する者,職員に反抗する者は罰せられるんですね。職員側にすれば,反抗するっていうふうに取るんだけれども,入園者からすれば,当たり前のことを言うわけでしょう。いろんな事をお願いする場合もあるわけですよね。それも職員からすれば,反抗するっていうことに結びつく。そういうふうなケースで入れられた人がたくさんいます。
一つ例を申し上げますと,戦時中,まだ特効薬のない時代ですから,いろんな試験薬があります。試薬といいますが,その試験薬をうかつに出して,多くの方が亡くなりました。モルモットですよ,早い話が。今でも生きてる私のある友だちが言うんですね。ある女の先生が,「あなた,この薬をやりなさい。」と言った。その薬は非常に副作用の強い危ない薬だったんです。その薬で亡くなった方がたくさんいる。だから,私の友だちは「いや,その薬はしません。」と言った。ところが,その先生は「あなた,ちょっと草津へいくか。」とこう言った。実は群馬県の草津に重監房というのがあったんです。その監房は,零下10度になる寒いところに作られて,せんべい布団1枚を与えて,麦飯のちいちゃな握り飯一つとコップ一杯の水を与えた。そういうふうに非常に虐待された監房です。そこに行けば,生きて帰ることがなかなか難しいと当時は思われていたんですね。確かに,22,3人はそこで凍死をしております。そこが,草津監房です。その先生は,彼を脅かしたわけですね。
③人権無視の「らい予防法」
そういうふうにして,ハンセン病療養所は,患者は治すというより,患者を無理矢理に入れて,そこで一生を飼い殺しにする。そうすることによって,社会から病気をなくすという,こういう考え方なんですね。だから,日本の「らい予防法」は,よその国に比べて,非常に人権をないがしろにした,人権を無視したそういう法律だったんです。一言で言えば,「らい予防法」は,「絶対隔離・絶滅政策」を盛り込んだ法律だったんです。これが「らい予防法」だったんです。
④ワゼクトミー(断種)
それから,皆さんには,新聞などの中で「断種」というのを聞く場合があると思います。これは,結婚をしたら子どもを産まないように,手術をするんですね。だから,愛生園の中で,子どもを産むってことは絶対にない。もし,子どもができても,堕胎をするということなんです。ほとんどもう,子どもが産まれる臨月に近いような場合も堕胎をするんです。堕胎をしたら,「おぎゃー」って泣いてたんです。どうしたかというと,ガーゼで息のできないように顔を押す。そして,その子どもを殺す。そういうことが,どの療養所でも平然と行われていたんですね。皆さん,どう思われますか。「らい予防法」というのは,本当に人権を無視した,ぞっとするような法律だったんですね。いったん療養所に入りますと,その法律をみんなが強いられます。私もさっき言いましたように,中に入ってからは,強制労働もさせられました。そして,なかなか帰してくれません。帰省はなかなかさせてくれないんですね。
⑤妻の死
私の例をお話ししますと,入って3年目に,妻の姉から手紙が来ました。「妹がたいへんな状態になっている。病気になっている。ぜひ,入院させたいから帰ってきてくれ。」このような手紙が何度も来ました。私はその手紙を持って,園の人事係に何度も帰省をお願いしました。
でも,ついに,私は帰してもらえなかったんです。もう逃げて帰ろうか,逃走しようかと,こうも思ったけれども,逃走する勇気もなくて,ついに,その年に帰れませんでした。その2年後の昭和32年には帰れましたけれども,もうすでに妻は亡くなっていたんですね。
ある会場で「金さんが一番辛いことは何だったか。」と質問されたことがあります。その質問を予期していなかったものですから,「何だったのかな。」と思った瞬間に,今言いましたように,昭和30年に帰省をさせてもらえなかったのが,やはり,一番辛かった,悲しかった,ということを言ったことがあります。今思いましても,もし,あの時帰っていたならば,たぶん二度と療養所には戻らなかったと思うんですね。もう,ほとんど身体も回復していたし,もちろん「菌」もないし,こういうふうに手足も悪くないし,若くて元気でしたから。それに第一,入って3年位ですから,そのころのいろいろなかかわりというのは消えていないでしょう。断絶がないですから,十分,まだ外で生きることができたと思うんです。ですから,もし,あの昭和30年に帰省を許されていたら,たぶん私は帰っていなかったと,こういうふうに思うんです。これ,やっぱり辛いことの一番にあげてもいいんじゃないんでしょうかね。
11.裁判について
皆さんの質問を楽しみにしてきているんですが,その前に一つだけ裁判のことがありますから,ちょっとだけ聞いて下さいね。それが済んで,質問をお受けしたいと思います。
①提訴
今から3年ほど前に熊本地方裁判所に「『らい予防法』違憲国賠訴訟」~ちょっと難しい用語なんですが ~ 「『らい予防法』は憲法に違反している,それに対して国は謝罪しなさい,また,損害賠償しなさい。」,そういうふうな裁判を提訴しました。私も,もちろん原告の一人です。そして,いろいろな証人を立てました。元厚生省の医務局長であった方,療養所の所長,現在,香川県の療養所の大島青松園の外科医長の方も証言しました。どの先生も,「『らい予防法』は憲法に違反している。行き過ぎだ。絶対隔離政策をする必要はなかったんだ。」と証言をしてくれました。そして,原告も自らいろんな被害状況を訴えました。
②熊本地裁判決 ~原告勝訴~
そういうことから,去る5月22日,判決が出るんですね。私も熊本地方裁判所に傍聴に行きました。そして,あの本当に日本の裁判史上,あるいは,人権史上と言ってもいいと思うんですが,本当に歴史的な判決,それは私たち原告勝訴の判決でした。「らい予防法」は違憲性の強い,違憲性のある法律だったと,だから厚生大臣は誤っていたという判決でした。
もう一つあるんです。もう一つ。ちょっと難しい話ですが,国会,法律を決めたりする国会。これは国権の最高機関といわれています。一番上に位置している。その国会が,そういう誤っている法律を何ら廃止もしない,手直しもしない,そのまま法律を見過ごしてきたというのは,これは,国会の誤りだ。「立法不作為」という難しい言葉があるんですが,この判決では,国会の誤りをも認めたんです。これは,大変なことなんです。今までの判決の中で,国会議員の誤りを指摘した,認めた裁判はかつてないんです。一度も。ところが,この裁判は国会の過失を認めました。控訴するか,しないか。一番問題になったのは,国会議員の「立法不作為」です。
もう一つ,判決の中で重要な点は,「除斥期間」というのがあるんですが,~ 提訴して20年前のものは,時効にかかって問題にならないんだということが民法に書かれているんですが ~ この除斥期間もこの判決の中ではまったく一蹴した。除斥期間なんてないんだ。早くから患者の被害はずっと今まで継続している。除斥期間は,「らい予防法」がなくなってからを基準にしているんですね。時効を認めなかった。大きくいってこの3つの,本当に私たちからすれば,輝かしい,すばらしい判決だったんですね。
③国側,控訴断念
ところが,あまりにも,すばらしい判決でしたから,絶対,国の方は高等裁判所に控訴する,みんなそう思っていました。原告の絶対勝利のすばらしい判決であるだけに,国は黙って認めないだろう。私もそう思いましたし,ほとんどのマスコミは控訴すると報道しました。それで,国に対して控訴してはいけないという運動をしました。
控訴する期間は判決から2週間以内なんですね。2週間の間に控訴するか,せんかが決まるわけですが,それで,私も5月21日,東京へ行きました。多くの人が集結したんです。一般の理解する人も,支援する人もたくさん,1000人近い人が,あの首相官邸前に集結したんです。私もマイクを持って,解説をしました。なかなか首相は会ってくれない。首相官邸の扉を叩いた。なかなか開かないんですね。「扉を開けろ」とシュプレヒコールをやっても開かない。私は,22日にいったん岡山に帰りました。
そして,テレビに出てましたように,23日の午後9時10分だと思うんですが,小泉首相が「例外的に控訴しません。」と言いましたね。控訴しなかった。控訴しないということは,熊本の一審判決が確定したわけですね。その後,目まぐるしく,国がいろいろなことをやってね,国会決議とか,内閣声明とか,厚生労働大臣の声明とかいろいろなものが出てくるんですが。
そういうふうにして,私は,自分が原告になって本当に良かったなとつくづく今でも思っております。「らい予防法」のことは,話せばいろいろありますけれども,憲法に違反する法律であったということを国も認めたわけですから,私はその点では,原告になって苦しかったけれども,闘ってきて良かったと思っております。
☆62日目(5.14)人権学習の内実を確かなものにしたい
金さんの講演の続き②
7.なぜ,感染するのか。
それで,どうしてうつるのか,ということが一つ問題になりますね。うつる病気,感染する病気ですから。しかし,みんなうつるわけじゃないんですね。本当にうつる人は,ごくわずかな人なんです。いわゆる「らい菌」に対して,病原性を持っている,ちょっとむずかしい言葉ですね,まあ,うつりやすい体質の人もいるわけですね。そういう人が,ごくまれに,ハンセンの「らい菌」にたくさん襲われると,感染をするということです。しかし,ちっちゃい時,本当にまだお乳を飲んでいる乳幼児期にうつるというふうにいわれます。もう大人になってからは,身体に免疫力,菌に対する抵抗力ができますから,大人になってからは,絶対と言っていいほどうつることはありません。
これもよく例に出される話なんですが,療養所で働いている職員は何万といます。そういう何万の職員の中で,一人とて病気にかかった人はおらない。このことを考えてもね,成人になっては,なかなか病気がうつらないということを皆さんに知ってほしいなと思います。
だから,うつりやすい体質,いわゆる病原性を持っている人が,あまりに小さいときにうつる。それで,今の日本列島における子どもさんたち,皆さんも子どものうちに入るでしょうか,しかし,皆さんぐらいになるとうつるということはほとんどないんですね,中学生ですから。今の日本列島における乳幼児期の子どもというのは,非常に免疫力が高い。免疫力が高いということは,栄養がいいということなんですね。だから,今の子どもたちは,感染するということは,ほとんどない。
8.特効薬「プロミン」と「DDS」の副作用
それから,特効薬ができました。戦後,昭和24年,1949年から,どの療養所でも「プロミン」と言う特効薬が使われました。奇跡的にあの薬はハンセン病を治していったんですね。さっき,校長先生のお部屋でちょっと話をしたんですが,私もほとんど3年ぐらいで菌がおらない無菌になりました。長く治療していませんでした。
ところが,少し神経痛がするもんですから,ある日,先生に相談してDDSと言う薬,「ダプソン」といいますが,それを1錠ずつ1週間ほど飲んだら,その副作用から,私は,一晩で,たった一晩で足が下がったり,手が下がったり,喉頭麻痺を起こしたり,たいへんな副作用に見舞われました。その後遺症が今でも残っているんですが。ところが,今は,一種類だけの薬は使わないんですね。3つの薬を同時に併用するんです。多剤併用療法と言うんですが,3つの薬を一緒に併用するものですから,絶対に私のように副作用が起きたり,あるいは,後遺症をもたらしたり,そういうことはないんです。早く治る。そのような多剤併用療法で,3日も飲めば,いかにその人が菌をたくさん持っていても,その菌は感染力を失うっていうふうに大きく変わったんです。身体から菌が完全になくなるには,すこし間がかかるんですが。
そういう具合で,たいへん今は完治するいい薬ができましたから,病気になったからといって,ちっとも恐ろしい病気だとは,私は思いません。ハンセン病のことについては,少しおわかり願えたでしょうか。また,わからないことは,後ほど,質問をして下さい。
9.発病,そして「強制収容」
それから,去る5月11日,熊本地方裁判所で,私たちが起こしております「『らい予防法』違憲国家賠償請求訴訟」の判決がありました。その全面原告勝訴の判決があってから後,いろいろな新聞,あるいはテレビなどで放送もされていますから,皆さんも時に聞かれているんではないでしょうか。その中で「らい予防法」がどういうものであるかっていうことは,あんまり報道はされてないんですね。でも,憲法に違反するような良くない法律であったということは,何となくわかっていただけたと思うんですが,くわしくはわからないですよね。どうして,憲法に違反するような良くない法律だったか,このことについて少しお話をしてみたいと思います。
まず,私の体験からお話しをしましょうね。私は,1949年,昭和24年に,このハンセン病の告知を受けるんですね。そのころは,まだ自覚症状はあまりありませんでした。でも,背中の方に麻痺,-痛くない-,麻痺をしている部分があることがわかったんですね。それは,偶然,気がついたんです。
私を診察した医師が,長く私を診察している。本を繰って,長く考え込んで,いろいろしていました。「先生,私はなんの病気ですか。」と聞いたら,「レプラだと思う。」このようにおっしゃいました。今はあまり「レプラ」という用語は使われていませんけれども,そのころは,「レプラ」というのは「らい病」を指してる言葉だったんですね。これは,ギリシャ語です。私は「レプラ」と聞いてすぐ,「らい病」だなって思ったんです。先生からそう言われて,約1週間ほどしましたら,私は大阪に住んでいましたので,大阪府庁の衛生部予防課の大浜さんという女性が私の家に来まして,「あなたは病気だから,長島愛生園に行きなさい。」こういうふうに言われました。「どうして,僕が長島愛生園に行かなきゃならんのか。」ということで,何度か押し問答があったんですね。
私はついに,1952年,それから3年後に,強制収容で長島愛生園に収容されました。どうして僕が病気であるということが,すぐ府庁にわかったか。これはちゃんと「予防法」に書いてるんです。その時は,「予防法」があるのも知らずにいたんですけれども。どういうふうに書いているかというと,「ハンセン病を診察した医師は,必ず患者の所属する都道府県の知事に届け出をしなければいけない。」と,こうあるんですね。もし,その届け出を医師が怠ったら罰金があるんです。私を診察した医師はちゃんと知っていて,ハンセン病患者を診察したと大阪府の知事に届け出をしたんです。だから,大阪府から私の家に来た,こういうわけですね。
これもよく話をすることなんですが,実は,私は親を頼らずにいましたから,生活もあります。学生結婚もしていたもんですから,妻もいます。病気になっても生計を立てなければなりません。大阪の繁華街の新世界という所で友人の家を借りて食堂をしたことがあります。あまり大きな食堂ではありません。非常にうまくいっていました。その当時は,食料とか生活物資は全部国が統制していました。自由に売り買いしてはいけない,配給制度ですから。そういう時代に食堂は非常に繁盛するんですね。私の食堂も非常に繁盛しました。
ところが,何ヶ月かたって,さっき言いました大阪府の予防課の大浜さんが,私の店に来て,私は,もう,少し顔が腫れぼったくなっていましたから,店へ出てませんでしたが,「こういう商売をしてはいけない。」と言われるんですね。初め来た時には,私は会いませんでしたが,何回か来るうちに私と会って,やはり,「この病気の人は,こういう商売をしてはいけない。だから,やめなさい」と言いました。私は非常に腹が立ちました。私も生活をしなければならない。何かしなきゃならんのに,どうして,商売してはいけないのか。その後も何回か,来ました。
ある日,浪速署の制服の警察官を一緒に連れてきました。警察官は黙って立っていたままでしたけれども,やはり,それは威圧になるんですね。脅しになる。そうしますと,私も自然,商売する気持ちがだんだんなくなってしまって,ついに商売もやめるわけですね。これも「予防法」の中にちゃんと書いてるんですね。「従業禁止」という項目があるわけです。
そして私はついに,1952年,昭和27年7月22日,大阪駅から,いわゆる専用列車,私たちはこれを「お召し列車」と皮肉って言うんですけれども,私と大浜さんだけ,2人だけしか乗らない客車に乗せられて,岡山駅に送られました。私の場合は,本当に強制収容でした。それから,今日まで長く療養所で生活しています。数えますと49年になるんですね。
☆61日目(5.13)人権学習の内実を確かなものにしたい
人権教育の推進に取り組むときに、例に挙げられているいくつかの人権課題がありますが、その内容を知ること(理解する)からさらに一歩進んだ取組に出来たらいいなあと思っています。それには、「人との出会い」を学習の中にきちんと位置づけることが大切だと思います。ハンセン病問題学習に生徒たちと取り組む際に、私はいつも、金泰九(Kim teagoo)さんとの出会いを演出します。残念ながら亡くなられましたが、創られたドキュメンタリー映画『虎ハ眠ラズ』は秀逸で、今も教材として色あせていません。著書『我が八十歳に乾杯』もあります。人の生き方を通して、人権課題を見つめ、自分ごとにする学習を今年も学年団の先生たちと創っていきたいと思います。金さんの講演会(2003)の一部を何回かに分けて紹介します。
中学校の皆さん,こんにちは。(こんにちは)返事があってとてもうれしいです。ありがとう。ただ今,紹介をいただきましたように,岡山県邑久郡邑久町にあります,国立療養所長島愛生園から参りました金 泰九と申します。よろしくお願いします。
こんな格好で本当に皆さんに申し訳ないんですけど,実は,1週間程前に風呂場で滑っちゃって,骨折をしました。ギブスをまいているんですが,あと1月半ほどギブスをまかなきゃならんということで,こういう格好になりました。しかし,身体は至って元気ですから,皆さんご安心下さい。
これから約1時間半あまり,お話をさせていただきますが,今日は1年生から3年生までですから,やはり,やさしい言葉で話をした方がいいんじゃないかなと思っています。退屈して眠たい人もたぶんいるんじゃなかろうかと思います。どうぞ遠慮なく,こっくりこっくりして下さいね。
まず話の順序として,やはり,ハンセン病がどういう病気であるかということをみなさんに知ってもらう方がいいんじゃなかろうかと思って参りました。 それから,今,新聞その他,あるいはテレビ等で報道がされていますように,「らい予防法」の違憲性が強いあの裁判ですね。その「予防法」がどういうものであるかということも,みなさんあんまりは知らないだろうと思いますので,そのことも,私の得た体験をもとにして話をしたいと思います。
最後には,裁判にかかわるいろいろな問題もできれば話をしたいと思います。それがすんだ後,皆さんの方からいろいろ質問を受けて,そして,話をした方がいいんじゃないか,こう思いますから,質問の時間にはどうか,どんな質問でもけっこうですから,質問をして下さい。よろしくお願いします。
2.病名の由来とハンセン病の歴史
横田真智子先生の方からハンセン病についてのいろいろな学習はしたようですが,その復習と言う意味で,ハンセン病を病んだ私の方から,ハンセン病とはどういうものであるか,ということを少しお話をしてみたいと思います。 私は先ほどからハンセン病と言っていますが,以前はハンセン病のことを「らい病」あるいは「らい」と,そのような名前で呼んでいました。お年寄りの方は「らい」とか「らい病」と言う方がよくおわかりだと思います。でも今は,「らい」と言う用語は使いません。ハンセン病と言うようになりました。
ハンセン病の「ハンセン」は,今から約130年程前に,北欧のノルウェーのお医者さんでハンセンという方がこの菌を発見したことにちなんでいます。このハンセン病が地球上に現れたのは,ずいぶん古いんですね。たぶん,紀元前2,3世紀には,この地球上にはハンセン病があったと古文書を調査してわかります。日本でも日本書紀あたりでは,670年頃には「らい」と言う名称が書いてあります。奈良時代でもすでにハンセン病は日本にあったと思っていいと思います。「ハンセン病はうつる,伝染病だ」と。にもかかわらず,日本列島でハンセン病が現れてから1300年にもなるのに,あまりこの病気は蔓延,広がっていないんですね。伝染病だともっともっと広がっていいはずなのに,広がっていない。このことを見ても,この病気はそれほどうつらないっていうことが,皆さんおわかり願えるのではないでしょうか。
3.ハンセン病は「遺伝病」ではない。
この病気をちょっと難しい定義で言いますと,「らい菌」による「慢性感染症」,感染症なんです。そして,遺伝病ではありません。ずいぶん昔から病気があって,そして,どちらかというと同じ家族の中でこの病気が発生しているものですから,当時はうつっていく病気ではなくて遺伝する病気だ,と長い間思われてきたんですね。「遺伝病」,というふうに明治の初期あたりまでは日本でもそう思っていたようです。
ところが,さっき言いましたように,ノルウェーのハンセンさんが「らい菌」を発見した。菌を発見したんですから,これはとても「遺伝病」じゃないということがわかってきたんですね。だから,「感染症」なんです。
4.「らい菌」の特徴
「らい菌」は,「結核菌」とほぼ同じ時代に発見されるんですけれど,「結核菌」は培養器の中で培養できるんです。皆さん,培養っておわかりですね。菌を増やしていくことですね。でも,このハンセンの「らい菌」は未だに培養できないんです。なぜ,培養ができないか。早く,もし,培養ができたんだったら,もっと病気に効く薬が発見されたんでしょうけれども,培養ができなかったために,特効薬が早く作れなかったともいえるんです。
それほど「らい菌」は弱い菌なんですね。非常に弱い。形も抗酸性という性質も非常に似ているんだけれども,「結核菌」は人の体の中に入っても,肺とか腸とか,そういうところへ入って増えていくんだけれども,「らい菌」はね,身体の見える所,衣服で覆われていない見える部分にたくさん生息するんですね。それはなぜかというと,どうも「らい菌」は冷たい所を好むからと言う説があります。
5.「末梢神経」への影響
そして,体の中に入ったら,まず,どこに入るかというと,「末梢神経」,人間には「中枢神経」と「末梢神経」がありますよね。その「末梢神経」に「らい菌」が入る。「末梢神経」の中で菌が増えていくわけですが,そうすると,いろいろな「末梢神経」の「障害」が出てきます。「末梢神経」は「感覚神経」でもあるわけですよね。「痛い」とか,「熱い」,「冷たい」こういう感覚を司るところでもありますから,「末梢神経」がやられると,感覚がなくなるんですよ。痛いのもわからない。火にさわってもわからない。これが,ハンセン病の悪い特徴といえば特徴ですが。
そして,もう一つは,運動神経,私も今,指が曲がっていますが,このように萎縮してくるんですね。そして,身体が麻痺する。
私もね,ひじのここからはほとんど感覚がないんです。だから,火に触れても熱くないから,よく火傷します。釘を踏んでも,私の右足は前半分の感覚がありませんから,血が出ない限りわからない。そのように,ハンセン病の症状の特徴と言うのは,麻痺がまずおこることですね。
そして,少しそれが進むと,指が曲がってくる。これが,一番ハンセン病における悪い特徴だと私は思います。
6.「多菌型」と「少菌型」
しかしですね,ハンセン病でも「型」があるんです。いわゆる「タイプ」が。私は「多菌型」。非常に菌をたくさん持っている型,前は「らい腫型」といいました。それから,それに反して,菌を少なく持っている「少菌型」と言うのがあります。大きくわけて2つにわかれますが,実は「少菌型」の場合は,身体の末梢神経に確かに菌は入っているんだろうけれども,体の表面には菌が検出されないんです。いくら,どこをとっても菌の検出が見られないんです。
皆さん,ここでちょっと考えてほしいんですが,身体から菌が出ない人,もちろん,麻痺をしているわけです。あるいは手も曲がっている。そういう症状があるけれども,身体から,どこをとっても菌が出ないっていう人は,公衆衛生上何ら問題がない人でしょう。普通に皆さんと一緒に生活しても,何ら問題のない人だと思います。 そういう人も,今,療養所の中には3分の1以上おります。今はですね,特効薬で戦後,療養所の中でも治療されまして,もう菌を持っている人は,ほとんどいません。持っていても,感染力を保持しているような菌は一人もない。だから,療養所の中では,もう,まったく感染源になる人は一人もおらない。どこの療養所でもそうなんですね。
そういう意味では,外一般よりも療養所の中の方が,ハンセン病の感染と言う点から考えれば,全く安心できる場所なんです。
☆60日目(5.10)仲間とともに取り組む平和学習
今年度、久しぶりに広島研修に同行し、リニューアルした資料館を初めて見学しました。リニューアル中の時期に一度、生徒引率した際に、事前に学年団の先生らと下見に行き、「学習ノート」をつくりました。この学習ノートが必要なのか?、今あらためて話し合ってみたいと思いますがどうでしょう?
☆59日目(5.9)仲間とともに取り組む平和学習
学年集団の違いや、教師集団の取組の深化などで「群読(2014)」も変化していますね。
☆58日目(5.8)仲間とともに取り組む平和学習
昨日、3年生は沖縄修学旅行を前に、中庭で、平和集会リハーサルを行いました。しっかりとした「群読」、願いをこめた「歌」には、他の学年への強いメッセージも感じらた、とてみ素敵な取り組みでした。クラスで進める「群読」や「平和学習の内容」についても一考しましょう。少し前に生徒実行委員会が創出したオキナワ平和学習時の「群読」です。

☆57日目(5.7)学びの共同体とは?その③教科教育における「真性の学び」
○文学教育にとって「真正の学び」とはどういう学びなのか
文学の教育は「言葉」の教育である。「文学の言葉・詩の言葉」は、象徴性、多義性を特徴としている。文学は「アート」である。他のアートと同様、「もう一つの世界、もう一
人の他者、もう一人の私」と出会い、日常に隠された「もう一つの真実」を認識し表現する技法である。
文学・詩のテクストは一つの「作品」であり、比喩的に言えば「ごちそう」である。文学・詩の読みの目的は<わかる>ことではなく<味わう>ことにある。
文学・詩の学びは<テクストとの出会いと対話>である。協同的学びにおいても、<テクストとの対話>が中心にならなければならない。そのために<仲間との対話>があり<自己との対話>がある。逆ではない。
文学の授業・真正の学びを実現するための要件(文学の学びが成立するための教師の活動の要件。)①主題を追求しない。②「気持ち」を問わない。③「なぜ?」と問わな
い。文学の読みに「一義的な正解」はない。「多義性・多様性」に文学の本質がある。そのためにも虚心坦懐にテクストの言葉に寄り添って読むことが必要である。言葉に触れ、言葉に出合い、想像力によって言葉の<織物>を描き出すことが、読みの快楽である。具体的には、①12分程度の音読の保障、②3回はグループにもどす、③3回はテクストに戻すを基本として授業をデザインする。
○数学における真正の学び
①数学は「量と空間の科学」。数学的思考の本質は、「数学的推論」(現実(かず)→半抽象(量)→抽象(数))における「帰納と演繹」と「パターン認識」にある。
②しかし、近年、数学的推論(mathematical reasoning)の意味と論理よりも、問題の解法とスキルが重視される傾向がある。(純粋数学よりも応用(工学)数学が重視される傾向にある。)数学の理解は「量的意味」(半抽象)と「操作的意味」(アルゴリズム)とが合致した時に成立するが、最近の数学教科書は「量的意味」が軽視されている。(タイル、数直線、線分図など)。これでは、分数、比、割合で躓く可能性が大きい。「式ー答」ではなく「図-式ー答」の解答欄を実施しよう。③学年ごとに細切れになっている。(小数第一位=3年、小数第二位以上=4年、正方形・長方形の面積=4年、平行四辺形・台形の面積=4年など。)これでは、10進法の意味理解も、あるいは面積の求積の構造も理解されない。④数学的思考と自然や社会との結びつきが弱い。(数学的リテラシーが狭く認識されている。)
○社会科における真正の学び
社会科の目的は「民主的市民の形成(市民性の教育)」にある。社会科の学びは、史資料とデータによる思考と探究にある。(教科書で社会科は教えられない。)社会科の学びに正解はない。多元的な思考と探究が求められる。「社会と出会う」「社会を知る」「社会を生きる」、この三つが社会科の学びに保障される必要がある。社会的な事象は、因果関係において生じているのではない。複雑な要因の構造的な関係において生じている。
○理科における真正の学び
理科の授業における「予想」→「実験」→「検証・討論」という定番の授業は、根本的に見直す必要があるのではないか。「理解」中心から「探究」中心の授業への転換をはかる必要がある。科学的探究の本質は、「仮説→実験→検証」にあるのではない。日常の現象への「疑問(question)」が科学的探究の「問題(problem)」になるには何が必要か。これを教師は認識する必要がある(事例:NHKラジオ「子ども科学相談室」)。協同的学びの根拠はここにある。
科学的探究の本質は「モデルの構築」にある(数学も同様)。「詳細な観察(見える現象)」→「知識・情報の活用(考察)」→「理論モデル(見えない原理・法則)の構築」(言語化よりも図による提示が重要)
学びの共同体の実践では、<共有の学び(教科書知識の理解)>の探究的協同的学びと<ジャンプの学び(教科書レベルを超える課題)>による「理論モデルの構築」を実践している。
○アートの教育における真正の学び
・「アート」は「芸術」より広い。アートとは「生きる技法」そのものである。したがって、「アートの教育」は、「言葉の教育」と並んで、教育の中心である。
・アートとは、「もう一つの現実」「もう一つの真実」「もう一つの世界」「もう一つの私」「もう一つの他者」を見出し、それを表現する技法である。
・アートは、想像力と創造性によってもう一つの現実(内的真実)を生きる技法である。(「技とスタイル」の学び)したがって、アートは「世界の秘密」との対話であり、一人ひとりの「私の秘密」(内的リアリティ)に根差している。
○どう英語において「真正の学び」を実現するか。全教科のなかで最も混迷している。
<共有の学び>=教科書使用=教科書レベル
<ジャンプの学び>=authenticなテキストを活用。
小高学年、中1では、「スイミー・どろんこハリー・おてがみ・はらぺこあおむし」の絵本の翻訳、暗唱など。中2以上は、「アナと雪の女王」の脚本翻訳、ビデオ視聴、暗唱により高2~3のレベルへ。もう一つ、アジア諸国の英語教育の問題:「第二言語習得論」による弊害がある。アジア諸国にとって英語は「第二言語」ではない。「外国語」である。
○創造性の学びは「批判的思考」と「アートの学び」によって達成される。「アートの学び」(文学、詩、美術、音楽、演劇、舞踊など)が創造性の教育として、いっそう尊重
される必要がある。「批判的思考(critical thinking)」は、日本では誤解され混乱している。「批判的思考」は「異なる視点からの思考」つまり「多元的思考」である。「批判的思考による学び」は「探究と協同」、特に「高いレベルの学び」(ジャンプの学び)において有効に達成される。
☆56日目(5.2)学びの共同体とは?学習集団づくりとなかまづくりは違うのか?その②
探究と協同の学びのイノベーションをどう開始するか
① 授業と学び、学校改革のヴィジョンと哲学と理論の共有が最初に行うべき事柄である。あらゆる改革において<ヴィジョン>の共有は最優先課題である。どんな学校をつくり たいのか、どんな教育を求めるのか、どんな教室、どんな授業、どんな学びを希求しているのか。この<ヴィジョン>の共有は、すべての改革に先行する。『新版・学校を改革する』(岩波ブックレット)を活用する。
② 探究と協同の学びの学習(教室)環境を準備する。学習環境の改革が行われない限り、何も改革は進行しない。(小学1.2年生はコの字型+ペア学習、3年生以上、中学校、高校は男女混合4人グループの机の配置による協同学習。
③ すべての授業を<共有の学び>と<ジャンプの学び>で組織する。
④ すべての教師が教室を開いて学び合い、校内に同僚性と専門家の学びの共同体を構築する。
探究と協同の学びが成立する要件:探究と協同の学び(質の高い学び)の要件は三つ。
①<聴き合う関係>(話し合いではなく聴き合い、教え合いではなく学び合い、ケアの共同体)、②探究を促進する<ジャンプの学び>、③現実の文脈に則して教科の本質を追求する<真正の学び>の三つである。
① 探究と協同の学びにおいて有効なのは「発表的会話」ではなく「探索的会話」である。Douglass Barnes‚ Neil Mercer
② わからないときに隣の子に「ねえ、わからない、ここ教えて」という「援助要請(help seeking)」が、探究と協同の出発点を準備する。
③ 学びには、ある知識を学ぶ Learning I とその知識の学び方を学ぶ Learning II がある。Gregory Bateson 学びの共同体の「真正の学び」は、この Learning II の学びを実
現している。
真正の学びをデザインするー探究と協同の学びのイノベーションー
◎「真正の学び」は多義的な概念である。
①現実世界の学び、②探索的で探究的な学び、③現実的な課題で多様な知識を関連付け統合する学び、④高次の思考を追求する学び、⑤正解が定まらない探究的な学び、⑥反省的思考や熟考を促進する学び、⑦学びのプロセスで多様な他者と協同し真実性を追求する学び、などなどである。
◎学習者(表現者)の「内的真実」=ジャン・ジャック・ルソー
・モノ(対象)のホンモノと偽物を区別する意味=「外的真実」
・現実の文脈に則して教科の本質を追求する学び=AUTHENTIC LEARNING=ホンモノの学び
☆55日目(5.1)学びの共同体とは?学習集団づくりとなかまづくりは違うのか?
本校でも授業改革推進員の先生が来校され、中学校の取組・課題に合わせた授業づくりを進めています。授業参観後、授業についていろいろとお話できることが、「新しい学び」となっています。その中で、岡山で学びの共同体の話題もあがりました。岡山の研修会(岡山学び工房)の代表、秋山先生から提供してもらった資料の一部です。(パワーポイントなので項目的です。いろいろ意見交流を進めましょう)
「21世紀型の授業と学び」の世界標準と学びの共同体ー聴き合う関係による卓越性-
<21世紀型の授業と学び>
:1989年以降①学習者中心の授業、探究と協同の学び
②一斉授業の教室から、コの字型(小学校低学年)と4人グループの机の配置
③学びのファシリテーターとしての教師
④反省的実践家としての教師(教える専門家から学びの専門家へ)
⑤教師の専門的共同体(PLC)あるいは同僚性(collegiality)の構築
<学びの共同体>の独自性
:1992年以降①子どもの学びの権利の実現、学びの主人公としての子ども。
②一人も独りにしない「ケアの共同体」としての教室
③聴き合う関係の構築(民主主義は「話し合い」ではなく「聴き合い」)
④共有の学びとジャンプの学びー真正の学びの実現
⑤学びを中心とする授業研究による教師の専門家としての成長。教師が専門家として育ち合う同僚性。授業研究のイノベーション。
☆54日目(4.30)子どもたちが主体的に活動するオキナワ
広島研修の事前指導時に、「子どもたちが、実行委員会を中心に、〈主体的に活動する研修〉のあり方、組み立て方ってどうすればよいのだろう?」と話題になりました。コロナ禍前のオキナワ修学旅行の際に、同僚らと共に、子どもたち自身が運営する修学旅行を計画・実施することができました。日程のデータにもたくさんの意図した工夫があります。
☆53日目(4.26)T先輩から「おわりに」
「大阪大学の志水宏吉氏によると『社会学の領域では、「マイノリティー」は、次のように定義づけられている。「何らかの属性的要因(文化的・身体的等の特徴)を理由として、否定的に差異化され、社会的・政治的・経済的に弱い地位に置かれ、当人たちもそのことを意識している社会構成員。具体的には、「先住民や歴史的・地位的少数者も含まれ得るし、場合によっては女性・子ども・障害者なども含まれる可能性がある。」とされている。この定義から明らかなように、マイノリティーとは、ある社会の構成員のなかで相対的に弱い立場に置かれた「社会的弱者」のことである。』彼は、ニューカマーと呼ばれる新たに日本に来た外国人の問題を論じ、『彼らが日本の地域社会や学校・教室に提起する文化的異質性は、例えば、「在日」や「部落」の人々が示すそれよりもずっと可視的なものであるにもかかわらず、それに対する日本社会の側での対応は思いのほか鈍い。ニューカマーに対する教育支援の方途を実践的に探求することは、彼ら自身にとって有益であるのみならず、それが我が国の学校文化の体質自体の変革につながるという意味で、われわれマジョリティーたる日本人にとっても大きなメリットとなるに違いない』『「彼ら」の問題は、実は「私たち」の問題である。マイノリティー問題にこだわる意義は、その点にこそあるのである。』(『学校臨床社会学』~教育問題をどう考えるか~)と指摘している。長年、同和教育が『差別を生み出す学校を変革する』と主張してきたことと同じである。被差別部落の子どもたちの教育権を保障する取り組みは、その子たちだけでなくすべての子どもたちの教育権を保障する取り組みにとって力を発揮してきた。
しかし、同和教育の長年にわたる取り組みにも関わらず、いまだに部落問題を自分の問題と捉えられない人は多い。いまだに差別はしないまでも問題を忌避したり、問題から逃避したりする人は、少なくない。差別問題やマイノリティー問題への関わり方を切開すると、自分の意識や生活のありようを規定するものが見えてくる。偏見は持っていなくても差別意識は持っていたというのが、個人的な経験である。その差別意識から自分を解放したいというのが、「私の」問題としてこの問題に関わり続ける所以である。
ニューカマー問題が日本人としての意識や生活のあり方をも照射するように、日本固有の問題である部落問題はこの国のあり方を明らかにする。この国が国際社会で名誉ある地位を得るためにも、すべての人が各自の能力を発揮し社会のために貢献できるようになるためにも、マイノリティー問題など社会に存在する諸問題に無関心であってはならないのである。子どもたちがこれらの問題を自らの問題として認識し、具体的な取り組みを通じて、その解決を展望できる力を学校教育は保障することが大事な仕事となるのである。」
☆52日目(4.25)個に応じた学習
今から20年前の論文を前提に読むとこれも意味深いと思います。
「情報教育はコンピュータ活用教育の域をいまだ脱することができない現状にあるが、徐々に個別学習での成果も上げつつある。近年、「個に応じた学習」という研究がはやっている背景もある。たしかにコンピュータを活用すれば、個々の興味や関心・能力に応じた学習プログラムが可能である。これまでも一斉授業の中でも個に応じた指導はなされてきたが、コンピュータの登場は授業の画期的な変化を予想させた。学校は、問題解決的な学習にとって有力な手段を手に入れたといえよう。
しかし、最近は個に応じた学習というと、小集団学習であり、習熟度別学習であると捉えられているかのようである。ここにも学力向上問題が影を潜めているといえるかもしれない。習熟度別に小集団を組織してそれぞれに応じた課題をあたえるという発想は、効率主義の発想であって、個に応じたものとは言いがたい。小集団としての把握はなされても個としての存在は想定されていないからである。答えのはっきりした課題を確実にこなす学習や技能の獲得を目的とする授業にはこれが向いているのであろう。
情報教育で注目されるようになった個に応じた教育活動は、相互教授と呼ばれる。1台のコンピュータを二人で使うことにより、友達がアドバイザーとなることによって、知らず知らずのうちに技能を修得する学びである。友達が自分のモデルとなるのであり、自分よりも優れた者から学ぼうとする学びである。このようにして個々の得意分野を互いの学習に生かす、これは協同学習の一つの形態ともいえよう。赤堀侃司氏によると、これらは教育学者ビゴツキーによって発達の最近接領域理論として整理された。『すなわち、この発達の最近接領域では、学習者個人の問題解決能力は、大人である教師や一定のエキスパートなどの指導下ばかりでなく、より能力の高い仲間がいる場合にも高められ、より高次の発達水準へ導かれ、引き上げられるとする。』同じ集団の中に近似的に能力や技能の違う生徒がいることによって、相互の助け合いや教え合いが効果的に行われるというものである。
人権教育はその学習過程の中に相互に認め合い、協力し合う学習が必要になる。なぜなら、人権教育はその目的が重要であるだけではない。その学習過程そのものが民主的でなければならない。そのような意味でも小集団学習を取り入れるとしても、集団編成は均質な小集団であるよりは、できる限り多様な価値が交錯するような集団編成が目的意識的に追及される必要があるのである。」(続く)
☆51日目(4.24)協同学習
「日本では古くから班活動など集団を活用した指導がさまざまな面で見られてきた。したがって協同学習といってもさほど抵抗なく導入できるように思う。この協同学習の概念は情報教育の進展に伴って脚光を浴びるようになってきた新しい領域である。
従来、教師から一方的な新たな知識が与えられ、生徒はそれをいかに効率よく吸収し、自らのものにするかがこれまでの学習であったといってよいだろう。つまり、知識は個人の頭の中に個人の努力によって蓄積されるものだという知識観が横たわっていた。しかし、技術革新やあふれかえる情報のなかで、知識は絶えず陳腐化し更新される高度情報化社会にあっては、知識は個人の頭の中に蓄積するものではない。知識は状況や活動の中で生成され道具や他者との間に分かちもたれるものであるという考えに変わってきている。インターネットを想起すればこのことはよく分かる。誰も呼びかけたわけではないにもかかわらず、さまざまな能力を持った個人がそれぞれの能力を生かしてサイトを創作している。利用者はそれらの中から自分に必要な情報・知識を引き出し、活用する。そうした営みを通じて自然淘汰されながら、結果としてそれらの情報・知識は社会に広まり共有されていく。だから、教師に必要なのは、何か教える内容を先に決定するのではなく、状況に応じて生徒の必要とするものを見つける手助けをする力である。こうした中では教師と生徒の関係は、教え-教えられるといった固定的な関係ではありえない。これを意図的に構想したものが協同学習だといってよい。
東京工業大学の赤堀侃司氏の『情報教育論~教育工学のアプローチ~』によれば、コンピュータを道具として活用することによって、お互いの知識・考えを共有し、問題を解決していく学習を協同(協調)学習(Collaborative Learning)と呼んでいる。教室で取り扱う学習内容が人権問題や環境問題のように多面的な観点からの考察を必要とする内容であれば、情報・知識は必然的に教室の枠組みを越え、世界中の他者と結びついて獲得される形となり、学習は発展する。いわば問題解決を通じて学習共同体が出来上がっていくのである。そうなると、学習とは、このような学習共同体に参加することとなる。ここでは学習は主体的に展開されるのであって、教育ではなく学習が目的となっている。「低学力問題」を学びからの逃避としてとらえる東京大学の佐藤学氏の「学びの共同体」も同様の課題を提起している。学力は能力の一部であると同時に人格の一部である。佐藤氏は、協同的で反省的な学びとそれを支える同僚性の構築こそが今日の学校を再生する道であるという。これまで人権教育とは縁の薄いと考えられてきた領域に共通する課題が発見できるようになってきたといえよう。」(続く)
☆50日目(4.23)~学校を基礎としたカリキュラム開発
「地方分権が今後の政治の重点課題となっており、学校教育についても開かれた学校づくり、特色ある学校づくりという形で、地域にしっかりと根を下ろした学校づくりが始まっている。今後、校長に経営責任の強化とともに予算権や人事権が付与されるなど学校としての独自性が発揮される条件は拡大していくであろう。
放送大学の新井郁男氏の『教育経営論~生涯学習社会形成の観点から~』(放送大学)によると、1979年にOECD経済開発機構の教育研究革新センター(CERI)は、子どもたちをトータルに育てるための学校組織の改革に関する報告を行い、その中で学校が法的・行政的に自立性を持ち、専門性に基づいて独自の教育活動を創造することの重要性を説き、それを学校に基礎を置いたカリキュラム開発(School Based Curriculum Development)と名づけた。SBCDが可能なのは、①学校が関連するさまざまな組織と有機的な関連を持ちながら、独自のカリキュラムを編成する自由を持っていること ②教師と生徒が各自の経験を教育的な力として生かす自由な活動が保障されていること ③地方から中央にいたる種々の機関や団体など学校以外のレベルでのカリキュラム開発も容認されていること、だとされている。こうすることによって特色ある学校づくりが持続できるとしている。今後の教育改革が児童の権利を保障する国際的な流れを受けて、このように理解されていくか、先に指摘したような偏狭なナショナリズムに収斂されていくかは大きな分かれ目といえよう。しかし、いずれにせよ、子どもたちの現実・地域の環境を踏まえて教職員が独自にカリキュラムを創造できるような力量を身につけていかねばならないことに変わりはない。
「学力低下」問題を経て、今日ではあたかも「基礎学力か問題解決力か」という二者択一的な発想を押し付けるような問題の矮小化も進んでいる。当然のことだが、「学力も問題解決力も」でなくてはならない。カリキュラム開発としては、それをどう構造化していくかが課題である。基礎的な学力をつける学習には教師の指導は必ず必要だし、授業形態も一斉授業による指導も有効性をもつ。また、こうした学習では、目標―下位目標―行動目標―教材―教授―評価といった一連の流れが一般的である。しかし、創造的・発展的・問題解決的学習には教師は指導よりも支援が必要で、授業形態も協同学習が有効である。また、目標から支援までの間は学習者の反応に応じ、支援者の創意を生かしながら創造的な学びが展開されるという『羅生門的アプローチ』(注5)が注目されている。人権学習のような考え方や感じ方にかかわる教育内容は行動目標による評価にはそぐわないことから、目標の途中変更も可能な授業形態が望ましい。どちらが優れているかではなく、内容や活動に応じて、一つの単元でも組み合わせるような取り組みが必要となるのである。人権学習の場合は、協同的で問題解決的な学習が適していることは明らかである。」
☆49日目(4.22)「人権教育の歩みとこれからの取り組み(2004)」から考える
2004年当時、同和教育が「人権教育」へ変わろうとしていた時にT先輩がまとめられた論文がとても参考となります。また20年前に「これからも取組」として書かれた内容を2024年現在に読み返すととても考えることが多いと思います。
『人権教育の歩みとこれからの取り組み』から一部
「例えば、子どもたちの主体的な活動を組織する場合、生徒会組織や学級会組織をよりよいものにしようと工夫する学校は多い。しかし、その組織化の過程から生徒の主体的な参加を保障する学校はそれほど多いとはいえない。まして指導教員があれこれと枠組みを作ったりすると、生徒の意識は「活動は教師の許容する範囲のものでよい」とすることになりやすい、といったことである。この場合、指導方針や具体的な助言が子どもの主体形成に大きな影響を与えていることになる。同和教育についても同じことが言える。部落問題学習のときだけ民主的な授業をしても子どもたちからの信頼は得にくいものである。つまり、学校生活全般が授業であろうと生徒指導であろうと施設設備の利用や時間の区切り方であろうと、どこを切り取っても民主的であり、人権の姿が見えるようになっていることが必要なのである。部落問題を扱えそうな特定の教科・領域だけでなくすべての教科・領域で人権の観点で教職員と子どもの関係ができていなくてはならないといえる。そのことが了解できれば、自分は体育の教師だから教科としては同和教育にはあまり関われないなどということはないはずである。問題は、こうした観点で学校教育のあらゆる場面を眺めてきたかどうかということである。
そのような意味では、学校にいる教職員だけでなく、学校教育にかかわるすべての人が自らの人権感覚を持って、お互いの仕事やその進め方に対する“気づき”を大事にしながら、協働できる体制作り=学校経営への参画を担う必要がある。全同教加盟同教組織では、教科・領域の壁を打ち破るべく同和教育教材の作成に力を入れた時代があった。いわゆる人権学習の時間設定である。そして今、同和教育は、総合的な学習の時間に期待を寄せ、人権総合学習という形で進められていこうとしている。それは大事な取り組みだが、文字通りあらゆる場面での取り組みとはならない。むしろ、同和教育・人権教育は総合的な学習の時間の中でといった囲い込みに絡めとられていく道でもある。そうではなく、潜在的なカリキュラムを顕在化させ、その評価を学校教育の中に取り込む方法を研究すべきだと思う。学校の中の何が子どもたちの人権意識を磨いているのか、何がそれを阻害しているのかということである。この作業は、別の言い方をすれば、学校における人権文化を構築するための作業とも言える。これからのカリキュラム開発でぜひとも考慮してほしいものである。」(続く)
☆48日目(4.19)「綴る」ことから。
前掲で、90年代の本であることにびっくりしたと声もありましたが、引き続き北窓さんの本から一部を紹介します。
「子どもが綴る、教師も綴る」(P90~P92から)
私はこれまでに、いくつもの胸に熱いもののこみあげる感動的な実践報告に接する機会を得ました。そのすべてが、子どもたちの姿を丹念に伝えてくださったものでした。「子どもを綴る」ことの延長線上にそれは位置しています。
そんななかの一つにこのようなのがあります。
心閉ざすもの
大阪と京都の国境に、天王山がある。そして天王山のふもとに、大阪水上隣保館「はるか学園」は建っている。
一弘くんとゆかりちゃんは、ここから学校に通っている。一弘くんには母がいない。四歳のときに病気で亡くなったのだ。弟はまだ二歳だった。一弘くんの父は、「一家心中するよりはましだ」と考えて、身を切られる思いで二人を「はるか学園」に預ける決心をしたそうだ。
子煩悩なお父さんは、日曜日には面会に来られ、一弘くんも弟も、そんな父にとてもよくなついているようだった。
しかし、他の大人には人見知りのはげしい子だった。入学当初、どんなににこやかに話しかけても返事がなく、蚊のなくような声で「ウン」だけが言えた。
一方、ゆかりちゃんはといえば、笑顔を見せることがまったくなかった。教材「おらたちにゃ口はねえだに」のあの「もりい」のように、心を固く閉ざしたまま口を開くことがなかった。
抱きあげて笑いかけても、逃げるように腕をすりぬける……そんな子だった。
ゆかりちゃんには両親がいるのだが、面会もほとんどなく、兄と二人「はるか学園」での生活を続けている。
もの心つく頃に親の愛情を欲しいままにできなかったさびしさが、ゆかりちゃんの心の扉を閉ざし、さらに言葉をうばったにちがいない……、そう思った。
こだわり
それは、7月7日のことだった。子どもたちに短冊をわたし、願いごとを書かせた。楽しそうに無邪気に鉛筆を走らせる子どもたちのなかで、まったく手を動かさない子が二人だけいた。一弘くんとゆかりちゃんだ。二人をよんで話した。
「ねえ、何かお願いごとないの?」「書けない字があるの?」「何書いてもいいんだよ」
うなだれる二人に、私はたてつづけに言葉をあびせていた。
いま思えば、あまりにも冷たくひどい言葉だった。自分たちの願いごとが容易にかなわぬことを知っているからこそ、何も書かずにいたのかも知れないのだ。
さらに私はぬけぬけと続けていた。「おとうさんやお母さんと会いたいでしょう」と。
二人は、じっと私の目を見つめていた。私の心のなかを見透かそうとするかのように。
私は、そのときすでに二人に、「感性の鈍い教師」として見切りをつけられても仕方なかったのだ。しかし、その場は救われた。
二人は短冊を書いてくれたのだ。
おとうさん たなばたです おとうさん 一弘
おかあさんと あそぶように してください ゆかり
「ああ、書かせるんじゃなかった……」
私はもう後悔していた。それは、頭を鈍器で殴られたかのような衝撃だった。二人のすがりつくような思いをどうしてやることもできないくせに、無責任に書かせた自分がどうしようもなく惨めだった。
実は私は結婚するとき、親の承諾の得られないまま強引に己の道を貫いたのだが、その代償は大きく、私は親から半ば勘当されたような形になっていた。
親に会いたくて会いたくて会えぬつらさを、私は痛いほど思い知らされたのだ。だから、一弘くんやゆかりちゃんの心と重ねられるにちがいないと、勝手に思いこんでいた。
しかし、二人の短冊はあまりに重すぎた。私は、この重たい思いを真摯にうけとめねばならぬと思った。私自身はもちろんクラスの子どもたちと、その重さを分かちあいたいと思った。
この短冊にこだわり続けることから、学級の仲間づくりは始まった。 (『仲間をつなぐ人権学習』解放出版社P50~53より)
☆47日目(4.18)現実とつなげる学級づくり
◆北窓正明さん著書『仲間をつなぐ人権学習』 第2章「人権主義の生き方を求めて」(P85~86より抜粋)を紹介します。
・・・差別事象は実践の弱さの投影
たとえば、次に紹介しますのは、小学校二年生の「おてがみ」の学習のなかでのことです。この作品はアーノルド・ローベル作、三木卓訳で、大阪の解放教育読本『にんげん』にも載せられているものですが、友だちのいないガマくんのその寂しさを自分のことのように感じたカエルくんが、ガマくんにおてがみを出すといったストーリーのものです。
誰からもてがみのこないガマくんは、「とても不幸せな気もちで……」というところの「不幸せ」を、先生は子どもたちに聞きました。「みんなにとって、不幸せってどんなことかな?」と。その言葉にひとりの子がたった二行つづったのです。
「ぼくのふしあわせ。スブ、きのしたひでお、たかだひでお、ぼくはわからないです。」
担任の先生はこの子の書いた作文を私の前において、大粒の涙をボロボロと流されました。
「きのしたひでお」というのは、お父さんの通名です。「スブ」っていうのは朝鮮名、本名です。そして、「たかだひでお」はお母さんの姓です。「ぼくのふしあわせ」と題して書いた小学校二年生のこの子の頭のなかを、否、暮らしそのものが、この三つの名前をぐるぐると回っているのです。そのことが痛いほど担任の先生に見えているから、涙せざるを得ないのです。
通名を名のり、本名を名のり、時には父さんと母さんが別れて、母さんの姓を名のり……。そういう暮らしの現実がこの子のなかにあるのです。
子どもたちが現実にくらしのなかで抱く疑問、それにどうきちっと答えていくのか、それは何年生から部落問題を教えるのかということじゃないのです。就学前の子であろうと小学校低学年の子であろうと、生活のなかで持つ疑問やおかしいなと感じることがあります。それが自分なりに答えが出ない時に、子どもたちは日常的に引っかかりをもち、いらいらし、そして高学年になり体力がついてくると「荒れ」るのです。それぞれの年令なりに深い浅いはあれ、部落問題学習が子どもたちの生活現実、生活意識から出発してすすめられねばならないのです。(1990年発行)
☆46日目(4.17)自尊感情をキーワードに。
人権教育を核とした学級づくりのキーワードのひとつは、「セルフエスティーム」。ちなみに、キーワードはあとふたつあります。「コミュニケーション能力」「アサーティブネス(非攻撃的自己主張)」がそれです。(大阪府同和教育研究協議会の「わたし 出会い 発見」から引用。)
すでに、もうよく聞かれる概念ですが、あらためて「自尊感情(セルフエスティーム)」について。これは、「一生懸命生きているから自分が好きだ」という気持ちである。自分を否定するのではなく肯定的に認め、「自分らしさ」に自信をもち、自分を価値あるものとして思えるようになることである。そうして、自分の立場と自分の生き方に「誇り」がもてるようになると、これがアイデンティティの確立ということである。逆に言えば、自分のことを大切に思えないならば、人のことを大切にしようという気持ちも起こりにくいということである。
これは例えば、これまでも部落の子の「どうせオレなんかあかんねん」「高校行かれへんねん」「どうせ差別されるねん」という叫びに対して、その子を立たせようと必死の思いでかかわってきたことにつながるものである。
また、「いじめ」問題や差別事件の解決についても同様の問題に突き当たったはずである。原因をたどっていけば、加害者自身がつらかったり寂しかったりという生活体験の中で自分を大事にされず(「どうせオレなんか」)、自分も人も信じられなくなり、相手や被差別の者への共感がもてず、そうした恨み・つらみのはけ口としてねたみや反感を抱き(「なんでアイツばっかり」「オレだってしんどいのに」「あいつなんかどうなっても構わない」)、いじめや差別をしてしまうという深いいたみに出くわすケースが多かった。
これらに対しても、これまで同和教育の中で、生活を綴ったり生い立ちを語る中で、自分や親を見つめなおし、これまでのつらいことや反感・憤りを克服し、自分の立場に誇りを持って、差別やハンディに負けない生き方を見つけようとしてきた。これは、まさに自尊感情を育て、アイデンティティを確立することである。逆に言えば、自尊感情がしっかりしていることは、差別に対してしっかりと向きあい、世界の諸問題にも目を向けて行動できる基礎となるのである。
☆45日目(4.16)八ツ塚実さんの学級通信(3の3)
1983~1985学級の記録第3集より
□世の中が、どんなに急テンポで変わろうとも、教育の世界の方法や理念は、そう安直に変わるものではない。やっぱり、手間ひまかけてかかわりきらなくてはならない。 私はひたすらに「まじめ」作りに専念してきた。 「まじめ」さの欠落こそ、諸悪の根源だと考えている。まじめさを失った社会は、無礼・非礼の温床となる。人と人の間には、お互い暗黙のうちに守りあってきた「けじめ」というものがあった。これがあるがゆえに、わたしたちはささやかな平安を守ることが出来た。無礼・非礼は、この大切な「けじめ」を足げにしてしまう。
「けじめ」なき社会・・・それは「いじめ」社会にほかならない。
「まじめ」「けじめ」「いじめ」という語呂合わせめくが、私は今こそ、この部分に着目する必要があると考えている。(中略)教育の基本は「人権への覚め」をうながすことであると考えているし、「市民の作りあげる礼儀」こそ人権の形として現れたものと考えている。
□さあ、わたしたちがつくる学級通信はどんなものであるか。
☆44日目(4.15)八ツ塚実さんの学級通信(3の2)
1978~1980学級記録第2集より
□工夫もなく、愛もなく、努力をおしまぬ情熱もないから、当然そうなる。永年のアグラのツケがいまつくつけられている。
□それに加えて、世の中心となる考えは「経済的な効率」の論理だ。粗雑な人権感覚だ。さらに「家庭の崩壊」が追いうちかける。はびこる口先だけの評論が、この荒廃論議を一層まぜかえす。
□私はまゆをしかめない。「荒廃」の語もしり馬に乗って使うつもりはない。むしろ結構なことだと思っている。
□押さえ込んで統制をつくろうときではない。全く新しい理念を、いまこそ創造するときだからだ。私はえたいの知れない「教育の権威」をかさにきてこの仕事を続けるつもりはない。
□教育は荒廃しているのではない。いつの時も新生の模索の中にある。もし今の状況に「荒廃」の語を使うなら、日本の教育史のどの時代が荒廃してなかったというのだろう。それぞれの時代がそれぞれの時代を背景にして、それぞれ荒廃していたではないか。
□切り捨てられて、学校へもいけない子どもたちが沢山いた時代。
かわいい義勇軍や兵隊さんの養成所であった時代。
死ぬことが美徳とされ、「死ね」と教えられた時代。
個人的な立身出世の手助けに明け暮れた時代。
それぞれの時代がぬきさしならない課題を提示しながら、日本の教育の歴史の中にある。
□なぜ、いまことあらためて教育の荒廃なのか。
□今のままで流されれば、過去のあやまりを読み落としてしまう。そればかりか、美化さえしかねない。国をあげての教育批判は,他の一切の失策から目をそらす役割すら果たしている。
□もともと教育が、そこだけエアポケットのように荒廃するはずがない。いつからそんなお化けみたいな社会力学が横行しはじめたのだろう。
□このしごとにたずさわる全ての日々は、出発の日ばかりなのだ。結論を下したり、結果として評価できる日なんぞ、あるわけないんだ。
□「変わるためにこそ変えない部分が必要だ」ということと「変わらないためにこそ変える部分がある」という2つのことを「学級記録」の中から学んだ。
□「あたらしい憲法のはなし」を懐かしみ惜しむ人もある。それを文部省の変節のねたにする人もある。私はどちらもとりたくはない。惜しければ、変節も許さないのなら、自分の手でつくればよい。つくらなくてはならない。無いものねだりも、あてこすりも腹の足しにはならない。
□刻みつづけてきて、私はそこへ行き着いた。教職にあるあものの使命はまさにそれではなかろうか。
□あらためて考えてみると、私は民主主義について学んだことはないのだ。なんとなく選挙をし、正の字を連ねて開票し、話し合いもしないで多数決をやってきた。こんなことがなんで民主主義と呼べよう。
□きざなものいいとしてではなく、私は「共に学ぶ」という言葉がわが身にしみる。作りつづけ、学び続けることでのみ、ほの見えてくる民主主義。なんで私が、はなから指導者で有り得よう。歩みの中からつかまなくてはならないことにおいて、子どもとおとなの区別はない。
□日本中の教室の数だけ「民主主義の教科書」がほしい。そこでしかつくれない教科書が。このことを怠って、生きる心得をどんなに口数多く語っても、それは安っぽい人生訓でしかない。事実にうらうちされない薄汚れた授業活動は、ますます民主主義を遠いものとする。
□中学生たちと教科書をつくっていると、容赦なくわたしは教えられる。「正義のスケールの小ささ」だ。どんな小さな不正も許さない人たち」が、寄ってたかって小さな不正狩りにうつつをぬかしてきた。それが学校の輪郭となった。もともと未完成な存在である若者を、糾弾する学校や社会とは何だろう。
□あらためてはびこる教育批判なるものに耳を傾けてみよう。なんと多くのチマチマした正義による放言が混じりこんでいることか。大きい大きい不正義は、いつもふんぞりかえっている。栄光の中にある。
□「教育の荒廃」の語が、このような風土の中で使われている事実をこそ、私はおそれる。今、ポケットに手をつっこんで、マユをしかめているだけなら、それはまぎれもなく、教育の挽歌を奏でる手助けをしているのだ。
□私は、このてみやげを携えて、あなたと教育を語りたい。あなたのてみやげから、たくさんのことを教えてほしい。このプリントは、私が中学生に教えたことではない。私も共に学んだことの数々なのだ。1981
☆43日目(4.12)八ツ塚実さんの学級通信(3の1)
いま、学級通信をスタートする人は多い時期かも知れません。
八ツ塚実さんの「学級記録」に書かれていた内容の一部を紹介します。
2002年、尾道にある自宅を改造した資料館に行かせていただきた時に、八ツ塚さんのお連れ合いさんに頂いた3冊の本からの内容です。『学級記録第1集~3集(復刻)』1975~
□教育の仕事は、「継続」という時間の軸と「集団」という人間との掛け算でできる平面の上に、「営み」のすべてをつなげて素材とした建造物を構築することである。
□随所に使われる柱や板は、すべて「人権」と「平和」の素材であること。
□一時的な「投げ入れ」は教える側の自己満足でしかなく、日常化以外には、解放教育・人権教育の目的は達成されないということ。
□生徒にとって、ひとりの人間が自分の教師であり、わけても学級担任であるとは、何であるのか。学級編成と担任任命が教育側の手で一方的に行われている現状の中で、始業式の日に即「教師」でありえるのか。
□一人の人間が、一人の子どもにとっての教師になるためには、継続して呈示した行為の評価を通じるしかないのではないか。
□「一人を大切にする」とは、何をどうすることであるのか。そのことをオームにように口でとなえるだけで達成できるのか。
□子どもの意識のすこやかな変革を願うなら「ゆっくりと、ゆっくりと」「少しずつ、少しずつ」たゆまず語りかけ、はたらきかけるしかないこと。
□珠玉にような教材は、まさに日常の自分たちの生活そのものであるということ。
□自分の生活の教科書は、自分の手でしか作れないということ。
□学校が企画し実行する年間数十を越す「行事」は、切れてそこにあるのではなくすべてつながっている。「すべてつながっている」ことこそ教材の最もたるものであること。「行事」は日常生活の総括であるということ。
□感動・悲しみ・ためいき・に対してこの「学級記録」は着目しきれたであろうか。
□私たちの仕事は、途中やめが出来ない仕事だということ。
□学校では、その活動を開始するやいなや、ただちに教科の学習が有無をいわさずに行われる。
□国・社・数・理・音・美・保体・技家・英の各教科の教授活動。人類の文化遺産のさまざまな分野を受け継ぐのだから当然のことだ。がしかし、「その前に」ないしは「それと並行して」学んでおかなくてはならないことがある。それを怠ったり、軽視したりするから学習の電車に乗り遅れたり、乗れなかったりする人ができるのだ。
○なぜ勉強するんだろう
○どうやって勉強したらいいんだろう
○誰もが例外なく通る道筋
○学力とは何だろう
○学びの成果で、人からとやかく言われたりすることはないんだということ。
○ささやかな勇気と自信
○自分がやっていることの意味
□教師集団ということばを、あまりにも安易に使いすぎる。教師集団とは、何人かの教師が一ヵ所で仕事をする上で、時間ややり方などの一線をそろえるくらいのことをいうのではない。ましてや、線をそろえて仕事をしないでもすむような協定を結ぶことではない。一人ひとりの全力をてみやげにして、集団の質を高めることだ。
□「これが、わたしのささやかな自己に課した実験です。ここまでなら私でも出来ます。」事実に裏打ちされたこのことばを、だれもが持ち寄らなくてはならない。集団とは、なれあいの場をいうのではない。
□私の「学級記録」は私のロマンだ。最後の最後、私がたったひとりで教室に立って、彼らと学習活動するとき時の「私の教科書」であり「私の指導書」だ。
□卒業式 その後ろ姿を未ながら毎年自問します。「今年もひたむきに教師になろうと努力した1年だったろうか」と。
□「花はすぐ咲くもんじゃないんだ。月日をかけて咲くものだ。」目の前の花壇がそう教えてくれる。1978年3月24日
☆42日目(4.11)教科書無償化の取組について
入学式の中で、教科書授与時にこれまで「この教科書は これからに日本を担う皆さんへの期待を込め、国民の税金によって、無償で支給されています。大切に使いましょう」と話していましたが、今年度は、相談してアドバイスを受けながら「この教科書は、よりよい社会を造っていくために、高知県からはじまり、多くの人々の努力によって、義務教育を受ける小・中学生のみなさんに無償で支給されています。大切に使いましょう」としました。わずかな内容でしたが、「何を子どもたちに伝えるのか。伝えたいのか」を考えた大切な出来事でした。
以下の文章は高知市立長浜小学校のホームページの一部です。「子どもたちは,新学期をむかえるたびに,真新しい教科書を手にし,ページをめくりながら,これからはじまる勉強に期待をいだき,進級した喜びをかみしめることができます。
しかし,この教科書も今から50年ほど前までは,みんなが新しい教科書をただでもらえるというわけではありませんでした。
その頃,教科書は,毎年,新学期をむかえる前に各家庭でそろえることになっていました。3月になると保護者たちは,古い教科書をゆずってもらったり,古くて使えないものや,ないものだけを買いそろえたりして苦労していました。新しい教科書を全部そろえると小学校で700円,中学校で1200円ほどかかりました。一日働いても300円ほどの収入しかなかったのですから,子どもの数が今に比べて多かったその当時は教科書をそろえてやるだけでもたいへんな出費でした。
1960年(昭和35年)ごろになると,物価も値上がりをはじめ,教育費の保護者負担を軽くしようという動きも出はじめました。このころ,長浜地区の中でも,学校の先生たちや市民会館の館長さんといっしょにお母さんたちの読書会がはじまりました。2年ほどたつうちに,「わたしたちが習った歴史と今の子どもたちが習っている歴史は全然ちがう。わたしたちも子どもの教科書を使って勉強しなおそう。」という声が出はじめ,憲法の学習もはじまりました。
その中で,憲法26条に記されている「すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。」という部分が問題になりました。「義務教育はこれを無償とするというのだから,教科書を買うのはおかしいのじゃないか。」「教科書はもともと政府が買いあたえるべきものだ。」「教科書がただでないということは,憲法で定められたことが守られていないということではないか。」ということが,話し合わされました。
そして,1961年(昭和36年)3月に,長浜地区で行われた会合の中で,「いくら請願しても効果はない。ただで配るまで買わずに頑張ろう。」という提案がなされ,校区のいろいろな団体が中心になって「長浜地区小中学校教科書をタダにする会」がつくられました。
この会は,各地で集会を開き,署名運動をはじめ,いっしょにたたかう団体もふやしていきました。教科書の無償要求は,憲法を守るための運動であるということに気づいた人々は,この運動をもりあげささえていきました。
その要求の正しさが理解され,1週間もたたないうちに長浜地区で1600名もの署名があつまりました。その要求を高知市の教育委員会にもちこみ,「憲法を守るために教科書を買わない。」というたたかいを始めました。運動は,新聞やテレビにもとりあげられ注目をあびました。
教育委員会は,「教科書をタダにする会」との交渉によって,無償の要求は正しいと認めましたが,全員に教科書を配るという約束は絶対にしませんでした。買える能力のある人は買ってほしいという教育委員会の要求をはねのけ,2000名の児童生徒のうち約8割にあたる1600名が,教科書を買わずに新学期がスタートしました。
学校では,教科書を持たない多くの子どもたちのために,先生たちはガリ版刷りのプリントを使って毎日授業を進めていきました。
その後,運動の正しさがたくさんの人々や団体・政党に支持され,全国的な運動に発展し,国会で大きな問題として取りあげられました。政府もついにこの要求の正しさを認め,1962年(昭37年)に法律をつくって,翌年から段階的に教科書が無償で子どもたちに配られることになりました。
私たちが,今なにげなく手にしている一冊一冊の教科書には,このような運動があったのです。
1961(昭和36)年からはじまった教科書無償の運動から今年で50年目を迎えました。この運動の歴史的な意義や当時のようすを,今の子どもたちや地域の方々など,たくさんの方々に知っていただきたく,教科書無償運動50周年記念パネル展を開催することになりました。
高知市立長浜小学校【教科書無償運動50周年記念パネル展資料より】

☆41日目(4.10)子どもにとっての特別支援学級②
2007年から、『特別支援教育』が学校教育法に位置づけられ、全国すべての学校において、障害のある子どもへの支援をより一層充実させていくことになりました。
もちろんそれまでも支援はしていたわけですが、一人一人のもっている力をさらに高め、より適切な支援をするために、このような名称となりました。
特別支援教育は英語でspecial needs educationまたはspecial supporteducationと表記されます。となると、説明の内容(草案)ですが、
・特別に助けが必要な時に、誰でも利用できる学級です。
・視力が見にくい人には、自分に合った「めがね」でサポートするように、たくさんの人と一緒の教室で学ぶのが苦手であったり、授業での進度がゆっくりがよかったり、静かな学習環境が落ち着いたりする人は、あなたに合う学習環境(教室)があります。
・あなたとおうちの人と学校の先生と一緒に教室利用について相談します。
・誰でも学習や学校生活の中で“助けてほしい”時があります。そんな時に解決するひとつとしての「特別支援学級」です。
特別支援学級の子たちの障害については説明する必要はありません。ただし、『接し方』については、子どもたちが疑問に思うことも出てくるでしょう。たとえば、『(特別支援学級の自閉症の)〇〇くんにあいさつをしても何も返ってこない。無視されているのかな?』と思う子が出てくるのも自然なことです。そういう時には『先生や支援員の先生ににどのようにしたらいいのか聞いてみてね』と話します。その子に合った接し方を具体的に教えてもらえることでしょう。
特別支援学級の子たちと交流することは、個々の違いを理解する上で大切なことです。早い段階で知ることにより、発達について偏見をもたずに接することができるようになるでしょう」障害イコールマイナスと考えているのは、以前の障害児教育の残滓かもしれません。
子どもたちの発達段階によって理解の仕方が変わってくるので、学年相応の働きかけの仕方があると思います。また、やはり子どもたちはまずは身近な大人の様子や考えに一番影響されると思います。
子どもたちの理解を深めるには実際に一緒に活動する「交流活動」が一番だと感じます。ただ、その際に大切なのは、その近くにいる大人が適宜適切な話しをすることだと思います。言葉を発することができない子はどんな思いをしてそれに取り組んでいるのか、なぜ彼はじっとそこに座ってられないのか・・・。そのためにも学校・教職員集団がもっともっと理解(更新)をすすめる必要があると思います。
ただ、やっぱり理解はすぐには深まりません。小学校1年生のその子が6年生のときに「あ~、私は1年生の頃あんなこと言っていたけど、あれは間違いだった。」と思えるように、豊かな出会い(正しい理解・ありのままをわかり合う相互の取組など)を少しずつ積み上げていくものだと思います。
☆40日目(4.9)子どもにとっての特別支援学級①
かなり以前、勤めていた学校での生徒総会議案検討時、いわゆる通常学級に在籍する生徒が「特別支援学級ってどんなところなのか知らない。説明してほしい」と発言した。そういえば、特別支援学級、特別支援教育について、生徒らの発達段階に応じて、正しい理解を深める学習や取組が出来てなかったことを反省した。私たち自身は、様々な書物や資料、研修から多文化共生社会やダイバーシティ、インクルーシブ教育などなどの内容を学んでいくが、子どもたちが理解できるような取組(伝え方)は、丁寧に考えていかねばいけないと思う。学校と教職員の特別支援教育観自体が問われることだと思う。
インターネットで検索すると、
[お母さんが、特別支援教育のニーズのある我が子にどう話すか?が多く記されています。]例えば
・支援学級の方が、先生が教えてくれる時間が長いんだよ。できること、今より増えそうだね!(本人のメリット)
・人数が少ない方が、話を上手に聞けるもんね。そっちの方が得意だもんね!(苦手の改善<得意を活かす)
・クラスの人数が少ない分、質問がしやすくて、すぐ教えてもらいやすいから。(本人の過ごしやすさ)
インターネットには、先生が本人のクラスメイトに話す例のNGな説明もありました。
①「Aさんは、支援学級に行って、みんなに追いつくために頑張っているよ」
『追いつくため』という言葉は避けたほうが良いです。支援学級の目的は、『その子に合った特別な支援を受けるため』です。
クラスの子に追くためのものではありません。
日本教育の歴史性からみると「みんなと同じ」がまだ根強いですが、ここの目的意識の違いは、お子さんの過ごしやすさを作る上で重要になります。
②「Aさんは、勉強が苦手だから、できるようになるために、支援学級に行っているんだよ。」
ポイントは『勉強が苦手だから』というところです。支援級は、欠点や苦手を改善するために行くところではありません。
「勉強ができない子の行くところ」という印象を子どもたちに与えてしまいます。
③「Aさんは、勉強をもっとできるようになるためだよ。応援してあげてね。」
『応援してあげてね』は、子どもの中で上下関係を作ってしまう可能性があります。
頑張っているのは、学校に来ている全ての子どもに当てはまり、そこに原(通常)学級や支援学級の違いはありません。
それぞれ、学びやすい場所や方法に違いがあり、別に支援学級に行くことが特別なことではなくて、自然と送り出す、迎える学級風土づくりが大切です。(続く)
☆39日目(2024.4.8)始業式 「綴ること」の意義
春休み中にも生活ノートについて協議し、新年度は「やりとり帳」というものを活用することとなりました。それに併せて、生徒(学校便り「ひとのあいだ」版にして保護者にも知っていただく形式)へ資料を配り、取組の説明を行います。参考に、補足説明文は以下の通りです。
「やりとり帳」へのねがい
長い間、担任をしていて、『やりとり帳』」などの〈ひとこと日記〉や〈生活の記録〉の取組には、いろいろな思いがあります。おもなねらいは,「君たちことをよく知り、しっかり応援したい」という思いが大きかったように思います。記入の様子や内容から,「君たちの学校生活が充実しているのか」、「悩んだり、困っていないか」などの変化を見逃さず、話を聞いたり、相談を受けたりするために大切にしてきた取組です。日記に書いてくれた内容を、時には、学級通信に掲載して、クラスへの提案や学級会での話し合いにもつなげたり、クラスのみんなに紹介したりして、学級をよくしていくための活動にも役立ててきました。
だから、皆さんが、学校生活での出来事や日常の暮らしを「綴る(つづる)」ことによって、自らの生活をしっかり観察し、自分たちの生活を認識し、たくましく生きていく力を高めてほしいと思うのです。
何か心配なことがあるのか、弱々しい文字でのつぶやきが書かれた生活ノート、うれしいことがあったのか、はずんだ文字の生活ノート、何度も消したり書いたりした跡が残る生活ノート、消しゴムの消しカスがはさがっている生活ノート、好きなキャラクターのイラスト・・・などなど、「やりとり帳」の記述を通して、しっかりと君たちの生活を知り、応援しようと思います。
「書くことは考えること、考えることは生きること」というコトバがあります。
「ひとこと」日記」を書くというのは、表現や伝達の手段であることは間違いなく、伝えるための技術をみにつけることは、将来社会に出てからとても役立ちます。しかし「綴る」ことにはもうひとつ、だいじな役割があります。それは「認識」といいます。残念ながら、最初から作文が好きな人は、あまりいないかもしれません。それは難しいからです。自分の前にある「人・もの・できごと」にぴったりな単語をみつけ、次には単語どうしを結びつけ文にし、さらに組み合わせていくという、頭をフル回転しなければならない作業です。時には、できごとをよいととらえるか、悪いととらえるかなどという、価値判断もしなければなりません。自分の視点で書いているので、うそはかけません。鉛筆を進めるのは、大変な仕事です。
小さい頃、君たちは「話しことば」の中で生活しています。相手が目の前にいて、視線やしぐさ・表情なども伝達の手助けとなるため、多少コトバや言い方や文法がまちがっていても、おおよそ通じてしまいます。しかし「書きことば」ではそうはいきません。目の前に相手はおらず、頼りになるのは文だけなのです。だからこそ、必然的に対象をしっかりみつめ、掴(つか)もうとし、価値判断をすることになります。家族・友達・社会・自然などを題材として「綴る」なかで、君たちはしだいに「認識」を深めていきます。こういった「認識」を獲得する学習を基盤とし(あるいは並行して)、プレゼン発表の原稿やレポートを書いていくなら実生活に根差した、重みのあるものとなるはずです。飛躍的に認識の幅が広がる中学校のこの時期なのですから。
もうひとつ、書くことの基本は、身の周りのことを、あったことを、あったように、自分のことばで、です。時間軸に沿って、「○○でした」「○○しました」というふうに、過去形で書いていきます(展開的過去形表現といいます)。これがある程度できるようになってはじめて、前述のさまざまな機能を持った文章を書けるようになっていきます。
新しい『自主学習ノート』と『やりとり帳』を使った取組にを大切に、チャレンジしてみましょう。
☆38日目 席替えではなく、なかまづくり2(生徒への配布資料)
席替えではない。班づくりである。
新班は、新しい級友と関わり、知り、
共にがんばり合う仲間になるための
取り組みなのだ
なぜ,班をつくるのか。
(1)この時期、これまでの先輩たちの学級を見ていると,
いくつかの仲良しなグループに分かれている様子が見られました。
もちろん気が合うという理由でグループが形成されるのは自然なことで,学校生活を楽しく過ごしていくには大切なグループです。
(2)しかしグループの中だけの友人関係にとどまり、クラスの中で自分の思いを語ることが少なくなってくる心配もありました。
さらには,人間関係の固定化により,「あの子は,いつもああだから」「きっと,あの子のせいにちがいない」といった決め付けや,「どうせ言っても変わらない」とあきらめて声をかけたりしない様子も見られることがありました。
(3)クラスはみんな一人一人にとって,お互いの人権が尊重され,安心して過ごせる場でないといけないことは言うまでもありません。
みんなが充実した学校生活を送るためには,
①「自分らしく生活していきたい」と思う気持ちをお互いが尊重して,
②係や当番活動、委員会活動に積極的に取り組み、
③「班のひとり、クラスのひとりである」という意識を持って協力、行動し,そして
④それをみんなで認め合うということが必要です。
(4)班活動は,授業中はもちろん,掃除や給食、係の仕事など学校生活の様々な場面で大切にしなければいけません。その班活動を継続して取り組むことで,自分の気持ちを伝え,仲間の思いを受け止め,がんばり合う仲間になっていくことを、○中学校では大事にしてきました。
(5)○中学校の班づくり(仲間づくり)は
①「約束を守らない」「何度注意しても言うことを聞いてくれない」「人に嫌なことを言う」など,話のやりとりの中で,様々な衝突やトラブルが起こることも予想されますが、その時は、自分をごまかしたり,人のせいにしたりしないように,「私」を主 語として,自分の気持ちを伝えよう。
②自分の気持ちを出せる班をめざそう。
③小さなことでも話し合おう。(言い合いなどが生じたときこそ,問題を解決していく 力を磨くチャンスと考えよう)
④相手の気持ちを深く聴こう。お互いを表面的な言動だけで判断するのではなく,納得がいかない友達の態度や様子に「何でなんだろう…」と疑問を持って終わるのではなく、粘り強くかかわる中で(班活動を行う中で),それまで抱え込んでいた不安や悩み・しんどさといったものを聞いたとき,「そうだったんだ」と,初めて友達の生活背景や言動に込められた思いを知ることはとても大切なことです。
そして,そのことに共感し,一緒になって考えてくれる仲間の存在を感じたとき,
「一緒にがんばり合っていこう」という学年の力はさらに深まっていきます。
☆37日目 通信のロゴづくりって何?
「通信のロゴ」って何ですか?に応えて。
生徒らの発想やセンスはすばらしいものがたくさんあります。ロゴを募集し、ストックして、発出する学級活動資料(通信)に添付します。書いてくれた枚数分全部使わないといけませんね。
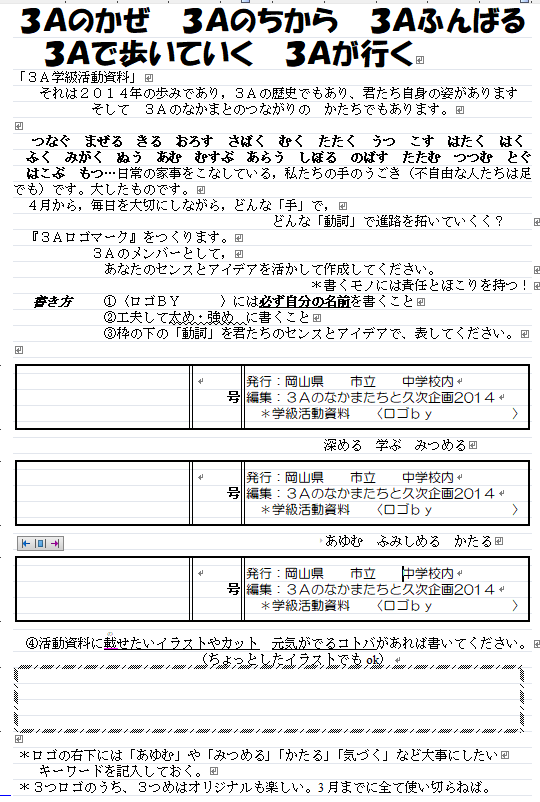
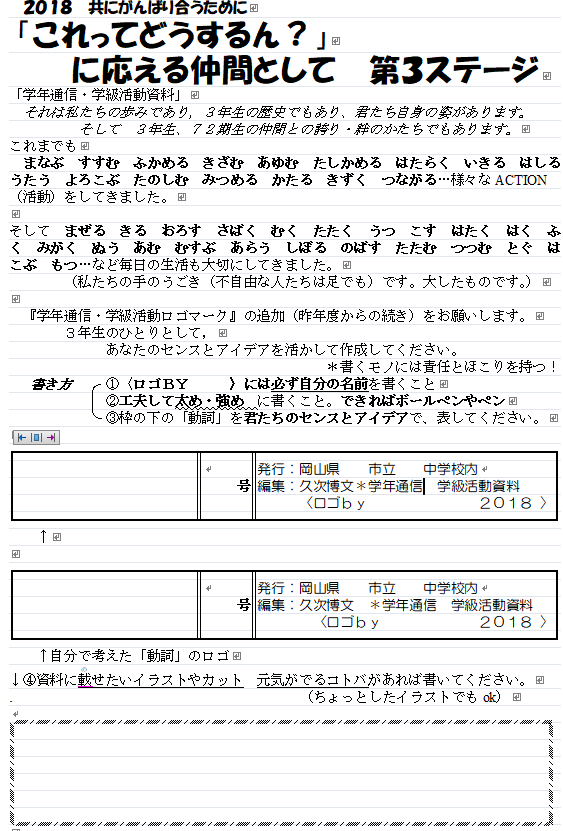
☆36日目 つらぬくこと こだわること
学級通信第一号については、年間・3年間をつらぬく指針がなくてはいけないと思います。また、通信の最終号でも、その内容に再掲示し「ふりかえり・まとめ」をせねばなりませんね。参照イメージのリクエストがありましたので、結構一方的なメッセージばかりで反省しますが、ご参考に。
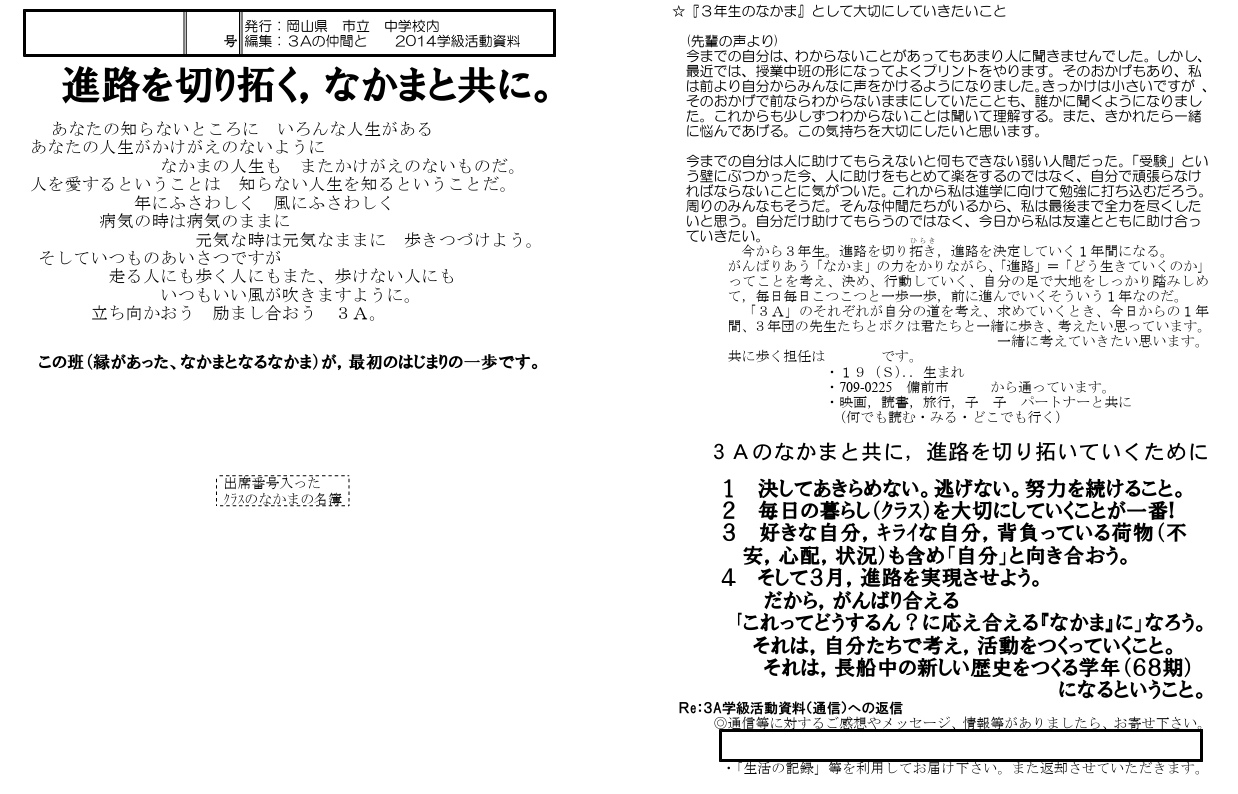
☆35日目 学級通信第1号の発行に向けて
子どもどうしが「しんどい」ことや「つらい」ことを語り合い、また「がんばり」合える集団になっていほしいと多くの教師が願っています。だからこそ、教師自身も自分自身の「生い立ち」や関わってる人権課題を「自己開示」しなければならないと思います。「4月最初から「暗い話」はちょっとしたくない」と聞いたことがありますが、人権問題は決して「暗い話」ではありません。真剣な生き方に関わる自「深い話」ならば中学生をきっと受け止めると思っています。またその語る内容によって、最初に書く「進級にあたって」などの作文の中身が大きく異なってきます。表面的な「進級して頑張ります~!」ではなく、やはり4月、自分自身の課題を深く見つめていくところからスタートしていけたらと思います。また子どもが開示した(取り組もうとしている課題)をしっかり受けとめ、寄り添い、覚悟をもって学級経営を進めていきたいと思っています。
新年度準備はいろいろありますね。
メモ
(1)学級通信1号 +当面の日程表
(2)学級通信「ロゴ」づくり
(3)生活班による春休み報告会
①単に点検にならぬように、班で春休みのできごとを話題にしながら、回収したいです
(4)朝の会、帰りの会改善①自主的な自治的活動の一助として
(5)提出物について 保護者とつながるために
・学校で子どもたちがおこなっている(取り組んでいること)を知ってもらう
(6)日直のしごと全
(7)班係活動一覧
(8)班長選出アンケート→班長会
(9)立候補(学級・専門委員)届
(10)道はいつもひらかれている色紙
(11)学級日誌(日直から日直へ)
(12)わたしはわたし(仲間を知るワークショップ)
(13)学級目標班会議WS
(14)最初の座席表
(15)自転車点検表 ①たかがされど
(16)誕生日原稿にお祝いメッセージ
☆34日目 今日は県立一般入試の結果発表の日。
残念な結果となった生徒らは、事前につくった「進路計画」表をもとに、新たな道を進んでいくことになるのですが、こころが揺れ動き、なかなか覚悟が決まらない場合も多々あります。そんな時、生徒(保護者)の気持ちをしっかり聴くことがやっぱり大切ですね。進路の決定は生徒たちにとって大変な作業です。特に、精神的、家庭的、経済的にハンディを負った生徒たちの気持ちを教員はどれだけ受け止められるかということ、それを受け止めた上で、的確に情報を伝え、考える場を提供することが重要です。そうすることで生徒は自ら選択し進路を決定していくことになります。
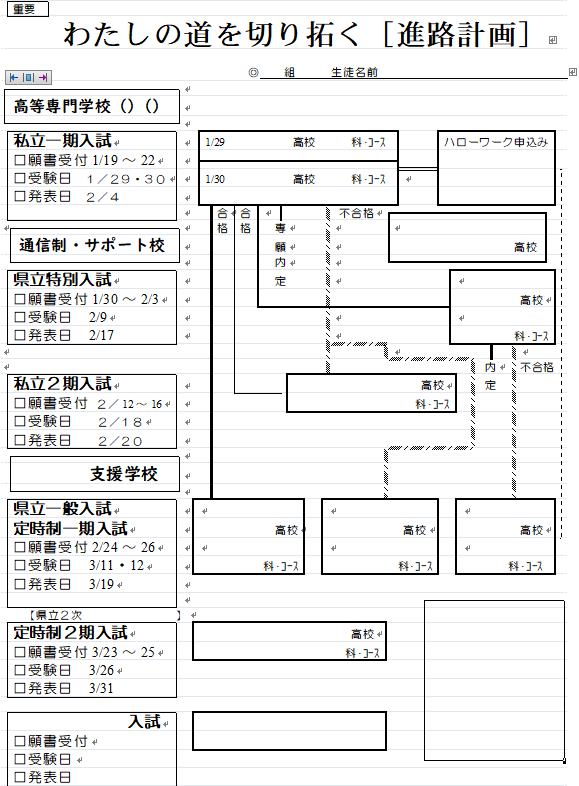
子どもたちにとって多種多様な進学先が増えました。進路指導には、私たちも謙虚に、正しい進路情報を更新していかねばなりませんね。
☆33日目 元気が出る行事(体育会・文化祭)へ
保護者から応援メッセージをいただく取組
おうちの方々からの子どもたちへのエールは、ちからがわいてきますね。当日より前に配布(お願い)し、2週間後くらいまで募り、「お便り」でかえします。
走り抜け!自分らしくせいいっぱい
体育会・「子どもたちへのがんばりメッセージ」をありがとうございました。
○中学校は、子どもの成長を軸として、保護者・地域と学校がパートナーとして連携・協働し、互いに意見を出し合い、学び合う中で、地域の将来を担う人財の育成を図るとともに、地域社会とのつながりを深めていく、「地域とともにある学校づくり」をめざしています。
いただいたメッセージの一部を紹介させていただきます。
○中学生ともなると、恥ずかしさから、なかなか本気を出しにくいものかと思っていましたが、皆、「真剣」に、「本気」を出し尽くしてる様子で胸が熱くなりました。(わが子も、筋肉痛に悩まされていま したが、それさえも「本気」「頑張り」の表れに感じられて、嬉しく思いました!)体育委員長の○○君の最後のコトバには本当に感激・感動しました。素晴らしい一日をありがとうございました。ここに 至るまでの先生方のご指導に感謝いたします。本当にありがとうございました。
○保護者観覧の体育会が開催できたことに感謝します。部活動で足の裏の皮が剥けてカットバンを貼った り、靴下を二枚履いたりして・・・、他の事はあまり言わないので、食事の時に「ポロッ」と言ってくれ る言葉で解ったり、「頑張っとるな~」と話したりしていました。中学校になりと、生徒がだんだんと 「主」になって動いて、成長を感じることができた初めての体育会でした。皆の一生懸命に頑張ってい て、親も頑張らんとな-と思いました。[みなさん頑張っておられますと思います。(_ _)PTA事務局)より]
○体育会に向けて、暑い中で先生方や子どもたちで毎日練習してきたことを聴いていました。「嵐の曲で体操をするんよ」って、少しネタばれしてくれたり、当日をとても楽しみにしていました。「リレーで 走るのが緊張する・・・」、「友だちが団長だから勝たせてあげたいんよ」って、早朝起きてランニングしたりまでしていました。子どものやる気と友だちを想う気持ちがとてもうれしかったです。最後の中学校の体育会は、私を幸せな気持ちにさせてくれました。暑い中、本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。
○中学生になって初めての体育会でしたが、とてもよくがんばっていたと思います。どの競技もほぼ全生 徒が出場する状況の中で、どの競技も白熱し、おもしろかったです。子どもは、自分の係の仕事も全うしていたようで、成長している姿にうれしくなりました。暑さのために、体調管理が難しい近年ですが、誰も大きなケガや体調不良になることなく遂行できて良かったです。
○久しぶりの中学校の体育会でした。子どもたちの人数も少なくなっており、寂しいかなと思いましたが、一人ひとりが頑張った様子もみることができ、何より、我が子がフル出場だったので、非常に充実 した、忙しい体育会を楽しませていただきました。毎日「足痛い」と、頑張ったかいもあり、この前まで小学生だった我が子も「ソーラン」を踊りきり、立派な○中生になったなあと嬉しく思いました。
中学3年間、走りぬけておくれ!!
☆32日目 何を綴るのか。何のための「振り返り」「感想」なのか?
ダルクさんとの出会い(例)
書くことは考えること 考えることは生きること
◎薬物乱用防止教室(人権集会「私らしく あなたらしく共に生きていくために」)の,生徒の「ふりかえり」を一部紹介します。
○お二人の話を聴いて,いろいろ辛い過去があって,薬物に手をつけてしまって,最後に言われたとおり,自分は薬物に手をつけたくないなと思いました。一人の方が 言われていた「良いウソをついて,相手をこまらせないようにしていた」というのに少し共感しました。依存というのは怖いことだし,回復するのにも時間がかかることが分かりました。
○自分の気持ちを日常の中で言えるようにしたい。薬を使わなくても「人生,楽しいことばかりでではない」ことを頭に入れて,辛いことも乗り越えて,命を大切にしていきたい。
○自分みたいに本音を言えない人がいたんだとびっくりした。一人ひとりに理由があって手を出しているんだと知り,僕は手をさしのべたくなった。今,お二人が,自分のことを素直に言えるのはすごいことだと思う。
○「自分みたいになるな」と自分を否定したことにとても驚いた。
○辛い,悲しいと思うことを一人で抱え込む,それから自分の人生が変わっていったということを聴いて,人間って全部を一人で抱え込んでしまうと「間違った道」を歩んでしまうこともあるんだと感じました。今の自分の生活をふりかえってみて,「どう生きていくか」をお話してくださったことを頭に入れ,過ごしたいと思いました。
○何か心配ごとや相談したいことがあれば,すぐに相談しようと思った。
○薬物はよくないし,やりたいと思わない。でも,自分が病んでいるときに誘われたらしてしまうと思ってしまった。もしも,病んでいる人がいたら,一緒にご飯を食べに行って,話を聴こうと思います。
○薬物以外でも,スマホなど普段いろんな人が使っているモノでも依存症になるから気をつけたい。
○自分も断るのが少し苦手なので,本当に嫌な時はしっかり断り,自分のやりたいことをやっていきたいです。
○今は,自分は絶対に関わることがないだろうと思っていたけど,以外と身近にあるから,人ごとでは済まされないなと思った。「一度のあやまちが,人生を大きく変 えてしまう依存をしてしまうと,一人では抜け出すことができない。周りの人がどんどん離れてしまう・・・。」この言葉に私は,薬物の怖さをあらためて感じ,すすめられても,断られるようになりたいと考えました。
○「ダルクにいても死んでしまう人がいる」というのを聴いて,びっくりした。薬物を一度やってしまうと,もう,後戻りができないことを知った。薬物で何もかも失うと聞いて衝撃的だった。薬物は絶対やらないと決めた。家族・友人を大切にしたいと思った。
○人に断れる自分になりたい。
○NOと言える人間関係をつくっていきたい。
○「他人事と思っている」という言葉を聞いて,もしかしたら,自分もそう思っているかもしれないと感じた。いつもの授業で習うのとは違い,言葉一つひとつに重み や現実味があり,その言葉が心に刻まれていくような気がした。孤立感などの負の 感情が精神的な理由だと知り,自分も気をつけなくては・・・と思った。
○僕は絶対やらないし,依存もしないと思っていた自分が心のどこかに居たのだと思います。ですが,今回のお話を聴いて,「絶対」なんてないんだとあらためて思いました。僕の人生の中で,今回の防止教室は一生消えない大事な1ページになった と思います。身近にある危険から目をそむけず,相手も自分にも優しくなれるようにしたいです。
○自分を大切に思ってくれている人がいるかもしれないから,その人たちとずっとか かわっていけるように,「薬物」は使わないようにしようと思った。親戚や友達が困っていたら,しっかり相談にのろうと思う。もし,自分が悩みをかかえていたら 友達を頼ろうと思った。「薬物」が日本からなくなってほしいと思った
☆31日目 何を綴るのか。何のための「振り返り」「感想」なのか?
「ホームレス問題」学習での学び(例)
◎川元さんとの出会い・「ホームレス問題学習」での「ふりかえり」の一部を紹介します。
○家があって,家族がいるのに帰れないし,頼れないのはすごく悲しいことだなと思った。岡山で実際にみたことがなくて,完全に他人ごとだと思っていた。本当にそういう人たちがいて,支援する人たちがいるのを学んで,自分でも何か出来ること があるかもしれないと思った。
○ホームレスの方に対する見方・考え方が変わった。いろんな苦労や恐怖がある中で 生きていて,僕たちよりもずっとすごいんだろうなと思った。安心して暮らせるよ うな,そしてホームレスの方がいない世界を作っていきたいと思った。僕は,ホームレスの人を下に見るようなことはせず,困っている時は助け,支えあうようになりたいです。
○私はあまりテレビや新聞などをみないので,今,社会にどんな問題があるのか余り 知りません。だから,これからはニュースや新聞で,今,どんな社会問題があるのか知っていこうと思います。ホームレスの人に出会っても,軽蔑するのではなく,周りの人と同じように接します。あと,生きる意味も考えていきたいです。
○生きる意味について考えた。僕は前から「人は死ぬものであり、死にたいと思うのなら死ぬのも別にいい」と考えている。それに加えて、「死んでもいい」という考え方が嫌いだ。生きたいのか死にたいのかはっきりしない、その考えを嫌悪している。しかし,今回のことを学び、生きる意味についての見解も少し変化があった。僕は今まで都会で生活に充実している人ばかりみて考えていた。しかし、孤立し、社会全体から否定されてきた人たちのことを学び、「人の生死は、その人たちが決めることだ」と思った。「死んでもいい」と思っている人たちが今も、生命活動をしているのは「生きたい」という本能があるからだと思う。その人たちはその本能に気づいていないだけではないかと思う。僕たちにできるのは、声をかけ、社会と結びつけることで、本能を感じさせることだけだと思う。人間は薄情だが、あたたかい心をもっていてほしいと思った。根本的に「死ぬのは自由」という考えは変化 していないが、その上にある「死にたいと思うなら死ねばいい」という考えが、「一度、生きたい気持ちがないか考えてみるほうがいい」という考えぐらいは変化した。
○今の僕はすごくめぐまれているのだと思いました。家族は優しいし、友だちと会話することが出来ている。だがいつか自分もホームレスになるかわからない今の世の中で、「これから僕はどう生きていけるのだろう」という考えがまた深まりました。何回かの授業では、自分にみえている明るい未来以外もみせてくれたことに感謝しています。大人は「君たちの未来は明るい」「社会は苦しいけどすばらしい場所だ」と言われますが、僕は社会にでるのは今は不安です。本当の幸せとは何なのだろう。僕たちは暗い世界を歩まなければいけないのか。大人が敷いたレールの上を走らなければならないのか。僕に分からないけど、一日、一日をがんばって生きていこうと思いました。
○ホームレスへの偏見がすごい中で支援活動をしているのはすごいと思った。ホームレスになる理由はそれぞれあった。ただ命をつなぐだけでなく、生きる上で大切な人間関係・信頼を創ろうとしている川元さんはすごいと思った。ボランティア活動に参加してみたいなと思った。
○信頼関係を築くこと,生きる意味について考えた。人数調査では,たとえ国が出した結果だとしても簡単に信じず,自分の目で,耳で,見たり聞いたりすることが大切だと思った。これから私は,周りの友人・家族・先生らと話し合いながら,生きる意味を見つけていきたいと思う。本当に困ったときは正直に「助けて」と言って,まわりの人に頼っていこうと決めた。
☆30日目 進路公開(28日目)へ、つながる3年間の進路・生き方学習
身近なひとに聴く(聞き取り)
1学期懇談資料
2024年7月20日~
1学年 保護者・生徒諸君へ
1年生総合的な学習の時間 夏休み聞き取り課題
身近なひとの「中学校時代」から学ぼう
~「進路」は「どう生きていくか」ということ。仲間と共に進路を切り拓こう~
への協力と子への励ましを!
保護者の皆様におかれましては、本校教育活動に対して多大なご支援をいただきありがとうございます。
さて、1年生は3年間の継続的な進路学習を進め、自分らしい能力や適性をもとにした進路実現をめざしていきたいと考えています。
そこで、夏休みには「身近なひとの中学校時代」についての聞き取りのご協力をお願いしたいと考えています。2学期には聞き取りの発表会を行い、生き方(進路)についての学習をさらに深め、そこから進路やしごとについての正しい認識や望ましい職業観について深く学んでいきたいと考えています。
これから自分の進路を切り拓いていく子どもに、身近な方から「生き方」についてさまざな経験を語ってもらいたいと思います。それによって進路に対する考え方や、職業観についての考えを学ぶことと思います。今回の「聞きとり」の協力をよろしくお願いします。
具体的内容
1 提出期日 ○年8月30日(2学期始業の集いの日)
2 内容 《身近な方からの「聞き取り」の内容は》
①中学校でがんばっていたこと(部活動、稽古事や勉強など)
②自分にとって苦手だったことや苦労したこと。そしてその問題にどう向き合ったか。
(克服しようとしたり、努力したり、折り合いをつけたことなど)
③自分を支えてくれた人々(身近なひとや友だちや仲間のこと)
④中学校時代を振り返って、中学生に応援メッセージ(願いや思い)
⑤聞き取りを終えての感想
・生徒自身が、身近なひとの中学校時代についての「聞き取り」をし、まとめる。
・文章化したものを見てあげてください。事実の確認とともに、さらに多くの内容が付け加えられるかもしれません。
・生徒自身が整理して、用紙に清書する。(完成)
・「聞き取り」をもとに、学級で報告発表会を行います。
◎そして、引き続いて、
1年生冬、「平和とは何だ~身近なところからの反戦・平和」
2年生夏、「はたらくって~身近なひとの生き様を知る~」、2年生冬「高校、進学、青春時代~ひたむきに・ひたすらに」
3年生夏、「進路決定にむけて、受験期をどうがんばったか」、3年生冬「個人答辞構想(案)」と、お家の方々と連携をしていきます。
☆30日目 3.11に、3.11を語る
その学年の全生徒たちの「総意」としての答辞の取組を以前に紹介しましたが、「いま・ここ」にあるコトについて、答辞や送辞では言及せねばならないと思います。折しも、13年前の出来事を過去の課題としてではなく、現在の課題としてそのことに触れ、そしてどう語るかはとても大切です。気仙沼市立階上中学校での梶原さんの卒業式答辞に触れるこはとても意味あることだと思います。
《 本日は未曽有の大震災の傷も癒えないさなか,私たちのために卒業式を挙行していただき,ありがとうございます。 ちょうど十日前の三月十二日。春を思わせる暖かな日でした。 私たちは,そのキラキラ光る日差しの中を,希望に胸を膨らませ,通い慣れたこの学 舎を,五十七名揃って巣立つはずでした。 前日の十一日。一足早く渡された思い出のたくさん詰まったアルバムを開き,十数時 間後の卒業式に思いを馳せた友もいたことでしょう。「東日本大震災」と名付けられる 天変地異が起こるとも知らずに…。 階上中学校といえば「防災教育」といわれ,内外から高く評価され,十分な訓練もし ていた私たちでした。しかし,自然の猛威の前には,人間の力はあまりにも無力で,私 たちから大切なものを容赦なく奪っていきました。天が与えた試練というには,むごす ぎるものでした。つらくて,悔しくてたまりません。 時計の針は十四時四十六分を指したままです。でも時は確実に流れています。生かさ れた者として,顔を上げ,常に思いやりの心を持ち,強く,正しく,たくましく生きて いかなければなりません。 命の重さを知るには大きすぎる代償でした。しかし,苦境にあっても,天を恨まず, 運命に耐え,助け合って生きていくことが,これからの私たちの使命です。 私たちは今,それぞれの新しい人生の一歩を踏み出します。どこにいても,何をして いようとも,この地で,仲間と共有した時を忘れず,宝物として生きていきます。 後輩の皆さん,階上中学校で過ごす「あたりまえ」に思える日々や友達が,いかに貴 重なものかを考え,いとおしんで過ごしてください。先生方,親身のご指導,ありがと うございました。先生方が,いかに私たちを思ってくださっていたか,今になってよく 分かります。地域の皆さん,これまで様々なご支援をいただき,ありがとうございまし た。これからもよろしくお願いいたします。 お父さん,お母さん,家族の皆さん,これから私たちが歩んでいく姿を見守っていて ください。必ず,よき社会人になります。 私は,この階上中学校の生徒でいられたことを誇りに思います。 最後に,本当に,本当に,ありがとうございました。 平成二十三年三月二十二日 第六十四回卒業生代表 梶原 裕太》

☆29日目 「落書きや掲示物のいたずら」をどう受けとめる?
もちろん、してしまった本人を特定して指導することが前提ですが、学年集団(仲間)全体の課題として捉えて、学年集会、または全校集会を行う視座が必要だと思います。(集会には学級委員や生徒会役員が語る場面をつくることが大切ですね)
少し古い資料ですが、学年通信として配布し、クラスの指導で参考した文書を紹介します。
【◎「人権と共生の時代」の中で。
それは与えられるものではありません。譲ることのできない“人権”と“共生社会”をつくるために、私たちは中学校生活の中で、一人ひとりを「大切」にして、「どう生きていくのか」考えていかなければなりません。今週は、残念ながら掲示物への侵害がありました。そのことについてあらためて一緒に考えてほしいと思います。
「掲示物の「目に穴をあける」という行為。例え、それが新聞やポスターだとしても、とても嫌な行為です。穴があいた人物の目が私に訴えてきます。「同じようにされたら、あなたはどうする?」と。『自分だったらどうする?』を心の中にいつも持ち続けることが、お互いの「人権」を大切にすることになるのです。やる人は、軽い気持ちかもしれません。でも「軽い気持ちだから許される」…ということはありません。いや、軽い気持ちでやるようになってしまった…ということは、とても大変なことなのです。初めての時、「やろう」とする時、心の片隅にある良心がブレーキをかけたはず。ほんのちょっとでも「ためらい」があったはずなのです。そして、何度も繰り返すうちに、平気になるのです。「良心、一人ひとりが大切」というブレーキを大切にしてほしいと思います。初めての時、ためらうようなことは、きっと「してはいけないこと」なのです。】
様々な指導をしても、本人が名乗ってこない場合、落書きはどのようにして消しますか?教職員が消さなくても、必ずその取組を大切に受けとめてくれる生徒たちはいます。本校でも5月頃に廊下の手すりに落書きがあり、その落書きを消す作業に参加してくれた生徒はなんと10人以上。次の日はクラスでその旨を報告。「落書きを許さない学級風土」が育まれていきます。

☆28日目 卒業を前に「進路公開」
今日と明日は、県立一般入学者選抜の日。卒業を目の前に最後の学級活動の準備をしている担任の先生らとの会話の中で・・・。
「進路公開」というのは、自らの進路(多くは高校進学や将来の夢や目標)をクラスの仲間の前で公開していくことです。
発表する子が、自分の暮らしをみつめ、自分をとりまく人々の願いを受けとめ、自分自身の可能性を高めるための進路を求めたことを語り、その発表を聞く側の子たちは、発表した子の暮らしに思いを馳せながら、強い声援を送る」そんな時間を、卒業式前にしっかりと取りたいですね。
だから、「進路公開」はお互いの暮らしを知らない者どうしの学級集団では成立しないとりくみとも言えます。すなわち「進路公開」の時間が大事なんじゃなくて、それまですごしてきた日々で、どれだけ本気で隣に座っている仲間のことを知ってきたかが必要なのです。
「仲間の語りを聴く・返す学級風土」とは、言い換えれば「クラスの仲間の語りに一生懸命に真剣に返していく文化」を作っていくことが「真のつながりのある学級集団づくり」ということです。本校でも「聞き取り課題の報告会」や、発達特性について考え、ゲストティーチャーからの提案で、自分の苦手なことや応援してほしいことを語り合う活動をおこないました。
「自分を見つめ、綴り、語る」取組は実はますます重要だと考えます。
☆27日目 東備学ぶ会で何をしている?
人権教育実践を中心に様々な教育課題について学習しています。2024年2月の学習会の内容を紹介します。
□特別支援教育と人権教育2「十八歳への進路保障」
障害者の権利条約の第14条では、「『障害に基づく差別』とは、障害に基づくあらゆる区別、排除は制限であり、『障害に基づく差別』には、合理的配慮を行わないこと」とあります。「共に学ぶ」「自立」とはどういうことか。
◎1/20は、通常学級の在籍する児童にかかわって小学校の先生からの報告をもとに、共生・合理的配慮について具体的な実践から考えていくことができました。
◎2/17は、地元の定時制高校の先生から、卒業生徒の進路保障に関する報告をもとに、小・中・高の連携や自立支援のあり方について考えたいと思います。
これまでも東備学ぶ会では、特別支援教育についてたくさん論議してきました。例えば、「子どもにとって、多人数の教室で、静かに座っているだけで子どもどうしのつながりが弱いような気がする。居ることが「共生」なのか悩む」「教室の秩序を乱してしまう子どもを「特別な場に連れ出す」ことは、合理的配慮なのかなあ」という声。また、クールダウンする部屋や、個別学習を要求する子どもに応えることは、合理的配慮か分離なのか。子どもがいじめや差別に合うことを心配して、保護者が特別支援学校や普通学級を希望する状況があるかを学校は把握できているか。発達特性が早期に発見され、早期治療が受けてもらうことが学校の役割なのか・・・などなど。日々の葛藤を受けて、今回の学習会は精神論や理念でなく、合理的配慮や共生について、具体的な日々の教育実践(現在の私たちの学校教育の内実)を問いながら、教育の本質に深くかかわる問題、「子どもの成長、学校の使命とは何か」という、この古くて新しい問いに対して、一緒に考えていけたらと思っています。
☆26日目 「地域を歩く・知る・学ぶ」取組は、東備地域で学び合う先生たちの会で開催しました。
「東備学ぶ会」の学習会の案内にある文書を紹介します。
東備学ぶ会は12年目を迎えました。本会は、2012年の第64回全国人権・同和教育研究大会/岡山大会開催を機に、≪人権教育の内実をつくり≫さらに、「豊かな」教育実践を創るために、「同和教育の財産」を大切にした学習会(研修会)を行なっています。
「同和教育」という名称が、「人権教育」と置き換えられ月日は経ちましたが、私たちは同和教育の一貫したテーマ「差別の現実から深く学ぶ」ことを活動の原点として考えています。同和教育を進めてきた諸先輩たちは、その時々に「きょうも机にあの子がいない」(長欠・不就学の問題)、「ひとりの落ちこぼれも出すな」(学力の問題)、「しんどい子を学級経営の中心に」(仲間づくり)などのかたちで問題提起を行いながら、日本における教育の前進のために数々の先駆的な実践を積み重ね、大きな成果をあげてきました。そしてその中で確立されてきた①差別の現実から深く学ぶ。②教育と運動を結合する。③弱い立場にある子どもを中心とする生活を通した仲間づくりをする。④差別と自己とのかかわりを大切にする。⑤教師・指導者の自己変革を大切にする。この五つの原則は、今日の教育課題を≪切り結んでいく≫ための重要な原則と重なります。同和教育と人権教育の関係は対立的ものでもなく、同和教育が人権教育に変わったわけでもありません。「普遍から個別へ」「個別から普遍へ」という不可分の関係として考えることが大切だと思います。同和教育で積み上げてきた豊かな教育内容と実践は、国際的な人権教育で提起されてきた内容と完全に一致していると確信をもっています。
多忙な毎日ですが、私たち自身が〈学び合うちから〉を高めることは、子どもたちの〈豊かなそだち〉へつながっていきます。一緒に語り合いましょう。学び合いましょう。
☆25日目 地域を歩く・知る・学ぶ
鶴島フィールドワークへ、日生、東備地域の先生方と一緒に行ってきました。この島は浦上四番崩れで大弾圧を受け捕らえられた3400人のうち117人が流刑され開拓を強制されながら改宗を迫られ、禁教が解かれるまでの三年半の間に、死者18名、改宗者55名を出す過酷な仕打ちを受けた地です。その後、私有地となり、ご家族がいなくなってから長い間、無人島となっていたため、日生港から、釣船に乗せていただき、島に着くことができました。伸び放題の木々の間を案内していただき、井戸の跡や石碑を見て、その後、18人の方のお墓と慰霊碑、そして真っ白なマリア像がある島の南側の丘陵地へたどり着きました。また、高台の上には改宗を迫った祠、そこに続く長い石段(強制労働で作らさられたものでしょう)を歩いて桟橋へ帰り、岐路につきました。地域の文化や人々にどもたちが出会う豊かな機会を創っていくことは、これからますます大切になっていきますね。教材化したなあ。

追記:日生諸島(岡山県備前市)の鶴(つる)島にキリシタン遺跡
明冶政府の外来思想排斥政策は、多くのキリスト教信者を心身ともに苦しめました。岡山城下から約50km離れた無人島「鶴島」に送られたキリシタンたち(長崎県浦上キリシタン教徒117名)は、自由な身になるまでの3ヶ年半をこの島で過ごしましましたが、すしづめ状態の長屋、土地の開墾、説教聴問などに耐えかね、改宗せざるえない人もいたといいます。この島は、草地で開墾するには適しており、大豆、麦、さつま芋などが作られていましたが、それらの作物を口にすることは許されていませんでした。この島で亡くなった18名のキリシタンたちは、島の南東の丘斜面に葬られています。
また、この島には、浦上の「四番崩れ」で、長崎から流された岩永マキさんがいました。彼女は、浦上に帰ったあと、神父をたすけ、看護婦、孤児院、十字会など社会奉仕の中心人物となりました。
1969年、岡山市のカトリック教徒により、殉教百年祭が盛大に行われ、殉教者碑・十字架などの建立とともに、めい福が祈られ、「殉教の島」となっています。
☆24日目 授業での複数指導(TTや支援員との協働連携)支援体制での効果的な取組は??
1 複数指導・支援の多様な活動例を参考に,効果的なさらなる授業づくりを。
(1)授業準備
①個々の生徒の実態や課題(個別の指導計画)を加味した授業づくり
②アイデアを出し合いながら、共同での授業計画の練り合い
③個々の教師の個性・特性を生かした担当や役割分担
④教材・教具の準備
(2)授業の中で
①教え合い・学び合いの実践(★1~★6参考)
・学習活動への意欲付け ・個人やグループ別指導場面での役割分担
・発達特性を踏まえた上での、課題への理解を支援するための補足や手本の提示、手立て、モデリング
②事前に検討した個別(抽出)指導の実施
③定性的評価・・・授業中の抽出生徒への指導・支援・見取り
・評価対象者を分担し細かく見取り、多面的な視点からの評価
④状況に応じた生徒の抽出指導 けがへの対応、事故の防止の確認
⑤教材・教具の出し入れ(提示)
⑥小テストの採点や提出物の確認
(3)授業後
①話し合いによる授業全体への客観的評価
②多面的な視点から、生徒一人一人についての情報交換と評価
③授業計画の見直しなどの協力
2 実践していくために
校内研修の中で
(1)これまで取り組んできた 「教え合い・学び合い」の授業とは子ども同士が学習課題を媒介にしてつながり,「聞き合い」「伝え合い」等の互恵的な人間関係の中で「学び」を深めていく学習方法である。ペアやグループの形で活動することが多いが,子ども同士の関わり合いの中で個々の「学び」を深めていくことが大切となる。学び合いの授業で教師は,学び合いの場を設定したり,子ども同士の学び合いが促進するような援助的な関わりを重視し,直接「教える」という行為を控え,子どもの「学び」の実態に合わせて授業を展開することとなる。
(2) 聴き合う場としてのデザイン
学び合いでは,「聴く」ことが重視されており,3から4人のグループでの指導や話し合いで行われる。子どもだけでなく教師を含めた集団の誰もが,顔を上げるだけで 誰かと視線を合わせて話を聴くことができる。教師は子ども一人一人の表情をつぶさに見て,非言語の情報を読んだりつぶやきを拾ったりする。
2 授業づくり
(1)教師は,落ち着いた声の大きさや調子で,授業を始める。その教師の穏やかな態度やしぐさに合わせて,子どもの気持ちの高ぶりが収まり,休み時間と学習時間の区別が自然と付けられる。
(2)教師は,終始,声の大きさを抑え,柔らかな口調で授業を展開していく。教室には,落ち着いた雰囲気ができ,その中で生まれる子どものつぶやきを教師が捉える。教師 自身が「聴くこと」を大切にする姿勢がモデルとなり,子どもも「聴くこと」のよさを意識し,友達のつぶやきにも耳を傾ける「聴き合う」関係がつくられる。
(3) 学び合いは,グループで行われる。しかし,必ずしも,意見をまとめ合ったり話しあったりすることが目的のグループ学習ではない。一人一人が自分の学びを進める時 にも机を付ける。分からない時,困った時,「分からない」「教えて」という言葉を自 然に口に出すことができる。そしてそれを受け止められる距離,その中でそれぞれの 学びを進め,互いに学び合うのである。2人組では,学びに広がりを生み出しにくい。3人では,2人と1人に分かれがちである。5人以上になると,頭を突き合わせるこ とが難しくなる。4人組は,ある程度の意見の多様さをもちつつ,机を付け合うことで,関わり合いが自然に生まれ,親密な距離感の中で,それぞれの学びを進行させる ことができる人数である。人間関係がまだ十分につくられていない時期や学級の実態によっては,簡単な意見や感想をペアで交換することもある。
(4) 子どもを学びに引き込む魅力のある課題は,課題を媒介とした関わり合いを自然に生み,子どもと子どもをつなぐ役割も果たす。「どう思う?」「分かる?」そんなつぶや きから自然と子どもがつながり始める。子どもの実生活につながる魅力的な課題づくりや子どもと学習課題を結び付ける具体物の提示等で課題の設定を工夫し,子どもを 学びへと引き込む。
佐藤(2009)の「トランポリンモデル」
*子どもを学びのステージに乗せることを「トランポリンに乗せる」と表現する。学びに入りにくい子どもの多くは学力が低位で,トランポリンに乗りにくい子どもである。同じトランポリンに乗っていれば学力の高位の子どもの跳躍によって,トランポリンの揺れが起き,低位の子どもも一緒に高い学びへの跳躍を始める。授業前半で「最低限学ばせたいレベル」まで低位の子どもを引き上げ,その上で,後半はさらに高い課題の設定をして高位の子どもの跳躍を大きくさせ,全体の子どもの学習レベルを引き上げる。
3 複数指導の役割・多様性
(1)子どもと子どもをつなぐために【実践例】
① 安心感のある場としてのデザイン
・突っ伏したままで机を動かす気配のない子どもがいると,教師は机をそっとグループの形へと動かす。突っ伏していても学級の一員として子どもを尊重しているという教 師のメッセージは重要。
・教室に居ない子どもの机を隣の席の子どもがグループの形に動かす。突っ伏している子どもをそっと起こして仲間に入れる。そんな関わりが子どもの中にも見える。
・子どもを学びへとつなげる教師の関わりは,教室の中だけではない。廊下には,常に教師がいて,教室に入れない子どもが教室へと足を向けるまで見守ったり,必要に応 じて教室に入って子どもの援助をしたりする。
・遅刻生徒に対しては職員室で手続きを促し、教室(授業)まで送っていく。
② 自由な学びの場としてのデザイン
・突っ伏したままで授業に参加していないと見える子どもが,実は,友達の発言を聴き,発言者の方を見ていることが多い。子どもは教室に居さえすれば学びに入るきっかけ
を自分でつかむ。「全ての子どもの学びを保障する」ために授業規律がある。学びに参加できていない子どもの姿を丸ごと受け止めることで,個の学びを保障している。 学びに入らせるために働きかけたり促したりすることはあっても,教師が押し付ける指導はない。反面,人と距離を置くことが学び合いを妨げることにつながると考え, 机と机はきちんと付ける,壁をつくらないように筆箱や教科書を人と人の間に置かない,といった指導・支援を進める。
(2) 指導能力の育成につながる生徒指導の三つの留意点に重なること
ア 子どもに自己存在感を与えること
聴き合うことを重視した場づくりは,子ども同士が,目を見合わせ,表情を読み合い,言葉を交わし合い,互いの存在を感じ合うことを可能にする。人との関わり合いの中で,自分の存在を確認できる場である。また,一人一人の「そうせざるを得ない」気持ちに寄り添い,子どもの姿を丸ごと受け止めようとする教師の姿は,自分たちが大切にされていて,価値のある存在であることを子どもに伝えている。
イ 共感的な人間関係を育成すること
学び合いでは,親密な距離感の中で,「分からない」と言って支え合うことが許され,一緒に学び合える仲間がいる。そこでは,「分からない」と言える学級の雰囲気をつくるのは,教師ではなく子どもである。共に学ぶ仲間に対する共感的な気持ちや態度は,仲間との関わりの中で,自分自身が実感して繰り返し経験していくことで育っている。
ウ 自己決定の場を与え自己の可能性の開発を援助すること
学び合いのグループは,一人一人の学びを進めつつ,課題という媒介を通して関わり合いが生まれる場である。だからこそ,教師が話題を焦点化したり効率的な学びを進めたりするために行う「発問」よりも,子どもの学び合いを自然に引き起こす「課題の設定」が重要になってくる。そして,グループで課題の解決に向けて取り組む中で,自分の学びを進めたり,つながりを求めたりする自由がある。このことは,学び合いの場が自由な場であり,自己決定のできる場として保障されていることを意味している。
(3)子どもの関わり合いを促進するために
「居場所」となる場がデザインされた子どもの間には,自然と関わり合いが生まれる。 しかし,この関わり合いは,子どもなりの関わり合い方である。そもそも,人と関わ ることを苦手としている子ども同士の関わり合いが更に進むための手だては?
★1 分からない子どもへ寄り添う
多くの学校では,グループ活動している時に学んでいない子どもに対して,グループに入って他の子どもと同じように学ぶことを指示する。しかし,これまでの実践研究 校では,学びに入ろうとしない子どもには,その気持ちを理解することから始める。教師は学びに入ろうとしない子どもは,学習面でのつまずきがあり,困っている子どもと捉えているからである。そこで教師は,授業が分からないという気持ちに寄り添い,受け止めながら,「分からないから,教えて」と他の子どもに聞くことを教える。
安心して「分からないから,教えて」と言えるようにするために,実践校には学校全体で決められた授業の声かけ(ルール例)がある。この声かけによって,子どもは自 分から学びに入ることができるようになっている。例えば,一人で困っている子どもは,「分からないから,教えて」とグループのメンバーに頼るように教師が教える。
「これってどうするん?」「分からないから教えて」を言えるための声かけルール
○ 人の話をよく聴くこと
○ 分からないことは「分からない」と言うこと
○ 困った時は「どうするん」と自分から言うこと
○ 頼られた時はしっかり対応(誠実)に応えること課題が分からずに学びに入れない子どもには,そっと寄り添って課題を具体的に伝え,まず課題を理解させ,それから,課題という媒介を通してグループのメンバーに頼ることを教える。こうした教師の関わりによって,子どもは,困った時には他の子を頼るることを覚え,自分から依存できる力を育もてると考えられる。その結果,学力が低位な子どもでも,グループのメンバーに依存することで,メンバーが援助する関わりが生まれている。そして,教師は本当に個別の援助が必要な子どもに関わることが可能になる。
★2 子どもの状態を丁寧に見取る
教師は授業中,常に子どもの状態を丁寧に見取る。見取るポイントは三つある。一つ目は身体からの見取りである。子どもの状態を目の動きや表情,手の動き,仕草な どから見取っている。二つ目は,つまずきやつぶやきからの見取りである。つまずいている様子はないか,分からないことを声に出してつぶやいていないかを見取っている。三つ目は子どものつながりからの見取りである。子どもは,課題とつながっているか,子ども同士がつながっているか,子どもと教師がつながっているか,さらに,一人一人の子どもと集団がつながっているかを見取っている。こうした見取りは,子どもがグループで活動している時だけでなく,教師が全体の場で発問している時や子どもの発言を聞く時などにおいて常に行われている。そして,見取りの結果から,教師は,次に何をすればよいか判断している。
★3 子どもを信じて待つ
学びに入っていない子どもがいても,丁寧な見取りの結果,学びに入りそうな時には,あえて声をかけずに,子どもが自分から学びに入るのを待つ。一見すると,教師は何もせず,子どもが偶然学びに入ったようにも見えるが,それまでの教師の見取りを追っていくと,そこには,あえて何もせずに待っている教師の姿がある。ある教科の授業中におけるグループでの活動で,学びに入らず,突っ伏していた子どもがいた。教師は見取りを行った結果,直接その子どもに声をかけず,学びに入るのを待つ方を選択した。その後,グループでの学び合いが進む中で,その子どもは身体を起こして自分から学びに入っていった。教師が「待つ」ことは,他にも様々な場面で重要である。グループで活動している時,子ども同士の学び合いがすぐに進まなくても,あえて声をかけずに待つ。子どもが学びに入り,学び合いが起きるまでの時間を保障しているのである。また,学び合いが始まっている時は,学び合いが十分に進むまで待つ。学び合いが始まっているにも関わらず,時間を理由に学び合いを止めるようなことはしない。むしろ,子どもの学び合いの状態に合わせて,柔軟に授業の進め方を調整している。こうした教師の「待つ」姿勢によって,子ども同士の学び合いが起き,関わり合いが主体的に行われる。さらに,全体の場で子どもを指名する時にも,教師は,その子どもが発言するまで待っている。どんなに時間がかかっても,子どもの発言を待ち続ける。ここで教師が望んでいるのは,正答や素晴らしい意見ではない。その子どもが自分から発言することである。教師は,子どもの発言をうなずきながら聞き,受け止める。
★4 学び合いが起きない時は,戻す
教師は授業中,常に子どもの状態や子どもと集団の関わりを見取り,関わりが起きそうなら待つことをしているが,子どもの学びが進まなかったり,学び合いが起きないない時には,一旦グループでの活動を止めて,課題を全体に戻す。そして,課題を丁寧に確認したり,課題の提示の仕方を工夫したりして,改めてグループでの活動を始める。学び合いが起きず進まない状態を見取り,素早く戻すことで,子どもが新たな学びに入れるようにしている。
★5 子ども同士をつなぐ
学びに入っている子どもが,教師に質問した時,教師は答えるのではなく,グループの他の子どもにその質問をつなぐ。教師は子どもAからの質問に対して,正解を伝えることも,ヒントを出すこともせず,同じグループの子どもB,子どもCにつなげる。子どもAの最初の質問を教師がつなげることにより,学び合いが起きた場面である。こうした教師のつなぐという関わりの中で,子ども同士がつながり,子ども同士の関わり合いが生まれてくる。また,教師がつなぐ先を変えて見せることで,子どもは誰とでもつながる機会を与えられるとともに,それぞれの子どもとのつながり方が分かり,次回から誰と,どうつながるかを自己決定するようになる。
さらに,子ども同士をつなぐことは全体の場でも行われている。多くの学校では,一斉授業の中で教師が発問し,子どもから何らかの回答があると,「そうだね」「よく分かったね」と返すことが多い。しかし,実践では,教師が発問し,子どもから発言があった時,その子どもに返さず,他の子どもに「今の発言についてどう思った」「もう一度,話してみて」とつないでいく。このように,教師が子どもの発言を直接他の子どもにつなぐことで,グループで活動していない時も,子ども同士の学び合いを意図的に起こしている。この「教師が,子どもへ発問し,子どもから返ってきた発言を他の子どもへつないでいく」ことを,実践校では「一往復半」と呼んでいる。
ここで,子どもの発言が他の子どもに聞こえなかった場合は,もう一度発言させるが,教師自身は復唱をしない。発言する子どもに「もう少し大きな声で」という指示もしない。学級全体に対して「聴くこと」に集中するように指示する。子どもが互いの発言を集中して聴くことで,子ども同士が自然につながり,他の子どもの発言を尊重するようになる。
★5 教師は「教える」ことに終始せず,常に子どもの「学び」を援助する立場
授業での教師の子どもに対する関わりの大部分は,教師が学習を「指導する」視点でなく,子どもの個の学びや集団による学び合いを「援助する」視点を大切にしたい。丁寧に子どもの状態や子ども同士の関わりの状態を見取り,分からなくても依存すれば学び合いに入れることを教え,学び合いに入るのを待ち,学び合いが起きないようなら「戻す」ことをしている。そして,学び合いがさらに促進するように,「つなぐ」ことを丁寧に行っている。こうした教師の関わりは,子どもの授業における学び合いを促進すると同時に,人間関係の希薄化が問題視される子どもをつなぎ,関わり合いを生む機会を提供している。この関わり合いの中で,子どもは,依存してもよいということ,誰とどうつながるかを自由に決められるということを知りながら人と関わる力を身に付けている。このことは,共感的な人間関係を育むとともに,選択の自由などの自己決定のできる場が保障されていると言える。よって,子どもの関わり合いを促進することは,よりよい人間関係づくりやコミュニケーション能力を育成する生徒指導を行うことであり,子どもの自己実現の基礎となる自己指導能力を育んでいく生徒指導となっている。
★6 授業者(複数指導者)の振り返り〈見取り〉
○分からない子どもが「分からないから,教えて」と周りに援助を求めていたか?○援助の求めに応じてくれる雰囲気がグループ・学級全体にあったのか?その状況 はどうであったのか?
○「訊かれた(援助を求められた)子どきもが,訊いた子どもの分からなさに寄り添って丁寧に説明できていたか?
○教師は,学びから逃避しようとする子どもをグループにつないでいく関わりができていたのか?
○子ども同士の学び合いの時間は十分に確保されていたのか?
○教師のグループの学び合いを見取る立ち位置は適切であったか?
○グループでの学び合いにするタイミングやねらいは適切であったか?
○グループでの学び合いを終えるタイミングはどうであったか?
○それを促進する教師の援助者としての関わりが有効であったか?
引用・参考文献
・平成22・23年度岡山県総合教育センター所員研究(共同研究;生徒指導)「学び合いを促進する教師の関わりについての研究-なぜ,あの子が学びに入れたのかを探る-」
・ 文部科学省(2011)『平成22年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」』
・文部科学省(2010)『生徒指導提要』,p.1
・佐藤曉(2009)『子どもも教師も元気が出る授業づくりの実践ライブ』学研,p.178
・佐藤曉・守田暁美(2009)『子どもをつなぐ学級づくり』東洋館出版
・新学習指導要領・生きる力:文部科学省(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.html)
☆23日目 新年度教育課程の編成の中で家庭訪問の意義をあらためて
家庭生活と学校をつなぐために同和教育において一貫して大切にされてきたものです。1つの方法であるだけでなく、そこに同和教育の精神が集約されています。
子どもを理解するためには保護者を理解することが必要です。家庭での親との関係が子どもの精神状態やものの考え方や感じ方をかたちづくっていきます。教師は教室にいる子どもを相手に教科指導や生活指導をしていますが、家庭での親と子どもの関係を把握したときに、その指導にこもる思いは強くなると思います。子どもと対するとき、教員が保護者から信頼を得ているかどうかは決定的に重要です。保護者はどんなふうに働き、どんな思いや期待をもって子どもを育てているのか。生活が厳しければ厳しいほど、保護者が誇りを失っていればいるほど、心を開いて教員と話すのは難しくなりやすいです。家庭訪問も回数を重ねてることとなります。保護者自身が自らの生き方に問題を感じていたり、乗り越えられない問題をかかえていたりする場合には、その保護者の精神状態は子どもにさまざまな影響を与えます。そのような保護者のかかえている問題を聞き取るという行為は、教師にとって、自らの生き方を省みる機会を提供するものです。「差別の現実から深く学ぶ」というスローガンのもとに、同和教育では家庭訪問による教師と保護者とつながりを教育実践の重要な過程とみなしてきたのです。
子どもの言動が落ち着かなかったり、荒れたりしているとき、その原因や理由を本人に聞いてもわからない場合もあります。そんな時は行くのです。電話ではありません。家庭を訪問し保護者と語り合いましょう。その際、できごとだけを伝えるのではなく、指導の内容やそのときの教員の願いやおもいをしっかり伝えましょう。問題行動を起こしてしまった子どもの保護者の多くは、子どもの教育について深く悩んだり不安をもったりしている場合があります。そんな保護者に「家庭でよく話をしてください」という一方的な気持ちで連絡しても保護者との距離は縮まりません。だから問題を伝えるだけでなく、良いところやがんばっているところも伝えましょう。「一緒に手を取り合って子どもを育てていきましょう」というメッセージを保護者に伝え続けていくことで保護者との関係は変化していきます。つい子どもにあたってしまうしかない親のしんどさ、悩みを誰にも言えず一人で悩む親の姿など、だんだんと語っていく中で子どもや保護者のくらしや願いが見えてきます。「今の親の感覚はどうなっとるん」「あたりまえの親ならこうじゃろ」と保護者と距離を置くのではなく、しんどさをありのままに語り合える関係をつくりましょう。「この先生は子どものことを一緒に考えてくれる」ということが伝われば、少しずつ保護者とのつながり、子どもとのつながりが深まっていきます。
☆22日目 コの字の席学習スタイル
先日の校内公開授業で、2年生の深い学びを創出したひとつである、コの字型の席について、「学びの共同体」に関する佐藤学さんの著書からいくつか挙げてみます。


○授業改革って
(1)教職員自身が非力であることを自覚すること。自分の非力を見せ合う中で謙虚に授業 改革に取り組もう。
(2)研修は他人のためにおこなうのではなく、教職員である自分自身のためにおこなう。 ひいては生徒たちのためになるという考えに立つこと。
(3)いわゆる「うまい授業」をしようと思わないこと。たとえ「ぶざまな授業」であって も生徒たちと誠実に向き合う授業を志向しよう。指導案どおりに進行する授業がよい のではなく、生徒が自分で考え、おおいに戸惑いながら進行する授業をめざそう。
○授業改革のための研究授業の改革
(1)一般的に従来の研究授業(授業の研修)の反省点として、①形式性を重視することで 研究授業としておこなうことが、一人ひとりの日常の授業にいきてこないこと。②授業 を見る視点が、所定の「仮説」に限定され、それ以外の授業の見方が制約されてしまう 点があげられる事がある。そこで本校の研究授業を以下の方法・方向性を検討しながら 取り組んでいきたい。
①授業をみて気づいたこと・考えたこと・学んだことを対等に、自由に発言する。一般論 や理論の紹介ではなく事実に即してコメントを出しあう。
②授業のコメントにおいて正答は無い。正否、優劣を評定することが目的ではない。授業 という複合的な事実を見る目を広げ、深めていくことが目的であり、自分と異なった意 見に触れ、その根拠を確かめつつ、自分の理解を深め、授業という複雑で奥行きのある 実体への理解へ近づいていく終わりなき課程であることを自覚する。
③教材の是非や教え方の是非は100とおりの正解がある。しかしその授業の進展における教職員の姿勢・願いや、生徒の発するメッセージの受け止め方はおそらく1とおりし かない。生徒一人ひとりを注意深く観察しながら,具体的な作業を提起して学びの展開 を触発し,多様な発見や意見の交流を組織し,学びの活動が豊かで深い経験になるよう に様々な働きかけを行うのである。「交わり」「つながり」を生み出す活動を,教職員 の仕事の中軸に構成する。
(2)研究授業の推進に向けて
①授業の上手下手は問わない。授業の巧拙は「生まれつき」であることを自覚し、「自分らしいいい授業」をめざす。
②授業公開にあたっては、事前に形式的な内容に多くのエネルギーを注がない。事後の研究会(校内研修)を充実させる。「やって」「おわった」という充実感だけを求めるも のになりがちだった研究授業。事前に時間をかける必要性はない。事後の検討にたっぷり時間をかける。授業の良し悪しを議論するのではなく、授業の「難しさ」と「おもし ろさ」を共有することこそが授業の研修の目的である。いつも生徒の学びの具体的な姿を話し合いの中で浮き上がらせることを研修で求めていく。
③教職員の発問や教材の解釈についてよりも生徒の学 びの具体的な様相と教職員のそれへの対応を中心に話し合う。
④多様な教育の考え方と多様な経験を備えた教職員たちが、同じ授業の事例と観察と批評を通して、教職員としての証を探索しあい、実践的なディスコース(実践を創造し反省 する言語)とそのディスコースで結ばれた実践者の共同体を育てあう営みが授業の研修である。
⑦研究資料による報告でも口頭による報告でも,固有名の生徒が登場して,自分の言葉で 表現するように心がけること。その研究を通して教職員一人ひとりが何を感じ何に挑戦 してきたのか,教室の生徒たちはどう学び,何につまずき,どう克服してきたのか等, リアルに語られる必要がある。
○生徒の自立性と自律性を促す授業のあり方を進めるために
(1)生徒(観)について
・生徒個々人がそれぞれ自主的に学ぶ授業に移行させない。
・一時間単位の検討ではなく、長い時間軸の中で一人ひとりの学びと成長を見据えなが ら日常の授業を検討していく。
・子ども一人ひとりの自然な言葉と身体による授業への参加を基盤として、具体的な事実を対象とする多様なイメージの交流を実現させる。
・「一人ひとりの生徒の思考そのものを参照にする意志決定の授業」をめざす。教職員は授業の絶え間ないデザインとその修正(授業の展開の選択や方針の修正)をおこなう。(授業デザインの作成)
・子ども一人ひとりの自然な言葉と身体による授業への参加を基盤として、具体的な事実を対象とする多様なイメージの交流を実現させる。
・個と個が摺り合わせられる授業→ディスコースコミニティ(議論しあう共同体)としての学級づくりを進めていく。また、発言しなくても一生懸命考えている生徒がいる 授業や、たどたどしい言葉が他の生徒の心に深く届き確かな説得力を持つような風土がある学級づくりを進めていく。
・級友の言葉をひとつひとつ味わって聴ける「学び上手」の生徒を育成する。
・どんな誤答の中にも、その答えを導き出した「理の世界」がある。必要なことは答えの当否を裁断することではなく、「理の世界」を洞察し、その省察を教室で共有し摺 り合わせて、真実へと至る筋道を共同で探索する。
(2)私たち教職員(観)について
・生徒だけが一方的に発達し成長することはありえない。学び成長し続ける者のみが教 えることを可能にする。《よく学ぶ者だけが教壇という舞台に立つ資格を持つ》
・教室に聴きあう関わりを築くことは、教職員の豊かな経験を基礎とする見識と粘り強 い取り組みを必要とする。
・ハンドサイン・起立礼・付け足し等、児童生徒を一方的な操作対象にしている授業, 教室の話し合いと切り離して人為的なゲームをしている授業,「虚偽」の主体性を演 じさせられている教室が見られる場合がある。生徒とじっくり「良い時間を過ごそう」 という意識で教室に立つことが,解決の確かな糸口を準備してくれる。発言を「引き 出し」たり「組織」したりする前に,生徒一人ひとりの言葉を「聞くこと」や「味わ うこと」へと教職員の意識をシフトさせる。求めるべきは「よく発言する教室」では なく「よく聴きあう教室」が発言を通して多様な思考や感情を交流しあえる教室を準 備する。この関係は逆ではない。
・教職員が一人ひとりの生徒の言葉に耳をすまして敏感に対応し,一人ひとりの生徒に ていねいに届く言葉を発すること(生徒一人ひとりの胸に届く言葉をていねいに選び ながら語りかける教職員の話し方)ができるようになって,はじめて生徒たちのなか に聴きあう関わりが生まれ,しっとりとことばを深く吟味しながら交換しあう関わり が教室に築かれることになる。
(3)教材(観)について
・「主体性」が理念として考えられる授業においては「自学自習」を理想化し,自己実 現や自己決定を理想化する傾向を生みだしている。しかし自学学習や自己実現や自己決定は独学の理想ではあっても,教材や仲間や教職員が介在する授業場面において理想化してはならない。
・生徒と集団(固有名としての生徒の存在)の実態や教育課題に即して、「生徒の状態」 「生徒にとっての意味」を考えて、特定の教材を選ぶ。何のためになぜこの教材を選ぶのかとその教材の意味を考えつつ教材を選ぶ。そしてその指導・支援にあたっては、その学習が生徒自身の課題となり、生徒が学習の主体となるために、どのような方法 で指導・支援するかが教職員の重要な課題となる。
参考文献 『授業研究入門』/『教育改革をデザインする』/『教育方法学』/『学力を問い直す』(岩波書店) 『授業を変える学校が変わる』/『学校を創る』(小学館)
『学び その死と再生』(太郎次郎社)から久次がまとめたもの。
☆21日目 生活ノートとICT・デジタル化 考察その2
「綴ることは認識すること」
―ひとむかし前までは、作文といえば、いわゆる生活文…くらしを題材とし、人のかかわりを綴ったもの…が定番でしたが、現在の教科書では、(小学校)2~3年生で生活文は「卒業」となり、あとは、ここでも表現活動の技術を習得する単元が中心となっています。手紙文・礼状・発表原稿・レポートなど、多様にとりあげ、最後はやはりプレゼンテーションをめざしていたるのでしょうか。
作文は、表現や伝達の手段であることは間違いなく、伝えるための技術をみにつけることは、将来社会に出てから役立ちます。しかし綴ることにはもうひとつ、だいじな役割があります。僕たちはこれを「認識」とよんでいます。残念ながら、最初から作文が好きなこどもは、あまりいません。難しいからです。自分の前にある人・もの・できごとにぴったりな単語をみつけ、次には単語どうしを結びつけ文にし、さらに組み合わせていくという、語彙論、文法論を総動員しなければならない作業です。時には、できごとをよいととらえるか、悪いととらえるかなどという、価値判断もしなければなりません。自分の視点で書いているので、うそはかけません。鉛筆を進めるのは、大変な仕事です。就学前の子どもたちは、「話しことば」の中で生活しています。相手が目の前にいて、視線やしぐさ・表情なども伝達の手助けとなるため、多少語彙や文法がまちがっていても、おおよそ通じてしまいます。しかし「書きことば」ではそうはいきません。目の前に相手はおらず、頼りになるのは文だけなのです。だからこそ、必然的に対象をしっかりみつめ、掴もうとし、価値判断をすることになります。家族・友達・社会・自然などを題材として綴るなかで、子どもたちはしだいに「認識」を深めていきます。こういった「認識」を獲得する学習を基盤とし(あるいは並行して)、発表原稿やレポートを書くのなら実生活に根差した、重みのあるものとなるはずです。現行の教科書が、中・高学年での生活文指導を放棄しているのは残念です。飛躍的に認識の幅が広がる時期なのですから。もうひとつ、書くことの基本は、みのまわりのことを、あったことを、あったように、自分のことばで、です。時間軸に沿って、「○○でした」「○○しました」というふうに、過去形で書いていきます(展開的過去形表現といいます)。これがある程度できるようになってはじめて、前述のさまざまな機能を持った文章を書けるようになるはずです。くらしを書きなれてないと、いくら技術を教えても、いきなり手紙やレポートは書けないのは、昔から言われてきたことです。(『教育 おかやま(2014年3月発行)』より 日本語教育を考える P2~P3 岡山県教職員組合教育運動推進センター:学力保障「日本語」研究部会
☆20日目 教室掲示物は片付ける?
毎年3月、学級の掲示物はもう処分してしまいますか?最近では、「学級通信」「学年通信」「保健だより」「クラス目標」「班メンバー表」「清掃分担表」「朝夕のめにゅー表」などの多くは先生たちがコンピュータで作成しているようですが。
残しておいて、新学期にも必要なモノ(例えば学級通信を掲示していた枠だけでなく、1年間を通して子どもがつくったモノを掲示する学級文化を構築したいですね)は新しいクラスの生徒が制作する(生徒一人ひとりひとつの掲示物を作る!(用意できます))のはどうでしょう。このときに前年度の掲示物を参考資料として、班に道具と一緒に渡します。必ず「これより(前年度の掲示物より)よいやつをつくるぞ!」とがんばります。作ったことがない生徒や苦手な男の子も、例示があると班のなかまと一緒につくることができます。子どもが班の仲間と楽しく語りながらつくる時間は貴重です。
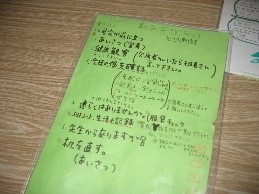
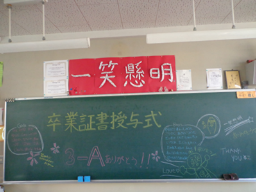
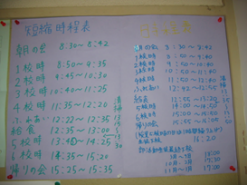
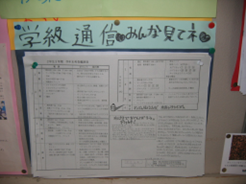
☆19 カウントダウンカレンダー」で、
クラスのつながりを確かめられる仕掛けをたくさん入れたいですね。
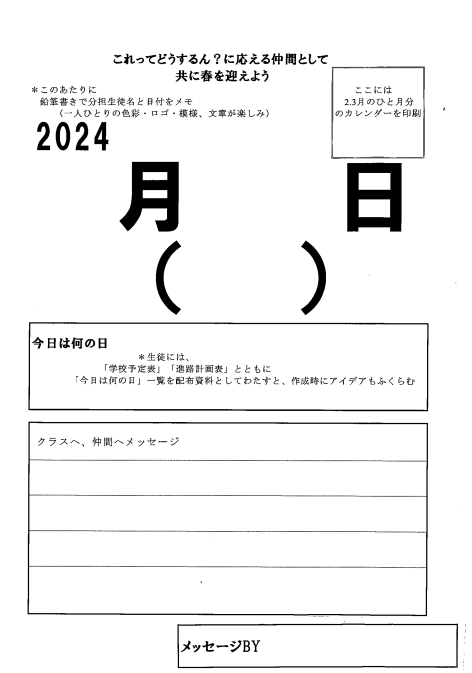
☆18 新入生歓迎新聞づくり(新3年生全員で!)
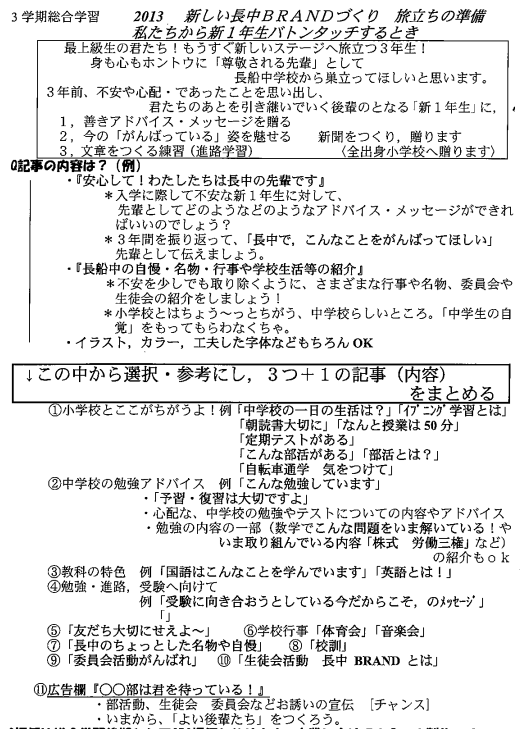
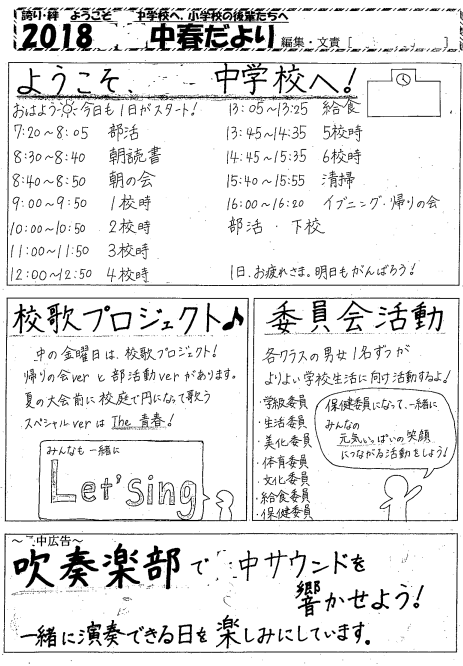
☆17 個人答辞をもとに、卒業答辞に。
代表生徒だけが考える「答辞」から、一人ひとりが三年間を振り返って個人答辞を綴り、それを集約したかたちで卒業生答辞を作成する取組をこれまでおこなってきました。子どもたちが取り組むワークシート文書を少し紹介します。
2024旅立ちの時にあたってー個人答辞ー 道をひらいていく
~私・わたしたちの○○中~
この時期、3年生のみんなは中学校での生活をふと振り返ってみたりすることもあるのではないでしょうか。一人ひとりが、いろんなことを経験し学んできたと思います。良かったことも、そして悔やんでいることがあったとしても、その一つ一つは、あなた達がこれから生きていくになっていくことだろうと思います。大切にしていかねばなりません。
もうすぐ旅立ちの時がやってきます。出発するためには、今の一人ひとりの姿勢が問われます。時の流れにまかせて、卒業式を迎え、そして進路先へ行く…そんな、ただなんとなくといった生き方をしないでください。自分の道を切り拓いていくためには、「いまの自分」がやっぱり大切です。
なかまたちと共に過ごす時間をどれだけ大切にできるか?
どう中学校生活を締めくくるかは、4月からの生活の土台となります。
そしてもうひとつは
これから自分がどんなことを大切にしていくのか?という生き方を決意することが大切になります。
この中学校で経験したこと、学んだこと、これからの生き方や夢を「思いをこめて」個人答辞としてまとめましょう。
| 個人答辞の柱 |
②三年間を通して、なかまから学んだこと (中学校入学時の自分と現在の自分を比 べて、心の成長や今の自分のつくったできごと・学級活動・生徒会・総合学習(職場体験、ヒロシマ・オキナワ研修、渋染一揆、閑谷、協同学習、ガンバリ合う、支え合うな かま、ハンセン病問題学 習、進路学習など)
③進路についての課題と決意、様々な進路
(進路や自分の夢・抱えている課題にどう立ち向かい、どうがんばっていくのか)
④自分たちの反省、課題及び決意(後輩たちや在校生に伝えたいこと)
⑤お礼のことば(今まで自分たちを支えてくれた人々に伝えたいこと)
⑥締めくくり
*○○期三年生として
・各クラスで書かれた、全員の個人答辞を集約する。
・集約したものをもとにして、3学年の答辞の全体像を考える。
・答辞代表を3年生全員で支える。3年生全員でよい卒業式を創る。
・卒業式を成功させるために、一人ひとりが大切にする意識を高め、声をかけ合い、あらためて団結する。
☆16 自立と依存は相反する?
「依存」と「自立」を対立的に考えるのは誤りである。「依存」できる子どもは「自立」でき、「自立」できる子どもは「依存」できるのである。『授業を変える学校が変わる』/『学校を創る』(小学館)等で佐藤学さんが書かれていた内容を初めて読んだ時には衝撃を受けました。それからずっと「自立」の中身について考えていますが、先日、車いすユーザーである東京大学の熊谷晋一郎さんは「自立とは依存先を増やすこと」と言われた文章に出会うことができました。
自立とは「依存先を増やすこと」
親は、「社会というのは障害者に厳しい。障害を持ったままの状態で一人で社会に出したら、息子はのたれ死んでしまうのではないか」と心配していたようです。でも、実際に一人暮らしを始めて私が感じたのは、「社会は案外やさしい場所なんだ」ということでした。
大学の近くに下宿していたのですが、部屋に戻ると必ず友達が2〜3人いて、「お帰り」と迎えてくれました。いつの間にか合い鍵が8個も作られていて、みんなが代わる代わるやってきては好き勝手にご飯を作って食べていく。その代わり、私をお風呂に入れてくれたり、失禁した時は介助してくれたりしました。
また、外出時に見ず知らずの人にトイレの介助を頼んだこともあります。たくさんの人が助けてくれました。こうした経験から次第に人や社会に関心を持つようになり、入学当初目指していた数学者ではなく、医学の道を志すことを決めたのです。
それまで私が依存できる先は親だけでした。だから、親を失えば生きていけないのでは、という不安がぬぐえなかった。でも、一人暮らしをしたことで、友達や社会など、依存できる先を増やしていけば、自分は生きていける、自立できるんだということがわかったのです。
「自立」とは、依存しなくなることだと思われがちです。でも、そうではありません。「依存先を増やしていくこと」こそが、自立なのです。これは障害の有無にかかわらず、すべての人に通じる普遍的なことだと、私は思います。(全国大学生活共同組合連合会インタビューより)
☆15 面接で不適切な質問? どう答えるの?
今日は、特別入試の結果発表でした。
生徒らは、教科の試験とともに、多くの子が初めて「面接」を体験したと思います。そして中学校では、「どんな質問が出たか」を報告書にまとめる取組をしています。それを受験校ごとにまとめ、「過去出題例」として蓄積し、次の年の三年生らが、それを参考に面接練習を行います。ここ数年は、業者の『面接ガイド』を活用しているようですが、やはり、自分たちが受けた質問をまとめることはとても大切だと思います。それは、後輩たちに「こんな質問内容がでたから、参考にしてガンバレ」という目的だけではありません。
就職試験は、応募者の適性・能力に基づいた採用基準とすることになっています。それは、応募者のもつ適性・能力が求人職種の職務を遂行できるかどうかを基準として採用選考を行わなければなりません。就職の機会均等とは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることですが、このためには、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。だから、面接での「これは、就職差別につながるおそれのある不適切な質問か」見定める力を生徒自身が持てる指導を進めていかねばならないと思います。合わせて、私たち教職員もそのようなことがないように、「面接での質問事項」をチェックし、子どもたちの進路保障を確かなものにしないといけないと思います。
家族、住んでいるところ、資産などに関する質問・・・応募者の適性・能力を中心とした選考を行うのではなく、本人の責任でないことがらで判断しようとしていることです。このことは、前近代的な身分制により形成された部落差別により、教育や就職の機会均等の権利を侵害されてきた人たちを排除することにもつながるものです。住宅環境や家庭環境の状況を聞くことは、地域の生活水準等を判断することになり、主観的判断に属する事柄です。これらは本人の努力によって解決できない問題を採否決定の基準とすることになり、そこに予断と偏見が働くおそれがあります。
思想・信条、宗教、尊敬する人物などに関する質問・・・思想・信条や宗教、支持する政党、人生観などは、信教の自由、思想・信条の自由など、憲法で保障されている個人の自由権に属することがらです。それを採用選考に持ち込むことは、基本的人権を侵すことであり、厳に慎むべきことです。思想・信条、宗教などについて直接質問する場合のほか、形を変えた質問を行い、これらのことを把握しようとする企業がありますが、絶対に行うべきではありません。
性別・男女雇用機会均等法に関する質問・・・性別を理由(または前提、背景)とした質問は、男女雇用機会均等法の趣旨に違反する採用選考につながります。また、男女共に同じ質問をしていても、一方の性については採用、不採用の判断に影響がなく、他方の性についてはその返答が採用、不採用の判断要素となるような場合は、採用において性別を理由として差別していることになります。
☆14 ひとに出会う授業のありようや、
学習のまとめについて、「はっ!」とした本。
知識を学んだり、当事者の語りを聴くことについて。『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育 誰のことばにも同じだけ価値がある』(野口晃菜 喜多一馬編著・学事出版)の星野俊樹(P115)には・・・《知識を学んでも当事者に心を寄せる経験がなければ(情動的共感なしの認知的共感)、子どもの反応は、政治的正しさに囚われたままで終わり、自分の発言に用心深くはなりますが、行動は型にはまった人目を気にしたものになりがちで、洞察や分析はできても当事者に冷たいものとなってしまうでしょう。逆に、知識を十分に学ばず、当事者のライフヒストリーを聞いて「感銘を受ける」だけでは、(認知的共感のない情動的共感)、当事者に対する、上から目線の「哀れみ」や「善意」が子どもたちに広がってしまうおそれがあります。そのため、「異質な他者に共感しよう」と子どもたちの心情にただ訴えかけるのではなく、情動的共感と認知的共感の両方を子どもたちが得られる機会を保障する必要があります。多様性や社会的公正を効果的に教えるためには、感性と知性の両方に働きかけることが重要です。》(*ダイアン・J.グッドマン『真のダイバーシティを目指して 特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育』上智大学出版、2017年等を参照のこと)とありました。
「ひとに出会う授業」をもっともっと丁寧につくっていきたいと思います。
☆13特別支援教育と仲間づくり
『関係支援を核とした学級づくり 「特別でない」特別支援教育をめざして』拝野佳生さんは、小学校と特別支援学校の教員経験をもとに、「関係支援」をキーワードとする学級集団づくりを提案し、「学び合い支え合う仲間づくり」という日々の教育活動から生み出した方法論を著者の実践を通じて具体的に提起されています。
2007年4月、学校教育法の一部改正で「特別支援教育」が正式に実施されることとなりました。「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。私も、前任校で(2012(平成24年))特別支援コーディネーターとなり、校内の支援体制の確立に取り組んだ中で、自立や社会参画するという視点に立った支援には十五年間の育ちを見据えて進めることの大切さを認識しました。それと同時に特性のあるその子への「個別支援の手立て」について語られることが多いけど、その子が所属する「クラスや学年集団のありようや関係性の構築」についてしっかりと実践を進めることが重要だと議論した覚えがあります。現在も同様で、当事者(特別支援教育のニーズの必要な生徒)を包括する「認め合う集団づくり」に果敢にアプローチしていかねばならないと思います。前述の拝野氏の著書をもとにしっかりと語り合いたいですね。
☆12 生活ノートと「効率化、働き方改革」
「自主学習ノート」を初めて取り組んだ時期には、生活ノートと併せて2冊の点検に多くの時間が必要となりました。思い切って、生活ノートの提出をやめました。一日中、自分で持っていて、授業中には、教科担当からの宿題や提出物などの連絡事項をいつでもメモする、帰りの会には、教科係が書いた明日の教科や準備物を書く「生活ノート」としました。(大人が持っている手帳と一緒です。現在はそのようなマネジメント手帳がたくさんつくられていますが、生活ノートを朝の会で提出し、帰りの会までに担任がコメントして返すシステムを廃止することに、職場ではとても抵抗がありましたが。)「自主学習ノートに思ったことや生活のふりかえりなどなど綴っていいよ(自主的に)」とし、担任団は、「文章があってもなくても、しっかりと自主学習ノートにコメントする」ことを共通理解し、三年間取り組みました。今年、二十歳の集いで久しぶりに会った彼らはステキな大人になっていたなあ。
☆11 生活ノートのデジタル化
担任生活を振り返ってみて、これまでの「生活記録ノート」の主なねらいは,「生徒指導の視点による生徒理解」の要素が大きかったように思う。記入の様子や内容から,普段の生徒の変化を見逃さず、対話を通した学級担任との信頼関係構築ための大切な手立てのひとつだった。また、同和教育実践が大事にしてきた生活綴り方教育の視点での記入指導、支援をおこない、学級通信に掲載し、クラスへの提案や学級会での話し合いにもつなげる実践を進めてきた。生活綴り方教育とは、社会の現実のなかで厳しい環境に置かれた子どもたちが、実生活を綴ることにより、自らの生活を観察し、自分たちの生活の事実を認識し、 それに働きかけて、たくましく生きていくように育てるという立場に立った教育実践の方法であ る。
何度も消したり書いたりした跡が残る生活ノート、消しゴムの消しカスがはさがっている生活ノート、採点ではないからと、青ペンでコメントを長年書いていた生活ノート・・・は、やはり生徒の「くらし」を知り、教育につなげる大切なアイテムであった。何かと「振り返り」が重要視される現在、「生活やものごとを見つめ、つづれる力」を育みたいと思う。また、私たち自身も表現の中の「子どもの真実を読む」力を鍛えなくちゃいけませんけど。
『さみしい夜にはペンを持て』(古賀史健 氏:ポプラ社 2023)を読み終えて、「書くことは考えること、考えることは生きること」という、かつて作文指導で教えてもらったコトバを思い出しました。この本をもとに「書くこと」について授業化をしてみたいと考えています。
☆10 生徒の作品展示・学級通信掲載の
生徒名は〈明らかにする?〉〈匿名にする?〉(2/8)
インターネット場の匿名のコトバを使って、誹謗中傷、ヘイトスピーチなど人を差別する状況があります。そんな中で、学校ではやっぱり、自分の書いた文章、発したコトバ、つくった作品には、誇りと責任をもってほしいと思います。「えーはずかしい」「みんなにみせるのいやだ」を越える指導、支援を行い、「お互いに相手の考えや指向などをわかり合える「仲間づくり」を進めていきたいものです。(仲間の文章や作品を受けとめる集団意識の涵養)さて、そのためには、発表した生徒の発言を教員自身が受けとめることは大前提ですが、まずは、教師自身もせいいっぱい「自分のことを語る」ことが大切ですね。ありきたりのことではなく、「こんなことも話してくれるんだ。自分も話していいんだ」と思える内容を吟味し「子どもたちのモデル」に先生自身がなることです。」
☆9 聲をきく(2/7)
2015(平成27年)年に、当時勤務していた中学校区の保護者の方々の願いと市・県の積極的な取組の中で、勤務校に新しく自閉症・情緒障害特別支援学級が開級された。担任として私が、大切にせねばならないと思っていたことは、〈子どもと保護者の〈こえ〉をしっかり聴くこと〉だった。さらに、開級にあたっては、学習環境の整備(教室の構造化等)と、必要かつ具体的な合理的配慮の提供についても、保護者と市と学校がしっかり話し合いながら、綿密に準備を進めた。その流れの中で、入級する子どもの保護者の方々が、自主的定期的に開催する「親の会」に自分自身も参加した。
親の会では、お茶を飲みながら、一人ひとりの子どもの日々の成長を喜び合ったり、「子育て」や「社会的自立」についての悩みや心配・不安なことを出し合ったりしたが、いつも大きなテーマになっていたのは、中学校卒業後の「進路」であった。中学校では、子どもらは、一年時から計画的に進路・キャリア学習を進め、保護者もオープンスク-ルや高校説明会で進路情報を手にしていくが、特別支援学級在籍の子どもたちの保護者が「自分の子どもの発達特性」等に合った進路情報を収集し、進路支援の見通しをもつ機会はほとんどなかった。そして私自身も特別支援教育のニーズのある子どものための進路についての情報の少なさに、課題を抱えていた。
そこで、親の会で話し合い、まずは勤務している中学校で高校を招き、「進路情報を自分たちで手に入れて、勉強をしていこう」と取組を始めることとした。今年度は、学区の小学校とも連携して親の会を開催している。
第3回ひなせ親の会(情報交流会)〈ご案内〉
◎特別支援教育について、保護者の方々と一緒に考えていく会です。◎これからの進級・進路について新しい情報を交換できる会です。◎お子さんのことについて参加者と一緒に話をする会です。(カウンセリングや講座ではありません)
日生中学校区の小・中学校が連携し、教育相談・情報交流の一環として、「親の会」を行っています。おもに上記の内容について、スクールソーシャルワーカー(SSW)の小寺さんからアドバイスもいただきながら、参加者がゆったりと「子どもたちのこれから」について、語り合う会です。(秘密厳守です。安心してご参加ください。)
お茶を飲みながら、日頃思っていることや気になること、学校生活の中での素朴な質問なども合わせて、参加者の交流の場として、大切な時間にできたらと思います。
ご案内が大変おそくなり、申し訳ありません。お気軽に、申し込み・ご参加ください。
第3回ひなせ「親の会」のご案内
1 日 時 2024年2月14日(水)17:45~19:00
2 場 所 日生中学校 E組教室(北棟1階)
3 内 容 「進級・進学どんとこい!? こころがまえと手立て」
「三年間、六年間を見通した成長をともに」をもとに意見交流
4 参加者 小・中学校の保護者
日生西・日生東小学校 日生中学校の先生
SC SSW 備前市地域おこし協力隊さんなど
主催:日生中学校区連携協議会(特別支援教育部会)
5 連 絡 会場準備の都合がありますので、参加の希望をお早めに
(2/9までに)各学校の担当までお知らせください。
◎なお、スクールカウンセラーの教育相談やSSWへのご相談
も各学校に問い合わせください。
6 予 定 新年度第1回:4月8日(火)17:00~18:30(予定)
☆8 班活動の可能性(2/6)
『ザ・席替え(家本芳郎著)』を読んでいると、「替え替えではなくて、班替えという視点で考えんといけんよ」とアドバイスを受けた。支え合う・がんばり合う仲間(集団)づくりが課題であった学校にいた頃、その先輩先生は、「出来るのなら、子ども同士が関わる環境や状況をなるべく多く創出できるかを考えたいと思う。その取組・活動は、「個人でできること」、「個人でせねばならないことなのか」、「班の仲間とせねばならないことなのか」、「班の仲間とでできることなのか」とも言う。
さて、個人でもできるけど、班活動でできること(ゆだねること)は例えば? □健康観察 □宿題・生活点検 □提出物あつめ(列の後ろから集めるのではなく) □班ノート □班に1枚(大きくコピー)だけ資料を配る □班紹介ポスター □新教科書への名前書き作業(始業式・入学式学活) □自転車整備点検 □長期休業明けの思い出語り合い □新入生歓迎新聞づくり □学級通信ロゴ作成・・・・関わる=わかり合うチャンスをどんだけ創れるかなあ。 そして、給食時間(コロナ禍からの、本当の脱却を!)あの、班の仲間と、たわいのない話をしながら、様々なことを知り合いなんと大事な時間だったか。(もしかししたら、コロナ禍で、一番、非認知能力等の育成を阻んでいたかもしれない時間)本校の1年団は復活させました。それも、子どもたちの「班のみんなと一緒に食べたいという要望」をカタチにしました。なんと楽しい豊かな時間だったか(*^o^*)。
☆7 受験期のなかまづくり(2/5)
クラスのみんなで、「それぞれの進路実現に向けてがんばっていこう」と、あらためて仲間意識を強めるクラス(学年)イベントはどうでしょう。内定合格を手に入れた生徒、これから第1志望校の受験にチャレンジする生徒、「受験でクラスがバラバラにならないよう」に楽しく、深く、豊かな、がんばり合える学級活動を創造したいですね。
1イベント名:「ほっと一息、お茶を飲んで、みんなで受験を乗り越えよう」学級活動
2事前準備:(内定合格の生徒がひとくちクッキーを焼いてくるだんどり) 実行委員による、飲み物アンケート
3用意するもの:飲み物を入れるカップ 飲みたい(お気に入りの)粉末のもと(お茶やココア、ミルクティーなど)一人分 お湯を沸かすポット
4当日:生活班隊形・円形
5式次第:①学級委員開会あいさつ (②クッキーありがとう披露) ③飲み物にお湯を入れる ④がんばろう乾杯 ⑤歓談・お代わり ⑥ひとりずつ、思いや願いを語る・聴き合う。⑦お招きしたゲストからのエール(先生等)(⑧歌やパフォーマンス))⑨閉会・かたづけ
☆6 今日は合格発表。(2/2)
合格発表とはいいますが、全員が合格を手にするわけではありません。合否発表の日です。
もう、あまり使われないコトバですが、それは「すべりどめ(受験校)」。若い頃、気軽に使ったワタシに、先輩先生がピシリと言われました。「ある生徒にとっては「すべりどめ」かもしれないが、ある子にとっては「第一志望校」なんよ。高校間格差を助長するような言い方(意識)はいけんな。本人が第1志望校が不合格で「すべりどめ」に行くこともあるよな。「すべりどめ」の高校で青春を送るという意識を子どもに持たせてええんか?あるいは、友達が、「すべりどめ」の高校に第1志望で入学する場合もある。お互いが違う学校を受験するんだけど、受験を乗り越える、ともにがんばりあう「クラス・学園集団」をつくるなら、とことんコトバは大事にせい。第一志望校、第二志望校と言わんとね。」
☆5 学校から地域・社会へ発信(2/1)
○三年生は、計画的に取り組んだハンセン病問題学習での「学び」を、邑久光明園さんや次世代ネットさんに協力いただき、「啓発パネル展」を開催しています。学習内容をプレゼンしたり、提言したりする取組が各校で行われていると思いますが、に発信・協働する「立ち位置」に生徒自身が立つこと(人権を大切にすることを他者に伝えようとする立ち位置)は「自分ごと」の意識が高まると考えられます。自身の展示会を観覧した生徒の振り返り(一部)。
○書いた人の気持ちがどの説明文にもしっかりこもっていたので、ハンセン病の差別をなくしたいという心がとても伝わってきた。たくさんのパネルを見て、ハンセン病療養所へ行ったことがない人でも分かりやすいと思った。
○パネルでよりハンセン病について知れたと思うので良かったです。あまり知識がなかった邑久光明園についての展示もあり、学べました。
○自分以外のパネルは初めて見たけど、詳しいところまで書いていて知らない知識がたくさんあった。中学生がこのような活動をして、地域の人にも知ってもらうというのは大切なことなんだなと思った。差別・偏見をなくす第一歩として、まずは正しい知識を得ることが重要である。
○みんな調べたことと、調べたことに対して考えたことを詳しく書いていた。この展示によって、正しいハンセン病の知識を持つ人が増えるといいなと思った。
○ハンセン病についての漫画も見て、知らなかったことも知れた。伝えていこうと思った。
○パネルの内容によって数字が割り振られていたり、内容への理解を深めることができるような写真も一緒に展示されたりしていたため、とても見やすかった。実際に行われてきたことをただ単に述べるのではなく、そこから考えたことも書かれていたため、読むことが楽しくなった。
○みんなテーマごとに大切なことをまとめられていました。書いて、見て、終わり、ではなくて、次の世代に伝えていくことが大切だと思うので、どういった形でも大切なことを伝えていきたいと思う。

☆4 先生は連絡係ではなああい(1/31)
少し前の、ある人権教育の研修会で、担任の先生が「朝・夕の会で私は連絡事項ばかり〈しゃべって〉いて、本当に大切なことを〈話して〉なかった。」という実践報告を聴いたことがあります。生徒へ伝えなくてはならないたくさんの事は、本当に、「担任」が言うことなのか?あらためて考えることができました。学級委員、係、日直、給食時間、ホワイトボードなど、子どもがこどもたちへ一生懸命に伝える場面や場所を、知恵をしぼってつくりたいなあと思います。係の子から仲間たちへ伝える「連絡票」にはしっかりと集中して耳を傾ける生徒が多いです。
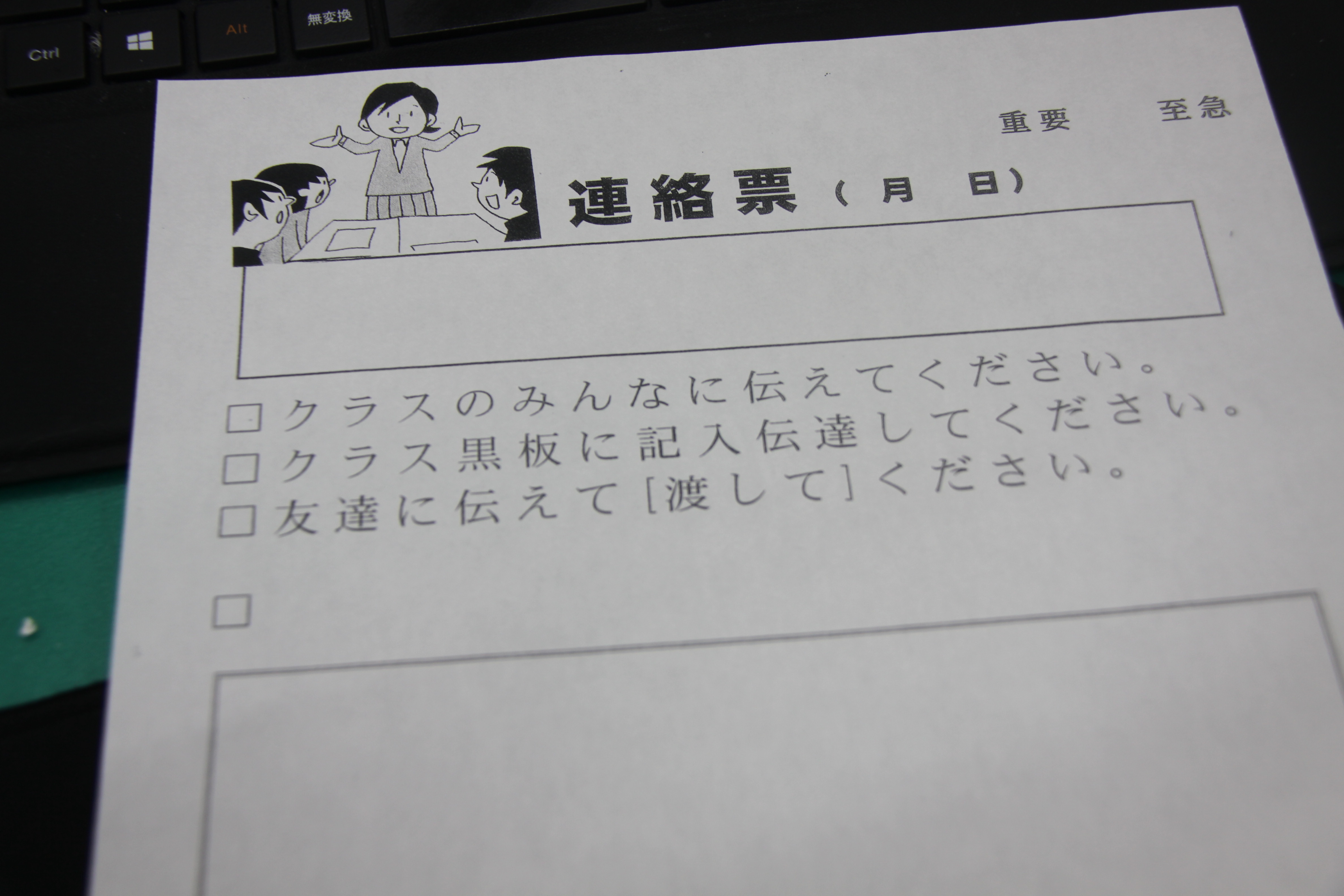
☆3 学級・クラス通信でのキャッチーな見出しは?
「私立一期入試」を終えて、どんな記事の見出しにするか?(1/30)
○〈私立一期入試 お疲れ様〉〈一期入試終える〉と無難な見出しになりそうなワタシですが、「誰」を意識して、「誰」のために、「何」のために(支えあうクラスづくり)の中での「こだわり」を大事にする」と考えると〈私立一期、みんなで乗り越えたぜ!〉〈共に乗り切った!またこれからも一歩一歩〉と、いうのもよいかも。〈がんばれ〉ではなく〈一緒にがんばろう!〉とすると、自分の立ち位置が変わりますね。
☆2 「弱さやニガテ」もわかり合えるクラスってステキ(1/29)
○得意なことや、趣味・特技を知り合う取組は多いが、自分の特性や、苦手なことを語り、共にわかり合い、支え合うクラス集団づくりはとても大事です。1年生は計画的な取組の中で、そんなことをお互いに語り合い、教室にも掲示しています。
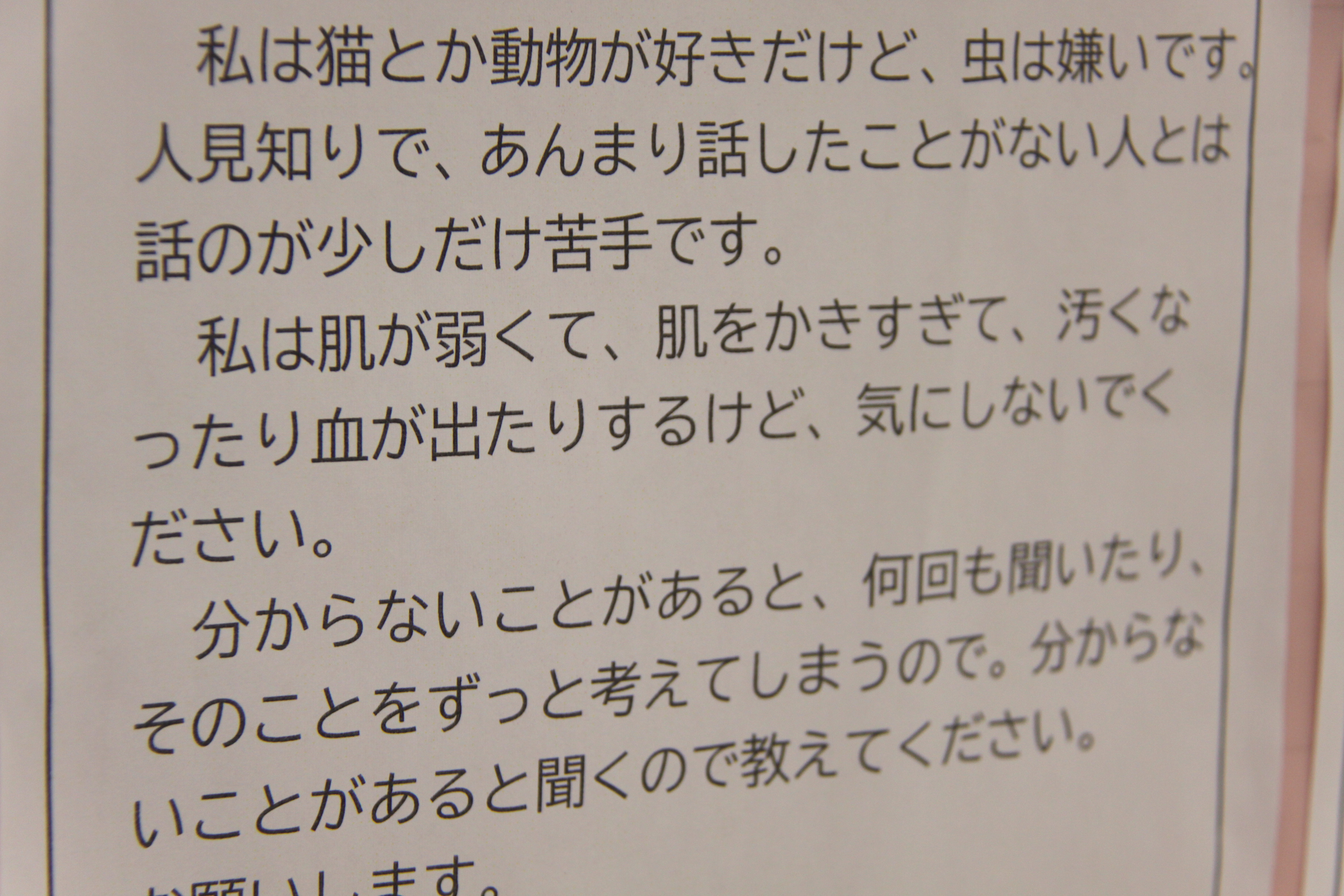
学習計画
【1時間目】『DVD君が僕の息子について教えてくれたこと』より
【2時間目】クラスでクラス わたし あなた なかまを〈よく〉しるために
・カレーライスワークショップ(トレーニング)、真実を見抜トレーニング2(BBCニュースから)
【3時間目】『わたしあなたそしてみんな」
・特徴や持ち味(動物)だけのヒントで、それが誰なのか当てるワークショップ
【4時間目】ワタシとワタシのとなりの「あなた」と共に生きていくために
・エリアテーチャー:東備地域自立支援協議会子ども部会 塚本さん、備前市役所障がい者福祉係 松下さんをお招きして~5時間目への提起
【5時間目】ここだけのみんなに知ってもらいたいこと。わかってほしいこと」ひとつ報告会
・これからがんばる「進路実現」や「学校生活」にむけて、クラスの仲間に知ってほしいことをまとめ、語る。報告を受けとめる。
☆1 受験事前指導(1/24)
○入試への心構えや注意事項、持ち物の確認などはとても大切です。そしてもうひとつ、生徒たち自身がお互いに、これまでの努力を讃え合い、「明日はがんばろうね!」と声をかけあう時間をとりたいものです。グータッチや握手、ハグをしながら、健闘を誓い合うことは、学年仲間の絆が一層強まるのではないでしょうか。学年の先生の一人は「先生の専門教科(理科)の知識を全部インストールするよ」と、希望生徒と握手で送電(?)してました。